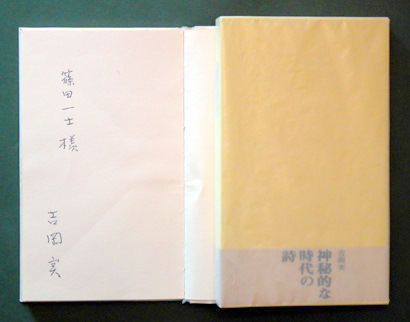

吉岡実が篠田一士に献じた詩集《神秘的な時代の詩〔限定版〕》の見返しと函(左)と同詩集の函と表紙(右)
最終更新日 2019年12月31日
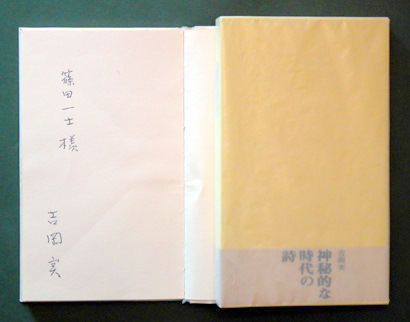

吉岡実が篠田一士に献じた詩集《神秘的な時代の詩〔限定版〕》の見返しと函(左)と同詩集の函と表紙(右)
はじめに―詩篇番号・引用文・ライナーについて/《神秘的な時代の詩》各詩篇の詩集掲載ページ一覧
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(序章)――追悼吉岡実
みなづきの水
〈日記〉――一九九〇年六月二日(土)~六月三〇日(土)
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(1)――〈青い柱はどこにあるか?〉
「暗黒の祝祭」
Ⅰ 詩で書いた暗黒舞踏/Ⅱ 〈青い柱はどこにあるか?〉評釈/Ⅲ 土方巽の秘儀/〔追記〕〈青い柱はどこにあるか?〉の仏訳について
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(2)――〈夏から秋まで〉
「愛と不信の双貌」
Ⅰ 天才・土方巽と《土方巽頌》/Ⅱ 「リアリティ」と引用の方法/Ⅲ 〈夏から秋まで〉初出と最終稿/Ⅳ 吉岡実が池田満寿夫と土方巽に出会った日/Ⅴ 〈編物する女〉と《薬玉》型〈夏から秋まで〉/Ⅵ ポール・クレーと《静物》の成立/Ⅶ 池田満寿夫における書名と画題/Ⅷ 〈ミルク色のオレンジ〉とふたりの詩人/付録 《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(3)――〈立体〉
「白紙状態」
Ⅰ 〈立体〉評釈/Ⅱ 〈立体〉と絵画/〔追記〕〈立体〉のスルスとしてのマグリット絵画
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(4)――〈マクロコスモス〉
「増殖と回転」
Ⅰ 評釈(付・英訳)/Ⅱ 時代/Ⅲ 本文――《静かな家》と比較して/Ⅳ 題名/Ⅴ 詩集/〔追記〕〈マクロコスモス〉の英訳について
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(5)――〈フォークソング〉
「造形への願望」
Ⅰ 〈フォークソング〉/Ⅱ 「造形への願望」
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(6)――〈色彩の内部〉
「細部の変遷」
Ⅰ 「色彩の内部」/Ⅱ 〈色彩の内部〉/Ⅲ 「拡散していく詩」/Ⅳ 「細部の変遷」
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(7)――〈神秘的な時代の詩〉
「意識のながれ」
Ⅰ 〈神秘的な時代の詩〉/Ⅱ 詩=卵の終焉/Ⅲ 神秘なる生死/Ⅳ 時代の人人/Ⅴ 詩の「言語」
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(8)――〈崑崙〉
「矢印を走らせて」
Ⅰ 〈スイカ・視覚的な夏〉/Ⅱ 〈波よ永遠に止れ〉/Ⅲ 〈崑崙〉/Ⅳ 〈葉〉あるいは《粘土説》/Ⅴ 「崑崙」すなわち《薬玉》/〔図版〕〈崑崙〉初出への手入れ
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(9)――〈雨〉
「固い雨なら両手で愛撫する」
Ⅰ 〈雨〉本文/Ⅱ 目の怡悦/Ⅲ 奇異な女流彫刻家/Ⅳ 〈肉体の叛乱〉のあとで/Ⅴ 〈雨〉周辺
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(10)――〈少女〉
「少女の夢のはらみ方」
Ⅰ 〈少女〉以前――最初の作品/〈面紗せる会話〉/詩・歌・句/支那の少女
Ⅱ 〈少女〉――〈少女〉〔初出〕/〔定稿〕/澁澤龍彦の《血と薔薇》/*/馬/少女/前期の終焉
Ⅲ 〈少女〉以後――名前と肖像/写真とキャプション/アリス/ロリータ/アリス詩集の夢
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(11)――〈三重奏〉
「わたしと女友だちと娘のような妹」
Ⅰ 〈スワンベルグの歌〉――初出一覧と詩集の編纂/詩篇〈スワンベルグの歌〉初出と再録/詩集のオーダー成立まで
Ⅱ 〈三重奏〉――「空胴/空洞の美学」/〈三重奏〉とその変奏曲/造形作家と吉岡実
Ⅲ 吉岡実の音楽――時間の相の下で/詩の音楽/題名の由来
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(12)――〈蜜はなぜ黄色なのか?〉
「恋する幽霊」
Ⅰ 色の疑問符――〈蜜はなぜ黄色なのか?〉/〈青い柱はどこにあるか?〉と疑問形のタイトル/〈聖母頌〉のヴァイオレット
Ⅱ 蜜と水――《吉岡実全詩集》巻頭作品/琥珀について/蜜/鷲巣漢詩と〈落雁〉
Ⅲ 神秘の虫たち――蜂蜜をめぐって/蜜蜂、木下夕爾の詩/《昆虫放談》と散文詩型
〔追記〕南方熊楠の〈虻と蜂に関するフォークロア〉をめぐって
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(13)――〈夏の家〉
「あるいは孤独な落下傘部隊」
Ⅰ 「言葉遊び」/Ⅱ 〈夏の家〉評釈/Ⅲ サイケデリックの時代の詩
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(14)――〈わが馬ニコルスの思い出〉
「死馬の眼」
Ⅰ 〈わが馬ニコルスの思い出〉評釈/Ⅱ 吉岡実と馬の詩/詩の馬/〔追記〕「ニコルス」という馬名について
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(15)――〈聖少女〉
「紅血の少女」
Ⅰ 〈聖少女〉評釈/Ⅱ ハンス・ベルメールから四谷シモンへ/Ⅲ 〈薄荷〉
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(16)――〈コレラ〉
「部分からその全体が現われるまで」
Ⅰ 〈ヘアー〉から〈鄙歌〉へ/Ⅱ 〈コレラ〉評釈/Ⅲ 「こんな散漫な詩」のあとに
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(17)――〈低音〉
「ブランコのりのナウシカア」
Ⅰ 〈わが馬ニコルスの思い出〉から〈低音〉へ/Ⅱ 〈低音〉評釈/Ⅲ 〈自転車の上の猫〉
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(18)――〈弟子〉
「花瓣的な奥深いもの」
Ⅰ 献詩としての〈弟子〉/Ⅱ 〈弟子〉評釈/Ⅲ 吉岡実詩と西脇順三郎
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈(終章)――長篇詩の試み
神秘的な時代の詩〔集〕
Ⅰ 神秘的な時代の絵画と音楽――クロヴィス・トルイユ晩年の作品/ビートルズ《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》の波紋/Ⅱ 吉岡実の自己評価/Ⅲ 現世をテーマの長篇詩
〔付録〕吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異(2009年12月31日〔2019年4月15日追記〕)
・本文中の吉岡実詩篇の題名のあとにある詩篇番号の丸中数字は何番めの詩集かを示し、アラビア数字はその詩集での収録順を示す(詳細は拙編《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第2版〕》(文藝空間、2000)やウェブサイト《吉岡実の詩の世界》の〈吉岡実年譜〔作品篇〕〉を参照されたい)。
・とくに断わらないかぎり、吉岡実の詩の本文は《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)に拠った。
・詩句のライナー(行番号やアルファベット)は評釈の都合上、引用者が付したものである。
・原則として、引用文のかなづかいは原文のまま、漢字は新字に統一し(人名・誌名・書名などの固有名詞では一部、旧字も使用している)、必要なふりがなや傍点は[ ]に入れるなどして残した。引用文の句読点は「、」と「。」に統一した。〔……〕は引用者が省略したことを表わす。
・引用文の出典は「#〔分類_番号〕」で簡略表示し、対応する文献を巻末の書誌〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉に列挙した。
| 詩篇題名 | 詩篇番号 | (1)限定版 | (2)特装版 | (3)普及版 | (4)全詩集 |
| マクロコスモス | ⑦・1 | 10-16 | 10-15 | 8-12 | 233-236 |
| 夏から秋まで | ⑦・2 | 18-23 | 16-21 | 14-18 | 237-240 |
| 立体 | ⑦・3 | 24-29 | 22-26 | 20-24 | 240-244 |
| 色彩の内部 | ⑦・4 | 30-33 | 28-31 | 26-29 | 244-246 |
| 少女 | ⑦・5 | 34-37 | 32-35 | 30-33 | 247-249 |
| 青い柱はどこにあるか? | ⑦・6 | 38-42 | 36-40 | 34-37 | 249-252 |
| フォークソング | ⑦・7 | 44-48 | 42-45 | 38-41 | 252-255 |
| 崑崙 | ⑦・8 | 50-62 | 46-57 | 42-52 | 255-263 |
| 雨 | ⑦・9 | 64-69 | 58-63 | 54-58 | 263-266 |
| 聖少女 | ⑦・10 | 70-72 | 64-65 | 60-61 | 267-268 |
| 神秘的な時代の詩 | ⑦・11 | 74-82 | 66-74 | 62-69 | 268-274 |
| 蜜はなぜ黄色なのか? | ⑦・12 | 84-86 | 76-78 | 70-72 | 274-276 |
| 夏の家 | ⑦・13 | 88-91 | 80-83 | 74-76 | 276-278 |
| 低音 | ⑦・14 | 92-94 | 84-85 | 78-79 | 278-279 |
| 弟子 | ⑦・15 | 96-100 | 86-89 | 80-83 | 280-282 |
| わが馬ニコルスの思い出 | ⑦・16 | 102-116 | 90-103 | 84-95 | 282-291 |
| 三重奏 | ⑦・17 | 118-124 | 104-109 | 96-101 | 292-295 |
| コレラ | ⑦・18 | 126-134 | 110-117 | 102-108 | 296-301 |
| (1)限定版:神秘的な時代の詩〔限定版〕 | 1974年10月20日 | 湯川書房 |
| (2)特装版:神秘的な時代の詩〔特装版〕 | 1975年6月1日 | 湯川書房 |
| (3)普及版:神秘的な時代の詩〔普及版〕 | 1976年8月15日 | 書肆山田 |
| (4)全詩集:吉岡実全詩集 | 1996年3月25日 | 筑摩書房 |
吉岡実が亡くなった。
昨日六月一日の夜、帰宅すると日経の夕刊を読むまえに嫌な予感がした。このところしばらくそれが顕著だったりそうでなかったりした、あの感じだ。三面を開くと、見慣れた(あまりによく見ているあの左右対象の)三文字の名前があった。二十行の死亡記事である。いつかこの日の来ることは避けられないにしても、こんなに早かろうとは思ってもみなかった。四月一五日の七十一歳の誕生日に《著作目録》を送った返信に、体の不調が書かれていた。それからわずか一月半である。記事を引用する(朝日や毎日の夕刊を求めて夜の町を自転車で走りまわったが、空しかった。家に戻ると静かな雨が降ってきた)。
吉岡 実氏(よしおか・みのる=詩人)5月31日午後9時4分、急性じん不全のため東京都目黒区の東京共済病院で死去、71歳。自宅は同区青葉台四ノ六ノ一七ノ八○七。告別式は3日午後2時から豊島区巣鴨三ノ二一ノ二一の真性寺で。喪主は妻、陽子(ようこ)さん。
戦前から詩作に励み、戦中に北園克衛らのモダニズムに影響を受ける。戦中経験から来る実存主義的な難解な詩風で知られる。昭和34年、詩集「僧侶」で第九回H氏賞を受賞後、「サフラン摘み」「薬玉」などを次々に発表し、大きな反響を呼んだ。舞踏、美術、俳句、短歌にも造詣が深く、本の装丁家としても有名。
これから新聞・雑誌に注目せざるを得ない。気の重いことだ。今日はかねてから〈スワンベルグの歌〉の初出確認に、駒場の日本近代文学館に行くつもりだった。追悼の意も込めて小雨のなかを出かけよう。吉岡実のいない東京とはなんとうつろなのだろう。いまつくづくとそのことを思う。
朝八時に田端の父母に電話する。葬儀の服の準備のことなど。今日の夕方、来ることになる。鷺宮図書館で昨夕の朝日、読売、毎日、産経、東京の各紙をコピー。立喰そば屋でもり。新宿経由、東北沢から駒場の日本近代文学館へ。「エクレア」というキャラメルを舐めながら。入館料三○○円。私家版詩集《雲井》(*)のために、雑誌のバック・ナンバー調査。《婦人公論》と《現代詩手帖》。正午から四時間ほど調べ物をして、まだ玉砂利の湿っている駒場公園を後に、井の頭線・駒場東大前から渋谷まで出る。吉岡実の最寄り駅の神泉を過ぎて。渋谷駅前を彷徨する。道玄坂センタービルB1の喫茶店トップ道玄坂店でアイス・コーヒーを飲み、吉岡を偲ぶ。《ダブル・ノーテーション》の談話取材に同行して、初めて対面したのがここだ。そして一九八九年五月に初めてさしむかいで話をしたのもここ。駅前ビルB1の渋谷駅前店のトップ(一九八九年一二月、最後に会って話をした)は改装中で、向かいのマルナンで装丁用布地を物色。後日を期す。道玄坂店では、文藝空間の増渕淳子さんと偶然、近代文学館で会ったあと来てみると、吉岡が憩っているのを見かけたこともある。渋谷以外で氏と会ったのは、下北沢の明大詩人会の忘年会と銀座のセゾン劇場のロビーでだけだ。つまり、吉岡実の東京とは渋谷なのだ。それらの日付も調べればはっきりするが、いまは空虚な東京に抱かれていたい。一八時すぎに帰宅。
一○時起床。すでに日が高い。ハムチーズ・トーストに珈琲の朝食。母は防災訓練に出かけた。練馬郵便局に不在配達の受取に行く。涼しい木蔭を自転車で。ついでに練馬図書館に寄って、《ヘンリー・ミラー全集》を借りる。〈梯子の下の微笑〉を読むためなり。昼食はそばを慌しく摂って、炎天のなかを礼服に身を包み、自転車で西武池袋線・中村橋駅に出る。本一冊持たずに。池袋でJRに乗り換え、巣鴨駅で下車。構内で「吉岡家」の立て札を抱える田野倉康一氏に会い、真性寺を教わる。
記帳する私の前の人物は水尾比呂志。菅野昭正の姿も見える。一三時五五分から吉岡実の告別式が始まる。司会進行は平出隆。六名の弔辞が続く。大岡信の言葉は途切れがちで「あんなに帰りたがっていた松見坂のマンションにきみが帰ったときは、遺体となってでした」というあたりでは私も思わず涙せきあえず。入沢康夫が曇りがちな声でその詩業を讃える。高橋睦郎がはっきりした口調で今日のこの日も「夏の宴」だと言う。中西夏之がとつとつと美術家から見た吉岡実を語る。金井美恵子が楽しいことしか思い出せないと故人との思い出に耽る。小田久郎が、私も吉岡自身から聞いたことのあるエピソードを交えて、日本の現代詩も別の局面に入ったと出版人として述べる。イチョウの脇のテントで日差しを避ける。入口が狭く、親族らの控える建物のなかまでは見えない。弔電が三通だけ披露された。永田耕衣と竹西寛子と伊藤比呂美(私の気持ちにいちばん近いのは、伊藤の「お目にかかれて嬉しかった」というものになる)。焼香。花の送り主に満六七五戦友会があって、目を引いた。列の左前に首の太い種村季弘の姿がある。遺影はまだ半白の《サフラン摘み》のころのものだろうか、たばこを指に挿んだお洒落な感じ。出棺の準備をしている最中、風が出て受付のテーブルが倒れた。親戚が菊の花を柩に入れたあと一般人も花を捧げる。お顔の脇に花を置く。薄く口を開けた小さな死顔が菊に埋もれていた。長く病んだようには見えなかった。深く礼をする。吉岡さんとは永遠のお別れだ。あの、だれもが言う、悪戯好きの少年のようにくるくるとよく動く大きな目玉が、この苛烈で無慈悲で粗雑で、そのくせ美しく切なく愛すべき現世を見ることは二度とないのだ。私にはその死がなんだか悪い冗談のように思えてしかたがない。参列者に「ごあいさつ」が配られ、葬儀委員長の飯島耕一と喪主の陽子さんが挨拶した。近しい人たちが町屋の焼き場に行く車を通りまで見送って、葬儀を終えた。時に午後三時一五分。参列者は、那珂太郎・鈴木志郎康・白石かずこ・天沢退二郎・北村太郎・吉本隆明・渋沢孝輔・安藤元雄・金子國義・土方巽夫人元藤燁子・粟津則雄など。出版社の人間も多かったろう。
本日はご多用のところ 吉岡実をお見送りいただきまことに有難うございました 吉岡実の肉体は地上を去りましたが その詩は皆様がたの心の天空で生きつづけることでしょう一度は母親の鏡と子宮に印された
美しい魂の汗の果物
だれにも奪われずに ―「死児」より―一九九○年六月三日
葬儀委員長 飯島耕一
喪 主 吉岡陽子
友人代表 大岡 信
友人代表 高橋睦郎
ひとりになって、池袋のリブロで本を買いこむ。供養である。ぱろうるの店員も告別式に出ていたようだ。思潮社の社員らしい人に、小田さんの話は良かったと声をかける。帰宅すると父母は買い物に行ったのか、鍵が掛かっている。風の吹く濡れ縁で読書。長い夏の日の太陽は、まだ西の空にある。
二○時過ぎ、移転して一週間めの日教販ビルで退社前の高岡氏と立ち話。吉岡実(彼はジツさんと呼ぶ)は剣豪のイメージなりき、「小兵だし」とは言い得て妙。もっとも会って一言でも交わせば、当方の緊張も氷解するのだが。久しぶりにわが《樹霊半束》(吉岡さんが読んでくれた唯一の私の作品)を書いたジョナサンで晩飯。キリンのラガー中瓶とビーフ・ストロガノフ。吉岡実の詩を十篇挙げるとなにになるか考える。思いつくままに順不同で。
〈サフラン摘み〉〈僧侶〉〈感傷〉〈雪〉〈青枝篇〉〈雲井〉〈聖あんま断腸詩篇〉〈水のもりあがり〉〈やさしい放火魔〉〈自転車の上の猫〉。
どれひとつとして忘れられない作品だが、一篇だけなら〈サフラン摘み〉を選ぶ。確かねじめ正一が最もエロティクな戦後詩だと書いていたが、いま読めば《薬玉》の民俗的かつ神話的な面も明らかだ。澄明なものの影に人類の記憶が黒黒と横たわる。《僧侶》の詩人の精進たるや恐るべし。いつの日かクレタ島を訪れ、吉岡さんに絵葉書を出す夢は失われた。しかし、そこでなにを書くかは想像できないでもない。まず、われわれは西脇順三郎に導かれた詩の徒であり、吉岡実はクレタを見ずにそれを詩に書き、私はクレタを書かずにそれを見た、というようなことを。北村太郎の「西脇よりも小味だが、その手腕は抜群」といった趣旨はまったくもって正しい。西脇はくり返しを恐れなかったが、吉岡実はそれを嫌った。おそらく「永遠」を信じていなかったためだろう。吉岡の体験は「現世」から離れることをついに肯じなかったのだ。
できたばかり本に問題があって、早めに出社。詩人であり出版人であることの困難さを思う。大学の先生だって大変だろうが、なまじ本の世界に近いと詩は書きにくくなる。有能な編集者であり、卓絶した詩人であることは、吉岡実にさえほとんど不可能に思える。昼食は、小石川後楽園に近い日中友好会館・地下の豫園で五目焼きソバ。生前、吉岡に見せることのできなかった未刊詩集《雲井》のファイルを再読する。刊本になっていない作品(〈波よ永遠に止れ〉は除く)を逆年順に十三篇集めたものなり。連載中の《神秘的な時代の詩》評釈に幾篇かを引用したが、〈哀歌〉の一節などそのまま〈内的な恋唄〉に利用されているから秘匿されたのも理解できる。〈休息〉の三行は〈雲井〉に生かされた。〈休息〉とは別に澁澤龍彦追悼詩篇が書かれたから、これも同じ運命をたどるはずであった、作者存命ならば。吉岡が未刊の著書を遺したということは、たぶんないだろう。その作品史は完璧である。若書きの日記さえ、きちんとした一冊にして逝ったのである。それは計算ずくのものではない。むしろもっとわけのわからない力のこもったものだ。《うまやはし日記》(吉岡さんから送っていただいた唯一の新刊)への礼状を再録しよう。
拝啓
五月になってもはっきりしない天侯が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。連休前の二日の夜遅く帰宅しますと、弧木洞版《うまやはし日記》が書肆山田から届いておりました。月刊雑誌を担当していると、連休だからといって遠出する気にもなれずにいたところへ、待ちわびていたご著書到来とあって、欣喜し、さっそく一読に及びました。
初出〈うまやはし日記〉や最近の〈日記一九四六年〉からも予想していましたが、それ以上に「私的事項」に満ちているのに驚きました。登場する人たちもさることながら、東京や松井田や盛岡のたたずまいが、とても小説ならこの分量では描ききれまいと思われるほど見事に定着されており(しかも、その眼の持ち主は二十歳前後の未だ詩人ならざる青年です)、これも日記という文体の勝利かと感じいりました。
いつぞや「子供のころのことはもう随筆には書きたくない」とお話しになっていましたが、今後はこの《日記》を読め、で済んでしまいそうな気がします。戦争直前の下町の生活がどのようなものだったかは、本書で充分でしょう。
そしてこれは意図的な扱いでしょうが、俳句や短歌を要所要所に配し、詩集(《昏唾季節》?)や歌集《歔欷》・句集《奴草》(未刊でしょうが)を出したいと書くあたりが興味深いことは言うまでもありません。
たかだか五十年ほど前なのに、なにやらゆかしい歌物語を読んだような気になるのもまた、文体、いや形式の魔力が与って大きいのでしょうか。《うまやはし日記》の地点から《昏睡季節》や《液体》を読みなおす作業が必要になりますが、いまはただこの典雅な文章を、吉岡さんの半世紀の文業の成果(もちろん《土方巽頌》のことです)と比較しつつ、慈しむことを自己に課したいと思います。
とりいそぎ本のお礼と感想をしたためました。
一日も早く健康を回復され、「長篇詩」のお仕事に取りくまれることをお祈りいたします。(拙論《神秘的な時代の詩》評釈の作業仮説は、あの文体で長篇詩を書くとどうなるか、ということです。いずれ〈マクロコスモス〉論もご覧いただきたく。)敬具
一九九○年五月六日
小林一郎
吉岡実様
告別式を締めくくった飯島耕一によれば、四月二四日に入院したとのことだから、この手紙もご覧いただけなかったかもしれない。人工透析によって一時もちなおしたそのときに、お読みいいだけたのだと慰めよう。「とどかないかも知れない故に深い愛のことばを告げる」(〈波よ永遠に止れ〉)のでは美しすぎるし、悲しすぎる。
ワードプロセッサによる《雲井》限定壱部本の原版出力。これでテクストは完成。装丁の考案に移る。秦恒平〈湖の本14〉の《みごもりの湖》届く。いつか、秦さんのまえで吉岡実の詩が好きだと言ったこともあった。
なんとか仕事を早めに切りあげて、鷺宮図書館で各新聞を閲覧。四日付けの朝日新聞の夕刊に飯島耕一が追悼文を寄せている。そのなかの吉岡のハガキ、「耐えて、再起したいと思っています」「生死の床の中で、がんばるつもり」が辛い。最後に飯島は結論する。「日本の戦後最大の詩的才能だった」と。大きく頷く。大岡信は「運命的に詩を作るためにのみこの世に送られてきた不思議な旅人」(弔詞)と呼んだ。ほんとうにそのとおりだと思う。次の文は「半歳におよぶ病いと不眠の日々」に書かれたものだろうか。刊行されたばかりの現代詩文庫の第一○○巻《平出隆詩集》の表四。
〈花嫁〉を迎えることは、〈完璧な死と誕生の儀式〉かも知れない。〈花嫁〉のめくるめく聖性の身体には、〈星と言葉と血〉が脈々と息づいている。その日々の共棲のなかで、〈花婿〉平出隆は冷厳に、孕まれる〈贋の花嫁〉を解体する。そして〈読める胎児〉や〈読めない事物〉を、白日の下に晒し出すのだ。この寡黙なる〈花婿〉は、発情する音楽や動植物の詩的迷路を彷徨しながら、〈待つ花嫁〉を探し求めているようだ。吉岡実
〈花嫁〉〈完璧な死と誕生の儀式〉〈花嫁〉〈星と言葉と血〉〈花婿〉〈贋の花嫁〉〈読める胎児〉〈読めない事物〉〈花婿〉〈待つ花嫁〉――これらの語を山括弧(もともと吉岡は作品の題名などにこの記号を使用してきた)で括りながら、来るべき詩篇を想像していなかっただろうか。〈聖あんま断腸詩篇〉以後の引用の凄みは、とおりいっぺんの独創性を信じていないところに存在する。〈雲井〉にボードレールの散文詩の一節(澁澤龍彦のエッセイからの引用と思しい)が出できたときは驚いたが、そのときの吉岡実宛の手紙(一九八九年一一月五日付け)を一部、引く。
お葉書をありがとうございました。そのあとさっそく大久保の俳句文学館でお作〈雲井〉を拝読し、(樹木の霊や/鳥獣の魂)だけでなく、ボードレールの散文詩の詩句を発見し、驚きました。私の深読みでなければ、フレイザーの最も甘美な部分が反映されていると思いましたが、(虹もまた炭化する)の見事さの前では、さして重要なことではありますまい。
さて、先にお約束しました評釈〔〈立体〉論〕をお届けします。一年も考えていると長長しいものになってしまいますが、調べながら細部を味わう楽しみからはなかなか抜けられません。見当違いの点あるようでしたら、お許しねがいたく存じます。《神秘的な時代の詩》全篇を異なったスタイルで論じてみたい、というのが当面の目標です。
母の誕生日。いつものとおり遅く帰って、なにもしてやれぬが。〈マクロコスモス〉論の第二稿に手入れ。《神秘的な時代の詩》の論考を吉岡さんは「どのようなものになるかわからないが、書かれた詩文を参照しているうちに迷宮ができあがるのではないか。ともかくこういう読み自体は面白い」というふうに言ってくれた。
一九時半から、新宿シアターアプルでシャドウ・ヴィネッツの〈津波コンサート〉。二時間強。指ではじく南アフリカの楽器に感動。終演後、ロビーでメンバーや関係者と簡単な打ちあげ。会社の人間と、ひととき悲しみを忘れる。外は嵐のような風雨。
引きつづき〈マクロコスモス〉論、二稿に手入れ。不要な節を削る。次回以降で触れるべき話題なり。この稿とは別に〈文藝空間・会報〉に本日記を追悼文として同時掲載しようと思う。《雲井》も和綴本に仕立てたいし、いよいよ忙しくなる。
飯田橋付近の神田川に緋鯉・錦鯉・真鯉が游泳している。水のない街は淋しい。帰り、会社の同僚とミツでビール。川風が心地良い。詩の形式を革新していく一方で、ポエジーを深めていくことが吉岡実の詩業であった。《ムーンドロップ》が《夏の宴》に似ていると告げると、吉岡さんは意外そうな顔をしていたが、どちらも西脇順三郎の絵をあしらうことで、西脇の詩的世界から離れようという意図はなかったか。〈永遠の昼寝〉のスリルは、ほとんど吉岡の地の文がないとさえ思えるほどに、西脇の章句が引用されていることだ。〈雲井〉の瀧口修造も意図としては同様だ。その意味でも、次の詩篇はぜひとも読みたかった。臆測だが、生前最後の〈沙庭〉は《薬玉》の時期の執筆ではあるまいか。
昼休みに神保町を歩く。雨雲が迫ってくる。これからの日本の詩はどうなるのだろう。おそらく暗澹たるものがあろう。詩、というよりも言葉の力と呼ぶべきかもしれぬ。岩波書店からの詞華集にCDが付くというので期待していたが、吉岡実の作品は入っていなかった。〈静物〉あたりならふさわしかろうに。土方巽の追悼公演での役者による〈僧侶〉の朗読は、良くなかった。活字なら明朝体のようなもののほうが、作品の奥行が出る。ラジオの土方巽の朗読は(吉岡によれば「教育勅語的発声」だが)そんなではなかった。私は吉岡実の詩の「歌」に魅了されたのだ。それは〈サフラン摘み〉にも顕著だが、深くは追求されずに《薬玉》が来た。晩年、もっと歌いたいと言っていたのは、時間の要素もしくはくり返しのことではないか。具体的な根拠があって言うのではないが、《うまやはし日記》がそのウォーミング・アップだとするなら、詩歌句の混然たる世界が「歌」の内実なのではあるまいか。それと、〈聖あんま断腸詩篇〉後の長篇詩がどのようにかかわるかは、なかなか思いえがけないが。
《新潮》七月号に四方田犬彦の《うまやはし日記》書評。十年前の吉岡実論は衝撃的だった(四方田氏の存在を知らなかったこともあるが)。今回も丁寧に読んでいるが、《僧侶》ではなく《土方巽頌》との関連が聞きたかった。《群像》の特集〈日本語へ! 詩人の立場から〉にももちろん吉岡実は書いていない。仮に元気でも執筆するテーマではなかろうが、これからさき誌上で吉岡のものを発見し、読めないのは淋しいかぎりだ。朝日の夕刊で小田久郎談。「吉岡実さんも亡くなり、つくづく『戦後詩』もおしまいのときが来たなあ、と感じます」と。
昼休みに神保町まで歩く。田村書店で《三好豊一郎詩集》。造本は杉浦康平。思潮社版《吉岡実詩集》を極端にしたような書物だ。明大詩人会の忘年会に入沢康夫と現れた吉岡実に装丁造本のことを尋ねたことがある(調べてみると、これが詩人と明大出身でもない私との出会いだった)。なんでも杉浦は、詩篇に字下げによるデコボコを作って、吉岡と対立したらしい。この会話は《薬玉》より後だったにもかかわらず、迂闊なことに両者の関係を聞くのを忘れた。また、刊本でも版面はかなり上なのに、ぎりぎりまで(「製本のときに落ちてしまうくらい」と吉岡は言った)上にあったのを少しでも下げたのだそうだ。この《吉岡実詩集》は美しい本だと思うが、《三好豊一郎詩集》の函が蛍光色で、判型がほぼ二対一の縦長本であることから想像するに、杉浦の純然たる仕事はもっと派手で、喩えて言えばテクストを痛めつけるような性質のものではなかったろうか。当初の過激なコンセプトが、著者であり装丁家である吉岡の反対によって、変更を余儀なくされた。その辺の事情は刊行当時の《現代詩手帖》のコラムに見える。奥付にある設計データの表示は、当時としても立派なものだ。ただ、フランス装にしては束がありすぎて紙も重いせいか、函から出して立てかけておくと真ん中が垂れさがってくる。ハード・カバーでしかるべきだろう。もっとも、フランス装の指定は吉岡からあったのかもしれない。
〈マクロコスモス〉論に手入れ。いつものことだが、これで良いのかという不安が湧いてくる。入沢康夫の言うように、吉岡実詩篇をすべて読解することなど、だれにもできないのかもしれない(作者にさえ)。そうした作品の不思議さに、入沢も大岡信も惹かれてきたのだ。大岡は初期を除いて吉岡論を書いていないが、その作品に寄せる時時の評価は吉岡を鼓舞してきたろう。真の友情と言うべきである。私もまた吉岡詩篇を味読し、そしてなにも語らないのが一番なのではないか。あるいは、吉岡とは別の「詩」を書かねばならないのではないか。理解できないものを自分から創りだすのでなければ、詩を書くことに意味はない。その点で私は吉岡実の徒でありつづけるだろう。
昼、急に強い雨。吉岡実逝去を報ずる《琴座》第四六○号届く。健在なら参加したであろう永田耕衣旭寿の会が葬儀の当日だった由。書かれざる《永田耕衣頌》を想像して、吉岡と耕衣の縁を偲ぶ。午後、ひきつづき〈マクロコスモス〉論に手入れ。WP上で訂正した第三稿をつくる。深夜、LDで《薔薇の名前》を観かえす。吉岡は小説《薔薇の名前》は読んだだろうか。〈僧侶〉の詩人の感想が聞きたかった。
蒲田で《雲井》和装本用の木綿布、お茶の水でレッド・ツェッペリンのブートレグ(なんとCD)を買ったら手持ちがなくなる。芳林堂書店で《西脇順三郎論》を見つけるも諦めて、このあいだ持ちあるいていて失くした《マラルメ詩集》を再び求める。鈴木信太郎訳の文庫本の恐ろしさは〈註〉〈年譜〉にある。吉岡が晩年に意識していたのは、西脇順三郎や瀧口修造よりもボードレールやマラルメだったような気がしてならない。《薬玉》と《荒地》の例から、エリオットも挙げるべきだろうか。海外の詩を翻訳で読みつづけたことは間違いあるまい。《静物》の成立にリルケが与っているとは本人の弁だが、《神秘的な時代の詩》あたりにピカソの詩が関わっていそうだ。例の瀧口訳とは別に大島辰雄訳のピカソの詩があって、複眼的図像や色彩感覚は大いに共通している。それはシュルレアリスムともキュビスムとも言えない、見ることの達人が書く詩だ。
「彼は、フォルムに対する過度の偏愛という十九世紀以後の伝統をあっさりと退けて、通俗性と猥雑な空間を逆手にとって、神話的想像力がそこから湧き出る秘密の地下水路を見出したようである」という結語を持つ山口昌男のクロヴィス・トルイュ論〈挑発的な祝祭世界〉(《知の祝祭》所収)から、《神秘的な時代の詩》を連想しないでいるのは不可能に近い。
「この画家の画風を一口に言い表わすとすれば、「挑発的」という点に尽きるように思われる。挑発という行為は、人が期待するような経過を全く満たさず、ただひたすらに、安定した秩序の感覚を逆なでにすることによって、日常生活の世界を越えた現実が存在するという事実を想起させる営みなのである。」
「女性は吉岡の世界の中心にある。吉岡は、西欧の古地中海文化、或いは遥かその彼方の時間に拡がる大地母神の崇拝の今日最も熱烈な信徒である。」
「どの一点を押しても、これまで大衆的低俗さとして、画材の中に殆んど採り入れられることのなかった要素を、吉岡は暴力的に導入する。この美学的暴力性と、宗教的涜聖という行為によって彼は、他の方法を以ては開示することの不可能な意識の神話的次元を伐り拓くのである。そういった世界に統一感を与えるのはエロスと祝祭性という、人間がそこではもはや、日常生活の規則性とつつましやかさを捨てた空間、そしてその空間の顕示の場を与えるのが見世物的世界である。この見世物的世界が、吉岡の教会であり、その主神が、大地母神の系譜を曳く生身の女性である。」
「女性的美しさを最も昂揚した形で示すのが見世物であることを吉岡は知っている。/彼の女性的世界は中心的象徴としての円鎖の上に組み合わされている。彼の作品の女性の胸もとは必ずコンパスで描いたような円で描かれている。」(トルイュを吉岡に置き換えただけで《神秘的な時代の詩》から《サフラン摘み》を予見する論となるのだ。)
川本三郎の言うように一九七○年代が山口昌男の時代であるとするなら、山口の学問領域とは別の地点から吉岡もまた同じ時代を把えたのだ。
吉岡実の詩の本質とは言わず、魅力とはなんだろう。私の物覚えが悪いせいだろうか、読みかえすたびに新たな発見がある。そこに自在な視点がある。長谷川龍生あたりが「猥褻な視線」と言うやつだ。つねに驚異に瞠目する眼とは、多くの人人が指摘する吉岡実その人の印象だが、なによりも詩に表れているそれをこう言いなおそうか。作者の先入主を破るような「驚異」を与えない詩を書こうとしなかった、と。どんな陰惨な(数は多くないが)作品でも、その詩を読むのはつねに楽しみである。雨の日にも愉悦の時があるのに似ている。作者も人間である以上、無限に詩篇が産みだされるわけはないが、一読者の予想を裏切る作品がもはや生まれないというのはなんという悲しみだろう。だが、それよりもなによりもその人を喪ったのが痛恨事だ。何度か手紙にも書き、本人にも「長篇詩」を期待していると言ったが、一行も書かなくて良い。せめてあと十年、なんとしても生きていてほしかった。そのとき吉岡実は彼の黄金の沈黙を生きただろう。ついに墓のなかに持ってゆくしかない主題というのは、ある。
家のまえに拡がる畑のトウモロコシが、はや人の背丈ほどになっている。今年の梅雨は雨の日が少ない。魔の五月の、あの雨が嘘のようだ。季節を切りとる吉岡実の手紙の出だしはいつも的確だった。随筆で筆不精だと書いているのは、幾分かは誇張だろう。その書簡は永田耕衣宛が《琴座》に〈青葉台つうしん〉として紹介されているくらいだが、味わい深いものだ。原稿を抱えていて返事が遅れたのを詫びたりしているから、頻繁にやりとりがあったわけでもなかろう。それでも《鰐》のころからだから、三十年にはなるわけだ。詩や俳句が書かれていなくても、美しい往復書簡が編めることだろう。
渋谷の中村書店でユリイカ版《吉岡實詩集》をついに発見、少し汚れていたが購入。六千円也。フランス装ふうのジャケットの背に破損があるので、和紙で補強する。手に取ってずいぶん正方形な本だと再認識。ロフト5Fのぱろうるで《るしおる》六号を求める。吉岡の〈日記 一九四六年〉の第二回掲載。まだ続くのだろうか。《うまやはし日記》が書籍になるというので、別に連載用の原稿を書いたのなら、今年の初めころか。ならば吉岡実が残したほとんど最後の文章と言っていいだろう。未発表の詩篇は書いているのだろうか。それとも、若き日の日記のように破棄されたか。評釈は、WPプリント・アウトに徹底的に手入れ。書きくわえた量くらい削る。いよいよ最終段階にさしかかりつつある。
夏至の真夏日、高温多湿で日本のようでない。外堀の水面の濃緑に水草の緑がマーブル模様を描いている。仕事の帰り、会社の仲間と大日本印刷の担当者と飯田橋の柳生で飲む、久しぶりに。論考の文献表の原稿起こし。前回よりも吉岡実以外の本の数が減る。《神秘的な時代の詩》評釈は五十ページ前後になりそう。四十字×二十行だから百枚だ。
原稿を書いていると、読了する本がめっきり減る。馬のことをいろいろと調べたいのだが、手が回らない。ずいぶん前に《現代詩手帖》に連載された岡田隆彦の文が面白かった(去る二日に日本近代文学館でざっと読んだだけだが)。先日はその進化の学術書まで買ってしまった。吉岡実は馬の詩を集めた選詩集の企画が沙汰やみになったと嘆いていた。目次を想像してみよう。〈静物〉〈牧歌〉〈僧侶〉〈苦力〉〈人質〉〈サーカス〉の馬が《吉岡實詩集》で目についたが、〈冬の休暇〉〈馬・春の絵〉〈わが馬ニコルスの思い出〉を逸するわけにはゆかない。さて書名はなにが良いだろう。《馬の肖像》あたりか。夜、ビデオで〈ラストエンペラー〉を観る。最後のコオロギの場面では落涙する。
朝、渋川の諸田の家に養子にいった叔母から電話。駅前の医院に入院中のおばあさんが重態ゆえ、長兄の父に見舞いに来てほしい由。老衰だという。父に伝言。盆の墓参りに行ったついでに諸田家まで足をのばして、手打ちそばをご馳走になったものだ。無慈悲な夏。午前中で論考の引用文のチェックを終え、原稿は一応でき。校正が続く。前の野菜畑はすっかり乾いている。妙な梅雨なり。このところBGMはジェスロ・タルのLDをカセットにダビングしたもの。私は一九五五年(《静物》刊行の年)生まれだから、その年に誕生したロックン・ロールの伸張が同時代的感覚として理解しやすいが、吉岡実のモダニズムもそれと似たところがあったのではないか。
各紙の評価。「超現実的な独特の作風で戦後詩に大きな影響を与えた」(朝日新聞)。「超現実的で難解な詩風で知られた」「グロテスクかつエロチックなイメージで、独特の幻視の世界を詩として構成」(読売新聞)。「戦後、戦中体験からの実存主義的と超現実的な手法を融合し」「現代の残酷のイメージをテーマにし、実験的な作品として詩壇に衝撃を与えた」(毎日新聞)〔しかしひどい文だね〕。「詩の言葉を世俗的な日〔目?〕差しから守ろうとした、その極北の詩的結晶を示した詩人」(荒川洋治・産経新聞)。「初期に北園克衛らのモダニズムの影響を受け、戦後は、戦争体験から実存主義的な手法も取り入れて新しい詩風を開いた」(東京新聞)〔これはまともな文〕。
なによりも「詩」への絶大な信頼がある。あれだけ多方面に亘る関心をもちながら、作り手としては音楽や舞踏はもちろん、絵にも書にも手を出さなかった(唯一の例外としての装丁作品)。三百篇たらずの詩篇とさして多いとも言えない散文が、吉岡実の全作品である。装丁は詩と同じ人間の手になるものとは信じがたいような、静謐なたたずまいを見せる。だが、見ること/見える物に対する確かな手応えという点において、詩と装丁、おのおのの構造物は見事な対応をなす。私はその成果を最後の詩集《ムーンドロップ》に見たいと思う。
深夜、論考の全貌がかたまる。引用の織物といったあんばいだが、いまはこれが精一杯だ。《神秘的な時代の詩》評釈を十八篇書くとして、各百枚で一千八百枚。《「死児」という絵》の何倍だろう。そのときは堅苦しい題はやめて、《〈吉岡実〉を探す方法》とでもしよう。WPのデータがあれば、組版代もたいしたことはあるまい。そんなことよりも、年に一、二本の今のペースでは今世紀中に完成するかおぼつかない。気長に、着実にやるしかないのだが。
《ダブル・ノーテーション》土方巽特集の取材メモが出てきた。一九八五年五月二三日、トップ道玄坂店で一四時から一時間、インタビュー担当の清水さんと同席。土方巽の人となりの二百字コメント(談話のまとめは私ではない)。二度めの対面となった吉岡実は、土方巽の詩を三篇書いているとまず言った。
――土方巽は(吉岡は「土方巽は…」とフル・ネームで呼んだ)戦後に表れた日本の天才、のひとこと。奇ッ怪な人間だろうし。十八年前から舞踏はすべて観ている。澁澤龍彦さんはそれ以前からか。芦川羊子、笠井叡、大野一雄もずっと観てきた。山海塾も。土方一派の舞踏の(すべてじゃないが)生成の過程は、門外漢では自分がいちばん詳しいだろう。〈金柑少年〉の初演。凱旋公演もふたつ。土方は六、七年間雲隠れの時期があった。《新劇》連載の〈病める舞姫〉の出版を拒否。大野さんを支えて、今年か来年は踊るだろう。たいへんな読書家で、吉岡詩のこわい読み手。氏の書くものは類型がない。土方語録のちりばめられている自伝、散文? ますますもって世界的な存在へ。そのすごさ。さしさわり。土方巽と同年齢の澁澤さんが土方をどう思うか、面白かろう。土方は酒の席ですごいことを言う。具体的には思い出せない。百鬼夜行の状況での特殊なことばだから消えてしまう性質のその語録は、将来出るだろうが。〈舞踏フェスティバル〉の講演では勉強をしたようだ。出会いは加藤郁乎さんのパーティ。「この気になる人はだれかな」と。着物を着て、女の人のような髪をして。当時はどんな舞踏か知らなかった。土方巽は《僧侶》を読んでいたが、声をかけてくるような人間ではなく。――
コメント以外の話も、もちろんした。署名してもらうべく持っていった(担当編集者でない強みだ)英訳詩抄《闇の祝祭》の由来。訳者(版元?)の命名は《闇のカーニバル》で、吉岡の代案は《闇のなかの絵画》か《闇の祝祭》。前者を薦したが「アンソロジーだからねえ」。《ライラック・ガーデン》は訳者とのあいだで了解ずみだった由。
天候のせいか気分すぐれず、校正作業もはかどらない。吉岡さんからのハガキをながめて慰む。愛する人ほど私から去ってゆく。こんなとき吉岡に《「死児」という絵》の紀行文の調子の長い散文が一冊あったら、どんなに良かったろう。「詩」では、純度が高すぎて頭が受けつけない。軍隊のことを書きたいと晩年まで語っていたが、実現すれば満洲や済州島も活写されただろう。〈ラストエンペラー〉の満洲は、黄色っぽい土挨が舞っているところだった。戦前の下町育ちの青年にとって、戦争とはそうした風土や軍馬の世話といった、それまでの生活とまったく異なる世界として押しつけられたものでもある。そこでの兵の姿や自然のありさまは、詩人の眼を変質させずにはおかなかった。醜さのうちに美しさを、美しさのうちに醜さを見ること。詩の、美学の問題だったモダニズムは、現実と拮抗しあう現代性にまで鍛えられた。その兵士に戦時中の詩はなくとも、彼はリアリティのある詩篇とはなにかとたえず思いをめぐらせたに違いない。
《現代詩手帖》と《ユリイカ》が吉岡実の追悼特集を組んでいる。とりわけ、笠井叡と中村稔の文に打たれた。入沢康夫の「来るべき吉岡実論」にも感じるところが多いし、城戸朱理の文も良かった。瀧口修造を筆頭に、西脇順三郎、鷲巣繁男、土方巽、澁澤龍彦への追悼詩が吉岡の晩年の三詩集に収められ、散文も(吉岡自身「義理のあるもの以外は書かないんだ」と言っていたが)高橋新吉、草野心平、鍵谷幸信、篠田一士らへの弔辞や追悼文が草せられた。土方も澁澤も、鍵谷も篠田も、吉岡より若かった。
篠田一士の死去直後だったせいか、私がいただいた最初のハガキは沈痛なものだ。
春の雨がふっています。もろだけんじ句集『樹霊半束』拝受いたしました。小生に献じられた、貴重な書、本当にありがとう存じます。「弧樹」になったこと、おそらく誰も知らないと思います。貴兄の心くばりに、驚いております。精密に小生の仕事を、辿られている故に、このような祝いを〔吉岡実の七十歳を祝した刊行日〕、して下されたのだと思います。句集はまだ読んでおりませんが、今の仕事〔篠田一士の追悼文か〕が終ったら、読みます。五月になったら、一度、お会いしたいと思います。 不一 実
昨年四月一六日、目黒局の消印のあるハガキだ。これに、この率直さにどんなに励まされ、慰められたことか。吉岡さん、あなたにはおわかりにならないでしょう。吉岡実の詩と、吉岡実の人物を知ったことは、私の生涯の幸福であったと、いまここに思う。
最後に会った吉岡実の矜侍は、ある歌人について「第六歌集がベストで、その後は自己摸倣に陥っているのではないか」と質した。「詩」と「独創」を信じた男の厳しさを目の当たりにして、その孤独がどれほど深いものか、私はほとんど想像もできなかった。
吉岡実追悼一句。「みなづきの水にびいろの空うつせ」(もろだけんじ)
…………………………………………………………………………………………………………
私家版詩集《雲井》(*)
初出一覧をもって吉岡実私家版詩集《雲井》(小林一郎編)のプランの紹介とする。
口絵〈永遠の昼寝〉 編者蔵(《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》展出品原稿に同じ)
沙庭 《文學界》 一九九○年一月一日(第四四巻第一号)九ページ
雲井 《鷹》 一九八九年一○月五日(第二六巻第一○号通巻第三○四号)四六~四九ページ
永遠の昼寝 《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》 一九八九年四月一日(新潟市美術館刊)一三一ページ
休息 《現代詩手帖》 一九八七年九月一日(第三○巻第九号)一四~一五ページ
白狐 《現代詩手帖》 一九八四年六月一日(第二七巻第六号)三○~三二ページ
スワンベルグの歌〔底本〕 《ユリイカ》 一九七三年九月一日(第五巻第一○号)一六八~一六九ページ
スワンベルグの歌 《婦人公論》 一九六九年二月一日(第五四巻第二号通巻第六三三号)二二○~二二一ページ
波よ永遠に止れ〔底本〕 《吉岡実詩集》 一九六七年一○月一日(思潮社刊)三一四~三三五ページ
波よ永遠に止れ 《ユリイカ》 一九六○年六月一日(第五巻第六号通巻第四五号)四八~五三ページ
哀歌 《鰐》 一九六○年一一月一○日(第六号)八~九ページ
夜曲 《近代詩猟》 一九五九年一○月一○日(第二七冊)六ページ
遅い恋 《現代詩手帖》 一九五九年六月一日(創刊号)六六~六七ページ
陰謀 《現代詩》 一九五六年七月一日(第三巻第六号)四八~四九ページ
敗北 《新思潮》 一九四七年九月三○日(第二号)二四ページ
即興詩 《新思潮》 一九四七年九月三○日(第二号)一一五ページ
今日までに私の知りえた吉岡実の〈未刊行詩篇〉のすべてである。なお〈遅い恋〉の本文は小田久郎氏のお手を煩わせた。記して感謝する。(一九九〇年七月七日)
奇怪にして典雅、ワイセツにして高貴、コッケイにして厳粛なる――吉岡実(文献番号〔以下#と略記。末尾〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉参照〕#A_25、一三~一四ページ)
吉岡実の詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)は、一九六七年、高井富子舞踏公演〈形而情学〉のチラシに発表された(公演当日以前に配布された可能性もあるが、公演日の七月三日の刊行としておく)。詩集《神秘的な時代の詩》(湯川書房、一九七四)にまとめられた諸作のなかで最も早く発表された詩篇である。初出形には刊本に見える「土方巽の秘儀によせて」という詞書がなく、末尾の「一九六七・五・一五」(おそらく吉岡実が記した脱稿の年月日)のあとにチラシ制作者によると思しい「この作品は吉岡実氏が土方巽におくったものです」という付記がある。この〈形而情学〉はガルメラ商会謹製高井富子舞踏公演で、演出は土方巽。出演は土方のほか、高井富子、大野一雄、石井満隆、笠井叡などで、美術は中西夏之、清水晃、谷川晃一。当日の公演を観た澁澤龍彦が《詩と批評》(一九六七年九月号)に〈踊る『形而情学』〉を寄せているので、引用する。
「今年の室生犀星賞の受賞作品となった、はなはだ高踏的なる加藤郁乎の詩集『形而情学』一巻を、日本のアンダーグラウンドの先覚者、知る人ぞ知る暗黒舞踊派のリーダー土方巽がバレエ化して演出し、新進女流舞踊家高井富子のリサイタルという形で、暗黒舞踊派の若いメンバー総出演のもとに、これを新宿は紀伊國屋ホールの舞台にのっけたというわけである。〔……〕開幕劈頭、何の音楽だか知らないが、ダンモ風の華麗な荘重な音楽とともに、ロオマ皇帝のそれのような輿にのって、四人の若者たちに担がれながら、客席のあいだを分けて、しずしずと舞台へ入場してきた土方巽は、伝え聞くところによると、十日間の絶食によって贅肉を落したというだけに、奇蹟の若返りぶりを示して、ニジンスキーもかくやとばかり、あくまで美々しく、その肉体を鞭のようにしなやかに、かつ色っぽく屈伸させたのであった」(#B_066、三八四~三八五ページ)。
同公演を観た吉岡の〈日記抄――一九六七〉の七月三日には「〔……〕ネロ・ヒジカタの奇怪にして典雅、ワイセツにして高貴、コッケイにして厳粛なる暗黒の祝祭」(#A_25、一三~一四ページ)とある。吉岡が土方巽を評したこの言葉は、吉岡自身の詩世界の形容として人口に膾炙していくことになるが、澁澤の評にしろ吉岡の日記にしろ公演後の執筆であり、それ以前に書かれた〈青い柱はどこにあるか?〉への影響を云云できるものではない。吉岡は〈形而情学〉原作の加藤郁乎詩集《形而情学》(昭森社、一九六六)をいつ読んだのだろうか。――冠称の「詩集」は原本にあるものだが、《形而情学》は一〇句集全二七三八句を収録した《加藤郁乎俳句集成》(沖積舎、2000)には《球體感覺》、《えくとぷらすま》に続く第三句集として収められている。なお本稿では初刊の表示に従って「詩集」と呼称する。――吉岡の《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》(筑摩書房、一九八三)の初めに次のようにある。「昭和四十二年二月九日の夕、築地の灘万で加藤郁乎の《形而情学》の室生犀星賞受賞を祝う会があった」(#A_24、八ページ)。当夜は吉岡が初めて土方巽と出会った運命的な日でもあるわけだが、この記述から吉岡が舞踏
公演〈形而情学〉の数箇月前に詩集《形而情学》を読んでいたことがわかる(土方巽から詩篇の執筆を依頼されてから、読みかえしたかもしれない)。吉岡は《土方巽頌》の巻頭に〈青い柱はどこにあるか?〉全篇を据えてから、こう続けている。
「この一篇は土方巽の求めに応えて書いたものである。まだ「暗黒舞踏」に二、三回触れたばかりで、十全にその「身体行為」を捉えていないが、その最初の詩篇ということで、想い出深いものがある。さて詩篇がどのように使われるのか、皆目わからなかった。或る日、奇妙なポスターが送られて来た。舞踏公演「形而情学」のもので、中央に朱塗りのタバコとビー玉が入った函が付いている。そして別の紙袋の中には、加藤郁乎の詩と「青い柱はどこにあるか?」がインディアン・ペーパーに印刷されていた」(#A_24、六~七ページ)。

舞踏公演〈形而情学〉ポスター(デザイン:篠原佳尾)〔封筒に加藤郁乎の文と吉岡実の詩が収められている〕
出典:川崎市岡本太郎美術館・慶應義塾大学アート・センター編《土方巽の舞踏――肉体のシュルレアリスム 身体のオントロジー》(慶應義塾大学出版会、2004)
土方巽は原作者の加藤郁乎(同公演チラシにはS・K・イクヤーノフ(加藤郁乎訳)〈燐寸譚〉を寄せているが、加藤郁乎評論集《遊牧空間》(三一書房、一九七〇)収録に際して「――高井富子の舞踏公演に寄せて」と書きくわえられた)と同等に、出会って半年になるやならずの吉岡実を遇したわけである。私は舞踏公演〈形而情学〉のポスター(デザイン:篠原佳尾)は観ていないが、高井さんに問いあわせたところ、加藤郁乎の高井富子宛速達封筒を複製した「別の紙袋」に入った吉岡と加藤の詩篇をお送りいただく栄に浴した者である。さて「詩集」と銘打ってはいるが、一行ごとに独立した全九九作=句から成る《形而情学》から五句、引用してみる(#B_026、九~一〇六ページ)。
理會は玉々でなくもがなの後門をすぼめる(〈ぽえしす〉)
別れ組紐の一理が三里の圓を切る(〈走句〉)
意識に流れなぞない舌人形のUたーん(〈遊戲律〉)
木がいく野でだ一句のむらさきをまはす(〈ラグタイム〉)
無我らない若干名の海綿としていかける(同前)
これらの作に〈青い柱はどこにあるか?〉のスルスを求めることは、必ずしも不可能ではない。もっとも吉岡は、土方巽と出会った《形而情学》受賞祝賀会の二箇月後の四月二日、アルトー館公演〈ゲスラー・テル群論〉で初めて土方の舞踏に触れているから、吉岡詩の出典を加藤詩=句に限定するのは正確でない。土方巽が加藤郁乎の詩に観たものを吉岡は土方巽の舞踏に観た、といったほうが近いかもしれない。そのあたりの具体的な証言は残されておらず、ここでは吉岡の詩篇執筆の前後関係が把握できれば充分である。〈青い柱はどこにあるか?〉は一九七四年の初刊以前、六七年一〇月の《現代詩手帖》吉岡実特集号に新作〈立体〉(⑦・3)とともに掲載(このとき「土方巽の秘儀によせて」という詞書が付けられた)のあと、翌六八年九月刊行の《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(思潮社)に〈未刊詩篇から〉として、後の詩集《神秘的な時代の詩》を構成する詩篇とともに収録された。さらに、六八年刊行の詩画集にも再録されている。この《土方巽舞踏展 あんま》(アスベスト館、1968年12月1日)は、土方巽公演〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉の一箇月半後の一一月に制作された限定五〇部のオリジナル豪華詩画集(出品・飯島耕一、池田満寿夫、加藤郁乎、加納光於、澁澤龍彦、瀧口修造、田中一光、中西夏之、中村宏、野中ユリ、三木富雄、三好豊一郎、そして吉岡実の13人)。土方巽へのオマージュたるこの記念碑的出版に新作詩篇ではなく〈青い柱はどこにあるか?〉を寄せているところからも、本篇に対する吉岡の愛着を量ることができよう。仕様は、版画に用いられるBFKリーブという用紙(383×562mm)に特色黄色とスミ文字(10ポ活字)の二色刷り。再録詩篇は初刊と異同なし(ただし、本文の「暁」「娩」に旧字を使用。13人の作者の署名を記した〈目録〉の葉では「靑い柱はどこにあるか?〔……〕吉岡實」と旧字が印刷されているが、これは吉岡の用法ではない)。
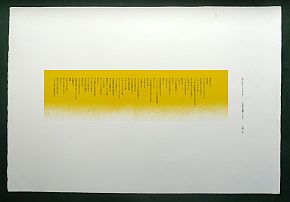

土方巽公演〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉を記念して出版された詩画集《土方巽舞踏展 あんま》(アスベスト館、1968年12月1日、限定50部)に再録された詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉の葉(左)と同書〈目録〉葉の13人の作者による自筆署名(右)
刊本の〈青い柱はどこにあるか?〉の本文にライナーを付して掲げる。なお初出と初刊(湯川書房版、一九七四)・三刊(書肆山田版、一九七六)の間で、本文に異同はない。
青い柱はどこにあるか?|吉岡実土方巽の秘儀によせて
01 闇夜が好き
02 母が好き
03 つとに死んだカンガルーの
04 吊り袋のなかをのぞけ
05 テル・テルの子供
06 ニッポンの死装束が白ならばなおさら
07 青い柱を負って歩き給え
08 円の四分の一の
09 スイカのある世界まで
10 駈け足で
11 ときには
12 バラ色の海綿体へ
13 沈みつつ
14 犬の四つ足で踊ること
15 かがまること
16 凍ること
17 天井の便器のはるか下で
18 ハンス・ベルメールの人形を抱き
19 骨になること
20 それが闇夜が好きなぼくたちの
21 暁の半分死
22 ある海を行き
23 ある陸を行き
24 ラッパのなかの井桁を吹き
25 むらさき野を行き
26 ふたたび闇夜を行く
27 美しき猫の分娩
28 そのしている夢
29 そのうえしてない行為
30 ぼくたちはどうしている?
31 すべてに同化する
32 末梢循環の恥毛性存在!
33 消えなん横雲の空
34 鋼鉄のビル・ビルの春
35 ビー玉の都市
36 そこにサクラは散るや
37 散らずや
38 赤い映像とは肉体の終り
39 ガニ股の父が好き
40 心中した姉が好き
41 古典的な死の隈取
42 闇夜が好き
43 かがり火が見えるから
44 大群衆が踊り狂っているんだ
45 亜硫酸ガス
46 濃霧
47 予定のない予定?
48 黄いろの矢印に沿って
49 柱に沿って
50 形而上的な肛門を見せ
51 ひとりの男が跳ねあがる
冒頭の詩句「闇夜が好き」は、二〇行めには「それが闇夜が好きなぼくたちの」という形で、四二行めには冒頭とまったく同じ形で登場し、本篇のライトモチーフとして機能している。吉岡はリフレインを多用する詩人ではないが、それはリフレインが不得意だったことを意味しない。あの〈僧侶〉(④・8)各節の第一行「四人の僧侶」の印象があまりに強烈だっただけに、その後は使用を控えたとみるべきだろう。いったい吉岡は、絶大な成功を収めた手法や詩語ほど以降は自ら使用を禁じる癖がある。この詩篇に〈僧侶〉のような節の区分はなく、「闇夜が好き」は〈桃――或はヴィクトリー〉(⑥・8)の奇妙な掛け声「わ ヴィクトリー」に近いものがある。それと同時に標題の「青い柱はどこにあるか?」という問いに対しては、青い柱が闇夜のなかにあることをうかがわせる。この「闇夜」の内実だが、吉岡にとって土方を象徴するもののようであり、後年の土方巽追悼詩〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)の〈Ⅴ(衰弱体の採集)〉の末尾では「噫乎〔ああ〕/闇夜なす/闇夜なす/闇……」と哀しみの声をそこに溶暗させることになる。《光より速きわれら》(新潮社、一九七六)の作者・石原慎太郎はその〈土方巽の怪奇な輝き〉の結語で「土方の舞踏の怪奇な輝きは、氾濫している安手な踊りの中で、黒い本物の宝石の、黒ゆえに鮮烈な光に他ならない」(#B_032、二四ページ)と書いており、土方舞踏と闇を関連づけている。
後続の詩句で「テル・テルの子供」「ガニ股の父」「心中した姉」が登場するが、ここは単に「母」である。なんの限定もないだけに、次行の「つとに死んだカンガルーの」「母」と解してみたくなる。「○○が好き」という軽い調子は吉岡詩には珍しく、この列挙法が読者をどこへ連れて行くのか期待が高まる。ときに、吉岡実には〈好きなもの数かず〉と題する一九六八年七月三一日に発表した未刊の散文がある。全文を引く。
「ラッキョウ、ブリジット・バルドー、湯とうふ、映画、黄色、せんべい、土方巽の舞踏、たらこ、書物、のり、唐十郎のテント芝居、詩仙洞、広隆寺のみろく、煙草、渋谷宮益坂はトップのコーヒー。ハンス・ベルメールの人形、西洋アンズ、多恵子、かずこたちの詩。銀座風月堂の椅子に腰かけて外を見ているとき。墨跡をみるのがたのしい。耕衣の書。京都から飛んでくる雲龍、墨染の里のあたりの夕まぐれ。イノダのカフェオーレや三條大橋の上からみる東山三十六峰銀なかし。シャクナゲ、たんぽぽ、ケン玉をしている夜。巣鴨のとげぬき地蔵の境内、せんこうの香。ちちははの墓・享保八年の消えかかった文字。ぱちんこの鉄の玉の感触。桐の花、妙義の山、鯉のあらい、二十才の春、桃の葉の泛いている湯。××澄子、スミレ、お金、新しい絵画・彫刻、わが家の猫たち、ほおずき市、おとりさまの熊手、みそおでん、お好み焼。神保町揚子江の上海焼きそば。本の街、ふぐ料理、ある人の指。つもる雪」(#C_052、〈私の好きなもの〉)。
吉岡の好きなもの尽くしを連想的に定着した興味深い文章だが、ここでは「黄色」「土方巽の舞踏」「唐十郎のテント芝居」「ハンス・ベルメールの人形」「多恵子、かずこたちの詩」「ぱちんこの鉄の玉の感触」「わが家の猫たち」あたりが本篇との関連で注目される。
有袋類のカンガルーは育児嚢で子を育てる。そこには「死児」でも入っているのだろうか。なにか目をそむけたくなるようなおぞましいものが潜んでいておかしくない詩句である。その強暴な牽引力は、冒頭数行にして早くも読者を作品世界に引きずりこむ。
「テル・テルの子供」とはなにか。まず「照る照る坊主」がくるが、吉岡が初めて観た土方が登場する舞台〈ゲスラー・テル群論〉のテルが関連するとも考えられる(舞台資料に乏しく、確認できなかった)。一方、語感からはカンガルーの子供の赤剥けの地肌さえ連想される。照る照る坊主は紙で作る場合と布で作る場合があり、後者はそのまま次の六行めへと連なる。
「死装束」は経帷子とも呼ばれ、帯を立結びにし左前にして着せた白木綿の着物。それを「ニッポンの」と形容するところに皮肉がこめられている。七行め「青い柱を負って歩き給え」から本篇の標題が生まれたか。一九六〇年の初リサイタルから土方巽の舞台を観つづけてきた種村季弘は次のように書いている。「〔……〕田中岑は、六〇年代の前衛よりはやや年長の世代に属するが、青をバックにゴッホ風の椅子を描く画家として私などの記憶にある。そういえば昭和三十五年初リサイタルの「種子」の箱も、もしかすると田中岑の椅子を箱に見立てたのかもしれない。/いずれにせよ青のバックは、その後もビートルズの「ガール」をソロで踊るとき(『ゲスラー・テル群論』)にも使われている。初期の土方巽舞踏は青のバックにバラ色の、白痴的なまでにキッチュな色彩感覚で私などには記憶されており、その頂点の一つがガルメラ商会謹製『バラ色ダンス――A LA MAISON DE M. CIVECAWA』や『性愛恩懲学指南図絵――トマト』ということになろうか」(#B_086、一四七ページ)。土方の舞台を記録した写真のほとんどはモノクロで、舞台や装置の色彩について触れた文章は多くないだけに、貴重な証言である。
「円の四分の一の/スイカのある世界まで」は後に「肉色のスイカの四分の一の円」(〈スイカ・視覚的な夏〉⑩・13)と変奏される。吉岡は「駈け足で」の詩句さながらに疾駆して、ここまでで「白→青→(赤)」と色彩を変転させてきた。過去に「赤粘土層のゆるやかな丘への駈け足」(〈模写――或はクートの絵から〉⑥・4)とあるが、「赤」と「駈け足」の符合はたまたまであろう。
海綿体は陰茎内部のスポンジ状の組織。詩句は勃起した陰茎と同時に舞踊と男色の光景を暗示する。「犬のたれさがる陰茎」(〈静物〉③・4)。「クレタの或る王宮の壁に/「サフラン摘み」と/呼ばれる華麗な壁画があるそうだ/そこでは 少年が四つんばいになって/サフランを摘んでいる」(〈サフラン摘み〉⑧・1)。この屈辱と恍惚の姿勢。
「かがまること」は跳躍のための前姿勢である。「凍ること」は「こおること」と読むべきだが、一五行めの音に引っぱられて「こごること=凝ること」と読みたくなる。吉岡もそれを意図したかもしれない。「四人の僧侶/井戸のまわりにかがむ/洗濯物は山羊の陰嚢」(〈僧侶〉)。「寒冷な下痢する近代の醜悪なかがまる催眠状態をぬけ」(〈下痢〉⑤・3)。「身をかがめて/凍った(形象)を追求し/私は路上を巡りつづける」(〈聖あんま断腸詩篇〉)。腰や膝を屈曲した姿勢は、舞踊ならぬ舞踏を象徴するものだ。
後の詩篇〈聖少女〉(⑦・10)にも登場するハンス・ベルメールについては〈聖少女〉評釈で述べる。ベルメールの人形も大事だが、《神秘的な時代の詩》に収められた詩のうちでいちばん最後に書かれ、西脇順三郎に捧げられた〈弟子〉(⑦・15)の引用符で括られた
「便所はどうして神秘的に
高い処にあるのだ」
の二行が思われてならない。詩集《神秘的な時代の詩》は「天井の便器」の土方に始まり、「神秘的に高い処にある便所」の西脇に終わる遠大な献詩群でもあったのだ。
「搬び出される担架の上で 糊づけの肉と骨の摩擦がはじまる払暁だ」(〈回復〉④・12)。この「半分死」は吉岡の造語だろう。これが「半分生」でないところが、吉岡実の吉岡実たるゆえんだ。
主語は「闇夜が好きなぼくたち」か、それとも「暁の半分死」か。ふつうなら人間の行動だが、「ラッパのなかの井桁を吹き」となるとわからない。試みにインターネットで「ラッパ」と「井桁」が同時に登場する文章を検索しても、そんなものは出てこない。先の澁澤龍彦の〈形而情学〉評に「開幕劈頭、何の音楽だか知らないが、ダンモ風の華麗な荘重な音楽と共に……」とあったのを想起すれば、このころの土方巽の舞台にモダンジャズが流れていて少しもおかしくない(これは土方の歿後だが、私はいくつかの暗黒舞踏の伴奏音楽でアラン・パーソンズ・プロジェクトのインストゥルメンタルナンバーが流れたのを聴いている)。トランペットの上ずったようなフレーズを、記譜法の嬰記号の♯に見立てて言ったものか。難句である。
《万葉集》の額田王「あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る」が踏まえられているが、吉岡は入沢康夫との対談〈模糊とした世界へ〉でこう発言している。「あの〔入沢康夫〈わが出雲〉の〕志向する世界はぼくもわかるんですよ。土方さんへの詩で「青い柱はどこにあるか?」という作品があるんですが、相当日本的なものの要素が強いんですよ。ぼくも及ばずながら、相当日本的なもの、それはもともともっていたんだし、勉強してきた世界だし、万葉とか古今の世界とぼくたちの現在の世界との混合ができたら、そういう世界をつくりたいという感じなんですよ。少しずつそういう日本の古典をとりこんでいきたいと考えている」(#C_005、五六~五七ページ)。しかしながら、このとき後年の《薬玉》を予想しえた人物は(吉岡本人を含めて)だれもいなかったのではあるまいか。なりふりかまわぬ古語の混入など、新たな冒険を試みる吉岡実詩から、《僧侶》の磐石の地殻を破ってマグマが噴出したごとき印象を受けるのは、私だけではないだろう。
この三行こそ本篇の最初のピークである。「分娩」は「深夜の人里から押しよせる分娩の洪水」(〈僧侶〉)や「古代の未開地で/死児は見るだろう/未来の分娩図を/引き裂かれた母の稲妻/その夥しい血の闇から/次々に白髪の死児が生まれ出る」(〈死児〉④・19)で、惜しみ惜しみ使われてきた。それでも人間についてのものだった。ここでは猫について、である。その唐突さに加えて「そのしている夢/そのうえしてない行為」と、読む者の脳をねじるような詩句が追い討ちをかける。猫もしくは猫の分娩がしている夢? そのうえ猫もしくは猫の分娩がしてない行為? こういう変哲もない言葉が創りだす異様な世界こそ、このころの吉岡実の詩の真骨頂である。
こうした日常会話を詩句にしてしまうのも、この時期の吉岡実詩の特徴である。もっとも所かまわず日常会話を入れさえすればよいわけではなく、前後の対比や詩句の運びが肝心であることはいうまでもない。詩的頂上を一気に脱力させる呼吸は無類である。“What are we doing?”とはなんだろう。答を求めない合いの手でもあろうか。
「末梢循環」はふつうの百科事典には見えない専門用語で、「毛細血管・前毛細血管・後毛細血管細静脈(血球が出入りする)から成り、血液と組織の物質交換の場」だという。戦前に医書出版社に勤めたころの知見によるか。それにしても「末梢循環」の「恥毛性存在」とは。難句である。極細の血管とでも解しておく。三〇行めからは「ぼくたち=末梢循環の恥毛性存在=はどうしているかというと、すべてに同化する」とパラフレーズできよう。
《新古今和歌集》の皇太后宮大夫俊成女「下もえに思ひ消えなん煙だに跡なき雲のはてぞかなしき」や藤原家隆朝臣「霞立つすゑの松山ほのぼのと浪にはなるるよこ雲の空」を踏まえた詩句。吉岡実の自宅の書架には岩波書店の〈日本古典文学大系〉(一九五七~一九六七)がおそらく全巻揃っていたが、本篇執筆当時は筑摩書房に勤務していたから、通勤途中に文庫版で親しんでいたのかもしれない。ならば新訂《新古今和歌集〔岩波文庫〕》(一九五九)あたりか。
詩句とその作者を混同してこのようなことを考えるのも、吉岡が文庫本を読んでいたかもしれない車中から見える首都のビル群を連想するからである。しかし「ビー玉の都市」とはなんだろう。鮮やかな色彩のガラスの高層建築のことか。「ビー玉」だと頭韻は揃うものの、いっそのことパチンコ玉でもふさわしい気がする。
《新古今和歌集》の実方朝臣「天の河かよふうき木にこととはんもみぢのはしはちるやちらずや」を踏まえた詩句。冒頭で触れた「一九六七・五・一五」が脱稿の日付なら、ひと月ほど前の光景を描いたものか。実景ととらずに、映画のポスターを観るように読んでもいい。
それかあらぬか「赤い映像」が登場する。ここしばらく色への言及がなかったが(サクラは桜色を喚び起こすものの)、風景から人間へ視覚を転換するにあたって、オーガニックな赤い色面に身体の輪郭を見ているようだ。「赤い映像」と「肉体の終り」が等価であるためだろうか、私はこの行にさしかかるたびに「肉体の終りとは赤い映像」と言いちがえそうになる。
きわめて土方巽的な詩行であり、二人にして一人の姿を描いたものである。土方の〈犬の静脈に嫉妬することから〉の「私は、私の体のなかにひとりの姉を住まわせている。私が舞踊作品を作るべく熱中するとき、私の体のなかの闇黒〔やみ〕をむしって、彼女はそれを必要以上に食べてしまうのだ」(#B_123、七ページ)に見える発想が吉岡をインスパイアしたかもしれないが、同時に吉岡の「かねてから、私のガニ股体型に興味をもっている土方巽は、「ヨシオカを抱いて風呂に入り、尻の穴を洗う」と宣言しているので、恐れをなしていた」(#A_24、一五五ページ)という追想をこの詩句の傍らに置きたいと思う。
父と姉の顔が肉親のそれから舞台の上のそれへと変容する。紅隈や藍隈などの歌舞伎の隈取への言及にも思えるが――。
――こう続くと薪能のようでもある。かがり火は御神火にして照明。歌舞伎もしくは薪能もしくは暗黒舞踏の舞台そのものがくっきりと荘厳された瞬間である。
舞台のクライマックスのような群舞である。暗黒舞踏の舞台にとどまらず、観客や無関係の群集までもが、火の粉をかぶりつつ、くんずほぐれつして踊っている。「ブルーの髪をなびかせて/とびあがる/モッブのおさげの女生徒たちを押えて/球なす汗の陰蔽だ!」(〈夏の家〉⑦・13)。
「亜硫酸ガス」は硫黄が空気中で燃えるときに発生する気体。有毒で、大気汚染の原因となる。大群衆を毒ガスと濃い霧が覆いかくし、詩篇は一挙に終局へとなだれうってゆく。
土方巽が歿した翌一九八七年の八月、銀座セゾン劇場で上演された土方巽追悼公演〈病める舞姫〉のポスターに吉岡実はこの五行を選んでいる(#B_032、一二六ページには「ポスター デザイン:吉岡実」とあるが、ほんとうにデザインも吉岡なのだろうか)。「予定のない予定?」は土方の舞台を端的に表現した行。詩はここからカデンツに入る。次行、《神秘的な時代の詩》に顕著な「矢印」が早くも登場する(ただし「矢印」そのものは《静かな家》後期の〈内的な恋唄〉(⑥・12)、〈ヒラメ〉(⑥・13)、〈恋する絵〉(⑥・15)に既出)。この「黄いろの矢印」は鮮烈で、本篇とほぼ同時期の執筆と思われる〈わたしの作詩法?〉の「わたしはそれらの方向へ一つの矢印を走らせてその詩的作品の最後を飾るだろう」(#A_25、八八ページ)という表明を具体的な作品において実践した詩句である。「柱に沿って」の色は限定されていないが、文脈から「青い」を補ってかまわないだろう。「黄い→(青い)→〔肛門の〕(暗紅色)」という色彩の乱舞が冒頭の「白→青→(赤)」を反復し、変奏する。「形而上的な」は加藤の詩集《形而情学》と土方の舞踏〈形而情学〉への挨拶。「ひとりの男」は一五行め「かがまること」以来の長い雌伏の時を経て、最終行で「跳ねあがる」。柱はかつて「大人の女の汗の夏を知らぬ/少女もいつかは駈けこむだろう/ぼくの箱の家/正面の法律事務所の畸型の入口の柱を抱くだろう」(〈感傷〉④・18)と期待されたが、その傍らに舞漢が立つことで、天井と地上を転倒させる新たな通路と化したようだ。
吉岡実は〈三つの想い出の詩〉で「この詩には、「土方巽の秘儀によせて」との詞書がある。飯島耕一の紹介で、土方巽を知り、初めて暗黒舞踏の「ゲスラー・テル群〔論〕」を、草月会館で観て、衝撃を受けた。また、高橋睦郎に誘われて、深夜の新宿の小さな喫茶店で、唐十郎のアングラ芝居「ジョン・シルバー」を観て、いたく感動したのも、この頃のことだった。以来、私は親しい芸術家たちの肖像を、数多く詩で描くようになった。それだけに、最初のこの詩は思い出深いものがある」(#A_23、二一〇ページ)と書いている。この詩以降、〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)、〈父・あるいは夏〉(⑨・12)、〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)と時を経るに連れて、吉岡がその詩篇に引用する土方巽のことばは増大してきたが、それを「パフォーマンスから言語活動へと比重を移していった土方巽の軌跡とぴったりと重なりあっている」と言っているだけでよいはずもない。思うに吉岡は、当初から土方の舞踏と同等、ことによったらそれ以上に土方の発した言語に震撼したのではあるまいか。確かに心象的自伝《病める舞姫》(白水社、一九八三)を初めとする土方巽の著書に依る詩句は枚挙に暇がない。しかし私が強調したいのは、あたりを暗くするのではないかとさえ思われる土方の「秘儀」としての発話である。土方巽著・吉増剛造筆録《慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる》(書肆山田、一九九二)にはこれと別に一九七六年八月、アスベスト館で大内田圭弥監督の映画《風の景色》撮影時に〈舞踏譜〉として土方巽が語ったことばの録音盤としてLPとCDがあるが(前者は香奠返しのレコードで、タイトルは吉岡の命名)、マイクロフォンを前にしてこのパフォーマンスなのであって、対座したときの土方巽のことばの力はその比ではなかったに違いない。私は土方巽のインタビュー取材に同席したことがある。そのときのことが夢幻のように思われる。土方さんを生身で見た最初にして最後の部屋は東京・目黒にあったアスベスト館の急な階段を昇った二階にあり、簡素な旅館のような造りだった。あたりに飾りらしいものはなにもなく、すっかり変色した三島由紀夫の四枚ほどの自筆原稿(〈前衛舞踊と物との関係〉だっただろうか)が額装されて掛かっていた。取材の一行はインタビュアーの浅野・岡本両氏 (SHY's)、カメラマンの梶洋哉氏、編集者の中原蒼二さん、そしてオブザーバーの私である。一九八五年六月二二日当日のやりとりは、UPU発行の雑誌《W-NOtation》第二号(一九八五年七月)に〈極端な豪奢(エクストラ・ヴァガンス)〉として掲載されている(吉岡は〈聖あんま断腸詩篇〉の〈物質の悲鳴〉などをここから採っている)。このインタビュー記事は《土方巽全集〔全二巻〕》(河出書房新社、一九九八)にも収録されていないから、見出しだけ録すると「パフォーマンス――機能への問いかけと「私」の意図/歩行を廃絶する/危機の要請としての舞踏/日本人・鍵のかからない肉体/言葉に対してめくらであること/分子活動が恋愛する/無救済的な、刹那に於いて即救済的である/未生の闇としての終身刑/物質の悲鳴を聞く/永遠に充たされぬ純粋飢餓」(#C_020、二~二七ページ)である。しかし、事前に一〇の質問を用意させた土方巽はほんとうは私にこう語ったのだ。
はみ出すこと/五七歳/ある種の光=闇/夢をむしって捨てること/視覚のあるない、ではない/溶暗 fade out/「流行」には喝采をおくっている/パフォーマンス/無意識のなかに恋愛は入っているか/歩くことの排除/足がない たんぽぽ 水母/ウサギの毛/浮游する/押し出されて歩くのである/絶えず危機を要請してきた/神/浴衣が階段を降りる(裸体ではなく)/バロンというウサギ/失われてなくなったものの総和が「記憶」/鍵の掛からない日本・日本人/石綿・絶縁体=アスベスト/バラバラではなく本来ひとつ/「永田耕衣」/皮膚を一枚めくってみること/男と女/写実主義/技術の場所のみを問いかけるな/何度も洗いなおせ/食べさせられるほうが主役/東北とは秋田の一地方ではない/飛躍を捏造する土地/人身売買 兵隊 馬 金鉱/見えざるものと格闘する肉体/脳内の物質/皿の上のメザシ 一〔千〕本の電線/季節からはぐれてしまう/足の裏から減ってゆき最後に/泥だけ残った/破片は破片のままに/土方巽を待望している/私はまだ生まれていない/という思いの肥大化/灰柱の方法/「死刑囚」から「終身刑」へ/真空の腰/そよぐ/はぐれる ぶれる足 なびく/舞踏家の足はどこに?/雅楽/「そうでしか言えない状態」/部屋がひとつの原稿用紙に/「Apparition」押し出されてくるもの/わからないから喋れる/(たろうというウサギ)/(よしおというイヌ)/存在は傷口/宗教や説法の世界ではなく/現存!/光もよれよれになってほしい/「衰弱体」/この異常な明るさは闇である/「稲垣足穂」/男は空っぽ カリントウのオバケ/脳の学問が/芸術の領域の仕事に/舞台の半ば粗雑に扱われている/着体の行為 面に顔を
「青い柱」がなにか、まだ特定していない。吉岡はさきほどの文章の締めくくりで「土方巽が自己の舞踏を、「命がけで突立った死体」と規定しているのは、禍禍しく美しい。しかし、私は、「形而上的な肛門を見せ/ひとりの男が跳ねあがる」と、捉えているのだ」(#A_23、二一〇ページ)と書いている。「青い柱」は土方巽の肉体の形容というよりその精神の似姿であろうか。迂遠なようだが、ここで〈青い柱〉という作品の画家ジャックスン・ポロックに関する記述を見よう。手許の美術事典にはこうある。「アメリカの画家で、抽象表現主義(アクション・ペインティング)の代表的な作家」、一九四八年ころから「床に大きなカンヴァスをひろげ身体ごと“絵のなかに”入って、流動性の絵具を注ぎしたたらせながら描く、いわゆる“ドリップ・ペインティング”あるいは“ポード・ペインティング”の手法を編み出した。激しい線跡が“画面一杯(オール・オーヴァー)”に絡み合う壮大な空間には、イメージの発生状態が直接に行為で捉えられている。〔……〕代表作は〔……〕『ブルー・ポールズ』(1953、ニューヨーク、個人蔵)など」(#B_169、一三七九ページ)。これが〈青い柱〉である。

ジャックスン・ポロック〈ブルー・ポールズ:ナンバー11、1952〉
出典:《ポロック〔現代美術 第6巻〕》(講談社、1994)
吉岡は本篇以外で〈青い柱〉にもジャックスン・ポロックにも言及していないが、大岡信が解説を書き、飯島耕一がポロック研究を翻訳している画集《ポロック〔現代美術17〕》(みすず書房、一九六三)掲載の原色版(部分)や単色版(全図)で〈ブルー・ポールズ(青い柱)〉に触れたのかもしれない。いずれにしても吉岡は土方巽の暗黒舞踏と同時にポロックの大画面を踏まえて本篇を執筆し、そこから題名を付けたと考えていい。ではなぜポロックなのか。その手法を高橋康也の〈吉岡実がアリス狩りに出発するとき〉に見える吉岡発言に〔 〕に入れて充填してみると、次のようになる。
「すでに『静かな家』あたりでいったん形式感覚が壊れているんじゃないかとおっしゃるのは、そのとおりなんで、『全詩集』のとき、自分で校正していて〔古典的デッサンに裏打ちされた〕『僧侶』の世界っていうのが耐えがたいのね。しんどくて、見直すのもいやになっちゃう。〔ポロックみたいに、流動性の絵具を注ぎしたたらせながら描くような〕もっとフワーッとした方へ行きたいな、と思ったのが『静かな家』なんですね。まあ、そのあと少し〔というのは量的にではなく、方法的にという意味ですが〕書いてから、二年あまりやめちゃうんですが。詩なんて〔イメージの発生状態が直接に行為で捉えられていさえすればいいというわけではないから〕、だらだら書くものじゃないって」(#B_081、三五九ページ)。
吉岡の絵画の好みは《私のうしろを犬が歩いていた――追悼・吉岡実〔るしおる別冊〕》(書肆山田、一九九六)の口絵〈吉岡実の小さな部屋〉からも明らかなように、抽象表現主義(アクション・ペインティング)からはほど遠かった(ちなにみ口絵に掲載されたのはポール・デイヴィス〈猫とリンゴ〉、アヴァティ〈かたつむりの散歩〉、ヘルマン・セリエント〈異邦〉、河原温〈浴室〉、片山健〈とんぼと少女〉、佐熊桂一郎〈婦人像〉、斎藤真一〈しげ子 母の片身〉、三好豊一郎(題なし)、永田耕衣〈白桃図〉、西脇順三郎(題なし)、小沢純〈グロヴナー公の兎〉、ゾンネンシュターン(題なし)である)。しかし〈青い柱〉の方法を援用してまでそこから脱却しなければならなかった《僧侶》の世界を考えれば、《静かな家》(思潮社、一九六七)とその深化発展形である《神秘的な時代の詩》の位置が明らかになってこよう。吉岡は、個人の神話から時代の神秘へとそのテーマをシフトさせる一方、詩語の多用からその節制へと詩法を変貌させてきた。それは吉岡の感性(むしろその詩の肉体、と言い換えたい)がそれまでの成果の重圧に堪えられなくなってのことではないか。おそらく《僧侶》の強力な引力圏を逃れることが先決で、そのためにはジャックスン・ポロックと手を結ぶことなど、新しい詩の領土を模索する吉岡にとってはなにほどのものでもなかった。時代は大きく下り、吉岡歿後になる一九九一年以降、彫刻家の吉江庄蔵はときには土方門下の和栗由紀夫の舞踏とのコラボレーションによる公演〈青い柱〉の舞台上で、皮膜彫刻を制作している(皮膜彫刻は「虚ろなトルソ」であり、熱して可塑性を持たせたプラスチックで人体を型どったもの)。私はこの舞台も彫刻も観ていないが、吉岡実詩を意識した作品なのだろう。吉江の皮膜彫刻を観ることができたなら、先の入沢康夫との対談で「ぼくが子供の頃、漠然と夢見たのは彫刻家ですね。いろんな事情で彫刻家が駄目になり、絵かきも駄目で、それで詩を書いてしまった」(#C_005、五六ページ)と語っていた吉岡はどう思っただろうか。加藤―土方―吉岡―吉江・和栗という詩文と舞踏・造型の奔流を。

吉江庄蔵の皮膜彫刻〈青い柱〉 H1700×W480×D300mm(写真:永瀬龍夫)
出典:http://www.cablenet.ne.jp/~itokoh/ao.html
詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉と同じ一九六七年、吉岡は重要な文章を発表している。詩論〈わたしの作詩法?〉である。初出は一一月二〇日発行の《詩の本Ⅱ――詩の技法》(筑摩書房)。この日付にわれわれは留意すべきである。思潮社から全詩集的な《吉岡実詩集》が出たのが前月の一〇月一日、次に引くあとがき〈詩集・ノオト〉が書かれたのも詩論執筆の前後だろう。「校正すべく、自己の詩を読みながら、たえず停滞感を味わつた。わたしは今、反省とある種の意図を試みようとしている」(#A_08、三六四ページ)。詩論の発表と全詩集の刊行というふたつを自らの詩業の中仕切りとすることによって、詩作における新展開を図っていることが読みとれる。このとき、吉岡実にとって未開拓な分野であった《静かな家》後期(〈内的な恋唄〉や〈ヒラメ〉や〈恋する絵〉)の語法の自動的な運用が注目された、と私は考える。加えて献詩の性格が《神秘的な時代の詩》をそれ以前の詩集から分かっている。それにしても〈青い柱はどこにあるか?〉に予告されている書法がその骨格になっている《神秘的な時代の詩》は、吉岡実にとって単にそこをくぐりぬけなければならない隘路にすぎなかったのだろうか。いまやわれわれは《神秘的な時代の詩》の全詩篇を検証して、その回答を見出さなければならない地点に立っている。
上の評釈の執筆中にどうしてもみつけることのできなかった〈青い柱はどこにあるか?〉の仏訳が出てきたので、全文を注とともに掲載する。出典は二〇〇二年六月にパリのEditions Belinから発行された《PO&SIE numero 100――Poesie Japonaise》(二二~二三ページ)である(同誌の詳細に関しては《吉岡実書誌》を参照されたい)。《吉岡実の詩の世界》のトップページにも書いたが、仏文の引用に際してシフトJISのテキストとしてアクサンが的確に表示できないことを遺憾とする。
OU EST LE PILIER BLEU ?En hommage aux rites esoteriques d'Hijikata Tatsumi
on aime la nuit noire
on aime la mere
regarde dans la poche suspendue
d'un kangourou des longtemps mort
enfant de Tell-Tell*
d'autant que les linceuls nippons sont blancs
marche un pilier bleu sur le dos
jusqu'au monde a pasteque
en quart de cercle
au pas de course
parfois
plongeant
dans un corps spongieux rose
danser a quatre pattes de chien
s'accroupir
geler
tout en dessous d'une chaise percee au plafond
une poupee de Hans Bellmer dans les bras
devenir os
c'est ca notre demi-mort a l'aube
nous qui aimons la nuit noire
allant par une certaine mer
allant par une certaine terre
soufflant une grille de puits dans une trompette
allant dans un champ violet
allant de nouveau dans la nuit noire
accouchement d'une belle chatte
son reve ou le faire
son acte qu'elle ne fait pas
comment faisons-nous ?
s'assimilant a toute chose
existence en poils pubiens d'une circulation capillaire !
ciel aux nuages etires se dissipant
printemps de Buil-Buildings en acier
ville de billes
des fleurs de cerisier y tombent-elles
ou non
l'image rouge est la fin de la chair
on aime le pere aux jambes arquees
on aime la soeur ainee suicidee avec son amant
grimage classique de la mort
on aime la nuit noire
des lors qu'on voit des fanaux
une grande foule danse a la folie
gaz sulfureux
brouillard epais
projet sans projet ?
au long d'une fleche jaune
au long d'un pilier
montrant un anus metaphysique
un homme bondit(trad. Isabelle Tonomura, Teramoto Naruhiko, Ono Masatsugu, Claude Mouchard)
――――――――――
*Nom propre plus ou moins ambigu, ≪ Tell-Tell ≫ semble faire allusion au titre de la ≪ danse du corps obscur ≫ d'Hijikata Tatsumi: La Theorie de groupe Gessler-Tell. Representee en 1967, cette piece est la premiere des danses d'Hijikata que le poete ait vue.
(Ecrit en 1967 a l'occasion de la representation de la ≪ danse du corps obscur ≫ d'Hijikata, La Meta(patho)physique, ce poeme est recueilli dans Les Poemes de l'epoque mysterieuse, Ed. Yukawa-shobo, Tokyo, 1975)
注に詩集《神秘的な時代の詩》が「湯川書房、東京、一九七五年刊」とあるのは、正しくは「湯川書房、大阪、一九七四年刊」である。「テル・テルの子供」の評釈は私にとっても難儀だったが、詩句に関する注のコメントはまず穏当なところだろう。訳者四氏の労を多とし、その訳業に深く感謝する。
私の場合、エロチシズムは何よりも想像力なのです。非常に集中した状態から、内にたまっていたものを一気に吐き出して制作する過程で、絵の場合は線が線を呼び、文章の場合は言葉が言葉を呼んで、それがどんどん一人で歩いて発展していくのです。――池田満寿夫(#B_013、二六ページ)
今回は詩篇〈夏から秋まで〉(⑦・2)を中心に、版画家にして小説家・池田満寿夫と詩人・吉岡実の作品を考察する。前回の〈「暗黒の祝祭」〉に引きつづいて、土方巽のことから始めたい。〈表① 散文にみる吉岡実・土方巽・池田満寿夫・澁澤龍彦の関連〉に掲げた文章からもわかるように、一九八六年一月と翌年八月にあいついで亡くなった土方巽と澁澤龍彦は、六○年代から池田や吉岡らと親密なサークルを形成していた。澁澤以外の三人をみると、永年出版社に勤務しながら詩を書いた吉岡実は会社員であり、生前に《犬の静脈に嫉妬することから》(湯川書房、1976)と《病める舞姫》(白水社、1983)の二冊の単行本を上梓はしたが土方巽は舞踏家であり、小説家として一家をなしたとはいえ池田満寿夫は版画がそのキャリアの中心であるという、文筆を主たる生業としない三人を含んで互いに文を寄せあっている様は、壮観と言わずになんと言おう。吉岡実には生前の土方巽への、池田満寿夫と澁澤龍彦には歿後の土方巽へのコメント・短文があるので見ていく。まず、吉岡実の談話から。
戦後日本の一大天才|吉岡実二○年ほど前に、加藤郁乎さんの出版記念会だったかなあ、灘万って店の座敷で偶然向かいの席に座ったのが土方さんとの出会いだったね。それから彼の舞台は殆んど見ているし、土方さんのことを幾つかの詩にも書いた。うん、土方語録から言葉を貰ってね。詩の読み手としてもこわい人ですよ。彼自身の書いている言葉も、詩でもないし物語でもない、まったく独得のものでしょう。舞踏という、それまでなかったものをつくった土方さんは、戦後の日本にあらわれたひとりの天才だよね。(#C_020、七一~七二ページ)
次の池田満寿夫のコメントは、テレビで放映された談話から起こしたもの。
〔土方巽の踊り〕|池田満寿夫初めて土方巽の踊りを観たときに、やはりこいつは天才だとぼくは思ったね。なんか殺気っていうんですかね、男性的なエロティシズム、官能的なものと、それからいま言った殺気ですね、彼の踊りは非常に生理的ななにかを与えるんです。ですから、土方の踊りの嫌いなやつはもう生理的な反発を持つと思う。で、好きになるともうとことんまで惚れこむような、そういうタイプの踊りでしたね。(NHK教育テレビ《土方巽と舞踏〔芸術劇場〕》、1986年9月28日放映)
そして最後は澁澤龍彦の文。
献詞|澁澤龍彦危機に立つ肉体。このことばはずいぶん何度も土方巽の口から聞かされた。いわば暗黒舞踏の出発点でもあり、また到達点でもあったのではないか。なぜなら土方巽は、これも彼自身の好んだことばであるパフォーマー(体験者)として、57年にわたる生涯の最後まで、肉体のぎりぎりの可能性を追求することをやめなかったからだ。舞踏家であるとひとしく彼は思索者でもあり、詩人でもあったと私はつくづく思う。(#B_002、四ページ)
同じく澁澤の、おそらくは弔辞の一節。「私たちのまわりには、もう土方巽のような破天荒な人間を見つけ出すことはできないでしょう。戦後の疾風怒涛時代が生んだ、彼もまた一個の天才でした」(#A_24、二四〇ページ)。――その六○年代の薄明のパースペクティヴのなかに、或る人物のくろぐろとした影が立っているのを私は認める。そう、土方巽の影である。おそらく私の六○年代は、土方巽を抜きにしては語れないであろう――と澁澤龍彦は土方の《病める舞姫》に寄せた。吉岡にしても池田にしても、同様の感慨はコメントから充分に汲みとれる。これら三人をして一様に天才と呼ばしめ、彼らをその暗黒の照明で輝らしだした土方巽。三人のうちでだれよりも土方について多く語らねばならない澁澤は、土方歿後わずか一年半にして逝き、吉岡はあたかもその遺言執行人であるかのように《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》(筑摩書房、1987)を土方巽に、そして誰よりも澁澤龍彦に捧げた(と読まなければ本書を読んだことになるまい)。
吉岡実は刊行後の鼎談でこう語っている。「僕は去年〔一九八六年〕の夏から、あるときは中断しながらも『土方巽頌』という、土方さんを讃えるものを一冊の本にまとめていたんですよ。これは去年の夏に少しやりまして、もうとても書けないという気になって放棄していたら、出版社の企画に通ってしまって、どうしてもやらざるをえなくなっちゃった(笑)。でも去年は全然やらなくて、今年の三月くらいからまたやりだしたのね。でも僕は、長いものというのはおそらく書けないと思ったし、どうやって書いたらいいか分からなくていろいろ考えましたよ。で、土方との交流というのはものすごくあるから、まず日記を調べて抜き出して行ったの。その日記を中心にして、さらに同時代の人たちの証言というか、土方の踊りや行動について書かれた文章をできるだけ探してきて、それを引用する。あとは、土方巽自身の言葉ということで、その三つで構成していったんですね。日記を中心にしたんで、彼との出会いから始まって、時間がずーっと流れていって、自然体の叙述になり、少しずつ展開して行ったのね。〔……〕これが、私家版とか小さな出版物だったら八○ページくらいの小冊子でいいんだろうけど、筑摩書房なんでそうもいかなくなっちゃって。やっぱり本になる体裁というのがありますからね。それで、やや無理してやっているうちに夢中になっちゃってね。やりだしたらけっこう面白くなって、結局二五○枚ということに……」(#C_041、二五六~二五七ページ)。
同様の趣旨は《土方巽頌》の〈補足的で断章的な後書〉にも見える(そういえば《土方巽頌》は〈西脇順三郎アラベスク〉の方法の大大的な運用ではなかろうか)。先に「遺言執行人」と言った意味は、澁澤の次の言を横に並べたとき明らかになるだろう。「それからの約十年間、すなわち私の六○年代と呼べるような時期、私は土方巽からいかに多くの刺激を受け、いかに多くの貴重な体験を共にしてきたことであろう。〔……〕事程さように、私は一時期、土方巽と深く結ばれていたのであり、アスベスト館と称する目黒の稽古場へはさしずめ木戸御免といったところだった。酒席を共にしたことは数えきれず、房総の海や、軽井沢や、京都の稲垣足穂邸にも同行しており、三島由紀夫が死んだときには、警戒厳重な馬込の三島邸へ一緒にお焼香しに行ったものであった。しかしまあ、こんなことをいくら書いても切りがないから、このへんでやめておくことにしよう」(〈土方巽について〉#B_122、二三一ページ)。
「事程さように」以下の具体的な記述こそ吉岡実の〈日記〉が余すところなく描いたものであり、中心に据えられた〈日記〉は自身の記録の〈引用〉であった。《土方巽頌》には初出の記載がないが、吉岡の地の散文すべてが書きおろしというわけではなく、これらも大魚に呑まれる小魚のように《土方巽頌》の一部分となった。試みに既発表の文章の記録を、目に触れただけだが掲げる。
既発表の散文はまだほかにもあるかもしれない。いずれにしても、澁澤龍彦のやらなかったところから始めたことが《土方巽頌》のリアリティを保証している。
吉岡実が土方巽に捧げた詩篇は三篇あり、いずれも《土方巽頌》に収録されている。
〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)1967年7月
〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)1973年2月
〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)1986年6月
また、土方巽のことばからの引用だと明記された詩篇は次の一篇。
〈螺旋形〉(⑨・10)1977年5月
これらの作品以外にも土方巽の「活字になった、対談や座談会で発言した、まるで箴言的な言葉を探し出し、それに触発されながら」(〈弔辞〉#A_24、二一四ページ)書いた詩がいくつもあるだろう。たとえば〈父・あるいは夏〉(⑨・12)について、高橋睦郎は詩篇の〈鑑賞〉でこう書く。「土方巽の文章というか語録というか、彼の言葉がなかったら生まれなかったろう、と作者はいう。不世出の実存的ダンサー、土方巽の常識論理回路を外れたセンテンスのいくつかを生命の指標[ライフ・インデクス]ふうに奪うことで成立した作品」(#A_23、一三七~一三八ページ)。吉岡は先の〈弔辞〉の言にこう続けている。「私は自分の考える言葉よりも、きみの独特の口調の奇妙な表現の言葉のほうが、リアリティがあって、ずいぶん借用させて貰っていますね。それらの詩篇は、いずれも自信を持っています。きみは寛容にも許してくれました」(#A_24、二一四ページ)。
他者のことばに己のリアリティを見出すという事態は、六○年代末、詩集でいえば《神秘的な時代の詩》以後、二十年余の吉岡実詩のメソッドの宣言である〈わたしの作詩法?〉には予感さえない。だが、この「リアリティ」こそ、戦後の吉岡実が一貫してその詩的世界の拠り所としたものだ。次に挙げるようないくつかの作品評(自身の作であれ他人の作であれ)で、「リアリティ」の一語はつねに決定的な重みをもって発せられる。
これらの「リアリティ」の内実と、仮にあるのならその変貌を探ることこそ《僧侶》(1958)から《サフラン摘み》(1976)への吉岡実詩の山脈の稜線をたどることだ。「リアリティ」に裏打ちされた作品を書きつづけるなかで、大きくは詩集ごとにスタイルを変えてきた吉岡は《夏の宴》(1979)の刊行後、金井美恵子とこう語る。
金井 前に、引用にきまった言葉を引用できる人と、あんまりできない人がいるという話をしてましたよね。最初にでてくる「池田満寿夫の」は、〈夏から秋まで〉ではなく〈草の迷宮〉(⑨・9)である。《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977)掲載の初出形を掲げるが、追い込みにする。
吉岡 そう、それが不思議でね。池田満寿夫のを書こうとしたのね、そしたら非常にむずかしいわけ。引用は、土方巽の言葉が一番引用しいいのね。
金井 ああ、あれは実に独特で奇妙な文章ですものね。
吉岡 そう。それで生[なま]なの。源初そのものの言葉なんだ。だけど満寿夫というのは頭がいいんで、文章が明解なの、だから意外に引用が困難だったわけね。
金井 うん、うん。わかりますね。土方さんの言葉ってすごく物質的な、具体的な言葉で、吉岡さんの詩というのも、すごく観念的で難解な詩と言われることは多いわけだけども、言葉の一つ一つは非常に具体的で物質的な言葉だけでできている詩で、観念的では絶対ありませんからね。
吉岡 だからぼくのはシュールレアリスムでも何でもなくてさ、一行、二行〔ママ〕すべてリアリティだという自負はあるのね。それの集積でちょっと異様なものができてるはずだよ。
金井 池田満寿夫の文章は明晰すぎるということなんでしょうかね。と言うか抽象的で陳腐に美しいということなんでしょうかね。
吉岡 抽象的でもないけど、非常に明晰で作りにくかった。で、土方巽のほかで作りやすかったのは飯島耕一。これまた野蛮な言葉を発しているわけ。ぼくにとって意外な言葉と言うか、生の言葉が必要なんだ。それだと作りいい。だから、あんまり文章が整いすぎちゃったエッセイからは、非常にとりにくい。宮川淳なんかその最たるものね。宮川淳はとるところが非常にむずかしいわけよ。だから、他の、外国の画家の言葉とかそういうのを散りばめないと宮川淳像は成り立たなかった。
金井 宮川さんの文章そのものが引用から成り立っているわけですものね。
吉岡 宮川淳のための「織物の三つの端布」、これが一番むずかしかったなあ。またおそらくうまく成功してないんじゃないかと思うよ。作品としてどうなのかちょっと疑問になる。
金井 宮川淳から引用できそうな言葉というのは、宮川淳が使っている言葉じゃないということがあるかもしれないですしね。
吉岡 そういうこともあるかもわかんないしね。あまりにも詩的な文体であるためにこっちの感興を呼ばなかった。
金井 一種の生々しさと言うか、言葉が物質として粒立っている肌ざわりのようなものを宮川さんの文章から見つけようとすると、それはちょっと困難ではあるような気がしますね。
吉岡 それがぼくの中にはっきり表われているのね。
金井 吉岡さんの選ぶ言葉というのは――もちろん単語というんじゃなくて詩とか散文全体のことなんだけど、全部手ざわりというか触覚的な選び方をしていると思うんですよね。
吉岡 まあ、本能的なんだけど、やっぱりそういう言葉を選んでいると思う。(#C_010、九六~九七ページ)
草の迷宮
〈目は時と共に静止する〉――池田満寿夫
1/「狼の鳴声や/天井をはっているサソリや/野ざらしの白骨」/その悪夢の表面を/「動きつづける線/そして 斑点のような色彩」/にとりまかれて/わたしは育ちつつあった
2/満州国/柳絮とぶ/奉天/暗いオンドルの部屋/張家口/「馬車でほこりをかぶりながら/支那街を通りすぎる」/そしてねじあやめ/咲く丘へ/ウォーターメロンを食べながら/わたしは朝鮮鴉を石で打つ/王者のように/死者のように/「突然マンホールに落ちる」/その時たしかに/わたしは少年になったのだ/見たまえ/青空にきみの心臓が浮び/鼓動している/「たまたまその/少女が裸でいるのも/不思議ではない」/となりの庭で/行為する両親たち/正面が赤く燃え……
3/「刻まれた眼はうごくか?」/頭部の両側にある/うごかないようで うごく/魚の眼/呼吸する氷の下で/夏は終るだろう/「描かれた眼はうごかない」/魚の眼は告げる/「きみらの眼は閉じられてゆく」/朝焼の草むらの/カマキリの交尾をみつめながら/「自然の暗さに接近している」
4/わたしは何物になったのか?/「音もなく岩石が宙へ昇り/ガラスが割れ/楽器類が燃える」/そんな奇蹟がいったいあり得るだろうか?/便器にしゃがみながら/三つの沼へ/わたしは頭髪のフケをふりそそぐ/見える観念がある/石の波/机の下の犬/「横に倒された/女陰」/金曜日は雨/「わたしは靴職人になりたかった」/耳濡れ/乳濡れ/武装した馬を曳き/下着の女が長靴をはいて来る/草の迷路を――
5/倒れる男/スプリンター/プリンター/眼は開きっぱなし/痛みの感覚があるかぎり/わたしは手に直結している物を信じる/切断された銅板や/人型や鳥型/すべてを平面化す/「虹のもつ永遠のスペクトル」/しかし海と樹木は立方体へ還元する/また涙も実物そっくり/用紙の上に滴らす/認識や感情の外に/だからいつまでも/「物体は裸のままの物体である/ことを保留されている」/タンポ/ヘラ/ローラー/油
6/わたしは不意の舟にのり/松脂粉末をもち/昆虫採集に出かける/迷宮では/線は死んでいる/扉と窓をあければ/シートをかぶったスフィンクス/わたしは攻撃する/「電気ドリルや鋼鉄の三角刀などの/道具を使って/傷をつけ たり/穴をあけたりする」/蟹星雲のはるか下で/いぜん聳えるスフィンクスの処女
この詩篇は方法的な面から見るとき、吉岡実の作品史のなかで新しいものとは言えない。〈田園〉(⑧・14)に始まる「ひとりの男の伝記的スタイルをとって書かれた作品」(高橋睦郎#A_23、八七ページ)の一篇として別の機会にじっくりと読むことにしよう。そのときは〈犬の肖像〉(③・16)を冒頭に据えたい。
さて〈夏から秋まで〉には《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1997)以前に四つの刊本のテキストが存在する。次のbからeまでである。
a初出《文学者》〔「文学者」発行所〕1967年8月(第10巻第8号)
b再録《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》〈未刊詩篇から〉(思潮社、1968)
c初刊詩集《神秘約な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、1974)
d再刊詩集《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、1975)
e三刊詩集《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、1976)
以下、a初出とe三刊詩集の定稿を校合する。
夏から秋まで|吉岡実
〔池 田 満 寿 夫〔改行〕銅版画展目録より→池田満寿夫の版画の題名を藉りて〕
レインちゃん 黄色い舌をして
素敵なソプラノの花嫁
それはなんですか
何にする非生物
花のクチナシ
木の机の下で
観念する
夏
聖なる川の楽園に死す
足なえの夏
鏡のうちの青
はずむブルーの球
カメがかむカヤツリグサ
四つ手の網のうえで
S字型の〔マス→鱒〕
わたしは食べたくない
姉妹と関係したくない夢
わたしはネコを抱く疑問符の人
すべてのものを満喫したくない
あらゆる壁を剃る
血を剃る
ころびたい愛
曲りたい矢印!
水からさきの水
道からさきの道
涙からさきの眼のランデブー
影からさきの影
具体的な物
賛成!
庭をよこぎる
メタフィジックな牛乳配達自転車
あるいは蛾
レインちゃんおしっこをして行きな!
横たわる人とみつめる人の
前で
ミシンのように
はずかしい
花嫁の領地を占める
ビタミン青空
母なるミカンの房
レインちゃんこぼしちゃだめよ!
赤いセーターを〔ぬ→脱〕ぐ
日まで
オムレツをつくる男
オムレツらしきものをつくる男
はずかしいオムレツをつくり
急ぐ人
ホタルの闇で
肉の入らない記念碑をなでる
秋ならススキがなびく
レインちゃん 靴下のまま
そこで何をみがくの
つかのまの亀甲体?
吊天井の恐しい花嫁のスカート
円を縮小する方へ
すすむ矢印
沼へ沈みゆけ
老婆の乳母車群
めずらしくむらさき色の
停る矢印
電気ウナギを釣っている〔(ナシ)→男〕
〔男→(ナシ)〕と同時に見える?
両側へ紐をたらしつつある
神〔祕→秘〕的な靴が――
念のために異同箇所を確認すれば、まず詞書である。bにもcにもdにも、初出にあった詞書に相当するものはない。つまり初刊詩集で詞書の付された詩は、土方巽に捧げられた〈青い柱はどこにあるか?〉だけということになる。本文の「S字型の〔マス→鱒〕」の手入れは、桝などに誤読されることを避けるためというよりも、イメージを鮮明にするための措置だろう。「赤いセーターを〔ぬ→脱〕ぐ」もほぼ同様のもの。これらとは異なり、最後の「神〔祕→秘〕的な靴が――」は入稿原稿から旧字「祕」が拾われたのを正したものだろう。
1967●昭和四十二年――三十三歳
一月、東京、京王百貨店に於て、美術出版社主催、ベニス・ビエンナーレ展グランプリ受賞記念の回顧展開催される。一九五六~六六年間の版画作品百二十点展示。(〈〔池田満寿夫〕年譜〉#B_013、四〇四ページ)
残念ながらこの回顧展(舞踏家なら凱旋公演か)に対応する記述は吉岡実の詳細な自筆〈年譜〉(#A_23)には見あたらない。しかし、次の池田満寿夫の文からうかがえるように、吉岡の観たのがこの銅版画展であり、詩篇の「生命の指標」の資料とした版画展目録をそこで求めただろうと考えて先に進む。かなり長いが、池田が吉岡の人と詩を語った唯一のエッセイのため、適宜引用する。
繁殖する感覚の細胞――吉岡実|池田満寿夫〔……〕
吉岡実氏にはじめてお会いしたのは、たしか新橋の灘万での加藤郁乎の出版記念だったか、受賞記念だったかの会だった。十年ほど前にもなるだろうか?
〔……〕
ぼくはオッチョコ・チョイでネ、彼は口をややとがらせながらまたそう宣言した時、私は吉岡実が、自分と非常に似ていることを直感した。
彼はまず人を安心させてしまう。そして、どことなくぎこちない喋り方と、風が吹けば飛んでしまうような軽やかな姿態。そして骨が笑うような感じ。いつも驚異をみつめているようなまなこ、決して閉ざされることのないまなこ、吉岡実は目で詩を書く詩人に違いない。目で感ずることの出来る詩人なのだ。だから彼の喋る言葉はいつもやさしい。あるいはいつも少々、あわてて喋っている。
最初に会った時から、私はこの詩人らしくない吉岡実がいっぺんに好きになった。
マスヲさんの版画の題名が好きでネ、今その題名だけで詩をつくっているんだよ。
その時、吉岡実はそういって私をひどく喜ばした。それから何年か経って、現代詩文庫の「吉岡実詩集」をわざわざ持参して来て、〝未刊詩篇から〟に収録された〝夏から秋まで〟の詩が、前に約束した版画の題名をとり入れてつくったものだ、と説明してくれた。私は自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄で、すっかりうれしくなっていた。それにしても、吉岡実にこんな茶目気があることを、それまで少しも気づかなかったとは、うかつであった。すると私はまったく〝僧侶〟の吉岡実を誤読していたことになるのに気がついた。〝僧侶〟がブラック・ユーモアであったことに気がつくまで私は十年も掛かったのである。そして、ひょっとすると、〝僧侶〟はロルカのバラードを意識していたかもしれないと考えた。また仮りにその推定が間違っていても、〝僧侶〟が現代詩のなかで朗読されうる最も優れた詩であることに間違いない。
したがって私が詩集〝静かな家〟を読んだ時、吉岡実の変貌に少々苦言をていしたのは、あきらかに彼の本質を見あやまっていたからである。〝僧侶〟の誤解が、次の誤解を生んでいたのだ。吉岡実の詩こそ、くりかえし読まれるべきものだ。純粋な感覚によってつくり出されたものは、読む方のものの感覚もまた純粋にとぎすまされていなければならない。彼の詩は理屈で納得されることを拒絶している。感覚の細胞がどんどん繁殖していき、ドモリ勝ちの詩語は雄弁になっていく。はにかみ勝ちなセックスは突然白日下にさらされる。吉岡実のエロスにはいつも少女的なニンフが小さなお尻を丸だしにして見え隠れしている。彼女はやわらかいうぶ毛を風になびかせながら、オート・バイに乗ってくる。不意に詩人の手は少女をあお向けにさせる。ふさふさとした少女の陰毛が私たちの目に飛び込んでやさしい残酷さで、詩人のニンフを私たちの身近に接近させる。しかし少女はたちまちイメージの世界へ逃げていくだろう。今目撃したものは次には消えていなくてはならない。
見えるものに詩的亢奮を与えたのが吉岡実の詩である。物体の一つ一つに心臓を与えたのが吉岡実の詩である。少女のなめらかな肌に毛を植えつけたのが吉岡実の詩である。残酷さとやさしさを唄うように連続させたのが吉岡実の詩である。
〔……〕(#B_010、三八〇~三八二ページ)
次に池田の〈目録〉から当夜(一九六七年二月九日)の部分を引く。吉岡の名は挙げられていない。
〔……〕六時、新橋の灘万で親友の加藤ノヴィチ郁乎ノフの受賞記念会へ出る。西脇順三郎、澁澤龍彦夫妻、加納光於、土方巽、野中ユリ、白石かずこ、飯島耕一、鍵谷幸信、森谷バルザック諸氏に会う。二次三次会を経て例の如く郁乎邸へくり込む。時に夜中二時頃、本来ならみんなと徹夜すべきところであるが、涙をのんで四時に別れを告げて帰宅。(#B_012、一六三~一六四ページ)
吉岡の〈変宮の人・笠井叡〉(1968年発表)で「いつのことか忘れたが」(#A_25、一六〇ページ)と日付がぼかされていた土方巽との出会いは《土方巽頌》で「昭和四十二年二月九日の夕」(#A_24、八ページ)と明記された。それはいま見たように池田満寿夫と吉岡実が出会った日でもある。同じ日のことを、飯島耕一は〈瀕死の白鳥――土方巽のこと〉で土方巽との出会いとともにこう書く。
「彼とはじめて会ったのは、安保から二年目ぐらいの頃、井の頭線の東松原にあった池田満寿夫のアトリエでだった。〔……〕行ってみると澁澤龍彦や出口裕弘、野中ユリといった定連がいて、そこに若々しく精悍なハンテン姿の寡黙な男がいた。実際は三十半ばだったのだろうが若く見えた。それが土方巽だった。加藤郁乎は遅れて来ることになっていて、郁乎が来たら初対面の飯島は殴られると澁澤龍彦が言い、恐ろしいグループだと思ったが、その晩郁乎はわたしを殴らなかった。深夜二人一組で寝ることになり、クジビキでわたしは土方氏と寝た。なつかしい六○年代のはじまった頃だった。/それからのち、土方巽の舞踏は大体全部見た。見たあとの酒盛りがまた楽しく面白かった。わたしが土方氏と会ってしばらくのち加藤郁乎の出版記念会が、新橋演舞場の側の灘万であり、西脇順三郎や吉田一穂も来たが、その夜、わたしは吉岡実を土方氏に紹介した。この二人はたちまち肝胆相照らす友となった。こう思い出を並べて行けばキリがない」(#B_008、一四〇~一四一ページ)。
すでに引いた澁澤龍彦の調子と極めて近いものがここにはある。一九六七年二月九日、初対面の吉岡実は池田満寿夫に「マスヲさんの版画の題名が好きでネ、今その題名だけで詩をつくっているんだよ」と言い、数年後、〈夏から秋まで〉がそのとき約束した池田の版画の題名をとり入れて作ったものだと説明した。池田は「自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄で、すっかりうれしくなっていた」。さてこれで、吉岡実の詩の系譜に今までなかったスタイルの詩篇がこの時期あいついで登場してきたことになる。版画家の作品の題名でつくった詩〈夏から秋まで〉、舞踏家の「求めに応えて書いた」(#A_24、六ページ)詩〈青い柱はどこにあるか?〉。あたかも、詩集《紡錘形》(1962)から見てさらに日常平俗的な《静かな家》(1968)のマニエリスムの世界に「芸術家」が跳びこんできた恰好だ。
親しい芸術家たちの肖像は、その引用の方法とも相挨って後の詩集《夏の宴》に多くを数えるが、〈夏から秋まで〉もその種の一篇であると言えるか。どうやらこの作品をそう見るには無理があるようだ。この作品には池田の版画の題名を拉しきたって己の詩句の駆動力としている趣がある。あくまでも主体は己の詩句であり、池田満寿夫(に擬せられる芸術家)の肖像を描くことが目的になっていないのである。〈夏から秋まで〉の主題の類例を強いて過去の作品に求めれば、《紡錘形》の〈編物する女〉(⑤・8)になろう。散文詩型の作品を行替えの形態に改変してみる。
編物する女たっぷりと畝編みにしたプルオーバー
今夜の料理には玉葱を使おう
彼女はじぶんのからだから何を編みだすのかしれたものではない
大きな衿はタートルネックの変り型
彼女は砂の力で一人の男を愛そうとした
ジャージーでピンクなら彼も大胆にさわれる
太陽の網目のなかの苺をつぶす愉悦の日々
男の住所をどこへ控えたか思いだそう
秋だからブルー グレーなどで模様を変え
袖口をゴム編みにして
男が独身者の血は冠の毛をぬらすと
二ヶ月前にもらした重大な口説
裏うちは三十糎幅の同色の布をはって横になる
しわにならぬから
男の部屋へは猫しか通わぬ秘密をかぎつける
裾は折返しを深く
男とこの夏は波の下へ
すべったことが忘れられぬ
単純なメリヤス編みですっきりさせよう
男の肉親・父・母・不具な姉を呪い
ドレス・ヤーンでなければ上手に仕上らぬ
長い胴のシルエット
男は貧しいから好色な壁画を描く
たくしあげて彼女が着るときココア色のスラックスが似合うと
老裁縫師にいわれた
もう冬だからやぼになる
船の底の貝の冷たい光りがとどく
彼女の眼に入る男は彼女にとって象牙色の魚形のハンガーだ
本当に死ぬならばセーターを脱ぎたいと彼女は考える
編物する女の内的独白、男との夏の想い出と季節のうつろい――意味をたどろうとすると必ずしも明確でなくとも、交互に情景の替わる一篇の映画のように観ていけばそこにおのずと別の物語が立ちあらわれる。そんな作風だ。しかしそれにも増してこの散文詩が想起されるのは、夏から秋、いや冬までの季節のうつろいの果ての最後の一行ゆえである。ここでの駆動力はいうまでもなく「編物」にまつわる女の描写だ。いったい吉岡実の詩には継続的な描写は数多くない。〈編物する女〉が同じ孤独な人間を描きながら《僧侶》の多くの「男」などに較べてどこかアンチームなのは、この継続的な描写による。〈夏から秋まで〉で継続的な描写に相当するのが、借用された池田満寿夫の版画の題名だ。吉岡が本篇を執筆するにあたって参照したのは、詞書に依れば「池田満寿夫銅版画展目録」である。ここで簡単にこの展覧会カタログを紹介しておこう。《ベネチア・ビエンナーレ グラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展》(〔刊記なし〕)は一九六七年一月、東京・新宿の京王百貨店で開かれた〈池田満寿夫銅版画展〉(主催・美術出版社)のカタログで、仕様はほぼ正方形のA5判変型・二八ページ・中綴じ、一ページに一点のモノクロ図版計一五点を収める(表紙の図版は〈Something(Ⅰ)〉)。本文図版の題名と制作年は、
である。カタログ全体の構成を概観する。表紙には、横書きで「ベネチア・ビエンナーレ/グラン・プリ受賞記念」と角書きふうの小字のあとに大きく標題が「池田満寿夫/銅版画展」と日本語で、小口寄りに下から上に(読みあげで)「1956―1966 M. IKEDA」と英文で別書名がある。三ページめ(本カタログにはどのページにもノンブルがふられていない)は扉で、
ベネチア・ビエンナーレ
グラン・プリ受賞記念
池田満寿夫
銅版画展
'67 1月13日―25日
新宿 京王百貨店 7階大催場
主催=美術出版社
とある。四ページめは酒井啓之撮影による制作中の池田満寿夫の写真。五~六ページが「池田満壽夫が地球を……」で始まる針生一郎の文章(無題)。七~二一ページが前掲本文図版。二二~二四ページが全一二一点の〈出品目録〉。二五~二六ページが資料(略歴・受賞・国際展出品・現代日本美術展出品・美術館企画展出品・個展・グループ展・銅版画集・パブリックコレクション)。二八ページが裏表紙で、二ページ・二七ページは白。この〈出品目録〉(#B_174)こそ吉岡の詩篇〈夏から秋まで〉のスルスなので、すべての題名を付録として掲げる(〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉)。ここで〈夏から秋まで〉を細かく追ってゆこう。数行のモジュールに分解すべく《薬玉》(1983)の詩篇と同じ形態に整えてみる。なお、( )内は池田満寿夫の版画の題名に見える語句である。
夏から秋まで
池田満寿夫の版画の題名を藉りて
01 (レインちゃん) (黄色い)舌をして
02 (素敵なソプラノ)の(花嫁)
03 (それはなんですか)
04 何にする非生物
05 花のクチナシ
06 木の(机の下)で
07 観念する
08 (夏)
09 (聖なる)川の(楽園に死す)
10 足なえの(夏)
11 (鏡のうちの青)
12 はずむブルーの球
13 カメがかむカヤツリグサ
14 (四つ手)の網のうえで
15 (S字型の)鱒
16 (わたしは)(食べたくない)
17 (姉妹)と関係したくない夢
18 (わたしは)(ネコ)を抱く疑問符の人
19 すべてのものを満喫したくない
20 あらゆる壁を剃る
21 血を剃る
22 ころびたい愛
23 曲りたい矢印!
24 水からさきの水
25 道からさきの道
26 (涙)からさきの眼のランデブー
27 影からさきの影
28 具体的な物
29 賛成!
30 (庭をよこぎる)
31 (メタフィジックな)牛乳配達(自転車)
32 (あるいは蛾)
33 (レインちゃん)おしっこをして行きな!
34 (横たわる人とみつめる人)の
35 前で
36 (ミシンのよう)に
37 はずかしい
38 (花嫁の領地)を占める
39 ビタミン青空
40 母なるミカンの房
41 (レインちゃん)こぼしちゃだめよ!
42 (赤いセーター)を脱ぐ
43 日まで
44 オムレツをつくる男
45 オムレツらしきものをつくる男
46 はずかしいオムレツをつくり
47 (急ぐ人)
48 ホタルの闇で
49 肉の入らない記念碑をなでる
50 秋ならススキがなびく
51 (レインちゃん) 靴下のまま
52 そこで何をみがくの
53 つかのまの亀甲体?
54 吊天井の恐しい(花嫁)の(スカート)
55 円を縮小する方へ
56 すすむ矢印
57 (沼)へ沈みゆけ
58 老婆の乳母車群
59 めずらしくむらさき色の
60 停る矢印
61 電気ウナギを釣っている男
62 と同時に見える?
63 両側へ紐をたらしつつある
64 神秘的な(靴)が――
初めの二行(01~02)を見よう。池田満寿夫の版画の最初期のモチーフが「花嫁」だったことは〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉からも見やすい。吉岡はこの花嫁を「レインちゃん」とすることで、池田の版画に敬意を表しつつ、早くも独自の語法を繰りだしてくる。「黄色い舌をした」なら文意はもっと滑らかになるが、原文だとそのようには読めない。
レインちゃん〔は〕素敵なソプラノ〔を〕
黄色い舌をして〔歌う〕花嫁〔だ〕
池田の版画〈姉妹〉(1965)のように、「レインちゃん」が大きく口を開け無邪気に声を張りあげる娘なら、「黄色い舌」は二行めに割って入ってくる感じになる。そこまでいかなくても、この二行を図示したときに「レインちゃん」と「花嫁」という同格を繋ぐ線を「黄色い舌をして」と「素敵なソプラノの」を繋ぐ線が横切る印象は動かない。詩句のジグザグ運動、あるいは二歩進んで一歩戻る感じ。
「それはなんですか」(03)のそれは「花嫁」にも読めるが、よく考えると分からなくなる。池田の版画〈それは何ですか〉(1964)には、読める文字として「Dogはイヌ」と横書きしてあるものの、詩のコンテクストを補強するわけではない。三行めを言い換えたのが次行(04)であり、その解答が「花のクチナシ」(05)という展開である。しかし、クチナシは植物であって、非生物ではない。山梔子の、熟しても口を開かない実にシンボリックな意味を読み、処女としての花嫁、という仮の答を出して先へ進む。
次の五行(06~10)はセットで読める、映像的にもくっきりした池田作品の引用に満ちた部分。池田の版画集の索引のように読める一方、土方巽の舞踏への言及のようでもある。
次の二行(11~12)も提示と換言のようだが、そうではない。「はずむブルーの球」は鏡像であり、前行は詩人の視覚が版画の紙面に潜りこんだことを示す。
13~15、子供がその茎を端から裂いて蚊屋を釣る形にするところから名付けられた蚊屋釣草。それをカメが咬むとはいかなる光景か。「四つ手の網」と蚊屋の形態の類似性。そこに捕えられ、身をくねらせる版画家としての鱒(池田はときに自身を魚に喩えている)。
16~17、食べたくない対象はカメか、カヤツリグサか、鱒か。「わたし」が「関係したくない」のはインセストなのか、他人の「姉妹」なのか。詩句の宙吊り状態は続く。
18~19、池田満寿夫の版画〈私の詩人・私の猫〉(1965)には猫を抱く女の詩人の姿と、「my poet」の文字が彫られてある。この行では猫は疑問符の形をしている。詩は謎である、ということの遠回しの言明。たたみかける否定の意志表示。
20~21、かつて〈僧侶〉(④・8)には「美しい壁と天井張り」があった。「血を剃る」という触覚的想像力の横溢。
「ころびたい愛」(22)は不倫のユーモラスな表現か。それをよろめくと言えば華奢で優雅だが。対句的な次行の「矢印」(23)は先端がとがってはおらず、水滴のような感嘆符かもしれない。
起承転結を絵に描いたような四行(24~27)。ミズとミチの頭韻の一方で、横に並んだ「水道」が見え隠れする。「眼」は池田に捧げたもうひとつの詩篇〈草の迷宮〉でもオブセッションのようにたびたび言及されていた。それにしてもこの「涙からさきの眼のランデブー」は美しい。
28~29、詩人は内省し、方向転換する。
次の三行(30~32)もきわめて池田的かつクレー的なセット。西脇順三郎は所有する〈庭を横切る昆虫〉(1962)をクレー的だと評したが、絵柄よりもむしろ画題を指して言ったのではないか。
33~35、「レインちゃん」は水も滴る好い女。「横たわる人」はもう一人の別の女であり、「みつめる人」は男である。
「レインちゃん」は「おしっこ」をがまんして「ミシンのように」震えているのだろうか。「ミシン」(36)はロートレアモン以来、シュルレアリスムの専売特許のようなオブジェだが、これが「はずかしい」(37)と結びつくことで新たな生命を吹きこまれた。
池田満寿夫の画題からの借用は「花嫁の領地」だけだが、次の三行(38~40)もはなはだ池田的なセット。「ビタミン青空」からはリトグラフ〈マググリットの空〉(1968)の青空が想いうかぶものの、吉岡が詩を書いた時点ではまだ発表されていないから、先読みである。
41~43、「レインちゃん」はオレンジジュース(それともおしっこ)をこぼしてしまう――この「してしまう」は《液体》(1941)に頻出する語法だ。「ビタミン青空」の青、「母なるミカンの房」の黄と来れば、セーターの色は赤以外ない。
44~47、炒めた玉葱・挽肉などを卵で薄く包んで焼いた食べ物が、なぜかくまでオムツに似てくるのか。それは篠田一士が言うように「オムレツ」から「レ」の音が脱落たのではない。詩の論理的展開が、詩内部の要請が読者をしてオムレツをオムツと読ませるのだ。
次の二行(48~49)はホタル/ホテルでの初夜の儀式ででもあろうか。
ヘアーではなく薄・芒。薄・芒のごときヘアー。池田はこの詩句(50)から確実にメッセージを受けとっている。
52、「レインちゃん」のいる「そこ」はどこか。足首まで埋まる毛深い絨緞の上か。
「つかのま」「の」「亀甲体」「?」(53)、難句である。――亀の甲の固い物質にふれる(〈わたしの作詩法?〉)。
「吊天井」(54)は固定せずに吊りさげておき、落として下にいる人を殺す仕掛けの天井。「花嫁」の「スカート」が吊天井なのか、それが吊天井にあるのか。どちらが恐ろしい。この行は次の二行(55~56)と同じ構造(ただし逆向き)である。のちの〈『アリス』狩り〉(⑧・12)の
わしの知っとる
「もう一人のアリスは十八歳になっても 継母の伯母に尻を
鞭打たれ あるときはズックの袋に詰められて 天井に吊る
される 美しき受難のアリス・ミューレイ……」
を先取りした詩句のように思われる。
57、「レインちゃん」はどこに行ってしまったの? 沼になってしまったの? ――わたしの中の乳母車は沼へ沈むべき運搬用に必要なのだ(〈わたしの作詩法?〉)。59、むらさきは充血の色、鬱血の色。決して迸る色ではない。
あれだけ無敵を誇った「矢印」(60)がはねかえされてしまうとは。あろうことか、鯰と鰻の中間形の長さ約二メートルの魚に姿を変えていたとは。両側に垂れているのは靴紐ではなく鯰のひげではないだろうか。それとも靴紐のような鮮血。詩を釣りあげようとする詩人を描くことで、〈夏から秋まで〉は終わる。
ここで池田満寿夫の版画作品〈レインちゃん〉(1964)を観ておこう。池田は未発表のデッサンについて書いている。「《レインちゃんシリーズ》のデッサンは「レインちゃん」に対応する習作の一部分であるように思われる。なぐり描きに近いこれらのデッサンは、またもやポール・クレーを思わせないでもない。ここにはスタイルへの関心よりも、素早く横ぎるイメージを大急ぎでとらえようとする姿勢の方が濃厚である」(#B_009、一一七ページ)。さらに版画作品については「このレインちゃんは〔……〕童謡の情景を連想させる。たしかにこの時、私はチャプ、チャプ、ジャプ、ジャプ、ラン、ラン、ラン、という擬音を視覚化しようとしていたのである」(同前、一二〇ページ)。むろん、北原白秋の〈アメフリ〉(1925)である。

池田満寿夫の銅版画〈レインちゃん〉(1964)
出典:美術出版社企画室編《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977)
吉岡実の拾遺詩集に《ポール・クレーの食卓》(1980)があり、《静物》(1955)にまとめられる詩篇を書きつづっていた当時、一九四九年八月一二日の日記に「クレーのような詩も書きたいと思った」とあるのを思いだそう。吉岡実を書いた前掲の池田満寿夫のエッセイにもあるとおり、この二人には気質的にも、さらに言えば芸術に対する姿勢にもかなり近いもの、多くの共通するものがある。話の流れからすれば、とりわけ大きいのがピカソとクレーに対する愛着である。池田に《私のピカソ 私のゴッホ》(中央公論社、1983)などの画家論があるのは驚くに値しないが、吉岡は〈わたしの作詩法?〉の核心的な部分で次のように書いた。〈夏から秋まで〉がこの意識に貫かれていることになんの不思議もない。
「〔……〕形熊は単純に見えても、多岐な時間の回路を持つ内部構成が必然的に要求される。能動的に連繋させながら、予知できぬ断絶をくりかえす複雑さが表面張力をつくる。だからわたしたちはピカソの女の顔のように、あらゆるものを同時に見る複眼をもつことが必要だ。中心とはまさに一点だけれど、いくつもの支点をつくり複数の中心を移動させて、詩の増殖と回転を計るのだ。暗示・暗示、ぼやけた光源から美しい影が投射されて、小宇宙が拡がる」(#A_25、八九~九〇ページ)。
《静物》は一九四九年から五五年までの七年間の書きおろし作品で構成されている。しかし、この詩集を論じる者がそれぞれの詩篇に触れながらその成立年代を云云しないのが以前から不思議だった。自費出版の《静物》の作品が、《僧侶》(1958)が脚光を浴びることでいったいどこにその詩の起源があるのかという興味の対象となったとき、戦前の《液体》(1941)には直接《静物》の作者が見あたらないことに安堵してしまい、《静物》がいかにして生成したかという吉岡実詩の魅惑の源泉の探求はなおざりにされたように思われる。《静物》には制作の記録がなく、別の方面から執筆順序・成立年代を推定する以外ないのだが。
次の詩集《僧侶》は書きおろし五篇を含む、一九五六年から五八年にかけで発表された一九篇から成る(〈表② 吉岡実発表詩篇(1956-58)〉参照)。一九五八年八月八日の日記にはこうある。「〈感傷〉出来。これで詩集《僧侶》の十九篇完成」(#A_10、一一九ページ)。この年七月に三篇を同時に発表する一方で書きおろし詩篇を進行させているのは、新しい詩集というゴールが見えているためだろうが、その後の吉岡の作品発表のペースを考えれば凄まじいまでの創作力だと驚嘆するしかない。この伝でいくと《静物》(とくにその終盤)にも爆発的な創作を想像することはあながち荒唐でもないだろう。詩集成立前後を書いた作者自身の証言のなかで最も注目されるのは、ただひとり「先生」と呼ぶ西脇順三郎の詩との出会いである。それ以前の吉岡実詩はどうであったか。たとえば、西脇詩と出会う前年の九月に《新思潮》は発表した〈詩二篇〉などまさに《液体》の世界に隣りあわせのもの、言うならば戦後版《液体》であり、その二年後から《静物》の諸作が書かれたとはにわかに信じがたい。ここから《静物》の世界を想像するのは、充分に困難だと言ってよいだろう。こうした溶液にいかなる塩が投げこまれれば《静物》の星の運行のような孤独の劇が生まれるのか。この観点から西脇詩と村松嘉津の《プロヷ〔ワに濁点〕ンス随筆》を手掛かりに解読することは、今後の《静物》論の課題だろう。
そして、日記のクレーの絵が来る。ポール・クレーのデッサンの表紙の《みづゑ》一九四九年三月の号には以下の図版が掲載されている。〈少女像〉〈陽気な食卓〉〈老人と海浜〉〈動物園〉のカラー四点、〈芸術家〉〈緑野の家〉〈赤色の幻惑〉〈R文字による風景〉〈橋梁風景〉のモノクロ五点(#C_032)。クレーの特集は好評だったらしく、同年一二月の号にも多くの図版が掲載された。〈青い夜〉〈熱帯の薄暮〉のカラー二点、〈夜の植物の成長〉〈静物(十字科植物)〉〈沙丘の小景〉〈公園〉〈埠頭〉〈魔塔〉〈幽谷の道化〉〈橋のある風景〉〈黒い艦〉〈幻影の逃亡〉のモノクロ一〇点(#C_033)。これらの複製のクレーがどう響いたのか、吉岡は日記にこう書く。「原始の素朴な夢と淋しさの底から滲みでる抒情。冷めたい知性を包む幻想の交響曲。仕事のあいま、またねどこの中でポール・クレーの絵をみたり、評伝をよむ」(#A_10、一一六ページ)。「詩」を発見するまえの吉岡実に対して、すでに「版画」を発見した池田満寿夫が〈ヨーロッパのリト工房〉でこう述懐しているのは興味深い。
私のドライ・ポイントの発見は、デッサンを途中で放棄してしまうということから始まったのである。そして、そこに最小限の色彩を最も有効に使用することが課せられた。最小限の色彩とは、青・赤・黄の三原色にほかならない。私の色彩の選択は、このように精神的なものからでなく、物理的な理由によって決定されたのである。私の銅版の色彩に装飾的な要素が多いのは、多分そのためであろう。その画面の単調さを救う唯一の方法は、色彩に心理的な要因を与えることではなく、物語の意味を画に回復させることだった。しかしこの物語性は、いつも人間と日用品、人間と動物との間に起こるちょっとした事件に限られていた。なによりも私が欲していたのは、身近な物質に言葉を与えることだったのだ。小さな驚き! それが私の主要なモチーフであった。(#B_010、二六一~二六二ページ)
吉岡の詩論〈わたしの作詩法?〉(1967)には、吉岡自身の詩篇に登場するいくつかのイメージがはめこまれている。そこで〈夏から秋まで〉に該当するのは「亀の甲の固い物質」であり「わたしの中の乳母車は沼へ沈むべき運搬用」である。ここで次に考えなければならないのは、こうした特権的なイメージが詩人の内部から湧出するのではなく、他者から借りられた場合である。《サフラン摘み》(1976)の〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)や〈ルイス・キャロルを探す方法〉(⑧・11)で開花する他者のことばの挿入や固有名詞の楔のような、核のような、塩のような、索引のような埋めこみかたが早くもこの作品に見られる。
加藤郁乎は〈絵にかいたような…池田満寿夫〉に書いている。「この頃の版画家マスオについてひとこと申し記せば、それぞれの絵につけられた題名のなんと詩的であることよ。エッチャー自身から聞き出したところによれば、プレス機から刷り上がった作品を前に数枚、ときには十数枚の紙片に手当り次第考え浮かんだ片言隻句を書きとめ、それらを並べるか、ごちゃまぜにしているうちにこれはと思う題名が決められるのだそうである。この打明け話を聞きながら、私はブルトンなどシュルレアリストたちによる「優美な夙骸」と名づけられた言語実験、詩的遊戲を思い浮かべた」(#B_013、二八二~二八三ページ)。
また、白石かずこは〈わたしの内なるマスオ〉にこう書く。「「戸口にいそぐ貴婦人たち」同様、わたしの好きなオドロキをもってみた作品は「虹を飲む女」で、この頃のマスオの作品とその題名に、わたしは、いちいちコーフンしていた。/特に気にいる題名が多く、ことに「戸口にいそぐ貴婦人たち」や「虹を飲む女」は題だけでポエジーが、いくつも虹になって湧いてくる」(同前、三五四~三五五ページ)。
はたして池田満寿夫は版画の題名が「詩的」であることを意図したのだろうか。私の目にしたかぎり、そのあたりの機微とプロセスに関して池田自身は書きしるしていないようだ。全エッセイの書名の由来についての〈魚[さかな]の眼――序文にかえて、タイトルに関する対話〉なる軽妙な対話体の文章があることにはあるが。
〈思考する眼〉〈考える眼〉〈スフィンクスの眼〉〈無限の子宮〉〈子宮の眺め〉〈思考の意匠〉〈感覚の細胞〉〈歩む眼〉〈眼の歩み〉〈感覚の集積〉〈眼の休暇〉〈思考しない眼〉〈言葉の視覚〉〈みつめの言葉〉〈視覚する言葉〉〈池田満寿夫の書いたエッセイ集〉〈池田満寿夫氏の半生と文章〉〈題名のないエッセイ集〉〈魚の眼〉〈眠った魚〉と数多くの候補を挙げたすえ、最後に〈思考する魚〉となる。「うんこれだ。これでいこう。ブルトンの詩集かなんかにありそうな題だが、あれはたしか「溶ける魚」だったネ。あるいはクレーの画題にもありそうだナ」(#B_010、一八ページ)。
決定的な題名にたどりつくまでの方法は加藤郁乎の書くとおりだが、エッセイ集のタイトルとしてはシュルリアリスティックであり、シンボリックである。だが、こちらの方が〈思考する眼〉よりも池田満寿夫のエッセイ集にはふさわしい気がする。イメージで思考する池田のスタイルが端的に現われているのだ。では、画題の場合はどうか。〈付録《池田満寿夫銅版画展》所収〈出品目録〉〉以降のタイトルだけを拾ってみよう。
〈空の空〉〈空の壁〉〈マググリットの空〉〈マリリンの半分〉〈天使の言葉〉〈ハートの位置〉〈遥かなる空〉〈この空の上〉〈私は眠りつづける〉〈空の寝台〉〈名もなきある街〉〈窓に向かって泳ぐ〉〈うつろなスフィンクス〉〈少し長い指を持ったスフィンクス〉〈スフィンクス・五月〉〈シーツを覆ったスフィンクス〉〈マグリットでなくマーガレット〉〈アリスの記憶〉〈草の上の劇場〉〈デューラーの恋人〉〈七つの大罪〉〈マグリット夫人の涙〉〈蒼白なる真珠色〉〈胚種〉〈マダム・ダヴィンチの肖像〉〈鳥のネックレス〉〈愛のあとのヴィナス〉〈ザクロ〉〈笑う女〉。
これらがここに引いた形で「詩的」であるのではなく、池田満寿夫が日本語で(もしくは英語で)題を付けた版画との関係において詩的であったりなかったり、ポエジーに満ちていたりいなかったりするのだ。絵画にとって詩とはなにか、画題とはなにか。それを考えることは、詩的であることとデペイズマン、引用とコラージュの共通点と相違点を考察することであり、池田の絵画全体を論じることに等しい。そのときは《月に吠える》についての池田のことばを手掛かりにして、さらにそこから装丁・ブックデザインの意味も探らねばならない。池田は〈〝月映〟の版画家たち〉でこう書く。「今日からみれば「月に吠える」は朔太郎の詩そのものだけで、充分な存在理由を持っているように見える。しかしこの一冊の詩集が刊行された時のそのままの形と内容のなかに、はかりしれないふくらみとやさしさの感情を見い出すことは、詩集というものの生成を考える場合、決して無関係ではないはずである。そこには美しい本という書誌的自覚があり、また詩集は必ず美しい本でなければならなかった。詩集は詩を印刷しただけのものであるはずはない。詩集とは言葉にまつわるいっさいのものを柔らかく包括した書物なのではあるまいか」(#B_010、一一九ページ)。
吉岡実が詩を書き、池田満寿夫が版画を創る一方で、装丁・ブックデザインを手がけたことは広く知られている。単行著書で見ると吉岡はほとんど自装なのに対して、池田は他人任せのもの、画の素材だけ提供したもの、自装、といった具合で、これといった方針はないようだ。そうしたなかで唯一ふたりのコラボレーションと呼べる書物が吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》(#A_34)である。《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(#A_10)からの選集に近いこの訳書は、本文挿画とジャケットのイラストを池田が、ブックデザインとタイポグラフィをClaire J. Mahoneyが担当している。《池田満寿夫 BOOK WORK》(形象社、1978)に紹介されている以外にも、扉イラストが一点ある。《池田満寿夫 BOOK WORK》では「装丁 装画」(#B_014、八七ページ)が池田となっているが、そうなのだろうか(いずれにしてもハードカヴァーは「飽きのこない」装本で、吉岡好みの落ちついた作りだ)。

池田満寿夫による吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》の挿画
出典:《池田満寿夫 BOOK WORK》(形象社、1978)
さて、五点の挿画に対応する詩篇は〈風景〉(③・10)、〈僧侶〉(④・8)、〈紡錘形Ⅰ〉(⑤・4)、〈ヒラメ〉(⑥・13)、〈ライラック・ガーデン〉(⑩・3)である。絵柄から見る限り、総点数で池田に依頼した装画を出版者側が随意に配置したのではなく、本文の展開を踏まえてそれぞれの詩篇に合わせて描いたもののようだ。となるとそこには〈夏から秋まで〉に対する池田からの返礼という意味が込められていはしまいか。「自分の版画の題名が詩人のパロディの材料に使われた光栄」の礼ともなれば、手法としてはコラージュ以外ありえない(後の池田に《コラージュ論〔白水社アートコレクション〕》(白水社、1987)の一冊があることを想いおこそう)。池田満寿夫は一九七九年に自身の全詩集の「装幀・装画」を担当している。それは本文挿画ではなく、各パートの半扉を飾るイラストおよびカットだが、コラージュのほかに手描きのデッサンも混じり、画のスタイルとしては《Lilac Garden》より幅が出でいる。「言葉にまつわるいっさいのものを柔らかく包括した書物」としての詩集は、池田にとってそのように捉えられているようだ。しかし、版画家の絵画作品からことばが生まれその画題となり、詩人の詩行に藉りられた先に返礼のコラージュのイラストレーションがあるだけではなかった。小説家となった版画家のことばの世界が繰りひろげられたからだ。
池田満寿夫は〈夏から秋まで〉をどう読んだのだろうか。解答のひとつは、すでに〈繁殖する感覚の細胞〉に書かれていた。もうひとつは、そこに現れた少女像を定着した短篇小説〈ミルク色のオレンジ〉(#C_021)である。担当編集者・田中耕平は〈はじめての小説〉で次のように証言する。「九年間いた『婦人公論』から『中央公論』に移ったとき、〝マスオとタエコに小説を書くようにすすめよう、必ずうまくゆく〟という確信のようなものがあった。〔……〕ともかくまず、富岡多恵子の作品は出来上り、『中央公論』に発表したのは昭和四十六年六月だった。彼女が渾身の力をふりしぼった作品であるはずだ。/池田満寿夫の作品が出来上るまでには、それから数年を要した。昭和五十年七月、侍望の手紙が来た/「ごぶさたしました。お元気ですか。いろいろそのごのこと聞きたいこと山ほどありますけど、今日は約束の小説の件にしぼります。数日前やっと第一行を書きはじめ現在十枚ぐらいまで進んでいます。それでこの分だとなんとかものになりそうな気になって来ました。……」/数年がかりで完成したこの作品は「ミルク色のオレンジ」として昭和五十一年二月の『中央公論』に発表した。彼の本格的小説の第一作である。数回書き直した苦心の作だった」(#B_013、三八九~三九〇ページ)。池田満寿夫の処女小説〈ミルク色のオレンジ〉(《エーゲ海に捧ぐ》所収)はこう始められる。
あの日、夕陽が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来た。
こんな風に物語の第一行を書き出したのは五年も前のことだったが、それから後が続かず、その一行だけを記したまま私は忘れてしまっていた。
〔二行アキ〕
あの日、すなわち五年前の八月のある土曜日、私はハドソン・リバーをフリーウェイ越しに見下す八階の安ホテルの部屋にいたはずである。〔……〕(#B_011、五九ページ)
この二行め、三行めは小説の語りのレベルからは浮きあがっている。仮に小説執筆の一九七五年九月を現在とすれば「物語の第一行を書き出した」「五年も前」とは一九七○年となる。ちなみに池田はこの一九七○年に三十六歳で、ニューヨークを中心に旺盛な制作活動を展開している。また池田が〈夏から秋まで〉を読んだ《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》は一九六八年に出ている。小説の冒頭の一行(鍵谷幸信は書評で「もはや散文のアクシデントではなく、ポエジーの屹立した一行のように美しい」とさえ書いている)だけが原稿用紙に記され、五年間ニューヨークのアトリエに放置されている図を想像することはなかなかチャーミングだが、まずは初出で同じ箇所を見ることにしよう。
あの日、夕日が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来た。
たしかそれは五年前の八月のある土曜日の午後だった。あの時私はハドソンリバーを真下に見下す八階の安ホテルの部屋にいたはずである。(#C_021、二二三ページ)
冒頭部分の大きな改変は、やはり二行の加筆とそれに続く二行アキの挿入である。そのために出来事の完結性はいっそう高められた構成にはなった。しかしそれは同時に語りを醒めた状態に置きなおすことでもあった。脱稿後の大きなオペレーションはほかにもあって、行アキ指示と同様の狙いであるアステリスクとアステリズムの挿入がそれだ。ディテールを補強するための細かなあるいはかなりの加筆訂正は処処に見られる(「〔雑誌発表時に〕誌面の都合で四百字十数枚分をカットした。本書に収録するにあたり、それをほぼ原型にもどした」と単行本後記(#B_011、二〇一ページ)にある)。しかし私の見るところ、最も重要な加筆はギヨーム・アポリネールの艶詩《秘めごと歌》の〈第一〉(あんたの肉体の九つの戸口)の最終節からの引用である。遠方にある婚約者マドレーヌ・パジェス嬢に宛ててアポリネールは「肉体の九つの戸口」をひとつずつ挙げてゆく。右の目、左の目、右の耳、左の耳、左の鼻腔、右の鼻腔、口、第八の戸口、そして第九の戸口すなわち肛門がくる。「コクトオははやくもブルジョア的な産物として色あせていて、アポリネールや、シュペルべールの新潮文庫版が愛読書の一つになっていた」(#B_015、一六八ページ)と〈現代詩人との交流――戦後詩への愛着〉に書いた池田は、〈ミルク色のオレンジ〉の女主人公ナオミにアポリネールの英訳詩集を読ませているが、アポリネールの艶詩に欲情する一六歳の少女など、果たして現実に存在するだろうか。リアリティはきわめて稀薄である。長いが、アポリネール詩の登場に至る、小説中もっとも美しい部分を引く。池田の文章の至芸である。
ナオミは私にはとうてい理解し難い弁明をこのように早口で言い終ると、はきかけたばかりの網タイツを足元までずり下げて屈み込んだのだった。そして心持ち開かれた太腿の内側から、素早い動作でなにかを取り出して来た。薄明りのなかで私の目の前に差し出されたものは、ミルク色に濡れた、まだ青味のあるゴルフ・ボールほどのオレンジだった。私は自分の心臓がナオミの指の先で躍っているような驚きを、その青いオレンジの上に見たのだった。次の瞬間、ナオミの柔かいしなやかな指が、それを再び彼女の膣の中に仕まい込んだに違いない。その青いオレンジはもう目に見える空間のなかには見えなかったのだから。ものも言えないくらい驚愕している私に向って、今度はナオミの謎の微笑が返って来た。
アシタニナレバ、コノオレンジガ黄色ニ変ルノ。ソウシタラ、天使ガモーター・サイクルニ乗ッテ、取り出シニ来テクレルワ。ソウシタラ、今度ハアナタノ番ヨ。アナタガ青イオレンジニナルノヨ!
あの好色なギョーム・アポリネールだって、こんなうまい話のポルノグラフィは作れなかったであろう。たとえあれが作り話であろうと、本当の話であろうと、少女の作り出したメッキ製のストーリーにしては、うまくオレも騙されたものだ、と二十三丁目の地下鉄でナオミにキッスして別れてから、私は考え続けていた。
あのストーリーの続きとして、まずモーター・サイクルに乗った天使とやらが見たいものだ。ナオミの天使なら皮のジャンバーを素肌の上に着ていなくちゃならないだろう。割れ目にめり込むほど皮のパンツがぴったり密着しているだろう。どうせ明日、土曜に会ったら、もうその天使ちゃんは雲の上かディスコティクに帰ってしまった後だと言うにきまっているさ。畜生め、ブロンクス野郎のゴルフ玉の代りにオレの玉が彼女の出口をふさいでやるなんて、十六歳の娘の話にしちゃあ出来すぎている。しかしナオミが青いオレンジとやらを、どうやって挿入したか、そいつが問題だ。真剣だが、みだらな顔をして、白いタイルのバスルームの、これも白い陶器で出来た便器の上にしゃがみ込んで、その未成熟な果実を挿入しているナオミの姿が浮んだ。ハッカ入りのチューインガムを噛みながら、彼女のアゲハチョウのなかにミルク漬の砂糖菓子が一緒に吸収されていく。十六歳にしては成熟しすぎた臀を丸出しにして、アゲハチョウが大口を開けてあえぎながら、砂糖液でべたつき、小さな人差指と中指がそれを押し開き、もう一方の人差指と中指が餌をやるように、青いオレンジを押し込む。それはギヨームと鳴る。誰もいない午後。冷房のきいたバスルームで、ナオミは両方の瞳を、前に見た時のように真ん中に寄せて、いっぱいに開いた太腿にのめり込みそうにまつげを接近させて、アゲハチョウがピンク色の外腔を開けて、ミルク漬の青いオレンジをぱくついている有様を、ハッカ入りのチューインガムを噛みながら、もう少しで自分の舌を噛みそうになって、眺めているんだ。誰もいない午後。それは小娘にとっては最も危険な時刻だ。何故なら彼女はお臀を丸だしにしたまま中庭に面したテラスに出てくることだって出来るからだ。彼女のお気に入りのカミュとアポリネールとドストエフスキーとプラトンの英訳本を書棚からひっぱり出して来て、テラスの鉄製の椅子に熱くなったお臀を乗せて、オレンジ・ジュースを飲みながら、さてなにから最初に読もうかしら? ってちょっときざっぽく、垣根越しに見える生まれたばかりの赤子のオチンチンを眺めながらつぶやくんだ。アポリネールかしら。日も暮れよ鐘も鳴れ、月日は流れ、わたしは残る。畜生、何故英訳本なんだ。わたしの残っている午後。いっそのことお臀の第九番目の穴にストローをつっこんで、オレンジ・ジュースを飲むがいい。(#B_011、九一~九四ページ)
続くアポリネールの艶詩は元になっている堀口大學訳の文庫版から引く。
二つの真珠の山の間に口をあく
より神秘な第九の戸口 おん身よ
他のどの戸口以上に神秘なおん身よ
語るさえはばかられる妖術の戸口よ
至上の戸口よ
おん身もまた
僕のもの(#B_004)
池田の小説では、全体が追いこみ表記になっており、膣にしまったオレンジの果実が肛門でジュースになる、高いテンションを示すコラージュと化した詩の引用である。
相澤啓三が〈時代の子〉で「「ミルク色のオレンジ」も十六歳の少女が性器の中に押しこんでいるゴルフボール大の青いオレンジのことだと説明されると、ニューヨークあたりでそんな未熟なオレンジを手に入れるのは大変で、なぜちょうどゴルフボール大で緑色のライムではいけないのか気になるし、ミルク色の体液ではこの少女は病気なのかしらと、ともかくいろいろなところでいろいろなことが気になったのである」(#B_013、三六九ページ)と書くとき、童話の道具立てがなぜかくも非現実的なのだといいがかりをつけているようで、なんとなくおかしくなってくる。目に見えるレベルで考えれば「ミルク色の▼オレンジ」とはそもそも形容矛盾でしかないし、仮にミルク色のライムとでもしてみたらその語と色彩によるイメージの衝突の鮮烈さは明らかに濁る。この作への非難はもっと別のところでなされなければならない。すなわちエロティクな童話として成功しているかどうかという点において。
小川国夫は〈[人身御供]としての男性〉でこう書く。「ところで、女性器は〈海〉であるというだけではない。ニューヨークの暗がりを飛ぶ〈あげは蝶〉でもある。男はそれを追いかけ、首尾を達するであろうか。彼は三十五歳、彼女は十二歳〔ママ〕。当然男が犯し、女が犯される関係なのだが、池田の見るところによると、その関係は逆になるらしい。男は犯され、女は犯す。要するにこのセックス・ゲームは女の勝ちといわざるを得ない。したがって、人身御供としての男性は、ここでもその姿を明らかにする。そして、悲劇よりも喜劇が好きな作者は、いわゆる倫理道徳を突き抜けた笑いを、いかにこのシテュエーションに響かせるか」(#B_013、三二七ページ)。
この「いわゆる倫理道徳を突き抜けた笑い」こそ池田が吉岡実のうちに見出した「彼の本質」(〈繁殖する感覚の細胞〉)と同じものではないだろうか。その事実の前では池田満寿夫の版画の題名と吉岡実の〈夏から秋まで〉と池田の〈ミルク色のオレンジ〉との間の類似性やら貸借関係はさして重要なことではあるまい。小説の終幕は冒頭のリフレインだ。
〔……〕誘蛾燈に寄って来た蝶は、燈が消えたら闇の中に消えるだけではないか。
ナオミは裸の全身をさらけ出し、あおむけになったまま眠っていた。無防備に投げ出された腿と脚。その付根に自信ありげに羽を広げきったアゲハチョウ。気のせいかオレンジ・ジュースが光沢をおびた昆虫の割目から少しずつ流れ出ていた。赤く染った光の線がその素晴しい渓谷の眺めを直射している。こうした光景はムンクが描きそうだなと私は思った。
ナオミは眠ったまま動きそうになかったので私は再び立ちあがり、今度は鎧戸をいっぱいに開放した。
その時、巨大な夕陽が私の顳顬〔かみ〕のなかに入って来たのだった。(#B_011、一一五~一一六ページ)
〈ミルク色のオレンジ〉はこのあと数行で終わる。他者のことばに自分のことば以上のリアリティを見出すことは文学の功徳にほかならないし、〈夏から秋まで〉における吉岡のように、他人のペンの下から生まれた作品が自分の作品だと主張することさえありうるだろう。かくして吉岡実と池田満寿夫の関係は次のようになる。
①その方法意識において 自作の画題が一篇の詩に織りこまれたのを見たとき、池田はそこに吉岡の本質を見、それはコラージュ作家でもある小説家・池田が描かなければならない世界となった。
②その登場人物において レインちゃんは童謡から生まれた。それがナオミに影を落としているのは見やすい構図だ。ただし、二度めはパロディとして? たとえば、やたらにオシッコを漏らしてしまう女(の子)の話。池田はこうしたキャラクターを〈テーブルの下の婚礼〉でも、《マンハッタン・ラプソディ》(角川書店、1982)でも《楽園のこちら側》(中央公論社、1984)でも繰りかえし描いている。
③そのテーマにおいて 性的な心象を芯棒としてそこにあらゆる人物や事件を巻きつけてゆく姿勢はふたりの作風を最もよく特徴づけている。池田のモチーフが吉岡の詩篇で増幅され、その結果、本人が改めて自己の世界に直面するという事態が出来したのだ。
《エーゲ海に捧ぐ》の評者のなかには、その文学的才能を認めつつ、あまりに色情的ではないかと嘆いた者がいた。池田満寿夫の小説はその後の《女のいる情景》(日本経済新聞社、1988)に至るまで、ほとんど変わっていない。――池田はこの長篇にあたかも六○年代の象徴であるかのように土方巽を、その名を隠しつつ登場させている。「何故か、舞踏とは舞台で必死になって立っている死体である、と言った前衛芸術家の言葉を思い出した。個人的には知らなかったが、東京で一度だけ彼の舞台を見たことがあった」(#B_016、二八六ページ)。さて、吉岡実は小説集《エーゲ海に捧ぐ》では〈テーブルの下の婚礼〉を好んでいたように記憶するが、どこで読んだのかいくら捜しても出てこない。そういえば〈テーブルの下の婚礼〉は池田満寿夫の《僧侶》のような気がする。
ここで最初にご登場ねがった土方巽と澁澤龍彦の両氏にも集まってもらって、池田満寿夫と吉岡実の作品をめぐるエッセイを締めくくることにしよう。一九七七年、池田満寿夫が〈エ-ゲ海に捧ぐ〉で芥川賞を受けた夏である。小畑祐三郎は〈MASUO IKEDA A HOT & SHORT SUMMER〉で書いている。
●八月一三日(土)
二子王川の岡崎家で、旧友や親しい仲間のパーティ。澁澤龍彦、吉岡実、加藤郁乎、鍵谷幸信、土方巽、吉田ルイ子各氏他、二十数名。夕方から深更に及ぶ。念願のナツメロ、大いに歌う。(#B_013、三九三ページ)
…………………………………………………………………………………………………………
●吉岡実について
●土方巽について
●池田満寿夫について
●澁澤龍彦について
吉岡実・土方巽・池田満寿夫の文章は、刊行時点でそれぞれの全エッセイ集と見ることのできる吉岡実《「死児」という絵〔増補版〕》(筑摩書房、1988)、土方巽《美貌の青空》(筑摩書房、1987)、池田満寿夫《思考する魚》(番町書房、1974)に依り主なものを挙げ、適宜ほかの詩集や単行本未収録の文章も補ったが、網羅的ではない。なお、土方の《美貌の青空》の命名は吉岡による。土方には吉岡の詩集から題を採った公演《静かな家》(1973)がある。池田には土方に与えた版画集《誕生》(1964)や澁澤の肖像(1964)などがあり、吉岡実英訳詩抄《Lilac Garden》(1976)の挿画がある。
●1956年
4月 告白(④・2、《新詩集》〔蜂の会〕4月〔3号〕)
5月 喜劇(④・1、《詩学》〔詩学社〕5月号〔11巻6号〕)
7月 陰謀(未刊詩篇・6、《現代詩》〔緑書房〕7月号〔3巻6号〕)
11月 島(④・3、《新詩集》〔蜂の会〕11月〔4号〕)
12月 仕事(④・4、《今日》〔書肆ユリイカ〕12月〔6号〕)
●1957年
3月 牧歌(④・7、《今日》〔書肆ユリイカ〕3月〔7号〕)
4月 僧侶(④・8、《ユリイカ》〔書肆ユリイカ〕4月号〔2巻4号〕)
5月 ポール・クレーの食卓(⑩・1、《現代詩》〔緑書房〕5月号〔4巻4号〕)
6月 単純(④・9、《今日》〔書肆ユリイカ〕6月〔8号〕)
10月 夏(④・10、《季節》〔二元社〕10月〔11月号・7号〕)
10月 固形(④・11、《現代詩》〔書肆パトリア〕10月号)
●1958年
5月 回復(④・12、《詩学》〔詩学社〕5月号〔13巻6号〕)
6月 苦力(④・13、《現代詩》〔書肆パトリア〕6月号〔5巻6号〕)
7月 聖家族(④・14、《季節》〔二元社〕7月号〔11号〕)
7月 喪服(④・15、《今日》〔書肆ユリイカ〕7月〔9号〕)
7月 死児(④・19、《ユリイカ》〔書肆ユリイカ〕7月号〔3巻7号〕)
11月 伝説(④・5、(詩集《僧侶》書肆ユリイカ、1958年11月20日)
11月 冬の絵(④・6、同前)
11月 美しい旅(④・16、同前)
11月 人質(④・17、同前)
11月 感傷(④・18、同前)
12月 ライラック・ガーデン(⑩・3、《今日》〔書肆ユリイカ〕12月〔10号〕)
●1956
1 洞くつの歌
●1957
2 古代/3 陽気な女たち/4 小さな喜び/5 太陽と女/6 コンポジション/7 荒野の花嫁/8 花嫁/9 さまよう顔
●1960
10 女/11 ビートガール/12 女・動物たち/13 女の肖像/14 女/15 子供/16 色の中の婦人
●1961
17 瞳の中の星/18 退屈な朝/19 月の祭/20 矩形/21 小さな小さな空間/22 女・その他/23 大きな女/24 女王/25 踊子・あるいは蛾/26 正面の赤/27 天使のいのり/28 室内の女/29 神の顔/30 鳥/31 女と風/32 女(1)/33 女(2)/34 女と鳥/35 女(4)/36 ふるえる女/37 坐せる少女/38 二人の女/39 歩む女たち/40 横たわる人と見つめる人/41 草の中
●1962
42 女・五月/43 水曜日の犬の散歩/44 金曜日は雨/45 急ぐ人/46 涙のように/47 草でつくった人形/48 森の祭/49 動物の婚礼/50 花嫁の領地/51 庭を横切る昆虫/52 夢の鳥/53 メタフィジックな風景/54 赤いセーターの女/55 アダムとイブ/56 S字型のヘビ/57 歌姫/58 歩む女たち/59 出来事
●1963
60 戸口へ急ぐ貴婦人たち/61 小さな沼たち/62 ぼくのものお前のもの/63 窓辺のイヴ/64 大きな沼・その他の沼/65 天使の扉/66 生徒の名はイヴ/67 恋人がくる/68 タエコの朝食/69 天使の靴/70 私のユーウツな日/71 飾窓の中/72 自転車に乗った貴婦人たち/73 サイズはサイズ/74 おどろき/75 出を待つ天使
●1964
76 レインちゃん/77 私をみつめる私/78 画家とモデル/79 東京オリンピック/80 それは何ですか/81 氷菓子を食べてはいけない/82 化粧する女/83 星をとる女たち/84 鏡の前の婦人/85 私は何も食べたくない/86 受胎告知/87 素敵なソプラノ/88 花嫁/89 夏(1)/90 夏(2)/91 机の下/92 ボーリングする婦人たち/93 天使シリーズ・子供の天使/94 天使シリーズ・机の天使/95 天使シリーズ・みつめる天使/96 天使シリーズ・天使不在/97 天使シリーズ・ミシンのような翼
●1965
98 黄色い顔/99 恋人たち/100 聖なる手(Ⅰ)/101 聖なる手(Ⅱ)/102 青い衣裳/103 海のスカート/104 私の詩人・私の猫/105 ロマンチックな風景/106 花園にて/107 みつめる天使/108 水/109 楽園に死す/110 鏡の中の青/111 姉妹/112 四つの手/113 虹をのむ女/114 天使のいる風景/115 動物の時間・ママの記憶/116 動物の時間・青い手/117 動物の時間・動物の食事の時間
●1966
118 夏の夢/119 Something 1/120 Spring and Springs/121 遥かなる女
以上一二一点の版画のリストは《ベネチア・ビエンナーレグラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展》(〔刊記なし〕)所収〈出品目録〉に見える番号と題名である(赤字は吉岡実詩篇のスルスとみなされる題名)。後年の《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社、1977年11月3日)所収〈全版画作品[1956‐1977]〉と異なる題名も散見するが、原文のママとした。詩篇の執筆時期(1967年上半期)に照らすと、吉岡がこのほかに《池田満寿夫版画集》(美術出版社、1967年6月1日)所収〈作品図録〉の題名を参照した可能性も捨てきれない。
わたしは詩を書く場合、テーマやその構成・構造をあらかじめ考えない。白紙状態がわたしにとって、最も詩を書くによい場なのだ。――吉岡実(#A_25、八七ページ)
詩篇〈立体〉(⑦・3)の初出は、一九六七年一○月号の《現代詩手帖》特集〈吉岡実の世界〉で、その号には〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)も再録されている。詩集において初出から変更されたのは次の二箇所。
囲り→まわり(三四行め)
書棚→書物(四○行め)
今いちばん容易に入手できる本文である《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(#A_10)では、まだ「囲り」となっており、「めぐり」と読まれるのを嫌った変更だと思われる。詩集《神秘的な時代の詩》(書肆山田、1976)の本文を定稿とみなし、行頭の数字は何行めかを示す。
〔標題〕 立体
〈立体〉という題名はなにを意味しているのか。当然それは絵画に対する彫刻という造形作品で、この語は吉岡実の詩ではほとんど使われたことがなかった。「たがいのたてがみも尾も回転する毛の立体にまで高まって」(〈冬の休暇〉⑤・12)を数えるだけで、その後も「立体的な物は越えられる しかし平面は走れない」(〈『アリス』狩り〉⑧・12)がやや近いくらいだ。高橋睦郎のように「この題名にもそれほど深い意味はない。シュルレアリスムの画家、たとえばルネ・マグリットの画集をめくって、その印象をきわめて自由に書いた詩と思えばいいだろう」(#A_23、五七ページ)と考えるのが普通だが、ここはぜひとも、詩人であり絵筆も執った西脇順三郎の詩論を引きたい。「彫刻。これはあまり詩の方ではよい一般の例がないが。僕の只今の如きところである。僕は彫刻や彫刻の写真をみて、その感じを詩で書きたいと思ふ。しかし絵画の方ではピカソの如きは彫刻的なものの例である。ロダンの彫刻は音楽的であつて、さすがサンボリスト時代のものだと思ふ」(#B_113、五五ページ)。
この文章は一九三四年九月発表で「ピカソの如き」がどの作品を指すのか決めがたいが、そうした個個のことよりも、またいままで再三引用してきた吉岡の〈わたしの作詩法?〉と似ていることよりも、今はその前の「絵画」の項が重要なのだ。「絵画。これも以上と同様な〔絵画で表されてる感覚とsentimentを詩で表現しようする〕ものである。ゴチエなどの如く、ルコント・ド・リイルの如く。imagismやスユルレアリスムなどは絵画的である。今日の詩が眼を尊ぶことはゴルもいつてゐる。これはサンボリストの音楽的なアナロジイに反動したものであつたか」(同前)。
シュルレアリスムが絵画的なのは断るまでもないと考えるところから、逆に吉岡の詩がシュルレアリスムの絵画のように見える理由が導けないか。吉岡実の詩が絵画を、ピカソのような彫刻的なそれを志向しているからだと言えば、人は先刻それは承知だと答えるだろう。「だからわたしたちはピカソの女の顔のように、あらゆるものを同時に見る複眼をもつことが必要だ」(#A_25、八九~九○ページ)という作詩法の言葉が、観る者である私たちと同時に画布の女自身が複眼を持つかのように響くとき、これはシュルレアリスムであろうか。いっそのこと藪睨みと名づけたくなる。
作者の捉えた外部は文章の線的な流れに位置づけられ、外部の刺戟による想像力の発動も同じ流れに、先程とは違った要素として位置づけられる。作者の捉えた内部が同様にしてあり、内的な想像力が同様にしてある。すべてを表現しなければならないと考える作者は、ひとつひとつ片づけてゆくことを欲しない。自身の全的状態と等しい短絡が要求され、そこにリアリティが存在すると考えられる。縦糸と横糸だけの布は頼りないのだ。予想外の角度からの言葉が曲がりくねって織りあげる生地。リアリティを追う詩人の視線は藪睨みにならざるを得ない。
「文章による彫刻や絵画」に詩人が伎癢を感じたのだろうか。ジャックスン・ポロックの〈青い柱〉は空間的になり、池田満寿夫の版画は時間的になり、この時期の吉岡はかつてないほど絵をモチーフ、というよりも詩句が迸る切っ掛けとして多用している。それは吉岡が作品における時間処理に長けてきたのと関係があるだろう。相当な無理をしても布地を織ることのできる靱い視線、藪睨み。それが《神秘的な時代の詩》を特徴づけている。
高橋睦郎は〈鑑賞〉の続きでこう述べている。「なお、この作品に三度出てくる「彼らは紳士だから」という定まった行と、「フロックコートの正装で」→「フロックコートのズボンをぬいで」→「フロックコートの正装のまま」と動く行がイメジの氾濫に歯止めをかけ、一種の統一感を与えている。このフロックコートの紳士をシュルレアリストの画家、あるいは画家に仮託した作者の自画像ととることもできよう。そのとき、彼らは一人から増殖した複数の画家、あるいは複数の作者ということになる」(#A_23、五七~五八ページ)。
最初から詩の主題や方法があるわけではない。詩論がなくても、絵から吸収したり、映画や芝居を観たり、現代の時代からも詩は成立する(#C_005、五二~五三ページ)と入沢康夫に語り、詩を書く場合、最良の一カ月のうち二〇日間は心の一点にとめて遊ぶ、あとの四、五日が半狂いの陣痛期だから、締切の一〇日ほど前から雑誌や本の気を惹くものを読み、原稿用紙に向かってわりあい一気に書く(#A_18、一一六ページ)と大岡信に語るように、吉岡の気を惹いた絵がマグリットだったことは充分ありえる(池田満寿夫がマグリットふうの青空を描いたり、マグリット論を書いたりしたのもこのころだ)。今回の評釈では吉岡実の詩と絵画の関係を考察し、詩篇の特質を明らかにしたい。
01 真夏の午後でも
注射器の午前九時十二分
露台の女の透明な胸奥に
麦藁蜻蛉の眼球の砕粉がちる
虹の輪を廻して鼻毛のふちを
鮑貝かぶつた懶惰な狩猟者達がゆく
氷菓子の断面に太陽が溶け
鶏が甃の上の黄色い精虫をついばむ(〈夏〉①・2全篇)夕光る鏡の上のチョコレートのうすき歯のあと夏はきたりぬ(《魚藍》)
と書いて出発した吉岡は「深い虚脱の夏の正午」(〈卵〉③・7)を経て、「真夏の反現場性の海の輝く」(〈崑崙〉⑦・8)や「夏の午後は入浴す」(〈白狐〉未刊詩篇・15)などの詩句を生む。〈夏から秋まで〉(⑦・2)に続いて夏である。私は〈夏から秋まで〉の次に〈立体〉が書かれたと考えるが、そこにどんな進展が見られるか。〈立体〉掲載誌の編集人であり《「死児」という絵》の担当者・八木忠栄によれば、脱稿は原稿受取予定の八月二六日の直前で――マグリットは八月一五日にブリュッセルの自宅で急死――、〈立体〉掲載誌併載の入沢康夫との対談は八月二三日夕方、新宿で行なわれた。その席で吉岡の言う「今度出る全詩集のあと二篇書いている」(#C_005、五三ページ)は〈青い柱はどこにあるか?〉と〈夏から秋まで〉に違いないだろう。〈夏から秋まで〉は詞書が示すように、池田満寿夫の版画の題名を随所に折りこんだ池田満寿夫讃だった。池田の画面が吉岡の詩句と化すのではなく、画題は詩句と等価に溶けこむのだ。〈立体〉、それは詩句がつくりあげた薄塗りの画布である。池田が版画の題名という一行の詩を書いたように、吉岡は詩という幻想絵画を描く。
散文では、この二詩篇の間で〈日記抄――一九六七〉が、〈立体〉のあとで《瀧口修造の詩的実験》推薦文と〈わたしの作詩法?〉が発表された。〈立体〉の発表誌は二度めの吉岡実特集号だった。原理的というよりも内省的な自作をめぐる思索とシュルレアリスムへの再度の接近が、吉岡のそれまでの自己の体験の記憶から詩篇を生みだすという方法から、土方巽の舞踏や池田満寿夫の版画や幻想画家の視点をモチーフにするものに方向転換させたと断定するのは難しいにしても、〈わたしの作詩法?〉で自らに課してきた禁忌を列挙し、その後それをつぎつぎに侵してゆくことの意味は大きい。詩法以前に語法が変わる。行は短くなり、行数は殖え、記号や符号が多くなる。散文詩型がなくなり、区分のための序数も消える。かつての凝縮された像の形成を担っていた言葉が、あたかもそれより先を追求することが不毛ででもあるかのように拡散しはじめる。吉岡実という固有名詞よりも時代共通の雰囲気が優先し、あるいは芸術と風俗の織りなす裏返しの詩人の密室が出現するのだ。
02 彼らは紳士だから
リフレインの一回めだが、この時点ではむろん「定まった行」(高橋睦郎)だとはわからない。一行めがイツイカナルトキデモと等しいものに変化して、あたかも夏、紳士でいるのが困難なように映る。「彼ら」もほとんど変数の扱いで、「紳士」であると規定されているものの、次の行ではシュルレアリスムの画家になるのかサーカスの芸人になるのかさえ定かではない。「でも」「だから」が詩句の推進力だ。
03 室内を歩き廻らないだろう?
入沢康夫が「『神秘的な時代の詩』では十九篇中十八篇までに、しかも一篇中にいくつもばらまかれてゐるケースを含めて、頻出する」(#A_18、一二九ページ)と指摘した「疑問符・感嘆符」の登場だ。この行を朗読するとき、行末を上げて疑問文であることを示すべきだが、どうも落ちつきが悪い。「でも」→「だから」→「だろう?」と鍵になる句がダ行で始まるのは偶然だとしても、なぜ平叙文ではいけないのか。話者の読み手への同意ととる以外ない。読者は冒頭から観客として立ちあわされることになる。作者は舞台の構造を詩に持ちこむためにここで疑問符や感嘆符を多用しているようだ。
04 フロックコートの正装で
このフロックコートは舞台衣装である。フロックコートと言われてもいまひとつわからないので、辞書を引くと「男子の礼服の一つ。黒ラシャで、上着はダブルで、たけはひざまである。ズボンはしま物」とある。説明の図版とマグリットの〈良いお手本〉(1953)は驚くほど似ているが、ズボンの縞までは判別できない。遠くアパルトマンの屋根あたりに雨滴のように浮かぶ数多くの紳士たちを描いた〈ゴルコンダ〉(1953)は、一九七○年ころロックのLPジャケットで使われた。「わが父は燕尾服のまま横たわる」(〈メデアム・夢見る家族〉⑧・21)
05 立っている
彼らは浮かんでいるのでも、降っているのでもない。三行めを受ける。
06 次のドアをひらいたら
「隣のドア」でないところから、今までひとつひとつのドアを開けてきたうえでの一連の動作であり、したがって今回の行為も特別なものではない、と読める。マグリットの〈意外な返事〉(1933)のドアは、どのような惨劇も見せずにドアであることをやめている。「ガラス戸の向うに/海鼠が存在する」(〈雷雨の姿を見よ〉⑨・14)
07 ネズミの死骸が少しずつなだれこむ
未刊詩篇〈白狐〉は《神秘的な時代の詩》から《サフラン摘み》にかけての時期に書かれた。初出の註記を読もう。「*「現代詩手帖」二十五周年記念号に是非とも作品を寄せよ、との小田久郎氏の要請をこばみがたく、十余年前の自動記述的な草稿に、若干の手を加え、『薬玉』の詩篇と同じ形態をととのえ、ここに発表する。/〔一九八四年〕五月九日」(#C_012、三二ページ)。「十余年前」は一九七○年代初めを指すだろう。このころ吉岡は「暗中模索」(#A_25、二八〇ページ)時代の「試行錯誤」(同前、三三二ページ)を切りあげて、新しい境地を求めていた。ここでは《神秘的な時代の詩》と同じ形態に戻して引用しよう。
白狐いなりの屋根を降りる
われらは無を漂ってはいない
血のかわりに言葉を発する
金屑がとぶ
バンソウコウをすべての
抽象物に貼る
何の目的で人は生きるか
バラ色の水にうかぶネズミの死骸へ問え
喩の叙述を替える
ザクロの外側では
老人から子供までの笑い声
蚊帳を吊った川の洲へ
われらは渡る
穀物を刈るために
もしくは
領巾ふす蛇の魂をしずめに
燈火をかかげた
頭上へ絵画の枠をつくる
鋸に挽かれる十本の杉
死ぬ時に書く十行の詩
足をそろえて冷たい母
白狐
それは呼ばれた
ムシロのざらざらした世界へ
思った思おうとした
あまさかさまの日々
将棋盤の上で
美しい相のやまとは昏れよ
のどかに
蜂をリンネルで
包む学者を見たことがある
われら人生派は今も
自然を通して
意味をつくる
商人は好きな葛湯をすすり
夏の午後は入浴す
見えるさわれる
開かれる事物はどこへ
こんかい
コン・クワイ
われらの奏でる嬉遊曲
姉妹を水門の上に立たせる
「あまさかさま」は天逆様で、理非の逆さまなこと。《神秘的な時代の詩》の「喩の叙述を替える」と《薬玉》にそのまま連続するかもしれないということ。〈白狐〉は《ムーンドロップ》期の拾遺詩篇に相当するが、確かにここには《神秘的な時代の詩》の「自動記述的」な部分と《薬玉》《ムーンドロップ》の「神話」や「民間伝承」と《金枝篇》的イメージの混淆(#A_25、三○五ページ)が見られ、全体の印象は必ずしも鮮明とは言えない。だが、最後の二行などさすがに見事なものであり「のどかに/蜂をリンネルで/包む学者を見たことがある」も《ムーンドロップ》を思わせる。
08 にちがいない今日の在り方
吉岡はきょうを「今日」と書くが、ここはこんにちだろう。前行とこの行ほどのはげしい句跨がりはかつてなかったような気がする。それに匹敵する例を求めるならば、〈自転車の上の猫〉(⑧・15)に如くはない。「旧式な一台の自転車/その拷問具のような乗物の上で/大股をひらく猫がいる/としたら/それはあらゆる少年が眠る前にもつ想像力の世界だ」
09 別のドアを出て行く
六行めを受ける。視点の主が入ってきたドアをAとすると正面にCがあり、これが「次のドア」だ。Cは状況を規定するためにだけ登場し、実際に開かれることはない。左右のどちらかの「別のドア」つまりBを出てゆくことになる。残るDはドアではなく、後出の出窓だろう。私たちは〈立体〉の舞台をマグリットの描くヨーロッパの個人邸の室内だとしてきたが、高度成長期の日本の結婚式の披露宴会場だと考えれば、シュルレアリスム絵画から、初出時の併載詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉の泥絵の世界に一変する。彼らはフロックコートを着ることでかろうじて意識下の欲望を抑えこんでいる、僧服が無意識を鎧う衣服であるように――と書くと〈僧侶〉(④・8)の変奏として捉える視点が出すぎるが、現代の僧侶はもしかすると彼らだ。
10 ふとった蝶
鳥や魚が吉岡偏愛の生物であるように、蝶もまた夥しく舞っている。華麗に生まれかわった人? 「貴婦人の蝶マスクせる尻の上で」(〈悪趣味な冬の旅〉⑧・6)ならそうかもしれないが、「ふとった蝶」とは蛾のことではないか。あるいは次の行を形容する同格の名詞。〈恋する絵〉の続く行「ひろがると同時につぼまる網」を見るまでもなく、蝶と網の組み合わせは極めて自然だ。
11 ひげのはえた紳士が
「須」ひげ。あごひげ。「髯」ひげ。ほおひげ。ほおのひげ。「髭」ひげ。くちひげ。口の上のひげ。「鬚」ひげ。あごひげ。動物のくちひげ。ひげ状のもの。
「ふとった蝶」としての「ひげのはえた紳士」ではなく「……蝶/ひげ……」のつながりを重視すると、蝶からの連想でここのひげは鬚となる。ところで紳士たちはいったい何人いるのだろう。「四人の僧侶/〔……〕/手のながい一人がフォークを配る」(〈僧侶〉④・8)
12 蓄音機の把手をぐるぐる廻すんだ
〈立体〉発表と同じ年、近年になるまでひとりのときに鼻歌さえ歌ったことがないという吉行淳之介は書いた。「しかし、おどろくべきことに、幼稚園へ入る前の私は、なかなかの童謡の歌い手であったそうだ。自分には記憶にないが、当時病気で寝ていた母親を見舞に行き、つきそいの女性が私をチクオンキと見立てて、私の横腹あたりに手を当てて、ギリギリねじを巻く素振りなどしてみせると(当時は電蓄などは普及しておらず、手まきのゼンマイ蓄音器であった)、たちまち私が、/いまは山中いまは浜/いまは鉄橋(以下不明)/とか、/汽笛一声新橋を/はやわが汽車は(以下不明)/とか、大声で歌い出したというのであるから、おどろく。とても自分のこととはおもえない」(#B_163、八三~八四ページ)。
あれだけ自己の趣味を開陳した吉岡実に音楽をめぐる一篇の随想さえないところを見ると、歌が得意だとは考えにくい。人は隠れた才能を匿しおおせるものではないし、ある対談で自分は音痴だとも言っている。幼稚園児の吉行は他人の見立てを幸いに、蓄音器という自動人形に化した。ねじを巻くエネルギーから得た童謡歌手の地位は、自意識が芽生えて以降、急速に失われる。歌うということは声帯の制御というすぐれて精神的(美的・批評的)な身体行為であるがゆえに、あるひとびとにとって快感であるのと同等、あるいはそれ以上の苦痛を与える。ぜんまいをねじまく音こそ、羞恥という自意識の水位がしだいに下がってゆくバロメーターである。他者の前に自己の美的・批評的な意識の原形のごときものが現われる、その瞬間。
13 暑い夏を暑くするために
脳波の専門家・三輪和雄は、ロベール・デスノスの「オートマティズムは、われわれに一つの扉を開いただけだったのではないか」という自動記述法への疑問を引いたあとで、ポール・エリュアールの詩〈マックス・エルンスト〉に触れてこう書く。「ところがこの詩人の生原稿は、一気に書かれたと思われる詩に、多くの削除訂正が行われているそうである。自由連想や催眠状態から、湧き上るように出た詩を、あとから冷静な目で訂正するという事実は、自動的に記述された詩ではなく、それを土台にして新しく練り直したもの、とみなければならないというわけである」(#B_149、六二ページ)。三輪がエリュアールの作詩法に興味をもつように、大岡信も金井美恵子も吉岡実の作詩法に大いなる興味を示しているが(#A_18、一○二ページ以下、および#C_010、九八ページ以下)、エリュアールと吉岡は反対方向から来て出会ったようだ(少なくとも《紡錘形》のころまでの吉岡の詩を一気に書かれたと思う人はいないだろう)。もちろん吉岡は、初発の勢いの大切さを強調することも忘れないが。
これは「一気に書かれた」詩句なのか、「多くの削除訂正が行われ」た挙句なった詩句なのか。このなんでもなさを後から生みだすのは難しい気がする。最初からここに置かれたのでなければ、別の行から移動してきた。他作との比較のしようもないような詩句こそ、和歌における地歌のように他の行をくっきりと際立たせ、染めあげる独自の価値をもつ。その間の呼吸こそ、《静かな家》から吉岡実が身につけたいと願っていたものではないか。それはかなり成功しているように思われる。「生理が文体を飼いならした」という言い方が許されるならば、成功がそのときであるのは当然だった。
14 ギイギイ音をたてる
吉岡実をオノマトペに長けた詩人だとは誰も言うまいが、この無造作さには注目しなければならない。吉行淳之介は「ギリギリねじを巻く」と書いた。私は蓄音器のぜんまいの音は聞いたことがないが、柱時計から類推するにおそらくギリギリかギイギイ(せいぜいギチギチ)だろう。吉岡はここで萩原朔太郎のように新しいオノマトペの開発に勤しんでもよかった。しかし、音楽に色目を使うことはしない。擬声語であれ擬態語であれ、吉岡の詩の場合、音そのものの面白さ以上に映像すなわち観念の明確な姿が表れてくる。鋏の動き、ヴァイオリンの弓を持つ腕が見える。〈立体〉はこの滑稽で不気味な音を切っ掛けに別の展開に入ってゆく。
15 なお想起せよ!
吉岡はこの行で感嘆符を由緒正しく用いた。「命令文あるいは平叙文で意味を強めたり感情をこめるとき」と英和辞典は教える。後出の五二行めも同じ。二四行めも同じだ。では、この「なお」はなんだろう。
①やはりもとのとおり。それでもやっぱり。②やはり。どう見ても。③まだしも。むしろ。それでも。④ますます。さらに。などの副詞なら④。「それに加えて」の接続詞となれば、われわれは今まで知らないうちに想起していたのである。では、いつ、どこで。詩の中で、夢の中で?
16 破瓜・分娩音
《神秘的な時代の詩》の詩を「笑い茸」に喩えた篠田一士は〈立体〉の中心的な行として「なお想起せよ!/破瓜・分娩音」をくり返し引用している(#B_054、六~一二ページ)。初めての性交と出産とは、いかなる音色なのか。出血や破水のたてる音。体液という液体、子宮という紡錘形。
17 彼らは紳士だから
この行をリフレインと呼ぶべきか。韻文で、同じ句を繰り返しで用いること。また、その部分。特に、一節の終わりの繰り返し、から誰でも思いうかべるのは、たとえばアポリネールの「日も暮れよ 鐘も鳴れ/月日は流れ わたしは残る」(堀口大學訳〈ミラボー橋〉)あたりだ。全体がおぼろでも、印象に残る箇所だ。高橋睦郎は「定まった行」と言い、リフレインと呼ばなかった。ここでの効果は決めの文句どころではなく、この詩句を据えることで最初から出なおすといった気配さえある。
18 フロックコートのズボンをぬいで
フロックコートのズボンは縞物だが、この行と次の行の間の意味の飛躍も大きく、ズボンの縞模様が投網を呼びおこすなどとは仮にも言えない。論理的にはそう考えるものの、映像の力がそれ以外のものを私たちに与えないのも確かだ。
19 出窓の端から投網をくりかえすんだ
真面目くさっているがゆえに奇怪な二行。脱いだズボンで網打ちしているようでならない。水のなかの魚。女の姿はまだ見えないが。「水のながれは止る その全面の硬い量の上をすべる 女と魚 たえずまくれるスカートのなかの鱗で飾られた脚」(〈水のもりあがり〉⑤・13)
20 ずるずるひろがる
同じページに三つめのオノマトペである。頻出と言ってよい。ぐるぐる。ギイギイ。ずるずる。しまりなく物を引きずるさま、また、その音。それに違いないが、どこか遠くで「汁や液体を吸ったり、鼻汁をすする音を表わす語」の連想が働く。液体である体液。
21 暗い網の底から
投網の形状と漁法は「円錐形で、網の裾を折り返して袋状にし、そこに鉛の重りを付けたもの。上端部の手網をにぎって水面に広げて投げ、手網を徐々にたぐって、綱口を閉し、中にはいった魚を網地にからませて引きあげる」。
〈色彩の内部〉は〈立体〉の翌一九六八年発表だが、普通に考えるとこの詩句は「暗く円のようにひろがる網」という気がするが、そうでないところをみると「暗い網」なる像は作者にかなり親しかったのではあるまいか。暗や闇の字句は多くの詩篇に散見される。吉岡実の無意識などと一括りするのもはばかられるが、散文にほとんど見られないのは注目しておいてよい。
22 錯誤の未来性
〈僧侶〉第三節の一部が思いだされる。「他の二人は手を見せず/今日の猫と/未来の女にさわりながら/同時に両方のボデーを具えた/毛深い像を二人の手が造り上げる」
作者はのちに《神秘的な時代の詩》を「暗中模索」の時代の「試行錯誤」の作品と呼ぶ。詩集に対する自己評価の変遷は本評釈の終章で述べるが、総じて刊行当時よりは肯定的(というか、ああいう試みも必要だった、決して無駄ではなかったといった具合)に変わってきている。
23 両の乳房をつきだして
この乳房の所有者は(それにしても彼女、乳母や母は二つや両の乳房だけでなく、四つ八つとなんと多くを持っていることだろう!)、〈スワンベルグの歌〉にいちばん近いようだ。「緑の布の上に/両側から吊るされる/なよなよとした双曲線の乳房」。まさにストリップ・ティーズだ。それが肉の正面性、左右対象性をもって堂堂と迫ってくるとき〈立体〉の詩句が生まれた。
24 花嫁があらわれる!
花嫁は〈夏から秋まで〉の「レインちゃん」よりも成熟したようだ。水の、体液のイメージをまといつつ。そうは言っても同一人物として考えるべきではなく、ここはやはり別物と見なければならない。彼らがズボンを脱ぐやたちまちにして網にひっかかってきた「花嫁」は、「矢印」なんかよりずっと重要である。矢印が私たちを額縁の外へと連れだす方向指示器なら、花嫁こそ絵画の実質だからだ。作者のいちばん好きな「観念」だとすれば、私は詩の実体などと言いたくない。
25 十字の紅い割れ目
用例の多くは女陰を指す。この行もそう考えていい。だが「十字の」とはいったいなんだろう。女陰が十字形をしているとしたら、衝撃である。それとも処女膜の破れ方、帝王切開とかのメスの入れ方だろうか(なにせ「破瓜・分娩音」である)。それは乳房が、あるいは存在そのものが「錯誤の未来性」である花嫁自身には驚きでもなんでもない。筆は深入りすることなく、鮮やかに次の場面へと切りかえられるからだ。残像は宙吊りのまま、フロックコートの紳士が再登場する。
26 彼らは停ったままの腕で
「停」は動いているものが一時的に止まるの意で、トマル。把手をぐるぐる廻していたのがやんだのである。年代を無視することになるが、この行からは金子國義の〈ザリガニ〉(1976)という、同じ顔をした三人の男たちの肖像画が想いだされてしかたがない。
27 蓄音機のラッパを抱く
拡声器としての朝顔型の管がラッパ。発声器官の代替物を確保するなどと言えば大げさになるが、この機械、音楽を流すためのものではない。《ユリシーズ》のレオポルド・ブルームの内的独白に「そうだな、声なら、まあ。蓄音機。墓場かそれとも家庭に一台ずつ蓄音機を置いとく。日曜の夕食後。なくなった曽祖父さんをかけてごらん、クラーフラーク! もしもしもしたへうれしいクラークうれしいよまた会えてもしもしたへうれしコプススス。写真で顔を思い出すみたいに声を思い出させる」(#B_071、一四二ページ)。
チクオンキは蓄音器と書くのが正しいようだ。「この〈器と機〉の使いわけは、大正末期の手動式・旧吹込み時代まで使われていた〈器〉が、昭和初期(一九二七年ごろ)に電動式・電気吹込み時代に変わってから〈機〉となった、という説明が蓄音機史上の通説になっています」(#B_018、一四二ページ)とある。
28 真鍮の花
ラッパの形態から想起される植物は、百合ではなく朝顔だ。しかし花の形の奥深いのを言うとき、吉岡は鉄砲ユリを引きあいに出す。憑かれていると言ってもよいだろう、おそらくは女性性器にして男性性器のこの花に。後出の朝鮮アサガオも「花弁がもうちょっと/まくれ上がっていたら」(〈ルイス・キャロルを探す方法〉⑧・11)、鉄砲ユリに近づく。
29 相談する瞑想する
フロックコートの紳士たちは互いに相談し、あるいは瞑想する。吉岡はこのころまで詩句の形態に非常に潔癖で、この行も「相談する 瞑想する」と書きたいところだが、無用なアキは拒まれている。《魚藍》の短歌にも空白や句読点はなかった。《神秘的な時代の詩》収録作品は〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)がアステリスクで区分されているほかは、行アキも節を示す区分けの数字もない同一の形であり、次の《サフラン摘み》の多彩なスタイルと著しい対照をなす。
30 喋らずうごかず
前行に続いて対句である。ここで動作は止まり、二七行めの中止形に対する終止といった趣となる。動かないことと動くことを周期的にくり返していくうちに、現実の感覚の領域を押しひろげ、やがてそこから外れていってしまう予感。これを対句の最もあらたかな効果、構造としての対句と呼びたい。
31 意思が次の波を呼ぶだろうか?
六行めの「次のドアをひらいたら」で予想外の光景が提示されたように、この行を蝶番にして舞台は一変する。「波」はどこから来たのか。今の波がなにになるのか。花嫁を沖からもたらした波か。語にはより観念的な感覚が込められていよう。
32 伝達のない世界へ
「世界」は《神秘的な時代の詩》で多用されている語のひとつだ。《静物》や《僧侶》にはこれほど意味の負荷の少ない用例はないだろうし、この語が登場するかさえ疑わしい。高橋睦郎の言う「制詞」(#A_23、二三ページ)が存在するにしても、この時期以降いっそう緩やかになった。「伝達のない」が「喋らず動か」ない紳士を受けるのはもちろんだが、「相談」し「瞑想」していた彼らも一人一人てんでんばらばらに、たまたまそのときにそういうポーズをしていただけで、伝達すべきなにものも持っていなかったのかもしれない。「意思」は彼らの、というより作者のそれのような気がしてくる。伝えるべきもののないこと、それ自体を詩句としてしまうこと。今まで画面に登場していたイメージを一掃して、白のうえに最初の筆を降ろすこと。比喩的に言えば、作品は振りだしに戻ったのだ。
33 テーブルの上で
吉岡実はここから真に絵筆を揮いはじめる。横にならないと詩が書けなかったが今は自宅のテーブルに向かってでなければ書けないとどこかにあったが、かつて寝床で書いていたころに「卓」を多用し食卓で書くようになってから「テーブル」になったようなのも面白い。腕の動きが楽になったせいだろうか。どんな姿勢でペンを握るかは作風に影響を与えるだろう。「わたしはいま「迫悼詩」を叙述するんだ/水に向っている/テーブルの男のように」(〈田園〉⑧・14)
34 化石の鳥が化石のリンゴのまわりをとぶ
マグリットの開発したイメージは、今日いたるところで目にする。広告の世界はもちろん、パッケージもそうだ。さすがに広告には生な形は少ないが、レコード・ジャケットには彼の作品がいくつも使われている。ジェフ・ベック・グループの《ベック・オラ》(1969)の巨大な青リンゴは〈盗聴の部屋〉(1953)、鳩にして鷲のシルエットの青空が沖に浮かぶ〈大家族〉(1947)もどこかで見た。石の鳥が磯を飛ぶ〈偶像〉(1965)は〈大家族〉を踏まえたものだろう。
35 化石の鏡がやわらかい出来たてのパンを映す
映しだされる仮象の世界が重要だ。その世界は仮象であるがゆえに重要になる。鳥もリンゴも化石だった前行に較べて、パンがずれてゆく。〈立体〉にはシュルレアリスム絵画以上に無声映画を思わせる行があるが、ここも化石だったパンが因果律を無視してたった今できたばかりのように感じられる。読む側はまずパンは化石でなければならないと考えるのだ。読み手の感覚の慣性をずらしてゆくことで異界をかいま見せる、それがここでの吉岡実の方法、というよりも目的だ。
36 化石の矢がやわらかい子供の首を刺しているか?
鏡がパンを映してなんらおかしくないように、矢が首に刺さっていても不思議はない。だが、これは疑問形だ。そして三行全体を疑問文に仕立てているのが疑問符である。想像力の寄り道とでも言うべきもの。いちど書かれた文字はなるべく消さないという吉岡の作詩法からすれば、この三行は他の部分から独立してかなり早くから今の形になっていたと考えることもできよう。次の行が暗示的である。
37 そんな時はすぎる
副詞の「そんな時」の場合も吉岡は漢字をあてるが、ここはもちろん名詞。テーブルという舞台の上で展開されるドラマを一括りにした表現と見るべきだ。やわらかい石の夢は終わった。
38 彼らの泥の瞳
ここからの三行は、泥の夢。現在の彼らの姿だ。私たちは吉岡実の構想するという長篇詩が《粘土説》であることを知っている。
「「粘土説」というのは、虚無の極致なんだ。人間が崩壊し、土に埋没するだろうという終末感――」(#C_010、一○七ページ)。
39 彼らの飼っている泥のライオン
石に、化石になりきれないライオン。マグリット〈旅の思い出〉(1955)のなかの絵(「画中画」と呼ぼう)に描かれた亀裂の入った廃塔は、マグリットの《粘土説》ででもあろうか。
40 泥の書物
吉岡は「本、新聞、雑誌類に関係した言葉」を「精神的に嫌悪している」(#A_25、八九ページ)。長いこと出版社で広告や編集の仕事をしていれば、確かにそういうこともあるだろう。しかし、それが詩の作風にどう影響しているかは計りがたい。「言葉」であって実体でないところは注意しておくべきだ(余談だが、吉岡さんが渋谷・道玄坂の喫茶店トップでひとりコーヒーを飲みながら新聞や雑誌を繰っているのを見うけたことがある)。なによりも、見る人である吉岡実が読まずにいると想像することは不可能である。初出「書棚」は誤記や誤植ではなく、これで正しかったのかもしれない。意識では書物と書くべきところを、意識下が嫌ったせいで書棚に変形されてしまったのだ。「詩は「文字」・「言葉」であるゆえに、直接にわたしは自己の詩の中に持ちこまないのである。しかしこれからは何ともいえないが」(同前)。
詩句は「彼らの飼っている」が省略されたようでもあり、そうすると書物が生物のようでおかしみが生まれる。粘土板の連想も働く。彫刻(立体)よりもレリーフに近いか。永遠性を獲得せんとする言葉とも読める。
41 それは可塑物?
手近な辞書に「可塑物」がないので「可塑性物質」を引くと、「可塑性(固体に弾性限界を越える力が加わった時、その力が除かれても、固体にひずみがそのまま残る性質。塑性)を有する物質。セルロイドや合成樹脂など。プラスチック」とある。この行では水を含んだ粘土だ。しかし、できるのは塑像でもなく、火を入れるのは陶器でもない。絵画であり、絨緞である。ここでも慣性からずらされる。読み手の予想を裏切ってゆくのが詩句の身上だと作者は思いさだめているようだ。
42 夏の暖炉で燃える敷物の道
感覚の慣性がそのうえに乗って移動する進路を断つこと。私たちはどこへ行くのか、どこへ連れてゆかれるのか。マグリットの〈釘づけにされた時間〉(1939)の煖炉から突きでた汽車に乗って?
43 彼ら汗をたらしながら
体温調節のためでありながら同時に精神的緊張のせいでもある汗。詩句の展開上の絶妙な転轍機。
44 心を凍らすべく
一見、文語のようだが「……ために」という現代の用法だ。新興俳句経由か。凍らせるために、となると間延びした感は否めない。ここは、身体だけでなく心も燃えさかっていると読まねばならない。
45 一つのカンバスに描くんだ
マグリットの油絵に登場する画架にセットされたカンバスのモチーフは、描くことと描かれることを主題として、恰好のものである。それは「見えないものを見えるように/見えるものを見えないように」描くことに尽きる。〈洞察力〉(1936)のように、卵を見ながら鳥を描くのは写実への皮肉でもなんでもなくて、人間の、自分の想像力とは本来そうしたものなのだというマグリットの「作画法」が述べられているにすぎない(マグリットは〈洞察力〉を描いている自分の写真を撮らせている)。パロディすれすれの信条の吐露、そうした形でしか表明できない芸術観こそ、その後のポップ・カルチャーとアートへの彼の貢献である。マグリットは生涯「絵についての絵」を描きつづけた。
46 花嫁のほしいままなる曲線を
「ほしいまま」は画家が心のままにするさま・勝手きままであるさまはもちろん、花嫁の放恣・放肆の意も含む。画家が想像力を発揮すると、花嫁のあられもない部分を描画したものになる。
47 走る矢印
三六行めの「やわらかい子供の首を刺しているか?」の「化石の矢」をまず考え、しかるのちに他の詩篇の矢印を思いうかべるのが順序だ。カンバスに描かれるのがこの行までか、前行までかも分かれるところだ。あるいはこの行を中間地点にして、もっと先の方までカンバスに押しこめる手もある。マグリットの〈危険な関係〉(1936)の鏡はほとんど画布だ。
48 オレンジ色に燃え
頭から読むと「走る矢印/〔は〕/オレンジ色に燃え」となるが、そう簡単にはゆかない。中止形のまま主語を明確に戴かない述語がくり出され、私たちは像の意味を把えて効果を確認するまえに次の行に移らねばならないからだ。
49 ながれる中心から
最後のものはレオナルドのスケッチを指すか。とすれば中心とは臍だ。この行も語が切りつめられており、中心がながれているようにも読めるが、やはりなにかが中心からながれているのだろう。「走る矢印」を主語に据えるには文脈がそれ以上のスピードを要求している。
50 同時に縦から横まで
二五行めの紅からオレンジ色に変化した(白熱した)女陰である。吉岡はこうしたシーンを厚塗りの描写こそしないが、どう見てもそれ以外には読めないように書く。
51 秘密のよろこびの声を明らかにする
明らかにする、の主語は「彼ら」でも「花嫁」でもなく次行の「肉」、つまりこの行は連体修飾するものだ。しかし「声」は誰の声だろう。単なる「よろこび」なら「花嫁」でおかしくないが、「秘密の」となると「彼らの」か。英訳でもするときには必ずやどれかに絞って解釈しなければならない行だ。ちなみに〈立体〉は佐藤紘彰訳の《Lilac Garden》(#A_34)にも尾沼忠良訳の《Celebration In Darkness》(#A_35)にも収録されていない。
52 内視の肉を輝かせよ!
明らかに四八行めを受けている。池田満寿夫ふうに言うなら、子宮の内部を覗く行為だ。内視なる言葉は一般に見なれないから、とりあえず内視鏡から類推する。
53 内耳の霊の秋
内耳には平衡感覚と聴覚とを感受する器官がある。別名「迷路」。ならばこの不思議な行にはどんなイメージと意味が込められているのか。前行との対句とすればこうだろう。
内視の・肉を・輝かせよ!
内耳の・霊の・秋
視る、聴くの対比がある。清音から濁音への転化がある。霊と肉の対立がある。輝く夏だとすれば、沈んだ秋がある。ここにもうひとつの〈夏から秋まで〉があると言えば、人は牽強付会と謗るだろうか。〈立体〉を〈夏から秋まで〉の変奏として読む誘惑には抗しがたい。篠田一士が後者を的確に評したように〈立体〉もまた「吊天井の恐しい花嫁のスカート/という、まさに戦慄的な美しさにみちみち、しかも、エロチスムの生々しさを嫌というほど経験させてくれる一行をひとつの絶頂にいただきながら、最終行まで、ほとんど一息に、性的人間の夏から秋にいたる内的季節の移行が、兇暴なまでの率直さをもって、唱いあげられているのである」(#B_054、一七ページ)。――〈立体〉の「絶頂」はむろん「花嫁のほしいままなる曲線を/走る矢印」であるが。
吉岡実は〈わたしの作詩法?〉を書くことでかつてない規模の内省を試み、この宣言を挺子に意図的に方向転換しようとしている。また吉岡は、広告の惹句を引いて他者からの規定をそのまま自己規定にスライドさせながら、変貌への希求をこう書いた。「「われわれに見えない場所で、疾走感のない不思議な疾走をつづけていた閉鎖的詩人」といわれる私は、「現在もっとも奔放でしかも真摯な、才気と情熱と内面の混沌とで、ダイナミックに武装された独自な世界を切り開いてやまない」白石かずこのきわめて、世俗的現象を巻き込み増殖する柔軟な詩法に深い羨望を感じている」(#A_25、一八九~一九○ページ)。
中心的なモチーフはこのころの作品を通じてほとんど変わらない。絵画の画布という表皮から肉感をどう読みとるか。肉感の香り、視覚の手ざわりを詩と等価にする試み。それがおのずから流露する場合は、詩句のテンションはそれほど高くないような気がする。
テンションの高い場合として「吊天井の恐しい花嫁のスカート」を考えよう。詩句の曖昧さはそれ自体求められたものではなく、「増殖する柔軟な詩法」のしからしむるものだ。詩句としての突兀とした感じは多義性に通じる。手許の辞書の吊天井は「つるしておいて、落とせば下の人を圧殺できるしかけの天井」。この構築された一行から、①「花嫁のスカート」すなわち「吊天井」で、それゆえに恐ろしい。花嫁に組みふせられる恐怖と愉悦。②「吊天井」に電灯の傘のようにくくりつけられた、おそらくは花嫁のペチコートを下から見あげる驚愕。③「吊天井」を恐れる花嫁の、肉体は消失し、脱ぎすてられたように残るスカートのぬくもりと香り。このくらいのものは読めるだろうと篠田一士も、そして吉岡実も言っているようだ。
「彼ら汗をたらしながら/心を凍らすべく/一つのカンバスに描くんだ/花嫁のほしいままなる曲線を/走る矢印」が真に戦慄的であるとしたら、内実もさることながら、稜線が角度によって様相を変える彫刻作品への視線と同質のものをこの「画布」が読み手に要求しているからだ。
54 その向うを
この「を」の使い方、米を研ぐときの螢の句の「前を」を思いださせる。
55 漂う湖
〈島〉は背景としての水である点でまったく等しいが、その語法の厳密さを散文ととりかねないほど〈立体〉の「その向うを/漂う湖」は白描による韻文と化している。
56 朝鮮アサガオの雨の朝がくる
「朝鮮朝顔」だと誤植のようで落ちつかない。私には特段の知識もないので、《国語大辞典》に教えを乞い、必要な部分のみ摘する。「ナス科の一年草。日本へは江戸時代に輸入され、薬用として栽培されたが、今日ではあまり見られない。夏から秋にかけ、葉腋にアサガオに似た白い漏斗状花をつける。花冠は筒部が長く、先は浅く五裂して裂片の先は尾状にとがる。全株にアルカロイドを含み、葉と種子は薬用。葉は曼陀羅葉と呼び、ぜんそくに用いる。猛毒なので量を誤ると発狂状態となる。漢名、曼陀羅草。気違茄子(きちがいなすび)、曼陀羅華(まんだらげ)」。
夏から秋にかけて花が咲くこと。その形態が蓄音器のラッパのようであること。他の漢名・和名とも「雨の朝」の前に置くには音の響きがよくないこと、が判明する。これがふつうのアサガオでないのは、狂気の状態を暗示する必要があったからだ。「内耳の霊の秋」が幻覚のように顕つのはこのときである。
57 彼らは紳士だから
彼らは「真摯」だから、と読んでも許されるかもしれない。すなわち彼らは、最初のときとも二度めのときとも異なるのだ。室内と屋外の区別もつかなくなって、さまよいはじめるようだ。
58 フロックコートの正装のまま
変化しない/できない恐ろしさ。マグリットの、五人の紳士のそれぞれの眼の前に貝殻やリボンやレモンやスポンジや水差しが浮かぶ〈みなれた物〉(1928)の不気味な静謐。
59 存在するために
五行めなどとはずいぶんと様子が違う。
60 共同幻想体として
「存在するために」と「共同幻想体として」はかなり激しく衝突する。今までの詩句の流れは、相当の飛躍はあってもある行はその前のどこかの行を受け、というふうだったのが、ここに及んで断絶的なイメージと意味をもった新しい詩句が登場したのである。吉岡実がモダニズム青年であったことを考えれば、「内的独白」だの「意識の流れ」だのといったタームが出てきても驚くには及ばないが、吉本隆明の著書《共同幻想論》(#B_162)が一本にまとまる前にこの語を書きしるすということはなにを意味しているのか、確答は得られない。もっとも、吉本の書物に「共同幻想」も「共同体」もあるが「共同幻想体」は出てこないところを見ると、この語そのものは吉岡の創案かもしれない。
61 スイートな金魚鉢を支える
「スイート」が曲者であって、甘美な金魚鉢では意味をなさないが、今までの水のエロティクな変化を見てくれば金魚鉢を花嫁の子宮にとったって不都合はない。残念ながら手品のように種明かしをすることもできず、篠田一士が〈薬玉〉(⑪・10)をエロティクに解釈した(#B_055、七四ページ以下)見事な手腕を思いだしながら、同じことはこの〈立体〉でも充分できただろうにと感慨にふけるほかない。
詩篇〈立体〉解読の手掛かりは「花嫁」だ。マグリットではなくエルンストの〈花嫁の衣裳〉(#B_064、一四○~一四四ページ)を媒介することで、次の吉岡実と澁澤龍彦の文章を思いだす。
「和田芳恵は早くから、私のなかに、夢想する魂と職人気質が共存する、奇妙な男と思っていたらしい」(#A_25、一七六ページ)。
「申すまでもなく、マグリットは、マックス・エルンストのようなロマン派の血をひく幻視者(ヴィジオネール)ではない。〔……〕ポール・デルヴォーのようなコンプレックスにみちたエロティシズムの夢想家でもない。〔……〕マグリットは、さよう、彼らすべてのシュルレアリストのなかでもっとも醒めた、もっとも冷静な批評的精神の持主であり、あえていうならば、イロニーを楽しむ哲学的精神の持主だったのである」(#B_065、一○八ページ)。
この伝で行くと《僧侶》の吉岡はエルンスト、《神秘的な時代の詩》の吉岡はデルヴォー、《サフラン摘み》あたりの吉岡がマグリットか。閑話休題。
「イメジの氾濫に歯止めをかけ」るべく、ゆるゆると始まったかに見える詩篇は、あるいはそれゆえに「花嫁」が登場するや、フロックコートの男たちが下僕になるしかない構造を持つ。「立体」とはフロックコートの紳士たちの織りなす平面に男根のように突きたった「花嫁」の謂ではないか。ときに、澁澤が言及したデルヴォーの、〈学者の学校〉(1958)はどうだろうか。この絵は一九七五年、東京国立近代美術館のデルヴォー展でも展示されたが、年代的に吉岡がこの展覧会を観て詩を書くことはありえない。しかし事この詩の場合、意図的に自分を混乱させて考えるほうが私には面白い。〈立体〉からまず想起した絵がマグリットでもエルンストでもなく、デルヴォーのそれだったのである。吉岡がデルヴォーに触れた文章を記していないのはこの連想の根拠を薄弱なものにするだろうか。そうでもあるまい。マグリットにしたがところでただ一度、三好豊一郎の寝姿に触れて出てくるだけだからだ。(#A_25、二○一~二○二ページ)
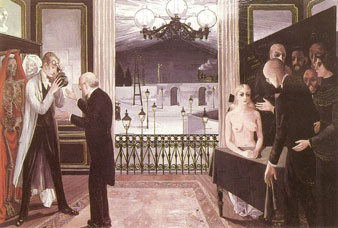
ポール・デルヴォーの油彩画〈学者の学校〉(1958)
ここで吉岡実と絵画全般について考えてみよう。吉岡の詩と絵画とりわけ二〇世紀の西洋絵画、現代日本絵画の関係は、次の二点において興味深い。①詩法そのものがピカソに影響を受けていると自ら言うように、作品が絵画的であること。②作品の題材を絵画作品に仰いでいるものが少なくないこと。だが「絵画」「絵画的」とはなんだろうか。まず、言語を絵具のように用いて詩篇を造形してゆくこと、と考えたくなる実例として。「翼ある毒物/肉のような絵が描かれて/あまねく拡がる霧の空」(〈コレラ〉⑦・18)。「絵が描かれて」を重視する必要はない。「翼ある毒物」から動物(鳥かコウモリか)が浮かび、それが「肉」といっても毒を含んだ肉塊のように思われてくると、視覚はパンしてゆき像は乳白色の空に没してしまう。絵を描きながら消す行為。消えることで完成する絵画、それがこの三行の造形の意味するところである。②の実例には、本篇〈立体〉がある。
吉岡の詩の言葉の持つ物質性を多くのひとびとが指摘するが、それはひとつ間違えるとカンバスに盛られた絵具も所詮は物質だというのと大差がない気がする。そうではないだろう。吉岡の詩の行が、余人のそれとは明らかに異なるマチエールで輝いている、それを「物質的」とでも呼んでみるしかないのだ。その濫觴はどこか。言うまでもなく、一九五五年発行の戦後最初の詩集《静物》だ。詩人はのちに当時を振りかえって、リルケの《ロダン》を共感を込めて引いている。「何物かが一つの生命となり得るか否かは、けっして偉大な理念によるのではなく、ひとがそういう理念から一つの手仕事を、日常的な或るものを、ひとのところに最後までとどまる或るものを作るか否かにかかっているのです」(#A_25、二八八ページ)。
「長いこと、新しい詩の方向を模索していた」(同前、二八七ページ)吉岡実は、このとき「夢想する魂」を「職人気質」で裏打ちするという、幻想絵画の作家の立場を明らかにした。その後、澁澤龍彦ほかの導きによるさまざまな絵画との出会いを経つつ、詩を「見〔え〕るもの、手にふれられるもの、重量があり、空間を占めるもの、実在――を意識してきた」(同前、八九ページ)詩人の作詩法を一言で要約すれば、幻想絵画の手法で書くということに尽きる。魂と気質はそれぞれの時期の見掛けの類似や差異を超えて、すべての作品に「実在」という刻印を残している。詩篇が絵画のようなのではなく、絵を描くのと同じ姿勢で詩を書くのである。できあがった詩が絵に似てくるのはあるいは偶然だ。
ここで、題名・詞書・本文・註・初出等を問わず、吉岡実の詩篇に登場する造形作家の総まくりをやってみよう(〈表① 吉岡実詩の造形作家名〉参照)。いま試みに澁澤龍彦の《幻想の彼方へ》(#B_065)の目次の画家名に、吉岡実の作品に登場するそれを当てはめてみると、一四件中一二件近くが該当する。
モローとブルックスに吉岡が言及したことはないが、どちらも異様に細長い体形の人物を描く。エロティクではあるが「男の肉性を刺戟」(〈首長族の病気〉⑤・11)することはほとんどない。これらの絵画と詩篇はどんな関係にあるのか。吉岡実にとって絵画作品とは言語と等価のものだ、という仮説を立ててみる。一九六○年二月二七日の吉岡の日記「永田力のアトリエでデッサン練習。三好豊一郎、那珂太郎、山本道子、伊達得夫など。モデルは恐しく立体感のある黒い女。詩篇〈冬の休暇〉出来」(#A_10、一二一ページ)を読むとき、むしろ〈冬の休暇〉(⑤・12)が絵のように見えてくる。吉岡は〈冬の休暇〉と同じ《紡錘形》に収められた〈沼・秋の絵〉(⑤・21)について書いている。「「沼・秋の絵」は、美術雑誌で見た、シュルレアリスムの女流画家レオノール・フィニの絵を題材にしたものだ。いってみれば、言葉で模写したようなものである。霊気の立ちこめる薄明の沼で、水浴している「わがアフロディーテー」と、解して下さってもよい。「わたしはいつ愛撫できる?」と、思慕し、願望しているのだ」(#A_23、二○二ページ)。
「模写」をそのまま受けとって詩篇とフィニの〈終末〉(1949)を較べてみると、一筋縄ではゆかない。模写のための模写のようなものは、詩的想像力を発動する切っ掛けなのだ。絵筆が外界の対象物をなぞるかに見える時間内に、言語は別の回路をたどり、言葉による素描のつもりで読んでいるといつのまにか対象の具体性は遠退き、限りなく箴言に近い吉岡の詩句に封じこめられている。「野蛮な深みに立ち/罰せられた岩棚で/わたしはいつ愛撫できる?」
風景や事物が心的状況に結びつけられ、それが「箴言的な言葉」(#A_24、二一四ページ)の定立として詩句と化すことが構造的な特徴だ。〈沼・秋の絵〉はこう続く。「鋸をもつ魚の口/蟻のひと廻りする一メートル半径の馬の頭蓋/それが侮辱されて骨へ代るとき/わたしは否でも愛を認識できる」
事物が時間の腐蝕で変化することを「侮辱」と受けとめ、それに対抗する別の行動が導きだされたとき、最後の行が詩篇の要となった。詩句がなにごとかを定立せざるを得ない領域に押しあげられた恰好だが、事情は逆かもしれない。「愛を認識」するためには「それが侮辱されて骨へ代る」必要があったのだ。吉岡の図像を脳裡に結びやすい詩句と箴言的詩句の平衡と、そこに至る展開の妙は他の追随を許さない。〈立体〉もその例に洩れない。
「次のドアをひらいたら/ネズミの死骸が少しずつなだれこむ/にちがいない今日の在り方」――「彼らの泥の瞳/彼らの飼っている泥のライオン/泥の書物/それは可塑物?」――「彼ら汗をたらしながら/心を凍らすべく/一つのカンバスに描くんだ/花嫁のほしいままなる曲線を」――「彼らは紳士だから/フロックコートの正装のまま/存在するために/共同幻想体として/スイートな金魚鉢を支える」
ここに論理的必然のみを求めても虚しい。最初の句跨がりの意外さ、ふたつめのもともと書物は泥だったのではないかという錯覚、みっつめの花嫁の肉体がカンバスを突きやぶってくる幻覚、最後のストップ・モーションによる判断中止と急激な幕切れ。これらは、図像を脳裡に結びやすい詩句と箴言的詩句の平衡と、そこに至る展開が作りだした吉岡の詩の勘所なのだ。そこからさらに機能として要の行を抜けば次のようになる。
「にちがいない今日の在り方」「それは可塑物?」「心を凍らすべく」「共同幻想体として」
これらの行とそうでない行の絶妙な配分があってはじめて「詩は、最初の一行からあんまり考えていっては動きがとれなくなるんだ。研ぎすまされた言葉の併置だけじゃ、その詩は動き出さないと思う。つまらない詩の行が、骨を包む肉のように挟まることが詩を柔軟にして、真のリアリティを保有させることになる」(#A_18、一一七ページ)と詩人をして言わしめることになる。《神秘的な時代の詩》の呼吸を、たとえば《僧侶》と較べてみれば「蔵言ふうの詩句が、肉に緊められる骨のように突出することが詩を剛直にして、真のリアリティを保有させることになる」とでも言いなおしたいくらいだが。リアリティを求める詩法の根本が変わったのではなく、混合比率が《紡錘形》を出発点にして《静かな家》を経ることで逆転したと考えたい。つまらない行がただ単につまらないのなら、どうしようもない。詩人はそういう行を書かないだろう。一見つまらなく感じられるが、そこに置くことで前後に「研ぎすまされた」行では不可能な関係をつけること、それは「箴言的な言葉」が外部を模写したと見える行を切ったり結んだりするのとほとんど同じだ。
《神秘的な時代の詩》は詩句の自在な展開のみを言いたてるには苦渋に充ちた詩集であるが、これは時代の文化状況を反映した、詩人にとっても革新的な文体だった。いったいに吉岡の詩は、どれほど観念的に見えようが具体的なものの肌ざわりを手放すことがないように、どれほどくっきりと見えるように書かれた詩でも幻想に変貌する一瞬をねらっていないものはないように思える。それが詩の本来もっている分量を超えてしばしば氾濫しがちなのが《神秘的な時代の詩》の詩篇ではなかっただろうか。
〈表① 吉岡実詩の造形作家名〉の人名――( )内は前記「造形作家の総まくり」の条件には当てはまらないが、作者自身が作品に触れつつ随想で書いたりしているもので、高橋睦郎が〈鑑賞〉で言及している画家は作者の談話に登場したものか――を美術事典で調べてみると、シュルレアリスムの画家がいちばん多い。巖谷國士は「澁澤龍彦の美術エッセーは、一九六○年代の後半以後、ある種の読者、とくに美術愛好家や若い芸術家たちのあいだに、大きな浸透力をもって迎えられた」(#B_065、二五四ページ)と書いているが、吉岡の作品に画家名が頻出しはじめたのがこの時代からなのはすでに見た。ところで、吉岡が澁澤と出会ったのは、高橋睦郎が書くように一九六七年二月九日(#A_23、一一九ページ)だったのではなく、一九六○年四月六日以前(#A_10、一二三ページ)ではないだろうか。だとすれば、六○年代後半の澁澤の書くものに吉岡がまったく無関心だったとは考えにくい。その澁澤だが、〈夏から秋まで〉評釈の表〈散文にみる吉岡実・土方巽・池田満寿夫・澁澤龍彦の関連〉に肝心のものを入れわすれたので、補っておく。〈現代日本文学における「性の追求」〉(#B_062)だ。この論文は逸することのできないものだが、先に調べたときはタイトルを見ただけで読みかえすことをしなかった。この文章はあとで検討する。
さらに画家に対する資料を充実するために、詩以外で吉岡が造形作家に言及している箇所を《「死児」という絵〔増補版〕》から抜いてみよう。こちらは五〇音順に並べた(〈表② 吉岡実散文の造形作家名〉参照)。
吉岡実の詩と幻想絵画の関係を考察するうえで、興味深い出版物が一点ある。《夜想》一九号の特集〈幻想の扉〉。この、東京・銀座の青木画廊が精力的に紹介してきた画家たちの総特集号に、吉岡の詩〈異邦〉(⑨・5、詞書は「セリエントの絵によせて」#C_036、
七二~七三ページ)と〈自転車の上の猫〉(⑧・15、詞書は「マツイ・キミオの絵によせて」、同、九四ページ)が再録されている。再録されなかったが、大竹茂夫への〈壁掛〉(⑪・5)や小沢純への〈秋の領分〉(⑫・5)も同画廊の発行するカタログやパンフレットに寄せられた詩篇だ。発表誌こそ違うが、これにゾンネンシュターン(⑧・24)や金子國義(⑨・22)や四谷シモン(⑫・6)を加えれば、どれほど吉岡が青木画廊の取りあげた画家に親しみを覚えているか、思い半ばに過ぎるものがある。
残念ながら私はこれらの展示を観ていないが、一九七九年一〇月のボナ展の芳名帳には吉岡の名があったと記憶する。ボナの夫アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグについて吉岡は、澁澤龍彦も訳したポルノグラフィ《城の中のイギリス人》の「官能的映像」に陶酔した、と書いている(#A_25、三五八ページ)が、澁澤から受けたであろう恩恵は翻訳にとどまらない。それを見よう。
同じ日のことを二人が書いている。吉岡は和田芳恵追悼文〈月下美人〉で「その日は生憎、私は仕事のため同僚と北鎌倉の澁澤龍彦宅に行っていた。打合せも終り、龍子夫人の運転するくるまで鎌倉へ出た。小町通りのひろみで天ぷらを食べ、たのしい一夕を過した。しかしその間も、長原の家〔和田芳恵宅〕のことを考え、心がおちつかなかった」(同前、一七三ページ)と書き、澁澤は週刊誌の連載随筆の一回分に仕立てている。その〈天ぷら〉のハイライト部分は要約できない。
吉岡さんは私の家へくるなり、
「今日はポルノを見せてもらいにきたんだ。きみのところには、たくさんあるだろうと思ってね」と言い出しました。
それも〔天ぷら屋に行くのと同様〕前からの約束だったので、私は書庫から、古いのや新しいのや、芸術的なのや通俗的なのや、アメリカのやフランスのや、写真のや絵のや、いろいろ取り揃えてきてテーブルの上に積み重ねました。
その日、吉岡さんが奥さんを連れてこなかったのは、一つには奥さんの父君の和田芳恵さんの病態が思わしくなかったためもありますが、もう一つには、ポルノを見るつもりだったからかもしれないな、と私はひそかに思いました。もっとも、これは吉岡さんに確かめたわけではありませんから、私の勝手な想像です。
父君の容態が明日をも知れぬという時に、ポルノを眺めるなどとは不謹慎だ、という意見があるかもしれませんが、私はそうは思いません。七十年の壮烈な生き方をした一作家の臨終に、数日来、親しく立ち会っていたればこそ、吉岡さんはその日、むらむらとポルノを見たくなったのではないでしょうか。いや、何もそんな理窟をつけるには及びますまい。私が勝手に吉岡さんの心中を忖度する権利も、むろん、ありません。ただ私は、和田さんの生涯にはポルノはむしろふさわしいので、これを眺めるのが必ずしも不謹慎なことだとは思わないだけです。
吉岡さんは懐中から取り出した眼鏡をかけて、アメリカやフランスの雑誌をぱらぱらめくりながら、ひとりごとのように、
「あんまり毛深いのや、割れ目がはっきり見えるようなのは好きじゃない。何というか、ふわふわと生えているのが好きなんだな」と言いました。(#B_063、一二○~一二一ページ)
ここで割れ目が女性性器だと確認できたことに安心するのもいいが、〈読書遍歴〉の回想「小学校の親しい友だち、裕福な町工場を経営しているKの家へ毎日のように遊びに行き、彼の持っている本を読んでいたのであった。時には三時のおやつまでご馳走になりながら」(#A_25、五五ページ)にも通じる熱中を読みとりたい。こうした交友関係にあった澁澤と吉岡の絵画の趣味が類似していたとて、なんの不思議があろう。その澁澤が吉岡実ではなく、吉岡実の詩をどう見ていたかが前に挙げた〈現代日本文学における「性の追求」〉である。そこには「金魚」「金魚鉢」も出てくる。
これは澁澤唯一の吉岡実論であり、ひとり吉岡の詩だけでなく澁澤の考える詩が普通のそれとはやや異なり、いわば吉岡の「特異な」詩こそ第一義のものだとしているように思える。そこではガストン・バシュラールの物質的想像力を引きあいに、「物体愛」が吉岡実の詩を貫く基本原則だと明言され、物体に対する愛がエロティクの所以であり、超越への契機がまったく見られないのもその詩の特徴だとされる。初出は〈立体〉発表の翌年一九六八年二月であり、詩集《僧侶》を頂点とする前期吉岡実詩の作風を、静物画の発想を鍵にして、図式的なくらい明快に捉えている。
吉岡自身その緊張に震える詩世界にあきたらぬ思いを抱き、それが〈わたしの作詩法?〉を書かせ、もう少しルースな世界へと向かわせたことも納得できる。では、ルースな語法・詩法とエロティクはどうむすびつくのか。自動記述法による内的イメージの解放は、ひたすらエロティクな対象に奉仕しているようだが、対象との関係性ではなく、語法・詩法そのものがエロティクにしているのではないか。題材を拡大したというよりも、語の選択やくり返しに対する自己規制を大幅に緩和した結果、文体がまず変革された。上記のような思いが自らに課していた禁制を放棄させた、と言っても同じだ。なぜなら、詩を書く楽しみの邪魔になるものはこれを捨てて省みないのが吉岡の生きかただからだ。澁澤の吉岡論の末尾、やや長いが重要の箇所なので引用する。
「金魚を鉢に入れることによって、世界を括弧に入れることによって、吉岡は「生きた自然」を殺し、これを「死んだ自然」に変化せしめる。つまり、彼は一個の気に入りの静物画をつくる。『僧侶』においては、しかし金魚鉢〔吉岡の表面張力嗜好の象徴〕がすでにふくれあがりつつあるから、この操作は難渋をきわめ、静物画は奇妙に歪み出し、ときに私たちにサディスティックな印象をすらあたえるほどである。ともあれ、彼は自然を殺し、気に入りの「死んた自然」を愛撫しようと懸命の努力をつづけるのだ。彼の物体愛は、あたかもネクロフィリア(屍体愛好)の趣きをおびる。そうだ、彼があれほど物体の表面に執着し、表面の触覚のみに官能の実在性を確かめようとしているのも、このネクロフィリアの明らかな証拠とはいえないか。なぜなら、ネクロフィリアとは、主体と客体の内面的な交流を一切信ぜず、ただ冷たい表面のみにとどまろうとする欲望だからである。吉岡実の詩は、人間のあらゆる連帯とコミュニケーションを嘲笑しながら、孤独の、不倫の、ネクロフィリアの、しかしながら詩人にとってもっとも本質的な、自己と世界との関係の快楽にひたすら執着しているように見える」(#B_062、四六五~四六六ページ)。
澁澤龍彦はなんらペジョラティフな意味を込めずに、ほとんど無惨なまでに吉岡実の詩の特徴とその限界を暴いた。これは吉岡の詩を否定してかかろうとする人間からは出てこない、恐ろしい評価であろう。「自己と世界との関係の快楽」(原文には傍点が打たれている)をそれまでとは異なるアプローチで追求すること。「孤独の、不倫の、ネクロフィリアの」とは一見して見えないアプローチで詩を書くこと。《神秘的な時代の詩》に新生面があるとすれば、これ以外にない。連祷詩〈葉〉の構想が変貌するうちに《サフラン摘み》の「誕生」という主題が展開されたことは、その成功を意味するだろう。「自己と世界との関係の快楽」の更新あるいは発見が結実したのだ。
朝吹亮二〈エニグム・アノニム〉(《現代詩読本――特装版 吉岡実》、思潮社、1991)にこうある。「アノニマといえばすぐに思い浮かぶ画家がいる。ルネ・マグリットだ。〔……〕この山高帽のフロックコートのシリーズの一枚に「脅かされる殺人者」というのがある。殺人者が死体のそばでラッパ付きの蓄音器を聞いている。手前には、その男を捕まえようと二人の男が、一人は棍棒をもち、もう一人は投網をもってまちかまえている。そして窓の外には三人の見物人がいる、という構図の作品だ」(同書、二四一ページ)。評釈本文でも触れた高橋睦郎の指摘(「シュルレアリスムの画家、たとえばルネ・マグリットの画集をめくって、その印象をきわめて自由に書いた詩と思えばいいだろう」)がこの作品を含むことは間違いない。だが、生前の吉岡さんにご覧いただいた最後の評釈である初稿をほぼそのまま掲載したいため、あえて本文には組みこまず、マグリットの〈脅かされる殺人者〉、すなわち〈殺人者危うし〉を参考図版として掲げる。

マグリットの油彩画〈殺人者危うし〉(1926)
…………………………………………………………………………………………………………
*吉岡実が自作に触れつつ随想で書いたりしている造形作家名は、( )に入れて補った。
死児(④・19)=(スタンチッチ)
狩られる女――ミロの絵から(⑤・18)=ミロ
沼・秋の絵(⑤・21)=(レオノール・フィニ)
模写――或はクートの絵から(⑥・4)=クート
スープはさめる(⑥・11)=アルプ
マクロコスモス(⑦・1)=キリコ
夏から秋まで――池田満寿夫の版画の題名を藉りて(⑦・2)=池田満寿夫
青い柱はどこにあるか?――土方巽の秘儀によせて(⑦・6)=ハンス・ベルメール
雨(⑦・9)=ルイズ・ニーヴェルスン
聖少女(⑦・10)=ハンス・ベルメール
夏の家(⑦・13)=(中村宏)、(横尾忠則)
サフラン摘み(⑧・1)=アルチンボルド
草上の晩餐(⑧・13)=(マネ)
自転車の上の猫(⑧・15)=松井喜三男
フォーサイド家の猫(⑧・17)=ローラン・ブリジオ、(松井喜三男)
異霊祭(⑧・19)=ルドン
舵手の書――瀧口修造氏に(⑧・22)=へンリー・ムア
白夜(⑧・23)=ムンク
ゾンネンシュターンの船(⑧・24)=ゾンネンシュターン
あまがつ頌――北方舞踏派《塩首》の印象詩篇(⑧・30)=ゴヤ
部屋(⑨・2)=(レオノール・フィニ)
異邦――へルマン・セリエントの絵によせて(⑨・5)=へルマン・セリエント
水鏡(⑨・6)=エゴン・シーレ
曙(⑨・8)=ジャスパー・ジョーンズ
草の迷宮(⑨・9)=池田満寿夫
形は不安の鋭角を持ち……(⑨・11)=飯田善國、アンリ・ローランス
雷雨の姿を見よ(⑨・14)=マグリット
織物の三つの端布(⑨・16)=(ジョルジュ・ブラック)、(マルセル・デュシャン)
夢のアステリスク――金子國義の絵によせて(⑨・22)=金子國義
謎の絵(⑨・26)=アンドリュー・ワイエス
ポール・クレーの食卓(⑩・1)=パウル・クレー
生徒(⑩・18)=片山健
ツグミ(⑩・21)=レオノール・フィニ
壁掛(⑪・5)=大竹茂夫
郭公――マックス・エルンスト石版画展に寄せて(⑪・6)=マックス・エルンスト
秋の領分(⑫・5)=小沢純
薄荷(⑫・6)=四谷シモン
銀幕(⑫・9)=梅木英治
スワンベルグの歌(未刊詩篇・12)=スワンベルグ
*アラビア数字は吉岡実《「死児」という絵〔増補版〕》(筑摩書房、1988)の掲載ノンブル。
飯田善國=246
池田満寿夫=246, 330
伊原通夫=215
ヴォルス=206
太田大八=71
岡崎和郎=330
小山内龍=16
片山健=162
葛飾北斎=11
加納光於=10
河井寛次郎=12
徽宗皇帝=343
国吉康雄=186
小林古径=343
アーシル・ゴーキー=206
合田佐和子=10
斎藤清=67, 257
下村観山=24
スタンチッチ=口絵, 70
高村光太郎=167
俵屋宗達=342
つげ義春=162
富岡鉄斎=11
中西夏之=344, 346
難波田龍起=166
浜口陽三=45
林静一=162
バルテュス=361
ピカソ=67, 89, 110, 335
ハンス・ベルメール=359
ルネ・マグリット=202
ホワン・ミロ=220, 362
四谷シモン=360
ロダン=287
あらゆる芸術家にはかつての自己の作品を、引用し、変形し、増殖してゆくという、営為がある。――吉岡実(#A_24、七一~七二ページ)
〔標題〕 マクロコスモス|吉岡実(小林一郎英訳)
Macrocosm|Yoshioka Minoru(Translated by Kobayashi Ichiro)
*
01 石の建築物といっても永遠
02 ではない二階から上は
03 紫の窓
though the building is made of stone that is not
everlasting above the second floor it has
the purple windows
〈マクロコスモス〉(⑦・1)の冒頭三行は変則的である。これを不用意にあるいは自然に読みながせば「石の建築物といっても永遠ではない/二階から上は紫の窓」。定稿の二行め行頭が強調されているのは見やすいし、全体が一連であることもはっきりしている。「紫の窓」というキャンバス、あるいはスクリーンが読者の脳裡に設定されるのは結果であって、ここには文体の新局面がある。語と語の衝突から発生する像、という超現実主義的手法に特徴的な傾向は、今や句と文のあわいに新しい詩美を生んだ。
*
04 なでられている
05 ビーナスの尻が見え
we can see the hips of Venus
stroked
「ビーナス」は元来、金の矢を持つキューピッドと共にあるが、ここは泰西名画的なそれではなく、若い女のすべすべの裸を示すにとどまっている。十年後に
「ヴィーナスは青い海に立つ波
の真白い泡から生まれた」
という神話をわたしはいまでも好きだ(〈紀行〉⑩・16)
と書く下地はあったと見るべきだが、高橋睦郎の指摘にもあるように(#A_23、一二九ページ)、典拠となった矢島文夫《ヴィーナスの神話》(#B_155)は、《サフラン摘み》の世界を形成するのに大きく与っている(〈紀行〉の引用符の中は、吉岡が矢島の著書に引かれた矢代幸雄《隨筆ヴィナス》(新潮社、1956)の章句「神話は、ヴィナスは青海に立つ波の真白い泡から生れた、と伝える」を改変している)。ここでは神話の世界に傾斜することなく、詩篇は続く。
*
06 戸棚のパイナップルのザラザラの皮が
07 精神を支配する
the rough rind of pineapple in the cupboard
controls our minds
鱗形の表皮に肉を包んだ果物の、球形体というより手榴弾のような実相を喚起せよ。
*
08 洗濯屋が汚れたワイシャツを
09 もってくる正午
at noon when a laundryman brings
the soiled shirt
ここが「洗濯屋」の仕事場でないからには、作業前のシャツを「もってくる」とは言えないはずだ。ありえないことが起こった「正午」。時間が捩じれる。
*
10 四階に住んでいる
11 画家と犬はなんだろう?
what are the artist and his dog
that have lived on the fourth floor?
アパルトマンの住人にして、疑問を抱かしめる存在。
*
12 白塗りの星条旗の下で
13 叩かれている犬
the dog beaten
under the Stars and Stripes painted white
壁に飾られている(いな、打ちつけられている)画家の作品。鳴き声も叫び声も聞こえない。ジャスパー・ジョーンズは一九六九年にマース・カニングハム舞踊団(土方巽が影響された)のアートカウンセラーになっている。
*
14 写真に撮られるべく
15 ハンバーグを食う
16 タライのなかの黒人
the black person in the washtub
who eats a Hamburg steak
to have his photograph taken
食べるのは生きるためでなく、水浴するのは生きるためでなく。犬を叩く芸術家のポートレート。
*
17 ぼくらの現況の雨の葦原から
18 暁の丘に至るまで
19 シナの娘が大鎌を振って行く
from the reedy field in the rain of our status quo
up to the hill at dawn
a Chinese girl shakes the scythe and goes
ここでフラッシュバック。巨人化した女体の陰毛から乳房へ。暗いオンドルのかげで老いた父へ粟粥をつくっていた黒衣の少女。
高天原=天上界
葦原中国・葦原瑞穂国=地上
黄泉国=地下
葦原将軍=「自ら将軍なりと信じ居る一種の誇大妄想患者。〔……〕転じて誇大妄想性の人間を葦原将軍といふことがある」(#B_096、二一七ページ)とは、昭和六年刊の《大百科事典》(平凡社)の記述。
*
20 馬のながい陰茎の岸べ
21 かくすハハコグサ
22 タケニグサ
23 自慰観音
the shore of a horse's long penis
hiding the cudweed
the plum poppy
Kwannon of masturbation
馬が主に食べる稲科の草は、一年のある時期には栄養価が低いうえに、馬は消化力が弱いので大量に食べる必要がある。ときに植物の茎という茎へ、まれには牡の茎にも刃物を当てる支那服姿の母娘。春の七草。竹煮草。
「新兵の生活は想像以上に悲惨なものがあった。早朝から馬に与える草刈りだ。朝露にぬれた笹や丈高い草を求めて、目黒川のほとりや駒沢の野原を駈け廻った。身をかがめ、馴れない鎌で草を刈り、束ねてみるとなさけないくらい草のかさはない。そのうえ竹煮草が混っていると、「馬を殺す気か」と上官になぐられた」(#A_25、一三八ページ)。
馬頭観音はハヤグリーバ(サンスクリット)の訳で、六観音のひとつ。馬が濁水を飲みつくし、雑草を食いつくすように、衆生の煩悩を断尽する尊とされる。近世になると馬頭を戴く忿怒の形象と六観音信仰で六道のなかの畜生道を救うとされるその性格によって、民間における馬の守護神として尊崇されるようになった、と《大百科事典》は教える。「自慰観音」とは、吉岡によるオナペットの漢訳か。
*
24 心はつめたく地は熱い今日
today the heart is cold and the ground is hot
心を凍らすべく一つのカンバスに描くんだ。
*
25 だんだんと減る
26 水のなかのトンボの卵
27 八月の暑い恋びとたちの
28 コルクのセンを咬む愛
the spawn of dragonfly in the water
running low less and less
the love; the hot lovers in August
bite the plug of cork
流れだすいったいなにを防ぐための栓。初出では二五行めが「だんだんと殖える」だった。「減る」と改めることによって、トンボのもつ象徴としての不死性が強く打ちだされたようだ。
*
29 ではどうしよう?
what shall we do?
作品を自在に方向転換するための蝶番。
*
30 肥大漢のぼくらの姉妹
31 双生児を生みに行く
our swollen sisters
go and bear twins
①「肥大漢であるぼくら」、②「肥大漢である姉妹」(女を漢と呼ぶ粗雑さは吉岡にはなかろうが)。③「姉妹は/双生児を生みに行く」、④「姉妹である/双生児を生みに行く」。この家族構成は詳かではない。
*
32 長いボール紙の筒があるかね?
is there a long cylinder of cardboard?
子宮にして陰茎の筒そのものが乳児の形。
*
33 それを廻って
34 ぼくらの肥大の子供は遊ぶんだ
turning around it
our swollen children play
双子座は、両性具有を表わす恋人の男女。子供は一人か。せり上る死児の円筒。そのすべすべのまわりを歩く。
*
35 ダンダン畑から採る
36 輪切りのパイナップル
the pineapple cut in round slices
taken from the layered fields
パイナップルの可食部は「肥大した」花序である。
*
37 食べる桃色の人食人種
pink cannibals who eat it
人肉嗜食、食人習俗。食べられる者によって①族内食人②族外食人③自食人。行為の動機によって①食通的食人②儀礼的ないし呪術的食人③生き残るための食人。「われわれは食べないが【 】は食べる」の空欄に入るものとして①異民族=隣の部族のやつら②妖術者=近親相姦を犯す者③大昔の祖先たち。「裸+乱婚+食人」のセットが野蛮人の象徴である――と阿部年晴は教える。一方、首狩りは農耕民のあいだに特徴的な慣習で、しばしば豊饒・繁殖の儀礼と関連している。ここからフレイザー《金枝篇》までの距離。
中野美代子は〈カニバリズム論――その文学的系譜〉に書く。「精神と肉体が一元的である未開人のカニバリズムも、精神と肉体のあいだの深淵に綱をめぐらし渡ってみせた「文明人」のカニバリズムも、その行為の中には、なんと明晰な精神と肉体が透けて見えることだろう。その状況は、私の遠い記憶の中にある戦争のそれと一つである。〔……〕カニバリズムも戦争も、人類がそれを禁忌としながらついに避けえなかったエロティックな欲求なのである。この二つながらを厳格なタブーとして見せかけの平和に酔いしれている現代は、精神も肉体もアモルフに融けあって、そして、さて、生命の尊厳なるものは、〔三島由紀夫の言う〕「鉄骨だけの建築のやうな論理的な高み」に在る法律的正義の前に脯肉[ほしにく]のように列[なら]べられているのだ。果敢なユーモリストだけが、この脯肉を試食するだろう。だが、脯肉とても、腐肉になることがある。その腐肉の本質から目をそらすかぎり、われわれはカニバリズムや戦争の恐怖を告発できないであろう」(#B_103、六四~六五ページ)と。
*
38 考える口が見える時まで
39 だんだんにふとるぼくら肥大漢の兄弟
until the thinking mouth is visible
us swollen brothers who grow fat more and more
「肥大」は、一般には生体の細胞・組織・器官の体積が増加することである。作業性肥大・代償性肥大・仮性肥大。
*
40 キリコの木の頭の点線の十字へ
41 赤い布をかぶせて
the cross-shaped dotted lines of Chirico's wooden head
covering it with red cloth
作風に支配的な建築的要素。顔のないマネキン人形や謎に満ちたオブジェ。近親相姦の恐怖から食人へ。あるいはカニバリズムからインセストへ。十字の紅い割れ目。
*
42 白夜の白衣の父なる医者
father the doctor in white of the nights under the midnight sun
ビャクヤノビャクエノ。/ハクヤノハクイノ。
*
43 椅子の上へすわる
44 異物分娩開始!
sits down to on the chair
begin to be delivered of a foreign body!
異類通婚談/馬娘通婚談。擬娩。日本ではかつて座産が一般的に行なわれていたが、仰臥位で分娩が行なわれるようになった。中国では、産婆は門口に「某氏収洗」あるいは「接生」などと書いた看板を掛け、その下に赤い布を垂らすという。
*
45 たまたまクロブタが鳴く
46 今夜だれか死にましたか?
the black pig happens to grunt
tonight did anybody die?
キリスト教では、ブタとりわけクロブタの場合、悪魔を表わす。「豚の奇妙な屠殺方法に感心する」(#A_25、九四ページ)。一人が産まれるとき、一人が死ぬ?
*
47 スズカケのシームレス靴下の下で
under the sycamore's seamless stocking
篠懸の木の樹皮は大きく斑紋状に剥げおちる。喪服にいつわられた美しい肢体の女が昨日からいる。今は組みあげられた脚線として、ぼくの寛容な肉情の下に在る。
*
48 答えて下さい
49 人のしてないことを
50 考える人
51 人のしているあらゆる行為を
would you please answer
a man who thinks
what people aren't doing
about all the actions people are doing
〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)に曰く。「美しき猫の分娩/そのしている夢/そのうえしてない行為/ぼくたちはどうしている?」
*
52 善なる悪なる共同幻想
virtuous and vicious communal illusion
白夜の白衣の父なる医者。フロックコートの正装のまま存在するために、共同幻想体としてスイートな金魚鉢を支える。
*
53 燃えやすい耳
54 夏のキノコ
flammable ears
mushroom in summer
火のようにほてった耳朶から汗ばむ茎へ。あるいはアトミックボム。
*
55 鳴けよブルーカナリヤ
sing blue canary
ダイナ・ショアに〈青いカナリヤ〉(1953)がある。この、危機の前兆のシンボル。
*
56 空とぶ黒色の
57 終りの矢印
the flying black
arrow of the end
「黒い馬、黒い鳥、黒い幹、黒い葉――ここでは黒が主役だ。ゴーギャンが激賞した〔アンリ・〕ルソーの黒!」(岡谷公二〈解説〉#B_114、一四ページ)
*
58 想像する
59 紅潮する戦車
imagining
blushing tank
①想像する戦車/紅潮する戦車。②私の想像する、紅潮する戦車。
*
60 そのなかのかずかずのスワン
a lot of swans in it
発砲し白熱した主火砲。両性具有としての白鳥は、男性(男根状)を表わす首と女性を表わす(丸い)体を持つ。サッフォーに依れば、アフロディテの黄金の戦車を白鳥が牽いた。ローエングリンになると、白鳥は夜、太陽を乗せた舟を引いて海を渡る。
*
61 ヨードチンキの臭う夜を
the night has a smell of iodine tincture
負傷兵の床。
*
62 印刷された死体の極彩色
brilliant coloring of printed corpse
ここまでの夥しい色の数数。「紫の」窓・「白塗りの」星条旗の下で・タライのなかの「黒人」・食べる「桃色の」人食人種・「赤い」布をかぶせて・「白夜」の「白衣」の父なる医者・たまたま「クロブタ」が鳴く・鳴けよ「ブルーカナリヤ」・空とぶ「黒色の」・「紅潮する」戦車。アンリ・ルソーの油彩画〈戦争〉(1894)には多くの死体が描かれているが、ほとんどが裸の男たちのそれが兵士なのか市民なのかはっきりしない。

アンリ・ルソーの油彩画〈戦争〉(1894)
*
63 明くれば涼しい風景を眺めよ!
take a view of the refreshing landscape when day dawns!
「下二・已然形十ば」の文語の効果は、①雅俗混淆による悲劇的現実の相対化と、②用法の持つ時代の規定である。――すでに明けたのだから。時代が変わったのだから。
*
64 ぼくらの豊饒な草むら・枯むぐら
our thicket and withered grass of fertility
欧文のカタカナ表記以外での中黒の使用は、吉岡の詩には珍しい。それを考慮するなら「豊饒な」は「枯むぐら」にも掛かることになる。音の類似的な変化に対して、意味とイメージは対立する季節を描きだす。ぼくらの現況の雨の葦原。
*
65 粘菌性のマクロコスモス
the macrocosm behaves like fungi
英文は文字どおり拙訳。あえて掲げたのは、原文では曖昧であったり多義的であったりする文意(とりわけ主述関係)に一定の解釈を施すためである。水洗便所はflush toiletだが、初め「紅潮する戦車」(五九行め)をflushing tankとしたものの、これは「(水洗便所の)瀉水槽」の意で、ことは多義性のレベルではなくなる。それにもまして処置に困ったのがこの行だ。粘菌世界のスケールは人間から見ればミクロコスモスのはずである。それが「性の」で結びあわされると、粘菌のイメージと大宇宙の粘菌化のイメージのふたつが選択を迫ってくる――そのような趣きだ。直訳的に反訳すれば「大宇宙は粘菌のごとくにふるまう」。
*
66 千紫万紅の高千穂の峯をふりかえり
67 鳥肌の世界を反省する
68 棒高跳選手
the pole-vaulter
who looks back at Takachiho-no-mine with many violet and crimson flowers
and reflects on the gooseflesh world
赤や紫の花花は満洲の曠野の咲いていなかったか。高千穂峰は天孫降臨(瓊瓊杵尊が天照大神の命を受けて葦原中国を治めるために、高天原から高千穂峰に降りてきたこと)の伝説の地で、山頂に天の逆鉾が立てられている。「雲に聳ゆる高千穂の、高根おろしに、草も木も、/なびきふしけん大御世を、あおぐきょうこそ、たのしけれ」とは、高崎正風作詞による唱歌〈紀元節〉の一番(#B_136、三○ページ)である。――雲の中にそそり立つ高千穂の高い峰から吹きおろしてくる風に、草木もその前に服従しうつぶす神=天皇の御治世を敬意をもって見る今日こそ、満足・安心している感じである。
*
69 バーを越えるとき
when he jumps over the bar
逆鉾と高跳の棒とではたいそう異なるようだが、ここでは勃起した男根の象徴において同一だ。女体は大地。
*
70 不条理な鉄の処女を感じる
we feel the iron maiden of absurdity
「若い女性をかたどり、中に釘が植えられている有名な中世の拷問具は〈鉄の処女 Iron Maiden〉の名で知られる」(荒俣宏)。ここでストップモーションするんだ。「わたしたち輜重兵は、馬運動と称して、毎日のように、馬にのって遠くの部落まで、高粱畑を越して行った。冬は刈られた高粱が、まさに鎗先を揃えて、どこまでも続く。万一にも落馬したら、腹にでも顔にでも突きささるだろう。そんな恐怖感があった」(#A_25、九三ページ)。
吉岡の典拠であろう澁澤龍彦の文章〈エルゼベト・バートリ〉にはこうある。「この鋼鉄製の人形は〔……〕裸体で、肉色に塗られていて、化粧をほどこされ、細々とした肉体の器官が、まるで本当の人間のように生ま生ましく具わっている。機械仕掛で口がひらくと、曖昧な、残忍な微笑を泛かべる。歯もちゃんと具わっているし、眼も動く。本物の女の髪の毛が、床にまで垂れるほど、ふさふさと生え揃っている。胸には宝石の首飾りが嵌めこまれている。/この宝石の球を指で押すと、機械がのろのろ動き出すのである。歯車の音が陰惨に響く。人形は両腕をゆるゆると高く上げる。やがて一定の高さまで腕を上げると、次に人形は、両腕で自分の胸をかかえ込むような仕草をする。そのとき、人形の手の届く範囲にいた者は、否応なく人形に抱きしめられる恰好になる。と同時に、人形は胸が観音開きのように二つに割れる。人形の内部は空洞である。左右に開いた扉には、鋭利な五本の刃が生えている。したがって、人形に抱きしめられた人間は、人形の体内に閉じ込められ、五本の刃に突き刺され、圧搾器にかけられたように血をしぼり取られて、苦悶の末に絶命しなければならない」(#B_059、一○四~一○五ページ)。
「不条理な鉄の処女」とは、吉岡実の「現世」にほかならない。
〈マクロコスモス〉のモチーフはなにか。これは難問である。〈死児〉(④・19)がそうであったようには、事前のモチーフはないという点においてこの詩が他の詩と区別される理由はない。むしろ、この詩もまた「わたしは詩を書く時は、家の中で机の上で書くべき姿勢で書く」(#A_25、八八ページ)例に洩れない。第一行(定稿の最初の行ではないかもしれない)を記す直前までなにが書かれるかは詩人にもわからない、というのはたぶん真実だ。ここにあるモチーフは個人の記憶の神話化のように思われる。個人とは吉岡実その人と限らない。自己の体験や見聞の直接的な表出を避けようとしてきたのが吉岡の作詩法であった。にもかかわらず、その記憶が作品を覆っているのはまぎれもない事実である。それを個人のものから現代を生きる人人のものにする点において、神話化と呼ぶのがふさわしい。悪夢はもはや、個人のものでさえない。モチーフではないが、タブーの排除が狙いかもしれない。それは例の〈わたしの作詩法?〉の「用語」ではなく、吉岡が題材として取りあげたことのなかった戦時が扱われていることを指す。太平洋戦争や昭和天皇や紀元節に対して吉岡は事実関係以外ほとんど書きしるしていないが、かろうじて高橋睦郎に問われてこう答えている。
「暗殺に限らず、殺人自体に否定的です。どういう状況でも、殺人はあってはならないと思う」――「〔軍隊では〕内務で馬の世話をしていました。だから前線の凄惨さは知りません。ただ、天皇のために死ぬことは考えられなくて、何が何でも生きたいと思いつづけました。同時に、紀元二千六百年という長い歴史を持つ国体への誇りもありました」――「〔小説のテーマとしては〕別にありませんが、自分の中で大きな比重を占めているある恋愛事件、それに軍隊体験はぜひ書きたいです」――「詩には個人的な事情は持ちこみたくないのです」(#A_10、一四一~一四五ページ)。
「個人的な事情」を書かないという規制は、戦争そのものを書くことも禁じていた。それは別のものに置き換えられる。カニバリズムとインセスト、食人と近親相姦である(当の戦争も出てくる)。それも明確に描かれるのではなく、神話的思考の下でデフォルメされている。吉岡は先の大戦において、輜重兵として新京、チチハル、ハルピンなど満洲の地で三年余りを過ごした。〈苦力〉(④・13)が満人を主人公にした、当時を背景に持つのに対して、この〈マクロコスモス〉はそれにベトナム戦争とアメリカが焼きかさねられている。《神秘的な時代の詩》の「戦争」は、そうした二重化されたものとして読むべきだ。どちらの戦争も、精神的風景として把握されている。それを反映した不安な文体。この詩と同時期の散文で最も重要な〈わたしの作詩法?〉では〈苦力〉執筆が回想されているが、「兵隊で四年間すごした満洲の体験」そのものが詩に書かれたことはそれまでなかった。
「独身時代の昭和三十三年ごろ、週末に、気が向くとよく谷川温泉へひとりで遊びにいったものである。〔……〕旅館はうす暗く、帳場は遠く、夜がふけるにつれ、水の音だけが聞えるうちに、耐えがたい孤独感というより、無気味さに眠られぬ状態になった。目の前の崖上に廃屋の窓が見える。わたしは朝が来るまで、詩を書こうと試み、そして「苦力」が暁近く完成した」(#A_25、九二ページ)。
ここでも戦争体験を書こうとしたのでなかった。生の不安が詩に「満洲の体験」を呼びこんだと言えようか。一九六○年代後半それ自体が「神秘的な時代」なのではない。一九四○年代前半との対比においてそうなのだ。《神秘的な時代の詩》はその意味で、《僧侶》よりも《静物》よりも《液体》に近い。そのモダンな語彙を洗いながし、もっと呼吸を大きくして、もっと見えるように書くこと。吉岡実におけるシュルレアリスムの再生だ。《液体》との関連は、時代と精神の向きあい方の話になる。そのときのシュルレアリスムは、私たちがふつうに物を見ているその仕方を疑い、書くことで初めて物が存在する詩学の謂だ。視線の強度ゆえに、現実よりも現実的な描写を含むだろう。それを夢と呼ぶならば、この現実こそ夢なのだ。現世で事物をくっきり見ることは困難だ。夢見ることはそれ以上に困難だ。シュルレアリスムが「現実を超える」のはその点においてである。吉岡実におけるすべての手法は、リアリティに奉仕する。詩篇発表の一九六七年はこういう年でもあった。
「〔一九〕六六年に〔……〕建国記念の日は、敬老の日、体育の日とともに、新たに国民の祝日に加えられた。六七年二月八日、建国記念日審議会は多数決で二月一一日を建国記念の日と決定して答申し、翌日政府はその旨を政令公布した」(赤沢史朗)。吉岡実は書く。
「〈日記〉 一九六七年八月二十八日
夜六時半、日比谷の第一生命ホールへ行く。土方巽の弟子石井満隆のリサイタル「舞踏ジュネ」を観る。開幕――舞台の左手の前で、照明が当ると、満隆の虎刈りの頭を、軽便カミソリで土方巽が荒々しく、剃りはじめる。過失か演出か、血がながれ出す。暗転――客席の方まで拡がる巨大な白い布をかぶった満隆が現われ、それを取ると、白塗り全裸で陰茎はバラ色に染められており、しばし狂気の踊り。またひと抱えもあるビクターの犬を、舞台の中央に置き、その廻りを巡るシーンは、美しい叙景詩。息もたえだえに舞手満隆は消えて行くのだ。その後のうす暗い背景に置かれた理髪店の看板が星条旗を付けて、ゆるやかに廻っていた……」(#A_24、一○~一一ページ)。
ここでもう一度、一九六七年を振りかえってみよう。吉岡実は、詩篇・散文ともに多産であった。一月に〈内的な恋唄〉(⑥・12)、二月に〈恋する絵〉(⑥・15)のいずれも《静かな家》の詩と〈春の絵〉(⑩・12)を書き、七月に〈青い柱はどこにあるか?〉、八月に〈夏から秋まで〉(⑦・2)、一○月に〈立体〉(⑦・3)、一一月にこの〈マクロコスモス〉を発表している。散文では、まず五月の〈軍隊のアルバム〉が注目される。また九月の〈日記抄――一九六七〉は、後年の吉岡実における「日記文学」の先駆けとなった。一一月二○日刊行の《詩の本》の〈わたしの作詩法?〉は、一二年後の同様の企画《短歌の本》の鑑賞文を三ヵ月半以上前から執筆していることを考慮すれば(#A_24、一一五ページ)、遅くとも八月初めころから準備していたと思しい。八月二三日に行なわれた入沢康夫との対談〈模糊とした世界へ〉(#C_005)で〈わたしの作詩法?〉の予行演習もしくは復習がなされていることは言うまでもない。このときの吉岡の思考は、全詩集上梓という中仕切りを機会に自作を客観視する作者のものだ。
私たちが《神秘的な時代の詩》の成果を把えられるようになったのは、ごく最近のことではないだろうか。吉岡実が次のように書くのは一九八九年、実に刊行して一五年も経ってからである。――『神秘的な時代の詩』はひとことで言えば、まがまがしい詩集である。言葉の「疾走感」、「浮力性」もしくは「破片の散乱」などと、友人、知己から厳しく、たしなめられるばかりだった。当然のことながら、さすがの私も意気消沈してしまった。そんな雰囲気が漂っていた時、篠田一士は好意的に評価してくれたのだ。〔……〕/私はこのひとことで、救われたのだ。感謝をこめて、手紙を書いたように思う。近ごろ、若い詩人たちに、この詩集は評価されはじめたようである。(#C_042、七○ページ)
省略した引用文で吉岡が触れている篠田の「評価」は〈詩人の運動神経について 現代詩髄脳Ⅰ〉(#B_054、六~四二ページ)である。もっとも、篠田は《僧侶》の詩人を発見〔ユリイカ〕して以来、一貫してその支持者だったから、吉岡の、あえて言えば無謀な試みにも讃辞を借しまない。こうした危険な領域に、なにゆえ吉岡は入りこまなければならなかったのか。一言で言えば、《静物》に始まり《静かな家》で終わる全詩集版《吉岡実詩集》(#A_08)と拮抗する詩篇を書きつぐためである。さらに言えば、その中核をなす〈僧侶〉(④・8)と〈死児〉という、今日でも吉岡の詩業を代表すると目される作品と対決するためである。しかし、その覚悟のほどは次のように控えめに述べられているにすぎない。「校正すべく、自己の詩をよみながら、たえず停滞感を味わつた。わたしは今、反省とある種の意図を試みようとしている」(#A_08、三六四ページ)。
(1)初出:《三田新聞》一一四六号、一九六七年一一月二二日
(2)所収:《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》一九六八年九月一日
(3)再録:《現代詩手帖》一九六八年一二月号〈現代詩年鑑69〉
(3)には〈神秘的な時代の詩〉(⑦・11)と〈マクロコスモス〉が再録されているが、〈神秘的な時代の詩〉は雑誌初出をそのまま原稿にしている。一方、〈マクロコスモス〉は(2)、(3)とも定稿と同じで、初出形の次の六箇所が改められている。
(a)白塗りの星〔條→条〕旗の下で
(b)ぼくらの現況の雨の〔葺→葦〕原から
(c)だんだんと〔殖え→減〕る
(d)水のなかのトンボの〔印→卵〕
(e)千紫〔萬→万〕紅の高千穂の峯をふりかえり
(f)不〔條→条〕理な鉄の処女を感じる
(a)(e)(f)は旧字から新字への変更で、初出形は原稿(未見)のとおりかもしれない。(b)(d)は誤植の訂正。吉岡実の詩稿は陽子夫人によって楷書で書写されており、誤植は起きにくいと考えられる。初出紙における二件の誤植は、校正の精度を疑わせるに足りる。傍証を挙げよう。〈マクロコスモス〉本文のあとにはイラストの廣瀬俊恵と吉岡実の紹介が載っているが、編集部の執筆と思しいその「吉岡実(よしおか・みのる)氏は、一九一九年東京生れ。一九五五年処女詩集「生物」刊行。一九五九年「僧侶」でH氏賞受賞。現在ワニの会々員」は「〔……〕一九五五年処女詩集「静物」刊行。〔……〕現在鰐の会会員」とあるべきところだ(ときに〈鰐の会〉はまだ存続していたのか?)。かくして、内容に関わる吉岡の訂正は(c)のみとなる。「だんだんと殖える/水のなかのトンボの卵」。
さて、当時ほかの詩人たちは吉岡の詩をどのように読んでいたのだろうか。次の〈私の選んだ今年の代表作〉は(3)〈現代詩年鑑69〉からの抜粋である。
《静かな家》ですでになされている「ある種の意図」の先蹤は、吉岡が一九六五年一○月一七日付永田耕衣宛書簡に「「無限」十九号に発表した《やさしい放火魔》はちかごろ好きな詩篇です。新刊ゆえ店頭でいちべついただければ幸甚です」(#C_047、二一ページ)と書く〈やさしい放火魔〉(⑥・9)である。ビートルズの〈ペニー・レイン〉(1967)を思わせるこの作品への並並ならぬ自負は明白だ。ところで、吉岡が《静かな家》に言及した最も早いものは、一九六六年一○月の《詩と批評》第六号の〈アンケート〉の「2 私のこれからの仕事の予定――「吉岡実詩集」(新詩集「静かな家」を含む全詩集)を出すこと」(#C_017、九五ページ)であろう。単行詩集として日の目を見たのは一九六八年の八月三一日だが(#A_24、二一ページ)、予告どおり刊本となったのは一九六七年一〇月刊の《吉岡実詩集》であって、アンケート時にまだ書かれていない詩が三、四篇あった。しかしすでに〈やさしい放火魔〉があり、アンケートの翌月に〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)がある以上、詩集としての《静かな家》は成立していたと見てよい。
ここで《静かな家》の構成を見よう。詩集《僧侶》では、眼目の〈死児〉を巻末に置くことで順序が入れかわっているが、詩篇の配列はおおむね発表順(正確には執筆順)である。《紡錘形》も〈紡錘形Ⅱ〉(⑤・5)を〈紡錘形Ⅰ〉(⑤・4)の直後に置くために繰りあげたのが目立つくらいで、ほぼ発表順に並べられている。逆に言えば、調べのつかない〈模写――或はクートの絵から〉(⑥・4)も一九六三年から六四年に書かれたのではないかと想像できるくらい、この《静かな家》も発表順の原則は揺らいでいない。【〔2016年10月31日追記〕詩篇〈模写――或はクートの絵から〉の初出掲載誌は、1963年8月発行の俳句同人誌《海程》9号〔第2巻9号〕だと判明した。】そこから大きく外れるのは、〈無罪・有罪〉(⑥・2、《僧侶》で最も後の〈感傷〉(④・18)と《紡錘形》で最も先の〈老人頌〉(⑤・1)の間で発表)と〈静かな家〉(⑥・16、《紡錘形》の最後の〈沼・春の絵〉(⑤・2)、〈修正と省略〉(⑤・22)の後産と言える)の二篇である。
《神秘的な時代の詩》の早い時期の作品は、書法としては《静かな家》後期の〈孤独なオーバイ〉や〈内的な恋唄〉に近いものでありながら、回転運動から、遠近や上下の直進運動が多くなっている。「矢印」は直進の方向指示である。家を中心にその周囲を旋回していた視線は、そこから時代に向かって放たれる――そうした構図が基本となっている。極めて似た素材を用いながら、次に引く〈恋する絵〉と〈マクロコスモス〉はその違いを示している。それは、〈わたしの作詩法?〉で自己と自作の過去を取りあげて、意識的に変貌を図っていることもうかがわれる。
恋する絵|吉岡実造る生活
造られる花のスミレ
ばらまかれたあるものをはさむ
洗濯バサミ・洗濯バサミ
それは夜の続きで
水中の泡の上昇するのを観察する
恋する丈高い魚
白いタイルの上では
考えられない黒人たち
その歯のなかの蜂
雨ふる麻
ぼくがクワイがすきだといったら
ひとりの少女が笑った
それはぼくが二十才のとき
死なせたシナの少女に似ている
肥えると同時にやせる蝶
ひろがると同時につぼまる網
ごぞんじですか?
ぼくの想像姙娠美
海へすすんで行く屍体
造られた塩と罪の清潔感!
幼時から風呂がきらいだ
自然な状態で
ぼくの絵を見ませんか?
病気の子供の首から下のない
汎性愛的な夜のなかの
日の出を
ブルーの空がつつむ
コルクの木のながい林の道を
雨傘さしたシナの母娘
美しい脚を四つたらして行く
下からまる見え
そこで停る
東洋のさざなみ
これこそうすももいろの絵
うすももいろのビンやウニ
うすももいろの耳
すすめ竜騎兵!
うすももいろの
矢印の右往左往する
火薬庫から浴室まである
恋する絵
「ばらまかれたあるものをはさむ」ために、「矢印の右往左往する」のもやむをえまい。ここの「肥えると同時にやせる蝶」は〈マクロコスモス〉では「肥大漢のぼくらの姉妹」「肥大の子供」「だんだんにふとるぼくら肥大漢の兄弟」という具合に、だれもかれもが肥大するばかりだ。福島章の「吉岡氏の詩の中で最も興味ある特徴は、対立し、矛盾する二つのことばの頻繁な接合である。〔……〕それらは、あるべき姿への常識的な期待に、はげしい衝撃を与える。/さらに、この矛盾はイメージとしてはスフィンクス的像を結ぶ」(#C_039、一三九ページ)という病理学的考察は、詩集《紡錘形》あたりまではまさにそのとおりだが、〈マクロコスモス〉では「矛盾する二つのことばの頻繁な接合」よりも、行と行の対立へと重点が移動している。詩人自ら語っている。
「一行一行で見れば、リアルなことしか書けない。「コップが人を飲む」なんてことは書かない。現実主義でやってきたと、ぼくは思っています。成り立ちというか方法からああいう詩になっていても、夢でなくて、現実を描いているつもりです。だから、一行一行分析してみれば、そんなに唐突なことは書いていないですよ。意識的にやった妙なものもなかにはあるけれども、リアリティのあるものの積み重ねを努めてやっているわけです」(#C_005、六○ページ)。
次の〈春の絵〉(⑩・12)も同様の書法である。全篇を引く。
「梨の畑で/きらきら輝くのは/カタツムリ?/それとも死んだ兵士の心?/ぼくたちが家畜小屋から眺める/奇妙な世界の絵は/円で造られた黒/その焦点を泳ぐスワン/天気はどうか?/ある種の水生植物を下の方へつける/黒人の歯のなかへ/春の蝶を/少女が捕えに行く」
短いだけに、この作品は〈恋する絵〉や〈マクロコスモス〉の大画面に比較すれば展開の豊かさに欠けるが、タッチはほとんど同じだ。「死んだ兵士」とは自己に隣接する存在だ。彼方の世界ではなく、日常のすぐ隣を描くこと。動植物もすべてシンボルだ。スフィンクス/キメラ的なイメージも減り、物は変化し、者は変貌する。もしくは行動する。同時に「円」から水平運動への変貌も見のがせない。最小ユニットが語から行になったことを考えれば、主題や動機とは別の角度から《静かな家》や《神秘的な時代の詩》を把えることができるに違いない。
《静かな家》所収の最も早い作品〈無罪・有罪〉は「詩と写真」として、大辻清司の写真を伴って大森忠行の構成で発表された。詩と写真のどちらが先行したか不明であり、詩と写真の双方に対応する事物はいくつかあるが、それが重要なのではない。重要なのは、四つの断章(「破片の散乱」の前兆?)によって作品が構成されることだ。この詩篇は書肆ユリイカ版の《吉岡實詩集》(#A_06)の〈未刊詩篇〉に収められながら、〈老人頌〉や〈果物の終り〉(⑤・2)のようには《紡錘形》に入れられず、〈ポール・クレーの食卓〉(⑩・1)や〈ライラック・ガーデン〉(⑩・3)や〈サーカス〉(⑩・2)のように二○年も拾遺詩篇として放置されたわけでもない。文体・詩型ともに《静かな家》のなかでは異色のものだが、犯罪/犯罪者というモチーフからすれば、まさにこの詩集になくてはならない詩篇である。犯罪をめぐる詩集のあとに、戦争をめぐる詩集が来る。《静かな家》の詩句を引く。
拡声器のように大きな声が父の不正な仕事をあばく/兄は女を孕ます罪をあばかれる
(〈劇のためのト書の試み〉⑥・1)
彼の記録は森林放火十四回
肥っていることが罪なら/チャリーの体重は零
(〈やさしい放火魔〉⑥・9)
運転手のくびを絞める
(〈春のオーロラ〉⑥・10)
殺人者のすきなストロベリージュース
少女を絞め殺すべき契約を欲する
ぼくは殺人者で/死にたがっている猫
ぼくの弟は痴漢で冬のさびしい森を行く
ぼくが殺した運転手/きみらが殺した服飾デザイナー/かれらが殺したミス・シナ
ぼくが殺人者になった/喜ばしい読書時だ
ぼくの不倫がつくる/麦畑へ/きみたちが火事をみちびく/ついでにケシの畑まで/灯る人家を焼き/密通した人妻の/幼女のマヌカンをぼくは抱くだろう?/糸杉の狂える夜ごと夜ごとを/きみがぼくを殺しにくる
かれらがきみらを殺しにくる
子供は育ってはいけない/むしろ生れてはなお罰せられるんだ
(〈内的な恋唄〉⑥・1)
とりわけ〈内的な恋唄〉は犯罪の百科全書のごときである。すべての子供たちは犯罪者となるべく育つ。それゆえ罰せられなければならない。だが、罰するのはだれ?
「ミクロコスモス」はいろいろ用例を挙げることができるのに対して、「マクロコスモス」はあまり使われないようである。〈わたしの作詩法?〉では〈苦力〉の引用の直前に「小宇宙」があるし、詩篇〈示影針(グノーモン)〉(⑧・27)の副題「澁澤龍彦のミクロコスモス」もある。周辺を見ても、吉岡が随筆(#A_25、二一五ページ)で触れている飯島耕一と伊原通夫の詩画集《ミクロコスモス》(書肆ユリイカ、1957)があり、大岡信には《ミクロコスモス 瀧口修造》(みすず書房、1984)がある。大岡の本は〈マクロコスモス〉の後の出版だから外すが、吉岡が標題を決めるに当たって飯島の《ミクロコスモス》が頭を掠めなかったとは考えにくい。吉岡は詩篇発表の翌一二月号《現代詩手帖》の〈今年の問題作〉に次のように書いている。
「今年の問題作は何かと問われても、簡単に答えられない。なぜなら、多く読んでないし、前半期の作品で失念したものがあるだろうから。〔……〕しかし一番印象にのこるのは、飯島耕一の連作詩《見えるもの》。それにつづく、近作《私有制にかんするエスキス》であろう。詩集《何処へ》の体験的世界から一転して、シュールレアリスムへの回帰というより、新しい面からの果敢な挑戦を試みている、二つの連作詩――実験的不安定さと奇妙に均整を保ちつつ大きく育成される詩的現実を注視している」(#C_006、六四ページ)。
「シュールレアリスムへの回帰というより、新しい面からの果敢な挑戦を試みている」のはほかでもない、この時期の吉岡実である。飯島の《ミクロコスモス》の一篇(水の磁石は)を評した「硬質の輝きに溢れた珠玉の詩」(#A_25、二一五ページ)とは異なる世界を築こうとしたとき(それは《静物》の世界、つまり吉岡にとって自家薬籠中のものだから)、吉岡の採用した語が「マクロコスモス」だったことはおろそかにできない。この作品の印象は他の作品以上に顕著である。詩集を大宇宙とするなら、この詩は小宇宙ということになる。だが、実際はこの作品こそ大宇宙=マクロコスモスと名づけられているのだ。高橋睦郎の言うように「この作者の場合、しばしば題名に深い意味はない」(#A_23、五四ページ)にしても、その寄って来るところは明らかにしなければならない。
村上陽一郎によれば、プラトンには「父ウーシアと母コーラの子たる宇宙」という創成の原理が見いだせ、宇宙を大宇宙[マクロコスモス]としたときに人間はそれと対比を持つ小宇宙[ミクロコスモス]として把握されるという。一方、吉岡にあってマクロコスモスは「現世」のリアリティが濃厚である。〈マクロコスモス〉が《神秘的な時代の詩》の諸篇の展開の礎、主題の提示であるという作業仮説。このギリシア語に対応する英語macrocosmの意味は「①大宇宙、大世界〔対語はmicrocosm〕②(下位体系から成る)全体系、大統一体」である。後者として考えればそのようになるだろう。詩篇固有の題名のときは「深い意味はない」が、詩集にまとめられ巻頭に置かれたときから、それは変化しはじめる。所収作品も〈マクロコスモス〉を受けて変貌しなければならない。すなわち「神秘的な時代の詩(複数)」であり、「善なる悪なる共同幻想」としての大宇宙、この苛烈な世界と吉岡実という美意識の優った詩精神がどのように出会ったか――その成果としての一七篇の異稿ということになりはしまいか。ここからただひとつの、かつてなくいまもってない〈神秘的な時代の詩〉という長篇詩に変貌するのはあと一歩という気がする。吉岡は、どこかのアンケートの「これから書きたいもの」という問に「現世をテーマの長篇詩」と答えていた。
吉岡実は一二冊の詩集を出している。戦前に①詩歌集《昏睡季節》(1940)、②《液体》(1941)があり、戦後の③《静物》(1955)、④《僧侶》(1958)、⑤《紡錘形》(1962)、⑥《静かな家》(1968)のあと、私たちがいま読みつづけている⑦《神秘的な時代の詩》(1974)が来る。⑧《サフラン摘み》(1976)、⑨《夏の宴》(1979)、⑪《薬玉》(1983)、⑫《ムーンドロップ》(1988)のほかに、⑩拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(1980)があるが、これらの詩集は螺旋階段のようなふたつのサイクルを構成する群と見なせる(下図参照)。すなわち《液体》および《昏睡季節》に始まり《静物》で第一段階に入る《僧侶》→《紡錘形》→《静かな家》のグループと、《神秘的な時代の詩》に始まり《サフラン摘み》で第二段階に入る《夏の宴》→《薬玉》→《ムーンドロップ》のそれである。独立的な位置にある《液体》および《神秘的な時代の詩》に対して《静物》:《僧侶》、《紡錘形》:《静かな家》、《サフラン摘み》:《夏の宴》、《薬玉》:《ムーンドロップ》というペアが生じ、それぞれの版元が書肆ユリイカ、思潮社、青土社、書肆山田に代表されるのも奇しきありさまである。
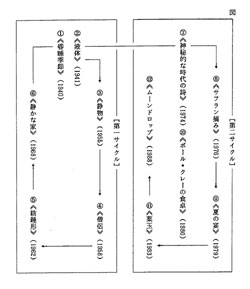
図 吉岡実の詩集群の関係
渋沢孝輔や入沢康夫や高橋睦郎のように、《紡錘形》《静かな家》《神秘的な時代の詩》をひとまとめにして、あたかも《僧侶》から《サフラン摘み》に至るまでの吉岡の低迷期とする見方がある。私見によれば《神秘的な時代の詩》はサイクルやペアを構成しない、詩集群のなかでは孤立した(《液体》と較べられるべき)新たな始まりなのだ。むろんそれは《静かな家》から試みられている文体の目覚ましい成果と大いに関係があるし、《サフラン摘み》の、とりわけ初期作品との類似も容易に指摘できようが、そうしたグラデーション的な差異に目を奪われていたのでは吉岡実の詩集群の関係は見えてこない。ペアを成すのにほぼ一〇年、ふたつのサイクルに約二〇年間のタイムラグがあることは興味深い――と一九九〇年当時には考えていたが、二〇〇六年時点では《静物》から《静かな家》までを大きく「前期吉岡実詩」、《神秘的な時代の詩》から《夏の宴》を「中期吉岡実詩」、《薬玉》と《ムーンドロップ》を「後期吉岡実詩」と考えていることを申しそえておこう。
吉岡実は大岡信にこう語る。「ぼくはやっぱり、絶えず変りたい。〔……〕われわれの道は戻る道なのか、戻らない行きっ放しの道なのかもわからないけど、行きっ放しでいいんではないか」(#C_039、一五八ページ)。
Ⅲで触れたように、〈マクロコスモス〉は一九六七年一一月の《三田新聞》に発表後、翌年刊の《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》の〈未刊詩篇から〉に〈立体〉〈青い柱はどこにあるか?〉〈夏から秋まで〉のあとに〈フォーク・ソング〉(⑦・7)を従えて収められた。そこでの配列は発表順を基本に、雄篇〈立体〉をトップに据えたものだ。吉岡自身と思われる編者の意向であろう。編者としての吉岡実は後年こう書く。編著がこれ以外ないだけに、貴重な証言だ。
「私は軽い気持で、永田耕衣さんにいずれそのうち、〈耕衣百句選〉をつくりますよと、いってしまった。〔……〕私は今その約束を果しつつあるが、根源自然な俳人の全句業から百句を選ぶのも、また困難な仕事である。/私は心すなおに、初期の句から再読、三読して採ってゆくことにした。出来るだけ年代順に従ったが、あえて冒頭の一句は入れ替えてみた。なぜなら、茅舎の名句「白露に金銀の蠅とびにけり」を、想起させる華麗な「絵馬の蜂牡丹の蜂に混りけり」で、耕衣百句を飾りたかったからである」(#A_37、一○七~一○八ページ)。
美的見地からは、〈未刊詩篇から〉がそうであったように〈立体〉を詩集の巻頭に据えてもよかった。だが、そうはならなかった。《ユリイカ》吉岡実特集号掲載の《神秘的な時代の詩・抄》(#C_039)の目次と〈注記〉を読もう(題名に付随する番号や年月等は論者による)。
〔《神秘的な時代の詩・抄》の目次〕(同誌、〔一五九ページ〕)
発表順 詩篇番号 題名 発表年月 17 ⑦・14 低音 1970年3月 7 ⑦・11 神秘的な時代の詩 1968年10月 11 ⑦・17 三重奏 1969年3月 12 ⑦・12 蜜はなぜ黄色なのか? 1969年4月 8 ⑦・8 崑崙 1968年10月 6 ⑦・4 色彩の内部 1968年8月 - 未刊詩篇・12 スワンベルグの歌 1969年2月 15 ⑦・10 聖少女 1969年11月 16 ⑦・18 コレラ 1969年12月 〔《神秘的な時代の詩・抄》の〕注記(同誌、一七一ページ)
詩集『神秘的な時代の詩』は、ここに掲載された作品のほかに、すでに思潮社版『現代詩文庫14・吉岡実詩集』に収められている
4 ⑦・1 マクロコスモス 1967年11月 5 ⑦・7 フォーク・ソング 1968年7月 2 ⑦・2 夏から秋まで 1967年8月 3 ⑦・3 立体 1967年10月 および、現代詩手帖に発表された
14 ⑦・16 わが馬ニコルスの思い出 1969年10月 などを含み、湯川書房より刊行される予定である。
《抄》での掲載作品数は九篇、言及作品は五篇。詩集は一八篇から成るから、余すところ四作品の勘定だが、〈スワンベルグの歌〉が詩集に収められなかったので、次の五作品になる。
| 1 | ⑦・6 | 青い柱はどこにあるか? | 1967年7月 |
| 9 | ⑦・9 | 雨 | 1968年11月 |
| 10 | ⑦・5 | 少女 | 1969年1月 |
| 13 | ⑦・13 | 夏の家 | 1969年8月 |
| 18 | ⑦・15 | 弟子 | 1972年8月 |
《抄》発表の一九七三年九月までに上記すべての作品が書かれているものの、「詩集」はまだこの時点でできていない。《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》に収録された作品群(すなわち〈立体〉〈青い柱はどこにあるか?〉〈夏から秋まで〉〈マクロコスモス〉〈フォーク・ソング〉の五篇)をAとすると、〈注記〉はAの目次の順番とは異なって〈マクロコスモス〉と〈フォーク・ソング〉を最初に挙げているのが注目される。しかし、これとて〈マクロコスモス〉を詩集の冒頭にもってくることには直結しまい。
《抄》の作品群をBとすれば、AとBで重複はありえないから、BはAよりも後に発表された(もしくは書かれた)というほか、さしたる意味はない。A・B以外の作品群をCとすれば、〈雨〉(⑦・9)、〈少女〉(⑦・5)、〈夏の家〉(⑦・13)、〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)、〈弟子〉(⑦・15)の五篇がCに該当する。そのうち、〈わが馬ニコルスの思い出〉は集中最大の一六三行の長尺ゆえ、また〈夏の家〉は同じ《ユリイカ》誌発表ゆえ、再録されなかったと考えられる。また〈少女〉と〈弟子〉は、定稿を見るかぎり、初出形への慊焉たる思いが《抄》に収録させなかった理由だろう。吉岡実が詩集の成立に触れた数少ない談話がある。《ムーンドロップ》刊行の前年、松浦寿輝がこう問いかける。――もう次の詩集も『ムーンドロップ』という題名だと伺っていますし。
「ええ。来年の秋にでもと思ってますけどね。あと四篇くらい書けば、二○篇になるんですよ〔刊本では一九篇収録(註)〕。この前の『薬玉』は、日本の古語とか土俗伝承とかで、わりと統一がとれていたでしょ。だから今度はモダンにいこうと思ってね。それでタイトルはもう『ムーンドロップ』に決めたんだけど、でも時々やっぱり雅語や古典的イメージが入ってしまってね。だからあとの詩篇はモダンな感じにしたいんですけど」(#C_041、二五八ページ)。
詩集の八割くらいの作品数を書いたところで書名が決まる(ちなみに《ムーンドロップ》はナボコフの、いや正確にはジョン・フランシス・シェイドの英雄対韻句の詩〈青白い炎〉の第九六二行「月明り[ムーンドロップ]的な題名」から来ている)。前作と較べて同じにならないよう、詩集の構造から要求される内容に詩篇を仕立てる。しかし、このやり方は《神秘的な時代の詩》には当てはまらないようだ。最後の作品が発表されてから詩集刊行までの二年以上の間に、次の《サフラン摘み》を形づくる重要な詩篇〈葉〉(⑧・4)や〈ルイス・キャロルを探す方法〉(⑧・11)が発表されているからである(もっとも最終の〈弟子〉の執筆はそれらに先立つかもしれない)。いったい吉岡は詩集をまとめるのに熱心な部類の詩人だが、《神秘的な時代の詩》は《静かな家》と並んでその数少ない例外のようだ。
筑摩書房での吉岡実は長く宣伝畑を歩んだが(あの引用の手腕は職業的にも鍛えられたのだ)、結婚前の陽子夫人も同社で働いていたことがある。また〈死児〉のころから、詩篇の浄書は夫人の役割だ。森茉莉が《記憶の絵》の〈後記〉に書いている。「吉岡氏が暑い最中を何度か、私の部屋の近くの邪宗門という喫茶店にお出でになる内に、本の造りのことも定り、頁数が少し足りないのを補うための書き足し十篇(三十枚分)も出来上り、推敲も終り、吉岡氏の夫人が、熊本日日新聞の切り抜きを一枚、一枚原稿紙に張って下さった部厚い原稿と、その三十枚の書き足しとは筑摩書房の厚いハトロン紙の袋におさまり、印刷所に廻すばかりになった」(#B_153、二二三ページ)とは、とりもなおさず吉岡の詩集のための原稿の物理的な姿でもあろう。「わたしの大切なもの」に「詩集《静物》の原稿(これは書下し故に、唯一の原稿の残っているもの)」(#A_25、四五ページ)を挙げる吉岡の詩稿のほとんどは、上記のようなものと思しい。そこになんら特別なものはない。自筆による浄書稿が存在しないことを除いては。吉岡は金井美恵子に語っている。
吉岡 「私の作詩法?」でも言ってるかわかんないけど、とにかく詩は最初の白い原稿用紙でできるだけ持続したいわけね。だから発想してきたものをそこへどんどん繰りこんでいく。できるだけ最初に出た言葉を大事にして、たとえつまらない言葉でも出てきた以上はそれを大事にしていく。つまってしまうと別の新しい原稿用紙で直しながらやる詩人も多いし作家も多いと思うのよ。だけどぼくは最初の一枚の原稿用紙というのを大事にして、そこにどんどん書きこんでいく。それであるところまでいくと、今度はそれを家内に清書してもらう。家内は、ぼくのひどい字も誤植を補足しながら書き写すでしょ、するともう客観的になっちゃうのね、自分の詩も。非常に小さな字で全貌がほぼわかるわけ。
金井 自分の筆跡とまったく離れちゃっているわけだから……。
吉岡 言ってみればほぼ活字体になってる、それを眺めつつ、またそこに書きこんで行く。その繰り返しが、物によっては何日も繰り返されて行く、そういう形でぼくの詩はできている。
金井 そのへんの推理〔推移か〕、変わり方を一番よく御存知なのは奥さんの陽子さんということになるわけですね。
吉岡 そうなの。それで全部放棄〔破棄か〕したかって言うと現在破いてなくて案外とってある。ただ、それをあえて読者の眼にさらすこともないんだし……。
金井 それは実に見てみたい(笑)。
吉岡 いや、それは人に見せられないひどいものよ。作家というのは自分が第一の鑑賞者になるけど、うちの場合は家内だね。だから笑い話になるけど、家内がある時期、『神秘的な時代の詩』をずうっと写しているでしょ。家内はかねてからにがにがしく思っていたんだって、こんな散漫な詩をどうして書いているのかって、あの中の最後の「コレラ」ができた時に初めて「いい詩ができたわね」と言ったんだ。それで他はみなよくないって言うわけよ。ぼくとしては「わが馬ニコルスの思い出」ぐらいは認めて欲しかったね。これは大変な喧嘩で夫婦の危機の一大事(笑)。こうなったら心中でもしようかと目張りまで用意したと、後年、家内から聞いて、笑うやら、ぞっとするやら。(#C_010、九八~九九ページ)
詩はこのようにして書かれる。では詩集はどのようにして作られるのか。まず素材。書きおろしを含めて、すべての原稿が机上にある。雑誌や新聞に載ったものなら、切りぬきが原稿用紙に貼られてある。一篇ごとに紙縒りで綴じられる。再読三読して詩篇の決定稿が作られていく一方で(訂正はあったりなかったり)、最終的な書名の吟味が行なわれる。出版社や編集者の要望もあろう。〈昏睡季節〉や〈液体〉や〈静物〉や〈紡錘形〉のように連作がある場合はもちろん、収録詩篇のひとつを転用するのが落ちつくだろう(粟津則雄や飯島耕一や吉増剛造が一九六八年の代表作に選んだ〈神秘的な時代の詩〉)。作品の出来もさることながら、書名となったときの感じや過去の作品との並び具合も重要だ。あるいは意図的にその傾向から外してみることも。ついに書名が決まる。詩集の方向性が決定したのだ。その下でひとつひとつの詩篇の順序配列が考慮される。とりわけ巻頭と巻末になにをもってくるかに腐心する。長短の変化に乏しいのも困るが、詩集全体に一本筋が通っているようなのも困る。理に落ちてはつまらないからだ。大きなクリップで仮留めした順番で良しとなれば、最後に目次と初出記録の原稿を起こして入稿作業のめどがつく。本文活字の大きさや基本版面もすでに考えてある。装丁のプランも平行して進める。初校の引きあわせは担当編集者と陽子夫人が行ない、一回めの素読みをする。再校で二回めの素読みをして、校了(責校)となる。
その順番が問題だ。この時期を締めくくるのはやはり一九六九年暮れの〈コレラ〉(⑦・18)である。巻末にはこれを据えてその到達点としよう。〈わが馬ニコルスの思い出〉も末尾近くに置く。この辺りの関係は《僧侶》の〈死児〉と〈感傷〉に近い。前の詩集《静かな家》の巻末はタイトルポエム〈静かな家〉で、それは《紡錘形》の最後の詩篇を書きあげた余熱がもたらした「自動記述」的作品だった。トップには「イメージのいけどり」として最も目覚ましい効果を上げていて、天沢退二郎も買ってくれた〈マクロコスモス〉をもってこよう。池田満寿夫や土方巽といった敬愛する芸術家たちから触発された詩篇には〈立体〉をからめて、そのあとに〈崑崙〉(⑦・8)や〈神秘的な時代の詩〉を配する。その間は適宜ほかの詩篇で繋いでゆく、あるいは切ってゆくと言っても同じだ。さて、〈スワンベルグの歌〉はどうしたものか。吉岡実は《神秘的な時代の詩》にいたって、初めて編年体でない詩集の構成という問題に直面した。ここに「中期吉岡実詩」が出現したのである。
(一九九○・二・四~六・二五)
末尾の初稿執筆期間が示すように、本評釈は吉岡実さんが亡くなられる数ヵ月前に起稿し、一九九〇年五月の急逝の翌月に脱稿した。その六月は、のちに追悼文〈みなづきの水〉となる日録を執筆しつつ、評釈を書くことで吉岡実の非在に耐えるしかなかった。〈マクロコスモス〉の英訳は余人の力を借りず自分の判断だけで作成した。そのため、英文として問題があるに違いない。初稿をほぼそのまま掲載した文字どおりの拙訳は、詩の「評釈」としてお読みいただければありがたい。
燃える暖炉へ薪をくべる下男らしい半裸の男の後姿は(至福)そのものである。――吉岡実(#A_25、三六二ページ)
一九九一年五月の吉岡実一周忌を前に《現代詩読本――特装版 吉岡実》(#A_32)が刊行された。大岡信、入沢康夫、天沢退二郎、平出隆選出の〈代表詩40選〉には、詩集《神秘的な時代の詩》から大岡選〈聖少女〉(⑦・10)と入沢・平出選〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)が再録されている。ほかに大岡が〈神秘的な時代の詩〉(⑦・11)、入沢が〈立体〉(⑦・3)、平出が〈コレラ〉(⑦・18)を選んでいるが、総じて票は割れていて、ここで評釈の対象とする詩篇〈フォークソング〉(⑦・7)は選ばれていない。すなわち「代表詩」ではない。これまで詩集《神秘的な時代の詩》としてまとめられることになる作品を発表順にとりあげてきたわけだが、念のためにそれを記すと〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)、〈夏から秋まで〉(⑦・2)、〈立体〉、〈マクロコスモス〉(⑦・1)、そして〈フォークソング〉で、〈代表詩40選〉に再録されている作品は〈立体〉一篇しかない。この詩集全体に関しては、松浦寿輝の「その散漫な文体[、、、、、]が始めから終りまで全行を疾走しつくしていて、散漫さの擬態でもって書物全体を統合している」(同書、一五五ページ)という評が核心に触れている。いましばらく評釈を続ける以外、その「散漫さの擬態」に匹敵する術はない。
〈フォークソング〉(黒の会発行の雑誌《同時代》第二三号、一九六八年七月)は、前作〈マクロコスモス〉以来八ヵ月ぶりの、一九六八年最初の詩篇である。この年は翌八月に〈色彩の内部〉(⑦・4)と〈スイカ・視覚的な夏〉(⑩・13)の二篇、一○月にも〈神秘的な時代の詩〉と〈崑崙〉(⑦・8)の二篇、一一月に〈雨〉(⑦・9)、と年の後半に作品が集中していて、〈マクロコスモス〉と〈フォークソング〉の間に短めのブランクを見ることになる。もっとも、年の前半には三篇の散文(三月の〈好きな場所〉、四月の〈白石かずこの詩〉と〈読書遍歴〉)が発表されているから、おそらく吉岡自身にブランクの意識はない。奥付の日付が七月二三日の詩集《静かな家》の刊行準備や九月一日発行の《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》にも時間を取られていたに違いなく、《同時代》の原稿依頼から発表の時期まで、上半期中この詩篇にかかっていたわけではないだろう。詩篇〈フォークソング〉の定稿を引く。
*
フォークソング|吉岡実01 むらさきのスミレが咲く
02 マダム・トラコーマはすきな形の
03 舟をみつける
04 その下は水でなく
05 ダイナミックに煮える粥のような波
06 たよれる
07 たよりになる棒とは?
08 どれほどの太さと長さを持っている人
09 ももいろのビニール製品の
10 たくさん垂れている
11 向う側とはどんな凹面! 突起態!
12 どんな赤ん坊が産まれているのかね?
13 梨籠のなかには
14 カルシュウム乳
15 もしくは釘
16 ナチスの制服の人型の空胴の青空を見よ
17 つるべうちにうたれた
18 兎のそよぐ春風の毛の下で
19 国家治安のために
20 母親たちがたれながしのまま
21 双生児をうむ
22 ながれる舟のなかに
23 発泡状の球体群
24 空は暗い菱形に見え
25 バロック風な鍋から
26 立ち上る
27 雄鶏
28 よく見れば
29 鉄製器具の寄せ集めでつくられた
30 危機の蝶番の結合
31 赤塗りのトウモロコシの
32 とさかをなびかせよ!
33 復讐とは
34 ねじること
35 それぞれの夕闇へ
36 コウモリをとばさんとする
37 処女の子宮をふさがんとする
38 灯る内装芸術
39 タクシー乗場から軍艦の丸窓まで
40 夜目にもしるく
41 金色の矢印をつける!
42 この前兆的なる
43 内的構図の終りか?
44 動くインテリア
45 ヒバリがしきりと鳴きのぼるとき
*
本篇の掲載状況を次に掲げる。
a 《同時代》第二三号(一九六八年七月一五日)〔初出〕
b 《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》〈未刊詩篇から〉(思潮社、一九六八年九月一日)
c 《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、一九七四年一○月二○日)〔初刊〕
d 《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、一九七五年六月一日)
e 《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、一九七六年八月一五日)〔定稿〕
定稿とそれより前の稿の異同は次のとおり。なお、各稿とも行数の増減はない。
(標題)aとbは〈フォーク・ソング〉と中黒がある。c以降〈フォークソング〉となる。
(11行め)aからbにかけて「向う側とはどんな凹面〔?→!〕 突起態!」
(13行め)bからcにかけて「梨籠のなか〔の甘いビラン体→には〕」
(20行め)bからcにかけて「〔花嫁→母親〕たちがたれながしのまま」
(25行め)aからbにかけて「バロック風な〔ナベ→鍋〕から」
(43行め)bからcにかけて「内的構図の終り〔(ナシ)→か〕?」〔ただしaは定稿と同じ形につき、bは単純な誤植か〕
以上を整理すると、aからbにかけての変更点はおもに表記上のもので、cの初刊時に詩句の変更が発生して定稿となっている。言うまでもなく「甘いビラン体」を抹消したのが肝である。この「ビラン」は当時の吉岡愛用の語であって、詩集にまとめる際にはずいぶん削られている。「腐爛」とともに吉岡実詩の「ビラン」関連の全用例を挙げる。
・めぐる豊かな腐爛の時間/いま死者の歯のまえで(〈静物〉③・1)
・ぼくたちにとっていかなる痛みのビラン体であるのか?(〈少女〉⑦・5の初出形)
・それともススキの茂る情死の腐爛期(〈雨〉⑦・9)
・求めている唇のよだれ/それらのただれ(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12の初出形)
・桃が籠のなかで/甘いビラン状になるとき/老人司祭の死の舌が必要か?(〈スワンベルグの歌〉未刊詩篇・12)
加えて、散文には「楊柳の下に、豪華な色彩の枢が放置されているのも、異様な光景だ。ふたをとって覗いて見たらと思ったが、遂に見たことはない。びらんした屍体か、白骨が収まっているのだろう」(〈わたしの作詩法?〉#A_25、九四ページ)がある。〈フォークソング〉では梨が腐った状態を言っているが、生の危機的状況を「ビラン」に託していることがうかがえる。初出形では産児との対立が即きすぎるので、カットしたものと思われる。産児がはやばやと退場してしまってはまずいのだ。陣痛はこらえられて「母親たちがたれながしのまま/双生児をう」み、それは「ながれる舟のなかに/発泡状の球体群」として葬られる。棺としての舟。ところで、この「ビラン」は五行めの「粥」から来ているのかもしれない。糜爛の糜には「糜粥」なる熟語があるからだ。放恣な連想を続けてゆけば、五~七行めからは粥の木、粥杖――小正月の粥を煮るときにかきまわす棒――が浮かびあがる。粥の木、粥杖は子供のない女の腰を打つと懐妊して男の子を産むと言われ、新年の季語にもなっている。私は《薬玉》的に読みすぎているだろうか。なぜ「甘いビラン体」は抹消されたのか。梨がただれくずれるにしろ外皮が脱落するにしろ、軟化を指示する方向が忌避されたのだ。それかあらぬか「カルシュウム乳/もしくは釘」の金属物質へと、詩句は旋回してゆく。梨籠の空虚には固形物が呼びいれられた。
*
「夏ははげ頭なんか刈りたくないと/チャリーはいつも思う/まして少女のうぶ毛の口のまわりを/剃りたくないと考える/ミルクのみ人形の腹のように/いやらしい雨期をおもわせるんだ/理髪師チャリーは毎日/冷蔵庫の白い肌をふいていたいと思う/それはすきな消防車の鐘のように/爆発しそうな内臓をしている」(〈やさしい放火魔〉冒頭)
「ペニー・レインには床屋がひとり/これまでに自分が刈った頭の写真を/一枚のこらず持っていて人に見せる/その店の前をとおる人たちはみんな/そこに立ちよっては「今日は」と言う/〔……〕/ペニー・レインには砂時計を持った消防夫/ポケットには女王陛下の肖像写真/消防自動車をきれいにしておくのが好き/きれいな消防自動車」(〈ペニー・レイン〉#B_165、一一一~一一二ページ)
他人の空似であっても、吉岡の〈やさしい放火魔〉(⑥・9)とビートルズ(ポール・マッカートニー)の〈ペニー・レイン〉(1967)くらい似ている曲は〈フォークソング〉には存在しない。だいいち「フォーク・ソング」とも掛けはなれている。この詩篇〈フォークソング〉に〈シャンソン・フォルクロリク〉と題を冠そうが〈民謡〉と名づけようが、そこには〈詩〉以上の意味は籠められていない。これが、あるジャンルの作品を当該ジャンルそのもので呼ぶという、吉岡一流の凝りかたである。ブラウン神父ものを書いたG・K・チェスタトンにも〈フォークソング〉という詩がある。新倉俊一の〈ノンセンスと正統――チェスタトンとエリオット〉にはこうある。
〔旧約聖書の〕ヨブが取組んだような永久に解読できない大きな謎にたいして、容易に解読できる小さい謎を扱っているのが、いわゆる〈ミステリー〉の世界であり、ノンセンスの世界である。『ブラウン神父の秘密』(一九二七)のオコーナー神父に宛てた献本に録された「フォークソング」という詩は、この小さなミステリーと大きなミステリーとの関連をほのめかしている。浜辺にそって釣りながら
探偵六人やってきた
一つの死体に気がついて
死んだ理由をいぶかったブラウン神父はにこやかに
皮肉でなしに返事した
「みなさんや私とおんなじに
生まれてきたから死んだのさ」「デイリー・ニューズ」の探偵が
「死者はどこに?」とたずねたが
ブラウン神父はおだやかに
ゴホン、と咳してこう言った「カスバート教会に来られたら
今日でもお教え致しましょう」
けれども五人の探偵は
そこから泣いて立ち去った(#C_043、一八五ページ)
ブラウンはこの詩においては探偵でもなく、神父でもなく、死体、いや死者である。だれもがみな死者であるという考えは、神学ではなくノンセンスによって染めあげられている。それを示すのが〈フォークソング〉という題名に託された寓意である。このとき民間の歌というのは、民間信仰の別名である。吉岡が〈フォークソング〉を書いたときに本篇を知っていた可能性は低かろうが、〈僧侶〉の詩人がこのチェスタトンの詩を喜ばなかったとは思えない。
*
「マダム・トラコーマ」(二行め)は結膜炎夫人、目病み女か。小宮清の《満州メモリー・マップ》は戦時中の大陸での日本の少年の暮らしぶりを伝えていて、防寒帽に兎の毛が使われていること、米の代わりに作られたコーリャンがトウモロコシのような背の高い植物であること、などに触れているが(註)、次の記述がある。「中国東北部の農村地帯は、文化のおよばない所だった。医療施設もほとんどなく、赤痢、コレラはもちろん、トラホーム、ハシカなどが発生すると、とめどなく広がっていった」(#B_046、七三ページ)。やはり「マダム・トラコーマ」とトラホームを病む夫人とは異なる。〈苦力〉(④・13)の「支那の男」がそうであるように、彼女は実在の人間というよりも神話の一人物に近い。視力が低下して失明するかもしれない女が「見る」ことは困難だから「すきな形の/舟をみつける」のは触覚的な行為となる。ここで「見る」ことは「触れる」ことと同水準に押しあげられ、視線が像を産む状態から、詩句には「見る」ことの変奏が続く。「ナチスの〔……〕青空を見よ」「空は〔……〕見え」「よく見れば」「夜目にもしるく」。同時に色への言及も増える。「むらさきの」「ももいろの」「青空」「赤塗りの」「金色の」。これを指して、吉岡がアニメーターのように絵柄に着色していると取るのは誤りである。「むらさきのスミレが咲く」(一行め)は、ある色合いから出現した物体が菫という植物だった、というに等しい。「薔薇咲けり、そは真紅なり」というフォークソング〈バラが咲いた〉(1966)とは逆なのだ。
*
一六行め(「ナチスの制服の人型の空胴の青空を見よ」)こそ特異な一行である。「の」でイメージを連鎖させていく一方で(ひとつひとつを分解すれば尻取りのように無理なくつながっている)、「ナチスの制服の人型の空胴」と「青空」との間に目も眩むような懸隔が存在する。ときに「空胴」とは見なれない文字だ。一九六九年二月《琴座》誌掲載の吉岡の文に「〔河原枇杷男〕句集「烏宙論」通読して独自な世界をつくられているのに感銘、一言でいえば、空胴の美学と思います」(#C_048、12ページ)というぐあいに「空胴」とあるが、「身体組織内に壊死が起こり、その部分が排出されたあとにできた穴」なる医学用語にしても「空洞」と書くのが本来だ。ここは誤記と取るよりも、「空洞の胴」を圧縮した表現と見たい。「空胴の青空」の章句からはルネ・マグリットの油彩画〈大家族〉(1947)が想いうかぶ。虚の、虚の世界に揺曳する白雲を浮かべた空。奥行のない、幕を吊るしたような青空。そうした図版化された空を見よ――それこそ私たちが二○世紀後半に見た空だ。空が虚であり嘘でもあることを補強するのが、人型(=ダミー)である。英語のdummyには「(洋服屋などの)人台、飾り人形」のほかに「(射撃練習用)標的人形」という意味がある。それは空ろでもあり、空でもある。この目も眩む懸隔には、「空」という一本の吊り橋が架けられている。
*
つるべうち(連打、釣瓶打)の音は読む者をしてその連想を「交尾ぶ、婚ぶ」へと運んでゆく。運ばれた先には「兎のそよぐ春風の毛」が待っている。兎(の毛)はその後こう定着された。
・兎の毛の内部には/洋服を縫う針や形をととのえる/コテやハサミが/秩序よく収納されている(〈ピクニック〉⑧・7)
・ウサギのように毛のある服を着て/おしっこしたくなる(〈ルイス・キャロルを探す方法――少女伝説〉⑧・11)
・わたしは探しているのだ/狩られた毛のなかの野兎を/深い傷口の奥に/もしかしたら甘い蜜がかもされている(〈田園〉⑧・14)
・兎の耳をつるす/国家を守護する人(〈異霊祭〉⑧・19)
・「濡れてささくれだつ板に/兎をなすりつける」(〈螺旋形〉⑨・10)
・うぶげの兎がまるで水子のように/二つの耳を折って/さかさまに浮んでいる(〈夢のアステリスク〉⑨・22)
これらの吉岡自身のどの詩句よりも、私は一九六二年九月、大岡信が《鰐》一○号に発表したあの〈マリリン〉の「体じゅうの毛をおとなしくそよがせて」との類縁を感じる。吉岡は〈ルイス・キャロルを探す方法〉をめぐって大岡に語る。「大岡だから言うけどね、最後のほら、「アイリス・紅い縞・秋・アリス/リッデル!」という二行。やっぱりきみの「マリリン」を意識したんだよ、実は。ぼくは、あそこのアリスの最後の一行では、大岡の「マリリン」には及ばないけど、それに近いものが出てるんじゃないかという自負はあるんだ」(#C_039、一五七ページ)。ここで詩句やイメージの貸借表を作ることが本意ではない。また「兎」がいかに動かない選択であるかを讃歎して終われば、ことはむしろ簡単である。これら狂暴性を帯びた詩句の生動を完璧に制御し、イメージの流出を紙面に定着しきっているさまを畏怖をもって見なければ、この行を読んだことにはならないだろう。
*
吉岡実の技を職人のそれになぞらえるのに、私はかねがね不満を抱いていた。世界の暗黒を白紙の上に反転させる吉岡の詩作の行為は、もっと別のものに喩えられるべきだ。それを端的に名指したのが中西夏之の「内側からの彫刻」(#C_044、三六ページ)的行為をする人、である。「鉄製器具の寄せ集めでつくられた/危機の蝶番の結合」は、言語がつくりあげた現代彫刻にほかならない。「自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち」(〈コレラ〉)が廃品芸術として再生するとき「今この店先の調理台のうえに 尾もない頭もない 一つの肉の原型 魅せられたように よこたわって」(〈寓話〉③・15)いた動物の世界からの距離を感じる。「それはたとえば/老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの」(〈雨〉)ジャンクアートへの共感に端を発しているのかもしれない。羽黒山を訪れたあとの吉岡との対談で飯島耕一が言う。「こんどの『神秘的……』のルイズ・ニーベルスンですか、よりも羽黒山を書いてほしいな(笑)」。吉岡は答える、「ニーベルスンは材料だったか、なんか絵具程度になっちゃうかわからないけどね」(#C_045、二○九ページ)。日常生活の中の廃物、がらくたを素材にすることで、良識的な美意識をおびやかす粗暴な表現を打ちだすこの傾向が、あらゆる面で工業化の進む現代文明への批判であり、同時に肯定であることは見やすい。「『僧侶』や『静物』は、日本のウェットな風土や近代性に反発して書いたものです」(#A_10、一三八ページ)という吉岡詩の文明批評をここに見ることも可能だろう。だが、鋼鉄のオブジェのてっぺんに「赤塗りのトウモロコシの/とさかをなびかせ」ることで、そうした生真面目な批評も哄笑のうちに包みこんでしまう。一瞬、歌舞伎の扮装を連想させて、すぐさま「アルチンボルドの肖像画」(〈サフラン摘み〉⑧・1)ばりの、滑稽でグロテスクな像へとスライドしてゆく。そこでは金属製の家禽が、ときに人物に見え、ときに植物に変貌する。ファインアート(「詩語」を駆使した詩作品)を冷笑するジャンクアート(「日常語」の活用による詩篇)の方法論がこの「蝶番」にはある。ハンス・ベルメールの人形の腹部の関節が双方向に それぞれの下肢をしどけなく開くとき、吉岡の「蝶番」は瞬時に開閉する。これを、吉岡実の作品にしばしば現われる詩による詩論と言ってもよい。
*
戦後、《静物》(1955)で出発して間もない詩集《僧侶》(1958)で早くも最初の頂点を究めてしまった吉岡実にとって、その世界を抜くことは難しかった。発表直後の「〈下痢〉をけなされて、内心憤然。しかし〈喪服〉はほめられる」(#A_10、一二○ページ)というのは、《僧侶》の世界の更なる深化を期待する周囲の人間にしてみれば、当然の評価だった。ここから吉岡の大きな方向転換が始まる。それは《僧侶》の「いかがわしさ」が醸しだす求心性を断ちきるために、必要以上に遠心力を発揮したようなものだ。その力は《紡錘形》(1962)ではまだ求心力に対抗しきれず、次の《静かな家》(1968)においてようやく釣りあっているように思われる。「円」と「円運動」の背後には、これらふたつの力の作用が働いている。「矢印」とは、円軌道から外れた力の謂いだ。「わたしはそれらの方向へ一つの矢印を走らせてその詩的作品の最後を飾るだろう。詩は小さく結実してはつまらない。詩は他の次元へまで拡がって行くべきだと思っている」(#A_25、八八ページ)。〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)の円軌道を逃れて「矢印」を大胆に駆使することが《神秘的な時代の詩》(1974)の、とりわけ発表時期の早い作品群に見られる。吉岡が「詩を書く場合、テーマやその構成・構造をあらかじめ考えない」(同前、八七ページ)こともあって、主題は隠されているが、紛れもなく戦時の体験がこれらの詩行に反映していよう。「満洲」こそ、ほとんど観念化しつつあった主題の具体的な顕現ではないか。〈苦力〉への厖大な註釈としての《神秘的な時代の詩》、すなわち《僧侶》を対立物とするもうひとつ別の世界の構築――それが吉岡実の一九六○年代後半の営みであった。《僧侶》の「満洲」ではない、かの地にあった二○年後の自己の内面に存在する「満洲」を剔抉することが時代における自身の役割であると思いさだめたとき、主題は確乎たるものとなった。吉岡の言う「神秘的な時代」である。そしてそれが要求したのが擬態としての「散漫な文体」であったのは、あるいは当然の帰結だった。なぜなら、詩句は「それ」を直接名指すことなく、迂遠にも無数の力線を「それ」めがけて放つ以外にないからである。
*
膓[はらわた]の先づ古び行く揚雲雀 永田耕衣《吹毛集》絵画は所有されることによって吉岡実の詩を、吉岡実の詩集を賦活する。「著者蔵」(その後、手放している)の片山健の鉛筆画(#A_32、〔二四ページ〕参照)は《サフラン摘み》のために描きおろされたものではないが、詩集の題名に陽子夫人の意見を入れることもなく、ジャケットが片山健の絵で飾られることもなく生成したなら、現在とはよほど違った書物になっていたはずである。所有・鑑賞された造形作品は、時を得て吉岡の詩や詩集に浮上する。私は吉岡が造形作家と組んで詩画集を遺さなかったことを残念に思う。しかし、一九六四年に初めて触れたゾンネンシュターンの絵が詩に結実するまでに一○年かかったことを考えれば、画家と詩人のコラボレーションが短時日に成立しえたかは疑わしい。「太田大八の画と吉岡の文で絵本を作る計画があるが実現せず」(同前、三○○ページ)は、絵本でなく詩画集であっても難しかったかもしれない。絵は、詩が書かれるまえに所有されるのだから、だれが吉岡の詩に絵を描けるだろうか。はしなくも吉岡詩以後の絵画の不可能性が露呈する。《夏の宴》の西脇順三郎の装画は、吉岡がこの本を最後の詩集にしようとしていた節を考えあわせれば、華やかな例外と呼んでも許されよう。
*
「『静物』は一九五五年、二百部自費出版した。無名画家が個展をひらくような期待と不安の裡で。未知の先輩、知己に配った。反響はなく、一行の紹介、批評も現われなかった」(#A_25、七三ページ)という吉岡の感懐は、比喩を超えてなまなましく迫ってくる。吉岡詩にとって絵画とはなんだったのか。戦前の日記には、文展で裸像彫刻に心惹かれ、斎藤清のアトリエで二科入選の油絵やデッサンを観た、とある。吉岡が造形作品の創作の機微を諒解していたであろうことが重要だ。パスティシュやパロディにおけることばと同様、絵画も引用され改変される。《サフラン摘み》と《夏の宴》には夥しい数の画家や絵画が登場するし、《ムーンドロップ》にはバルテュスやベーコン、クロソウスキーへの没入なくしては書かれなかった詩句も多い。「静物画」に始まり、もうひとつの「物語」に至る詩集のなかの絵画が、大きな円弧を描く。吉岡詩の絵画は、まず題名として登場する。〈春の絵〉(⑩・12)、〈馬・春の絵〉(⑥・5)、〈夏の絵〉(③・9)、〈沼・秋の絵〉(⑤・21)、〈冬の絵〉(④・6)、〈恋する絵〉(⑥・15)、〈絵画〉(⑧・18)、〈謎の絵〉(⑨・26)に〈ポール・クレーの食卓〉(⑩・1)と〈ゾンネンシュターンの船〉(⑧・24)も加えよう。詩人はまず「これは絵だ」と言う。絵(画家)を書いた詩だと思って読者が読む、その像を実際の画面に復原する行為と、読み手が新たに画面を構成する行為とはどう違うのか。パウル・クレーの〈陽気な食卓〉(1928)を観ながら〈ポール・クレーの食卓〉を読むことはできない。詩を読みつつ脳裡に像を形成してゆく。創造することは思い出すことだ。吉岡が絵画に触発されて詩を書くことと、読者が詩行に触発されて絵画を思い出すことは往還の関係にある。ならば詩行は媒介に過ぎないのか。行を追うごとに像が顕ちあらわれ詩句が消えてゆく感覚こそ、吉岡の詩を他の詩と分かつ最大の特徴である。
*

1990年、吉岡実の自宅にて吉岡陽子さんと小林一郎(撮影:大日方公男氏)
後ろの絵はポール・デイヴィスの〈猫とリンゴ〉(カンバスにアクリル、61.0×51.0cm、1977)
吉岡実の居間には、日記にも登場する飼い猫の想い出のためだろうか、最期までポール・デイヴィスの猫のアクリル画(#A_33、〔一九ページ〕参照)が掛けられていた。そのまえは〈フォーサイド家の猫〉(⑧・17)に書かれた松井喜三男の絵(#A_32、〔一○六ページ〕)だ。二匹のシャム猫、松井の猫の油彩画、〈フォーサイド家の猫〉の猫、デイヴィスのアクリル画。絵画は観る者の記憶と想像力の反映である。その索引は複製であり画題だ。詩に絵画を埋めこむには図版化する方法と画題を引用する方法がある。どちらも詩作品以外に(口絵や挿絵や装画のように)絵画は実在するが、詩行で絵を書くとその絵画は読む側の脳裡にしか存在しない。脳裡の絵画を出現せしめる事業において、吉岡実ほど辣腕を振るった作家を知らない。その先に存在するのは高橋睦郎の「作者は言葉によってそれまでどこにもいなかった動物を創造したのだ」(#A_23、一○四ページ)という世界である。吉岡の詩がしばしば難解な印象を与えるとき、そこには過剰な像と過少な意味があるように思われる。過剰な描写と過少な説明、ではない。見えすぎる絵画。「きみの所持する絵は/万有の闇のベールの向うに/存在するだけではないか」なる〈フォーサイド家の猫〉の「反問」は、大方の読者の反応とは違うのではないか。詩人は「できるだけ古典的な描写で試みようか」と続けるが、どうしてこの古典的な描写が曲者だ。読者の記憶と想像力のなかの絵画は鮮明になってゆくが、それが戻るべき像はもはや詩の行には存在せず、その意味が明示されることもない。
*
吉岡実の詩にとって造形作品はどのような意味をもつのか。吉岡自身は装丁のカットを含め造形作品を残しておらず――「思潮社主催〈現代詩オブジェ展〉に参加、詩篇〈裸婦〉と蓋のない赤い木箱に入った白塗りの拳玉を出品」(#A_32、三○○ページ)という例外はあるが【詳細は〈吉岡実の拳玉〉を参照のこと】――、造形物を創作する意思はあっても果たされなかった。「或る人は、わたしの詩を絵画性がある、又は彫刻的であるという。それでわたしはよいと思う。もともとわたしは彫刻家への夢があったから、造形への願望はつよいのである」(#A_25、八九ページ)。もちろん詩が造形作品の代替物だという意味ではない。逆だ。吉岡はこう続ける。「詩は感情の吐露、自然への同化に向って、水が低きにつくように、ながれてはならないのである。それは、見〔え〕るもの、手にふれられるもの、重量があり、空間を占めるもの、実在――を意図してきたからである」(初出では「見えるもの」とあった)。それは空間や次元よりも、時間の了解の仕方の差として現われる。吉岡はさらにこう書く。「だから形態は単純に見えても、多岐な時間の回路を持つ内部構成が必然的に要求される。能動的に連繋させながら、予知できぬ断絶をくりかえす複雑さが表面張力をつくる」(同前)。こうした志向にとって、絵画を描写的に詩に導入することに本質的な意味はない。詩行は強靱な膜のごときもので被われる。「形態は単純」どころか、巧みに巧まれた詩篇の構造を有する。それも、おそらくは大いなる直感に支えられて。その表面の分子である具体的な詩句を引きよせる中心に存在するのが、造形物であった。
*
詩は、絵画を読むように、見よ。
(註) 《満州メモリー・マップ〔ちくまプリマーブックス〕》(筑摩書房、1990年12月5日)の著者・小宮清氏は1940年から46年にかけて(四歳から九歳まで)、満洲で過ごした。吉岡の詩篇や散文の理解に欠かせないと思われるくだりを同書から摘する。冷凍のウンコは、匂いも発せずもくもくと成長してきて、踏板から顔を出し、ついにはおちおちまたいでなどいられなくなってしまう。塔の低い所をさがしてから用を足すのだが、いよいよどこもこれ以上は無理ということになると、外に回って汲取口から長いバベンの塔倒壊専用棒でひと働きしてから、用を足すのだった。(〈バベンの塔〉一一ページ)
手足をしばられた豚は、頚動脈を切られて、体液を全部出しつくすまで、そのまま放置される。その間中、豚はかん高い絶望的な悲鳴をあげつづける。その声は〔開拓〕団全体を包むほどだった。体液を出しつくすと、悲鳴もいつの間にかとだえる。すぐさま解体が手際よくはじまる。(〈中国人の小屋のまわりで〉一六~一七ページ)
五月になると、何もかも白くしていた雪が消え、雪どけ水があたり一面をびちゃびちゃにする。(〈カエルの風船〉一八ページ)
この時に撮った写真が、日本の親戚に送られていて、満州時代の唯一の記念となった。というのは、ぼくたちが戦後満州から引き揚げるとき、中国の役人は日本人に写真を持ち帰ることを禁じたからだ。(〈チチハル〉二六ページ)
秋も深くなると、雁がへの字になって何組も何組もぼくの頭の上をわたっていった。(〈大空の四季〉四八ページ)
そんなドラマも夕方には、すべてを朱色に染める夕焼けによってしめくくられた。(同前)
ラクダのももひきをはいて、股間にトウモロコシの綿毛をおおげさに縫いつけ、頭にもフサフサとつけて登場。「私のラバさん酋長の娘……」の大合唱の中をクネクネと腰を振りつつ踊りめぐった。かたむいた秋の陽が逆光になってトウモロコシの毛にあたると、それははなばなしい赤茶色の光を自らが発しているように見えた。(〈西の丘 その一 収穫祭〉六九ページ)
酒は、〝リャンチュウ〟といって、コーリャンから造られ、火にかけると、はぜるように燃える強力なもので、男たちはこの酒によってしばしば足腰をうばわれた。(〈リャンチュウ〉七八ページ)
開拓団の医療施設は団本部にある診療所だけで、医師の専門はどうであれ、人間も動物も診察した。開拓団にとって馬は大切な労働力だったから、馬をはじめ豚やにわとりの手当ても当然重要な任務となる。(〈アル中ドクター〉八三ページ)
出産の場合は、ある部落にいたひとりの老婆がお産婆さんをいってに引き受けていた。(同前)
やがて、その歌声にまじって馬のけたたましい悲鳴が聞こえてきた。農場の満州馬改良のために連れてこられた日本馬が、日本人にかわって手はじめに彼ら〔中国人〕の怨念を晴らす対象となったのだ。満州馬より背が高く気位の高い日本馬は、小屋につながれたまま、ガラス片や石を投げつけられ棒でなぐられ血みどろになっていった。(〈天皇の放送〉一二一ページ)
八月一七日早朝、大量の軍靴の音で目が覚めた。もうソ連軍がきてしまったのかと一瞬ゾッとしたが、それは日本兵で、全員が武装を解除されて、手ぶらの行進だった。(〈逃れ逃れて〉一二四ページ)
わずかばかり持っていたお金で、仲間が交代で食糧を買いこんで飢えをしのぎ、時には畑にしのびこんで、まくわうりや西瓜を失敬したりもした。(〈父帰る〉一四〇ページ)
満州にはなぜか常緑樹が見当たらず、冬には緑がいっさいなかった。(〈カラスの子〉一六六ページ)
思考、言葉の選択と湧出、いってみれば増殖運動の秘密は解明できない状態である。――吉岡実(#A_25、八七ページ)
大野一雄舞踏公演〈花鳥風月〉初日の一九九一年八月二日、銀座セゾン劇場のロビーで詩人の田野倉康一さんと出あった。大野氏の傑作のあと、久しぶりの雑談で、吉岡実は人を引きあわせるのが好きで大野氏も吉岡さんから紹介してもらったのだと聞いた。その田野倉さんが《少年アリス》の長野まゆみを引きあわせたとき、文藝賞受賞作をぱらぱらと見ていた吉岡は「アンドロギュヌスだね」と言ったそうだ。これがどうして偶然に思えない。〈色彩の内部〉(⑦・4)初出の切りぬき(吉岡家蔵)の冒頭はこうだ。( )内は文字のサイズ。
えるまふろじっとのうた(約13Q)
〈色彩の内部〉(約18Q)
〔カット一点〕
吉岡 実(約18Q)
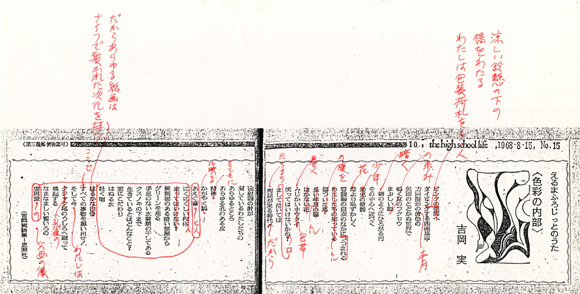
〈色彩の内部〉初出(吉岡家蔵のモノクロコピー)を最終稿で校合したもの(赤字は小林が記入)
〈色彩の内部〉は、一九六八年八月一五日、高校生向けの月刊読書新聞《the high school life》(MAC〔マーケティング・アド・センター〕発行)の第一五号に発表された。同紙の編集者・松岡正剛が「えるまふろじっとのうた」というコーナーで多くの詩人に依頼した詩の一篇と思われるが、吉岡実がこのコーナーをどの程度意識して本篇を執筆したのかはっきりとわからない。当時の吉岡は、〈わたしの作詩法?〉から明らかなように、作詩以前にテーマを求めなかった。執筆時から判断すれば本篇はあらかじめテーマを設定することなく書かれた時期に当たり、それなら「えるまふろじっとのうた」を云云する必要はない。だが、このコーナーが続きものだったことを重視するなら、事情は変わってくる。執筆依頼時の見本の印刷物には他の詩人の「えるまふろじっとのうた」が載っていただろう。
――念のために吉岡実の詩が掲載された一五号よりも前の同紙を調べてみると、詩の連載は六月一日発行一三号の岸田衿子〈旅の若者〉に始まる。ただしこのときは「えるまふろじっとのうた」と謳われておらず、次の七月一五日発行(それまでの発行日一日が一五日に変更されている)の一四号(吉岡詩掲載の前号)の長田弘〈叫ぶ子供〉に「えるまふろじっとのうた・2」とあるのが初出である。この号には〈予告〉として「次号の「えるまふろじっとのうた」は吉岡実氏です。さらに谷川俊太郎氏、大岡信氏、寺山修司氏、富岡多恵子氏、鮎川信夫氏の作品を予定しております。ご期待ください」(同紙、一〇ページ)とある。編集者は「えるまふろじっとのうた」が詩のコーナーであることを読者に周知させており、執筆陣にも同様の説明をしたうえで原稿依頼したものと推定される(註)。――
このコーナーを連載のよる詩の競作と捉えるなら、執筆に当たって吉岡が「えるまふろじっとのうた」を手掛かりにしたことは大いにあり得る。それが本篇のモチーフになったとする考え方である。わたしには、吉岡実が詩作行為そのものを「えるまふろじっとのうた」と認識したように思えてならない。つまりモチーフではなく、テーマだったのではないか。だが、この詩が両性具有の原理の上に成立しているとか、両性具有と等価である、ということが言いたいのではない。〈色彩の内部〉は「えるまふろじっとのうた」そのものを「描いた」詩のように思えるのだ。
ときに大野一雄〈花鳥風月〉の新聞評(無署名)にはこうある。――「月光」「幽霊馬車」「鳥」「暈狂う舞」と名付けられた四つのパートから成るこのステージ、クレモナの町と地霊が呼び起こしたというイメージで埋めつくされ、人間存在の〈痛ましさ〉と〈いとおしさ〉がひしひしと伝わってくる。/色とりどりの薄い布が降る中、ミニスカートにリボンの大野がワルツで踊るラストの、何という歓喜!(#C_024、三八面)――。この〈暈狂う舞〉は大野の吉岡実追悼文〈暈狂う舞を〉(#C_014)を受けているようだ。大野の文章は土方巽のそれより求心的とでも言おうか、土方の男根的であるのに対して子宮的である。さらに、両性具有(エルマフロディトであれアンドロギュヌスであれ)を言うとき、大野とともに笠井叡の名を逸することはできない。〈色彩の内部〉と同じ一九六八年の八月、吉岡は〈変宮の人・笠井叡〉を《ANDROGYNY DANCE》第一号に発表している。
土方巽の舞踏詩〈ゲスラー・テル群論〉に、肉体を感じ、創造の心を、なによりもなまなましい存在感を見た。詩にも映画にも劇にもかつてない、新しい世界をかいまみて慄然とした。なかでもある場面が印象深かった。その前の喧噪のシーンをうけて、うす暗く静謐な舞台、右の方にイーゼルに大きな白いカンバス(紙)が置かれ、天井から函がおりてくると、突然、一番前の客席の中央にいた女が椅子の上にのり、ライトの中でふりむいた。白塗りの顔に一刷け紅い絵具をつけた異様な美しさ。支那服から出た細い脚。函が地に着くと死んだ子が入っているらしい。嘆くごとく、なぶるごとく、狂った静かな踊りというより行為だ。しばらくして、白いカンバスのかげからビビーッと緊張した空気をふるわせ、巨大な白紙を突然やぶって、うごめく黒い長い手袋に覆われた腕。それから一つの世界が開かれるのだった。私は終ったあと、この踊手は何者だろう? 土方巽の動に対して静でみごとに受け止めたこの女装の人は、誰だろうと思った。これが笠井叡が私の前に出現した時であった。(#A_25、一六○~一六一ページ)
わたしはこの記述から吉岡の軍旗祭での女装姿(#A_32、〔一二ページ〕)を連想せずにいられないのだが、それはさておき、ルーチョ・フォンタナの切りさいたカンバスに触れた〈色彩の内部〉の「だからあらゆる絵画は/ナイフで裂かれた次元を持つ」は当然この一節から来ていると考えたくなる。ところが初出にその二行はない。となると詩句は「色彩の内部」と直接結びつくものではなかったのだろうか。初出〈色彩の内部〉は色にまつわるいくつかのモデュールからも構成されていたが、それと「えるまふろじっとのうた」とが充分なじんでいなかったのではないか。初出のあと少なくとも三度の手入れを経て、「色彩」は一九六○年代末の社会的な、物質的な一要素から、吉岡実固有のタブロー上のそれへと変貌していったように思われる。
松浦寿輝は〈後ろ姿を見る――『サフラン摘み』の位置〉で次のように「絵画」に言及している。「〔……〕後期吉岡実に遍在している「絵画」の主題が、めくるめくばかりの無根拠性の輝きを放ちつつ運動しているあの「イメージ」群を捕獲し保持し作品として構造化するため装置としてあることは言うまでもないことながら、同時にそれが、しばしば性器形象と不可分のものとして提示されているのは興味深いことだと思う」(#A_32、一五九ページ)。松浦はこの論考で「主題=装置」としての男根を〈三重奏〉(⑦・17)に、女陰を〈マダム・レインの子供〉(⑧・5)に見ており、「性器形象」は男女二様である。明快であり、正しいだろう。だが、わたしたちは〈色彩の内部〉に両性具有の「主題=装置」を発見できるだろうか。吉岡にしては珍しく改稿の跡をとどめた本文を見ることにしよう。
・初版以前
A=《the high school life》(MAC)〔初出〕 一九六八年八月一五日
B=《ユリイカ》(青土社)〈神秘的な時代の詩・抄〉〔二稿〕 一九七三年九月一日
・単行詩集ほか
C=《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房刊)〔三稿(定稿)〕 一九七四年一○月二○日
D=《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房刊)〔三稿(定稿)〕 一九七五年六月一日
E=《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田刊)〔四稿(最終稿)〕 一九七六年八月一五日
F=《新選吉岡実詩集》(思潮社刊)〔三稿(定稿)〕 一九七八年六月一五日
なお、四稿は三稿(定稿)の一五行め「ホウタイ」を「包帯」に改めただけだが、最終稿として扱う(《吉岡実全詩集》にもこの形が採られている)。時間的に後のFが三稿なのは、この文庫版が初版〔限定版〕を底本としているため――厳密に言えば、同文庫五六ページの出典「(『神秘的な時代の詩』一九七五年湯川書房刊)」(#A_18)とあるのはDの特装版を指しそうなものだが、初版を差しおいてこの版を底本にすべき根拠はない――である。以下のテクストに施した【 】はA~Fの全稿で同一詩句であることを、同じく[ ]は行単位ではなく字句として全稿に共通することを示す。すなわち【 】と[ ]ではさまれていないところが訂正箇所である。
A=初出
えるまふろじっとのうた
01 ピンクの空間へ
02 ダイビングする四頭馬車
03 [方向指示の]黄[色の]
04 【矢印のとどかぬ世界で】
05 【鳴く夏のフクロウ】
06 [まぶしい眼]
07 [網のようにひろがる円]
08 【その中心へ近づく】
09 幼児[の便器]
10 母[より恥ずかしく]
11 [看護婦の白衣のなかに][つつまれる]
12 わたしたちの知っている
13 [傷ついた馬]
14 長い年月の腸
15 はかない花
16 [みじかい]ホウタイ
17 [笑ってはいけない]かね?
18 [まして泣いては]
19 [肉屋が来る時代]!
20 【注射器の針が】
21 【刺しているわたしたちの】
22 【あらゆるところ】
23 【あらゆる孔のある皮】
24 [精神]
25 [かがやく鏡]
26 [あえぐ葦]
27 【にくにくしい肉体】
28 走ってはいけない?
29 【解剖図のある暗い部屋から】
30 【グリーンを走る】
31 【手足のない水着類の干してある】
32 【クスノキの下まで】
33 【生きているとはどんなこと?】
34 【恋にこだわり】
35 【はねる水】
36 【吐く闇】
37 はるかな白骨
38 [すべての事物を想い出せ!]
39 [そして今]
40 クジャク[尾のうしろへ廻って]
41 【喚起する】
42 【なまなましい藍いろの】
43 [表現愛]
B=二稿
01 凉しい鈴懸の下の
02 橋をわたる
03 わたしは包装荷札をもつ人
04 [方向指示の]青[色の]
05 【矢印のとどかぬ世界で】
06 【鳴く夏のフクロウ】
07 [まぶしい眼]の歩み
08 暗く[網のようにひろがる円]
09 【その中心へ近づく】
10 幼児[の便器]
11 花[より恥ずかしく]
12 [看護婦の白衣のなかに][つつまれる]
13 わたしたちの知っている墓地
14 [傷ついた馬]の腹を巻く
15 [みじかい]ホウタイ
16 [笑ってはいけない] [まして泣いては]
17 たちまち[肉屋が来る時代]だから
18 【注射器の針が】
19 【刺しているわたしたちの】
20 【あらゆるところ】
21 【あらゆる孔のある皮】
22 [精神]
23 [かがやく鏡]に映る
24 [表現愛]
25 【にくにくしい肉体】
26 【解剖図のある暗い部屋から】
27 【グリーンを走る】
28 【手足のない水着類の干してある】
29 【クスノキの下まで】
30 【生きているとはどんなこと?】
31 【恋にこだわり】
32 【はねる水】
33 【吐く闇】
34 [あえぐ葦]
35 だからあらゆる絵画は
36 ナイフで裂かれた次元を持つ
37 ここで[すべての事物を想い出せ!]
38 [そして今]わたしは
39 クジャクの[尾のうしろへ廻って]
40 【喚起する】
41 【なまなましい藍いろの】
42 父母の像
C・D・F=三稿(定稿)
01 涼しい鈴懸の下の
02 橋をわたる
03 わたしは包装荷札をもつ人
04 [方向指示の]青[色の]
05 【矢印のとどかぬ世界で】
06 【鳴く夏のフクロウ】
07 [まぶしい眼]の歩み
08 暗く[網のようにひろがる円]
09 【その中心へ近づく】
10 少年[の便器]
11 花[より恥ずかしく]
12 [看護婦の白衣のなかに]
13 [つつまれる]
14 [傷ついた馬]の腹を
15 巻く[みじかい]ホウタイ
16 [笑ってはいけない] [まして泣いては]
17 たちまち[肉屋が来る時代]だから
18 【注射器の針が】
19 【刺しているわたしたちの】
20 【あらゆるところ】
21 【あらゆる孔のある皮】
22 [精神]もともに
23 [かがやく鏡]に映る
24 [表現愛]の
25 【にくにくしい肉体】
26 【解剖図のある暗い部屋から】
27 【グリーンを走る】
28 【手足のない水着類の干してある】
29 【クスノキの下まで】
30 【生きているとはどんなこと?】
31 【恋にこだわり】
32 【はねる水】
33 【吐く闇】
34 [あえぐ葦]と人
35 だからあらゆる絵画は
36 ナイフで裂かれた次元を持つ
37 ここで[すべての事物を想い出せ!]
38 [そして今]わたしは
39 孔雀の[尾のうしろへ廻って]
40 【喚起する】
41 【なまなましい藍いろの】
42 父母の像
E=四稿(最終稿)
〔……〕
15 巻く[みじかい]包帯
〔……〕
吉岡との対談で金井美恵子はこう言っている。「実は、読者としては吉岡さんの詩のどれをとってもそうだけど、どういう過程でそれが生まれたのかに非常に興味があるわけですよね。どういう言葉を削除し、どういう言葉を付け加えたのかというふうな過程を見られたら非常におもしろいと思っている」(#C_010、九八ページ)。〈色彩の内部〉の四つの本文でその「過程」を見よう。四稿(最終稿)を一読して頭韻にも似た響きの多さ(とりわけ初めの七行に顕著)に驚く。
〈すず〉しい〈すず〉懸の〈した〉の
橋を〈わた〉る
〈わた〉しは〈ほう〉装荷札をもつ〈ひと〉
〈ほう〉向指示の青色の
矢印のとどかぬ世界で
〈な〉く〈な〉つのフクロウ
〈ま〉ぶしい〈め〉の歩〈み〉
詩の音楽的効果をこれほど直截に狙った詩句はかつて吉岡詩にはなかった。頻度こそ下がるが、後半でもフランス詩法で言う「畳韻法」は依然として発揮されている――「〈かが〕やく〈かが〉みに映る/表現愛の/〈にくにく〉しい〈にく〉体/〈かい〉剖図のある〈くらい〉部屋から」(二三~二六行)や、「〈こ〉いに〈こ〉だわり/〈は〉ねる水/〈は〉く闇/〈あ〉えぐ〈あ〉しと人」(三一~三四行)ほか――。だがこの響き具合を〈色彩の内部〉の一特色、吉岡にしては珍しい音楽的達成とだけ言って片づけてしまいたくない。狙って得られる効果などたいしたものではないし、だいいち吉岡がそれを目的にしたのか。「色彩」という絵画の一要素を扱うときに、詩人が畳韻法を用いたことが問題なのだ。わたしはこの時代の芸術シーンで、ビートルズの《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》に始まるサイケデリック文化が猛威をふるっていたことを過小評価してはならないと思う。音響と映像の意図的混滑による幻覚的効果。それが一九六〇年代末のバックグラウンドである。当時の吉岡の日常的な嗜好を示す未刊の散文がある。一九六八年七月、筑摩書房労組機関紙《わたしたちのしんぶん》九○号に「私の好きなもの」として発表した〈好きなもの数かず〉だ。
ラッキョウ、ブリジット・バルドー、湯とうふ、映画、黄色、せんべい、土方巽の舞踏、たらこ、書物、のり、唐十郎のテント芝居、詩仙洞、広隆寺のみろく、煙草、渋谷宮益坂はトップのコーヒー。ハンス・ベルメールの人形、西洋アンズ、多恵子、かずこたちの詩。銀座風月堂の椅子に腰かけて外を見ているとき。墨跡をみるのがたのしい。耕衣の書。京都から飛んでくる雲龍、墨染の里のあたりの夕まぐれ。イノダのカフェオーレや三條大橋の上からみる東山三十六峰銀なかし。シャクナゲ、たんぽぽ、ケン玉をしている夜。巣鴨のとげぬき地蔵の境内、せんこうの香。ちちははの墓・享保八年の消えかかった文字。ぱちんこの鉄の玉の感触。桐の花、妙義の山、鯉のあらい、二十才の春、桃の葉の泛いている湯。××澄子、スミレ、お金、新しい絵画・彫刻、わが家の猫たち、ほおずき市、おとりさまの熊手、みそおでん、お好み焼。神保町揚子江の上海焼きそば。本の街、ふぐ料理、ある人の指。つもる雪。
ここには「音楽」がない。だが、この食べ物飲み物や人物や土地や店や芸術や詩や風物や動植物や家族などの連想を貫く好ましい記憶の湧出を、類似の音のそれに置きかえたのが〈色彩の内部〉の畳韻法とは言えないか。吉岡は金井に語る。「とにかく詩は最初の白い原稿用紙でできるだけ持続したいわけね。だから発想してきたものをそこへどんどん繰りこんでいく。できるだけ最初に出た言葉を大事にして、たとえつまらない言葉でも出てきた以上はそれを大事にしていく」(#C_010、九八ページ)。初出稿はこうした作業を経たものだが、二稿もしくは三稿以降で姿を消した七つの詩句が含まれている。
01 ピンクの空間へ
02 ダイビングする四頭馬車
――
12 わたしたちの知っている
――
14 長い年月の腸
15 はかない花
――
28 走ってはいけない?
――
37 はるかな白骨
初めの二行は「では未経験的なピンクの空間へ/ダイビングする/四頭馬車の喪服ずくめ」という〈崑崙〉(⑦・8)の冒頭に転生する。一九九〇年の夏、わたしは初めて吉岡家蔵の初出の切りぬき(そこに著者の手入れはなされていない)を読んで衝撃を受けた。Bの二稿発表の一九七三年九月まで、吉岡実は類似の詩句で始まる二篇の作品を持っていたことになる。一二行めは二稿で「わたしたちの知っている墓地」と加筆され、それは〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)冒頭の「花咲くスミレの墓地で/わが馬ニコルスは快心の脱糞する」を想起させる。畳韻法は一五行めと三七行めでも見られ、後者は「ぼくら仮想の老人の遙かな白骨のアーチをくぐり」(〈聖少女〉⑦・10)に転生する。吉岡は言う。「そうね、好きなイメージというのはあるね。だから、ぼくの過去の詩は、そんなに広がりはないんで、まあ『サフラン摘み』あたりからわりとのびやかになってね。その前の『神秘的な時代の詩』で方向がバラバラになって、飯島〔耕一〕に指摘されたのもあったけど。あそこでは拡散していく詩になってしまった」(同前)。
金井美恵子が興味があると言う「拡散性」は、吉岡の言う「そんなに広がりはない」イメージと表裏をなしていると捉えるべきだ。ひとたび記された詩句は、仮に消されても他の詩篇に紛れこむ。類似のイメージが強迫観念のように詩人に付きまとう。「わたし」の登場しない初出は、ややもすれば無重力的な詩句が止めどなく展開した(それを大大的に駆使したのが〈崑崙〉である)。〈色彩の内部〉という題と「えるまふろじっとのうた」という別題が本文と釣りあっていなかったのも初稿だ。二稿以降、ここでの「えるまふろじっとのうた」の追求は放棄され――「血の出るテープ一万呎をなびかせて/は寝る妊娠可能の少年たち」(〈神秘的な時代の詩〉⑦・11)にはその残響がある――、フォンタナに触れた二行が全篇を際立たせた(吉岡は、一九六八年の九月に他界したこのイタリアの彫刻家への敬意を込めて「あらゆる絵画は女陰を持つ」と言いたかったのか)。もっともそれをいちばん重要な詩句だと決める必要はない。むしろ「わたしは包装荷札をもつ人」――「わたしはネコを抱く疑問符の人」(〈夏から秋まで〉⑦・2)――に着目したい。「わたし」は絵画を移動させているのか。
・だから愛とは熱く/油絵具のなかにたむろして/出る骨をくるむ(〈三重奏〉⑦・17)
・裂かれたカンバスよりもっと永遠でない闇から 愛撫する馬の腹へ わたしは口をつけて囁く(〈馬・春の絵〉⑥・5)
・ぼくは画家だから 実体を他に移す破服の施術者にすぎぬから(〈裸婦〉⑤・7)
「ぼく」が画家であったようには「わたし」は画家ではない、「実体を他に移す破服の施術者」ではない。自身が移動する人物、動きまわる視線の所有者にすぎない。「わたし」が橋をわたる冒頭は象徴的だ。その「方向指示の青色の/矢印のとどかぬ世界」を他界と呼んでもよいだろう。そこで「すべての事物を想い出」さねばならないのだ。だから「わたし」の喚起するのは「なまなましい藍いろの/父母の像」であり、それこそがおそらくは「包装荷札」を付けられるべき荷物だった。
・肉体と紐を使って/苦い荷をはこぶんだよ(〈低音〉⑦・14)
「吉岡実は生前、約二八○篇一一○○○行の詩を発表した」(#A_32、三二七ページ)が、刊本に収められた詩句と未刊詩篇の詩句との間でごく一部の重複がある。未刊詩篇〈休息〉(《現代詩手帖》一九八七年九月号)という澁澤龍彦追悼詩篇の二九行めから三一行めの
どんなものの上にも
止まることは許されない」
〔イデアの世界〕
は同じく未刊の詩篇〈雲井〉(《鷹》一九八九年一○月号)に嵌めこまれており、前者の「〔透視図法〕」も後者の「〔透視図法〕を視よ」として再生している。〈雲井〉は吉岡の死のほぼ半年前の、最後から二番めの詩だったから生前の刊本には収められていない。一方《ムーンドロップ》刊行前に発表されている〈休息〉が未刊なのは、のちに〈銀鮫(キメラ・ファンタスマ)〉(⑫・17)という別の澁澤追悼詩篇が書かれたためだが(吉岡が「アンドロギュヌスだね」と言ったのは澁澤の《夢の宇宙誌》に負っているか)、作品そのものに慊りなかったことが詩句の再生さえ許した原因だろう。そして、この関係の先蹤とも呼ぶべきものが未刊詩篇〈哀歌〉(《鰐》六号、一九六○年二月)の二八~三五(最終)行と〈内的な恋唄〉(⑥・12)の六五~七二行との間にある。
28 ぼくの不倫・ぼくの殉教精神
29 麦畑へ火事を導びく
30 ついでにけしの畑
31 灯る人家を望み
32 ぼくと密通した人妻の
33 幼女のマヌカンを
34 ぼくは抱くだろう
35 糸杉の狂える夜ごと夜ごとを
65 ぼくの不倫がつくる
66 麦畑へ
67 きみたちが火事をみちびく
68 ついでにケシ〔初出:けし〕の畑まで
69 灯る人家を焼き
70 密通した人妻の
71 幼女のマヌカンをぼくは抱くだろう?
72 糸杉の狂える夜ごと夜ごとを
行数こそともに八行だが、細かい手入れによって完全に同一の詩句は引用部分の最後の行しかない。詩集《紡錘形》制作時期の他の作品(〈遅い恋〉や〈夜曲〉)と同様に刊本に収められなかっただけでなく、後の拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》にも入れられていないのは、吉岡がこの重複を避けたことに依るに違いない。〈内的な恋唄〉(一九六七年一月発表)の執筆時にこの八行を引きうつした段階で〈哀歌〉の切りぬきは破棄されたとも考えられる(ちなみに連作以外、同じ標題で三篇あるのは〈哀歌〉――他は②・31と⑪・13――だけである)。
ところで、吉岡実には書きあげた詩篇を未発表のまま手許に置く習慣があっただろうか。その歿後、草稿の詩篇はひとつも発表されておらず、依頼が来てから詩を書くという執筆態度には例外がなかったようだ。吉岡が手許に詩篇を置かないことは「手帖を持ち歩かない」(#A_25、八八ページ)ことにも通じる。「わたしは詩篇が完成したと確認した時、草稿的なもの、書き損じ類を一切破棄してしまう」(同前、八七ページ)という作者のことばを信じるならば、唯一完成形の原稿が存在し、それ以外は詩集収録時に手が入るだけで、入稿原稿と初出稿を同一と見なせば初出稿→定稿という流れと、初出稿と定稿のふたつのテクストが、書きおろし詩篇を除く詩集《紡錘形》以降のすべての吉岡実詩に共通する。また、大半の場合、両者に異同はない。とすれば、詩句の流用とは先行作品を「骨抜き」にする行為そのものである。先行作品はその全体性を見かぎられることで、一部の詩句が生きのびるのだ。〈内的な恋唄〉は、六五行めから七二行めにかけて〈哀歌〉の結末部を流用した。《紡錘形》をまとめるときに捨てた詩篇は《静かな家》を書きつづけている時期に必要な詩句を含んでいたのだ。手入れは詩句の相互関係を明らかにする方向でなされるが、改稿形(〈内的な恋唄〉)が初期形(〈哀歌〉)よりも明快ではないところに、むしろ「詩篇の細部の変遷〔……〕は解明できない状態である」(同前)という吉岡実詩の秘密を解く鍵があると思われる。
〈哀歌〉の八行と〈内的な恋唄〉の八行での大きな違いは、体言止めをなくしたこと、中黒を取り疑問符を付けたことである。いったい吉岡は、入沢康夫が〈吉岡実の転生〉(#A_18)
で指摘しているように、文字以外の符号や記号の使用に対して極めて禁欲的だった長い期間を持つ。「ぼくの不倫・ぼくの殉教精神」の中黒を「そして」「にして」「あるいは」「すなわち」といった具合に多様に読みかえることができるゆえに、「・ぼくの殉教精神」は削られた。あるいは「不倫」を「殉教精神」と把握する次元を通過した。この中黒は同格か言い換えと読みたくなるのをいかんともしがたい。そこが出発点だろう。まず「ぼくの不倫〔・ぼくの殉教精神)/麦畑へ火事を導びく」の二行をつなげるべく動詞をはさむ、と言っても「ぼくの不倫」を主語にするわけではない。「ちなみに、小生の詩のほとんどが、前と後に掛かるように出来ています」(#A_34、〔ⅳページ〕)とあるように、動詞の終止形と連体形が同じであることを活かして詩句を連ねてゆく。だが「ぼくの不倫がつくる」のは「嫡出でない子」ではあっても「麦畑」ではあるまい。ここにひとつの抵抗が布置された。その勢いで、以下を改行する。「つくる」に合わせて「導びく」をひらいてひらがなにする。初出では〈哀歌〉の三○行めはそのまま〈内的な恋唄〉の六八行めとなりかけて、「麦畑へ」を受けて「けしの畑まで」となる。「灯る人家を望み」では弱いし、なんだか「ぼく」がしつこい。「火事をみちびく」のは「ぼく」ではなく「きみ」、いや〈内的な恋唄〉は「ぼく」と「きみたち」と「かれら」の唄なのだから、ここは「きみたち」だ。「きみたち」が女たちかどうかは断言すまい。「火事」ならばストレートに「焼き」だ。「不倫」と来るからには、単に「密通した」で通じるはずだ。あるいは「ぼく」が「人妻」と「密通し」その「幼女のマヌカンを」「抱く」では忙しすぎよう。「幼女のマヌカンを/ぼくは抱くだろう」を追いこむと、
・密通した――人妻の――/幼女の――マヌカンを――ぼくは――抱くだろう
と漸進的に現実から遊離してゆく調子が出る。「糸杉の狂える夜ごと夜ごとを」には緑の炎の形をした植物とゴッホの画面からの連想があり、「灯る人家を〔望み〕焼き」を強め、繰りかえしが時代を「狂える夜」と捉えている感じがよく出ているから、そのままとする。なお、前の行末には、疑問符をつけてグロテスクさを高めた。
というふうに「増殖連動」を想像してみると、吉岡が行わけの詩に手を入れていくありさまは絶妙と呼ぶしかない。削除する、追加する、別行に立てる、主語を書きこむ、追加する、置きかえる、主格を省く、追いこみにする、疑問形にする。そうした作業の素材になっているのが、たまたますでに発表した自分の過去の作品であるというだけであって、実際は白紙の原稿に初めて置かれたあるモデュールのほうが多いというのが「増殖運動の秘密」の背景ではなかろうか。その「秘密」はわたしたちの眼前に、本文紙に印刷された文字としてだけ存在している(吉岡実の草稿――「詩篇の細部の変遷」を跡づける真の意味でのそれ――に関する研究はほとんどなされておらず、わずかにわたしの《静物》全篇の草稿調査〈吉岡実詩集《静物》稿本〉があるだけである)。
眼前の文字そのものが「秘密」であるとき、いかに作者であれそれが「解明できない状態である」のは当然だろう。そのとき〈吉岡実詩の評釈〉とは、わたしが文字を書きながら見るもうひとつ別の夢、文を綴りながら深めるもうひとつ別の謎である。「秘密」を解く鍵はどこか遠くの、奥深い所に匿されているのではなく、わたしたちの眼下にすでに、いまも、これからも存在している。
(註) 吉岡実の詩篇〈色彩の内部〉(《the high school life》15号)以降に掲載された「えるまふろじっとのうた」の作者名を掲げておく。
- 16号(一九六八年九月) 白石かずこ
- 17号(一〇月) 山本太郎・田村隆一・飯島耕一・天沢退二郎
- 18号(一一月) 入沢康夫
- 19号(一二月) 富岡多恵子
- 20号(一九六九年一月) 清岡卓行
- 21号(二月) 吉増剛造
- 22号(三月) 吉行理恵
- 23号(四月) 関根弘
- 24号(五月) 谷川俊太郎
- 25号(六月) 高橋睦郎
- 26号(七月) 高良留美子
- 27号(八月) 宗左近
- 28号(九月) 那珂太郎
- 29号(一〇月) 織田達朗
- 30号(一一月) 金井美恵子
- 31号(一九七〇年一月) 清水昶
- 32号(三月) 岩成達也
いくつか補記すれば、17号の「えるまふろじっとのうた――5」には「ハイスクールのための四つの書きおろし作品とトミー・アンゲラーによるイラストレーション」とあり、四人の詩人による小特集になっている。32号は「えるまふろじっとのうた・最終回」で、岩成達也の詩の題名は〈模写その3――あるいはエルマフロジットの帰還〉。同号は《the high school life》の終刊号である。
聖母像の光背〔ママ〕は仏像の光輪のやうに輪形でなく中央が尖つてゐるが、これは「神秘のアマンド」と名づけられてその処女性を象徴するのだといふ。――村松嘉津(#B_150、五九ページ)
〈神秘的な時代の詩〉(⑦・11)は、一九六八年一○月一日発行の《季刊藝術》第七号に発表された。吉岡実は同月、一〇月号の《南北》にも〈崑崙〉(⑦・8)を発表している。吉岡が二篇のうちどちらを先に執筆・脱稿したのか、正確なことはわからない。次号予告があれば依頼時期は判明するだろうと《季刊藝術》の前号を見ると、編集人の古山高麗雄が〈編輯後記〉で、次号予告はうっかり出せない、「いままでの例から言っても、次号に掲載予定のものが、さらに次の号にのびたということが再三あったからである」(#C_002、二四八ページ)とまで書いている。この後記を書くころには、次号概要は決まっているはずだから、依頼は遅くとも六月と見たい。九月某日の原稿渡し予定日よりもかなり前に《南北》からも「長詩」を頼まれたため、〈神秘的な時代の詩〉を早めに切りあげてから次の〈崑崙〉に取りかかったのではあるまいか。のちに吉岡がこう書いているからだ(一九七五年八月三一日付永田耕衣宛書簡)。
それから過日、〈琴座〉三百号記念号へ執筆せよとの速達の手紙を頂きながら、今日まで明快な返事が出来ず困っておりました。それは、西脇順三郎《詩と詩論》月報の締切が同じころという巡りあわせがあるのです。その構想も出来ず、まず十五枚という小生うまれて初めてともいうべき枚数に、毎日おろおろしているところです。その上、運わるく(これもすでに二カ月前に依頼されたもの)ある文芸誌に長い詩を書かねばなりません〔のちの〈悪趣味な内面の秋の旅〉(⑧・31)〕。小生は、二つも原稿書きがあると、どうしても気が散ってうまくゆきません。そこへ耕衣さんからの依頼のお手紙、小生の困惑わかって頂けますか。とはいうものの〈琴座〉の輝かしい歴史的三百号故、何か文章と思いましたが、とてもうまく書けません。そこで《冷位》五百五十句から、小生の好きな句を二十六句選んでみました。(#C_049、四~五ページ)
このように苦労した〈西脇順三郎アラベスク〉執筆の経験が、書きおろしの《土方巽頌》で活きることになるのだが、それはさておき、詩篇〈神秘的な時代の詩〉を初出形で読もう。
001 走っている電車のなかで 本文への手入れは初出以降ほとんどないが、漢字に三箇所訂正がある。三七行め「鐘」が「鍾」へ(書肆山田版詩集ほかいくつかの版で「鐘」が活きている)、七○行め「龍」が「竜」へ、八五行め「姙」が「妊」へ。
高橋康也は〈肉のようなものが甲羅のなかへ〉という詩集《神秘的な時代の詩》書評で注目すべき見解を述べている。「「一篇の詩」は「今日 生卵の黄味のゼリーの表面に」つまり、目に見えぬ殻の中に、印刷され、詩人の書く「血の出るテープ一万呎」は「小さな鉄のボックス」のなかへ「走り込んで行く」のである」(#C_040、二二一ページ)。私はこれを読んで正直言って困惑した。「生卵の黄味」というのは旅館の朝食に欠かせないあの小鉢に割りいれた食べる寸前の状態を考えていたからだが、なおかつ厄介なのはそれでいながら「今日」をコンニチと読んでいたのだ(むしろキョウと読むべきだった)。吉岡はこれまでにも単に「卵」で殻に包まれた状態を表現しているし、「黄味のゼリー」とあるのも食膳の姿を彷彿させる。《静物》以降、初めて「生卵」が登場し、そこに「詩が印刷される」というのは只事でない。それがDNAの喩だとしても、吉岡の詩に「詩」が出現したことが異例なのだ。吉岡の詩と「卵」の関係を見ることから、評釈を始めたい。
吉岡実が一九四九年八月一日の日記に「或る場所にある卵ほどさびしいものはないような気がする。これから出来るかぎり〈卵〉を主題にした詩篇を書いてみたいと思う」(#A_10、一一六ページ)と書いて以来、卵は詩はもちろんその周辺に数多く登場してきたが、今ざっと思いつくだけでも三種類ある。①著書における卵の図像(詩集《静物》函・表紙の真鴨や中鷺の卵大のペン画――真鍋博の手になるが(#B_140、六ページ参照)、クレジットはない――や《土方巽頌》ジャケットの中西夏之作の卵形オブジェ)。②散文・日記における卵の記述(母との訣れになったときに食べた茄卵や前述の詩の主題として思いさだめられた卵)。③他者の書物に現れた卵(われわれがそれを知るのは②に依ってである)。ちなみに《「死児」という絵〔増補版〕》には卵の短歌が二、三首見えるが、俳句は登場しない。卵から孵るのは、蛇なのか鳥なのか。
・蛇よ匍ふ 火薬庫を草深く沈め 富澤赤黄男
・吹き沈む/野分の/ 谷の/耳さとき蛇 高柳重信
・なまぐさき/眠りの/蛇を/雪降りつつみ 高柳重信
・禿山を転がる金剛力の蛇 夏石番矢
・音楽漂う岸侵しゆく蛇の飢 赤尾兜子
・枝を垂れし蛇にさびしき沼明り 飯田龍太
・冬の日の凝れば無為なる蛇の貌 吉岡実
――
・花粉の日 鳥は乳房をもたざりき 富澤赤黄男
・石を積む宿命 鳥は水平に翔び 富澤赤黄男
・鳥や雲 にんげん哄笑ふとき 泪 富澤赤黄男
・外套やこころの鳥は撃たれしまま 河原枇杷男
・鳥帰る一羽は天の裏門より 河原枇杷男
・鳥の巣のわづかに見えて冬木立 吉岡実
一方、短歌の方は鳥の卵である。
・大きなる手があらはれて昼ふかし上から卵をつかみけるかも 北原白秋
・鶏[にはとり]のたまごがわれて黄なりしを朝がた寒くひとり見てをり 前川佐美雄
これらは〈静物〉(③・4)の「そこには夜のみだらな狼藉もなく/煌々と一個の卵が一個の月へ向っている」卵黄と満月が重さを均しくする全き世界、曇りなき球形につながるものではない。《静物》の卵はまた、ファロスのように「大地」(〈卵〉③・7、〈雪〉③・14)に屹立する。吉岡は北原白秋の短歌世界から超現実的な詩へ移ったころをふりかえって、次のように書いた。
私は十五歳から十九歳まで、《桐の花》の世界にいた。〔五首略〕の官能と雰囲気を愛した。それにつづいて《雲母集》の〔四首略〕の野性と生命感とに驚嘆した。やがて《雀の卵》のうちの〈葛飾閑吟集〉の〔三首略〕のいわゆる枯淡な障子の世界に入ってきたので、私はここで停った。私の求めるものは乾燥した事物でないだろうかと考えた。新しい刺戟を欲した。いうならば、コンクリートの壁に冷酷にも触れたバラの花の痛ましさを。私は前川佐美雄や石原純の新短歌をみつけて、ためらいもなく真似た。だが中途半端な気がしてやめた。その頃、〔……〕ピカソの詩を発見し、興奮した。〔……〕/短歌をつくるより、未知の感覚とイマージュを呼び入れるに絶好の詩型を発見したのだ。それが超現実派の詩であることがやっとわかった。(#A_25、六六~六七ページ)
この「コンクリートの壁に冷酷にも触れたバラの花の痛ましさ」は、徴兵を目前にした青年自身であると同時に女陰の隠喩でもあろう。詩集《液体》はこうして準備された(歌のわかれは前作《昏睡季節》の後半でなされた)。《静物》の「卵」は死を充填した生、戦後の吉岡が発見した「詩」だった。卵は〈陰画〉(⑤・6)を最後に吉岡の詩の主題の座を降りるが、それを岡井隆は「「陰画」の卵は、一対の男女のあいだにあって、ころがったり輝いたり、すさまじく通りすぎたりしながら、人間の「愛と死の共存」のさまを、その内部へと閉じこめている卵である」(#A_32、一一九ページ)と述べて、《静物》以後の変貌を指摘した。〈神秘的な時代の詩〉の卵は、後年吉岡が随筆で引いた高柳蕗子の短歌「人類の長い余生の庭先で夢見心地に卵抱く鳥」を想起させる。佐美雄の割れた卵に較べて、ほとんど無精卵である。前作〈色彩の内部〉(⑦・4)まで作品に「詩」という文字を定着したことさえなかった吉岡は、本篇でひとつのタブーに挑んだ。「詩」への言及だ。〈わたしの作詩法?〉で詩篇において「使わぬ文字」(#A_25、八九ページ)に「詩」が挙がっていないのは、自明だったためにすぎない。だが〈陰画〉のあと卵に「詩」が仮託できなくなれば、自ら課した禁を犯すしかない。タブーにふれてでも「詩」の領土を開拓する以外にない。〈神秘的な時代の詩〉に見える展開の意外さは、論理の世界からかけはなれるほど逆にリアリティが増す夢のそれに等しい。これでいけば、詩に取りいれられない題材はなく、表現のために検討されない語はなくなる(そう「詩」でさえも)。吉岡実が詩を書くのではなく、詩によって吉岡実が書かれる逆転現象が、当時指摘された「雅俗折衷の文体」に現れる。しかし雅と俗をひとつにコンバインした「芸術的胃下垂」はすぐさま「おお陳腐!」と揶揄されてしまい、続けざまに「今日 生卵の黄味のゼリーの表面に/一篇の詩が印刷される!」と揚言される。卵は日記に書かれて以来、二○年にわたる使命を終えて〈わたしの作詩法?〉という墓碑の前に花束として捧げられた。その供物を手に吉岡は自らの危機を中央突破した。卵黄と卵白のあわいに「詩」がある。卵白にあるのは「活字」よろしく反転した文字だ。黄色の補 色「むらさきの眼」の「未生児」は、もう一人の「死児」かもしれない。では次に、吉岡実の「神秘」の実相を求めて、散文を渉猟してみよう。

村松嘉津《新版 プロヴァンス隨筆》(大東出版社、1970年3月15日)と《プロヷ〔ワに濁点〕ンス隨筆》(東京出版、1947年8月20日)
村松嘉津著《プロヷ〔ワに濁点〕ンス隨筆》(東京出版刊)は、西脇順三郎の詩集《あむばるわりあ》《旅人かへらず》(同)とともに戦後の吉岡に感銘を与えた書物である。吉岡が一九六九年五月号の《文藝》の〈名著発掘〉欄で同書を取りあげて、この「ユニークな随想集」の「美しい造本の再刊」(#A_25、一五ページ)を希んだのを受けたかのように、翌七○年三月に大東出版社から《新版 プロヴァンス隨筆》が刊行された。村松の新版〈序〉から、新字に改めて引く。
〔……〕最近に到り、東大仏文教授井上究一郎氏が雑誌『文藝』(昭和四十三年八月号)の「名著発掘」欄に同書を「発掘」して下され、更に昨〔一九六九〕年四月二十八日の朝日新聞学芸欄「旧刊紹介」に、作家菊池重三郎氏が同書を挙げてをられる旨を他から知らされ、いづれにも意外な喜びを覚えた。(#B_151、一~二ページ)
吉岡は菊池文を読まずに〈名著発掘〉を書いている勘定だが、はたして九ヵ月前の井上文を読んでいなかったかどうか。知らなかったからこそ同書を取りあげたと思う一方で、井上文を機に再読に及び、あえて〈名著発掘〉に村松の本を選んだという考えを私は捨てきれない。――井上が指摘した「美しい「地中海の霊感」の書」(#C_029、六一ページ)の側面が吉岡詩で明らかになるにはしばらく時を必要として、詩集《サフラン摘み》まで待たなければならない。――元版、新版とも《プロヷ〔ワに濁点〕ンス隨筆》の巻頭は〈にんにく〉である。村松の文章を味わう意味も込めて、少し長いが元版から引用しよう(旧字は新字に改め、くの字点はひらがな・カタカナに変更した)。
にんにくを用ゐた最も有名なプロヷ〔ワに濁点〕ンス料理はアイオリーだ。それはこの地方の豊かなオリーヴ油を得て世にも結構な御馳走となる。ある夏の日、料理部屋からコトコトといふ音がしきりに続くので、何のお料理かと這入つて見ると老婢が乳鉢様のものゝ中に乳棒様のものを以て懸命に敲いてゐる。今日はアイオリーをしようといふのである。わたくしにもさせて頂戴、と代つて乳棒を握らうとする手を押へて、「少くとも貴女は今御病気ではないでせうね」といふ。穢れた者が触るとアイオリーは崩れてしまつて出来なくなる、といふのである。「これは昔の馬鹿気たことだとお仰るでせうけれど、何しろさういふ言ひ伝へですからね……本当に昔者は馬鹿なんですよ」と微笑しながらも真剣だ。さうしてアイオリーの作り方を教へて呉れる。先づ鉢の中に一人当り一鱗片の割でにんにくを入れる。それにこの地方で専ら用ゐられる粒状の塩塊を、大中小と三粒入れる。大きいのは父[ペール]、中位のは子[フイス]、小さいのは聖霊[サンテスプリ]と呼んで三位一体に擬するのだといふ。それをコトコト砕いて大体砕けたら卵の黄味を入れ、それから徐々に滴々とオリーヴ油を加へながら絶えずかきまはしてだんだんにコッテリと練り上げて行く。下手をすればそれが固らずに落ちてしまふ。早い話がにんにく入りのマイヨネーズなのだが、たゞ酢を入れずに油だけで展ばして行くので、しまひには棒が動かなくなる程固くなつて、山のやうに盛り上る。信仰深いこの国の古い愛すべき風俗は、マイヨネーズの失敗にも何か神秘的なものを絡めて不浄を避け、三位一体に呼びかけるところが可憐ではないか。(#B_150、六~七ページ)
吉岡が〈名著発掘〉で引用した下線部分のあとに注目したい。「卵の黄味」(ふつう「黄身」と書くべきところ、吉岡も「黄味」と書いている)が登場するだけでなく、にんにく入りマヨネーズの失敗に「神秘的な」理由が挙げてあるではないか。これが単なる偶然だろうか。吉岡が村松の随想に読んだ食の官能性が、詩篇に「時代の食の官能」とでも言うべきものをもたらしている。「ニンニクの肉房のように/忘却されている」(〈コレラ〉⑦・18)。ところで「それから、「きみ」とか「あなた」とか呼びかける二人称を使って詩の構造を複雑にする方法をとっていない。「きみ」「あなた」とは、神であり、社会であり、そして肉親、恋人、そして未知の人である、一種のあいまいさが、わたしにはどうしても納得できなかったからである」(#A_25、八九ページ)にしても、「黄味」ならざる「きみ」はこう書かれる以前、すでに〈内的な恋唄〉(⑥・12)に登場していた(〈色彩の内部〉評釈で指摘した未刊詩篇〈哀歌〉からの再生部分直後の第七三行)。
きみがぼくを殺しにくる
「ぼく」は一度死ぬことで、詩における禁忌と同水準に引きあげられることを待望しているようだ。そのような、死と再生の局面を吉岡は「神秘的」と呼んだのではないか。散文での用例を見よう。
①あと卵の黄味を入れ、オリーヴ油を緩々に滴して練り上げてつくるマヨネーズの一種なのだが、料理にも神秘なものを求める素朴さが出ている。(#A_25、一五ページ)②たしか集中の圧巻は、オオムラサキ蝶の生態観察で苦心さんたんの暁、遂に転身、羽化の一瞬の神秘的な劇をみごとにとどめていたように思う。(同、一六ページ)
③美しい庭をながめながら、その婦人はつれづれなるまま、寺の説明をしてくれたが、その多くは忘れてしまった。ただ五月すぎには、縁の下にほんのわずか、ひかりごけが発生するという。なんとなく神秘的な思いがあったので、記憶にのこった。(同、二九ページ)
④大岡信の言葉によると、伊達得夫はすでに伝説的人物になったという。死者は誰でもがそのように神秘的になれるものではない。(同、六九ページ)
⑤〔……〕ありきたりの悲劇なのだ。きわめて現実感にみちた、画面の流れが止ると、一つの神秘的な儀式がはじまる。夫は死んだ妻の裸身を、小さな湯舟で、洗い浄めて、おもむろに屍姦するように見える。(同、三五四ページ)
①②はともに〈名著発掘〉から。①は引用した村松文の末尾に対応する。②は「変態」の仕上げ、生誕の瞬間だ。③で武田泰淳〈ひかりごけ〉が作者の脳裡に浮かばなかっただろうか。④は優れた人物の死後である。⑤は田中登監督の映画〈人妻集団暴行致死事件〉についてのもの。吉岡はこれらの散文で、ほとんど宗教的な死生観の発現のたびに嘆声をあげているようだ。
詩篇〈神秘的な時代の詩〉に戻ると、詩は現在と過去のある一時点の二点を中心に構成されている。二点を行き来する動きが詩を用意する。そのとき〈神秘的な時代〉の〈詩〉は〈神秘的〉な〈時代の詩〉を包括しようとするようだ。二点間に存在する幾多の時代とそこに生き死にする人人。この詩には異様なほど多くの人物が登場する。
①わたしたち ②△マネキンたち ③青年たち ④△母なる獣 ⑤老婆のむれ ⑥夫人 ⑦商人 ⑧密着美人 ⑨マリリン・モンロー ⑩覗く人たち ⑪△広告用ビーナス ⑫黒人 ⑬群衆 ⑭女 ⑮未生児 ⑯△オバケ ⑰少年たち ⑱少女たち ⑲夜警たち
△印は厳密には「人物」ではないが、一九人(うち半分は複数形)は一○三行の詩には多いだろう。詩は、登場人物が脈絡もなく舞台に現れては消えてゆく暗黒舞踏やアングラ演劇のようだ。前詩集《静かな家》でほぼ同じ長さ(一○二行)の〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)を見れば、人物は次の一一である。
①青年 ②姙婦 ③△精霊たち ④△父母の像 ⑤ベビー ⑥恋人たち ⑦男女 ⑧少年 ⑨少女 ⑩女 ⑪葬儀人夫
詩のテーマがオートバイである点を考慮しても、〈神秘的な時代の詩〉は多くの人物を擁しており、詩句は二、三行を単位に人物ごとにカメラアイを切りかえている。人物を次次に繰りださなければ生じなかったであろうとりとめのなさを考えることは、吉岡の詩法を考えることだ。ここでもう一度、人物表を書きあらためてみる(下線部は原文と同形であることを示す)。
「いくつもの白塗り頭のマネキンたち、両手をつく青年たちにしてさかだちの母なる獣、マタニティ・ドレスをひらひらさせた老婆のむれ、かがやく鍾乳洞の美しき夫人、死の塩の商人、密通密着美人、燐光塗料のかつらをかぶるマリリン・モンローの肉体はちぢんだ!、殺到する覗く人たち、くびれた存在の痔の広告用ビーナス、ニンジンを抱いて死んで行く黒人、群衆の中の腰巻きの海軍旗を口にくわえた鎖の女、未生児のむらさきの眼、音楽や木の芽のように出るオバケ、血の出るテープ一万呎をなびかせては寝る妊娠可能の少年たち、いかがわしい蘭のからまる少女たち、夜景をまわる夜警たち、わたしたちの有罪期の半跏思惟像!」
これらの人物は「スフィンクス製造の原理」によって産みだされたと考えられないだろうか。むろん吉岡自身がそんなことを言っているわけではない。古代エジプト人が人頭のライオンを呼んだスフィンクスの第一義は「生ける彫像」(#B_043、一九三ページ)である。人頭のライオンたる不可解な人、なぞの人物を造形することこそ、「人間への愛と不信」の「双貌」(#A_25、九四ページ)をこの詩に刻した吉岡実の目的だった。もっともそれは、吉岡が「スフィンクス製造の原理」だけで作詩したことを意味しない。この時期、吉岡の詩句の展開には、前作〈色彩の内部〉に見えた畳韻法あるいは類似の音の多用が強く働いている。「走っている/
白昼|白塗り頭」「アメ/青と赤/アンモニヤ」「密教/妄想|密通/密着美人」「シナ/神秘的」「よこたわる/弓張月」「マタニティ/むれ/ミシン」。これらすべてが意図的ではないかもしれないが、次の詩句ならどうだろう。
「死の塩の商人」、「口にくわえた鎖の女」、「夜景をまわる夜警たち」、「黒くなるべき孔雀」。
いったいこれらはことば遊びなのだろうか。過度の意識の集中が無意識と粉う状態に到るまで、「像」からではなく「音」から対象に接近すること、論理的な構造物として記憶を綴りあわせないこと、そうした前提がこの詩をかくあらしめているように思われる。では書かれたのはなにか。「シナの枕はどうしてあんなに長いのか?/神秘的なほど重く」が問として成立する場に、中国大陸に在った戦時と都市に在るこんにちの生と滅を詩が指ししめす。この枕は長木枕(「一端を木槌で叩かれると、その衝撃による振動が木の端まで伝わり、頭がしびれて痛いので、皆一斉に飛び起きた」#B_067、二二ページ)よりも、長枕(括り枕で「長さが普通の枕という感覚の枕より長くて、二人用のものもあった」同、二六ページ)のように思われるが、二人用の枕であるならそれは満人夫婦のものだろうか。また、「シナの枕」が長木枕であるなら、多くの中国人と多くの日本人が死の床に横たわるためのものでなくてなんだろう。
高柳重信は吉岡の詩法を連句の作法と比較しながら、〈苦力〉(④・13)は「それによく似た構造を感じさせるが、更に、もう少し複雑に組み立てられて」おり、「螺旋状の運動を繰り返す」(#C_039、一八四ページ)と指摘した。〈苦力〉から一○年を経た本篇において、吉岡の筆の運びはさらに複雑、大胆になってきている。「青と赤のウズマキの上昇する」なる詩句は「アメの棒」の捩れた形の描写であると同時に、床屋の店先の静脈と動脈を象徴する看板である。かつては行と行の間にあった関係を詩句自体に取りこむこと。吉岡詩はその「螺旋状の運動」の徹底によってスフィンクスを製造したのだ。この詩や同じ月に発表された〈崑崙〉が、〈苦力〉の六○年代的な変奏となったのは偶然ではない。下半身が深深と闇に溶けこんでいるスフィンクスの謎。あらゆるものが同時に二方向に動こうとすることによって捩れが生じる。それが解けるまで、詩句は意味においても、像においても変転することをやめない。
私はこの詩を何度も読み、文藝空間の例会で口頭発表するにあたっては、準備のために朗読したカセットテープを繰りかえし聴きさえしたが、確かに読解したという感触は得られなかった。さらに全行に及ぶ語釈の作成まで試みたが、その営み自体まったくの無駄ではなかったにしろ、詩の肝を掴むには覚束ない。ときに、五七~六一行の五行は次のように組みたてられていた。
A①わたしたちの言語のなかで/②腐るもの・③変るもの/a①永遠の明暗のなかで/②痛むもの!/③くびれた存在の痔
この箴言的対比、もしくは詩論の断章において、Aとaの関係をどう読みとくべきか。私は吉岡さんにベルギーの画家ポール・デルヴォーについて尋ねたときのことを想いだす。本評釈の〈立体〉論の初稿を書いたあとだったが、デルヴォーはお好きですかという問に、前は好きだったけれど「夜の画家」だとわかってしまって……、という返事だった。あえてそれ以上は訊かなかったが、どうも「夜の画家」であるだけでは本質的に興味がもてない、というふうだった。「明暗」はそうした両面性の謂に思えてならない。――漱石《明暗》の「二」の初め「電車に乗った時の彼の気分は沈んでいた。身動きのならない程客の込み合う中で、彼は釣革にぶら下りながら只自分の事ばかり考えた。去年の疼痛がありありと記憶の舞台に上った」(#B_109、七ページ)がこの詩の冒頭を用意していると想像することは愉快だが、それは一八行めと七一行めに〈美しき天然〉と〈ああ世は夢か幻か…〉(#B_136、一二七ページ)を附会するようなものだ。
「わたしたちの言語」とは日本語ではあっても、詩ではない。むしろ「腐るもの・変るもの」の側に吉岡の言う詩がある(詩が不壊の輝きを帯びているかどうかは、また別である)。吉岡は自作の和歌をまとめるにあたって採用した〈蜾蠃〔スガル〕鈔〉という標題に触れて、《万葉集》の腰細の娘を喚起している(#A_25、八一ページ)。《明暗》よりもこれが「くびれた存在の痔」を読みとく鍵にならないか。もうひとつの「痛ましき薔薇」。それより前では黄金探究者が詩人に準えられる。四五~四六行めの「恥らう楕円のなかの裂け目で/黄金をみつけるか?」は充分にエロティクな像を描きつつ、七六~七七行めの「卵」と「詩」の関係を先取りしている。おそらく「言語」とは白身のごとき存在ではないか。この言語観は吉岡にとってそう古いものだったとは思えない。「詩」が問題にならないところで「言語」が問われることはないからだ。だがここで、詩/言語、黄身/白身、生/死という対が織りなすマトリクスがあまりにシンプルであるとするなら、〈神秘的な時代の詩〉は吉岡詩においていかなる位置を占めるか。この時点で全詩集的な《吉岡実詩集》(#A_08)およびその詩的発想を開陳した〈わたしの作詩法?〉を乗りこえる宣言、それが出発点である。そして、その卵型の造形性を放棄することで、横へ横へと展びひろがってゆく新しい書法を確立したというのが終着点である。中心はどこにもない。〈静物〉(③・1)を無重力空間に置いたところでこうはならない。
「意識のながれ」(#A_25、八八ページ)の定着にあたって、あくまで物や像の側から接近するのが吉岡の身上だった。神秘は物の誕生や消滅それ自体にあるというよりも、物がある地点から別の地点に動くことの裡にある。意識という川を物体が移動することでながれが生じる。このながれそのものは以前から吉岡詩に存在していたが、題材が多様化し、詩の文体が軟化してゆくにつれて、その極北である詩集《神秘的な時代の詩》において最も鮮明な形をとることになった。その詩法の根幹をなすのが、私の言う「スフィンクス製造の原理」である。それらの試みの成果はどうだったか。厳しく言えば、音を挺子に詩句を連
ねる展開の不協和音、カタカナ表記の名詞に代表されるある種の軽さ、本来は求心的な発想・語法の書き手が長い詩で起こす主題との肉離れ現象がなかったとは言えない。事態はむしろ逆で、もっと崩れなければならないのに崩れきっていない、と言ったほうが近いか(感嘆符や疑問符には断言や自問自答のニュアンス以上に、もっと崩れたい、崩してしまいたいという願望が見える)。詩句が動機に沿って同じ方向に並びはじめるや否や、その効果を打ちけそうとするように、話頭を転じ、転じ、さらに転じる。それが吉岡の苦渋に満ちた退却戦でありながら、図らずも「時代」を写す進撃となったのは、現時点から振りかえって見れば明らかだ。変貌する時を不動の点から裁断して、そののちにランダムに再構築し、移動と変化を描いた詩篇が〈神秘的な時代の詩〉だった。だが「不動の点」とは穏やかでない。おそらく中国大陸における吉岡の戦中体験に基づくなにかが、それだ。暗黒からの眼差しが移動と変化を見すえる。その累積がこの詩集の別名かもしれない。そしてそのすぐ隣にあるのは、長(篇)詩〈波よ永遠に止れ〉が果たさなかった、同時代との接点である。詩篇〈崑崙〉の登場だ。
太史公曰く、『禹本紀』に、「黄河は崑崙の山から源を発する、崑崙は高さが二千五百里余りあり、日と月が光明をかくすところである、その上には醴泉と瑶池がある」としるされる。/ところが張騫が大夏に使者として赴いたあと、ひとはついに黄河の水源をきわめた。かれらは『禹本紀』に言う崑崙の山など見つけはしなかった。――《史記》(#B_056、九九ページ)
ハミ瓜の姉妹品――西瓜も新疆の特産である。『五代史』には、西域から西瓜を内地にとり入れたという記載がある。明の科学者徐光啓も『農政全書』に、「西瓜 西域より出づ、故にこの名あり」と書いている。近年、新疆出土の文物といっしょに一千余年前の西瓜の種が発見された。新疆が中国の西瓜の里だったということはこれからも知られよう。新疆の西瓜は大きく糖分も多く、水分に富んで甘い。ゴビ砂漠をいく旅行者がのどの渇きをいやすには、この西瓜にかぎる。一口で心身ともに爽快になる。――王思華〈瓜の香りで匂うシルクロード〉(#B_089、一八二~一八三ページ)
*
〈スイカ・視覚的な夏〉(⑩・13)は一九六八年八月一九日付の《読売新聞》の夕刊に、橋本彰禧記者の写真(ふたつ割りのスイカ、サンダル、如露の置かれた砂浜にビーチパラソルの影が射す)を添えて、〈八月のうた〉として発表された。長詩〈崑崙〉(⑦・8)の載った《南北》一○月号は九月の初旬には出ていたのだから(〈「意識のながれ」Ⅰ〉参照)、この二篇は相ついで書かれたと考えてよいだろう。
スイカ・視覚的な夏|吉岡実スイカを割る
今晩八時ハーン
肉色の姉妹
肉色のスイカの四分の一の円
恋する二匹の猫
高いヘイから見おろす
肉色の月は明晩どこに出るかね?
肉色をえぐるサディストのサジの先
紳士は見つけるだろうか?
さびしい家
さびしいスイカのタネ
歯型のある青い皮
この世界には見とどけられぬものが多い
甘い汁でふとるふとる
肉色の姉妹の老婆
吉岡実が生まれる二年前に刊行された萩原朔太郎の詩集《月に吠える》には〈猫〉なる一篇が収められている。「まつくろけの猫が二疋、/なやましいよるの家根のうへで、/ぴんとたてた尻尾のさきから、/糸のやうなみかづき[、、、、]がかすんでゐる。/『おわあ、こんばんは』/『おわあ、こんばんは』/『おぎやあ、おぎやあ、おぎやあ』/『おわああ、ここの家の主人は病気です』」(#B_117、五○ページ)。
猫の恋は春の、スイカは秋の季語だが、吉岡の描いたのは夏の情景だ。「まつくろけの猫」の「ぴんとたてた尻尾」に相当するのは「肉色をえぐるサディストのサジの先」(ここにも畳韻法が見える)である。だが「スイカ」と「姉妹」を除いてしまえば、萩原の〈猫〉と異なるのは「肉色」だけだと言ってもよい。「実=果実の皮と種子の間にある柔らかな部分」の色は、二分割されたスイカを「肉色の姉妹」と呼んだ瞬間から(四半分のそれは「恋する二匹の猫」か)、霊に対する肉体の、皮膚の色に変化して、最もわかりにくい「肉色の月」の「肉色」となる。「肉色」は〈崑崙〉にも登場するのでここで性急に究明することは避け、そのかわりに別の面から考えよう。〈スイカ・視覚的な夏〉も〈猫〉も、その短さゆえに味わいが薄いということはない。換言すれば、謎に充ちている。吉岡実は萩原朔太郎の詩についてほとんど語ることがなかった(だからと言って、その影響を無視してかまわないということはなかろう)。ここでは両者を主題や技法の面から比較するのではなく、端的に一篇の詩の長さを手掛かりに両者に接近してみたい。幸いなことに《萩原朔太郎全詩集》(#B_117)が、重複の多いこの詩人の詩集の作品を見事に腑分けしているので、それを基に算出すると、
| 創作順 | 詩集名 | A篇数 | B総行数 | C平均行数 | 同順 |
| ② | 月に吠える | 55 | 708 | 12.87 | (2) |
| ④ | 青猫 | 55 | 1032 | 18.76 | (6) |
| ③ | 蝶を夢む | 44 | 619 | 14.07 | (3) |
| ① | 純情小曲集 | 28 | 325 | 11.61 | (1) |
| ⑥ | 氷島 | 21 | 354 | 16.86 | (4) |
| ⑤ | 定本青猫 | 22 | 405 | 18.41 | (5) |
| 全体 | 計、平均 | 225 | 3443 | 15.30 | ― |
平均行数(C=B/A)の少ない順に並べると(《定本青猫》を《青猫》と不可分の詩群とみなせば)《氷島》が(4)に繰りあがって乱れるが、そのまま萩原の創作順になるではないか。朔太郎詩は、詩集としての作品群ごとに行数が長くなっていったのである。では、吉岡詩はどうか。吉岡実の場合、詩の創作と詩集刊行の順序は一致している(参考に①と②の戦前の二冊も掲げるが、①の短歌・旋頭歌は省いた)。
| 創作順 | 詩集名 | A篇数 | B総行数 | C平均行数 | 同順 |
| ① | 昏睡季節 | 20 | 133 | 6.65 | (1) |
| ② | 液体 | 32 | 305 | 9.53 | (2) |
| ③ | 静物 | 17 | 437 | 25.71 | (3) |
| ④ | 僧侶 | 19 | 737 | 38.79 | (5) |
| ⑤ | 紡錘形 | 22 | 624 | 28.36 | (4) |
| ⑥ | 静かな家 | 16 | 737 | 46.06 | (6) |
| ⑦ | 神秘的な時代の詩 | 18 | 1179 | 65.50 | (7) |
| ①~⑦ | 計、平均 | 144 | 4152 | 28.83 | ― |
| ③~⑦ | 計、平均 | 92 | 3714 | 40.37 | ― |
ここでも《紡錘形》で乱れるが、行数はふえる傾向にある。もっとも、細かいことを言えば行数は、吉岡の多用した行分けの詩が同じ字詰めで書かれていない以上、一行が何字平均かも検討しなければならない。行数とは改行の回数プラス一である。何文字くらい書いて何回くらい改行するかが、その詩の、詩集の、詩人の特徴になるはずだ。試みに《紡錘形》以降のタイトルポエムの行数と各詩句(行)の平均的な字数の変化を次に見てみよう(散文詩型は全角空きを改行とみなした)。
| 詩篇番号 | 題名 | 行数 | 行平均字数 |
| ⑤・4 | 紡錘形Ⅰ | 22 | 13.5 |
| ⑥・16 | 静かな家 | 52 | 10.0 |
| ⑦・11 | 神秘的な時代の詩 | 103 | 9.0 |
| ⑧・1 | サフラン摘み | 42 | 12.2 |
| ⑨・20 | 夏の宴 | 120 | 8.9 |
| ⑩・1 | ポール・クレーの食卓 | 37 | 12.4 |
| ⑪・10 | 薬玉 | 80 | 10.1 |
| ⑫・10 | ムーンドロップ | 80 | 8.1 |
⑫・10を除くと、一○○行以下は一○字以上、一○○行以上は一○字以下というのがひとつの目安になる(⑪と⑫の詩篇は詩句に頻繁に字下げが施されているため、見掛けの行は行平均字数よりも長く感じられる)。吉岡は《昏睡季節》《液体》や《紡錘形》の版元名でもある「草蝉舎」という名入りの三二字×二○行の特製原稿用紙を詩作に用い、散文にはコクヨの二○○字や四○○字詰めなどの市販品を使っていた。本文が一○○行五枚を超える長い詩と、それよりも短い詩とで詩句の長さが変わるとすれば、必ずやそこに構造に関わる問題が含まれていよう。〈スイカ・視覚的な夏〉は、ある漢字・漢語をカタカナに開いた詩である。詩の本文を読みなおすと、「サディスト」以外〈すなわち西瓜、半、塀、匙、種)をカタカナで書くことによって、漢字で表記するよりも詩句の字数は多くなっている(さらに初出では二行め、一二行め末に感嘆符が打たれていた)! ちなみにこの詩は一五行から成り、詩句(行)の平均字数は一○・○である。
繰りかえされる「肉色」がつねに行頭に置かれているのは〈猫〉の会話が「お」で始まるのに通じる。一方「スイカ」「姉妹」「さびしい」「ふとる」もまた繰りかえされているのが注意を引く。後年、吉岡は金井美恵子との対談でこう語った。「だから、意識的に卵の詩を書く場合は卵が何回か出るけど、多くの詩の場合は、「薔薇」なら「薔薇」でもいいや、それが一度出たらもう出てこないはず。極力避ける。それがぼくの詩を弱くしているってこともあるかな。詩には繰り返しの強さというものがあるわけだけど、ぼくの潔癖性が繰り返しを避ける。だから将来コンピューターで調べてくれる人がいたらわかると思うけど(笑)」(#C_010、九八ページ)。
繰りかえしは意図的に避けられてきた。短い詩だからこそ繰りかえしを使って、ふだんの吉岡にも似ず読者に一種のサービスをしたのだろう。にもかかわらずわかりやすいとは言えないし、繰りかえしが詩を強くしているわけでもない。むしろわたしはこの詩篇が永田耕衣の俳句――《驢鳴集》の「戀猫の戀する猫で押し通す」(#B_100、六二ページ)である――の繰りかえしに触発されたものかもしれないと想像する。連想はさらに拡がり、小澤實の昭和五七年の句「尾を水平に猫の恋了はりけり」(#B_022、三五ページ)を萩原朔太郎、永田耕衣、吉岡実のあとに置きたくなる。
〔一九六○年〕四月九日 〔……〕NHKの放送詩集の締切迫る。/四月十五日 四十一歳の誕生日。〈波よ永遠に止れ〉夜十二時に完成。陽子に浄書してもらう。――吉岡実〈断片・日記抄〉(#A_10、一二三ページ)
*
こと吉岡実の詩に関するかぎり一五行の詩だからわかりやすくて、百数十行の詩だから難解だということは、まったくない。ただ、読めば理解できる長い詩が、一篇ある。それは〈波よ永遠に止れ〉という吉岡最長の二五七行の作品で、年譜には「NHKラジオの放送詩集〈波よ永遠に止れ〉(雑誌掲載稿から八○行を削徐して〔五月〕一一日に放送)の本番録音に立ちあう」(#A_32、二九四ページ)とある。この詩は吉岡にとって特別の意味を持つ作品で、ひとつはもちろんその長さである。そして(こちらの方が重要なのだが)吉岡はここで軍隊の体験を書く小手調べをしたのではないかと思われる点である(吉岡は随筆の類を除いて、それと明瞭にわかる形で軍隊経験を書いたことはない)。
わたしは前回〈神秘的な時代の詩〉(⑦・11)の「シナの枕」に触れつつ吉岡詩の「シナ」の探求を約したから、この章の本題に入るまえに、この時までの全作を照合してみることから始めよう。――初期の詩には人名・地名などの固有名詞は登場しなかったから「いまでもビルマのカレンニ地方に二千人も住んでいるとのこと」(〈首長族の病気〉⑤・11)あたりが地名の最も早い登場だろう。吉岡家蔵の切りぬきファイルには〈ビルマの「クビナガ族」〉を紹介したコラムがあるが、どの新聞にいつ掲載されたものか判明していない【その後の調べで《朝日新聞〔朝刊〕》1959年11月3日付〔第26503号〕3面のコラム記事〈だんだん首輪ふやす――ビルマの「クビナガ族」〉だと判った】。だが〈波よ永遠に止れ〉よりも半年前に発表されたこの作品に、典拠と引用の作詩法の先蹤を見ることは妥当だ。――さて「支那」である。
・いちじくは皿の中心でとがる といったずっと自然な内腔への愛 それはいつでもわたしの考えている 支那の幼児の食べる物を想像させる(〈修正と省略〉⑤・22)
・アメリカの高層気流から/シナのさかれたフカの水墨の海へ/逃げるチャリーが見えるか?(〈やさしい放火魔〉⑥・9)
・ぼくが殺した運転手/きみらが殺した服飾デザイナー/かれらが殺したミス・シナ(〈内的な恋唄〉⑥・12)
・ぼくがクワイがすきだといったら/ひとりの少女が笑った/それはぼくが二十才のとき/死なせたシナの少女に似ている(〈恋する絵〉⑥・15)
・コルクの木のながい林の道を/雨傘さしたシナの母娘/美しい脚を四つたらして行く/下からまる見え(同前)
「支那」が「シナ」へ変わったのは《静かな家》からで、これは《僧侶》が漢語を、《サフラン摘み》がカタカナを詩句の重要な要素としているのと符節を合わせたかのようである。手許の辞典の【支那】には「外国人による中国の呼称。〔……〕わが国では江戸中期から第二次世界大戦まで、中国の一般的呼称として用いられた」とある。江戸中期、享保以来の吉岡の家系で吉岡実はおそらく初めて中国大陸に渡り、輜重兵ゆえに戦闘はせず、再び故郷へ戻った。吉岡が軍隊経験を書いた数少ない文章のひとつに〈済州島〉がある。短文なので全文を引く。
朝鮮の一孤島済州島で終戦をむかえた。いつわりのないところ、私はほっとした気持だった。多くの兵隊もそれにちかい心情であったろう。ねじあやめ咲く春の満洲を出てから四ヶ月目であった。済州島は日本帝国の最後の橋頭堡であったらしい。恐らくあと一ヶ月戦いがつづいたら、済州島の山の中が、私の立っていた最後の地上になったであろう。それが反対に、死から私を庇護し、なつかしい再生の土地となった。済州島へ上陸以来、毎日輓馬で弾薬や食料を山の奥へ奥へと搬んでいた。そして野営をした処が新星岳だった。そのうち馬は倒れた。食料のとぼしい時なので、倒れた馬は殺して喰べた。ろくな飼料を与えられていない馬たちの肉は、脂がなく味気なかった。暇ができると、野苺をつみながら山の中腹で憩うのだ。われわれの島をかこむ夕映の海が見え、その輝く波の中に青々とした飛揚島が泛んでいた。ふりむけば、峯々が重なり、その奥深くに、名峯漢拏山がそびえていた。あっちこっちに石をつんだ垣がつらなっていた。そのかげのところどころに、馬の墓が簡単な石で象どられて、野草が供えられていた。われわれ人間のあいだには、異郷でさびしく死んだ人……などという哀悼の言葉がある。しかし異郷で死んだ馬にはそれがない。石の下で、今では完全な白骨となっていることだろう。(#A_25、四四~四五ページ)〔傍線は引用者、以下同〕
大方の日本人にとってこの二○○年間、支那の実態を知ること、いかほどであったろう。支那は文明の大国であるなどと言っても、江戸や明治・大正の人間に「崑崙」に関する知識がどれほど備わっていただろうか。つい崑崙にまで筆が及んでしまったが、散文で「支那」を追ってゆくと該当するものはちょっと見あたらず、そのかわりに「満洲」を〈わたしの作詩法?〉に見いだすことになる。自作〈苦力〉(④・13)全篇を引いてから(ここでは「支那の男」が実に七つの詩句に登場する)、吉岡はエッセイをこう締めくくる。
ここに、「苦力」という一篇がある。なぜこれをとりだしたかというと、わたしの中で異色ある作品であると同時に、旅先の一夜で出来た唯一のものである。わたしは日常雑多な自分の家で、しかも食卓に向ってしか書く状態にない。独身時代の多くは、寝床の中でしか、ものを考え、まとめることができなかった。その時は机、本棚はなく、畳の上に本の砦をつくり、汚れた寝床で、水平にならないと、詩が書けなかった。しかし家庭をもってからは、食卓で書くようになった。現在でも一部屋なので机は無いから。独身時代の昭和三十三年ごろ、週末に、気が向くとよく谷川温泉へひとりで遊びにいったものである。或る時、早春かと思うが、前夜は合客にアベックが一組いた。つぎの日は、帰った。日中は、谷川の渓流をさかのぼり、巨大な流れの中に浮んでいる平らな岩にねて英気を養った。旅館はうす暗く、帳場は遠く、夜がふけるにつれ、水の音だけが聞えるうちに、耐えがたい孤独感というより、無気味さに眠られぬ状態になった。目の前の崖上に廃屋の窓が見える。わたしは朝が来るまで、詩を書こうと試み、そして「苦力」が暁近く完成した。これは兵隊で四年間すごした満洲の体験である。
「支那の男」とは、当時の満人である。満人というより、「支那の男」の方がスケールが大きいと思ったからである。彼らは裸馬を巧みに乗りこなしていた。馬は満馬といって、小形であるが、大変気質が激しく、乗りにくい。
わたしたち輜重兵は、馬運動と称して、毎日のように、馬にのって遠くの部落まで、高粱畑を越して行った。冬は刈られた高粱が、まさに鎗先を揃えて、どこまでも続く。万一にも落馬したら、腹にでも顔にでも突きささるだろう。そんな恐怖感があった。「瓜のかたちの小さな頭」とは、彼らの頭が小さいわけではないが、裾の長い藍衣を着ているので、そう見える。それと、兵隊はいつも飢えていたから、部落で食う瓜がとてもうまかった。内地のマクワ瓜の味より格別にうまい。夏はそれで渇をいやしたものだ。そこで瓜と頭が結びついた詩句になる。「排泄しながらのり越える」とは、兵隊とはいえ、わたしたちの中には、排泄の場所は習慣として、一定のところへするが、満洲では、満人部落の周辺といわず、曠野に道に、排泄物がちらばっている。もちろん家畜のものもあるが、排泄物こそ彼らの力であるように思えた。極寒の兵舎の厠のぞっとする底で、火山の噴出物のような排泄物の氷った塊の山をつるはしで崩していた満人の見えない顔。
またここに「支那の男は巧みに餌食する」とある。餌食[、、]は「エジキ」だから、〝餌食にされる〟〝餌食にする〟が正しいが、この一行のときは、どうしても「ジショクする」と発音していたのである。これは誤りであるが、わたしにとって、〝餌食する〟は〝ジショクする〟でなければならない。今では別に〝餌食[エジキ]する〟でよいと思っている。或る別の部落へ行った。兵隊たちは馬を樹や垣根につなぐと、土造りの暗い家に入って、チャンチュウや卵を求めて飲む。或るものは、木のかげで博打をする。豚の奇妙な屠殺方法に感心する。わたしは、暗いオンドルのかげに黒衣の少女をみた。老いた父へ粥をつくっている。わたしに対して、礼をとるのでもなければ、憎悪の眼を向けるでもなく、ただ粟粥をつくる少女に、この世のものとは思われぬ美を感じた。その帰り豪雨にあい、曠野をわたしたちは馬賊のように疾走する。ときどき草の中の地に真紅の一むら吾亦紅が咲いていた。満人の少女と吾亦紅の花が、今日でも鮮やかにわたしの眼に見える。
楊柳の下に、豪華な色彩の柩が放置されているのも、異様な光景だ。ふたをとって覗いて見たらと思ったが、遂に見たことはない。びらんした屍体か、白骨が収まっているのだろう。みどりに芽吹く外景と係りなく。やがて黄塵が吹きすさぶ時がくるのだ。
反抗的でも従順でもない彼ら満人たちにいつも、わたしたちはある種の恐れを抱いていたのではないだろうか。「万朶の雲が産む暁」、この詩章こそ、満洲の曠野と遠い高い空をあらわしているとひそかに自負する。「万朶」につづく言葉は、恐らく「桜」しかないであろう。わたしは、あえて比類ない華麗な満洲の夕焼雲を「万朶」の下へつけた。
彼らは今、誰に向って「陰惨な刑罰」を加えつつあるのか。
わたしの詩の中に、大変エロティックでかつグロテスクな双貌があるとしたら、人間への愛と不信をつねに感じているからである。(#A_25、九二~九四ページ)
長長と引いたのは、ほかでもない。吉岡が井上靖の中篇小説〈楼蘭〉に触れれば(おそらく触れただろう。吉岡は井上に関する文章を遺さなかったが、林浩平氏に依れば、氏の詩を評するのに井上靖の文学に及んだことがあるという)、必ずや次の箇所に感応したに違いないからだ。
楼蘭だけで見られる濃い朱と紫と青と、色とりどりに輝く美しい日没が彼女〔尉屠耆の兄王の若い后〕の新しい墓地を飾つた。
彼女を葬つた墓土の上には、ロブ湖畔から伐り取られて来た一本の太い檉柳[タマリスク]が墓標として立てられた。そしてその前には、花を飾るための大きい石の花いけが据えられた。(#B_017、四四ページ)
〈楼蘭〉は一九五八年の《文藝春秋》七月号に発表され、翌年五月、歴史小説集として刊行された(吉岡が〈苦力〉を谷川温泉の宿で一夜にして書きあげたのが、五八年の早春である)。井上が末尾で「(作中に引用したヘディンの記述は岩村忍氏訳の〝彷徨へる湖〟から借用したことを附記しておきます)」(同前、九二ページ)と註したように、この作品の結末には七七行にのぼるヘディン文が象嵌されている。もっとも先に引いた后の設定は虚構で、福田宏年は「因みに、ヘディンが発掘した若い女のミイラから、井上は楼蘭の自殺した美しい王女のイメージを創り出しているが、これはもちろん井上独自の永遠の女性像につながるものである」(#B_126、二○五ページ)としている。井上が拠ったのは、岩村忍が矢崎秀雄と共訳して一九四三年に筑摩書房から刊行した版だろう。第七章〈世に知られぬ王女の墓場へ〉の冒頭は「五月五日! [*]紀念の日。三十九年前、私はきはどいところでホータン河[ダリヤ]の河床に水を見つけ、奇蹟的に救はれたのだ」(#B_128、九一ページ)であり、章末(井上が〈楼蘭〉で借りた文のすぐ後)に次のような註記を従えている。「* 一八九四年二月十七日、スウェン・ヘディンの一行はカシュガールからマラル・バシイに向つて出発し、四月十日、メケット・バザールの緑地を経て、ヤルカンド河[ダリヤ]からホータン河[ダリヤ]に向つてタクラ・マカン沙漠を横断せんとし、二十六日間言語に絶する悪戦苦闘の末、五月五日漸くホータン河[ダリヤ]に達し、辛くも一命を救はれた。この間の事情はヘディン著、岩村忍訳「中央亜細亜探険〔ママ〕記」に詳し。(訳者註)」(同前、一○四ページ)。
整理しよう。早ければ一九五八年の初夏、《僧侶》の後半の詩を書きついでいた吉岡実は、井上靖の〈楼蘭〉から岩村訳のヘディン《彷徨へる湖》に至り(戦前かつ入社前の刊行だが吉岡にとって自社出版物である)、さらにそこから《中央アジア探検記》を(改めて)発見し、それを手にする――という連鎖反応が想像されはしまいか。では註記の「ヘディン著、岩村忍訳「中央亜細亜探険記」」とはどんな本か。これは旧字表記の《中央亞細亞探檢記》が最初の標題で、初版(#B_127)は一九三八年に刊行された。訳とは言い条、岩村みずから述べたように「ヘディンの初期の中央アジア探検記を縮小し、再編集し」(#B_132、二三五ページ)たこともあってか、好評の裡に迎えられ、戦後には文庫本化された。すなわち、一九五三年九月に角川書店から《中央亞細亞探檢記》(#B_129)が、また同年同月に創元社から《中央アジヤ探検記》(#B_130)が、相ついで訳者も同じ岩村忍で出されたのである。ところで〈波よ永遠に止れ〉の副題は刊本では、
ヘディン〈中央アジア探検記より〉(#A_08、三一四ページ)
だが、初出の
ヘディン〈中央アジア探検記〉より(#C_037、四八ページ)
を変更する理由に想到しないので、わたしは後者を採りたいと思う。吉岡の読んだのはどの版だろうか。戦前に《中央亞細亞探檢記》を読んでいたことも考えられるが、(これは小説についてだが)「二○歳ごろの私は、当時の風潮で、西欧の翻訳文学を、読みあさっていたものである。とくにフランスの小説を好み、ジョルジュ・サンド『笛師のむれ』やスタンダール『パルムの僧院』そしてアンドレ・ジイドの諸作品であった。/だから、中国の文学には関心がなく、わずかに魯迅の『阿Q正伝』ぐらいしか、読んでいない」(#A_25、二七三ページ)と書いているところからも、ヘディンとの真の出あいは吉岡の「満洲以後」と考えてしかるべきだろう。――岩村の《中央アジア探検記》はその後、訳文に修正を加え〈現代世界ノンフィクション全集 1〉(#B_088)として吉岡在社中の筑摩書房から刊行された。わたしが最初に読み、まさに長詩が「ヘディン〈中央アジア探検記〉より」だと感じいったこの版は、前編の〈タクラ・マカンの横断〉(第一~一五章)のみで後編〈ロプ・ノールへ〉(第一六~二五章)は収められていない。――
吉岡が典拠としたのがどの版か調べた結果、一九六○年執筆の〈波よ永遠に止れ〉の底本は創元文庫版だと推定される。角川文庫版は書名表示が元版と同じであるばかりでなく、本文内容が旧字旧仮名と元版のままなのに対して、創元文庫版は角川文庫版にはない元版の訳者による附録〈中央アジヤ探検とスウェン・ヘディン〉を活かし、さらにあとがきとして〈創元文庫版への言葉〉――そこには「旧版の漢訳地名をカナ書きにそしてカナ使いを修正する」(#B_130、二七二ページ)とある――が添えられた。吉岡が長詩の最終節で引用した部分(ヘディン=岩村本における最終第二五章〈移動するロプ・ノール〉)を比較すれば、両者の関連は明らかだ。参考のために創元文庫版の本文最終段落と〈附記〉を引く。
クム・チャパガンの漁村はいわばタリム河の墓の入口を示している。そこでは、人間の意志も水流の巨大な力も、同様にその狂暴さを征服し得ない。恐るべきタクラ・マカン沙漠が地上の森羅万象を支配する神の名において「この地まで来れ、されど此地より進む勿れ、此地において汝等誇らしげなる波よ、永遠に止れ」と宣言しているのである。附記/ヘディンはロプ・ノールよりチェルチェン河に沿い、一旦コータンに帰り、更に北部チベット、及びツァイダム盆地を経てクチヤ・ノール畔を過ぎ、内蒙古を横切って包頭から北京に入った。それは一八九七年三月二日であった。そして外蒙古シベリヤを経て故郷ストックホルムには同年の五月十日に帰着した。(同前、二五○ページ)
長詩の題名がここから採られているのは言うまでもない。さらに吉岡が初出本文で「亜細亜」や「アジア」ではなく「アジヤ」と書いているのも傍証になるだろう(刊本では「アジア」と訂正)。さて重要なのはここからである。あとがきの一節で岩村は次のように書いている。
一九三五年以後のヘディンは専ら最後の探検の学術報告と旅行記の編集、執筆に従事し、他に伝うべき事はない。もしあるとすれば、第二次世界大戦中にもドイツを讃え、ヒットラーの賓客としてドイツに招かれ、世界に話題を播いたぐらいのものであろう。ヘディンが一生を通じてドイツびいきであったことは、彼が日本びいきであったことと同様、別に探検家、科学者としての彼の偉大さを傷つけるものではない。科学者としてのヘディンの業績については、他日、語ることもあろうかと思う。探検家としての彼については、本書自身が最もよく語っている。蛇足を加える必要はあるまい。(同前、二七一~二七二ページ)
吉岡実は「探検家としてのヘディン」を語りなおしたくなったのだ。なぜ《中央アジア探検記》なのか。むろん、朗読のためのかなり長い詩を書かねばならない、という表向きの理由は用意されている。まずは二五七行の長詩の最初の節(実際には「1」と数字が振られているだけ)を読もう。
わたしは 二人の従者と一人の宣教師とともに 1
四頭馬車で砂漠の入口に着いた 2
ここからわたしの夢がはじまる 3
わたしにだけ見えて 4
ほかの三人の男には見ることのできない夢 5
幾世紀もの間 砂にうずもれた 6
伝説の王 眠りの女王の生活の歴史 7
もしかしたらわたしだけの幻覚だろうか 8
死んだ都のステンドグラスの寺院の窓から 9
ながれ出る河のながれ ともにながれる時のながれ 10
朝は凍りつき 夜あらゆるいきものの 11
骨を沈めているヤルカンド河のつめたいながれ 12
ヘディン=岩村は「一八九五年二月十七日午前十一時私はイスラム・ベイ、宣教師ヨハネス、ハシム・アクヌの三人と共にマラル・バシイに向け東行の途に就いた。/一行は各々四頭の馬が牽引する大きい鉄縁の車輪を有するアルバ若しくはアラバと称されるバネなしの車二台に分乗した」(同前、八ページ)ときわめて具体的に筆を起こし、「その時期にはキジル・スウ河には殆ど流れの無いのが普通で、いくらか残っている水は氷結していた」(同前、一○ページ)、「一台のアルバにつけてある四頭の馬の中三頭は先頭に並べ、残りの一頭は轅の中間に結わえて車の中心を保つようにして進んだ」(同前、一一ページ)と書いているが、吉岡の三~五行め、八行めのような記述はどこにも見あたらない。七行めに〈僧侶〉(④・8)のレミニサンス(「一人は世界の花の女王達の生活を書く」)が窺えるほどである。むしろわたしたちがここで注目しなければならないのは「わたし」を含む四人の人物と「四頭馬車」であり、それは〈崑崙〉の冒頭が〈色彩の内部〉(⑦・4)初出からの転生であるという事実(〈「細部の変遷」Ⅲ〉参照)を凌駕するだろう。こうして〈波よ永遠に止れ〉は、ヘディン=岩村と〈僧侶〉あるいはこの長詩と執筆の時期を同じくする《紡錘形》諸篇と重なりつつ始まる。以下、10節までの吉岡は、細かな挿話までほとんど忠実にヘディン=岩村の記述を拉しきたっているので、この詩よりも後に書かれたものだが、吉岡の長詩を相対化する意味でも《中央アジア探検記》の全訳に当たる《アジアの砂漠を越えて》に付けられた深田久弥の〈解説〉を借りよう。
ヘディンの一行が砂漠の奥深く進むにつれ次第に困難に落ち入り、遂に全滅の一歩手前まで行ったことについては、私は余計なことは言わないで置こう。ヘディンの紀行を読み進む方が迫真的であるからである。ヘディンの従者は、イスラム・バイ、カシム、モハメッド・シャー、ヨルチであったが、それぞれの人物の性格が鮮やかに描かれていて、ヘディンの筆致に優れた小説家的才能をさえ感じる。
一滴の水も得られぬ砂の海を一行は進んで行く。従者とラクダは次ぎ次ぎと落伍し、或いは倒れて行く。五月一日のキャンプをヘディンは「死のキャンプ」と呼んでいる。彼のアジア旅行の全部を通じてこのキャンプほど惨憺たるものはなかった。ヨルチとモハメッド・シャーの二人はこの「死のキャンブ」かその付近で死んだ。イスラム・バイはよろめいて砂の上に倒れ、もう歩けないと洩らした。残るヘディンとカシムの二人はそれから絶望的な砂漠の彷徨を続けた。
五月五日、カシムも動く力がなくなった。そこでヘディン一人で水を求めて進んだ。しばしば崩れてうずくまった。睡魔が押し寄せてきて自然に眼が閉じようとするのを、全力を振りしぼって防いだ。疲れた体が一度眠ったなら永久に醒める時はないからである。彼の生命は危機一発〔ママ〕の域まで来ていた。
突然、水鳥の飛び立つ音に驚かされて立止った。そして次の瞬間、枯れた河床の中に水溜りを見つけたのであった。彼は飲みに飲んだ。無茶苦茶に飲んだ。渇き切った体は海綿のように水分を吸収した。羊皮紙のように硬かった皮膚も軟かくなり、額も潤ってきた。
ヘディンは長靴の中に水を汲んで、倒れたカシムのところへ持って行く。私が感嘆するのは水を飲んだ時のヘディンの態度である。死に瀕した彼が飲む前に自分の脈搏を数える。非常に弱く、四十九あった。飲んで数分後に数えると五十六になっていた。数字を細かく書くのはヘディンの科学者らしい習癖であるが、この危急の時に自分の脈搏を正確に数えてその数を記憶するとは! そんな余裕があり得たのであろうか。呆れた男である。
ヘディンが助かったのはコータン河の河床であった。増水期には水が流れるが、彼の時には枯渇して水溜りが残っているだけであった。コータン河はコンロン山脈から流れ出て、タクラマカン砂漠の中に注ぎ入る河で、辛うじて断続しながらその末はタリム河に合流する。(#B_131、三一四~三一五ページ)
ここにようやく崑崙がその姿を現すのだが(ヘディン=岩村本でも〈附録〉に「崑崙山脈」が出てくる)、とりあえずここでは崑崙山脈と崑崙は異なるとだけ言っておこう。吉岡は〈波よ永遠に止れ〉の10節を「聖なる靴 一人の生命を救った この創造主 靴屋に幸いあれ」と結んだあと(すなわち崑崙は片鱗も見せない)、最終の11節をこう締めくくって筆を擱く。
わたしは故国への帰路につく
ゆれる船 かたむく帆柱 さらば陸地よ さらば砂漠よ「そこでは 人間の意志も水流の巨大な力も 同様にその狂暴さを征服し得ない 恐るべきタクラ・マカン砂漠が地上の森羅万象を支配する神の名において宣言する 《この地まで来れ されどこの地より進むなかれ この地において汝らほこらしげなる波よ 永遠に止れ》」
ここに至るまで吉岡はヘディン=岩村をそのままなぞるのではなく、重要なトピックを択ぶ一方で、前後を小刻みに入れかえたり、深田解説にはある従者の名前を剥奪して「毛皮の男」や「女中」と呼ぶなどして、いくつかの創意を見せている。だがなんと言ってもこの11節が注目されるのは、鍵括弧で括られた部分(そのなかがさらに入れ子になっている)こそ、後年の吉岡詩において跋扈することになる引用の濫觴だからである。そして、これこそ井上靖の〈楼蘭〉におけるヘディン=岩村の《彷徨へる湖》の象嵌部分を踏襲した構造だと言える。
初出には本文後に註記として「(本稿より八十行を削除して〔一〕九六○年五月一一日NHKより放送)」(#C_037、五三ページ)とあったが、刊本では省かれている。二五七行から八○行を減じると一七七行となり、例えば〈崑崙〉ともそれほど差がなくなるが、残念ながら削除版の形態は調べられなかった。三つ以上の節での合計が八○行の組みあわせも考えられなくはないが、わたしにはどうも全体に影響が出ないように、各所で抓んだように思われる。逆に言えば、これは要約可能な作品だったのだ。いったい〈波よ永遠に止れ〉を除いて、吉岡詩に簡略版(作者自身の手によるものであっても)の存在を許す詩がありえるだろうか。この長詩の最後の、そして最大の特徴は、全長版と削除版の二種の本文が存在した(はずだ)という点にある。【〈波よ永遠に止れ〉の「削除版の形態」については、二〇〇三年五月、新たな知見に基いて本節を改稿した〈吉岡実の長篇詩〉で自説を発表しているので、その〈四 簡略版の存在〉と〈五 削除された詩句〉を参照していただけるとありがたい。】
吉岡が本作を単行詩集に入れなかったのは、決してヘディン=岩村に依拠したからではなく、作品の構造が他の古岡詩全作と対立する「削除のきく本文」で成立していたからではあるまいか。それでは、なぜこの題材にあえて取りくまざるを得なかったのか。そこには相応の理由があるはずだ。それは、吉岡が〈死児〉(④・19)で描いた「私の戦中戦後」(#A_25、七○ページ)の主題に立ちかえり、しかも今度はその作で果たせなかった「深部」へより接近するため以外には考えられない。ここで言いそえておけば、吉岡は伊達得夫のように「残虐きわまる戦場の最前線に立たされ」(#B_119、九五ページ)たことは、やはりなかっただろう。長谷川郁夫は次のように書いている。
戦後生まれの私は、軍隊生活の実際を知らない。小説や戦記によってわかることは、ただ、その経験が各個人個別のものであるということだ。出身、環境、階級、性格、体力、さまざまな立場によって、それぞれの体験の意味内容がまるでちがう。外的な状況あるいは思想は抽象化できるが、人間は共通項でくくることができない。さらに、異常な体験も、それが思い出に変質するとき、甘酸っぱいものが漂いだすだろう。たとえば、のちに伊達得夫と出会うことになる詩人の吉岡実氏が、満洲での軍隊生活を回想して「あの残酷で滑稽な」と呼ぶのを知るとき(「軍隊のアルバム」)、そこには、暗い、といった形容だけでは語れないものが潜んでいるのを感得する。(同前、九○ページ)
このアンビヴァランス(反対感情併存)が、吉岡をしてわたしの言う「スフィンクス製造の原理」なる詩学を生ましめた、と言えば言いすぎだろうか。吉岡は〈波よ永遠に止れ〉を当時の全詩集《吉岡実詩集》(#A_08)に収めただけで、その後はこうした構えの大きな作品を追求することがなかった。済州島をタクラ・マカン沙漠に置き換えた死と再生の物語は、人間(軍隊/ヘディンら一行)と動物(馬/らくだ)の関係を描くことに成功したものの、圧倒的な外部(戦争/自然)との距離を計りかねている気味がある。自ら択んだ探検行と避けがたい進軍を同一視すべきでないのはもちろんだが、死と再生の物語を「直接」書けなかったところに、吉岡における〈波よ永遠に止れ〉とその後の長詩がより困難になった真の理由を見るべきではないか。
「朝は砂袋に見える/岬」と始まる〈異霊祭〉(⑧・19)を手掛かりに、吉岡詩の海洋生物に着目したのは四方田犬彦だったが(#C_010)、海は女が、人間がそうであるように吉岡がそこに愛と不信の双貌を見たものだった。海軍に入って海と出あうのではなく、陸軍で馬と出あった吉岡の極限的テーマは、「岸べなき砂の大洋」の長詩で展開された。自身の満洲体験を容れる器として、一種の、しかも他者の冒険譚が借りられたのだ。黄金探究(高邁ではなくとも、この壮大な夢!)ともとられかねない試みは、最後は靴に充たすべき水を求めることで落着する(詩人の日本軍への批評か)。死が偶然であるように、生もまた偶然であり、僥倖である。化石化された波としての沙漠。満洲に出征した吉岡にとって、中央アジアの巨大な沙漠は想像の世界だろう。しかしこの作品を脱稿したとき、吉岡はシナのなんたるかを改めて問わずにはいられなかったはずだ。
輜重兵として馬上から眺めたシナの広大な大陸。小柄な日本兵が馬の背に跨がって見た世界はなんだったのか。一九六八年、高橋睦郎からベトナム戦争について問われて「ベトナムはベトナム人に委せろ」(#A_10、一四一ページ)と発言をしているように、ベトナムを筆頭とする各地の戦争紛争が軍隊を、軍隊がかつての日本軍を、中国大陸を想いださせた。それは吉岡の詩に
大きな影を落としている。そのことはあまりにはっきりと見えたために、かえってこれまで指摘されなかったように思う。先走って言えば、「その時と今」を往き来する試みは一九六九年の〈コレラ〉(⑦・18)で打ちきられるまで継続し、詩集に伏流するモチーフとなった。恋愛(あるいは失恋)が《僧侶》を準備したように、戦争は一九六○年に〈波よ永遠に止れ〉を産出し、六○年代末には《神秘的な時代の詩》を用意した。〈波よ永遠に止れ〉が「いま、ここ」の死と再生の長詩にならなかったのは、この主題が吉岡にとっていかに扱いにくいものだったかを逆に証明していよう。ついには詩で書くことを諦めたかのごとき、次の発言に至るのである(インタビュアーは高橋睦郎)。
◆小説の計画
問=小説を書きたいとおっしゃっていましたが。
答=小説と言ってしまっていいかどうか。ただ、評論の根本には比較があるが、小説は具体的に書いていけば何かできるのではないか、そんな考えが自分の中にあるのです。
問=どんなテーマを?
答=別にありませんが、自分の中で大きな比重を占めているある恋愛事件、それに軍隊体験はぜひ書きたいです。
問=表現は?
答=ふつうの文体で坦々と書くか、再構成するか、まだわかりません。
問=詩で書けないところを?
答=詩には個人的な事情は持ちこみたくないのです。(同前、一四五ページ)
はたして「個人的な事情」を持ちこんだ詩は想像/創造できないのか、この「神秘的な時代」において。
旗を揚げて崑崙を払い/伐鼓(戦闘合図の太鼓)蒲昌〔ロプ・ノールのこと〕を震わす/太白(金星)官軍を引き/天威 大荒に臨む/西のかた望めば雲は蛇に似て/戎夷 喪亡するを知る/渾べて大宛の馬を躯り/楼蘭の王をば繋ぎ取らん――岑参〈武威にて劉単判官の安西行営に赴くを送り高開府に呈せしむ〉抄(#B_146、八三~八四ページ)
*
崑崙|吉岡実では未経験的なピンクの空間へ 1
ダイビングする 2
四頭馬車の喪服ずくめ 3
さかさまになる 4
四つに分けられた馬の頭は見えず 5
きみは驚き 6
ぼくは悲しい顔を剃り 7
きみの彼女はふとる 8
墜ちるにはふさわしい水面 9
ぼくの彼女が笑う月 10
じゃだれがトップで死ぬんだろう 11
母の恥しい腹のなかにいる 12
ぼくかしら? 13
妻の詰った子宮から出てくるきみかね? 14
ほんとうのことを云うべきだ 15
生まれるより先に死ぬべき同行者・同義語 16
きみの彼女が父の尻の孔の奥まで戻る 17
これは一種の自負であって 18
生でなく死でもなく 19
赤いネオンの透明なはかない消滅法 20
車輪がとんで行く 21
めもさめる型式美 22
とざす障子の棧に巣食う鳥 23
来るべき潜水艦が丘を越えて 24
迷宮入り 25
忘れられているのではないだろうか? 26
ぼくの彼女の主知的に 27
あまもる唇 28
類型の多い死ではないかね 29
贋金 30
先頭をだれが行く 31
ぼくの足の黒い鼻緒のゲタ 32
きみの胸のエンドマーク 33
ぼくの彼女のアミタイツの脚 34
きみの彼女のタワーのようなヘアー 35
たよりない人体 36
四つの部分で真の人間は出来ていないだろう 37
すくなくも一万部分の集積 38
あるいは九個のフラスコのミカン水 39
ビニールのような耐久性と劣情を示せよ 40
在るべき時間とは 41
在らざる愛のこころ 42
在るべき空間とは 43
在らざる光線銃 44
ここはどこか? 45
ここは深くも浅くもない軟着感がある 46
ぼくの彼女が至りつく 47
冬のフトンの果てから 48
まっすぐ歩いて 49
くびれた母型を認識し 50
似たような荷物をみつける 51
なにが入っているかもわからぬ観念 52
歯型 53
電子音楽 54
ムラサキ 55
未来の 56
愛 57
ではきみの彼女の運命とは 58
それは生まれる 59
むなしい稼業から 60
もり上ってくる 61
非情緒的な廃品同様 62
むしろなんでもなくなりつつある 63
周辺をかこんで 64
イチジクの葉 65
かくすラクダのコブの相似性 66
同円のスリ鉢叩いて 67
日常言語の床屋の白い布を裂く 68
記号の罐 69
開かれる開かれる 70
自在に無意味に褐色の床から天井へ 71
横断する横断する 72
電気芝刈り機 73
ニクロム線の庭 74
静電気そのもののウェーブで 75
カメをくすぐる 76
彼女たちのハッピー・バースディ 77
はるさめの降るころ 78
煙突掃除用ブラシはススでなく 79
幼児をこするものへ 80
変化する 81
壁を掻く老人たちとうとう壁をつきぬけて 82
けむりを出す 83
魂と秋 84
女は自身の手でなにを変える? 85
虹彩の遊び場で 86
女はもろもろの疑似割れ目を表現し 87
毛のはえた裁ちバサミで 88
紙テープを切る 89
そしてダンス 90
そして銃殺シーン 91
そしてそして想い出を想い出す 92
まるくまるく 93
ハリネズミを追いつめ 94
恍惚たる少年の藍をあびて 95
水槽では血気の尻 96
さめるサメ肌をふるわせる 97
共謀的な彼女たち 98
めざすメザシの 99
目をつらぬく矢印 100
死への 101
橋がかり 102
金切声 103
さらにとどろくぼくらの白骨期 104
真鍮の棒で砕かれる 105
あるところへ戻ったら 106
形が変り色が変る 107
物が物をのむときは闇 108
吐くときは光るか? 109
彼女らはすべて見えずと反対のバラのトゲをつかむ 110
これが芸術だ 111
それは偶然の自律自慰! 112
肉色をしていることが 113
罪悪ならば 114
ぼくたちになにができる? 115
藁の上で 116
肉色の幽霊と化して 117
にもかかわらず 118
そのうしろに眠るきみの彼女の蛍光体 119
なめるなぐさめで 120
分裂するきみの水色の舌 121
ハンバーグをつくる 122
ハリボテのハンバーグをつくる 123
そしてぼくの彼女はヌード 124
清掃車がくる 125
起伏がくる 126
水葬の夜明け 127
ももいろの回虫の環境 128
ももいろの夢 129
凍結がある 130
そこでぼくらは行く 131
写真のなかで永遠に 132
首を吊られている人々の下を 133
真夏の反現場性の海の輝く 134
金輪 135
サイコロ 136
過去からカブトガニの内部は 137
はたして 138
うごいているのかゼリーのように 139
ピンクから白色の世界へ 140
むしろ次から次へと変革している 141
そうしてうずまき模様の 142
ののののの 143
のたれ死を承認せよ 144
ノオ 145
今日ぼくたちにも存在しないだろう? 146
崑崙! 147
初出と前掲書肆山田版詩集の本文との異同を校合する。まず漢字の字体の違いが二箇所。
(二三行め)桟→棧
(一一九行め)螢→蛍
手入れは以下の一二箇所である。
1(三二行め)ぼくの足の〔赤→黒〕い鼻緒のゲタ
2(三四行めと三五行めを入れかえ)
3(三六行め)た〔(ナシ)→よ〕りない人体
4(四六行め)ここは深くも浅くもない軟着感〔!→がある〕
5(四八行め)冬のフトンの果て〔(ナシ)→から〕
6(七一行め)自在に無意味に〔赤い→褐色の〕床から天井へ
7(七五行め)静電気〔(改行)→(追込)〕そのもののウェーブで
8(七六~七七行め)カメをくすぐる〔(ナシ)→(改行)〕
彼女たち〔(ナシ)→の【(改行)→(トル)】〕
〔玉鳴るソロバン→(トル)【(改行)→(トル)】〕
〔ハプニング→(トル)【(改行)→(トル)】〕
ハッピー〔(ナシ)→・バースディ〕
9(七八行め)はるさめ〔(ナシ)→の降るころ〕
10(七九行め)煙突掃除用ブラシ〔が→は〕ススでなく
11(九八行め)共謀的〔(ナシ)→な〕彼女たち
12(一三三行め)首を吊られている人〔(ナシ)→々〕の下を
1と6の「赤」が他の色に換えられたのが目を引く。これでこの詩の赤は二○行めだけになり「ももいろ」「ピンク」が優勢になった。三二~三五行めの「ぼく」「きみ」「きみの彼女」「ぼくの彼女」の順番は、六~一○行めの「きみ」「ぼく」「きみの彼女」「ぼくの彼女」と対応するように変更された。3、11の措置は、誤植の訂正か字句の手入れか微妙だ(11は〈〔図版〕〈崑崙〉初出への手入れ〉参照)。4や5、7は〈葉〉(⑧・4)の初出→定稿でも見られる傾向だ(Ⅳを参照)。8は少しく込みいっているので、初出形を掲げて( )内にその音節数を記せば、
カメをくすぐる彼女たち(3・4・5)
玉鳴るソロバン(4・4)
ハプニング(5)
ハッピー(4)
はるさめ(4)
と畳韻法が効果的でないばかりか、(4・4・5)という音数律もどこか上調子だし、ここは手入れもやむをえないところだ。12によって、一三二~一三三行めは〈僧侶〉の最終九節との類縁を強調することになった。
詩集《神秘的な時代の詩》の特徴として、他の詩集でしばしば見られた散文詩型(一定の字詰めで改行して詩句と詩句の間は全角空きとするもの。例としてはⅡで触れた〈首長族の病気〉)や、数字で詩節を切る型(〈波よ永遠に止れ〉もこれ)が採られていないことが挙げられる。詩節をアステリスクで区切った〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)が唯一の例外で、ほかには行空きさえない。ところで吉岡はこれらの詩篇(その集積が詩集だ)と長篇詩を区別して考えていたらしい。「〔食母〕という言葉が拓くイメージ。吉岡実氏の詩は御自身が最後の、と言われる作品です」(#C_022、三四四ページ)と掲載誌の〈編集後記〉が書く〈〔食母〕頌〉(⑫・19)ははからずも最後の詩集《ムーンドロップ》の掉尾を飾る詩となったが、その後も折あるごとに長篇詩への願望を語っていた。吉岡にとって〈波よ永遠に止れ〉が長篇詩か決めかねるけれども(生前の刊本は《吉岡実詩集》(#A_08)だけなので、単行本への収録の状態から判断できないから)、ここで吉岡の長い詩を振りかえっておくことにも意味があるだろう。行数から見た上位の一○作品は、次のごとくまさに壮観である。
| 順位 | 行数 | 題名(詩篇番号) | 詩節区分 |
| (1) | 257 | 波よ永遠に止れ(未刊詩篇・10) | アラビア数字 |
| (2) | 196 | 聖あんま断腸詩篇(⑫・12) | ローマ数字+題 |
| (3) | 189 | 死児(④・19) | ローマ数字 |
| (4) | 163 | わが馬ニコルスの思い出(⑦・16) | アステリスク |
| (5) | 161 | 異霊祭(⑧・19) | アラビア数字 |
| (6) | 147 | 崑崙(⑦・8) | 〔なし〕 |
| (7) | 145 | 悪趣味な内面の秋の旅(⑧・31) | アラビア数字 |
| (8) | 134 | 田園(⑧・14) | アラビア数字 |
| (9) | 126 | 雷雨の姿を見よ(⑨・14) | アラビア数字 |
| (10) | 125 | 葉(⑧・4) | 〔なし〕 |
二種の数字に使いわけの区別があるか不明だが、こうした「詩節区分型」があらかたを占めるなかにあって、〈崑崙〉と〈葉〉は《神秘的な時代の詩》に顕著な詩型における長大な実例である。ではどうして吉岡はこのような長い詩を書くようになったのだろうか。長い詩が書きたくなった、書けるようになったときにその種の依頼が来たからだとしても、なぜ、長い詩、なのか。当時の吉岡に「長詩」についての興味深い文章がある。〈今年の問題作〉なる依頼に応えた〈飯島耕一「見えるもの」・他〉の全文を引く。
今年〔一九六六・一一~一九六七・一○〕の問題作は何かと問われても、簡単に答えられない。なぜなら、多く読んでないし、前半期の作品で失念したものがあるだろうから。記憶にあるままあげると、連祷千行の長篇詩―高橋睦郎《讃歌》(改題して「頌」)。白石かずこ《My Tokyo》。吉増剛造《波のり神統紀》。鈴木志郎康の〈プアプア詩〉の終末篇《番外私小説的プキアプキア家庭的大惨事》。入沢康夫《『マルピギー氏の館』のための素描》。しかし一番印象にのこるのは、飯島耕一の連作詩《見えるもの》。それにつづく、近作《私有制にかんするエスキス》であろう。詩集《何処へ》の体験的世界から一転して、シュールレアリスムへの回帰というより、新しい面からの果敢な挑戦を試みている、二つの連作詩――実験的不安定さと奇妙に均整を保ちつつ大きく育成される詩的現実を注視している。(#C_006、六四ページ)
高橋詩の一○○○行を筆頭に、短い鈴木詩さえ八○行ほどある作品群が、吉岡のこの時期の「問題作」だった。――飯島の二篇は詩集《私有制にかんするエスキス》の巻頭に収められたが、それに続く〈過ぎし戦いの日々を想う八月の詩〉の末尾に「(この詩は一九六八年八月十一日、文化放送から土方巽の朗読によって放送された)」(#B_006、一○八ページ)とあるのが目を引く。――吉岡がこれらの作品から刺戟を受けることで〈崑崙〉や〈神秘的な時代の詩〉(前の表には入っていないが一六位に相当する)などの長い詩が生まれただろうことはほぼ間違いない。だが、やはり「戦後詩の進展の原基であった」(#B_023、一八五ページ)西脇順三郎の存在を逸するわけにはゆかない。吉岡と西脇、吉岡詩と西脇詩の詳細は〈弟子〉(⑦・15)評釈時に譲るとして、長詩との関係に絞って鍵谷幸信の西脇論から引こう。「高見氏は西脇氏が使ったようなことば、心象、象徴、隠喩、類推のコラージュやアッサンブラージュ、そして長詩になるとモザイク性を全面操業し、回転させてモンタージュ的詩を書く詩法を採用しておらず、起承転結の折り目正しいことばの選択と配置によって、ことばを己れの自我の内部で封鎖し、凍結凝固させるのに腐心している」(同前、一四四ページ)。
「高見氏」に《静物》の吉岡を、「西脇氏」に《神秘的な時代の詩》の吉岡を重ねてみたいという衝動を禁じえない。さらに西脇の長篇詩と吉岡が直接かかわったことについて、鍵谷はこう書く。
「いや、『近代の寓話』の頃は詩をなんとかして作品にしよう、作品を作ろう、いい詩を書こうとして書いている。つまりいい詩人になろう、という希望をもって力を入れて書いている。いい詩人になろうという下心が自分でもわかっているんだ。力をぬいて詩を書いた方がいい、と思うようになったのは『失われた時』の第四部を書いたときからだ。それに君が詩を書け、詩を書けといってぼくを責めたてるから、ぼくは長い詩を書いたんだ。とにかく冴子〔西脇夫人〕と君はぼくを働かせた」
詩人の顔にうらめしさがほのみえた。
詩人は『壌歌』で名利栄達を棄てるべきだ、と書いている。筑摩書房の会田綱雄、吉岡実両氏から二千行の書き下し長篇詩を書いて下さい、と頼まれ約束した。約二か月、詩人はこれにかかりっきりであった。(同前、四三ページ)
もっとも《壌歌》は一九六九年一二月の刊行だから、〈崑崙〉よりも一年あとの話になる。この長篇詩をめぐって、西脇順三郎追悼座談会での興味深いやりとりがあるから、これを機会に録しておこう。
吉岡 今日のためにぼくは改めて『壌歌』(昭和四十四年)を読んだんだよ。刊行当時はあまり感心しなかったんだけど今度読んでみて『壌歌』ももっと間引いたらよかったんじゃないかと思ってるんだ。
大岡〔信〕 『吉岡実選・新版壌歌』を作るか(笑)。
吉岡 何しろ天文学的で集中的に出て来るから、天文学が地に墜ちちゃって意味をなさなくなっちゃってるんだよ。ぼくがもっと刈り込むともう少しきちっとまとまったものになるんじゃないか、なんて思っちゃうんだ。でも『壌歌』は見直したな。飯島〔耕一〕が病いの時は西脇さんの詩を読んだっていうけど、しみじみとしたところはありますね。案外日本的なんですよ。
鍵谷 ぼくは『壌歌』は苦手なんですよ。本当に疲れちゃうんです。
吉岡 西脇さんの緩やかな流れに乗らないと読めないんだよ。波に乗れば一緒に漂えるよ。ただ刈り込みたくなる欲望は消えないけどね。(#C_011、三二~三三ページ)
このあたりにも吉岡が《神秘的な時代の詩》から《サフラン摘み》を経て《薬玉》に向かった要因がありそうだ。話柄は西脇の吉岡詩への評価に移る。
吉岡 好奇心はすごく強い人だったね。西脇さんが読んでた若い詩人層っというと、どのあたりまで下れるのかな?
鍵谷 まずここにおられる皆さん〔座談会の他の出席者は那珂太郎、入沢康夫〕のものはお読みでしたね。ある時期吉岡さんの詩が長くなったのを見て「吉岡君の詩はよくなったね」っておっしゃってましたよ。長くなったからよくなったっていう感じでしたけど(笑)。(同前、三三ページ)
「ある時期」というのは、前掲の吉岡長詩の表から考えれば《神秘的な時代の詩》ともとれるが、《サフラン摘み》のような気がしてならない。西脇はもとより、鍵谷も吉岡も亡い現在、確かめる術はない。さて〈崑崙〉である。わたしは吉岡の詩篇以前に崑崙のなんたるかを知らなかった。それゆえその後に求めて、あるいは偶然に「崑崙」に出あっても、詩の印象と切りはなして考えることができなかった。しかしそこからこの詩に迫るのは得策でないような気がするから、崑崙の神話学は後述しよう。戦前の日本で崑崙がどのようなものであったかは、松田壽男が一九四一年の《國学院雑誌》に〈崑崙国攷〉と題して次のように書いているのが参考になる。「崑崙という言葉は、我々日本人にとって、それほど耳遠いものではない。しかし、それにも拘わらず、その的確な概念は、専門の研究者ですら未だ掴んでいないようである。まことに厄介な代物といわなければならない。最もよく知られているのは、崑崙山脈である。新疆省の南境に聳えているこの山脈が、崑崙と命名されたのは、有名な漢朝の武帝の時である」(#B_139、二五一ページ)。
わたしはこの詩から無重力空間、螺旋、水分、死後の世界と芸術、などの項目をノートに書きとったが、詩のモチーフを一言に要約することは難しい。タイトルの〈崑崙〉が何なのかわからないままずるずると作者に引っぱられて、気が付いてみたら最後で「崑崙!」に出あったと言ってもよいし、詩のなかで「のたれ死」しなかっただけでも儲け物だと言ってもよい。〈崑崙〉と題されたのがいつかも気になるところだ。〈色彩の内部〉初出冒頭に酷似した書きだしで詩篇が始められる前か、それとも最終行で詩篇が終えられた後か、両者の間のある時点か、確かなことはわからないし、それがいつかも重要ではない。だが、なぜ〈崑崙〉なのかは重要だ。
崑崙は吉岡の詩の題に初めて登場した固有の地名である、と同時に古代中国の神話に照らせば、架空の地名(崑崙山)である。また〈波よ永遠に止れ〉や〈苦力〉も想起させる、二〇世紀中国の現実的な地名(崑崙山脈)である。《静物》以来、吉岡の詩は普通名詞を題にすることが最も多かった(そう言えば〈ポール・クレーの食卓〉が順当に単行詩集に収められなかったのは、固有名詞(人名)の異質さゆえだったか)。標題が〈南山〉や〈天山〉や〈カラコルム〉でない以上、わたしたちはたとえ崑崙の謂れに詳しくなくても、なにかしら単純でない印象を受ける。あたかも平地に住む読み手が、語り手に伴われて山地に分けいるのにも似た感慨だ。旅程の最終目的地は崑崙である。だがそれは一読するまではわからない。まさに「未経験的な」「空間へ」の旅となるのだ。
ここでの登場人物は四人だ(過去の詩では〈劇のためのト書の試み〉がもっとも近い)。舞楽に〈崑崙八仙〉(略して〈崑崙〉とも。嘴をつけた面を被り、羽を拡げたような冠を着け、四人が手をつないで輪になって舞う)があるが、詩篇〈崑崙〉や吉岡の文章からは「四人であること」以上の類縁を見いだすことはできない。きみ、ぼく、きみの彼女、ぼくの彼女はどうやら「四頭馬車の喪服ずくめ」で、登場するや、「さかさまになる」。吉岡はもはや「ここからわたしの夢がはじまる/わたしにだけ見えて/ほかの三人の男には見ることのできない夢」とも「もしかしたらわたしだけの幻覚だろうか」とも書かない。ヘディン=「わたし」たちがあれほど渇望した水。だがそれは四人にとって「墜ちるにはふさわしい水面」だ。生と死は、その方向性を喪い、彼ら・彼女たちは一様に奇妙な退行現象を示す。矢印の向きが乱れ、「生まれるより先に死ぬべき同行者・同義語」と言葉の地軸も揺らぐのだ。
吉岡詩の「言語」への接近はとどまるところをしらない。「日常言語の床屋の白い布を裂く」のは「だからあらゆる絵画は/ナイフで裂かれた次元を持つ」(〈色彩の内部〉)と異なり、たぶん手によってだろう。行き場を失くした矢印はあろうことか「さめるサメ肌をふるわせる/共謀的な彼女たち/めざすメザシの/目をつらぬく矢印」として現れ、いまやほとんどその使命を終えている。「彼女らはすべて見えずと反対のバラのトゲをつかむ/これが芸術だ」と吉岡は「ビニールのような耐久性」で己れの詩学を示す一方、その「劣情」をも示す。
「ぼくの彼女のアミタイツの脚/きみの彼女のタワーのようなヘアー」「イチジクの葉/かくすラクダのコブの相似性」「虹彩の遊び場で/女はもろもろの疑似割れ目を表現し/毛のはえた裁ちバサミで/紙テープを切る」――「中西夏之の樹脂で造られたラグビーボールほどの卵のオブジェ」は「透明体の中に、大きな裁断用鋏が入っている。半ば開いた刃には毛のようなものが、密生しているようだ。よく見るとそれは砂鉄だった。なによりも美しいのは、一本の紅い糸がふるえるように沈んでいることだ」と《土方巽頌》(#A_24、一八ページ)にはある。――「恍惚たる少年の藍をあびて/水槽では血気の尻」。
そして〈スイカ・視覚的な夏〉で保留しておいた「肉色をしていることが/罪悪ならば/ぼくたちになにができる?/藁の上で/肉色の幽霊と化して/にもかかわらず/そのうしろに眠るきみの彼女の蛍光体」。もはやそれはスイカの色ではない(もしかしたら肉の断面?)。「肉色の幽霊」まで出現するのだから。これら「未経験的なピンクの空間」での出来事は「ももいろの回虫の環境/ももいろの夢」か。そして終曲が来る。「過去からカブトガニの内部は/はたして/うごいているのかゼリーのように/ピンクから白色の世界へ/むしろ次から次へと変革している」。前作〈神秘的な時代の詩〉の「今日 生卵の黄味のゼリーの表面に/一篇の詩が印刷される!」の卵は早くもここで攪拌される。「卵としての詩」は名実ともに放棄された、のだろうか。だが、それが生であり、死であり、詩であるとしたら――。
そうしてうずまき模様の
ののののの
のたれ死を承認せよ
ノオ
今日ぼくたちにも存在しないだろう?
崑崙!
前作《静かな家》での吉岡は、円と円あるいは回転・旋回運動とに憑かれていた。詩型と文体の面から《静かな家》を二極に引っぱっていた詩篇が〈馬・春の絵〉(⑥・5)と〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)である。《紡錘形》となる作品群が《僧侶》の成功と吉岡自身の結婚のあと、同人詩誌《鰐》を主な発表の場として一気に書かれたのに比べると、この詩集は統一感に乏しい。あるいは実験的側面が強い。《静かな家》で吉岡が試みたのは、スタイルの摸索である。もうひとつの〈僧侶〉ともいうべき〈劇のためのト書の試み〉(⑥・1)がそれを代表していよう。
A 父母の死骸は回転している洋服ダンスの中(〈劇のためのト書の試み〉⑥・1)
B それが輪を形づくる(〈無罪・有罪〉⑥・2)
C 空走る一つの自転車のからまわり(同前)
D 軍艦は全部円を廻る/ときには円を割る(〈模写〉⑥・4)
E 終りに孔のたくさんある鉄の筒の胴廻りを計る(〈馬・春の絵〉⑥・5)
F 円が回避する円(〈滞在〉⑥・7)
G 桃がゆっくり回転する(〈桃〉⑥・8)
H ふたたび回ってくる/桃の半球を(同前)
I 火縄の円/ぐるぐる廻っているんだ(〈やさしい放火魔〉⑥・9)
J 肉が心でなく孔ある筒から出る(〈春のオーロラ〉⑥・10)
K それは大きな円の復活!(同前)
L 存在する円をくぐりぬける(〈スープはさめる〉⑥・11)
M テーブルの円をまわり(〈内的な恋唄〉⑥・12)
N 反回転(〈ヒラメ〉⑥・13)
はなはだしきは〈孤独なオートバイ〉である。
O 廻っている/円形のコンクリートの床?
P 同心円が猛然と回転する
Q 円の癒着性!
R 円の迷路へ
S 走る車輪/筒をぬける鳥
T それから処女性のシリンダーが
U 走る車輪の下のまだ青いバナナ
V まわる車輪へ白髪が発生し/ゴムのタイヤの象皮性を見せよ
W 同心円の反復から/停止する半円の透明度
X ある日の暁まで廻るハンドルへ
――以上が詩集《静かな家》から。
a 長いボール紙の筒があるかね?/それを廻って(〈マクロコスモス〉⑦・1)
b 輪切りのパイナップル(同前)
c はずむブルーの球(〈夏から秋まで〉⑦・2)
d 円を縮小する方へ(同前)
e 蓄音機の把手をぐるぐる廻すんだ(〈立体〉⑦・3)
f 化石の鳥が化石のリンゴのまわりをとぶ(同前)
g 暗く網のようにひろがる円(〈色彩の内部〉⑦・4)
h 孔省の尾のうしろへ廻って(同前)
i 肉をラセン巻きにするガードルに沿って(〈少女〉⑦・5)
j 円の四分の一の(〈青い柱はどこにあるか?〉⑦・6)
k タクシー乗場から軍艦の丸窓まで(〈フォークソング〉⑦・7)
l 車輪がとんで行く(〈崑崙〉⑦・8)
m 同円のスリ鉢叩いて(同前)
n まるくまるく/ハリネズミを追いつめ(同前)
o そうしてうずまき模様の(同前)
p スイ星の球のつまった(〈雨〉⑦・9)
q だからトウモロコシ畑のうしろへ/廻って(同前)
r その球体の少女の腹部と(〈聖少女〉⑦・10)
s 水の回転する泡の苦界の(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12)
t 木の球(〈低音〉⑦・14)
u それは点になるまでコイルで巻かれて(同前)
v 円にかこまれる(〈弟子〉⑦・15)
w 白地に赤く死のまる染めて(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
x ナイトテーブルをまわり(同前)
y 球体からながれる藍の水(〈コレラ〉⑦・18)
――以上が詩集《神秘的な時代の詩》から。
《神秘的な時代の詩》に「始原の渦巻く状況を象徴的に示す〔……〕中国神話にみえる創生神伏羲と女媧の兄妹あるいは姉弟の物語」(#B_079、
三四ページ)のような兄と妹(〈劇のためのト書の試み〉)の姿はなく、ましてやiやoやuに神話的人物の面影はない。むしろそれゆえに、渦巻き、螺旋形であらねばならないのか。それにしても吉岡の「ののののの」は不気味である。ここで電熱器のニクロム線など想起してもだめだ。千田稔は螺旋について次のように書いている。
たとえば密教で用いられる両界マンダラのうち、金剛界にも巡回する仕組みがある。それは〔……〕①、②のような二通りの順序でもって観想を行う。①の流れは従因至業という観想の順序で、外から上へ上がり、左回りに展開して内へ入り中心に到達する。②は従果向因と呼ばれる観想で、中心から右回りに外へ出る。①は向上門とも呼ばれ、密教の修行によって、日常的な俗の世界から、仏によって象徴される聖の世界への移行を示している。一方、②は向下門と呼ばれ、仏によって救われるという救済論的な道程を教義的に説明したものである。いずれも螺旋を描くプロセスであって、その方向が上昇するか下降するかの違いだけである。いずれにしてもマンダラは螺旋を描いているということは明らかである。ユングの心理学の立場にたてば、人が自己を実現する過程は、金剛界マンダラにしたがえば、向上門というべきかもしれない。徐々に悟りの境地に螺旋の図を巻きながら上昇していくのだから。(同前、一三六ページ)
この従果向因、向下門(「の」の字の螺旋)が吉岡の円運動からの離脱を直截に表す「教義」である。そこから「褐色の巻貝の内部をめぐりめぐり/『歌』はうまれる」(〈サフラン摘み〉⑧・1)だろう。思えば円運動こそ、吉岡にとっての「のたれ死」だったのかもしれない。《神秘的な時代の詩》の「矢印」はこの詩篇を最後に、矢のように放たれ二度と戻らなかったのである。
〈葉〉をいただいた後も、私は《粘土説》の続篇をいただこうとねばった。私の考えではそれは現代文明の総体を詩人の眼で批判的に捉える試みにほかならなかった。それは吉岡実の『ドゥイノの悲歌』であり『荒地』であると私には思われたのである。二年間の中止以前の詩、すなわち詩集『神秘的な時代の詩』(一九七四)に収められることになる詩篇がすでにそれを予告しているではないか、と私は考えた。――三浦雅士〈葉の言葉〉(#C_010、八八ページ)
*
吉岡の〈高遠の桜のころ〉には「〔……〕まだ四月なのにいろいろなことがあったなあと思った。暗中模索のため、二年間中止していた詩作を試み、〈葉〉という百三十行の連祷詩の一篇が出来たこと、それに続いて、〈ルイス・キャロルを探す方法〉すなわち、アリス詩二篇が出来たことだった。これは私の詩業のなかでも、独自性と新領域をきり拓いたものだった。私はこのときから、詩行為がつづけられるという兆を感じはじめていた」(#A_25、二七ページ)とある。吉岡実は〈葉〉の一篇をもって復活せり、と自ら信じていたふしがある。《ユリイカ》吉岡実特集号の〈詳細年譜〉一九六九年に「一○月、季刊詩誌「都市」のために詩「コレラ」を執筆、以後ほぼ二年間、作品を発表せず」(#C_039、一七四ページ)とあるように、のちに詩集《神秘的な時代の詩》としてまとめられる作品群のスタイルを踏襲しつづけることを、この時期にはっきりと断ちきろうとしていた。
それまでのどの詩集よりも短い《神秘的な時代の詩》の詩句を追う目は、すぐさま上から下へと読みくだし、詩句は次から次へと猛烈な速度で飛びさってゆく。疾走するのは作品ではなく、われわれ読者だった。しかしこの傾向は「詩なんて、だらだら書くものじゃない」(同前、一○二ページ)と言う吉岡自身によって否定される。創作家がおのれの技倆から半ば自動的に生みだされるスタイルにあきたらなくなったときに構じる手段は、いくつもあろう。吉岡が選んだのは創作停止、そしてそれに続く長い沈黙である。細かいことだが、〈コレラ〉から《神秘的な時代の詩》と《サフラン摘み》の重なる一九七二年に至る初出作品は次のごとくである。
⑦・18 〈コレラ〉 一九六九年一二月 《都市》
⑦・14 〈低音〉 一九七○年三月 《風景》
⑧・4 〈葉〉 一九七二年四月 《ユリイカ》
⑧・3 〈ヒヤシンス或は水柱〉 六月 《風景》
⑧・11 〈ルイス・キャロルを探す方法〉 六月 《別冊現代詩手帖 ルイス・キャロル》
⑧・6 〈悪趣味な冬の旅〉 七月 《中央公論》
⑦・15 〈弟子〉 八月 《無限》西脇順三郎特集
全き沈黙の二年間を飛びこえてまで〈弟子〉を《神秘的な時代の詩》へ繰りこんだ吉岡の西脇順三郎に対する負債は、詩集《夏の宴》まで持ちこされることになるのだが、それはさておき、この〈葉〉こそ詩集《サフラン摘み》の成立にもかかわる重要詩篇である。その理由は大きくふたつある。三浦雅士も〈葉の言葉〉(#C_010)で指摘しているとおり、初め〈葉〉が連祷詩《粘土説》の一部として構想されながら、結局は長めの一篇の詩となったこと、そしてそれまで吉岡がタブーとしてきた「作品」や「言葉」などの語彙を挑戦的に使用していることである。後者について、〈葉〉からはすでに三浦が挙げているので、その前兆とも言える詩句を《神秘的な時代の詩》から引こう。
・泥の書物/それは可塑物?(〈立体〉⑦・3)
・言葉を犯罪的に使って/紅色の闇へ/イタリア貂を狩りに出る(〈少女〉⑦・5)
・生まれるより先に死ぬべき同行者・同義語(〈崑崙〉⑦・8)
・罪ぶかい行為とは空間を穿つこと/関係のない物体や言葉を/同次元へ置くこと(〈雨〉⑦・9)
・言葉の次に/他人殺しの弟が生まれるよ!(〈聖少女〉⑦・10)
・夜は単純な言葉を喋れ(〈コレラ〉⑦・18)
・反自動的な書き方による詩の試み(同前)
・言語幻滅の治世に/水間という空間等価の世界があるとしたら/水中銃を撃て!(同前)
・ぼくは詩句を書きながら/それを見ていればよいのだろうか?(同前)
・ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか(同前)
とりわけもう一篇の〈死児〉である〈わが馬ニコルスの思い出〉からは次の詩句。
・あらゆる死体をとび越えた/その荒野に/言葉が必要か?
・一つの言語から生まれる/生死の観念の在り方
・暁の叙事詩の直立性を押しわけ/母娘の子宮を絞めて/恍惚の子供が泳ぎ出る
・潜在的世界には/犯罪的な言葉が屹立する
従来《神秘的な時代の詩》では「矢印」だけが注目されていたため、「犯罪的な言葉」はみごとにその存在を隠しおおせていた。それにしてもこれらの「言葉」は、あまりに滅びと結びついている。吉岡は死を厭うように「言葉」を忌避する。死児はニコルスに姿を変え、死の方向を指ししめす。「言葉」が「矢印」で指ししめす世界こそ、仮想された《粘土説》ではなかったか。吉岡は語る。
あれ〔〈葉〉〕は本来は「粘土説」という一つの長篇詩になるべきものであったのだけれど……だけど力つきてさ、単独の作品になってしまった。将来そういう詩を書くとしたら、おそらく「粘土説」だろうとは言える。「粘土説」というのは、虚無の極致なんだ。人間が崩壊し、土に埋没するだろうという終末感――。(#C_010、一○七ページ)
吉岡にとっての「粘土説」とは、田村隆一にとっての「腐敗性物質」のようなもの――モータルな存在としての人間の象徴――だと思われる。ここで、長篇詩一般に目を転じることにしよう。対談などの席にめったに出ることのない吉岡が、珍しく多くを語っている座談会〈思想なき時代の詩人〉がある。とりわけその〈一篇の長篇詩への夢〉の部分が刺戟的だ。鈴木志郎康と吉増剛造の詩に対して、吉岡が形を見たい、額に入ってほしいと要望すると、出席者の一人である佐々木幹郎が「額縁」の説明を求める。
やっぱりぼくは眼の方[、、、]の人間でしょ。だから、全貌がいっぺんに、絵みたいに捉えられないと困るんだ。とはいっても、詩は詩であるからたいがい捉えられますよ。日本に長篇詩で、成功した作品は、きわめて少ないな。そのなかでは、入沢康夫の『わが出雲・わが鎮魂』が完成度が高いと思う。〔……〕ぼくは長篇詩的なものを書こうと思ってやりだしたけども、とてもだめだった。誰でもいいから、本当によい長篇詩を書いて欲しいね。(#C_008、一二八ページ)
先に述べた「創作停止」の背後には長篇詩への、野望と呼んでもよいものが潜んでいたのである。
モップの棒の立てかけてある
その起源のなんと遠いこと
一二五行(初出では一○行多くて一三五行)の〈葉〉はなんの変哲もない光景で始まる。しかし「その起源」が遠いという二行めからすでに疾走は始まっている。続けて初出(#C_038)を引く。「デパートの洗面所の/衛生的な木蔭の抒情詩/ぴかぴかした床がすきだ/だから/われわれの恥しい/擬似排便を見よ!」。
〈葉〉の評釈ではないので、すべての異同を挙げることはしないが、初出と詩集に収められた形で違いの目立つのが、二行を一行に追いこんでいる詩句だ。八例ある。
・われわれの恥しい〔(改行)→(追込)〕擬似排便を見よ!
・かくして〔(改行)→(追込)〕緋色の衣はなびき
・舟で〔(改行)→(追込)〕層の下の層を求めて
・やがて苔むす消火器〔(改行)→(全角空けて追込)〕臼砲
・ちらちら覗く〔(改行)→(追込)〕反橋の下〔(ナシ)→には〕
・さかさまの〔(改行)→(追込)〕袋にたまるものがある
・書くこと〔(改行)→(全角空けて追込)〕書かれること
・「問題」は〔(改行)→(追込)〕在るか?
同様に、名詞止めは少しでも詩の展開に有機的に働くように減少する。
・浮袋の黒人の唄〔(ナシ)→が聞え〕
・菜の花畑〔(ナシ)→の【(改行)→(追込)】〕なまなましい夫婦群〔(ナシ)→を〕
・あでやかな春〔(ナシ)→の川まで〕
・発泡スチロールの函〔(ナシ)→は積まれる〕
・作品の終章は多くの場合パターン化の傾向〔(ナシ)→がある〕
だがこれらのどれよりも、三浦も言うように結末の「ハアハアする肺魚/――/葉」の直後にあった
(連祷詩《粘土説》の一部)
がなくなったのが最大の差異である。これはいったい何を意味するのか。「推敲は本来、いくらやってもしすぎるということはないといえる。しかしそれは習作のうちに、未完成なうちにやるべきであり、まだ公表すべきものではないのである」(#A_25、八九ページ)と明言している吉岡にとって。
「ユリイカ」の三浦雅士に「書け、書け」って頼まれた時、本当に不安だった、詩が書けるのかどうかね。だけどやらざるを得ないし、それで書いたのが「葉」なんで、あれは『神秘的』の形も受けて、ふっきれてないわけ。〔……〕あの時は、緊張していたでしょ、二年ぶりで詩を発表するということで。だからどういうの書いていいのかわからなくてああいうものができたんだけどね。(#C_010、九九および一○七ページ)
〈葉〉は、結果的には〈わが馬ニコルスの思い出〉や〈コレラ〉で展開された吉岡の「戦中戦後」をテーマに据えた詩篇と同工でありながら、時代を現代に設定した、作品の生成を主題とした詩篇となった。二年の歳月は否応なく自作への内省を促した。
・手法の変則を試みては散文的に
・肉 言葉/それについて語るのはむずかしい
・言語/その甘皮かぶり/構造上から固有名詞の乱用を避け
・あらゆる読者を驚かせる/でも批評家は火山と家畜の運命を語る/作者を探しに谷へ/意味とリアリティとは別のものか/省察せよ
・作者の主題の外れたところで〔……〕
・修辞学的に考えても最良でない
・作品営為とはそのようなものの彼方の/籾の山
・書くこと 書かれること
・作品の終章は多くの場合パターン化の傾向がある/意識のあるうちに注意せよ
・装飾性をすなわち消せ
・歩むことができない作者の姿をはじめて見つけた!
・書物の帝国
・もしかしたら作品の終りの冬がくる
・われわれはこれを読むことが可能だろうか?
〈コレラ〉の最終部では〈僧侶〉のパロディを行いつつ「春きたりなば/離魂/これから何処へ/浮遊せんとする!!」と苦渋に充ちた表情で神秘的な時代に別れを告げた。吉岡実における一九六○年代とは《僧侶》で完成をみた詩語、詩法、語法への反逆、あるいは離脱の試みの時期と思しい。〈死児〉を六○年代的な手法で謳いあげ、変奏した〈わが馬ニコルスの思い出〉と〈コレラ〉が、詩集を代表する作とみなされる所以である。それにしても〈葉〉とはなにか。
作品自体は血の気の乏しい夢をはらむ
それら「血の気の乏しい夢」を賦活し、滅びの意識のただなかにある「生誕」を中心主題に据えよ、と〈葉〉は語っているように思われる。吉岡実の作品から意味だけを抽出することは困難をきわめるが、この詩篇はその最たるものだ。まさに「思考は移る」のだ。この主題と《粘土説》の「虚無の極致」の主題を同時並行で進めることは、吉岡にしても不可能だった。野心的なライフワークは延期され、のちに一代の名作となる《サフラン摘み》の構想が浮上してくる。
死者の肉体は、さらに二つの壺を組合わせたもののなかにおかれる。この壺もまたひさごである。ところで壺はときには、ミニチュアの世界がおかれた水そうのかわりをするということであった。つまりその世界はひさごであり、壺であり、崑崙(葫蘆)の仙境であり、さらに死者と仙人の世界でもある。――スタン《盆栽の宇宙誌》(#B_077、一五四ページ)
*
Ⅳ章は、かつての〈「内面のリアリティ」――吉岡実論のためのノート〉の一節(#C_030、四~九ページ)である。〈葉〉がもうひとつの〈崑崙〉であることを、ここで改めて念押ししなければならないだろうか。さて「崑崙」だ。長谷川郁夫の評伝伊達得夫には次のような箇所がある。もしかしたら、吉岡はこの事件によって「崑崙」という名に触れたのだろうか。
関釜連絡船崑崙丸がアメリカの潜水艦によって撃沈され、五百四十四人の死者を出したのは、この四日後、〔一九四三年〕十月五日のことである。内地と植民地とのあいだの海はすでに安全海域ではなくなった。(#B_119、八一ページ)
とはいえ吉岡が中国大陸に渡ったのは二年前一九四一年の夏であり、軍隊でこうした情報に接しえたかは疑問だ。Ⅲの題辞に岑参を引きながら言うのも妙だが、吉岡が戦前に岩波文庫版で需めている(#A_27、八○ページ)《唐詩選》経由だという確証もないし、宮澤賢治――金子民雄に依れば宮澤は「天山山脈についてふれながら、むしろ崑崙の玉や崑崙山と西王母伝説で名高い崑崙山脈について、ただの一度もふれたことがない」(#B_029、四五ページ)という。むしろ吉岡と宮澤はスウェン・ヘディンを介してつながる。――でもないし、草野心平――草野が詩篇に「崑崙」と書きしるしたのは最晩年の〈異常天然〉(#B_041、一三九ページ)においてだ。――でも、井上靖――林浩平氏に依れば井上は晩年、吉岡に詩集を送っているが、わたしには《新潮》一○○○号に井上、吉岡と大岡信の三人の詩が載ったのが契機だったのではないかと想われる。――でもないだろう。もっとも井上には一九六七年七月号《オール読物》掲載の短篇小説〈崑崙の玉〉があって、そのころ吉岡は詩集における最初期の詩〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)を書いているから、読んでいれば記憶には新しいはずだが、そこで初めて「崑崙」と出あったわけでもあるまい。また、陳舜臣の言うように「むかしは旧制高校の寮歌などで、崑崙がロマンチシズムをかきたてる地名として知られてい」(#B_090、二六五ページ)たとしても、吉岡の送った青春は次のようなものだった。「暗い切通坂を上りきると、すきやきの江知勝がある。ここでは毎晩のように、帝大、一高の先生や学生たちが放歌高吟していた。奉公人たちには縁のない世界だった。私は店に戻り、帰店時間を書き入れて、寝たものである」(#A_25、四○ページ)。
*
さる日、わたしは文藝空間の原善から「崑崙」に関する耳寄りな情報を得た。JR赤羽駅構内に崑崙なる店があるというのである。赤羽といえば、一九五九年の秋から新婚間もない吉岡実が当時の国電赤羽線の板橋駅前に住んでいたから(#A_25、二七八ページ)、まんざら見当違いでもあるまいと、さっそく次の休日、探訪に出かけた。
JR埼京線だと池袋から九分で赤羽だ。なるほど「赤羽駅ビルアルカード店舗案内図」に「ニュー酒蔵崑崙」とある。その店は高崎・東北線の七番線ホーム(宇都宮方面)の南口あたりにあった。あいにく臨時休業で、二間ほどの店のシャッターは降りていた。とはいうもののそれほど落胆したわけではない。プラットホームも「アルカード」も吉岡が〈崑崙〉を書いた一九六八年当時ここに在ったとは思えないからだ(別の場所になかったとも断定できないが)。店の看板は「ニュー酒ぐら崑崙」で、命名者もさすがに読みにくいと心配したのか、それぞれ漢字に「コン」「ロン」とフリガナを付けている。食事もできるらしい。午後一一時三○分までとあるので、機会があればまた訪れ、名前の由来やいつごろからここでやっているのか尋ねてみたいものだと思いつつ、赤羽駅を後にした。一九九二年六月二一日のことである。
*
閑話休題。こうして「崑崙」がいつどのようにして吉岡実とまみえたかの探求は放棄せざるをえない。それならば「崑崙」はどのように吉岡詩のなかで変容を遂げたか。わたしたちはここで中野美代子に依らなければならない。近著《龍の住むランドスケープ》(#B_106)のⅠ〈蓬莱のデザイン〉(とりわけその4〈蓬莱案内〉、5〈蓬莱は南海へ〉、6〈崑崙は西洋へ〉)とⅢの1〈北辰の石〉が重要であり、《ひょうたん漫遊録》(#B_105)の諸篇も必読だ。だが、これらは「崑崙」がその論述のなかで完全に咀嚼されているので、かえって引きにくい。
そこで一九八○年の《孫悟空の誕生》を読む。Ⅲの1〈地名の虚実〉は《西遊記》の地理学であり、玄奘の辿ったルートの説明に崑崙が登場するし、「崑崙河源説」への言及があるし、明刊本第五九回の「崑崙山」にも触れている。続くⅢの2〈『西遊記』の空間論〉では玄奘が訳した《阿毘達磨倶舎論》の須弥山を中心とした世界の構造を定方晟によって図示している。なんとその図に〈崑崙〉の一三五行めの「金輪」(こんりんざいのこんりん、であってかなわ、ではない)があるではないか。中野はこう書く。
「インド亜大陸を模した贍部州〔……〕の北部にある無熱悩池から流れ出る四つの大河のうちの一つ徒多[シーター]河は、じつはヤルカンド河であるから黄河の源であるとも考えられ、結局のところ、中国もまた贍部州〔われわれの住む世界〕に属するということになろう」(#B_102、一六九~一七○ページ)。ここにおいて「金輪」が〈波よ永遠に止れ〉につながった。一方、須弥山は定方晟の要約を引けば、「仏教的宇宙観によると、虚空に風輪という風(空気)の巨大な円筒が浮かんでいる。風輪の上に水輪が、水輪の上に金輪(地輪)がのる。金輪の上に大海があり、その中央にそびえたつのが須弥山である。〔……〕須弥山の上半分は帝釈天(インドラ)などの天(神)の住む世界で、さらにその上空には何層もの神の世界が重なっている。このような宇宙観を俗に須弥山宇宙観と呼ぶ」(#B_171、二六○ページ)である。
吉岡がなにに触発されて〈崑崙〉を書いたかは依然としてはっきりしないものの、須弥山宇宙観ならぬ「崑崙宇宙観」が詩篇で繰りひろげられたのは確かなようだ。崑崙宇宙観とはなにか。秋山さと子は螺旋のシンボリズムについて「一般的にいって宇宙の誕生と進化にかかわる象徴的図形であり、成長、上昇と下降、統合と多様化、収縮と拡張などを意味する。〔……〕迷路の象徴的主題ともかかわり、本能的な力、母の子宮への退行、または中心への道を表す図形として、天国や聖地への巡礼路を示すこともある」(#B_172、三六二ページ)としているが、〈崑崙〉は「宇宙の誕生と進化」を描いていないまでも、生死の両義性を掬いとろうとする試みではある。それにしても「きみ」「ぼく」「きみの彼女」「ぼくの彼女」の関係は、どう見ても謎である。「ぼく」と「きみ」を男性としよう。
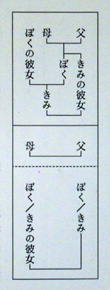
〈崑崙〉の登場人物関係図
図の上のような「家系」としても読めるのは、母や妻や父がだれのという限定なしに現れるからである。「ぼくの」でそれを統一するとはなはだ奇怪な関係となる。姉か妹が「きみの彼女」であるのはともかく、「ぼくの彼女」が「母」だったら、どういう系図を書けば良いのだろう、要素は図の下のように三組の男女にすぎないのに。「ぼくの家系は秩序をうしなうだろうか」(〈喪服〉④・15)。「彼女たち」は「ぼくの彼女」と「きみの彼女」だろうし、「幼児」が「きみ」で「老人たち」は「父」「母」? では「女」は? もしかしたら西王母だ。白川静は次のように書く。「西王母は、卜辞に東母、西母とみえてもと日神であったのであろうが、『山海経』〔大荒西経〕には、西海の南、流沙の浜に、赤水を前にし黒水を後にした大山崑崙の丘があり、その神は人面虎身、その下には弱水の淵をめぐらし、その外には炎火の山があり、そこに虎歯豹尾、頭に勝(髪飾り)を戴くものが西王母であるという。漢代の神仙化した画像にも、なお虎を従えた形にかかれている」(#B_074、二二三~二二四ページ)。「浴槽のなかで虎みたいに重い/シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる/あまりにも水が熱く/貝のなかの舌というものは乾く/モモイロのその舌がいくつにも裂けるよ」(〈コレラ〉)。
吉岡は中心としての「天国や空地への巡礼路を示すこと」はない。「今日ぼくたちにも存在しないだろう?/崑崙!」なのだから。だがそれを無としての崑崙宇宙観と呼んではなるまい。蹌踉たる足取りの四人は、それでもやはり曽布川寛の述べる「基本的には人間が死ぬとその死者のもとへ、天上の天帝から使者が遣わされ、崑崙山からも迎えの神が降り、ここに死者は乗物に乗って崑崙山へと昇仙する」(#B_080、一六八ページ)例として読めるのだから。吉岡自身が死後の世界をどう捉えていたかは、今後の課題としよう。
私は生きている者
そ〔/と〕して一度は通って
みたいような(処)へ差しかかる
(〈聖あんま断腸詩篇〉⑫・12)
物事の順序から言ってありえないにもかかわらず、中野美代子の著作に負っているのは以上にとどまらない。一九八九年に一書にまとめられた《仙界とポルノグラフィー》には崑崙だけでなく「蓬莱」「葫蘆」が登場する。
ところで、蓬莱山をはじめとする三神山が壺に見立てられたというのは、いったいどういうことなのであろうか。さきに述べたように、三神山を壺に見立てたのは晋代になってからだということになっているが、『列子』では、方丈山のことを早くも方壺と称しているのを想起されたい。〔……〕
〔……〕方壺すなわち方丈山には、崑崙という別名があると記した北魏(三八六~五三四年)の酈〔レキ〕道元の『水経注』に注目しておこう。崑崙とは、西の果ての仮想の聖山の名であり、やがて実在の大山脈に与えられた名であるが、それがどうして東海の果ての「浮き島」の別称になったのであろうか。
そのことを理解するためには、崑崙の中国音kun-lunの上古音が、klunという二重語頭子音を持つKL-型の一音節構造であったのが、K-L-型の二音節に分かれkun-lunとなったという、音韻上の変化があったという事実をご記憶いただきたい。じつは、壺も、このKL-型の二重語頭子音をもつ言葉であった。瓢箪のことを、中国語でhu-luといい、葫蘆とも壺蘆とも書くが、これまた上古音ではKL-型の一音節構造であったものが、K-L-型に二音節化したものである。KL-型の一音節構造の言葉は、「ころん[、、、]とまるい、ぐるり[、、、]ととり巻く、くるん[、、、]とひっこむ」といった基本義を共通に有するとされるが、崑崙も、さらには崑崙や壺の異名をもつ東海の三神山も、「ころん[、、、]とまるく、内部はくるん[、、、]とひっこんだもの」、すなわち瓢箪や壺のようなものと考えられていたのである。(#B_104、七三~七四ページ)
漢語におけるkとlの複合した言葉への言及は、藤堂明保《西域紀行》(#B_097、四三~四四ページ)でも読むことができるが、崑崙とはまさしく吉岡好みの「形態としては寸のつまった丸いもの」(#C_010、一○六ページ)に通じる基本的な意味を含んでいたのである。ところで〈蓬莱〉(⑪・18)は詩集《薬玉》後期の作品だったし、同じく《薬玉》に収められた西脇順三郎追悼詩篇〈哀歌〉(⑪・13)の第二章は、まるまる西脇の《詩學》(#B_111)の〈音の世界〉からの抄出で成りたっていた。すなわち
言語の世界は一つの立派な音の象徴の世界であるから、「ヒョータン」という音はいかにも実体の「葫蘆[ころ]」をよく象徴しているように思われる。しかしこれは日本人だけであって、日本語を知らない人にはこの音は何か「橋」のような印象を与えるかも知れない。反対にフランス語のグルド(gourde)=瓢箪=はフランス語を知らない人には、この音はむしろ「いもむし」をよく象徴すると思うかも知れない。
〈アポコペ〉
一九八二年六月五日の西脇逝去後、吉岡は《現代詩手帖》七月号の追悼座談会(Ⅲで触れた)に出席し、《新潮》八月号に〈西脇順三郎アラベスク(追悼)〉を執筆し、《ユリイカ》七月号にこの〈哀歌〉を寄せており、追悼詩にそれほど多くの時間が割けたとは思えない。そうしたなかで「葫蘆」を西脇詩学に探りあてたのは単なる偶然だろうか。末尾の「〈アポコペ〉」(ギリシア語で「語尾消失」の意)は《詩學》のこの箇所には見られず、吉岡が置いたものだが、本来の意味もさることながら「あべこべ」にも聞こえ、それさえ「コロ/コンロン」を想起させるのは「崑崙」の「混沌」ゆえだろうか。ときに「「ふくべ棚のあなたより/現われ出でる/北斗七星」」(〈聖童子譚〉⑫・4)とは、最後の詩集《ムーンドロップ》からの印象的な詩句である。秘教のにおいの立ちこめる《薬玉》に〈崑崙〉からの水脈がどれほど走っているか、以下に引用する詩句が自ら語るところに耳を傾けよう。
ここは何処だと問えば
山海境[せんがいきよう]
桃やすももが咲きみだれ
白玉多し(〈巡礼〉⑪・7)
曠野を越え
桶屋は円形のタガを地に置き
つるつるした白玉や
赤い腰巻の内部を夢む(〈天竺〉⑪・9)
煙突掃除夫が現われる
(鏡にうつる顔は
近くもなければ遠くもない)(〈春思賦〉⑪・11)
(身毒)の園は何処
野山を越え 書物を越え
霞める滝や
観念を踏破して
見えるだろうか(〈垂乳根〉⑪・12)
(碾臼的装置)
(水輪)の上を
(金輪)はゆるやかに廻っている
(〈甘露〉⑪・14)
ほうらい (宝来)
(飲食[おんじき])するはらからの宴も終る
(いずこにも不死の人はいない)(〈蓬莱〉⑪・18)
日は高く 鶴は舞い
岩根は低く 亀は這っている
(可視線の書き割り)(同前)
唯ひとつの(葫蘆[ころ])と
(種婆[たなば])へと化身する
わが母がいるだけだ
(〈青海波〉⑪・19)
中野は前掲《仙界とポルノグラフィー》の〈瓢箪の宇宙〉でも葫蘆にふれていて、スタンの訳書をそのまま援用してから次のように書いた。
ところで、スタンも述べている葫蘆[hu-lu]という言葉だが、瓢箪を意味する英語のgourd、フランス語のgourde、はてはラテン語のcucurbita〔……〕など、いずれも上古中国語の[kl-]型となんらかの関係があるのではないだろうか。〔……〕gourdという英語が登場するのは、オックスフォード辞典によれば、十四世紀以後のことらしい。とすれば、[hu-lu]系の中国語がヨーロッパに伝わった可能性があるのではないだろうか。(#B_104、二三四ページ)
西脇順三郎が聞いたら、手を打って悦びそうな説ではないか。吉岡が引いた西脇の《詩學》は本来こう続く。「音質は全く主観的なもので印象的であるから、その象徴はどうしても不完全である。/マラルメが詩作の世界を感覚的にみる場合はいつも音の世界ばかりである」(#B_111、一○三ページ)。吉岡実が〈骰子一擲〉のマラルメに出あうのは〈崑崙〉の十数年後、《薬玉》以後のことである(#A_25、三六七ページ)。だが、吉岡が「崑崙」と口にしたそのときすでに「ころんとまるく、内部はくるんとひっこんだ」《薬玉》の世界は約束されていたのかもしれない。満洲に在った兵士は、詩人として、遠く中央アジアの土地の霊と呼びかわしたのである。
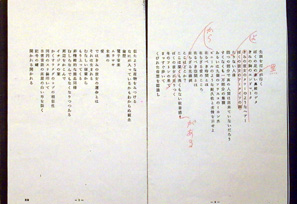
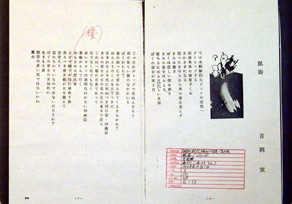
〈崑崙〉初出への手入れ〔評者による再現〕(右から、4見開きの①②)
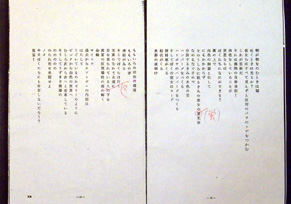
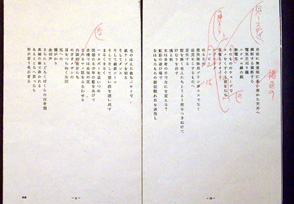
〈崑崙〉初出への手入れ〔評者による再現〕(右から、4見開きの③④)
吉岡実の生前に印刷された〈崑崙〉本文には、次の六種がある。なお、入稿原稿は未見である。
・初版以前
(1)《南北》誌 一九六八年一〇月 〔初出〕
(2)《ユリイカ》誌〈神秘的な時代の詩・抄〉 一九七三年九月 〔再録〕
・単行詩集ほか
(3)《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、一九七四年一〇月二〇日) 〔初刊〕
(4)《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、一九七五年六月一日) 〔再刊〕
(5)《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、一九七六年八月一五日) 〔三刊〕
(6)《新選吉岡実詩集〔新選現代詩文庫110〕》(思潮社、一九七八年六月一五日)
漢字の字体を含めて細かく比較していくと、すべての本文に異同がある。本評釈では段階的な手入れに主眼を置かなかったので、上掲図版〈〈崑崙〉初出への手入れ〔評者による再現〕〉は、(1)の初出と定稿と見てよい(5)の三刊との間の異同だけ挙げた。異同の詳細は本評釈のⅢを参照されたい。定稿の九八行め「共謀的な彼女たち」の初出形「共謀的彼女たち」は(2)→(3)の時点で定稿形になったが、(3)→(4)の時点で再び初出形に戻ってしまい、(5)以降は定稿形である。これは(4)の組版のとき(全面的に新組である)、刊本である(3)を本文とせずに、(3)用の入稿原稿を使用したためかと思われる。つまり(3)用の入稿原稿はおそらく初出形「共謀的彼女たち」のままであって、この詩句に「な」を挿入して「共謀的な彼女たち」としたのは(3)の校正時だったのではないか、という推測を許す。
〔付記〕
本評釈は、一九九一年一二月八日の文藝空間例会での口頭発表を骨子としている。宇佐見森吉、原善、福田淳子、星野久美子の文藝空間同人諸氏ならびに斎藤美季、高根沢紀子の両氏に感謝する。初稿は一九九二年五月一日から六月二二日にかけて執筆し、発表誌には吉岡実による題字、たなかあきみつ撮影の写真を配した。完成した冊子を何人かの先達に送ったところ、ほどなく書肆季節社の政田岑生氏から「塚本邦雄さんのところで評釈を見た。周囲の人に読ませたいので、十部ほど入手したい」という電話をいただき、恐縮した。なお、本文中でも触れたが、Ⅱの〈波よ永遠に止れ〉はのちに改稿して〈〈波よ永遠に止れ〉本文のこと〉(《吉岡実の詩の世界》、二〇〇三年三月)と〈吉岡実の長篇詩〉(《日本ペンクラブ:電子文藝館》、二〇〇三年五月)とした。併せてお読みいただければ幸いである。
雨はひとつの層となって降る。――土方巽(#C_051、三九ページ)
吉岡実は一九六八年を《現代詩手帖》一一月号に発表した詩篇〈雨〉(⑦・9)で締めくくった。
雨〔初出形〕|吉岡実それはたとえば 1
老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの 2
スイ星の球のつまった 3
箱をさがすように 4
レインコートの黄色の美人がすきだよ 5
だからトウモロコシ畑のうしろへ 6
廻って 7
赤毛のやさしい愛撫から 8
少年がぞろぞろ出る 9
こんなにノビのきく夢 10
ビニールの紐がどこにある? 11
知覚できる具体的メカニックの世界から 12
ひとつの堅牢な白い箱をしばりあげよ! 13
踏台のように 14
他によりかかる映像がないので 15
中世の女のように 16
しゃべらず 17
黄色のレインコートをぬぎ 18
それにほそい脚を 19
かける 20
あまがける! 21
箱の下はいまなお血生臭い戦いの世界? 22
或は老人たちのあそんでいる砂場? 23
それともススキの茂る情死の腐爛期 24
どうでもいい日々 25
肩から乳房までさらして 26
その女は大きく股をひらくんだよ! 27
では灰かぐら 28
箱は水面へ泛びあがり 29
なによりも流れる 30
罪ぶかい行為とは空間を穿つこと 31
関係のない物体や言葉を 32
同次元へ置くこと 33
であればこの白昼のなかで 34
ザクロの粒々の 35
果肉がはじき返えされるんだ 36
太陽から遠く 37
金属の小さな柱の森へ 38
たのしんでいる鳩 39
たのしんで叩くピアノ 40
たのしんで突つく浴室の孔 41
老人になる日まで永遠に 42
にがにがしくスパイとして 43
具体性のある物をつくり 44
肉色の箱を担いで歩く 45
それの内側は金色の塗料ですみずみまでぬられ 46
回復できない肉体の周囲 47
パラシュートの兵士は宙吊り 48
女の帽子が風でとぶ 49
その単位 50
その恍惚の夜は 51
同時にくるか同時に戻る 52
トーテムの上で泣く幼児の声を聞く 53
火をくぐる美しい女の腰 54
建築物の空間の 55
あらゆる余白を横切るものはなに? 56
それは音楽? 57
それは暴力的な甘い蜜? 58
痛みまで感じる 59
黒髪のゆたかなカーブを見よ! 60
はみだしたものはくびれ 61
平らな面は割れ 62
秋のあかつきがくる 63
箱は黒色の角を緊張させたままぬれる 64
いつからと問うことはなく 65
雨のなかに 66
・初版以前
(1)一九六八年一一月一日 《現代詩手帖》〔初出〕
(2)一九六八年一二月一日 《詩と批評》〔再録〕
・単行詩集ほか
(3)一九七四年一○月二○日 《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房刊)
(4)一九七五年 六月 一日 《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房刊)
(5)一九七六年 八月一五日 《神秘的な時代の詩〔普及版)》(書肆山田刊)
(6)一九七八年 六月一五日 《新選・現代詩文庫 110 吉岡実詩集》(思潮社刊)
吉岡実生前に印刷された〈雨〉の本文は以上の六種類である。(3)、(4)、(5)巻末の〈初出一覧〉に「一九六九年」とあるのは「一九六八年」が正しい。(2)は〈特集現代詩(一九六八年度作品)〉と銘打った年鑑で、現在の《現代詩手帖》の年末号と同種の企画だ。(1)と(2)の間には一箇所、次に述べる手入れの4と同じ漢字の字体変更があるだけで、意味に関わる直しはない。(2)のようなコンピレーションの場合、直前の形態の本文すなわち初出形を再録するのが趣旨で、漢字の字体の差異は印刷所の事情に拠るものでこそあれ、著者の意向に依るものではないと考えられる。(3)のための次の四箇所の変更の結果、定稿となった。
1 (四行め) 箱をさがす〔ように→(トル)〕
2 (二九行め) 箱は水面へ〔泛→浮〕びあがり
3 (四三行め) にがにがしく〔スパイとして→(トル)〕
4 (五二行め) 戻(字体変更、旧字→新字)
(4)では2が再び「泛」に先祖返りして(〈「矢印を走らせて」〉図版解説を参照のこと)、四二行めは「老人になる日まで求遠に」と誤植されている。(5)と(6)の本文は(3)に同じ。ただし二四行め「爛」は(5)と(6)が正字で、それ以外は火偏に門構えの中が東の拡張新字体だ。こうした違いは本文校訂上わずらわしいだけなので、以降の評釈では本文の意味に関わらないかぎり言及しない。また三六行めの「え」は衍字で、校訂すべき箇所である。吉岡の散文〈三橋敏雄愛吟抄〉の初出形(花神コレクション版《三橋敏雄》所収の同文はその再録)にも「全句業を読み返えした」(#B_147、一○五ページ)と出てくるから、書き癖が残ってしまったもののようだ。勤務先の筑摩書房での業務の広告文案作りは時代の送りがなの方針を尊重するはずだから、吉岡は自作でも送りたりないことを気にするあまり、不要の「え」を書いてしまったのかもしれない。
1、2、3の校異をどう読もう。1の四行め「ように」の削除はみごとだ。吉岡の「ように」「ような」の用法は稿を改めて述べたいが、一四行めと一六行めは残して四行めを除いたのは正しいと思う。無用だというのとも違うし、強いて言えば四行めのそれは滑らかすぎた。2の「泛」は〈わたしの作詩法?〉に「喫茶店で、街角で、ふいに素晴しいと思える詩句なり意図が泛んでもわたしは書き留めたりしない」(#A_25、八八ページ)と記されているように、浮も泛もうかぶ意だ。中村稔の詩集に《浮泛漂蕩》(思潮社、1991)があるが、吉岡の脳裡に熟語「浮泛」がうかんだかもしれない。ただ漢和辞典が教える微細な使いわけがここにあったかどうか。3の手入れは本文内容に即してⅤで考えよう。
一九九二年の秋、ジョゼフ・コーネル展の会場となった鎌倉・鶴岡八幡宮の神奈川県立近代美術館に足を運んだ。ここを訪れるのはポール・デイヴィス(吉岡がその猫のアクリル画を求めた)の展覧会以来だから、一七年ぶりだ。他の人は知らず、わたしは図像の記憶が長期間にわたっては保たれない。デイヴィス作品のアメリカの田舎の懐かしさと美術館の中庭の印象以外、具体的な像がひとつとして浮かばないのだ。さらに重要なことだが、デイヴィスに猫を描いた作品があったかどうかさえ想いだせない。蓮のある中庭だと思いこんでいたが、水面に蓮の葉はなく、建物の配置からすれば前庭と呼ぶほうがふさわしい。
造形作家は違うはずだ。他人の絵をあまり観ない画家がいるそうだが、それは画面が鮮明に焼きついてしまっては自分が描く段でいろいろと支障をきたすからではないか。吉岡の目の記憶は画家のそれに近く、しかも描いたのではなく書いたのだから、自作のなかでは表現することと亨受することの邂逅が約束されていた。吉岡が戦後の一○年間、詩を書く意志に充ちつつ手を着けかねていたのは、目と手を結ぶこの関係に確信が持てなかったことも理由のひとつだろう。わたしの〈吉岡実年譜〉(#A_32、二九二ページ)から抄する。
・一九四五(昭和二○)年 二六歳
従軍中に日記一冊と詩一冊のノートを記し短歌や俳句も若干作るが、超現実主義的な作風の詩篇は引きあげ時に失われた〔上官に託したものだという〕。
・一九四七(昭和二二)年 二八歳
七月、一行の詩も書けず《鹿鳴集》で心を鎮める。一○月、《新思潮》に掲載した詩〔〈敗北〉〈即興詩〉の二篇〕の稿料を日高真也の友人下野博が持って来てくれる(生まれて初めての原稿料)。
・一九四九(昭和二四)年 三○歳
八月、「卵」を主題に詩を書く。《みづゑ》でクレーの絵と評伝に触れる。九月、詩〈ぽーる・くれーの歌――又は雪のカンバス〉脱稿(未発表)。
「静物」すなわち「死んだ自然」の発見が目と手のぶれを正した結果、吉岡実詩が誕生したというのはそのとおりだろう。しかし、書きおろしの詩集《静物》は出発点である以上に戦後一○年の到達点だった。一九四九年の「卵」を主題とする詩が〈卵〉(③・7)か断定を許さないが、そのままの形で詩集に収められたとは考えにくい。さらに〈ポール・クレーの食卓〉(⑩・1)とは別の〈ぽーる・くれーの歌〉が《静物》に収録されていないことからは、吉岡が実在の画家と対抗しうる骨法を体得していなかったことが推察される。絵画をめぐる固有名詞は、危険な素材だったのだ。では次はどのような絵か。

難波田龍起の「半具象の作品」(吉岡実〈昆虫の絵――難波田龍起〉)〔モノクロコピー〕
出典:《造形の詩魂――難波田龍起自選展》(フジテレビギャラリー、1974)
私は奇妙な一枚の油絵を所持している
四号ほどの大きさの板に
昆虫らしきものの形態が描かれている
まるで森の中のような暗緑の世界で
その昆虫らしきものは這い廻っているようだ
子供たちがしばしば草むらのなかで捉えるバッタに近似している
それはやがて生命力が充溢して
いままさに飛び跳ねる寸前に思われる
――とは単純にいってはならない
むしろその昆虫は自覚もなく存在する故に
深い傷を負っていて
光の差さぬ寝所で休息しているようにさえ見える
長い脚をいくつにも折り曲げ
成長を止めた植物のかげから
重いからだを遠くへひきずってゆく
触角にふれるのは
瓦壊せる夢の空間しかない
頭部の下にこれは孔といったほうがいいのか
あいまいな大きな二つの眼のまわりは
にぶい朱色で隈取られているからだ
餌食を探しているのでなければ
恐らくそれは〈愛〉を求めているのだろうか
よく観察すれば
奥行ある大地の上に太い胴体が繋がれているという悲劇
黒と灰色の蛇腹の中心の部分には
矩形に窓がうがたれ
そこから人間の瞳がまばたきをしているのだ
この創造された昆虫はたしかに孕んでいる
永遠に生まれざる人間を
これは吉岡実の散文〈昆虫の絵〉(#A_25、一六六~一六七ページ)の冒頭だ。原文の句読点で改行していくと上のようになる文章で、この緊張度の高さは吉岡実散文では珍しい。それにしても難波田龍起の「半具象の作品」で「今、私の眼の前にこの絵は置かれている」(同前、一六七ページ)ためだろうか、傍線を付した箇所は吉岡の詩ではこれほど頻繁には見られない、ときに刈りこみたくなるくらいの婉曲表現である。次に〈謎の絵〉(⑨・26)を読もう。
岸辺に近く、ごつごつした岩がある。そのかたわらで漁夫が漁具を砂地に置き、しばし休息しているように、わたしたちには見えた。それはアンドリュー・ワイエスの素描だった。
「そこは存在や意識の地上に対し、イマージュの地上と呼ぶべきものかもしれない」
同じ処に暗褐色の濡れた岩がある。人は消え、釣竿と櫂が置かれたままだ。ここには仰ぐ月はなく、打ちよせ、引きさがってゆく、波の音が聞える。
画家の完成させた絵を、わたしはそのように認識し心ひかれた。家に戻って語りあったら、岩に置かれたものはたしかに、〈猟銃〉と〈斧〉だったと妻は言いつづける。
ある展覧会を二人で観たとする。親しい者どうしが感想を語りあうと、まったく印象が異なるのに愕然とする。原因となった作品を観かえすこともできず、奇妙な感覚だけが残る――もちろん詩〈謎の絵〉は上の散文の形ではなく、句読点もない行分けの詩だが、〈昆虫の絵〉より婉曲な言いまわしが少なく、構造もはっきりしている。それを決定しているのが「アンドリュー・ワイエスの素描」だ(対象となった作品は〈決闘〉とその予備的習作)。仮にワイエスの絵を一点も観たことのない読者がこの詩を読んだとしても、固有名詞ゆえにこの短い詩(ぜひ原文に就いて読まれたい)の謎は、吉岡の詩的散文〈突堤にて〉(#A_25、四八~五一ページ)に匹敵するだろう。漁夫から猟師へ。〈ぽーる・くれーの歌〉以来三○年を閲した吉岡実の詩は、ここに至った。
〈神秘的な時代の詩〉評釈時にも触れたマルセル・デュシャンが、一九六八年の一○月二日に八一歳の生涯を閉じたが、二五~二七行を遺作〈1.水の落下、2.照明用ガス、が与えられたとせよ〉に結びつけることはできない。「遺作」はまだ公開されていなかったのだから。ただ「原型」たる〈照明用ガスと水の落下が与えられた、とせよ〉(一九四八~四九年)があって、まさに「肩から乳房までさらして/その女は大きく股をひらくんだよ!」という構図だ。しかしそれは、村岡三郎〈マダム〝ローズ・セラヴィ〟〉のことばを借りれば「どうみても、乳房と、位置の不自然な割目だけしかない性器をもった、まさに男性の裸体としか思えない「遺作」のためのレリーフ」(#C_027、一二三ページ)という奇妙な図像だ。ほのめかしが「遺作」のためのレリーフなら「その女」が女か怪しい。吉岡の書く伝記的事実「〔一九五四年〕秋、軽井沢で、同居の画家吉田健男が年上の女と心中。〔太田〕大八と健男の弟とともに、遺骨を迎えに行く。風呂敷で骨壺を包み、床の間へ安置し、湯の宿に一泊する」(#A_23、二三一ページ)を二四行めに引きつけるのは危険だとしても、四九行めまで女が登場しないのはどう考えたらいいのだろうか。吉岡がデュシャンから「存在や意識」ではなく「イマージュ」を手渡されたのか。
わたしの知るかぎり〈雨〉全体を論じた文章はない。吉岡本人は飯島耕一との対話〈詩的青春の光芒〉で、〈あまがつ頌〉(⑧・30)の創作意図に触れつつ語っているので、少し長いが引用する。
吉岡 こないだ飯島くんが言ったとおり、ぼくがこんど羽黒山へ行ったでしょう、で羽黒の詩を書けっていう、それが非常に抵抗があるわけね、わが心のなかで。羽黒山をおれがどう書くか……羽黒体験というものを。それを言われて考えてる、羽黒山を書けるだろうか、というのが、まだいま課題なんだけど。
飯島 ぼくもほんとにそう思う。こんどの『神秘的……』のルイズ・ニーベルスンですか、よりも羽黒山を書いてほしいな。(笑)
吉岡 ニーベルスンは材料だったか、なんか絵具程度になっちゃうかわからないけどね。なるほど。
飯島 それはやっぱり冒険ですよね。
吉岡 だから、そこのところをむしろ散文なら書けるんじゃないだろうかと。わが詩というのはさ、西洋ダネっていうかね、そういうもんでしょ、わりと。だけどおれは日本人が書いてるんだから、日本の詩だと、ぼくは信じてるんだけど。だから羽黒山というのはどう関ってくるか。また書くかもわからないしね。むしろ散文形体で書いたほうがうまくゆくかも知れん。
飯島 やっぱり散文はあくまで散文ですからね。だから、方法的冒険という場合、そういうテーマもかかわってくるんで、やっぱりそういうふうな羽黒山とか運慶とか、そういうものは一種のまあテーマとしてタブーだったわけですね。ひろくとってモダニズム系の詩の。そのタブーに挑んだほうがいい結果が出ると思うな。散文に書くと、なんか、やっぱり詩と違った折れ方をしてしまうから、落着いたものになるだろうけどね。でもそれじゃ、なんかいい随筆に近い、詩的随筆を読んだというふうなことになって、ちんまりおさまったら、そういう冒険ということと離れてきますからね。
吉岡 でまあ羽黒山書くならさ、やっぱり何回か参詣しなきゃいけないんじゃない。(笑)それにしちゃちょっとね。羽黒体験がすぐ出ないかわからないけど、まあそれは課題としておくよ。(「あまがつ頌」で少し試みました。)(#C_045、二○九ページ)
末尾に話者の補筆があるからといって対談の原稿や校正に吉岡の手が入っているとは限らないが、それにしても文意の取りにくい箇所がある。「ニーベルスンは〔詩篇〈雨〉にとって〕材料だったか、〔羽黒山はこれから書く予定の詩にとっては〕なんか絵具程度になっちゃうかわからないけどね」とでも解さなければ意味不明だからだ。あるいは「ニーべルスン」自体が〈雨〉にとって「絵具」だとも取れる。一体、吉岡詩には美術作品を独鈷にとったものが多いが、それが生みだす効果について考えてみよう。「老嬢ルイズ・ニーヴェルスン」とは何者か。《鰐》同人だった飯島や大岡信たちとともに〈シュルレアリスム研究会〉(吉岡はメンバーではない)の一員だった東野芳明は、一九六一年刊行の美術全集にこう書いた。題して〈奇異な女流彫刻家〉。その全文――。
「最後に、最近、急に注目されてきた奇異な女流彫刻家ルイズ・ニーヴェルスンに触れておこう。円柱、球、らせん、手すり、ハンドルなどの形をした木片をつめた木箱が累々とつみあげられ(そのひとつひとつが独立した作品でもある)、すべてを真黒あるいは真白に塗ったものが、その作品である〔挿図は〈夜のカテドラル〉1958〕。彼女はロシアのキエフで生まれ(一九○○)、五歳のときアメリカにつれてこられた。メキシコで考古学の研究をしたことがあるというが、モニュメンタルな性格は、そんなところから来ているのかもしれない。まるで鐘〔ママ〕乳洞が自然に成長するように、小宇宙の箱が見る見るうちに変形し、重なりあい、自然増殖をとげる。彼女は自分の作品を「仲介の場所(inbetween place)とよんでいる。つまり、人間の意識内部の小宇宙と、未知の大きな世界との間の、これは入口であり、門である。これはシュヴィッタースが家の三階までぶちぬいて作った〝メルツ・バウ〟を思わせる」(#B_098、九七ページ)。
ここでLouise Nevelsonのカタカナ表記を確認しておこう。Louiseは「ルイ〔ー〕ズ」で音引の有無の違い、Nevelsonは「ニー/ネ」「ヴェル/ベル」「スン/ソン」の違いがあって、これらを組みあわせると一六とおりが考えられるので、Google検索で多い順に並べてみる(検索では音引を無視して件数を表示しているか)。本篇の表記は3「ルイズ・ニーヴェルスン」で、前掲東野文と等しく、後出《みづゑ》の特集号も同じだったところを見ると、吉岡実が〈雨〉を書いたころの一般的な書き方だっただろう。
ニーヴェルスンは一九八八年四月一七日に亡くなった。八六年の埼玉県立近代美術館の〈現代の白と黒〉展には〈スカイ・ザグⅡ〉(一九七四年作)が出品されたが、残念ながら観ていない。この作品も九五×一三六×二二センチメートルの黒塗りの木片を木枠に収めた彫刻だ。同展覧会図録の略年譜から、わたしたちに関係深い事項を摘する。「ルイーズ・ニーヴェルソン――1967 回顧展(ホィットニー美術館、ニューヨーク)、グッゲンハイム国際展(グッゲンハイム美術館、ニューヨーク)。1970 万国博美術展(大阪)。1975 個展(南画廊、東京)、(クリーヴランド美術館)。1982 個展(ウィルデンスタイン東京)。1984 20世紀彫刻の展望(滋賀県立近代美術館)」(#B_047、一五四ページに拠った)。
〈雨〉執筆以前の初の回顧展(1967)の紹介記事で吉岡の眼にとまった可能性が高いわけだが、東野の文からもわかるように六○年代初頭から日本でも注目されていたから、その間の美術雑誌を博捜すべく調べた《みづゑ》の一九六二年九月号に同じ東野の〈ルイズ・ニーヴェルスン――あるいは黒壁と老嬢〉という作家論があって、これが吉岡詩のスルスであることはほぼ確実である。ただし同文が東野の《現代美術――ポロック以後》(美術出版社刊)に収められたのが一九六五年だから、〈雨〉が依ったのはこちらかもしれない。四六行めに対応する一文を引くに留めよう。――黒い塗料、あるいは最近では白、または金色の塗料をすみずみまで塗ることによって、ニーヴェルスンは、家具や自然の流木のオブジェを、一きょに、非在化する。――吉岡のこうした「作詩法」をどう考えたらよいのだろうか。吉岡詩の発表当時の美術やメディアの事情に明るい人びとには目新しくなくとも、意外なほど多くの詩行のそこここに目の怡悦が痕跡をとどめていることに、同時体験的に知らないわたしは驚くのだ。
この詩での「ニーヴェルスン」がなにかを考察して先を急ごう。それは音ではなかろうか。すなわちラ行とザ行、サ行の乱舞の誘い。「ろうじょうルイズ」「ニーヴェルスンの/すいせいの」の「スイ星」は水星ではなく彗星と読みたい。太陽の隣の惑星(Mercury)よりも「ぼやっとした淡い小さな雲のように見える天体で、数日間のうちに、夜空の星ぼしの間を動くもの」(#B_157、一一ページ)のほうが「仲介の場所(inbetween place)」を創造した彫刻家にふさわしい。いま彗星の説明を藉りた藪下信は、こう書いている。「彗星は英語ではコメット(comet)と呼ばれます。これはラテン語のコマ(coma)に由来すると考えられています。ラテン語のコマとは、女性の髪の毛のことです。たとえば、かみのけ座を表わすラテン語はComaで、これが学名となっています。彗星が髪の毛にたとえられるのは、彗星のもつ長い尾(テイル)が女性の髪の毛に似ているからです。このことからもわかるように、彗星のもっともはっきりした特徴は尾(テイル)です」(同前、九ページ)。遠く六○行めが呼応する。五行め「黄色の美人」が若い女の像として結ばれれば、二行めは文字どおりに読みすすむべきだが、文脈を読みかえると「アッサンブラージュの手法で廃品芸術をものした女流彫刻家」となる。これで「レインコートの黄色の美人」は、先行する「ニーヴェルスン」(結婚歴のある彫刻家に「老嬢」なる呼称を与えることで、吉岡は評伝的世界とのあいだに一線を画す)という固有名詞のもつ説明抜きのリアリティと対抗しうるものを有した。彼女がレインコートに身を包んでいるのは、テニスボール大くらいの雨粒を避けるためだ――三~四行めはそんな光景を想起させる。「トウモロコシ」は「黄色」から来た。「赤毛」はその絹糸を指しているか、コーカソイドの女の頭髪を二重映しにして。一九四一年の「雨にぬれた青い葦の葉/羊たちはのびたり縮んだり」(〈牧歌〉②・10)が想いだされる。一一行めの「ビニールの紐」は当時の吉岡詩の美学を如実に示している。《僧侶》の「紐」がビニール製だったと思えないだけに、こうした合成物が廃品芸術と絶妙なアンサンブルをなしている。
〈雨〉に限らず、吉岡実詩の行間は深い谷であって、そこに落ちずに稜線を伝ってゆくには相当の緊張を強いられる。一方、ごくありふれた言いまわしが夾雑物となって、詩句を読みとろうとする者を撹乱することもある。第一行の「それ」とはなにか。第六行の「だから」はなにに対してなにが「だから」なのか。吉岡自身はこうした詩句の「デコボコ」は書いたあとから操作したものではないと言うが(#C_039、一五五ページ)、天沢退二郎との対談では別様に語った。「若い人はいいすぎて落ちを作るのが多い。あれは避けるべきだと思うね。最後の二行はけずるつもりでいた方がいい」(#C_004〉、四一ページ)。ならば、最初の二行が削られなかったとどうして言えよう。
吉岡実詩はどう書かれているか。わたしの問はつねにここに立ちかえってくる。この〈雨〉にしても生原稿を見ていないので、以下はわたしの想像である。第一行から書くのだが、それが脱稿まで同一のものか。「それはたとえば/〔……〕/レインコートの黄色の美人がすきだよ」の冒頭からすでに文意がねじれていて、一読しただけでは「それ」がなにか解らないようになっているが、ここは切ったり貼ったりしたふしがある。初出形のほうが文意は通りが良かったけれども、手入れの1のごとく「ように」は削られた。「それ」を強いて言い換えれば標題の「雨」とするしかなく、第六六行のあとに第一行を繋げて円環状にしてしまえば、冒頭「それ」は五七~五八行めを受けつつ、なおのこと「雨」のように思えてくる。しかし「雨」が「美人がすき」というのはやはり妙で、本篇を語っている(作品には登場しない)人物が、ある情景を指して「それ」と称しているのか。さらに目を引くのが「箱」だ。語の繰りかえしにあれほど意を尽くした詩人が書いた本文であるからには、相応の扱いが必要だ。「箱」が直方体の立体として出現するや〈立体〉(⑦・3)が想起される。内部に「スイ星の球」が充満しているとしたら、それはなんのためにか。応えを待つ間もなく「トウモロコシ」に変貌して、一粒一粒くらいの小ささの少年が出てくる。〈劇のためのト書の試み〉(⑥・1)が不条理劇の台本(しかも台詞なし)のようだという意味で〈雨〉は映画、ナンセンスアニメのシナリオのようだ。極彩色の箱が幾度も登場する。それは大きさも、ときには色あいも変わる。吉岡はサイズや状況の混乱を、説明的にではなく描きだす。
〈雨〉はいつ書かれたのか。記録がないので前後の情況から推定するしかないのだが、一一月一日付で発行の《現代詩手帖》は一○月二五日ころの発売か。それならば脱稿は遅くとも二週間ほど前で【〈〔付録〕吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異〉の〈雨〉でも触れたが、初出誌《現代詩手帖》の編集人・八木忠栄の〈編集日録抄⑬――九六八年八月~十一月〉の「10月7日(月)」に「筑摩書房近くの喫茶店で吉岡実と会い、詩「雨」をもらう。このところ調子が悪かったというが、とてもいい作品だ。「いつも題名に困るんだ」と吉岡さん」(《現代詩手帖》2010年7月号、一五五ページ)とある】、わたしの〈吉岡実年譜〉一○月の「土方巽舞踏公演〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉を観る、土方夫人元藤燁子と初めて会う」(#A_32、二九六ページ)は《土方巽頌》の吉岡の日記に拠っているが、その一○月一○日木曜日(体育の日で国民の祝日)の全文――。
〈季刊芸術〉七号届く。「神秘的な時代の詩」掲載。夕方、陽子と神宮外苑の日本青年館へ「土方巽と日本人――肉体の叛乱」を観に行く。入り口の脇には夥しく花が飾られている。その前に繋がれた白い馬が霧雨のなかに立っていた。受付で土方夫人を呼び出し、入場料を払う。これが初対面だ。グリルで、陽子のいとこ田村紀男・朋子兄妹と、お茶をのみながら開場を待つ。そこで加藤郁乎と会った。何が始まるのだろうか、この空間では……。全裸の土方巽が金色の擬似男根を勃起させて、吊り下げられた数枚の大きな真鍮板の間を、踊り狂う。血のアクシデントを予感し、観客は興奮するばかりだ。そしてラストは、手足をロープで吊り上げられ、さながら息も絶えだえに、キリストの如く昇天する……。終演後、関係の人々と、大松寿司で祝宴となる。十一時過ぎ、飯島耕一と抜け出して帰った。(#A_24、二四ページ)
当夜の天候は「霧雨」だ。これで舞台に「箱」が登場すれば〈雨〉の道具立ては揃うのだが、そうはゆかない。残された写真や記録フィルムを観るかぎり、箱の存在を裏付けるものはない。むしろ注目すべきは真鍮板である。舞台美術を担当した中西夏之は、後年こう書いている。
「一点で吊られた真鍮の板が捩れ、廻転し、知覚・意識・意志が遠心分解する、眩暈」(#B_101、四九ページ)。「薊、猟犬、風の翻訳者、最初の花、犬の歯、犬の歯は燃えている、鐘、馬の背に蓋をするもの・鞍、共同の食事、十七歳、蛙、歯型、朝鮮薊、硫黄、回虫、笑い声、沸騰、恋の球体、トマト、大ホーズキ、朝鮮朝顔、空想的な飲物、櫛、温室、甲冑の虫、天道虫……/これらは、一九六八年「肉体の叛乱」を計画するにあたって、土方巽が最初に私に発した言葉である。薄暗い喫茶店で計画を打ち明けられ、彼が発したそのままを書きとめた。波打ち際の無数の礫群の中から拾い集めたような言葉が、彼が踊る上で最初に、励ましとして必要だったのだろう」(同前、五二ページ)。
引用した二番めは、語だけで土方世界が現前する場面だ。傍線部は当時の吉岡詩に親しい語彙である。土方巽の踊り(さらにそのことばも)こそ、吉岡が詩を書く「上で最初に、励ましとして必要だったのだろう」が、中西の次の結語ほど詩人にとっての舞踏家を髣髴させるものはない。「あの真鍮板は八丁堀の「白銅」という専門店で購入したものだが、私は土方巽にオハナシを作った。この真鍮板はこのような板では売ってはいない。球形をしていて棚におかれていた。それを私が叩きのめして真っ平らにしたのだと。真鍮の原型は球体であると。なぜなら、原型的な真鍮、原型的なもの、そういうものは無いのだが、無いものを所有できる権利をもつのは、肉体者・舞踏者のみであるといいたかったからである」(同前、五五ページ)。
吉岡の《土方巽頌》に別の所が引かれていたのは、すでに〈雨〉が書かれていたからか。土方巽の舞踏がどれほど吉岡に深甚な影響を与えたかは、出会いを語った吉岡の文章に見るにしくはない。
土方巽の舞踏詩〈ゲスラー・テル群論〉に、肉体を感じ、創造の心を、なによりもなまなましい存在感を見た。詩にも映画にも劇にもかつてない、新しい世界をかいまみて慄然とした。(#A_25、一六○ページ)
肉体を、創造心を、生なましい存在感をそこに見たそれまでに無かった世界――舞踏。舞踏に対抗しうる詩をこれからは書かねばならない。そのためにはそれまでに無い世界に自分が押しだされていったように、今度は自己の表現世界の全領域である詩をそこに押しだしてゆかねばならない。こんにち振りかえれば、土方巽の代表作となった〈肉体の叛乱〉後の吉岡は、そうした地点に立っていた。それが土方舞踏の絶頂期と重なっているのはおそるべき偶然だったとしても、わたしには吉岡実詩の前期がここで終わったように見える(「前期の終焉」についてはこの次の評釈で述べよう)。
*
吉岡詩と別の詩〈雨〉がある。北村太郎の〈雨〉を吉岡が意識していなかったか。――北村は送られた《静物》(私家版、1955)で吉岡を認めたが、二人が初めて顔を合わせたのは一九六七年で、親しく口をきいたのは一九八三年ごろだ(#A_32、二六七ページ)。――いずれにしても〈雨〉を収めた一九六六年刊の《北村太郎詩集》(#B_036)を吉岡は読んでいてよい。北村の〈雨〉は、時間的には今とやがてくる死、空間的には窓のこちらと丘のうえの共同墓地の間を埋めつくして降る。運命の象徴であろう車輪の音と雨の音は互いに溶けあい、そこに無音の世界が拡がる(最終行は、初出「春の冷酷な咽喉をさがす」から定稿「横たえた手足をうごかす」へと下降して、その感を深める)。吉岡の〈雨〉は人為的な騒騒しさに充ちているが、《神秘的な時代の詩》ではなく《静物》の吉岡が書けばこうもなろうかと思わせるのが北村の〈雨〉だ。一体に吉岡は固定的な語り口に陥ることを嫌った。戦後初の詩集《静物》は紛れもなく吉岡の声を響かせてはいるものの、《僧侶》に三好豊一郎の影響を指摘する者もあって、それは北村自身だった。「彼の出している残酷さ、性的なもの、矛盾、醜悪だとか、暗い中のすばらしい美しさだとか、そういうもののイメージは、あとの吉岡さんを予告するように非常に苦労して書いてると思いますよ。だけどこの一篇ということで〔〈死児〉を〕出した意味を考えると、どんなに言語世界だ、抽象の世界だと言っても、ちょっと本音が出てるという感じがするね。〔……〕ただ、言葉の使いかたやリズムということになると、三好豊一郎と田村隆一の影響がそうとうあるんじゃないかなという気がしましたね。とくに三好の詩をそうとう詳しく読んでるんじゃないかなという気がしましたね」(#C_009、一〇四ページ)。三好や田村、北村たちが《荒地》に発表した作品は、ただひとり詩を書きすすめていた吉岡の導きの星ではなかったか。
*
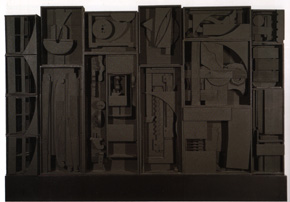
ルイズ・ニーヴェルスンの黒く塗られた木〈無題〉(1959) 230.0×376.0×32.0cm(セゾン現代美術館)
出典:http://www.smma-sap.or.jp/col2-8.htm
Ⅲで紹介したかったのだが、ニーヴェルスンの「スイ星の球のつまった/箱」が確認できない。国内美術館所蔵品で吉岡が実物を観たかもしれない作品も特定できないし、詩篇発表当時の美術雑誌のそれらしい図版も見あたらない。〈雨〉全行の平面性は、同年のビートルズのアニメーション映画〈イエロー・サブマリン〉に通じるし、ジョゼフ・コーネルのオブジェによる紙芝居の懐かしさから遠くない。入沢康夫は《神秘的な時代の詩》の作風を「もっとも私には、〔渋沢孝輔が指摘する〕「疾走感」「浮力」といふよりも、エナメル絵風の全体的な「平板化」が気になった。あるいは、同じ印象を違う言葉で表現してゐるだけかも知れないが」(#A_18、一四三ページ)という評言で要約したが、「エナメル絵」とは言い得て妙だ。吉岡の詩が《静物》と一九五八年の《僧侶》で「文学」(密室での作家の孤独の営み)を究めたとすれば、一九六二年の《紡錘形》とこの年一九六八年の《静かな家》の二詩集は、清岡卓行がかつて「ぼくの言う抛物線の下降のカーヴは、詩の教会の懺悔聴聞僧にも似た吉岡実が生活へいわば遣俗する過程をかたどるものであり、かつてその上昇のカーヴが孤独に支えられていたのに対し、今度は家庭をはじめとする連帯に支えられているようである」(#B_040、二八○ページ)と評したように「文学」との乖離だった。「同時にあらゆる記念碑の土台の大理石が食違う」(〈巫女――あるいは省察〉⑤・14)。詩人は「エナメル絵」ふうのアッサンブラージュの世界とでも呼ぶしかない場所へと転進したのだ。
*
「パラシュート」(四八行め)の登場は唐突に感じられた(土方巽の舞台姿をほのめかしたのか)。パラシュートすなわち落下傘で、雨と傘は付きものだという程度でお茶を濁していたところへ、有力な傍証が現れた。三陽商会会長の吉原信之氏が〈創業のころ〉という新聞のコラムに書いている(見出しは「落下傘用絹布をレーンコートに」)。戦後、米軍の飛行機の防弾用ゴムからゴムまりを製造して好評だったが、「そのうち原料が尽きてしまい、また仕事がなくなった。ところが今度は落下傘用の絹布が手に入り、生地にオイルを塗って女性用レーンコートを作ってみた。それが大いに当たった」(#C_025、一四面)。これで黄色だったら面白いのだが、残念ながら色には触れていない。黄色のレインコートは当時もあっただろうから、吉岡の「パラシュート」の背後にこうした事情を考えるなら、「黄色のレインコート」とは戦後の女のお洒落なような実用的なような、妙に苦みのあるファッションだった。
*
〈雨〉を吉岡の詩論として読む、頻出する「箱」こそ原稿用紙の桝目のアナロジーだと。箱と桝と桝目はそれぞれ重なりつつずれる。吉岡が自身の創造に思いを巡らすとき、原稿用紙と筆記具なしに「具体性のある物」を想起することはできないが、当時の吉岡が詩篇に「筆記具」だの「原稿用紙」だのと書くことはありえない――とすれば、あたかも禁忌を破るように自身の創造に言及しても不思議ではない。そのとき箱はほとんど柩である(最近では辻井喬の長篇詩《群青、わが黙示》(#B_094)のⅡ〈ブラウン管上のゲーム〉に柩としての箱が登場する)。土方巽の〈肉体の叛乱〉の六枚の真鍮板が、解体された箱の上面や側面や底面に見えたかもしれないし、真鍮板自体が原稿用紙の「白紙状態」(#A_25、八七ページ)と映ったかもしれない。箱は、そこに詩が充満した/詩を充填すべき空間だったか。さらに〈雨〉を造形用語で綴られた試論であると考えてみる。三一~三三行はルネ・マグリット、四九~五二行は川上澄夫、六一~六二行はハンス・ベルメールの作品か。五三~五四行からは吉岡も通っただろう神保町の喫茶店さぼうる店頭のトーテムポールが想起される(ニーヴェルスンにもトーテムポールの連作がある)。加えて箴言ふうの詩句。A=(一一~一三行)。B=(三一~三三行)。C=(四二~四五行)。どれも彫刻家の創作ノートに書かれていておかしくない。Bの「罪ぶかい行為とは空間を穿つこと/関係のない物体や言葉を/同次元へ置くこと」は〈雨〉を離れても吉岡の詩論・断章として通用するだけあって、多くの評家が好んでここを引用している。そして、Cの初出への手入れはこうだった(Ⅰ参照)。「老人になる日まで永遠に/にがにがしく〔スパイとして→(トル)〕/具体性のある物をつくり/肉色の箱を担いで歩く」。
*
各詩篇の評釈を書くにあたって、短い詩なら諳誦できるようになってから、吉岡の全詩篇と《「死児」という絵〔増補版)》を読みかえすのを常としてきた。吉岡はほかの所で「スパイ」と書いたことはなかったし、捕物帖はともかくスパイ小説を愛読していたとも思えない。と書いて、モームの名前を忘れていたことに気がついた。サマセット・モームの《雨》は中野好夫訳の岩波文庫が一九四○年に出ているが《うまやはし日記》には見あたらない。中野は一九五九年に新潮文庫から再刊するにあたって書名を《雨・赤毛――モーム短篇集Ⅰ》としたから、吉岡の記憶のどこかで「雨→赤毛」の連想が働いたかもしれない(これらに一九六二年刊の朱牟田夏雄訳の岩波文庫版《雨・赤毛》を並べて、吉岡がどれかを読んだかを忖度しても虚しいだろう)。その「スパイ」だが、モームには《秘密諜報部員》(原題は主人公の名の《Ashenden》)がある。その目次を見て考えてしまった。全一六章のうちに「老嬢キング」「髪の黒い女」があるのだ。詩句との類縁は紛れもないが、「雨―赤毛―スパイ―老嬢―黒髪」と続くモーム的展開を断ちきるために「スパイとして」を削ったと方向づけるのもぞっとしない。偶然にすぎまい。ところで、短篇作家としてモーパッサンを良しとするモームは、もう一方の雄・チェホフ派への皮肉のように書いている。「それ〔スパイとしての自分の働きのなんたるか〕はちょうど、なんのつながりもないいくつかの挿話[エピソード]を読者のまえに投げ出して、さあひとつ、自分でこれをつなぎあわせて、まとまりのある物語を構成してみて下さい、というタイプの現代小説に似て、まことに素っ気ないものだった」(#B_152、一六ページ)。吉岡が《秘密諜報部員》を読んで共感したとすれば、チェホフ派の「現代小説」のようにして詩を書くことの方だったのではないか。
*
前作まで登場していた「矢印」が〈雨〉に出てこないのをどう考えるべきか。後の〈示影針(グノーモン)〉(⑧・27)の冒頭をもじれば「矢印は消え失せ/はしなかったけれども/もう二度と姿を現わしはしなかった/現われて出てくる/やいなや/矢印はすぐさま形態を/なくした」。〈わたしの作詩法?〉(一九六七年二月発表)を読みなおすと、こんな箇所にぶつかる。「わたしはそれらの方向へ一つの矢印を走らせてその詩的作品の最後を飾るだろう。詩は小さく結実してはつまらない。詩は他の次元へまで拡がって行くべきだと思っている」(#A_25、八八ページ)。矢印なしでは「詩的作品」は「詩」になれないような書き方である。詩句展開の手探り状態は〈崑崙〉以来、哀えるどころか加速された。「矢印」の語こそ見えないが、力学の合力としての矢印は、ある。分力は本稿で述べてきた固有名詞と造形作品だ。だが、吉岡は矢印を分解することで固有名詞と造形作品を獲得したのではない(現に〈青い柱はどこにあるか?〉には「ハンス・ベルメールの人形」と「黄いろの矢印」が出ていた)。矢印の担っていた機能がふたつに分岐したというよりも、矢印は遍在することで見掛け上は消失し、結果、作品内部の圧力が高まったのだ。おのおのの詩句が見えない矢印を合力とすべく、海胆の棘とげになろうとする。
*
こうして「踏台」のような一九六八年が過ぎて、吉岡実はその前期を打ちあげた。
「私はねあの――私は少女だわ」とアリスは申しましたが、その日はずいぶん幾度も変ったのを思いだして、あやふやな調子でした。――ルイス・キャロル(#B_038、五九ページ)
「少女らは五月の胸を高くゆく〔……〕
「少女らは」は、昭和十四年三月号〔《旗艦》誌〕の「輪型陣」に入選した作品。吉岡は、昭和十四年五月七日の日記に次の「春雨や〔人の言葉に嘘多き〕」の句について「たわむれに出した句が掲げられてあり、驚く」と記すが、掲載誌は五月号であり、最初に「旗艦」で活字になったのは、「少女らは」の句であった」(#C_046、六○ページ)と宗田安正が〈「吉岡実句集」解題〉で書いている。一句は吉岡が、皚寧吉名であれ、世に問うた最初の作品だろう。「五月」が前年の昭和一三(一九三八)年なら、当時の勤務先の医学出版・南山堂に初めて入社した女子社員中村葉子や古川英子の姿か。中村葉子の生年等は未詳だが、一九歳の吉岡から見たおそらく一七歳は、少女だ。恋しい者の姿をとどめおくことは、創作者の最も根源的な欲望である。
今日の吉岡詩の読者であるわたしたちは「白馬を少女涜れて下りにけむ」(《旗》#B_048、一一ページ。初出は昭和一一年)の西東三鬼の「おそるべき君等の乳房夏来る」(《夜の桃》同前、八○ページ。初出は昭和二一年)や「少女二人五月の濡れし森に入る」(同前、九三ページ)を想いうかべるが、吉岡の句には作中の少女のういういしさに見あう少年の作者のそれがある。三鬼は一九六二年四月に亡くなっており、吉岡はそれに先立って、同年一月号の《俳句》に次のように書いた。
「大岡信から西東三鬼と富澤赤黄男の両氏が大病だといわれた時、私はたいへんな衝撃をうけた。敬愛するこの二人の創造活動が一時なりにも停止し、また再起できないようであったら、俳句界のためというより、むしろ私のために痛恨事である。久しい間、私は両氏の近業をまとめて読むことを切望していたから」(#A_25、一○九ページ)。
三鬼の三句を含む句集《夜の桃》については、一九六七年五月一三日の吉岡の日記「K書店で三鬼の『夜の桃』をみつける。阿部青鞋句集など買う」(同前、一二ページ)がその敬愛ぶりを物語っている。いずれにしても頭書の一句は、作品以前に恋しい者の肖像だった。さらに二一歳の吉岡には次の少女の一首があって、偶然だが《不思議の国のアリス》の結末に酷似している(《アリス》にはⅢでふれよう)。「軽井沢/夏野ゆく金髪少女の横顔を/かすめる影あり落ち葉なりけり」(#A_01、五二ページ)。
詩篇〈面紗せる会話〉(①・12)は次の二点で当時の吉岡詩と異なっている。一、複数の女の対話を叙したスタイル。二、句跨りの多用。《昏睡季節》の代表的な作風は、全体を統べる立場で書かれている一群のものだ。吉岡が随筆で紹介している〈春〉〈夏〉〈秋〉〈冬〉〈白昼消息〉〈昏睡季節2〉(①・1、2、3、4、10、20)などがそれである。一方で「私」が女の〈遊子の歌〉や「きみ」への呼びかけの〈あるひとへ〉や短歌の叙情に類する〈断章〉や旋頭歌三首に等しい〈葛飾哀歌〉(①・5、8、14、15)というぐあいで「二十篇の文体に統一なく、まさに雑多」(#A_25、七六ページ)と吉岡が慨歎するのも無理からぬものがある。
そうしたなかで〈面紗せる会話〉は軽いスケッチふうでありつつ、極度の手入れの挙げ句に成った作品には見られない部分が印象的だ。初出の《昏睡季節》が和紙の袋綴じであるため、一一行めと一二行めの間に一行アキがあるのか、丁の替わりめと重なっていて判別しにくい。行アキがあるとして、女が二人(AとB)だと、
A・一~五行め(五行分)
B・六~一一行め(六行分)
A・一二~一六行め(五行分)
B・一七~一九行め(三行分)
という対話が本文となる。初刊以後、半世紀以上も活字化されなかった作品だが、論の展開上、引用しておきたい。
面紗せる会話|吉岡実花びらのうへに死んでゐる指のあとを 1
見ると あたし泣けるの 2
銀の針で その背後を失つた哀れな人を 3
女のやはらかな耳朶から 4
ほりだしたいの 5硝子のやうにたのしい触手をもつ 6
あたしたちよ あなたの泪が靴の裏で 7
汚れるわ 十字架の蔭に 鼻孔をひろ 8
げる喪服の男のことなんか ぬれてゐる 9
樹液の香を唇にぬつて 忘れなさいな 10
紅の茸は湖のほとりに 咲いてゐるわよ 11蒼黝い幹の疣に 夕ぐれを巻き 12
つけ 黄色の布と 13
距離のない春の光線を 14
明日の虹の流れへ すててきて 15
あきらめるわ 16空をとべない風より 草むらに 17
墜ちてくる星を拾つて 掌の上にのせて 18
あたためませう 19
女A・花びらのうへに死んでゐる指のあとを見ると、あたし泣けるの。
銀の針で、その背後を失つた哀れな人を、女のやはらかな耳朶からほりだしたいの。
女B・硝子のやうにたのしい触手をもつあたしたちよ。
あなたの泪が靴の裏で汚れるわ。
十字架の蔭に鼻孔をひろげる喪服の男のことなんか、ぬれてゐる樹液の香を唇にぬつて、忘れなさいな。
紅の茸は湖のほとりに咲いてゐるわよ。
女A・蒼黝い幹の疣に夕ぐれを巻きつけ、黄色い布と距離のない春の光線を明日の虹の流れへすててきて、あきらめるわ。
女B・空をとべない風より、草むらに墜ちてくる星を拾つて、掌の上にのせてあたためませう。
記述の形態を改めると、一と二の特徴はいっそうはっきりする。妖精劇の台本のようだ。案外、浅草あたりの舞台の印象が反映しているのかもしれない。ただそれも文末の女言葉調によるのであって、それらと「あたし」「あなた」を隠してしまうと、どこが「会話」なのかわからなくなる。「花びらのうへに死んでゐる指のあとを/見ると 泣ける/銀の針で その背後を失つた哀れな人を/女のやはらかな耳朶から/ほりだしたい」では、作品は単一の構造へと変わるのだ。
ギヨーム・アポリネールの詩集《カリグラム》に、のちに「会話詩」と呼ばれることになる詩篇〈月曜日、クリスチーヌ街〉がある。ピエール=マルセル・アデマによれば「詩における絵画的な同時性のこの採用」「一見無秩序に見える、イマージュの、表現の不調和音にまで達する詩」「アポリネールの〔……〕もっとも貴重な理論のひとつ、驚き、の応用を追求する意識的な気持の証拠」(#B_003、二六三ページ)たる会話詩。アポリネールは〈月曜日、クリスチーヌ街〉で「人いきれのむんむんするホールの正確な印象を、カンバスに再現したいと思って、あるカッフェに入ってゆく画家の、直接のヴィジョンの詩的な絵に絵筆を振っている」(同前、二六三~二六四ページ)。周辺のリリスムの記録にとどまらず、視覚の同時性の追求が「会話詩」なら、後年〈わたしの作詩法?〉で開陳されることになる吉岡の詩法との類縁がここに見られる。そうした観点から〈面紗せる会話〉を読みなおすと、会話を叙しているように見えながら、詩が成立する磁場を形成する意識が鞏固にある。このとき、会話とはなにか。凝縮しようとする詩的磁場に他者の話し言葉を導入することで、世界を押しひろげようとしているかのようだ。
《昏睡季節》以来、吉岡は原則的に単行詩集にあとがきを付けなかったし、詩の自解的な文章も残さなかった。ましてまとまった形でその詩集観を披瀝しなかったから、次の〈高柳重信断想〉は貴重だ。「重信はなぜか、新しい句を注入し、句集を編み替え、増殖させ、一つの『作品集』を構築しているのだ。作者の必然的な営為として理解できるが、一読者としてどうも読みにくく感じる。私は反対に『詩集』は一巻で完結するように、試みているから、なおさらなのかも知れない」(#A_25、三一七ページ)。
その吉岡が詩歌集《昏睡季節》の和歌作品だけを抽出して歌集《魚藍》の題で一書と成したのは、同集の他の詩篇を抹消したいとする「作者の必然的な営為」である(私が〈面紗せる会話〉を引くのにためらいを覚えたのはそのためだ)。《うまやはし日記》一九三九年九月には「歌集『蜾蠃[すがる]抄』を出したいと思う」、一一月には「いつか句集『奴草』を編みたいと思う」、そして一二月には「処女歌集『歔欷』と決める」(#A_27、七四、八七、一○三ページ)とあって、詩歌句をほぼ同時平行的に書いて、それぞれの集を構想している(実現したのは《昏睡季節》に収めた和歌集だけだが、ジガバチの古称スガルは、細腰の少女がスガルオトメに喩えられるように、そのテーマは少女だ)。
この時期の吉岡は、失恋の痛手もあって南山堂を退き、来るべき召集を目前に作品を書かずにいられない状態だった。充分とは言いがたい文学的素養と永くはない自身の生涯を基に、いかに作品としてまとめあげるかに最大の関心があるとき、三つの詩型の選択など重要ではない。詩歌句をそれぞれに吉岡実が必要としていたのは《昏睡季節》ほかに見えるとおりだ。後年の作者が最初期の作品として認知したのは短歌であり、吉岡の出発は短歌である。
吉岡実における詩歌句の合金状態は、一年あまりのちの紛れもない詩集《液体》で終わりを告げる(〈相聞歌〉(②・11)の〈反歌〉に「横顔を 魚族よぎれば 胸廓の/花くづほれぬ 君よいづこに」があるが)。戦後も散発的に書かれた俳句に対して、短歌はこのあと発表されることはなく、ようやく吉岡実最後の、そして最大の巨篇において自身の詩的決算のように、墓碑銘のように登場する。「ひさかたの/天の奥処ゆ/日の照れば/さはに/利鎌にさ渡る鵠」(〈聖あんま断腸詩篇〉⑫・12〈Ⅵ 挽歌〉の〈反歌〉)。まさしく《古事記歌謡》二七を踏まえた「白鳥の歌」であろう。
詩歌句の少女体験の劈頭が中村葉子だとすれば、続いて二○歳台前半の兵士吉岡実を震撼させたのが支那の娘、満洲の黒衣の少女だった。
「或る別の部落へ行った。兵隊たちは馬を樹や垣根につなぐと、土造りの暗い家に入って、チャンチュウや卵を求めて飲む。或るものは、木のかげで博打をする。豚の奇妙な屠殺方法に感心する。わたしは、暗いオンドルのかげに黒衣の少女をみた。老いた父へ粥をつくっている。わたしに対して、礼をとるのでもなければ、憎悪の眼を向けるでもなく、ただ粟粥をつくる少女に、この世のものとは思われぬ美を感じた。その帰り豪雨にあい、曠野をわたしたちは馬賊のように疾走する。ときどき草の中の地に真紅の一むら吾亦紅が咲いていた。満人の少女と吾亦紅の花が、今日でも鮮やかにわたしの眼に見える。〔……〕反抗的でも従順でもない彼ら満人たちにいつも、わたしたちはある種の恐れを抱いていたのではないだろうか。〔……〕彼らは今、誰に向って「陰惨な刑罰」を加えつつあるのか。/わたしの詩の中に、大変エロティックでかつグロテスクな双貌があるとしたら、人間への愛と不信をつねに感じているからである」(#A_25、九三~九四ページ)。
唯一の詩論ともいうべき文章〈わたしの作詩法?〉の末尾に吉岡がこの挿話を登場させている意味は大きい。
・半病人の少女の支那服のすそから/かがやき現われる血の石(〈珈琲〉⑥・3)
・ぼくがクワイがすきだといったら/ひとりの少女が笑った/それはぼくが二十才のとき/死なせたシナの少女に似ている(〈恋する絵〉⑥・15)
・コルクの木のながい林の道を/雨傘さしたシナの母娘/美しい脚を四つたらして行く/下からまる見え(同前)
これらの詩句に黒衣の少女が投影されているようでならない。ここで高橋康也の顰みに倣って《静かな家》の「少女・処女・姉・妹」を見れば、共通の特性、すなわち生理中だったり、病人だったり、死人だったりする少女の姿が容易に読みとれる。
・妹・月経帯が大きくてキララいろ
・妹は火山口のような水洗便所のふちで
・妹《わたしは飢えているわ》
・兄妹はレンガの上に腰かけ
・兄妹立ちあがる未来の形で
以上〈劇のためのト書の試み〉(⑥・1)
・少年少女の心中死体が導火される
・一人の美しい裸形の少女のトルソの二叉
以上〈無罪・有罪〉(⑥・2)
・死んだ少女の股までの百合の丈
〈模写――或はクートの絵から〉(⑥・4)
・まして少女のうぶ毛の口のまわりを
・血のうえに母と妹をカモメのように
以上〈やさしい放火魔〉(⑥・9)
・犯された姉のたらしている繃帯
・凍る都会の学校で/孔雀の母をころして/ひとりの少女が歩いてくる
・少女の雨傘
以上〈春のオーロラ〉(⑥・10)
・天然色の処女の肉体は
〈スープはさめる〉(⑥・11)
・少女を絞め殺すべき契約を欲する
・かれらの妹の植物化した直腸の液
以上〈内的な恋唄〉(⑥・12)
・少女の脱脂綿にふれたくなる
〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)
吉岡の「シナ詩篇」の究極に《サフラン摘み》の〈生誕〉(⑧・10)が来る。ここでも詩人は「人間への愛と不信」を変奏している。
生誕|吉岡実横板の上に支那服の上半身をのぞかせ
一人の男が祈っている
手を組み合せて
半数の爪は黄色い木片のようだ
かたわらの毛布の下に横たわっているものが
その妻かも知れない
大きな口のなかで鋸歯を挽く
膿の花をところどころに染めて
包帯がその琺瑯質の太股を
遠くから巻いてくる
傷つく母なる声
支那服の男の裾は遥かなる闇へ拡っているようだ
竜や香華の紋章をつけた
朱塗りの太い柱の方へ
そこだけが明るく
男と女のまわりは停止しているのに
回転している壺やナツメの実
よく見れば
一人の男が生れつつある
少女そのものはいかがわしくも清らかでもないが、すでに見たように吉岡の詩では清らかゆえにいかがわしい、とでも言うしかない役割を負わされてきた経緯がある。ここで、吉岡実詩のいかがわしさを考えたい。それはきわめて重要な問題だ。大岡信や入沢康夫も述べたように(#A_32、三五ページ以下)、吉岡は自身の詩につねにいかがわしさを要請していたのではないか、あたかもそれが人間の生の本質であるとでも言うように。そんなふうに思えるくらい吉岡の詩は、この〈少女〉にしたところで、公然と読むのをはばかられる部分がある。朗読するときの衝撃を想像すれば、私のいわんとすることが理解してもらえるだろう。まだ《静物》はそれほどでもないが、《僧侶》以降は言うもおろかである。そこに戦争と恋愛の影は容易に想像されるが、吉岡実個人の、あるいは吉岡実詩のいかがわしさというよりも、わたしたちの生がそのようであるということかもしれない。いかがわしくない生がかつて存在しない以上、いかがわしくない詩が意味を持つはずもない。吉岡実詩の身上はそこにある。
〈少女〉〔初出形〕四五行→〔定稿形〕四二行客観的状況で
塩がほしい〔のよ!→(トル)〕
ぬれたハイヒールをさかさまにして
その尖筒を〔(ナシ)→機関手が〕なめるとき
晩夏の街には〔(ナシ)→セーラー服をぬいだ〕どんな〔モモイロの→(トル)〕少女がいるのか?
言葉を犯罪的に使って
紅色の闇へ
イタリア貂を狩りに出る
ぼくたちにとって〔(改行)
→(追込)〕死はとりとめもなく
自動ドアを入る
肉をラセン巻きにするガードル〔(ナシ)→に沿って〕
まばゆい丘の上〔で→に出ると〕
馬の交尾
その影のしていることが
暁の彫刻〔?→である〕
血豆の大理石〔(ナシ)→の頂で〕
マンダラ模様の〔千羽鶴→夢をはらみ〕
そこから少女は成長するんだよ
樹と外套でかこわれて
〔少女の夢のはらみ方→(トル)〕
〔すきなエクレヤ→(トル)〕
ブルガリヤ人の男根〔(ナシ)→は立ち〕
〔(ナシ)→孔雀の羽は散乱する〕
きわどいレールを
バクシンする蒸気機関車が正面から〔(改行)
→(追込)〕入ってくる〔!→(トル)〕
呻きの乳色の霧〔(ナシ)→の彼方より〕
まるで虎刈りの老人がきた〔のよ→(トル)〕!
ほそいほそい靴下をぬぎながら
口をふさいで
血の波紋の少な〔くな→(トル)〕い世界へ
〔毛の→夜光〕捕虫器かざし
〔モモイロの→ヒルガオの咲く〕柵に
だんだんよりかかる
だんだん裂ける
蜜房はなぜいつまでも〔黄色→暗〕く苦く
夕陽のように
一つのゲーム〔の→を〕終〔り→らせるんだ〕
浴室で裸になって
今宵から花嫁たらんとする
心なき少女の自己誘拐
〔(ナシ)→それは〕ぼくたちにとっていかなる痛みの〔(追込)→(改行)〕〔ビラン→六面〕体〔(ナシ)→の鋲〕であるのか?
〔声する恋の夕暮れの→(トル)〕
家のなかで顔を巻く包帯をとけ!
格子が見える
吉岡の詩篇〈少女〉(⑦・5)は責任編集・澁澤龍彦、美術・堀内誠一による「エロティシズムと残酷の綜合研究誌」《血と薔薇》(天声出版)第二号(一九六九年一月発行)に巻頭作品として掲載された。種村季弘の評伝が当時の澁澤を要約して、余すところがない。「大まかにいえば、澁澤龍彦の六○年代はサド裁判(昭和36〈一九六一〉)にはじまり、三島由紀夫割腹事件(昭和45〈一九七○〉)をもって終わる。五○年代末に澁澤龍彦に注目した二人のうち、一人はサド裁判で六○年代の幕を開け、もう一人は自決によって六○年代の幕を下ろした。そしてこのイデオロギー的には極左と極右、時代状況的には始まりと終わりの限界のなかに、両極限にひとしく触れながら、いくつものグラデーションにおいて彼の未知の細部を引き出す編集者に囲まれて澁澤龍彦がいた。けれども六○年代も末期に近づくと彼自身が編集者となってネガをポジに逆転し、時代の代表的な才能を発掘蒐集して、博物誌家のように六○年代の奇妙なコラージュを合成しはじめる。それが澁澤龍彦責任編集による雑誌「血と薔薇」である」(#B_085、四九ページ)。
ところで後年、吉岡が澁澤のために書いた詩〈示影針(グノーモン)〉(⑧・27)の鑑賞で高橋睦郎が「作者と澁澤龍彦の出会いは一九六六年発行の加藤郁乎句集『形而情学』の新橋なだ万での出版記念会のおりだった。彼が自分を評価してくれていることを知って以後急速に親しくなった、と作者はいう」(#A_23、一一九ページ)と書いているが、これは澁澤ではなく土方巽との出会いだろう。吉岡が日記に「〔一九六○年〕四月六日 渋沢龍彦夫妻とお茶をのむ。マルロー《王道》」(#A_10、一二三ページ)と書いているからだ。記述の調子からも初対面ではなさそうだ。澁澤は一九五八年の一月に伊達得夫の書肆ユリイカからロベール・デスノス著《エロチシズム》の訳書を出版しているから(吉岡の《僧侶》は同社から一○カ月後に刊行)、このあたりで面識があってもおかしくない。吉岡の日記の翌日に澁澤訳のサド《悪徳の栄え 続》が発売禁止処分になっているのには驚かされる。吉岡はこの騒ぎから、自身のいわゆるH賞事件を思いだしていたかもしれないが、閑話休題。
詩篇の原稿依頼がいつだったか、公刊された資料からではわからない。澁澤が《血と薔薇》に参画したのは一九六八年六月ころからだというから、それ以降を見てゆくと、
・七月三日 芦川羊子処女公演〈常に遠のいてゆく風景〉
・八月三一日 笠井叡公演〈稚児之草子〉
・一一月二三・二四日 土方巽の詩画集《あんま》制作
の吉岡の日記(#A_24)に澁澤が登場するが、対面時に依頼されたかは読みとれない(芦川の公演タイトルは、澁澤が中村宏画集《望遠鏡からの告示》(#B_107)に寄せた序文〈つねに遠のいてゆく風景――中村宏のために〉から採られており、むろん澁澤は吉田一穂の詩篇〈母〉に拠っている。舞踏と詩や文学のタイトルの貸借関係はしばしば見られ、土方巽も吉岡から《静かな家》を借りているし、吉岡も土方をはじめとする舞踏家に捧げる詩の題名に多くその代表作を藉りている)。
それはさておき、前号の《血と薔薇》創刊号は〈第2号予告〉で「12月1日発売予定」と謳っているから、詩画集《あんま》制作時では遅い。しかし「(一部交渉中を含む)」の但書にもかかわらず予定執筆者に吉岡の名が挙がっていないのは、巻頭掲載の厚遇とは矛盾していて、よくわからない。いずれにしても執筆当時の吉岡と芦川、笠井、澁澤、中村、土方らが、《血と薔薇》や《あんま》を通じて、しばしば顔を合わせていた事実はまぎれもない。いま考えてもなにやら異様に熱気をはらんだカオスである。吉岡が《あんま》に寄せたのは一九六七年に土方に捧げた〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)の再録で、著術家・澁澤や舞踏家・土方が出版人・吉岡に原稿依頼をすること自体、まさに「奇妙なコラージュ」であり、そうしたウロボロス的状況こそこの時代ならではのものだった。
00 〈少女〉
吉岡実の題名における普通名詞への偏愛は健在だ。
八木忠栄の〈桃をのぞく〉はその副題に「吉岡実の詩行を核に、少女へ」とあるように、特異な少女論であり、吉岡論でもある。〈少女〉の05行「晩夏の街にはセーラー服をぬいだどんな少女がいるのか?」を標題に戴く節は、全文を引くに如かない。
「猛暑の夏中、塩をほしがって赤目をむき出しにしたり、舌をだらありと垂らしてみせたり、なかなかロシア人顔負けの芸人だったよ、あんたは。
「塩がほしい」「塩、ほしい」
なんてきれいな声なんだろうねえ。
初夏から晩夏へ、股ぐらにガキどもぶらさげてひとっとび。産みの親になんぞ、とてもじゃないけど、お見せできるような絵図じゃないんだよ。
〈虎刈りの老人〉が太鼓腹を叩きながらわめきちらしているじゃないか。「ロシア人またはブルガリアの男根どもをして、塩の山を運ばしめよ!」
まったくひどい街だ。血のつまった西瓜を闇夜の格子に吊るして、眼をぬぐう。すると、猫の分娩がよく見える。少女のうなじをべたべた舐めまわしながら、眼をこらす。とてもいいことだ。地上では信じがたい事件が目白押し。なんてきれいな声なんだろうねえ。
〈ガニ股の父が好き〉
〈心中した姉が好き〉
そんなことをしおらしくつぶやきながら、少女は成長するのさ。おそろしい勢いで〝女〟が萌え出してくる。ときとして、ロシア人の男根ひっこぬき、ブルガリアのヨーグルトをかきまわしかきまわしして、少女はずんずん成長するんだ。たまらないよ、そりゃあ。
〈ガニマタノ、チチガ、スキ〉
〈シンジュウシタ、アネガ、スキ〉
脱ぎすてられたセーラー服をくわえて、街を駆けずりまわる三本足のイヌ。イヌめ! 塩をほしがったあげくに、あんたにやれることといったら、そんな胡散くさい芸当さ。ああ、なんてきれいな声なんだ。私たちはやっぱし狂っちまったのかしら?」(#B_030、八五~八六ページ)。
実在の人物として吉岡実の周囲にあった少女に、一九六七年一九歳の金井美恵子がいる。吉岡は太宰治賞応募作品のなかから金井の小説〈愛の生活〉を認めた。のちに〈少女・金井美恵子〉で出会いの様子を書いている。
「或る日〈展望〉の編集者が私を呼びにきた。殺風景な社の応接室で、金井美恵子とはじめて会った。プロフィール用の写真を撮りにきたのですと、この可憐な少女はつぶやいた。近くの白門という喫茶店で改めて少女を見た。高崎から来たというのに、近所を歩くような普段着といってもよかった。デニムのスラックス姿で、なによりも印象的だったのは、子供が持つ赤い麦藁の小さなハンドバッグを持っていることだった」(#A_25、一九六~一九七ページ)。
吉岡がさして長くもない随想で全篇引いているのが金井の詩〈ハンプティに語りかける言葉についての思いめぐらし〉であることや、プロフィールの写真撮影とくるあたり、いやでもアリスやルイス・キャロルの世界を連想してしまうが、それらについて吉岡が書きはじめるにはあと数年待たなければならないし、いくら金井が若いとはいえ〈少女〉のころには成人しているわけで、モチーフを彼女やあるいは別の周辺の人物に特定するのは見当外れであろう。ならばそのモチーフとはなにか。ひとことでは言いつくせなが、この一九六九年に満五○歳を迎える吉岡にとって「老い」たる男と「若い」女の関係は、実生活においては知らず、詩のテーマとして不足のない設定ではなかったろうか。それかあらぬかのちに吉岡は詩〈聖少女〉(⑦・10)の第一行を「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!」と始める。
01 客観的状況で
この、次行へ突入する感覚、口のなかでもつれる感じのやや速いワルツは、文脈のどこにも落ちつかないような、題名との裂け目を露出しながら、犯罪の予感を立ちのぼらせる。「状況証拠」を想起させるゆえだ。あるいは、以下の言説が恣意ではないという前振りを兼ね、そう見れば発声もわりあいにフラットである。だが詩句はまだなにも明示しえず、画布の下塗り的効果にとどまる。一方で「詩的な言語」の混入を拒む姿勢は明白であり、詩句の短さからは詩篇がはらむある種の深刻さ(といってもこの行の段階ではジグソーパズルの一ピースだが)が感じられる。
02 塩がほしい
・造られた塩と罪の清潔感!(〈恋する絵〉⑥・15)
「太平洋戦争末期に中国の洛陽近くで作戦を展開した日本軍は、戦争に倦きて士気が低下していた。第一線はともかく、留守部隊では花札賭博にふけるものが出るしまつで、「朱家埠事件」というのが発生した。宮崎隆氏の『憲兵』によると、兵隊たちが賭博の張り金にしていたのは、第一線の兵士が血と汗の結晶として得た戦利品や、現地調達の塩を売った代償の金だったという。賭けにふけっていた一兵隊の捨て台詞に、「塩を売りさえすれば金は無尽蔵だ」といったことも記されている」(#B_124、二五○ページ)と平島裕正の《塩》にある。
03 ぬれたハイヒールをさかさまにして
以下は河上治の〈ハイヒールへの旅、ハイヒールの歴史。〉に依りながら書くのだが、ハイヒールが成立したのは一六世紀後半のルネサンス期。高く重たかったチョンピン(中近東の木台サンダル)がヒールの付いた男性用のブーツスタイルの乗馬靴と合体して、今日のハイヒールの原形が出現した。ちなみにヒール靴を最初に履いた女性は、カトリーヌ・ド・メディチとエリザベス一世という「女王様」だと記録にある。背の低さをカバーするためルイ一四世が履いたくらいで、当時は男女兼用靴だった。その後、男たちは機能的なヒール無しに戻ったから、ハイヒールは女たち専用の靴になり、一八世紀には底がゆるやかなS字曲線を描く今日的なデザインの靴が登場した。フランス革命後のブルジョワの擡頭で機能性が追求された結果、素材・加工技術・デザインは飛躍的な向上をみてハイヒールはほぼ完成し、一九世紀後半には記号としての意味を持ちはじめた。「脚を出す彼女達〔娼婦や酒場の女達〕にとって、ハイヒールは魅力的に脚を演出させる小道具だった。それはハイヒール=淫らなイメージ、を世に認識させる事になる。この時以来ハイヒールは高貴な他にエロスのシンボル記号となってしまったのである。その事は、また当然の事ながら従来の脚フェチシズムと結びついていった。/特に大きく想起させたのが纏足(てんそく)願望である。ハイヒールのその非日常的な機能は拷問機械を思いおこすのに充分であった」(#B_049、〔七三~七四ページ〕)。
日本で初めてハイヒールを履いたのは大正期のモダンガールたちだと言われ、完全に普及したのは、大量生産され低価格になった昭和四○年代である。吉岡は馬(このガラスの踵をした動物!)に乗るとき、どんな靴を履いていたのか。
04 その尖筒を機関手がなめるとき
後出23行の「バクシンする蒸気機関車」の「機関手」である。実際にはSL、蒸(気)機(関車)を運転する乗務員は「機関士」と呼ばれ、進行方向に向かって左に位置する。釜に石炭をくべたりするもう一人は「助士」と呼ばれ、右側に位置する。だがこの詩の乗務員は一人であろう。彼の運転用の服と少女のセーラー服との対比を見るべきだ。あるいは蒸機が石炭だけでなく、水を必要とするように、彼もハイヒールの尖をなめるのだろうか。
05 晩夏の街にはセーラー服をぬいだどんな少女がいるのか?
丸谷才一に〈セーラー服〉なる考証に始まり哄笑に終わる随筆がある。私の知るかぎり唯一の女子学生の「セーラー服考」だ。丸谷はまず「われわれ日本の男にとつて、少女を指示する記号の第一はセーラー服」(#B_143、九~一○ページ)だとしてから、そのセーラー服趣味は「歴史的な事情」によるのかそれとも「本質、衣裳としてのフォルムと機能」(同前、一一ページ)が魅惑の源なのかと転じ、太田臨一郎の論文(イギリス海軍の軍服としての水兵服考)に依りつつ、明治時代に「ジョンベラ」(丸谷は「ジョン・ブル」から来ているとする)と呼ばれていたことを手掛かりに、次のように結論づけている。「〔……〕セーラー服が与へる脱ぎやすいといふ印象は、少女たちがこれを着るやうになつて、ズボンがスカートに変るといよいよ強まつた。〔……〕ズベラ→ズンベラ→ジョンベラ→だらしない→不品行→淫乱、と意識下の連想は放恣に進行し、そこで日本の男はセーラー服に興奮するやうになつたのではないか」(同前、一五~一六ページ)。
吉岡と丸谷が一夕、セーラー服談義にうつつを抜かしたということはあるまいが、「意識下の連想は放恣に進行し」あたりは吉岡の、そして丸谷が訳した《ユリシーズ》のジェイムズ・ジョイスの方法を言いあててはいまいか。いつの時代の少女のセーラー服にも永遠の少年が感応している。そんな図を詩行は描いている。のちに吉岡は《サフラン摘み》のジャケットに片山健の鉛筆画を採用したが、それはまさしく「少女蝉蛻図」とでも呼びたい光景だった。
06 言葉を犯罪的に使って
《現代詩手帖》一九六八年七月号に鈴木志郎康が〈言葉を犯罪的に使うこと〉という文章を寄せていて、それがこの行の淵源かもしれない。同号は本章の末尾で触れる種村季弘のルイス・キャロル論や中村宏の描くセーラー服の少女や蒸気機関車も掲載しており、それらが〈少女〉の背景をなしているとすると、吉岡が生前に語っていたように「詩は詩から創らない」というのは、狭義に捉えなければならなくなる。「月刊の詩誌から詩を創っていた」のだから。むろんそれを指して吉岡詩を貶める意図はない。独創的であらねばならないとする当時の吉岡がむしろそうした危険な領域に踏みこんでいった、いかざるをえなかったのはなぜか。モチーフの処理、テーマそのものに要因を求めねばなるまい。そのとき「犯罪的な言葉を使って」ではなく、本行のように書くのには、よくぞ言ったりの感慨を禁じえない。06~08行は本篇だけにとどまらず、以降《神秘的な時代の詩》の後半期に執筆される詩篇を覆いつくす。
07 紅色の闇へ
「べにいろ」か「くれないいろ」かそれとも「あかいろ」か「こうしょく」か。03、05行の「ハイヒール」「セーラー服」からいけば、口紅を想わせる「べにいろ」と読みたいが、初出05行「晩夏の街にはどんなモモイロ〔桃色=とうしょく〕の少女がいるのか?」との対比からは「こうしょく」とも読める。私は諳誦時に字面に復元可能な「べにいろ」を採用している。ときに「モモイロ」から「紅色」という変化は、単に色調が深まっただけではない。「みせものの/なつかしい風情」(〈聖あんま語彙篇〉⑧・8)を漂わせた唐十郎主催の状況劇場が紅テントを小屋としていたのが、まさにこの時分だった。「紅色の闇」という空間でもあり時間でもあるわくわくするような場には、官能の極致の小動物(少女かイタリア貂か)だって潜んでいる。だが目をこらすぼくらにもまだそれは視えてこない。狩りの道具はといえば「言葉」しか持ちあわせていないんだ。
・つまりぼくの愛が鴎のくちばしを紅色に染めるまで(〈寄港〉⑤・19)
08 イタリア貂を狩りに出る
貂は鼬をずっと大きくした感じの動物で、安間繁樹によれば、日本で最も美しい野生動物だ。
「雪のように白いまん丸な顔に、碁石のような黒くて円い形をした両眼と鼻鏡、黄金色に輝く胸と体。美しさとかわいらしさの中にも、しかし、肉食獣の冷血さが、ありありと感ぜられる。それがまた、この動物をたくましく見せ、いっそう美しく感じさせるのだ。/テンは林道などで偶然に出くわした時、ただ一目散に逃げることなく、遠ざかりながらも途中で立ち止まっては数秒間ふり返ってこちらを見る。そんなことを繰り返しながら、やがて、わきの林へ消えてしまうのであるが、そんな時に、その愛らしい顔を見ることが出来るのである」(#B_156、一九八~一九九ページ)。
日本にはテンとクロテンの二種類が住んでいるが、「イタリア貂」とはなんだろう。「カラフト、中国北部〔ということは「満洲」も〕、シベリアからヨーロッパ〔ということはイタリアも?〕にかけて分布するクロテン」(同前)の亜種ででもあるのか、私にはわからないが、コゲ茶色から灰褐色までさまざまあるという体色は「紅色の闇」に映える。貂はおもに夜、活動するというからぴったりだ。〈タコ〉(⑧・2)がテレビ番組から生まれたように、この行もテレビや動物写真から生まれたのか。
09 ぼくたちにとって死はとりとめもなく
「ぼくたち」とはだれか。作者と読者のことか。それとももっと一般的に we Japanese などの we なのだろうか。08行めが以下に係る連体詞ならば、「イタリア貂を狩りに出るぼくたちにとって死はとりとめもなく」となって、狩りに出ようとするほどの者にとって死がとりとめのないものであろうはずがない。貂に逆襲されたところで危険ではないというのは理由にならない。形容詞「とりとめのない」に続くのは「話」とか「様子」とかで、通常「死」ではあるまい。ここにあるのは一般的な命題の逆転現象である。が、それゆえ詩句には力瘤が出て、詩篇内部の圧力が一瞬、押しあげられた。それは「死」と「とりとめのない」というとりあわせのミスマッチが出発点で、気がつくと「狩りに出る」のはどうやらぼくたち(読み手の私も)らしいという一拍遅れた認識が、作品への参加を有無を言わせず要請するのが第二段階である。詩篇のなかで幻の小動物を追うぼくたち。
10 自動ドアを入る
初稿を書いている一九九四年現在、自動ドアはなんの珍しさもない。しかし二五年前はまだ少なかったし(銀行や百貨店あたりが最初に導入したか)、詩句に堂堂とおさまっている例をほかに知らない。この手の詩語ならざる語が吉岡詩に見えるようになったのは《静かな家》からで、そういう意味では吉岡は意図的に舵を切って、自己の進路を難所からかわしてきた。さてドアを入る歩調はまっすぐである。このころだと、マットに人の乗った重さが開閉動作に連絡している方式だろうから、前行の「死」が主語だとすると、足のない幽霊が歩いているような凄みが漂うが、ここは「ぼくたち」としておこう。むろん次行の「肉」も主語たる可能性を有するが、そうなれば「セーラー服をぬいだ〔……〕少女」のそれだ。そのどれでもあり得るが、読む人間はそれらをすべて同時に想定し、その三択からひとつを自分の読みとして採用する、というようなやりかたをするのではない。ふりかえって初めて成立するまだらに変わる模様のようだとでも言えばいいのか。
11 肉をラセン巻きにするガードルに沿って
・兄・靴が大きくてラセン巻き(〈劇のためのト書の試み〉⑥・1)
足と腰に「ラセン巻き」が係わるのは偶然か。靴はアラビアンナイトに出てくるような尖端が反って丸まったデザインが想いうかぶ。胸下から腰にかけてはボードレールが〈女巨人〉で「その豊満なあだ姿を悠然として跋渉し、/巨大なる膝の斜面に這いのぼり、/夏には屡々、不健康な日光に照らされて、//女巨人がけだるくも野づらを越えて寝そべるとき、/私は山裾に平和な里がまどろむように/乳房の蔭にのんびりと好んで昼寝をしたことであろう」(#B_134、四一ページ)と歌ったのも想いうかぶが、それとは逆に、高い地点から蜂腰を経由して降りることになる。
12 まばゆい丘の上に出ると
吉岡は〈赤尾兜子秀吟抄〉でこう書いている。
「昨〔一九八一〕年の梅雨の頃、「渦」の兜子追悼号に、私は小文を寄せている。それには、淡い三度のふれあいを追想して、わずか四句〔冬の雁霊界のこと聴きをれば/本を売り心の隅に鎌鼬/大雷雨鬱王と会うあさの夢/空鬱々さくらは白く走るかな〕を掲げているだけだった。その時は、枚数の都合で、書けなかったことを、ここに書きとめておきたい。
八年ほど前、私は久しぶりに、『神秘的な時代の詩』を上梓した。試行錯誤にみちたこの詩集は、当然のことながら理解されなかった。そのような折、兜子から手紙が来た。今、その手紙はわが家のいずこかに、ある筈だが見ることは出来ない。しかし文意は覚えている。
まばゆい丘の上に出ると
馬の交尾
その影のしていることが
暁の彫刻である
この四行に、感動したとあった。「少女」と題する四十二行の詩である。私はやさしく慰撫された思いであった。
横道にそれたが、「俳句思へば泪わき出づ朝の李花」と、俳句への執念を燃やしつづけた、兜子を偲ぶにしては、引用の句が少なかった。改めてここに、私の愛誦する句を、若干抄出してみる」(#A_25、三三二~三三三ページ)。
以下に、私が引用文中で補った句などを含めて一八句が選ばれているが、かつては iron horse とも呼ばれた「蒸機」の戦慄的な一句「機関車の底まで月明か 馬盥」(赤尾兜子句集《歳華集》、角川書店、1975)が見えないのは残念至極だ。もっとも吉岡にとって自家薬籠中のイメージすぎて、あえて掲げるまでもなかったのかもしれない。
13 馬の交尾
「太平洋戦争中、北満洲(現在の中国東北地区)へ出征したある兵士の話であるが、現地へ配属されたところ、その部隊は、都会出身者ばかりで編成されていたため、軍馬の扱いを知っている者がおらず、馬の飼料づくりの知識は皆無であった。馬の飼料は、燕麦、乾し草、切り藁に、塩(岩塩)を混ぜ合わせてつくらなければならない。ところが、知識をもたない悲しさ、輸送の途中、狭い貨車の中の場ふさぎとばかり、だいじな岩塩を放棄してしまっていた。そのため、馬には塩抜きの飼料をやることになってしまった。/塩欠乏の飼料ばかり与えられた馬たちは、塩なしにたまりかね、自然の生理的要求から隣りに繋がれている馬の尻尾をたがいに喰いちぎり、その毛のもつ塩気をとることによって、わずかに塩分を補充した。そこで、どの馬も尻毛が短くなり、細く毛のない豚の尻っぽさながらの馬が並ぶ奇観を呈したという。このことがあってから、さすがに兵隊たちも気がついて、塩を加えた飼料をやるようになったので、馬も尻っぽを喰いちぎることはやらなくなり、四~五ヵ月で、馬の尻っぽが元のように長くなったという」(#B_124、一八ページ)。
14 その影のしていることが
「そこでは灰色の馬と灰色でない馬とがすれちがう 灰色の馬が牝らしく毛が長く垂れさがり 別の馬は暗緑の牡なのだろうはげしく躍動する たがいのたてがみも尾も回転する毛の立体にまで高まって 少女にはそれが見える 完全な円のふちから ときどきはみ出るものがオレンジ色に光り 中心はもう時間が経過したので黒い 或晩にお父さんとお母さんがのぞかせた一角獣のように恐ろしく 少女は自身の腿に熱を浴びる まだすれちがっている馬たち ピエロでない赤い帽子の男は 少女が気づいた時から人ではなく だれもが持っている共犯のはにかみの心 テントの底が深くなればなるほどゆっくり 馬の方へちかづく 命令するために非常に細長い棒をふりおろす 電光もひきあげる街の看板の方へ 今夜は充分泣けると少女は思う 灰色の牝馬のすんなりした腹に異父弟が宿ったから このみじかい冬の休暇が終るとともに」(〈冬の休暇〉⑤・12)
15 暁の彫刻である
大江健三郎の、一九六三年発表の〈性的人間〉の「若い詩人」の印象的な台詞。「彫刻〔ローマ風の裸の石像、アポロンとゼウス〕のあいだを裸の娘があるいてくるシーンは、地獄のなかの風景ということになるのかい?」(#B_019、一七ページ)
16 血豆の大理石の頂で
「血」のモチーフの最初の登場。
・半病人の少女の支那服のすそから/かがやき現われる血の石(〈珈琲〉⑥・3)
17 マンダラ模様の夢をはらみ
初出の「千羽鶴」の削除は、川端康成の長篇小説へのほのめかしと取られることを避けるための措置か。それよりも、螺旋形との関連は。曼荼羅すなわち円輪具足、あるいはユングの心理学用語の「マンダラ」が悠久の時を示すならば、螺旋形こそ少女の日日の変貌を暗示していよう。
18 そこから少女は成長するんだよ
「「仕方がないのよ」とアリスはやさしく申しました「成長しているんだから」」(#B_038、一三七ページ)。
19 樹と外套でかこわれて
「雨のぬらした藁の寝床から/若い女は鮮明な姿態で起き上る/そのかたちについて/樹も起き上る/まぶしい太陽の下で/羞恥の斑が花のように/女のかくれた幹をながれる/うずくまる裸の樹/その渇く内部/やがてまた地から/充分な樹液が注がれ滑らかになる/さえぎるもののない野へ/しなやかな姿勢で/根の瘤から/いまはじめて樹は/男のように立ち上る」(〈樹〉③・6)
20 ブルガリヤ人の男根は立ち
この行はなにをいわんとしているのか。一九六○年代末のブルガリアはソヴィエト連邦に極めて近い東欧の社会主義国家で、吉岡が当時のブルガリアをどう見ていたかを裏づける資料は見いだせない。目を転じて戦前に、さらに網を大きく打って「バルカン」とすると、ウィルヘルム・マイテル博士の小説《バルカン戦争》とアルフレッド・ヒッチコックの映画《バルカン超特急》(一九三八年作品、ただし日本公開は〈少女〉発表後の一九七六年)が登場する。20行めからは前者が想起される。吉岡は〈ポルノ小説雑感〉で《バルカン戦争》についてこう書いている。
「戦後の昭和二十六年頃、それらに類する外国文学が花開くごとく、一斉に刊行され始めたのである。『ガミアニ』、『南北戦争』、『蚤の浮かれ噺』、『ジュリアンの青春』、『トルー・ラブ』そして『バルカン戦争』などであった。私は一通りそれらを購って、読んでいる。ほとんどが発売と同時に、禁止処分を受けたようだ。そのなかで、今でも忘れ難い小説は、W・マイテル『バルカン戦争』である。これは二、三種類ほど出版されており、私はそのうちの二冊を持っていた。完訳本ではなく、二冊とも抄訳されたもので、「挿話」が異っていたりするので、補足しながら読んだ。しかしいずれも迫力に欠けて物足りなかった。なぜなら戦前に『バルカン戦争』の完訳本と思われる、秘密出版の『指揮官夫人と其娘達』を、私は読んでいたからである。今、本も参照する資料もないので、うまく紹介できない。「戦争」という諸悪の根元を捉え、自制心も誇りも失った人間の肉欲を露呈するポルノ文学の傑作。戦争の裏面にかくされた、女性たちの受難の諸相を活写している。異国の兵隊たちから、嗜虐的な暴力の数々を受ける、美しい人妻や娘たちの姿態は悲惨というよりも、むしろ耽美的でさえあった。この貴重な本を、年嵩の友人に返し、間もなく私は出征した」(#A_25、三五五~三五六ページ)。
《バルカン戦争》の発行人・梅原北明や小説の本文については、城市郎の《性の発禁本》(#B_073)に詳しい。昭和二(一九二七)年の初版発行後も、別の版元からの再販本や《戦乱秘史》と改題された上下巻合本など、何種類かが数年のうちに刊行されている。吉岡の《指揮官夫人と其娘達》もこれらのどれかだろうが、不明だ。三木幹夫の書誌を参考にすると、戦後本は矢野正夫訳《バルカン戦争》(昭和二六年、東京書院)、松戸淳訳《秘話バルカン戦争》(同年、紫書房)、藤井純逍訳《バルカン戦争》(昭和二八年、銀河書房)のようだが、いずれも実見していない。《バルカン戦争》はその後も数年に一度は新訳や覆刻版や抄録本が出ているから、吉岡が新刊や古本の棚にそれらを見つけるたびに、彼女たちの「受難の諸相」をちらりと想いうかべ、しばし感慨に耽ったことは充分あるだろう。
21 孔雀の羽は散乱する
孔雀のシンボリズムは日本人にはなじみが薄いが、その羽は、古くは吟遊詩人に詩才への褒賞として城主の奥方から贈られた栄誉の飾りだったという。ならば、散乱したそれは、詩想の放縦あるいは枯渇を意味するのか。安西冬衛に通じる華麗な修辞の行使である。また、旧約聖書列王紀略上一○・二一、二二参照。
22 きわどいレールを
〈少女〉掲載号の《血と薔薇》の小特集なのだろう〈殺人機械〉に、中村宏は〈蒸気機関車式殺人機械〉なる二色画を寄せていて、おそらく当時も「人間的な機械」などと称されがちだった蒸機に対する大方の観方に冷水を浴びせている。
23 バクシンする蒸気機関車が正面から入ってくる
兜子の蒸機の句は静止せる鉄の塊という風情だったが、山口誓子からの影響が大きかった三鬼には以下の作が《夜の桃》にある。
・汽車と女ゆきて月蝕はじまりぬ(#B_048、七三ページ)
・機関車が身もだへ過ぐる寒き天(同前、八五ページ)
・夏の闇火夫は火の色貨車通る(同前、九六ページ)
24 呻きの乳色の霧の彼方より
三つの「の」によって、詩句には音声と映像の、聴覚と視覚の意図的な混交が生じる。どれかひとつを「が」と置き換えて読みたくなったとしても、次行とのつながりがそれを拒む。しかしそれ(主格を限定する助詞の位置)がひとつずつずれて「呻き」「乳色」「霧」が音としても像としても一段ごとに表面に浮かびあがり顕ちあらわれるさまは、吉岡独特の詩句の成果と呼ぶにふさわしい。
25 まるで虎刈りの老人がきた!
「近くの森で、大きな機関車がぱっと煙を吹いたような音がしたからです。しかし、アリスは機関車ではなくて、野生の動物のようだと心配したのです。「この辺には、ライオンか虎がいるんですか?」とアリスはこわごわ聞きました」(#B_039、五八ページ)。「虎刈り」それとも「虎狩り」?
26 ほそいほそい靴下をぬぎながら
「朝、短い靴下を片方だけはいて立っている四フィート十インチの彼女はローだ」(#B_110、一三ページ)。
・羞恥のセックスで靴下を穿く(〈果物の終り〉⑤・2)
27 口をふさいで
これがどうしても脱いだ靴下で口をふさぐように読める。猿轡だ。
28 血の波紋の少ない世界へ
初出「血の波紋の少なくない世界へ/毛の捕虫器かざし/モモイロの柵に」の三行はそれぞれに手が入った。続く「だんだん」までをクレッシェンド(次第に強く)で乗りきるためには、ここは謂わば身を屈める動作が必要な箇所で、手入れもその方向に沿ってなされた。では「血の波紋」とはなにか。16行めの「血豆の大理石」の前状態か。
29 夜光捕虫器かざし
吉岡実最晩年の〈雲井〉(未刊詩篇・19)から「1」を引く(原文の表示は《薬玉》スタイルだが追い込みの形で)。
「(とろとろと眠りこむ/〔牧神〕ではなく)/森の沼のほとりで/(捕虫網をかざしてゆく/長い髪の寛衣の少女)/を見かけたような気がする/わたしは灌木の間を/〔雨後の茸[くさびら]〕を探しまわった/(明暗の境いを越え)/さまよいつづける/(樹木の霊や/鳥獣の魂)/どんなものの上にも/止まることは許されない/〔イデアの世界〕/わたしはなぜか思う/(書かれた/〔言葉〕は/〔骨〕のように残るだろうか?)/手の届かぬ高みに/〔月輪〕のように/〔かたつむり〕がいる」
30 ヒルガオの咲く柵に
「吉岡 あれ〔〈感傷〉④・18〕は意外な人に好かれてるのね。あれは、ジョゼフ・ケッセルの『昼顔』という小説をぼくは戦前から読んでいるからね。映画の影響ではない」(#C_010、一一○ページ)。
31 だんだんよりかかる
32 だんだん裂ける
この二行は「A‐B、A‐C」という構造ゆえに、A=Aで、B‐Cの対比に関心が向かうが、B「よりかかる」の主語は「老人」(もしくは超法規的に「少女」?)で、C「裂ける」のそれは「蜜房」と読むべきだろう。と、まずここでB‐Cの対比が揺さぶられ、ためにA=Aという自明の前提も崩れる。A「だんだん」は自動ドアの右扉と左扉のように、詩句を読みすすむわたしたちのまえで大きく開かれてゆく。
33 蜜房はなぜいつまでも暗く苦く
「蜜房」は蜂蜜のつまった蜜蜂の巣、ハニカム(honeycomb)。自然界のなかで最も強度に優れたその六角形の巣は、最小の材料(蜜蝋)で間にあう。文字面からは別の連想が働く。すなわち蜜柑の房や、蜜のように甘い乳房や、蜜月の閨房やといった蜜の(ような)房だ。オレンジ色(黄色から紅色の途中)の天体が沈むと、「少女」は初夜を迎えている。どこかで蜜月(ハネムーン)も響いているようだ。
ときに「蜜房」くらいの由緒正しい詩語になると、スルスの探求も道がつけやすい。杜甫から一首全体を引く。〈秋野五首〉の「三」(#B_044、一八六~一八七ページ)。
礼楽攻吾短 礼楽もて吾が短を攻め
山林引興長 山林には興を引くこと長し
掉頭紗帽側 頭を掉えば紗帽側き
曝背竹書光 背を曝せば竹書光る
風落収松子 風落として松子を収め
天寒割蜜房 天寒くして蜜房を割く
稀疎小紅翠 稀疎なり 小紅翠
駐屐近微香 屐を駐めて微香に近づく
34 夕陽のように
これまた、33行を受けるようにも、35行に係るようにも見える double entendre 的な詩句である。
35 一つのゲームを終らせるんだ
「でも〔アリスは〕、ゲームが終わったかどうかをたずねるのは、別段いけないことでもないだろうと思い、こわごわ赤の女王を見ながら、切り出しました」(#B_039、一三七ページ)。
36 浴室で裸になって
・看護婦アリス・バアナム
・女中アリス・リイヴル
・老嬢ベシイ・コンスタンス・アニイ・マンディ
・牧師の娘マアガレット・エリザベス・ロフティ
・カロライン・ビアトリス・ソウンヒル
・メイ・ベリスフォウド
・マアガレット・グロサップ
・ルウス・ホフィ
・サリイ・ロウズ夫人
これらはみなジョウジ・ジョセフ・スミスによる浴槽の花嫁事件 Brides of the Bath Mystery の犠牲となった女たちの姓名だ(牧逸馬〈浴槽の花嫁〉#B_138、一三九~一七四ページ)。
37 今宵から花嫁たらんとする
「農奴たちは妻を娶っても、初夜は領主に捧げるものであって、その権利を買い取らないかぎり、新妻を処女として迎えることはできず、妻も愛する夫に自分の掛け替えのない処女性を与えることはできなかった。処女の名誉は犠牲にされ、税としてあがなわねばならなかった。代価のきまりは、花婿が塩をひとかたまり、花嫁が自分の臀部の大きさと重さに相当するだけのバター、もしくはチーズを納めるということになっていたという」(#B_124、二二九ページ)。
38 心なき少女の自己誘拐
「〔……〕彼〔キャロル〕が交際の対象とした少女たちは厳密に十歳までに限られた。それ以上の年齢に成長すると、彼と少女たちの間にはかならず「難破」が訪れたからである。この部屋で彼は幻想の童話を少女たちに口述し、さらに写真スタジオ「ガラスの家」を作らせてからは、そこでつぎつぎに少女たちを乾板のうえに永遠に十歳のままに固定したのである」(#B_084、一五四ページ)。
39 それはぼくたちにとっていかなる痛みの
「いかなる」という重重しい語句の投入によって詩篇の終了を予告する。すなわち〈コレラ〉(⑦・18)の終わりから七行めを見よ。
40 六面体の鋲であるのか?
「ビラン体」改め「六面体の鋲」も難句だ(六面体が立方体なら「塩」の結晶でもある)。〈支那の少女〉の節での引用の中略部分、「楊柳の下に、豪華な色彩の柩が放置されているのも、異様な光景だ。ふたをとって覗いて見たらと思ったが、遂に見たことはない。びらんした屍体か、白骨が収まっているのだろう。みどりに芽吹く外景と係りなく。やがて黄塵が吹きすさぶ時がくるのだ」(#A_25、九四ページ)を下敷に、仮に「びらんした屍体」から「豪華な色彩の柩」への置き換えだとして「鋲」とはなにか。釘より頭が丸くて大きい、物を止めるものがそれなら、ここは「白骨」なのか。死体から死者へ移行する時間こそ「痛み」の根源だ。
41 家のなかで顔を巻く包帯をとけ!
20行めで《バルカン超特急》に触れたのはこの「顔を巻く包帯をとけ!」にぴったりのシーンがあるからだ(詩篇内部の力学としては11行めを受ける恰好になる)。画面で「きわどいレールを/バクシンする蒸気機関車が正面から入ってくる」そのすぐ後だ(七三分あたり)。「包帯」に言及しているフィルモグラフィーはそれほど多くなくて、《ヒッチコック ヒロイン》が「イギリス情報部のミス・フロイを捕えた敵側スパイの博士らは、途中で運び込んだ包帯姿の患者とすり換えていたのだ」(#B_024、一五八ページ)と触れたあと、《アート・オブ・ヒッチコック》が「〔……〕ハイヒールをはいた妙な尼僧や包帯でグルグル巻きにされた患者をめぐって疑惑は深まり、患者の包帯をといてみるとミス・フロイが現れる」(#B_078、一一二ページ)と書いた。
〈少女〉の書かれた一九六八年末に日本未公開だった映画。吉岡が影響されたのは一本の未見のフィルムによってではなく「映画」という想像力によってだ。吉岡は記憶のストックから最適のものをひっぱりだして、詩句中にイマージュとしてそそり立たせた。それがイギリス生まれの映画監督のイマージュと類似していたとて、とやかく言う必要はないだろう。
42 格子が見える
いちばんの難物が最後の「格子」だ。私には詩句という暗号の解読格子に「見える」。家のなかの格子なら、障子か。
「山人たちは迷信深く、オオカミは悪口を聞かされると祟りをするものだといい伝えられていた。オオカミは、障子の桟のようなところにも、千匹隠れていて、じっと、聞き耳をたてているといわれたものである。それというのも、人間の周囲には塩があるので、オオカミは塩を求めて寄ってきていたものと考えられる」(#B_124、二二~二三ページ)。
障子ではどうも流れにそぐわない。作品の舞台が満洲であるようなときに、ここだけ日本とするのが、そうした印象を与える。
頭部と顔面の包帯の巻き方の基本的な方法は「ターバン巻き」で、頭部の輪巻き(鉢巻き)を逐次ずらせた形で、耳の上で交差するような8字巻きに似た覆い方をするという(水野祥太郎《包帯》#B_145、三四ページ)。また「頭部のみの包帯ははずれやすく、顔面は、眼・耳・鼻・口など、おおいかぶせては困る部位があり、〔……〕眼は視野を妨げないために、おおわないようにするのが原則」(同前)だから、ここは「顔を巻」いたのではなく、眼に対しての処置であった。見ることの一旦停止とその解除。これが吉岡実が設定したクライマックスへの道のりである。
「眠っている時は永遠の花嫁の歯のように/ときどきひらかれる/言語格子」(〈わがアリスへの接近〉⑧・11)。
二八○篇、約一一○○○行の吉岡実の全詩篇、全詩句を検討の対象にするのは別の機会に譲って、本詩集中で「馬」と「少女」(もしくは類似の語)がどのように登場するか見てみよう。そしてこのさい「矢印」や「花嫁」「幽霊」も。
| ⑦・1 | マクロコスモス | 矢印・馬・娘/処女 |
| ⑦・2 | 夏から秋まで | 矢印・花嫁 |
| ⑦・3 | 立体 | 矢印・花嫁 |
| ⑦・4 | 色彩の内部 | 矢印・馬 |
| ⑦・5 | 少女 | 馬・少女・花嫁 |
| ⑦・6 | 青い柱はどこにあるか? | 矢印・姉 |
| ⑦・7 | フォークソング | 矢印・処女 |
| ⑦・8 | 崑崙 | 矢印・馬・幽霊 |
| ⑦・9 | 雨 | ―― |
| ⑦・10 | 聖少女 | 少女 |
| ⑦・11 | 神秘的な時代の詩 | 矢印・少女 |
| ⑦・12 | 蜜はなぜ黄色なのか? | 幽霊 |
| ⑦・13 | 夏の家 | 女生徒・花嫁 |
| ⑦・14 | 低音 | 少女・花嫁 |
| ⑦・15 | 弟子 | 娘 |
| ⑦・16 | わが馬ニコルスの思い出 | 馬・女生徒/少女・幽霊 |
| ⑦・17 | 三重奏 | 馬・娘 |
| ⑦・18 | コレラ | 乙女・花嫁・幽霊 |
詩集の並び順ではわかりにくいが、制作順では〈崑崙〉を最後に「矢印」が姿を消す一方で、その前作(と言っても発表は同時の)〈神秘的な時代の詩〉の次の詩句で初めて「少女」が登場した。
・いかがわしい蘭のからまる少女たち
もはや〈少女〉に「矢印」はなく、続く〈わが馬ニコルスの思い出〉(「少女の腹部をあつかましくも求めて」)や〈聖少女〉(「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!」)や〈低音〉(「ブランコのりの少女がひとり」)と同じ詩篇内にも「矢印」は共存しない。これをもって「少女」が「矢印」に取って替わったとするのは早計で、「矢印」詩篇には「少女」だけでなく「娘・処女・姉」があるのは先に見た。ならば両者は男女のようにふたつで一対をなす組みあわせなのか。言い換えれば「矢印」が指し示す方向は「少女」なのか。そうではない。
・めざすメザシの/目をつらぬく矢印/死への/橋がかり
〈崑崙〉
・夜は見えないから/乳色の矢印にみちびかれ/肉のようなものが甲羅のなかへ/入って行く
〈神秘的な時代の詩〉
というぐあいに、「矢印」はどんづまりに突きあたってそこで停止し、そして熄んだ。彼女たちと結びあうのは「馬」である。
・ぼくらの現況の雨の葦原から/暁の丘に至るまで/シナの娘が大鎌を振って行く/馬のながい陰茎の岸べ
〈マクロコスモス〉
・花より恥ずかしく/看護婦の白衣のなかに/つつまれる/傷ついた馬の腹を/巻くみじかい包帯
〈色彩の内部〉
・紫紅の下着の/女生徒たちのハイキングの賑わいよ!/白いストッキングに覆われた/かたい両腿の跳ねるたび/わが馬ニコルスは呼吸を止め/歓喜し
〈わが馬ニコルスの思い出〉
つまりこうだ。「馬」は陽根のシンボルであるには弱弱しく、彼女たちの方が優位に立っているのだ。「わたしはだれにも聞けないのだ 女は死んだ馬なのか」(〈馬・春の絵〉⑥・5)。あるいは、馬は死んだ女なのか。
前回の詩〈雨〉(⑦・9)が吉岡実の「前期の終焉」だと述べたが、創作家の業績を輪切りにすることに便宜以上のものはない。言挙げするからには、前期は前期なりに吉岡実詩を特徴づけるものが必要だ。この時期の吉岡は怒れる独身者の詩集《静物》《僧侶》と異なる世界を意図していた。思潮社版《吉岡実詩集》(#A_08)の上梓は、それまでの過去を封じこめる墓碑の建立となった。完成すなわち死からの再生の希求が、土方巽の総合芸術・暗黒舞踏に触発されたことは疑いないが、吉岡が土方でない以上、詩が舞踏ではない以上、その等価物の創造はいかにして可能かが問題として残る。そこにこの時期の吉岡の詩法の、と言うよりも詩に対する向きあい方の変化の原因を見ねばなるまい。
奇しくも〈雨〉と同じ《現代詩手帖》一九六八年一一月号に種村季弘の連載《ナンセンス詩人の肖像》第八回〈どもりの少女誘拐者――ルイス・キャロルの場合〉が載っている。アリス詩篇執筆を振りかえった吉岡は「あの印象深い緑の一冊の書物――《ナンセンス詩人の肖像》がなかったら、私のアリス詩篇すなわち〈ルイス・キャロルを探す方法〉が現在のような形で、まとまったかどうか疑わしい。当時はまだ、ルイス・キャロルへの言及はほとんどなく、私は種さんの書いたチャールズ・ラトウィジ・ドジソンの略伝〈どもりの少女誘拐者〉を、唯一の参考文献としたものである」(〈逸楽的刺戟と恩恵と〉#B_173)と書くことになる。
一九六八年後半を〈吉岡実年譜〉(#A_32)から拾うと、七月に詩集《静かな家》を(実際の出来はたぶん九月)、九月に現代詩文庫版《吉岡実詩集》を刊行、後者の〈詩人論〉のために、夏、高橋睦郎からインタヴューを受けている。土方巽を筆頭とする舞踏も数多く観ており、それらはキャロルの《不思議の国のアリス》(岩崎民平訳の角川文庫版か)やハンス・ベルメールの人形や日活ロマンポルノなどとともに、吉岡の新たな詩世界を形成する背景となっている。また《吉岡実詩集》には文庫共通企画としての〈自伝〉があり、〈断片・日記抄〉が昭和二一~二四年、三一~三六年の日記として抄出されている。後の《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》や《うまやはし日記》や絶筆〈日記一九四六年〉に連なる吉岡実日記のさきがけだ。詩に個人的なものを持ちこみたくないとする吉岡にとって、日記の意味は小さくない。日記によって詩の謎はますます堅固になると言っても、日記が詩の純度を保証すると言っても同じことだ。それゆえ詩は雑駁になりうる。
「前期の終焉」には、連続性を見る立場からは意味が見いだせない。第八詩集までの戦後の詩集の冒頭一行を読む(「前期の終焉」たる一九六八年、吉岡実は語から言い回しへの、用語から統辞への旋回を試みた。場の設定、すなわち画然たる詩世界の建設の意識が薄れたことも指摘できる)。
③夜の器の硬い面の内で
④台所の隅で
⑤さびしい裸の幼児とペリカンを
⑥それまでは普通のサイズ
⑦石の建築物といっても永遠
⑦・8 では未経験的なピンクの空間へ 〈崑崙〉
⑦・9 それはたとえば 〈雨〉
*
⑦・5 客観的状況で 〈少女〉
未刊詩篇・12 ものの成熟について 〈スワンベルグの歌〉
⑦・17 わたしは自分の描いた絵を 〈三重奏〉
⑧クレタの或る王宮の壁に
自己の得意なスタイルをあえて遠ざけようとする意志の実験の場が本詩集だった。前作〈雨〉には馬も少女も幽霊も花嫁も矢印も登場せず、彫刻家ルイズ・ニーヴェルスンが現れたのは意味深い。慣れ親しんだイマージュを禁じて他の芸術家の「作品」(池田満寿夫や土方巽など「人物」に捧げた詩がなかったわけではない)に言い及んでいる点に、なみなみならぬ決意を見るべきだ。
私は〈マクロコスモス〉の評釈で戦前の二冊を含む全一二冊の詩集が螺旋状に二つのサイクルを描いているという説をなしたが、ここでは〈吉岡実年譜〉から戦後の吉岡実著作年表を作ってみよう(別表参照)。
単行詩集以外は( )で括ったが、前・中・後期を代表する詩集は、衆目の一致するようにH賞の《僧侶》、高見順賞の《サフラン摘み》、藤村記念歴程賞の《薬玉》だ(事情はむしろ逆であって、三詩集がピークをなす山容を仮に前・中・後に割りふったとするほうが正しい)。だが著作となれば、前期吉岡を概観する最良の選集たる現代詩文庫版詩集、本評釈がその内実を語るであろう《神秘的な時代の詩》、詩法を散文に拡大した書きおろしの《土方巽頌》の三作に指を屈する。ただし「前期」が少しく微妙なのは、年間発表・執筆作品数の谷の年で区切ってゆけば(吉岡が立ちどまるのは変貌の前兆だ)、《紡錘形》刊行後の一九六三年の次は一九六八年ではなく、一九七一年である点だろう。フェイズとして括れるこの山状の詩篇発表期間からずれこんで上梓された唯一の詩集が《神秘的な時代の詩》であることに注目しておけば、いまは足りる。
| 区分 | /西暦年 | /刊行著書(算用数字は月、太字は単行詩集) | /年間発表詩篇数 | /フェイズ |
| 前期 | 1955 | 8静物 | 17 | Ⅰ |
| 前期 | 1956 | 5 | Ⅰ | |
| 前期 | 1957 | 6 | Ⅰ | |
| 前期 | 1958 | 11僧侶 | 11 | Ⅰ |
| 前期 | 1959 | (5魚藍)・(8吉岡實詩集) | 16 | Ⅰ |
| 前期 | 1960 | 7 | Ⅰ | |
| 前期 | 1961 | 7 | Ⅰ | |
| 前期 | 1962 | 9紡錘形 | 5 | Ⅰ |
| 前期 | 1963 | 2 | Ⅰ | |
| 前期 | 1964 | 3 | Ⅱ | |
| 前期 | 1965 | 2 | Ⅱ | |
| 前期 | 1966 | 8 | Ⅱ | |
| 前期 | 1967 | (10吉岡実詩集) | 7 | Ⅱ |
| 前期 | 1968 | 7静かな家・(9吉岡実詩集) | 6 | Ⅱ |
| 中期 | 1969 | 9 | Ⅱ | |
| 中期 | 1970 | 1 | Ⅱ | |
| 中期 | 1971 | 0 | Ⅱ | |
| 中期 | 1972 | 6 | Ⅲ | |
| 中期 | 1973 | 9 | Ⅲ | |
| 中期 | 1974 | (4異霊祭)・10神秘的な時代の詩 | 10 | Ⅲ |
| 中期 | 1975 | 6 | Ⅲ | |
| 中期 | 1976 | 9サフラン摘み | 8 | Ⅲ |
| 中期 | 1977 | 8 | Ⅲ | |
| 中期 | 1978 | (6新選吉岡実詩集) | 9 | Ⅲ |
| 中期 | 1979 | 10夏の宴 | 9 | Ⅲ |
| 中期 | 1980 | 5ポール・クレーの食卓・(7「死児」という絵) | 2 | Ⅲ |
| 後期 | 1981 | 3 | Ⅳ | |
| 後期 | 1982 | 9 | Ⅳ | |
| 後期 | 1983 | 10薬玉 | 7 | Ⅳ |
| 後期 | 1984 | (1吉岡実) | 4 | Ⅳ |
| 後期 | 1985 | 5 | Ⅳ | |
| 後期 | 1986 | 7 | Ⅳ | |
| 後期 | 1987 | (9土方巽頌) | 4 | Ⅳ |
| 後期 | 1988 | (9「死児」という絵〔増補版〕)・11ムーンドロップ | 4 | Ⅳ |
| 後期 | 1989 | 2 | Ⅳ | |
| 後期 | 1990 | (4うまやはし日記) | 1 | Ⅳ |

ルイス・キャロル撮影のアレクサンドラ〔クシイー〕・キッチン(1873年、クライスト・チャーチにて)
出典:http://signormori.clarence.com/archive/images/0000001a.jpg
思潮社版《吉岡実詩集》(#A_08)はあとがきでY・Y(むろん夫人の陽子さんである)に捧げられているが、《サフラン摘み》には戦後の単行詩集として初の献辞がある。半扉裏の「K・M・Yに献ず」がそれだ。K・M・Yなる頭文字をもつ一人の人物を想像するのは現実的でない。《「死児」という絵》には、姓だけ名だけの頭文字表記も登場している。ここから先は推測でしかないのだが、たとえば名だと、
K・飯島耕一
M・大岡信
Y・入沢康夫
の三詩人はいずれも吉岡の友人でもあり、それぞれ一九七五年の〈詩的青春の光芒〉(#C_045)、七三年の〈卵形の世界から〉(#C_039)、六七年の〈模糊とした世界へ〉(#C_005)と、数少ない対談相手を務めてもいる。詩集成立にまつわる、読者には見えない部分でのなにごとかの貢献があったのかもしれない。さらに想像をたくましくして姓だと、
K・〈ルイス・キャロルを探す方法〉(⑧・11)を書かせた《別冊現代詩手帖 ルイス・キャロル》の編集人、桑原茂夫
M・〈崑崙〉評釈時にも触れた〈葉〉(⑧・4)を書かせた《ユリイカ》の編集人、三浦雅士
Y・〈サフラン摘み〉(⑧・1)発表当時の《現代詩手帖》の編集者、山村武善
これはKとMとYという献辞を贈られて不思議がない三人の組みあわせという仮定での当て推量で、著者の真意とは関係ない。詩人自ら「それにしても、《紡錘形》や《神秘的な時代の詩》、それから《サフラン摘み》などの詩集の生成の記録がないのは、今にして考えれば残念なことである」(#A_25、三六九ページ)と書いているように、献辞の頭文字は今もって明らかにされていない――などと綴ってきたのも《サフラン摘み》における特異な二篇〈葉〉と〈ルイス・キャロルを探す方法〉の産婆役の編集者に敬意を払っておきたかったからだ。
初出〈ルイス・キャロルを探す方法〉(#C_015、一五七~一六四ページ)は、冊子ではそこだけほかの白の本文用紙とは別の黄味がかった紙に刷られ、次のような構成になっていた。
・一ページめ タイトル〈ルイス・キャロルを探す方法〉(描き文字はキャロルに敬意を表してのものか。子供っぽい字だが、吉岡の手になるかもしれない)、執筆者名。そして
Photo by Lewis Carroll
Poem & Montage by Minoru Yoshioka
ときて(これは写真のキャプション、つまり説明文を意識したレイアウトに見えなくもない)、その左にキャロル撮影による乞食の少女に扮したアリス・リデルの全身像の「扉」。
・二~三ページめ 〈わがアリスへの接近〉と合計七人の「アリスたち」の写真〔後出《Lewis Carroll―Photographer》の図版番号32、54、34、60、17=ノートリミング、42、29〕。
・四~八ページめ 〈少女伝説〉と、合計二五点の写真に閉じこめられた「アリスたち」〔同じく15、53、49、5、37、59、4、16、51、39、43、30、13、44、40、28、36、14、10、3=ノートリミング、50、46、52、26、62=ほとんどトリミングしていない〕。
写真の少女たちの表情は一様に暗い。塚本邦雄のアリス論にある描写を借りれば「たとへばマリー・ミレーは独房さながらの部屋の隅に、追ひつめられた揚句力尽きたかにくづほれ、華奢な脚を斜に投げ出してゐるが、その容貌はジャンヌ・モローそつくり。また、アリス・ジェーン・ド〔ママ〕キンは二階の出窓から脱出しようとして女忍者もどきに繊い縄梯子に脚をかけてゐるところ。エリザベス・ヒュッセーはたゆげに寝椅子に靠れかかつて、その媚を含んだ伏目はオダリスクの風情である」(#B_092、八○ページ)で、この類の写真が都合三三点ある。
吉岡実は高橋康也に〈少女伝説〉の作詩法をこう語っている。「『不思議の国のアリス』を読んでまず感動し、つぎに『鏡の国』を読んだ、これもいい、と参った。実は、そこで止まっていたのを、たまたま桑原茂夫君に『別冊現代詩手帖キャロル特集号』のために書けってせっつかれたのね。そこで種村さんの『ナンセンス詩人の肖像』の中のキャロル論を読んだりしているうちに、少し開けてきた。とにかく、キャロルの撮った少女たちの写真を机の上に並べておいて、名前を書き出してみた。そしてそのキャプションみたいなつもりで詩を書いてゆけばいいんだと思うと、一種の気楽さが湧いてきて、相当なスピードで「少女伝説」が書き上がったんです。この名前というのが、かなり決定的な重要性をぼくに対してもつことになるのね」(#B_081、三五八~三五九ページ)。一九世紀イギリスの童話作家・写真家と二〇世紀日本の詩人・装丁家が出あった瞬間である。
ときに「キャロルの撮った少女たちの写真」とは具体的になにか。種村季弘の《ナンセンス詩人の肖像》(竹内書店、1969)には「キャロルの写真(『ドウ』誌より。右上はキャロル)」(#B_084、一五○~一五一ページ)というキャプション付きで雑誌の複写が見開きで載っているが、少女のカットは全部で九点〔14、42、15、36、29、39、50、51、17〕と少ないから、吉岡が依ったのは矢川澄子が〈不滅の少女〉で触れている「ヘルムート・ゲルンシャイム著『写真家ルイス・キャロル』。一九六九年ドーヴァーの新版で、原著は四九年にロンドンで刊行されている」(#C_015、一八一ページ)か、そのコピーだろう。キャロルの撮った六三点の写真を掲載した新版(#B_175)はわりあい容易に入手できるから実物を観れば一目瞭然なのだが、私は百年以上前の男の、少女への眼の欲望に驚愕・讃歎を禁じえなかった。徹頭徹尾、眼の人であった吉岡実がこれらの写真に感応しなかったと考えることは不可能である。――《Lewis
Carroll―Photographer》はその後、邦訳が出た。ヘルムット・ガーンズハイム著、人見憲司・金澤淳子訳《写真家ルイス・キャロル〔写真叢書〕》(青弓社、1998年2月20日〔底本は1949年刊の原著〕)である。ドーヴァーの新版に収録されているキャロル撮影の写真も、〈ルイス・キャロルの写真作品〉として全点掲載されているが、キャプションの多いページなど一部にトリミングが施されており、吉岡のモンタージュ素材とまったく同じ絵柄というわけではない。――
詩篇執筆の順序は、おそらく〈少女伝説〉のⅠに続いてⅡが書かれ(このとき末尾の詩句から総題が生まれた可能性がある。本文よりも進行を急ぐ初出誌の別刷目次が正式な題名〈ルイス・キャロルを探す方法〉と異なり、単に〈キャロルを探す方法〉となっているのは、総題がいちはやく初案のまま編集者に伝えられた結果か)、さらに角川文庫版《鏡の国のアリス》を読みなおし、行わけの〈わがアリスへの接近〉が書かれた、という按配だろうか。(以下の〔 〕内は対照のための《Lewis Carroll―Photographer》および《写真家ルイス・キャロル》の図版番号)。
ルイス・キャロルを探す方法|吉岡実わがアリスへの接近
三人の少女
アリス・マードック〔5〕
アリス・ジェーン・ドンキン〔15〕
アリス・コンスタンス・ウェストマコット〔42〕
彼女らの眼は何を見ているのか?
彼方にかかる縄梯子
のびたりちぢんだりするカタツムリ
刈りとられるマーガレットの黄と白の花の庭で
彼女らの脚は囲まれている
どこからそれは筒のようにのぞくことができるか?
「ただ この子の花弁がもうちょっと
まくれ上がっていたら いうところはないんだがね*」
彼女らの心はものみなの上を
自転車で通る
チーズのチェシャ州の森
氷塊をギザギザの鋸の刃で挽く大男が好き
鞄のなかは鏡でなく
肉化された下着
歴史家の父の死体にニスをかけて
床の下の世界から
旅する谿のみどりの水をくぐる
一人の少女を捕えよ
なやましく長い髪
眠っている時は永遠の花嫁の歯のように
ときどきひらかれる
言語格子
鉛筆をなめながら
わが少女アリス・リデル〔12〕
きみはたしかに四番目に浅瀬をわたってくる
それは仮称にすぎない
〈数〉の外にいて
あらゆる少女のなかのただひとりの召女!
きみはものの上を通らずに
灰と焔の最後にきた
それでいてきみは濡れている
雨そのもの
ニラ畑へ行隠れの
鳩の羽の血
形があるようでなく
ただ見つけ出さなければならない浄福の犯罪
大理石の内面を截れ
アイリス・紅い縞・秋・アリス
リデル!〔45〕*ルイス・キャロル〈鏡の国のアリス〉岡田忠軒訳より
少女伝説
Ⅰ
ドジソン家の姉妹ルイザ マーガレット ヘンリエッタ 緑蔭へ走りこむ馬 読書をつづける盛装の三人 見よ寝巻のなかは巻貝三個〔7〕
*
父ジョージ・マクドナルドはひげをのばし 長女リリーの唇は イチジクの汁でよごれる 婦人帽の下からツタの葉を茂らせる継母 父に抱れて 鳥の巣を採る弟〔30、31〕
*
アグネス・フロレンス・プライスは今日も一つの大きな人形を抱く 中世のかつらをつけた裁判官の姿をした人形を わたしの罪を罰して! 縞の下着をつけていることを〔34〕
*
エリザベス・ハッセー よい名それとも変な名 ロバー・ハッセー教授の娘 絹のソファーへ横たわって 午後は母を待つ 母は医者を待つ 夜は父を待つ 母を待つ父を わたしは待つ 絹を傷つける虎を待つ〔36〕
*
ああアイリーン・ウィルソン・トッドよ 風に吹かれたあの長い髪が庭の木を巻く 恐ろしいことに木の幹がつるつるしている 死んでいる木 生きている木 叩くなら木の股を 大梯子へあがって兄の首を吊すこと〔53〕
*
窓から見えるエフイー・ミレエー 父と母と娘がこの窓から飛びおりるのを 上からのぞいたような気がする〔50〕
*
フフフ笑うフランクリン夫人の娘時代に似ている うつむくバラのなかのローズ 子守唄は自分で唄うのよ バラよ眠るなかれ!〔44〕
*
マリリア・ホワイトの白いマリがころがってゆく 止るところがあるだろうか ランベス・パレスの荘重な門で止る 恐しい顔をして叔父が門を閉めたから〔43〕
*
マデライン・キャサリン・パーネル 水兵服が好き 水浴びが好き 横顔が好き〔40〕
*
C・バーカー牧師の娘メイは椅子の上へ立っている 靴のまま この狼藉の恍惚 十二歳になったら飛びおりる〔37〕
*
メリークリスマス 病める雪 病める七面鳥の声 わたしはメアリー・マクドナルド ジョージ・マクドナルドの娘 うずくまる母と姉 鮭の燻製がきらい〔28〕
*
エラ・モニア・ウイリアムズ 廊下をほうきで掃く どこまでもどこまでも暗い家 教授は今朝は「寒い」とひとこと云った〔59〕
*
首席裁判官デンマン卿の娘グレイス・デンマン 石の階段の一番下が彼女の憩いの世界 重い大きな鎚で赤いカニを一撃したら 恋する女の心にちかづく〔39〕
*
父は芸術家アーサー・ヒューズ つくられたものアグネス ウサギのように毛のある服を着て おしっこしたくなる 春から夏まで キヅタの棚の下の召使たちの恋〔32〕
Ⅱ
テ ニソン夫人の姪アグネス・グレイス・ウェルド〔10〕は赤い乗馬頭巾とマントを着け 馬のうしろに幼い友だちを呼ぶ クロフト牧師館の使用人の娘 仇名は「コーツ」〔4〕 教授の娘エリザベス・ハッセー〔36〕 芸術家の娘エミイ・ヒューズ〔29〕 T・B・ストロング博士の姪ゾーイ〔26〕 ジョージ・マクドナルドの娘 髪がうまくとかせないアイリーン〔16〕 その姉メアリー〔28〕 パトニーの教区牧師の娘ベアトリス・ヘンリー〔14〕 エレン・テリイの妹たちマリオンとフロレンス〔46〕 リポン僧正の娘フローレンス・ビッカーステス〔54〕 ピュージー博士の孫娘ケイティー・ブライン〔60〕 ジョン・ミレーの娘メアリ〔51〕 クランボーン教区牧師の娘ディンフナ・エリス〔52〕
遅れてきたのは誰? あら支那の娘の扮装したアレクサンドラ・キッチン〔62〕だわ いとしのクシイー けさ水汲みに行って 最初に見たのはなんなの? 串の魚それとも舟を漕ぐ農夫 蝶を捕える青空の下の網 聞かせてよ 支那のウグイスはどんな鳴き方をするか? ペルシャ模様の八個の箱の上で 夢みるクシイーよ 川のほとりで最後に見たものはなんなの? あなた自身の肉体 その影に心があるようで ないように見える なまめかしくも幼い聖痕?
みんなでこれからキャロルおじさん〔1〕を探すのよ それは包帯で巻かれた幽霊群のなかで 副葬花束を持った人だわ!
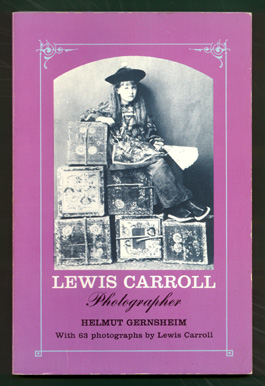
Helmut Gernsheim《Lewis Carroll―Photographer》(Dover Publications、1969)の表紙
新版の表紙になったのが「支那の娘の扮装したアレクサンドラ・キッチン〔62〕」だ(Ⅲ冒頭に掲載した写真はsignormori.clarence.comのアーカイヴからの別カット)。キャロルはこの箱に Chinese boxes(入れ子)の寓意をこめたのだろうか。ことここに至って吉岡の「支那の少女」はG・W・キッチン牧師の娘とうち重ねられ、ためにクシイーとアリスは詩篇においてその重みが吊りあった(キャロルには、リデル姉妹にも支那の娘の扮装をさせた写真があって、そこでアリスがまとっているのはクシイーと同じ衣装だ)。吉岡が高橋康也に語った、名前自体が詩の修辞になり得るという点に注目しつつ、写真のキャプションみたいなつもりで詩を書く、という点を見てゆこう。散文集《「死児」という絵》から引く。
①わたしの幼年のころの面影をしのぶ、唯一の古い写真が一葉のこっている。それは十歳位の兄と三歳位のわたしが、祭半纏、股引姿で、兄は鉢巻だが、わたしは花笠をかぶって、カメラのフラッシュにおびえたのか、大きな眼をみひらいている。(#A_25、六ページ)
②メリー・ピックフォード、純情ジャネット・ゲーナー、妖花ブリギッテ・ヘルム、清楚フランシス・ディ、シルビア・シドニー、明眸ジョン・クロフォード、アナ・ベラ、ミリアム・ホプキンス、銀髪ジーン・ハロー、キャロル・ロンバート、東洋の花アンナ・メイオン、マリー・ベル、春の調べのヘディ・キースラ、ドロテア・ウィーク、アンナ・ステン、マーナ・ロイ、ダニエル・ダリュウ、ルイゼ・ライナー、ジーン・アーサー、悲劇のコリンヌ・リュシェール……。(一八ページ)
③もし将来、わたしがあの残酷で滑稽な軍隊生活を書くとしたら、これら数葉の写真が一つの記憶をよみがえらせてくれるだろう。馬に乗ったのや、銃剣術をしている二十三歳頃の勇姿。防寒服姿で蒙古人然としたもの。最も印象的なのは、軍旗祭で芝居をしたときのものだ。まるでロシアの娼婦みたいに婉然たる女形姿もある。(四五~四六ページ)
④半ズボンの裾から回虫を垂らして、校庭を歩く男の子や新聞紙をからだに巻きつけて、放尿する女の子の姿態を見ていると、〈男生徒女生徒〉と呼ぶのがふさわしい時代の雰囲気がそれは色濃く《美しい日々》のなかに漂っていた。(一六三ページ)
⑤その絵は一種の白日夢である。――夏草の茂る林のなかの大きな木の幹のかげで、悩ましくも脱皮する裸の少女と、草むらに寝そべり、幼い陰茎に蝉をとまらせ、恍惚としている少年を描いた鉛筆画であった。(同前)
⑥それは地の泥に埋った、木の切株や胎児らしきものの形態である。(一六四ページ)
さて、⑤は《サフラン摘み》のジャケット装画に用いられた片山健の〈無題〉、⑥は同じく見返しに配した作品についての吉岡のキャプション、というより言語による描写であり創出だ。④は片山健の画集《美しい日々》からの衝撃に続く部分だが、これが詩になると次の姿を採る(⑩・18、初出時は無題で、題名は詩集収録時に付けられた)。
生徒|吉岡実木造の古い小学校の便所の暗がりで
女生徒は飛びあがりつつ小水をするんだ
もし覗く者がいるなら それは虎の仮面をかぶった神
男生徒は夏の校庭を影を曳きながら 歩きまわる
半ズボンの間から 回虫を垂らしつつ 永遠に
④の「時代の雰囲気」を出すために詩の方が書きこんであるが、初出の片山健個展案内状では《美しい日々》の一点の鉛筆画(#B_025、〔一○四~一○五ページ〕)とともに紙面を構成していた。一種のキャプションだ。
③の吉岡自身の写真は〈吉岡実アルバム〉(#A_32)に登場する。「わたしの大切なもの」として軍隊のアルバムを挙げる吉岡にとって、写真とは「その男に欠けた/過去を与えるもの」(〈過去〉③・17)のごときである。
②の列挙は写真と直接関係ないが、まさに〈少女伝説〉で獲得した方法の散文への転用だ(②が〈初出一覧〉で一九六六年とあるのは一九七六年の誤り)。
「こころみに先の少女たちの名前をもう一度つぶやいてみるがいい。耳をすませば、わたしたちのごく身近にその正確な反響が聞こえてくるはずである」(#B_084、一五二ページ)という一節を含む種村の〈どもりの少女誘拐者――ルイス・キャロルの場合〉が吉岡のアリス詩の誕生に大きく与っていることはすでにふれた。ここの「先の少女たち」とは、種村の著書に引かれた「九歳乃至十歳の少女ばかり」(同前、一五一ページ)の九つの、すなわち《ドウ》誌に紹介されている被写体だ。
「アリス・ジェーン・ド〔ママ〕キン、エリザベス・ヒュセイ、ベアトリス・ヘンレイ、アリス・コンスタンス・ウェストマコット、マリー・ミレー、イレーヌ・マクドナルド、エッフィ・ミレー、グレイス・デンマン、エイミー・ヒューズといった愛らしい名前をもったこれらの少女たちは、それぞれ成熟した女の着るようなドレスや、トルコ風、ギリシア風の衣裳に身を固め、あるいは物憂げに、あるいは夢見るように、大方は「囚われの女」の風情で、その幼い肢体を痛々しくさらしており、ときにはひそかにこじ明けた囚われの窓から、繩梯子伝いに「脱出」しようとしている演出場面さえあるではないか。/そう、どんなあからさまなポルノグラフィーより、それはわたしにとってポルノグラフィックであった。そこには外見の平穏な柔和さのかげに、ほとんど目をそむけさせるような衝撃的なエロチシズムと下等といっていいほどの犯罪的欲望が、いまにも均衡を破って姿をあらわそうと脅かしているように思えたのだ」(同前、一五一~一五二ページ)。
種村は「その正確な反響」は、ウラジーミル・ナボコフの《ロリータ》のラムズディル学校のクラス名簿を覗きみたハンバート・ハンバートのこの世ならぬ浄福を叙した一節に聞こえる、と指摘する。「キャロルの撮った少女たちの写真」がモンタージュの素材であるのはもちろん、その姓名は吉岡にとっての「クラス名簿」だった。現に〈わがアリスへの接近〉に《ロリータ》への反歌的部分が見えている。大久保康雄の訳によれば「それから、そのなかにかくれて、いつも鉛筆をなめ、教師たちからきらわれ、すべての男の子の視線を髪と首すじに集めている」(同前、一五三ページ)のがナボコフの小説の中年男にとっての「わがロリータ」であるとき、吉岡の詩の「わがアリス」は「鉛筆をなめながら/わが少女アリス・リデル/きみはたしかに四番目に浅瀬をわたってくる/それは仮称にすぎない/〈数〉の外にいて/あらゆる少女のなかのただひとりの召女!」だった。高橋康也は吉岡の発言をこう記している。
「ええ、そこへ『アリス』が来るわけですが、ああ、『静かな家』でも「少女」がそんなに何回も出てきますか〔文庫本で数えても六回、ほかにも「処女」や「姉」「妹」などがある〕。そう、少女エロティシズムか……だから、もともと悪い人間なんだな、私は〔「アリス詩」には「なまめかしくも幼い聖痕」「浄福の犯罪」といったキャロルの無意識を抉ったような句が見出せる〕。成人のストリップは見られるけど、少女のは見られない。願望というやつかな。へえ、キャロルは芝居好きだったの? ストリップがあったら、きっと見たろうね。ただ、アリスという少女そのものは、『アリスの絵本』の方の詩に書いたけど、ぼくにとって「非像」なんですね、「実像」というよりは。キャロルにとっても、そうじゃないかな、物語のアリスを肉付けしたり、丸味や厚味のあるものにしていないものね。写真の方はすごく実在感があるけど。ぼくなんか、美少女と接する機会はないんだけど、キャロルがやったように、こっちも少女をダシにしてやれっていう気持ね」(#B_081、三五九ページ。〔 〕内も高橋原文)。
これら、すなわちキャロルの《アリス》二部作、キャロルの撮った「アリスたち」の写真、種村の《ナンセンス詩人の肖像》中のキャロル論、ナボコフの《ロリータ》が引用(モンタージュこそヴィジュアルにおける引用だ)によって、吉岡実詩でも珍しい可憐でどこか哀切なタピスリに織りあげられた。そして素材と渡りあう新たな詩法の開発を可能にしたのが、装丁家(写真もレイアウトする)としての吉岡実だった。〈「想像力は死んだ 想像せよ」〉における次の述懐が指している地点こそ、詩篇〈少女〉と〈ルイス・キャロルを探す方法〉の分水線だ。
「ある時期から、詩を書きながら、私は自己の想像力の枯渇したことを感じた。今までは豊かなイメージの湧出に、愉悦とその定着への抑制に精神を集中すれば、私はそれなりの詩の生成に立会えた。しかしこの頃は他人の言葉の引用と、素材的資料、地名、人名を挿入しながら内なるリアリティの確立を試みているのである」(#A_25、八四ページ)。
「吉岡実がアリスに出合う前にも少女は吉岡実の詩にとって重要な要素であった。いまちょっと出典を見失ったが、「少女の脱脂綿にさわりたくなる」という刺激的なフレーズもぼくの記憶にある。要するに吉岡実は内在したみずからの少女にたまたま「アリス」という固有名詞を付したにすぎないかもしれない。そして象徴としての「アリス」によってみずからをヴォキャブラリーの自在な海へ解き放ったのである。ついでに引用詩にふれれば、「ニラ畑への〔ママ〕行隠れの」。この一行にぼくは吉岡実が敬愛する俳人永田耕衣の匂いをかぐ。吉岡実編による「耕衣百句」は名著だ。永田耕衣を読んだことがない詩人がいたら、そのひとはタイマンだ。さてぼくは吉岡実のアリス詩篇にすっかり参ってしまってあつかましくもそれを雑誌発表直後に吉岡さんに報告した。左はそれへの吉岡さんの返信の一部である。ふたたび非礼の罪を重ねる。
拝復 お手紙いただきながら、大変おくれましたことをおわびします。アリス詩ほめていただきありがとう存じます。いずれあと二、三篇を作って一冊の本を夢見ています。………
吉岡さんが夢みたアリス詩の一冊の本は実現しなかった。アリスの詩は一応は〈サフラン摘み〉に収録されてしまった。しかしぼくはいまだアリス詩の一冊の本の夢をみつづけている。いつの日か吉岡さんを説き伏せて美しい限定本を作る本屋さんの力をかりて一冊の美しいアリス詩集を作る仲立ちをしたいものだとぼくは夢みている」(#C_016、三八ページ)と鶴岡善久が書く「アリス詩集」をわたしたちも夢みようではないか。すなわち〈ルイス・キャロルを探す方法――わがアリスへの接近/少女伝説〉(⑧・11)、〈『アリス』狩り〉(⑧・12)、〈夢のアステリスク〉(⑨・22)、〈人工花園〉(⑩・19)、さらに書かれなかったアリス詩篇を。だがここではそれらを引用しない。かわりに〈少女〉の翌月に発表され、のちには手入れもなされながら、結局は詩集に収録されなかった〈スワンベルグの歌〉(未刊詩篇・12)の展開形を思わせる作品を引く。〈ピクニック〉(⑧・7)がそれだ。
ピクニック|吉岡実まるで音楽のように
アジサイの花の色は変る
過去のカテドラルのように
われわれの「偉大な悪と愛」の時代は終るだろう
夕焼の林のなかで
ウラジーミル・ナボコフは記述する
水浴せる少女の手から脚へ さらに届かないところへ
口は淋しく記号のような
パンセを求める
兎の毛の内部には
洋服を縫う針や形をととのえる
コテやハサミが
秩序よく収納されている
この家では女中がしゃべったり
しゃべらなかったり
長い靴下を干しにチシャ畑へゆく
草の上に置かれる一個の籠には
うまく焼き上った鶏冠の肉と
それをとりまく野菜の数々がある
これがピクニックのたのしみ
すすむ少女
ずるずる沈む中年男の夢枕
ゆるむ脱腸帯のまま
番人が柄杓を持って
青い水を汲みにきたりこなかったり
考えを替える川はながれ
石はとどまる
死垂る紫の葡萄棚の下で
シャワーを浴びる母娘を
遠巻きにして
われわれは「暗喩」に近い存在である
ヘアーピンの山をはるか
夜鷹がとび越える
わたしは画家の作品を見せてもらう為に、彼のアトリエに来ていた。――金井美恵子(#B_028、二七ページ)
発表場所が処処方方の新聞や雑誌の文章をまとめた書物の巻末に初出一覧が載っている。いつごろからの風習なのか詳らかにしないが、まことに好いものだと思う。著者や編集者の創意によって並べられた文章を、その要請する構成・順序から切りはなして、発表の順序や媒体を意識しながら読むことも可能だからだ。一体に創作家はその表芸である短篇小説集や詩集を編むのには熱心だが、エッセイや随筆に関しては編集者まかせということも少なくないようだ。吉岡実の随想集《「死児」という絵》(#A_21)の担当編集者だった詩人の八木忠栄が〈吉岡実〉に書いている。
あるときは特に用もなく、詩をめぐる雑談をし、あるときは雑誌の原稿依頼や装幀の相談でコーヒーを飲んだ。そんなふうに喫茶店でコーヒーを飲むなかで、あるとき「全エッセイをまとめませんか」という話を切りだした。吉岡さんはしばらく笑って相手にしなかった。しかし、私にしてみれば大まじめだった。編集者として十年以上おつきあいしていながら、まだ一冊も吉岡さんの本を担当する機会がなかった。
「吉岡さんの本を、是非ぼくにも作らせてください」と執拗にくりかえした。「いやあ、ぼくのエッセイなんか、小さい出版社で趣味的な本にして出すのがいいんだよ」という返事。お酒で口説くならともかく、コーヒーで口説くのはむずかしい。しかし、私はあきらめなかった。吉岡さんのエッセイの発表誌紙を調べあげ、初出リストを作ってお見せした。
「そこまで言うんなら、八木君が思潮社にいるかぎり任せるよ」という返事をもらったときは、まるで鬼の首でもとったような感激だった。
『「死児」という絵』上梓まで四年余りかかった。その間に吉岡さんは定年退職された。A5判、三四五ページ、大冊の初エッセイ集になった。書名は陽子夫人による。装幀はもちろん著者。貼函には、書名にちなんでM・スタンチッチの奇妙な絵「死児」の写真が飾られた。(#B_154、一七~一八ページ)
吉岡が「この四、五年の間、きわめて怠惰な私をたえず叱咤激励し、散逸した文章を丹念に集め、編集してくれた、八木忠栄に感謝する」(#A_21、三四五ページ)と〈あとがき〉を結んだように、元版随想集のⅠ〔生い立ちの記〕、Ⅱ〔詩作をめぐるさまざま〕、Ⅲ〔愛読した短歌俳句について〕、Ⅳ〔西脇順三郎はじめ詩人との交流記〕という構成(ただし〔 〕内は原本になく、筑摩叢書〔増補版〕刊行案内から引いた)には吉岡の意見も反映されていようが、原案は回想文に見える気合いからいっても、八木によるものだろう。増補版で追加された三二篇がⅤとして括られながら、そのなかがⅠからⅣに準じて小分けされていることからも、著者は元版の構成に満足していたと思われる。
さて、吉岡実の詩集の編みかたについてである。以前にも触れたが、第六詩集《静かな家》までは基本的に発表順、ということはあらかた執筆順、が採られていた。ただし巻頭巻末に据えた詩篇が眼目なのは言うまでもなく、わけても掉尾をなにで飾るかが重要だった。吉岡の詩集観を知るには、平出隆が伝える逸話が適切である。飯島耕一の《ゴヤのファースト・ネームは》の「「サイトウ・モキツ」は詩集の最後におかれた作品。詩集編集過程で幾人かの親しい詩人が、この軽みの詩は前にもってきて「前橋へ」のようなまとまりの大きな詩で終るようにしたら、と忠告した。飯島氏は頑として聞かなかったという」(#B_007、一三四ページ)とあるように、吉岡は飯島とは異なって〈死児〉(④・19)や〈悪趣味な内面の秋の旅〉(⑧・31)や〈青海波〉(⑪・19)のような「まとまりの大きな詩で終る」ことを好んだ。あるいは「まとまりの大きな詩」を書きおえるまでは、吉岡は詩篇を編んで詩集とすることができなかった。全一二冊の詩集がそれを物語っている。ちなみに大岡信・入沢康夫・天沢退二郎・平出隆の四詩人が討議の前作業として選んだ吉岡詩を基に編まれた〈代表詩40選〉(#A_32)には、全部で一二篇の詩集巻末の作品から以下の③・④・⑧・⑨・⑪・⑫が採られている。
①昏睡季節2
②夢の翻訳
③過去
④死児
⑤修正と省略
⑥静かな家
⑦コレラ
⑧悪趣味な内面の秋の旅
⑨円筒の内側
⑩ツグミ
⑪青海波
⑫〔食母〕頌
〈静かな家〉(⑥・16)は一九六六年四月に発表(執筆は早くも一九六二年一月)、〈コレラ〉(⑦・18)は一九六九年一○月に執筆、一二月付で発表される。われわれはいま、⑥と⑦の間にいることになる。
吉岡実は一九六九年二月号の《婦人公論》に詩〈スワンベルグの歌〉(未刊詩篇・12)を、三月には《本の手帖》二・三月号に〈三重奏〉(⑦・17)を発表した。一月には〈少女〉(⑦・5)が《血と薔薇》に載っているから、かなりのハイペースだ。四月の〈蜜はなぜ黄色なのか?〉(⑦・12)で詩篇発表は四ヵ月連続となって、一○年前に《僧侶》がH氏賞を受賞した後のころのような活況を呈している。〈スワンベルグの歌〉の初出形から見よう(なお〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕、およびライナーは便宜的に論者が付けたもの。〔Ⅰ〕初出=《婦人公論》一九六九年二月号(五四巻二号)〈MY POESY/まい・ぽえじい・2〉〔二二○~二二一ページ〕、〔Ⅱ〕再録=《ユリイカ》一九七三年九月号(第五巻第一○号)〈神秘的な時代の詩・抄〉一六八~一六九ページ)。
スワンベルグの歌〔Ⅰ〕|吉岡実ものの成熟について 1
ひとは考えるべきだ! 2
桃が籠のなかで 3
甘いビラン状になるとき 4
老人司祭の死の舌が必要か? 5
ひとりの男と女の恋 6
暁の熱い舟をつくり 7
そこでももいろの花火をかぶる 8
それらはきっと 9
すすまず浮かばず 10
聖なる母の毛のかたまりをすべる 11
星も輝かない 12
ももいろの氷の世界 13
ももいろの中年 14
ゆがんだ弓なりの 15
やがて美しい五月が来るだろう 16
緑の布の上に 17
両側から吊される 18
なよなよとした双曲線の乳房 19
青空の孔から 20
ああなやましく 21
想起せよ 22
花模様の一角獣 23
水をたらす 24
ビニールの漏斗で 25
ももいろの電話機の声 26
それから深夜 27
それからレモン 28
それから涙 29
暗い靴下をはいて 30
さびしい少年が来るんだ! 31
遠景の円柱を廻って 32
包帯のなかの処女性を 33
求めて・・・・・ 34
※スワンベルグスワンベルグの歌〔Ⅱ〕|吉岡実
ものの成熟について 1
ひとは考えるべきだ! 2
桃が籠のなかで 3
甘いビラン状になるとき 4
老人司祭の死の舌が必要か? 5
ひとりの男と女の恋は暁の熱い舟をつくり 6
そこでももいろの花火をかぶる 7
それらはきっと 8
すすまず浮かばず 9
聖なる母の毛のかたまりの間をさまよう 10
星も輝かない 11
ももいろの氷の世界にとじこめられる 12
ももいろの中年の鳥 13
ゆがんだ弓なりの 14
やがて美しい五月が来るだろう 15
緑の布の上に 16
両側から吊るされる 17
なよなよとした双曲線の乳房 18
夕日のなかの 19
なやましい頭韻 20
その花模様の花に 21
水をたらす 22
ビニールの漏斗で 23
ひとは老衰すべきだ! 24
錫の皿を廻し 25
もろもろのももいろの電話機の声 26
それから深夜 27
それから疑似果実 28
それから涙 29
暗い靴下をはいて 30
さびしい少年が来るんだ! 31
遠景の円柱を廻って 32
包帯のなかの処女性を 33
求めて・・・・ 34
スワンベルグとは幻想の画家マックス・ワルター・スワーンベリ。初出末尾はいかにも途中で切れた感じだ。当然「※スワンベルグ」のあとに、注記の原稿が書かれてあったのだろうが、詳細は不明だ。スワーンベリは一九一二年スウェーデンに生まれた。一九七六年春にはグリフィンス・コーポレーションによって銀座フマ・ギャラリーで日本初の展覧会が開かれ、七月には澁澤龍彦編著《M・W・スワーンベリ》(#B_060)が河出書房新社から出た。その〈シュルレアリスムと画家叢書〉のカタログに曰く「イマジスト・グループの創設者。奔放な想像力の限りをつくして女の夢想を追い求める北欧のヴィジォネール。妖しく燃える女の抑圧されたリビドーを絢爛たる装飾的イメージの中に描き出す第一人者。真珠モザイクや「イルミナシオン」の挿絵は白眉である」。
詩篇とスワンベルグはいかなる関係にあるのか。〈吉岡実の近作をめぐる二、三の感想〉で〔Ⅰ〕の精緻な読み(「彼は、一方では、このような加速と促進と飛躍とにつとめていながら、また一方では、それらのイメージに、隠密かつ周到に、一種残酷な出発禁止をも課してもいるのであって、この二つの志向の共存が、彼の詩に、明るさと苦さとの混りあった、緊張とも弛緩ともつかぬ、独特の味わいを与えている」#C_039、一二六ページ)を開陳した粟津則雄も、題名の考察はしていない。われわれにはM・W・スワーンベリというパラメータを詩篇に導入することが必要だ。
澁澤龍彦がわが国にスワーンベリを紹介した初の本格的なエッセー〈空間恐怖と魔術――スワンベルクとブロオネル〉(初出は《新婦人》一九六五年九月号〈幻想の画廊から〉第九回。ただし澁澤は当時はほかでも「スワンベルク」と表記しているから、吉岡詩の典拠は飯島耕一の〈スワンベルグの汎女論的世界〉(#C_034)の可能性が高い)で書いている。「まず、スワンベルクの描く絵には、ほとんど必ず妖しい魅惑の女が登場していることに注目したい。レモンのような紡錘形の乳房を張り出し、胸をぐっと反らし、顎をあげて、ややのけぞった姿勢の少女めいた女は、スワンベルクの無意識のなかの女の原像であるかのようにも思われる。それは時にエロティックな法悦の姿勢をすら思わせるが、童話のように抽象的に様式化されていて、生まの肉感とはきわめて遠い。画家の好む「想像妊娠」という題名が示す通り、目の大きい、首の長いこれらの少女たちは、ともするとダフネ・コンプレックスにとり憑かれた潔癖な処女たちであるかもしれない。〔……〕そこにはシンメトリイと、同じイメージの分裂増殖と、花冠のような放射状ないし求心的な形体に対する偏愛も見出される」(#B_058、一〇ページ)。澁澤はまた〈女の楽園〉では「天使的な冷たさ」を言い、それが「静的な印象ともつながる」(#B_060、二四ページ)と指摘する。吉岡の〈スワンベルグの歌〉はその「レモンのような紡錘形の乳房」を取りこみながら、これもまたスタティックな祝祭の趣だ。
冒頭の「ものの成熟について/ひとは考えるべきだ!」は粟津も指摘したようにかつての〈静物〉(③・1)を踏まえつつ、後半で「ひとは老衰〔漏水にあらず〕すべきだ!」と変奏される。「もの」とは桃であり、話者でもある。「老人司祭の死の舌」とはなに。教会で儀式は行なわれないまま、処女の肌のように傷みやすい果実は爛れてゆく。そもそも桃は司祭のために供されたのではなかった。水のうえに横たわる男が司祭でないと誰に言えよう。籠のなかの桃が崩れつつあるとき、舟の上の男女は「成熟」しているのだ。音もなく停る舟の進行。果物も永遠に腐ることができない。マリアがイエスを産んだあたりは闇の世界だ。どこにも行くことができない。それも外から見ればももいろだ。身を反らせた鳥までいるではないか。初夏には氷も解け、木木も芽吹いた。巨大な乳房の下の布。ふたつのリズムのような乳暈に夕陽がともる。花弁には水を、一角獣の角のように。現世の食事を終えると、ほうぼうから電話が架かってくる。また闇が落ちてきて、桃のようなもの、レモンのようなもの。涙も少し。額に星形の塩を浮かべた少年まで来る。成熟するために、ひとを老衰に導くために――。
この展開はスワーンベリの世界というよりは、あまりに吉岡の世界である。三○行め以降は前作〈少女〉の残響も揺曳しつつ、のちの〈サフラン摘み〉(⑧・1)の異稿と言っても通用しそうだ。〔Ⅱ〕掲載の前前月にあたる一九七三年七月の《現代詩手帖》に発表された吉岡実一代の傑作に〔Ⅱ〕の結末が影を落としている。
吉岡が繰りかえしを嫌ったのは、詩句のレベルにおいてだけではない。本篇は作者自身による〈静物〉(③・1)や〈僧侶〉(④・8)などへの明白な反逆である。「『静物』か『僧侶』に戻っていってああいう詩を書きなさいといわれるけど、あれはあれ、しかたないわけよね、もう」(#C_039、一五八ページ)。それは過去の自己の作品世界に対してである以上に世人の吉岡詩理解に対する反撥であった。〔Ⅰ〕の前月発表の〈少女〉は初出形に相当の手入れを施して《神秘的な時代の詩》で定稿化された。対して〈スワンベルグの歌〉は「少年」が思わせぶりに登場するにもかかわらず、詩集という最終的な処を得なかった。詩人にとって桎梏と化した過去のある時期への反逆は試みられ、「吉岡実」総体は揺さぶられ、その構造的変革は達せられた。〈スワンベルグの歌〔Ⅰ・Ⅱ〕〉の扱いからは、そうした経緯さえ見えてくる。所期の目的が叙上のようであってみれば、おそらくどんな内容の作品であっても斥けられざるを得なかった。
《神秘的な時代の詩》のほとんどの詩篇が刊本収録以前に次のどちらか、
・〈未刊詩篇から〉(現代詩文庫版《吉岡実詩集》、一九六八年九月一日、思潮社)――以下Aと書く
・〈神秘的な時代の詩・抄〉(《ユリイカ》特集吉岡実、一九七三年九月号、青土社)――以下Bと書く
に再掲されたなかにあって、〈スワンベルグの歌〉だけは詩集に収められる際にBから脱落して、以後は拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》を含めていかなる形でも刊行されなかったという特異な履歴を持つ。いい機会だから、詩集を構成する各詩篇の再録状況を整理しておこう。まずAがまとめられた時点での既発表作品は、発表順に次の六篇(ただし(6)の発表紙とAとでは、発表紙の入稿の方があと、つまりAの作品取りまとめ時には(6)はまだ執筆されていなかったと考えられるので、厳密には五篇)。
| (1) | 青い柱はどこにあるか?(⑦・6) | 1967年7月 | |
| (2) | 夏から秋まで(⑦・2) | 1967年8月 | |
| (3) | 立体(⑦・3) | 1967年10月 | |
| (4) | マクロコスモス(⑦・1) | 1967年11月 | |
| (5) | フォークソング(⑦・7) | 1968年7月 | |
| ▲ | (6) | 色彩の内部(⑦・4) | 1968年8月 |
A〈未刊詩篇から〉では(3)の〈立体〉が繰りあがって冒頭に据えられた結果、
| (3) | 立体(⑦・3) | |
| (1) | 青い柱はどこにあるか?(⑦・6) | |
| (2) | 夏から秋まで(⑦・2) | |
| (4) | マクロコスモス(⑦・1) | |
| (5) | フォークソング(⑦・7) |
の順になった。Bの末尾に付された〈注記〉では「詩集『神秘的な時代の詩』は、ここに掲載された作品のほかに、すでに思潮社版『現代詩文庫14・吉岡実詩集』に収められている「マクロコスモス」「フォーク・ソング」「夏から秋まで」「立体」〔(4)~(5)~(2)~(3)〕および、現代詩手帖に発表された「わが馬ニコルスの思い出」〔(15)〕などを含み、湯川書房より刊行される予定である」(#C_039、一七一ページ)と、解体されてしまった。土方巽の詩画集《あんま》(#B_121)に再録された(1)を省いて、(3)を(4)+(5)と入れかえたうえ、集中最長の詩篇すなわち1969年10月発表の(15)〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)を追加すると〈注記〉の順番になるが、これとて詩集のオーダーには活かされなかった。B〈神秘的な時代の詩・抄〉を編む時点でこれらすべての詩篇は発表されていたから、Bの本文とその〈注記〉からの遺漏は次の四篇となる。
| ▲ | (9) | 雨(⑦・9) | 1968年11月 |
| ▲ | (10) | 少女(⑦・5) | 1969年1月 |
| ▲ | (14) | 夏の家(⑦・13) | 1969年8月 |
| ▲ | (19) | 弟子(⑦・15) | 1972年8月 |
〈スワンベルグの歌〉は残るBの九篇中に含まれており(詩集は一八篇から成るが、〈スワンベルグの歌〉を含めると一九篇)、B〈神秘的な時代の詩・抄〉本文のオーダーは、詩篇の発表順とも初刊詩集の並び順とも異なっている。すなわちこうだ。
| (18) | 低音(⑦・14) | 1970年3月 | |
| (7) | 神秘的な時代の詩(⑦・11) | 1968年10月 | |
| (12) | 三重奏(⑦・17) | 1969年3月 | |
| (13) | 蜜はなぜ黄色なのか?(⑦・12) | 1969年4月 | |
| (8) | 崑崙(⑦・8) | 1968年10月 | |
| (6) | 色彩の内部(⑦・4) | 1968年8月 | |
| (11) | スワンベルグの歌(未刊詩篇・12) | 1969年2月 | |
| (16) | 聖少女(⑦・10) | 1969年11月 | |
| (17) | コレラ(⑦・18) | 1969年12月 |
これら(A→B→詩集)の複雑きわまる変遷はなにを意味しているのか。単に新しい詩集の構成に、その時時の吉岡が腐心したというだけのことなのか、いまは明快な回答を持ちあわせていない。詩集における並び順は、別項を設けて論じたい。
〈スワンベルグの歌〉が、〔Ⅰ〕から〔Ⅱ〕への手入れにもかわらず詩集編入とならなかった点について、〔Ⅰ〕を調べよう(〔Ⅱ〕になったのは〔Ⅰ〕の直後、つまり〈三重奏〉(⑦・17)発表のころとは考えにくく、おそらくはBの直前だろう)。前作〈少女〉の四二行に対し〔Ⅰ〕は三四行と似たようなサイズで、掲載誌の判型こそ違うものの両者とも見開き誌面であり、コラムなどを除けばほぼ最短の詩行から成る(詩集《神秘的な時代の詩》の各詩篇の算術平均は六五・五行)。そこから詩句の展開が急であることが生じる。イメージが飛びちってゆかないように繰りかえしも出てくるが、狙いほど成功していないようだ。スワーンベリ特有の、宝石や貴金属を象嵌したような冷たいマチエールも「ももいろ」のためか、ぼんやりとしている。作品のテーマは中年男の恋物語のように読める(そういえば〈少女〉の削除された詩句に「声する恋の夕暮れの」があった)。「そこでももいろの花火をかぶる」の詩句がチャーミングで、「塵とくもの巣を頭から傘のごとくかぶる時/ぼくの家系は秩序をうしなうだろうか」(〈喪服〉④・15)が高柳重信の《伯爵領》の句「遂に/ 谷間に/見出だされたる/桃色花火(花火の谷間Ⅲ)」(#B_082、九三ページ)と出あった按配だ。そのような断片的なことを言っていてもしかたがない。が、なぜこの題名なのかという疑問が残っている。スワンベルグ、そして歌。「聖なる母の毛のかたまりをすべる」の「をすべる」が「の間をさまよう」となったことで、いまや「ス」ワン「ベル」グの行き処がなくなった、詩篇の定位置が詩集にはなく、さまよっている――というのは付会だが、スワーンベリではなくスワンベルグでなければならなかった理由のひとつにはなろうか。
〈ポール・クレーの食卓〉(⑩・1)以来の、泰西の画家の名を標題に据えた詩篇の試みは頓挫し、この次われわれが接することができるのは〈ゾンネンシュターンの船〉(⑧・24)となる。
吉岡に〈枇杷男の美学〉なる河原枇杷男論があって、その一節に「当時私は一本〔処女句集《烏宙論》〕を贈られて、感想を求められた。その文章が今見つからないので、いかなることを書いたかは忘れたが、ただ一つ「空洞の美学」であるといったことが記憶に残っている」(#A_25、一三○ページ)とある。その逸文、一九六九年二月の《琴座》二二六号の〈続烏宙論愛語抄〉全文はこうだ。
句集「烏宙論」通読して独自な世界をつくられているのに感銘、一言でいえば、空胴の美学と思います。好きな句を抄します。
骨ごときものを蔵して梨静か
外套やこころの鳥は撃たれしまま
心身の大部分は水碧揚羽
めし時暖く断崖に母尾を垂らす
母の忌の蛍や籠の中を飛ぶ
野菊まで行くに四五人斃れけり(#C_048、一二ページ)
文中「空胴」は誤植ではなく、吉岡の書き癖と思しい。以前にも触れた「ナチスの制服の人型の空胴の青空を見よ」(〈フォークソング〉⑦・7)もそうだが、ここでも吉岡はどうやら空虚な人体を想定しているようだ。吉岡は〈枇杷男の美学〉の他のところで、彼の作品は「外側の風景や自然を描いているというよりも、常人には視えぬ内部の物のいのちの生成消滅の神秘を、みごとに捉えていると思う。シュルレアリスム的な「外套やこころの鳥は撃[ママ]れしまま」を一つの頂点に、枇杷男の作品を「空洞の美学」とかつて評したのも、あながち私の思いつきだけでないことを、改めて認識した」(#A_25、一三〇~一三一ページ)と回顧しているが、ここで注目しなければならないのは吉岡の読みの鋭さ・不変ではなく、「空胴/空洞の美学」という揚言である。
・長いボール紙の筒があるかね?(〈マクロコスモス〉⑦・1)
・肉の入らない記念碑をなでる(〈夏から秋まで〉⑦・2)
・内視の肉を輝かせよ!(〈立体〉⑦・3)
・手足のない水着類の干してある(〈色彩の内部〉⑦・4)
・樹と外套でかこわれて/ブルガリヤ人の男根は立ち/孔雀の羽は散乱する(〈少女〉⑦・5)
・つとに死んだカンガルーの/吊り袋のなかをのぞけ(〈青い柱はどこにあるか?〉⑦・6)
・処女の子宮をふさがんとする(〈フォークソング〉⑦・7)
・ハリボテのハンバーグをつくる(〈崑崙〉⑦・8)
・美しき夫人の/かがやく鍾乳洞(〈神秘的な時代の詩〉⑦・11)
これらに見える空虚な人体や肉体の内部空間こそ「生成消滅の神秘」の場所であり、吉岡はこの時期、河原枇杷男の《烏宙論》に「空胴/空洞の美学」なる一語をもってそれに反応したのである。
〈三重奏〉(⑦・17)は〈スワンベルグの歌〉と枇杷男句集の感想の翌三月、《本の手帖》一九六九年二・三月合併号に発表された。編集・発行人の昭森社社主・森谷均は編集後記で、同じ版元から出ていた《詩と批評》の刊行中止を一月に決意したと述べてから「自然、同誌に寄せられた西脇順三郎先生以下の諸作品に新たに二十数人の新作を加へ、こゝに特集「現代詩集」を編んでわれらが詩に対する尊敬と愛惜の一端を表明するものである」(#C_031、一三○ページ)と口述したが、この年三月二九日に七一歳で長逝。吉岡は青山斎場での友人葬に参列している。詩篇は前出〈神秘的な時代の詩・抄〉に収められてから、詩集(一九七四年の限定版、一九七五年の特装版、一九七六年の普及版)を経て、《新選・現代詩文庫 110 吉岡実詩集》(#A_18)とその増補版にあたる《現代詩文庫 129 続・吉岡実詩集》(#A_28)に収録された。初出は雑誌の方針からか拗促音も並字で組んであって、最終行の「帚」が詩集で「箒」と変わったほかは、特筆すべき異同はない。このところ〈少女〉〈スワンベルグの歌〉と手入れが多かったが、初出がそのまま定稿となる傾向は、吉岡詩全体としては珍しくない。
三重奏|吉岡実わたしは自分の描いた絵を 1
見てもらいたいので 2
女友だちを家につれてくる 3
その女友だちはバカにして笑った 4
わたしの絵は観測というものでなく 5
むしろ昆虫群 6
わたしは女友だちに絵の構造を説明すべく 7
本物を見せる 8
それはピンクの長方形 9
やわらかくなると同時に 10
寒ざむとキララ色の袋に収まる 11
その縄文模様 12
この夜のムーヴマン 13
だから愛とは熱く 14
油絵具のなかにたむろして 15
出る骨をくるむ 16
女友だちは絵よりも蝋化した 17
観念がすきだといって 18
わたしのベッドを塗り変える 19
それがヴァイオレットなら 20
ヴァイオレットの乳房 21
鉄の歯のようなものを 22
にょきにょき生やす 23
絵としてわたしが描いた心 24
低い空でも処女は犯せるか! 25
鉄砲ユリの奥は深く 26
わたしの絵はぬれることを知らない 27
表面というものがない 28
闇を所有しているわけでもないから 29
すくなくともわたしには持ち歩くことができる 30
おそらく女友だちには 31
それはできぬだろう 32
絵のなかの馬がそれを拒む 33
母が息子を拒み 34
息子が父を拒み 35
サボテンが露を拒むように板の下を 36
日と河がながれる 37
わたしは淋しいことは絵に告げ 38
死にたいときは 39
絵のうしろを歩く 40
そのときはきまって 41
暴風雨がくる 42
女友だちは明日は帰ってゆくだろう 43
彼女の行手に立ちはだかる 44
わたしの絵のなかの森の道へ 45
女友だちが手をひく 46
娘のような妹は悪霊だな! 47
こちらをふりかえって 48
鼻血をたらす 49
わたしは便所へかけこみたい感じだ 50
彼女たちの前で 51
なぜわたしの描いたものを絵といったのか! 52
それはすみからすみまで肉化 53
されたものであって 54
輝やくバクテリアではなかったか? 55
細い管と太い管で編まれた 56
長い長い人生のトンネルかもしれず 57
光学的には暗く 58
建築的にはもろく 59
自然的にも不自然で赤く 60
わたしが無意識的に模倣している 61
女友だちのこれから 62
作りつつある再生芸術だろうか? 63
彼女たちが午餐をすませて 64
水着で泳ぐのを 65
わたしは見に行くんだ 66
女友だちの娘のような妹の 67
孕んだ腹を裂くよ 68
夏とはそんな一日であることを 69
感謝しながら 70
みずみずしい箒を買ってくる 71
〈三重奏〉の顕著な特徴が、筋のある話であることは見やすい。吉岡詩と筋のある話とは奇妙な取りあわせだが、長詩(〈僧侶〉でも〈感傷〉(④・18)でも〈死児〉でも)には避けがたく話の筋が混入している。だが〈三重奏〉はそれらとは異なり、はなから筋のある話を構築しようとする意思が見える。吉岡は一九八○年、金井美恵子との対談〈一回性の言葉〉で次のように述べている(吉岡発言の「中期」は、わたしのクロノロジーでは「前期」に相当する)。
自分の使いたくない言葉というかタブーはいくつかあるんだよね。/ここでぼくの秘密を公開すれば中期までの作品は、たとえば「魚」が出たら二度と「魚」は出ないし、「窓」が出てきたら二度と「窓」は出てこないというように、すべて一回性で来ている。同じものを繰り返さないのが特色なの。おそらく皆無ですよ。一回出てきたらそれはもう出てこない。/〔……〕/だから、意識的に卵の詩を書く場合は卵が何回か出るけど、多くの詩の場合は、「薔薇」なら「薔薇」でもいいや、それが一度出たらもう出てこないはず。極力避ける。それがぼくの詩を弱くしているってこともあるかな。詩には繰り返しの強さというものがあるわけだけど、ぼくの潔癖性が繰り返しを避ける。だから将来コンピューターで調べてくれる人がいたらわかると思うけど(笑)。(#C_010、九八ページ)
詩篇に登場するのは、三人の人物とそのうちの一人である「わたし」が描いた「絵」だ。三分の二あたりまでは「わたし」「女ともだち」「絵」の話だったのが、それ以後は「わたし」「女ともだち」「女ともだちの娘のような妹」の話に変化している。
「わたし」が描いたと思い、読者であるわれわれも読んだと思っているものは絵なのか。詩篇にはいたるところに仕掛けが施してあって、描かれた画面には焦点を合わせがたい。吉岡の書きぶりからは、絵をめぐるひとつひとつの謎解きが読者に任されている(「持ち歩くことができる」にもかかわわらず、「女友だちを家につれてくる」のはなぜか。人目をはばかる絵なのか)。作品から与えられる要素を画布に構成していった挙句が、「彼女たちの前で/なぜわたしの描いたものを絵といったのか!」に至って、絵ではない別物の気配が立ちこめてくる。女体のようでもあり、音楽のようでもある別物。それは作者から解決を与えられないまま終わってしまう。吉岡詩には珍しく筋のある話が導入されていながら、わけのわからなさにかけてはそうでない(吉岡にとっては普通の、それ以外の詩人にとっては特異な「一回性」のスタイルの)詩篇におさおさ劣らないのが、この詩篇である。われわれは新しい読み方を開発しなければならない――と言ったところで、妙案があるわけではなく、地道に詩句をたどっていくしかない。今度は絵を気にしすぎないように、他篇の詩句も思いだしてみれば、詩は別の表情を見せてくれるかもしれない。
*
・「その指ききにあらゆる物体が溶化し/て虚空に剥奪される神々は軽く震揺/し累積された存在が瞬間の映像と接/触する血液が氷下で計量され枝を離/れる二重奏は緑の帽子に均衡を失い/夥しい両側の皮膚が透かしになりな/がら植物類へこぼれ忘れた約束と薄/明を華麗な王冠にうけまもなく地図/へおりてくる子供らを季節風にめく/られた金属で支え換気筒を出てゆく/朝の驢馬を音もなく粉砕する水の上」〈液体Ⅱ〉(②・27)――吉岡実の詩句に三重奏の用例はほかになく、ここに二重奏があるだけだ。
・わたしは自分の描いた絵を/見てもらいたいので/女友だちを家につれてくる。
「わたしの部屋に一枚の小さな絵が掛けてある/だがこの絵を見た人はいない/この絵を描いた画家だって見たとはいえない/ただマチエールを造っただけだから」〈フォーサイド家の猫〉(⑧・17)――画家のアトリエで絵を見る女友だち、が存在するか。
・その女友だちはバカにして笑った。
「わたしは不可視のものを/笑ったりしないだろう」〈滞在〉(⑥・7)――すべからく見えるものは笑われるべきだ。
・わたしの絵は観測というものでなく/むしろ昆虫群。
「生きている空間のピンク色より鮮やかに/その昆虫は負の形態の固定観念を示し/輝く徐々に」〈悪趣味な冬の旅〉(⑧・6)――随想〈昆虫の絵――難波田龍起〉(#A_25)が想起される。
・わたしは女友だちに絵の構造を説明すべく/本物を見せる。
「わたしは複雑な構造のものは嫌いだ/単純なものは/月の光を浴びてよく見える」〈子供の儀礼〉(⑨・4)――絵と本物、それらの互いに異質なもの。
・それはピンクの長方形/やわらかくなると同時に/寒ざむとキララ色の袋に収まる。
「これこそうすももいろの絵」〈恋する絵〉(⑥・15)――桃色の画面から雲母色の子宮への移行。
・その縄文模様/この夜のムーヴマン。
「しかしマダム・レインの所有せんとする/むしろ創造しようと希っている被生命とは/ムーヴマンのない/子供と頭脳が理想美なのだ」〈マダム・レインの子供〉(⑧・5)――動く模様と動かない生命の逆転の構図。
・だから愛とは熱く/油絵具のなかにたむろして/出る骨をくるむ。
「偶然の配色の緑や黄のもやから/一人の女が生まれる/〔……〕/その女の腰から左右に突きでる/棒の両端にとまる鳥」〈狩られる女――ミロの絵から〉(⑤・18)――生成する絵画。
・女友だちは絵よりも蝋化した/観念がすきだといって/わたしのベッドを塗り変える。
「「花嫁」/わたしの一番好きな〈観念〉!」〈田園〉(⑧・14)――マルセル・デュシャンの〈エナメルを塗られたアポリネール〉(#B_115、図版19)がスルスか。
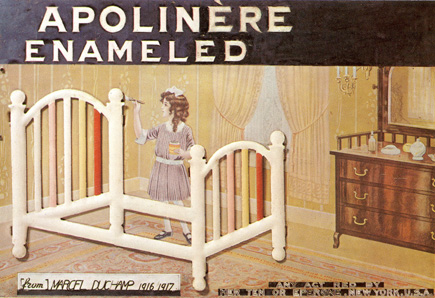
マルセル・デュシャンの既製品(広告)〈エナメルを塗られたアポリネール〉(1916~17)
出典:日本アート・センター編《デュシャン〔新潮美術文庫〕》(新潮社、1976)
・それがヴァイオレットなら/ヴァイオレットの乳房。
「わたしたち再びうまれるとしたら/さびしいヴィオレット色の甘皮からだ/それはいじるより見る方が美しい」〈聖母頌〉(⑥・6)――デュシャンにあらず。最もクロヴィス・トルイユな色、紫。
・鉄の歯のようなものを/にょきにょき生やす。
「男児ならば鉄の歯を生やしている」〈青枝篇〉(⑪・4)――歯のあるヴァギナ。交合への、膣への恐怖か。
・絵としてわたしが描いた心/低い空でも処女は犯せるか!
「言語がはらむ/観念の内容をつきとめよ/「処女陵辱」/この文字は美しい」〈円筒の内側〉(⑨・28)――凌辱、は観念の運動である。
・鉄砲ユリの奥は深く/わたしの絵はぬれることを知らない。
「匂いのつよいテッポーユリ/の全開期」〈内的な恋唄〉(⑥・12)――行末の句点は次節に係る読点であるべきかもしれないが、こうしておく。
・表面というものがない。
「「肉体はいかなる/〈表面〉をも有していない」/多くの人もその断面を眺めるだけだ」〈使者〉(⑨・18)――表面はどこにある。表面は遍在している。
・闇を所有しているわけでもないから/すくなくともわたしには持ち歩くことができる。
「人はそれでは/「きみの所持する絵は/万有の闇のベールの向うに/存在するだけではないか」/と反問する」〈フォーサイド家の猫〉(⑧・17)――前節の句点も本節に係る読点かもしれない。
・おそらく女友だちには/それはできぬだろう。
「もしあの時/凍れる肉屋の/(心的[メンタル]な空間)を想起していたら/おそらく/「泳ぐ女や/唇から垂れる蜜」/を描いていたかも知れない」〈叙景〉(⑫・11)――絵の人物にどうして「それ」ができよう。
・絵のなかの馬がそれを拒む。
「裂かれたカンバスよりもっと永遠でない闇から 愛撫する馬の腹へ わたしは口をつけて囁く」〈馬・春の絵〉(⑥・5)――むろん馬にもできようはずがない。
・母が息子を拒み/息子が父を拒み/サボテンが露を拒むように板の下を/日と河がながれる。
「ぼくは生まれる/ところをえらばずに火事の家で/やがて水平になってゆく/板の下の聖なる母」〈家族〉(⑩・11)――サボテン:露=日:河、か。
・わたしは淋しいことは絵に告げ/死にたいときは/絵のうしろを歩く。
「画家の高熱期も終り/わたしは現在をさびしい時代だと思う」〈模写――或はクートの絵から〉(⑥・4)――絵画による慰撫から、絵画を慰撫することへ。
・そのときはきまって/暴風雨がくる。
「子供二人を先頭にして/やってくるのだ/春の嵐!」〈静かな家〉(⑥・16)――かように現世はつねにたちさわいでいる。
・女友だちは明日は帰ってゆくだろう、彼女の行手に立ちはだかる/わたしの絵のなかの森の道へ。
「受胎せるタコのメスは海の底の石の巣へゆっくり帰って行く 二十万粒の透明な卵を生むために」〈タコ〉(⑧・2)――書肆山田版詩集の出版広告で引かれた詩句。ポール・デルヴォーが木立の中の機関車を描いた油彩画〈森のなかの駅〉(#B_135、図版27)が想起される。
・女友だちが手をひく/娘のような妹は悪霊だな!
「(女と聴いた音楽会の/赤い薄ぺらな切符)/それは(悪霊)を退散させる/(護符)であるかもしれない」〈落雁〉(⑪・17)――「句集『悪霊』には「死蛍に照らしをかける蛍かな」の呪術的な妖気があり」(#A_25、三一一ページ)と〈耕衣粗描〉にある。女友だちとその娘のような妹。いずれかが蛍で、他方が死蛍である。
・こちらをふりかえって/鼻血をたらす。
「むしろ正面をむくとき/急にドーナツを食う老婆たち」〈春のオーロラ〉(⑥・10)――悪霊の鼻血とは、嘲笑の図なのだ。
・わたしは便所へかけこみたい感じだ。
「箱のなかに匿れた一人の男/便器にまたがるぼくをあざわらう/桃をたべる少女はうしろむき/〔……〕/少女もいつかは駈けこむだろう/ぼくの箱の家」〈感傷〉(④・18)――シェルターとしての個室。
・彼女たちの前で/なぜわたしの描いたものを絵といったのか!
「わたしがいま描く画面とはなに?」〈春のオーロラ〉(⑥・10)――変化が起きる。ここまでの展開はなんだったのか。
・それはすみからすみまで肉化/されたものであって/輝やくバクテリアではなかったか?
「ぼくが仕上げつつある/〔図像〕そのものは/〔不吉な不調和〕に輝く/〔黄金と紺青〕の/色彩のしとねの上で/廃棄された」〈晩鐘〉(⑫・15)――輝く肉、この聖なる物質。
・細い管と太い管で編まれた/長い長い人生のトンネルかもしれず。
「ぼくは数ある血管を張りめぐらし 或は押出して 複数の眼と口をもつ女を創る」〈裸婦〉(⑤・7)――人ならば産道。
・光学的には暗く/建築的にはもろく/自然的にも不自然で赤く。
「((いまは(自然)がむしろ/(不自然)に見える時である))」〈蓬莱〉(⑪・18)――この螺旋状に立ちのぼるレトリック。
・わたしが無意識的に模倣している/女友だちのこれから/作りつつある再生芸術だろうか?
「「子供として死に/大人として再生する」/手順を模倣せよ」〈産霊(むすび)〉(⑫・1)――こういうことが実際上、起こりえるのか。
・彼女たちが午餐をすませて/水着で泳ぐのを/わたしは見に行くんだ。
「「この夏もある海岸で/黄色い海水着をきる/娘」/の裸を妄想せよ」〈この世の夏〉(⑨・24)――見る人とはすなわち覗く人の謂だった。
・女友だちの娘のような妹の/孕んだ腹を裂くよ。
「赤えいの生身の腹へ刃物を突き入れる/手応えがない/殺戮において/反応のないことは/手がよごれないということは恐しいことなのだ/だがその男は少しずつ力を入れて膜のような空間をひき裂いてゆく」〈過去〉(③・17)
「背中を裂かれた卵が泛び上る」〈喜劇〉(④・1)
「裂かれぬ魚の腹はたえず発光し/たえず収縮し/そのうえ恐しく圧力を加えて/エロチックであり/礼儀正しい老人を眠らさぬ」〈老人頌〉(⑤・1)
「亀裂せる妹の腹を越え/やがて翼をつけた砲身のように飛ぶ/仮想敵がいるようだ」〈メデアム・夢見る家族〉(⑧・21)
「情緒てんめんと/ぼくの姉妹たちは開腹されて」〈猿〉(⑩・20)
「兄の悪しき妄想だろうか/牝牛の腹を割く/血肉は消尽し」〈東風〉(⑪・15)
「妹はうらわかく/孕んだはらを裂かれて/死んでゆき」〈蓬莱〉(⑪・18)
「鯉は腹を割かれつつ/一つの(呪文)をくりかえす/その口唇はやわらかく/今宵の(姉)のようだ」〈聖童子譚〉(⑫・4)――これらが吉岡の描いた開腹図のほぼすべてである。
・夏とはそんな一日であることを/感謝しながら/みずみずしい箒を買ってくる。
「はるさめの降るころ/煙突掃除用ブラシはススでなく/幼児をこするものへ/変化する」〈崑崙〉(⑦・8)――絵筆は、最後に至って箒にとってかわられた。
*
吉岡がここで描いたのは油彩による具象だ。なにかをモデルにしている? 低空での処女凌辱? 持ちあるかれることを拒む、画材としての馬。息子を拒む母、父を拒む息子、露を拒むサボテン(没交渉の極)のように流れる日日と河。そして女友だちの前に立ちはだかる森の道。マックス・ワルター・スワンベルグ/スワーンベリではなく、クロヴィス・トルイユとの類縁。マルセル・デュシャンの「蝋化した/観念」よりも、トルイユの「油絵具のなかにたむろして/出る骨をくるむ」「愛」を。
一九六○年代になると、詩集《静かな家》ではまだ同時代の造形作家の影響は顕著でないが、これ以降の吉岡詩には作家や作品への言及が急増する。池田満寿夫、ハンス・ベルメール、ルイズ・ニーヴェルスン、詩句にその名が登場しない横尾忠則や中村宏もこれに加えるべきだろう。彼らの特徴を一言で言えば、エロティクであり同時にユーモラスであることだ(ベルメールのユーモアは黒いが)。この時期の吉岡の詩句に、池田やベルメールやニーヴェルスンが出てくるのはなぜか。造形作家の眼と掌が形にしたものをそれとは無関係のものと同列に並べ、次元の違う両者をミクスチュアすることで平面化し、詩篇に取りこむこと。すなわち自他の作品のもつ高貴さを奪いとり、低位の部分を引きあげること。この均質化のため、題材の渾沌にもかかわらず、詩篇の手触りは妙にひっかかりのないものとなる。どこを採っても似たような印象――長篇詩の一部のような。吉岡はこれらの美術家の視点を借りて世界を見たのではない。彼らが捉えた外界を引用し、読者に対しては彼らの視点を強要するのだ。それがこの時期の吉岡が造形作家に言及することの意味である。
一篇の作品がどこから始まってどこで終わってもかまわないような書法で書かれたのが、《神秘的な時代の詩》である。そこではイメージの生け捕りが試みられ、表現形態への配慮は吉岡実のすべての詩集で最も稀薄になった。代表的な三冊の詩集、《僧侶》《サフラン摘み》《薬玉》がもつ「劇」や「ノンセンス」や「神話」と同等のものを期待してはならない。われわれは意味とイメージを同時にもたらす詩句そのものを掴むことに専念しなければならない。廃品芸術[ジャンクアート]がそうだったように、不要となった物体を組みあげることで作品の現場が再現される。そうした操作のあとには、作者の心象、語ろうとしなかったものまでが出現するかもしれない。おそらくその延長線上に、次の詩(集)の主題がせりあがってくる。
吉岡実の音楽というテーマは、むろん〈三重奏〉から来ているのであって、こうした無謀な設定はしたくなかったのだが、事ここに至って音楽に触れずにすますわけにもいくまい。
ふつうの意味での音楽は吉岡実にとってなにほどのものでもなかった。さすがに若いころには音楽会に足を運んだ形跡があるが(「三月四日 夕方から日高君たちと飛行会館の希望音楽会に行く。初めて日高君の妹(惇子)と会う。清純な少女だと思う。巌本眞理のヴァイオリンと平岡養一の木琴がよかった」#C_050、三一ページ)、これとて付きあいの要素は大きいだろう。
陽子夫人によれば、吉岡にウォークマンを聴かせたところ、こんなものはいやだといってすぐにヘッドフォンを外してしまったそうだ。耳に込め物をするのが身体的に耐えられなかったこともあるだろう。しかし吉岡がスピーカーから流れる音楽に耳を傾けている図を想像することも難しい。視ることが対象に攻撃をしかけることなら、聴くことは対象からの攻撃に身を曝すことだといってもいい。両者は本来は別別の作用だが、吉岡の場合、視ることへの傾倒と聴くことへの無関心が一体となっているようだ。だが、詩の音楽、詩人がわれしらず実現してしまった詩における音楽ということになれば、話は変わってくる。〈静物〉(③・1)を聴こう。
静物|吉岡実夜の器の硬い面の内で
あざやかさを増してくる
秋のくだもの
りんごや梨やぶどうの類
それぞれは
かさなったままの姿勢で
眠りへ
ひとつの諧調へ
大いなる音楽へと沿うてゆく
めいめいの最も深いところへ至り
核はおもむろによこたわる
そのまわりを
めぐる豊かな腐爛の時間
いま死者の歯のまえで
石のように発しない
それらのくだものの類は
いよいよ重みを加える
深い器のなかで
この夜の仮象の裡で
ときに
大きくかたむく
「くだもの〔……〕の類〔……〕はかさなったままの姿勢で〔……〕大いなる音楽へと沿うてゆく」から詩の音楽なのではない。時間の相の下ですべての詩句が、存在が、揺るぎなく(「かたむく」ことさえ揺るぎなく)定着されているがゆえに、この詩は音楽を引きあいに語られるべきものなのだ。時間のなかの音の構造物こそ音楽である。傍線を引いた副詞的部分は、この語(の組みあわせ)はここにこのように置かれるために存在したのかと見紛うばかりである。
吉岡実の耳の良さにはまったくもって脱帽する。正直に告白すれば、吉岡の散文における読点の位置にはごくまれに首を傾げざるをえないところもあるが、こと詩に関しては行の変え方が異様であっても、そこにはまぎれもない吉岡実の音楽と呼ぶべきものが鳴りひびいている。吉岡の音楽は巧んだ結果ではなく、ほとんど生得の、初案がそのまま定稿にまで至った結果ではないか。
「よるのうつわのかたい▼めんのうちで/あざやかさを▼ましてくる/あきのくだ▽もの/りんごやなしやぶどうのたぐい/それぞれは/かさなった▽ま▽まのしせいで/ね▽むりへ/ひとつのかいちょうへ/おおいなるおんがくへとそうてゆく/▼めい▽めいの▼もっともふかいところへいたり/かくはお▽も▽むろによこたわる/その▼まわりを/▼めぐるゆたかなふらんのじかん/い▽まししゃのはの▼まえで/いしのようにはっしない/それらのくだ▽もののたぐいは/いよいよお▽も▽みをくわえる/ふかいうつわのなかで/このよるのかしょうのうちで/ときに/おおきくかた▽むく」
作られた音楽とは、音の記憶に関わる技術の美的な行使だ。語のレベルでの繰りかえしは吉岡の忌むところだが、音(響き)では逆だ。このマ行は計算によるものではないだろうが、詩句中で比較的強く読むところ(▼を前に付けた)とそうでないところ(▽)のバランスが絶妙だ。「夜の器の硬い面の内で」という室内楽ふうの響きはもっぱらマ行の魔術によりながら、終わりから三行め「この夜の仮象の裡で」で再びモチーフの提示を見て、一応の安定を見る。このとき「内で」/「裡で」がおなじ音であることはたまたまかもしれない。ここに見ることができるのは、最後の二行の静寂のカタストロフを用意すべく音の記憶をあやつる吉岡実の姿である。
音楽の比喩は〈三重奏〉に則して語られてこそ意味がある。三重奏はtrioの訳語で、英語やフランス語のトリオは三重唱を含み、元来三声部の曲や演奏形態のことをいう。Trioはこの「三重奏〔唱〕/三重奏〔唱〕曲〔団〕」のほかに「三つ組、三人組、トリオ、三つ揃い」の意があるから、音楽だけを解読格子に見たてることは窮屈である。吉岡の詩篇の「三」はなにか。ひとつには三人の登場人物(わたし、女友だち、女友だちの娘のような妹)の織りなす、およそ吉岡実の詩にふさわしい言いまわしとも思えないが、人間模様と言おう。もうひとつは「絵」の三相である。この絵くらいあやしげな代物も珍しい。わたしは高橋睦郎をして「作者は言葉によってそれまでどこにもいなかった動物を創造した」(#A_23、一○四ページ)と言わしめた〈動物〉(⑧・20)を想起する。詩篇は言語が描写し、説明し、それに関する記録が堆積すればするほど実体が錯綜してくる古代生物についての記述を読んでいるようだった。
・わたしは自分の描いた【絵】を/見てもらいたいので/女友だちを家につれてくる
・わたしの【絵】は観測というものでなく/むしろ昆虫群/わたしは女友だちに【絵】の構造を説明すべく/本物を見せる
・女友だちは【絵】よりも蝋化した/観念がすきだといって/わたしのベッドを塗り変える
・【絵】としてわたしが描いた心
・鉄砲ユリの奥は深く/わたしの【絵】はぬれることを知らない/表面というものがない/闇を所有しているわけでもないから/すくなくともわたしには持ち歩くことができる/おそらく女友だちには/それはできぬだろう/【絵】のなかの馬がそれを拒む
・わたしは淋しいことは【絵】に告げ/死にたいときは/【絵】のうしろを歩く
・女友だちは明日は帰ってゆくだろう/彼女の行手に立ちはだかる/わたしの【絵】のなかの森の道へ
・彼女たちの前で/なぜわたしの描いたものを【絵】といったのか!
この「絵」をなにかの喩ではないかと考えるところから混乱が始まる。イーゼルに架けられた一枚の油彩画を想像するところに迷妄が生じる。これは主題と変奏、モチーフとその展開という音楽の方法を吉岡が描いていると見るべきなのだ。繰りかえしを避ける自身の詩法の潔癖性への言及は先に引いたが、あれは大方の詩人が音楽の手法を用いて書くようには自分は詩を書かないという言明だった。音楽の功徳が繰りかえしにあるとすれば、それをさらに何度も聴きかえすことと詩を何度も読みかえすことのあいだに違いはない。音楽を記憶するにもテクニックが要る。最も原形に忠実なのは、享受する立場からは、音源が録音されていればそれを何度も再生して脳裡に刻むことだし、再現する立場からは、楽譜を読み、歌いあるいは奏でることだ。〈三重奏〉の一節にこうあった。
わたしが無意識的に模倣している 61
女友だちのこれから 62
作りつつある再生芸術だろうか? 63
「再生芸術」とは耳慣れない語だが、とりあえず再現芸術と同義としよう。それに「音楽」を代入してみる。「わたしが無意識的に模倣している/女友だちのこれから/作りつつある音楽だろうか?」では、詩句として魅力的でないだけではなく、以下の部分で重要になる生殖のイメージが分断されてしまうから、「再生芸術」は動かしがたい。しかしそれがなにを指すかとなればやはり「音楽」以外にない。吉岡がその語を避けたのはなぜか。なぜここで「音楽」に出てきてもらっては困るのか。それが〈三重奏〉の意味を解く鍵になる。
おそらく音楽は再生芸術でありながらそうではなく、再生は生殖でありなりながらそうではない。そのようなものとして限りなく近く、かつ異なる。「女友だちのこれから/作りつつある再生芸術」はそう認識された。しかも「わたし」はそれを「無意識的に模倣している」かもしれないのだ。それは自分の絵が女友だちに理解され、愛されない以上に恐るべきことだ。「わたし」が作らねばならないのは彼女たちの存在を映しだす鏡であって、彼女たちの存在そのものではないからだ。再生という語は「わたし」の「絵」にあってはならない。ではそれは、吉岡実に詩にとっても同様であるのか。もう一度、絵画と音楽について考えよう。
吉岡実における視ることを「一瞬の凝視」として、見えるものしか視ないその特質を「一瞥の天才」(#B_037、七五、七三ページ)と指摘したのは城戸朱理だったが、一瞬のうちに見ることのできない音楽とは、吉岡実の理解の外のジャンルだった。それはあまりに文章に似ている。吉岡の散文が異様に鮮やかにその時の記憶を保っている理由のひとつに、時間の処理を故意にずらしている点が挙げられる。次の例〈私の生まれた土地〉全文でそれを見てみよう。
①本所業平で生まれた。おそらくドブ板のある路地の長屋であったろう。近くに大きな製氷工場があったと聞く。そこで関東大震災に遭遇した。火の海のなかで燃える氷の山。
②それから本所東駒形で少年時代をすごした。塀のある二軒長屋。小さな庭で、母は小さな植木を丹精していた。
③水戸様(隅田公園)へ遊びに行き、透明なエビを釣ったり、隅田川の岸の石垣の間でカニをつかまえたりした。大河原屋というイモ屋で尻をカマであたためながら、ガキ大将として暮した。篠塚の地蔵サマの縁日の夜は十銭の小遣いをたのしく使った。星乃湯の女湯をのぞいた。高等小学校のころから、厩橋に移った。奉公に行き、そして兵隊に行き、生まれ故郷本所という土地を失った。(#A_25、五ページ)
①は父母からの伝聞、②は吉岡自身の最初期の記憶で、③がこの文の本題だが、これらの三つの段落を跨ぎこした下線部が少年時代の想い出であり、ためにそれは極めて充実した印象を読者に与え、幼年期や決して楽しい日々ばかりではなかったであろう奉公や兵隊の時期は一顧だにされず、一瞬のうちに故郷は、吉岡自身はそれを見ていないにもかかわらず火の海のなかで燃える氷の山と呼応するように、焼失するのである。
こうした散文のありかたは、発表誌がアンケート形式を採ったことも作用していようが、吉岡の時間に対する感覚に帰すべきである。凝縮した叙述の展開は、紙幅からの要請を超えて、著者の時間感覚、過去の一点をこの現在と太い筆致で結びつけるという目的のために採られた。そこにはかつてあったものが今は無く、どのように失われていったかはたどりようもない、という疎外された意識が濃く立ちこめている。たとえ自分になにもできなくとも、決定的な瞬間から閉めだされたという感覚。それは〈私の生まれた土地〉では触れられていないが、戦地にある間に父母を失い、さらに兄の計らいによってしばらくその死を知らされなかったことでいっそう深い痕跡を与えたであろう。時間に対する不感症的傾向を増長しただろう。時間に冷たくされた以上、なぜ時間に義理立てしなければならないのか。
題名は符牒として機能する。それが内容を規定するのはいわば余徳である。本文より前にしかるべき文句があれば、読者はそれをタイトルだと了解し、内容にそぐうかどうかの判断は本文を読みおわるまで保留される。あるいは、なぜそぐわないかを自問する時間を与えられる。
「わたしは自分の描いた絵を/〔……〕/みずみずしい箒を買ってくる」という文章は〈三重奏〉と呼称されている。両者はそもそも対等の関係ではない。七十数行の題名のあとに三文字の本文が来ることはない。符牒として機能しないし、題名がより一般的であって本文がより個別的であるとき、題名はともかく本文はオリジナルでなくてはならない。世の中には同じ題名の作品がなんとたくさんあることか。吉岡の詩でも〈哀歌〉(②・31、未刊詩篇・9、⑪・13)、〈静物〉(②・15、③・1、2、3、4)、〈夏〉(①・2、④・10)、〈挽歌〉(②・1、③・12)、〈風景〉(②・19、③・10)、〈牧歌〉(②・10、④・7)が同じ標題で複数篇あって、〈哀歌〉〈挽歌〉〈牧歌〉と「歌」が並ぶのも偶然ではない。タイトルを労せずして付けたいと作者が念じたとき、いちばん簡単なのはその作品ジャンルと順番の組みあわせである。某作曲〈交響曲第何番〉。これで世界にひとつしかない作品の題名として機能する。
唱歌|吉岡実男は不足なものをさがす
夏の植物が少年たちと絡みあう
薄明の世界から出る
ある愛の生きながらえている邦へ
古代の氷山を背景にして
こわれた軍艦がひもで岸につながれる
雨と光熱のありあまる港
異端の音楽を聴く
男は見なければならぬ
他の人がひとりもいない真昼の首都
窓わくの奥のうごかない海のなかで
おぼれるリボンの輝き
すべての毛をぬぎさった
ひとりの少女をめぜめさせるため
男は小声で祈り
シナの墨でぬられたフカの腹を裂く
美しい汗の夜のはじまり
那珂太郎によれば、氏がのちに《音楽》となる詩集の装丁を吉岡に頼んだおり、すでに三島由紀夫の小説に《音楽》があるので《波の音楽》にでもしようとしたところ、吉岡から言下に《音楽》でいくよう示されたそうだ(#C_014、三三ページ)。吉岡実が本詩篇を〈詩篇七の一七番〉などとしなかったことに感謝しつつも、〈三重奏〉がそうした楽曲のタイトルへの羨望をいささかなりとも含んでいないようにみえないのだ。音楽作品で避けて通れない問題を自身の作品に適用すること――それが吉岡実がこの詩で試みた、本文と題名に籠めた自負のように思える。
ハチミツは瞳を暗化させるものを取り除く。――《ディオスコリデスの薬物誌》(#B_095、一五五ページ)
〈蜜はなぜ黄色なのか?〉(⑦・12)は郵政弘済会発行の雑誌《郵政》一九六九年四月号(二一巻四号)に発表された。詩の読者にとって《郵政》とは聞きなれない誌名だが、吉岡実はこれ以前、一九六四年七月号にも〈聖母頌〉(⑥・6)を寄稿していて、〈蜜はなぜ黄色なのか?〉で再度の登場となった。吉岡はよほどのことがないかぎり散文の執筆依頼は引きうけなかったが、詩作品の依頼は休筆中以外なるべく応えたようだ。きちんとした媒体であれば詩や文芸の専門誌でなくても執筆していて、一般誌だからわかりやすく書くということがない点は一貫している。吉岡の詩への配慮は発表媒体の選別にほとんど働かなかったのではあるまいか。〈蜜はなぜ黄色なのか?〉を郵政事業の関係雑誌に寄せるのも、〈三重奏〉(⑦・17)を森谷均の詩誌に書くのも、執筆態度に逕庭はない。詩篇本文の初出と定稿を、校異がわかる形で掲げよう(ライナーは定稿のもの)。
蜜はなぜ黄色なのか?|吉岡実 〔(現代詩人会会員)→(トル)〕蜜はなぜ黄色なのか? 1
永遠に 2
瞑想的でなく 3
愛すること〔で→(トル)〕もなく 4
虎のように 5
フォルムを所有する 6
秋の青空はあくまで疾走し 7
眼と眼は暗く 8
向きあった男と女の立体感覚! 9
内臓へまでとどく 10
四つの腕の様式美 11
求めている〔唇のよだれ→森の〕 12
〔それらのただれ→(トル)〕
紅葉の錦 13
いま近づけば発火する? 14
格子を出てゆく金蠅 15
かくてモノトーンの夜を 16
なまめかしい水槽で 17
恋する幽霊 18
水の回転する泡の苦界の 19
男声・女声 20
ながながと哭〔[な]→(トル)〕く老婆 21
ながながと鳴くウグイス 22
白地に赤く 23
燃えるランジェリー 24
燃えるフロア 25
コカコーラの〔罎[びん]→壜〕のうしろの沖を 26
走るあらゆる船は静止し 27
蜜のような物質で 28
徐々に包まれる 29
題名と第一行とが同じである。吉岡が詩のタイトルをいつどのように付けたかはこれまでの評釈でもたびたび取りあげてきたが、本文の詩句と題名が同じ場合は、手掛かりが多いにもかかわらず、いや多いだけにいっそうわかりにくい。題名で読者に問を投げかけておいてその興味の持続で最後まで引きつけておくという効能があるにしても、詩篇の叙述は問いかけをかわしながら最後の行に至っているように見える。応答は必ずしも成立していないのだ。
ここで詩全体の印象を語っておこう。この詩には運動と静止をめぐる省察が見られる。「秋の青空はあくまで疾走し」はいうまでもなく、「いま近づけば発火する?/格子を出てゆく金蠅」を追う視線は、その先にある直立せる「恋する幽霊」を捉えずにはいない。視線は、見ることが物体を出現させたかのような「コカコーラの壜のうしろの沖を/走るあらゆる船は静止し/蜜のような物質で/徐々に包まれる」に突きあたることで、ようやく停止する。
この末尾を読みかえすたびに、三島由紀夫《豊饒の海》(とりわけ最後の《天人五衰》)が想いうかぶ。気になったまま年月が経ってしまったが、本篇の評釈を機に《豊饒の海》四部作を読みかえしてみた。吉岡の詩と三島の遺作小説を関連づけるものは発見できなかったが、興味深い暗合があった。《天人五衰》の「すでに肉眼でもはつきりとわかる船が、しかしなほ棚の上に忘れ物をしたやうに、水平線上に黒く置かれて見える。距離が縦に積まれてゐるので、いつまでも水平線の棚の上の黒い酒罎のやうに見えるのだ」(#B_144、一〇〇ページ)には取材の成果が感じられるが、吉岡の詩と三島の小説の類縁はなにを物語るのか。船と海を舞台に、疾走と停滞を扱う両者の手つきが似かよっているということがある。三島も《天人五衰》で俗悪なアメリカ文明の象徴として「コカ・コーラ」を登場させて、一九六〇年代後半の日本の精神的風土を代表する物として描きこんでいるが、吉岡の詩句にそこまでの底意は感じられない。
私には別の風景がメロディとともに浮かんでくる。荒井由実が「ソーダ水の中を 貨物船がとおる」と〈海を見ていた午後〉(#B_005)で歌った横浜・山手のレストランルーム〈ドルフィン〉である。ユーミンの歌の方が吉岡の詩より発表はあとだ。〈蜜はなぜ黄色なのか?〉には秋の陽光が感じられる。
吉岡の数少ない疑問形の題名の詩のひとつに〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)がある。この題にも色を表わす語が含まれているが、二篇は似せようとしたのではなく結果として似てしまった、といったところか。《神秘的な時代の詩》の諸篇はタイトルにも構えのない、自ずから流露するものが多い。タイトルの次元にとどまらず、たとえば「白地に赤く/燃えるランジェリー」といった、いわばあとさきを考えない詩句が《神秘的な時代の詩》以外の吉岡の詩集に登場することは想像しにくい。疑問形の題名の詩もほかの詩集にはなかったはずだ。疑問形の題名というのは、人の抱く感嘆の最も原初的な声に近い。そういう詩人の口調に近い生な書きぶりは、上手くいって自然体、下手をすると作文に堕しかねない、ある長さの文章を牽引するにはよほどの力量を要する、素人は手を出さないほうが無難な方法なのだ。
詩篇〈青い柱はどこにあるか?〉については本評釈〈「暗黒の祝祭」〉ですでに取り上げたが、そこでは色について触れなかった。いま読みかえしてみると、色の使い方は意図的なものであることがわかる。青い柱と黄いろの矢印と(たぶん赤い)肉体の男を等分の比重で描いたキャンバスが〈青い柱はどこにあるか?〉という詩だった。――ジャクソン・ポロックの大規模な壁画〈青い柱[ブルー・ポールズ]〉は、深い瞑想性を有した、表現主義的な心情の発露だ――というハンター/ジェイコブスの指摘は、なるほどと納得できる。吉岡のこの詩にも、舞踏表現に仮託して語らんとした「心情の発露」を読みとるべきだ。そこでさまざまな色を塗りわけた最後に来た色が黄だった。ちなみに《神秘的な時代の詩》初刊詩集の函は目に鮮やかな黄色である。
《郵政》一九六四年七月号掲載の〈聖母頌〉を読もう。吉岡の詩をいま全詩集で読みかえすことの功徳のひとつに、詩篇相互に張りめぐらされた関連を見いだすことがあるけれども、〈聖母頌〉は最後の詩集《ムーンドロップ》の巻末に置かれた〈〔食母〕頌〉(⑫・19)と対に見たてて読みたい詩篇である。
聖母頌|吉岡実わたしたち再びうまれるとしたら
さびしいヴィオレット色の甘皮からだ
それはいじるより見る方が美しい
ところどころ夏のくだものの房をつけ
しずかに稲妻を走らせる
亜鉛のドームの下はやわらかい馬の口
こぼれる一粒の燕麦
わたしたち再びうまれるとき
西瓜の畑で月は輝くか
いま いまとはいかなる紐の切れ目
大小の羊が下半身の毛を刈られる
わたしたちの母を匿すんだ
青や赤で染められた
地図の上に
分割されつつある暗い世界の一つの小屋
そこでわたしたちの母は長い髪をかきあげる
力でなく心でどこまでも高く
モノクロームの禿山
そこは叩くところでないんだ
わたしたちの死せる父を埋める聖地
つねに
苦悩の虹・熱い滝
わたしたちの母は誠実だから次のものを見る
ランプの光に
殺虫剤のなかで色を変える染色体
セロファンで包まれた
乳歯
それがわたしたち・二十世紀のわたしたち
スピードを加えて水がながれる
ここにある女陰や膨れた胎らしきものは吉岡の詩ではお馴染みのものだが、「染色体」や「乳歯」は形をとらぬまま死産してしまうようである。それを「聖母」と頌えることで「二十世紀のわたしたち」の生を、むしろ再生を描いた吉岡独得の生命観あふれる詩篇である。さらにこの詩は過去の家族の詩(〈聖家族〉④・14)や出産の詩(〈紡錘形Ⅰ〉〈紡錘形Ⅱ〉⑤・4、5)を連想させずにはおかない。〈蜜はなぜ黄色なのか?〉と比較すれば、〈聖母頌〉の主調色は青と赤が作りだす紫色である。かつてともに《今日》の同人だった難波律郎は《僧侶》について「彼の描くべき対象は発想と同時に半凝固的形姿で眼前し、彼の制作の手続きとは、対象とまったく同質のもの[、、]、すなわち作品をつくりあげることで終了する」(#C_035、一六九ページ)と述べたが、〈聖母頌〉でもその事情はほとんどかわらない。とにかく、その詩と等価のものがでてこなければ作品は終わらないのだ。〈聖母頌〉のおだやかな疾走感は次の詩集《神秘的な時代の詩》を予告するに充分であり、名品のひとつであろう。
一九九六年三月二五日、待望の《吉岡実全詩集》(#A_29)が刊行された。活版印刷による大冊である。底本に対する本文校訂もなされているが、対校表は付されていない。本文校異の詳細は、来るべき《吉岡実全集》に期待しよう。この全詩集には、吉岡の最初の著書である詩歌集《昏睡季節》(#A_01)から最後の詩集《ムーンドロップ》(#A_26)に至る全刊行詩篇はもちろん、数はそれほど多くないものの雑誌や新聞に掲載されたままになっていた未刊詩篇や、《昏睡季節》所収の和歌まで収録されており、吉岡実の韻文世界を窺いしるに足る。これに著者が生前まとめることを潔しとしなかった俳句――歿後に吉岡実句集《奴草》(#A_31)がある――を加えれば、吉岡実の詩・歌・句のテクストはその全貌を現わしたことになる。本評釈では、吉岡実詩の引用はとくに断らないかぎり全詩集の本文に拠るが、今後も適宜初出や異本からも引きながら、吉岡実詩の生成を見ていきたい。
《吉岡実全詩集》の読者が最初に読む作品は、詩歌集《昏睡季節》に〈序歌〉として掲げられた次の一首である。短歌・旋頭歌の本文は全詩集ではのちの単行本、歌集《魚藍》(#A_05)として巻末に繰りさげられたから、一首はそれらと切りはなされた。
あるかなくみづを
ながるるうたかた
のかげよりあはき
わかきひのゆめ
八×四=三十二文字の矩形マイナス一で三十一文字の、漢字かな交じり文(「有るか無く水を流るる泡沫の影より淡き若き日の夢」)に書きなおせば失われてしまうだろうたゆたう調べは、ひらがな書き表記によるところが大きい。「水辺愁吟/みつみれはなせかうれひのひえひえとこころなかるるあきのゆふくれ」が秋艸道人會津八一を意識しすぎているのに対して、序歌は現行表記で動かない。序歌は《吉岡実全詩集》以前に三度――〔A〕詩歌集《昏睡季節》、〔B〕歌集《魚藍》、〔C〕現代詩文庫版《吉岡実詩集》(#A_10)――印刷されているが、基本的に同じ本文だ。ただし、詳しく見るとBだけ次の表記になっていた(ちなみに前掲「水辺愁吟」は初出では序歌と同じ「八×四=三十二マイナス一」表記だった)。
あるかなくみつを
なかるるうたかた
のかけよりあはき
わかきひのゆめ
濁音が清音に変わったのが三箇所。このため「みづ(水)/みつ(蜜)」というあやうい連想が生じることになった。つまり一九五九年、Bで「あるかなくみつを/なかるるうたかた/のかけよりあはき/わかきひのゆめ」と変更したのを、一九六八年、Cで再びAの初出形に戻した吉岡は「みつ」が水を指し示さない、「みつ」が蜜でありうることを念頭に置いていたことになる。吉岡自身が旧仮名表記から遠ざかっていたこともあろうが、活字による表記がそのまま音に還元される時代が到来し、それを意識せざるをえない状況にあったとも言えよう。みつはみづにあらず。――「欲しいよ 水と蜜」(〈異邦〉⑨・5)
詩篇〈蜜はなぜ黄色なのか?〉を朗読すればこうであろうかというのが、以下に掲げる散文的表記である。
「蜜はなぜ黄色なのか? 永遠に、瞑想的でなく、愛することもなく。虎のようにフォルムを所有する。秋の青空はあくまで疾走し、眼と眼は暗く、向きあった男と女の立体感覚! 内臓へまでとどく四つの腕の様式美。求めている森の紅葉の錦。いま近づけば発火する? 格子を出てゆく金蠅。かくてモノトーンの夜を、なまめかしい水槽で恋する幽霊。水の回転する泡の苦界の男声・女声。ながながと哭く老婆、ながながと鳴くウグイス。白地に赤く燃えるランジェリー、燃えるフロア。コカコーラの壜のうしろの沖を、走るあらゆる船は静止し、蜜のような物質で徐々に包まれる。」
本文は「蜜はなぜ黄色なのか?」と始まり、二行め以下の数行は第一行にかかる副詞句にも読める。すなわち、
・蜜はなぜ〔永遠に〕黄色なのか?
・蜜はなぜ〔瞑想的でなく〕黄色なのか?
・蜜はなぜ〔愛することもなく〕黄色なのか?
・蜜はなぜ〔虎のように〕黄色なのか?
ここまではいいが、六行めになると成立しないのでこう読み換える。
・〔虎のように/フォルムを所有する〕蜜はなぜ黄色なのか?
「〔虎のように/フォルムを所有する〕蜜」から想いだされるのは、黄色と黒の縞模様の蜜蜂の腹部だ。もっともこれだと蜂ではあっても蜜ではない。ここは《ちびくろさんぼのおはなし》(#B_120)の物語でいこう(サンボの虎は、溶けて蜜ではなくギー=バターとなったが)。溶けたのに「フォルムを所有する」では面妖なとなれば、ここで真に想起すべき物質は、蜜でもバターでもなく琥珀である。伝承に依れば「古代の中国人は、虎が死ぬと精魄が地に入り、化してコハクになると考えた」(#B_170、一〇二七ページ)。吉岡がこの虎魄=琥珀説を踏まえている事実は確認できないが、ここは蜜よりも虎に引きつけて読みたい文脈である。琥珀は「大プリニウスによれば、〈黄コハクが最初は液体状の浸出物だったことは明らかだ。というのは、それが透き通っていて、その中にある種の生きもの、たとえばアリとかハムシとかトカゲとかいった生きものの見えることがあるからだ。これらの生きものが、ねばねばした物質にとらえられ、物質が凝固するとともに、その内部に閉じこめられたのであることは申すまでもない〉といっている」(同前。この項目の執筆者は澁澤龍彦)――詩篇の末尾が想いおこされる。
ここまで「〔虎のように/フォルムを所有する〕蜜」と読んできたが、実情はやはりそれを許さないだろう。「虎のように/フォルムを所有する/秋の青空はあくまで疾走し」というフレーズが登場し、この時点で終止形・連体形両用の「所有する」は連体形の方に傾くからだ。そこでは「虎のように〔/フォルムを所有する/秋の青空はあくまで〕疾走し」と、見えない虎さえ疾駆している。サンボを追って椰子の樹の周りを走るあの虎が。するとさらに「眼と眼」の間を流れる空気、すなわち風が生じる。蜜はここに至ってしばらく後方に退く。吉岡の随想〈「官能的詩篇」雑感〉には「向きあった男と女の立体感覚!」を思わせる次の記述があるので、その「2」を全文引く。
2 愛の詩私はしばらく前から、メキシコの詩人オクタビオ・パスの作品を読んでいる。散文の『弓と竪琴』の詩論的なエセーもよいが、詩もイメージが鮮明ですばらしい。さて「愛の詩」といえばなぜかポール・エリュアールのエロチックな詩篇を想い浮べる。だが今資料がないので、パスの詩から選んだ。この「二つのからだ」は短いものだが、一つの典型だと思う。
むかいあう二つのからだ
あるときは夜の海の
二つの波むかいあう二つのからだ
あるときは夜の砂漠の
二つの石むかいあう二つのからだ
あるときは夜の底で
からみあう根むかいあう二つのからだ
あるときは夜の稲妻の
二つの刃むかいあう二つのからだ
あるときは虚空に落ちる
二つの星 (桑名一博訳)二年前の秋、オクタビオ・パス夫妻が来日した。私は数人の詩人と共に招かれて、一夕歓談したことがあった。残念ながら、パスの詩はまだ四十余篇しか訳出されていない。しかし、いずれも佳品、秀作で、流麗な訳文に依って、パスの詩業の片鱗がうかがえた。私はそのことを伝え、とくに長詩「白」に感動したと言った。パス氏は微笑しながら、大変苦心した作品で、「両界曼荼羅」とマラルメの『骰子一擲』に触発されたものであると、応えた。そういえば「回転する記号」のなかで、パスは『骰子一擲』を精密に論じている。(#A_25、三六五~三六七ページ)
ここではパスの〈二つのからだ〉が吉岡の詩心を揺さぶった点に注目したい。いったい吉岡はこの手の詩篇を書きのこさなかったが、「愛の詩」に無縁なわけではない。題辞にラマ僧の呪祷「われら今夜というこの時/この黄教の馬の放中せる陰茎を/中心にして/雨の地に拝跪した」を引きながら祝婚歌を〈呪婚歌〉(⑤・9)として書くような詩人ではあったが。
吉岡実が鷲巣繁男に直接言及した散文は、詩集《行為の歌》(小澤書店、一九八一)の高見順賞の選考をめぐる〈感想〉以外ないように思う(〈感想〉は単行本未収録)。しかし、吉岡には後に述べる鷲巣への追悼詩〈落雁〉(⑪・17)があり、その交友を偲ばせる。鷲巣は漢詩(《不羣鈔》の〈幌北詩存 一九六七~一九七〇年〉所収)を吉岡に贈っており、一九六七年、札幌の鷲巣に宛てた次の吉岡の葉書がその間の事情を物語っている。
「拝復 急に東京も寒くなりました故、さぞかし北海道はきびしい風物の日々と思います。さて、「蠻族の眼の下」と、蒼古なる漢詩をいただき、貴兄の厚情を感じます。過日、岡井隆「眼底紀行」の会で、高柳重信と会い、貴兄の話が出ました。これは小生の希いですが、来年は是非、句集を刊行して下さい。不一。/十二月十二日 実」
神谷光信は鷲巣繁男の評伝で句集についてこう書く。「当初は句集を出すつもりであった。そうすることにより、十年続けた俳句との関わりに区切りをつけようとしたのであった。それを詩集出版に切り替えたのである。「俳句が私にとつて形式とのたゝかひであるとすれば、詩は形式の発見にある」。これは繁男のあとがきの一節である。あとがきには、句集も暮には出版予定と記してあるが、実際に俳句が活字となったのは二十一年後の『定本鷲巣繁男詩集』においてであり、句集『石胎』として一冊になったのは、さらに八年後の昭和五十四年(一九七九年)のことであった。一年に二冊を自費出版するには、資が乏しかったのであろう。あるいはむしろ、費用は次の詩集の出版に充てるべきだと考えたのだろう。繁男は原稿用紙を綴じ、私家本として句集『石胎』をつくった」(#B_031、一五〇~一五一ページ)。さて、鷲巣が吉岡に贈った漢詩〈贈吉岡実詩契〉(#B_166、五三二ページ)はこうだ。
人事悉茫漠 火宅何営営
老大相会難 素白封夜醒
去鳥啄句急 腐蝕成語驚
空林点虚影 夢魂遶三精
美僧催臘涙 死児誦古経
迢迢流光過 寂蓼如石英
「寂蓼如石英」の句が迫ってくる。対する吉岡は鷲巣の歿後、詩〈落雁〉でその人物と詩業を追悼した。そのエピグラフ「(言葉よ 死の底より自らの蜜を分泌せよ)」は鷲巣の詩〈大流蜜期〉から引かれたものだが、〈大流蜜期〉は吉岡の葉書にある第三詩集《蠻族の眼の下》(さろるん書房、一九五四)ではなく、その次の第四詩集《メタモルフォーシス》(日本未来派、一九五七)に収められている。《行為の歌》の〈附記〉には「もともと『神人序説』の諸長篇はその前集『メタモルフォーシス』の末尾の長詩「大流蜜期」の延長であり、特にそれは印度哲学を軸に旋回する哲学詩であつたが、今後どのやうな世界をわたしの中に形づくることができるか、いささかの怖れと共に愉しみもある」(#B_167、二六六~二六七ページ)とあり、追悼詩篇を構想する吉岡がその「哲学詩」によく呼応しようと試みたことは充分考えられる。〈落雁〉の本文を追込で引く。なお《薬玉〔特装限定版〕》には、識語に「来てみれば秋/ここは落雁の見える/寂しい水の上の光景」を揮毫した一本がある(吉岡家蔵)。
1/((すべて(現世)は火をつけられ/すべて(現世)は燃えひろがり))/倒壊する/淫祠邪教の(都会)/蓬頭の(死母)が全身で支える/(大梁の下で/わたしと弟は救われた)/来てみれば秋/ここは(落雁)の見える寂しい/水の上の光景だ/(西空へ裂かれた/血潮雲)/わたしは(負)の荷を担いつつ/(古き世の母親)のうるわしい/(((霊魂[プネウマ])の立ち上り))を見た
2/(迂遠なり言語空間)/振りむくな/いのこずちは茂り/(空缶山をなす)/いたる処/((見えるような(道)は/風化した(道)だ))/わたしは遊行する詩徒か/(歩めば 炎え上る身体/発すれば 炎え出ずる言葉)/ささら打ち/たたら踏み/(肉が霊にあこがれ/霊が肉をいとおしむ)/全人的な(善悪)の概念を/変容せしめ/習合する日々/丁子の樹はいま花咲き/薬油をたっぷりたくわえる/(瓦斯体より/甦れ つねに新しく/わたしの言葉)
3/粉挽き唄が聞こえる/(孤屋)の羽目板から覗け/(荒服)の人は胡坐かく/破れ畳のささくれた上に/(存在する詩)/それを待伏せしているようだ/風にとばされし/(女と聴いた音楽会の/赤い薄ぺらな切符)/それは(悪霊)を退散させる/(護符)であるかもしれない/(天国もあれば まだ地獄もある)/床下の(不可侵)の暗い穴/くちなわ たにぐく こおろぎ/ひむし くえびこ いきすだま/(陋巷のトラコーマの老婆)の夢の冬籠り
4/原義として言えば/(青年は肉体をもち/老年は知恵をもつ)/その(不可分の関係)を知れ/違和感もなく/わたしは認識する/(形而上学は/深山に無く/密室に無く/典籍に無く/凡庸なる炉辺の猫にある)/生きている限り/人等よ/(((時空)と(謎)に身をまかせよ))
吉岡は前述の鷲巣繁男詩集《行為の歌》の高見順賞の選評〈感想〉で「長い時間をかけ、討議したところ、〔大岡信〕『水府』と鷲巣繁男『行為の歌』の二冊にしぼられた。〔……〕それから、『行為の歌』は、たしかに深遠で、荘重な世界がある。しかし、私には充分に解読できないところがある。信仰の問題だけではないだろうが、一種のもどかしさが残る。/談笑のあとの長い沈黙――そして時間が経つ。しばらく休息して、全員で『行為の歌』を、受賞作に決めた。ほっとした空気がながれる。矮小化して行く、現代の詩のなかで、孤絶した『行為の歌』が選ばれたのも、意義があると、私は思った」(#C_019、四ページ)と書いているが、そうした世界に、鷲巣のようには信仰をもたない吉岡が挑戦した成果が〈落雁〉である。関東大震災を思わせる冒頭の記述には、他人事でないものがある。
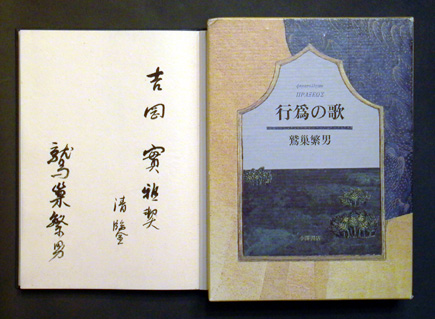
鷲巣繁男が吉岡実に贈った詩集《行為の歌》(小澤書店、1981年4月20日) 毛筆による署名ページと函
蜂蜜のことを考えはじめると際限がない。本評釈も、蜜の周辺を巡っているうちにうかうかと一年余が過ぎてしまった。それを踏まえて言うのだが、蜂蜜のシンボリズムを深追いしても実ある成果は出てこない気がする。そもそもそういう迫り方だけで詩はわからないが、とりわけ吉岡実の詩がわかるとは思えない。だが、この間に知りえた事柄もある。題辞に引いた、ローマの医者で古代の薬物学の大成者でもあるディオスコリデスはこう言っている。「最も好ましいとされるものは、最も甘く刺激性があり、芳香の点でもすぐれ、淡黄色をしたもので、液状というよりは粘着性と硬性をかねそなえ、さらに、それをひき寄せるとあたかも指にはねかえってくるような感じのものである」(#B_095、一五五ページ)。この、物質としての官能性はいかにも吉岡好みだ。
また「蜂蜜は色や質に大きな変異があるが、これはもっぱら、蜜が集められた花の種類によるものであり、その香りは、花にある香りのある揮発性油からくるものである。この揮発性油はまた、花の香りの本源である」(#B_042、一三四ページ)とクラウセンの《昆虫のフォークロア》にあるように、蜂蜜の色は花の種類に依る。「黄色」の蜜はごく普通の色のようである。それにしても「蜜はなぜ黄色なのか」――「蜜の色は花に依る」のか。
蜂蜜の色については、福田邦夫の〈ハニー・イエロー(Honey Yellow)〉の説明が手掛かりになる。「蜂蜜のような色のこと。1611年という早い時期から使われている色名で、最初はイエローが付かなかった。近代になってから、ハニー・ベージュ(honey beige〉、忍冬[すいかずら]を表わすハニーサックル(honeysuckle)、ある種の蜜のことをいうハニーデュー(honeydew)というような紛らわしい色名がいろいろできたので、イエローを付けるようになり、1928年には、もとのハニー・イエローと同じ色のことを、特にハニースイート(honeysweet)と、蜜のように甘い、といういかにも商業的な名前で呼ぶようになった。/この色名は、蜂蜜のような色を表わす一般的な色名として用いら
れるのはもちろんだが、蜜色の髪、というように、欧米人に多い、金髪よりやや濃い色の頭髪の形容にもよく用いられている」(#B_125、二〇六ページ)。
題名の「蜜はなぜ黄色なのか?」を英語にすると“Why is honey yellow?”とでもなろうが、福田説を踏まえれば「蜜はなぜ蜂蜜のような〔黄〕色なのか?」というニュアンスに近い。これはわれわれ日本人がふつう黄色から連想する原色のそれとは異なり、西洋的な薫りを漂わせている。――「軽井沢/夏野ゆく金髪少女の横顔をかすめる影あり落ち葉なりけり」(歌集《魚藍》)という一首は実際の光景なのかはっきりしない。むしろフランスの翻訳詩か当時親しんだ木下夕爾詩の影響を受けて、想像力が織りあげた一首かもしれない。〈木下夕爾との別れ〉(#A_25、二一七ページ)から引く。
しかし私が夕爾を好きになったのは、限定百部の処女詩集《田舎の食卓》を手に入れて、読んだ時からである。昭和十四年に刊行されたこの詩集は、文芸汎論詩集賞を受けた。たしか一部の人から、日本のフランシス・ジャムだと高く評価されたようでもあった。乾草いろの歳月が燃される
僕のまはりで
あの蜜蜂の翅[はね]の音が
僕を煮る
悲哀の壺で
ああ とろ火で 〈田舎の食卓〉
吉岡実は一九六九年五月号《文藝》の随筆〈名著発掘〉欄の末尾を次のように結んだ。「ほかにもう一冊ここにあげておきたい。それは、漫画家として知られた小山内龍の『昆虫放談』である(題名に誤ちあるかも知れぬ)。このすぐれた昆虫観察記は、科学者の冷徹な眼とは別な、画家の眼が捉えるあたたかい生命感に彩られた昆虫の世界だ。本が手元になく、記憶もあいまいなので、はっきりしたことは言えないのは残念だ。たしか集中の圧巻は、オオムラサキ蝶の生態観察で苦心さんたんの暁、遂に転身、羽化の一瞬の神秘的な劇をみごとにとどめていたように思う。もう一度読みたい書物である」(#A_25、一六ページ)。小山内龍は明治三七(一九〇四)年、函館に生まれた漫画家・絵本作家。独学のすえ昭和一一(一九三六)年ころから動物漫画を描き、自ら昆虫を飼って昆虫漫画の名手になった。当時は社会諷刺漫画を描いていたから、出征前の吉岡も小山内の画に触れていたかもしれない。《昆虫放談》は①一九四一年・大和書房、②四八年・組合書店、③六三年・オリオン社(このときの書名は《昆虫日記》)、④七八年・築地書館、と何度も版元を変えて出ている名著だ(引用は④に依る)。
六月十一日午後三時二十七分弱 この時間に ついに待望のオオムラサキの雄は 世紀の騎士のような ケンランたる姿を現わした 蝶はぬけ出た蛹体に しっかりと 中脚と後脚とで ぶらさがっている 徐々にのびた四枚の翅は その裏面がやや 黄緑色だ 前翅上方は 表翅の紫部が 裏へにじみ出たように 黒くなって その中に黄緑色の 斑点が見える 後翅の裏面は内側に 一点紅色の斑点が表からとおったように 出ていた 複眼と ショッカクの先端は茶色で 胸と尾の表面は 灰黒色で 裏面は黄緑色であった(#B_021、二一九ページ)
ペン描きの線画に絵筆で彩色したような、小山内の精細な書きぶりだ。吉岡の〈タコ〉(⑧・2)の第二節が好対照をなす。
タコの生殖はとても呪われたフォームを見せる それは濡れて裂かれた傘のような肉の散乱にちかい タコのオスの七つの足は水を抱きこむ そして残されたごく先細りの一つの足がくだの器官の役目をする ちょっと見ると 靴の紐のようにみすぼらしく タコのメスの小さな孔を探し求めて入りこむ これが交接といえるだろうか 水は起伏してながれる 透明な世界では悦びもなく射精は終る すぐそばにタコのメスのみひらかれた眼がある それには汎神論的な悪意が感じられる〔……〕
四方田犬彦が〈内部の貝と外部の袋――吉岡実の海洋生物学〉で指摘したように「生物のあらゆる常識からおよそ懸け隔たったこの醜い軟体生物の生態は、読む者に感傷よりもグロテスクな生の戯画の印象をもたらす」(#C_010、一三四ページ)にしても、それは吉岡の視点が「汎神論的な悪意」に染められているからである。オオムラサキの雄にしてもタコのメスにしても、画家や詩人がその生の営みを永遠化することは、いわば琥珀と成すことだった。オオムラサキの生態観察に「羽化の一瞬の神秘的な劇」を観た詩人は「格子を出てゆく金蠅」に「仔牛を出てゆく蜂」を潜ませてはいなかっただろうか。「ブーゴニア(Bugonia)」とは、渡辺孝に依れば、古代ギリシアやローマが伝える牡牛の屍体から蜜蜂が発生するという信仰である(#B_168)。養蜂の見地からすれば迷信だが「ミツバチが牡牛から生まれるとする例のブーゴニアなども、古代農耕祭にルーツをもつと考えたほうが理解しやすい」(同前、一九六ページ)とき、私は後年の《薬玉》の世界を想わずにはいられない。人類の遠い記憶を詩的作品に結晶させるという後期吉岡実詩の世界を。
飯倉照平監修、松居竜五・田村義也・中西須美訳《南方熊楠英文論考[ネイチャー]誌篇》(集英社、二〇〇五)の第三章は〈虻と蜂に関するフォークロア〉である。
その一篇〈蜂に関する東洋の俗信〉の「(四)蜂から琥珀を作ること」には「同じく『西陽雑俎』に一一巻に、『南蛮記』からの次のような引用がある。「寧州の砂地には折腰蜂がおり、土手が崩れると姿を現す。土地の人々は、これを焼いて琥珀を作る」。この誤った推論は明らかに、琥珀のなかに膜翅類の昆虫の残骸がみられることに由来するのであろう」(同書、六八ページ)とあり、〈琥珀の起源についての中国人の見解〉には「まったく荒唐無稽な説もある。〔……〕「琥珀」という中国語の語源にしても、神話がかっている。古代にはこの語は「虎魄」と書かれ、「虎の魂」を意味した。そのため、次のような説明がなされたのである。/「虎は夜になると片目を光らせて闇を照らし、もう片方の目で者を見る。矢で射られると、虎の魂である目の光は地中に沈み、白い石と化す。……琥珀はこの石によく似ており、そのために虎魄と名づけられた」」(同前、七六ページ)とある。また〈ブーゴニア俗信に関する注記〉の南方自身による注に「honeyを表す言葉として日本で唯一用いられているのは「みつ」(古くは「みち」)だが、これは中国語の「蜜[ミー]」の転訛である。honey-beeにあたる言葉は異なる二語を組みあわせたミツ・バチである(一〇世紀に書かれた『和名[類聚]抄』一六巻および一九巻)」(同前、一〇二ページ)とあり、詩篇〈蜜はなぜ黄色なのか?〉の背景として南方熊楠のこれらの論考を勘案すると、詩集《神秘的な時代の詩》が想いのほか《薬玉》の民間伝承の世界に近いことを感じる。
あら心もとなと散らしつる花や。や。さればこそ人の候。落花狼藉の人そこ退き給へ。――《雲林院》(#B_052、四六〇~四六一ページ)
詩篇〈夏の家〉は、青土社の清水康雄が復刊した《ユリイカ》の第二号(一九六九年八月号)に掲載され、一九七四年一〇月に詩集《神秘的な時代の詩》(湯川書房刊)に収められた。《月刊ポエム》一九七八年一月号の特集〈ことば遊び詩アンソロジー〉に再録されたとき、吉岡実は新たに短文を付した。
私には言葉遊びと呼べるような詩はまったくといっていいほどない。この作品が、かろうじてそう呼べるものかもしれないが。人が言葉遊びと呼びそうなところでも、私は遊んでいない。(#C_003、七二ページ)
自作、とりわけ詩集《神秘的な時代の詩》の詩について語ることの少なかった吉岡にしては珍しい発言である。今回は、吉岡の自作へのコメントを手掛かりにして、作品を読んでいくことにしよう。
〈ことば遊び詩アンソロジー〉の扉ページには「現代の詩人たちは、どんなことば遊びをやっているんだろう/というわけで、現代の第一線で活躍中の詩人たちに、それぞれの作品の中で〈ことば遊び〉と考えられる一篇を提出していただきました。また必要に応じて説明も添えていただきましたのでご覧ください」(同前、六四ページ)と企画の主旨があり、特集の末尾には「(掲載は到着順)」と付記されている。ちなみに吉岡の〈夏の家〉は、アンソロジーのいちばん最後の作品で、付記のあるページに掲載されている(詩の本文は詩集収録形と同じ)。再録する詩篇と説明の原稿を編集者から求められて承諾したものの、なかなかまとまらず、催促されてどうにか書いた、といったところだろうか。
一九七七年の吉岡実といえば、《神秘的な時代の詩》の次の詩集《サフラン摘み》を前年に刊行しており、のちに《夏の宴》(一九七九年刊)としてまとめられる詩篇を書きついでいた時分である。〈夏の家〉は、作品発表のほぼ十年後に、作品史における中期までの吉岡が言葉遊びの詩を請われて「かろうじて」提出しえた詩篇、という一面をもっていた。ここで言葉遊び全般について概観しておこう。
英文学者の高橋康也に拠れば、言葉遊びとは言語の「〈能記[シニフィアン]〉〔言語の二要素のうち、音声および文字〕と〈所記[シニフィエ]〉〔同じく、意味内容〕の通常受け入れられている結びつきを解きほどいて、〈能記〉に過剰な力点を置き、そこに生ずる意外性を楽しむゲーム」(#B_170、六九ページ)である。高橋は、言語遊戯の代表的なもの一四を、具体例とともに挙げている。(1)アクロスティック(2)折句(3)沓冠・八重襷(4)回文(5)アナグラム(6)図形詩(7)音響詩(8)鏡文字(9)懸詞(10)カバン語(11)地口(12)軛語法(13)早口言葉(14)ファトラジー。軛語法zeugmaとは「複数の異質な目的語を一つの動詞で支配する語法」で、セルバンテスに「私は家と忍耐を捨てた」があり、吉岡にも「回虫が老人と死にみきりをつけ」(〈死児〉④・19)がある。ファトラジーfatrasieは「でたらめ歌」で、「死んだ鮭が 星のめぐりを 罠でとらえたとき 角笛の音が 雷の心臓を 酢につけて食べた」(一三世紀フランスで流行した支離滅裂な詩)など。ファトラジーは、通常の文脈の限度を超えて語を酷使する吉岡実の詩法に通じるものがある。もっともその傾向は、強弱の差はあれ吉岡の詩全般について言える特徴であって、この〈夏の家〉独自のものというわけではない。
歌人の塚本邦雄の《ことば遊び悦覧記》には、いろは歌・回文・文字鎖・折句・野馬台詩・形象詩[カリグラム]・詞絵・幾何学形詩・輪状詩・循環詩などが取りあげられており、幾何学形詩の項には吉岡の《液体》から〈灯る曲線〉(②・30)と〈夢の翻訳〉(②・32)が引かれている。「改行を避けつつ、結果的には各行の並列が矩形、正方形になるやうに按配した散文詩作品」(#B_093、一二八ページ)以下の分析は興味深いが、残念ながらこれら二篇と異なる書法の〈夏の家〉の参考にはならない。
定稿として〈夏の家〉本文を書肆山田版の詩集《神秘的な時代の詩》(一九七六年刊)から引く。
夏の家|吉岡実森の青葉の下に来て 1
双頭の美女と逢びき首びき 2
考えてもみて下さい 3
花飾りの下着の太い胴廻り 4
そのなかで落下蝋石! 5
それはよいともわるいともいえない 6
子供の描く絵のように 7
露のつらなるはずかしい 8
夏の男と女 9
すべる多面体 10
狭い入江の奥へ至る 11
笹鳴る夕べ 12
わたしはアンチ・ロマンに食傷し 13
そぞろに思う 14
トリカブトの毒 15
スダレ・ふうりんの夢 16
入日の都市では 17
鉄棒こそかりそめの永遠よ! 18
ブルーの髪をなびかせて 19
とびあがる 20
モッブのおさげの女生徒たちを押えて 21
球なす汗の陰蔽だ! 22
長い地下道を通過する 23
貨車や 24
影の火薬 25
もしくは仕度の了った死体? 26
南が曇れば北上する 27
暑い日 28
花嫁のかつらをかぶって 29
泳ぐ人 30
今を時めく 31
双頭の老婆を 32
正面から抱く人 33
ミスティックな水の音 34
ミモザは茂り 35
暗い菊形のパラシュートで 36
淋しい家の梁から 37
わたしはほそいほそいランニング姿で 38
おりるんだ! 39
一読して、どこが言葉遊びの詩なのか、と考えこんでしまうような詩である。なるほど地口と解る詩句が一箇所ある。しかしそれならこれまでにも「にくにくしい肉体」(〈色彩の内部〉⑦・4)といった例が、本篇のあとにも「白地に赤く死のまる染めて」(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)といった例があり、この詩が特別というわけではない。それとも一読しただけでは判らない、一見してそうとは見えない言葉遊びが試みられているのだろうか。ここで方向転換して〈夏の家〉と同じ三九行から成る吉岡の詩を《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第2版〕》(#B_045)で調べてみると、全部で七篇ある。
・苦力(④僧侶・13)《現代詩》(書肆パトリア)一九五八年六月号(五巻六号)
・衣鉢(⑤紡錘形・16)《ユリイカ》(書肆ユリイカ)一九六一年一月号(六巻一号)
・劇のためのト書の試み(⑥静かな家・1)《鰐》(鰐の会)一九六二年九月(一〇号)
・夏の家(⑦神秘的な時代の詩・13)《ユリイカ》(青土社)一九六九年八月号(一巻二号)
・天竺(⑪薬玉・9)《毎日新聞(夕刊)》(毎日新聞東京本社)一九八二年八月一六日(三八二〇〇号)
・秋思賦(⑪薬玉・8)《ユリイカ》(青土社)一九八二年一二月臨時増刊号(一四巻一三号)
・銀幕(⑫ムーンドロップ・9〉梅木英治銅版画集《日々の惑星》(ギャラリープチフォルム刊)一九八六年一二月三日
これら七篇の、標題を含むすべての詩句を「あ」「いん」「しゃ」「てぃっ」など、音としての比較が可能な最小単位にまで分解して、七篇全体の平均的な頻度と〈夏の家〉一篇の頻度とを比較してみた(助詞の「は・へ・を」は便宜的に「わ・え・お」と見倣した)。吉岡の「言葉遊び」が地口なら、詩句を構成する語(とくにその音)に偏向があるに違いないからだ。分解した最小単位での比較は、対象の登場回数が少なすぎるため、ア行・カ行(ガ行含む)・サ行(ザ行含む)・タ行(ダ行含む)・ナ行・ハ行(バ行・パ行含む)・マ行・ヤ行・ラ行・ワというまとまりにして比べてみた。〈夏の家〉で全七篇の平均値一から〇・一(10%)以上の差があるのは、「カ行(ガ行含む)」の〇・八四(一六ポイント少ない)と、「サ行(ザ行含む)」の一・一四(一四ポイント多い)である。「言葉遊び」の特徴が高橋康也の言うように〈能記〉に過剰な力点を置くことにあるのなら、ある種の音の語を選択しないことよりも選択することに発現するだろうから、「サ行(ザ行含む)」の語が関連すると想定される。それらを抜きだしてみよう(*印を付けた一一件は、詩句の行頭がその「サ行(ザ行含む)」の音をもつ語であることを示す)。
「下」、「*双頭」「美女」、「下さい」、「花飾り」「下着」、「*その」「蝋石」、「*それ」、「*すべる」、「*狭い」、「*笹」、「食傷し」、「*そぞろに」、「*スダレ」、「都市」、「こそ」「かりそめ」、「なびかせて」、「おさげ」「女生徒」、「なす」「汗」、「する」、「貨車」、「もしくは」「支度」「死体」、「する」、「*双頭」、「*正面」、「ミスティック」「水」、「ミモザ」「茂り」、「パラシュート」、「*淋しい」、「ほそいほそい」「姿」。
ここでは「下」と「下着」、それぞれ二度登場する「*双頭」と「する」、「ほそいほそい」などが目を引くが、その用法は吉岡の通常の作品の守備範囲内であって、ある種の意図(リフレインなど)を反映したものではない。これらの語を押しのけて前面に出てくるのが「蝋石」である。むろん「落花狼藉/落下蝋石」が意図されている。吉岡の「人が言葉遊びと呼びそうなところ」とは、これを指すとみていい。そうはいうものの「らっかろうぜき/らっか ろうせき」では完全に同じ音ではないし、イントネーションも異なる。意味の面から言っても、落花・狼藉がほぼ同義の内容の二様の表現であるのに対し、落下・蝋石は語と語の関連性が低い。ふつうに考えれば落下する蝋石なわけで、意味の側から遊びの要素は見つけがたいが、これを落花狼藉の地口だと受けとれない読者はいないだろう。吉岡が「人が言葉遊びと呼びそうなところでも、私は遊んでいない」と主張するのはなぜか。初出の媒体は通常の詩作品として掲載している。おそらく見開き二ページ(四〇行)の詩として依頼したものだろう。できた作品は言葉遊びの詩でなくてもかまわないが、言葉遊びの詩であってもかまわないのではないか。
ここから〈夏の家〉を評釈していくが、前に述べた本文に登場する「サ行(ザ行含む)」の語を太字にして引く。
第一行「森の青葉の下に来て」。初出形は「森のアオバの下に来て」だった。そこからは、自宅のある東京都目黒区「青葉」台への連想を絶とうとした所作が読める。地面には木洩日が揺れ、見あげれば葉が緑に光る。初夏の穏やかな風景だ。「下」はどうか。ドラマの開幕。
第二行「双頭の美女と逢びき首びき」。「双頭」はふつう「双頭の鷲」などと使われるが、「美女」に係ることで読者の注意を引く。鷲のような美女? 次の「逢びき」はとりあえずいいとして、「首びき」がなんだかわからない。中型辞典には「互いに頸に輪形にした紐をかけてひっぱり合い、引き寄せられた方を負けとする一種の遊戯」とある(#B_075、六三九ページ。ちなみに吉岡の自宅には《広辞苑》があった)。文の流れからすれば「わたし」が「双頭の美女(のどちらか)」と「逢びき」して、それから「首びき」したと読める。もうひとつの「互いに競いあうこと」という意味だと、「双頭の美女」どうしが争っているようにも読める。次に大型辞典で「首引」を見ると、ほかに「男女交合の一態」の義があり、さらに狂言〈首引〉が挙げられている。鎮西八郎為朝が印南野で鬼に出会い、姫鬼と腕押しなどの勝負をしたうえ、さらに大勢の鬼どもを相手に首びきの仕合いをしてそのどちらにも勝つ、という曲だ(#B_116、五七三ページ参照)。吉岡歿後の一九九六年刊だが、新日本古典文学大系58《狂言記》だと〈首引〉の「おれは腹押しがしたい」(#B_118、二三五ページ)と言う姫鬼に親鬼が慌てる所が面白い。吉岡が読んだかもしれない岩波文庫《能狂言(中)》の大蔵虎寛本〈くびゞき〉には「腹押し」が出てこず、替わりに「すねおし」が出てくる。腕押しのあとになにをするかシテ(親鬼)に問われて、為朝はすねおしと答える。女(姫鬼)も応じるが、腕押し同様、再び為朝に強く擦りつけられ、
(女)アアいたいたいた。(シテ)ヤイヤイ姫、何としたぞ何としたぞ。(女)申申とと様、わらはが此和らかなももへ、あのおそろしい毛のはへたあしを入て、又したたかにすり付まして御ざる。(#B_050、四一三ページ〔繰りかえし符号は用いなかった〕)
と続く。〈夏の家〉第三行以下を読めば、吉岡がここで狂言〈首引〉を暗示していることは充分に考えられる。しかし事の性質上、確証は得られない。いずれにしても「双頭の美女」と「姫鬼」が「首びき」の一語でもって縫いあわされている事態は動かない。
第三行「考えてもみて下さい」。この詩句は、読者への呼びかけである以上に、「想像せよ」と自らを鼓吹しているように読める。それは前の行にかかるようでも、次の行にかかるようでもある。語句的には不明なもののないこうした詩句の評釈がいちばん厄介だ。ここで読者に詩への参加を促しているのは、その喋り口調である。地の文としてなら、「考えてもみよ」あたりになるところが、現行の行文になっているわけだ。作者の発話というよりも、「わたし」のそれに近い。
第四行「花飾りの下着の太い胴廻り」。「(太い)胴廻り」は、他の吉岡の詩にはスズメ蛾の形容として何度か登場する。この翅の色の美しい、体が太く紡錘形の蛾はのちにこう謳われている。
・スズメガの太い胴まわり(〈葉〉⑧・4)
・胴はスズメ蛾のようにふくらみ(〈螺旋形〉⑨・10)
さらには「そして「すがる乙女」を撮った」(〈竪の声〉⑪・2)も、「胴廻り」としてのウェストラインを想わせる詩句だ(「すがる」はジガバチの古称で、美女の細腰の喩え。吉岡の歌集《魚藍》の原題〈蜾蠃〔スガル〕鈔〉としてもなじみ深い)。
第五・六行「そのなかで落下蝋石!」。当然、第四行の「花飾りの」からは「落花」と進むべきところをあえて「落下」としたことで、意味の関節がはずされていく。下着のなかで落下する蝋石とは、感嘆符を付けたくなるほどの代物か。「それはよいともわるいともいえない」。第三行と同じような機能の詩句だ。ひらがな書きが、内的独白のようなニュアンスを醸しだしている。
第七~九行「子供の描く絵のように」。初出では「子供の描く絵」。地面に蝋石で描いたものか。手入れの結果、七音・五音となった詩句。「露のつらなるはずかしい」。「つ[、]ゆ」「つ[、]らなる」と頭韻を踏み、ここも前行に続いて七音・五音からなる詩句。「夏の男と女」。ここで初めて「夏」が登場した。
第一〇行「すべる多面体」。露によって「すべる」なら、遠く二行めの「首びき」の余韻とみるべきか。詩句は「蝋石」の言い換えであろう。わたしはここで、ステファヌ・マラルメが自身の言語の比喩として「多面体」の語を用いたことを想起する。吉岡実が自身の詩を「すべる多面体」と認識していたのなら、愉快なことだ。ちなみに《ムーンドロップ》冒頭の詩句「〔聖なる蜘蛛〕」(〈産霊(むすび)〉⑫・1)はマラルメの書簡からの引用――おそらく菅野昭正経由で――である(#B_034、二八六ページ参照)。
第一一・一二行「狭い入江の奥へ至る」。人が移動するのなら、ここでは当然、船によるものだが、性的な行為の暗示とも読める。「笹鳴る夕べ」。「篠笹の鳴る方へ/オシドリが二羽/すいすい游いでいる/(菱形の池)」(〈ムーンドロップ〉⑫・10)。笹の鳴る光景に男女・雌雄が結びあわされている。
第一三行「わたしはアンチ・ロマンに食傷し」(初出は「「わたしはアンチ・ロマンに食傷して」)。「食傷」にはふたつの意がある。「食中り」と「食いあきること/同じ物事にしばしば接して、いやになること」である。ここでは後者のようだ。――わたしはアンチロマンに食いあきて。アンチロマンとはなにか。「アンチ・ロマン」はなにか。菅野昭正は「《アンチ・ロマン》という言葉は、周知の通り、サルトルが〔ナタリー・サロートの〕『見知らぬ男の肖像』の序文のなかで使ったものである。サルトルはその序文で、小説ジャンルの根本にかかわる反省にもとづいて、従来の小説形式を破壊しようとする意図をもつ小説作品、といったような意味あいをこの言葉に含ませている」(#B_035、一八一ページ)と解説し、「アンチ・ロマン」は「日本ではかなり頻繁に用いられたが、〔……〕フランスで
はあまり使用度は高くなかったはずである」(同前、一一九ページ)と述べている。吉岡は当時の訳書を通じてアンチロマンに触れたのだろうか――勤務先の筑摩書房からは、一九七〇年に〈世界文学全集65〉として《アンチ・ロマン集》(#B_053)
が刊行された――。「アンチ・ロマン」の語は、六〇年代末には「ヌーヴォー・ロマン」より優勢だっただけでなく、その「反」の性格が色濃かった。詩句を意訳すれば「詩ジャンルの根本にかかわる反省にもとづいて、従来の詩形式を破壊しようとする意図をもつ詩作品」を読むこと(書くことも?)に飽いて……となる。《神秘的な時代の詩》の作品群こそ「従来の詩形式を破壊しようとする意図をもつ詩作品」と思惟するわたしにとって、大いなる逆説である。あるいは、「物語」の虚妄を暴いて「現実」をありのままの様相でとらえる、という「ヌーヴォー・ロマン」の特質(菅野による)こそ、吉岡実が詩作のうえで身上とした「リアリティ」追求を換言したものと考える者にとっても。
第一四~一六行「そぞろに思う/トリカブトの毒/スダレ・ふうりんの夢」は興味深い。まず「そぞろに」は、吉岡がしばしば意図的に用いる古風な言い回しのひとつだが、ここでは「スダレ」の音韻と通じあい、かつ「気もそぞろ」的な雰囲気も醸している。しかし、ここでなによりも決定的なのは一五行めの「トリカブトの毒」である。西脇順三郎の詩集《Ambarvalia》の〈紙芝居Shylockiade〉には「我が言語はドーリアンの語でもないアルタイの言/である、そのまたスタイルは文語体と口語体と/を混じたトリカブトの毒草の如きものである。」(#B_112、三二ページ)という詩句があった。新倉俊一の《西脇順三郎全詩引喩集成》もこれに注していないから、この宣言になにか典拠があるわけではないだろう。おそらく吉岡はここで、西脇の《Ambarvalia》の詩的スタイルに言及している。しかも続けて「スダレ・ふうりんの夢」とあるところが吉岡らしい。簾や風鈴は生まれ育った東京・下町の情緒あふれる風物であり、端的に夏を示している。これに朝顔とくれば、夏の涼の代名詞である。しかもそれは「の夢」であって、西脇的な世
界も下町の夏も夢想するしかない対象だと慨嘆しているのがこの詩句の意味するところだろう。
第一七・一八行。「入日の都市では/鉄棒こそかりそめの永遠よ!」。水平の「鉄棒」の向こうに墜ちる夕陽。「鉄棒」は初出では「棒」だった。単に「棒」とくれば誰もが〈僧侶〉(④・8)の冒頭「四人の僧侶/庭園をそぞろ歩き/ときに黒い布を巻きあげる/棒の形/憎しみもなしに/若い女を叩く/こうもりが叫ぶまで」を想起する(ここにも「そぞろ」があった)。同時に〈マクロコスモス〉(⑦・1)の末尾「棒高跳選手/バーを越えるとき/不条理な鉄の処女を感じる」も想いだされる。ここは、それらを回避するための改稿だったか。鉄棒のある公園や学校が連想される。
第一九行「ブルーの髪をなびかせて」。この行の前で詩の展開に断絶がある。つまり、まず前行末尾の感嘆符がここで一呼吸おいたような印象を与えるのだ。さらに「入日」の橙・朱・赤をこきまぜた絵巻のなかから一転して青を登場させてきた点も見のがせない。ところで「ブルーの髪」とはなんだろう。文字どおり青い毛髪。それは遠く第一行の「青葉」を受けているかもしれない。若若しく生える「葉」と「髪」。女の緑の艶のある美しい黒髪。さらに「青毛」すなわち「俗に馬一般の代表名」からは、馬の鬣さえ浮かんでくるではないか。
第二〇~二二行の「とびあがる/モッブのおさげの女生徒たちを押えて/球なす汗の陰蔽だ!」は、当然一九行めを受けて「ブルーの髪をなびかせて/とびあがる」と続くのに違いない。違いないが、「とびあがる」で一詩句を成しており、それこそこの行だけとびあがっているように感じられる。次行の「モッブ」は詩語としては珍しい(わたしは〈夏の家〉以外の詩で見たことがない)。心理学では「乱集(モッブ)」は、暴動やテロなどに見られるような情動的で積極的に行動する群集、と定義される。噺く馬を宥める様子さえ彷彿とする詩句である。「球なす汗の陰蔽だ!」の詩句は読みときにくい。「球なす汗」と「陰蔽」を結ぶ「の」の機能が特定できないからだ。「わたし」は「モッブのおさげの女生徒たち」の「球なす汗」を「陰蔽」する――というのがストレートな解釈だ。それでも「汗を陰蔽する」が不明だ。「抑えて」ではな
く
「押えて」はなにか。「女生徒たちを〔わたしは〕押えて」「〔わたしの〕球なす汗」がなにかを「陰蔽」する――ということか。それとも「モッブのおさげの女生徒たち」=「球なす汗」で、「押えて」=「陰蔽」の言い換えか。それならば「押える〔すなわち〕」と活用しなければ続かないはずだが。
高橋睦郎は一九八四年に刊行された《現代の詩人 1 吉岡実》の〈鑑賞〉で次のように書いている。
「夏の家」。マスコミでさかんにサイケデリックがいわれた時代の荒唐無稽な精神風景をそのまま定着した詩といったらいいだろうか。中村宏の「モッブのおさげの女生徒」や横尾忠則の「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」も出てくる。しかし、このノンシャランな風景の連続写真も、最後に「暗い菊形のパラシュートで/淋しい家の梁から」「ほそいほそいランニング姿で/おりる」「わたし」を持ってこなければ、おさまりがつかないらしい。(#A_23、六三ページ)
〈夏の家〉鑑賞の全文である(ここからだけでは判りづらいが、高橋は〈鑑賞〉執筆にあたり吉岡に取材している。中村や横尾の名は吉岡本人から出たものかもしれないが、断定はできない)。吉岡実の詩としては稀なことに、冒頭にも引いた作者のコメントに加え、鑑賞者の側からのコメントが並んだ恰好だ。《神秘的な時代の詩》の評釈において作品以外の材料がこれだけ揃ったことはかつてなく、おそらく今後取りあげる詩篇でもこうした事態は起こりえないだろう。吉岡と高橋の発言を奇貨とする所以である。
横尾忠則には別のところで触れるとして、中村宏はどうだろうか。当時の中村と吉岡の接点は、ひとつは一九六八年一一月、年譜に「土方〔巽〕の〈肉体の叛乱〉と舞踏生活一〇周年を記念する《あんま――愛欲を支える劇場の話》に〈青い柱はどこにあるか?〉を再録、〔二三日、〕この限定五〇部で大型箱入りの豪華な詩画集制作のために目黒のアスベスト館を訪ねる」(#A_32、二九六ページ)とある詩画集制作プロジェクトで顔を合わせていることだ。もうひとつは中村宏が一九六九年の《現代詩手帖》の表紙画を一年間、連載していることである(#B_108、六一~六三ページ参照)。中村の作品は、横尾の絵画がプリミティブであるのに対して、暴力的である。吉岡が詩篇〈少女〉を寄せた《血と薔薇》第二号(一九六九年一月発行)に、中村も作品〈〔特集・未来のイヴ〕衣服崇拝〉と〈〔特集・殺人機械〕蒸気機関車式殺人機械〉を掲載していることを追加しておこう(同前、一四〇ページ参照)。
第二三~二五行の「長い地下道を通過する/貨車や/影の火薬」には頭韻の跡が見やすい。すなわち「ながいち[、]かどうをつ[、]うかする/か[、]しゃや/か[、]げのか[、]やく」。地下道は〈無罪・有罪〉(⑥・2)の判事が入っていった場所でもあった。第二節を追込にして引こう。
判事は地下道へ入る/優しい妻と子は劇場で歌劇を見る/兇器がみつかるまで/判事は長い歳月を孤独な壁を撫でる/不具の記憶のくりかえし/なみだぐましく妻のぬれた躯は今はレンガ色/彼はもぐらのように洞察した/一人の美しい裸形の少女のトルソの二叉/眼を近づければ兇器/細い線の針金/それが輪を形づくる/判事は霧の密室からはい上る/犯罪の起源は/人の心の細胞の花火/兇器は真の犯罪には不要のものかも知れず
〈無罪・有罪〉は最後の節でこう終わる。「ストップ/永遠に/彫刻された男女のために/可能ならば/無罪も有罪もなく」。ここでは男は女のために犯罪を起こさざるを得ない、という認識が詩句を染めている。「貨車や/影の火薬」にしたところで真の犯罪には不要の兇器であり、戦争において使われるだけだ。それらは精神の空隙に向かって放たれた不要のものの代名詞である。
第二六行「もしくは仕度の了った死体?」も頭韻「し」が構造の中心となっている詩句だ。「し」に加えて「た」まで続くところからも、吉岡の音への執着は紛れもない。「長い地下道を通過する」「仕度の了った死体」とはなにか。ここだけを見れば、衣服を調え死出の旅支度をすませた屍体が霊枢車のようなものに乗せられて地下を移動している、というところだろうか。こんなものにいきなり出てこられても、読者はとまどうばかりだ。しかし、そこに巧妙に仕掛けられているのが、法令文で「または」よりも下位の結合に使用される「もしくは」である。「貨車・または・影の火薬・もしくは・仕度の了った死体」?――と、疑問符はこれら全体にかかる。なぜなら、「地下道」(すなわち道路)を「貨車」(軌道は線路)が通過することで詩句は小さな違和を醸成しており、読者はこれはリアルな描写ではなく作者の騙りではないか、という疑いを抱くことになるからだ。そのとき「し」および「た」の繰りかえしは、催眠的な色を帯びている。
第二七行「南が曇れば北上する」。「曇れば」をどう解釈したらいいか、雲を掴むような行ではある。わたしは次のように読んでみる。前行の「死体」の火葬の煙で南が曇っているという光景は「雲煙となる=死んで火葬の煙となる」であり、さらに「雲の林=雲のむらがり立っているさまを林に見立てていう語。雲林院にかけていうことが多い」から、落花狼藉の関連で題辞に引いた「雲林院」に至る。われながらうまい解とも思えないが、この詩句をどう読むかとなれば相当の意味付与をしなければ読みきれまい。「南下」するのではなく「北上」するからには、曇り・雲を忌避してのことだろう。夏の太陽を冀求しての行動か。後年、吉岡は「北」への紀行から生まれた大作〈あまがつ頌〉(⑧・30)の第Ⅲ節で、
干葉汁をすする歯黒〔=羽黒〕の童女かな
*
葛山〔=月山〕麓糞袋もたぬかかし達
*
湯殿〔山〕より人死にながら山を見る
*
雪おんな出刃山刀〔=出羽三塔〕を隠したり
*
喪神川〔=最上川〕畜生舟を沈めける
*
〔以下、二句略〕
と、通常なら〔 〕内のように書く地名をまがまがしく変奏して、松尾芭蕉の《奥の細道》の向こうを張った。
第二八行「暑い日」。陽の当たる「北」に移動したのだから、当然のように「暑い日」となる。それと同時に季語「暑き日」と芭蕉の句「暑き日を海にいれたり最上川」(#B_076、八九ページ)が想われる。ここで作者は芭蕉の俳諧紀行を暗示しているのだろうか。


横尾忠則の1966年作のアクリル画〈お堀〉(左)と〈花嫁〉(右)
出典:難波英夫監修《横尾忠則全絵画》(平凡社、1996)
第二九・三〇行の「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」は、先に引いた高橋睦郎〈鑑賞〉に拠れば、横尾忠則の作品から来ている。たしかに横尾には一九六六年作の〈花嫁〉(#B_160、一九ページ)と題する絵画がある。さらに「泳ぐ人」なら、同年の〈お堀〉(同前、二八ページ)か。しかしながらそれらはどう観ても女の顔だ。二九・三〇行めは男でなければならない。なぜなら(あと数行、読まなければわからないのだが)この「泳ぐ人」こそ「わたし」、すなわち「双頭の美女」や「女生徒たち」と対抗する唯一の男であり、この詩における光源だからである。光源自体は可視である必要はないが、それがなければ「双頭の美女」も「女生徒たち」も存在しえない。
第三一~三三行めの「今を時めく/双頭の老婆を/正面から抱く人」は、二九・三〇行の「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」と同格だ。「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」=「今を時めく/双頭の老婆」の可能性もないではないが、やはり「双頭の老婆」には「双頭の美女」の時代からずっと「森の青葉の下に」いてもらいたい。ところでこの「正面から」が曲者である。なぜ側面や背面からではなく、正面からなのか。かつての「夏がくると白くぬりかえる/天使の顔/むしろ正面をむくとき/急にドーナツを食う老婆たち!」(〈春のオーロラ〉⑥・10)や、このときはまだ発表されていない「薔薇型の大きな帽子をかぶった女/薄いランジェリーの女/印度衣装を全体にかぶった女/いずれも下半身を露わに出している/肉性が正面をむくとき/予言者を狼狽させる/シンメトリーの偏愛図」「悲劇の少女にはふりむく真の正面がない/水色のスカートの腰をよじって/ねぐらへ鳥の飛ぶのを仰ぎつづける」(〈フォーサイド家の猫〉⑧・17)を参照すれば、ここでの「正面から」は、相手から見られている状況を明示しているととれる。見る者を見る目。
第三四行の「ミスティックな水の音」に注目したい。水は二九・三〇行の「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」から導かれたと考えるのが妥当だ。ここからは牽強付会の謗りを免れないのだが、先の「暑き日を海にいれたり最上川」をこの詩句に絡めてみたい。句は芭蕉が酒田で日本海に沈む落日を見た
ときの作とされるが、吉岡が芭蕉の句を知らなかったことはありえない(前掲〈あまがつ頌〉では出羽三山と芭蕉を顕彰している)。ここまでくれば「ミスティックな=蛙飛び込む」と代入しても面白かろう。そういえば、西脇順三郎が自作の絵画の披露の日、「古池や蛙とびこむ音がする」ばかりを染筆していたと吉岡が〈西脇順三郎アラベスク 5 伝法院の「龍虎図」〉(#A_25、二三三ページ参照)で嗟嘆したのは、一九七四年ころのことだ。
さて、「ミスティック」こそ「神秘的」という意味をもつ外国語であり、吉岡の詩において初めての登場となった。吉岡は詩において外国語・外来語の使用に禁欲的で、一見するとここも「神秘的な水の音」で充分な気がする。だがそれは二重に――第一は続く「水」の、第二は次行の「ミモザ」の二語の頭韻からの要請で――拒絶される。
A=ミスティックな〔水の音〕
B=〔ミスティックな水〕の音
では印象が異なる。ここは「A=ミスティックな〔水の音〕」ととりたい。なぜなら、ミスティックなのは水ではなく、音であろうから。
第三五~三九行の「ミモザは茂り/暗い菊形のパラシュートで/淋しい家の梁から/わたしはほそいほそいランニング姿で/おりるんだ!」で〈夏の家〉は終わる。ミモザは二種類の植物の呼称であり、一つはオジギソウ、一つはギンヨウアカシア=ハナアカシアだ。ミモザはむろんミモザの花を指す。この詩句が指すのは、続く「菊形」から菊の花が連想されるところから、それに似たギンヨウアカシアと思われる。と言うよりも、実体はむしろ逆で、「ミモザ」→「菊形」→「パラシュート」という意識の流れがまずあり、それが落下傘での降下という最終局面に至るのが大筋の流れだ。ここは「わたし」ではなく、「ランニング姿」が肝心だ。遠く、黒髪の「モッブのおさげの女生徒たち」(おそらくセーラー服)と響きあい、白い「ランニング姿」で独り落下するのがほかならぬ「わたし」だった、とすべきところだ。
ところで「ランニング姿」は、吉岡の未刊の散文〈篠田一士追想〉の冒頭に登場する。「篠田一士が私との出会いを、次のように書いている。/――吉岡さんに初めて会ったのはいつだったか、もう記憶がさだかでない。〔……〕ぼくは「秩序」の広告を貰いにゆき、当面の責任者である吉岡さんに、いろいろレイアウトの指示を仰いだりした。なんだか大変威勢のいいひとで、ランニング・シャツ一枚の小柄な上半身をせわしげに動かしながら、取引先から掛ってくる電話にでて、しきりに「出しますよ、出しますよ」と大声でわめきたてていた。〔……〕――/これは、昭和三十六年七月三十一日付の「読書新聞」のコラムの「人物スケッチ」の冒頭である。当時、私は広告担当として、新聞、雑誌などの広告掲載のための交渉から、原稿まで、一人でこなしていたものである。〔……〕/――それでも、ぼくには、あのランニング・シャツの忙しい人物と『静物』のなかに磨きあげられたガラス球のようにかがやく沈々たる世界とはどうしても結びつかない、ふたつのイメージであった。――/この時から、私は真の知己を得たのである。篠田一士はことあるごとに、私の仕事を高く評価し、支持してくれた」(#C_042、六七~六九ページ)。一九五二年ころ、おそらくワイシャツ姿の巨漢の文学青年と小柄な未来の詩人は出会う。篠田の「ランニング・シャツ」が生身の詩人の優れた運動性能を証言したのを受けて、吉岡はこの追悼文で、あたかも《静物》(一九五五年刊)に至る「永遠の夏」と言うべき詩の胎動期を振りかえっているのだ。
詩篇が発表された一九六九年は、高橋睦郎の言を俟つまでもなくサイケデリックの時代だった。「サイケデリック」とは、LSDなどで起きる幻覚状態や幻覚的なことを言うが、極彩色のイラストレーションやグラフィックデザイン、ファッションなどの形容にも用いられた。当時の音楽にはサイケデリックの影響が顕著で、ビートルズ一九六七年六月発表のアルバム《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》はその震源であった。吉岡が音楽を聴くことに熱心でなかったこともあるが、この時期に限らず、ビートルズに言及したのは土方巽の舞踏で流れた〈ガール〉についてだけだろう(もう一曲は加藤郁乎からの引用文中の〈イェスタデイ〉)。吉岡がビートルズの楽曲や歌詞に精通していた可能性は、まずない。では、次の暗合はどうとらえたらいいのか。佐藤良明はジョン・レノンの楽曲について書いている。
『ラバーソウル』まで、つまり「ガール」、「イン・マイ・ライフ」、「ノルウェーの森」、「ラン・フォー・ユア・ラィフ」あたりまでは、ジョンも基本的にロックンロールやリリカル・バラードを歌っていた。それが『リボルバー』の過渡期を経て1967年になると、ロック史上空前で、その後も絶えてないという感じの歌詞ばかりになってくる。特徴だけ簡単に並べておくと――●1●言葉遊び――しゃれと地口が増殖し、多義性とナンセンスが支配している。
●2●サイケデリック・トリップヘの招待。
●3●リラクセーション――“nothing to do”とか“it doesn't matter”という種の言葉が目立つ。倦怠と流動。社会的自己の消散。
●4●ランダムな言葉の機関銃。
●5●引用とパロディ。(#B_051、三二~三三ページ)
これら五つの特徴は、《神秘的な時代の詩》とその前後の詩集(《静かな家》と《サフラン摘み》)の吉岡の詩ひとつひとつと対照してみるに値するものである。「言葉遊び」についてはⅠで触れた。吉岡に言葉遊びの自覚は薄く、読者にそのようにはとられたくないという意識が働いていたことも見た。従前の吉岡の「意識的に無意識を書く」という作詩法から、この詩において実体的には「無意識的に意識を書く」領域へ歩みでているにもかかわらず、視線はまだ「リラクセーション」に没入できずにいるのではないか。サイケデリックヘ「トリップ」する意志は封じこめられているのだ。吉岡は〈夏の家〉でサイケデリックヘ「トリップ」せんとする人物・事物を点綴した。その展開がいかにアクロバティックに見えようとも、人物・事物は重力の作用を受けてこの地上に存立しており、あくまでも目に見えるものとして描かれている。しかるに、六年後の〈悪趣味な内面の秋の旅〉(⑧・31)の「1」は次のようだ。追込で引く。
内なる旅とは負の回路をめぐり/霧のたちこめる入江から/ねこじゃらしの茂る道を行く/「目覚めて夢みる人」/殺虫剤の臭う街の日々/生者は苦役にはげみつつ/死者はサングラスをかけて休息する/バイオリン形の女を求めて/旅する者はときに少年のように/転倒する/旅[トリップ] 夢遊状態[トリップ]/こわれるものがあり こわれないものがあり/こわれつつあるものがあり/その中間に分裂するものがある/転倒する道化師/転倒するフラスコ/転倒する言語/転倒する建築物/すべて過剰なもの/一茎のアネモネのほかは
「目覚めて夢みる人」の詩句が語るように、ここで旅する者は「トリップ」し、幻視の世界の住人と化す。作者の視線がとらえる人物・事物は無重力の状態に置かれ中空をさまよう。サイケデリックを咀嚼した詩境というべきだろう。
「ランダムな言葉の機関銃」と「引用とパロディ」はどうか。前者は第三・五・六・一八・二二・三九行などの世話にくだけた調子の行や、感嘆符で彩られた行に著しい。後者はⅡの評釈で触れたように、狂言や能、俳句、同時代の詩人や画家の作品へのほのめかしに現われている。それにしても、〈夏の家〉の作詩法はほんとうに〈首引〉や〈雲林院〉や《奥の細道》や《Ambarvalia》や横尾忠則・中村宏の絵に依拠することを自覚的にもっているのだろうか。詩の本文はそれらへの言及のように見えるが、作者が意識してそうしたのか無意識のうちにそうなったのか、わたしには読みきれない。意識的な無意識か、無意識的な意識か。先行する諸作品や外界の出来事は、作者が詩作に集注したあかつきに訪れる真空状態に吸いこまれ、攪拌され、選別不能となり、作者はそれらを取捨する間もあらばこそ、応対に暇ないというのが実際ではなかったろうか。
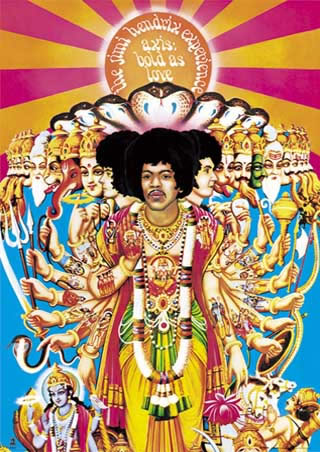
Jimi Hendrix Experience《Axis: Bold as Love》(1967)のアルバムジャケット〔部分〕
ところで、すでに評釈した詩篇〈三重奏〉(⑦・17)の鑑賞で高橋睦郎はこう書いていた。「この作者にはめずらしく一種アンティロマンの短篇小説を読むような作品だ。〔……〕この一篇を短篇小説と見るなら、芸術家であるわたしと、観念的な女友だちと、肉感的で小悪魔的なその妹をめぐる芸術と性の葛藤を描く芸術家小説ということになろう。この小説的方法に深入りしなかったが、深入りしてみるだけの価値はあった、と作者は述懐している」(#A_23、六五~六六ページ)。〈三重奏〉は〈夏の家〉の半年前、一九六九年の二・三月号の《本の手帖》に発表された。吉岡の述懐はおそらく一九八三年の〈鑑賞〉のための高橋の取材時の発言で、「一種アンティロマンの短篇小説を読むような作品」は〈三重奏〉執筆のあと、〈夏の家〉前半で試みられているのではないか。前半(1~12行)と後半(17~39行)を統べる原理の違いがそれを裏づけている。
〈夏の家〉のなかほどに登場する「わたしはアンチ・ロマンに食傷し/そぞろに思う/トリカブトの毒/スダレ・ふうりんの夢」をこの詩篇自体に言及したものとして読むと、今まで書いてきた評釈が、一変するとまではゆかないけれども、かなり表情を変えてくる。文の単位を意識しながら、詩句を散文ふうに書き換えてみよう。
森の青葉の下に来て、双頭の美女と逢びき首びき。
考えてもみて下さい――花飾りの下着の太い胴廻り、そのなかで落下蝋石!
それはよいともわるいともいえない。
子供の描く絵のように、露のつらなるはずかしい夏の男と女、すべる多面体。
狭い入江の奥へ至る笹鳴る夕べ。
次に自己言及的な部分がくるので、この前半までを字義どおり「アンチ・ロマン」として読んでみる。それまでの客観的な記述は、この「アンチ・ロマン」もしくは「アンチ・ロマン的な現実」に飽き飽きしているひとりの男「わたし」の視点を得ることで、にわかになまなましいものとなる。外部からの描写と見えていたものが、「わたし」をカメラアイとする言説に姿を変えたのだ。そのときこの分裂的な発語を支えるのは作者=吉岡実ではなく、「わたし」である。さらに「わたし」は、詩篇の自己言及部分以後はアンチロマン的な言説から現代詩あるいは俳諧的な言説にギヤを入れなおすことになる。われわれもここで引用のスタイルを変えよう。
入日の都市では/鉄棒こそかりそめの永遠よ!ブルーの髪をなびかせて/とびあがる/モッブのおさげの女生徒たちを押えて/球なす汗の陰蔽だ!
長い地下道を通過する/貨車や/影の火薬/もしくは仕度の了った死体?
南が曇れば北上する/暑い日
花嫁のかつらをかぶって泳ぐ人
今を時めく/双頭の老婆を/正面から抱く人
ミスティックな水の音
ミモザは茂り/暗い菊形のパラシュートで/淋しい家の梁から/わたしはほそいほそいランニング姿で/おりるんだ!
後半「花嫁のかつらをかぶって泳ぐ人」が俳句の音数律に近似したのは偶然の産物だろうが、感嘆符や疑問符をこれでもかとばかりに繰り出して、主に二つないし四つの句というユニットを単位として詩をドライブしていく作者は、前半部とは別人のようである。〈夏の家〉がこのようなキメラ的な展開を作者に強いた要因はなんだろう。おそらくアンチロマン的手法一本槍では、作品世界をまったき姿で描けないと考えたためだ。アンチロマン的手法は小説においてはユニークなものであっても、吉岡実詩においてはそれほど画期的な手法ではなかったと思しい。「双頭の美女」が「双頭の老婆」となる時間こそ流れるものの、それはアンチロマン的手法によるのではなく、前半と後半が、扉(中程に登場する詩句)で仕切られた、板の間と畳敷きほど異なる二つの部屋を接合することで具現化された。この、詩篇の「腰を折る」ことこそ〈夏の家〉における詩作の要諦である。
題名の夏と家は、音読みすればどちらもカで、小学校の〈学年別漢字配当表〉の第二学年に「〔……〕何科夏家歌〔……〕」と隣りあわせに並んでいる。「の」が作品名で多用されることは言うまでもない。最も簡単な部類の漢字二字を最も多用されるひらがなで結び、それ自体なんの衒いもなくたたずんでいる標題。その本文は、今まで見てきたように、謎に充ちた、あえて言えば神秘的でさえある詩句を含んでいた。作者はこの家に二つの部屋を用意することで、異形のものが異形のままに年を経ることを可能にしたのだ。
読者はそこで起こるドラマを観なければならない。作者の分身(やはりそう言っていい)「わたし」が最後に「暗い菊形のパラシュートで/淋しい家の梁から〔……〕ほそいほそいランニング姿で/おりるんだ!」と、悲惨ささえ通りこした滑稽きわまる姿で身を曝すのは、詩自体の「キメラ的現実」に対応したがゆえである。この現実に対抗するには、牛刀をもって鶏を割かねばならなかった。
吉岡は、分裂的に統合するという離れ業でいまここに〈夏の家〉をまとめあげた。吉岡が本来得意とする語や詩句のイメージよりも、語や詩句のたてる響きに耳をそばだてながら行をドライブしていくその姿は、わたしには未知の領域にきわめて低空から降下する孤独な落下傘部隊の隊員のように想われてならない。
「洪水や梁にはえゐるひそかな毛」(河原枇杷男句集《流灌頂》#B_033、五七ページ)
彼らは裸馬を巧みに乗りこなしていた。――吉岡実(#A_25、九三ページ)
〈わが馬ニコルスの思い出〉(《現代詩手帖》一九六九年一〇月号発表)は、*印(印刷用語でアステリスクといい、注などを添えるときに使う)で五つのパート(以下、本稿では「節」と呼ぶ)に分かたれた一六三行から成る長詩である。詩篇本文の引用に先立って、各節の行数を見ておこう。( )内は全体に占める比率だ。
〔第一節〕・三六行(22%)
〔第二節〕・一六行(10%)
〔第三節〕・二七行(17%)
〔第四節〕・七四行(45%)
〔第五節〕・一〇行(6%)
平均すれば約三三行のところ、節によって行数にずいぶん開きがあるので、みな同列に扱うよりも集注的にポイントを絞って見ていったほうがいいだろう。以下、本文(太字で表示、三桁数字のライナーは引用者が付したもの)を引用しながら、注釈を加える。
花咲くスミレの墓地で 001
わが馬ニコルスは快心の脱糞する 002
〔第一節〕冒頭である。いつのころからか、私は〈わが馬ニコルスの思い出〉は吉岡実が〈死児〉(④・19)を一九六〇年代風に書きなおした詩篇だと思いこむに到った。詳細はあとで述べるとして、その第一印象は、冒頭の「花咲くスミレの墓地で/わが馬ニコルスは快心の脱糞する」から〈死児〉の「死児は医者の記録にのこるのでなく/歴史家の墓地の菫で物語られる」という詩句を想起するせいである。「歴史家の墓地の菫で物語られ」た「死児」から「花咲くスミレの墓地で」「快心の脱糞する」「わが馬ニコルス」へ。これが吉岡実の一九五〇年代から六〇年代にかけての歩みである――と言うことができるとして、その内実を探っていくことが本節の目的である。
それからかるがると 003
あらゆる死体をとび越えた 004
その荒野に 005
言葉が必要か? 006
吉岡の〈わたしの作詩法?〉(#A_25)を読んだ者なら、誰しも「言葉」という語の登場に衝撃を受けるであろう。仮にそうした背景に想いが及ばなくても、詩句にまがまがしい空気が立ちこめていることは容易に見てとれる。ここで「あらゆる死体」とは、人に限らず馬匹も含んだ全生物の死体のように思われる。わが馬ニコルスの跳躍する荒地に言語は不要(もしくは無効)であると宣言することで、長詩はここに重重しくも開幕する。
それとも主題なき愛の労働がのぞましいか? 007
そこには底なく 008
負目のみの 009
蝋の道の続きだ 010
「主題なき愛の労働」とは、吉岡にとっては詩作行為そのもののことである。が、この詩においてはニコルスと「わたしたち」とが何事かを成す共同作業の謂であろう。「そこには底なく」という軽い地口のあと、「負目のみの/蝋の道の続きだ」は、前作〈夏の家〉の「落下蝋石」を想いださせる。
夏の嘆きのふかい沼地 011
「Natsu no nageki no fukai numachi」――「n」音で韻を踏み、「u・a・i」と母音を揃える結果になったが、巧んだ末の詩句ではなかろう。むしろ注意したいのは「ふかい」が「嘆き」「沼地」双方にかかるように働いていることだ。この、流れるような文体は吉岡詩には珍しい。
紫紅の下着の 012
女生徒たちのハイキングの賑わいよ! 013
「紫紅」はシコウだろうが、小さな辞書には載っていない。それにしても「紫紅の下着」とは。ここでも〈夏の家〉の「花飾りの下着」が想われる。さて「女生徒」の登場する詩句に以下がある。
・モッブのおさげの女生徒たちを押えて(〈夏の家〉⑦・21)
・「ピアノ教師のように
女生徒のうしろへ廻る」(〈曙〉⑨・8)
・女生徒は飛びあがりつつ小水をするんだ(〈生徒〉⑩・18)
女子学生でも女学生でもなく女生徒。〈夏の家〉は前回触れた。〈曙〉の「うしろへ廻る」は、簡潔な言いまわしながら吉岡ならではのイマジネーション豊かな詩句として、記憶に値する。〈生徒〉は片山健の鉛筆画から触発されたストップモーション。モノクロームの色調が懐かしい。〈ニコルス〉の女生徒たちは「紫紅の下着」を履いて「ハイキングの賑わい」を演出している。もっとも人物というより、パンジーかなにかの花のような印象を与えるけれど。
白いストッキングに覆われた 014
かたい両腿の跳ねるたび 015
主語は「女生徒たち」のはずだが、私は「わが馬ニコルス」の脚部のクローズアップを幻視してしまう。
わが馬ニコルスは呼吸を止め 016
歓喜し 017
熱い鉄の蹄鉄をはめて 018
ずーっと遠景まで 019
シナゲシを越え 020
このいささか大仰な動きが、本詩のエンジン部分となっている。馬が読者の鼻面を引きまわしていると言ったら言いすぎだろうか。馬の足部のクローズアップ。ときに「シナゲシ」はヒナゲシの訛りではなく、支那罌粟だ。実体がわからないので、インターネットで検索すると、富良野のシナゲシの写真――深紅の罌粟が荒野に咲きみだれている――があった。一面に咲くころは見事だろう。
水晶を砕く 021
死都の一部が見えるよ! 022
「水晶を砕く」の詩句は、前行「シナゲシを越え」を受けるようにも、後行「死都」にかかるようにも読める。前者なら「わが馬ニコルスは」「水晶を砕く」だし、後者なら「水晶を砕く」のは「死都(の一部)」である。両方が相俟って二重の解釈を許し、文意のねじれが感じられる。
わが馬ニコルスのキララで包まれた陰頭が青空へせり上る 023
難句である。「陰頭」は見なれぬ語だが、「陰茎」と「亀頭=先端の膨大部」の合成の感じが出ているから、よしとしておこう。問題は「キララで包まれた」の方だ。キララは雲母。「雲母で包まれた陰頭」? 私はここで土方巽の舞台写真を思いだす。それは人形作家の土井典制作による一種の張型を装着した場面で、張型の表面は金属様に輝いている。雲母が引かれているわけはなかろうが、異様なまでに充実したファロスこそ、ニコルスに持たせたい逸物だ。
痛みの金櫛でこすられて 024
自立し 025
転調する 026
一九七四年一〇月一二日、土曜日。午後九時五分から五五分間、NHKラジオ第一放送《文芸劇場》の〈詩と詩人〉シリーズ第二回として〈吉岡実の世界〉が放送された。ゲストは土方巽・加藤郁乎(対談)――対談の写真が加藤郁乎の《後方見聞録》(#B_027、三九ページ)に掲載されている――、大岡信(談話)、天沢退二郎・金井美恵子(対談)。吉岡本人はスタジオ録音には加わらず、勤務先・筑摩書房での番組スタッフとの打ち合わせ時の談話の形で参加した。このときの談話はカセットテープに録音されたこともあって、非常に聴きとりにくい。この放送で朗読された最後の作品が〈わが馬ニコルスの思い出〉で、二瓶鮫一の朗読をバックに、馬に関わるかなり長い吉岡の談話がコラージュふうに登場する。番組の構成・演出は平野敦子(平野氏に依れば、吉岡は自分の談話を放送に取りあげることに依存はないが「ぼくが朗読するとぼくの詩のイメージと違ってしまう」と打ち合わせ時に言い、朗読は断った)。その「馬に関わるかなり長い吉岡の談話」を番組を録音したテープから文字に起こしてみよう。これは前にも書いたことだが、私が吉岡実の詩に真に出会ったといえるのがこのラジオ番組を通じてだったから、実に懐かしい。下町風の速い口調の吉岡さんの話しぶりが想いだされるが、ここでは喋り言葉をそのまま再録してもしかたがないので、吉岡発言を談話記事程度に加工する。
「〈わが馬ニコルスの思い出〉のニコルスという馬は、実際にはいない。ニコルスはぼくが作ったものだ。軍隊にはたくさんの馬がいて、それら複数の馬をケツケしたのがニコルスだ。ケツケとは「毛を付けるもの」という意味だが、ケツケしたので〈わが馬ニコルスの思い出〉ではたえず馬が代わる。実際に世話をしたなかには……や「めすず」〔馬名は確認できず〕という馬がいた。いろいろな馬の面倒をみた。なかに「めぎし(?)」という箸にも棒にもかからない馬がいた。いわゆる暴れ馬だ。蹴る、噛むばかりでなく、人を乗せない、そういう悪い馬だった。ニコルスは……や「めすず(?)」や「めぎし(?)」の複合体だ。ただ、実在の馬の名前ではなんだから、自然にできたニコルスと命名した。日本名を避けたほうが、ある種の新しさがあると考えたのだ。
詩の展開はもちろんぼくの想像だが、現実に立脚する点がたくさんある。たとえば、馬の体からは毎日フケが出るから、金櫛という金属のギザギザの櫛で擦ってフケを取るのだ。カッカカッカと馬体を掻いてやって、フケを出す。「痛みの金櫛」とあるように、ものすごく痛いものだ。それが金櫛だ。これは詩だから勝手にどんどん作ってはいるが、そういう点では実際の光景だ。
もちろん馬には乗れる。乗るときのコツは、馬に合わせることだ。「はや=ギャロップ」は難しい。最初は、自分の尻の動きと馬の動きが合わなくて大変だ。ぼくにとって馬は、詩のなかでいちばん使われやすい形態だ。漢字の「馬」も美しい。これは自分自身が馬を三年間、世話してきていることが大きい。馬はきっと利口なのだろう。軍馬は、商業馬の性の悪いのや、田舎の馬や、農耕馬をかき集めてきたものだから、世話するのに苦労した。だから、馬の詩が多いのだ。馬は、好きだ。馬は、頭から詩的イメージである。」
細部のリアリティは体験や実景に依りながらも、複数の軍馬を「ケツケ」してニコルスを創造したという点が重要である。
地獄より暗い地上で 027
一度は見たい桃いろの植物群 028
「地獄」が吉岡実の詩に登場したのは初めてだ。この「地上」の認識は鮮烈であり、尋常でないものが感じられる。地獄が地下にあるものならば、それよりも暗い地上は、上下が逆転しているような印象を与える。さて、桃色と名が付く植物には次のようなものがある。桃色秋丁字・桃色菊咲き半鐘蔓・桃色蒲公英・桃色凌霄花・桃色半鐘蔓・桃色昼咲き月見草。「桃いろの植物群」がこれらのどれかであるにしろ、植物群そのものではなく、前出「紫紅の下着の/女生徒たち」の言い換えであることは間違いない。
そのなかへ 029
時間錯誤にかかわりなく 030
群衆を匿せよ! 031
「時間錯誤」は時代錯誤の言い換えのようだが、微妙に異なることによるおかしみがある。次の「群衆」は〈夏の家〉の「モッブ」に通じるものがある。
そして瞑想 032
擂鉢をする疑問符の人 033
「相談する瞑想する」(〈立体〉⑦・3)、「瞑想的でなく」(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12)など、この時期の吉岡実の詩句にはしばしば「瞑想」が登場した。前回触れたサイケデリックの影響と言えようか。次の「擂鉢をする疑問符の人」は「わたしはネコを抱く疑問符の人」(〈夏から秋まで〉⑦・2)の変奏か。もっとも「擂鉢をする」のが擂り粉木ならば、形態的には疑問符(?)より感嘆符(!)がふさわしい。
白地に赤く死のまる染めて 034
みにくい未来へ 035
わが馬ニコルスはギャロップ! 036
〈蜜はなぜ黄色なのか?〉の「白地に赤く/燃えるランジェリー」もそうだったが、吉岡が高野辰之作詞の文部省唱歌〈日の丸の旗〉(「白地に赤く/日の丸染めて」)を参照している詩句だ。戦前の東京・下町ではどの家庭でも祝日に国旗を掲げていたから、吉岡にもなじみの光景だったろう。
・ヒナゲシ → シナゲシ
・日の丸 → 死のまる
という音の変換(下町ふうの訛りでもある)が現実を暴きたてる構造は、共通している。「みにくい未来へ」も頭韻を意識したふしがある。「ギャロップ(騎乗疾駆)」は馬の最も速い駆け方で、吉岡の談話にあったように、いちばん難しい乗り方でもある。ニコルスの跳躍に近い形で〔第一節〕は終わる。
〔第二節〕はニコルスが食うニンジンの描写で始まる。
雨にぬれて恐ろしい緑の 037
葉はちぢれる 038
そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ 039
不用意に読むと「雨にぬれて恐ろしい緑の葉」となるが、詩句の切り方からして、「雨にぬれて恐ろしい緑」を独立的に扱われなければならない。雨にぬれた緑の葉ならごくふつうだが、「緑」を「恐ろしい」と認識する方が恐ろしい気がする。その葉をたぐっていくと、当然のごとく「赤くほそい根」が現われて、わたしたちはこれがニンジンらしいと気づく。「つるつるした」はちぢれた葉との対比で登場したのだろう。第三九行は、初出および初刊(一九七四年、湯川書房)にあった末尾の「!」が、定稿である三刊(一九七六年、書肆山田)で削除された。この改変は厄介な問題で、作者の真意が測りがたい箇所である。以下に、感嘆符のある本篇の行をすべて引く。
・女生徒たちのハイキングの賑わいよ! 013
・死都の一部が見えるよ! 022
・群衆を匿せよ! 031
・わが馬ニコルスはギャロップ〔せよ〕! 036
・そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ〔!〕 039
・だれも近づくな! 042
・蹴りあげるんだよ! 047
・わが馬ニコルスのゴムのようなおとがいを愛撫せよ! 078
・わが馬ニコルスのまるまるとした尻を見よ! 088
・わが馬ニコルスの笑う歯の薄明よ! 102
・その同時性こそ女の弾性だよ! 108
・生まれる子供の意味を伝えよ! 130
・その一人の子供だけでも欲しいわよ! 141
・断罪してよ! 147
・行った河と時を記憶せよ! 157
第三六行を〔 〕のように補って読めば、命令と呼びかけ、あるいは断定の「よ」には、すべて感嘆符が付けられていることになる。唯一の例外が「そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ」だ。無理やりこじつければ、「そのさきのつるつるした赤くほそい根」こそ感嘆符の形であったがために、その重複感を嫌ったか。
この田園の悪夢とは 040
わが馬ニコルスがニンジンを食うとき 041
だれも近づくな! 042
感嘆符の削除は、あるいは「この田園の悪夢とは」=「そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ」の二詩句が倒置の関係にあることを明瞭にするための措置だったのかもしれない。それなら、「真意を測りがたい訂正」という前言は撤回しよう。ニコルスだから「ニンジンを食うとき」に近づいてならない、というわけではない。馬全般の性質として、食餌中は警戒を怠らないのだ。
病人・幼児・鶏・妊婦を憎む 043
あらゆる個の 044
虚像・銅像 045
初出では「妊」が「姙」だった。一方、後出「藪」(第四六行)は
・藪(初出)→薮(初刊)→藪(三刊)
と二転しているが、これは雑誌・書籍の組版を担当した印刷所の事情だと推測されるから、以下、本稿では詩句の解釈に影響が出ないかぎり漢字の字体問題には触れない。
・びょうにん・ようじ・にわとり・にんぷ
ここに共通性は見いだせない。ならば対語はなにか。
・健康人・大人・卵・?
これとて完成させることのできない問いだった。「憎む」の主体は「あらゆる個」だろうが、それが「あらゆる個の/虚像・銅像」と続くことで、据わりが悪くなる。難句である。
藪があればそのいばらの果へ 046
蹴りあげるんだよ! 047
「藪があれば」というのは言葉の綾で、この用法は吉岡詩ではお馴染みのものだ。藪があるので、その茨・荊・棘の果て目掛けて、ニコルスは「虚像・銅像」を蹴りあげる。
自負の白塗りの柵をとび 048
ねはりの綱で囚われるときまで 049
黒雲千里 050
まれなる涼しい雷雨のゆうべの 051
できごと 052
「自負の白塗りの柵」とはなんだろう。単なる「白塗りの柵」なら、その方が通りがよいが。
・これは一種の自負であって(〈崑崙〉⑦・8)
・白塗りの星条旗の下で(〈マクロコスモス〉⑦・1)
・いくつもの白塗り頭のマネキンたち(〈神秘的な時代の詩〉⑦・11)
・白塗りの老人は叫ぶ(〈裸子植物〉⑨・25)
・白塗りの女戦士のようだ(〈薄荷〉⑫・6)
「自負」の用例は、他の詩篇では〈崑崙〉に一箇所しかない。一方「白塗り」を解読していけば、〈マクロコスモス〉ではジャスパー・ジョーンズの絵画、〈神秘的な時代の詩〉では舞台美術、〈裸子植物〉では大野一雄そのひと、〈薄荷〉では四谷シモンの人形の形容、か。〈ニコルス〉以外ことごとく美術や舞踏であるのは「自負」となにか関係があるのか。この詩句の圧力の高さからは、白塗りの柵をとぶことをニコルスが自負している――と採ることも不可能ではない。さて、次の「ねはり」がどうもわからない。辞書に見える「根張り」や「寝腫り」という語が適切とは思えない。奔放不羈の馬は、通常の方法では捕えられず、「ねはりの綱」でようやく捕獲できるということなのだろうが【その後、〈「ねはり」と「受菜」あるいは〈衣鉢〉評釈〉で「「ねはり」は根張り(根が土中に張り広がること。根がはびこること)だろうが、「ねはりの綱」となるとわからなくなる。もつれた根のように絡みあって、綱が強靱さをいやましているさま、とでもしておこうか」と書いたように、いまだに明確な解を得ていない】。「黒雲千里」は、馬を描いたもうひとつの傑作〈苦力〉(④・13)の詩句「万朶の雲が産む暁」を想起させる。と同時に「千里の馬」の連想も働く。結句「まれなる涼しい雷雨のゆうべの/できごと」は、この〔第二節〕が不吉な馬の、過去のある一点を描いたものであることを追認している。
〔第三節〕では「父母」や「兄弟」が登場してくる。
刺された父が窓までゆき 053
刺された母が窓までゆき 054
前後の脈絡がなく始まるこの詩句からは、「化石の矢がやわらかい子供の首を刺しているか?」の行をもつ〈立体〉(⑦・3)の評釈で触れたルネ・マグリットの絵画が浮かんでくる。すなわち〈殺人者危うし〉(#B_070、一〇七ページ)である。いったい吉岡実は対句的な表現をしばしば用いてはいるが、ほとんど同一形であるこのような例は珍しい。詩句の無機質的な手触りがマグリットの画風に通じているかもしれない。
それは 055
フォルムではない 056
それは起源ではなく 057
まして成就ではない 058
第五五・五六行の初出形は改行の位置が刊本と異なって、「それはフォルムでは/ない」であり、初刊におけるこの改稿は適切な処置といえる。そう考えると第三九行で感嘆符を削除した三刊での処置は、やはり異例なものとして映る。ここは「フォルム」=現状、「起源」=原因、「成就」=結果、と読みかえたくなる詩句だ。それにしてもこの「父母」は誰の父母なのか。作品の話者である「わたしたち」か、「わが馬ニコルス」か。詩句からは人間の姿が浮かんでくる。
なによりもまず 059
あらゆる戦いの認識の変形 060
「それ」は「あらゆる」「戦いの」「認識の」「変形」であるという。難句である。とりあえず先を読むことにしよう。
芸術・手術・忍術 061
第六〇行を敷衍したものである。「あらゆる戦いの認識」から、芸術も手術も、はては忍術までが生まれたのだ。痛快な詩句である。当時、芸術の領域ではカウンターカルチャーが澎湃として起きていた。「手術」は、日本初の心臓移植(一九六八年八月)かもしれないし、反体制を標榜した学生運動のことかもしれない。一方「忍術」は、この一九六九年の年譜に「白石かずこの小学生の娘に白土三平《カムイ伝》全巻を贈る」(#A_32、二九七ページ)とあり、忍術(忍法?)劇画が吉岡の念頭にあったのか。
はねる血の父 062
はこばれる函の母 063
ハねるチのチチ/ハコばれるハコのハハ――言葉遊びというよりは、音によるイメージの拡散といいたい。血は第五三行の結果だ。ハコは〈雨〉(⑦・9)の冒頭「それはたとえば/老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの/スイ星の球のつまった/箱をさがす」の印象が強烈だった。「母のつまった函」。
カシの木の生えた森のような室内 064
〈雨〉には「金属の小さな柱の森へ」の行があったし、前作〈夏の家〉は冒頭が「森の青葉の下に来て」だった(〈夏の家〉評釈を読んでくださった秋元幸人さんから、西条八十作詞になる、高峰三枝子主演の映画《純情二重奏》主題歌の冒頭「森の青葉の蔭に来て」との類似をご指摘いただいた。それを踏まえると、白井鐵造作詞の《パリゼット》主題歌の冒頭「すみれの花咲く頃」と本篇冒頭の類似は意図的なものとしか思えない)。樫は山毛欅科の常緑高木だが、室内と森が一挙に通底するこの詩句の形容は卓抜であり、本篇で最も印象的な一行でもある。
そこでカタツムリを発見し 065
ゆがめられた金の道のべで 066
わが馬ニコルスは死病の疝痛をこらえる 067
カタツムリの登場する〈春の絵〉(⑩・12)はこんな詩だ。追込の形にして引く。「梨の畑で/きらきら輝くのは/カタツムリ?/それとも死んだ兵士の心?/ぼくたちが家畜小屋から眺める/奇妙な世界の絵は/円で造られた黒/その焦点を泳ぐスワン/天気はどうか?/ある種の水生植物を下の方へつける/黒人の歯のなかへ/春の蝶を/少女が捕えに行く」。この「家畜小屋」は馬小屋ではなさそうだが、「春の絵」そのものは馬と切っても切れない関係にある。〈馬・春の絵〉(⑥・5)だ。
わたしはそのとき競馬場の芝生にねて 円柱球の馬を見ている 一二回跳ねるのを見た! もしかりにわたしの家の戸棚のなかに 馬が死んでいると確認したら どれほどわたしを悦ばせることか わたしは早速そのスポンジ化した馬の臀を両手で抑える それは夜まで続く 不惑の人生をかえりみて 少数者の自由を守ろうと思う 戸棚からころがりだす酒壜と血まみれのハンドル 終りに孔のたくさんある鉄の筒の胴廻りを計る 水に打たれて伸縮度を加える馬の首 それはわたしにとっては過ぎた戦いの心の患部だ それが女の首と太さが同等だった時のわたしのおどろき リンゴのように半分噛られた星の下で 隣人みんなの哀れみを受ける 裂かれたカンバスよりもっと永遠でない闇から 愛撫する馬の腹へ わたしは口をつけて囁く 《人間の幸福は各個人の生得のもの》 女は蹄鉄の下からスカートをつける ピンクとグレーのゆるやかなカーブの藪の道へ帰って行く わたしはだれにも聞けないのだ 女は死んだ馬なのか 雨のなかでいまでも跳ねる かつてわたしが光で見た円柱球の馬なのか 朝がきたらしいああいちじるしいナツメの実 わたしは歯刷子で歯をみがき それを取りおとすだろう 世界はいつも余分なものをつくり わたしに余分な仕事を与える
〈馬・春の絵〉全篇
馬の部位をつぎつぎとクローズアップする手法や、馬と女を重ねていく視点は、考察するに値する問題だが、いまはa「水に打たれて伸縮度を加える馬の首 それはわたしにとっては過ぎた戦いの心の患部だ」、b「リンゴのように半分噛られた星の下で 隣人みんなの哀れみを受ける」、c「ピンクとグレーのゆるやかなカーブの藪の道へ帰って行く」の三箇所に注目して、それらは割愛しよう。a「わたしにとっては過ぎた戦いの心の患部」は看過できないフレーズだ。「水に打たれて伸縮度を加える馬の首」は具体的に想像しづらい光景だが、実際に馬の世話をしている人間にはごくふつうのものかもしれない。bは後出の第七九行「母の半欠け乳房のように」を先取りしたような詩句だ。cは第四六行「藪があればそのいばらの果へ」、第六六行「ゆがめられた金の道のべで」を想わせる。第六七行「死病の疝痛」が胆石症発作なのか腎石発作なのか腸閉塞なのかよくわからないが、aの情景とも重なる。
冬ごもりの廃屋で 068
誠実な兄弟たち 069
「誠実な兄弟たち」はニコルスのそれなのだろうか。「燐光塗料の書物を読」むのなら人間だろう。それは誰か。
弱々しく 070
燐光塗料の書物を読みあげる 071
続く部分では、「燐光塗料のかつらをかぶり/マリリン・モンローの肉体はちぢんだ!」(〈神秘的な時代の詩〉⑦・11)に始まり、どこかで出あったことのある吉岡実の世界がシンフォニーの終曲かドラマの大団円のように繰りだされる。
他界の闇の 072
ナイトテーブルをまわり 073
「他界」は「他界への通路の標識かもしれない」(〈雷雨の姿を見よ〉⑨・14)が他の唯一の用例、「裂かれたカンバスよりもっと永遠でない闇から 愛撫する馬の腹へ わたしは口をつけて囁く」(〈馬・春の絵〉)、「テーブルの上で/化石の鳥が化石のリンゴのまわりをとぶ」(〈立体〉)。
少女の腹部をあつかましくも求めて 074
水位へ出る 075
老人十字軍 076
「ハンス・ベルメールの人形/その球体の少女の腹部と/関節に関係をつけ」(〈聖少女〉⑦・10)。〈聖少女〉はこの時点でまだ発表されておらず、この詩句が直接のスルスと思われる。
ともに浮遊する 077
わが馬ニコルスのゴムのようなおとがいを愛撫せよ! 078
母の半欠け乳房のように 079
「老人の口/それは技術的にも大きく/ゴムホースできれいに洗浄される/やわらかい歯」(〈桃――或はヴィクトリー〉⑥・8)。この老人は、ほとんど馬である。
〔第四節〕は七四行あって、本篇で最長の節だ。
ピンク色のハマムギを成長させる 080
荒野の納屋で 081
わが馬ニコルス 082
水をねながら飲む 083
「ハマムギ」はふだんあまり見かけない植物だ。インターネットで検索した写真には、砂浜にヒョロヒョロと生えている雑草が映っていて、麦に似ているかどうかまではわからない。いったいこんな儚げな草が馬の飼料になるのだろうか。「荒野の納屋」に生えるのなら、馬は食わないのか。「水をねながら飲む」ニコルスは弱っているのだろう。
浮いている藁の下の方に 084
恋する幽霊たち 085
或はナメクジの類 086
ここで吉岡実の「幽霊」をピックアップしてみよう。
・死児は不老の家系をうけつぐ幽霊(〈死児〉④・19)
・幽霊船を組立てる(〈老人頌〉⑤・1)
・幽霊の見物人(〈田舎〉⑤・10)
・その男はふとった幽霊になるだろう(〈模写――或はクートの絵から〉⑥・4)
・肉色の幽霊と化して(〈崑崙〉⑦・8)
・恋する幽霊(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12)
・恋する幽霊たち(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
・いかなる幽霊の姿勢で/全員で吊りさがればよいのか?(〈コレラ〉⑦・18)
・それは包帯で巻かれた幽霊群のなかで/副葬花束を持った人だわ!(〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉⑧・11)
・自己か他者/「いずれかが幽霊である」(〈野〉⑨・21)
・(葦縄でしばられた/幽霊)(〈春思賦〉⑪・11)
・柳の葉のかげから/現われた幽霊?(〈聖童子譚〉⑫・4)
・「幽霊との出会いは延期された」(〈ムーンドロップ〉⑫・10)
・「幽霊の乳を飲んでいる」/(赤児)のようなものが見える(〈聖あんま断腸詩篇〉⑫・12)
「幽霊」が登場するすべての詩句だ。詩集では《神秘的な時代の詩》の詩が目立つ(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉には単数の「恋する幽霊」さえ登場している)。それらは「或はナメクジの類」と言い換えられる、目鼻もない生物だ。〈崑崙〉の「肉色をしていることが/罪悪ならば/ぼくたちになにができる?/藁の上で/肉色の幽霊と化して/にもかかわらず/そのうしろに眠るきみの彼女の蛍光体」は本篇の先駆けのような詩句だが、人間としての幽霊の実在感がある。〈わが馬ニコルスの思い出〉は〈死児〉に似ていると最初に述べたが、同時に〈崑崙〉にも似ているのだ。発表の時期が近いだけに、発想や語の繰りだし方は、むしろ〈崑崙〉に近似している。
潜水艦に類似した 087
わが馬ニコルスのまるまるとした尻を見よ! 088
それに乗る人がこの世にいるか? 089
加うるに「来るべき潜水艦が丘を越えて/迷宮入り」も〈崑崙〉にある。「わたしは早速そのスポンジ化した馬の臀を両手で抑える それは夜まで続く」は先の〈馬・春の絵〉のもの。さらに「最後の放屁のこだま/浮ぶ馬の臀を裂く」は〈苦力〉(④・13)から。ここでは引かないが、吉岡詩では「尻」「臀」とも、馬より女のそれとして登場するほうが多い。ギャロップでは騎手の尻の動きが難しい、という先の談話が想起される。
寒い冷たい人 090
砲弾とともにとぶ淋しい人 091
横から眺めれば 092
先祖ごろし 093
「寒い冷たい」は重複している印象を与える。が外気が寒くて、心身が冷たいの意ととりたい。私は第九一行を読むたびに、ザ・ビートルズの〈エリノア・リグビー〉(《リボルバー》)の詩句「All the lonely people, where do they all come from」を脳裡に響かせるのを常とする。「横から眺めれば」は、吉岡がしばしば用いる特異な手法。単なる同格よりも、味が濃く、深い。
血の雲がたなびく少年の夢 094
ここでもやはり「万朶の雲が産む暁」(〈苦力〉)。
絹につつまれた 095
姉妹のくろい種子が 096
ひざの間で 097
白水でぬれて 098
消毒飛行 099
「やわらかい真紅の絹はグラスをつつむ」(〈孤独なオートバイ〉⑥・14)、そして「一枚の絹に包まれる」(〈ゾンネンシュターンの船〉⑧・24)。以下は堕胎のイメージだろうか。
ツバキの花びら散らし 100
正面を占める 101
わが馬ニコルスの笑う歯の薄明よ! 102
この「ツバキ」も女の秘密の部分を暗示している。「正面」は〈夏の家〉の「正面から抱く人」でも触れた。ここでは「となりの庭で/行為する両親たち/正面が赤く燃え……」(〈草の迷宮〉⑨・9)を挙げておこう。
すべからく 103
皮一重の腐り方への悦び 104
「すべからく中心の孔を開示せよ」(〈葉〉⑧・4)は通常の呼応に近いが、第一〇三行は「べし」という受けが存在しない変則的な用法である。「須く」に「なすべきこととして」と代入すると、事態はさらにはっきりする。「皮一重」はニコルスの笑う歯の近く、口角あたりか。「馬が上唇と鼻端にしわを寄せ、笑っているような表情をすることがある」(#B_057、一二二ページ)のをフレーメンというが、チェシャ猫のニヤニヤ笑いならぬニコルスのフレーメンといったところだ。
トカゲの湿った心で 105
宗教的物質と 106
やわらかい肉も食べる 107
その同時性こそ女の弾性だよ! 108
「切断される蜥蜴の尾の悲しさよ」(〈歳月〉①・7)、「とかげの磔刑」(〈果物の終り〉⑤・2)、「黒雲やトカゲが姿を見せる」(〈青枝篇〉⑪・4)と、吉岡のトカゲは蛇に比べて圧倒的に少ない。切りすてることの可能な心、ということか。「宗教的物質」がよくわからないが、「やわらかい肉」との対比を見るべきだ。「同時性」は「背反性」のように使われている。
もしも楽園があるとしたら 109
それは紫色の 110
葦毛が脱けおちる 111
わが馬ニコルスの虹のような 112
股がまたぐ 113
独身者の燃える棘冠 114
「染物屋の主人は紫の馬を染めあげる」(〈蝉〉⑨・3)はなまなましい詩句。「独身者」が吉岡詩に少ないのは意外だった。「男が独身者の血は冠の毛をぬらすと 二ケ月前にもらした重大な口説」(〈編物する女〉⑤・8)、「「この欲望のモーターは独身者の機械の/最後の(もっとも/突起した)部分である」」(〈織物の三つの端布〉⑨・16)。「もし人類が在ったとしたら人類ののろわれた記憶の荊冠」(〈死児〉)。
或は濡れるシャツのプライベートな 115
その汚辱 116
「洗濯屋が汚れたワイシャツを/もってくる午後」(〈マクロコスモス〉⑦・1)。「まるで/きみらの汚辱の家から/なめくじが母国を探すように/星への旅をつづける」(〈異霊祭〉⑧・19)。凌辱・侮辱・汚辱・陵辱・恥辱・屈辱……。
その辻便所の孤独から 117
内的建築を求めて 118
ずーっと近景まで乗り入れる 119
斑点のある戦車 120
貨車への接続詞・終止符。 121
「辻便所」は公衆便所のことだろうが、そう言うよりも中国大陸的な感じがする。《神秘的な時代の詩》は「石の建築物といっても永遠/ではない二階から上は/紫の窓」(〈マクロコスモス〉)と始まるから、もしかしたらこの詩集は、建築にひとかたならぬ関心をもった作品集かもしれない。ほかにも「建築物の空間の/あらゆる余白を横切るものはなに?」(〈雨〉⑦・9)や「光学的には暗く/建築的にはもろく/自然的にも不自然で赤く」(〈三重奏〉⑦・9)という魅力ある詩句がこれ以前に書かれていた。第一一九行は遠く第一九行の「ずーっと遠景まで」と対応している。「一人は猿と斧と戦車の歴史を書く」(〈僧侶〉④・8)、「想像する/紅潮する戦車」(〈マクロコスモス〉)、「「ガルボは鉄の戦車」だとわたしは讃え」(〈竪の声〉⑪・2)が吉岡の「戦車」のすべてだ。「長い地下道を通過する/貨車や/影の火薬/もしくは仕度の了った死体?」(〈夏の家〉)は他の唯一の「貨車」。第一二一行の「。」、これこそ究極の言葉遊びだ。吉岡は自作の詩篇にはいっさい句点を使用しなかったが、ここ第一二一行と、最後の詩集《ムーンドロップ》の掉尾〈〔食母〕頌〉(⑫・19)の最終行「野の丈なす草むらに……。」がその稀な例外だった。
単語のつながる末尾の 122
赤い毛のかつらの下の大砲 123
吉岡の一〇〇行を超える詩篇群のなかから、私は本篇と関連の深い作品として、次の作品を挙げたい(▽以下は初出記録)。
(1)死児(④僧侶・19)Ⅷ節一八九行▽《ユリイカ》(書肆ユリイカ)一九五八年七月号(三巻七号)
(2)崑崙(⑦神秘的な時代の詩・8)一四七行▽《南北》(南北社)一九六八年一〇月号(三巻一〇号)
(3)本篇(⑦神秘的な時代の詩・16)*印で五節に分かつ一六三行▽《現代詩手帖》(思潮社)一九六九年一〇月号(一二巻一〇号)
(4)葉(⑧サフラン摘み・4)一二五行▽《ユリイカ》(青土社)一九七二年四月号(四巻四号) 初出注記「(連祷詩《粘土説》の一部)」。
これらは〈僧侶〉や〈立体〉〈サフラン摘み〉に比べると、完成度の点では一籌を輸する。しかし執筆における冒険心で、それらを凌ぐ。詩集《僧侶》や《神秘的な時代の詩》《サフラン摘み》にこれらが入っていなかったらどんなに淋しいことだろう。さて、この四篇の関係はおおよそ次のように位置づけることが可能だ。Nの字の右上に〈死児〉、右下に本篇〈わが馬ニコルスの思い出〉、左上に〈崑崙〉、左下に〈葉〉。本篇からみれば、(1)とは死せる者との対話において、(2)とは馬による移動において、(4)とは言葉の犯罪性において、それぞれ深い関連を示している。さて「単語のつながる末尾」とは、ここでは詩句の行の最後のことだ。この内省的な句には〈葉〉を想わせるものがある。「ブルーの毛の股をつつましく見せる」(〈聖少女〉⑦・10)、「赤毛のやさしい愛撫から/少年がぞろぞろ出る」(〈雨〉)、「そよぐ死せる青い毛」(〈サフラン摘み〉)。「燐光塗料のかつらをかぶり」(〈神秘的な時代の詩〉)、「花嫁のかつらをかぶって/泳ぐ人」(〈夏の家〉)、「中世のかつらをつけた裁判官の姿をした人形を」(〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉)。色の着いた髪と「かつら」を含むすべての詩句だ。では「大砲」はどうか。「死者の生きのこりの兵士をはげまし大砲を打つ」(〈人質〉④・17)、「大砲と共に沈んで行った男たちの重い睾丸をひびかせる」(〈死児〉)、「大砲の車輪のひと廻りする時」(〈果物の終り〉⑤・2)、「今晩だって砂浜へ大砲をすえたまま」(〈模写――或はクートの絵から〉)、「大砲の砲身をあたためる」(〈田園〉⑧・14)。これらの大砲は、萩原朔太郎《青猫》の大砲を感じさせる。
その投影 124
その三角又は四角形 125
その装飾をつきぬけて 126
黒と白の格子 127
大砲なら円柱形だろうに、「その投影」が三角形とはいかなる事態を指しているのか。「人びとの死面の格子」(〈受難〉⑤・17)、「格子が見える」(〈少女〉⑦・5)、「格子を出てゆく金蠅」(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12)、「正面の格子のなかに/飾られている馬蹄形の星々がある」(〈悪趣味な冬の旅〉⑧・6)、「言語格子」(〈ルイス・キャロルを探す方法―わがアリスへの接近〉)。「格子」のイメージも吉岡実詩には親しいが、詩句の内容に沿って解読しようとすると、どうしても縦横の桟がつくる形に目がいってしまって、その意味するところが判然としない。ここはチェッカーフラッグのような目立つ模様、といったところか。
テーブルに坐って 128
母娘が比喩的に語る 129
生まれる子供の意味を伝えよ! 130
吉岡の詩には、数はそれほど多くはないが、実に印象深い母娘たちが登場する。
・由緒ある樅の木と蛇の家系を断つべく/微笑する母娘(〈聖家族〉④・14)
・かみ合う黄色い歯の馬の放尿の終り/母娘の心をひき裂く稲妻の下で(同前)
・雨傘さしたシナの母娘/美しい脚を四つたらして行く(〈恋する絵〉⑥・15)
・死垂る紫の葡萄棚の下で/シャワーを浴びる母娘を/遠巻きにして/われわれは「暗喩」に近い存在である(〈ピクニック〉⑧・7)
そして第一二九行のあと「母娘の子宮を絞めて/恍惚の子供が泳ぎ出る」が再び現われる。
一つの言語から生まれる 131
生死の観念の在り方 132
第一三一行に登場する「言語」は「日常言語の床屋の白い布を裂く」(〈崑崙〉)、「わたしたちの言語のなかで/腐るもの・変るもの」(〈神秘的な時代の詩〉)に続く、最初期の用例の一つである。一方「言葉を犯罪的に使って/紅色の闇へ/イタリア貂を狩りに出る」(〈少女〉⑦・5)という詩句もすでに書かれているから、なにもここで大仰に驚いてみせる必要はないのだが、これが〈わたしの作詩法?〉を書いた詩人の行であることは肝に銘じておかなければならない。この「一つの言語から生まれる/生死の観念の在り方」を合図に、詩篇は大きな山場を迎える。
彼方の水へ 133
泳ぐ百人の子供 134
彼方の塔へ 135
のぼる百人の子供 136
彼方の砂へ 137
もぐる百人の子供 138
彼岸の彼方の白布へ 139
つつまれる百人の子供 140
その一人の子供だけでも欲しいわよ! 141
第一三三行から第一四〇行までを対応させてみよう。
(1)彼方の水へ/泳ぐ百人の子供
(2)彼方の塔へ/のぼる百人の子供
(3)彼方の砂へ/もぐる百人の子供
(4)彼岸の彼方の白布へ/つつまれる百人の子供
「水へ/泳ぐ」「塔へ/のぼる」「砂へ/もぐる」と、いわば彼方の陸海空に遍在するするのが、これら「百人の子供」であって、「百人の子供」は最後には「彼岸の彼方の白布へ/つつまれる」。吉岡実の詩の読者は、ここから「大きなよだれかけの上に死児はいる」に始まる〈死児〉の
[水]水の夜伽は退屈だと静かな骨はつぶやく
[塔]軍艦は砲塔からくもの巣をかぶり
[砂]金髪の森の死児あまたの砂の死
[つつむ]父親と共に働き藁でつつまれる
などの詩句を思いださないわけにはゆかない。あやうく「百人の子供」に「死児」を代入しそうになるほどだ。だが、早まるまい。〈死児〉は単数だった。ありえたかもしれないもうひとりの自分でこそあれ、断じて「百人の」ではない。
血のように燃えて 142
わたしたちの分裂のくらがりに 143
遍在する 144
つねに黒い手袋をした子供が―― 145
「輝く王道をきりひらき/古代の未開地で/死児は見るだろう/未来の分娩図を/引き裂かれた母の稲妻/その夥しい血の闇から/次々に白髪の死児が生まれ出る」(〈死児〉)。
要するに客観的状況を 146
断罪してよ! 147
「客観的状況で/塩がほしい」(〈少女〉)。
暁の叙事詩の直立性を押しわけ 148
母娘の子宮を絞めて 149
恍惚の子供が泳ぎ出る 150
「詩」! 「ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか」(〈コレラ〉⑦・18)、「衛生的な木蔭の抒情詩」(〈葉〉)、「わしも医者だから抒情詩の一篇や二篇は暗誦できる」(〈『アリス』狩り〉⑧・12)、「わたしはいま「追悼詩」を叙述するんだ」(〈田園〉)、「わたしはしばしば/「女が野原でしゃがむ」/抒情詩を書いた」(〈夏の宴〉⑨・20)、「麗しい(農耕詩)の一節だ」(〈青海波〉⑪・19)。「遊び場は母の子宮」(〈固形〉④・11)、「すべての女性の子宮を叩く」(〈人質〉)、「一度は母親の鏡と子宮に印された/美しい魂の汗の果物」、「八月の空に子宮の懸崖」(〈死児〉)、「火事は血を浴び 母の子宮へ移りつつ燃える」(〈紡錘形Ⅰ〉⑤・4)、「両極から子宮を挟む/大きなレンズが南から北へ廻る」(〈灯台にて〉⑤・20)、「ぼくが水子で/きみたちが多淫な猫の腹と子宮」(〈内的な恋唄〉⑥・12)、「処女の子宮をふさがんとする」(〈フォークソング〉⑦・7)、「妻の詰った子宮から出てくるきみかね?」(〈崑崙〉)、「この世の最初の淫らな形をした/古代人が崇拝する/〈蛇の卵〉/すなわち子宮の表徴のしたたり」(〈紀行〉⑩・16)、「鍛冶屋のふいご(子宮)は収縮する」(〈雞〔ニワトリ〕〉⑪・1)。「突然の死と空間の恍惚たる交感状態 夜でも昼でもなく」(〈ジャングル〉③・13)、「ぼくは恍惚として街に入る」(〈固形〉)、「さめの歯のかみあう恍惚の日々」(〈死児〉)、「恍惚たる少年の藍をあびて」(〈崑崙〉)、「その恍惚の夜は」(〈雨〉)、「この狼藉の恍惚」(〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉)。本篇で喇叭が喨喨と吹きならされる部分、と言えばよかろうか。
そんな広域な 151
ネハン 152
の湾 153
子宮であると同時に外界であるところの海!
すえながく生きつづける仮想の敵 154
ブランコのりの子供たち 155
わが馬ニコルスが荷車に積まれて 156
行った河と時を記憶せよ! 157
空鳴りの肉色の鉄橋の弧のかたちを破壊し 158
消滅する 159
わが馬ニコルスの水色の大きな瞳孔の 160
ふたたびまばたくまで 161
潜在的世界には 162
犯罪的な言葉が屹立する 163
〔第五節〕は、一〇行と全体でいちばん短い。「仮想の敵」からは、のちに「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!」と始まる〈聖少女〉がこの行を変奏するようにして書かれることになる(詩集では本篇よりも先に登場する)。さらに「ブランコのりの子供たち」からは、のちに「ブランコのりの少女がひとり」と書きおこされる〈低音〉(⑦・14)がこの詩句の変奏のようにして書かれる(詩集では本篇より先に登場)。すなわち、《神秘的な時代の詩》を巻頭から読んできた読者は、〔第五節〕を、さまざまなモチーフを最終楽章で再帰させる交響曲を聴くようにして読むことになる。そして作者は万感をこめて「わが馬ニコルスが荷車に積まれて/行った河と時を記憶せよ!」と見おくるのだ。「空鳴りの肉色の鉄橋の弧のかたち」は、先の「紫色の/葦毛が脱けおちる/わが馬ニコルスの虹のような/股」を思わせるが(「葦毛」はふつう白色と説明されるから、ここは形容矛盾をあえてしているのかもしれない)、あたかも虚無に没するように「破壊し/消滅する」しかないのだ。「わが馬ニコルスの水色の大きな瞳孔」、これこそ馬の肉体について吉岡実が書いた最も印象的な詩句だ。最終行の「犯罪的な言葉」は、――すでに〈崑崙〉評釈のⅣ章(〈葉〉あるいは《粘土説》)でふれたことを繰り返すことになるが――、吉岡は死児がニコルスに姿を変えてその死の方向を「矢印」とともに指ししめす図を描いた。「されば/四人の骨は冬の木の太さのまま/縄のきれる時代まで死んでいる」僧侶が「言葉」を獲得した瞬間である。
吉岡実には幻の詩集が何冊かあって、詩集《ライラック・ガーデン》と選詩集《馬・春の絵》、そして題名が明らかにされていないが〈アリス〉詩を集成したもの、以上の三つが知られている。
詩集《ライラック・ガーデン》は一九六〇年に企画された〈鰐叢書〉の一冊で、同年四月四日の吉岡の日記にこうある。「六時から鰐の会。〈鰐叢書〉二十冊刊行決定。第一冊は岩田宏詩集《永久革命》次は吉岡実詩集《ライラック・ガーデン》。三冊目、大岡信の詩とエッセイ集《声のパノラマ》。次は飯島耕一詩集《睡眠》。五冊目は清岡卓行初期詩集。小B6判三十二頁の小冊子」(#A_10、一二三ページ)。吉岡が後年《瀧口修造の詩的実験 1927~1937》の内容見本で「滝口修造詩集は〈鰐〉グループ編集によって、〈鰐叢書〉第一集として刊行される筈であった。それは永遠に全容を現わさない幻の詩集――それをぼくらがみずからつくり、心ゆくまで耽読したいからである。しかし不幸にして伊達得夫の死によって挫折した」(一九六七年一一月一日、思潮社)と書いたとおり、〈鰐叢書〉が実現されることはなかった。もっとも吉岡が編んだであろう《ライラック・ガーデン》を想像することは可能だ。《吉岡實詩集》(#A_06)で「未刊詩篇」としてまとめられた六篇(〈ポール・クレーの食卓〉〈ライラック・ガーデン〉〈サーカス〉〈無罪・有罪〉〈老人頌〉〈果物の終り〉)が中心となったはずだからだ。これらに、当時すでに発表されていた〈牧歌〉(のち〈唱歌〉と改題)〈斑猫〉〈哀歌〉の三篇を加えれば「小B6判三十二頁の小冊子」は編集できる(私は《吉岡實詩集》の組体裁に倣った一部本《ライラック・ガーデン》をDTPと手製本で作ったことがある)。全体として後年の拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(#A_20)に似たものだが、《僧侶》に続く新詩集としては小粒と言わざるをえない。もっとも吉岡はこの題名が捨てがたかったようで、最初の英訳詩集を《Lilac Garden》(#A_34)と題している。
〈アリス〉詩を集成したものについては詩篇〈少女〉の評釈で触れたので、ここでは繰りかえさない。
さて、選詩集《馬・春の絵》である。まず吉岡の述懐を聴こう。〈兜子の一句〉の全文を引く。
絵馬の馬うしろに懸る春の月
私は馬が好きである。それゆえ、今までに数多く馬をテーマにした詩を書いてきた。四、五年前に、馬の詩ばかりを収めて、《馬・春の絵》という小冊子をつくる筈だったが、沙汰やみとなっている。さて、兜子の近作一句を選ぶように言われたので、手元にある〈渦〉七冊を読みかえした、そこで、六月号のきわめて古典風な一句に心惹かれた。
絵馬の馬――もうそれだけで、私は美的陶酔に浸ってしまうのだ。これは実景であると同時に、実景ではなく、作者の創作の虚の絵であるように思われる。とある社寺の軒に掲げられた、古色の小さな絵馬。深夜そこから抜け出して、馬は巨像と成り、巒気の立ちこめる清浄な世界で、まさに月と対峙しているのであった。(#A_21、二〇三ページ)
選詩集《馬・春の絵》にはどの詩篇が含まれるか。〈苦力〉〈冬の休暇〉〈馬・春の絵〉〈わが馬ニコルスの思い出〉は確実だが、私はこれに〈田舎〉〈サーカス〉を加えたい。この六篇で《ライラック・ガーデン》よりも四、五ページ少ない小冊子になるだろう。
吉岡実にとって「馬」とはなんだったのか。伝記的事実は措いて、作品のなかにそれを探ろう。以下に、未刊詩篇を除く全作品に登場する「馬」(「木馬」などは除いた)を含むすべての行を抜き書きして、コメントを付す。まず戦前の二詩集《昏睡季節》と《液体》から。
・赤馬の鼻孔に夜行列車が到着した 〈冬〉(①・4)
・一頭の青く濡れた馬かけのぼる 〈誕生〉(②・12)
・喪服の馬車が通ってゆく 〈忘れた吹笛の抒情〉(②・16)
《昏睡季節》に特徴的な馬は登場しない。この「赤馬」は文字どおり赤毛の馬だろう。後半の和歌〈蜾蠃〔スガル〕鈔〉に「馬車」は出てくるが、「馬」は登場しない。〈忘れた吹笛の抒情〉も特別な「馬」ではない。《液体》では〈液体Ⅱ〉(②・27)の「朝の驢馬を音もなく粉砕する水の上」が目を引くが、これとて「馬」ではない。そして戦後となる。昭和三〇年刊の《静物》から。
・馬の腸のながい管を巻かぬ 〈静物〉(③・3)
ここに至ってようやく吉岡実の馬が登場した、という感が深い。北川冬彦の一行詩が想いだされる。そして《僧侶》で吉岡の馬は跳躍する。
・眠らぬ馬をつれだす 〈牧歌〉(④・7)
・一人は街から馬の姿で殺戮の器具を積んでくる 〈僧侶〉(④・8)
・支那の男は走る馬の下で眠る 〈苦力〉(④・13)
・馬の陰茎にぴったり沿わせて (同前)
・縄の手足で肥えた馬の胴体を結び上げ (同前)
・馬の耳の間で (同前)
・走る馬の後肢の檻からたえず (同前)
・支那の男は人馬一体の汗をふく (同前)
・はげしく見開かれた馬の眼の膜を通じ (同前)
・馬は住みついて離れぬ主人のため走りつづけ (同前)
・浮ぶ馬の臀を裂く (同前)
・かみ合う黄色い歯の馬の放尿の終り 〈聖家族〉(④・14)
・黄色い馬のたてがみの奥でだき合う半分ずつの月と太陽 〈人質〉(④・17)
・馬のひずめにとじこめられて 〈死児〉(④・19)
・首のない馬の腸のとぐろまく夜の陣地 (同前)
馬の姿をした僧侶のグロテスクな姿。〈苦力〉の馬の陰茎・胴体・耳・後肢・眼・臀。なまなましさと同時に、奇妙に厚みのない印象がたちのぼる。〈聖家族〉という題名は、堀辰雄の同名の小説からきているのだろうが、なんという違いだろう。〈人質〉は秘教的な図柄を描きだしており、キング・クリムゾンの《太陽と戦慄》のアルバムジャケットが連想される。伝記的事実に渉るが〈死児〉の「馬のひずめにとじこめられて」からは、吉岡が軍隊時代、懲罰のために蹄鉄を銜えて街を歩かされたという光景が想起される。「首のない馬の腸のとぐろまく夜の陣地」も戦争を想わせるシーンだ。そして《紡錘形》。
・馬や犬の経験もしないであろう 〈下痢〉(⑤・3)
・跳ね出る夜行性の馬 〈田舎〉(⑤・10)
・覆面の馬 (同前)
・にんじんを食う馬 (同前)
そこでは灰色の馬と灰色でない馬とがすれちがう 灰色の馬が牝らしく毛が長く垂れさがり 別の馬は暗緑の牡なのだろうはげしく躍動する たがいのたてがみも尾も回転する毛の立体にまで高まって 少女にはそれが見える 完全な円のふちから ときどきはみ出るものがオレンジ色に光り 中心はもう時間が経過したので黒い 或晩にお父さんとお母さんがのぞかせた一角獣のように恐ろしく 少女は自身の腿に熱を浴びる まだすれちがっている馬たち ピエロでない赤い帽子の男は 少女が気づいた時から人ではなく だれもが持っている共犯のはにかみの心 テントの底が深くなればなるほどゆっくり 馬の方へちかづく 命令するために非常に細長い棒をふりおろす 電光もひきあげる街の看板の方へ 今夜は充分泣けると少女は思う 灰色の牝馬のすんなりした腹に異父弟が宿ったから
このみじかい冬の休暇が終るとともに 〈冬の休暇〉(⑤・12)全篇
・そこから馬は出発して行き 〈鎮魂歌〉(⑤・15)
・蟻のひと廻りする一メートル半径の馬の頭蓋 〈沼・秋の絵〉(⑤・21)
〈下痢〉は普通名詞としての用法である。〈田舎〉の馬には名前こそないが、手で触れることのできる肉感がこもっている。ニコルスの前身といっていい。〈冬の休暇〉の「灰色の〔牝〕馬」と「灰色でない〔暗緑の牡〕馬」のいる「そこ」はサーカスのテント小屋のようだ。この作品は、大きく観れば《僧侶》の硬質な世界から《神秘的な時代の詩》の柔軟な世界に移行するちょうど中間的な地点に位置しており、この時期の傑作である。〈鎮魂歌〉の「馬」も詩では「ぼく」を乗せて走るようである。〈沼・秋の絵〉の蟻を一メートル以内に近づけない馬の頭蓋はまがまがしい。まさに霊気が立ちこめている。次に《静かな家》がくるが、〈馬・春の絵〉(⑥・5)の詩句は省略する。
・亜鉛のドームの下はやわらかい馬の口 〈聖母頌〉(⑥・6)
・川をながれながれて行く馬と兵隊の 〈静かな家〉(⑥・16)
〈聖母頌〉は「亜鉛のドーム」と「やわらかい馬の口」が同格に見えてくるから不思議だ。〈静かな家〉には明らかにニコルスの前兆がある。そして《神秘的な時代の詩》だが、〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)の詩句は省略する。
・馬のながい陰茎の岸べ 〈マクロコスモス〉(⑦・1)
・傷ついた馬の腹を 〈色彩の内部〉(⑦・4)
・馬の交尾 〈少女〉(⑦・5)
・四つに分けられた馬の頭は見えず 〈崑崙〉(⑦・8)
・絵のなかの馬がそれを拒む 〈三重奏〉(⑦・17)
「陰茎」「腹」「交尾」「頭」と具体的に描かれているものの、〈わが馬ニコルスの思い出〉を除くと《神秘的な時代の詩》に登場する馬は想いのほか寡黙である。それを、黙することで内部にその精力を蓄積している、と言い換えてもいい。現実の馬から記憶の、映像の馬に変容しつつある観念のみがもつリアリティ。そして《サフラン摘み》になると馬の登場する作品数が増えて、九篇となる。
・馬丁は死馬を繋ぐ 〈ヒヤシンス或は水柱〉(⑧・3)
・〈聖あんま語彙篇〉――〈馬を鋸で挽きたくなる〉土方巽(⑧・8)
・麻袋をかぶった馬が立ちあがり立ちあがり 〈聖あんま語彙篇〉(⑧・8)
・緑蔭へ走りこむ馬 〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉(⑧・11)
・テニソン夫人の姪アグネス・グレイス・ウェルドは赤い乗馬頭巾とマントを着け (同前)
・馬のうしろに幼い友だちを呼ぶ (同前)
・馬をすすましめ 〈『アリス』狩り〉(⑧・12)
・その奇妙な像が馬みたいに水を飲む姿を 〈田園〉(⑧・14)
・「馬のかたちをした煙」に 〈異霊祭〉(⑧・19)
・食べる馬が見えるんだ 〈白夜〉(⑧・23)
・馬に四つの脚」 〈ゾンネンシュターンの船〉(⑧・24)
・馬がいるじつに寂しく 〈あまがつ頌〉(⑧・30)
・チューブの馬は同一のままである (同前)
〈聖あんま語彙篇〉の題辞は土方が現代詩文庫版《三好豊一郎詩集》に寄せた〈内臓の人〉からの引用だが、原文は「私は三好さんを見る度に、馬を鋸で引きたくなる」(#B_148、一四六ページ)だ。吉岡が他者の文章からの引用を意識的に行使しはじめた最初の詩篇〈聖あんま語彙篇〉には、〈内臓の人〉からの章句がいくつもちりばめられている。その引き金が「馬」なのはまことに興味深い。吉岡自身「詩を書こうとするたびに、馬を鋸で挽きたくな」ったのではないか。吉岡は執筆の姿勢を談話〈審査の感想(俳句)〉でこう語っている。
僕は詩を書くという場合は、非常に姿勢をはっきりしまして、たとえば、あるところから詩を頼まれると、期間は長ければ長いほどいいんですが、だいたい一ヵ月以上前に頼まれないと――。なにも詩には一ヵ月なんぞかかってないんで、毎日あそびくらして、パチンコやったり、映画へ行ったり、それで詩は書かなくちゃいけないなあと、たえず気にはしている。気にしていて、だいた一週間ぐらい前から、いよいよ締切りが迫った――、詩を書かなくちゃいけないと、机に向い、ぜんぜん違ったものを読む。絵の本を読んだり、何かして、そこから三日ぐらいで、すべて書いてしまう。ものを作るという姿勢〔……〕を、非常に大事にするんです。ものは作らなくちゃいけない。ものは手作りだという、はっきりとした意志をもって作ってゆく。(#C_026、二四ページ)
談話は前年(一九六七年)発表の〈わたしの作詩法?〉と同様の主旨だが、パチンコ・映画・絵の本で詩作のポテンシャルを高めていくさまは耳新しい。ここで馬をひきあいに出せば、吉岡実にとってほとんど「もの」としての詩の等価物である。さて、次は《夏の宴》である。
・染物屋の主人は紫の馬を染めあげる 〈蝉〉(⑨・3)
・武装した馬を曳き 〈草の迷宮〉(⑨・9)
・うまごやしを食べている馬の影を見よ 〈夏の宴〉(⑨・20)
〈蝉〉は紫の馬(の模様)を染めあげる、ということなのか。いまやニンジンではなく、うまごやしを食べている馬。ここに来て吉岡は自在の境地を歩んでいるようだ。拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》の〈サーカス〉は選詩集《馬・春の絵》に欠かせない詩篇である。
小さな街には小さな火事があり/樽と風を入れる場所がある/そこでガリ氏はぬけめなく/サーカスを開催する/大きな土色の心臓の真ん中に/最初の太い鉄の棒をつきさす/ガリ氏の凍えた血や皮膚がうごき/極彩色の天幕をはりめぐらす/急に明るみにさしだされた/臓腑や膀胱は/悲しいラッパ クラリネットの類/ガリ氏のほそい手足は/縄とびの上手な猿/となりに眠る女の臀部/炎の輪をくぐりぬけてゆく/光る馬/興行主の娘だけが/全体のからだを賭ける/それで一座の花形玉乗り/ぐるりに眼玉の観客を呼び入れよう/猫の眼玉も賑やかに光らせよう/ガリ氏たちの深刻で猥雑なサーカス/子供たちには眼の毒だ/両親の間に眠らせる/開幕時間が迫ってきた/見物人が来ない/着飾った男女が来ない/枯葉や骨になったものたちが集まるばかりだ/そして次々と暗いさじきへのぼっている/陰気な天幕のサーカスでは/ラッパも息がぬけて出る/太鼓は盲腸の手術/叩く手がすべる/骨についてきた少しの毛の端が/くすくす哄いだす/何も始まらぬ前から嗤われてはおしまいだ/天幕の外の寒い星のなかへ引込んでくれ/ガリ氏は精根つきて/心臓の鉄の棒によりかかる/玉乗り娘は切符売と逃げてゆく/女は完全な馬になって/敷藁の上に倒れてしまう/これが終演!/つぶれた天幕をひきずる/雨のなかの道化師はガリ氏一人でたくさんだ
サーカス(⑩・2)全篇〔ただし追込の形にした〕
「女は完全な馬になって」しまわなければ、サーカスは終わらないのだ。続いて《薬玉》。
・ 死馬の眼におびえ 〈影絵〉(⑪・3)
・((馬に起ることは 〈蓬莱〉(⑪・18)
この「死馬の眼」はニコルスの終局を髣髴させる。〈蓬莱〉では人馬一体、というよりも人馬同一視の思想が展開されているようだ。そして《ムーンドロップ》がくる。
・ 「このとき競走馬を調教している 〈叙景〉(⑫・11)
・馬が風雪に晒されている光景 〈聖あんま断腸詩篇〉(⑫・12)
ここで吉岡実の《土方巽頌》、一九六八年一〇月一〇日の日記の一節を引かないわけにはゆかない。「夕方、陽子と神宮外苑の日本青年館へ「土方巽と日本人――肉体の叛乱」を観に行く。入り口の脇には夥しく花が飾られている。その前に繋がれた白い馬が霧雨のなかに立っていた」(#A_24、二四ページ)。こうして馬は土方巽の思い出とも分かちがたく結びつく。吉岡実は自己の詩が貧血状態に陥ったとき、まがまがしくも愛すべき馬のイメージを呼びおこし、それが発散する無限ともいえるエネルギーを引き金として自己の詩を物質化してゆく。そういった手順が〈わが馬ニコルスの思い出〉以降はとりわけ顕著のように見える。つまり、吉岡は〈わが馬ニコルスの思い出〉のあとは馬を「主題」にするのではなく、馬とともに詩を生きるようになっていくのである。
どうして「わが馬」に「ニコルス」という名前が付けられたのか、残念ながらわからない。インターネットやウィリアム・H・P・ロバートソン《アメリカ競馬史》(鈴木豊雄・佐藤長秀訳、中央競馬振興会、二〇〇二)で調べると、一六六四年にリチャード・ニコルズ(Richard Nicholls)総督が、オランダ領ニューアムステルダムをペーター・スタイヴサント総督から引き継いでイギリス領ニューヨークと改名して間もなく、アメリカ初の本格的な競馬場が開設されたという。しかし、吉岡実がこの事実を踏まえて執筆したという根拠はなく、馬と「ニコルス」を結びつけるこれ以上の資料は見つかっていない。読者の方に「ニコルス」という馬の名に関して、ご教示をお願いしたい。
蠍[さそり]ガ蠍ヲ癒ヤス。――パラケルスス(#B_133、一二九ページ)
詩篇〈聖少女〉(⑦・10)は《小説新潮》の一九六九年一一月号(第二三巻第一一号)に発表された。《吉岡実全詩集》(#A_29)から定稿を引こう。
聖少女|吉岡実少女こそぼくらの仮想の敵だよ!
夏草へながながとねて
ブルーの毛の股をつつましく見せる
あいまいな愛のかたち
中身は何で出来ているのか?
プラスチック
紅顔の少女は大きな西瓜をまたぎ
あらゆる肉のなかにある
永遠の一角獣をさがすんだ!
地下鉄に乗り
哺乳ビンを持って
ぼくら仮想の老人の遥かな白骨のアーチをくぐり
冬ごもる棲家へ
ハンス・ベルメールの人形
その球体の少女の腹部と
関節に関係をつけ
ねじるねじる
茂るススキ・かるかや
天気がよくなるにしたがって
サソリ座が出る
言葉の次に
他人殺しの弟が生まれるよ!
第七行、初出の「紅血」が定稿で「紅顔」へと変えられたほか、異同はない。言うまでもないが、今回の標題はこの初出形から拝借している。初出誌《小説新潮》では小説の本文ページにコラムのように組まれており、おそらく「二〇行前後の詩を」と依頼されたものであろう。
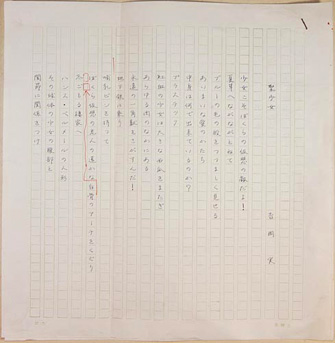
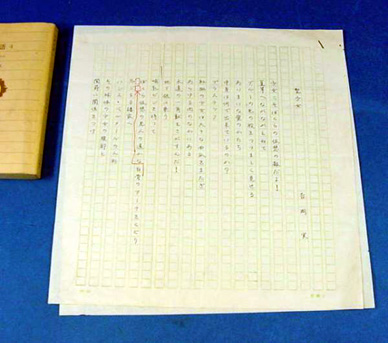

詩篇〈聖少女〉印刷用原稿 ペン書、640字2枚完(森井書店の売価:262,500円) 出典:http://www5f.biglobe.ne.jp/~morii/tokusen/gazo/gp2593.jpg? (左)とYahoo!オークションに出品された詩稿〈聖少女〉の全体(中)と第一葉の部分(右) 出典:http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h53308709
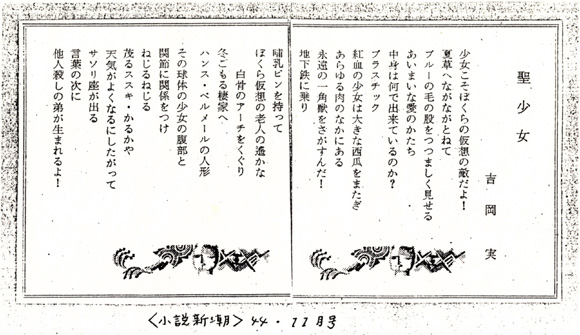
詩篇〈聖少女〉初出(《小説新潮》1969年11月号)の切り抜き〔吉岡家蔵のコピー〕
最初に、本篇に登場する人物を列挙する。
・少女
・ぼくら
・仮想の敵
・ぼくら仮想の老人
・他人殺しの弟
そしてそれに準じる者として、
・永遠の一角獣
・ハンス・ベルメールの人形
が挙げられる。ここでは「人物」としたが、「少女」は詩行が進んでゆくにつれて、意図的に「人形」と混淆され、ほとんど物体化している。あるいは死体化していると言ってもいい。少女は生ける人形、ならば人形は死せる少女か。それが本稿のモチーフである。
さて、吉岡実における「少女」のテーマについては本評釈の詩篇〈少女〉で書いたため、新たに付けくわえるべきものはほとんどない。今回は「ハンス・ベルメールの人形」に着目することにするが、その前に各詩句の評釈を記す。
少女こそぼくらの仮想の敵だよ! 01
・すえながく生きつづける仮想の敵/ブランコのりの子供たち(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
第一行のインパクトは強烈だ。この行を冒頭に据えたことによって、本篇は成立したも同然である。吉岡実は自分が書いた文章の一節から新たに別の文章を書きはじめることがある。ここでは〈飯島耕一と出会う〉の冒頭を見てみよう。
伊達得夫の経営していた書肆ユリイカから、一九五九年の夏、〈今日の詩人叢書〉の一冊として、私の総合詩集が刊行されている。そのあとがきの替りに書いた「詩集・ノオト」の一節に「偶然の機会で飯島耕一と知合った。まさに出会いであり一つの運命だと思う。」とある。
「一つの運命」だと認識したほどの大切な事柄であるのに、私は今までこのことを少数の人に、語ったかも知れないが、書いてはいない。すでに二十年以上も経ってしまったので、正確に想い出すことができるだろうか――。(#A_25、二一一~二一二ページ)
このように、同じ文をもう一度書きながら、今度は別の方向へと話柄を転じていくのは、なにも散文に限らない。ある詩の(多くは途中の)詩句を冒頭に据えて、転轍機を切り換えるようにして詩を書きついでいくスタイルが、吉岡の方法のひとつとして存在した。
・亀裂せる妹の腹を越え/やがて翼をつけた砲身のように飛ぶ/仮想敵がいるようだ(〈メデアム・夢見る家族〉⑧・21)
「仮想の敵」「仮想敵」という語は、詩的にこなれているとは言いがたい。むしろ、その抵抗感こそここで希求されたものだ。「少女」が「ぼくらの仮想の敵」であるなら、「ぼくら」は「少女の仮想の敵」なのか。それとも「少女」からは見むきもされないのか。
夏草へながながとねて 02
・ながながと哭く老婆/ながながと鳴くウグイス(〈蜜はなぜ黄色なのか?〉⑦・12)
なつくさえ・ながながと・ねて――頭韻と五七調が、最初の詩句との違いを際立たせる。
ブルーの毛の股をつつましく見せる 03
・肩から乳房までさらして/その女は大きく股をひらくんだよ!(〈雨〉⑦・9)
・ブルーの髪をなびかせて(〈夏の家〉⑦・13)
私はここで、マルセル・デュシャンの〈遺作〉を想起しないわけにはゆかない。
・「少女はそこに寝て/下肢をそっと閉じている」(〈寿星(カノプス)〉⑫・8)
あいまいな愛のかたち 04
・十字の紅い割れ目(〈立体〉⑦・3)
中身は何で出来ているのか? 05
「中身」は、微妙な違和感を読む者に起こさせる。「少女」は「仮想の敵」であり、生身の人間ではないように書かれているのだ。
プラスチック 06
・発光する水晶でなければ/それはプラスチック(〈低音〉⑦・14)
やはり「少女」は「プラスチック」でできているのだった。
紅顔の少女は大きな西瓜をまたぎ 07
・円の四分の一の/スイカのある世界まで(〈青い柱はどこにあるか?――土方巽の秘儀によせて〉⑦・6)
初出「紅血」が定稿「紅顔」へと変えられたことは、すでに述べた。あるいは西東三鬼の「白馬を少女涜れて下りにけむ」(《旗》#B_048、一一ページ)に付きすぎることを嫌っての改稿か。
あらゆる肉のなかにある 08
・すべての肉はアルミ箔で包まれた!(〈神秘的な時代の詩〉⑦・11)
前者は肉体、後者は食肉、であろう。
永遠の一角獣をさがすんだ! 09
・或晩にお父さんとお母さんがのぞかせた一角獣のように恐ろしく 少女は自身の腿に熱を浴びる(〈冬の休暇〉⑤・12)
「一角獣」が「いる」のではなく「ある」とあるところから、「一角獣〔の一角〕」のような印象がでてきて、そこから存在全体というよりその一部分という連想が働く。
地下鉄に乗り 10
・長い地下道を通過する/貨車や/影の火薬(〈夏の家〉⑦・13)
地下鉄は、通勤や通学のための手段のように読める(飯島耕一の吉岡実追悼文の残像ゆえか)。
哺乳ビンを持って 11
・死児の哺乳をつづける(〈喪服〉④・15)
この主格がわかりづらい。文頭から読むかぎり主語は「紅顔の少女」だろうが、一〇行め以降の文意を探るなら、「ハンス・ベルメールの人形」が「哺乳ビンを持って」いるように読めるからだ。
ぼくら仮想の老人の遥かな白骨のアーチをくぐり 12
・さらにとどろくぼくらの白骨期(〈崑崙〉⑦・8)
この詩句に至って登場人物のサイズは混乱し、あたかも「ぼくら」の肋骨が恐龍のそれででもあるかのように巨大化する。空間が変容すると同時に、時間も西瓜の夏から冬ごもる季節へと急ぎ足で過ぎていく。
冬ごもる棲家へ 13
・冬ごもりの廃屋で(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
この閉塞感、むしろ閉塞願望は吉岡実の詩の要でもあって、後半へ向かって詩はその内部の気圧を押し上げていくところである。
ハンス・ベルメールの人形 14
・ハンス・ベルメールの人形を抱き(〈青い柱はどこにあるか?――土方巽の秘儀によせて〉⑦・6)
この詩句のもつ意味については、次の節で論じよう。ここでは、人形がゴロリところがっている情景に戦慄するだけで充分だ。
その球体の少女の腹部と 15
・少女の腹部をあつかましくも求めて(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
・球体からながれる藍の水(〈コレラ〉⑦・18)
「球体の少女の腹部」は、「〔球体の少女〕の腹部」か「球体の〔少女の腹部〕」か。後者ならば、「少女の球体の腹部」と書くことも可能だったわけで、にわかには断じがたい。あくまでも想像だが、まず「その球体の腹部と」と初めに書いて、後から「少女の」を加筆したのではあるまいか。結果、われわれが読むようなダブルミーニングの詩句ができたのではないか。
関節に関係をつけ 16
この「関節」こそは「ハンス・ベルメールの人形」の最大の特徴であって、吉岡とも親交が深かった澁澤龍彦はベルメールを論じた文章で再三にわたって関節人形に触れている。〈聖少女〉よりも前に発表された澁澤の文から、関連する箇所を引用する。
ベルメエルの「関節人形」についても、一言しておこう。/それは幾つかの関節によって繋がった、一種の奇妙な人体模型である。胴体を中心として、上半身も下半身も脚である。その伸びあがった脚のあいだから覗いている女の首が、愛くるしい。あるいは、そこに首がなくて、少女めいた陰部の溺孔がふかく刳れていることもある。関節によって痙攣的に身をよじらせた人形は、おおむね裸体であるが、パンティをはいていることもあり、ストッキングや、ソックスや、短靴をはいていることもある。その生ま生ましい、未熟なエロティシズム。(〈女の王国――デルヴォーとベルメエル〉〔初出は一九六五年三月〕#B_058、三四~三五ページ)
写真で見ればお分りのように、この最初の人形の顔と胴体は、リアリスティックで生ま生ましく(ウルスラの顔を模したと言われている)、しかも関節でつながった身体の各部分が取り外し可能なので、いろんな姿勢をとらせることができるのである。立ったところ、寝たところ、坐ったところ、あるいは関節を外してばらばらにして、敷物の上に並べたところなどを、ベルメールは写真に撮り、これに自分の文章を付して、一九三四年、自費出版で世に出した。これがオリジナルのドイツ語版『人形[デイー・プツペ]』である。(〈ハンス・ベルメール、肉体の迷宮〉〔初出は一九六八年一一月〕#B_061、八二ページ)
これらの文はもとより、同時に掲載された図版から吉岡実が多大な感化を受けていることは、恐らく間違いないところだ。ちなみに、一点を除いて初出の図版はすべてモノクロ。後述するベルメールの人形写真集を吉岡が「着色写真集」と呼んでいるのは、その「色」から受けた衝撃の大きさを物語っている。これらの素地があって初めて、ベルメールの写真集に眼を奪われたのであろう。
ねじるねじる 17
・復讐とは/ねじること(〈フォークソング〉⑦・7)
茂るススキ・かるかや 18
・かくすハハコグサ/タケニグサ(〈マクロコスモス〉⑦・1)
・ぼくらの豊饒な草むら・枯むぐら(同前)
・秋ならススキがなびく(〈夏から秋まで〉⑦・2)
・それともススキの茂る情死の腐爛期(〈雨〉⑦・9)
「ねじる」「復讐」、「ススキ」「情死」といった関連が詩集の内部に張りめぐらされていることを考えれば、あだや読みとばされる詩句ではない。ここに伏流している情景は、草深いなかに隠された、復讐のために関節をねじられた物体――人形とも少女とも見える――の横たわる姿である。
天気がよくなるにしたがって 19
サソリ座が出る 20
美川憲一うたうところの〈さそり座の女〉が大ヒットしたのは、昭和四七(一九七二)年のことだから、ここでそれを想起すべきではない。
言葉の次に 21
・言葉を犯罪的に使って(〈少女〉⑦・5)
・潜在的世界には/犯罪的な言葉が屹立する(〈わが馬ニコルスの思い出〉⑦・16)
他人殺しの弟が生まれるよ! 22
・胎生の(弟)が浮かび上る(〈聖童子譚〉⑫・4)
吉岡自身が末子の「弟」であったためか、吉岡実詩に登場する「弟」は、「父母」や「姉兄」に較べて影が薄い気がする。そんななかにあって、この詩句の「弟」は珍しく存在感がある。だが、「他人殺し」が難解だ。先行する詩篇から類推するに、「言葉」~「犯罪」~「殺し」の連想の流れに浮かびあがってきたのではあるまいか。
以上のように、《神秘的な時代の詩》(#A_16)の詩句を中心に比較してみると、この〈聖少女〉には多くの詩句が参照されているようだ。いや、参照という言い方は正確ではないだろう。それぞれの詩篇の詩句は〈聖少女〉において転生したと見るべきではないか。それほどにこの詩に不可欠なものとして新たな生を生きている。
この詩で注目すべきは、一四行め「ハンス・ベルメールの人形」である。いったい吉岡実の詩に造形作品を彷彿させる詩句は珍しくないが、このようにあからさまに登場することは稀だ(詩集で本篇の直前に置かれている〈雨〉の「老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの/スイ星の球のつまった/箱をさがす」という詩句が想起される)。吉岡の散文〈官能的な造形作家たち〉から〈1 ハンス・ベルメール〉の全文を引こう。
瀧口修造には「ハンス・ベルメール断章」という、造形作家を讚えた、美しい断章がある。適宜引用させて貰う。――ベルメールの人形における球体は anagramme(語句の解体と組み替え)のためのメカニズムであり、一種の自在関節。/それはまた一箇の完全な真珠であり、/忍び寄る夕闇のなかのアナグラムによって、/一箇の完璧な疣であり、涙一滴の孤独な結石である。――。私もある一時期、ハンス・ベルメールに魅せられ、古本屋で着色写真集[、、、、、]を購ったものだ。ドイツ語の限定本である。読めないが充分たのしむことができた。そして「聖少女」と題する一篇の詩を書いた。その終章「その球体の少女の腹部と/関節に関係をつけ/ねじるねじる/茂るススキ・かるかや/天気がよくなるにしたがって/サソリ座が出る」
「断章」の一節を引用する。――人形作者としてベルメールは、孤独な原型人間のひとりとして出発することを宿命づけられていた。けれどなんと多くのそんな人たちが地上に彷徨していることだろう。不幸にも互いに知らず、視えぬ人形作者として……。――。やがて一人の青年が、澁澤龍彦の紹介文に依って、ハンス・ベルメールとその人形を知り、深い啓示を受ける。数多い潜在的なファンのなかから、視える[、、、]人形作者がうまれたのだ。(#A_25、三五九~三六〇ページ)
吉岡がベルメールについて書いた唯一の文章に、はからずも〈聖少女〉が登場していた。この〈官能的な造形作家たち〉は〈聖少女〉から一七年ほど経った一九八六年に発表されており、瀧口の断章も自身の詩篇もほとんど同じ手つきで扱われている。瀧口修造の〈ハンス・ベルメール断章〉は、《gq》(創刊号、一九七二年九月)が初出だが(未見)、のちの《余白に書く 2》(みすず書房、一九八二年七月)には収録されておらず、吉岡の典拠がどれか決定しかねる(以下は《コレクション瀧口修造》所収の本文に依る)。吉岡が引用しているのは、〈ハンス・ベルメール断章〉の最初のブロックと、四番めのブロックの冒頭である。この選択はいかにも的確であって、吉岡の眼力を示して余りある。ところで、瀧口の〈ハンス・ベルメール断章〉には〈聖少女〉の読者にとって興味深いくだりが四箇所ほどある。それはまず
「蠍は蠍を癒やす」(パラケルスス)
という部分であり、次に
ベルメールの絵画化方法は一種の球化運動といったものに従っているかと思われる。
であり、
もっとも刺刺しいもの、ハイヒールの踵も、尖った指の爪も、三角定規でさえも、みやびた(あれはどこから来たものか)腰のひとひねりのうちに抱きすくめられるだろう。
であり、さらに
それよりも何よりも少女はすでに「死」のからだじゅうを知りつくしていて、なんと優雅に振舞うことだろう。(以上、#B_083、七三~七六ページ)
である。第一の「蠍は蠍を癒やす」はベルメールの《肉体的無意識の小解剖学あるいはイマージュの解剖学》にも引用されているエピグラフで、すぐさま吉岡の「サソリ座が出る」を連想させる。ところが、前後関係を考慮すると、吉岡が〈聖少女〉を書いた一九六九年に瀧口の文章はまだ発表されていないのである。それにしてもこの類似、これは単なる偶然だろうか。第二の「球化運動」は「その球体の少女の腹部と」という詩句を記した吉岡実における球体嗜好を刺戟したであろう。吉岡は金井美恵子との対談で「丸くて寸づまりのもの」について、こう語っている。
金井 鳥もそうですね。ダルマインコのダアちゃん。あれもコロッとしている感じで。
吉岡 そうねえ。誰か心理学者が解明してくれればね。形態として丸っこいものが好きなのは何なのかをね。天へのびて行くものより、地にかがまるものに愛着があるんだ。(#C_010、一〇七ページ)
第三の部分は、吉岡の散文〈官能的な造形作家たち〉の〈2 四谷シモン〉の結語として置かれた文であり、第四は同じくその文の最初の段落中に見えるが、そこだけ読むと瀧口修造の〈ハンス・ベルメール断章〉からだとは一見してわかりにくい。このあたりは難しい問題を含んでいるので、のちほど考察することにしよう。
ところで、吉岡が詩篇にハンス・ベルメールの人形を登場させたのは、〈聖少女〉が初めてではない。Ⅰでも一行だけ引いたが、一九六七年七月発表の〈青い柱はどこにあるか?――土方巽の秘儀によせて〉(⑦・6)の一七行から一九行にかけて「天井の便器のはるか下で/ハンス・ベルメールの人形を抱き/骨になること」という詩句が存在するのだ。ここはどうしても、吉岡の言う「古本屋で購ったドイツ語の限定本の着色写真集」が観たくなるというものだ。そこでウェブサイト《ハンス・ベルメール:日本への紹介と影響―球体関節人形を中心に―》で調べてみた。しかし確証がもてないので、サイトを運営するBlaue Katzeさんにお尋ねしたところ、確定はできないものの最も可能性が高いのは、Hans Bellmer《Die Puppe》(Gerhardt Verlag, Berlin, 1962)で、これはベルメールの三冊の著作(〈人形〉〈人形の遊び〉〈イマージュの解剖学〉)のドイツ語版を纏めて集録した二〇〇〇部限定本であり、河出書房新社版の《イマージュの解剖学》の原典となったものだという。吉岡の「着色写真集」に該当するのはその〈人形の遊び〉で、オリジナルの仏語版はモノクロ写真に手彩色をしているそうだ。Blaue Katzeさんのご教示に感謝しつつ、これも教えていただいたサイトで《Die Puppe》の書影や書誌を見ると、追加すべき情報は以下のごとくである。
これは実見することができなかったので、訳書である河出書房新社版の《イマージュの解剖学》(#B_133)につくことにする。以下に、参照のための図版を掲載する。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
最初の写真には番号がなく、二つめから「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……」と続く。まず注目すべきはⅢだ。これはトルソであって、少女の像ではない。むしろその肉塊は成熟した女を感じさせる。これが少女のように見えるのはその無毛性ゆえである。またⅥは、紅の関節人形と樹影の男の設定が〈聖少女〉の直接のスルスのひとつであることをうかがわせる。これらの作品に吉岡が鋭く感応したであろうこと、言うも愚かである。ところで、吉岡実は「聖」を題名にいただく詩を六篇書いている。
・聖家族(詩集《僧侶》#A_04)
・聖母頌(詩集《静かな家》#A_09)
・聖少女(詩集《神秘的な時代の詩》)
・聖あんま語彙篇(詩集《サフラン摘み》#A_17)
・聖童子譚(詩集《ムーンドロップ》#A_26)
・聖あんま断腸詩篇(同前)
これらのなかで是非とも取りあげたいのが〈聖家族〉(④・14)である。
聖家族|吉岡実美しい氷を刻み
八月のある夕べがえらばれる
由緒ある樅の木と蛇の家系を断つべく
微笑する母娘
母親の典雅な肌と寝間着の幕間で
一人の老いた男を絞めころす
かみ合う黄色い歯の馬の放尿の終り
母娘の心をひき裂く稲妻の下で
むらがるぼうふらの水府より
よみがえる老いた男
うしろむきの夫
大食の父親
初潮の娘はすさまじい狼の足を見せ
庭のくろいひまわりの実の粒のなかに
肉体の処女の痛みを注ぐ
すべての家財と太陽が一つの夜をうらぎる日
母親は海のそこで姦通し
若い男のたこの頭を挟みにゆく
しきりと股間に汗をながし
父親は聖なる金冠歯の口をあけ
砕けた氷山の突端をかじる
ここでもう一度「ブルーの毛の股をつつましく見せる」という詩句を振りかえれば、人間であるかぎりそれは極めて不自然である。「すさまじい狼の足を見せ」る「初潮の娘」が「聖家族」の一員なら、この時点でわれわれの「少女」は聖化の第一歩を歩みはじめていたのだ。つまり、最初に色による異化があり、次にプラスチックの中身という素材による異化が少女を襲うのだ。その行く手に「人形」が待っていることは、詩行の必然である。
いずれにしても、吉岡は着色写真集を神田・神保町あたりの古書店で入手したことだろう。今日のわれわれなら、原本・訳書を問わずベルメールの人形写真集は手軽に観ることができるから、逆にこの詩にこめられた「電圧」のようなものはなかなか感じとりにくい。ここで、吉岡実の散文〈官能的な造形作家たち〉から〈2 四谷シモン〉の全文を引こう。
私が初めて四谷シモンの名を知ったのは、雑誌「太陽」の人形特集の写真に依ってだった。その少女人形は、ベルメールの球体と関節をみごとに再現し、すべすべの股間には、聖痕さえ刻まれている。――何よりも少女はすでに「死」のからだじゅうを知りつくしていて、なんと優雅に振舞うことだろう。――。私はシモンの実物の人形を見たこともないが、親近感をおぼえた。
土方巽の暗黒舞踏派の会か唐十郎の状況劇場・赤テントの下で、私は四谷シモンと出会ったように思う。その頃、彼は人形つくりを中止し、アングラ芝居の女形として活躍していた。新宿の花園神社の境内で催された、唐十郎作「由比正雪」に客演した四谷シモンの女形の凄艶な演技に、賛嘆したものだ。それから四、五年ほど役者稼業をして、また人形つくりに没頭しはじめる。その再生作品が「ドイツの少年」であった。まさしくベルメールの桎梏から脱した記念すべき人形体。金髪の等身大の裸形は、包茎を勃起させて、なんら恥入ることなく、爽かである。
四谷シモンの第一回個展「未来と過去のイヴ」が、銀座の青木画廊で催された。等身大の女体十二体が陳列される。ガードルを付け、ハイヒールをはいた、金髪のアメリカ女のように見える。陰毛と秘所を婉然とさらしていた。――もっとも刺々しいもの、ハイヒールの踵も、尖った爪も、三角定規でさえも、みやびた(あれはどこから来たものか)腰のひとひねりのうちに抱きすくめられるだろう。――。(#A_25、三六〇~三六一ページ)
この《太陽》の人形特集号は、一九七〇年の第八〇号だ。すなわち吉岡実はシモンの「ベルメールの球体と関節をみごとに再現し、すべすべの股間には、聖痕さえ刻まれている」ところの「少女人形」を見ずに〈聖少女〉を書いている。吉岡の書いた詩句を後づけるようにして、瀧口の断章やシモンの人形が登場するのはどうしたわけだろう。その末尾の「もっとも刺々しいもの〔……〕」が瀧口修造の〈ハンス・ベルメール断章〉から引かれたことは、すでに見たとおりだ。つまり吉岡は瀧口の〈ハンス・ベルメール断章〉を、ベルメールにふれた散文だけではなく、シモンにふれた散文にもまったく同じ調子で(引用文の前後を二倍ダーシで括って)織りこんでいくのだ。これはまことに興味深い事実であって、吉岡はベルメールの人形観を具現した人形作者として四谷シモンを観ており、それは着色写真集から詩篇を産みだした直感に支えられていよう。では、吉岡がベルメールの名を知ったのは、なにに依ってだったのだろうか。前掲Blaue Katzeさんの資料に依拠しながら、適宜補記する。
年:日本への紹介
1936:山中散生編の《L'ECHANGE SURREALISTE》(ボン書店)に、早くもベルメールの〈人形〉の写真が別刷図版で掲載される。
1937:瀧口修造・山中散生らの企画による〈海外超現実主義作品展〉で、ベルメールの素描と写真が紹介される。この展覧会の出品作品の主なものを収録した《ALBUM SURREALISTE》(《みづゑ》388号)に人形の写真と素描が掲載される。この中には前掲参照図版の写真Ⅸ〔最後に近い黒女神の青春〕やⅩ〔隠れたる待望〕も含まれている。
1939:山中散生〈ベルメエルの人形幻想〉(《アトリヱ》10月号)。まず、ベルメールの著書《人形》(ジョルジュ・ユニエ構成)の外観写真が眼を引く。それは写真アルバムよりも厚い感じで、背の綴じ紐が編上靴の紐のようで、異様な雰囲気を醸しだしている。前掲参照図版の写真Ⅵにふれた一節にこうある。「〔……〕その著色術は可なり大胆な、しかも繊細〔な〕もので、例へば「森の中の人形」などは、森其の他人形の背景となるものは可なり天然色に近い色彩が用ひられてゐるが、主題の人形のみは、われわれの予想を裏切るかの如く、真紅色に塗りつぶされてゐる。それは眼に痛い程に画面から前面に推し出されてゐて、恰も焔の塊の如き感を抱かせるのである。著色写真に於けるかかる絵具の使用法は、おそらく一種のマジックに属するものと云はなければなるまい。」(#C_001、四三~四四ページ)。山中の眼に吉岡の眼と同質のものを感じるのは、私だけではあるまい。
1960:瀧口修造(〈芸術とエロス〉)・秋山邦晴(〈新しい想像力の挑戦〉)が〈シュルレアリスム国際展〉を紹介し、ベルメールに言及(《みづゑ》 663号)。
1962:澁澤龍彦〈彼女は虚無の返事を怖れる〉(《あんま――愛欲を支える劇場の話》)で澁澤が初めてベルメールに言及する。
1963:澁澤龍彦〈玩具について〉 (《現代詩》 1963年3月号・4月号)。長文のエッセイの最後にベルメールが登場。
1964:澁澤龍彦 《夢の宇宙誌》 (美術出版社)に〈玩具について〉収録。
1965:澁澤龍彦〈女の王国 ポオル・デルヴォーとハンス・ベルメエル〉(《新婦人》3月号)〔のち《幻想の画廊から》に収録〕は、〈宙吊りにされた人形〉の写真(〈シュルレアリスム国際展〉と同じカット)が衝撃的である。澁澤龍彦〈玩具考〉(《美術手帖》4月増刊号)。
1967:瀧口修造〈ハンス・ベルメール〉(〈ハンス・ベルメール展〉、南天子画廊、2月)。澁澤龍彦〈痙攣する女性の美 ハンス・ベルメール個展〉 (《SD》4月号)〔のち《幻想の画廊から》に収録〕。澁澤龍彦 《幻想の画廊から》 (美術出版社)刊行、ベルメールの人形の写真が六点掲載される。
1968:澁澤龍彦〈ハンス・ベルメール 肉体の迷宮〉(《みづゑ》 766号)、ベルメールの人形の写真が八点掲載される。〔のち《幻想の彼方へ》に収録〕
一九六二年以降、それまでの瀧口修造(昭和一〇年代前半には山中散生も)に代わって澁澤龍彦が精力的にベルメールを取りあげていることがわかる。その成果は主として《幻想の画廊から》(#B_058)と《幻想の彼方へ》(#B_061)にまとめられている。澁澤のベルメール論から引用する。
人形の場合も、グラフィックの場合も、ベルメエルの扱う対象はもっぱら女であり、女の肉体のスパスムである。彼はまた、みずから『イメージの解剖学』という本を書いているが、そこに挿入された何枚かのデッサンにおいても、線によって自在に表現された肉体のスパスムが、まさに解剖学者の目でとらえられていて、ふしぎなエロティックな効果を生んでいる。(〈女の王国――デルヴォーとベルメエル〉#B_058、三三~三四ページ)ヌード写真の上に鏡を直角に立てて、この鏡の位置を少しずつ動かしてみると、写真の面と鏡との交わる一線を軸として、シンメトリックなシャム双生児のようなヌードが、大きくなったり小さくなったり、さまざまに変化する。ヌードはみるみる伸び拡がって、乳房が二つで脚が四本の怪物になったり、逆にみるみる縮まって、脚が二本で乳房が四つの畸形になったりする。――こんな秘密めいた遊びも、ベルメエルの好むところであったようだ。(〈イメージの解剖学――ふたたびベルメエル〉〔初出は一九六七年四月〕、同前、四〇ページ)
女の肉体のスパスムといい、秘密めいた遊びといい、澁澤の典型的な言説である。吉岡が残した文章には、これらへの言及は見当たらないが、一九六七年刊の《幻想の画廊から》は熟読玩味したのではあるまいか(もっとも吉岡は、ここでも図版を中心に楽しんだかもしれない)。なにせ同書に登場するスワンベルグも、ベルメールも、レオノール・フィニーも、バルテュスも、マグリットも、ゾンネンシュターンも、アルチンボルドも、郵便屋シュヴァルも、(さらには一角獣も!)吉岡実の詩や散文にその姿をとどめているのである。
吉岡実には四谷シモンに捧げた〈薄荷〉(⑫・6)という詩篇がある。初出は一九八五年刊の《四谷シモン 人形愛》(#B_164)。定稿を全篇引用しよう。ここにおいて吉岡は、瀧口のベルメール論(の球体と関節)を梃子にして、ベルメールからシモンへと自己の人形詩篇を展開させた。
薄荷|吉岡実(人形は爆発する)――四谷シモン
1
夏が過ぎ
秋が過ぎ
「造花の桜に
雪が降り
灯影がボーとにじんでいる」
池之端の(大禍時[おおまがとき])
振袖乙女の幾重もの裾の闇から
わたくしは生まれた
(半月[はにわり])の美しい子孫か
「神は急に出てくるんだよ」
(非・器官的な生命)を超え
(這子[はうこ]) ひとがた
人形は人に抱かれる
(衣更忌[きさらぎ])の夜を
2
母親の印象は
裸電球の下で
白塗りの女戦士のようだ
赤い乳房が造り物に見える
「カミソリでサーとなでると
中からまた肌色の乳房が
殻をやぶって生まれてくる」
それに噛みつくから
わたくしは消化不良の子供
(唐子[からこ]の三つ折れ
人形を背負って
鈴虫の音色に聴きほれる
父親は冷酒をあおっては
(毒婦高橋お伝)をたたえ
ヴァイオリンを弾く
キー・キー・ギー
「天国がどんどん遠くなる」
3
窓まで届かない月の光
ニーナ・シモンの唄が好き
縫いぐるみの(稲羽[いなば]の白兎[しろうさぎ])が好き
「固い真鍮のベッドで
わたくしは紗のような
薄い布を身にまとって寝る」
薄荷の花のように
「ゆるやかな酸素に囲まれる」
少女の輝く腹部を回転させよ
アー・アー・アァー
(官能的な生命)
「人形にだって
衣食住が必要である」
4
揚げ物を食べた後は淋しい
この部屋の外は
「巨大な蓮池の静寂を思わせる」
水音 羽音
「何のおしらせもなく
(土星)が近づく」
ここで〈聖少女〉と〈薄荷〉を読みくらべてみたいが、その前に吉岡実詩における「人形」の変遷を概観しておこう。
・聖人形をおろし(〈僧侶〉④・8)
・ミルクのみ人形の腹のように(〈やさしい放火魔〉⑥・9)
・〔ここに〈青い柱はどこにあるか?――土方巽の秘儀によせて〉と〈聖少女〉が来る〕
・「上に行けば精霊 下にあるもの/が人形」(〈聖あんま語彙篇〉⑧・8)
・アグネス・フロレンス・プライスは今日も一つの大きな人形を抱く 中世のかつらをつけた裁判官の姿をした人形を(〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉⑧・11)
・精神的な女は人形をつくる/「木毛 ハリコ 桐粉 鉛などで/形づくりをして/蝋絹 ときにはメリヤスを張る」/現在もっとも必要とする/うつろな頭をすげかえ 手足をとりかえ/血肉の壊滅は行われた(〈あまがつ頌――北方舞踏派《塩首》の印象詩篇〉⑧・30)
・アリスのすてていった人形たちと赤錆のストーブ(〈人工花園〉⑩・19)
こうして並べてみると、「聖」なるものや、「アリス〔少女〕」との観念連合が多いのに驚く。それ以上に、〈あまがつ頌〉のディテールに目を瞠る。鍵括弧内は製作にふれた人形作者(四谷シモン?)の文からの引用であろうか(少なくともベルメールの文章ではなさそうだ)。これらの詩篇の果てに究極の人形詩篇として〈薄荷〉が登場する。この詩の印象をひとことで言うなら、ヴァイオリンの音色やニーナ・シモンの唄声に彩られた、闇のなかに切れぎれに浮かびあがる人形作者の伝記映画である。上野・不忍池を背景に、人形作者はしだいに自身の作る人形と一体化して、闇に消える後ろ姿はひとかひとがたか見分けがたい。つまりここにあるのは「聖少女」→「ハンス・ベルメールの人形」の逆を行く、人形の人化であり、その変貌の中心点こそ「少女の輝く腹部を回転させよ」の詩句であろう。
最後に高橋睦郎の〈鑑賞〉を検討して、この稿を終えよう。
「聖少女」。成熟あるいは老化した男にとっての少女とは何か、ありきたりの表現でいえばロリータ・コムプレクスの詩である。「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!」という一行は「ぼくら」と「少女」の関係を端的に表現している。「仮想の敵」とは自衛隊の演習計画などで有名になった言葉だろうが、ここには「仮想の敵」はじつは真の敵だというニュアンスと、どんなに真の敵だと思ってもむこうで相手にしてないから結局「仮想の敵」なんだというニュアンスと、二つながら含んでいよう。だから少女はぼくらとは無関係な「大きな西瓜をまたぎ/あらゆる肉のなかにある/永遠の一角獣をさがすんだ!」。しかし、つぎの「ぼくら仮想の老人」は「仮想の敵」をもう一度ひっくり返している。少女がぼくらを老人と思うのは仮想にすぎず、老人はたちまち父親になって少女を姦す。この父子相姦から「言葉の次に」(はじめに言葉ありき!)「他人殺しの弟が生まれる」というわけだ。(#A_23、六一~六二ページ)
たしかに「仮想」を《広辞苑 第二版》(#B_075)で引くと、【仮想敵国】に「近い将来に戦争の発生する危険が予想され、国防上作戦計画を立案しておく必要のある相手国」とある。なるほど。だがはたして、「ぼくら」は「少女」の父なのだろうか。「ぼくら仮想の老人」を字義どおりにとれば「ぼくら老人にあらざるもの」であって、「ぼくら」と「少女」に血縁はなく、ために「父子相姦」は成立しない。むしろ、「他人殺し」の「他人」こそ「ぼくら仮想の老人」の隠微な言い換えではなかっただろうか。
当時考えるところがあって、私は二年間ほど詩作を止めていた。――吉岡実(#A_25、二三六ページ)
一九六九年――この年、吉岡実は九篇の詩作品を発表した。ここでもう一度それらを振りかえって見てみよう。
・一月 少女 四二行
・二月 スワンベルグの歌 三四行
・三月 三重奏 七一行
・四月 蜜はなぜ黄色なのか? 二九行
・八月 夏の家 三九行
・一〇月 わが馬ニコルスの思い出 一六三行
・一一月 聖少女 二二行
・一二月 ヘアー 二六行
・一二月 コレラ 九七行
このうち〈スワンベルグの歌〉と〈ヘアー〉は詩集《神秘的な時代の詩》(#A_15)には収録されず、前者は未刊詩篇となり、後者は〈鄙歌〉と改題改稿されて拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(#A_20)に収められた。前回は〈聖少女〉の、今回は〈コレラ〉の評釈になるわけだが、〈ヘアー〉はこの二篇に挟まれて発表されている(初出は《文學界》一九六九年一二月号)。全篇を引こう。
ヘアー|吉岡実
わたしの好きな常套句の引用
ヘアーの下の果実
ヘアー
そこでは恐怖の麩を煮つめて
ヘアーの黄金の下で身もだえする恋人
枯木のかげへ入り
ヘアー かみにくい皮を噛み
固い函で未熟なイチゴをかこむ
部分からその全体が現われるまで
甲冑を洗え!
そこにはどんな形態の蛇が赤い舌を出す
あるいは砂かむりで
花咲く母の吸盤が見えるか?
ヘアーの夕焼
まさに淋しいドラムカンを叩く旅
股旅人が来る水路から道路へ
雪ふる舟 来る車
それから父離れの幼児は死出の
天翔ける種子
ヘアー
次にわたしに確認できるのはなに?
傾斜とはいかなる位置から測ればよいのかね
ヘアーの下でなく疾走する車の下で
塩のように新鮮に
見れば見るほど大きい
わたしの恋人 反処女!
この詩の「ヘアー」を「髪」と読むか「毛」と読むかで、印象は大きく変わってくる。試みに「髪」を含む詩句を他の詩篇から抜きがきしてみよう(「金髪」「束髪」などの熟語は省いた)。
・その女の髪の中で(〈讃歌〉③・11)
・その夜の窓をのぞく鳥はどれも 死んだ妻の髪のかたちをするので射ち落す(〈喜劇〉④・1)
・女の髪の上に滝が懸けられて凍る(〈感傷〉④・18)
・死児の髪を垂らし(〈死児〉④・19)
・全部の母親のさかまく髪のなかに(同前)
・髪と藻の暗いみどりの輝き(〈裸婦〉⑤・7)
・その女の髪の毛の巣で(〈水のもりあがり〉⑤・13)
・髪のたなびく春(〈鎮魂歌〉⑤・15)
・髪の毛の下にうごく櫛(〈受難〉⑤・17)
・女はぬれた髪の毛をしぼられ(〈沼・秋の絵〉⑤・21)
・犬藻や中世の戦死者の髪の毛を(〈模写――或はクートの絵から〉⑥・4)
・そこでわたしたちの母は長い髪をかきあげる(〈聖母頌〉⑥・6)
・ブルーの髪をなびかせて(〈夏の家〉⑦・13)
・なやましく長い髪(〈ルイス・キャロルを探す方法―わがアリスへの接近〉⑧・11)
・風に吹かれたあの長い髪が庭の木を巻く(〈ルイス・キャロルを探す方法―少女伝説〉⑧・11)
・髪がうまくとかせないアイリーン(同前)
・「髪をしなやかにしたいわ」といった一人の少女(〈『アリス』狩り〉⑧・12)
・なんじの髪 体毛は葡萄のごとし(〈悪趣味な内面の秋の旅〉⑧・31)
・舟板の上で可憐な少女の緑の髪を梳く(〈夜会〉⑩・5)
・死んだとは信じられぬ拡りをもつ髪(〈斑猫〉⑩・6)
・貯蔵庫へたくわえられる髪の毛(〈霧〉⑩・7)
・髪をとくそれは老婆でなく(〈花・変形〉⑩・14)
これらからは大きな傾向として「女」の「長」い「緑」の「髪」という像が導きだされる。一方の「毛」は、熟語を除くと、兎や馬などの動物の毛、玉蜀黍の毛、人の体毛全般の用法がほとんどで、大方の予想を裏切って「陰毛」を指ししめすことは稀である。ならば「ヘアー」はどうか。
・きみの彼女のタワーのようなヘアー(〈崑崙〉⑦・8)
これが唯一の「ヘアー」だ。はたしてこれは「髪」か「毛」か。前後の詩句を読みこんでみても、にわかに決めかねる。ここは素直に双方の像を脳裡に描いておくことにしよう。前掲の〈ヘアー〉も「髪」に軸足を置きつつ、両者を重ねあわせて読むのが味わい深いように思う。さて《吉岡実全詩集》(#A_29)には異稿や初出稿は掲載されていないから、この〈ヘアー〉ではなく、改稿改題作品である〈鄙歌〉(⑩・15)が載っている。全篇を引用しよう。
鄙歌|吉岡実
わたしの好きな常套句 1
ヘアー 2
ヘアーの森 3
そこではふらちな麸を煮つめて 4
通草の下で身もだえする乙女 5
枯木のかげに入り 6
かみにくい皮を噛む 7
野ずえの川で 8
部分からその全体が現われるまで 9
甲冑を洗え! 10
そこにはどんな先祖の悪霊が浮び出る? 11
ヘアーの夕焼 12
まさに淋しいドラムカンを叩き 13
旅人は去る 14
水路から道路へ 15
雪ふる舟 来る車 16
朱の鳥居をくぐり 17
天翔ける乙女 18
ヘアー 19
わたしに確認できるのはなに? 20
風景とはいかなる位置から測ればよいのか 21
石塔の下でなく疾走する車の下で 22
塩のように新鮮に 23
ヘアー 24
見れば見るほど大きい 25
わたしの恋人 死兎 26
いったい吉岡実は、既発表の作品を詩集に収める際に加筆訂正することがあまりなかった詩人だが、本篇は例外的に多く、詩集《ポール・クレーの食卓》の〈収録作品初出記録〉でも、唯一「(改稿改題)」(#A_20、八七ページ)と断わっているほどだ。ことほどさように〈ヘアー〉と〈鄙歌〉の両稿を並べただけでは手入れの箇所がわかりにくいので、少しく書きなおしてみよう。
〔ヘアー→鄙歌〕|吉岡実
わたしの好きな常套句〔の引用→(トル)〕 a
ヘアー〔の下の果実→(トル)〕 b
ヘアー〔(ナシ)→の森〕 c
そこでは〔恐怖の→ふらちな〕麩を煮つめて d
〔ヘアーの黄金→通草〕の下で身もだえする〔恋人→乙女〕 e
枯木のかげ〔へ→に〕入り f
〔ヘアー →(トル)〕かみにくい皮を噛〔み→む〕 g
〔固い函で未熟なイチゴをかこむ→野ずえの川で〕 h
部分からその全体が現われるまで i
甲冑を洗え! j
そこにはどんな〔形態の蛇が赤い舌を出す→先祖の悪霊が浮び出る?〕 k
〔あるいは砂かむりで→(トル)〕 l
〔花咲く母の吸盤が見えるか?→(トル)〕 m
ヘアーの夕焼 n
まさに淋しいドラムカンを叩〔く旅→き〕 o
〔股→(トル)〕旅人〔が来→は去〕る〔(ナシ)→改行〕水路から道路へ p
雪ふる舟 来る車 q
〔それから父離れの幼児は死出の→朱の鳥居をくぐり〕 r
天翔ける〔種子→乙女〕 s
ヘアー t
〔次に→(トル)〕わたしに確認できるのはなに? u
〔傾斜→風景〕とはいかなる位置から測ればよいのか〔ね→(トル)〕 v
〔ヘアー→石塔〕の下でなく疾走する車の下で w
塩のように新鮮に x
〔(ナシ)→ヘアー〕 y
見れば見るほど大きい z
わたしの恋人 〔反処女!→死兎〕 A
まず、標題が変えられた。吉岡実の詩にあって、表記上の変更以外で改題された作品は、ほかには〈唱歌〉(⑩・4、初出標題〈牧歌〉)、〈青枝篇〉(⑪・4、初出標題〈春の伝説〉)があるだけだ。改題の理由として、〈唱歌〉は〈牧歌〉という先行作品が二篇あったことが大きかろうし、〈青枝篇〉は詩集《薬玉》(#A_22)に《金枝篇》の要素を注入するための措置であろう。一方、〈鄙歌〉にはそうした外的な要因は見あたらない。ならば作品の内部にその理由を探らなくてはならない。ところで「鄙歌」とはなにか。手許の辞典には「①田舎で歌われる流行歌。俗謡。民謡。②狂歌」とある。つまり吉岡は〈ヘアー〉という、主題を明示する標題を引っこめて、代わりにその作品そのもののジャンルを示すことにしたのだ。本文の改稿は、この詩を「鄙歌」と呼ぶ方へ、それと平衡する力でなされていると見るべきだ。はたして〈鄙歌〉は「田舎で歌われる流行歌」か「狂歌」か。
a「わたしの好きな常套句〔の引用→(トル)〕」は、《夏の宴》(#A_19)という「引用詩集」をすでに持っている吉岡にしてみれば、当然の手入れだろう。なぜなら、これは「声明」であって「引用」ではないのだから。
d「そこでは〔恐怖の→ふらちな〕麩を煮つめて」、形容を無化したいのだが、単に取るのではではなく、頭韻的なおかしみを持ちこんでいる。
f「枯木のかげ〔へ→に〕入り」。「へ」と「に」の使いわけは難しい。たとえば次の〈春〉(①・1)の第一行
朝は蝶の脚へ銀貨を吊す
は「朝は蝶の脚に銀貨を吊す」とどう違うのか、うまく説明しきる自信はない。ただこういうことは言えるだろう。吉岡は原稿を書く段で自分の感覚に照らしての違和に敏感であり、ひとたび稿が成ってもその基準は絶えず更新されていて、ある種の矯正装置のように機能していただろう。また、「kareki no kage ni」という音の並びの影響も働いているだろう、と。
h「固い函で未熟なイチゴをかこむ」やk「蛇が赤い舌を出す」などのエロティクな詩句が削られたことからは、「これはそういう詩ではないのだ」という主張が汲みとれるものの、いささか残念だ。それかあらぬか、m「花咲く母の吸盤が見えるか?」もばっさりと切られている。私はここから、前回の〈聖家族〉(④・14)や〈タコ〉(⑧・2)を連想した。
l「あるいは砂かむりで」、この「砂被」の唐突な登場など、なかなか味わい深いものがあるが、これも棄てられた。
q「雪ふる舟」から、雪舟の画幅が幻影のように立ちのぼる。
r「それから父離れの幼児は死出の」は〈葉〉(⑧・4)の「ときにはバケツ抱き父を抱き/土離れ」を先取りしたような詩句である。
それにしてもこの改稿でいちばん見事なのは、A「〔反処女!→死兎〕」である。私など仮に「反処女!」はいささか凡庸でほかのなにかに置き換えたいと思ったところで、「死兎」が思いうかぶことは金輪際ない。おそらくこの世界には、それを思いうかべることのできる人間と、それを思いうかべることはできなくとも感じとることのできる人間と、それを思いうかべることも感じとることもできない人間の三種類がある。
詩篇〈コレラ〉(⑦・18)は、一九六五年一二月一五日発行の《都市》(都市出版社)創刊号に掲載された(《都市》は「詩を中心とする文学・芸術季刊誌」を謳う季刊雑誌で、責任編集が田村隆一、製作は《血と薔薇》を製作した八牧一宏)。田村隆一の〈年譜〉(田野倉康一編)の「一九六九年」から、本論に関連する項目を抜粋する。
一九六九年(昭和四十四) 四十六歳
六月、季刊「都市」、刊行準備に入る。
八月、都市出版社開業祝い。社名は田村の命名。
十二月、田村隆一の編集による季刊「都市」(都市出版社)が創刊。記念講演と朗読会を開催する。B5変形版で以降本号四冊、別冊一冊を刊行し、廃刊。発行人はかつて「世代」の中心メンバーであった矢牧一宏。
同月、思潮社より、『緑の思想』〔刊行は一九六七年九月〕以来の未刊詩篇と、詩論、エッセイを集めたアンソロジー『詩と批評A』を刊行する。(#B_087、一四五八~一四五九ページに依る)
この《詩と批評A》の装丁は吉岡実である。都市出版社の開業祝いをした八月ころ、田村から吉岡に詩の原稿依頼があったのだろう。吉岡には「田村の創刊雑誌に書く」という意識が、それも強烈に、働いたことだろう。後年、吉岡は〈田村隆一・断章〉にこう書いている。
ある日、田村隆一と小川町のシンコーグリルでビールを飲んでいたとき、おれは今度、〈青いウンコ〉という詩集を出すと云った。私は一瞬、え、〈青いインコ〉――ずいぶん可憐な題の詩集だと思った。いや〈青いウンコ〉だと呵々大笑。彼には会心の表題らしく、いいだろうをくりかえした。私は内心困っていた。もしかしたらその頃、不摂生な生活をやめて、健康のために彼は毎日苦労して、青汁を飲んでいたためかもしれない。そしてひそかに、青いウンコを排泄していたのだろう。それからだいぶたって、新しい詩集が世に出た。それは《緑の思想》である。(#A_25、一八六ページ。初出は《ユリイカ》一九七三年五月号)
吉岡実は《緑の思想》をどう読んだのだろうか。「全世界は炎と灰だ/燃えている部分と燃えつきた部分だ/部分と部分の関係だ//部分のなかに全体がない/いくら部分をあつめても全体にはならない/部分と部分は一つの部分にすぎない」や「球体のなかにとじこめられている球体/たえまなく増殖したえまなく死滅する/緑色の球体」(#B_087、一二七~一二八ページ)といった〈緑の思想〉の詩句から触発されるものがなかっただろうか。ここで〈コレラ〉の定稿を引こう。
コレラ|吉岡実
戦争を考える 1
子供連れの男はルーマニア展へゆけ! 2
女中がめくるめく 3
下着の三色スミレの群落を見よう 4
翼ある毒物 5
肉のような絵が描かれて 6
あまねく拡がる霧の空 7
センニンカズラの葉が延びるのを刈るベランダの老人の 8
そのまわりから近代性を超え 9
未来へ至る 10
押し石が一つ欲しいよ 11
生理的な花咲く乙女 12
腸チフスで休校の庭は 13
棺のかたちの 14
人びとが列をつくるに快適な 15
オルガンを演奏する 16
兵士の断たれた手 17
それを見物する人たちがどこにいるのだろう? 18
ニンニクの肉房のように 19
忘却されている 20
火事のように地で燃えて 21
夜は単純な言葉を喋れ 22
ぼくの胸の上で灰色の猫がこうばこする 23
サクランボが七・八個赤い台所を通り 24
反自動的な書き方による詩の試み 25
愛の不在をたしかめ 26
手は手袋をはめ罠をはめ針金の上の骨をつまむ 27
それは流れそれは口をあける 28
その毛織物の下で 29
生まれる鉱物 30
人びとは誰のためにそれを鍛えるのか? 31
海鳥のように飛ばし 32
モグラのように恐怖の汗をかかせる 33
苔むす火薬庫の日の出 34
変りやすい書割り 35
靴屋・肉屋・パン屋・花屋そして管理人 36
必要な品を持って 37
夕焼の入江から歩いてくる 38
或は這って 39
反対に帰ってゆく 40
犬や洋服屋の針だらけのボデーがある 41
言語幻滅の治世に 42
水間という空間等価の世界があるとしたら 43
水中銃を撃て! 44
とぶ飛魚 45
やわらかな魚雷の内部の真珠母類 46
波にもまれる母親と赤ん坊 47
冷血・れいろうたる血 48
過去は王冠のギザギザに傷つく心 49
そこでカキフライを食べてあくびだよ 50
高層温室で眠るべくエレベーターで昇る 51
みにくい花嫁花婿 52
同時にブドウが熟れる 53
まず大切なのは水の飲み方 54
船の帆を墨染にする 55
海の上のコレラに罹らぬために 56
裸になって蝶のように 57
ゼンマイの口でしずしず水を吸うんだよ! 58
またはプラスチックの管で 59
かこまれてあらゆる廊下を走れ 60
球体からながれる藍の水 61
窓から今度は 62
セメント樽がおろされる 63
ぼくは詩句を書きながら 64
それを見ていればよいのだろうか? 65
〈金魚鉢をかかえて駈ける騎兵隊〉 66
途中でとまった 67
自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち 68
その卵の黄色い内部の霊媒を 69
たしかめて 70
コーヒーをのんで庭へ出て 71
明るい透明な巨人のゴムの木を伐る 72
そんな土の遊びをつづける 73
悪い私生活 74
雪ふる紐の首都 75
ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか 76
浴槽のなかで虎みたいに重い 77
シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる 78
あまりにも水が熱く 79
貝のなかの舌というものは乾く 80
モモイロのその舌がいくつにも裂けるよ 81
死声と雷の双曲線で 82
移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的 83
血の彫刻を仰げ 84
とうもろこしの堅い粒々で下痢する 85
ぼくたちはどんなデザインの勲章をつけて 86
廃校近い朝の運動場を駈け廻り 87
迷路・退路を進み 88
雨のアメリカのジャングルジムへ 89
しめなわを張り 90
いかなる幽霊の姿勢で 91
全員で吊りさがればよいのか? 92
男女の区別はなくなってほそくほそくなる 93
春きたりなば 94
離魂 95
これから何処へ 96
浮遊せんとする!! 97
《都市》創刊号には吉岡の詩(詩ではトップに掲載)のほかにも入沢康夫の〈声なき木鼠の唄の来歴〉などが掲載されており、それぞれ作者によるコメント(田村隆一の発案か)が付されているが、吉岡作品にはコメントがない。この素っ気なさはいっそ快い。さて、初出本文への手入れは二箇所。二四行め、〔七、八個→七・八個〕、七二行め、木偏だったのを人偏の「伐る」に変えたほかは、内容上の直しはない。ただし、末尾にあった脱稿日と思しい「〈一九六九・一〇・五〉」が削除されている。本稿のⅠで一九六九年発表の詩篇に触れたから、ここではこの年発表された散文を一覧しよう。
・二月 河原枇杷男句集《烏宙論》愛語抄(《琴座》226号)〔未刊行〕
・五月 『プロヷ〔ワに濁点〕ンス随筆』のこと(《文藝》)
・一一月 日記抄――耕衣展に関する七章(《琴座》235号)〔未刊行〕
〈日記抄――耕衣展に関する七章〉は、発表こそ一一月だが、内容はこの年七月に日本橋・三越で開かれた永田耕衣展(およびその準備)のことだから、〈コレラ〉執筆との関連は薄い。むしろ、ここで想起すべきは「一九六九年の九月二十四日は、私にとって忘れられない日になるかも知れない。」(#A_24、三四ページ)と始まる散文〈スペースカプセルの夕べ――奇妙な日のこと〉である。私はいまこれを《土方巽頌》から引いたが、これは初め《三好豊一郎詩集》(サンリオ、1975年2月15日)の栞〈人と作品〉に掲載され、後に《「死児」という絵》(#A_21)に収められた。初出は単に〈奇妙な日のこと〉という題で、たしかに三好のひととなりに触れてはいるのだが、大方の読者は吉岡実がただ一度三島由紀夫に会ったことを録した文章だと記憶しているだろう。吉岡は〈コレラ〉脱稿の一〇日ほど前に、三島と挨拶を交わしていたのだ。それが〈コレラ〉に直結していようはずはないが、そうした時期に書かれた詩篇であることは背景としておさえておきたい。
ではここで、〈コレラ〉を詳しく読もう。この詩は一〇〇行近くあって、詩句は「意識の流れ」に従って連想と断絶を繰りかえしながら進行していく。その間の機微を味わうために、あえて句読点を付けた散文形に詩句を書きなおしてみる。どこで改行してどのように段落を構成するかは、ひとつの読みを示すに違いない(各段落には便宜的に番号を振った)。それに対してコメントを付す。
一九六九年当時「戦争」といえば、ヴェトナム戦争だ。それを日本で「考える男」は特別な存在ではない。ならば「ルーマニア展」とはなにか。ルーマニア近代絵画の展覧会などではあるまい。おそらくルーマニアの物産(家具・ガラス製品・繊維製品等)展の類だ。ならばそこにゆく「戦争を考える子供連れの男」はだれか。話者が命じる対象は作中人物だが、発話の調子の高さからは読者をも巻きこんでいる気配がある。「めくるめく」はもちろん「目眩めく」だが、そこからは「女中がめくる下着」という音が響いてくる。それは意図したものだろう。文意は「女中がめくるめく三色スミレの群落」で、「下着」は挿入句、本題からは外れる。しかしそれが入ることで、紛れもない吉岡実の詩句となる。ヨーロッパには野生の三色スミレ(パンジー)があって、その基本色である黄・紫・黒の三色が組みあわさって多彩なパンジーの園芸種ができたという。その華やかさが「下着」を喚びおこしたともいえる。「翼ある毒物、肉のような絵」は謎めいた詩句だが、後年の吉岡がフランシス・ベーコンへの関心を語っていることを考えれば、まことに興味深い。視界は霧で狭まりつつある。センニンカズラ(仙人葛)はサトイモ科、ブラジル原産で、茎は蔓状に伸びる。園芸用にベランダで育てるのも難しくないようだ。このセンニンカズラ、光沢のある鮮緑色の葉の形が俳諧的だ。それを考慮に入れると、続く「押し石が一つ欲しい」は軽さを地上に繋ぎとめるための方策に思えてくる。はたして「乙女」は「女中」と同一人物か否か。
② 腸チフスで休校の庭は、棺のかたちの人びとが列をつくるに快適なオルガンを演奏する兵士の断たれた手。それを見物する人たちがどこにいるのだろう? ニンニクの肉房のように忘却されている。火事のように地で燃えて夜は単純な言葉を喋れ。ぼくの胸の上で灰色の猫がこうばこする。サクランボが七・八個赤い台所を通り、反自動的な書き方による詩の試み。最初の一文、「コレラ」のはずが「腸チフス」なのはどうしたことだろう。文脈も少なからずたどりにくい。だが、映像的にも音響的にも展開が明快なのは、「兵士の断たれた手」が①の「戦争」と「肉のような絵」を踏まえているからだ。このヒトデのような部位が葬送の調べを奏でる。「それを見物する人たち」とは、詩句内部の見物人であると同時にわれわれ読者でもある。だがかれらはひとしなみに「忘却されている」。そして「ニンニクの房」ですむところをことさら「肉房」と書くところに、私は①の残響を聴く。「燃えて」は状態を表わすのか、命令(続く「喋れ」のように)を表わすのかわかりにくいが、前者と取りたい。「夜は単純な言葉を喋れ」がひとつのまとまりをなしているから。ところで《僧侶》にあれほど頻出していた「猫」は、この《神秘的な時代の詩》には「美しき猫の分娩」(〈青い柱はどこにあるか?〉⑦・6)とここ「ぼくの胸の上で灰色の猫がこうばこする」にしか登場しない。「こうばこ」を手近な辞書で引くと「【香箱】香を入れる箱。香合(こうごう)」とあり、「こうばこする」は見あたらない。かつて「餌食する」(〈苦力〉④・13)という造語を成した吉岡であってみれば、ここも「においを発する」というほどの意味であろうか。「サクランボが七・八個赤い台所を通り」からは「七年ほど前に、二回分割で求めた、浜口陽三のエッチング〔正しくはメゾチント〕の佳作「白菜」」(#A_25、四五ページ)という記述を想起してしまう。むろん、浜口のカラーメゾチントのサクランボが存在するからだ。猫とサクランボが活動する夜、「反自動的な書き方による詩の試み」をする人物はこの詩の作者であろうか。
③ 愛の不在をたしかめ、手は手袋をはめ罠をはめ針金の上の骨をつまむ。それは流れそれは口をあける。その毛織物の下で生まれる鉱物。人びとは誰のためにそれを鍛えるのか? 海鳥のように飛ばし、モグラのように恐怖の汗をかかせる。苔むす火薬庫の日の出。変りやすい書割り。靴屋・肉屋・パン屋・花屋そして管理人。必要な品を持って夕焼の入江から歩いてくる。或は這って反対に帰ってゆく犬や洋服屋の針だらけのボデーがある。「愛の不在」の確認が「反自動的な書き方による詩の試み」なら、次に来るのは存在する事物以外にない。そこで古生物学者のような手つきで、魚のようでもあり獣のようでもある「それ」を扱うことになる。「毛織物の下で生まれる鉱物」は鍛鉄ででもあろうか。空に、地にその意志をあまねく広げんとする。そして遂に「火薬庫」が登場する。吉岡の書評〈富澤赤黄男句集《黙示》のこと〉から引く。
蛇よ匍ふ 火薬庫を草深く沈め蛇は私たちであり、赤黄男の自画像であろう。草にかくれた火薬庫は、「世界」の形相と見てもよいであろう。私たちは、そこを去るか、いつまでも匍い回っていることだろう。(#A_25、一一二ページ。初出は《俳句》1962年1月号)
吉岡実にはすでに「火薬庫から浴室まである/恋する絵」(〈恋する絵〉⑥・15)という詩句があるが、わたしがここで挙げたいのは(「火薬庫」こそ出てこないが)〈〔食母〕頌〉(⑫・19)の末尾(すなわち刊行された詩集の最後の詩句)の「(かげろうは消え/蛇はかえってゆく)/野の丈なす草むらに……。」である。赤黄男の蛇は〈コレラ〉の一場面から這いつづけて〈〔食母〕頌〉にまでたどりついたと思しい。それかあらぬか「犬や洋服屋の針だらけのボデー」は「這って反対に帰ってゆく」。「必要な品を持って夕焼の入江から歩いてくる」「管理人」はムンクの絵の人物のようだ。
④ 言語幻滅の治世に水間という空間等価の世界があるとしたら、水中銃を撃て! とぶ飛魚、やわらかな魚雷の内部の真珠母類、波にもまれる母親と赤ん坊。冷血・れいろうたる血、過去は王冠のギザギザに傷つく心。そこでカキフライを食べてあくびだよ。「言語幻滅の治世」とは言いえて妙ではないか。いったい〈コレラ〉には詩を書くことへの内省に充ちた詩句が散見されるが、この部分には詩人としての吉岡自身の言語だけでなく同時代の言語に対しても「幻滅」しているのだろう慨嘆が感じられる。しかも「水間という空間等価の世界」がその言語によって想定されており、ここからしばらく詩は水や海をめぐって展開する。水中銃の銛が水面を滑空し、飛魚へ、魚雷へと変じる。さらにそのなかの真珠母から母へ、乳児へと変じる。乳から血へ、冷と玲瓏が頭韻でつながり、血のあとに(心の)傷がくる。再び過去とカキフライの頭韻。ここであくびとなり、場面転換が訪れる。
⑤ 高層温室で眠るべくエレベーターで昇るみにくい花嫁花婿。同時にブドウが熟れる。まず大切なのは水の飲み方。船の帆を墨染にする、海の上のコレラに罹らぬために。裸になって蝶のようにゼンマイの口でしずしず水を吸うんだよ! またはプラスチックの管でかこまれてあらゆる廊下を走れ。球体からながれる藍の水。窓から今度はセメント樽がおろされる。ぼくは詩句を書きながらそれを見ていればよいのだろうか?「高層温室」がなにを指しているのかちょっとわからない。後段を読むと、ホテルかなにかのようだ。部屋に向かう新郎新婦と昇降機に乗りあわせた図か。「ブドウが熟れる」からはワインを想像するが、出てくるのは「水の飲み方」である。続いて「海の上のコレラに罹らぬために」「船の帆を墨染にする」。ようやくコレラの登場である。《平凡社 大百科事典》に依拠しながら、コレラの症状を摘すると、
コレラはコレラ菌が産生するコレラ毒素によって起こる、極めて伝染力の強い下痢疾患。経口的に摂取されたコレラ菌は、胃を通過し小腸に達すると盛んに増殖して毒素を産生し、腸粘膜上皮細胞膜の透過性を亢進させ、その結果、細胞内の水分および電解質が腸管腔へ多量に放出されて下痢の原因となる。重症の場合、腹部の不快感と不安感に続いて、突然の下痢と嘔吐で始まりショックに陥る。重篤な脱水症状を起こし、便は〈米のとぎ汁様〉で、白色ないし灰白色の水様便となり、多少の粘液が混じり特有の甘くて生臭いにおいがある。下痢便の量は一日一〇リットルないし数十リットルに及ぶこともある。激しい脱水症状のために皮膚の弾力が失われ、血圧下降・脈拍微弱・チアノーゼを呈し、四肢は冷たくなる。指先の皮膚には皺が寄り〈洗濯婦の手〉と呼ばれる外観を示すようになる。顔貌は目が落ち込み、頬がくぼんで〈コレラ顔貌〉を呈する。四肢の筋肉がときおり痛みを伴う痙攣を起こす。意識は正常のことが多いが、ときには昏睡状態に陥ることがある。口のかわき、声がれを訴える。(#B_170、一一七六ページに依る)
後段の記述は、土方巽による暗黒舞踏の舞台さながらである。そうすると、「水の飲み方」にも意味があることがわかるが、「船の帆を墨染にする」が民間伝承なのかそこのところはわからない。コレラの疾病史について、同書から引く。
コレラは元来インドのガンガー(ガンジス)川流域、とくに下ベンガル地域に盤踞していた風土病的性格の伝染病であった。ところが一九世紀の近代文明の進歩、とりわけ交通の活発化とともに、国際交流の波に乗って文明諸国に流行していった。つまりコレラのパンデミー(世界的流行)は、いわば世界の〈近代化〉の一現象ともいえる。〔……〕第二次大戦後、日本では一九四六年いわゆる〈復員コレラ〉として戦地から引き揚げてきた兵士たちが持ち込んだコレラが流行し、死者五六〇人にも達した。その後、日本からコレラは姿を消していたが、〔……〕(#B_170、一一七七ページ。数字や句読点の表記を改めた)
つまりこうである。コレラのパンデミーを避けるべく、身にまとうものすべてを脱ぎすて、中空に浮かびあがり、水分を補給するのだ。だれが? 「みにくい花嫁花婿」も「ぼく」も。しかし状況は予断を許さない。飲めるかどうかわからない「藍の水」に続いて「セメント樽」までやってくる。ほんとうに「詩句を書きながらそれを見ていればよいのだろうか?」
⑥ 〈金魚鉢をかかえて駈ける騎兵隊〉、途中でとまった。自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち。その卵の黄色い内部の霊媒をたしかめて、コーヒーをのんで庭へ出て、明るい透明な巨人のゴムの木を伐る。そんな土の遊びをつづける悪い私生活。雪ふる紐の首都。ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか。「〈金魚鉢をかかえて駈ける騎兵隊〉」の山型括弧は、これが初めての登場ではない。古くは《僧侶》の〈感傷〉に「〈わたしの妻は蟻の世界へ売渡される/溶けるもの かがやく裸形の砂糖の袋〉と口走る」という詩句があり、近くは《静かな家》の〈スープはさめる〉(⑥・11)に「〈肉にかこまれた星〉」、同じく〈孤独なオートバイ〉(⑥・14)に「〈くださいアスピリンを二錠〉」の詩句があった。一方、引用符としてははるかに一般的な一重鍵括弧(「 」)は、驚くなかれ〈コレラ〉が書かれた時点では詩句に使用されていない(のちに盛んに使用されることになる)。要するに、会話や強調のための符号として、吉岡実は山型括弧を採用したのだった。そのよって来るところは想像するしかないのだが、小説などで常用されるために、一重鍵括弧の使用を潔しとしなかったのではあるまいか。さて、金魚鉢は〈感傷〉に「金魚鉢の水の上で睡蓮が咲く」という印象深い詩句が、〈立体〉(⑦・3)に「彼らは紳士だから/フロックコートの正装のまま/存在するために/共同幻想体として/スイートな金魚鉢を支える」という詩句があった。〈コレラ〉のこのシーンはルネ・マグリットの画布を想起せしめる。いやむしろその画題を。だが「途中でとまった」この詩句は静止画ではなく、動画であることを思わせる。廃品芸術のような「自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち」、「その卵の黄色い内部の霊媒」は難句である。霊媒は「(medium)神霊や死者の霊と意思を通じ得る媒介者。巫女・神女・口寄の類」(#B_075、二三四二ページ)だが、吉岡には〈巫女――あるいは省察〉(⑤・14)や〈メデアム・夢見る家族〉(⑧・21)という詩篇があり、「それらの(霊媒[メデイアム])」(〈聖童子譚〉⑫・4)という詩句もある。牝鶏―卵(黄身)―霊媒、と時間と空間は逆流して、再び「私生活」に戻ってくる。「雪ふる紐の首都」は美しい。作品は終曲へと向かう。
⑦ 浴槽のなかで虎みたいに重い。シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる。あまりにも水が熱く、貝のなかの舌というものは乾く。モモイロのその舌がいくつにも裂けるよ。死声と雷の双曲線で、移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的血の彫刻を仰げ。「浴槽のなかで虎みたいに重い」のは自分の体だろうか。〈鄙歌〉の「部分からその全体が現われるまで/甲冑を洗え!」から「シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる」を推し量ると、「妻」の「部分」と「全体」が「甲冑」をまとってたたずんでいる。「貝のなかの」「モモイロのその舌」は貝であると同時に妻の肉体の一部でもあるようだ。「死声と雷の双曲線」も難句である。音響としての「死声と雷」と、形態としての「死声と雷」つまり稲妻型の「双曲線」の二重映しであろうか。「移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的血の彫刻」という禍禍しい姿が、この詩の頂点のように出現する。
⑧ とうもろこしの堅い粒々で下痢する。ぼくたちはどんなデザインの勲章をつけて、廃校近い朝の運動場を駈け廻り、迷路・退路を進み、雨のアメリカのジャングルジムへしめなわを張り、いかなる幽霊の姿勢で全員で吊りさがればよいのか? 男女の区別はなくなってほそくほそくなる。「赤塗りのトウモロコシの/とさかをなびかせよ!」(〈フォークソング〉⑦・7)「だからトウモロコシ畑のうしろへ/廻って」(〈雨〉⑦・9)と、玉蜀黍は《神秘的な時代の詩》でもその姿を見せていた。ここは玉蜀黍の生食で下痢をしたのか。さらに「どんなデザインの勲章」といい「いかなる幽霊の姿勢」といい、本篇において最も激烈な詩句が続く。「四人の僧侶/固い胸当のとりでを出る/生涯収穫がないので/世界より一段高い所で/首をつり共に嗤う/されば/四人の骨は冬の木の太さのまま/縄のきれる時代まで死んでいる」という〈僧侶〉(④・8)の最終節は、ここでは脱水のあげくの脱力に変じ、「縄のきれる時代まで死んでいる」「冬の木の太さのまま」の「四人の〔僧侶の〕骨」の硬さの欠片も見られない。おそらく「しめなわ」が切れるまえに「ぼくたち」は消滅するだろう。
⑨ 春きたりなば離魂。これから何処へ浮遊せんとする!!ここでもう一度〈僧侶〉と〈コレラ〉の最終部を比較対照する。
四人の僧侶 : ぼくたちはどんなデザインの勲章をつけて中世の暗黒の世界から現代の薄明の世界へ、という対照は意図されたものであろう。冬のあいだじゅう、死ぬこともできずに注連縄に吊りさがる幽霊姿の「ぼくたち」には、僧侶への道は堅く閉ざされている。《神秘的な時代の詩》の結句「春きたりなば離魂/これから何処へ浮遊せんとする!!」こそ、真の意味で「神秘的な時代」の幕引きであった。〈コレラ〉には、世界をひとつの総合的な像として把握して、ときにそれを肯い、ときにそれを否むという《僧侶》に始まる確固とした認識=方法論から最も遠い(そう呼んでもよいのなら)世界がある。作者自身を含めて、この詩を読む者は「戦争を考える子供連れの男」として、一九六〇年代末の(日本とは言わず)ある状態が音もなく崩れていくのを、目を見開いて聴くことを強いられるのだ。それは⑦の「とうもろこしの堅い粒々で下痢する」からも容易に連想される吉岡実の傑作〈下痢〉(⑤・3、初出は一九五九年八月、《鰐》創刊号)の消失感と通じる。
下痢|吉岡実ぼくは下痢する のぞむところでなく 拒む術もなく 歴史の変遷と個人の仕事の二重うつしの夜にまぎれて ぼくは下痢する 紅いろの花と 薄月の空をそめる痰の吐かれる地下室の水 それはぼくだけの現象だろうか 今日もそれをする昨日もしたんだ 考えれば昔の記憶のなかの青い膚のとうがんの内房を覗きながら 下痢はぼくらの日常の習慣 洗いたての世界の便器が集められる ぼくの下痢はぼくの精神を飲みくだし 他人の多くの心へ伝達され 飢えの大衆の糧を腐らせてゆく そのときから寝そべる老若男女のむれ そのささやかな声 そのいじらしい手足の運動 それらの生きている証拠の排泄の愛 誰もが流木の位置 ぼくはどこかもう少し高いところから 直接灰をかぶる 被虐的な食事をするため 馬や犬の経験もしないであろう 滑稽な形而上の下痢をする 力なくむしろ生きることを認証する 痛みの導くところ 雷の格闘の終りの空間に聳える塔をみる ぼくの死すべき肉体の鳴りひびく殉教の血のながれの高まる時 ぼくは下痢する 耕される傾斜の土地に 汲まれる泉の絶えざる岩や石の下に 永久に心の内乱の契機の腸を断つ ぼくは忘れられる ぼくは人と物を忘れる 仮設のなかにめぐりあった交友だから 寒冷な下痢する近代の醜悪なかがまる催眠状態をぬけ 回復する驚異な暗が次元を替える 中心に自然の光の接触をくりかえす 二十世紀の庭に ぼくは総合体として健康な男の一人になる まず梨から食いはじめる ここに新しい関係・対話がはじまる
「二十世紀の庭に ぼくは総合体として健康な男の一人になる」という宣言に見られるように、ここには再生への希望がきざしているが、一〇年後の〈コレラ〉にはもはやそれさえない。あたかも〈僧侶〉―〈下痢〉―〈コレラ〉と「病状」は深刻化していくようだ。
ここでどうしても、吉岡実の「休筆」に触れないわけにはゆかない。吉岡自筆〈年譜〉の「昭和四十四年 一九六九年 五十歳」の全文はこうだ。
田村隆一編集の季刊詩誌『都市』へ詩「コレラ」を寄せる。この時期の作品を、妻に批判されて憤然とする。これより約二年間、詩篇を発表せず。(#A_23、二三三ページ)
抑えた書き方だが、〈コレラ〉のあと約二年間(厳密に言うと翌一九七〇年に〈低音〉が発表されているが、いまは吉岡の記述に従う)、詩篇を発表しなかったことに想いを致すべきである。そのせいかどうか、吉岡は一九八〇年、金井美恵子との気のおけない対談で、詩作の方法を語りつつ、問わずがたりに〈コレラ〉誕生の秘話を明かしていた。
吉岡 〔陽子夫人が原稿を清書することによって〕言ってみればほぼ活字体になってる、それを眺めつつ、またそこに書きこんで行く。その繰り返しが、物によっては何日も繰り返されて行く、そういう形でぼくの詩はできている。
金井 そのへんの推理〔「推移」の誤記か〕、変わり方を一番よく御存知なのは奥さんの陽子さんということになるわけですね。
吉岡 そうなの。それで全部放棄したかって言うと現在破いてなくて案外とってある。ただ、それをあえて読者の眼にさらすこともないんだし……。
金井 それは実に見てみたい(笑)。
吉岡 いや、それは人に見せられないひどいものよ。作家というのは自分が第一の鑑賞者になるけど、うちの場合は家内だね。だから笑い話になるけど、家内がある時期、『神秘的な時代の詩』をずうっと写しているでしょ。家内はかねてからにがにがしく思っていたんだって、こんな散漫な詩をどうして書いているのかって、あの中の最後の「コレラ」ができた時に初めて「いい詩ができたわね」と言ったんだ。それで他のはみなよくないって言うわけよ。ぼくとしては「わが馬ニコルスの思い出」ぐらいは認めて欲しかったね。これは大変な喧嘩で夫婦の危機の一大事(笑)。こうなったら心中でもしようかと目張りまで用意したと、後年、家内から聞いて、笑うやら、ぞっとするやら。(#C_010、九九ページ)
一〇年経てば笑い話だろうが、執筆当時、⑨の「これから何処へ浮遊せんとする」は笑い事ではなかっただろう。詩作のうえの手詰まり状態に加えて、制作における最も身近な協力者とも言うべき存在からの否定的評価。それは詩人本人がはっきりと自覚していないながら、いやむしろ実際はおそらくそこはかとなく感じていただけに、予想以上の痛撃となったのではあるまいか。同時に〈コレラ〉のような方法では、もはやこれよりもすぐれた作品は成しようがないと実感したがゆえの「休筆」ではなかろうか。
もっとも私は、後に詩集《神秘的な時代の詩》としてまとめられる作品を吉岡実が書きついでいた時期の作品として、〈コレラ〉がその最高の達成だとは必ずしも思わない。むろん、力篇には違いない。しかし、《神秘的な時代の詩》に関して言えば、「篇」として個個の作品を論うことに格別の意味があると思えないのだ。これらの作品は、その総体として、あたかも長篇詩の一節(それぞれの節にはそれぞれの標題がついているのだが)のように読んで初めて、作者の意図を超えたこの作品が内包している禍禍しい姿を顕わすのではあるまいか。沈黙の二年のあと、その産道を潜りぬけたあかつきに新たな局面が待ちうけているのだが、詩集《サフラン摘み》期の作品の口火を切る詩篇〈葉〉(④・4)までの道のりはまだ遠い。
きわめて、世俗的現象を巻き込み増殖する柔軟な詩法――吉岡実(#A_25、一九〇ページ)
前回の詩篇〈コレラ〉(⑦・18)のあと、約二年間、吉岡実は詩篇を発表しなかった――とはしばしば見かける記述だが(たとえば、吉岡自筆の〈年譜〉一九六九年の項)、実際には〈コレラ〉の翌一九七〇年三月に〈低音〉が《風景》(一一巻三号)に発表されており、正確ではない。《風景》は悠々会発行の月刊誌で、なにかの事情で〈低音〉の掲載や雑誌の発行が遅くなったとは考えにくいから、この〈コレラ〉と〈低音〉を吉岡がどうとらえていたかは考察に値する問題である。ところで、吉岡はこの《風景》にしばしば作品を寄せているので、一覧してみる。
・一九六一年二月 鎮魂歌(⑤・15)
・一九六六年三月 春のオーロラ(⑥・10)
・一九六八年三月 好きな場所〔散文〕
・一九七〇年三月 低音(⑦・14)
・一九七二年六月 ヒヤシンス或は水柱(⑧・3)
・一九七四年三月 父の面影――さがしもの〔未刊行散文〕、五月 絵画(⑧・18)
初登場は創刊(一九六〇年一〇月)の翌年。一九六六年からは二年に一度は登場しており、一九七四年には二度、寄稿している(なお、《風景》は一九七六年四月号で終刊)。五つの詩篇は詩集《紡錘形》《静かな家》《神秘的な時代の詩》《サフラン摘み》と連続して収録されており、吉岡もこれらの作品には自信をもっていたはずだ。さて、私の手許に吉岡実が家蔵していたスクラップブック(コレクト製で品番「S―101」の「SCRAP BOOK」)のコピーがある。以下にその概要を記してみる(〔 〕内は、吉岡陽子夫人による掲載紙誌等の記載)。
・詩篇〈ヘアー〉〔〈文学界〉44・12月号〕
・詩篇〈低音〉〔〈風景〉45・3月号〕
・入沢康夫〈グループから離れて――源流に峻立する吉岡実〉〔〈東京〉45・5・4〕
・金井美恵子〈「この詩人、鳥だな」――猫は粘稠質の液体包み〉〔〈読書〉45・7・13〕
・滝本明〈陸封された語――吉岡実「突堤にて」〉〔〈読書〉46・1・1〕
・渋沢孝輔〈詩壇時評――なぜ沈黙する戦後詩の旗手〉〔〈東京〉夕刊46・7・1〕
・散文〈小鳥を飼って〉〔〈ユリイカ〉1971・4月号〕
・滝本明〈表出への原基――夢を殺した血の系譜〉〔〈読書〉46・7・5〕
・未刊行散文〈風信〉〔〈東京中日 夕刊〉47・8・1〕
・天沢退二郎〈詩壇時評――沈黙批判は核心を誤るな〉〔〈東京〉夕刊46・11・4〕
・清水康雄〈詩人図鑑――汎神論的エロティシズム〉〔〈図書〉48・2・17〕
・散文〈「死児」という絵〉〔〈ユリイカ〉1971・12月号〕
・散文〈飼鳥ダル〉〔〈朝日〉夕刊〕昭和48年(1973年)6月2日
・岡田隆彦〈ブック・ストリート――装幀家・吉岡実〉〔〈出版ニュース〉6月上旬号 1973〕
ここからもわかるように、前回取りあげた詩篇〈ヘアー〉のあと、詩は〈低音〉一篇のみで、以降は散文や他者による吉岡実論しか収められていない。これらの論を吉岡がどのように受けとったかは興味あるところだが、今はこれ以上触れない。いずれにしても、詩作のない内省の季節が続いたわけだ。それに先立って、吉岡は一九七〇年初めには〈低音〉の原稿をまとめている。ただ、その淵源が一九六九年一〇月発表の〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)だとすることは許されるだろう。確認のために、再びその最終〔第五節〕を読んでみる。
すえながく生きつづける仮想の敵
ブランコのりの子供たち
わが馬ニコルスが荷車に積まれて
行った河と時を記憶せよ!
空鳴りの肉色の鉄橋の弧のかたちを破壊し
消滅する
わが馬ニコルスの水色の大きな瞳孔の
ふたたびまばたくまで
潜在的世界には
犯罪的な言葉が屹立する
〔第五節〕の「仮想の敵」から、まず「少女こそぼくらの仮想の敵だよ!」と始まる〈聖少女〉(⑦・10)が書かれた。さらに「ブランコのりの子供たち」から「ブランコのりの少女がひとり」と書きおこされる〈低音〉が生まれたことは〈わが馬ニコルスの思い出〉の評釈時に述べた。しかしなぜ「子供たち」が「少女がひとり」に変じたかは、〈わが馬ニコルスの思い出〉と〈低音〉の二篇を見るだけでは判らない。それに関しては、次のⅡで考察することにする。
最初に詩篇〈低音〉の定稿を引く。
低音|吉岡実ブランコのりの少女がひとり 1
辻公園にいる 2
とわたしは想像し 3
肉体と紐を使って 4
苦い荷をはこぶんだよ 5
方解石 6
漆 7
いまとびあがる少女の薄布の 8
支離滅裂の 9
尻を大写しで見よ 10
その移動することだま 11
発光する水晶でなければ 12
それはプラスチック 13
木の球 14
花嫁 15
みずみずしく 16
防疫人が調べる 17
輝かしい孔類 18
それは点になるまでコイルで巻かれて 19
青空へ至るんだ 20
母恋うる声 21
向うを老人や草刈機が通り 22
わたしが通る 23
初出との異同は次の三箇所。初出一〇行め「尻を大写しで見よ!」、一一行め「その移動することだま?」、二〇行め「青空へ至るんだ!」の感嘆符・疑問符が、定稿ではみな削除された。ここで問題となるのは二番めの疑問符の削除だが、詳しくは以下の逐行の評釈で触れることにする(初めに、文意に応じた散文型を掲げる)。
「ブランコのりの少女がひとり辻公園にいる、とわたしは想像し、肉体と紐を使って苦い荷をはこぶんだよ」――「すえながく生きつづける仮想の敵/ブランコのりの子供たち」のうちの一人の少女が辻公園にいるとするよりも、無人であるはずの辻公園に人がいることが驚きをもって想像されるのでなければこの詩は始まらない。〈わが馬ニコルスの思い出〉の「ブランコのりの子供たち」は〈僧侶〉(④・8)の「非常に高いブランコに乗り/三人が合唱している」「僧侶」を想起させる。
「方解石、漆」――これは難句である。無色透明・玻璃光沢の方解石と、乳白色から褐色に変じる粘稠液の生漆。詩句の流れからすれば「苦い荷」の実体がこれだが、硬くて透きとおったものから、どろりとした色の着いたものへの変化をわずか二語で描いた、と取るのがいいか。
「いまとびあがる少女の薄布の支離滅裂の尻を大写しで見よ」――やや長い引用になるが、ジェイムズ・ジョイス《ユリシーズ》の〈〔13 ナウシカア〕〉の一節を読んでみると、吉岡実詩との類縁に驚かざるをえない。
彼女は思い切りそり返って花火をながめながらうしろに倒れないように両手で片膝をかかえ、彼と彼女のほかに誰ひとり見ているひとはないのですからなよやかに柔かく繊細にふくよかな、形のいい優美な両脚をあらわにしたのですが、〔……〕そしてジャッキー・キャフリーが、ごらんよ、またあがったよと叫び彼女は上体をそらして透きとおった靴下によくうつる青い靴下留が覗[のぞ]いてみんなが見あげながらほら、あそこにと叫び彼女が花火を見るためにますますそり返ったとき何か奇妙なものが空中をここかしこと飛びまわるのが見えました、なんだか柔かい黒い影が。そして長いローマ花火が一つ木立を越えて上へ上へと昇ってゆくのが彼女の眼に映り、みんなは張りつめた沈黙のうちにそれが空高く昇りつめてゆくのを眺めながら興奮のあまりに息を殺し、高く、高く、ほとんど見えなくなるまで昇ってゆくのを追うために彼女はますます弓なりにそり返り、無理にそったために彼女の顔には神々しい魅惑的な赤味がさし、ほかにもいろいろなものが見え、肌を愛撫する印度モスリンのズロースは四シリング十一ペンスの緑いろの下着よりも白地なのでずっとよく見えるし、彼女は隠そうともせず彼の視線を感じているうちに非常に高く昇って一瞬見えなくなってあまりそり返ったために彼女の手足は震えはじめブランコに乗ったり浅瀬を渡るときでもまだ誰の眼にも触れたことがないくらいずっと膝の上まで完全に彼に見えてそれでも彼女は恥かしいとも思わず、彼のほうもあんなに露骨にまじまじと見つめて恥かしくなかったのは紳士たちの眼の前で露骨にふるまう踊り子たちがどうぞ見てくださいとばかりにさし出すのと同じでこの驚くべき露出を前にして彼は眼をそらすことができず貪[むさぼ]るように眺めて眺めつづけたのです。(#B_072、二九~三一ページ)
私はこれを一九六四年刊の丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳から引いた。吉岡実はジョイスに関してなにも書きのこしていないが、この訳文で《ユリシーズ》に触れた可能性は極めて高い(吉岡は丸谷から一本を贈られたかもしれない)。そして《ユリシーズ》を読む吉岡が〈〔13 ナウシカア〕〉に期待しただろうことは、想像に難くない。「いまとびあがる〔ブランコのりの〕少女」の「尻」が、美少女ガーティ・マクダウエルの「なよやかに柔かく繊細にふくよかな、形のいい優美な両脚」や「ブランコに乗ったり浅瀬を渡るときでもまだ誰の眼にも触れたことがないくらいずっと膝の上」とともに(しかも、支離滅裂に)クローズアップされるこのシーンは、吉岡実の独壇場と言っていい。
「その移動することだま、発光する水晶でなければ、それはプラスチック。木の球。花嫁」――この五行こそ吉岡実の詩作の粋とも言える華麗な展開部である。まず「いまとびあがる少女の薄布の支離滅裂の尻」を「移動することだま」と受けておいて、同時にいくぶん〝幽体化〟する。こうすることで尻はブランコのりの少女から離れて、あたかもマネキン人形の腰部のようにそこだけとなり、次の自在な変貌を準備することになる。六行めの「方解石」の残響のように「発光する水晶」が登場し、それは「プラスチック」に劣化し、さらに「木の球」と化す(ここは〈聖少女〉のハンス・ベルメールの関節人形を思わせる)。そこから大きくジャンプするようにして、詩句は「花嫁」へたどりつく。体言止めに否定の仮定をからめた語法が特別なわけではない。一行一行、一語一語見てゆけば異様なものはどこにもないのに、連続して、それもかなりのスピードで読みくだすとそこには言語でなければ描けないイメージの連なりが顕われる。これこそ吉岡が「今後は、言葉としてはわかりやすく、内容はよくわからないもの、もどかしくてゾッとするもの、俗性をまといつつも高いものができたらと思います」(#A_10、一四五ページ)と語った、その輝かしい成果であろう。一一行めが初出の「その移動することだま?」だと疑念が強すぎて、定稿のような物体=イメージのうねりが出ないこと、言うまでもない。
「みずみずしく防疫人が調べる輝かしい孔類」――「防疫人」とは見なれないことばだ。伝染病の発生を予防しその侵入を防止する人、とはだれか。「少女」か「わたし」か、それとも「花嫁」か。おそらくそのいずれでもないだれかだ。伝染病からは前作〈コレラ〉を思い出さないわけにゆかない。だとすれば「輝かしい孔類」は、粥状の便にまみれた「花嫁」の肛門を聖化しているとは読めないだろうか。
「それは点になるまでコイルで巻かれて、青空へ至るんだ」――「肉をラセン巻きにするガードルに沿って/まばゆい丘の上に出ると/馬の交尾」(〈少女〉⑦・5)とあったように、身体を細いもので巻いてどこかへ連れさる行為が、詩篇の頂点を形づくっている。そういえば、「わたし」も「紐を使って/苦い荷をはこ」んでいた。のちには「すでに秋/自転車のチューブのようなもので/全身を巻かれ/雨のなかに立って/馬がいるじつに寂しく」(〈あまがつ頌――北方舞踏派《塩首》の印象詩篇〉⑧・30)と始まる力篇がある。
「母恋うる声」――詩集《薬玉》(#A_22)には「「心は閑[しず]かにして 目を遠く見よ」/母恋いのちりめん模様の空のもとをさまよう」(〈竪の声〉⑪・2)と「母恋うる夕べ/わたしは数珠玉を刈り/巫女の膝の門をくぐりぬける/青蛙を踏んだ」(〈青枝篇〉⑪・4)という具合に母恋が登場するが、二一行めは「声」である点が注目される。天の奥底から「花嫁」が発したものだろうか
「向うを老人や草刈機が通り、わたしが通る」――「辻公園」の「向う」を通るのだろう。植物を刈る老人は吉岡の詩にしばしば登場する。「紅紫のヒースの荒野へ/芝刈機をゆっくり/押して行く/ひとりの老婆を見たことがある?」(〈スープはさめる〉⑥・11)。「自在に無意味に褐色の床から天井へ/横断する横断する/電気芝刈り機/ニクロム線の庭」(〈崑崙〉⑦・8)。「あまねく拡がる霧の空/センニンカズラの葉が延びるのを刈るベランダの老人の/そのまわりから近代性を超え/未来へ至る」(〈コレラ〉)。だが、ここでは老人と草刈機は別々に(少なくとも老人が草刈機を押すのではなく)現われる。草刈機は「わたし」が押しているのではあるまいか。スクリーンをまず老人が横切り、しかるのちに草刈機が姿を見せ、それを操作する人物が通る。場面が暗転してなお、かすかな機械音があたりを満たしている。こうして、吉岡実は〈低音〉を最後に、約二年間沈黙することになる。
吉岡実には〈低音〉の後日譚のような〈自転車の上の猫〉(⑧・15)という作品がある。
自転車の上の猫|吉岡実闇の夜を疾走する 1
一台の自転車 2
その長い時間の経過のうちに 3
乗る人は死に絶え 4
二つの車輪のゆるやかな自転の軸の中心から 5
みどりの植物が繁茂する 6
美しい肉体を 7
一周し 8
走りつづける 9
旧式な一台の自転車 10
その拷問具のような乗物の上で 11
大股をひらく猫がいる 12
としたら 13
それはあらゆる少年が眠る前にもつ想像力の世界だ 14
禁欲的に 15
薄明の街を歩いてゆく 16
うしろむきの少女 17
むこうから掃除人が来る 18
同じ「想像力の世界」(一四行め)を描いて、吉岡は次の詩集《サフラン摘み》(#A_17)ではかくも自在な境地に達している。〈低音〉の結末さながらに、結語の「むこうから掃除人が来る」が、この愛すべき詩篇を鮮やかに締めくくる。
君の名は、私の詩の中で永遠になったのだ――西脇順三郎(#A_25、二二五ページ)
吉岡実の詩篇〈弟子〉(⑦・15)は、政治公論社の季刊詩誌《無限》第二九号(一九七二年八月一日)に掲載された。この号は西脇順三郎の総特集で、西脇の新作詩篇〈桂樹切断〉のほか、献詩(一一篇)、詩人論(一八篇)、作品論(一一篇)、二つの座談会(一方には西脇本人も出席)、六〇人が稿を寄せた随想〈西脇順三郎と私〉から成る。編集は鍵谷幸信と慶光院芙沙子。献詩の作者と標題を挙げる。会田綱雄〈地獄谷〉、飯島耕一〈ルッソーと西脇さんの帽子〉、岡崎清一郎〈西脇順三郎先生〉、加藤郁乎〈Credo――西脇順三郎詩伯に〉、草野心平〈或る永遠〉、慶光院芙沙子〈詩人なりせば――西脇順三郎氏に捧ぐ〉、多田智満子〈秋の詩人――西脇順三郎先生に〉、田村隆一〈灰色の菫――西脇順三郎先生へ〉、瀧口修造〈青い羽根のあるコラージュ文――西脇順三郎氏に〉、村野四郎〈ゴムの木の下――西脇順三郎氏に〉、そして吉岡実〈弟子〉である。「西脇順三郎氏」であったり「西脇順三郎先生」であったりするが、献詩であることを謳った詩が多いことに留意しつつ、〈弟子〉の初出形を読もう。
弟子それは違った意味に使われる
言葉
笊のように
晩夏へ向うよ
淡黄色
見えなくなったら
ハツラツとして
眼薬をさす男
砂かぶりの丘をゆき
職業を意識する
この世に歌があるだろうか
たとうれば
草上の露命
〈永遠とは今の現在のこと〉
だから心は重く
死んだカモのように
岸べに寄る
われわれには切ない
私生活があって
紐のすべてが濡れているように
円にかこまれる
紺染のはるかなるアザミ
花瓣的な奥深いものを信仰というのか
われわれは明晰でありうるか
疫神の午後
紅藻類のなかで娘をみつけて抱く
力ない血祭
どこから起伏せるなやましい大理石
吹きながしのチリメンの鮮緑色群
たたずめばスルメの足
過ぎれば燐
戻れば雪の嶺が見え
わずかに
夢みる鋸歯の海を
ラジィカルに泳ぐ
老人をたたえよ
そして箴言集をみよ
「便所はどうして神秘的に
高い処にあるのだ」
女神の水色のスミレの酢を求めて
梯子をよじのぼる唯一の弟子
さて簀子は乾いた!
春は曙
牛乳屋が来る
ご覧のように、〈弟子〉が西脇順三郎に宛てた詩であることは、他の一〇篇とともに目次(中面の別刷と表紙)に〈献詩〉とくくられている以外、どこにも誌されていない。ところが吉岡はのちにこう書いている。「私はいつか西脇先生に捧げる詩を書かなければならないと考えていた。なぜかというと、今から六、七年ほど前、「無限」の西脇順三郎特集号に、〈弟子〉という短い詩を書いて献げていた。当時考えるところがあって、私は二年間ほど詩作を止めていた。そんな精神状態のなかで書いた詩なので、詩集《神秘的な時代の詩》を編むとき、先生への献詩である詞書を、削除してしまったのである」(#A_25、二三六ページ)。本篇は〈弟子――西脇順三郎先生へ〉だったかもしれないわけだが、田村隆一〈灰色の菫――西脇順三郎先生へ〉ならともかく、吉岡実〈弟子――西脇順三郎先生へ〉ではあまりにつきすぎてはいないか。結果的にそうならなかったことに私は安堵する。初出は何箇所か手を入れられて、詩集《神秘的な時代の詩》では次のようになっている。
弟子|吉岡実01 それは違った意味に使われる
02 言葉
03 笊のように
04 不可解なるもの
05 淡黄色の夕陽のなかで
06 見えなくなったら
07 ハツラツとして
08 眼薬をさす男
09 砂かぶりの丘をゆき
10 職業を意識する
11 この世に歌があるだろうか
12 たとうれば
13 草上の露命
14 〈永遠とは今の現在のこと〉
15 だから心は重く
16 死んだカモのように
17 岸べに寄る
18 われわれには切ない
19 私生活があって
20 紐のすべてが濡れているように
21 円にかこまれる
22 紺染のはるかなるアザミ
23 花弁的な奥深いものを信仰というのか
24 われわれは明晰でありうるか
25 疫神の午後
26 紅藻類のなかで娘をみつけて抱く
27 どこから起伏せるなやましい大理石
28 力ない血祭の終りは
29 吹きながしのチリメンの鮮緑色群
30 たたずめばスルメの足
31 過ぎれば燐
32 戻れば雪の峯が見え
33 わずかに
34 夢みる鋸歯の海をラジィカルに泳ぐ
35 老人をたたえよ
36 そして箴言集をみよ
37 「便所はどうして神秘的に
38 高い処にあるのだ」
39 女神の水色のスミレの酢を求めて
40 梯子をよじのぼる唯一の弟子
41 さて簀子は乾いた!
42 春は曙
43 牛乳屋が来る
異同を整理すれば、①「晩夏へ向うよ/淡黄色」→「不可解なるもの/淡黄色の夕陽のなかで」、②「力ない血祭/どこから起伏せるなやましい大理石」→「どこから起伏せるなやましい大理石/力ない血祭の終りは」、③「夢みる鋸歯の海を/ラジィカルに泳ぐ」→「夢みる鋸歯の海をラジィカルに泳ぐ」が詩句上の変化で、④「花瓣」→「花弁」、⑤「嶺」→「峯」が字句上の変化である。詩句上の変化はおおむね前後のつながりをよくするための改変だが、④はどう考えればいいのだろうか。吉岡の入稿原稿を見ることができないので想像するしかないのだが、原稿には「花瓣」と書いてあったに違いない。瓣の字は両側の辛が瓜をはさんでいる。吉岡は三行めの笊(爪であって瓜ではないが)にひっぱられて、ふつうなら花弁と書くはずのところを花瓣と書いたのではあるまいか。⑤は④を受けて、画数の少ない、左右対称に近い字になったものと思われる。
いきなり「それ」が文頭に来ている。指示するものはあとで出てくるかもしれないが、読者にとって、まず「弟子」がそれの内実かと思われる。「〈弟子〉は違った意味に使われる言葉」。弟子ではない弟子? という疑問で詩は始まる。ここで想いだされるのは〈雨〉(⑦・9)冒頭の「それはたとえば/老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの/スイ星の球のつまった/箱をさがす」である。詩集では〈雨〉の方が先に出てくるから、「ああ、またか」と軽く流してしまいそうだが、断定であるだけに〈弟子〉の始まりは荘重でさえある。
笊。吉岡実の作品に登場する笊、ざるを引く。
笊に充たされた青蜜柑。一方、むなしく伏せられた笊のごとき存在。ざるをかざせばさるすべりの紅。天狗の面やおかめの面が掛けられた粗い壁、濡れた笊。これらこそ「不可解なるもの」? のちの詩篇〈楽園〉(⑨・1)に「私は不可解な麩という食べものを千切り」とあるが、小説家の中上健次は〈翻訳した詩〉(初出は《ユリイカ》一九七六年一一月号)というランボーをめぐるエッセイで〈楽園〉をこう「翻訳」している(#B_099、二五一ページ)。
俺は引用した。
張りつめた樹皮のオルガン
空っぽの空は黄金のザイルだ
百千の花菖蒲
翼の折れた鳥はこの夏に焼かれた
俺の舟は
純粋の、純金の海にいま裂けた
俺は不可解な麩という食べものを千切り喰い
かかる時、地の上に何が遺るか、俺に啓示を与えたのは誰か
水の上に何が浮ぶか
幾つもの岩石の
灼った黄金の
黄金なる
謎[エニグマ]
沖に在る溺死体、その閉じた
黄金の眼
太字化は中上によるもので、吉岡の詩を引きうつした部分である(一部、吉岡詩の雑誌掲載原文と異なる)。吉岡実のものとも中上健次のものともつかない奇妙な詩篇というべきだが、興味深いのは「不可解な麩という食べものを千切り」が、あたかも触れてはならない聖餐ででもあるかのように、そのまま手つかずで残されていることだ。笊もまた、不可解にして不可触のものだった。
前掲〈衣鉢〉は「たたみの黄いろ」という一行で開始されたが、ここでは「淡黄色の夕陽」に笊の形と色が引きつがれている。「見えなくなったら」「眼薬をさす」というのならわかるが、そこに「ハツラツとして」が入ると、係りぐあいが妙にねじれて、同時にえもいわれぬ滑稽さが醸しだされる。
かつて〈ヘアー〉(初出は《文學界》一九六九年一二月号、のちに〈鄙歌〉と改題改稿して拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》に収録)に「砂かむり」が出てきた。〈ヘアー〉の前半を引用しよう。
わたしの好きな常套句の引用
ヘアーの下の果実
ヘアー
そこでは恐怖の麩を煮つめて
ヘアーの黄金の下で身もだえする恋人
枯木のかげへ入り
ヘアー かみにくい皮を噛み
固い函で未熟なイチゴをかこむ
部分からその全体が現われるまで
甲冑を洗え!
そこにはどんな形態の蛇が赤い舌を出す
あるいは砂かむりで
花咲く母の吸盤が見えるか?
〔……〕
なんと〈楽園〉に似ていることか。それと同時に〈コレラ〉(⑦・18)にも似ているが。もしかすると、吉岡は〈ヘアー〉を〈鄙歌〉と改題改稿する一方で、〈ヘアー〉を(中上健次がしたように?)書きかえて〈楽園〉をつくったのかもしれない。その背景には〈弟子〉が扇の要のように存在している。
「草上の露命」は典拠がありそうな詩句だが、不明にして西脇からは該当する章句を見出せなかった。――後年の吉岡の詩篇には次のものがある。「あけぼのや七人七夢にらの露」(〈垂乳根〉⑪・12)――。しかしこの詩は西脇順三郎に宛てて書かれたものである。詩句は当然、西脇に旋回してゆく。
この山括弧は引用符である。「永遠とは今の現在のこと」という詩句は西脇順三郎の文章に容易に見つかりそうなものだが、私の探し方が悪いのか、未だに発見できない。しかしこの詩句が西脇の書きつけた文であろうがなかろうが、西脇なら言いそうだということがわかれば、ここではそれで充分なのだ。仮に「西脇ならこうも言うだろう」と吉岡が考えて作ったものであったとしても。
「永遠」=「今」「現在」だから、心は重い。力なく水に身をまかせる鴨の死体が、岸辺に打ちよせられるように。
前後の文脈を考えると「死んだカモのように岸べに寄るわれわれ」と係るところだ。現世の短さ(草上の露命)と長さ(永遠)を同時に併せもつ「現在」を生きざるをえない「われわれ」。だからその「私生活」は「切ない」のだ。
「悪い私生活/雪ふる紐の首都」(〈コレラ〉)といい、この詩句といい、「私生活」と「紐」が対になって登場するのはどうしたわけだろう(「紐の首都」は紐育を想わせる)。紐といえば、吉岡は河原枇杷男の句「西方を紐来つつあり巻貝在り」(句集《閻浮提考》、序曲社、一九七一年六月)に関して次のように書いている。
河原枇杷男句集「閻浮提考」には、死と紐の句が多い。この作家の志向する美学に、私は同感するが、しかし「死」を詠みすぎるのは一考を要する。紐のイメージは、私も好きなので紐八句のなかからこの一句を採る。
この濁世のわれら人間世界をはるばる通過して、このひとつの紐は夢の座へ現われたように思われる。そして実用性を超越し、肉体の手の届かぬところで、自立と転身を試みているようだ。この紐は果して地上を這ってきたのだろうか。或は空間を飛行してきたのだろうか。損傷や風化もなく、白く発光さえしているように見える。しかも計るべき長さ[・・]はすでに失われている。
この評は《琴座》一九七二年一月の二五七号に掲載されているから、同年八月の〈弟子〉の「紐」にも反映している見解だろう。二〇行めの紐は「円」を形容するために登場したようなものだが、それがあたかも「切ない私生活」を縛りあげているように映る。
吉岡はこの詩句以前にA「鉄砲ユリの奥は深く」(〈三重奏〉⑦・17)と書き、この詩句以後にB「「ただ この子の花弁がもうちょっと/まくれ上がっていたら いうところはないんだがね」」(〈ルイス・キャロルを探す方法―わがアリスへの接近〉⑧・11)、C「翼の折れた鳥のような花弁を垂らす」(〈楽園〉⑨・1)と書いている。Bはキャロルの邦訳からの引用だからここでは措いて、すでに触れたCの〈楽園〉の花弁は花菖蒲である。Aが補強しているように「花弁的な奥深いもの」はたぶん百合で、《新約聖書》の「又なにゆゑ衣のことを思ひ煩ふや。野の百合は如何して育つかを思へ、労せず、紡がざるなり。然れど我なんぢらに告ぐ、栄華を極めたるソロモンだに、その服装この花の一つにも及かざりき」(太六・二八―二九)を暗示しているか。それとも《旧約聖書》の「女子等の中にわが佳耦〔とも〕のあるは荊棘の中に百合花のあるがごとし」(歌二・二)を想いだすべきか。さらには「死んだ少女の股までの百合の丈」(〈模写――或はクートの絵から〉⑥・4)や「筒深い百合の花が咲く」(〈メデアム・夢見る家族〉⑧・21)という吉岡自身の詩句を。
吉岡実はその詩で「明晰」という語をただ一箇所、この詩句において用いている。「われわれ」とは師と弟子であろう(西脇―吉岡ではなく、マラルメ―ヴァレリーか)。明晰であることを誇る師弟が明晰でなくなりうる状態とは、そもそもいかなるものか。次行の「疫神」がこの「われわれ」を呼びよせたのか、「われわれ」がこの「疫神」を呼びよせたのか。疫神(ヤクジン)はエキジン、疫病をはやらせる悪神、疫病神だ。この語を発見した時こそ〈弟子〉を吉岡が詩たらしめた瞬間だろう。
西脇順三郎訳で「原始の光線の洪水の下でひとり直立する/百合の花よ! 天真爛漫は君たちの一人」や「おお神聖な/裸の重荷は何と野生の快感だ、その重荷は/震える電光のように肉体の神秘の恐怖を/飲む火焔のおれの唇をのがれ滑り行く」といった詩句をもつステファン・マラルメ〈牧神の午後――牧歌〉(#B_141、七〇~七三ページ)を「疫神の午後」と言い換えたのは、吉岡が西脇の詩法に学んだものだ(ただし、西脇詩に〈牧神の午後〉への言及は何度も見られるものの、「疫神の午後」という詩句は存在しない)。吉岡は〈詩集・ノオト〉に「清岡卓行がいつか、ぼくのことを〝独身〟〝毒身〟〝涜神〟としるした」(#A_25、七三ページ)と書いているが、ここから汲みとれるのは自己肯定のニュアンスである。ここでの吉岡は、二年ほど詩作から離れている自らを「疫神」と任じていたのか。
ドビュッシーがマラルメの詩から《牧神の午後への前奏曲》を紡いだように、吉岡もまた〈牧神の午後〉をこのように展開した。類似する詩句を西脇順三郎訳から引く。「あんなに透明な/ニンフの浮薄な淡紅の色は、眠そうな/繁茂する森のまどろんだ空気の中を飛びまわる」(#B_141、六六ページ)。「エトナ山よ、ヴィーナスが訪れたのは君の山中だ/うぶな娘の踵を君の溶岩の上にふみつけて。/悲しい睡眠が鳴り響く時、火焔が燃えきる時/おれはこの女王を抱く」(同前、七四ページ)。吉岡はここにいたって詩篇に官能のモチーフを導入して、しかもなお「明晰でありうるか」、挑戦を試みている。
異同の説明で触れたように、初出は「力ない血祭/どこから起伏せるなやましい大理石」で、体言止めが続いて意味の脈絡が希薄だった。定稿の詩句だと、大理石=血祭のように、娘の肌が血に染まったかのようにも読むことができる。
難句である。吹きながしは「旗の一種で、幾条かの長い絹を半月形の輪にとりつけ、長い竿の端に結びつけて風になびかせるもの」という辞書の説明を読んでも、ほんとうに「幾条かの長い」縮緬でいいのか、いまひとつ自信がもてない。ましてそれが鮮緑色群とくるとお手上げだ。文字どおり、吹きながしの輪につけられた縮緬がさまざまな鮮やかな緑をなしているさま、と取るしかない。
「たたずめば」の主語は、前行のチリメンではなく、英語のtheyなどと同様、(人)である。すなわち「たたずめば〔チリメンは〕スルメの足に見え」。吹きながしとスルメの足の形態の類似性。
当然「立てば芍薬、坐れば牡丹、歩く姿は百合の花」という江戸期からの美人の譬喩が想いうかぶ(ここにも百合が登場する!)。しかし「スルメの足」「燐」「雪の峯」という列記は、美人とはほど遠い組みあわせというしかない。吉岡は〈西脇順三郎アラベスク〉の〈1 断片四章〉の第三章に相当するところで「〔西脇先生は〕こんどみんなで、板橋を歩こうと云われる。あすこは、江戸の宿場であり、要路だったからな――/犬殺し/菜の花/女郎/恐るべきスピードで叫ばれた」(#A_25、二二三ページ)と書いている。この文の初出は一九七二年四月の《西脇順三郎全集Ⅶ》月報で、発表の時期としては〈弟子〉のわずか四箇月前である。吉岡が「スルメの足」「燐」「雪の峯」において西脇の造型した「板橋のイメージ」(同前)の方法に倣ったことは確実だろう。
さて、吉岡は〈1 断片四章〉の第四章に相当するところでは次のように書いている。「詩集《鹿門》に〈ヨシキリ〉という詩がある。/〔……〕/西脇詩には数多くの友人、知己の名が愛情深く鏤められている。しかし十年近いおつきあいだが、私の名はいままで現われていない。それは、先生と旅行や散策をする機会がほとんどなかったことも、その理由かもしれない。/神田小川町のタカノという小さな喫茶店で、先生とコーヒーをのんだ時、雑談のあとで、微笑しながら、静かに云われた――君の名は、私の詩の中で永遠になったのだ――と」(同前、二二五ページ)。吉岡の文の引用で中略した部分は、西脇の詩篇〈ヨシキリ〉全文である。原文を引く。
ああ
またタマ人の絶望の川よ
わが脳髄のつくるまで
歌えよ
梨畑の中をよこぎる
まむしのような歌を
ヨシキリのヨシオカのような
入道雲の鼻のようなものを
ただグニャグニャ流れさえすれば
最高のパイオーンだ
人間の病める心を
さすつてくれるおつさんよ
あの浅瀬につなぐ
トホのいない小舟の幽霊は
だれがのつて来たのか
いずれチョウフの方から来た人間だ
ウドンを買いに来たのか
それとも将棋をさしに
それとも狐つきに祈祷する
みこのオコゼかトリアゲか!
〈弟子〉の四箇月前に西脇の〈ヨシキリ〉(初出は詩集《鹿門》、筑摩書房、一九七〇年七月)を全文引いて《西脇順三郎全集》の月報の文章を書いた吉岡にとって、詩篇が〈弟子〉であろうが〈弟子――西脇順三郎先生へ〉であろうが、気持のうえでは同じことだったに違いない。だからこそ、冒頭で触れたように「献詩」であることにあれだけこだわったのではないか。つまり〈弟子〉はなによりもまず〈ヨシキリ〉への返礼として書かれたのである。そうであれば「〈永遠とは今の現在のこと〉」は〈ヨシキリ〉における吉岡の名の永遠化を指し、もはや西脇の章句である必要はないに等しい。
〈ヨシキリ〉は西脇の詩篇ではわかりやすいほうだが、ここはやはり新倉俊一の《西脇順三郎全詩引喩集成》(筑摩書房、一九八二年九月)に付くに如くはない。それに依れば「またタマ人の絶望の川よ/わが脳髄のつくるまで/歌えよ」は英詩人スペンサーの〈プロサラミヨン〉(「結婚前歌)の意で、すでに《近代の寓話》に〈プロサラミヨン〉――「この多摩の女のせゝらぎに/鳴くよしきりに」の詩句が見える――がある)の詩行のもじり。「ヨシキリのヨシオカのような」は「詩人吉岡実。葦切は鳥の名。ここでは頭韻をするために枕言葉として使っている」(同書、三三九ページ)。「パイオーン」はギリシア語でアポロンに捧げる讃歌の意。「あの浅瀬につなぐ/トホのいない小舟の幽霊は/だれがのつて来たのか」は杜甫〈野望〉の末二行(扁舟 空しく老い去り/聖明の朝[ちょう]を補う無し)への言及であるという。
ところで最後の「みこのオコゼ」とはなんだろう。オニオコゼはカサゴ目で砂泥の底深く生息。胃に収まりきらない餌を咥えたまま徐々に呑みこむあたりは、貪婪な魚というイメージであり、背鰭の棘には毒腺があって刺されると激痛がするあたりは、過剰なる防御性といったところだ。いずれにしても「チョウフの方から」「小舟」に「のつて来た」のが巫女/御子/皇子/皇女/神子の「オコゼ」だ、いやそうではないトリアゲ婆だ。それは必ずしも「ヨシキリのヨシオカ」を指しているわけではないが、そこから流れでた気味があるのも否定できない。新倉俊一によれば「オコゼという醜い魚を山に入るとき樵がお守りにもっていく習慣がある。それをみると山の神は和らぐと言われる。柳田国男『笑の本願』九参照」(同前、二七三ページ)と《宝石の眠り》の〈きこり〉の項にあるから、これらと「折口〔信夫〕の多摩人[たまびと]のユーフラテスの」(《禮記》の〈愛人の夏〉)という詩句を考えあわせると、ここでもそうした民間伝承や古代文学を踏まえているのかもしれない。〈ヨシキリ〉で、西脇は多摩川への呼びかけを詩にしたのだ。
吉岡は海を泳ぐ老人を描くことで、西脇をたたえる。しかもそれは「夢みる鋸歯の海をラジィカルに泳ぐ」のである。「わずかに」はそうした存在の稀であることを示している(西脇は知らず、伝記的事実として吉岡は泳げなかったようだ)。
これも難解である。とりあえずの手掛かりは「便所」。前掲《西脇順三郎全詩引喩集成》に事項索引はないが、マラルメ関連の調べ物をしていたら、《鹿門》巻末の〈醮〔ショウ〕〉の「便所が新式に改造されても/そのシュール的な美は水流と/共に流れ去つてしまつた」は「昭森社のこと」(同前、三四三ページ)という記述を見つけた(森谷均の昭森社は、一九六二年一二月に西脇の詩集《えてるにたす》を出した出版社で、神田神保町の小さな木造建ての一三階段を昇った二階に、伊達得夫の書肆ユリイカや小田久郎の思潮社とともにあった)。この〈醮〔ショウ〕〉は《無限》一九六八年七月の二四号が初出で、吉岡は詩集《鹿門》の装丁も担当しているから、初出であれ詩集であれ、この詩篇を読んでいることは間違いない。そう思って読みなおしてみると、「便所」以外にも〈弟子〉をインスパイアしたであろう詩句がぞろぞろ出てくるではないか。適宜引用する。
・マラルメがさびしがる肉体も/走つている黒板に白墨が/水仙の雲のように走つている
・ああまた/牧人のかすかな葦笛の/さざなみが――/午後になると/水精はみな逃げてゆく/水浴びの少年だけが/牧神と将棋をしている
・こんなに抽象的な会話は/マラルメのように/あまりおもしろくないが/これも空間的な仕事だ
・またそれは牧神の/葦の中のみだらなせせらぎであるから
・自然を賭けるバクチは/マラルメのサイコロのように/アイマイの運命だ
吉岡はマラルメを果敢に換骨奪胎した「老人」をたたえていたのだ。
前後のつながりから、ここはどうしても西脇の「渡し場に/しやがむ女の/淋しき」(《旅人かへらず》九〇)を想起せざるをえない。〈醮〔ショウ〕〉の「便所が新式に改造されても/そのシュール的な美は水流と/共に流れ去つてしまつた」の後には次の詩句が続いている。「切断された鎖は女神の/くびかざりのようにサンゼンと/して輝いたものは/あの偉大な断絶は/バケツの水にあると/ヒュームが言つている」。ここでは、吉岡にしては珍しく「め―み―す―す―も」と頭韻を駆使して、詩的な高みへと登攀を試みている。
「梯子」としての西脇の詩句を足掛かりにして、高みに登る吉岡実自身のことをいっている。敢えて付言すれば、「梯子」から木偏を取りのぞけば「弟子」である。
三行めの「笊」が遠くこだまして、ここにいたって「簀子」となった、とすれば冒頭の「それは違った意味に使われる/言葉」とは簀子のことであったのか。それを濡らしていたのは「女神の水色のスミレの酢」という恩寵であろう。
《枕草子》冒頭の章句である(西脇の詩に紫式部は出てこないが、セイショーナゴンは《禮記》の〈神々の黄昏〉に出てくる)。ここで二五行めの「疫神の午後」を振りかえれば、古代、疫神祭が季春の候、疫神を鎮めるために執り行なわれたから、それと呼応する形にもなっている。さて、久しぶりに執筆した詩篇も擱筆のときがきた。気がついてみれば、春の夜は白白と明けているではないか。なにか飲むものでもないだろうか。
「庭をよこぎる/メタフィジックな牛乳配達自転車/あるいは蛾」(〈夏から秋まで――池田満寿夫の版画の題名を藉りて〉⑦・2)。
一九七〇年三月の〈低音〉(⑦・14)以来、詩篇を発表していなかった吉岡は、一九七二年四月に〈葉〉(⑧・4)を発表して「復活」した。六月には〈ヒヤシンス或は水柱〉(⑧・3)と〈ルイス・キャロルを探す方法〉(⑧・11)を、七月には〈悪趣味な冬の旅〉(⑧・6)と、後の《サフラン摘み》の詩篇を陸続と発表しだした。しかし、私には二年間の「休筆」明けの最初の執筆作品が〈弟子〉のように思われてならない。ここでもう一度、〈弟子〉がいつ執筆されたか考えてみよう。
〈弟子〉初出誌が《無限》二九号(一九七二年八月)であることは冒頭で触れた。《無限》のバックナンバーをひもとくと、季刊詩誌とはいいながら、このころは毎年八月九月ころの年刊ペースになっている。前号(二八号)は草野心平特集で、一九七一年八月の発行。前前号(二七号)は村野四郎特集で、一九七〇年九月刊。同号の〈編集後記〉には一九七〇年四月三〇日の日付をもつ慶光院芙沙子の「今年は村野四郎特集につづき、草野心平特集、西脇順三郎特集と「無限」の編集スタッフをつぎつぎに特集する決意である」(同誌、二一二ページ)という記述がある。さらに次号予告として「今秋11月発刊」の草野心平特集の目次プランの末尾に「続刊「西脇順三郎」特集」とあることから、遅くとも一九七〇年前半には西脇特集の企画が現実性を帯びていたことになる。特集企画が決定してすぐに原稿依頼があったとは思えないが、吉岡が〈低音〉を最後に詩篇の執筆から遠ざかっていた時期に「西脇順三郎特集号に献詩を寄せられたい」という話が(おそらく鍵谷幸信から)あったに違いない。そのときの吉岡の心理を忖度するに、ぜひ書きたいという気持と、どのように書いたらいいかという気持がせめぎあっていたのではあるまいか。
吉岡実と西脇順三郎の違いを秋元幸人が次のように指摘している。「自ら《弟子》と矜持を保ちながらも吉岡実が決定的に西脇順三郎とは異なるタイプの詩人だったことは、まさにこうした執筆のスタイル〔一種の憑依、神がかりの状態を頼んでいたかに思われる吉岡の詩作に対する姿勢〕という一点に拠って証明されうるものではないかと私は考える。周知の通り西脇順三郎は二十四時間三百六十五日これ詩人という立場を貫き通し、〔……〕行住坐臥の悉くを詩のかたちで身裡に取り込んでは弛まず吐き出しつづけた詩人だったからである」(#B_001、三八一ページ)。
ふだんから神憑り状態でなければ詩が書けない「弟子」である詩人が、常に全身これ詩人である「師」への献詩の執筆においてその詩法にあやかろうとしたのは、ある意味で自然なことであった。もちろん吉岡には、池田満寿夫の版画の題名を藉りた〈夏から秋まで〉や土方巽の秘儀によせた〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6)の方法を踏襲して、この詩が西脇順三郎への献詩であることを明示しつつ献詩を書くことはできたはずだ。しかし、吉岡はその方法をとらなかった。〈弟子〉で西脇順三郎頌の形を借りて、その後、明確な方法意識を伴って全開することになる引用と典拠の詩法を自然発生的に、無自覚に、言い換えれば西脇の詩の方法を自分流になぞることで展開したように思われる。すなわち、自らの地の文と他者の引用文のほかに、主に先行する文献を自在に変容させた詩句をおりまぜながら詩行を連ねていくという方法である。そのとき吉岡の目の前にあったのは西脇の詩集《鹿門》の諸作(とりわけ〈ヨシキリ〉と〈醮〔ショウ〕〉)、さらに西脇が訳したマラルメの〈牧神の午後〉であったと思われる。西脇が訳したマラルメの詩は《世界詩人全集10》のマラルメとヴァレリーの二人集に収められており、その付録に井上究一郎が〈マラルメとヴァレリー〉という興味深いエッセイを書いている。
ただヴァレリーは、マラルメの詩的快感にあまりにも打たれすぎたといえる。そして『魅惑』はついに象徴に満ちた「官能の森」(ヴァレリー「曙」)の出口を、現代の詩人たちにたいして封じこめてしまったかに見える。〔……〕ヴァレリーの魅惑の森の封印を解いた〔……〕ブルトンには早くからそのような使命を身に感じていた気配がある。一九一三年に、ポール・ヴァレリーにささげているソネット、おなじく一九一八年の「ムッシュー・V[ヴェ]」と題する極めて難解な献呈詩は、その点で、これから十分な含みをもって解読されなくてはならないと私は思う。(#B_141付録、二~三ページ)
吉岡が自分をヴァレリー(あるいはアンドレ・ブルトン)に、西脇をマラルメ(あるいはポール・ヴァレリー)になぞらえていた、などと言いたいのではない。西脇に対する恩義と同等もしくはそれ以上に感じたであろう呪縛を脱するには「西脇順三郎」と徹底的につきあうしかない、と思いさだめたのが、この当時の吉岡だったのではあるまいかと言いたいのである。
吉岡実は〈弟子〉のあとの詩篇を《サフラン摘み》(青土社、一九七六年九月)にまとめ、一九七八年一〇月に〈夏の宴――西脇順三郎先生に〉(⑨・20)、一九八二年七月に〈哀歌――追悼・西脇順三郎先生〉(⑪・13)、一九八九年四月に〈永遠の昼寝〉(未刊詩篇・18)を、と三度にわたって西脇に詩を捧げている(一九八二年六月の西脇順三郎逝去に際しては追悼文を草し、追悼座談会にも出席)。吉岡からこれだけ詩を捧げられた人物は、後にも先にも西脇をおいてほかに存在しない。これら〈弟子〉のあとの詩篇と、吉岡がおりおりに綴った全一三篇の散文〈西脇順三郎アラベスク〉をつぶさに見ることで吉岡実の詩法の変貌をあとづけることは、別に機会に譲りたい。
瀧口修造はクロヴィス・トルイユをアールヌーヴォーの唯一の生き残り作家だといったそうだが、横尾忠則は〈天国と地獄が同居する世界――クロビス・トルイユ「魔術師」〉という文で、実作者の強みを発揮して「ぼくはむしろピンナップ・ガールの衛生博覧会的、レビュー的、サーカス的、カーニバル的、遊園地的、マジック・ショー的、ドサ廻り的、大衆演劇的、わが日本の紙芝居的、宝塚歌劇団的な熱狂性を想像するのである」(#B_161、一七〇~一七一ページ)と反論している。
クロヴィス・トルイユ(Clovis Trouille、1889~1975)はフランスの画家。一九三〇年、日曜日と余暇に画家としてのキャリアを積みはじめ、革命的芸術家作家たちのサロンを通じてシュルレアリストたちとのつながりをもった。代表作に〈メデュース号の遭難〉〈祝日〉などがある――と同書にあるが、この二作、レイモン・シャルメ著、種村季弘訳《クロヴィス・トルイユ〔シュルレアリスムと画家叢書「骰子の7の目」第4巻〕》(河出書房新社、1974)に載っていない。ただし〈祝日〉は、吉岡実が〈少女〉(⑦・5)を寄せた《血と薔薇》(第2号、1969年1月)に掲載されている〈お祭り〉である。その〈血と薔薇コレクション〉には責任編集の澁澤龍彦が〈ネクロフィリアの画家〉という紹介文を書いていて、トルイユのことを「フランスの横尾忠則」と呼んでいるから、横尾が共感を寄せるのも無理はない。現に横尾は、トルイユの作品を一点所蔵しているばかりか、前掲文の冒頭に「ぼくの好きな画家にクロビス・トルイユがいる。/できれば彼のような絵描き[、、、]になりたいとずっと思ってきた」(同前、一六六ページ)と書いて、自作の〈お堀〉を掲載しているほどである。
横尾はこの文で、実験演劇集団「天井桟敷」を率いた寺山修司の精神にトルイユほどぴったりした画家はいないと指摘するが、吉岡実は寺山の演劇に耽溺した風はない。さらに吉岡はトルイユの名を詩はもちろん随想にも記したことがなかった。しかし、のちに《神秘的な時代の詩》を構成する詩篇と拮抗する絵画としてトルイユくらいふさわしいものはない、と私は考える。序章〈みなづきの水〉で触れた山口昌男のいうこの画家の「挑発的な画風」は、一九六〇年代末の日本で、とりわけ寺山の演劇や吉岡の詩と共振した。
「石の建築物といっても永遠/ではない二階から上は/紫の窓/なでられている/ビーナスの尻が見え」(〈マクロコスモス〉(⑦・1)の冒頭部分)
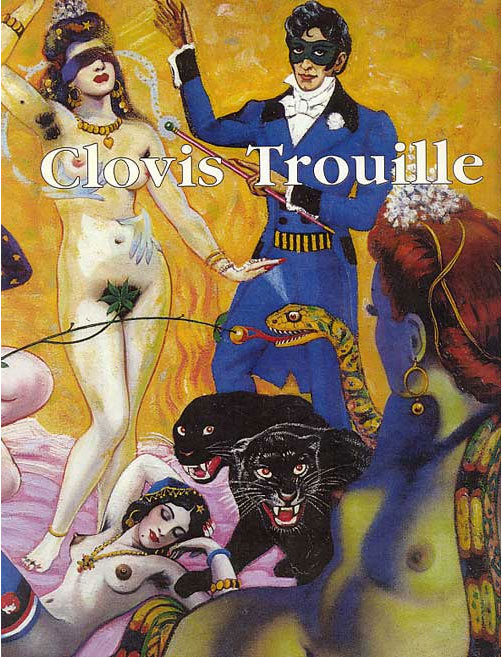

Clovis Prevost《Clovis Trouille》(ACTES SUD、2003)の表紙(左)とClovis Trouille〈La rue des enfants trouves〔捨て子の街〕〉(1934-1966)(右)
代表作〈魔術師〉を表紙にしたClovis Prevost《Parcours a travers l'oeuvre de Clovis Trouille, 1889-1975》(ACTES SUD、2003)なる大冊を見ても、トルイユが一九六〇年代に完成した作品は多くないので、この「ポップアートの先駆者」晩年の七〇年代の作品二点を観てみよう。

Clovis Trouille〈Ceremonial saphique〉(1971)
まず〈Ceremonial saphique〉。キャプションには「1971/Technique mixe : collages photographiques et huile/60×90cm」とあるから、過去の自作の写真版をコラージュしたものと知れる(下方中央の鰐と左の女たちは油彩か)。注意深い読者なら、ここに〈女魔術師たちの儀式(Ceremonial des magiciennes)〉や〈聴罪司祭の接吻(Le baiser du conffesseur)〉や〈カルメル修道会内の対話(Dialogue au Carmel)〉や〈僧院の夢(Reve claustral)〉や〈覗く娘(Voyeuse)〉や〈魔術師(Le magicien)〉や〈おお! カルカッタ! カルカッタ!(Oh! Calcutta! Calcutta!)〉や〈わが埋葬(Mes funerailles)〉といった河出書房新社版《クロヴィス・トルイユ》(#B_069)でおなじみの図版を認めるだろう(その原書であるフィリパッキ版の画集を参照した山口昌男のトルイユ論〈挑発的な祝祭世界〉(#B_158)の挿図としてこれほどふさわしいトルイユの一点はほかにない)。写真ではわかりづらいが、この絵は額装されている。額を付けたのがトルイユ本人の意向なら、自作のフォトコラージュとはいえ、これが立派な「作品」であることの証しである。
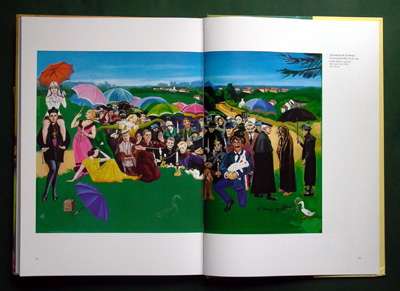
Clovis Trouille〈Apparition de la Vierge a une jeune fille de 13 ans〉(vers 1970)
もう一点は〈Apparition de la Vierge a une jeune fille de 13 ans〉。こちらはキャプションに「Ultime tableau, inacheve/Sans date (vers 1970)/38×61cm」とあり、おそらく未完だ。トルイユは自作をほとんで手放さず、ときには数十年にわたって手を入れたから、本作も描きこんで完成するつもりだったのだろう。一九七〇年という制作年代を前提とするなら、この絵にビートルズの《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》(一九六七年発表)のアルバムジャケットが影響していることはかくれもない。トルイユは作品の素材として雑誌や新聞の切り抜きをコラージュしており、メディアの掲載するヴィジュアルに対する嗅覚はたいへん鋭かった。前掲《Clovis Trouille, 1889-1975》(#B_176)を見ると、気に入ったものは模写して自作に登場させているが、驚くべきことにほとんど原形のままで、自分の絵筆を用いたコラージュといったほうが実態に近い。素材を吸着するトルイユのオリジナリティはあまりに強烈で、そこにはマックス・エルンストのコラージュに顕著な懸けはなれたものの衝突からくる美的なスパークは感じられない。トルイユの画布では、すべては一元化して、あるべきものがあるべきところにあるべくしてあるのだ。
吉岡実は生涯にわたって、ビートルズに限らず、ポップミュージックを意識的に聴いた形跡がない。吉岡の詩とビートルズの曲を比較するなら、個個の作品の類似性ではなく、一冊の詩集、一枚のアルバムが総体としてどのようであるか、という一点に尽きる。
《リヴォルヴァー》を発表したビートルズは一九六六年の暮れから新たなレコーディングセッションに入った。一方、吉岡は六七年初めにはのちに《静かな家》となる詩篇を書きおえて、数箇月の休息を経て、初夏から《神秘的な時代の詩》の諸作を書きはじめている。ここで一九六七年の両者の創作状況を概観しよう。吉岡が発表した詩篇に、ビートルズが《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》(SPと略記)と《マジカル・ミステリー・ツアー》(MMと略記)に収録した楽曲を録音開始順に組みこんで年表にする。
一九六六(昭和四一)年
11.29~12.21 Strawberry Fields Forever(MM・08)
12.6~21 When I'm Sixy-Four(SP・09)
12.29~〔1967年〕1.17 Penny Lane(MM・09)
一九六七(昭和四二)年
一月 内的な恋唄(⑥・12)
1.19~4.21 A Day In The Life(SP・13)
二月 恋する絵(⑥・15)、春の絵(⑩・12)
2.1~3.6 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band(SP・01)
2.8~3.29 Good Morning Good Morning(SP・11)
2.9~21 Fixing A Hole(SP・05)
2.17~3.31 Being For The Benefit Of Mr. Kite!(SP・07)
2.23~3.21 Lovely Rita(SP・10)
3.1~2 Lucy In The Sky With Diamonds(SP・03)
3.9~23 Getting Better(SP・04)
3.15~4.4 Within You Without You(SP・08)
3.17~20 She's Leaving Home(SP・06)
3.29~30 With A Little Help From My Friends(SP・02)
4.1 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)(SP・12)
4.25~11.7 Magical Mystery Tour(MM・01)
5.11 Baby You're A Rich Man(MM・10)
6.14~25 All You Need Is Love(MM・11)
七月 青い柱はどこにあるか?(⑦・6)
八月 夏から秋まで(⑦・2)
8.22~9.29 Your Mother Should Know(MM・05)
9.5~28 I Am The Walrus(MM・06)
9.6~10.6 Blue Jay Way(MM・04)
9.8~28 Flying(MM・03)
9.25~10.20 The Fool On The Hill(MM・02)
一〇月 立体(⑦・3)
10.2~11.2 Hello Goodbye(MM・07)
一一月 マクロコスモス(⑦・1)
《神秘的な時代の詩》で最後に書かれた詩篇は一九七二年発表の〈弟子〉(⑦・15)だから、解散前までのビートルズの楽曲はすべてこの年表に含まれてしまう。よって、以降は割愛する。ここで興味深いのは《サージェント・ペパーズ》の収録順と録音順がまったく相関していないことである。さらに、マッカートニーが一六歳のときに作った〈ホエン・アイム・シックスティフォー〉は措いて、アルバムを決定づける〈ア・デイ・イン・ザ・ライフ〉がセッションの冒頭に登場していることである。つまり《サージェント・ペパーズ》の世界は最初から現前していて、あとはしかるべき時間をかけて全貌を彫琢し、最もふさわしい時間と空間に配置することがバンドに課されたのだ。その枠組みとして採用された架空の楽団のショーという形式自体が重要なわけではない。「現前する総体」の最も顕著な実例である《サージェント・ペパーズ》の個個の楽曲をみれば、前作《リヴォルヴァー》(一九六六年発表)に一籌を輸する。だが《サージェント・ペパーズ》のLPにひとたび針を落とした者は、必ずやレコードを裏返して最後まで聴かなければならない。この量感は《リヴォルヴァー》に求めても得られないものだ。CDのシャッフル機能で曲順を変えたり、ましてや〈ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー〉と〈ホエン・アイム・シックスティフォー〉の代わりに、新アルバムまでのつなぎとして発表された両A面シングル〈ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー〉と〈ペニー・レイン〉を入れたりしたら、《サージェント・ペパーズ》の世界は崩壊する。私がこのアルバムにコンセプトよりもトータリティを見たいのは、これがためである。一九六〇年代末のポップカルチャーの中心に存在したのが本作だった。

ビートルズ《サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド》(1967)のLPとCD
プロデューサーであるジョージ・マーティンの「創作者たち〔ビートルズの各メンバー〕同様、《ペパー》も、各パートの合計としてよりも、全体としてより優れていた。曲は個々に捕らえられることがあるだろうし、場合によってかなりわかりやすい曲もある。ところがこれらがひとつになると、何か深くて不思議な――完全解釈を拒むようなものになってしまうのだ」(#B_137、一一ページ)という見解は、アルバムの総体を物語っている。
ではなぜ《サージェント・ペパーズ》が《神秘的な時代の詩》の音楽なのか。私がビートルズを意識的に聴いたのは一九六九年発表の《アビー・ロード》からで、当時一四歳の中学二年生だった。友人の兄がビートルズマニアで、芝生に陽の当たるクラスメートの社宅で聴かせてもらった。購読していた音楽雑誌の《アビー・ロード》の楽譜特集に〈サムシング〉が載っていなかったので、のちに友人に楽譜(といってもギターコードだけだが)を書いてもらったくらいだから、気に入っていたのだ。一方、《サージェント・ペパーズ》はバンドが解散してから一枚ずつ揃えていったLPのひとつに過ぎなかった。もっともリアルタイムで聴いたところで、小学生の分際では理解できなかっただろう。私が吉岡実を意識的に読んだのは《サフラン摘み》からで、《神秘的な時代の詩》は刊行時に読んでいない。この、リアルタイムでの享受への渇望は紛れもない。しかし個人の受容史で作品を両断してはならない。
吉岡が個個の詩篇を自在に配置して、詩の集まりとは別の「詩集」を成立させたのは《神秘的な時代の詩》をもって嚆矢とする。それは詩篇を発表順に読んだときと(本評釈の章立ては詩篇の発表順を採用している)、詩集の収録順に読んだときとでは明らかに異なると体感できる。だが、詩集の構成の原理を探るべく本評釈でいろいろ推測したにもかかわらず、納得できる結論は得られなかった。このとき「詩集」に関心をもつ者にとって《サージェント・ペパーズ》をめぐるジョージ・マーティンの回想はまことに興味深い。
完成したアルバムの曲順を決める作業が私には残された。この決定には最終的にビートルズの同意が必要だった。〔……〕
レコーディング業界における私の昔ながらのやり方は、明らかに商業的な理由から〝サイド1を強力に〟作ることだった。〔……〕
アルバムを組み立てるときに私がもうひとつこだわっているのは、出だしは力強く、そしてその面の終りのほうに弱い作品を持ってきて、そのあとに再び賑やかなものを入れる、ということだ。〔……〕
ついにアルバムの組み立てが完成すると、ずいぶんおかしな歌のコレクションだ、と私は思った。どの歌も関連性もなければ共通点もなかった。これらの歌に目を通しながら、私は、これみよがしで利口ぶりすぎたのではないかと、本当に心配になりだした。〔……〕
私が心配していたのは、我々が速く先に進みすぎて、大衆を置き去りにしてきてしまったのではないか、というようなことだったと思う。〔……〕
アルバムの編集作業で、私は非常にタイトなフォーマットにまとめた。すると不思議なことに、アルバムは生命を持ち、ひとり歩きをはじめたのである。(#B_137、二一九~二二二ページ)
《サージェント・ペパーズ》の曲順の具体的な根拠まで汲みとれるコメントで、そこからはアルバムの「現前する総体」の背景がうかがえる。詩集のプロデューサーとしての吉岡は、これに類する編纂の記録を残さなかった。しかも自作については沈黙を守るのが、吉岡実の流儀だった。次に少し方向転換して、吉岡が《神秘的な時代の詩》に下した評価の変遷をたどってみよう。
吉岡実は、《昏睡季節》や《液体》、あるいは《サフラン摘み》や《薬玉》を語ったようには《神秘的な時代の詩》に関してまとまった文章を書きのこしていない。それでも吉岡の散文には同詩集への言及が散見される。自身による《神秘的な時代の詩》評価の変遷を確認するため、該当箇所を発表順に摘録する(題名の前の*印は生前、書籍として未刊行の散文を表わす)。
(A)
私はこの二年間、詩を書かずにきた。それが果たしてよいことであったが、わるいことであったか知らない。とにかく私は今年から詩を書きはじめた。二年前までの作品を一区切りとして、一冊の詩集にまとめる準備をしている。出版社は小さいところが望ましいから、社主一人の湯川書房・湯川成一にまかせることにした。その本は、《神秘的な時代の詩》となるはずである。(*〈風信〉、《東京新聞〔夕刊〕》、一九七二年八月一日)(B)
今から二年前に、この詩集は湯川書房から刊行されている。しかし七百部の限定本であって、広く読まれることもなく、埋れてしまった。だがこのたび、山田耕一氏のすすめで、再び世に出ることになったのは、私にとっては望外の喜びである。とはいえ、新しい詩境を求めている時、この詩集の試行錯誤にみちた詩篇は、いっそ陰匿してしまいたいという、矛盾した気持にもなっている。(〈覚書〉、《神秘的な時代の詩〔普及版〕》、書肆山田、一九七六年八月一五日)(C)
〔詩篇〈夏の家〉再録〕(詩集『神秘的な時代の詩』)
私には言葉遊びと呼べるような詩はまったくといっていいほどない。この作品が、かろうじてそう呼べるものかもしれないが。人が言葉遊びと呼びそうなところでも、私は遊んでいない。(*〔私には言葉遊びと……〕、《月刊ポエム》一九七八年一月号〈ことば遊び詩アンソロジー〉)(D)
私はいつか西脇先生に捧げる詩を書かなければならないと考えていた。なぜかというと、今から六、七年ほど前、「無限」の西脇順三郎特集号に、〈弟子〉という短い詩を書いて献げていた。当時考えるところがあって、私は二年間ほど詩作を止めていた。そんな精神状態のなかで書いた詩なので、詩集《神秘的な時代の詩》を編むとき、先生への献詩である詞書を、削除してしまったのであった。はたして、先生はそのことに気づかれていられるかどうかは知らない。しかし、私は心苦しく感じていた。だいぶ前に刊行された詩集《鹿門》のなかに、〈ヨシキリ〉という短い詩がある。先生が私のために書いてくださったからである。(〈西脇順三郎アラベスク7――「夏の宴」〉、《東京新聞〔夕刊〕》、一九七八年一〇月二四日)(E)
八年ほど前、私は久しぶりに、『神秘的な時代の詩』を上梓した。試行錯誤にみちたこの詩集は、当然のことながら理解されなかった。そのような折、兜子から手紙が来た。今、その手紙はわが家のいずこかに、ある筈だが見ることは出来ない。しかし文意は覚えている。まばゆい丘の上に出ると
馬の交尾
その影のしていることが
暁の彫刻であるこの四行に、感動したとあった。「少女」と題する四十二行の詩である。私はやさしく慰撫された思いであった。(〈赤尾兜子秀吟抄〉、《赤尾兜子全句集》、立風書房、一九八二年三月一日、栞〈赤尾兜子ノート〉)
(F)
私は今まで、自作の解説をしたことがない。なぜなら、「詩自体」より、明解な説明が出来ないし、また書けないからだ。俳句、短歌そして詩のような短詩型では、作者の作品自解ほど、興醒めなものはないと、つねづね私は思っているのだ。この詩〔〈青い柱はどこにあるか?〉〕は、昭和四十九年に刊行された、詩集『神秘的な時代の詩』に収められている。(〈三つの想い出の詩〉、《現代の詩人1 吉岡実》、中央公論社、一九八四年一月二〇日、〈自作について〉)(G)
昭和四十二年 一九六七年 四十八歳
土方巽の秘儀に寄せて、詩「青い柱はどこにあるか?」を書く。
昭和四十三年 一九六八年 四十九歳
『季刊芸術』に、詩「神秘的な時代の詩」を発表。
昭和四十四年 一九六九年 五十歳
田村隆一編集の季刊詩誌『都市』へ詩「コレラ」を寄せる。この時期の作品を、妻に批判されて憤然とする。これより約二年間、詩篇を発表せず。
昭和四十九年 一九七四年 五十五歳
詩集『神秘的な時代の詩』の限定本を湯川書房より刊行。
昭和五十一年 一九七六年 五十七歳
夏、山田耕一の要望で普及版『神秘的な時代の詩』を書肆山田より刊行。
(〈年譜〉、《現代の詩人1 吉岡実》、中央公論社、一九八四年一月二〇日)(H)
その夜の赤坂プリンスホテル旧館のホールは、祝宴の大勢の客にまじって、女性の姿も多く、華やいだ空気をかもし出していた。私は友人代表として、新境地を拓いた受賞作品を讃えたあと、「いずれ、私もこの賞を頂きたいと思います」と、冗句で祝辞を結んだ。『ゴヤのファースト・ネームは』と同じ年に、私も新詩集『神秘的な時代の詩』を刊行している。しかし、暗中模索の作品が多く、わずかに一部の知己の支持しか得られなかった。(〈「受賞前後」の想い出〉、《樹木》2号、一九八四年三月五日、〈高見賞の詩人たち〉)(I)
「二十数年間に亘る雑文の数々を通読して、気づいたことは、処女詩集《液体》にまつわる、《昏睡季節》や《魚藍》に就ての言及の多いことだ。まだ世に知られることがなかった私が、詩への没入を語れば、必然的に処女作周辺の説明におち入ってしまったわけである。それにしても、《紡錘形》や《神秘的な時代の詩》、それから《サフラン摘み》などの詩集の生成の記録がないのは、今にして考えれば残念なことである。」(〈あとがき〉、《「死児」という絵〔増補版〕》、筑摩書房、一九八八年九月二五日)(J)
『神秘的な時代の詩』はひとことで言えば、まがまがしい詩集である。言葉の「疾走感」、「浮力性」もしくは「破片の散乱」などと、友人、知己から厳しく、たしなめられるばかりだった。当然のことながら、さすがの私も意気消沈してしまった。そんな雰囲気が漂っていた時、篠田一士は好意的に評価してくれたのだ。「まるで音楽のように/アジサイの花の色は変る」をエピグラフにして、数篇作品を解読している。
――『神秘的な時代の詩』をはじめて読んだとき、ぼくは何度か声を出して笑った。日本語で書かれた詩作を読んで、そういう経験をするのは、滅多とないことだ。以来、この詩集を、ときおり読みかえすたびに、忘れていた詩行から、思わず、笑いがこみあげてくる。なにか、笑い茸といったものを食べたような具合だ。――
私はこのひとことで、救われたのだ。感謝をこめて、手紙を書いたように思う。近ごろ、若い詩人たちに、この詩集は評価されはじめたようである。(*〈篠田一士追想〉、《ユリイカ》一九八九年六月号、〈追悼=篠田一士〉)
一九七〇年代の初め、吉岡実は二年近く詩を発表していない。その間に《静かな家》に続く第七詩集をまとめてもよかったはずだ(最新の〈弟子〉はまだ書かれていないが、《僧侶》における〈死児〉の重要性はない)。詩集を出すべく吉岡が始動したのは、のちに《サフラン摘み》となる詩篇を書きはじめてからである(A)。逆算すれば、沈黙の期間中、具体的な詩篇の形こそとらなかったものの、第七詩集の詩想は吉岡の内部で継続していたことになる。それゆえ「暗中模索の作品」(H)を書いていない沈黙期こそ、真の「暗中模索」の時期なのだ。
連祷詩《粘土説》の構想が第七詩集の詩想を終熄させたことは、吉岡実の随想〈高遠の桜のころ〉の次の一節に照らして、疑問の余地がない。「妻のからだに寄りかかり、午睡しながら、まだ四月なのにいろいろなことがあったなあと思った。暗中模索のため、二年間中止していた詩作を試み、〈葉〉という百三十行の連祷詩の一篇が出来たこと、それに続いて、〈ルイス・キャロルを探す方法〉すなわち、アリス詩二篇が出来たことだった。これは私の詩業のなかでも、独自性と新領域をきり拓いたものだった。私はこのときから、詩行為がつづけられるという兆を感じはじめていた」(#A_25、二七ページ)。
吉岡は連祷詩(同一テーマの複数の詩で構成した一種の長篇詩と考えられる)と引用詩(先行する作品を独自に展開した、典拠のある詩と考えられる)の両面攻撃を開始した。いずれも《神秘的な時代の詩》にその萌芽が見えるものである。すなわち連祷詩の萌芽は〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16)に、引用詩の萌芽は最初期の〈夏から秋まで〉(⑦・2)と最後期の〈弟子〉(⑦・15)に読みとれる。連祷詩と引用詩に逢着するまでを「暗中模索」とするならば、一九六七年から七〇年まで(七二年の〈弟子〉は余燼である)、時代の喧騒の余波を受けつつ、吉岡は自身の詩を後戻りのできない地点に押しやったことになる。めざすところは《僧侶》の作品風土からの完全な脱却。厳密に言えば、これは二度目の試みとなる。《紡錘形》の詩篇(標題の〈紡錘形〉は二篇だが、これも連祷詩の試みで、本来なら続篇が生まれたはずだ)を書きつづけるかたわら、長篇詩〈波よ永遠に止れ〉や典拠のある詩篇〈首長族の病気〉(⑤・11)でそれを試みたものの、時期尚早の形で頓挫した経緯があるからだ。沈黙の二年間はそのための、おそらくは詩人自身にとっても不可視の助走期間だった。
吉岡実は《神秘的な時代の詩》全体の構成配列を〈抄〉と詩集と、少なくとも二度、模索している。これはなにを意味しているのか。おそらく《静かな家》までの詩集は、ある世界(「静物」なり「僧侶」なり)を描ききったと考えられる一篇(〈過去〉なり〈死児〉なり)の誕生ととともに詩集は成立し、吉岡にとって詩集の編纂は極論すれば事後処理に近いものだった。しかし《神秘的な時代の詩》は、いくら詩篇の数を積みかさねても詩集が成立したという感覚を作者に抱かせない底の作品群だった。それを詩集にするためには一にも二にも構成配列に気を砕く以外なかった。「詩集」となった作品群を前にして吉岡は、それがなにかと問うたあげく、時代に対する連祷と認識したのではあるまいか。神秘的な時代の詩による神秘的な時代の詩集。ならば次なる試みは、結果としての連祷ではなく、目的としての連祷である。それが、〈葉〉(⑧・4)一篇で終わったとはいえ、連祷詩《粘土説》が出現する背景だった。〈崑崙〉の方法で〈わが馬ニコルスの思い出〉のモチーフを現代的に(ということは〈波よ永遠に止れ〉のようにではなく)展開すること。これが《神秘的な時代の詩》という詩集をまとめた後の吉岡が描くべき世界となった。
吉岡は変貌することを恐れなかった。《僧侶》のような作品世界をもった詩人なら、それと大同小異の、実際には縮小再生産の詩篇を陸続と書く道すらありえた。むろんそれを選択するような吉岡ではなかったが、ひとたびこうと決めた目標に対しては、達成すべく長い期間をかけて詩作/思索を持続させている。思潮社版の「全詩集」後の入沢康夫との対談で、吉岡はこう述べている。
あの〔入沢康夫〈わが出雲〉の〕志向する世界はぼくもわかるんですよ。土方さんへの詩で「青い柱はどこにあるか?」という作品があるんですが、相当日本的なものの要素が強いんですよ。ぼくも及ばずながら、相当日本的なもの、それはもともともっていたんだし、勉強してきた世界だし、万葉とか古今の世界とぼくたちの現在の世界との混合ができたら、そういう世界をつくりたいという感じなんですよ。(#C_005、五六~五七ページ)
こうした関心は一五年あまり後の《薬玉》に結実した。入沢との対談で吉岡はこうも言っている。「ぼくは思うんだけれども、詩論はなくても詩は成り立つし、ぼくは現に書いてきたし、書けるという感じなんですよ。絵から吸収したり、映画や芝居を観たり、それから現代の時代から……もう雑多です」(同前、五二~五三ページ)。あたかも詩論〈わたしの作詩法?〉のところに詩人はいないと言わんばかりである。詩論や随想に詩の足跡が刻まれているわけではないのだ。
吉岡のその時時の試みは詩集(に収められた詩篇)に最もはっきりと見てとれるが、その萌芽はおそらく数年から十数年、ことによると半世紀近く遡れるもので、それと執筆時の同時代のあらゆるアート(とりわけ視覚芸術)が混淆して一篇の作品が生成する。すべては詩句とその集まりである詩篇、詩篇とその集まりである詩集、詩集とその集まりである全詩集に、刻まれているのだ。
吉岡は一九七〇年代に《サフラン摘み》と《夏の宴》という二冊の引用詩集を刊行したあと、ふたたび沈黙し、《薬玉》で「後期吉岡実」の旗色を鮮明にして再登場する。《薬玉》刊行の翌一九八四年の《現代日本執筆者大事典77/82第四巻(ひ~わ)》(日外アソシエーツ)の吉岡実の項、〔最近関心のあるテーマ〕に「現世をテーマの長篇詩」とある。おそらくこれは編集部のアンケートに吉岡自身が回答したものだ。城戸朱理は吉岡の長篇詩についてこう書いている。
吉岡さんは最初にお会いしたときから、いずれ長篇詩を書きたいと語っておられた。そのためには自分の今までの書き方ではなく、新しい方法が必要だとも。それは様々な種類の散文も混入する混沌とした外貌を持つコラージュのようなものにはるはずだった。彼はウィリアム・カーロス・ウィリアムズの長編[ママ]詩『パタソン』を参考として考えていたし、オクタビオ・パスの「白」、そしてチャールズ・オルソンの「カワセミ」といった長詩を高く評価し、たびたび語ったが、おそらくは前者の作者自身が曼荼羅をならったという構造を、そして後者の散文と韻文が織り成すカオティックな言語世界を、自分自身の長篇詩のなかに顕現せしめようと考えていたようだった。もし実現していたら日本語による詩の曼荼羅たりえたかも知れないその長編は、しかし、結局、実現されなかった。(#B_037、四九~五〇ページ)
吉岡実は詩の形式でやれることはすべてやりつくしたと考えていたようだ。亡くなる半年前、私が最後に会ったときも――一篇一篇の詩はもう書けないんじゃないか。これからは長篇詩か散文だ。とくべつ何の準備もしてないが――と語っていた。最後の詩集となった《ムーンドロップ》(持てるかぎりの書法で土方巽を追悼した長詩〈聖あんま断腸詩篇〉を収めている)の次に、生涯の決算として長篇詩を想定していたことは間違いない。最晩年の吉岡実は《神秘的な時代の詩》を「近ごろ、若い詩人たちに、この詩集は評価されはじめたようである」(J)と受けとめている。一九六〇年代後半という神秘的な時代を定着したという自負がそうさせたのであろう。この「まがまがしい詩集」こそ、来るべき「現世をテーマの長篇詩」(そのときそれは《粘土説》と呼ばれただろうか)のふたつとない先蹤であった。
(畢)
〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉はA:吉岡実の著書・編著、B:A以外の書籍やパンフレットや音盤、C:新聞・雑誌、の三部から成る。配列はBが著者名等の、Cが紙誌名の五十音順で、あとはおおむね発行順。最小限の補足説明を備考欄に記した。
凡例 部:分類 〔分類_番号〕 著者名等 書名 発行年月日 発行所名 備考
目次
A:吉岡実の著書・編著
B:A以外の書籍やパンフレットや音盤
C:新聞・雑誌
A_01 吉岡実 詩集 昏睡季節 1940年10月10日 草蝉舎 第①詩集、のちの《魚藍》含
A_02 吉岡実 詩集 液体 1941年12月10日 草蝉舎 第②詩集
A_03 吉岡実 詩集 静物 1955年8月20日 〔私家版〕 第③詩集
A_04 吉岡実 詩集 僧侶 1958年11月20日 書肆ユリイカ 第④詩集
A_05 吉岡実 歌集 魚藍 1959年5月9日 〔私家版〕 初刊は第①詩集内
A_06 吉岡実 今日の詩人双書 5 吉岡實詩集 1959年8月10日 書肆ユリイカ 第③④詩集は全篇収録、篠田一士編集解説
A_07 吉岡実 詩集 紡錘形 1962年9月9日 草蝉舎 第⑤詩集
A_08 吉岡実 吉岡実詩集 1967年10月1日 思潮社 第③~⑥詩集は全篇収録
A_09 吉岡実 詩集 静かな家 1968年7月23日 思潮社 第⑥詩集
A_10 吉岡実 現代詩文庫 14 吉岡実 1968年9月1日 思潮社 第⑦詩集までを抄録、《魚藍》ほか
A_11 吉岡実 吉岡実詩集 1970年2月15日 思潮社 A_08の普及版
A_12 吉岡実 詩集 液体 1971年9月10日 湯川書房 第②詩集〔再刊〕
A_13 吉岡実 歌集 魚藍 1973年8月28日 深夜叢書社 A_05の新装版
A_14 吉岡実 異霊祭 1974年4月25日 書肆山田 のち第⑧詩集に所収
A_15 吉岡実 詩集 神秘的な時代の詩 1974年10月20日 湯川書房 第⑦詩集
A_16 吉岡実 詩集 神秘的な時代の詩 1976年8月15日 書肆山田 第⑦詩集〔三刊〕
A_17 吉岡実 詩集 サフラン摘み 1976年9月30日 青土社 第⑧詩集
A_18 吉岡実 新選・現代詩文庫 110 吉岡実 1978年6月15日 思潮社 第⑨詩集までを抄録
A_19 吉岡実 詩集 夏の宴 1979年10月30日 青土社 第⑨詩集
A_20 吉岡実 詩集 ポール・クレーの食卓 1980年5月9日 書肆山田 第⑩詩集
A_21 吉岡実 随想集 「死児」という絵 1980年7月1日 思潮社 A_25〔増補版〕にない5篇を含む
A_22 吉岡実 詩集 薬玉 1983年10月20日 書肆山田 第⑪詩集
A_23 吉岡実 現代の詩人 1 吉岡実 1984年1月20日 中央公論社 第⑨詩集までを抄録、大岡信・谷川俊太郎編集
A_24 吉岡実 土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る 1987年9月30日 筑摩書房
A_25 吉岡実 「死児」という絵〔増補版〕 1988年9月25日 筑摩書房 A_21の再刊、筑摩叢書328
A_26 吉岡実 詩集 ムーンドロップ 1988年11月25日 書肆山田 第⑫詩集
A_27 吉岡実 うまやはし日記 1990年4月15日 書肆山田 りぶるどるしおる 1
A_28 吉岡実 現代詩文庫 129 続・吉岡実 1995年6月10日 思潮社 A_18の増補版
A_29 吉岡実 吉岡実全詩集 1996年3月25日 筑摩書房
A_30 吉岡実 詩集 赤鴉 2002年5月31日 弧木洞 歌集〈歔欷〉、句集〈奴草〉
A_31 吉岡実 句集 奴草 2003年4月15日 書肆山田
A_32 平出隆 監修 現代詩読本――特装版 吉岡実 1991年4月15日 思潮社 代表詩40選、ほか
A_33 吉岡実 他 私のうしろを犬が歩いていた――追悼・吉岡実 1996年11月30日 書肆山田 るしおる別冊、吉岡実遺稿ほか
A_34 Yoshioka Minoru Lilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka 1976年 Chicago Review Press tr. Hiroaki Sato
A_35 Yoshioka Minoru Celebration In Darkness 1985年 Oakland University tr. Onuma Tadayoshi、第⑧詩集までの英訳(原文付)詩抄
A_36 Yoshioka Minoru Kusudama 1991年 FACT International tr. Eric Selland
A_37 吉岡実 編纂 耕衣百句 1976年6月21日 コーベブックス
B_001 秋元幸人 吉岡実アラベスク 2002年5月31日 書肆山田
B_002 アスベスト館 監修 土方巽舞踏写真集 危機に立つ肉体 1987年1月20日 PARCO出版局
B_003 アデマ、ピエール=マルセル 虐殺された詩人アポリネール 1977年11月16日 講談社 鈴木豊訳
B_004 アポリネール、ギヨーム アポリネール詩集 1969年12月30日 新潮社 堀口大學訳、新潮文庫
B_005 荒井由実 MISSLIM 1974年10月5日 ALFA
B_006 飯島耕一 飯島耕一詩集 2 1978年2月20日 小沢書店
B_007 飯島耕一 現代の詩人 10 飯島耕一 1983年10月20日 中央公論社 大岡信・谷川俊太郎編集
B_008 飯島耕一 虹の喜劇[コメディ] 1988年7月15日 思潮社
B_009 池田満寿夫 my imagination map――未発表デッサン 1956-1965 1974年9月10日 講談社
B_010 池田満寿夫 思考する魚 1974年11月25日 番町書房
B_011 池田満寿夫 エーゲ海に捧ぐ 1977年4月30日 角川書店
B_012 池田満寿夫 私の調書 1977年10月30日 角川書店 角川文庫 3996
B_013 池田満寿夫 池田満寿夫グラフィティ 1977年11月10日 潮出版社
B_014 池田満寿夫 池田満寿夫 BOOK WORK 1978年3月1日 形象社
B_015 池田満寿夫 池田満寿夫全詩集 1979年11月15日 水兵社+深夜叢書社
B_016 池田満寿夫 女のいる情景 1988年7月25日 日本経済新聞社
B_017 井上靖 楼蘭 1959年5月10日 講談社
B_018 梅田晴夫 蓄音機の歴史 1976年9月10日 PARCO出版局
B_019 大江健三郎 大江健三郎全作品 6 1966年4月25日 新潮社
B_020 大岡信 ミクロコスモス 瀧口修造 1984年12月24日 みすず書房
B_021 小山内龍 昆虫放談 1978年1月10日 築地書館
B_022 小澤實 砧 1986年1月25日 牧羊社 処女句集シリーズ Ⅱ・5
B_023 鍵谷幸信 詩人 西脇順三郎 1983年7月1日 筑摩書房
B_024 梶原和男 編 ヒッチコック ヒロイン 1991年5月30日 芳賀書店 シネアルバム 129
B_025 片山健 美しい日々 1969年12月10日 幻燈社
B_026 加藤郁乎 形而情学 1966年9月30日 昭森社
B_027 加藤郁乎 後方見聞録 2001年10月19日 学習研究社 学研M文庫
B_028 金井美恵子 愛の生活 1968年8月20日 筑摩書房 〈愛の生活〉の初出は《展望》1967年8月号
B_029 金子民雄 宮沢賢治と西域幻想 1988年1月25日 白水社
B_030 カマル社・桑原茂夫 編 COLLECTION少女図鑑 1983年11月30日 冬樹社
B_031 神谷光信 評伝 鷲巣繁男 1998年12月25日 小沢書店
B_032 川崎市岡本太郎美術館・慶應義塾大学アート・センター 編 土方巽の舞踏――肉体のシュルレアリスム 身体のオントロジー 2004年1月10日 慶應義塾大学出版会
B_033 河原枇杷男 河原枇杷男全句集 2003年9月23日 序曲社
B_034 菅野昭正 ステファヌ・マラルメ 1985年10月25日 中央公論社
B_035 菅野昭正 セイレーンの歌――フランス文学論集 1993年12月20日 小沢書店
B_036 北村太郎 北村太郎詩集 1947~1966 1966年11月1日 思潮社
B_037 城戸朱理 吉岡実の肖像 2004年4月15日 ジャプラン
B_038 キャロル、ルーイス 不思議の国のアリス 1952年3月30日 角川書店 岩崎民平訳、角川文庫 317
B_039 キャロル、ルーイス 鏡の国のアリス 1959年10月10日 角川書店 岡田忠軒訳、角川文庫 1847
B_040 清岡卓行 抒情の前線――戦後詩十人の本質 1970年3月30日 新潮社 新潮選書
B_041 草野心平 詩集 絲綢之路――シルクロード詩篇 1985年12月20日 思潮社 大半の詩篇は既刊詩集からの再録
B_042 クラウセン、ルーシー・W 昆虫のフォークロア 1993年5月10日 博品社 小西正泰・小西正捷訳
B_043 クレベール、ジャン=ポール 動物シンボル事典 1989年10月25日 大修館書店 竹内信夫ほか訳
B_044 黒川洋一 注 中国詩人選集 9 杜甫 上 1957年12月20日 岩波書店 吉川幸次郎・小川環樹編集・校閲
B_045 小林一郎 編 吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第2版〕 2000年12月31日 文藝空間
B_046 小宮清 満州メモリー・マップ 1990年12月5日 筑摩書房 著者による挿画多数、ちくまプリマーブックス 48
B_047 埼玉県立近代美術館 編 現代の白と黒 1986年10月か 埼玉県立近代美術館
B_048 西東三鬼 西東三鬼句集 1965年8月30日 角川書店 神田秀夫解説、角川文庫 2329
B_049 坂巻良亮 撮影 High Heel――踵の形而上学 1993年8月20日 心交社 フェティシズム叢書 8
B_050 笹野堅 校訂 能狂言(中) 1943年7月26日 岩波書店 岩波文庫
B_051 佐藤良明 ラバーソウルの弾みかた――ビートルズから《時》のサイエンスへ 1989年7月10日 岩波書店
B_052 佐成謙太郎 謡曲大観 第一巻 1930年10月20日〔影印版:1982年4月20日〕 明治書院
B_053 サロート・ロブ=グリエ・C・モーリアック アンチ・ロマン集 1970年11月1日 筑摩書房 平岡篤頼・天沢退二郎・三輪秀彦訳、世界文学全集65
B_054 篠田一士 現代詩髄脳 1982年2月10日 集英社
B_055 篠田一士 現代詩人帖 1984年6月20日 新潮社
B_056 司馬遷 史記列伝 5 1975年12月16日 岩波書店 小川環樹・今鷹真・福島吉彦訳、岩波文庫
B_057 柴田健作・十河和康 馬――その生涯 1977年3月5日 保育社 カラーブックス 389
B_058 澁澤龍彦 幻想の画廊から 1967年12月20日 美術出版社
B_059 澁澤龍彦 澁澤龍彦集成 第Ⅴ巻 1970年6月30日 桃源社
B_060 澁澤龍彦 編著 M・W・スワーンベリ 1976年7月30日 河出書房新社 シュルレアリスムと画家叢書「骰子の7の目」別巻
B_061 澁澤龍彦 幻想の彼方へ 1976年8月5日 美術出版社
B_062 澁澤龍彦 ビブリオテカ澁澤龍彦 Ⅵ 1980年3月15日 白水社
B_063 澁澤龍彦 玩物草紙 1986年3月10日 中央公論社 中公文庫、初刊は1979年
B_064 澁澤龍彦 幻想の肖像 1986年10月4日 河出書房新社 河出文庫、初刊は1975年
B_065 澁澤龍彦 幻想の彼方へ 1988年10月4日 河出書房新社 河出文庫、初刊は1976年
B_066 澁澤龍彦 澁澤龍彦全集 9 1994年2月12日 河出書房新社
B_067 清水靖彦 日本枕考 1991年10月25日 勁草書房
B_068 ジムフェレール、ペル マグリット 1987年10月30日 美術出版社 横倉れい訳、現代美術の巨匠
B_069 シャルメ、レイモン クロヴィス・トルイユ 1974年9月25日 河出書房新社 種村季弘訳、シュルレアリスムと画家叢書「骰子の7の目」第4巻
B_070 シュニーデ、ウーヴェ・M 解説 シュールレアリズム 1980年5月25日 美術出版社 山脇一夫訳、世界の巨匠シリーズ
B_071 ジョイス、ジェイムズ ユリシーズ Ⅰ 1964年8月10日 河出書房新社 丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳、世界文学全集 Ⅱ-13
B_072 ジョイス、ジェイムズ ユリシーズ Ⅱ 1964年11月15日 河出書房新社 丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳、世界文学全集 Ⅱ-14
B_073 城市郎 性の発禁本 1993年2月4日 河出書房新社 河出文庫
B_074 白川静 中国の神話 1980年2月10日 中央公論社 中公文庫 し-20-1、初刊1975年
B_075 新村出 編 広辞苑 第二版 1969年5月16日 岩波書店
B_076 杉浦正一郎・宮本三郎・荻野清 校注 芭蕉文集 1959年10月5日 岩波書店 日本古典文学大系 46
B_077 スタン、ロルフ 盆栽の宇宙誌 1985年11月6日 せりか書房 福井文雅・明神洋訳、アジア文化叢書
B_078 スポトー、ドナルド アート・オブ・ヒッチコック――53本の映画術 1994年3月10日 キネマ旬報社 関美冬訳
B_079 千田稔 うずまきは語る――迷宮への求心性 1991年5月24日 福武書店 Fukutake Books 26
B_080 曽布川寛 崑崙山への昇仙――古代中国人が描いた死後の世界 1981年12月20日 中央公論社 中公新書 635
B_081 高橋康也 ノンセンス大全 1977年1月10日 晶文社
B_082 高柳重信 作品集 黒彌撒 1956年7月 琅玕〔カン〕洞
B_083 瀧口修造 コレクション瀧口修造 5 1994年5月25日 みすず書房 〈余白に書く Ⅱ 1971-1979〉
B_084 種村季弘 ナンセンス詩人の肖像 1969年9月15日 竹内書店
B_085 種村季弘 編 澁澤龍彦 1993年8月10日 新潮社 新潮日本文学アルバム 54
B_086 種村季弘 土方巽の方へ――肉体の六〇年代 2001年5月30日 河出書房新社
B_087 田村隆一 田村隆一全詩集 2000年8月26日 思潮社
B_088 筑摩書房編集部 編 現代世界ノンフィクション全集 1 1966年5月25日 筑摩書房 スウェン・ヘディン著・岩村忍訳《中央アジア探検記》ほか
B_089 中国人民美術出版社 編 新疆の旅 1981年4月20日 美乃美 中国カラー文庫 1
B_090 陳舜臣 シルクロードの旅 1991年6月15日 講談社 講談社文庫 ち-1-35、初刊は1977年
B_091 塚本邦雄 麒麟騎手――寺山修司論 1974年7月10日 新書館
B_092 塚本邦雄 評論集 煉獄の秋 1974年11月15日 人文書院
B_093 塚本邦雄 ことば遊び悦覧記 1980年3月20日 河出書房新社
B_094 辻井喬 詩集 群青、わが黙示 1992年7月1日 思潮社
B_095 〔ディオスコリデス〕 ディオスコリデスの薬物誌 1983年5月15日 エンタプライズ 鷲谷いづみ訳
B_096 出久根達郎 古本綺譚 1990年3月10日 中央公論社 中公文庫
B_097 藤堂明保 西域紀行――シルクロードの歴史と旅 1984年1月25日 旺文社 旺文社文庫 228-1、初刊は1978年
B_098 東野芳明 ほか 世界名画全集 25 今日の世界絵画 1961年5月30日 平凡社 〈未来の象徴と記号の探検〉
B_099 中上健次 夢の力 1979年2月27日 北洋社
B_100 永田耕衣 還暦記念句集 與奪鈔 1960年4月11日 琴座俳句会 《驢鳴集》の初刊は1952年
B_101 中西夏之 大括弧――緩やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置 1989年4月1日 筑摩書房
B_102 中野美代子 孫悟空の誕生――サルの民話学と『西遊記』 1980年10月5日 玉川大学出版部 のち福武文庫
B_103 中野美代子 カニバリズム論 1987年7月15日 福武書店 福武文庫、初刊は1972年の《迷宮としての人間》(潮出版社)
B_104 中野美代子 仙界とポルノグラフィー 1989年6月30日 青土社
B_105 中野美代子 ひょうたん漫遊録――記憶の中の地誌 1991年5月25日 朝日新聞社 朝日選書 425
B_106 中野美代子 龍の住むランドスケープ――中国人の空間デザイン 1991年10月22日 福武書店
B_107 中村宏 画集 望遠鏡からの告示 1968年2月25日 現代思潮社
B_108 中村宏 図画蜂起 1955-2000 2000年9月1日 美術出版社
B_109 夏目漱石 明暗(上) 1969年9月15日 新潮社 新潮文庫、初刊は1917年
B_110 ナボコフ、ウラジーミル ロリータ 上巻 1959年2月12日 河出書房新社 大久保康雄訳
B_111 西脇順三郎 詩學 1968年2月29日 筑摩書房 のち筑摩叢書 136
B_112 西脇順三郎 定本西脇順三郎全詩集 1981年1月20日 筑摩書房
B_113 西脇順三郎 雑談の夜明け 1989年4月10日 講談社 講談社学術文庫、初刊は1978年
B_114 日本アート・センター 編 ルソー 1975年3月25日 新潮社 新潮美術文庫 33
B_115 日本アート・センター 編 デュシャン 1976年4月25日 新潮社 新潮美術文庫 49
B_116 日本大辞典刊行会 編 日本国語大辞典 第六巻 1973年11月1日 小学館
B_117 萩原朔太郎 萩原朔太郎全詩集 1979年12月20日 筑摩書房
B_118 橋本朝生・土井洋一 校注 狂言記 1996年11月20日 岩波書店 佐竹昭広ほか編、新 日本古典文学大系58
B_119 長谷川郁夫 われ発見せり――書肆ユリイカ・伊達得夫 1992年6月15日 書肆山田
B_120 バナーマン、ヘレン 作・絵 ちびくろさんぼのおはなし 1999年5月20日 径書房 なだもとまさひさ訳
B_121 土方巽ほか 詩画集 土方巽舞踏展 あんま 1968年12月1日 アスベスト館 〈土方巽と日本人――肉体の叛乱〉公演記念出版
B_122 土方巽 病める舞姫 1983年3月10日 白水社
B_123 土方巽 美貌の青空 1987年1月21日 筑摩書房
B_124 平島裕正 塩 1973年5月10日 法政大学出版局 ものと人間の文化史
B_125 福田邦夫 色の名前ポケット図鑑 1994年11月10日 主婦の友社
B_126 福田宏年 増補 井上靖評伝覚 1991年10月10日 集英社 初刊は1979年
B_127 ヘディン、スウェン 中央亞細亞探檢記 1938年11月10日 冨山房 岩村忍訳、冨山房百科文庫 48
B_128 ヘディン、スウェン 彷徨へる湖 1943年4月20日 筑摩書房 岩村忍・矢崎秀雄訳
B_129 ヘディン、スウェン 中央亞細亞探檢記 1953年9月15日 角川書店 岩村忍訳、角川文庫 658
B_130 ヘディン、スウェン 中央アジヤ探検記 1953年9月30日 創元社 岩村忍訳、創元文庫 D78
B_131 ヘディン、スウェン アジアの砂漠を越えて(上) 1964年7月25日 白水社 横川文雄訳、ヘディン中央アジア探検紀行全集 1
B_132 ヘディン、スウェン さまよえる湖 1968年3月30日 角川書店 岩村忍訳、角川文庫 2505
B_133 ベルメール、ハンス イマージュの解剖学 1975年10月30日 河出書房新社 種村季弘・瀧口修造訳
B_134 ボードレール 全訳 悪の華 1961年3月5日 角川書店 村上菊一郎訳、角川文庫 18
B_135 ポール・デルボー展カタログ編集委員会 編 ポール・デルボー展 1975年3月か 毎日新聞社
B_136 堀内敬三・井上武士 編 日本唱歌集 1958年12月20日 岩波書店 岩波文庫
B_137 マーティン、ジョージ メイキング・オブ・サージェント・ペパー 1996年5月1日 キネマ旬報社 水木まり訳
B_138 牧逸馬 浴槽の花嫁――世界怪奇実話Ⅰ 1975年6月15日 社会思想社 現代教養文庫 851
B_139 松田壽男 松田壽男著作集 4 1987年3月25日 六興出版 〈東西文化の交流Ⅱ〉
B_140 真鍋博 コレクション瀧口修造 10 1991年5月30日 みすず書房 月報
B_141 マラルメ・ヴァレリー マラルメ詩集・ヴァレリー詩集 1969年8月20日 新潮社 西脇順三郎・平井啓之・菅野昭正・清水徹訳、世界詩人全集 10
B_142 丸谷才一 遊び時間 2 1983年7月10日 中央公論社 中公文庫、初刊は1980年
B_143 丸谷才一 猫だつて夢を見る 1989年10月25日 文藝春秋
B_144 三島由紀夫 天人五衰――豊饒の海 第四巻 1971年2月25日 新潮社
B_145 水野祥太郎 包帯 1982年11月29日 文光堂
B_146 水村孝 楼蘭の詩 1990年6月10日 朝日新聞社 岑参詩は中野美代子〈楼蘭の詩〉に依る
B_147 三橋敏雄 三橋敏雄 1992年9月25日 花神社 花神コレクション〔俳句〕 藤田湘子監修
B_148 三好豊一郎 現代詩文庫 37 三好豊一郎 1970年11月1日 思潮社
B_149 三輪和雄 夢の科学 1984年6月20日 新潮社 新潮選書
B_150 村松嘉津 プロヷ〔ワに濁点〕ンス隨筆 1947年8月20日 東京出版
B_151 村松嘉津 新版 プロヴァンス隨筆 1970年3月15日 大東出版社
B_152 モーム、サマセット 秘密諜報部員 1959年5月21日 東京創元社 龍口直太郎訳、創元推理文庫 115-1
B_153 森茉莉 記憶の絵 1968年11月30日 筑摩書房
B_154 八木忠栄 詩人漂流ノート 1986年8月25日 書肆山田
B_155 矢島文夫 ヴィーナスの神話 1970年12月25日 美術出版社 美術選書
B_156 安間繁樹 アニマル・ウォッチング――日本の野生動物 1985年7月15日 晶文社
B_157 藪下信 彗星の本 1984年6月10日 地人書館
B_158 山口昌男 知の祝祭 1977年11月20日 青土社
B_159 山下愉一 禁断の絵本――幻想と美と陶酔と 1970年5月1日 ベストセラーズ
B_160 横尾忠則 横尾忠則全絵画 1996年4月25日 平凡社 難波英夫監修
B_161 横尾忠則 名画 裸婦感応術 2001年6月15日 光文社 知恵の森文庫
B_162 吉本隆明 共同幻想論 1968年12月5日 河出書房新社
B_163 吉行淳之介 詩とダダと私と 1986年7月15日 福武書店 福武文庫、初刊は1979年
B_164 四谷シモン 四谷シモン 人形愛 1985年6月10日 美術出版社 篠山紀信写真
B_165 レノン、ジョン・マッカートニー、ポール ビートルズ詩集(二) 1973年6月15日 角川書店 片岡義男訳、角川文庫
B_166 鷲巣繁男 定本 鷲巣繁男詩集 1971年9月1日 国文社
B_167 鷲巣繁男 詩集 行為の歌 1981年4月20日 小澤書店
B_168 渡辺孝 ミツバチの文化史 1994年5月25日 筑摩書房
B_169 ―― 新潮世界美術辞典 1985年2月20日 新潮社
B_170 ―― 大百科事典 5 1984年11月2日 平凡社
B_171 ―― 大百科事典 7 1985年3月25日 平凡社
B_172 ―― 大百科事典 15 1985年6月28日 平凡社
B_173 ―― 種村季弘のラビリントス〔内容見本〕 1979年1月か 青土社
B_174 ―― ベネチア・ビエンナーレ グラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展 〔1967年1月13日 京王百貨店〕
B_175 Gernsheim, Helmut Lewis Carroll-Photographer 1969年 Dover Publications 初刊は1949年
B_176 Prevost, Clovis Parcours a travers l'oeuvre de Clovis Trouille, 1889-1975 2003年 ACTES SUD 初刊は1999年
C_001 ―― アトリヱ 1939年10月1日 アトリヱ出版社 第16巻11号
C_002 ―― 季刊藝術 1968年7月1日 季刊藝術出版 第2巻第3号
C_003 ―― 月刊ポエム 1978年1月1日 すばる書房 第3巻第1号
C_004 ―― 現代詩 1963年1月1日 飯塚書店 第10巻第1号 〈新春対談〉
C_005 ―― 現代詩手帖 1967年10月1日 思潮社 第10巻第10号
C_006 ―― 現代詩手帖 1967年12月1日 思潮社 第10巻第12号
C_007 ―― 現代詩手帖 1968年12月1日 思潮社 第11巻第12号
C_008 ―― 現代詩手帖 1975年5月1日 思潮社 第18巻第5号
C_009 ―― 現代詩手帖 1978年10月1日 思潮社 第21巻第10号 特集=戦後詩の10篇
C_010 ―― 現代詩手帖 1980年10月1日 思潮社 第23巻第10号
C_011 ―― 現代詩手帖 1982年7月1日 思潮社 第25巻第7号
C_012 ―― 現代詩手帖 1984年6月1日 思潮社 第27巻第6号
C_013 ―― 現代詩手帖 1987年7月1日 思潮社 第25巻第7号
C_014 ―― 現代詩手帖 1990年7月1日 思潮社 第33巻第7号
C_015 ―― 別冊現代詩手帖――ルイス・キャロル 1972年6月1日 思潮社 第1巻第2号.〈アリスの不思議な国あるいはノンセンスの迷宮〉
C_016 ―― 詩学 1977年2月28日 詩学社 第32巻第3号通巻第320号〔3月号〕
C_017 ―― 詩と批評 1966年10月1日 昭森社 第1巻第6号
C_018 ―― 鷹 1989年10月5日 鷹俳句会 第26巻第10号通巻第304号
C_019 ―― 高見順文学振興会会報 1982年1月30日 高見順文学振興会 第1巻
C_020 ―― W-NOtation(ダブル・ノーテーション) 1985年7月23日 ユー・ピー・ユー 第2号
C_021 ―― 中央公論 1976年2月1日 中央公論社 第91年第2号
C_022 ―― 中央公論文芸特集 1988年9月25日 中央公論社 第5巻第3号秋季号
C_023 ―― 投壜通信 1994年12月15日 矢立出版 通巻第19号
C_024 ―― 日本経済新聞 1991年8月10日 日本経済新聞社 Weekend Nikkei
C_025 ―― 日本経済新聞 1992年9月23日 日本経済新聞社
C_026 ―― 俳句評論 1968年3月30日 俳句評論社 第10巻第3号
C_027 ―― 美術手帖 1981年8月1日 美術出版社 第485号
C_028 ―― 文學界 1959年11月1日 文藝春秋新社 第13巻第11号
C_029 ―― 文藝 1968年8月1日 河出書房新社 第7巻第6号
C_030 ―― 文藝空間 1983年8月1日 文藝空間 第2巻第1号通巻第5号
C_031 ―― 本の手帖 1969年3月1日 昭森社 第9巻第2号
C_032 ―― みづゑ 1949年3月3日 美術出版社 通巻520号
C_033 ―― みづゑ 1949年12月3日 美術出版社 通巻530号
C_034 ―― みづゑ 1967年11月3日 美術出版社 通巻754号
C_035 ―― 無限 1959年9月1日 政治公論社 第2号
C_036 ―― 夜想 1986年10月 ペヨトル工房 第19号
C_037 ―― ユリイカ 1960年6月1日 書肆ユリイカ 第5巻第6号
C_038 ―― ユリイカ 1972年4月1日 青土社 第4巻第4号
C_039 ―― ユリイカ 1973年9月1日 青土社 第5巻第10号
C_040 ―― ユリイカ 1975年10月1日 青土社 第7巻第9号
C_041 ―― ユリイカ 1987年11月1日 青土社 第19巻第12号
C_042 ―― ユリイカ 1989年6月1日 青土社 第21巻第7号
C_043 ―― ユリイカ 1989年7月1日 青土社 第21巻第9号
C_044 ―― ユリイカ 1990年7月1日 青土社 第22巻第8号
C_045 ―― ユリイカ臨時増刊号 1975年12月20日 青土社 第7巻第12号
C_046 ―― 雷帝 1993年11月28日 深夜叢書社 創刊終刊号
C_047 ―― 琴座 1966年1月1日 琴座俳句会 通巻第192号第18巻第1号
C_048 ―― 琴座 1969年2月1日 琴座俳句会 通巻第226号
C_049 ―― 琴座 1975年11月10日 琴座俳句会 11・12月号 通巻第300号記念特集号
C_050 ―― るしおる 1990年5月31日 書肆山田 通巻第6号
C_051 ―― るしおる 2006年7月25日 書肆山田 通巻第61号
C_052 ―― わたしたちのしんぶん(筑摩書房労組機関紙) 1968年7月31日 筑摩書房 第90号
みなづきの水――追悼吉岡実
《文藝空間 会報》第17号(1990年7月7日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第46号(2007年1月31日)
標題はもろだけんじによる吉岡実追悼句の一節。二〇〇七年一月、ウェブページ《吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈》掲載にあたって、初稿の字句を整えた。末尾註の「吉岡実の〈未刊行詩篇〉」には追記すべき数篇の作品があるが、あえて追悼文執筆時のままとした。未刊詩篇の詳細に関しては、本サイト上の拙編《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第3版〕》(文藝空間、2012)や冊子体の《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第2版〕》(文藝空間、2000)を参照されたい。
「暗黒の祝祭」――〈青い柱はどこにあるか?〉
《文藝空間》第7号(1987年12月1日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第33号(2005年8月31日)「愛と不信の双貌」を改題
標題は吉岡実の日記(一九六七年七月三日)から藉りた。初稿を本文に則して改題し、二〇〇五年七月二六日から八月三一日にかけて全面改稿した。
「愛と不信の双貌」――〈夏から秋まで〉
《文藝空間 会報》第7号(1988年11月2日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第34号(2005年11月30日)「暗黒の祝祭」を改題
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。初稿を改題し、二〇〇五年九月二三日から一一月三〇日にかけて加筆訂正した。《ベネチア・ビエンナーレ グラン・プリ受賞記念 池田満寿夫銅版画展》の所蔵情報に関して、横山朝夫さんからご教示いただいた。記して感謝する。
「白紙状態」――〈立体〉
《文藝空間 会報》第14号(1989年11月5日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第35号(2006年1月31日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年一月、ウェブページ掲載にあたり、初稿を訂正した。初稿のモノクロ図版(本文で言及したマグリットの〈釘づけにされた時間〉〈良いお手本〉〈旅の思い出〉〈危険な関係〉の四点)は割愛した。
「増殖と回転」――〈マクロコスモス〉
《文藝空間 会報》第17号(1990年7月7日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第36号(2006年2月28日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年二月、ウェブページ掲載にあたり、初稿を訂正し、図版一点を追加した。
「造形への願望」――〈フォークソング〉
《文藝空間 会報》第18号(1991年7月7日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第37号(2006年3月31日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年三月、ウェブページ掲載にあたり、初稿を訂正し、写真一点を追加した。撮影者の大日方公男さんに感謝する。
「細部の変遷」――〈色彩の内部〉
《文藝空間 会報》第19号(1991年9月28日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第38号(2006年5月31日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年五月、ウェブページ掲載にあたり、初稿に訂正を施した。
「意識のながれ」――〈神秘的な時代の詩〉
《文藝空間》第8号(1992年4月16日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第39号(2006年6月30日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年六月、ウェブページ掲載にあたり、初稿に訂正を施した。
「矢印を走らせて」――〈崑崙〉
《文藝空間 会報》第21号(1992年8月31日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第40号(2006年7月31日)
標題は吉岡実の詩論〈わたしの作詩法?〉から藉りた。二〇〇六年七月、ウェブページ掲載にあたり、初稿に加筆訂正を施した。
「固い雨なら両手で愛撫する」――〈雨〉
《文藝空間》第9号(1993年10月1日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第41号(2006年8月31日)
標題は吉岡実の詩篇〈固形〉から藉りた。二〇〇六年八月、ウェブページ掲載にあたり、初稿(一九九三年五月三一日脱稿)に加筆訂正を施した。
「少女の夢のはらみ方」――〈少女〉
《文藝空間 会報》第24号(1994年10月20日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第42号(2006年9月30日)
標題は初出〈少女〉にありながら定稿で削除された詩句から藉りた。Ⅲは旧稿〈「内面のリアリティ」――吉岡実論のためのノート〉の一節「〈ルイス・キャロルを探す方法〉あるいは詩人・装幀家」(《文藝空間》第5号、1983年8月1日、九~一三ページ)を訂正加筆したもの。二〇〇六年九月、ウェブページ掲載にあたり、初稿(一九九四年九月一八日脱稿)に訂正を施した。詩篇〈ルイス・キャロルを探す方法〉の初出形に関しては、《〈吉岡実〉の「本」》の〈吉岡実のレイアウト(2)〉に掲載誌面の写真を掲げ、本稿の一部を引用している。
「わたしと女友だちと娘のような妹」――〈三重奏〉
《文藝空間 会報》第25号(1996年9月28日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第43号(2006年10月31日)
標題は対象詩篇〈三重奏〉本文の詩句を元にした。二〇〇六年一〇月、ウェブページ掲載にあたり、初稿(一九九六年一月六日脱稿)に訂正を施した。初稿擱
筆後、日ならずして住居の建てかえに及び、引用文の照合に支障をきたした。春先に母すみえを喪くした(享年六十八)。夏に組版をMacintoshの
PageMaker 6.0J(当時の最新版)で作業し、八月三〇日に校了した。心覚えとして記しておく。
「恋する幽霊」――〈蜜はなぜ黄色なのか?〉
《文藝空間 会報》第26号(2000年9月28日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第44号(2006年11月30日)
標題は対象詩篇〈蜜はなぜ黄色なのか?〉本文の詩句から藉りた。二〇〇六年一一月、ウェブページ掲載にあたり、〈三重奏〉評釈の発表から思わぬ間が空いてしまった初稿に訂正を施した。
「あるいは孤独な落下傘部隊」――〈夏の家〉
《文藝空間 会報》第27号(2001年11月30日)〔初稿〕
《文藝空間 会報》第45号(2006年12月31日)
二〇〇六年一二月、ウェブページ掲載にあたり、初稿に訂正を施した。
「死馬の眼」――〈わが馬ニコルスの思い出〉
《文藝空間 会報》第28号(2003年6月30日)
標題は詩篇〈影絵〉の詩句から藉りた。執筆は二〇〇一年から二〇〇三年六月にかけて行なった。Ⅱで言及した「〈アリス〉詩を集成したもの」はそこにも書いたように本評釈の詩篇〈少女〉で触れているが、その後、架空の書《詩の国のアリス――吉岡実による『アリス詩集』》(文藝空間、2015年11月30日)を編んだ。詳細は〈吉岡実の〈アリス詩篇〉あるいは《アリス詩集》〉を参照されたい。
「紅血の少女」――〈聖少女〉
《文藝空間 会報》第29号(2003年8月31日)
標題は詩篇〈聖少女〉初出形の詩句から藉りた。執筆は二〇〇三年七月から八月にかけて行なった。
「部分からその全体が現われるまで」――〈コレラ〉
《文藝空間 会報》第30号(2003年10月31日)
標題は詩篇〈鄙歌〉の詩句から藉りた。執筆は二〇〇三年九月から一〇月にかけて行なった。
「ブランコのりのナウシカア」――〈低音〉
《文藝空間 会報》第31号(2003年12月31日)
標題は対象詩篇〈低音〉と《ユリシーズ》の〈〔13 ナウシカア〕〉から藉りた。執筆は二〇〇三年一二月に行なった。
「花瓣的な奥深いもの」――〈弟子〉
《文藝空間 会報》第32号(2005年3月31日)
標題は詩篇〈弟子〉の初出形から藉りた。執筆は二〇〇五年三月に行なった。
神秘的な時代の詩〔集〕――長篇詩の試み
《文藝空間 会報》第47号(2007年5月31日)
標題は対象詩集の題名を元にした。執筆は二〇〇七年四月から五月にかけて行なった。〈文献表――吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〉の内容が定まったので、#〔分類_番号〕を変更して振りなおした。
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異
二〇〇九年一二月三一日、本サイトに初めて掲載したので、先行する印刷物は存在しない。
必要があって《吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈》を全ページ(A4判縦位置で印刷すると約306ページ)、プリントアウトして読みかえした。公開時に充分チェックしたつもりだったが、何箇所か誤りを見つけた。最終更新(2013年5月31日)以降の状況の変化に対応した修正も必要だったので、字句の訂正や追記の形で本文に手を入れた。→で異同を示す箇所の(削除)は(トル)に統一した。KompoZerのバグによる不要の半角スペースは、ひとつひとつ手で修正した。引用した詩篇のふりがなは 〈ruby〉のタグを用いて原文を再現していたが、画面上でもプリントアウト上でも意図した表示になっていないので、ふりがなを[ ]に入れる方式に変更した(傍点も同じ)。引用といえば、詩句の行数を表示するライナーが行頭にあったり行末にあったりしてまちまちだが、各評釈の執筆時点で良かれと思う書き方に拠ったのであえて統一しなかった。これをもって現時点での定稿とし、吉岡実歿後二十六年の記念としたい。(2016年5月31日)
詩集《神秘的な時代の詩》各詩篇の解釈に関わる詩句の異同は、それぞれ吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈で言及したが、以下に全詩篇の本文校異を掲げる。本稿では、0 雑誌・新聞掲載用入稿原稿形、1 初出雑誌・新聞掲載形、2 《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、1974)掲載形、3 《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、1975)掲載形、4 《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、1976)掲載形、5 《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)掲載形のうち、1から5までの詩句を校合した本文とその校異を掲げた。これにより、吉岡が詩集《神秘的な時代の詩》各詩篇の初出形本文にその後どのように手を入れたか、たどることができる。本稿は印刷上の細かな差異(具体的には、漢字の字体の違い)を指摘することが主眼ではないので、シフトJISのテキストとして表示できる漢字はそれを優先した。このため、ユニコードによる「蠟」の代わりに、不本意ながらシフトJISの「蝋」を使用している点をご諒解いただきたい。なお、漢字が新字の本文の新字以外の漢字は、シフトJISのテキストで表示可能なかぎり、校異としてこれを載録した。初めに《神秘的な時代の詩》各本文の記述・組方の概略を記す。
0 雑誌・新聞掲載用入稿原稿:詩集掲載用入稿原稿とともに2009年12月の時点で未見だが、漢字は新字、かなは新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字すなわち捨て仮名)で書かれたと考えられる(〈聖少女〉の原稿を参照されたい)。
1 初出雑誌・新聞:各詩篇の本文前に記載した。本文の表示は基本的に新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用なので、特記なき場合はこれを表わす。
2 《神秘的な時代の詩〔限定版〕》(湯川書房、1974年10月20日):初刊詩集。本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号12行1段組。
3 《神秘的な時代の詩〔特装版〕》(湯川書房、1975年6月1日):再刊詩集。本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、12ポ13行1段組。
4 《神秘的な時代の詩〔普及版〕》(書肆山田、1976年8月15日):三刊詩集。本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号15行1段組。
5 《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996年3月25日):本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ19行1段組。なお《吉岡実全詩集》の底本は4 《神秘的な時代の詩〔普及版〕》。
ひらがな・カタカナの拗促音の表記は、最終形を収めた《吉岡実全詩集》に合わせて小字に統一した。詩篇のアステリスク(*)の位置すなわち字下げは、《吉岡実全詩集》に倣って三字下げに統一し、何字下げかは校異の対象としなかった。詞書(改行箇所は「/」で表わした)や註記の字下げも《吉岡実全詩集》に合わせた。なお《ユリイカ》1973年9月号〈特集=吉岡実〉掲載の〈吉岡実新詩集神秘的な時代の詩・抄〉――〈低音〉〈神秘的な時代の詩〉〈三重奏〉〈蜜はなぜ黄色なのか?〉〈崑崙〉〈色彩の内部〉〈スワンベルグの歌〉〈聖少女〉〈コレラ〉の9篇を再録――は刊本でないため、割愛した(〈吉岡実新詩集 神秘的な時代の詩・抄〉については〈詩集《神秘的な時代の詩》解題〉を参照されたい)。なお〈吉岡実詩集本文校異について〉を参照のこと。
…………………………………………………………………………………………………………
《神秘的な時代の詩》詩篇細目
詩篇標題(詩集番号・掲載順、詩篇本文行数、初出《誌紙名》〔発行所名〕掲載年月(号)〔(巻)号〕)
〈マクロコスモス〉(⑦・1、70行、《三田新聞》〔三田新聞学会〕1967年11月22日〔1146号〕)
〈夏から秋まで〉(⑦・2、64行、《文学者》〔文学者発行所〕1967年8月号〔10巻8号〕)
〈立体〉(⑦・3、61行、《現代詩手帖》〔思潮社〕1967年10月号〔10巻10号〕)
〈色彩の内部〉(⑦・4、42行、《the high school life》〔MAC〕1968年8月〔15号〕)
〈少女〉(⑦・5、42行、《血と薔薇》〔天声出版〕1969年1月〔2号〕)
〈青い柱はどこにあるか?〉(⑦・6、51行、高井富子舞踏公演〈形而情学〉チラシ1967年7月3日)
〈フォークソング〉(⑦・7、45行、《同時代》〔黒の会〕1968年7月〔23号〕)
〈崑崙〉(⑦・8、147行、《南北》〔南北社〕1968年10月号〔3巻10号〕)
〈雨〉(⑦・9、66行、《現代詩手帖》〔思潮社〕1968年11月号〔11巻11号〕)
〈聖少女〉(⑦・10、22行、《小説新潮》〔新潮社〕1969年11月号〔23巻11号〕)
〈神秘的な時代の詩〉(⑦・11、103行、《季刊藝術》〔季刊藝術出版〕1968年10月〔秋・2巻4号〕)
〈蜜はなぜ黄色なのか?〉(⑦・12、29行、《郵政》〔郵政弘済会〕1969年4月号〔21巻4号〕)
〈夏の家〉(⑦・13、39行、《ユリイカ》〔青土社〕1969年8月号〔1巻2号〕)
〈低音〉(⑦・14、23行、《風景》〔悠々会〕1970年3月号〔11巻3号〕)
〈弟子〉(⑦・15、43行、《無限》〔政治公論社〕1972年8月〔29号〕)
〈わが馬ニコルスの思い出〉(⑦・16、*印で5節に分かつ163行、《現代詩手帖》〔思潮社〕1969年10月号〔12巻10号〕)
〈三重奏〉(⑦・17、71行、《本の手帖》〔昭森社〕1969年2・3月号〔9巻2号〕)
〈コレラ〉(⑦・18、97行、《都市》〔都市出版社〕1969年12月〔1号〕)
――――――――――
初出は《三田新聞》〔三田新聞学会〕1967年11月22日〔1146号(創刊50周年記念号)〕9面、本文新聞活字1倍扁平35行1段組、70行、「イラスト・廣瀬俊恵」。
石の建築物といっても永遠
ではない二階から上は
紫の窓
なでられている
ビーナスの尻が見え
戸棚のパイナップルのザラザラの皮が
精神を支配する
洗濯屋が汚れたワイシャツを
もってくる正午
四階に住んでいる
画家と犬はなんだろう?
白塗りの星〔1條→2345条〕旗の下で
叩かれている犬
写真に撮られるべく
ハンバーグを食う
タライのなかの黒人
ぼくらの現況の雨の〔1葺→2345葦〕原から
暁の丘に至るまで
シナの娘が大鎌を振って行く
馬のながい陰茎の岸べ
かくすハハコグサ
タケニグサ
自慰観音
心はつめたく地は熱い今日
だんだんと〔1殖え→2345減〕る
水のなかのトンボの〔1印→2345卵〕
八月の暑い恋びとたちの
コルクのセンを咬む愛
ではどうしよう?
肥大漢のぼくらの姉妹
双生児を生みに行く
長いボール紙の筒があるかね?
それを廻って
ぼくらの肥大の子供は遊ぶんだ
ダンダン畑から採る
輪切りのパイナップル
食べる桃色の人食人種
考える口が見える時まで
だんだんにふとるぼくら肥大漢の兄弟
キリコの木の頭の点線の十字へ
赤い布をかぶせて
白夜の白衣の父なる医者
椅子の上へすわる
異物分娩開始!
たまたまクロブタが鳴く
今夜だれか死にましたか?
スズカケのシームレス靴下の下で
答えて下さい
人のしてないことを
考える人
人のしているあらゆる行為を
善なる悪なる共同幻想
燃えやすい耳
夏のキノコ
鳴けよブルーカナリヤ
空とぶ黒色の
終りの矢印
想像する
紅潮する戦車
そのなかのかずかずのスワン
ヨードチンキの臭う夜を
印刷された死体の極彩色
明くれば涼しい風景を眺めよ!
ぼくらの豊饒な草むら・枯むぐら
粘菌性のマクロコスモス
千紫〔1萬→2345万〕紅の高千穂の峯をふりかえり
鳥肌の世界を反省する
棒高跳選手
バーを越えるとき
不〔1條→2345条〕理な鉄の処女を感じる
初出は《文学者》〔文学者発行所〕1967年8月号〔10巻8号〕二〇~二三ページ、本文9ポ17行1段組、64行。
〔1池 田 満 寿 夫/銅版画展目録より→23(トル)→45池田満寿夫の版画の題名を藉りて〕
レインちゃん 黄色い舌をして
素敵なソプラノの花嫁
それはなんですか
何にする非生物
花のクチナシ
木の机の下で
観念する
夏
聖なる川の楽園に死す
足なえの夏
鏡のうちの青
はずむブルーの球
カメがかむカヤツリグサ
四つ手の網のうえで
S字型の〔123マス→45鱒〕
わたしは食べたくない
姉妹と関係したくない夢
わたしはネコを抱く疑問符の人
すべてのものを満喫したくない
あらゆる壁を剃る
血を剃る
ころびたい愛
曲りたい矢印!
水からさきの水
道からさきの道
涙からさきの眼のランデブー
影からさきの影
具体的な物
賛成!
庭をよこぎる
メタフィジックな牛乳配達自転車
あるいは蛾
レインちゃんおしっこをして行きな!
横たわる人とみつめる人の
前で
ミシンのように
はずかしい
花嫁の領地を占める
ビタミン青空
母なるミカンの房
レインちゃんこぼしちゃだめよ!
赤いセーターを〔1ぬ→2345脱〕ぐ
日まで
オムレツをつくる男
オムレツらしきものをつくる男
はずかしいオムレツをつくり
急ぐ人
ホタルの闇で
肉の入らない記念碑をなでる
秋ならススキがなびく
レインちゃん 靴下のまま
そこで何をみがくの
つかのまの亀甲体?
吊天井の恐しい花嫁のスカート
円を縮小する方へ
すすむ矢印
沼へ沈みゆけ
老婆の乳母車群
めずらしくむらさき色の
渟る矢印
電気ウナギを釣っている〔1(ナシ)→2345男〕
〔1男→2345(トル)〕と同時に見える?
両側へ紐をたらしつつある
神〔1祕→2345秘〕的な靴が――
初出は《現代詩手帖》〔思潮社〕1967年10月号〔10巻10号〕六二~六五ページ、本文五号21行1段組、61行。3では、本篇の標題だけ他よりも3文字分、下に組まれている。
真夏の午後でも
彼らは紳士だから
室内を歩き廻らないだろう?
フロックコートの正装で
立っている
次のドアをひらいたら
ネズミの死骸が少しずつなだれこむ
にちがいない今日の在り方
別のドアを出て行く
ふとった蝶
ひげのはえた紳士が
蓄音機の把手をぐるぐる廻すんだ
暑い夏を暑くするために
ギイギイ音をたてる
なお想起せよ!
破瓜・分娩音
彼らは紳士だから
フロックコートのズボンをぬいで
出窓の端から投網をくりかえすんだ
ずるずるひろがる
暗い網の底から
錯誤の未来性
両の乳房をつきだして
花嫁があらわれる!
十字の紅い割れ目
彼らは停ったままの腕で
蓄音機のラッパを抱く
真鍮の花
相談する瞑想する
喋らずうごかず
意思が次の波を呼ぶだろうか?
伝達のない世界へ
テーブルの上で
化石の鳥が化石のリンゴの〔1囲→2まわ→3囲→45まわ〕りをとぶ
化石の鏡がやわらかい出来たてのパンを映す
化石の矢がやわらかい子供の首を刺しているか?
そんな時はすぎる
彼らの泥の瞳
彼らの飼っている泥のライオン
泥の書〔1棚→2345物〕
それは可塑物?
夏の暖炉で燃える敷物の道
彼ら汗をたらしながら
心を凍らすべく
一つのカンバスに描くんだ
花嫁のほしいままなる曲線を
走る矢印
オレンジ色に燃え
ながれる中心から
同時に縦から横まで
秘密のよろこびの声を明らかにする
内視の肉を輝かせよ!
内耳の霊の秋
その向うを
漂う湖
朝鮮アサガオの雨の朝がくる
彼らは紳士だから
フロックコートの正装のまま
存在するために
共同幻想体として
スイートな金魚鉢を支える
初出は《the high school life》〔MAC〕1968年8月〔15号〕10面〔コラム〈えるまふろじっとのうた〉〕、本文新聞活字1倍扁平1段組、43行。
〔1ピンクの空間へ→2345涼しい鈴懸の下の〕
〔1ダイビングする四頭馬車→2345橋をわたる〕
〔1(ナシ)→2345わたしは包装荷札をもつ人〕
方向指示の〔1黄→2345青〕色の
矢印のとどかぬ世界で
鳴く夏のフクロウ
まぶしい眼〔1(ナシ)→2345の歩み〕
〔1(全角アキ)→2345暗く〕網のようにひろがる円
その中心へ近づく
〔1幼児→2345少年〕の便器
〔1母→2345花〕より恥ずかしく
看護婦の白衣のなかに〔1(追込)→2345(改行)〕つつまれる
〔1わたしたちの知っている→2345(トル)〕
傷ついた馬〔1(ナシ)→2345の腹を〕
〔1長い年月の腸→2345(トル)〕
〔1はかない花→2345(トル)〕
〔1(ナシ)→2345巻く〕みじかい〔123ホウタイ→45包帯〕
笑ってはいけない〔1かね?→2345(トル)〕〔1(改行)→2345(追込)〕
〔1(ナシ)→2345(全角アキ)〕まして泣いては
〔1(ナシ)→2345たちまち〕肉屋が来る時代〔1!→2345だから〕
注射器の針が
刺しているわたしたちの
あらゆるところ
あらゆる孔のある皮
精神〔1(ナシ)→2345もともに〕
かがやく鏡〔1(ナシ)→2345に映る〕
〔1あえぐ葦→2345(トル)〕
〔1(ナシ)→2345表現愛の〕
にくにくしい肉体
〔1走ってはいけない?→2345(トル)〕
解剖図のある暗い部屋から
グリーンを走る
手足のない水着類の干してある
クスノキの下まで
生きているとはどんなこと?
恋にこだわり
はねる水
吐く闇
〔1(ナシ)→2345あえぐ葦と人〕
〔1はるかな白骨→2345だからあらゆる絵画は〕
〔1(ナシ)→2345ナイフで裂かれた次元を持つ〕
〔1(ナシ)→2345ここで〕すべての事物を想い出せ〔1!→2345!〕
そして今〔1(ナシ)→2345わたしは〕
〔1クジャク→2345孔雀の〕尾のうしろへ廻って
喚起する
なまなましい藍いろの
〔1表現愛→2345父母の像〕
初出は《血と薔薇》〔天声出版〕1969年1月〔2号〕一四~一五ページ、本文9ポ24行1段組、45行。
客観的状況で
塩がほしい〔1のよ!→2345(トル)〕
ぬれたハイヒールをさかさまにして
その尖筒を〔1(ナシ)→2345機関手が〕なめるとき
晩夏の街には〔1(ナシ)→2345セーラー服をぬいだ〕どんな〔1モモイロの→2345(トル)〕少女がいるのか?
言葉を犯罪的に使って
紅色の闇へ
イタリア貂を狩りに出る
ぼくたちにとって〔1(改行)→2345(追込)〕
死はとりとめもなく
自動ドアを入る
肉をラセン巻きにするガードル〔1(ナシ)→2345に沿って〕
まばゆい丘の上〔1で→2345に出ると〕
馬の交尾
その影のしていることが
暁の彫刻〔1?→2345である〕
血豆の大理石〔1(ナシ)→2345の頂で〕
マンダラ模様の〔1千羽鶴→2345夢をはらみ〕
そこから少女は成長するんだよ
樹と外套でかこわれて
〔1少女の夢のはらみ方→2345(トル)〕
〔1すきなエクレヤ→2345(トル)〕
ブルガリヤ人の男根〔1(ナシ)→2345は立ち〕
〔1(ナシ)→2345孔雀の羽は散乱する〕
きわどいレールを
バクシンする蒸気機関車が正面から〔1(改行)→2345(追込)〕
入ってくる〔1!→2(トル)→3!→45(トル)〕
呻きの乳色の霧〔1(ナシ)→2345の彼方より〕
まるで虎刈りの老人がきた〔1のよ→2345(トル)〕!
ほそいほそい靴下をぬぎながら
口をふさいで
血の波紋の少な〔1くな→2345(トル)〕い世界へ
〔1毛の→2345夜光〕捕虫器かざし
〔1モモイロの→2345ヒルガオの咲く〕柵に
だんだんよりかかる
だんだん裂ける
蜜房はなぜいつまでも〔1黄色→2345暗〕く苦く
夕陽のように
一つのゲーム〔1の→2345を〕終〔1り→2345らせるんだ〕
浴室で裸になって
今宵から花嫁たらんとする
心なき少女の自己誘拐
〔1(ナシ)→2345それは〕ぼくたちにとっていかなる痛みの〔1(追込)→2345(改行)〕〔1ビラン→2345六面〕体〔1(ナシ)→2345の鋲〕であるのか?
〔1声する恋の夕暮れの→2345(トル)〕
家のなかで顔を巻く包帯をとけ!
格子が見える
初出は高井富子舞踏公演〈形而情学〉チラシ1967年7月3日、本文12ポ1段組、51行。
吉岡は「この一篇は土方巽の求めに応えて書いたものである。〔……〕或る日、奇妙なポスターが送られて来た。舞踏公演「形而情学」のもので、中央に朱塗りのタバコとビー玉が入った函が付いている。そして別の紙袋の中には、加藤郁乎の詩と「青い柱はどこにあるか?」がインディアン・ペーパーに印刷されていた」と書いている。
〔1(ナシ)→2345土方巽の秘儀によせて〕
闇夜が好き
母が好き
つとに死んだカンガルーの
吊り袋のなかをのぞけ
テル・テルの子供
ニッポンの死装束が白ならばなおさら
青い柱を負って歩き給え
円の四分の一の
スイカのある世界まで
駈け足で
ときには
バラ色の海綿体へ
沈みつつ
犬の四つ足で踊ること
かがまること
凍ること
天井の便器のはるか下で
ハンス・ベルメールの人形を抱き
骨になること
それが闇夜が好きなぼくたちの
暁の半分死
ある海を行き
ある陸を行き
ラッパのなかの井桁を吹き
むらさき野を行き
ふたたび闇夜を行く
美しき猫の分娩
そのしている夢
そのうえしてない行為
ぼくたちはどうしている?
すべてに同化する
末梢循環の恥毛性存在!
消えなん横雲の空
鋼鉄のビル・ビルの春
ビー玉の都市
そこにサクラは散るや
散らずや
赤い映像とは肉体の終り
ガニ股の父が好き
心中した姉が好き
古典的な死の隈取
闇夜が好き
かがり火が見えるから
大群衆が踊り狂っているんだ
亜硫酸ガス
濃霧
予定のない予定?
黄いろの矢印に沿って
柱に沿って
形而上的な肛門を見せ
ひとりの男が跳ねあがる
〔1一九六七・五・一五→2345(トル)〕
〔1この作品は吉岡 実氏が土方 巽におくったものです→2345(トル)〕
初出は《同時代》〔黒の会〕1968年7月〔23号〕四二~四四ページ、本文9ポ18行1段組、45行、初出時の標題は「フォーク・ソング」(ただし目次では「フォークソング」)。
むらさきのスミレが咲く
マダム・トラコーマはすきな形の
舟をみつける
その下は水でなく
ダイナミックに煮える粥のような波
たよれる
たよりになる棒とは?
どれほどの太さと長さを持っている人
ももいろのビニール製品の
たくさん垂れている
向う側とはどんな凹面〔1?→2345!〕 突起態!
どんな赤ん坊が産まれているのかね?
梨籠のなか〔1の甘いビラン体→2345には〕
カルシュウム乳
もしくは釘
ナチスの制服の人型の空胴の青空を見よ
つるべうちにうたれた
兎のそよぐ春風の毛の下で
国家治安のために
〔1花嫁→2345母親〕たちがたれながしのまま
双生児をうむ
ながれる舟のなかに
発泡状の球体群
空は暗い菱形に見え
バロック風な〔1ナベ→2345鍋〕から
立ち上る
雄鶏
よく見れば
鉄製器具の寄せ集めでつくられた
危機の蝶番の結合
赤塗りのトウモロコシの
とさかをなびかせよ!
復讐とは
ねじること
それぞれの夕闇へ
コウモリをとばさんとする
処女の子宮をふさがんとする
灯る内装芸術
タクシー乗場から軍艦の丸窓まで
夜目にもしるく
金色の矢印をつける!
この前兆的なる
内的構図の終りか?
動くインテリア
ヒバリがしきりと鳴きのぼるとき
初出は《南北》〔南北社〕1968年10月号〔3巻10号〕六~一三ページ、本文10ポ四分アキ20行1段組、150行、目次には「長詩」とある。
では未経験的なピンクの空間へ
ダイビングする
四頭馬車の喪服ずくめ
さかさまになる
四つに分けられた馬の頭は見えず
きみは驚き
ぼくは悲しい顔を剃り
きみの彼女はふとる
墜ちるにはふさわしい水面
ぼくの彼女が笑う月
じゃだれがトップで死ぬんだろう
母の恥しい腹のなかにいる
ぼくかしら?
妻の詰った子宮から出てくるきみかね?
ほんとうのことを云うべきだ
生まれるより先に死ぬべき同行者・同義語
きみの彼女が父の尻の孔の奥まで戻る
これは一種の自負であって
生でなく死でもなく
赤いネオンの透明なはかない消滅法
車輪がとんで行く
めもさめる型式美
とざす障子の〔123桟→4棧→5桟〕に巣食う鳥
来るべき潜水艦が丘を越えて
迷宮入り
忘れられているのではないだろうか?
ぼくの彼女の主知的に
あまもる唇
類型の多い死ではないかね
贋金
先頭をだれが行く
ぼくの足の〔1赤→2345黒〕い鼻緒のゲタ
きみの胸のエンドマーク
〔1きみの彼女のタワーのようなヘアー→2345ぼくの彼女のアミタイツの脚〕
〔1ぼくの彼女のアミタイツの脚→2345きみの彼女のタワーのようなヘアー〕
た〔1(ナシ)→2345よ〕りない人体
四つの部分で真の人間は出来ていないだろう
すくなくも一万部分の集積
あるいは九個のフラスコのミカン水
ビニールのような耐久性と劣情を示せよ
在るべき時間とは
在らざる愛のこころ
在るべき空間とは
在らざる光線銃
ここはどこか?
ここは深くも浅くもない軟着感〔1!→2345がある〕
ぼくの彼女が至りつく
冬のフトンの果て〔1(ナシ)→2345から〕
まっすぐ歩いて
くびれた母型を認識し
似たような荷物をみつける
なにが入っているかもわからぬ観念
歯型
電子音楽
ムラサキ
未来の
愛
ではきみの彼女の運命とは
それは生まれる
むなしい稼業から
もり上ってくる
非情緒的な廃品同様
むしろなんでもなくなりつつある
周辺をかこんで
イチジクの葉
かくすラクダのコブの相似性
同円のスリ鉢叩いて
日常言語の床屋の白い布を裂く
記号の〔1234罐→5缶〕
開かれる開かれる
自在に無意味に〔1赤い→2345褐色の〕床から天井へ
横断する横断する
電気芝刈り機
ニクロム線の庭
静電気〔1(改行)→2345(追込)〕
そのもののウェーブで
カメをくすぐる〔1(追込)→2345(改行)〕彼女たち〔1(ナシ)→2345の〕〔1(改行)→2345(追込)〕
〔1玉鳴るソロバン→2345(トル)〕
〔1ハプニング→2345(トル)〕
ハッピー〔1(ナシ)→2345・バースディ〕
はるさめ〔1(ナシ)→2345の降るころ〕
煙突掃除用ブラシ〔1が→2345は〕ススでなく
幼児をこするものへ
変化する
壁を掻く老人たちとうとう壁をつきぬけて
けむりを出す
魂と秋
女は自身の手でなにを変える?
虹彩の遊び場で
女はもろもろの疑似割れ目を表現し
毛のはえた裁ちバサミで
紙テープを切る
そしてダンス
そして銃殺シーン
そしてそして想い出を想い出す
まるくまるく
ハリネズミを追いつめ
恍惚たる少年の藍をあびて
水槽では血気の尻
さめるサメ肌をふるわせる
共謀的〔1(ナシ)→2な→3(トル)→45な〕彼女たち
めざすメザシの
目をつらぬく矢印
死への
橋がかり
金切声
さらにとどろくぼくらの白骨期
真鍮の棒で砕かれる
あるところへ戻ったら
形が変り色が変る
物が物をのむときは闇
吐くときは光るか?
彼女らはすべて見えずと反対のバラのトゲをつかむ
これが芸術だ
それは偶然の自律自慰!
肉色をしていることが
罪悪ならば
ぼくたちになにができる?
藁の上で
肉色の幽霊と化して
にもかかわらず
そのうしろに眠るきみの彼女の〔1螢→2345蛍〕光体
なめるなぐさめで
分裂するきみの水色の舌
ハンバーグをつくる
ハリボテのハンバーグをつくる
そしてぼくの彼女はヌード
清掃車がくる
起伏がくる
水葬の夜明け
ももいろの回虫の環境
ももいろの夢
凍結がある
そこでぼくらは行く
写真のなかで永遠に
首を吊られている人〔1(ナシ)→2345々〕の下を
真夏の反現場性の海の輝く
金輪
サイコロ
過去からカブトガニの内部は
はたして
うごいているのかゼリーのように
ピンクから白色の世界へ
むしろ次から次へと変革している
そうしてうずまき模様の
ののののの
のたれ死を承認せよ
ノオ
今日ぼくたちにも存在しないだろう?
崑崙!
初出は《現代詩手帖》〔思潮社〕1968年11月号〔11巻11号〕三二~三五ページ、本文五号20行1段組、66行。編集人・八木忠栄の〈編集日録抄⑬――九六八年八月~十一月〉の「10月7日(月)」に「筑摩書房近くの喫茶店で吉岡実と会い、詩「雨」をもらう。このところ調子が悪かったというが、とてもいい作品だ。「いつも題名に困るんだ」と吉岡さん」(《現代詩手帖》2010年7月号、一五五ページ)とある。
それはたとえば
老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの
スイ星の球のつまった
箱をさがす〔1ように→2345(トル)〕
レインコートの黄色の美人がすきだよ
だからトウモロコシ畑のうしろへ
廻って
赤毛のやさしい愛撫から
少年がぞろぞろ出る
こんなにノビのきく夢
ビニールの紐がどこにある?
知覚できる具体的メカニックの世界から
ひとつの堅牢な白い箱をしばりあげよ!
踏台のように
他によりかかる映像がないので
中世の女のように
しゃべらず
黄色のレインコートをぬぎ
それにほそい脚を
かける
あまがける!
箱の下はいまなお血生臭い戦いの世界?
或は老人たちのあそんでいる砂場?
それともススキの茂る情死の腐爛期
どうでもいい日々
肩から乳房までさらして
その女は大きく股をひらくんだよ!
では灰かぐら
箱は水面へ〔1泛→2浮→3泛→45浮〕びあがり
なによりも流れる
罪ぶかい行為とは空間を穿つこと
関係のない物体や言葉を
同次元へ置くこと
であればこの白昼のなかで
ザクロの粒々の
果肉がはじき返えされるんだ
太陽から遠く
金属の小さな柱の森へ
たのしんでいる鳩
たのしんで叩くピアノ
たのしんで突つく浴室の孔
老人になる日まで〔12永→3求→45永〕遠に
にがにがしく〔1スパイとして→2345(トル)〕
具体性のある物をつくり
肉色の箱を担いで歩く
それの内側は金色の塗料ですみずみまでぬられ
回復できない肉体の周囲
パラシュートの兵士は宙吊り
女の帽子が風でとぶ
その単位
その恍惚の夜は
同時にくるか同時に戻る
トーテムの上で泣く幼児の声を聞く
火をくぐる美しい女の腰
建築物の空間の
あらゆる余白を横切るものはなに?
それは音楽?
それは暴力的な甘い蜜?
痛みまで感じる
黒髪のゆたかなカーブを見よ!
はみだしたものはくびれ
平らな面は割れ
秋のあかつきがくる
箱は黒色の角を緊張させたままぬれる
いつからと問うことはなく
雨のなかに
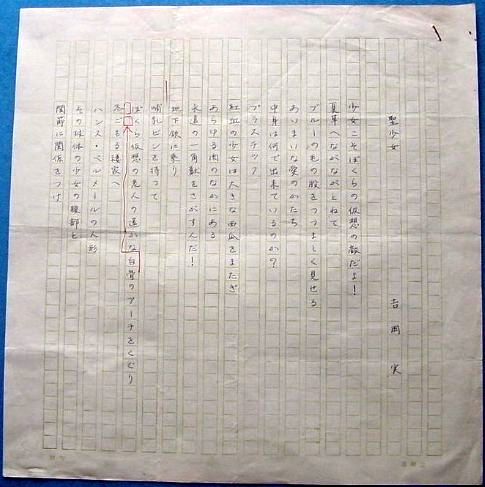
吉岡陽子夫人の手になる〈聖少女〉の雑誌掲載用入稿原稿
この雑誌掲載用入稿原稿で注目すべきは、編集者が記入したと思しい赤字による指定である。指定は原稿の改頁の箇所(10行めと11行めの間)に施されているほか、12行めを2行に分けて新たな行を二下から起こすよう記されている(これは「改行」というより、詩句をコラムの天地に収めるための「折り返し」だろう)。初出誌面もこれらの指定どおり組まれているが(吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〈「紅血の少女」〉の〈Ⅰ 〈聖少女〉評釈〉参照)、本校異では原稿の形を尊重して「ぼくら仮想の老人の遙かな白骨のアーチをくぐり」を1行として扱った。
初出は《小説新潮》〔新潮社〕1969年11月号〔23巻11号〕一七六~一七七ページ〔コラム〕、本文9ポ13行1段組、22行。
少女こそぼくらの仮想の敵だよ!
夏草へながながとねて
ブルーの毛の股をつつましく見せる
あいまいな愛のかたち
中身は何で出来ているのか?
プラスチック
紅〔1血→2345顔〕の少女は大きな西瓜をまたぎ
あらゆる肉のなかにある
永遠の一角獣をさがすんだ!
地下鉄に乗り
哺乳ビンを持って
ぼくら仮想の老人の〔1234遙→5遥〕かな白骨のアーチをくぐり
冬ごもる棲家へ
ハンス・ベルメールの人形
その球体の少女の腹部と
関節に関係をつけ
ねじるねじる
茂るススキ・かるかや
天気がよくなるにしたがって
サソリ座が出る
言葉の次に
他人殺しの弟が生まれるよ!
初出は《季刊藝術》〔季刊藝術出版〕1968年10月〔秋・2巻4号〕一一六~一一九ページ、本文9ポ27行1段組、103行。
走っている電車のなかで
白昼いそいそと
わたしたちは見るんだ
いくつもの白塗り頭のマネキンたち
なめられるアメの棒
青と赤のウズマキの上昇する
アンモニヤ
密教芸術
妄想してはいけないかね?
両手をつく青年たち
さかだちの母なる獣
だんだん垂れる
トイレットペーパーの王道
夜は見えないから
乳色の矢印にみちびかれ
肉のようなものが甲羅のなかへ
入って行く
それは天然の美
よみがえるメロディ
シナの枕はどうしてあんなに長いのか?
神秘的なほど重く
よこたわる
弓張月
マタニティ・ドレスをひらひらさせて
老婆のむれ
ミシンの針のように進んで行く
どこか?
どこへ
わたしたちの自意識自滅の
闇の砂漠の三千世界
ここから恥入るべき
現代の凱旋門
すばやくすき透る
チェリー・ピンクのありあけの
静かに成長する
美しき夫人の
かがやく〔1鐘→23鍾→45鐘〕乳洞
しみじみとさわり
しみじみと仰ぎみよ!
金属の含有する方形の気孔類
そこにいかがわしい十二変態のサナギ
腐るものから腐らぬものへ
変らぬものから変るものへ
着色マッチをすりつつ
恥らう楕円のなかの裂け目で
黄金をみつけるか?
死の塩の商人
ふとることを恐れる
ももいろの飛行機
ももいろの影
トラコーマの眼
密通
密着美人
燐光塗料のかつらをかぶり
マリリン・モンローの肉体はちぢんだ!
殺到する覗く人たち
わたしたちの言語のなかで
腐るもの・変るもの
永遠の明暗のなかで
痛むもの!
くびれた存在の痔
広告用ビーナス
天竺牡丹
やがて六月へ
自動車の中でそよぐ脚
公園の石獅子
記念写真ですかこれは?
ニンジンを抱いて
死んで行く
黒人と恐〔1龍→2345竜〕
それは夢かまぼろしか?
群衆の中の腰巻きの海軍旗
口にくわえた鎖の女
芸術的胃下垂
おお陳腐!
今日 生卵の黄味のゼリーの表面に
一篇の詩が印刷される!
未生児のむらさきの眼も
わたしたちのテープの走り込んで行く
小さな鉄のボックス
出る音楽
出る木の芽
出るオバケ
血の出るテープ一万呎をなびかせて
は寝る〔1姙→2妊→3姙→45妊〕娠可能の少年たち
いかがわしい蘭のからまる少女たち
夜景をまわる夜警たち
その市松模様
暑い夏がくるまで
蛇行セレモニイ
黒くなるべき孔雀
白くなるべきポスター
いつ赤くなる?
フライパンの上でマカロニの孔
すべての肉はアルミ箔で包まれた!
河へながされる汚水の
野菜類
じゃ終りかね?
金看板
来たるべき絵画
来たるべき時
わたしたちの有罪期の
半跏思惟像〔12!→3!→45!〕
初出は《郵政》〔郵政弘済会〕1969年4月号〔21巻4号〕一四~一五ページ〔コラム〕、本文8ポ1段組、30行、目次は「蜜はなぜ黄色なのか」。執筆者名の後に「(現代詩人会会員)」とある。
蜜はなぜ黄色なのか?
永遠に
瞑想的でなく
愛すること〔1で→2345(トル)〕もなく
虎のように
フォルムを所有する
秋の青空はあくまで疾走し
眼と眼は暗く
向きあった男と女の立体感覚!
内臓へまでとどく
四つの腕の様式美
求めている〔1唇のよだれ→2345森の〕
〔1それらのただれ→2345(トル)〕
紅葉の錦
いま近づけば発火する?
格子を出てゆく金〔1蠅→23蝿→45蠅〕
かくてモノトーンの夜を
なまめかしい水槽で
恋する幽霊
水の回転する泡の苦界の
男声・女声
ながながと哭〔1[な]→2345(トル)〕く老婆
ながながと鳴くウグイス
白地に赤く
燃えるランジェリー
燃えるフロア
コカコーラの〔1罎[びん]→2345壜〕のうしろの沖を
走るあらゆる船は静止し
蜜のような物質で
徐々に包まれる
初出は《ユリイカ》〔青土社〕1969年8月号〔1巻2号〕七六~七七ページ、本文9ポ23行1段組、39行。
森の〔1アオバ→2345青葉〕の下に来て
双頭の美女と逢びき首びき
考えてもみて下さい
花飾りの下着の太い胴廻り
そのなかで落下蝋石!
それはよいともわるいともいえない
子供の描く絵〔1(ナシ)→2345のように〕
露のつらなるはずかしい
夏の男と女
すべる多面体
狭い入江の奥へ至る
笹鳴る夕べ
わたしはアンチ・ロマンに食傷し〔1て→2345(トル)〕
そぞろに思う
トリカブトの毒
スダレ・ふうりんの夢
入日の都市では
〔1(ナシ)→2345鉄〕棒こそかりそめの永〔1違→2345遠〕よ!
ブルーの髪をなびかせて
とびあがる
モッブのおさげの女生徒たちを押えて
球なす汗の陰蔽だ!
長い地下道を通過する
貨車や
影の火薬
もしくは仕度の了った死体?
南が曇れば北上する
暑い日
花嫁のかつらをかぶって
泳ぐ人
今を時めく
双頭の老婆を
正面から抱く人
ミスティックな水の音
ミモザは茂り
暗い菊形のパラシュートで
淋しい家の梁から
わたしはほそいほそいランニング姿で
おりるんだ!
初出は《風景》〔悠々会〕1970年3月号〔11巻3号〕五八~五九ページ、本文10ポ16行1段組、23行。
ブランコのりの少女がひとり
辻公園にいる
とわたしは想像し
肉体と紐を使って
苦い荷をはこぶんだよ
方解石
漆
いまとびあがる少女の薄布の
支離滅裂の
尻を大写しで見よ〔1!→2345(トル)〕
その移動することだま〔1?→2345(トル)〕
発光する水晶でなければ
それはプラスチック
木の球
花嫁
みずみずしく
防疫人が調べる
輝かしい孔類
それは点になるまでコイルで巻かれて
青空へ至るんだ〔1!→2345(トル)〕
母恋うる声
向うを老人や草刈機が通り
わたしが通る
初出は《無限》〔政治公論社〕1972年8月〔29号〕三八~三九ページ、本文20級22行1段組、44行。「「便所はどうして神秘的に」の起こしのカギカッコ(二分モノ)の位置は、1が全角下、234が二分下、5が天ツキである(なお吉岡は単行詩集では本篇を最後に、引用文の2行め以降の字下げをしていない)。
吉岡は「〔……〕今から六、七年ほど前、「無限」の西脇順三郎特集号に、〈弟子〉という短い詩を書いて献げていた。当時考えるところがあって、私は二年間ほど詩作を止めていた。そんな精神状態のなかで書いた詩なので、詩集《神秘的な時代の詩》を編むとき、先生への献詩である詞書を、削除してしまったのであった」と書いているが、印刷に付された本篇に西脇への「献詩である詞書」はない。同誌の目次には〈献詩〉の見出しの下に、会田綱雄から村野四郎までの10名の詩篇の標題(献辞がある場合、2倍ダーシでつないで表示)に続けて、吉岡作品が〈弟子〉とだけ記されている。
それは違った意味に使われる
言葉
笊のように
〔1晩夏へ向うよ→2345不可解なるもの〕
淡黄色〔1(ナシ)→2345の夕陽のなかで〕
見えなくなったら
ハツラツとして
眼薬をさす男
砂かぶりの丘をゆき
職業を意識する
この世に歌があるだろうか
たとうれば
草上の露命
〔1〈→234<→5〈〕永遠とは今の現在のこと〔1〉→234>→5〉〕
だから心は重く
死んだカモのように
岸べに寄る
われわれには切ない
私生活があって
紐のすべてが濡れているように
円にかこまれる
紺染のはるかなるアザミ
花〔1瓣→2345弁〕的な奥深いものを信仰というのか
われわれは明晰でありうるか
疫神の午後
紅藻類のなかで娘をみつけて抱く
〔1力ない血祭→2345どこから起伏せるなやましい大理石〕
〔1どこから起伏せるなやましい大理石→2345力ない血祭の終りは〕
吹きながしのチリメンの鮮緑色群
たたずめばスルメの足
過ぎれば燐
戻れば雪の〔1嶺→2345峯〕が見え
わずかに
夢みる鋸歯の海を〔123(改行)→45(追込)〕
ラジィカルに泳ぐ
老人をたたえよ
そして箴言集をみよ
「便所はどうして神秘的に
高い処にあるのだ」
女神の水色のスミレの酢を求めて
梯子をよじのぼる唯一の弟子
さて簀子は乾いた!
春は曙
牛乳屋が来る
初出は《現代詩手帖》〔思潮社〕1969年10月号〔12巻10号〕三六~四三ページ、本文9ポ23行1段組、*印で5節に分かつ163行。なお区切り記号は、1・2・4の6片のアステリスク(*)に対して、3は8片の米印(PCで表示不能)になっている。初出掲載誌編集人・八木忠栄の〈編集日録抄〉の「1969年8月25日(月)」に「筑摩書房へ行き、吉岡実から詩「わが馬ニコルスの思い出」をもらう。170行を越す力作」(《「現代詩手帖」編集長日録 1965-1969》思潮社、2011年9月15日、二四四ページ)とある。
花咲くスミレの墓地で
わが馬ニコルスは快心の脱糞する
それからかるがると
あらゆる死体をとび越えた
その荒野に
言葉が必要か?
それとも主題なき愛の労働がのぞましいか?
そこには底なく
負目のみの
蝋の道の続きだ
夏の嘆きのふかい沼地
紫紅の下着の
女生徒たちのハイキングの賑わいよ!
白いストッキングに覆われた
かたい両腿の跳ねるたび
わが馬ニコルスは呼吸を止め
歓喜し
熱い鉄の蹄鉄をはめて
ずーっと遠景まで
シナゲシを越え
水晶を砕く
死都の一部が見えるよ!
わが馬ニコルスのキララで包まれた陰頭が青空へせり上る
痛みの金櫛でこすられて
自立し
転調する
地獄より暗い地上で
一度は見たい桃いろの植物群
そのなかへ
時間錯誤にかかわりなく
群衆を匿せよ!
そして瞑想
擂鉢をする疑問符の人
白地に赤く死のまる染めて
みにくい未来へ
わが馬ニコルスはギャロップ!
*
雨にぬれて恐ろしい緑の
葉はちぢれる
そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ〔123!→45(トル)〕
この田園の悪夢とは
わが馬ニコルスがニンジンを食うとき
だれも近づくな!
病人・幼児・鶏・〔1姙→2妊→3姙→45妊〕婦を憎む
あらゆる個の
虚像・銅像
〔1藪→23薮→45藪〕があればそのいばらの果へ
蹴りあげるんだよ!
自負の白塗りの柵をとび
ねはりの綱で囚われるときまで
黒雲千里
まれなる涼しい雷雨のゆうべの
できごと
*
刺された父が窓までゆき
刺された母が窓までゆき
それは〔1(追込)→2345(改行)〕フォルムでは〔1(改行)→2345(追込)〕
ない
それは起源ではなく
まして成就ではない
なによりもまず
あらゆる戦いの認識の変形
芸術・手術・忍術
はねる血の父
はこばれる〔1凾→2函→3凾→45函〕の母
カシの木の生えた森のような室内
そこでカタツムリを発見し
ゆがめられた金の道のべで
わが馬ニコルスは死病の疝痛をこらえる
冬ごもりの廃屋で
誠実な兄弟たち
弱々しく
燐光塗料の書物を読みあげる
他界の闇の
ナイトテーブルをまわり
少女の腹部をあつかましくも求めて
水位へ出る
老人十字軍
ともに浮遊する
わが馬ニコルスのゴムのようなおとがいを愛撫せよ!
母の半欠け乳房のように
*
ピンク色のハマムギを成長させる
荒野の納屋で
わが馬ニコルス
水をねながら飲む
浮いている藁の下の方に
恋する幽霊たち
或はナメクジの類
潜水艦に類似した
わが馬ニコルスのまるまるとした尻を見よ〔1!→2(トル)→345!〕
それに乗る人がこの世にいるか?
寒い冷たい人
砲弾とともにとぶ淋しい人
横から眺めれば
先祖ごろし
血の雲がたなびく少年の夢
絹につつまれた
姉妹のくろい種子が
ひざの間で
白水でぬれて
消毒飛行
ツバキの花びら散らし
正面を占める
わが馬ニコルスの笑う歯の薄明よ!
すべからく
皮一重の腐り方への悦び
トカゲの湿った心で
宗教的物質と
やわらかい肉も食べる
その同時性こそ女の弾性だよ!
もしも楽園があるとしたら
それは紫色の
葦毛が脱けおちる
わが馬ニコルスの虹のような
股がまたぐ
独身者の燃える棘冠
或は濡れるシャツのプライベートな
その汚辱
その辻便所の孤独から
内的建築を求めて
ずーっと近景まで乗り入れる
斑点のある戦車
貨車への接続詞・終止符。
単語のつながる末尾の
赤い毛のかつらの下の大砲
その投影
その三角又は四角形
その装飾をつきぬけて
黒と白の格子
テーブルに坐って
母娘が比喩的に語る
生まれる子供の意味を伝えよ!
一つの言語から生まれる
生死の観念の在り方
彼方の水へ
泳ぐ百人の子供
彼方の塔へ
のぼる百人の子供
彼方の砂へ
もぐる百人の子供
彼岸の彼方の白布へ
つつまれる百人の子供
その一人の子供だけでも欲しいわよ!
血のように燃えて
わたしたちの分裂のくらがりに
遍在する
つねに黒い手袋をした子供が――
要するに客観的状況を
断罪してよ!
暁の叙事詩の直立性を押しわけ
母娘の子宮を絞めて
恍惚の子供が泳ぎ出る
そんな広域な
ネハン
の湾
*
すえながく生きつづける仮想の敵
ブランコのりの子供たち
わが馬ニコルスが荷車に積まれて
行った河と時を記憶せよ!
空鳴りの肉色の鉄橋の弧のかたちを破壊し
消滅する
わが馬ニコルスの水色の大きな瞳孔の
ふたたびまばたくまで
潜在的世界には
犯罪的な言葉が屹立する
初出は《本の手帖》〔昭森社〕1969年2・3月号〔9巻2号〕七〇~七三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ23行1段組、71行。
わたしは自分の描いた絵を
見てもらいたいので
女友だちを家につれてくる
その女友だちはバカにして笑った
わたしの絵は観測というものでなく
むしろ昆虫群
わたしは女友だちに絵の構造を説明すべく
本物を見せる
それはピンクの長方形
やわらかくなると同時に
寒ざむとキララ色の袋に収まる
その〔1繩→23→縄→4繩→5縄〕文模様
この夜のムーヴマン
だから愛とは熱く
油絵具のなかにたむろして
出る骨をくるむ
女友だちは絵よりも蝋化した
観念がすきだといって
わたしのベッドを塗り変える
それがヴァイオレットなら
ヴァイオレットの乳房
鉄の歯のようなものを
にょきにょき生やす
絵としてわたしが描いた心
低い空でも処女は犯せるか!
鉄砲ユリの奥は深く
わたしの絵はぬれることを知らない
表面というものがない
闇を所有しているわけでもないから
すくなくともわたしには持ち歩くことができる
おそらく女友だちには
それはできぬだろう
絵のなかの馬がそれを拒む
母が息子を拒み
息子が父を拒み
サボテンが露を拒むように板の下を
日と河がながれる
わたしは淋しいことは絵に告げ
死にたいときは
絵のうしろを歩く
そのときはきまって
暴風雨がくる
女友だちは明日は帰ってゆくだろう
彼女の行手に立ちはだかる
わたしの絵のなかの森の道へ
女友だちが手をひく
娘のような妹は悪霊だな!
こちらをふりかえって
鼻血をたらす
わたしは便所へかけこみたい感じだ
彼女たちの前で
なぜわたしの描いたものを絵といったのか!
それはすみからすみまで肉化
されたものであって
輝やくバクテリアではなかったか?
細い管と太い管で編まれた
長い長い人生のトンネルかもしれず
光学的には暗く
建築的にはもろく
自然的にも不自然で赤く
わたしが無意識的に模倣している
女友だちのこれから
作りつつある再生芸術だろうか?
彼女たちが午餐をすませて
水着で泳ぐのを
わたしは見に行くんだ
女友だちの娘のような妹の
孕んだ腹を裂くよ
夏とはそんな一日であることを
感謝しながら
みずみずしい〔1帚→2345箒〕を買ってくる
初出は《都市》〔都市出版社〕1969年12月〔1号〕五〇~五一ページ、本文9ポ25行2段組、97行。
戦争を考える
子供連れの男はルーマニア展へゆけ!
女中がめくるめく
下着の三色スミレの群落を見よう
翼ある毒物
肉のような絵が描かれて
あまねく拡がる霧の空
センニンカズラの葉が延びるのを刈るベランダの老人の
そのまわりから近代性を超え
未来へ至る
押し石が一つ欲しいよ
生理的な花咲く乙女
腸チフスで休校の庭は
棺のかたちの
人びとが列をつくるに快適な
オルガンを演奏する
兵士の断たれた手
それを見物する人たちがどこにいるのだろう?
ニンニクの肉房のように
忘却されている
火事のように地で燃えて
夜は単純な言葉を喋れ
ぼくの胸の上で灰色の猫がこうばこする
サクランボが七〔1、→2345・〕八個赤い台所を通り
反自動的な書き方による詩の試み
愛の不在をたしかめ
手は手袋をはめ罠をはめ針金の上の骨をつまむ
それは流れそれは口をあける
その毛織物の下で
生まれる鉱物
人びとは誰のためにそれを鍛えるのか?
海鳥のように飛ばし
モグラのように恐怖の汗をかかせる
苔むす火薬庫の日の出
変りやすい書割り
靴屋・肉屋・パン屋・花屋そして管理人
必要な品を持って
夕焼の入江から歩いてくる
或は這って
反対に帰ってゆく
犬や洋服屋の針だらけのボデーがある
言語幻滅の治世に
水間という空間等価の世界があるとしたら
水中銃を撃て!
とぶ飛魚
やわらかな魚雷の内部の真珠母類
波にもまれる母親と赤ん坊
冷血・れいろうたる血
過去は王冠のギザギザに傷つく心
そこでカキフライを食べてあくびだよ
高層温室で眠るべくエレベーターで昇る
みにくい花嫁花婿
同時にブドウが熟れる
まず大切なのは水の飲み方
船の帆を墨染にする
海の上のコレラに罹らぬために
裸になって蝶のように
ゼンマイの口でしずしず水を吸うんだよ!
またはプラスチックの管で
かこまれてあらゆる廊下を走れ
球体からながれる藍の水
窓から今度は
セメント樽がおろされる
ぼくは詩句を書きながら
それを見ていればよいのだろうか?
〔1〈→234<→5〈〕金魚鉢をかかえて駈ける騎兵隊〔1〉→234>→5〉〕
途中でとまった
自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち
その卵の黄色い内部の霊媒を
たしかめて
コーヒーをのんで庭へ出て
明るい透明な巨人のゴムの木を〔1杙→2345伐〕る
そんな土の遊びをつづける
悪い私生活
雪ふる紐の首都
ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか
浴槽のなかで虎みたいに重い
シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる
あまりにも水が熱く
貝のなかの舌というものは乾く
モモイロのその舌がいくつにも裂けるよ
死声と雷の双曲線で
移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的
血の彫刻を仰げ
とうもろこしの堅い粒々で下痢する
ぼくたちはどんなデザインの勲章をつけて
廃校近い朝の運動場を駈け廻り
迷路・退路を進み
雨のアメリカのジャングルジムへ
しめなわを張り
いかなる幽霊の姿勢で
全員で吊りさがればよいのか?
男女の区別はなくなってほそくほそくなる
春きたりなば
離魂
これから何処へ
浮遊せんとする!!
〔1〈一九六九・一〇・五〉→2345(トル)〕
――――――――――
3の再刊詩集の本文が奇妙であることは以前にも書いたが、《神秘的な時代の詩》全詩篇の校異を踏まえて、次の詩句を問題としたい。
以上の七つの異同の共通パターンは〔1△→2○→3△→45○〕で、初出の表記をなんらかの理由で替えて初刊詩集に収めたあと、再び初出の形に戻して再刊詩集に収めたことになる。一方で〔1○→2△→345○〕というパターンは
わが馬ニコルスのまるまるとした尻を見よ〔1!→2(トル)→345!〕
を除いてひとつもなく(逆にいえば、2の直しが不適だったことが怪我の功名的に3でリカバーされたともとれる)、初出と再刊の形が最終的に採られなかった箇所はなんとも据わりの悪い印象を与える。では3の再刊詩集が存在しなかったとしたら、これらの詩句の変遷はどうなるだろうか。
と〔1△→245○〕のパターンですべてがすっきりと収まり、安定感も増す。ここから浮上してくるのは、3の底本(というか原稿)は直前の刊本2ではなく、2用の入稿原稿だったのではないか、2と3は同じ原稿から別別に組版されたものではないかという疑問である。出版元が2の入稿原稿としたのは1に手を入れたもので、3の入稿原稿もそれと同じだったと仮定すれば、問題の七つの詩句がかくあるという不可解な現象を説明できる(通常、再刊するときの底本には善本たる最新の印刷物を採るのが原則で、湯川書房社主がそれを知らなかったはずはないのだが)。七つの詩句に関しては、入稿原稿の本文が校正作業のある時点で刊本2の本文に替えられた、と想定するのである。もっとも、3の仕上がりが入稿原稿に完全に忠実でないことは〈雨〉の「老人になる日まで求遠に」ひとつ見ても明らかで、それは3に著者校正が入らず、版元校正だけで本文ができたことの証左になろうか。そのうえで、実際に各本文が印刷物として登場した順序を度外視して、詩篇の生成面に注目すれば、0→1→3(ほぼ2の入稿原稿の形)→2→4→5という流れが詩句変遷の時間軸上に並ぶ。これらの堆積した層に〈神秘的な時代の詩・抄〉(前出)の諸篇や《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(思潮社、1968)の〈未刊詩篇から〉の5篇を嵌入すれば、吉岡の手を経て印刷に付されただろう詩篇の推移を詳らかにたどることができる。だが残念なことに、1の手入れ稿、それにきわめて近いはずの2の入稿原稿(それが手書きの浄書稿であれ、切り抜きベースのものであれ)、2の校正紙などの未公開資料や制作担当者の新証言が出てこないかぎり、詩句変遷の経緯をこれ以上トレースすることはできない。その検証作業をまってはじめて、吉岡実の単行詩集としては唯一、三つの刊本(1年10箇月という短期間に出版されている)・三つの本文を持つこの詩集《神秘的な時代の詩》の特殊性を本格的に論じることが可能になるはずだ。(2009年12月31日)
〔2019年4月15日追記〕
吉岡実の生誕100周年(2019年4月15日)を記念して、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉(小林一郎 編)〔A4判縦位置で印刷すると、約[292]ページ〕を新規ページとしてアップした。ただし、本サイトでは《〈吉岡実〉を語る》の一項目という位置づけのため、トップページの〈目次〉には掲出しない。
吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈 了
| リンクはトップページ《吉岡実の詩の世界》に設定してください。 | ||||
| ご意見・ご感想などのメールはikoba@jcom.home.ne.jpまで。 | ||||
| Copyright © 2002-2019 Kobayashi Ichiro. All Rights Reserved. | ||||
|
本ウェブサイトの全部あるいは一部を利用(コピーなど)する場合は、
著作権法上の例外を除いて、著作権者および小林一郎の許諾が必要です。 |
||||
![[Brought to you by LaCoocan]](image/ym_hanga_03_A.jpg)