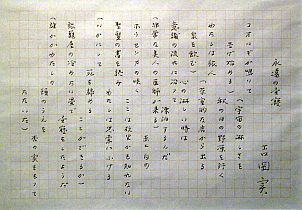 �@
�@
�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l�i���j�Ɠ���ւ�����Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi�E�j
�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��
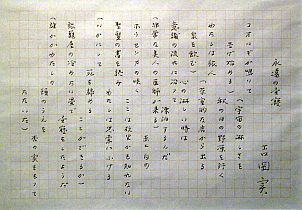 �@
�@
�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l�i���j�Ɠ���ւ�����Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi�E�j
�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#15�z�`�y#16�z�i2021�N9��30���j
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����5�z�\�\����Y����̊��i2021�N9��30���j
�g�������ɂ����锭�z�@���邢�́u�����_���h���v�Ƃ��ẴX�^���`�b�`�q�����r�i2021�N9��30���j
�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#17�z�`�y#22�z�i2021�N8��31���k2021�N9��30���NjL�l�j
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����4�z�\�\�]�X���F����̊��i2021�N8��31���j
�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#23�z�`�y#25�z�i2021�N7��31���j
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����3�z�\�\����N�v����̊��i2021�N7��31���j
�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#26�z�`�y#29�z�i2021�N6��30���j
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����2�z�\�\�ѓ��k�ꂳ��̊��i2021�N6��30���j
�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#00�z�q�ڎ��r�i2021�N5��31���j
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��i2021�N5��31���j
�W�����W���E�T���h�̓c�������s�J�t�̂ނ�t�̂����i2021�N5��31���j
�g�������̎��^�\�\�U�����^�i2021�N4��30���j
�V���Z�{�{�V�����S�W�Ɓq��͓S���̖�r�̂����i2021�N4��30���j
�̌�肠�邢���F�V���F�s�ς̂���Ԃ���t�i2021�N4��30���j
�k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�̂����i2021�N3��31���j
���\�Ƃ��Ă̘_�����邢�́q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�Z���i2021�N3��31���j
�S�i�����̓y���F�]�i2021�N2��28���j
�k�ߑ��ƔN���W���l�̂����i2021�N2��28���j
�������Ƃ͒N�i2021�N2��28���k2021�N3��31���NjL�l�j
�s�y���F��t�{���Z�فi���j�i2021�N1��31���j
�q���ш�Y���I�ԋg������3���r�i2021�N1��31���j
�g�����Ƒ剪�����\�\���삠�邢�͈��p���߂������i2020�N12��31���j
�������M��W�s���A�t�̂����i2020�N11��30���j
�g�����Ƒ��c�q���q�i2020�N10��31���j
�g�����Ɠ��x�ےj�i2020�N9��30���j
�g������i�̊O������i2020�N9��30���j
�g�����ƕB�c俕��i2020�N8��31���j
�o�q�������s�����܁t�̂����i2020�N7��31���j
�g�����Ɖ�������\�\�ӂ���̓��L�𒆐S���i2020�N6��30���j
���W�s�m���t�����i2020�N6��30���j
���Ƃ����Ɍ���W�J�~�ꂳ���i2020�N5��31���k2020�N6��30���`2021�N9��30���NjL�l�j
��a�����̍�i�\�\�g�����Ɖf��i3�j�i2020�N4��30���j
�g�����Ǝ��㏬���i2020�N3��31���j
�s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ��f��\�\�g�����Ɖf��i2�j�i2020�N2��29���j
�g�����ƍ]�ː에���i2020�N1��31���j
�g�����Ƌg��O�i2019�N12��31���j
�g�����Ɓs�J���C�`�t�i2019�N11��30���j
�g�����ƃN�����g���邢�́u���Ƃ��Ă̖��v�i2019�N10��31���j
�g�����ƐX�Ƃ̐l�l�i2019�N9��30���j
�g�����Ɛi1�j�\�\�i���X�A���a�F���X�i2019�N8��31���k2020�N10��31���NjL�l�j
�����̏W�s崉ԁt�̂����i2019�N7��31���k2021�N5��31���NjL�l�j
���A���̂Ȃ������p�̞x�k�����N�父�l�i2019�N6��30���j
�q���̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�r�W�̂����i2019�N6��30���j
�g�����Ɠ���N�v�i2019�N5��31���k2019�N6��30���NjL�l�j
�g�����S���сk���o�`�l�i2019�N4��30���j
���l���̉�q�g���������͂�Łr�̂����i2019�N3��31���j
�s��ʁt�����p�J�[�h���邢�͓y��ꐳ�̂����i2019�N2��28���j
�g�����Ɠc���~��������͑�ꏑ�[�̎��W�i2019�N1��31���j
�g�c���j�̏ё��i2018�N12��31���j
�ϊw�̋g�����_�i2018�N11��30���j
�g�����ƕ��w���i2018�N10��31���k2019�N2��28���NjL�l�j
�g�����ƒ������O�i2018�N9��30���j
�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎����i2018�N8��31���j
�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�Ɓs�ӓ��̒��̐��E�t�i2018�N7��31���j
�g�����̎����i2018�N6��30���j
�����낵�ɂ��p���q���q�r�̂����i2018�N5��31���j
�g�����Ƙa�c�F�b���邢���F�V���F�̎U���i2018�N4��30���j
�g�����ƃw���}���E�Z���G���g�i2018�N3��31���j
�g�����Ǝl�J�V�����i2018�N2��28���j
�F�숟��ǂƎ��c���j�̎���W���邢�́s��ʁt���߂����l�@�i2018�N1��31���j
�q�}�сr�Ɓs���}�сt���邢�́s�����̎}�t�i2017�N12��31���j
�g�����������і{���Z���i2017�N11��30���j
�g�����ƕa�C���邢�͋g�����̕a�C�i2017�N10��31���j
�g�����Ƌ��q�����i2017�N9��30���j
�q�~�̋x�Ɂr�Ɩї����F�̔n�̊G�i2017�N8��31���j
�g�����ƎO���R�I�v�i2017�N7��31���j
�s���㎍�蒟�t�n�����̂����i2017�N6��30���k2019�N3��31���NjL�l�j
�g�����ƍϏB���i2017�N5��31���j
�g�����ƃs�J�\�i2017�N4��30���j
�g�����ƃP�����i2017�N3��31���j
�s���㎍�厖�T�t�̐l�������q�g�����r�̍��̂����i2017�N2��28���j
�g�����̈��p���i3�j�\�\�y���F��^�i2017�N1��31���j
�s�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t���쐬�����i2017�N1��31���j
�g�����̈��p���i2�j�\�\�剪�M�s���q�V�S�t�i2016�N12��31���j
�g�����̈��p���i1�j�\�\�����r�Y�q�ӏ܁r�i2016�N11��30���j
���c�唪������Â��i2016�N10��31���k2019�N8��31���NjL�l�j
���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���o�����L�i2016�N10��31���j
�H���K�l�q�X�仂Ƌg�����r�̗]�����i2016�N9��30���j
�s�y���F��t�́q40 �u�Â��ȉƁv�r�̍\���ɂ����i2016�N8��31���j
�g�����ɂƂ��Ă̕x�V�ԉ��j�i2016�N7��31���j
�g�����Ɛ����O�S�i2016�N6��30���j
�g�����ƐΓc�g���i2016�N5��31���j
�o�l�̍���i2016�N4��30���j
�s�w�����v�l�Ƒ����B�t���邢�́s�o���J���E�N���[�Q�t�̂����i2016�N3��31���k2021�N5��31������l�j
�g�������L�̎����ɂ����i2016�N2��29���j
�i�c�k�߂̏���Ƌg�����i2016�N1��31���j
�s���܂�͂����L�t�̂��߂��i2015�N12��31���j
�g�����́q�A���X���сr���邢�́s�A���X���W�t�i2015�N11��30���k2020�N9��30���NjL�l�k2021�N8��31���NjL�l�j
�g�����̃t�����X���i2015�N10��31���j
�u���s�������v�ɂ����i2015�N9��30���j
�u�˂͂�v�Ɓu��v���邢�́q�ߔ��r�]���i2015�N8��31���j
�g�����Ɖ��n�F�l�Y�i2015�N7��31���j
�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�̂����i2015�N6��30���k2016�N10��31���NjL�l�k2018�N4��30���NjL�l�j
�g�����ƃ}�O���b�g�i2015�N5��31���j
�g�����Ɩ؉��[���i2015�N4��30���k2021�N2��28���摜�lj��l�j
�t�����E�I�u���C�G���i���V������j�s��O�̌x���t�̂����i2015�N3��31���j
�g�����ƕ��i���F�i2015�N2��28���k2017�N3��31���NjL�l�j
���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�]���i2014�N12��31���k2016�N10��31���NjL�l�j
�g�����Ƙh���ɒj�i2014�N11��30���j
�g�����������i2014�N10��31���k2015�N3��31���NjL�l�k2020�N4��30���NjL�l�j
�g�����Ǝʐ^�i2014�N9��30���j
�g�������ɂ�����G���i2014�N8��31���j
�g�����Ɨ������i2014�N7��31���k2014�N8��3���NjL�l�j
�g�����Ɛ^�甎�i2014�N6��30���j
���蕐�u�E�R�{�P�s���ӔC�ďC�s�C�܂�����{���{�S�W 57 �g�����t�ڎ����i2014�N5��31���j
�s�����t�Ƌ��Ս��i2014�N4��30���k2014�N8��31���NjL�l�j
�g�����Ɣѓ��k���i2014�N3��31���j
�g�����Ɖ�������i2014�N2��28���k2020�N5��31���NjL�l�j
�q�g�����̑�����i�r�̌����i2014�N1��31���j
�q���̖ʉe�r�Əo���̋L�O�ʐ^�i2013�N12��31���j
�g�����ƍ����t�v�i2013�N11��30���j
�g�����ƐԔ����q�i2013�N10��31���j
�g�����Ɖ��䗲���邢�͐��c�����̑����i2013�N9��30���j
�s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�́q�͂������r�i2013�N8��31���j
�s�V���W�t���邢�͑�X���s�̂����i2013�N7��31���j
�g�����̑ѕ��i2013�N6��30���k2013�N8��31���NjL�l�j
�g�����Ɠc�������i2013�N5��31���j
�g�����ƃW�C�h�i2013�N4��30���j
�q���̕a�C�r�Ɓq�^�R�r�i2013�N3��31���j
�O���q�Y��W�s�g�̏�t�\����̂����i2013�N2��28���j
�g�����Ɩx�C�Y�i2013�N1��31���j
�s�i�c�k����\�\�q�莆�r�Ɓq���r�Ɉ˂�t��҂���i2012�N12��31���j
�s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t���쐬�����i2012�N11��30���k2017�N1��31���NjL�l�j
�g�������̕ϑJ���邢�͎��ꂩ��̒E�p�i2012�N10��31���j
�ۑ��Y�ƕ��i�̃T�t�����̃X�P�b�`�i2012�N9��30���k2015�N12��31���NjL�E2016�N12��31���C���l�l�j
�g�����Ǝc��m���邢�͎��I����Ƃ͂Ȃɂ��i2012�N8��31���j
�g�����ƍ��������i2012�N7��31���j
�{�A��̏W�s�R���ȁt�ƒ��J��f����W�s�C�ԁt�̂����i2012�N6��30���j
�g�����Ɖ��������i2012�N5��31���j
1919�N���܂�̋g�����i2012�N4��30���j
�g�����̋ߑ�o��I�i2012�N3��31���j
�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t���邢�͕S�����o�̂����i2012�N2��29���k2021�N7��31���NjL�l�j
�u�g�������v�Ɩk�쑽��q���W�s���t�̂����i2012�N1��31���k2019�N12��31���NjL�l�j
�g�������W�{���Z�قɂ����i2011�N12��31���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�������̏W�s�����G�߁t�{���Z���i2011�N11��30���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�������W�s�t�́t�{���Z���i2011�N10��31���k2019�N4��15���NjL�l�j
��˔����Y�s��������̗��ꂩ��t�̂����i2011�N9��30���k2014�N1��31���NjL�l�j
�q�g�������w�فr���l�����i2011�N8��31���k2013�N5��31���NjL�l�k2016�N10��31���NjL�l�j
�g�������W�s���t�{���Z���i2011�N7��31���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�������ɓo�ꂷ��A���i2011�N6��30���j
�약��Y��ȁqDashu no sho, for voice and alto saxophone�i2003�j�r�̂����i2011�N5��31���j
�g�������W�s���[���h���b�v�t�{���Z���i2011�N4��30���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����Ƌg���M�q�i2011�N3��31���j
�g�������W�s��ʁt�{���Z���i2011�N2��28���k2019�N1��31���NjL�l�k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����̖������сq�G�̂Ȃ��̏��r���i2011�N1��31���j
�g�������W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�{���Z���i2010�N12��31���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����q���܂�͂����L�r�{���Z���i2010�N11��30���j
�}�������s鍎q�ꝱ�t�̂����i2010�N10��31���j
�g�����ƃt�����V�X�E�x�[�R���i2010�N9��30���j
�s�k�C���̌���`���t�̂����i2010�N8��31���j
�g�����ƒ������i2010�N7��31���j
�g�������W�s�Ẳ��t�{���Z���i2010�N6��30���k2019�N4��15���NjL�l�j
�����{���������s�g�����g�[�L���O�t�i2010�N5��31���j
�g�����Ƒ���C���i3�j�i2010�N4��30���j
�g�����Ƒ���C���i2�j�i2010�N3��31���j
�g�����Ƒ���C���i1�j�i2010�N2��28���j
�g�������W�s�T�t�����E�݁t�{���Z���i2010�N1��31���k2019�N1��31���NjL�l�k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����̖����s���т��i2009�N12��31���j
�g�������W�s�Â��ȉƁt�{���Z���i2009�N11��30���k2016�N10��31���C���l�k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����Ɓs���㎍�蒟�t�i2009�N10��31���j
�g�����q�k���M�l�N���r�̂����i2009�N9��30���k2009�N10��31���NjL�l�j
���c���Y�́q�g�����_�r�Ɓq�͎ʁr�̏��o�i2009�N8��31���k2016�N10��31���NjL�l�j
�P�b�Z���́s����t�Ǝ��сq�����r�i2009�N7��31���j
�g�����̏W�s�����t�{���Z���i2009�N6��30���j
���сq�▋�r�Ɣ~�؉p���̓��ʼn��i2009�N5��31���j
��|�Εv�W�Ǝ��сq�NJ|�r�i2009�N4��30���j
�g�������W�s�a���`�t�{���Z���i2009�N3��31���k2019�N4��15���NjL�l�j
�g�����ƕЎR���i2009�N2��28���j
�g�����ƃ����P�i2009�N1��31���j
�q�킽���̍쎍�@�H�r�Z���i2008�N12��31���j
�g�������W�s�m���t�{���Z���i2008�N11��30���k2019�N4��15���NjL�l�j
�R���g�̂����i2008�N10��31���k2009�N3��31���NjL�l�k2018�N12��31���NjL�l�j
�g�����̏��i2008�N9��30���j
������{�����W�听�Łs�m���t�{���̂����i2008�N8��31���j
�g�����Ɩ{���E�����\�\�q�g�����r������i2008�N7��31���j
�g�����Ƃ��`�t�i2008�N6��30���j
�g�����Ɠy���F�i2008�N5��31���k2008�N7��31���NjL�l�j
�g�����ҏW�̒J���Z�Y�����i2008�N4��30���j
�g�c���j�̑�����i�i2008�N3��31���k2010�N8��31���NjL�l�j
�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�i2008�N2��29���j
�g�����ƎO�D�L��Y�i2008�N1��31���j
�g�����Ɖf��i1�j�i2007�N12��31���j
�g�����Ɛ��e���O�Y�i2007�N11��30���j
���z�q�w�ɑr���r�̂����i2007�N10��31���j
�g�����̈������i2007�N9��30���j
�g�����Ɓs�A���r�A���i�C�g�t�i2007�N8��31���k2013�N6��30���NjL�l�j
�����V�A���E�N�[�g�[�Ɠ�т̋g�������i2007�N7��31���k2011�N6��30���NjL�l�k2016�N10��31���NjL�l�j
�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�̖{���Z���i2007�N6��30���j
�g�������F�V���F�i2007�N5��31���k2019�N12��31���NjL�l�k2020�N7��31���NjL�l�j
�g�����Ƌg�c���j�i2007�N4��30���j
���сq���L�r�̎����e�i2007�N3��31���j
�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i2�j�i2007�N3��31���j
�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i1�j�i2007�N2��28���j
�s������Ƃ̐l�X�t�̂����i2007�N1��31���k2014�N9��30���NjL�l�j
��������܈��A�i2006�N12��31���j
�g�����̏��ȁi4�j�\�\�s�g�������W�t�̂����i2006�N11��30���j
�����g�������Ɩk�����q�E���삿���i2006�N10��31���k2010�N11��30���NjL�l�j
�g�����ƃT�~���G���E�x�P�b�g�i2006�N9��30���j
�g�������̒��̖��O�i2006�N8��31���j
���̖��O�i2006�N7��31���j
�g�����̒Z���i2006�N6��30���j
�g�����ƍ��삿���i2006�N5��31���j
�g�����ƕx�V�ԉ��j�i2006�N4��30���j
�g�����́u�u���v�Ɣo��I�]�i2006�N3��31���j
�g�����́q���`�r�i2006�N2��28���j
�g�����U���̍��@�i2006�N1��31���j
�g�����Ɖ��y�i2005�N12��31���k2006�N3��31���NjL�l�j
�g�����̏��ȁi3�j�i2005�N11��30���j
�g�����̏��ȁi2�j�i2005�N10��31���k2020�N12��31���NjL�l�j
�g�����q�˒�ɂār�Z���i2005�N9��30���k2006�N4��30���NjL�l�j
�g�����̏��ȁi1�j�i2005�N8��31���j
�g�����ƃW�F�C���Y�E�W���C�X�i2005�N7��31���j
���сq�����r�̐�����i2005�N6��30���j
�g�����Ƃ̒k�b�i2�j�i2005�N5��31���j
�g�����Ƃ̒k�b�i1�j�i2005�N4��30���j
�g�����ƃI�N�^�r�I�E�p�X�i2005�N3��31���j
�g�����̎��e�q���w�r�i2005�N2��28���k2005�N5��31���NjL�l�j
�s�y���F��t�Ɖו��́q�ljԗ]���r�i2005�N1��31���j
�X��������i1�j�i2004�N12��31���j
���X�r������Ȃ̋g�����̉̋��i2004�N11��30���j
�g�������̒�������i2004�N10��31���j
�g�����ƃi�{�R�t�i2004�N9��30���k2017�N9��30���NjL�l�k2021�N5��31���NjL�l�j
�g�����̎����o�����i1�j�i2004�N8��31���k2007�N4��30���NjL�l�j
�|���m�����s�A���X�̐l���w�Z�t�i2004�N7��31���j
�g�����̖����s���O�т��i2004�N6��30���k2004�N9��30���NjL�l�j
�g���������̋H�Q���i2004�N5��31���j
�u�g�����v����u�g�����v���i2004�N4��30���k2008�N1��31���NjL�l�j
�g�����̔o���i2004�N4��30���k2005�N2��28���NjL�l�k2017�N12��31���NjL�l�j
�g�����Ƒ���l�Y�i2004�N3��31���j
�g���������ȁk1989�N11��5���t�l�i2004�N2��29���j
���낾����W�s���씼���t�̂����i2004�N1��31���j
�����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�i2003�N12��31���k2004�N7��31���NjL�l�j
�k�����H���I�̏W�s�Ԋ~�t�i2003�N11��30���j
�s�����܁t�ҏW�ҁE�g�����i2003�N10��31���j
�C���^�[�l�b�g��́u�g�����v�i2003�N9��30���k2003�N10��31���NjL�l�j
�g�����Ɓs���}�сt�i2003�N8��31���j
�g�������W�s���t�e�{�i2003�N7��31���k2010�N6��30���NjL�l�k2011�N7��31���NjL�l�j
2003�N�Łq�g�����r��T�����@�i2003�N6��30���j
�q���l�̔����ё��r�i2003�N5��31���j
�g���ܑI�l�ψ��E�g�����i2003�N5��31���j
�q���̐�F�A�g�����r�i����p�ꂳ��A2003�N4��22���j
�q���̕a�C�r�̃X���X�i2003�N4��15���k2012�N3��31���NjL�l�j
�q�g��i���Ɏ~��r�{���̂����i2003�N3��31���j
�g�����̘b�����i2003�N2��28���j
�g�����̌����i2003�N2��28���k2006�N9��30���NjL�l�j
�g�����{�̑ѕ��̕ϑJ�i2003�N1��31���k2004�N9��30���NjL�l�j
��ƃN�[�g�Ǝ��q�͎ʁr�̏��o�i2002�N12��31���k2016�N10��31���NjL�l�j
�g�����̔N���i2002�N11��12���k2012�N8��31���NjL�l�k2021�N5��31���NjL�l�j
�i�ʃy�[�W�f�ڂ����Y�L���ɂƂԁj
2018�N12��31���A���t�I�N�I�Ɂq�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r���o�i���ꂽ�B���i�����ɂ́u���l���̉�ւ̍��k��o�ȏ����̌��E�ۑ���ԗǍD�ł��B�v�Ƃ������B���D�̊J�n���N��������������A��͂蓯������o�i���ꂽ�g�����̍����N�父���Ȃ̓��D�ɂ��܂��Ă��������������āA���D���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���܍l����ƁA�����Ǝ��X�Ƀt�H���[���ׂ��ł������Ɖ���܂��B�Ƃ���ŁA�ȂɂɌ��炸�R���N�V�����M�������Ă���ƁA�s�̂̃u�c�̃R���v���[�g�A����̂���̃R���v���[�g�i���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ɓ���j�A�Ōオ��_���̂̏N�W�A�Ɛ[���肵�Ă����킯�����A�����̏ꍇ�͎s�̖{�A����{�A1�_���{�̃������[���A���҂̐����e��F���E�Z���A���Ȃ���L�Ƃ����������ɁA�n�[�h���͂ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����B���͂��܂��Ɏ��̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j����ɓ���Ă��Ȃ��n��ȃR���N�^�[�ɉ߂��Ȃ����A�u�c�Ƀt�F�e�B�b�V���ɂ��������́A���m�̏��ɐڂ������Ƃ����C�����̕����������Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������A�s�����G�߁t�Ƌg�����̓��L�������l�i�Ŏ�ɓ���Ƃ������Ԃɗ������������Ȃ�A���킸���L��I�ԁi�s�����G�߁t�́A�K�^�ɂ��g���Ƒ��̎��{�\�\�Ƃ����Ă��������݂Ȃǂ͈�Ȃ��\�\�����炭�苖�ɒu�����Ƃ��ł����Ƃ�����������邪�j�B�Ђ邪�����āq�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r�̏��I���l�������Ȃ�A����͑�ꋉ�̂��̂������B�x�܂��Ȃ���A����������������ƌ������Ă݂����B�͂��߂Ƀ��t�I�N�I�Ɍf����ꂽ���i�ʐ^�����悤�B

�q�g�����@�t���Q�ʁ@�e�y���V�s�@���l���̉�@���a�R�W�N�S���r�k�o�T�F���t�I�N�I�l
���ʂ�����Ȃ������A��U��̂��߉摜���ڂ₯�Ă��āA���ʂ̔��ǂ͍�����ɂ߂�B�Ȋw�{���������̎����āA�摜��͂��������炢���B���͂œǂ݂���������A���̂悤�ɂȂ�B
�k�c�c�l
�����������Ǝv���܂��B
�܌��\����̘Z������܂łɎQ���
���ł��ˁB�q���̐܂܂ŁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�k�c�c�l
�������͂މ�ɂ��Ă��������āA���肪��
�������܂��B�����͗��_�I�ɋؓ���
���b���ł��Ȃ�����ł��B������]��
�Đ\��܂���B�܌��\����ɊF�l
�Ƃ����̂����̂��݂ɂ��Ă���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��
�n�K�L�̕\�m�I���e�n�ʁi���t�I�N�I�f�ڂ̎ʐ^�͌f���Ȃ����j�Ɍ����鈶���͋��l���̉��\�̒|�����O�Y�ŁA���M�l�͏Z����Ж���������ꂽ�}�����[�̎Зp�n�K�L�Ɂu�g�����v�Ǝ菑������Ă���B�܂��Ɂu���l���̉�ւ̍��k��ɏo�Ȃ����������v���e�Ȃ̂����A���l���̉�̂��Ƃ͂��̃n�K�L�ŏ��߂Ēm�����B����A��������}���ق̏������錎�������s���l���t�i���l���̉�j�̓����̃o�b�N�i���o�[���{�������B�c�O�Ȃ���A�g�����̊�e���g�����o�Ȃ������k��̋L�����ڂ��Ă��Ȃ������B�����ɁA���l���̉��Â����q�u�t�������Ă̌������r�̈ē��������āA���̗l�q���킩�����B
 �@
�@
�s���l���t��25���i���l���̉�A1963�N8��10���j�́q�u�t�������Ă̌������r�̈ē��Ɖ��t�̃y�[�W�i���j�Ɠ��E��26���i���A1963�N9��14���j�̌������̈ē��i�E�j�k����������m�N���R�s�[�l
����}���ُ����́s���l���t��1�`107���i1959�N11���`1971�N8���j�ŁA3����11���������B��25���̌������̈ē��Ɂu�f�k���S�`�l�v��u9�|�v�Ə������̂́A�����̕ҏW�����s�l�̒|�����O�Y���̐l�ł͂Ȃ����낤���i�ق��ɂ��A������Ƃ���ɏ������݂��ʂ�������A�G���̐���Ɏg�������̂Ǝv�����j�B���ڂ������̑�26���̕������N�����Ă݂悤�B�Ȃ��A9��10�͑�25�����������B
���l���̉�
�u�t�������Ă̌������
(�ǂȂ������C�y�ɂ��o������)
�������y�j���ߍ@�T�������@�@�@��� ���s���Ȉ�t���
9�@�ߑ㎍�ƌ��㎍�@�،��F��
10�@�O�Z�N���d�̖��_�@���c�O�Y
11�@���Ɖf��@������s
12�@���̒��̊�@����l�Y
13�@���̘N�ǂɂ��ā@�߁k�������l��
14�@�^�S�[���̈������ƒ�R���@��]���Y
15�@�R���钹�ɂ��ā@������
16�@���㎍�����@���R�ꐶ
17�@�������l���͂�Ł@�V��a�]�@���R�o���q
18�@���l�u����@���q�����@�⍲����Y
19�@�{���ɂ��ā@�R�{���Y
20�@���������Y�̂��Ɓ@����S��
21�@�O�l�̎����@�_�ی����Y
22�@���㎍�̖����@���J�엳��
23�@�A�����J�̌��㎍�ƃ��g���}�K�W���ɂ��ā@�z�K�D
24�@�g���������͂�Ł@�g����
25�@��c�G�����͂�Ł@��c�G
26�@��㎍�̈ꎋ�_�@�x�쐳��
27�@�i�㌎�j�@�ɓ��M�g
28�@�i�\���j�@���e���O�Y�@����\�O�Y�@�c������i�\��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���h��)
�q�u�t�������Ă̌������r�̍u�t�Ɖ���͔��������킯�����A����̓��e�͂قƂ�ǎ��ʂɎc����Ă��Ȃ��B�g�����̉�ȑO�ł́A��21���i1963�N4��13���j�̒��J�엳���q���㎍�̖����r�i�����A��`��O�y�[�W�j����O���i���j�B�{�e�́u�i�����j�v�ŁA�����ɂ́u�{���͎O��������s���Ȉ�t��قɂ�����^������搶�̋��Čf�ڂ������܂����B�v�Ƃ���B��24��́q�g���������͂�Łr�́A�v���ɁA���J��̍u�����f�ڂ�����21�������{�Ƃ��ēY���ċg���ɍu�t�����˗������Ƃ���A�����́u���_�I�ɋؓ��̗��b���ł��Ȃ��v�Ɠ�����ł��ꂽ���߁A����Ȃ�t���[�g�[�N���邢�͎��^�����������k�ŁA�Ƃ������Ƃɗ����������̂ł͂Ȃ����B����Ƃ��A���N�̂s�u�ԑg�s���Ă����Ƃ��I�t�̃g�[�N�R�[�i�[�q�e���t�H���V���b�L���O�r�̂悤�ɁA�u�t�����Ɏ��̍u�t���w���������͐��E���Ă������̂��낤���B�z�K�D�Ƌg�����̐ړ_�́u�L�v���炢�����v�����Ȃ����A�g�����Ɗ�c�G�́A�̂��ɒ�������������̂́A�O�N1962�N�ɋg������c�̎��W�s���]�̐푈�t�i�v���Ёj�����Ă��邭�炢������A�����́s�k�t�̋����l�Ƃ��ĉ��������������͂����B�܂��A���J�엳���܂ł́s����t�Ȃ���̍u�t�w�������ł��Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�������̉��ƂȂ������s���Ȉ�t��ق�2019�N���݂̏��ݒn�́A�_�ސ쌧���s���捻�q2-10-10�ŁA���w��������k����5���̏����Ƃ����B
�Ƃ���ŁA���l���̉�̍u�t�߂�1963�N�Ƃ́A�g���ɂƂ��Ăǂ�ȔN�������̂��B�g���͂��̔N4����44�B1���Ɂq�n�E�t�̊G�r�i�E�E5�j�A2���Ɂq����r�i�E�E3�j�����������ƁA��i�͔��N���8���Ɂq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�����邾�����B����A�V�V�ޓ�Y�Ƃ́q�V�t�Βk�r�i1���j�⍂���d�M�����Ƃ́q����o��]�_�ܑI�l���k��r�i2���j�A����S�������Ƃ́q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�i7���j�ɏo�Ȃ��Ă���A�M�������[������Ƃ͂����A���l���̉�̌������Œ��邱�Ƃ͉����ł͂Ȃ������Ǝv�����B����ɂ��Ă��A����m�e�[�}�n���w�肳��Ęb���Ƃ����̂͋g���̖{�̂Ƃ͂������A���ǁq�g���������͂�Łr�Ƃ����A�قƂ�ǁq�薢��r�̂悤�Ȃ��Ƃɗ������������B���̂Ƃ��ɁA���H���R�Ǝ��g�̎��_�����Ȃ��������Ƃ������ڂƂȂ����̂��낤�i���l���̉�̌������ł́q�ǂ̂悤�ɂ��Ď����������r�Ƃ������肪�����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��\�\�Ƃ��������A���̎����A�g�����ɐq�˂������Ƃ�����Ƃ���A����ɐs����j�B���ꂪ�A4�N��Ɂs���̖{�t�i�}�����[�A1967�j�̊��Łq���̋Z�@�r�����ꂽ�ۂɁA�q�킽���̍쎍�@�H�r�����������錴���͂ƂȂ����A�ƌ���̂͂������������B
���āA���̈ꌏ���g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�́u���Z�O�N�i���a�O�\���N�j �l�\�l�v�ɕt��������Ƃ���A
�w���e���O�Y�S���W�x��}�����[���犧�s�������Ő��e���O�Y�̒m����B
�܌��\����[���A���s���Ȉ�t��قł́u���l���̉�v�i��\�E�|�����O�Y�j�̌���̌������ōu�t�߂�B����́u�g���������͂�Łv�B
�Ƃł��Ȃ낤���B���̌�A�s���㎍�蒟�t��s�����C�J�t�Ȃǂ̎��̎G�����k�g�������W�l��g�ނ��тɁA�l�ƍ�i�ɂ��ċg�����Ƌg���ɋ߂������l�Ƃ̑Βk����悵�������ɂ́A���̌��J���k��������ƌ���ׂ����낤�B�g�����������������J�̏�Ŏ��g�̎���������̂́i������ɈႢ�Ȃ��ƍl���邪�j�A���̒m�邩���肱�̂Ƃ��������B���쎍�̘N�ǂ������J�̏�ł������Ƃ͂Ȃ������̂�����A���̌�̋g�����u���ɗނ��邠����˗������ݑ������̂���������ʂ��̂�����B
�@�����u���Ƃ����̘N�ǂ̉�Ȃǂ́A�ǂ����D���ł͂Ȃ��B�����玄�͒d��Řb���������Ƃ��A���̘N�ǂ��������Ƃ��Ȃ��B����͎��̂���߂Čl�I�ȍl���ɂ����Ȃ��B���̂悤�ȉ�������̐l�B�ɗL���ɂ͂��炭���Ƃ����邾�낤�Ǝv���B������w�ɂ́A���̐e�����F�l�������l���̋��t�Ƃ��āA���X���d�ɗ����Ă���B�ނ�����͂��āu������w���l��v�̊w���̗L�u�ŁA��̉���Â����Ƃ��Ă���B���s�����萬�����邱�Ƃ��A�]�܂����B�i�q���ՂɊār�A�s������w���l���Ñ�P�Ձt�q���ƘN�ǂ̗[�ׁr�A1984�N6��24���A�܃y�[�W�j
���@�g�����u�t��5��11���̑�24����ȍ~�ł́A�x�쐳���q��㎍�̈ꎋ�_�r���s���l���t��25���i���l���̉�A1963�N8��10���A��Z�`��l�y�[�W�j�Ɍf�ڂ���Ă���B���J�엳���i3��9���̑�22��j�Ɩx��i7��13���̑�26��j�̂ӂ�����O�I�Ɍf�ڂɂ��������o�܂́A�����́s���l���t�̎��ʂ���͓ǂ݂Ƃ�Ȃ��B
�g�����͐��z�q�������܁r�i���o�́s�V���t1985�N11�����j�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B
��ʁ\�\���낢��̍����E����ꂽ�܂ɁA�Ҋ���䈂̑��Ԃ�����A�ܐF�̎������炷�A���̖������B���ꂪ�{���̖�ʂ̂������炵���̂ł����A���݂ł́A�i������J�X�j���ȂǂɎg���Ă��܂��B�u���C�v�Ɓu���C�v���Ƃ����߂��A���قȂ�u�ʁv�����̂������u���`�̐��E�v���A���W�w��ʁx�Ȃ̂ł��B�@���̂悤�ȕ��͂��A���͏����p�̃J�[�h�Ɉ�����āA�o��������̎��W�ɓY���A�e�����l�����ɑ������B���N�̔ӏH�̂��Ƃł���B
�@�\�\���Ƃ��܁A�����܁A���炽�܁A������������ȌÌ�̂Ђт����A���͍D�����B�����ɗގ����āA���܂��u���́v�̃C���[�W�����u�������܁v�����ɁA��т̎����������B���̎����łɁA�V�������W�̑薼�͌����������R�ł������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���܃y�[�W�j
���́u�����p�̃J�[�h�v��2018�N11��24���A�q���l�g�������M�T�C���r�̃^�C�g���Ń��t�I�N�I�ɏo�i���ꂽ�B�o�i�҂͐��{�́udaichan412�v�A��Ԃ́u��⏝�≘�ꂠ��v�A���D�J�n���̉��i��200�~�A���i�����Ɂu���O�e���̂������\�͂��ߏ�������g��������̃T�C���B���ʂ͐V���{�̈ē��ł��傤���H�^�͂�����菭���傫�ȃT�C�Y�ł��B�^�o�N�̂��߂₯�͂���܂��B���Ȃ蒃�F�ɏĂ��Ă��܂��B�^�m�[�N���[���A�m�[���^�[���ł��肢���܂��B�v�Ƃ���B���D�̌��ʂ́A�Ƃ����ƁA���t�I�N�I�ł͂��̂Ƃ��땉���Ă��肢���̂����A���蔼�ŊJ�n���i��10�{�̒l��t���āA�����ɗ��D���邱�Ƃ��ł����B
 �@
�@
�s��ʁt�����p�J�[�h�i�\�ʁj�́k����l�����i���j�Ɠ��i���ʁj�̕��́i�E�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l
�s��ʁt�����p�J�[�h�i���ʁj�̋g���ɂ�鎍�W���s�̈ē������N�����Ă݂悤�B���i���́A��f�̐��z�q�������܁r�ł͏������ύX����Ă���B
�@�H���[�܂��ė��܂����B�O���W�w�Ẳ��x���o���Ă���A�������̂Ŏl�N�̍Ό�������܂����B���̊ԁA��̎U���Ǝ����������ɂ����܂���B�ꐡ���т����C�����܂��B���āA�قڎO�N�Ԃ̎d���̏\��т����߂��A�V���W�w��ʁx���㈲�������܂����B
�@�\�\���낢��̍����E����ꂽ�܂ɁA�Ҋ���䈂̑��Ԃ�����A�ܐF�̎������炷�A���̖������\�\�B���ꂪ�{���́u��ʁv�̂������炵���̂ł����A���݂ł́A�i������J�X�j���ȂǂɎg���Ă��܂��B�u���C�v�Ɓu���C�v���Ƃ����߂��A���قȂ�u�ʁv�����̂������u���`�̐��E�v���A���W�w��ʁx�Ȃ̂ł��B
�@��؈ꖯ�E���j���ӂ��肪�J�������܂��ɁA�v���ǂ���̂��̂��Ă���܂����B
���t�I�N�I�̎ʐ^�łׂ͍������܂œǂ݂Ƃ�Ȃ����A����������ƁA�Ð��^�ۉ�^�������n�́i�u�o�N�̂��߂₯�͂���܂��B���Ȃ蒃�F�ɏĂ��Ă��܂��B�v�ł͂Ȃ��j�A�n�K�L�����t�Ȏ�G��̗p���i�V�n161�~���E111mm�j�ɒ��F�̃C���N�ō��������ň�����ŁA�\�ʂ̈����̏���ĂԒ��̃J�b�g�͂����܂ł��Ȃ����W�s��ʁt�̂���ł���i�J�b�g�̐��@�́A�g�����̓\���ӂ̂���Ɠ����j�B�g���̕��̂͊��S�ɏ��ȕ��ŁA��������܂łɓǂ��̂̂Ȃ��ł́A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�N9��30���j�̌��{���ɓ��������q���������r�Ƃ�����̏��ȁi������j���߂��B
�@�������̌h�������y���F�������Ă���A�����N���]���o���Ă��܂��܂����B�F�l�ɂ́A���ꂼ��̑z���ŁA�̐l��Ǖ炳��Ă��邱�Ƃł��傤�B���āA��N�̉āA�o�ŎЂ̂����߂ŁA�y���F�ɏA�Ắu�{�v���������ƂɂȂ�܂����B�������A���́u��̓V�ˁv���\�S�ɑ����邱�Ƃ́A����Ȃ��Ƃł��B�����ŁA���͎����́u���L�v�𒆐S�ɐ����A���ӂ̗F�l�A�m�Ȋe�ʂ̏،��������āA�w�y���F��x���܂Ƃ߂܂����B
�@���̖{�ɂ́A�F�l�̕��͂��A���f�ł�����߂Ēf�ГI�Ɂu���p�v�����Ē����Ă���܂��B�{���Ȃ�A�ȉ����̂���V�Ƃ͑����܂��B�������A���ԓI�Ȃ��ƁA�܂����q���@������A���̂悤�Ȃ��Ƃɐ����Ă��܂��܂����B�����A�����e�̂قǂ����肢�\���グ�܂��B����͓y���F�Ǝ��Ƃ̓�\�N�̌𗬂��琶�܂ꂽ�A�����₩�ȁu�{�v�ł��B�����Ɉ�����点�Ē����܂��B�L��������܂����B
�@�@��㔪���N�㌎��\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@���@�@
�u��㔪���N�㌎��\�����v�Ƃ����̂́A���{��ɑ��錩�{�̂ł����������A�܂��ɂ��̓��̓��t�ł��낤�B�g�����ƕ��ԁs�y���F��t�̒��ҁi�����j�Ƃ�������l�l�ɂ́A�ꍏ�������{��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂�����B
�����g�����犧�s���ɂ����������������s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j�����ł���B���̂Ƃ��́A�Z����̏���Ⳃɑ����}�[�J�[�Łu��@�@�@�g�����v�Ƃ������B�{�̐��藧���Ȃǂ͓����́q���Ƃ����r�ɐs������Ă��邩��A���A�����s�v���������Ƃ�����B�����A�g���͂��łɕa���ɂ����āA�V���Ɏ��M�ł��Ȃ������̂ł͂���܂����B�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j���s�Ẳ��t�i���A1979�j�ɂ͈���������A���͂Ȃ��悤�����A���ƍl������̂́s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j���炢�����A�͂����Ă�����̂��Ȃ����̂��A���������Ȃ��B�\�\�ƁA���e�������Ă��ās���{�̌Ö{���t�Ō�������ƁA��pⳂɏ����̂���s���[���h���b�v�t���o�i����Ă���ł͂Ȃ����B�b�̓W�J���炷��A�������肵�Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���������w���̐\�����݂����ĕԐM��҂��Ă���ƁA�Ȃ�Ǝ�Ⴂ�Ŕ����̏������݂��ł��Ă��炸�A�ɐ�ɂ��A�u�����L�����Z���v�ƂȂ��Ă��܂����B���Ȃ݂ɔ�����\16,200�������B�c�O�B
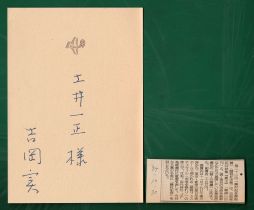
�g�������y��ꐳ�Ɉ��Ă��s��ʁt�����p�J�[�h�Ɠ����ɋ��܂�Ă����V���̐蔲��
�Ƃ���ŁA���t�I�N�I�̏o�i�ҁA���{�́udaichan412�v���N���͋g�����̂��Ƃ����N�����ׂĂ���Ό��������킯�Łi�������j�A���̏o�i�Ƃ͕ʂɁs���{�̌Ö{���t�Ō������������p�J�[�h�t���́s��ʁt�𓌋��E�؏��X����w�������Ƃ���A���ꂪ�y��ꐳ���̈�{�������B�y��͋g���̐�y�i�̒}�����[�̕ҏW�҂Łi�s���{�̌Ö{���t�ɂ͎u�꒼�Ƃ�O�H���Y����y��Ɉ��Ă����M���Ȃ��o�i����Ă��邩��A�����ł͂Ȃ���������Ȃ��j�A�{�T�C�g�ł̓y��ꐳ�ւ̌��y���܂Ƃ߂�A
1950�N�㔼�A�S�����o�̉��Łs������{���{�S�W�t�i�����͉��n�F�l�Y�j�̕ҏW��S���A�̂��ɕҏW�����ƂȂ����B
�s��t�S�W�k�S7���l�t�i1953�`56�j��a�c�F�b�s��t�̓��L�t�i1956�j��S���i������2�_�Ƃ��g���j�B
�s�����܁t�i1969�N5���n���j�̏���ҏW�҂ŁA1�N8�����Ԋ��s�̂��ƁA�ҏW���g���Ƀo�g���^�b�`�����B
�ƂȂ�B�}�����[�Ɍ��炸�A�ҏW�҂͌�����ނ��ƒS���Ҏ���̕��M�ƂƂ̌𗬂���z�����肷����̂����A�y��ɂ͂����������삪�Ȃ��A�n��ɂ������߂Ă��Ȃ��悤���B����āA�g�����Ɋւ��镶�͂��c���Ă��Ȃ��B�����A�����؏��X����w��������{�ɂ́A�g�����s��ʁt�œ����L�O����܂���܂����ƕ�V���̐蔲�������܂��Ă����B���̐蔲�����y��ꐳ�̎�ɂȂ�Ƃ����m�͂Ȃ����̂́A���͂������Ǝv���B�y��͂�������W�ɋ���ŁA���Ă̓����̊������сA�L�O�Ƃ����̂��낤�B�����@�����A�V���̐蔲���̕��ʂ��N�����Ă������i���ʂ̗��O�Ɂu'84�E10�E30�v�Ɖ��M�Ŏ菑�����ꂽ�A15�s�̃x�^�L���ł���j�B1984�N10���́A�����E�����E�ǔ��E���{�o�ς̊e���̏k���łׂĂ݂����A���Y�L���͌������炸�A�f�ڎ��͖��ځB���Ȃ݂ɁA10��30���̋��s�V���ɂ͓��l�̋L�������������A�k�C���ƒ����̗����ɂ͂Ȃ������B
�@���\���u�����L�O����܁v�i����Ў�Áj�́A�g�������̎��W�w��ʁx�i����R�c���j�ƁA�����Ǝ��̐��E�������Ȃ������œW�J���Ă���e�n�M�`���́u�����̋Ɛсv�Ɍ��܂����B���܊e��\�ܖ��~�B
�@�����͏\�ꌎ�\����ߌ�Z������A�����E�V�h�̒��������z�[���ŊJ�����u����t�F�X�e�B���@���q�������Ղ�r�v�̐ȏ�ŁB�Ȃ��A�ߑ㎍�̇��������蓡���Ɍh����\���āA����܂̖��̂Ɂu�����L�O�v���������Ƃ����B
�g�����́A�s�T�t�����E�݁t�̍����������̂��Ƃ͐��z�ɏڂ��������Ă��邪�A�s��ʁt�̓����L�O���������
�@���N�̏H�A���\���u�����L�O����܁v���A���͎��W�w��ʁx�ŁA�e�n�M�`�́u����̋Ɛсv�ňꏏ�Ɏ�܂����B����ƂƂ��Ă͏��߂Ă̂��Ƃł���B���́u���ܗ��R�v�̂��Ƃ��I�m�ɁA�e�n�M�`�̑��ꗝ�O�𑨂��Ă���B�\�\��҂Ɠǎ҂̂������Ɉʒu���Ȃ���A�����ŔZ���Ȉ��̋��Ƃ��āA��i�̉���ł��Ȃ��O�I�ȑ���ł��Ȃ�����Ǝ��̐��E������߂ď����Ȃ������Ō������X�ɓW�J���Ă���\�\�ƁB�Ə����������ŁA�ǂ̂悤�Ȑl�l�����ɗ�Ȃ����̂��͂킩��Ȃ��B
�@�V�h�̒��������z�[���ł̎����̓���A���͋e�n�M�`�Ɍ������B�u���ِ݂͕オ���ƕ����Ă���B���͈��A�����œ����邩��A���̂Ԃ������Ă����v�B�ނ͎��M�ɂ݂��āA�����Ă��ꂽ�B�e�n�M�`�͒d��ŁA�c�X�ƌ��͂��߂�B����͐l���_�I�ŁA�����̒��O���[���ɖ����ł������������B�������b�͂������A�����ɂ���āA���܂��܂Ƃ߂��Ȃ��悤�������B�ׂ̐Ȃł͂�͂炵�Ȃ���A�D���e�n�M�`�̊���A���͒��߂Ă����̂��B�i�q�e�n�M�`�̂��Ɓr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�l���y�[�W�j
�@�u����܁v�̎��^���̓�̐ȂŁA���������������S�������݊��A���̎����������ƈ����āA�u�܂����Ă���Ă��肪�Ƃ��v�ƌ������B����Łw��ʁx���j�����ꂽ�̂��B���ꂩ��ܔN�̍Ό�������Ă���B�i�q�S���f�́\�\�u�g�������v�ق��r�A�s���㎍�ǖ{�@����S�����鑒���t�A�v���ЁA1989�N3��1���A���y�[�W�j
�@�ܔN�O�̂��ƁA���W�w��ʁx�̗�����^���̓��A���Ȃ��͏j���̌��t���q�ׂɁA�������Ă���܂����ˁB��ŕ����A���@���Ò��̕a�@���o���āA����ꂽ�Ƃ̂��ƁB�i�q�u�P�l�v���������Ȃ��ցr�A�s���㎍�蒟�t1989�N3�����q�k���J�K�M�l�����r�A��l�Z�y�[�W�j
�y���F���F�V���F���͂��ߊ����̒m�F�ɒǓ�����Ǔ����A�����������1990�N5���ɟf�����g�����ɂƂ��āA�s��ʁt�̓����L�O�����܂͍Ō�̐���̕����p�ӂ����`�ɂȂ����B�s��ʁt��ꂽ�y��ꐳ���A1984�N11��19���̎��^���ɂ͏o�Ȃ����̂��낤���B
�\�\�����܂ŏ����Ă��āA2019�N1�����߁A���t�I�N�I�ɋg���������N��Ɉ��Ă��n�K�L���o�i����Ă��邱�Ƃ�m�����i�o�i���̃^�C�g���́u�g���� �����M���M �^�M �t���������N�� �������[�O�i�[�w�j�[�x�����Q���̎w�x���w��ʁx �����܁��w�m���xH������l�v�B�n�K�L�̐����Ɂu���C�X�E�L�������A�T�~���G���E�x�P�b�g�A�V�F�C�N�X�s�A�Ȃǂ̌����Œm���A�p�����CBE�M�͂���͂����A�����N��̋����i���\�^���㎍�̂ЂƂ̓��B�_�Ƃ����w�m���x�Ȃǂ̍�i�ŁA���ō��̎��l�̈�l�ɐ�������A�g�����B�^����̂��i�́A�g�����́A���M�t���ł��B�^�����N��ֈ��Ă�ꂽ���̂ŁA�����́w�j�[�x�����Q���̎w�x�̊���̂��j���ƁA�����́w��ʁx������܂���܂������Ƃ����������́v�Ƃ���j�B�����ɗ��D�ł����̂����̃n�K�L�B
![�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j](image/kusudama_ymshoka_takahashi_1.jpg)
�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j
�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�i1984�N9��25���t�A1984�N9��26���k18�]24�l�ڍ��Ǐ���j�̕��ʂ��N�����Ă������B
����ƏH����̓����Â��悤�ɂȂ�܂����B
���[�O�i�[�́w�j�[�x�����Q���̎w�x�̊�����A
���j���\�グ�܂��B��������Ƃ̔���
����������Ƃ̔��킵�������I
�ȂƊ������ӂ������Ă���Ƃ���ł��B
���āA�����₩�Ȃ���B�킪�w��ʁx
������܂��܂����B���\�́A�\����
�{����ɂȂ�Ǝv���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�㌎��\�ܓ��@�@��
�����I�������L���Ă����B�s�j�[�x�����Q���̎w�t�͍�F���q�����g�E���[�O�i�[�A�G�F�A�[�T�[�E���b�J���̑S4���{���V���ق���o�Ă���B��҂́A��1���q���C���̉����r�i1983�N4��10���j�����R�C�i���������A���N5���Ɏ��R���}���������߁A�㑱��3���������N��E�����N�v�Ȃ����Ă���B���Ȃ킿�A
�@��2���q�����L���[���r�i1984�N1��20���j
�@��3���q�W�[�N�t���[�g�r�i1984�N4��20���j
�@��4���q�_�X�̉����r�i1984�N9��10���j
�g���̗��̒��O�ɍ������������̂��A��4���q�_�X�̉����r�����������̂��A�i��1�����܂ށj�S���������̂��A�͂�����킩��Ȃ��B���ł̑�1�������3���܂ł́A�W���P�b�g�̑��Ɂq�����͂ƈ��̍s�����Ђ߂��^���̎w���߂��鑑���ɂ��Ċ��\�I�ȉp�Y����\�\���R�C�i�r���A�����đ�4���̃W���P�b�g�̑��ɁA�q�����ꂽ�w���߂��鐒���ȉp�Y�̔ߌ��\�\���̉~�̍\���ɂ��ā\�\�����N��r���f����ꂽ�i�E���{���X�I�j�B�g���f��ɂ́s���C���̉����\�\�j�[�x�����O�̎w�t�i1999�N4��25���j�������N��E�������i��4���̍����N��ɂ�����ɂ́u������͂邩�ɗ��킷�郏�O�l���A���ł��鑧�q�E���v�Ə�����Ă����j�̋���ŁA�����V���ق���o�Ă���B�����́kThe Originals of Great Operas and Ballets�l�V���[�Y�̈���ŁA���V���[�Y�ɂ͍N��E�N��q�����L���[���r�A�N��E����q�W�[�N�t���[�g�r�A�������q�_�X�̉����r���܂܂��B����ł悤�₭�u��������Ƃ̔��킵��������Ƃ̔��킵�������v�����������킯���B�Ȃ������N��́A�\��́s�j�[�x�����Q���̎w�t�͎��R����p�����܂łŁA�������́s�j�[�x�����O�̎w�t���Ƒ�4���Ŏw�E���Ă���B
�k�NjL�l
�s����t�̃X�|�[�N�X�}���Ƃ������ׂ����Ñ��Y�́q���l�����̃t�F�X�e�B���@���r�i���{�o�ϐV���A1984�N11��25���j���s��ʁt�̗�������ɐG��Ă���̂ŁA�֘A����ӏ��������B
�@�k�c�c�l���ɍ��N���A�g�������̎��W�u��ʁv�ƂƂ��ɁA�e�n�M�`���̑����̋Ɛт���܂��Ă���B�k�c�c�l
�@��܂�������l�ɂ��ẮA���J�K�M���ƌÈ�R�g���ɘb�����Ă�������B���J���́A�����ɂ����̐l�炵���X�i�b�v�E�V���b�g����˂��悤�Ȍ�肭����ʂ��āA�g�����̐l�ƍ�i�������₩�ɕ����т����点�Ă������A�È䎁�́A�È䎁�̍�i���������������Ă���e�n���Ƃ̂����������Ȃ���A��ƂƑ����ƂƂ̓�ƕs�����͂���I�ȊW���A�È䎁�̏������E���v�킹��悤�ȈÂ��܂Ȃ����ŕ`���o���Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ̎�҂̈��A���A���������Ƃ��ɂ��肪���Ȓʂ肢����̂��̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̌����ނ��o���̂������Ō����Ă��āA���́A�����ȂǂƂ����U���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�ӂ����ȑΘb���ɗ��������Ă���悤�Ȏv���������B�i�����A��l�ʁj
���Â̓`����A���J�ɂ��g���́u�l�ƍ�i�v�͂Ȃ�Ƃ��Ă��������������i���ꗿ������ł��Q���ł����Ƃ�������A�������ł͂Ȃ����j�B�����ō���}���ُ����̓����̃o�b�N�i���o�[���J���Ă݂�ƁA�s����t��315���i1985�N1�����j�Ɉ��Ấq���l�����̃t�F�X�e�B���@���r���f�ڎ��̋��ē]�ڂ���Ă�����̂́A�s��ʁt�̗����܂Ɋւ���L���́A���J�̂��̂��܂߂āA��������Ȃ������B���J�K�M�͂ق��̏��ł��g���́s��ʁt�ɂ��ď����Ă��Ȃ��悤�ŁA�c�O���ɁB����ɁA��313���i1984�N11�����j�̕\�S�Ɂq��\�������t�F�X�e�B�o���w�������Ղ�x�r�̍��m�L�����o�Ă���B���̃v���O�������ʔ����̂ŁA�������ďЉ�悤�B
���Ƃ������a59�N11��19���i���j�ߌ�5��30���J��E6���J���@���Ƃ������V�h�����E���������z�[���@�����ꗿ���P�T�O�O�~
�q��T���r
�@�`�@����呾���c�c�c�c�c�c���{���g
�@�a�@��22���L�O����ܑ��掮
�@�@�@�@�I�l�o�߁c�c�c�c�c�c���Ñ��Y
�@�@�@�@�ܑ���c�c�c�c�c�c�c����S��
�@�@�@�@�g�����ɂ��āc�c�c���J�K�M
�@�@�@�@�e�n�M�`�ɂ��āc�c�È�R�g
�@�@�@�@��҈��A�c�c�c�c�c�g����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�n�M�`
�@�@�@�@�ԑ�����
�@�b�@�P��E2���ԃX�s�[�`�@�k�c�c�l�i�������������j
�@�@�\�\�\�\�\�x�e�@10���\�\�\�\�\
�q��U���r
�@�`�@���쎍�N�ǁq���́r�@�i��R�{���Y
�@�@�@�@����ꟁE�F�����p���E�a��F��E�@���߁E�O�D�L��Y
�@�a�@������w�����ǂ��֍s���x�@�쁁���J�엳��
�@�@�@�@�k�c�c�l
�@�b�@�t�B�i�[��
�@�@�@�@����̑升��
�@�@�@�@�g���u�����݁v�i��c�c�c�������S�R�s�E�������X��
�q��V���r�@���e���i�ߌ�9�����j
�@�@�@�@�����ѓX�u����v�i�V�h�����n�����E�X�o���r�����X�X�a�Q�E���������r���n���ׁE���l��~�E�ǂȂ������C�y�ɂǂ����j
�@�@�i��c�c���q�E�E�ԍⒷ�`�E���{���E�@���߁E�ԓc�p�O
�@�@�i�s�c�c�{���E�������
�@�@����c�c���Ñ��Y�E�V���y�q�E�������q�E�҈䋪�E�R�{���Y
�v���O���������邾���ŁA���l�������C�x���g�ɏn�B���Ă��邱�Ƃ��悭������B�ȗ������l�����܂߂�ƁA�g���E�e�n���������s����t���l��W�҂�50�]���ɂ̂ڂ�B�s�ςƂ��������납�ł���i���㌒������J�Y�����Q�������Ƃ����t�F�X�e�B�o�������̗l�q�́A�O�f���Õ��ɏڂ����j�B�Ƃ���ŁA�s�g�����N���t�̖`���Ɂq�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�ƃN���A�t�@�C���u�b�N�i�g���Ƒ��j�r�̔w�\���̎ʐ^���f���Ă���B5�����邻�̐^�̗ΐF�̃N���A�t�@�C���u�b�N�Ɂq���\���u�����L�O ����܁v�̂��m�点�r�Ƒ肷���������ۑ�����Ă����B�g�����̎��M�Łu�i1984.10.19�j�v�u19�����v�ƃ��������鏈������ƁA�X�����ꂽ���̂Ǝv�����B�����ɂ́A�g�������W�s��ʁt�́u���ܗ��R�v�����̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B
�@�ؕ|�ƌ����̈�ȂŌ��������[����̂��A�ʎ��ԁi���j�j�Ƌ����ԁi����j�j�����˂����Ȃ���A�ؗ�Ɍ͎����Ă��鐸�_�̌����E�̐�ɂ̃X�y�N�g������˂���s��ʁt�B����́A�ߋ��̌|�p�̑O�q�̋Z�@�̑���ƍĐ��a���ɍs����֓I�ȋL�O��B��\���I�����{���炵������Ȃ����E�ɗނ����Ȃ��Ǝ��Ɍ����Ȏ��Ƃł���B
�e�n�M�`�́u�����̋Ɛсv�̎��ܗ��R�́u��҂Ɠǎ҂̂������Ɉʒu���Ȃ���A�����ŔZ���Ȉ��̋��Ƃ��āA��i�̉���ł��Ȃ��O�I�ȑ����ł��Ȃ������Ǝ��̐��E������߂ď����Ȃ������Ō������X�ɓW�J���Ă���B���̎����I�ȓw�͂ƐV�N�Ȍ����͐��܂���ɑ����B�v�ł���A�g���͑O�f�q�e�n�M�`�̂��Ɓr�ł͌����́u�����v���u����v�Ɓi�ς��āj�L���Ă���B�Ȃ��A���܂̂��̂Ƃ��̑I�l�ψ��͈������j�A����N�v�A����S���A�a��F��A�@���߁A�߉ϑ��Y�A�����N���A���J�열���A�R�{���Y�A�O�D�L��Y�A���Ñ��Y�ŁA���ܗ��R���������͈̂ψ����̈��Ñ��Y�ɈႢ�Ȃ��B
�g�����͐�O�̓Ǐ��̌��ɂ��Ă͂��Ȃ�ڂ������z�ɏ����̂����Ă��邪�A���ǎ��i�Ƃ�킯���W�j�ɂ��Ă͂قƂ�NjL���Ă��Ȃ��B����͎��l�Ƃ��Ă̊�Ɣ閧�Ƃ������ނł͂Ȃ��A�P�s���W�قǁA���邢�͔o��̎G���قǁA�M�S�ɓǂ�ł��Ȃ������Ƃ��������̂��Ƃ�������Ȃ��B����ł��s���Y�Ę_�t�i1931�`44�A�S150���j�ɂ͓�_�̎����̏o�ōL���\�\�s�����G�߁t�i1940�j���s�t铁t�i1941�j�\�\�����ꂼ��ڂ��Ă��邩��A���̎G���Ƃ��ĕ]�����Ă������Ƃ͊m�����B���Ȃ݂�Wikipedia�ɂ́q���Y�Ę_�r�̍��ڂ��Ȃ��A�u�����̍��ڂ���"���Y�Ę_"����������v�ɂ��ĒT���ƁA
�@�⍲����Y
�@�팩�P�g
�@���ڌ���
�@���c��
�@�R���U��
�Ƃ������l�̖���������B�g���͂����̎��l�ɂ��ď��������Ƃ͂Ȃ��A�k�����q�̐V�삪�ǂ݂����ă`�F�b�N���Ă����A�Ƃ������Ƃ���ł͂Ȃ����낤���i����̃e�[�}�ł���c���~����s���Y�Ę_�t�ɂ͎��\���Ă��邪�j�B
�@���͉J�ɂȂ��^�슛�����肽�^���͍z��h�̍��~�ɕa��ł�\�\�B��ꏑ�[�̏��G���u�Z���p���v�̍L�����ŁA���W�w�R���x�̈��p����Ă����A���̎O�s�̎���ɁA�s��炿�̏��N�́A�������薣����ꂽ�B�₪�āw�R���x����ɓ���A���͏��߂ēc���~���m�����̂������B����߂ē��{��̔Z���A�c�ɂ̐�����R��̕��i���A�_�Ԃ��Ȃ���A�s�v�c�ƁA�����I�œ����x���悢�A�������Ǝv�����B���ꂩ��A���͎��̎��W�w�ԗ₦�x����ɓ���A��ʂ̒Z�͂����u�����B�\�\�J�ɈÂ����^�������Ȃ�������̓X�^�Ԋ��ɂ͏��Y�ԁm���݂Ȃւ��n�Ɩ��_���m�قƂƂ����n�������Ă����\�\�B
�@���łɒ^�ǂ��Ă����A�����t�v��k�����H�̂��������̎��тƂ���ׂāA�~��̎��ɂ́A�o�~�I�Ȗ��ƁA���_���Ȋ��o�Ƃ��Z�����Ă����B����䂦��R�����Ȃ��A��ꂽ�S���A�����ΈԂ߂�ꂽ���̂��B���ꂩ�炶�ɁA�����I�߂��o�Ă��܂����B������A���ɂƂ��ẮA���m�̎��l�ƌ����Ă��悢�B���̑S�W���s���_�@�ɂ��āA���̑S�e��m�肽���Ǝv���B�����₩�ȑz���o�̂��߂ɂ��B
�g�����s�c���~��S�W�t�̓��e���{�i�}�����[�A1984�N11���j�Ɋ��q�z���o�̎��l�r�Ƒ肷�鐄�E���ł���B�����ŗ]�k�������BWikipedia�Ɂu��ꏑ�[�i������������ڂ��A1923�N �n�� - 1944�N3��31�� �p�Ɓj�́A���đ��݂������{�̏o�ŎЂł���B�吳���N�����O�̏��a���ɒ��J�얤�V�g���n�Ƃ��A�����̔��Ƀt�F�e�B�b�V���ɂ������A��ࣂƂ������{�̍��ؖ{�����s�A�u��ꏑ�[�����v�Ǝ]����ꂽ���ƂŒm����v�Ƃ���悤�ɁA���Ђ͐�O�̎��W�̓ǎ҂ɂ͊i�ʂ̑��݂ŁA���̓��e�����邱�ƂȂ��瑢�{�E�������҂�s�������{�Â���ňꎞ����悵���B�����J�X���s�����P���W�t�i1939�j��20��O���̋g���̎��X���₵���A�����Ă�����͓ǂ������s�������A�P�b�Z���i�x����{��j�s����t�i1932�j�́q�����r�i�C�E18�j�ɉe����^�����Ǝv�����A���Њ��s�̖|�ł���B�������G���̃r�u���I�O���t�B�ɂ́u�w�Z���p���x�A�ҏW�E���s���J�얤�V�g�i�̂��t�R�s�v���ҏW���j�A1931�N5��1�� �n���v�ƌ�����B���c���Y���s�ÎG���T���t�i�_�n�ЁA2009�j�ň����Ă���悤�ɁA�������́s���a���w�����j�t�i�u�k�ЁA1965�N9��25���k�����͕��Y�t�H�V�ЁA1958�l�j�ɂ́u�k�c�c�l�����̏o�ŊE�̒q�d�Ғ��J�얤�V�g�i��ꏑ�[�j���w�Z���p���x�Ƃ����G����n�������B���̎a�V�ȕҏW�A����ꂽ�`���́A�\�K�Ƃ����j�i�̒艿�Ƒ��ւ��āA���́u���E�����E�v�z�E���p�E���y�E��]�v�i�ƁA�\���ɂ������B�j�̎G���̏o�����Z���Z�C�V���i���Ȃ��̂ɂ����B�u�p�����̃p���͂Ƃ炸�Ƃ����̃Z���p���͏������v�Ƃ�����`�����l��H�������̂������B���́w�Z���p���x�̕ҏW�ɂ��������̂��A�w�V�Ȋw�I�x���l�̕��c���l�ł������v�i�q��\��� �|�p�h�̌Q�r�A�����A��Z���y�[�W�j�Ƃ���i�t�R�s�v�͕ҏW�҂ɂ��Ď��l�E���M�ƁA���c���l�͂̂��Ɏ������w��ƁE���|�]�_�Ɓj�B��N�A���łɒ}�����[�̎Ј��������g�������ɒB���v�́s�����C�J�t��ɂ��Ď��d�ɓo�ꂵ���w�i�ɂ́A�s�Z���p���t�i1931�`41�j�ɐe�����Ƃ���������������Ȃ��B���Ă��̂�����ŁA�c���~��̎��ɖ߂낤�B�g�������E���ň������s�R���t�i��ꏑ�[�A1935�j�Ɓs�ԗ₦�t�i���X�ЁA1936�j�̎��́A�s�c���~��S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1984�N12��15���j�ł͈ȉ��̂Ƃ���B
��
���͉J�ɂȂ�
�슛�����肽
���͍z��h�̍��~�ɕa��ł
���̂v�E�v�O���[�i�̓���e�m�ɂ�䂤�n�����Ă��܂�
���͂�Â��ɋ����ƃJ�����X���݁m����ׂ��n�Ɓ@���ʂ̃O���[�v�E�W���E�X����邳��Ă
���͐������Ám�ނ��ځn��
��ӂ���@�����m�܂ǂ�݁n�̒��m�����n�@���̓A���J�����Y�_�́@�z��̐������݂����鉹��������
���t�m�����́n�̓��Ђ������ĉJ�������������͂��߂�
�g�������E���Ɉ������̂͂��̎��̖`��3�s���������A���̎��͑S�тł���B
���_��
�J�ɈÂ���
�������Ȃ�������̓X
�Ԋ��ɂ͏��Y�ԁm���݂Ȃւ��n�Ɩ��_���m�قƂƂ����n�������Ă���
���ɂ́q���r���������g���̐S��킩��C������B�Ƃ����̂́A�ق��ł��Ȃ�����R�c�ł̋g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1976�j�̏o�ōL���ɁA�q�O�d�t�r�i�F�E17�j�́u���F�����͖����͋A���Ă䂭���낤�^�ޏ��̍s��ɗ����͂�����^�킽���̊G�̂Ȃ��̐X�̓��ցv�Ƃ���3�s��������Ă������炾�i�s�_��I�Ȏ���̎��t�̍L���́A�������s�����C�J�t�ɍڂ����͂����j�B
��
���J���v�s�����Ɗv�X�\�\��ꏑ�[�E���J�얤�V�g�t�i�͏o���[�V�ЁA2006�N8��30���j�ɂ́A�c���~��̑�W�s�C�̌�����Βi�t�i1930�j���k�����̎��l�p���l�̈���Ƃ��Ċ��s���ꂽ���Ƃ�������Ă���B���p���ɂ͋g�����e���i�Ǝv����j���ڂ������B�O�D�B���s���ʑD�t�A������s�����t�A�|����s�ۉ�C�݁t�Ȃǂł���B
�@�k���a�ܔN�l��������̉�k��ꏑ�[�u�����̎��l�p���v���s�́u�ō����[�H��v�l�ɂ́A�x������Ɩ��V�g�A�����ēc���~��A�⍲����Y�A�鍶��A������A�H�R�C�O�A���R�ȎO�Y�A�O�Y��Y���W�܂����B�O�D�B���A�|����̓�l�͓s���ŗ����Ȃ������A�Ƃ����i�c���~��u���т�������v�j�B
�@�u�����̎��l�p���v�̓����̌v��͏\���B���^���l�E��i�̑I��ɂ͖x�������������B
�@�k�c�c�l
�@�x������k���@�����[�u���w�_�v�i�x����{��j�l�������āA��������V�i�ɂ����������͑�W�i��O�́u�q��p�v�A����͊⍲����Y�̑�O���W�j�B�ŔN���͓~��̎O�\�Z�B����A�O�\��A�B���͂��������O�\�B�ȉ���\�㔼���l�l�A�ŔN���̕H�R�C�O�͓�\��B���V�ȃC���[�W�̊�悾�����B�uPANTHEON�v�u�I���t�F�I���v���邢�́u���{�v�̊�e�҂����ł���B
�@�l�Z���A�㐻�i�w�v�̌p�\���j�A�\������B����畔�A�艿�͈�~�B�{���͕S��\�ł܂łƂ���B�����������j����������܂łɂ́A�e����҂ɓ`�����Ă������̂Ǝv����B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j
�@�c���~��́A��������̒鍑�z�e���ł̗[�H��ɏ�����āA�x������ȉ��o�ȎґS���ɂ͂��߂ĉ�����Ƃ����B�u�ȗ����ꂪ�䉏�Ő搶��撊P�ɐڂ���Ɏ������B���Ƃ��Đ��U�̍K���Ǝv���Ă���v�i�u�x����{�搶�̃v���t�B���v�j�ƋL���Ă���B�k�c�c�l�~��̑�O���W�́u�R���v�A�\�N�����ɑ�ꏑ�[����o�ł��ꂽ�B�u�ԗ₦�v�i�\��N�����A���X�Ёj�A�u�̉��̉́v�i�\�ܔN�����A�A�I�C���[�j�Ǝ��W�͂Â��B�i�����A��Z��y�[�W�j
���J���v���w�E����悤�ɁA���́k�����̎��l�p���l�i���W�͗\�����ꂽ�S7���A�O�D�B�����W�s���ʑD�t�A�⍲����Y���W�s�q��p�t�A�鍶�厍�W�s�ߐ������t�A�c���~�W�s�C�̌�����Βi�t�A�����䎍�W�s�����t�A�|���莍�W�s�ۉ�C�݁t�A�H�R�C�O���W�s���R�t�����s���ꂽ�j�̃��C���i�b�v����悵���͖̂x����{�ł���A�g�����̏��a10�N��̎����̎�e�́A���J�얤�V�g����ꏑ�[���x����{���擱�������l�����i�s�R���t�̓c���~���M���Ƃ���j���傫�Ȓ����Ȃ��Ă����B���Ȃ݂ɁA���a30�N��A�ɒB���v�̏��惆���C�J�����s�������㎍�l�̌l�I�W�i�g�������܂܂��j�̃V���[�Y���́A��ꏑ�[�̂���Ƃ͂킸���ꕶ���Ⴂ�́k�����̎��l�o���l�������B����͂��͂�m�M�Ƃł���B�����[�����ƂɁA�g���́q�f�ЁE���L���r�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�j��q�k���M�l�N���r�i�s����̎��l�P �g�����t�A�������_�ЁA1984�j�ł́A�s�g�������W�t�i���惆���C�J�A1959�j�̃V���[�Y�����ꏑ�[�łƓ����u�����̎��l�p���v�Ɍ�L�E��A���Ă���B
���āA�g�����͓c���~��ɂ��āA�S�W�̐��E���Ƃ����`�ŕ��͂��₵�����A�c���~��i�g�����25�ΔN���j�͋g�����̍�i�ɂ͌��y���Ă��Ȃ��悤���B�܂��A�g�����ƕ��w���ɏ������悤�ɁA��l��1961�N�t�̑�11��g���܁i�g�����s�m���t�Ŏ�܂��������N�j�̑I�l�ψ���ŐȂ������Ă��邪�A�c���͑I�l�ψ����Ƃ��āu�R�c�ɓ��Ă͊e�ψ����e�̈ӌ����[���ɓf�I����Ƌ��ɁA���e���ׂ��͗e��A���̖{�̂������ɂ߂ăX���[�Y�ɑI�l�𗹂��������ƂL����v�i�s���w�t1961�N5�����A�܈�y�[�W�j�Ə����������ŁA���̑I�l�ψ��i�؉��푾�Y�E���e���O�Y�E����l�Y�E������Y�E���c�O�Y�E������s�E�O�D�L��Y�E�g���E�R�{���Y�j�̈ӌ��ɐG��Ă��Ȃ��B��N�ɂȂ邪�A�c���~��͎��l�Ƃ��̍�i�S�ʂɂ��āA���̂悤�ɏ����Ă���i�s�ޗǓc�̂قƂƂ����t�A�M�������[�ᔪ�A1973�N7���j�B
���l�̃T�u�X�^���X
�@���l�̍�i�́A���̎��l�̃T�u�X�^���X�ł��邱�Ƃ́A���X�����܂ł��Ȃ����Ƃ��B�Ƃ���ŁA���̎��l�̐��s����퐶���̏�Ԃ�m�邱�Ƃ́A��i�Ƃ͕ʂ̎�������łȂ��A����͕L��T�u�X�^���X�̌���ɒ��ڐG��邱�Ƃɂ��Ȃ�B���Ƃ��Γ��L���Ȏ�L�m�[�g���A�����ɂ͂��̐l�̋����Ȃ������̂��̂�������B������Ȃ�ł����L�̃t�B�N�V�����͂Ȃ����낤�B�����������̂̒�����A��i�ȏ�̃G�g���X�����o�����肷��B����͂����ւ̂������Ƃł���B
�@�捠���͂���l�̜ϜȂŁA��L�̈ꕔ������G���ɔ��\���邱�Ƃɂ����B����͎��̉��m�ӂƂ���n�\�\�䏊���A���̂܂܂��ڂɂ�����悤�Ȃ��̂��B�e�[�}�́u�T���O���X�̕����v�Ɵ����Ă݂����A�����������̂ł͂Ȃ��B���e�͎v�O���͂��ߊ��z�A�����炵���Z���X�ƃj���A���X�̂悤�Ȃ��́A�Q�֓I�̖��A�������̃n�C�}�[�g�A�������팩���������ƁA���ꂩ��ЂƂ��܂ւ̎莆�̈�߁A�ЂƂ��܂���̎莆�̈�߁A���̒��ɂ͏�������̊Â����t������i���ꂾ���͌��\�o���Ȃ��j�B�e���p���̎�L�͎����g�����Ă����̂����B����ł��ꂩ��������Â��Ă䂭���肾�B�����Ď��@�����Ĉ���̏����ɂ܂Ƃ߂����v���Ă���B�ʒi�ЂƂ��܂���������A�Љ�̈��J�����𗐂����̂łȂ�����A���������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B
�c���~��̎��͈�_�������낻���ɂ��Ȃ��������Ɋт���Ă���B�Ō�̎��W�ƂȂ����s���\����t�i���Ȃ̓��{�̉�A1979�N3��1���j�̖����ɂЂ�����ƒu���ꂽ���̎��ł����A��O�ł͂Ȃ��B�^���҂́A�u�o�����^�C���v�u�C���v�A�u�v���v�u�����v�̗p�@������B
�Y�ꂦ�ʂЂ�
���e��࣏n��������
�Z�N�V�[�Ŕ���X���Ă�
�E�B���N�ɖ��������
���̂ЂƂƊ��x���f�[�g����
���̋A�肵�Ȃɂ��̂ЂƂ͎���
����Ƃ��̓E�C�X�L�[�̃o�����^�C�����܂�����Ƃ��͌C�����v���[���g�Ƃ��Ă��ꂽ
���̌C���̐F�����̍D�݂ɂ҂����
���̂ЂƂ̃Z���X���悭�M�m�������n���Ă䂩������
�f�[�g�����x���d�˂Ă��Ďv��������Ȃ�������Ɏ���Ȃ���
���ꂪ���Ē����t�������ƂȂ��ƌ����悤
���ʎ��͂��̂ЂƂ̝����m���n�ɖ|�M�m�ق�낤�n����Ă����̂����m��Ȃ�
����ɂ��Ă����͂��̂ЂƂ���m������n�߂邱�Ƃ͏o���Ȃ�
�����ۂ��A���̎U���i�Ⴆ�Ώ�f�q���l�̃T�u�X�^���X�r�j�͗��߂����Ƃł����������̂��A���̗͂����������E�Ȃ��̂��B�}�����[�őS�W�̑�1���k���T�l�Ƒ�2���k���U�l���悻�s���̂������܂����p���Ƃ���A��3���́k�o��E���z�l�̐��z�͎����Ŋ����p�ł���A�������Q�]�����ēǂ߂����ȋC������i�o��͏������p���𐳂��K�v�����邪�j�B�����܂��ɁA�ŏ��̋�W�s�s�l�t�i���܂����[�A1946�j�̖`����ƁA�q�o��E��r�̖�����i��M�ł���j���f����B�Ƃ��ɁA�H�ו������肱��ł���̂��������B
�����ďt�̎������ċ���
�y���ɓ����̍��≺�J�V�d�i�s�o����_�t���a55�N�k1980�N�l6���j
�k�t�L�l
�g�����́s�����̈�Q�t�i����͐��̓��L�ɓo�ꂷ��j��s�ߑ㌀�S�W�t�A���ؔł̑S���W�Ȃǂ̑�ꏑ�[�̏o�ŕ���ǂ�ł���͂������A�����ɂ��ď����L�������͎̂c���Ă��Ȃ��B�����ŁA�q���L�@���l�Z�N�r�ɓo�ꂷ������䎍�W�s�����k�����̎��l�p���l�t�i��ꏑ�[�A1931�N1��20���j���Ƃ肠���悤�B�����A�������[�ɋΖ����Ă����g���͂��̓��L�ŁA
�@�ꌎ�\�Z���@���A��X�̑����Ԏq���̂Ƃ���֊��B�u���Ȃ��͎����������̂ł����Ăˁv�ƌ����A�v�킸���������߂�B�l�����炳��l�ł���B�ߌ�A�ؓc�������������˂�B�Δ���������ŎG�k�B�����ӂ������Ƃ������o���Ă�������B�S���̂����ꍏ�B�r���̖{���Ő����䎍�W�s�����t���B�O���ɐ_�c�̎������֖߂�B�x�����сB�\�d�ɂ̏��q������������������Ă����B�₳���������B�i�s�邵����t5���A1990�N1��31���A�O�l�y�[�W�j
�Ə����Ă���i���̂���ؓc�����r���ɏZ��ł����j�B������͖x����{�剺�̎��l�����A���J���v���u�u�����v�͂Ȃ����ԁA������̂���������̎��W�������B�i���a�O�\�ܔN�Ɂu�����O��v����듴�ł܂Ƃ߂�ꂽ�B�j�k�c�c�l�u�������V��ƏW�v�A�k�c�c�l���N���e���u���t���v���ꏑ�[����|��o�ł��Ă���B�����A���ɂ́u�I���t�F�I���v��O�\�����ɘA�ڂ��ꂽ���[�g���A�����u�}���h���I���̉́v���A������ł������ɂ���A�o�ł���Ȃ��������Ƃ��ꏑ�[�ɂƂ��Ďc�O�Ȃ��Ƃ������Ǝv����v�i�s�����Ɗv�X�t�A��Z��y�[�W�j�Ə����悤�ɁA�����ł͖|��ƂƂ��ċL������Ă���B���[�g���A�����́s�}���h���I���̉́t��1994�N�ɍu�k�Ђ̕��|���ɂɓ���������A�悯���ɂ���������̂�������Ȃ��B���̎��W�s�����t�́A�g���̓��L�̎��_�ŁA���s����15�N���o���Ă���B���s���ɂ͓���ł��Ȃ������ŗ��̏���������������Ȃ��B�s�����t�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�͊v�A���͎��j�E�V���E�\���i�������A�苖�̈�{�͂���������j�B�{���ɑ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����̂́A���J�얤�V�g�̈ӌ��������Ă��邱�Ƃ͂܂�����Ȃ��B�Ƃ���ŁA�㐻�۔w�p�\���͔ӔN�̋g�������p�������{�E�����̗l���ł����邪�A�k�����̎��l�p���l�̂���Ƃ̊֘A���͔����悤���B�g���͌p�\�����`�T����e���̖{�ɍ̗p���Ă��邪�A�����菬�����l�Z���́k�����̎��l�p���l�́A�ؔ��Ƃ������ނ���ݏd�Ȉ�ۂ�^����B�{���p���i���͖{�������j�����������Ȃ����ɁA�V�����܂߂āA�O����̓I�[�o�[�X�y�b�N�ł͂Ȃ��������B�ۑ��̏�Ԃɂ���낤���A�����̈�{�̔w�v�i�˂����ŁA�\����̖��͂Ȃ��悤���j�́A�\�P���̃~�]�̏���㟊���āA���c�Ȃ܂łɗ��Ă���B�g���͐���s�����t�Ɏ��߂�ꂽ�A�Y�s�L�t�̌��ڂ��̂悤�ȕW�莍���ǂ��ǂ̂��낤�iShift JIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��鋌���͕\�������j�B
�����b������
���Ám��������n�������m�ւ�n�̂��݂�
�ЂƂ薰�m�˂ށn�Ă��͕a���m�т₤���n�̂ЂƂł�
����m�͂��ځn�̂ق̂��Ȃ邠�����
������̉ԁm�͂ȁn�̟ފJ�m�܂��n�͂��������F�m����n����
�Y�m������n�Ӕӏt�m���n�̂������ȓ��m�Ёn����
�����ɂȂ����܂ւ���ċz�m�����Ӂn����̂�
���ق��Ȓ��m�ĂӁn�̂͂����₤��
�������m�����n�����m���ȁn�̂��锧�m�͂��ցn�̂��ւ�
���т������m�Ȃ܁n�߂������낢�̂ɂق�
�ځm�߁n���ނ�[�m�ӂ��n���˂ނ�ɂ�����
���܂͂����������m�˂ށn�鎞�ԁm������n�ł�
�₳�����@������ɑ��m�����n�Â�
�Ƃق��H���m�����߂��n���������
�ЂƂ�
���܂�ɈÁm����n���@�Ám����n��
���Â��ɂ��@������̉ԁm�͂ȁn�̂₤��
����킭�����߂��铁m���炾�n�͓��m�ɂفn��
 �@
�@ �@
�@
�����䎍�W�s�����k�����̎��l�p���l�t�i��ꏑ�[�A1931�N1��20���j�̔��i���j�Ɠ��E�\���i���j�Ƒ�ꏑ�[���s�́k�����̎��l�p���l�̂����̎��W6���k�o�T�F�s�c���~��W�\�\���铹�̎��l�t�i�R���������w�فA1995�N9��30���A��Z�y�[�W�j�l�i�E�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���r���@�����t�v�쐬�q�ؓc�����N���r�́u�吳�ܔN�i����Z�j�@��\�Z�v�̍��ɂ́A�u�k�����l�{���k�L���S���c���厚���ΐ�i�ϒˁj���Z�Z�Ԓn�i�̂��A�L����G�i���J�Z���ڈ�ꔪ�ܔԒn�A���E�L���搼�r�ܓ�\�O��\�Ԓn�j�Ɉړ]�B�Ȍケ���ɒ�Z����v�i�s�ؓc�����S�W�k��12���l�t�A�V���ЁA1978�N5��20���A�O���Z�y�[�W�j�Ƃ���B�g����������u�r���̖{���v���r�܂Ȃ̂��A�ǂ����ق��̏��Ȃ̂��킩��Ȃ����A���̓��A�ؓc��K�˂��̂́A�������[�i�����s�_�c���ђ���m�Z�j�����̔N��7��15���Ɋ��s���银�b�W�s�ِl���~�t�i�����F�������j�̑ł����킹�̂��߂�������������Ȃ��B10��30���ɂ͓������������̑����œ��b�W�s���@�̒�t���������[����o�Ă��邪�A�g���͂����҂����A8���ɓ��Ђ�ނ��Ă���B
�g���������W�s�Õ��t�i���ƔŁk���s�l�͑��c�唪�l�A1955�j�ɂ܂Ƃ܂鎍�������Ă�������A�ł��e���������F�l���A���c�唪�̑����鍑���p�w�Z�}�ĉȎ���̌�y�A�g�c���j�ł���B�g����1952�N���납��A���Ս�ɋ߂����ϒn�����̊␣�Ƃ̓�ԑ����̕����ɋg�c���j�ƏZ��ł������A���̎Ⴂ�G�`����1954�N�A�N��̏����ƐS�����Ă��܂����B�g�c���j�́A�G�{��ƂƂ��đ听�������c�唪�i1918�`2016�j�⏺�a������\���鎍�l�ƂȂ����g�����i1919�`90�j�̂悤�ȁA���g�̎d�����Ȃ��܂��Ɏ��疽�������i�����Ŏ����������͂��ނȂ�A���̐̂̉�Ђœ����������g�́A���̌�A�o�c�����܂������Ȃ��Ȃ��Ď����������A��͂蓯���������l�́u���������Ŏ��ʂȂ�Ƃ������A�d���̂��߂Ɏ��ʂȂ�āv�ƒV�����B���ɂ������������j�B���͋g�c���j�̎��т����^�������邽�߂ɁA����܂Łq�g�����Ƌg�c���j�r�i2007�N4���j�Ɓq�g�c���j�̑�����i�r�i2008�N3���j�����������A���������q�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎��݁r�i2018�N8���j�������i�ɂȂ��āA���̐��N�����킩��Ȃ����Ƃɜ��R�Ƃ����B���Ɍf����̂́A�q�g�������y���`��Ɩ��E��i������ ���r�̋g�c���j�̍��i����e�j�ł���B
�g�c���j�i�悵���E�������A192?-1954�j
���N�͖��ځB���c�唪�i1918-2016�j�̑����鍑���p�w�Z�}�ĉȎ���̌�y�̉�ƂŁA�g�����̔N���̗F�l�B�g�c���j�̃I�W�i�H�j�͖|��ƁE�p���w�ҁE�������w�҂̋g�c�b�q���Y�i1894-1957�j���Ƃ����i���c�唪�k�j�B
�@�@�\�\�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u�R�@���ϒn���̎��Ӂv�ŁA���j�Ɠ������Ă�������̂��Ƃ���z���Ă���B�܂��q�k���M�l�N���r�Ɂu���j�̎����_�@�ɁA���ꂽ�����s�E�h�Ɗ�ȗ����V�Y�v�Ə����Ă���B
�@�@�\�\�g�����Ƌg�c���j
�@�@�\�\�g�c���j�̑�����i
�g�����Ƒ��c�唪�S�����ƁA�g�c���j������̂͑唪�̍ȁA���c�\�l�q�����[���Ăق��ɂȂ��B2018�N��9�����{�A1951�N���狏���\���铌���E���n�̂���ɁA�\�l�q����ƁA���j�ŃC���X�g���[�^�[�E�G�{��Ƃ̑��c��コ���K�˂��i��コ���1953�N�̐��܂�ŁA1960�N3��27���̋g���̓��L�ɂ́u���j�@���@�Ƃ�q�A�G���J�A���A�L�����ɗ���v�Ƃ���B�g���̓N���X�}�X�ɂ̓v���[���g�̊ߋ�������A��������̂悤�ȑ��݂������Ƃ����j�B�c�O�Ȃ���A�g�c���j�̐��N�͔������Ȃ������B�l���Ă݂�A�����I�ȏ�O�ɖS���Ȃ����F�l�̌o�����ڍׂɋL�����Ă��邱�Ƃ̂ق����������낤�B�����Ɋς邱�Ƃ̂ł����̂��A���c�Ə����̃A���o���Ɏ��߂�ꂽ�g�c���j�̏ё��ʐ^�ł���B�g���������̐��z�q�����݂��̂��s�r�i���o�͒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t1959�N6��10���\�\���Ȃ킿�z�q�v�l�Ƃ̓��k���s�̂܂��ɂЂƌ���̔��s�j�ŐV�����s�̏o���ɂ������āA�u�J�������~�����Ȃ����̂ŁA���c�唪�ɓd�b���Ď����ė��ĖႤ���Ƃɂ����B�k�܌��\���l�\���A�_�c�W�H���̃C�G���[�J�b�v�ŗ��������B�\�ܕ��قǑ���������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�y�[�W�j�Ə������A���̃J�����ő��c�唪���B�e�������̂��낤���B�\�l�q����̂������āA�g�c���j�̏ё����f����B��������B�e�̔N���ꏊ�͕s�������A���ʒu��2���͕������炷��Ɠ����Ƃ��̂��̂��낤�B�����ł�2�_�́A�ǂɉf��e�܂ʼn��o����Ă���悤�ŁA�B�e�҂̂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʋZ�ʂ�����������B4�_�Ƃ��֎q�ɍ������Ă���̂́A�|�[�g���[�g���B��Ƃ����i���c�唪�́j�B�e�Ӑ}�������Ă������߂��B�Ȃ��A�����ɂ͌f���Ȃ��������A�g�c���j��1950�N�̉āA���c�唪�����Ɛ_�ސ�E���q�̊C�݂ɗV��ł���B
��
�g�c���j�̑}�G��ƂƂ��Ẵf�r���[��Ǝv�����H�c���X�ҏW���ҁs�ӂ����Ȃ��Ă�\�\���E�̂��b�k���ǂ��G����23�l�t�i�H�c���X�A1950�N12��20���j�͍�������}���كf�W�^���R���N�V�����ʼn{���ł���i���̖{�Ƃ��Ă͉{���ł��Ȃ��j�B2018�N11��22���A���n�旧�����u�}���ٓ��ʼn{���i���ǁj�����̂ŁA�T�v���L���B�q�������r�̎��ɂ���N���W�b�g�Ɂu�Ђ傤���@�������@�@���c�唪�v�u�������@�@�g�c���j�^���c�唪�^���c�����v�Ƃ���悤�ɁA�O����̎哱�����������̂͑��c�唪�ŁA���ʂ̃��B�W���A�����g�c�Ƒ��c�Ɖ��c�������������̂́A�N���̍Q���������̂Ȃ��ŁA�}���ŊG���d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������̂��i�����ɍ̂�ꂽ��т��q�������r�ł́q�ӂ����� ���Ă�r�A�{���y�[�W�ł́q�͂���̂����̂��Ă�r�Ƒ肳��Ă��āA���e���炷��Ίm���Ɍ�҂̂ق����ӂ��킵���̂����A�����D�悾�����̂��낤�j�B�N���ǂ̘b�ɑ}�G��`�����̂��A�G�����炾���ł͒f��ł��Ȃ��BWebcat Plus�̖ژ^���Q�Ƃ��A�q�������r���L���B
���������ς�� ����̂��́@�A�����J�̂��͂Ȃ� / 5
�炭���� �˂����@�����̂��͂Ȃ� / 12
���ł����� ���@���V���̂��͂Ȃ� / 18
�͂�Ԃ�� �Ђ悱�@�X�y�C���̂��͂Ȃ� / 31
�ӂ����� ���Ă�@�C���h�̂��͂Ȃ� / 40
����� �͂Ȃ�߁@�t�B�������h�̂��͂Ȃ� / 57
���t�ɂ́u���a���ܔN�\�\�ܓ�����^���a���ܔN�\��\�����s�^�艿��܁Z�~�^���s���@�����s���c��_�c�x�͑�O�m�l�@������ЉH�c�m�͂��n���X�v�i�����͏�p�����ɉ��߂��j�Ȃǂƌ�����B�J���[����̗��\���ɂ́k���ǂ��G���Ɂl�������̑S22�����Љ��Ă���B��1���͑��c�唪�����߂đ}�G����|�����u�������Ƃ��˂̂���������i�A�����J���b�j���g�����v�ŁA��22���́u�A�t���J�̈̐l�c�c�i�Љ�ȁj�O��ߎq�v�\�\���������ANDL-OPAC�ɂ��ΊG�͑��c�唪�\�\�B���̌�ɁA�Ԃ������Łu�ȉ������^�H�c���X�v��搂��Ă���B�H�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl�́A���c�唪�Ƌg�c���j�Ƃ�����l�̑}�G��Ƃ킯�ł���B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�g�c���j�i4�_�Ƃ��j�k�ʐ^�F���c�唪�Ɓl
��
�苖�Ɂs���ꐶ���t��37���i1954�N10��1���j������B�������ꌤ�������ďC���A�}�����[�����s�����G���̖{���̓��W�́k��Ƃ̗p���p��l�B�q�ڎ��r�̍Ō�Ɂu�\���c�c�c�c�g�c�@���j�v�u�J�b�g�c�c�c�c���c�@�唪�v�Ƃ���B���j���S�������̂�����1954�N�̉Ă������͏H������A�Ō�̎d���̂ЂƂ��낤�i�g���́A���̎G���̕ҏW���ɂ͊ւ���Ă��Ȃ��悤���j�B�\���Ƒ��c�唪�̃J�b�g�̃y�[�W���f����B�g�c���j�̕\���́A�w�p�I�ȎG���ɂ悭�݂���悤�Ȗڎ������e��D�肱�@�\�I�Ȃ��̂����A�o�b�N�̊w�I�Ȗ͗l�͂����ɂ��͎キ�����Ă��܂��B�����ۂ����c�唪�̃J�b�g�́A�X�s�[�f�B�����肵���^�b�`�i�N�������̂悤�ȕM�v�j�ɂ��芵�ꂽ�d���ŁA���ɂ͏��M���`����Ă���B�\�l�q����ɂ��Β���̊C�ӂň�����唪�͐É��E�ɓ��̊C���D���ŁA�悭�o�������Ƃ����B�u���v�k���g���l���u�c�v���k�唪�l�ƍs�����u�����Ƃ������тꂽ�����v�i�����͎��I�U���A�̂��ɐ��z�̈����ɂȂ����q�˒�ɂār�̖`���j���֓��ߌ��̂悤������A���������ɓ��̊C�łł����낤���B���̒n�ŕҏW���ꂽ�Ɛ��@����鎍�W�s�Õ��t���o��̂́A��1955�N�̉Ăł���i�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�́k2010�N6��30���NjL�l���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
 �@
�@ �@
�@
�s���ꐶ���t��37���i�ďC�F�������ꌤ�����E���s�F�}�����[�A1954�N10��1���j�̕\���k�g�c���j�l�i���j�Ɠ��E���̃J�b�g�k���c�唪�l�i���j�Ɠ��E�{���y�[�W�̃J�b�g�k���c�唪�l�i�E�j
�k�t�L�l
���c�唪�́A���̎��`�Ƃ������ׂ������s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�N7��1���k���o�͊G�{�W���[�i���sPeeBoo�t1990�`94�l�j�ŁA�g�c���j�̂��Ƃ����̂悤�ɏ����Ă���B
�@���̍��k1950�N���l�悭���Ǝd���������Ă����������̌�y�ŋg�c���j�Ƃ����j�ƈꏏ�ɁA�w�Z�}���֘b���ɍs�����Ƃɂ��܂����B
�@���͐펞�����炸���ƒ����܂�܂́A���w����̃I�[�o�[���������č�����W�����p�[�Ƀu���V�������A�ꏏ�ɍs�����j�Ɍ����܂����B
�@�u���̂ق������Ȋ������ȁB�����ē��X�ƍs�����v
�@�w�Z�}���ɍs���ƁA���O�͊o���Ă��܂��ۊ���̎В����炪����Ă���܂����B
�@����͂ƂĂ��Ȃ��d���̗ʂ������̂ł��B
�@�A�蓹�A���j�Ɠ�l�ŋi���X�ɓ���A�K�̔�Z�p���n�߂܂����B��l�ł������萋����A�����̎������̐����ł͎v�������ʋ��z�ɂȂ锤�ł����B�������d���̗ʂƊ����̊W�ŁA���ɉ����𗊂܂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�H�c���X�̎d���̂������ŁA���Ђ̎d�����͂��Ȃ���`���邵�A���̍ہu�{���ƂȂ������ƂȂ�Ȃ���v�Ƃ��������厞��ȃX���[�K���������ēƗ������ӂ��A�f�g�p��ސE���܂����B�i�����A�ܘZ�y�[�W�j�B
�u�d���������Ă����v�Ƃ����̂͌��t�̈��ŁA�d��������Ă����̂͂����ς瑾�c�唪�������̂ł͂Ȃ����B1944�N�A���c�唪�Ƌg�c���j�͎G���s�������p�t�w�k�o�w���̕ҏW�ψ��߂Ă��邪�A�����ł����c���ҏW��Ƃ̏��͂��g�c�Ɉ˗������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�����A�����Ȃ肻���ɍs���܂��ɁA�����[�����������Ă��������B�������p��w�Ɋw�сA2012�N�܂œ���w�ɕ�E���������m�Y�i1943�N���j���q�������p��w�̗��j�i�����m�Y�u�`�m�[�g�j�r�ɂ́q�Q�l�����r���t����Ă��āA���́q��3�� �w�����鍑���p�w�Z�x�@�@�����P�\����w�k�o�w�ց@���ёO�� (11�N��)�r��1944�N�̍��Ɂu����v��gif�摜�Ōf���Ă���B�����ɂ́u���a�\���N�㌎����v���Ƃ܂ł��L�ڂ���Ă���A�����쐬���ꂽ�����Ǝv����B���c�唪�̖��͂��́q�j�q�����Ɛ�����r�ɂ͂Ȃ��q�j�q���{������r�̕��ɁA�g�c���j�ȂǂƂƂ��ɂ���B���Ȃ킿�A1943�N�����A���c�唪�͍݊w�����������ƂɂȂ�B�͂����Ă���͐M���ł��邩�B���}����A���c�Ƌg�c�̋L�ڂ��N�����Čf����B

�q�j�q���{������r�i�����j�B�ʼn��i�Ɂu���ĉȁv������A��l�ڂ����c�ō��[���g�c�B�k�o�T�l
���c�唪�@�����s�_�c�����쒬��m��
�g�c���j�@�k�����s�l���z��⠒�����
���c�唪�̏Z���͑O�f�̎��`�i�s���̃C���X�g���[�V�����j�t�j�ɂ�����\�\1928�N�i���a3�N�j�A10�̂���A��Ƃ͒��肩�瓌���Ɉڂ�A�_�c���쒬�̌����_�̊p�ɗm�i�X���J�����B�_�c�ł̐����́A1945�N�i���a20�N�j2��25���̋�P�ŏĎ�����܂ł̖�20�N�ԑ������i�����A���y�[�W�Q�Ɓj�\�\�Ƃ������e�Ƃ������B���͎��Ɍf�����q�����鍑���p�w�Z �w���ꗗ�r�����������琶����B���c�唪�́u��10�Ɛ�(���a19�N)1944�N9/23�@1940�N���w�v�Ƃ������o���̂��ƂɁA�}�ĉȂ̑��Ɛ��Ƃ���
���c�唪�@�@1918 ���茧�^1944�u�������p�v�w�k�o�w���ҏW
�ƋL����Ă���B���̎����ɂ͖}�Ⴊ�Ȃ����A�L�ڂ͐��N�E�o�g�n�E�����鍑���p�w�Z������֘A�����A�ł��낤�B�����c�̎��`�ƏƂ炵���킹��ƁA������������̂��B���`�̋L�ڂ��܂Ƃ߂�Ƃ����Ȃ�B�u1918�N�i�吳7�N�j12��28���A���c�ǎO�Y�Ƃӂ��̒��j�Ƃ��đ��ɐ��܂��B1938�N�A�����鍑���p�w�Z�ɓ��w����B��q�g�i�̂��̑听���݁j�̌o�c����X�}�g���̔_��ēi�R���j�̎d���ɏA�����߂ɁA�Z���E�����ɒʏ����N�������Ə؏��������Ă��炢�A1941�N�A�����鍑���p�w�Z�}�ĉȂ𑲋Ƃ���v�B����܂��Ȃ����茧�Ɉڂ�������A���^����̌��͖��ɂ��Ȃ��B�����A����́u1944�N�i���a19�N�j9��23���i��10�Ɛ��j�v�Ǝ��`�́u1941�N���Ɓv�̈Ⴂ���ǂ��l����ׂ����B���c�唪�̎��`�ɂ͐��A�u�������̓������ŕ������Ă����i�c�v�����Ɓu�����f�U�C���ЁA�X�^�a�I�E�g�[�L���[�v���̂r�E�s�̊Ŕ��グ�邱�ƂɂȂ����v�i�����A�܁Z�y�[�W�j�Ƃ���A����ł͂��̉i�c�v�������c�Ɠ���1944�N���ƂƂȂ��Ă���B��������́A�u1944�N���Ɓv���L�͂̂悤�Ɏv���Ă���B�����ۂ��A�g�c���j�́u��12�Ɛ�(���a21�N)1946�N3/23�@1942�N���w�v�Ƃ������o���̂��ƂɁA�}�ĉȂ̑��Ɛ��Ƃ���
�g�c���j�@�@1944 �ΘJ����2�w�N�^�u�������p�v�w�k�o�w���ҏW
�ƋL����Ă���B���́u�ΘJ����2�w�N�v���킩��ɂ����B�ΘJ�������Ȃ킿���p�ŁA1943�N�ɂ͒��p���x�̐����ƌ��������}���A1944�N3���܂ł�288���l�]�肪���p����A��ʘJ���ґS�̂�2�����߂�܂łɂȂ����iWikipedia�j�Ƃ�������A1943�N����44�N�ɂ����ĐV�K���p���ꂽ�Ƃ������Ƃ��B������ɂ��Ă��A1942�N�ɓ��w����1946�N�ɑ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B������x�������悤�B�g�c���j�i���N���ځj�̍݊w���Ԃ́u1942�N�`46�N�v��4�N�ԁA���c�唪�i1918�N���j�̍݊w���Ԃ́A���`�ł́u1938�N�`41�N�v��3�N�ԁA����ł́u1940�N�`44�N�v��4�N�ԁB���`�̋L�q���̂�ƁA���c�Ƌg�c�̍݊w���Ԃ��d�Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�������Ȃ���A���`�Ɍ�����Z���Ƌ����ɕt���͂��܂ł��ČJ��グ���Ƃ�����Ƃ����}�b�i���ۂɂ̓X�}�g���ɍs�����A���N�قǂőގЂ��ĕʂ̌��z�n�̐E�u���{���E����������v�ɏA�����̂����j�����\���Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B������1944�N�́s�������p�t�k�w�k�o�w���l�ҏW�Ƃ����ʂ̎������ł���B

�s�������p�t�k�w�k�o�w�L�O���S�l�i1944�j�k�o�T�A�\���F�g���F���A�ҏW�ψ��F��؍��E���X���O�E���c�唪�E�x�F�O�Y�E�g�c���j�l
���{�����Ȃ̂ŁA�����m�Y�ɂ��L�q�ȏ�̏ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B��������ł́A�ҏW�ψ��̒��X���O�i���m��j�E��؍��i�����ȁj�̓�l�Ƃ����c�Ɠ���1944�N���ƁA�x�F�O�Y�i���F�j����1945�N���ƂƂȂ��Ă���i�g�c��1946�N���Ɓj�B�s�������p�t�k�w�k�o�w�L�O���S�l�ɂ́q����r��q�ҏS��L�r���ڂ��Ă���Ƃ��邩��A�������画�����邱�Ƃ������Ɗ��҂����i�g�c���j�̐��N���킩��ƁA�Ȃ��̂��Ƃ��肪�����̂����j�B���c�唪�̍�i���T�ς���̂ɍœK�ȁs���c�唪��i�W�t�i���b�ُo�ŁA2001�N4��20���j�́q���c�唪 �N���r�ł́A���`�Ɠ����u1938�N���w�A41�N���Ɓv�ƂȂ��Ă���B�����Ƃ��A�s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�j�́q���c�唪 �N���r�͓��R�s���c�唪��i�W�t�̂�����Q�Ƃ��Ă���͂�������A�������e�ł��T�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��B���̑�w�ݐЊ��Ԃɂ��ẮA����̒����E�T���ɘւ������B
�C���^�[�l�b�g�ŕ����T�����Ă���ƁA�Ƃ��ǂ��u����́v�Ƃ��������ɏo���킷�B�����Ԃ�O����ϊw�s���ƌ��g�t�i���A���e�̉�A1982�j�Ɂq�g�����E�o���r�����^����Ă��邱�Ƃ͒m���Ă����B�����A���̈�т����̂��߂ɌÏ���4,000�~�𓊂���̂͂��߂��ꂽ�B�}���قœǂ߂Ȃ����Ɖ�����̂́A����}���قɂȂ����߁A���ݑݎɂ��ߗׂ̌����}���قł̉{�������Ȃ�Ȃ��i�Ƃ���ŁA����}���ٓ���1���̒P�s�{��1���œǂނ��Ƃ́A�s�\�ł͂Ȃ��ɂ���A������ł���j�B���݂̍j�̓��{�ߑ㕶�w�ق��������Ă��炸�A�v�ē����������i�_�ސ�ߑ㕶�w�قɂ������͂������A���̖{��ǂނ��߂ɉ��l�܂ŏo������͉̂������j�B������q���{�̌Ö{���r������ƁA���z2,000�~�̂��̂��o�Ă����̂ōw���ɓ��݂������B������@�ɃC���^�[�l�b�g�Œϊw���������Ă݂�ƁA����6���ɓc�����X����s�ϊw�S��i�k�S3���l�t���o�Ă���ł͂Ȃ����B�q�g�����E�o���r�͑S��i�̑�1���Ɏ��^����Ă��邩��A���{�̋H�����l������Ĉ����o�܂��悤�ɂȂ����̂��B���_�W�s���ƌ��g�t�̓��e�i���j�͂������B
 �@
�@
�ϊw�s���ƌ��g�k���A���e�p��2�l�t�i���A���e�̉�A1982�N3��1���j�̕\���i���j�Ɓs�ϊw�S��i�k�S3���l�t���e���{�i�c�����X�A2018�j�̕\���i�E�j
�T
�������z�\�\��iX�ɂ�����o���k�������낵�l
�X��`�M�E�o���\�\�d�����S�k�u�S�v�T���i��㎵�l�E�\��j�l
�ߍX���M�E�o���\�\���_�̎}�k�uapocr.�v�S���i��㎵�Z�E�܁j�l
�g�����E�o���\�\������Ă䂭���Ԃ̑܁k�uapocr.�v�R���i��㎵�Z�E��j�l
���C�ւ̑k�s�A���邢�͂킪�I�u�Z�b�V�����k�uapocr.�v�U���i��㎵���E�l�j�l
�U
�֏�̌ǓƁ\�\��X�a�v�K���W�w���̕��x���߂����āk�u����v�T���i��㔪��E��j�l
�]�X���F���_�\�\���̓�����̈�ʁk�����\�l
�钹�f�z�\�\���̌��k�uWho's�v20���i��㎵���E�O�j�l
�G���Ƃ��āk�u�������v74�`77���i��㎵�O�E��`��㎵�l�E���j�l
�������̕Ћ�����k�u���Ǝv�z�v�i��㎵�O�N�\���j�l
�V
����s�k�����\�����̔����l
�@���ڂ�����
�ڎ��ɂ͕��肪�L����Ă��Ȃ��̂ŁA�\�\�̂��ƂɌf���A����Ɂq���ڂ������r�ɂ��鏉�o�̋L�^���k�@�l���ɕ�����BWikipedia�́q�ϊw�r�Ɉ˂�A�g�����_�̏��o���sapocr.�k�A�|�N�`�t�@�l�t���́u1975�N�k�c�c�l7���A�uapocr�v���X�a�v�K�Ƒn���v�Ƃ���B�s�g���������ژ^�t�ɂ��f�ڂ������̂ŁA���̏��o����T���̂����A�c�O�Ȃ��Ƃɏ������Ă���}���ق͌�������Ȃ��B���āA�s�ϊw�S��i�t���e���{�́q���N���r�ɂ��A�ς�1938�N9��26���A���쌧�����s�ɂďo���B1994�N9��23���A55�ŕa�v���Ă���B�s���ƌ��g�t�́q�T�r�ōł��������y����Ă��鎍�l�́A�ςƓ����̐X��`�M�i1918�`42�j�ł���A�����ŐX��Ƃ��e���̂������A����܂������̈ߍX���M�i1920�`2004�j�ł����āA�g�����i1919�`90�j�ł͂Ȃ��B
�@���o���������l�����ɂƂ��āA�푈�͂���_�ł͋ߑ�I�o���̂����Ƃ�����Ȏ����������Ƃ������Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�ڂ�������͂ǂ��炩�Ƃ����A�ނ���I�ɏo���������l���������A�ꐢ��Ȃ�����x��Ă���Ă������l�����A�܂苌�u�����C�J�v�ɂ�鎍�l�̎����D��ł����B�u�r�n�v�𒆐S�ɂ������l�����̎��ɂ͂ǂ����Ă��i�C�[���ɂ͓����Ă����Ȃ��������̂��i���Ƃ����炪��B�̈�l�ߍX���M���̎��W�i�v���ДŁj���݂Ă��A�����ɂ����Ă��̝R��͗₽���A�ǂ������o�I�Ȗ������Ƃَ͈��̂��̂��B�`���ɂłĂ���u���̌������ɐV�����݂��v�Ƃ�����i���A�薼�̊���Ƃ��ǂ��e�Ղɂ͎��ꂪ������a��������B����ǂ��ŋ߉��ƂȂ��킩�����̂����A���̊�ȑ薼�̎������́A�ߍX���M�Ƃ�����l�̎��l�̐��I���ӂ̈�[��\��������i�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł���B���쌧�̓c�ɂ���A���I�����̉Q���ł܂��V���ɂ����Ȃ����A�₪�Ă��������Ɩ����ɂȂ��ċP�������ł��낤�����̒��Ԃ����A�u�r�n�v�O���[�v�̎��l�����֑�������т̃��b�Z�[�W�������̍�i�̈Ӗ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ������c�c�j�B�i�q�G���Ƃ��ār�A�{���A���Z�y�[�W�j
�u�ꐢ��Ȃ�����v�ł͂Ȃ��\�N��\�N���낤���A����͂Ƃ������A�ς��e�ߊ���\�����Ă���u���u�����C�J�v�ɂ�鎍�l�̎��v�ɖ{���ŐG��Ă���̂��g���̎��������Ƃ����̂͒��ڂɒl����B�����ĐX���ߍX���́u�����̐�B�v�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�u�u�r�n�v�𒆐S�ɂ������l�����̎��v�̏�����Ƃ��ēo�ꂵ�Ă��邱�Ƃ��l�����킹��A�ς����̎��_�W�Ŏ��݂Ă���̂́A�Ȃ����������������̂ւ̐ڋ߂ɑ��Ȃ�Ȃ��B�W��Ɂu�o���v���p�o����̂�����䂦�ł��낤�B�q�g�����E�o���\�\������Ă䂭���Ԃ̑܁r��
�@�g�����̎��ɂ��Ďv�����߂��炷�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��H�@�悭�킩��Ȃ����i�N�̓ǎ҂̈�l�Ƃ��ċC�Â������Ƃ�f�ГI�ɏ����Ƃ߂Ă݂����B
�@���㎍���Ɂw�g�������W�x�i�v���Ёj���߂����Ă��čŏ��ɋC�Â������Ƃ́u�҉́v�Ƃ�����̍�i�̌a��ł���B��͍ŏ��̎��W�w�t�́x�̖`��������u�҉́v�ł���A������͎��W�w�Õ��x�ɂ���u�҉́v�Ƃ�����i�ł���B�i�{���A�Z�Z�y�[�W�j
�Ǝn�܂�B�����Ēς������̂́A�q�҉́r�i�A�E1�j�̑S�s�ł���B���̂��Ƃɂ�������B
�@����́w�t�́x�́u�҉́v�ł���B���W�w�t�́x�͓�����㈲���ꂽ�Ƃ������Ƃł��邩��A���̍�i�͎��l�̓����O��̍�i�Ƃ����Ă����ł��낤�B�������A�f�ГI�Ɏ��������A�킸���ȍ�i���c���ē���ŕ��������X��`�M�̎��Ɣ�ׂ�ƁA�������ď��ȍ�i�Ƃ͂����Ȃ����낤�B�X��`�M�̎��̓����Ș_�����͍ŏ�����g�����ɂ͂Ȃ������悤�Ɏv����B������������͓�����̃��_�j�Y���̈���̈�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���������Ȃ��B�X��`�M���]��̓����Ȗ������䂦�ɕ��������Ƃ���A�g�����͂��̕s�����ȋ��܂��̂т��̂��Ƃ����邩������Ȃ��B����������͋g�����̗ł͂Ȃ��ċg�����Ƃ�������߂Đ��I�Ȏ��l�̎����ł��������̂��B�g�����̎��ɂ�����ʑ��I�ȈӖ��ł̓�����́A���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��Ǝv����B�i�{���A�Z��`�Z��y�[�W�j
�ς͂��̂��Ƌg�������̓����̂���Ă����鏈��ǐq����̂����A�g�����_�̍��i�͂��̖`�������ɐs����B���Ȃ킿�A�u�k�w�t�́x�́u�҉́v�́l������̃��_�j�Y���̈���̈�v�ł���A�u�k�X��`�M�̗]��̓����Ȗ������ɑ��l���̕s�����ȋ��܂��̂т��v�u�g�����̎��ɂ�����ʑ��I�ȈӖ��ł̓�����́A���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����Ƃ��낪���Ȃ��Ȃ��v�\�\���ς̋g���_�̊̂ł���B�ȉ��A�������̕����������āA�ς�������ǂ̂悤�ɓW�J�������������Ă݂悤�B
�@���̃C���[�W�B���I�Ȃ��́m�A�A�n�̃C���[�W�͎��W�w�t�́x�ɂ��S�R�݂��Ȃ����̂ł͂Ȃ����A�剪�M�Ƃ̑Βk�ł��w�E����Ă���Ƃ���A����͎��W�w�Õ��x�ɂ���ē˔@���m�ȗ֊s���l���������̂ł���B�m���ɂ���͑��^�I�Ȃ��́m�A�A�n�̎肴�����D�ގ��l�̋C���I�Țn�D�̎Y���ɂ͑���Ȃ��̂����A�u�_���s�݂̎��v�u���W������������^�_�̂��Ƃ����̂������v�Ȃ���u��̗�����n�v�Ɂu���܂ꂽ�v�Ɖ̂����Ƃ��A���炭���l�́u�o�ƌ���ɂ݂����ꂽ�^��̗��v�̂Ȃ��ɌȂ�̑̌��̍\���A�u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�𖧕������̂��B�u���W���������v�Ƃ͎��l���g������������푈�Ƃ����ٗl�Ȏ���̕ʏ̂ł����������낤�B�i�����A�Z���`�Z��y�[�W�j
���i�̃C���[�W�j�̂Ȃ��Ɂu������Ă䂭���Ԃ̑܁v�i�q�҉́r�B�E12�A3�s�߁j�𖧕������\�\���ꂱ���ς̋g�����_�̊j�S�ł���i����ɑI�ꂽ�̂�����䂦�ł���j�A�u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�Ƃ́u�s�����ȋ��܁v�Ɠ����́A�����̂тȂ���Ȃ�Ȃ��������l�̕��ׂ̂܂��̖��ł���B
�@�u���̂悤�ȋ�Ԃ��Ђ��Ă䂭�v�̂́u�艞�����Ȃ��v�u�E�C�v���������ꂽ���l�̕��{�ł���B�������Ď��l�́A�u�Â��[�x�v����u�����l�v�ƂȂ��đh��A���W�w�Õ��x�́u�i�����݂̎��v���o�Ď��W�w�m���x�́u�[���Ȏ��̏d���Ɖ~�݂����������v�̐��E�ւƓW�J���Ă����̂ł���B
�@��i�u�m���v�͂��̂悤�Ȏ��l�̈يE�̌��̋Ɍ��I�ȓˏo�ł������B�����č�i�u�����v�͂ق��Ȃ�ʁu�����l�v�̐����������Ƃ������Ƃ��ł��邾�낤�B
�@�u�l�l�̑m���v�Ƃ͋��炭���l�̕��g�Ƃ��Ắu�l�l���n�d���v�ł���A���̐��I�ȁs���t�̍\���ł���B���́u�l�l�̑m���v�̐��E�Ƃ̊�Ȋm�������A���n�d�����l�g�����̊m���ł����������낤�B�i�����A���l�y�[�W�j
�q�m���r�͈يE�̌��̋Ɍ��I�ȓˏo�ł������\�\�u�l�l�̑m���v�͎��l�̕��g�Ƃ��Ắu�l�l���n�d���v�ł���A���̐��I�ȁs���t�̍\���ł���\�\���Ȃ킿�u�يE�v�Ƃ͋g���ɂƂ��Ắu�푈�v�ł���A�u�m���v�́u�n�d���v�̕��g�m�A�A�n�ł���\�\�Ƃ����ς̎w�E�͑N��ł���B�����V�g���A�����k�Ƃ��āu�m���v�ɂ��V�����ǂݎ�����i�s���w�t1959�N5�����q�F�t�ψ����z�r�j�̂Ƃ͐^��������Η�����l�������A���ɂ́u���̎��l�̊��ɂ��錾�ꊴ�o�̔�_�����ɕ����v������m�A�A�A�n������̂����������ʂƂ����v���Ȃ��B
�@�܂�u�p���v�Ƃ͋g�������������ꂽ�펞�̌��ł���Ɠ����ɁA���l��������������̌��ł��������Ƃ����ׂ����낤�B���l���u��̗��v�̂Ȃ��ɖ����������̂́A���{��i���{�l�j�Ƃ����o���̍\���́u������Ă䂭���Ԃ̑܁v�������̂��B����͂ǂ������̍��̓`���I�ȕ��y�̂Ȃ��œ��قȈʒu���߂Â��Ă��������E���H�����̕��I�Ȗ��l�|�̐��E�ɒʂ��鎑���I�Ȋ�ł��̏ؖ��ł��������B�����āu�n�ォ��͂���ꂽ�ׁv�u�������蒆�����ʂ��Ƃ�ꂽ�܁v�Ƃ́A���̂悤�Ȏ���̕s�^�i�H�j��S���Ă��̂Ƃ����l�����ʂ��������Ԃُ̈̂������Ƃ����Ă������낤�B�܂莍�l�͋ߑ㎍���\�H���������I�R��A�����̏ꍇ�ȋ��{��`�Ɠy���I��Ƃ̘a���ܒ��ɂ����Ȃ������ߑ�I�m����O��I�ɔے�E���₷��i���l�̗p��������u��������v�j���Ƃɂ���ċt�Ƀ��_�j�Y���Ŗ\���������̍��̕s�K�Ȋ�����襘H�n�����̂ł���i���Q�j�B�i�����A���Z�y�[�W�j
�u�p���v�Ƃ͐펞�̌��ł���A����̌��i�����ԁj�������\�\�����I�R��Ƌߑ�I�m�����u��������v���ƂŁA������襘H�n�����\�\�̑O�ҁA���Ȃ킿�펞�̌��Ɗ����I�R��͑����̋g���_�ł����Ύw�E����Ă������A��ҁA���Ȃ킿����̌��i�����ԁj�Ƌߑ�I�m���͒ϊw�Ǝ��̒���Ƃ����Ă悢�B�u���̍��̓`���I�ȕ��y�̂Ȃ��œ��قȈʒu���߂Â��Ă��������E���H�����v����̓I�ɒN���w���̂��ς͖������Ă��Ȃ����A���͎��l���������Ԃ�u�꒼�ƂȂǂ̎U����Ƃ�z�N���Ă��܂����B�����Ēi���Ō�́i���Q�j�́A���̋g�����_�̖����ɒu���ꂽ�㒐�ł���B
�i���Q�j���W�w�m���x�ɂ́u�����v�Ƃ�����i������B�u�Z�˂����낷�^�ڂ��ɂ͏�l�̏K�����Ȃ��^���_�܂œS�̔��͂��ɂ���v�Ƃ������Ƃ��A�u�S�̔v�ň͂����̂��͂�ꂽ�̂��B����́u��l�v�̔��f�������ċg�����̊�łȊ��̂��肩�����Ă���Ƃ����ׂ����낤�B�i�����A����y�[�W�j
�ς��{�_�ŗp�����e�N�X�g�́A���㎍���ɔŁs�g�������W�t�i�v���ЁA1968�j�Ɓs�����C�J�t�i1973�N9�����k�g�������W�l�j�̓�_�����̂悤���B��ׂ����ƂɁA�������ӂ��̕�������ł��g�����_�͉\�Ȃ̂��B�����ۂ��A���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�����s���ꂽ�Ƃ��ς͓�\�������B����400���̏����s�m���t����ɂ��邱�Ƃ��ł����̂��A�ڍׂ͕s���ł���B
�k�NjL�l
�s�ϊw�S��i�k�S3���l�t�i�c�����X�A2018�N6��5���j�́A�ߔN�ł͂��̊��s���������u���㎍�l�̑S�W�v�ł���B�ϊw�v�l�M�q����Ɉ˂�A���̑S�W�̖{���͒��҂����O�p�ӂ��Ă��������̒����{���{�Ƃ��Ă����i�����j���A�{�e�ł͋g�������ڂɂ����ł��낤�������������i�����������A�ϊw�͂͂����ċg�����Ɂs���ƌ��g�k���A���e�p��2�l�t�����������낤���j�B�Ԃ��ɍZ�������킯�ł͂Ȃ����A�S�W�łׂ͍��Ȍ�������������āA�ǂ݂₷���Ȃ��Ă͂�����̂́A�_�|�ɉe������悤�Ȓ����͎{����Ă��Ȃ��B���R���낤�B�Ƃ���ŁA�k��3���l�ɂ͒ϊw�̍�i�̂ق��A�q���^�r�Ƃ��Ēm�F�ɂ��Ǔ������Ę^����Ă���B�R�{�N��́A�ς̈�����ɓ�����1995�N9���ɔ��s���ꂽ�s����t19���k�ϊw�Ǔ����W�l�ŁA�q�ϊw�̂����ꏊ�r�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B�u���Ƃ��Βϊw���ߍX���M�ɂ��ď����A�R���钹�ɂ��ď����B�g�����ɂ��āA�X��`�M�ɂ��āc�c����͒ϊw�ɂƂ��đΏۂւ̕Έ��ł��Ȃ���A�܂��Ĕᔻ�ł��Ȃ��B����́A�������ǂ��ɂ��邩�Ƃ����ώ��g�̂��߂̎��Ȋm�F�ɂق��Ȃ�Ȃ������v�i�s�ϊw�S��i�k��3���l�t�A�O�Z�Z�y�[�W�j�B�s���ƌ��g�t�̏����͂��u���l�̎U���v���ƌ������Ƃ���ŁA������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B���Ƃ��Ă͂����ɁA���l�ɂ��������Ȃ��A�����߂��镶�͂Ƃ����قǂ̈Ӗ������߂����肾�B�ǂ����ŁA�ꊪ�{�̊ȕւȁs�ϊw���W�t���o���Ă���Ȃ����낤���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�ϊw�̎��q�Â��ǂ�����r�i�s���w�t1989�N3�����j�Ɂu�₪�Ă���k�c�����̑��q�l�͒��ɔM�����^���邩��Ƀ]�b�Ƃ���悤�ȃJ�}�L���̋���Ȃ���^���R�Ə��ɂ̂��Ă��߂����߂^�����ȃX�P�b�`���Ă����Ȃ������^�i�ڂ��̎G���W�w���ƌ��g�x�̓����̃J�b�g�́A���̍��̑��q�̂��̂��j�v�i�����A��O�`��l�y�[�W�j�Ƃ������傪����B���сq�Â��ǂ�����r�����߂�ꂽ�ς̑掵���W�s䈁t�i����ɍH�[�A1992�N6���j�͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�s�ϊw�S��i�t�ɂ�����{���͂���Ə�������Ă��āA���R�̂��ƂȂ���A���o�Ɏ肪���������̂����W�Ɏ��߂�ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B
�i�����j�u�k�ϊw�́u�⌾��v�ɏ����ꂽ�܂̂����́l�Ō�̈�ɁA
�@��A�S���W���s���̍ۂ́A�����{���{�Ƃ��邱�ƁB
�@�Ƃ���܂����B���͋���˂����v���ŁA�����ɏ��ւɂ���܂̖{�I�̈���T���܂����B�����āA�g�r���̂���N�㕨�̖{���̍ʼn��i�̒��ɁA�Ђ�����Ƃ��ꂪ���ɕ��ׂ��Ă���̂������܂����B�v�i�ϐM�q�q���܁A�v�����Ɓ\�\���ׂ��ґz�Ɓr�A�s�ϊw�S��i�k��3���l�t�c�����X�A2018�N6��5���A�O��Z�y�[�W�B���o�́s����t19���k�ϊw�Ǔ����W�l�A1995�N9���j
�E�F�u�T�C�g�s���w�܂̐��E�t�i�Ǘ��l�Fpelebo@nifty.com�j�������[���B����26�N�i2014�N�j11��1���̓��T�C�g�J�݂̍ہA���̂悤�ȏ������f����ꂽ�i�����̉��s�ӏ���ǂ����݁A�i�����^�Ŏ������j�B
����12�N/2000�N�Ɂi�Ђ�����Ɓj�n�߂��u���؏܂̂��ׂāv�A��������h�����ĕ���19�N/2007�N�ɊJ�݂����u�H��܂̂��ׂāE�̂悤�Ȃ��́v�A�Ƃ��܂��āA����ɂ��̂��сu���w�܂̐��E�v���I�[�v�����邱�Ƃɂ��܂����B�^�u�����v�Ɋւ�����̂���ƂȂ�܂����A���{�ł���܂ōs���Ă������w�܁i�₻��ɗނ�����j�̐��X�������܂��B�^�Ƃ����܂��̂��A���^�N�V���g�A���w�܂Ɋւ��鎑���͂ǂ����s�\���ȕ����������A�Ƃ������Ƃ��A�����������Ă��邩��ł��B�^�i�����Ă���Î҂��ҁE��܍삾�����Љ��Ă��āA�I�l�ψ������o�[��I�l���A���ҁE����A����̂��̂ł���Ή��呍���ȂǂȂǁA���w�܂�m�邤���ŏd�v�ȗv�f���ȗ�����Ă�����̂������A�Ƃ����Ӗ��ł��j�^�����������؏܂ƊH��܂̃T�C�g���������̂ŁA������������b������������Ƃ܂Ƃ߂Ă��������A�Ǝv���Ďn�߂邱�Ƃɂ��܂����B�^�܂��܂����א�Ă��Ȃ��܂�����������̂ł����i�c�c�ȂǂƁAwikipedia�݂����Ȍ����āA���݂܂���j�������ł��[�������Ă�����Ǝv���܂��B�i�q�T�u�T�C�g�J�݂ɓ������āB�r�j
�u�I�l�ψ������o�[��I�l���A���ҁE����A����̂��̂ł���Ή��呍���ȂǂȂǁA���w�܂�m�邤���ŏd�v�ȗv�f���ȗ�����Ă�����̂������v�Ƃ����w�E�͉s���B���������u�g�����v�ׂ��Ƃ���A�S����7���̋L�ڂ��������i�ے������͏��т��X�I�ɕt�������́j�B
�@1959�N04�� ��9�� �g���� �w�m���x ���
�A1968�N02�� ��19�� �ǔ����w�� �w�g�������W�x ���
�B1969�N01�� ��20�� �ǔ����w�� �w�Â��ȉƁx ���
�C1977�N01�� ��7�� �������� �w�T�t�����E�݁x ���
�D1984�N03�� ��2�� ���㎍�l�� �w��ʁx ���
�E1989�N03�� ��7�� ���㎍�l�� �w���[���h���b�v�x ��⎫��
�F1989�N03�� ��4�� ���̕��w�ُ� �w���[���h���b�v�x �����
�g������܂����@�ƇC����ю�܂����ނ����F�͖{�T�C�g�ł����т��ѐG��Ă��邪�A�A�ƇB�ƇD�̌�₨��чE�̌�⎫�ނ͏����ł���B���Ƃقǂ��悤�Ɂs���w�܂̐��E�t�̔��{�Ԃ�ɂ͓���������B�����Ƃ��s�T�t�����E�݁t�̖����܂̎���ނ͂Ƃ������A�s��ʁt�̓����L�O�����܂��R��Ă���͉̂����Ȃ��B�����v���āA���T�C�g�����̕��w�܂Ƃ��Čf�ڂ��Ă���Ώۂ��m�F�����Ƃ���A�ȉ���11�̏܁A���Ȃ킿
�g���܁^���F�G�Y�܁^�������܁^���㎍�����܁^���㎍�l�܁^���㎍�Ԓ֏܁^�����Y�܁^��������܁^����\�O�Y�܁^�O�D�B���܁^����M�v��
������ŁA�����L�O����܁i2017�N����u����܁v�ɉ��́j�͊܂܂�Ă��Ȃ������B�ƂȂ����̂˂��肾�����̂ŁA�p������B���āA���T�C�g�Ŋ��S�����̂́u�u���w�܂̐��E�v�� �I�l�ψ��������v�Ƃ����y�[�W�ւ̃����N�ŁA�g���̏ꍇ�A��܂����ӂ��A�g���܂ƍ������܂�����ɊY������B�����A�܂���܂̕����炢�����B�@�̑�9��g���܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���i�����͌r�𑽗p�������₷�����C�A�E�g�����A���p�ɂ������Ă̓X�y�[�X�̊W�ʼn��s�ӏ���ǂ�����Ł^�Ŏ��������߁A�Ώۏ��Ђ̑p�������k�@�l�Ŋ������j�B
���a34�N/1959�N�x
��[ ���� ] ���a34�N/1959�N4��6��
��[ �}�� ] �w���w�x���a34�N/1959�N6�����A�w���㎍�蒟�x���a34�N/1959�N7�����I�l�o�ߌf��
��� �g���@�� �w�m���x ���a33�N/1958�N11���E���惆���C�J��
��� �l�c�m�� �w�l�c�m�͑�W�x ���a33�N/1958�N7���E�R�͏o�ŎЊ��^������C�u �w�Đ_�_�x ���a33�N/1958�N3���E���惆���C�J���^�А����q �w���̖���̉ʎ����x ���a32�N/1957�N10���E�R���{�I���b��^�g�{���� �w�g�{�������W�x ���a33�N/1958�N1���E���惆���C�J�k�����̎��l�o��3�l�^�R�c���� �w�s����x ���a33�N/1958�N2���E�R�X���X�Њ��^�V��@�� �w�P���Ȑ��U�x ���a33�N/1958�N9���E�R���{�I���b��^���R�o���q �w�ЂƂ�̉āx ���a33�N/1958�N1���E�����Ёk�s�|�[�p��43�l�^�q�n�G�� �w���݂̍��x ���a33�N/1958�N2���E���{�����h���s�����^�k�쑽��q �w���x ���a33�N/1958�N12���E���ԎЊ��^��̂�q �w�����Ȃ��z�B�v�x ���a33�N/1958�N11���E�ђˏ��X�k���㎍�W3�l�^�������a �w���x ���a33�N/1958�N11���E���남���Њ��^�鑺�p�� �w�������̂̉́x ���a33�N/1958�N6���E���惆���C�J��
������[�̏��13���W
������[�ɂ�鐄�E���22���W
�܋�3���~
�I�l�ψ� �����ρi�a�C���ȁj�^������Y�^�ɓ��M�g�^�������^��їQ�v�^�،��F��^����S���^�����V�g�^�y�����d�^�����O�F�^���e���O�Y�^�O�D�L��Y�^����l�Y�^�R�{���Y
�S����ɂ��A���P�[�g���[���i����55�ʁj
��1��I�l�ψ��������a34�N/1959�N4��2����@�m���n�����u�g�~�E�O�����v
��2��I�l�ψ�����4��6����@�m���n�����u�g�~�E�O�����v
������5��27��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E�ԍ�u������كz�[���v
�s���w�t�i1959�N6�����j�̎��ʂ��ڂ������悤�i�ȉ��A���p���̋����͏�p�����ɉ��߁A���Ȃ̓}�}�Ƃ����j�B�܂��q���d�̓����r�́u�c�́v�̍ŏ��̍��Ɂu���㎍�l��E�g�܌����B���㎍�l��ł́A����S���U���ߌ�U�����A�����E�g�~�[�O�����ɂ����Ċ�������J���A��X��g�܂̑F�t�ɂ��������A���[�̌��ʁA�g�������W�u�m���v�Ɏ��܂ƌ��肵���B�Ȃ��A���_�͖k�쑽��q�W�u���v�B�v�Ƃ���A���Ɂk���̎��l�l�Ƃ����l���Љ�̃y�[�W�ɁA�������i�ҏW���̖،��F��̃y���ɂȂ邩�j�̋L���q�g�܂�������g�����r���ё��ʐ^�t���Ōf�ڂ���Ă���B���C���́q��X�㎍�l��g�ܑF�t�r��3�y�[�W�ɂ킽��ڕ�B�`���Ɂu���㎍�l��g�܂ɂ��ẮA�]�����̑F�t�o�߂����\���ꂽ���Ƃ͂Ȃ������A���ɋ�l�̎���l�𐔂��鎍�d�B��̎��l�܂Ƃ��Ă̈Ӌ`���l���A�{���͓��Ɍ�Ď������ǂ̑F�t�o�߂ƁA�F�t�ψ��̊��z�������Ɍf���邱�ƂƂ����B�v�Ƃ����O�U�肪���邪�A�F�t�o�߂����\����ɂ��������̂́A���ɂ����u�g�������v���N�������߂ł���B�g�����i�́s�m���t�j�Ɍ��y�����F�t�ψ��̊��z�͈ȉ��̂Ƃ���B
�u�l�͋g�������́w�m���x�ɂ�����d���̔������A�����̉s���B�f�Ƒ�_�ȁA�ΏƂ�慎h��[���A��e���o���ʔ����Ɉ�������ꂽ�B��ꎍ�W�w�Õ��x�̍D�܂������L���ɂ���A�X�ɂ��ƍ���Ȏ����ɐi��ł��銸�R�Ƃ����ԓx�́A�Ⴂ���l�ɍł��ӂ��킵���Ǝv���B���̎��͂ǂ��Ȃ邩�A�傫�Ȋy���݂ł���B�v�i������Y�k����l�S���j
�u�k�c�c�l�^���̒��ɍŌ�Ɏc���ꂽ�̂́A�g�����́u�m���v�ƁA�k�쑽��q�́u���v�ł����B�g�����̍�i�́A�G���Łu�m���v�����ǂ�ł��Ȃ����̂ŁA����x�͂��߂Ď��W��ǂ킯�ł��邪�A�S�̂�����̑����K�c�`���Ƃ����d���\���ɕ�܂�A�����I���̌Â����Y���ɂ͉������^������悤�Ɋ�����ꂽ�B�����āA���̎��l�̎��U���I�ŁA�v�l�Ւf�̃X�^�C���ɂ́A���L�̎��ȕǂ��������A�f���ȗ��������܂����̂������B�^�k�c�c�l�v�i��їQ�v�q���z�r�j
�u�ڂ��́A�A���P�[�g�̍ۂ́A�w�ǎ��W��ǂ�ł��Ȃ��̂Ŕ�r���o�����A�������o�����B����̑I�t��ɁA�A���P�[�g�̏W�v�����Ƃɂ��ď\�O���̎��W���I�t�ΏۂƂȂ�ɋy��ŁA����̑I�t��܂ł̎l���ԂɑS���ǂB���̂Ȃ��ŁA�ڂ����\�I�Ƃ��čl�����͈̂������a�A��̂�q�A���R�o���q�A���Ǘ����q�A�g�����A����ɖk�쑽��q�̌܁m�}�}�n���W�ł���B�Ƃ���ŁA�����̂́A�D�ꂽ�̂��͂��߂̎O�т����ł��Ƃ͂��̐������̌J�Ԃ��B���R�A���ǂ͂Ƃ��Ɋ��o�I�Ŏ�X�����B�g���͍͗�m����т����ŁA���̃g�{�P�����͑����ʔ�������Ǖ\�����U���ō̂�Ȃ��B���ǁA���Ӂm�}�}�n�I�ȓ��e�������A���̓��e�ƕ\���Ƃ��~���ł���A���̑��Ă���̂́A��̂�q�Ɩk�쑽��q�̓W�ł���B����P�L���[�ɂ́A�ڂ��͗�Âɍl���āA�k�쑽��q�ɓ��[�����B��̂�q�̐��E�͂��܂�ɂ��P���Ŋ���Ă���̂ɂ���ׂāA�k�쑽��q�̐��E�͕��G�Ő[���؎��ł���ƍl��������ł���B�^�k�c�c�l�v�i�k��~�F�q�ڂ��̈ӌ��r�j�k�k��~�F�́s���w�܂̐��E�t�ł��A���́s���w�t�́q��X�㎍�l��g�ܑF�t�r�ł��L�ڂ���R��Ă��邪�A������Ƃ����I�l�ψ��̈�l�ł���B�t������Ȃ�A�k�쑽��q�̕v�N�ł�����B�l
�u���W�u�m���v��ǂ�őm���Ƒ肷�鎍�͖ʔ��������A���̑��̍�i�́A���܂�悢�Ǝv��Ȃ����B�m���Ƃ��������A�\�����ꂽ�`�Ԃ̖ʔ����ŁA�Z�@�̐V����������ǁA�����k�̎��́A�@���ɂ��o�J�ɂ���߂��Ă���C�����āA��[�𓊂��邱�Ƃ͂��Ȃ����B�v�i�����V�g�k����l�S���j
�u���͍Ō�̑F�t�ψ���ɉ��āA�u���v�𐄂������A�u�m���v�Ɍ��܂��̂ŁA����ł��悢�Ǝv���B�u���v�͌��㎍�Ƃ����g�̂Ȃ��ł������Ă���ق��A�t�قȂƂ��������B���̘g����݂͂ł��i�����͏�������Ƃ���Łj�Ǝ��Ȏd�������Č������_�Ă������B�u�m���v�͌��㎍�̘g�̂Ȃ��ł͂��邪�[�������d���������A�\���̓A���o�����X�ȂƂ�������邪�Z�p�I�ɂ͊m�����B���͂ǂ���ɂ��ׂ����Y�B�k�c�c�l�v�i�y�����d�k����l�j
�u���N�̂悤�ɂg�܂̑I�l�ɓ��Ă������A�܂̂��Ƃ������ƁA����܂ł̎���W�̂����ɂ́A����܂�C��肵�Ȃ��̂ɁA���[�̌��ʁA��܂ɂ��܂Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ����x�������B�Ȃ�ƂȂ��_�����������Ƃ����悤�Ȃ̂́A���W�̏ꍇ�ł́A�ǂ����������낢���Ƃł͂Ȃ��悤���B�^�����A���N�̋g���N�́u�m���v�̎�܂́A�ڂ��ɂƂẮA���ɂ����肵���C�������B�ڂ��́A���̎��W���o��₷���V���ɏ��]�����ďo�����A�C�ɓ������W��������ł���B�^��̍�i�W���A�펯�ɂ�ē_�����������m�}�}�n�̂ł͂Ȃ��āA�I���W�i���e�C�̋����ɂ�Ď�܂����Ƃ������Ƃ́A�I�l�ɓ�����l�Ƃ��Ă��A���Ɍ㖡�̂������̂ł����B�^���̎��W�͈ꌩ����ŁA��ʂ̓ǎ҂̎��ɂ͕����Ȃ���������Ȃ����A�펯�I�Ȏ��ɂ������l�X��\���ɃV�������A���Y�������������l�X�ɂƂẮA���ɋ����[�����W�ł���B���@�̌����Ƃ��ẮA�u���g�������Ɠ��n������ǂ��A���������ӎ��I�ŁA��]�I���B�����Ă��ׂĂ̍�i�̎�肪�A���J�ƈ��ӂɂ݂��������I�̏X���ɔ����Ă���B�^���̃C���[�W�̐R���I�Ռ��͂������炵�����̂ł����B�����Ă��̂悤�ȏՌ��͈͂�̍�i���A���w�Ƃ��Ĉ�Ԋ댯�ȏ�Ԃɂ�����Ă͂��߂Ċl�������Ƃ���̂��̂ł��邱�Ƃ��v�킹���B�^���́u�m���v�̂ق��ɂ��A���ڂ���Ă������W��������Ƃ��m�������A���́u�m���v�ɂ���ׂ�ƁA��͂肻���̎��W�͂ǂ����A���K�͂Ȏ��̋@�\��`����E�o������Ă���m�}�}�n�Ƃ��낪�����B���낢��ȈӖ��ŁA���̎��W����܂������Ƃ́A��ς蓖�R�Ȃ��Ƃł���Ȃ���A�قƂ����C�����ł���B�v�i����l�Y�q���W�u�m���v�̎�܂ɂ��ār�S���j
�u�k�c�c�l�^���̌��ʁA�ŏI���̑I�t�ψ���ŁA�S�ψ���v���������ȕ��@�ɂ�āA���͎��̂��Ă��[���s�g�����킯�ł��邪�A�����ő���g�܂��g���@�����W�u�m���v�ɂ��܂���u�B���͂��܂܂œ��̒��ɂ��������Ԃ肩�̏d�����ْ����A���Ƌ�C�̂悤�ɉ�������̂����ڂ����B�����ē����Ɏ��͈ψ��Ƃ��Ă̏d�J���������ꂽ���ƂɂȂ�킯�����A���͂ЂƂ�̎��l�Ƃ��Ď�c�m�}�}�n�ҋg���@���ɐS��肨�߂łƂ��Ɠ`�ւ����Ǝv�Ă���B�v�i�����O�F�k����l�j
�������A�C�̑�7�����܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
���a52�N/1977�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a50�N/1975�N12��1���`���a51�N/1976�N11��30��
��[ ���� ] ���a51�N/1976�N12��20��
��[ ���\ ] ���a52�N/1977�N
��[ �}�� ] �w���㎍�蒟�x���a52�N/1977�N2�����I�]�f�ځy�g�����́q���A�r���q��������܈��A�r�Q�Ɓz
��� �g���@�� �w�T�t�����E�݁x ���a51�N/1976�N9���E�y�Њ�
��� �����@�� �w�H���̔�ԕ��i�x ���a51�N/1976�N6���E�y�Њ��^���@�m �w�ہx ���a51�N/1976�N8���E�v���Њ��^�V��ޓ�Y �wles invisibles�@�ڂɌ����ʂ��̂����x ���a51�N/1976�N10���E�v���Њ��^�k�����Y �w����̋F��x ���a51�N/1976�N4���E�v���Њ��^�ߍX���@�M �w�M�\���̑��̎��x ���a51�N/1976�N7���E����G�ߎЊ��^����M�V �w�����\�x ���a50�N/1975�N12���E���w�Њ�
�I�l��Řb��ɂ̂ڂ�������
�I�l�Ώ�24��
���܁{����30���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� ����N�v�^�剪�M�^�c������^�����^��Y�^�R�{���Y
�I�l�������a51�N/1976�N12��20��17:00�`�@�m���n�����E�s���J�u���̋{�v
���掮�����a52�N/1977�N1��28��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�ԑR���鏈���Ȃ��Ƃ́A�����������Ƃ������̂��낤�B�ƂȂ�A�����Â��A��1968�N02�� ��19�� �ǔ����w�� �w�g�������W�x ���A�B��1969�N01�� ��20�� �ǔ����w�� �w�Â��ȉƁx ���A�D��1984�N03�� ��2�� ���㎍�l�� �w��ʁx ���A�ׂȂ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�ȉ��ł́A�g�����Ɋւ���L�ڂ��Ԏ��ŕ\�����悤�B
�A�̑�19��ǔ����w�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���i���̔o��܈ȊO�́A�U���ɂ��e�܂̏ڍׂ͏ȗ������j�B
���a42�N/1967�N�x
��[ �}�� ] �w�ǔ��V���x���a43�N/1968�N2��2�����\�A�����[���I�]�f��
�����܁k�c�c�l
�Y�ȏ܁k�c�c�l
���M�E�I�s�܁k�c�c�l
�]�_�E�`�L�܁k�c�c�l
���̔o���
��� �y������ �̏W�w��W�x[��](��) ���a42�N/1967�N11���E���ʏ��[��
��� �R�{���Y ���W�w����҂̘f���̉S�x ���a42�N/1967�N-���E�v���Њ��^�@�@���� ���ю��w�������x ���a42�N/1967�N10���E�퐶���[�� �^�g���@�� ���W�w�g�������W�x ���a42�N/1967�N10���E�v���Њ��^�ؖ��@�C �̏W�w���N���N�x ���a42�N/1967�N9���E�Z�̌����Њ��^�������c�j ��W�w���c�x ���a42�N/1967�N11���E�݂������[���^������� ��W�w�܂ڂ낵�̎��x ���a42�N/1967�N12���E�v���Њ��^�R�����q ��W�w��{�R�����q�S��W�x ���a42�N/1967�N11���E�W�p�Њ�
�����E�|��܁k�c�c�l
���܋L�O�i�{����20���~
�I�l�ψ� ��c�L�Y�k�Y�ȏܑI�]�S���l�^��Ŏ��Y�^�͐��D���^����S���^���яG�Y�^�������^�i�䗴�j�k�����ܑI�]�S���l�^�������v�k�����E�|��ܑI�]�S���l�^�O�H���Y�^�і[�Y�^�����ّ��Y�k�]�_�E�`�L�ܑI�]�S���l�^�x����{�^�����H���q�^�{�A��k���̔o��ܑI�]�S���l�^�R�{���g�k���M�E�I�s�ܑI�]�S���l
���掮�����a43�N/1968�N2��10��11:30�`�@�m���n�����E�L�y���u�ǔ���ًM�o���v
�s��̐V���k�[���l�t�i1968�N2��2���A�ܖʁj�ɑI�]�q��19�� �ǔ����w�܂ɋP���Z��i�r������A���̖����Ɂq����i�r�Ƃ��āy���́E�o�啔��z�u�k�c�c�l�u�g�������W�v�k�c�c�l�v�Ƃ���B���̂Ƃ��͎��̎�܍�i���Ȃ������B
�������A�B�̑�20��ǔ����w�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
���a43�N/1968�N�x
��[ ���� ] ���a44�N/1969�N1��23��
��[ �}�� ] �w�ǔ��V���x���a44�N/1969�N2��1�����\�A�����[���I�]�f��
�����܁k�c�c�l
�Y�ȏ܁k�c�c�l
���M�E�I�s�܁k�c�c�l
�]�_�E�`�L�܁k�c�c�l
���̔o���
��� ����N�v ���W�w�킪�o�_�E�킪�����x ���a43�N/1968�N4���E�v���Њ�
��� �ѓc���� ��W�w�Y���x ���a43�N/1968�N11���E�q�r�Ёk����o��15�l�W�l
��� �剪�@�M ���W�w�剪�M���W�x ���a43�N/1968�N2���E�v���Њ��^�g���@�� ���W�w�Â��ȉƁx ���a43�N/1968�N7���E�v���Њ��^���c�h�� �̏W�w�����炬���Ёx ���a43�N/1968�N5���E�Z�̐V���Ёk�Í��̏W�l�^�ߓ��F�� �̏W�w���^�x ���a43�N/1968�N10���E�Z�̌����Њ��^��؊щ� �̏W�w�쐤�W�x ���a43�N/1968�N8���E�V�����[���^���@�ΓC ��W�w��{�ΓC��W�x ���a43�N/1968�N10���E���������^�x������ ��W�w�P���Ȍ�x ���a43�N/1968�N4���E�������p��
�����E�|��܁k�c�c�l
���܌��{����20���~
�I�l�ψ� ��c�L�Y�^��Ŏ��Y�^�͐��D���k���M�E�I�s�ܑI�]�S���l�^����S���k���̔o��܁w�킪�o�_�E�킪�����x�I�]�S���l�^���яG�Y�^�������^�i�䗴�j�^�������v�^�O�H���Y�k�����܁w�s�ӂ̐��x�I�]�S���l�^�і[�Y�^�����ّ��Y�k�]�_�E�`�L�ܑI�]�S���l�^�x����{�^�����H���q�k���̔o��܁w�Y���x�I�]�S���l�^�{�A��^�R�{���g�k�����܁w���x�I�]�S���l
�ŏI�I�l�ψ��������a44�N/1969�N1��23��
���掮��3��3��16:00�`�@�m���n�����E�ۂ̓��u������فv
�s��̐V���k�[���l�t�i1969�N2��1���A���ʁj�ɑI�]�q��20�� �ǔ����w�܂ɋP���Z��i�r������A���̖����Ɂq����i�r�Ƃ��āy���́E�o�啔��z�u�������k�c�c�l�u�Â��ȉƁv�g�����k�c�c�l�v�Ƃ���B��܂��������i�ɂ��ẮA����S�����q��㎍�̂���s�Ȗ`���\�\���w�I�ȑ���r���Ă���B�ǔ����w�܂Ɋւ��ăR�����g����A�A�́s�g�������W�t�i���s�����ɂ�����S���W�ɑ�������j�͂Ƃ������A�B�Ŏ��W�s�Â��ȉƁt���m�~�l�[�g����Ă���̂ɂ͋����B�Ƃ����̂��A�����͒P�s���W����1968�N�̊��s�����A���W�̖{���͑O�N�A1967�N�́s�g�������W�t�i���a42�N/1967�N�x����i�I�j�Ɏ��߂��Ă�����̂Ɛ������Ȃ�����ł���B�����͂ǂ��ۛ��ڂɌ��Ă��A����N�v�́s�킪�o�_�E�킪�����t�ɕ�������B
�D�̑�2�㎍�l�܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
���a59�N/1984�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a58�N/1983�N1��1���`12��31��
��[ ���� ] ���a59�N/1984�N3��3��
��[ �}�� ] �w���w�x���a59�N/1984�N6�����I�]�f��
��� ���ˁ@� �w�͔Ȃ̏��x ���a58�N/1983�N8���E�v���Њ�
��� ������q �w����̎d���x ���a58�N/1983�N8���E�Ԑ_�Њ��^�@�@���� �w�����x ���a58�N/1983�N11���E�v���Њ��^�������H �w�e�̂킩��x ���a58�N/1983�N6���E�����Њ��^���V�@�� �w�z�n���͊݁x ���a58�N/1983�N11���E�O�B�o�Ŋ��^�������� �w�G�́x ���a58�N/1983�N8���E���_�Њ��^�����@�� �w�Úg�̉āx ���a58�N/1983�N5���E�q�r�Њ��^��@�� �w���ہx ���a58�N/1983�N5���E����G�ߎЊ�
��⎫�� ���x�ےj �w�����������鎍�x ���a58�N/1983�N8���E�_�_����
������[�̏��9���W�i����Ꟃ��܂ށj
��� �L�c���Y �w�Z�����b�N�̉āx ���a58�N/1983�N5���E����R�c���^�ݖ{�}�`�q �w�R�U�@���̒��u���[�X�x ���a58�N/1983�N11���E�Ԑ_�Њ��^�k��@�� �w�����I�@�B�x ���a58�N/1983�N5���E�|���Њ��^��؎u�Y�N �w�Z�_�m�T���x ���a58�N/1983�N7���E����R�c���^�g���@�� �w��ʁx ���a58�N/1983�N10���E����R�c��
��⎫�� �a��F�� �w�K�N�E�߉́x ���a58�N/1983�N8���E�v���Њ�
�I�l�ψ���ɂ��lj�6���W
����30���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �H�J�L�^���C�i��^�����N�j�^���R����^�y�����d�m�ψ����n�^�߉ϑ��Y�^���x�ےj
�I�l�ψ�7���ɈϏ���9��12��
�S����ɂ�铊�[�����a58�N/1983�N1��31�����i����246�[�E�������[����і���46�[�j
�J�[��2��4��15:00�`�@�m���n�����E�_�c�u�g�~�[�O�����v
��1���I�l�ψ���������18:00�`�@�m���n��
��2���I�l�ψ����������@�m���n��
��3���I�l�ψ�����3��3��13:00�`�@�m���n�����E�R�u�����V���ЁE�R���v
�s���w�t�i1984�N6�����j�́q����q���㎍�l�܁r�I�l�̂��Ƃr�őI�l�ψ����g�����i�́s��ʁt�j�ɐG��Ă���ӏ��������B
�u�k�c�c�l�^�܂͈���Ƃ����̂����O�����珇���ɂ��ڂ��čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���k�̏�S�ψ��̓��[�Ŕ����ɂ��ڂ邱�Ƃɂ����B�^���̌��ʁA����ꟁA��ؔ��A�L�c���Y�A�g�����A�ݖ{�}�`�q�̌����c�����B�k�c�c�l�^�Â��đ��i�ł͋g�������Ɗݖ{�}�`�q�����������B�g�����̌Ñ�����������Ǝ��̐��E�A�ݖ{���̌��㎍�Ƃ��Ă̎��݂ȃu���[�X���\���ɔF�߂������̂��Ƃł������B�v�i�y�����d�i�I�l�ψ����j�q�I�l�o�߂Ǝ����r�j
�u�k�c�c�l�^���͌�����́w�͔Ȃ̏��x����̌��Ƃ��ĈӒ��ɒu���A�I�l�̐ȏ�A�ݖ{�}�`�q����́w�R�U���̒��u���[�X�x���ψ����E���W�Ƃ��Ēlj������Ă����������B�������A���̓W�ɂ����܂ł��Ŏ�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A���̋g�������w��ʁx�A�@���ߎ��w�����x�A��؎u�Y�N���w�Z�_�m�T���x�A��ؔ����w���ہx�ȂǁA����������̒��ڂ��鎍�W�ł���������i�Ƃ��Ɏ��ɂ͂Ȃ����I���E������A���z���͂��h�����A���g���Ă��ꂽ�j�A���̂ǂꂩ���L�͌��Ƃ��Ďc��A������x�����Ă��悢�ƍl���Ă����B�^�k�c�c�l�v�i�H�J�L�q����������ځA�u�͔Ȃ̏��v�r�j
�u�k�c�c�l���͂ނ���A�g�����́u��ʁv�́A���Ȃǂ̏���������s�ɔZ�k�����A��E��C�����A���[���A����g���āA⼌����̓�߂������W�J����ʔ����ɐ�������āA������p�����������v�������A�ݗ��̎��Ƃ���ނ����Ȃǂ̋^�₪�����o���ꂽ�B�^�k�c�c�l�v�i���R����q�I�l���z�r�j
�u�k�c�c�l�^�������I�l�̉ߒ��ŊO���ꂽ�g�����w��ʁx�́A�ǎ҂̑z���͂����鏑�@�̓Ǝ��������Q�ł���A�����ꂽ���W�ł��邪�A�u���㎍�l�܁v�̑ΏۂƂ��Ă͓��ق�����Ɗ�����ꂽ�B�^�k�c�c�l�v�i�߉ϑ��Y�q���z�r�j
�u�k�c�c�l�^�g�����w��ʁx�B�g�����Ɠ��̐��݈ӎ��I�C���[�W�A���A�~�]�̗U�N�A���e�̒��̒��قƃm�X�^���W�A�B�����������ی�ł͐���������Ȃ��ɂ��Ă��A�g���̂��̎O�N�Ԃ̎d���͂�͂蒅���Ɂ\�\����ٗl�ɓ����Ă����B�c�Ȃ��������Ɛl�������������ۂ��ē����A���邢�͓_�ł��Ă���g�����w�́A���q���S�Ɂr���B�����C���ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă����B�^�k�c�c�l�v�i���x�ےj�q�ᑋ�b�r�j
���Ă����ŁA�������ނ����E�̑�7�㎍�l�܁i�D��5�N��j�����Ă������B���܂͂����L�ڂ���Ă���B
����1�N/1989�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a63�N/1988�N1��1���`12��31��
��[ ���� ] ����1�N/1989�N3��4��
��[ �}�� ] �w���w�x����1�N/1989�N6�����I�]�f��
��� �����@�� �w�`�F�[�z�t�̗e�x ���a63�N/1988�N10���E�Ԑ_�Њ�
��� �������a �w�L���߂���x ���a63�N/1988�N12���E�ҏW�H�[�m�A���^��g���Y �w���a�̎q�ǂ��x ���a63�N/1988�N11���E���ƔŁ^�@�@���� �w�����G�߁x ���a63�N/1988�N10���E�v���Њ��^�k�����Y �w�`�̐l�x ���a63�N/1988�N10���E�v���Њ��^�Љ����Y �w�Y���݁x ���a63�N/1988�N6���E�y���o�ŎЊ��^���c�B�� �w�z���E�T�s�G���X�̚o���x ���a63�N/1988�N8���EAlmee�̉
��⏜�O �V��L�� �w�����𐁂����̉́x ���a63�N/1988�N10���E�Ԑ_�Њ��i�g���܂̌��Ƃ��Ďc���j
������[�̏��8���W�i�����ς��܂ށj
��� �a�Y �w�ʐF�L�x ���a63�N/1988�N5���E�ؕЎЊ��^����K�g �w�m��x ���a63�N/1988�N10���E���w�Њ�
��⎫�� ������v �w�x�[�Q�F�b�g���x ���a63�N/1988�N10���E�v���Њ�
��⎫�� �g���@�� �w���[���h���b�v�x ���a63�N/1988�N11���E����R�c��
�I�l�ψ���ɂ��lj�4���W
���܍����u���v�{����50���~
�I�l�ψ� �H�J�L�^�V��a�]�^�҈䋪�^�������i���ȁ^���ʉj�^�l�c�m�́^���q�N�m�ψ����n�^���x�ےj
�I�l�ψ�7���ɈϏ������a63�N/1988�N9��14��
�S����ɂ��L�����[������1�N/1989�N1��31�����i����323�[�E��������3�[�E���[47�[�E�L��273�[�j
�J�[��2��4��14:30�`�@�m���n�����E�V���u���O�H�Ɖ�فv
��1���I�l�ψ���������18:30�`�@�m���n��
��2���I�l�ψ�����3��4��13:30�`�@�m���n�����E�V���u���O�H�Ɖ�فv
�s���w�t�i1989�N6�����j�̓��{���㎍�l��̉�E��їQ�v�ɂ��q�掵�㎍�l�ܑI�l�o�߁r�̂����A�g���̎��ނɊւ��q��ꎟ�I�l�ψ���r�����ƁA����ɑ����q��I�l�ψ���r�̖`���̋L�q�������B
�u���㎍�l�ܑI�l�ψ���ł́A�������\����ꂽ��⎍�W�ɒlj����ׂ����W�����邩�ǂ��������c���A���̎l���W�̒lj������肳��A���v��ꎍ�W��掵�㎍�l�܂̌�⎍�W�ƌ��肵���B
�@�����@��v�u�x�[�Q�F�b�m���v
�@�a��@���Y�u�ʐF�L�v
�@����@�K�g�u�m��v
�@�g���@�@���u���[���h���b�v�v�v�i�q��ꎟ�I�l�ψ���r�j
�u�O���l���ߌ�ꎞ�����瑠�O�H�Ɖ�قő�I�l�ψ���J���ꂽ�B
�@�܂��A�֓�����������A������v�A�g�����̗��������ނ��ꂽ�|������A���Ȃ̒������ψ����瑗�t����ė�����⎍�W�ɂ��Ắu�����v�����I�l�ψ����ɂ������đI�l���J�n���ꂽ�B�v�i�q��I�l�ψ���r�j
5�N�O�̑�2�㎍�l�܂Łi�����I�ϓ_���炷��u����g�������v���\����j�s��ʁt����܂��Ȃ������ȏ�A���Ȃɂ����҂ɂ���]��̌������g�����A���̂��т̑�7�㎍�l�܂Łs���[���h���b�v�t�̎�܂����Ȃ������Ƃ���ŁA�Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��B
�E�Ō������ނ����\���قǂ̂��A�g������܂����ނ����F�̑�4�̕��w�ُ܂͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
����1�N/1989�N�x
��[ ���� ] ����1�N/1989�N
��[ �}�� ] �w����x����1�N/1989�N6�����I�]�f��
�� ��܍�Ȃ�
����� �g���@�� �w���[���h���b�v�x ���a63�N/1988�N11���E����R�c��
�ŏI�I�l�Ώ�5��
�Z�� ��� �n�ꂠ���q �w���̐߁x ���a63�N/1988�N12���E�������[��
�o�� ��� ���z���� �w�����x ���a63�N/1988�N5���E�l���s���k�l�p���l
���܋S�����蒤��ʁ{���܊e50���~
�I�l�ψ� �����m�ψ����n
�� �����ρ^����N�v�^�O�ؑ�m�I�]�S���n
�Z�� ����O�F�^�˖{�M�Y�m�I�]�S���n�^���i���q
�o�� ���q�����^���V�ߎq�m�I�]�S���n�^�O���q�Y
�ŏI�I�l������1�N/1989�N3��14��
������5��20���@�m���n�k��s
�g���̂��̎���ނ͍ŏI�I�l�̂̂��A���̂悤�ɐV�����ꂽ�B
���̕��w�ُ��^�g�����͎���
�@��l�̕��w�ُ܁i���{���㎍�̕��w�ِU����A��c���������c���Áj�̑I�l��\�ܓ��J����A�Z�̕���͔n�ꂠ���q���́u���̐߁v�A�o��Y��͑��z���Ύ��́u�����v�Ɍ��܂����B���㎍����͋g�������u���[���h���b�v�v�Ɍ��܂������A�g�����͖{�l�̈ӎv�Ŏ��ނ����B�����͌܌���\���A��茧�k��s�ōs����B�i�s�����V���t1989�N3��16���A��Z�ʁj
�܂��s����t�i1989�N6�����j�́q��l�̕��w�ُܔ��\�r�́u���㎍�v�̍��ɂ́A�u�I�l�ψ���ɂ����āA�g�����u���[���h���b�v�v�i����R�c�j���I��܂������A �g����������܂����ނ��܂����B�v�ƌ�����B����ނ̌��ɂ��āA�I�l�ψ���\�̎O�ؑ�́q����Ȃ��Ԃ������r�Ƒ肷�錻�㎍����̑I�]�i900���]��j�Łu��⎍�W�͌܍����������A�O�l�̑I�l�҂̈ӌ�����v���ċg��������́u���[���h���b�v�v�i����R�c�j�𐄂����ƂɂȂ�܂ŁA���Ԃ͂�����Ȃ������B�^�k�c�c�l�^�ȏ�̂悤�Ȃ킯�ŁA�킽���́u���[���h���b�v�v�ɂ�����g������̌��t�̐��E�̈�w�̐[�܂�Ə[���Ɋ�������Ƌ��ɁA��������̕��w�ُ܂ɑ����������̂Ƃ��Đ������B�g������ɎĂ��������Ȃ������̂́A�Ԃ��Ԃ����c�O�ł���B�v�i�����A��܈�y�[�W�j�Ə����Ă���B����A�g���͓����ނɐG�ꂽ���͂����ɂ��Ă��Ȃ��B
�����͑O�シ�邪�A�����œ�������܂����ނ�����4���܂����Ă������B���܂͓��O�A�\�V�G�[�c�ҁs�ŐV ���w���T�t�i���O�A�\�V�G�[�c�A1989�N10��25���j�ł͎��̂悤�ɋL����Ă���i�����܂��s���w�܂̐��E�t�Ɍf�ڂ���Ă��Ȃ����߂̑[�u�ł���j�B
������
�������ɂ���ď��a48�N�ɑn�݂��ꂽ�܁C�P�s�{�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�����ꂽ���W�ɗ^����B
��� ������
�I�l�ψ� �i��P��j���e���O�Y�C����l�Y�C����S���C�ҏW��
�I�l���@�@�P�s�{�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���W���ΏہB
���E���\�@���ʂ́u�����v����ɔ��\�B
�܁E�܋��@�L�O�����[�t�Ə܋�20���~
���
��P��(��48)�@������Y�u���Łv
��Q��(��49)�@�V�쒉�u�V�쒉���W�v
��R��(��50)�@�O�D�L��Y�u�O�D�L��Y���W�v�T�����I�o��
��S��(��51)�@�k�����Y�u����̋F��v�v����
�k�c�c�l�i�s�ŐV ���w���T�t�A�ꎵ���y�[�W�j
�G�������s�����t��40���i1977�N1��5���j�́q��l����܍�i���\�r�ɂ́A�I�l�ψ��i���e���O�Y�E����S���E���ˉ�v�E�c������E�R�{���Y�j���\���Ē��˂��q���z�r�Ƒ肵�Ď�܍�i�̖k�����Y���W�s����̋F��t���̗g���Ă��邪�A�g���́s�T�t�����E�݁t�ւ̌��y�́A���R�Ȃ���A�Ȃ��B�Ȃ��g���́A�����̐��z�q�S���f�́\�\�u�g�������v�ق��r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ ����S�����鑒���t�A�v���ЁA1989�N3��1���j�ɂ��̌��̂��Ƃ��L���Ă���B���Ȃ݂ɂ��̂Ƃ��I�l�ψ�����������S���́A���ċg�����s�m���t�Ŏ�܂�����9��g���܂ƁA�̂��Ɂs��ʁt�Ŏ�܂��邱�ƂɂȂ��22���L�O����܁i���Ɍf����j�̑I�l�ψ��ł��������B
��܈ȊO�̂����̕��w�܂��g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�i�s�g�����S���W�t�}�����[�A1996�j�ɒlj�����Ƃ���A���̂悤�ɂȂ낤���B
���Z���N�i���a�l�\�O�N�j �l�\���
�A�w�g�������W�x����\���ǔ����w���́E�o�啔��̌���i�ƂȂ���A��܂��킷��B
���Z��N�i���a�l�\�l�N�j �\��
�ꌎ�A���W�w�Â��ȉƁx�����\��ǔ����w���́E�o�啔��̌���i�ƂȂ���A��܂��킷��B
��㎵���N�i���a�\��N�j �\����
�\�ꌎ�A���W�w�T�t�����E�݁x�̑�l���܂̎�܂����ނ���B
��㔪�l�N�i���a�\��N�j �Z�\�܍�
�O���A���W�w��ʁx�����㎍�l�܂̌��ƂȂ���A��܂��킷��B
��㔪��N�i���a�Z�\�l�N�E�������N�j ���\��
�O���A���W�w���[���h���b�v�x���掵�㎍�l�܂̌��ƂȂ���A���ނ���B�܂��A�����W�̑�l�̕��w�ُ܂̎�܂����ނ���B
���̍ۂ�������������A�s���w�܂̐��E�t�Ɍf�ڂ���Ă��Ȃ������L�O����܂��^���Ă������B�������A��҂̍��ڂ͒��������B
�����L�O�����
���d�Ɏh����^���邽�߁C�u����v�Ɋ�ꂽ��t�������Ƃɂ��āC�u����܁v�����a38�N�n�݂��ꂽ�B���a59�N�Ɂu�����L�O����܁v�Ɖ��̂����B
����@������l
�I�l�ψ��@���Ñ��Y�C���q�E�C�ɓ��M�g�C����N�v�C����S���C�a��h�s�C�@���߁C�߉ϑ��Y�C�ԓc�p�O�C�R�{���Y�ق��B
�I�l���@�@���̔N�Ԃ̊����ƂȂ������⎍�_����łȂ��C�L���Ӗ��ł̎��I���_�Ɋт��ꂽ�d���ɑ��Ă�������B
���E���\�@�u����v����ɔ��\�B
�܁E�܋��@50���~
�A�����@�k�Z���E�d�b�ԍ��͗��l
���
��1��i��38�j�@�ɒB���v�u�����C�J���v�Ɛ��O�̏o�Ŋ����ɑ���
�k�c�c�l
��22��i��59�j�@�g�����u��ʁv����R�c�@�e�n�M�`�i����̋Ɛтɑ��āj�i�s�ŐV ���w���T�t�A�ꎵ�Z�y�[�W�j
�s��ʁt�͑I�l�ψ�����u��\���I�����{���炵������Ȃ����E�ɗނ����Ȃ��Ǝ��Ɍ����Ȏ��Ɓv�ƕ]�����ꂽ�B�g���͐V�h�E���������z�[���ōs��ꂽ�����̂悤�����A���z�q�e�n�M�`�̂��Ɓr�i���o�́s���ꁁ�e�n�M�`�t�t�B�����A�[�g�ЁA1986�N12��1���j�ɏ����Ă���B
��
�ٕ��s�g�����N���k������2�Łl�t�ŋg�����I�l�ψ��߂����w�܂ׂĂ݂�ƁA�g���܂ƍ������܂̂ӂ��ł���B�s���w�܂̐��E�t�Ɉ˂�A�O�҂́u��ÁF���{���㎍�l��i��9��܂ł̖��́F���㎍�l��j�A�Ώۊ��ԁF1��1���`12��31���ɔ��s�i���t�̔��s�N������j�A�ΏہF���s���ꂽ�V�l�ɂ�邷���ꂽ���W�A�n�݁F���V���Y�̊�t�ɂ�菺�a25�N/1950�N�n�݁v�Ƃ���A��҂́u��ÁF���������w�U������c�@�l�i���v���c�@�l�j���������w�U����A�Ώۊ��ԁF���N12��1���`���N11��30���Ɋ��s���ꂽ���́A�ΏہF�e�N�x�̗D�G���W�A�n�݁F���a45�N/1970�N1��24���A�������̈�u�ɂ��A���ԏH�q�v�l����w�������S�W�x�̈�ł�L�\�Ȏ��l�̌����ɂ��Ă����A�Ƃ̐\���o���v���Ђ̏��c�v�Y�В��̂��Ƃɂ���A���Ђ��^�c������S���������őn�݁B�Ȃ��v���Ђ́A���a56�N/1981�N�ɉ^�c���������ނ��邱�ƂƂȂ�A�Ȍ�A���������w�U����̎����ǂœ��������s�����ƂɂȂ�v�Ƃ���B�O�q�����悤�ɁA�ǂ������܂̎��т�����̂͋��R�ł͂Ȃ����낤�B�������s���w�܂̐��E�t�Œ��ׂĂ݂�ɔ@���͂Ȃ��B�܂��A�g���܂ł͑�11��i���a36�N/1961�N�x�j�E��12��i���a37�N/1962�N�x�j�E��13��i���a38�N/1963�N�x�j�A�Ƃ�ő�18��i���a43�N/1968�N�x�j��4�߂Ă���B
��11�� �g����
���a36�N/1961�N�x
��[ ���� ] ���a36�N/1961�N4��1��
��[ �}�� ] �w���w�x���a36�N/1961�N6�����A�w���㎍�蒟�x���a36�N/1961�N5�����I�l�o�ߌf��
��� �ΐ��q �w�T�E�������x ���a35�N/1960�N3���E�ђˏ��X�k���㎍�W7�l
��� ����c�q �w�����x ���a35�N/1960�N6���E����Њ��^�����N�� �w��̂��镗�i�x ���a35�N/1960�N9���E����Њ��^�������� �w�Ղ̗V�Y�x ���a35�N/1960�N9���E����Њ��^�R�{���Y �w�S�����x ���a35�N/1960�N11���E���惆���C�J���^�n�ӏC�O �w�J�Ԃ̐l�x ���a35�N/1960�N12���E���@���^�����@�� �w�����x ���a35�N/1960�N8���E���惆���C�J���^���c�q���q �w���Z��x ���a35�N/1960�N7���E���惆���C�J��
������[�̏��8���W�i�ΐ��q���܂ށj
��� ��@�� �w�s���_�Ȑ��U�x ���a35�N/1960�N8���E�����Њ�
�I�l�ψ���ɂ��lj�1���W
�܋�5���~�{�O�������N�M
�I�l�ψ� �؉��푾�Y�^���e���O�Y�^����l�Y�^�c���~��^������Y�^���c�O�Y�^������s�^�O�D�L��Y�^�g�����^�R�{���Y
�S����ɂ�铊�[
�J�[�����a36�N/1961�N2��13��
��1��I�l�ψ�����2��17��
��2��I�l�ψ�����3��27��
���蔭�\��4��1��
������5��27��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E����J�u��ꐶ���z�[���v
�s���w�t�i1961�N5�����j�̑I�l�ψ����E�c���~��̃y���ɂȂ�q�I�l�o�߁r�ɂ��A�g�����́u������̈Ϗ��̈ψ��v�̂����̈�l�ŁA����I�l�ψ���i2��27���j�A����I�l�ψ���i3��27���j�̑o���ɏo�Ȃ��Ă���B�����́u�R�c�ɓ��Ă͊e�ψ����e�̈ӌ����[���ɓf�I����Ƌ��ɁA���e���ׂ��͗e��A���̖{�̂������ɂ߂ăX���[�Y�ɑI�l�𗹂��������ƂL����B�v�ƌ���Ă��邪�A�g�����܂ފe�ψ��̊��z���͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�܂��s���㎍�蒟�t�i1961�N5�����j�ɂ́q���d�͏������l�u�[���\�\�g���܂ƕ����r�q�܁r�i�ڎ��̕\�L�j�Ƃ����������̋L���������āA�g���܂̑I�l�o�߂ɂ��G��Ă���B�L���ɂ́A�c���ψ����̃R�����g�Ɩ؉��푾�Y�E�c���~��i�ψ��Ƃ��āj�E�O�D�L��Y�E���c�O�Y�̊e�I�l�ψ��̊��z�͂��邪�A�g�����̂���͌f�����Ă��Ȃ��B
��12�� �g����
���a37�N/1962�N�x
��[ ���� ] ���a37�N/1962�N4��28��
��� ���R�ꐶ �w��n�̈���x ���a36�N/1961�N7���E�n���Њ�
��� �r��@�� �w�����Ձx ���a36�N/1961�N6���E���R�Њ��^���x�ےj �w���m�ȞB���x ���a36�N/1961�N6���E���ԎЊ��^�����v�Y �w���݁x ���a36�N/1961�N5���E�v���Ё^�k���㎍�l�o����1���l�^���@�� �w�����̂ɂ����`���x ���a36�N/1961�N8���E�v���Ё^�k���㎍�l�p��3 �l�^�ɓ��j�� �w�|�̎v�z�x ���a36�N/1961�N12���E���ƔŁ^�h���ɒj �w�_�l�����x ���a36�N/1961�N8���E�p�̉�^�V��@�� �w�N���X�g���̂��ȉS�x ���a36�N/1961�N10���E�����Њ�
������[�̏��8���W�i���R�ꐶ���܂ށj
��� ����N�v �w�Â��y�n�x ���a36�N/1961�N10���E���R�����^�킽�Ȃׂ��� -
�I�l�ψ���ɂ��lj����W
�܋�5���~�{�O�������N�M
�I�l�ψ� ������Y�^�H�J�L�^�����ρ^����S���^���C�i��^������^���ˉ�v�^�O�D�L��Y�^����l�Y�^�g�����^�g��O
�S����ɂ�铊�[
�J�[�����a37�N/1962�N3��5��
�I�l�ψ�����4��28���@�m���n�����V���u���O��فv
������5��26��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E����J�u��ꐶ���z�[���v
�s���w�t�i1962�N5�E6�����j�́q���d�̓����r�́u�c�́v�̍ŏ��̍��Ɂu���{���㎍�l��E�g���܌���B����4��24���̑F�t�ψ���ɂ����āA���R�ꐶ���W �w��n�̈���x�Ɏ��܌��肵���B���_�͓���N�v���W �w�Â��y�n�x�B�v�Ƃ���B����ƕʂɕ��R�ꐶ�ɂ��q�g����܂̊��z�r���f�����Ă��邪�A�����͑I�l�o�߂��I�l�ψ��̊��z���Ă��Ȃ��B3�N�O�́u�g�������v�̋L��������A���ܕɔM��������Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������͓����̕Ɩڂ��B�t������A������s�Â��y�n�t�́u���{�v�̓J�b�g�������A�\�����g�����ł���B
��13�� �g����
���a38�N/1963�N�x
��[ ���� ] ���a38�N/1963�N4��8��
��[ �}�� ] �w���w�x���a38�N/1963�N7�����I�l���k��f�ځy�q�g���ܑI�l�ψ��E�g�����r�Q�Ɓz
��� ���Ǘ����q �w�ꏊ�x ���a37�N/1962�N12���E�v���Њ�
��� ���_�@�� �w��p�b�x ���a37�N/1962�N8���E�������g�k�ߑp��4�l�^�e�n��O �w��ȉʎ��x ���a37�N/1962�N11���E���X�Њ��^�x�ꐴ�q �w��x ���a37�N/1962�N6���E�~�����[���^�А����q �w���܂��̔j��͊C�̂悤�Ɂx ���a37�N/1962�N9���E�v���Њ��^�R�{���q �w����x ���a37�N/1962�N11���E�v���Њ��^���c�@�W �w�����C�@�ʂ��Ȃ���ԁx ���a37�N/1962�N9���E���㎍���������^�֓��L�u �w�r��x ���a37�N/1962�N-���E���Ɣ�
������[�̏��8���W�i���Ǘ����q���܂ށj
��� ����N�v �w�����Q���n���X���̓��x ���a37�N/1962�N7���E���Ɣ�
�I�l�ψ���ɂ��lj����W
�܋�5���~�{�O�������N�M
�I�l�ψ� ����S���^�H�J�L�^������Y�^���C�i��^����l�Y�^�g�����^�g��O�^�����ρ^���ˉ�v
�S����ɂ�铊�[
�J�[�����a38�N/1963�N3��21��
��1��I�l�ψ�����3��28��
�I�l�ψ�����4��8��18:00�`�@�m���n�u�g�~�[�O�����v
������5��25��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E����J�u��ꐶ���z�[���v
��12��́s�Â��y�n�t�A�����Ă��̑�13��́s�����Q���n���X���̓��t�Ƃ��т��ь��ɋ������Ă�������N�v�����A�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t�i�B���ЁA1965�N10��20���A200������j�łg���܂���܂����̂�1966�N�̑�16��ł���B
��18�� �g����
���a43�N/1968�N�x
��[ ���� ] ���a43�N/1968�N
��� ���㏺�v �w�������́x ���a42�N/1967�N9���ELa�̉
��� ��؎u�Y�N �w㣐��������͊��v�ւ̓����x ���a42�N/1967�N3���E�G�ߎЊ�
�܋�5���~�{�O�������N�M
�I�l�ψ� ������Y�^�剪�M�^����S���^���c�O�Y�^�R�{���Y�^����N�v�^���m�^������Y�^���_���^�O�D�L��Y�^�g����
������5��10��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E�V�h�u�I�ɚ����z�[���v
�i�N�A�g���܊֘A�̋L�����f�ڂ��Ă���s���w�t�����A��18��̑I�l�ł͊֘A�L������������Ȃ��B����1968�N5�����́A���c�O�Y�ɂ��q���d���]�r�̖`���ɂ�������̂��ڂɂƂ܂����B�u�܌��\���i���j�̗[���A��������A�����V�h�̋I�ɍ����z�[���Ō܌��̎��Ղ��J�Â���A���㏺�v�A��{�u�Y�N�̗����ɓ��{���㎍�l��g���܂�������ꂽ�B�^���̎�̉�ɂ������N�l�͎Q���������Ƃ��Ȃ��������A���N�͑I�l�ψ��ł�����A�܂������ł�����̂ŁA�S���܂��ďo�Ȃ��Ă݂��B�����Ƃ܂ł͂����Ȃ��������A�������A�Ȃ��Ȃ������̂�����ł������B�×{���̑��㏺�v���ɑ��A�킳���������ꂽ���A�y��Ӑ���܂̂����̑��㎁�̐V���̌��e����݂����A���̐S���ɂ͐S���������̂��o�����B����ɗ�؎u�Y�N���́A�s���ɂ��Č��A�����܂ɂ��A����܂ŐE��ł͒m���Ă��Ȃ��������삪�I�[�v���ɂȂ�A�Ƃ������Ƃɂӂ�Ă����������B�������A�Ō�ɂ́A���J�̐ȏ�ł͘N�ǂɕs�K���Ǝv����v�A�v�A�����A����N�ǂ��Ă��̖ʖڂ��������B�^��������P�Ȃ�V��ɏI��Ȃ������̂��悩�����B����l�Y�A����N�v�̗����ɂ��B�u�������́v�u㣐������A���͊�㩁m�}�}�n�ւ̓����v�ɂ��Ă̘b���悩�����B�^������ʂ��āA�l�ɂ͗����̎��������Ɛe�����킩��悤�ɂȂ����悤�Ȋ������������B��؎��������Łu���t�����v�A�A�v�m�}�}�n���ƒ�I�A�C�E�G�I���s���v��N�ǂ������Ƃɂ��A�l�ɂ͐V���ȗ������J���ꂽ��ۂ��������B�v�i�����A��l�y�[�W�j�B
����͑I�l��ŗ�̎��W�𐄂������c�́q���z�r�ɑւ�镶�͂����A�g�����܂ޑ��̑I�l�ψ����q���z�r���L���Ă��Ȃ��̂͂��т����B
�g���͗�̎���W�Ɋւ��āA��N�A�u�k�c�c�l�ڂ����v����؎u�Y�N�Ƃ����̂́A�w㣐������c�c�x�ɂ����āA����͏��ߑ�����̌��삾�낤�Ǝv����ł��ˁB�Ȃ�ł���Ȃ��̂��ł����̂����l���Ă݂�ƁA��͂蓯����́A�V��ޓ�Y�Ƃ��g�������Ƃ��A�܂��A�����Ȍ�̐l�B�ɂ́A���{���ʂ������̌��t������Ƃ������݂Ȃ��̂������Ƃ��Ă������B���̂Ƃ��A��؎u�Y�N�́A�K���s�K���L���ɗ�����āA�F�B�Ɨ��ꂽ�B�t�Ɍ����ƁA�L���Ƃ����y�n�ŁA���ɏ���C�Ԃɏ����Ă������Ƃ������Ƃ��A�v�A�v�A���т��łĂ������ƂɂȂ����Ă����Ȃ����Ǝv���킯�B�k�c�c�l�����̎��тŌ����A�u�ؖځE�g�E�ǁv�A�u���t�v�A�u�Θb�v�A�u�����v�A�ǂ���������낢�ȁB�w�V���s�s�x�ɂȂ�ƁA����������������낢�̂͂��邯�ǁA��͂�w㣐������c�c�x�ւ̏����Ƃ������Ƃ�����Ǝv���B����ŁA�v�A�v�A���тƁw�ƒ닳�P���c�c�x�̎��т�ǂނƁA��؎u�Y�N�͂ǂ��Ȃ�낤�Ǝv���Ă�����A�w���炩���ł̖��x�ŁA�N�₩�ȓ]���������킯�ˁB�ڂ��Ȃ́A�������Ƃ�[�߂Ă����l�����A�ς���Ă����l�ɋ��������邩��A��؎u�Y�N�̓]���͑f�������Ǝv�����B�v�i�g�����E�ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�k���k��l�q�v�z�Ȃ�����̎��l�r�A�s���㎍�蒟�t1975�N5�����q���W����؎u�Y�NVS�g�������r�A��ꔪ�y�[�W�j�ƕ]���Ă���B
���ɍ������܂ł́A��9��i���a54�N/1979�N�x�j�����13��i���a58�N/1983�N�x�j�܂ŁA5��A���őI�l�ψ��߂Ă���i���̂����A��12��Ƒ�13���2��͍��������C�j�B�g���͑I�l�Ɋւ��镶�͂��A��9��́s���㎍�蒟�t1979�N2�����ɁA��10��́s���㎍�蒟�t1980�N2�����ɁA��11��́s���㎍�蒟�t1981�N2�����ɁA��12��́s���������w�U������t1���i1982�N1���j�ɁA��13��́s���t1���i1983�N3���j�ɔ��\���Ă��邪�A������������ɂ͖����^�ł���B
��9�� ��������
���a54�N/1979�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a52�N/1977�N12��1���`���a53�N/1978�N11��30��
��[ ���� ] ���a53�N/1978�N12��21��
��[ ���\ ] ���a54�N/1979�N
��[ �}�� ] �w���㎍�蒟�x���a54�N/1979�N2�����I�]�f�ځy�q�g�����ƎO�D�L��Y�r�Q�Ɓz
��� ���J�열�� �w���I�����x ���a53�N/1978�N4���E�v���Њ�
��� ����M�v �w�h���s�x ���a53�N/1978�N11���E�v���Њ��^�����@�� �w���t�x ���a53�N/1978�N5���E�q�r�Њ��^�O�D�L��Y �w�ђ������x ���a53�N/1978�N5���E���X���^�@�@���� �w�ꕶ�x ���a53�N/1978�N11���E�v���Њ��^���X�؊��Y �w�S�N�푈�x ���a53�N/1978�N6���E�͏o���[�V�Ёk�p���E������̎�8�l�^�͂�� �w�_�C�o�[�Y�N���u�x ���a53�N/1978�N9���E�v���Њ��^�n���@�F �w��̍l�x ���a53�N/1978�N11���E���w�Њ�
����8��
�I�l�ΏۂƂ��Ă̎Q�l����34��
���܁{����30���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �ѓ��k��^����N�v�^�����^��Y�^�R�{���Y�^�g����
�I�l�������a53�N/1978�N12��21��18:00�`�@�m���n�����E�s���J�u���̋{�v
���掮�����a54�N/1979�N1��30��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�@�����s�J�̗��ٔ��̋{�ɒ������̂́A������̘Z���ܕ��������B����Ȃ̂ɁA�Ȃɂ͑S���̕���������Ă���A�V�Q�҂̎��͋��k���Ă��܂����B�킸���A�ܕ��̒x���ł���������ǂ��B
�@���̐ȂŎ����ǂ���A�剪�M���W�s�t�@�����Ɂt�̔��s�����A�\�ܓ��ɂȂ��Ă���̂ŁA���O����Ƃ̕����B���N�́A�\��̐l�̎��W�ɁA�����ꂽ���̂����������������A���͂Ђ����ɁA�s�t�@�����Ɂt�𐄂��l���ł����̂ŁA�Ƃ܂ǂ��Ă��܂����B
�@�����I�Ԃ��߁A���̎茳�ɓ͂��Ă��Ȃ��A���ǂ̎��W��������A�ǂ܂˂Ȃ�Ȃ������B�����������悢��I�l�ɓ������B���͈���M�v�s�h���s�t�ƈ����ρs���t�t�̓�����������B�v���Ԃ�ł܂Ƃ߂ēǂ���̎��т́A���ɂƂ��ĐV�N�ŁA�������o������̂ł������B�i�����Ď֑���������A�a�J���}�v���U�́A�Ⴂ�j���̂Ђ��߂��I�ɍ������X�ŁA���͗��ǂ݂����B�X�͍Ζ����i�������j�B���ꂩ������ς́s���t�t�����A���̍I�k�ȕ\���ƍ\���ɂ���āA���͖������ꂽ�B�����ɓ����āA�ǂނɂӂ��킵����l�̎��ł���B�O���ڂ�������悤�Ɍ���ꂽ���A���͂����Ă��Ȃ������B���̐l�̐����鎍�W���A���ɂ͍m�肵�A�܂��ے肵���B
�@����X�����B���͈���ɍi��i�ɂȂ��āA���J�열���s���I�����t�𐄂����B�Ȃ��Ȃ炱���O�A�l�N���͓I�Ɂs��m�t�A���^���n�Ƃ����w�t�A���ꂩ��s�����̕��i�t���o���A���܂܂��͍쎍�W�𐬏A�������A���J��̉ʊ��Ȏ��I�����m�A�A�A�A�n�Ɍh�ӂ�\�������Ȃ�������ł���B
�@����M�v�A�����ςƂ͂܂��ʎ�́A���n���������֓��B�����A�O�D�L��Y�s�ђ������t���A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����W���ƁA���͎v���Ă���B�i�q���z�r�A�s���㎍�蒟�t1979�N2�����q�������ܔ��\�r�j
��10�� ��������
���a55�N/1980�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a53�N/1978�N12��1���`���a54�N/1979�N11��30��
��[ ���� ] ���a54�N/1979�N12��12��
��[ ���\ ] ���a55�N/1980�N1��10��
��[ �}�� ] �w���㎍�蒟�x���a55�N/1980�N2�����I�]�f��
��� �a��F�� �w���L�x ���a54�N/1979�N10���E�v���Њ�
��� ���c��v �w�s�A���x ���a54�N/1979�N4���E�v���Њ��^���ˉ�v �w��Ђ̐l���x ���a54�N/1979�N10���E�����Њ��^���Á@�� �w��x ���a54�N/1979�N6���E�v���Њ��^�E�c�ʜ\ �w���b�@�x ���a54�N/1979�N1���E�v���Њ��^��؎u�Y�N �w�Ƃ̒��̎E�Ӂx ���a54�N/1979�N5���E�v���Њ��^�Ί_��� �w�����x ���a54�N/1979�N5���E�Ԑ_�Њ��^�g��@�O �w���i�x ���a54�N/1979�N11���E�y�Њ�
����8��
�I�l�ΏۂƂ��Ă̎Q�l����24��
���܁{����30���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �ѓ��k��^����N�v�^�����^��Y�^�������^�g����
�I�l�������a54�N/1979�N12��12��18:00�`�@�m���n�����E�s���J�u���̋{�v
���\�����a55�N/1980�N1��10��
���掮��1��31��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�@���N�̑I�l�͂��܂�ɂ��A����Ȃ茈���Ă��܂����B��⎍�W���A���ꂼ��̑I�l�ψ����A���_���������܂����i���Ȃ��A���̂���Ȃ��ʂ������B���͍ŏ��ɁA�a��F��s���L�t�A��؎u�Y�N�s�Ƃ̒��̎E�Ӂt�A���Õׁs��t�𐄂����B�s���L�t�͍d���̝R����߁A����߂Ċ����x�������B�s�Ƃ̒��̎E�Ӂt�́A�V�������n���蒅���͂��߂Ă���B
�@�����ās��t�́A���̂���Ƃ݂ɑ����A���펍��Ô��ȝR��̂Ȃ��ɂ����āA�܂�Ȃ�U���I���ł���B������̎��W�Ɍ����Ă��ǂ��Ǝv�����B���������Ԃ����v�����̂́A����N�v�������ˉ�v�s��Ђ̐l���t�ƍ��c��v�s�s�A���t�����������Ƃ������B��N�́A�Ⴂ���l��B��l�Ő����Â������炾�B�������ɋߔN�A��҂��V����Ă���Ǝv���B���āA�s��Ђ̐l���t�����A�������ɐ��n�����ǂ����W�����A��������Ȃ��Ƃ��������B�s�s�A���t�͎��Ȃ̕��̂����炵���J�삾�B������[�𓊂����������ʂł������B
�@�a��F��́s���L�t�́A�ŏ����疞�[�ł���A���ꂪ��܂������Ƃ͓��R�ł���A�[���ł���B���ɂƂ��āA�a�͓���ȕ����������A���S�ɓǂݐ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓�̕������܂����͂̈�ł�����B
�@�V���������������ψ��ɉ�������B�u���ɋH��Ȃ鎍�̓ǂݎ�v�Ǝ��̂��Ă��邻��������A�S�������Ƃł���B�i�q���z�r�A�s���㎍�蒟�t1980�N2�����q��\�����ܔ��\�r�j
��11�� ��������
���a56�N/1981�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a54�N/1979�N12��1���`���a55�N/1980�N11��30��
��[ ���� ] ���a55�N/1980�N12��19��
��[ ���\ ] ���a56�N/1981�N
��[ �}�� ] �w���㎍�蒟�x���a56�N/1981�N2�����I�]�f�ځy�q�g�����̑�����i�i64�j�r�Q�Ɓz
��� �������Y �w���̒��̍Ό��x ���a55�N/1980�N10���E�v���Њ�
��� ���c�q���q �w�@�тƁx ���a55�N/1980�N10���E����ь牮���^��؎u�Y�N �w�킽�����̗H��x ���a55�N/1980�N6���E����R�c���^������s �w�p�k�̂����̉��y�x ���a55�N/1980�N10���E�y�Њ�
����4��
�I�l�ΏۂƂ��Ă̎Q�l����24��
���܁{����30���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �ѓ��k��^�c��m�^�������^�g�����^�g������
�I�l�������a55�N/1980�N12��19��18:30�`�@�m���n�����E�s���J�u���̋{�v
���掮�����a56�N/1981�N1��30��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�@�����^��Y�A����N�v���I�l�ψ�����߂��A�V�����c��m�A�g������������������Ă̑I�l��ł������B���̓�l�����ΖʂƂ����̂��ӊO�ł������B������V�N�ł���Ɠ����ɁA���ْ̋��������͋C��������ꂽ�B���ꂼ�ꂪ���ǂ̎��W��ǂ݂͂��߂鍠�ɂ́A���������Ԃ��낢�ł����B
�@�������������Ǝv�������W�́A�V��ޓ�Y�s���P�l�t�A���c�q���q�s�@�тƁt�A��؎u�Y�N�s�킽�����̗H��t�����āA�������Y�s���̒��̍Ό��t�̎l���ł������B�������A�\�I�͎O���Ƃ������ƂȂ̂ŁA�s���P�l�t���O������Ȃ������B�ߗ��V��N�͎��Ȃ̍z�������A�����ꂽ�U���`�̎��������Ă���Ǝv���B�����s���P�l�t�̒��ɂ͏퓅�����ꂽ��i������B�s���҂̍ԁt�́q�X��l�܂Łr�q���V���r�̂悤�Ȏ�����A�O�т���Ǝv�����B���c�q���q����́s�@�тƁt�́A�����ɂ͒��������m�I�ɍ\�����ꂽ�ǂ����W���Ǝv�����B������O���̓��w���ȍ�i�����O������A���W�̓��ꂪ�Ƃ�ċ��������Ǝv�����i���̈ψ������ӌ��j�B��؎u�Y�N�N�́s�킽�����̗H��t�́A�V���n���Ђ炢�����W���Ǝv�����B���̒��S�ɐ�����ꂽ�q���x�̗��J�r�͋ߗ��̏G�삾�B�����܂ł̑O���ɂ���ׁA�㔼�̍�i�Q�ɁA���ւ̎v�����ꂪ�����A�^����o���Ă��܂����B
�@���͂��낢��ƍl���A�������Y�N�́s���̒��̍Ό��t�𐄂����ƂɌ��߂��B�Ǎ�Ȏ��l�Ɉ˂��Â���̎��W���Ǝv�����B��J�N�Ƃ�������������Ԃɂ���ꂽ�A�����j���A���X�̈Ⴄ���т��I�k�ɔz�A�݂��Ƃɓ��ꂵ�����W�ł���B��ш�т̎��͂���قNj����Ǝv���Ȃ��̂ɁA�S�̂Ƃ��Č���ƁA�ӎu�i�ӎ��j�̋�����������B���Ȍ����������m��Ȃ����A�����ɂ͓��ς̔�������B�i�q���z�r�A�s���㎍�蒟�t1981�N2�����q��\������ܔ��\�r�j
��12�� ��������
���a57�N/1982�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a55�N/1980�N12��1���`���a56�N/1981�N11��30��
��[ ���� ] ���a56�N/1981�N12��17��
��[ ���\ ] ���a57�N/1982�N
��[ �}�� ] �w��\������܂̂�����@���������w�U������x�m���a57�N/1982�N1���n�I�]�f�ځy�q�u������H��v�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i12�j�\�\�q���͂Ȃ����F�Ȃ̂��H�r�r�́u��/�h�������Ɓq����r�v�Q�Ɓz
��� �h���ɒj �w�s�ׂ̉́x ���a56�N/1981�N4���E���X��
��� �m�O�h�� �w���߂�x ���a56�N/1981�N4���E���ώɊ��^�k�����Y �w���̉ԁx ���a56�N/1981�N10���E�v���Њ��^�剪�@�M �w���{�@�݂��Ȃ��܂��x ���a56�N/1981�N7���E�v���Њ��^�����a �w���u�z�e���̑�Ƒ��x ���a56�N/1981�N5���E����R�c���^��؎u�Y�N �w�����̈ړ��x ���a56�N/1981�N10���E�v���Њ��^�w���a�̔g���@�Ώ����e�x ���a56�N/1981�N10���E����R�c���^�͂�� �w�~�̃A�^�}�������Ă����x ���a56�N/1981�N11���E�v���Њ��^�k��@�� �w��Ȍ�x ���a56�N/1981�N10���E�A�g���G�o�Ŋ�抧
����9���W
���܁{����50���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �ѓ��k��^�c��m�^�������^�g�����m�����n�^�g������
�A���P�[�g�i200�l�j����̉{�����ǂɂ���č쐬���ꂽ�ꗗ�\�{�I�l�ψ��ɂ�鐄�E���W18��
�I�l�������a56�N/1981�N12��17��18:00�`�@�m���n�����E�x�͑�u�R�̏�z�e���v
���掮�����a57�N/1982�N2��1��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�@�悸�́A�\��N�̒����ɘj��A���������w�U����̈Ϗ��������A�������܂̉^�c�ɂ���������Ă����A�v���ЂƂ��̊e�ʂɁA����J���܂Ƃ����\�グ��B
�@����̑I�l�ψ���ł́A�����N���̌̂ɁA�������Ƃ߂邱�ƂɂȂ����B�s���̂��߁A���������i�s��������B
�@�����̎��W�̒�����A���͎l���𐄂����B�剪�M�w���{�x�A�����a�w���u�z�e���̑�Ƒ��x�A�m�O�h��w���߂�x�����Ėk�쓧�w��Ȍ�x�ł���B�ق��̈ψ������ꂼ��A�l���Ȃ����O����I�B
�@�������Ԃ������A���c�����Ƃ���A�w���{�x�Ƙh���ɒj�w�s�ׂ̉́x�̓���ɂ��ڂ�ꂽ�B�w���{�x�͑��ʂȌ���\������g���āA����̎��ֈ�̕x�������Ă���Ǝv�����B���ꂩ��A�w�s�ׂ̉́x�́A�������ɐ[���ŁA���d�Ȑ��E������B�������A���ɂ͏[���ɉ�ǂł��Ȃ��Ƃ��낪����A�M�̖�肾���ł͂Ȃ����낤���A���̂��ǂ��������c��B
�@�k�̂��Ƃ̒������ف\�\�����Ď��Ԃ��o�B���炭�x�����āA�S���Łw�s�ׂ̉́x���A��܍�Ɍ��߂��B�ق��Ƃ�����C���Ȃ����B�⏬�����čs���A����̎��̂Ȃ��ŁA�ǐ₵���w�s�ׂ̉́x���I�ꂽ�̂��A�Ӌ`������ƁA���͎v�����B�i�q���z�r�A�s���������w�U������t1���i1982�N1��30���j�q��\������܂̂�����r�j
��13�� ��������
���a58�N/1983�N�x
��[ �Ώۊ��� ]�����a56�N/1981�N12��1���`���a57�N/1982�N11��30��
��[ ���� ] ���a58�N/1983�N1��18��
��[ �}�� ] �w���x1���m���a58�N/1983�N3���n�I�]�f�ځy�q�g�����̑�����i�i44�j�r�q�g�����̃��C�A�E�g�i3�j�r�Q�Ɓz
��� ����N�v �w���҂����̌Q���镗�i�x ���a57�N/1982�N10���E�͏o���[�V�Њ�
��� �����a �w���{�̎��͂ǂ��ɂ��邩�x ���a57�N/1982�N7���E���q�����[���^�������� �w�����x ���a57�N/1982�N7���E����R�c���^���@�m �w�ڊo�߂鐡�O�x ���a57�N/1982�N9���E����R�c���^��c�j�Y �w���Z�掅�Z�x ���a57�N/1982�N10���E��o�Ŋ��^�����@�s �w���̌��ہx ���a57�N/1982�N3���E����G�ߎЊ��^�����@�� �w���O�i�[�̌ǓƁx ���a56�N/1981�N12���E�v���Њ��^�ŏ��W�q �w���������ցx ���a57�N/1982�N10���E�y�Њ�
����8���W
���܁{����50���~�{�L�O�i
�I�l�ψ� �c��m�^�������^���J�열���^�g�����m�����n�^�g������
�A���P�[�g�i200�l�j����̉{�����ǂɂ���č쐬���ꂽ�ꗗ�\�{�I�l�ψ��ɂ�鐄�E���W13��
�I�l�������a58�N/1983�N1��18��17:00�`�@�m���n�����E�x�͑�u�R�̏�z�e���v
���掮��3��11��18:00�`�@�m���n�����u�ԍ�v�����X�z�e���v
�@�����炻�̓��͑�J�ł������B���ׂ������点�Ă������ɂ́A�[������̊O�o�͂炢�B�����̐��w�߂��̒����قŁA�M���R�[�q�[��T��A�C�����Ђ����āA�x�͑�̎R�̏�z�e���֕������B�����̐Ȃ͘a���ŁA���łɐV�����ψ����Ƃ߂�A���J�열���������Ă����B���炭�A�G�k���A���Ƃ͐����̖����̌���i��ǂB
�@���N�́A�����ꂽ���W�������B���̂Ȃ��ŁA���������w�����x�A�����a�w���{�̎��͂ǂ��ɂ��邩�x�A�r��m���w�����x������A�Ⴂ����ł́A���o���w�ӓ��̐�ӂ̂��߂Ɂx�ȂǂɁA���͐S��ꂽ�B
�@�I�l��͂��܂�ƁA���́w�����x�Ɓw���{�̎��͂ǂ��ɂ��邩�x�����ē���N�v�w���҂����̌Q���镗�i�x�̎O���𐄂����B���������́A�u�����Ɛl�ԁv�Ƃ����s��Ȏ����A�ٖ��Ȃ镶�̂Ō��A����������B�����a�́A�O��́w���u�z�e���̑�Ƒ��x�ŁA����Ő�[�̕����𑨂��āA����U�����B���x�͈�]���āA�ÓT�I�ȕ���̐��E���A�j��u�����Ђ��߂Ȃ���A�̂��グ�Ă���B���̓�̂����ꂩ���A��܍�i�ɑI��Ă��A���͔[���������낤�B
�@����N�v�w���҂����̌Q���镗�i�x�ւ̎�܂����肵���B�N������\�����Ă������Ƃ����m��Ȃ��B���Ă̖���w�킪�o�_�E�킪�����x�����������܂Ɖ����قǁA���̒��јA�쎍�́A���҂Ɛ��҂̌������A���G����ɏ��q���Č����ł������B�i�q���֊�]�����Ă��c�c�c�r�A�s���t1���i1983�N3��10���j�q��\�O�����܁r�q�I�]�r�j
�������g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�ɒlj�����Ƃ���A���̂悤�ɂȂ낤���B
���Z��N�i���a�O�\�Z�N�j �l�\���
�l���A��\���g���ܑI�l�ψ��߂�B
���Z��N�i���a�O�\���N�j �l�\�O��
�l���A��\���g���ܑI�l�ψ��߂�B
���Z�O�N�i���a�O�\���N�j �l�\�l��
�l���A��\�O��g���ܑI�l�ψ��߂�B
���Z���N�i���a�l�\�O�N�j �l�\���
�l���A��\����g���ܑI�l�ψ��߂�B
��㎵���N�i���a�\�O�N�j �\���
�\�A�������ܑI�l�ψ��߂�B
��㎵��N�i���a�\�l�N�j �Z�\��
�\�A��\�����ܑI�l�ψ��߂�B
��㔪�Z�N�i���a�\�ܔN�j �Z�\���
�\�A��\������ܑI�l�ψ��߂�B
��㔪��N�i���a�\�Z�N�j �Z�\���
�\�A��\������ܑI�l�ψ��߂�i���������C�j�B
��㔪�O�N�i���a�\���N�j �Z�\�l��
�ꌎ�A��\�O�����ܑI�l�ψ��߁i���������C�j�A������Ō�ɓ��ܑI�l�ψ���ނ��B
�g���������ӂ��̎��̏܂̑I�l�ψ��߂��̂́A��������ɁA���Ď������g�����܂Ƃ����`���������āA�f��ɒf��Ȃ��������߂�������Ȃ��B�����āA�}�����[�Ƃ������|������|����o�ŎЂ̎Ј��Ƃ������ꂪ�A�����ȊO�̕��w�܂̑I�l�ψ��ɏA�����Ƃ�j�̂�������Ȃ��i�Ђ̋Ɩ��Ƃ��ẮA���Ɏ����̉��ǂ݂Łq���̐����r�̋�����b�q�������o�܂����z�q�����E������b�q�r�ɏ�����Ă���j�B��������ȏ�ɁA���������܂̑I�l�Ɋւ�邱�Ǝ��́A���S�������Ă����Ƃ����̂����ۂ̂Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B�g�������̂悤�ɏ����Ă��邩�炾�B�u�ޏ��Ƃ����Ή�����̂́A����̃T���O�T�ł������B�����傫�ȑ܂����A�O�\���̌��e����肾���āA�ǂ߂Ƃ����̂ŁA���͓��f�������̂ł���B�N�̂ł���i�}�̌��e��ǂ܂����قnj��Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A���܂ł��o���邾�����ۂ��Ă������炾�B�i���X�Ō��e��ǂސl�����݂�̂������͍D���łȂ��v�i�q���������̎��r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꔪ��y�[�W�j�B�����킢�Ȃ��ƂɁA�g�����I�l�Ɋւ�������̏܂͐����e�i�ނ���͎菑���ł���j��ǂތ`���ł͂Ȃ������悤���B
�k�NjL�l
���̏܂̑I�l�ȊO�ł́A�g�����͍����d�M�Ɍ���āq�o��]�_�܁r�̑I�l�Ɋւ���Ă���B�\�\���q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�g�����E�������q�k���k��l�q����o��]�_�ܑI�l���k��r�i�s�o��]�_�t25���A1963�N2���j��A�q�g�����́u�u���v�Ɣo��I�]�r�Ɉ������q���z�\�\�o��]�_�܌���܂ŁE�o�ߕƑI��]�r�i�s�o��]�_�t72���A1967�N9���j�����̑I�]�ł���B�V�l�̎���i�ł́A�s�����C�J�t�̓ǎғ��e���̑I�]�ɃQ�X�g�Ƃ��ĎQ���������Ƃ�����B���̂Ƃ��̒k�b�́k���Y���P�E��������E�g�����i�Q�X�g�j�̑Θb��]�l�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t1987�N11�����j�œǂނ��Ƃ��ł���B�V�l�̎��ɂ��ď������I�]���Ȃ������ɁA�g���̎��ς�����������M�d�ȓ��e�ł���B
�k2019�N2��28���NjL�l
���{���㎍�̕��w�ِU����E��c���������c�ҁs���̕��w�ُO�Z�N�m���E�Z�́E�o��n�t�i���{���㎍�̕��w�ِU����E��c���������c�A2016�N3��5���j�Ƃ���700�y�[�W������������B���{���㎍�̕��w�يْ��ʼn̐l�̎O�������Ɂq���̕��w�ُ܂̎O�Z�N�\�\�������̑n�ӂ���r�������Ă���i�����Ɂu��Z��ܔN��v�Ƃ���j�B�����ɑ������镶�͂ł���B���́u�S�@�{�܂̃G�s�\�[�h�v�ɁA�g�����̎���ނɊւ����Ӗڂ��ׂ��،����L����Ă���B�g���{�l�͂������A��l��̎��̑I�l�ψ��i�����ρE����N�v�E�O�ؑ�j�������炭���\���Ă��Ȃ����낤�������A���߂Ė��炩�ɂȂ����B
�@�����ŁA���k���l�I�l�ψ�������̏o�����Ƃ��āA��l��̎�����ɂ�����u����ށv�ɐG��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�g�������̎��W�w���[���h���b�v�x�i'88�E11�j���I�l�ψ��ɐ�������܂��B�k���l�搶�́A�������}�����[�̕ҏW�҂ł�����������ʎ�������A���l�Ԃ̑��݂͓I�ɖ₤���̏d���̎���ւ̎��܂Ɏ^������Ă���܂����B
�@�I�l��̂������k���l����N�O����l���̖�A�I�l�ψ��̈�l�̈����ρm�����ЂƂ��n���Ǝ����A�ڍ���t��̂����K��A��ꎞ�Ԃɂ킽���ē��ӂ����Ƃ߂܂������A�s���ɏI���܂��B���̐܂̋g�����̌����́A�����̎O��܂ł̎��̎�܍삩��́u���̕��w�ُ܂̐��i���킩�炸�A�V�l�܂߂������̂ɘA�Ȃ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƌ������̂ł����B�m���Ɏ��̕���́A�Z�́E�o��̕���ƈقȂ��āA�����ɂ����đI�l�ψ������N��̎Ⴂ�A����Ό㔭�̐V�s�̎��l����܂���Ă���܂����B�����ɓ��������̋@��ɁA�g��������܂��Ă������邱�Ƃɂ���āA�u�O�N���Ɋ��s���ꂽ�ł��D�ꂽ��i�W�v�Ƃ��������ɗ����߂肽���A���̐�w����ė~�����|���������܂������A�e����Ȃ������̂ł��B
�@�������A���̋g�����̂��т������ۂɑ����āA�{�܂̎��ɂ�����]���̎ړx���C������Ă܂���܂��B���̒[���ƂȂ����u����ށv�ł���A�ނ���g�����̏����ƕ]���Ɋ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�i�����A��Z�y�[�W�j
�q�g���������r��҂�1991�N����A���������̒����̂��߂ɏ��c�v�Y������v���ЂɖK�˂����Ƃ�����B���̂���A���낢���b�������������B���̎��̕��w�ُ��ނɊւ��ẮA�g�����炻�̌o�܂��Ă������̂̎��ɂ͌��ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��ꂽ�̂��낤�A�����������ꂽ�B�g���{�l�������Ă��Ȃ��ȏ�A�����҂ł͂Ȃ����c�����ɓ`���Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͂Ȃ��B�����A���E���{���㎍�̕��w�يْ��̎O�́A�����܂��ɏ܂��^�c���闧��̓����҂������킯�ŁA���̏،��͏d�v�ł���i�u�����̎O��܂ł̎��̎�܍�v�������A�����Ă��̂Ƃ��̑I�l�ψ����N���́A�s���̕��w�ُO�Z�N�m���E�Z�́E�o��n�t�̖{���ɏڂ����j�B���ǁA�{���ɂ͋g���́s���[���h���b�v�t���u��l��i�������N�j������I�o��v�Ƃ��ċL����Ă�����̂́A�q��܂̂��Ƃr�̂����Ɂu�I�l�ψ���ɂ����āA�g�����w���[���h���b�v�x�i��㔪���N�\�ꌎ�A����R�c�j���I��܂������A �g�������͎�܂����ނ���܂����B�v�i�����A��Z��y�[�W�j�Ƃ��邾���ŁA��i�̑I�o���ё��ʐ^�E�����̌f�ڂ��Ȃ��i�����݂͂ȁA���̎�܍�ɂ͂���j�A�I�l�ψ���\�̎O�ؑ�̑I�]�q����Ȃ��Ԃ������r�i�Ę^�j���g���̎���ނ̗��R�ɂ͐G��Ă��Ȃ��B�g�����̎���ɑ��������ƁA���w�܂̑I�l�ɑ��錩�����v�����炳�ꂽ�ꌏ�������B
2018�N7��28���A���t�I�N�I�Ɂu�y���I�z�g�������ȁ@�������O���@��28�i�y�������2���@�����j�v���o�i���ꂽ�B�J�n���i��15,000�~�B�s�b��Ȃ����ƂɁA��ɂ���ė��D�������Ȃ������A���Ȃ̕��ʂ���|����ɋg�����ƒ������O�̊W��T���Ă݂����B�܂��A���Ȃ̔N��́u��28�v�����A����𐼗�ɂ����1953�N�ŁA���̎ʐ^�ɂ�����u�k���a�l53�k�N�l�v�̂ǂ����ǂ��ǂ݊Ԉ�����̂��A1953�N�����a28�N�Ƃ������ŁA�����܂ł��Ȃ����a53�N��1978�N���������B����āu��28�v�ł͂Ȃ��A�u��53�v�B���������A�g���̏��������a28�N�����̂��̂ł͂Ȃ��B
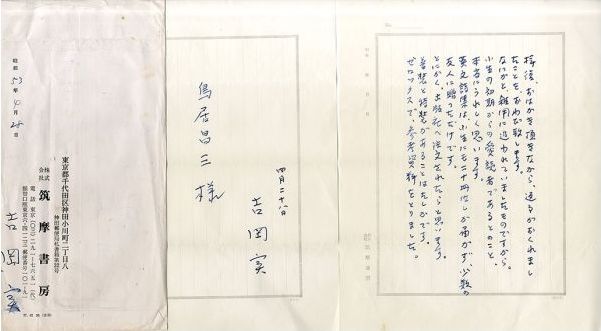 �@
�@
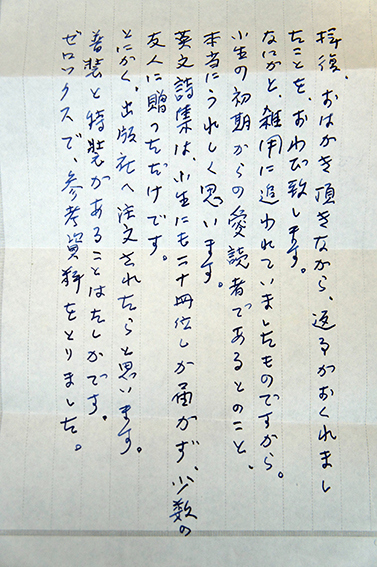
�������O���g�������ȁi���a53�N4��28���t���B�j�i���j�Ɠ��E�����i�E�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l
�O�̂��߂ɁA�������O���g�������ȁi���a53�N4��28���t���B�k�����̕\��4��28���u���쒬�v�̏���E4��29���u�ɓ��v�̏���l�j�̕��ʂ��N�����ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�k�}�����[�̕�ⳂɁl
�q���A���͂��������Ȃ���A�Ԏ���������܂�
�����Ƃ��A����ђv���܂��B
�Ȃɂ��ƁA�G�p�ɒǂ��Ă��܂������̂ł�����B
�����̏�������̈��ǎ҂ł���Ƃ̂��ƁA
�{���ɂ��ꂵ���v���܂��B
�p�����W�́A�����ɂ���\���ʂ����͂����A������
�F�l�ɑ����������ł��B
�Ƃɂ����A�o�ŎЂ֒������ꂽ��Ǝv���܂��B
���m�}�}�n���Ɠ��������邱�Ƃ͂������ł��B
�[���b�N�X�ŁA�Q�l�������Ƃ�܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l����\����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g����
�@�@�������O�l
�k�}�����[�̕����̗��ʂɁl
�k���a�l53�k�N�l4�k���l28�k���l
�k�c�c�}�����[�c�c�l
�g����
�������O���g�����ɑ������n�K�L�̓��e�́A1976�N�m�t���n��Chicago Review Press���獲���h����Ŋ��s���ꂽ�p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t�̓�����@�ɂ��Ăł��낤�B���������̑��݂�m�����̂́s�ǔ��V���k�[���l�t�i1979�N10��20���j�́q�蒠�r���̏Љ�L���q�g�������̉p�W�D�]�\�\�A�����J�Ŋ��s�r�i�������j����������A�����͂���ȑO�ɖ{����m�������ƂɂȂ�B�Ƃ���A�V�q�r�ꂪ�s�p��N�t1977�N12�����Ɋ����]�q�g�����̉p�W�r��ǂ��A�����ǂ����sVOU�t�̒��Ԃ����肩�畷�����ꂽ���B���\�[�X�̑F���͂Ƃ������A�����͒��҂̎莝���̈����Ђ��Ă��炦�܂����ƈ˗������̂ł��낤�B����ɑ���g���͕̉��ʂ̂Ƃ���ŁA�[���b�N�X�i���������Ƃ���̃t�H�g�R�s�[�k�d�q�ʐ^���ʁl�j�ʼn��t�y�[�W������ē��������Ǝv�����B���҂ɒ��ږ₢���킹�邠����A�Ȃ��Ȃ���M�I�ȓǎ҂����i�g���́u��������̈��ǎ҂ł���v�I�j�A�N�W�ɂ������Ă͍D��ۂ�^���Ȃ������ƁA����V�܂̌Ï��X�傪���Ɍ�������Ƃ�����B�Ȃɂ��������̂���̓I�ɂ͕����Ȃ��������B�Ƃ���ŁA�������O�ɂ��ăC���^�[�l�b�g�Ō������Ă��A�d�v�Ȃ��Ƃ͂Ȃɂ��o�Ă��Ȃ��i�摜��������ƁA���W�̏��e�������q�b�g����̂������Ƃ����悤���j�B���O�A�\�V�G�[�c�҂̏����A�s���{�̎��� �S���@27/90�t�i���O�A�\�V�G�[�c�A1992�N3��19���A����O�y�[�W�j�ɂ́A�����̒����Ɋւ��Ď��̂悤�ɂ���B
���� ���O�@�Ƃ肢�E���傤����
���A���t�@�x�b�g��㩁\�������O���W�@�������O
�@���@�ɓ��@�C�l�Ɂ@1984.6�@1���@21cm
�@�@�q�wTrap�x�ʍ��@����Łr
�������`����w�@�������O���@�����@Press�m�}�}�n
�@bibliomane�@1961�@67p�@21cm
�����W�@�̑��u�@�������O���@�����@Presse
�@bibliomane�@1959�@45p�@17cm�@�q����Łr
�{�e���M�̂��߂ɁA�����̋H�����W���W�߂�̂������܂��̂ŁA�s�������O���W�t�i�w���ЁA2013�N11��15���j�ő�p�����Ă��炤���Ƃɂ���i���Ȃ݂ɓ����́A�ΐ_�䏑�т���w�������j�B����͒������O�f�㊧�s�̑S���W�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���҂̐��N�E�f�N�����L����Ă��Ȃ��A�͂Ȃ͂��Ԃ�����ڂ��ȕҏW�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��A�����ꂽ���̂����ׂĂŁA������߈����ׂ������̌`�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł����Ȃ�A���l�������Ƃ������܂�Ă������ȂǁA�ǂ��ł��������ƂȂ̂�������Ȃ����B�s�������O���W�t�́q�ڎ��r��������B
�������с@VOU No. 56-60, 1957-1958
�̑��u
�����`����w
�������с@VOU No. 80-95, 1961-1964
�w���̍���
�A���t�@�x�b�g���
���̊C
���̋L��
���������qVOU�N���u�̒������O�̎��Ƒ��{�ւ̈��̗��r
�����[�q�q�C�l�ɂ̂ЂƁr
���W�s�����`����w�t�`���̎��сq�������r��3�߂��琬��A���́u�R�v�ɃM���[���E�A�|���l�[�����o�ꂷ��B���Ȃ݂Ɂs�������O���W�t�̎��і{���́A���ׂĉ��g�݂ł���B
�@�R
�^���̉����낢���ł�����ꂽ�X�p�ɋ���Ȍ��������������V�g�����ы���������Ă���
�X���G�g���قǂ̏������킾�炯�̋��̂����Ă���
�ˑR�̕��ƂƂ��ɍ�������������
�����낢���
�U�l�̓�������������̐l�Ԃ��R�{�̌��̂������p���\���������}���ŗ�����n���Ă���
�������̍L�����̏�ŃM���I�����A���x�G�����E���W�~�C�����A���N�T���h�����A�|���l�G���E�R�X�g�����B�b�L�C�Ƃ������̎��l�Ɏ����q���t�������т����Ȃ���O�p�̃g�����v����Ă���
�L�����̒����獕���K�l�̔����̏��������^�p�R�E�p�E�`�̒�����䑢�������Ђ������������ƐH�ׂ͂��߂�
���v���ɜ���Ă��鑾�z
���ɉ����Ƃ���ňꔭ�s�X�g������
������
���������s���Ă���ɂ���
������
���ׂĂ�����͂��߂�
����Ǝ���̊Ԃɂ�1�s�A�L������B�t�ł���k�����q�ɂ��̌`���̍�i������̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ����A12�Ԃ߂̎���u�����āv�͑�_�ȗp�@�ŁA�݂��ƂɌ��܂��Ă���i�u�Q�v�ɂ́u�����ā^�܂��v�u�����ā^�������v�Ƃ��������������k�^�͉��s�l�j�B����VOU�ɍݐЂ��A�����Ƃ͖k���̟f��A�����Ԍo���Ă��������Ƃ������������́A�{�������̉����
�ނ́u�Ⴂ�o�b�J�X�v�����ʂ܂łÂ����B�����ď�Ɂu�j�Г��v���Ȏ��g�Ŕ������ɂ�������炸�A���̓��̂���܂ł͒��ق̐��ɂ����������{�̂��߂ɁA�����Ɏ��𓊂����ނ��߂ɐ������������Ƃ��A�ނ̕Иr�ł��鏗�_�ɂ܂ł��������Ƃ����B����̂ɔނ͂��̐����A�͂�߂ɋ��������Ƃ��Ȃ̑@�ׂɂ��ĉs���j�������A�C���j�J���E�r���[�e�B�Ɖr�Q�̎���i�݂̂Ȃ炸�A���H�̉ʂĂȂ��x�y�ɂ������������ɁA�܂Ԃ����G��A����悤�Ȗ{������������A���Ɏc�����B���̉e�ɂ͑傢�Ȃ�v�l�́A�o�x���̓������Â����@������J�ƃt�����X�����{�ɂ����Ă͓��{�ŗB��A����Ǝv�����Ɨ��v���������Ƃ��A�����ɖ��L���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�킽����������̉��b�������ނ�A�܂��Ƀs���N�ƃI�����W�ƐƗ̂ӂ����Ȃ鎍�W�u�l�̑��v�◎�������V���o�[���������O���C�́u�r�����̌ߍ@�v�̓����{�������ď����̉i���̍��Ɏc����h�ɗ~�m�}�}�n�����̂ł���B�i�����A���l�y�[�W�j
�Ə����Ă���B�u�ނ̕Иr�ł��鏗�_�v�͒����[�q���w���̂��낤�B�����āA�u��Ɨ��v�v�͖{���̔��s�҂ł���B�l�Z�������{�́s�������O���W�t�́A�����̐l�l�i�Ɩk�����q�j�̎�ɂ���āu�����Ɏ��𓊂����ނ��߁v�̈���ƂȂ����B

�s�������O���W�t�i�w���ЁA2013�N11��15���j�̕\���k�J�b�g�͖k�����q���l
�Ō�ɁA�s�������O���W�t�ōł���ې[��������т��f����B�O�f�����Ɉ˂�A���W�s�A���t�@�x�b�g��㩁k�wTrap�x�ʍ��l�t�i�C�l�ɁA1984�N6���j�́q���@�舤�p�r�k���ɂ́Z�ň͂�������x������l�ł���B
�}���h���S���̖��ɂ͂��܂�
���z�̃~�C���������Ă�
����Ȃ��Ȏւ̓G���`�b�N��
�G�N�X�t���v�l�̓��W�������������Ă���
����Ȋ����̒��ł�
�����Ȏ����������uKLORAN�v��N��
����
���E�͗ڂ��炯��
�����̎w�͖��ԉʂɓM��
�Ӗڂ̃v�����v�^�@��
�Ȑ��̃`���R���F�g������Ȃ�
���H�b�ɂȂ肽���G�N�X�t��
�ɂƂ��Ă͔��ɔ߂������Ƃ�
��������g�����N���̋L�ڂ��m�F���Ȃ���A�@�ǂ{�A�A�ς�����E�f��A�B�K�ꂽ�y�n�A�ƂƂ��ɇC�ς����p�W�A�����̍�i�Ɛl����_����ۂ̏d�v�ȃe�[�}���Ɗ������B�g���̐��z����L�A���M�N����ǂ�ł���ƁA���ɂ��܂��܂ȓW����ɑ����^��ł��邱�Ƃ��킩��B���\���ꂽ�L�^�Ɏc���Ă��Ȃ����p�W���ǂ�قǂ���̂��z�������Ȃ����A�g�������͂Ɏc�������̂ɂ͂���Ȃ�̈Ӗ�������A�Ƃ���������{�ɂ����B���̋L�^����R�ꂽ���p�W�̂����A���Ƃ��q�|�[���E�f���{�[�W�r�͎��Ƃ̖ʒk�̂���ɋg�������y�������߁A�܂��q�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�r�͎�������E�؉�L�̖F�����ɋg���̖����m�F�������߁A�L�ڂ��邱�Ƃ��ł����B�g�������ς��G�⒤���i����ѕ����j�A����ʐ^�����������`��Ƃ��߂���{�i�I�Ș_�l�̂܂��ɁA���̏�����ƂƂ��ċg���̎��т␏�z�A�����s�g�����N���k������2�Łl�t�\�\�g���̖����s�̎U���⎄�Ƃ̖ʒk�ŐG���ꂽ���e���܂ށ\�\�ɓo�ꂷ���Ƃ⒤���Ƃ𒆐S�ɁA���X�g�����Ă��������B�L�q�̂��������s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�ɏ����邪�A����͂��̑O�����Ƃ��āA���`��Ɩ��E��i���E�W����̍������f����B���Ȃ킿�{�e�q�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎��݁r�ł���B�㔼���𐬂��A����瑢�`��Ƃƍ�i�E�W����̉��͌�������������B�S�т����������������ɂ́A�Ɨ������y�[�W�s�g�������y���`��Ɩ��E��i�������k���t�l�t�Ƃ��āA�{�T�C�g�Ɍf�ڂ���\��ł���B�i�ҎҁE���ш�Y�j
���s �@ �@���s �@ �@���s �@ �@���s �@ �@�ȍs �@ �@�͍s �@ �@�܍s �@ �@��s �@ �@��s �@ �@��s
��c�j�Y�m�������E�Ȃ��n�c�cM182
�@�@�\�\���Ə��̌W�c�cM182, N334
�R����m������܁E�܂��݁n�^�R���g�m������܁E�܂������n�c�cM45, 51, 56, 223
�Ԑ��쌴���m����������E������n�c�cH76, 129, 159, 205
�\�\���C�����c�cS42, Se26, YS19
�A�o�e�B�^�A���@�e�B�mMario Avati�n�c�cN342, M79
�@�@�\�\�q�����ނ�̎U���r�c�cW�k20�l
�\�\����ɔ@���i��ڗ����j�c�cSe308
�A���`���{���h�mGiuseppe Arcimboldo�n�c�c�T�t�����E�݁i�G�E1�j
�A���v�mJean Arp / Hans Arp�n�c�c�X�[�v�͂��߂�i�E�E11�j
�k�A���O���mJean-Auguste-Dominique Ingres�n�l
�@�@�\�\�A���O���q��r�c�cM164, N348
�@�@�\�\�q�A���O���W�r�c�cM164, N348
�ѓc�P���^�ѓc�P���m�������E�悵���Ɂn�c�c�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�j, H165, Se246, YS161, N342, 350-351
�r�c���Y�m�������E�����n�c�cH14, 87, 134, 138, 159, 166, 205, 211, YS170
�r�c�����v�m�������E�܂����n�c�c�Ă���H�܂Ł\�\�r�c�����v�̔ʼn�̑薼���S��āi�F�E2�j, ���̖��{�i�H�E9�j, S284, H20, 21, 28, 36, 131, 152, 154, 155, Se201, 246, 330, YS161, 168, N334, 344, 337, 350
�Ή��l�q�m���������E�������n�c�cH59
��x�@���m�������イ���������n�c�cM177
�ɓ���t�m���Ƃ��E���Ⴍ���イ�n
�@�@�\�\�q�ɓ���t�W�r�c�cM160, N339
��㕐�g�m���̂����E�Ԃ����n�c�cH130
�Ɍ��ʕv�m���͂�E�݂����n�c�cS302, Se215, YS128
�@�@�\�\����W�s�~�N���R�X���X�t�c�cS302. Se215, YS128-129
���H���X�mWols�n�c�cS291, Se206
�~�؉p���m���߂��E�������n�c�c�▋�i�K�E9�j
�@�@�\�\�~�؉p�����ʼn�W�c�cN355
�~�����O�Y�m���߂͂�E��イ���Ԃ낤�n�c�cS330, H207, 209, Se231, YS142, M43, 156, N327
�@�@�\�\�K�b�V���̊G�c�cS330. Se231, YS142
�|�{����m���̂��ƁE��傤�����n�c�cH181
�}�b�N�X�E�G�����X�g�mMax Ernst�n�c�c�s���\�\�}�b�N�X�E�G�����X�g�Δʼn�W�Ɋāi�J�E6�j
���z�m�m�����悤�E�����n�c�cSe258, U40
�@�@�\�\�u�㐬�{�Ґ���v�c�cU51
�剪���I�m���������E�����n�c�cS287, H182
���c�唪�m�������E�����͂��n�c�cS34, 107, Se20, 71, M21, 48, 54, 157, N328-330, 347
��|�Εv�m���������E�������n�c�c�NJ|�i�J�E5�j
����a�Y�m���������E�������n�c�cSe330
���R�����m�����Ȃ��E��イ�n�c�cS28, Se16
���m������E�����n�c�c�H�̗̕��i�K�E5�j, H192, N358
�@�@�\�\�q�O�����i�[���̓e�r�c�cW�k29�l
�����m���������E������n�c�cN330, 359
���q���m��������E���傤�n�c�cH129-130
�ЎR���m������܁E����n�c�c���k�i�I�E18�j, S230-234, H114, 205, Se162-166, N340, 345, 360
�@�@�\�\��W�s���������X�t�c�cS230, Se162, N338
�@�@�\�\�W�c�cS233, Se165
�@�@�\�\�W�c�cS234, Se166
�@�@�\�\�ЎR���W�c�cN340, 335
�@�@�\�\�ЎR���W�c�cH205
�@�@�\�\����W�s�G���[���E�A���[�t�c�cS231, Se163
�@�@�\�\��O��W�s���q�̓Ɗy�t�c�cS233, Se165
�@�@�\�\�f�b�T���W�c�cS231, Se163
�@�@�\�\�q�Ƃ�ڂƏ����r�c�cW�k23�l
�k�����k�ցm�������E�ق������n�l
�@�@�\�\�x�ԎO�\�Z�i�c�cS21, Se11
�@�@�\�\�k�֓W�c�cS21, Se11, N334
���{�x�m�Y�m�����ƁE�ӂ����n�c�cM45, 56
����v���q�m���Ȃ��E���݂��n�c�cH38, 55, 139, 165, 182, N356
���q���`�^���q���`�m���˂��E���ɂ悵�n�c�c���̃A�X�e���X�N�\�\���q���`�̊G�ɂ悹�āi�H�E22�j, H140, N359
���q�����m���˂��E�݂͂�n
�@�@�\�\�q���q�����W�r�c�cM160, N336
���[�����m���̂��E�݂��n�c�cS20, H28, 132, 135, 138, 158, 175, Se10, YS168, N334
�@�@�\�\�u������k�i�V���́l�I�v�W�c�cS20, Se10, N334
��������m�����܁E�������n�c�cM112
���R�����m����܁E�܂������n�c�cH94, 215
�k�͈䊰���Y�m���킢�E���낤�n�l
�@�@�\�\�͈䊰���Y���W�c�cS22, Se12, M159, N335
�͌����m�����E����n�c�cM51
�@�@�\�\�q�����r�c�cW�k22�l
��P�m���n�c�cN341
�@�@�\�\�`��P�M�q���R�E���}�r�c�cM162, N341
�@�@�\�\��^�ցq��寓S���}�r�c�cM162, N341
�\�\�q�؍��Ñ㕶���W�r�c�cM166, N351
�k�Ӑ^�a��m����킶�傤�n�l
�@�@�\�\�q�Ӑ^�a�㑜�r�c�cSe309, M164, N348
�e�n�M�`�m�������E�̂Ԃ悵�n�c�cSe346-347
�@�@�\�\�w����^�u�e�n�M�`�̖{�v�W�x�c�cSe346
�ݓc�����m�������E��イ�����n�c�cH27
�@�@�\�\�q�ݓc�����W�r�c�cM163, N346
�@�@�\�\�u��q���v�c�cH27
�J�@�c��m�������������n�c�cSe343
�@�@�\�\�u�R���}�v�c�cSe344
�@�@�\�\�u�����}�v�c�cSe343-344
�@�@�\�\�`�J�@�c��M�u�L�}�v�c�cSe344, M165, N350
�k��H�D�R�l�m�����������E�낳��n�c�cS250, 252, Se177-178, N344
�@�@�\�\�l�p�ȊD�M�c�cS250, 252, Se177-178
�\�\�g�˓V�����i��ڗ����j�c�cSe308
�ؗt��x�q�m�����E�����n�c�cH205
�\�\�q���s���r�i�O�䎛�k���鎛�l�j�c�cM161, N340
�L���R�mGiorgio de Chirico�n�c�c�}�N���R�X���X�i�F�E1�j
�@�@�\�\�q�f�E�L���R�W�r�c�cM161, N340
��m���E�����Ȃ�n�c�cSe256, U34
�k����S���m�����́E������n�l
�@�@�\�\�q����S���W�r�c�cN353
�N�[�g�mLucien Coutaud�n�c�c�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����i�E�E4�j
���g�N�Y�m���ɂ悵�E�₷���n�c�cS263, Se186
�|�[���E�N���[�mPaul Klee�n�c�c�|�[���E�N���[�̐H��i�I�E1�j, �ہ[��E����[�̉́q���͐�̃J���o�X�r�i�����\���сE2�j, Se73, 245, YS53, 152, M45, 119, 163, N327
�\�\�q���㎍�I�u�W�F�W�r�c�cN347
�\�\�q���㓹�ߐl������ʓW�ρr�c�cN341
���R�J�m�����E�����n�c�cM60, N337
���c���a�q�m�������E���킱�n�c�cS20, H19, 38, Se10, M208, N334
�@�@�\�\�I�u�W�F�W�c�cS20, Se10, N334
�k�O�@��t�m�����ڂ��������n�l
�@�@�\�\�q�O�@��t�Ɩ������p�r�W�c�cM165, N351
�A�[�V���E�S�[�L�[�mArshile Gorky�n�c�cS291, Se206
�t�B���Z���g�E���B�����E�t�@���E�S�b�z�mVincent Willem van Gogh�n�c�cM227
���ьÌa�m���₵�E�������n�c�cSe343
���N�Y�m���܂��E�Ă낤�n�c�cN332
�@�@�\�\�������j�Ƌ��N�Y�̎���W�s�����ǂ肦�t�c�cM158, N332
�S���mFrancisco Jose de Goya y Lucientes�n�c�c���܂�����\�\�k�������h�s����t�̈�ێ��сi�G�E30�j, H89�k���q���܂�����r�̈��p�l
�֓����m�����Ƃ��E���悵�n�c�cS102, Se67, 257, U35, 71, 85, M154, 226, N322
�֓��^��m�����Ƃ��E�����n
�@�@�\�\�q�����q ��̕Аg�r�c�cW�k25�l
�k��{�ɓ�Y�m�������ƁE�͂낤�n�l
�@�@�\�\�q��{�ɓ�Y�Ǔ��W�r�c�cM160, N338
���F�j��Y�m�����܁E���������낤�n
�@�@�\�\�q�w�l���r�c�cW�k24�l
�W���[�W�E�V�[�K���mGeorge Segal�n�c�cH109
�k���������m���݂��E�܂��ӂ݁n�l
�@�@�\�\���������W�q�Ǝ�p�r�c�cN355
�����ώR�m�����ނ�E����n�c�cS40, Se24, YS15
�@�@�\�\���̐}�c�cS40, Se24, YS15
�V���K�[���mMarc Chagall�n�c�cH137
�@�@�\�\�q�V���K�[���W�r�c�cN357
�V�����@���mJoseph Ferdinand Cheval�n�c�c���J�̎p������i�H�E14�j
�@�@�\�\�q���z�̋{�a�r�c�c���J�̎p������i�H�E14�j
�\�\�q���q�@�q�ϓW�r�c�cM163, N348
�\�\�q�����ɖ����W�r�c�cN357
�k����R�c�l
�@�@�\�\�q�e�N�X�g�ɂ����ā\��ƂƑ���ƂƁ\����R�c�́q�{�r�W�r���c�cN359
�W���X�p�[�E�W���[���Y�mJasper Johns�n�c�c���i�H�E8�j
�\�\�q�\��_�������r�Ƃ�킯�q���ܗ��叫���r�i�V��t�������j�c�cSe307, N328
�G�S���E�V�[���mEgon Schiele�n�c�c�����i�H�E6�j
�@�@�\�\�q�G�S���E�V�[���W�r�c�cN346
���؎u�Y�m�����E�������n�c�cH173
�X�^���`�b�`�mMiljenko Stancic�n�c�cS107, ���t, Se���G, 70, YS50
�@�@�\�\�����c�cS107, ���t, �k�\���l, Se���G, 70, YS50
�X�[�`���mHaim Sutin / Chaim Sutin�n�c�cM227
�X�����x���O�mMax Walter Svanberg�n�c�c�X�����x���O�̉́i�������сE12�j, N340
�w���}���E�Z���G���g�mHermann Serient�n�c�c�ٖM�\�\�փ��}���E�Z���G���g�̊G�ɂ悹�āi�H�E5�j, H205
�@�@�\�\�q�ٖM�r�c�cW�k21�l
�@�@�\�\�q�w���}���E�Z���G���g�W�r�c�cN354
�\�\�v���R����c�cSe24, YS16
�������C�m�������܁E���������n�c�cM60
�]���J���m�����E���傤�͂��n�c�cM160, N339
�@�@�\�\�q�ߐ��ْ[�̌|�p�W�r�c�cN339
�]���l���V���^�[���mFriedrich Schroder-Sonnenstern�n�c�c�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j, N333
�@�@�\�\�i��Ȃ��B����p���ɉ��M�Łj�c�cW�k30�l
�\�\�q����������r�c�cM165, N350
�k������\�Y�m�������܁E�₶�イ�낤�n�l
�@�@�\�\�q������\�Y�W�r�c�cM208, N356
�k�����V�g�m�����͂��E�����n�l
�@�@�\�\�q�����V�g����W�r�c�cM182, N339
���������Y�m�����ނ�E�������낤�n�c�cS238, Se167-168
���R�ב��m������܁E���������n�c�cM60
����C���m���������E���イ�����n�c�c�ǎ�̏��\�\����C�����Ɂi�G�E22�j, H11, 13-14, 16-17, 19, 28, 38, 41, 55-56, 58-59, 71, 102, 115-117, 138, 153, 157, 165, Se210, M154, N322, N340, 341, 346
�@�@�\�\����C���ƃW���A���E�~���̎���W�s�~���̐��Ƌ��Ɂt�W����c�cS316, Se210, N345
�c�ߕl�m��Y�m���Â͂܁E�悤�����낤�n�c�cH167, 174, 187, 193
�c������m���Ȃ��E���������n�c�cH28, 133, YS168
�c�����m���Ȃ��E�������n�c�cH77
�J���Z�Y�m���ɂ����E�낭�낤�n�c�cM35, N326
�J��W��m���ɂ���E���������n�c�cH25, 52
�U���@�B�m������E�������n�c�cSe342
�@�@�\�\�u�e���}�v�^�u���}�v�c�cSe342-343
�@�@�\�\�u���_���_�}�v�c�cSe342
�@�@�\�\�u���y�}�v�c�cSe342
�@�@�\�\�u�@�r���א}�v�c�cSe342
�\�\�q�����̊G��W�r�c�cM165, N349
�\�\�q���������S�I�r�c�cM54, 158, N331
�\�\�q���R���������W�r�c�cM164, N348
褚���ǁm����E������傤�n�c�cSe257, U37
���`�t�m���E�悵�͂�n�c�cS230, H43, Se162, N338
�@�@�\�\�q�˂����r�c�cS230, Se162
�k�|�[���E�f�C���B�X�mPaul Davis�n�l
�@�@�\�\�|�[���E�f�C���B�X�̃A�N������q�L�ƃ����S�r�c�cW�k19�l, N344, 355, 358
�@�@�\�\�q�|�[���E�f�[�r�X�̐��E�W�r�c�cN355
�k�|�[���E�f�����H�[�mPaul Delvaux�n�l
�@�@�\�\�q�|�[���E�f���{�[�W�r�c�cN341
�\�\����c�cSe282-283
�x���S�ցm�Ƃ݂����E�Ă������n�c�cS21, H194, 197, Se11
�@�@�\�\�q�S�֓W�r�c�cM161, N341
�@�@�\�\�q�x���S�֓W�r�c�cN354
�k�x�{���g�m�Ƃ݂��ƁE�����n�l
�@�@�\�\�q�x�{���g���W�r�c�cM160, N338
�x�{��Y�m�Ƃ݂��ƁE�������n
�@�@�\�\�k���e���O�Y�́l�傫�ȃJ���[�̏ё��ʐ^�c�cSe241, YS155
�A���h���E�h�����mAndre Derain�n�c�cH168
�������m�Ȃ����E���傤�n�c�cM222
����I���m�Ȃ�����E������n�c�cM45
�����b��m�Ȃ�����E�낹�n�c�cM160, N339
�@�@�\�\�q�ߐ��ْ[�̌|�p�W�r�c�cN339
�i�c�k�߁m�Ȃ����E�������n�c�cS21, 151, Se11, H18, 82, 167, 172, 192, 214, M20, 21, 30, N332-333, 338, 353
�@�@�\�\�q�H�ɏ��_���r�c�cM175
�@�@�\�\�u�����ǂ�}�v�c�cS22, Se11, N334
�@�@�\�\�q�ԍg�r�c�cM168
�@�@�\�\�q����g���}�r�c�cM60
�@�@�\�\�q�ߊC�n���r�c�cM60, 61
�@�@�\�\�u�����v�c�cS21, Se11, M59, 125-126, 174
�@�@�\�\�q�H���s���}�r�c�cM60
�@�@�\�\����W�c�cM121
�@�@�\�\�q���ƊG�ɂ��i�c�k�ߓW�r�c�c M59, 71,N337
�@�@�\�\�i�c�k�ߓW�c�cN339
�@�@�\�\�i�c�k�߂̏���W�s���t�c�cM174, N354
�@�@�\�\�q�ΘŁr�c�cM60, 70, 71, N338
�@�@�\�\�u�����}�v�c�cS21, Se11, W�k27�l, M159, N334
�@�@�\�\�q�������_���r�c�cM60, 61, 71, N337
�@�@�\�\�q�s���r�c�cM79, 174
�@�@�\�\�q�V��[�Đ}�r�c�cM61
�i�c�́m�Ȃ����E�肫�n�c�cM52, N331
�\�\�q�ߒq��}�r�c�cN353
�����ĔV�m�Ȃ��ɂ��E�Ȃ䂫�n�c�cS284, H14, 18, 20, 25, 28, 33, 36, 41, 53, 56, 83, 85, 87, 104-105, 131, 137, 147, 159, 206, 211, ���t, Se201, 344, 346, YS167-168, 170, N336, 359
�@�@�\�\���̃I�u�W�F�c�cH�k�W���P�b�g�l, �k�{���l, N336
�@�@�\�\�W�w�ނ炳���x�c�cSe346, N350
�@�@�\�\�q�����ĔV�W�r�c�cN357
�����G�m�Ȃ��ނ�E�Ђ낵�n�c�cH28, 62, 236, YS168
��g�c���N�m�Ȃ���E�������n�c�cS236-238, Se166-168, M204, N328
�@�@�\�\�q�k���̉Ɓr�c�cS237, Se167
�@�@�\�\��Ȉꖇ�̖��G�c�cS236, Se166
���C�Y�E�j�[���F���X���mLouise Berliawsky Nevelson�n�c�c�J�i�F�E9�j
���e���O�Y�m�ɂ��킫�E����Ԃ낤�n�c�cS23, 26, 88, 209, 213, 330-331, 342, H26, 34, 45, 85, Se222-247, 285-286, 298, 300, 304, 314-315, N342, 344-349, 353, 360
�@�@�\�\�q�i���̗��l ���e���O�Y ���E�G��E���̎��Ӂr�W�c�cM199, 202, N356
�@�@�\�\�W�c�cSe246
�@�@�\�\�k���W�s�Ẳ��t�́l����Ɏg�������e���O�Y�搶�̊G�c�cS209, 342, Se153, 239-240
�@�@�\�\�i��Ȃ��B�X�P�b�`������j�c�cW�k28�l
�@�@�\�\�嗝�̎ցc�cSe245, YS159
�@�@�\�\�����Ȗ��G�c�cS335, Se234, YS146
�@�@�\�\���e���O�Y�G��W�c�cM132
�@�@�\�\�q���e���O�Y��W�r�c�cN336
�@�@�\�\�u���e���O�Y�̊G��v�W�c�cSe246, M164, N348, YS161
�@�@�\�\�x�Ԑ}�c�cS331, Se232
�@�@�\�\�q�e��^���Εv���\�\���a�S�N���e���O�Y���̎��ƊG��r�W���c�cN360
�@�@�\�\���̊G�c�cS332, Se233, YS144
�@�@�\�\�u���̐}�v�u�Ղ̐}�v�c�cS331-332, Se232, YS143, N341
�\�\�q���{�̎��̓W�\�\���E�Z�́E�o��̈�Z�Z�N�r���c�cN359
�\�\���{���p�W����c�cM222, N326
�쒆�����m�̂Ȃ��E���n�c�cH11, 28, 59, 79, 126, 135, YS168
�k���h���t�E�n�E�Y�i�[�mRudolf Husner�n�l
�@�@�\�\�q���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�r�c�cM164, N349
���B�m�͂�����n�c�cSe11, H154, M60, 177, N337
���J�쓙���m�͂�����E�Ƃ��͂��n�c�cH191
�\�\�q���哶�q�����r�i���������j�c�cM165, N351
�H�i�����m�͂Ȃ��E�݂Ƃ��n�c�cH210, 238, YS177
�l���z�O�m�͂܂����E�悤�����n�c�cS74, Se45, YS11, N331
�@�@�\�\�k�G�b�`���O�����]�`���g�l�̉���u���v�c�cS74, Se45, YS11
�ѐÈ�m�͂₵�E���������n�c�cS230, Se162, N338
�\�\�q�ς邱�E�ۂ��Ƃ肢�W�r�c�cN339
�o���e���X�mBalthus�n�c�cH168-169, 194, 196, Se361
�@�@�\�\�u���������X�v�c�c Se362
�@�@�\�\�u�M�^�[�̃��b�X���v�c�c Se361, 362
�@�@�\�\�u�����v�c�c Se361
�@�@�\�\�u�q�������v�c�c Se361
�@�@�\�\���i��u�R�����X�E�T���^���h�����H�v�c�c Se361, 362
�@�@�\�\�o���e���X�W�c�cSe362, M168, N352
�@�@�\�\�u�����v�c�c Se361
�@�@�\�\�ё���u�z�A���E�~���Ƃ��̖��h�����X�v�c�c Se362
�@�@�\�\�u�X�v�c�c Se361
�@�@�\�\�u���v�c�c Se361
�r�A�Y���[�mAubrey Vincent Beardsley�n�c�cH94
�s�J�\�mPablo Picasso�n�c�cS87, 102, 133, 161, H94, Se57, 67, 89, 110, 335, YS82, M101, 138, 154-155, N322, 350
�@�@�\�\�q�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�r�c�cM164, N348
�����t�m�Ђ����E�����悤�n�c�cS250, Se176
�@�@�\�\�Z���c�cS250-251, Se176-177
�y���F�m�Ђ������E���݁n
�@�@�\�\����W�s�y���F�����W ����܁t�c�cN336, YS169
�@�@�\�\�u�y���F�����ʐ^�W�v�c�cYS179, N355
���I�m�[���E�t�B�j�mLeonor Fini�n�c�c�c�O�~�i�I�E21�j, M146
���c�k���m�ӂ����E���͂�n�c�cU129
�@�@�\�\�ʼn�u��l�v�c�cU129
�����p�Y�m�ӂ��ނ�E�Ђł��n�c�cH150
���[�����E�u���W�I�mRoland Bourigeaud�n�c�c�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�j
���O���m�Ԃ�E���傤�n�c�cM60
�\�\���W�c�cU84
�\�\�q���Ɣ[�o�r�c�cM161, N339
�t�����V�X�E�x�[�R���mFrancis Bacon�n�c�cN355
�n���X�E�x�����[���mHans Bellmer�n�c�c�����͂ǂ��ɂ��邩�H�\�\�y���F�̔�V�ɂ悹�āi�F�E6�j, �������i�F�E10�j, H54, Se359, M30, 151
�@�@�\�\���F�ʐ^�W�m�A�A�A�A�A�n�c�cSe359
�@�@�\�\�n���X�E�x�����[���s�l�`�ʐ^�W�t�c�cN337
�\�\�q�{�X�g�����p�ُ������{�G�於�i�W�r�c�cM165, N350
�]�p���m�ق����E���������n�c�cH13-15, 131, 236, N336
�@�@�\�\�u�ƂĂ��Ȃ��ߌ��I�Ȋ쌀�v�c�cH14, N336
�x���ʒq�q�m�ق肤���E�������n�c�cM51
���l�E�}�O���b�g�mRene Francois Ghislain Magritte�n�c�c���J�̎p������i�H�E14�j, S285, H37, Se202
�����O�j�m�܂��E���݂��n�c�c���]�Ԃ̏�̔L�i�G�E15�j
�^�甎�m�܂ȂׁE�Ђ낵�n�c�cM53, N331
�k�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�mBona de Mandiargue�n�l
�@�@�\�\�q�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�r�c�cN346
�O�ؕx�Y�m�݂��E�Ƃ݂��n�c�cH28, 76, YS168
�~�P�����W�F���mMichelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni�n�c�cH138, M38
���J�E�v�m�݂����ɁE�������n�c�cH194, 240, YS179
�{����߁m�݂₳���E���Â�n�c�cH53
�O�D�L��Y�m�݂悵�E�Ƃ悢���낤�n
�@�@�\�\�i��Ȃ��j�c�cW�k26�l
�z�A���E�~���mJoan Miro i Ferra�n�c�c����鏗�\�\�~���̊G����i�D�E18�j, S316, H115, 168, Se210, 220, 362
�@�@�\�\����C���ƃW���A���E�~���̎���W�s�~���̐��Ƌ��Ɂt�W����c�cSe210, N345
�\�\���ӕ�F����v�ґ��c�cS41, Se25, YS16
�փ����[�E���A�mHenry Spencer Moore�n�c�c�ǎ�̏��\�\����C�����Ɂi�G�E22�j
�@�@�\�\�q�w�����[�E���[�A�W�r�c�cM160, N336
�����u���m�ނȂ����E�������n�c�cM59
�����N�mEdvard Munch�n�c�c����i�G�E23�j
�@�@�\�\�q�����N�W�r�c�cM164, N348
�\�\���闅���c�cSe308
�و��m��������n�c�cM162
�@�@�\�\�u�l���}�v�c�cM162
���؈�v�m�€�E�������n�c�cM60
�\�\��t�@���c�cSe307
����\���Y�m�₷���E�������낤�n�c�cM43, 156, N327
���������m�悱���E�����̂�n�c�cH14, 16
�g�]�����m�悵���E���傤�����n�c�cH94
�g�c���j�m�悵���E�������n�c�cS328-329, Se229-230, M157, N328
�g���v�M�m�悵�ނ�E�܂��̂ԁn�c�cH128-129
�l�J�V�����m���E������n�c�c���ׁi�K�E6�j, H17, 19, 38-39, 41, 43, 76, 79, 112-113, 139, 179, 197, 208, 211, Se360, N338, 345, 353
�@�@�\�\�����l�`�c�cSe360
�@�@�\�\�u�h�C�c�̏��N�v�c�cSe360
�@�@�\�\����W�u�����Ɖߋ��̃C���v�c�cSe360, N340
�@�@�\�\�l�J�V�����l�`�W�q�����[���E�����[���r�c�cN349
�\�\�u���E��䶗��v�c�cSe367
�k�NJ��m��傤����n�l
�@�@�\�\�q�NJ��W�r�c�cM163, N347
�������mLi-lan�n�c�cS284, H20-21, 28, Se201, YS169
���h���mOdilon Redon�n�c�c�ٗ�Ձi�G�E19�j
���_���mFrancois-Auguste-Rene Rodin�n�c�cS88, 103, 143, Se57, 68, 97, 287-288, YS35, 37-39, 48, 90, M155, N327
�A�����E���[�����X�mHenry Laurens�n�c�c�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�j
�A���h�����[�E���C�G�X�mAndrew Wyeth�n�c�c��̊G�i�H�E 26�j
�a�c�F�b�m�킾�E�悵���n�c�cS244, Se173
�@�@�\�\���M�́u��v�c�cS244, Se173
�k�n�ӌ��l�m�킽�ȂׁE���˂�ǁn�l
�@�@�\�\�n�ӌ��l�ʐ^�W�q�t�|�s�s�r�c�cH139, M164, N349
�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@���@�@ �@�� �@�� �@�� �@�� �@���@�@ �@��
���c�唪�i�������E�����͂��A1918-2016�j
�u���a�E�������̊G�{��ƁC�C���X�g���[�^�[�D���茧�o�g�D�����鍑���p�w�Z�}�ĉȑ��D��Ȏ�ܗ��́C���{�����܁i���a30�N�j�C���w�يG��܁i���a33�N�j�C�A���f���Z���܍����܁i���a34�N�j�C�T���P�C�����o�ŕ�����܁i���a40�N�j�C���ۃA���f���Z����2�ȁi���a45�N�j�s�n�ʂ��тƁt�C�h�C�c���勤�a�����C�v�`�q���ې}���|�q�W����܁i���a50�N�j�C�����Ȏ������������܁i���a51�N�j�CIBA���ې}���|�p�W���܁i���a52�N�j�C�u�k�Џo�ŕ����܁i�G�{�܁j�i���a56�N�j�C�����������J�ҁi��29��j�i����1�N�j�C�Ԃ��������G�܁i��4��j�i����2�N�j�s�����Ȃ��G�{�t�C���{�̊G�{�܊G�{�ɂ��ۂ�܁i��15��j�i����4�N�j�s���������Ƃ��݁t�C�T���P�C�����o�ŕ����܁i���p�܁C��45��j�i����10�N�j�s�G�{���V�L�t�C���[�r�����������܁i��34��j�i����11�N�j�C�Y�o�����o�ŕ����܁i��49��j�i����14�N�j�s����̏����t�D���c�͏��a24�N���玙���}����G�{�Ȃǂ̃C���X�g���[�^�[�Ƃ��Ċ���D�����o�Ŕ��p�A���̐ݗ��ɎQ���C���N�ɂ킽���ė��������Ƃ߁C�G�̒��쌠�m���ɐs�͂����D��\��Ɂs�n�ʂ��тƁt�s�����t�s�Ȃ��������t�s�ߐ��̂��ǂ��Ύ��L�t�s���������Ƃ��݁t�s�G�{���V�L�t��SF�����s�X�p���L�[�t�ȂǁD�v�i���O�A�\�V�G�[�c�ҁs20���I���{�l�����T ���`���t�A���O�A�\�V�G�[�c�A2004�N7��26���A�l�����y�[�W�̋L�q�����ɃA�����W�����j
1951�N�A�}�����[�ɓ��Ђ����g���́A�S�������k���w���S�W�l�̑}�G��V�i�̑}�G��ƁE���c�唪�Ɉ˗������B�u����Ƒ��c�唪�E�\�l�q�v�Ȃ�m��B�Ȍ�A���̎��ƂƂ��āA�Ɛg����̌e���̏ꏊ�ƂȂ�v�i�q�k���M�l�N���r1952�N�̍��j�B�₪�đ��c�̎��ӂɂ����F�l�����Ƃ��e�����Ȃ�A�g�c���j�Ƃ�1954�N�Ɍ��j���S������܂œ��������B�g�����^�̎��I�o���𐋂������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̔��s�l�͑��c�ł���B1959�N�A�g�����a�c�F�b�̒����E�z�q�ƌ�������ɍۂ��ẮA���l�߂��B���c�́A�ŔӔN�܂ŋg���̎��ɐG�����ꂽ�G��`���\�z������Ă������A��������Ȃ������B���c���g������������͂Ɂq�J�����I���̊�r������B
�@�@�\�\���c�唪������Â�
�����V�A���E�N�[�g�[�iLucien Coutaud�A1904-77�j
�u�k���E��l�K�[�������[�k�ɉƋ�E�l�̎q�Ƃ��Đ���B�j�[���̔��p�w�Z�Ɋw��A�p���ɏo�ē�A�O�̌������ɒʂ��B���N������i�\���o�������A���̌�C�^���A�ɗV�сA�������l�b�T���X�A���Ƀs�G���E�f���E�t�����`�F�X�J�Ɋ��������Ɠ`������B�A����̓V���[�����A���X���̍�i�\���Ă��邪�A�l��N���͎�Ƃ��ăT�����E�h�I�g���k�y�уe���C�����[�ɏo�i�A�l�ܔN�ɂ̓T�����E�h�E���G�̐ݗ��ɎQ�������B���̓Ɠ��́A�j�Ǝh��z�킹��悤�Ȑ��ƌ`�̑g���킹�ɂ��l�̂���́A���̔߈��̏�Ɩ������s�v�c�Ȍ������ƂȂ��āA�����ɔ����Ă���B�ŋ߂̔ނ̓^�s�X�g���[�̉��G�A���z�����A�o���G�̑��u�ȂǁA�������p�̕��ʂɂ��A���̑��˂Ԃ�����Ă���B���݁A�t�����X�̒�����ƒ��A�ł����ڂ�����l�ł���B�i�Ö�k���Y�l�j�v�i����Ēj�E�R�c�q�O�Y�ҁs���m���p���T�t�A�������A1954�N11��30���A��㔪�`����y�[�W�j
�g���͎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�������Ă���ق��A�s�Õ��t�i1955�j�����́q���i�r�i�B�E10�j�͍e�{�̒i�K�ł͖ڎ��E�{���Ƃ��q�N�[�g�[�̕��i�r�Ƃ����薼�������B
�@�@�\�\1953�N1���ɂ킪���ŏ��̌W���_�ސ쌧���ߑ���p�قŊJ����A4�y�[�W�̃��[�t���b�g�Ȃ���ژ^�����s���ꂽ�i�g�������W���ς��L�^�͂Ȃ����A�ςĂ��Ȃ�����������j�B1963�N�ɂ͗������āA�����Ƒ��ŌW���J���Ă���B
�@�@�\�\���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���o�����L
�g�c���j�i�悵���E�������A192?-1954�j
���N�͖��ځB���c�唪�i1918-2016�j�̑����鍑���p�w�Z�}�ĉȎ���̌�y�̉�ƂŁA�g�����̔N���̗F�l�B�g�c���j�̃I�W�i�H�j�͖|��ƁE�p���w�ҁE�������w�҂̋g�c�b�q���Y�i1894-1957�j���Ƃ����i���c�唪�k�j�B
�@�@�\�\�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u�R�@���ϒn���̎��Ӂv�ŁA���j�Ɠ������Ă�������̂��Ƃ���z���Ă���B�܂��q�k���M�l�N���r�Ɂu���j�̎����_�@�ɁA���ꂽ�����s�E�h�Ɗ�ȗ����V�Y�v�Ə����Ă���B
�@�@�\�\�g�����Ƌg�c���j
�@�@�\�\�g�c���j�̑�����i
�l�J�V�����i���E������A1944-�@�j
�u�����ɐ��܂��B�{���͏��ь����B1959�N���w�Z�𑲋Ƃ��A���{�f�U�C���E�X�N�[���ɓ��w���邪�A�Ԃ��Ȃ����ނ���B�c��������l�`�̐���ɔM�����A1963�N�n���X�E�x�����[���̐l�`��m�������Ƃ���A�V�������A���X���ɐ[���X�|����ƂƂ��ɁA������߂̓������g��l�`�̐�����͂��߂�B1967�N�ŋ��Ɏg���l�`��������̂����������œ��\�Y�ƒm�肠���A71�N�ɑޒc����܂ŏ���ɖ��҂Ƃ��ďo������B���̊ԃf�p�[�g�̃f�B�X�v���[�p�̐l�`�����A��㖜��������ق̎d���Ȃǂ��肪����B1973�N�؉�L�i����j�ŏ��߂Ă̌W���J�ÁA�����̓��g��l�`12�̂�W�����đ傫�Ȕ������ĂԁB1974�N��11����{���۔��p�W�ɁA82�N�x�R�����ߑ���p�ق́u����C���Ɛ����p�v�W�ɏ��ҏo�i�B1978�N�G�R�[���E�h�E�V�������J�Z���A�l�`����̎w���ɂ�����B���݂����قȃG���e�B�V�Y����Y�킹��l�`�̐���ɂ�����ƂƂ��ɁA���҂Ƃ��Ă����Ă���B�v�i��ʌ����ߑ���p�ٕҁs�Ȃ����C�ɂȂ�l�ԑ��\�\�s�J�\�A�_���A�z�b�N�j�[�Ȃǁ@���������ߑ���p�ُ������i�W�t��ʌ����ߑ���p�فA1992�N�k8��12���l�A����y�[�W�j
�g���͎��сq���ׁr�i�K�E6�j���s�l�J�V���� �l�`���t�i���p�o�ŎЁA1985�N6��10���j�ɊĂ���B
�@�@�\�\�g�����l�J�̐l�`�ɍŏ��ɐG�ꂽ�G���s���z�t1970�N2�����k���E�̐l�`�l�́u�l�`�ƕ�炷�R�@�l�J�V�����\�\�Ƃ��ꂽ�ߋ�v�ɂ́A�O�̂̐l�`�i�x�����[���̐l�`�ʐ^���Q�Ƃ��Ė͑��������́A���̓��g��̖{�i�I�Ȃ��́A�}�O���b�g�ւ̈������߂Ă��������́k�ƂƂ��ɗ���Җ{�l�l�j��5�y�[�W�ɘj���ďЉ��Ă���i�ʐ^�B�e�͐Ό��ה��j�B
�@�@�\�\�g�����Ǝl�J�V����
�`���̏����̑��e���������̂́A���������̂ڂ邱�Ɛ��N�O�\�\�����炭2014�N���q�g�������ɂ�����G��r���������O��\�\���������낤�B�ʏ�̋L���ƈ���āA���������������̏ꍇ�A��悵�Ă���E�e����܂Œ����N����v����̂���ł���i�g���������������ɏo���̂Ȃ�A�Ғ��s�k�ߕS��t������ł���B�i�c�k�߂̑S��Ƃ���S����Ď�̉���������Ƃ����̂��A���̊Ȃɂ��Ė��Ȃ��悾�����ɈႢ�Ȃ��j�B�Ƃ���ŁA�l�������⎖�������͌l�S�W�̊̂ł���Ɠ����ɁA�ő�̓�ł�����B�s�F�V���F�S�W�k�S22���E�ʊ�2�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1993�`95�j��CD-ROM�̍�����t����v�������������ƕ������i�S���w�ǎ҂ւ̓��T�H�j�A���������ɂȂ����悤���B�O��A�s�ӓ��̒��̐��E�t��S�W�{�ōēǂ����Ƃ��A�l�������i���Ƃ��A�A���`���{���h�j�⎖�������i���Ƃ��A���e�j�j���Ȃ��̂��ǂ�قǎc�O�Ɏv�������Ƃ��B���҂��F�V�قǂ̒m�̒~�ς���������͕s�v���낤���A��l�����̐��E�ɕ�������̂ɕK�v���s���ȍH����A�����̍����ł���B���ꂩ�s�F�V���F�S�W�t�̍���������قǂ̖Ҏ҂͂��Ȃ����B�i2018�N8���j
�u�����A�g�����F�V�̕��@�����Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ����̂́u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�������ɂ����сq���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�������Ě���Ƃ���B���т��F�V���F�s�ӓ��̒��̐��E�t�i�y�ЁA1974�j�̊W�ɂ��ẮA���������������v�Ƃ́A�q�g�����Ƙa�c�F�b���邢���F�V���F�̎U���r�̌��т̕��������B����͂��̖��ʂ����ׂ��A�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�Ɓs�ӓ��̒��̐��E�t�i�y�ЁA1974�N10��1���j��ǂ݂���ׂĂ݂悤�B
 �@
�@
�s�����C�J�t1975�N9�����q���W���F�V���F ���[�g�s�A�̐��_�r�\���i���j�Ƌg�����q���e�j�i�O�m�[�����j�r�̖`�����J���i�����A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j�i�E�j
�܂����т̕W��ł���u���e�j�i�O�m�[�����j�v���F�V�̒����ɁA���̂悤�ɓo�ꂷ��B
�@���̌������͈�Z�O�O�N�A�p�����`���[���Y�ꐢ�̖��ɂ��A�{��t���̐H�̒��ł������W�����E�~�����Ƃ����҂��A�������H�̃W�����E�o�g�D�[���Ƌ����Ő��삵���B�ނ𐳓�\�ʑ̂ɐ����w�I�ȓ����v�ŁA���̊e�ʂ͔�����ɉ��܂���A���������Ɏ��e�j�m�O�m�[�����n��A���낢��ȑ����I���������肱�܂�Ă���B�i�����A�O���y�[�W�j
�×��̓����v�ɂ͑����̎�ނ��������邪�A�F�V�́u�k���O��N�Ɏ��Ɛ��肳���A�����I�̍ł����w�ȃt�����X�̘B���p�����Ɓl�t���J�l�����̒f������Ƃ���ɂ��A���̃G�f�B���o���̓�\�ʑ̂̓����v�́A�����̂ǂ̌`���Ƃ���v���Ȃ��B���^�Ǝv������͈̂���Ȃ��̂ł���B�������M���V�A�ɂ���������v�̌Ï̂ł���u�O�m���[���v�́A�ꌹ�I�ɃO�m�[�V�X�i�m���j��O�m�[���i�n���̐��j�Ɠ����ŁA�B���ꂽ�m�����`���Ӗ����邩��A���̌Ë`�ɑ����čl���Ă݂�Ȃ�A�G�f�B���o���̓����v�����̏ے��ł��邩�́A���̂����疾�炩�ɂȂ�ɂ������Ȃ��B���Ȃ킿�A�����v�̓�\�ʑ̂́A���ۓI�Ȏ��v�̌��p��L����ƂƂ��ɁA�܂��O�m�[�V�X�I�ȘB���p�̉��`�ɋ߂Â����߂́A�閧�̌�������킵�Ă�����̂ł���v�i���O�A�O��y�[�W�j�Ƒ����āA������ڂ炩�ɂ��Ă����B���Ȃ킿�S13�т����߂��s�ӓ��̒��̐��E�t�́A�`���q�̖��r�Ɏ������сq�v���g�����́r�̈�߂����A�����Œ��ꂽ���v�̃��`�[�t�͏I��肩��O�߂ɒu���ꂽ�A�{���̔����q���[�g�s�A�Ƃ��Ă̎��v�r�őS�ʓI�ɓW�J�����B�Ƃ��ɁA�ےJ�ˈ�́s�ӓ��̒��̐��E�t���s�����i1974�N10���j�́s�����V���t�́q���|���]�r�ň푁���{������肠�����B�u��]�Ƃ��݂�Ȃ����Ɓw�ɐ��x�w�����x��_���鍡�����̂���A���s�����ڂŌ��āA���R�Ɨm�w�ɂ������ނЂ˂���҂̑�\���F�V���F�Ƃ���v�i�s��̂����k�������Ɂl�t�����V���ЁA1986�N8��20���A��O��y�[�W�j�Ǝn�܂�ےJ�̎��]�́A�����̂قƂ�ǂ��q���[�g�s�A�Ƃ��Ă̎��v�r�ɔ�₵�Ă���B���Ȃ݂ɁA�����̋Ɩ���̕K�v���炢���Ă��A�܂����l�Ƃ��Ă̊S���炢���Ă��A�g�����e���̕��|���]�ɖڂ�ʂ��Ă������Ƃ͊m���ł���B
�@�F�V�́A���ʁA�����̔����Ƃ��Ă̓O�[�e���x���N�̈���p���������邾���ŁA����������Ƒ傫�ȉe�������Ɛ[���Ƃ���ŗ^�ւ����ԑ��u�̎��v�̔�������������Ă��ƁA���͂�Ă݂�܂��Ƃɂ��Ƃ��Ȃ��Ƃ��w�E����B�����āA���v�̔����҂Ɠ`�ւ���l�������������������Ă͂��肼�����������A�\�ꐢ�I�̃x�l�f�B�N�g�C���m�q���T�E�̃M���[�������ꂾ�Ƃ��Ӂu�t�����X�̈���_�ҁv�̐����Љ��̂����A���́u�����v�i�������킽���������j�̐��͔ނ������Ԃ������₤���B�@�B���v�ƃ��[�g�s�A�̃A�i���W�[���A�C���@��}��ɂ��Ă��ꂢ�ɐ������邩��ł���B�u�@�B���v�����яo���Ă���̂́A���͂⎩�R�̎��Ԃł͂Ȃ��i�����j���ۓI���_���I�Ȏ��Ԃł����Ȃ��v�B�Ƃ��낪�C���@�Ƃ��ӂ̂́u���ꂽ�A�܂��Ƀ��[�g�s�A�I���v�ŁA�������u���[�g�s�A�Ƃ͌����A���j�̖������ȗ���Ƃ͑Η��������̂ł���A�_���I�ł����āA�������u��������̂ł���B���[�g�s�A�̍\�����x���鏔�����́A���Ԃ̂悤�Ɍ݂��Ɋ��ݍ����āA�ł����ꍇ���Ă���B���[�g�s�A�Ƃ́A��{�̎��𒆐S�ɉ�]����@�B�̐��E�Ȃ̂ł���B�@�B���v�̒��ۓI�Ȏ��Ԃ́A���̂܂܃��[�g�s�A���E�̎��Ԃł����낤�v�Ƙb�͐i�ނ̂����A�����͂����ŁA�������ւw���[�g�s�A�x�̒��҃g�}�X�E���A�́A�ꎞ�͏C���@�ɂ͂��炤�Ƃ����A�Ƃ��A�n�̖тŐD���C���m�̃V���c�𒅂Ă�A�Ƃ��v�Е��ׁA���̂₤�ɋ֗~�I�Ȑl�Ԃ��C���@�̋K�����ɋy�ڂ����Ƃ��āA���̐V���̂₤�Ȍ`�̓��̋��Y���z�����Ƃ��ӂ̂͗����ɍ��Ă��A�Ɣ[�����䂭���Ƃ��炤�B�i�����A��O�O�`��O�l�y�[�W�j
�{��ɖ߂낤�B�g�����̕W��q���e�j�i�O�m�[�����j�r�������肳�ꂽ���͕s�������A�����́u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�͋g�������т̎��M���n�߂��������猈�肵�Ă����Ǝv�����B�g�����F�V�ɕ����鎍���s�ӓ��̒��̐��E�t����̈��p�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂�ƌ��߂��̂́A�����́q���Ƃ����r�̎��̈�߂ɋ�����������ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ킿�����ɂ́u�w�ӓ��̒��̐��E�x�́A���̓��e���猩�āA���̃������X�N�Ȕ������Ɩ��Â��Ă��悩�����낤���A���邢�͂܂��A�`�ێv�l�Ƃ��������D�Ƃ��������ϓ_����A�薼�����Ă��悩�����낤�Ǝv����悤�Ȏ�ނ̖{���B�G���u�����C�J�v�ɘA�ځi���a�l�\���N�ꌎ���l�\��N�ꌎ�܂Łj�̂������́A�b��I�Ɂu�~�N���R�X���X���v�Ƒ肵�Ă����B���̐_�̓~�N���R�X���X�ɏh��˂Ȃ�ʂƐM���Ă������A����ɉ������A���Ē����l��]�ˊ��̐��M�Ƃ̍D��ŗp�����Ƃ���́A���Ƃ������t����x���Ўg���Ă݂��������̂ł���v�i�s�ӓ��̒��̐��E�t�A��ܘZ�y�[�W�j�Ƃ���B���Ɂq���e�j�i�O�m�[�����j�r�̖{�����s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j���^�`�Ōf���悤�B���o�Ƃ̈ٓ��́A�܂��ُ̍�̖ʂł́u�@�v�i�ꊇ�ʁj�����p�����i�ꉺ�k�ꎚ�����l�j�������̂��i�V�c�L�k�������l�j�ɕς����ق��́A���p�����̉��s�ӏ������߂����炢�ŁA������̖ʂł́u�Q�v�́u�����Ă���v���u�����Ă���v�ɕς����̂ƁA�u�S�v��
�u�t�b�v���v
�k�킽�������̑ΏۂƂȂ蓾�Ȃ����́��E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�Ɩ��Ȃ���l
�k��������V�g�܂ł̂����鑶�݂Ɂ������̂Ȃ��Łl
�k�ϐg����\���������n���̐�����������l
�u�t�b�v���v
�Ƃ����ق��́A����̕ύX�͂Ȃ��B�{�e�ł́A�g�������F�V���F�̏͋���ǂ̂悤�ɝf���������������ׂ��A���ׂ�����������̎���̓T�����f����B���Ȃ킿�A�����i�s���̐����͘_�҂̕t�������C�i�[�j�������ċg���̎���Ƀ����N��A�����N����F�V�̌��T����ׂ��i�����ł��܂����悤�����A�Y������͋�����ŕ\�������j�B�ƍ��́s�ӓ��̒��̐��E�t���Łi�y�ЁA1974�N10��1���j�Ɍ������B���T�ł����F�V�̕��͂́A�g���̎���̏��Ԃł͂Ȃ��A�s�ӓ��̒��̐��E�t�ɓo�ꂷ�鏇�ԂƂ����B�Ȃ��A�����ɂ�����k���o����e�l�̈ٓ��̏ڍׂ��q�g�������W�s�T�t�����E�݁t�{���Z�فr������ꂽ���B
���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j��13-15�s�߁@�u�f���^�̓D�y�̂Ȃ��Ł^�Ԃ��炩����Ƃ����^�傢�Ȃ錴���̔��@�m���[�^�X�n�v
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N9�����k7��8���l��Z�l�`��Z���y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A5��79�s�B�g����1975�N8��31���t�̉i�c�k�߈����ȂŁu�ҏ��̉Ă������ŏI��\���̔����̍Ō�̖�A����Ƃ��Ԏ����o����悤�ɂȂ�܂����B�V��W�s��ʁt���ꑁ���A�n�ӈ�l�N��ʂ��Ē����Ȃ���A�����\�グ���ɂ������Ƃ�[������ђv���܂��B���x���̂���A�����C�J�㌎���q�a�F�\���[�g�s�A�̐��_�r�Ƃ������W���̌����������Ă��܂����B�����ċ������S�g�����Ղ��Ă�������ł��v�Ə����Ă���B
�@�@�@�@�F�V���F�̃~�N���R�X���X�@00
�@�@�@�P
�u�����͏��������@01
�͂��Ȃ���������ǂ��@02
������x�Ǝp�����킵�͂��Ȃ������@03
�����ďo�Ă���@04
�₢�Ȃ�@05
�����͂������܌`�Ԃ��@06
�Ȃ������v�@07
����͂Ƃ�킯���J�̂͂�������@08
�킽���͊ϔO�Ǝ��݂Ɓ@09
�˂Ɉ�v����@10
�q�̂Ƃ��Ă̏��������߂Ă���@11
���̓����ɂ͂����ΖȂ��߂��Ă���@12
�u�f���^�̓D�y�̂Ȃ����@13
�Ԃ��炩����Ƃ����@14
�傢�Ȃ錴���̔��@�m���[�^�X�n�v�@15
�����͌��t�傷�邱�Ƃ��Ȃ��@16
�@�@�@�Q
�u�킽���͗c�N����@�����[�E�~���N�Ƃ����~���N���@17
㣂̃��b�e���Ɂ@���̎q�������[�E�~���N��㣂�����@18
�Ă���p�̕`����Ă���v�@19
����㣂�����Ă��鉮�~�̏��̎q�߂Ȃ���@20
�킽���͐��vጂɜ���Ă����@21
�ǂ�₳�₦��ǂ����̂Ȃ�@22
�c�ɂ̓��X�@23
�̑����鏭���̂͂邩�Ȃ鎋�_�Ł@24
�킽�����⏬���@25
�u�����ƐA���̒��ԂɈʒu�����@26
�L�k�⍜��X�蒎�v�@27
�����ΊD���̐��E�ց@28
�ʉߋV�������݂�@29
�@�@�@�R
���t����������@30
�_�b��������Ƃ��������܂��@31
�߂������̂��@32
��C�����@33
�u�����{�X�̗�v�@34
�킽���̒����ł��@35
�u�����{�X�Ȃ���̂̎��̂��@�܂�ʼn_�������@36
�悤�ɂ����܂������Ƃ��ā@���Â����������v�@37
�킽���̍D���Ȗ��֕�d���铹���@38
�����u���I�@39
�u�A�p�b�`���̃V���[�}���́@�����{�X����]�������@40
�s���g�ɂȂ�����@������\������v�@41
���������@42
�����ɂ͎�ق����Y���Ȃ��@43
�u�����{�X�Ƃ͎q���̊ߋ�ȊO�̉����ł��Ȃ��v�@44
�f�p�ȚX�萺���Ă����@45
�u���̓Ɗy�v�@46
�����m��Ȃ��@47
�@�@�@�S
�킽���̖��݂铮���ނƂ́@48
�u�s�����m�t�G�j�c�N�X�n�@��p�b�m�E�j�R���j�X�n�@���厁m�T���}���h���n�v�@49
�Ƃ��ɒ��d������̂��@50
�u�t�b�v���v�@51
�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�Ɩ��Ȃ����@52
�����̂Ȃ����@53
�n���̐������������@54
�u�t�b�v���v�@55
�u������̕��̂̑��ւƋ߂Â���v�@56
�}��������@57
�T�b�^�̓���q�𑽐����܂����@58
�u�t�b�v���v�@59
��x��������Ƃɂ��Ă͓�x��邱�Ƃ͂Ȃ��@60
��x�s�Ȃ������Ƃɂ��Ă͓�x�s�Ȃ����Ƃ͂Ȃ��@61
�u�t�b�v���͕꒹�����ʂ��@62
���̎r�̂̏�ɂ̂����@63
�����̏ꏊ��T�����߂�v�@64
�̂Ȃ����@65
���̂Ȃ����@66
���͓y�̂Ȃ����\�\�@67
�@�@�@�T
�u�l�Ԃ̑z���͂́@���镨�̂����̑傫���̂܂��@68
���܂��Ă��邱�ƂɁ@�������Ȃ����̂̂悤�ł���v�@69
����Ɠ����Ɂ@70
�D���̖ڂ��g�債�@71
�������k��������@72
�킽�������l�ނƂ������̂́@73
�u�ŏ��̎��v�����@74
�ŏ��̃Z�R���h����яo���Ĉȗ��@75
����܂Ő_���s�N�ƍl�����Ă����@76
���R�̎����@77
�_�̎��Ԃ����ɐ₦�@78
���͂��x�ƕ������邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���v�@79
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����e�j�������v�̂���
�߉��@�Z�̃p�A�g�́A���₤�Njg������́w�T�t�����E�݁x���������܂ɂȂ��Ƃ��ӂ₤�Ȏ����I�Ȃ��Ƃ����āA����͓��ɋg������Ɛe�������A�g������̂���ǂ̎��W����q���āq�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�r�Ɠ���Ă݂���ł��B��34�s�߁@�u�����{�X�̗�v
�����@����͂Ȃ��Ȃ����������Ȃ��ł������B���̌`��肾���Ԃ悭�Ȃ��Ǝv�Ђ܂��B���������ł�����A�q�t�h�t�h�r���o�Ă���̂́A�l�����@���Ƃ̊ւ͂�i�l�����@���́u�ł̏����Ɛ���̕���v�ɁA�����R�I�ȗ͂������t�h�t�h�Ƃ��Ӓ����o�ė���j�����܂ЂƂ��߂�Ӗ��ł��A���������Ȃ��ł������B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j

���䕐�Y�̓���
�u���v�͍݂邩�H
�ŁA����͈��p�ł͂Ȃ��A�����ł���B���o�ɂ����Ď��Ɂu�@�v���o�ꂷ��q�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�i�q���C�X�E�L��������T�����@�r���\�������сj�̑�11�E12�s��
�u�����@���̎q�̉ԕق������������
�܂���オ���Ă�����@�����Ƃ���͂Ȃ����ˁm���n�v
�͈��p�̗��[�ł���A�g���͗��V�ɂ����і����Ɂu�����C�X�E�L�������q���̍��̃A���X�r���c��������v�Əo�T�𒐋L���Ă���B���̌�́q����ȓ~�̗��r�i�G�E6�j��A����́s�T�t�����E�݁t�̑O�̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�̎��߂��邱�ƂɂȂ�̂����\�\�q��q�r�i�F�E15�j�́u�u�֏��͂ǂ����Đ_��I�Ɂ^�������ɂ���̂��v�v�Ȃǂ��o�āA�q�}�_���E���C���̎q���r�i�G�E5�j��
�u������
���͎̂��̊��
���߂���I�v
��I�����̂悤�ɂ��āA�y���F��^�ڂ����q������܌�b�сr�i�G�E8�j���o�ꂷ��B�����܂ŗ�����Ƃ͈��b�痢�ŁA�u�@�v�����łȂ��q�@�r�i�R���ʁj���o�ꂵ�āA���p���������������s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t�́u����g�������v�܂ł͂����n�����ł���B�����A�����łǂ����Ă��G��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u����C�����Ɂv�̌��������q�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�̑��݂��B
�P�u�l�Ԃ̎��̏[������^���Ắ^�ǂ����Ă���قǁ^�y���e��Ȃ̂��H�v
�Q�u�����������������߁^����t�Ɉł�����߂��肷��v
�R�u�܌��̃X�t�B���N�X�v
�S�u���͊��S�Ȃ���̂����킦�Ĕ�ԁv
�T�u�ޏ��͖��m�̉���Ȃ��ނ�^��f���ŐV�̌����́v
�U�u���H�̂Ƃ�����͂��܂�v
�V�u�B���Ȋ��Ɖ����Ƃ́^��������㫂߂悤�Ƃ��Ă���v
�W�u�ق��ā^�����Ă����Ă��܂����v
�X�u�߂����̂̐��������v
�ȏ�́A����i���s�j�P�ʂł͂Ȃ��u�@�v�Ŋ���ꂽ�����݂̂����������̂����i�s���̑����̐����͍����ԍ��A�^�͌������s��\���j�A�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�Ƃ͕ʂ̈Ӗ��ŁA��a�ɏ[�������p�����傾�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�g���͂����ŁA���Ď���ւ����Ƃ���̑��҂̎��т���̈��p�A�����玍�����邱�Ƃ������Ă��Ă��邩��ł���B�o�T�̔������Ă�����́i��҂͂����������C���j���������
�P�͎��сq���Ăɏ[������l�Ԃ̎��r�̕W�肩��
�Q�́s�]���ɏ����t�̎U���q�h���I�ȓ����p�\�\���[�����Ɂr�̕���
�R�͎��сq�܌��̃X�t�B���N�X�r�̕W��
�S�͎��сqTEXTE EVANGELIQUE�r�̎��傩��
�T�͎��сq�������ɂ����鑾�z���ւ̌��J��r�̎��傩��
�U�́s�]���ɏ����t�̎U���q���H�̂Ƃ�����n�܂�r�̕W��
�V�͏o�T����
�W�͏o�T����
�X�͏o�T����
���҂̍�i�̕W������g�̎��т̎���Ƃ��Ĉ����Ƃ����_�ł́A�����Ɂu���]���l���V���^�[���́u�����ҁv�Ƃ�����ْ[�̘V�l��ƁB���p��́A���W����ژ^���ؗp�����B�v�ƒ������q�]���l���V���^�[���̑D�r�i�G�E24�j�\�\���o�́q�ǎ�̏��r�ɑ����A�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�ɐ旧���с\�\�����������A������͊G���i�i�̖M���j������A�����玍������Ƃ������ł�Ƃ�Ă��镪�������p�̊����x�������A��a�̍����Ƃǂ߂Ă��Ȃ��B
����A�s�ӓ��̒��̐��E�t���ēǂ��Ă݂Ďv�����Ƃ́A���̈��p�ɂ����p�A�ɂ����t���C�U�[�́s���}�сt��͂Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��i�����Ƃ��F�V�́q�M���V�A�̓Ɗy�r�̖`���Łu�A�h�j�X�Ձv�Ɋ֘A���ăt���C�U�[�Ɍ��y���Ă�����̂́A�u�A�h�j�X�̉��v��_�k�V��̈��ƌ��Ȃ����̃C�f�I���M�[�ɂ͋^���悵�Ă���j�B�{�e�̖`���Ɂu�g�����F�V�̕��@�����Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ����̂́u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�������ɂ����сq���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�������Ě���Ƃ���v�ƌf�����̂͂��̂��ƂŁA��@�I�ɂ͈��p�ƓT���̂��ꂪ�F�V�R���̂��̂ł������A���I�ɂ͋g�����Ƃ����u�킽���v�̋L����o���ɂƂǂ܂�Ȃ��A�W���I�ȁu�킽���v�́A�����Č����Ȃ疯���I�Ȃ���ւƑǂ�邫�������ƂȂ����̂��A�F�V���F���J�����������̃~�N���R�X���X�������̂ł͂Ȃ����B�g�����i�c�k�߂Ɉ��Ă����ȂŁu�����C�J�㌎���q�a�F�\���[�g�s�A�̐��_�r�Ƃ������W���̌����������āv�u�������S�g�����Ղ��Ă����v�ƋL�����̂́A�g�������̗��j�ɂ�����R�y���j�N�X�I�]��ɑ��闦���Ȋ����������悤�Ɏv����B�ł́A�g�����̎��сq���e�j�i�O�m�[�����j�r���F�V���F�̒����s�ӓ��̒��̐��E�t�͂ǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��B�ܒJ���m�͖{���́q���r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�����ЂƂA�{���́q�������X�N�ȁr���ʂɂ��Ă��t�����Ă������B�F�V���F�̑����̔������ӂ��̏����̂Ȃ��ł��A�����炭����قǔ����ӏ̖ڗ����̂͏��Ȃ��ɂ������Ȃ��B���܂����A�Ƃ��ɂ͓���̏����̋L�q�����̂܂ؗp���āA�����̂��Ƃ��W�J���Ă䂭�Ƃ�������ʂ�������B�����Ύw�E����Ă���悤�ɁA�����̖|��E���p���n�̕��ɗn������ł��܂��̂ł���B�k�c�c�l�F�V���F�̕��͂ɂ����Ό���ꂽ���̏����̗��p���邢�̓p���t���[�Y�̌X���́A���́q���̃������X�N�Ȕ������r�ł��傢�ɕ����������Ă���̂ł���B
�@�Ƃ͂����A�������݂̂������Ĕ�Ƃ���ɂ͂�����Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ瑼�҂̏����Ƃ̗Z�������́A�F�V���F�̑����ꏭ�Ȃ��ꎩ�o�I�ȕ��@�̂ЂƂł���A�������A�ނ̍�Ɛl�i�i���q���r�j�̍\���ɂ������K�R�ł��������ƍl�����邩�炾�B�ނ͂����Α��҂̂����Ɏ��Ȃ�����B���Ȃ̂����ɑ��҂�����B�ނ́q���r���̂����قȁq����q�r�ɂ����āA�ق��Ȃ�ʁq�ӓ��̒��̐��E�r�̂��Ƃ����̂����o����B���ʁA�����炱���܂��A�������ǎ҂ɂƂ��Ă��A���̏����́A����Α��҂̂��̂Ƃ͎v���Ȃ��悤�ȕs�v�c�Ȑe���������т錋�ʂƂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�Ƃ����ꖣ�͓I�Ȓ���ł͂���B�w�V�҃r�u���I�e�J�x�ł̊����ɂ����߂�ꂽ�������q�ɂ��u����v�ɂ��A���̂悤�Ȏw�E�����������Ƃ�z�N���Ă������B
�@�q�k�c�c�l�ǎ҂��鎄�����́A�~�V�F���E�����X�̕��̒��ɒ��҂̕����Ƃ߂��܂�A����ɂ��̒��҂̕����Ɏ������̗c���̌����Ƃ߂��܂�Ă���Ƃ���῝�ɏP���Ȃ���A�ǂݐi�݁A���ɂ͖{���S�̂̑��l�ȃ��`�[�t���A���̈ꕶ�ɓ���q�̂悤�ɛƂ߂��܂�Ă���̂ɋC�Â��ł��낤�B���F�������w�����������A�����ĉ������뉀�����v���B�r�i�s�F�V���F�S�W�k��13���l�t�A�͏o���[�V�ЁA1994�N6��15���A�Z��Z�`�Z���y�[�W�j
���̋g�������̃X���X�Ŗ{���ȊO����Ƃ�ꂽ��Ȃ��̂��u�����v�֘A�������̂́A���C�X�E�L�����X�́s�A���X�t���̗̂쌱�����炽�����������Ƃ̏؍����낤�B�g���͓�V�����{���́u�����ӏv�ɂȂ��������ŁA�t���C�U�[�s���}�сt�̐��E�ɂ��قǂ̒�R�Ȃ������Ă������Ƃ��ł����B���̉�����Ɂs��ʁt�̐��E���W�J�������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�Ƃ���Œ������q�͌�N�A�{���́q�����뉀杁r�i�g���͎��Ɉ��p���Ă��Ȃ��j�ɓo�ꂷ��C�G�Y�X��̓`���t�ł���C�^���A�l�̉�Ƃł���l������l���ɂ��āA���я����s�J�X�e�B���I�[�l�̒�t�i���Y�t�H�A1997�j���������B�W���P�b�g�E�\���E���Ԃ��E�{���ɓ��ʼn�s���t�����m�O�}�t�̂����q�C�哰�r�̓�����k�̎l�ʂ�z�����A�e�n�M�`�̑����ɂȂ��������{�ł���B
 �@
�@
�g�������W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�N9��30���j�̃W���P�b�g�k���Ҏ����l���F�V���F�s�ӓ��̒��̐��E�t�i�y�ЁA1974�N10��1���j�̃W���P�b�g�k���Ҏ����l�i���j�Ɓs�T�t�����E�݁t�Ɓs�ӓ��̒��̐��E�t�̉��t�i�E�j
�D���@�����A�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�����^�����s�T�t�����E�݁t�Ɠ����̓T���ƂȂ����s�ӓ��̒��̐��E�t�̎d�l�ɂ��ĐG��邱�ƂŁA�{�e�̌��тƂ��悤�B�s�g���������t�Ɍf�����s�T�t�����E�݁t�����̋L�ڂɍ��킹�ās�ӓ��̒��̐��E�t�̂���������A�����Ȃ�B
���W�s�T�t�����E�݁t�����@��㎵�Z�N�㌎�O�Z���@�y�Ёi�����s���c��_�c�_�ے���̓��@���s�Ґ����N�Y�j���@�艿�ꔪ�Z�Z�~�@���Z�~��l��@�����l�Ł@�㐻�۔w�z���@�W���P�b�g�i�ЎR����u����v1973. ���ґ��j�@�g�����@�с@����ЎR���@�{���V���V���ȁ@10�|��l�s�g���Ł@��������@���{������
�s�ӓ��̒��̐��E�t�����@��㎵�l�N��Z������@�y�Ёi�����s���c�搼�_�c��̎O�̈�O�@���s�Ґ����N�Y�j���@�艿��l�Z�Z�~�@���Z�~��l��@����Z��Ł@�㐻�۔w�N���X���@�W���P�b�g�k����N���W�b�g�Ȃ��l�@�с@�r�j�[���J�o�[�@�{���V���V���ȁ@9�|�l�O���l�߈ꔪ�s�g���Ł@��������@���{������
�����o�ŎЂ́i�����炭�j�����S���ҁi�s�ӓ��̒��̐��E�t�́q���Ƃ����r�ɂ͏o�ŕ��̎O�֗����\�\1999�N3��5���A�]���o���Ŏ����A55�B�������q�Ɏ��сq����Ȃ�A�ђ��\�\�O�֗�������𓉂ށr�i���o�F�s���w�t1999�N5�����A�Ę^�F�s���㎍�蒟�t1999�N12�����j������\�\�ƍ������q�ւ̎ӎ���������j����|�����{�����玗�Ă���͓̂��R��������Ȃ����A�g�������߂Đy�Ђ��玍�W���o�����Ƃ����Ƃ��A���̐��Ɂs�ӓ��̒��̐��E�t�����������Ƃ́i�������ŗL�͂̂���ł��������Ƃ́j�A�قƂ�Nj^���Ȃ��悤�Ɏv����B�s�ӓ��̒��̐��E�t�̂`�T���i�����j�E�㐻�۔w�N���X���E�W���P�b�g�E�сE�r�j�[���J�o�[�ɑ���ɁA�s�T�t�����E�݁t�̂`�T���ό^�E�㐻�۔w�z���E�W���P�b�g�E�g�����E�сB�d�l���ߐڂ��Ă���̂����邱�ƂȂ���A�����Ƃ�������������A���{���������Ђł���̂́A���R�Ƃ����ɂ͂ł������Ă��Ȃ����낤���B�{���p���i�N���[���n�̏��Зp���j�̖����͂킩��Ȃ��B�F�V�{�̕����A�g�����W����1�����܂ł͂����Ȃ������������āA���ʂ����t�ł���B���߂ɁA�����ɋ��ʂ���u�s�����m�t�G�j�c�N�X�n�v�u��p�b�m�E�j�R���j�X�n�v�u���厁m�T���}���h���n�v�̃��r���r����Ɓi�����̃T�C�Y��4.5�|��5�|�ŁA�����ɈقȂ���̂́j�A�F�V�{�̕���������C���ł���B�g�������W�̖{���Ń��r���g���͂��߂��̂́s�T�t�����E�݁t����ŁA�����܂őz�肵�Ė{���p������̂��͂킩��Ȃ����A�Ȃ��Ȃ������Ȏd�オ��ɂȂ��Ă���B��r�I�傫�ȁi�{���Ɠ������炢�̃T�C�Y�́j�����ł������Ƒg���t�͐y�Ђ̓`�������A�F�V�{�Ɍ�����u���@�ҁ\�\�F�V���F�v�Ȃǂ̓�{�_�[�V�͋g���̉������Ƃ���ŁA�u���@�ҁ@�g���@���v�ƂȂ��Ă���B
�k�NjL�l
���p�]�_�ƂŐ��c�J���p�يْ��ł�����䒉�N�̍u����^�����q�F�V���F�̑z���̉�L�r�̖`���u�F�V����̒��Ԃ����v�ɁA���̂悤�Ȉ�߂�����B
�@�F�V���F����̎��͂ɂ͂�����w�҂����������āA���̕��w�҂̒��ɂ͑傢�Ɍ[�����ꂽ�O���R�I�v��A���邢�͐�㕶�w������ł͌����ĊO���킯�ɂ����Ȃ��D�ꂽ���d�����������w�҂��������������܂��B���͉��߂Ď����̏��˂����F�V����́w�Έ��I��Ƙ_�x�𐔓��O�Ɏ��o���āA�F�V����̊S�̂����Ƃ��m���߂Ă݂܂����B����́A��\�l���炢�̍�Ƃ̍�i�_�Ȃ����l���_�A���邢�͎����Ƃ̊ւ��ɂ��ď������{�ł��B�ΐ�~�i�ꔪ���\��㔪���j�A�k�c�c�l���ꂩ�璆��p�v�i�����\��O�j�⎍�l�̋g�����i�����\��Z�j����������Ă���B
�@�]�k�ł����A���́A�g��������Ƃ͐��O�ɖ��ȂƂ���łƂ��ǂ�������邱�Ƃ�����܂����B�ƂĂ��D�����l�Ȃ�ł����ǁA��̖��悤�Ȑ��łЂ��Ђ���������A���[���A�̃Z���X�̂���l�ł����ˁB����Ƃ����̎t���̓y�����i���Z�l�\���Z�j���A���̐l�́u�m���v�Ƃ���������ɍ����]�����āA���s����Ă����ɂ��̎��W���Ă����ƌ����̂ŁA�������A��̓d�Ԃ̒��œǂ�ŏՌ������v���o������܂��B�}�����[�ɂ��߂��Ă��āA���ʂ̗F�l�ɒ����Ƃ̔ѓc�P���i����O�\��Z�Z�Z�j�����܂����B�i���쏺���ҁs�F�V���F�̋L���t�͏o���[�V�ЁA2018�N4��30���A���O�`���܃y�[�W�j
���͔ӔN�̋g�����Ɖ��x���ʒk����@��Ɍb�܂ꂽ���A�u���[���A�̃Z���X�̂���l�v���Ɗ����邱�Ƃ͂����Ă��A�g�����u��̖��悤�Ȑ��łЂ��Ђ��������v�Ƃ����L�����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��g���̐l�ƂȂ�����䒉�N�ɂ悤�Ɍ�����l���͂��ĂȂ������B�Ђ��Ђ����Ō�鎍�l�A���p�W�҂Ƃ����A���Ȃǂ������ɑ���C���Ɏw��������̂����i�c�O�Ȃ��ƂɁA�����撊P�ɐڂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������j�A���܂͋^����o����ɂƂǂ߂悤�B
�g�����́s�����C�J�t1971�N4�����́q��ꔭ������r�̗��i�q�ҏW��L�r�E���t�̏㕔�ɐݒu���ꂽ�A�M�҂������ւ���L���j�Ɂq�����������ār�\�����B�����A�g����51�B�O�N��1970�N�ɂ�2���Ɂs�g�������W�k���y�Łl�t�i�v���Ёj�����s�������̂́A3���Ɏ��сq�ቹ�r�i�F�E14�j�\�����ق��́A�s�o��t11�����Ɂq�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�������肾�������A1971�N�ɂ�9���Ɂq�p���n���鋛No.2�r�Ƃ��Ď��W�s�t�́t�i���쏑�[�A����300���j�����s�������̂́A�s�Ս��t3�����Ɂq�k�͌����f�j��W�l�s���t������r���A4���ɂ��́q�����������ār���A9���́s��ԁt�i�H�̍��j�Ɂq�i�c�k�߂Ƃ̏o��\�\�k�ߋ叴�r���A10���ɏo�ł��ꂽ�s����������W�k���㎍���Ɂl�t�i�v���Ёj�Ɂq�o��r���������ق��A�߂ڂ������̂Ƃ����s�����C�J�t12�����́q�u�����v�Ƃ����G�r���炢�������B����̕M��܂��āA��������s���A�`������G���ɔo��W�̕��͂��ۂۂ����Ă����A����Ɋւ��邩����ᒲ�Ȏ����������Ƃ����Ă悩�낤�B
�����������āb�g����
�@�\�\�~�\�[�i���̌ď́j�A�������������Ȃ�
�@�ˑR�Ȃ��]���������B�Ȃ͐����A��E���E�������炢�Ȃ̂ŁA���͋����B
�@�\�\�~�\�[�A�ǂ�Ȓ����悢���A�]���Ă݂Ȃ�I
�@�\�\�傫���̂��������A�L���炢�̂��B�L�{�[�V�C���R���A�L�o�^���I�E���͂ǂ����낤�H
�@�\�\�~�\�[�A�����I�E���́A���̖{���݂�ƁA���A���\�N�������A�����l�̎���������Â����A��ɑ����ׂ��q�����Ȃ���
�@�\�\�C������邢�@����ł������
�@�\�\�~�\�[�A�ނ��������̍�}�̃E�C���h�ɂ����L���C�i�����ق���
�@�\�N���炢�O�A��}�S�ݓX�̃E�C���h�����ς��ɁA�����ȏ���������Ă����̂�z���o���B�������������G�v�����p�ŁA���┯�ɐ≩�F�̏������Ƃ܂点�A���Ȃ₩�Ȏ肩��a��^���Ă���̂����̊G�̂悤�Ɍ������B
�@�\�\�~�\�[�A�L�̈�������߂������A���������ɂ䂱����
�@���ꂩ�珬�����A�f�p�[�g�������낵���T������āA��l�̒��̐����\�\�L�G���N���{�^���Ƃ������Ȉ�Ԃ����B�Z�L�Z�C�C���R����^�ŁA���͔Z���ŁA���т��I�����W�I���F�A�S�̂��������ŁA�����ڂ𔒂��ւ��Ƃ�܂��āA�ߋ�̂悤�ȏ����B�J���t�H���j�A�ł��̏t���܂ꂽ�炵���B
�@�\�\�~�\�[�A�����A�{���[�R���A�a���A�a�A�ǂ���������Ă������낢
�@�\�\�~�\�[�A�L�G���N���{�^���̓J���C�C�ȁA�J���C�C�ȁA�J���C�C�ȁA�J���C�C��
�@�H�߂��A�C���̕ω����A�a�C���A�Ȃ̖��Ղ��̃J���C�C�Ȃ̎����ŁA��H�������B�Ȃ͟����ށB
�@�\�\�����Ƃ͂������t��
�@���������y�b�g��҂��ٌ������ɁA��Ԃ̈�H�����ʂƁA�c������H�����Ȃ炸���ǂ��Ƃ����B���ꂩ��ꃕ���ڂɐ������H�������B�Ō�܂ł����ꂪ���Ă��s���������B�l���Ă��݂Ȃ��������}���`�b�N�Ȑ����̐��E�B�����Ȃ��A�����₩�ł͂��邪�A�u�������v���������m��Ȃ��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z�`�O��y�[�W�j
�q��ꔭ������r�́A�����s�����C�J�t�\�\�A���L���f�X�̌��t�Ƃ����gEureka�i�G�E���J�j�h�\�\�ɂ��ȂށB���炩���߃e�[�}���^�����Ă������z�Ȃ킯�ŁA���߂�ꂽ�����i��800���j�̂Ȃ��łǂ��W�J���邩�͕��M�Ƃ̘r�̌����ǂ���ł���B�����̔L�̈�����Ƃ����̂́A1968�N���A�v�Ȃ��k�����̌��c�Z���ڍ���t��̃}���V�����ɓ]������ہA�����Ă����V�����L�̃f�b�J�i���j���ǂ������ɕ���Ď��H���A�G���i�āj���܂��Ȃ������Ƃ��w���B�Ō�̒i���́A�L�G���N���{�^���̔Ԃ̘b�ȑO�ɃV�����L�̎��Y�̍Ŋ���z�肷��ƁA�v�Ȃ̒Q�����ЂƂ���g�ɐ��ށB���͒������������Ƃ��Ȃ��A���̐��Ԃɏڂ����킯�ł��Ȃ��B�����������Œ����������ς�ƁA���������߂��Ă݂����Ȃ�C�����͂킩��B���̕��e���炵���Β��ɂȂ��炦��ꂽ�g�����ɂ��Ă݂�A����L�Ƃ͂܂�������Ӗ��ŁA�ł��e���݂��������������������̏����������̂ł͂���܂����B
 �@
�@ �@
�@
������@�u�L�{�E�V�C���R�i���X�q�_�F�j�v�̓C���R�ȃ{�E�V�C���R���A�u�L�o�^���I�E���i���m�U�_���j�v�̓I�E���ȃL�o�^�����A�u�L�G���N���{�^���C���R�i���ݍ����O�q�_�F�j�v�̓C���R�ȃ{�^���C���R��
�L�G���N���{�^���C���R�́u�^���U�j�A�����Y�n�Ƃ��鏬�^�C���R�ł��B���{�ɂ��A������A������ʓI�ȕi��Ƃ��Ēm���Ă��܂��B��̑N�₩�ȉ��F�ɑ��čA�����͕��ʂ����Ԃ������̂悤�ɍ����A�N�`�o�V�̓I�����W�F�ł��B���ɂ͔Z���ɉ��F���A�����ɂ͒W���ɉ��F���������Ă��܂��B�������łW�ƁA��x�ɑ����̗����Y�݂܂��B�������u���u�o�[�h�v�̈��ł��郋���R�V�{�^���C���R����������n��ł́A���R��z�����������܂��v�i���N��ďC�E�J���В��s���E�̃C���R�\�\�P�O�O��̂��킢���������t���g���Y�A2016�N10��31���A�O��y�[�W�j�B�g���͂��̌�A�q�����_���r�i���o�́s�����V���i�[���j�t1973�N6��2���j�Ɓq�킪���_���r�i���o�́s�Q���t1975�N2�����j�Ń_���}�C���R�̃_���̂��Ƃ𐏑z�ɏ����Ă���B�s���E�̃C���R�t�͂�������̃C���R�̃J���[�ʐ^�����߂��������{�����A�_���}�C���R�́u�ڂƖڂ̊ԂȂǁA��ɂ��鍕���͗l������܂̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��A���{���̗R���ɁB�p�ꖼ�ł́u���Ђ��C���R�kMoustache Parakeet�l�v�Ƃ����Ӗ����t�����Ă��܂��B�D��S�����Ől�Ȃ����A�Ќ�I�Ȑ��i�̎�����B�����̂ŁA�l�̌��t�������Ɋo���A���ɂ�����ׂ肵�Ă���܂��B�����ɂ͋����A��v�ŁA���炵�₷���C���R�ł��B�������A�Ƃ��ɑ傫�Ȑ����邱�Ƃ�����̂ŁA�ߗׂɖ��f��������Ȃ��悤����ꏊ��I�ԕK�v������܂��v�i�����A�Z��y�[�W�j�Ƃ���B�q�����������ār�Ɏn�܂邱���3�т̐��z�ɂ��A�g���������������ɂ́A�_���}�C���R�ȑO�ɃL�G���N���{�^���A�\�o���A�щؒ�������B���z�i��������ɂ܂Łj�ɂ��̖��O���L����Ă���̂́A�_���}�C���R�̃_�������ł���B���̎ʐ^�ŋg���̌��ɍڂ��Ă���̂��_�����낤�B
 �@
�@
�C���R�ȃz���Z�C�C���R�����u�_���}�C���R�i�B���_�F�j�v�i���j�Ƌ���ˈ�j�k�ʐ^�l�q�O���r�A �g�����̊�r�i�s�����C�J�t1973�N9�����A���Z�y�[�W�j�i�E�j
�����q�g�������̒��̖��O�r�Ŏw�E�������Ƃ����A�g���̎��M�������тɃ_���}�C���R�͓o�ꂵ�Ȃ��B����ǂ��납�C���R��I�E���̗ނ́q�����r�i�A�E5�j���_�����o�ꂷ�邾�����i�u�������_���̋������̚{�́v�j�B�����̐��z�Ɋւ��邩����A�u������̏��i���A�����̌o�R��Ԃ����A���픽�f�̋L�^�ɂ����Ȃ��v�i�q���Ƃ����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z��y�[�W�j�́A�z�ʂǂ���Ƃ��Ă悢�悤���B
�g�����͐��O�A12���̒P�s���W�����s�����B���Ȃ킿�A
�@���̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j
�A���W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j
�B���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j
�C���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j
�D���W�s�a���`�t�i����ɁA1962�N9��9���j
�E���W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�N7��22���j
�F���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�N10��20���j
�G���W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�N9��30���j
�H���W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�N10��30���j
�I�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�N5��9���j
�J���W�s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j
�K���W�s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�N11��25���j
�ł���B���̂�������ɂ͋g���̎������A�B���܂߂Čv4�������ƔłƂ������ƂɂȂ�B���������ďo�ŎЂ��犧�s�����̂́A�c���8���\�\���惆���C�J��1���A�v���Ђ�1���A���쏑�[��1���A�y�Ђ�2���A����R�c��3���\�\�ƂȂ�B���惆���C�J�͈ɒB���v���N�������Ō��ŁA�v���Ђ͈ɒB����O���������c�v�Y���N�������������́A���쏑�[�͓��쐬�ꂪ�N����������{���S�́A�y�Ђ͈ɒB�̂��ƂŎ����s�����C�J�t�̕ҏW��⍲���������N�Y���N�������o�ŎЂł���B�����č���Ƃ肠���鏑���낵�ɂ��p���q���q�r��1973�N����78�N�ɂ����Ċ��s�����̂��A�R�c�k��̋N����������R�c���i���݂̑�\�҂͗�؈ꖯ�j�B��̈ꗗ����킩��悤�ɁA1970�N��܂ł̋g���́A���d�ւ̓o����㉟�������ɒB���v�Ƃ��̎��ӂ̏o�Ől�����Ƃ̔Z���ȊW�̂��ƂɁA���W�����s���Ă����i�s�a���`�t�̔��s�͑���ɂ����A�����͎v���Ёj�B�s�_��I�Ȏ���̎��t�̓��쏑�[�́A����ȑO�A�q�p���n���鋛No.2�r�Ƃ��ās�t�́t�i1971�N9��1���j��300������ōĊ����Ă���i�p���̕ҏW�͒߉��P�v�Ɛ��c�����j�B�g���ɂ��Ă݂������ݔq���Ƃ���������������������Ȃ����A�剪�M�����C���A�y���F�A�ѓ��k��Ƃ������q�p���n���鋛�r�̒��҂����̃��C���i�b�v�ɂ��S�����ꂽ��������Ȃ��B����Ƃ悭�����o�܂��A����R�c�Ƃ̏ꍇ�A�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�Ƃ���ȑO�ɏo�����s�ٗ�Ձt�i1974�N4��25���j�ɂ����Č�����B�������̂܂��ɁA�q���q�r�S�̂̃��C���i�b�v���m�F���Ă������B�]�k�����A��L�G����J�܂ł�4���W�́A�n�ӈ�l�̏���g�Ԏɂ��h���ǁi�i�c�k�߂̌���{�Ȃǂ���|�����j��������{�����s�^��������Ă���B
![����R�c���s�̏����낵�ɂ��p���q���q�r�̂P�F����C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���t�i1973�N2��25���k�����F1979�N11��10���l�j�A�Q�F�V��ޓ�Y�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�i1973�N10��10���j�A�R�F�g�����s�ٗ�Ձt�i1974�N4��25���j�A�S�F�ѓ��k��s�S��������܂Łt�i1974�N8��25���j�A�T�F�O�D�L��Y�s�V���Ȉ�t�t�i1974�N11��25���j�A�U�F��B�Ɓ{���q���s���b�X���E�v���O�����t�i1978�N7��10���j�A�V�F�����r�Y�s���l�`���t�i1978�N7��10���j�A�W�F�J��r���Y�s����W�t�i1978�N9��20���j�́A��������](image/soshi_series_1.jpg)
����R�c���s�̏����낵�ɂ��p���q���q�r�̂P�F����C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���t�i1973�N2��25���k�����F1979�N11��10���l�j�A�Q�F�V��ޓ�Y�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�i1973�N10��10���j�A�R�F�g�����s�ٗ�Ձt�i1974�N4��25���j�A�S�F�ѓ��k��s�S��������܂Łt�i1974�N8��25���j�A�T�F�O�D�L��Y�s�V���Ȉ�t�t�i1974�N11��25���j�A�U�F��B�Ɓ{���q���s���b�X���E�v���O�����t�i1978�N7��10���j�A�V�F�����r�Y�s���l�`���t�i1978�N7��10���j�A�W�F�J��r���Y�s����W�t�i1978�N9��20���j�́A��������
�E�q���q�P�r����C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���t�i1973�N2��25���A�̂��s�R���N�V��������C��3�\�\�}���Z���E�f���V�����^���Ɣ��p�̎��́^鍎q��7�̖ځ^���b���t�A�݂������[�A1996�Ɏ��^�j�A�ʂ�������������B
�E�q���q�Q�r�V��ޓ�Y�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�i1973�N10��10���A�̂��s���E�V��ޓ�Y���W�k���㎍����112�l�t�A�v���ЁA1993�Ɏ��^�j�A�ʂɋg����������������������B
�E�q���q�R�r�g�����s�ٗ�Ձt�i1974�N4��25���A�̂����W�s�T�t�����E�݁t�A�y�ЁA1976�Ɏ��^�j�A�ʂɋg����������������������B
�E�q���q�S�r�ѓ��k��s�S��������܂Łt�i1974�N8��25���j
�E�q���q�T�r�O�D�L��Y�s�V���Ȉ�t�t�i1974�N11��25���j
�E�q���q�U�r��B�Ɓ{���q���s���b�X���E�v���O�����t�i1978�N7��10���j
�E�q���q�V�r�����r�Y�s���l�`���t�i1978�N7��10���j
�E�q���q�W�r�J��r���Y�s����W�t�i1978�N9��20���j
�ȑO�ɂ����������Ƃ����邪�A2009�N11��28���̃A�g���G��10���N�L�O�W�q�C���f�B�y���f���g�E�v���X�̓W�J�r�i�a�J�̃|�X�^�[�n�E�X�M�������[���J��j�ɂ�����R�c�k��E�ԓޔ��q�E�S�~��Y�̎O���ɂ��M�������[�g�[�N�q����C���̖{�Ə���R�c�̍ŏ���10�N�r�̉��œ��ʓW�����ꂽ�s���ƍ��Ɓt�̌��e�i�y���M�F�����j�͎��ɋ����[�����̂������B�y���̌��e�p���uLIFE C 155 20�~20�v17���ɂ킽�������M�̈�����e�p���e�ŁA1���ߖ`���Ɂu���̑g�ݕ��A���q�̑S�̂̍\���ɂ��čl�v�Ƃ��A�ߕ\���̃A���r�A�����ɑ��āu�ȉ��R�m�����n��r�I��L�i�C�^���b�N�f�@�ʒu�n�{���g�������G���J�H�v�Ƃ������g�łɊւ��郁�����L����Ă��āA������q���q�r�̑����Ɩ{���g�ɐS���ӂ����l�q���܂��܂��Ɠ`����Ă���B�����e�̖`���ɂ́A���M�����Łi�u���q�v�ł͂Ȃ��j�u�����P�v�Ƃ���B�Ȃ��A�g���͑���C���ɕ��������сq�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�̎���ɁA�����̏����u���ƍ��Ɓv�����p���Ă���B
���āq���q�r�̊��s�������Ă���Ɩʔ������ƂɋC���t���B�q���q�P�r�͑p���̔��Ď҂ł���A�����҂ł�����������w����Ă��āA�q���q�Q�r�̓V��i�Ɓq���q�R�r�̋g���A�q���q�S�r�̔ѓ��A�q���q�T�r�̎O�D�j�͂�������{�ɑn�삵���ɈႢ�Ȃ��B�V����G���Ɏ��������̂Ƃ͈قȂ�A���q���ǂ̂悤�ȑ̍قȂ̂��́A���̏������낵�V���[�Y�̍ŏd�v���ڂ������͂����B�{���̖{�̂͐ܒ������̍��q�����i�l���T�q���q���{�����E�݂܂��Ắi56�j�r�ɂ́u����C�����A���h���E�u���h�����炨����ꂽ��܂�́u���W�v�����̂������̃A�C�f�B�A�̂��ƂŁA�u���q�v�̖��͐��܂�i���q�j�̎R�c�k�k��l����ɂ��₩���ĂƂ�����������A�ƁA���Ȃ���R�c�����b���ɂȂ����v�Ƃ���j�A���̏����я�̕�̗��ʂɂ́q���q���s�ē��r�Ƃ����L�����ڂ��Ă���B���F�̕�́q���q�P�r����q���q�T�r�܂łƁA����́q���q�U�r����q���q�W�r�܂łƂł͂��̕\���̃X�^�C�����ς���Ă���i���҂̊Ԃɂ�4�N�߂��Ό������݂��Ă���j�B��������ɑO���X�^�C���ƌ���X�^�C���ƌĂڂ��B��i�@�\�I�ɂ͕\���������̓W���P�b�g�Ɖ��t���L���ɑ�������j�ɍ����̕\���͂Ȃ����A�苖�́q���q�P�r�͑����i1979�N11��10���j�̍ۂɌ���X�^�C�����Ƃ������̂炵���A�������̏�Ԃ��m�F�ł��Ȃ��B�ȉ��A�Q������W���܂ł́q���q���s�ē��r��E����B�Ȃ��A�^��͉��s�ӏ���\���B
�E�q���q�Q�r�V��ޓ�Y�F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^���ȉ����s�\��@�g�������@�剪�M���@����N�v���@�����⍆�@�g��������
�E�q���q�R�r�g�����F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~
�E�q���q�S�r�ѓ��k��F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~�^�S�@�ѓ��k��@�S��������܂Ł@�R�U�O�~
�E�q���q�T�r�O�D�L��Y�F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~�^�S�@�ѓ��k��@�S��������܂Ł@�R�U�O�~�^�T�@�O�D�L��Y�@�V���Ȉ�t�@�R�U�O�~
�E�q���q�U�r��B�Ɓ{���q���F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~�^�S�@�ѓ��k��@�S��������܂Ł@�R�U�O�~�^�T�@�O�D�L��Y�@�V���Ȉ�t�@�R�U�O�~�^�U�@��B�Ɓ{���q���@���b�X���E�v���O�����@�S�T�O�~�^�V�@�����r�Y�@���l�`���@�S�T�O�~�^�W�@���X�؊��Y�@�ߊ��^�X�@�g�������^10�@�F�V�F��^11�@�剪�M
�E�q���q�V�r�����r�Y�F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~�^�S�@�ѓ��k��@�S��������܂Ł@�R�U�O�~�^�T�@�O�D�L��Y�@�V���Ȉ�t�@�R�U�O�~�^�U�@��B�Ɓ{���q���@���b�X���E�v���O�����@�S�T�O�~�^�V�@�����r�Y�@���l�`���@�S�T�O�~�^�W�@���X�؊��Y�@�ߊ��^�X�@�g�������^10�@�F�V�F��^11�@�剪�M
�E�q���q�W�r�J��r���Y�F�P�@����C���@���ƍ��� ���^���@�R�O�O�~�^�Q�@�V��ޓ�Y�@�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁@�R�O�O�~�^�R�@�g�����@�ٗ�Ձ@�R�U�O�~�^�S�@�ѓ��k��@�S��������܂Ł@�R�U�O�~�^�T�@�O�D�L��Y�@�V���Ȉ�t�@�R�U�O�~�^�U�@��B�Ɓ{���q���@���b�X���E�v���O�����@�S�T�O�~�^�V�@�����r�Y�@���l�`���@�S�T�O�~�^�W�@�J��r���Y�@����W�@�S�T�O�~�^���X�؊��Y�@�ߊ��^�g�������^�F�V�F��^�剪�M
����Ȃ܂łɈ��p�����̂́A�q���q���s�ē��r�̈ڂ肩��������ɂ��A�V���[�Y���̂̊��s�������ɂ܂܂Ȃ�Ȃ����g�ɂ܂���邩��ŁA�q���q�Q�r�ɂ��������s�\��́u�g�������@�剪�M���@����N�v���@�����⍆�@�g���������v�̂����A���ۂɏo���̂͋g���̍������ł���B�������s�́q���q�U�r�Ɓq���q�V�r�Łu�ߊ��v�Ƃ���Ă������X�؊��Y�̍��͌��ǁA���s���ꂸ�A2������ɂ͂��̍��X��ǂ������āA����܂Ń��C���i�b�v�̂ǂ��ɂ����O�̂Ȃ������J��r���Y�̍������s����Ă���B�������āA�q���q���s�ē��r�ŗ\������Ă��ē��̖ڂ����Ȃ������̂́A�剪�M�E����N�v�E������E�g�������E���X�؊��Y�E�F�V�F��̊e���Ƃ������ƂɂȂ�B�g���́s�ٗ�Ձt���\��1974�N�����A�̂��Ɏ��W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�Ƃ��Ă܂Ƃ܂邱�ƂɂȂ鏔����������ł��āA����͂܂��ɐ�D���������B����ɂ��Ă��A�S8��161�s�Ƃ������ڂ��������낷�̂͌����ĊȒP�ł͂Ȃ��������낤�B��1�тƂ͂����A������Ƃ������Ђł���B���͂����A�q���q�r�̋g�������̊�悪�������ꂽ���Ƃ���Ԃ������B
�q���q�r�V���[�Y�����������Ȃ������̂ɂ́A�������������l������B������s���ł͂Ȃ����߁A�����̓����Ǘ������܂������Ȃ������B�������q�̂��߁A�̘H�⏑�X�̒I���m�ۂ��Â炩�����B�ቿ�i�̕��y�łƍ����i�̓�������ł̈ʒu�Â����͂����肵�Ȃ������B���B���Ȃ킿�A�i�s�E�̔��E�����Ǘ���̏����B
�������Ȃɂ����A��̐V�K������������i�Ɍb�܂�Ȃ��������Ƃ��������邾�낤�B����́A���т�U����i�Ƃ��Ė��͂��R�����������Ƃ��Ӗ����Ȃ��B�����q�ٗ�Ձr�́A�s�T�t�����E�݁t�œǂނق����q���q�r�̈�тƂ��ēǂނ�肶�����薡�ǂł��邱�Ƃ��܂��m���Ȃ̂ł���B��Ƃ��Ă̋H�������o���ɂ́A����W�Ƃ������������肦�����A����C���̍\�z�ɂ��̑I�����͂Ȃ������̂��낤�B�q���q�r�̐g�y���Ɣ��p��i�͗����������ɂȂ��B�������A�O�D�L��Y�s�V���Ȉ�t�t�ɂ͏鏊�˂̖ؔʼn悪�A��B�Ɓ{���q���s���b�X���E�v���O�����t�ɂ͕��q�̃f�J���R�}�j�[���A�����r�Y�s���l�`���t�̌��G�ɂ͒��ҁi�H�j�ɂ��J�b�g���A���ꂼ��Y�����Ă���B�ق��ɂ���̐F�̕ύX��A����ւ̕����̍��F�̕ύX�i�P�E�Q���̓X�~�A�R�`�T���͎��A�U�`�W���͐j�Ȃǂƕ����āA�p�����s���ɍו��̏C�����������Ă��������̂Ǝv�����B
�g�����q�ٗ�Ձr���M������U�肩���������͂͌�������Ȃ��B�����A���o�����ɂ���u1974�E2�E14�v�����т̒E�e�����Ƃ���A����10�����1974�N2��24���i���j���j�̓��L�Ɂu�[������J�B���j����{�����A��̓����̕l�c�R�֏o��B�����̂ʼnw�̋߂��̓X�ŃR�[�q�[���̂݁A�n�}�������ɕ����B����̌m�Ï�J���ł���B���\�Y�A�����Ɍ}������B�܂��q�͏����A�ᏼ�F��A���������ɏЉ�ꂽ�B�v���Ԃ�̓y���F�Ƒ傢�Ɍ��B�������Ȃ�A�F�V���F�A�푺�G�O�A���R�r���Y�A�l�J�V�����A�Ԑ��쌴���A�O�ؕx�Y�A�����Ă猻����B���悢������ɓ���A�]���ɂȂ�B��Ԏ�͏��ьO�ŁA�u�����Đ_�ˁv�̔����ɒ����ق��B���\�Y�̎���N�ǂ����ė����̉S�̏I�����Ƃ���ŁA�����o���ƁA�O�͐�ɂȂ��Ă����B�₪�ďC����Ɖ������낤�Ƃ̗\���B�[��̐Â��ȖL�������Z�̒���A��B��������C�̌��������Ă����v�i�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A���Z�y�[�W�j�Ƃ���B�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�j�̏����́A�g����1948�N7��12���i���j���j�̓��L�u���Ƃ�̊������݂��^������炵�ĕ����^�i�����̂����̂��炪�����Ă����^�p�k�̊G���������^���̂���������������Ă����v�i�����A��܃y�[�W�j����̂�ꂽ�B���́A�l�����I�̂��̂�����C�́u���̏ё��v�Ƃ̏Ɖ��ɐ�ɂ���B���s�ٗ�Ձt�́A�����������o�̎�����ɂ���Đ��݂����ꂽ�B���сq�ٗ�Ձr�i�G�E19�j����u�P�v�������B
���͍��܂Ɍ�����
��
�Ă̔g�̊鏈��
��e���ĂԂ悤��
�g���z���
��̂悢�������Ђ��Ƃ�
�A����
���݂����q�����⏬�푰�̍D�ޓ��F�̓�
�q���́r
�I�p�[���̑�̂Ȃ��̔��e�̖�
���ޚނɓ����Ă���
��
�����߂Â���
�܂��j��������炷
�V�N�ȋ��̖ڂ̂悤��
����҂�
�A����
�ߌ��Ƃ͉����̂Ȃ��̉���
�q�g���������r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�j��҂ނ��߂ɁA�g�����̏��o�����̌��ő��O�̒}�����[�ɒW�J�~�ꂳ���K�˂��܂肾�����B�Ȃɂ��̔��q�ɁA�g�������̘b�ɂȂ����B�W�J����͑����Ɂu���͍��܂Ɍ�����^���v�Ƃ����q�ٗ�Ձr�̏o�����͑f���炵���A�ƌ���ꂽ�B�����������A�Y�ꂪ�����z���o�ł���B
�k�NjL�l
�C���^�[�l�b�g�Łq�ٗ�Ձr���������Ă�����A�i��{�𒆐S�Ƃ������]�y�[�W�s����ꂽ�{�����߂ā@�A�T�Ȕ��N�@�O���b�N�t�ŁA�u�Ō�ɁA���́w�A�T�Ȕ��N�x���A�ЂƂ�̓��{�̎��l�ɃC���X�s���[�V������^�����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����������Ă����B�g������1974�N�ɕ`���������u�ٗ�Ձv�Ƃ��������B�m�͂Ȃ����A��̑I�ѕ�����@����ɁA�킽���ɂ͂���ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B����ɋg�����͓����A�}�����[�ɋΖ����Ă����̂�����A�{������Ɏ�������Ƃ��[���ɂ��肦�邾�낤�B�ł́A���́u�ٗ�Ձv�����1�߂����p���Ă݂悤�i���̎��͋g�����̑�\��w�T�t�����E�݁x�Ɏ��^����Ă���j�v�Ƃ���̂��������B���]�҂�takahata���i�����̖����ɂ́uby takahata: 2004.11.30�v�Ƃ���j���N���킩��Ȃ����A���̋M�d�Ȏw�E�����߂����킯�ɂ͂����Ȃ��B�������Ȃ���A�W�����A���E�O���b�N�i������L���j�s�A�T�Ȕ��N�t�i�}�����[�A1970�N7��25���j�͐�łŁA�Ï��l�����ɂȂ�Ȃ��B�����ŁA���V�Ђ���2015�N5��1���Ɋ��s���ꂽ�Ċ�����肵���Ƃ���A��҂ɂ��q���Ƃ����r�ɒW�J����̖��O�����o�����B
�@��҂��܂��A���N�̓�����v�������̍�Ƃɑ��āA�Ƃ��ɂȂ������̏����ɑ��ĂЂ����ȕΈ�������Ă������i���N�́A�������̌������ւ̂���������A���̂悤�Ȃ������ŁA�܂�u�Úg�I�Ȏd���Ƃ͂܂������ʂȁv�������ŁA�������Ă�����Ƃ����㑼�ɂ��邾�낤���H�j�A������҂��w���w�E�x����ɂ��̏����̍ŏ��̕����̌E�c�[�쎁�ɂ��������|���ǂނƂ������R�Ɍb�܂�Ȃ������Ȃ�A�܂������}�����[�ҏW���̒W�J�~�ꎁ����̉����m�A�A�n�������₦����͂��܂����Ȃ������Ȃ�A���́m�A�A�n�͐���Ă��Ȃ��������낤�B��킭�A�������̌������A�邱�ƂȂ������u�Ԃ̂��̂߂܂��m�A�A�A�n�����������ł��Ɉڂ���Ă���悤�ɁI�i�W�����A���E�O���b�N�i������L���j�s�A�T�Ȕ��N�t���V�ЁA2015�N5��1���A�O��O�y�[�W�j
�g�������W�J�~��i�g���ɏ������낵�̕]�`�s�y���F��t������������y�̕ҏW�҂ŁA�}�����[�̃t�����X���w�n�̑S�W��咘�𐔑�����|�����j����āA������L���̃W�����A���E�O���b�N�s�A�T�Ȕ��N�t�ɐG�ꂽ�\���͂���߂č����B

�W�����A���E�O���b�N�i������L���j�s�A�T�Ȕ��N�t�i�}�����[�A1970�N7��25���j�̕\���Ɠ����̍Ċ��i���V�ЁA2015�N5��1���j�̃W���P�b�g
�O�ftakahata���̏��]�ɂ��������悤�ɁA�g�������ɃO���b�N�����̒��ڂ́m�A�A�A�n���f��������킯�ł͂Ȃ��B�������Ȃ���A�������ɑS�̂̏����������͋C�ɂ͋��ʂ������̂���������B���݂ɏ����ƍĊ��̑ѕ����f���ās�A�T�Ȕ��N�t�́A�A�����E�p�g���b�N�E�~�����V�\���̕ЗɐG��Ă݂悤�B
�m�����ѕ��n
���͑��l�̉��ɂ܂������Ă��鎀���䂳�Ԃ�A�ڊo�߂�����A���傤�Ǐ��̕��̂Ȃ��̎q���̂悤�Ɂc�c�c�c�c�c
�A�����Ƃ͒N���H
���邢�͉����H�i�\�P�j
�u���^�[�j���C�݃z�e���̔����q�����A�����{�[����������W�F���[���A�m�I�����W���b�N�A�V�����X�̃C���[�k�ƃA�����A�N�O���S���[�A�����ĎႭ�������ւ�₩�Ȗ��N���X�e���A���ׂƌ��ӂ��x�z���郔�@�J���X�ɓo�ꂷ��u�A�T�Ȕ��N�v�A�������߂��鈤�Ǝ��\�\���̐_��I�ȏ����́A�����Ɍ��ł���u�_�b�v�ł���B�i�\�S�j
�m�Ċ��ѕ��n
����῝���~�߂Ȃ���A���̖��Ӗ��Ȏ����\�\
���@�J���X�̌��ӂ��A�s���Ɉ�ς�������N�A�A�����Ƃ͒N�Ȃ̂��H�i�\�P�j
��L���X�g���́A�c�c���̒n����ł��������Ȃ��Ȃ������ł��傤�A�����L���X�g���~�Ղ��Ȃ�������B�L���X�g�������݂��邽�߂ɂ́A�L���X�g�����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������A���̑��ɁA���̓��ɐ���A�_��M���Ȃ��l�ԂɓB�t���ɂ��ꂽ���̎�������A�����ĉB�g�I�Ȏd���Ƃ͂܂������ʂ̎d���ŕ悩���������˂Ȃ�Ȃ������̂ł��B���̂悤�Ȑ^���̂ł��ʌ����Ȃ����Ăǂ����Ĕނ��ЂƂтƂ�����ł����ł��傤�H��i�\�S�j
�Ċ��ѕ��̕\�S�̓A�������W�F���[���Ɍ�������t�B������܂ށu�����\����v�̃W�F���[���̓��L�́u����A���ɁA�A�����ƒm�荇���ɂȂ邱�Ƃ��ł����v�i�����A����y�[�W�j�Ǝn�܂�B�����A�����̌��t�ōł��䂩�ꂽ�̂́A���̃L���X�g���^�L���X�g�̈�߂ł͂Ȃ��B���̂ق�̐��y�[�W�܂��̕ʂ̉ӏ��ł���B�����́A�g�����ǂ�������Ȃ���������������Ƃɂ���B
�k�c�c�l�����炭�A��i�̊����m�A�A�n�́A�|�[�́w�ȉ~�`�̏ё��x�ɂ�����悤�ɁA���邢�͐l�Ԃ̎��������炷��������܂���B�����ꂽ���t�̂��łɂ���߂Ċ댯�Ȗ��Â��Ƃ����Ď��l��m�炸�ɓ����Ă䂭���̓������ɂȂ����e�N�X�g�A���̎������ꂽ�ڂɌ����Ȃ��e�N�X�g���A�����Ȃ閂�͂����Ă��邩�A�N�ɂ킩��܂��傤�B���ׂĂ̍�i�͂������������������Ă��̏�ɂ܂������L�����r�玆�Ȃ̂ł��\�\������A��i���������Ă���ꍇ�́A�����ꂽ�e�N�X�g�͏�ɖ��@�̃e�N�X�g�ł��B�i�����A���O�y�[�W�j
�Ƃ�킯�u���ׂĂ̍�i�͂������������������Ă��̏�ɂ܂������L�����r�玆�Ȃ̂ł��v����́A�g���������Y���P���W�s�E�T�M�̃_���X�t�i�������A1982�N11��15���j�̞x�Ɋ������̎U���q�������̏�ɕ����łȂ����̂����u�����鎍�r��z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�����Ƃ̘a�c�F�b�͋g�����̊x�������A�����ł͐��M�q���d�̕Ћ�����r�i���o�́s�C�t1974�N8�����j�̏���������ǂ�ł݂����B
�@�D�y�̉Ԍ����Ƃ����a�َq���ɗ��܂�āA�u�Z�h�m�������n���v�Ƃ����Z�����͂��������B�k�C���̎l���ɂӂ��킵�����t�������Ƃ������Ƃ������B�������猩��A�قځA�Ђƌ��قǒx��č��̉Ԃ��炭�B���́A����ȕ��͂��������B
�@���������́u�����h���v�ƌ��������A�ʂȌĂт���������炵���B���肪�n�ʂɎh���������������̎h�����ނ����ŁA�͂����Ƃ��q���̗V�сB���܂��A�͂����A�����̂��̂ɂȂ����B
�@�Ⴊ�����āA�����y������o������A�����������A�͎R�ւ͂���A�������ƁA������������B������ڂ��炢�ŁA�悫���s������Ă����B
�@�u�����h���A���ׁv�ƗU�������A���ی�̏��w�Z�̍L���ςŁA�����ɓ����������B
�@���̐��܂ꂽ�����������D�́A�k�C���ł͒g���ق������A�����h���͎l�������_�ŁA���ꂩ�烁���R�V�тɂȂ����B
�@�ǂ����āA�l���������h���Ɍ������Ƃ����A�ᐅ���[���ɋz�����y�́A���߂�������A���炩�߂����A�ł����Ȃ��A�˂��Ƃ�Ƃ��������̂����ł���B�a�َq�́u�˂肫��v�̐G���Ɏ��Ă����B
�@����������A�s��������������B
�@��{���Ȃ��A�������܂��������āA���������ƋA��Ƃ��́A�݂��߂����炵���C���B
�@���̓��͕t���Ă��āA������K���A������Ȃ��������A��ō�����������A�w�����Ė߂�Ƃ��́A���ꂪ�܂����B
�@�����ɂ����D�ŁA�����̂̔w�����悲���Ă��܂����ƋC�Â��̂́A�����A�Ƃ߂Â������낾�����B
�@��Ɏ����Ȃ���A���͘F���ŁA�E���������̓D���A���킩�������̂������B��
�@�����ŕς�A���́u�U�炵�v�́A���̂Ƃ���œ�S�\�Z��ɂȂ��Ă���B��\�O�N�O����A�n�߂��Ƃ������ƂȂ̂��낤�B
�@�k�c�c�l�i�s���Ԃ�����܂Łt�k�m�ЁA1978�N1��20���A���`���y�[�W�j
���@���Ŋ������ܕS�O�\���オ���g�̋���ɂȂ�킯�����A�q�Z�h���r�͘a�c�̂ق��̕��W�ɂ͎��߂��Ă��Ȃ��悤���B�ł́A���̋ɂ߂ĒZ�����z�͉��N�́u�l���v�ɔ��\���ꂽ�̂��낤���B���p�����炻����������Ƃ��ł���B�q���d�̕Ћ�����r�̏��o���i1974�N8���j��u�����ŕς�A���́u�U�炵�v�́A���̂Ƃ���œ�S�\�Z��ɂȂ��Ă���B��\�O�N�O����A�n�߂��Ƃ������ƂȂ̂��낤�v�Ƃ����L�ڂ��l�����킹��ƁA�`���V������������Ɣ��s����Ă���Ƃ���Ȃ�A�n����1951�N1���i���Ȃ킿1974�N�́u��\�O�N�O�v�j�A��������N�Z����Ɓq�Z�h���r�����\���ꂽ�̂�1972�N4���ƂȂ�B�q���d�̕Ћ�����r���s�C�t�ɔ��\����1974�N��2�N�O��1972�N�́A�x���Ƃ����t�ɂ͒E�e�������͂������Ƃ������ƂɂȂ낤�B�����������Ƃ�ՂÂ��邱�Ƃ̂ł���A�a�c�̎U���̂�����ׂ����k�x�ł���B���e�̂��Ƃ������A�t��̓y��a�َq�u�˂肫��v�̐G���ɒʂ���Ƃ��邠����ɁA�a�c�Ȃ�ł͂̊��\�������邱�Ƃ��ł���B�������������Řb��ɂ������̂́A�a�c�̕��͂��g���̎U���ɂȂɂ������̉e����^�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����_�ł���B���������l�͏��߂ĂȂɂ�����ꍇ�A�܂邫�薳�菟���ŗՂނ��Ƃ��Ȃ��Ƃ͌���Ȃ����A������ׂ��������Ԃ�����Ȃ�A��߂Ȑ�Ⴉ��w�Ԃ̂����Ǝv���邩��ł���B�g��������ĎU���\���͂��߂��̂́A���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�����s���ĈȌ�A���ꂪ�����̐l�̖ڂɐG���悤�ɂȂ����̂́A�����s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�����s���Ď��l�Ƃ��Ă̒n����z���Ĉȍ~�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�����̋g���̓Ǐ������̏ڍׂ͂킩��Ȃ��B�����A1953�N�ɂ͋Ζ���̋Ɩ��ʼn��c�Ǖ��E�a�c�F�b�҂��s��t�S�W�k�S7���l�t�i�}�����[�A1953�`56�j�̑�����S�����Ă��āA�g���͓����A�a�c�F�b����t�̌����҂Ƃ��Ēm�����B����ɁA1956�N�ɘa�c�̏������낵�s��t�̓��L�t�i�}�����[�j�̑�������|���邱��ɂ́A�����Ƃɂ��Č������G���̕ҏW�҂Ƃ������̌o���ɂ��ʂ��Ă����B�܂�A�g�������\��z�肵���U���������͂��߂������A�ł��g�߂ɂ������M�Ƃ̈�l���a�c�F�b�������킯�ł���i�Ȃ��g����1959�N�A�a�c�̒����E�z�q�ƌ������Ă���j�B

�g�����Ƙa�c�F�b�k�o�T�F�É͕��w�ٕҁs�a�c�F���W�\�\��ƁE�����ҁE�ҏW�҂Ƃ��āt�É͕��w�فA1999�N10��23���A�܈�y�[�W�l
�����Ŗ`���Ɉ������q���d�̕Ћ�����r�ɛƂ߂��܂ꂽ�q�Z�h���r�ɖ߂낤�B�g���̎U���͘a�c�̐��z�ɂ����邻��قlj��s��Ǔ_�������͂Ȃ����A��r�I�Z������ς݂����˂Đ��ւƕ���i�߂�ċz�ɂ́A�݂��ɋ߂����̂���������B��N�̂���̑z���o�����Ƃ��鐏�z����߂�����ۂ̎�@���A�a�c�́u��Ɏ����Ȃ���A���͘F���ŁA�E���������̓D���A���킩�������̂������v������Ɋw��ł���悤���B�Ȃ��A�����a�c�̏����ł͂Ȃ����z���������̂́A�������Δ䂷�ׂ��g���ɏ�����i���Ȃ��Ƃ������Ƃ����ɂ��邪�A�a�c�̏����Ƌg���̎����r����ɂ͂��̊Ԃɐݒ肷�ׂ��}����G�����Ď�ɗ]��A�Ƃ�������ɂ��B�a�c�̏����̕��̂Ɋւ��ẮA������悵���ےJ�ˈ�̕]�u�����Ęa�c�̓�т̏�s�����k�q����r�Ɓq�ږ̑�r�l�́A���Â���A���c�H�߂����[�N���Ɏ����ɍ����������Ԃ̍\���ƌ��Ёi�a�c�����̋Z�@�ɏK�n���Ă�邱�Ƃ͋������قǂł���j�A�p�ɂȉ��s�ƌ��ЁA��b�̑��p�ƌ��ЁA�܂����������k���a�\�N��l�̏����Ƃ̋ߐڂ������Ă��B�ނ͂Ђ�Ƃ���ƁA�ł��x��ė������a�\�N���ƂȂ̂�������Ȃ��B����͂������A����ɂӂ��͂��������̐��n�����͂Ă��Ƃ��ӈӖ��Ō��ӂ̂�����ǂ��v�i�s��̂����k�������Ɂl�t�����V���ЁA1986�N8��20���A�ꔪ��y�[�W�j�ɐs���Ă���B

�A���L�T���h���A�Ǘ��ցs�n���̏ё��\�\����Y���ё����������H�W�t�i�A�p�b�V���فA1969�N�k���t�Ɍ����̋L�ڂȂ����A9���ȍ~�Ɋ��s���l�j�Ɏ��^���ꂽ�g�����́q�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r�Ɠ����̃|�[�g�t�H���I
�g�����Ɂq�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r�Ƒ肷��O�S�\���قǂ̒Z��������B���o�́s�n���̏ё��t�i�A�p�b�V���فA1969�j�����A�����̃N���W�b�g�̕\�����������B���Ȃ̂ŁA������̂��肳�܂��Č����Ă����B�����Ï�����ɂ��琔�N�܂��ɋ��߂���{�́A�V�n300�~���E415�~�����[�g���قǂ̃|�[�g�t�H���I�\�\�m���̛�ŁA�\�́uPORTFOLIO�v�Ƃ������S�̏�ɋ�̒n�������đ傫���u�n���̏ё��v�i�����ł��낤�j�A���̉����̃|�[�g�t�H���I�̐��n�ɂ�⏬�����u�A���L�T���h���A�Ǘ��ցv�i���ꂪ����Ȃ̂��A���҂������͕Ҏ҂������v���W�F�N�g���Ȃ̂��A�͂����肵�Ȃ��j�ƁA��������X�~�ŕ����i���g�݁j�������Ă���\�\�ɁA�V�n290�~���E410�~�����[�g���قǂ̎��t��13�����߂��Ă����y���P�z�B�����܂��āA�X�I�ɖ{�����A���L�T���h���A�Ǘ��ցs�n���̏ё��\�\����Y���ё����������H�W�t�i�A�p�b�V���فA1969�N�k���t�Ɍ����̋L�ڂȂ����A9���ȍ~�Ɋ��s���l�j�Ƃ��Ă����B�g���́q�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r�́s�y���F��t�i�}�����[�A1987�j�́q18 �u�n���̏ё��v�r�ɁA�������ӏ��i�s�@�t�Ɓ\�j���߂������ŁA����͂��̂܂܂ɋz�����ꂽ�B
�@�y���F�Ɗ}��b�Ƃ�������ׂ���l�̕����Ƃ̎t�Ƃ�����A����Y�͋v�����ԁA���ɂƂ��Ă͌��̕����Ƃł������B���̂܂������ǖقȕ\���҂́A�Ȃ��Ȃ��������̑O�ɂ��̑S�e�����킵�Ă���Ȃ��B���̐l�����x�w�n���̏ё��x�Ƃ������j�[�N�ȉf����H�̋��͂őn�����B���Ȍ����~�̛����Ǝv�������Y���A�ˑR�A�f���n�����̂ɂ͈�u��قȂ��̂��A���͊��������\�\�B�ꎞ�ԏ\���Î����Ă��邤���ɁA���Ȃ��Ƃ����A����͑��҂Ɋς��鉉�Z�ł͂Ȃ��A�܂��ĕ����ł��Ȃ��A���̂ł��Ȃ��Ǝv���Ă���B����͂�����������A����Y�̂���߂ē����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�Ȃ̂����m��Ȃ��ƁB�����Â����E�̓��w�ŁA�������������łȂ����܂݂�̋��̂��A�g�C���b�g�y�[�p�[�ŕΎ��I�ɕ�݂���ł䂭�p�ɁA���͂����ɂ����ڂ����B�i�����A�O��`�O�O�y�[�W�j
�g���́q18 �u�n���̏ё��v�r�ŁA�܂��y���̏͋�������Ă���A���g��1969�N8��24���̓��L���f���Ă���B���Ȃ킿�u�[��A�a�J�̃t�����Z�ɍs���B���łɔѓ��k��A��؎u�Y�N�v�Ȃ����āA����Y�ƒ����H���҂��Ă����B�x��āA�y���F�A�O�D�L��Y�������̂ŁA�����ȉf�掖�����ցB�����Ē����H�B�e�A����Y�o���́u�n���̏ё��v���ς�B�I���ĉ��ΐ�Ŏ����̂ށB�y���F�̓f�������t���S�Ɏc�����B��҂������ʂ炷���͋��̂�����B�������V�k�A���{�̘V�k�͐Â��ɂ�����ł䂫�A�w�悩�炷�[���Ɛ��̂Ȃ��֓����Ă䂭�A�Ɓ\�\�v�i�����A�O��y�[�W�j�B�����Ĉ�s�Ă���u�w�n���̏ё��x�̋L�O���q�����Ƃ����̂ŁA���͈ꕶ���Ă���B�v�i���O�j�Ɨ��āA��f���p���ɂȂ�i�Ȃ��A�W��́q�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r�͋g�����������̂ł͂Ȃ���������Ȃ��j�B���ɂ͂��̗��V���A�{�e�̏��߂Ɍf�����a�c�̍��@�ɒʂ�����̂Ɏv���Ă��������Ȃ��̂��B
�F�V���F�y���Q�z�̂悤�ȁA���M�������͓͂I�ɏ����ɂ܂Ƃ߂Ă������M�ƂƊr�ׂ��Ƃ��A�g���́q�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r���A���Ƃ��u���E���v�Ƃ����悤�ȃJ�e�S���[�������Ď����Ɏ��^����Ƃ͍l���ɂ����B�a�c�͋g���Ɣ�r����͂邩�ɑ����̒����L���āA�f��ɂ͑S�W�y���R�z�����邪�A����ł��k�C���̘a�َq���̃`���V�ɏ������q�Z�h���r��P�̂ŏ��Ђɑg�݂��ނ悤�ȕҏW�͂��Ȃ��������낤�B�����A���g�̋����V��ɛƂ߂���ŕ��͂�W�J�����@�́A�N�����̂���̂ł͂Ȃ��悤�Ɏv���B����͕ҏW�I�Ȓ��q�̕��@�ł͂Ȃ��낤���i������A�a�c�F�b�A�g�����A�F�V���F�̎O�l�Ƃ��A�ҏW�҂���������������j�B�F�V��1960�N��̎咘�Ɂs���̉F�����\�\�R�X���O���t�B�A �t�@���^�X�e�B�J�k���p�I���l�t�i���p�o�ŎЁA1964�j������B�ܒJ���m�����́s�F�V���F�_�R���N�V�����k�S5���l�t�i�א��o�ŁA2017�`18�j�Ŏw�E���Ă���悤�ɁA�{���͎G���f�ڍe������߂ĕҏW�I�ɍč\�����������������B�Ƃ���ō������s��ҏW���ҁs�����̉F�����\�\�F�V���F�����ژ^�t�i�������s��A2006�j�́u�F�V���F���₵�������P���]���̑S�f�[�^�Ƒ����̎ʐ^���D��Ȃ��A���Ƌ��ق̑����ژ^�v�����A�g�����F�V�ƒ����̂��Ƃ��ʂ��āA���s�����A�s���̉F�����t��ꂽ���ǂ����͂킩��Ȃ��B�����A���̎����͂Ƃ������A�g�����s���̉F�����t��ǂ��Ƃ͋^���悤���Ȃ��B�����`���́q�ߋ�ɂ��ār�������Ă��A�����ɂ͓����v�i�C���m�W�F���x�G���\�\�̂��̃��[�}�@���V�����F�X�e���\�\���������Ƃ����j�A�_�C�_���X�ƃN���^���A�{��ё���ƃW���[�b�y�E�A���L�m�}�}�n���{���h�A�u�S�̏����v�A�A�X�^���e�Ƃ������A�̂��̋g�������Ɍ���邳�܂��܂ȃA�C�e�����o�ꂷ��B�ނ��A���ׂẴX���X���F�V�̒��삾�Ƃ͒f���ł��Ȃ����A�F�V�o�R�ł����ɐe�����Ƃ͖��炩���낤�B���ɃA���`���{���h���u��Ɖʎ��ƉԂ����g�ݍ��킹�āA���[�����X�ȁk���h���t�l�c��̊��`�����v�i�s�F�V���F�S�W�k��4���l�t�͏o���[�V�ЁA1993�N9��13���A����y�[�W�j�Ƃ���́q��t�r���}�łŌf�ڂ���Ă���B���ꂪ�q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�́u�t�̉ʎ��Ƌ��ō\�����ꂽ�^�A���`���{���h�̏ё���̂悤�Ɂv�̕����̂ЂƂł��邱�Ƃ͓����Ȃ����낤�B�ƁA�����܂ŏ����Ă������A���͂���ȏ�A��̓I���F�V���F�̕��͂Ƌg�����̂������ׂĔ�r���邱�Ƃ͔��������Ǝv���B�U���Ɋւ��邩����A�E�ƓI�ȏ�����ł����F�V�Ƌg�����Ƃ������l�̏����U����˂����킹�Ă݂Ă��債�������͓����Ȃ����낤�A�Ƃ����\��������̂��B�ނ���A�F�V�̃G�b�Z�C�i���z�ł͂Ȃ��j�̒f�͌`���ƁA�g���̐l���]�ɂ�����f�́E�f�z�Ƃ����`�������{���I�ȗގ������������[���B����͕\�����@�̎����ɗ��܂炸�A���E��F������p���ɂ����鋤�ʐ��������Ă��悤�B�g����1950�N��ɘa�c�̕��͂���w�悤�ɁA1970�N��ȍ~�A�F�V�̒��삩�瑽�����w���Ƃ́A������b�q���ё��q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�Łu�F�V���F�v�ȂƉ��N���O�l�J�V�����̐l�`�W�ňꏏ�ɂȂ������A�{�C�Ő^�ʖڂɍ��̂Ƃ���A������F�V������ԋC�ɓ����Ă��邩��ˁA�ƌ����A�F�V���F���A���̂Ƃ���m�A�A�A�A�A�n�A�����A�Ƒ�������v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A���l�y�[�W�j�Ə����Ă��邱�Ƃ��T�ƂȂ�B�����A�g�����F�V�̕��@�����Ɩ��Ē��̂��̂Ƃ����̂́A�u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�Ǝ����ɂ��鎍�сq���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�������Ě���Ƃ���B���̎��т��F�V���F�s�ӓ��̒��̐��E�t�i�y�ЁA1974�j�̊W�ɂ��ẮA���������������B
���ɂ́A�a�c�F�b�i1906�`77�j���F�V���F�i1928�`87�j�Ƃ����A���悻���G�I�ȗ���̕��w�҂���U���̕x���p���������l���g�����������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
�y���P�z�@�s�n���̏ё��t�́A�y���F�����q�y���F�Ɠ��{�l�\�\���̂̔����r�̈�J������Ɋ��s���ꂽ����50���̃I���W�i�����؎���W�s�y���F�����W ����܁t�i�A�X�x�X�g�فA1968�N12��1���A�ҏW�F�A�X�x�X�g�فj�قǒm���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���ڂ����L���Ă��������B13���̎��t�i�m���u���Ȃ��j�ɁA���Ɋے������Ŕԍ���U���ē��e���T������B�Ȃ��A�{���͂��ׂďc�g�݂ł���B
�@����̃g���[�V���O�y�[�p�[�ɁA�g�p�ς݂̃`�F�R�X���o�L�A�̐؎�i��������n�̊G���j��\��A�X�~�Ől���i�n���H�j�̔��g�����A��F�Łu�A���L�T���h���A�Ǘ��ցv�i���g�݁j�ƁA�����炭�V���N�X�N���[���ō����Ă���B�{���̔��ɑ�������B
�A�ȉ��A�p���͂��ׂĔZ���N���[���F�ɒW���s���N�̃}�[�u���͗l���������t�@���V�[�y�[�p�[�B�A�́q�ژ^�r���Ȃ킿�ڎ��ł���B�ǂ����݂ōĘ^����B�u����Y���ё����������H�W�^�ژ^�^�y���F�@�V�r���b�g�v�l�^��������@������̃L���X�g���^�O�D�L��Y�@�I�i���̔@���^�ѓ��k��@�n���̉^���^���c���j�@�n���̏ё��ց^��؎u�Y�N�@���Ƃ����Ƃ�������[���[����܂����I�^�����ĔV�@���݂邷�o�Ȑ��^�J��W��@OHONO-FARMAN TYPE-PIPE BIPLANE�^�g�����@�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�^�F�V���F�@�j���ߌ����ҁv
�B�y���F�k���ȕ��l�i�W��Ȃ��j
�C��������k�U���l�q������̃L���X�g���r
�D�O�D�L��Y�k���l�q�I�i���̔@���r
�E�ѓ��k��k�U���l�q�n���̉^���r
�F���c���j�k�U���l�q�n���̏ё��ցr
�G��؎u�Y�N�k�U���l�q���Ƃ����Ƃ�������[���[����܂����I�r
�H�����ĔV�k�}�ƎU���l�q���݂邷�o�Ȑ��r
�I�J��W��k�ʼn�l�qOHONO-FARMAN TYPE-PIPE BIPLANE�r�c�c�����̎l�Ԗ{�͕ʂ̃I���W�i���i74/100�j���J���[�R�s�[�ŕ�����������
�J�g�����k�U���l�q�����Ȉӎ��̌l�I�Ȕ�V�r�c�c�{����18��20���l��18�s�B�W�肪1�s�A������1�s�i�ǂ�����Ԍn�̍��F�j�Ȃ̂ŁA400���l�ߌ��e�p��1���A�������̓y��2���̌��e�������ƍl������B
�K�F�V���F�k�U���l�q�j���ߌ����ҁr�c�c�����́q���r�i�ܒJ���m�j�ɂ́u���Z��N�A�A�p�b�V���ق��犧�s���ꂽ�w�n���̏ё��\�\�A���L�T���h���A�Ǘ��ցx�ɔ��\�B����́u����Y���ё����������H�W�v�̃��[�t���b�g�`���́u�ژ^�v�ł��������B�y���F�A��������ȉ��A�����̕��x�ƁA���l�A��]�ƁA��Ƃ���������Y�ւ̃I�}�[�W���������Ă���v�i�s�F�V���F�S�W�k��9���l�t�͏o���[�V�ЁA1994�N2��12���A�O��y�[�W�j�Ƃ���B
�L���L�B�ǂ����݂ōĘ^����B�u��蔋�S�Z�E��N�^�A���L�T���h���A�ǁ^���H�|�Ё^�N���t�g�E�t�H�g�E�^�C�v�^�����C���L�^���s�@�A�p�b�V���ف^�k��⏬�����l�����s���c�J��匴2�\21�\3�^����S���l�k�M�����l�ԁv
�y���Q�z�@�F�V���F���a�c�F�b�����ǂ��Ă������͒肩�łȂ����A�G�b�Z�[�W�i�Ƃ����������M�W�ƌĂт����j�s�ߕ������t�i�����V���ЁA1979�N2��25���j�́q�V�Ղ�r�i���o�́s�����W���[�i���t1978�N5��5�����j�ɐG��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@���̓��A�g�����������A��Ă��Ȃ������̂́A��ɂ͉�����̕��N�̘a�c�F�b����̕a�Ԃ��v�킵���Ȃ��������߂�����܂����A������ɂ́A�|���m��������肾�������炩������Ȃ��ȁA�Ǝ��͂Ђ����Ɏv���܂����B�����Ƃ��A����͋g������Ɋm���߂��킯�ł͂���܂���A���̏���ȑz���ł��B
�@���N�̗e�Ԃ����������m��ʂƂ������ɁA�|���m�߂�ȂǂƂ͕s�ސT���A�Ƃ����ӌ������邩������܂��A���͂����͎v���܂���B���\�N�̑s��Ȑ��������������Ƃ̗ՏI�ɁA�������A�e������������Ă���������A�g������͂��̓��A�ނ�ނ�ƃ|���m���������Ȃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����A��������ȗ��A������ɂ͋y�т܂��܂��B��������ɋg������̐S����u�x���錠�����A�ނ��A����܂���B�������́A�a�c����̐��U�ɂ̓|���m�͂ނ���ӂ��킵���̂ŁA����߂�̂��K�������s�ސT�Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v��Ȃ������ł��B
�@�k�c�c�l
�@�k�V�Ղ牮�Łl�H�����I���A�i���X�ŃR�[�q�[�����ނƁA�g������͂`����k�}�����[�̕ҏW�ҁA�W�J�~�ꎁ�l�ƈꏏ�ɁA�����ӂ��Ɖ��{����œ����A���čs���܂����B
�@���̓��̖邨�����A�a�c�F�b����͖S���Ȃ��܂����B
�@���͘a�c����ɂ͈�x�����ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��A���̍�i���A�g�����ēǂ��Ƃ���x���Ȃ��悤�Ȑl�Ԃł����A���̓��̃G�s�\�[�h�́A�a�c����̎��Ƃ���߂āA�����炭���ʂ܂ŖY��邱�Ƃ�����܂��Ǝv���܂��B�����������Ƃ�������̂ł��B����͋��N�̏\���l���ł����B�i�����A���l�`����y�[�W�j�B
���̗I�g�Ƃ��Ĕ���ʒ��q�́i�ł��E�܂��̕��̂Ƃ����ւ��āj�A���҂̖��𖾂����Ȃ���A�F�V���F���Ƃ킩��Ȃ��̂ł͂���܂����B�����Ƃ��u���́A�a�c����̐��U�ɂ̓|���m�͂ނ���ӂ��킵���̂ŁA����߂�̂��K�������s�ސT�Ȃ��Ƃ��Ƃ͎v��Ȃ��v�Ƃ���������A�܂�����Ȃ��F�V�̕��͂ł���B�a�c�̎��͋g���ɂƂ��Ēɐȏo�����������B�s�Q���t1977�N12�����k�a�c�F�b�Ǔ��l�́q�������l�\�\�a�c�F�b�ՏI�L�r�́A�|�����q���]�Q�����悤�ɋg�����̎U���̂ЂƂ̋ɒv�������Ă�����̂����A���̂悤�ȉӏ�������B
�@�\���l���͒������J�ł������B���������Γ��@�̋㌎�\������\�ꍆ�̉J�䕗�̓��������B���̂n�a�@��މ@���āA���₶����͒����̉Ƃɖ߂����B�A�̗ɂ����܂ꂽ�킪�Ƃɓ��鎞�A�a�l�̊�͂��܂܂Ō��������Ƃ̂Ȃ����X�������������ׂ������ł���B���Ɉڂ�a�@����������̂ŁA�r�����Ԃ�낵���A�Ƃł������ÂƉh�{��ۂ邽�߂��ƁA�Îq�v�l�Ǝ厡��̌��ł������B�������A���͑O��f�����A�A����_�H�����Ă����a�l�̏�Ԃ��v���ƁA�s�g�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B
�@���̓��͐����A���͎d���̂��ߓ����Ɩk���q���F�V���F��ɍs���Ă����B�ō������I��A���q�v�l�̉^�]���邭��܂Ŋ��q�֏o���B�����ʂ�̂Ђ�݂œV�Ղ��H�ׁA���̂�����[���߂����B���������̊Ԃ��A�����̉Ƃ̂��Ƃ��l���A�S���������Ȃ������B�㎞�߂��ɒ����ɍs�����B���炩���ߍ����̂��Ƃɔ����A�{���{�I�����̑��̊함�����яo���Ă��܂����̂ŁA�����͈�ς��Ă����B�V�����Z�~�_�u���̃x�b�h�̏�ɕa�l�͐Q�Ă����B���₶����̊�����āA�������߂��Ǝv�����B���t�ɂȂ��Ă��āA�O�����낵�������Ă���B�Ȃɂ����A�ꂵ�ޗ͂��������������B�Îq�v�l���Ȃ����������k�a�c�F�b�̒��j���Ȃ킿�g���z�q�̌Z�A���l���A���������ӂ��Ƃ��Ă����B
�@���̓N�b�V�����̑ւ�ɁA���₶����̔w�ɉ����ĐQ���B�����Č��⍘�ł�������d���Ȃ������B�\�߂��A��x�A���������Ăі߂���ĐV�Â̐搶���킯�����B���łɓf���Ɖ������͂��܂�A���͋߂������B�搶�͈�ԑ�ŁA�ނ��������_�H�����邩��A��������a�l��軀���������ĉ������Ƃ������B���s�͂�邳��Ȃ��Ƃ����ْ����������S���ɂ������B���F�ɂ͂���������������Ȃ́A�^���ȕ\��������Ă����B�܂��ɒ��˂��邻�̏u�ԁA���炮��ƉƂ��h��o�����B����͑傫�Ȓn�k�������B���ꂩ��O�\�����������낤���A�������͂��₶����̂Ԃ��Ă����Ⴊ�}�ɊJ���A�����Ȃ�̂������B�Îq�v�l�͕a�l�̖j�ɕ���ł����āA�Ȃɂ����B
�@���e�����ɊłƂ��ď\���ܓ��ߑO�ꎞ�O�\�A�a�l�͎��B��Ƙa�c�F�b�͎��B
�@�g�c�̂�����ƖÂ̕���������`���ɂ��Ă��ꂽ�B�܂Ƃ͖��Ȃ��̂��B��l�̎҂̗܂ɗU���A��������܂𗬂��Ă����B
�@�݂�ȂŁA���₶���p�̍��̗��߂𒅂����B���͈�[�������グ�Ȃ���A�����т������������Ɗ������B�w���͂܂��ʂ邢���݂��������B�ܐ�͂�ƓV�������Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꎵ�O�`�ꎵ�l�y�[�W�j
�F�V���F�͋g�����́q�������l�\�\�a�c�F�b�ՏI�L�r���G���œǂ�ŁA���M�q�V�Ղ�r�������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���i�u�����ӂ��Ɓv�Ƃ����A�̂ɂȂ錾���܂킵���o���ɏo�Ă���j�B�F�V�Ȃ�́q�a�c�F�b�Ǔ��r�Ƃ��āB
 �@
�@
�^�����F�V���F�́s�ߕ������t�i�s�����W���[�i���t�A�ځj�̐蔲�����萻�{�������q�́q�V�Ղ�r�̎��ʂ�1�y�[�W�i���j���F�V���g�����ɑ������s�ߕ������t�i�����V���ЁA1979�N2��25���j�W�莆���̃y���������提���i�E�j
�y���R�z�@�a�c�F�b�̑S�W�i���������e�́q���c�_���r��q����r�Ȃǂ̒Z�я����Q�A�q�o�̒��r�Ɓq�Â�����r�̓я����A�q�����t�r�Ɓq��t�̓��L�r�̈�t�����A�q�ЂƂ̕��d�j�r��q���`���r�Ȃǂ̑�\�I�Ȑ��M�����^�������̂ŁA���m�ɂ́u�I�W�v�Ƃ����ׂ��\���j�́A�͏o���[�V�Ђ���܊��{�ŏo�Ă���i1978�`79�j�B�F�V���F�̑S�W�͌������ꂽ�S��i��ԗ������s�F�V���F�S�W�k�S22���E�ʊ�2�l�t�i1993�`95�j�Ɓs�F�V���F�|��S�W�k�S15���E�ʊ�1�l�t�i1996�`98�j���A�����͏o���[�V�Ђ���o�Ă���B�t������A�g�����̑S�W�ɂ́A�������ꂽ���ׂĂ̎��W�ق������߂��s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�����邪�A�o����͂��ߎU������L�܂Ŏ��߂��u�S�W�v�͂܂����s����Ă��Ȃ��B
�C���^�[�l�b�g�̉摜�����ȂǂƂ����֗��ȃc�[�����Ȃ���������A��Ƃ��Ă̐��G���̉��l�͍����͂邩�ɍ��������B�g�����̎��сq�ٖM�r�i�H�E5�A���o�́q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�A�؉�L�A1977�N5��31���j�̎����u�փ��}���E�Z���G���g�̊G�ɂ悹�āv��ǂ�ŃZ���G���g�̊G���ς����Ă��A��������Ɗς邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������̂ł���B�����Z���G���g�̊G�̐}�łɏ��߂Đڂ����̂́A�y���g���H�[�́s��z�t��19���k���W�����z�̔��l�i1986�N10��17���j�������Ǝv���B�q�ٖM�r���Ę^���ꂽ�s��z�t��72�`73�y�[�W�ɂ́A�Z���G���g�́q�W��r�Ɓq�y�e���t�r�i1976�j���f�����Ă����B�Ȃ��A���т��u1974�N�W�p���t���b�g���v�ƒ��L�ɂ���̂́i�O�q�̂悤�ɁA77�N������j���B���̌��J���i74�`75�y�[�W�j�ɂ́q�������r�i1977�j�A�q��̗��r�A�q��i�r�A�q�X�i�b�N�o�[�r��4�_�̐}�ł��A�O�̌��J���Ɠ��l�A���m�N���Ōf�ڂ���Ă��āA�����͂���炪�M�d�Ȏ����������B�g���́q�w���}���E�Z���G���g�W�r�̃p���t���b�g�͂����܂ł��Ȃ��A�s��z�t���ςĂ���͂������A���̟f��ɏ��̕��A�փ��}���E�Z���G���g�̉�ɂ��s�t�F�C�N�t�i�p�����ɁA2001�N11��26���j�Ƃ������Ђ����s���ꂽ�B���݂܂ł̂Ƃ���A���{�ł͂��ꂪ�փ��}���E�Z���G���g�̊G������߂��ł��d�v�Ȉ�����Ƃ������ƂɂȂ낤�B
 �@
�@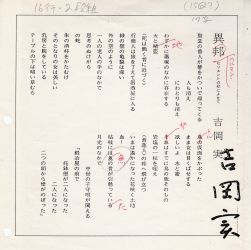
���̕��A�փ��}���E�Z���G���g�̉�ɂ��s�t�F�C�N�t�i�p�����ɁA2001�N11��26���j�̃W���P�b�g�k�\���G�́q�M�����b�p�����̖��l�r�l�i���j�Ƌg�����̎��сq�ٖM�r�i�H�E5�j�̏��o�k�o�T�F�q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�i�؉�L�A1977�N5��31���j�l�̃R�s�[�ɏ��ш�Y�����W���^�`�Ƃ̈ٓ����鏑�������́i�E�j
�w���}���E�Z���G���g���Љ���؉�L�̃E�F�u�T�C�g�ɁA�Z���G���g�̃y�[�W������B�����ɂ͍앗���������摜�i�A�쓺�ʼn� �gMasken und Maskierte�h�i���ʂƉ����j���j�◪���ƂƂ��ɁA�{���̈ē�������i�Ȃ��A�{���̃T�C�Y�͈ꎵ�l�~���Z�~�����[�g���j�B
[��W]�w���}���E�Z���G���g/���E����/�ufake�v
Serient�̐V�E�����ʍ�i��36�_���^�i�I�[���J���[�j�B��W�Ƃ��Ă�������������܂��B(�I���W�i���C���X�g/�T�C������)
2001�N11��26���p�����ɔ��s
�`�a�k�}�}�l���㐻36�Ł�\1,400+��
��Ƃ̗��ꂩ�炷��u��W�v���낤���A�킽�������͂ӂ�������u�G�{�v�ƌĂ�ł���B���̃X�g�[���[�ɍ��킹�āA�w���}���E�Z���G���g����i��`�����Ƃ͍l���ɂ����B�Ƃ���A�g�����q�w���}���E�Z���G���g�W�r�̎����̎ʐ^���ςȂ���q�ٖM�r�����M�����ł��낤�̂Ɠ��l�A����i���������̑n���𑽐����j�����̏��Ђ̂��߂̎����ʐ^���ςĕ����a�������Ƃ͏[���ɍl������B�{���̓��e�Љ�ɂ́A�u�ڂ��̐��܂������y�n�ł́A�f������炵����A�����̖{�����ނ��o���ɂ����肷��̂��A���ނׂ����Ƃƍl�����Ă��܂����c�B����Z�ԣ����ƣ�ȂǃZ���G���g�̊G36�_�ƁA���̃X�g�[���[�ɂ��G�{�v�Ƃ���B�����ė��\�Ȋ����������Ȃ�A�{���ɂ�����Z���G���g�̍앗�́u�]���l���V���^�[���̎�@�ŃA���\�[���̎���`�������́v�Ƃł��Ȃ낤���B�����Ƃ��]���l���V���^�[���͐F���M�A�Z���G���g�͖��ʁA�ƕ\�����@�̈قȂ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ����B�����́gfake�h�́A�ł����グ�Ƃ��U���E�͑��Ƃ����Ӗ��̖����ł���B����A�W���Y�~���[�W�b�N�̐��E�ł́u�������t���邱�Ɓv���Ӗ�����i�������t�́A�A�h���u�A�C���v�����B�[�[�V�����Ƃ��j�B�����ɂ��A�Z���G���g�͓�\�ΑO�ɋ��H�w�Z�ɍ݊w���Ȃ���W���Y�ɔM�����ăo���h��������������������A����͂���܂��ăZ���G���g�Ɓu�������t�v�����A�Ƃ����Ƃ��Ă���̂��낤�B����Ƃ����̂��A�ӂ��ɍl����u���ʁv��D�肱�薼�̂ق������e�\�\�G�ɂ��Ă��A�b�̒��g�ɂ��Ă��\�\�Ɏ����킵�����炾�B
�؉�L�ҁs��p�b�̕ϐg�\�\�؉�L�N���j�N��1961-2016�t�i�����ЁA2017�N5��31���j�́A�����̎������Ȃ�A�u�k�c�c�l�E�B�[�����z�h�̏Љ�A���q���`�A�l�J�V�����̓W����f�r���[�ŁA1960�N��`70�N��̓A���@���M�����h�̉��ƂȂ�A����C���A�F�V���F���I�u�U�[�o�[�I�ɂ���������Ǎ��̉�L�B���̉�L���_�͌��݂ɂ������p����A�F�V���F�H���u�����̉�Ɓv���������\�̏�����߂Ă���B�؉�L�ŌW���J����70����ƁA��e��7�{�A���k��5�{�A�W����p���t���b�g�̃e�N�X�g90�{�ŒH��55�N�Ԃ̋O�ՁA�؉�L��S�I�v�ł���B�g���͐��O�A�؉�L�ŊJ���ꂽ�W����ɑ��ɂ��ʂ��A����ĉ�L���s�̃p���t���b�g��4�т̎����Ă���B
���]�Ԃ̏�̔L�i�G�E15�j
�ٖM�i�H�E5�j
�NJ|�i�J�E5�j
�H�̗̕��i�K�E5�j
�����̎��т͂��̏��o�`���s��p�b�̕ϐg�t�Ɏ��߂��Ă��邪�A�q�ٖM�r�͓����̊����q�G�����X�g�E�t�b�N�X�r�i�����ɂ������ꂽ����C���́q��p�b�̕ϐg�\�\�G�����X�g�E�t�b�N�X�̍�i���}���ār�����^�j�̍��ɑ����āA��Ԃ߂̂փ��}���E�Z���G���g�̍��ɁA���̖��ʍ�i�q�X�i�b�N�o�[�r�i1968�j�A�q�̔Ԑl�r�i1970�j�ƂƂ��Ɍf�����Ă���B���Ȃ݂ɁA�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�N11��30���j�̃J���[�}�Łq�g�����̏����ȕ����r�ɂ́A�Z���G���g�́q�ٖM�r���f�ڂ���Ă���B������ς邩����A�g���̎��сq�ٖM�r���s�t�F�C�N�t�́u���ʁv���́A�gfake�h�ɋ߂��W�肾�Ƃ�����B���邢�́A���͂����܂ŊG�悩�痣��Ă��܂��Ă����܂�Ȃ��A�Ƃ����m�M���s�t�F�C�N�t�̍�҂ł��鏬��Ɉ����p���ꂽ�ƌ���ׂ����B
���p�]�_�Ƃ̐��؊�́q���z���A���X���Ɛ؉�L�r�ŃZ���G���g�������]���Ă���B�u�u�����v���O���I�����̎Ւf�A���ĂƂ���A�u�B�فv�͂�������ّ̓��ŁA���ɁA�����ے�ɔ�����މ��I�ȏ����ƌ����Ȃ����Ȃ��B�G�Ɖ��y�֔M���������4�N�Ԃ̃��[���b�p�u�Y���v�Ƃ��������ɒ�������Ȃ�A�w���}���E�Z���G���g�ɂƂ��Ďs���Љ�A���␢�E�́A�O�����猩��ΏۂȂ̂��낤�B�ނ́A�Ղ�̉�����l�`���̐l�`�⓹���ŋ��̓������҂̂��Ƃ��h��ɑ����A����ׂ�A���A�̂��A�x��̂��߂��l�Q���`���B���A�����ɁA���ʂ̉��ʂ��\����A���Ă����ނ�̕\��̗����������Ă��܂��Z���G���g�́A��i�̒P�����A�f�t�H�����A�N��ȐF�ʂƂ����E�B�[�����z���A���X������̐��ʂ��ȂāA�l�Ԑ��E�ւ̕��h�I��]���������獓���ɕ`�o���Ă��܂��v�i�s��p�b�̕ϐg�t�A�ꔪ�O�y�[�W�j�B
�ٖM�i�H�E5�j���o�́q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�i�؉�L�A1977�N5��31���j�A�k�O�y�[�W�l�A�{��15��16�s2�i�g�A31�s�B�y���o�`�����W���^�`�z�ňٓ��������B�@�@�@�@�y�i�i�V�j���փ��}���E�z�Z���G���g�̊G�ɂ悹��
�����̔Ԑl��ⴂ������ŋA���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ�Ƃ������
�킸���ɘm�˂̂Ȃ��ɑ��݂���
�Ɓy�����n�z��
�q���͓����҂ɋ߂Â��r
�s���l�͗��𗹂��ċ������ɓ���
�̕ǂ̋T��͐[��
�O�̋�̂悤��
��l�̘V�l�̎�̂Ȃ���
�v�l�̂ʂ�����
�̎�
��̎�t�������ނ�
���̂ƂȂ�̏��͔�����
���[�Ƙr�����Ă���
�e�[�u���̉��͈Â����ނ�
�y���́��i�g���j�z���ʂ����Ԃ���
�܂��͖ڂ�������
�~������@���Ɩ�
�y���ꁨ���z�͂��łɒ��̖e���̂���
�≖�̈ꗱ�����
�q�H�@�l�r�̖M�֔�ї���
���܂�ꡂ��ɂȂ����ԍ炭�y�n
���I
�͎}�ɂ͋��̍����������Ă��y�遨���z
�����̂Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�����̎q��S��������
�@�@�u�b�艮�̑O��
�@�@�@�@�@��m����l�ɂȂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��l�ɂȂ���
�@�@�@��̓����牌���̂ڂ����v
 �@
�@
�փ��}���E�Z���G���g�q���ʂ�j�r�k�o�T�F���i���j�E�փ��}���E�Z���G���g�i��j�s�t�F�C�N�t�i�p�����ɁA2001�N11��26���j�A���t�̑O�̃y�[�W�Ɍf�ځl�i���j�Ɠ��q�ٖM�r�k�o�T�F�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�N11��30���A�k���y�[�W�l�j�l�i�E�j
�g����1986�N1��10���́q���L�r�Ɂu���B�ߌ�x���A����֏o�A�؉�L�ŁA�w���}���E�Z���G���g�W���ς�B�O�_�قǂɐԊۂ��t���Ă����v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A��Z�܃y�[�W�j�Ƃ���B���̓W�����10������23���܂ŊJ���ꂽ�q���ʂ̍s���l�����r�ŁA�؉�L�ł̃Z���G���g�W�͏���1968�N�A�ȍ~�A1977�N�A1980�N�A�����Ă���1986�N�ɊJ����Ă���i�g���f��ł́A1991�A95�A97�A2000�A15�N�ɊJ�Áj�B���L�́u�Ԋہv�͔���ς̂��Ƃ�����A�g�������̂Ƃ��Z���G���g�̍�i�̔���s�����C�ɂ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�g�����Z���G���g��i�́q�ٖM�r�������肵���̂��A�ڂ����o�܂͂킩��Ȃ��B������Ȃ��ƂɁA�g�������сq�ٖM�r�����M����ɍۂ��ĎQ�Ƃ����Z���G���g��i�́A���́q�ٖM�r�ł͂Ȃ��A�s�t�F�C�N�t�̉��t�̑O�̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���q���ʂ�j�r�ł���B�g���̟f��Ɋ��s���ꂽ�{�ɍڂ��Ă��Ă��ؕ��ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���́q���ʂ�j�r�A�g���̎��сq�ٖM�r�̏��o�}�̂ł���O�f�q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�i�؉�L�A1977�N5��31���j�Ɍf����ꂽ�Z���G���g��i�������̂ł���i�p���t���b�g�\���̍�i�́q�J�[�j�o���r�j�B�g���́A�Ȃ�炩�̎���Łq���ʂ�j�r����ɓ���邱�Ƃ��ł����A�i����ɁA���邢�͌�N�A�q�ٖM�r����肵�����̂́j�苖�ɒu�����Ƃ̂ł��Ȃ������G��������̂��Ƃɒu��������Ƃ�����������āA���т����M�����̂��낤���B������ǂ��l������悢�̂��B�g�����q���ʂ�j�r�Ɓq�ٖM�r�ɂ��ڂ����̂��B����͎ʐ^�����������̂��A���悾�����̂��B����N�����͂����肵�Ȃ��q�ٖM�r�������肵���̂��i�q���ʂ�j�r�͂ق�Ƃ��ɓ���ł��Ȃ������̂��B�P�Ɂq�g�����̏����ȕ����r�ɍڂ��Ă��Ȃ������ł͂Ȃ��̂��j�B�����āA���сq�ٖM�r�͊G��q�ٖM�r�Ƃǂ������W�ɂ���̂��B�����A�����������_�͐��������A�����_�ł͏ڂ������Ƃ��킩��Ȃ��B
�G��q�ٖM�r���[���̋A�҂��Ƃ���A�q���ʂ�j�r�͑����̏o���Ƃ����������ŁA���ɂ͂��ꂪ�g���̒��ю��q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE10�j�̃^�N���}�J�������ւ̏o����z�N������Ǝw�E���āA���܂͑O���̂悤�ɉ������������w���}���E�Z���G���g�̊G��Q���߂ł邱�Ƃɂ��悤�B
�g��������y�m�F�Ɍ��������́A���ɑ�ʂł���B���Ȃ킿�����ƒǓ����ł���i�ǂ���̏ꍇ���ΏۂƂȂ�l���̏͋��莫�Ɉ�������A�N�Ɍ��������������ɋL�����肵�āA����𖾂炩�ɂ��Ă���j�B�g���̐��O�Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j���ɂƂ�A�l�J�V�����ɕ������q���ׁr�i�K�E6�j�������A�y���F��Ǔ������q������ܒf�����сr�i�K�E12�j���F�V���F�̒����̂��߂́q��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�r�i�K�E17�j���Ǔ����ł���B�s���[���h���b�v�t�̑O�̎��W�s��ʁt�i1983�j�ɂ́A���e���O�Y��Ǔ������q���́r�i�J�E13�j�A�������h���ɒj��Ǔ������q����r�i�J�E17�j�͂��邪�A�s�Ẳ��t�i1979�j�ɐ���������ꂽ��������l�����������͂Ȃ��i��1�j�B���Ȃ킿�q���ׁr�́u����g�������v�ŗB��̌����ł���A�N�����l�J�V�������̐l�ɓǂ܂�邱�Ƃ�O��ɂ��ď����ꂽ��i�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�����A�����Ȃ�q���ׁr�i���o�́s�l�J�V���� �l�`���t���p�o�ŎЁA1985�N6��10���j�ɂ����܂��ɁA�q���\�I�ȑ��`��Ƃ����r�i���o��1986�N6���́s�G�������~�G�[���t4���j�̂P�ƂQ�A���Ȃ킿�g��������C���Ɉ˂�n���X�E�x�����[���Ǝl�J�V�����ɂ��ď��������͂����悤�B
�@�P�@�n���X�E�x�����[��
�@����C���ɂ́u�n���X�E�x�����[���f�́v�Ƃ����A���`��Ƃ�櫂����A�������f�͂�����B�K�X���p�����ĖႤ�B�\�\�x�����[���̐l�`�ɂ����鋅�̂�anagramme�i���̉�̂Ƒg�ݑւ��j�̂��߂̃��J�j�Y���ł���A���̎��݊߁B�^����͂܂���ӂ̊��S�Ȑ^��ł���A�^�E�ъ��[�ł̂Ȃ��̃A�i�O�����ɂ���āA�^��ӂ̊������n�ł���A�܈�H�̌ǓƂȌ��ł���B�\�\�B��������ꎞ���A�n���X�E�x�����[���ɖ������A�Ö{���Œ��F�ʐ^�W�m�A�A�A�A�A�n���w�������̂��B�h�C�c��̌���{�ł���B�ǂ߂Ȃ����[�����̂��ނ��Ƃ��ł����B�����āu�������v�Ƒ肷���т̎����������B���̏I�́u���̋��̂̏����̕����Ɓ^�߂ɊW�����^�˂���˂���^��X�X�L�E���邩��^�V�C���悭�Ȃ�ɂ��������ā^�T�\�������o��v
�u�f�́v�̈�߂����p����B�\�\�l�`��҂Ƃ��ăx�����[���́A�ǓƂȌ��^�l�Ԃ̂ЂƂ�Ƃ��ďo�����邱�Ƃ��h���Â����Ă����B����ǂȂ�Ƒ����̂���Ȑl�������n��ɜf�r���Ă��邱�Ƃ��낤�B�s�K�ɂ��݂��ɒm�炸�A�����ʐl�`��҂Ƃ��āc�c�B�\�\�B�₪�Ĉ�l�̐N���A�F�V���F�̏Љ�Ɉ˂��āA�n���X�E�x�����[���Ƃ��̐l�`��m��A�[���[������B���������ݓI�ȃt�@���̂Ȃ�����A������m�A�A�A�n�l�`��҂����܂ꂽ�̂��B
�@�Q�@�l�J�V����
�@�������߂Ďl�J�V�����̖���m�����̂́A�G���u���z�v�̐l�`���W�̎ʐ^�Ɉ˂��Ă������B���̏����l�`�́A�x�����[���̋��̂Ɗ߂��݂��ƂɍČ����A���ׂ��ׂ̌ҊԂɂ́A�����������܂�Ă���B�\�\�����������͂��łɁu���v�̂��炾���イ��m������Ă��āA�Ȃ�ƗD��ɐU�������Ƃ��낤�B�\�\�B���̓V�����̎����̐l�`���������Ƃ��Ȃ����A�e�ߊ������ڂ����B
�@�y���F�̈Í������h�̉���\�Y�̏���E�ԃe���g�̉��ŁA���͎l�J�V�����Əo������悤�Ɏv���B���̍��A�ނ͐l�`����𒆎~���A�A���O���ŋ��̏��`�Ƃ��Ċ��Ă����B�V�h�̉ԉ��_�Ђ̋����ōÂ��ꂽ�A���\�Y��u�R�䐳��v�ɋq�������l�J�V�����̏��`�̐����ȉ��Z�ɁA�^�Q�������̂��B���ꂩ��l�A�ܔN�قǖ��҉ҋƂ����āA�܂��l�`����ɖv�����͂��߂�B���̍Đ���i���u�h�C�c�̏��N�v�ł������B�܂������x�����[���̞~������E�����L�O���ׂ��l�`�́B�����̓��g��̗��`�́A��s��u�N�����āA�Ȃ��p���邱�ƂȂ��A�u���ł���B
�@�l�J�V�����̑���W�u�����Ɖߋ��̃C���v���A����̐؉�L�ōÂ��ꂽ�B���g��̏��̏\��̂����B�K�[�h����t���A�n�C�q�[�����͂����A�����̃A�����J���̂悤�Ɍ�����B�A�тƔ鏊��U�R�Ƃ��炵�Ă����B�\�\�����Ƃ��h�X�������́A�n�C�q�[���������A������܂��A�O�p��K�ł������A�݂�т��i����͂ǂ����痈�����̂��j���̂ЂƂЂ˂�̂����ɕ��������߂��邾�낤�B�\�\�B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܋�`�O�Z��y�[�W�j
�����Œ�����A�s���z�t�̐l�`���W��1970�N2�����q���E�̐l�`�r�́u�l�`�ƕ�炷�R�@�l�J�V�����\�\�Ƃ��ꂽ�ߋ�v�ŁA�O�̂̐l�`�i�x�����[���̐l�`�ʐ^���Q�Ƃ��Ė͑��������́A���̓��g��̖{�i�I�Ȃ��́A�}�O���b�g�ւ̈������߂Ă��������́k�ƂƂ��ɗ���Җ{�l�l�j��5�y�[�W�ɘj���ďЉ��Ă���i�ʐ^�B�e�͐Ό��ה��j�B�g���͂����葁��1968�N6���A���\�Y���������́s�R�䐳��t�Ŏl�J�V�����̏��`���ςĂ��邩��A���҂Ƃ��Ēm�����̂���ł���B�q�������r�i�F�E10�j�̏��o�́s�����V���t1969�N11����������A�g���̓x�����[������ăV�����̐l�`�Əo��ׂ����ďo������Ƃ����悤�B�ł́A�g���ƃV�����͂��o������̂��B�q�l�J�V�����N���r�ɋ���A1969�i���a44�j�N�A25�A�u���̍��A���c���a�q�A����C���A�g�����k�c�c�l���m��v�i�sSIMONDOLL�t�������A2014�N5��31���A��ܓ�`��O�y�[�W�j�Ƃ���i�Ȃ���o�s�l�J�V�����O�ҁt�́q�l�J�V�����E�v���t�B�[���r�ɂ́A���l�̎�|���O�N��1968�N�̍��ɏ�����Ă���j�B�g�������z�ɏ����Ă���悤�ɁA�݂��Ɏh��ʂ����̂����ǂ��ł������̂��͂͂����肵�Ȃ����A�V�����́q���L�E���Z��N�ār�ɋ����[���L�ڂ�����i�g�����̓��L�ɓo�ꂷ��l�J�V�����Ɋւ��ẮA��2���Q�Ɓj�B
���L�����Z��N������\����
�@�V�h�I�ɍ������X�ɂċg�����̎��W���i320yen�j�B����Ǝ���ǂޑO�Ɏ��_�Ǝ��`���ɓǂ�ł��܂����i���x�̎��Ŏ��͖{�Ƃ������̂�K���㏑������ǂނ���������j�B���̎��`��ǂ݂���ƂȂ��ނ˂��܂点�����ł��낤�B�n���S�̏a�J�ʼn���Ă������������Ȃ��牺�̍L��Ŏ��Ƌg�������A���������Ă��鏊���ڂɂ���B
�@���̖�A�g�����ɓd�b�����č����̂�����b�����B�g��������낱��ł���l�q�A���͖������L����������E�߂���B���łɑS���W���Ă��炤���ɂ����B����Ƃ₳�������̒ʂ����l�Ԃł��낤�B����l�l�Ԃ�m�肦���B���̋g�����ɑ���C�����������ɂȂ����B�����̓��L���A����ŏI��Ƃ����������A����Ƒ傢�Ȃ�n�܂�ł��낤�B
�k�c�c�l�k���Ȃ݂ɁA�q���L�E���Z��N�ār�͂��̓��̋L�ڂ���n�܂�B���҂͋g���̒������������^�������̂Ǝv�����B�l
�@�����O�\���
�@�c�����z�ɉƂ����ɂ䂭
�@����Łk���c�l���a�q�Ƌg�����ɉ
�@�g�������S���W�𑗂���
�@��@�������J�ɍs��
�@���k�\�Y�l�����A���i�s�@�B�d�|�̐_�t�C�U�����[�A1978�N10��30���A���`���y�[�W�j
�g���́q�Q�@�l�J�V�����r�Œ��ڂ������̂́u���̏����l�`�́A�x�����[���̋��̂Ɗ߂��݂��ƂɍČ����A���ׂ��ׂ̌ҊԂɂ́A�����������܂�Ă���v�Ɓu�A�тƔ鏊��U�R�Ƃ��炵�Ă����v�Ƃ����ӏ��ł���B�V�������q�����������l�`�̂��b�r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��邩�炾�B
�u�ڂ��͏��߂��瑼�̐l�`��Ƃ̍����Ȃ�Ă��̂�����A�ǂ�Ȃ�Ă��Ƃ͑S�R�Ȃ������킯�Ȃ�ł��B��������ɐF�X����Ă��āA�x�����[���ɂ͂��Ƃ����Ƃ������ƂȂ�ł����A�x�����[���̐���̂����Ă̂͂������Ǝv���܂����ˁB�����Ă���Ƃ�����Ȃ��āA�p�b�N���Ƃ��������ŁA�`���Ƃ��Ă��悩�����ł��ˁB����Ƃ��ƉA�т̕����ł��ˁB�l�`�ɖт����Ă���Ƃ����̂͂����ł��ˁB�c�����Ƃ��Ă��锧�ɖт���{��{�A�����ɂ������Ă���Ȃ��Ă����悤�ɁA�T���T���T���Ă��������ɂȂ��Ă���̂���Ԃ����ł��ˁB�t���[�Ƃ��Ă�����Ă����̂��ȁA���������A�тĂ̂͐l�`�ɂƂ��Ă���������ł���B�x�^�[�ƉA�т��͂���Ă���Ƃ����̂͑S�R���߂ł��ˁB�тƂ����̂͂ނ��������ł���B���т��Ⴈ���������A������x�̒����������āA�Ȃ݂����Ȋ����ɂȂ��Ă��Ȃ��Ƃ��߂ł�����ˁv�i�s�V�����̃V�����t�C�U�����[�A1977�N8��25���A�Z�l�`�Z�܃y�[�W�j�B
�P�l�X�E�N���[�N�����Ƃ���́gnude�i���̑��j�h�ɑ���gnaked�i�͂����j�h�̕���ǂ��Ƃ���V�����̉A�т̍D�݂Ƌg���̂��ꂪ�����Ȃ̂͋����[���B�F�V���F�́q�V�Ղ�r�i���o�́s�����W���[�i���t1978�N5��5�����B�P�s�{�ł͏��o�Ɉꕔ�A���M����j�ɂ�������B

�^�����F�V���F�̃G�b�Z�[�s�ߕ������t�i�s�����W���[�i���t�A�ځj�̐蔲�����萻�{�������q�̕\��
�u�g������͎��̉Ƃւ���Ȃ�A�^�u�����̓|���m�������Ă��炢�ɂ����B���݂̂Ƃ���ɂ́A�������邾�낤�Ǝv���Ăˁv�ƌ����o���܂����B�^������k���q�̓V�Ղ牮�ɍs���̂Ɠ��l�l�O����̖������̂ŁA���͏��ɂ���A�Â��̂�V�����̂�A�|�p�I�Ȃ̂�ʑ��I�Ȃ̂�A�A�����J�̂�t�����X�̂�A�ʐ^�̂�G�̂�A���낢���葵���Ă��ăe�[�u���̏�ɐςݏd�˂܂����B�^�k�c�c�l�^�g������͉���������o�����ዾ�������āA�A�����J��t�����X�̎G�����ς�ς�߂���Ȃ���A�ЂƂ育�Ƃ̂悤�ɁA�^�u����܂�ѐ[���̂�A����ڂ��͂����茩����悤�Ȃ͍̂D������Ȃ��B���Ƃ������A�ӂ�ӂ�Ɛ����Ă�̂��D���Ȃȁv�ƌ����܂����v�i�s�ߕ������t�����V���ЁA1979�N2��25���A���l�`���܃y�[�W�j�B
�g�����V�����̐l�`�����������`�Ղ͂Ȃ����A�F�V�̓V�����l�`���������Ă����B�F�V�@�̏��ւ́A���J���ꂽ�ʐ^������킩��悤�ɁA���Ȃ�L���B���Ȃ݂ɁA�g���v�Ȃ͓s�S�̃}���V�����Z�܂����������߂��A�N�W�������̕��͚����Ε��ȂǁA��肠�����U��ȍ����������B
![�s���z�t1991�N4�����q���W�E�F�V���F�̐��E�\�\Encyclopedia Draconia�r�f�ڂ́q�V�u�T���E�R���N�V�����@�l�J�V�����̏����l�`�r�i�ʐ^�E�]�p���j�Ǝl�J�V�����q�l�`�r�̌��J���y�[�W](image/simon-doll_01.jpg) �@
�@
�s���z�t1991�N4�����q���W�E�F�V���F�̐��E�\�\Encyclopedia Draconia�r�f�ڂ́q�V�u�T���E�R���N�V�����@�l�J�V�����̏����l�`�r�i�ʐ^�E�]�p���j�Ǝl�J�V�����q�l�`�r�̌��J���y�[�W�i���j�ƓW����qSIMONDOLL �l�J�V�����r�i���������p�فA2014�N5��31���`7��6���j���ɏ���ꂽ�F�V���F�̏ё��ʐ^��u�҂ݏグ�̍����C�v�̓������K���X�P�[�X�i�E�j
�q���ׁr�ɂ��āA���Ď����q�u�g���̏����v�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i15�j�\�\�q�������r�r�ɏ��������Ƃ�����i��3�j�B�{�e�ł́A�g�������l�J�V�����̏͋���ǂ̂悤�ɝf���������������ׂ��A���ׂ�����������̎���̓T�����f����B���Ȃ킿�A�����̏��o�`�i�s���̐����͘_�҂̕t�������C�i�[�j�������ċg���̎���Ƀ����N��A�����N��ɃV�����̌��T����ׂ��B�o�T�͎�Ƃ��Ďl�J�V�����̒����A�s�V�����̃V�����t�i�C�U�����[�A1975�N1��31���k�����F1977�N8��25���l�j�Ɓs�@�B�d�|�̐_�t�i�C�U�����[�A1978�N10��30���j�ł���B�Ȃ��A���o����e�̈ٓ��̏ڍׂ��q�g�������W�s���[���h���b�v�t�{���Z�فr������ꂽ���B
���ׁi�K�E6�j�k���o�`�l
�@�@�@�@�@�i�l�`�͔�������j�l�J�V����
00
1
�Ă��߂� 01
�@�@�@�@�H���߂� 02
�@�@�@�@�@�@�@�@�u���Ԃ̍��� 03
�Ⴊ�~�� 04
�@�@�@�@���e���{�[�Ƃɂ���ł���v 05
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�̒[�́i��Ў��m�����܂��Ƃ��n�j 06
�U�������̊�d���̐��̈ł��� 07
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽���͐��܂ꂽ 08
�i�����m�͂ɂ��n�j�̔������q���� 09
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�_�͋}�ɏo�Ă����v 10
�i��E�튯�I�Ȑ����j�� 11
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���q�m�͂����n�j�@�ЂƂ��� 12
�l�`�͐l�ɕ������ 13
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ߍX���m�����炬�n�j�̖�� 14
2
��e�̈�ۂ� 15
�@�@�@�@�@�@���d���̉��� 16
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���h��̏���m�̂悤�� 17
�Ԃ����[�����蕨�Ɍ����� 18
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�J�~�\���ŃT�[�ƂȂł�� 19
������܂����F�̓��[�� 20
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k����Ԃ��Đ��܂�Ă���v 21
����Ɋ��݂����� 22
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽���͏����s�ǂ̎q�� 23
�i���q�m���炱�n�j�̎O�܂�l�`�� 24
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w������ 25
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�钎�̉��F�ɒ����ق�� 26
���e�͗�����������Ă� 27
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ŕw�������`�j�������� 28
���@�C�I������[�� 29
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�[�E�L�[�E�M�[ 30
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�V�����ǂ�ǂ��Ȃ�v 31
3
���܂œ͂��Ȃ����̌� 32
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�[�i�E�V�����̉S���D�� 33
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D������݂́i��H�m���Ȃn�̑f�e�m���낤�����n�j���D�� 34
�u�ł��^�J�̃x�b�h�� 35
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽���͎т̂悤�� 36
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����z��g�ɂ܂Ƃ��ĐQ��v 37
�Ԃ̂悤�� 38
�@�@�@�@�@�u���₩�Ȏ_�f�Ɉ͂܂��v 39
�@�@�@�@�@�����̋P����������]������ 40
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�[�E�A�[�E�A�@�[ 41
�i���\�I�Ȑ����j 42
�@�@�@�@�@�@�@�@�u�l�`�ɂ����� 43
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߐH�Z���K�v�ł���v 44
�g������H�ׂ���͗҂��� 45
�@�@�@�@�@���̕����̊O�� 46
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ș@�r�̐Î���v�킹��v 47
4
�u�҂ݏグ�̍����C 48
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɂ͔Ƃ������� 49
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���I�j�ȉe�����݂���v 50
�i�y���j���߂Â� 51
�@�@�@�@�@�@�@�@���̂����点���Ȃ��c�c 52
��00�s�߁@�i�l�`�͔�������j�l�J�V����
���͂��̐l�ƌ|�p�Ƃ��l�`���̘b�����Ă��āA���̐�������`���Ă��̎��u�l�`����������v�Ƃ������悤�Ȏ����ł��l�������Ƃ��Ȃ���ȃC���[�W�������B�\�\�q�l�̌N�̖��͓��L�r�s�V�����̃V�����t�l��y�[�W
��01-02�s�߁@�Ă��߂��^�H���߂�
���̔w���ɓ�̎�ꕨ��������ł��A�ŏ��͉����y���̂ł����Ɏ���܂킵�Ă����ɐG��邪�A���̂����ɒɂ݂��o�n�߁A���]���|�̋ꂵ���𖡂킢�A��ꕨ�͔^��s��ᎂ̂悤�ɂȂ��Ă��܂��A���͉������A���≽�������낹�ŕ�炳�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�A���M���������������������A�H�ו��͍A��ʂ炸�A�₽�����݂̂̐����������A�~���߂��t���߂��A���낻�돉�Ăɂ��������鍠�A�^���w�����Ƃ߂ǂȂ�����n�߁A��ꕨ�̒��̐�������忂��B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t��Z�y�[�W
��03-05�s�߁@�u���Ԃ̍��Ɂ^�Ⴊ�~��^���e���{�[�Ƃɂ���ł���v
��̎O���Ŗ�B�����h��Ă��đ��Ԃ̍��ɐႪ�~���Ă��āA���e���{�[�Ƃɂ���ł�B�\�\�q�݂ɂ������̍l�@�r�s�V�����̃V�����t��l��y�[�W
��07�s�߁@�U�������̊�d���̐��̈ł���
�@������������́A�Ԃ��e���g��n�ׂ��ɗ��ĂĘH��Ŏŋ�����̂���ł�������A����ɂ͐��]����A�J�̓��͂ʂ���݁A�^�ẴA�X�t�@���g�̎�������A�����֎��͐U���p�ŏo�čs���̂ł��B�O���Â��Ȃ�Ȃ��Ǝŋ������܂���ł����̂ŁA�r���̂��������Ƀl�I���������鍠�̊J���ł����B�\�\�q���Ƃ������Ɓr�s�@�B�d�|�̐_�t�O�O�y�[�W
��10�s�߁@�u�_�͋}�ɏo�Ă����v
�_�͋}�ɏo�ė���̂��B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t����y�[�W
��16�s�߁@���d���̉���
�@�����V�䂩��́A���Â��d�����A�Ԃ牺�����Ă��邾���ŁA�ǂ͌ł��R���N���[�g�A���ɂ͔����o���̕֊킪�ЂƂu���Ă���܂��B�\�\�q��l�̂��d�u���r�s�@�B�d�|�̐_�t�l��y�[�W
��17�s�߁@���h��̏���m�̂悤��
�ڂ��͐키���A����m���D���ł��B�\�\�q�݂ɂ������̍l�@�r�s�V�����̃V�����t��l��y�[�W
���Y����鎄�͔��h��̏���m���������A�ǂ�߂��l�X�́A�ڂ̑O�ɏ������ƍ����Ă����q�������̂�����B�\�\�q�l�`�͔��������ɂÂ���r�s�@�B�d�|�̐_�t��y�[�W
��18-21�s�߁@�Ԃ����[�����蕨�Ɍ�����^�u�J�~�\���ŃT�[�ƂȂł�Ɓ^������܂����F�̓��[���^�k����Ԃ��Đ��܂�Ă���v
���̃o���̐�m�͂ǂ������̏��N�Ɏ��āA����͐Ԃ����[����蕨�Ɍ����邩��ł���B�Ԃ��J�~�\���ŃT�[�ƂȂł�ƒ�����܂��A���F�̓��[���v��j�����悤�ɐ��܂�Ă���B�\�\�q���p���W�F���k�E�E�E�t�F���b�N�X�E���r�b�X�r�s�V�����̃V�����t���l�y�[�W
��24�s�߁@�i���q�m���炱�n�j�̎O�܂�l�`��
���{�̐l�`�ōD���Ȃ͍̂]�ˎ���̖��ғ��q�Ă̂�����܂��ˁB�O�܂�l�`�ɂȂ��Ă��āA���ݐl�`�Ȃ�Ă����Ă���l�`�Ȃ�ł��B�\�\�q�����������l�`�̂��b�r�s�V�����̃V�����t����y�[�W
��26�s�߁@�钎�̉��F�ɒ����ق��
���̉��͂��܂�ɂ��傫�����āA���̎��ɂ͕������Ȃ��B���������͂��̉����Ă���̂�������Ȃ��B�钎�̉��F�͐_�̉��B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t���Z�y�[�W
��27�s�߁A29�s�߁@���e�͗�����������ẮA���@�C�I������[��
�ޏ��k�l�̕�e�l�̕v�A�܂�l�̕��e�͑�����݂̃��@�C�I�����Ђ��A�ޏ��͖l�����w�Z�l�N���̂Ƃ��A�Ƃ��Ƃяo�����B�\�\�q�l�`�Ƃڂ��Ƃ̋��������r�s�V�����̃V�����t�܁Z�y�[�W
��28�s�߁@�i�ŕw�������`�j��������
�ޏ��k��l���D�ނ̂͋������A�o���v�^�̏��B���̋ɒv�Ƃ��āu�ŕw�v�������`�ɂ͑��h�ɋ߂������������Ă��܂����B�\�\�q�l�`�Ƃڂ��Ƃ̋��������r�s�V�����̃V�����t�܈�y�[�W
��30�s�߁@�L�[�E�L�[�E�M�[
�����@�k�N�̂�������́l�������Ȃ��Ȃ���������́B
�V�����@10�̂��낾����ˁA�������@�C�I�������L�[�L�[����Ă��ˁB���ꂾ�������Ă�B����ǂ������ˁB�y�t�����A�^���S������Ă��ˁB�k�c�c�l�^����Ȃ��ƁA�͂��߂Ęb�����ȁB���b����������Ƃ��������B�\�\����F���q�k�A�[�g'74�k�`�\1�l�l�J�V�������l�`�t�����߂����Ƃ��r�s�݂Â�t��827���i1974�N2���j�ܓ�y�[�W
��31�s�߁@�u�V�����ǂ�ǂ��Ȃ�v
�V���Ƃ͂���ȏ��Ȃ̂��낤���B����Ȃɂ������Ȃ̂��B���������͕K���A���ė������B���Ƃ����̐��ɂ���Ȃ������������Ă��A���͋A�肽���B���Ƃ��Ăł��A���ė������B�V���Ȃǂ���͂����Ȃ��B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t����y�[�W
��33�s�߁@�j�[�i�E�V�����̉S���D��
���ɂƂ��Ă̐t�͂܂��V�h�̃L�[���̎���ŁA�悭�j�[�i�E�V�����̃��R�[�h�������Ă����B���͔ޏ��̈��D�̂���̂�������D���ň��������ċ����҂�����R�[�h�W�߂ɂ�����ɂȂ��Ă����B�\�\�q�l�̌N�̖��͓��L�r�s�V�����̃V�����t�l��y�[�W
��34�s�߁@�D������݂́i��H�m���Ȃn�̑f�e�m���낤�����n�j���D��
�@���ꂩ�炸�[���Ɛl�`����n��o���āA�܂��[���̍��͖D������ݐl�`����Ȃ��̂�������ł����A�����Ń~�V����ŁA�Ȃ����A��̖ڕ@�������ƂƂ̂��āA���������Ȃ��Ƃ��肵�đS�R�����Ȃ�������ł��ˁB�\�\�q�����������l�`�̂��b�r�s�V�����̃V�����t�ܔ��`�܋�y�[�W
��35-37�s�߁@�u�ł��^�J�̃x�b�h�Ł^�킽���͎т̂悤�ȁ^�����z��g�ɂ܂Ƃ��ĐQ��v
�ł��^�J�̃x�b�h�ŁA�A�[���̂����z���̃x�b�h�ŁA���͎т̂悤�Ȕ����z��g�ɓZ���ĐÂ��ɐQ�����B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t���y�[�W
��39�s�߁@�u���₩�Ȏ_�f�Ɉ͂܂��v
���́A���₩�Ȏ_�f�ɐg�̂��͂܂�Ă���B�\�\�q���Ȃ���ցr�s�@�B�d�|�̐_�t����y�[�W
��40�s�߁@�����̋P����������]������
�@�V�˂ł��邪�̂ɏ��܂����l�`�̂ݐ��U�̌Ȏq�Ƃ��Ė��@�̐��ɐ�������������\�N�A���Ƃ���������̌Ȏq�̔��A���̊��炩�����Ȕޕ��A�͂ꂽ�C�ӂ̊������є��A���������鏭���̋����A����m�G�i�����n���̎����ق�̏��������p�炢�Ȃ����ᎋN�������F�̉A���ƃC���W�S�u���[����ڎg���Ɍ������鏭���A����̔������A���̂��Ȃ����A�₳����������~�܂邱�Ƃ�����ʋꂵ���ȏ����̕����A�]��D�܂݂�̖ځA�����炢�̎�����p�m���}�����鎩�ݐl�`�̃��}���͊w�A�֊s��_�ɔ��炵���낪�鐅�C�̂Ȃ����A�̂�ؒf���閜�͂ɂ�郏�C�Z�c�ȎE�C�A�_��̗[���˂����ޔ��N�̕����A�_�݂���ӂ���͂��A�����ƐO�������Ă鋅�̂̂Ђ����݁A�̓�����̋�ɂA��ɂ�����₩�ȍ��܂ւ̗��B�\�\�q�v�l�̖�Ⴢ̓������r�s�V�����̃V�����t��Z���`��Z��y�[�W
��43-44�s�߁@�u�l�`�ɂ����ā^�ߐH�Z���K�v�ł���v
��͂�l�`�͈ߐH�Z�������ł��B�\�\�q�l�`�Ƃڂ��Ƃ̋��������r�s�V�����̃V�����t�l��y�[�W
��45�s�߁@�g������H�ׂ���͗҂���
���m���u�}�v�ɑ��_�n�^���m�I�N�T�}�n�@�o�^�[�m�A�u���n�@�t���C�m�A�Q���m�n�\�\�q�˂�|�G���ƃI�����c�ۂ������r�s�V�����̃V�����t���y�[�W
��46�s�߁@���̕����̊O��
���͂ƌ�����
���̕����̊O�ɂ���
�J�[�e���̂�����ꂽ���������Ǝ���Ă���̂ł��B�\�\�q���̐��@�r�s�@�B�d�|�̐_�t�����`����y�[�W
��47�s�߁@�u����Ș@�r�̐Î���v�킹��v
�@�̉Ԃ��炢�Ă��āA�����ŋx�����Ƃ��̂��낤���B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t����y�[�W
�@���͂ǂ��܂œ͂��̂��낤���B���͒��̂悤�ɏ������B�i���͓G���B���ɂ͓G������B���͉i�����D�����B�i���Ƃ͋������B�`���鋗�����B�_�ɂ͋���������̂��B���ɂ͂킩��Ȃ��B��������Ȃ����E�A�����̐��E�A�Â��Ȑ��E���B���������̐��͐Â��ł͂Ȃ���������Ȃ��B����������ƕ������������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����������B�_�̉����B�\�\�q�V�����X�L�[�̎�L�r�s�V�����̃V�����t���Z�y�[�W
�@���̍��A���a��\�ܔN���́A�܂��̂��̂����Ă����B�������A�����Ƃ����Ƃ������������B�����͋����A�������̓X���܂��̂����Ă������A�����ȏ����X���M�b�V���ƌ�����˂Ă����B���̍��̕s�E�r�����������B�^���Ă̖��̗��Ȃ�Ƃ��ꂢ�ŁA�@�̉Ԃ̂Ȃ�Ƒ傫�����������B�^���d�_�����玵������ʂ��čL���H�̉f��قɁA�e�̋��������˂���ʁm����n���Ă������́A�Ă̕s�E�r�B�\�\�q�܂���r�s�@�B�d�|�̐_�t�Z���y�[�W
��48-50�s�߁@�u�҂ݏグ�̍����C�^����ɂ͔Ƃ��������^�i���I�j�ȉe�����݂���v
���炳��Ƃ��������A����ɃK���X�̐���A����ɐl�`���g�̂ɂ�����̂ň�ԑ厖�Ȃ̂��҂ݏグ�̍����C�ł��B���������ɔƂ�����I�Ȃ��̂�����݂����ł��ˁB�\�\�q�����������l�`�̂��b�r�s�V�����̃V�����t�Z��y�[�W
��51-52�s�߁@�i�y���j���߂Â��^���̂����点���Ȃ��c�c
�k�c�c�l�n���̂��������ɂ��̂�����̂���ł������y�������̂����点���Ȃ��߂Â����ς��Ɍ������Ƃ�����k�c�c�l�\�\�q�C���r�s�V�����̃V�����t�Z�y�[�W
06-08�s�߂ɂ͓T������������Ȃ��B�O�f�q�l�J�V�����N���r�ɓ����E�ܔ��c�̐��܂�i�����A��ܓ�y�[�W�Q�Ɓj�Ƃ��邩��A�l�J�V�������u�킽�����v�i��e�ł́u�킽���v���u�킽�����v�Ɖ��߂��j���u�r�V�[�́i��Ў��m�����܂��Ƃ��n�j�^�U�������̊�d���̐��̈ł���^�킽�����͐��܂ꂽ�v�Ƃ����̂́A�g���̎��I���\���낤�i�������s�V�����̃V�����t�́q�l�̌N�̖��͓��L�r�Ɂu���݂������炿�̓�l�́i���m�\�Y�n�͏��Ŏ��͒r�̒[�������Ő��܂ꂽ�j�悭�q���̍��̏�b�m�͂Ȃ��n�����ẮA�k�c�c�l�v�i�����A�l�l�y�[�W�j�Ƃ��邩��A�g���͂���ɋ������̂�������Ȃ��j�B�u�ܔ��c�Ƃ����y�n�́A���܂ʼn��̂Ȃ��Ƃ��낾�����B�Ƃ��낪��Ђ��|�Y�������߂Ɏ��E���A��N�k1979�N�l�A���͂��炭�̊Ԃ��������A�ܔ��c�����E�ƈ��菊�֒ʂ��͂߂ɂȂ����B���ƕی�����Ⴄ���߂������B���̋A��݂��A�r�c�R�̏������ō��̉Ԃ��������Ƃ��������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l�`�܃y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�g���͌ܔ��c�ɂ͓���݂��Ȃ������B�܂�1979�N���A�ܔ��c�i�����炭�͓암�Ï���فj�̌Ï��W�ɏo�i����Ă������g�̒����s�����G�߁t�i1939�j���ЂƖڌ������Ǝv���āA�����֍s���Ă���B���������s�ē��ȓy�n�������̑Ώۂ���l���̒a���̒n�Ƃ��邱�Ƃ��S�O�����������̑[�u���낤�B����A�g���̐��z�q�����ؒʍ�r�\�\���o�́s���������{ 22 ���w�̔w�i�t�i���E�����ЁA1982�N�k�����L�ڂȂ��l�j�́q�q�k�C���E���k�E�֓��E�����r�Y���̂��܂����r���̈�с\�\�́u���͏��L���H�܂ŕ����A�r�V�[�̘@�ʈ��֊�����B�X���O�́w��x�̂Ȃ��ɁA�����Ώo�Ă��鋼�����ł���B�]�˖���������̓X�ł���炵���B�����߂��ɁA�@�̑����s�E�r������v�Ƃ������͂ŕ����Ă���B�g���ɂƂ��āA��R���ɕ�����Ă����\��㔼�A�����̂悤�ɉ��������Ă��������`�r�V�[�`���L���H������Ȃ�A�����w���悤�Ȃ��̂��B���ꂪ06-08�s�߂ɒr�V�[���o�ꂷ��w�i���Ǝv����B
11�s�߂́u�i��E�튯�I�Ȑ����j�v�̓h�D���[�Y���K�^���́u�튯�Ȃ��g�́v���v�킹��B�l�J�V�����̒���ɓo�ꂵ�Ă����������Ȃ����A�u��E�튯�I�Ȑ����v�ɂ���u�튯�Ȃ��g�́v�ɂ���A�V�����̐l�`�ɑ��鑼�҂̕]���T����������Ȃ��B
12�s�߂́u�i���q�m�͂����n�j�@�ЂƂ����v�̔��q�́u�q���̂����̈�B�z��D�����킹�A���ɖȂ����Ԃ�V�̂͂��p�ɂ����ǂ������́B���܂��B�͂��͂��l�`�B�͂����v���Ƃ����B�ЂƂ����͐l�`�E�l���ŁA�u�l�̌`�B�l�̌`�Ɏ����č�������́v�B���q���u�͂��͂�����Ԃ�V�v�ł�����_�A�ЂƂ������l�ł�����l�`�ł����邱�Ƃ͋����[���B09�s�߂́u�i�����m�͂ɂ��n�j�v���u���A�z�B�ӂ��Ȃ�v�������悤�ɁA�u�킽�����v�͗��҂̋��E��ɑ��݂���҂ł���B
14�s�߂̉A��u�����炬�v�́A�����ł͂ӂ��u�@���v�u�X�߁v�u�ߍX���v�Ə����B�u�ߍX���v�Ƃ����̂͋g���̑���̉\��������B���Ȃ݂ɓ̋G�ꂩ��������E���A����i������j�A�`�����A�������Ȃǂ����邪�A�g�����������ق̂߂����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B
45�s�߂́u�g������H�ׂ���͗҂����v����́A�܂����������Ċ�ȘA�z���Ə�ꂻ�������A06-08�s�߂ł��G�ꂽ�r�V�[�̋������E�@�ʈ��̂����g�������z�N�����B���X��1860�N�i����6�N�j�̑n�ƁB�����̕�����֓��g�E�v�ۓc�����Y�E�r�g�����Y�������������X�����A���Ă͒m�炸�A���ƒl�i�Ɋւ��Ă͌���ʂ��ԂƂ������̂��낤�B
�Ƃ��Ɂu3�v�̌㔼����́A���e�ɂ����Ԏ肪�����Ă���̂ŁA�ȉ��ɒ�e���f����B�Ȃ��������͒�e�Œlj����ꂽ����ł��邱�Ƃ�\���B
���ׂ��Ԃ̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�u���₩�Ȏ_�f�Ɉ͂܂��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�����̋P����������]������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�[�E�A�[�E�A�@�[
�i���\�I�Ȑ����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�u�l�`�ɂ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߐH�Z���K�v�ł���v
4
�g������H�ׂ���͗҂���
�@�@�@�@�@���̕����̊O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����Ș@�r�̐Î���v�킹��v
�����@�H��
�@�@�@�@�@�u���̂����点���Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�y���j���߂Â��v
���߁m�X�g���t�n�̐�����ς�����̂����邱�ƂȂ���A���e��
�u�҂ݏグ�̍����C 48
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɂ͔Ƃ������� 49
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���I�j�ȉe�����݂���v 50
���������ꂽ���Ƃ��ő�̑���ł���B����3�s���폜���ꂽ���R�ɂ��čl���Ă݂����B���̓V�����l�`�����ׂČ����킯�ł͂Ȃ����A�����̐l�`�������Ă���C�̓X�i�b�v�{�^�����߂̏��̎q�p�̃t�H�[�}���V���[�Y�ŁA�u�҂ݏグ�̍����C�v�𒅗p���Ă���̂͏��N�̐l�`���Ƃ������Ƃ͎w�E�ł���B�Ƃ���ŁA�g�����̎��т��f�ڂ������o�̈�����ōł������������̂́A�s���[���h���b�v�t�́q�▋�r�i�K�E9�j�̔��\�}�̂ł���~�؉p���̃I���W�i�����ʼn�W�s���X�̘f���t�i�M�������[�v�`�t�H�����A1986�N12��3���j�ł���B���͂�����w���������ŁA�����܂����݂������~����̐V��W���a�J�̃A�[�g�X�y�[�X�������Ŋς��B�K�^�ɂ������ŁA���o�̎l�J�V��������q���ׁr���o�Ό��y�[�W�f�ڂ̓��ʼn�i�傫�ȖX�q�����āA�t�����̕t�����h���X��Z���A�Z�߂̃n�C�\�b�N�X�ɃX�i�b�v�{�^�����߂̃t�H�[�}���V���[�Y�𗚂��Ă��鏭���A����Ƃ������̐l�`�H�j�͂��܂����ƌ��J���ɂȂ����̂ɂ������A�g�����G���ςĎ����������킯�ł͂Ȃ��|�A�u�����Ƃ��ł����B�g���͏��o�̑Ό��y�[�W�̂��̍�i���ςāA�u�P���������v�����u�����v�Ɂu�҂ݏグ�̍����C�v�͂ӂ��킵���Ȃ��A�ƈ�u�ɂ��Č�����̂ł͂���܂����B���ꂪ�u�����̓��g��̗��`�́A��s��u�N�����āA�Ȃ��p���邱�ƂȂ��A�u���ł���v�Ƃ���́u�h�C�c�̏��N�v�i�q�Q�@�l�J�V�����r�j�ɂ������������тł���Ȃ�̖����Ȃ������͂����B����3�s���폜���邱�ƂŁu4�v�͖�����2�s�ɂȂ��Ă��܂��B���������āA���u3�v�Ƃ̃o�����X���Ƃ邽�߂Ɏ��߁m�X�g���t�n�̐����ς��A�u�����@�H���v��t���������̂���e�쐬���̋g���̎���ꂾ�����B�u�Ԃ̂悤�Ɂv���u���ׂ̉Ԃ̂悤�Ɂv�Ƃ����̂́A�W�肪�q���ׁr�Ƃ���ȏ�A�s�v�c�ł��Ȃ�ł��Ȃ��悤�Ȃ��̂́A�Ȃ��u���ׁv�Ȃ̂��͂��܂ЂƂs���Ƃ��Ȃ��B�l�J�V������2���̒����ɔ��ׂ͓o�ꂵ�Ȃ��i�����ōł��ڂ������͖̂��ł���j�B����͂悢�Ƃ��Ă��A���т̓������甖�ׂɂ��ǂ���Ȃ��̂��Ȃ�Ƃ����ǂ������B�u�l�`����������v����A���^�n�b�J�^���ׂ��Ƃ��v���Ȃ��B�W����߂���l�@�͍���̉ۑ�Ƃ������B
��
�g�����͐��z�q�{���������E�G�r�i���o�́s���t1978�N12�����́q�������̓����@MY TOKYO STORY�r�j���u�H�̂�����̌ߌ�A���͒n���S�̓����ō~��A�ؒʍ���̂ڂ����B�V���X�P�Ƃ��������������������ɂ����āA�Ȃ������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O���y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���B�V�����̕��͂��W�������s�l�J�V�����O�ҁt�ɏ��߂Ď��߂�ꂽ�q�Ă̓����Łr�i���o�́s�T�������t1990�N8��17�����q�C�̍������ԂƖ��ȓX133�\�\�V���X�P�r�j�ɂ͎��̂悤�ɂ���B
�@�����̃V���X�P�ɂ͂܂�������قǂ������Ă��Ȃ��l�����ǁA�ŏ��ɓ��������̕��͋C���ǂ�҂��Ⴞ�����̂��^�̂��B�X�̍�肪�����ς肵�Ă��ė������Ȃ̂��B���̐��̒��Ŗ{���ɓ����̐���T���̂͗e�Ղ���Ȃ��B�L���Ȃ��܌�墁m���邳�n���Ȃ��A�ڏ�肶��Ȃ��A�����������̂��Ė{���ɂȂ��Ȃ��Ă���B
�@����ōŏ��͋��s�̋A��ɍ����m�����݁n�i�]�g�ǎq�j���ɘA��čs�������āA���������̑��ŖK�˂��B���̖�͗F�����ƍD���ȓX�ɂ������̂��������đ啪�o���オ���Ă��܂����B��������ɓd�b����ꂽ��A������O��������Ƃ��Ă��āA���̐��̒��ɂ͂Ȃ����̂�����Ƃ����Ă����B����ō��x�͂ǂ����Ă����R�i�r���Y�j����Ƃ��ꏏ�Ɉ��݂����Đ�����q�̋A��Ɋ�����B
�@���R����̓C���h�N�w������Ă��āA�@�̌������ꐶ�̎d���̂悤�Ŗl�ɂ͂ƂĂ��Ȃ�����l�����ǁA��Ƃ��������͌����Ƃ����Ă���₳�����ϐl���B����ŏ��R����ɂ������Ă݂���]�˂ƏH�c�̗��V�����������Ă���X�Ƃ����Ă����B�l�̓V���X�P�Ɉ�ڍ��ꂵ�����������ꐶ�����ʂ�Ȃ�������B�i�s�l�J�V�����O�ҁ\�\Yotsuya Simon �n��E���z�E�����W���t�w�K�����ЁA2006�N12��20���A��܁Z�`��܈�y�[�W�j
���҂̈ӌ����ޕӂɂ��邩�͑[���āA���͂����1990�N5�����ɟf�����g������Ǔ����镶�͂��ƓǂB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
��1�@�s�Ẳ��t���^���т̎����⒐�L��E���āA�W��̂�����ɂ��镶���ɂ́\�\���A���і{���̌�ɂ��钐�L�ɂ́�����t���Čf�����B�����̎��ђ��A�莫�ɓo�ꂷ��l���̂����A���є��\�����̕��̎҂͋{��~�Ƒ���C���̂ӂ���ł���B
�ٖM�i�H�E5�j�\�\�փ��}���E�Z���G���g�̊G�ɂ悹��
�����i�H�E6�j�\�\�q���̛̂s�ޖ��͂��ɑ��l������߂Ă���r�@������b�q
���i�H�E8�j�������@���p��͎�ɁA�G�Y���E�p�E���h�i�V�q�r���j�A�ѓ��k��̏͋���ؗp�����B
���̖��{�i�H�E9�j�\�\�q�ڂ͎��Ƌ��ɐÎ~����r�@�r�c�����v
�����`�i�H�E10�j�������x�P�b�g�i�����N���j�A�y���F�Ȃǂ̏͋�����p�����B
�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�j�\�\�q����̏��L�҂͗J�D�Ƌ����ɐS��I�܂��r�@�ѓc�P��
���J�̎p������i�H�E14�j�\�\�u�ڂ��̓E�j�Ƃ��i�}�R�Ƃ��q�g�f�Ƃ������^�������Ƃ炦�����̂��^�����͂���瞙�瓮���Ɏ��Ă���v�^�ѓ��k��
�D���̎O�̒[�z�i�H�E16�j�\�\�u�C�}�[�W���͂����������ց^�������܂������Ɂ^�Ӗ��������Ƃ���v�^�{��~
�g�ҁi�H�E18�j�\�\�}��b�̂��߂̑f�`�̎�
�Ẳ��i�H�E20�j�\�\���e���O�Y�搶��
���̃A�X�e���X�N�i�H�E22�j�\�\���q���`�̊G�ɂ悹��
���q�A���i�H�E25�j�\�\����Y�̕����q���E�A���փ��`�[�i��r�Ɋ�
�u�Ɣ�������v�i�H�E27�j�\�\�u�����̂Ȃ��ɔ�т��ނ͍̂����v�@�@����C��
�~���̓����i�H�E28�j�\�\�u����Ƃ������̂͌ő́^���ł���Ɠ����ɔg���ł���v�@�剪�@�M�����i��㎵��E�ꁛ�E��j
��2�@�g�����́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�ɂ́u�l�J�V�����v��14��o�ꂷ��B�I�ȊO�͗v�Čf����B
�@1968�N6��22���A���\�Y���������́s�R�䐳��t�i�ԉ��_�Ёj���ȂƊς�B�u�l�J�V�����̏��`�̗d������������v�B�i�q7�@���\�Y��ƂƐԃe���g�r�A�ꎵ�y�[�W�j
�A1968�N7��3���A����r�q�̏��������s��ɉ��̂��Ă䂭���i�t�i������فj���ȂƊς�B�q�̎l�J�V�����̊������B�i�q9�@�A�X�x�X�g�ق̗d���r�A���y�[�W�j
�B1969�N11��15���A���c�l�������T�C�^���s�Ԃƒ��t�i�����N�����z�[���j���ς����ƁA�������J�̓��\�Y�̉Ƃ֍s���B�l�J�V���������������A�肪�n�܂��Ă����B�i�q22�@�u�Ԃƒ��v�̗[�ׂ̌�Łr�A�O���y�[�W�j
�C1970�N6��13����A����߂̉Ԃ�������������āA�l�J�V����������B�l�`��F�l�����̂��Ƃ�B�i�q23�@����߂̉ԁr�A�O��y�[�W�j
�D1970�N8��28���A�����S�ݓX�E�t�@�E���e���z�[���ŃR���N�V�����W�������q�y���F��ฑ哥�Ӂr�i�K�����������Áj���ȂƊς�B��Ŏl�J�V���������Ǝ�B�i�q24�@�u���]�哥�Ӂv�r�A�l��y�[�W�j
�E1970�N9��30���A������b�q�̗[�ׁi�m�A�m�A�j�֍s���B�u�l�J�V�����̋�������S�v�B�i25�@���h��̉��ʁr�A�l�O�y�[�W�j
�F1974�N2��24���A����̌m�Ï�J���ɍs���B�������Ȃ�A�l�J�V���������������B�i�q43�@��̖�̉��r�A���Z�y�[�W�j
�G1974�N11��28���A�V�A�^�[�A�X�x�X�g�ٗ����L�O�̔����[���������s�T�C�������t���ȂƊς�B�I����A��K�Ŏl�J�V���������Ǝ����B�i�q46�@�u�T�C�������v�r�A�����`����y�[�W�j
�H1978�N7��9���A���R�r���Y�v�ȁA�y���F�v�ȂƑ�Ŏ��Y�L�O�ق������B���c�l�v�Ȃ̐s�͂��F�V���F�v�ȁA�푺�G�O�v�ȁA���\�Y�E�����v�ȁA�l�J�V�����Ƌ����̈�[�B���[���J�Łu�R�[�q�[���݂̂Ȃ���A�l�J�V�����̉S�ɒ����ق�A�����ʂ�����ށv�B�i�q58�@�`�y�����́z������u�����Łr�A����`���O�y�[�W�j
�I�q���L�r�@��㔪��N��\���
�@�[���A����̐؉�L�֍s���B�l�J�V�����l�`�W�k�q�����[���E�����[���r�l���ς�B���������̗��`�̎O�̂ɂ́A���_�����犴����ꂽ�B�߂��̋i���X�ɐȂ����炦���A�����r�Y�A�n�ӌ��l�A����v���q�����Ƃ�����ׂ�B�x����F�V���F�v�ȂƋ��q���`������ꂽ�̂ŁA�����ȉ����₮�B�i�q67�@�V�����l�`�r�A��O��`��l�Z�y�[�W�j
�J1985�N2��19���A�l�J�V�����̂��߂ɏ��������сq���ׁr�𐄝Ȃ���B�i�q92�@�u���̌��v�r�A�ꎵ��`�ꔪ�Z�y�[�W�j
�K1985�N12��10���A�]�������܂����o���̍����r�Y����ȂƖK��B���q���F�V���F�v�ȁi�u�F�V���F�Ƃ́A�V�����w�l�`���x�o�ŋL�O��ȗ����v�j�A�l�J�V�����B�i�q103�@�\�͎c���Ȍ��r�A��㎵�`��㔪�y�[�W�j
�L1986�N1��18���A�ȂƓ������q���t���a�@�ɓy���F���������B�y���́u�E��������ĕʂ��������B�i�����̈֎q�ł͎l�J�V�����ƌÑ�r�����҂��Ă���v�B�i�q104�@�Â��V�t�r�A��Z���`��Z��y�[�W�j
�M1986�N1��21���A�y���F�e�Ԉ����̕�œ��@��ɋ삯����B�u�O�K�̑ҍ����i�����̂�����ɂ́A����Y�E�c�l�A�����A�����ĔV�A�l�J�V�����͂��ߑ吨�̐l���߂����Ă����v�B����A�̍d�ϊ̑��������œy���F�����A�\���B�i�q104�@�Â��V�t�r�A���Z�`����y�[�W�j
��3�@���͂��́q�������r�]�߂́u�V �q���ׁr�v�ŁA�g�������ɂ�����u�l�`�v�̕ϑJ���T�ς��A�q���܂�����\�\�k�������h�s����t�̈�ێ��сr�i�G�E30�j�̎��̎�����������B
�E���_�I�ȏ��͐l�`������^�u�ؖс@�n���R�@�˕��@���ȂǂŁ^�`�Â�������ā^�X���@�Ƃ��ɂ̓������X��v�^���݂����Ƃ��K�v�Ƃ���^����ȓ������������@�葫���Ƃ肩���^�����̉�ł͍s��ꂽ
�����āu�����ʓ��͐���ɂӂꂽ�l�`��ҁi�l�J�V�����H�j�̕�����̈��p�ł��낤���i���Ȃ��Ƃ��x�����[���̕��͂ł͂Ȃ��������j�v�Ə��������A����ɑ�������͋�͍���A�l�J�V�����̎�v�������ēǂ��������茩������Ȃ������B��͂肱�̈��p��͓V���E�V��m���܂��n�̐�����@�ł����āA�V�����h�[���̂���ł͂Ȃ��̂��낤�B�l�J�V�����́u���̐�����@�v�����̂悤�Ɍ���Ă���i���o�F�s����̊�\�\���������ߑ���p�كj���[�X�t538���A2003�N2���j�B
�@ ���̐�����@�́A�܂��S�y�Ō��^������A�p�Ō^����������̂ɘa�������w�ɂ����荞��Ŋ���������B�����O��Ŋ����Čq�����킹�����̂ɍ�Ƃ����Ă����܂��B�w�̒܂��̕\��ȂǍׂ����d���ɂ͋ˑY�m�Ƃ����n�A��̓K���X�ŁA�̃{�[�������ꂼ��̊߂ɂ��܂��B�g�̑S�̂ɂ��ˑY���{���A���ꂢ�ɖ�������������͌ӕ��m���ӂ�n��p���܂��B��h��ӕ��Ŕ��F��\�킵�܂�����ו��̍ʐF�A�܂��͔��A���ꂩ��j�ɉ��ϕi�̖j�g�����荞�݁A�ʖт���{��{���ߍ��ށB�j�g�����荞�ނƁA���̋C���p�b�Ƒ����āA�����A�Ǝv���܂��B�i�q���̐l�`�j�r�A�s�l�J�V�����O�ҁ\�\Yotsuya Simon�n��E���z�E�����W���t�w�K�����ЁA2006�N12��20���A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j
�˖{�M�Y�́s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j���߂����āu���ؖ{�A���Y�N���f�U�C���͖ڎ��܂ł��G���A���Ƃ͈ӏ��͒W�ɂ����Ă��т����B���Ƃ��F�숟��ǂ̉A�S�ȃJ�b�g�Ȃǂ����瑊�E����ċp�Ė��Ӗ��ɂ��Ȃ邾�炤���v�i�s�i�ًR��\�\���R�C�i�_�E���ȏW�t�A�V���فA1974�N7��10���A��l��y�[�W�j�Ə������B�g�����̎��i�˖{�͏I���A�q�m���r�����������Ă����j�Ɠ��ނ̂��̂Ƃ��ĉF�숟��ǂ̃J�b�g�����Ă����킯�����A���̔��z�����Ȃ��������̂͂Ȃ����̂��A���˂Ă���C�ɂȂ��Ă����B1967�N�����A�F��Ƌg���Ƃ̊ԂɘA�q���������悤�ɂ͌����Ȃ����炾�B�ŋ߁A�F�숟��ǂ̃C���X�g���[�V�����������c���j�́q�V�E�Y�q�`�r��m��ɋy��ŁA���ꂪ�˖{�̔��z�̌��������̂ł͂Ȃ����A�Ƒz���������B�܂��ŏ��ɁA�q�V�E�Y�q�`�r�ɐG�ꂽ�F�숟��ǂ̕��͂��������i�u�����v�̓T�E�X�|�[�ł���F��̔o���j�B
�����j�L���̍��̂�����䂭�@����
�@�o��Ƃ������{�̒�^���Ɋ��������̂́A�O�\��̏I���ł����B
�@���c���j����Ƃ����o�l�ƁA�w�Y�����Y�x�Ƃ����G�{��������Ƃ��ł��B���m�ɂ����ƁA�c������E���������E�i��ꐳ�E��{�B�l�Ƃ������l�����ƍ�����w���{���b�O���t�B�b�N�x�Ƃ����G�{�̈�̃p�[�g�ł����B
�@���c����̋�́A�ŗL�̏�i���d�˂āA�Ō�ɂ͑取�����I�ȁw�V�E�Y�ׁm���炵�܁n�q�`�x�ɂȂ��Ă��܂����B
�@���Ƃ��A�u�v�M�Ɍǁm�ЂƁn��Z�m���n���g�m�Ёn�����̂��炵�܁v�Ƃ�����B�v�M�͂��܂���{�I�ł͂���܂���A�k�̂ق��́A������Ñ�I�ȃC���[�W�ł��B���̏M���A���̌��̂悤�ȁA�o���b�N�I�Ȍ`�Ԃ̓��A���Ă����傩��n�܂��āA�u�����̐��I���K����N�O�Ɩʗւ������m���n���v�Ƃ�����ŏI�����}���܂��B���R�̂��Ƃł����A���ꂪ���w�I�ŁA�Úg�̓I�u�W�F�I�ł�����C�����܂����B
�@���̂��Ǝ��R�C�i�̋��ǂ肷��ƁA�ǂ����o��͈ꉞ�̒�^�͂��邯��ǁA���\���R�Ȃ��̂炵���Ƃ����C���ɂȂ��Ă��܂����B
�@���̃R�����Ŕo��炵�����̂����[�h�R�s�[�̂悤�Ɏg���Ă���̂́A�G�ƕ��͂Ƌ�̂悤�Ȃ��̂ƁA�O�����ꂼ��A���Ƃ��Εʂ̂��Ƃ������Ă��Ă��A�ǎ҂̕��̓��̒��ł��ꂼ��̊��o�ŗZ������āA���ꂼ�������ǂݕ������܂ꂽ��y�����Ǝv���Ă��邩��ł��B
�@��́A�Y�����Y�̖��H�ł��B�i�s���̉����\�\Aquirax Labyrinth 2007-2008�t�A���Y���[�A2009�N5��8���A�ܔ��y�[�W�B���c��̈��p�́s���{���b�O���t�B�b�N�t�ɏƂ炵�čZ�������j
�����́w���{���b�O���t�B�b�N�x�́A��{�B�l�E�i��ꐳ�E�F�숟��ǁE�c������E���������̊G�ɂ��ꂼ��ꗈ�q�s�E���S��E���c���j�E���O�E�����r�Y�̕���g�݂��킹�����̎���W�i�̃I���j�o�X�Łj�ł���i�s���{���b�O���t�B�b�N�t�A���p�o�ŎЁA1964�N12��30���k�����E���\���F��{�B�l�l�j�B�F�쁁���c�́q�V�E�Y�q�`�r�̓T���͉Y�����Y�B���l�ɁA��{���ꗈ�́q���ǂ남�ǂ낵���ꐡ�@�t����������l�ɕ����r�͈ꐡ�@�t�A�i�䁁���́q����_�ƕ����̋L�^�r�͓����Y�A�c�������́q�h���{�E�ƌx���r�͉ԍ��A�����������́q���X�R�v�w��P�r�͂��������R��T���ɋ��A���삵�Ă���B�܂������̊����ɂ́A����C���ƋT�q�Y���͂��Ă��āA�C���X�g���[�^�[�����̑D�o���j�����銆�D�ɂȂ��Ă���B���̎��c���j�̔o��ƉF�숟��ǂ̊G�̃p�[�g��P�s�{�ɂ����̂��A����400���́s�V�E�Y�q�`�t�i�g���Y�{�b�N�X�A2002�j�̂悤���i�����j�B�s���{���b�O���t�B�b�N�t�̎d�l�́A��܁Z�~��Z�Z�~�����[�g���E��O��y�[�W�i�{�����g�݁A���t���Ȃ��j�E�㐻�p�w�p�\���i�w�E�N���X�A���E���j�B�C���^�[�l�b�g�ʼn摜��������ƁA�i�{�[���ɓ\���ӂ̗A���p�����t���Ă����炵�����A�����̌Ï��͂���������B�{���p���͐F����̔��F��ǂ����邽�߂��낤�A���h�H���Ǝv�����A�V�~�Ȃǂ̌o�N�ω����ڗ��͔̂��Ȃ��̂��߂��B4�F�i�t���J���[�j�̃C���X�g���[�V�����������Ȃ��ɂ����āA�F�쁁���c�́q�V�E�Y�q�`�r��24�y�[�W�́A�G�i����j���X�~�A���i�o��j�����n�̍��F�i�F��ɂ��u���[�A���o�[�v�j�Ƃ����֗~�I�ȔŖʂɂȂ��Ă���A�����̂Ȃ��ňٍʂ�����Ă���B
 �@
�@
�F�숟��ǁi�G�j�E���c���j�i���j�q�q�V�E�Y�q�`�r�Y�����Y�r�́u�v�M�Ɂ@�ǂ�Z���g���^���́@���炵�܁v�f�ڂ̌��J���y�[�W�i���j�Ɠ��u�����́@���I���K����^�N�O�Ɓ@�ʗւ������m���n���v�f�ڂ̌��J���y�[�W�i�E�j�k�o�T�͂ǂ�����s���{���b�O���t�B�b�N�t�i���p�o�ŎЁA1964�N12��30���j�l
�g������1960�N��̌㔼�A�����d�M���������s�o��]�_�t���ӂ̔o�l�����i���c���j�����̗L�͂Ȉ�l�ł���j�̍앗�ɐe�ߊ�������Ă����悤���B
![>���c���j��i�W�s�����D�t�i�o��]�_�ЁA1964�N3��7���j�̕v�w���k����150���̂��������{10���́u��Q�ԁv�l](image/fukusousen_case_1.jpg) �@
�@![>���c���j��i�W�s���ꂤ���q�C�L�\�\The Verses of the St. Scarabeus�t�i�o��]�_�ЁA1969�N5��15���j�̃W���P�b�g�k�����E��F���A�l](image/galliot_jacket_1.jpg)
���c���j��i�W�s�����D�t�i�o��]�_�ЁA1964�N3��7���j�̕v�w���k����150���̂��������{10���́u��Q�ԁv�l�i���j�Ɠ��s���ꂤ���q�C�L�\�\The Verses of the St. Scarabeus�t�i���A1969�N5��15���j�̃W���P�b�g�k�����E��F���A�l�i�E�j
���c���j�̍ŏ��̍�i�W�s�����D�t��1964�N3��7���A�o��]�_�Ђ��犧�s���ꂽ�B�g���͑���i�W�s���ꂤ���q�C�L�\�\The Verses of the St. Scarabeus�t�i�o��]�_�ЁA1969�N5��15���j���q�����r���Ă���B�������ł͂Ȃ��B�g�������������O���܂��ɂ��Ē������q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S����� �^���Ձr�̈�߂ɂ�������B
�@���c���j����́A������ςɍ˔\�̂���l�ŁA����ł����S�̂��A��ς����ꂽ���Ȃ�ŁA���͂������Ԃɐ�������ł����ǁA��������Ƃ��A���������h�ɋ߂��Ȃ��āA�����o��Ƃ���Ȃ��Ă��A��s���Ƃ������A���ł�������Ȃ����B����́A������Ǝ��̕��ֈ����ς��Ă݂����悤�Ȑl�Ȃ�ł����ǁA�܂��o��ɂ����Ƃ��ĈِF�����ƂƁ\�\�B�܂���������Ȃǂ�����܂����A������ِF�����Ƃł��傤�B�i�s�o��]�_�t78���A1968�N3���A��O�y�[�W�j
���̔����͎��g�̔o��]�_�܂̑I��]�������̂ŁA���N�O�̑I��]�q���z�\�\�o��]�_�܌���܂ŁE�o�ߕƑI��]�r�ɂ́A���̂悤�ɂ���i�O�L�q�����r�͂��̑I��]��~���������̂ƌ��Ȃ���j�B
�@���c�@���j�@�R�_�k�q���ꂤ���q�C�L�r�l
�@�����i�̒��ł́A�ł����I�ŁA�S��̗������낢�A��̐��E������B�ꐡ�A��������̒����̎�����������B�ЂƂ��ƂŁA�����A�܂��ɁA���邽�̊��G�B
�@�@���ɂ�������ނ��Ӑ��v�������ӂ���
�@�@�������肩������@凁k[�����͂܂���]�l���͂�
�@�@���Ȃ�k�@���A�l�R���ЂƂӂ���̂��Ђ���
�@�@�����܂��ق났�Ɏ��������邠�ӂނ�
�@�@���炷���F���{���������̂Ă��炪��
�@�@���߂��邠�܂����˂��݂ӂȂ����
�Ȃǂ͏G��Ǝv���B�i�s�o��]�_�t72���A1967�N9���A�O�Z�y�[�W�B�����̎��c��ɏƂ炵�čZ�������j
���c�͉Ǎ�̍�ƂŁA1964�N�̍�i�W�s�����D�t�A���N�̎���W�q�V�E�Y�q�`�r�A1969�N�̍�i�W�s���ꂤ���q�C�L�t�ȍ~�A�����Ƃ��Ă�1994�N�̍�i�W�s�Ȕ����t�i�����q�C�ЁA����30���B�����j�A2002�N�̈��̍Ċ��A�s�V�E�Y�q�`�t�����Ȃ��i���j�B���̑���W�s�����D�t�ɂ͉F�숟��ǂ̃C���X�g���[�V����2�t���f�����Ă����B����W�q�V�E�Y�q�`�r�Ƃǂ��炪��̊�悩�킩��Ȃ����A����͑��O�サ�Đi�s�������낤�B1964�N��3����12���Ɋ��s���ꂽ�s�����D�t�Ɓs���{���b�O���t�B�b�N�t���˖{�M�Y�Ƌg�����̊�ɐG�ꂽ�\���͂���߂č����B���ꂪ�˖{�ɂ́s�g�������W�t�̃��B�W���A�����߂��銴�z�ƂȂ����̂��낤���A�g���ɂ́q���ꂤ���q�C�L�r��s���ꂤ���q�C�L�t�Ɋ鋤���̕z�ƂȂ����̂��낤�B�������A�g�������ɂ��̉e�����������܌��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B1980�N�ȍ~�̂�����x�M�̊��Ԓ��A�g���́s�Î��L�t��M���Ƃ�����{�̌ÓT���w�ɐe���B�F��Ǝ��c�́q�V�E�Y�q�`�r�̍Ō�̃y�[�W�ɂ́A������������̓T�������邩�̂悤�ɁA�q���y�L�핶�E�O�㍑�r�̎��̈�߂�������Ă����B
�����ɁA�ׁm���܁n�q�A�O�m�����n�̓��m�Ёn�̊��m������n��Y�m�킷�n��A
���m�����܂��n�ɋʙ��m���܂������n���J�m�Ђ�n������A
���m���Ȃ́n���ہm�߂ɂ݁n����ԁm���Ђ��n�ɁA�F���m�����́n����铁m�������n�A
���_�m���������n�ɗ��m�������n�Ђđ��V�m���߁n���ǔ�m�Ƃт��n���肫�B
�Y�����Y�����P�Ƃ̖�Y��ċʎ蔠���J����ƁA�u���ɂ��Ă��̂����킵���͕̂��Ɖ_�ɏ���Đ�ɔ�ы����Ă��܂����A�Ƃ����̂��B���̒m���Ă���q�Y�����Y�r�́A�ʎ蔠���J���≌�������̂ڂ��Ĕ����̘V�l�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ����A�s�䉾���q�t�Ɏn�܂菬�w���́i�����O�Y�쎌�j�ɗ��ꂱ���b�����A���̌����͋g��������m��҂ɂƂ��ďՌ��ł���B�u�Y���͒߂ɂȂ�A�H���̎R�ɂ��Ђ��Ȃ��B�T�͍b�ɎO�����̂��������ȂցA������o���Ɩ�B�M�����߂ł����l�ɂ��A�ߋT�������\����ցB���l�ɂ͏��A��̗L��l�͍s���߂œx�R�\���`����B����Y�����Y�́A�O�㍑�ɉY���̖��_�ƌ���A�O���ϓx�����ւ�B�T���������ɐ_�Ƃ���͂�v�w�̖��_�ƂȂ苋�ӁB�߂ł����肯�邽�߂��Ȃ�v�i�s�䉾���q�k���{�ÓT���w��n 38�l�t�A��g���X�A1958�N7��5���A�O�l�܃y�[�W�B���r���Ȃ��ȂǁA�\�L�����߂��j�B�����A�g�����s��ʁt�ŕ`�����q�H���r�A�u�H���R�v�ł���B���̊ϓ_���玍��W�q�V�E�Y�q�`�r��ǂ݂Ȃ����ƁA���̂悤�ȋ傪����i��p�����ɂ��銿���͂����p�����j�B
���X�Ƃ��肽��
��T�̔w�́@�H
�[��́@�V�\���m�Ă����n�ɂƂ܂�
�U�����@�����ȓV���m���܂��n
���̂܂́@���𐌂ւ�
���������n���@���R����
���Ȓ��Ȃ́@���P��
���߂Ă̕������@�ނ܂ꂯ��
�ڂ荁���@�����m���낭�Án��
���łɁ@�珈���炽��
���ꗬ���́@���炪���
�����Ђ��\�m���n�́@����D��
����I�͂Ɂ@�C��
���ׂ@���ւȂ�
���R�ꂨ�Ȃ��q�쐅�E�ו��E�����r�ɂ͎���W�q�V�E�Y�q�`�r���u�ЂƂ莛�c�̋�W�Ƃ��āw�����D�x��w���ꂤ���q�C�L�x��肷����Ă������łȂ��A���Z�Z�N��̑O�q�n�̋�W�Ƃ��ċ��w�̂��̂ł͂Ȃ����ƕ]�҂͐M���Ă���v�Ƃ��邪�A�����̎��c�̋傱���g�����ӔN�̎�������肵�����E�ł͂���܂����B���傪�K�i��ɘA�Ȃ�s��ʁt�̎��^�������d�M�̋�̑��s�`���ɐG�����ꂽ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����w�E�͂��˂Ă���Ȃ���Ă����B�����A�d�M��M���Ƃ���s�o��]�_�t�̔o�l�����\�\�Ƃ�킯���c���j�\�\�̍�i���s��ʁt��U�����鎍���̂ЂƂ������A�Ƃ����̂����̊����ł���B�u�剪�M���q��ˁr�𐄂��A�킽�����q�Ⓦ�r���]�����̂ŁA�d�M�͎��M�������ĐV�����앗���m�������B���ꂪ�s�R�C�W�t�ł���B�����̐V�[�ÓT���ȍ�i�Q���A�킽���͈��u����v�i�q�����d�M�E�U�炵�����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���l�y�[�W�B���o�́s����o��S�W�k��3���l�t�A�������[�A1977�N11��5���j�B�u���͒x�܂��Ȃ���A�w�Î��L�x����c���j�w���앨��x��Γc�p��Y�w�����Y�̕�x�Ȃǂ́u�_�b�v��u���ԓ`���v�ɁA�S�䂩���悤�ɂȂ����B���̂����Ƃ��V�������W�w��ʁx�́A�����ƃt���C�U�[�w���}�сx�̌����Ɉ˂��āA�������Ă���̂��v�i�q���H���߂���f�́r�A���O�A�O�Z�܃y�[�W�B���o�́s���H�S�W�k��17���l�t����10�A��g���X�A1985�N9��5���j�B����o��́u�V�[�ÓT���ȍ�i�Q�v�A�u�_�b�v��u���ԓ`���v������g�������ɗ^�����e���͌v�肵��Ȃ��B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j���c���j�P�Ƃ̒����ł͂Ȃ����A�����d�M���҂s���a�o��I�W�t�i�i�c���[�A1977�N9��10���j�ɂ́A���a34�N����51�N�܂ł̎��c�̋�A34���߂��Ă���B�����ɂ͎��̋�i�e�N�̖`����j��������B
�@�@���a34�N
�@�@����炭���Ɓ@�m�l�`�́@�ς�ꂯ��
�@�@���a35�N
�@�@������@���R�r�̑قɁ@�C��D�Ѝ���
�@�@���a38�N
�@�@ ��
�@�@���邶�́@���
�@�@�����͉����Ɂ@�ł��ɂ���
�@�@���a39�N
�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@��
�@�@���Ɏ��ā@���ɂ͂��炸
�@�@�M���l���Ł@�ЂƂ����x��
�@�@���a41�N
�@�@���Ȃ�@�R���ЂƂӂ���̂��Ђ���
�@�@���a42�N
�@�@���炷���F���{���������̂Ă��炪��
�@�@���a43�N
�@�@�S�y���̂����날�邫�̖�����
�@�@���a44�N
�@�@���Ⴕ�Ă̂������킠�����ꂯ��
�@�@���a45�N
�@�@�D�����ނȂǂ��ē얳���邭������
�@�@���a46�N
�@�@���_�ɂ����ׂ��Ă��C���D
�@�@���a47�N
�@�@�ӂƒ\�y���Y�ꂭ�鐅�v�Ȃ�ׂ�
�@�@���a48�N
�@�@�Εv���p�܂����炤�ނ��͕����Ȃ�
�@�@���a49�N
�@�@�t���Ƃ�m���������͉����Ȃ��
�@�@���a50�N
�@�@�F�����玆��s�@���Ђ�Ђ���
�@�@���a51�N
�@�@���̂̊���Ђ��Ђɒu�����D��
�����d�M�͊����́q���Ƃ����r�Łu���̍�����W�́A�͂��߁u�o��]�_�v�̑n����\���N���L�O���Čv�悳�ꂽ���A������������Ӌ`���炵�߂邽�߂ɁA�܂��u�o��]�_�v�ɍݐВ��Ɍ̐l�ƂȂ��l�����������A�܂��X�ɁA����Ɠ����u�����т��ė����Ǝv����߉��̐����̔o�l�̋Ɛт����A����ɕ�ۂ��邱�Ƃɂ����B���a�S����ʂ��Ċi�ʂȈӋ`������̃G�R�[���̗��j�I�ȗ���́A����ɂ�肢�������m�ɂȂ��Ǝv����v�i�����A�O�Z�O�y�[�W�j�Ə����Ă���i������Ƃ̋�͎��I�̂悤���j�B�����́s���a�o��I�W�t���s��1977�N�ɁA�s����o��S�W�k�S6���l�t�i�������[�j�̕ҏW�ψ����g�����E�ѓc�����E�剪�M�Ɩ��߂Ă���A�g���͂������A���̕ҏW�ψ����{����ڂɂ����ɈႢ�Ȃ��B�{���ɉ���̂悤�ɂ��Ď��߂�ꂽ�얼��́q���a�o��j�r�́A�s����o��S�W�t�Ɠ�����Ԃ�ŕ҂s�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l�t�i�������[�A1980�`1981�j����ɘA�ڂ����ҏW�ψ������̍��k�� �q����o������r�̊�{�����̂ЂƂƂ��Ă̖������ʂ������悤�Ɏv����B
�����q�g�����Ɓs���}�сt�r�Ƒ肵�āA�t���C�U�[�i�i������j�s���}�сk��g���ɁE�S5���l�t�i��g���X�A����F1966�`67�j�������āA���W�s��ʁt�i1983�j��s���[���h���b�v�t�i1988�j�̎���̃X���X���Ǝw�E�����B���̂Ƃ��́A�g�������́u�Ɏw�E���Ȃ����A�s���}�сt�̂��������Ɂu����g�����v�̐��E�ƒʂ�����̂�F�߂��ɂ͂����Ȃ��v�Ə����āA��̓I�ɋ����Ȃ������B����͂��̐��_�������B���߂Ɂs���}�сt�̖i�q�͖��r�A�����k�������l�E�y�[�W���k�A���r�A�����l�j���q���і��r�i���W�ԍ��E���̎��W�ł̏��ԁj�^�g�����̎�����A5�ӏ��f����B
�E�o�C�G�����̃��C���n���A���邢�͂܂��w�b�Z���̔_���́A��r���r��܂����ꍇ�ɁA�֎q�̋r�ɕ��������}�т����邻���ł���B�i�q��O�� ������p�r�A��E114�j
���q�킾�݁r�i�K�E3�j
�u��т������ꂽ
�@�@�@�@�@�@�@�@���̋r������
�@�@�@�@�@�@�@�@�֎q�̐܂ꂽ�r�������v
��
�E���̓��V�������������l���ł������낳��Ă���ԂɁA�^����������˂�����@�����肵�ăM���[�Ɩ�����B�i�q��\�� �ߑト�[���b�p�ɂ�������ؐ��q�̖��c��r�A��E277�j
���q�ØI�r�i�J�E14�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�^����������˂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����肵�ăM���[�Ɩ�����j
��
�E���̋����ɂ͐F�X�Ȍ`�����邪�A�ڕW���邢�͌����_�͑�Ă��u�܌��̎��v���u�܌��̖_�v�ƂȂ��Ă���B�i�q��\�� �ߑト�[���b�p�ɂ�������ؐ��q�̖��c��r�A��E279�j
���q�ØI�r�i�J�E14�j
���܂����r�ꂽ�n�ցi�܌��̖_�j�������Ă�
�@�@�@�@�@�@�@�Z�����́@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ׂ����́@��������
�₪�āi�܌��̎��j�͔ɖ��邾�낤
��
�E���ɂ��̉����Ɍ��������A��オ�H�т̖[�ł����Ă�������썰���͂������ނƁA��������ɗނ�����̂̒f�Ђ̂悤�Ȍ`�������썰��⥁m�ނ���n�ŎƂ߂���B�i�q��\���� �썰�̊�@�r�A��E85�j
���q�ØI�r�i�J�E14�j
�i�������炨����썰��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@䭂ŎƂ߂�j
��
�E����Ɠ����悤�Ƀ��F�[�_����̃q���h�D�[�́A���J�P�X�ɔx�a�킹�ĕ������B�i�q��\�� �Ж�̓]�ځr�A�l�E126�j
���q�ØI�r�i�J�E14�j
�i���J�P�X�ɔx�a�킹��j
�������Č���ƁA�q�ØI�r�i�J�E14�j�̎���ɓ]�p����Ă���̂����|�I���Ƃ킩��B��ŐG���悤�ɁA�q�ØI�r�̏��o���e�̖����ɂ͈��p���s���}�сt�Ɉˋ�����|�̒��������āA�{�т������ɂ�肩��������i�ł��邱�Ƃ���҂ɂ���Ė�������Ă���B����A�q�킾�݁r�i�K�E3�A���o�́s�����V���k�[���l�t1985�N1��5���j�ɂ͂����������L�͂Ȃ��A��f�̎O�s�́s���}�сt�̖���ɋg�����V���ɕ`�����G�̎�������āA���p�����ꊇ�ʂ͂����������̊G�������ƒ��߂�z���̂悤�ł���B��g�𑱂���Ȃ�A�q�ØI�r�̈��p�����p�[�����͖�ʂ̂悤���B�����A�g�������Ɓs���}�сt�Ƃ̗މ��ƍ��ق��l����Ƃ��܂�������ׂ��́A�s���}�сt�̏͋����肱�����̎��тł͂Ȃ��A���Ɍf����q�}�сr�i�J�E4�j���Ǝv����B�����ɂ́A�q�ØI�r��q�킾�݁r�Ɍ����钀���I�ȁA���邢�͉��ϓI�ȏ͋�̎ؗp�����Ȃ����̂́A�u����g�������v�ɓ����I�Ȕ��z������������ł���B
�}�сb�g����
�@�@�@�T�@�n�̗�
�J��̋V���Ƃ͂Ȃ�
�A�l���l�̔�F�̒�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ЂƂ�̖����ۗ��ɂȂ�
�����ăV�L�~�̎}��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���@�D�@�S�y�̂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j���̑��v��`��
�Z���@����
�Z���@�\��
�@�@�@�@�@���Ƃق��@���Ƃ�������
�c�O�~��Z�L���C���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������
���_��g�J�Q���p��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ꂽ��n��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�ނ���ŕ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�ɑł����
�P�̌`�̂悤�ȏ����̂܂��
�͂͂��t�̂��悮
�@�@�@�@�@�@�@�@��̂��Ƃ���鍡��
���͑o���������悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̗������߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������o���
�V�����ɒ��˂�
�@�@�@�@�@�@�@�傫�Ȍ�
���҂͖łт�
�@�@�@�@�@�@�݂ǂ�̉萁���Ƃ���
���_����������
�@�@�@�@�@�@�@�c����������
�@�@�@�U�@���̖�
�V�C�̂悢���ɂ�
���Ȃ�J�V���̖̊Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ꂷ��i��j
���t�̎p������
����C�^�`��ǂ��Ă���̂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�}�̕�̂�����ӂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�E�l���G�r�����˂Ă���
�����͋߂��悤�ʼn���
�S�Ƙm�Ƃ̋��E��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���삪������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������v
�������[��
�킽���͐���ʂ�����
�ޏ��̕G�̖��������ʂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�^��
���łɗ��͕���
�ЂƂтƂ͔[���̂Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�j�_�̌`�̃p��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ڂ���̗t�ŕ�ށv
�y��ɐ���@���a����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܍��L��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ܑ̖���
���b�p�X�C�Z���̍炭��̖閾��
�˂Ɏ���
�@�@�@�@�@�@����镨�̊W�͈�����
�@�@�@�@�@�@�͗t�ƂƂ��ɃC�m�V�V�����֗�������
�킽���͐��̖ʂɑz���`��
�����ꂽ��߂����Ƃ��Ƃ��E��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���g���\�\
�@�@�@�V�@�̘T
�������ӂ���
�@�@�@�@�@�@��������������
���̕�����o�Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�⍻�q���T����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��n�ɗ����������N��
�J�[�e���̂����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̂��ɂ��@���ׂ̍�������
���̐��͖��ƊD��
�@�@�@�@�@�@�@�@���炴�炵�Ă���
��������ς�
���t�݂̂ǂ��Y����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�a�m�݂��n�Ŏ��҂��h�������
�������ӂ���
�@�@�@�@�@�@���������@�������̂��炾��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����m�Œ@������
�������g�̂�������ۂɂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʉߋV��̏I��
�ЂƂ͑P�������݂��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������݂�
�r�����߂���@��n���߂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�҂͎������Ă���悤��
�u��낸�̂��Ɓ@�݂ȁ@�����炲�Ɓv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��䕂⓶�b�̐��E���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�v�Ǖ����ꂽ
�쐶�́u�����v����݂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�͐}�̂Ȃ���
�����@����^�_
�@�@�@�@�@�@�@���͔R����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������[���̐X��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킪�T�͋킯�ė���
�@�@�@�W�@���̉�
����������
�@�@�@�@�@�@�@�@���ƂłƂ�Ƃ�{���ӂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@��������������O����
�̂��炵�̖���s��
�t�N���l�Y�~�̑���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̎��𓊂������@�}�c�J�T�̎��ƂƂ���
�₪�ďt�̗�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������⒍�A������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������͓|���@����o����@�߂���
�j���Ȃ�ΓS�̎��₵�Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͂��ԕ�@��e��j��Z
����N���ׂ��@���͗��ɂȂ�
�����̓E�C�L���E�̌O�肳������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���Ƒ��}�v�̂悤��
����ǎ��͐����@�l������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���݂̎d�g�͂܂��ɍ��ז���
�ԍ炭�n����
�͂�闷���Ă������N������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ċ��̌`�̖X�q�����Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���{���~�v�����݂�
�Ζ������Ė����Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o��T���Ă���悤��
�J�ɂʂꂽ�|����`����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʂ��ł���
��ɂ̓n�g��X�Y������ь���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�n�����_���v�͔��̒��ɗ���
�����R�r�̂ނ�Ɉ͂܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���N�̗��g�͉���@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킵���܂Ђ��
�u���Ԍ��͉������C�Â��Ȃ��v
���́q�}�сr�i���o�́s���{�o�ϐV���t1982�N3��7���E14���E21���E28���A�ڂ́q�O���̎��T�`�W�r�B�Ȃ����o���̕W��́u�n�̗�i�t�̓`���P�j�v�E�u���̖��i�t�̓`���Q�j�v�E�u�̘T�i�t�̓`���R�j�v�E�u��m�����n�̉i�t�̓`���S�j�v�ł���j�̐V���A�ڎ��̑���q�t�̓`���r�́A���W�s��ʁt�ɂ����āq�}�сr�ɉ��肳�ꂽ�B���̒��ׂɘR�ꂪ�Ȃ���A�{�т̎���Ƀt���C�U�[�i�i������j�s���}�сt����̈��p�͂Ȃ��i���j�B���݂Ɂu�@�v�Ŋ���ꂽ�i���p�Ǝv�����j������ȉ��ɔ����o���A�㒐�G���b�N�E�Z�����h�Ɉ˂�p���i�����j�L����B
�@�@�u���@�D�@�S�y�̂����Ɂ^�j���̑��v
�@�@�gSand ashes atop of the clay / The image of a man and woman�h
�@�@�u���삪�������^����������v
�@�@�gThe spirit of the word grows / And the rocks grow also�h
�@�@�u�j�_�̌`�̃p��������^���ڂ���̗t�ŕ�ށv
�@�@�gMake bread the shape of a male god / And wrap it in pumpkin leaves�h
�@�@�u��낸�̂��Ɓ@�݂ȁ@�����炲�Ɓv
�@�@�gAll things are illusion�h
�@�@�u�����v
�@�@�gA dream�h
�@�@�u���Ƒ��}�v
�@�@�ga picture of the holy family�h
�@�@�u���{���~�v
�@�@�gthe descent to Hades�h
�@�@�u�n�����_���v
�@�@�gA goddess with a horse's head�h
�@�@�u���Ԍ��͉������C�Â��Ȃ��v
�@�@�gThe dead watchdog unconcerned�h
��Ɉ��������сq�ØI�r�i���o�́s����t1983�N1�����j�̖����Ɂu�i���p��͂����Ƀt���C�U�[�s���}�сt�i��������ؗp�����j�v�ƒ��������_�Œx���Ƃ��g���͖{���ɐG��Ă���킯������A�q�t�̓`���r�́s���}�сt�܂��q�}�сr�ɉ��肳�ꂽ���ƂɂȂ�B���̓t���C�U�[�́sThe Golden Bough�t�̖M�肪�s���}�сt�ƂȂ����o�܂�m��Ȃ��i���Ȃ݂Ɂu���}�v�Ƃ̓��h���M�k�h��E�h�E�l�̂��Ƃł���j�B�Ƃ��ɁA�ےJ�ˈ��x�m��`�V�͂��̖M��������ās�����̎}�t�Ƃ��Ă���B�t���C�U�[�_�����߂��x�m��i�i�{�R�t�́s�������t�̖�҂ł���j�́s�p���̐��I���t�͋g���f���1999�N��������[���Ƃ��Ă��A�ےJ���s���}�сt��ނ��ās�����̎}�t�Ə����Ă����̂��̋g�����ڂɂ��Ă����\���͂���B���̋g�������z�Łu�s���}�сt�v�Ə����̂́A��g���ɔł̖��w������ł���B�ł́A�s��ʁt�ɂ�����q�}�сr�̓��������ڂ������Ă������B
�g���͂��̎����u�J��̋V���Ƃ͂ȂɁv�Ǝn�߂Ă���B���̎���i���炾���ł͂킩��ɂ������A�g���́u���v�ւ̂Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʊS�������Ă����B�i�c�k�߈��t���i1980�N6��25������j�ɂ́u���̂Ƃ���A���V�Â��ŁA��~�J�ɂȂ肻���ł��B�����l��{�A�u���v�̂��Ƃ��l���Ă���̂ŁA�Ă̐��s�����S�z�ł��B�k�c�c�l�v�Ƃ��邵�A������������t�����A�t�̉J���~���Ă��܂��A�Ƃ����������Ŏn�܂��Ă����B��O�̓��������Ɉ�����g���ɂƂ��āA�~�J�͔_��Ƃɏ]������҂ɂƂ��Ă̂���قǐ[���ȊS���ł͂Ȃ�������������Ȃ��B�����A�n���g���A���F�̎R����s�R�����펞���̋g���ɂƂ��āA�V��͋G�߂̈ڂ�䂫�ƂƂ��ɁA�G�Ƃ̐퓬�Ɏ����ő�̊S���������ɈႢ�Ȃ��B�V�H�Ƃɒ�������Ƃ����Ӗ��ł́A�t���C�U�[�̕`�������J�̔_���̐S�����牓�����̂ł͂Ȃ��������낤�B��������l�匳�f�i�E��C�k�������͕��l�E���E�y�j�Ƃ����l��̎�肪���サ�Ă���̂́A���ΕK�R�ł���B
�����ŁA�������g�̂��߂ɏd�v�Ȍ��ɒ����Ă����B��Ƃ��ās���{��S�ȑS���k�S26���l�t�i���w�فA��2�ŁF1994�j��p�����i�����͏c�g�B�������̓A���r�A�����ɉ��߂��j�B����ȊO�̎����ɂ�����ꍇ�́A��������\������B
�E�A�l���l
����_�j�ɂ��A�l���l�́u��2��\���R�����i1147�j�̂���A�C�^���A�̃s�T�吹���̃E���x���g�m�����^�������n����̓y�̒��ɃA�l���l�̋������������Ă���A���̓y���g�����\���R�}���҂̕�n���猩����Ȃ����̂悤�ȐԂ��Ԃ��炢���Ƃ����v�i��4���A433�y�[�W�j�B
�E�V�L�~
�V�L�~�Ȃ̏���B��V���͎��ɂ��Ξ�́u�}�t���ƈ��̍��C���Y���̂ŃR�E�m�L�A�R�E�m�n�i�A���邢�͕�ɋ������邱�Ƃ������̂Ńn�J�o�i�Ƃ������v�i��10���A649�y�[�W�j�B
�E�Z������
���䋳���ɂ��u�u���m����n�v�̓T���X�N���b�g��̃C���h����indriya�̊����ŁA���o�튯�Ƃ��̊튯�̗L����\�͂Ƃ����Ӗ��B�Z���Ƃ́A��m����n���i���o�튯�Ǝ��o�\�́j�A���m�Ɂn���i���o�튯�ƒ��o�\�́j�A�@�m�сn���i�k�o�m���イ�����n�튯�ƚk�o�\�́j�A��m���n���i���o�튯�Ɩ��o�\�́j�A�g�m����n���i�G�o�튯�ƐG�o�\�́j�A�Ӂm���n���i�v�ҁm���䂢�n�튯�Ǝv�Ҕ\�́j��6��������A���̘Z��������ɂȂ邱�Ƃ�Z������Ƃ����v�i��24���A600�y�[�W�j�B
�E�V����
�{�{���v�ɂ��ΓV�����m�Ă������n�́u�P�ɓV���Ƃ����A�]�ˎ���A�J���m���܂݂��n�i�V���j���J��m���܂ǂ��n�Ȃǂ�������A�h�Ηp�ɂ��߂Ă��������B�k�c�c�l�����Ȍ�A���h�ݔ��̋ߑ㉻�ɂ��A�������ɔp���ꂽ���A����E��풆�ɂ́A�h�Ηp�����ƁX�̌���ɒu���ꂽ�v�i��16���A366�y�[�W�j�B
�E�J�V��
�u�i�Ȃ̗��t���B�����M��ɂ��J�V���́u�����t�ƌ������炪���邽�ߕ��Ւn��ΎR���Ӓn��A�R�Ύ��Ւn�ɒ�؏�̏��т��悭����B�k�c�c�l��p�A���N�A�����S���܂ŕ��z����B����̓^���j���̊ܗL�����u�i�Ȃł����Ƃ������A���F��v�Ȃ߂��Ƃ��ėp����ꂽ�B�J�V���͐��m�������n�t�̈Ӗ��Ŕ��݁m����������n�ɁA�܂��_���ɗp����ꔐ��ƂȂ�c���Ă���v�i��5���A227�y�[�W�j�B
�E�z�E�l���G�r
���c���ςɂ��ΖL�N�ڂ́u�ߑ�������b�k�j���b�ڃz�E�l���G�r�Ȃɑ�����W�������B�b�k�ނ̌��^���v�킹�錴�n�I�Ȍ`�Ԃ����B�̒�2�Z���`�قǂ̍ג����~���`�ŁA�b�������Ȃ��B�k�c�c�l�唭������N�͖L�N�ł���Ƃ��������`��������A���͂���ɗR������v�i��21���A394�y�[�W�j�B
�E�����
����_�j�ɂ��ΐ���ʂ́u�L�j�ȑO���痘�p����A���c���j�m��Ȃ������ɂ��n�́w�l�ƃY�Y�_�}�x�i1952�j�ŁA���̌ꌹ�ƗR����_�����B���c�́A�W���Y�_�}�̖��͕����̐���m�W���Y�n�Ɋ�Â��̂ł͂Ȃ��A��m���܁n�◱�Ɗ֘A����Ì�̃c�X��c�V�^�}����A����������Ɏc��Y�Y�_�}���o�āA�W���Y�_�}�ɂȂ����Ɛ��@�����v�i��11���A649�`650�y�[�W�j�B
�E�^
�q�{���ɂ��A�I�K�G���́u�����j�����ڃA�I�K�G���Ȃɑ�����J�G���̂����A�̕\����l�ɗΐF�����Ă����̑��́B�k�c�c�l��ʂɎR�ԕ���R�����̎��n�A���c�̎��ӂɐ�������B�k�c�c�l�Y�����ɕ��ڂ������Y���㎈�Ń[���[��̗�����������߁A�����A��ƂȂ�B���ӂ̒n���y��̊ԂɎY�����邪�A�����A�I�K�G���̂悤�Ɏ���ɎY������������v�i��1���A96�`97�y�[�W�j�B
�E���b�p�X�C�Z��
�h�ڐ���́u�q�K���o�i�Ȃ̏H�A���������B���F�܂��͔��F�Ԃ��J���A���Ԋ��͂���Ϗ�B��ԁA�Ԓd�ɗp����v�i��23���A754�y�[�W�j�B
�E�_�a
�����t�F�ɂ��ΐ_�a�́u�_�ɏ����オ�蕨�Ƃ��ċ�������H���B�~�P�Ƃ������B�~�P�͌�H�̋`�ŁA�_���̓~�L�Ƃ����B�_�a�͕āA���A���A������{�ŁA����ɖ�A�ʕ��A���L�ނȂǂ���������ɋ�����B�k�c�c�l���s�̐_�Ѝ��J�m�������n�ɂ�����_�a�̕i�ڂ́A����������鏇�ɋL���ƁA�a��m�ɂ����ˁn�i���k�m���݂���n���Ƃ����āj�A�r��m���炵�ˁn�i���k�̂����āj�A���A�݁m�����n�A�C���A�싛�A�쒹�A�����A�C���A��A�ʕ��A�َq�A���A���ƒ�߂��Ă���v�i��12���A593�y�[�W�j�B
�E�ʉߋV��
�����P�Y�ɂ��ΒʉߋV��̉ߒ��́u�ʉߋV��Ƃ������Ƃ����߂ėp�����̂́A�I�����_�̖����w�҂Ńt�����X�Ŋ����t�@���E�w�l�b�v�ł���B�ʉߋV��ɂ���r�I�P���Ȃ��̂��畡�G�Ȃ��̂܂ł��낢�날�邪�A��ʂɂ͋V��̉ߒ����������̒i�K�ɕ������Ă��邱�Ƃ������B�t�@���E�w�l�b�v�́A�����Ƃ��悭�݂���ʉߋV��̋敪�́A�����̋V��rites de séparation�A�ߓn�̋V��rites de marge�A����ѓ����̋V��rites d'agrégation��3�敪�ł���Əq�ׂĂ���B���i�K�̕����̋V��́A�l������܂ł�������Ԃ���̕������ے�����`�ōs����B�k�c�c�l���i�K�̉ߓn�̋V��́A�l�����łɂ���܂ł̏�Ԃɂ͂Ȃ��A�܂��V���ȏ�Ԃɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��ߓn�I������ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ������Ă���B�k�c�c�l�܂��A�ߓn�V��ɂ����ẮA�j�̏����A���̒j���Ƃ����������A�i�Ղɂ�鐹�Ȃ鉤�̔l�|�m�Ƃ��n�Ƃ������l�̓]���A�َ������ے�����n����A�I�s���ȂǁA�ߓn�I�s����������s�����ώ@�����B�k�c�c�l��O�i�K�̓����̋V��́A�����V��Ɖߓn�V����I�����l���V������ԂƂȂ��ĎЉ�}���������V��ł���A��ʂɑ�K�͂ȏj�Ղ��s����v�i��15���A777�y�[�W�j�B
�E�^�_
�^�_�m�܂��݁n�́A���{�ɐ������Ă����T���_�i���������́B����^�_�m���������̂܂��݁E���������܂��݁n�A��_���Ƃ��Ă��B���c���ɂ��ΎO���_�Ђ́u��ʌ������m�����ԁn�s���m���������n�n��O��ɒ����B�k�c�c�l�×��R���ɐ��������T�m�������݁n�Ђ��ő��_�m��������n�u����^�_�m���������܂��݁n�v�Ƃ��A�Γ����m��n���̐M�������v�i��22���A372�y�[�W�j�B
�E����
���x��s�ɂ��Ό����́u�M���m�قɂイ�n�ނ̎��̈��ŁA�厕�̎��Ɉʒu���A�~���m�����n�`�܂�����m�����n�`�ŁA���ʂ͏㉺���{�m�����n�̍��E�Ɋe1���v4�{����B�k�c�c�l�q�g�̌����͎��莕�Ƃ������A�悪�Ƃ����Ă��邪�A�؎��i�厕�j��P���m���イ���n�ɔ�ׂēˏo���Ȃ��B�q�g�̎��͑S�̂Ƃ��đމ��X���ɂ���A�Ƃ��Ɍ����ł͂��̌X���������v�i��8���A327�y�[�W�j�B
�E�t�N���l�Y�~
�I�|�b�T���́u�ʖ��R�����l�Y�~�C�t�N���l�Y�~�B�����������l�Y�~�Ɏ����p�̃I�|�b�T����Didelphidae�ɑ�����L�ܗނ̑��́B�k�c�c�l�k�A�����J�ɂ��ޗB��̗L�ܗނł���B�^�傫���̓l�Y�~�傩��l�R��̎�܂ł���B�������͑����̎�ō����Ƌ߂��ȊO�͖т��Ȃ��C�̎}�ȂǂɊ������C����ł̓�����������B�l���͒Z���C5�w��L���C�㑫�̐e�w�ɂ͂߂��Ȃ��Ό����ŁC�}������̂ɓK����v�i�s���E��S�Ȏ��T�k�����V�Łl�t�A���}�ЁA2007�A��4���A354�y�[�W�j�B
�E�E�C�L���E
���쐴�e�ɂ���䠍��m�������傤�n�́u�Z���Ȃ̑��N���B�S���ɓ��L�̍��C������B�k�c�c�l�Ñ�G�W�v�g�ō͔|����A�Ñネ�[�}�ł͎Ⴂ�s���H�p�Ƃ��ꂽ�B�������[���b�p�ŁA���قȍ���Ɩ���̂��ߖ��@�̑��Ƃ��Ēm���A�������Ƀt�����X�A�C�^���A�A���V�A�����ɕs���ȃX�p�C�X�ƂȂ����v�i��2���A872�y�[�W�j�B
�E���Ƒ��}
����l�Y�ɂ��ΐ��Ƒ��́u�L���X�g�����p�̐}���̈�B�c���C�G�X�ƕ�}���A�A����ї{�����Z�t�̎����ɖ������Ƒ��}�B���Z�t�̂����Ƀ}���A�̕�A���i���������\�������Ƒ��}�ł��邪�A���̏ꍇ�͉ƌn�}�̗v�f�������B������ɂ���A�c���C�G�X�𒆐S��3�l�����ɂ���č\������A�n��̐��O�ʁm����݁n��̂��ے�����B���̕\���`����14���I�ɓo�ꂷ�邪�A�Ƃ���15�A16���I�ɃC�^���A���͂��߁A�h�C�c�A�X�y�C���Ȃǂŗ��s�����B���A���i�̂��鐹�Ƒ��}�ł́A���I�i���h�E�_�E�r���`�́w���A���i�Ɛ���q�x�i���[�u�����p�فj�������Ƃ��L���ł���v�i��13���A273�`274�y�[�W�j�B
�E���{
���{�́u����ɂ����ނ����E�̈�B���E�C����m��݁n�ȂǂƂ������C�p���hell������ɑ�������B�k�c�c�l�Ñ㒆���ł́C���҂̗썰�̋A���鏊�́q����r�q���r�q�H�s�r�ȂǂƌĂ�C�{���n���ɂ���ƍl����ꂽ���C��ɂ͖k���H�Â̒n�ɂ���Ƃ�������������v�i�s���E��S�Ȏ��T�k�����V�Łl�t�A���}�ЁA2007�A��28���A36�y�[�W�j�B
�E�Ζ�
�Ô����ɂ��ΐΖ��́u�Õ��ɗp����ꂽ�ΐ��̖��B���m���������n��֖��m�������n�A�ÊD������H�A�푒�҂̓�����n���m�Ă��n�`�܂��̓��`�̒��荞�݂�����̂����ʂł���B���ɓ�Ȃ����O�d�ɒi��o���A�����ɍE�m���ȁn�����炵�A���ԂƂ�����ʁm�܂����܁n��w�����킹�ɓ���킹���悤�ȏ�������������̂���t���k���A��錧�암�𒆐S�Ƃ��ē����{�ɕ��z���Ă���B�����{�ɂ͔n���`�̒��荞�݂����̒P���Ȃ��̂������v�i��2���A246�y�[�W�j�B
�E�Ԍ�
���́u���E�̐_�b�Ɍ���錢�̒��ł��C�Ƃ��ɍۂ����Ă���̂̓M���V�A�_�b�̖��{�̔Ԍ��P���x���X�ł���B�����n�f�X�Ƃ��̔܃y���Z�t�H�l�����ފق̓����ɂ��āC������ʂ鎀�҂������Њd�����҂̒ʉ߂͋����ʂƐM����ꂽ���̖Ҍ��́C�����̉��e���t�H�����C�㔼�g�͐l�Ԃ̏��ʼn����g�͎ւ̌`�����������G�L�h�i�ɐ��܂����C�ǂ�����낵�������̎q�̈�ŁC�O�̌��̓��������C���͐������ւŁC�w���������������̎ւ̓��������o�Ă���C���̐��͑S����50�Ƃ�100�Ƃ������Ă���v�i�s���E��S�Ȏ��T�k�����V�Łl�t�A���}�ЁA2007�A��2���A490�y�[�W�j�B
�q�t�̓`���r���q�}�сr�Ƃ����ɂ��ẮA�������̗��R���l������B�܂��{�т��s���}�сt�ɃC���X�p�C�A���ꂽ��i�ł��邱�Ƃ̕\���ł���B���ꂪ�O�I�ȗv�����Ƃ���A���т̕W��Ƃ������I�ȗv��������B�q�t�̓`���r�Ƃ����̂́A����ł����߂��s��ʁt���т̕W��Ƃ��Ă͊ԉ��т��Ă���i�g�����߉ϑ��Y���玍�W�̑薼���s�g�̉��y�t�łǂ����낤�Ɩ���āA�����Ɂs���y�t�ł����悤�ɂƓ������}�b���z���N�������j�B�����s�m���t�Ɂq�`���r�i�C�E5�j������ȏ�A���̕��ʂ͋p�������B�����ŁA�{�т̒��ړI�T���ł����Ȃ������z�̊�ƂȂ����s���}�сt���ʂ��������āA�q���}�сr�Ƃ����Ă����シ��B���́u���v�ɂ́u���v�Ȃ�ʕʂ̐F�����������B�q�t�̓`���r�́u�`���v��������ւ��Ɂu�t�v���������A�A�z�܍s����̘A�z�ɂ��u���t�v�Łu���v�Ɂu�v�������āq�}�сr���B�\�\���ɂ͂��̂悤�Ȍo�܂��z�������B
���͖S���H���K�l�́q�g�����A���x�X�N�r�́q3�s�T�b�́t�r�Łq�C�g�r�i�J�E19�j�̈�߂������āA
�@�@((����@����@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����āi���m���悤�n�j�̎n�߂ɈÂ�))
�̎���ɂ��āu�k�c�c�l�O�@��t��C���킷�Ƃ���́w���U���o�x�ȂǂƂ����A�ɂ߂ČÂ��܂�����ȕ���������̈��p�v�i�s�g�����A���x�X�N�t����R�c�A2002�N5��31���A�O�܃y�[�W�j���Ǝw�E���Ă���B�g���͋�C�̂��̏͋�Ƃǂ��ŏo������̂��낤�B���т̏��o�́s�C�t1983�N6����������A����ȑO�Ɋ��s���ꂽ�����Ƃ������ƂɂȂ邪�A�܂�������|���肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂��A�ȑO�̋Ζ���ł���}�����[����o�Ă���
�@�@�i1�j�n�ӏƍG�ҁs�Ő��E��C�W�k���{�̎v�z 1�l�t(1969�N9��20���j
�@�@�i2�j�{��G���s�������E�̍\���\�\��C�w�鑠���o�x�k�}���p���l�t(1982�N2��25���k��6���F1984�N4��10���l)
��2�������݂��邩��ŁA�Ƃ�킯�i2�j�́s�������E�̍\���t�i���ł́s�l�Ԃ̎�X�� �鑠���o�w��C�x�k���{�̕��� ��4���l�t�}�����[�A1967�j�����ڂ����B�}���p���ł́q�l �l�Ԃ̎��o�r�́q�i���̒Q���r�ɂ͂�������B
�@�w�鑠���o�x�̏����o���́A���̂悤�ȉi�����Î�������������ł͂��܂�B
�@�@�I�I�m���������n����I�I����A�͂Ȃ͂��I�I����B
�@�@���O�m�Ȃ����n�i�����ƕ����ȊO�j��縑緗�m���₤�n�i�����j�A�疜�̎��m�����n����B
�@�@�����m���������n���� ��������A�͂Ȃ͂���������B
�@�@���Ƃ��ЁA���Ƃ��ӂɁA�S��̓�����B
�@�@���m����n�i���ʁj���m���n��慁m�ӂ��n�i�Ǐ��j���m���n���Ȃ܂����A���Ɖ��m�����n����B
�@�@�m�炶�m�炶�A��m���n���m�炶�B�c�c�i�ȉ�������匇���J�j
�@�@�v�Ўv�Ўv�Ўv�ӂƂ����m���₤�n�i���ҁj���S�m���n�邱�ƂȂ���B
�@�@�����i�����Ñ�̐_�_�j�A�����R�m�ȁn�߂ĕa�҂�߂��݁A
�@�@�f菑�m���n�i���U���j�A�Ԃ��@�m����n�Ė����m�߂��͂��n�𜼁m���́n��ށB
�@�@�O�E�i���̐��j�̋��l�m���₤����n�͋��m���₤�n���邱�Ƃ�m�炸�B
�@�@�l���i�����Ƃ���������́j�̖ӎҁm�܂�����n�͖Ӂm�܂��n�Ȃ邱�Ƃ����m���Ɓn�炸�B
�@�@���m���܁n�ꐶ�ꐶ�ꐶ��Đ��m���₤�n�̎n�߂ɈÁm����n���A
�@�@���m���n�Ɏ��Ɏ��Ɏ���Ŏ��̏I��ɖ��m����n���B
�@���̎��́A��������̂̉i���̒Q�����ق��Ă���B�k�c�c�l
�@����Ӗ��ł́A��C�̖���ς́A�����l�̂���̐��Ƃ݂�����A�ނ��뒆���l�Ɠ����悤�Ȑ[���A�e���h���Ȃ�����A�l�Ԑ����̎]�̂ɓ]���邽�߂́A���邢���N�Ȑ����͂ɗ��Â����Ă���悤�ȂƂ��낪����B�E�́w�鑠���o�x���̎��Ɠ����悤�Ȑ����̒Q�����A�w�����o�J��x�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B����A���͂킪��Ђɂ��炴��ǂ��A�����m�ނ݂₤�n�̕��A����B���͉䂪�~����ɂ��炴��ǂ��A���Ɓm���Ӂn�̋S�A����E���B���͂���y�ɂ��炸�A�O��̂��܂�Ƃ���B�����܂���тɂ��炸�A�������̗J�ցA�����܂��ɂ��܂�B���͍���̂��Ƃ��Ȃ�ǂ��A��餁m�����т�n�����܂��ɍÂ��B���s�͍����A�a���͖��[�Ȃ�B�����Â�ɏH�t�̕���҂������̂�ŁA��m�ނȁn�������I�̓��ɍÂ���������{�ӁB���̐g�̐Ɓm����n�����ƁA�A���m�͂��܂n�̂��Ƃ��A�킪���̉��Ȃ邱�ƁA�����m�ނ���n�̂��Ƃ��B�@�����āA����ɑ��A�|�m�Ђ邪�n�����Ď��̂悤�ɂ����B
�߂������ȁA�߂������ȁA�O�E�m�����n�̎q�B�ꂵ�����ȁA�ꂵ�����ȁA�Z���̋q�B�P�m���̑P�U�m�����n�̗́A�哱�t�̑�߂̌��ɂ��炸���́A�����悭�A���]�m��Ă�n�̋Ɨցm���ӂ��n��j�āA��Z�̕��ʁm�Ԃ���n�ɓo���B�@�����̖���ς��_�@�Ƃ��āA�l�Ԃ̎��o�ւƗU�m�����n�Ȃ��Ă䂭�̂ł���B�i�����A�܌܁`���y�[�W�j
��̂ɋg���͎��тɂ����Ă��A�U���ɂ����Ă��A�i�c�k�߂⍂���V�g�̂悤�ɂ͏@���I�ȕ����𑽗p���邱�Ƃ͂Ȃ������B�����A�K�v�Ƃ���Βn�̎���ł���A���p�ɂ�鎍��ł���A�v��������߂邱�Ƃ��S�O���Ȃ������B�s��ʁt�̝{�������鎍�сq�C�g�r�́u((����@����@����^����āi���m���悤�n�j�̎n�߂ɈÂ�))�v������ł���A�q�}�сr�́u�u��낸�̂��Ɓ@�݂ȁ@�����炲�Ɓv�v������ł���B��ҁA�u�u��낸�̂��Ɓc�c�v�v�͐e�a�̌�^�s�V�ُ��t�Ɍ�����͋�̈��p�Łi�����ꕔ�A���ς�����j�A��߂ȃe�N�X�g�ł�
�@�@�k�c�c�l���Â̂��ƁA�݂Ȃ��Ă����炲�ƁA�k�c�c�l�i���q��h�Z���s�V�ُ��k��g���Ɂl�t��g���X�A1981�N7��16�����Łk1991�N3��15���F��76���l�A�����y�[�W�j
�ƌ�����B���я����s�e�a�t�����ܖ؊��V�́q���� �V�ُ��r�Ɉ˂�A�u�k�c�c�l���ׂĂ͋ȁA�U��ɂ݂����A�]���̂����܂�Ȃ��ނȂ������E�ł���v�i�s�V�ُ��̓�\�\�e�a���߂����āE�u����V�ُ��v�E�����E�Βk�E�֘A���ꗗ�k�˓`�АV���l�t�˓`�ЁA2009�N12��25���A��y�[�W�j�B�s�V�ُ��t����̂��̈��p�́A�s�鑠���o�t����̈��p�Ɋr�ׂĖڗ����Ȃ��B���ꂩ����ʂ��A�H���K�l�����̎���������Ă��Ȃ����A���R�̂��ƂȂ���T�������Ă��Ȃ��B����قǁu���ׂĂ̂��Ƃ݂͂ȊG���v�Ƃ��������͐܂�ɐG��ĂӂƑz�������ׂ�A�����̂����ɂ��e�������̂��Ƃ�����B��������́A�e�a�̔ߒV����C�̂���Ɋr�ׂĐy�����Ƃ��Ӗ����Ȃ��B�g���ƂāA�����悤�Ȑؔ��̓x�����ň��p�����ɈႢ�Ȃ��B
�Ō�ɁA�����o�邩�ǂ����킩��Ȃ�����Ă݂�B�g�����ɂƂ��ās���}�сt�Ƃ͂Ȃ����̂��A�Ƃ����^��ł���B�s���}�сt�Ǝ��Ƃ̊֘A�ł���ꂪ�����ɑz�N����̂́A�s�E�r�E�G���I�b�g�̒����s�r�n�t�i1922�j���낤�B�[����͂��́s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N10��25���j��
�@�V���t�H�j�[�w�r�n�x�̈Ӑ}������̂ɂ��Ă͎�X�̉��߂��������ł��炤���A�S�Ȃ𗬂�Ă�郂�`�[�t�Ƃ��Ďg�p����Ă��̂́A�G���I�b�m���炱�̎��ɕ��������ɂ����炩�Ȃ₤�ɁA�~�X�E�E�F�X�g���iMiss Jessie L. Weston�j�̐��t�`���Ɋւ��錤���w���J��胍�}���X�w�xFrom Ritual To Romance�ł����B�����ɃG���I�b�m�̓t���C�U�[�iFrazer�j�́w���̎}�xGolden Bough�ȂǃC�M���X�����Ȍ��n��������������q���g���A�A���ՁiVegetation ceremonies�j�Ȃǂ̌��n�����̍��J�`������Ă��̎��̍��g�����݂��Ă��̂ł����B�i�����A���܃y�[�W�B�����͐V���ɉ��߂��j
�Ǝ�����W�J���Ă���i���Ȃ݂��s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�́u�ĔŁv�͋g�����̑����ɂȂ�ƍl������j�B�[���͖`���́q�����ɂ��ւār�ł́A�d�E�l�E�t�H�[�X�^�[�́u�킽���͖��̒��j�ւЂƎv�Ђɔ�э���ŁA���������́w�r�n�x�Ƃ��ӎ��͉��̂��Ƃ��r�Ă�鎍�Ȃ̂��[�I�ɑł������悤�B����́A����ׂ����Ă��͂�肨����ƂȂĂǂ����悤���Ȃ��t�̐����A�����̉J���r�Ă��̂��B����͐�ɋ��|�̎��Ȃ̂��B��Ȃ��n�͌͂�A�C���͉��̑��ƂȂ�A��n��|�ӂׂ����J�͖��͂������A���͂������Ƃ̍Ղ肾�B�������Ă��̐�ɋ��|�����܂�ɂ�����Ȃ��߂ɁA���l�͐オ���т�Ă��܂āA���̂��Ƃ����R�ƌ��ɂ��邱�Ƃ��S���s�\�ɂȂ�̂ł���c�c�v�i�����A���y�[�W�j�Ƃ����]���Ɏ^�ӂ�\���Ă���B���̎��̗����ɂ́u���t�`���v�\�\���v�������I�\�͂����������ʁA���y�͍r�p����B�����ֈ�l�̋R�m���o�ꂵ�āu�댯�̐����v�ɋ߂Â��A�Ñ�ɒj�Ə��̏ے����������Ɛ��t��D�҂��邱�ƂŎ͉�����A�r�n�Ɏ��J�ƖL�`�����A����\�\���������Ȃ��Ɛ[���͎w�E����B�����Ăi�E�k�E�E�F�X�g���i�ۏ��N�Y��j�s���J���烍�}���X�ցk�p���E�E�j�x���V�^�X�l�t�i�@����w�o�ŋǁA1981�N11��2���j�́q���� ���_�r�ɂ́u���N�O�A�i�E�f�E�t���C�U�[���̉���I�Ȓ����w���}�сx���͂��߂Č��������ہA�킽���͐��t����̂������̓����Ƃ����ɏ��q����Ă��鎩�R���q�̓��قȍו��Ƃ̊Ԃɂ݂���ގ����ɋ�����ۂ��������B�����Ȗ��ɕ��͂������قǁA�܂��܂����̗ގ����͍ۗ����ė��āA���ɂ킽���́A���̕s�v�c�ȓ`���\�\���̐��i�A���̓ˑR�̏o���A����ɋA�����Ă��閾���ȏd�v���A�����đ����ċN�铂�˂Ŋ��S�ȏ��łƂ������_�ɂ����Ă��������s�v�c�ȓ`���\�\�̒��ɁA���Ă͖��Ԃɗ��z���Ă������A�̂��ɂ͌������閧�̏����̉��ɐ����̂т邱�ƂɂȂ����ЂƂ̍��J�̞B���ȋL�^���c����Ă��������m��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ͉ʂ��ĉ\���ǂ��������ɖ₤�Ă݂��̂ł���v�i�����A�l�y�[�W�j�Ƃ��邱�Ƃ��l����A�s���}�сt����s�r�n�t�����������u���t�`���v�܂��āA�g�����q�}�сr���\�z�������Ƃ͏[������悤�Ɏv����B�Ȃɂ����A���o�W��q�t�̓`���r�Ɂu���t�`���v���e�����Ă��Ȃ����낤���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�������Ɂq�}�сr�ɂ��ꊇ�ʁi�u�@�v�j�Ŋ���ꂽ����̒���I���p���������Ȃ����̂́A�u�J��v��u�T�^���v�u�R�r�v�Ȃǂɂ́s���}�сt�̉����c����������悤�i���Ȃ݂ɏH���K�l���q雞�r�i�J�E1�j�Ƃ̊֘A�Łs�g�����A���x�X�N�t�́q�g�����ӔN�̎����r�Ō��y�����̂́A�s���}�сt�́q��l�\���� �����Ƃ��Ă̍�����r�́q�O �Y�{�Ƃ��Ă̍�����r�������j�B�Y������ӏ����A�{���Ɉ������̂Ɠ��l�̌`���Ōf����B
�E�v���X�J�̑��ł́A��鯂��I�点�ĉJ���~�点�邽�ߑ��̏��������������镪�ɗ��̂ƂȂ��đ����܂ōs���A�����Œn�ʂɐ������������B�i�q��� �V��̎�p�I���߁r�A��E153�j
�E�ꔪ��O�N�l���̖����Q�[�̂��߃V�V���[���ɑ傫�ȍ����̏P���������Ƃ�����B��鯂͔��ɂ��y�B���z�͖��������A�_�̕Љe���ɂȂ���ɏ����Ă͒��B����킵���̑т̂悤�Ƀp����������芪�����R���J�E�h�D�I���̉��́A���̂��߂Ɍ͂ꂩ�����Ă����B�H�Ƃ͒f��ɕm���Ă����B�Z���͑傫�ȋ��|�ɂ��̂̂����B���悻�m���Ă������̉J��̕��@�͎��݂�ꂽ���A��������X�Ɍ��ʂ͂Ȃ������B�s��͊X�ɂ����ɂ��A���������炸�������B�j�������q�������ł�����A������܂���Ȃ���A���邩�����䑜�̑O�ɔq�������B�i�q��� �V��̎�p�I���߁r�A��E173�j
�E�k�c�c�l���v���V�A�̃t�@�C�����z�[�t�̋ߖT�ł́A�T�����𑖂��čs���̂�������ƁA�_�v�����͔��𗧂Ă��邩���炵�Ă��邩�ɒ��ӂ���̂ł������B�����T������n�ɐ��炵�Ă����Ȃ�A��������čs���ĕ��������ė��Ă��ꂽ�ƌ����Ċ��ӂ��A���̑O�Ɍ�y����u���Ă�邱�Ƃ��炠�����B�Ƃ��낪�A�������𗧂ĂĂ����Ȃ�A������_���ĎE�����Ƃ����B�܂肱�̘T�́A�L��̗͂����̔��ɂ�����������Ȃ̂ł���B�i�q��l�\���� �����Ƃ��Ă̍�����r�A�O�E242�j
�E�M�G���k�ł́A�Ō�̍�������������ƁA��C�̋����r���イ�����܂킷�B����́u���̘T�v�ƌĂ�Ă���B���̊p�͉Ԋ⍒���̕�ŏ����A�������ԑ���F�R�ŏ�����B�����͎c�炸���̗r�̌�ɂ��āA�̂��Ȃ���s�i���čs���B�Ō�ɗr�͔��œj�E�����B�t�����X�̂��̒n���ł́A�Ō�̊��葩�̂��Ƃ������ coujoulage �Ƃ����B�܂苎���r�Ƃ����Ӗ��ł���B����ŋ����r��j�E���邱�Ƃ́A�Ō�̊��葩�ɏh���Ă���ƐM�����Ă��鍒����̎���\�킷�̂ł���B�����������ł́A������̓�̈قȂ����`�\�\�T�Ƌ����r�\�\����������Ă���B�i�q��l�\���� �����Ƃ��Ă̍�����r�A�O�E246�j
�E�k�c�c�l��o�C�G�����̃}���N�g�D���ߖT�ł́A���葩���u�m�R�r�v�܂��͒P�Ɂu�R�r�v�ƌĂ�ł���B���葩�͍L��ɎR�Ɛς܂�A���݂��Ɍ����������ė����̒j��������������Ȃ��̂ł��邪�A�ނ�͂������ƘA�g��ł����낵�Ȃ���A���̒��Ɂu�m�R�r�v��������Ƃ����悤�Ȏ����̂��̂ł���B�Ō�̎R�r�A�܂�Ō�̊��葩�́A�X�~�����̑��̑��Ԃ̉Ԋ�A���ɒʂ����َq�Ȃǂŏ���B�����đ��̎R�̐^���قǂɈ��u����B�ō��҂̈�l�����ɂƂт��āA���̂��܂��Ƃ�����������炨���Ƃ���B���̎҂����́A���Ƃ��Ĕ]�V�������������邱�Ƃ����邭�炢�A�����e�͂Ȃ��A�g���������낷�̂ł���B�k�c�c�l�^�k�c�c�l��o�C�G�����̃g�D���E���V���^�C���ł́A�����̍Ō�̊��葩�ɂ́u�����R�r�v������ƐM�����Ă���B����͗��Ă����Ђŕ\�킳��A�Ó�œ��������炦��B�q�������͂��́u�����R�r�v���E�����Ƃ���������̂ł���B�i�q��l�\���� �����Ƃ��Ă̍�����r�A�O�E257�A258�`259�j
�i�����j�@���сq�}�сr�ɂ́A�G���b�N�E�Z�����h�����W�s��ʁt�S�т��p���sKusudama�t�iFACT International�A1991�N�k�����s���l�j�����́qCollection of Green Branches�r������B�s�g���������t�́q�p�W�sKusudama�t���r�ł��G��Ă���Ƃ���A�sKusudama�t���瓯�����܂�3�т�duration press�̃T�C�g�Ɍf�����Ă���̂ŁA�ȉ��Ɂq�}�сr�́q�T �n�̗�r�q�U ���̖��r�q�V �̘T�r�q�W ���̉r�̉p��̊e�y�[�W�Ƀ����N���Ă����B �q1 Earth Spirit�r �q2 Dream of Water�r �q3 Fire Wolf�r �q4 Wind Flower�r
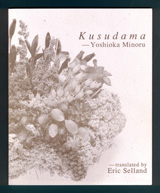
�G���b�N�E�Z�����h�ɂ��p�W�sKusudama�t�iFACT International�A1991�N�k�����s���l�j�̕\��
���߂ɁA����2011�N6��18����Amazon.co.jp�ɓ������s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�̃J�X�^�}�[���r���[���Čf����i�W�蓙�̕\����{�T�C�g�̂���ɉ��߂��j�B�������т̃^�C�g���ɒ����������N�́A�{�e�f�ڂɂ������Đݒ肵�����̂ŁA���e�̃��r���[�ɂ͂Ȃ��B
�{�����s�i1996�N�j�܂łɊm�F���ꂽ�g�����̑S���т��W�听�����A�����ǂ���̋g�����S���W�i���̏W�s�����G�߁t�����̘a�̂��܂ށj�B�`���̎��сq�t�r���������������o��������A�Ō��̓K�ȏ��u�ɂ��ŏ��������r�ŐH���Ƃ߂�ꂽ�B�q�{���̕ҏW�ɂ��ār�̕��j�Ɋ�Â��{���Z�����قƂ�ǖ��Ȃ����A�q�������r�Ŏ����^�����̂悤�ɑg�܂�Ă���u���m���v�j�v�́A���o��������킩��悤�ɁA�{���̈�s�߁i�����������j���낤�B�q�������с@1947-90�r�́s�����G�߁t����s���[���h���b�v�t�܂ł̎��W�ɓ����Ă��Ȃ�15�т��琬��A�{�����s��ɐV����6�т���������Ă���B�S���W�����^���тɁ����t���āA�ڎ��̑̍قŌf����B
�������с@1947-90
�s�g�����S���W�t�̃J�X�^�}�[���r���[��2017�N11�����݁A��f�̎��́q��������Łw�g�����S���W�x�������́w�g�����S�W�k��1���l���W�x�̊��s���ؖ]�����r���܂߂āA2007�N5��25���f�ڂ̃]�[�C�q����̖쐶�ɒB���Ă���r�A2015�N8��31���f�ڂ̈ĎR�q�q���Ƃ��Ă̐�捂ȈÍ������r��3�����A�b�v����Ă���i���������5�̖��_�j�B�����Ƃ�������ǂl���s�g�����S���W�t���w�����悤�Ƃ��邩�͋^��ŁA���r���A�[�������̂����Șb�����A������ǂ݂����Ǝv���قǂ̎҂̓��r���[�ɂȂ�Ƃ��낤�����肷��ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁuAmazon�v�ł̒��Ẩ��i�́A24,890�~����320,000�~�܂łŁi�u���{�̌Ö{���v�ł�37,800�~����200,000�~�܂Łj�A2���~��Ȃ�A�������̉��i12,000�~���炢���āA�����Ȃ��B����킩��Ƃ���A���̃J�X�^�}�[���r���[�́s�g�����S���W�t���ł̍w���𑣂����Ƃ���͂قlj����A���̊��S�Łi�ɋ߂��j���s��]�ނ��̂������B�c�O�Ȃ��ƂɁA2017�N11�����݁A���ꂪ��������C�z�͂Ȃ��B�ȉ��ɁA�g�����̊����̊e�P�s���W�̖{���Z�قƓ����`���Ŗ������т̖{���Z�ق��f���A����ׂ���������Łs�g�����S���W�t�������́s�g�����S�W�k��1���l���W�t�̊��s��҂������B�Ȃ��A����̖�������15�т̖{���k�@�l���̍Z�ق́k���o�`���s�g�����S���W�t���^�`�l��\���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�n�����ā@���т����Ȃ���
�C�֍s����
���ꂽ���̊C�֍s����
�ł��������������ˏ��
�ǂ��ɂ����̔g�����ӂ�Ă���
�ߌ�̕����͂������
���ꂳ��̓��[�̂悤�ɂ₳����
�͂邩�����Ł@�����_�������Ă���
�����ĂЂƂ�ڂ���
���т�����ȁ@������̊₩����
�I���A�𐁂��ċ����肵�Ă��邵
�܂��ꂽ�Ԃт�݂����ɉ����Ƃ�ł���
�����ė[�Ă̕l�ׂ�
�ʂꂽ�炢��̊L������Ђ낢
���w���S�Ă����낤
���̂Ƃ����@�Ƃɂ����낤
���s�k�i�������сE2�j
�_�̏����Ђ炩�ꂽ��
�e�ɂȂ�����ɂ�
�D�F�̔g���d��
�c�X�q�֏������
�ւ�S���������Џo��
���̍����c��
���������i�������сE3�j
�@�@���m���v�j
���K�g�r�R���_
�X���g��m����܂����ԃ�
���������m���K
�샌�_�V
�C�c�y���j
�ăm���n���P�e�V�}�c�^
����ɂ��i�������сE4�j
�Ђ���̂Ȃ������킽���͂��邢�Ă
�Ȃɂ������Ƃ߂Ă��邢�Ă
�킽���̂䂭�����ɂ��ꂩ�̂������Ƃ��̂��Ă
�Ă�Ă�Ƃ킽���̂��Ȃ��݂��͂邩�ɂӂ������Ȃɂ��Â�ł
������킽���������䂤���Ă��������Ƃ͂Â��Ă
���ꂪ����Ȃ��т������̂��̂����Ă����̂�
���Ȃ͂������ɂ��킢�Ă߂�����
���������̂܂������̂�����ɂ��܂��Â��Ă
�Ƃق��Ȃ������݂̂��ւ������߂��ЂƂƂ�ł
�ɂ���ǂȂ��Ȃ��炳�Ă��܂�
�킽���͂킽���̂܂ւ��䂭�ЂƂ����Ƃ߂Ă��邫�Â���
�����̂ڂ�Ƃ��ɂ��̂ЂƂ����Ђ����ĂȂ�Ȃ���
���f���i�������сE5�j
�i���ɏM�̋���䂭
�����̊C�ɍ��̂ӂ邳�Ƃ�����
��ꕂ��ׂ̕��p���
�ܜ������������̂�
�����킪��Y�̎�
���^�����̔g�ɐ�͂�
�ӂ����і��C�̌���݂��ւ�
�͂邩�Ȃ��A�����z��
�����̂��̂������܂�Ƃ�
���A�d�i�������сE6�j
�S�C�̔L�ɂ͕S�C�̓G������@�����C�̐S�₳�����L���x���`�̕Ћ��ŐV�������ł���ƌ��Ȃ�ʎ�̐܂ꂽ�L������ŐV������݂͂��߂�@�X�q�����Ԃ����S�₳�����L�̓X�|�[�c�̋L������݂����Ǝv���Ă���̂����@�ׂ̔L���푈�̔ߎS�ȃj���[�X����ނ悤�Ɏw�}����@�S�₳�����L�͔������Ȃɑ������������̂��@���ϕi�̍L�����݂����Ǝv���@�܂ꂽ��ŗׂ̔L���ɂ�ɂ���Ȃ���@�R�͂̒��v���Ă䂭��ʂ̎ʐ^�������̂Ł@����㢂̗ނ�ޕ��ɒ��߁@�������M�����鐅���̕������ĊC���ɒ���ł��܂��@�������ׂ̔L�͕ʂ̌R�͂̍b�Ő܂ꂽ���U���Ă���@�S�₳�����L�͌������o�ă��X�g�����Ɍ����@��̐܂ꂽ�L�������ꂽ��т������Ȃ���@�����H��̑O�ɍ�������@�S�₳�����L�͖����̎d���̂��߉h�{���̂�����̂𒍕�����@��̐܂ꂽ�L�͂����������������Ƃ������炾�����傤�Ԃ��Ƃ����@�A�d�͐H���ɊW�������@���C�̗��X�[�v�̂����Ɂ@�����P�̕�H��̏�ɒu�����@�S�₳�����L�͋̂܂܂����g�ɂ��ĂƂт����@�����܂��\���C�𗁂ѐ펀����@�܂ꂽ��ŔL�͉J�łʂꂽ�����𐂂炵�ˌ���������Ă��܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ܘZ�E�܁E��\��
�K�����̏㔼�g�͗����@�ނ���͖̑��݂ɂ������@���炷�̂ނ����Ł@����搶�������p�ɂ��������Ă̂������ށ@�K�����̐�k�����l���������@���������K������㵂����̂��@�������菗��搶�������Ȃ̂Ł@�������l�Ԃ̊튯�������ȁk�����l�ā@�[�����Ɏx�����ĂȂ��@�����̕��̂ł���@���̑��قǂ̖������������@�݂��݂������l���̗t�ɏ����ĂȂ����Ƃ��@���k�����l�����������͂��炫�̂Ȃ����̂ɂ���@�������̂Ȃ��Ől�Ԃ͐^���̗����ł��悤���@����搶�͂������ɐE�Ƃ̗������͂��߂�@�߂�����Ɗ�Ł@�K�����̊������������Ȃ���@�����Ăӂ��肾���́@�Â��ꏊ���Â����̓����ł݂����@�Ӗڂ̐��E�ŋL�^���ꂽ�J���e�͉i���ɔ��ǂ���ʂ��낤�@���̂��ׂĂ̗��l�����̎莆�̂悤��
�邻������Ă̖�@�ڂ��͏��g�Ƃ��Ă܂�������@����ł�����^�Ԃ̉���Ƃ炦��@�ق������N���̍Ȃ̂��߂ɂ��@�ڂ�����F���ʂł������@��̂��������̓��̂͐K�ւڂ܂�@�^�ْ̋������쐫���֎�����@�Ȃ̊�̂Ȃ��ł���ɉ����ā@���̂̂��A���̐��L���ЂƂȂ��̕��@�����܂ł��Ȃ��@�Ȃ̐S�͂��₨�����Ȃ��@��̉s�����œ��H�����@�ԕ��Ɗ����Ȃ����Ȃ̑S�g�𔒎��̃V�[�c�ʼnA�������@���i�ȏ��g�̂��������납��@������̘X�̂ɂԂ�������@���Ăɂ͔S�y�̒��@�܂��ɂ͑S���܂Ԃ����Ƃ������Ƌ�ށ@�ڂ��ƕm���̍Ȃ͓���̊ǂŁ@�����ɐ����z��������@�����A�̂Ȃ���@���̖��݂鑕���с@�ł�������l�̊ԂɐԂ�V�������Ȃ��犄�肱�ށ@����Ȍ��o���f���ĕX�R�����荞��ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ܔ��E���E�l
�������i�������сE9�j
����͈��͕������낤
�ڂ��ƌ����������Ȃ����̒���
�̂肱��
�ڂ���s��ȕ����Ŏh��
�L���x�c�E�W���K�C���ɊŎ�����
�ڂ��͕m���̋q
�X�[�v�̓��C�̑��̊Ԃ̖�
�e�[�u���̏��
�������̔���������������
���ʂ��猌�𗁂т�
�Ȃ悱���낹��
���ꂪ�ڂ��̎����S
�ڂ��̋����l�֔̕��
�ʂ�����������݂�
�������瑼���ւȂ�����
�������ꂽ�{�̎��
�ڂ��̓����m�Ō����
�����̐��ʂ�����
�O����
�ڂ��͑ς��E��
�kઁ��ׁl�Ƒَ���
���ƛK�w������ւ���
�ڂ��̖����̍��p
�霂ƕ��я��
��̒��ŔԂ̂����炵�𓀂炷
���̕��Q�̋L�O��
���̓�j�҂����ċ�����
�ڂ��̕s�ρE�ڂ��̏}�����_
�����։Ύ��т�
���łɂ����̔�
����l�Ƃ�]��
�ڂ��Ɩ��ʂ����l�Ȃ�
�c���̃}�k�J����
�ڂ��͕������낤
�����̋�����邲�Ɩ邲�Ƃ�
���g��i���Ɏ~���i�������сE10�j
�@�@�@�@�w�f�B���q�����A�W�A�T���L�k�r��聨���r�l
1
�킽���́@��l�̏]�҂ƈ�l�̐鋳�t�ƂƂ���
�l���n�Ԃō����̓����ɒ�����
��������킽���̖����͂��܂�
�킽���ɂ���������
�ق��̎O�l�̒j�ɂ͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���
�����I���̊ԁ@���ɂ������ꂽ
�`���̉��@����̏����̐����̗��j
������������킽�������̌��o���낤��
���s�̃X�e���h�O���X�̎��@�̑�����
�Ȃ���o��͂̂Ȃ���@�Ƃ��ɂȂ���鎞�̂Ȃ���
���͓�����@�邠���邢�����̂�
���߂Ă��郄���J���h�͂̂߂����Ȃ���
2
�����@�킽���͏]�҂̈�l���Ă�
�킽���͂��̒j��є�̒j�Ɩ��Â���
�����̂̔���͂��̂����̒j�̐_���ȐE�Ƃ���������
�є�̒j�̓����J���h�֔����̂炭���ƕ������߂ɍs����
������l�̏]�҂͋߂��̎x�ߐl�̎s�ꂩ�琅�Ɣ����I�����܂Ȃǂ̕K�v�i���Ė߂�
���̒j���킽���͏����ƌĂ�
�ނ͉k�̃^�u�[��`���@���̏o�O�ɕ���H��������
�Y���������s��ɂ���
�����j�ł͂Ȃ��̂�����
���o�̔w�ɂ̂���ꂽ�܂�
���̂悤�ȋ��������������̂��~����
�����̓T���g�l�ɂ��������
���k�̖̖݂�
�Ƃ��ɂ͐��Ȃ��n���悲���ɍs��
�F���t�̑��ۂ̂Ȃ��ދł܂�
����̂��ǂ�����ǂ�̂�
�鋳�t�ɂ͎d���͂Ȃ��@�ނ͒��͊�������
�[���͂���ӂ��r�̓���H��
��͋F���t�̎c������̂�ł͓f��
�킽���͋C�ۂ̊ϑ���
�S�u�����D�̂悤�Ȓn�}���Ђ낰��
���̒n�}����
���o���N��������@�����̕n�����L�����o������
���̒n�}�̕ʂ̕��p�@�ΐF�ɓh��ꂽ��̂Ƃ��납��
㷗r�������@�킫���ӂ�@�b�����Ƃт܂��
���̒n�}�̊��F�ɂ���ǂ�ꂽ�u�������
���z����e��@�����̎����Ƃ炷
�o�ዾ�̎��E�̂�����@�U�Ȃ����̌�
���̐�̂悤�ɉ���ĂȂ��ӂ���݂�����
�����ɂ킽���ȊO�̎҂̑��Ղ������Ă͂Ȃ�Ȃ�
������l�ԁE������l�Ԃ̂��̂ł���
�ŏ��̉����ҁE�킽���̋�̏d�݂��x����
�킽���̑��ՂłȂ���Ȃ�Ȃ�
�_�X�ƂÂ��_�X�Ə����܂��Â�
�킽���̐����̏��łȂ���Ȃ�Ȃ�
�T���i������
�T��������菓��҂�����ł���
�킽���̊�]�̂��߂�
���Ɛ��̗̈������ė����Ă���̂�������
�����ނ����@�����ނ���
�킽�����鋳�t��
�������ЂƂ�˂̖���ɂ����邾�낤
�є�̒j�͂��߂邩
�M�̗����̂悤�Ȃ����܂������̒j��
�킽���͐M�����đ҂�
�����Ƃ������@�������ĂƂ�����
3
�^�N���E�}�J�����������f����L�����o��������Ƃ�����
�킽���̏h����l�̘V�l�����Ƃ��ꂽ
���̂��炷�̂悤�Ȃ��ݐ��̘V�l
�ނ͂킽���̖ړI��T��ɂ����̂����m���
�ˑR�@�����̒��ɉi���Ɏp��������
���̓s�̍����
�킽�������������ɂ����̂��Ǝv���Ă���̂��낤��
�V�l�͌��̂ł���
�Ⴂ���̋��낵���̌���
���삪���܂Ȃ��p�Ђ̎��͂ɂƂǂ܂�
�����T���҂��������ɂ݂��т�
�݂��݂������ʕ�������ĂȂ��M
�����₩�Ȗ����̎M
���̂܂��Ŋ����Ȃ��物���T���҂͎���Łk�䁨�s�l��
���g�͍��ɂ�������
���Ƃ̔��g�͂߂�������̊��ɂ�������
�R�L�̂ނꂪ��
���Ⴑ���˂��݂̂ނꂪ��
�͂��߂͎R�L�����̐l�`�̂悤�ȉa�H���݂���
���ɂ��Ⴑ���˂��݂̂���ǂ���������
���̂Ȃ��̓���
���̂Ȃ��̍���
���̂Ȃ��̔��̖т�
�Â̂Ȃ��̐H���͂������ɍs����
���̂����̐H���͂������ɏI��
���ꂩ����S�N���
�ʂ̉����T���҂����͍���̂�����
�ʂ̂��̂��݂��o�����낤
��ȐF�ƌ`��������������̎x�߂����U�����Ă���̂�
��ɂƂ낤�Ƃ���Ƃ�
�x�߂��͂����܂��o�̂��Ƃ�������
���Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂�
�c�c�c�c�c�c�c�c
�V�l����肨��邱�뒿�����J������
�킽���͂��̌���E�`������Ɂk�����t�l�����Ƃ͂ł��Ȃ�
�����킽���̊댯�ȗ��s�͒��~����ʂ��낤
�킽���ɂ͐������̔ޕ���
�������N�����鍻�u�̌ۓ������ɂЂт��Ă���
�킽���̃��}���`�b�N�ȉ������k�x�^���S�p�A�L�l���m�̐��E
���m�̋�ԂL�^����邩������Ȃ�
�����s�K�ȉ^�����킽���̗����Ă��鍻�̏�
���̍��̉��ւ��̂т��Ȃ����
4
�킽���͂�������
�t�˔M�Ƒ�C�̂Ȃ��ɂ���o�̗ʂ�
���x�̖��ڂȊW�����ĕ邷
�鋳�t��
�����܂��������̐����ʂ�����
��x�̋��Z���l�̖�݂̂���Ȏ����ɂ���
�x�鏗�̂ւ��ɂ͂߂��Պ���P��
�[���Ė߂邷�ׂ̂Ȃ���
�킽���͂��܂����Đ鋳�t���F��������Ă���̂�
�y���̕a�l�̊Ō삷��p���݂Ƃ߂Ȃ�
�ނ���x�͐S�����߂ċF�鎞������
�݂����炪�ˑR�̎��ɂ��т��鎞
�H��Ȃ����̂�����
�H��Ȃ����̂�����
�y���̂����Ȃ炷�W�C�U�[�Ƃ����y���
�������V���̓����őt�łĂ���
�Y�����������l�Ԃ̍������������R���C
�����̂Ȃ��̐����������A���悤�Ȗ邾
5
�є�̒j���߂��Ă����@�����̂炭�������
���ꂼ��̂炭���̔w�ɂ܂ꂽ�����̓����͊Â�
�킽���͗Βn�n�т̗���������������z�����
�p�����Ă��}�����E�o�V�C�̑��̌i���ƂƂ���
�є�̒j�͔��k���̑�������
�����ꌂ�������ނƂ��̉��Q��@�k�������l���Â��Ă���є�
�召���܂��܂Ȃ炭�����~�`�ɂȂ�
�b���C�܂܂ɐH�ׂ�̂��݂Ȃ���
�킽���͈�ӂ̊G���Ϗ܂��Ă���₷�炬�����ڂ���
�����͗��l�ɂӂ����щ���悤�ɂ͂��Ⴌ
�є�̒j�̂��߂ɐH���̏���������
��������@�}�J���j�𖭂�
��H�̌{�̎�Œf��
�킽���ɂ͂����̂��Ƃ��܂��q�̓I�ȊG��
�����n���Ă͂��Ȃ��@�k�������l���߂������̑傫�ȉ�
�ǂ��ǂ��߂�������肩�����������
���ꂷ��킽�������̉^���̈Î��Ƃ͍l������
�킽���͐����ĖړI���ʂ��ł��낤
�V���̓������炽�����ɍ����ւÂ��Ă���s��
���ꂩ��������킪�����ׂ���
�킪���ނׂ���
���m�̐X�@���m�̋�
���m�̉́@���m�̐�����
���m�̐��E��i�ނ��߂ɂ�
�������ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킽�������������̂���
6
�����̔N��L�ɋL�ڂ����ׂ���
�킽�������͏o������
��o���j�����鐔�\���̎x�߂̐��K����ւ܂��ꂽ
�킽���͂炭���̔w�ɏ��Ȃ���
�R���p�X�𖢒m�̕����֊m�M�̂����ɂ̂�
�鋳�t�͕a�C���Ƃ�����ċ�����
�ނ͍��@�����ɏW��Q�W�̈�l�Ƃ��Č����邾�낤��
�������鉮���@��������l
���������
�A�W�k�����A�l�̔������t��
�r���Ƃ�����������
�킽�������ߌ��̃L�����o���̗邪�Ђт�
�����̂炭���̂��Ă���S�̐������
�݂��т��̗��@�����̗��
�s�g�ł���@�K�^�ł���@�킽�������͂ǂ��܂ł�
�Ƃ��ɗ�����ł��낤
�A�W�k�����A�l�̔������t��
7
�k�����͏I�������Â�
��ɂ͐��̂����ɍ����Ȃ����
���ׂĂ̐A���ނ��e���Ђ��߂邱��
�킽�������͋���ȍ��u�̖��{�ɂƂ����߂�ꂽ
���鍻�@�炭���̑��߂鍻
������ςw���炭���������
�\�ܙ������Ζʂʼnׂ����낵�Ă炭�����x�܂�
�������b�̗t��^����
�킽�������͏��ʂ̐��ł̂ǂ����邨���j�b�L������
�����Ȗт̂悤�ȉ_�̔ޕ��ɋ����͏�������
�є�̒j���擪�̂炭���̏�ŋ���
�k���Ɉꎞ�i�H��ς���
�킽���̂炭���������@�����̂炭��������
�ו���ςܓ��̂炭���������@��������������
�Ăэ��u���\��̍����Ŕ�ꂽ�L�����o�����Ƃ肩����
�����̔g�`�̉e�����ׂĂ̍��u�̒����𑖂�
����ƕ��R�Ȑo�̏�ɏo��@�r�т̂悤�Ȃ��炩���o
�Ƃ����܂炭���̒��ɂӂ݂�������鉖�̌����̕s�C���ȉ�
�킽����������c�n�ɂ��O�ɖ邪����
�є�̒j�Ə�������˂��@��
���̂܂������ƌ{���[���S���悹�Č����
��˂��ق邱�Ɓ@�����Ă��̂��̐��邱��
���ꂪ�킽�������̋��ȋʏ�
�����邱�Ɓ@�O�l�̐l�ԁ@�����̂炭���@��C�̌��@����琶�����̂������邱��
����͐���������ł��낤���@���̂悤�ɊÂ�����
�����͕����Ղ�
8
�킽�������͖����̑卻���ɂ������������
������悢���̔����@��̔��˂ɂ����₭�����݂̉�
�G�V���E�R�[���Ƃ���u�̌v�͂ǂ��ɂ���̂�
�є�̒j���������m��Ȃ��@�܂ڂ낵�̌�
�����ŗr�̍Ō�̈ꓪ��j�E���@�j�����ꂽ�H��������
���Ƌ����͌��ɗ^����
�����̐^���@�V�������O������@�~���̉�����
��D���̂����肪�Ƃтł��̂ɋ���
�����͔������k�J�Ə���n�j���k�����i�H��ς���
�邪�����Ă���@���C�t���Ō��@��͌Ǘ������R������
�ߌ�̏��ׂ݂̊͊^�̖����@��̋���
�킽���ɂƂ��Ē����Ȃ��n��̊y���ƂȂ낤
�є�̒j�Ə����͐����т���߂�Ȃ�
�킽���͍ȂƎq�̂��߂̎莆������
�ȂƎq�̂����ȃ^�}���X�N�̉Ԃ̓��������߂�
�Ƃǂ��Ȃ������m��Ȃ��̂ɐ[�����̂��Ƃ�������
9
���̐l�Ԃ̐��܂ʉʂň�l�̒j�ɏo�
�������ߎR���֓����čs���ǓƂȁk�S�p�A�L���g���l���̎�l���n��ł̍Ō�̐l��
�V�N�Ȑ��邱�Ƃ̂ł���Ō�̓y�n
���f�̌k�J���ď\�������o��
���u�͔S�y�̒n�\�֍���@�͂邩�쐼�֊g���Ă���
����嗋��ɂ������L�����o��
�킽�������͂����ށ@�����ށ@�ړI�n���w��
��x��������s��
�ׂ݂Ȃ����̑�m�k�m�������݁n���g���l�@���F����g�@�M������
���k�Ɨr���g���l�����C�̂��Ƃ������ɋߊ��
���������C�̂��Ƃ����������������ĚL��
��̐j�Ɏh���ꂽ���̑��z�@�ӂ��čs���킽�������̐S��
�Ȃ߂鉩���̐��@���̂Ȃ��̉����̐�
���̗[���Ȍ�炭���ɂ͈�H�̐����^���Ă��ʂ��낤
�������鍻�̒����ɂ͂킽�������̑����Ȃ��n
�_�̂Ȃ��ɏ�����
���̂炭���̂���
���܂킵���������̂���킽�������̂���
�B��Ƃ��ĉi���̍��u���悶�̂ڂ�炭��������
����̗��������点
�ޕ��̕X�ɂƂ����ꂽ�镃�Ȃ�R��
���̂䂽���ȕX�Ɛ���k�n���Ƃ��l��
�����͍Ō�̈�H�̐��܂œ��ݍs��������܂�
10
���ꂩ�������@��H���T�����Ƃ�ł��Ċ�]���߂��߂�����
�є�̒j�͂炭���̔A��|�ƍ������܂��Ă̂䂦
�������q�f�̂��ߕm���̏�Ԃɂ���
�킽���́k�����������ā��������߂āl���̃L�����o���𗣂��
�ڈ�̃J���e�������̕\�ʂ��������ɂ������ɏƂ�
�܂ǂ�݂ƌ��z�̂����ɐ����̐��ƃ��C���b�N�̓���������
�������͂���������@�킽���̓~�C���̖���
�R�[�^���͂̐X�̕�����
�r���̂�����тł������ʂł��낤��
���܂��̒��ق̖邪�L�����o���̍Ō�̏�ʂȂ̂�
�۔ۂ킽���ɂ݂͂��Âꂪ����
����̐��@�|�S�̐��_�@���̕��̏�
����̕��p�����Ɋ�����Ă���̂�������
���ɟ�ƈ��̂����ނ�
���ɉ݂͊ɂ��ǂ������
�킽�����퉹�Ɋ����Ƃї����@���炭���Đ�����������
�V�N�ł߂�����������
�������̐��̏�Ɍe���Ă����̂�����Ȗ`���Ɏv��ꂽ
�킽���͖������v�肻�ꂩ��̂M���V���̐_�X�̔�����
������䩔��Ƃ��Ĕ��ސl���̔ߎS�ȍs�����ɂȂ��u
�킽���͗������R�ʼn������������̂��Ȃ�
�����̂Ȃ��̓V�̌[��
�킽���͖h���C�ɂ����ς������[����
�����̗т̂Ȃ������ɂ���L�����o���̕��֖߂��čs��
���Ȃ�C�@��l�̐������~�����@���̑n����@�C���ɍK������
11
�킽���͌̍��ւ̋A�H�ɂ�
����D�@�����ނ������@����Η��n��@���������
�@�@�u�����ł́k�A���S�p�A�L�l�l�Ԃ̈ӎu�������̋���ȗ͂��k�A���S�p�A�L�l���l�ɂ��k�x�^�����s���ē����l�̋��\�k���s�����s���x�^�ŒǍ��l
�@�@���𐪕������Ȃ��k�B���S�p�A�L�l����ׂ��^�N���E�}�J�������k�x�^�����s���ē����l���n��̐X���k���s�����s���x�^�ŒǍ��l
�@�@���ۂ��x�z����_�̖��ɂ����Đ錾����k�B���S�p�A�L�l�k�x�^�����s���ē����l�s���̒n�܂ŗ���k�A���S�p�A�L�l�k���s�����s���x�^�ŒǍ��l
�@�@����ǂ��̒n���i�ނȂ���@���́k�x�^�����s���ē����l�n�ɂ����ē���ق��炵���k���s�����s���x�^�ŒǍ��l
�@�@�Ȃ�g��@�i���Ɏ~��t�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�i�{�e��蔪�\�s���폜���ċ�Z�Z�N�܌������m�g�j�������j���g���l
���̂Ƃ���Ɍ��͖���
�}�X�N�����͖̏����ȉ~�`��
�ЂƂ�̗c�����͂�ł���
�ΉԂ̋L���̂Ȃ���
��������ꂽ�H���̐��E
���݂̐��������c���̓��C��
�������Ԃ��Ă�������������
�t�N���E�̋��̒܂ł����ꂽ
��̌��͈Â�
����͖��Â��悤���Ȃ��ߋ�
�����Ƃ͗r���̂������H
��̃E�T�M�̌����z����H
�c���͖₢�Â�
���ɑ吺�ɂȂ�
���X�����x���O�̉��i�������сE12�j
���̂̐��n�ɂ���
�ЂƂ͍l����ׂ����I
�����Ă̂Ȃ���
�Â��r������ɂȂ�Ƃ�
�V�l�i�Ղ̎��̐オ�K�v���H
�ЂƂ�̒j�Ə��̗��k�i�V���́l�k���s���Ǎ��l
�ł̔M���M������
�����ł�������̉ԉ����Ԃ�
�����͂�����
�����܂�������
���Ȃ��̖т̂����܂�k�����ׂ遨�̊Ԃ����܂悤�l
�����P���Ȃ�
��������̕X�̐��E�k�i�V���ɂƂ����߂���l
��������̒��N�k�i�V���̒��l
�䂪�|�Ȃ��
�₪�Ĕ������܌������邾�낤
�̕z�̏��
��������݁k�i�V����l�����
�Ȃ�Ȃ�Ƃ����o�Ȑ��̓��[
�k��̍E���灨�[���̂Ȃ��́l
�k�����Ȃ�܂������Ȃ�܂������C�l
�k�z�N���恨�g���l
�k�i�V�����́l�Ԗ͗l�́k��p�b���ԂɁl
�������炷
�r�j�[���̘R�l��
�k�i�V���ЂƂ͘V�����ׂ����I�l
�k�i�V�����̎M���l
�k�i�V���������́l��������̓d�b�@�̐�
���ꂩ��[��
���ꂩ��k���������[���ʎ��l
���ꂩ���
�Â��C�����͂���
�������N������I
���i�̉~���������
��т̂Ȃ��̏�������
���߂āk�E�E�E�E�E���c�c�l
�k���X�����x���O���g���l
���邽��z�N������
�a�m�ܒ��̐��_�ƐF�ʂ�����
�����ɂ��đs��ȘQ���̐��E
�������i�������сE14�j
���n�֔��������ނ͋A��
���肠���̔�����������
���G�̂Ȃ��̏��i�������сE15�j

�u�����낤�͏���
���I�͂������čs���v
��̏�Ȃ����ނ�
�����łЂƂ�̏��������Ђ˂���
�n��_
�C�i���i�̖��̂������ǂ���̈ł���
�����Ȃ鋛�̂悤��
�u���ҁv��u���ҁv�����݂��Ƃ��ꂽ
�u�ԐړI�i��ԁj���E�v
�ɂ���m�A�A�A�n��A�Ō`���������
��������
�u�����G�̂Ȃ��̒��v�ł��肦�Ă�
�u�����G�̂Ȃ��̏��v�ł���Ƃ͂�����Ȃ�
�e�[�u���̒[�Ƀ��[�\�N��R�₵
�h���A����H�ׂ鏗�����
�r��Ԃ鍰�̒j�͗҂���
��̐Ώ��̏���͂��܂���
�u�˂��݉ԉ͏����c�c�v
�������i�������сE16�j
���Ȃ�̉������~���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͖���Y���Ă͂��Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂����Ɍ��t����
�������Ƃ�
�@�@�@�@�@�o���\�E�R�E�����ׂĂ�
���ە��ɓ\��
�@�@�@�@�@�@���̖ړI�Ől�͐����邩
�@�@�@�@�@�@�o���F�̐��ɂ����ԃl�Y�~�̎��[�֖₦
�g�́k�ā����l�q��ւ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�U�N���̊O���ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�V�l����q���܂ł̏���
�ᒠ��݂�����̏F��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͓n��
���������邽�߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�̋Ђӂ��ւ̍��������߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
����֊G��̘g������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɔ҂����\�{�̐�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʎ��ɏ����\�s�̎�
�������낦�ė₽����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͌Ăꂽ
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���̂��炴�炵�����E��
�v�����v�����Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂������܂̓��X
�����Ղ̏��
�@�@�@�@�@�@���������̂�܂Ƃ͍����
�̂ǂ���
�I�������l����
��ފw�҂��������Ƃ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����l���h�͍���
���R���߂���
�@�@�@�@�@�@�Ӗ�������
���l�͍D���Ȋ�����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă̌ߌ�͓�����
�����邳����
�J����鎖���͂ǂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���E�N���C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̑t�ł��V��
�o���𐅖�̏�ɗ�������
���u���㎍�蒟�v��\���N�L�O���ɐ���Ƃ���i����A�Ƃ̏��c�v�Y���̗v�������݂������A�\�]�N�O�̎����L�q�I�ȑ��e�ɁA��̎�������A�w��ʁx�̎��тƓ����`�Ԃ��ƂƂ̂��A�����ɔ��\����B �܌����
�������i�������сE17�j
�u�ԂƗ̐��ŏo����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�̒��ɕ��肱�܂�Ă���v
�j�Ə�
�@�@�@�u�����[�̓W�����������Ă���
�@�@�@�@�W�����̓����[�������Ă���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ǔ����͔`���Ȃ�
�G��≹�y�̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�Ə��͏@���I�ȍՋV���s��
�u��̋u�݂����Ȃ��́v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͕��ɂȂт��قǐ�������
���x���i�������сE18�j
�Ƃ̎�w������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�v�l�̕��I���錊�l
�~�V��̃A�g���G��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H�ו���͂��ɖK���
�u�S���̕��܂̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q��̂�����
�p�I�����͖����Ă���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̉�Ƃ̎����͂�������
�`�������̉�z��`��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ӗ��̂Ƃ����
�@�@�@�@�@�@�@���E���v
�ɉ��̂Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�u�������̋r���{
�@�@�@�@�@�@�@������Ɏ��������Ă���v
���������n��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����}�@�l
�R�������
�@�@�@�@�@�X����
�����ł͉��ߖ@������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����m�̌C�̒��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���`�̕e�������ė���
�u���͉̂��̏��ł�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�Ɏ��Ă���v
���͂ڂ��ڂ��ɖ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂���ƗN���o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�̉^�s
�Q�H��Y���p�I������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���̊��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ�Ȃ��̂̏�ɂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�܂邱�Ƃ͋�����Ȃ��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C�f�A�̐��E�l
�u���݂�҂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�n�݂邱�Ƃ͂Ȃ����낤�v
�����̂��ׂ��ׂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���炾�̕\�ʂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̒|�āv
�H�̉ߏ�Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�������h������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�V���F�Ɠy���F�̌��t�����p���Ă���k�i�V���B�l
���i���̒��Q�i�������сE19�j
�R�I���M������
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�F���̗҂�����
�@�@�����n�߂�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�H�̓��̖쌴���s��
�킽���͗��l
�@�@�@�@�@�@�i�����I�Ȋ₩��o��
�@������ށj
�@�@�@�@�@�@�S�̗҂�������
�ӎ��̗���ɉ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�������
�i���Ȕ��l�̈�t������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԂƔ���
�z�E�Z���J�̍炭
�@�@�@�@�@�@�@�@�����̗͌������m��Ȃ�
�����̏���ǂ�
�@�@�@�@�@�@�@�킽���͎v���ɂӂ���
�i�����ɂ���
�@�@�@�@�@�@������߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ��ł��邩�j
���ĉ��̂߂������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Q�������悤��
�i�N�����킽����
�@�@�@�@�@�@�@�@���̂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ̎���������
�@�@�@�@�@�@�@�@���������j
���_���i�������сE20�j
1
�i�Ƃ�Ƃ�Ɩ��肱��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�q�_�l�ł͂Ȃ��j
�X�̏��̂قƂ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ߒ��Ԃ��������Ă䂭
�������̊��߂̏����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����������悤�ȋC������
�킽���͟�̊Ԃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�J��̑�[�����т�]�l��T���܂����
�i���Â̋������z���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂悢�Â���
�i���̗��
�@�@�@�@�@�@���b�̍��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ�Ȃ��̂̏�ɂ�
�~�܂邱�Ƃ͋�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C�f�A�̐��E�l
�킽���͂Ȃ����v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����ꂽ
�@�@�@�@�k���t�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���l�̂悤�Ɏc�邾�낤���H�j
��̓͂��ʍ��݂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�k���ցl�̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����ނ�l������
2
�i�x�ߐl�͔L�̊��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ԃ�ǂށj
������B�҂̎����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽���͂���������
�g�ɐ����
�@�@�@�@�@�@�C���̑���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂́k�D��[�ǂ낮��]�l
�@�@�@�@�@�@�@�g������
���̐��́k��l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����}�@�l������
�k�_��l�Ɍ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����܂��Y������j
3
�i����������Ȃ��U��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���t�l��k���k�l
�@�@�@�@�����āk�L���l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́k����[���ɂ�]�l��������Ȃ�
�i�R������@��������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����k���C�l�̉���
�k�ωʕ�[�R���|�[�g]�l��H�ׂȂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�@�̂ڂ�
�@�@�@�@�@��̂��ڂ݁j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������̂悤�ɏ����Ă���
�i���́k�����l�͂܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�Ɂk�n��l��
�~�藧���Ă��Ȃ��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������C�����̂ق��̏͋�����p���Ă���B
�������i�������сE21�j
�����̂Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�k���n[�����炳��]�l�̍��~��
�ޏ��̂悤��
�@�@�@�@�@�@�k����[���݂���]�l�𒅂Ďo�͂Ԃ₭
�i�˂��݂�
�@�@�@�@�@�@���킲������ق����j
�c�����
�@�@�@�@�����p�̑�M�̌�������
�k�n��[�����ꂽ����]�l
�@�@�@�@�Ƃ����J��ꂽ
����Ƃŕ��́k�ԐH[���ɂ���]�l���ق���
�@�@�@�@��́k�ю��ʁl�Ɏ��𗧂Ă�
�i��������
�@�@�@�@�@�@�l�Ԃ̌`�����L��������
�̂Ȃ��ƌn�H�j
�@�@�@�@�@�@�@�ڂ��Ɩ��͑|���𗹂����x���ɂ���
�m�̂ɂ���
���̓|��鉹
�@�@�@�@�@�@�i�W��ɂ̂��k�_�l�l��
�Ƃ̂Ȃ��ɓ����ė���j
�g������1990�N5��31���A���@��̕a�@�ŖS���Ȃ����B�f��A�ŔӔN�ɏ����Ƃ݂���q�����i���l���N�E�ė�j�r���s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�N11��30���j�ɔ��\���ꂽ���A����ȑO���A����ȍ~�������\�̎��т�����������邱�Ƃ͂Ȃ������B���́s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�����́q�g���������r�쐬�̂��߂Ɏv���Ђ̈˗����A�g�����v�l�z�q����ؗ������֘A����������Ȃ��ŁA�g�������M�̑��e����2�т̖����\���������B�q�����r�Ɓq�ہ[��E����[�̉́q���͐�̃J���o�X�r�r������ł���B�ȉ��ɁA�q�g�����������і{���Z�فr�Ɠ����̍قɐ�����2�т��f����B����ɁA�g�����̑n��Ƃ͌��Ȃ��Ȃ��������ߔԊO�I�Ȉ����ɂȂ邪�A�k�����q���W�s�ł����t�̎���̈��p�������琬��q���l�̔����ё��r���⎍�тƂ��Čf���A3�т�{�e�̕t�^�Ƃ���B�g���̐��O�Ɋ��s���ꂽ�P�s���W���^�̎���262�сA��������21�сA�����\����2�с\�\�ȏオ�����܂łɒm����g�����́u�S���сv�ł���B����285�сB�g�������̋������ł���s�g�����S���W�t�́A���̂����P�s���W���^���т̂��ׂĂƖ�������15�т̌v277�т����^���Ă���B�����\���сi����ѕ�⎍�сj�Ɂ����t���āA�ڎ��̑̍قŌf����B
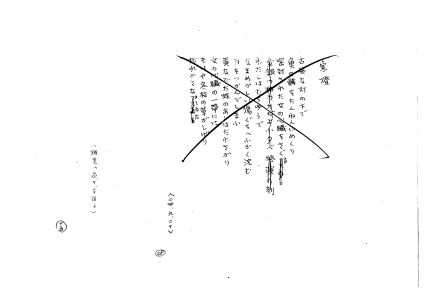
�Õ��ȓ��̉���
���̗�����˂�ɂ߂���
�������ꂽ���̐S���������k�Ă��l��
�k����̕��̂�����ӗ[�ׁ��g���l�@�k�I���̍����g���l
�킽���͂ނ��䂤��
�Ȃ܂߂������������ւӂ�������
��������ł��܂�
���Ȃт��^�̂����͂��ꂳ����
���̐S���̈�тɂ�
���͂�~�͂̑���������
�܂ꂩ���ȁk�Ă�遨�Ă�l
�@�q��l�A��A��\�r
�@�ے������Łu28�v�@�k�����l�ے������Łu45�v
�@�i����֓�l�A�\�A��\����j
�@�ے������Łu�\�܁v
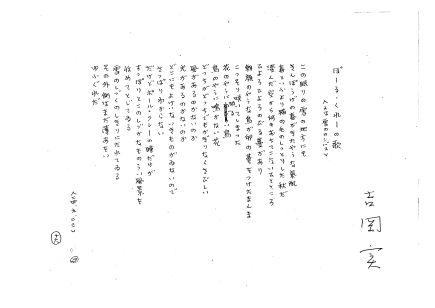
���̖���̐�̒n���ɂ�
����ۂ����̏t�������₤�ȋC�z
�t�Ƃ��ӂ��L�̖т̂��Ƃ肵���H��
���牽�������Ă��Ȃ��ЂƂƂ���
�Ђ��Ђ��̂т閠������
����̂₤�Ȓ��������ӂ������܂��
������炢�Ă��܂�
�Ԃ̂₤�Ɂk��т�������l����
���̂₤�ɖ��Ȃ���
�ǂ����ǂ��ł�������Ȃ����т���
��������̂��Ȃ��̂�
��������̂��Ȃ��̂�
�ǂ��ɂ��悯���Ȃ������̂���Ȃ��̂�
���ς�킩��Ȃ�
�����ǃ|�[���E�N���[�̓�������
���ۂ�Ƃ��̂��Â��Ȃ��̂������i��
���߂ĂƂ��Ă��
��̂������̂�����ɂ���Ă��
���̊O���͂܂���������
��ӂ��ꂾ
�@�q��l�A��A��O�r
�@�k�����l�ے������Łu46�v�@�ے������Łu29�v
�@�ے������Łu�\�Z�v
1�@�k�q�C���N�̎ցr�l
�_���̖��Ă���̂���
���N�B�͓J�𐁂�
�₪�đӂ��Đ��̒��ɓ���Ђ���
2�@�k�q�����h�N�g�����r�l
�l�̉e�������̎��̂₤�ɂ��˂�
3�@�k�q�꒼���̓��r�l
��Z���̓����������ł���
���ɏo��
�����T�������g�̏�����邫
4�@�k�q�x�ɂ̃o�K�e���r�l
�˂��ꂽ�֎q�ɂ�����
�p�C���A�k�b���c�l�v�����k�H����l��
5�@�k�q���M�̐����r�l
���@�����ɂ�
�ő��Ȃɂ��Ȃ�
6�@�k�q�ߑO�̏ё��r�l
�ÓT�ɋ߂�
�t�́k�恩��l���Ȑl��
���H��
�v�ЂƂƂ���
7�@�k�q�����ȃI�u�a�G�r�l
�y���L�̉���
���P�k�b���c�l�g
����Ђ̓g�����N
8�@�k�q�q���V���X�̋G�߁r�l
�k�����y�l�����ዾ������
���̃~���N������
9�@�k�q���������r�l
�͂ꂽ���̉��̎K�т����k�]�����l�Ԃɂ����ꂽ
10�@�k�q�������̃J�X�P�c�g�r�l
���ׂ̍��F��
11�@�k�q���邢�h���A���r�l
�ӓ��̔������̖j��
氓���Z���Ƃ�
12�@�k�q�������L�����h���r�l
��������L�̏��
13�@�k�q���̃��P�c�g�r�l
�삦���v�l�͐i�܂�
14�@�k�q�D�̃u���I�`�r�l
�v�l�̕\�ʂ��L�k�������l�x�c�̂₤�ɏk���
15�@�k�q�����ȃO���e�X�N�r�l
����͏[���ɑދ��ł���
16�@�k�q�����h�N�g�����r�l
�����Ȃ�d���ɖn��h��
17�@�k�q�A�R�C�e�X�̉́r�l
���̎��͋T�̂₤�ɐS���Â�����
�l�͋T�̑��̌`���������ō����̏d����ʂ�
�����ɐ_�̏d�������ʁk�����l�Ă
�g�����ƕa�C���邢�͋g�����̕a�C�ɂ��čl�@���Ă݂����B�܂��A�u�a�C�v�Ȃ�тɂ��̎��ӂ��g�������ɂǂ��`����Ă��邩�A�S���W�ɓo�ꂷ�鏇�Ō��Ă������B��������e���т���Y�����鎍��������̂ł���B
���҂͔������|�Ɏw���Y��
���̐���ɂ��̂����v����i�q�a���r�@�E18�j
��ꎍ�W�s�����G�߁t�i1940�j�ł́A�g���ŗL�̐��Ƃ������́A���삿���̐��F�ʼn̂��Ă���A�Ƃ����ӂ��ɂ�������B
�������Ł@�a�߂鏗�́@���������
�������ꂽ�@�ꖇ�̍��v���@��Ԃ�
�r����ā@���͏H�̋���
���܂悢�@���̌��ԂɁ@�ؗj����
�C����݂�@���Ȃ��݂�
�Ƃ����@�ь�̂Ȃ��ɖY�ꂽ�i�q�����́r�A�E11�j
��W�s�t�́t�i1941�j�ł́A�H�̗�C��Y�킹�鑧�̒������q��W�J���Ă��āA�s�����G�߁t�Ƃ͕ʐl�̊�������B
�ڂ��͕a�C�ɂȂ肫��@�ѕz�̉��ł��т̐^�������Ă���i�q�~�̊G�r�C�E6�j
�l�l�̑m��
��l�͖͌̒n�ɐ�l�̂����������Y��
��l�͉��ƌ��̂Ȃ��C�ɐ�l�̂������������Ȃ���
��l�͎ւƂԂǂ��̗��܂锉�̏��
������Ґ�l�̑�������Ґ�l�̊�̍t�ʂ̓������̂ɋ���
��l�͎���ł��ĂȂ��a�C�i�q�m���r�C�E8�j
������傤������@���ꂪ�ڂ��̍D�݂̎����@�a���̖ѕz�̐[���Ђ��ɋ��܂�@�ڂ��͔E�ςÂ悭�҂@�����łȂ����łȂ��@���̏��Ղ̋P�����i�q�r�C�E12�j
�͂��������J���ꂽ�n�̊�̖���ʂ�
�Ԗڂ̏����E���ꂽ�y�̉ƁE�k���̗ŕ�܂ꂽ�l
���F�����̗�������˂�
�x�߂̒j�͕a���̗��j�ށi�q��́r�C�E13�j
���ׂĂ̏����̎q�{��@��
���m�̔����͂��炩�������͕a�C�Ōł܂�i�q�l���r�C�E17�j
�@����Ƃ��돗�͐l���E���Ă����炵��
�����a��ȕv�łȂ����
���Ⴊ�����̖��܂����邪��S����v�i�q�����r�C�E18�j
�����̔���ƕa�C�ɂ���
���ׂĂ̈�҂͒��ق����i�q�����r�C�E19�j
���l�̘V�ԂȎZ�p���a�C������i���O�j
�����̕a�C�̌o�߂�
�H���ƕ��̋���̊W��
�����̈�r�����ǂ�
�Ō�͖��̏ɉ��ŏ�����i���O�j
��l���W�s�m���t�i1958�j�ł́A�u�ڂ��v�́u�a�C�v�͂قƂ�ǁu�ǓƁv�Ɠ��`��ł���B����ŁA�m���⎀���ɂƂ��ẮA���̒�ɂ��邳��ɐ[���A���ĂȂ�ƌ����悢�̂��낤�A�Ж�̂��Ƃ���Ԃ�悵�Ă���B
���т������̗c���ƃy���J����
�V�l���A�����
�a�l�̉��҂Ƃ��Ď��ʎ��̂���
���̓����ƐS�̌Ǘ������m�F����i�q�V�l��r�D�E1�j
�Ƃ�����ڂ��ɂ͕ʂ̂��Ƃ��C�����肾�@���܂��ܔޏ��������a�C�ɂȂ����ꍇ���i�q���̕a�C�r�D�E11�j
���������ɂЂƂ肢��
���[�̉�������
���a�ⓔ�S���Ɠ����悤��
���֒���
���n�̓����̂�����{�������
���̂₳�����a�C����������
�����Ȃ��т̂Ђ��ɐG��Ă���i�q���E�H�̊G�r�D�E21�j
�ƍs�҂̎��傫�Ȗ͗l�@���̑N���ȐԂ⍕�̎Ȃ��Ƃ���܂��n�}�̏���@�����������l�@���������������@�������������������킷�@�O������c����ꂽ�x�̂Ȃ��̕a�C�i�q�C���Əȗ��r�D�E22�j
����W�s�a���`�t�i1962�j�ł́A�u�a�C�v�͂Ƃ�킯�������ɕ������܂ꂽ�u�����v�̕ʖ��ł͂Ȃ��낤���B
���a�l�̏����̎x�ߕ��̂�������
���₫�����錌�̐i�q����r�E�E3�j
�킽�������ܕ`����ʂƂ͂ȂɁH
�������Ƃ͊W�Ȃ�
�^�]��̂��т��i�߂�
�ЂƂ�̏��N�̋����b�L�̒E���т�
�ڋ߂���
����͕a�C�̂Ȃ��ł�����
�쐶�̓��i�q�t�̃I�[�����r�E�E10�j
����s��̊w�Z��
�E���̕�����낵��
�ЂƂ�̏����������Ă���
�s���拃���āt���̂��Ȃ���
������������~����
�a�M���̂��́i���O�j
���R�ȏ�Ԃ�
�ڂ��̊G�����܂��H
�a�C�̎q���̎牺�̂Ȃ�
�Đ����I�Ȗ�̂Ȃ���
���̏o��
�u���[�̋ށi�q������G�r�E�E15�j
��Z���W�s�Â��ȉƁt�i1968�j�ł́A�u�a�C�v�͉�z���[�����u��C�v�̂��Ƃ����݂ł���B
����͂�������̕a�l�̖����������Ȃ����Ȃ��
�q�ދp���Ă䂭����⌌�̏o�����r
�킵����҂�����R��̈�т��т͈��u�ł���
�����@���������̈�l�̘V�k�������Ɏ���
���ꂱ��e�j�X�����̎���������
�J�����Ǝ��Ă邾���̕��������ĐX�܂ōs��
�܂������e�ރ{�[����Nj�����@��������킵�������邩
�ނ��������j���̊Ԃɐ�����@�J���t�����[�@��
���̐��ɒɂނ��̂��͂����Ă��邩
�킵���f�@����̂͋��̒��̊��҂̊�������
������ꂸ�@���L���Ȃ�
�ł�����@���̕\�ʂɂƂǂ܂�I�����W�̂悤��
�k�c�c�l
�����Ɠ��[�u����͂������ɐ؊J����v
���ꂪ�I������͂̂����肠�����n���@�肩������
�������o��@�����ɐ�����̂��o��
���̂Ƃ��͊Ō�w���Ă�ŕ�т����邮�銪������
�k�c�c�l
������ׂ���p������
������ׂ��a���Ȃ��Ƃ���
������ׂ������
������ׂ����̂���i�q�w�A���X�x���r�G�E12�j
�킽���͕a�C�����i�q�c���r�G�E14�j
�����������N�̊G�̎���
�q�a�߂鏭���r
�Ƃ����̂�����i�q����r�G�E23�j
�u�ߐ[�����͉j�����p���܂������Ă���v
����͕a�l�̂��킲�Ƃ��i�q�]���l���V���^�[���̑D�r�G�E24�j
�攪���W�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�ł́A�u�a�C�v�́i�U�́j���`�̈ꕔ�ɑg�݂��܂�Ă���B
�ڂ������a�l�̂ЂƂ�̏������~���Ƃ�
�^�����Ȃ����ԂƓ����̓�
�����̂ڂ��Ȃ�����i�q���Ƒ��ׂ݂̊Łr�I�E9�j
���Z���W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�ŁA�u�ڂ��v�͍Ăє��a�l�̏����Ƃ܂݂���B�����炭�́A�Â��I���h���̂����ŘV�������Ɉ����������Ă������߂̏����ƁB
�@�@�@�c���͊�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c����S����ށi�q�ØI�r�J�E14�j
�i���J�P�X�ɔx�a�킹��j�i���O�j
���ꎍ�W�s��ʁt�i1983�j�ŁA�c�����A�s�ł͂Ȃ����a��ł���̂͏ے��I���B�܂��u���J�P�X�ɔx�a�킹��v�́A�s��ʁt�̒ʑt�ቹ�Ƃ�������t���C�U�[�i�i������j�s���}�сt����̈��p�ł���B
�l�̂̓~�^���Y�̂悤�ȕa�C�̒j���^�����Ƃ̕��ۂŐ��������Ă���i�q������ܒf�����сr�K�E12�j
���W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�ł́A�u�a�C�v�͉i���̑��̉��A�������тɖ������Ă���悤���B
�킽���͂��܂����Đ鋳�t���F��������Ă���̂�
�y���̕a�l�̊Ō삷��p���݂Ƃ߂Ȃ�
�ނ���x�͐S�����߂ċF�鎞������
�݂����炪�ˑR�̎��ɂ��т��鎞�i�q�g��i���Ɏ~��r�������сE10�j
�����̔N��L�ɋL�ڂ����ׂ���
�킽�������͏o������
��o���j�����鐔�\���̎x�߂̐��K����ւ܂��ꂽ
�킽���͂炭���̔w�ɏ��Ȃ���
�R���p�X�𖢒m�̕����֊m�M�̂����ɂ̂�
�鋳�t�͕a�C���Ƃ�����ċ������i���O�j
���̋g�������Œ��̖������тł́A�����ɂ�����u�킽���v�̕m���̊�����鋳�t�����肵�Ă���ƌ�����B�o���O�ɐ鋳�t�����S�������ƂŁu�킽���v���������т��Ƃ��A���̂����Ŏ��ɕm�����Ƃ������悤�B
��
�����Ŏ��_��ς��āA�g�����q�k���M�l�N���r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�j�Ɍ��ꂽ�a�C�̋L�ڂ��E���Ă݂悤�B�Ȃ��A�����́i�@�j���ɏo�T�����������̂͋g���̐��z����̈��p�ŁA�q�k���M�l�N���r�̋L�ڂł͂Ȃ��B
�@�吳�\��N�@����O�N�@�l��
�㌎����A�֓���k�Ђɑ�������B�g�@�̋�ɔw�����Č���B����Ŕx���ɂ�����A�㎀�Ɉꐶ��B
�m�吳�\�O�N�@����l�N�@�܍n
����͊֓���k�Ђ̗��N�̏H�̂��ƁA�܍̎��͖��]�ɂ�����A�o���b�N���̏����ɓƂ�Q�Ă����B�O������̋~�ϕ����̐ԃQ�b�g�����Ԃ�A�������̗��e�̋A���҂��Ă����B�S�ׂ���C�����c���ɂƂ��āA��̑O�̋�n�ɖ�A�R�X���X�̉Ԃ��Ȃɂ��̈Ԃ߂ł������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�́q�c�������������r�j
�@�吳�\�܁i���a���j�N�@����Z�N�@����
�{�������q�포�w�Z�ɓ��w�B��A�O�N�����܂Œ����𒅂Ă���B�l�N���̎��]������a�݁A��w���x�w����B
�m���a�l�\��N�@���Z���N�@�l�\���n
�l����\���@�ߌ�A������ƒ֎R���ցB�S�o�Ől���ʼni�N�Α��҂Ƃ��ĕ\�������B�k�c�c�l�}�����[�ɓ��Ђ��Ă���A�����Ŗ��\�Z�N�B�a�C�������悭����Ă����Ǝv���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�́q���L���\�\���Z���r�j
�@���a�l�\�ܔN�@��㎵�Z�N�@�\���
�V�t�A���Ɍ��ɁA��i��a�@�֒ʉ@�͂��܂�B
�m���a�\�N�@��㎵�ܔN�@�\�Z�n
�k�c�c�l���āA��N�k��㎵�ܔN�l�̏t����A���͈ݒ���a�B�����Ƃ��Ă��邻�̎��A�ӂƁu���̐�ÌÂэs���g�_���v���S�̂Ȃ��ɕ��B����͎����I���傾�Ɖ��߂Ďv�����B�i�s�k�ߕS��t�́q�o���r�j
�@���a�\��N�@��㎵���N�@�\����
�Ă͓V��s���ʼnJ�~��Â��B�x���a�c�F�b���a�A����Â̖��A���w�O�̑��c�a�@�֓��@����B
�@���a�\�l�N�@��㎵��N�@�Z�\��
�k�c�c�l�H�A�����Â̂��ߐቺ���Ȃ֒ʉ@�͂��܂�B
�@���a�\�ܔN�@��㔪�Z�N�@�Z�\���
�k�c�c�l��J�̓��A�Ղ̖�a�@�Őf�@����B�����̕a�C�ł͂Ȃ����g����B
��ɂ͋g�����̕a�̋L�ڂ������������A��_�����A�x���a�c�F�b�̕a�̋L�ڂ��܂��Ă������B�Ƃ����̂́A�ق��ł��Ȃ��A���҂̕a��ɂ��ċg�����ł��ڍׂɏ������̂��q�������l�\�\�a�c�F�b�ՏI�L�r�i���o�́s�Q���t1977�N12�����j������ł���B�a�c�ՏI�̑O����10��4���A�g���͎d���Ŋ��q���F�V���F���K��Ă����i����̂��Ƃ��F�V�̐��M�q�V�Ղ�r�ɏڂ����j�B��9���߂��A�g���͒����̘a�c�F�b��ɍs�����B�u���̓N�b�V�����̑ւ�ɁA���₶����̔w�ɉ����ĐQ���B�����Č��⍘�ł�������d���Ȃ������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�ꎵ�O�`�ꎵ�l�y�[�W�j�B�����āu���e�����ɊłƂ��ď\���ܓ��ߑO�ꎞ�O�\�A�a�l�͎��B��Ƙa�c�F�b�͎��B�k�c�c�l�݂�ȂŁA���₶���p�̍��̗��߂𒅂����B���͈�[�������グ�Ȃ���A�����т������������Ɗ������B�w���͂܂��ʂ邢���݂��������B�ܐ�͂�ƓV�������Ă����v�i���A�ꎵ�l�y�[�W�j�B
��
1990�N6��1���t�̗[���e���̕ɂ��A�g������1990�N5��31���ߌ�9��4���A�}���t�s�S�̂��ߓ����s�ڍ���̓������ϕa�@�Ŏ��������B71�������B�}���t�s�S�͐t�s�S�̂ЂƂŁA�}���t��Q�Ƃ��Ă��B�u��̓I�ɂ́A�A�f�Ȃǂ̒��f�����������t���ɒ~�ς��鍂�A�f���f���ǂ���a�ԂŁA�}���Ȑt�@�\�ቺ�̌��ʁA�̉t�̐����Ɠd�����o�����X�̍P�퐫�ێ����ł��Ȃ��Ȃ�����Ԃł���B�Ǐ�͐H�~�s�U�A���S�A�q�f�B���Â��s��Ȃ��ꍇ���z���A�����ւƐi�s����v�iWikipedia�j�Ƃ����B�l�́A���g���ǂ̂悤�ȍŊ����}����̂��A���m�Ȃ��Ƃ͒N�ɂ��킩��Ȃ��B�g���͐܂�ɂӂ�ē��L�����Ă������A���ɂȂ������ŔӔN�̓��a���ɂ͏����̂����Ă��Ȃ��悤���B�����r�Y�́q�g�����������L�r�ɂ́A�g���̕a����߂����Ăق��̂ǂ̕��͂����ڂ������e���L����Ă���B�ȉ��ɂ��̌o�߂�E���āA�s���Ɂ����t���A�s���i�@�j���ɓ��t���L����B����ɁA�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�́u����Z�N�i������N�j���\��v�̍�����A�s���Ɂ����t���ĊY�����ɔz����B
����A�̕s���������Ă����悤�����A�H�~�����ʂɂ���A���قNjC�ɂ��~�߂Ȃ������B�i�����炭1989�N10��21���j
���\�ɂȂ��ēd�b����ƁA��A�̕s�������Ɉڂ����Ƃ��ŖK��͉����ɂȂ����B�i1989�N12���j
���N���ς���ēd�b�ŐV�N�̈��A���Ă�̒���₤�ƁA��������炸�H�~���Ȃ��Ƃ����Ԏ��������B�i1990�N1���j
���ꌎ�A��������Ő��������̉̕�����ς�B�u���w�E�v�ꌎ���Ɏ��u����v�\�i�Ō�̎��тƂȂ�j�B
���d�b���ɏo���z�q�v�l�̘b�ŁA�o�߂͂��܂肢���Ƃ͂����Ȃ��悤�������B�ʉ@���Ă��鋤�ϕa�@�̐����x�ݒ��Ɏ��̎��o�ǏĔ����A���̂����H���������ł��Ȃ��Ȃ�A���錩�鑉�����B����悭����Ȃ��ӂ��ŁA��������イ�N���オ���Ă���B��������o�X�ɏ���ċ��ϕa�@�܂ōs���ق��A�ߏ��̕a�@�ɂ��A�I�̎{�Ï��ɂ��ʂ��Ă��邪�A�a���͂킩��Ȃ��A�ŋ߂͋N���̂��тɐ[���P���o��A�Ƃ����B�i1990�N2����{���j
���k����R�c�́l��k�ꖯ�l����d�b���������̂͏\�ܓ��߂��������낤���B�S���A�����b�s�A���������g�Q���A�݃J������f�Ă�����������ׂĈُ�Ȃ��A�Ȃ��A�P�̌�����m�邽�߁A��t�̏Љ�Ŕx�̐��Ƃ̂��铌�M��w��w���t���勴�a�@�Ƀ����g�Q���ʐ^�����Q���Đf�Ă�������Ƃ���A�x��ǂ̏����Ɛf�f���ꂽ�A�Ƃ����B�i1990�N2��15���߂����j
����\�����ɂ͐���������A���ϕa�@�Ő��і�ჂƐf�f���ꂽ�B�i1990�N2��20�����j
���A��c�j�Y�����B���і�Ⴢ̂��ߐ����m�ꚋ���͂������H�~���ׂ�B
���k�l��\�����A������S���X�̓��ږx����֍s���i���N�e���X�g���b�v�E�V���[�̌��[�߁j�B
�����ɂ͑̏d�����Ɏl�Z�L�����������B������m�邽�߂̌������J��Ԃ������ʂ̓V���ŁA���̂��Ƃ��������Ă��炾�������߁A����Ȃ��邪�������B�i1990�N2�����j
���O���A���ϕa�@�œ��Ȃ̐������������ʂ͐���B�܊}���H�����B
���l���\�ܓ��A����Œa�������j���B��Ԃ�ǂ邵����̈���Ƃ��āw���܂�͂����L�x����R�c��芧�s�B��؈ꖯ�A���j���A�F��M�ꂪ����B������̗����ƃ��C���ŏj�t�B�ߏ��ɏZ�ދg���������畜���Ղ̃`���R���[�g�̋ʎq�Ƈ��a�������߂łƂ����̃��b�Z�[�W���͂��B�������̏d�O���E�܃L���̒ɁX�������\��B��T�Ԃő̏d��L�������邪�s���B���̍b���T�̂悤�ɕ���ށB
���k�l���l��\����A�J�̒��a�J�w�O�Ō������̔ѓ��k��v�l�ƍȂ�����@�����߂���B
���k�l���l��\�O���A���ϕa�@�Ō����̌��ʁA�������@�B�t�s�S�̂��ߏT�O��̐l�H���͂���B��l���ԑ̐��Œ��S�Ö��̉h�{�_�H�B�w���܂�͂����L�x�ʖؓ��Ō����Z�Z���A����R�c��芧�s�B
���k�c�c�l��\�l���[�邾�������������d�b����A�̏d���}�Ɉ�L���������ɂނ��݂��o���̂ŁA�z�q�v�l�Ƌ��ϕa�@�ɍs���ē��@��v���A��������A���ꂽ���ƁA���t�����̌��ʁA�t�ɕa�@������d�b�������ċً}���@�������Ƃ̂��ƁB�t�����͂𑱂����������A�Ƃ������Ƃ炵���B�����ƘA�����Ƃ�A�m���܁Z�p�[�Z���g�Ƃ����������F��ق��Ȃ��B�i1990�N4��24�����j
�������̓d�b�ŁA�����N�����Ă��̊o������߂�B�i1990�N4�����j
���܌�����A�����L�O���B���߂Ă̗A���B���j�����瑡��ꂽ��̃X�v�[���Ń[���[�Ђƌ��H�ׂ�B
���g������Ζʂ������o�����̂́A���̓��A�z�q�v�l����t�ɐq�˂����ʂ��A�t���͍���悭�Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A���͂ɂ͐��U�ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ɠ`�������ʂ炵���B�i1990�N5��11���j
���������ɑ��������A�ڂɂ��������茌�F���悭�A���̊��z�𗦒��Ɍ��ɂ������A�C�x�߂ɕ���������������Ȃ��B����u���̓��̗͂����͔�r�I���C�Ȃ̂��A�ƌ�ŕ������B�i1990�N5��12���j
���k�܌��l��\�ܓ��A�������Z�Z�Z�����Z�Z�Ɍ��������Ɉڂ���ʉ�Ӑ�B
����\�ܓ��[�邾�������A�����̓d�b�ŁA���������˔@�������A���ێ��Î��ɓ���Ƃ����S���I�e���𗶂��Č��Ɉڂ����R�B�i1990�N5��25�����j
����\�����ɂ��d�b�ōŏI�I�i�K�ɗ������Ƃ��m�F����B�i1990�N5��28���j
���k�܌��l�O�\���A�Ȃ̖�̕t���Y�����������B�d�ԁB
�������̎O�\����́A�k�c�c�l���������A����ҋ@���̑���d�b�ŕ߂܂������A���ӂ��イ�͎����������Ƃ����̂ň��S���āA�k�c�c�l�g������̗ՏI�͋㎞�l���Ƃ�������A�k�c�c�l�i1990�N5��31���j
���k�܌��l�O�\����A�ߌ�㎞�l���A�}���t�s�S�̂��߉i���B�ՏI�ɂ͍Ȃ̑��A�����킹����؈ꖯ�A�Ȃ̐e�F�҈��q�A�]�����c���q������������B
���Z������A����ʼn��ʖ�B
���k�Z���l����A�����̈㉤�R�^�����Ŗ{�ʖ�B
���k�Z���l�O���A���V�B�����Α���Œ����ɕt���ꂽ�B�i�ȏ�A�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�v���ЁA1991�A��܈�`��l�y�[�W�A�s�g�����S���W�t�}�����[�A1996�A����Z�y�[�W�j
�����̓ǎ҂Ɠ����悤�ɁA���͐V������Ő���������܂ŁA�g���̕a�C�̂��Ƃ͂܂������m��Ȃ������B�����A1989�N12��20���A�܂�S���Ȃ锼�N�قǂ܂��A�i���X�g�b�v�E�a�J�w�O�X�̓��������E��̐Ȃ�13������14��20���܂ň�Έ�Ŗʒk��������i���ꂪ�g������Ƙb�����Ō�ɂȂ��Ă��܂����j�A�̒����D��Ȃ��ɂ�������炸����Ă����������̂ɁA���k�������Ƃ������Ă���B���̂Ƃ��A�g������͂Ȃɂ���\�����Ă����̂��낤���B�\�\15�����玩��߂��̎���ҁk�ቺ���ȁH�l�ɍs���\��ŁA���͒��ڍ��́k�������ρl�a�@�Ŏ��Â��Ă���A�����ԑ������i2�L���H�j�Ƃ̂��ƁB���v�̃R�[�g�ɑ����l�̃Z�[�^�[�Ƃ��������i�q�g�����Ƃ̒k�b�i2�j�r�j�\�\�B���Ƃ��Ə����������g������́A���قǑ������悤�ɂ͌����Ȃ��������A�@�����������Ă��āA���ׂ��ۂ��悤�������B����ł������ŁA���N��ɖS���Ȃ�Ƃ͂܂������\�z�ł��Ȃ������B�����̕�ɁA�V���Ă����悤�Ɋ��������̂��B���̓�����27�N���i�Ƃ����A�g�����}�����[�ɋΖ��������Ԃɑ�������j���o�Ƃ��Ƃ��Ă���B

�g�����͏��̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�₵�āk�}���p���l�Ɏ��߂�ہA�u�X�v��32�т�lj��������ŁA���ł́u�W�v�܂łɎ��^�����q�Ђ�߂��r�q���q�̈��r�q��c�j�Y�w�c�x�o�ŋL�O��L�r�q�s痏����Ȏ��l�\�\���q�����r�q�g�c���̎��r��5�т��������B�H���u���ẮA�ӂɂ݂��Ȃ��ܕт��Ȃ����v�i�q���Ƃ����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�O���Z�y�[�W�j�B�g���͂܂��u���̏����́A�k�e���`�T�l���\�|�k�O�l�O�܁Z�l�ŁE�z���㐻�����Ȃ̂ŁA���R�Ȃ���A�����������A�����Ƃ��Ă͉��z�������������̂ł���v�i���O�A�O�Z��y�[�W�j�Ƃ������Ă���B���ł̒S���ҏW�҂��������ؒ��h�̘b���ƁA�������瑝���͑z�肹���A���ł̐��암����1200�`1300���ɐݒ肵���Ƃ����B����������Ă��A�g�����̎U����S�Ƃ��Ċ��s���_�ł̂����镶�͂����^����Ƃ������̂Ǝv�����i���ۂɂ́A�����^�̕��͂��U������邪�j�B��L��5�т͑����ĒZ���Łi�k�}���p���l�̑g�̍ق��Ɓq���q�̈��r��1�y�[�W�ŁA�����q�g�c���̎��r�ł�3�y�[�W�A����3�т�2�y�[�W�j�A���ł̂������Ƃ����g�̍فi10�|39���l15�s�g�j�Ȃ�Ƃ������A�k����Łl�̋l�g�̍فi13��44���l19�s�g�j���ƁA���Ƃ���Z���������̂�������Ȃ��B���Ȃ݂Ɍ��Ŗ{���̑g�w��͋g���ł͂Ȃ��A������̎�ɂȂ�B�q�Ђ�߂��r�͋����[���H�ו����z�����i�������̓X�́A�t�o�t���_�c���쒬�ɂ���������A�悭�ʂ������̂��j�A���̎�̕��͂́k����Łl�ɂȂ��A�g���͂��������X�����������̂�������Ȃ��B���q�Ɋւ��ẮA��Ɏ��M�����q�Ԕ����q�G�Ᏼ�r���k����Łl�Ɏ��^���ꂽ���A��c�j�Y�E���q�����E�g�c���̎O���l�Ɋւ��ẮA���ɑւ����̂��Ȃ��A�P�ɏȂ��ꂽ�`�ɂȂ����B����͂��́q�s痏����Ȏ��l�r����|����ɂ��āA�g�����Ƌ��q�����ɂ��čl�������B

�����̏��o�́s�T���Ǐ��l�t1960�N9��12�����̏��]�q���q�����S�W�@�S�l���r�B�����ő�1�����s���̓��S�W�̊T�v�����Ă������B�Ƃ����̂��A�������s���N���1961�N1���A�Ō��ł��鏑�惆���C�J�̈ɒB���v���S���Ȃ������߁A��2���ȍ~�͈ɒB�̖��F�A�X�J�ς̏��X�Ђ��犧�s����A��������4���{�́u���S�W�v�ɁA��5���̎U���W��������5���{�S�W�ƂȂ������߂��i�����͑�1�������4���܂ł�800���A��5����1000���j�B���o�̋g���̏��]�̂��Ƃɂ́A�q���q�������W�k�}�}�l�E�S�l���r�Ƃ��āA���̂悤�ɂ���B
�u�ҏW�\�H�R���E�������j�E������s����ꊪ���u�����˒��v�ق��i�����j������u�������ւ̃G���W�C�k�}�}�l�v�u�����P�v�u�L�v�u��v�u�S�̎��̉S�v�u���v�u�����v�u�l�Ԃ̔ߌ��v����O�����u�ԓy�̉Ɓv�������сi�������W�j�A�����]�_�W����l��������]�_�W�^�e�a�U�E���ώl�O�Z�ŁE��Z�Z�~�E���惆���C�J�v�B
�s���q�����S�W�k�S5���l�t�i���惆���C�J�E���X�ЁA1960�`1971�j�̊T�v�S�W���̋L�ڂ�������B
�E�s���q�����S�W�k��1���l�t�i���惆���C�J�A1960�N7��15���j�������˒��^�啅���^���̗��Q�^�撾�ށ^�H�T�̈��l�^�V�K�N��
�E�s���k��2���l�t�i���X�ЁA1962�N11��30���j���L�^�������ւ̃G���W�[�^�����P�^�S�̎��̉S
�E�s���k��3���l�t�i���A1963�N10��25���j����^�l�Ԃ̔ߌ��^���^����
�E�s���k��4���l�t�i���A1964�N10��20���j�����̂₤�ȉS�^�V���W�^�������ڂꂽ�����Ђ�Ђ��߂����́^�ԓy�̉Ɓ^������i�^���L�ꑩ
�E�s���k��5���l�t�i���A1971�N8��1���j���}���[����I�s�^�|�p�ɂ��ā^�����y�V���_�^���鏘�ȁ^���l�^�V���@��\�N���j���ā^���{�l�̔ߌ�
 �@
�@

�g�������̏��]�����M�����w�i�ɂ́A�u�k�ѓ��k��ƈɌ��ʕv�̎���W�s�~�N���R�X���X�t�́l���惆���C�J�ɂƂ��ẮA����I�o�łł���A�����̏o�ŊE�ɂ��H��Ȕ������{�ł������B�����͕S���ŁA�Љ���~�Ƃ��������Ȃ��̌́A���̔���s�����ɒB���v���ѓ��k����S�z���Ă����B��l�͒m�ȁA�F�l�ɂ���ƂȂ������Ă����悤�ɁA�����߂ĕ������炵���v�i�q�ѓ��k��Əo��r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A���܃y�[�W�j�Ɠ��l�́A�`���S�̂悤�Ȃ��̂��������̂ł͂Ȃ����B����́A�g���̏��]������ɔ��\���ꂽ�c������ɂ���1���̏��]�i�s�}���V���t1960�N8��27�����A����q���q�����Ƃ������l�\�\�J��������M�������Ƃ��̂��Ɓr�j�Ɗr�ׂĂ݂�Ζ��炩���B�c���͂����ŋ��q�����Ƃ̏o��i���q�̃J�������A�c���̃h���E�z�Z�A���q�̍Ȏq���o������8�~���f��s�J�������t���B�e��A�\���قǂ��Ď��g���x�a�œ��@������b�j��I�I�ƌ���āA�u�����Ƃ����ƁA�u�����v�Ƃ������t���킽���̓��ɂ�����ł���v�i�q���q�����Ƃ������l�r�A�s���Ɣ�]�`�t�v���ЁA1969�N12��25���A��Z��y�[�W�j�ƌ��_�Â��Ă���B�����͂������B�u���{�͋ߗ��̏o�F�B�����ɁA�^�ʖڂɐ����悤�Ƃ�����̂́A���ׂčw���ׂ��I�v�i���O�j�B�����ǂ�ł���͂��̋g���́A�c�����Ƃ��Ԃ�Ȃ��悤�ɁA���g�Ƌ��q���W�Ƃ̊W�A���q���̈�ۂ𒆐S�Ɏ茘���܂Ƃ߂Ă���B�S�W�̓��e�Ɋւ��ẮA�c�����قڑ�1���ڎ��̈��������Ȃ̂ɑ��āA�g���̏��]�ɂ́A�s��t�i1948�j�A�s���t�i1955�j�A�s�l�Ԃ̔ߌ��t�i1952�j�A�s�����t�i1956�j�A�s�L�t�i1937�j�A����ɂ́s�ԓy�̉Ɓt�i1919�j�A�s������峁t�i1923�j�A�s�啅���t�i1960�j�A�s���̗��Q�t�i1926�j�A�s�撾�ށt�i1927�j�A�s�H�T�̈��l�t�i1960�j�A�s�V�K�N���t�i1960�j�ƁA����12�����o�ꂷ��B�c���̏��]���ɒ[���������A�g���̂���������������ԓI�������悤���B�����A�u���̛g���ƕs�ρA���̓����̔��ƏX�̒Nj��ɏI�n���āA�i�炭�ڂ����������v���W�Ƃ��ās��t��ǂ݂Ȃ������Ƃ́A�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�ւ̐V���ȃA�v���[�`�Ƃ��Ȃ邾�낤�B
�g�������q�ɂ��ď��������͂͂��́q�s痏����Ȏ��l�\�\���q�����r���������A���̌�A�Βk�œ�x�A���q�ɂ��Č���Ă���B�ȉ��Ɍf���悤�B
�ѓ��Ƃ̑Θb�͋��q�������S���Ȃ��Ĕ��N��̂��́B���̂Ƃ��g���́A���q�̈⒘�s���͑��Ɂ@�������� �Z���t�i�p�쏑�X�A1975�N9��30���j��ǂ�ł��Ȃ��B�ѓ��̋��q���ւ̌X�|�Ԃ�Ƃ͌a�낪����ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B����Ƃ̑Βk�́A�g�������l�̏����U���ɂ��Ďv�Ă��Ă��������������悤���i�g�����g�A�t�B�N�V�������������U���A���Ȃ킿�����ւ̊�]������Ă������Ƃ�����j�B���q�̎��`�O����i�s�ǂ���t�t�s�˂ނ�b���t�s���Ђ����t�j�́s���q�����S�W�k��7���l�t�i�������_�ЁA1975�N11��20���j�̂��ƁA1976�N����77�N�ɂ����Ē������ɂɓ����Ă��邩��A�g���͂���œǂ̂��낤���B�����s�ǂ���t�t�s�˂ނ�b���t�͓ǂ�ł����̂ŁA��\���N�Ԃ�ɓǂ݂��������i�s���Ђ����t�͏��߂ēǂj�B���q�̎��`�ɂ́A���y����Ă��Ȃ��d�v�Ȏ����������悤�����A���͂͑����ė����ŁA�g�p����̐l�����������߂ɂ͂����������̂̌������傫�������B�g���̎w�E����Ƃ���A�J�肩����㆓ǂɂ�������̂��Ƃ������ƂɂȂ�Δ����ŁA����������x�ǂނƂ����͂��\���N��A���e����������Y�ꂽ����ɁA�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���B
�k�t�L�l
�g�����͋��q�����Ƃ̌l�I�ȕt�������ɂ��āA�Ȃɂ������̂����Ă��Ȃ��B�����A���e���O�Y�E���q�����ďC�s���̖{�k�S3���l�t�i�}�����[�A1967�j�̑������肪���Ă��邭�炢������A�ʎ��͂������ɈႢ�Ȃ��i���q�́q�T ���̌����r�̊����Ɂq���Ƃ͉����r�����M���Ă���j�B�܂��A�،��͂Ȃ����s��{ ���q�����S���W�t�i�}�����[�A1967�N6��30���j�̑������g����������������Ȃ��B�����O���ҁq�k���q�����l�N���r�́u���a42�N�i1967�j�v�ɂ́u11��20���A�w��t�̂����x�w��{���q�����S���W�x�̏o�ŋL�O��i�l�J�q��w��فr�j�J�ÁB�������j�A���{���A���Ɏ��A�H�R���A���~�A�g�����A���A�u�����Ȃ߁v���l�Ȃǂ��o�ȁv�i�����O���ҁs���q�����k�l��������n15�l�t���O�A�\�V�G�[�c�A1986�N10��9���A��l�y�[�W�j�Ƃ��邵�A����1967�N�ɂ́A12��15���t�Ō��提������́s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�����q�ɑ����Ă���B����́A�s���̖{�t�̍ŏI��z�{�q�V ���̊ӏ܁r��12��15���̔��s������A�o�ŎЂ̎Ј��Ƃ��Č��{���ďC�҂ɓn�����łɁA���l�Ƃ��ās�g�������W�t�����悵���Ǝv�����B��������̔N�A���q�����Ƌg�����̑S���W���o�������킯���B�g���́A���q���������i1975�N6��30���j�̍ۂɂ́A���g���ҏW����s�����܁t77���i1975�N9���j�ɉ�c�j�Y�́q���q�����搶�i�����j�r���ڂ��Ă���B�Ȃ��A���q�������g�����Ɍ��y�������͂����͒m��Ȃ��B
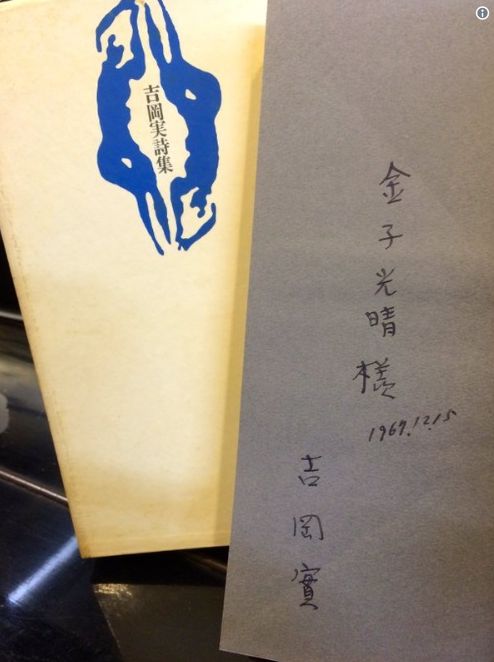
���q�����Ɉ��Ă����提������s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�k�o�T�F�ق��낤��o�U�[���@2016�N1��9���i�y�j& 10���i���j�l
�H���K�l�́q�g�����́s�n�t�̎��Q�r�́A�q�g�������s���t��u���ꏊ�r�ƕ���ŁA���w�̃��m�O���t�s�g�����A���x�X�N�t�i����R�c�A2002�N5��31���j�̂Ȃ��ł��o�F�̘_�l�����A���͂����ŏ��߂Ėї����F�i1920�`2010�j�̑��݂Ɩї��̔n�̊G�̂��Ƃ�m�����B
�H���́A���p�����̏ȗ������Łs�ї����F��W�t�i�������A1991�N3��31���j�́q��i�ɂӂ�ā\�\��Ҋo���r�����i�q30-�n�Ɛl�r�k1969�N�^224.0�~151.8�^�����C�P�ʁ^��33��V���싦��W�^�����E���m�ΐ�����p�ّ��l�̊o���������Ă���A�u�R�n�̐��b��C���ꂽ���m��������X�܂ł��Y�ꂩ�˂邱�Ƃ̈�́A�ǂ����s���A�܂݂�̘m�t�Ƃ������ƂɏW���悤�Ȃ̂ł���v�i���O�j�Ƒ����Ă���B���{���ɂ߂��H���̕����T���͂����ł��j�S��˂��Ă���A�����܂���f�ȗ������ŏH�����������ї��ɂ��o�����f���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�H���K�l���ї����F�Ɍ��y�����̂́A�s�g�����A���x�X�N�t�Ő�������̔��s�����������B���̖{���Ɠ�̒��L�ɑ�����Ėї��̉�W�Łq�n�Ɛl�@1969�N�@150�ρr���ςāA���͂������܋g���̎��сq�~�̋x�Ɂr�i�D�E12�A���o�́s���{�Ǐ��V���t1960�N3��7�����j��z�N�����B�O��W���炢���āA�g�����ї����F�̊G���ςĂ��玍�т��������Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ����A�ї����g�����̎���ǂ�ł����Ƃ������Ƃ��A�����炭�Ȃ����낤�B�����A���͂����ɗ��҂���ׂĊr�ׂĂ݂����Ƃ����U�f�ɋt�炤���Ƃ��ł��Ȃ��B�g�����̎��Ɩї����F�̊G�ɂ́A�Ƃ��ɔn�̃t�H�����A�n�̐����͂ɑ���ɂ��݂Ȃ��]�Q������悤�Ɏv���B

�ї����F�́q�n�Ɛl�r�͕s�v�c�ȉ�ʍ\�����Ƃ��Ă���B��O�����ɁA�قډ������̍����n�Ƃ��̎�Ɏ�������������������l�̃V���G�b�g�B��i�E���ɁA����Ȃ������F�̔n�Ɍׂ�l�Ƃ��̉E���ɗ��l�B��〈���ɂ������A��i���p�̍����X�y�[�X�ɂ́A�E�ɓ������������n�̔w�Ɏ�Ă��l�������ɗ����Ă���B�����O�g�̔n�Ɛl���A���ꂼ��Ɨ�������ʂłł����邩�̂悤�ɁA�݂Ȃ��݂ȁi�n���l���j���g�ł�������ł���B�O�g������P�Ƃ̎��_����ʂ̎�O�ɐݒ�ł��Ȃ��̂��A���̊G���߂������̂ɂ��Ă���B�ї��̈Ӑ}�́A�n�̎O�Ԃ�ʂ��Ă��ׂĂ̔n�̎p��`�����Ƃɂ������ƌ����悤���B
�H���̘_�l�q�g�����́s�n�t�̎��Q�r�Ŏ����Ƃ�킯���ڂ���͎̂��̓�ӏ��ł���B
�u�s�n�t�́A�]���ē��R�ɂ��A�g�����ɂƂ��Ă͐킢����������ЁX�����������ł��������B���̂��߁A�ނ̎��ɍ݂��ẮA�m�n��הn�����͂���𑀂�҂͂����������L��тсA�����̉^������Ƃ���̂��͎̂E���͂���������́A����𑍂��Đ�捂ȓ����~���������݂ƂȂ邱�Ƃ����������v�i�O�f���A��Z���y�[�W�j�B
�u���̈���ŁA�g���́s�n�t���{�������Ă���`�Ԕ��Ɍ×��t�^����Ă������x�ŗY�ӂȐ����͂Ƃ��������̂ɂ����ӂ����Ƃ�Y��Ă��Ȃ��B����͑������\�I�ȕ����ɕ~������A���Ƃ��Ă���́A�ނ��K���∤�u���Ă������̐����O�S�̖���u���n����������ĉ���ɂ��ށv�̖��ӎ��̉e���������^���Ă��A���̂̔����̂��̂Ƃ����ꎋ����邱�Ƃ��������v�i���O�A����y�[�W�j�B
���́A��҂̌��̌�ɏH���������g�����������q�~�̋x�Ɂr�ł���B�����͎�����ꎚ�Œǂ�����ł����U�����^�����A�����ł͈ꎚ�̏��Ŏ�������s���ēǂ�ł݂悤�B�����ɂ͂����Ď���ꂽ���́A����͎���̍��ׂł���A���Ɍf������ό^���s�����\�L�ɂ���͎̂��Ԃ̐i�s�ɔ������B���ł���B
�@�����ł͊D�F�̔n�ƊD�F�łȂ��n�Ƃ����ꂿ����
�@�D�F�̔n���Ă炵���т��������ꂳ����
�@�ʂ̔n�͈×̉��Ȃ̂��낤�͂�������������
�@�������̂��Ă��݂�������]����т̗��̂ɂ܂ō��܂���
�@�����ɂ͂��ꂪ������
�@���S�ȉ~�̂ӂ�����
�@�Ƃ��ǂ��͂ݏo����̂��I�����W�F�Ɍ���
�@���S�͂������Ԃ��o�߂����̂ō���
�@���ӂɂ�������Ƃ��ꂳ�̂���������p�b�̂悤�ɋ��낵��
�@�����͎��g�̑ڂɔM�𗁂т�
�@�܂����ꂿ�����Ă���n����
�@�s�G���łȂ��Ԃ��X�q�̒j��
�@�������C�Â���������l�ł͂Ȃ�
�@������������Ă��鋤�Ƃ̂͂ɂ��݂̐S
�@�e���g�̒ꂪ�[���Ȃ�Ȃ�قǂ������
�@�n�̕��ւ����Â�
�@���߂��邽�߂ɔ��ɍג����_���ӂ肨�낷
�@�d�����Ђ�������X�̊Ŕ̕���
�@����͏[��������Ə����͎v��
�@�D�F�̖Ĕn�̂���Ȃ肵�����Ɉٕ��킪�h��������
�@���݂̂������~�̋x�ɂ��I��ƂƂ���
�u�s�G���łȂ��Ԃ��X�q�̒j�́@�������C�Â���������l�ł͂Ȃ��v�Ƃ����̂́u�D�F�łȂ��n�v���u�×̉��v���w���̂��낤���B������ɂ��Ă��A�I��肩���s�߂́u�D�F�̖Ĕn�̂���Ȃ肵�����Ɉٕ��킪�h��������v�Ƃ������傪�Ȏ҂ł���B�����ɂ������āA�g���̕`�����l�n��̂̌����}�͊������݂�B�u���ӂɂ�������Ƃ��ꂳ�̂���������p�b�̂悤�ɋ��낵���v�́A�����q�������r�i�F�E10�j�́u�g��̏����͑傫�Ȑ��Z���܂����^��������̂Ȃ��ɂ���^�i���̈�p�b���������I�v��p�ӂ��Ă��悤�B���ꂪ�����t��łȂ����Ƃ́A�����̌����u���t�̎��Ɂ^���l�E���̒킪���܂���I�v�Ŗ��炩���Ƃ�����B����ɂ��Ă��q�~�̋x�Ɂr�̍��i�݂͂��Ƃł���B�����ɁA�U�����^�ɂ����čō��x�̌`���Ƃ��Ă��邻��ɗD��Ƃ����Ȃ����͂ȖT������BBurton Watson�҂̉p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t�iChicago Review Press�A1976�j��Hiroaki Sato��qWinter Vacation�r�i�����A�Z�܃y�[�W�j�ł���B
�����ǂނƁA�g���������ɂ��̎���Έʖ@�I�ɓW�J���Ă��邩���킩��B�sLilac Garden�t�́A�����Ɂs�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�f�ڂ̎��тP�����I�����������A�����Ɏ��߂��Ă��Ȃ��q�~�̋x�Ɂr�������h���i�ƃo�[�g���E���g�\���j���I��Ŗ�ڂ������Ƃ��[���ł�����тł���B�ї����F�����̎��т����̂ł͂���܂����B
�F�V���F��1970�N11��25���̎O���R�I�v��������ɑ������q�O���R�I�v���𓉂ށr�i���o�́s�����C�J�t1971�N1�����A�s�Έ��I��Ƙ_�t�y�ЁA1972�N6��10���A�����j�ł��������Ă���B
�u�O���R�I�v���́A���������̓��{�̏ے��I�l���ł��������A���ɂƂ��ẮA���������̂Ȃ����h���ׂ���y�ł���A�F�l�ł������B���t���������͂��߂��͖̂�\�ܔN�ȑO�ɂ����̂ڂ邪�A���͎����̓�����҂̂Ȃ��ɁA���̂悤�ɗD�ꂽ���w�҂����������K������u���Y�ꂽ���Ƃ͂Ȃ������B���̍�i�������삩���M�ɂ�����܂ŁA���ׂĔ��\�̎��_�Łm�A�A�A�A�A�A�n�ǂ�ł���Ƃ�����Ƃ́A���ɂƂ��āA�O������[���đ��ɂ��Ȃ��B�����������Ƃ́A���܂��ܐ���������Ȃ�����蓾�Ȃ����Ƃł���B���̂����₩�ȍ��̔��W�́A���̂���Ɗ��S�Ƀp�������ł������ƌ�����v�i�s�F�V���F�S�W�k��11���l�t�͏o���[�V�ЁA1994�N4��12���A����y�[�W�j�B
�u���ׂĔ��\�̎��_�Łv�̖T�_���F�V���g�ɂ����̂����A�����炭�͋g���������́u������v�Ɓu��M�v��ǂ�ł���̂ł͂Ȃ����B�g���͎O���̏����Z�яW�s�Ԃ�����̐X�t�i���䏑�@�A1944�N10��15���j���s�����A�ꕺ�m�Ƃ��Ē����嗤�ɂ���������u���\�̎��_�œǂ�Łv���Ȃ����A1945�N11���ɕ��������O������ɂ͑������������w���Ă���̂��B�u�\�ܓ��i���j���j�@���t�̂悤�Ȓg�����B�O���R�I�v�s�Ԃ�����̐X�t�ƒZ�̕��w�W�s��狋�ҁt���v�i�q���L�@���l�Z�N�r�A�s�邵����t6���A1990�N5��31���A�O�Z�y�[�W�j�B����A���M�N���́u���a�l�\�ܔN�@��㎵�Z�N �\��v�ɂ́u���~�A�O���R�I�v�̊������ɏՌ�����v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A��O�O�y�[�W�j�Ƃ���A���L�́u��㎵�Z�N�\�ꌎ��\�ܓ��v�ɂ́u���e���O�Y�搶�Ɖ�c�j�Y�ƃ��h���I�Ŋ��k�̐����B�ߌ�ꎞ�߂��A�x�͑䉺�p�̎O�����[�̃K���X�˂́u�O���R�I�v�ؕ��A���S�I�v�Ƃ̓\��������䂭�B�Ȃ�ƂȂ����ꂵ���A��Ђɖ߂�ƁA����͎����ł���A���R�Ƃ���B�[���ŏ��킩�����B�|�̉�̐N�����ƁA�s���J�̎��q���֏�荞�݁A�n���������ƁA�O���R�I�v�͐ؕ������Ƃ����B������������A�a�藎���ꂽ�Ƃ̂��ƌ́A���������Ռ������B�u���Ɂu�`���̐l�v�ƂȂ��Ă��܂�������A������@��͎���ꂽ�B���̖�͐Q�ꂵ���A�������܂Ŗ���Ȃ������v�i�q27�@�O���R�I�v�̎��r�A�s�y���F��t�}�����[�A1987�A�l�܃y�[�W�j�Ƃ��̏Ռ����L���Ă���B�����O�N�̋㌎�A�g�����͂�����x�A�O���R�I�v�ƑΖʂ��Ă���̂��B�s�y���F��t�́q20�@�X�y�[�X�J�v�Z���̗[�ׁ\�\��ȓ��̂��Ɓr�i���o�q��ȓ��̂��Ɓr�́s�O�D�L��Y���W1946�`1971�t�x�A�T�����I�A1975�N2��15���j�̑O���͂������B
�y���F�͎O���R�I�v�̒��я����̑薼���S�肽�����i�q�F�r�i1959�j�Ŏ����I�Ƀf�r���[���Ă��邭�炢������A�O���Ɛe���������B���̖�̏o����A�y���F���g�������O���R�I�v�Ɉ������킹���悤�Ȃ��̂������ƌ����Ȃ��͂Ȃ��B�������āA�g���́s�y���F��t�ɂ͎O���R�I�v�����т��ѓo�ꂷ��B
�q27�@�O���R�I�v�̎��r���F�V�̎O���R�I�v�Ǔ��������p�i�{�e�̖`���Ƃ͕ʂ̉ӏ��j���Ă���悤�ɁA�g���ɂƂ��ĎO���R�I�v�̎������ǂ�قǂ̏Ռ���������������v���Ȃ��B���������A���͒��w�O�N�����������A�Ȃ����V�����������̂e�l�����̃��W�I�j���[�X����ۂɎc���Ă���i���W�I�ł̓O�����h�E�t�@���N�E���C�����[�h�̃��C���A���o�����������Ă������A����̂a�f�l�Ƃ��Ȃ�A���N4���Ƀ����[�X���ꂽ�}�C���X�E�f�C���B�X�s�r�b�`�F�Y�E�u�����[�t���낤�j�B�O����EXPO'70�ŕ�����Ă������{�ɁA���̂�̓��ƌ��Ђ������Ă��̎��f�������������B�ł́A�g���͎O���R�I�v�̕��w���ǂ��v���Ă����̂��B�ѓ��k���M���Ƃ��鎍�l�����Ƃ̍��k��ɏA���ɔ@���͂Ȃ��B
���͋g�������̍��k��ŎO���̒��я����s�F�t�i�V���ЁA��ꕔ�s�F�t�F1951�A��s��y�t�F1953�j�Ɍ��y���Ă��Ȃ��̂��c�O�Ɏv���B�g���͓����ǂ̂��A�ǂ܂Ȃ������̂��B����Ƃ����̂��A�F��M�ꂪ�q�O���R�I�v�Ƃ���������l�r�i�s�y���F�\�\����̂̎v�z�t�݂������[�A2017�N2��10���j�Łu��ɗ�O�I�ň�ۂɎc��v�i�����A��l�y�[�W�j�Ǝw�E�����A��l���ł��铯�����҂̔��N�i��I��j���Ⴂ�ȁi�N�q�j�̏o�Y�ɗ������ʂ��A�g�����̎��сq�}�_���E���C���̎q���r�i�G�E5�A���o�́s�����C�J�t1973�N1�����j��z�N�����邩��ł���B�F��͂����Łs�F�t���琔�s�������āA�u���X�Ƒ����|���I�ȋ����̂��Ƃɕ`���ꂽ�܂�������O�I�ȏ�ʂł���B�N�͂��̂Ƃ��Ƒ����J�ɖڊo�߂��킯�ł͂Ȃ��A���܂�Ă��鐶���̑��������o�����킯�ł��Ȃ��B�ނ��낱��͎����̓]���Ƃ����o�����Ȃ̂ł���B�����Ď����̓]���ɂ́A�o�Y�Ƃ����u���v�̏o�����A�����̌��ɗ������ʂ��K�v�ł���A�O�����w�̗��m����ׂ��|�������̏o������������ΓI�ȋ��ЂƂ��Č}���Ă���v�i�����A��܌܃y�[�W�j�ƕ]�����B�u�����̓]���v�Ƃ́A���Ɍ��킹��u�����邱�Ƃɑ���h�䂩��A���邱�Ƃɂ��U���ւ̓]�g�v�ł���B�O���́s�F�t�́q���\�� �]�g�r�ɂ͂�������B
�O���R�I�v�́s�F�t���M�E���s������20��㔼�ŁA�܂��������Ă��炸�i1958�N�A33�̂Ƃ�21�̐��Rꢎq�ƌ����j�A���̂悤�ȏo�Y�̌���ɗ�������Ƃ��ł����̂��A���ɂ͔��f����ޗ����Ȃ��B�����Ƃ��A�����̗\�s���K�̂悤�ɂ��āq�J���r�̐ؕ��V�[���������Ă��邭�炢������A�u�l����l�`�̂��Ƃ��������v�u���\�I�ɂ������Ƃ����A�V�������������낤�Ƃ����v���M�ԓx�͎O���̐^�����ŁA�����ɂ͂�����Ȃ��B�Ⴂ����㏑�o�ŎЂɋ߂Ă����g�����ɂ����Ƃ���ŁA�����Ɂu�o�Y�Ƃ����u���v�̏o�����v�ɗ�����o�����������Ƃ͎v���Ȃ��B���Ȃ݂ɋg���v�ȂɎq���͂Ȃ��B
���p�����s�F�t�̒��O�ɂ́u�}�[�L�����ł����Đ^�g�ɓh��ꂽ�ڂɂ��Ă���ꂽ���̔��z�́A�͂��������o�ɂ͉��������Ă��B�Ǐ������̒��˂ɂ͂��܂�A���X�����m�͂��݁n���A�ڂ�����ɂЂ낰�ėA���̌������z�ɂقƂ����ė��ꂽ�Ƃ��A�N�q�̐^�g�̍����m���������n�����������A���������c�E�ȂƂ���̂Ȃ��Ⴂ�ǐl�̖ڂɂ����ɉf�����B�I��͂���قǓ���̂悤�ɖ����̂��̂Ǝv���Ă����Ȃ̓��̂��A�������Ĕ畆�m�́n������Ă��̓����������ɂ���̂����ẮA���͂₻����̂悤�Ɍ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������ɂ��ǂ낢���v�i�O�f���A�O�Z���`�O�Z���y�[�W�j�Ƃ���B�g�������p���Ŋ������u�����^���͎̂��̊�Ł^���߂���I�v�̏o�T���Ȃɂ��킩��Ȃ����A����̂悤�ȓ��̗̂ڂ̉��Ɍ�����^�g�̍������������Ƃ����A�u��ΓI�ȋ��Ёv���܂��ɂ����Ƃ��̎Ⴂ�v�̋��قƓ���̂��̂ł��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B
�@�E�}�_���E���C���̎q�����^���l�́u���Ȃ��v�^�������q���̑̑�����Ƃ�����^�u������v
�@�E���̃}�_���E���C���͔������^�ł��ƂĂ��u�����Ȃ��v�ו��������Ă���
�@�E�c�Ɍ��̐�����Ȃ��ā^���̖��[������ł���悤�Ɂu������v
�@�E����ꂽ��̔����^�ڂ���̗����Ă��鐅�̏�������čs���^�}�_���E���C���͂�����u������v
�O���̏����̎�l�����i��f���p�̏�ʂł́j���邱�Ƃɜ߂��ꂽ�l���ł������悤�ɁA�q�}�_���E���C���̎q���r�̘b�҂����Ȃ��猩�邱�Ƃɜ߂��ꂽ�l���ł���B�����u���l�v�͂�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�b�҂��u�����v�Ƃ������̂��A�Ђ�����ǂނ��Ƃ��ł��邾�����B
�Ƃ���ŁA�u�O���R�I�v�����̎����Ђ����ɓǂ�ł���v�Ƃ����A���̋g�������Ƃ͂Ȃ����̂��B����́A����̓ǎ҂������ł������悤�ɁA�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j���ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ����B�܂��u�Ђ����Ɂv�Ƃ́A�O�����g�������ɂ��ď��������Ƃ��Ȃ��A�g�����O���Ɏ��W�������Ă��Ȃ��̂ŁA�O��������肵��������̐l�Ԃ����B���������ēǂA�Ƃ����ӂ��ɂƂ��B���̏ꍇ�͕����̏��Ȃ��P�s���W�ł͂Ȃ��A�s�g�������W�k�����̎��l�o���T�l�t�i���惆���C�J�A1959�j��������������Ȃ��B�ӔN�̎O�����W�F�t���[�E�{�[�i�X�ƂƂ��ɕ҂sNew Writing in Japan�t�iPenguin Books�A1972�j�ɂ́A���g�̒Z�сq�J���r�Ȃǂ̏�����H�R�x�̕]�_�ƂƂ��ɁA�g���̎��qStill Life�k�Õ��i�B�E2�j�l�r�ƁqPast�k�ߋ��l�r�i�{�[�i�X��j���f�ڂ���Ă��邪�A��тƂ��s�g�������W�t�Ɏ��߂��Ă���̂��B�q�m���r�ł͂Ȃ��A�s�Õ��t����̓�тƂ������ɕҎ҂Ȃ�ł͂̒�����������B�O���ɂ��qIntroduction�r�i�{�[�i�X��j�ɂ́A���l�E�g�����ɂ��Ă̎��̌��y������B
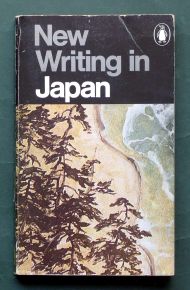
Yukio Mishima, Geoffrey Bownas�ҁsNew Writing in Japan�t�iPenguin Books�A1972�j�̕\��
�����ς̎��́qRain�k�J�l�r�qNightingale�k��l�r�qHitomaro�k�l���l�r�A�c������̎��́qFar-off Land�k�������l�r�qFour Thousand Days And Nights�k�l��̓��Ɩ�l�r�B�ȉ��A���̋�̍�Җ�����������A�҈䋪�A�J��r���Y�A���������A�����r�Y�i�ȏ�A���j�A�˖{�M�Y�i�Z�́j�A�����g�Ái�o��j�B���̂Ȃ��ł́A�����g�Á\�\��W�Ɂs�����W�t�i�����D�ЁA1969�j�̂ق��A�s�����k�r�̑p���o��сl�t�i�����[�A1969�j������Ƃ̂��Ƃ����A��҂͖����\�\�̓�l�傪�ٍʂ�����Ă���B�����炭�����̐���ɂ�邽�߂��낤�A�{���ɂ͐l�I�Ƃ�����i�̑I���Ƃ����A�Ҏ҂̋��x�Ȏu�������܂�Ă���B�O���̑I�qStill Life�k�Õ��i�B�E2�j�l�r�́A�������낵�̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j���e�i�K�̍e�{�ł́A�q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�i�B�E1�j�̂܂��Ɉʒu���銪�����т������i���j�B����A�q�ߋ��r�́s�Õ��t�����ɒu���ꂽ�A�W���ōł��Y�ӂȍ�i���B������������ȑI���ł���B���̑I���Ɋr�ׂ�ƁA�O�f�qIntroduction�r�̃��g���J���ȕ]���͂����������̑���Ȃ��B�O���f��̓�\�N�����g�����̎��̑��̂��l�����Ƃ��A�������́qBiographical Notes on Authors�r�́gYOSHIOKA MINORU: born in 1919 in Tokyo, he is one of the leading surrealist poets of the post-war years.[...].�h�i�����A��l��y�[�W�j�́u���̑�\�I�ȃV�������A���X�����l�̈�l�v���z���̂ق��I���˂Ă����ƌ����悤�B���s�̎������炢���āA�O�������́q���҂Ɋւ���o���r�ɖڂ�ʂ��Ă����Ƃ͎v���Ȃ��̂����B
�k�t�L�l
�剪�����E���J�Y���k�Βk�l�s�剪���� ���J�Y���@��̓�����j�t�i��g���X�A1984�N7��23���j�́q�O�������̍��r�ŁA���J�́sNew Writing in Japan�t�ɐG��āu�k�c�c�l���ĎO���R�I�v���y���M���E�u�b�N�X�Łu�j���[�E���C�e�B���O�E�C���E�W���p���v�Ƃ����A���\���W�[��ҏW�������Ƃ�����B��_����Ƃ����́w�ł̂Ȃ��̍����n�x�́w�F���̋��x�Ƃ����̂������Ă��邵�A�g�s�~�V��ƈ����͑��Y�A��]���O�Y�ƈ������[�A���ꂩ��]�_�͏H�R�x�A���Ǝ��l�œc������Ƃ��g�����Ƃ��̐l�̒˖{�M�Y�܂œ����Ă���s�v�c�ȂقǂɍL���͈͂ɂ킽�����O���D�݂̕ҏW�ŁA�W�F�t���[�E�{�[�i�X�Ƃ����l�����͂��ĖĂ���v�i�����A�O��Z�y�[�W�j�Ƒ剪�Ɍ���Ă���B�Ō�ɁA�sNew Writing in Japan�t�̎U����i�i��������܂ށj�̖ڎ����f����B
�@�@Geoffrey Bownas�@�@�@�@�@Translator's Preface�@�@11
�@�@Mishima Yukio�@�@�@�@�@Introduction�@�@15
�@�@Inagaki Taruho�@�@�@�@�@Icarus�@�@27
�@�@Haniya Yutaka�@�@�@�@�@Cosmic Mirror�@�@32
�@�@Abe Kobo�@�@�@�@�@Stick and Red Cocoon�@�@41
�@�@Oe Kenzaburo�@�@�@�@�@The Catch�@�@51
�@�@Yoshiyuki Junnosuke�@�@�@�@�@Sudden Shower�@�@99
�@�@Yasuoka Shotaro�@�@�@�@�@The Pawnbroker's Wife�@�@123
�@�@Ishihara Shintaro�@�@�@�@�@Ambush�@�@133
�@�@Mishima Yukio�@�@�@�@�@Patriotism�@�@152
�@�@Akiyama Shun�@�@�@�@�@The Simple Life�@�@182
�@�@�k�c�c�l
�@�@Biographical Notes on Authors�@�@247
�i���j�@�q�Õ��r�A��̎l�ђ��Ŋe��̃A���\���W�[�ɂ������̂��Ă���̂́A�`���́q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�i�B�E1�j���B����A���́q�Õ��k��͂��������������ɂ���l�r�i�B�E2�j�́A����M�v�E�֍��O�E�،��F��E�R�{���Y�E������s�E�剪�M�ҁs���㎍�S�W�k��3�W�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�Ɂs�Õ��t�s�m���t�����16�т̏��^�Ƃ��ēo�ꂵ���̂��ŏ��ŁA�����sNew Writing in Japan�t�̃W�F�t���[�E�{�[�i�X�ɂ��p��ł���B�����͂��̌�A�sTen Japanese Poets�t�iGranite Publications�A1973�j�A�sContemporary Japanese Literature; An Anthology of Fiction, Film and Other Writing Since 1945�t�iAlfred A. Knopf�A1977�j�A�sSei Budda di pietra�\�\Antologia di poesia giapponese contemporanea�t�iEmpiria�A2000�j�A�sPO&SIE numero 100�\�\Poesie Japonaise�t�iEditions Belin�A2002�j�A�s[Four] Factorial�\�\Speed Round & Translation�t�iFactorial Press�A2005�j�Ƃ����������̃A���\���W�[�ɉ����f�ڂ���Ă���B���̐�w������{�[�i�X������悤�i�sNew Writing in Japan�t�k��Z�O�y�[�W�l�j�B
�@�@STILL LIFE�bYoshioka Minoru
�@�@Night crowds in
�@�@Bones
�@�@Pleced for a moment
�@�@Among the fish
�@�@Steal from the star-lit sea
�@�@And decompose quietly
�@�@On the plate
�@�@The light
�@�@Moves to another plate
�@�@In whose hollow
�@�@Lurks only living famine
�@�@Begetting first the shadow
�@�@And then the seed
�Ō�̍s�́gthe seed�h�́u��E��q�v���낤����A�u���v�̖��Ƃ��Ă͈�a�����o����B���ɍ����h���̉p����f����i�sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�tChicago Review Press�A1976�A�ꔪ�y�[�W�j�B
�@�@Still Life�bMinoru Yoshioka
�@�@The night recedes the further to encircle them
�@�@The bones pleced
�@�@Temporarily in the fish
�@�@Extricate themselves
�@�@From the sea where stars are
�@�@And secretly dissolve
�@�@On the plate
�@�@The light
�@�@Moves to another plate
�@�@Where life's hunger is inherited
�@�@In the hollow of the plate
�@�@First the shadows
�@�@Then the eggs are called in
���͏��ǂ̂Ƃ�����u���v���gegg�h�Ɠǂ�ł����̂Ł\�\�����ł͂Ȃ��{���\�\�A�����h���̉p��ɌR�z�����������Ǝv���B�W�F�t���[�E�{�[�i�X��7�s��6�s�ɕ�����1�s�ɂ��Ă���̂������Ȃ��B�����ɋ͂Ȃ��B
�i�����ƒT���Ă����s���㎍�蒟�t�̑n�������s���{�̌Ö{���t�Ō������̂ŁA�q�g�����Ɓs���㎍�蒟�t�r�ŐG��Ă��Ȃ����Ƃ����������B1959�i���a34�j�N6��1�����s�́s���㎍�蒟�t�n�����i���t�ɂ͕ҏW�l�E���s�l�͖�X�R�o�u�v�Ƃ��邪�A��o�s��㎍�d���j�t�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɏ��c�v�Y�̕ҏW�ɂȂ�j�̊����\�����u��1����1���v�ł͂Ȃ��u��2����6���v�Ȃ̂́A�p���O���́s����t�������������߂ŁA��������}���ق�NDL-OPAC�Ɉ˂�u�Ҏ҂���яo�ŎҁF4��2���i���a36�N2���j�܂Ő���Ёv�Ƃ���i���̌�͌��݂Ɏ���܂Ŏv���Ёj�B���́u�������v�Ɂu2��7���i1959�N7���j�`�i���F2��10���C4��11���C8��5�C8�C10���j�v�Ƃ���Ƃ���A�n�����͓��قɏ�������Ă��Ȃ��B�����s�g�����S���ѕW������t�i���Y��ԁA1995�j��҂ނ��߂ɑS���т̏��o��T�����Ă�������A�������s�����đn������T���������邱�Ƃ����킸�A�Ō�ɂ͎v���Ђ̏��c�v�Y�����ς킹���B20�N�ȏ�O�̂��Ƃ��B���̂Ƃ����肵���̂͋g�������q�x�����r�i�������сE7�j�̌��J���y�[�W�Ɩڎ��E���t��3�ӏ��̃R�s�[�������������A�̂��ɂȂɂ��̏����ŋg�����A���P�[�g�i�H�j�ɓ����Ă���̂�m�����B���������߂ď��c����ɗ��ނ̂��C�������āA�����Ɏ������B����A�O�̂��߂ɑn�����̑S�y�[�W�ɖڂ�ʂ����Ƃ���A���̎������������������łȂ��A�g������s�m���t�A�g�܁i�����́u�g���܁v�ł͂Ȃ������j��u�g�����v�ւ̌��y���E�����Ƃ��ł����B�����A�܂��́q�����ǂ{�r�̋g���̍������悤�B���Ȃ݂Ɂq�����ǂ{�r�͖ڎ��ł́u�ǂ�����悢���������邩�v�Ƃ����傫�Ȋ���̂Ȃ���
�@�Ǐ��m�I�g
�@�ǂނׂ��{�@�������j�@���@�Z�l
�@�����ǂ{�@�剪�M�@���@��l
�Ƃ����āA�g�����̖��O�͌����Ȃ��B�{���́u�g�����v�̏����̂��ƂɁA��������i�s���㎍�蒟�t�n�����A1959�N6���A��l�y�[�W�j�B
�����́A�i�{�R�t�i��v�ۍN�Y��j�s�����[�^�k��E���l�t�i�͏o���[�V�ЁA1959�N4��20���j�A�x���g���[�i��������j�s�g�����g�Ō�̎����k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1958�N11��29���j�i���j�A������s���W�s�X�������t�i���惆���C�J�A1959�N2��1���j�Ƃ݂���B�Ƃ��ɁA�q�����ǂ{�r�̎��M�҂͌f�ڏ��Ɂu�������j�@�ѓ��k��@�剪�M�i�����j�@���c��v�@���C�i��@���ˉ�v�@�߉��~��@���ؐT��@�g�����@�H�g�L�v��10�l�����A����t�����ϑ��I�ŁA�^�C�g���̂��ƈ������j���璆�ˉ�v�̍��̓r���܂ł���܃y�[�W�i���J���̍����j�ɁA���˂̍��̓r������H�g�L�̍��܂ł���l�y�[�W�i���J���̉E���j�ɁA�R�����̂悤�ɁA���ߑ��I�ɑg�܂�Ă���B�z���ɁA����͌��J���̉E�y�[�W�ƍ��y�[�W��g�݈Ⴆ�����̂ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɁA�{���͑���l�Y�I�q�������i�r�Ȃ�10�y�[�W�ɂ킽��q�����̐V�l�r�i�ڎ��ł̕\�L�j���Љ��L���ł���B
 �@
�@
�q�����ǂ{�r���f�ڂ���Ă��錩�J���i�s���㎍�蒟�t�n�����A1959�N6���A��l�`��܃y�[�W�j�i���j�Ƌg�����̎��q�x�����r�ƎU���q���l�̃m�I�g�r���f�ڂ���Ă��錩�J���i���A�Z�Z�`�Z���y�[�W�j�i�E�j
�q�����ǂ{�r�̋�܃y�[�W�̒��˂܂ł͎��M�҂�50�������B�����̓��e���ɂ͑O�L��6�l�܂ł̌��e�����Ȃ��āA�߉��~��E���ؐT��E�g�����E�H�g�L�̍��͂��̌�ɁA���e���W�܂������ɑg�܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����B����ȍQ������z�肷��ƁA�s�g�����g�Ō�̎����t�̒��Җ��������Ă���̂��A�g���������������̂��A�g�Ŏ��ɒE�������̂��A���f�ł��Ȃ��Ȃ�B
������ׂ��L�ڂƂȂ낤�B�����q�g�����ƃi�{�R�t�r�ɏ������u�s�l�Ԃ̕��w ��28�t�����肪�i�{�R�t�Ƃ̏o���������Ȃ��B�������ȑO�ɋg�����s�����[�^�t��ǂ݂��������Ƃ͂��肦��B�ȂǂƂ����Ă܂��������������������A1959�N�̍ŏ��̑�v�ۍN�Y���`���Č��Ȃ������A�ƍl����ق����s���R���ƌ������ق��������v�Ƃ������̐���́q�����ǂ{�r�ɂ���ė��t����ꂽ�킯�����A���M�����A�s���㎍�蒟�t�n�����������ł��Ă�������A�Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��B�������ċg���́s���㎍�蒟�t�n�����ɁA���q�x�����r�i5�ьf�ڂ��ꂽ�q��i�r�̖`���ɂ����ꂽ�j�Ƃ���ɕt�����U���q���l�̃m�I�g�r�A�Ǐ��m�I�g�q�����ǂ{�r�����킯�����A�g�����Ɋւ��錾�y�͂ǂ����Ƃ����ƁA���̂悤�ɂȂ�B�Ȃ������͎��M�Җ���W��Ȃǂ��A�i�@�j���́q�@�r�͈��p���̏����o�����A�����͓����̌f�ڃy�[�W��\���B
�\�\�q���ꂪ���d�����Ă��邩�\�\���d�n�}������l�����r
�k�s�����C�J�t���l���Ԃ����̎G���Ƃ�����䂦���u�����v�n���̕��ѕq�F�A�剪�M�A�ѓ��k��A�g�����A��c�G�A�������j�k���̌�ɒE�������邩�l�n�̌I�c�E�A�]�����A���C�i��A�����k�S���C�l��A����F���A�u�����v�n�̎c��m�A�ےJ�ˈ�k�A�l���R���j�A������n�̒������A���{�ꖾ�k�A�l�u�����]�v�n�̐�����s�A����M�v�A�g�{�����Ƃ��������M�u���[���͂��Ȃ苭�͂Ȃ��̂��B�i�q��Â���M����ǁu�����C�J�v�r�A11�j
�\�\�q�ǂ�����Ď��d�ɏo�邩�\�\���̐l�͂������Ď��l�ɂȂ��r
���Ƃ��Α����̏�������肼���āA���d�Â������̂قƂ�ǂȂ����g�������u�g�܁v�����炢�A���̍�i�������ɕ]�������悤�ɂȂ��ł͂Ȃ����B�i�q�����̂��̗̂͂����̐l�����l�ɂ���r�A20�j
����l�Y�E����M�v�k�Βk�l�q���ꂩ��̎��͂ǂ��Ȃ邩�r
�@�ҏW���k���c�l�@���܂̎��d�Ɋ���ڂ��āA�\���̂��鎍�l�Ƃ��X�����Ƃ肠����Ƃ���Ɓc
�@�����@���낢�날�邾�낤�ˁB�J��r���Y�N�ɂ��A���x�̋g�����N�̎��ɂ��A�����炵���\�����݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��ˁB
�@�����@����Əے��I�ȉ]������������ǂ������ɂ��������܂��ˁB�S�R����������ǂ��ɒ[�Ɖ]�Ă������Ǝv������ǂ��B
�@�����@�ǂ��ł����A�g�����N�́B
�@�����@�ڂ��͂����Ǝv���܂��B�u�Õ��v�Ƃ������W���o�����Ƃ�����B
�@�����@���ɑf���̂���l�ł��ˁB���ϓI�ɉs���B�ڂ��͂ق��ɂ�����������ǂ��A���@�Ƃ��Ă͂���̓u���g���ł��ˁB�u���g���Ƃ��������A���ƈӎu�I�ȓƑn������ł��悤�B��i�̒��ɂ������������̎Ȗڂ��݂���ˁB
�@�����@���ꂩ��A�P�ɓ��ʓI�ȗ����̃C�}�W�l�[�V��������Ȃ��āA��肠���ɂ��̂Ђƌ��ꊴ�o���̂��̂ɑ���C�}�W�l�[�V����������ˁB���������Ƃ���A����Ƃ����̃V���[���̈����Ƃ������Ǝv����ł����ˁB
�@�����@���������A���������C�}�W�l�[�V����������Ƃ������ƁA��͂肱��͂��̎��l�̔F���̖��ɂȂĂ���Ǝv���B�������낢�̂̓e�[�}�̂����������B�܂肠��́A��\���I�̃X�L�����_�������Ƃ��Ƃ����̃e�[�}�ɂ��Ă���B������C���[�W�Ƃ��ĕ`���o�����o�I�Ȃ��������ɂ������낭�Ă����炵���ł��ˁB
�@�����@����Ӗ��ʼn]���猇�_�݂����ȂƂ�����ˁB
�@�����@������\���Ɗ댯���̋Ɍ��ɂ��鎍���ȁB���ꂩ�炿��Əo���炠�ԂȂ��ȂĂ���B�������Ƃ������̂͂��������ꏊ�łȂ��Ƃ���Ȃ��B
�@�ҏW���@�J�삳��̉\���Ƃ����̂́B
�@�����@�܂肠�������̂͂ڂ������v����B�傰���Ȕ�]�ɂȂ邯��ǂ��A���������p������A���n���Ă���ƐV���������P�I�Ȃ��̂��o�Ă����Ȃ����Ƃ������҂��������Ă���킯�ł��B
�@�����@�����g�������݂�Ȃ������Ɖ]���o���Ƌ^�₪�����Ă���B�O����ڂ��͂����Ǝv�Ă������ǁA���̎��͍��{�I�ɂ́c�c����Ƃ��܂��]���Ȃ�����ǂ��A���{�I�ɂ͍������̖��������Ƃ��琶�܂�Ă����Ȃ����Ǝv����ł��B�����̍l���ڂɕ\���������Ƃ͔��Ȏ��ŁA�`����w�I�ȂƂ��낪���邯��ǂ��A�ɓx�ɓ��ʉ����ꂽ���Ǝv����ł����A���������ɓx�ɓ��ʉ����ꂽ��������Ȃɂ݂�Ȃ��悭�킩��Ƃ����̂́c�c���������i�j�Ȃ��ւƂ����C������B�����v�ł��ꂪ�����Ƃ������Ƃ����܂��肷��ƁB�ǂ����ςɂ܂܂ꂽ�݂����c�c�B
�@�����@����A�����v����Ȃ��ˁB�����v����Ȃ��Ă��A���ꂪ�ߔ����ł��܂��Ƃ������Ƃ́A���㎍�l��̊������݂Ȃ������Ƃ����������B���Ȃ��Ƃ����̂Ȃ��ɂ́A�����ȏ�͂��������̂��킩�鎍�l�������Ƃ������Ƃ��ȁB�\�\�������邩�ȁB�i�q���㎍�����̉\���r�A52�`53�j
�\�\�q���ꂪ���㎍���\�\�����̎��d�r
�Ƃɂ����A��܂����₷�邾�낤�Ƃ����Ă����g�������Ƃ����痎�������悤�Ȃ��̂́A���܂�㖡�̂悢�I�l�o�߂łȂ������Ƃ����͊m���Ȃ悤���B�g���̎�܂́A�ꉞ����ɂł��A��܂��ׂ��l����܂����Ƃ������������������ł��낤�B�k�c�c�l�O�ɍ��k�遨��l�M�V�����㎍�l��ɓ���̂͌����Ƃ��Ăg�܂��R�����Ƃ��������A������ł�����l�A�g�������g�܂����₷��A���̎��l�M�͂̌������͂��肷��悤�ɂȂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B�g���Ɏ�܋��ۂ̋C�������Ƃ������Ƃ��Ă��������ɁA����Ǝc�O�ȋC��������B�i�q�g�܂��߂���������r�A79�j
SAN�q���ꂪ���㎍���\�\�����̎��W�r
�@��N�̕邩�猻�݂ɂ����āA���ڂ���鎍�W����o�Ă���B����g�����́u�m���v�ł���A������͍ŋߊ��s���ꂽ������s�̏������W�u�X�����v�ł���B�g���͂��̎��W�ɂ�Ăg�܂�^����ꂽ�킯�����A����͂���Ӗ��ł͓��R�̂��Ƃ����Ƃ����悤�B�Ƃ����̂��A�ŋ߂����������������d�ɂƂāA�u�m���v�������������g��́A�ӊO�ɑ傫�Ȃ��̂�������ł���B�������A���������ܕS�����畔��������Ȃ��̂��A���݂̎����̏o�Ŏ���Ȃ̂�����A�傫�Ȕg��Ƃ͂��Ă��A���̉e���͈͂͂�������ꂽ���̂ɂ������Ȃ��B����ł��A�Ⴆ���������̂悤�Ȑl�܂ł��q�u�m���v�Ƃ������W���o�Ă���ĂˁB�ڂ������Гǂ݂����Ǝv�Ă���r�ƌ��Ă���̂��킽���͕��������Ƃ�����قǂ�����A���Ȃ��Ƃ��A���d�ɂƂĂ͂�͂肿��Ƃ����Z���Z�[�V���i���Ȏ����ł����ɂ������Ȃ��B�g���́A�����̈�_���݂߂鎷�X�Ȃ܂łɗ₽������Y�펖�̍�i����p�ɂ܂Ƃ߂����邱�Ƃ��������Ă������l�����ɂƂāA���Ȃ��炸���قł����ɂ������Ȃ��B���ɁA���̎��W�̑薼�ɂȂĂ����i�q�m���r�́A�����ԈȑO�ɔ��\���ꂽ���̂����ɂ߂ăV���b�L���O�ȍ�i�ł����B���̈Ӗ��ŁA���̎��W�̂Ȃ��ł��A���Ƃ����͓I�ȍ�i�̈�ł���B���W�u�m���v�́A���̈Ӗ��Ŏ��l�����Ɏh����^���邱�Ƃɂ͐��������̂����A�������A���̎��W�𐳓��ɕ]�����邽�߂ɂ͂����������Ԃ������Ă݂�K�v������ł��낤�B�g�܂������W�́A�Ⴆ�A���N���x�������q�́u�ԗ��v�̏ꍇ���݂Ă����Ȃ�����悤�ɁA�P�Ȃ�q���̎��W�r�ł����Ȃ��ꍇ����������ł���B�g���̍�i�������̖ڐV�����ɂ�Ăł͂Ȃ��A�ق�Ƃ��̈Ӗ��ŁA�����ꂽ��i�Ƃ��ĕ]������邽�߂ɂ́A�Ȃɂ͂Ƃ�����q�����i�r�ɂȂ邱�Ƃ��K�v�ł���B����ȍ�i�Ƃ����̂́A�����Ă��̏ꍇ�A���`�[�t���\���ɔR�Ă������炸�ɏ������Ƃ��琶�܂��B���`�[�t���\���ɔR�Ă�����Ƃ������Ƃ́A������x�܂ł́A��������\�͂Ƃ������ƂƏd�Ȃ���̂ł���B�킽���̓ǂނ�����ł́A�g���ɂ͂܂����̈Ӗ��ł̌�������[���݂͂��Ȃ��B�u�m���v�͂��Ȃ�]���̂悩�����W�����A���̕]���͑����Ɏ��d�̕��a�������ɂ��ƂÂ��Ă�����̂Ƃ킽���ɂ͎v����B�낭�ɓǂ݂����Ȃ��ŁA�N���������ƌ������̌��t�����̂܂��肵�ĕ������ӔC�ȓz�������̂ł͂Ȃ����낤���B���̏؋��ɁA���̎��W���o�Ă���A�킽���͑����̎��l���������̎��W�ɏA�Č��̂������A����Ƃ���Ŗ₢�Ԃ��ƁA��O�̐l�������ẮA�܂Ƃ��ɂ͓������Ȃ��̂��˂ł����B�������A���̓�A�O�̐l�����́q���ۂ̂Ƃ���A�킽���͂��Ƃ��ʔ����Ƃ͂�����Ȃ��̂����ˁr�ƌ��Ă����B����������ƁA���Ɉ��p�����i�q�r���r���A�����̖ڂɂ͂��Ȃ�ȑO����ӂ�Ă����g���̋g���炵����i�ŁA�����ɂ��ނ̒����ƒZ�����悭������Ă���B
�@�ڂ��������肽���̂͋�`�̉�
�@�����ň�Ă�����Ȃ�ʉ~���̎���
�@���Z�Ȃ��킢�ɑ������ׂ�
�@�����̍Ȃ��N���Ă͂����Ȃ�
�@�S�y�̓��̂��Ԓf�Ȃ��ω������邽�߂�
�@�u�N�ƃG�[�e���̑ޒ�
�@�[���̑e���z�̉��Ŗ钋�̕ʂȂ����˂�
�@�ڂ��͐ΒY�̓��鏰�ɂ͂�����
�@�����̚M�����Â���
����͖`���̐��s�����A�������ɂ����͂��̂Ȃ��ɁA���t�ɑ���ނ̓��قȊ��o�A�ُ�Ȏ��X���A�Ƃ������̂�F�߂邱�Ƃ��ł���B��������́A����Ǝ��_���ڂ��Ă݂�킩��̂����A��A�O�\�N�O�̓��{�̃V���[���̉�Ƃ������A�L�����o�X�ɓh�肽���Ă������̖��Ӗ��ɍ������Ă����G���A���̂܂ܕ����Ŏʂ��Ă݂��ɂ����Ȃ��̂ł���B�t���I�Ɍ����A���̃A�i�N���j�Y�����������M���ׂ��ނ̍�i�̖��͂Ȃ̂ł���A���㎍�̖ӓ_�������݂ɂ������Ƃɂ��Ȃ�̂ł��낤�B�i�q���Ƃ������_�}���ꂽ�u�m���v�r�A82�`83�j
�����̂Ȃ��ŋ����[���̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��Βk�q���ꂩ��̎��͂ǂ��Ȃ邩�r�ł̈���M�v�̔������B����l�Y�͂��łɁs�����V���k�[���l�t�i5��19���j�Ɂq�g�܂��������g�����́u�m���v�r�������Ă������A����͂��̎��_�ł͋g����s�m���t�ɂ��Č��y���Ă��Ȃ���������ł���B�u�������̖��������v�u�ɓx�ɓ��ʉ����ꂽ���v�Ƃ����w�E�́A����Ȃ�ł͂̂��̂��낤�B�Ƃ���ŁA�������]�Ŏ��W��S�������uSAN�v���N���́A���c�v�Y�s��㎍�d���j�t�i�V���ЁA1995�N2��25���j�ɏA���ɔ@���͂Ȃ��B�u�k�s�����C�J�t�œ������]�������Ă����l���̐����k�N�Y�l�̉s���g��́A�₪�đn�����ꂽ�u���㎍�蒟�v�̓������]���ł��A���c���������悤�ȗ������������邱�ƂɂȂ�B���Ƃ��Αn�����ł͑������A�u���ڂ�������̎��W�v�Ƃ����]����O��ɂ��Ȃ�����A�g�����́w�m���x�Ɛ�����s�́w�X�������x�����Ȃ肠�����܂ɂ������낵�Ă���B�����ق�����������ق����A���������������̒m�炸�Ō����݂��Ȏ�҂������̂ł���v�i�����A��O�O�`��O�l�y�[�W�j�B�g���́q���l�̃m�I�g�r�̖����ɂ́u�i�悵�����E�݂̂鎁�͑吳���N�A�������B���W�u�m���v�Ŗ{�N�x���㎍�l��g�܂���܁B���̌܌��ɂ͒����Ɛg�������瑫��Ƃ̂��ƁB���A�}�����[�L���������B�j�v�i�s���㎍�蒟�t�n�����A1959�N6���A�Z���y�[�W�j�Ƃ���B������������ł��낤���c�v�Y�͓���28�A�̂��ɐy�Ђ������ās�����C�J�t�����邱�ƂɂȂ鐴���N�Y��27�������B
 �@
�@ �@
�@
�s���㎍�蒟�t�n�����i1959�N6���j�̉��t�i���j�Ɠ��E�ڎ��i���j�Ɠ��E�\���i�E�j
���@�G�h�}���h�E�N�����q���[�E�x���g���[�́s�g�����g�Ō�̎����t�́A�g�����̓Ǐ��X���̂Ȃ��łِ͈F�̏��ڂł���B�����E�������킸�g���̈₵�����z�ɖ|�̃~�X�e�����o�ꂵ�����Ƃ́A�t���C�}���E�N���t�c�́s�N���C�h�����\�O�\���t�Ɓs�M�t�i����ƂĐX�仁q��L�\�\���e�����̋L�r�����p���������ɏo�Ă�����́j�̂ق��ɂ͂Ȃ��������炾�B�W�p�Е��ɔŁs�g�����g�Ō�̎����t�i1999�N2��25���j�̐V�۔��v�q����\�\��������̊J��������������r�Ɉ˂�A�{��̏����́q�����鎀���l�r�ŁA���a���j���ҏW�������Ă����G���s�T�㏬���t�Ɍf�ڂ��ꂽ�B����ɖ������ꂽ�]�ː에���͒��сq�Ξցr�����̂����Ƃ����B����́u���s�ɏo���������́A���h�������قŁw�g�����g�Ō�̎����x��ǂ�ł��钖���Ƃ����j�Əo��B�k�c�c�l�v�iWikipedia�j�Ƃ���������������A�g���������o�R�Łs�g�����g�Ō�̎����t�ɋ�����������Ƃ��������܂������l�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����A�g�������������ǂ��Ă����̂͏��N����ŁA�͂����āq�Ξցr�i���o�́s�������_�t1934�N9�����j�܂œǂ�ł������ǂ����BNDL-OPAC�Œ��ׂ�ƁA1958�N�܂łɊ��s���ꂽ�s�g�����g�Ō�̎����t�͎���6�_�ł���i���̌�A��v�ۍN�Y��A�F�엘�ז�A�吼���m��Ȃǂ�����j�B
�@�@��������A�������[�ŁA1935
�@�A��������A�Y�{�ДŁq����ǂ�݂��Ă肢�r�A1950
�@�B��������A�V���ДŁq�T�㏬�����Ɂr�A1956
�@�C�����L��A���쏑�[�Łq���E�T�㏬���S�W�r�A1956
�@�D�c������A�����n���ДŁq���E���������S�W8�r�A1956
�@�E��������A�V���ДŁq�V�����Ɂr�A1958
�g������ɂ������C���D�Ƃ������Ƃ����肦�Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�q�����ǂ{�r�Ƃ��������e���炢���Ă��A��y�Ȕłł���A���߂̊��s�ł�����E�̉\�������������낤�B

�x���g���[�i��������j�s�g�����g�Ō�̎����k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1958�N11��29���j�̕\��
�Ƃ���Ŗ{���ɂ́A���̗��Ɂq�o��l���r�̋L�ڂ������āA���̎��̃y�[�W�Ɂu�M���o�[�g�E�L�[�X�E�`�F�X�^�g���@�ցv�Ƃ��������ɑ����āu�M���o�[�g�N�A�l�͂��̏������N�ɕ�����A���̗��R�́A�k�c�c�l�^�d�E�b�E�x���g���[�v�Ƃ���B�����Ŏ����͂��Ȃ����v���o���̂́A�u�M���o�[�g���݂͑P�ǂ�����^���v�̗����������Ȃ���^�݂�I����꒚�������Ƃ�o���ā^���֏o��v�Ǝn�܂�g���̎��сq����ȉĂ̗��r�i�G�E26�A���o�́s�V���t1975�N7�����j�ł���B�����Ƃ��g���{�l�͋�����b�q�Ƃ̑Βk��
�@�����@�G�b�Z�C�ŁA�N�ƌĂт��������͂��܂܂ŏ��������Ƃ͂Ȃ�����ǂ��A���ꂩ������������珑�����Ƃ����邩���m��Ȃ��Ƃ������ɂȂ��Ă������͂��������ł���i�j�A�����ǂ�ŁA���A�Ȃ�قǂȂƎv������ł����ǂˁB
�@�g���@�ł��Ȃ���ˁB
�@�����@�w�T�t�����E�݁x�̒��ɓ����܂���ˁB
�@�g���@���t�͂ˁB
�@�����@�ŗL�����ŏo�Ă��āA�u�ٗ�Ձv�̃A�����A�u����ȉĂ̗��v�̃M���o�[�g�ˁB
�@�g���@�M���o�[�g���Ă̂͂ˁA�̂����������j�o�D�������́A�卪�����ǁB
�@�����@�Ӂ[��B�����f�掞��́H
�@�g���@���Ǝv���̂ˁB���ꂪ�ӂƖ��O�Ƃ��ďo�Ă����̂ˁB�i�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�Z�y�[�W�j
�ƌ���Ă��邩��A�`�F�X�^�g���̂��Ƃł͂Ȃ��̂��낤�B�����A�����Ń��~�j�T���X�i���ӎ��I�L���j���܂����������Ă��Ȃ��Ƃ������Ȃ��C������B
�����@�剪�M�́A�W�����W���E���j�F�i�]������j�s�_�_�̖`�� 1916-1922�t�i���p�o�ŎЁA1959�j�A�����i���Y�s�����̕��w�`���\�\�a�̕��w�_�k���a�I�V���l�t�i���{�����o�ŋ���A1940�j�A�x�[�R���̐��M��3�_�������āA�Ă��˂��ɃR�����g���Ă���B�ڍׂ��ɂ߂��s�剪�M�E�S�O�� �N���t�i�剪�M���ƂΊفA2013�N8��1���j�ɂ������Ȃ����͂Ȃ̂ŁA�����Ă����B���������A���͂Ȃ��I�����C�����Xbk1�̃E�F�u�T�C�g�̈Č��Łq�����ǂ{�r�Ɠ��l�̊���ӔN�̑剪����Ɉ˗������Ƃ���A�V���͓ǂ�ł��鎞�Ԃ��Ȃ��̂Ŕ���Ȃ��|�̕ԐM������������Ƃ�����B
�k2019�N3��31���NjL�l
�x���g���[�ƃ`�F�X�^�g���Ƃ����A�����^���̏������낵�s�z�[���Y�Ɛ��������̎���k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2018�N3��10���j�́q��� ���������̉�������i�C�M���X�̏ꍇ�j�r�̑��͂��A���̓�l�̂��߂Ɋ�����Ă���B�u�k�c�c�l�w�g�����g�Ō�̎����x�͕��G�ȃg���b�N�̉𖾂ƁA����ɂ���u���߂̏��v�Ƃ̃��}���X�����݂������ҏ����ƂȂ��Ă���B�R�i���E�h�C���́u�z�[���Y�v���̂͂قƂ�ǂ��Z�҂ł��������A�`�F�X�^�g���́u�u���E���_���v���̂��Z�҂������B�x���g���[�̓g���b�N�Ɛl�ԃh���}�I�ȗv�f���A���҂ɂ��Ă��̗��҂���������ƕ`�����̂ł���v�i�q�d�E�b�E�x���g���[�\�\��x���Ɛ��������r�A�����A��Z�܃y�[�W�j�B�g�������z�[���Y�ȍ~�̂��̎�̏����ɔM�������`�Ղ͌����ɂ������A���N�̂���ɂ͉��{�Y���̕ߕ��������ǂ����Ƃ����i�q�Ǐ����r�j�B���_�j�X�g�ƃ~�X�e���[�͑������D���悤���B�g���ɋ߂����l�ł����A���e���O�Y�i�A�K�T�E�N���X�e�B�s�O���̔ߌ��t��Ă���j�A�ےJ�ˈ�i�����Ɂs���y�Ƃ��Ẵ~�X�e���[�t������j�A�c������i�N���X�e�B�𑽂��Ă�����肩�A����̎��ł����y���Ă���j�����̑�\�ł���B�����̖{�ɂ��A�s�E�r�E�G���I�b�g�ƃz�[���Y���̂̊W�i�Z���y�[�W�j�A�W�F�C���Y�E�W���C�X�ƃt�����\���E�E�[�W�F�[�k�E���B�h�b�N�i�p���x�����n�������̖���j�́s��z�^�t�̊W�i��Z���y�[�W�`�j�ȂǁA���낢��Ȃ��Ƃ��l���������|���肪�[���Ă��āA�����͐s���Ȃ��B���܂��ܓ���N�v�̕]�_�W��ǂ݂������Ă�����A�q�ו��̐_�r�Ŏ��Ɛ��������̊W���q�ׂĂ���̂��ڂɂƂ܂����B
�u�k�c�c�l��p�␄�������ł́A�Ƃ����l�̌����������́A�Ƃ�ɑ���Ȃ��i���̂��Ƃ��j�ו��m�f�B�e�[���n�ɁA�ł��d�v�Ȍ����Ђ���ł���P�[�X�������킯�����A���́u�^�̖��́v�ɂ��Ă��A�������Ƃ�������B���ł��Ȃ�������A���邢�͉��C�̂������ȋ��Ȃǂ��A��т̎��̗^������x�̂قƂ�ǂ��x���Ă���Ƃ��������Ԃ́A��ʂɋC�t����Ă�������͂邩�ɑ����̂ł͂���܂����B���̂悤�ȁu�ו��ɂЂ��ސ_�v������̂��A���������̏ꍇ�ɂ͖��T��A���̏ꍇ�ɂ͗ǂ��ǎ҂Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B�^�Ƃ���ŁA���̂悤�Ȗ��T��̓o�ꂷ���i�A���x�ł��ǂݕԂ������Ȃ鐄�������Ƃ́A���O�ɂƂ��Ă͉��Ȃ̂��A�Ƃ������A���Ƃ��Ă̓`�F�X�^�[�g���́u�u���E���_���v�V���[�Y�������邱�ƂɂȂ�B�k�c�c�l���悻��\�N�A���N�Œ�܉�͓ǂݕԂ��ė��Ă���B�����ł��A�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����̂��A���������s�R�Ȃ��炢�����A���������Ȃ̂�����d�����Ȃ��B����������A��ɏq�ׂ��Ӗ��ł́u�ו��̐_�v�̌������u���E���_���ɁA�����č�҂f�E�j�E�`�F�X�^�[�g���Ɋ����Â��Ă���Ƃ������ƂȂ̂��낤�v�i�s���ɂ������t�A�v���ЁA2002�N6��20���A��`��y�[�W�j�B
��x�A�g������ɕߕ����␄�������ɂ��Ă��������Ă������������B�����������j�[�N�Ȍ������������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ƃ��u�ŋ߂���A�������̂��̂�����܂��ǂ܂Ȃ��v�Ƃ��A�u���������ƒT�㏬�����Ă̂͂ǂ��Ⴄ���H�@����������͂Ȃ�Č����Ă�낤�v�Ƃ��B
���͎i�n�ɑ��Y�̂悢�ǎ҂ł͂Ȃ����A�܂ɂӂ�ēǂ݂������{�̂ЂƂɁs�X�����䂭 28 �^���I�s�k�������Ɂl�t�i�����V���ЁA1990�N8��20���j������B���́u�^���m�^��/�^��/�g���^���ނ�n�v�Ƃ͂Ȃɂ��B���݂́u�ϏB���́A�Ñ�A�^���Ƃ����Ɨ����������̂ł���v�i�����A��l�y�[�W�j�ƊX�����䂭�l�͌��B�ł͍ϏB���Ƃ͂Ȃɂ��B����{�鍑���R�̕��m�������g�����i����26�j���A����܂œ]�킵�Ă������F����n�����^���I�ȓy�n�ł���B�����s�g�����N���k������2�Łl�t��1945�i���a20�j�N�̍��Ɂu�l���A���F���璩�N�ϏB���֓n��B�㗤�ȗ������m�n�ŕ�������юR���ֈړ��B�V���x�Ŗ�c���|�ꂽ�n��H�ׂĐ����̂т�B�����\�ܓ��A�s����}����v�ƋL�������A����͋g���̐��z�q�ϏB���r�i���o�͒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t1955�N8��20���j�Ɉ˂�B�q�ϏB���r�̑S���������B

��g���@�o�T�F���R����N�s�ϏB���E�l�G�ʁ\�\FROM CHEJU�t�i�C���ЁA1991�N10��22���A�ܓ�y�[�[�W�j
�g�������̕��͂\����1955�N8���͂܂��ɐ��10�N�A�������������W�s�Õ��t�i���ƔŁj�����s�������ŁA�����͐푈�̋L�����������������ϏB���̊T�����q�ׂ�܂ł��Ȃ������B���������̂����́A�K����������ɒʂ��Ă��Ȃ��B����j�j�s�؍��ϏB���\�\�����ނ��ԓ��V�i�C�̗v�k�����V���l�t�i�������_�V�ЁA1996�N10��25���j�ɂ́q���퉺�̏r�Ƃ��āA���̂悤�ɂ���B
�u����E��풆�A�ϏB���쐼���Ɩk���ɓ��{�C�R�q����̊�n���݂����A�����嗤�ւ̍q����i�싞�n�m�����Ȃǁj�̋��_�Ƃ��ꂽ���Ƃ�����B�܂��ϏB�������V�i�C�̗v���Ȃ��Ă���Ƃ����헪�I�ʒu�̏d�v������A��햖���ɂ̓A�����J�R�̍ϏB���ւ̏㗤��킪�\�z���ꂽ���߁A���{�R�啔���i���Ƃ�����j�����Ԃ��A�S���v�lj��̍H�����Ȃ��ꂽ�B�C�݂̊R�ɂ͓��U���̐l�ԋ����p�̓��A���@���A���[�R�k�����̌�搶�m�I�X���Z���n�x�i���Z�チ�[�g���j�ɂ͎i�ߕ��p�̃g���l�����g�[�`�J���z���ꂽ�B�����̘J���ɂ͓����������I�Ɏg�����ꂽ�B�^�K���ɂ��ē��͐�ꉻ���邱�ƂȂ��I��ƂȂ������A���{�R�͕���������A�����g����ɍۂ��Ď�̏��Ί�A�e������[�R�̉ΎR�n�`�𗘗p���������w�n�ȂǂɉB�������Ƃ���A���ꂪ�̂��Ɂu�l�E�O�����v�̍ۂɎg�p����邱�ƂɂȂ�v�i�����A�O���y�[�W�j�B
�g���̖�c�����V���x���ǂ��ŁA�R���I�ɂǂ̂悤�Ȗ�����S���Ă����̂��킩��Ȃ��i��g���������낷�n�_�Ȃ�A�˗іʂ��낤���j�B�u�S���v�lj��v���K�����Ƃ���A�A�����J�R�����{�R�������쒀����̂����Ԃ̖�肾�������낤�B�g���͋㎀�Ɉꐶ���z���������ɈႢ�Ȃ��B���̂Ƃ��A��y�����ɂ��Ă����R�n��j���Đ����̂т邱�Ƃ͂ǂ�Ȃ��������i�g�����������̎��тɔn�̎p��`�����̂́A�����̈ӂ��܂܂�Ă��悤�j�B�g���̋L�q����́A���̌R�n���ǂ�������ނ������̂��s���ł���B���̏H���K�l�̉���I�ȁq�g�����́s�n�t�̎��Q�r�i�s�g�����A���x�X�N�t����R�c�A2002�N5��31���A�����j���n�̕i��ɂ��Ă͐G��Ă��Ȃ��B���E�푈�j�̌����ҁA���s�⎡�Y�́s�x�����n�\�\�E�}����݂��ߑ���{�k�u�k�АV�����`�G�l�t�i�u�k�ЁA1999�N2��10���j�ɂ͂�������B
�u���a�\��N�����\�N�܂ł̊Ԃɒ������ꂽ�R�n���́A�s��ŌR����̂���Ă��܂������߂ɐ��m�Ȑ��l�͎����Ă��܂������A�����悻�Z�\���Ȃ������\�����ɋy���̂Ɛ��������B�܂��A���F�ł͂��Ȃ�̐��̌��n�_���̔n���w���������A�푈�����ɂ͌��n�̎Y�Ƃ��ێ����邱�Ƃɒ��ӂ������A��Ƃ��Ė×V�q�n���w�������B�^���Ȃ݂Ɏ��ϖu������I��܂łɌR�n�������Ƃ������p�����̂́u�x�ߕ��ʁv�ł���A���̑��o���n���͓�\�l���O�S�\�㓪�ŁA���N�Ԃɏ\�ꖜ�Z��S�\�ꓪ�Ղ��A�I�펞�c���n���͏\�l���S�����ł������B�^���̓���́A���{�n���Z���ܐ�S���\�l���i�ܓ�p�[�Z���g�j�ŁA�嗤�n���ܖ����O�\�l���i�l���p�[�Z���g�j�ł������B����ʂł́A��n�A�C���m�n�A�C���ʔn�y�ѐ��ʔn�͂��ׂē��{�n�������ď[�Ă��A�n�d�n�͂��ׂđ嗤�n���[�Ă��Ă����B�^�����c���n�̖��p�[�Z���g�ɂ�����㖜�ܐ�l�S�\�㓪���A�V�ÁA�k���A�ΉƑ��A�R���A���ȂǓ�\�n��̒n�_�Œ������Ɉ����n���ꂽ�v�i�����A���܃y�[�W�j�B
��������́A�u�n�d�n�͂��ׂđ嗤�n�v�ŁA���F�̔_���̔n��×V�q�n���ČR�n�Ƃ������Ƃ��킩���i���j�B
�i�n�́s�^���I�s�t�́q�����S���鍑�̔n�r�ɂ́u�Ôn�́A�A���u�⒆������̔n�̂悤�ɔn�i���傫���Ȃ��B�̂������������ɓ����傫���A�r���݂������ӂƂ��A�Ȃ��s�i�D�Ȃ̂����A���r�̍s�R�ɓK���Ă���A�ϋv�͂͂��ɂ悢�B�`���M�X���Ƃ��̎q�������͂��̏����Ȕn�ɋR�m�́n���Ă͂邩���[���b�p�܂ōs�����̂ł���B�^���݂̃����S�������̔n�͍����ɂ���ė��j�I�Ôn�Ƃ͂����Ԃ��������̂ɂȂ��Ă���B�^�\�O���I�̑僂���S���鍑�̔n�́A�ϏB���ɂ����̂����Ă���Ƃ����Ă����v�i�����A��ܘZ�y�[�W�j�Ə�����Ă���A�����͂��Ȃ��B

�u�n�Ƒ劙�v�@�o�T�F�����s�ϏB���t�i������w�o�ʼn�A1966�N5��31���k2���F1971�N3��25���l�A���G�ʐ^ 73�j
�����Ƃ��A�������i�n�́s�^���I�s�t�Œ��ڂ���̂͂��̂܂��̏́q�_�哇�r�̎��̈�߂��B
�g���̎��сq�H���r�i�J�E18�A���o��1983�N5���́s���j�ƎЉ�t2���j���v���邩��ł���B
�Ƃ�킯�u((�n�ɋN�邱�Ƃ́^�i�l�ԁj�ɂ��N�肤��))�v�Ǝn�܂�u�S�v�́A�g���́q�ϏB���r�ɓo�ꂷ��n��z�N������B���s�́u�s�V�����̖�v�ɂ��Ă��A�����ɂ��s��ʁt�ɂӂ��킵�����A�q�G�̐��r�i�J�E2�A���o�́s���㎍�蒟�t1981�N9�����j�̈�߁A
�Ƃ�����������A�ϏB���̕����Ɛ�͂Ȃ��Ȃ��悤���i�����j�B�q��́r�i�C�E13�j�����F�̕��y�ƕ��������������тł��邱�Ƃ͂Ƃɒm���邪�A�g�����I����}�����u���N�̈�Ǔ��ϏB���v�����̎��ɐ[�����܂�Ă��邱�Ƃ��܂��^���Ȃ��悤�Ɏv���B�{�e�̏��߂Ɉ���������j�j�s�؍��ϏB���t�ɂ́u���̓��͖k���̑嗤�A�W�A�Ɠ���̊C�m�A�W�A�̐��i�������A�܂����N�C���ɂ�����Δn���̑��݂ɂ����āA���ؗ������Ȃ���ѐ̂悤�Ȗ������ʂ����Ă���̂ł���v�i�����A���l�y�[�W�j�Ƃ���B�g�����͐}�炸���u�k���̑嗤�A�W�A�v���F��m�����킯�����A�u����̊C�m�A�W�A�v�����ۂɖK��邱�Ƃ͂Ȃ������B���͂��܁A�s�Õ��t�Ɍ�����ɖ��邢��C�̃C���[�W�̒�ɂ���̂́A�g����1945�N�t����H�ɂ����đ؍݂����ϏB���̂���ł͂Ȃ����A�Ɗ����Ă���B�s�Õ��t�ِ̈F��q�Ă̊G�r�i�B�E9�j�����A���̓�C�Ɓi�q���i�r�������������悤�Ɂj�����V�A���E�N�[�g�[�̊G�̕����ȍ����ł͂Ȃ��������B
�Ă̊G�b�g����
���`�⟲�֑D�����̉Ă�
���M�I�ȗ̋V���֎Q������
������
�}�X�g�͂ɂ��₩�ɏ��ƂȂ�
���̔��̂��闑����������������
�傫�ȗt��
�D���̖X�q�֓��������
�������܂ɂЂ����肩�������D���̌҂ɖ̎����n���
�O�i���扫��
�̔g�̒���
�g���̃��U�C�N�̗t
��~����
���̗ɑD�̊����j����
�̏j����
���z����̂�������
���ւ���D���̌�
������̂Ƃ���
�c���ɂ݂ǂ�̖ю��łЂ��������Ă���
�������قǂ��ƌ͂ꂾ��
�D�͏㗤����
�������
�傫�Ȏ��ɂȂ���
���ɂ��������̐����Ƃ�
�}�X�̊Ԃ���
��̒���
���̔g�ɂ����܂ꂽ
�݂��݂��������̂Ȃ�
���A�点��
�����m����{�C���̓��͍��n�ƉB�����B�����A���̓������{�C�E���V�i�C�E���C�̂������ɂ���ΎR���A�ϏB����K��Ă݂����B����j�j�s�؍��ϏB���t����u���R�����Ȃ��i���E�i�F�m�������䂤�n�\��i�v�i�����A��O��y�[�W�j���f���āA�{�e���I���邱�Ƃɂ��悤�B
�@�@��R���o
�@�@��������
�@�@�i総t��
�@�@�k�яH�F
�@�@���[�Ĕ�
�@�@���K�Ӑ�
�@�@�R�Y�ދ�
�@�@���M�q�n
�@�@�쎺���
�@�@�R�[�A��
�@�@�����锿
�@�@�����V��
���@�g������1941�N����1945�N�܂��n�d���Ƃ��Ē����嗤����эϏB���ɂ������B���s�⎡�Y�́s�x�����n�\�\�E�}����݂��ߑ���{�k�u�k�АV�����`�G�l�t�i�u�k�ЁA1999�N2��10���j�ɂ́u�n�d���Ƃ͐퓬���ȁi���E�R�E�C�E�H���j���x�����镺�ȂŁA���a�E�e��E�ߕ��Ȃǂ̌R���i�̉^���ɔC�������̂ł���B�����͒e��i��A�ƐH�i��A�ˋ��i����\�����ČR���ɑ��s���A�ʏ킱��ɉq�����A���a�@�Ȃǂ��܂߂��n�d�Ə̂����B�܂��A�펞�ɂ͎t�c�̗\���n���Ǘ�����n���m���悤�n�⏝�a�n��ۈ炷��a�n����Ґ������v�i�����A���Z�y�[�W�j�Ƃ���B
�����@�����s�ϏB���t�i������w�o�ʼn�A1966�N5��31���k2���F1971�N3��25���l�j�ɂ́u�҉P�ikale�j�@���a�l�܃Z���`���[�g����̐�g�݂��킹�����̂Łi2�j�k�����P�l�ƂƂ��ɉƒ�łӂ��g���Ă���v�i�����A���O�y�[�W�j�Ƃ���A���G�ɂ́u���������v��u�����i�����j�v�̎ʐ^�i1936�N�B�e�j���f�����Ă���B�܂��A��Ɉ˂�u���N�k�{�y�l�ɑ����J�T�T�M�́k�ϏB���Ɂl�������Ă��Ȃ��v�i�����A���y�[�W�j����A�q�G�̐��r�́u�F�͑�������v�͖��F�̌��i���낤���B�Ȃ��A�g������́s�ϏB���t�i�i�n�ɑ��Y�������]�������j�ɐG�ꂽ���͕s���ł���B

�u�����i�����j�v�@�o�T�F�����s�ϏB���t�i������w�o�ʼn�A1966�N5��31���k2���F1971�N3��25���l�A���G�ʐ^47 a 1936�N�j
�g���z�q�ҁq�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�j�ɂ̓s�J�\�Ɋւ���L�ڂ�2�ӏ�����B�u���O���N�i���a�\��N�j �\���^�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łu�݂Â�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������B�Ȍ�A�k�����q���W�w���̃A���o���x��w���삿�����W�x�Ȃǂ�ǂށB�F�l�����Ɣo������v�i�����A����Z�y�[�W�j�Ɓu��㔪��N�i���a�\�Z�N�j �Z�\��^�O���A�k�c�c�l�ɐ��O���p�قŁq�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�r�k���ς�l�v�i���O�A���Z�O�y�[�W�j�ł���B�q�g�����Ƒ���C���i3�j�r�̒��i�T�j�ɋL�����Ƃ���A�g�����͐��z�ŘZ��ɂ킽���āu�s�J�\�̎��v�Ɍ��y���Ă���B�������Čf����B�����́i�@�j���͐��z�̔��\�N���B
�@�@�u���̍��A�֓������̎l�J�̃A�p�[�g�ŁA�s�J�\�̎������A���������B����́u�݂Â�v���Ȃɂ����낤�v�i1959�N8���j�B
�@�A�u���X�̏K������݂����o��ł��Z�̂ł������ł����A���p�G���ł݂��s�J�\�̎��ɐG������Ď��ֈڍs�����v�i1962�N1���j�B
�@�B�u�k�����q�ƃs�J�\�A���ꂩ�獶�삿���̎��ɂӂ�āA���^�I�Ȃ��̂֓]�ڂ��Ă������̂ł���v�i1968�N4���j�B
�@�C�u�����s�J�\�̊G�Ǝ��������̂́A�������\���A���̂���̂��Ƃ��v�i1982�N3���j�B
�@�D�u�k�����H�̒Z�̂⍲���t�v�̎��ɖ������Ă����A���N���̎��͋��R�ɓǂs�J�\�Ɩk�����ʂ̎��ɂ���āA�ʂ̎��̐��E������̂�m�����v�i1983�N4���j�B
�@�E�u�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łw�݂���x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������v�i1984�N1���j�B
�O�f�N���̓T���ƂȂ����E���g�����������Ƃ��ɎQ�ł�������C���̖�́s�ߑ�|�p�k���p�I���l�t�i���p�o�ŎЁA1962�j�̉\�����������A����͏��o�q���������s�J�\�r�i1937�j�Ȍ���s�J�\�̎��ɂ��т��ѐG��Ă���A�q���������s�J�\�r�����^�����s�ߑ�|�p�t�̍Ċ���O�����܂߂āA1949�N�ȗ���3�x�ɂ킽��q�s�J�\�̎��r��1973�N�́q�u�s�J�\�̎��v�]�k�r������B������q���������s�J�\�r�Ŗ�o�����s�J�\�̎����
������B�܂�
�Ƃ������͂�����B�u����́v��u�g�����Łv�͋g���̐�O�̎�����A�u����俐F�̌����v����ᰋ����̓��А������v�͑�����g�́s���I�����t�̏�����A�z������������B�g���̎��I�o���ɂ�����s�J�\�̎��̉e���́A�k�����q�⍶�삿���̎��ƂƂ��ɁA���ア�������ڂ炩�ɂ����K�v������B�N����i�A�q�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�r�i�ɐ��O���p�فA1981�N3��5���`4��7���A��Ó����V���j�́A1881�N�A�X�y�C���ɐ��܂ꂽ20���I���p�̋����p�u���E�s�J�\�̐��a100�N���L�O����W����ł���B�g���͏�Ɉ������悤�Ƀs�J�\�̎��ɂ��Ă͉��x�����������A���̊G�ɂ��ď��������M�͂Ȃ��B�����g���ɂƂ��čł��d�v�ȃs�J�\�Ɋւ���L�q�́A�B��̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�i���e���O�Y�E���q�����ďC�s���̖{ �U ���̋Z�@�t�}�����[�A1967�N11��20���j�̎��̂�����ł���B
����A�{�e���������߂Ɂs���̖{ �U ���̋Z�@�t�i���j���ēǂ����B�u���̋Z�@�v�����ہA�����ŊG����Ƃ����������ɏo���Ă��镶���f����B
�������Č���ƁA���l�ɂƂ��Ă̌��t�Ɖ�ƂɂƂ��Ă̊G��Ƃ����A�i���W�[���قƂ�ǂł���Ȃ��ŁA�q�킽���̍쎍�@�H�r�ɂ�����g���́u�G��v�u�G�搫�v�u�s�J�\�̏��̊�v�������ɐ[�����Ȃ̍�i�ɑ��������y�ł��邩������������i�q�킽���̍쎍�@�H�r�͐�Ɉ������u�Î��E�Î��A�ڂ₯����������������e�����˂���āA���F�����g����v�̂��ƁA���сq��́r��S�s���p���āA����ɂ܂�閞�F�ł̕����������ڂ��ďI���j�B���ꂩ����ʂ��A�����̌����
�ƁA���������u�s�J�\�̏��̊�v���̂��̂ł���B����܂��āA�ȉ��ł͋g�������ɂ�����u�s�J�\�̏��̊�̂悤�ɁA��������̂��Ɍ��镡������v���Ƃ̈Ӗ���T���Ă݂����B
�P�c�����́s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�j�́q�͂��߂Ɂ\�\�o�ŊE�̃��[�����f���Ƃ��Ă̎�����閣�́r�ŁA��w�ɓ����ďo������}�����[�̏��Ђ̕M���ɍ��K�G���s������p�k�O���[���x���g�E�V���[�Y73�l�t�i1965�N11��30���j�Ɠ��s�s�J�\�\�\���ނ̘_���t�i1964�N10��10���j�������Ă���i�����A�l�y�[�W�j�B�̂��ɔ��p�o�ŎЂɋΖ����邱�ƂɂȂ�P�c�����K�̓���Ɋ��������̂́A�قƂ���ɑ���Ȃ��B����ŁA������p�Ɍ��炸�ς邱�ƑS�ʂ��ÛY�ȊS������Â��Ă����g�����A����玩�Ђ̏o�ŕ��Ɋ��ʂ��Ȃ������ƍl���邱�Ƃ́A���ɂ͂ł��Ȃ��B�g�������K�́s������p�t�Ɓs�s�J�\�t��Ǘ������Ƃ����؋��͍��܂ł̂Ƃ���Ȃ����i�����j�A���̔����I�O�Ɋ��s���ꂽ����̎˒��́A�g�����f����1990�N�͌����܂ł��Ȃ��A2017�N�̌����_���������Ă���B���Ȃ݂Ɏ������߂ĐG�ꂽ�̂́A�s������p�t�₵�ās20���I���p�k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A1993�N4��7���j�Ɖ��肵�����ɔł́u��\���v�i2005�N11��10���j�ƁA�����s�s�J�\�\�\���ނ̘_���t�₵�����p���_�ДŁi1983�N10��10���j�ɉ������s�s�J�\�\�\���ނ̘_���k�����܊w�|���Ɂl�t�i���A1995�N1��9���j�ł���B�ȉ��ł́A�g���f�㊧�s�́k�����܊w�|���Ɂl�ł͂Ȃ��s������p�t�Ɓs�s�J�\�t�̏����Ɉ˂��āA�g�������ɂ�����s�J�\�̈Ӗ����l���Ă��������B�Ƃ����T���當�ɔŁs�s�J�\�t�����́q����ɂ������ār���������ƂɂȂ�̂����A���K�ɂ��A�s�J�\�́u���ށv�Ƃ͎��̂悤�Ȃ��̂��B
��������z�N�����̂́A�g���̐�O�̒���ł��鎍�̏W�s�����G�߁t�i1940�j�Ǝ��W�s�t铁t�i1941�j�̎��т��A�k�����q�⍶�삿���̃��_�j�X�����A�x�V�ԉ��j�̐V���o��Ȃǂ�ێ悵�Ȃ���A���ړI�ɂ͑���C����ɂ��s�J�\�̃V�������A���X�������_�@�Ƃ��ď����ꂽ�Ƃ��������ł���B�s�s�J�\�t�����́q�s�J�\�N���r��1935�N�ɂ́u�{���W�����[�ŏ������V�������A���X�����̎����o�Łv�i�����A�k��t�l��Z�y�[�W�j�Ƃ��邩��A�O�f�̑�����2�N��ł���A18�������g���������́u�V�������A���X���i��������`�j�̎���v����u�Q���j�J�̎���v�ɂ����Ẵs�J�\�̊G��������̎��ɌX�|�������Ƃ́A���ЂƂ��������Ă��������B�u�̎���v�ȗ��A�s�J�\�͖��菟���̂悤�ł��āA�˂ɉߋ��́i�s�J�\�ɂƂ��Ắj���������̍�i�ɐ[���w�сA����ނ����������Ƃ́A���K�́s�s�J�\�t�̐����ɂ��̎w�E������A���p����ςɊ����Ȃ��B�����A�s�J�\�̒�������ɂ����āu�L���r�X���̎���v�����͂���ƈَ��������A�ƍ��K�͋L���B
��������b�͂�₱�����Ȃ�B�g�������s�J�\�łȂ��ȏ�ɁA�g�����̎��̓s�J�\�̎��ł��A�܂��Ă�s�J�\�̊G��ł��Ȃ��B�����A�s�J�\�ɂƂ��ẴL���r�X�����A���ɂ͋g���̐��́i�Ƃ������Ƃ͐^�́j���I�o���ł��鎍�W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̍�i�Əd�Ȃ��Č����Ă����������Ȃ��̂ł���B����قǂɁs�Õ��t�́A����ȑO�̍�i�Ƃ��i���̊Ԃɂ͕��m�Ƃ��Đ��ɋ�肾�����Ƃ������]�L�̑̌����������j�A����ȍ~�̍�i�Ƃ������Ȃ܂łɒf���ꂽ�p��I��ɂ��Ă���B�����Ő�O�̍�i�͑[���Ƃ��āA�s�Õ��t�i�Ƃ��̃O���e�X�N�ȕϑt�ł���s�m���t�j�̂��ƁA�g���͉A�ɗz�ɍ�i�̓T�����A��s���镶�w��i��G��║��|�p�ɋ��悤�ɂȂ�B�����������ɂ����Ắu���p�v�̖��͂����܂ł��Ȃ��B�����݂͂ȁA�s�J�\�ɂ�����u���ށv�������́u�ϑt�v�ƕ��s����B������������u���ӋZ�v���ւ����s�Õ��t�́A�����A�����ăL���r�X���ӂ��ł��܂��Ă�V�������A���X���ӂ��ł��Ȃ������B�����Łq�킽���̍쎍�@�H�r�����\���ꂽ�̂�1967�N11���A���Ȃ킿���W�ł����s�a���`�t�i1962�j�Ɓs�Â��ȉƁt�i1968�j�̂������A���\�����������тł����̂��́s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�̎������������Ƃ�z���N�������B�܂�A�u�s�J�\�̏��̊�̂悤�ɁA��������̂��Ɍ��镡������v���Ƃ̈Ӗ��́A�L���g�������S�̂�����ɓ����̂ƁA1960�N��㔼�Ƃ����A�����肳�ꂽ����i������u���@�I�͍��̎���v�ƌĂ�ł��A���Ȃ����I�O��ł͂Ȃ����낤�j�ɒu���̂Ƃł͈Ӗ��������قȂ�̂��B�����ł͑��f����������Ǝv���B�Ƃ���Łu�s�J�\�̏��̊�̂悤�ɁA��������̂��Ɍ��镡������v�̎��́u�킽�������v�������B������x�A�������f����B
���́u�s�J�\�̏��̊�̂悤�Ɂv�́A�����Ɍ���m�A�A�n�ɌW��̂��A��������m�A�A�n�ɌW��̂��B����Ƃ́u�����̏����Ȗڂ��W�܂��Ăł����ځv�̂��Ɓi��F�g���{�̖ڂȂǁj�ŁA�����ށE�b�k�ށE�N���ށE���J�f�ނȂǂ̐ߑ������Ŕ��B���Ă���B�䂦�ɁA�����ɂ͉��}�̂悤�ȃL���r�X���ӂ��̐l���̊���w���̂ł͂Ȃ��B�������A���낢��Ȋp�x���畨������Ƃ����Ӗ��́u����I�Ɍ���v����z�N����̂́A�܂��Ƀs�J�\�̃f�b�T���q����̒��`�r�i1961�j�\�\�g���ɂ̓}�l�́q����̒��`�r�܂��������q����̔ӎ`�r�i�G�E13�j������\�\���̂��̂ł���B���́u���Ĕނ�����Z�N��ɗp�����悤�ȁA���m�ŗ₽���`���ɂ���āA�Ώۂ�I�m�ɑ�����ÓT�I�f�b�T���v�i�s�s�J�\�\�\���ނ̘_���t�A��l�l�y�[�W�j�����A��������̂��Ɍ���m�A�A�n�Ɠ����ɂ�������̂��Ɍ��镡������m�A�A�n�ŗǂ̎��Ⴞ�Ƃ����悤�B
 �@
�@ �@
�@
�}�l�q����̒��`�r�i1863�A�J�����@�X�ɖ��ʁj�i���j�ƃs�J�\�q�}�l�ɂ��u����̒��H�v�̃��@���G�[�V�����r�i1961�A�J�����@�X�ɖ��ʁj�k�o�T�F�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�\�\���a100�N�L�O�t�}�^�i�����V���Ac1981�j�A�}��68�l�i���j�ƃs�J�\�q����̒��`�r�i1961�A�f�b�T���j�k�o�T�F���K�G���s�s�J�\�\�\���ނ̘_���t�i�}�����[�A1964�N10��10���A��O�܃y�[�W�j�l�i�E�j
�ޏ��̉E�ڂ͒��̖��邢���E�����Ă��邪�A�����Ɂm�A�A�A�n���ڂ͖�̈Â����E�����Ă��邽�߁A���̓��E�͊J���Ă���B�����āA�ޏ��̃M���V�A�ӂ��̕@���͐^���������Ă���̂ɁA�@�o�͂ӂ��Ȃ���Ɍ����Ă���B�قȂ鎞�ԂƋ�Ԃ����ʂɒ蒅���邱�ƁB������C���[�W�ł͂Ȃ��A�I�u�W�F��p���čs�����ƁB�g�������s�J�\�̊G����w�̂́A���́u���@�v�������B���K�̓L���r�X���ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
���̎w�E�̂��Ƃɋg���́u���S�Ƃ͂܂��Ɉ�_������ǁA�������̎x�_�����蕡���̒��S���ړ������āA���̑��B�Ɖ�]���v��̂��B�Î��E�Î��A�ڂ₯����������������e�����˂���āA���F�����g����v��u���ƁA�g�������̓������i���ꂪ�ꌩ�A�ǂ�قNJG��I�E�����I�Ɍ����悤�Ƃ��j���Ԃ���肱�A����I�Ȑl�i���������遁���Ԃ��̂��Ȃ����Ԃ����ɂ���A�Ƃ����Ă������S���Ɏx�����Ă��邱�Ƃ������ɂȂ�B�g�������тɂ����āA�����E���ł�Ƃ�����������p���ăI�u�W�F�����݂��m�F����ނ̍s�ׂ����X�ɕ`���̂́A�u�������Ă��܂����v�I�u�W�F�����Ă������e���Ȏ���ɒu���Ȃ����㏞�s�ׂɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�u���ɂƂ��āA�G�Ƃ͔j��̏W�ςł���B���͕`���A�����Ă������킷�v
�@�����Έ��p�����s�J�\�̂��̌��t�́A�s�J�\�̊G��̖{�����������ɂ������ĂĂ���B�s�J�\�́A���Ȃ̊G��Ƃ���e���܂Ȃ��B�ނ́u�l�͎������g�̃t�@���ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����B�ނ͎����̍��o�������E�Ɉ��Z���邱�Ƃ��D�܂Ȃ��B�ނ͂˂Ɍ��������x�����A�Œ艻�������B�����̉�Ƃ����́A�����ꏭ�Ȃ��ꎩ�Ȃ̊G�搢�E�Ɠ��e���ށB���̎ア���p�Ƃ͒N�����l�̗l����͕킵�A�����̃p�^�[���P���邱�ƂŎ��Ȃ̐��E�����A�����ɋ����߂�B���Ƒn�I�Ȍ|�p�Ƃ͎��ȌL�̗l����n�����Ă�������Ȃ̐��E�Ƃ���B�������A���̂悤�ɂ��č��グ�����Ȃ̐��E���A�В[����ł����킵�čs���҂͂܂�ł���B�����Ă����Ƀs�J�\�́q�V�˂̔閧�r������B�i���K�G���s�s�J�\�ƒ��ۊG��\�\�ߑ㐢�E���p�S�W�V�k���㋳�{����457�l�t�Љ�v�z�ЁA1964�N2��28���A�Z�O�`�Z�l�y�[�W�j
�g�������u���ɂƂ��āA���Ƃ͔j��̏W�ςł���B���͏����A�����Ă������킷�v�ƌ������ƂāA����������܂Ȃ����낤�B�s�����G�߁t�i1940�j�Ɏn�܂�A�s���[���h���b�v�t�i1988�j�Ɏ��邻�̍�i�̏W�ς������A�s�J�\�ɑ���g�����̍ő���������Ǝv���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���@���e���O�Y�E���q�����ďC�s���̖{ �U ���̋Z�@�t�i�}�����[�A1967�N11��20���j�͌��_�q�T�@��������r�Ɗe���l�ɂ��q�U�@�킽���̍쎍�@�r�̇U���\���ŁA�W��E���M�҂͈ȉ��̂Ƃ���B
�T�@��������
�@�������邱����@�@�R�{���Y
�@���̑f�ށ\�\���㎍�̋Z�@�P�@�@�O�D�L��Y
�@���̃C���[�W�\�\���㎍�̋Z�@�Q�@�@�ѓ��k��
�@���̃��Y���\�\���㎍�̋Z�@�R�@�@������
�@���̍\���\�\���㎍�̋Z�@�S�@�@����N�v
�U�@�킽���̍쎍�@
�@�����ȎO�̗�@�@����S��
�@�|�p�Ƃ��Ă̎��@�@�k�����q
�@�ڂ��̋ꂵ�݂͒P���Ȃ��̂��@�@�c������
�@���Ă���ځ@�@���c�O�Y
�@�s�тƖ��\����̏o���@�@���J�열��
�@�핪���ҁE��}���҂̕��@�@�@���c��v
�@���b�@�@�֍��O
�@�킽���̍쎍�@�H�@�@�g����
�@��@�@��c�G
�@����̂��鎍�@�@�Ί_���
�@�����̋L���@�@���c�O
�����@�剪�M�̐��M�W�s�{�����˂���݂ł�Ƃ��t�i�Ԑ_�ЁA1975�N7��10���j�ɂ́q���K�G���r�̕W��̂��ƁA�s�s�J�\�\�\���ނ̘_���t�Ɓs������p�t�̓�т̏��]�����߂��Ă���i�s�s�J�\�t�]�̏��o�����N���́s�����W���[�i���t1964�N11���A�s������p�t�]�̂���́s���{�Ǐ��V���t1966�N1���j�B�s������p�t�]�ɂ����đ剪�́A�����_�I�ϓ_����u�k������p�́l���Ƃ��Ε���Ƃ�������A�e���r��f��A�{�̑��ꂻ�̑����܂��܂ȏꏊ�Ɍ`��ς��ďo�v���A�l�тƂ̐����ɂǂ�ǂ�N�����Ă���̂ł���v�i�����A����y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�s�����W���[�i���t�͂Ƃ������i��N�̂��Ƃ����A�����͓ǂ܂Ȃ����F�V���F�Ɍ��������������j�A�}�����[�Ő�`�L����S�����Ă����g�����s���{�Ǐ��V���t�̏��]��ǂ\���͂���߂č����B
�������@���K�G���́u�I�u�W�F�v�Ɓu�C�}�[�W���v�����̂悤�ɒ�`���Ă���B�u�I�u�W�F�Ƃ́A���̌ꌹ��������炩�Ȃ悤�ɁA�����̓���������^���ɑ��āu�����o���ꂽ���́v�ł���A�������Ƃ�܂��O�E�̂��܂��܂́u�Ώہv�A�u�q�ϓI���݁v�ł���A�k�c�c�l�����ʂ�́u���́m�A�A�n�v�̐��E�ł���B�C�}�[�W���́A�k�c�c�l���o�I�f���̐��E�ł���A�d�݂��A�������A���ʂ������Ȃ����̐F�ƌ`�̐��E�ł���B�I�u�W�F���l�Ԃ̐G�o�I�����������Ƃ߂���̂Ƃ���A�C�}�[�W���͐l�Ԃ̎��o�I�����������Ƃ߂���̂ł���ƌ����Ă��悢�B�v�i�s������p�t�A�O�Z�`�O��y�[�W�j
�����q�g�����̌��ʁr�Ƒ肵�ċg�������삵�����ʂ̃I�u�W�F���Љ�����Ƃ�����B����͋g�����ƃP���ʂ̊W���l�@���Ă݂����B�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�ɂ́A���ʁi�P���ʁj��2�ӏ��A�o�ꂷ��B
�b�̓s����A�q�P���ʒB�l�@�g�����r�̑S�����f���悤�B�k�@�l���͏��тɂ���L�B
�P���ʒB�l�@�g�����i���l�j�\�\�B�l�A�a��e���O�̕@��܂�b�k�������l
�@�u�ڂ��́A���[���[�A�����R�A�P���ʁA����̃K�L�V�ь�k�}�}�B�x�C�S�}�i���j�������Ă���l���Z�̂�����ɂ������B���ɋ����̂̓P���ʂŁA����͒B�l�ł��ȁv
�@�ƁA���N�Ƃ���49�̋g�������B�{����`�Ő��܂�Ĉ�����B�K�L�V�ь틣�Z�ɋ����̂������͂Ȃ��B���W�w�m���x�ōō��̂g���܂���������L���Ȏ��l�����A�����ɁA�P���ʂɂ����Ă͇������ł���B
�@�g�����́A��c�G�A�ѓ��k��A������s�A�剪�M�i����������l�j�ƈꏏ�ɇ��k�̉�������Ă��邪�A���N�O�k����N�O�l�ɂ݂�ȂœȖ،��̑����R�ɗV�тɍs�����B�w�O�̃I���`�����łӂƖڂɂƂ܂����̂��P���ʁB���������������߂ė��قŃP���ʑ����J�����̂����A�l�l�̗F�l�̓A�b�P�ɂƂ�ꂽ�B
�@�g�����̂��܂��͔��Q�B�܂�Ŗ��p�I�������̂ł���B
�@���̂��킳���āA�d�b�������Ă����̂��A�a�F���i�|��Ɓj�̕v�l�B
�@�u�����̎�l��������ł���B����͌܉�A�����Č��ɂ��ꂽ��ł��B���킳���܂���v
�@�a�A��߂Ă����悩�����̂��B�ʂ�Â��ɂ邵�ĐT�d�ɑ_���A�Ȃ�قnj܉�A���Ō��ɂ��ꂽ�k�u�g���P���v�l�B
�@�Ƃ��낪���肪�����B�g�����̓j�b�R������A�ʂ𒈂ɃN���N���Ԃ�܂킵�ẮA�X�|�X�|�J�`���Ƃ���Ď��s���邱�Ƃ��Ȃ��k�u�t���P���v�l�B���܂��ɁA���͋ʂ���ɂ����A����Ԃ�܂킵�ăX�|�X�|�J�`���Ȃ̂ł���k�u��s�@�v�l�B
�@�u�a��N�A���ꂪ�V���b�N�łˁB���ɂ�߂������ł���v
�@�Ȍ�A����҂͂ЂƂ�Ƃ��Č����Ȃ�����A���{�P���ʖ��l�ʂ͋g�����̂��̂Ƃ����Ă�낵���낤�B�Ƃ���ŁA�g�����ɂ͔ߊ肪����B
�@�u�P���ʂ͐��m���炫�����̂łˁB�̂̉f��w�y�y�k�E�l���E���R�x�k���w�]���x�l�ɂ������V�[�����������B��l�����������j���E�����Ƃ���Ƃ��ł��B��ʂ͕s�C���ȐÂ����B�ƁA�������ň�l�̒j���J�`���A�J�`���ƃP���ʂ���ĂȂ��B�f��ł�����ł������B�ڂ��ɃT���O���X���������āA����Ȗ���点�Ă���Ȃ����Ȃ��B����Șb����������A���Ђ����b���������v�i���o�u�T���v���C�{�[�C�v���Z���N�\�ꌎ�j�k���o�f�ڎʐ^�͎�������s�k�����̌��c�A�p�[�g�ŎB�e�������̂��l
���̋L���Ɠ����N�A�g�������}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t90���i1968�N7��31���j�́q���̍D���Ȃ��́r���ɔ��\���������̎U���q�D���Ȃ��̐������r�́u���b�L���E�A�u���W�b�g�E�o���h�[�A���Ƃ��ӁA�f��A���F�A����ׂ��A�y���F�̕����A���炱�A�����A�̂�A���\�Y�̃e���g�ŋ��A���哴�A�L�����݂̂낭�A�����A�a�J�{�v��̓g�b�v�̃R�[�q�[�B�k�c�c�l�����B�v�Ƃ���400���]��̏��������A���̒��قǂɁu�V���N�i�Q�A����ۂہA�P���ʂ����Ă����B�v�Ƃ���B�\�\���Ȃ݂ɋg�������Ɂu�V���N�i�Q�^���Ⴍ�Ȃ��^�Γ�ԁv�͈�x���o�ꂹ���A�u����ۂہv�u�^���|�|�v��1�o�ꂷ�邾���ŁA�P���ʂ��o�ꂵ�Ȃ��\�\�B����܂ŋ����Ă������������n��ɉ����ĕ��ׂ�ƁA
�@�@���N����i�吳���`���a���߁j�̓K�L�V�ь틣�Z�A�Ƃ�킯�P���ʂӂƂ����B
�@�A1959�N10���Ɂs�k�t���l�ƓȖE�����R�ɗ��s��������A�P���ʑ����J���A���p�I�Ȃ��܂����I�����B
�@�B1968�N1���A�P���ʂ���y�Y�ɉ�������ƂƂ����F�V���F���K�₵�A�u�_�Z�v���������B
�@�C1968�N7���A�u�P���ʂ����Ă����v���D�����ƁA�Ζ���̘J�g�@�֎��ɐ��z�\�����B
�@�D1968�N11���A�T�������g���̃P���ʂ���肠���A�g���͉f��║��ŃP���ʂ����������肽���ƕ\�������B
�@�E1980�N7���A�W�̂Ȃ��Ԃ��ؔ��ɓ��������h��̃P���ʂ��q���㎍�I�u�W�F�W�r�ɏo�i�����B
�s�k�t���l�͋g���̃P���ʂɂ��ď����Ă��Ȃ��̂ŁA�F�V���F���s���i�t1968�N2�����ɔ��\�����q���ʍl�r�\�\�����炭�g�����̌��ʂɌ��y�����ł����������̕��́\�\�̑O���������B
�@���l�̋g��������A������A���������ʂ��Ă����������B�������a�\�Z���`�قǂ�����A���F���h��������Ȍ��ʂł���B���N�����������ɑz���o������A����͊��������Օ��ł���B
�@���̕���Ȃǂ́A���ʂƌ��킸�ɁA�����m�����n�{�[���Ə̂��Ă����B�吳����ɁA�����������O�ňꎞ���s�������Ƃ�����炵���B�������������w���̍��A�܂�x�ߎ��ς̎n�܂肩�������a�\�N��ɂ��A���ʂ͎q���̂������ɑ傢�ɗ��s���Ă��āA�Z��ɏo���Ȃ��J�̓��̋x�ݎ��ԂȂǁA���Â������̂Ȃ��ŁA�j�̎q���������Y�{���̍����Ђ傢�Ђ傢�������Ȃ���A������Ɍ��ʂ̋��𑀂��Ă����悤�������B
�@���̗V�тɂ��R�c�������āA�����グ�������Ƃ߂�Ƃ��A�G���Ȃ��A�������Y�~�J���ɏ㉺�ɓ������Ȃ���ΐ�ɑʖڂȂ̂ł���B���͏��N����A���������V�т���肾��������A�Y��Ă����g�̂̋L���������܂��Ăт��ǂ��A���ł́A�����ď\������ɓ���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@�Ƃ���ŁA�g������ɂ������������ʂ́A���̎q���̍��̌��ʂƂ͊�炩�`������Ă��āA�ǂ���炱��̓��[���b�p�̌Â��`�̂��̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����q���̍��Ɏg�������ʂ́A���傤�ǖ݂����n�̂悤�ɁA�\���`�ɂȂ��Ă��āA������M���O�������B�܂����������̌���_�̐�[�ɂ͂߁A���ꂩ�狅�𗎂����ɁA���X�ɎO�̎M�ɎĂ䂭�������A�������́u���E����v�ȂǂƌĂ�ł����B�_�̐�[�ɉ��M�̃T�b�N���͂߂āA��������₷���悤�ɂ��Ă���҂������B
�@���A���̎���Ƃɂ��錝�ʂ́A����Ƃ͈���āA�\���`�̉��̂Ȃ��A�C��̂悤�Ȍ`�̂��̂ł���B������A������M�͈�����Ȃ��B������݂Ɂw��\���I�����[�X���T�x�������Ă݂�ƁA��͂蓯���`�̐}���o�Ă��邩��A���Ԃ�A���ꂪ���[���b�p�̌Â��`�Ȃ̂��낤�ƍl������B�i�F�V���q�ҁE��n��ʐ^�s�F�V���F �h���R�j�A�E���[���h�k�W�p�АV�����B�W���A���Łl�t�W�p�ЁA2010�N3��22���A�ꎵ�Z�`�ꎵ���y�[�W�j
��L�̇@�`�E�̃P���ʂ��ǂꂩ���l����ƁA�����u�P���ʁv�ł͕���킵���̂ŁA�q���ʍl�r�́u�����{�[���v�Ɓu�r���{�P�ibilboquet�j�v�i�ȗ����������̌㔼�ɏo�Ă���A�u�\���`�̉��̂Ȃ��A�C��̂悤�Ȍ`�́v�P���ʂ̃t�����X��j�Ƃ����������ɋ�ʂ��ČĂׂA
�@�@�����{�[��
�@�A�����{�[��
�@�B�r���{�P
�@�C�r���{�P
�@�D�r���{�P
�@�E�����{�[��
���낤�B���́s�T���v���C�{�[�C�t�̋L����ǂ�ňȗ��A��n�B�����s�F�V���F �h���R�j�A�E���[���h�t�̎ʐ^������܂ł�30�N�ȏ�A�g�����f��║��ŃP���ʂ����������肽���ƕ\�����Ă������̃P���ʂ��Ă�����u�����{�[���v���Ǝv������ł������i�����j�A����͂ǂ��l���Ă��u�r���{�P�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��i�s�T���v���C�{�[�C�t�f�ڂ̎ʐ^���A�悭�ς�r���{�P�ł���j�B�ł́A1967�N����1968�N���߂܂łɂ͓��肵�Ă����r���{�P�i�ЂƂ͎��g�̂��߂́A�����ЂƂ��F�V�ɑ��邽�߂́H�j���A�g���͂ǂ��Œ��B�����̂��낤���B����Ƃ����̂��A���Z�p�̂��̂��܂߂āA�����{�[���^�̃P���ʂ͎��鏈�Ŕ̔�����Ă��邪�A�r���{�P�͍����ł��ɂ߂Ē��������炾�B�Ƃ���ŁA�`���ɋ������F�V�́q�g�����̒f�́r�ɂ̓P���ʂ�����g���̎p�������[���`����Ă���B
�@���͐��N�O�ɁA�g������傫�Ȍ��ʂ�����������Ƃ�����B�ǂ������o�܂���A�g�������Ɍ��ʂ�����邱�ƂɂȂ����̂��A���ł͑S�����O���Ă��邯��ǂ��A���܂��Ɏ��̊��ɂ��肠��ƏĂ����Ă���̂́A���̌��ʂ𑀂�g������́A�܂��ƂɑN���Ȏ���ƁA���ӑR�Ƃ������̏���Ȃ̂ł���B
�@�E�����y������O�ɓ��ݏo���A�E��Ɍ��ʂ̕�������A���̐�ɂ����d�����̂̉��S�͂����܂����p���āA����ɋ��̂��ԁ[��Ɣ���]�����Ȃ���A�Ƃ��������̐�[�ɁA���̂��������̂����ۂ�Ƃ͂߂��ދg������̋Z�p�����A�S���S���A�܂��ɐ_�Z�ƌĂԂɂӂ��킵�����̂������B
�@���͂��̂Ƃ��A���̌��ʂ𑀂鏬���ȃ��}���X�E�O���[�̎��l�̎p�Ɠ�d�ʂ��ɂȂ��āA�ڂ̂��肭�肵���A������������܂����ȁA�����炿�̋g�����N�̎p��������ł���̂��A�@���Ƃ��������������B�吳���N���܂�̋g�����N�́A�����̒����𒅂Ă����낤���B����A����ς蔼�Y�{���̗m�����낤�B���ʂ���łȂ��A�ނ̓����R�ɂ��x�[�S�}�ɂ��A�����݂Ȏ���݂��������ɂ������Ȃ��B�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j
���͍K�^�ɂ��ӔN�̋g������Ɖ��x�����b������@��������Ƃ��ł������A��������a�J������X���������߁A�P���ʂ��I���Ă��炤�悤�ȏł͂Ȃ������B������c�O�Ɏv���B�����A�g���͐e���������N�ɂł��P���ʂ��I�����킯�ł��Ȃ��������B
�Ə������̂͋g���v�ȂƐe��������������������b�q�����A�����g���̃P���ʂ������̂��ǂ����A�������炾���ł͂킩��Ȃ��B�P���ʂ��������Ƃ̂Ȃ��l�Ԃ����̖��Z�ɐڂ��Ă��{���̂��肪���݂��킩��Ȃ����߁A�g���͂ނ�݂ɐl�Ɍ������肵�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�s�k�t�̓��l�������F�V���F�͌��Ă���B�s�T���v���C�{�[�C�t�̋L�ҁi�ƃJ�����}���j�����Ă���B���܂݂��邱�Ƃ͂Ȃ��������낤���A�ˊя��m���ؕx�v�▟��Ƃ̑�c�䂤�ɂ͌������ɈႢ�Ȃ��B�y���F��푺�G�O�ɂ������邾�낤�B���ɂ͌����Ȃ�������������Ȃ��B�n�ɂ����Ȃ��A�P���ʂ����܂�����Ȃ��悤�Ȏ҂Ɏ����̉^�������I����ɂ͋y�Ȃ��B�����A����ƂȂ�Θb�͕ʂ��B�q��́r�i�C�E13�j�ɕ`���ꂽ�^�����́A��n�͂�������A�����đ_�����O�����Ƃ̂Ȃ��P���ʂ̐_�Z�ɒʂ�����̂�����B����́A�����甭�����|�낵���܂ł̋Z���B�y���F�̑��V�ψ����߂��F�V���F�ƂƂ��ɁA���̂Ȃ��̓y���Ɏ��U�����g���������̐��I�̃K�L�叫�ɑ��ĕ����Ă����������A����ɓ������낤�B�y�������̉^�����ɐk�������u�����v�ȍ~�̋g���́A���t�ƌ��t������̂̊ԁm���킢�n�ɕ��������Ă䂭�B�y���F�i1986�N�f�j���F�V���F�i1987�N�f�j�̂��Ƃ�ǂ��悤�ɂ��Đ������g�����̊��ɂ́A���H�̏W�s�Ԋ~�t���[�߂�ꂽ�B������_�Ȃɂ��[�߂�Ƃ���A���p�̃P���ʁi�����{�[���ł͂Ȃ��A�r���{�P�j�����Ȃ��B�����Ńt�����X�̔�]�ƃ��W�F�E�J�C�����́s�V�тƐl�ԁt�������Ă������t��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B�J�C�����͂��́q�܁@�V�т��o���_�Ƃ���Љ�w�̂��߂Ɂr�ł��������Ă���B
�g�������ӂƂ����u���[���[�A�����R�A�P���ʁA����A�x�C�S�}�̃K�L�V�ь�v�̗R���͑[���Ƃ��Ă��A�����Ƌ|�A�|�A����A�Γ�����⌝�ʁA�Ɗy�Ƃ̗މ��͖��炩���B�G�X�L���[�̌��ʗV�т��t�������ŁA�u���̗����͎��ɍs���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����w�E�́A���̊Ԃɂ������̌��ߓ_�������u����g�������v�̖����w�I���E�ɘA�q���Ă��悤�B�Ƃ���Łs���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j��1939�N4��3���̏��ɂ́u�J�B������{�����֍s���B�u�]���v�̃W�����E�M���o���͑f�������B�ƂȂ�̏��w���������Ă����B�O�͊����ӂ邦���v�i�����A��܃y�[�W�j�ƌ�����B�g���͂����ł����炭���߂ăr���{�P���ς��B������P���ʂƔF���������ǂ����킩��Ȃ����A�K���Ȃ��Ƃɏ��ї��V�E�R�{����s�f��ēW�����A���E�f�����B���B�G�t�i�������s��A2010�N11��1���j�ɁA���N�̓��{�ł́s�]���t���蓖���̔ѓc�S���ɂ��]�����^����Ă���i�����A��l��`��܁Z�y�[�W�j�B
�u���̉f��Ɍ����閣�͂́A�܂��S�̂��^�Ԙb�p�̍I���ł���B�V�[�N�G���X����V�[�N�G���X�Ɉڂ鏇���A�l���̌J��o�����A���ꂪ�ނƂ��Ă��Č����Ȃ��قǂ̍I���Ō����B�������V�i���I�̂悳�ɂ��˂�̂ł��낤���A�����ɂ�����f�����B���B�G�͏]���̔ނƂ͕ʐl�̊�������B����ɉ����Ďʎ��I��@���������J�b�g�y�я�����̎g�������A�e��ʂʂ�����̂ɂ��Ă���B�k�c�c�l�ŏ��̖��{�X�J�X�o�̏Љ�A���W�X�E���̏�ɂ�����s�G���̏o�����A�����s�A�m�̉��A�q���̈�l���₦����ɂ���ؐ��ߋ�A�㔼�̘V���ƃ��R�[�h�ȂǁA�����܂ʼn��o�͂��͂��A�������h�Ȃ��̂ł���B�����ɂ́A����܂ł̃f�����B���B�G��i�̂悤�Ȉӗ]���ė͑��炸�A�Ƃ����Ƃ��낪�Ȃ��B���ׂẲ�ʂ͔ނ̕\���������̂��[���ɕ\���Ă���̂ł���v�i�k�c�c�l�͓����j�B
�u�q���̈�l���₦����ɂ���ؐ��ߋ�v�Ƃ́A���{�̃P���ʂ̂悤�ł���Ȃ��炻��Ƃَ͈��Ȃ�����́��r���{�P�𐳊m�ɕ\�����邽�߂̋���̍����B
�k�NjL�l
�g�������������s�y�y�E���E���R�i�]���j�t�̃P���ʂɂ��āA�N�������Ă��Ȃ����ƃE�F�u������������Aant's PUZ-T�����q�f��w�]���x�ƁA����ʁr�Ƃ����L�����A�b�v���Ă����B
������6�����Ƃ���ƁA�g�����W�~�C�i�K�X�g���E���h�j�̖�����肽�������̂́A�����Ȃ琬����100�p�[�Z���g������A�i�ē≉�o�Ƃ̈ӂɏ]���āj�������������̂͂���̕����A�Ƃ������M�����������߂��B�T���O���X�p�̋g�������f���Ɏ��߂��Ă�����A�������F�V���F�̎ʐ^�Ƃ��������������̂ɁA�ɂ������Ƃ������B�E�F�u�Ō������āA�悤�₭�w�������r���{�P�i�������j�̎ʐ^���Ō�Ɍf����B���̃t�����X�Y�̃P���ʁA�A���e�B�[�N�V���b�vunikk��5,000�~�������B���F���������C�̖ؐ������A�����Ƌ�ɂł��g��ꂻ���Ȃ��̍ގ��������A���ɂ͔���Ȃ��B�Ȃ�ƂȂ��A���̎����ƌ`�Ԃ������C�Y�E�j�[���F���X���̔p���|�p�m�W�����N�A�[�g�n��A�z�����B�f�X�N�ɒu���Ē��߂Ă���ƁA�n���V�̂悤�ɂ��A�������̂悤�ɂ������Ă���B���Ȃ݂ɃP���ʑf�l�̎����g���P���ŋʂ��P���ɓ����܂łɁA25���v�����B����Ńt���P�����s�@�����߂�̂́A����̋Z�ȏ�̂��̂�����Ǝv���B
�{�e���̂��]�k�̂悤�Ȃ��̂�����A�ǂ��ł�߂Ă��悢�̂����A���łɋL���Ă����������Ƃ�����B�F�V���F�Ɖf��s�]���t���߂����ł���B���F�̖��E�K�q�͏o���T�O�̃C���^�r���[�ɂ��������Ă���B�u�k���F�́l�t�����X��́A�܂������֗���O�́A��m���̂�������̉Ƃɂ��鍠����n�߂��B�Ƃ����͔̂�c�]�l�Y�i�{���E�P�c�Òj�j�Ƃ����f��̃X�[�p�[�C���|�[�Y������Ă��邨�����ׂɂ�����ł��B��c�]�l�Y�Ƃ�������A���̍��̃X�[�p�[�̑��l�ҁB�y�y���E���R�k�}�}�l�́w�]���x�Ƃ��A�w�V��V�~�̐l�X�x�Ƃ������A�Ƃɂ������̎�̌Â��t�����X�f���S�����l�v�i�q������݂��Z���F�r�A�w�F�V���F�S�W�x�ҏW�ψ���ҁs��z���F�V���F�t�͏o���[�V�ЁA1996�N5��24���A�l�Z�y�[�W�j�B����𗠕t����悤�ɁA���O�[��s�����̖��H�\�\��c�]�l�Y�ƃt�����X�f��t�i�����ЁA2011�N4��15���j�ɂ́A�F�V���F���]�l�Y�̍Ȃ䂫�Ɨ��F�̖������i�ЂƂ�͍K�q�j�Ƃɋ��܂�āA�r��g�݃X�e�b�v�ގʐ^���f�ڂ���Ă���B�u�����A�Ќ��_���X�����s���Ă��āA�_���X�����ӂ������䂫�͎؉Ƃ̃t���A�ŋߏ��̎�҂����ɋ������肵���B���̂Ȃ��ɗ��F�₻�̖��������������Ă����v�i�����A���Z�y�[�W�j�B�F�V���f��s�]���t�Ɍ��y�������͂����邩�ڂ炩�ɂ��Ȃ����i�B��A�g�s�~�V��ɐG�ꂽ�q�I���O�N�ځc�c�r�ŁA��c�]�l�Y�̐l���Љ�ƂƂ��Ɂs�]���t�����������ɏo���Ă���̂��ڂɗ��܂����j�A�g�����l�A��c�]�l�Y��������t�����s�]���t���A�킯�Ă����̃P���ʂ̃V�[�����O�����A�ǂ����̉f��قŊςĂ���ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�������������c�u�c�ɂ͓��{��̎����X�[�p�[�̃N���W�b�g���Ȃ��āA�N�̎�ɂȂ���̂��킩��Ȃ��B

�E�F�u�Ō������ăA���e�B�[�N�V���b�v����w�������t�����X�Y�̃P���ʁu�r���{�P�v�B�w�i�̎ʐ^�́A�O�f�s�F�V���F�h���R�j�A�E���[���h�t�����A�q���ʍl�r�����肵���q���ʁr�i�ʐ^�F��n��j�̂��̂ŁA�L���v�V�����Ɂu���l�E�g�������瑡��ꂽ�A���M�̂Ȃ����ʁB�v�i�����A�ꎵ���y�[�W�j�Ƃ���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j1932�N�A�����掛�����ɐ��܂ꂽ����Ƃ̑�c�䂤�́A1968�N�A�s�K���t�Ɂq��������杁r�̘A�ڂ��n�߂��B���̐}�q�ʂ̈�G���q�r�i���o�́s��������t1970�N��11���j�̔��G�ɂ́A�����{�[������ɂ������q��������杁r�̎�l���L���V��L���V�̕�e�i���^�⊄�B���p���g�����̕�e��f�i������j�ȂǂƂƂ��ɁA���̃g�R�i���j�ɍڂ����x�C�S�}���`����Ă���B

��c�䂤�q�ʂ̈�G���q�r�̔��G�i�s��c�䂤�W�k��Q�� ���㖟�� �E�l�t�}�����[�A1971�N1��30���A�k��y�[�W�l�j
�u���̐�[�̓ˋN�����ɋ��̌���˂����ĂėV�ԂƂ������ʂ́A���Ƃ��w��������杁x�ł͉����Ɉ������c�䂤�̍�i���E�ɓƓ��̃m�X�^���W�A��Y����I�u�W�F�v�i�l���c���F�s���挴�_�k�����܊w�|���Ɂl�t�}�����[�A1999�N4��8���A���Z�y�[�W�j�ł���A�q��������杁i��j�r�����߂��s��c�䂤����فk��ꊪ�l�t�i�}�����[�A1992�N8��20���A�����F���c�i�j�̃W���P�b�g�ɂ́A�\�\���ɖ��|���̓����{�[���́A���\���Ƀx�C�S�}�Ƃ��̕R�̎ʐ^���A�����|�C���g�ŃJ�b�g�̂悤�ɂ�������Ă���B�Ȃ��A�g���ɂ͐��z�q�x�C�S�}���l�\�\���N����̂ЂƂ̑z���o�r�i���o�́s��t1983�N7�����j�������ās���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�ɂ����߂��Ă��邪�A�����ɃP���ʂ͓o�ꂵ�Ȃ��B
�i�����j�F�V���F�����̃r���{�P���ŏ��Ɍ��J���ꂽ�̂́A�s�F�V���F�S�W�k��4���l�t����4�A�͏o���[�V�ЁA1993�N9��3���j�̕���G�E�O����v�k�C���^�r���[�l�i������E�o���T�O�j�q���w�Z����̂��Ɓr�̕\���Ɍf����ꂽ���m�N���ʐ^���낤�B���ʐ^�̃L���v�V�����ɂ́u�F�V���F���D�̃��[���[�i���j�ƃR�}�i���j�ƃP���_�}�i�E�j�B�P���_�}�͋g�����̃v���[���g�B�u�g������̓P���_�}����Ϗ��ł����v�i�k���q�l�v�l�k�j�B�v�i������A��Z�y�[�W�j�Ƃ���B���ʐ^�͑S�W������W�������w�F�V���F�S�W�x�ҏW�ψ���ҁs��z���F�V���F�t�i�͏o���[�V�ЁA1996�N5��24���j�ł͉P�䐳���q���w�Z����̂��Ɓr�̃J�b�g�Ƃ��Čf������Ă��邪�A�L���v�V�����́u���D�������[���[�A�R�}�A�P���_�}�v�i�����A�Z�܃y�[�W�j�Ɗȗ��ɂȂ�A�g�������������Ƃ͋L����Ă��Ȃ��B
�i�������j�苖�̃r���{�P�́A�P����ɋʂ��h�����ʐ^�̏�Ԃō�����21cm�A�ʂ̒��a�͖�9cm�A�P���̍����͖�16.5cm�i�F�V���F�́q���ʁr��s�T���v���C�{�[�C�t�̋L���̎ʐ^�ɏƂ炷�ƁA�g�����g�����r���{�P���������������傫���̂悤���j�B���̒��a�͖�3.5cm�B�S�̂̏d���͖�380g�B
�������Y�E�剪�M�E�������ďC�s���㎍�厖�T�t�i�O�ȓ��A2008�N2��20���j�́A�`�T���E�㐻�@�B���E�{��12.5���E�O�i�g�E832�y�[�W �i�ҏW�ψ��F��ˏ���E��������E������q�E�V���G�E�����P�E���Y�ÁE�{��^�f���E�a�c�����j�B�����́q�g�����r�̍��͕ҏW�ψ��ł������V���G�����M���� ���āA�g���̗����͖{�T�C�g���s�q�g�����r�l�ƍ�i�t�Ɍf���Ă���B�܂�s���㎍�厖�T�t�̋L�ڂ����������킯�ŁA�������̂�
�@�앗�i25�s�j
�@���W�E�G���i6�s�j
�@�]���E�����j�i4�s�j
�@��\���ӏ܁i20�s�j�k�̂肠����ꂽ���т́q�Õ��k��͂��������������ɂ���l�r�l
�@�Q�l�����i7�s�j
�ł���B������37�s�ɑ��āA���������͌v62�s�A�S�̂�99�s�ɂȂ�B���Ȃ݂ɋg���Ɖ��̐[���k�����H��208�s�A�����t�v��100�s�A���e�� �O�Y��203�s�A����C����105�s�B�������Č���ƁA���H�Ɛ��e��200�s�A�t�v�Ƒ���i�Ƌg���j��100�s�Ō��e���܂Ƃ߂�悤�Ɋ�}���ꂽ�Ǝv�� ���B���āA�{�e�̕W��ł��铯���T�̐l�������͋ߌ��㎍�̌����ҁE�D�c�돺�̍쐬�ŁA
�Ƃ���B�����́u696�v�͌��o����������Ă���A�����܂ł��Ȃ��V���G���M�́q�g�����r���w���i�Ȃ��A�V�́q�앗�r�q���W�E�G���r�Łu�����v�Ƃ� �ās�����G�߁t�s�t�́t�A�u�O���v�Ƃ��ās�Õ��t�s�m���t�A�u�����v�Ƃ��ās�a���`�t�s�Â��ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�A�u����v�Ƃ��ās�T�t�����E �݁t�A�u�ӔN���v�Ƃ��ās�Ẳ��t�s��ʁt�s���[���h���b�v�t�̊e���W�������Ă���j�B���̃m���u���̌��o����͎��̂Ƃ���B
�@46�F�ѓ��k��
�@375�F����Z�N��̎�
�@378�F��㎵�Z�N��̎�
�@379�F��㔪�Z�N��̎�
�@728�F�k
�q�ѓ��k��r�ł́A�q�k�r�֘A�Ƃ��ċg�����̖����o�ꂵ�Ă���B�q�k�r���l�̑��̃����o�[�A�q��c�G�r�q�剪�M�r�q������s�r�ł͂ǂ�������Ă��� ���B��c�̍��ɂ́A�q�k�r����݂ŋg�����o�ꂵ�Ă���i�剪�Ɛ����̍��ɂ́q�k�r���g�����o�ꂵ�Ȃ��j�B�Ȃ����̂悤�Ȏ��ԂɂȂ����̂��B�{���T�̑O�t�� �́uXML�f�[�^����v�uXML�g�Ńv���O�����쐬�v�Ƃ����N���W�b�g�����邩��A�l���������쐬����ߒ��Ŗ{������u�g�����v��ԗ��I�ɒ��o����A�� �R�͐����Ȃ��͂����B�ɂ�������炸�A�����ƃy�[�W���J���������ł��A�ق��ɂ��u�g�����v�̐l����������R��Ă��鍀�ڂ�����������B�ȉ��Ɋ�c�̕��� �܂߂Čf���A�k�@�l���ɋg���Ƃ̊֘A�𗪋L����B
�@59�F���l�ƐE�Ɓk�����Ɓl
�@87�F��c�G�k�q�k�r�l
�@187�F��ˎ闝�k�s��S�t�l
�@195�F�����k���l�l
�@202�F�ߑ㎍�k���M�ҁl
�@296�F���Ɣ�]�k�Q���l
�@338�F���I�k�����l�̘_�l
�@490�F�߉ϑ��Y�k�s�����C�J�t�l
�@691�F�����C�J�k�q�����r�l
���̂Ȃ��Łq�ߑ㎍�r�̍��i���M�͓��C�I�q�j�Ȃǂ悭�܂Ƃ܂��Ă��邪�A�l�������̋g���Ŋ֘A�Â����Ă��Ȃ�����ł́A�g�����ɊS�����ǎ� �����̍���ϋɓI�ɓǂނ��ǂ����A�^�킵���B�����킢���͔ӔN�̋g������u�s�ߑ㎍�t�ɖ����s�̎��т\���Ă���v�|�̃n�K�L����������i�� ��A�T���Ă݂Ă���Ƃ����Ӂj�A���{�ߑ㕶�w�قŁq��ȁr�i�������сE8�A���o�͓���1959�N10���k27���l�j���{�����āA��i�N���ɍ̘^���邱�Ƃ� �ł����B�Ƃ��ɁA�����T�̃������[�Ŏ��M�҂̕Ό����w�E���鐺�����������A�����̕肪�������Ȃ��ȏ�A�l���⎖���̍����Ƃ��������\����Րɂ��� �����A�ǎ҂ɗL�������킹�ʌ`�Ŗ{���̉��l��F�߂������ł��낤�ɁB���������ϓ_���猩��ƁA�q�l�������r�̖}��Ɂu�y���o����z�ȊO�̐l���E�������ڂ� ���ẮA�L�q�̓��e�ɉ����ēK�X�f�o�����B�v�i�{���A�k��t�l��y�[�W�j�Ƃ���̂́A�����ɂ������Ƃ��炵�������������A�o���ɂ��݈ȊO�̂Ȃɂ��̂ł� �Ȃ��B�{���Ƃ����ő�̎��Y�������������Ă��Ȃ��̂��B���̈ꎖ�������Ė{���Ɂu�H��v�Ƃ��Ă̋y��_�͗^�����Ȃ��B�����A�s���㎍�厖�T�t�̖{���� �J��ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�l���E�����̍��ڂ��S�̌��іڂɂȂ�̂Ȃ�A��������Ԃ�D�肠���Ă������Ƃ͓ǎҊe�l�ɉۂ���ꂽ������`������ ���B���͓n粍_�j���M�́q���|�Ę_�r�̍��������[���ǂB�g�����̎�N�̎��ɑ傫�ȉe����^�����G���Ƃ��āA�������L�����Ă������炾�i�g�����s�����G���t���s�t铁t�̏o�ōL�����s���|�Ę_�t�ɏo���Ă���j�B�g�����ߓ����i�k�����q�⍶�삿���Ɠ�������ɓǂA�Ǝ��Ɍ�������Ƃ�����j��؉��[���Ȃǂ̐V�i���l���������̂́A���́s���|�Ę_�t����ł͂Ȃ����낤���B
��
�����ȍ~�̎�v���W��35�y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ����t�^�̏����ҁq�߁E���㎍�N�\�r�́A�u�{�N�\�̍쐬�ɂ������ẮA��Ɏ��̎������Q�l�ɂ����v�i�{���A���l�܃y�[�W�j�Ƃ���
��5�_�̔N�\�������Ă���i�k�@�l���̔N���͔N�\�̑Ώ۔͈́A�����͏����I�Ɋȗ��ɉ߂����̂ŕҎҁE�o�ŎҁE�o�ŔN���������j�B����ɓ���
�������āA�g���̐��O�Ɋ��s���ꂽ���ׂĂ̒P�s���W�\�\�@�s�����G�߁t�i1940�j�A�A�s�t�́t�i1941�j�A�B�s�Õ��t�i1955�j�A�C�s�m���t �i1958�j�A�D�s�a���`�t�i1962�j�A�E�s�Â��ȉƁt�i1968�j�A�F�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�A�G�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�A�H�s�Ă� ���t�i1979�j�A�I�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�A�J�s��ʁt�i1983�j�A�K�s���[���h���b�v�t�i1988�j�\�\�̌f�ڂ̗L�����}�g���N�X�� ���Ă݂�i���͌f�ځA�~�͔�f�ځA�\�͔N�\�̑Ώ۔͈͊O�ł��邱�Ƃ�\���j�B
| �@ | �A | �B | �C | �D | �E | �F | �G | �H | �I | �J | �K | |
| �i�A�j | �\ | �\ | �� | �� | �� | �� | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| �i�C�j | �~ | �~ | �� | �� | �� | �~ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| �i�E�j | �~ | �~ | �� | �� | �� | �� | �~ | �\ | �\ | �\ | �\ | �\ |
| �i�G�j | �~ | �� | �� | �� | �� | �~ | �~ | �� | �~ | �~ | �� | �~ |
| �i�I�j | �\ | �\ | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �~ | �� | �� |
| �i�J�j | �~ | �~ | �~ | �� | �� | �~ | �~ | �� | �� | �~ | �� | �� |
�i�J�j�́s�Õ��t�̈����ɕs�����c�邪�A�܂��͉����ȏ����낤�B�u�R�{�́w�����吳���������x�Ƃ����{�������ɘJ�삾�������悭����B�Ȍ�A�� �a���ɂ��̌�p�I���̎�̏����̂Ȃ��̂��A�o�ł̓_���̐��{�ɂȂ������a���ł͂ǂ�Ȃɓw�͂��Ă��A�R�{���̘J��̐����ɂ͂Ƃ��Ă����B�ł��Ȃ��Ƃ����\ �������邩��ł��낤�B���ƂɁA���A��������a�O�\�N��Ȍ�ɂȂ�ƈ������ς�A���X�Ǝ����{�̎��W�����s�����B���������ςɌ��Ă����ϖ��N��Z �Z�Z�_�����邾�낤���v�i����a�C�q�u�N�\�v�쐻�̗J�T�r�A�s��㎍��n�W�t����S�A�Z�y�[�W�j�B���T��N�\����s���鎑����������̂́A�P�ɋV���̂� �̂ł͂Ȃ��B�������ǂ��]���������Ƃ������m�Ȉӎv�\���ł���B
 �@
�@
�������Y�E�剪�M�E�������ďC�s���㎍�厖�T�t�i�O�ȓ��A2008�N2��20���j�̔��i���j�Ɓs�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�Ɓs���㎍�厖�T�t�̔w�i�E�j
�g�����̎��тɓ�����̓��{�l�̌ŗL�������o�ꂵ���̂́A�掵���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j����ł���B�q�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�j�Ɂu�r�c�����v�̔ʼn�̑薼���S��āv�A�������q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�Ɂu�y���F�̔�V�ɂ悹�āv�Ǝ����ɂ���̂����ꂾ�B����A�T���̂���g�������Ƃ������ƂɂȂ�A���p���̂Ȃ��s�a���`�t�i1962�j�́q���̕a�C�r�i�D�E11�A���o��1959�N11���́s�k�t4���j�A���p���̂���P�s���W�����^�̒����q�g��i���Ɏ~��r�i���o�́s�����C�J�t1960�N6�����j�������Ě���Ƃ���B���p���Ɋւ��ẮA�g���z�q�ҁq�N���r�i�s�g�����S���W�t�}�����[�A1998�A�����y�[�W�j�ɂ�������B
�s�g�����S���W�t�����ɓǂ�ł����ƍŏ��ɏo��u�@�v�i�ꊇ�ʁj���̎���́q��q�r�i�F�E15�A���o��1972�N8���́s�����t29���j������A�N���̋L�ڂƕ����āA���̓o���1972�N�ƌ��Ă悢�B�ȉ��Ɍf�ڂ��鎍��̍s���̎����̐����́A07�����W�̏������A15�����Ԃ߂̎��т��A037�����s�߂���\���B
�s�_��I�Ȏ���̎��t�ȍ~�A�g���̎��ɂ͎��̑薼�̌�Ɏ����A�q�@�r�i�R���ʁj��u�@�v��i�@�j�i�ۊ��ʁj�Ŋ������͋�܂�莫�m�G�s�O���t�n�Ƃ��̍�Җ��A���������p����A���̖{���̌�ɒ��L�A�o�T�A�����p�o����i�Ȃ��A�s�t铁t�ɕ���A�s�Õ��t�Ɓs�m���t�Ɍ����A�s�a���`�t�Ɓs�Â��ȉƁt�Ɏ������U�����邪�A�{�e�̌����ΏۂƂ��Ȃ��j�B����������
�@����
�@�莫�m�G�s�O���t�n�Ƃ��̍�Җ�
�@����
�@���L
�@�o�T
�ɕ����āA�S���W�̓o�ꏇ�ɋ�����B���̑薼�̌�i�\�\�ɑ����ĕ\���j�Ɩ{���̌�i�A�L�ɑ����ĕ\���j�ɕ����̂��鎍�т��A���ꂼ��Y������敪�Ɍf����B
����
�q�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�j�\�\�r�c�����v�̔ʼn�̑薼���S���
�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�\�\�y���F�̔�V�ɂ悹��
�q�T�C�����g�E���邢�͍��r�i�G�E25�j�\�\����r�q�̉�������q�T�C�������m���₯�n�r�Ɋ�
�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�\�\�F�V���F�̃~�N���R�X���X �����e�j�������v�̂���
�q���܂�����r�i�G�E30�j�\�\�k�������h�s����t�̈�ێ���
�q�ٖM�r�i�H�E5�j�\�\�փ��}���E�Z���G���g�̊G�ɂ悹��
�q�g�ҁr�i�H�E18�j�\�\�}��b�̂��߂̑f�`�̎�
�q���̃A�X�e���X�N�r�i�H�E22�j�\�\���q���`�̊G�ɂ悹�� ���@�A�X�e���X�N������p���`�̂���
�q���q�A���r�i�H�E25�j�\�\����Y�̕����q���E�A���փ��`�[�i��r�Ɋ�
�q�s���r�i�J�E6�j�\�\�}�b�N�X�E�G�����X�g�Δʼn�W�Ɋ�
�q���́r�i�J�E13�j�\�\�Ǔ��E���e���O�Y�搶 �����͂͐��e���O�Y�w���w�x��菴�o�����B
�q��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�r�i�K�E17�j�\�\�F�V���F�������� ���F�V���F�Ƃ��̒m�Ȃ����̌��t�����p���Ă���B
�莫�m�G�s�O���t�n�Ƃ��̍�Җ�
�q������܌�b�сr�i�G�E8�j�\�\�q�n�����Ŕ҂������Ȃ�r�y���@�F
�q�����r�i�H�E6�j�\�\�q���̛̂s�ޖ��͂��ɑ��l������߂Ă���r������b�q
�q���̖��{�r�i�H�E9�j�\�\�q�ڂ͎��Ƌ��ɐÎ~����r�r�c�����v
�q�`�͕s���̉s�p�������c�c�r�i�H�E11�j�\�\�q����̏��L�҂͗J�D�Ƌ����ɐS��I�܂��r�ѓc�P��
�q���J�̎p������r�i�H�E14�j�\�\�u�ڂ��̓E�j�Ƃ��i�}�R�Ƃ��q�g�f�Ƃ������^�������Ƃ炦�����̂��^�����͂���瞙�瓮���Ɏ��Ă���v�^�ѓ��k��k�^�͉��s�ӏ��B�ȉ����l
�q�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�\�\�u�C�}�[�W���͂����������ց^�������܂������Ɂ^�Ӗ��������Ƃ���v�^�{��~
�q�u�Ɣ�������v�r�i�H�E27�j�\�\�u�����̂Ȃ��ɔ�т��ނ͍̂����v����C��
�q�~���̓����r�i�H�E28�j�\�\�u����Ƃ������̂͌ő́^���ł���Ɠ����ɔg���ł���v�^�剪�@�M
�q����r�i�J�E17�j�\�\�i���t��@���̒��莩��̖��傹��j�@�h���ɒj
�q���ׁr�i�K�E6�j�\�\�i�l�`�͔�������j�\�\�l�J�V����
�q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�\�\�q�_�̌���ՏI���Ă���r�\�\�y���F �����̍�i�́A�����ɓy���F�̌��t�̈��p�ō\������Ă���B�܂��ނ̗F�l�����̌��t����A�⏕�I�Ɏg�킹�Ė���Ă���B�Ȃ��`���̃G�s�O�����́A�ނ̎����ł���B
����
�q�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�\�\����C������
�q�Ẳ��r�i�H�E20�j�\�\���e���O�Y�搶��
���L
�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�\�\�F�V���F�̃~�N���R�X���X �����e�j�������v�̂���
�q���̃A�X�e���X�N�r�i�H�E22�j�\�\���q���`�̊G�ɂ悹�� ���@�A�X�e���X�N������p���`�̂���
�q�G�̐��r�i�J�E2�j ��������̓`���ɂ���u���m�����n�m���v�i���邭�O���I�ő����������j�B�u�G�m����n�m���v�i�����I�ł��炩���ׂ��ɈÂ������̐��j���ϐ����v�̉���B
�q���ρr�i�������сE16�j ���u���㎍�蒟�v��\���N�L�O���ɐ���Ƃ���i����A�Ƃ̏��c�v�Y���̗v�������݂������A�\�]�N�O�̎����L�q�I�ȑ��e�ɁA��̎�������A�w��ʁx�̎��тƓ����`�Ԃ��ƂƂ̂��A�����ɔ��\����B   �܌����
�o�T
�q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�G�E11�j�\�킪�A���X�ւ̐ڋ� �����C�X�E�L�������q���̍��̃A���X�r���c��������
�q�]���l���V���^�[���̑D�r�i�G�E24�j ���]���l���V���^�[���́u�����ҁv�Ƃ�����ْ[�̘V�l��ƁB���p��́A���W����ژ^���ؗp�����B
�q���r�i�H�E8�j ���@���p��͎�ɁA�G�Y���E�p�E���h�i�V�q�r���j�A�ѓ��k��̏͋���ؗp�����B
�q�����`�r�i�H�E10�j ���x�P�b�g�i�����N���j�A�y���F�Ȃǂ̏͋�����p�����B
�q���́r�i�J�E13�j�\�\�Ǔ��E���e���O�Y�搶 �����͂͐��e���O�Y�w���w�x��菴�o�����B
�q�ØI�r�i�J�E14�j �����p��͂����Ƀt���C�U�[�s���}�сt�i��������ؗp�����B
�q���[���h���b�v�r�i�K�E10�j ���薼�Ǝ�̏͋���i�{�R�t�w�������x�i�x�m��`�V��j����ؗp�B
�q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�\�\�q�_�̌���ՏI���Ă���r�\�\�y���F �����̍�i�́A�����ɓy���F�̌��t�̈��p�ō\������Ă���B�܂��ނ̗F�l�����̌��t����A�⏕�I�Ɏg�킹�Ė���Ă���B�Ȃ��`���̃G�s�O�����́A�ނ̎����ł���B
�q���@�r�i�K�E13�j ���F��M�ꂻ�̑��̏͋�����p���Ă���B
�q��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�r�i�K�E17�j�\�\�F�V���F�������� ���F�V���F�Ƃ��̒m�Ȃ����̌��t�����p���Ă���B
�q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE10�j�\�\�w�f�B���q�����A�W�A�T���L���r
�q�x���r�i�������сE18�j ���F�V���F�Ɠy���F�̌��t�����p���Ă���B
�q�_��r�i�������сE20�j ������C�����̂ق��̏͋�����p���Ă���B
�����ŁA�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�̎��тŁu�@�v�̗p�����Ă��鎍����A�ŏ��Ɍf�����q��q�r�Ɠ����`���œE���Ă݂�i���o�̔��\���ɕ��ׂ��j�B�s�T�t�����E�݁t��I�̂́A�g�������o�I�Ɉ��p��������͂��߂��̂����̎��W���炾����ł���B
�t�i�G�E4�j
���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�j�\�킪�A���X�ւ̐ڋ�
���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�j�\�����`���k�U�����^�̂��߁A���A�L�Ŏ���𐔂����l
����ȓ~�̗��i�G�E6�j
�}�_���E���C���̎q���i�G�E5�j
������܌�b���i�G�E8�j
�w�A���X�x����i�G�E12�j
�T�t�����E���i�G�E1�j
�s�N�j�b�N�i�G�E7�j
�c���i�G�E14�j
�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�j
����̔ӎ`�i�G�E13�j
�ٗ���i�G�E19�j
�G���i�G�E18�j
�s�ł̌`���i�G�E16�j
���f�A���E������Ƒ��i�G�E21�j
�ǎ�̏��i�G�E22�j
�����i�G�E23�j
�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j
����ȉĂ̗��i�G�E26�j
���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j
�J�J�V�i�G�E28�j
����ȓ��ʂ̏H�̗��i�G�E31�j
���܂������i�G�E30�j
���N�i�G�E29�j
�������Č���ƁA�����͋����̈Ӗ��ŗp�����邱�Ƃ̑��������ꊇ�ʂ��A����ɑ��҂̏͋�̈��p�ł̎g�p�ɕς���Ă��������Ƃ��킩��B���p�ł̎g�p�łƂ�킯�����Ȏ��т�
�@������܌�b�сi�G�E8�j�F�y���F�ɕ������Ă���
�@�c���i�G�E14�j
�@�ǎ�̏��i�G�E22�j�F����C���ɕ������Ă���
�@�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j�F�]���l���V���^�[���ɕ������Ă���
�@����ȉĂ̗��i�G�E26�j
�@���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j�F�F�V���F�ɕ������Ă���
�@����ȓ��ʂ̏H�̗��i�G�E31�j
�̎��тł���B�q�c���r�͎��l���g�����`�[�t�ɂ��Ă��邩��A�����ɕ������ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B�q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�ɂ��ẮA�����s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�Łu�@�v���̏͋�̏o�T�����v�s���B�[�i�X�̐_�b�k���p�I���l�t�i���p�o�ŎЁA1970�N12��25���j�𒆐S�ɂ��Ďw�E�����̂ŁA�Q�Ƃ��ꂽ���i���l�ɁA�q�ǎ�̏��r�̏o�T�Ɋւ��Ă��q�g�����Ƒ���C���i2�j�r�ŏڏq�����j�B�ȏ���T�ς��ĉ��߂Ċ�����̂́A�s�_��I�Ȏ���̎��t�ȍ~�̋g�������ɂ�����y���F�́A�Ƃ�킯���̌�^�̏d�v���ł���B
�g�����̈��p���́q������܌�b�сr����n�܂����B�����r�Y�́q���E���邢�͉ār�i�H�E12�j�ɂ��āq�ӏ܁r�i�s�g�����k����̎��l �P�l�t�������_�ЁA1984�N1��20���j�Łu�y���F�̕��͂Ƃ�������^�Ƃ������A�ނ̌��t���Ȃ������琶�܂�Ȃ������낤�A�ƍ�҂͂����B�s���o�̎����I�_���T�[�A�y���F�̏펯�I�_����H���O�ꂽ�Z���e���X�̂��������̎w�W�m���C�t�E�C���f�N�X�n�ӂ��ɒD�����ƂŐ���������i�v�i�����A��O���`��O���y�[�W�j�Ə����Ă���B�c�O�Ȃ��ƂɁA�q������܌�b�сr�́s�g�����k����̎��l�P�l�t�ɍ̘^����Ȃ���������A�q�ӏ܁r��������Ȃ������i�q������܌�b�сr�̑���ɁA���R���p�N�g�ȁq���E���邢�͉ār���̂����Ƃ��l������j�B
�g�����́u���p���v�錾�ł���B�g���̎��I�㔼���͂�������n�܂�B�{�e�̏��߂ɋ����������E�莫�m�G�s�O���t�n�Ƃ��̍�Җ��E�����E ���L�E�o�T�Ɂu�y���F�v���o�ꂷ�鎍�сA���Ȃ킿�q������܌�b�сr�i�G�E8�j���O�́q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�ƁA��́q�����`�r�i�H�E10�j�A�q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�A�q�x���r�i�������сE18�j�Ɍ����銇�ʗނŋ��܂ꂽ��������Ɍf����i�Ȃ��A�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�Ɋ��ʗނ͎g���Ă��Ȃ��j�B
�����`�i�H�E10�j
������ܒf�������i�K�E12�j�\�\�q�_�̌���ՏI���Ă���r�\�\�y���F
�x���i�������сE18�j
�\�\�y���F�͂����ւ�ȓǏ��ƂŁA�g�����̂��킢�ǂݎ�B���̐Ȃł��������Ƃ������B��̓I�ɂ͎v���o���Ȃ��B�S�S��s�̏ł̓���Ȃ��Ƃ���������Ă��܂������̂��̌�^�́A�����o�邾�낤���B�i1985�N5��23���̋g�����̒k�b�j�\�\

�A�X�x�X�g�قɂēy���F�Ƌg�����i1980�N����j�B�k�����܂łɌ��J���ꂽ�B��̃c�[�V���b�g�l
�o�T�F�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�N4��15���A�k��Z�y�[�W�l
�k�t�L�l
�g�{�����́q�����_�r�i1989�N2��22���A�{�f�B�T�b�g���@������������Ás��������̕��Q�t��ꕔ�q�g�[�N�f�B�X�J�b�V�����s���̘_�t�r�ɂ����锭���j�Łu�Ƃɂ������^�t�@�[�ɂ́A�g�傳���ׂ����̂�����B�k�c�c�l�ہi��_�j��������Ă��܂��Ε��͂̃��Y�����܂�ň���Ă��āA�܂������Ⴄ�Ӗ��ɂȂ��Ă��܂����Ƃ����Ă��蓾��B�y���k�F�l����̕��͂Ƃ����̂͂��Ȃ���g�����̎��̂悤�ł�����A�����������Ƃ����Ă������Ȃ��ł���v�i�s�g�{�����q�����^�r�u���W11�\�\�|�p�\���_�t�}�����[�A2015�N10��10���A��l�Z�`��l���y�[�W�j�ƌ���Ă��邪�A��q���]�|���Ă���悤�ŁA�����Ȃ��B�{�e�ŏq�ׂĂ������Ƃ��疾�炩�Ȃ悤�ɁA���Ԃɑ����Ă���̂́u�g�����̎��Ƃ����̂͂��Ȃ���y���F�̌�^�̂悤�ł�����A�v�ł͂Ȃ��̂��B���̂��ƂƁA��т��ċg�������ɋ�_���p�����Ă��Ȃ����Ƃ͕ʂ̖��ł����B
2012�N11��30���\�\�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t���J�݂���10���N�̋L�O�̓��ł���\�\�Ɍ��J�����s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t�i���Y��ԁj�Ɏ����ꂽ�k������4�Łl���쐬�����̂ŁAPDF�t�@�C�������J����B�ȉ��ɓ������̂��Ƃ����q�g�����S���ѕW������k������4�Łl �ւ̒NjL�r�Ǝd�l��^���āA�s�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t�̏Љ�ɑウ��B
�g�����S���ѕW������k������4�Łl�ւ̒NjL���@�s�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t�@2017/1/31�@�yPDF�t�@�C���z�@760KB
2016�N9��20���A30�N���̌��Ă������q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�̏��o�����������B����ŁA�E�F�u�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�\�\���l�E�����Ƌg�����̍�i�Ɛl���̌����t���f�ڂ��Ă���������ЃW���s�^�[�e���R���i�u�����h����J:COM�j��WebSpace�̒���߂邱�ƂɂȂ�A�J�݈ȗ�14�N�̒����ɂ킽��e����ł���URL�Ƃ����ʂꂷ��i�V����URL��http://ikoba.d.dooo.jp/�j�B������@�ɁAPDF�Łs�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t�����J����B�k������3�Łl����̂����ȕύX�_�́A�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�Ɓq�����k���邽��z�N������l�r�̍��̏C���A�{�����̔Ŏ��E���J���̐V�\���ł���B�����炸�{���������q�̂Ƃ��Ĉ�����s�������B�i2016�N12��31���j
�s�g�����S���ѕW������k������4�Łl�t�@���ш�Y�Ҏ[�A���Y��Ԋ��BA5���E�{��64�y�[�W���g�E2�F���B�����ጾ�A���іژ^�A�����{���k�S286�сi�}�����[�Łs�g�����S���W�t�����^��6�т�Ǖ�j�̎��єԍ��E���ѕW��E����E��݂��ȁE�S���W�f�ڃm���u���A���і{���`��1�s�A���ѐߐ��E����̖{���s���E���o�}�̂̏ڍ��E�����^�P�s���W���邢�͕ω��z���������сA���l�l�A�����o�����f�ځB�i2017�N1��31���APDF�t�@�C�����J�j
���H���q���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���o�����L�r�����ǂ݂����������S�~��Y����u�u�͎ʁv�����A���߂łƂ��������܂��B�g�����ƁA�ނ��C���f�b�N�X�Ƃ���ߑ���{�o�Ŏj�S�̂̋M�d�Ȓm���ƁA���̕��@�_��ɂ��݂Ȃ����J���ĉ�����A�S��芴�ӂ��Ă���܂��v�Ƃ����ߖJ�Ȃ邨�t���������������B����Ƃ��A���ʁi�����₩�ł͂��邪�j�Ƃ����Ɏ���o�܂𖾂炩�ɂ��Ă��������Ǝv���B�S����A���肪�Ƃ��������܂����B
�g�����̈��p�����l����ۂɁA�莫�ɑ剪�M�����������сq�~���̓����r�i�H�E28�j�����̋�̓I�ȍ�i�Ƃ��đI�сA�����Ɉ��p����Ă� �鎍����� ���Ɍ��������B���߂ɁA�S���W�Ɏ��߂�ꂽ��e�������i�s����2�������͘_�҂ɂ�郉�C�i�[�j�B�����N���͂��āA�����r�Y�́q�ӏ܁r�i�s�g�����k����� ���l�P�l�t�������_�ЁA1984�N1��20���j�Ƒ剪�M�̌��������f����B�Ȃ��A�������̂��Ƃ́i�@�j���̐����́q�ӏ܁r�̕��͂̌f�ڃy�[�W��\���B���� ���̌����͒��������ꍇ�����k�c�c�l�ƕ\�����A�O���E�㗪�̏ꍇ�͓��i�̕\�������Ȃ��B00�s�́^�͉��s�ӏ��B
�@�@�~���̓����b�g����
�@�@00�@ �u��
��Ƃ������̂͌ő́^���ł���Ɠ����ɔg���ł���v
�^�剪�@�M
�@�@�@ �P
�@�@01 �u��
��Ƃ����Ɍ��т��Ă���v
�@�@02 �q���̍�
�@�@03 ����̂قƂ��
�@�@04 �n
���E�}���^�E�t�i��ނ�
�@�@05 �ڂ��͉��҂��ʂ炷
�@�@06 ���̕��
�@�@07 �ʂ�ʂ邵�Ă���
�@�@08 �d����
�@�@09 �����ɕ߂�
�@�@10 �u���݂Ƃ��Ă̎��R�ł͂Ȃ�
�@�@11 �����Ƃ��Ă�
�@�@12 ���R�v
�@�@13 ���̂��̂�m����
�@�@ �Q
�@�@14 �u�q
���͋����ɐ�������v
�@�@15 �̉莞
�@�@16 ���юR�������
�@�@17 �u�Ƃт������ė���
�@�@18 �v
�@�@19 �ڂ��͊Ԃ��Ȃ�
�@�@20 �A�f�m�C�h�̎�p�����
�@�@21 �ނ��Ƃ���ł̂��Ȃ�
�@�@22 �u�����ɋ���ȏ����������
����
�@�@23 ���Ƃ�z������v
�@�@ �R
�@�@24 �u�~
���̒��͐Â܂肩����v
�@�@25 �L�͎��ɂ䂫
�@�@26 ������ɂ䂫
�@�@27 ������ɂ��Ă��҂����H��
�@�@28 ������������
�@�@29 �l������ł䂭
�@�@30 �u�����̖[
�@�@31 �݂����Ȃ������v
�@�@ �S
�@�@32 �I�����Ƃǂ�
�@�@33 ���R���z��
�@�@34 �����Â炨��̌a���~��Ă���
�@�@35 �u�܂��ׂȂ����
�@�@36 ����������v
�@�@37 ���ꂪ�͂��
�@�@38 �ϔO�̓��e�����Ƃ߂�
�@�@39 �u��
���ːJ�v
�@�@40 ���̕����͔�����
�@�@41 ������������ނ���@��
�@�@42 �u���ƌ�����
�@�@43 ���ԁv
�@�@44 �ɐ��݂���
�@�@45 �u�c�N�l�C���R���v
�@�@46 ���̂͂邩��Ɍ���
�@�@47 �u�Ⴆ�Ⴆ�Ƃ���
�@�@48 ���v
�@�@49 �ڂ����V�l�������炱�̂悤�ɂԂ₭
�@�@50 �u���t�̕�����̂�
�@�@51 �l���߂�Ɛl����
�@�@52 ���̂��Ƃ��v
�@�@ �T
�@�@53 �u�����ƍz���̗�����������
��
�@�@54 �킫�����Ă���
�@�@55 �n�\�v
�@�@56 �����ł̐����͂炢
�@�@57 �u�q��̐H���ł�
�@�@58 �ނ��{�����Ƃ͏o���Ȃ��v
�@�@59 �ڂ��̂͂炩���
�@�@60 �Ђ�����v�l��
�@�@61 �u��
�قɕ�������\�́v
�@�@62 �������킦��
�@�@63 �����͊��L�̂悤�Ȑl������
�@�@64 �u�₦�������n���v
�@�@65 ���̋����߂����̂���
�@�@66 ����䂦��
�@�@67 �u���炾�̂Ȃ��ɂ˂�
�@�@68 �t�H�������o�������Ȃ��`��
�@�@69 ���ݏo�����v
�@�@70 ���̂܂��ɎU������
�@�@71 �����◑�q
�@�@72 �i���t�j
�@�@73 �������̋�ۂ�
�@�@74 ⴂ�͂�����������
�@�@75 ���������点��
�@�@76 ���~�I
�@�@77 ���������ꖇ�̐���
�@�@ �U
�@�@78 �u����ʂ���
�@�@79 ������Ɓv
�@�@80 ����ڂ��͗��ɏo��
�@�@81 �����̒������������Ƃ����
�@�@82 �i�_�ŐM���j����
�@�@83 ��������
�@�@84 �u�X�͂��n����
�@�@85 ���E�̍^�����͂��܂�v
�@�@86 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��㎵��E�ꁛ�E��j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�u����Ƃ������̂͌ő�
���ł���Ɠ����ɔg���ł���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�剪�@�M
�������i169�j
��
�ɂ���đ薼�̂�����̊��ʂ̒��͌�����ꂽ����̌��t�A�������A�u�剪�M�v�Əo�T�����L����Ă���ɂ�������炸�A�����́u��̓E�F�[���B�N���̗ޓ���
�ł͂Ȃ����낤���B����͕s���Ō��I�ȗ��q���������A�����ɁA�g�����ɂ����Đ^�Ɂq���Ƃr�̐����������v�i�w�ʎ��L�x�u�f�͇[�v�j�B
���剪�i�s�ʎ��L�t�����q�f�͇[�r�B�s�剪�M����W13�t�y�ЁA1978�N2��28���A98�`99�y�[�W�j
�@��̓E�F�[���B�N���̗ޓ����ł͂Ȃ����낤���B
�@����͕s���m�C���f���B�f�����A���n�Ō��I�m�C���f���B�f�����A���n�ȗ��q���������A�����ɁA�g�����ɂ����Đ^�Ɂq���Ƃr�̐����������B
�u��Ƃ����Ɍ��т��Ă���v
�������i171�j
�u��Ƃ����Ɍ��т��Ă���v�͏o�T���ځB
���剪�i���W�s�V���̐Q�Ԃ�̉��Łt�����q��m����n�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0554�y�[�W�j�́u�ꕔ����ɂ����p�v
�i�s�V���̐Q�Ԃ�̉��Łt�����́q���i�m�[�g�j�r�A�s�剪�M�S���W�t�A0598�y�[�W�j�Ɏv����B
���҂�@���̊�����������ɐ��݁@������ꡂ��Ȏ����ɐ���
�n���E�}���^�E�t�i��ނ�
�������i170-171�j
�u�n���E�}���^�E�t�i��ނ�^�ڂ��͉��҂��ʂ炷�v�c�c�}���^�ƃT���}�^�̉��̋��������́A�Â��s�́u���̕���v�Ƃ������t���̗p��ƂƂ��ɁA���C��
�������ɂ���剪�ւ̌h�ӂ̕\�����낤�B
���剪�i���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�����q壉Ε{�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��
16���A0778�y�[�W�j
���ԂȂ�
�}���^���n������̒������c�����A
�͂����Ő����ɂ��₪�݁A�I�C�x�b�T�������т����݂��A���̍������ނ���A�n����}���^��ނ�a�Ƃ���B
�i�����A0779�y�[�W�̎U���j
�u���݂Ƃ��Ă̎��R�ł͂Ȃ�
�����Ƃ��Ă�
���R�v
�������i170�j
�ѓ��́u�����Ƃ��Ă���^�A�������^�����Ă�����́v�Ƒ剪�́u���݂Ƃ��Ắ^���R�ł͂Ȃ��^�����Ƃ��Ă̎��R�v�i�w��E���ƂE���[���b�p�x�u�|�p��
���R�v�j����ׂ�A����͎��Ă���B
���剪�i�s��E���ƂE���[���b�p�t�́q�|�p�Ǝ��R�r���̈�сq���R�̕����\�\���i�悩�玩�R��ցr�B�s�剪�M����W11�t�y�ЁA1977�N2��25
���A182�y�[�W�j
�@
�A���t�H�������i�ڂ��̓A�N�V�����E�y�C���e�B���O�����܂߂����̂Ƃ��Ă��̌��t��p���Ă���̂����j�G��́A���������đ��`���p�̒p���ɒ��ڎ��������
�ׁA���̔閧���������Ƃ����̂ł���B�Ƃ����̂��A�E�̂悤�Ȏv�z�Ɏx�����Ă������A�G��Ƃ������̂́u�݁m���n��v���̂ł͂Ȃ��A�ނ���u����v
���̂��Ƃ����A����߂Ė��͓I�ł������댯�ȐM��������̂́A�K�R�̐��s��������ł���B��\���I�̒��ۊG��́A��ʂƂ������̂��O���̑Ώۂ��犮�S��
�Ɨ������A�F�ƌ`���琬�鎩���I�ȓ����ʂł���Ƃ��������̊m�F����o�������B��ʂ͂��ꎩ�̂ő��݂���V������̎����ł���A���ۊG��̑��ݗ��R
�����̈�_�ւ̐M�������Ă͂��蓾�Ȃ������B�����A�A���t�H�������̎v�z�́A���ꎩ�̂̒��ɁA���̐M�������h���Ԃ�v�f���܂�ł����̂��B��ʂ͂���
���̊������������ł͂Ȃ��A���̔w��̑������I�ȁi���炭�́A�Ƃ�킯���Ԃ̎��������܂j�������鐢�E�ւ́A�ЂƂ̒ʘH�̂��Ƃ����̂Ƃ݂Ȃ���
�˂Ȃ�Ȃ������B����́A�V���ȁq���R�r�ւ̐ڋ߂��Ӗ����Ă����Ƃ͂����Ȃ����낤���B���݂Ƃ��Ă̎��R�ł͂Ȃ��A�����Ƃ��Ă̎��R�A����ނ���A����
�Ƃ��Ă̎��R�Ƃ����M�����ϔO�ւ̐ڋ߂��B
�u�q���͋����ɐ�������v
�������i171�j
�u�q���͋����ɐ�������v�i���w���{�x�u���z�u�v�j�B���T�ł͑剪�̎q���ɂ��Ă����Ă���ӏ������A�����ł͑剪������̂��ƂɁu�����Ɂv�����Ȃ����
����B
���剪�i���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�����q���z�u�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0743�`0744�y�[�W�j
�q�ǂ��͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ邪
�e�݂Â���ɂ͘V���䂭���o�̂Ȃ����Ƃ�
������ӂƕ|�낵���ƒm��
�H��̌Ӑl�A�ڂ��Ƃ��ӑ��l
�u�Ƃт������ė���
�v
�������i171-172�j
�u�Ƃт������ė���^�v�Ɓu�����ɋ���ȏ�����������Ă���^���Ƃ�z������v�́w���㎍����24�剪�M���W�x�u���L���v���B���T�ł͔����ɓo���Ă�
��ۂł�����̂������ł͏��N������N���ւ̉ߓn�I�����̐S�ە��i�Ƃ��ė��p����Ă���B
���剪�i�q���L���r�A�s�剪�M���W�k���㎍����24�l�t�v���ЁA1969�N7��15���A110�y�[�W�j
�k�P�X�T�P�N�i���a26�N�j�l�U�E30
�@
�R��o��Ȃ��猩�����̔������X���[�v�̗A����͖l�ɂЂƂ̌[����^����B���Ƃ͋����ł���ƃ{�I�h���G�������������A����͌ꌹ����l�����邱��
���Bsurprendre�́u�Ƃт�����v�̈Ӗ��ł����āA��X��surprendre�����Ƃ������Ƃ́A�܂�A�Ώۂɂ���ĂƂт������邱�ƂȂ�
���B�Ώۂ�����̂ł͂Ȃ��A�Ώۂ���X�ɂƂт������Ă���̂��Bsurprendre�i�Ώہj��surpris�i���ȁj�A���̊W�����A�����`����B����
�̂��̏\�����̗̃X���[�v�́A�������ɖl�ɂނ����ĂƂт������Ă����B
�u�����ɋ���ȏ�����������Ă���
���Ƃ�z������v
�������i171-172�j
�u�Ƃт������ė���^�v�Ɓu�����ɋ���ȏ�����������Ă���^���Ƃ�z������v�́w���㎍����24�剪�M���W�x�u���L���v���B���T�ł͔����ɓo���Ă�
��ۂł�����̂������ł͏��N������N���ւ̉ߓn�I�����̐S�ە��i�Ƃ��ė��p����Ă���B
���剪�i�q���L���r�A�s�剪�M���W�k���㎍����24�l�t�v���ЁA1969�N7��15���A110�`111�y�[�W�j
�k�P�X�T�P�N�i���a26�N�j�l�V�E�P
��
�̈łɕ�܂ꂽ�L��ȃX���[�v�A������邱�Ƃ͕|�낵���B����Ȏ������B�����Ɉ�l�̋���ȏ���������Ă��邱�Ƃ�z������B�ނ����������B�����
�N�́A�s�ӂɌ������~��g���ɋN��̂�������B���̏��́A�N�̗~��̑Ώۂł���A�������N�̗~��ꎩ�g�ł���B�N�͔ޏ��̋���ȏ_����������T��ł�
�낤�B����͂����Ƃ�ƔG��ĉ������A��������������Ă���B���������c�c�ނ��돗�̓����B�N�͎���ɐ[�݂֖v���Ă䂭�B�N�͐[���p�ɖ������ށB�_�����A
�G�ꂽ�S���B���t�̕���B�N�͈�̋a�ł���B�N�͈�̎��A��������ł���B�N�͔ޏ��́u���Łv���肽���B�N�͂₪�Ė���ł��낤�B�N�͂��̎��P�Ȃ�
�u������́v�ɂ����Ȃ��B�R�����ł��A�l��̐��͖���̂��߂ɔ��邵�A����ȊO�̖ړI�������Ă͂��Ȃ��̂��B
�u�~���̒��͐Â܂肩����v
�������i172�j
�u�~���̒��͐Â܂肩����v�́u�c�c�Â܂肩�������R�b�v�̂Ȃ��́c�c�v�i���w�����}�@�\�\�Ă̂��߂́x�u㢂ƃR�b�v�̂���v�j�̉��ρB�u�R�b�v�v���u�~
���v�ƂȂ����ɂ��ẮA�A�f�m�C�h�̌��o�ɏے�����鏭�N�̓����̕\���Ɂu�~���v���ӂ��킵���ƍl����ꂽ���߂��B
���剪�i���W�s�����}�@�\�Ă̂��߂́t�����q㢂ƃR�b�v�̂���r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0511�y�[�W�j
�X�H�̂Ђт������������悤�ɐÂ܂肩�������R�b�v�̂Ȃ��́A�O�����������������A�������ȏ��C�������Ă���B�������̎��z���z���Ƃ�B���͏��X�ɂʂ�
����A�R�b�v�����ɂ����፷���́A���}�ȐÕ��̃E�B���N�ɂ����Ȃ��Ȃ�B
�@�@�Ƃǂ܂��A�H�g�I
�@�@�����A���g�I
�L�͎��ɂ䂫
������ɂ䂫
�������i172-173�j
�u�L�v��u��v�́u���v���Ƃ����āu�l�v�́u���v�̈Ӗ���m��B
���剪�i�q���L���r�A�s�剪�M���W�k���㎍����24�l�t�v���ЁA1969�N7��15���A113�y�[�W�j
�k�P�X�T�P�N�i���a26�N�j�l�X�E13
�@
�L�����ɁA����B���Ƃ������Ƃ̉��Ƃ����s�v�c�B�u���̂̎��v�Ƃ����ɂ߂ĊϔO�I�Ȏ�������A�s�ӂɁu�����́v�Ƃ����ɂ߂ĘI�o�I�Ȏ����̒���
�˂��o����A���͈������肱�܂�A�l�͌��������f��������B�����ɂ���f�w�A����͉�X���ʏ펩���̂��ƂƂ��Ă���A��Ɍ����邷�ׂĂ̂��̂͗����ł�
��A�Ƃ����ϔO����u�̂����ɕs���̒��֓˂��������Ƃɂ���āA�[����ɓI�ł���B��X�͎����̂���O�Ɍ���B����������͉�X�̖}��闝����₵��
����B���Ƃ������l�̂Ȃ������B
�u�����̖[
�݂����Ȃ������v
�������i173�j
�u�����̖[�^�݂����Ȃ������v�i�w�剪�M���W�x�u�n���_�v�̒��́u���y�̖[�v�̉��ς��j�́u���v�B
���剪�i���W�s�킪��̂������̂����t�����q�n���_�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0419�y�[�W�j
�����@���m��ʓy�n������Ȃ�
���������邱�Ƃ�
�ǂ����Đl�����̂悤��
���y�̖[�ł����ς��ɂ���̂�
�u�܂��ׂȂ����
����������v
�������i173�j
�u�܂��ׂȂ���Ł^����������v�́u����ǂ��ЂɁ^�܂Ȃǒm��ʊ�Ɂ^����n�Ă��^���Ƃ����^�G�v�i�w�߉̂Əj���x�u�n��j�v�j�̉��ς��B
���剪�i���W�s�߉̂Əj���t�����q�n��j�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0615�y�[�W�j
����ǂ��Ђ�
�܂Ȃǒm��ʊ�m���فn��
����n���
���Ƃ���
�G
�u�����ːJ�v
�������i173-174�j
�u�����ːJ�v�ɂ��Ắw�댎
�L�x�u�f�͇Y�v�ɁA������k��ɏo�Ȃ�����̑��L�^�Ɂu���J�v�Ƃ���ׂ�������̂Ƃ��낪�u�ːJ�v�ƂȂ��Ă������Ƃ���n�܂�A�u���v�Ɓu�ˁv�́u����
���͂�ށ^�ϔO�̓��e�����Ƃ߁v���Ɖߒ����q�ׂ��Ă���B�����炭��҂͑剪�̂��̕��͂�ǂ�ŁA�u�����ːJ�v�̕����ɐV�N�Ȑ�ɂ��o�����̂���
���B
���剪�i�s�댎�L�t�����q�f�͇Y�r�B�s�剪�M����W13�t�y�ЁA1978�N2��28���A296�`300�y�[�W�j
�@������k��ɏo
���B���L���e���܂���Ă��āA���̔����̒��Ɂu�����ːJ�v�Ƃ�������������̂������B�������Ɏ��́u�����E�W���N�v�Ƃ������t���g�����̂����A���̓���
�������̂́u���J�v�Ƃ��������������̂ŁA�u�ˁv�̎��ɂ͌˘f�����B�͂��߂͑��L�҂̃~�X�ł��낤���Ǝv�����B�������A���̕��������x���o�Ă���̂ŁA��
�f���͘T���ɕς����B
�@���̑��L�͂܂������Ă���A�Ǝ��͎v���A�u�ˁv���u���v�ɒ��������B�������A���L�҂͕������悭�m���Ă���l�X�ł���B�C�ɂȂ��āA�L�������J���Ă�
���B
�@��傤���傭�y���J�E�ːJ�z�@�l�����Ȃǂ�͂������߂邱�ƁB�A����\�͂ŔƂ����ƁB
�@���͂��Ȃ����B�ːJ�����������������Ȃ̂��B�u���v�̎��͓��p�����ł͂Ȃ��B���������āA�u�ˁv�̎����̗p���ꂽ�̂ɂ������Ȃ��B���͑��L�҂ɕs����l
�т�v���ŁA�Ăсu���v���u�ˁv�ɖ߂����B
�@���̌o�߂͂��ꂾ�����������A���̋C���͂��̌��ʂ�����Ȃ�Ǝ���ꂽ����Ȃ������B�����Ă݂�A�ꊴ�Ɛl���ĂԂ��̖̂��炵�������B
�u���ƌ�����
���ԁv
�������i174�j
�u���ƌ����́^���ԁv�́u���ƌ����̂������Ɍ��Ԃ�����Ƃ����l���̗U�f�v�i�w�댎�L�x�u�f�͂h�v�j�̏ȗ��B
���剪�i�s�댎�L�t�����q�f�͂h�r�B�s�剪�M����W13�t�y�ЁA1978�N2��28���A241�`242�y�[�W�j
�@���ƌ����̂������Ɍ��Ԃ�����Ƃ����l���̗U�f�B
�@��ߑѐ��B����͖��ɁA�����͌����ɘA���Ă���A����ł��Ȃ��ׂ��Ђ낪��B
�@������A����l�X�͌��̂��Ƃ����̂Ƃ��đz�����邾�낤�B
�@�ʂ̐l�X�́A�ł̂��Ƃ����̂Ƃ��đz�����邾�낤�B
�@��ԂƂ����֗��Ȍ��p���邱�Ƃ��ł���Ȃ�A���ƌ����̂������̌��Ԃ́A�����Ă��ē����Ɍ����Ȃ���ԂƂ������ɂ����\���ł��Ȃ���ނ̋�Ԃł���B
�u�Ⴆ�Ⴆ�Ƃ���
���v
�������i174�j
�u�Ⴆ�Ⴆ�Ƃ����^���v�́u�����͂������Ⴆ��v�i�w�߉̂Əj���x�u�Ƃ����ւ̏H�̂����\�\�����r���ɂ��v�j�̕ό`�B
���剪�i���W�s�߉̂Əj���t�����q�Ƃ����ւ̏H�̂����\�\�����r���ɂ��r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0638�y�[�W�j
�@�X��
������̗��ɕX�����
�����͂������Ⴆ��
���Ƃ̉e�����ǂ点�ĕX�̏�ɂ���ꂪ�~��
�X�͌ł����܂�
�킽���̐S�͂�������
�@������X�̂��ւɂ����~��S�������ʐ�̂���
�u���t�̕�����̂�
�l���߂�Ɛl����
���̂��Ƃ��v
�������i174�j
�u���t�̕�����̂݁^�l���߂�Ɛl���́^���̂��Ƃ��v�́w�댎�L�x�u�f�͇U�v���B
���剪�i�s�댎�L�t�����q�f�͇U�r�B�s�剪�M����W13�t�y�ЁA1978�N2��28���A257�`258�y�[�W�j
�@���t�͋��낵���B
�@�l���͉��̂��Ƃ����B
�@���t�̕�����̂ݐl���߂�ƁA�l���͉��̂��Ƃ��Ƃ����ق��Ȃ��̂��B
�@����ł́A���t�ȊO�̂ǂ����̕�����l���߂�Ƃ�����B�I�}�G�͌��t�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��ł͂Ȃ����B
�@������A���������낤�H�@�l�����A�����A�����悤�ɂ킩�����̂Ȃ�ł��ƁB�������A�l���͂��̖������ɂ����āA���t�͂��̒����ɂ����āB
�u�����ƍz���̗�������������
�킫�����Ă���
�n�\�v
�������i175�j
�u�����ƍz���̗��������������^�킫�����Ă���^�n�\�v�́u�����ނ瑛���^���낪�˗Z����n�\�Ɂv�i�w�߉̂Əj���x�u����ցI�v�j�̕ό`�B�Ȃ�قǁA�u��
���ނ�v�i���A�W�K���̌Q�j�͐��������A�u���낪�ˁv�i����B�����܂ł��Ȃ��j�͍z�����B
���剪�i���W�s�߉̂Əj���t�����q����ցI�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0618�y�[�W�j
�����ނ瑛��
���낪�˗Z����n�\��
���Ђ��������̂�����
�����̂͂��Ԃ�
�c��̂��炾�̔��Ɗǂ͉�����
���剪�i�J��r���Y�Ƃ̑Θb�s��]�̐����t�v���ЁA1978�N7��15���A138�y�[�W�j
�u��
���ނ瑛���v�Ƃ����̂̓A�W���̌Q�����������ɑ������Ă�悤�Ȃ��Ƃ�����ǂ��A�����̃C���[�W�̂Ȃ��ł͂����ƈ�ʓI�ɁA���ɑ������������̌Q�Ƃ���
���ƂŁA�u���낪�˗Z����v�͏ے��I�Ɍ��������ނ��킫�����Z���Ă�������Ƃ������ƂȂȁB�����琶���ƍz���̗��������������킫�����Ă���悤��
�n�\�Ƃ����C���[�W�B
�u�q��̐H���ł�
�ނ��{�����Ƃ͏o���Ȃ��v
�������i175-176�j
�u�q��̐H���ł́^�ނ��{�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�́u�����ɂ͂܂��t�Ȃ��\��l�̒킽���Ɂ^�_�炩�����@�d������^���邽�߂Ɂ^���e�͎���ŒўւƂ�
��v�i�w�t�@�����Ɂx�u��Ȃ̉͑��ցv�j�̖|�Ă��B
���剪�i���W�s�t�@�����Ɂt�����q��Ȃ̉͑��ցr�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0704�y�[�W�j
�U
�����ɂ͂܂��t�Ȃ��\��l�̒킽����
�_�炩�����@�d������^���邽�߂�
���e�͎���ŒўւƂȂ�@�r�n�ɗ���
���݂͞D��Ō䂵�������ām�߂��n�n�ƂȂ�@�f��m�Ȃn���������
�u���قɕ�������\�́v
�������i176�j
���̉Ƒ��́u���قɕ�������\�́v�i�����炭�w�ʎ��L�x�u�f��XIV�v�́u�Î�����Ƃւ́A�ЂƂ�̐l�Ԃ̐[�܂�v�̖|�āj�������}�j�X�e�B�b�N��
�Ƒ��A���̃��}�j�X���́u�����͊��L�̂悤�ȁv�ƕ\�������B
���剪�i�s�ʎ��L�t�����q�f��XIV�r�B�s�剪�M����W13�t�y�ЁA1978�N2��28���A170�`173�y�[�W�j
�@�S���w�҂ɂ��킹��Ɓ\�\�����ĐS���w�҂ƌ��邱�Ƃ��Ȃ����\�\���鏭�N�Ȃ菭���Ȃ肪�u�킽���͍��A�Â����̒��ɒ��������Ă���v�Ƃ����悤�ȂƂ��A
���̏��N���邢�͏����́A���łɐN�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����B
�@�Ȃ�قǂ��̒ʂ肾�Ǝv���B
�@���ړI�Ȓm�o�Ƃ��Ẳ��������Ƃ���A�m�o�z�����Î�����Ƃւ́A�ЂƂ�̐l�Ԃ̐[�܂�́A�����Ƃ������t�̓��e���̂��̂����[�߂�B
�@�k�c�c�l
�@
����䂦�A����̌ŗL�̖{���́A�P�ɖ|��\�Ƃ����_�����ł͂��蓾���A�����Ɂm�A�A�A�n�|��s�\�ȌŗL�������_�ɂ����A���̌ŗL�̖{��
�m�A�A�A�A�A�n������Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B����͖����̉��ł���B�����A���̖����䂦�ɁA�������͐₦�����̂����Ȃ�L���ɂ��ڂ����Ƃ̂ł��Ȃ��A����
�ŗL�̐Î�ɒ�������m�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�n���Ƃ��ł���̂��B
�@�������������A���Ƃ����A��ɒ�`�̔ޕ��ɓ��ꋎ����̂ɂނ����ċ�肽�Ă�Ƃ����āA���̌���̐Î�ɒ������邱�ƈȏ�Ƀ_�C�i�~�b�N�Ȏh���͂Ȃ���
�ł���B�������́A���̐Î�ɒ�������Ƃ��A��ɁA���N����N�ɂȂ낤�Ƃ���u�Ԃɂ���B
�u���炾�̂Ȃ��ɂ˂�
�t�H�������o�������Ȃ��`��
���ݏo�����v
�������i176�j
�u���炾�̂Ȃ��ɂ˂Ɂ^�t�H�������o�������Ȃ��`�Ł^���ݏo�����v�͏o�T���ځB
���剪�i�J��r���Y�Ƃ̑Θb�s��]�̐����t�v���ЁA1978�N7��15���A129�y�[�W�j
��
�R�E�����ۂɕ����Ă���Ƃ��ɂ͌X�̂��̂ɐڂ��Ă���킯������ǂ��A�����ɖ{���̈Ӗ��Ō`��^����̂́A�������g�̂Ȃ��̈Ӗ����邢�͊��o�̑̌n��
�Ǝv���B���E�ςƂ��l���ςƂ������������ł��邯��ǂ��A���̂��炾�����X���S�Ȍ`�̗��q�ݏo���Ă���݂����ɁA�l�Ԃ̂��炾�̂Ȃ��ɂ˂Ƀt�H
�������o�������Ȃ��`�Ő��ݏo����Ă��āA�����Ɍʂ̈�̂��̂��Ђ��������Ă����Ƃ��Ɍ��t�ɂȂ�B���������l�����l�ɂ͂���B
�i���t�j
�������̋�ۂ�
ⴂ�͂�����������
���������点��
���~�I
�������i176�j
�Ȃ��A���ʂɊ����Ă͂��Ȃ����A�u�i���t�j�^�������̋�ۂ��^ⴂ�͂����������ā^���������点��^���~�I�v�́w�߉̂Əj���x�u���̂Ȃ�����o������
�D�̂��߂���́v�́u���t��^���~�I�v���痈�Ă��邱�Ɩ��炩�ł���B
���剪�i���W�s�߉̂Əj���t�����q���̂Ȃ�����o������D�̂��߂���́r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0664�`0665�y�[�W�j
�l�̗������e��
�c���_�_�̖j�ޓy�n���悬��
��n�͒Ⴍ������
�}�b�N�X�E�G�����X�g�͑��ɋA�炸
�w�����E�~���[�̓I�����W�̖F���ɖ�����
�X���F�[�f���{���͖ؐ��l�Ɛ�����
�n�ɕP�E�����
�y���͂�����Ƃ���Ő��g�������
���������̌��t��
���܂����y�n�̌��ǂ����
���ق났���ޑ��̍���������قЂ���
���t��
���~�I
�u����ʂ���
������Ɓv
�������i177�j
�u�ǂ�ʂ��ā^������Ɓv�́u�ǂ͔��������āA���Ȃ���ɂ��ĕǂ�ʂ��Đ�����悤�ȉƂ������̂��v�i�w����̎v�z�x�u�C���[�W����̒��̃f
�U�C���v�j�̏ȗ��B�剪���ƒ�������Ă͂��߂ďZ�Z���̋L�q���剪�܂��͎�l���̐����̌��_�Ƃ��ė��p����Ă���B
���剪�i�s����̎v�z�t�����q�C���[�W����̒��̃f�U�C���r�́u�z�E�L����|���@�ցv�k�����o���l�B�s�剪�M����W11�t�y�ЁA1977�N2��25���A
317�`318�y�[�W�j
��
�����Ƃ̑O�ɂ̓o�X��҂l�X������ŁA�ɂԂ��ɖl�̉Ƃ����낶��̂������ށB�̂������ނ̂������ŁA���̉Ƃ͌����������Č��ւ͋v�����O���炠������
�ł��Ȃ��Ȃ��Ă������A�ǂ͔��������āA���Ȃ���ɂ��ĕǂ�ʂ��Đ݂���悤�ȉƂ������̂��B�F�l�����́A�����݂̉��ɒ|�������Ă���悤�Ȃ��̉�
��ʔ������āA�厖�ɂ���Ƃ͂��܂��Ă���邵�A�l�����̉Ƃ������Ă����̂����A�ƂĂ�����Ȃ̂Ȃ��Ƃ������Ă͂����Ȃ��Ȃ����B
�u�X�͂��n����
���E�̍^�����͂��܂�v
�������i177�j
�u�X�͂��n�����^���E�̍^�����͂��܂�v�́u�^�����܂�^���k�Ђ݂̂₱�v�i�w�߉̂Əj���x�u���̂Ȃ�����o������D�̂��߂���́v�j�̖|�Ă��B
���剪�i���W�s�߉̂Əj���t�����q���̂Ȃ�����o������D�̂��߂���́r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A0662�y�[�W�j
���Ă��݂͗₦��
�|��Ԃ͖�
��ދY�m���́n�ꏗ�m�߁n
���邵�ދY�m���́n��j�m���n
�^�����܂�
���k�Ђ݂̂₱
�L��̔����͓����ɂȂ�
�ӂ�ւ�
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�����r�Y���q�ӏ܁r�Łu�Ȃ��A���̍�i�Ɉ��p���ꂽ�o�T�ɂ��ẮA�Ƃ��ɑ剪�M���̋������B��҂���т̍�i�̊����x�̂��߂ɂ�
��قnj��T��
�������A���邢�͂܂�����邩�̗�Ƃ��āA�����Ɏ����̂��Ӗ��̂Ȃ����Ƃł͂���܂��v�i�O�f���A��Z��`�ꎵ�Z�y�[�W�j�ƒf���Ă���悤�ɁA�g�������p
�����͋�̒��҂łȂ���킩��Ȃ��A���ρE�ό`�E�|�Ă��ꂽ����̏o�T�̎w�E�͂Ƃ�킯�M�d�ł���B�ȉ��ł́A��������R��Ă��邢�����̏o�T�̓T��
����ӂ̎������߂������ꡂ��Ă݂����B
��00�s�߂̑莫�u�u����Ƃ������̂͌ő́^���ł���Ɠ����ɔg���ł���v�^�剪�@�M�v�̓T����
�O�o�̂Ƃ��肾���A�J��r���Y�́q�剪�̒m�\�\����Ɗ���r�ł����w�E���Ă���B�u�ȑO�ɏ����������̒��ŁA���͑剪���E�F�[���B�N���ɂ��Ƃ�������
������B�E�F�[���B�N���Ƃ̓C�M���X�̓V�̕����w�҃A�[�T�[�E�G�f�B���g���̂������V��ŁA�����̊�{��Ԃł���p�[�e�B�N���i���q�j�ƃE�F�[���i�g
���j�̗����������ŕ\�������̂����A�剪�����g�̐��z�Ɂu��̓E�F�[���B�N���̗ޓ����ł͂Ȃ����낤���v�Ə����Ă���̂�ǂ�ŁA���̌��t�������ɑ剪
���g�����悭����Ă���Ɗ������̂��v�i�s���㎍�ǖ{�\�\
�����ő剪�M�t�v���ЁA1992�N8��20���A��y�[�W�j�B���ܒJ��́u�ȑO�ɏ����������v�𖾂炩�ɂ����Ȃ����A�܂��剪���G�f�B���g���ɂ��V��
��u�E�F�[���B�N���iwavicle�j�v�Ɂu��v�Ƃ̗ޓ��������������A�O��W�͕s���Ȃ���A���̑剪����ǂJ����g�����A�E�F�[���B�N���ƃE�F�[
���B�N���Ɋ�������剪�Ƃ̊Ԃɗޓ������������������ƂɂȂ�B�J�앶���i�U�����������āj�剪�̏������܂܂������A�g�������i���̑莫�ł͂����Ă��j��
���̏������܂܂Ƃ͑傢�ɈقȂ�\�L���Ă���̂́A�����[���B�剪��^���ɒu�����J��Ƌg���̔�r�_�̎�|����ɂ����Ȃ肻���ȋC������B
��01�s�߂́u��Ƃ����Ɍ��т��Ă���v�̓T���Ǝv�����剪�̎�����f���Ă݂����A����������Ƌg����������b�q�Ƃ̑Βk�q��� ���̌��t�\�\ �t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����j�Łu�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��Ȃ� �v�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō������ �p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB�k�c�c�l��������Ȃ��ƁA�����������A���e�B���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ��� ��ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���v�i�����A��Z�y�[�W�j�ƌ���Ă���u�����̎�������ʂɂ���v������̂悤�ɂ��v���A�����Ȃ� ���낾�B�ѓ��k��ɕ������q���J�̎p������r�i�H�E14�j���u�u�X�i�K�j�������@���ā^�Ђ���ł��錊�v�v�Ǝn�߂��̂Ɠ����M�@�ł��̎����n�߂��������� �߂��ƌ����A���ق��낤���B
��04�s�߂́u�n���E�}���^�E�t�i��ނ�v�̏o�T�Ɋւ��ẮA��f�̂Ƃ��莍�W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j
�����q壉�
�{�r�̖{���Ǝ��тɕt���ꂽ�U�������A����04�s�Ɍ��炸�A�u�P�v�u�Q�v�ŋg�����T���Ƃ����̂��剪�́q�����r�i�J��r���Y�Ƃ̑Θb�s��]�̐����t�����j
�ł��邱�Ƃ͓����Ȃ��B�������珴����B
���剪�i�J��r���Y�Ƃ̑Θb�s��]�̐����t�v���ЁA1978�N7��15���A12�y�[�W�j
���w�ܔN�̎��G���B���ƃA�f�m�C�h�̎�p�����Ă���A������v�ɂȂ����B�k�c�c�l
���������́\�\�ڔ��i���H���j�A�{�A��i�����Ă������ߒZ���j�A���L�A�A�̂��ɎR�r�i���������ʼn��̖��ɂ��������j�B�k�c�c�l
�߂������́\�\�������܂��܁A�n���A�}���^�A�t�i�Ȃǐ�̐����A壂�������B�k�c�c�l
���w�Z�͏��Ò��w�i�����Ó���Z�j�B�w�Z�͏��Ó��x�̍��сm���ʂ��n�R�Ǝ���ɑO���������߂���ʒu�ɂ������B
�q�~
���̓����r�ő������ꂽ�q壉Ε{�r�̎���͑剪�̌�N�̎��W�s�̋��̐��ւ̃��b�Z�[�W�t�ɍĂт��̎p��\���B�q�r���r�ɂ��i��鼂Ɗۑ��j���A�q�Y������
�x�m�r�ɂ́i鼂Ɗۑ��Ɓj���i�����ł̓i�}�Y���w���Ƃ����j���o�ꂷ��̂��B���є��\�̑O��W���炢���āA����炪�u�ʂ�ʂ邵�Ă���^�d�����^����
���ɕ߂��v�i07-09�s�߁j�̓T���ł͂��肦�Ȃ��B�剪���g�̎��偨��������ρE�ό`�E�|�Ă����g���̎��偨����ɂ���܂����剪�̎���A���Ȃ킿
�s���{�t���s�Ẳ��t���s�̋��̐��ւ̃��b�Z�[�W�t�Ƃ�������ɂȂ낤���B
���剪�i���W�s�̋��̐��ւ̃��b�Z�[�W�t�i�Ԑ_�ЁA1989�N4��10���j�����q�r���r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N
11��16���A1194�y�[�W�j
�T�������@�����L���@�D�P����
�@�����ā@�g�b�|�[���@��A����
�k�c�c�l
�I�G�x�b�T����鼁m�͂�n���ނ�
�@�ۑ�����͂݁@�s�V���[��
���剪�i�����W�����q�Y������x�m�r�B�s�剪�M�S���W�t�v���ЁA2002�N11��16���A1228�y�[�W�j
���l�r�m���͂܂������n�ɂ��@�`�c��m���������́n�ɂ�
鼁m�͂�n�E�ۑ��E���̂���߂�
���݂̗���ʼnj���Ƃ�
�ڂ���̂ӂ���ނ���ۂ���
�����܂��k���
�����̃s�X�g���ɂȂ���
��45�s�߂́u�u�c�N�l�C���R���v�v�́A�����ɋ���u�剪�̌��t�ɊԈႢ�Ȃ����o�T���ځv�i174�j�B�E�B�L�y�f�B�A�q���r�̍���
�u���{���v
�Ɂu����20�N�Ƀt�F�m���T�A���q�o�O�i�V�S�j�哱�̓������p�w�Z�J�݂Łu���ˈ��R���v�Ƃ��ă}���l�����������͋��h�Ƃ��Ĕr�����ꂽ�v�Ƃ��邩��A
���͂Ă�����剪�M�s���q�V�S�k�����]�`�I4�l�t�i�����V���ЁA1975�N10��15���j�ɂ�����̂Ɠ��č���œ������ēǂ����̂����A���ɂ͂�����
�u�c�N�l�C���R���v���u���ˈ��R���v���o�ꂵ�Ȃ��B����ďo�T���ڂ����A�������q�s���̏Z�ރ����h�X�P�[�v�\�\�����l�̋�ԃf�U�C���t�i�������X�A
1991�N10��22���j�́q�U �n�����̂Ȃ����i�\�\11
�j�шē��r�Ɂu���ˈ��̎R���v�Ƃ�����������B�u��d�Ёs���{���i�_�t�i�����ЁA1894�j�́q���{�̕��i�ƒ��N�A�x�߂̕��i�r�̈�߂������Ă��钆��
�́A���́u�P���m�c�N�C���n�����`��`���Ę�`�I�ɎR������O�Ɍ��͂��A�k�c�c�l�v�ɒ��ڂ��āA�u�������ؐ��Z�m�܂���n�̕��͂Ɂu���ˈ��̎R����
��㉂̕��i�قǛ����������v�k�q�x�߂��Ԃ�r1936�l�Ƃ���̂Ɉ�������Ă���B�����Ƃ��́A�̂��Ɂu���̎R���͖���ɍD���ɂȁv�k���O�l��A
�w�]��t�x�ɂ����āA�]��̕��i�╗���̑@�ׂ����������ƌ��ɂ��������v�i�����A��O�l�y�[�W�Q�Ɓk�ꕔ�\�L�����߂��l�j�Ǝw�E���Ă���B�Ȃ�A�o
���̂킩��Ȃ��u�u�c�N�l�C���R���v���剪�̌��t�v�͐��T�����B
��64�s�߂́u�u�₦�������n���v�v�ɂ��č����́u�o�T���ځv�i176�j�Ə����Ă��邪�A�����ꊇ�ʂŊ���ꂽ����̔w�i�ɂٕ͐��s�g�����N���k������2�Łl�t��1979
�N�u�\���A�؉�L�Łq�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�r���ς�v������ɈႢ�Ȃ��B���܁A���ɂ�������ł��Ȃ��̂����i�����ł͂Ȃ������j���N10���A����
����E�؉�L�Łq�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�r�i�J�Ê��Ԃ�10��3���̐��j����20���̓y�j�܂Łj���ςĂ���B���̂Ƃ���L�̖F�����ɋg�����̏�����
����̂������i�g���̓I�[�v�j���O�̓��ɑ����^�̂�������Ȃ��j�B63�s�߂́u�����͊��L�̂悤�Ȑl�������v�̓{�i�̍�i�܂��Ă���B�{�i�̕v�N
�A���h���E�s�G�[���E�h�E�}���f�B�A���O�́s�{�i
�킪���ƊG��k�p���n���̏��a�l�t�i�V���ЁA1976�N9��10���j�̊����߂��Ń{�i�́u�����͊��L�̂悤�Ȑl�����v�̍�i�ɂ��Ă��������Ă���B
�u�k�w�ĘT�x�́l�Ă̐l�T�͐g�����Ă���A���̋�������́A�D�P��{�i�ɂ���ĕ`���ꂽ�������̏��������ނ�ɔޏ����������镠�̂ӂ���݂�����ɋ�
�����Ă���A�����̕�����q�����Ƃяo���悤�ɁA�����ނ�̊p�̐�����������������Ƃяo������A�����͒j���̕��̉�����j���킪�˂��o��悤�ɓ˂��o
���Ă����肷��A�Ñ�A�X�e�J�l�̂��̂Ƃ����Ă��ʗp�������ȕ`�ʁv�i���c�k���A�����A��Z�܁`��Z���y�[�W�j�B
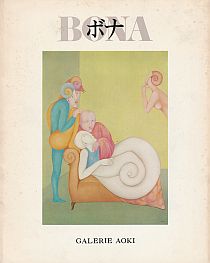 �@
�@
�q�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�r�i�؉�L�A1979�N10��3���`20���j�J�^���O�̕\���i���j�Ɠ��E���\���i�E�j
�苖�Ɂs�{�i�\�\BONA�t�Ƒ肵�����W�̃J�^���O������̂ŁA�T�v���L���B�d�オ��232�~186mm�̊��O��
�܂�i6�y�[�W���́j�ŁA���g�B�\���̐}�ł̂݃J���[�A�ق��̓X�~����B�B���m���u���Ȃ̂ŁA���ɕ\�����珇��ǂ��ăm���u����U��B
�@�i�\���j�J���[�}��1�_�i�薼�s���j
�@�ip.2�j�F�V���F�qSPIRA MIRABILIS DE BONA�r
�@�ip.3�j���m�N���}��1�_�i�薼�s���j
�@�ip.4�j�A���h���E�s�G�[����h�E�}���f�B�A���O�k�|�{���Y��l�q�{�i�\�\���̃G���`�b�N�E�f�b�T���̖q�̓I�s�v�c�r�^�o�i�ژ^�i����4�_�A�F���M
10�_�A�ʼn�17�_�j
�@�ip.5�j���m�N���}��9�_
�@�i���\���j�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�����^�ё��ʐ^�iPhoto by Irina Ionesco 1975
Paris�j�^�؉�L�̏Z���E�d�b�ԍ�
�F
�V���F�́qSPIRA MIRABILIS DE
BONA�r�́u�{�i�̊G�̂Ȃ��ɁA�r�̊p�̂悤�ȁA�O���K�ǂ̂悤�ȁA���邭��Ɗ������J�^�c������������悤�ɂȂ����̂́A�����납�炾�낤���B��
��قǐ̂̂��Ƃł͂���܂��B�Ƃ�����A�ЂƂ��яo�������J�^�c�����́A��������Ȍ�A�ޏ��̊G�̐��E����e�Ղɂ͏o�čs���������Ȃ��C�z�ł���A���邭
��Ɗ������J�^�c�����̗����́A�ǂ����ޏ��̐��E�̖�͂ƂȂ������̂悤�Ȏ������B���̃J�^�c�����A���̃X�s���E�~���r���X�i�����ׂ������j������
������v�Ǝn�܂�B�g���������̕��͂�ǂ��Ƃ͊m���ŁA
�@59 �ڂ��̂͂炩���
�@60 �Ђ�����v�l��
�@61 �u���قɕ�������\�́v
�@62 �������킦��
�@63 �����͊��L�̂悤�Ȑl������
�́A�剪�́u�Î�����Ƃւ́A�ЂƂ�̐l�Ԃ̐[�܂�v��|�Ă����u�u���قɕ�������\�́v�v����A����
�@64 �u�₦�������n���v
�@65 ���̋����߂����̂���
���q������Ƃ��āu�����̎�������ʂɂ���v���̓����̌��ʂ��A�F�V�̏͋�܂��āi�ꊇ�ʂŊ���Ȃ��ŁA���ρE�ό`�E�|�Ă��āj���������̂ƍl�����
��B������
�@�Î���@���@���@���@�O���K�ǁ@���@���L�̂悤�ȓ���
��
�����A�z�������Ă��邱�Ƃ͋^����e��Ȃ��B����ɑz���ɂ���Ȃ�A�W����̃I�[�v�j���O�p�[�e�B�[�Łu�₦�������n���v�������ꂽ�̂��������
���B���݂������g�����g������N�v�Ƃ̑Βk�q�͌ЂƂ������E�ցr�i�s���㎍�蒟�t1967�N10�����j�́u��i�ƌ����Ƃ̂��������v�̍��Ō���Ă����
�͂Ȃ����B
�g���@ �k�c�c�l�����ŐU�肩�����Ă݂āA�� �͂��̓��^�Ƃ��������L�ɋ߂����̂ɂڂ��̂Ȃ��ł͂Ȃ��Ă��܂���B���e�搶�̂��̍��̎���������L�ł���Ɠ����悤�ɁA�ڂ����U�肩�����Ă݂āA�� �̎��セ�̎���̓��^�ɋ߂����̂ɂȂ��Ă��܂��ˁA���l���猩����킩��Ȃ��Ǝv�����ǁB�i�����A�Z�Z�y�[�W�j
����ɁA�g���͓��̑剪�ɂ͂�������Ă����ł͂Ȃ����B
�g���@ �k�c�c�l�ڂ������������ꍇ�A���܂� �Ă����J�����ŗǂ̊��ԂȂ́B��J���̂�����\���Ԃ͗V�Ԃ킯��A�S�̈�_�ɂƂ߂āB���Ƃ̎l�A�ܓ����w�Ɋ��B�k�c�c�l��������̏\�����炢�O����A ������ŎG���ǂ�{�ǂ�A������ƋC���������̂�ǂށB�ł���nj��e�p���Ɍ����A����ŁA�܂����ƈ�C�ɏ����Ă�B�����Ǐ����Ă��A�����Ȃ��B �Ƃ����̂́A����܂�l�������Ă͂����Ȃ��B���͎����ōl���ď�������ǂ��A����Ƃ��납��A�_������Ƃ������A�^�����邱�Ƃ��o�Ă��銴�� ������B���̍ŏ��ɏo�Ă������Ƃ��ł��邾����ɂ������B�����v������A�����ŏ����������Ƃ����Ȃ��B�����������A�ʂ̍l�����܂������œ����Ă��� ���x���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�����̓z�ɐ����𗊂݁A�������ɂ��đ҂B��������ƍr������̌����I�Ȏ��̑��e���o�����킯��B����Ɏ����� �Ă�����Ƃ𑱂���B������O�炢�J�Ԃ��čŌ�̎O�����炢�łЂƂ̂��̂�����������B�����炫�݂��������A�����ł��Ă�Ȃ������Ă̂́A�܂� �ɂ������B���́A�ŏ��̈�s���炠��܂�l���Ă����Ă͓������Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�������܂��ꂽ���t�̕��u��������A���̎��͓����o���Ȃ��Ǝv���B�܂� �Ȃ����̍s���A�����ޓ��̂悤�ɝp�܂邱�Ƃ������_��ɂ��āA�^�̃��A���e�B��ۗL�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃڂ��͐M���Ă���B�Ƃ͂����Ă��A�܂��P���Ȃ� ����ˁB�i�g�����E�剪�M�k�Θb�l�q���`�̐��E����r�s�����C�J�t1973�N9�����A��܌܃y�[�W�j
��72�`76�s�߂́u�i���t�j�^�������̋�ۂ��^ⴂ�͂����������ā^���������点��^���~�I�v�͑O�o�̎w�E�̂Ƃ��肾�낤���A�剪
�́s���q�V
�S�t�́u���̕��́k�u�ԑ��܂Łv�l�̍Ō�̕��ɏo�Ă���u������v�A���̕s�v�c�Ȗ��͂������́A�u�꒼�ƂƂ��������Ƃ̈��쐫�I�Ȓ��ϗ͂̈�؍���
���Ă�����ꂤ����̂����A�V�S�Ƃ����l���A�p���̕��͂������Ȃ���A�����I���ϓI�ɗN�������Ă��邱�̎�̌��t�~�ƎƂ߂�s�q���ƐS�̖�����
�����Ă����l�̂悤�Ɏv���v�i�����A��y�[�W�j���e�����Ă��邾�낤�B
���āA����̓T�����߂���T���͂ЂƂ܂��I������B�c���͎��т̂��Ƃɕt���ꂽ���̕����i����86�s�߂Ƃ����j�ł���B
�@86 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��㎵��E�ꁛ�E��j
����͂������1979�N10��9����\�����A���̓��͂������Ȃ낤�ƍl����ƂȂ��Ȃ��ɓ���B�g�������e�ɑ傫���~���t��
�Ė����������сq�����r�ɂ́A�{���̏I��������Ƃ�
�@�q��l�A��A��\�r
�Ƃ���A�����
�@�i����֓�l�A�\�A��\����j
��
������Ă��邱�Ƃ���A���т̂��Ƃ̓��t�i���a24�N9��20���j�͂����炭�E�e���ƍl������B�����A����ɂ����邱�Ƃ̂ł���g�������̏��o�`�ɂ���
���̃X�^�C���̒E�e���͎c���Ă�����̂́A���W�Ɏ��߂�ꂽ���t�͂��́q�~���̓����r�́u�i��㎵��E�ꁛ�E��j�v�����Ȃ̂��B���o���_�Łq�����͂ǂ�
�ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�Ɂu���Z���E�܁E��܁v�Ƃ������̂��A�q�R�����r�i�F�E18�j�Ɂu�q���Z��E��Z�E�܁r�v�Ƃ������̂��A�q������܌�b�сr
�i�G�E8�j�Ɂu�i�����E�����j�v�Ƃ������̂��A�q�ٗ�Ձr�i�G�E19�j�Ɂu1974�E2�E14�v�Ƃ������̂��A�q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�i�G�E31�j��
�u1975�E9�E22�v�Ƃ������̂��A���W�ł͂��ׂďȂ���Ă���Ƃ����̂ɁB�����āq�~���̓����r�������Ƃ́q���́r�i�J�E13�j�ł����o���_�ɂ�
�������u�i��㔪��E�Z�E��Z�@�ʖ�̓��j�v�����W�ŏȂ���Ă��邱�Ƃ́A�O����ɂ��Ă���B����͂�������ƍl����ɒl�����肾���A���̑O�ɑ剪�M
�s���q�V�S�k�����]�`�I4�l�t�Ƌg�����̊ւ��ւƉI�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�剪�́s���q�V�S�t�́q���@�܉Y�s�r�Ŏn�܂�B�����͋g�����ҏW��S�����Ă����s�����܁t1975�N5���̑�73���Ɍf�ڂ��ꂽ�B����
�o�܂͋g����
���z�q�剪�M�E�l�̒f�́r�́u�R�v�i���o�́s�剪�M����W�k��14���l�t����i�y�ЁA1978�N3��31���j�́q�剪�M�E��̒f�́r�j�ɏڂ�����
��A�����ł͑剪�̒k�b�q�q���A�V�S�A�q�K�A���q�ɂ��ār���������B
�s���q�V�S�t�̎��M�E���s�̔w�i�͂����ɐs������Ă���B�ł́A�g���͑剪�̂��̖{���ǂ��ǂ̂��B�ѓ��k��Ƃ̑Βk�Ɉ˂�ɔ@����
�Ȃ��B
�g���̔����łƂ�킯�d�v�Ȃ̂́A�Ō�́u�ڂ��́u���p�v���Ă������ƂɁA���܂ƂĂ��S�������ł���B�]�_�Ƃ������̂̑����͈��p
�̍I�k�ȁA�g
���ĕ��ƁA������Ő������Ă��邾�낤�B�w�V�S�x�ǂ�łāA�ق�Ƃɂ����������Ƃ��l�����v�ł���B�����āu�ڂ����U�������Ƃ�����������ŁA���_��
�Ȃ��ꍞ��ł��܂����ǁA�剪�̂����ǂނƂ��A�T���ւ̓�������A���ɍI���Ȃ̂ˁB������Ƃ���ŁA�T���֓������Ă䂭���A���̎��Ɏg������
���ЂƂЂƂ���Ă�̂ˁB����͋���ׂ����ƁB���������Ƃ����אS�Ȃ̂ˁv����邪���ɂł��Ȃ��B������A��Ɉ������g���̍쎍�@�u���́A�ŏ��̈�
�s���炠��܂�l���Ă����Ă͓������Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�������܂��ꂽ���t�̕��u��������A���̎��͓����o���Ȃ��Ǝv���B�܂�Ȃ����̍s���A�����ޓ�
�̂悤�ɝp�܂邱�Ƃ������_��ɂ��āA�^�̃��A���e�B��ۗL�����邱�ƂɂȂ�v�ƏƂ炵���킹�Ă݂�ƁA���сq�~���̓����r�̏��@�����A�剪�́s���q�V
�S�t�̗I�g���炴�鏑���Ԃ�i�Ƃ�킯���́q��@�����ς̌��e�r�j�Ɋw���̂��Ƃ͂����Ȃ����낤���B���̂Ƃ��g�����ە������̂�
�Ƃ����A���Ɋ�剪�̊m�M�ł������ɈႢ�Ȃ��B�������ċg���́A����������Ƃ��ꂪ�Ō�̎��W�ɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����\���ɕ��
��Ȃ���i��
�Ɏw�E�����E�e���̋L�ڂ͂����ɋA������j�A�剪�M�ɕ��������сq�~���̓����r�Ŏ��g�́u���p���W�v���Ȃ킿�s�Ẳ��t����߂��������̂ł���B�剪����
���Ă���悤�ɁA�sThe White
Fox�i���ρj�t�͓V�S���n�삵���p���ɂ��O���I�y���ŁA�C�U�x���E�K�[�h�i�[�v�l�ɕ�����ꂽ���A�����ɏۛƂ���Ă���C���h��聏G���l�v���������B
�_�E�f�[���B�E�p�l���W�[��̎����剪��ň����B
�@���t�͎v�z�̉Ǖw�m����߁n�ł����Ȃ�
�@���Ɣ��́A�Ȃ�Ƃ����₢���ő����āI
�@���̉̂͂���킢��h
�@�����肽���̒�����u�Ȃ��
�@�����Ƃ߂悤�Ƃ��ĂȂ��p�m���ׁn���Ȃ��B
�@�킪�ЂƂ�A���ɂ͂��Ȃ��𑨁m�Ƃ�n����p���Ȃ�
�@���Ȃ���p���Ȃ��A���t�ɂ���Ă��C�ɂ���Ă��B
�@�킪�ЂƂ�A���Ȃ��𑨂���p���Ȃ�
�@���ɂ͏p���Ȃ��A����Ȃɂ����Ȃ������̉̂ɕ҂�ŁA���̂��̂ƌĂт����̂ɁB�i�s���q�V�S�t�A��Z���`��Z���y�[�W�j
��
�̉ӏ������s���ρt�̖䒆��Ƃ������ׂ��{�т̒��S�I���ł���i�剪�͈�l��`��܁Z�y�[�W�ł����̓V�S���p�l���W�[�̎�����A���x�͂��Ƃ̉p���ƂƂ�
�ɂ�����x�����Ă���j�B�V�S�ɂ�����sThe White
Fox�t�͑剪���ł��͂����ď����Ă��鏈�Ȃ̂œ����ɂ��Č���ɔ@���͂Ȃ����A�g�����������瓾���̂͐�s���鎍�������̎��тɈ��p���邱�Ƃ̖�
ῂ����p�������̂ł͂Ȃ����낤���B����܂Ō��Ă������Ƃ�����킩��悤�ɁA�g���͈��p���тɂ����Ċ�{�I�ɑ��̎��l�̎U������͋���������Ƃ͂�����
���A��������̂܂܈������Ƃ��������Ă����B����䂦�A�剪���w�E�����p�l���W�[�̎���̓V�S�I�y���ւ̓]���ɏՌ������̂ł͂���܂����B���ɂ͂���
�v���ĂȂ�Ȃ��B�����p�v�́s�Ԃ���Ԃց\�\���p�̐_�b���p�̌��݁t�i�V���ЁA1997�N6��25���j�̍ŏI�́q�����_�b�̌��݂ց\�\���p�ƌ��t�m�~���g
�X�n�r�œ���N�v�Ƒ剪�M�̓�l���u���p���l�m�|�G�^�E�L�[�^���X�npoeta citans�v�ƌĂB
�@�Ƃ͂�����l�̎��̑���������Ȃ��B�w���˂���E���˂ցx�ł����Ăł��邪�A�剪�M�́u���ҁv���˂ɓ������A �u���ҁv������ ���ђʂ��悤�Ƃ���悤�Ȉ��p�́u�ɒ[�v�Ȋg�[�҂�����ł���B�剪�M�̈��p�́A���l�̎���╶�͂�����Ă͂߂��ރR���[�W���̈Ӗ��ł̈��p�ł͂Ȃ� �i�������A����������̂ł͂��邪�j�B�̂ł����҂̒P�ƓƑn���A�l���L���̂悤�ȊϔO��\��������H�����������ꐢ�E���܂��c�肵�A���̐��E�̒� �ɁA���̂������̌`�Ԃ�@�\�Ƒg�ݍ�����Ȃ�����p���܂��o�����Ă���A���ꂪ�剪�M�ɂƂ��Ă̈��p�ł���B�i�����A��㔪�y�[�W�j
�g�����̈��p�͊�{�I�Ɂu���l�̎���╶�͂�����Ă͂߂��ރR���[�W���̈Ӗ��ł̈��p�v�ł���B����������A�g���̈��p�̎�@ �́A�R��쌛�� �������Ȃ�u�_�j�Ȓ���̒�����A�����ƂȂ�v���𒊏o�����v�u�\�͖{�v�i�c��`�m��w�����������z�����ɕҁs�}�������w�\�\�ÓT�Ђ��w�ԁt�א��o �ŁA2010�N12��24���A���Z�y�[�W�j������s�ׂɑ�������B���̂Ƃ��A�剪�̈��p�͂���Ƃ͑傫���u����B����Ƃ��āA�剪���s���㎍�蒟�t 1980�N10���̋g�������W���Ɋ����сq�H����t�ցE���g�����K��W�r�ɔ@�����̂͂Ȃ��B�q�Õ��r�q�`���r�q���̂��肠����r�q�]�́r�Ƃ����A�g �������̕W������̂܂ܝf��������4�тł���B�ł������q�]�́r���f����B
�]�́b�剪�M
�v�N�v�N����Q���Ɉ��������
����z��
�L���J�N�V�ɋ��������Ԃ���
�V�l�ɂȂ�
�ƍߐ��͕K������
���ĂłȂ�
��������
�댯�l��
���ĂȐ����̓����Ƃ�
���̉��ɖт�����
���x�̂��Ƃł͂Ȃ�
��g�Ƃ��ċ����̂�
�u���@���t
����ɂ��Č��̂͂ނ��������v
�u�킪�n���X�B�R���v�̃M�����b�v��
�܂�܂�Ƃ������z�̐K�̃��R���[�V����
�u����ɂ��Č��̂͂ނ��������v
�t�͏�
����������̗��b
�������͂₭���_����
���ǂ݂�����
���͐_��I�ɍ������ɂ���
�֏��̑�����
���������Ă��̂�
�E���̉�����
���c��̖��_�̉_��
�܂��v�͂���
�v�N�v�N����
�n�c���c�ƍ�����
����̘I�̖�������
���̂ق����ق���
�����ɂ����Ȃ郉���j���O�p
���̊�⑫������
���P�����v�Ȕ��
�v�N�v�N�����ꂽ
���ʓI�Ȉ���̗��͌ǓƂ�
�I�[�g�o�C�����
���X�ƈ�̌����Ă䂭
��̑�C�̗���
�����ɂ͈����Ȃ��������A�q���̂��肠����r�ɓ�x�o�ꂷ��u�u�ڂ��͉�Ƃ�����v�v�́q���w�r�i�D�E7�j����̒���I���p�B��Ɉ��� ���q�]�́r�́u�@�v�i�ꊇ�ʁj�̂��鎍��̂����A
�@�u���@���t
�@����ɂ��Č��̂͂ނ��������v
�́q�t�r�i�G�E4�j����̒���I���p�B�u�u�킪�n���X�B�R���v�v�́q�킪�n�j�R���X�̎v���o�r�i�F�E16�j�̉��ςŁA�g�����q����r �i�H�E13�j�� �u�X�����I���X�܂ł��āv�ōs�����̂Ɠ�����@�i�����r�Y�́u�X�����I���̓��I�����X�̋t�B���邢�̓t���I�����X�̋t�Ńt�����������v�i140�j�Ɓq�� �܁r�Ŏw�E���Ă���j�ɂ����̂��낤�B�剪�ɋg������肤�������̊������鎍��ł���B
�@�ÓT���̂̓lj��A�ӏ܂̎d���̊g�[���A�����������͍��[��A����ɂ����ăp���f�B���܂���Ɏ������̂� ���A�����͖� ����硂��Ȃ��B��т̂��ׂĂ��ÓT����̍̎�A�܂�ԏW�߁m�A���g���M�A�n�ł���悤�ȍ������B�k�c�c�l�����̌n��̉�����ɁA�剪�M�̔���ȓǏ� �Ǝv���ɔ������u�Ǐ����v�i���ɁA���������Ăԁj������A���͂���ɂ��܂��āw�I�єV�x�w���l�E�������^�x�w���q�V�S�x�Ȃǂ̕]�`����э�ƁE��i�_�A�� �̌��_�w�������ƌǐS�x�A�������̘A��W�A�C�O���l�Ƃ̘A���W�������āA����炷�ׂẴW���������剪�M�ɂ����āu���ҁv�Ƃ����g�|�X�w�̐ڋ߂Ȃ��� �u���ҁv�����̕���ƂȂ�A���p�I���E�̕ό�����߂����������ւ̕��ՓI�Ή��ƂȂ��Ă���A�Ǝw�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�s�Ԃ���Ԃցt�A�O�Z�O�y�[�W�j
�����p�v�͑剪���u���ҁv�Əo������ō��̏�Ԃ̈��Ƃ��ās���q�V�S�t�́q���Ƃ����r�������B���̈��p���A�g�������z�q�剪�M�E�l�� �̒f�́r�ň� �����ӏ��Əd�Ȃ�̂��i�����Ƃ������Ƌg���̈��p�ŏd�Ȃ�̂́u�����o���Ă���A�k�c�c�l����u�ԂӂƂ��܂����ݍ������Ɗ����邱�Ƃł���B�v�̕����ŁA �O��͏������قȂ�j�B�q�~���̓����r�̑莫�ŋg�����J��r���Y�ƌ����������悤�ɁA�s���q�V�S�t�́q���Ƃ����r�ŋg���������p�v�ƌ��������B�ے��I�Ȍ� �i�ł���B
�g���Ɂu���u���㎍�蒟�v��\���N�L�O���ɐ���Ƃ���i����A�Ƃ̏��c�v�Y���̗v�������݂������A�\�]�N�O�̎����L�q�I�ȑ��e
�ɁA��̎�
�������A�w��ʁx�̎��тƓ����`�Ԃ��ƂƂ̂��A�����ɔ��\����B
�܌�����v�Ǝ��ь�̒��L�ɂ���q���ρr������B���o�`�́s�g�����S���W�t�Ɏ��߂��Ă��邩��i���o�́s���㎍�蒟�t1984�N6�����j�A�u�\�]�N�O��
�����L�q�I�ȑ��e�v�\�\�Ƃ������Ƃ́s�_��I�Ȏ���̎��t�̖������s�T�t�����E�݁t�̏����ɑ������邪�A�앗���炷��ΑO�҂��낤�\�\�ɋ߂Â���ׂ��A��
��̎��������L�����Z�����Ēǂ����݂Ōf����B
�u�\�]�N�O�̎����L�q�I�ȑ��e�ɁA��̎�������v���ӏ����ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��B�����A�{�т��q���ρr���q�ω�m�����n�r�Ƃ� ���A�`����̌� �u���̗t�v����l���Ƃ���n�̂�l�`��ڗ��E�̕���܂��Ă��邱�Ƃ͖��炩���B�s�y���F��t�i�}�����[�A1987�N9��30���j��1973�N1��18 ���̓��L�Ɂu��A�㎞����A�ˑR�ɓy���F�͋�����������A�푺�G�O��䕈ꔟ���݂₰�Ɍ�����B�k�c�c�l�u��\���Ӂv�̕���̂��ƁA���w��ʂ̂��Ƃ� �ǁB�܂��e���r�Ŋς�����̔\�����u�ތρv�̂��������b��ɏ��v�i�����A�Z��y�[�W�j�Ƃ��邩��A�ςɑ���S�͂��̂��낷�łɂ��������̂Ǝv��� ��B�g���̌ςɊ�z�����q�ρr�i�H�E 15�A���o�́s���{�E�t1978�N1�����q���̎��r�j���Ă߂��Ă���B���Ȃ݂ɋ����q�ތρr�̍뗬�ł̖��̂́u��噦�m�����n�v���Ƃ����i�u�ω�v�� ���Ď��j�B�g�����剪�́s���q�V�S�t��ʂ��ās���ρt��m�����̂�1975�N���Ƃ���A���сq���ρr�̎����L�q�I�ȑ��e�͂���ȑO�A���e�Ɂu��̎�� �����A�w��ʁx�̎��тƓ����`�Ԃ��ƂƂ̂��A�����ɔ��\�v�����̂�1984�N�B�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N�@6�@��q�v�l�̒ʖ�r�i���o��1975�N6 ���j�Ɂu���̂����i�v�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�܃y�[�W�j�ƋL���Ă���B����͐����{�̔N�z�҂��p���邱�Ƃ̂���ď̂� �Ƃ�������i�֓��ł͂ӂ��S���I�ȁu����i�v��p����j�A�����̋g���̔]���ɔ��ρ^���̗t�^�M���E�M�c�̃��`�[�t�����݂��Ă����Ƃ��l������B�q�� �ρr�͈��p���̈��ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�u�@�v�i�ꊇ�ʁj��p���Ă��Ȃ��B���̈Ӗ��ő剪�́q�H����t�ցE���g�����K��W�r�ɕ�������̂Ƃ�����B�g������ �剪�M�ƂƂ��ɂ����Ŋ�V�Ȃ�t�łĂ���̂��B
�剪�M�͋g�����̈��p���Ɋւ��āA���̟f�㑁�������a�������Ă����B
�剪�͋g�����̈��p���ǂ������R���Z�v�g�Ő����ꂽ���킩��Ȃ��Ɠ�����A�ނ�����p��̃R���e�N�X�g���ǂ߂Ȃ����Ƃ��w�E���ׂ�
�������B�剪��
�q�~���̓����r�𗝉������悤�ɁA�����炭���q���`�́q���̃A�X�e���X�N�r�i�H�E22�j���A�{��~�́q�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j���i���������̒Ǔ�
�����{�삪�ǂނ��Ƃ͂Ȃ��������j�������������낤�B�剪�́q���{��~���Ăт����Ƃ育�Ɓr�i���W�s���̂Ƃ�Łt�Ԑ_�ЁA1997�j�ŁA�g���̒Ǔ���
�Ɠ��l�A�莫�ɋ{��̕��i�����ǗY�����ȁj�\�\�u����ɁA�ڂ��́^���������p�j�ȂǂƂ������̂Ɂ^�����������Ă���̂����悢��^�����Ă���v�\�\������
�Ȃ���A�g���Ƃ͂܂������قȂ�M�@�ŋ{����Â�ł���B����͋{��̑莫�����u����Ȃ牽�Ɂ@���݂͋����������Ƃ��ӂ̂��^�{��~��v�Ƃ����Ă�
�����Ɏn�܂�A�����߂��ɂ�������B
����Ƌg���́q�D���̎O�̒[�z�r��
�Ɗr�ׂ�Ɓ\�\���p���͂Ȃ����A�o�T�́s���ЂƊ፷�Ƃ̂������Ɂt�Ɏ��߂�ꂽ�q���l�E�}�O���b�g�̗]���Ɂr�́u�s�\�ʁt�ɂ��čl�� �Ȃ���A���� ���Ε\�ʂƂ��̂��܂��܂Ȕh���I�ȕ\���ɂ��āA�\�ʁm�A�A�n�A�\�ʓI�m�A�A�A�n�A�\�ʉ��m�A�A�A�n����c�c�B�v�i�����ǗY�E�����O�E�푺�G�O�E�L��� ��E�����C��ҁs�{��~����W�k��T���l�t���p�o�ŎЁA1980�N5��1���A���O�y�[�W�j�ł���\�\�A�剪�̕s���̗��R���悭�킩��B�g���̈��p�͌��� �̃R���e�N�X�g��c�����Ȃ���Η���s�\�Ƃ������Ƃ͂Ȃ����A�R���e�N�X�g��c�����邱�Ƃ����т̗����傳����B���l�̂��Ƃ́s���t�W�t����`�{�l�� �C�u���e�ɂ킪�g�͂Ȃ�ʋʂ�����ق̂��Ɍ����ċ��m���n�ɂ��q�̂Ɂv�̈ꕔ�u���e�ɂ킪�g�͂Ȃ�ʁv������̎��q���E���Õ��}���r�������剪�ɂ����� �͂܂�B�����A�剪������ɐG��ĒJ��r���Y�Ɂu�u���e�ɂ킪�g�͂Ȃ�ʁv�ɗR��������Ɠǂ݂Ƃ��Ă����Ȃ��Ă��A���ꂾ���ň����̃C���[�W�͕��Ԃ� ����Ȃ����A����ł����Ƃ������f�ł���Ă���킯�B�������Ђ���Ƃ��āA��������Ǝv���Ē��ׂĂ����A����͂���ň�w�����v�i�Θb�s��]�̐����t �v���ЁA1978�N7��15���A117�y�[�W�j�ƌ��悤�ɁA�ÓT���w�̑S�W��Ìꎫ�T����T�����\���Ƃ����_�ɂ����āA�剪�̈��p�͋g���̂���Ɋr�� �ĊJ����Ă���B���҂̂��̍��͑傫���B�剪�̒Ǔ����̏ꍇ�ɂ����Ă��A�����ɟ���ĕ�����lj�����܂ł��Ȃ��A����͗����\���B�ނ��剪�Ƌ{��A�g ���Ƌ{��̌l�I�W�̐[������邾�낤���A�{��~�Ƃ����l���Ɣނ̏����̂��������͂���z����R���Z�v�g��������ł���Ȃ���A���p�ɑ���剪�Ƌg�� �̃A�v���[�`���ʂ̂��̂ł��������Ƃ̏؍��ł���B�\�\����A�剪�́q���q���`�̂��߂̏����O�ԁr�i���W�s�̈⌾�t�Ԑ_�ЁA1994�j���g���́q���̃A �X�e���X�N�r�ɋ߂�������̂́A���q�̕`���������ɐG�����ꂽ���ёn��̉�H���g���̂���Ɠ��l���������߂��낤�B�����A�����ł��u�@�v���̏����̑䎌�� ���S�ɑ剪�̂��̂ɂȂ��Ă��āi�����炭���q����̈��p�ł͂Ȃ��j�A�g�����́u�@�v���̎��傪�����܂ł����҂̏͋�ł���i�Ƒ����Ă���j�̂Ƃ͕ʂ̎��� �ɂ���\�\�B�剪���{��~�̏��Ȃɉ�����悤�ɂ���116�s�̎��̖{�����������̂ɑ��āA�g���̈������͋�́A�莫�́u�C�}�[�W���͂����������ց^���� ���܂������Ɂ^�Ӗ��������Ƃ���v�ȉ��A�{��̑��̂�\���i�Ƌg�������f�����j���̂���������A���̏o�T�́s�{��~����W�t�̏��������ɂ킽��A�R���e �N�X�g�D���ꂽ�͋傪����Ƃ��Ă킩��ɂ������̂ɂȂ邱�Ƃ͔����������B�剪�M�̃��m���[�O�������E���S�I�ɑ��A�g�����̃_�C���[�O���f�ЁE���S �I�쎍�@�ƌ����ׂ����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�����ł悤�₭�A���o���т̖{���̂��Ƃɒu����A��e�̎��W�ł����̂܂c���ꂽ1979�N10��9���Ƃ������t�i�u86
�i��㎵��E�ꁛ�E��j�v�j�̈Ӗ��ɗ��������邱�Ƃɂ������B�g�����͎��M�́q�N���r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�j�́u���a�\��
�N�@��㔪�Z�N
�Z�\��v�̏��Ɂu��J�̓��A�Ղ̖�a�@�Őf�@����B�����̕a�C�ł͂Ȃ����g����v�Ə����Ă���B���̌��Ɋւ��Đ��z�ł͂��������G��Ă��Ȃ����A��
�̂܂��ɑ̒��Ɉٕςł����������̂��낤���B
�������đO�O�N�ƑO�N�̔N���̋L�ڂ�ǂނƁA�Ζ���̓|�Y�����đސE�A�җ�A����C���̎����A���W�s�Ẳ��t�̏o�łƐg�ӂ͍Q������ ���B�����āA�� ��1980�N�ɂ͏E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�Ɛ��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�����Ŋ��s���Ă���B�܂�łȂɂ��ɂ������Ă��邩�̂悤�ɁB���� �����ׂđ̒��ٕ̈ςɂ����̂ł͂Ȃ��ɂ���A���l�Ƃ��Ă̑��܂Ƃ߂ɂ������Ă����ۂ͐@���������B���̒��S�Ɉʒu����̂͂����܂ł��Ȃ��s�Ẳ��t�� ����B���ɂ́A���ꂪ�Ō�̎��W�ɂȂ邩������Ȃ��Ƌg�����l���Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�ЂƂɂ͏����̂��ƂɂȂ������сq�Ẳ��r����������e�� �O�Y�̑���Ŗ{���������Ă��邱�ƁB�����ЂƂ��A����܂ŏq�ׂĂ��������̎��сq�~���̓����r���A���W���s����t�Z����Ώ������낵�̂悤�ɂ��đ剪�M �ɕ����Ă��邱�Ɓ\�\�g����剪�̎��I�ǖʂƊւ����̂ł͂Ȃ����A1979�N8���A�剪�͓��{���㎍�l��̉�i�C��2�N�j�ɑI��Ă���\�\�A�ł� ��B���ꂪ��y��F�l�ɑ���g���̈��A�������B
�g�����̑I���W�Ƃ��Ĉ���̏��Ђ̌`���Ƃ��Ă���̂́A����5�^�C�g���ł���B
�@�P���g
�������W�@�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�\�\�s�t�́t�s�Õ��t�s�m���t�q�������сr�̌v54��
�@�Q���g�������W�@�s�g����
���W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�N9��1���j�\�\�s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s�Â��ȉƁt�q�������т���r�s�����t�q�E�⎍�т���r�s�t�́t
�̌v72��
�@�R���V�I�g�������W�@�s�V
�I�g�������W�k�V�I���㎍����110�l�t�i�v���ЁA1978�N6��15���j�\�\�s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s�Â��ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�s�T�t�����E
�݁t�q�������т���r�̌v53��
�@�S���g�����@�s�g�����k��
��̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j�\�\�s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s�Â��ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�s�T�t�����E�݁t�s�Ẳ��t�̌v
45��
�@�T�����E�g�������W�@
�s���E�g�������W�k���㎍����129�l�t�i�v���ЁA1995�N6��10���j�\�\�s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s�Â��ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�s�T�t�����E
�݁t�s�Ẳ��t�̌v60��
���̂����T�s���E
�g�������W�t���R�s�V�I�g��
�����W�t�̑�������łŁA���݂܂ł̂Ƃ���30�N�ȏ�O�Ɋ��s���ꂽ�S�s�g
�����t�ƂƂ��ɁA�ł��˒��̒����I���W�Ƃ�����B�Ȃ��s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s�Â��ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�̊e���т́A�Q������R�i��
�Ȃ킿�T�j�ɕ������Ă��̑S
�т����߂��Ă���B�P�s�g
�������W�t�́u�ҏW����c��m�v��
搂��Ă��邪�A�Ҏ҂����L����Ă��Ȃ�����4�^�C�g���ɂ͒��҂ł���g���̈ӌ����Ȃ�炩�̌`�Ŕ��f���Ă���ƍl������B�����̂Ȃ��ŋg���̎��쎩��
���܂܂��̂́A�Q�s�g����
���W�t�̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�i�q��́r�Ɍ��y�j���S��
����ɂ��Ắq�O�̑z���o�̎��r�i�q���E�H�̊G�r�q�Â��ȉƁr�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�Ɍ��y�j�ɂ����Ȃ��B�S�ł́A�{���Ɍf�������ׂĂ̋g�������ɑ�
�č����r�Y�́q�ӏ܁r���������Ă���A�����͎��M�ɓ������ċg���{�l�Ɏ�ނ��Ď��쎩���Ƃ͕ʂ̃A�v���[�`�ł��̎��̓�ɔ����Ă���B���̑I���W�ɂ͌�
���Ȃ����́q�ӏ܁r�𒆐S�ɁA�g�����̈��p�����l�@�������B
��
�����r�Y�́s�F�B�̍����\�\�����r�Y��Friends Index�t�i�}�K�W���n�E�X�A1993�N9��22���j�͑���77�l�̗F�B�̊����琬�邪�A�����͂����ŋg�����Ƃ̏o������̂悤�ɏ����Ă���i�g�� �́A�F�V���F�A�y���F�A�]�p���A�g��j��A�i�c�k�߁A��������A���e���O�Y�A�������j�A�R�{���g�A����ǐ��A���J���v�̊��ɂ��o�ꂷ��j�B
�@�g������Ƃ͈��Z�Z�N�ɒm��A�Ȍ�l�����I�ɂ킽���Đe���������Ă���������A���̂��������͉��������������B ����������N �v����̎�܃p�[�e�B�[�̗��ꂾ�����A�Ǝv���B���܂��܂ڂ��̑O�ɍ��|�����g������́A�����̂���傫�Ȗڂłڂ�������Ȃ�A�����r�Y�N���낤�A�������� �̑���ʼn����Ă������炷���킩������A�Ƃ������B�i�q�g�����̊��r�A�����A���Z�y�[�W�j

�����r�Y���W�s����ƔƂ��Ɨ����Ɓt�i�����A�[�g�Z���^�[�A1965�j�k��F�O���R�I�v�A�����F���������A�ʐ^�F��n��l�̕\
���ƒ���
�o�T�F�s���������S����W 1957-2012�t�i�p�C �C���^�[�i�V���i���A2013�N6��9���A��Z�y�[�W�j
���́u����N�v����̎�܃p�[�e�B�[�v�͎��W�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t�i1966�j�Ŏ�܂�����16��g���܂��낤�i�g���́s�m���t�ő� 9��̓��܂� ��܁j�B����A�g���́s���Ɣ�]�t1966�N10�����́q�A���P�[�g�r�́u�R�@�������̂���D���Ȏ��l�i�Í���������Ȃ��j�v�Ƃ�����Ɂu���������@ �����r�Y�v�Ɖ��Ă���B�܂��A��1967�N�́s���㎍�蒟�t12�����ł��̔N�̖���͉����Ɩ���āA�u�k�c�c�l�A����s�̒��ю��\�����r�Y�s�] �́t�i���肵�āu��v�j�B���������sMy Tokyo�t�B�k�c�c�l����N�v�s�w�}���s�M�[���̊فx�̂��߂̑f�`�t�B��������Ԉ�ۂɂ̂���̂́A�ѓ��k��̘A�쎍�s��������́t�B����ɂÂ��A�� ��s���L���ɂ���G�X�L�X�t�ł��낤�v�i�q�ѓ��k��u��������́v�E���r�A�����A�Z�l�y�[�W�j�Ɠ����Ă���B�����č����Ɋ���҂̑傫��������� ���ł���B�����1968�N9�����s�́s�g�������W�k���㎍����14�l�t�́A�����r�Y�ɂ�鎍�l�_�q�g��������76�̎���r��ѓ��k��̍�i�_�q�g������ ���r�ƂƂ��Ɍf�ڂ���Ɏ���B���̍������g�������ɐ��ʂ����肭�̂��A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�́q�ӏ܁r�ł���B�O�҂̎��l�_�͋g���� �Ƃ��Ă��d�v�Ȃ��̂ŁA�s�g�����t�ɏ������낵���q�N���r�́u���a�l�\�O�N�@���Z���N �l�\��v�̏��Ɂu�āA�k�c�c�l�������p�[���[�ŁA�����r�Y�̃C���^�����[����i�u�g��������76�̎���v�j�v�Ə����Ă���B�����̃C���^�����[��� �̑���Ƃ��āA�����r�Y�����œK�̐u�����������̂ł���B�����ɂƂ��Ă����̍�Ƃ͑傫�ȈӖ��������Ă����B�\�\�u�ڂ����g������̎d���ɐ^���ɑΛ����� �͓̂��B�Z���N�āA�v���Њ����㎍����14�w�g�������W�x�̂��߂Ɂw�g��������76�̎���x��L�y���̒������X�ł����Ȃ������ƁA���O�N��͂�āA���� ���_�Њ�����̎��l�P�w�g�����x�̍�i�ӏ܂̂��߁A���x�ɂ킽���Ă���ŕG�˂����킹�Ĉ�ш�т̐��藧���ɂ��ׂ������₵�������B�Z���N�͂܂������� ���o�����قǐ[���łȂ��A���O�N�͏�����E���Ă�������A�܂���������s�����A�Ǝv���B�^���ƂɌ�̂ق��́A�ڂ��ɏ�����E��������̍��g������������ ��A��Ƃ͑�ςł͂��������A���̂Ԃ�[�����Ė����������B�g���������ƏI����A�u����Ȕ��邱�Ƒ��肪�r�����Ȃ��Ⴕ�Ȃ��ˁv�Ƃ��������A�o ���オ��͂���Ȃ�ɋC�ɓ����Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ������낤���v�i�q�g�����̊��r�A�O�f���A���O�y�[�W�j�B
��
�s�g�����k����̎��l�P�l�t�͑S12�����琬���㎍�l�̑p���̑�1���B���p���ɋg�������s�A�ѓ��k��A�剪�M�Ƃ������s�k�t�̓� �l�A����M �v�A�c������A���c�O�Y�Ƃ������s�r�n�t�̓��l�A���m�A�J��r���Y�Ƃ������s�D�t�̓��l�A�Ί_���A��̂�q�A�g���K�q�Ƃ������������l�i�ȏ�͕X �I�ȋ敪�ł���A�����Ȃ���ł͂Ȃ��j�𑵂����̂́A�S���ҏW�̑剪�M�ƒJ��r���Y�ł���B�������_�Ђ́A�{�p���ɐ�삯�ē������^�ł�͂�ӏ܂�F���� �ɂ����k���{�̎��́l�S30���E�ʊ�1�i1967�`1970�j�����s���Ă���B�]�k�����A���̑�20���͒���d���E����\�O�Y�E�����V�g�E�R�V�����̎l�l �W�ŁA�ѓ��k�ꂪ�ӏ܂������Ă��鍂���V�g�W�̖{����94�y�[�W���ł���i�k����̎��l�l�͈�l��1���j�B�g���͒Ǔ����q�_�K�o�W�W���M�a����A���悤�� ��r�i�s�����C�J�t1987�N7�����q�Ǔ������V�g�r�j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���āA�����V�g����͂Ȃ����A�����̃V���p�I�Ȏ҂ɑ��Ă��Aᒂɂ����Ɨe�͂Ȃ��ɔl�����т���̂ŁA���͂��� ���͂�͂炵 �ǂ����ł����B������A���h���I�ɌĂяo����āA�u���x�������A�ѓ��k��̓z���Ԃ��Ă��v�ƁA���˂Ɍ����āA�����܂����B���̗��R�Ƃ́A������ �_�Ёw���{�̎��́x�̉���̂Ȃ��ŁA�ѓ��k�ꂪ�^�u�[�́u���鎖���v�ɐG��Ă��邩��Ȃ̂ł����B���͗F�l�̂��߂ɕٖ��ɂƂ߂܂��B���Ȃ��͂��łɓ`�� �̐l�ł�����A����������Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����������Ƃ������Ƃ́A���̐l�Ǝd���h���Ă��Ȃ���Ώo���Ȃ����ƂȂ̂ł�����A�ƁB
�@�ѓ��k��ɑ����`����ƁA���ĉ������̂ł����B�����V�g���x�X�d�b�������ė��āA���e�̐i���A���܂������Ă��邩�A�Ȃǂƌ����̂ŁA������ �����f���Ă����悤�ł��B��҂Ƌ����������Ă����A�u��Ƙ_�v�͐�������䂦�A���͔ѓ��k��ɓ�����̂ł����B�i�����A�l�O�y�[�W�j
�ѓ��k�ꂪ�G��Ă���^�u�[�́u���鎖���v�Ƃ͂Ȃ낤�B�������g�́q���`�r�i�����ɂ��җ�ȑ}�b���L����Ă���j����̈��p�łȂ� �Ƃ���A�� ���`���Z�y�[�W�ɂ����ẮA���邢�͓�O��y�[�W�̋L�ڂ��w���̂��낤���B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�ɖ߂�A�����Ɏ��^����āA�����r�Y�q�ӏ܁r ���t���ꂽ�g�������͈ȉ���7���W����A�v45�тł���B
�s�Õ��t�S17�т���5�с@�Õ��i�B�E3�j�^�҉́i�B�E12�j�^��i�B�E14�j�^���b�i�B�E15�j�^���̏�
���i�B�E16�j
�s�m���t�S19�т���6�с@�q�́i�C�E7�j�^�m���i�C�E8�j�^�ā\�\�x�E�v�Ɂi�C�E10�j�^��́i�C�E13�j�^���Ƒ��i�C�E14�j�^�����i�C�E19�j
�s�a���`�t�S22�т���3�с@�a���`�T�i�D�E4�j�^�a���`�U�i�D�E5�j�^�c�Ɂi�D�E10�j
�s�Â��ȉƁt�S16�т���1�с@������i�E�E6�j
�s�_��I�Ȏ���̎��t�S18�т���4�с@���́i�F�E3�j�^�������i�F�E10�j�^�ẲƁi�F�E13�j�^�O�d�t�i�F�E17�j
�s�T�t�����E�݁t�S31�т���14�с@�T�t�����E�݁i�G�E1�j�^�^�R�i�G�E2�j�^�}�_���E���C���̎q���i�G�E5�j�^�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�i�G�E9�j�^
���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�j�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�^����̔ӎ`�i�G�E13�j�^�c���i�G�E14�j�^�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�j�^����
�i�G�E20�j�^�ǎ�̏��i�G�E22�j�^�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j�^���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j�^�J�J�V�i�G�E28�j�^���N�i�G�E29�j
�s�Ẳ��t�S28�т���12�с@�y���i�H�E1�j�^�����i�H�E2�j�^�Ӊāi�H�E7�j�^���E���邢�͉āi�H�E12�j�^����i�H�E13�j�^���J�̎p������i�H�E
14�j�^�D���̎O�̒[�z�i�H�E16�j�^����ȏt�̗��i�H�E19�j�^�Ẳ��i�H�E20�j�^��i�H�E21�j�^��̊G�i�H�E26�j�^�~���̓����i�H�E28�j
��������I���W���P���Q�Ɋ܂܂��s�Õ��t�s�m���t�s�a���`�t�s��
���ȉƁt�s�_��I�Ȏ���̎��t�̎��тɔ䂵�āA����ȍ~�̎��W�ł���s�T�t�����E�݁t�s�Ẳ��t����̍�i�Ɏ�������Ƃ����̑I�̓����ł���B�����̊ӏ�
���ߍ�̓W�Ɍ����ȁu���p���v�Ɍ��y���邱�Ƃ̑����̂��ނׂȂ邩�ȁB
�u�Õ��v�B����͎��W�w�Õ��x�����̓�����i�l�т̂����̑�O�сB���̎O�т���r�I��l�����̂ɑ��āA���̈�т� �̂��́w�m ���x�ȍ~�̋g�������̕��G�ȍ\���̖G����܂�ł���悤���B���̍\�����ӊO�ɂ킪�����w�̔��z�\�\�ŏ��ɒ�o���ꂽ�C���W�����̃C���W���Y�݁A���̃C�� �W������ɂ��̃C���W�����N����Ƃ����L�I�̗w�ȗ��̎��@�ƒʂ���Ƃ��낪���邩������Ȃ����Ƃ��w�E���Ă������B�u�Ȃ����v�u��A�v�Ƃ����ג��� �C���W���u���ڂ������́v�Ɍq����A�u���ڂ������́v���u�������ցv�����сA�u�ցv���u���ƂƂ��ɌX���v�w�����[�X�́u�ցv�ł��邱�Ƃ���u���̏d�݁v �Ɂc�c�Ƃ����ӂ��ɁB��҂͂��̕��@����N�A�Z�́E�o��ɐe�������疳�ӎ��̂����ɋz�������̂��낤�B�o��Ƃ����A�Ӗ��Ƃ��ĂłȂ����Ƃ��Ē�o�� ��Ƃ����o��Ǝ��̕��@�����A��т����g�������̕��@���B�u���̂Ȃ��r�̓��́^�R���N�ɂȂ����^�ڂ���̈�A�v�Ɏn�܂�A�u�����M�ꂽ�܂܁^�ڂ���� ���^����ʂ��̂�ɐB����v�ɏI��邱�̈�сA�����ƋQ���̎���̐Õ���̕��@���肽���摜�A�Ƃ������ƂɂȂ낤���B
�{���̖`�����сq�Õ��r�i�B�E3�j�́q�ӏ܁r�ł���B�\�\���̈�т͂̂��́w�m���x�ȍ~�̋g�������̕��G�ȍ\���̖G����܂�ł���\�\ ���̍\������ �O�ɂ킪�����w�̔��z���L�I�̗w�ȗ��̎��@�ƒʂ���Ƃ��낪����\�\��҂͂��̕��@����N�A�Z�́E�o��ɐe�������疳�ӎ��̂����ɋz�������\�\������ �Q���̎���̐Õ���̕��@���肽���摜�\�\�B�����̑n��������̌�߂ɐD������Ă����s���͌������B�����͋g���̃R�����g�����g�́q�ӏ܁r�̑f�ނƂ� �ĕ����ɗn�����܂��ċL���Ă��邪�A�g�������Ď��M�������͂⍂���̎���ɓ������i�Ɣ��f�����j���e���I�Ɉ��p�����Ă��炨���B�Ȃ��A�W��̂��� �́i�@�j�̎��єԍ��Ɓ\�\�ȉ��͏��тɂ���L�ł���B
�E�u��v�i�B�E14�j�B���Ƃ������̂Ƃ̏o����A���Ȃ킿�Õ��Ƃ������Ƃ̏o��������A�ƍ�҂͂����B�\�\�g���̏��a24�N8��
1���̓��L����B
�E���̎��I�t�̒����琶�܂ꂽ�̂��w�m���x�A�O���W���Õ������ɂ��Ă���̂ɑ��āA�l�Ԃ����ɂ��Ă���Ƃ����邩������Ȃ��A�ƍ�҂͂�
���B�Ȃ��Õ��̂��Ƃ��l�Ԃ��H�@�ɂ��āA���l���W�܂��Ắw�Õ��x�̏o�ŋL�O��̂����A�o�Ȏ҂̂ЂƂ肪�u���ꂩ��͐l�Ԃ������Ă��������v�Ɣ�������
���Ƃ����������ɂȂ����A�ƍ�҂͏q�����Ă���B�\�\ �g�����E�剪�M�k�Θb�l�q���`�̐��E����r����B
�E���̍�i�k�u�m���v�i�C�E8�j�l�̒��Ő��������̂ŁA�Ȍ�J�Ԃ��̎g�p�݂͂�����ւ����A���łɂ����u�m���v�Ƃ������t�A�I��̃p�[�g�ɏo�Ă���
�u����v�Ƃ������t���A�Ȍ�̎g�p�����ւ����A�ƍ�҂͂����B�k�c�c�l�Ȃ��A�u����ł��ĂȂ��a�C�v�Ƃ����\�����A��҂͈Ȍ�̐����Ƃ��Ă���B
�E�k�u�����v�i�C�E19�j�l�h�������̒B�X�^���`�b�`�́u�����v�̉e���͑薼�̂ق��قƂ�ǂȂ��ƍ�҂͂������A�`���ɒ����u�傫�Ȃ悾�ꂩ��
�̏�v�́u�����v�͂����炩�ɃX�^���`�b�`��i���痈�Ă���B�k�c�c�l�Z�������̉i���̑��B�B�k�c�c�l�u�o���s�݁^�o���Y�ށv���炾�B���̃p�[�g�̍Ō��
�Z�s�͍�҂ɂ��ΈɒB���v���ł��܂߂��Ƃ��낾���A���߂̌�������ۂ��Ă���Ƃ����Ӗ��ł��ł����̌���Ƃ��č��܂��Ă���Ƃ����邾�낤�B�\�\�g����
���z�q�u�����v�Ƃ����G�r����B
�E�u�O�d�t�v�i�F�E17�j�B�k�c�c�l���̏����I���@�ɐ[���肵�Ȃ��������A�[���肵�Ă݂邾���̉��l�͂������A�ƍ�҂͏q�����Ă���B
�E�u�T�t�����E�݁v�i�G�E1�j�B�w�����V���x�[���������́u�����m�[�g�v�A�O�Y��Y�����ɂ��lj�u�T�t�����E�݁v�����̋L�������z�̌��_�ɂȂ��Ă���B
�j�����������߃T�t������E��ł���̂����N�ł��邩���ł��邩�s���Ƃ����L�q����҂̒��ӂ��䂫�A���̈����ׂ���т��Y�܂�邫�������ɂȂ����B
�k�c�c�l�����A�_�����Ƃ����Ă��U���̘_���ł͂Ȃ��A�����܂ł����̘_���ł���A��҂����͓�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������̓�́A�_�����̂䂦�ɂ�������
��������ƍۗ��Ƃ������ʂ��l�m���n�Ă���B
�E�u�^�R�v�i�G�E2�j�B�k�c�c�l�e�����B
�W�����Ō����^�R�̌�ځE�r���̉f�����_�@�ɂȂ��Ă���ƍ�҂͂������A���̉f���̂��Ȃ�v���~�e�B���ȕ`�ʂ��܂̎U���`�����ŁA���������œ��
�s��������������Ƃ����T���h�C�b�`�\�����A���̍�i�̓����ł���B�\�\�g���̎U���q�q�^�R�r�����r����B
�E�u���C�X�E�L��������T�����@�v�i�G�E11�j�B�������@�_�̗����Â��Ă�����҂��v���Ԃ�̎v�������Ȃ��݂��݂������œǎ҂��������A��҂��V������
�n�ɓ��������Ƃ��������L�O���ׂ���i�B�w���㎍�蒟�ʍ��x���C�X�E�L���������W�̎ʐ^�y�[�W�ɃL���v�V�����ł��ƌ����ċC�y�Ɉ������ʂ����̍�i
�ƂȂ����B�\�\�����N��q�g�������A���X���ɏo������Ƃ��r����B
�E�u�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�v�i�G�E17�j�B�k�c�c�l��ҏ����̏����O�j�Ƃ����Ⴂ��Ƃ̔L�̊G�����z�̊j�ɂȂ��Ă���A�ƍ�҂͂����B�k�c�c�l�u������
���đ�E�����������L�v�ɂ��Ă͂������낢�}�b������B�G���͂������Ƃ��̔L�ɂ����E���Ȃ��̂ɋC�Â��ĉ�Ƃɓd�b����ƁA�����������ē��ʑ傫�ȕE��
�`�����A�ƁB
�E�u�ǎ�̏��v�i�G�E22�j�B�k�c�c�l���̍�i��������ꂽ����C���Ƃ͓y���F�Ⓜ�\�Y�̉�A���邢�͒N�ނ̌W���ŏo����ĉ�b������x�̕t��������
�����A�ނ̎��͂ɏW�܂�l�l�̂������ł͂�����N��߂��Ƃ������Ƃ������āA�̒_���Ƃ��Ă����Ǝv���A�ƍ�҂͂����B�k�c�c�l�薼���́u�ǎ�v�͍��
�̍D���Ȍ��t�̂ЂƂ����A�����܂ތ���|�p�̐Â��ȁA���������R���铱����ł���Â�������C���ɂ͂܂��ƂɓI�m�Ȍ`�e�Ƃ����ׂ����낤�B
�E�u�]���l���V���^�[���̑D�v�i�G�E24�j�B�k�c�c�l��҂̃]���l���V���^�[���Ƃ̏o��͈��Z�l�N����؉�L�̌W�̎����A�Ƃ����B
�E�u���e�j�i�O�m�[�����j�v�i�G�E27�j�B�k�c�c�l��҂��F�V���F�̏o��͈��Z�Z�N���s�̉��������W�w�`����w�x�̐V���Ȃ����ł̏o�ŋL�O��̂���
�������B�ނ�������]�����Ă���Ă��邱�Ƃ�m���ĈȌ�}���ɐe�����Ȃ����A�ƍ�҂͂����B�k�c�c�l�P���`���̈��p�͉�����̂��̂��s�ځB��҂�����ɂ�
�L�����Ȃ��B���̈��p�����̋L�����s�m���Ƃ����̂����̍�҂̑傫�ȓ����ŁA���ꂾ���n�̕��ƈ��p���������ɗn�������Ă���Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�\�\
�u��҂��F�V���F�̏o��͈��Z�Z�N���s
�̉��������W�w�`����w�x�̐V���Ȃ����ł̏o�ŋL�O��̂��肾�����v�́A�F�V�Ƃ̏o��ł͂Ȃ��y���F�Ƃ̏o����낤�B����Ƃ����̂��A�g����
1960�N4��6���̓��L�Ɂu�a�F�v�ȂƂ������̂ށv�Ə����Ă��邩�炾�i�L�q�̒��q���炢���Ă��A���Ζʂł͂Ȃ��������j�B
�E�u���N�v�i�G�E29�j�B�k�c�c�l�Ȃ��A���p�̂قƂ�ǂ͖���v���w���B�[�i�X�̐_�b�x���B
�E�u�����v�i�H�E2�j�B�k�c�c�l���p�̓C�[�Y���E�p�E���h���̑��B���p�ł͂Ȃ����A�q�y��m�t���[�Y�n�r�Ƃ��������p�E���h�ɂӂ��킵���B
�E�u���E���邢�͉āv�i�H�E12�j�B�y���F�̕��͂Ƃ�������^�Ƃ������A�ނ̌��t���Ȃ������琶�܂�Ȃ������낤�A�ƍ�҂͂����B�\�\�g���̒����q���_��
���Ƃ��r�ɂ����l�̎�|��������Ă���B
�E�u����v�i�H�E13�j�B�k�c�c�l���p�͔ѓ��k��A�C�[�Y���E�p�E���h���̑��B
�E�u���J�̎p������v�i�H�E14�j�B�k�c�c�l�ѓ��k�k��l�͍�҂��͂��߂ďo��������l�ł���A�������̏o����Ȃ������玍�������Â������ǂ����킩
��Ȃ��Ƃ����A�d�v�ȗF�l�ł���B�\�\�g���̐��z�q�ѓ��k��Əo��r����B
�E�u�D���̎O�̒[�z�v�i�H�E16�j�B�k�c�c�l��҂Ƌ{��k�~�l�̊ւ��͋{��̐����������̈���ł���w���p�̐D���x�̑��B����҂��S�����A���̏o����
������{�삪���Ƃ̂ق���A�Ƃ����W�����̂��B�k�c�c�l���ꂾ�������̈��p�����Ȃ���A�g�ӂɏ�����u���Ȃ��Ƃ����G�s�\�[�h�ɂ��䂩�ꂽ�B�k�c�c�l
�{��~�͂܂��������̂����������Ȃ��l�A���_�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv��ꂽ�A�ƍ�҂͂����B�k�c�c�l�����p�͂�����R���Z�v�`���A���E�A�[�g�̌��_��
�������ׂ��}���Z���E�f���V�����̑�\��u�ޏ��̓Ɛg�҂����ɂ���ė��ɂ��ꂽ�ԉł������v�ɂ��Ă̋{��~�̕��͂���B
�E�u�Ẳ��v�i�H�E20�j�B�k�c�c�l�������A����͕��͂̐����Ƃ������̂ŁA��҂͌��݂��q�Ȃ̂������r�ƌĂ�ł���悤���B�k�c�c�l���p�̎��͂قƂ�
�ǐ��e�̎U������B���e�̎U���̊�ȍ��C�͂��̎��ɗ�炸��҂̈�����Ƃ��낾�B�k�c�c�l�W�����e���O�Y�̌��t�ō�҂��ł��D���Ȃ��̂̂ЂƂB����
�����āA�����ł���ɕt����������͉̂����Ȃ��A�ƁB�\�\�g���̐��z�q���e���O�Y�A���x�X�N�r����B
�E
�u�~���̓����v�i�H�E28�j�B�k�c�c�l�剪�k�M�l�͔ѓ��ƂƂ��ɍ�҂̍ł��Â��A�S���������������l���Ԃł���B�k�c�c�l���R�̂��ƂȂ����҂ɂƂ��Ă�
���p�̐��m�x����i�̊����x�̂ق������Ȃ̂ł���B�Ȃ��A���̍�i�Ɉ��p���ꂽ�o�T�ɂ��ẮA�Ƃ��ɑ剪�M���̋������B��҂���т̍�i�̊���
�x�̂��߂ɂǂ�قnj��T�ɉ������A���邢�͂܂�����邩�̗�Ƃ��āA�����Ɏ����̂��Ӗ��̂Ȃ����Ƃł͂���܂��B�\�\�g���̐��z�q�剪�M�E�l�̒f�́r��
��B�Ԃ��Ɍf���邱�Ƃ͂��Ȃ��������A�q�~���̓����r�́q�ӏ܁r�͑剪�M�Ɂu�������v�����ɁA�s�Ẳ��t�̈��p���тƂ��̃X���X�Ɋւ���ł����ׂ�
���͂ɂȂ��Ă���A�q�~���̓����r�_�Ƃ��ę��ڂɒl����B�g�����g�A���p���Ƃ��ğӐg�̗͂����߂��Y�тł���B
��
�ȏ�̖{�тɑI��i�Q�ƁA�g�����������낵������ɂ��Ắq�O�̑z���o�̎��r�̎O�т͏d�����Ȃ�����A������̎O�тɂ�����g
�������̋����[���ӏ������Ă��������B
�E�u���E�H�̊G�v�i�D�E21�j�́A���p�G���Ō����A�V�������A���X���̏�����ƃ��I�m�[���E�t�B�j�̊G���ނɂ������̂��B�����Ă݂�A���t��
�͎ʂ����悤�Ȃ��̂ł���B��C�̗������߂锖���̏��ŁA�������Ă���u�킪�A�t���f�B�[�e�[�v�ƁA�����ĉ������Ă��悢�B�\�\�u�͎ʁv�����̂܂�
�Ƃ��Ď��тƃt�B�j�́q�I���r�i1949�j���r�ׂĂ݂�ƁA��ؓ�ł͂䂩�Ȃ��B�͎ʂ̂��߂̖͎ʂ̂悤�Ȃ��̂́A���I�z���͂�������|���Ȃ̂��B
�i�u������ԁv�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i3�j�\�\�q���́r�j
�E���̎��сk�q�Â��ȉƁr�i�E�E16�j�l�́A���̕��Y���̂悤�Ȃ��̂������B�u���E�H�̊G�v�͂��łɏo���A���̖�́A�u�C���Əȗ��v�ɖv�����Ă����B�[
��ꎞ����A���Ɋ��������B�ق��Ƃ��A���ł�����ĖႨ���ƁA�ׂ�̕�����`���ƁA�Ȃ̎p�������Ȃ��B�����A�����֍s�����̂��낤���B���܂łɂȂ����Ƃ�
�̂ŁA�s���ɂ���ꂽ�B���͏��݂Ȃ��܂܁A���e�p���Ɍ����Ă����B����ނ���S����߁A�C���܂���킷�ׂ��A�����L�q�̕��@�Ŏ��������͂��߂��悤�Ȃ���
�������B�^���ꂩ��A�ꎞ�Ԃقǂ��āA�Ȃ��A���ė����B���x���̎��A���̎����A�u��������l�A���Ă���v�̈�s�ŁA�������Ă���̂��B�k�c�c�l�u�Â���
�Ɓv�́A���̍�i�̒��ł��A�Z���ԂŐ��������ٗ�̎��тł���B�\�\���͂��̂������ǂނ��тɁA1965�N6��14���A�킸������Ńr�[�g���Y�̃���
�o�[�S���ɂ��qI've Just Seen A Face�r�ƁqI'm
Down�r���A�|�[���E�}�b�J�[�g�j�[��l�ɂ��qYesterday�r��^���������Ƃ�z���o���i��Ȃƃ��[�h���H�[�J���͂�������}�b�J�[�g�j�[�j�B
�qYesterday�r����҂����钩�A�N�����炷�łɊ��S�ȋȂ̌`�ő��݂��Ă����Ƃ����i�̎��͂��Ƃ�������ɏ[�Ă͂߂āA���t�����l�ɂ��Ƃ��珑��
���j�B
�E���̎��k�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�l�ɂ́A�u�y���F�̔�V�ɂ悹�āv�Ƃ̎�����������B�ѓ��k��̏Љ�ŁA�y���F��m��A���߂ĈÍ�������
�u�Q�X���[�E�e���Q�y�i�i�V�j���_�z�v���A������قŊςāA�Ռ�����
���B�k�c�c�l�ȗ��A���͐e�����|�p�Ƃ����̏ё����A���������ŕ`���悤�ɂȂ����B���ꂾ���ɁA�ŏ��̂��̎��͎v���o�[�����̂�����B�k�c�c�l���͍��܂ŁA
����̉�����������Ƃ��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u�����́v���A�����Ȑ������o���Ȃ����A�܂������Ȃ����炾�B�o��A�Z�̂����Ď��̂悤�ȒZ���^�ł́A��҂̍�
�i�����قǁA�����߂Ȃ��̂͂Ȃ��ƁA�˂Âˎ��͎v���Ă���̂��B
�������Č���ƁA�s�T�t�����E�݁t��s�Ẳ��t�i����т���ȍ~�̎��W�j�Ɂu���p���v�������ɑ傫����^���Ă��邩���킩��B�q�����r ��q���E�H�� �G�r��������̊O���̑��`��Ƃ̍�i����G������Đ��������Ƃ����ڂɒl����B�Í������`�̈��Ƃ���Ȃ�A�g�������y�ɂقƂ�ǎ䂩��Ȃ������� �́A���ꂪ���Ԃ̒��ɕϖe����|�p�ł��邱�Ƃ����邱�ƂȂ���A�u���v�������Ȃ����Ƃ��ő�̗v���������̂ł͂Ȃ����B�������������̍D���Ȃ����y�Ɓu�� �p���v�����A�g�������ɋ�̓I�Ȋy�Ȃ��قƂ�Ǔo�ꂵ�Ȃ����Ƃ͕ʓr�l����K�v������B
�G�{��ƁE�}�G��Ƃ̑��c�唪����2016�N8��2���A�S���Ȃ�ꂽ�B97�������B�q�ŋ߂́q�g�����r�r�ɏ������悤�ɁA���c����͋g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̔��s�҂ł���B1955�i���a30�j�N�Ƃ����A���c���}�G��ƂƂ��Ċ������n�߂ĊԂ��Ȃ����낾�B�O�Y��m�ҏW�́s�����C�J�t1973�N9�����k���W�E�g�����l�Ɋ��q�J�����I���̊�r�͋g�����Ƃ̏o���l��������ė]�����̂Ȃ���z�����A���c����̒����ɂ͎��߂��Ă��Ȃ��悤���B�Ǔ��̈Ӗ������߂āA�������f����B
���c����̐�������e������\��Ƃ��ċ����Ă���̂́A����̊G�{�s�����t�i�����o�ŁA1975�j�Ɓs���������Ƃ��݁t�i�����ُ��X�A1979�j�A�����đ��c����̊G����������E���s�ҁE���R���q���肽�Ă�s�G�{���V�L�t�i���S�ЁA1997�j�ł���B��������ʌ��삾���A�����ł͑}�G�{�Ƃ��Ă̏�����A�W���[�G����`�����h���[��n���X��E���g������s�������Ƃ��˂̂�������ׁ\�\���[�}�X������̖�b�k���ǂ��G���ɂP�l�t�i�H�c���X�A1949�N11��10���k���ł̔��s��1949�N10��5�����l�j��ǂ�ł݂����B���c����͂��̖{�ɂ��āu�G�{�ւ̓��͓ˑR�J�����v�Ƃ��āA�����ُ��X ��̗F�ҏW���s�G�{��Ƃ̃A�g���G �P�t�i�����ُ��X�A2012�N6��10���j�ł�������Ă���B
�s�������Ƃ��˂̂�������ׁt�͐j����2�ӏ��A���Ԃ������t�ڂ̖{���p�������\���ł���p�w�E�����̏㐻�{�ŁA�ꔪ��~�ꎵ�Z�~�����[�g���A�����y�[�W�B���Ԃ��̌��J���ɐԈ�F�ɂ�铮���̃J�b�g10�_�i�O���Ԃ��E�㌩�Ԃ��Ƃ������}���j�A�����Ɏl�F�̕ʒ����G�ƐF�ƐԐF��F�̖{���B�{���i�X�~��F�j�ɑ}�G�v25�_�B�s���b�Y��t�i�������㖖���`���q���㏉���j��f�i�����錩���ȏo���ŁA�����삩�炱�̐����̍�i�ݏo�������ƂɊ��Q����B
 �@
�@
�W���[�G����`�����h���[��n���X��E���g������s�������Ƃ��˂̂�������ׁ\�\���[�}�X������̖�b�k���ǂ��G���ɂP�l�t�i�H�c���X�A1949�N11��10���k���ł̔��s��1949�N10��5�����l�j�̕\���i���j�Ɠ��E���Ԃ��̌��J���i�E�j
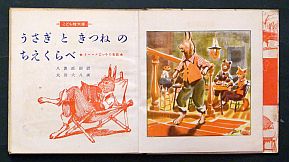 �@
�@
���E�{���ƌ��G�i���j�Ɠ��E�{���Ō�̑}�G�i�E�j
�i�E�b�E�n���X�́u���[�}�X������v�iUncle
Remus�j���̂́A�ߔN�̔łł͉͓c�q�Y��s���[�}�X������̕���\�\�A�����J���l���b�W�k�u�k�Е��Ɂl�t�i�u�k�ЁA1983�j�����肵�₷���B�����ŁA1960�N��܂ł̔��g����T�ς��Ă������B
 �@
�@ �@
�@
�W���[�G����`�����h���[��n���X��E���g������s�������Ƃ��˂̂�������ׁ\�\���[�}�X������̖�b�k���ǂ��G����
�P�l�t�i�H�c���X�A1949�N11��10���k���ł̔��s��1949�N10��5�����l�j�́q�������́@�����ȂƂ�r�̑}�G�i���j�ƃ`�����h����n���X��E���g������ҁs�������ǂ� ���˂ǂ�P�k�q�ǂ��}���فl�t�i����{�}���A1967�N12��10���j�́q�������ā@�����@���́@�����@���́r�̑}�G�i���j�ƃ`�����h����n���X��E���g������ҁs�������ǂ� ���˂ǂ�P�k�q�ǂ��}���فl�t�i����{�}���A1967�N12��10���j�Ɠ��Q�i���A1969�N7��10���j�̕\���k�����F���c�L�l�i�E�j
�@�̐��E���w�Дł͖{���Ɠ��N��2��25���̊��s������A���c�����̎Q�l�ɂ������킩��Ȃ����A�B�̊�g���N���ɔł̂`�E�a�E�t���[�X�g�̊G�͌��{�ɂ��������̂��낤����A���Ă���͂����i�u�k�Е��ɔłɂ̓t���[�X�g�̂ق��A�R���f�A�`���[�`�A�P���u���A�r�A�[�h�̑}�G���ڂ��Ă���j�B�D�E�͑������ŁA���c����͇A�Ƃ͂܂������قȂ�A���w�Z��w�N�����̊G�{���̊G��V���ɓ�F�ŕ`���Ă���B���c����̍ēo�́A��҂ɂ���]���낤���B67�N�O�̖{���i�A�j�̖��Ȃ�Ƃ��f���炵�����̂Ȃ̂ŁA�q�������́@�����ȂƂ�r�i�D�ł́q�������ā@�����@���́@�����@���́r�ƂȂ��Ă���j�������B
��T��@�������́@�����ȂƂ�
�@������̂��ƁA�������ǂ��A���˂ǂ��A���炢���܂ǂ��A���܂ǂ�ȂǁA�݂�Ȃ�����āA���߂�������₵�A�Ƃ����т������A���邱�Ƃɂ����ˁB
�@�݂�ȁA��������ɁA�͂��炢�Ă�B���Ă�Ƃ��@����Ă����B�������ǂ�A����Ă��܂����B����ł��A�݂Ȃ���@�Ȃ܂����̂��Ɓ@����ꂽ���Ȃ������̂ŁA���m�����n���Ђ��ʂ��āA�݂�������Ȃ��Ă��B����ǁA���炭����ƁA
�@�u�������I�@��ɂ���m�A�A�A�n�̂Ƃ������������I�v
�ƁA�傫�Ȃ����łǂȂ�A�݂Ȃ̂���Ƃ��납��@�͂Ȃ�āA�m���n�����ւ������Ɓ@�łĂ������B���炭�����ƁA��ׂ̂��������@���ǂ��������ˁB
�@�u�����́A�������������B�ЂƂA���̂�ׂ̂Ȃ��Ɂ@�͂����āA�Ђ�˂����Ă�낤�B�v
�ƁA�������ǂ�A��ׂ̂Ȃ��ɁA�҂��ƂƂт��ȁB����ƁA��ׂ́A�ǂ��Ȃ����Ƃ������ˁH
�@�����B�����A��ׂ́A���邷��ƁA���ւ��ׂ肨���Ă�������B�������ǂ�A���ǂ낢���̂Ȃ�́I�@�ǂ��܂Ł@�����Ă����A�킩�����̂ˁA
�@�Ƃ��낪�A�����ɁA�ς����ƁA��ׂ����ɂ��������B�������́A�����Ƃ������܂��Ă��B���ꂩ��@�ǂ��Ȃ���̂��A�ƁA�������łȂ��B�Ԃ�Ԃ�A�Ԃ�Ԃ�A�ӂ邦�Ă������B
�@�͂Ȃ�������āA�͂����̂��˂ǂ�B�������ǂ�@�ڂ��͂Ȃ��Ȃ��ł���ƁA�������ǂA�͂��炭�̂���߂āA�łĂ�����������A�����ƁA���̂��Ƃ���A���Ă������̂��B
�@�Ȃɂ�������肾�낤�A�ƁA�݂Ă�ƁA���ǂ̂Ȃ��ɂƂт��ނȂ�A�݂��Ȃ��Ȃ�������Ȃ����I�@���ǂ낢���ˁA���˂ǂ�B���m�����n�̏�ɁA�ǂ���Ƃ����ƁA���т��Ђ˂��Ă������B
�@����ǁA�����ς�@�킯���킩���B
�@�u�����́A�т����肵���ˁB�͂ĂƁB�������ǂ�A���̂��Ȃ̂Ȃ��ɂ����˂ł��������Ƃ�̂��ȁH�@����Ƃ��A��������̂ł��@�݂��������̂��ȁH�@�悵�A�ЂƂA�݂ɂ������Ƃɂ��悤�B�v
�@�ƁA���ǂ̂��ցA�͂�����āA�������Ă����A�Ȃ�̂��Ƃ��@�������Ă��Ȃ��B�����������āA���̂Ȃ����@�̂����Ă݂����A�Ȃ�ɂ��݂��Ȃ��B
�@���āA�������ǂ�̂ق��́A���킭�ĂȂ�Ȃ��B�������ł��A�݂�����������A��ׂ��炨���Ă��܂��Ƃ������ƁA���������������A�����̂�̂��Ƃ��@�ƂȂ��Ă��B
�@����ƁA���˂ǂ�̂����������B
�@�u�������I�@�������ǂ��I�@�����ŁA����Ƃ����Ă���H�v
�@����ƁA�������ǂ@�ւ����B
�@�u�ڂ����ˁA����A������Ɓ@�����Ȃ���@����Ă�̂��B�݂Ȃ���̂��Ђ�́@���������ɁA�����Ȃ����������悤�A�Ƃ������ĂˁB�v
�@�u�������ǂ�A���̉��̂Ƃ���̐��ɂ́A�����Ȃ��������邩���H�v
�@�u������ł������A���˂ǂ�B�Ȃ�\�҂��A�Ȃ�S�m�т₭�n�҂����ĂˁB�����ȂŁ@�����@�킫�����邭�炢����I�@�ǂ������A���˂ǂ���A�����ւ���Ă��āA�����ȂƂ�́@�Ă��������Ă���Ȃ����ˁH�v
�@�u�ǂ�������A�����ւ���Ă�������H�v
�@�u�����́@��ׂɁ@�Ƃт���@�����B���邷����ƁA���ւ�����邺�I�v�@
�������ǂ�̂͂Ȃ����A�ƂĂ����܂��āA���̂��������������̂�����A���˂ǂ�A����ꂽ�Ƃ���A��ׂɂƂт̂����B����ƁA��ׂ́A���邷�邷��I
�@�Ƃ��낪�A���˂ǂ�̂������ŁA����ǂ́A�������ǂ�̂̂�����ׂ��A�͂��ɁA���邷�邷��A�ƁA��ւ������Ă����ȁB���傤�ǁA�܂�Ȃ��̂Ƃ���ŁA�ӂ��̂�ׂ��A���ꂿ�������Ƃ����B�������ǂA����Ȃ������@�����������B
�@�@����Ȃ�@���˂ǂ�@��������悤
�@�@�����Ă����ł�@����������
�@�@�������Ă������́@��������
�@�@���́@���邷��@���ǂ̂���
�@���ǂ̂��Ƃւł�Ȃ�A�������ǂ�A�ǂ�ǂ������A�ɂ��̂���Ƃ���ւ����āA
�@�u���˂ǂA���ǂ̂Ȃ��ւ͂����āA�������́A�̂ސ����悲���Ă܂���B�v�ƁA�ǂȂ����B�����āA�܂��A�������łЂ��������A���ǂ̂Ȃ��́@���˂ǂ�ɂ������B�\�\
�@�@�Ă��ۂ������ā@�ɂ�ǂ�
�@�@�������Ł@�������ց@����Ă���
�@�@�Ђ�������ꂽ��@���˂ǂ�
�@�@�����Ɂ@�ɂ������@������������I
�@
���ꂩ��A����������قǂ����Ƃ��A�͂����ł́A�������ǂ�Ƃ��˂ǂA�ƂĂ��������Ɓ@�͂��炢�Ă����B����܂ŁA����ȂɁA�˂�����ɁA�͂��炢�����Ƃ́A�����ǂ��Ȃ��������炢�ɂˁB�����A�Ƃ��ǂ��A�������ǂ�́@�Ղ��Ƃӂ������Ă�炢�A���˂ǂ�́A�������������悤�Ɂ@�ɂ�ɂ�A�ɂ���炢�����Ă��Ƃ��B�i�s�������Ƃ��˂̂�������ׁt�A��Z�`��l�y�[�W�j
���l��́m�S�X�y���n�������b�N�����[���i1949�N�����A�܂��a�����Ă��Ȃ����j��z�킹�邱�������앗�\�\�n���X�̌����ɂ�����̂Ȃ̂��A���g�̖̂��̂Ȃ̂��킩��Ȃ��\�\�ɁA���c�����A���ȃy����̑}�G�ʼn��������ƂɏՌ����o����B�u�k���a��\��N�l�\�\����@�����̂Ƃ���ŁA�ˑR����ς�������F���ɂ������Ȃ���ꂽ�B�ɂ��������ǂ����悤���Ȃ��B���O�B�ł����͑��v�Ȃ̂ň��S����B�s�Ԃƍ��t����݂Â���v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j�BNDL-OPAC�Ō�������ƁA���c�����1949�N����50�N�ɂ����ĉH�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl�ŁA�Z�M���[���v�l�i��͉ؗq��j�s���o���̂�����t�A�O��ߎq�s�A�t���J�̈̐l�\�\�V�����C�c�F�����m�t�A���L���Y�s�R�C�̎q�̗��t�A���c�O�Y�s�������̐l�C���́t�A�a��G�Y�s���̕�t�A�k�쓹�F�s�������̂�����t�A��Y���V�s�ق����D�ɂ̂��āt��7�^�C�g���̊G��S�����Ă���B�H�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl20�����i1949�N�`51�N�j�́A�}�����[�́k���w���S�W�l�S100���i1951�N7���`1957�N11���j�ɐ�s�����悾��������A�g�������c�����K�˂��̂́k���ǂ��G���Ɂl�Œm��������ɈႢ�Ȃ��B�u�܂��}�����[�̏��w���S�W���n�܂����Ƃ��A���̑}�G�̈˗��ɗ����g�����́A����Z�N�ނ��v����܂ʼnƑ����l�̐e�����F�l�ƂȂ�܂����B�ނ͐��ő�̎��l�ƌ����A�ނ̎�������r�W���A���ȃC�}�W�l�[�V�����́A���̃C���X�g���[�V�����̂悢�h���ɂȂ��Ă���ɂ���������܂���v�i���c�唪�s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�A�a�k�o�ŁA2009�N7��1���A���`�ܔ��y�[�W�j�B���Ȃ݂�NDL-OPAC�Łu���ҁ����c�唪�~�o�Ŏҁ��}�����[�v����������ƁA����23�����q�b�g����i���X�g�́u�V�Łv�͍Ċ����낤����A�^�C�g���̎�����23��������j�B�������Ă��Ȃ����A���L���Y�̋��̖{�A��Y���V�̕ߌ~�̖{�����c����̎�|�������V���[�Y�ɓo�ꂵ�Ă��āA�����[���B�����ŗ]�k���B�����E���̓��{�ߑ㕶�w�ُ����́s�}������Ԃ�t�i��3��A1���E11���E21�����s�j��6���E7���E9���E10���i1959�N6��11���`7��21���j�ɐ��Y�w�҂Ő��M�Ƃ̖��L���Y�i1904�`88�j���R�����s���̍Ύ��L�t��A�ڂ��Ă���i�q�A���r�q�h�W���E�r�q�}���{�E�r�q�E�i�M�r�j�B�s�}������Ԃ�t���̂ɋg�����֗^�����`�Ղ͌����Ȃ����A�k���w���S�W�l�ȗ��̒S���҂Ƃ������ƂŁA���̘A�ڂɊւ���Ă��邩������Ȃ��B�]�k�I���B
������ɂ��Ă��A���c���G�{��}�G�̎d���Ƌ��R�o�����āA�H�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl����ɁA�}�����[���k���w���S�W�l��k���w���S�W�l�ɘr�������Ă������a20�N��㔼�A�g���͂̂��́s�Õ��t�ɂ܂Ƃ߂鎍�т��Ђ����ɏ������ł����B�����̋g���ɂƂ��čł��g�߂ȊG���i�Ƃ́A���c�唪���g�c���j���q���̖{�̂��߂ɕ`���������̑}�G�������ƌ����Ă��������낤�B���܂�ɐg�߂����āA���W�s�Õ��t�̃��B�W���A���ɋN�p����̂����߂��ꂽ�قǂ������i�����W�́u���v�̊G�͐^�甎�̎�ɂȂ�j�B�������A���c����͋g�������߂Ď��l�̎��o�������ďo�ł������ƔŎ��W�̔��s�҂Ƃ����h�_��S�����B��N�A�g�����̓��b�i�I�j�ɑ��c�唪���G������Ƃ�����悪�������Ƃ������A�������Ȃ������B���܁s�Õ��t�̒��҂Ɣ��s�҂͓V��̂ǂ����ŁA��l�����т������낤�s�������Ƃ��˂̂�������ׁt��O�ɂ��āA������܂������̒�߁A�ƌ�肠���Ă���̂ł͂���܂����B

���c�唪�q�E�T�M���p���Ȃ�Ƃ��r�i1977�j�k��쐟�q�u�����w���̐��E����v�^���E�����Ёl
�o�T�F�s���{�̓��� 13�k�������E���c�唪�E�x������l�t�i���@�K�o�ŁA1981�N8��10���A�l�l�y�[�W�j
��쐟�q���i��F���˃P�C�R�E����q�E���I�q�E�F�숟��ǁE���c�唪�E���쎛�}�����E�i�C�E���]�^���E����G�V�E�q���q�E���i���Y�E�����j���j�s�����w���̐��E����k�����w���̕���3�l�t�i���E�����ЁA���s�N�����L�ڂȂ��j�ɑ��c�����q�E�T�M���p���Ȃ�Ƃ��r�i1977�j�ɓo�ꂷ��l���́A�h���E�L�z�[�e�ƃn���t���[�E�{�K�[�g�ƃA���X���B�����A���̊O�̊X�p���E�T�M���Ȃ��鏈�́A�ǂ����Ă��o���e���X���i�������s�A���X�t�̃E�T�M�Ȃ̂����A�s�������Ƃ��˂̂�������ׁt�̂������ƍ��o�������ɂȂ�j�B���Ƃ̃R���{���[�V�����̐�ɁA�`����邱�Ƃ̂Ȃ������g�����Ƃ̓��b����W��z���������Ȃ�͎̂������ł͂Ȃ����낤�B�Ƃ���ő��c�唪�Ǝ��l�̃R���{���[�V�����Ƃ����A�J��r���Y�Ƃ̎���W�s���l�̕�t�i�W�p�ЁA2006�j�ƁA�������Βk�k������F�R�c�]�l�s���l�ƊG�`���\�\�q�ǂ��E�G�{�E�l����������t�i�u�k�ЁA2006�j���z�������ԁB���c����͌�҂Łu�����̈���̊G�{�v�Ƃ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă���B
�R�c�@���c����́A���炭�͒����d������߂āA�����ɊS������d�������ɏW���������Ƃ���������Ă��܂����ˁB���̂�����̂��Ƃ�b���Ă��������܂����B
���c�@���̂��Ƃ̒��ɁA���A���e�B�[����������̂ƒ��ۓI�Ȃ��̂�����Ɠ����悤�ɁA�G�̒��ɂ��A�����I�Ȃ��̂ƒ��ۓI�Ȃ��̂�����Ǝv����ł���B�ڂ������������肽���̂́A���܂����e�[�}�Ɍ����ĕ`���Ƃ����̂���Ȃ��āA�����̐S�̒�ɂ��钊�ۓI�ȕ�����`���o�������킯�ł��B������ˁA�G�{�ɂł�������ȂƎv���Ă���B���ꂪ������̊�]�ł��B�́A�F�B�ɋg�����i���l�A�����`��Z�N�j�Ƃ������l�����ĂˁB�ނ̎������`�[�t�ɂ��ĕ`�������ȂƁA�v�������Ƃ������ł���B�ł��ނ̏ꍇ�ǂ������Ƃ����Ƃ��Ȃ�Â��ʂ���������A�[���Ȗʂ��������肵�āA���邳���Ȃ��B���邢���́A�Â����́A�����ɏo����ĕ`������̂����ȂƎv���킯�ł��B���������肢�������ł���B
�R�c�@���������G�{�����肽����ł��ˁB
�J���@����̓e�L�X�g�������Ă��A�C�ɓ������Ă������Ƃ��������ł����B����Ƃ��ŏ����玩���őS�����Ƃ��������ł����B
���c�@������ˁA���l�Ɖ�ƂƂ�����̗��ꂪ�Ԃ������Ƃ���ŁA�����N���邩�킩��Ȃ��A�ł��������N����B���������̂��ˁA�������낢�Ǝv���Ă����ł���B���ۓI�ɕ`�����Ƃ́A�ł��Ȃ����̂��Ȃ����炢�ɕ\���̕����L�����ˁB�ł���Ǝv����ł��B���̎���ǂ�ŁA�C���[�W���ӂ����ł����A�����������̂��ł����炢���ȂƎv���Ă�킯�ł��B
�J���@�ڂ��ɂ́A����͑��c����ɕ`���Ă�������������ȁA�Ƃ���������ƒ��߂̎��������ł����ǁB���ɋ�̓I�Ȏ��Ȃ�ł��B����ɂȂ��Ă����ł��B���c����́A�������N�͎����̍D���Ȃ��̂��������Ă������������ŁA�������Ă���ł����ǁB�����ǂ�ł���������̂ł���A�R�s�[��u���Ă����܂��B���Б��c����ɕ`���Ă������������Ǝv���Ă��܂��B
���c�@�킩��܂����B�O�ɒJ�삳��Ƃ����d���́A�w�Ƃ��x�Ɓw�����̂��ǂ�����x�ɂ��ẮA���낢��b���܂�����ˁB�ǂ�������Ȃ��̓I�ȊG�����܂����B
�J���@���x�͒��ۓI�ȊG�ɂȂ��ł����H
���c�@�����Ƃ��ẮA��������ɕ`������̂��Ă����̂����ꂵ����ł��B
�J���@������Č������̂́A�u���l�̕�v�Ƃ������Ȃ�ł���B�k�c�c�l�i�����A��`��y�[�W�j
���b�ɊG���i������Ƃ��������̊��͋g���̎��ɂ���Ă��������A���c����́s���l�̕�t�ŃN���[�̂悤�ȁA�~���̂悤�ȁA�J���f�B���X�L�[�̂悤�Ȍ����Ȓ��ۉ��`���Ă���B�����̂Ȃ��ŁA�����炭�g������ɈႢ�Ȃ��f�t�H�������ꂽ���̂����ɐ��������B
�k�t�L�l
����O���W�s���b�t�i���y�ЁA1974�j�̖ڎ��̍ŏI�s�Ɂu����@���c�唪�v�Ƃ���B���̑�W����ꎍ�W�Ɠ��l�A���҂̂��w���̂悤���B���c����|��������E�����{�́A���̉�ƂɊr�ׂċ����قǏ��Ȃ��B���ו��������̂��A�����̎苖�ɂ��鑾�c�����̒��҂̂��߂ɑ��������{�͏�L�̈�������B�g���ɊW�̂��肻���Ȗ{�ł́A���c�~�s�̐ڕ��t�i�}�����[�A1955�N7��20���j�\�\���c����̓W���P�b�g�ɃN���[�̂悤�ȊG��`���Ă���\�\�ƎR�{�a�v�s���̍����k����S��14�l�t�i�|�v���ЁA1965�N1��15���j�\�\�����͓�g�~�Y�i�g�������������Ί_���U���W�s���Ɏ���������āt�i�}�����[�A1980�N3��5���j�̃J�b�g��A�g�����ҏW���Ă����s�����܁t��1976�N1�N�Ԃ̖{���̃J�b�g��S�����Ă���j�A���c����̓J�b�g�ɋ߂��}�G��`���Ă���\�\�̓���B�g���������{�͂��炩�����苖�ɑ����Ă��邩��A������͑��c�唪�����{�Əƍ����āA���҂̊֘A�𖾂炩�ɂ��������̂��B
�q�_�ސ�ߑ㕶�w�َ��������r�́u�������ځv�́A���肪�������ƂɎO�|�����킹�Č������邱�Ƃ��ł���B�Ƃ�킯�u����E�}��Җ��i�}���̂݁j�v��I�ׂ�̂��f���炵���i���s�u�N�����v�̕\�����j�B�����Ƃ��A����Łu���c�唪�v��������Ɏw�肷��ƁA���R�Ȃ���u���ꁁ���c�唪�v�Ɓu�}�恁���c�唪�v����ʂȂ��q�b�g���Ă��܂��B�Y�����鎑��189���̂����A�d����������菜����186���͈ȉ��̂Ƃ��肾�i�s���́k�l���͐}���̐����L���j�B�Ȃ��A�}�����[�́q���w���S�W�r�Ɓq���w���S�W�r�̌v12�^�C�g���ɂ́����t�����B
�k2019�N8��31���NjL�l
���c�唪���S���Ȃ��Ċ�3�N���o�����B���c�����1918�N12���̐��܂ꂾ����i�g�����1�ΔN���j�A��2018�N�͐��a100�N�������B����A106�Ԃ̈�����Y�����s���E���b���w�S�W 6�k�A�����J���b�W�l�t�i�u�k�ЁA1959�N11��10���j����肵���B�����́u���{�v�͏H���F�v�A�u���C�A�E�g�v�͈������ł���B���c����͊����́q�I�Y�̂܂ق������r�i�k�E�t�����N�E�o�E����A���ؖΖ�j�ŁA2�F�ƃ��m�N���́u�������v��S�����Ă���ق��A���v4�_�̃J���[�̌��G�E��������`���Ă���B2�F�̂���������1�y�[�W��̂���5�_���ׂĂ��A�J���[���G�E����������2�_�����ŁA�ȉ��Ɍf����B�����̉��t���L���ɂ��A�s���E���b���w�S�W�k�S18���l�t�͑�1�����M���V�A�_�b�A��18�������E���w�W�B�\���͔w�E�v�A���E�N���X�A�\���P�ɂ͂��ڂ݂����āA�J���[�̃J�b�g�i�{���Ƃ͕ʂ́q�I�Y�̂܂ق������r�j�ƕʃ^�C�g���A����������������ӂ�\��Ƃ������Â�悤�ŁA�����ڂ͔h��Ȃ����ɁA����͌��S�B�艿��360�~�B�{���̑O�N�Ɋ��s���ꂽ�g���̎��W�s�m���t�i���惆���C�J�j��300�~����������A�q�������̖{�Ƃ��Ă͂��Ȃ荂�z���B�l�ł̍w�ǂ����A�w�����ɂ�}���ق̍w����z�肵�����{�̂悤���B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@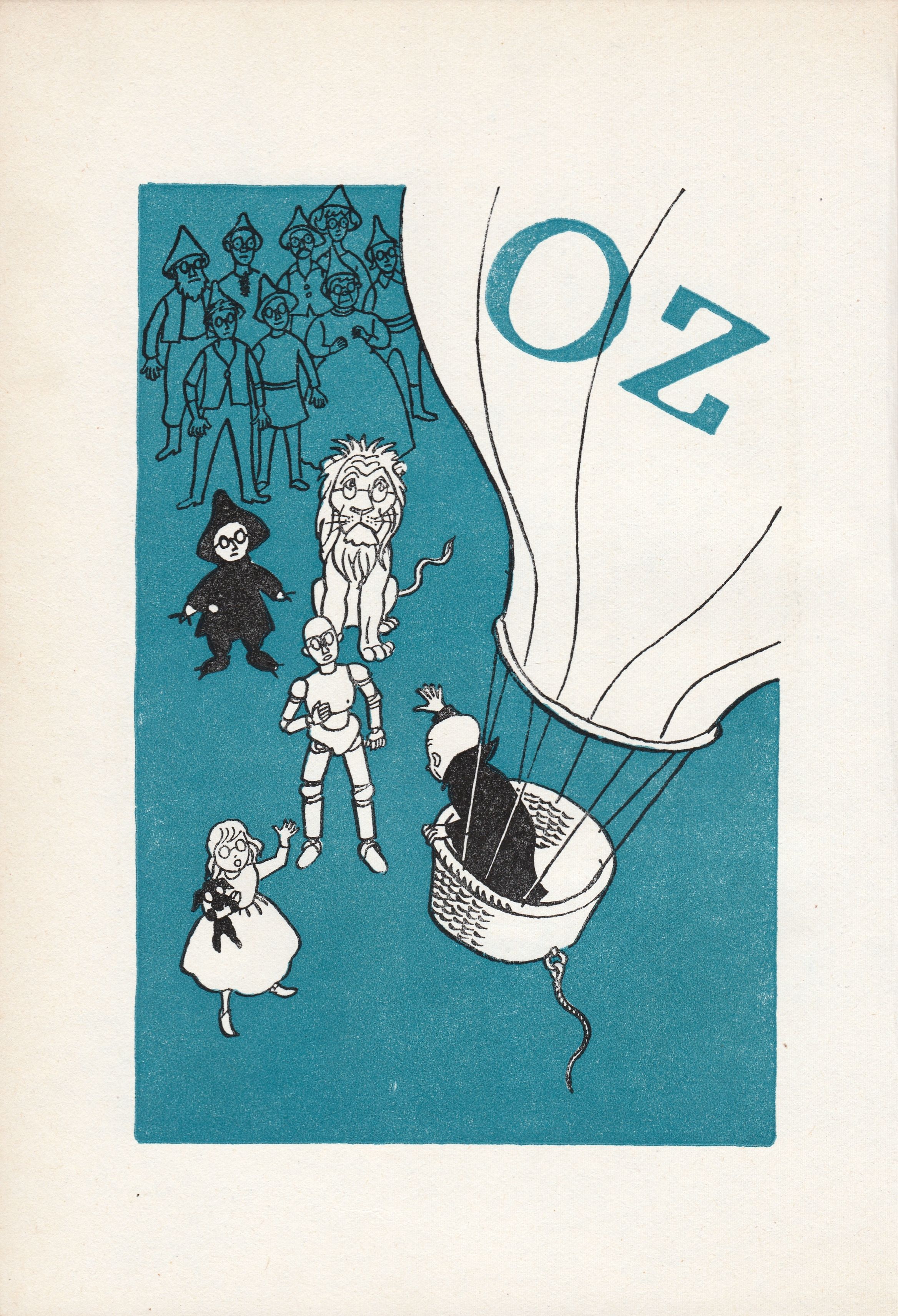 �@
�@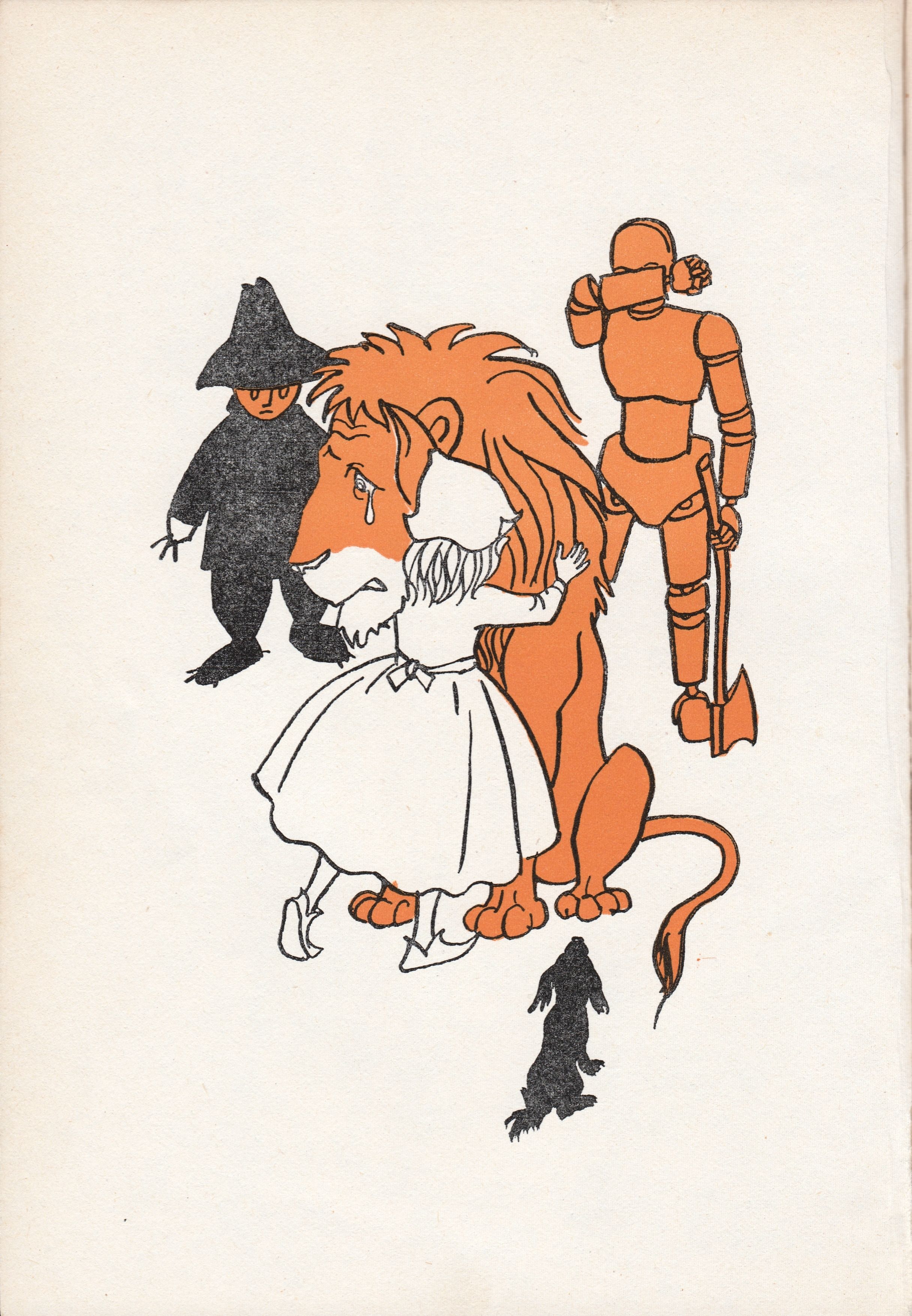 �@
�@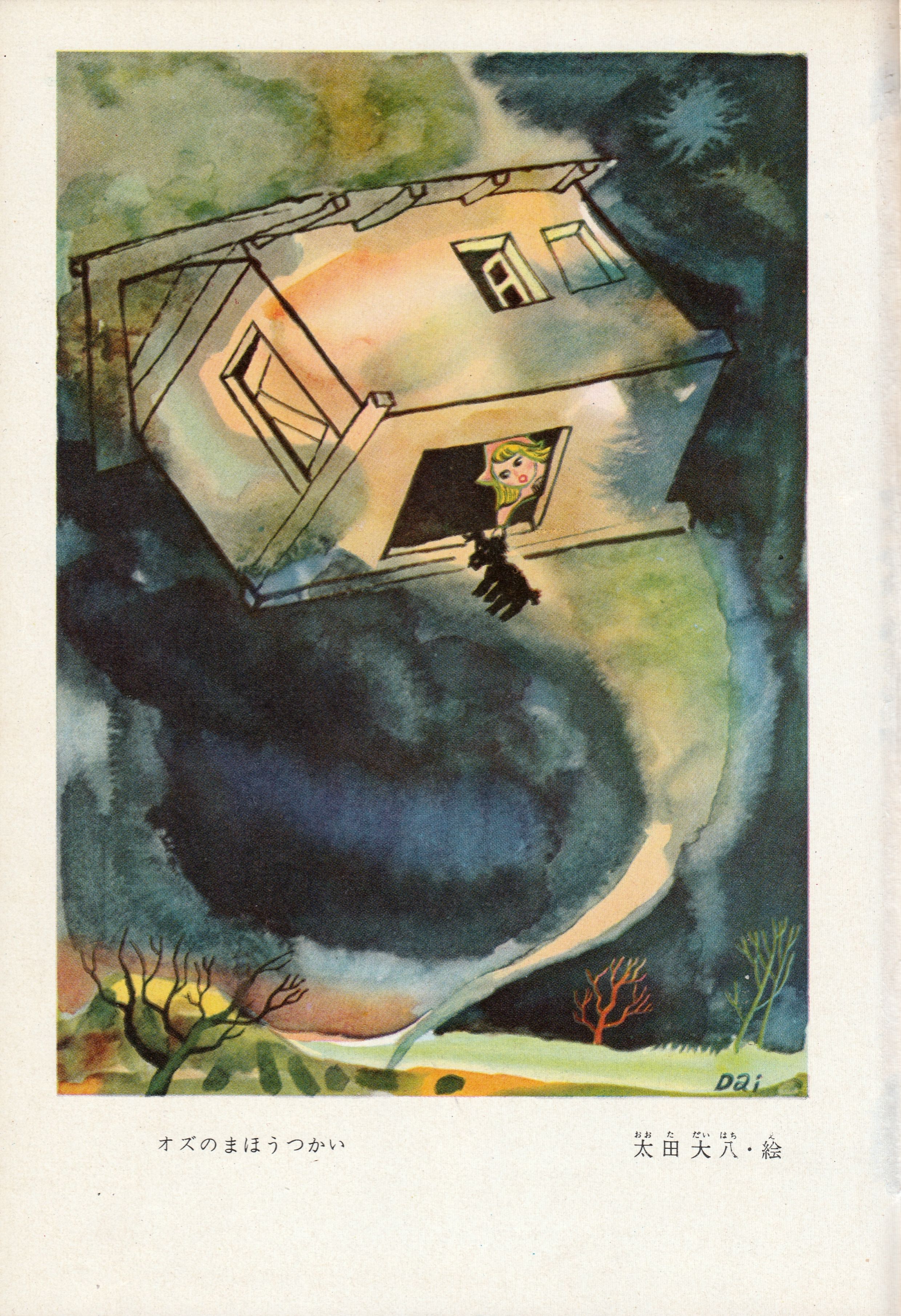 �@
�@ �@
�@
�i������j�q�I�Y�̂܂ق������r�i�k�E�t�����N�E�o�E����A���ؖΖ�j��2�F�������i5�_�j�Ɠ��E�J���[���G�E�������i2�_�j�Ɠ�������^�����s���E���b���w�S�W 6�k�A�����J���b�W�l�t�i�u�k�ЁA1959�N11��10���j�̕\���k���{�F�H���F�v�l�@�G�͂���������c�唪
��f��186���ȊO�ɂ��A���c�唪�ɂ��}�G�͐��������݂���B���̂ЂƂA�q�g�����Ɓs�A���r�A���i�C�g�t�r�Ɍf�����X�c�����s�A���r�A���i�C�g�k���w���S�W63�l�t�i�}�����[�A1955�N2��5���j�̕\���G�A���G�i��������J���[�j�Ƒ}�G�i���m�N���j��5�N��Ɏ�|�������ߓ��ӂ��̑}�G�\�\�s���N�������E���w�S�W 41�k���m�� 1�l�t�i�u�k�ЁA1960�N11��20���j�Ɏ��^�́q��������r�Ɓq�g���R���b�r�\�\���f����B�Ȃ��A�q��������r�̑}�G��5�_����A�q�g���R���b�r�̑}�G��3�_����A���B���ɂ݂ɁA�����N�����{���̍�������}���ق̏����́A���B�W���A���Ɋւ�����������Ă���B�{������E���A�u���{�v�͒r�c��O�Y�A�u�������v�͑�c�d���E�c���c�ߎq�E���쐽��E���c�唪�E�c������E�����6�l�ł���B
 �@
�@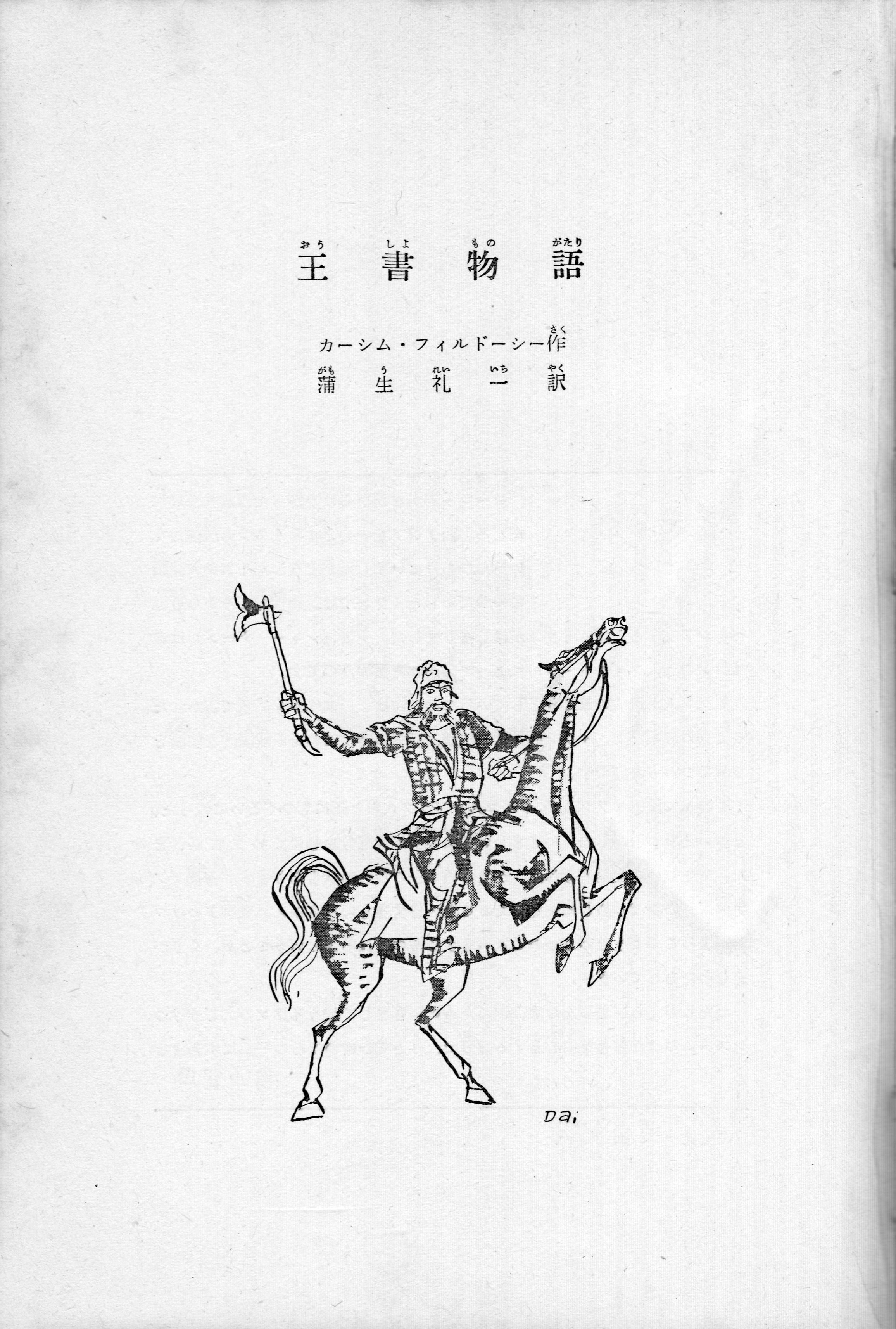 �@
�@ �@
�@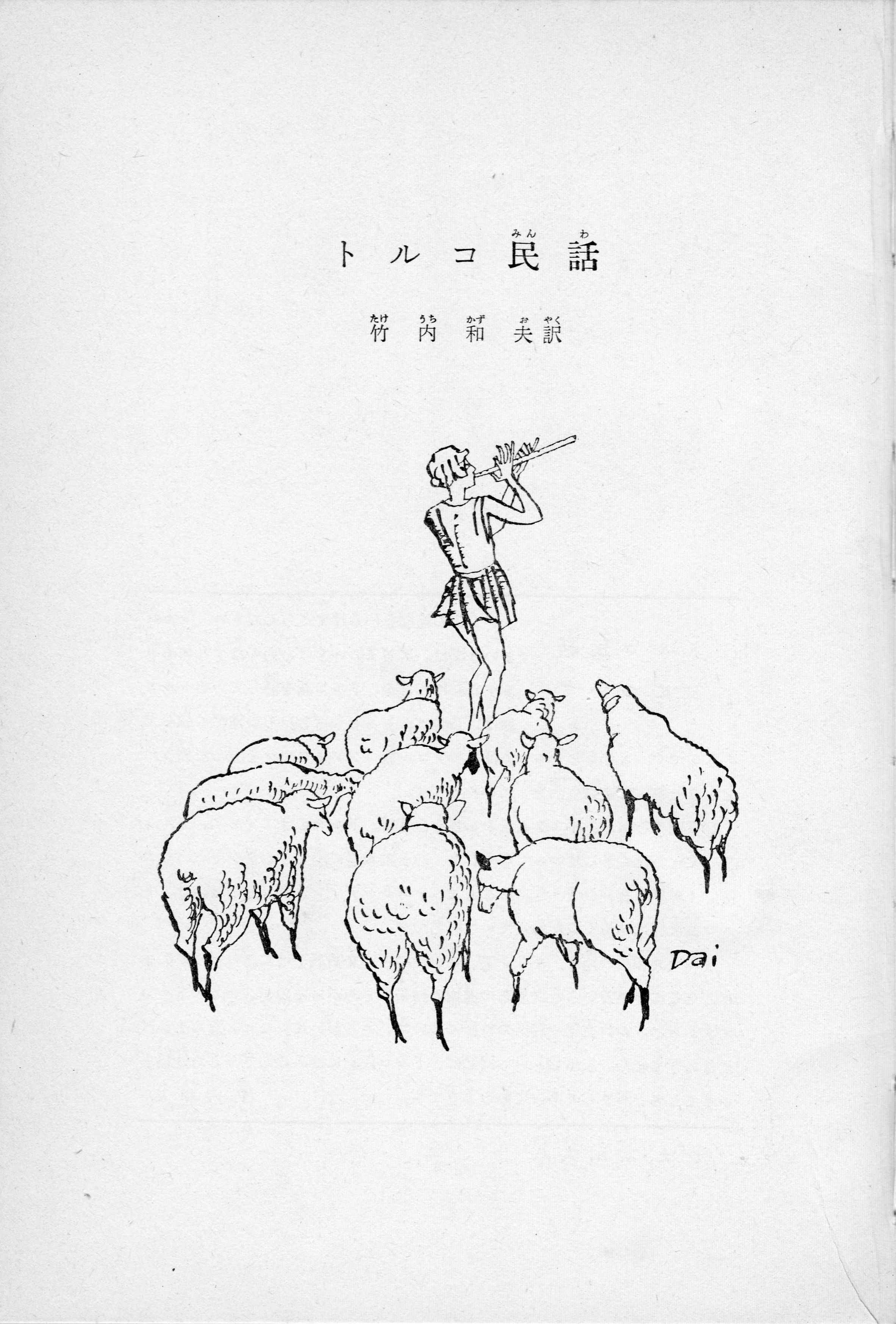 �@
�@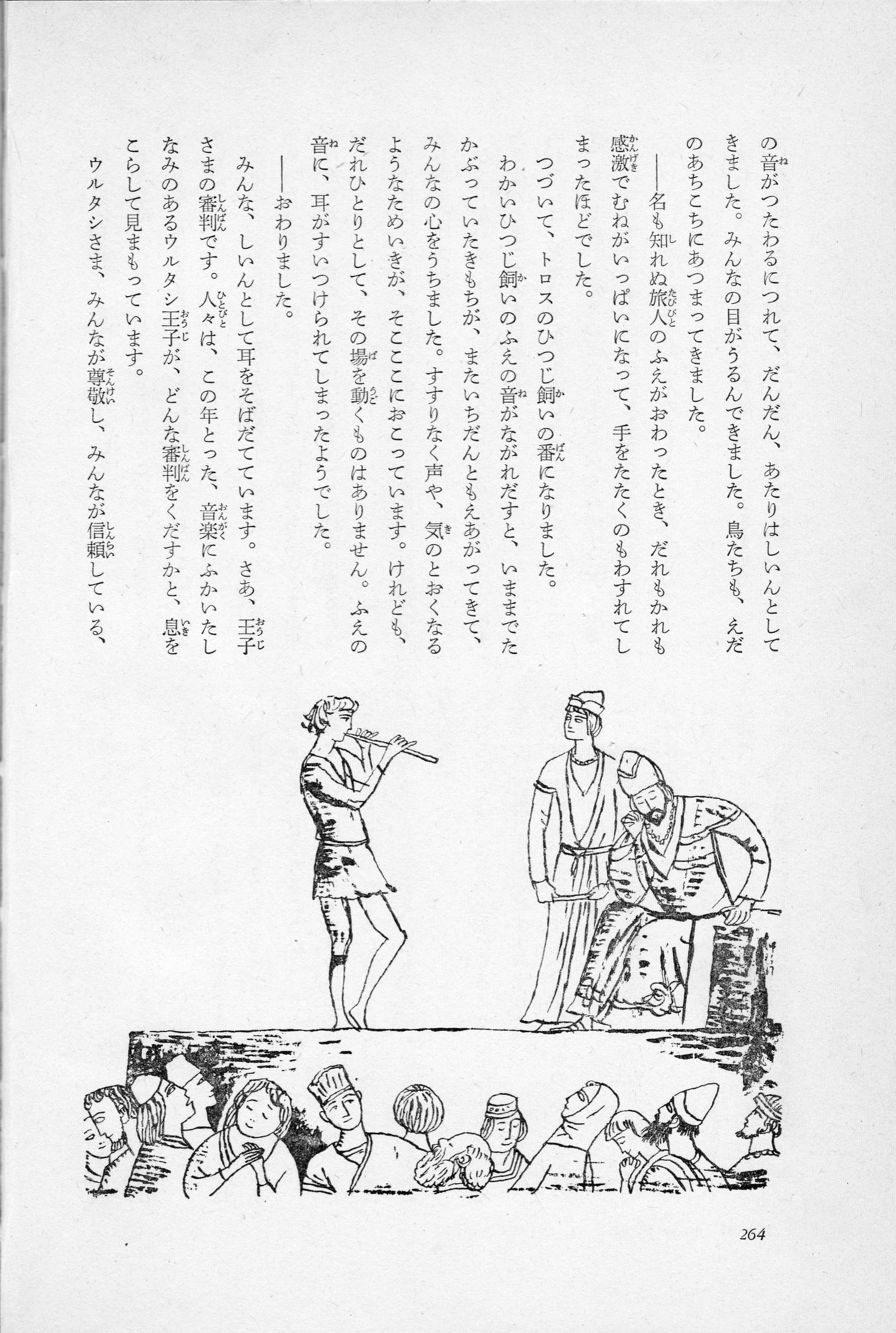
�i������j�q��������r�̃J���[���G�A���E���m�N�����G�A���E���m�N���}�G�A�q�g���R���b�r�̃��m�N�����G�A���E���m�N���}�G�@��������s���N�������E���w�S�W 41�k���m�� 1�l�t�i�u�k�ЁA1960�N11��20���j���^�̑��c�唪�̊G
2016�N9��20���́A���T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�ɂƂ��ċL�O���ׂ����ƂȂ邾�낤�B1967�N10�����s�̎v���Д��s�g�������W�t�Ɏ��^����Ĉȗ��A���̏��o�f�ڔ}�̂Ɓi���R�̂��ƂȂ���j���o�{��������Ȃ����������q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̂��ꂪ���������̂ł���B���Ƃ̎���͂������B9��18���i���j�A�q���t�I�N�I�r�Ɂu���w�C���x���a�R�W�N�W����X���ҏW���q�����v���o�i���ꂽ�i�o�i�҂�imagon427����j�B�����ɂ͕\���Ɨ��\���̎ʐ^�ƂƂ��ɁA
�Ƃ������B���́u�u���ʊ�e��i�������v�g���@���v�Ƃ���1�s�������Ƃ��A�u����A�g�����̐V�����̖����s���т��v�ƐF�߂������A�u���a�R�W�N�W���v�Ƃ���̂ɋC�����āA�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�ɈႢ�Ȃ��ƒ��������B����Ƃ����̂��A���܂Łs�q�g�����r�����t��
�ȂǂŎU�U�������悤�ɁA�����т�1963�i���a38�j�N�Ɏ��M�E���\���ꂽ�\���������ƍl���Ă������炾�B��ȗ��R�́A���̔N�A�t�����X�̉�ƃ����V�A���E�N�[�g�[�i���Ȃ킿�u�N�[�g�̊G�v�̍�ҁj���������Ă��邱�ƁA���l�̒��c�O�������炭���o����3�s�����p���ăR�����g���Ă��邱�ƁA��2�_�ł���B�������A1963�N���M�E���\�Ɛ��肷��܂łɂ́A���O�̋g������{�l��z�q�v�l�A����ɂ͒��c����ɂ܂Ŗ₢���킹�����Ƃ��Ȃ���A���ɏ��o�T���ɂȂ�������Ȃ������Ƃ����o�܂�����B�Ƃ���ŁA�O�f�I�[�N�V�����̏I��������1�T�Ԍ��9��25���i���j�ߌ�8���߂��ł���B�J�n���i�́u300�~�v�Ǝ荠�Ȃ̂łȂ�Ƃ��Ă����D���������A�ꍏ���������ʂ����āq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�Ȃ̂��V�����̖����s���тȂ̂��m�F�������B����獑������}���ق�OPAC�Łs�C���t������������A���Y���͏�������Ă��Ȃ��B���ɔo�啶�w�ق�OPAC�Ō�������ƁA���肪�������Ƃɂ����Ə�������Ă���i���Ȃ݂ɓ��{�ߑ㕶�w�ق��������������Ă��邪�A���ɂ͕ʌ��őO�̏T�ɍs�������肾���A�Ȃɂ����킪�Ƃ���͔o�啶�w�ق��߂��j�B��19���i���j�͎d���œ����Ȃ������B�J�͗l��20���i�j�ɐV�h�E�S�l���̓��ق�K�ˁA�s�C���t9�����{�������B�q�ڎ��r�ɂ͂܂�����Ȃ��u��e�\�͎��@���̓N�[�g�̊G����c�c�c�c�c�g�@���@�@���c2�v�Ƃ���B30�N���A�T�����Ă������тƂ̏o��ł���B�y�[�W���J��Ԃ����ǂ������{���ɖڂ�ʂ��ƁA�ǂ����ٓ��͂Ȃ��������i�V�C���ǂ��Ȃ������̂ŁA�Z���ׂ��{���ł��鎍�W�s�Â��ȉƁt�͎��Q���Ȃ������j�B�悤�₭���������Ăق��̃y�[�W������ƁA�\��3�i���t�����y�[�W�j�́q�ҏW��L�r�Ɂs�C���t�̕ҏW�ҁi�ł��蓯�l��\�j�ł�����q�������u�g��������̐V��������������B�N�Ԃǂ��ɂ���i�������Ă��Ȃ��̂ŁA�g���t�@���̑����o�d�ւ̗ǂ��v���[���g�ł���͂��B�v�Ə����Ă���ł͂Ȃ����B�m���ɋg���͂��̔N�A�����q����r�i�E�E3�j���s���p�蒟�t2�����ɔ��\���Ĉȍ~�A���\���Ă��Ȃ��i���q�Ƌg���̊ԂŁu�ŋ߁A���̕��͂ǂ��ł����H�v�u����A���̔��N�قǏ����ĂȂ�������łˁv�Ƃ��������Ƃ肪��������������Ȃ��j�B�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�̔��\�����Ɋւ��邩���莄�̐����͓I���˂Ă������̂́A�f�ڎ��́s�C���t�ɂ܂Œ��ׂ��y�Ȃ������B��������30�N�قǂ܂��A�g�����̒P�s���W���^�̑S262���т̏��o�̒T�����u���Ĉȗ��A�`䒂Ƃ��č����Ɏ������B�g���́A�i�c�k�߂́s�Ս��t�⍂���d�M�́s�o��]�_�t�ɂ͉��x����e���Ă��邪�A�摖���Ă����A���q�����́s�C���t�ɂ́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���������ł͂Ȃ����낤���B����̒����ɘւ������B
�{�e�́A�s�����T��2007�t�i���ފt�A2008�N�j�Ɍf�ڂ����q�l�����s�g�����̎��̐��E�t��web�T�C�g�ɂ���r�ɕ킢�A���M�����B�Ō�ɍ���̃I�[�N�V�����œ��肵���A�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���f�ڂ������q�����ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�i1963�N8���j�̎ʐ^���f���āA�{�e���I���悤�B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�s�C���t9���i1963�N8���j�́q�ҏW��L�r�Ɖ��t�A���E�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�̖{���A���E�q�ڎ��r�A���E�\���i������j
�����Ɂq�������e�搶�K��L�r��t�^�̂悤�Ɏ��߂��H���K�l�̐��M�W�s�g�����ƐX�仂Ɓt�i�v���ЁA2007�N10��25���j�͏�����
�Ƃ���O����
�g�����ɁA�㔼��X�仂ɏ[�Ă��\���ɂȂ��Ă��āA�g���Ɋւ���3�сA�X�Ɋւ���2�т̐��M���������������̒��Ԃ̂悤�ɂȂ��̂��q�X�仂Ƌg�����r��
����B����͋g���������ɂȂ�X�仂�3���߂̐��M�W�s�L
���̊G�t�i�}
�����[�A1968�N11��30���j���s�ɂ܂��X�Ƌg���̕��͂𒆐S�ɐ������A���҂̌�V�����ǂ�_�l�ł�����B�H���̕����̔��{�Ԃ�͂ӂ���ɂ�����
�čL���A�C���������Ă���B�Ə���������Ƃ����āA�����������H���̕M������ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A�X�仂ւ̌��提������̎v���ДŁs�g������
�W�t�i1967�N10��1���j��_�c�E�_�ے��͓c�����X�̓X�傩�瑡��ꂽ�F��ɁA�����W�����Ƒ�����a���Łu�ł����d������̂̂ЂƂv�i�{���A�Z
�܃y�[�W�j�ƒ��߂����邠����A���M�ƂƂ��Ă̏H���̗͗ʂ�������Ȃ���������Ă���B���Ƃ��Ắu�X�仂Ƌg�����́A���@�����Ⴆ�A���ɏ�Ӂm����ׁn
���牜�ցA�\�w����[���ւƉ�X�ǎ҂�͋������������Ă����Ă�����҂����Ȃ̂ł����āA�ނ�͑ދ��ȍ��݂ɗ��܂�l�ł�����Ȕފ݂ɍs�����ςȂ��̐l
�ł��Ȃ������v�i�{���A�Z�O�y�[�W�j�Ƃ����f�Ă��܂ޖ{���𖡓ǂ���A�ƌ����ς�ł��܂��̂����A2�_�����H���̐G��Ă��Ȃ��X�仂̕��͂��Љ��
���B�{�e�̕W����u�]���Ɂv�Ƃ��鏊�Ȃł���B
�k���ȁl�{��܂� �q���i���Z���N�H�@��Z���l���t�j
�@ ���̊Ԃ͍��̔��\�[�X���R������ƃg�}�g�ʔK�T���_�ƁA�ē��������������܂ł����B������������o��A�F���́A���̎O���̓L�̒��́u���̔��\�[�X�v�� �u���E���̔��\�[�X�v�𑁂��ǂ�ł�������������B�F���̎O�����ܐ�̂����Ђ͖ʔ������Ƃ̂Ƃ���͑��ɁA���X�܂ł���̂ł��B���̏����o�p���i���� �ЂȌ��t�ł��j�̎����Ă������ĉ������A���ł͎��l�ʼn��Ƃ��܂̋g�������A���̌F���̂����Ђ������Â��Ă�āA�g������́A�܂��݂����Ƃ̂Ȃ� ������͕s�K�Ȃ��ƂɎ��̎��X�����Ă��炵�����ܐ����A��A�̏��ɕS�������ʂɒ�����Ă�����₢�܂��B�����ǂ�ł����U�������Ǝv�Ă�܂� �����A�܂Ï��ɂ͂���Ă���̂��Ƃ炵�����₤�ł��B�k�c�c�l�i�s�X�仑S�W8�k�}�h�D���@�[���E���E���E�l�t�}�����[�A1994�N1��10���A����� �y�[�W�j
�u�Ă̊ԁv�\�\����c������
�@���N�̉Ă͎S�W����Ă����B���́A�����Ƃ͂��ւȂ��Ƃ��ӂ��ނ���ア���ɁA��N�����O����Ƃ�߂���Ă����́i����͐[���ȋ��|�Ɛ�]�ł���j �����āA���̂Ƃ�߂������̂͂Ƃ�߂����܂܂ŁA�����֓�N�O�i������N�O�j�ɁA�F�{���X�ɘA�ڂ��ꂽ���M���Ǝv�ӂƏ����̐�ς��̂₤�ȁA�O���� �ɂ��ܐ�ɂȂ����̎O���̈ꐶ�L���}�����[����o�邱�ƂɂȂ��B�i���x�ǂ����ɏo���}�����[�̍L���ɁA�l�����̈�̎��`�A�Ə����Ă����͓̂{ �m�����n��ł���B��\�Z�܂ł��������̂ł��邩��A�l�����̈�ƌ��ӂƁA���ݕS�l�ɂȂ锤�����炾�j�Ƃ�߂��Ă����̂Ƃ��ӂ̂͋��N�̓ɒ��� ���o���������я����i���Ƃ��Ă͂ł���j�̌�т��A�����o���̓Ŏ~�܂Ă��܂Ăǂ����Ă��������Ă��o�ė��Ȃ��Ƃ��Ӑ�]�ł���B�i���̓t�B�N�V�� ���̏����̎��ɂ͂����A�s���x�͏����Ȃ��t�Ƃ��Ӌ��|�ɂƂ�߂���A���ꂪ���������Đ�]����̂ł���j�}���̖{�̕��́A���Ȃ��y�����A�ł�����Ȃ��� �߂̏�������������〳〵�y�� �̎��_�z�o�����̂ŕʂɎS�W�ł͂Ȃ����̂����A���̏����������\�O�сA��ςɂ��܂��o���āA�V���̐ؔ�����\��������̑��ƈꏏ�ɁA�}�����[�Ə����� �����傫�Ȏ��܂ɂ����܂����A���͂�����O����������ւ悤�ƌ��ЁA�S���̋g���������^�������̂ŁA���͂��̋M�d�Ȏ��܂����ĕ����ɋA���B �Ƃ��낪���̎��܂������Ɏ��čs���ꂽ�̂ł���B�k�c�c�l�ۋC�Ƃ��ӂ̂��A�n���Ƃ��ӂ̂��A�ǂ�Ȃ��Ƃ��N�Ă����̐c�܂ł͓͂��Ȃ���ŁA�בR�Ƃ� �Ă�鎄���i����͒_�����Ă��̂ł͂Ȃ��āA�_�o���ْ����鎞�̜̋]�k�x��������キ�Ēo��ł�邽�߂̂₤�ł���j�A���e�̑܂��V���̎R�ƈꂵ ��ɏ��������̂��������ɂ͓��̐c���₽���Ȃ��B�g�������ǂ�Ȃɕ���Ԃ邾�炤�A�Ƃ��Ӎl�ւ������̂��A�����ɕ�点������̉Ƃɍ݂邩���m�� �Ȃ��A�Ƃ��ӂ��Ƃɂ��C�����Ȃ��āA����〳〵�y�� �̎��_�z���f���ŎO���Ԃ�邵���̂ŁA�V���̐ؔ�����\�������ƁA��x�Ƃӂ����сA����Ɠ����ɂ͏����Ȃ��A�悭�o�������������Ƃ́A�ǂ����̗n��F �̒��ł�߂̔@���ɗn�������̂��B
�@�k�c�c�l�i�s�X�仑S�W3�k���̔��̐��E�^�L���̊G�l�t�}�����[�A1993�N9��20���A�Z�O��`�Z�O�l�y�[�W�j
���̒m�邩����A�X�仂��g�����Ɍ��y�����͈̂ȏ��2�с\�\���ȁE���M�Ƃ��X�仁k���쒨�q�ҁl�s�n�R�T���@�����k�����ܕ��Ɂl�t �i�}�����[�A 1998�N1��22���j�Ɏ��^����Ă���\�\�ƁA���M�����Ƃ��Ă͂��̒��ԁi1968�N�H�j�Ɉʒu����s�L���̊G�t�́q��L�\�\���e�����̋L�r�̌v3�� �ŁA�H���̐��M�͏�f2�тɂ͐G��Ă��Ȃ��B�������A�X�仂Ƌg�����Ɋւ��ĕ��тȂ��������L���ւ�H���������m��Ȃ������͂��͂Ȃ��B���q�̓W�J ��A�G���ɋy���Ɣ��f��������ɂ����܂��B�q�u�Ă̊ԁv�\�\����c������r�͏�������q�́q���r�ɂ��Ɓu�{���k�s�X�仑S�W3�t�l�����u�L���� �G�v�́u��L�v�i�y�� ���ܓz�Łj�ɋL����Ă���o�������ڏq���Ă���v�i�����A���Z�Z�y�[�W�j���̂ŁA���e���炷��Β}�����[�̂o�q���s�����܁t�ɍڂ��Ă����������� �����͂����A�����͂Ȃ�Ȃ������B���A�s�����܁t�̑n����1969�N��5���A�ƐX���s�Q���t���N2�����ɐ��M�\����������ł���B����������� �Ȃɂ����A�s�L���̊G�t�̊����Ɂq��L�\�\���e�����̋L�r������ȏ�A���㉮���˂��K�v�͂Ȃ��B�����Ƃ��A���̐��M���s�L���̊G�t���s�̃v�����[�V���� �Ɉ�������ǂ����͋^�킵���B�X�从��g�A�q�u�Ă̊ԁv�\�\����c������r���ǂ̒P�s�{�ɂ����ꂸ�A��������ꂪ ��y�ɓǂ߂�悤�ɂȂ����̂́s�X�仑S�W3�k���̔��̐��E�^�L���̊G�l�t�́q���Z�Z�N��̃G�b�Z�C�r�ɏ��߂Ď��^����Ă���ł���i�O�q�̂悤�ɁA�� ���̍ł����肵�₷���ł́s�X�仑S�W�t���{�Ƃ��āu�H�v�̒Z�т�҂��ɃI���W�i���́s�n�R�T���@�����t�j�B�s�L���̊G�t�̒P�s�{��1968�N�̊� �s�����A���̌�A�����Е��Ɂi1982�N4��23���j�Ƃ����ܕ��Ɂi1992�N2��24���j���o���B�����Е��ɔłɂ͔���������������Ă���B�u�� ���A���ÓI�ȋC�����ł��̖����吳���M���ʐ^�قɂ͂��������̂́A��݂����ނɂ�A����͈ꖋ���̔b���ʼn�������ŋ����ƍ��o���A����A�Z�т̒��Z�� ���̂����A�����A�����Ǝv���Ă��邤���ɁA�X�仂̏c���ȕM�̒��ŁA���̂܂ɂ�����̒��Ŗ��点�A���������Ă��������Ƃ������t�B�X�g���Ԃ点�A�� �_�̎��R�Ɣ��̔��������ɁA��Â݂������Ă��鎩���ɋC�Â��̂ł���v�i�����A��ܘZ�y�[�W�j�B���Ȃ݂ɋg�����ɐX�仂̐V���A�ڂ̕��͂���{�ɂ܂Ƃ� ��悤�˗������̂́A���������ł���B�Ȃ������ɔłł́A�o�܂͕s�������A����́q��L�\�\���e�����̋L�r���Ȃ���Ă���B

�H���K�l�s�g�����ƐX�仂Ɓt�i�v���ЁA2007�N10��25���j�̃W���P�b�g
�s�g�����ƐX�仂Ɓt�́A�q�g�����Ɩk�����q�\�\�w�������W�x�����㎍�ցr�q�g�����Ƒ剪�M�\�\Voil�� deux
collines
enchantees!�r�q�g�����̐H��\�\�g�����Ɠy���F�r�q�X�仂Ƌg�����r�q�X�仂Ɣb���r�q�X�仂Ɖ����r�q�������e�搶�K��L�r��7�т�����
��A���̂Ƃ���H���K�l���g�����̂��Ƃ��������Ō�̒����ł���B
�g�����̕]�`�s�y���F��t�i�}�����[�A1987�N9��30���j�͕���Ɂu�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�v�Ƃ���Ƃ���A�g���́q���L�r�ƁA�y���F����т��̐l�ƍ�i�ɐe�t�����l�l�̋L�������͂́q���p�r�����i�Ƃ��Ă���B�����Ė{���𑼂̓y���F�֘A�̏����ƕ����悤�ɁA�v���v���ɋg�����y����y���ȊO�̈Í������̗x���ɕ��������т�z���Ă���B�{�e�ł́A�g���̎��W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�N7��23���j�̏����P�����y���̕���s�Â��ȉƑO�сE��сt���߂���L�q����|����ɁA�s�y���F��t�̐��肽�������Ă݂悤�B�\�����A�X�x�X�g�فA�S�������c���j�E���g�a�q�q�y���F�N���r�ɂ́u���a�l�\���i��㎵�O�j�N�@�l�\�܍v�̍��Ɂu�㌎�@���]�哥�ӁA������������i�x��q�t�[�s�[�Ɛ�������̂��߂̏\�ܓ��ԁj�u�Â��ȉƑO�сE��сv�̉��o�E�U�t�E�o���i��������j�A�o���҂ɂ͑��Ɉ���r�q�A���э���A�m�����q�A�a�I�R�I�v�A�R�c�ꕽ�A��{��E�A��B�^�\���@���p�k�́E�V���T���u�z���_杁v�i���{�N�فj�ɓ��ʏo���B����o���̍Ō�B�Ȍ�A���o�E�U�t�ɐ�O�v�i�y���F�╶�W�s���e�̐�t�}�����[�A1987�N1��21���A��l���y�[�W�j�Ƃ���B���Ȃ킿�y��������ɗ������Ōォ��ӂ��߂̍�i���A���ꂾ�����B�s�y���F��t�́q40 �u�Â��ȉƁv�r�̖{���ɔԍ���U���āA�ȉ��Ɍf����B
�@�u�q�Â��ȉƁr�ł����ƂĂ�����ł͌����܂���B����́w�c�̑������͐푈�͊y���x�Ƃ����w�i��ʉ߂����̂ł��B���̐��Ƃ����Ắw�p��̉Ɓx�Ƃ����\�D���������Ă��܂������A���̊ԋA���Ă݂����͉Ɖ��~�͐Ռ`���Ȃ����{�̏��������������I�ɐ����̂тĂ���̂�ڌ����܂����B�v�@�i�y���F�j
�A�q���L�r�@��㎵�O�N�㌎���
�@�߂�����A�����p���R����֍s���B�o��������ŁA�u�Í������h�v�̕���Ƃ��Ă͈ꐡ���h������B�y���F��i�E�x��q�t�[�s�[�Ɛ�������̂��߂̏\�ܓ��ԂƏ̂��A�u�Â��ȉƁv�O�ь�т���ɕ����Ă̌����������B�Ⴂ�j���̕������\�l�A�ܐl�̕������ł������ɗ͍�ł͂��邪�A�疟�ŒP���ȍ\���Ɍ������B�������A�y���F�̓ƕ��͏G��B����C���v�ȁA�V��ޓ�Y�v�ȁA���c���F�v�Ȃ�Ɖ�����B�^�����\�ܓ��E�ߌ�ꎞ����A�p���R�̃E�G�A�n�E�X�ŗz�q�ƃR�[�q�[���̂݁A����֍s���A�u�Â��ȉƁv��т��ς�B�O���ԋ߂��A�ْ����������镑�䂾�����B�\�\������|�p�Ƃɂ͂��Ă̎��Ȃ̍�i���A���p���A�ό`���A���B���Ă䂭�Ƃ����A�c�ׂ�����B���̍�i�ɂ����ꂪ����悤�Ɏv��ꂽ�B�߂��炵���A�N�Ƃ���킸�A��t�̓y���v�l�Ɉ��A���ċA��B
�B�u�Ă̐���̊^�̍����A���̉��A���Ȃǂ̂������钹�̐��A���o�̂悤�ɉʂĂ��Ȃ��r��������ڏ��̉̂Ȃǂ��B�����܁A�퓬�̎ˌ����̗��ˁA�ْ����������Ă�d�b�̉�����Ԃ��P�C���������A�s���ĂȁA�G���̌��������O��������c�c�B�����ĕ��������h�e���̏��B�̉��ʂ̉��A�����Ƃ����k�ق̃Z���t�A�����̐���[�܂��ĐK���q�ȂɌ����ẴA���[�Ƃ������A���悤�ȋ��ѐ��A�j�B���l����ɂȂ肾���Ɛ�������A�n�A�n�A�Ƃ͂������錢�̓f�����c�c�B�W�b�N���Ǝ��Ԃ������ĉ�������B���ɓy���F�̓��̂́A�Q�b�\���Ƃ₹�A���������m�ɋؓ��ƍ��Ɠ��������_�Ȃ������ꕪ�̃X�L���Ȃ��B���鎞�͏��̋��Ŕj�ꂩ�Ԃ�̃h�e���̋ɍʐF���܂Ƃ����w���q�ȂɌ����A�킸���������Ɍ����ĕ��݂Ȃ���A���X�ɔw���炸�藎���Ă䂭�ߏցA�I��ɂȂ锒�h�̔w�A���A���A���X���[�r�f�I�Ō���悤�ɁA���O�ɏo�����Ȃ����A��������������A�������ɗ����Ă䂭�̂ɁA�傰���ɂ����Ήi���̎����Ă���悤�Ɍ������B�v�@�i�Ñ�r���j
�C�u����ɗ������̎d�グ�̂ł����Ƃ��A�ނ̑̂���͓��Ƃ��������킬������Ă����B�������畠�ɂ����āA�����Ȃ��Ƃ��������w���x���I�o���Ă���Ƃ����������������B�r��ڂɂ��A���͂�ؓ��ƌĂԂׂ����̂͂Ȃ��A����ȁw�x�����������Â��ɓ����Ă���B��������߂Ȃ���A�ނ̐ߐH��b�B���v���`���Ă݂Ă��A���������{�N�T�[�̌��ʂ̋ꓬ�Ƃ͎����������Ă���B�y���F�̏ꍇ�A���̍킬�����͂��łɂ��Ď�i�ł͂Ȃ����ȖړI�Ȃ̂��B�v�i�o���T�O�j
�D�@���ǁ@�ȂƂ̓o���b�N�|�p�̉ԏ���
�@�@�قƂ��邱�Ƃ��o����H
�@�@�����̐��ʂ�
�@�@�Ăѐ���������c�^�̗t�������邩�ˁI
�@�@�@���I�ȃX�e���h�O���X��
�@�@�i���ۑ����\�Ȃ��
�@�@�܂䂭�J��
�@�@�U��s���ʂ̂Ȃ���
�@�@�唞�̎�q
�@�@���炩���ߎ���˂Ȃ�Ȃ�
�@�@�v�����������
�@�@����鎽��̏����ȊG
�@�@�X�M�̖̌����ɂ���
�@�@����Ȃ���Ȃ���čs���n�ƕ�����
�@�@���E�̐Â���
�@�@��������l�A������
�u�Â��ȉƁv���
���Ă̂Ƃ���A�@�͓y���F�̕��́B���o�́u���]�哥�Ӂu�Â��ȉƑO�сE��сv�@���a�l�\���N�㌎����\��Z���@��������v�i�s���e�̐�t�A��O��y�[�W�j���Ƃ���\�\�����炭�����̃v���O�������q�����A�����\�\�g�����˂����̂́s���e�̐�t�̖{�����낤���B�s���e�̐�t�ł̋L�ڂ�
�@�Â��ȉƂɏZ��ł݂����Ǝv���Ďl�\�Z�N�����܂������A�Â��ȑ呛�����N���Ă���Ƃ̒��Ɍ��݂��Z��ł���Ƃ�����ł��B
�@�k�c�c�l
�@�u�Â��ȉƁv�ł����ƂĂ�����ł͌����܂���B����́u�c�̑������͐푈�͊y���v�Ƃ����w�i��ʉ߂����̂ł��B���̐��Ƃ����Ắu�p��̉Ɓv�Ƃ����\�D���������Ă��܂������A���̊ԋA���Ă݂����͉Ɖ��~�͐Ռ`���Ȃ����{�̏��������������I�ɐ����̂тĂ���̂�ڌ����܂����B�k�c�c�l�i�q�Â��ȉƁr�A�����A�㔪�y�[�W�j
�ŁA�g���́u�@�v���q�@�r��w�@�x�ɉ��߂Ă��邪�A����͓y���̕��͂���d�ꊇ�ʁi�u�@�v�j�Ŋ����Ĉ��p�������߂̑[�u�Ǝv����B
�A�͋g���̓��L�B�u��㎵�O�N�㌎����v�͕��䏉���ŁA�O�т��ςĂ���B�u�����\�ܓ��v�͐�H�y�̑O���ŁA��сB���̂��߂��u�߂��炵���A�N�Ƃ���킸�A��t�̓y���v�l�Ɉ��A���ċA�v���Ă���B���Ȃ݂�1973�N9��15���͓y�j���ŏj���i�h�V�̓��j�������B
�B�͌Ñ�r���̕���]�B���o�́s���{�Ǐ��V���t1973�N9��24���i���j���j8�ʂ́q�����r�B�W��́q�Â��ȉƁr�B�u�h�����鎀�́v�A�u���X�Ə��ƌ���𗪒D�\�\�l����̓��̂��i���̎����ނ��o���v�Ƃ������o����u���ݓn�镗�̉��v�A�u���Ɨׂ荇���̃����c�v�Ƃ��������o�����z����Ă���B�g���͏ȗ������ӏ����u�c�c�v�ŕ\�L���Ă��邪�A���ꂪ�ȗ��ł���Ƃ������Ƃ͔���ɂ����B�ʏ�A�i���j�A�i�����j�A���Ȃ�k�c�c�l�ƕ\�L����Ƃ��낾���炾�B�ȉ��ɊY������ӏ��̌������k�@�l���ɕ���Čf����i���邢�́k�B�������l�j�B
�@�k�X�R�b�g�����h�̐X�тɂЂт��킽��o�b�O�E�p�C�v�̎��̉��A���t�O�̊��҂��������āA���������ʂĂ�Ƃ��Ȃ��I�[�P�X�g���̗��K���A������̂��߂̌y���ȃ����c�A�j�Ղ̂��߁A�����̓��O�i�[���̑��d�ȃt�@���E�t�@�[���A���鎞�͏������݂ɂ������ɁA�����č��炩�ɗ͋������Y�����J��Ԃ��召�̏��E���ہE�V���o���Ȃǂ̑Ŋy��A�d�q���A���T�p�̃I���K���A����ȃo�C�I�����ƃs�A�m�g�ȁA�E�s�����ȉ^����ɗ�����鐁�t�y�Ƃ������ɂ߂ă��[���b�p���́i����Ȍ������͍������܂�g���Ȃ����A�����������Ƃ��������悤�̂Ȃ��j�y�̉����w�Ǎ^���̂悤�Ɏ咲���Ƃ��ď���������߂��钆�ł킸���ɂ��ڂ����ԟ[�I�ɍi��o�����̂��A�l�Ă̐���̊^�̍����A���̉��A���Ȃǂ̂������钹�̐��A���o�̂悤�ɉʂĂ��Ȃ��r��������ڏ��̉̂Ȃǂ��B�����܁A�퓬�̎ˌ����̗��ˁA�ْ����������Ă�d�b�̉�����Ԃ��P�C���������A�s���ĂȁA�G���̌��������O��������k�c�c������A������i�H�j�����A���D�̎����ӂ�킹�钩�N�̉́i�H�j���A�������������l�B
�@�����ĕ��������h�e���̏��B�̉��ʂ̉��A�����Ƃ����k�ق̃Z���t�A�����̐���[�܂��ĐK���q�ȂɌ����ẴA���[�Ƃ������A���悤�ȋ��ѐ��A�j�B���l����ɂȂ肾���Ɛ�������A�n�k�A���@�l�n�k�A���@�l�Ƃ͂������錢�̓f�����k�c�c�B���A���w���̏��B�̍����Ȃǂ��x��莩�g�ɂ�鉹���B
�@�q�ȁA�Ō���Ō��Ă��āA�������������肫���Ă����킯�ł͖��_�Ȃ��B����̃\�f�ƃz���]���g���������ăR�̎��`�ɉJ�˂��^�e�O�i�Ɍ\���قNJۑ��ɒ݂邳��A�n������̍��n�����X�Ɗ��Ɣ����h�[�����ŐZ�H�����Ă����x���̓��̂̏W�ς͊m���ɕ���ŌJ��Ђ낰���Ă����B�x��̋Z�@�͂���܂ʼn���ƂȂ��A�C���Ƃ����قnj��Ă����Í������̂��̂����A����ȏ�ɁA�ɂ߂Ċɖ��ɁA�l�W�b�N���Ǝ��Ԃ������ĉ�������B���ɓy���F�̓��̂́A�Q�b�\���Ƃ₹�A���������m�ɋؓ��ƍ��Ɠ��������_�Ȃ������ꕪ�̃X�L���Ȃ��B���鎞�͏��̋��Ŕj�ꂩ�Ԃ�̃h�e���̋ɍʐF���܂Ƃ����w���q�ȂɌ����A�킸���������Ɍ����ĕ��݂Ȃ���A�k�������l�X�ɔw���炸�藎���Ă䂭�ߏցA�I��ɂȂ锒�h�̔w�A���A���A���X���[�r�f�I�Ō���悤�ɁA���O�ɏo�����Ȃ����A��������������A�������ɗ����Ă䂭�̂ɁA�傰���ɂ����Ήi���̎����Ă���悤�Ɍ������B�k�����đ��̐��E�Ɠ��{�̕��x�ƃn�b�L���Ⴄ�̂́A���ɂ��������ɐQ�āA�����͈��y�֎q�̏�ł̈����̎p�Ԃł̖w��ǁA�d�a�������͎��Ɨׂ荇�킹�̃����c���낤�B���̎��قǏ���ɂȂ�Ђт��A�����c���̂��̂ƑΔ�I�ł������A�������炵��������������x��͑��ɂȂ��B�l
�������ɋg���̈��p�͓I�m�����A�������ʂ≹�y�̉��o�Ɋւ���L�ڂ��������Ă���_�������[���B����ɁA�u���X�Ɂv���u���X�Ɂv�ƒ����Ă���ӏ����ڂ������B�{���̍Z�����ɂ������������\�������邪�A�����������e�͌Ñ�̕���]�̕��ʁi�R�s�[�j�Ɏ����ꂽ���̂Ȃ̂��A����Ƃ��g�������ʂ���ꎚ��发�����������̂Ȃ̂��B
�C�͏o���T�O�̕���]�B���o�́s�|�p�����t1973�N1�����i��ܔ��y�[�W�j�ŁA���m�N���ʐ^�\���́q�ӏܐȁr�i����`��܋�y�[�W�j�́q�y���F�̈Í������u���]�哥�Ӂv�r�ɓY�����Ă���B����������́A�o�����q�u���v�ɋt�炤�r�̖����ɁA���s���āu�i10�E26�`11�E22�@�����E�V�h�����j�v�Ƃ���Ƃ���A1973�N9���́s�Â��ȉƑO�сE��сt�ł͂Ȃ��A1972�N10���`11���́s�y���F��i�W�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\���]�哥�ӁE��Í������h�����L�O�����t�ł���B�B�e�҂́u�{���@�q�����v�B�g���̈��p�ɊY������o�����̒i���͈ȉ��̂Ƃ���B
�@����ɗ������̎d�グ�̂ł����Ƃ��A�ނ�軀����͓��Ƃ��������킬������Ă����B�������畠�ɂ����āA�����Ȃ��Ƃ��������A�u���v���I�o���Ă���Ƃ����������������B�r��ڂɂ��A���͂�ؓ��ƌĂԂׂ����̂͂Ȃ��A���Ăȁu�v���������m��n���Â��ɓ����Ă���B��������߂Ȃ���A�ނ̐ߐH��b�B���v���`���Ă݂Ă��A���������{�N�T�[�̌��ʂ̋ꓬ�Ƃ͎����������Ă���B�y���F�̏ꍇ�A���̍킬�����͂��łɂ��Ď�i�ł͂Ȃ����ȖړI�Ȃ̂��B�k���Ȃ��Ƃ��A�ނ�軀���ϋq�̊�ɂ��炳���ŏ��̈�u�ɂ́A�����Ƃ����v���Ȃ��B�l
�g���̈��p�Ɍ�����u�́v�͏o���̌����ł́u軀�v�A�g���̈��p�ł́u�����Ȃ��Ƃ��������v�̂��Ƃ̓Ǔ_�i�A�j���E�����Ă���B�܂����o�ł́u�����v�Ɂm��n�ƃ��r���U���Ă��������A�o���T�O�s���̍q�Ձt�i�ח��ЁA1978�N2��15���A����y�[�W�j�̖{���ł̓��r���U���Ă��Ȃ��B���l�ɁA���o�u���āv�͒P�s�{�ł́u����v�ɉ��߂�ꂽ�i�Ȃ��P�s�{�ł̕W��́q�y���F�E�u���v�ɋt�炤�r�j�B���r�̗L���Ɗ����̋��V���炾���ł́A�g�����ˋ������̂����o�����P�s�{�����肵�Â炢���A�P�s�{�̉\���������悤�Ɏv���B�������A�o���Ƃ��s�y���F��t�����́q���p�����r�ɂ͋������Ă��Ȃ��B�g�������o�����̌������ɒ��ڂ��Ă���A�C�̏o���̕���]���s�Â��ȉƑO�сE��сt�̍��ɂ͈����Ȃ�������������Ȃ��B���邢�́A����ƒm����̍��ɐ������̂Ȃ�A�������Ɓs�y���F��i�W�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\���]�哥�ӁE��Í������h�����L�O�����t�Ƃ̘A�����E�ގ��������������������̂�������Ȃ��i�u�\�\������|�p�Ƃɂ͂��Ă̎��Ȃ̍�i���A���p���A�ό`���A���B���Ă䂭�Ƃ����A�c�ׂ�����B���̍�i�ɂ����ꂪ����悤�Ɏv��ꂽ�v�j�B�����鎑�����炾���ł́A�����̂Ƃ���͂ǂ���Ƃ����f�����˂邪�A������ɂ��Ă��A�k�́�軀�l���琄������A�g�����o���̌������������������̂ƍl������B�Ȃ��A�o���T�O�́s�y���F��t�ł�����ӏ��A1974�N11��28���́q���L�r�ɓo�ꂷ��i�����A����y�[�W�j�B���̓��A�g���Ƌ��ɔ����[���������s�T�C�������t���ςĂ���B
![�s�|�p�����t1973�N1�����A�q�ӏܐȁr�i����`��܋�y�[�W�j�́q�y���F�̈Í������u���]�哥�Ӂv�r�̏o���T�O�q�u���v�ɋt�炤�r�i��ܔ��y�[�W�j�k���m�N���R�s�[�l�B����ʐ^�́s�y���F��i�W�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\���]�哥�ӁE��Í������h�����L�O�����t�̂��̂ŁA�B�e�҂́u�{���@�q�����v�B](image/hijikata_deguchi_1.jpg) �@
�@
�s�|�p�����t1973�N1�����A�q�ӏܐȁr�i����`��܋�y�[�W�j�́q�y���F�̈Í������u���]�哥�Ӂv�r�̏o���T�O�q�u���v�ɋt�炤�r�i��ܔ��y�[�W�j�k���m�N���R�s�[�l�B����ʐ^�́s�y���F��i�W�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\���]�哥�ӁE��Í������h�����L�O�����t�̂��̂ŁA�B�e�҂́u�{���@�q�����v�B�i���j
�c������f�U�C������ฑ哥�Ӂs�Â��ȉƑO�сE��сt�̃|�X�^�[�ɂ��s�y���F��i�W�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�t�̑�ܖ�q�M�o�T���r�i�g����1972�N11��16���ɊςĂ���j�̕���ʐ^���g��ꂽ�i�B�e�F�R�蔎�A�^�C�g�������F�O���R�I�v�A���F�푺�G�O�j�B�i�E�j
�D�͋g���̎���q�Â��ȉƁr�i�E�E16�A���o�́s���㎍�蒟�t1966�N4�����j��37�s�߂���ŏI52�s�߂܂ł̈��p�B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j�́q����ɂ��ār�̂��߂̏������낵�q�O�̑z���o�̎��r�ŁA�{���тɂ��Ă��������Ă���B
�@���̎��т́A���̕��Y���̂悤�Ȃ��̂������B�u���E�H�̊G�v�͂��łɏo���A�k���a�O�\���N�����́l���̖�́A�u�C���Əȗ��v�ɖv�����Ă����B�[��ꎞ����A���Ɋ��������B�ق��Ƃ��A���ł�����ĖႨ���ƁA�ׂ�̕�����`���ƁA�Ȃ̎p�������Ȃ��B�����A�����֍s�����̂��낤���B���܂łɂȂ����ƂȂ̂ŁA�s���ɂ���ꂽ�B���͏��݂Ȃ��܂܁A���e�p���Ɍ����Ă����B����ނ���S����߁A�C���܂���킷�ׂ��A�����L�q�̕��@�Ŏ��������͂��߂��悤�Ȃ��̂������B
�@���ꂩ��A�ꎞ�Ԃقǂ��āA�Ȃ��A���ė����B���x���̎��A���̎����A�u��������l�A���Ă���v�̈�s�ŁA�������Ă���̂��B�u�܂��b����ˁA�i��������l�A���Ă���j�Ȃ�āv�A�Ȃ͏Ƃꂩ�����ɁA�{���Č������B�C�����ɁA�a�J�܂ő���L���A�X������Ă����Ƃ̂��ƁB�܂��A����ɔM�����Ă��鎄�̎p���A�����A���������ς��Ɋg����A�ƂĂ����ɋ����Ȃ��Ƃ��A�����̂������B�u�Â��ȉƁv�́A���̍�i�̒��ł��A�Z���ԂŐ��������ٗ�̎��тł���B���a�l�\�O�N�̉āA�ق��ɏ\�ܕт̎������߁A���W�w�Â��ȉƁx�͊��s���ꂽ�B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j
���т̐��삪1962�N�A���\��1966�N�A���W�̊��s��1968�N�i�g����1967�N4��2���A���߂ēy���̕����ɐڂ��Ă���A���W�s�Â��ȉƁt�͓y���Ɍ��{���������炭�ŏ��̐V�����W�j�A�y���̕��䂪1973�N�B�u�Â��ȉƁv�́A10�N�ȏ���̂������[���Â��ɐ��s���Ă����B�g�����ȗ��������і`������36�s�߂܂ł̑O���������������B
�@�@�p�Z���̗t�݂̂ǂ�����o�q�Â��ȉƁr�������̐��쎞�̂܂܂��ǂ����킩��Ȃ����A������ɂ��Ă��y���F�̕����ɐڂ���ȑO�̋g�������Ƃ������ƂɂȂ�B�y���͂��̎��тɋg�������̂��̂ƈقȂ�Ȃɂ��i���̑������A���̐e���������Ȓ��������j��k�����āA��������Ȃ̕�����\�z�����̂��낤���i�u�Â��ȉƂɏZ��ł݂����Ǝv���Ďl�\�Z�N�����܂������A�Â��ȑ呛�����N���Ă���Ƃ̒��Ɍ��݂��Z��ł���Ƃ�����ł��v�j�B�s�Â��ȉƁt�ȍ~�̋g���́A�s�|�[���E�N���[�̐H��t�Ɓs��ʁt���������ׂĂ̎��W�\�\���Ȃ킿�s�_��I�Ȏ���̎��t�s�T�t�����E�݁t�s�Ẳ��t�s���[���h���b�v�t�\�\�ɓy���ւ̌�����Ǔ����A�y���̕����⌾�t����G�����ꂽ���т����߂Ă���B�����y��������̑薼���S�肽�̂͂����ł͂Ȃ��A�����g�������̍Ō�����鎍�W�Ƃ��̃^�C�g���|�G���������B����͋g�������̋H��̓ǂݎ�Ƃ��Ă̎����łł��������B
1991�N10���A�E�ؔn���Łq�g�������Âԉ�r�i���N�l�ѓ��k��E�剪�M�E����N�v�E�푺�G�O�E�����r�Y�j���J����A�߂��̎��
�œ
�������B�{���Ȃ玄���o��悤�ȏ�ł͂Ȃ��������A�}�����[�̒W�J�~�ꂳ��Ɋ��߂���܂܁A�o�Ȃ����Ă�������B�o�Ă悩�����B�ׂ�ɂ͒����ĔV����A
�������ɂ��ѓ����q����Ƃ������A����
�����Ȃłł��Ȃ������ł��Ȃ��悤�ȕ����琶�O�̋g������̂��Ƃ�������ł���B�o��̘b�Ɍ���A�s��t�Ɏ��M�𗊂ނƁA������ɓ���Ȃ���
�Ȃ�Ȃ��▭�̃^�C�~���O�Ō��e���͂��A�g������͔o���̐i�s�̗����\���m������Ă���Ƃ����ѓ���
��̘b�������[���������A�g������������D���������o�l�͕x�V�ԉ��j�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����w�E�ɂ͋������B����̐l�Ƃ̊��k�ł̔����������̂ŁA��
��ȏ�ڂ����������Ƃ͂ł��Ȃ��������A�i�c�k�߂ł��R�����q�ł��Ȃ��ԉ��j���A�Ƃ����̂͋L���Ɏc�����B�����Ă��̑O�N�A�g�����S���Ȃ���1990
�N�̉āA�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�́q�g���������r�̂��߂̑ł����킹�ŊďC�̕��o������A�ҏW�̑�������j����ƂƂ��ɋg���z�q���������ɖK
�����Ƃ��A�����d�M���}�������ہA�g������͖{���ɋC���������Ƃ����������B�s���łȂ������Ƃ͂����A�������5�ΔN���̍�����60�̎Ⴓ�ő��E������
�Ƃ́A�ɍ��̋ɂ݂������i�ڍׂ͋g���̐��z��Ǔ����ɏڂ����j�B�����̔o���]�_�ւ̐M�������ɂ������̂͂�������A�ԉ��j�̒�q���������Ƃ��傫
���A�ƍ��ɂ��Ďv���B�s��t1972�N10�����f�ڂ́q����o�偁���̒f�ʁr�̖`���u�o��Ƃ̏o��v�ɂ͂�������B
�g���͌�N�A���z�q�킪�������W�s�t�́t�r�i���o�́s���㎍�蒟�t1978�N9�����j�ɂ��̂��Ƃ������Ă���B
�@���݁A�s�����G�߁t�����L���Ă���̂́A�ق�̐��l�̗F�l�����ł���B���̂Ȃ��̈�l�ɍ����d�M������B�ނ̌��t �ɂ��ƁA�t ���E�x�V�ԉ��j�̖v��A���̏��˂����Ă������A���̎��W�����������ł���B�ނ͕x�V���S�l�ɖႢ���炵���B���̂Ȃ��ɁA�u�莆�ɂ��ւāv�Ƃ� ����t���}������Ă����̂ł���B�ނ̓R�s�[���Č��ꂽ�B�������Y��Ă������͂ł������B
�@�k�c�c�l
�@�܂��Ƃɒp�������͂����p�������A���́s�t�́t�̏o�ł̓��@�������悤�Ȃ��̂ł������B��������q�⏑�r�̂��肾�����̂ł���B�s�t�́t�́y�O�\�O�� �O�\��z�т���A�\��т�������ʂɌ��\���Ă��邪�A�s�����G�߁t�͂܂���т��A���̂悤�ȈӖ��ł͊���������Ă��Ȃ��B�F�l�������M�`�����A��s�Ƃ� ���ǂ����p���炵�Ă��Ȃ��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���l�`���Z�y�[�W�j
�s�����G�߁t�͂��鎞���܂ŋg�����G�ꂽ���Ȃ��b�肾�����B�����A�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�́s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�� ��f�q�킪�� �����W�s�t�́t�r�����肩��g���̎p���ɕω��������B�s�����G�߁t�����̎��т�O�҂ł�5�сA��҂ł�1�ш��p���Ă���̂��B���k��q����o�偁���̒f �ʁr�ł̍����̔����������������낤���A�s�����G�߁t���������g�̎��I�o���������Ƃ������o���������̂ł͂���܂����B�k�����q�̎��тƂƂ��ɓ����̋g�� �����ɑ傫�ȉe�𗎂Ƃ��Ă���̂��A�x�V�ԉ��j�̔o�傾�����B
�@�@�@�ԉ��j�厄��
�@�@ࣁX�ƌՂ̊�ɍ~�闎�t �q�V�̘T�r�@
�@�@�������C�̋��V�𝓂�
�@�@�Ό��͓��̂ۂ˂�Ƃ݂Â��܂�
�@�@�I�̑��ɖ��̂��ӂ����̂�������
�@�@�e�͂��������c�̌m�킽��ǂ�n
�@�@���ɌÓT���X�Ƃӂ鉲�O��
�@�@���Ă��đ剹���̌��X��
�@�@�~�̐�L���L������ӂƂ����
�@�@�֎U�邠���Ȃ܂ʂ邫���̉Ύ�
�@�@�ԕ��̓��@���͓��[���������肫
�@�@�C���͐�C���悩�˂Ȃ��
�@�@ꀂ̉ԃC�X���G������ЂƂ�����
�@�@���̖C�R���g���Ĕn�͝˂�
�@�@�䂭�D�֊I�͂��ЂȂ����������
�@�@�����_�䂯��ӂ邳�Ƃ̎_�䂳����
�@�@���тƂ͓y���̂₤�ɂʂ�Ă��
�@�@��n���܂��Â��ɗh���@���� �q�ւ̓J�r�@
�@�@�̏�Ɂ@�H�̋S��ĉ���
�@�@�b���������ւ@�n�̏ł�������
�@�@����@���߂ē���ނ��ė����
�@�@��I�Ɂ@�����肵���Ƃ�����
�@�@�H�V��@�������Ȃ����ˎ�m���тƁn�̂ЂƂ�
�@�@����㞂����j�`��@�ꒃ�̊�
�@�@�₯�����ɋ�㣁m����n��@���@�����v����
�@�@�؊��͂�������Ɓ@�Ђт��Ȃ�
�@�@�j���̈ӎ��@�����܂�醔n�e������
�@�@�������@�t�̂͌ċz���� �q�َ��r�@
�@�@�����m�A�m�j���n�̋�ԁ@���я��@�����_
�@�@���R�́@�啎P���@�|��Ă��
�@�@�~�y�ꁨ墁z��@��m�N�E�n�ɂЂ炢���y��̖�
�@�@�D�́@�J�́@���́@�w���s�����咣����
�@�@�ւ晳�Ӂ@�Ζ�ɂ𑐐[������
�@�@���₩�ȍ��v�m���邽�n�̗��ʁm����n�̂��݂����G �q�E��r�@
�@�@�J�̖�̂ӂ��肪���鉖����ׂ�
�@�@�ь�͍g�����ܑ��͍���Ă䂭
�@�@������V�Ђ�ꕶ�|�̂��Ƃ͌�炸
�@�@���ɂ̂��̒��̙֎썹��
�@�@壏��ɂ��肻�߂��Ƃ͌��͂�����
�@�@�J�^���ݓŔu�������ނ���
�@�@����✱�R�Ƃ��ē��ɑ�
�@�@�H�����@���V�����ɂ��͂܂��
�g���������s�̐��z�q�ԉ��j�厄���r�i�s�x�V�ԉ��j�S��W�t�x�A����ь牮�A1976�N12��10���j�ŋ������ԉ��j�̋�ł���B�x�V�ԉ��j���o
��Ƃ����`�����S��Ĉ�s�����������悤�ɁA���Ƃ����`���Ŏ��т��������Ɓ\�\���ꂱ�����ԉ��j�̐��_�������Ƃ��Ǝv�������߂āA�o�傩�玍�ɓ]��
���g���̍ŏ��̒��삪���̏W�s�����G�߁t�i1940�j�ł���A���������ɉ��������߂��̂����W�s�t铁t�i1941�j�������B���̂��Ƃ𗠏������邩�̂�
���ɁA�g���������W���������邱�Ƃ͐��U�Ȃ������B
���͒��̋r��݂�݂�
�������A���̌s�̓�����
�t�̂Ƃꂽ���炪�n�܂�
�X�Ӑ��̏L�Ђɔ����ދ�C��
�����蓅������ɐ���
���Ԃ��ȂĂ䂭����
���ǂt���܂ɑ̉���\��
��q�̉��_�œܓV���z�ЂƂ�
��ԏ�̋��ɗ،`�̖���Y��
�듃�֑r�͂ꂽ����Ɛ������� �i�q�t�r�@�E1�j
����Ղ̎��̉��Ԃ���
�]���̌ߐ��֍������͂���
�������_���̋������̚{��
�d�ʂ��������̓��[�ɒ���
��܂ɔ�s�@�͓���ʂƂ�
�������̗���������
�����鏭�N�ƌ��̐�̗₢
�s�������I��Ȃ����ɔ���
�̎��ł܂�Ă��܂� �i�q�����r�A�E5�j
�ԉ��j�̏�����W�s�V�̘T�t�̊��s��1941�N8��1���ŁA�g���͂��łɏo�����Ă������ߓ��肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�q�ԉ��j�厄
���r�ɂ��A
�g�����ԉ��j�̑S�e����Ղ����̂́A1960�N����ɍ����d�M�Ǝ����ās�V�̘T�k��������Łl�t�i1951�j�Ɓs�ւ̓J�t�i1952�j���Ă��炾��
�����B����܂ŋg���͂ǂ̔łŐԉ��j�̍�i��ǂ�ł����̂��낤���B���́s����o��W�k������{���{�S�W
91�l�t�i�}�����[�A1957�N4��5���j�́q�x�V�ԉ��j�W�r���Ǝv���B����́s�V�̘T�t����184��A�����́s���i��t����70��A�s�ւ̓J�t����
238��̍��v492������������̂ŁA�Ҏ҂͐ԉ��j���g���낤�B�g�����q�ԉ��j�厄���r�ň������s�َ��t�Ɓq�E��r��������̑唼�͂��́q�x�V�ԉ��j
�W�r�Ɍ�����B���҂��Ƃ炵�Ă݂�ƁA�����̋�قLj������[���A�ߍ�ɂȂ�قǒW���Ȃ��Ă���i�s�َ��t�͎��^����Ă��Ȃ����A���̌X���͂���Ɍ���
���j�B�s����o��W�t���s�����A�̂��́s�m���t�̎��т������������g���ɂƂ��āA�x�V�ԉ��j�͉i���Ɂs�V�̘T�t�̍�҂������̂ł���B
�u�f�p�Ȕo��̓ǎ҂ł��鎄�ɂ́A����璊�ۉ��̋��͂ȍ�i�́A�o��̘g�����u��E�̗l���m�X�e�C���n�v�̎��Ƃ����v���Ȃ��B�k�c�c�l������̎��l�k
�����q�̎���ɔ��ɗގ����Ă���A���̃��A���e�B�����������o��͎��ɂ͈����Ȃ��v�i�q�x�V�ԉ��j��W�s�َ��t�̂��Ɓr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����
�Łl�t�A����y�[�W�j�B���A���e�B�̗L���\�\���ꂪ�ԉ��j�̋傾���łȂ��A�L���g���̎�e���鎍�̂̍D���̊�ɂȂ����B���A���e�B���������Ȃ�����
�́A���Ƃ�����ł����Ă��i����ł���Ȃ��̂��Ɓj�F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���ꂪ1960�N��O���A�s�����G�߁t��20�N��́A�g���̏s������܂�Ȃ�
�p���������B����́A��i�̃��A���e�B����i���ꎩ�̗̂��ɋ��߂�ԉ��j�̔��w�\�\�ӔN�́s�َ��t�̎��w�ƁA�g���̋��߂郊�A���e�B���ΉԂ��U�炵���u��
�ł��������B�Ƃ��ɑc�^���s�V�̘T�t�ɋ��Ȃ���A���̌��u��ԉ��j�Ƌg�����̂��ɕ��̓��̈Ⴂ�i��Ǝ��j�ɂ����A�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�o��^���ɋ���
����̂̈Ⴂ�����҂̘��������ʂ����ƌ���ׂ����낤�B
�q�g�����̔o���r��
�����ď����Ȃ���������
������B���ŗp�����o���u�l�G�j�m�������n�v�͐ԉ��j�m�������n�̉��܂��Ă��܂����B�s���́t�ɓ��e�����Ƃ��̕M���uJ�g�v�͔����᫂�A�z����
�邪�A�����ȑz���𑱂���Ȃ�A���̔��́u���v�H�Ɓu�ԁv�u���v�j�̌����������̂ł͂Ȃ����B���̋g���́A�c�K�t����֍��Y�Ȃǂ̋��F�����Ƃ̋�
��ɂ����Q���������̂́A�厏�ɂ͂��ɍ�i���Ȃ������B���g�̔o������ׂĎ��т̒��ɕ������̂��B

�x�V�ԉ��j�̑S��W�O��\�\�s��{�E�x�V�ԉ��j��W�t�i��{�E�x�V�ԉ��j��W���s��A1965�N11��1���j�Ɓs�x�V�ԉ��j�S
��W�t�i����
�ь牮�A1976�N12��10���j�̖{���ƌ���o��̐��E16�s�x�V�ԉ��j �������H
�n粔���k�������Ɂl�t�i�����V���ЁA1985�N5��20���j�̃W���P�b�g
�g�������x�V�ԉ��j�Ɍ��y�����͋��T���Ă�����A�s�o��]�_�t��200���I�����q�Ǔ��E�ɕʂ̍����d�M�r�i1983�N12���j�Ɋ�
���q�����d�M
�f�z�r�ɂ������Ɂu��O�A�w���́x�Ŋ����A���̂����Ƃ��D���Ȕo�l�A�x�V�ԉ��j�̈���q���d�M�ł���̂��A�h���Ƃ����悤�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k��
��Łl�t�A�O��܁`�O��Z�y�[�W�j�Ƃ������B�ǂ���玄�́u�w���́x�ł����Ƃ��D���Ȕo�l�v�Ɠǂ�ł����炵���B�����͑f���Ɂu���̂����Ƃ��D���Ȕo�l��
�x�V�ԉ��j�v�ƎƂ�ׂ��������B�܂��q�����d�M�E�U�炵�����r�i�s����o��S�W�k��3���l�t�������[�A1977�N11��5���j�ɂ́u�d�M���B��̎t��
�h�炷�郂�_�j�Y���o��̎n�c�E�x�V�ԉ��j�̑S��W���A�킽���͂��ܒʓǂ��Ă���̂����A���s�l���̔o��́A���Ɉ������o�����Ȃ������B���̂����ɁA
�ԉ��j�͐������̎��т��Ђ����ɏ����c���Ă���v�i���O�A��ꔪ�y�[�W�j�Ƃ����w�E������B�g������W�o�ł̔��N�l�i�����d�M�瑼�S30���j�̈�l�ƂȂ�
���s��{�E�x�V�ԉ��j��W�t�i��{�E�x�V�ԉ��j��W���s��A1965�N11��1���j�́q�⒍�r��q�E��r���Ђ��Ƃ��ƁA���s�l���̔o��Ǝ��сi�H�j���f��
����Ă���B���a15�N�́s�����W�t�]�ɂ�
�@�@�����̒f�R�ɗ���
�@�@���܂����܂��̊L�k���Ȃ���
���a17�N5�����́s���߁t�ɂ�
�@�@�t��
�@�@�n���M�A
�@�@�c�c
�@�@�����P���̂ēn��
�@�@���R�͂͂邩�ɂ�
�@�@�c�c
�@�@���̉�
���a21�N9�����́s���z�n�t�ɂ�
�@�@�t����
�@�@�߂����_�䂫�ʎ�
�@�@����
���a21�N10�����́s���߁t�ɂ�
�@�@�ނ炳���́A
�@�@���܂�
�@�@�\�O��B
�Ƃ���B�����i�܂�ɂӂ肪�Ȃ�t����j�ƂЂ炪�ȂƃJ�^�J�i���ׂ�����������O�́s�V�̘T�t����^�@�^�i�ꎚ�A�L�j��^�\�\�^�i��{�_�[�V�j�𑽗p����
���́s�ւ̓J�t��s�َ��t�Ɏ���ԉ��j��̕\�L�̕ϑJ�́A�s�Õ��t�̐ߐ��֗~����s���[���h���b�v�t��㇗������Ɏ���g�������̕\�L�̂���Ƌ@����ɂ�
�Ă���悤�ŁA���������ʂɂ����ڂ��Ȃ��킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B
�@�剪�M���琼���O�S�ƕx�V�ԉ��j�̗�������a���Ƃ���ꂽ���A���͂����ւ�ȏՌ����������B�h�����邱�̓�l�̑n ���������ꎞ �Ȃ�ɂ���~���A�܂��ċN�ł��Ȃ��悤�ł�������A�o��E�̂��߂Ƃ������A�ނ��뎄�̂��߂ɒɍ����ł���B�v�����ԁA���͗����̋ߋƂ��܂Ƃ߂ēǂނ��� ��ؖ]���Ă�������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z��y�[�W�j
�O�S���O�Ō�̋�W�s�ϐg�t�͓��N2���A�p�쏑�X���犧�s���ꂽ�B�����s�ϐg�t����f���̎��M�O�ɏo�Ă���A�ԉ��j�́s�َ��t�ƂƂ� �ɕK����ӏ� �̑ΏۂƂȂ������낤�B�g���ɖ{�i�I�ȎO�S�_���Ȃ������ɁA���������������ɂ��܂��B����Ƃ����̂��A�q�K�ȍ~�̔o�l���c���Ɍ�������k��\�\�ѓc�� ���E�剪�M�E�����d�M�E�g�����q����o������r�\�\�ł��A�O�S�̋�́u�����K�o���Ɗ����C������v���o�ꂷ�邾��������ł���B���k��́q�u�����Ė�v �̈Ӗ��r�̈�߂Ɍ����铯��̑O����s�ӏ܌���o��S�W�k��10���l���o�l�W�T�t�i�������[�A1981�N1��20���A����\�j��������B
�g���@ ������Ɛu�����ǁA�������H�́u���̒��Ŕ����Ė�ƂȂĂ��v�̋傪�A�o��ł͈�̃��_�j�Y���Ƃ������ራ�����ǁA����̈�̌��_�Ȃ́H
�����@����܂ŁA������ ����͂Ȃ�������ł��ˁB
�g���@�������H�Ƃ����� �͎���ǂ�ł��Ȃ������̂�����B���Ƃ��Έ����~�ʂ��Ƃ��c�c�B
�����@�ǂ�ł����Ǝv�� �܂���B
�g���@�ق��̂��������e �����Ђ���Ƃ�����Ă����Ȃ����ȁB�ڂ��͂��̍�i�͔o��Ƃ��čۗ����Ă��邯�ǁA���̈�s�Ƃ����ꍇ�A�|��������邵�A�����~�ʂ������ ��B�����瑋�H�Ȃ͂ނ���
�@�@�@�R���挩��Ή��ɐႪ�~��
�@���������̂��ڂ��͐�i���Ǝv����B
�����@�܂��Ȃ��A������ ����������悤�ɂȂ�܂����ˁB
�g���@���H�͑����Ɏ��� �ǂ�ł�����Ȃ����ȂƂ�������������ǂȁB
�����@����������i���� �����Ƃ��̑��H����́A��\�ꂩ��ł��傤�B
�ѓc�@���̖�肪���ܔo �d�ł�����킩��Ȃ��Ƃ���B���Ɣo��Ƃ̂������B
�����@ �V���o��n�̔o�l�ŗǐS�I�ȕ��Ƃ́A����Ȃ�Ɏ��W�⎍�̎G����ǂ�ł����Ǝv���܂��B�����A����͂ڂ��̑̌��ł�����܂����A�����鎍�_�̌`�ł́A �Ȃ��Ȃ��̐t�ȂƂ��낪�ۂ݂��� �Ȃ��̂ł��B���t�̖������t�Ő����Ă��邩��ł��B�����Ŕ��p�G���Ȃǂ���ɂ��Ĕ��p�_�̌`�œǂނƁA��肠���ɔ[����������ł��ˁB������A���P�� �̓��L�Ȃǂ�ǂނƁA�u���Ȃ��Ƃ���P���Ɉ���͔��p�G����ǂނ��Ɓv�Ə����Ă���B�Ƃɂ����V�������|�v����g�ɂ��悤�Ɠw�͂͂��Ă���̂ł��B
�剪�@���X�����˂��B �i�j
�����@ ������ɂ���A�����ł悤�₭���펟������Ɨ��������t�̐��E�ֈ���ݏo�����Ƃ���킯�ł��B���H�́u�����Ė�v�́A���̑���Ƃ������ƂɈӋ`���� ��B��������㎍�ł͓�\�N���O�\�N���O����m���Ă���ƌ����Ă��A�Ƃɂ��������ݏo���Ȃ���A����Ɏl�\�N���\�N���u������ɂȂ�B�܂��� ������o�Ȃ�ł��B
�剪�@���̏ꍇ�A�ŏ��� �o��^������Ƃ����̂���̑O��Ȃ�ˁB�Ƃɂ��������o��^���̒��ł�肽���B�����������Ƃ��Ǝv���́B
�g���@�������H������� �������c�c�B
�剪�@�Ƃɂ����N���ŏ� �ɂ�邩�Ƃ������Ƃ��d�v�ɂȂ��Ă���B
�g���@�����O�S�̗��
�@�@�@�����K�o���Ɗ����C������
�@����Ȃ��F�V���F�ɂ��Ă�ςɂ��ꂽ�B����Ȃ̂��Ȃ�Ŗ��傾�Ȃ�Č������ǁA���j�I�ȉ��l�ł��ˁB
�剪�@���j�I�ȈӖ��̖� ��B
�g���@����͗��j�I�ɖ� ��ȂȁB�ǂ��Ƃ������ƂȂ����ǁB�i������A�O�`�l�y�[�W�j
�F�V���F�́q�g�����̒f�́r�\�\���́u�f�́v�Ƃ����`�����g���̐��z�̂ЂƂ̃X�^�C���ł���\�\�ł��������Ă���B�u�����K�o���Ɗ� ���C������@ �@�O�S�^�^���Đّ�Ŏ�������ł���Ƃ��A�����E�̖������O�S�̋���A�u�I�m�}�g�y�Ɣ�g���ʑ��ł��߂��v�ƓO��I�ɔے肵�A����ɑ��ĉ�������Ƌg �����O�S��i�삵�āA���ʂĂ�Ƃ��Ȃ��c�_�������Ƃ��������B���̂����A�������͗�ɂ���ēD�����āi�����Ƃ��A�g������͈��܂Ȃ�����ǂ��j�A�c �_�̍ŏI�I�Ȍ���������ɂ͂�����Ȃ��������A���͍��ł��A���̎��̈ӌ���P��C�͂��炳��Ȃ��̂ł���v�i�s�����C�J�t1973�N9�����A�Z��y�[ �W�j�B�m���Ɉ����~�ʂ̎��т̑��d�ȈÚg�ɐe�����F�V�ɂƂ��āA�u�����v�u�K�o���Ɓv�u�����C�v�͂����ɂ��y���f�������낤�B�����A�o��̗��j�Ƃ����� ���ɒu�����Ƃ��A���͂�͂�̂Ƃ���ɑ���B���g�A���Ȉ�t�ł��������O�S�ȑO�ɁA�a���̌Ȃ����̂悤�Ɍ���������͑��݂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���� �Ă��̋���܂ޑ���W�s���t�i�O�ȓ��A1940�j�����W�s��̓��t�i���m�ЁA1948�j�́A�g���̍�i�Ƒ����̂��̂����L����B����������́A�g�� �̏����̔o��ƁA�Ƃ��������A�g���̒����̎��тƁA�Ƃ������ق��������������m�Ȃ̂����B
�E���̉Ԟl�Ԃ̋��̕��̂���k�s���t�l�\�\�}��l�Ԃ̋Ȃ�X�͂Â�k�s�z���t�l
�E
���l�̏��m�ān�̓��F�ɃN���X�}�X�k�s��̓��t�l�\�\�l�K�ɏZ��ł���^��Ƃƌ��͂Ȃ낤�H�^���h��̐������̉��Ł^�@����Ă��錢�^�ʐ^�ɎB����
�ׂ��^�n���o�[�O��H���^�^���C�̂Ȃ��̍��l�k�}�N���R�X���X�i�F�E1�j�l
�E ���n������瀆��ĉ���ɂ��ށk�s���t�l�\�\�g���̏����͑傫�Ȑ��Z���܂����k�������i�F�E10�j���o�`�l
�E
�،͂�n�̑傫�Ȋ�ɗ܁k�s��̓��t�l�\�\�킪�n�j�R���X�̐��F�̑傫�ȓ��E�́^�ӂ����т܂����܂Ł^���ݓI���E�ɂ́^�ƍߓI�Ȍ��t����������k�킪�n
�j�R���X�̎v���o�i�F�E16�j�l
�E
���~�@���Â��ɗ��̖������k�s���t�l�\�\���w�����Ŗ���ׂ��G���x�[�^�[�ŏ���^�݂ɂ����ԉʼnԖ��^�����Ƀu�h�E���n���^�܂���Ȃ̂͐��̈��ݕ��^
�D�̔���n���ɂ���^�C�̏�̃R�����ɜ��ʂ��߂Ɂ^���ɂȂ��Ē��̂悤�Ɂ^�[���}�C�̌��ł������������z����I�k�R�����i�F�E18�j�l
�E
�Έ��ɎO�l�̘V�k���ւ肫�k�s���t�l�\�\�h�W�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�w�����G�b�^�@�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@����Q��
�̂Ȃ��͊��L�O�k���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�j�\�\�q�����`���r�l
�E�C����a�����鐅���ɓ��܂�k�s�ϐg�t�l�\�\�ЂƂ�̏��������z�����炤�܂��悤�Ɂ^���Ɛ�����^�R�͏o�������̂��^�����̒��ۊG��^���͍��ɂ��
�Ė��܂�^�L�͓����Ő�����^����͉ߋ��̂��Ƃ����m��Ȃ��^�Ẳ�����j����������k�^�R�i�G�E2�j�l�\�\�u���̉Ă�����C�݂Ł^���F���C����������^
���v�k���̐��̉āi�H�E24�j�l
�g�����i�c�k�ߋ�W�s���яW�t�i�ߓ����X�A1955�j�ȑO�ɐ����O�S���ǂ�ł������Ƃ͊m�������A���̏��߂͂��Ȃ̂��B�c�O�Ȃ��炻����L�������͂�
��������Ȃ��B1940�N�O��A���Ȃ킿�g�����s���́t�̕x�V�ԉ��j�̋�Ɏ䂩�ꂽ����ɁA�V���o��̍�ƂƂ��ĎO�S�̑��݂�m�����\���͏[���ɂ���B
�s���t���s���ɍw�ǂ��Ă���A�O�S�ɐG�ꂽ���͂�k�b�ɏo�ė������Ȃ��̂��B�f���͂ł��Ȃ����A��O�͋�W�̌`�ł͓ǂ�ł��Ȃ��̂�������Ȃ��B�����
���Ƃ����ꂱ��l����̂��A�g�����s���́t�ɓ�������͂Ƃ������A�e�{���W�s����t�i�ʖؓ��A2002�N5��31���j�Ɏ��߂�ꂽ�������̋�e�q�z���r��
�傪�A�ԉ��j�����O�S�ɋ߂��Ɗ������邩�炾�B�g������W�s�z���t�i����R�c�A2003�N4��15���j��������B
�@�ԊL�̂Ђ炭���Ȃ�J�����k�q�z���r�l
�@���̍��f����̐Q���邵��
�@���Ƃق��Ƃ�I�̂悬��䂭
�@�[���̂��ƂɎ��v�̉��̂���
�@�Ⴜ���M�ɗ��䂭���̎�
�@���̓�������Â��l�̉e
�@�����₳�����܂ɂ䂭�l�̉e
�@�@�@�@��
�@�t���C�W�����N�����z�����߂ʁk�E��l
�@���M����ЂƂ̂����т�A�}�����X
�@�䂭�t�┒�����肵���ꑜ

�ѓc�P�����s�����Ȃ������t�o�ŋL�O���̖F�����i1977�N�j�̐��e���O�Y�E�g�����E�ѓ��k��̖n��
�o�T�F�Ėڏ��[�u�ѓc�P�����F�����^���e���O�Y/�g����/�ѓ��k��/�g������/���P�v/�C�����o�j/�����q���q/�ѓc�P��
��<<�Ï� �Ö{ ���� �_�c�_�ے��E�r�܁v
�얼��́s����o��
��k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2001�N5��9���j�́q�����O�S�r�ŁA���̍앗������������Ă���B�u�����O�S�̍�i�����͏��a�\�N��̐V���o��^
����ʂ��Ė��G�o��̉\����Nj����������ƁA���A�R�����q�m�������n�́u�V�T�m�Ă�낤�n�v���l�Ƃ��Ď���i��Ő��q�ƍs�������ɂ��������Ƃɑ傫��
�����B���a�\�ܔN�����Ɂu����o��v�e�������Ō�������ĈȌ�A�풆�ɒ��ق�]�V�Ȃ����ꂽ�������u�ĂāA���G�o�傩��`���I�ȗL�G�o��ւ̓]����
�������킯�ł��邪�A����͒P�Ȃ�G��̗L���Ƃ����`����̖��ł͂Ȃ��A���@��̑傫�ȓ]���ł������B���������ĎO�S�o��̕]���͐�O�Ƃ���҂ƁA
���Ƃ���҂Ƃɕ�����Ă���v�i�����A��Z�O�y�[�W�j�B�g���͐�O�Ɛ��̎O�S�o��̂ǂ���Ƃ����ł��낤���B��Ɉ����������g���������ڂ�
�ɁA��͂��O�̋�Ɉ������������̂ł͂Ȃ����낤���B���Ȃ݂ɑO�f�g���������̎��т́A�O�S�̟f��ɏ�����Ă���B
�@�悭�V�����o�ł䂭��O�L�k�s�ϐg�t�l
�@���ɑD�X���r�ߎ���̐�
�@�̗ւ̏�ɓ̗֓~�Ɍ���
�@�@�@�@��
�@�֒f�̏��m�ӂ݁n��Z�[�h�̗Ό��Ɂk�E��l
�@���A���Y���Ƃ͉��������_�ς���
�k�t�L�l
�ʉ�F�́s�~�Ɨ��`�\�\�g�����m�[�g�t�i�v���ЁA1975�N6��15���A���o�F�s��p�҂����t10�`23���k1966�N6��
�`1969�N5���l�́q�g�����ɑ���m�[�g�r�j�́q��O�́@�~�\�\�o��r�Ő����O�S�̋��_���Ă���B�ʂ͂����Łs���t�̏��a�\��N�́q�O�́r�̑S��
�u���]���₵�����������݂�v�u�����K�o���Ɗ����C������v�u�s���Nj��͉����C�ɂ��v�������āA�u�k�c�c�l���̈��k�u���]���₵������������
��v�l�ɎO�S�����̎�X�ȃ��A���e�B�[���A����̎������f�A���ꂻ�̂��̂��`�̏œ_�Ƃ����A�e�̗����̊�������̂ł���A���ꂪ���߈ꌩ�P���Ɍ�����
���̈��ɁA�S�l�I�Ȃ��̂��A����ɂԂ����܂�āA���悤��ƁA�킸���\�������̊Ԍ��ɓ��߂��Ă���̂����݂Ƃ�ė���v�i�����A�l�y�[�W�j�Ə����Ă�
��i�ʂ́q��l�́@���ˁ\�\����o��r�ł��O�S�̋��_���Ă��邪�A���̍s���͊A�a���ɂ߂�j�B��̂ɒʂ̂��̖{�́A�g�������̓������u�~�v�Ɓu���`�v
�Ƒ����A�c��ȁu�m�[�g�v��ς݂����Ă���̂����A��f��������킩��悤�ɁA���Ƃ��ΎO�S�i�̋�j�Ƌg���i�̎��j���ǂ��茋�Ԃ��ɂ��Ă͂���������
�����ł͂Ȃ��B���������u�łтs�A�m��ƊI�Ԃ��v�u�I�Ƌ��Ē��ɐꂽ������v�u�_���Ă萅�Ɏ��ɂ�ĊI�Ԃ��v�i�s�����t�j��A�ق��O��Ƃ�����
�O�S��i�����������Ă���̂�����A�g�������Ƃ���炪�ǂ��W����̂��u�������Ǝv���͎̂������ł͂Ȃ����낤�B���́u���]���₵�����������݂�v
�����̂悤�ɓǂށB���̋�́u�����K�o���Ɗ����C������v�̒��O�ɒu����Ă���A���̐��I�ȃ��@���G�[�V�����ł���B�u���]���k�����Łl��₵�A����
�k��]�̔�債���l�ԂɊr�ׂāl���]�����������Ɖ^���n�������ǂ鏬���̗L���鎋�o����肤�������̂悤�ɁA�����C������܂��v�\�\���̂悤�ɐ[��
�݂��Ă͂��߂āA�g���̓M���ւ̊�]�^���|�ƁA�O�S�̋�Ƃ̂�������ݒ肵���邾�낤�B�u�s���Nj��͉����C�ɂ��v�́q�Õ��r�i�B�E2�j��z�킹�鏈��
������̂́A�o��Ƃ��Ắu�����v��u���]���v�ɋy�Ȃ��B�����Ă܂��u�I�v�O���ق��O�傪�q�O�́r���邱�Ƃ��Ȃ��B
�g�������Γc�g���̐l�Ɣo��ɐG�ꂽ���͂��߂����āA���Ď����q�g
�����U���̍��@�r���������B�����ł͋g�����������g���́u�����ƛ�㕂��o�Â�S���g�v���f�����������������A���z�W�s�u�����v�Ƃ���
�G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�ł́A�f��̂ق���
�@�p��ԋ��肽��X�ɉ���k�s�߂̊�t�l
�@�o�X��҂���H�̏t���������͂��k�s�߂̊�t�l
�@����̍��̔ޕ��̌������ȁk�s���t�l
��3�傪������Ă���B�s���t�́u�����Ɓv���܂߂āA�����Ƃ����Ă悢���낤�B�s�߂̊�t�i�������X�A1939�j�A�s���t�i������[�A
1943�j�ƁA��������g�������̋�W�ł���B�����Ŕg���̋�W���s�Γc�g���S�W�k��ꊪ�l�o��T�t�i�p�쏑�X�A1970�N11��30���j�̑��R�Ë��q��
��r�i�����A���Z�`����y�[�W�Q�Ɓj�ŊT�ς��Ă������B
�@�@�Γc�g����W�i�������X�A1935�N11��25���j
�@�A�߂̊�i�������X�A1939�N8��25���j
�@�B�s�l���i�O�ȓ��A1940�N3��25���j
�@�C�呫�i�b�����сA1941�N4��20���j
�@�D���i������[�A1943�N5��5���j
�@�E�a��i��o���A1946�N11��20���j
�@�F���@�č��Łi�P�䏑�[�A1947�N5��25���j
�@�G���؈Ȍ�i�R�����[�A1947�N12��15���j
�@�H�J���i���m�ЁA1948�N3��25���j
�@�I���`�ρi�������[�A1949�N11��15���j
�@�J�ɖ��i��i�ЁA1950�N6��15���j
�@�K�瑜�i�V�b���A1954�N5��20���j
�@�L��e�ɖ��i��玕���A1955�N5��20���j
�@�M�t���i��玕���A1957�N3���j
�@�N�𒆉ԁi�������p�A1968�N4��15���j
�@�O�𒆉ԈȌ�i�������p�A1970�N5��26���j
�g���͔g���̋�ƑS�̂��������͂�{�Ɏ��߂Ȃ��������A�O�f�q�g�����U���̍��@�r�ł��̑S�����������q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�ɂ́u�����g���̋����
�ɂ���悤�ɂȂ��̂́A���ł���B�^�S���Ƃ��݂킽���Ƃ��w�ɖ��x�ꊪ���⏥���Ǝv���v�i�s�o��t1970�N11�����q�Γc�g�����W�i�S�W�����L
�O�j�r�A�Z��y�[�W�j�Ƃ���B�܂��A���k��\�\�ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�E�g�����̘A�ڍ��k��q����o������r�i�s�ӏ܌���o��S�W�k��11���l���
�o�l�W�U�t�������[�E����X�A1981�N2��20���j�\�\�ł͎��̂悤�Ɍ���Ă���B
�g���ɂ���
�g���@���c�j�͔g���� ���ƁA��������͔����Ă���킯�ł��ˁB�ڂ��͑��c�j�A�D���ł���B�����o��Ƃ������̂͏h��������Ǝv���́B�g���̂����鋃������Ƃ���ŁA����_�� �Ƃǂ܂����Ⴄ�Ǝv���̂ˁB
�ѓc�@�₽���ȁA�g���� ��́B�i�j
�g���@���c�j�A������� �D����B��_�Łc�c�B�����A�g���͑������̂ˁB���c�j������Ŕ��\���炢�ɂȂ����Ⴄ�ƁA��Α�����Ǝv����B�g���̂��̔��K�̐��U�ƁA���̋����� ��o��̂ق���������Ȃ����Ɓc�c�B
�剪�@ �ڂ����g�����D����������ł����ǁA���̂��늴���Ă���̂́A�g������̋�ɂ́A������ł��Ȃ���Ȃ��ƈ�{�Ńs�[���Ɨ����Ă��Ȃ��Ƃ��낪����� �Ȃ����Ƃ������Ƃ������Ă����ł��B����͂��̐l���o��͕��w�ł͂Ȃ��Ƃ��A���������������Ō����Ă��邱�ƂƂ��Ɖ�����킯�ŁA�����Ă݂�A������ �c�j�̋�͂���ς蕶�w�ł���B���̈Ⴂ�̂悤�ȋC������̂ˁB�g������̋�͍D���Ȃ��A�ǂ����s���Ƃ��Ȃ����̂�����B
�����@ �D�������Ō����A�ڂ����g�����D���Ȃ�ł��B�Ɠ��ȏ������܂��B�s�풼��A���̔g���́w���`�ρx�Ƃ������a�o�傪�]���ɂȂ����Ƃ��A��͂�a�C�Ŏ� �ɂ����Ă����ڂ��́A����ɒ��킵�܂����B�g���o��͕a�������̂悤�Ȃ��̂ƏƂ炵���킹�ď��߂Ă悭�킩���ŁA���S�ɓƗ��������ꐢ�E�ɂ͂Ȃ��Ă��� ���B������������̎����ɂ����ꂩ����ʍ�i��ڎw���āA���ꂪ�w���q�x�ɂȂ����B�����A�o�l���������ۂɍ�i��ǂޕ��ϓI�ȗ͂��炷��ƁA���܂茵���� ���t�̐��E�֓˂��i���͓̂���߂Ȃ��悤�ŁA�ނ���g���̂悤�ɏ�I�ȞB�����̂���傪���}�����B������ �����Δg���o��́u�Ăɂ��́v�͏�������ӂ�ŁA���Ȃ�L���ȋ�ɂ��剪����̌����悤�ɂȂɂ�����Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ����̂�����܂��B
�g���@ ����͂킩��B������ڂ������݁A�g�����ō��ɔ����Ă����Ȃ��āA����͗₽���ƌ���ꂽ���ǁA��������o��ŏI����Ȃ����ƁA�ǂ����v�� ���Ⴄ�̂�B�V�������̏o�Ă����B���������ǁA����������ς�f�\�ɂ����ƌ����Ă����ł��傤�B���q�̑�������Ȃ��āB�����炻�������Ӗ��ŁA�� ���͎v�����Ⴄ�́A�Ђ���Ƃ�����g�������i���������Ƃ����ӂ��ɁB�i�j
�剪�@����ƌN���g���� ��ł�����̂͂ǂ������傩�ȁB
�@�@�@���̕�����N�����ꂵ���݂���k�s�ɖ��t�l
�ѓc�@�����Ԍ������Ȃ� �Ă����ȁB
�剪�@���̋���Ȃ��Ȃ� �ނ���������Ȃ�ˁB�Ȃ����A�E�̋�c�c�B
�g���@��������E���� �����`�ρk�s�ɖ��t�l
�剪�@�������������肩 �ˁA����ς�B
�g���@���ĂΏ\�O�� ���ّ����k�s�ɖ��t�l
�Ƃ��A���܂ɂȂ�ƁA�����ނ̈ӋC���݂Ƃ������̊ӏ܂͈Ⴄ���ǂˁB
�@�@�@����̍��̔ޕ��̌������ȁk�s���t�l
�@���������͉̂i���ɐ����̂тĂ�����������̂�ˁB
�����@�g���́u�o��͐� ���Ђт�����v������A�u���E����v�Ƃ����������ō�҂���ǎ҂ւȂɂ�����������ŁA���ꂪ���͂ł��B�܂��g������͔o�l�łȂ�����o����O����y�� ��ł����������ŁB�i�j
�g���@ ����A����Ȏ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂�B���܂����ĎႢ�l�̔o����ǂނ���A�o��͍D�������B�����ǁA���{�̎��̒��Œ�������Ƃ����̂����ܔ��Q�̐l�C�ł��� ���B�剪�͂ǂ����m��ǁA�ڂ��Ȃ�����đS�R�D������Ȃ��l�B�����ǁA���̒��̈ڂ�ς�c�c����͎d���̂Ȃ����Ƃł����āA���炪���܍ō��̐l�C �ł���ˁB�����Ȃ�̂ɂ��킩��Ȃ�����ǁA�ǂp����Ă�����ł��ˁB�����炻��ɋ߂��g���͂�����ł͂Ȃ����Ɓc�c�B
�����@ �o�l�Ƃ��Ď��ۂɔo�����鑤�́A���Ȃ薳�������m�Ŗ��������܂��ˁB������A�����Ă��͖��Ȃ��ƂɂȂ�B�ł��V�����o��`���ɕx�������炷���߂ɂ́A�� �̖��������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���c�j���A���̖�����������l�ł��傤�B�������A�g���͔o���j�邱�Ƃ����ꂽ�B�Ƃɂ������܂蒷����������Ƒʖ� �ɂȂ�܂��ˁB�i�j
�g���@����A����͎��l ����������B
�剪�@�������܂Ő����� �������̂́A���_���q��������B�A�n�n�n�B�i������A�l�`�܃y�[�W�j
���k��Ȃǂ̒k�b�̏�ŁA�g�������̗v�|�͂��ǂ�ɂ������A�������t�ӂ��ɂ܂Ƃ߂Ă݂�Ύ��̂悤�ɂȂ邾�낤���B
�@�ѓc�����ɂ��A�����u�l�ԒT���h�v�ł��������c�j�͐Γc�g������Ƃ̂��Ƃ����A�������c�j�͍D�����B�Ƃ�킯���̑�_��
�Ƃ��낪�B�����A�o��ɂ͔o��̏h���������āA�g���́u��������Ƃ���v�łƂǂ܂����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B�g���͑����Ɏ����A���c�j�������Ŕ��\��
���炢�ɂȂ�Ɛ�ɑ�������B�g���̔��K�̐��U�Ƌ�������o��̂ق��������̂ł͂Ȃ����B
�@�������ɑ剪�M�⍂���d�M���w�E����悤�ɁA�Ɨ��������ꐢ�E�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ���i�A����̎����ɂ����ꂩ��������i�A�Ȃɂ�����Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ�����
���g���̔o��ɂ͂���B������A�g�����ł����������Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ǂ����Ă���������o��ŏI���悤�Ɏv����B�����A����䂦�ɔg���̋�͖��i��
�������̂��낤�B
�@�@���̕�����N�����ꂵ���݂���k�s�ɖ��t�l
�@�@��������E���������`�ρk���l
�@�@���ĂΏ\�O�錎�ّ����k���l
�@����������́A�����ł͔g���̈ӋC���݂قǂɂ͐[���ӏ܂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������A
�@�@����̍��̔ޕ��̌������ȁk�s���t�l
�͉i���ɐ����̂тĂ�����������B�Ƃ���ŁA���ܓ��{�̎��ł͒������炪���Q�̐l�C�ł���B���͒���̎��͑S���D���ł͂Ȃ����A���̒��̈ڂ�ς�͎d����
�Ȃ����ƂŁA�����Ȃ闝�R���͂킩��Ȃ����A�ǂp����Ă����B�g��������ɋ߂��̂ł͂Ȃ����B
�@�����d�M�́A�o�l�͂��܂蒷����������ƑʖڂɂȂ�ƌ������A�Ȃɂ�����͔o�l�Ɍ���Ȃ��B���l�ɂ��Ă��������Ƃ��B
�����ŋg���̔g���ւ̌��y���s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t��������Ă݂悤�B�o�߂��킩��₷���悤�A���o�̔��\���ɔԍ���t���ĕ� �ׂ�B
�@���N���ォ��D���������o��ɂ��܂���ψ���������Ă���B���q�A���ɁA���q�A�ԉ��j�A�O�S�A��絁A���c�j�A�g�� ����O�q�o�� �̉�������܂ł������ǂ�ł���B�ނ���ǂ܂��ɂ����Ȃ��̂ł���B������̈�̈Ԃ߂Ƃ����悤���B�Ƃ�킯�A�_�ˉB���̉i�c�k�߂��킷��킯�ɂ͂� ���Ȃ��B�\�O�A�l�N�O�A���R�ǂ�W�w���яW�x�ꊪ�ŁA���m�̂��̔o�l���ꋓ�ɂ킽���ɐe�����l�ƂȂ����B�����I�Ƃ������A�l�Ԑ�i����������Ǝ��Ɖ� �̍k�߂̔o��́A���炭��̋ɓ_�Ǝv����B���G�ȓǏ�������̔�ނȂ����Ƃ̏o����Ă��ꂽ�Ƃ�������ł��낤�B�\�\�q�Ǐ����r�i�� �o�F�s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8���j
�A������A�o����̖{��������̖{�������Ă����B���ꂪ�i�c�k�ߋ�W�w���яW�x�ł������B���ɂƂ��āA����͖��m�̔o�l�ł��������w���яW�x�Ƃ����� �����C�ɓ������B���͓ǂ݂Ȃ�����Q�����B���q�A�g���A����A�O�S�Ƃ�������܂łɓǂ�ł����o�l�Ƃ܂������َ��̑N��Ȍ������Ƃ��������� ���B�\�\�q�i�c�k�߂Ƃ̏o��r�i���o�F�s��ԁt��7���A1971�N9��30���j
�B�q�R�@�g���̎O��r�\�\�q��z�̔o��r�i���o�F�s�����V���t1976�N7��18���j
�C�킽���͂��܁A�u�F�݂͂Ȑ�����Ƃ����Ӊ���v�̂��ƂɁA�Γc�g���̈���u�������Ƃ����U�f�ɂ�����B�\�\�q�����d�M�E�U�炵�����r�i���o�F�s���� �o��S�W�k��O���l�t�������[�A1977�N11��5���j
�D���ɂȂ��āA���͔����Y�̎���ǂ݁A���e���O�Y�̎��������A�V�������̐��E�̖��͂ɂƂ����Ă��܂����B�܂�����ł́A�֓��g�̒Z�̂ƍ��l�� �q�̔o��ɂ���������Ă����̂������B�����̉e���ɂ���āA�y�������A�{�A���̒Z�̂�ǂ݁A�R�����q�A�Γc�g����̔o���ǂ�ł���B���͍����A���� �ƉC���̂����ꂽ��̒�`�����A���R�ƈ��D���Ă���̂ɁA�����Ȃ��̂��B������ƂĂ����߂Ƃ��ӏ܂��s�����Ƃ́A���̔C�ł͂Ȃ��䂦�A�����Ɏl�l�̉̐l �̍�i��I��ŁA�f���邾���ł���B�\�\�q�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�i���o�F�s�Z�̖̂{�k��ꊪ�l�Z�̂̊ӏ܁t�}�����[�A1979�N10�� 20���j
�E��������~悖������ӂ�A�]������ǂ�ł����A�H���q��q���ꂩ��g����̒[��Ȕo��Ƃ́A����قɂ��Ă���B���͂����܂��k�ߔo��ɖ������Ă� �܂����B���ƂɁu�V�S�ɂ��Ęe������t�̊�v���D�����B�����ł͎��ԁE��Ԃ���u���������~�߁A�������U�������̎p�݂̂��I�R�ƌ�����B���͂��鐏�M �̖��������̈��ŏ������̂��A���v���o�����B�������A���������Ƃ���������̂́A�A��q�Ώΐ}�r����ł���B�\�\�q�k�ߏG�叴�r�i���o�F�s�o��̖{ �k��ꊪ�l�o��̊ӏ܁t�}�����[�A1980�N4��8���j
������v����ɁA1955�N10���ɏ��߂ĐG�ꂽ�i�c�k�߈ȑO�ɐe����ł����o�l�̑�\���R�����q�ł���Γc�g���������A�Ƃ����\�}
�ɂȂ�B����
�ł́u�����g���̋�����ɂ���悤�ɂȂ��̂́A���ł���B�^�S���Ƃ��݂킽���Ƃ��w�ɖ��x�ꊪ���⏥���Ǝv���v�Ƃ����]���͂ǂ����琶�܂ꂽ�̂���
���B����������A�g���͂ǂ̔łŔg���̋��ǂi�ǂ݂Ȃ������j�̂��낤�B
�@�s�Γc�g����W�k�p�앶�Ɂl�t�i�p�쏑�X�A1952�N3��15���j
�@�s��{�Γc�g���S��W�t�i�n���ЁA1954�N4��30���j
�@�s�g�����I��W�k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1957�N10��5���j
�����̂����ꂩ���낤���A�s�Γc�g����W�k�p�앶�Ɂl�t������̂悤�ȋC������B�{���ɂ́s�߂̊�t�i1�j�A
�s���t�i2�j�A�s�a��t�i3�j�A�s�J
���t�i4�j�A
�s�ɖ��t�i5�j��5
��W�A���吔1525�傪���߂��Ă���B�̂��Ɂs�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�ƂȂ鎍�т������Ă��������\�\�k�߂̋�ɏo����O�\�\�̋g���́A�s�߂�
��t�́u���~�@�e�����点���F�Ə��v�́q�n���ؔ��s��
�܋�r�Ȃǂ����������ǂނƂƂ��ɁA�u���c����݂̂Ȕ������v�u�H�̖�̕��낵�����X���v�i�s�a��t�j�A�u���̊Ԃ⊦�_�R���ċ��œy�v�i�s�J���t�j�A
�u�����͓~���ɂȂ����ɓ����v�u�������ٌ_����T��Ɂv�u��͂��Â��ɂ䂽���ɂ͂₵�r���v�u���鐅���߂��̍ŏ��̗|�]��v�i�s�ɖ��t�j�Ƃ�������
�̂����Ă��鎄���A�Ƃ���������҂̐��ɑł��ꂽ�̂ł͂���܂����B���͂����̋�̂��ƂɁA�u�킽���������l�ł���^�ЂƂ̌́^������Ă䂭����
�̑܂ł���Ƃ������Ƃ��^�����ꂪ�m���邾�낤�v�Ǝn�܂�q�҉́r�i�B�E12�j��u�������Ƃ����U�f�ɂ�����B
����A�o���O�́i���Ȃ킿�_�c�E�W�H���̏o�ŎЂɋ߂Ă��āA���g�̔o�l�������܌��Ă�������́j�g���́A�g�����s�߂̊�t�ŕ`�������E�ɋ߂��������B
�q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�Łu���łɔg���͔o�d�̋P���鐯�ł����B���͔g���߂Â����Ƃ����Ȃ����B�����Ȃ���o����̂āA���͂Ђ����ɒ��������Ȏ�
������݂�������B�^�����͂��ƂŁA���W�w�t�́x�ɂȂ�͂��ł����v�i�O�f�s�o��t�j�ƋL�������A�o����������Ƃ������߂����̂́A�u��������
�Ȏ���v�ł���͂��́s�t铁t�͎v���̂ق��u�v���^�i�X����݂ǂ�Ȃ�Ă͗��ʁv�u�������Ȃ��K�N������Ώt�̗��v�́s�߂̊�t�̝R��ɒʂ��Ă���B�k
�����q�ӂ��̌�@�ɂ����f�킳��Ȃ���A����͗e�ՂɌ��ĂƂ�邾�낤�B
���āA�g�������ő�̋��ܓ_�͑�W�s�t铁t�i����ɁA1941�j�Ƒ�O���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̊Ԃɑ��݂���B���̔w�i���Ȃ��Ă���̂́A
1941�N����45�N�ɂ����ĕ����Ƃ��Đ��ɋ�肾���ꂽ���ƂƁA�킪�������̐킢�ɔs�ꂽ���Ƃł���B�g�����25�ΔN���̐��e���O�Y�ɂƂ��Ă��A��
���̉e���͑傫�������B���{��ɂ�鐼�e�̑�ꎍ�W�sAmbarvalia�t�i�ł̖؎ЁA1933�j�Ƒ�W�s���l���ւ炸�t�i�����o�ŁA1947�j��
�Ԃɂ͋��ܓ_������B�����A���܌�̐��e�ɂƂ��Ă͉ߋ��̎��g�̌�@�̔ے肾�������̂��A�g���ɂ͎��Ȃ̑��݂̔ے�ɂȂ��肩�˂Ȃ���@�������Ƃ����_
�ɂ����āA���̊p�x�͂��������傫�Ȃ��̂������i�ӂ���ɂƂ��Ď��W�̃C���^�[�o���͂Ƃ���14�N���������A���e�̋��܂͐풆�ɁA�g���̋��܂͐��ɖK��
���j�B���̊�@��c������̂ɍۂ��āA���A�a�Ď��������܂�����g���̋傪�A���̐����g���̑O�ɑ傫�������͂��������̂ł͂Ȃ����낤���i�g����
1944�N3���A�ؖk�ŋ������a�j�B�s���l���ւ炸�t�͋g���̎�����o�����������A���̔g���̋�͋g���̐������������i6�j�B
���̌o�����g�������Đ��U�A�o��Ƃ����킹��v���̂ЂƂƂȂ����B���͎��̔g������q�Õ��r�̖T�ɒu���Ȃ���A�����l����B
�@������S�����ނ���̕��k�s�J���t�l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���R�Ë��́q���r�ɂ��A�s�Γc
�g����W�k�p�앶�Ɂl�t�́u�w�߂̊�x
�w���x�̏��Ŗ{�͎l�G�ʂł��������A�{���ł͍��N�㏇�ɕҐ��������A�e���N����L�����Ă���B���̎O��W�͂��ׂč��N�㏇�ҏW�ł��邩��A�{����
�S�����N�㏇�Ƃ����_�ɓ��F������B�^�k�c�c�l�A���^��ɂ́A���Ŗ{�Ɣ䂵�āA���Ȃ�����̎肪�������Ă���B�^����ɔg���̎ʐ^�A�����ɎR�{���g��
�u����v�A�g���́u�N���v���������Ă���v�i�s�Γc�g���S�W�k��l�o��U�t�p�쏑�X�A1971�N2��27���A�O����y�[�W�j�ł���B
�i1�j�s�߂̊�t�F�����{���20��
���폜�A96��₵��339������߁A���Ŗ{�̎l�G���ނ����N�㏇�ɉ��߂Ă���B
�i2�j�s���t�F��
�Ŗ{���l�G���ނł���̂�N�㏇�l�G�ʂɉ��߁A77��폜�A34�������275����^�B
�i3�j�s�a��t�F��
�ނ͏��Ŗ{�Ɠ��l�ł��邪�A���v28����폜���A28��₵�āA111��̎��^�吔�͏��Ŗ{�Ɠ����B
�i4�j�s�J���t�F��
�Ŗ{���~�t�ďH�̏��Ŏl�G�ʂł���̂���̂��A���N�㏇�ɉ��߁u�쑺�v�u�œy�v�u�\��v�u�앪���v��4�тɕ����A�吔��14����폜����17�呝
��A���Ŗ{���3�呝��276��B
�i5�j�s�ɖ��t�F��
�Ŗ{�i���吔506��j��21����폜���ĐV����39��������A524������߂�B
�i6�j�����̗×{���Ŕg���� �����a���ɂ������鏹���́q�g������Ǝ��r�Łs�ɖ��t�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B�u�g������͋�s�����ڂ��Ȃ��l�������B�{�邱�Ƃ͂��������A�Q���� �����Č��ɂ��Ȃ������B�����ċ��炭�A�h���Ƃ��߂����Ƃ��͔o��Ɉ�O���Â炵�Ă����B�a�ꂪ����n�ꂪ���������A�����ɂ͋��O���̖������������B�u�� ���v�ꊪ�͂��̓��R�̐��ʂł��낤�B�����Ɏ蒠��u���āA������̈Â���̒��ł����M�𑖂点�Ă��邱�Ƃ��������Ȃ������B���͔g���o��̖��͂Ɏ�߂��� �Ĉꎞ�͋��ɔM�����A�₪�ĕs�т̂܂ܔo�傩�牓���������҂����A���̈���ɂ͐Γc�g�����z�����Ȃ������疳�Ӗ����Ǝv��������������B����͐Γc�g ���Ƃ����l���Ɣo��ɐg�߂ɐG��Ă��܂����s�K�Ƃ������邵�A���邢�͙F�K�������Ƃ��l������B�Ƃɂ����A�g������́u�o��̒����͂��ꂪ�����Ă��v �ƌ���ꂽ���������A�m���ɂ��̎����𐬂��������Ǝ��͎v���Ă���v�i�s�Γc�g���S�W�k��ꊪ�l�t�����1���A�l�y�[�W�j�B�g���̐g�߂ɂ��č�傩�痣�� ���̂͋g���������ł͂Ȃ������B
�g�����̖����̎U���Ɂq�Y�꓾�ʈ�o�l�̈��r������B���o�͑�쐽�v�E�n�ꂠ���q�E�����؍K�j�ҁs�Z�̂̂����߁\�\����ɐ�����s��
�̖��O���k�L
��t�I���l�t�i�L��t�A1975�N8��10���j�B���́q���̈��u�́r�Ƃ����R�[�i�[�ɔ��\����Ă���B�����̑O���́A��ɂ���Ď��l�ł��鎩���ƒZ�̂Ƃ�
�ւ�����M�����������̂ŁA����Ȃ��������B
�@���ɂ͈���̉̏W������B����́A���̔Ӎ����j���Ă��ꂽ��y�E�m�F�L�O�Ƃ��Ĕz�������ɔ��y�\�Z����\���z�� �̏����q�ł� ��B������Ă��ꂽ�̂��A���͌̂��ɒB���v�ł������̂��������v���o���B�薼�́s�����t�ŁA�Z�̎l�\��A�����̓������߂Ă���B��������\��㔼 �����\����܂ł́A�t�قȂ��̂���ł���B
�@�@��̉w�̎��v�̐j�̂������̂��ӂƂ݂����Ƃ̂��͂����Ȃ���
�@�@�H�Ђ炭���W�̗]����ӂ��a�̂������ƂӂƂ����ɂ���
�@�@���Â̒j��╂Ŕ��肠�邭�������ɓ��̕�ꂻ�߂�
�@���N�̍�����A���낢��ƒZ�̂�o��̖{��ǂݒ^���Ă������̂��B���Ƃɔo��̂ق��͏\�l�قǂ̒��ԂƂŁA��s���������ĕ��������A�Z�͓̂ƏK�� ���ɂ����Ȃ��B���̍������Ƃ����ǂ����k�����H�̉e�����Ă���B�ق��ɂ́A��A�[��A�q���A��~�̉̂�ǂ݁A���ꂩ��O�썲���Y�ւƈڂ�A�₪�Ď� �̐��E�֓����Ă������̂ł���B
�@���ɂ́A�������ɂ́s����壁t���������Ă����L��������̂�����A���R�g�̉̂ɂӂꂽ�Ǝv���̂����A�[���S�������Ȃ������炵���B�i�����A�O�` �l�y�[�W�j
�g���̐��z�ɐe����ł����҂ɂƂ��āA�ڐV�������Ƃ�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����Œ��ڂ��ׂ��́A�̏W�s�����t���牽��I�Ԃ����� ���i�u���� �́c�c�v�͑剪�M���g���Ƃ̑Βk�ŖJ�߂Ă���悤�ɁA�̂��̎��l�g��������肵����ŁA�{�l���C�ɓ����Ă������j�B������ɂ��Ă��A����������Ă̎� �ȏЉ�Ƃ������Ƃ���ł���B���́u�Y�꓾�ʈ�o�l�̈��v�͌㔼�œW�J�����B
�@���̐S�̂Ȃ��ɁA�s�v�c�ɂ����̉̂������܂�Ă���B����́A
�@�@������݂ɂ����ɂ����݂Ă킷�ꂯ���߂݂̂��݂Ȃ��Ȃ��Ƃނ�
�@����͎������̔o��̎w�������Ă��ꂽ�A�c�K�t���̗B��̒Z�̂ł���B�~�̖铹������Ȃ���A�ނ����ɚ����悤�ɕ������Ă��ꂽ���̈�A�O�\�N�ȏ� �o�������ł��A�Ƃ��ǂ����̌������y�Ł��āz�o�Ă���̂��B
�@ �t���́u���n�������ւ͊C�̐^�̈Łv�̎����̈����Ō�ɁA�S���Ȃ�ǂ��ē������E�����Ă��܂����B�t���̐e�F�̔o�l�֍��Y����e��W�s���n���t�ꊪ�� �҂�ł��邪�A���̔ނ̌��t�ɂ��ƁA�Z�́A���R���A���z�A���L�ވ���ċp���āA�ȂɂЂƂc���Ȃ������Ƃ̂��Ƃł���B����́A���̈����m��Ȃ��� �̂��ƁB�͂����āA����͒N�̉̂Ȃ̂ł��낤���B�t���̉̂��\�\����Ƃ����̉̂Ȃ̂��\�\�A�Ƃ�����A���̐t����̑�Ȉ��ł���B�i�����A�l �y�[�W�j
�H䇓��l��Ô����̑��Ђ炪�ȏ����́A�c�K�t�������`���ʼn̂��I�������߂ŁA���ɂ���������������ĕ\�L����Ȃ�
�@�@���݂ɍ����ɒu�����ĖY�ꂯ���߂̌�_���������y�q��/����/�K�ށz�y�~��/����/��ށz��
�ƁA�u�Ƃށv�i�}�s����i���p�j����`�ɂ킽�邩�B�ǂ���ɂ��Ă��A�u������݂Ɂv�u�����Ɂv�u�݂��݁v�u�Ȃ��Ȃ��v�Ƃ������������� �߂��ċ����� �̈Ӗ������ǂ邱�Ƃ͓���B�Ƃ�킯�u��߂̌�_�v����ł���B�^���̐_�A�ȂǂƂ��Ă͂��̍��ׂƂ����s���𑨂������Ȃ��悤�Ɏv���B
��
�g�����̔o��ɂ��ẮA�l�G�j�EJ�g�Ƃ����o���𒆐S�ɏ��������Ƃ�����i�q�g�����̔o���r�j�B �����ł͐G��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�g���ɂ́q�o��Ƃ̏o��r��������d�v�ȍ��k�����B�s�n���t�̐����H���q�̖嗬�Ƃ��ēo�ꂵ�����h�o�l�A ���c�Îq����ɂ���o���s��t1972�N10�����f�ڂ́q����o�偁���̒f�ʁr������ł���B�g�������z�ɏ������b����������A�c�K�t���̂��Ƃ𗦒��� ����Ă���M�d�Ȓk�b�Ȃ̂ŁA�ς��}�킸�Ɉ����B
�@���c�@
���傤�͎��l�̋g���k���l����A�̐l�̍����k�K�j�l����A����ɔo�d������q�k�����l�A�����k�d�M�l�̂���l�ɂ����ł��������܂����B���ꂼ��̃W����
���Ŋ��Ă��������ł����A�͂��߂ɁA�ǂ�Ȃӂ��ɂ��Č���\���Ƃ�����荇���悤�ɂȂ����̂��A�`���Ƃ̏o��Ƃ����܂����A�ł���Δo��Ƃ̏o
��A���̂ւ�̂Ƃ�����A���������b�˂����܂��B
�@�����@�k�c�c�l
�@�g���@
�k�c�c�l�^�ǂ������o��̌����ȁA���I�̌��Ƃ����̂��킩��Ȃ����ǁA����ς�ڂ��ȂA��l�̐l�̏o��Ƃ������Ƃ�����Ǝv����ł���B�����
�{����`�̓����ɂ��Ă��̂Ƃ��\��A�O���ȁc�c�B���������z�̉Ƃ����Ă邽�߂ɁA���z�̉Ƃƌ������邱�ƂɂȂ�����ł���B���z�̉ƂƂ����͉̂X����
�����āA���z�������ɂ́A�����̂Ƃ��̏�ɉ��h�l��u���Ă���A�������邯�ǁA�������A���̉��h�l�����̂܂�ܒu���Ăق����Ƃ��������������āA��������
�킯�ł��B�����ɍ����t�˂Ƃ����A���Ƃŏ��ƂɂȂ����l�ł����ǁA�M�k�Ƃ����̂��A�}�łƂ��n�}�A�L���̃`���V�̉������Ƃ�����āA�ׁX�ƕ�炵�Ă��킯
��ˁB���̐l�����w�N�������A�����̐l�Ȃ��ǁB����łڂ��͊O�ŗV�Ԃ��ǁA���Ԃ܂�Ȃ��Ȃ�Ɣނ̂Ƃ��֍s���B����Ɣނ��{��ǂ�ł��ꂽ��A�o
��A�Z�̂̎�قǂ������Ă��ꂽ�B��ȂA�������ɃS�[���L�[�́w�ǂ��x��ǂ�ł��ꂽ��Ȃ����B����łڂ����o���A�Z�̂��A�����ɂ�������
���B���̂Ƃ��̎�{�Ƃ����̂���A�q���A��~�̉̏W�łǂ���������ɂ������B�����āA��Ԉ��ǂ����̂����H�́w�Ԋ~�x����B���ł��ڂ�ڂ�ɂȂ��Ă���
�̂������Ă����B���ꂩ��O�c�[��́w�����сx���ȃ@�c�c�B���������̂��y���݁z���Ă���āA������œǂ���A�o����̂̂ق����悾��
���悤�ȋC�����܂��˃F�A�ڂ��́B�ŁA���̐l���D�����������A�ڂ����g�������Ƃ����̂��D���c�ȂڂɌ�����悤�Ȃ̂ˁA���ɂ͂��肢���킯�ˁB����
��ڂ���
�Ƃ��āA�m�ԂƂ����͔̂��ɂނ��������āA���������N�ł��قڂ킩�銴���c�c�B����ȂƂ�����{���ɂ��钇�Ԃ����l���W�܂��āA�o���݂����Ȃ̂����
���킯�ł���B
�@���c�@���a�̏����ł����B
�@�g���@�����ł��ˁB���c��
����m���Ă�c�K�t���Ƃ����l���w���҂݂����ł����B
�@���c�@���A�����p�Őg��
�����ĖS���Ȃ����c�c�B
�@�g���@
�������S�����ꂽ���ƁA�܂��Ȃ��A�g��������������B�����Ȏʐ^������ł�����B�ނ͗��_�h�ł���������������ς��Ă���āA���̂Ƃ��Ȃ�Ă�����
�O�ŋ�������Ă����A���܂�����ƖY�ꂿ��������ǁk���̖��́u��鵶���v�l�A�K���łō����āA�\�l���炢�W�܂��āc�c�B
�@���c�@���͐_�c�́c�c�B
�@�g���@
�����Ȃ�ł��B�֍��Y����̉ƂŁB���܂ł��o���Ă��ǁA��O�A�̗���̊p�Ɂu�u���W���v�Ƃ����i���X�������āA�����ŋ���������̂��A�ڂ���
�͂������ۂɎc���Ă܂��ˁB�u������݂̂��ڂ��D�Д���Ɂv�͂����̕��i�ł��B���Ƃ͊e�l�̉Ƃ֍s������Ȃ��āc�c�B���������l�̎�����ɂ����
�Z�̂Ɣo��ƂقƂ�Ǔ��������ǁA�ǂ������Ƃ����ƒZ�̂̂ق��𑽂��������ȁB
�@���c�@�����ł����B
�@�g���@�����B�ŁA����͐�
��ɂÂ��킯�ł����ǂˁB�����ǁA�������傭�o���ƂɂȂ�Ȃ������ˁB�o��͂��܂肤�܂��Ȃ��������Ă����킯�ȂA�ǂ����B���̂����ɖd�����N��
���āA����́u���́v�̂ق����������낢�Ƃ������ƂɂȂ��āA�u���́v�֓�A�O�e�����ł��ˁB
��
��͂��������Ƃ͊m�������ǂ��A���̂Ƃ��̈�傪�u�ԂƂ�ڏ��w�̊��c�����Ă���v�B���̂���x��ԉ��j�A�ЎR���j�����Ă����킯�ł���B����ł���
���̓y�C�y�C�ŁA���łƂǂ܂��Ă����܂��ɂȂ���������ł����ˁB
�@�������@�o�l�̕��ɂ͂���
�Ԃ�ɂȂ��Ă���킯�ł����A���̂���́B
�@�g���@����A����B
�����ē����̏�������ȂƂ��ł���āA������̂��̂͂��̓c�K�t�����Ă����l�ł��c�c�B����͗]�k�ł����A�ւ��������ЂƂ�ŁA�w�c�K�t���S��W�x
������܂����B�a���Ɏ菑�ŁA���{�܂ł��Ă��܂��B�ڂ����҂��Ă���̂͂��̔����ڂł��B
�@���c�@�u�n���v�̎O�勉
�̐l�������ł��ˁB�t������͂ڂ��炪���܂��Ȃ��u�n���v�ő����m����悤�ɂȂ����Ƃ��ɁA�_�c���ӂŁc�c�B
�@�g���@���]�삳��Ƃ�����
������̓�K�֏W�������̂ł��B
�@���c�@�����ł��ˁB���̏�
�]��Ƃ����̂��֍��Y�A���܂ł��A�u�߁v�ɂ��܂���B�H���q�������q�ɂ����Ƃ��ɁA�Ƃ��ǂ������q�֍s���ē������Ă��l�Ȃ�ł���B�g�����A�u�o��
�]�_�v�̑��̂Ƃ��A�ڂ��̋�W��҂��Ă�����ƕ����āc�c�B
�@�g���@�w�r��x�ł��ˁA
�����Ă܂��B
�@���c�@�����A�т����肵
������ĂˁB
�@�g���@���̂���݂͂�Ȃ�
��W���ēǂ킯�ł���B
�@���c�@�����ł����B
�@�g���@����͏��a��\�O�N
����ŁA�o���̖��́u�H��v�Ƃ��������ȁA���ƂŖ��O���Ȃς������ł���B�u�b���v�ɁB
�@���c�@�ڂ��̒m���Ă����
�́u�b���v�ł��ˁB
�@�g���@�u�H��v�Ȃ�ł���
���́B���ꂪ�u�b���v�ɂȂ����B
�@���c�@�K���ł̋�e���A��
��Y���H���q�ɑI���Ă�����Ă��̂��������Ƃ�����B
�@�g���@
�����ǂ���ς�A�c�K����̂��Ƃ��̂������߁m�A�A�n�ɂȂ�܂����ˁB����҂Ƃ��Ă����j�[�N�����ǁA���_�h�Ƃ��ĂˁB���̐l�͕s�K�ɂ��āA
�u�n���v�ɂ������߂ɂ悭�Ȃ�������ł��B���̐l�͐����o��ł���A�������i����Ȃ��ĂˁB�c�K����Ƃ��Ă͐�������ꂿ���������s�����������
�����B
�@���c�@�g������͂�����
�炢�c�c�B
�@�g���@
���ꂪ�˂ڂ�����\���A�ザ��Ȃ����ȃ@�B�����ǁA�ڂ��͂��̑O�ɂ������łɁw�t�́x���Ď��W�����Ă܂�����ˁB�����瓯���ɗ����ł��Ȃ��B�o���̊y��
���Ƃ����́A����܂��ˁB�Ԓ��Ƃ��َq�ŁA�����̋傪�̂��邩�̂��Ȃ����Ƃ����y���݂ˁB���̊y�����ɂ��ڂ�Ă͂����Ȃ��A�����ł݂�Ȃƌ��ʂ��ׂ�
�ł���ƁB����œ�\�ギ�炢�̂Ƃ��A�����̎����m�����邽�߂ɁA�܂��̂�Ŕo��ƌ��ʂ����������ł��B�����A���D�Ƃ��Ĕo���ǂނ��Ƃ��D���ł��B��
�܂�����Ɠǂ܂Ȃ����ǂ��A�����Ȕo�l�����������ēǂł���B�i�����A���`��l�y�[�W�j
�g�������k��ʼn�z����u���D�Ƃ��Ă̔o��v�͂����悻���̂悤�ȍ\�}�������B
�s�n���t�̓c�K�t���͐�O�A��\�ΑO��̋g���⓯�����s�n
���t�̒֍��Y�i�{���E���]��O�Y�A���͐Γc�g���́s�߁t�ɓ������j�̑����Ă����q��鵶���r�̎w���҂ŗ��_�h�A�����o���g��Ƃ����B����
1948�N����A���́q�H��r�i���̌�q�b���r�j�ƂȂ�A�g���������s�ɎQ�����Ă���i�����̔o���́u�l�G�j�v���j�B��O�̋g���́A���n�{���ł̋C
�̒u���Ȃ������y���ވ���ŁA�����̃��_�j�X�g�C��������쑐��́s���́t�ɂ��ڋ߂��Ă����B�x�V�ԉ��j��ЎR���j�Ɏ䂩��A��i��ǂނ����ł͑���
���A�V���o��̓����ɓ�����͂��߂�i�M���͏I�����̈��̂݁u�g�����v�����A���͂��ׂāuJ�g�v�j�B�����̂��Ƃ��A�g���̔o��̔w��ɂ́s�n���t��
�s���́t�������āA�o�������Ɠ���Ƃłӂ��������Ɏg���킯�Ă����B���������u�o�v�Ɓu���v���邢�́u�������v�Ɓu�ǐS�v�̂悤�ɁB���c�Îq�̌Ăт�
���ɉ����Ă��̍��k��ɔo�l�Ƃ��ďo�Ȃ����̂��A������絁i�͂��߁s�n���t�ɋ������j�Ɏt���������q�����ƁA�s���́t�̕x�V�ԉ��j���t�Ƌ��������d�M
���������Ƃ́A�͂Ȃ͂������[���B
�g���̔o���ł̍��́A1949�N1��30���̋�s��ł́u���~��ӂ邫���炩�̔g���Ă�v�\�\�s���Y�t���N2�����́i�����炭�͋g���̕ϖ��ł���j�t�C
�~���q���T�~���r�́u���~��^�Ŕ��ϔY�̈ӂȂ��v�u�g�~��^�ڂ݂ɂ�����Ԃ̑��v�u���~��^�ӂ邫���炩�̏Ƃ邵�Â��v��3��\�\���Ō�ɏI����
�����A�g�����Ăєo��Ɏ����߂�̂́A���l�u�g�����v�Ƃ��ās�����C�J�t1975�N12���Վ��������ɔ��\�����q���܂�����\�\�k�������h�s����t�̈�
�ێ��сr�i�G�E30�j�ɂ����Ăł���B�����ɂ���̂́u�]�Z�Ƃ��Ă̔o��v���u���l�o��v�ł͂Ȃ��A���т��ٖ��ɍ\������A�h�邬�Ȃ��o���i�������B
��
���a�\�l�N�i��� �O��j�\�\����
�@ ��A�t�ˎR�l�ƍ̎s�ւ䂭�B�r���A�t����l��U���o���A�����B�����������A����������l�g�ɂ��܂�ĕ����B�ω��l���ΑK�������A�����̉H�q�s �����ĉ��B��ࣂƍʂ�ꂽ���E�B�|�W����A�H�q�����l�������B�A��A�j���[�g�[�L���[�Ńr�[���A���ł�ʼńA�o��k�`�B���ꂩ��u���W������X �ŁA�t����l�̒Z�̂̐��X�������B�l�\�܁A�Z�ł��̎�X�����ɁA��������B���̕����ӂƌ���ƁA���X���̂ЂƂ肪�A�R�[�q�[�p�̃~���N����ɂʂ��� �����B�i�s���܂�͂����L�t����R�c�A1990�A��Z��y�[�W�j
�g�����c�K�t���̒Z�̂Ɍ��y�����̂́A���̓��L�����̂悤���B��́u�~�̖铹������Ȃ���A�ނ����ɚ����悤�ɕ������Ă��ꂽ�v�Ƃ���
�L�q�Ƃ͏�
���قȂ邪�i����Ƃ��A����̋A��̂��Ƃ��j�A�g��������\�ΑO��Ɏw�������o�l�����߂�����������ꂽ���Ƃ͕�����Ȃ��B�g���͐�������
���͏t������Y�����ƌ𗬂��d�˂ċ�s�܂ł��Ă��邪�A�Z�̂�V���ɍ�����`�Ղ͂Ȃ��B�c�K�t�����g�����́u������݂ɂ����ɂ����݂Ă킷�ꂯ����
�݂̂��݂Ȃ��Ȃ��Ƃނ�v���Ō�ɁA��̂��̂��낤���B��͐s���Ȃ��B����ɂ��Ă��g���͂Ȃ����̐��z���s�u�����v�Ƃ����G�t�Ɏ��^���Ȃ�������
���낤�B�Z�̂Ƃ̐G�ꂠ��������������͂������ɑ��̐��z�Əd������B������폜����i�܂���p������i�������̂�j�A���e���ʂ����܂�ɂ��Z��
�Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ����ēc�K�t���̂��Ƃ����A�b�͂��̂��Ɣo��ɌX���B����ł͂��������́q�Y�꓾�ʈ�o�l�̈��r�Ƃ�����|����O���B����₱
���ŁA������Ă܂Łs�u�����v�Ƃ����G�t�Ɏ��߂�ɂ͋y�Ȃ��Ɣ��f�����Ƃ��l������B�����A���͂���Ȃӂ��ɂ��v���B�\�\���z�̖����Ō��O������
���ɁA����������Ƃ���͏t���̈��ł͂Ȃ��A�����̍�����̂������̂ł͂Ȃ����\�\�B���ꂪ�g�������ĒP�s�{�ɓ���邱�Ƃ��S�O�������ق�Ƃ��̗��R
�������̂ł͂���܂����A�ƁB
�����܂ŏ����Ă��āA�O�̂��߂ɋg���������s�U���W�i�{�T�C�g�ɃA�b�v���Ă��錩�o�������̂��̂ɁA�{���m�e�L�X�g�n����ꂽ��Ɨp�̊��S�Ńt�@�C���j��
�g���̒Z�̂�T���Ă݂��B����ƁA�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�N11��30���j�Ɂq�g������
�e�r�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�q�����i���l���N�E�ė�j�r�́u�Z����\���v�̓��L�Ɏ��̒Z�̂�����ł͂Ȃ����B
�@��{�̎|�����̖��̂т��܂肽��Ε��ɂ�ꂨ��i�����A��y�[�W�j
����́A���Ắs���܂�͂����L�t�̒Z�̂������������悤�ɁA�g���̎���Ǝv����B1939�N�ɓc�K�t������`�����ꂽ���낤�u������݂ɂ����ɂ���
�݂Ă킷�ꂯ���߂݂̂��݂Ȃ��Ȃ��Ƃނ�v�Ƃ��̈�ǂ�������邩�́A�ɂ킩�ɒf�����Ȃ��B�g�����{�i�I�Ɂs�Õ��t�̎��т������͂��߂�͓̂��L
�̗���1950�N���炾����A�u���̖��v�������ċg�����̉̂̂킩��Ƃ���U�f�ɂ͍R���������B�����A���̓_�ɂ��Ă͍e�����߂Ę_���悤�B
�k�t�L�l
���r���E�O�}�ДV�E�����؍K�j�E�H��P�v�ҁs����Z�̃n���h�u�b�N�t�i�Y�R�t�o�ŁA1999�N7��20���j�́q����E�̏W100�r
�ŏ��r�����s�����t�̍��ڂ����M���Ă���B�u���^�̐��͂������Ȃ������H�̃��_�j�Y�����悭�������Ċ����x�����̂̂������܂��������v�Ƃ��āA�u�y�K���
�ւ��ǂ���e�ɂ܂͂�q���[���f�̉ԁv���������Ă���i�����A����y�[�W�j�B����ȂǁA���H�̒Z�̂����c�K�t���̔o��ɋ߂����̂���������
��B
�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�͌��ł́s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�ɑ�X�͂₵�����̂����A���́u�X�v�A���Ȃ킿�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�̍Ō�ɂ̓|���m���߂���4�т̕��͂����߂��Ă���B4�т̏��o�͈ȉ��̂Ƃ���B�Ȃ��q�u���\�I���сv�G���r�Ɂu�u�|���m���ɏA���ď����܂��H�v�ƁA�`�N�͌����v�i�����A�O�Z�O�y�[�W�j�Ƃ���Ƃ��납��A�s�G�������~�G�[���t�̘A�ڃR�����q�|���m�r�̕ҏW�S���́s�y���F��t�i�}�����[�A1987�j����|���邱�ƂɂȂ�W�J�~�ꂳ�낤�B
�@�����}���E�|���m�f��G���@�s�G�������~�G�[���t1���i1985�N9���j
�@���|���m�����G���@�s�G�������~�G�[���t3���i1986�N3���j
�@�����\�I�ȑ��`��Ƃ����@�s�G�������~�G�[���t4���i1986�N6���j
�@���u���\�I���сv�G���@�s�G�������~�G�[���t5���i1986�N9���j
�s�G�������~�G�[���t2���q���W���t�����\���E�g�����t�H�[�ƃt�����X�f��r��1985�N12��20���ɏo�Ă��邩��A�x�ڂ͋g���̑��̎���낤�B�����T��ׂ��A�q�g�����N���r�����Ă݂悤�B
��㔪�ܔN�i���a�Z�\�N�j �Z�\�Z��
�k�c�c�l�����A�y���F�A�����Y�q�ɏ�����ċ��s�֍s���B�O�D�L��Y�A�����ׂ�A����r�q�Ƌ_���Ռ����B�V�����A�O��@�A����@�A�@�؎��A�֎�@�A���哰�A�q�ω@�A�O�\�O�ԓ��Ȃǂ�q�ς���B�_�ސ�ߑ���p�قŁq���a�S�N�L�O�E���c�ܘY�W�r�B�\�ꌎ�A��؈ꖯ�Ƌ��s�s���p�قŁq�x���c�֓W�r���ς�B�G��A���ՁA��߂ȂnjܕS�]�_�Ƃ����s�ς��Ɉ��|�����B����O���Z�ł̐}�^���B�ޗǂ֍s�����c��L��A���c�l��ɏЉ��A������~�Ɉꔑ�B�\�A�o���̍����r�Y��֏������B�F�V���F�v�ȁA�l�J�V�����Ǝ藿���⊛��̉�H�B�\�O���A�����a�J�̓��a�a�@�ɌZ���������B�\�l���A�����Y�q�ƍL���ʼn�y���F�̕a�C��m�炳���B�a��͖{�l�ɓ`���Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�\�ܓ��A�A�X�x�X�g�قɓy���F�������������C�ȗl�q�ŁA��q�ɕ����̐U���t���Ă����B��\�l���A�Z��Ă̕ōȂƓ��@��ɍs���������������g����B�i�g���z�q�ҁq�N���r�A�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A���Z���y�[�W�j
12��13���ȍ~�͐g�ӂ��Q�����������A�R������2��̎��M�ɏ[�Ă�ׂ��H���ɂ́A���i�����W����v�������o���Ȃ��B�u�|���m�����v�Ƃ����e�[�}���̂������ɂ��������̂��낤���i�A�ڂ̈˗��������͊J�n���ɉf��E�����E���`�E���тł����Ƃ�����g�͌��܂��Ă����͂����j�B�g�����q�|���m�����G���r�Ō��y���Ă����i�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�P�@�w�w�����v�l�Ƒ����B�x�\�\�w�K�~�A�j�x�@�@�w��k�푈�x�@�@�w�a�̕����ꔶ�x�@�@�w�W�����A���̐t�x�@�@�w�g���[�E���u�x�@�@�w�o���J���푈�x�@�@�w�w�����v�l�Ƒ����B�x����́q�P�@�w�w�����v�l�Ƒ����B�x�r��1���s�w�����v�l�Ƒ����B�t�A�ʑ�s�o���J���푈�t���邢�́s�o���J���E�N���[�Q�t�̂��Ƃ������i���̖{�́A�����ꏑ���@������낤�j�B�u�|���m�����v�ɂ��ď����ɂ������ċg������J���A����ɂ�������炸5���ڂ��邤���̍ŏ��ɐ������̂����̏����������B�܂�A�ǂ����Ă����̍�i�ɐG��Ă������������B�Ƃ���Łs�o���J���E�N���[�Q�t����y�ɓǂ߂�悤�ɂȂ����̂́A�g���f�㊧�̏�s�Y�ďC�q���̔�{�R���N�V�����B�r�̃E�B���w�����E�}�C�e���s�o���J���E�N���[�Q�k�͏o���Ɂl�t�i�͏o���[�V�ЁA1997�N6��4���j���炾���A�g���͓��R�����ǂ�ł��Ȃ��B��s�Y�́q�͂��߂Ɂr�ɂ́u�{���ł́A�k�����́l���Y�s��Дł����Ƃɂ��A�k�\�w�ɗ]��l�e�튧�{���Q�Ƃ��A����̓ǎ҂ɓǂ݂₷�����͂Ƃ���悤�����낪�����v�i�����A�O�y�[�W�j�Ƃ���B�g���́q�P�@�w�w�����v�l�Ƒ����B�x�r�̑S���������B
�@�u���~���h�����i���A�l������㵒p�����̊��������߂���́v���A�@�̋K�肷��|���m�����ł���̂��낤�B���̏��a��\�Z�N���A�����ɗނ���O�����w���ԊJ�����Ƃ��A��ĂɊ��s����n�߂��̂ł���B�w�K�~�A�j�x�A�w��k�푈�x�A�w�a�̕����ꔶ�x�A�w�W�����A���̐t�x�A�w�g���[�E���u�x�����āw�o���J���푈�x�Ȃǂł������B���͈�ʂ肻�����w���āA�ǂ�ł���B�قƂ�ǂ������Ɠ����ɁA�֎~���������悤���B���̂Ȃ��ŁA���ł��Y�������́A�v�E�}�C�e���w�o���J���푈�x�ł���B����͓�A�O��ނقǏo�ł���Ă���A���͂��̂����̓���������Ă����B����{�ł͂Ȃ��A����Ƃ����ꂽ���̂ŁA�u�}�b�v���ق��Ă����肷��̂ŁA�⑫���Ȃ���ǂB����������������͂Ɍ����ĕ�����Ȃ������B�Ȃ��Ȃ��O�Ɂw�o���J���푈�x�̊���{�Ǝv����A�閧�o�ł́w�w�����v�l�Ƒ����B�x���A���͓ǂ�ł�������ł���B���A�{���Q�Ƃ��鎑�����Ȃ��̂ŁA���܂��Љ�ł��Ȃ��B�u�푈�v�Ƃ��������̍����𑨂��A�����S���ւ���������l�Ԃ̓��~��I�悷��|���m���w�̌���B�푈�̗��ʂɂ������ꂽ�A���������̎��̏��������ʂ��Ă���B�ٍ��̕�����������A�n�s�I�Ȗ\�͂̐��X����A�������l�Ȃ►�����̎p�Ԃ͔ߎS�Ƃ��������A�ނ���^���I�ł����������B���̋M�d�Ȗ{���A�N���̗F�l�ɕԂ��A�Ԃ��Ȃ����͏o�������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܌܁`�O�ܘZ�y�[�W�j
�s�o���J���E�N���[�Q�k�͏o���Ɂl�t�̊����ɂ́A��s�Y�̉���q�w�o���J���E�N���[�Q�x�Ɠ�h�o�ł̒鉤�E�~���k���r��48�y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ���Ă���B�g�������y�����łɊւ��鏑���I��������������E����B�Ȃ��y�@�z���͉摜�����Ŏ����������t�ɂ��銧�s���A�m�@�n���͗�ؕq���s���̔�{�k�͏o���Ɂl�t�i�͏o���[�V�ЁA1996�N4��4���j�����Ɍf�ڂ��ꂽ��s�Y�q�킪���������{���X�g�i���j�r�ɂ���L�B
�@�i1�j�s�w�����v�l�Ƒ����B�t�i�O�c���@�A���a7�N5�����j�m�l�Z���@�����v���@�{��2�F���@�Љ�3�~50�K�n
�@�i2�j��쐳�v��s�o���J���푈�t�i�������@�A���a26�N6���y30���z�j�m�l�Z���@325�Ł@280�~�@�J�o�[�сn
�@�i3�j���ˏ~��s��b�o���J���푈�t�i�����[�A���a26�N7���y10���z�j�m�a�U���@238�Ł@200�~�@�J�o�[�сn
�@�i4�j���䏃疖�s�o���J���E�N���[�Q �ɉ��̂����Ɂt�i��͏��[�A���a26�N�m12���n�j�m�\�\�n
��s�Y�q�킪���������{���X�g�i���j�r�ɂ�
�@�@�u�o���J���푈�v���ݒB�v��@�Q�����[�@���a40�N9���@�V�����@211�Ł@280�~
�Ƃ�����{���f�����Ă���B���܂����̏�������s�J���[�� �o���J���푈�t�i�Q�����[�A���a43�N1��15���j���������ݒB�v��ŁA�{���͏��a40�N9��20�����̔ł𗬗p���āA�V���ɑO�t��R�J�q���̌��G�A�q����r��Y���čĔł������̂ł���B���݂̖͂���Ȃ��������B
�u���̎��̖��ɂ́A���̍D�F�ȏ��B�́A�ڗ����Ȃ����i���𒅂Č���ꂽ�B�����Ă��������C�ʂ̍����㗬�K���̒�i�ȕv�l��ߏ�̂悤�ȋC�����ŐU�����̂ŁA�j�B�́A�����߂Â��������Ќ��������āA�M�w�l��U�f����Ƃ����`���I�ȁA�D��S�ň�w�̎h�����������̂����B�^�܂�����ӂ̖��ɂ́A�v�l�►�����́A�����̕v��Z��̐����𒅂Ă����ꂽ�B���̋U���҂̕��m�́A�傫�����[�Ɣ����������Ɠ��Â��̂悢���K�����A���낵���G���`�c�N�ȕ����B�ł����B���ɂ́A�Y�{�������ׂ��ׂɐ����āA�{�^�����O���Ă���҂������B���ꂪ�A�j�����̓��~���ُ�ɂ����藧�Ă����Ƃ͓��R�ł���v�i�����A���Z�`�����y�[�W�j�B
�����ӏ�����s�Y�s�o���J���E�N���[�Q�k�͏o���Ɂl�t�ł͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B
�u���̖��ɂ́A���̍D�F�ȏ������͕��i���𒅂Č���ꂽ�B�����Ă���������i�ȗߏ��i���̂悤�ɐU�������̂ŁA�M�w�l����ɓ����Ƃ����`���I�Ȏh���������āA�j�����̋����͂����������܂����B�^�^�܂��A�����A�v�l�►�����͎����̕v��Z��̌R���𒅂Ă���Ă����B�^���̊�̕��m�����͔g�ł��[�ƁA����肵���r�ƁA�f���炵���K�����A�܂��Ƃɖ��͓I�ȕ��������������B�Ȃ��ɂ̓Y�{�������ׂ��ׂɂ͂��āA�{�^������������͂����Ă���҂������B�^����ŁA�w�����v�l�́A�����̊y���݂��Ƃ͑S�����̓����𗘗p����悤�ɂƖ��߂��A����͂��������ꂽ�v�i�����A��O�܃y�[�W�j�B
���݂̖����̕������ł̖���ɂ��Ă���Ƃ����邪�A���ꂾ���Ⴄ�ƌ��̕����ǂ����������C�ɂȂ�B�����ɂ����Łs�o���J���푈�t�����łƓ����{���́s�w�����v�l�Ƒ����B�t���苖�ɂȂ����A�����ʼn��ɂ��ĕ��������Ǝv�����ؐM���ҁs�o���J���푈�q��r�k��{�}���� �C�O�Łl�t�i�}���o�Ŕ��w�فA1982�N6��17���j���������̂ŁA�����ӏ������悤�i�����͐V���ɉ��߂��j�B
�u����̈���̎��A�����̍D�F�ȘA���͔ޏ��B�̕���܂Ƃ��ċ��钅���𒅂Č��͂ꂽ�B�����Ċ������h�Ȓ�i�ȏi����ߏ�̗l�ɐU�����B�^�����̋M�w�l����ɓ���鎖�����̑Łk�}�}�l��邱�Ƃ̂₤�ɊO�Ϗゾ���ł��v�͂��̂͒j�B�̋��������߂��B�^�����鎞�͕v�l�►�B�͎����̕v��Z��̐����𒅂ė����A�����đ��̎��ɂ͉������ق���̂������������ʈʂł����B�^���̂ɂ��̕����͎��ɖ��͂̂��銆�D�����ċ����A�g�ł��[������A�L�c�`�������r������A�����đf�j�炵���\�����ċ����A���ɂ̓Y�{�����A�x�R�x�ɐ����ă{�^����������͂Â��ċ�����̂���R�����B�^�w�����v�l�͍����͓a���͑S���w��̓����𗘗p����₤�ɂƖ��߂��A����͖ܘ_���ꂽ�v�i�����A��Z��`��Z�O�y�[�W�j�B
���ł̖{���ɋ߂��̂͏�̕������A�g���̕��͂ɐe�a��������̂́A���݂̕��ł���B
�b�x��B�g���́u����͓�A�O��ނقǏo�ł���Ă���A���͂��̂����̓���������Ă����v�̂́A�i2�j�i3�j�i4�j�̂���2���Ƃ������Ƃ��낤�B�s���V���{��̗x�q�t�s�a�̕����ꔶ�t�s�W�����A���̐t�t������������a26�N�ɓ������@����o�Ă��邱�Ƃ��l�����킹��A�i2�j��쐳�v��s�o���J���푈�t�Ɓi3�j���i4�j�̂ǂ��炩�Ƃ������ƂɂȂ낤���B�������i1�j�`�i4�j�̂ǂ���������Ă��Ȃ��̂ŁA����ȏ�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B�s�w�����v�l�Ƒ����B�t�Ƃ͂ǂ�ȏo���̖{�Ȃ̂��B��̉���ɂ͂�������B�u������߂ɂ��ꂽ�k���́A���a���N�ɓ���ƒn���ɂ�����A���̖ڂ��݂邱�ƂȂ��������ꂽ�w�푈�u���I�x�i�w�o���J���E�N���[�Q�x�̖{�M���o�Łj�𓉂�ŁA���Y�s��Ђ̏ے��Ƃ������ׂ��w�o���J���E�N���[�Q�x�̍Ċ�����}����B�x�@�̖ڂ��\�����߂Ɂw�w�����v�l�Ƒ����B�x�Ɖ��肵�A���v���E�{����x���E�I�[�i�����g����̔����{�Ɏd���āA�O�~�\�K�Łk�́��Ёl�z������肾�������A���O�Ɏ@�m����Ă����Ȃ���p�ƂȂ�A���낤���Č��{�����c���������Ŗv������A�Ō�̖����������ɒׂ��A���S�ɑ��̍����~�߂��Ă��܂��A�g�������Ƃ�Ȃ��Ȃ�A��������h�o�ŊE�̒鉤���A�ϔO���Ċ����ʂ��A���ɓ�h�o�ł����؎���������ƂɂȂ��Ďd�������v�i�O�f���A�O����y�[�W�j�B�g�����ǂ̂́u�N���̗F�l�v����ؗ��������́u���{���v�������̂��낤���BWikipedia���w�o���J���E�N���[�Q�x�̍��ɂ́u�O�������N�v�Ƃ��ās�b����@XX���w�̊فt���������Ă���B�����qXX���w�̊� ��{���N �u�o���J���E�N���[�Q�v�r�Ɂs�w�����v�l�Ƒ����B�t�����e�ƂƂ��Ɍf�����Ă���̂ŁA����Ə����������i�\���Ɩ{���̏��e�͓��T�C�g�ł������������������A��s�Y�́q����r���̏��e�i���m�N���j��ʍ����z�s���֖{�\�\�����E�吳�E���a�E������s�Y�R���N�V�����t�i���}�ЁA1999�j�f�ڂ̕\���i�J���[�j���X�~�⍮�F�Ȃ̂ɑ��āA���邢�u���[�O���[�Ɍ�����̂͂ǂ������킯���낤�B�ʐ^�Ō��邩����A�{���̊����y�[�W�������ł��邾���ɁA�ǂ��ɂ������Ȃ��j�B
�u���a���N�Z�����A�O�c���@���犧�s���ꂽ���̂ƌ����Ă��܂��B��s�Y���͖k���̎�ɂȂ���̂Ƃ��Ă��܂����A�����ƂȂ�������܂���̂ŁA�m��͍T���܂��B�v
�u���^�F�l�Z���@�Ő��F371�Ł@���s�F�O�c���@�@���N�F���a���N�Z���i�H�j�@���{�F�{����x���A���v���@���e�F�㊪ ���� �` ���ҁ^���� ���ҁ^�lj��v
�g���́u�N���̗F�l�v���N�Ȃ̂������̈���o�Ȃ����A�n���o�łɒʂ����҂ł������Ƃ��Ă��A������Ƃꂽ�u���{���v�i�Ƃ����ƍ��{��ԂŖ����{�̂悤�����A�����炭�Ō����{�͂���Ă������j����肷��̂͗e�Ղł͂���܂��B�o���O�̋g���̂悤�Ɏ����ł����l�Ԃ́A���̂��ƌ����Ă��悤�B��s�Y�͑O�o�̉���i�����A�O�O���`�O�O��y�[�W�j�ł����q�ׂĂ���B
�@�w�o���J���E�N���[�Q�x�́A���������s�Ԃ�ԗ��������C�̒n���}�G��`�j���������ߑ㐏��̉��{�Ƃ��Ă��Ă͂₳��Ă������A�������������Ȃ�Ӑ}�������ď����ꂽ���̂��͂��肪�����Ƃ��낪����B�푈�ւ̑����ƍR�c�����߂�ꂽ���핽�a���C�������݂Ƃ邱�Ƃ��ł��A�Ђ���Ƃ�������ٗl�Ȕ��포���ł͂Ȃ��낤���Ƃ��v����B
�@��Ƃ̍������i���Z�ܔN�f�j�́A���̓_��F�߂���ŁA���̂悤�Ɍ����Ă���B
�@ �w�o���J���푈�x�́A�������ɒP�Ȃ�D�F�{�Ƃ��������ł͂Ȃ��āA���������`�Ő푈�̍߈���\�I���Ă���̂��ƁA�����v�킹����Ƃ��������B�N�[���s���ʖ��������A����Ă������ĔƂ�����A������E���āA�쌴�Ɏ̂Ăčs���B���������b�́A�D�F�{�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��c�E������B������c�E������Ƃ���D�F�{�Ƃ��Ă��A����͂Ђǂ�����B
�@�����A���������b�͂ق�̈ꕔ�ŁA�S�̂Ƃ��Ă͂�͂�D�F�{�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�D�F�I�h�������߂邽�߂ɁA�푈�̎c�E�������p����Ă���Ƃ����������B���I�h���̂��߂̍D�F����ɁA�푈�Ƃ������̂𗘗p���Ă���B�D�F�̖����̂��߂ɐ푈�𗘗p���Ă���B
�i�w�G���X�̏����x���a�O�\�O�N�A�V���Њ��j
��s�Y���������������̕��͂́A�s�G���X�̏����t�́q���\�l�́@�����̌Q�r�`���̓�i���ł���i���o�́s�T���V���t1957�N10��28�����j�B�����͑O�̑��\�O�͂Łu�c�E�ƌ��ւA�w�a�̎����`�x�Ɠ������A���̕��ł͗L���Ȃ��̂��Ƃ��Ӂw�o���J���푈�x�\�\���̍D�F�{�������₤�Ȏc�E�����ڗ��̂ł���B����A���ƂЂǂ��v�i�s�������S�W�k��18���l�t�������[�A1970�N6��25���A��Z��y�[�W�k�����͐V���ɉ��߂��l�j�Ə����Ă���B����ɁA�����炭�͓������@�ł��苖�ɒu���āu�o���J�����������Ċ��x���������푈��w�i�ɂ��āA�푈�̎c�E���̂��ߖ�b�̂₤�ɂȂ��l�Ԃ̎c�E�ȍs�ׂ������ɕ`����Ă��B�j�̎p���ЂƂ�������Ȃ��u�������̓s�v�ɐN�������R�����A�����Ƃ�ւĈ��s�̂�����������B����A���̕��ł������Ȃ�ƁA�����ɂ��Ƃ�Ȃ����ς̂��܂�����Ђ낰��v�i���O�j�Ɨv�������́A�u�k�c�c�l�푈�����������ӌ`�Œɗ�ɖ\�I�������̂ł���ƁA�������Ӑ����Ȃ��l������B�P�Ȃ�D�F�{�ł͂Ȃ��Ƃ��Ӗ�ł���v�i���O�j�Ƃ��Ȃ��Ă���B�g���͑O�f���Łu���A�{���Q�Ƃ��鎑�����Ȃ��̂ŁA���܂��Љ�ł��Ȃ��v�Ə����Ă��邪�A�����̎��M�ɍۂ��č����̕��͂��i���o����P�s�{�A����Ƃ��S�W�{�Łj�ǂƂ��̋L�����������̂ł͂Ȃ����i�g�����h�����鎍�l�E�����Ƃ̏T�����A�ڂ̃G�b�Z�C�\�\�������薼���u�G���X�̏����v�ł���\�\�����̂����Ă����Ƃ͍l���ɂ����j�B�邪����ň������悤�ɁA�����̕��͂͐��A�s�o���J���푈�t�Ɍ��y�����_�]�̂ЂƂ̓T�^�������B�푈���̖\�I�Ƃ��������肽�u�P�Ȃ�D�F�{�v�ɉ߂��Ȃ��Ƃ����킯�ł���B���̍����́u���I�h���̂��߂̍D�F����ɁA�푈�Ƃ������̂𗘗p���Ă���v�Ƃ������ɗ͓_��u���āA����ɂ�������������̂��g���́u�ٍ��̕�����������A�n�s�I�Ȗ\�͂̐��X����A�������l�Ȃ►�����̎p�Ԃ͔ߎS�Ƃ��������A�ނ���^���I�ł����������v�Ƃ����]�ł͂Ȃ����B���͗ϗ��ɗD�悷��Ƃ����̂��s�w�����v�l�Ƒ����B�t��ǂ����̋g���̕]���Ƃ���A���m�Ƃ���4�N�ȏ�̍Ό��F�⒩�N�ʼn߂�������̋g���̕]���͂ǂ��Ȃ̂��낤���B���̐���̔Ŗ{��ǂ݂���ׂĂ݂��̂́A���̂�����̂��Ƃ��m�F�������������߂ł͂Ȃ��������B���Ȃ݂Ɏ����{���ōł����ڂ����̂́q�푈�Łm�����Ȃ�n�Ȃ肵���\�\�o���J���E�N���[�Q�@�㊪�\�\�r�̑��ҁE��͂̏b���̑}�b�i�s�b����@XX���w�̊فt�ɂ́u�R�������v�l�͂��̎₵���������ɕ���킵�A���̍s�ׂ�`���������������тɔ����āc�v�ƏЉ��Ă���j�������B�X�^�C�������r�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����̂́A�����~�ʂ̑�ꎍ�W�s�R���仁k������Y�p�Ɣ�]�p��2�l�t�i�����t���X�A1929�N4��18���j�ɋ߂����̂��������̂��i�q�I�_���X�N�r��q���r�j�B�����āA�g���������~�ʂ̎��Ƃɒʂ��Ă��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��B
���Ƒ��b�g����
�������X������
�����̂���[�ׂ�������
�R��������̖Ǝւ̉ƌn��f�ׂ�
������ꖺ
��e�̓T��Ȕ��ƐQ�Ԓ��̖��Ԃ�
��l�̘V�����j���i�߂��낷
���ݍ������F�����̔n�̕��A�̏I��
�ꖺ�̐S���Ђ���Ȃ̉���
�ނ炪��ڂ��ӂ�̐��{���
��݂�����V�����j
������ނ��̕v
��H�̕��e
�����̖��͂����܂����T�̑�������
��̂��낢�Ђ܂��̎��̗��̂Ȃ���
���̂̏����̒ɂ݂𒍂�
���ׂẲƍ��Ƒ��z����̖�����炬���
��e�͊C�̂����Ŋ��ʂ�
�Ⴂ�j�̂����̓������݂ɂ䂭
������ƌҊԂɊ����Ȃ���
���e�͐��Ȃ�������̌�������
�ӂ����X�R�̓˒[��������
���́s�m���t�̎��сq���Ƒ��r�i�C�E14�A���o�́s�G�߁t1958�N7�����j�ɐ푈�́A�u�|���m�����v�̉����c�����B�����r�Y�͖{�т́q�ӏ܁r�Łu�ꂢ�ɂ���Ĕ����Ƒ��Ɠǂ߂����B���̂��납��Љ���ɂȂ��Ă�������Ƒ������ɂȂ��Ă���B�������A���̕���Ƒ��͎����ȓ��{�̕��y�ɂӂ��킵���Ȃ��A�������炩��Ƒs��ɕ���v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A�O�O�`�O�l�y�[�W�j�Ɗ��j�����B���ɂ́A�g�������̍r�p�����Љ�S�ۂ�`���ɂ������āA�嗤�I�ȁu���������s�Ԃ�ԗ��������C�̒n���}�G�v�i��s�Y�j�Ƃ����D�F�{�܂����̐ݒ�������Ă����A�Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B����Ƃ��A���̈��ӂƒ݂肠�������̐�]���̍�҂͒X���Ă����Ƃ����ׂ����B
�k�t�L�l
�s�Ԃ邤�ӂ���ޕ���t�i�������[�A1975�j�̒��ҁA�O�؊��v�i1925�N���܂�j���s�o���J���푈�i�S�j�t�i�t�����X���@�A1982�N9���j�ɕt��������q��ɕ�܂ꂽ����n�[�h�|���m�r�ɂ͎��̂悤�ɂ���B
�@����́A���{���푈�ɕ����ĊԂ��Ȃ��A���a20�N��̔����낾�����B�����ɋQ���Ă������ɁA�E��̐�y���P���̌Ö{��݂��Ă��ꂽ�B�v���̂��̓��e�́A����ƐN���ɓ���������̎��ցA����܂�Ռ���^�����B���ꂪ�w�o���J���푈�m�N���[�Q�n�x�ł���B�k�c�c�l�^��nj�A���̖{���ق����Ă��܂炸�k�c�c�l�A��y�ɏ����Ă����悤���肵�����B�ނ́u���Ȃ����Ö{���ł�������A����1���~�����Ă����Ă���B�����Ƃ��A����͒N�ɂ�����C�͂Ȃ����ǂˁv�ƁA��������f���ꂽ�B�k�c�c�l���݂̑���Ȃ��20���~���B�^��N�A�킩�������Ƃ����A���̖{�͏��a�����ɁA���̗L���ȇ����։����~���k���i1900�`1946�j�̕��|�s��Ђ��o�����w�o���J���E�N���C�Q�x�������B�^�k�c�c�l���ɕ��|�s��Ж{��݂��Ă��ꂽ��y�́A���Ђ���ʔ̂ɂ��10�~�œ��肵���Ƃ����Ă����B�^�k�c�c�l���̏���{�Ȍ�̖M��ٔł͂��ׂĔ~���{�̊C���łŁA�Ɩ�{�╧��{�Ȃǂ���V���ɖM�ꂽ���̂͊F���Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B���ɖʗd�Ȕ����|���m�Ƃ����悤�B�i�����A�O��O�`�O���y�[�W�j
�g������O�ɓǂ閧�o�ł́s�w�����v�l�Ƒ����B�t�i�O�̉���ɂ��̏����͓o�ꂵ�Ȃ����j���A�O�ƌ��Łs�o���J���푈�t�Ǝ����悤�ȊW�������Ǝv�킹��B�s�w�����v�l�Ƒ����B�t���~���k���̎�ɂȂ���̂Ȃ�A�u���̋M�d�Ȗ{���v�g���ɑ݂����u�N���̗F�l�v�͂�͂�ʔ̂œ��肵�����̂��낤���B�{������O�̋g���ɐ[���e����^�������Ƃ́A�^���Ȃ��悤�Ɏv���B
�g�����̐��O�Ō�̖{��1938�N����40�N�ɂ����Ă̓��L�������s���܂�͂����L�k��Ԃ�ǂ邵����P�l�t�i����R�c�A1990
�N4��15
���j���������A���O�Ō�ɔ��\���ꂽ��i�́q���L�@���l�Z�N�r�ł���A�i���݂܂ł̂Ƃ���j�Ō�̍�i����e�Ƃ���1996�N�ɔ��\���ꂽ���L�q����
�i���l���N�E�ė�j�r�ł���B���̍ŔӔN�ɁA�o���O��̎Ⴋ���̓��L���܂Ƃ߂��g���̐^�ӂ𐫋}�Ɍ��_�Â��邱�Ƃ͍T���邪�A���L�Ƃ����W���������`��
���d�v�ȈӖ��������Ƃ͋^���Ȃ��B�g�������g�̓��L�Ƃ��čŏ��Ɍ��������̂́s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�N9��1���j�Ɏ��߂�
�ꂽ�q�f�ЁE���L���r�ł���\�\�G�����\���܂߂�Ɓq���L���\�\���Z���r�i�s���Ɣ�]�t1967�N9�����ł̌���́q���L�r�j���ŏ��\�\�B�k���㎍��
�Ɂl�ɂ̓V���[�Y�̊e���ɋ��ʂ�����Ƃ��Ď��`�I�ȕ��͂̏������낵�����邪�A�g���͓��L�������Ă���ɑウ���B���̊Ԃ̎���͎��̂Ƃ��肾�B�u���`�I
�Ȃ��̂��܂����������ł��Ȃ��B�܂��A�N���I�Ȃ��̂�����ώG���ɂ��ς����Ȃ��B���܂��܋������L�̒f�Ђ�����̂ŁA���������̎��̕��͋C��`�����
��������o���A�Ԃ荇���Ă݂�B���L�������Ȃ������N�オ�����A�������̂ɂȂ��Ă���B����́A���ɂƂ��Đ��X�̑�Ȏ����������Ă��܂������A������
�H�삷�邱�Ƃ�������v�i�����A���܃y�[�W�j�B�q�f�ЁE���L���r�́u���a��\��N�ꌎ�ܓ��v����n�܂��Ă���B����A�q���L�@���l�Z�N�r�i�s�邵��
��t5���A1990�N1��31���j�́u�ꌎ����v����n�܂��Ă��āA���́u�s����N�̂������͂������ɖ݁A�������������������肾���A�Z��ƂƏj���B
�t�q�i���j�A�ڔ��q�i�Z�j�͏��̎q�炵���A���Ȓ����p�B�Â��Ȍߌ�A�����H�����̉�������B��A�s�Í��a�̏W�t��ǂށv�i�����A�O��y�[�W�j�Ƃ�
���L�ڂ́A�g�������̓�������̓��L�������͂��߂����Ƃ��������킹��B
�@���́u���܂�͂����L�v�́A���̈ꕔ����㔪�Z�N�́u���㎍�蒟�v�\�����́u�g�������W�v�ɂ悹�����̂ŁA���̂� ���ɕt�L���� ����B�\�\��O�́u���L�v������������܂ʂ���Ďc�����B����������a�\�O�\�\�ܔN�̂��̂ł���B�璷�ȋL�q���Ȗ��ɂ��A�����Ɏ��^����B��������ׂ� �Ȃ��B���x�����䂦�A���A���͂Ȃǂ̍�i����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�t�قȓ�\�́u���L�v���Ȃ��āA���̔C���ʂ��\�\�ƁB
�@�ŋߊ��s����͂��߂��A����R�c�̏����q�u�邵����v�ɁA��i�E���͂����߂�ꂽ���A�x�M���Ȃ̂ŁA�u���܂�͂����L�v�̕��ŁA���̂��߁m�A�A�n���� �����Ǝv�����B�ȗ���������߂āu���I�����v���E���o���āA�}�����Ă䂭�����A�v�킸���M������A���\�]���̌��e�ɐ����Ă��܂����B�k�c�c�l
�u����Z�N�����v�Ƃ������t�����s���܂�͂����L�t�́q���Ƃ����r�i�����A��l��`��l�O�y�[�W�j�ł���B���̍Ō�Ɂu�w���� ��͂����L�x ���s�̋ŁA�����I�ȓ���́u���E���L�v�͏��ł���͂��ł���v�Ƃ���ȏ�A�g���ɓ��L�̌��{���₷�ӎv�͂Ȃ������B�{�e�ł́A�q�f�ЁE���L���r�Ɓq���L�@ ���l�Z�N�r�ɏd������1946�N1������3���ɂ����Ă�4�����̓��L�̓��e���������邱�ƂŁA�g���̓��L�ւ̎������l���Ă݂����B�i�ȉ��A�q�f�ЁE�� �L���r�̋L�ڂ����A�q���L�@���l�Z�N�r�̋L�ڂ����ŕ\���B�Ȃ��y�@�z�̗j���͈��p�҂̕�L�j
���a��\��N
���ꌎ�ܓ��y�y�j�z�@�����Ԏq���̉Ƃɂ䂫���e������Ă�����B���c�̈Ŏs�͐l�ƕ��i�̔×����B�C�\�~�B���`�܂\�~�B���ܖ{�\�~�A�Ȃ�Ƌ��������� ���B�s�m���@�[���X���L�t����ށB
���ꌎ�ܓ��y�y�j�z�@�����Ԏq���̉Ƃɂ䂫���e������Ă�����B���c�̈Ŏs�͐l�ƕ��i�̔×����B�C�\�~�B���`�܂\�~�B�Ȃ�Ƌ��������̒��B�s�m ���@�[���X���L�t��ǂށB
���ꌎ�\����y�y�j�z�@KUSAKA��Ƀ��C�E�G�����́s���������n�t�������āA�ޏ�����C�v�Z���̖{�������B�g�́s����壁t�B
���ꌎ�\����y�y�j�z�@KUSAKA��Ƀ��C�E�G�����́s���������n�t��݂��A�ޏ�����C�v�Z���̖{����B�g�s����壁t�B
������y�y�j�z�@�����A������݂������_�ЎQ�q�B�l����肽�s�Z���j�F�v�l�莆���t���Ȑ��d�Ԃ̂Ȃ��ł�ށB
���i�V
���O����\�l���y���j�z�@�ߑO���͌Z�Ɛd����B�\���Ƀs�[�X���ɂ䂭�B��ӎ��~�B��������s�Q���t��݂������B�V���̈Ŏs���̂�����M�܉~�̂ӂ��� ����H���B
���O����\�l���i���j�j�@�ߑO���͌Z�Ɛd����B�\���Ƀs�[�X���ɍs���B����~�B��������s�Q���t��ǂ݂������B�[���A�V���̈Ŏs���̂����A��M�� �~�̂ӂ�������H���B
�q�f�ЁE���L���r�̒E�e�����Ȃ̂��A���m�ȓ��t�͂킩��Ȃ��B�����A�k���㎍���Ɂl�V���[�Y�̊��s�J�n��1968�N������A�����Ă�
67�N�A����
�炭�s�g�������W�k���㎍����14�l�t���s�̔N�A1968�N�O���̂��Ƃ��낤�B���̂Ƃ��u�������L�̒f�Ђ�����̂ŁA���������̎��̕��͋C��`����Ƃ���
�����o���A�Ԃ荇���Ă݁v���̂����q�f�ЁE���L���r�ł���A�������L�i���{�j���A�s���܂�͂����L�t�Ɠ��l�Ɂu�ȗ���������߂āu���I�����v���E���o��
�āA�}�����Ă�v���A�u�璷�ȋL�q���Ȗ��ɂ��A�����Ɏ��^�v�����̂����q���L�@���l�Z�N�r���낤�B�܂�A���Ɏ����ꂽ�̂����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����u��
�����L�̒f�Ёv����1968�N�O��Ɂ����A1990�N�O��Ɂ����Y�݂����ꂽ�A�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����B
�E1946�N1��5���́u���ܖ{�\�~�A�v�́��ɂ͓��ꂽ���A���ɂ͓���Ȃ������B�g���̒P�Ȃ�]�L�R�ꂩ������Ȃ��B
�E2��9���́u�����A������݂������_�ЎQ�q�B�l����肽�s�Z���j�F�v�l�莆���t���Ȑ��d�Ԃ̂Ȃ��ł�ށB�v�́��ɂ������ꂽ�i�s�Z ���j�F�v�l�� �����t�͂����炭1943�N���̈�㋆��Y��̊�g���ɔŁj�B�g������N������Ӑ}�I�ɏȂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�́A�u�����_�ЎQ�q�v���낤���i����ŁA �g���̓]�L�R��̉\�����ے�ł��Ȃ��j�B�g���́A�s��̔��N���1946�N2���A�ǂ̂悤�ȋC�����Ŗ����_�Ђ��Q�q�����̂��낤�B��|���肪�ق����āA �ؓ��S�O�s�����k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA2001�N8��1���j���ēǂ����B�ؓ��͓����̑�11�͂ŁA�����ߕv�i1908�`69�j��1945�N�H�A�����_�� �ɊԎ肵�Ă����\�y�������ނ����܂�̂��Ƃ���z����1967�N8���ɔ��\�����q�Ό��r�i�s�킽���̓����t�������A1968�N1��15���j�������Ă� ��B�����V���������L�҂̈����́A���̓��̌ߌ�2������5���߂��܂ł̖�3���ԁA�u�k�c�c�l�Ж����́A�����͂Ȃ���������A�������A�͂����莋���̒��ɓ� ��ꏊ�ɂ��āA��ނ����Ă����̂�����ǁA���̂��������A�܂������A�N�ЂƂ�A�ʂ�Ȃ������B�^�A�肪���A�k�\�y����́l�O���ɁA�����A����Ȃӂ� �ɁA�N�����������_�ЂɌw�m�����n�ł�ЂƂ͂��Ȃ��̂ł����A�ƁA��������A�͂��A�܃A�A�����ł��ȁA�Ƃ������B�^�ЂƂ�ŁA�܂��A�ʍ�����ŁA�_�a �ɂʂ��������B�N�����Ȃ��̂ŁA�N�ɁA�������A�C���˂��Ȃ��A�������B���܂��ɁA�����o�A���ꂪ�ԚL�m�ǂ������n�ɂȂ����v�i�s�����k�V�����Ɂl�t�A�O�� �Z�y�[�W�j�B�g����1946�N2���ɂ́A�O�N12���ɓ��Ђ����������[�ɋΖ����Ă���A���̓y�j���͐_�c�x�l�b�`�O�̓��Ђɏo�Ђ����̂��낤�B�u������� ���v�Ƃ����̂��A�������Ă����Z�i���v�j�̒r��̉Ƃւ̋A�H�Ƃ������ƂȂ�A���݂̂i�q���i���Ă̏Ȑ��j�̍Ŋ�w�͐������w���䒃�m���w�ŁA�����_�Ђ� �����i�k�͂��̒ʂ�r�ł͂Ȃ��B��̈����̕��ƏƂ炵�Ă݂�ƁA�g���͎Q�q���邽�߂ɂ킴�킴�����^�悤�ɂ��v����B������ɂ��Ă��A�ڂ������Ƃ� �킩��Ȃ��B
�E3��24���́u�[���A�v�́��ɂ͓���Ȃ������B
�����₩�Ȃ̕\�L�̈Ⴂ�ȂǁA���ӂɉe���̂Ȃ��Ⴂ����������ƁA�����Ȉٓ��͈ȏ��3�_�ł���B�g�������L�̌��T�Ɏ������̂́i���̋L�ڂ�
�̗p���邩���Ȃ����Ƃ���������傫�ȃ|�C���g�������j�A�����ނ˂��������X���ł���Ɣ��f�ł���B���Ȃ݂Ɂq���L�@���l�Z�N�r�ɂ́A1����1����
��31���܂Łi9�����̋L�ڂȂ��̓��������āj22�����A2����1������27���܂Łi14�����̋L�ڂȂ��̓��������āj14�����A3����1������31����
�Łi13�����̋L�ڂȂ��̓��������āj18�����A4����2���E3���E6���E8���i�L�ڂ��ꂽ�Ō�̓��j��4�����A���v58�����̓��L���f�ڂ��ꂽ�B�����L
�̋L�ڂ��Ӑ}�I�ɏȂ������́A�i���ɂ��ꂪ�������Ƃ��āj���قǑ����Ȃ��A�Ƃ������G������B�ڍׂ́q���L�@���l�Z�N�r�ɏA���Č���ꂽ�����A�����ō�
�������[���̂́A��������ǂ肵���{�̒��Җ��Ə������p�o���邱�Ƃł���B�����̐��A����42�ɋy�ԁi���̂ق��ɍ�҂̖��O����������Ă��Ȃ��{����
��������j�B���L�̋L�ڂ�58����������A�ق�75�p�[�Z���g�A�P����4����3���̊��œo�ꂵ�Ă��銨��ɂȂ�B�֘A���镶�i�́j��E����B
1��1���y�Ηj�z�@��A�s�Í��a�̏W�t��ǂށB
1��2���y���j�z�@������L������������炵�Ȃ���A�����ƂɎU�炩���Ă���x�C�Y�̖{��g�s����壁t��ǂށB
1��4���y���j�z�@�݂₰�ɖ݂ƒJ�菁��Y�s���́t���B������́s���ߏW�t���B
1��5���y�y�j�z�@�s�m���@�[���X���L�t��ǂށB
1��6���y���j�z�@���c�C�s�ݗt�A���V�l�t����\�~�Ŕ����B
1��10���y�ؗj�z�@�鏰�̒��ŃW�C�h�s�c�������y�t��ǂށB
1��11���y���j�z�@��A�s���ːߌ����t��ǂށB
1��12���y�y�j�z�@�k�����H�s���앗�t���B�\�~�B
1��15���y�Ηj�z�@���A�����P�s�}���e�̎�L�t�������ǂށB
1��16���y���j�z�@�r���̖{���Ő����䎍�W�s�����t���B
1��17���y�ؗj�z�@�����ДŁs��̎��T�t���B
1��19���y�y�j�z�@KUSAKA��Ƀ��C�E�G�����́s���������n�t��݂��A�ޏ�����C�v�Z���̖{����B�g�s����壁t�B
1��20���y���j�z�@�x�C�Y�s�������ʁt���܂��ǂ݂͂��߂�B
1��24���y�ؗj�z�@�ו��s�x�q�t�B
1��25���y���j�z�@�X�L�O�s�n�ӛ��R�t�B
1��26���y�y�j�z�@���쒬�̌Ö{���Ŕ��H�s�Ɂt���B
1��29���y�Ηj�z�@���{�\���s���V���t�����߂��B�ɓ�����Y�s�X���O�t��ǂށB
1��31���y�ؗj�z�@�����ؐM�j�ҁs�ݗt���T�t��\�~�B�ۓc�o�d�Y�s�㒹�H�@�t�l�~���B
2��4���y���j�z�@�J�菁��Y�s���͓ǖ{�t�Ɗ�g���Ɂs������Ɖ̏W�t���B��x���܂Ŕ����Y�s��e���t��ǂށB
2��10���y���j�z�i���j�j�@�_�c�̌Ö{��������A�s�m���@�[���X���L�t�ƌ����Ŗx������s�ݗt��a���y�L�t���B
2��14���y�ؗj�z�@��A�����삩��肽�o���U�b�N�s��̒T���t�ǂށB
2��15���y���j�z�i���j���j�@�O���R�I�v�s�Ԃ�����̐X�t�ƒZ�̕��w�W�s��狋�ҁt���B
2��26���y�Ηj�z�@���[���X�E�o���X�s�G���E�O���R�t�����߂�B
3��1���y���j�z�@�����A���ɂނ����Ĕ��H�s�Ɂt��ǂށB
3��10���y���j�z�@�R�����ɒY���������A���䌉�s�����t��ǂށB
3��24���y���j�z�i���j�j�@��������s�Q���t��ǂ݂������B
3��26���y�Ηj�z�@�����Y�s�E�G�t��ǂށB�ߌ�A�ؓc�����s�y�����فz�l���~�t�̑�����]�Óc�̒��������̂Ƃ���ɗ��݂ɂ䂭�B
3��27���y���j�z�@��A����Y�s�����峁t��ǂ݂͂��߂�B
3��30���y�y�j�z�@�s�����̈�Q�t���B���^���v�{�Ŏ��\�~��B
4��2���y�Ηj�z�@�����q�t���珐������́s�����t���B
4��3���y���j�z�@�A��_�c�Łs��{�g��E�̏W�t�����߂��B��A��������s�@�B�t��ǂށB
4��8���y���j�z�@��A�����N����肽�i��ו��s�r����ׁt���y���݂Ȃ���ǂށB
��������͂��܂��܂Ȋ��S���N�����A���m�Ƃ���4�N���ɘj���Ď��R�ɓǏ����邱�Ƃ̂܂܂Ȃ�Ȃ������T�ς��g�������Ă����̗��ǁi�� �����Č����� ���j�ɑ��点���A�Ƃ݂邱�Ƃ͓I�O��ł͂Ȃ����낤�B���ɂ͂����̏������A�����Ƃ����s��`�Ȋl���ɏP��������A�Ȃ�Ƃ������|�����Ƃ���Q�����T�� �Ӑg�̒܍��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�����ɁA���̈��������ЂƂЂƂ̎���Ɍ����Ă���̂�������Ƃ����������B
���l�Z�N�i�� �a��\��N�j ��\����
�� �W�̎d���ő����Ԏq�A�ؓc�����A���n�F�l�Y�A��������Ɍ��e������˗��B�����̓����^��ɗU���āu�V�v���v�ɓ���B��R������̐�y�S�����o���琁B �����A�������[��ގЁB�\���A��Ɏ��߂������^��̐s�͂œ��m���֓��ЁB�K�c���F�̃J�����w���{�剤���u�x�A���c���j�w���ޔ_����b�x�̕ҏW��S������B �w����壁x�ꊪ�����m��Ȃ������֓��g�̑��̉̏W�w�Ԍ��x�w���炽�܁x�A�����Y�̎��W�w���ɖi����x�w�L�x�����߂ēǂށB�i�g���z�q�ҁq�N���r�A �s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A�����y�[�W�j
���l�Z�N�i���a��\�� �N�j ��\����
�ꌎ�A�֓��g�̏W�s����壁t��ǂ݂̂��Ɂs�Ԍ��t�s���炽�܁t�Ɋ����B�������[�̎d���ő����Ԏq��ؓc�����Ɍ��e���˗�����B��R������̐�y�S�����o ���琁B�ܔN�Ԃ�̌����B�A���n�F�l�Y��֑����̎ӗ�����Q�A������@�ɂ������̌����ɗ�ނ悤�ɂȂ�B�����ŗF�l�̓����^�炪�����������͂��߂�B �O���A���M�ŕ�点��悤�ɂȂ����͎̂l�\�Ή߂����Ƃ����ؓc�̘b�Ɏ�������������i�������Ă��������ƍl����B�ؓc�����s�ِl���~�t�̑����𒆔����� �˗��B���{���p�W����œ��{����Y�킷����̂ɋ����B�l���A�^��̕������q�t���琹������B�ؓc�����A�����Ԏq�炪�o�Ȃ��ăL���X�g���n�̏o�ŎЍ� �����[�̑n���j���B�����A���Ђ�ނ��B�\���A�����^��̐s�͂œ��m���ɓ��ЁB�K�c���F�̃J�����s���{�剤���j�t�A���c���j�s���ޔ_����b�t�Ȃǂ��肪�� ��B�\�ꌎ�A�����Y���W�s���ɖi����t�s�L�t�ɏ��߂Đڂ���������B�s���`�t��s�����t�ŎR�����q�̋�Ƃ��܂Ƃ߂ēǂށB�i���ш�Y�ҁs�g���� �N���k������Q�Łl�t�Aweb�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�A2012�A��O�܁`��O�Z�y�[�W�j
��Ɍ���悤�ɁA�������܂łɕ҂g�����N���́A�g���̐��z����L�̋L�ڂɑ������Ă���B�g�������z����L�Ō��y�����{�̂��ׂ�
���A�����ł�
�ǂ�ł݂����Ǝv���B�Ȃ��Ȃ�A�����ɂ͋g�����̐��_�̋O�Ղ����݂��܂�Ă���ɈႢ�Ȃ����炾�B�Ƃ�킯�A���삩�痣��Ă��������̓Ǐ��͏d�v���ƍl��
��B�g�����̂��Ɂs�Õ��t�ƂȂ鎍�т�{�i�I�ɏ����͂��߂�̂́A���̓��L�̐��N��\�\�����炭1949�N����ł���B
���a��\�l�N��������@����ꏊ�ɂ��闑�قǂ��т������̂͂Ȃ��悤�ȋC������B���ꂩ��o���邩����q���r����� �ɂ������т������Ă݂����Ǝv���B�i�q�f�ЁE���L���r�j
���Ď����q�i�c�k�߂Ƌg�����\�\�w�k�ߕS��x�Ƃ�
�̌�r�Ɂu�g�����ɂƂ��ĉi�c�k
�߂́A�������ł��Ĉ�ۂƂ����H�L�Ȑl�i���̂��̂������v�Ə������B����͍k�߂̏���W�s���t����|����ɁA�g���ƍk�߂̏���̊ւ���T���Ă݂����B
�����Ɂs���t�̔̔����i�p�̃`���V������i�V�n190�~���E160mm�j�B�Жʂ̓J���[����ŁA�㕔�Ɂu�������q�v��`�����k�߉�A
�����ɖ{
�����s�̔��N�l��\�E���J�g�H�̈��A�����f�����Ă���B

�i�c�k�ߏ���W�s���t�i�i�c�k�ߏ���W���s��A1986�N5��1���j�̃`���V
�Жʂ̓X�~��F�ŁA�{���̊T�v���������Ă���i�������g�݁k�^�͉��s�ӏ��l�j�B
�u�i�c�k�ߏ���W�@���^����500��
�S��i�J���[���^�i166�_�j�^���^�`�S���E���z�N���X���^�������[
��e��
�C���b�@�����r�Y�^�����u��
���e���O�Y�^�O�D�L��Y
�����ɓs�q�^�˖{�M�Y
�{�c�����^���c�@�b
�{�i���F�^���q�@��
��������^�����d�M
���㐉���^�����ĉ_
�O���q�Y�^���⍁���@�g���@��
�Еz�@1986�N5��1���^�Љ��@15,000�~�v
�ȉ��A�i�c�k�ߏ���W���s��̏Z���i�n���Г��j�A�d�b�ԍ��A�X�֔ԍ��A�U�����ԍ����L����Ă���B���łɁA�{���̉��t�������Ă������i�Z�����͏�
���j�B
�@���ҁ@�i�c�k��
�@���s�@���J�g�H
�@����@�n����
�@���{�@�{�쐻�{��
�@����@����M�́k���쐬�ꂪ�����҂Ƃ��Ė{���̊O�Ɏg�p�����ʖ��l
�@����@���쏑�[
�@���s�@�i�c�k�ߏ���W���s��
�@���a�Z�\��N�܌�����@�ܕS�����s
�@�Љ��@���ܐ皢�i�������j
���Ɍf����̂́s�Ս��t417���i1986�N7���j�́q�i�c�k�ߏ���W�E���@����W�q���r�r�Ɍf�ڂ��ꂽ�g���̍k�߈����Ȃł���i�����A��O�y�[�W�j�B
�@�q�[�@�v�������Ԃ����������Ă���܂����A�����C�̂��ƂƔq�@�������܂��B���̂��сA�����ȁw�i�c�k�ߏ���W�E ���x���o���܂� �����Ƃ��A���j���\�グ�܂��B�悸�Ȃɂ������������Ƃ́A���������́u�s���v���ŏ��Ɍf�ڂ���Ă�������ł��B���h�Ƃ����Ă͖��ł����A���ł��܂��B �u�����v�̖��i��_�����܂��k�ߗl�̎茳�ɂ���̂�m��A���S�������܂����B��i�Ə����҂����т��邽�̂��݁A����ƑI�ꂽ�k�ߗl�̂���S���������� ���Ă���܂��B���R�Ȃ���A�����ҕs���ŁA���X�̏G�삪����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�́A�c���Ɍ����Ă����A����Ȑԋ��A���ꂪ�Ȃ��͎̂c�O�ł��B ��������ԂɐS�䂩�ꂽ�̂́A�u�H�ɏ��_���v�ł��B�傫�����킩��܂��A�V�n�����ς��ɑ��݂��Ă���悤�Ɍ����܂��B�������q����鑠�Ƃ����̂��A�� �ł������Ƃł��B�{���ɂ���Ԃ����Ă��̂���ł���܂��B���āA���M�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�k�ꕷ���Ƃ���A���l�̕a�͂��������Ȃ��Ƃ̂��ƁA�k �ߗl�̂��S�ɂ̂قǁA�Ȃ�Ƃ��Ԃߐ\���Ă悢���A�r���ɕ��Ă���܂��B
�@�܌��\����
�s���t�ɂ́A�]���]�Ɏn�܂�g���ŏI���77���̎�����50�����ŋL�����q�i�c�k�ߏ���W���s���^�Җ���r���ڂ��Ă���i��O�Z�`�� �O���y�[ �W�j�B�����炭���ꂪ���s���x������ł��L���W�ҖԂł���A���̓����Ɍf�ڍ�i�̏����҂����āA����ɂ��̓����ɖ{���ւ̊�e�҂�����ƍl������B�g �����́A���̂��ׂĂɖ���A�˂Ă���B�q�ڎ��E���^��i�ꗗ�r�ŋg���Ɩ{���̊ւ������悤�i���ڂ́u�Łv�u��i���v�u�����ҁv�A�Q�l�܂łɍk�߂����|�� ���^���k�@�l���ɕ�����j�B
�@�E13�@�s���i���j
�g����
�@�E15�@�u��
�L�v���@�g����
�@�E109�@���ԔӔN����
�g�����@�k�ӔN�▲���荞�߂̗��Ԉ�}�l
�@�E110 �����Y�}
�g�����@�k���Â��l�ޖ�����̉ԁl
�@�E116�@�Βm�a���b��
�g�����@�k�a�̉��͒m�炸�H�̕�l
�@�E117�@���_������
�g�����@�k���������܋����������H���l
�q�u���L�v���r�͋g���̕��́A���Ȃ킿�{���̓c���ɍk�߂�K�˂����Ζʂ�1967�N4��27���̓��L�̍Ę^�i��㔪�Z�N�v���Њ����z �W�w�u�����v �Ƃ����G�x�����u���L���\���Z���v���j�ŁA�Ό��y�[�W�ɂ͓c�������ɂȂ�q�����i���j�r���z����Ă���B�O�f�g�����Ȃɂ�����悤�ɁA�k�߂̏����i ���g���������́q�s���i���j�r�Ŏn�߂�������A��҂́A�����Ė{���̐���҂����̋g���ւ̌������ǂ݂Ƃ��i���Ȃ݂Ɂq�s���i���j�r�̑Ό��y�[�W�̕��� �́A�����u���q�i�c�k�ߓW���j���r�̍Ę^�j�B�Ƃ���ŁA�g���ɂ́s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�⓯���̑���Łi�}�����[�A1988�j�Ɏ��^�� �����͈ȊO�ɂ��A�k�߂̋�⏑��ɐG�ꂽ���͂⏑�Ȃ�����������A��v�Ȃ��͍̂k�ߎ�ɂ́s�Ս��t���Ɍf�ڂ���Ă���̂ŁA���������Ă݂悤�B
�� ��o��\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t163���i1963�N5���j�@�q�[�@����Ət�炵���Ȃ�܂����B�����C�ŏ���̎d���ɐ��i����Ă��邱�ƂƎ@���܂��B���������k�߂̏����~�����Ǝv���Ă� �܂��������肢����̂������܂����Ǝv���Ă��܂Ă��܂����B���̓W������ �Â����Ƃ́u�Ս��v�Œm���Ă��܂������A�Ђ��Ă��������Ȃ����낤�Ƃ�����߂Ă����Ƃ������㉇����ɂȂ�Ώ���i����ɓ���Ƃ̂��Ƒ����\���݂܂� ���B�{���Ȃ珑��W�ɎQ��S�䂭�܂łɖn�ւ������Ɍ������̂ł����d���̂��ߍs���܂���B���炵����ł���܂��悤�ɁB�k�c�c�l
�� ��o��\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t166���i1963�N8���j�@ �J���ЂƂ₷�݁A������A�O���Ă炵���Ȃ�܂����B��T�̓��j���A�Q���̂Ȃ��ŁA�M�d�ȏ���i�q�܂����B���炵���n�ցA�߂Â��Č��A���������Č��� ���̂���ł���܂��B�K���ȑ傫���Ȃ̂��A���������Ȃ̂łƂĂ�����悢�̂ł��B�����A���o�ɂ��炵�����Ȃ��̂ŁA���I�̒��ɑ����Ă��܂��B�k�߂���� �{�ӂɂ��ނ��s�ׂƂ͒m��Ȃ���B�Ԏ��������ꂽ���Ƃ�����т��܂��B
�Z���\������
�@�ǐL�B
�@���A���������䐷������̂ł��傤�B�Q��Ȃ������̂��c�O�Ɏv���� ���B���čŋ߁A��{���g����A�r�߂����
�@�S���ɍ�������̉Ԃ�����
�̒Z�����������܂����B�܂������\�グ�ĂȂ��̂ŁA����ɂ��莆�������܂��B�����A���N�̊ԂȂɂ����Ă��܂���B�k�߂���̂��d���Ԃ�ɒp�������B����{���g�������k1963�N6�� 18���l�@�s�ʉp���H�Q�{���ځt275���i�ʉp�����X�A2004�N5���j
�q �[�A�����C�ł��d���̂��ƂƎv���܂��B�����ɁA�k�ߒZ�����Ƃǂ����������Ȃ���A�����\���̂��A�����ւ���Đ\�����܂���B���d�b�ł��Ǝv���� �̂ł����A���������Ƒ����A�莆�����������悤�Ƃ��Ă��邤���ɁA���ɖ��C�͏�ԂɂȂ�A�����Ɏ���܂����B����邵�������B�M�d�Ȃ��́A�{���ɂ��肪 �Ƃ������܂����B���x�̏���W�̈�_��Ђ��Ă����������̂ŁA������� ��_���U���邱�Ƃ��ł��Ă��ꂵ���Ƃ���ł��B�h��
�� ���L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�́@�s�Ս��t235���i1969�N11���j�܌���\�Z���@��A�M�Z���̌����ŁA����A�d�M�A����Ə��Ζʂ̊C���b�A���c�@�b���Ɖ�B�����ɎO�z�œW������i�c�k�ߓW�̑ō����B�������A��������҂̈˗��̕��S�A�ē���̔����Ȃǂɂ� �āB�㎞�ꉞ����B�����̕���������A�u���̛����A�|���̓��M�����炵���B�k�c�c�l
�Z���\�O���@�I�ɍ����T�����ŁA�n�đO�̂�������������S�����Ɖ�B�k�ߓW�̂��߂̂�������҂ɂȂ��Ē����ׂ��B�����Ƃ��ċ�W�A���̎ʐ^���݂���B �q�����r�̓��݂āA����͖{�����A�������̂������Ă��ꂽ�\�\������B�ق��Ƃ��Ĕ��\���ŃR�[�q�[���̂ށB�[���B
�����\�l���@�ߑO���̉�c�����܂��A���{���̎O�z�ւ䂭�B�z�q���a���Ō���ꂽ�̂Ɉꐡ�т�����B�k�߂���ɗz�q���Љ�A�ꏏ�ɃT����������B�ǖʂ� �����������ꂽ�G�Ə����܂Ԃ����B��v���ė~���������̂́A�q�H���s���}�r�Ə̂��F�̂��т�����i���B���łɔ���ρB�}�̂̑傫�ȐԂ����̎p�ɐS�䂩 �ꂽ�\�q����g���}�r��������łɐԎD�����Ă���B���߂Ȃ̂ŊO�֏o�A�g�c�̂���H�ׂ�B���̋��������܂��ׂ��߂��̋i���ŃR�[�q�[���̂ށB�߂�� �k�߂���͋��m�̐l�����ɂƂ�܂���A�Ƒ��̕����A���J�g�H�����q�̉��ڂł��������������B�S���̍�i�J�ɂ݂�B�q�ߊC�n���r�͔���������������q�� �C�ɑ�r���韸�ϑ��r�̎]�������D�̂��́B�z�q�̍D���ȁq�Ε��r�͒[��B���������A���i�ł��邪�q�������_���r��\��B���F�Ɩn�̒W�ʂ����A���� �����܂��Ė��͂�����B�q�^���r�̕��y�ł̈���͔ѓ��k��֑����邽�߁B�Ԃ����̃I���W�i���������Ă���̂œ����ł���������B�����ߌ�B
�����\�ܓ��@�k�c�c�l
�����\�����@�k�c�c�l
������\���@���j�@�h���N�̃p���̒��H�B�z�q����B�Ђ�ˁB�F���Ń��[������H���O�z�ւ䂭�B�����d�M�A�O���q�Y�A���c���j�A�������q����Ɖ�B�d�M�v �ȁq�V��[�Đ}�r�Ɏ��S������A�Ԉꔯ�̍��œ���o�����A���߂āq�ߊC�n���r�����߂�B�ߌ�Z���I���B�������i������������k�߂���̎p������B������ �q�������_���r������������B���킽�������ʂ�B�{�v��̃g�b�v�ŗz�q�Ƃ��������B�킪�L�G������͂�������]�I�ƂȂ�B���Ă̕ǂցq�������_���r���� ��B�� �q�ΘŁr�Ɓq�������_���r�@�i�c�k�ߑS��W�s��Łt�x�q�c�����́r�i�����ɁA1973�N6��15���j�@������A�i�c�k�߂��甖���đ傫�ȉו����Ƃǂ����B����Ƃ��āA���ƍȂ͐����������B��������A�k�߉�q�ΘŁr���o�Ă��� ����ł���B��ʂ̎莆���Y�����Ă������B
�@�\�\�����C�̂��ƂƔq�@���Ă���܂��B�������i�u�ΘŁv���g���l�̋��ɋ��肽�����Ă��܂��̂ŁA�v�����炨���肷�ׂ��Ȃ̂ɒx��Ă��܂��܂������A���� �傫���̃T�L�̊z�Ɏ��X����ւ��Ăł����߂Ē�����Ƃ��肪���������܂��B�ނ���Œ��\�ギ�邵�����ł��B�{�c�{�c�M�~�ɔR�������Ă��܂��B�䐴�˂Ɍ� �z�N���B���l�ɂ�낵���B�\�\
�@����͏��a�l�\�l�N�̕�̂��Ƃł������B�v�����������A���Ȑʂ̂��n�����܂��g���@���������āA�킪�Ƃɓ����Ă����̂ł���B����ɂ͎��̈�傪 ������Ă���B
�@�@�a�̉��͒m�炸�H�̕�
�@�����̂ڂ��āA���̔N�̉Ă̂��ƁA���{���̎O�z���u���ƊG�ɂ��i�c�k�ߓW�v�� �J���ꂽ�̂ł���B���ł͍ĎO�Â���Ă͂������A�����͏��߂ĂȂ̂ŁA���̗F�l�܁A�Z�l�����ʂ��グ��ׂ��A����`���������̂��B���������S�z���Ă� ���̂����A����͞X�J�ɂ����Ȃ������B�k�߂̋�Ə��ƊG�̎O�ʈ�̂̋���ȍ��̋�́A�m�l�͂��Ƃ��A�����̐l�X�𖣗����Ă��܂����̂ł���B
�@���͂Ђ����ɍ����d�M�Ɍ��������̂ł���B�����̉i�c�k�߂����܂ł��B�����āA�������������ƁB�K���s�K�����̖��͔j�ꂽ�B
�@���ƍȂ͉������邮����A�킪�Ƃ�����ɂӂ��킵����i��T�����B�����čȂ́q�ΘŁr��I�сA���́q�������_���r�Ɏ��������B���������A�k�߂���� �ӌ������߂�Ƃ����A����`���Ă��܂����̂ł���B���ǁA�q�������_���r��Ђ��Ē������B���ꂩ��l�N�A���̕����ɂ���͗g�����Ă���B�M�����ꂽ�� ���́A
�@�@���������܋����������H����� �t�䏑�ȁ\�\�i�c�k�߈��@�s�Ս��t300���i1975�N11���j�@�k�c�c�l����A�܂��n�ӈ�l�N�������A�u�s���v�̊z�������Ă��Ă���܂����B���̍��h�̔��������̊z�ɁA�����k�ߏ������A�� �ւɌ����܂�����A���܂܂ŏ����Ă������A�A�o�e�B�̐F�ʓ��ʼn�Ǝ����ς��āA���������͋C�ɂȂ�܂����B�k�c�c�l
�� ������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t351���i1980�N7���j�@�P���̉�ɎQ���ł��Ă悩�����Ǝv���܂��S�̂��������f��������[�ł����B����ɁA�� ��W���������܂����B�_�˂Ƃ����y�n�ɂ��e���݂��o���A�܂��Q�肽���Ȃ�܂����B�o������A���̏H�ɂł��A�k�߂���̂���ɎQ��A�� ���̊G����ɂ��������̂ł��B�k�c�c�l
�����q�� ���@�s�Q�t1981�N6�E7�����i1981�N6���j
�@�k�c�c�l
�@��N�̏t�A�i�c�k�ߎP���̉�_�˂̘Z�b���ōÂ��ꂽ�B��́A�O�{�̂ǂ��Ƃ����X�ŁA�S�S��s�I�Ȗ邾�����B�������ēc���Ŋς��u�����v�̑� ���������Ă���Ƃ����A�o�[���Ԃ�ցA�܁A�Z�l�̐����Ɩ�̊X�����܂悢�s�����B�����ɁA�����������������q�������B���ꂪ�O�x�ڂ̏o�����ł���A �Ō�ł������B�u�����v�̓́A���̐���������̂ł͂Ȃ������B
�@�k�c�c�l�� �A���P�[�g�u�����āA�W���P���́c�c�v�@�s�i�فt4���i1983�N10���j�q�����٘^�a�r���i�c�k�߂́u�����}�v���A���Ԃ̕ǂɊ|����B����܂ł́A���̎����ɋ}�������A�킪�F�����d�M�𓉂݁u���^���͂́^�C�Ɓ^��� �̉ԁv�̐��M���f���Ă������B�b���q��A�R���v��A�₷�炩�ɐ�������B
�k�c�c�l�� �t�������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t397���i1984�N9���j�@ ���̂Ƃ���A�������������A���������������ł����B���̓x�̓c���K�₩�炾���ԓ��������A���܂��남���\���グ��̂��A�C���Ђ��܂��B�ǂ����������� �����B�y���F������O����ʂ��āA���ł���܂����B�k�߂���̗e�p�ƁA�����n���̂���b���Ԃ�ɂ́A���S���Ă����悤�ł��B���̖�́A���R�̏h�ɔ���A �����͋��s�s���p�قŁA�ۂ�̉�ƃo���`���X�W���ςāA�[���A�������֎Q��A�����q�̊��g�����ǂ��H�ׂċA��܂����B�{���́A�k�߂���Ƃ�����肨�b�� �����������̂ł����A�y�����Ⴂ�F�l���l���A�h�ɑ҂����Ă������̂ł�����B�����Ȃ��炠�̏��ւ͂��났�܂��B���ւ́u�ԍg�v�̓́A�f������ �Ǝv���܂����B���l�A�Έ���v�l�ɂ�낵�����`���������B
�k�c�c�l�� �t�������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t422���i1987�N1���j�@ �q���@���̂� �т͂��莆�ƍk�ߒZ����q�Ċ����������܂����B�S�����l�̊���������ꂽ�Ƃ̂��ƁA�܂��Ȃ�Ɣ�������������ꂽ���Ƃł��傤���B�ō��̂����{�� �Ǝv���܂����B���āA�������Z���ɂ́A�s�ł̖���u�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�v�����M����Ă���A�i���X�D���̏����ɂ͉����̂��̂ł��B���Ă��P���̉��̐܂ɒ������Z���̕M�����A��x�I�ł���Ȃ�A����ɂ͔��B�̕��C������ �܂��B�����ɁA�����Ε��̘e�ɒu���āA���X���߂Ă���܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ������܂��B�k�c�c�l
�� �t�������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t428���i1987�N7���j�q �[�A�ߓ��͂��S�̂����������莆�Ƒf�������G��q�����܂����B�k�c�c�l���莆�ɂ��ƁA�����̒t�قȕM�ɂȂ�u�K���\���v���A���Œ������ꂵ���v ���܂��B���̂����A���h�Ȋz�ɓ�����A�c���̈���ɁA����ꂽ�Ƃ̂��ƁA�ʉf�䂢����ł��B�q�����܂����A�Ñ㉩�y�痿�ōʂ�ꂽ���ȕ��� �܁B�����ɂ͂Ȃ����A���q�̂悤�Ɍ����܂��B�ނ����l�l���瑡��ꂽ�A�Ñ�����ꂽ�z�ɂ҂���������āA�����Ε��̂킫�ɒ������Ă���܂��B�{���ɂ��� ���Ƃ��������܂��B�k�c�c�l
�g��������W�s�K���t�i���ώɁA1987�N4��24���j�������k�ߋ�̐��M
�����̏��Ȃ╶�͂Ō��y�������̂̊O�ɁA�g���̏����ɂȂ�k�߂̏��悪���邱�Ƃ͂����܂ł�����܂��B�����āA�s�Ս��t�Ɍf�ڂ��ꂽ �ȊO�ɋg���� �k�߂Ɉ��Ă����Ȃ����������邱�ƁA����͂��łɊm�F���Ă���B�����Ŏ��͂���ȏ����݂�B�g�����Ɖi�c�k�߂̊ԂŌ��킳�ꂽ�������鏑�ȂM�� �Ɏ��߁A���Ȃ╶�͒��ŋg�������y���Ă���k�߂̏���A���y���Ă͂��Ȃ������O�ɏ������߈������������J���[�}�łɂ��Čf�ڂ���B�I��W�s�k�ߕS��t �i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�j�̂��߂ɋg�������M�����k�ߔo��̉�����q�o���r���A�t�^�Ƃ��ĉ�����B�����҂ނ��Ƃ����ɋ������̂Ȃ�A�`���ŐG�ꂽ �q�i�c�k�߂Ƌg�����\�\�w�k�ߕS��x�Ƃ��̌�r�i�s�V�t2011�N8�����q���W�E�i�c�k�߁r�j��Ҏ҂̉���Ƃ��čĘ^����B���āA�����͂Ȃɂ��������� ���B�g�����̕��͂����Ȃ�s�y���F��t�ɕ���ās�i�c�k����\�\�q���ȁr�Ɓq���z�r�Ɉ˂�t�Ƃł��������Ƃ��낾���A���́u�i�c�k�߁E�g�����������ȏW �\�\�k�ߏ���ځv�ɂ͂ǂ̂悤�Ȗ��������Ȃ����̂�����B
�k�t�L�l
�q�����L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�́@�s�Ս��t235���i1969�N11���j�r�ɂ́u�܌���\�Z���v�u�Z���\�O���v�u�����\�l���v
�u�����\�ܓ��v�u�����\�����v�u������\���v�ƘZ�����̋L�ڂ����Ȃ����A�����̃}�}�ł���B���e�̒i�K�ł͂��ƈ�����̋L�ڂ������āA�Ȃ�炩�̗��R�ł�
����폜�������̂́A�薼�́u���́v�͂��̂܂c���Ă��܂������̂��B�ŏ�����u�Z�����v�̋L�ڂ����Ȃ��āA�W���t����Ƃ��Ɂu�����v�Ɗ��肵�܂�����
��������������Ȃ����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�ȉ��́A�i�c�k�ߏ���W�s���t�i�i�c�k�ߏ���W���s��A1986�N5��1���j�����̐Έ���v�ҁq�i�c�k�ߌ�
�W�N���r�i�����A��l�Z�`��l��y�[�W�j�̌��o���ƊJ�É�ꂾ�������������́B�k����͋g�������ς��W��\���l
����@�i�c�k�ߏ���W
�@���O���E�܁^�_�ːV����ٕ����Z���^�[
����@�i�c�k�ߏ���W�@���l�Z�E��^�_�ːV����ٕ����Z���^�[
��O��@�i�c�k�ߏ���W�@���l�Z�E�O�^���s�E�l���u�g�v��L
��l��@�i�c�k�ߌW�i���ƊG�j�@���l��E�܁^�_�ˁE�����u�݂Ȃ��v��L
��܉�@�i�c�k�ߏ���W�@���l��E�܁^�_�˂������X���p��L
��Z��@���ƊG�ɂ��i�c�k�ߌW &
nbsp; ���l�l�E���^�����E���{���O�z���p�T�����@��
�掵��@�i�c�k�ߏ���W�@���l�܁E�܁^�_�˂������X���p��L
�攪��@�i�c�k�ߓW�\�\���ƊG�ɂ��@���l�Z�E��^���E��}�S�ݓX���p��L
����@�i�c�k�ߓW
���l���E�܁^�����E������t���@��
��\��@�i�c�k�ߏ���W�@���l���E�܁^�_�˂������X���p��L
��\���@�i�c�k�ߓW�@���l��E��^�_�ˁE�O�{�����M�������[
��\���@�i�c�k�ߏ���W�@���܁Z�E��^���E������L
��\�O��@�i�c�k�߉�^���i�W�@���܈�E��^���E���V���w�g�X���x�i�V�����r����K�j
��\�l��@�i�c�k�ߓW�\�\���ƊG�ɂ��@���܈�E���^���E��}�Ï��̂܂��w���[�`�x
��\�܉�@�c���i�c�k�ߌW�@���ܓ�E���^�_�ˁE������L
��\�Z��@�i�c�k�ߎP���̉�^�W &
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
amp;
nbsp; ���܌܁E�܁^�_�ˁE������L�@��
�g���z�q�ҁq�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�j�ɂ��A�g�����́u����Z�N�i�吳�\�܁E���a���N�j�v�u�{�������q��
���w�Z�ɓ�
�w�v�A�u���O��N�i���a���N�j�v�ɓ��Z�𑲋Ƃ��āu�{���������w�Z�ɓ��w�v�i�����A������y�[�W�j�B�u���l���N�i���a��\��N�j
��\���v�u�A�{���̒��ؗ����X�Ŗ����q�포�w�Z�̃N���X��i���̃N���X��͔ӔN�܂ő�����ꂽ�j�v�i���O�A�����y�[�W�j�B�����āA�u��㔪�ܔN
�i���a�Z�\�N�j
�Z�\�Z�^�k�c�c�l�Z���A�{�����w�Z�Ŗ����q�포�w�Z�̓�����B�L�O�ɋ��߂��w�����J�Z�S�E���N�L�O���x�́q�����b�ɂȂ����l�тƁr�̃A���o���̒��ɗ��e
�̎ʐ^��������B��O�̕���̎p�ɏo��[���������o����v�i���O�A���Z�Z�`���Z���y�[�W�j�Ƃ���B����A���̓�����̂��Ƃ��������g���̐��z�q�w�ɑr
���r�i���o�́s���{�E�t1985�N9�����q���̕��i�r���j�͂������B
�@���Ă̌ߌ�A���͒n���S�̐ō~��A��ȋ����킽�����B�u�₦�ʋ��c�̐�̐��v�Ƃ͂킪�Z�̖̂`���̋�ł���B ���͂���������ʂ͑����Ă��邪�A���c��͂��₩�ɗ���Ă���B�������A���̊w���w�Z�́A���Ԃ��Ȃ��A�p�Z�ƂȂ�A���łɖ����B
�@�u�����J�Z�S�E���N�L�O�v�̍Â��̂���A�{������`�̖{�����w�Z�������B���̒��w�Z�����̐V�����p�ł���B�u�Z���v�ɂ́A�p�Z�̌o�R�����L����Ă��� ���B�������̋L���ł́A�Ă��c�����Z�ɂɁA��Ў҂������Z�݂��A�čZ�̎��@���������̂ł������B
�@ ���͎�t�ʼn����͂炢�A�ʃr�[���ƕٓ������āA�傫�ȉ��ɓ������B���łɎ��T�͎n�܂��Ă���B���炭�T�����A����Ɓu���a���N���Ǝҁv�̕\���� ����A�Ȃ��������B�j�����A���l�ňꐡ�A�C����������Ȃ��B�����������炪�������B�V���̃T�u�����A���i���̃}�A�����A�Ĉ����̒��N�V�����ĉ��ʉ� �̉h�������́A���Ă̏����k�����̑���ɒ����Ă���ł͂Ȃ����B���������A���y�̏\�l�������I�����l�ؑ��`�Y���A���ʉ��̑��q�������ƕ����B�u���b �����悭�����I�v�ƌ}����ꂽ�B�T�u�����͐펀�����Z�ɑւ��āA�ƋƂ��p�������A�ق��̎҂͂��ꂼ��Ⴄ����������悤���B
�@���͂Ƃ������ƕʂ�A�u�X�́v�̕����Ɓu�L�O���v���āA���֏o���B���N������߂��������̕ӂ�́A�ƕ����ς��Ă͂����肵�Ȃ��B�x�V���̔��X�� �Ȃ��Ă��鏈�̂悤�Ɏv��ꂽ�B�܂������֍s�����A�e�������āA��`�����킽��A��`���ɂ��Q��������B������ꂩ�����Ă����B
�@�@����̈ꐺ�e���Ă悬��䂭����̋��ɓ��̂Ƃڂ肽��i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��`��y�[�W�j
���̂قǁs�����J�Z�S�E���N�L�O���\�\�����Z�F�����E���N�t�i���̏����́u���v�͋����j����肵���̂ŁA�����̋L�ڂ��Q�Ƃ��Ȃ�
��A�s���܂��
�����L�t�i����R�c�A1990�j�ɕ`���ꂽ�g���̋��F�����ɓo�ꂵ�Ă��炨���B�܂����t������ƁA���s���́u���a�Z�\�N�܌��\�l�����s�v�ŁA�u����Łv��
���邪���蕔�����̋L�ڂ͂Ȃ��B�u���s�@�����Z�F��^�����s�n�c�擌��`�O���ڈ�ԏ\���^�n�c�旧�{�����w�Z���v�A�u�ҏW�@�����J�Z�S�E���N�^�L�O���Ǝ�
�s�ψ���^�L�O���Ҏ[�ψ���v�A�u����@�������������Ё^�k�Z���E�d�b�ԍ��͗��l�v�ł���B�{���̎d�l�́A�a�T���㐻�z���A�g�����A��228�y�[�W�i��
���̑��4�F�A��̓X�~1�F�B���ϔ���2�y�[�W���ȊO���ׂăR�[�g�n�̗p���Ȃ̂́A�ʐ^��}�ł���Ɍf�ڂ��邽�߂��낤�j�B�O�t�́q�����J�Z�S�E���N�L�O
���Ɓr�ɂ́u�L�O���̔����A�L�O��̌����A�A���A���̑��A���������X�͂̕����E�A�т�搂���Z�F�o�c�W�̐���E���݂܂Ŕ�����������e�ʂ̖���i��W�j
�̔��s�Ȃǁv�i�k��܃y�[�W�l�j�Ƃ���A�g���̋L�q�ƍ��v����B���Ɂq�ڎ��r�̑區�ڂ������B
�@�O���r�A
�@�����̎�����яj��
�@�������Ɍ��閾�����w�Z
�@�������w�Z�̈�i
�@�������w�Z�ƍZ�F��̉��v
�@�������̃A���o��
�@�w���W�c�a�J�^���L
�@�ҏW��L
���̒��́q�N�\ �������w�Z�ƍZ�F��̉��v�\�\���тɒn��E�Љ�̗��j�r�ŁA�g�����a����1919�N���瑲�Ƃ�32�N�܂ł̊Ԃ̏d�v���ڂ��E���Ă݂悤�B
�@1923�i�吳12�j�@9��1���@�֓���k�Ђ̂��ߍZ�ɏĎ��B
�@1929�i���a4�j
11��25���@�Зe�������ă��_���ȓS�؎O�K���̐V�Z�ɂ������B�~�n�ʐρE�܌܈��u�A�Z�ɉ��ʐρE���u�A����Z�ő�B
�@1930
�i���a5�j
3��31���@�s���u���a�}���فv���A���a���w�Z����u�����q�포�w�Z�v�Ɉړ]���Ă����B�̂��u�s���E����`�}���فv�Ɖ��́B�^5��1
���@����
�Z�͊w������\�Z�A�E���O�\���A��������l�Z�Z���A�قڐk�БO�Ɠ����̃}�����X�Z�ƂȂ�B�^�E���̔N�A�V�Z�́u�₦�ʋ��c�̐�̐��c�v�𐧒肷��B�i�{
���A�Z�O�`�Z���y�[�W�j
�{����͂����邪�A�����Z�F��̑��k���ő吳6�N���Ƃ̖ؑ��`�Y�́q��ځr�i�q�����̎�����яj���r�j������ƁA�u���k�{����\
���l�̒�����
�˒n���Ƃ������n���l�������āA���̂����l�̓��������œ����������B����قǍL�����Ȃ����������A��X����������Ŏ��ŋ��̉����������ł����B���ŋ�
������͐��F�����܂��A�����͂��������B�ŁA�Ԙa���D�q�[�Ƌ�䗴�j�i�Ƃ́A�ᒆ�̌���Ƃ�����ʂ���Ɋ����������v�i�{���A���y�[�W�j�Ƃ����q����
�����[���i�g���̓��L�ɂ��˒n�������o�Ă���j�B���Ȃ݂ɖؑ��I�����l�͋g�����14�ΔN���B�g���͖ؑ��`�Y�̂悤�ɂ͎��M���Ă��炸�A�����炭�ǂ̋L
���ɂ��o�Ă��Ȃ��B�{���ŗB��u�g�����v���o�ꂷ��̂́q�������̃A���o���r�\�\�����ɂ́u�������w�Z�̖����E�吳�E���a�̎O��ɘj�鑲�ƋL�O�ʐ^����
���B���ݏN�ߓ�������̏W�听�ł���A�����ē����̂܂܂̕����Ƃ��܂����B�v�Ƃ���\�\�́q���a���N�@��g�r�̑��Ǝʐ^�ɕt����ꂽ�u�Z�m��v�̐��k����
�Ƃ��Ăł���B

�{�������q�포�w�Z�A���a7�N6�N1�g�̑��ƋL�O�ʐ^�i�g�����͏ォ��2�i�߂̉E����3�l�߁j
�o�T�F�����J�Z�S�E���N�L�O���Ǝ��s�ψ���E�L�O���Ҏ[�ψ���ҁs�����J�Z�S�E���N�L�O���\�\�����Z�F�����E���N�t�i�����Z�F��A1985�N5��14
���A��ꎵ�y�[�W�j
�{�������q�포�w�Z�A���a7�N����6�N1�g�̒S�C�c���M���Y�搶�ƑS���k57���̎�����^����i�ʐ^�̏�i���牺�i�ցA������E�ցB�\ �L�ɂ͋������p�����j�B����́s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ��l���ŁA�����͓����̃m���u���i�ȉ����j�B
���{�@���U�E���������Y�E���љB���Y�E��ˁ@���j�E�R���@�M�Y�E���{�@�����E�_�@���j�E�쓇�P��Y�E�����@�r�Y�E���@�r��E���݁@
��Y
���V�@��Y�E����p�@�P�j�E�����@�́E�����V�@���E�����R�@�c�i�E�����@�o�E���R��粎O�Y�E���@��q�E�������@ꝕv�E�����@�Z�Y�E�g���@���E���R�c�@
�O�E�ђˁ@��
���r�c�����Y�E��с@���ʁE�����@�v�E�|���@���Y�E���F�y��Y�E�q��@���O�E���{�@�z��E�����{�@���N�E�����씪�Y�E�ɓ������Y�E���с@���ׁE�x�c�@�v
�@�ɁE�x�z�@���v�E�x�c�@���E�������@�ď��E���C�с@���E�˒ˁ@�эƁE���v�ہ@���Y�E������@�a�Y�E�����@���j�E�R�X�@�d�[�E�����c�@�r�Y
�Ώ�@�O�s�E�c���@�F�E�����@���O�E���y�@����E���y���@�c�F�E���c���@�搶�E�H�c�@���b�E����@�E�V�����V���E�{�{�c���Y�E�J���@���O
����p�@�P�j��94
�����V�@����24�u���O��N�l������^�[��ǂ��A�˒n���̑O�ŁA�R��ӎO�Y�Əo��B�������̏���
�E�m��n��ꂽ�Ƃ̂��ƁB���w�Z���ƈȗ��A���i�H�j�ɂ͉���Ă��Ȃ����A�\�ł͊������\�l�����Z���m�A�A�n�������炵���B�������ȋC�������B�z��
�o�͔��l�������B�v�k�{���ɂ͏��V���̎o�Ƃ��ڂ��������k�̑��Ǝʐ^���ڂ��Ă���l
�����R�@�c�i��19�E47�E52�E64�E68�E69�E79�E94�E112�E120
���R��粎O�Y���q�w�ɑr���r�E19�E24�E57�E59�E66�E79�E89�E93�E94
�������@ꝕv��94
���R�c�@�O��79�E94
���r�c�����Y��89
�����{�@���N���q�w�ɑr���r
�������@�ď����q�w�ɑr���r
���v�ہ@���Y��93
������@�a�Y��94
�����c�@�r�Y��93
���y�@����19
���y���@�c�F��39�u���O��N�܌��\�ܓ��^�y���S�F�N�̈�e�W�w������m�x��ǂ�ŁA���̕��˂ɋ����B�����A�Z����̓y�����F�i���J�^�j�֊��z�̎莆��
�����B�v�A120�u���l�Z�N�ꌎ��\���i���j�^���A�\������ԉH�̖@�P���֍s���B�y���S�F�N�̎O����̖@�v�B�\�N�Ԃ�ʼnƑ��ɉ�B�Z�̗��F����ƚ��
�����F�̑z���o�ɂӂ���B��Ƃ������Ƃ��u�]���Ă����������B�u�̕�n�ɂ��Q�肵�ċA�����B�ߌ�O���߂����z�։��B�c�����Ɩʉ���͖̂��z�O������
���̚��̐����A�����[��B�v�k�{���ɂ͓y�����F�̑��Ǝʐ^���ڂ��Ă���l
���c���@�搶��79�E94
�c�O�Ȃ��ƂɁA�u�܂��V�v�i���Ɂu�}�A�V�v�u�}�A�����v�Ƃ��j���N�����킩��Ȃ��i�q�w�ɑr���r�E54�E89�E94�E121�j�B���a 7�N����6�N 1�g��57�l�̖��O���猩��������ƁA�u���ѐ��ׁv�u�������j�v�u�y�ؐ���v��3�l�����A�u�g�����v���u���b�����v�̗��V�ł����ΐ��̉\��������� ���ŁA����͍���B�Ƃ͌������̂́A���Ƃ��ẮA����ɉX���̒ʂ�̉�����i�́u���V�v�i48�E57�E60�j�������āA�u�y�ؐ���v���A�Ƃ��������ɌX ���Ă���B���O�Ƃ����A�g���ȊO�ɂ��u���v���u�x�c���v�u���C�ћ��v�ƃN���X��2�l������̂ɂ͋��������B���Ȃ݂ɁA�������j�q����56�l��6�N2 �g�Ɂu���v�͂��Ȃ��B���c�Z���i79�E94�j�������q�포�w�Z�̓������̂悤�����A�ǂ������킯�����ƋL�O�ʐ^�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B�s���܂�͂����L�t�� 1939�N9��19���ɓo�ꂷ��u���c�x�h�搶�v�i76�j�́A�g�������Ƃ����Ƃ���6�N4�g�i���k�͏��q53���j�̒S�C�ł���B�g���ɂ́A�O�f�q�w�ɑr ���r�ȊO�ɓ������̓�����ɂ��ď��������z�͂Ȃ��B�����g�����������������r�Y�̕��͂�����A�K���Ȃ��Ƃɂ��̍ŏI�����ɋg���̓������������o�ꂷ��� �ŁA��Ⓑ�������p����B�g�����ڂ����͏����Ȃ�����������̕��͋C������������B
�@������A���͈�ʂ̗t�����Ƃ����B�����ɂ́u�g�����N�̑��V�A����J���܂ł����B���͏��w�Z��N����Z�N�܂� �����Ƌg���N �Ɠ����ł����v�Ƃ���B�\���Ɂu��������M�v�Ƃ��邻�̖��O�́A������N�O����I�����Ă���u����S�_�v���o�嗓�̏�A���e�҂ŁA�G��ɂ��̂����L������ ��B�u���N����̋g������ɂ��Ă��낢�남���������������������̂ł��v�ƕԎ����������B���悳��͂܂��t�������āA�g������ƍ��悳��͍ŋ߂ł� ���N����̂܂܁u���b�����v�u�J�[�V�v�ƌĂт����Ă������ƁA���w�Z����̒��Ԃ������Ɏ���܂ň�N�Ɉ��W�܂��ė������Ƃ�m�����B
�@���������Ή߂��A�z�q�v�l����d�b���������B�g���̓������̓�����Ɏ��Ɩr�����ƗU���Ă�����ǁA�s���H�@��������Ԏ��ŏo�Ȃ��邱�Ƃɂ� ���B�ǂ��č��悳��莆������A������̏ꏊ�Ɛ��b�l�̓d�b�ԍ���������ꂽ�B�������b�l�́��R�m�ӎO�Y����ɓd�b���āA�o�Ȃ����Ă��������|�`�� ���B
�@������\�O���[���Z�����A�n���S�w��ȋ����ɏo�����͌}���̎R�m�ӂ���̈ē��Ō�ȋ���n��A�����ɂ������̏��������̕���̉��A�����I�ɍs�� ���B�o�Ȏ҂͏\��A�O�l�������낤���A�z�q�v�l�̊�����łɂ������B�z�q�v�l�ׂ̗ɂ͋g������̎ʐ^�������Ă����B���ׂ̗̘Z�\���������ɂ��������� ���ዾ�̐l���A����ł��A�Ǝ��ȏЉ�������B
�@�z�q�v�l�Ǝ��Ƃ������o�Ȏ҂��ׂĎ��\���z���Ă���͂��Ȃ̂����A�����ɂ��Ȃ��u���b�����v��A�����A���������c�N����̒ʏ̂ŌĂт����Ă��邤 ���A���a���N�̖{�������q�포�w�Z�̘r���̏W�܂�Ɠ�d�ʂ��ɂȂ��Ă���B��ő����ė����X�i�b�v�ʐ^������ƁA�ǂ̎ʐ^�̗z�q�v�l���������ꂵ������ ���Ă���B��H�����܂Ȃ��u���b�����v������Ō�܂ŕt�������������ŁA�g�������̏W�܂���ɂ��Ă������Ƃ��킩��B
�@�z�q�v�l�ɂ��ƁA�g������͎O�\�N�̌����������A�܂ŗ��Ă��z�q�v�l���ċ��̂������ɗ������Ƃ͈�x���Ȃ��A�Ƃ����B����قǑ�ɂ����c�N ����̐���ւ̎v���͈⒘�w���܂�͂����L�x�ɋÏk���Ă���B�N���w���܂�͂����L�x���f��ɂ��Ă݂悤�Ƃ����A�ӗ~����ē͂��Ȃ����B�u���N�����v �u�ߏ��s�v�̑�p�́k��l�F���ēł͑ʖڂ������A�ȂǂƎv���v�����Ă���B�i�����r�Y�q�g�����������L�r�A�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�v���ЁA1991�A��܌܁`��ܘZ�y�[�W�j
��������M������@�a�Y
���R�m�ӎO�Y���R��粎O�Y
���ƋL�O�ʐ^�Ƃ����ɋL���ꂽ�������̎����́s���܂�͂����L�t�ɂ�����g���̌�F�W��ǂ݂Ƃ����߂̍ł��d�v�Ȑ}���������ł���i�{���������w�Z�̑�
�ƋL�O�ʐ^�͎c���Ă��Ȃ��̂��낤���j�B���l�ɁA�o
�����̋L�O�ʐ^���g���̐e����ǂ݂Ƃ����߂̍ł��d�v�Ȑ}���������Ƃ������ƂɂȂ�B�Ō�ɁA�`���ň������q�N���r�ɓo�ꂷ��u�A��
�o���̒��Ɂv�������u���e�̎ʐ^�v���f���āA�{�e����߂����邱�Ƃɂ��悤�B

�ʐ^�̏�i���牺�i�ցA������E�ցB
�@���ؒ|���Y�E�g���@���ƁE���n�@��
�@�g���䑾�Y�E�V�c���ܘY�E���c�ɔV��
�s���܂�͂����L�t�ɂ��o�ꂷ��g���̏f���i���䑾�Y�̒�j�ł����V�c���ܘY�i76�E77�E78�E104�j��1939�N10��1���ɖS
���Ȃ��Ă��邩��A������O�̎B�e�B
�k�NjL�P�l�g�����̐��̓��L
�s���܂�͂���
�L�t�ɂ́A1939�N8��4���̐̂Ƃ��u�쑽���v�ł̃N���X��̂��Ɓi64-65�j�A8��11���́A���̃N���X��̋L�O�ʐ^�̂��Ɓi66�j�\�\
�s�����C�J�t1973�N9�����A���܃y�[�W����сs���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t���G�́u�o����ɂāv�̎ʐ^�͂��ꂩ�\�\�A10��15���̖����q�포�w�Z������̂��Ɓi80-81�j�\�\�s�����C�J�t�����A����y�[�W�̎ʐ^�͂�
��ɈႢ�Ȃ��\�\�A11��26���̕������ł̖{���������w�Z�̃N���X��̂��Ɓi92-93�j���`����Ă���B�s���܂�͂����L�t�ɂ��т��ѓo�ꂷ�閡�`
�i19�E70�E74�E93�E118�j�́A�{���������w�Z����̃N���X���[�g�ł���i�����q�포�w�Z����̋��F�́u�c�N����̒ʏ́v�ŁA�{���������w�Z����
�̋��F�͕c���ŌĂ�邱�Ƃɒ��ڂ������j�B����A�g�����̐��̓��L�ɂ́A�����q�포�w�Z�̃N���X��i1947�N2��2����1948�N7��3���j�̗l�q
���`����Ă���B���̓��L�̋L�ڂɂ��ẮA�剪�M�Ƃ̑Θb�ɋg���̃R�����g������̂ŁA������܂߂Ĉ����B
���a��\��N����@���j�@���w�Z�̃N���X���{���̒��ؗ����X�ł���B���c���搶���V����ꂽ�������Ⴂ�B���}�A�V�A�������A���Z
���A���r��A
���h�����W�����B�����̂킩���Ă�����́A����p�A�������A�����R�̌c�����펀�B���Ȃ����́����Ԃ�����Ȃ��̂͂��т����B�����ƕ����͂���
�������B�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�A��Z���y�[�W�j
���c���搶���c���M���Y
���}�A�V
�����������{�@���U
���Z�������c�Z��
���r�ꁁ���@�r��
���h���������@�ď�
����p����p�@�P�j
�������������@�v
�����R�̌c������R�@�c�i
�����Ԃ���R��粎O�Y
�����O���i�y�j�j
�@�q�N���X��r
�@����m�A�A�n�̑����n���S�ɂ̂�^���ˁm�A�A�n�������Ă��Ȃ�����^���S���Ăڂ���^�f��
�̃r�������Ă����^���c�����͍r��ʂĂĂ��Ă��^���݂̐l������������Ă����^��̐��������炩����ŗ���Ă����^�ނ����̂悤�ɍ��ł��^�Ί_�ɊI���Ђ�
��ł��邩�ȁ^�Ȃ�������������ȋ����킽��^���тƂ����̃{�[�g����������Ă����^�l�͋��̏�̗҂����j�H�^��Z���߂��^���������ɏ\�l�قǏW��
���^�����q�포�w�Z���a���N���Ɛ��^���Ȃ����́����Ԃ����͓����Â��ē�l�̎q�̐e�^�������́��낭�����͑��������������̎o�������[�^�������́��܂�
�V�͂��y�؉��̎�l�^�x�߂��Ή��́�������������펀�^���t���c���搶�͂��̏t�Ȃ��Ȃ�ꂽ�^���c����Ȃ���̉��^�嗱�̉J���~���Ă����i�q����
�i���l���N�E�ė�j�r�A�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t����R�c�A1996�A��O�y�[�W�j
�����Ԃ���R��粎O�Y
���낭���������c�Z��
���܂��V
������������R�@�c�i
���c���搶���c���M���Y
�剪�@��
�Ƃ����݂̏ꍇ�A��͂���L�łˁA�I�풼�ギ�炢�ɓ����������āA�����ɏo�Ă��閼�O�������Ă���킯�ˁB���ꂪ�c���͂ЂƂ��o�Ă��Ȃ��B
�g���@�����A�����Ԃ�����
�����}�A�V�Ƃ��B
�剪�@�����������O�ŏo�Ă�
��l�����܂������̂́A���ɓ���Ǝv
���B�����ǁA��������������ɖʔ����낤���Ă����C������B�k�c�c�l���������W�̂����Ă镵�͋C�𐳊m�ɏ������炢������ƂȂ���ȁB�g
���́A���������̌��������邩������Ȃ��l���Ǝv���B������������ƂˁA���̕��ō���Ă������ɍd���̂��̂Ƃ��ꂪ�ǂ����т����A���B
�g���@�ɂ����Ƃ������ˁA��
��Ȃ�B�ڂ��ɂƂ��Ė{���̐�������
�̂́A�����炭������Ǝv���́A������x�܂łˁB�������w�Z�̍��Ȃ�Ă̂́A�Ĉ����ւ����Ă��A���ꂪ�����̗��܂��ˁB�~�Ȃ�ďĈ��̊��ɂ�����
�āA�_�x���Ă������̂��ȁB���Ȃ����́����Ԃ����A���i���́��}�A�����A���������l�ԏ�����Ǝv���̂�B�����A�剪���������A���ł��܂܂ōl���A�\�z
���Ă������ƂƁA�ǂ��Ȃ���̂��Ƃ������ƂˁB
�剪�@�����瑽�����������
���āA���̃G�b�Z�C���낤�ˁB���i�Ȃ牓�i�ɁA���������l�����������ƛƂߍ��߂A�g�����i���ł���Ǝv���B�i�g�����E�剪�M�k�Θb�l�q���`�̐��E��
��r�A�s�����C�J�t1973�N9�����A����y�[�W�j
�����Ԃ���R��粎O�Y
���}�A�V
���}�A�����
�k�NjL�Q�l�]�ː에���̉X��
�]�ː에���̒��я����s�H�S�̓��t�i�����͔�}�t�A1941�N7��29���j���A�����Дō]�ː에���S�W�i1963�N7���j�̕�
���œǂ�
�i�s�]�ː에���S�W�k��\�܊��l�t���ώɁA2009�N6��19���j�B�f�l�T��A�͒ÎO�Y�i���q���ܘY���v�킹��j�����ł̘A���o�����߂�������������b
�����A�`���̈�߂����p���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@�ނ͂��̂���A���ӂ̂悤�ɍ��̔w�L�A���̒��ŖX�Ƃ����A�E�p�g���̂悤�Ȃ��ł����ŁA���c��̋��̏�֏o������ �s�����B���� �����ɂ��������邻���̋��̏�ɂ́A�v�҂̍D�݂̍\�}�ɂ���āA����ȓS�����������l�H�̓���`���Ă����B�������̑f�l�T��͐[��\�O��ɁA�� ���ԂɃ^�N�V�[�����̂āA�l�ʂ�̂Ƃ������Ƃ���������܂��āA���̐l�H�̓��̓S���̏�ɂ悶�̂ڂ�̂ł������B
�@�ł̂Ȃ��̕��̍L���S���́A�������̂ЂƂ�̐l�Ԃ��[�����E����B�����Ƃ��ł����B�ނ͂��̗₦�₦�Ƃ�����S���̏�ɐg���������A�܂�œS���̈ꕔ�� �ɂȂ��Ă��܂������̂悤�ɁA�g���������Ȃ��ŁA�ԁA�O���ԁA�ł̒��Ɋ���݂͂莨�����܂��āA���̉���ʂ肷����A���̉��ɗ����ǂ܂�l�X���ώ@�� ��̂ł������B
�@�k�c�c�l
�@���̕���̔��[���Ȃ��l���ܓ��̖�A�͒ÎO�Y�͗�̍������ɐg�������߂āA�X���̓S���̏�ɉ�������Ă����B
�@�����\�ɋ߂������B���݂̃l�I���̓d���������A�͂����̉ƁX�̑����Ƃ�����A���̏�̎����Ԃ̉��������Ƃ��������ɂȂ��āA���ԎG�B�̏ꏊ�����ɁA ���̕��҂����͂ЂƂ����ł������B�i�����A��܋�`��Z�Z�y�[�W�j
����ɁA����͋��R�Ƃ����ق��Ȃ����A�����߂��ő��ƋL�O�ʐ^���o�ꂷ��B�u�Z���ɖʉ�āA������݂��āA���Ɛ������A���ƋL�O��
�ʐ^��������
����������A���̎ʐ^�̈ꖇ�ɂ́A�i���A�A��c���̎O�l�͂������A�O�c���܂ł��A�l�ݕ��𒅂��q���X�X���������ׂĂ����̂ł���B�^�͒ẤA����
���������߂�����ł͖������Ȃ��ŁA�Ȃ������̔��\���l�̑��Ɛ��̊���A�ЂƂ�ЂƂ���O�ɒ��߂Ă������B����ƁA�ނ̊Ⴊ�n�b�ƈ�̊�ɂԂ���
���B�\�����I�������̂��B�����ɁA���̍ŏ��̎�݂�j�ߓc���Y�Ƃ�������̊���������N���A��������̂������蓪�̒�����A�q���C�Ƃ̂����Ă����̂ł�
��B�^����ׂĂ݂�ƁA��͂肱��͒ߓc���Y�ɈႢ�Ȃ����Ƃ��킩�����B�����A�Ȃ�Ƃ������Ƃ��B�����ƂƑ�c�m�Ɖ�ƂƎG�ݖ≮�Ƃ��A����������
�āA�������w�̑��Ɛ��ł��������肩�A���̊���Ȏ�݂�j�܂ł��A�ނ�̓������ł��낤�Ƃ́v�i�����A��l�܃y�[�W�j�B
�����́q���Ƃ����r�ɂ��A�{��́s���̏o�t1939�N4��������40�N3�����܂ŘA�ڂ��ꂽ�B�g���̊x���A�a�c�F�b����O��10�N�Ԃقǁs���̏o�t��
�ҏW�҂������Ƃ����̂�����ł���B
�H���K�l�́q�s�A���X���сt�����r�Ɂu������ɂ��Ă��A�u���C�X�E�L��������T�����@�v�Ƃ���ɑ����A�u�w�A���X�x���v�Ƃ��琬��g���́s�A���X���сt�́A���ǂ���Ɋy�����A�����ĐS�n�悭�A�Â��ɌJ��L������C���[�W���v���`���Ĕ�������i�ł���B�k�c�c�l���̐��U�̑S���т�ʓǂ��鎞�ɂ́A�l�͕K�����̓�т���A�g�����̐V�V�n���g�����Ă䂭�̂�Ɋ����邱�Ƃ��낤�v�i�s�g�����A���x�X�N�t�A����R�c�A2002�N5��31���A�܁Z�y�[�W�j�Ƃ���Ƃ���A�g�����́q�A���X���сr�́q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�G�E11�j�Ɓq�w�A���X�x���r�i�G�E12�j���琬��B��������͋��`�́q�A���X�сr�A���Ȃ킿�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�Ɏ��߂�ꂽ������2�тł����āA�g���ɂ͂������܂ށu�A���X���W�̖��v���������B�߉��P�v�́q�q�T�t�����E�݁r�Ɋւ��邁���炅�܂ł̎��I�Ȓf�Ёr�i�s���w�t1977�N3�����j�Ɉ�����Ă���g������̕ԐM�́u�A���X���ق߂Ă����������肪�Ƃ������܂��B�����ꂠ�Ɠ�A�O�т�����Ĉ���̖{���Ă��܂��B�c�c�c�v�i�����A�O���y�[�W�j�����̏ł���B�����Œ߉����g�����Ȃɑ�����
�@�g�������݂��A���X���̈���̖{�͎������Ȃ������B�A���X�̎��͈ꉞ�́q�T�t�����E�݁r�Ɏ��^����Ă��܂����B�������ڂ��͂��܂��A���X���̈���̖{�̖����݂Â��Ă���B���̓����g���������������Ĕ���������{�����{������̗͂�����Ĉ���̔������A���X���W����钇���������������̂��Ƃڂ��͖��݂Ă���B
�Ə����Ă���悤�ɁA�A���X���̈���̖{�͎������Ȃ������i�����́u����������{�����{������v�́A�߉������c�����Ƒg��ŕҏW�����q�p���n���鋛�r�\�\�g���́s�t�́t�Ċ��͑p���̑�2�W�\�\���o�����Ō��A���쏑�[��z�N������j�B���������ɁA����Ȃ�����ɋ߂�����������݂���B�s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�i���������R�����A1976�N2��4���j�����ꂾ�B�{���ɂ́q���C�X�E�L��������T�����@�r���\������2�т̂�����1�сq�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�̍Ę^�ƁA�̂��ɏE�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�Ɏ��߂�ꂽ�q�l�H�ԉ��r�i�I�E19�j�̏��o���f�ڂ���Ă���̂��B�s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�i�ȉ��s�Ԃ̍��̃A���X�t�j�́A1975�N10��3������8���ɂ����ĐV�h�����S�ݓX�ŊJ���ꂽ�q����O�l�W ���R����E���R�i�V�E���R���q�r���L�O���āA���N2���Ɍ���1000���Ŕ��s���ꂽ�}�^�I�ȍ��q�ł���B�����̖ڎ��i�k�@�l�͏��тɂ���L�j�Ɖ��t��^����B
�Ꙟ�m�ЂƂЂ�n�̕Ł������O 6-7
Please be our guest.....�k�p���l 8-9
�k�Ԃ̍��̃A���X�E�ڎ� 10-11�l
���Ȃ���̂����ۂ����ƁE���R���၁��� �� 14-23
�킪�A���X�ւ̐ڋ߁��g�� �� 25-32
�Ԃ̍��̃A���X�W�k�}�^�l 33-96
�����ɂ����Ȃ�F�� the cosmos�����R���� 42
�u�����R�ɂ̂藷�ɏo�悤 function�����R���q 49
���ׂȂ��̂����� micro-cosm�����R�i�V 61
�Ԃ̍��̃A���X�W�ɂ��ā����R���� 66-67
�����Ȃ���݂��Ȃ������R���q 76-77
�����ɂÂ������灁���R�i�V 86-87
�C���h�E�i�^�}���̌��z�������v 98-103
�l�H�ԉ����g�� �� 104-107
�����ȋ�ԉ��o������ǗY 108-109
�Ăт������ԁ��L�� �� 110-113
��������@�_���l�k�������l 116-121
�A���X���p���݂���܂Łk��� ���l 122-128
�k�W����X�^�b�t 128�l
�N���k���R����E���R���q�E���R�i�V�l 130-149
�k�M�ҏЉ� 150-151�l
�k���t 153�l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�����Z�Z�Z���Q�E�Q�k�ԍ��͕M�����l��
�Ԃ̍��̃A���X
�ʐ^����{����E�{���G���E�����ƍK
�u�b�N�f�U�C���������ƍK
�C���X�g���[�V�������W�����@�e�j�G���E�t�C���b�v�@�K�[�t
���a�܈�N�l�����s
�ҏW��������Ж���
���s�ҁ����R����
���s�������������R�����
���s�k��t�����l��@�X�֔ԍ����O�Z�@�d�b�����k���l
�����s�`��ԍ⎵�\��\��Z�\�O�Z�Z�@�X�֔ԍ�����Z���@�d�b�������k���l
���a�܈�N�ꌎ��ܓ����
�������������������
���{�����M���{
 �@
�@
�q�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�i�G�E11��1�сj�̍Ę^�y�[�W�i�`���̌��J���j�k�o�T�F�s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�i���������R�����A1976�N2��4���A�u�b�N�f�U�C���F�����ƍK�j�l�i���j�����̕\���i�E�j
�{���̍\�������Ȃ�ɂ܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ȇ\���ɂȂ�B
�T�@��
�@�Ꙟ�m�ЂƂЂ�n�̕Ł����� �O 6-7
�@Please be our guest.....�k�p���l 8-9
�U�@�ڎ�
�@�k�Ԃ̍��̃A���X�E�ڎ� 10-11�l
�V�@�I�}�[�W��
�@���Ȃ���̂����ۂ����ƁE���R���၁��� ���@14-23
�@�킪�A���X�ւ̐ڋ߁��g�� ���@25-32
�W�@�}�^
�@�Ԃ̍��̃A���X�W�@33-96
�@�����ɂ����Ȃ�F�� the cosmos�����R����@42
�@�u�����R�ɂ̂藷�ɏo�悤 function�����R���q�@49
�@���ׂȂ��̂����� micro-cosm�����R�i�V�@61
�@�Ԃ̍��̃A���X�W�ɂ��ā����R����@66-67
�@�����Ȃ���݂��Ȃ������R���q�@76-77
�@�����ɂÂ������灁���R�i�V�@86-87
�X�@�_�l
�@�C���h�E�i�^�}���̌��z�������v�@98-103
�@�l�H�ԉ����g�� ���@104-107
�@�����ȋ�ԉ��o������ǗY�@108-109
�@�Ăт������ԁ��L�� ���@110-113
�Y�@���Ƃ���
�@��������@�_���l�k�������l�@116-121
�@�A���X���p���݂���܂Łk��� ���l�@122-128
�Z�@�N���W�b�g�i1�j
�@�k�W����X�^�b�t�@128�l
�[�@����
�@�N���k���R����E���R���q�E���R�i�V�l
130-149
�\�@�N���W�b�g�i2�j
�@�k�M�ҏЉ�@150-151�l
�@�k���t�@153�l
���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA���Ɂu�_�l�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��X�ɒu���ꂽ�g���́q�l�H�ԉ��r���i�U���j���Ƙ_�l�̒��Ԍ`�Ԃ̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�����A�q�l�H�ԉ��r�͒i���`����1�������Ŏn�߂鏑���������Ȃ����̂́i�X�̑��̕��͂ɂ����������Ȃ�����A�{���̃��C�A�E�g�̕��j�Ɉ˂���̂������ꂸ�A�g���������������������Ă��Ȃ����͌��e�����̒i�K�ł͕s���j�A���o�ł͋�Ǔ_������A���R����U���̌`���ŏ�����A�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�ւ̎��^�ɍۂ��Č��s�̎U�����^�ɉ��߂�ꂽ�B���A����A�L���̕��͕]�_���ł���A�g�����K����q����O�l�W ���R����E���R�i�V�E���R���q�r�̉��ɑ����^�сi�Œ�ł������ʐ^��ڂɂ��āj�A�{�������������̂Ǝv����B���`�́q�A���X���сr�ɂ�����A���C�X�E�L���������B�����A���X�����̎ʐ^�ɑ���������̂ł���B�c�O�Ȃ��玄�͓��W���ςĂ��Ȃ����A�{���Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^�����邩����A1970�N�̑�㖜�����ɂ�����ߖ������C���[�W���������̓W������z�킹����̂�����B���č���A�������݂��̂́A�s�Ԃ̍��̃A���X�t�̋g�������̑g�̍قŁA�ˋ�̏��s�A���X���W�t�𐧍삷�邱�Ƃł���B���������́q�l�H�ԉ��r�̊�{�Ŗʂ͎��̂Ƃ���B
�q�l�H�ԉ��r�i�s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�����j�̊�{�Ŗ�
�V�n250mm 12�|�C���g 25���l�� �ŖʓV�n105mm�i300�|��105.42mm�j �V�A�L72.5mm �n�A�L72.5mm ���E150mm 13�s�g �s��12�|�C���g �Ŗʍ��E105mm�i300�|��105.42mm�j �����A�L30mm �m�h�A�L15mm
���Ȃ킿�����`�̔Ŗʂ�p���̓V�n�����Ɂu�����A�L�F�m�h�A�L���Q�F�P�v�Ŕz�u���Ă���B�����Ɛ���ɂ���L�̐��l���e���v���[�g�Ƃ��āAInDesign�őg�̂����}�́i�E�j�ł���B
 �@
�@
�q�l�H�ԉ��r�i�I�E19�j�̏��o�f�ڃy�[�W�i�`���̌��J���j�k�o�T�F�s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�i���������R�����A1976�N2��4���A�u�b�N�f�U�C���F�����ƍK�j�l�i���j�Ɓs�Ԃ̍��̃A���X�t�̊�{�ŖʂōČ������q�l�H�ԉ��r�̒�e�i�`���̌��J���j�kInDesign�ɂ��l�i�E�j
�q���C�X�E�L��������T�����@�r���\���������1�сq�����`���r����сs�T�t�����E�݁t��̎��W�Ɏ��߂�ꂽ�q���̃A�X�e���X�N�r�i�H�E22�j�Ȃǂ̍L�`�́q�A���X���сr�A�����ɐ�삯�ď����ꂽ�q�����r�i�F�E5�j�A�q�������r�i�F�E10�j�A����ɂ́q�w�A���X�x���r�Ƃقړ������ɏ����ꂽ�q�s�N�j�b�N�r�i�G�E7�j��������ƁA���̍l����s�A���X���W�t�͎��̂悤�ȓ��e�ɂȂ�B
���C�X�E�L��������T�����@
�@�@�\�\�킪�A���X�ւ̐ڋ߁c�c6-9
�@�@�\�\�����`���c�c10-16
�w�A���X�x���c�c18-25
���̃A�X�e���X�N�c�c26-31
�l�H�ԉ��c�c32-35
�@�@�@��
�����c�c36-39
�������c�c40-41
�s�N�j�b�N�c�c42-44
�g�����̓A���X��܂肱�����q���C�X�E�L��������T�����@�r�q�w�A���X�x���r�q���̃A�X�e���X�N�r�q�l�H�ԉ��r��4�т��������Ȃ������B�����Ȃ������A�Ƃ�����������������������Ȃ��B�����͂�������H���K�l���������悤�ɁA�ٓǂɂ����ǂɂ�����������тł���B�s�A���X���W�t����҂̂ЂƂ�ł��鎄�́A���̑z���������āA���Łs�g�����ɂ��w�A���X���W�x�t��҂݁A���܂��������{�E��������|���邱�ƂŁs���̍��̃A���X�t��n���Ă��܂����B�{�����H���K�l�Ɍ��Ă��炢���������B�s�A���X���W�t�̂��߂ɏ������������f���āA�{�e���I���邱�Ƃɂ��悤�B
�����₩�ȋL�O�b���ш�Y
�g�����ɂ́A�������Ȃ��������W������������B�q�k�p���r�̈���s���C���b�N�E�K�[�f���t�A�q��́r�Ȃǂ̔n�̎��т��W�߂��I�W�A�����āq�A���X���сr���W�߂��s�A���X���W�t���B��Z��Z�N�Ɏl�\���Ő������g���������Ƃ̏H���K�l�́q�A���X���сr���������B���l�ŁA����C�������Œm����߉��P�v�́s�A���X���W�t�̊��s�݂��B���͔ނ炪�ʂ����Ȃ������������ł̌`�Ŏ����������Ǝv���B�g�����̟f���\�ܔN�Ƃ����N�ɁA�x����ɒ�o���邳���₩�ȋL�O�ł���B�{������̂��������ƂȂ����s�Ԃ̍��̃A���X�\�\ALICE IN FLOWERLAND�t�i���������R�����A��㎵�Z�j�̔��s�ҁE����X�^�b�t�ɐS����̎ӈӂ�\����B
��Z��ܔN�\�ꌎ
 �@
�@
�ˋ�̏��A���ш�Y�ҁs���̍��̃A���X�\�\�g�����ɂ��w�A���X���W�x�t�i���Y��ԁA2015�N11��30���j�̕\���k�����F�Ҏҁl�i���j�Ɠ����̌��G�i�E�j
 �@
�@
�ˋ�̏��A���ш�Y�ҁs���̍��̃A���X�\�\�g�����ɂ��w�A���X���W�x�t�i���Y��ԁA2015�N11��30���j�̖ڎ��i���j�Ɠ����́q���o�Ə����ꗗ�r�i�E�j
�k2020�N9��30���NjL�l
����]�_�Ƃ̉i�R�O�̓o���`���X��_�����q���B�Ə���̗����̒��Łr�ŁA�u���x���ێ����邽�߂̎Љ�I�}�`�Y���v���K�v�Ƃ��Ă������������^�u�[�Ƃ���u�h�g��v�́A�u�ʐ^�p�ƈ���p�̐i���ɂ���ʐ��Y��ʏ���̍r�g�ɐZ�H����A���ɂ͌���B�^���̈��Z��N���甪��N�ɂ����Ă̌���̌o�܂���{�𒆐S�Ɏ��n���Ă݂悤�B�v�Ƃ��āA�@�`�C�̎����ݒ肷��i�u�h�g��̌���v�̐߁j�B
�@�@��㎵�Z�N�O��\�\�����k�[�h���n��
�@�A���Z�N��O���\�\�A���X�u�[��
�@�B���Z�N��㔼�\�\�����k�[�h�̑��B
�@�C���Z�N��\�\�����[�^�u�[������
�g�����̃A���X���́A���̇A������w�i�ɂ��Ēa�������B�i�R�͇A�������ڏq����B
�@�w�ʍ����㎍�蒟��@���C�X�L�������x�i�v���ЁA��㎵��j�A�����N��ҁw�A���X�̊G�{�x�i�q�_�Џo�ŁA��㎵�O�j�����肩��B�f�B���b�^���g�I�Ȓm���w���d�|�����A���X�u�[�����n�܂�B�e�j�G���̑}�G�ƂƂ��ɂ���܂ňꕔ�ɂ����m���Ă��Ȃ��������C�X�E�L�������B�e�̗l�X�ȉ������������̎ʐ^���Љ�ꂽ�B����ɃC���X�p�C�A����đ听�������߂��̂���n��B�e�́w�����A���X�x�i�͏o���[�V�ЁA��㎵�O�j�ł���B��n�́w�s�v�c�̍��̃A���X�x�̃C���[�W�����p���A���̃��f���i�T�}���T�j�ɗl�X�ȃR�X�`���[�����܂Ƃ킹�A���z�I�Ȑ}����W�J���Č������B���ꂪ�A���̌�̏����ʐ^�u�[���̔��Γ_�ƂȂ�B���p�̐��E�ł͋��q���`�̔ʼn�W�w�A���X�̖��x�i�p�쏑�X�A��㎵���j�Ɠ��W�i���t�H������L�����X�A��㎵���j�A��W�w�A���X�̉�L�x�i���p�o�ŎЁA��㎵��j�A�W�u�A���X�̃N���X�}�X�v�i�a�J�����f�p�[�g�j�A�o���G�s�A���X�̖��t�i���h���t�H�[���~���[�W�A���A��㔪��A��������A��㔪��j�ւƑ����A���݂��������l�C��ۂ��Ă���B�i�s�����C�J�t2014�N4�����k���W���o���e���X�\�\20���I�Ō�̉�Ɓl�A��O�O�`��O�܃y�[�W�j
�茘�������}�ł����āA�g�����͑�n��̎ʐ^�W�ɂ����ւ���Ă��Ȃ����A���q���`�̔ʼn�W�s�A���X�̖��t�i�̓��e���{�j�A��W�s�A���X�̉�L�t�܂ł̂��ׂĂɁA�A���X����݂̎��т��Ă���B���Ȃ킿�A�q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�q�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�Ɓq�����`���r�j�A�q�w�A���X�x���r�A�q���̃A�X�e���X�N�r�k���o�l�A�q���̃A�X�e���X�N�r�k�Ę^�l�ł���B��n��́s�����A���X�t�ɂ��ẮA�C�M���X�̃f�U�C���W�cHipgnosis�ɐG�ꂽ�q�ҏW��L 157�r�i2015�N11��30���X�V���j���Q�Ƃ��ꂽ���B
�k2021�N8��31���NjL�l
���C�X�E�L�������̃A���X�́A�����ɓY����ꂽ�W�����E�e�j�G���̑}�G�ȗ��A���܂��܂Ƀ��B�W���A��������Ă����B�ߔN�ł́A�q�A���X���z�r�W�i��ꁁ�X�p���A�[�g�M�������[�A�����c2007�k�摜��������ƓW����̍��m�n�K�L���q�b�g����̂����A������L����Ă��Ȃ��I�l�j���J����A�}�^�Ƃ��ās�L�������l���w �܂��� �A���X���߂��錶�z�t�i�����і{�H�[�A2007�N11��26���j�����s���ꂽ�B���܂łɃA���X���e�[�}�ɂ��Ă������`��Ƃ����̂ق��A���߂đn�삵���i�Ǝv����j��Ƃ������B���q���`�i��i�́q�����ɕ������A���X�r2007�j���n��i��i�́q�w�����A���X�A1973�N�x���#13�v�j�ɂ͂��łɃA���X���߂����i�W���������A�l�J�V�����i��i�́q�|�[�g���[�g�r2007�j�͏��߂ăA���X��`�����̂ł͂Ȃ����낤���B�۔����L��R�{�^�J�g�̕`�����낵���A���݂ɃA���X�𗿗����Ă��āA�����[���B�ȉ��ɁA26�l�̏o�W��Ƃ̎������f����i�\�����j�B
����q�^��c���q�^�F�숟��ǁ^��F���[�R�^���{�݂�^���q���`�^�k�����^�K���O���^�����q�^��n��^��V�i�C�t�^�������j�^���ΏC�u�^�J��W��^�y��T�^�g�����@�[�E�u���E���^�i�C�W�F���E�n���X�^�����G�^���R��q�^�q���^�T�g�~�^�۔����L�^�X���T��^�R�{�^�J�g�^�g�c���F�^�l�J�V�����^�a�c��
�{���̊e��i�͂`�S���̃|�[�g�t�H���I�̕ЖʂɈ������Ă��邽�߁A���ꂼ��z�����ď��邱�Ƃ��\���B�Ȃ��A�L�����[�^�[�͉F�숟��ǁA����͒J�숭�A���͎푺�i���i��f�s�A���X�̊G�{�t�Ő}�ŊďC�������푺�G�O�̎q���j�ŁA�O�l�͉�����q�ɕ��͂��Ă���B
�g�����̒P�s���W�̑����œ����I�Ȓn�ʂ��߂�̂́A�t�����X���i�t�����X�\���j�i*1�j�ł���B�t�����X���ɋ߂��A���Ȃ킿���S�ȃt�����X���ł͂Ȃ����̂��܂߂�A
�@�@�����G�߁i1940�j
�@�A�t铁i1941�j
�@�B���i1955�j
�@�D�a���`�i1962�j
�@�E�Â��ȉƁi1968�j
�@�F�_��I�Ȏ���̎��i1974�j
�@�I�|�[���E�N���[�̐H��i1980�j
�ƁA12����7���ɋy�ԁB�g���̒P�s�{�͊�{�I�ɒ��Ҏ��������A��L�̂����F�͓��쐬��́A�I�͘��߂̑����ƍl������B�܂��@�̓t�����X�����ǂ��A�A�͏o�����̋g���ɑ����ėF�l���������Ă����s��������A�����I�ɋg���̎�ɂȂ�t�����X���͇B�D�E��3���ƂȂ�B�g�������g�̑����Ɋ֘A���ăt�����X���Ɍ��y�����̂́A�y���F���s�a�߂镑�P�t�i1983�j�ɂ��Ă����ł���A�Ώۂ��u�t�����X���̏����v�Ɋg���Ă��A����2�тɉ߂��Ȃ��B
�@�i1�j�q�s���́t�̍D���ȉ́r�F���̖����s�̕��͂́s�V���j�S�̏W�t���e���{�i��a���[�A1977�N10���j�ɔ��\����A�̂��A���̐��E���̈��p�̌`�Łq�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�\�\���o�́s�Z�̖̂{�k��ꊪ�l�Z�̂̊ӏ܁t�i�}�����[�A1979�N10��20���j�A��e�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i���A1988�A��l��`��܋�y�[�W�j�\�\�́q�S�@�֓��j�r�ɍĘ^���ꂽ�B
�@�i2�j�q�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�́q�R�@�O�썲���Y�r�\�\���o����ђ�e�Ƃ��ɓ��O
�i1�j�̖`���k�\�L�́q�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�́q�S�@�֓��j�r�ɏƂ炵�Đ������l�\�\
�@����肠�E�������ĂƂ�����ȏo�ŎЂ��犧�s���ꂽ�q�V����肠�p���r�̈������ɁA�����̕��w�N�̑����͐S��点�����̂ł������B�������̉��t�����X�Ƃ��̌y���{�ɖ�����ꂽ���̂ł���B��\���قǏo�������ŁA���͈ɓ�����Y�̒��я����s�Ԃ̉��t�A�Ñ��M�v�́s�ˉB�̊G�{�t�����ƂɈ��ǂ����L��������B�����Ăق��ɂ͑O�썲���Y�́s����Ȃ�t�ł���A�֓��j�́s���́t�ł������B�̏W�͂��̓�������o�Ă��Ȃ������悤�Ɏv���B
�@���A���������s����Ȃ�t�͌Ö{���ŒT�����߂āA�ēǂ��Đt����̒Z�̓��ۂ̐S��Ǒ̌������B�������s���́t�ɂ͉i���߂��舧�����ɂ������A�l�A�ܔN�O�̂��ƁA�Ȃ̎��ƂŌ����ĖႢ���B
�@���ł͏��a�\�ܔN������\�����s�ł��邪�A���̎����Ă���̂͏\�Z�N�\�����s�̍ĔŖ{�ł���B���̉Ԃ��m��ʂ���ւ̂����ȉ��Ԃ��͂��܂��Ă���̂��A�܂����ꂵ���B���A�O�S���\�O���ʓǂ��āA�����Ɏ��̍D���ȉ̓�\�Z����f����B
�i2�j�̑S���k���p�͍̂Ō�̈����c���đ��͏ȗ������l�\�\
�@���a�\�l�N�ɁA����肠�m�A�A�A�A�n�E�������ām�A�A�A�A�n�Ƃ������o�ŎЂ��犧�s���ꂽ�A�O�썲���Y�̎��I�̏W�s����Ȃ�t�ꊪ���A���͓ǂ�ł����B�`���I�ȒZ�̂�o��ɂ�������Ȃ��Ȃ��āA���͑O�q�h�̐Ό����̎w������q�V�Z�́r�����w�ǂ��A�܂�����ł͓��쑐��̎�ɂ���q���́r���āA�V�����Z�̂�o��̏K������݂Ă����B�����ŕK�R�I�ɁA�O�썲���Y�̍�i�Ɏ䂩��Ă������̂ł���B
�@�k3����p�l
�@������̒Z�̂ɂ��A�t�̓����Ȑ��_�Ƃ������ׂ��F��A���s�A�s�����I�悳��Ă���B���̉̏W�́A�s�A���Ձt�A�s���P�t�A�s��a�t�̎O�̏W����ܕS�o���ꂽ���̂ł���B���͈ȏ�̎O�̏W���������Ƃ��Ȃ���A�T�����߂����Ȃ������B���t�����X���{�s����Ȃ�t���������A����Ŗ������Ă����B��O����̂��̂͂ڂ�ڂ�ɂȂ����̂ŁA�����������̂��������Ă���B
�@�k2����p�l
�@�T�䏟��Y�̕��͂ɂ��Ɓu�O�쎁�͑�a�̋��Ƃɐ��ꂽ�l�ł���B���̐N����ɁA�`���I�Ȃ��̂ւ̒�R�Ƃ��ӂ��A��̂̏�ł������̉̕�����̌������E�o��������݂����Ƃ́A�w�A���Ձx�w���P�x�Ȃǂɂ����炩�ł���B�������O�\�ꕶ���Ƃ��Ӎł��`���I�Ȍ`����I�B����͈��̎��ȑ����ƌ����Ă悢�B�v�Ƃ������B
�@�k2����p�l
�@�����Y�̒Z�̂ɂ͂�����ł��A�ߑ�l�̗J�D�\�\�����Ă݂�A�ǓƂȍ��̙������o�����Ƃ��o����B�����Đ��F�I��i�����߂�A�����Y�́s���ɖi����t�̎��тƂ������ƂɂȂ낤���B�ĂыT�䏟��Y�̌��t�������u�O���Ɍ����Ĕ��U���ׂ����̂���ɕ����߁A���U�����Ȃ���A���U�̋ɓ_�ɂ����Ĕ����Ƃ��Ӑ����̂��������a�̒n�Ō`�����čs�����₤�Ɏv�͂��B�v�\�\�ƁB
�@���̂����Ƃ����u��������A�Ō�Ɍf���Ēu���B
�@�@��ӕ��ɔ��ނ�̔��炫�o���킪���܂��Ђ̒ʂ�݂�����
���͋ߔN�܂ł���2���̌��{���������Ƃ��Ȃ������B�悤�₭���肵��2���͂܂������t�����X���i*2�j�ŁA����炪�g���̎��������{�ɉe����^�������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�Ƃ�킯�A���t���̑O�썲���Y�̏W�s����Ȃ�k�V����肠�p���l�t�i����肠�E�������āA1939�N9��28���j���g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�̑����̎�{�̂ЂƂɂȂ������Ƃ́A�^���]�n���Ȃ��B
 �@
�@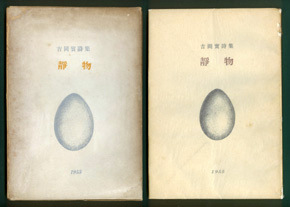
�O�썲���Y�̏W�s����Ȃ�k�V����肠�p���l�t�i����肠�E�������āA1939�N9��28���j�̔��ƕ\���k�����F�����u���l�i���j�Ƌg�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�̔��ƕ\���k�����F�g�����l�i�E�j
�q�g�������W��{�Ŗʁr�Œ��ׂ��s�Õ��t�ƁA�O�썲���Y�́s����Ȃ�t�̊T�v���f����B�Ȃ������͓������l�ł��邱�Ƃ������B
�s�Õ��t���V�n���@188mm ����10.5�|�C���g 30���l�� �ŖʓV�n111mm �V�̃A�L49mm �n�̃A�L28mm ���E���@131mm 11�s�g �s��10.5�|�C���g �Ŗʍ��E77mm �������@34mm �m�h���@20mm
�s����Ȃ�t���V�n���@188mm ����10�|�C���g 25���l�� �ŖʓV�n88mm �V�̃A�L32mm �n�̃A�L63mm ���E���@128mm 4��k11�s�g�l �s��10�|�C���g �Ŗʍ��E80mm �������@34mm �m�h���@17mm

�g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�̔��ɓ��ꂽ�O�썲���Y�̏W�s����Ȃ�k�V����肠�p���l�t�i����肠�E�������āA1939�N9��28���j�̖{�́A�s����Ȃ�t�̔��ɓ��ꂽ�s�Õ��t�̖{��
���^�i�l�Z���j�̓V�n�����S�ɓ������@�ł��邱�Ƃ́A���Ɩ{�̂����ւ�����Ƃ������ƂŁA���܂��ܑ����ߎ����Ă��邽�߁A���҂����ւ��邱�Ƃ��ł����i�ʐ^�Q�Ɓj�B����Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA�s�Õ��t�̃t�����X�\���́s����Ȃ�t�̂�������̂܂܂Ȃ����Ă���ƂƂ��邩������Ȃ����A����͈Ⴄ�B�{�̂��O���猩�������ł͂킩��Ȃ����A�\���������Č��Ԃ����O���Ă݂�ƁA�m�h���̕\���̐�����s����Ȃ�t�͂܂������̎ΐ������A�s�Õ��t�̓J�[����`���Ęp�Ȃ��Ă���̂��B�Ȃ�قǁA��������Ίp���s�p�ӂɐ܂�܂��邱�Ƃ��������B���̘p�Ȃ�������́s�Õ��t�ȊO�Ō������Ƃ��Ȃ�����A�g���������͐��{�S���҂̑n�ӂ�������Ȃ��i�������A�g�����g�͂��̕������̂��̃t�����X�\���ł͍̗p���Ă��Ȃ��j�B
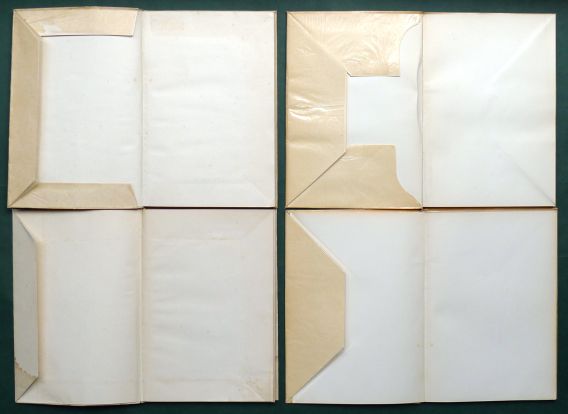
�t�����X�\���̃m�h�����Ő����O�썲���Y�̏W�s����Ȃ�k�V����肠�p���l�t�i����肠�E�������āA1939�N9��28���j�i����2���j�ƋȐ��Ő����g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�i�E��2���j
���������i�͌��Ԃ��̌����������t�����X�\������O���ĕ\���̎d�グ���킩��悤�ɂ�����ԁA���i�͕\���ɋ��{���̏�ԁi�����́s����Ȃ�t�̕\���́A�������ꂽ���ߌ����ɂ������O���V��������������Ă���j�B
�O�썲���Y�̏W�s����Ȃ�t�̎d�l���ڏq����B�u�@�v�͌��{����̈��p�B�^�͉��s��\���B
���\�\
�{�[�����̋@�B���ɘa������ӓ\��i�X�~1�F����j�B
�\�P���p�����E�����E���Җ��A�����ɐA���̃��`�[�t�Ɓu����肠�������āv��M���������J�b�g
�w�������E���Җ�
�\�S���u�킪���̒Z�̂{������^���́A�v�Ǝn�܂�25���l�߁~10�s�̐��E���A�Ɩ�̂悤�ȃ}�[�N�i�s�Ԃ̉��t�ɂ������}�[�N����j�A���s�����E�艿
�\���\�\
�l��������ɐ܂荞�t�����X�\���B�S�ʂɃO���V�����������i�V�n�̒[3mm�قǂ��Еt���j�A�V�E�n�E�O������30mm�̕��Ő܂�Ԃ��Ă���B
�\�P���E���獶�ɉ��g�Łu���Y������O�^��Ȃꂭ�^�W�́v�A�A�������`�[�t�ɂ����J�b�g�Ə���r���X�~�ƐԂ�2�F����B
�w���u�̏W�@����Ȃ�@�O�썲���Y���@�k�\���̐A���Ɠ����J�b�g�l�@�V����肠�p���v�i�����̓X�~����A�J�b�g��2�F����j
�\�S�����̕\�S�Ɠ����}�[�N�i�X�~����j
���Ԃ��\�\
�\���Ɠ����n���́A�җʂ̂��y�����n�̗p���i�O��Ƃ���܂�4�y�[�W�j���A�\���ɐڂ���������ɑ���������̒����t�����X�\���̐܂�Ԃ��ɋ��ށB����A�V�ю��̕��̒��͑O���Ԃ��͖{���ɁA�㌩�Ԃ��͖{�̂̍Ō�̐ܒ��̃m�h�ɂ��ꂼ��Еt���B
�{���\�\
�ʒ��ŃX�~�Ɛ��F��2�F����B�ォ�珇��
�E�E���獶�ɉ������Łu���p����낮�V�v�Ǝ菑�����ď���r�͂݁i���F�j
�E�c�g�Łu�O�썲���Y���^�̏W�@����Ȃ�v��2�s�ɂ킽���ăX�~����
�E�E���獶�ɉ��g�Łu�����^���Ă������E����낮�v�i���F�j
�ȉ��͖{���p���ŁA�O�t�i6�y�[�W�j�E�{���i150�y�[�W�j�E��t�i8�y�[�W�j�̌v164�y�[�W�i8�y�[�W�~20��k���w��l�{4�y�[�W�~1��k�\�荞�݁l�j�B�i�O�t�E�{���E��t�́k�@�l�̐����͉B���m���u���j
�O�t�\�\
�@�k1�l�@�@�i���j
�@�k2�l�@�@�u����Ȃ�ڎ��v
�@�k3�l�@�@���O
�@�k4�l�@�@���O
�@�k5�l�@�@���O
�@�k6�l�@�@�i���j
�{���\�\
�@�k1�l�@�@����u�̏W�@����Ȃ�v
�@�k2�l�@�@�i���j
�@�k3�l�@�@�u�A���Ղ��@���吳�\�ܔN�^�����a�O�N�v
�@�k4�l�@�@�i���j
�@5�@�@�u�铹�̔G��v3��
�@�k�c�c�l
�@45�@�@�u㵖��v2��
�@�k46�l�@�@�i���j
�@�k47�l�@�@�u���P���@�����a�Z�N�^�����a�\�N�v
�@�k48�l�@�@�i���j
�@49�@�@�u���݁v3��
�@�k�c�c�l
�@94�@�@�u�_�_�v4��
�@�k95�l�@�@�u��a���@�����a�\��N�^�����a�\�l�N�v
�@�k96�l�@�@�i���j
�@97�@�@�u�C���v3��
�@�k�c�c�l
�@150�@�@�u�؍g�v3��@�u����Ȃ�@�I�v
��t�\�\
�@151�@�@�u��L�v
�@152�@�@���O
�@�k153�l�@�@���t�A�u����肠�������āv�̕������f�U�C�������Ď�����͂�������\�荞��
�@�k154�l�@�@���t���L���s�Ԃ̉��t�k�V����肠�p���i1�j�̈����l
�@�k155�l�@�@���t���L���s�ڔ��t�t�k�V����肠�p���i2�j�̈����l
�@�k156�l�@�@���t���L���s����̔o��t�k�V����肠�p���i3�j�̈����l
�@�k157�l�@�@���t���L���s�����e���͉��̎����t�k�V����肠�p���i5�j�̈����l
�@�k158�l�@�@�i���j
�s����Ȃ�t���s���́t���A�{�̂ɂ́k�V����肠�p���l�̔ԍ����L����Ă��Ȃ����A�s���́t�̉��t���L���ɂ́A��̒��L�̂悤�Ɋ��s���Ǝv�����ԍ����U���Ă��āA�s����Ȃ�t�͐V����肠�p���i4�j�̈����ł���B
�s����Ȃ�t�̓��e�Œ��ڂ��ׂ��́A�܂�
�@�k3�l�@�@�u�A���Ղ��@���吳�\�ܔN�^�����a�O�N�v
�@�k47�l�@�@�u���P���@�����a�Z�N�^�����a�\�N�v
�@�k95�l�@�@�u��a���@�����a�\��N�^�����a�\�l�N�v
�̂悤�ɑS�̂�3���ɕ����ĒZ�̂������E�����̉̏W���珴�^���Ă���_���B�s�Õ��t��17�̎��т��琬�邪�A���̑O���́q�T�@�Õ��r�i10�сj�A�㔼�́q�U�@�]�́r�i7�сj�ł���B����2���\���Ɂs����Ȃ�t�͂Ȃ�炩�̉e����^�����̂ł͂Ȃ����B�����ЂƂ�
�@150�@�@�u�؍g�v3��@�u����Ȃ�@�I�v
�́u����Ȃ�@�I�v�ŁA�s�Õ��t�͉��t�̑Ό��y�[�W�Ɂu���W�@�L�v�Ƃ���B�����Ƃ��s�t铁t�i1941�j�̉��t�Ό��y�[�W�ɂ��łɁu���W�@�t铁@�L�v�Ƃ��邪�A����Ƃās����Ȃ�t�ɕ�������̂łȂ��Ƃ͌����Ȃ��B�Ȃ��A�s����Ȃ�t�s�Õ��t�Ƃ��m���u���̈ʒu�͒n�̍��E�����ł���B�ȏ�̂悤�ɗގ�����_������A�قȂ�_������B�s�Õ��t���@���ɑ��ӓ\������Ă��Ȃ����ƁB�A�q��L�r�������Ă��Ȃ����ƁB�B����\���Ă��Ȃ����ƁB�C���t���L�����ڂ��Ă��Ȃ����ƁB�D�Ō��̃}�[�N���ڂ��Ă��Ȃ����ƁB�傫���A�ȏ��5�_���قȂ�B�C�ƇD�͎��Ɣł�����Ȃ��̂����R�ŁA�@�ƇB�͓\�荞�݂���������ʂ��B���͇A�����A�P�s���W�ɂ͎��M�̂��Ƃ��������^���Ȃ��Ƃ����g���̕��j�����������܂��Ă����ƍl�������B������ɂ��Ă��s�Õ��t�̑��{�E�������l����ɍۂ��āA�g�����s����Ȃ�t���Q�Ƃ������Ƃ͊m�����Ǝv����B��̂ɐV�����{������������Ƃ͂����ւ�ȘJ�͂�v����i�s�Õ��t�͑S�я������낵�j�B���{�E�����������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɣłł͂Ȃ����炾�B���̂Ƃ��A�i�N���ǂ����{�̌`������A������Ȃ��낤�Ƃ���s�ׂ́A�P�ɘJ�͂̌y����ړI�Ƃ��邾���ł͂Ȃ��B�����ɃI�}�[�W���̈ӂ����߂��Ă���A�ƌ���ׂ��ł���B�J�肩�����ǂ܂ꂽ�������A�ڂ�ڂ�ɂȂ�悤�Ȗ{�����邱�Ɓ\�\���ꂪ�����̎��W�Ƀt�����X�����̗p���Â����g�����̊܈ӂ������悤�Ɏv����B
�t�����X�]�����@�d�T�E�y�\���z�k���l�����{�̈�B���̎l����܂�Ԃ��A�{�[�����ŗ��������Ȃ��\���ŁA���Ԃ��������g������݁A�f�ق���Ă��Ȃ������A�V�n���y�[�p�[�i�C�t�Ő�B�킪���ł͈�ʂɎd�グ�f���������g������ށB�����Ƃ������{���{�ɉ������邱�Ƃ�\�z���čl���o���ꂽ���́B�i�s���{����厫�T���Łk��\�ꊪ�l�t���w�فA2001�N11��20���k��O���F2003�N3��10���l�A��Z�l�l�y�[�W�j
�s�Õ��t������3�N���1958�N8���A�g�����Ԃƍ��̊v���́u�{���{�ɉ����v���������̈�{�́A���g��㆓ǂ��Ă����u�ڂ�ڂ�ɂȂ����v���Җ{�������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�i�q���W�s�Õ��k�v���{�l�t�̔��ƕ\���k���c�唪�������l�r�Q�Ɓj
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i*1�j�t�����X���i�t�����X�\���j�̗��j�I�W�]�́A�M�c���s���m�̏����H�[�\�\���[�b�^�E�X�g�[�����烂���b�R�v�̖{�܂Łk�����I���l�t�i�����V���o�ŁA2014�N2��25���j�́q��Z�́@�t�����X�̊v���{�r�́q��@���Ԗ{�̒a���r�ɏڏq����Ă���B�����ɂ�
�@�t�����X�ł͏����O�܂ŁA���w���𒆐S�Ƃ��āA�����̖{�����Ԃ��Ŕ����Ă����B�k�c�c�l�킪���ł��t�����X���Ə̂��āA�H�Ɏ��W�Ȃǂ����Ԗ{�Ƃ��Ĕ����邱�Ƃ�����B�������A�Ȃ��t�����X�ŏ����⎍�W�����Ԃ��̂܂܂œǎ҂̎茳�ɓn��悤�ɂȂ����̂��A���̗��R�͏\���ɗ�������Ă��Ȃ��悤�ł���B
�@���Ԗ{�Ƃ͐ܒ������ł����ȒP�ɂ������A���̐ܒ��̔w�ɔ���̕\�����j�J���Ōy���Ƃ߂�ꂽ�A�����Ƃ��ăA���J�b�g�̏�Ԃ̖{�������B���Ԗ{�̏ꍇ�́A�A���J�b�g�̐ܒ��̑��𔖎�̕\���ŕ�����ł���B�����̏ꍇ�̕\���͖{�i�I�ȕ\���łȂ��A���\���ƍl�����Ă���B�A���J�b�g�Ƃ����̂́A������ꂽ���t��܂��č��ܒ������ύق�����Ȃ��܂܂ŕ\���̂����{�������A�V��O�����ɑ�ɂȂ����ӏ����ł���B�����Ńy�[�p�[�i�C�t���K�v�ƂȂ�B�ǎ҂͑܂Ƃ��ɂȂ��Ă���y�[�W���y�[�p�[�i�C�t�Ő��ĊJ���A�ǂݐi��ł䂭�B�������A�킪���̉��Ԗ{�ł͐��m�̂��̂ƈقȂ�A������ł̃y�[�W�̑g�t�����t�����Ȃ��߁A������ꂽ���t�����y�[�W���Z�y�[�W�̐ܒ��ƂȂ����ꍇ�A�n�ƑO�����ɑ�ɂȂ����ӏ����ł���B����ł̓y�[�p�[�i�C�t�������Ԃ�g���ɂ����B�y�[�p�[�i�C�t�������Ɍ����āA���n����悤�Ƀi�C�t�����A�ܒԂ��ɂȂ��Ă���y�[�W���J���邱�ƂɂȂ�B�킪���ŋH�ɏo�ł����t�����X���ł͂��̂��Ƃɔz�����āA�͕킷��Ȃ����̒i�K����܂˂�ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ԗ{�Ƃ͂܂��A�o�Ō����{�i�I�Ȑ��{�������A���̖{���w�������l�������̍D�ޏ����Ɏd�グ�邱�Ƃ̂ł���{�Ƃ�����B�k�c�c�l���������オ�i�ނɂ�āA���Ԃ��ɂ��o�ŕ��́A�t�����X�ꌗ���̂����A�قƂ�ǎp�������Ă��܂����̂ł���B�i�����A����`���O�y�[�W�j
�Ƃ���B�u���Ԗ{�v�Ɩ{�e�ɂ�����킪���́u�t�����X���v�Ƃł́A�O�҂��܂��ɉ��́A�����O�̏�Ԃł���̂ɑ��āA��҂��ŏI�`�ł���_�ŁA����I�ɈقȂ�B���Ԗ{�ɔ����t�����ƂȂǁA���肦�Ȃ����낤�B
�i*2�j���{�ɂ�����t�����X���̗��j�́A��ѐL���s���{�T���t�i����w��o�ŕ��A2005�N9��20���j�́q�t�����X���̗��j�r�i�����A����`��y�[�W�j�ɏڂ����B���������y���Ă���u�t�����X���v�̏��ڂ͈ȉ��̂Ƃ���i���L�������j�B
�c�ӗ����ҁw���_�ǖ{�x�i��ꏑ�[�A���a�\���N�j
����ߋg�w��㉎����x�i���|������Џo�ŕ��A���a��\��N�j�@�@�����Ԃ��ƕ\�����Еt��
���c�H�߁w�k�}�x�i���R���X�A���a��\��N�j
��������Y�w�O�������m�x�i��M���X�A���a��\��N�j
���F��Y�w��ǁx�i�����ЁA���a��\�l�N�j
�䕚����w�{���x�f�x�i���Y�t�H�ЁA���a��\�ܔN�j�@�@���l���̐܂肪���G�Ŗʔ���
��œ�Y�w�A���x�i�Z���o�ŎЁA���a��\�ܔN�j
��������Y�w�V�����p���V�����t�����X�x�i���Y�t�H�ЁA���a��\���N�j
�O�H���Y�w�O�H���Y��i�W�x�i�p�쏑�X�A���a�O�\��N�j�@�@���c�{�[��������
�J�菁��Y�w�Ӗڕ���x�i�������_�ЁA���a��\��N�����Łj
���x���q�w�����x�i�����_�ЁA���a�\�ܔN�j
���،���w���M�Ə��i�x�i�͏o���[�A���a�\�Z�N�j
�p�c��v�Y�w���A�x�i�������@�A���a��\��N�j
�ѕ����q�w���炵�x�i���ƔV���{�ЁA���a��\�O�N�j
�{�{�S���q�w�����ւ̐��_�x�i���ƔV���{�ЁA���\�ܔN�j
�ܓc�w�w����ς�́x�i��O���@�A���a���N�j
�������E�t�F���i���f�X�A���ؗC��Y��w���ɓq����x�i�ŏ��X�A���a�\��N�j
���C�����E���f�B�Q�A�x����w��w�h���a�F�����̕�����x�i�����ЁA���a�\�l�N�j
�W���E���E���i�A���A�ݓc���m��w�������x�i�����ЁA���a�\�ܔN�j
�H�열�V��w�͓��x�i�א쏑�X�A���a��\��N�j
��������Y�w���w�̏W�x�i�ÐM�ЁA���a�\���N�j
��������w�����܂��n�����x�i���ƔV���{�ЁA���a�\�l�N�j�@�@������
�R���`�Y�w��x�i�����ЁA���a�Z�N�j
�|�I���E���@�����C�w���@���G�e�x�i�����ЁA���a�Z�N�j
�A���h���E�W�C�h�w�V���L���x�i�����ЁA���a�\��N�j
�K�،����w�v���g���u�`�x�i�t�H�ЁA���a�\�O�N�j
�g�c����Y�w�킪���̋L�x�i��ꏑ�[�A���a�\�O�N�j
�|�I���E���@�����C�w���@���G�e�x�i�����ЁA���a�\�N�j
�R�{�L�O�w�s�ɐg���x�i�n���ЁA���a�\�l�N�j
�w���N���p�فx�i��g���X�A���a��\�Z�N�j
�O�D�B���w���W�@���؏W�x�i���ЁA���a��\��N�j
�K���������t�����X���i�O���B�������{�����Ƀt�����X�\���𒅂������́j�A���Ȃ킿�{�e�ł����u�t�����X���v�̖{����ł͂Ȃ����A�t�����X���{���T�ς���̂ɖ𗧂B��������́s�����܂��n�����t�i���ƔV���{�ЁA1939�j�Ɂu������v�ƒ��L������Ƃ��������ƁA�t�����X���͊�{�I�ɔ����Ȃ����́A�ƍl������B
�g�����̎��M�N���ɂ́A�w�i��m��Ȃ��Ɨ����ł��Ȃ����m������n������B���Ƃ��u���s�������v������ł���B�u���a�\�ܔN�@���
���Z�N
�Z�\��^�k�c�c�l���H�A�r�܂̖��s���ŁA�퐶�y����B�X��E�����S���i���j�Ɨ��j�A���w�̘b������B�X���E���엳�����E�B���i�[�R�[�q�[�������
�����i�̂��A���s�������N����j�v�i�q�N���r�A�s����̎��l�P�@�g�����t�������_�ЁA1984�A��O�܃y�[�W�j�B���s���́u�Ô��p
��ᶑ��v�B�u���s�������v�Ƃ́A�������m�₷���n���s���s���ɂȂ�A���열�����E�l�e�^�őߕߋN�i����A�L�߂ƂȂ��������ł���B���͍����ɈÂ��A
�u���s�������v�������ꂽ1982�N�͉�Ј��ɂȂ��ĂقǂȂ��A�d�����o����̂�����t�łs�u���T�������낭�Ɍ��Ȃ���������A�����̋L���͂܂�������
���B���������āA�g���̎��M�N���ŏ��߂āu���s�������v�ɐڂ����B����1982�N�́A�Ô��p�⍜���ɊS������Α傢�Ɏ��ڂ������Ă��ɈႢ�Ȃ��厖��
�\�\�u�O�z�̋U����v���N�����N�������BWikipedia�́u�O�z�����v�ɂ́u���N8��29���A�������{���{�X�ŊJ�Â��ꂽ�u�Ñ�y���V�A���W�v
�̏o�W���̑唼�����ł��鎖�������V���̕ɂ�蔻���B�ꕔ�͊��ɉ��P�ʂ̒l�����Ă����Ƃ����[2]�v�Ƃ���B����[2]�̏o�T���s����V���t�ŁA���́u�����̂��끄�O�z�̋U����^���c�В���C�ɔ�
�W�v�ɂ͂�������B
�P�X�W�Q�i���a�T�V�j�N�W���Q�S���A�u�Ñ�y���V�A���W�v�������E���{���̎O�z�{�X�ŊJ�Â��ꂽ���A�W���i�S�V�_ �̑唼���U���ƊԂ��Ȃ����������B�Q���~�̔��l���t�����i���������B�f�p�[�g�ƊE�̘V�܂����ɑ傫�Ȗ��ƂȂ�A���c�ΎВ��̉�C�ւƔ��W�����B
���M�N���Ɂu�O�z�����v�̋L�ڂ͂Ȃ����A�g���͓��{���̎O�z�{�X�ł́s�Ñ�y���V�A���W�t���ςĂ��邩������Ȃ��i�O�f�N���̒��O��
�́u�O�z�{�X
�ŁA�NJ��W���ς�B�V��啗�v�ƋL����Ă���j�B����Ƃ����̂��A�u���s�������v�����ɂ����{�ɍ����F�V�s���̎r�\�\���s���E�l�����̓��ǂ��t�i����
���[�A1985�N4��15���A�����F����b��j�������āA�㌩�Ԃ��Ɍf�ڂ���Ă���u���`������i�䕨�j�v�i���j��
�p�`���A�����ɂ��g���D�݂Ȃ̂��B
 �@
�@
�u���`������i�䕨�j�v�k�o�T�F�����F�V�s���̎r�\�\���s���E�l�����̓��ǂ��t�i������
�[�A1985�N4��15���A�㌩�Ԃ��j�l�i���j�Ƌg�����s�ٗ�Ձk�����Łl�t�i����R�c�A1974�N7��1���A�����F�g�����j�̕\���i�E�j
�i���j
�{���ɂ́u�O�z�̔��W�Ɂu���`������v�i�����Ԃ���
�ʐ^�Q�Ɓj�Ɩ��t����ꂽ�����W������Ă����B��C�̉��������r��܂�Ȃ��č����Ă���B�J�^���O�̐����ł́A�������E�܃Z���`�A���\��E���Z���`�B�I
���O�Z���I�̍�ŁA�샍�V�A�̃X�L�^�C�n���ŏo�y�������̂Ƃ���A�l�S�\���~�̒l�������Ă����B�u���`������v�̃��f���́A�G���~�^�[�W�����p�ق�
����v�i�s���̎r�t�A��Z�Z�y�[�W�j�ƌ�����B
�u���s���E�l�����v�̊T�v�Ƃ��������A�����̃W���P�b�g���̕��Ō��悤�B�u��㔪��N�����A�������{���O�z�f�p�[�g�{�X�ŊJ�Â��ꂽ
�u��y���V
�A���W�v�̓W���i�͂��ׂĊ䕨�Ɣ����B�}�X�R�~�̘b�肪��������Ȃ��A���j�Z��̃��[�g�Ɋւ��ƌ���ꂽ�Ô��p�X�u���s���v�̓X��E�������́A
���łɔ��N�O�A���H���Ă��邱�Ƃ������炩�ɂ��ꂽ�B�{�����ǂ́A�X���̍��열�����E�Q�̗e�^�ŋN�i�������A�@��ɗ���������͖���������ł���B��
���̎��̂͂��܂��ɔ������ꂸ�A���̏�A�E���ꂽ�͂��̒����ɉ�����Ƃ����҂������œo�ꂵ���B�u���̂Ȃ��E�l�v�u�����Ă��鎀�l�v�Ǝ����̓�͂����
�������\�\�B�v
���̃W���P�b�g�̑��ɂ́A�{���ɂȂ��N�\���f�����Ă��Ă��肪�����B��������Ă������B
��1982�i��57�j�N
2�����@�u���s���v�X��E�������A�s���s���B
4��1���@���X�X���E���열���A�r���Ɏ��H�͂��o�B
8��24���@�������{���O�z�f�p�[�g�{�X�ɂ����āu�Ñ�y���V�A���W�v�J�ÁB
8��29���@�W�����͇��j�Z���m���Ɣ����B
9�����{�@�u���s���v�ƃj�Z���Ƃ̊ւ���艻�B
9��25���@�{�����ǁA�����E�Q���\�B
12��4���@���열���A���̗e�^�ŕʌ��ߕ߂���B
12��8���@����A�����u�E�Q�v�Ɓu���̈���v�������B
12��12���@���ǂɂ�苞�l�^�͂̎��̑{�����s�Ȃ�ꂽ���A���̔����ł����B
��1983�i��58�j�N
2��7���@�E�l�E���̈���e�^�ŁA������đߕ߁B
2��28���@�E�l�߂ŋN�i����B
4��1���@��������B
��1984�i��59�j�N
12��17���@���@���A����15�N�����Y�B
��1985�i��60�j�N
3��13���@�������L�߁i����13�N�j�B
�g�����O�f�N����E�e�����̂�1983�N�̏H�ƍl�����邩��A���łɍ��삪�E�l�߂ŋN�i����A����������J���ꂽ�ゾ�B���������w
�i���i���ڂ�
���ɂł͂����Ă��j�������Ȃ��ƁA�u�r�܂̖��s���ŁA�퐶�y����B�X��E�����S���i���j�Ɨ��j�A���w�̘b������B�X���E���엳�����E�B���i�[�R�[
�q�[������Ă����v�Ə�����������Ȃ������g�����̐S���͗ʂ肪�����B����́A���ċg�����g���������܂ꂽ�g�������i�q�u�g�������v�Ɩk�쑽��q���W�s���t�̂��Ɓr�Q
�Ɓj�ƕ���ŁA�g�߂ŋN�������ɂ�����ł�����Ȏ����������i���ɂ�����A�ƌ��肷��̂́A�g�����]�R�����哌���푈�������̍ő�̂��̂����������
����j�B�s���̎r�t�ɂ��Β������͑吳15�i1926�j�N�A���q���܂�B�����F�V��
�@���������A�����́u���s���v���n�߂ď\�N����o���Ă����B�������Ƃ��Ă͋삯�o���ɓ������B�Â��͍]�ˁA������ ���ォ�瑱�� �Ă���X�͏��Ȃ��Ȃ��B�J�Ƃ킸���\�N�́u���s���v���Ȏ��W�Ƃ�Ô��p���D�Ƃ��ۛ��ɂ��Ă����B�l�ԍ���̓`���|�\�ƁA���{���w�̈�t�A�₪�Ď����� �ւ�邱�ƂɂȂ铌�����������فi�ƊE�ł͗����āu�����v�ƌĂ�ł���j���p�ے��̏����Δ��B�قƂ�Ǘ��j���Ȃ��X�ɂ��ꂾ���̋q���Ăׂ鍜�����͂܂�� ����B�����͂���ɑ��Ă��ڋ��ɂȂ炸�A�����ɌŎ������A�Γ��ɋc�_�킹���B�Ƃ������A���������p�������ŁA���Ƀ}�V���E�K���̂悤�Ɏ��_���܂� �����Ă��B����͂���ŋq�𖣗������B�Ǐ����悭���A�Ɠ��Ȕ��ӎ��������Ă����B�������g���u���s���v�̊Ŕ������B
�@�u��������ɂ͈��̃J���X�}�����������B���ꂪ�q�𖣂������v
�@�ƁA����Ô��p���͎w�E���Ă���B
�@�g���S���\�Z���`�A�̏d���\�L���̑̋�ɁA���悻�N�߂Ɏ����킵���Ȃ��h��ȈߏցB�V�哪�B��قȐ��B���������g�̓I���J�́A�Ȃ��̂��ƃJ���X�}���� ���߂Ă����B
�@�J�X�����u���s���v�́A��������ӂꂽ�`���I�ȌÔ��p�i�������������������B���N�����m���́n�ɂ͂������̂��������Ƃ����Ă���B�i�����A�ܓ�`�O �y�[�W�j
�ƒ����̎p�����ʂ��Ă���B���Ȃ݂Ɂs���̎r�t�̔��s�l�́A�g�����̌Â�����̒m�F�ł����� �씎�m�����E�Ђ�ށn�����A�g����������ǂ�ł��邩�͔���Ȃ��B
30���N�Ԃ�ɊO�R����Ấs�ٖ{�_�t�i���ł�1978�N11���A�݂������[���j��ǂ݂������Ă�����A����Ȉ�߂ɏo������B
�@�ÓT��i��ǂނƁA�Ƃ���ǂ���ɁA�������X�Ƃ��Ē�܂鏊��m�炸�A�ƌ��������Ȃ��ɑ�������B�l���Ă��� �ƁA����܂ŏo���ꂽ�ǂ���������Ƃ������邵�A�t�ɁA�ǂ���s�����ŁA�ʂ̎����̍l���̕��������悤�ɂ��l������B
�@ �ǂ����āA���������������X�̉ӏ��������̂��B�l���Ă݂�ƁA�����炭�����ɁA����ڂ��ł��Ă��āA�ǎҁA�����҂̇��|�����̗ڂ������� ��������̂��ƍl���邱�Ƃ��ł��������B�ǂޑ��̇��|�͌����̂��ׂĂ̕����ɑ��ĂȂ���Ă��邪�A���ʂ̂Ƃ���ł́A�哯���ق̗����ɂȂ��Č덷�� �\�ʉ������A���݂����܂܂ɂȂ��Ă���B���ꂪ�����̗����ڂɂ�����ƁA�e�l�̇��|�̍����͂����肵���`���Ƃ�悤�ɂȂ�B���ꂪ�������X�� ���̂ł���B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�����͂��ׂĖڂɌ����Ȃ��|��ł��邱�Ƃ��F�߂���悤�ɂȂ�ł��낤�B�i�s�ٖ{�_�k�����ܕ��Ɂl�t�}�����[�A2010�N7�� 10���A���Z�`����y�[�W�j
�e�L�X�g�i�{���j���D���ł���Ȃ�A���̌o���ƈ��͂������ߌ�ƃV���^�b�N�X���낤�B�g�������̃e�L�X�g�́A��̃��x���ł͂Ȃ�Ƃ�
�Ȃ��Ă��A��
�̃V���^�b�N�X����V�ƂȂ肩�˂Ȃ��ꍇ�������B�Ƃ��낪�����ɁA���ǂ̂Ƃ�����Ӗ��̂킩��Ȃ����\�\�O�R���w�E����Ƃ���̇������ɂł��Ă���A��
��ڇ��\�\���ӂ�����B�������ӂ������Ȃ��̂��ƌ�����ƍ��邪�A���̂ЂƂ́u�˂͂�v�ŁA�����ЂƂ́u��v�ł���B�q�킪�n�j�R���X��
�v���o�r�i�F�E16�j�Ɓq�ߔ��r�i�D�E16�j�̎�����A�O��̂���ƂƂ��Ƀ��C�i�[��t���Ĉ����B���̌ꂪ�ǂ�����u�Ƃ��v����݂Ȃ̂́A�P�Ȃ���R��
�낤���B�����[���Í��ł���B
�@48�@�����̔��h��̍���Ƃ�
�@49�@�˂͂�̍j�Ŏ�����Ƃ��܂�
�@50�@���_�痢
�@32�@�����ł킽�������͌���
�@33�@�鍳�̏�������������@��
�@34�@�Ղ�炷�܂̎�̂Ƃ���
�@35�@����V��
�u�˂͂�v�͍�����i�����y���ɒ���L���邱�ƁB�����͂т��邱�Ɓj���낤���A�u�˂͂�̍j�v�ƂȂ�Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�B���ꂽ���̂悤�ɗ��݂����āA�j
�����Ղ�������܂��Ă��邳�܁A�Ƃł����Ă��������B����A�u��v�ɂ������ẮA�����ȁA�Ȃ̂��W���T�C�Ȃ̂������킩��Ȃ��B��i��1�j��t����Ƃ��̃^�[����������Ȃ��ƌ��������āA������
���T�C�g�̌f���ɋ����𐿂��������݂��������Ƃ����������A�͂Ȃ������B�����܂ŏ����Ă��āA��t���V��҂̋{�铹�Y���M�W�s�V��
�t�̊C�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2002�N11��15���j��Ǘ��B���c�S����
�w���������������āA�{��̐��M�͌��q�M�L�ɂ�镽�ՂȌ����܂킵�Ȃ���A�Ƃ��ɋ��낵���܂ł̐ꖡ�������i�q��̓�d�t�r�̋`��̘b��q�����J�[
�l�[�V�����r�̈�����r�����b�j�B
�u�����̏H�Ղ̑��ہm�������n�A�J�m�ӂ��n�A�_�y�m������n��A��_�`�m���݂����n�������Œʂ鐺�Ȃǂ��A���Œ������A�������璮����������̏�
���������Ėʔ����Ǝv���B���͍Ղ̋C���͍D���ł��邵�A�����Ƃ��ẮA�����������Ƃ́A���܂ł�������ʕ����悢�Ǝv���Ă���v�i�q�l�G�̎�r�A�����A
����y�[�W�j�B���̈�߂���́A���́A�����̐����Ȃ̂ɖ��ɕ��߂��������ȏ����q���Ձr���z���o�����B�{��Ɗ���������i�q���Ձr�́u���̒���̐_�l��
�^�����͂߂ł�����Փ��B�^�k�c�c�l�v�͊����̍쎌�ƌ�����j�͐e�������������������łȂ��A�����쎌�E�{���Ȃ̉̋��q���R��
�ד��r�����邭�炢������A���̑z�N�͂܂猡���t��Ƃ����킯
�ł��Ȃ����낤�B
�b�x��B�g����ⵂ̐�发��ǂނ��Ƃ͂���܂��Ɠ���ŁA�{��̐��z�W�ɂ�����������킯�����A�uⵒ܁m���ƂÂ߁n�v�i��O��y�[�W�j��u�ܔ��v�i��
��O�y�[�W�j�Ƃ�����ⵂ̐��p�ꂪ�o�Ă�����̂́A�̐S�́u��v�͓����ɂ͓o�ꂵ�Ȃ������B���̕��ʂ�T���Ă����Ă��b�オ�Ȃ���������Ȃ��B�o���_
�ɖ߂��āA�q�ߔ��r�̕]�߂����݂Ă݂悤�B�����̏��o�͏��惆���C�J�́s�����C�J�t1961�N1�����k6��1���i52���j�l�B����͋g�������������́A
25�N�ȏ�O�̂��ƁB�_�c�_�ے��̓c�����X�̓X���̃E�B���h�E�Ɂq�ߔ��r�̓��M���e�i�����炭�z�q�v�l�̎�ɂȂ���́j������ł����B���̎��Ȃ牽��[��
�Ă������Ă��炤�������A�����A����Ȃ��Ƃ͑z������炸�A���e��\�����郉�x�����K���X�z���ɓǂ�������������A�l�i���킩��Ȃ��B�[����w������
�C���Ȃ������̂��낤�B
�@�ߔ��b�g����
�����݂̉�����
�킽�������̔畆�̃n�A���j�C
�킽�������̎l�p����������
�n�c���獡�ɂ�����܂�
�����݂��mᝐ�
�v�w������
�Ԃ�V������
�������������ΊC�֏o��
�������������
���邷�ׂ�̍g
�Ԃ�V�͗͂����������͘V�l������
�Ύ��̍\�������q�̐��E
�Ȃ݂̑b���銢�̋�
�V�l�͔���
��������
�V�l�͎������炵�ęꂭ
�Ɩ�Ƒ������͉���
���̔�������߂�����
���H�̍��͍��̊�̒�
�V�l�͗͂���������
�X�s�[�h��������
���炩�ȑۂ̏�ł�
�����[�邿����
�҂��҂��̊��`�̌�
�@�I�ł��ꂢ�ɐ���݂₤��
���̔������J�[�������������
���~�̓��ׂ̂�
�������邽�߂�
��������܂��Â�
�D�Ɛ����܂��ׂ��|��҂݂���
����̖�̂悤�ȕ�
�����ł킽�������͌���
�鍳�̏�������������@��
�Ղ�炷�܂̎�̂Ƃ���
����V��
��邽����
�킽�������͉Ƃɓ���
��C�̂ނ��ł��E������
�������̔\�ʂ̓`���̂�����
�������i��2�j��v�w�������A�Ԃ�V
�������A�Ԃ�V�̂����ɘV�l�������A�V�l�̂�����
���������B���ꂪ�q�ߔ��r�̃x�[�V�b�N�ȍ\���ł���B�u�����݂̉�����^�킽�������̔畆�̃n�A���j�C�v�Ƃ����`����2�s����A�g�������Ɠ��̃V���^�b�N
�X�͑S�J�ł���B�z�ɏĂ��A�щH����������u�����݂̉�����v��7�����Ŋ��N���A�������܁u�킽�������v�����F�l��m�����S���C�h�n�Ƃ��Ă̓��{�l�̔���
��̐e�a����錾����B�mᝂ̓q�[���_�j�̊ɂ��畆�����ǂŁA�ӂ������Ċ������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������A�Âт���̂����ق��݂��Ƃɑ�������
��B�u�\������v�u�b����v���g����Ƃ����Ă������낤�B�u�Ύ��̍\�������q�̐��E�^�Ȃ݂̑b���銢�̋�v�͊֓���k�Ђ��ق̂߂����Ă��邩�B��
�̂�����A�q�ߔ��r�����߂����W�̕W���q�a���`�r���v�킹����̂�����B�u�Ɩ�Ƒ������͉����v�́u�n�c���獡�ɂ�����܂Łv�̉ƌn��ۂ��ƂƂƌ���
�̑单�����x���邱�Ƃ̍����\���Ă���B���̂������낤���A�u���̔�������߂������^���H�̍��͍��̊�̒��v�Ƃ����̌��i��O�ɂ��āA�u�V
�l�͗͂����������v�B�����́u�����݂��mᝐ��v�ł͂Ȃ��A�u���炩�ȑۂ̏�v���Ƃ����̂ɁB�l���v���o�Ă��Ă��A�O�Ƀq�[���_�j�������̂�����A����
�����͋����Ȃ��B�u��������܂��Â��^�D�Ɛ����܂��ׂ��|��҂݂��^����̖�̂悤�ȕǁv�Ƃ��邪�A��O�̎��傩��͂̂��́q�킪�n�j�R���X
�̎v���o�r�́u�˂͂�̍j�Ŏ�����Ƃ��܂Łv��z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�������疾�炩�Ȃ悤�ɁA�Ȃɂ��̂��Ɏ�����Ƃ��A����̋K�͂���E����
�ł�����ɍR�����Ƃ��錃�����g�U�肪�g�������̓����Ƃ��ċ�������B�����Ɂu�鍳�̏������v�Ƃ͂����A�u������@�v���Ƃ͐q��ł͂Ȃ��B�u�Ղ��
���v�ɍ��킹��Ȃ�A�����Œ@���a�y��͐��ށm�`�����`�L�i�R���`�L�j�n�łȂ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ݂Ɂu�Ղ�炷�܁v�͋Ւ܁i�����ɂ�ⵒ܁j�Ƃ����A��
���|�łł��Ă���B�O�o�́u���v��u�ׂ��|�v�Ƃ̊֘A�͋��R��������Ȃ����A�݂��Ƃȕ��߂ƌ��邱�Ƃ��ł���B�u��v�́A�����ł͂��߂������B�u��
��V��^��邽���݁v���k�Ёi�g����4�Ŋ֓���k�Ђɑ������Ă���j�̈Î���������Ȃ��B������ɂ��Ă��u��
���������v�́u�Ɓv�́A�Ɨ�̂��Ƃ��S���ɓ�������Ă���B�ł͂����ŁA�g�����q�ߔ��r���ǂ��Ƃ炦�Ă��������Ă݂悤�B
�@�G���q�����C�J�r�ʊ��\�O���̂����A���͌ܕт̎��\���Ă���B����͑����Ƃ͌����Ȃ����A�܂����Ȃ��Ƃ��� ���Ȃ��B��� ���N�̎l�����Ɂu�m���v�A�ܔ��N�������Ɂu�����v�A�܋�N�̏\�����Ɂu�́v�A�Z�Z�N�Z�����Ɂu�g��i���Ɏ~��v�A�����čŌ�͘Z��N�ꌎ���ŁA�u�� ���v���f�ڂ���Ă���B�i�q�u�����v�Ƃ����G�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�Z��`���Z�y�[�W�j
���̕��́i���o�́s�����C�J�t1971�N12�����j�͈ɒB���v��e�W�s�����C�J���t�i1962�j���邢�͓��{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ� �̍Ċ��s���l �����\�\�����C�J���k�G�f�B�^�[�p���l�t�i1971�j���苖�ɒu���ď�����Ă��邩��A�����́q�G���u�����C�J�v�ژ^�r�Ɉ˂������̂Ǝv����B
�g���@ �ł��A���u�����C�J�v�ɁA�ѓ��͉��т��炢���\���Ă�H�@�ӊO�ɏ�����Ȃ��B
�ѓ��@�ĊO�����B�Z�A�� �т���Ȃ����ȁB
�g���@�ڂ����l�сk�} �}�l�����B�ӊO�ɁA�u�����C�J�v�ɔ��\���ĂȂ��Ǝv����B
�ѓ��@�����ˁB�����C �J�A�����C�J���đO�́u�����C�J�v�̂��ƌ����Ă邯�ǂˁA��肠�����\���Ă鐔���������B�ڂ��ȂZ�A���є��\���ĂˁA�܂��܂����ܓǂ߂���Ă͓̂�� ���炢�����Ȃ��B���Ƃ͂Ђǂ�����Ȃ��ǂ��B�i�j�܂��ŗ��O���Ȃ�ɒB�͕���͌���Ȃ��B
�g���@ �������ˁB�������͂��ƂˁB�ŏ����u�m���v�B���̎��͔ѓ����ɒB�ɐ��E���Ă���Ă���ƁA�u�m���v���ڂ����B���ꂩ��u�����v���ڂ�A���Ɓu�� ���́v�Ɓu�ߔ��v�c�c�B������́A�ꐡ�ŗ����������ȁB�i�ѓ��k��Ƃ̑Θb�q���I�t�̌�䊁r�A�s�����C�J�t1975�N12���Վ��������q��i�����W ���㎍�̎��� 1975�r�A���Z�y�[�W�j
�ǂ���ɂ��Ă��A�ɒB���v�̎G���s�����C�J�t�Ɍf�ڂ��ꂽ���Ƃ������Ƃ��ďq�ׂ��Ă��邾���ŁA�]���͉�����Ă��Ȃ��i4�Ő�2���� ��5���A�ƌ� �������̂��낤�j�B�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�͎��W�s�Â��ȉƁt�܂ł̎��т����^�����I���W�����A�����Ɂq�ߔ��r�͎��߂��Ă��Ȃ��i�����̑��� �s�V�I�g�������W�k�V�I���㎍����110�l�t�Ɏ��߂�ꂽ�j�B������q�ߔ��r�ɑ���]���ƌ��Ă悢���̂��A�f�肵�ɂ����B�Ƃ����̂��A���̑I���W�ɂ� �s�m���t�����́q�����r�i�C�E19�j�Ɓs�a���`�t�����́q�V�l��r�i�D�E1�j�������Ď��߂��Ă��邩�炾�B�s�g�������W�k���㎍����14�l�t���炱��2 �т��O���킯�ɂ͂����Ȃ�����A���ʂƂ��āq�ߔ��r���R�ꂽ�ƍl����Β���͍����B�q�����r�́u�V�v�Ɓq�V�l��r�̑S�s�������B
�@�V
�����͋��R������
���E���̐Q�䂪
�s�V�悭�V�l����l���悹���a�ނ̂�
�����X�̎�����
���V�l�Ǝ��ɂ݂������
�͂������Ă䂭������
��Ɠ��̐ς܂ꂽ
�����ݑ܂����������
�Ƃ��ǂ��S�C�̓��悪��������
�ߖ�������
�V�l�̏��F��
�������R���������͂���
�����痁����
���P�̗��l�E�v�w�����̐Q���
������̗��R�Ŏ����͚L��
�Z�b�N�X�����L���Ȃ��̂�
�̂��Ƃ��p����
�����Ȃ�Ό���̋�
���炩�Ȍ��̐Q��
���̔��̗��������̏ꏊ�ɏZ�߂�
�����͘V������e�̑r���̂�݂�
���肩�����ЂƂ�̗��s��
���炠�炵���̔����
���̑��B�@�f��̌��h
�ł���Ώ��ł̒m�����܂Ȃ�
���܂͗�㌎q�̌C�ɓ��܂��X�̋G��
�����̕����͂���߂�
���ڂ���̉Ԃ�����
�����͐��E���̎�����V�l�Ɠ�����
�@�V�l��b�g����
���т������̗c���ƃy���J����
�V�l���A�����
�a�l�̉��҂Ƃ��Ď��ʎ��̂���
���̓����ƐS�̌Ǘ������m�F����
�X�̖̑S�̂����Ŕ҂�
�o���邾���������
�H��D��g����
���ꂪ�Q���̉����猩����
�ύ��܂ꂽ�̂͌�����������
���Ɣx���̌̍����
�V�l�͏o�Ă䂭
��̉����瑱���[���g�̂��˂�֏��
���т̍Ȃ����Ԃ��ɂ���
�������[�̓őf��
�l�̐S�����킪�����݂���
���炰�̑̂��܂��Ă���
�V�l�͕����Ȃ���
��
��
��x�͎����V�����̌�������
���Ԃ̂͂��ꂽ���E���z������
��ʋ��̕��͂�����������
���������k��
���̂������������͂�������
�G���`�b�N�ł���
��V�������V�l�炳��
�K�[�[�̌��̂Ȃ܂߂�������
�V�l�͉�z����
���m�ɂ����Ȃ�Αn������̂�
�ݑ܂��N���̂��߂�
���̂Ȃ������̖��
�͂����Ȃ�Ñ�̚e��������
���ƍ��̑Γ��̎s��
�����ď��ɂ̉��̒��S�ɍ���
���҂̐S���̊��
�����Ȍ��������悤�Ƃ���
�ނȂ���������ꂽ
╂̂��Ƃ�����
�݂��Ƃȗ��̗x�q��������
�s���Ȗт̐��E��
�����̎�l���䓁���Ђ�߂���
�V�l�̑哪���肠����
�p�̂߂���
���������҂Ƃ���
�c���ƃy���J���̎��_�Ƃ���
���l�ɂ͎ז��ɂȂ�ʏ��ֈڂ����
�������c�����Ԃ�V�A�ƘV�l�̑���͕ς����̂́A�����3�т����ʂ������z�����ɂ����Ƃ͖��炩���B����͉ƌn�ɑ��錙���ł� ��A�g�������� �r�Y�Ɍ���������{�̃E�F�b�g�ȕ��y��ߑ㐫�ւ̔������ł���B�������ĘV�l�i�����j�́u���Ԃ̂͂��ꂽ���E���z���k�c�c�l���l�ɂ͎ז��ɂȂ�ʏ��ֈڂ� ���v�B���̂Ƃ��A�u�ނȂ���������ꂽ�^╂̂��Ƃ����݁v�́u������������^���邷�ׂ�̍g�v�ɋ��������B
����W���T�C���낤�������Ȃ��낤���A���T�Œ��ׂĂ݂�K�v������B�����A�����Q���s�势�a熓T�k�k����
�ɓ�l�t�i��C�ُ��X�j�́u��v�Ɏ�͂Ȃ��B�q��m�W���T�C�n�r�Ƃ��������p�ꂪ�����邾�����i�������q��a��сm�W�����W���T�C�n�r�̍��ڂɁu�Â�
�悭���̖��ƒ��a���A���͂悭���̐F�ɐ���B���h�Ȑ�����L���Ă��҂́A�{����悭�g�ɂ���Ƃ��Ӛg�v�Ƃ���j�B��߂ȌÌꎫ�T�⍑�ꎫ�T�ׂĂ�
�Ă��A���Ƃ��Ώ��w�ق́s����厫�T�t�Ɂq��Ձm�W���T�C�n�r�����邭�炢���B�g���́q�k�ߑe�`�r�i���o�́s����o��̐��E13�@�i�c�k�߁@�H���s���j�@
�����Ó��W�t�i�����V���ЁA1985�j�́q�����r�j�Łu�����̋ߍ��ǂނ��тɁA���܂�ɂ��u����v���p�o����̂ŁA���͕����邱�Ƃ�����B�k�c�c�l��
������̂Ȃ��ŁA�����u����v��}�����邪�A�ƂĂ��c����l�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O��O�y�[
�W�j�Ə����Ă��邩��A����u����v�ł���\�����̂Ă���Ȃ��B�g�����͑���Ɋւ��āA�ǂ��l���Ă����̂��낤���B�P�s�{�����^�̕��͂�������B
�Q�@�����������}�@�u���K�v����͏����̑���ł͂���܂��A�����ɂ͂���܂���ˁB��O�̃��_�j�Y���o�傠���� �Ɏg��ꂽ�� ���Ɏv���܂��B�u�R�E�J�C�v�Ɠǂ݂܂��B�����Ă݂�A���{�̓����̃z�e���I�Ȍ܁A�Z�K�ʂ̊����ł��B��O�̓��{�ɂ́A���݂����ɏ\�K�A��\�K�͂Ȃ����� ����ł��B�������A�A�����J�ł͌܁A�Z�K�ł͖��ł��傤�ˁB���܂������܂��B�i�k1974�N10��10���t�����h�������ȁl�A�sLilac Garden�tChicago Review Press�A1976�Aiv�y�[�W�j
�@�w�����[�^�x�̍�҂̃E���W�[�~���E�i�{�R�t�̑�\��ɁA�u��ނȂ�����F���̍\�z�v�ƈ����钷�я����w�������x������B�ꎍ�l�̋�S��\��s�̎� �т̓���A���̗F�l���u�𖾁v�Ɓu���߁v�����݂�Ƃ����\���ł���B
�@���͂��܂��܂��̎��т�ǂ�ŁA�u���[���h���b�v�v�Ƃ������t�ɁA�S�䂩�ꂽ�B�����ł́u������v�Ɩ�o����Ă���B�������A�i�{�R�t�̑���ŁA�d�w�I �ȈӖ����B����Ă���悤���B�e�����p���w�҂ɂ����˂���A�u�ˑR�̎����v�Ƃ����u�Ӂv���A�܂܂�Ă���炵���ƌ����B�i�q�u���[���h���b�v�v�r�A�s���� ���̎��t1989�N4�����A�O�y�[�W�j
��O�̃��_�j�Y���o��i�H�j�ɓo�ꂷ�鑢��A�i�{�R�t�̒��я����ɓo�ꂷ�鎍��ɂ��鑢��i�g���͂�������т̕W��Ƃ��������łȂ��A
���W�̃^�C�g���Ƃ����j�ɐG������ŁA���g�̑���Ɍ��y�������Ƃ͂��ĂȂ������B���Ȃ݂ɑO�f�q�k�ߑe�`�r�̒��������͂����ł���B
���Ƃ��A�u���V�l�v�u��ӔN�v�u�r�_�v�u����v�u�����v�u�f墁v�u�[�ځv�u���W�v�u�Â݂���v�Ȃǂ͎��I�ɂ����� ��Ă��邩�� �悢�B�������A�u�^�����v�u�E����v�u�͂ꚺ�v�u���~���v�u������v�u������v�u���v�u�ÐO�v�Ȃǂ̓����͌���Ȃ�����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k���� �Łl�t�A�O��O�y�[�W�j
��i�̒_�ƂȂ�j�ɑ���߂��ނ��Ƃ́A������Α傫�����A�O���Ƃ肩���������Ȃ��B���ꂾ���̘b��������Ȃ��B���āA��� �͕����ǂ��� ���邱�ƂƂ����̂ł́A����ɂ�����Ӗ��͒ʂ��Ȃ��B���ǂ݁u��v�u��сv��P�ǂ݁u�����ȁv�����l�ł���B�����œ����ǂ݁A�d���ǂ݂����݂�� �u�W���ȁv�Ƃ������������т������Ă���B����ƂĂ��̂܂܂ł͒ʂ��Ȃ����A�W���i���������������������̂Ƃ���A���̕��i�͂ɂ킩�ɕς���Ă���B
�@�����ł킽�������͌�������ňꌏ�������B�����ł͂���܂��B�g���́u��v�Ə������̂ł����āA�u���v�Ƃ͏����Ȃ������B�u���v�͂ǂ��֍s�����̂��B�� �����W�s�a���`�t�Ɏ��߂�ꂽ�q���r�i�D�E17�j�ł���B
�@���b�g����
��̉��ɂ˂ނ�B
�l������I
���D���̗��̌@����
�q���ƍ������Í������̈���
���݂Ă��锼���I���O�̎�
�����݂�����ΉP�̂Ђт�
�l�тƂ̎��ʂ̊i�q
�ڂ��̎��ɂ��ꂪ�i����
�����l���̋�̉���
�݂������̊C�̔g��
�ڂ����M���������Ƃ��ꂪ�j��
�Ȃ������o��
�g�}�g�̎R��������
�����̎��̖��
�������������čs����
�ڂ��͎��ʂ�薳�S�ɂȂ낤
���⓹��̂������
���u�����ǂ낭�قǂ҂�ƒ����Ă���
�M������I
���̖т̉��ɂ�������
�q�ߔ��r�Ɠ���1961�N1���́s�ߑ㕶�w�t�k16��1���l�ɔ��\���ꂽ�q���r��14�s�߂́A���o�`�u�`���̎��̖�Ɂv�����W�s�a ���`�t�ł͒� �e�`�u�����̎��̖�Ɂv�Ɖ��߂�ꂽ�B�q�ߔ��r�̍ŏI�s�u�������̔\�ʂ̓`���̂����Ɂv�ƕt��������̂����������߂Ǝv����i�s�a���`�t�ɂ́q�� ���r�q���r�̏��ŁA�����Ď��^����Ă���j�B�g�����͈���Łq�ߔ��r����q���r�Ƃ���������u��v�Ƃ�������i�ł��낤�j�ňÎ����i�s�g�����S ���W�t�ł́u��v�Ɓq���r���������J���Ɍf�ڂ���Ă���j�A�����Łu�`���v�Ƃ��������E���Ȃ����ԇ�����x�͏����āA�̂��ɏ������ƂŊW����f�� �����B����1961�N1���A�ɒB���v���}�������B���惆���C�J����o����������Ȃ����W�s�a���`�t�́A1962�N9���A����ɂ���g���̍ł��������t�� ���X���̎��ƔłƂ��Ċ��s���ꂽ�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�i��1�j
�g�������Ɂuⵁv�͓o�ꂵ�Ȃ��B�u�Ձv�́u�d����
�Ȃ��ɗ[�̖؋Ղ���v�i�q�ߐ��r�A�E28�j�A�q�ߔ��r�i�D�E16�j�̖��̎���A�u���̗[��̋Ս��̐�����v�i�q�����`�r�H�E10�j�A�u�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�G�Ձv�i�q�����q杁r�K�E4�j��4����Ɍ����邪�Aⵂɑ�������̂́q�ߔ��r�����ł���B
�i��2�j
�O�c���́s���� ���w�e�N�X�g����t�́q��O��
���t�Ɛg�́r�́q�������p���r�ł����w�E�����B�u�����������J���̎���ɂȂ��Ă��Ƃ��A�����݂̏�ɍ����Ă��K�������Ă������q�������w�Z�ɂȂ��āA
�֎q�Ɗ����������܂��B�܂�A�����J���̎��ォ�珉�߂ē��{�l�̓��[���b�p�ӂ��̍�������Ƃ����p�����w�Ԃ��ƂɂȂ�̂ł��B���̍�������Ƃ����p��
���w�Z����ɂ��т����P�������B���邢�͂܂��A�ߑ�I�ȌR����n�݂��Ă����d�����������{�ɉۂ��ꂽ�킯�ł�����ǂ��A�������ꂽ�_���ɑ��āA�u�C��
���v�u�x�߁v�A���邢�͑����݂����낦���s�i�A���������P�����قǂ����B���������g�̓I�ȓ����́A����܂ł̔_���̐����̂Ȃ��ɂ͂܂������g�ݍ��܂��
���Ȃ������g�̓I�ȏK���ł��B�܂�ߑ�̓��{�l�́A���邢�͊w�Z�ŁA���邢�͕��c�ŁA���܂ł̓��{�l�̐g�̂̂Ȃ��ɂ͑g�ݍ��܂�Ă��Ȃ������p�����P��
����邱�ƂɂȂ����B����������́A�����̓��{�l�̂����Ă̐����ł����āA�ƂɋA��Α��ς炸�����݂̐����ŁA�����ɉ������Ƃ����`���I�Ȑ������K����
���Ďc���Ă���B�������邨���Ă̎p���ƁA�����݂̏�ɉ������p���A����������d�\���������Ă����̂ł�����ǂ��A�k�c�c�l�v�i�s����
���w�e�N�X�g����k�����܊w�|���Ɂl�t�}�����[�A1993�N9��7���A���Z�y�[�W�j�B�㏑�o�ł̓�R����ނ���19�̋g���������F���m�ō����t�˂�⍲
���Ďq�ǂ������ɏ����������Ă����̂́A�����炭�����ݕ~���̘a���������B�����ɂ́u�����݂̏�ɉ������p���v�����������낤�g���́A�q�ߔ��r�ł͂���
�����������P������B
�g�����̑����Ƃ��Ēm����ł������̍�i�́A���c�Ǖ��E�a�c�F�b���s��t�S�W�k�S7���l�t�i�} �����[�A1953�N8��10���`1956�N6��20���j�����A���^��i�Ƃ��đO�N1952�N�̃O���A���E�O���[���i�ےJ�ˈ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A 1952�N5��20���j������A�����������܂߂�g�������W�s�t 铁t�i�� ��ɁA1941�N12��10���j���ŏ��̍�i�ƂȂ�B�ߔN�ł����u����v�u�����v��薼�ɂ������Ђ͊����[���̗l����悵�Ă��邪�A��O�ł͒Óc���s�� �ꚤ�ďW�t�i�|䇓��A1929�j���炢�������i������1974�N�Ɍ���500���ŕ����Ċ����ꂽ����A���O�q�Óc���̑���}�ār�Ƒ�͓������q��i�� ���r���t���ꂽ�j�B�g�����ŏ��̒����s�����G�߁t�i1940�j��s�t铁t�����s����ɂ������ĂȂɂ��Q�l�ɂ����̂��A�悭�킩���Ă��Ȃ��B�����g�����ʊ� ���������s�t铁t�̕\���G�́A�|�v����̑��a���̃��_���Ƃł��������y��ɊJ�Ԃ������̂ƌ��Ȃ���B�ΐ�j�q�́A�ʍ����z�s�|�v����̐��E�t�i���} �ЁA2014�N9��6���j�́q����E�}��r�Łu�����̕\���A���Ԃ��A���A�J�o�[�A���̈ӏ�����|���邱�̎d���ɂ����āA����͕S�l�ȏ�ɋy�ԍ�Ƃ̏��Б� ���S�Z�\�]���ɉ����A���g��������s���Ȃ����W�E���W�E�G�{���̒������\������|�����v�i�����A���Z�y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�|�v�́A�g���������� �e���݂͂��߂�1930�N�㔼�A���m�Ɍ�����1934�N��49�şf���Ă��邪�A�|�v���g�̒���͂Ƃ������A���̑����{�͋g������Ɏ�邱�Ƃ��������� �Ⴂ�Ȃ��B�����A�����̒|�v�����{�̂Ȃ��Ƀt�����X���i�s�t铁t�͕����t�����X���ł���j�����������Ƃ͊m�F�ł��Ă��Ȃ��i��1�j�B
 �@
�@
���|�G���s�ᑐ�t1925�N12�����̕\���k�\���G�F�|�v����l�i���j�Ƌg�������W�s�t铁t
�i1941�j�̔��ƕ\���k�\���G�F�g�����l �i�E�j
�s�t铁t�ƕ��ׂāA�|�v���\���E���E�J�b�g����|�������|�G���s�ᑐ�t���f���Ă݂��B�����Ƃ��A�g�����؉��[���̎���ǂ���́s��
���t�͂��ł�
�|�v�̕\���ł͂Ȃ�������������Ȃ����B���́u����w�Z�v�Ɋw�̂��A�ʼn�Ƃ̉��n�F�l�Y�ł���i���n�F�l�Y�����{���������������A�����Y���W
�s���ɖi����t�i1917�j���낤�j�B�g����1946�i���a21�j�N2��17���̓��L�Ɂu���j�̒��A�ԑ҂��Ă���ƃs�[�X�����ɓ����B���т͂�
�͂��ƃV�`���[�Ŗ��x�B���E�̉��n�Ƃ֑���̂�����Ƃǂ���v�i�s�邵����t6���A1990�N5��31���A�O�Z�y�[�W�j�Ƃ����L�ڂ�����B�u���E�̉��n
�Ɓv�͉��n�F�l�Y��낤�i�N���ɂ��A���n��1932�N�A���삩�琙���擌����88�Ԓn���������扬�E4-2-22���ɓ]�����Ă���j�B1946�N2
�������A�g���͑O�N��12���ɓ��Ђ�������̍������[�i���Ă̋Ζ���A�������X�̎В������m�͂����͎҂đn�����o�ŎЁj�ɍݐЂ��Ă��邩��A���n
�̑�����i�ژ^�ɓ���������ɂł������������Ȃ��̂����A�Y�������i�͂Ȃ��B�ȉ��ɁA�g�����������X�ɓ��Ђ���1940�N�i�}�����[���n�Ƃ����N�ł�
����j������L��1946�N�܂ł̉��n�F�l�Y�������A���n�F�l�Y������p�_�W�s���{�̎g���t�i�����o�ŁA1992�N2��1���j�́q���n�F�l�Y�����i��
�^�r�ɋ����Čf����i��R���ڂ́����t���ĕ�����j�B
���l�Z�N �k���a�\�ܔN�l
���l��N �k���a�\�Z�N�l
���l��N �k���a�\���N�l
���l�O�N �k���a�\���N�l
���l�l�N �k���a�\��N�l
���l�ܔN �k���a��\�N�l
���l�Z�N �k���a��\��N�l
�g�����Ɖ��n�F�l�Y���Ȃ����Ђ����ɂǂ��ɂ����Ēm�肽�����̂����A�ڂ��M�̂悤�ɂ��Ă��g���̋Ζ���̏o�ŎЂƊւ��̂��肻���� ���Ђ͌����� ��Ȃ��B����A�����t�����ɓ�����Y�́s�X���O�t�i����{�Y�ى�u�k�ЁA1946�N11��20���j�͍Ċ��{�̂��߂��q���n�F�l�Y�����i�ژ^�r�ɂ͂� ���B1944�N1��21�����̓����̏��ł͖ژ^�ɋL�ڂ���Ă���A�g�����ǂ̂͂�����ł���i1946�N1��29���̓��L�Q�Ɓj�B���Ȃ݂Ɉɓ��́s�X ���O�t�́A���́q�ˍZ�r�̏͂��g�����������s�X ���O�S�W�k�ʊ��l�t�i�}�����[�A1960�N3��30���j�Ɏ��߂�ꂽ�B���́s�X���O�t�̍Ċ��{�i�����͏��łƈقȂ�j�̂悤�ɖژ^�� �̂��Ȃ�����������邩��A�������[�������͐������X���̉��n�F�l�Y�����{�����݂��Ȃ��Ƃ͂�����Ȃ��B����̒T���ɘւB

�ɓ�����Y�s�X���O�t�i����{�Y�ى�u�k�ЁA1944�N1��21���j�̃W���P�b�g
�Ɠ����̍Ċ��{�i���A1946�N11��20���j�̕\���k���������
���F���n�F�l�Y�l
���n�F�l�Y�q���{���p�̍\���r�i���o�́s�����t�k���{����������s���l7�`14���A1935�N10���`1936�N6���j�ɉ����i�t�� ���X���j�Ɋւ���L�q������̂ŁA���p����B
�@�����́C����������������C�ȒP�ȏ��ŔV�ЁC�Ԃ������̝B���炸�C�����A���J�b�g���퓹�ł���B���ɂ��� ��āC���͓� �Ɍ`����ʂȂ��̂ɂ��邽�߂ɂ͝B����邪�C�O���܂�����̂܂܂��{�R�̎p���B�V�͂܂�C�ǎ҂������̍D�݂ɖ{�������邽�߂ɗp�ӂ��ꂽ�`���ł��āC ���s�҂͒������������Ƃ��ӂ킯�ł���B�V��B���Ȃ��̂́C�{���̐܂ɝB�f�ɂ�Ė{�����`�ɂȂ邱�Ƃ����ނ��߂ł���B���̐ܓs���������ƕ� �̌`�C���R�̌`���ςւ����ꍇ�ɂ́C���ɐ��Ђ�đ����o�����肷��B���ꂾ���ł݂�Ɛ����ςȊ�ԂȊO�ς�悵�Ă��B�����́C�J�ԔV���t�����X ���Ƃ��Ӓ��C�t�����X�̖{�͉����������B�������ł͏����Ƃ����炳���鏊�����Ԃ����y���B���Ă�邵�C������肪���đ��{�����̂��ނ́C�ލ��̔��p�S�̔� �B�ɂ����̂Ɖ]�ւ悤�B���{�̉����͈�ʂɑ����e�ɒԂ����Ă�邪�{��̉����̒Ԃ��͊e�F�����C�����U��U��ɂȂ�ʒ��x�̂��������Ȃ��̂������B �R������l�ւ����ł����킯�ł��āC������{�͍ēǎO�ǂ��邽�߂ɂ͖{�������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�t�����X���̖����o���Ă�邾�����ē��{�̖{�� ���Ԃł��������J�ɂ������Ă�邵�C�����Ȃǂ��悭����ւĂ�����̂������Ȃ��B�W�����{�̂₤�ɍĐ����{���啔�����ꂽ�{�̍��Ȃق���m�[�g�̍��� �ʂɂ����p�Ђ��ʏK����C���|�p�I�Ȑ��{����鐻�{�Ƃ��S�����B���Ă�Ȃ�����ł͂����������Ƃ�����@�ł���C���������h�Ɉꑕ�{�`�ԂƂ��ēƗ����� �����Ɏ��ė���킯�ł���B���̉������C���̊ϔO���X�Ɉ�w�O�ꂳ���āC�����p�ӂ����C�����ʂ��Ȃ��o�ł�����B��������ɑ��Ĉ�w���Ȋ��s�ł� ��B���V�́C�]��Ő��̑������̂�C�U�c�Ȃ��̂ɂ͗]�茩�����Ȃ��B���{�ł͓�O�������Ȃ����̉Ǐ��ȕ��@�ł���B�i�s�V�����y�� ���n�F�l�Y ���{�̋Ɓt�O�ȓ��A2011�N1��20���A��Z�܁`��Z�Z�y�[�W�j
�Ō�́u���̊ϔO���X�Ɉ�w�O�ꂳ���v���u�����v�́A�ܒ��𑩂˂������̂��̂̂悤�ŁA���������i����������Ƃ��Ȃ��j�B�g����
���n���̏��o
��ڂɂ����W�R���͍����Ȃ����A�nj��ɓ������������O�ɂ�����ł��ڂ��������i�t�����X���j�̐����ł���B�����Ƃ��A�s�V�����y�� ���n�F�l�Y
���{�̋Ɓt�̐}�łɂ͉��n�ɂ��t�����X����i�������Ȃ��B���n���t�����X������|�������Ƃ͂���̂��낤���i�s���{�̎g���t�����̕��ɂ��A����̃t����
�X���ւ̌��y�͂Ȃ��j�B�|�v�����{�Ɠ��l�A���Вm�肽�����̂��B�����ʼn��n�̗������A�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑���
1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�̋L�q����Čf����B
���n�F�l�Y�i�� �E�������낤�j
�� �����N�������܂�B�n��ʼn�̃p�C�I�j�A�ł���A�ʐ^�ƁA���l�A����ƂƂ��Ċ���B����ƂƂ��Ă͗��_�ʂł������I�ȑ̌n�Â��������Ȃ��A�ߑ㑕��p�� �m���������т͔�����o�Ă���B�莚�ނ̏��������u���n�����v�̊i���̍����ł��m��ꂽ�B���܌ܔN�v�B�i�����A��Z��y�[�W�j
���n�F�l�Y�����{�̑�\��Ƃ��āA����1�_�A�s���e�̐X�t�ɍ̂�ꂽ�̂��k������{���{�S�W34�l�́s���\�쎟�Y�E�����P�U�E�q��M
��E���E��
�W�t�i1955�N9��5���j�����A�{�e�ł͌�q����k������{���{�S�W89�l�́s���㎍�W�t�i1958�N2��10���j����肠����B���n��1955�N6��
��63�ŖS���Ȃ��Ă��邩��A���������ۂɎw�肵�āA�������炵�߂��̂͒}�����[�����̐l�ԂɈႢ�Ȃ��i���ꂪ�g�����ł����ď��������������Ȃ��j�B�F
�l�Y�̎q���A���n�M�Y�́q�ƂƂ��Ă̑��{�r�Łk������{���{�S�W�l�����̂悤�ɕ]���Ă���B�\�\1953�i���a28�j�N����1955�i���a30�j�N�ɂ���
�Ẳ��n�̑����́A
�~�n�Ǝ���̋Ƃ��݂��Ă͂��邪�C��@�͏]���̂��肩�����������Ȃ��Ă���B
�@�������C�}�����[�́w������{���w�S�W�x�i���a28�N�j�̂悤�ɁC�v�z�ƋZ�p�̋Ì��������Ă�����̂�����B�����̕ҏW�S���҂ł������y��ꐳ���͂� �̂悤�Ɍ���Ă���B
�@ �͂��߂ďd�v�Ȏd����S�����C�ْ����Č��e���Ƃ�ɉ��n�Ƃւ����ނ����B�搶�͕@�̂܂���Ō��e���d�グ�C�n���ꂽ�B����̓g���[�V���O�y�[�p�[�ɁC���� �ʼn悩��C�ƂĂ����ꂪ����̌��e�Ƃ͎v���Ȃ������B�A�Ђ��āC�Óc�В��C�P��g�����Ȃǂɑ��k����ƁC�搶�������̂Ȃ�C����ł����̂��낤�Ƃ������� �ň���ɂ܂�����B�Ƃ��낪�ł��オ���Ă��ė��h�ɂł��Ă���̂ł��ǂ낢���B�ǎ҂̔������悭�C����ւ̌��y�����������B���́C�}���̍ł��ւ�鑕��� �������Ǝv���Ă���B�@���͂��̑S�W�����̍Ō�̂����ꂽ���̂ƍl���Ă����̂ŁC��ɕҏW�����ƂȂ����y�䎁�̈ӌ������߂��̂ɑ��ē�����ꂽ�G�s�\�[�h�ł���B�i�s�V���� �y�� ���n�F�l�Y ���{�̋Ɓt�A���O�`���l�y�[�W�j
�s���{�̋Ɓt�́q���n�F�l�Y�����i�W�r�ɂ́k������{���{�S�W53�l�́s�֓��ΉJ�E�؉����]�E���c�D���E��i�����W�t�i1957�N 10��8���j�� �J���[���e���A�q���n�F�l�Y�����i�J�^���O�r�ɂ́k������{���{�S�W37�l�́s��[�N���W�t�i1955�N11��5���j�̃��m�N�����e���f�����A��҂� �́u�H�q�F�N���X�Ƀj�b�P�����Ŋw�͗l�C�w�����͍��������v�i�����A��Z��y�[�W�j�ƊT�v���L����Ă���B���c�N�v����͂��́u�w�͗l�v��n�ł� �Ȃ����Ɗ��j�����B�Ȃ�قǂ�����������Ȃ��B����A�����Ƃ��������Ȃ��B�ł͂����ŁA�}�����[�̑S�W���p���̉��䍜����������̃V���[�Y����A�O�q �̉��n�F�l�Y�����k������{���{�S�W89�l�́s���㎍�W�t�Ƌg���������k������{���{��n93�l���s���㎍�W�t�i1973�N4 ��5���j�̔��k�\�P�l�̋L�ڂ��f����i������V���ɉ��߂��ӏ�������j�B
���㎍�W
�͈���䪁E�ɗǎq�����E������J�E��H�����E�����Í��E���m�K���Y�E�O�x���t�E�������\�E�x
����{�E���V�@���E�k����
�Y�E���c�t���E�����@���E�x�c��ԁE�����Ȍ�E�S�c�@���E�R���钹�E������t�E�����y�V���E���E����씪�E���q�����E�|�������Y�E�[���{���q�E���
�Օv�E�g�c���E������p�E�����V�g�E����S���E���؏d�g�E���������Y�E���Ɏ��E����\�O�Y�E���{�@���E���F�G�Y�E�ɓ��M�g�E���e���O�Y�E�t�R�s�v�E�k
��~�F�E�����~�ʁE����l�Y�E�|���@��E�k�����ʁE�ߓ��@���E�O�D�L��Y�E����M�v�E�c������E���萴��Y�E������Y�E�H�R�C�O�E�ɓ��@���E���V�����E��
�@����E�⍲����Y�E�U���L��Y�E�R�V���@���E�e���v���E��]���Y�E�팩�P�g�E�����@��E���`ꝔV���E�R�{���Y�E�ێR�@�O�E�c���~��E�x�i���Y�E������
��E���������E�Ñ��M�v�E�ɓ��×Y�E�c�����ȁE�_�ی����Y�E�J��r���Y�E��{�z�Y�E��@���E���ؓ�Z
���㎍���j�i����l�Y�j
������{���{�S�W�@89
�}�����[��
������{���{��n
93
���㎍�W
�x�i���Y�@�x�i���Y���W�@�@�����~�ʁ@�R���仁@�@�팩�P�g�@�E���g���}�����@�@�c���~��@
�C�̌�����Βi�@�@�|����@
�ۉ�C�݁@�@���@���F��寁i���j�@�@�ێR�O�@���ێ��W�@�@���Ɏ��@���Ɏ��S���W�i���j�@�@�k�����ʁ@�����@�@�J��r���Y�@��\�����N�̌ǓƁ@
�@�|�������Y�@���^�@�@�ѓ��k��@���l�̋�@�@�R�{���Y�@���s�҂̋F��̉S�i���j�E�R�{���Y���W�i���j�E�P�Ǝ҂̈��̉S�i���j�E����҂̘f���̉S�i���j�E
���@�i���j�@�@�J���@��n�̏��l�@�@����M�v�@����̐l�@�@�c������@�l��̓��Ɩ�@�@�剪�M�@�L���ƌ��݁i���j�@�@��c�j�Y�@�c�@�@�g�����@�m���@
�@������s�@�X�������@�@��c�G�@����ȉS�@�@�������j�@CALENDRIER�@�@�V�V�ޓ�Y�@���̉́@�@�������@�L�����i���j�@�@���V�N�v�@�킪�o�_�@
�킪�����@�@�Ί_���@�\�D�Ȃǁ@�@�F�V�F��@�����邢�͐�������
�t�^�@����i�c��m�j
�}�����[
���n�F�l�Y�����́k������{���{�S�W89�l�i�`�j�Ƌg���������́k������{���{��n93�l�i�a�j�̑������r����܂��ɁA���҂̓�����
�q�ׂ�B�܂�
�{���̊�{�g�B����͂قړ����B�y�`�F20���~28�s�~3�i��1680���i400���~
4.2���j�@�a�F20��
�~29�s�~3�i��1740���i400���~4.35���j�z�B���y�[�W�����قړ��������A���^
���e�͂`�̊e���l�̑�\��
�т̏��^�ɑ��āA�a�̌����A��\���W��S�ю��^������j�֑傫���ς�����B���Ȃ킿�y�`�F445�y�[�W��75���l�̎������߂�@�a�F424�y�[�W��27
�̎��W�����߂�z�B���̂�����̂��Ƃ��A�c������̎��тƎ��W���Ɍ��悤�B�y�`�F5�y�[�W��8�сi��������l ���̈�A��������l
���̓�A��������l
���̎O�A�l��̓��Ɩ�A�\���̎��A���߁A�����A�O���߁j�����߂�z�B�����Ɂu�i�ȏ�u�l��̓��Ɩ�v�\���a�O�\��N���\�j�v�Əo�T�\�L������悤�ɁA��
�W���s�̗����N�A���������Ђ���S�W�ɏ��^���ꂽ�̂ɋ����B�y�a�F12�y�[�W�ɑS26�сi�T�@��������l
�l�сANu�A���с^�U�@������A���߂鎛�A�������z�A�H�A���A�\���A�C���W�A�c��A�~�̉��y�^�V�@�l��̓��Ɩ�A�\���̎��A���߁A�ĉ�A�ԗ�
���̒f�ЁA�������A�ׂ����A�ɂԂ��S�^�W�@���l�Z�N��E�āA�����A�O�̐��j�����߂�z�B�����Ɂu�i���Ł@���a�O�\��N�O���A�����n���Њ��j�^�ҏW����
�@�{���W�͎v���Дł̌��㎍���Ɂu�c�����ꎍ�W�v�ɂ��B�v�Ƃ���B�{���ɓc���̎��W���S�ю��߂��Ă��Ă��A�����N�������Ȃ��B�����ŁA���V���M�s�Óc
��`���t�i�͏o���[�V�ЁA2003�N2��28���j����k������{���{�S�W�l�̐���Ɋւ���L�ڂ��������B
�@�}�����[�́w������{���w�S�W�x�́A���蓡�������z�{�ɂ��邱�Ƃɐ�����肤�����������B����́A�Óc��A�P ��g���̈،h���铯���̋P�����ł���A��s����w���a���w�S�W�x������z�{��������Ȃ�������������������ł���B
�@����́A�p��ł̌��O�ɑ��A��O�̃��_�j�Y���̉e��Y�킷���n�F�l�Y�Ɉ˗����A���邢�����I�ȉ��y�F��\���ɗp�����B���̐F���́A���̌�̒}�����[�o �ŕ��ɁA�傫�ȉe�������������قǂł������B
�@���^�����ƁA���쌠���p������⑰�Ƃ̌��ɂ́A�ҏW���̑S�����蕪�����ē����������A��q���鑊��ɂ͎В��̌Óc�肪�A�݂�����o�������B�i�����A ��Z�܃y�[�W�j
�@ ���w�S�W��搂����\�Z���̒��Ɂw���c���j�W�x�����^������A�^�Ӗ슰�E�^�Ӗ쏻�q�E�ΐ��E�k�����H�̎l���l���ꊪ�Ɏ��߂�A���邢�́A�w���蓡�� �W�x�w�H�열�V��W�x�w�X���O�W�x�ɂÂ������z�{�ŁA�w�֓��g�W�x�Ă�Ƃ��������j�[�N�Ȋ����ĂƁA����̍L���́A��s����p��ł́w���a���w�S �W�x���͂邩�ɒ������{�i�I���w�S�W�̕��͋C��Y�킹�Ă����B
�@�ŏ��̎������{���o�������A�S�Ј��͉��n�F�l�Y�̊i����������ƁA���蓡���̍�Ƃ̃X�^�[�g������Â����w�j���x�̏��Ŗ{�̕����Ɋ��������B
�@�u����Ȃ炢����I�v
�@�����ȋ������x������Ȃ����ŁA�ނ�͒}�����[�����̑����̊m�M���A�������������̂������B�i�����A��Z���y�[�W�j
�P��g���̂��ƂŁk������{���{�S�W�l�̐w���w�����������̂��S �����o�� ����B�g���́u�����v�̒S���҂ł����Ȃ��������i���n�Ƃ̐Ղ͑O�q�̂悤�ɓy��ꐳ�����������j�A�S���̏Љ�Œ}�����[�ɓ��Ђ����̂�����A���炩�̊� ��肪�������͂����B�c�O�Ȃ���g�����u�����v�ɐG�ꂽ���͈͂₳��Ă��Ȃ��̂ŁA�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B�}���̊����ꝱ�̑�v���W�F�N�g�i�P��͓��� 100���̗\���56���ɏk���A�ŏI�I�ɑS97���ʊ�2�Ƃ����j���g�����i�̑����j�ɗ^�����e���́A����ȍ~�̋g����������i�̂����Ɍ��Ă��������Ȃ��B
 �@
�@
���n�F�l�Y�����́s���㎍�W�k������{���{�S�W89�l�t�i�}�����[�A1958�N2��10���j
�Ƌg���������́s���㎍�W
�k������{���{��n93�l�t�i���A1973�N4��5���j�̔��ƕ\���i���j�Ɓs���㎍�W�k������{���{�S�W89�l�t�Ɓs���㎍�W�k������{���{��n93�l�t
�̔��Ɩ{���E���Ԃ��i�E�j
�`�Ƃa�̍ł�������甒�͖{���p���ɂ���B��̂ɑ��{�E�����Ƃ����ƊO������A���Ȃ킿�сE���E�W���P�b�g�E�\���E���Ԃ��E�{���A�̏�
�Ɏ��o�̑؋�
���Ԃ͒Z���Ȃ��Ă����B���������ƁA�W���P�b�g�ŕ����Ă���\�����ǂ�Ȃ��̂����Ȃ����Ƃ�������B����̖{�ł����o�̑؋Ԃ������͖̂{��
�y�[�W�ŁA���\���̒Z�тł��������ł͓ǂ߂Ȃ��B������400���l�߂�1600���́k������{���{�S�W�l��k������{���{��n�l�i��2�j�̏ꍇ�ɂ����Ă���ł���i�g���́s�m���t�S�т�16�y�[
�W�Ɏ��܂��Ă��܂��̂��j�B���n�͗p���ɂ��Ă����q�ׂ�B
�@����䢂ɁC�{���̗p���C���������Ĕ��C�}��C���Ԃ����̍ޗ����q�ׂ�K�v�����炤�B�{���̗p���͕��ʑ��Ď҂͊֗^ ����ꍇ���� �����C���������̖{�̔��p���ʂ̏ォ�炢�đ��{�ӏ��̒��ɉ��ӂׂ��ł���B��ւΐr���s�d�ȊO�������{�̖{�������y���ȃR�b�g�����ł����肷�邱 �Ƃ́C��ɂƂ���̂����Ă��܂��ꂽ�l�ȋ���^�ւ�B��͂葕�Ď҂Ƃ̋�����o�Ē�߂�������ʂ�����B�������V���L�q�͈ꐡ�ȒP�ɂ䂩�ʁB��ނ��r ���������C���̂������邾���ł͉��ɂ��Ȃ�ʂ��炾�B�嗪�̏����q�ׂāC�ׂ������͎����ɂ��čl�ʂ��Ė�Ђ����B�T�ʂ���Ɩ{��������Ƃ��ėp�Ђ��� ��鎆�́C���ʂ̂��̂Ƃ��Ă͏㎿���C���H�C���H�C�����C�Ԗ�C���X�C�k�c�c�l�B�㎿���͎��̏W���̏㋉�o�ł�屢�X�p�Ђ��Ă��B���ɔ��̗p���Ƃ��ēK ���Ȃ̂͏㎿���ł����Ԗ���ł���C�{����菭������̂��̂������B���̎��ł��Ă�����͓��l�ŁC�����Ƃ����̕ł̍����������Ȃ����x�̂��̂͐���p �Ђ˂Ȃ�ʁB�i�q���{���p�̍\���r�A�s���{�̋Ɓt�A�ꎵ�Z�`�ꎵ��y�[�W�j
�`�̖{���p����I�̂����n�F�l�Y�Ȃ̂��A�ڂɂ���������̎�������͂킩��Ȃ������B�p���̑I����N���哱�������͕s���Ȃ���A��
�I�I�ɉ��n��
�u������o�Ē�߁v�����Ƃ͂������ŁA���̖{���p�����A���s��60�N�߂��o�Ƃ����̂ɁA�����قǔ����B���������m��ʒ}�����[���u�����v�̏����̖{���p
���ɖ�����������A�Ƃ����C��������i����Ɋr�ׂ�A�`�Ƃa�̕\���܂��̈ӏ��̈Ⴂ�ȂǁA�����҂��Ⴄ�ȏ�A���R���ƌ�������ōςށj�B���s���ɂ�
�ڂɒɂ��قǂ̔��������̂ł͂���܂����B����A�a�̔����N���[���F�̖{���p����I�̂͋g�������Ǝv����B�Ƃ���ŁA�g�����̑�����_���������Ƃ�
�Ĉ킷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ɁA�S�~��Y�ɂ�钆�����ق�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�i�s�����C�J�t2003�N9�����j������B��
���ɑS�ш��p�������قǂ����A�����������Ȃ��̂ŁA�k������{���{��n�l����ёS�W�̑����Ɋւ�镔���𑶕��Ɉ����B�����́i�@�j���̐����͓����̌f��
�y�[�W�B
�g�����肪�����S�W�ނ̑���������ɂȂ�킩��悤�ɁA�^�C�g���A�����A�o�ŎЖ��Ƃ����K�v�ŏ����̕����ƁA �����|�C���g �̃J�b�g�ō\�����Ă���̂ł����A�u�q���v�i�{�̕\���┟�̕\�ʁj�̃^�C�g�����قƂ�lj��g�݂̖����̂Ȃ�ł��ˁB�g������̓S�V�b�N�̂́A�قƂ�ǎg�� �Ȃ������Ǝv���܂��B�g�����ɂ����Ƃ���ŁA�S�W���p���ނ̑����ɂ��Ĉ�ƌ��������ɈႢ�Ȃ����A�ɂ��ނׂ��A�������ق��}���̎Г��ő�����S�����l�l�i�Ȑ܋v���q�A�g�c ���A���������Y�A���q�����j�ɂ�������Ă��Ȃ��悤���B�����͉��n�F�l�Y�̌����ɏA���ɔ@���͂Ȃ��B
�@�����āA�^�C�g���̊�{�ɂȂ�̂������i�l��|�C���g�����j���ꍆ�i�E�܃|�C���g�����j�̊����Ȃ�ł��B�����ƈꍆ�ł͕����̓������قȂ�܂��ˁB �����͑S�̂ɓ��������āA�ꍆ�A�Ə������Ȃ�ɏ]���ďc�_���ׂ��Ȃ��Ă䂭�B�k�c�c�l�g������͂����炭�A���ɂ��̏��������̓����̕����̃o�����X�� ���D���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i139�j
���ꂩ��g�������Ƃ������ƂŌ����ƁA���Ƀt�@���V�[�E�y�[�p�[��\��ƁA�Ђ̐����Ŏ��������L�т��ł��ˁB���̃q���ɉ��g�݂̃Z���^�[�����Ń^�C�g�� ������ꍇ�A���E�����ɑ����ă��C�A�E�g����ƁA�w���N�_�Ɏ���\��܂�����A�q���̕�������������Ă��܂���ł��ˁB���̃Y���������v�Z�ɓ���ĕ��� �̈ʒu�����߂�̂�����ǂ��A�u�������w�̂ق��Ɋ���Ă���̂͂����v�Ƃ����̂��g������̃A�h�o�C�X�ł��B�������͂����Ȃ��ƌ����܂����ˁB�V �n�̈ʒu���A�{���ɓV�n�����ɕ�����u���Ɨ����Č����邩��A������ɂ��炳�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ƌ����܂����B�i141�j
�\�����J�����Ƃ���ɂ��錩�Ԃ��ɂ��ẮA�g������͒W�N���[�����E���ȂǁA�����N���[���F���D��Ŏg���Ă��܂����B���܂�͂����肵���F�̌��Ԃ��� �D�܂�Ȃ�������ł��B�i�`�������ȁA���邳���Ȃ����B��ʓI�ɂ͕\���̐F�Ƃ̃o�����X�ŁA���Ԃ��ɂ͂�����ƐF�̂�������p���邱�Ƃ������̂ł����A �\�����J������A�������炷�łɖ{�����n�܂��Ă���Ƃ����ӎ����g������ɂ͂������Ǝv���܂��B����ƑS�W�͂����Ă������ďd���̂ŁA��͂��v �Ȏ��łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��������ł��傤�ˁB��N�́A�t�@���V�[�E�y�[�p�[�ł̓V�}���������D���ł����ˁB�i143�j
�}�����[�ł́A�{���͕ҏW�҂������Ŏw�肵�Ă��܂����B�т������ł��ˁB�ł��g������́A���������Ŗʂ̍����Ȃǂɂ��Ă̑��k���Ă����������� �v���܂��B�����A�����Ŗ{����g�ނƂ����̂͐������āA���̂ɂ��Ă������̑傫���ɂ��Ă��A������x���R�Ɍ��܂��Ă��܂���ˁB���Ԃ̓x�^�g����{�� ���A�s�Ԃ͓i�{���̕����̑傫���̌܁Z�p�[�Z���g�j�͋l�܂肷���A�S�p�i��Z�Z�p�[�Z���g�j�͋���������l���i���܃p�[�Z���g�j����{�� �����悤�ɁB�i144�j
�\�\�@��������Ƌg��������ŋ�����Ƃ��ꂽ���Ƃ͂���܂����B
�����@��ƂȂ�A���Ƃ� ��ł���`�������Ă��������܂����B���Ƃ��Ή��F���N���X��\���Ɏg�����w������{���w��n�x�i�S�㎵���A���Z���|���O�N�j�Ȃǂ������ł��ˁB���̃}�[ �N���A�g�����u����Ȃ̂ǂ��H�v���Ă��`���ɂȂ����̂ł���B
�\�\�@���^��Ɩ��͏��������A���̑��̕����͎ʐA�ł��ˁB
�����@ �����ł��ˁB������������ȑS�W�̃^�C�g���͏��������ł����ˁB�w���E���w�S�W�x�i�S�Z�㊪�A���Z�Z�\���Z�N�j��w�}�����E���w��n�x�i�S���㊪�A��� ����\�㔪�N�j�������ł��B�S�����炢�̑S�W�͏��������ɂ���̂��A�Ȃ�ƂȂ����܂莖�̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�k�c�c�l
�����@����k���������� �����w�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�x�l�́u�}�����[�}�����ژ^�v�Ƃ������������A�I�t�Z�b�g�łȂ����łʼn����Ă����ł��B�����獕�X���Ă���ł��傤�B�����ɂ��}���� �����A�����ċg������D�݂ł��ˁB
�\�\�@�u�g������D�݁v�H
�����@��قǂ��\���グ ���悤�ɁA�ϋv��������A��������Ƃ����d��������Ƃ����̂��傫���ł��ˁB�u�{���Ă��̂͏d���Ȃ�����v���āA�g������A�悭����������Ă܂����B���� �������Ђ̑����{���o���オ��ƁA�܂��d���i��3�j���� �ŗʂ��ł���B�u���̏d�݂������v���āi�j�B�����āu�O�������Ȃ��A���ǂ��Ȃ��A���N�����Ă����I�ɒu���Ă��邳���Ȃ��{�������v�Ƌg������ ����������Ă����̂͊o���Ă��܂��B�i145�j
����ɂ��ẮA���₩�Ȃ������܂��A���܂Ōo���Ă��O�������Ȃ����́A�Ό��ɌÂтȂ����́A�V���v���ŗ������Ă��邱�Ƃ��悵�Ƃ���Ă��܂����B�� �������Ă��܂����Ƃ����F����ŁA�C���L�̐F���͂��낢�날�邯��ǁA�������܂����ȂƋ�������������Ă��܂����B���ꂩ��A�u�`�v�Ƃ������̂� ���ɑ厖�ɂ���Ă��܂����ˁB�i147�j
�k�c�c�l�p���ނ͂��̓��e�ɂ�đ����̉ؑf�̍��ʂ͂��邪�C���đԓx�Ƃ��Ă͖�C�q�\���q�����Ă��B�Ȋw�� �ɂ��Ă͒P ���������c�����𑽗ʂɂ������B�܂葽���̘A��ɂ��̒P��������������߂ł��B�V�����e�̑n��ނł���ꍇ�́C�n�쏑�̏ꍇ�Ǝ����n�ĉߒ������͂� �Ȃ���Ȃ�Ȃ����C�������e���P�����̏ꍇ�Ƃ͈قĂ��Ƒ��l�ł���킯�����炻�̓_���Ǝ�������ӁB�P���̏ꍇ��肸�ƒq�\�I�Ɉ��Ă����B ���Ɨތ^�I�ɂȂ�B�����Ȃ��ƈ���̖{�ɂ͓K�����Ă����ɂ͕s�K���Ƃ��ӗl�Ȕj�ڂɊׂ�B�������S�̂�ʂ��Ă̐S���������ɐ������đ��Ă���B���� �đp���ɉ��ẮC���I�ŗ�����ꂽ�ꍇ�̔�������\�ߍl�ւė��Ă���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������Ƒ�ς������C������ԂƂƂĂ����邳���āC�������ď��� ��ʂƂ��ӗl�Ȃ��ƂɂȂ�ʗl���ӂ���K�v������B�i�q���{���p�̍\���r�A�s���{�̋Ɓt�A�ꎵ��y�[�W�j�g�������t���ȂɌ�������Ƃ��A����Ƒ卷�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���Ȃ킿�k������{���{�S�W�l�ɂ����鉶�n�̍��@���悭�w��ŁA�}�����[�̑S�W���p���� ���̊�Ղ�z�����̂ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�i��1�j
�|�v����́q����ɏA���Ă̎��̈ӌ��r�i���o��
�s�V���t1924�N11�����j�Łu���ǂ̏��́A�����̍D�݂ɏ]���Ď����ő��ꂷ��Ȃ�A���{���֒������Ď����̍D�݂ō�点��͂��̂��̂��B���ׂĂ̖{
�́A�t�����X���ȉ�����ő�R�Ȗv�i�s����f�U�C���t�s�G�E�u�b�N�X�A2005�N4��11���A���y�[�W�j�Ǝ咣���Ă���B�������˗����ꂽ���l�̒�
���͑[���Ƃ��Ă��A���g�̒����ɂ͒|�v�̑�������������Ǝ{����Ă���̂�����A�u�t�����X���ȉ�����ő�R�v�Ȃ̂́u���ׂĂ̖{�v�ł͂Ȃ��A�|�v���ǂ�
�|�v�ȊO�̐l�Ԃ����������{�ł����Ȃ����낤�B
�i��2�j�k���㕶�w��n�ʍ��l�Ƃ��ċg�c�����s������{���w�j�t�i��
���i�j�����s���ꂽ�悤�ɁA�k������{���{��n�ʍ��l�Ƃ��ĉ��쌒�j�s���㕶�{���y�L�t�i�i�j��1968�N8��25���ɒ}�����[���犧�s����Ă���
�i���������̕ʍ��͋g�����̑����ł͂Ȃ��悤���j�B�Ȃ��s���㕶�{���y�L�t�����ɂ͋g�c����ҁq������{���{�N�\�r���t����Ă���A����͋g�c���g�́s��
����{���w�j�t�f�ڂ̔N�\�̑�������łɂ�����B
�i��3�j
�`�̎d�l�́A��ꔪ�~��l���~�����[�g���E�l�ܓ�y�[�W�E�㐻�N���X���E�@�B���B�d���͋@�B����50g�A�{�̂�725g�B�a�̎d�l
�́A��ꔪ
�~��l���~�����[�g���E�l�O�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�\���B�d���͓\����115g�A�{�̂�765g�B���Ȃ݂ɖ{�̂ƕʍ�������\����
���߂�
�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�͑S�̂Ŗ�2.6kg�B
�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�����s���ꂽ�B�����{���̊��s�\���m�����̂́A������S������ѓN�v����̃u���O�ɂ����Ă������B��ʂɏ��Ђ̊��s�\���́A��悪�����Ƃ��ς܂��āA���Ƃ͍�Ǝ��Ԃ𓊓�����Δ��s�ł���Ƃ����m������ꂽ�i�K�ŃI�[�v���ɂȂ�B���s���\�����ꂽ���Ƃ́A�ǎ҂͖{�����X�ɕ��Ԃ̂�҂����Ȃ��킯���B�Ƃ��낪�т���́A�{���̃��C�A�E�g�i2014�N�̌㔼�������Ƃ����j���I���ĕ\���܂��̍�Ƃɓ������i�K����A���{�E�����̐i�s��Ԃ��u���O�Ō��J����Ƃ����u�������p�v�����œǎ҂̑ҋ@���Ԃ肠���Ă��ꂽ�B�H�L�Ȃ��Ƃł���B�����܂ł̂��̗l�q�́A���N1�����{����4���ɂ�����6��ɂ킽���āsdaily-sumus2�t�Œ��p����Ă���A����2�x�قǃR�����g���������B�����[�����ƂɁA�q���e�̐X�@�}�����[�̑���1940-2014 �čZ�r�Ɍ�����u�g������Ǝv����O�i�����L���v�Ɋ֘A����L�����A6�N�O��2009�N6��16�����q�g���̃T�����c�r�ɂ��łɓo�ꂵ�Ă���i�u�^���v�Ƃ͉��������낤���j�B
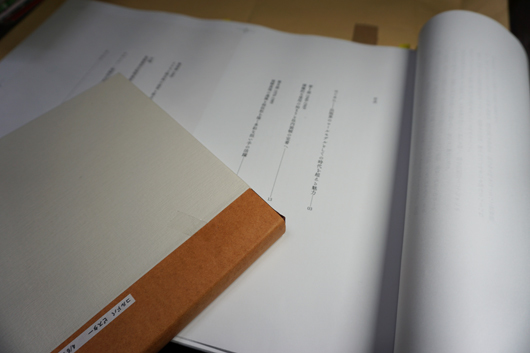 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�sdaily-sumus2�t�Ɍf�ڂ��ꂽ�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�k�����F�ѓN�v�l�̐����`����ʐ^�i�o�T�F�������f��1�A3�A4�j�Ɠ����̖{���ƕ\���i������E�j
�Ғ��҂̉P�c��������́A����܂ł�5���̒P�����o���Ă���B�s���ꎞ��t�i�����ЁA1999�j�A�s���㑕��t�i���w�o�ŁA2003�j�A�s�����`�\�\�{��v����d���l�����k���}�АV���l�t�i���}�ЁA2004�j�A�s���Y�N���̃f�U�C���k���l�t�i���A2010�j�A�s�H��ɕ���\�\���肽���Ȃ���������t�i���E�ЁA2014�j�ł���B�g���̑����́s���ꎞ��t�Ɓs���㑕��t�ŐG����Ă��āA�O�҂́q�g�����E�Ȑ܋v���q�\�\�o�ŎЂ̃J���[�����������́r�͋g�����̑����Ɠ����ɒ}�����[�̑����Ɋւ���ł��d�v�ȕ��͂̂ЂƂł���B�������т��сs�q�g�����r�́u�{�v�t�ň��p�����Ă�������B����܂ł̉P�c�{�������Ƃ�u�b�N�f�U�C�i�[�Ƃ����ŗL��������ɂ������j������ł������̂ɑ��āi���Y�N���_�����������ƁA��������������H��ɂ�ɁA1970�N��ȍ~�̎�҂����̌Q����`���������肩��A�P�c����̑Ώۂւ̔�������ς���Ă����悤�Ɏv���j�A�{�������ň����������̑�\�I�����Ƃ��Ē}�����[�̊��s������肠�����̂͗��ɓK���Ă���B�������ł������炵����������̒ʎj��`���̂ɁA���Ђ̏o�ŕ��قǂӂ��킵�����̂͑��Ɍ��o�����������炾�i���̗v���́A��o�̖{���ѕ��ɏڂ����j�B�}�����[�̑n�Ƃ�1940�N�A�g���������Ђɓ������̂͐���1951�i���a26�j�N�ł���B
�@�Ƃ���ŁA���̔s���̋�ߎ�����A�}�����[�͂ǂ������w�e�ł�����ʂ��Ă����̂��A�肩�ł͂Ȃ��B�����܂��茳�ɂ���A��ԌÂ��Ј����������ƁA���O�i���a�j�N�ꌎ����t���̂��̂�����B�܂�A���͂Ō��u�����v�������O�̋ꋫ����̂��̂ł���B���������ƁA���E�P��E�����̎O�ږ�������āA�Óc�ȉ��O�Z�l�̍\���ɂȂ��Ă���B�s����r�I���������ɂ��̐l���ɒB���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�������d������{�m�}�}�n�̉����������Ƃ����悤�ȏ������̂�����A���̐l�����H�ׂĂ����̂͑�ςȂ��Ƃł������Ǝv����B�i���������s�F �P��g���ƌÓc��Ɓ\�\�o�łɏ�M��R�₵�����U�t�g���[�A2013�N11��28���A��l���y�[�W�j
���������ꓬ��������ꂽ�o�ŎЂ��A����ł����邢�͂���䂦�Ɏ�ʂ̂悤�Ȉ������݂����Ă��������Ƃ͋��Q�ɒl����B������x���Â����l�тƂւ̈،h�̔O���}���������B���������z�������e�ł��ǂ����̂��{���ł����āi�Ō��͓��̒}�����[�ł͂Ȃ��A�݂��̂�o�ł����j�A�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�Ƃ̌������Z�����Ƃ͉��߂ďq�ׂ�܂ł��Ȃ��B��Ɉ��������������s�F �P��g���ƌÓc��Ɓt�̊����Ɂq�����ɂ��ār�Ƃ��������̎Q�l�E���p�����̈ꗗ���ڂ��Ă���̂ŁA�E����B���̂��������������s�Óc��L�O�َ����W�t�́A���K�s���}���قɖ₢���킹�ē��肷�邱�Ƃ��B

�s�k�n��50���N�l�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�̃W���P�b�g�E���ƎN�����ҁs�Óc��L�O�َ����W�t�i�Óc��L�O�فA2003�N10��30���j�̃W���P�b�g
��������Ă��킩��悤�ɁA1��2�̊Ԃɂ�1973�N10��30���̌Óc��̎����������B�}�����[�Ƃ́A1970�N��̏��߂܂ł́A�Óc��̕ʖ��������B�n��30�N�߂�1970�N�ɂ́s�}�����[�̎O�\�N�t���i�Ƃ��āA������50�N�߂�1990�N�i�g�����̖S���Ȃ����N�j�̗��N�ɂ́u�n��50���N�v�Ɗ������s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�\�\�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�u���̒[�����ƃO���}���X���������ċg�����ƐΉ��l�q�̃n�C�u���b�h�Ƃ������ׂ�������L����̌����钆�����ق�̑���v�i�M�{���n�j�\�\��9,800�~�Ŏs�̏��ЂƂ��āA���ɏo���B�����A70�N�߂�2010�N�ɂ͑�K�͂ȎЎj�������̊��s�͂Ȃ��A���N�ɘa�c�F�b�s�}�����[�̎O�\�N 1940-1970�t�Ɖi�]�N�s�}�����[�@���ꂩ��l�\�N1970-2010�t���o�����̂́A���ʍɂ����߂��̔��̂��߂̐}���ژ^�ȊO�͍���Ȃ������B�n��75�N�̍��N2015�N�A���̌��������ė]�肠��{�����A�œK�̒��҂Ƒ����҂Ċ��s���ꂽ�B�P�c����͏��Ђ�G���̐��쌻���m��A���������ƃO���t�B�b�N�f�U�C������Ƃ��鏑����ł���A�т����PR���s�����܁t�̕\���G��S���������Ƃ������Ƃɂ��āA�Ï��ɒʂ����u�b�N�f�U�C�i�[�ł���B���̓�l���g�ȏ�A�u�ӂ��̖{�v�ɂȂ�Ȃ����Ƃ͖ڂɌ����Ă���B
�Ȃɂ͂Ƃ�����A�g�����Ɋւ���L�ڂ����邱�Ƃɂ��悤�B�{���̊����ɂ́A�Ғ��҂ƃu�b�N�f�U�C�i�[�i�g�ŒS���ł�����j�̘J��q�f�U�C�i�[�E����S���җ����{�����r������B���̋g�����̍��̃y�[�W�m���u���ɁA�f�ڂ���Ă�����e�̂���܂����L����B�Ȃ��y000�w�@�x�z�̐����͐}�Ŕԍ��A�����E�����͏��e�i��������J���[�ʐ^�j�ł��邱�Ƃ�\���B
����t�����L���͖{���ɏ��o�B���̗ѓN�v�E�Ȑ܋v���q�E���c�N�v�́A��������g����������]�����ł��d�v�ȏ،��̍Ę^�B199�y�[�W�i�����ɂ͌f�o����Ă��Ȃ��j�ɂ́q�}�����[�̎O�i�����V���L���r�������āA����͋g���Ɍ��y���Ă���B��T���E��U���̂����肪�s�}�����[�̎O�\�N�t�E�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�ɑΉ����邱�Ƃ͋��R�ł͂Ȃ����낤�B�����āA��V�����܂ޑS�̂��s���e�̐X�\�\�}�����[�̑���1940-2014�t�ɑΉ����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�����Ŗ{���̑ѕ��������āA���̊��s�Ӑ}��T���Ă������B
�}�����[�͂킪���̑��ꕶ�����A������킸�L����˂��J���Ă����悫�`����̌����Ă����̂ł���A�܂��ɂ��̕��݂́A���ꕶ���̏k�}�ł���A�݂��ƂȌ����}���Ƃ����Ă悢�B���ہA���͂���قǂ̃��[�����f�����ق��ɒm��Ȃ��B�}���{�̎��㐫�������тł���A���тȂ����͂ł���B�{���́A�}�����[�̑���Ɍg����������̃f�U�C�i�[�A�ҏW�ҁA�Г��f�U�C�i�[�̎d���̏Љ���Ƃ����āA���͂��ӂ��L���Ȏ���̌n����W�]���悤�Ɗ�}�����B���̂��ƂŁA�킪���̏o�ŕ����j�ɗނ��Ȃ���䊂���ƂƂ��ɁA�o�ŊE�̂ЂƂ̎w�W�ƂȂ��Ă��铯�Ђ̑��ꂪ�ʂ����Ă�������𑽊p�x���畂������ɂł���A�Ǝv���B
�ȉ��ɁA�{���ɓo�ꂷ��f�U�C�i�[�E����S���Җ���������B�����j�̗��ꂪ�킩��₷���悤�ɐ��N���i�{���̍�����50�����j�Ɍf���邪�A��䍎�V��1888�N���܂�A���˕�����1979�N���܂�ł���i�_�c���a�^������q�q�^�~���L�B�E�C�\�x�͐��N���ڂ܂��͖����J�j�B
��䍎�V
���n�F�l�Y
����ꐭ
�R��Y
�n�ӈ�v
���O
�ɓc叕
�ԐX����
���Ԋ�
�g����
�c���`��
�������
�Ȑ܋v���q
����
�c�����
���Y�N��
����N�j
�V��S�g
���[����
�����j
���c����
�c���Ԍh��
�i�C
��������
�a�c��
���c�i
�Ή��l�q
����b��
������
�e�n�M�`
�����W��
�������ق�
�n�Ӑ�q
���c��
���헲�F
�H�Ǒ����g
��L�V
���������Y
��������
�v�ې���
���ΏC�u
���V�
��؈ꎏ
�]���ʗz
�ԑ��r��
������V
���Y�����q
�c���]�T
���c���b
�N���t�g�E�G���B���O�����k�g�c�čO�l
��ؐ���
�L�R�B��
�ؒ�M�M
���˕���
�@��
�_�c���a
������q�q�k�NjL�F�i�]�N�s�}�����[ ���ꂩ��̎l�\�N�@1970-2010�k�}���I���l�t�i�}�����[�A2011�N3��15���j�ɂ��A1944�N���܂�l
�~���L�B�E�C�\�x
���Ԋ��i1919�`2003�j�͋g�����Ɠ��N�̐��܂ꂾ���A��䍎�V�i1888�`1969�j�^���n�F�l�Y�i1891�`1955�j�^����ꐭ�i1893�`1991�j�^�R��Y�i1901�`79�j�^�n�Ӂi�n粁j��v�i1901�`75�j�^���O�i1903�`86�j�^�ɓc叕�i1907�`94�j�^�ԐX�����i1911�`78�j�������A�����ɂ�����g���̐�y�i�ɓ�����B���̂Ȃ��ŋg�������y�������Ƃ�����̂́A���n�F�l�Y�������낤�B�}�����[�ł̋g���������̃��[�c��T�邤���Łk������{���{�S�W�l����|���������ƁE���n�̑��݂͑傫���B���̂�����̂��Ƃ͍e�����߂Ę_�������B
�}�Łi���e�j�╶�͖͂{���ɂ��Č���ɔ@���͂Ȃ����A�����������Ȃ��̂́A�{���Ɛ}�ł����ꂱ��Q�Ƃ��ēǂ�łق����Ƃ����Ғ��҂̈ӌ���������Ȃ��B����قlj��x�ł��y�[�W��|���Č��A�ǂނׂ������Ȃ̂ł���B���傤�ǁs�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�������ł���悤�ɁB���������Ȃ��ŁA�t�^�́q�}�����[�o�Ŋ֘A�����}�Łr���ʔ����B�g�����f�U�C���E���C�A�E�g�������e���{������̂��낤���B�Ō�ɂ��̏����̉��t��^���邱�ƂŁA���M�E�Ҏ[�A�g�ŁE���{�E�����A����ѐ���Ɋւ�����l�l�Ɍh�ӂ�\����B�����܂ł��Ȃ����{�͏c�g�ŁA���i����ɂ��Č��ŁA�\���ł͂Ȃ����j������̂��y�����A�т���炵�������ȃ��C�A�E�g�B
���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014
��Z��ܔN�܌��O���@���ő������s
�Ғ��ҁ@�P�c����
���s�ҁ@��������
���s���@�݂��̂�o��
�R�����哇�S���h�哇�������������k�l�� ���斯�ٓニ
�����l��\�Z�Z
�d�b�E�t�@�N�X ������Z�\�����\�ꎵ�O��
E-mail ; �k�ȗ��l
URL ; http://www.mizunowa.com
��拦�́c�c�c�c�c���c�i�^���c�N�v�^������q�q�^�ѓN�v
��ދ��́c�c�c�c�c���������Y
�f�ږ{�c�c�c�c���c�i�^���������Y�^�ѓN�v
�֘A�}�ŁE�����c�c�c���c�N�v�^�ѓN�v
����c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c������ЎR�c�ʐ^���ŏ�
���{�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c������Џa�J����t
����{�G�f�B�g���A���f�U�C���c�c�c�c�c�ѓN�v
�v�����e�B���O�f�B���N�V�����c�c�c�c�c���q�V�^���c�T�F�i������ЎR�c�ʐ^���ŏ��j
© Shoji Usuda, 2015�@Printed in Japan�@ISBN978-4-86426-032-9 C0071
�k�NjL�l
2015�N5��19���A�_�c�_�ے��̓��������X�̃z�[���ʼnP�c�����E���c�N�v�E���c�i3���ɂ��s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�̊��s���L�O����g�[�N���C�u���J�Â��ꂽ�B�Ғ��҂̉P�c����ƕ��Ԃ��̖{�̂����ЂƂ�̗����ҁA�u�b�N�f�U�C���S���̗ѓN�v�����7���ɍT������i�W�̐���̂��ߌ��Ȃ������̂��ɂ��܂��B�݂��̂�o�ł̖�����������̈��A�̂��ƁA�P�c���@��̒��������Ă���ԁA�ҏW�҂Ƃ��Ē}�����[��40�N�ԁi���Ђ͍��N�n��75�N������A�����ȏ�I�j�߂����c����������B���Ђ���1969�N�����A�P�s�{�͂���قǂȂ��A�p����l�S�W�Ƃ������S�W�ނ������ēy�ǐF�̖{����ŕς������Ȃ��Ɗ��������A������o���Ă݂�ƑN�₩�ȃN���X�̕\���������B���l�ł��������g���������������l�S�W�ŁA�V���v�������͋����}�����[�̑����̃C���[�W���������̂�����炾�����A�Ǝ��_��W�J�����B���̌�͉P�c�����삷��s���e�̐X�t�̃L���v�`���[�摜�����Ȃ���A���c�����������3�l�ő�����i�ɃR�����g���Ă����`���Ői�B���e�������Ƃ킩��ɂ����Ƃ��́A��L�V�����ɂȂ�Ԑ��쌴���s�V�l�́t�i1998�j�ȂǁA���Ɏ������������̌��{�����ꂽ�B�����̃�������ɁA��ۓI���������ڂ�I��ŋL���B
�ق��ɂ��A�����[���w�E�ɏ[����2���Ԏ�ł������B������ׂ��Ƃ��ɏЉ�ł���A�Ǝv���B
�k2018�N4��30���NjL�l
�g�[�N���C�u�����A�����ƂŃC���X�g���[�^�[�̌j�쏁�́q�w���e�̐X�x�i�݂��̂�o�Łj�ɂ��ār�i���o�́s�o�Ńj���[�X�t2015�N8����{���j�Łu���l�Z�N�n�Ƃ̒}�����[�̑����X�^�C���́A���Ђ̃}�[�N���f�U�C�����A���n���̑�����S�������R��Y�Ɏn�܂�A���n�F�l�Y�����ɂ���q�b�g�u������{���{�S�W�v���o�āA���l�Ƃ��Ă��m��ꂽ�Г��f�U�C�i�[�g�����m�݂̂�n�ɂ���Ċ������ꂽ�A�Ƃ����̂��O�l�k�P�c�E���c�E���c�l�̈�v�����������B�}�������̓����́A�Z���^�[���킹�ŃV�����g���J���Ȋi�������X�^�C���B�}������o�ł����������������t�����X���w�ҁE�n�ӈ�v�̑������}���X�^�C���Ƃ҂���Əd�Ȃ�B�[���Ȓ}���X�^�C���́A�Ȑ܋v���q�A�������ق�A���������Y�Ƃ��������͔h�̎Г��f�U�C�i�[�Ɉ����p����A�܂��ЊO�X�^�b�t�ɂ��d�����A�����ƒ}���X�^�C���f�����V�����g���J���ȑ����������B����Ă�킸�A���M�����A���m���ԁn����̂悤�ȑ������肾���A����Ȗ{�̊炪�����قǑN���ɋL���ɏĂ��t���Ă���̂͂Ȃ����낤�B�k�c�c�l�}�������ł́A�\�ʓI�ȃf�U�C���Z�@�ł͂Ȃ��A�{���܂邲�ƕ҂�ł����͂����߂�ꂽ�B���c���u�}���ɂ͕�����ǂނ����ł͂Ȃ������ꂽ�ҏW�҂����������B����ɐs����v�ƌ���Ă����̂���ۓI�������v�i�s�����A���ꂱ��t�ʗ��ЁA2018�N1��30���A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j�Ə����Ă���B���̒m�肦���A�����̑����Ƃɂ��{���Ɋւ���ł��^���Ȕ����ł���B
��o�r�K����\�߂�q�{�̉�r�͍��܂ł�350��ȏ�̗����J���Ă��邪�A���ׂĂ݂�Ǝ��̓����̋Ζ���A�t�o�t�̋g�V�����u�w�G�X�N�@�C�A���{�Łx�̑D�o�v������ɍu�t�Ƃ��ė��Œ������̂�1989�N2���������i�g�V����͓����̑n���ҏW���j�B���̂Ƃ��͔����Ɩ��݂����Ȍ`���������A�����[������ƍu�t�̂Ƃ��ɂ͎��Ԃ�s�����Ē����ɍs�������̂��B�P�c��������i2000�N4���́u�����̉ߋ��E���݁E�����v�j�⏼�c�N�v����i1990�N1���́u�}�����[��50�N�Ɓg���w�̐X�h�v�j�A�I�c����Y����i1992�N6���́u���e���{�Ɍ���o�ŏ��a�j�v�j�Ə��߂Ă��ڂɂ��������̂��q�{�̉�r�̗��Ƃ��̓�ł������B���������A�ѓN�v����ɏ��߂Ĉ��A�����̂������Ï���قł̃g�[�N�C���F���g�ł������B�s���e�̐X�t�̃g�[�N���C�u�̂��ƁA���Q�����ۑ��p�̈���ɉP�c���珐�����Ă�����������łȂ��A�P���ŖZ�������Ă����������A����ɂ͏��c����ɂ��T�C���i����G����j���Ă����������B���̂��Ƃ�т���ɕ�����A�����Ă����Ώ������ĕԑ�����i�j�ƕԎ����������B�т���A���x���ЁB�}���{�̘b�����낢�뒮�����Ă��������B
�k2016�N10��31���NjL�l
�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�j���A��50�{����R���N�[���œ��{���Џo�ŋ�������܁k��发�i�l���Љ�Ȋw���E���R�Ȋw�����j����l����܂����B��Ɏ҂̔��\�Ɂu�����F���e�̐X�\�}�����[�̑���1940-2014�^�o�ŎЁF�݂��̂�o�Ł^����ҁF�ѓN�v�^�����ЁF�R�c�ʐ^���ŏ��^���{��ЁF�a�J����t�v�Ƃ���悤�ɁA���m�u�c�n�Ƃ��Ă̖{���]�����ꂽ���̂��B��47��́A���R���N�[���̉����i�̂������ꂽ���̂́A��������}���ق́u�����k���E�J�o�[���̊O�����܂ށl�ۑ��R���N�V�����v�Ƃ��ĕۑ�����邱�ƂɂȂ����Ƃ�������A���X�ɓK�����[�u�Ƃ����悤�B�����̃f�W�^���������\�����i�ٓ��{�������ł��Ȃ��̂́A�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��j�A���̑��{�������������ꂽ�o�ŕ�����ʏ�Ŏ����Ƃ���łȂ�ɂȂ낤�B�܂�ɂӂ�Ė{���������āA���ׂ���肪�z�킸�ǂ݂ӂ����Ă��܂��̂́A���m�u�c�n�Ƃ��Ă��Ƃ���������ł���B�P�c����A�т���A��������A�����Đ���Ɍg��������m�̑����̕����ɏj�ӂ�\����B��܁A���߂łƂ��������܂��B
�Ȃ��q�g�����̑�����i�i1�j�r�ŐG��Ă���s�Z�{ �{�V�����S�W�k�S14���i15���j�l�t�i�}�����[�A1973�`1977�j�͋g�����������\������̂����A�u�攪�{����R���N�[���ŁA�{�S�W�����{�}���ً���܂���܁v�i�}�����[�́s�V���j���[�X�t�j���Ă���B
�\�\�����ꂽ���́A��Ɍ����Ȃ����̂ł���A�`���ꂽ���́A���̎p�����邱�Ƃ��ł���B�������l�́A�g�߂Ȍ��t�ɂ���čl����B�`�����l�́A��Ɍ�����g�߂Ȍ`�ۂɂ���čl����B�����ꂽ���̂Ƃ́A�v�l�̊�Ɍ����Ȃ��`�ʂł���A�G��Ƃ́A���̊�Ɍ�������̂̕`�ʂł���B�i���l�E�}�O���b�g�q���Ƃ́c�c�r1967�N��e�j
�i�s�u���l�E�}�O���b�g�W�v�}�^�t�����V���ЁA1994�A�k�܁Z�y�[�W�l���j
�g�����͐��z�q��ȓ��̂��Ɓ\�\�O�D�L��Y�r�i���o�́s�O�D�L��Y���W1946�`1971�t�x�q�l�ƍ�i�r�A�T�����I�A1975�N2��15���j�����̂悤�Ɍ���ł���B
�@���ւ̎��̕������̂����ƁA���������ŋ��̏����̂悤�Ɉ�i�������ɁA��ȍ��~������̂��B�����ɂ́A�҂��҂��̓Ó��I�ȑ哪�̒j�������Ă����B����͂킪�s���l�t�̎O�D�L��Y�ł͂Ȃ����B���͂���Ƌ~��ꂽ�v���ɂȂ�B�����ŗ]�T�̏o�����͂܂��܂��ƁA���͉��̂��Č���̂��B�܂�Ń��l�E�}�O���b�g�̊G�̒��̐l���̂悤�ɁA�����ׂ��j����������ƌŒ肳��Ă���悤���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z��`��Z��y�[�W�j
�����Ŏ��͕s�R�̔O�ɂ�����B�}�O���b�g�̊G�Ɂu�҂��҂��̓Ó��I�ȑ哪�̒j�v�����������낤���ƁB��߂ȃ}�O���b�g�̉�W�́A�ǂ���݂Ȏ��^��i�̐������Ȃ��ĐS���ƂȂ��̂ŁA400�_�ȏ�̃J���[�}�ł��f�ڂ���Robert Hughes�����sThe Portable Magritte�t�iUniverse�A2002�j���Ђ��Ƃ��B�����ƌ����Ƃ���҂���Ɠ��Ă͂܂��i�͂Ȃ��������A�qLe Discours de la methode�i���@�����j�r�i1965�j���߂����B�}�O���b�g�͓��{�ŏo����W��}�^�A�G���Ɍf�ڂ��ꂽ��i�������̂ŁA�g�������y�����G�����݂��Ȃ��Ƃ͌�������Ȃ��B����̒T���ɘւB
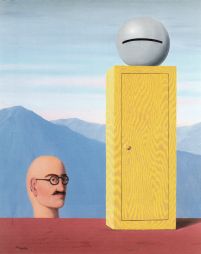
�}�O���b�g�̖��ʁqLe Discours de la methode�i���@�����j�r�i1965�j
�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�Ń}�O���b�g��T���Ɖ�W���o�Ă����̂ŁA�L�ڂ������i�l���̊����̓}�}�j�B�g�����{���ɖڂ�ʂ��Ă��邱�Ƃ͊m�����B�Ȃ��s�}�O���b�g�̓��{��ʼn�W�t�ɂ��A����́u1971�N�̓��{���̃}�O���b�g�W�J�Âɂ��킹�ďo�ł��ꂽ����1000���̉�W�v�ŁA�g�������̓��{���̃}�O���b�g�W�A���Ȃ킿���������ߑ���p�فi1971�N5��22���`7��11���j����ы��s�����ߑ���p�فi7��20���`9��5���j�ŊJ���ꂽ�s���l�E�}�O���b�g�W�t���ςĂ���\���͂���߂č����B����Ƃ����̂��A�g�����ҏW���Ă����s�����܁t��27���i1971�N7���j�ɉ��c���F�́q���Ă��邱�Ɓ\�\�}�O���b�g�̓�d�̃C���W�r���f�ڂ���Ă��邩�炾�B���c�͓����s�����܁t�ɃG�b�Z�C��A�ڂ��Ă���A���W�����������ɂ��āA�}�O���b�g�ɂ��ď����Ƌg���Ɍ������������Ƃ��낤�B
���l�E�}�O���b�g��W
���l�E�}�O���b�g�ɂ��āi�G�~�[���E�����M�j�@���l�E�}�O���b�g�̐��E�i�a�F�j�@��i����i�����q���j�@��
����@�u��I�q
�a�S�ό^���^�㐻�E�����^�}��106�_�@�����46��
1971�N12��21���@14,000�~ 4384
32�_�̃J���[�}�ł�\�肱���̑唻�̉�W�ɂ��u�҂��҂��̓Ó��I�ȑ哪�̒j�v��`�����G�͎��߂��Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�ژ^�̖����ɋL�ڂ���Ă��鐔���͌��{�ԍ��ŁA�}�����[�Г��Ő����̂��߂�1�_���ƂɊ��s���ɕt�������́i�������A���m���Ɩԗ����Ɍ�����j�B
�}�O���b�g�͋g�����̎��Ɉ�x�����o�ꂷ��B�ѓ��k��̌��t��莫�Ɉ������q���J�̎p������r�i�H�E14�j�ł���i���o�́s�C�t1978�N5�����j�B���́u2�v�̐߂̑S�s�͂������B
�ڂ��́q�댯�Ȏv�z�r�Ƃ������̂�
������������������̂��Ǝv��
��ɂ͏t�̎���
�u�}�O���b�g��
���
����y������ł���v
�����Ɉ��p���ꂽ����̏o�T�{���������r�Y�́q�ӏ܁r���A���̐߂Ɋւ��Ắu�ѓ��k��̈��̊y�V���ւ̋����B�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A��l�l�y�[�W�j�ƋL�������ŁA�o�T�𖾂炩�ɂ����Ă��Ȃ��B�����Ƃ��g���́A������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����j�ň��p���ɂ���
�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB�k�c�c�l�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ����ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���B�i�����A��Z�y�[�W�j
�Ɣ��l���Ă��邭�炢������A�u�@�v�������p���߂���ѓ��̕��Ȃ̂��A�g������́u���p�v�Ȃ̂��킩��Ȃ��B��������Ō��y����Ă���̂̓}�O���b�g�̖��ʁqLe Chateau des Pyrenees�i�s���l�[�̏�j�r�i1959�j�ŁA3�s�߂́u��ɂ͏t�̎����v���ォ��}�����ꂽ���Ƃ��l�����킹��A1�`2�s�߂����ѓ��̌��t�ŁA4�`6�s�߂͋g���������̌��t���u�@�v�Ŋ����ă��A���e�B���炵�߂Ă���A�Ƃ����������琬�肽�B
�Ƃ��ɁA�g�����}�O���b�g�̖����������ɂ��̊G���X���X�Ƃ������̑����q���́r�i�F�E3�j�ŁA����ɂ��Ă��q�q���́r�̃X���X�Ƃ��Ẵ}�O���b�g�G��k�NjL�l�r�Ő}�ł��f�����B���]�߂̖{���Ɓk�NjL�l�ɕt�����킦��ׂ����Ƃ͂Ȃ��B
����Ɂs�Ẳ��t����A�}�O���b�g�̖��͓o�ꂵ�Ȃ����A�}�O���b�g����݂̈�сB�q���J�̎p������r�Ɠ��l�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�ɂ����߂��Ă���A������͒Ǔ����B
�����ł͂ЂƂ͐^�Ɍ��Ă͂��Ȃ���͋g�����{��~�i1933�`77�j�ɕ������q�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�Ɍ����鎍�傾���A���̃X���X�͋{��́s���ЂƊ፷�Ƃ̂������Ɂt�Ɏ��߂�ꂽ�q���l�E�}�O���b�g�̗]���Ɂr�́u�s�\�ʁt�ɂ��čl���Ȃ���A���Ƃ��Ε\�ʂƂ��̂��܂��܂Ȕh���I�ȕ\���ɂ��āA�\�ʁm�A�A�n�A�\�ʓI�m�A�A�A�n�A�\�ʉ��m�A�A�A�n����c�c�B�v�i�T�E���O�E2-3�j�ł���B���܈����ǗY�E�����O�E�푺�G�O�E�L�����E�����C����s�{��~����W�k�S3���l�t�i���p�o�ŎЁA1980�`81�j�\�\���Ȃ݂ɓ����͋g�����̑����\�\���J���Ă݂�ƁA�q���l�E�}�O���b�g�̗]���Ɂr�ɂ�
�\�ʁm�A�A�n
�\�ʓI�m�A�A�A�n
�\�ʉ��m�A�A�A�n����
�����̓���i��
���ɂ͂��ꂼ��̎��̂�
���p�Ɏv����
�i���C�X��L�������ƃ}�O���b�g�̊W�ɂ��čl���邱�ƁB�j
�Ƃ����͂Ȃ͂���ۓI�Ȉ�s���L����Ă���i�T�E���܁E6�j�B�����Y�ꂽ���A�i�T�E���܁E6�j�́s�{��~����W�t��T���A���܃y�[�W�A6�s�߂������B�s�{��~����W�t�̓������́q�\�ʂɂ��ā@���C�X��L�������r���J���ƁA�\�z�ɂ����킸�}�O���b�g����̈��p������B���Ȃ킿�u���̂͂��̔w��ɑ��̕��̂����邱�Ƃ�\�z������B�v�i�T�E�O�O�E6�j�ł���A�u���̂͑��ɂ����Ƃӂ��킵�����̂����o���Ȃ��قǂ��ꎩ�g�̖��̂ɖ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�v�i�T�E�O�l�E8�j�ł���B�s�{��~����W�t�Ɍ�����}�O���b�g����̈��p���A�����ЂƂf���悤�B
�킽���̃^�u���[�̓C���[�W����Ȃ�B�ЂƂ̃C���[�W�̉��l����`�ʂ͎��R�ւ̎v�l�̕����Â��Ȃ��ɂ͂Ȃ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�i�T�E�O�Z�O�E3-4�j
������u�킽���̎��т̓C���[�W����Ȃ�B�ЂƂ̃C���[�W�̉��l����`�ʂ͎��R�ւ̎v�l�̕����Â��Ȃ��ɂ͂Ȃ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ɠǂ݂�����U�f�ɂ́A�R�����������̂�����B�Ƃ��ɋg���́A�O�f�̑Βk�Łq�D���̎O�̒[�z�r�ɂ��ċ�����b�q�Ǝ��̂悤�Ɍ���Ă���B
�����@ �r�c�����v�̕��͖͂���������Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB�ƌ��������ۓI�Œ��ɔ������Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB
�g���@ ���ۓI�ł��Ȃ����ǁA���ɖ����ō��ɂ��������B�ŁA�y���F�̂ق��ō��₷�������͔̂ѓ��k��B����܂���Ȍ��t���Ă���킯�B�ڂ��ɂƂ��ĈӊO�Ȍ��t�ƌ������A���̌��t���K�v�ȂB���ꂾ�ƍ�肢���B������A����܂蕶�͂�����������������G�b�Z�C����́A���ɂƂ�ɂ����B�{��~�Ȃ��̍ł�����̂ˁB�{��~�͂Ƃ�Ƃ��낪���ɂނ��������킯��B������A���́A�O���̉�Ƃ̌��t�Ƃ����������̂��U��߂Ȃ��Ƌ{��~���͐��藧���Ȃ������B
�����@�{�삳��̕��͂��̂��̂����p���琬�藧���Ă���킯�ł����̂ˁB
�g���@�{��~�̂��߂́u�D���̎O�̒[�z�v�A���ꂪ��Ԃނ������������Ȃ��B�܂������炭���܂��������ĂȂ���Ȃ����Ǝv����B��i�Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂��Ƃ�����Ƌ^��ɂȂ�B
�����@�{��~������p�ł������Ȍ��t�Ƃ����̂́A�{��~���g���Ă��錾�t����Ȃ��Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��ł����ˁB
�g���@�����������Ƃ����邩���킩��Ȃ����ˁB���܂�ɂ����I�ȕ��̂ł��邽�߂ɂ������̊������ĂȂ������B�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A�㎵�y�[�W�j
�{��~��Ǔ����邽�߂ɋ{���i������p���悤�Ƃ���ƁA�n�̕��ł͂Ȃ����p���ꂽ���ɂȂ肪�����Ƃ����w�E���ʔ����i�����r�Y�́q�ӏ܁r�ɋ���A�u���́A�O���̉�Ƃ̌��t�v�̓}�O���b�g�̌��t�ł͂Ȃ��A�W�����W���E�u���b�N�̂���j�B�܂��A�ѓ��k���y���F�̌��t�͈��p���₷���āA�r�c�����v�̂���͈��p���ɂ����Ƃ������������[���B�{���r�c�ɔ��p�Ƃ�킯�G�悪��݂̕��������A��l�Ƃ��}�O���b�g�ɐe�t���Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���p���߂���g�����^���l�E�}�O���b�g�A���^�G��̔�r�����͑����̉ۑ���܂�ł���Ǝv����B���̍ہA�O�f���́u�q�댯�Ȏv�z�r�v�Ɓi�A���h���E�u���g���̒���j�V�������A���X���Ƃ̊W���ő�̑��_�ɂȂ邾�낤���A�����͂����{�i�I�ɘ_�����ł͂Ȃ��B�����������B
��
2015�N�A�����E�Z�{�̍����V���p�قő�K�͂ȁs�}�O���b�g�W�t���J���ꂽ�i�����3��25���`6��29���j�B�g���́A�O�q�̂悤�ɎU���Ǝ��Ń}�O���b�g�Ɍ��y�����A���z��N���ł̓}�O���b�g�i�W�j�ɐG��Ă��Ȃ��B1971�N����ł́s���l�E�}�O���b�g�W�t�i�a�J���}�S�ݓX�{�X�E�x�R������ٔ��p�فE�F�{�������p�فA1982�N8���`12���j�A�s���l�E�}�O���b�g�W�t�i�R���������p�فE���������ߑ���p�فA1988�N4���`7���j�A�����Ă���͋g���̟f�ゾ���s���l�E�}�O���b�g�W�t�i�O�z���p�٥�V�h�E��۔~�c�X��ۃ~���[�W�A���E�����s���p�فA1994�N11���`1995�N5���j���J����Ă���B�g�����ǂ����Ō�����ςĂ��Ă��������Ȃ��̂����A�}�O���b�g�̊G�͐}�łŊςĂ�����Ȃ�Ɋ������N���앗�Ȃ̂ŁA������A��ړW���ςĂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ����蓾��B���Ȃ݂Ɏ��͍��߂ă}�O���b�g�W���ς��B�}�łł��Ȃ��݂́qL'Homme au journal�i�V����ǂޒj�j�r�i1928�j��qLa Clairvoyance�i�����j�r�i1936�j��qL'Empire des lumieres,�U�i���̒鍑�U�j�r�i1950�j��qSouvenir de voyage�i���̑z���o�j�r�i1955�j�\�\�q���́r�̕]�߂��������҂ɂƂ��āA����͊ᕟ�������\�\��O�q�́qLe Chateau des Pyrenees�i�s���l�[�̏�j�r�i1959�j��Ƃ�킯�qGolconde�i�S���R���_�j�r�i1953�j�����\�����B�o�i����Ă��Ȃ������qLa Duree poignardee�i�˂��h���ꂽ�����j�r�i1938�j�́A�x���M�[���̔���ȊG�n�K�L�Ŋ�����₵���B�O��̉�ړW��2002�N�ABunkamura �U�E�~���[�W�A���i�����7��6���`8��25���j�ق��ŊJ���ꂽ�s�}�O���b�g�W�t�ł���B���Ắs���l�E�}�O���b�g�W�t�������̂��A����2��́s�}�O���b�g�W�t�ɂȂ��Ă���B���l�E�}�O���b�g�ł͂Ȃ��A�}�O���b�g�B����ɂ��A����20���I�̃��[���b�p�G��̋��������{�l�ɂƂ��āi�܂��܂��j�g�߂ȑ��݂ɂȂ������Ƃ̏����낤�B
�s�}�O���b�g/�~���k�T�����p�� 10�l�t�i���w�فA2000�N4��11���j�́q�}�O���b�g����\�\�u�����b�Z���ɂЂ��ޓ�̏��s���r�ɂ�������B�u���l�E�}�O���b�g�B1898�N�x���M�[���܂�B���i�͂��ƂȂ����܂��߁B15�ŏ������o�����A���̑����23�Ō����B�ƒ�������A���U�̂قƂ�ǂ��x���M�[�̎�s�u�����b�Z���ʼn߂����\�\�B�^�����A���̍�i�ɏo�Ă���a�m�����̂悤�ɁA�}�O���b�g�͂�������ӂꂽ���s���������B���Ȃ��Ƃ����̊O���́c�c�B�^����ǂ��̏��s���A���܂�ɂӂ�������Ƃ��낪�������ĕς��B�Ⴆ�A�ނ͂ӂ��̊i�D�ŁA�܂�O���낢�̃X�[�c�ɎR���X�Ƃ����i�D�ŁA�G��`�����B�A�g���G�͑䏊��H���A���Ԃ̕Ћ���]�X�Ƃ���B�ǂ̏��ɂ������ĊG������ڂ��Ȃ������Ƃ����B�^���Ԃɂ����m�������B�҂����킹���Ԃɂ������Ēx��Ȃ��B���Ƃ��F�l�̌|�p�Ƃ������A�ׂ̕����ŔM���ۂ��c�_���Ă���Œ��ł��A�҂������10���ɂ͏A�Q�B�قƂ�Ǐ�O���킵�����s���Ԃ�ł͂Ȃ����H�v�i�����A��Z�y�[�W�j�B��X���̃_�C�j���O�e�[�u���Ŏ��������\�\�g���́q����ɂ��ār�Ɍ�����u����ɔM�����Ă��鎄�̎p���A�����A���������ς��Ɋg����A�ƂĂ����ɋ����Ȃ��v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A��Z�Z�y�[�W�j�Ƃ́A�Ȃ�Ƃ��}�O���b�g�I�Ȍ��i�ł͂Ȃ����\�\�A�킪���L���̏o�ŎЂ̖����܂ŋ߂����炪���l�̂��Ƃ�z���B�g�����͑O�f�̋�����b�q�Ƃ̑Βk�ŁA�����������l�E�}�O���b�g���̐l�ł��邩�̂悤�ɁA��������Ă����B
������ڂ��̂̓V���[�����A���X���ł����ł��Ȃ��Ă��A��s�A�k��l�s���ׂă��A���e�B���Ƃ��������͂���̂ˁB����̏W�ςł�����ƈٗl�Ȃ��̂��ł��Ă�͂�����B�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�y�[�W�j
�Ō�́qLe Chateau des Pyrenees�i�s���l�[�̏�j�r�i1959�j�Œ��߂Ă��炨���B�}�O���b�g�̗F�l�ł���ٌ�m�n���[�E�g���N�c�B�i�[���A�j���[���[�N�̎����̎����� �́A�ׂ̃r���ɖʂ��Ă����c198�~��142cm�̑����ǂ����߂Ɂi�I�j�˗�����200�~145cm�̍�i�ł���i�}�^�s�}�O���b�g�W�t�A�ǔ��V�������{�ЁA2015�k���s�����̋L�ڂȂ��l�A��㔪�y�[�W�ɂ��j�B�p�r�ƃT�C�Y���w�肳��āA���ꂾ���̊G��𐬂��}�O���b�g�̖ʖږ��@���錆��B�g�����}�O���b�g�̍�i�Ƃ��Đ^����ɋ������Ƃ���ŁA�Ȃ�̕s�v�c�����낤�B

�}�O���b�g�̖��ʁqLe Chateau des Pyrenees�i�s���l�[�̏�j�r�i1959�j
�ےJ�ˈ�͑Βk�q�u�����v�̎��ƒZ�́r�Ŗx����{�ɂ������B
�ےJ�@�Ƃ���ŁA�u�A���\���W�[�����̎��v�Ƃ������t���p��ɂ����āA�u�A���\���W�[�E�s�[�X�v�Ƃ�����ł����ˁB����͂ق߂�ꍇ�ɂ��g����B�܂�A���\���W�[�ɂ悭����悤�ȁA�Ƃ����c�c�B
�x���@�����Ă���Ƃ����Ӗ��ł��傤�ˁB�킩����悭�ĉ��s��������B
�ےJ�@�����A���ꂩ�犄��ɒZ���B����ł܂�������ƌy�̓I�A�ے�I�ȈӖ��ɂ��g���邱�Ƃ�����B�܂薜�l�����Ƃ��ˁB
�@���[�Y���[�X�̐���̎��ȂA�Z���āA�F�ɂ悭�킩�邵�A�F�m���Ă���B�܂�F�Ɍ����肪���������Ƃ����̂ŁA�悭���������A���\���W�[�����̎��Ƃ������ƂɂȂ�B�i�ےJ�ˈ�s�G��łk���t���Ɂl�t���Y�t�H�A2015�N2��10���A�O�l�`�O�܌܃y�[�W�j
���̓`�ł����ƁA�g�����̃A���\���W�[�E�s�[�X�͂������߁q�Õ��r�i�B�E1�j�A�q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�Ƃ������ƂɂȂ�B�q�m���r�i�C�E8�j�͊e��̑I�W�⎌�؏W�Ɏ��߂��Ă��邪�A�A���\���W�[�E�s�[�X�ƌĂԂɂ͗ł����肷���͂��Ȃ����B�����A�Ό���H�ďC�E�V�����ɕҏW���ҁs�V�����Ƃ̔��\�\���ȏ��ŏo�����������Z�Z�k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA2014�N11��1���j�Ɏ��^����Ă���g�������́q�Õ��r�ł���B�����Ĕѓ��k��q���l�̋�r�ƈ��̂�q�q�킽������Ԃ��ꂢ�������Ƃ��r�̂������ɁA�x���Ɍ��o���ꂽ�؉��[���̐Ȃ��p�ӂ���Ă���B�q�Ђ�̂��r�ł���B�����Ɏ��^����Ă���̂́A�����Y�Ⓡ�蓡���ȂNJ��l���������Έ�l��т�����A���̎��l�̑�\��Ƃ������ƂɂȂ낤�B�؉��́s�������W�t�̎��l�ƌ��Ȃ���Ă���̂��B
�Ђ�̂��b�؉��[��
�Ђ�̂�
�݂���
�܂�������m��Ȃ�
��������
���ԏ����̂킫
�����傤����̐Ԃ������݂̂���
���̂ނ�������
���������܂���
�܂Ȃ��ł�
�܂�����ɂ�����Ȃ�
���̊Ȍ��ɂ܂闪���ɂ́u���̂����E�䂤���^�i����l�`�Z�܁j�^�L��������B�u�ᑐ�v�ɓ��e���������x����{�ɔF�߂��A���ڂ����B���l��N�Ɏ����u�،C�v��n���B�o��ɂ������G����̂������B��\��Ɂw�������W�x�w�J�𐁂��ЂƁx�Ȃǁv�i�����A�l�y�[�W�j�Ƃ���B�؉������O�Ɋ��s�������W�͈ȉ���6���ł���B
�@�s�c�ɂ̐H��t�i�����w������A1939�j
�@�s���ꂽ�Ɓt�i�����w������A1940�j
�@�s�̂̉́k�V�I���l�p���l�t�i���܂����[�A1946�j
�@�s�Ӊāt�i���鏑�[�A1949�j
�@�s�������W�t�i�،C���s���A1955�j
�@�s�J�𐁂��ЂƁt�i�I�ꏑ�[�A1958�j
�܂���W�Ɂs�앗���t�i�������{�̉�A1956�j�A�s�����k�t���p���掵�S�l�t�i�t���ЁA1959�j�A�f�㊧�Ɉ��Z�֕ҁs��{ �؉��[����W�k�t���p����O�\�O�S�l�t�i�q�r�ЁA1966�j�A�ق�������B���āA�g�������؉��[���i�̎��j�Ƃ̊ւ������߂Č��\�������z�q�؉��[���Ƃ̕ʂ�r�͎��̂悤�ȓ��e�ł���B������1979�N5��18���A�s�����V���k�[���l�t�ɔ��\���ꂽ�B�Ȃ��A�g�����̈��p�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�A���Z�`����y�[�W�j����B
�\�\3�N�O��1976�N��7���A�����s�����V���t�Ɂq��z�̔o��r��4��A�ڂ����B��肠�����̂́A1�F�x�c�ؕ��ƎO�P�R�F�q�A2�F�g���̎���A3�F�Γc�g���A4�F�c�K�t���ƒ֍��Y�ŁA�؉��[���͖��������������Ȃ������B�����āA�����̋�W�s�����t����3������p�B���̐��]�B����W�́q���Ƃ����r����u�펞����������ɂ����邵�Ă���́A�o��Ƃ��Ӗ��m�̎��^�ɐe���ނ��Ƃɂ�Ă�Â��ɓ��X�̌ǓƂ��Ȃ����߂��Ă��܂����v�����p�B���l���o��ɖv�������C�����������ł����̂́A�����������A�K��I�Ȏ���o��������Ă������炾�A�Ƃ��Ă���������B
�@�؉��[���Ǝ��Ƃ̌𗬂��͂��܂����̂́A���a�\�ܔN���납�炾�낤���B�����̊����I�Ȏ���̂����̈��D�����G���q�ᑐ�r�̎��l����E�炵�āA�[���́q���|�Ę_�r�ɍ�i�\����V�s���l�ł������B�L���ȁq�l�G�r�ɂ��A�Ƃ����获�M���Ă����悤�Ɏv���B���d�ɔw���ނ��A���Ǝ��l��D������������̃X�}�[�g�ȎG�����A�����̕��w�N�����ǂ��Ă����B
�@�����������[�����D���ɂȂ����̂́A����S���̏������W�s�c�ɂ̐H��t����ɓ���āA�ǂ�����ł���B���a�\�l�N�Ɋ��s���ꂽ���̎��W�́A���|�Ę_���W�܂����B�������ꕔ�̐l����A���{�̃t�����V�X�E�W�������ƍ����]�����ꂽ�悤�ł��������B
�\�\�����āA���сq�c�ɂ̐H��r��S�s�i�Ƃ����Ă�6�s�����j���p����B����2�s�߁A�g�����ł́u�l�̂܂͂�Łv�ƂȂ��Ă��邪�A�����Ă���͋����������Ƃ��Ă��������̂����A���ł̎��W�s�c�ɂ̐H��t�ł́u�l�̂܂��Łv�������̂��B�g�������z�����M�����Ƃ��ɋ�������{�́A���ł̎��W�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B����Ƃ��A���\�}�̂̐V���Ђ��Z�������̂��낤���B
�@��l�̃t�@���Ƃ��āA�����莆���o�����̂��A�[���Ƃ̂��ꂩ���N�Ԃ̕��ʂ̂͂��܂肾�����B�܂��ɂ́A����������F���Ȃ��A�t�قȎ���̂������Ă������ɂƂ��āA�Ƃ����ܓ͂��[���̎莆���B��̈Ԃ߂ł������B���������m��ʍL���̓c����������퐶�������A�[���̔������M�Ղ̕��͂��A���͎���ǂނ悤�ɂ��肩�����ǂ��̂��B
�\�\�ŏ��̒����A���̏W�s�����G�߁t�𑗂����Ƃ���A�؉��[�����������B���тɂ͐G�ꂸ�A3��قǂ̒Z�̂�J�߂Ă����B�u�[���̎莆�ނ͐�ЂŏĎ����Ă��܂����̂ŁA���͊m���߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�k�c�c�l�[�������W�s���ꂽ�Ɓt�������Ă����̂��A���̂���ł���B�v�����āA���сq��r�̈��p�B����͏��ł̎��W�s���ꂽ�Ɓt�ɋ��������B
�@���͈�N��A���ׂĂ̐e�����l�тƂƕʂ�ďo�������B�����Ė��F�A���N�̌x��ɂ�����A��ܔN��̔s��̔N�ɕ��������̂ł���B���łɖ؉��[���͐l�C�̂��鎍�l�ɂȂ��Ă����B���͖����A�҂������Ƃ��A�����������A�������������߂�̂����R�̂Ȃ�䂫�����������m��Ȃ��A������������Ȃ������B���̎��_�ŁA���͖؉��[���ƂЂ����Ɍ��ʂ����̂ł���B�ȏオ�q�؉��[���Ƃ̕ʂ�r�̂���܂��ł���B�����œ�l�̎��W�̊��s��Δ䂵�Ă݂�Ƌ����[���B
�@���U����邱�ƂȂ��A�ȑf�����Ȃ鎍����ʂ����A�؉��[���̍Ō�̎��W�s�J�𐁂��ЂƁt�́k���a�O�\�ܔN�����a�O�\�O�N�l�Ɋ��s����Ă���B�����N�A���W�s�m���t�ɂ���āA���͂悤�₭���ɔF�߂���悤�ɂȂ����B
| �؉��[�� | �g���� | |
| 1939�i���a14�j | �m1�n�c�ɂ̐H�� | �\�\ |
| 1940�i���a15�j | �m2�n���ꂽ�� | �@�����G�� |
| 1941�i���a16�j | �\�\ | �A�t� |
| 1946�i���a21�j | �m3�n�̂̉� | �\�\ |
| 1949�i���a24�j | �m4�n�Ӊ� | �\�\ |
| 1955�i���a30�j | �m5�n�������W | �B�� |
| 1958�i���a33�j | �m6�n�J�𐁂��Ђ� | �C�m�� |
����܂ŋg���́A��N�̂���ɐe�����̐l�Ƃ��Ė؉��[���̖������������Ƃ͂Ȃ������B�؉����g���i�̎��j�Ɍ��y�������Ƃ��Ȃ������͂����B���������Ă��̐��z�͋g�������I�ɏo������1940�N�O��ɖk�����q�⍶�삿�������łȂ��A�x����{��؉��[���ɂ��߂��������Ƃ𖾂��������̂Ƃ��āA�g���̓ǎ҂͂������A�؉��̈��ǎ҂ɂ������̏Ռ���^�����悤�ł���B�����܂��q�؉��[���Ƃ̕ʂ�r�ɂ���ė��҂̊W�����߂Ēm��A�؉��̎���ǂB
�@�@�@���N�b�؉��[��
�@�@�@�Ŏւ̐�̂₤�ɂ�͂炩���J��
�@�@�@��̕����痈�Ėj��G�炵��
�@�@�@�l�͂�����������̖{�����Ă��邢��
�@�@�@�����̔閧�̂₤��
�@�@�@�N����Ȃ��Ƃ���ł�����Ђ炢�Č���̂���
�@�@�@�܌��̂����ނ�ɂ˂���Ԃ�
�@�@�@�����Ȃ�傫���r���l��ډB������̂����c�c
�q���N�r�́s�c�ɂ̐H��t�ƁA�̂��́s�̂̉́t�ɂ����߂��Ă��邩��A�����̍�i�Ȃ̂��낤���A���ɂ͐��e���O�Y�Ɩk�����q�Ɣ����Y�̐��F���o�����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�g�����������W���q�c�ɂ̐H��r�͏[���ɖ؉��[���̍�i�ƂȂ��Ă������A����͂���Ńt�����V�X�E�W�����̕��Ԃ肪�����Č�����悤���B�����Ƃ��؉��̎��ɂ̓W�����̎��ɒ��������ɑ��銉�]���R�����B�Ƃ���ŁA�g�����ɂ͂�����сA�؉��[���̎��ɐG�ꂽ�U�������݂���B���܂ŏ��ЂɎ��߂�ꂽ���Ƃ̂Ȃ��q�[���̎���сr�i�s�o��ƃG�b�Z�C�t1982�N1�����j�ł���B�k�@�l���͏��тɂ��Z���B
�@�؉��[���̎���i�̂Ȃ�����A�D���Ȉ�т��f����Ƃ����A���͏������蓖�f�����B�Ȃ��Ȃ�A���̗[���̎��т́A�ǂ�ł��Ȃ����炾�B��N�قǑO�ɏ������u�؉��[���Ƃ̕ʂ�v�Ƃ������͂ŏq�ׂ��悤�ɁA��\�̂���w�c�ɂ̐H��x�Ɓw���ꂽ�Ɓx�̓�̎��W�ɁA�ڂ����ɂ����Ȃ��B�{���Ȃ�S���Ƃ�ʓǂ��A���݂̎��̎��_�ŁA��т�I�Ԃׂ��ł��邪�A�c�O�Ȃ���A������o���Ȃ������B�l�\�N�O�ɁA�[�����瑡��ꂽ�k������l�W�w���ꂽ�Ɓx���K���������̂ŁA�Ȃ������������ÂтA�ǂݕԂ��Ă݂��B
�@�`���̎��u�X��^���v���u��ӂ���v���D�������A�\��ɂȂ����u���ꂽ�Ɓv���A��邭�Ȃ��Ǝv�����B�������W���̖��т́A�u�̂̉́v�iFragments�j�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�邪�����@���@�s��ȉĂ̒�����̂Ȃ��ɑ��͂��@�������Ď������Ђ��܂��̂����@������ʑ傫�����̂̂Ȃ��Ɂ\�\�@�u�����P�̎��W�c�c�v�Ƃ������傪�����悤�ɁA�������Ƀ����P�̉e����������B��r�I�������̎��́A���̉��ȝR��ƈقȂ��Ă���B�������鎞�ԂƋ�Ԃ̗��ɁA�S��ƌi�����I�݂ɕ��u����A�A�Ȃɕx��ł���B�[���̑�\��Ƃ����Ă悢�A��т��B�����̑����̎����D�ސN�����ƁA�����悤�ɁA�x�C�Y�̕��͂ɐG������āA���̓����P�̍�i��ǂݏ��߂Ă����B�����炭�A�킪�[���������ł������ł��낤�Ǝv���B�����āA�ǂ�ł����e�L�X�g�́A�����J�X�̖���w�����P���W�x�ł������悤�ȋC������̂��B�i�����A�O�Z�`�O���y�[�W�j
�@�\�\����@���̓����P�̎��W���݂ɂ����Ă˂ނ�
�k�V�c�L���ꎚ���Q�l�����ȓ��̉��Ł@���̔����k�ā��Łl�̂Ƃ���ǂ���Ɂ@���̏`�ł����w�䂪���˂Ă�@������́@���ł����ꂽ���̂����ނ�ɂ��͂邱�Ƃ��ł����@�������ā@���͕߂ւ邱�Ƃ��ł����@�K�����\�\�X�q�𓊂��č�����߂ւ�₤��
�@�������̗т̂Ȃ��̃v�����i�A�h��\�\����������������ʂ�̂́@�����_�_�̏j�Ղ̏I�����Ƃ��@��Ɍ��Ĕw�̂������֎q�̑����Ȃ�с@�p�����݂����ȉԂ��_�_�Ƃ��ڂ�Ă��c�c�������ł܂Ă��@�₵���p���Z�̂₤�Ɂ@�Ƃ�����@�r�̓W���b�m�̂₤�Ɍ��ā@�܂����̊z�ɂ��܂Ă�閲�����������c�c
�@���͍D�@��Ɩ̏��Ƃ�����o���@���̃G�G�e���̂₤�Ȑ��E���@�܂��@���Ɛ��Ƃ�����@���̔��������̐��E���\�\�Ƃ����莄�͂����ɍ݂肽���Ɗ���\�\����ǂ��������ꂪ�o������@�����@����@���Ԃ͂����ɂ��ւė����ł����@���ւė��ā@���������ł��ς��ȁ@���̂܂ւɂ��͂�ł����@�������ĕ���@���́@���̉Ԃ̎�q�����������ǂ��������Â˂�ł����@��Ȃ��Ȃ����̂��Ƃ�b�����肷��ł���
�g���́q�[���̎���сr�ɐG���܂��ɁA�q�̂̉́iFragments�j�r�̖{�������Ă������B�����͏��߁s���ꂽ�Ɓt�Ɏ��߂��A�̂��Ɂs�̂̉́t�ɕW���Ƃ��čĘ^���ꂽ�B�s��{ �؉��[�����W�t�i�q�r�ЁA1972�N5��30���j�ɍ̂�ꂽ�{���͌�҂ł���B�Z����A���̂����2�����r���悤�i���^�������W�����ꂼ��m���n�m�́n�m��n�Ɨ��L�����j�B���l�߂��e���W�ǂ���Ƃ���B
�@�\�\����@���̓����P�̎��W���݂ɂ����Ă˂ނ�
�@�����ȓ��̉��Ł@���̔����ł̂Ƃ���ǂ���Ɂ@���̏`��
�����w�䂪���˂Ă�@������́@���ł����ꂽ
���̂����ނ�ɂ��͂邱�Ƃ��ł����@�������ā@���͕߂ւ�
���Ƃ��ł����@�K�����\�\�X�q�𓊂��č�����߂ւ�₤�� �m���n�k�����͐V���ɉ��߂��l
�@�\�\����@���̓����P�̎��W���݂ɂ�
���Ă˂ނ��@�����ȓ��̉��Ł@���̔�����
�̂Ƃ���ǂ���Ɂ@���̏`�ł����w�䂪��
�˂Ă�@������́@���ł����ꂽ
���̂����ނ�ɂ��͂邱�Ƃ��ł����@������
�ā@���͕߂ւ邱�Ƃ��ł����@�K�����\�\�X
�q�𓊂��č�����߂ւ�₤�� �m�́n�k�����͐V���ɉ��߂��l
�\�\����@���̓����P�̎��W���݂ɂ����Ă˂ނ��@�����ȓ�
�̉��Ł@���̔����ł̂Ƃ���ǂ���Ɂ@���̏`�ł����w�䂪����
�Ă�@������́@���ł����ꂽ���̂����ނ�ɂ���邱
�Ƃ��ł����@�������ā@���͕߂ւ邱�Ƃ��ł����@�K�����\�\�X�q
�𓊂��č�����߂ւ�₤�� �m��n
�s�̂̉́t�́k�V�I���l�p���l�́u��l�S�v�ŁA���҂́q�W�̂��͂�Ɂr��V���ɉ��߂Ĉ����u�����u�c�ɂ̐H��v�y�сu���ꂽ�Ɓv�̓������Ƃ��Ă��̕n�������W��҂ނ��Ƃɂ����B�����Ȃ���������߂��A�����ǂق�̉̂ł���B�v�i�����A�Z��y�[�W�j�Ƃ���Ƃ���A�؉��[�����g�̕҂ɂȂ�B���͂��̑�2���́m�́n�̌`���̂�ׂ����Ǝv���B�m�́n�Ɓm��n�̈Ⴂ�͖`���̈ꎚ�����̗L�����������i���̗��������j�A������m��n�̂悤�Ɉꎚ���������ɂ��鍪���́A���Ȃ��Ƃ��s��{ �؉��[�����W�t�̕Ҏ[�̕��j���q�ׂ����Z�ւ̕��͂�ǂނ�����A�Ȃ��B���������ċg�����O�f�q�[���̎���сr�ň������q�̂̉́iFragments�j�r�̑�2����
�@�\�\����@���̓����P�̎��W���݂ɂ����Ă˂ނ��@�����ȓ��̉��Ł@���̔����ł̂Ƃ���ǂ���Ɂ@���̏`�ł����w�䂪���˂Ă�@������́@���ł����ꂽ���̂����ނ�ɂ��͂邱�Ƃ��ł����@�������ā@���͕߂ւ邱�Ƃ��ł����@�K�����\�\�X�q�𓊂��č�����߂ւ�₤��
�Ƃ��ׂ����ƍl����B����āA�g���́q�[���̎���сr�Łu�k�V�c�L���ꎚ���Q�l�����ȓ��̉��Łv�Ƃ����ӏ��́u�k�V�c�L���ꎚ�đO�s�ɒǂ����ށl�����ȓ��̉��Łv�Ɖ��߂�B�������A�����Ŗ��Ȃ��Ƃ������B�m��n���m���n�m�́n�́u���͂�v���u�����v�Ɖ��߂Ă���̂��B������������A����͂���Ő������[�u�Ȃ̂����A�{�e�ł͒��ҁi�؉��[���j�ƈ��p�ҁi�g�����j�̌�L�E��p������鏈�܂ł͓��݂��܂��ɂ����B�g���̖����s�̐��z�ɖ߂낤�B
�\�\�؉��[���̎�����D���Ȉ�т������邪�A��O�̓W�����ǂ�ł��炸�A���҂��瑡��ꂽ�s���ꂽ�Ɓt��ǂ݂��������B�q�X��^���r�q��ӂ���r�q���ꂽ�Ɓr���D�������A�W���̈�тƂȂ�q�̂̉́iFragments�j�r���i�����̑S�ш��p�͌��T�̕��ʁm�R�s�[�n�ł͂Ȃ��A�肸���珑���ʂ������́j�B�����āq�[���̎���сr�̊j�S����������B
�@�u�����P�̎��W�c�c�v�Ƃ������傪�����悤�ɁA�������Ƀ����P�̉e����������B��r�I�������̎��́A���̉��ȝR��ƈقȂ��Ă���B�������鎞�ԂƋ�Ԃ̗��ɁA�S��ƌi�����I�݂ɕ��u����A�A�Ȃɕx��ł���B�[���̑�\��Ƃ����Ă悢�A��т��B
�g���Ƃāq�Ђ�̂��r��ڂɂ��Ă����͂����B�����A���������u�ȑf�����Ȃ鎍���v�̍�i�ł͂Ȃ��A�s�����G�߁t��s�t铁t�������������̋g�����ǂ��܂Ŏ��o�I���������͂킩��Ȃ����A�u�x�C�Y�̕��͂ɐG������āv�u�ǂݏ��߂Ă����v�u�����P�̍�i�v�ɐe���ł��낤���l�̍�i�ɒ��ڂ���B���̖؉��������P�̎w�����߂������Ƃ͈قȂ�s�������W�t�����̂Ƃ͑ΏƓI�ɁA�g���̓����P�̍ēǂ�ʂ��ās�Õ��t�Ƃ����^�̏���������B�g�����ɂƂ��Đ�O�́s�c�ɂ̐H��t�Ɓs���ꂽ�Ɓt�̖؉��[���́A�����̐i�ނׂ�����������B�̈�l�Ƃ��ĉf�����̂ł͂Ȃ����낤���B�s�J�\�i����C����j�\�k�����q�\���삿���A�ɑ��郊���P�i�x�C�Y��j�\�x����{�\�؉��[���Ƃ����g���C�A���O���́A����܂ňȏ�ɏd������Ă悢�悤�Ɏv���B
���Ɉ����q���ҁr�́A�g�����ǂ�ł��Ȃ��Ƃ������́s�J�𐁂��ЂƁt�̈�сB���W�ł́u�L���������ɂ�����v�Ǝ������ɂ���q�̋L���r�i���o�͔��10���N�ɂ����鏺�a30�N���Ȃ킿1955�N8���A�s�����V���t�ɔ��\�j�̂��Ƃɒu����Ă���B�䂦�ɁA�����̎��т��܂ޏ͂̑�q�~�̕����@�����N�\���O��N�r�͂ǂ��l���Ă��N��I�ɂ��������B�q���a���N�\���a�O��N�r���{������ׂ��p�ł͂Ȃ����B
���ҁb�؉��[���g�������A�������Ă����F�l���g�c���j�i�N��̏����ƐS�������j�ɕ����Ă����������Ȃ��Ǔ����ł���B
�Ђт炫�̊Z�˂�
�镗���a�Ă���
�����~��
�l�͂��̉�����
�N������Əo�����Ă��鎞�Ɠ������Ǝv���Ȃ���
���ꂩ�牽���o���낤
�Âт��Z�˂�����
�₦�ԂȂ��a��Ȃ���
�����N��҂Ă���悤�ɂ݂���
�l�͌���
�}���g�𗃂̂悤�ɖ炵��
�N���A�Ă���̂�
�_���Â����ɔ���������
�������玩���̕����ւ͂��낤�Ƃ���̂�
�镗���������������o�����Ƃ���̂�
���̂��тɊZ�˂��J����������肷��̂�
�l�͗����~��
�O���̂����炠�����
������݂�
��
�Ō�ɖ؉��[���̔o��ɂ��āB�q�̂̉́iFragments�j�r�̑�2���ɂ́u��Ɍ��Ĕw�̂������֎q�̑����Ȃ�сv������������A�֎q�ɒ��ڂ��Ă݂��B�s�����t�́q�Ď蓅�r�Ɏ��̋傪����B
�@�@�Έ��ɂ��ċr���낭�ق����֎q
�܁E���E�܂ŋ���ēǂނƁu��傭����Ɂ^���Ă������낭�^�ق��������v�ƂȂ�B����ɂ͂Ȃ����A���ɂ�7����3���A�O��ɂ�5����2���A�T�s�̉�������A�Ƃ�킯�u�������낭�v���s�������B�u���ɂ������炢���B������Ӗ��ŋ���ēǂނƁu�����N�C���j�V�e�^�A�V�V���N�z�\�L�^�C�X�v�̎��E���E��ƂȂ낤�B������̑���͐l���i�Ƃ�킯����Ⴋ���j�̔����đ@���r�̕`�ʂɂ��ǂ߂�B�����Ƃ��A�G���⏑�ЂɈ�����ꂽ��Ԃł͖����́u�֎q�v���ڂɔ�т���ł��邩��A�قƂ�Ljӎ�����Ȃ����B�s��{ �؉��[����W�t�i�q�r�ЁA1972�N5��30���j�ɂ͑���5��A�֎q�̋傪����B�i�@�j���̐����͓����̌f�ڃy�[�W�B
�@�@�Έ��̈֎q�l���������݂ɂ��� �s�����t�q�Ď蓅�r �i39�j
�@�@���ق났�₢���̌ߌ�̂����̈֎q �s�����t�q�R�����r �i67�j
�@�@�t�̗������Ƃ߂��w�̈֎q�a�� �s�t�����̑��t�q�t���r �i103�j
�@�@�Έ��̈֎q�݂Ȏ��Ă�l�{�̋r �s�t�����̑��t�q�܌����ʁr �i121�j
�@�@�p�C�v�֎q�S�̊D�M�����̉� �s�����Ȍ�t�q��̐X�r �i171�j
�u�t�̗��v�͍�҂̐g���났�܂œ`����Ă���悤���B���͋g���̗Y�сq����ȓ��ʂ̏H�̗��r�i�G�E31�j�́u�H�̖�͔Җ_��̋r�^��q��̔w������̂���^�֎q�ɍ������^������҂͍l����v�Ƃ��������z�N�����B�s���Y�t1975�N11�����ɔ��\���ꂽ���̎��̖����ɂ́A�E�e�����Ǝv�������t�u1975�E9�E22�v���L����Ă����B�g�����s�����V���t�Ɂq��z�̔o��r��A�ڂ���O�N�H�̂��Ƃł���B
�k�NjL�l
���W�s�J�𐁂��ЂƁt�̊����ɂ͈䕚����̏����q����𑗂�r���f�����Ă��āA�莫�Ɂu�ӂ邳�Ƃ̖؉��[���N�̎��u�Ђ�̂��v��ǂ�ŁA�k�c�c�l�v�Ƃ�����肩�A���т̖{���Ɂq�Ђ�̂��r��S�s�����Ă���B�؉��[���̑�\�쁁�q�Ђ�̂��r�́A��i���̂��̗̂͂����邱�ƂȂ���A�䕚�̏����̑��݂��^���đ傫�������i�����͊�g���ɔŁs�䕚����S���W�t�ɂ����߂��Ă���j�B���Ȃ݂ɁA���̉��̖��́q����𑗂�r��5�s�߂ɏo�Ă���䕚�̂��G���A���E�́u�����q���a�@�v�ŎY�܂ꂽ�B���͓��a�@�ɉ������тɁA����ʂ�i�a�@�̓L���X�g���n�j�����������������B�ʂ�Ɂu�������M�́^�b�Ɏ����d����ɂ́^��C����[�C�܂ł́^�F�Ƃ�ǂ�̏��i������ł���v�i�q����r�H�E13�j�j�̂悤�Ȑ���m�N���[�j���O�n�������邩�炾�B

�����E���E�̋���ʂ�ɂ������m�N���[�j���O�n�X�u�����Ёv�i2021�N2��16���B�e�j
�t�����E�I�u���C�G���̒��я����s��O�̌x���t���ēǂ����B�ŏ��ɓǂł͏����̒P�s�{�i�}�����[�A1973�N9��25���j�ŁA�g�� �����ǂ� ������B����ēǂ����̂́A�������V������̔������u�b�N�X�Łi�����ЁA2013�N12��20���j�ŁA�����́q�C�O���� �i���̖{�I�r�Ɩ��ł���Ă���B�����Ƃ��u�b�N�X�ł��Ԃ��ɏƍ������킯�ł͂Ȃ����A���肪�Ȃ𑽂߂ɂ������炢�ŁA��{�I�ɓ����̂悤���B

�t�����E�I�u���C�G���i�����j�s��O�̌x���t�i�}�����[�A1973�N9��25���j�̖{
���Ɠ����̔������u�b�N�X�Łi�����ЁA2013�N12��20���j�̃W���P�b�g
�g�����͐e�����l�Ƃ̒k�̂���A�Ȃɂ��ʔ����{��ǂ��q�˂�̂��킾�����i���ł����u���ꂽ���炢������A���邱�Ƃ����� ���ƂȂ���A ���肪�ǂ̒��x�̐l���Ȃ̂�����ł���C�z�������āA���v���������Ă���⊾���o��j�B���Ɉ���������b�q�q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�Ə�ˎ闝 �q�g�����Ǝw�r�ɂ���������i���`����Ă���B
�@���������N�����N���A�k�c�c�l���ꂱ�����ŕ����ȏƖ��ƊO�ɖʂ����傫�ȃK���X���̂���i���X�ŁA����� �g������A�� ��Ɏ��Ǝo�Ǝl�l�ŃR�[�q�[������ŎG�k�����A�g������Ƃ̎G�k�̂Ȃ��ł́A���ł��u�����ŋ߂������낢�{�͂Ȃ��H�@�����Ă�v�Ƃ���������邱�� �ɂȂ��Ă���̂����A���̎�������������A�w�����[�^�x�͂ނ�ǂ݂ł��傤���A�i�{�R�t���ŋ߂܂Ƃ߂ēǂA�Ǝo�������A����́w�Z�o�X�`�� ���E�i�C�g�̐��U�x�͎��ɖʔ��������������ƌ����A�������͂���ɂ��Ȃ����A����͈��ڂ܂��̂���悤�ȉA�S�Ŋ��m�ȏ����ł���A�ƒN���������̂����A �g������̔����͈Ⴄ�B
�@�i�{�R�t�H�@�����A�w�����[�^�x�ˁB�O�Ɉ�x�ǂ݂���������ǁA����͖��Ƃ�ł��Ȃ���������H�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA 1984�A���Z�`��ꎵ�y�[�W�j
�k�c�c�l�g������ׂ͂��߂����̌����ŁA�����̈������Ƃ��i�̂��Ƃ�b����A�R�[�q�[��������肵�A�����Ď��Ɂu�ŋߖʔ��������{�͉������H�v�� ���A�u���ɋ���������́H�v�Ƃ�����������p����ɔ�������̂��킾�����B����v�z�̂��Ƃ�C�O�̎��̂��Ƃ�q�˂��邱�Ƃ������A�W���b�N�E�f�� �_��W���E�h�D���[�Y�ɑ傢�ɊS������A�v�E�b�E�E�C���A���Y��`���[���Y�E�I���\����A�����J�̎��l�����̂��Ƃ�m�肽����ꂽ�B�g�����g������ ����̂Ɋւ��ẮA�U���W�w�u�����v�Ƃ����G�x�ɂ��킵�����A�g�����悭�����������Ęb����Ă����̂́A�I�N�^�r�I�E�p�X�́u���v�A�`���[���Y�E�I�� �\���́u�J���Z�~�v�Ƃ�����������G���U�x�X�E�r�V���b�v�̎��u�l�ԉ�m�}���E���X�n�v�Ȃǂ̂��ƂŁA�܂��W�F�[���Y�E�W���C�X�̈ߔ����p���A�C�������h �̍�ƁA�t�����E�I�u���C�G���̍�i�����Ƃ̂ق�������Ă����悤�Ɏv���B���̎茳�ɂ͐�łɂȂ����I�u���C�G���́w��O�̌x���x�����邪�A����͋g���� �킴�킴�Ō��ɘA�����Ď��A���ɑ����ĉ����������̂Ŕ��ɂ͎��̂悤�Ȍ��t��������Ă���B�u���̏�������ˎ闝�ɓǂ�ŖႢ�����A������B�@ ��㔪�l�E�Z�E�l�v�B�i�s�g�����̏ё��t�W���v�����A2004�N4��15���A���O�y�[�W�j
�g�����ƃi�{�R�t��
���Ă͂��ď������̂ŁA�C�O�̎�
�ɐG��Ă����B�I���\���i�o������j�́q���킹�݁r�ƃp�X�i�ے���j�́q���r�́A�c��m�ҁs���㎍�W�k�W�p�ДŐ��E�̕��w37�l�t�i�W�p�ЁA1979�N
2��20���j�Ɏ��߂��Ă���B�g�����i�Ҏ҂��瑡���āH�j�ǂ̂����ꂾ�낤�B�G���U�x�X�E�r�V���b�v�ɂ́A�g���f�㊧�̏������U�ҁE��ɂ��s�G
���U�x�X�E�r�V���b�v���W�k���E���㎍���Ɂl�t�i�y�j���p�Џo�Ŕ̔��A2001�j������A�q�l�ԁ\��m�}���\���X�n�r�͑�ꎍ�W�s�k�Ɠ�t�i1946�j��
��тƂ��Ď��^����Ă���B�Ȃ��A���c�����Y�E���J�K�M�ҁs����A�����J�E�C�M���X���l�_�t�i�����ЁA1972�j�����̓��i���O�q�G���U�x�X�E�r�V���b
�v�r�ɂ͕��c�����Y��́q�l�ԉ�r���S�s������Ă��邩��A�g�����ڂɂ����̂͂��ꂩ������Ȃ��B�����̊C�O�̎��ɐG������Đ������g���������s��ʁt
�i1983�j��s���[���h���b�v�t�i1988�j�Ɍ����������Ƃ́A�t������܂ł��Ȃ��B�g���͂��̂悤�ɂ��āA�|��m�F�����̕]���Ɋ�Â��Ď�ɂ���
��A�ǂ肵�Ă����悤���B�s��O�̌x���t�����̏o�Ō��͒}�����[������A�W�J�~�ꂳ����y�̕ҏW�҂���A�q�m���r�i�l
�l�߂́s��O�̌x���t�̌��肳�Ȃ���A�J�������E����邪�A�I���܂ő��̎O�l�̑m���Ɠ��l�́A����O�l�ȏ�̊��������j�̎��l�D�݂̍�i�Ƃ��Đ�����
�ꂽ�̂��낤���i�s��O�̌x���t�͂��̌�A1998�N���́q�}�����E���{��n68�r�́s�W���C�X�U�E�I�u���C�G���t�Ɂs�X�E�B���E�g�D�[�E�o�[�Y�ɂāt��
�Ƃ��Ɏ��^���ꂽ�j�B�����ŋ����[���̂́A�����̖��o�Ă���1�N�ȏ�o����1974�N11���A�g�����ҏW����s�����܁t67���ɑ��V�����́q�t�����E
�}�C���Y�E�u���C�A���\�\�A�C�������h�̕��l�r���f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��i�����ɂ͌r�݂͂Łu�t�����E�I�u���C�G���^���V������@��O�̌x���@�}�����[�^��
���Z�Z�~�v�ƐT�܂������Ђ̍L�����L����Ă���j�B�\�\�����͂̂��Ɂs�X�p�[�N�^�I�u���C�G���k�W�p�ДŐ��E�̕��w16�l�t�i�W�p�ЁA1977�N12��
20���j�́A���V�ɂ��q����r�ɋz�����ꂽ�B�\�\�q�t�����E�}�C���Y�E�u���C�A���r�ɂ͎��̂悤
�ȋL�ڂ�����B
���̂Ƃ���ށk�t�����E�I�u���C�G���l�͑���ɗD��ƂЂ����Ɏ������Ă�������w��O�̌x���x�̌��e�������O�} ���Y�Ёk����w�X�E�B���E�g�D�[�E�o�[�Y�ɂāx�̔Ō��l�Ɉς˂Ă����̂����A�펞���̂��ƂƂďo�ł��Ӑ₳�ꂽ�̂������B�i�����A��y�[�W�j
�� ����N�A�C�������h�k���̃X�g���x�C���ɐ��ꂽ�I�m�[�����k�t�����E�I�u���C�G���̖{���l�͈���O�N�Ƀ_�u�����֓]������܂Ő��K�̊w�Z����������� ���Ȃ��B�Ƃ��n������������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�k�c�c�l�P���B���k�t�����E�I�u���C�G���̒�l�̕M�͐��C�ɂ��ӂꂽ�I�m�[�����Z��̓�������������Ǝ� �������Ă���B�����Ȓm���~�ɋ�藧�Ă��Ď蓖���莟��̖{�𗐓ǂ��A�u���b���v��n�荇���ċ����A�k�c�c�l�B�i�����A�Z�y�[�W�j
�Ƃ���ŁA����ɐ旧��1971�N5���́s�����܁t25���i������g���ҏW�j�f�ڂ́q�`���C���h�E�z���b�h���ߖʋI�s�\�\�A�C�������h ���w�̌Â��� �V�����r�́A���V�́s�t�B�l�K���Y�E�E�F�C�N�t�_�W�ł���s�W���C�X�̂��߂̒����ʖ�t�i�y�ЁA1988�j�Ɏ��߂���ہA�q�g���l���Ŏ�Z��r�Ɖ��� ���ꂽ���A���̍Ō�ɃI�u���C�G���ɂ��W���C�X�_�A�q�g���l���Ŏ�Z��r���Љ��Ă����i�������s��O�̌x���t�ւ̌��y�͂Ȃ��j�B�����炭���ꂪ�A�g �������t�����E�I�u���C�G���̖���m�����ŏ����Ǝv����B
�s��O�̌x���t�͎��]�Ԃ��߂����z�����Ƃ�����������ʓI�����A�W���C�X�̌�y�ɂ�鏬�����������āA�ȒP�ɗv�邱�Ƃ��ł���
���B�K���Ȃ���
�ɁA��҂��s�C�M���X�W�k�W�p�ЃM�������[�m���E�̕��w�n5�l�t�i�W�p�ЁA1990�N1��24���j�ɕt�����q���w��i�L�C�m�[�g�r�ɖ{���́q���炷���r��
�ڂ��Ă���̂ŁA�����q����B
�@���̍�i�̌���͖��O���������A�����͖̋`���ł���B���̓M���V�A�̐̂��狥���ƌ��т��Ƃ���Ă���A���� ���肪�u�� ��ɂ����̂͂������̕����v�Ȃ̂��B�ނ̊S�͂����Ђ����畨���w�҂ɂ��ēN�w�҂���h�E�Z���r�B�Ɍ������Ă���B�w�����ォ�炱�̐w�m���������n �ɌX�|���Ă����ނ͒��N�̌������ʂ̏o�Ŏ����邽�߂Ɍِl�W�����E�f�B���j�B�Ƌ��d���ĕx�T�ȘV�l���C�U�[�Y���E�Q����B���X�R�[���j�R�t�̘V�k�E�� �Ɏ����A�S�Ȑݒ肾���A����͂����܂ł����\��ɁA���풃�ю������ɂ���悤�Ȃ��肰�Ȃ����q�Ō��Â���B�����̂قƂڂ肪���߂����m����n�A��� ��̓��C�U�[�Y�@�ɔE�э��ށB�V�l����D�������������̏����ɉB���Ă������Ƃ����f�B���j�B�̌��t�ɏ]�����̂ł���B�ނ͏����Ɏ�����������B�����ɐG ���B����Ƃ���͂����Ɗ��藎����B�f�B���j�B�����̂����ɔ�����d�|���Ă������Ɣ�������̂͌����߂��ɂȂ��Ă���ł���B�ٗl�Ȏ��ԂɌ˘f���� ���肪�ӂƖڂ�������ƃ��C�U�[�Y�V�l���֎q�m�����n�ɂ����܂��Ă���B�V�l�̖S�삾�A�Ɣނ͒�������B����ގ��g���S��ɂȂ��Ă���Ƃ͖��ɂ��䑶�m �Ȃ��̂ł���B���C�U�[�Y�V�l�Ɗ�Ȗⓚ�����킵�Ă���Œ��Ɍ���̍��W���[���Ђ傢�Ɠo�ꂵ�Ă��āA���ꂩ���A����̍s��������������]������ ���邱�ƂɂȂ�B�ނ͍������������߂Ăǂ��������������Ă���V���[�����A���X�e�B�b�N�Ȍx�@���ɏo�����A�J�t�J�́u�����v��w�R���x���v�킹��s�𗝂� �ٔ��ɂ�����ꎀ�Y�̐鍐��������B�O�l�̌x���\�\���������v���b�N�A�����}�N���X�L�[���A�����Č����߂��܂Ŏp�������Ȃ��u��O�̌x���v�t�H�b�N�X���� �\�\�̊NJ��m���n���ɂ��邱�̈ٗl�ȗ̈�̏Z���͂��ׂĎ��]�Ԑl�Ԃł���B�x�������̎�v�ȔC���͎��]�ԂƎ��]�ԏ��Ƃ̊Ԃ̌��q�������琶���鎩 �]�Ԑl�ԁi���邢�͐l�Ԏ��]�ԁj�̏�Ԃ��m�F���邱�Ƃł���A�v���b�N���������͓���Ԃ̑{�������ɂ�������ł��邪�A���q�������̒ቺ��_���Ď��]�Ԃ� ���݉B���m����Ƃ��n����̂͂ق��Ȃ�ʔގ��g�Ȃ̂ł���B
�@�v���b�N�ƃ}�N���X�L�[���ɓ����ꂽ����̓��t�g�ɏ���Ēn���̗̈��K���B�����͖����̔�������A�u���ׂĂ̕����͉��x����������Ă��āA�ǂ̏� �������̏ꏊ�ł���v�~�m�^�E���X�̉Ɓi�z���w�E���C�X�E�{���w�X�u�A�X�e���I�[���̉Ɓv�����N�j���̂܂܂̖��{�ł���A���Ԃ���~���Ă���u�i���v �̗̈�ł���B���肪���X�Ǝv�������Ȃ����Ԃɑ������邽�тɃW���[�������͂���Ŋ|�������˂߂�����b��W�J���邪�A�E���Ƃ݂��Ď��͎��Ԃ̖{���� ���яオ�点��d�|���Ƃ��č�҂̓W���[�̂ق��Ƀh�E�Z���r�B���������Ă���B�h�E�Z���r�B�w�̌��y�͎�Ƃ��ċr���Ƃ����`�ōs���邪�A�ނ͉Ɖ��A�� �H�A���s�A�B�m�����n�ł��A���Ȃǂ���Ƃ����鎖�ۂɂ��Ċ�Ȉ�ƌ��������Ă���N�w�I�Ȋw�I�ٍ˂Ƃ��ēo�ꂷ��B�ނ��߂��鏖�q�͂��Ƃ�����Ȋw �m�����n�I�ȕ��̕��̂��p�����Ă���A����̎��R�ȁA�Ƃڂ��������Ƒ����m�����܁n���č�i�S�̂̂������݂����Ă���B���̐w�ɑ��� �Ĉ�c�̃h�E�Z���r�B�]�ߎ҂���������A����ɔނ�̃h�E�Z���r�B�_��_�]���錤���҂����̐����Љ���B���̌��ʁA�`�Ȃ�]�ߎ҂̃h�E�Z���r�B�_��_ �]����a�Ȃ��]�Ƃ�ᔻ���錤���҂̐����J����A���]�Ԃ̎ԗւ̉�]�^���Ɏ������X�߂��肪�W�J���邱�ƂɂȂ�B�i�Ȃ��h�E�Z���r�B�́w�h�[�L�[�Õ� ���x�ɂ����p�I�ȉȊw�̓V�˂Ƃ��čēo�ꂵ�A���͌h�i�m��������n�ȃJ�g���b�N�M�҂Ƃ��ċ������ɋ߂Ă��镶�w�̓V�˃W�F�C���Y�E�W���C�X�Ƃ̑Ζʂ��� �Ă���Ƃ�����Ȑ��s���ƂȂ�j�B�h�E�Z���r�B�́u�Ȋw�����v�̈�ɁA���u�������ɂ�����Ƃ킪�g�̉f����]�����Ŕ`�m�̂��n�����݁A�����ɌJ ��Ԃ����킪���g�̉ʂĂ����͂��悤�Ƃ�����̂�����B�܂��A�}�N���X�L�[���̎葢��ɂȂ��i�̈�ɐ��I�Ȕ��H�������āA���̔��͂ЂƂ܂�肸�� �����������|���͑S������̔������X�ɓ������Ă���A���̂��������ł͖ڂɂ͌����Ȃ��������̔��̐��삪�i�s���ł���B���u���ꂽ���ɔ��������f���A�� �����ɒB���锠�H�\�\����Ώz�����̉ʂĂ��Ȃ��J��Ԃ����w��O�̌x���x�̍\�������Ȃ̂ł���B���̐��E�ɓo�ꂵ�Ă���l���͂��ꂼ��A�d�҂Ƌ��d �ҁA�E�l�ƂƔ�Q�ҁA���Y���s�l�Ǝ��Y���Ƃ��������Ȃ��A�h�E�Z���r�B������̘c�m�䂪�n�߂�ꂽ�����ł���悤�ɁA���݂ɔ��f�������� ����B�����Č���̓����ɃW���[���Ђ��݁A�t�H�b�N�X�������l�߂Ă�����̌x�@�������C�U�[�Y�V�l�̉��~�̕ǂ̓����ɂ���悤�ɁA���ׂĂ͏d�˂����� �H�Ɠ����������֓����ւƂ̂߂肱�݁A�����m�点��n��̏z�^��������̂ł���B���̏����̌��тŌ���͍Ăьx�@���ɂ���Ă���B���x�͓ڎ��m�� �n�����W�����E�f�B���j�B�Ɠ�l�A��ł��邪�A�`�ʂ͑O��Ɩw�m�قƂ�n�Ǔ���ł���B����͐U��o�����������x�i�����Ă����炭�͉ʂĂ��Ȃ��J�� �Ԃ��āj��蒼����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�i�����A��l�Z��`��l���y�[�W�j
�����Łu�}�N���X�L�[���̎葢��ɂȂ��i�̈�ɐ��I�Ȕ��H�������āA���̔��͂ЂƂ܂�肸�����������|���͑S������̔������X �ɓ������Ă� ��A���̂��������ł͖ڂɂ͌����Ȃ��������̔��̐��삪�i�s���ł���v�Ƃ���̂��A�����̖{���̊G�i�O�f�ʐ^�Q�Ɓj�̃��`�[�t�ɂȂ��Ă���B�������� �����̔����Ƃ���ɂ͕N�NJ��i�u���u�������ɂ�����Ƃ킪�g�̉f���v�j�́s��O�̌x���t�ɒ��������̂ŁA�N��������������邩�炾�낤�A�I�u���C�G�� �̟f��ɂ悤�₭���s���ꂽ�����sThe Third Policeman�t�i1967�j�̕\���܂��̑��悪�܂��ɂ��̖{���̊G�������B��������́u�u�킽���͗c�N����@�����[�E�~���N�Ƃ����~���N�́^�ʂ� ���b�e���Ɂ@���̎q�������[�E�~���N�̊ʂ�����^�Ă���p�̕`����Ă���v�^���̊ʂ�����Ă��鉮�~�̏��̎q�߂Ȃ���^�킽���͐��vጂɜ���Ă����v �Ƃ���������܂ދg�������q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E 27�j���z�N�����B�����т�1975�N9���̔��\�ŁA�u�@�v���̎�����F�V���F����̈��p������A���ꂪ�g���̒��ŃI�u���C�G���́u���H�v�Ƌ��U���� ���낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�����āA���q���`�̊G�ɂ悹�������q���̃A�X�e���X�N�r�i�H�E 22�A���o��1978�N3��20�����s�̋��q���`�ʼn�W�sLE REVE D'ALICE�\�\�A���X�̖��t�i�p�쏑�X�j�̏o�ňē��J�^���O�i���A1978�N2���j�j�ɂ́u�傫�Ȕ�����^�����ɏ������Ȃ锠���^�J����@�J����v�� ���H���̂��̂��o�ꂷ��̂ł���B
��
�I�u���C�G���̎��]�Ԃ̕`�ʂ͈��|�I�ŁA�Ƃ��Ɍ����i��萳�m�Ɍ����Ȃ�A���̏����̍ŏI�y�[�W�j�ɋ߂�3
�y�[�W���͂��Ј��p��������
���낾���A��Ɂq���炷���r���ƈ������̂ŁA�Y���ӏ��������ɂƂǂ߂�B���Ȃ킿�u���̎��]�Ԃ��̂��̂ɂ͉����Ɠ��̒��q�Ƃ��������Ƃ��������̂�
����悤�ŁA�v����u�L�\�ȋ�C�|���v���ޏ��k���]�ԁl�̌�̂ӂƂ����ɂʂ��ʂ��Ƃ����݂��Ă���Ǝv���Ό��Ɍ����\�킹�Ȃ��قǐS��v�Ƃ������̂�
���B�v�i�����F��Z��`��Z�O�y�[�W�A���E���{��n�ŁF�l�l�܁`�l�l�Z�y�[�W�A���u�b�N�X�ŁF���O�`���܃y�[�W�j�܂ł̈�i��������ł���B�Ƃ���
�ŁA���̒m�l�Ƀo�C�N�����܂킷�����Ɏ��]�Ԃ������Ȃ��l�������B���Ȃ݂Ɏ��́A�G���W���i���[�^�[�j�̕t����蕨�Ƃ͂��������ւ��Ȃ��悤�ɂ��Ă�
�邩��A�����ő̊��ł���ō����x�̏�蕨�͎��]�Ԃł���B�g�����͂ǂ��������낤���B�����̃K�L�叫�������g�����A���]�Ԃɏ��Ȃ������͂����Ȃ��B
�I�[�g�o�C�i�����q��
�ƂȃI�[�g�o�C�r�i�E�E14�j�ɁA�^�]����҂̎��_���������Ă���̂͋����[
���j�͂������̂��ƁA����܂����܂킷�g���Ƃ����̂��z���ł��Ȃ��B�g���ɂ͔n�⎩�]�Ԃ��������B�����ŋg�����̎��ɓo�ꂷ�鎩�]�Ԃ����Ă݂悤�B
�@�E���]�ԋ����I�肪�Փ˂���i���������A�@�E10�j
�@�E���̎��]�Ԃ̂���܂��
�@�E���]�Ԃ̂���܂��i���߁E�L�߁A�E�E2�j
�@�E���^�t�B�W�b�N�ȋ����z�B���]�ԁi�Ă���H�܂ŁA�F�E2�j
�@�E���]�ԂŒʂ�i���C�X�E�L��������T�����@�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�A�G�E11�j
�@�E���]�Ԃ̃`���[�u�̂悤�Ȃ��̂Łi���܂�����A�G�E30�j
�����āA���������āq���]�Ԃ̏�̔L�r�i�G�E15�j���o�ꂷ��B�S�s���������B
�@�ł̖����������
�@���̎��]��
�@���̒������Ԃ̌o�߂̂�����
�@���l�͎��ɐ₦
�@��̎ԗւ̂��₩�Ȏ��]�̎��̒��S����
�@�݂ǂ�̐A�����ɖ���
�@���������̂�
�@�����
�@�������
�@�����Ȉ��̎��]��
�@���̍����̂悤�ȏ敨�̏��
�@��҂��Ђ炭�L������
�@�Ƃ�����
�@����͂����鏭�N������O�ɂ��z���͂̐��E��
�@�֗~�I��
�@�����̊X������Ă䂭
�@������ނ��̏���
�@�ނ�������|���l������
�q���]�Ԃ̏�̔L�r�̏��o��1974�N4���A�q�����O�j�W�u��
�N�����v�r�̃p���t���b�g��
�f�ځA���̂Ƃ��́u�}�c�C�E�L�~�I�̊G�ɂ悹�āv�Ǝ��������������i���W�ł͍폜�j�B���W��1970�N�ɋ��q���`�̍ŏ��̒�q�ƂȂ��������O�j
�i1947�`81�j�̐؉�L�ł̏��̌W�ŁA����ɂ͂��̖����q��
�]�Ԃ̏�̔L�r�i1971�j�Ƃ����G���������B�g���̎��͂���Ɋ����̂����A�����ɂ́s��O�̌x���t�̗]�C���Y���Ă��Ȃ����낤
���B
��
�I�u���C�G���̑�\�I�Ȓ��я����͂��ׂđ��V�����ɂ���ĖM��Ă���B�ߔN���s�̔ł�������Ȃ�A�s�X�E�B���E�g�D�E�o�[�Y�ɂ� �k�������u�b �N�X�l�t�i�����ЁA2014�j�A�s�n�[�h���C�t�t�i�������s��A2005�j�A�s�h�[�L�[�Õ����t�i�W�p�Ёk�s�C�M���X�W�k�W�p�ЃM�������[�m���E�̕��w�n 5�l�t�����l�A1990�j��3�삪���ꂾ�B�����A�����ŐG��Ă��������̂͂����ł͂Ȃ��A1941�N���\�̒Z�сA�Ƃ�����菶�т́q�W�����E�_�t�B�[�� ��r�i�V����E���V�i�ҁs���̗V�����\�\�C�M���X�E���[���A���w����I�k�������u�b�N�X�l�t�����ЁA1990�N3��5���A�����j�ł���B�u�t���l�[���� �ĂԂ͍̂����T����v�i�����A����y�[�W�j���߁A��l���́u�W�����E�_�t�B�[�̒�v�ƌĂ�邪�A�{��ł���ނ̘b�ɓ���܂��Ɏ��̂悤�Ȑl���������o �ꂷ��B���������M�������B
�@�W�����E�_�t�B�[���u�W�����E�_�t�B�[�̒�v�̌Z�B
�@�K�����[���W�����E�_�t�B�[����肠���A���ꎞ�Ԍ�Ɍ��Ƃ�����ҁB
�@�}�[�e�B���E�X�}�������e���A���A�X�e�b�L�������Č����̍��������j�B���ނ�������@�։^�]�m�B
�@�S�M���Y�v�l���}�[�e�B���E�X�}�����̎o�B���n�����̌̃|�[���E�S�M���Y�̖��S�l�B
�@���[�I�E�R�[���S�M���Y�v�l�̂��Ƃ��B�U�D����̗��ŌY�����ɑ���ꂽ�B
�@�_�t�B�[���W�����E�_�t�B�[�̒�̕��ɂ��āA�ނ̎����Ă��鏬�^�]�����i����Ń}�[�e�B���E�X�}���������Ă���j�̏��߂̏��L�ҁB���D�̑D�����������A
1927�N7��4��4���ɔ������āA���̔ӁA�g�����S�����鏈�ֈڑ����ꂽ�B
�I�u���C�G���͂����܂łŖ�3�y�[�W���₵�Ă���i���Ȃ݂ɂ��̏��т̖{����8�y�[�W���j�A�ʂ��ʂ��Ƃ���������B
�u�O�q�̑����̎�
���̓W�����E�_�t�B�[�̒�̘b�Ƃ͂قƂ�ǖ{���I�ȊW���Ȃ��Ƃ������悤���A����̕��w�́A�P���Ȏ������A���̎����������N�������w�i�ɂЂ���ł���S
���w�I�E��`�I�v����m���|����������^�����ɁA�^��̒��ŏq�ׂ�i�K��ʂ�߂��Ă��܂������̂Ǝv�������B�������A���ꂾ���̂��Ƃ������Ă����A��
���A�W�����E�_�t�B�[�̒�̖`�����ǂ�Ȃ��̂ł��������A��Z�ɋL�����Ƃ͋������B
�@�ނ́A���钩�\�\���O��N�O������\�\�N�����A���ւ��A���f�Ȓ��H�𗿗������B���̒���A�����͋D�Ԃ��Ƃ����s�v�c�ȍl���Ɏ��߂���Ă��܂����B��
�����͐����̂��悤���Ȃ��B�����Ȓj�̎q�������͋D�Ԃ��Ƃ����ӂ�����邱�Ƃ��ԁX�m�܂܁n���邵�A���̒��ɂ́A�������猩��ƁA�D�ԂɊ������Ă��Ȃ���
�Ȃ����������������̂ł͂��邪�B�������A�W�����E�_�t�B�[�̒�́A�����͋D�Ԃł���m�A�A�A�n�Ɗm�M�����\�\�������C�����X�������𗧂Ăđ�������R
��A���˂̂���Ƃ��납�瑾���X�萺�����Y�~�J���ɔ�����A�����A���R�Ƒ��鋐��ȋD�ԁB�v�i�����A���l�`���܃y�[�W�j
���́u�D�ԁv���s��O�̌x���t�́u���]�ԁv�Ɠ��ނł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�̒��̂�����Ȃ������ŔӔN�̋g�������̖�ǂƂ͎v���Ȃ����A�I�u
���C�G���̋@�֎Ԑl�Ԃ������͐l�ԋ@�֎ԂɐG�ꂽ�Ȃ�K������Ƃ������Ƃ��낤�B���́q�W�����E�_�t�B�[�̒�r����}�O���b�g�`���Ƃ���́qLa
Duree
Poignardee�i�˂��h���ꂽ�����j�r�i1939�j��z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B�m���Ɂu�^��̒��ŏq�ׂ�i�K��ʂ�߂��Ă��܂����v�u����
�̕��w�v�͂��̂悤�ɂł����������Ȃ��̂��A�Ǝv���Ȃ���B���Ȃ݂ɁA�}�O���b�g�����ʂ�`������1940�N�ɋg���́s�����G�߁t�����s���A����ɂ��̗�
41�N�ɋg���́s�t铁t���o���A�I�u���C�G���͂��̏��т\���Ă���B
�\�\�u�Ă̓�����̒�Ł^�܂�Ő��H�ו��̂悤�Ɂ^���C���o���^����������v�i�q����ȉĂ̗��r�G�E26�j

�}�O���b�g�̖��ʁqLa Duree
Poignardee�i�˂��h���ꂽ�����j�r�i1939�j
�苖�ɋg���������i���F�ɑ��������W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j������B��2014�N11���A�{�T�C�g��12���N�����j���ė���ɂ���w�������Ï����B�ʐ^������킩��Ƃ���A���Ԃ���
�@�@���i���F�l�@1963.3.25�@�g����
�ƃu���[�u���b�N�̃y���i�����炭�g�����p�̖��N�M�j�ŏ�����Ă���B���Ȃ݂ɁA1963�i���a38�j�N3��25���͌��j���i��y����m�F�ł���A���s����Ɍ��提��������Ă��邾�낤�j�B���͋g������ɉ���тɐV����Ï��œ��肵�����W�ɏ������Ă���������A�ӂ���͖��N�M���������킹�Ă��Ȃ����߁A���̃u���b�N�C���N�̃p�[�J�[�ɂ����̂������B�ʐ^�́s�T�t�����E�݁t�̌��提���́u���ш�Y�l�^1984.12.9�^�g�����v�ŁA���t�̃X�^�C���͕��i�̏ꍇ�Ɠ����ł���i���̓��̖�����w���l��̖Y�N��̂��Ƃ��q�g�����̘b�����r�ɏ������j�B�܂��A����Ō��提���������̂ɂ͕M�y���ɂ����̂�����B
 �@
�@
�g���������i���F�ɑ��������W�s�a���`�t�i����ɁA1962�N9��9���j�̌��Ԃ��y�[�W�i���j�Ƌg���������ш�Y�����̎��W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�N9��30���j�ɏ����������Ԃ��y�[�W�i�E�j
�s�a���`�t�́A�Ȃ̋g���z�q�s�l�Ƃ��đ���ɂ������400���Ŋ��s���ꂽ�B���c�v�Y�͎��̂悤�ɏ����Ă���B�u����A���̔N�A�P�s���W�Ƃ��ẮA��c�G�́w���]�̐푈�x�������A�g�����́w�a���`�x���㌎�ɏo�ł����B�g���̂́A���ƔłƂ��ċg������������̂̔��s�A�����������������������k���s�͎v���Ђł͂Ȃ��l�A�v���Ђ�������Ă��������������Ƃ����ԂɊ������Ă��܂����v�i�s��㎍�d���j�t�V���ЁA1995�N2��25���A��l��y�[�W�j�B�܂�A���s�����̂��Ȃ�̐��͎v���Ђ��̔����A�c��͋g�����苖�ɒu���Ă����A�Ƃ������ƂɂȂ�B�g���̎��M�N���́u���a�l�\�ܔN�@��㎵�Z�N�@�@�@�\��v�ɂ́u�g�������A�o��������́w�������сx�������āA��Ђ�K���B�w�a���`�x��v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A��O�O�y�[�W�j�ƌ����邩��A�Ζ���ɂ��ۊǂ��Ă����悤���B����ɋ����[�����ƂɁA�g���̐��z�q���q�f�z�r�ɂ́u�R�����q���ɗB��x�A���͏o����Ă���B�㋞���ꂽ�܁A�d���̂��Ƃő��k�������Ƃ�����B�s���̃z�e���Ŕ����ԂقǁA�G�k�������������A���ɂƂ��ėL�Ӌ`�ȂЂƂƂ��ł������B�o��������̎��W�s�a���`�t�����グ������A���a�O�\���N�̂��Ƃ��Ǝv���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A���l�`���܃y�[�W�j�Ƃ���B���Ζʂ̔o�l�ɏo�ŎЂ̐l�ԂƂ��ĉ���āA���l�Ƃ��āi����A���Ԃ��炢�������炪�悾���A���ǎ҂Ƃ��āj�����̐V��̎��W��B����Ǝ��������i���F�Ƃ̊ԂɌJ��Ђ낰��ꂽ�\���͔ے�ł��Ȃ��B�������A�g���̔N���i�g���z�q�ҁj�́u���Z�O�N�i���a�O�\���N�j�l�\�l�v�ɂ́u�w���e���O�Y�S���W�x��}�����[���犧�s�������Ő��e���O�Y�̒m����v�Ƃ�����s���������ŁA�ڍׂ͕s�����B
�g�����͕��i���F�̖���������x�A�����Ă���B�s�������Y���W�k���㎍����79�l�t�i�v���ЁA1983�N4��1���j�̗��\���Ɍf�ڂ��ꂽ����̕��͂ł���B�S���������B
�@�Ö{���̎G���Ȃ�͐ς̈ł���A���͈���̔����{���A���̂Ȃ��֒����o���A�ԕ�����B�܂��^�V�����A����͈������Y�̏������W�s�H�̒����t�ł������B���i���F�̊��q���r�̌��t�����̎��l�̎v�O�̖{�����A�I�m�ɑ����Ă���悤�Ɏv����B�\�\���i���ނ̓����ɒ���ŗ���ƁA�����ňӎ��̕������͚��k�����l�ۂ��������̏ۂ��k�i�i�V�j���āl�A�Â��b��ᏋC��Y�킹�n�߂�\�\�B�����œ��ȓI�Ȃ��̎��l�́A�i�����Ԃ��������A�s�D�Ɓ@���̉́t���A��ߒ��Ƃ��A�₪�Đ��n�����A��i�s���̒��̍Ό��t��n��グ���B
�s�H�̒����t��1957�N�́A�s�D�Ɓ@���̉́t��1972�N�́A�s���̒��̍Ό��t��1980�N�̊��s�B�����Ŏv���o�����̂́A�������Y���g���ɂ��Č�����q�C���^�r���[�E����ɂ��ār�ł���B
�@���̎��W�k�s�D�Ɓ@���̉́t�l�̔����͂����Ԃ���܂������B
�@�\�\����͂���܂����B��������]��Ȃł͂Ȃ��`�ł������݂����ł��B�k�c�c�l��ꎍ�W�́w�H�̒����x���A�l�͂܂��������܂łƎv��Ȃ�������ł����ǁA�g�������ˁA�����Ŕ����ēǂ�łĂ���Ă��B�l�͋g������ɂ͓��������Ȃ������Ǝv����ł��B�Ƃ����̂͋g������Ă����̂͐����x���X�^�[�g�������l�ł����A�x�C�Y�Ƃ��������̌n���ł��Ȃ���������B�l�̂����郊�X�g�ɓ����Ă��Ȃ�������ł��B��������g��������́A�Ȃ�ƌÖ{���Ō�������ʔ�����������Ƃ����̂ŁA�����ēǂ�ł���Ă��B�k�c�c�l�i�s�k�O�����w�ٓ��ʊ��W �����Y��ғW����}�^�l�������Y�\�\�w�H�̒����x����w�߂���̉́x�܂Łt�i�����Y�L�O�@���ƗƎ��̂܂��@�O�����w�فA2000�N3��4���A��܃y�[�W�j
�����ɂ��A�g���́u�x�C�Y�\���i���F�\�������Y�v�Ƃ����n���ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�������Ɍ�y�̒����ɏ�����悤�Ȋԕ����n���ƌ����Ȃ�A�g�����͒N�̌n���ł��Ȃ������B�����ŁA1963�N�܂ł̖x�A���i�A�����̒��슈�������Ă������B�x��1953�i���a28�j�N��48�ŕa�f���Ă���A�s�x�C�Y�S�W�k�S7���l�t�i�V���ЁA1954�`57�j�̕Ҏ[�ɂ͕��i��������Ă���B���i���F�i1918�`79�j�́s�{�I�h���G���̐��E�t�i1947�j�A�s���t�i1948�j�A���W�s����t�t�i���j�A�s���y�k��ȗ��Łl�t�i1952�j�A�s���̉ԁt�i1954�j�A�s���{�t�i���j�A�s���{�E�[���t�i1956�j�A�s���̎��݁t�i���j�A�s���y�k���S�Łl�t�i1957�j�A�s���S�ƍ߁t�i���j�A�s�S�̒��𗬂��́t�i1958�j�A�s���̎��݈��̏I��t�i���j�A�s���E�̏I��t�i1959�j�A�s�p�s�t�i1960�j�A�s�S�[�M�����̐��E�t�i1961�j�A�s���ʁt�i1962�j�A�Ƒ����̒����A�Ƃ�킯�����i�W�j������B�������Y�i1934�`�j�́s�H�̒����t�i1957�j�B���Ȃ݂ɋg�����̒����́s�����G�߁t�i1940�j�A�s�t�́t�i1941�j�A�s�Õ��t�i1955�j�A�s�m���t�i1958�j�A�s�����t�i1959�j�A�s�g�������W�t�i���j�A�s�a���`�t�i1962�j�B�Ƃ���ŕ��i�̖��F�E�����^��Y�ɂ��āA�g���́q���A�k��������܁l�r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@��Ƃ̒����^��Y���Ƃ́A�ʎ���������x�ł��邪�A���̑I�l�ψ��݂͂�ȁA�e�����F�l�ł���A�܂����䂽���Ȏ��l�ł���B���̂悤�Ȑl�����ɁA�s�T�t�����E�݁t���F�߂�ꂽ���Ƃ��A���ɂ͂Ȃɂ������ꂵ���B�i�s���㎍�蒟�t1977�N2�����A����y�[�W�j
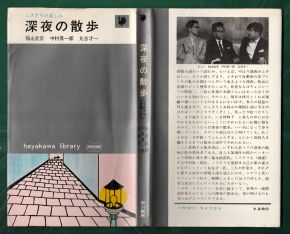
���i���F�E�����^��Y�E�ےJ�ˈ�s�[��̎U���\�\�~�X�e���̊y���݁k�n���J���E���C�u�����l�t�i���쏑�[�A1963�N8��31���j�̃W���P�b�g���g�����Ƃ���
���i�A�����ƂƂ��Ɂs�[��̎U���\�\�~�X�e���̊y���݁k�n���J���E���C�u�����l�t�i���쏑�[�A1963�N8��31���j�����ےJ�ˈ�́A�O���A���E�O���[���i�ےJ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A1952�j�̑����S���҂̋g���ƒm��A���W�s�Õ��t���s�����t���l�ɂ��ėF�l�ł���c��m�i1927�`89�j�ɑ���悤�Ɋ��߂Ă���i�s�[��̎U���t�W���P�b�g���\���̎ʐ^�A���i�E�����E�ےJ�̃X���[�V���b�g���q�g�����̑�����i�i4�j�r�ŐG�ꂽ�ےJ�́s�G�z�o�̊������āt�o�ŋL�O��̂Ƃ��̂��̂��j�B���́A�ےJ���g���Ɏ��W�s�a���`�t�i�ɑ���悤�Ɋ��߂��̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B�����āA�����܂ŏ����Ă����Ɩ������Ȃ����������Ă݂����A�������Ȃ��܂ł��A�������ƌ��߂邾���̍����Ɍ�����B�܂��A��o�s�{�t���s�����x���B�v�i�g���͖x�����m���[���̈ɓ��M�g�s������e���ЂƁ\�\�����Y�̉��y�����t��1971�N�ɑ������Ă���j�̐��́A�N�ォ�炢���čl�����Ȃ��B�����A�l�I�Ȃ�������u�x���Ă��n�܂�Ȃ��̂ŁA�s�a���`�t�̓����ɕ��i�Ƃ̊W��T���Ă݂��B�ǂނ̂͂�����提���{�ł���B���̕��i�����{�́A����1989�N5���ɋ{�v��̒������X�ōw�����Ă��̔N�̕��ɋg������Ɓi�Ō�Ɂj��������Ƃ��ɏ������Ă��������{�Ɋr�ׂāA�ɂ߂ĕۑ���Ԃ��悢���{�ŁA�������ݓ��͈�Ȃ��B
���i�͎��l�Ƃ��ďo���������������āA�����ƂƂ��Ĉ�Ƃ𐬂������Ƃ����\���Ă���B�������s�ҔN�́E�]�`���i���F�t�i���؏��сA1982�N5��25���k����2���F1986�N5��25���l�j�́q��S�ƍ��܁@���a�O���N�i�l�l�j�r�ɂ́u���������f���Ă������A���a�O�Z�N�Ɂu���ʁv���A�O���N�Ɂu���݂���̒��߁v���A��������u�����ɂ���āv�������B�O�҂́u���ʁv�́A��҂́u�c�N�v�̌��^�ł���v�i�����A�l�Z�y�[�W�j�Ƃ���B�q���ʁr�Ɓq���݂���̒��߁r�́s���i���F���W�t�i�S�W��13���j�́q���Ɠ]���@�y�т��̑��̎��r�Ɋ܂܂��B�q���̑��̎��r�͂���2�тƁq�k���̂���ׂ���a�@�r���琬��A���o�͎��̂悤�ł���B�Ȃ��A���i�����̂��Ɣ��\�������́q�J�̖Ɋār��������肾�B
�@�q���ʁr�\�\�s���i�t1961�N4�������ʂ����Ԃ��z�炪�ւɂȂėx��o���ƁA
�����z��͈���₤�ȑ��ۂ̉��𑁂��A�����A
�P���ɁA���т̕��I�y�̏�ɑ���o���A
���̉��͉ΎR�̍����̂₤�ɒn���r�߂đ���A
����Ɩ邪�����悹����A���̍��}�Ƌ��ɁA
�t�Q�͋��|�Ɏ�����Ȃ���A�����͎�����݁A
���͂����̂͂Ȃ��A�����ȑ��̒��ɐg�������߂�A
�b�͂����o�����Ȃ��A��������ߖ�ɉ��g����A
�����Ƃ�������҂͈��O�Ǝ��f�Ƃ̈����ɂ��т���B
�z���͂��܂��܂̉��ʂ̒��ɑf����������A
�z�����闼��͑��ۂ�@���A�R������͔M������f���A
�Ђ�뒷�����r�͕s�C���ȗx���x�蔲���A
�z��͂�����߂��ʁA���̑��ۂ̔炪��܂ŁA
���̋r����ɐ܂�A�����z��ɏ��ڂ�܂ŁA
�����@�������Ԃ��֎~��Ȃ��A���ʂ̒��̊炪����Ɏ��ʂƁA
���߂����A��т���ΉԁA�߂܂��邵�����]��
�ԂƔ��Ƃ̌G�̂Ђ��݂ɐV�������C�𐁂����ށB
���̎����������Ȃ��肪�z��̉��ʂ����������Ȃ�A
�z��݂͌ЂɌ��邾�炤�A���Â���̂�����̊�A���Ȃ����B
�s�a���`�t���q���̕a�C�r�i�D�E11�B���o��1959�N11���́s�k�t4���j���v�킸�ɂ͂����Ȃ���i�����A���i�����o��ǂ��s���ł���B�����͍l�����Ȃ����낤���B�G���s���i�t�i�����炭���������Ă���j�ŕ��i�́q���ʁr��ǂg���́A����܂ł̏����Ɓ����i���F�Ƃ������Ɏ��l�����i�̗v�f���������A�Ɓi1948�N���s�́s�}�`�l�E�|�G�e�B�N���W�t�Ȃǂ̋����͂��������A�������W�s����t�t���܂ޕ��i�̑S���т����߂��s���i���F���W�t���m���[����ŏ��Ɋ��s�����̂�1966�N5���ŁA1963�N�����A���i�̎��l�Ƃ��Ă̈�ۂ͔��������Ǝv����j�B1960�N��A���i�͒}�����[�́k�ÓT���{���w�S�W�l�Łq�Ñ�̗w�r�i�Î��L�̗w�A���{���I�̗w�A�Չ̕��A�_�y�́A�Ôn�y�A�����́j��q�������q�r�i�������q�A�Y�����Y�A���y���ҕ���j��Ă��邪�A�����ł͂Ȃ����A�g������������|���Ă���킯�ł��Ȃ��i�ʐ^�Q�Ɓj�B���߂Ɍ��y�����A���҂Əo�Ŏ҂̐l�ԂƂ����R�����q�̏ꍇ�Ɠ��l�̊W�͑z��ł��Ȃ��悤���B

���i���F��q�Ñ�̗w�r�����߂��s�Î��L�E���y�L�E���{��ًL�E�Ñ�̗w�k�ÓT���{���w�S�W�P�l�t�i�}�����[�A1960�N5��4���j�̕\���k�����F�ɓc叕�l
�Ō�ɋg�����ƕ��i���F�̓��L�Ɩ`���̌��提���{�ɐG��Ă������B���͂����q�ҏW��L 110�i2011�N12��31���X�V���j�r���q�ҏW��L 63�i2008�N1��31���X�V���j�r�ɂ����������B
1945�N9��1���`12��31���A1946�N1��3���`6��9���A1947�N6��18���`7��31���̓��L�����߂��s���i���F �����L�t�i�V���ЁA2011�N10��30���j���o���B�g�����q���L�@���l�Z�N�r�i�s�邵����t5���A1990�N1��31���E6���A1990�N5��31���j��1946�N1��1������4��8���܂ł̓��L������A�����ēǂނƋ����[���B1946�N3��20���̋L�q�\�\�u�O����\���@�܁A���j�^��⒩�Q�����A��������Ԃɂĉ����Ƌ��ɏ��w�𗧂B���Ȃ���B�Ǖ��w�ɂĒ����Ɨ����Ў�؉��ɂĊՒk�B�M�B�̑��t�͎n�߂ĂȂ�B�[�H�O�x�k�C�Y�l����K�ӁB���X�̕������؉��̂����ɂ�����ׂ��v�i���i���F�j�B�u�O����\���@�ؓc�����搶�̘b���B���M�ŕ邹��悤�ɂȂ����͎̂l�\���z���Ă���Ƃ����B����Ă���������i�������Ă䂫�����Ǝv���v�i�g�����j�B�s���y�t�i1952�j���s�Õ��t�i1955�j���܂��a�����Ă��Ȃ����̂Ƃ��A���i�͐��c�J�E��i���́k�����́l�H�g���Y�ƂɁA�g���͌Z�̋g�����v�Ɓi��c�E�r�ォ�j�ɉ������A���ꂼ������ǁk�Вc�@�l���{��������l�Əo�ŎЁk�������[�l�ɋΖ����Ă����B
�Ï�����ɂ��s���{�̌Ö{���t�ɋg�����̎��W�s�a���`�t���o�i���Ă���B�Ȃ�Ɓu���i���F�����提���v����ł���B�Ƃ���߂��̂Ō��ɍs�������Ƃ��낾���A�ʐM�̔����X�Ȃ̂Ŏ�Ɏ��Ȃ��̂��c�O���B�ژ^�ɞH���u�a���`�@���W�^�g���@���A����ɁA��37�^����S�O�O���q���i���F�����提���r���Ŕ��^�Ï�����Ɂ@�@95,000�~�v�B���i�͒}�����[����1960�N�Ɂs�ÓT���{���w�S�W�k��1���l�t�́q�Ñ�̗w�r���A���N�Ɂs���k��18���l�t�́q�������q�r3�т�Ă���i�����͌ɓc叕�j�B�s�V�I������{���w�S�W�k��32���l�t�i1960�A�����͉��n�F�l�Y�E���n�M�Y�j�ɂ͒Z�сq���E�̏I��r�����^���Ă��邪�A�P�Ƃ̒����͂Ȃ�����A�g���Ƃ͏����ƂƎ��l�̊W���낤�B�k�f��l�s�p�s�t�i1984�j���B������ѐ�F����A�Ƃ��ɐ���ɏZ��ł��Ȃ���A�h�����镟�i�Ƃ͂��ɉ��Ȃ������A�Ɛ���̂�����ł������������Ƃ�����B�g������ɁA���i�Ɩʎ������������͐u�����炵���i���i���F�������̂����ŋg�����ɐG�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��j�B
��������S�Ƃ����Ε������͂������A�l���邱�Ƃɂ�������i�W�������Ȃ��͎̂c�O���B�@�����A���a���\���邱����l�̎��l�Ə����Ƃ̂��Ƃ����߂čl���Ă݂����B
�k2017�N3��31���NjL�l
���i���F��1962�N5���A���q���݂���̒��߁r���s���Y�t�ɔ��\���Ă��邪�A8����10���ɂ͓����ɉ��O�_�ڂ��Ă���i�q���O�A���̖�S�r�Ɓq���O�A���̍��܁r�j�B����́A�T�؊�T�̏}�������́s���T��t�ɗ^�����e����_�����ےJ�ˈ�́q���������҂Ƃ��ẲĖڟ��r�ƍD��𐬂��s�D���t�_�ł�����̂����A���̖�����
�Ƃ���B�����ƂƂ��Ă����������ȏ�A���i���u�l�̐S�́u�Í��̍�v��`���v���Ƃ�ڎw�����͕̂K�R�ł���i���Ƃ��s��̎O����t������j�A�����ɂ����镟�i�̎p���͎��ɂ����铯�����̋g���̎p���Ƃ��d�Ȃ�i���Ƃ��s�m���t������j�B�c�O�Ȃ���A�g�������i�̉��O�_�ɐG�ꂽ�`�Ղ͌�������Ȃ����A�Ƃ��Ɂu��\���I���w�̐V�������ł���ӎ����̐��E��`�v�����Ƃ�����ɉۂ��������ƂƎ��l���A�`���̎��W�s�a���`�t���P�m���������n�̂��Ƃ��ɂ��Č��������ƌ���̂́A�͂����Ď��̕Ɩڂ��낤���B
��
����y���g�������|����i1904�`82�j�ɑ��������提������́s�a���`�t�i��쏑�[�̏o�i�j�ɂ͔N�������L����Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�|����͋g���̎U���ɂ͓o�ꂵ�Ȃ����A�s�ӏ܌���o��S�W�k��10���l���o�l�W�T�t�i�������[�A1981�A����IX�j�̔ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�Ƃ̘A�ڍ��k��H�q����o������r�ŋg���́u�������H�Ƃ����͎̂���ǂ�ł��Ȃ������̂�����B���Ƃ��Έ����~�ʂ��Ƃ��c�c�B�k�c�c�l�ق��̂��������e�����Ђ���Ƃ�����Ă����Ȃ����ȁB�ڂ��͂��̍�i�k�u���̒��Ŕ����Ė�ƂȂĂ��v�l�͔o��Ƃ��čۗ����Ă��邯�ǁA���̈�s�Ƃ����ꍇ�A�|��������邵�A�����~�ʂ������v�i�����A�O�y�[�W�j�Ɣ������Ă���B
�g�����̒����ƕҎ[���A��i�f�ڎ��A������i�̏��e�A�����Ă��̏������܂މ���I�ȍ��q����������o�ꂵ���B�s�A�C�f�A
idea�t367���q���W�E���{�I���^�i���w�� 1945-1969 ���E�����E�C���r�i�������V���ЁA2014�N10��10���j�Ɓs�A�C�f�A
idea�t368���q���W�E���{�I���^�i���_�� 1970-1994
�ے�`�̃u�b�N�f�U�C���r�i���A2014�N12��10���j�ł���B�ǂ�����\���͌S�~��Y�i���̈ꕔ���j�B�S����̒T���Ώۂ̊j�ɂ͈�_���䂪���邪�A��
�惆���C�J����шɒB���v�̋ƐтɊ֘A���āA����ȍ~�i����т���ȑO�j�̋g�����̕��ƂƑ�����i�ւ̖ڔz��ɂ����������ӂ�Ȃ��B�K���Ȃ��ƂɁs�g����
�����t�Ɍf�ژR��̏��Ђ͂Ȃ��������A���c���ɂ�銈���Ӓ�ɑ���������́A���̏����Ɍ������Ă�����̂��B�q���{�I���^�i���w���r�����́q�����T�C�Y
�ꗗ�r�ɕt����ꂽ���c���̕��͂ɂ�������B�k�@�l���͏��т̕�L�B
�@���a4�N�A�܍���10.5pt��8����1�ƂȂ�u�g�^���r�v�T�C�Y��傫���̊�Ƃ��č̗p���A�l���\�ꍆ�̌n�����܍���1�E 25�{��2�E5�{�ɂȂ�悤���������u�V�l���v�u�V�ꍆ�v�Ə̂���u�[�{���V�����v������o���ꂽ���Ƃɒǐ����銈����Ђ�����A�ŏI�I�ɏ��a37�N �k�s�a���`�t���s�̔N�ł���l�A���{�H�ƋK�i�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�u�����̊���@�v�́A�A�����J���E�|�C���g�������̋��菊�Ƃ��č̗p���A���́u�g�^ ���r�̐����{�v�ɂ���ď������甪���܂ł̍����������T�C�Y���`�����B����܂��Đ�{�v�쐬�̏�����ǂނƁA�������₷���B�����Łq���{�I���^�i���w���r�f�ڂ̋g�����̒����Ƒ�����i�i�K�������g�����{���g���w�肵���� �͌���Ȃ��j�̊����������Ă݂悤�B�����́i�@�j���̐����͏����̖{���f�ڃy�[�W��\���B�����N�͖{�T�C�g�́s�g���������t�Ɓs�q�g�����r�́u�{�v�t�̊Y �����鏑�Ђɒ����Ă���B
�k�}�ŗ��l
�s��O�̊����́A��{�I�ɁA���������ō��ꂽ�^�����č��ꂽ���̂������B������傫�����Ⴆ�ΈقȂ鏑�̂ƂȂ�̂ŁA�u�z�n����܍��v�u�z�n�|�C���g�n�܍��v��u�G�p�d��9�|�v�Ƃ������Ăѕ�������B
�@���a30�N�k�s�Õ��t���s�̔N�ł���l�㍠����A�x���g����^�����@�ɂ���đ���ꂽ���������������悤�ɂȂ��Ă������A�{���T�C�Y�ƒ����o���T�C�Y �ł͈قȂ�p�^�[�����}���g�p���Ă����悤�ł���i�匩�o���͌��������n�̏��̂������c���Ă����j�B���炩�ɈقȂ鏑���ƔF�߂���ꍇ�A�u��c�x���g�� ���^�n�v�u��c�x���g�����^�n�v�Ƃ������Ăѕ�������B�X�Ɍ�́u�p���`��^�v�ƌĂԐ��@�̊����Ɂu�x���g���n�v���珑���̕ω����F�߂���ꍇ�A�u��c �p���`�n�v�Ƃ������Ăѕ�������B�i�����A�l�`�܃y�[�W�j
��������킩��̂́A���惆���C�J�ł͓����A�v���Ђł͊�c�ƍW�����A����R�c����c�ƍW�����A�}�����[���W�����̊�������Ɏg�p���Ă���Ƃ����X �����B�����܂ł��Ȃ����A��L���Ђ̉��t�ɂ͈�����̖��O�͍ڂ��Ă��Ă��A�g�p�����̃��[�J�[�u�����v��u��c�v��u�W�����v���\������Ă���킯�ł͂� ���B��O�́u�����Ёv���̂������ЁA�u�ʔŏ��́v���ʔň���̊J�������������Ƃ������Ƃ��B���������Ȃ��ɂ����āA�s�g�������W�t�̉��t�͒��ڂɒl����B������ȉ��̕\���ɂ������邩�炾�B�����͂������A���݂ł������܂ŋL�ڂ��邱�Ƃ͋H���낤�B
������\��t����@���{�\�⍲���{�@�������\�i�䐻��
���^�\�a�T�ό`�@��O�Z�~��l��~��
�����\�{���E��c��^��|�����s�ԏ\��|�S�p�A�L�@�m���u���E�W�����Z�|�Z���`�����C�I�[���h
�p���\�{���E�_�萻�����X�g���J���[����Z�j
�\���E���퐻���}�[���C�h���b�v�������@���ԁE�����a�тm�s�P���g
�u�b�N�f�U�C���\���Y�N��
���������͎��̑z�������A�{���Ɂu��c��^��|�����v��I�������̂̓u�b�N�f�U�C�i�[�̐��Y���낤�B����Ɠ��l�ɁA���̕\���Ă����̂͐��Y��
����A�o�Ŏ҂̏��c�v�Y������Ɏ^�����A���҂̋g�������ӂ����A�Ƃ������Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B�������I�Ԃ��Ƃ́i�Ƃ�킯���ň���̏ꍇ�j�A���̎�
��������銈�������̂��g�p���邱�Ƃ��Ӗ�����B���ۂɂ͔Ō��̎v���ЂƎ���̂��������̊������g�p���邱�ƂɂȂ�킯�����A�{�������̑I���͑g�Ŏw��
�ҁi�s�g�������W�t�ł͐��Y�j�̖����ł���B�����l����ƁA�g�����̎��ƔŎ��W�i�g�Ŏw��͋g���{�l�j�̈�����A���Ȃ킿�s�����G�߁t�̖P�ѓ��A�s�t铁t
�̑���{���������ЁA�s�Õ��t�̒������{���������ЁA�s�a���`�t�̊�����А����Ђ�4�Ђ��g���̑I������Ƃ������ƂɂȂ�i�s�m���t�̒������ň�
��������Ђ�����ɉ����Ă�����������Ȃ��j�B�P�ѓ��Ƌg���̊W�͕s�ڂŁi����܂ŋ߂Ă�����R���Ƃ̐����l�����邪�A�������j�A����{����͓���
�̋Ζ���̐������X�Ǝ���W���������i�S���҂������j�B�������{����������̋Ζ���ł���}�����[�̎����A���Ȃ킿�u�����k�g���l�̋߂Ă�o�Ŏ�
�ɏo���肵�Ă���ǂ���̈�����v�i����N�v�q������v�Ǝ��r�A�ےJ�ˈ�ҁs������v��ᔻ����k���{��̐��E16�l�t�A�������_�ЁA1983�A���
�y�[�W�j�B�����Ђ��}�����[�̎����̈�����B���Ђ̑g�ŗ����͂Ƃ��ɍ����킯�ł͂Ȃ��悤�����A�s�m���t�̒������ň���Ɋr�ׂĈ����Ƃ������Ƃ͂Ȃ���
�낤�B�����Ђ̊�����Ŗʂ̔������́A�g�����̎��W�����ꂾ�ƌ����Ă悢�B
�]�k�����A��ˎ闝�ɂ��A�g�����́s���[���h���b�v�t�̕\���̎��ނɂ����āA�O���s��ʁt�ł͕����I�ɂ����g��Ȃ����������Ȏ��ނ�S�ʓI�Ɏg�p����
�Ƃ����i�s�g�����̏ё��t�W���v�����A2004�N4��15���A�l�`�܌܃y�[�W���Q�Ɓj�B�s�a���`�t�̓t�����X��������A���ނɋÂ����ɁA��������g
�p�����ɂ����ċC��f�����`���B���l�̂��Ƃ́s�T�t�����E�݁t�i1976�j�A�s�Ẳ��t�i1979�j�ł������āA�����ł͕ЎR���̉��M��ɐ��e���O�Y�̐�
�ʉ�A�Ƃ����Δ�ɂȂ��Ă���B�g�����͎���W�̎��̒����̑��{�E�����ɋÂ�̂���ł������B
������g���A��c�A�W�����Ƃ������������[�J�[�A�ʔň���A�����ЂƂ����������Ђ̏��̂̓����ɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ́A���̎��ɂ͎�ɗ]��B�����Ƌg�����̑I����ɂ��ẮA�Ȃ�����ł���B����̉ۑ�Ƃ������B�����ɗѓN�v����̎����ɕx���@���f���悤�B�q�����G�߁r��
��߂ł���B�Ȃ������ɂ́A�P�ѓ��ɂ��Ă̍l������ق��A���������q蜾蠃��r�́u�R�s�[�̔ŖʂȂ̂Œf��͂ł��Ȃ����A�����͂��������r��Ă�
��B���̉́k��̉�̂߂��铕��̂ЂƂƂ���^�߂��肵�D�̓X�[�h�̏����l�ɂ́u�́v���l�g���Ă���Ȃ��Ɉ�����ʎ�̊������������Ă���B����
�Ȉ�����ł͗L�菟���Ȃ��Ɓv�Ƃ����w�E������B�т���ɂ́A���Г������ʐ^�E�}�œ���ňꏑ�ɂ܂Ƃ߂Ă��������������̂ł���B
�k���̏W�w�����G�߁x�̖{���́l���͓̂����z�n���Ő�������9�|�C���g�����́i����44�N���j�Ƃقړ���̂悤���B�Ђ炪�ȂŌ� ���u�Ӂv�̓��̓_���E�ɂ����ƃG�r������S�J�[�u���ւ��Ⴐ�������ɂȂ��Ă���̂������I�B�G�p�Ɂ`�����Ђ́u�Ӂv�͂����悻�^�e�̃Z���^�[���킸�� �ɍ�����S�������Ɣw���L�т��ӂ��ɂȂ��Ă���B�ׂ������Ƃ����A����͌Â����̂��鏑�̂ł͂Ȃ����낤���B�g���̍D�݂����f����Ă���̂��A�P�Ȃ� ���R���B
��
�u�����s�́s�A�C�f�A idea�t�̎����A368���́q���{�I���^�i���_���r�ł���B354���́q���W�E���{�I���^�i�o�Ŏj 1923-1945 �ق�Ƃ��ɔ������{�r�i�������V���ЁA2012�N8��10���j�Ɏn�܂���{�I���^�i�O����́A�����Ɋ��������B�O���Ɠ��l�ɁA�g�����̒����A�Ҏ[���A���� ��i�̎g�p���������Ă������B
�����c���Y�ɂ��q�g�����F�}�����[�r���k���`�l�́u�� ���ɂ��Ȃ鑾�Ɏ��̂ق��A��t�A���V��A�����A���O�Y�A�Y�S�W�Ȃǂ́u�S�W�̒}���v�̈ꎞ��̊��������Ƃ�����B�g�ł̖��ƁA�~悂��������i�i���� ���鑕��͂˂ɕς��Ȃ��B�y���F�w�a�߂镑�P�x�́A����҂̂��߂ɂ��L������ׂ������ƂȂ����v�i�����A���y�[�W�j�ƌ���Ă���B�����Ɂs�a�߂� ���P�t�̏������f���āA�O����̐�S�����Ȓ����Ɋ��Q���悤�ł͂Ȃ����B�������̂܂��ɁA�Ę^�ɒl����q�}��r�������Ă������B�\�\�u�������́A���e�� �f�ڂ����o�ŕ����{�i�ȉ��u���{�v�ƌĂԁj�̎�ɉ��t����̘^���A�ҎҁE��ҁE���ҁA�q�G�����W���r�A�w�W��E����x�A�s�p�����t�A���s���A�Ő��i����� �L���Ȃ����{�͏��Łj�E���s�N�����A����X�^�b�t�i���s�ҁE�ҏW�ҁE����ҁE����ҁE���{�҂Ȃǁj�A���ށA���^�i���{�̎����l���琄��j�A���s�����A�艿 �i����œ�����͖{�̉��i�j�A�{�������i�T�C�Y�E���́j�A�����҂̏��ɋL�ڂ����v�i�����A�k���y�[�W�l�j�B
507�b �y���F �w�a�߂镑�P�x�����ЁA1983.3.10�A���s�ҁF���X�G�Y�A����F�g�����A����F�����ЁA����ҁF�ؗE�A���{�F����{�A�e���A2700�~�A�����F9�|�E�����Ёi���O�A�ꎵ�y�[�W�j
�g�����̎����Ƒ�����i�́A�������{�I���^�i�O����̐V���ȃl�b�g���[�N�̂��Ƃő����Ȃ����ꂽ�B�{�̃W���P�b�g���Ŕw������������悤�ɒI�ɔr�������e�̑s���́A�g�p�����̊Ӓ���L���������ƂƂ��ɁA�����]�����悤�B�O����́A���E�ɒu���ׂ��H��ł���B
�q���c���Y�́q�g���� �_�r�Ɓq�͎ʁr�̏��o�r�ŏ������悤�ɁA�����q�� �ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�͖��ڂ����A1963�N���܂łɔ��\���ꂽ�ƍl������B����́q�͎ʁr�̕]�߂�ʂ��� ��i�������琧��N����l�@���Ă݂����B�g�����́s���Ɣ�]�t6���i1966�N10���j�́q�A���P�[�g�r�̊e�l�ւ̋��ʂ̎���
�@�P�@�߂��늴���������́i��ނ���Ȃ��j
�@�Q�@���̂��ꂩ��̎d���̗\��
�@�R�@�������̂���D���Ȏ��l�i�Í���������Ȃ��j
�Ɏ��̂悤�ɓ����Ă���i�����A��܃y�[�W�j�B
�@�P�@�f��u�T���_�[�{�[���k��l��v�̊C��ɂ�����i���̃V�[���B���l���q�̋�W�B
�@�Q�@�u�g�������W�v�i�V���W�u�Â��ȉƁv���܂ޑS���W�j���o�����ƁB
�@�R�@���������@�����r�Y
�܂�A1966�N10���ȑO�Ɂs�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�i��1�j�̊�悪�i�s���Ă���A�����ɂ͓��������̐V���W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�N7��23���j�����߂邱�Ƃ����܂��Ă����킯���B�����Łs�Â��ȉƁt���^�̑S16�т\���ɕ��ׂĂ݂悤�B
���ѕW��i���W�ԍ��E�f �ڏ��j ���o�s�����t�k���s�����l�@�f�ڔN���i���j
���߁E�L�߁i�E�E2�j �s���㎍�t�k�ђˏ��X�l�@1959�N3����
�@�@�\�\
���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j �s�k�t�k�k�̉�l�@1962�N9��
�@�@�\�\
�n�E�t�̊G�i�E�E5�j �s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl�@1963�N1����
����i�E�E3�j �s���p�蒟�t�k���p�o�ŎЁl 1963�N2����
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����i�E�E4�j ���� 1963�N12���܂łɔ��\��
�@�@�\�\
�؍݁i�E�E7�j �s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl 1964�N4����
������i�E�E6�j �s�X���t�k�X���O�ω�l 1964�N7����
�@�@ �\�\
���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j �s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl�@1965�N3����
�₳�������Ζ��i�E�E9�j �s�����t�k�������_�Ёl�@1965�N11��
�@�@�\�\
�t�̃I�[�����i�E�E10�j �s���i�t�k�I�X��l�@1966�N3����
�Â��ȉƁi�E�E16�j �s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl�@1966�N4����
�X�[�v�͂��߂�i�E�E11�j �s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl�@1966�N5����
�q�����i�E�E13�j �s����t�k�o�b�e���{�\���O���[�v�l�@1966�N10��
�ǓƂȃI�[�g�o�C�i�E�E14�j �s�O�c���w�t�k�O�c���w��l�@1966�N11����
�@�@�\�\
���I�ȗ��S�i�E�E12�j �s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl�@1967�N1����
������G�i�E�E15�j �s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl�@1967�N2����
�q���߁E�L�߁r�͔��\�����������A�앗���Ⴄ�ƌ��ꂽ�̂��A�s�a���`�t�i1962�j�Ɏ��^���ꂸ�ɒu���ꂽ����B���W�s�Â��ȉƁt
�̑n����Ԃ�
�u1962�\66�v�ƋL����Ă���B�q���̂��߂̃g���̎��݁r�́s�k�t�I��10���Ɍf�ڂ��ꂽ�A�u�ɒB���v�̌����v�𗣂ꂽ�ŏ��̍�i�B�{�т������ɐ���
���̂́A�g���Ɋ�����Ƃ��날���Ă̂��Ƃ��낤�B��i����1963�N��3�сA64�N��2�сA65�N��2�тƎ�T���Ԃ����������A���N�́q�₳��������
���r�\�\�g���͉i�c�k�߂Ɉ��Ă����ȂŁu�u�����v�\�㍆�ɔ��\�����s�₳�������Ζ��t�͂�������D���Ȏ��тł��B�V���䂦�X���ł����ׂ���������K�r
�ł��B�k�c�c�l�\���\�����v�i�q�c�����ꏴ�r�A�s�Ս��t192���A1966�N1���A���y�[�W�j�Ǝ��M�̂قǂ�`�����Ă���\�\�������Ăӂ����ꂽ�̂�
���낤�A��1966�N�ɂ�5�т����\����Ă���i1967�N���\��2�т�66�N���܂łɂ͒E�e���Ă��悤�j�B�O�f�q�A���P�[�g�r�Ɂu�u�g�������W�v�i�V��
�W�u�Â��ȉƁv���܂ޑS���W�j���o�����Ɓv�Ə��������_�ŁA���Ȃ��Ƃ��q�q�����r�܂ł�13�т͏��������Ă����͂����B���邢�́u���鏬���ȉ�L�ŁA����
���������V�g�ɂق߂��A�E�C�Â�����v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A��O�O�y�[�W�j�Ǝ��M�́q�N���r�ɂ���q�ǓƂȃI�[�g�o
�C�r�����łɏ��������Ă������B�q���I�ȗ��S�r�͑n��2�N�߂́s���Ɣ�]�t�ɁA�q������G�r�͗�N�t�ɍ�i���Ă���s���㎍�蒟�t�ɔ��\����Ă���A
1966�N�H�ɂ͐V���W�s�Â��ȉƁt�̍\�z���ł܂��Ă����ɈႢ�Ȃ��i�g���̐S�����l����ƁA�q�ǓƂȃI�[�g�o�C�r�̊����������Čł܂����A�ƌ������j�B
�s�Â��ȉƁt�œ����I�Ȑ}�`�͉~�ł���B��̂ɋg���͂���C���[�W�i�}�`�j���C�ɓ���Ǝ��X�Ȃ܂łɂ�������Ɏg���X��������A�s�_��I�Ȏ���̎��t�ɂ�������\�Ⴞ�B���قǒ��ڂ𗁂тĂ��Ȃ����A����ɐ旧���ās�Â��ȉƁt�̉~������B���т̔��\���ɁA�~�̓o�ꂷ�鎍��������ʂ��Ă݂悤�B�i�~�̃��@���G�[�V�����Ƃ��Ă̓��i��2�j������A�A�i��3�j������B�f��s007 �T���_�[�{�[�����t�̊C��ł̊i���́A�A�������邽�߂̊��D�̐ݒ肾�����B�j
���߁E�L�߁i�E�E2�j
�i�Ȃ��j
���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j
�i�Ȃ��j
�n�E�t�̊G�i�E�E5�j
�E�~�����̔n�����Ă���
�E���Ă킽�������Ō����~�����̔n�Ȃ̂�
����i�E�E3�j
�i�Ȃ��j
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����i�E�E4�j
�E�R�͂͑S���~�����
�@�Ƃ��ɂ͉~������
�؍݁i�E�E7�j
�E�~���������~
������i�E�E6�j
�i�Ȃ��j
���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j
�i�Ȃ��j
�₳�������Ζ��i�E�E9�j
�E�Γ�̉~
�t�̃I�[�����i�E�E10�j
�E����͑傫�ȉ~�̕����I
�Â��ȉƁi�E�E16�j
�i�Ȃ��j
�X�[�v�͂��߂�i�E�E11�j
�E���݂���~��������ʂ���
�q�����i�E�E13�j
�i�Ȃ��j�������u���̐Ԃɉ����āv�̎��傠��
�ǓƂȃI�[�g�o�C�i�E�E14�j
�E�~�`�̃R���N���[�g�̏��H
�E���S�~���ґR�Ɖ�]����
�E�~�̖������I
�E�~�̖��H��
�E���S�~�̔�������
�@��~���锼�~�̓����x
���I�ȗ��S�i�E�E12�j
�E�e�[�u���̉~���܂��
�u���v�̎��傠��
������G�i�E�E15�j
�i�Ȃ��j�������u���̉E����������v�̎��傠��
�����ł��q�ǓƂȃI�[�g�o�C�r�͓����I�Ȉʒu���߂Ă��āA�s�Â��ȉƁt�ł̉~�̑����炢�����Ă���悤���B�q�n�E�t�̊G�r�́u�~���� �̔n�v�͗��� �h�m�L���r�X���n�̊G����Î����Ă��邪�A���̃��J�j�J���Ȏp�`�͗e�ՂɃI�[�g�o�C�ɓ]������B�����ł̓T�[�L�b�g�̉~�ƃ^�C���̉~�����S�~�𐬂��B���� �Ƃ��A�~�́s�Â��ȉƁt�ŏ��߂ēo�ꂵ���C���[�W�ł͂Ȃ��B���Ƃ��ΑO�̎��W�s�a���`�t�́A�q�͎ʁr�Ƃ悭�����u�~���̊G����v�Ƃ�����������q���� �鏗�r�i�D�E18�j�Ɂu�ڂ��̐S�ɉ̉~��`���v������A����́q�₳�������Ζ��r�́u�Γ�̉~�v��z�킹��B���ł����珑���Ă������A�q�������邢�� �^���́����r�Ƃ����W������g�������ɂ́q�͎ʁr�̂ق��Ɏ���5�т�����B�Ȃ��A�g���͎���ł��u���́v�u���邢�́v�̗�����p���Ă���A�O�� �i�B�`�G�j�͊������A����i�F�`�K�j�͂Ђ炪�Ȃ���Ƃ��Ďg�p�������A�W��ɂ����̌X���͌���Ă���B
�@�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�j
�@���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j
�@�q���V���X���͐����i�G�E3�j
�@�T�C�����g�E���邢�͍��i�G�E25�j
�@���E���邢�͉āi�H�E12�j
���̕W�肾�������Ă���Ɩʔ������ƂɋC�����B�����ɂ�3��ނ̕\�L�̃p�^�[��������B���Ȃ킿�A
�@�i1�j�����\�\���邢�́^���́����@�Ɓ\�\�łȂ�
�@�i2�j�������邢�́^���́����@�ƃx�^�łȂ�
�@�i3�j�����E���邢�́^���́����@�ƁE�łȂ�
���n��ɂ��ω��Ǝ��ׂ����낤���A�����Ɂq�n�E�t�̊G�r�i�E�E5�j��u���Ă݂�ƁA����́i3�j�́q�n�E���邢�͏t�̊G�r�̐��` �ł͂Ȃ��������Ƌ^����B�Ƃ��Ɂq���E���̊G�r�Ƃ������͋g����2�т���B�ЂƂ́q�n�E�t�̊G�r�A�����ЂƂ́s�a���`�t��
�@���E�H�̊G�i�D�E21�j
�ŁA��������q���E���邢�͏H�̊G�r�Ɠǂ߂�B���̍ۂ�����b����g���Ă��܂��A�����2�тɐ旧����
�@�Ă̊G�i�B�E9�j
�@�~�̊G�i�C�E6�j
������A�g���͗��V�ɂ��B�s�Õ��t�i1955�j�A�C�s�m���t�i1958�j�A�D�s�a���`�t�i1962�j�A�E�s�Â��ȉƁt�i1968�j�ƘA �����鎍�W�� ��т����߂Ă���i��ˎ闝�͂��̒����s�g�����̏ё��t�́q�l�G���߂���G�r�ɁA�������ďH�~�t�̏��ɕ��ׂčĘ^�����j�B�b����₱��������悤�� ���A�q�n�E�t�̊G�r�̂��Ƃɔ��\���ꂽ���Ɂq�t�̊G�r�i�I�E12�j������i���o�́s��̐V���t1967�N2��5���j�B�܂�A�q�n�E�t�̊G�r�Ɓq�t�̊G�r �͕ʕ����Ƃ����ӎ����g���ɂ������킯�ŁA����́u�n���t�̊G�v�ł͂Ȃ��u�n���邢�͏t�̊G�v�Ɣ��f��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B�b����q�������邢�́^���� �����r�ɖ߂����B�q�T�C�����g�E���邢�͍��r�ɂ́u����r�q�̉�������q�T�C�������m���₯�n�r�Ɋ�v�Ǝ����������āA���̕W�肾���͒n���߂��Ă��� ���A����ȊO�݂͂�
�@�ޏ��^�Ȏ@
�@���^���B�N�g���[
�@�q���V���X�^����
�@���^��
���Ȃ킿�A�`�^�a�Ɩ��m�ȍ\���������Ă���B�����ł`�E�a�͂Ƃ��ɖ��������A���e���قȂ邽�߁A�ǂݎ�͉��������Ɋׂ�B���ꂪ�ޏ��^ �V���[�}���A���^�I�ł͒N�������Ȃ��B�����̂Ȃ��ł��q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�ٍ͈ʂ�����Ă���B
�@�͎ʁ^�N�[�g�̊G����
�͕���Ƃ������������ɋ߂��A�N�[�g�̊G����͎ʂ������A�̈ӂɎ��邩�炾�B�����Łq����鏗�r�i���o�́s���w�t1961�N5��
���j��ǂ�
���B��ɂ���ċg�������̓W�J�i�Ƃ�킯�O��̎���ւ̂����肮�����j�͓���ł���B�K���ɂ������́ABurton
Watson�ҁE�����h����̉p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t�iChicago
Review Press�A1976�j�́qFrom Spindle
Form (1959�]62)�r�ɖ�ڂ���Ă���̂Łi�����A���Z�y�[�W�j�A�����ɑ����Čf����B
����鏗�\�\�~ ���̊G�����i�D�E18�j
���R�̔z�F�̗≩�̂��₩��
��l�̏������܂��
��{�̕R��g�������Ȃ���
�ڂ��̐S�ɉ̉~��`��
���̏��̍����獶�E�ɓ˂��ł�
�_�̗��[�ɂƂ܂钹
����͂����q���̂悤�ɚL��
����������t������܂�
���ɐ^��������
���킷��
�ł̋��
����Ẳ��̊C�ɂ��܂�
�e�킪���E��ς���
���̓��e�����肩���������F����
�����Ȃ�
�����Ȕ���
�X�y�C���̓���
���j�̑��̒��̌�
�Ă݂�������
���̖��̔]���̂Ȃ���
������������
�ڂ��͌��������Ă��邩���m���
�����ɂ݂����C�g�̒n���
�����]������
��Ԕ������w�l�X��
�ӂ����ё��z�����ʂɋP���Ȃ��
Hunted Woman
�@from Miro's painting
Out of the haze of an accidental color scheme of greens and yellows
A woman is born
Making the wavy motion of a string
Draws a circle of fire in my heart
From the woman's hips, jutting out to left and right
A stick, on both ends of which birds are perched
They always cry like children
Until the modeling is completed
Turn their serious faces to the moon
And challenge
In the sky of darkness
And in the sea under a vegetable basket
A receptacle changes the world
Its contents turn from putrefying brown
To black
A small peninsula
A civil war in Spain
Blood in history's frost
Hunting summer tangerines
Flow of their honey brains
It's possible
I have overlooked
A beautiful ladies' hat
Which shifts direction
From the ground of gun barrels full of astonishments
And flies
If the sun again shines ahead
�G��`���Ƃ��������̂��ƂɁA�g���͎v�������ɐF�ʂ̗�����W�J����B�����ɂ��W���A���E�~���̖��ʂɂ��肻���Ȑ}�������A��̓I�ɂ� �̍�i�A�Ɩ� �w�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�����ċ�����q�A�����J���̎ӓ��Ձr�����肾�낤���j�B�������A�g���̎���̃X���X���~���̊G�Ɍ�������Ȃ�����Ƃ����ĒQ�� �ɂ͋y�Ȃ��B�u�~���̊G����v�͎ʁm�A�A�n�������̂��q����鏗�r�ł͂Ȃ��̂��B����鏗�̓~���̊G����o�ꂷ��̂ł͂Ȃ��A�u���R�̔z�F�̗≩ �̂��₩��m�A�A�n�v���܂��B�g���̎��Ƃ�����z�ɂ͈�l�̏����o���_�Ƃ��āA�u���̏��̍�����m�A�A�n���E�ɓ˂��ł�^�_�̗��[�ɂƂ܂钹�v���`�� ��A�u���̓��e�����肩���������F����m�A�A�n�^�����Ȃ�^�����Ȕ����^�X�y�C���̓����^���j�̑��̒��̌��v�ƁA���������u����v����u���v�ɕϖe������ ���ɁA�s��I�ɐi�s����B�����A�u�Ă݂�������k����̂́u�ڂ��v���u����鏗�v���A�����炭���̗����ł��낤�l�^���̖��̔]���̂Ȃ���v���~�� �̂悤�Ɍ���������B���₤���ۂ݂��܂ꂻ���ɂȂ����u�����ɂ݂����C�g�̒n���m�A�A�n�v�u�w�l�X�v�̂�����P�����E���K���B���ꂪ�u�����ɂ݂��� �C�g�̒n����m�A�A�n�v�łȂ��̂́A�W����܂�4�x�o�ꂷ��u����m�A�A�n�v�𗽉킷����̂Ƃ��āA�Ӑg�̐g�U����������߂��B�~���̊G�ɐG������ā\�\ �~���̊G��T���ɂ��āA�ł͂Ȃ��\�\�J�n���ꂽ�ӎ��̗���́u�Ă݂���v�ɂ���ċ~��ꂽ�B
�@�@�Ė������Â��������v�͂�� �k��
���ꂪ�u����鏗�^�~���̊G����v�����B���������������B�ł́A����2�N����ɂ͂��łɏ�����Ă����Ɩڂ����u�͎ʁ^�N�[�g�̊G�� ��v�͂ǂ����i����̂��Ƃ̃��C�i�[�͕]�҂ɂ��j�B
�͎ʁ\�\���̓N�[ �g�̊G����
���̋��͂��������j�� 01
�������炾�S�̂ɒ���o���� 02
�����⒆���̐펀�҂̔��̖т� 03
�Â��肩��@�Â���܂łȂт����� 04
���̏�̐�������Ō���̂́H 05
������т�ꂽ�����̋����� 06
���ӂ����č��l�֑�C���������܂� 07
���N�̒j����l�Ő푈���͂��߂邾�낤 08
�����o��܂ł� 09
���̒j�͂ӂƂ����H��ɂȂ邾�낤 10
����悭�s���� 11
���j�I�Ȋy����������H 12
�����ꂽ���@�����ꂽ�I 13
�ԖڂƗ� 14
��̂��闤�n���� 15
���̌R�͂̊��z���Ȃ��ꂽ���ւ��� 16
���������j�Ə��̂��悢�_��̈� 17
�킽���͏j�Ղ��Ă�肽���Ǝv�� 18
��ƂȂ�Δ����������� 19
�葫���瓷�܂Ŗ_�̂悤�� 20
�܂����� 21
�����͂�������܂ŗ������Ă��� 22
�����Â���@���͊^�̂Ƃт܂�鐅���̂Ȃ��� 23
���܈���̕��݂���� 24
�������̌҂܂ł̕S���̏� 25
�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯�� 26
���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S�� 27
�s���S�ȔR�Ă� 28
�~���N�E�[���[�Ɨ₽���� 29
��Ƃ̍��M�����I�� 30
�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv�� 31
�H����~�ւ����Ē��Ӑ[�� 32
�R�͂͑S���~����� 33
�Ƃ��ɂ͉~������ 34
��؉��̂���i���ւ����ݏՓ˂��� 35
�������ꂽ�j���W���E�L���x�c 36
�킽���͑���E���˂錩���l�Ƃ��� 37
�����N�̂ނ�@���̂����������� 38
�������A�X�p���K�X 39
��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv�� 40
�ɕ`���ꂽ�Ⴂ�ւ̋�Y�̓��̂͂��� 41
�^�łȂ��Ȃ�g���镽�� 42
�Ƃ�����̉J�ɂʂ炳��邾�낤 43
�܂��`����Ȃ��G���@�G�����L����ׂ��ׂ��R 44
�e�[�u���̌����ɎR�ԁ@�X��b���̗� 45
�킽���ɂ���炪�����Ȃ� 46
�^�g�ȐF�̎������̂���ł��� 47
�q�͎ʁr��1963�N���܂łɔ��\���ꂽ�Ɛ��肳��邩��A�q�͎ʁr�ٍ̈e�̂悤�ȂƂ��낪����q����r�i�s���p�蒟�t1963�N2��
���j�́A���O
�サ�Ĕ��\���ꂽ���тƂ������ƂɂȂ�B�莝���̎�������͂ǂ��炪��Ɏ��M���ꂽ�����߂������B�����n��Ƃ�����́A47�s�̎������������Ƃœ����
�e�[�}��10�s�̎����������̂��낤���B1958�N�A189�s�́q�����r�i�C�E19�j��29�s�́q�r���r�i�C�E15�j������7���ɈقȂ�G���ɔ��\����
���B�q�r���r���f�ڂ����s�����t�����l���ł��邱�Ƃ����Ă���A�����炭�E�e�́q�r���r����ŁA�s�����C�J�t���\�́q�����r�͂��̌�ɏ���������ꂽ��
�l������B��̂ɑn��Ƃ͐V��������Ƃ��A�܂������V������т������̂ł͂Ȃ��B����܂ł̂��ׂĂ̎���ɁA�V���Ȉ�т������A������̂ł���B�q��
��r���q�͎ʁr�Ƃ����̂����M���ꂽ���Ȃ�A�q����r�́q�͎ʁr��25�`31�s�߂܂Łi�y�@�z�Ŋ���������j����肵�Ă��悤�B
����
�킽���͔������y�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv���z
�����邽�߂ɂ����ɂ���
�킽���͓��Ӂ@�X�X�L�̖݂̂Ȃ���
�킽���͕������@����y���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S�́z
���a�l�̏����̎x�ߕ��̂�������y�������̌҂܂ł̕S���̏�z
���₫�����錌�̐�
�킽���͂���ɂ���苩��
�M���������t�y�~���N�E�[���[�Ɨ₽�����z
�����������˖C��ւ̂ڂ�j�y�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯���z
�킽���ȊO�ɂȂ��Ɠ�����
����ŁA�{�т̖`���u���̋��͂��������j���^�������炾�S�̂ɒ���o���āv����z�N�����̂́A�q�n�E�t�̊G�r�Ƒ��Ȃ��q���E�H��
�G�r�i�D�E
21�j�ł���i���o�́s���Y�t1962�N3���̕�����ꍆ�j�B�g���́q�O�̑z���o�̎��r�Ɂu�u���E�H�̊G�v�́A���p�G���Ō����A�V�������A���X���̏���
��ƃ��I�m�[���E�t�B�j�̊G���ނɂ������̂��B�����Ă݂�A���t�Ŗ͎ʁm�A�A�n�����悤�Ȃ��̂ł���B��C�̗������߂锖���̏��ŁA�������Ă���u��
���A�t���f�B�[�e�[�v�ƁA�����ĉ������Ă��悢�B�u�킽���͂������ł���H�v�ƁA�v�炵�A��]���Ă���̂��v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A��Z��y�[
�W�j�Ə����Ă���i�T�_�͈��p�ҁj�B�����͂��ЁA�T���ƂȂ����t�B�j�̊G�Ǝ����r�������B
���I�m�[���E�t�B�j�̖��ʉ�q�I���r�i1949�j
���E�H�̊G�i�D�E21�j
���������ɂЂƂ肢��
���[�̉�������
���a�ⓔ�S���Ɠ����悤��
���֒���
���n�̓����̂�����{�������
���̂₳�����a�C����������
�����Ȃ��т̂Ђ��ɐG��Ă���
��Ȑ[�݂ɗ���
������ꂽ��I��
�킽���͂������ł���H
���������̌�
�a�̂ЂƉ�肷��ꃁ�[�g�����a�̔n�̓��W
���ꂪ���J����č��֑��Ƃ�
�킽���͔ۂł�����F���ł���
���ł��B���Ȑl�Ԃ̎������肩������
���͂������ׂ݂���ׂ݂ւ�
�킽���̔A�⌌����������܂�
�������o�łȂ���ΗՏ��I��
���͂ʂꂽ���̖т����ڂ��
����������������֎�����������
�Ȃ�̘c�݂��Ȃ�
�����ɐ�����
���ҋחނ̉H�т�爂�Â���
�u�͎ʁv�����̂܂Ƃ��āq���E�H�̊G�r�ƃt�B�j�́q�I���r�i1949�j���r�ׂĂ݂�ƁA���͒P���ł͂Ȃ��B�͎ʂ̂��߂̖͎ʂƌ�
������̂́A
�z���͂�������|���Ȃ̂��B�G�M���O�E�̑Ώە����Ȃ��鎞�ԓ��ɁA����͕ʂ̉�H�����ǂ�A���t�ɂ��`�ʂ̂���œǂ�ł���Ƃ��̂܂ɂ��Ώ�
�̋�̐��͉��̂��A����Ȃ�⼌��ɋ߂��g���̎���ɕ������߂��Ă���B�u��Ȑ[�݂ɗ����^������ꂽ��I�Ł^�킽���͂������ł���H�v�\�\���i�⎖
�����S�I�Ɍ��т����A���ꂪ�u�܂��⼌��I�Ȍ��t�v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A���l�y�[�W�j�̒藧�Ƃ��Ď���Ɖ����Ƃ����̂��\���I
�ȓ����ł���B���т͂��������B�u���������̌��^�a�̂ЂƉ�肷��ꃁ�[�g�����a�̔n�̓��W�^���ꂪ���J����č��֑��Ƃ��^�킽���͔ۂł�����F����
����v�\�\���������Ԃ̕��I�ŕω����邱�Ƃ��u���J�v�ƎƂ߁A����ɑR����ʂ̍s�������������ꂽ�Ƃ��A�u�킽���͔ۂł�����F���ł���v�����т�
�v�ƂȂ����B���傪�Ȃɂ��Ƃ���藧������Ȃ��̈�ɉ���������ꂽ���D�����A����͋t���낤�B�u����F���v���邽�߂ɂ́u���ꂪ���J����č��֑�
��v�K�v���������̂��B�g���́A�}����]���Ɍ��т₷�������⼌��I����̕��t�ƁA�����Ɏ���W�J�̖��͑��̒ǐ��������Ȃ��B��҂́A���̎��̏ꍇ�A�͎�
�Ȃ����Ă͐��܂�Ȃ��������̂����A�O�҂�������ς݂����Ă����Ă�⼌��I����ɂ͓��B���Ȃ��B���҂̊Ԃɂ͖ڂ�ῂނ悤�Ȓf���݂���B����͑��҂�
�e�[�������Ȃ������o�̌���Ő��܂��B�ł́q�͎ʁr�́u�N�[�g�̊G�v�����t�Łu�͎ʁv������i�Ȃ̂��B�����ł�����x�A�����d���Ȃ��玍�т�������
���̃u���b�N�ɕ����ēǂ�ł݂悤�B
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����
���̋��͂��������j��
�������炾�S�̂ɒ���o����
�����⒆���̐펀�҂̔��̖т�
�Â��肩��@�Â���܂łȂт�����
���̏�̐�������Ō���̂́H
������т�ꂽ�����̋�����
���ӂ����č��l�֑�C���������܂�
���N�̒j����l�Ő푈���͂��߂邾�낤
�����o��܂ł�
���̒j�͂ӂƂ����H��ɂȂ邾�낤
����悭�s����
���j�I�Ȋy����������H
�����ꂽ���@�����ꂽ�I
�ԖڂƗ�
��̂��闤�n����
���̌R�͂̊��z���Ȃ��ꂽ���ւ���
���������j�Ə��̂��悢�_��̈�
�킽���͏j�Ղ��Ă�肽���Ǝv��
��ƂȂ�Δ�����������
�葫���瓷�܂Ŗ_�̂悤��
�܂�����
�����͂�������܂ŗ������Ă���
�����Â���@���͊^�̂Ƃт܂�鐅���̂Ȃ���
���܈���̕��݂����
�������̌҂܂ł̕S���̏�
�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯��
���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S��
�s���S�ȔR�Ă�
�~���N�E�[���[�Ɨ₽����
��Ƃ̍��M�����I��
�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv��
�H����~�ւ����Ē��Ӑ[��
�R�͂͑S���~�����
�Ƃ��ɂ͉~������
��؉��̂���i���ւ����ݏՓ˂���
�������ꂽ�j���W���E�L���x�c
�킽���͑���E���˂錩���l�Ƃ���
�����N�̂ނ�@���̂�����������
�������A�X�p���K�X
��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv��
�ɕ`���ꂽ�Ⴂ�ւ̋�Y�̓��̂͂���
�^�łȂ��Ȃ�g���镽��
�Ƃ�����̉J�ɂʂ炳��邾�낤
�܂��`����Ȃ��G���@�G�����L����ׂ��ׂ��R
�e�[�u���̌����ɎR�ԁ@�X��b���̗�
�킽���ɂ���炪�����Ȃ�
�^�g�ȐF�̎������̂���ł���
��Ƃ��đO����4�s���A�㔼��3�s�𒆐S�ɂ��āA�Ƃ���2�s���������u���b�N�\���ł���B��̂ɋg���͎���̐������낦�Ď��߂�ς݂�
���Ă����쎍
�@�Ƃ͉������A�{�т�4�s�Ȃ�3�s�Ƃ����̂��ӎ��I�ȑ���Ƃ͎v���Ȃ��B���ꂾ���Ƀu���b�N�̍ŏ��Ɉʒu���鎍��́A���т��쓮���Ă����d�v����S���Ă�
��B���Ȃ킿�A23�`24�s�u�����Â���@���͊^�̂Ƃт܂�鐅���̂Ȃ��ց^���܈���̕��݂�����v�����A�q����鏗�r��11�s�߁u�ł̋�Ɂv�ƁA
�q���E�H�̊G�r�̃t�B�j�̖��ʉ�A����ɂ́q����r�S�т̐�������āA�g��������i�߂��A�v�ƂȂ鎍��Ƃ�����B���ꂩ����ʂ��A����2�s�̑O��22
�s�A���23�s�Ƃقڋύt����B���ꂾ���ł͂Ȃ��B�O��22�s�̍ŏ��i�u���̋��́k�c�c�l�Ȃт����āv�j�ƍŌ�i�u��ƂȂ�k�c�c�l�������Ă����v�j��
�u���b�N�́A�z�����J�[�h���������悤�ɁA�����Ȃ܂ł̑Δ��������B�����A����ƂČv�Z�����̂��̂ł͂���܂��B���т̔��ŃM�A��ς��邽�߂ɁA��
�Ƃ܂����̏I����}�������ʂ��Ǝv����B���̒��~��Ԃ��A�㔼23�s�̔����I�ȓW�J��p�ӂ���B�u���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S�́v�ȉ���3�s�́A���J����
�������̚g�ł͂Ȃ����B����ɑΉ�����u�����N�̂ނ�@���̂������������v�ȉ���3�s�́A�A�s�B�̂��߂Ɏg�����ƂȂ����҂����ւ̃��N�C�G��
�ł͂Ȃ����B�N�Ⴂ�j����ʂƂƂ邩�A��n�ŎU������N�҂ƂƂ邩�͓���������B����ɑ����A���т���߂�����Ō��7�s���ǂ��ǂނׂ����B�͂��߂�3
�s�͏��N�����̖살�炵�̎p�̂悤�ł�����A�Δʼn�̐���菇���������悤�ł�����B���Ȃ͎̂���3�s�́u�R�v�u�R�ԁv�u���v�ł���B�����̃C�}�[
�W���́u�܂��`����Ȃ��G�v���������āA�N�[�g�[�̃^�u���[�����}�O���b�g�̂���i���Ƃ��q�A�����n�C���̗̒n�r�j��z�킹��B�������u�킽���ɂ���
�炪�����Ȃ��v�̂ł���B�����čŏI�s�́u�^�g�ȐF�̎������̂���ł���v������B�{�тɂ͐F�ʂ�\����́u�ԔS�y�w�v�����邾�����B���́u�^�g�v�͋���
�ł���B�N�[�g�[�͐F�ʂ̎g�p�ɋ֗~�I�Łi���Ƃ��A���̞����炯�̐l�̂ɂ͂����ނˈÂ��D�F��Z���ΐF���{����Ă���j�A���ꂾ���Ɂq�C�݂̃G���e�B�R
�}�W�[�\Plage de
l'Eroticomagie�r�i1954�j�̐^�g�͒��������ʂ��グ�Ă��邪�A�g�����Ō�̎���ł���ɕ�������̂Ƃ݂���B
�����V�A���E�N�[�g�[�q�C�݂̃G���e�B�R�}�W�[�\Plage de l'Eroticomagie�r�i1954�j
�q�g����������r�ł��G�ꂽ�� ���ɁA�g���͗B��̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�Ɂu�V�i �̏����v�i���_�ł́u���߂́v�u���l�̏����v�j��o�ꂳ�����B����A���������X�́A�����ƕ���ŋg���̍ł��e���n�D�i�ł���A�e���̏ꏊ�ł���B�g ���ɂƂ��ăV�i�̏����ƈ�t�̔M������͐��ɂ����Č��̂悤�Ɋ������ꂽ�q���r�̕ʖ��ł͂Ȃ��������B�Â��ȉƂ��o�āA����X�ɓ���B��t�̔M������� �O�ɂ��āA�ᖒ�g�̈Íg�F�̕��}��ɂ��āA�q���r�ɓ����Ă����B����ł�����X�Ŏ����������ƂȂǂł��悤�͂����Ȃ��B���r�E�X�̗ւ����ǂ�悤�ɂ��� �����o�̓����ɓ��肱��ł��܂����҂ɂƂ��āA���т������Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A�Ô��ȋ�ɂ����J���������ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�u������킽���͎蒟������ �����Ȃ��B�i���X�ŁA�X�p�ŁA�ӂ��ɑf�������Ǝv���鎍��Ȃ�Ӑ}���������m�����n��ł��킽���͏������߂��肵�Ȃ��B����͖Y���ɂ܂����邱�Ƃɂ��� ����B�킽���ɂƂ��Ė{���ɕK�v�ł�������A����͍Ăь�����ɈႢ�Ȃ��ƐM���Ă���B�킽���͎����������́A�Ƃ̒��Ŋ��̏�ŏ����ׂ��p���ŏ����v �i�q�킽���̍쎍�@�H�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�����y�[�W�j�A�u�i���X�Ō��e��ǂސl�����݂�̂������͍D���łȂ��v �i�q���������̎��r�A���O�A�ꔪ��y�[�W�j�̐^�ӂ��낤�B�u��Ɓv�Ƃ͂����炭�A������ꂽ���l�̎p�ł���B
��
�`���ŏq�ׂ��悤�ɁA�s�Â��ȉƁt�͒P�s���W�ȑO�ɓ����̑S���W�ł���s�g�������W�t�ɖ������W�Ƃ��Ď��߂�ꂽ�B���̂��߂��낤�A
�s�m���t�ȍ~��
���ׂĂ̎��W�̊����ɕt���Ă���q���o�ꗗ�r�������B����đ��̎��W������Ԏ�������A16�ђ�15�т܂ł͏��o�����ł����i���̐��ʂ��q�g�������W�s�Â��ȉƁt�{���Z�فr�ɋL���Ă���j�B�����q�͎ʁr�̏��o�́A�T�����n�߂Ďl�����I���o�Ƃ����̂ɁA�����ɔ����ł��Ȃ��B�����u���o���ځv�Ƃ����L�ڂł��A�s�g�����S���ѕW������t�i1995�j�ł́u�k1967�N10���܂łɔ��\���l�v�Ƌy�э��ŁA�s�g�������W�t�ɖ������W�Ƃ��Ď��߂�ꂽ���_�������Ƃ��Ă���B���́s�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�i2000�j���L�ړ��e�͓����B�ŐV�́s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t�i2012�j��
262�@�͎��\�\ ���̓N�[�g�̊G����i������@���邢�̓N�[�g�̂�����j�m191-194�n
���̋��͂��������j��
47�s�����o���ځi���c�O�́s���㎍�蒟�t1964�N2�����̋g�����_�Ŗ{�т�3�s���A�����炭���o������p���Ă��邩��A1963�N12���܂łɔ��\�� �ꂽ���j���E�Â��ȉƁE4
�Ə��߂ĉ������J�肠�������B�������N�A���܂��܂ȏ�����f�[�^�x�[�X��1963�N�܂ł̋g���������������āq�͎ʁr�̏��o��ǂ����� �Ă���̂����A���̉e���������Ȃ��B�Ȃ�Ƃ����킵�����̂���A����ɂƂ��ĕs���̂Ȃ��ۑ�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�k2016�N10��31���NjL�l
�g�����̎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�������������B1963�N8�����s�A���q�����ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�����ꂾ�B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�i���W�s�Â��ȉƁt���^�j�̊Ԃɂ́A�Ђ炪�Ȃ̑����i�u���v�^�u�v�j�̕\�L�������āA����Ɉٓ��͂Ȃ��B
��
�i��1�j�@�s�g�������W�t�t�i�v���ЁA1967�j�́s�a���`�t�i����ɁA1962�j�̔̔�����|�����v���Ђ��p���k������{���W�l�i1962�`64�j�ɋg�����̊����m�~�l�[�g���Ȃ�������Ɏ���Ȃ��������Ɓi���ꂪ�����͕s�������j�A���サ����悾�Ǝv����B�u�b�N�f�U�C���ɋN�p���ꂽ���Y�N���̎d���Ԃ�����ւ��āA�����̐���͕K�������X���[�Y�ɂ͐i�����Ȃ������B�܂��A�g����1967�N3��1���̉i�c�k�߈��͂����Ɂu�S���W���Z���ƂȂ�A�l���ɂ͊��s�����Ǝv���܂��B���̂��݂ɑ҂��Ă��ĉ������v�Ƃ���A����ɓ��N8��2������̂͂����ɂ́u�S���W�ǂ���甪���ɂ͏o�ł���邱�ƂƎv���܂��B���܂��炭���҂����v�Ƃ�����̂́A���ۂɊ��s���ꂽ�̂�10���ł���i���Ҍ��{��9�����ɏo���j�B
�i��2�j�@���̓o�ꂷ�鎍��
�E�I��ɍE�̂�������S�̓��̓������v��i�n�E�t�̊G�A�E�E5�j
�E�����S�łȂ��E���铛����o��i�t�̃I�[�����A�E�E10�j
�E�����ʂ��钹�i�ǓƂȃI�[�g�o�C�A�E�E14�j
�i��3�j�@�A�̓o�ꂷ�鎍��
�E�����̖A�̂Ȃ��Łi���A�E�E8�j
�E���łɂȂ��O������A�����ڂ��i�ǓƂȃI�[�g�o�C�A�E�E14�j
�E�����₭�A�̂Ȃ���̂Ȃ�����i���I�ȗ��S�A�E�E12�j
�E�����̖A�̏㏸����̂��ώ@����i������G�A�E�E15�j
�g�����Ƙh���ɒj�ɂ��ẮA���сq���͂Ȃ����F�Ȃ̂��H�r�i�F�E12�j�̕]�߂ł���q�u������H��v�r���q��/�h�������Ɓq����r�r�� �����߂ŁA�h���ւ̒Ǔ����q����r�i�J�E17�j�������ď��������Ƃ�����i�q�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁r�����j�B����́A���炭�܂��ɐΐ_�� ���т���g�����̘h���ɒj���͂����E���Ȃ��w�������̂Łi�����Ĉ����������ł͂Ȃ����A�g�����́u�V��v���ǂ߂�ƂȂ�Ζ��ʂȏo��ł͂Ȃ��j�A������� �ɋg�����Ƙh���ɒj�̂��Ƃ��l���Ă݂����B�܂��A�s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t93���i2014�N7���j���f����B
548�@�g�������M���ȥ�t���i�h��
�ɒj���j 108,000
����1�ʁA�t��3�ʁA���i����j5�ʁB���Ȃ͕��4���������i��56�N�j�A�h���ɒj�̋�W�w�Αفx�ւ̗��B�u�D ���ȋ������ �܂��v��17��J�Ɏʂ��A�����ɂ́u�d�b��������ق��̂��Ƃ͂����Ăł���ɎQ��܂��v�Ƃ���B�h�ӈ��镶�ʁB�t���͏��a40�N��A�y���� 8�`10�s�B�w�V�̘T�x�������Ă��炢�u�܂ڂ낵�̖���W�v�u�Ȃ��������������܂��v�A�w��̉ʂĂւ̗��x�ւ̗��ɂ́u�M�Z�������������ꂽ��ƍl���� ���B�ꌾ�ꌾ���E�E�E�v�B������ɂ͋`���a�c�`�b�̑r���t��������u�����ɂƂ��Ă����_�I�x���v�Ƃ���B�i���ژ^�A��l�y�[�W�j
���ɁA�͂����E���Ȃ̔��M���Ɋے�������U���ĊT�v�������B�Ȃ��u�^�v�͉��s�ӏ��A�����̘h���́u���v�͂��ׂċ����A���L�ȊO�͏c�� ���E�c�g�݂ł���B
�@1966�N11��3���@�����͂����k�T
�~�͂����ɂT�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l�D�y�s�k�O�\�����l���ځ^�h���ɒj�l
�@�k�͂����\�l�����s�k����쎵�m�O�^���c����A�p�[�g�l�Z�l�^�g����
�@�i�ȏ�y�������k�C���N�̓u���[�u���b�N�A�ȉ����l�j
��
�q���@���܂܂Œg�����������̏\�ꌎ���A�����O������}�Ɋ����Ȃ�܂����B���������k�C���͊����ł��傤�B���W�u��̉ʂւ̗��v�Ƃ��͂���������
���܂����B���������i����Ă���A�M�Z�ɂ͓���������܂��B�M�Z�̓Ǝ��Ȏ��`�A�߂������E���A�u�o���v����ނƁA�킩��悤�ȋC�����܂��B���́u�o���v��
�͊������܂����B�������U���ł��B�����̎v�����ʼn]���A�M�Z�������������ꂽ��ƍl���܂��B�ꌾ�ꌾ���A�����������t�H�����́A��x�A�����I�Ȃ��̂�
�����āA�݂���Ǝv���܂��B�h��
�@�i�ȏ�y�������j
���F�h���̑�Z���W�s��̉ʂւ̗��t�i�����ЁA1966�j�́q�o���r�ɂ�
�u�k�c�c�l�吳�\��N�֓���k�ЂŁA��͎��Ɨc��������A�傫�ȗ�����g�Ɏx�ւ��������v�i�s��{
�h巢�ɒj���W�k���y�Łl�t��2���A�����ЁA1976�N4��15���A��O��y�[�W�j�Ƃ���B
�A1967�N8��28������@�����͂����k�V
�~�͂����l
�@�k�͂����\�l�D�y�s�k�O�\�����l���ځ^�h���ɒj�l
�@�k�͂����\�l�����s�k����쎵�m�O�^���c�A�p�[�g�l�Z�l�^�g����
�@�i�ȏ�y�������j
��
�q���A�����͎c���Ƃ����A�A���O�\�x�����������ŁA�Q���Ă��܂��B�s�V�̘T�t�������肢�����܂����B�����ɂ��m�点���ׂ��Ƃ���A����ɒǂ��
�āA�S�Ȃ炸�����炵�܂����B�܂ڂ낵�̖���W�A�{���ɂ��肪�Ƃ������܂��B�������U�������܂��B�ߙ��̂��߁A���ׂ��Ђ��ꂽ�����ł����A�����炾����
�ɁA�����i�̂قǁB
�@�i�ȏ�y�������j
�B1968�N�i�\�N�j�N��@�����͂�
���k�V�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l�D�y�s�k�O�\�𐼎l���ځ^�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j
��
�����܂���
���߂łƂ�
�������܂�
�k�T���̐����ԐF����l
�g�� ���E�z�q
�����s�k����쎵�̎O
���c����A�p�[�g�l�Z�l
�@�i�ȏ㊈������j
�C1969�N7��30������@������
�����k�V�~�͂����l
�@�k�͂����\�l�D�y�s�k�O�Z���l�^�h���ɒj�l
�@�k�͂����\�l�����s�ڍ���t��^�k�c�c�l�^�g����
�@�i�ȏ�y�������j
��
�q���A�������������肪�Ƃ������܂��B���N�͂��܂�������A�V���łȂ܂��Ă��܂��B�M�Z�ɂ͑��ς������C�Ŏd�������Ă��邱�ƂƎv���܂��B��N�̕�A��
�z�ʒm�ƐV�N�̈��A����������̂ł����A戾���Ă��܂����B�������Ԓn���ԈႦ���̂ł��傤�B���炢�����܂����B��
�@�i�ȏ�y�������j
�D1970�N�i���N�j�N��@�����͂�
���k�V�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l065�^�D�y�s�k�O�Z���l�^�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j
��
�k�C�k�̔ʼn���F����l
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
�P�X�V�O�N���U
�����s�ڍ���t��k�c�c�l
�k�c�c�l�@�d�b�k�c�c�l
�@�i�ȏ㊈������j
�E1972�N�i�q�N�j�N��@�����͂�
���k�V�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l�D�y�s�k�O�\���l�^�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j
��
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
1972�N�E���U
�k�l�Y�~�̐����ԐF����l
�g�����E�z�q
�����s�ڍ���t��k�c�c�l
�@�i�ȏ㉡�g�݂Ŋ�������j
�F1973�N�i�N�N�j�N��@�����͂�
���k10�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l�o��s�~���\�l�O�^�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j
��
�����܂��Ă��߂łƂ��������܂�
1973�N�E���U
�k�E�V�̔ʼn���F����l
�g�����E�z�q
�����s�ڍ���t��k�c�c�l
�@�i�ȏ㉡�g�݂Ŋ�������j
�G1977�N11��28���@�����͂�
���k20�~�؎�\�t�l
�@�k�͂����\�l��{�s�厚���۔����O��Z�m��^�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j
��
���~�̌�@�݂Ȃ��܂ɂ͂����h�̂��ƂƎv���܂�
���ā@���̏H�̂��Ɓ@�Ȃ̕��a�c�F�b�V�h�}�̂��ߒ����������܂���
�ȂɂƂ��Ă͂��Ƃ��@�����ɂƂ��Ă����_�I�x���Ƃ������ׂ��l�̎��������������܁@�S���Ԃ������̂�����܂�
���Ắ@�N���N�n�̂����A���������Ē����܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�\��N�\�ꌎ��\����
�@�i�ȏ�O���[�̌r�݂͂Ŋ�������j
�H1981�N5��4���@�����@���4
���k60�~�؎�\�t�l
�@�k�����\�l330�^��{�s�厚�쒆�۔����^�O��Z�\��\��Z��^�h���ɒj�l
�@�k�������l�����s�ڍ���t��k�c�c�l�^�g����
�@�i�ȏ�y�������j
��
�q�[�A�����C�ł��d���ɐ��i����Ă��邱�ƂƎv���܂��B�k�c�c�l
���āA�����ԈȑO�ɁA��W�w�Αفx���Ȃ���A�����\���グ��̂��A�x��܂��āA�{���ɐ\��܂���B��A�O���O�ɂ���ƒʓǂ������܂����B������
����A�D���ȋ���f���܂��B
�@�@�~�@�C�E�@����Ȃ̂����ь�Ɍ��� 34
�~�@�C�E�m���Ȃ����n�@����Ȃ̂����ь�Ɍ�����
�@�@�����̔w�Ɉ��Ђ�����̉� 36
�����̔w�m���т�n�Ɉ��Ђ�����m�ЂƂЁn�̉ʁ�
�@�@�����߂@�q���g���@���������ɂ����� 40
�����߂@�q���g���@���������ɂ����Ɓ�
�@�@�F���ɑe�����֑���̂� 43
�F���ɑe�����֑���̂݁�
�@�@�������銾�̍r������Ȃ� 44
�������銾�̍r������Ȃ���
�@�@�t�Չ����@�𒎂悱���͂� 46
�t�Չ����@�𒎂悱���͂�
�@�@���������ƌ{���悱���镗�ׂ̍� 55
���������ƌ{�m�Ƃ�n���悱���镗�ׂ̍ȁ�
�@�@�n�̎����Ƃ��ӂԂ��@�R�Ɍ��� 58
�n�̎����Ƃ��ӂԂ��@�R�Ɍ���
�@�@�I�������ȂԂ�@�ÎR�݂̂̓~ 81
�I�������ȂԂ�@�ÎR�݂̂̓~
�@�@��������́@��ӂׂ��Ȃ������z�� 98
��������́@��ӂׂ��Ȃ������z�Ӂ�
�@�@������������ޕ�Ƌ�Ӄg�}�g�Ȃ� 103
������������ޕ�Ƌ�Ӄg�}�g�Ȃ�
�@�@�Ƃ����݂̂�v�����@�Ԝ悫 105
�Ƃ����݂̂�v�����@�Ԝ�m����n����
�@�@�k������@�����L�������������ڂ��Ēp�� 107
�k������@�����L�������������ڂ��Ēp�Á�
�@�@���̎���ǂ�̓��c�_�e�� 120
���̎���ǂ�̓��c�_�m���Ȃǁn�e�m���فn��
�@�@�S���炯��@���ɂ��͂�̗������� 145
�S���炯��@���ɂ��͂�̗������m����n��
�@�@����Ȃ��炩�ӝۂ̎R�̒�蟬�� 152
����Ȃ��炩�ӝۂ̎R�̒�蟬��
�@�@�ĕ����̎��Ɂ@�{�}�I�邩�� 158
�ĕ����̎��Ɂ@�{�}�I�邩��
�����͂�͂�A������i�ɐS���܂����B��l���������l�ɁA�o�l�łȂ��A��������l�ԂɂȂ��āA�悩�����ȂƎv���܂��B��X�B�s�S�߂��ɏo��ꂽ���A�d
�b��������A���̂��Ƃ́A�e���Ă��A��ɎQ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܌��l��
�@�h���ɒj�l
�@�i�ȏ�y�������j

�h���ɒj���u�g�����v�Ɉ��Ă�����W�s�Αفt�i�����ЁA1981�N2��20���j�̌��Ԃ�
�y�[�W�Ɠ����̕\��
���F�g�������p������̂��Ƃ̐����̐����Ƌ�́A�h���ɒj�p�咟�s�� �فt�i�����ЁA1981�N2��20���j�̌f �ڃm���u���ƌf�ڋ�`�ŁA��p�����͐V���ɉ��߂��B�s�Αفt�͋����\�L���̗p���Ă��邪�A�g���͏�p������V���ɉ��߁A�ǂ݉����i���r�j���ȗ����Ă���B �h���ɒj�̑���W�s�Αفt�́A�P�s�{�ɐ旧����640������́s��{ �h巢�ɒj���W�t�i�����ЁA1971�N9��1���j�����́q�c������r�Ɂq�u�p�咟�E�Αفv���r�Ƃ��ď��߂Ď��^���ꂽ�B����āA�g�����I��Łq���r�i�g ���͓��R�����ǂ�ł���j�Ɏ��^����Ă�����ɂ́����t�����i�q���r�̕\�L�́A�Ђ炪�ȁ^�����E���r�ŒP�s�{�ƈقȂ�ӏ������邪�A�ώG�ɂȂ�̂� �G��Ȃ��j�B

�g�������h���ɒj�Ɉ��Ă��͂���3�ʁA������ق�5�ʁA����1�ʁi1966�`81�j
�H�̍Ō�ŐG��Ă���悤�ɁA�i�����Ə������������Ȃ��������̂́j�g���͘h���ƂƂ��ɔo��E�Z�́E���E�U���ƁA���㎍�l�Ƃ��Ă͒��� �����ނɓ��� ���`���ւ̒���҂������i���Ȃ��Ƃ��g���ɂ́A�h���̑��d�ȏ@�������������̔o��̂ق����߂���������ꂽ���Ƃ��낤�j�B��l�̋��ʂ̒m�F�ł��鍂���r �Y����͂肱�̌^�̎��l�ł��邱�Ƃ͂܂��Ƃɋ����[���B�g���Ƙh���͂��݂��̑��݂�m�����̂��낤���B�g���͘h���Ɋւ��Đ��z���c���Ă��Ȃ��̂ŁA�_�J ���M�s�]�` �h巢�ɒj�t�i���X�A1998�N12��25���j�œ�l�̊W�����ǂ�ƁA�u���̍��i1966�N���j����A�ɒj�͋g�����A�F�V���F�A���������A�����̎� �l�����ƕ��ʂ�ʂ��Ă��Ȃ�q����������Ă����B�k�c�c�l�ɒj�͔\���ł���A�莆�͔�������ŏ�����Ă����B�k���a�l�\��N�i���Z���N�j�l�����\�� ���A���l�̌p��G���i�Ȃق���ď�ԂƂȂ�A�ɒj�͎D�y����}篋삯�t�����B�k�c�c�l�D�y�ɋA��O�A�ɒj�͏��X�Ђ�K��A���ʂ��ėF������ł����g�� ���A�����ρA��������A�����r�Y��Ƃ������������v�i�����A��O���`��O��y�[�W�j�Ƃ���A�ǂ���炱�̂Ƃ������Ζʂ̂悤���B�����A�q��/�h�������� �q����r�r�ň��p����1967�N12��12���t�̋g�������Ȃɂ�����Ƃ���A�g�����Ƙh���ɒj�_�I�Ɉ������킹���͍̂����d�M�ł���A���̎t���̕x�V �ԉ��j�������ƌ����ׂ����낤�B�����d�M�͘h���̉̏W�s�ڈ̂킩��t�i���� �ь牮�A1974�N1��17���A����1000���j�̏��]�q�؎��ɉ̂킴��Ȃ��S�r�i���o�́s���{�Ǐ��V���t1974�N3��25���j�������n�߂Ă���B
�@�h���ɒj��菭���x��ē����x��ԉ��j���t�Ƌ����l�ɂƂ��āA�ނ͋v�����ԁA�ǂ����֍s���Ă��܂����܂܁A���� �܂ł��A���Ă��Ȃ��Z�M�ł������B
�@ �s��̗��N�A�J��c�̈���Ƃ��Ėk�C���֓n�����܂܁A�قƂ�Nj��m�̐l�Ɖ���ƂȂ��A���܂��܂ȋ����̕ω��̒��ʼn߂��Ă������h���ɒj�̎O�\�N�߂��Ό� �́A������ɂ��Ă��q���l�̂��̂ł͂Ȃ������͂��ł��邪�A���̊Ԃ̂킸���ȏ�����`�����̂́A�w�����x�Ɏn�܂�w����̊��x�w�ؑ��̊�̉��x�w���^�� ���t�I�[�V�X�x�ƁA���X�ɏo�ł���邽�тɕx��ԉ��j��ʂ��Ď�ɓn�鎍�W�����ł������B�i�s�����d�M�S�W�k��O���l�t�������[�A1985�N8��8���A�O �Z��y�[�W�j
��f�̂͂����E���Ȃ�����ƁA��ꎍ�W�s�����t�i�k�����b��A1950�j�������W�s�_�l�����t�i�p�̉�A1961�j������܂ł͊�
�s���ɋg����
�����Ă��Ȃ��悤���B�����Řh���ɒj�̎��Ƃ𑍗����ċg�����̎��ƑΔ䂷�邱�Ƃ��ł���A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��̂����A���܂̎��ɂ͎�ɗ]��B����A
���̐悢���玞�Ԃ������Ă��u��������v���ƂȂǂł������ɂȂ��B�����ŁA�h���̏����̎��������Ă��̍e���I�������B�G�s�O���t�ɃA�|���l�[���̎��W�s�A
���R�[���t�i1913�j����q��̊p�J�r��2�s�i�x����{��ł́u�v���o�͎�̊p�J�^���̂Ȃ��ɉ��m�ˁn�͏����Ă䂭�v�j�������ň������q�����r�ł���B
�����͘h����1967�N�A�g���ɑ�������O���W�s�ő��̊�̉��t�i�����[�A1954�j�Ɏ��߂��Ă���B
�����b�h���ɒj
��������̒��ɂڂ��͂ڂ��̎q��������
��������̒��ɂڂ��̌�����ʎq�����ӁB
�ق̂ڂ̂ƒn�M�̒��̗����B�������̂́A
�ق��Č��͂ʂނ����̊�̗����B
�ӂݖ����H�n�łڂ��͗��j�̔���@���B
�R��铔�͂���̐S���Ƃ炵�͂��Ȃ��B
�Ћ��ň����������I�ԂЂƂ�B
���̂����Ȗ����͂����ނ��̂�B
�Ղ₵�͂������Ă��邪�A�Ȃ�ƍr�X�����䂫���̌ċz�m�����n���B
�ڂ��̖ȉَq�͂Ȃт��Ȃ��B
��������̒��ɂ��݂͂��݂̎q�������ӁB
��������̒��ɂ��݂̌��m��ʎq�����ӁB
�ق̂ڂ̂ƒn�M�̏�̗����B�䂫�Ă��ւ�ʁA
���̋��́A���X�����Ă䂭�����B
�R���j�C�̝��������c����������B
����Ȃ͖���߂���B
�u�ق̂ڂ̂ƒn�M�̒��̗����v�u�ق̂ڂ̂ƒn�M�̏�̗����v�u�R���j�C�̝��������c����������v���o��߂��悤�Ȃ̂́A�Ӑ}�I �Ȃ��̂��� ���B�g�����͂����@�ŗv�]�����u�����I�Ȃ��́v���\��Ă���悤�Ɏv���B���́A�g�����q�c������E�f�́r�ň����Ă���c���̎��сq�ɂԂ��S�r��z�N�����B
�@�@�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�@�@�k��
�g�����́q�s�E�Łt�O���r�Łu���\�����A���킢�Ȃ��傾�Ǝv���Ă������A���x�ǂ�ł݂āA�R�[�q�[�D���A�i���X�D���̎��ɂƂ��āA��Ȉ�傾�Ɗ������v�i�s�Ս��t333���A1978�N11���j�Ɠf�I���Ă���B�����̋g�����q�i�c�k�ߋ�W�s�E�Łt����叴�r�ȗ��A���̋�͊����グ�A8�N��́q�t�������\�\�i�c�k�߈����ȁk1986�N10��26���t�l�r�ɂ�
�@�q���@���̂��т͂��莆�ƍk�ߒZ����q�Ċ����������܂����B�S�����l�̊���������ꂽ�Ƃ̂��ƁA�܂��Ȃ�Ɣ�������������ꂽ���Ƃł��傤���B�ō��̂����{���Ǝv���܂����B���āA�������Z���ɂ́A�s�ł̖���u�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�v�����M����Ă���A�i���X�D���̏����ɂ͉����̂��̂ł��B���Ă̎P���̉�̐܂ɒ������Z���̕M�����A��x�I�ł���Ȃ�A����ɂ͔��B�̕��C�������܂��B�����ɁA�����Ε��̘e�ɒu���āA���X���߂Ă���܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ������܂��B����͋v���Ԃ�ŁA�J���~���Ă��܂��A�H�̉J���B�~�̖K�ꂪ�����Ƃ̂��ƁB���ꂮ������g��ɁB�i����422���A1987�N1���A��܃y�[�W�j
�Ƃ����āA87�N3���́s����D�t�ʍ���2���f�ڂ́q�k�ߎO�\��r�ɂ����āu�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�v�̖����͒�܂����B�k�߂̂��̋��ڂɂ��邽�тɁA�g���́q����r�i�E�E3�j���v���o���B
����b�g����
�킽���͔�����
�����邽�߂ɂ����ɂ���
�킽���͓��Ӂ@�X�X�L�̖݂̂Ȃ���
�킽���͕������@����
���a�l�̏����̎x�ߕ��̂�������
���₫�����錌�̐�
�킽���͂���ɂ���苩��
�M���������t
�����������˖C��ւ̂ڂ�j
�킽���ȊO�ɂȂ��Ɠ�����
���̂킸��10�s�̎��ɂǂ�قǂ̓䂪�܂܂�Ă��邩�A���낵���قǂł���B1941�N����45�N�ɂ����āA�g���͒����嗤��]�킵�Ă������A�q�킽���̍쎍�@�H�r�ɓ����̂��Ƃ��o�Ă���B���ꂪ���_�ɓo�ꂷ��̂́A�g�������̊j�S�̂ЂƂ�����ł���B�u����ʂ̕����֍s�����B�k�c�c�l�킽���́A�Â��I���h���̂����ɍ��߂̏������݂��B�V�������֊��������Ă���B�킽���ɑ��āA����Ƃ�̂ł��Ȃ���A�����̊��������ł��Ȃ��A�������������鏭���ɁA���̐��̂��̂Ƃ͎v���ʔ����������B���̋A�荋�J�ɂ����A�D����킽�������͔n���̂悤�Ɏ�������B�Ƃ��ǂ����̒��̒n�ɐ^�g�̈�ނ�ᖒ�g���炢�Ă����B���l�̏����ƌᖒ�g�̉Ԃ��A�����ł��N�₩�ɂ킽���̊�Ɍ�����B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�`��l�y�[�W�j�B�u�ᖒ�g�v���Ȃ�Ƃ������Ă���B���́u���߂́v�u���l�̏����v���q����r�́u���a�l�̏����v�ɂ��A���́q������G�r�i�E�E15�j��
�ڂ����N���C���������Ƃ�������
�ЂƂ�̏���������
����͂ڂ�����\�˂̂Ƃ�
���Ȃ����V�i�̏����Ɏ��Ă���
�k�c�c�l
�R���N�̖̂Ȃ����т̓���
�J�P�������V�i�̕ꖺ
�������r���l���炵�čs��
������܂錩��
�́u�V�i�̏����v�u�V�i�̕ꖺ�v�ɂ������Ă���̂�������Ƃ����������B�q����r�ɖ߂�A�ŏ���2�s�\�\�����̎��傱���i���X�őz�������сA�Y���܂܂ɂ܂����A�Ăѕ��サ�Č��ǂ͌��e�p���ɒ蒅���ꂽ���̂ł͂���܂����\�\�͂Ƃ�킯��ɏ[���Ă���B
�@�킽���́i�������j������
�@�i�����Ɓj�����邽�߂ɂ����i�������j�ɂ���
�Ƃ����ӂ��ɁA���炯�Ȃ̂��B����߂邽�߂̍ޗ���3�s�߈ȉ��ɂ���B���Ƃ��u�킽���́i���̐��j�������^�i�u������v�Ɓj�����邽�߂ɂ����i���X�X�L�̖݂̂Ȃ��j�ɂ���v�B�������Ȃ���A���̂悤�ɓ��Ă������Ă����������ɓ䂪�������C�����Ȃ��B���̍��݂ɏ���u�j�v���u�킽���v�i10�s����5����o�Ă���j���Ƃ��������ЂƂ̓�ƂƂ��ɁB
�g�����Ɓu����v�ł���B�ѓN�v�s�i���X�̎���\�\���̂Ƃ�����ȓX���������t�i�ҏW�H�[�m�A�A2002�N2��22���j�́q�ؓ��r�̖����ɁA�g���́s���܂�͂����L�t������1938�i���a13�j�N8��31���̋L�ځi�u��y��l�Ɩ{���O���ڂ̐ؓ��ŃR�[�q�[���̂ށv�j��������Ă���B�s�i���X�̎���t�͑�15�����G���L�O��O���w�����܂���܁A�т���͂���Ɋ֘A���āA���{�o�Ŋw�������Ŕ��\���s���Ă���B���̗v�|�Ɂ\�\�w�i���X�̎���x�Ƃ����{�����܂��[���́C���I�Ȕ��������E�X�N���b�v�ł������D�Ǐ��̉ߒ��ɂ����Ē��ӂ������ꂽ�H���C���X�g�����C�i���X�Ȃǂ̋L�����W�߂Ă���Ƃ��C����̋i���X�ɂ��Ă��܂��܂Ȑl���������y���Ă��邱�Ƃ��C�ɂȂ����D���Ƃ��Ζ{���O���ڌ����_�߂��ɂ������u�ؓ��v�ł���D�i���{�o�Ŋw�� - �w�i���X�̎���x���߂����ā@�@�с@�N�v�@�i2003�N2��17���j�j�\�\�Ƃ����āA�Ï�����g���������̔��{�Ԃ肪����������B�������߂ās���܂�͂����L�t���Ђ��Ƃ��Ă݂��B
�����a�\�l�N�i���O��j�@�^���^���@�[����艼�����Ŗ{��������֍s���B�������w�Z�̃N���X���[�g�R��ӁA�y�A���R�A���`�炪����B���߂͊�̌����������B�u�Ⴊ���l�͓���m�A�A�n�������o����悤�ɂ��Ƃ��Ȃ����v�̐��ɁA�ǂ��Ə����Ђт��B�u�`���|�R��������Ȃ�Ă��₾�Ȃ��v�B�݂�Ȗ����ʉ߂��B���O�ʂ�̓쉮�ŃR�[�q�[���̂݁A�k���ĕʂꂽ�B
���\�ꌎ�\�O���@�ߌ�A�{��������֕����̌��ōs���B�R�������̉ƂɊ�����B�������[���؏��̎��^�����͂��܂�B�O���ɗ������B�A��͂܂��V�A�����Y�ƈꏏ�ɂȂ�A�Ό����́u���v�ɓ����āA�R�[�q�[�ƃp����H�ׂ��B�߂��܂��V�͂��Ԃ����ƈɓ��֗V�тɍs���ƌ����B�b�퍇�i�̂��Ԃ����͗�������ɓ��c���邻�����B
���\�ꌎ��\�O���@��ɂȂ��ĉJ�B�t�˂���Ɨ���O������X�u���W���֍s���B���������̐Ȃ��B����������u��鵶��v�̂߂�߂�A�����A������A��߁A�t���A���b�A�s�F�A�l�G�j�i�����j�ƏW���B�R�[�q�[�A�T���h�C�b�`���Ƃ�Ȃ���A�ݑI�ƂȂ�B���ʁA�т�ɂȂ肪������B���\�K�͂₷���Ǝv�����B���ʕ���H�ׁA�\���U��B
�@�@������݂̂��ڂ��D�Д����
���\�\�����@��A�t�ˎR�l�ƍ̎s�ւ䂭�B�r���A�t����l��U���o���A�����B�����������A����������l�g�ɂ��܂�ĕ����B�ω��l���ΑK�������A�����̉H�q�s�����ĉ��B��ࣂƍʂ�ꂽ���E�B�|�W����A�H�q�����l�������B�A��A�j���[�g�[�L���[�Ńr�[���A���ł�ʼńA�o��k�`�B���ꂩ��u���W������X�ŁA�t����l�̒Z�̂̐��X�������B�l�\�܁A�Z�ł��̎�X�����ɁA��������B���̕����ӂƌ���ƁA���X���̂ЂƂ肪�A�R�[�q�[�p�̃~���N����ɂʂ��Ă����B
�����a�\�ܔN�i���l�Z�j�@ �ꌎ��\�O���@�����痚�����������B��߂Ď���ɂӂ������B�v���Ԃ�ł܂��V���U���ɂ���B�������O�ւ̃L�l�}�n�E�X�փo�X�ōs���B�f��͂܂�Ȃ���������B�����I�[�o�[�̃p�[�}�l���g�̎Ⴂ�����ׂɍ���B�q�Ȃ͂����Ă���̂ɂƁA�v�����B��{�ڂ̉f��u�j�̐��E�v�͌��Ă����̂ŁA�o�悤�Ƃ������A���̖����I�ł��B��������A�����t�q��B����ɋ����Ă��܂��B���̍����̂������ς̏����͂ǂ��ւ����Ă��܂����̂��B�����v�炵�Ă����A�����̂ЂƁB���悤�Ȃ�A��̖��B�o�X�Ő֏o�A�i���X�X�^�A�ŃR�[�q�[���̂B
���\�l���@���������e�́w�k�C���̌���Ɠ`���x�̐����ɖv������B�o����ƁA�V�c�É��Ɍ��シ��Ƃ̂��ƁB�ߌ�A���ї�����B�����A��������͒��N�֗������ƌ����B�Ȃ�̗p�Ȃ̂��낤�B�[���A�r�c�s�F�������˂Ă���B�_�ے��̋i���X�ŁA�������̂݁A�����t�q�̂��Ƃɂӂ��B�܂��X�ɂ����A�o�������j�̋A���҂��Ă���Ƃ̂��ƁB�����̊X�ŕʂꂽ�B
���肪��݂̋L�q���ȗ������Ɉ������B�͂��炸���s���܂�͂����L�t�̐��I�̂悤�ɂȂ����̂́A����X���g���̐��_�����̒��S���߂Ă�������ł���B�̎��I�ɃA���R�[���Ɏォ�����g���́A�l������ɑ���������Ƃ��ł��A�i���X�������O�ɂ��낮���Ƃ��D�B��R���ɋ߂Ă�������͍��咬�߂��̔m�ԊقŔ������̔o��G����ǂ肵�Ă��邵�A�������̓��{�ߑ㕶�w�ق̋A�������X�g�b�v�a�J������X�ɓ���ƁA�V����ǂ�ł���Ƃ��낾�����肵���B����X�Ō��e���������Ƃ����Ȃ��������A�g���ɂƂ��Ď���ƕ���ōł��S���܂�ꏊ�������B
 �@
�@ �@
�@
���[�u���J�v�̃`�[�Y�P�[�L������̃Z�b�g�i���j�ƓX�̑O�̐ԂƔ��ӂ��̃r�[�`�p���\���i���j������X�g�b�v�a�J������X�̃`�[�Y�P�[�L������̃Z�b�g�i�E�j
�g����������������X�Ƃ����A�����ł��A���a�F���X�i�j�A���h���I�i�_�ے��j�A�g�b�v�i�a�J�j�A���s�ł̓C�m�_�R�[�q�i�䒬�O���j���v�������ԁB�s���܂�͂����L�t�̓X�i��������̂��j���܂߂āA�����̓X�����肪�ǂ�Ȃ��̂�������Ă݂����B���l�̌����_�ސ�ߑ㕶�w�قɍs�������N�i2014�N�j��7��6���ɎB�����ʐ^���f���Ė{�e���I���悤�B1978�N7��9���A�g�������y���F�����Ɓu�l�J�V�����̉S�ɒ����ق�v�i�s�y���F��t�}�����[�A1987�A���O�y�[�W�j���Ƃ������[�u���J�v�B���̃`�[�Y�P�[�L������̃Z�b�g�A�����Ē��[�O�̐ԂƔ��ӂ��̃r�[�`�p���\�����B�X�̓`�[�̗��ɂ́uCE COIN ME SOURIT�i���̈���͎��ɔ��݂�����j�v�ƈ������Ă���B�͂�����36�N�O������������́A�g�������ɔ��݂����Ă������낤���B
�k2015�N3��31���NjL�l
����A�v���Ԃ�ɓ��j�̒��Ԃ̏a�J�E���������������A�l�o�̑����ɂ͋��������B�ꕞ���邽�߂�����X�g�b�v�ɓ������B�g�b�v�~�b�N�X�i�X�Ǝ��̃u�����h�R�[�q�[�j�ƃ`�[�Y�P�[�L�𒍕����āA�v�킸���������Ă��܂����B���̂Ƃ��̎ʐ^���A�b�v���Ă������B
�k2020�N4��30���NjL�l
2020�N4��10���A�ѓN�v�s�i���X�̎���\�\���̂Ƃ� ����ȓX���������t���k�����ܕ��Ɂl�ōĊ����ꂽ�B�����Ɂs�{�����X�̌��\�\���_�j�Y���o�ŎЂ̌��Ɖe�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A2008�j�̒��҂ł�����ΐ_�䏑�т̓��x�O���q������L�r�������Ă��āA�u�ꌎ�\�ܓ��i���j�^�ѓN�v����̌W�����ɁA�a�J�̋i���X�E�B���A�� �����X�ɏo������B�v�i�����A�O�Z���y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���B�������̌W���ςɍs���āA�т���Ɉ��A�����A�ؓ��S�O�}������肠�������̂��B���Ȃ݂ɒؓ��S�O�͖{����2�ӏ��\�\�s�����t�̒��҂Ƃ��āA�T�a�c���Ƃ̃g�[�N�V���[�̑����Ƃ��ā\�\�o�ꂷ�邪�A���p�͂���Ă��Ȃ��B�����ŁA�������m�点���B�����V�h���E�s���Ɛ��w�O�̋i���X�u�ӂ��̖v��2018�N�ɕX���ċh�����_���Ă����Ƃ���i2009�N5���ɂ͔��l�o���ŗL���������w�O�́u��ѓ����X�v���X�j�A���������u�p�e�B�X���[�@�ӂ��̖v�Ƃ��Ĉړ]�ăI�[�v�������B�w������A���l�����s���t�̏����Y���g�V�C�������ƖO���邱�ƂȂ���肠�����u�킪�Ð��v�\�\�g�����͕����쒃�L�������Ă\�\�������������Ƃ́A���тɂ����Ȃ��B
�g�����Ǝʐ^�A�g�������Ǝʐ^�ɂ��čl�������B�ё��ʐ^���Ȃ����ƂŒm���鐼��������1828�i����10�j�N�ɐ��܂�A1877 �i����10�j�N �ɟf���Ă���B������̍�{���n�i1836�`67�j�ɂ̓|�[�g���[�g�����邩��A�ʐ^�ɎB����̂��D���Ȑl�Ԃƌ����Ȑl�Ԃ�����Ƃ������Ƃ����������� �Ȃ��B�g�����͖��炩�Ɍ�҂������B�s�����C�J�t1973�N9�����̋g�������W�ɂ́A����ˈ�j�B�e�ɂ��q�O���r�A �g�����̊�r��8�y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ���Ă��邪�A�G���̓��W�łȂ���ΎB�e�����Ȃ��������낤�B���l�Ƃ��Ă͋��ۂ��Ă��A�ҏW�҂Ƃ��Ă͎��ꂴ�� �����Ȃ������̂��B�q�g�����̃��C�A�E �g�i3�j�r�ɂ����������A���������w�U������́s���t��2���i1984�N3��5���j�ɂ́q�����܂̎��l�����r�Ƃ��Ĕѓ��k��A�g �����A�����N����3�l���o�ꂷ��B�g���̏ё��ʐ^�͍��g�ɂ��B�肨�낵�ŁA���Ԏ���́q�ҏW��L�r���B�e�̗l�q��`���Ă���B
����A�g�������́u�ʐ^�͂�����}�B���炭�l�������Ă�v�B����͂قƂ�ǎB�e���ۂɋ߂����B�O������A�u���� �������̔M�� �ɕ������v�Ǝp�����킵�Ă����������g������A�����Ȃ�����ǂ��ɂł������A�ǂ��ł�������B������������������J�����̑O�ɐg�����炷�̂́A�����炭 ���ꂪ�Ōゾ�v�ƁB�l���݂�D������̂ڂ�A�I���͊ՐÂȌ����̃x���`�B�ʂꂬ��A���l�́u���͓�v�̌��t���̂����A�q����Ɠ�Ƃɐg���܂����r�邩�̂� ���ɁA�ӂ����ѓs�s�̎G���̂Ȃ��Ɂc�c�B�i�����A�l�Z�y�[�W�j
1989�N3���A���W�s���[���h���b�v�t����4�̕��w�ُ܁i���㎍����j�ɑI�ꂽ���A�g���͎�܂����ނ��Ă���B���͂�����g��
�����Ȃ̎���
�ɑ��Č������i����������j�ԓx�ŗՂ��̂Ɨ������Ă����B���ꂪ���́A�����čő�̗��R�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B�����A��̏،����ēǂނƁA�ʐ^�Ŏ���
�̎p���N�������Ȃ��Ƃ����v�����傫�������̂ł͂Ȃ����i�g����70�ɂȂ낤�Ƃ��Ă����j�B�푺�G�O�́q�g�����̂��߂̊o�����r�łƂɎw�E���Ă���B
�u���̎��l�̏퓯���ւ̍D�݁B�k�c�c�l�_�[�N�E�X�[�c�̒j�́A�X���ł͌Q�O�Ƃ����B�ꖪ�𒅂Ďp�������Ă��܂��B�c��̂͊�B���邱�ƁB�`�����Ɓv�i�s��
���C�J�t1973�N9�����A���`��O�y�[�W�j�B��ʑ̂Ƃ��Ďʐ^�ɎB���邱�Ƃ��D�܂Ȃ������g�����B���̌���l�A�`���l�̎��ɁA�u�ʐ^�v�͂ǂ̂悤��
�o�ꂷ�邩�i�����͈��p�҂������̂��߂ɕt�������́j�B
�E����Ƃ݂��������ꂳ��̎ʐ^�i�q�D�F�̎蓅�r�A�E25�j�\�`
�ʕ��̏I���i�D�E2�j �\�a
�˂Ɏ��ʐl�̂܂��ɂ���H�т̒��̂Ȃ���
�����ӎ��̊O�ʂł͂������
�E���̌��̗�
���̐^�V�����������̊��т̐[�w��
���I�Ɣ������肩����
���ʐl�̗c�N�����ё��� ����
�܂ꂽ�َq�̊Ԃ�������
���� ��̂䂦�ɉ�������
�Ɗy�̉��X�s�[�h�Ŏ����Ă䂭���M�̎���
㵒p�̃Z�b�N�X�ŌC�������
�c���̂܂邢����Ԃ��ւ̕��̂ƂƂ���
��،^������ �S���I�|�Y������
���Ɣ��̔��̌���瀎������N�� ������]������
�閧�ʐ^��
�_�����Ȑ��̂��т��������D����
���n������ ��
�����悢���� ����̂��ڂ݂�
�s��܂�̏��N���̒x�����̎n�܂�
�炢��̖��������]�o�� ���炳��
�邢�ꂫ�̂��������f���� �⊴�Ő�ɂ���
���ւ̉�蓹
���B�ˑ��ւ̓��M�Ɖ��@
�Ƃ��������Y
�܂��ʂ̏����ւ̂₳�����ܟB
���R�ƍ^���͂��������N�̐g�̏�����肠����
�㐢�̍����̂Ȃ���
���̖��q���Z�� ���͂ȉƂ̒����������
�I�y���ق̋ɍʐF�̕���̗\�����̎� ����
���ۂŐ������쌀���҂���
�K���{�� ��ւ̉��ߊ�
�A�i�x���� ���̐O�̐G�}
�i���̎��_���W�C�h�������P�̏�������Ղ����
�g���l���̈łŎ��ł���
�ƒ{�̑����̏L����������
���e�������N�̐��_���X�̉͂����������
���łɔc�������������̉^�s��
�[���Ȏ��̋��|�̓`����
�ɂ鏬���̔��̐��ւ̏W�ς̓{��
���N�͌ǓƂ̌��������ɂ�
���̌ł��p���o�����͂��߂�
�����������v�̔��[����I���܂ł���������
����������̐푈
��C�̎ԗւ̂ЂƉ�肷�鎞
���Ӗ��Ɍ��̂ӂ����鎞
�����̐l�ނ̎��E���ɂȂ�˂Ȃ�ʖ����̎�
�����ȗ����ނ̊��ݍ��������̒Ⴂ�p��
������鎀�E���ĉ�����鎀
�Ñ�̖�O�~�`����̑��z�̉��̏X���ȏ��p���
��l�����̏��N�͚L����߂�
����̕����̐��E��
�R�b�v�̗��̂Ȃ���
�܂��ɋt���܂�
������
�����ʐl�̔����������}
�ё��� ���N�͖͕킷�邾�낤
��l�̏K���̂ʂꂽ�H�т����炷����
���݂�鏌���̊g����
�E����V���L���Ŏ��̂��Ƃ����߂Ēm�����@���܂ł��r���}�̃J�����j�n���ɓ��l���Z��ł���Ƃ̂��Ɓ@�ʐ^���ڂ��Ă���̂ł��Â������i�q�� �̕a�C�r�D�E11�j�\�b
�E�i���ɐV�����푈�ʐ^�i�q�₳�������Ζ��r�E�E9�j�\�c
�E�ʐ^�ɎB����ׂ��i�q�}�N���R�X���X�r�F�E1�j�\�d
�E�ʐ^�̂Ȃ��ʼni���Ɂi�q���ār�F�E8�j�\�e
�E�L�O�ʐ^�� ��������́H�i�q�_��I�Ȏ���̎��r�F�E11�j�\�f
�킪�Ƃ��L�O�ʐ^�i�G�E 9�j�\�g
������������ ����������l
���̃^���̖ɂ����Ă䂫
�����͂̂ڂ�
���̕挴��
�S�H�̃c�O�~��H���҂��l
���ꂪ�`���������Ƃ������� �Â��S
����ɂȂ�Ȃ�
��������Ƃ�ł���
���O�r�[�{�[�����X�J�[�g�̂Ȃ���
���˂������� �B�����܂܂�
�Ȃ̂���h�̔L��
���ʂ𑖂�J�ɂʂ��
�H�S�̂悤��
���������� �P�ӂ̗������Ă���
���r�J�������X��
�݂Ȃ����܂�����
�ł͋L�O�ʐ^���Ƃ�܂���
��ւނ�����
�ɂ�������ĉ�����
�ł����܂��f�邾�낤��
�����ł��ڂ���
�n���C���ݒn���̉��n��
�R���N�̖ƂƂ��ɐ������Ă���
�E������ �ʐ^�@�R�_�b�N�̌ܕC���L�� �ʐ^�@�D���� �ʐ^�@�Ԃ�V�̎ʐ^�@�ė�������s�@�� �ʐ^�@�������̎ʐ^�@�R��̎ʐ^�@���D�̃k�[�h�ʐ^�@�`���[ ���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\���������B�����A���X�̎ʐ^�i�q�w�A���X�x���r�G�E12�j�\�h
�E�G�ꂽ�D�̏�����������^ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���� �ʐ^�����Ă���v�k�^�͉��s�ӏ��l�i�q�����i�J�m�v�X�j�r�K�E8�j�\�i
�E�R�͂̒��v���Ă䂭����� �ʐ^�������̂Łi�q�A�d�r�������сE6�j�\�j
�q�ʕ��̏I��r�͎ʐ^�^����^�f��^���w�Ƃ��������W�������ւ̌��y����������قȎ��тł���A�q�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�r�͎ʐ^���̂���
������������
�ł��邽�߁A�S�т��������B��f�̂`����j�܂ł́u�ʐ^�v���A�i�T�j��掆�ɏĂ�����ꂽ���Ďʐ^�ƁA�i�U�j�V����G���A�ʐ^�W�ȂǂɈ�����ꂽ�����
�^�A�Ƃɕ����Ă݂悤�i�d�͂ǂ���Ƃ����Ȃ��B�Ƃ������A���Ďʐ^���ʐ^�W�ɓW�J����V�[���Ɠǂ݂����j�B
�@�i�T�j���Ďʐ^�c�c�`�E�a�E�f�E�g
�@�i�U�j����ʐ^�c�c�b�E�c�E�e�E�h�E�i�E�j
������̏ꍇ���A�u�ʐ^�v�͂���ɂ��嗬�̃f�W�^���摜�̃J���[�ʐ^�ł͂Ȃ��A�A�i���O�̔����ʐ^�ƍl������B�������A�g�E�h�E�i�̓J���[�ʐ^�ł�����
�����Ȃ��B�i�T�j�Ɓi�U�j�͔}�̂̓��������قȂ���̂́A�Ƃ��ɉ摜�̃R���e�i�Ƃ��Ď��тɖ��߂��܂�Ă���B�����@�\�́i�T�j�����̓o��l���̎��`�I�v
�f�i�蒅���ꂽ�p���˂ɒE���邱�Ƃ��g���Ƃ��Ă���j�Ƃ��ēo�ꂷ��̂ɑ��āA�i�U�j�͕s���ȎЉ�Ƃ��Ă̊O�E�̃C�}�[�W���Ƃ��Č����������B��
�����c�E�h�E�j�͐푈��z�N������B�i�T�j�������ނːe���Ȃ��̂��Ƃ���A�i�U�j�͉ЉЂ������̂Ƃ��ĕ`����Ă���B����͂ǂ��������Ƃ��낤���B����
�̊Ǘ����ɂ���i�T�j�͌�����̂Ƃ��čm�肵�A�����łȂ��i�U�j�͌�������̂Ƃ��Ĕے肷��B�������������^���e�B���A�͂��炸���ŏ��ɏq�ׂ��g������
�ё��ʐ^�̊W�ɕ��s���Ă���B�q�ʕ��̏I��r�Ƃ������\���ꂽ���`�ɂ́A�f�ނƂ��ċg�����g�̑̌�����������Ă���悤�Ɏv���B�����ɐ�s����u�閧��
�^�v�ł���u�ǁv����u���v�ւ̚g�́A���̌�̋g�������ɂ͌��o���������B�u���v�Ƃ������҂����˂��Ȃ����ʕ���Έ�����Ɏ��邩��ł���B���l�̕ω���
�q�ʕ��̏I��r�Ɓq�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�r�̉Ƒ��̕`�����ɂ��\��Ă���B����ŁA�g�́u��h�̔L�́^���ʂ𑖂�J�ɂʂ��^�H�S�̂悤�Ɂv�Ƃi�́u�G�ꂽ�D
�̏����������^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�҂̎ʐ^�����Ă���v�v�̂悤�ɑ��������C�}�[�W�����o�ꂷ��B�܂��A�h�́u�`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\��
�������B�����A���X�̎ʐ^�v�́q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�G�E11�j�ւ̎��Ȍ��y�ɂȂ��Ă���B�Ƃ���ŁA�g���������]���������e���O�Y���W�s�ߑ�
�̋��b�t�i�n���ЁA1953�N10��30���j�̊����ɂ͏��ɓ����镶��
������B���̈�߂́A���e�̎ʐ^�_�Ƃ��Ă��o�F���B
�@���͌l�Ƃ��Ă͎��W�Ƃ������悤�ȑ㕨�Ŏ������ɂ������͂Ȃ������̂����F�B�̂����߂ŏo�����Ƃɂ����B����� ���ꓙ�̎��� �啔���͂��łɐV����G���ɏo�������̂ł��邪�A���������̎��W�̂��߂ɂ������������Ƃ��낪�����B���̍l���ł͈�̍�i�͗^����ꂽ�u�Ԃɉ��Ă͗B ��̌`�e�������Ă��邪�A����͏�ɕω����čs���ׂ��Ƃ����m��Ȃ��̂ł����āA�����Ē�܂�Ƃ��낪�����̂��Ǝv���B���̎��Ȃǂ͌���̉�ƂƓ����� �i�v�ɒ������U����̂ł����āA����͉�l�����l���������Ƃ��B��̎��̑��݂͐��ɖ��ɂȂ�܂ŕω����U����̂ł���B���̐����̓p���h�b�N�X�ł� �����_�Ƃ��Ă͖��ł���Ǝv���B
�@���T�ɏo�Ă��鎍�͖ܘ_�ꎞ��~����Ă���`�ɂ����Ȃ��B���������̒�~����Ă��邻�ꓙ�̌`�����܂łɓ�\�y���ȏ���F�����������Ă���̂ł��� �āA���̌`�̂��Ƃ������Ȃ��̂ł���B�s�J�\��}�e�B�X�̂悤�ɎႵ�ʐ^�������玟�ւƎ���Ďc���Ă݂�Ɩʔ������̂��Ǝv���B�i�����A��`��y�[�W�j�B
�g�������̏����ǂ̂悤�ɎƂ߂����͂킩��Ȃ��B�������A�̂��́s�Õ��t�ƂȂ鎍�т������p���ł��������̎��l�ɂƂ��āA�����`��
�́u���̎��W
�͒P�Ɂu����ꂽ���_�v�Ƃ��u���̐�̊Â��v���W�߂��̂łȂ��A��̎��I���n����l�Ԃ��Ԃ߂邽�߂Ɏ��X���������̂��W�߂��̂ł���v�i�����A��y�[
�W�j�ƂƂ��ɁA���Ƃ͂ǂ�����ׂ����A���W�Ƃ͂ǂ�����ׂ������l�@���邽�߂̗L�͂Ȏ�|����ɂȂ������Ƃ͏[���ɍl������B����͐��e�̎��M���@����
�̂܂܂Ȃ��邱�Ƃł͂������Ȃ��B�ނ��낻�̈Ⴂ���ۗ���������̂��B�g���́A�ߑ�̋��b�Ȃ�ʌ���̋��b�A����ߑ�̎��b���������Ƃ�ړI�Ƃ��Ă�
���B�M�������Đ^���ʂ����ƁA���ꂪ���10�N�Ԃ̋g�����̎��I�ȉc�݂ł���A�풆�E���̑̌��͋ߑ�̋��b�Ɉ��Z���邱�Ƃ������Ȃ������B�ϓ]����܂�
�Ȃ����̂Ƃ�����`�ɗ��߂���̂Ƃ��Ă̎ʐ^�����݂��邱�Ƃ͑傫�Ȍ[���ƂȂ�A���ւ̐M����[�߂��ɈႢ�Ȃ��B���ꂪ�ŏ��Ɍ��������̂��A�s�a���`�t��
���сq�ʕ��̏I��r�������B�g���͂��̉�Ȑ����������ČJ�肩�������Ƃ͂����A�����������ǂ������Ă����Ƃ���悤�Ȏ��Ƃ��āq�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�r�ւ�
�����ނ����B
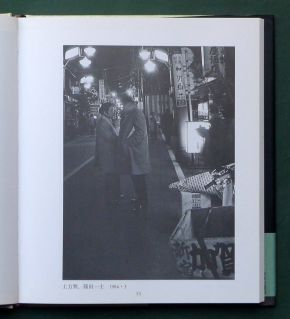 �@
�@
�q�y���F�A�c��m�@1984�E3�r�i���c���ʐ^�W�s��Ƃ̎��Ӂt�V���ЁA1994�N10��
20���A�O�܃y�[�W�j�i���j�ƐV�h��V�h6-10�̊������B�u����齁v�O�̓����ꏊ�k2014�N8��6���ߌ�5�����B�e�l�i�E�j
���ۂ̎ʐ^�Ƌg���̕��͂���ׂĂ݂悤�B���c���ʐ^�W�s��Ƃ̎��Ӂt�i�V���ЁA1994�N10��20���j�̓��y�[�W�ɂ́q�g�������A
�g���� 1984�E3�r�������āA�O�f�s��
�t�i��2���j�ƃO���X����ɂ����g���̃����b�N�X�����p�����߂��Ă���B�����A�����Œ��ڂ������̂́q�y���F�A�c��m
1984�E3�r�i�����A�O�܃y�[�W�j��1984�N3��9���̋g�������L�ł���B
�u���B
�[�����犦�����߂�B�ԍ〈���֏o�A�o���ŃR�[�q�[���̂݁A�v�����X�z�e���ʊق̍��������֍s���B���W�w�Ă̕��x�Ŏ�܂̎O�D�L��Y�̓Ó����P���Ă�
��B�吨�̒m�ȂƉ�B�y���F�ƌ����v�l�������B�p�[�e�B�[���I��A�V�h��齉����ꂪ��̐ȂƂ����̂ŁA���ꂼ��^�N�V�[�Ō����B��K�̍��~�ɏ��
�ƁA�c��m�A�ѓ��k��A����N�v�A�a��F��A���c�v�Y�����āA�O�D�L��Y�Ƃ��삳�����Ă����B�剪�M�Ɠy���F�ɂ͂��܂ꂽ�������ɂȂ�B���t�̉���
���Ƃ炳�ꂽ�v�i�q80 �u�Ă̕��v�\�\�j���̗]�g�r�A�s�y���F��t�}�����[�A1987�A��Z��y�[�W�j�B
���c�̎ʐ^�W�ɂ͓�K�̍��~�œƂ�{��ǂގc�̎ʐ^������i�k�O��`�O�O�l�y�[�W�j�A�g���̓��L�ƕ����ēǂނƋ����͐s���Ȃ��B���������A�y���F�Ǝc
��m�Ƃ����g�ݍ��킹���A�O�D�L��Y�i���邢�͋g�����j��}��ɂ���ȊO�̂ǂ�ȏꍇ�ɍl�����邾�낤�B�q�y���F�A�c��m�@1984�E3�r����������
����ƁA�d���̊ŔɁu�������B�@����齁v�Ƃ���A�Z���̕\�����u�V�h6-10�v�Ɠǂ߂�BGoogle�̒n�}�����ŃX�g���[�g�r���[������ƁA����炵
���d���̘e�ɒ�߂Ă���z�B�p�̎O�փo�C�N�̉ב�ɂ�������Ă���ؔ����q�y���F�A�c��m�@1984�E3�r�̔��Ɠ����悤���i�ʐ^�̎�O�̃o�C�N��
�X�[�p�[�J�u���j�B30�N�̎����u�Ăē���̔����f��͂ł��Ȃ����A�ʐ^�E�摜�̗͂��܂��܂��Ɗ�����������B
���N�i2014�N�j��5��31���̓y�j���A�g�����̖����ɑ����̐^�����̕�Ɍw�łāA���łɂ����߂��́u�������c���v�̑O��ʂ����� ����A���X�� 5��25���������ĕX���Ă����̂ɂ͋������B�@�v�̂��Ƃ̒�������ł���Ă������炾�B�K���J���������Q���Ă����̂ŁA�B�e�����u�������c���v�̊Ŕ� �Ƌg�����̕�̎ʐ^���f���āA�{�e����߂����낤�B
 �@
�@
�u�������c���v�̊Ŕi���j�Ɛ^�����̋g�����̕�i�E�j�k2014�N5��31���B�e�l
�k�t�L�l
�g�����̈�e�q�����i���l���N�E�ė�j�r�Ɂu����̉�����������ƋȂ�^�`�������O�ɂ͂���^�a�D�݂̕ǂɃO���A�E�K�A�X���̎�
�^���\���Ă���^�������ɕ�܂ꂽ���̂��ɂ̂��͂���m��ʁ^�ٍ��̏��O���A�E�K�A�X���͔��������ȁ^�k�c�c�l�v�i�邵����ʍ��s���̂����������������
�����\�\�Ǔ��E�g�����t����R�c�A1996�A���y�[�W�j�Ƃ���B���t�́u�Z�����������v�����A�O��W����u��\�l���̖ؗj�v���B���ڂ��ׂ��́u�O��
�A�E�K�A�X���̎ʐ^�v���B�C�M���X�̏��D�O���A�E�K�[�X���i1904�`96�j�̂����炭�̓X�`���ʐ^���낤�i����Ƃ��f��G���̐蔲�����j�B�ޏ��́A
1953�N���{���J�̂l�f�l�f��q�t�H�[�T�C�g�Ƃ̏��iThat Forsyte
Woman�j�r�Ŏ�l���̃A�C���[���E�t�H�[�T�C�g�������Ă���B���ꂪ�s�T�t�����E�݁t�Ɏ��߂�ꂽ�u�L�̎��ɂ�钷�ю��v���q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�i�G�E17�j�̃X���X�̈����
�z�����邱�Ƃ͊y�����B
���m�T�E���h�n�ŊG��`���̂��B�����o�邽�߂ɂˁB�\�\�W�~�[�E�y�C�W�i�G���b�N�E�f�C���B�X�k������l�s���b�h�E�c�F�b�y�����W�k���b�N�̖��ՁI�l�t�����ЁA2013�N1��1���A���l�y�[�W�j
�g�������ɂ�����G��̎��Ӗ��ɂ��čl�������B�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j���Ђ��Ƃ������Ƃ̂���قǂ̐l�Ȃ�A�N�����g���͊G��`���悤�Ɏ����������Ƃ�����ۂ�������낤�B�g�����g�A�q�킽���̍쎍�@�H�r�Łu����l�́A�킽���̎����G�搫������A���͒����I�ł���Ƃ����B����ł킽���͂悢�Ǝv���B���Ƃ��Ƃ킽���͒����Ƃւ̖�������������A���`�ւ̊�]�͂悢�̂ł���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����y�[�W�j�Ə����Ă��āA�����o�邽�߂ɁA���ŊG��`�����Ƃ��u�����Ă����B�g���́u�����v���\���鎍�W�s�T�t�����E�݁t�ɂ��̖����q�G��r�Ƃ�����т�����i���o�́s���i�t1974�N5�����j�B
�G��i�G�E18�j
��Ƃ��e�[�u����`���Ƃ�
�ŏ��ɊD�F�̕�����
�S�̂Ȃ��ɓh��
�u����Ƃ�
����Ƃ��邱�Ƃ��v
����ɂ����
�Ă̐��ꂽ�B��䰓�
�̖�ؗނ��X�g�C�b�N�ȉe��������
�Z���̌ߌ��
���ނ��ςȂ���
���悢�捂�݂֎���
���̉�����
�����̎w������
���̌`���o�Ă���
�����Ńe�[�u���͑O���X��
���͒�֖߂�
�M�̏�œ����
���m���́q�ԁr�͎����̒��S�ɂȂ�
�����H�ׂ�q����
�����̌�������
�������ɊO�ς͂����܂��ɂȂ�
�n���
�u�����̌�����
���͐������Ȃ��v
�Ӟ��҂���ӓ�����
�����̊������݂��Ȃ��Ȃ�
������
������̔w�i��
�������̋L���Ɖ��K�ɕ�������
�ł֗��o����
�ےJ�ˈ�́q�e�Ȃ܂��r�Łu���N�k��㎵�Z�N�l������y�����W�͋g�����́w�T�t�����E�݁x�����B�w�Õ��x��w�m���x�̂���̖��f�����Ɩ��̔Z�����̂ɂȂč��o����Ă�āA���Ȑ��АS�n�ɂȂ�̂��B��ɂ����̂́w����ȉĂ̗��x�Ƃ��ӈ�тŁA���Y���ƔF���̗h�����ٗl�Ɋ��\�I�ł���v�i�s�V�ю��ԂQ�k�������Ɂl�t�������_�ЁA1983�N7��10���A�Z��y�[�W�j�Ə������i�q����ȉĂ̗��r�ɐG�ꂽ�]���ق��ɒm��Ȃ��j�B�ےJ�ł͂Ȃ����A���́q�G��r��ǂނ��тɁs�Õ��t�i1955�j�̊������т�z���o���B
���i�B�E1�j
��̊�̍d���ʂ̓���
�����₩���𑝂��Ă���
�H�̂�������
��◜��Ԃǂ��̗�
���ꂼ���
�����Ȃ����܂܂̎p����
�����
�ЂƂ��~����
�傢�Ȃ鉹�y�ւƉ����Ă䂭
�߂��߂��̍ł��[���Ƃ���֎���
�j�͂����ނ�ɂ悱�����
���̂܂���
�߂���L���ȕ�ࣂ̎���
�����҂̎��̂܂���
�̂悤�ɔ����Ȃ�
�����̂������̗̂ނ�
���悢��d�݂�������
�[����̂Ȃ���
���̖�̉��ۂ̗���
�Ƃ���
�傫�������ނ�
�����Ŏw�E�������̂͑z�̗ގ��Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��B�g���͂��̓�тŁA�u�G��`���悤�Ɏ����������v�̂ł͂Ȃ��A�u���������悤�ɂ��ĊG��`�����v�̂��B�܂��W��B�q�Õ��r�Ƃ͐Õ��悷�Ȃ킿���`�[�t�ł���A�q�G��r�Ƃ͖��ʉ��A�N������Ƃ��������`�G���w���B�������A���̍��͖��ɂȂ�Ȃ��B������ɂ��Ă��G���`�����Ƃ͐��E�̌����̒ł���A���邱�Ƃ͂��Ȃ킿�u����Ƃ��邱�Ɓv���B���o�ɉf��O�E���ʂ��̂ł͂Ȃ��A�S�̂Ȃ����̂������ނ��Ƃ��B�g�����̎������u�����I�v�ƌĂԂƂ��A�����͌��z������Ƒ������������A�ዅ������Ɍ����Ĕ��]��������ԂŖڂɉf����̂�����̂ł����āA�u���v�����炩���ߊO�݂���킯�ł͂Ȃ��B���������ɏ������邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�����Ă���B���������猩����B�`�������䂦�Ɍ�����̂��B����͂������Ɍ��邽�߂ɕ`���A�����Ƃ������顚�|����B�����������o�̌����͈�ʓI�ɊG��`�����Ƃŋ�������B�ł���A���ꂪ���Ƃ��������i�ł����Ă��u�G�v�ƌĂ�ō��������Ȃ��B�g�������̌����̍\���́A�q�Õ��r����q�G��r�Ɏ���܂ň�т��Ă���B
��
�g�����̃R���N�V���������J���ꂽ�̂́A2003�N5��1���`10���A�����E�L�y���̌Ô��p�X�u�D�c�L�iODAU�j�v�ŊJ�Â��ꂽ�s����W�t���B��̂��̂ŁA���̏���������p��i�����ɂ��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�������A����ł̃R���N�V�����̌��J�ƂȂ�A�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�i����R�c�A1996�N11��30���j�̍�{�^�T�B�e�̃J���[�}�Łq�g�����̏����ȕ����r������B��Җ��ƍ�i�����f����̂ŁA�ǎ҂͂�낵���s���̂���������������Ă����t�ɏA���č�i������ꂽ���B
1. �́s�T�t�����E�݁t�̈�łōw�������A�N������i�q1990�N�A�g�����̎���ɂċg���z�q����Ə��ш�Y�r�Q�Ɓj�B2. ��1975�N9��17���t�i�c�k�߈��ď��ȂɁu����A�܂��n�ӈ�l�N�������A�u�s���v�̊z�������Ă��Ă���܂����B���̍��h�̔��������̊z�ɁA�����k�ߏ������A���ւɌ����܂�����A���܂܂ŏ����Ă������A�A�o�e�B�̐F�ʓ��ʼn�Ǝ����ς��āA���������͋C�ɂȂ�܂����v�i�q�t�䏑�ȁr�A�s�Ս��t300���A1975�N11���A�Z�y�[�W�j�Ƃ���B3. �͎����q�ٖM�r�i�H�E5�j������B9. ��1985�N9��30���̓��L�Ɂu���A�C���]���ɁA���Ԃ̍k�߁u�����}�v���A����ꂽ����́A���́u�O�����i�[���̓e�v�̖��G�ɂ����ւ���v�i�s�y���F��t�}�����[�A1987�A����y�[�W�j�Ƃ���B10. �͋g�����O�Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�̕\���ɋ�����������Ă���B11. �͎����q�H�̗̕��r�i�K�E5�j������A12. �͂��̖����q�]���l���V���^�[���̑D�r�i�G�E24�j������B�g���̂��������G��̍D�݂��ȂɂɗR�邩�͋����[���ۑ肾���A�s�݂Â�t��s���p�蒟�t�A�s�|�p�V���t�Ƃ��������p�G����V���̋L���A����炪���m������p�W�A��L�̌W�ŕ�����������ςĂ����i�z�q�v�l�̒k�ɂ��A�g���̈��ǎ��́s�����V���t�ł���A���ǎ��́s�T�����t�t�������B�ނ��ȊO�̎����ɂ��Ζ����i���X�ȂǂŖڂ�ʂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��j�B�����̏Љ�҂ɑ���C�����F�V���F���������Ƃ͈ȑO�ɂ��������B
�g�����̟f��̏o�ł����A������b�q�s�X�N���b�v�E�M�������[�\�\��ʂ����p�فt�i���}�ЁA2005�N11��1���j�̍�i�̑I���͂܂��Ƃɋg�����ӂ��ł������āA���Ă��ĖO���Ȃ��B�g��������ɑE�߂���Ƃ�����A���䂪�g���ɐ�������Ƃ����邾�낤�B�Ȃ��ł��q��������r�͂Ƃ�킯�g�����̊G�̎��f�i������B�\�\�u���h�ȏ��̊ԂɁA�����Ȑ��n�̒|�̊G���|�����Ă���B�u����́H�v�ƕ����ƁA�u����ŒT�������̂���v�Ɠy���F�͏��B�u���߂āA��������̌Ղ̊G���A���B�̒B���}���炢�~�����ˁv�Ǝ�����������A�u�ǂ��ɂ���Ȃ̂���̂�v�B������R�ӂ�̌Ô��p�X���l�ŕ��������Ǝv�����v�i�q76 ���q�̎R���̈��r�A�s�y���F��t�}�����[�A1987�A��l�y�[�W�j�B�y���F��������b�q�ł����Ă����������Ȃ��B�s�X�N���b�v�E�M�������[�t�̔��p�Ƃ̖��O�Ƌ���̕��̕W����f���悤�i����͋g�������y�������Ƃ̂�����p�ƂȂ̂ŁA�f�ڐ}�ł̍�i�����ԍ���U���Ę^����j�B
�����J��潾��Y�\�\�Â��ȉƂ̔L�����i�ڍׂ͌�q�j
�������X�E�n�[�V���t�B�[���h�\�\�������Ə_�炩���̃e�N�X�`���[
���}�b�N�X�������^�[�E�X�����x���N�\�\���ɜ߂��ꂽ�����@�@�@�O���j �킪�S�̒�ɂ����ЂƂ肢��l �A��ȉ��فA�O���̂P �B���̏ё� �C���̐l���̍ł����������̂��j���C�}�W�j�Y���̐��� �D�o�q�̐��̊�ȓ��A�\���̂R
���I�[�M���X�g�E���m���[���T�\�\�W�����̕��e�̕`�����G
���I�[�M���X�g�E���m���[���U�\�\�����q�����������������B
���A�����E���\�[�\�\��ȋߑ���
�������V���\�\�v���m�p���Z�n�Ƃ��Ă̎O�F�X�~���m�p���Z�n
���t���E�A���W�F���R�\�\�V�g�̕`��������
���_���B�b�h�A���S���\�\�������R�X�`���[���@�@�@���̃}�n �A�A���o���ݕv�l �B�}�k�G���E�I�\�[���I�E�f�E�X�[�j�K �C���߂̃}�n
���}�e�B�X�\�\�}�e�B�X�̑�
���V�����[�_�[���]���l���V���^�[���\�\�h���E�L�z�[�e�Ƃ��Ẳ�Ɓ@�@�@�|�[�v�����m �A�l���̖͎� �B����Ԃꂽ�����݂̂Ȃ��������^���L����� �C���̐��̍q�H���s�����Ƃ̖��@�̑D �D�|�b�z���q�F���A�m��ꂴ�镽�a�̓V�g �E�`瀆���ꂽ��
���~�R�����\�\����Ǝʐ�
�����B���Z���g�E���@���E�S�b�z�\�\�S�b�z�Ƃ���
�����g�[�\�\�V�e�[�����ցc�c
����������T�\�\�Ր}�̌���Ȃ����́@�@�@�Ր} �A�Ր} �B�Ր}
����������U�\�\������{�̋�ԁ@�@�@�@�ؐ} �\�ț����i�����j �A���[�}�i�̂����̈ꖇ�j �B�@�ؐ} �\�ț����i�����j �C�@�ؐ} �\�ț����i�����j �D���[�}�i���ț����̂����Z�ȁj
���T�[�J�X�@�|�X�^�[�\�\�T�[�J�X�̖��Ɖ^��
���G�h���[�h�E�q�b�N�X�\�\���a�Ȃ鉤���̓�������
���G�h���[�h���i���V�[�E���f�B���E�L���z���c�\�\���C�h�E�C���E�t�r�`�̃G�����@�C�������g
���o���e���X�\�\���摜�̂܂Ȃ����@�@�@�L�����̉� �A�G�~���E�u�����e�w�����u�x�̂��߂̑}�G��� �B�z�A���E�~���Ɩ��h�����X �C�n���C�̔L
���W���N�\���E�|���b�N�\�\�|���b�N�A�A�����J���E���_���E�A�[�g�̐_�b�@�@�@�u���[�E�|�[���Y�E�i���o�[11 �A�H�̐����F�i���o�[30
���t�����V�X�E�x�[�R���\�\�t�����V�X�E�x�[�R���Ɖf��@�@�@�x���X�P�X�̖@�� �C�m�Z���g10���̏ё��ɂ��K�� �A�\���˂̎O�̏K�� �B�}�C�u���b�W���F�o�P�c���鏗���ƍ���q��
�����E���E�f���t�B�\�\��������
���t�����V�X�R�E�f�E�X���o�����A�t�@���E�f�E�X���o�����A�~�P�����W�F���E�����W�E�_�E�J�����@�b�W���A���n�l�X�E�t�F�����[���\�\�X�e�B�[���E���C�t �\�\�����Ȃ���
�������R��ƒ��J��潾��Y�\�\�����E�ۊ����E���q
���W�I�b�g�\�\������l�Ƃ��Ẵt�����`�F�X�R
���W���Z�t�E�R�[�l���\�\���̗��l
���A���g�j�I�E���K�u�[�G�\�\���҂Ɠ�������
�g�������̔��p��i�̂Ƃ��Ƃ͈قȂ�A�g�������Ƃ̊֘A���w�E����ɂƂǂ߂�B
 �@
�@
�W�����E�\�Z�ҁi�F�V���F���j�s�}�b�N�X�E�����^�[�E�X���[���x���k�V�������A���X���Ɖ�Ƒp���u鍎q��7�̖ځv�ʊ��l�t�i�͏o���[�V�ЁA1976�N7��30���j�W���P�b�g�Ɣ��A�s�X���[���x���W�t�i�O���t�B���X�R�[�|���[�V�����A1976�N3��30���j�̕\���i���j�Ɓs�X���[���x���W�t�̒��ʃy�[�W�i�E�j
�s�X�N���b�v�E�M�������[�t�́A�q���J��潾��Y�\�\�Â��ȉƂ̔L�����r�̎��̕��͂Ŏn�܂�B
�@���h��ŃO���[�ƃG���W�ɓh��ꂽ�L�����o�X�̕z�ڂ�������w�i�ɁA�K�������ɖ������肽�Q��Ǝ��̂ŁA�܂�ŁA�����ƂĂ��C���̗ǂ��������Ă�������Ƃ������ׂ݂Ă��邩�̂悤�ɁA�Ȃ�Ƃ����炵���l�q�Ŗ����Ă��鍕�g�����̔L�̊G��`������ƁE���J��潾��Y�̂��Ƃ�m�����̂́A���l�̋g�������A������q�L�̊G�̌���r�ƌ����ċ����Ă��ꂽ����Ȃ̂����A���Z�Z�N�ɔL����āw�L�x�Ƒf���C�Ȃ����t����ꂽ�G�̃I���W�i���������̂́A�����ƌ�ɂȂ��Ă��炾�����B
�@���̊G���A���̔��p�قɊ��ꂽ�F�V���O�̃R���N�V�����ɓ����Ă���̂͒m���Ă�������ǁA�Ȃ��Ȃ����܂ŏo������@��Ȃǂ͂Ȃ��A�\�N�قǑO�ɂ������Z�{�X�g���C�v�E�M�������[�ł̒��J��潾��Y��ړW�ɂ��A���̖��O���u���Y�v�Ƃ����A�����Ɨ��ł�Ă������g���̊G�͏o�i����Ă��Ȃ������̂��c�O�������̂����A�Ƃ͌����A�����ł�����C�́A�Ƃ����������ꖇ�̔L�̊G�ɂ߂��肠�����̂�����A�c�O�Ƃ������t�́A�{���͂��Ă͂܂�Ȃ����낤�B�i�����A���y�[�W�j
�F�V���O�́s�C�܂�����p�فt�i�V���ЁA1978�j�ɂ͋g�����o�ꂷ�邩��A�����L�Łq�L�r�Əo������ƍl������B�����A���ꂪ���Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B����A�����L�i1960�N�ɒ҈䋪�̒m�l����킯�Ă������2�C�̃V�����L�j�̓��S�⎀�̂��ƁA�L�̊G����ɓ��ꂽ���Ƃ�����]�͋g�����Ƃ炦�Ă����ɈႢ�Ȃ��B���J��潾��Y�́q�L�r�i1966�j����ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A1976�N�H�Ɋ��s���ꂽ�s�T�t�����E�݁t�͋g���̒���Ƃ��čő�̈�ł������炵�A�|�[���E�f�C���B�X�́q�L�ƃ����S�r�i1977�j����肵�Ă��邩�炾�B�����W�ɂ͔L���r�����q���]�Ԃ̏�̔L�r��q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�̑��ɂ��A�q�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�r�q�w�A���X�x���r�q�c���r�q�ٗ�Ձr�Ƃ��������тɔL���o�ꂵ�A�q�ٗ�Ձr�͂������Ɂu�����ԗ�Ձv��A�z������B���Ȃ݂Ɂq�G��r�́A�O��Ɂq�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�Ɓq�ٗ�Ձr���]���ās�T�t�����E�݁t�Ɏ��߂��Ă���B���J��́u�L�̊G�̌���v���g���ɔL�̊G�ƂƂ��ɂ��邱�Ƃ̍K�������������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���ɏ������Ƃɂ���Ď����L�̗���Ԃ߁A����ɂ͔L��`�����G��ɈԂ߂���B�����ł͔L���₷�炢�A�ʕ��������̒��S�ɂȂ�B�����������ƊG��̟ӑR�Ƃ������̂��g�������ɂ�����G�悾�A�ƍl�������B�g�������e���O�Y��i�c�k�߁A���邢�͎O�D�L��Y�̂悤�ɂ͊G�M������K�v���Ȃ��������Ȃł���B

�g������2�C�̃V�����L�k�ǂ��炪�f�b�J�i�I�X�j�łǂ��炪�G���i���X�j���͕s���l
�o�T�F�q�O���r�A �g�����̊�r�i�s�����C�J�t1973�N9�����A��Z���`��Z��y�[�W�j
��������g�����̂��ׂĂ̑�����i�i�k�����l����ł̈ꕔ�������j�̏Љ���I�����B�g���������{�̑���E�J�b�g��U�肩����ƁA�����̑��`��Ƃ̂Ȃ��ŗ�������ۂɎc���Ă���B���������Ȃ藎����i�ɂ����܂��ɁA�g�����O�̒P�s�{�̔���\�������������`��Ɩ��ƃW�����������s���Ɍ��悤�B�ŏ��͎��W�E���сB�Ȃ��A����ƃJ�b�g�̋�ʂ͌����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
��O��2���̎��W�i1.��2.�j�̏����͕M�ɂ�鏑�������ŁA�����炭�g�������M�̏����B�܂��s�t�́t�̕\���̏��̊�́A�g���������̐l��`�������̂ɈႢ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�q�n����ԁr�i�A�E4�j���u�����t�q�Ɂv�������Ă��邩�炾�B���̎��W�E���сi3.�ȍ~�j�͏������݂Ȗ����̂�S�`�b�N�̂̊����őg�܂�Ă���B���������ł͎₵���Ǝv�����̂��A���ׂĂ̔��������͕\���ɑ���E�J�b�g�A�ʐ^�Ȃǂ̃��B�W���A���v�f���Y�����Ă���B�ɒB���v�̏��惆���C�J�̎��W�̑����������ł������悤�ɁB9.�̃W���P�b�g�ɂ́A�q����r�Ƒ薼�̃N���W�b�g�܂ł���B�I���W�E�p�W�͎��̂悤���B�p���̈���ł��邱�Ƃ������B
2.�̃��[���V���b�n�e�X�g�̃C���N�̐��݂̂悤�ȃJ�b�g�́A�u�b�N�f�U�C���S���̐��Y�N������z�������̂��낤���B2.�i�����������4.���j�́A�P�s���W�ɏ������i���ꂼ��̑p���̃t�H�[�}�b�g�ɔ����Ȃ��j�f�U�C���̋����ꂽ��悾�������B�U���E���̑��͎��̂悤���B
1.�̍ז��ȉ͓̑���́A�����̎��W�����Ɉ��������Ă����^�甎���낤���B2.�ɂ́A�q�����r�Ƒ薼�̃N���W�b�g�܂ł���B�����̎��т̎��M��G��������i�䂦�A�[�����B�g���͒P�s���W�ɂ��Ƃ�����t���邱�Ƃ��Ȃ������B�s�|�[���E�N���[�̐H��t�ɂ͗�O�I�ɂ��邪�i�������q���Ƃ����r�Ƃ����W��͂Ȃ��j�A�B��̏E�⎍�W���������߂ł���A��i�͍�i�����Č�炵�߂�Ƃ����S���͗h�邪�Ȃ��B���W�̊����Ɂq���o�ꗗ�r���t���̂����̏��ł���B�������A����̎��W���܂Ƃ߂Đ��ɖ₤�ɓ������āA������������Ƃ����邾�낤�B���������Ȃ���A�����J�b�g�A�ʐ^�Ȃǂ̃��B�W���A���v�f��Y���邱�Ƃɂ́A���͂Łq���Ƃ����r���������ƂƓ����������͂���ȏ�̊��������߂��Ă���i���Ȃ݂ɁA���Ƃ������t���ꂽ�s�|�[���E�N���[�̐H��t�͋g���̑����ł͂Ȃ��B�g���̈ӂ������낤���߂��Ƒ��j���̑������j�B���̌X���́A�����ȊO�̋g���������{�ɂ�������B�g���́A���l�̕��w��i���]�ł��Ȃ��A�ǂ������������邾�����A�Ƃ��Ƃ��邲�Ƃɕ\�����Ă������A�������邱�Ƃ����ő�̔�]�s�ׂ������B

������b�q�s�e�t�i�}�����[�A1973�N12��20���j�̖{���ƃW���P�b�g�k����F�����l
�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�j�ɂ��ڂ��Ă���悤�ɁA������b�q�̒Z�я����W�s�e�t�i���A1973�N12��20���j�̑���͗����ŁA���t�Ɂu����@�����@�v�Ƃ���B�ߔN�̋���̒����̑���E�����͂����ς�o�̋���v���q�̎�ɂȂ邪�A�s�e�t�́s���̐����t�i�}�����[�A1968�j�A�s���̎��ԁt�i�V���ЁA1970�j�Ɏ���3���߂̏����W�ŁA���ꂪ�g���������̂悤�ł�����A�����łȂ��悤�ł�����i�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��Ƃ��������ƁA�}���̎Г����ł��邱�Ƃ͊m�����j�B�l�Z���E�W���P�b�g���͓������������|���̃X�^���_�[�h�ŁA���ꂪ�}���̊��s���ŗ����Α���Ƃ���A���˓I�ɋg���������ƍl�������Ȃ�B�����A���̏����ƒ��Җ��Ƒ���̃I�[�\�h�b�N�X�ȃ��C�A�E�g���g�����ɂ��ƌ�����̂́A�Ȃ������炽�߂����B�����́u�e�v���ꕶ���Ƃ����̂��Ȏ҂ŁA���f�������˂�̂��B����ɂ��Ă����̑���̓e�A�l�ԂɎ������ł͂Ȃ����B���̔����́A�W���̒Z�я����q�e�r��ǂ߂܂������������Ƃ킩��B�{���̑����҂��l�ԂɎ��������e���W���P�b�g��\���Ɍf�����������̂Ȃ�A�����̗͗ʂ�ւƂ����̂́A�܂��Ƃɂ����ė��R�̂��邱�Ƃ��B���̏o���f���ɖ����������܂�A���������Җ��������Ƃ��������̂ň���B���ꂪ���i�ɂȂ��g���������{�ɂȂ����A�Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B�������A�V���ȏ،����nj��ɓ���܂ŁA�{�����g���������ƔF�肷�邱�Ƃ͍T�������i���^��i�Ƃ��Ă�����Ȃ��j�B
 �@
�@
����N�v�E�����s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�N7��1���j�̕\���ƃW���P�b�g�i���j�ƃW�����E�e�j�G����̃A���X�ƃh�h�i�E�j
�g���������{�Ƃ����ϓ_���痣��ė����̑���������Ƃ��A�ЂƂ��퍂�����т���̂��A����N�v�Ƃ̋����A�s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�N7��1���j���B���Ɂs�����Q���n���X���̓��t�̓���̕��Ɨ����̊G�̍\�����L���B�ԍ�.�i�G�̌f�ڃy�[�W�j�u�G�ƑΉ����镶�͂̌��o���i�ԍ��j�v�\�\�G���k���l�l�A�̏��ł���B
�{���̕\���ƃW���P�b�g�A���t�ɂ͐����`��45�x�X�����z�Ɏ��܂�����ł������h�h���f�����Ă���B���̔ʼn�i�Ƃ͓���̕��ɂ���ݒ�j�A�ǂ����Ă����C�X�E�L�������́s�s�v�c�̍��̃A���X�t�ɃW�����E�e�j�G�����t�����G����̈��p���B��̍\���ŏq�ׂ��悤�ɁA�d�|���Ƃ��Ėʔ����̂�17.��18.�ł���A�G���ň�ۓI�Ȃ̂�4.�̃N���V�b�N�J�[�ł���B�{���̑O�N�A1961�N�Ɋ��s���ꂽ����̎��W�s�Â��y�n�t�i���R���j�͍ŏ��̋g���������ɂȂ����̒��������A���̔��ƕ\���ɂ������ɂ���ăN���V�b�N�J�[���`����Ă����B
 �@
�@
����N�v���W�s�Â��y�n�t�i���R���A1961�N10��15���j�̔��ƕ\���k���{�F�J�b�g �����^�\�� �g�����l�i���j������N�v�E�����s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�N7��1���j�́u7�v�̊G�i�E�j
�s�����Q���n���X���̓��t�͓���N�v�Ɨ����̋����ɂȂ��Ă���B47�y�[�W�̖{����20�_�̊G������̂�����A����W�ƌĂ�ł��܂�Ȃ����낤�B����Ȃ�A����̕��͂Ɨ����̊G��̂ǂ��炪��ɂł����̂��낤���B�Ȃǂƍl����̂��A4.�́u�i10�`11�j�u7�v�\�\�N���V�b�N�J�[��w�i�ɂ��Ⴊ��ŋ��̍���ꖂ�j�v�́A�����̊G����ł����Ă������Ƃ����������Ȃ��Ɗ������邩�炾�B���邢�͓���̔��ĂŃ^�N�V�[�Ƃ��̉^�]��̘b�A�Ƃ������Ƃ����܂������_�œ�l�������ɐ�����J�n����B�����Ƃ��ł����������i�K�ŕ��ƊG��˂����킹�Ă݂�\�\��������������@���[���ɍl������悤�Ɏv���B1.�E8.�E15.�E20.��4�_���f�ڂ����s����N�v���W�k���㎍����31�l�t��1�_�����^���Ă��Ȃ��s���V�N�v�q���r�W���t�i�y�ЁA1973�E1979�E1996�k�㊪�l�j�ł͂��̗��҂̏Փ˂Ȃ����Z���̑S�e�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�{����A1977�N�ɏ���R�c���畢�����ꂽ���ɑ��݈Ӌ`�����鏊�Ȃ��B�Ƃ���ŁA�{���̉��t�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ��B��q����悤�ɁA�����̓���Ɨ����̌��Z���܂ŋL����Ă���Ƃ����̂ɁB����͓��R���Z�v�g���Ă��A�����i����̂ق��A��������|����j����̉������A�܂葕���͋����҂̓�l�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B17.�E18.�����Ă����v���B����N�v�̎��W�Ƃ��Ắs�����Q���n���X���̓��t�̋g�����̕]���q�g���ܑI�l�ψ��E�g�����r�ŏЉ�����A����������ł��邾���Ɍ�⎍�W�̑I�l�ɏW�����Ă��āA�����̑���Ɍ��y���Ă��Ȃ��̂��ɂ��܂��B���̎���W�Ɋւ��ẮA�g���ܑI�l�ψ���ɂ����鑐��S���ψ����̕]�������̂��œK�ł���B
�@����N�̍�i�ɂ��Ă͂����ȕ��������܂������A���ƊG�̃R���r�l�[�V�����Ƃ����`���A�����{�̎��W�̂Ȃ��ɂłĂ��܂�������ǂ��c�c����͊O���̎��ɂ͑O���炠���ł��悤����ǂ��A����ȂɃs�c�^���������͂Ȃ����B���������Ӗ��Ŋy�������B�ڂ��͐�O�u�^�v�̎��W�ŁA���낢��Ȑl�Ɋ^�̃f�c�T������Ă��炢�܂�������ǂ��A����́A�����̍D���ȉ�ƂɁA����Ɋ^�̃f�c�T����`���Ă���āA������w�^�x�̂Ȃ��Ƀf�c�T���Ƃ��ĂԂ����B���ꂾ���̘b�ł��āA�����ɂ͒P�Ȃ�F��݂����Ȃ��̂͂���܂�������ǂ��A���ƊG�Ƃ̗L�@�I�Ȋ֘A���͔��ɏ��Ȃ����̂ł��B�ł�����A���{�̎��̂Ȃ��ŁA�͂��߂ĊG�Ǝ��Ƃ������̂��A���������n�c�L�������`�ŁA���Ԃ̂悤�Ɂ\�\��҂̈Ӑ}�ƁA�G�����̈Ӑ}�Ƃ����킳�āA��l�ł����悤�Ȗ{�͂Ȃ����悤�ɂ������܂��B���������Ӗ��ł���͔��Ɋy�����{�ł��B�Ƃ��ǂ������̎��W���݂Ă������낢�Ƃ��������Ƃ�����܂�������ǂ��c�c�ڂ��͂��܂�O���̎��W���݂Ă��Ȃ�����k���l���m��܂���ǂ��A�����̖ڂł݂��͈͂ł́A���܂ŊG�Ǝ��ƃR���r�l�[�V�����ŁA�s�c�^�����̂������W�͂Ȃ����B�Ƃ��낪����Ȃɂ��̂������W�����ꂽ�Ƃ������Ƃ͑�ς������Ƃ��Ƃ������܂��B���{�̎��W���A�݂�Ȃ����ȂĂ͂��܂�܂�����ǂ��c�c�g���܂̑I�l�́A�ڂ��l�Ƃ��Ăނ������������������܂����B�i�q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�A�s���w�t1963�N7�����A�܈�y�[�W�j
���̂Ƃ��̂g���܂͍��Ǘ����q�s�ꏊ�t�i�v���ЁA1962�j����܁B����́s�����Q���n���X���̓��t�̎��̎��W�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t�i�B���ЁA1965�j��1966�N�̑�16��̓��܂���܂����B
 �@
�@ �@
�@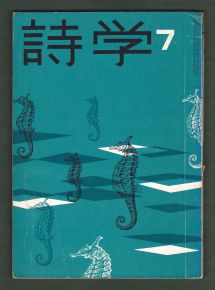
���J��l�Y�s���낵���{�k�������N�}���فl�t�i�}�����[�A1970�N5��20���j�k�u�������v�F�����l�i���j�Ƒ��R�g�A��ҁs�����Θb�W�k���㋳�{���Ɂl�t�i�Љ�v�z�ЁA1972�N12��30���j�k�u�J�o�[�f�U�C���v�F�����l�i���j�Ɓs���w�t1963�N7�����̕\���k�����l�i�E�j
�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��A�����̉�Ƃ͂قƂ�Ǐo�Ă��Ȃ��B�����ŁA�����OPAC�⏑���̃T�C�g�Œ��ׂ����ʁA����2�_�̍�i�����������B�ЂƂ̓C���X�g���[�V�����ŁA���J��l�Y�s���낵���{�k�������N�}���فl�t�i�}�����[�A1970�N5��20���j�B�}���̊��s�������A�g���������ł͂Ȃ��Ǝv����B�����ЂƂ͕��ɖ{�̃W���P�b�g�f�U�C���ŁA���R�g�A��ҁs�����Θb�W�k���㋳�{���Ɂl�t�i�Љ�v�z�ЁA1972�N12��30���j�B���̃W���P�b�g�̐���́A�����̌��T��������Ă������̂̂悤�ŁA�{���ɂ������̕`�����G�͂Ȃ��B
�����̓C���X�g���[�V������J�b�g�ȊO�ɂ��A�����ȂǍL���O���t�B�b�N�f�U�C���S�ʂ�����͈͂Ƃ��Ă����悤���B����������A�F�l�̓���N�v�̑�ꎍ�W�s����Ƃ��s�k���сE��сl�t�i���惆���C�J�A1955�j�̑����E�}��́A�����ƒ��ˏ���i���˂�����̗F�l�ŁA�I�J���i�̐���҂Ƃ��Ē����j�ł���B�����́A�c���x�ɋ���u�a�T�������W���P�b�g���̓���g�i���ꂼ�ꒆ�Ԃ��̔����j�B�����\�����W���P�b�g���\���ɂ͈�؈�����Ȃ��A�����Ȃǂ͓�����܂Ƃ߂Ĕ[�߂�r�j�[���܂̉����ɂ܂��������Ă���B�W���P�b�g�̓����A�O���̑��Ƀ^�C�g���⒘�Җ����������A���ꂪ�\���̊�����Ă���B���т̑��͐Ԃ�����F�̔������A��т̑��͐Ԉ�F����B���̌`�Ɍĉ�����悤�ɁA���т̌��̑��ɒ��҂̂��Ƃ����Ɖ��t���A��т̌��̑��ɂ͖ڎ����n���肳���B�k�c�c�l����͍��A���͖n�Ƃ�����F����ŁA���R�ȑg�ł����o�I�ɂ��y�����A����W��A�z��������ł���v�i�q����̊�����l�r�A�s���惆���C�J�̖{�t�y�ЁA2009�N9��15���A�Z��y�[�W�j���B���̉ߌ��Ȏd�l�E�̍ق���i���̂��̂̂�����ɓK�������̂��s�����Q���n���X���̓��t�������ƌ�����B�������ō̗p�����u�₳�����j���[�g�����ȎU���v�i�쑺��a�v�j�́A���������ϓ_����Ƃ炦���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����́A�g�������ҏW���Ă����}�����[�̂o�q���s�����܁t�̖{���̃J�b�g���A1972�N1���̑�33������1974�N12���̑�68���܂ł�3�N�ԁA36���S�������B�g���������{�ő���E�J�b�g��S�������ȉ���13���̂����A�D����H�܂ł�5�������̊��ԂɏW�����Ă���B
�@����N�v���W�s���y�n�t�i���R���A1961�j
�A�߉ϑ��Y���W�s���y�k����Łl�t�i�v���ЁA1965�j�A�߉ϑ��Y���W�s���y�k���y�Łl�t�i�v���ЁA1966�j
�B�g�������W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j
�C�X���s�L���̊G�t�i�}�����[�A1968�j
�D�c�������s���Ɣ�]�b�t�i�v���ЁA1972�j
�E�c�������s���Ɣ�]�c�t�i�v���ЁA1973�j
�F�g�������s�ٗ�Ձk�����Łl�t�i����R�c�A1974�j
�G�V�V�ޓ�Y�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����Łl�t�i����R�c�A1974�j
�H����N�v���W�s�u���v���̂ق��̎��t�i�v���ЁA1974�j
�I�쌴��v�s��㵂̐l�\�\��z�̌Óc��t�i���Y�t�H�A1982�j
�J�|�����q�s�Ǐ��̍Ό��t�i�}�����[�A1985�j
�K���ѕq�F���W�s���ӂ̌��@��㔪���N�~�t�i�̒��ЁA1988�j
�L�������Y���W�s��̉��t�i����R�c�A1988�j
�g���ɂ��Ă݂�A�����͎G���̖{���J�b�g�����߂邵�i������A�O�f�s���w�t1963�N7�����̕\���Ɩ{���̃J�b�g�������������j�A���Ђ̑����p�̃J�b�g�i�������͎G���̖{���J�b�g�̗��p�ł���j�����߂�C�S�̒m�ꂽ��Ƃ������B�s�Â��y�n�t��s�����Q���n���X���̓��t��ʂ��ċg�����瓾���M���́A���̌ア���������h�炮���Ƃ��Ȃ������B�����́A40�N�߂��g���������{�̗��j�ɂ����čŏ��Ɏw�������ׂ����`��Ƃł���B
�k�t�L�l
����������́s�G�H�n�j�q�p�j�L�t�i�������f�U�C���������A2010�N5��1���j�́q���꒬�̎�����`���r�ɂ́u���]���w�̍⍪����̓����A��ƁE��������̏Z���͌����u�퐶���ɂ������̂ŁA�{���̎��̉��h����߂����x���f�����B��ɋg�����̑����i�ɐ��k�ȃJ�b�g�𑽂��`�����̂����A�����͓d�@���[�J�[�̃f�U�C���Ɍg���Ă���ꂽ�悤���v�i�����A��y�[�W�j�Ƃ���B�u�⍪����v�́A�A�[�g�f�B���N�^�[�̍⍪�i�B���������Z���̂Ƃ��̔��p�̐搶�ł���ʼn�ƁE�Ö�R�j�̑O�C�n�A�������]���w�ł̋����q�ŁA1957�N�����A������`���Ŋ��Ă����B�{���ŐG�ꂽ�s�����Q���n���X���̓��t�̉��t�L�ڂ̒��҂̏Z���́A����i�����s�`��Ŕ����������c�c�j�E�����i�����s��������P�u�퐶���c�c�j�ƂȂ��Ă���B�s�G�H�n�j�q�p�j�L�t�́s�����Q���n���X���̓��t�����ł̏��e���f���Ă���A��������͐܂肱�܂ꂽ�C���X�g�y�[�W���u�G�{�Ȃ�ł͂̑�_�Ȕ��z���ʔ����v�i���O�j�ƕ]���Ă���B
2004�N8��31�����q�ҏW��L 22�r�Ɂu��������̎p��q�������̂́A�̖�쐟�q����A�̑��c�q���q������o�Ȃ��ꂽ�q�g�������Âԉ�r�ł������v�Ə��������A�i��̍����r�Y�̎w���ɂ�������炸�A�����͓o�d�����i�\�肳��Ă����l�Ԃ́A�����ȊO�S�����o�d�����j�A�g�����̎v���o����邱�Ƃ��Ȃ������B�c�O�����A�ǂ����ɕ��͂\�����Ƃ������Ƃ��Ȃ����낤�B
�k2014�N8��3���NjL�l
�ٕ������ǂ݂������������������炳���������[���Ղ����B��������͂����Łu���̋L���ɂ��闎������̃A�p�[�g�́A�s�E�ʂ���{���ʂ������Č���ʂ����A���̖퐶���p�ق֍s�����̊p���Ȃ����āA��������ɂ�������K���Ėؑ��������悤�Ɏv���܂��v�Ə����Ă��āA�����̏Z����������m�A�n�ƂȂ��Ă����Ƃ������́A���̌�̒��ׂŎ��l�E����N�v�Ƃ͖��W�������ƌ��_�Â��Ă���B����āA�ٕ��Ɉ������Y���ӏ����폜�����B
�C���X�g���[�^�[�A�A�j���[�^�[�A�G�b�Z�C�X�g�Ƃ��Ċ����^�甎�i1932�`2000�j�́A�g�����̓��L�Ɏ��̂悤�ɓo�ꂷ��B �u�k���a�O�\�� �N�l�O���\����@�y�j�@�Ȑ܋v���q�Ɛ^�甎�̐V���֍s���B���ȉ�����B�O�J���ʂ̐Ԃ�V�B�O��~�̉ƒ������ς��Ǝv���B�Z�C�u�c�E�A�����J���q�� �̖т̂Ȃ��̉ʕ��r����Ă��܂��v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�B�y�j���͒}�����[�����h�� ���������낤���A�����A�^��̒����͓��Ђ���o�Ă��炸�\�\������i�ɂ͉~�n���q�s���Ă̗��t�i1959�N11��15���j�����������\�\�A�K�₪�d���̑� �����킹�������̂��A�V���ƒ��j�a���̂��j���������̂��킩��Ȃ��i���Ԃ��ɍ�i�������̂��낤�j�B�e������Ƃɉ�Ђ̌�y�i�����͓Ȑ܂��}���̎Ј��j ���������킹���A�Ƃ������Ƃ��납�B�^�甎�́q����C���ɓ�����ār�i�s�R���N�V��������C��10�k����l�t�݂������[�A1991�N5��30���j�͑���C ������z����400��5���قǂ̕��͂����A�����ȏ���ɒB���v�A���惆���C�J�A�s�����C�J�t���̘b��ɓ��ĂĂ���B1957�N2���A�^��͑���̐��E�� �āA�_�c�x�͑�i�}�����[�����쒬�ɂ������j�̃^�P�~����L�Łu�����v���e�[�}�ɂ����W��L�Ō�i�Ɛ^��͉�z����j�̖����W�Ƃ��ĊJ�����B�ɒB�� �v��������ςɗ����B
�@�ʂ�ɖʂ����K���X�˂̂��̈֎q�ɍ������ɒB����́A�Ȃ�ƁA���������ʂ��͂��Ă������A�N�c���̐F�́A���E �������Ă� ���B���W�⎍�����炤���鐴�V�ȃC���[�W�Ƃ͂������A�i�D�͂ǂ��ł��悢�A�Ƃ��������������B�ɒB����̎d����́A�����߂��̎O�ȓ��̌����̗��������B�� �ɁA���̎������������ˁA�H�n������ē�K�֏��}�ȌX�ׂ̍��Â��K�i�������Ă����ƁA�Ȃ�Ə��~���̕���������A���������ł��āA���ꂪ�u���惆 ���C�J�v�������̂ł���B
�@�Ȍ�A��C�̎���ŁA�킽���͎��R�z���Ƀ����C�J�̎d���������Ă�������B�ɒB����́A���܂��Ă݂Ă���悤�ł��Ȃ���A�������̔��ӎ����܂ł킽 ���Ɏ����Ă���Ă����B�����������Ƃ������A��������q���g�����āA�������J�b�g���d�グ�A�\���������A�g��������̎��W�w�Õ��x��w�a���`�x�� �\���┟�ɊG�����A�����u�k�v�i���l�E�ѓ��k��A��c�G�A�剪�M�A������s�A�g�����j�̕\����`�����ƂɂȂ�̂ł������B
�@�k�c�c�l
�@�킽���ȂǁA�������ɂ��Č���قǂ̃G�s�\�[�h����������Ȃ����A���ʓI�ɁA���̌W�����ɁA�Ƃ��Ƃ��w���[�g���A�����S�W�x�ɁA�Ȃ�Ƌ��N �Y����Ƃ�������l�A�G�b�`���O�Łu�}���h���k�[���I�l���̉́v��}�������d�������邱�ƂɂȂ��Ă��ꂽ�}��ҁ\�\��}�t�ł������B�i�����k����l�A �܁`�Z�y�[�W�j
���Ɂq�^�甎�̗��N���r�i�s�^�甎�̃v���l�^���E���\�\���V��̝��G�����k�����ܕ��Ɂl�t�}�����[�A2013�N8��10���A�k��Z�Z
�y�[�W�l�j��1955�i���a30�j�N����1964�i���a39�j�N�܂ł��������A��f�̌W�͐G����Ă��Ȃ��i�y�@�z���͏��т̕�L�j�B
��������ƁA�s�a���`�t�i1962�N9��9���j�̔��E�\���E�{���̔n�Ɨr�̃J�b�g�i�z�q�v�l�͌ߔN�́A�g���͖��N�̐��܂�j���g������
�^�甎�̋�����Ƃ̒��_�������悤���B����ƕ��Ԃ̂���c�G���W�s��
�]�̐푈�t�i�v���ЁA
1962�N7��1���j�ŁA������ɂ́u�C���X�g���[�V�����^�^�甎�v�u�f�U�C���^�g�����v�ƃN���W�b�g����Ă���B�ȏ�2���̑����ɂ́A�g�����c������
���l�����s�k�t�i�S10���j�̕\����^�炪9���܂ŒS���������Ƃ��^���đ傫���B�q�����w�k�x - �c���x���L - Yahoo!�u���O�r��
�u�Ȃ��A��9���܂ł͕\���G��^�甎���`���Ă����B�F���肳�ꂽ�k�̃C���X�g���I���e�\������E���\���Ɍׂ�悤�ɔz���ꂽ�_�C�i�~�b�N�ȃ��C�A�E�g�ł�
��B�^�Ō�̑�10�������͗����̔ʼn悪�\��������A�ʏ��A5���j�����Ԃ��Ƃ������q�ɂȂ��Ă���B�^�{���g�ł͂���܂łƓ����Ȃ̂����A�\���f�U�C
���ƒԂ����ς�邾���ŁA�ǂ��ɂł����镽�}�ȏ����q�ɕϖe���Ă��܂�����s�v�c���v�Ƃ���悤�ɁA9���܂ł͈ɒB���v�̏��惆���C�J�����s���Ă���
�i1961�N�̈ɒB�}����A�x�����Ă���10���̔��s���́u�剪���@�k�̉�v�j�B
 �@
�@
�g�������W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ����̖{���i�E�j�k�J�b�g�F�^
�甎�l
 �@
�@
�g�������W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ����̖{���i�E�j�k����F��
���l
�s�a���`�t�̔��s���͑���ɂ����A�v�͎��Ɣłł���i�����͎v���Ёj�B�s�m���t���o�ł������惆���C�J�����ł����ȏ�A���Ɣłŏo���ق��Ȃ�����
�g�����ɂƂ��āA�q�ɒB���v�����惆���C�J���s�k�t���^�甎�r�Ƃ����n�́A�s�a���`�t���I���̎p�Ƃ��ĕ����B����A�s�a���`�t���s�Ɠ���1962�N9��
�ɔ��s���ꂽ�s�k�t�̏I�����Ɋ����сq���̂��߂̃g���̎��݁r�i�E�E1�j�́A�����Α���̎��W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�̊���������i�s�a��
�`�t�̂Ƃ��Ɠ��l�A�s�Â��ȉƁt�̔��Ɩ{���ł͔n�Ɨr��g�ݍ��킹���}������������Ă���j�B�����Ɂq���c�v�Y���v���Ё��������l�����Ȃ��������r�Ƃ�
���V���Ȍn�̒a���������B�������A�g�����Ɛ^�甎�Ƃ̋�����Ƃ��Ȃ��̂́A���������w�i��z�肵�Ȃ������藝�����ɂ����B
 �@
�@
�v���Ђ́k������{���W�l�i1962�`1964�j�͑S���^�甎�����ɂȂ�p���ŁA�s�k�t���l�ł͔ѓ��́s�����ցt�i1963�j�A�剪��
�s�킪���Ɛ^
���t�i1962�j�A�����́s����t�i1962�j���o�Ă���B�g���Ɗ�c�̎��W�������Ȃ��̂́A1962�N�Ɂs�a���`�t�Ɓs���]�̐푈�t���o�����肾����
���낤�B�苖�̑���l�Y�s�����ȋI�s�t�i1963�N2��1���j�̉��t���L���������A�k������{���W�l�́u�`�T�Łk�}�}�l�{�t�����X���^���ꁁ�^�甎�^�e
���O�Z�Z�~��40�v�BNDL-OPAC�ɋ����1�F����\�O�Y�s�Ƃق����Ȃ��˂����t�A2�F���q�����s���̂₤�ȉ́t�A3�F���e���O�Y�s�L�`�̏��_�t�A
4�F������s�s����t�A5�F�J��r���Y�s21�t�A6�F�����V�g�s��t�A7�F������Y�s�������t�A8�F�剪�M�s�킪���Ɛ^���t�A9�F���c��v�s�n���̕�
��t�A10�F�������s�킪�����t�A11�F����l�Y�s�����ȋI�s�t�A12�F����M�v�s����̐l�t�A13�F�ѓ��k��s�����ցt�A14�F�������j�s���E
CALENDRIER�t�A15�F�֍��O�s�����ЂƁt�A16�F�O�D�L��Y�s�����ȏ��t�A17�F�R�{���Y�s�������t�A18�F�����v�Y�s�ł��łƂ�
�āt�A19�F��c�j�Y�s�����t�A20�F�����ρs���酉J�t�A21�F���c�O�Y�s�����ƍ����t�A22�F��ԍG�s���j�̒w偁t�����s����Ă���B�S30���\����
���C���i�b�v�ɂ͋g�����̖��������邪�A���NJ��s���ꂸ�A������U���邩�̂悤�ɑS���W�̊�悪�i�s�����B
�����̖{���ƃt�����X���̕\���܂��͐^�甎���S�����āA�{���g��ҏW�҂��w�肵���̂��낤�B�t�����X���Ƃ����g�����̏\���Ԃ����A�^�瑕���́k����
���{���W�l�͋g���̒P�s���W�s�Â��ȉƁt�̑��{�ɉe����^�����悤�Ɏv���B�s�g
���������t��
�G�ꂽ�Ƃ���A�s�Â��ȉƁt�̖{���g�ł͓����W�̑O�N�Ɋ��s���ꂽ�s�g�������W�t�̖{���g�ł̗��p�ł���B���̂��߂��낤���A�����̑��{�E�����͋g���̒P
�s���W�̂Ȃ��ł͐��V���������B�S���W�Ȃ�Ƃ������A�P�s���W�Ŗ{��������9�|�Ƃ����̂͂��т������A�@�B���̓����ɕ\���Ɠ������������Ă���̂��A�[
���ȈӐ}�Ɋ�Â��Ƃ������A�Ȃɂ��̎��s�������Ƃ����v���Ȃ��B���o�ꗗ���Ȃ����Ƃ́A�Q���Ă��Q������Ȃ��B���t��{���̍ŏI�y�[�W�̑Ό��ɒu������
���Ȃ�A������
�y�[
�W���Ăł����o�ꗗ���܂ތ�t�Ɏ����������Ăق��������B�����̂��ׂāA�g���ɂ��Ă͒������l�߂̊Â����k������{���W�l�̑��{�E�����Ɋ�肩��������
�߂ɐ������Ƃ͌����Ȃ��ɂ��Ă��A���̌`��f�������āA���_�Ղɂ����悤�Ȃ͎̂c�O���i�^��͗��\���Ɩ{�����e�C�X�g�ł܂Ƃ߂āA�V���ʂ��o����
����j�B�����Ƃ��A��������������Ƃ����ās�Â��ȉƁt�̎��W�Ƃ��Ẳ��l���|��������킯�ł͂Ȃ��B���ɂ́A����E���{���҂��Â炵���s�a���`�t���
���A�g���́u����o�Łv�^�̑��{�i�т̕t���Ȃ��Ō�̎��W�ł���j�Ƃ��āA���̗͂�����Ȃ��������܂����D�܂�����������B�s�Â��ȉƁt�̃t�����X����
�͔�����m�A�A�A�n���ӂ��킵���B�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�ȍ~�̋g���̎��W�́A�u�{�t�����X���v�Ƃ����e��Ɏ��܂�Ȃ��L�`�ȍ앗�ւƕϖe���A����
��̎��т����e�������Ҏ����̏����͌��\���̏㐻�{�d�l�ƂȂ�B
���蕐�u�E�R�{�P�s�s�Ö{���߂��肪�y�����Ȃ�
�V�E���{����t�i�H��ɁA2008�N6��20���j�͌������̃|�b�v���Ƃ͗����ɃS���S���́u���w���v���ł���B�ҏW����R�b���s��U�b�p�_�\�\20���I�S
�ˉ��y�Ƃ̑S�̑��t�s��U�b�p�_�Q�\�\�S�ˉ��y�Ƃ̑��� 1967-1974�t�⍕��䍲�q�s�Ï��̐X
�ꡁ\�\�����E�吳�E���a�̈������G�������t����|�����Ό�����Y�����ɁA�{���i�����q�{���l�������r��10�y�[�W�I�j�E�����Ƃ��d�|���͏[���ŁA
�W���P�b�g���B�������̕ό^�т��y�����B���̃W���P�b�g�̑��ɂ�������B
�@�u���w�v�C�R�[���u�����v�ł͕�����Ȃ��B
�@���M�⎍���܂߂��W�������̑S�̂������܂��Ɂu���{�v�I
�@�u�ψꏬ�m�v���蕐�u�ƁA�u�Ö{�\�����G�v�R�{�P�s��
�@����s�����ɉ���y�u���{�v�k�`�B
�@�Ö{���߂���̉x�y�̉ʂĂɁA
�@�ˋ�́u���{���{�S�W���v���S�e�����킷!!
�����̑Βk�i���{���k�j�ł܂������̂́A�}�����[�����ɖ{���o���̂�\�����Ă������Ƃ��B
�}�������ɂ��I�@ ��k�������ƂȂ���
�����\�\���Z�N��㔼�� ���Z�N�㔼�ɂ����āA���ɂ̐��E�ŎR�{��������g�s�b�N�X���ĉ����ȁB
�R�{�\�\����A�Ȃ�ƌ� ���Ă��܂��u�����ܕ��Ɂv�̑n���i��㔪�Z�N�j��ȁB�悤��l�Ō����Ƃ�����Ȃ����B���ɂɊւ����k�Łu���̂����}�������ɂ��o�����肵�Ăȁv�� ���c�c�B
�����\�\���̂Ƃ��́A�� ��Ȃ��Ƃ��肦��Ƃ����C�����Ō����Ă��B�u�}�������ɂőS�W�o�����肵�ĂȁB�{���S�W��������v�Ƃ��������Ă��B
�R�{�\�\ �����Əo�Ă邪�ȁi�����ܕ��ɔŁw�{���S�W�x1�`10�A��㔪�Z�`����ܔN�j�i�j�B�������A���̂Ƃ��͋������B�}�������ɂ��o����Ȃ�A������ ��œ��{�ɉ����N�����Ă��s�v�c��Ȃ��Ǝv�����ȁB���܂Ȃ�A�u�݂������Ɂv��u�����Е��Ɂv��������Ȃ��B���������A����܂ł̃C���[�W����}���ƕ��� �����т��ւ����B�����ɂ́u�}���M�v�Ƃł������ׂ��A����Ȏv�����ꂪ���邩��ȁB�}���ƌ�������A������̃J�`�b�Ƃ�������̖{������� �ăC���[�W���������A�y���̕��ɂ͎�����ւ�C�����Ă��B
�����\�\�������A�f�U�C ���Ɉ��������N�p���āA���������ꂢ�ȑ���̕��ɂɂȂ����ȁB�N���[���C�G���[�œ��ꂵ���w�\�����ڗ����c�c������Ɣw�̐F�������₷�����ǂȁB�Ö{ ���ł��u�k�Е��|���ɂȂƕ���Œl�i���ʊi�Ƃ����Ƃ��낪�����B
�R�{�\�\�{�I�ɕ��ׂ�� �����A�����܂�u�k�Е��|���ɂ͒��ҕʂ�Ȃ��ďo�ŎЕʂɕ��ׂ����Ȃ�B���ɂŔw�������͂���̂́A�����܁A�u�k�Е��|�A�������炢���B�i����`���O �y�[�W�j
�����āA��ŕ��ɂ̏��ڂ̗��i���\���Ɉ�����炢�̊��ŏ����̕��ɂ�����j�B1970�N��㔼�A��w�����������낪�����ɖ{�� �����������ŁA ���ꂪ40�N�قǑO���������������ŕ��ɂ������Ă��Ă��悳�����Ȃ��̂����A�����ɂ����҂����̂悤�Ȑ挩�̖����T���S���������킹�Ă��Ȃ������B�E�c �ʖ��̏����Ђ̍����P�s�{�\�\�}�b�N�X�E�G���X���g��f�i������i�C�̑���E�����������\�\����ې[���A�|���l�[���s�ْ[���c������Ёt�̕��ɂ̘b��� ���������i���l�y�[�W�Q�Ɓj�A�W���P�b�g���悪�r�A�Y���[�Ɨ���u�p�앶�ɔŁv�ł͂Ȃ���ؖL��̍u�k�Е��ɔł��B
�q���{���k�E���̌܁@�V�E���W����r�͊J�n�����A�s�T�t�����E�݁t�̏��e���f���āA��������B�����\�\ �k�c�c�l�������A�R�{�����܂��Ɏ��W��ǂނ��A�ڂ������܂��ɓǂ�ł�B�{�ǂ݂͑������ǁA���̑�l�ɂȂ��Ă�������W��ǂނƂ����l���Ȃ��Ȃ����Ȃ��B ���������ȁB
�R�{�\�\�������ƂȂ��� ��ȁB��l���d�Ԃ̂Ȃ��Ŏ��W��ǂ�ł�́B�k�c�c�l���Z�N��͎��W���悭����Ă����A�悭�ǂ܂ꂽ��ƈႤ���B���W�̃R�[�i�[�����܂��傫�������Ǝv ���B�Ö{���ł������������W�͕���ł����A�l�i������������ƈႤ���ȁB
�����\�\ ���������B�悭���ꂽ����ȁB�J��r���Y�A�c������͕ʊi�Ƃ��Ă��A�ѓ��k���g�����A������m������n�̐̂̎��W�̉��t������ƁA�����Ă���������� ����B�������l���A�܍��Ƃ������Ă�B�V���̎��W���ԈႢ�Ȃ����㕶�w�̍őO���ɂ����āA��]���O�Y��J�����̐V�삪�b��ɂȂ�悤�ɁA�g�����́w�T�t�� ���E�݁x�i�y�ЁA��㎵���k�}�}�l�N�j�Ȃ�Ď��W���b��ɂȂ����B
�R�{�\�\ �����������Ƃ́A���̎���Ŏ������Ă���҂�����Ă����Ȃ��ƁA�،��Ƃ��Ďc��ɂ����B���ƂɂȂ�ƁA�Ⴂ�҂ɂ͕������悤�ɂȂ邩��ȁB����Ȏ� �オ�������Ƃ������Ƃ��B�k�c�c�l�G�����w���㎍�蒟�x�i�v���Ёj�̂ق��A�w���w�x�i���w�Ёj�A����Ɂw�����C�J�x�i�y�Ёj�A���̂ւ�͂��܂ł����邯 �ǁA�����ƔM���ۂ��������A�w�J�C�G�x�Ƃ����~���Ђ���o�Ă����G���i��㎵���`��㔪�Z�N�j�ɂ����̃y�[�W���������B����Ȏ������C���������オ�A���Z �N��̏��߂��炢�܂ł͑��������ȁB�i���Z�`����y�[�W�j
�^�ł́q���{���k�E���̘Z�@�V�E���{�S�W�𗧂�������r�B�{�e�̏�����ݒ肷��厖�ȉӏ��Ȃ̂ŁA�ȉ��ɏ�����B���҂̓�l�͊H�열�V ���ԓc�� �P�܂ł����߂��s�����ܓ��{���w�S�W�k�S60���l�t�i1991�`93�j��]�����Ă���i�������A��o�̏�ыł͎��^����Ă��Ȃ��j�B
�����\�\ �k�c�c�l�Ƃɂ����A�ڂ���̐V�������{���w�S�W�����낤�B�u�����ܓ��{���w�S�W�v�ɕC�G����悤�ȕ��ɃT�C�Y�̑S�W���ȁB��ыł͎R�{�̕ҏW�ŁA�ꊪ�� ��邱�Ƃ��܂����߂Ă������B�i�O�����y�[�W�j
�R�{�\�\�ҏW��C���ꂽ �̂͂��ꂵ�����A���͏�ыł̍�i�̉���I�Ԃ���B�P�s�{�����^�𒆐S�ɂ������Ƃ��v�����A��\����W�߂����Ƃ��v���A�G�b�Z�C�����ꂽ�����A����͂� ���Ȃ��ɂނ��������B�M���Z���N�g�ɂȂ�߂��邩���ȁB
�����\�\ �������A�܂��Ë��͂����ɂ�낤�B�ܐ畔�̕����ŁA�艿����܁Z�Z�~�ɗ}���邮�炢�̂Ƃ���ōl���Ă������B�ڂ���̌�̐���̌Ö{�D�����h������悤�� ���̂ɂ������ȁB�̂��ɌÏ����̕t�����w�S�W�ɂ������B�k�c�c�l�܂��A�S�Z�Z���Ƃ��Ă������B�u�����ܓ��{���w�S�W�v�����K���_�͂���������Ǝv���� �ǁA�ǂ����ȁB
�R�{�\�\�������������� ���ǁA��l�ꊪ�ɂ������ƁB����͑傫�������ȁB�i�O�����`�O����y�[�W�j
�����\�\�k�c�c�l�u���� �ܓ��{���w�S�W�v�̂ق��́A�T�C�Y�����ɔ��Ƃ������Ƃ����邯�ǁA���ʁk�Ŗʁl�̑傫���́u�����v�k�}�����[�́u������{���{�S�W�v�l�̔����ŁA��y�[�W ���^�e�O�Z���A���R����k�s�l�̈�i�g�B���ό܁Z�Z�y�[�W�B
�R�{�\�\���̈�i�g�A�� �����̂��A�V��ɂȂ������܂͂��肪�����Ȃ��B
�����\�\�������Ɠ��� ���A�l���Z�y�[�W�����P���w�H�열�V��x�i�����N�j�Ŏ����𐔂��āA�l�Z�Z�����Z����Ɩ�Z�S���\���B�u�����v�̎O���̈ꂵ���Ȃ��B�P�s�{�Ō��� �A��E�܍����������炢�B�i�O���y�[�W�j
�����\�\ �u�����ܓ��{���w�S�W�v���o�Ĉȍ~�A����͂��܂Ȃ������A�Ƃ��������ȃ��C���������Ă��������B�Ⴆ�A�����O�A�㓡�����A�����M�v�A�R�����A�푺 �G�O�A���c�S���q�A�{��֎q�A�F�V���O�A�|���J�Ȃ�ĂƂ���́A�Ö{���ł̐l�C���܂߂āA���R�����Ă�����B�c�Ƃ̂��Ƃ��l���āA���̂ւ�̖��O�͗~�� ���B���A�܂��䑶���₯�ǁA���쏁�O�����悤�B���삳��͂ڂ����ҏW����炵�Ă��炤�B�F�V���O�́w�����������x���l�ʼn�Ƃ̗ѓN�v����ɗ������B���A ���������l�̃��C�^�[������������ɂ͌ÎR����Y���A�ҏW�҂̓�ɘO���ɂ���ɂ͉ԐX����������Ă��炨���B
�k�c�c�l
�R�{�\�\�k�c�c�l���W�� ���ꂽ���B�w��������W�x�w���R�ő����W�x�B��W�����ꂽ���B�w�i�c�k�ߋ�W�x�B�i�c�k�߂̓G�b�Z�C������悤�B�w�킪���S���x�i�����o�ŋǁA��㔪�Z �N�j����ꂽ���B�k�c�c�l
�����\�\ �k�c�c�l�w��������W�x�Ȃ�čl���Ă���A��Z�Z�����炢������g�܂Ȃ����B�������w�i�c�k�ߏW�x�������āA��ƃG�b�Z�C������͎̂^���B����� ����ŖڋʂɂȂ�Ǝv���B����ł����l�̋g�����ƃy�A�ň�����ȁB���l��o�l�ň�l�A�ꊪ�͑����������B�i�O���`�O��l�y�[�W�j
�����\�\�k�c�c�l���� �k�O�l�Ɍ��炸�A�Ƃɂ������̑S�W�ɂ́A�Ȃ�ׂ��Βk����ꂽ���B�Βk�Ƃ����Ə��������͂���Ȃ�����A����܂ł̑S�W�ł͌y���邱�Ƃ����������B �ł��A���̐l���ǂ������l�����̑�������ɂȂ邵�A������������B�i�l�Z���y�[�W�j
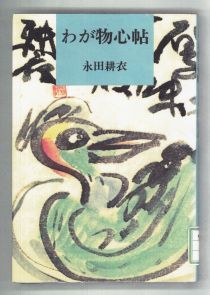
�i�c�k�߁s�킪���S���t�i�����o�ŋǁA1980�N11��30���j�̃W���P�b�g�k�����s������
�}���ُ����{�̃J���[�R�s�[�A����F�i�c�k�߁l
�i�c�k�߁s�킪���S���t�i�����o�ŋǁA1980�N11��30���j�ɐG��Ă������B�����́q���포���r����q�@�������̃}�X�N�r�܂ł� 78�т̕��� ���A�c���ł̃��m�N���ʐ^�ƂƂ��Ɏ��߂�B�k�߂́q�͂��߂Ɂr�ɂ��A��ɂ���o���s�Ս��t�ɏ\�N���A�ڂ��Ă������̂ŁA�q�������� ���O�}�r�̖`���͂������B�N�͂��邱�ƂȂ��A�u�ώ��v���J��Ђ낰�Ă��鏈���k�߂̐^�����ł���B
�@���a�l�\�l�N�����\�l���`��\���A�������{���O�z�{�X���p�T�����ŁA�u���ƊG�ɂ��i�c�k�ߓW�v�J�ÁA�C���b�� �̐��m�Ɗ̐� ��ł������B������̎����\�����A���͎��l�A�g�������ɐ����A�Y�a�s�̊C�㎁�@�i�ԉe�����j��K�˂��B���̎��߁A�C�㎁�̃R���N�V������q�����ɁA�ʐ^�� ��������u���O�}�v���A�ˑR���z�̂��Ƃ��o�������B���͐⋩�����B����ȊG���`�������̂��A�Ƃ�����Ő��������B
�@���㌎�����o�قǂɁA���̉��O�}���ώ��̂��Ƃ��Y����Ȃ��Ȃ�A���͎v�����āA�ԉe������ɂ��̖ώ���ł��������B�ώ��̃A���������āA�������� ���炨�Ԃ�����A�Ƃ͂��������A�����͎���ł�������ʁA�䂪��̔鑠����Ƃ���ƂȂ��Ă���B�i�����A���y�[�W�j
���莁�̒�Ă���u�g�����ƃy�A�ň���v�Ȃ�A�g���̑��ɂ������̂��Ƃ��������q���L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�́r�i�s�Ս��t235���A 1969�N 11���j�Ɓq�q�ΘŁr�Ɓq�������_���r�r�i�i�c�k�ߑS��W�s��Łt�x�q�c�����́r�����ɁA1973�j��2�т����邪�A�ɂ��ނ炭�͂ǂ�����P�s�{�����^ ���B����āA�����{����̃Z���N�g���|�Ƃ����q��57���m���ш�Y���ҁn�s�g�����t�̖ڎ��ār�i��q����j�ɐ��荞�߂Ȃ������͎̂c�O�ł���i�q���L���r �ɂ́u�k�߂���͒��N�̑f�p�ȉԂ̊G�ɐ���������v�Ƃ���j�B�{�_�ɖ߂낤�B�R�{�E���藼���ɂ���ꎟ�܁Z���̃��X�g�����ꂾ�B
���R�{�P�s���I�@��ꎟ�i�\�����j
��������@�V�쒉�@�����Ɉ�@�q�։��i�|�W�j�@�����O�@���\�쎟�Y�@�����r�q �@�͐��D���@��ыŁ@���o��d�@�k���l�@���R���@�����O�@�ˈ�c���O�@�a�R�i�@�i�䗴�j�@�i�c�k�߁@���J�F�g�Y�@��C�M���@�����ّ��Y�@����V���@��� ���q�@�R�����v�i����W�j�@�R�njN���@�g�c����
�����蕐�u���I�@��ꎟ�i�\�����j
����M�v�@�����ߕv�@�r�c�����v�@�Γc�ܘY�@�ɒO����E�\�O�@��㋆��Y�@���È���Y�i�w��������x�S�J�b�g�A�V�i���I���^�j�@�v�����F�@���c����@���� �M�v�@�㓡�����@���q���Z�@���Y�����q�@�F�V���O�@���c�S���q�@�푺�G�O�@�c������@�ԐX�����@�ÎR����Y�@�{�e�r�O�@�R�����@�R�{���g�i���ɉ���W�j�@ �g�����@���쒷���@���㖼�얟�ˏW�i�l��Z�y�[�W�j
�����l�W�i�ɒO����E�\�O�͐e�q�ň�������j�̐l�I�����������A�R�����v�i����W�j�A�R�{���g�i���ɉ���W�j�\�\����ɂ͎Q�����B�� ���y�[�W�ɂ͑S60���\�z�ɉ����āA�H��ɂ����삵���_�~�[�i�W���P�b�g�̌��{�j�܂ŎB�e�A�f�ڂ��Ă���i�q�V�E���{����/�C�܂�����{���{�S�W/�H��Ɂr�Q �Ɓj�B���҂ƕҏW�҂����肠�����Ă���l�q���ڂɌ�����悤���B�����đ�엘�q�ˋ���I�@���蕐�u�E�R�{�P�s���ӔC�ďC�u�C�܂�����{���{�S�W�v�S�Z�Z ���\�z�r������B���̒��L�ɞH���u�{�S�W�͂����܂ʼnˋ�m�E�E�n�̊��ł��B�e���̓��e�A�I�҂ɂ��Ă͗����Ă���킯�ł͂���܂���̂ŁA���炩�� �߂������肢�܂��v�i�l�O�Z�y�[�W�j�B��57�����m���o�����ҁn�́s�g�����t�ł���B����͓ǂ�ł݂����B�������S�W�́A�Βk�ɂ��ĎO�o�ꂷ���20�� �m�R�{�P�s���ҁn�s��ыŁt�̖ڎ��Ă����邾���ŁA�����̎��^���e�͂��ׂċȂ̂��i��06���́s�r�c�����v�t�́m�����z�q�ҁA���`�G�b�Z�C�E���p�G�b �Z�C���^�n�ŁA���ꂪ�ł��ڂ������̂̂ЂƂj�B�K���Ȃ��ƂɁA���o���҂̋g�������͌��������B�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�Ɍf�ڂ��ꂽ�剪�M�E����N�v�E�V��ޓ�Y�E���o���̓��c�̑O�i�Ƃ��Ďl������30�т��̎���I��ł��āA���o���҂̋g�� �����͎���34�т���������ł���i�ŏI�I�Ɍf�ڂ��ꂽ�A���\���W�[���q��\��40�I�r�j�B���W���Ƃɂ܂Ƃ߂Čf����B
�s�Õ��t�s�m���t�s�T�t�����E�݁t�s��ʁt�Ɏ�����A�s�Â��ȉƁt��4�т��ۗ����Ă���B���z�́A��������o���ďC�́s���㎍�ǖ{�\�\ ������ �g�����t�ɍĘ^���ꂽ�q�G�b�Z�C�r������悢�B
�c�O�Ȃ��ƂɑΒk���̂��Ă��Ȃ��B�����řG�z�Ȃ���A�����҂ނȂ炱�����Ƃ����ڎ��Ă�`�����悤�B���т͐��O���s��12���W����A �v30�т�I �o�����B�Ȃ��A�R�{�P�s�҂ɂȂ�s��ыŁt�́s�����T�����X�\�\��ѝ����쏬���W�t�i�ėt�ЁA2011�j�Ɓs�̋��̖{���\�\��ѝ����쐏�M�W�t�i���A 2012�j��2���Ɍ������Ă���̂ŁA�O�q�̑�20���m�R�{�P�s���ҁn�s��ыŁt�̖ڎ��ĂƔ�r����Ƌ����[���B
��57���m���ш�Y���ҁn�s�g�����t�̖ڎ���
�m�T�����сn
���́A���������i�@�����G�߁j
���i�A���̖|��\�\�����������N�̓��̉S�i�A�t�́j
�Õ��i�B�E1�j�A�Õ��i�B�E2�j�A�ߋ��i�B�Õ��j
�m���A�����A�����i�C�m���j
�V�l��A���̕a�C�i�D�a���`�j
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����A�؍݁i�E�Â��ȉƁj
�Ă���H�܂ŁA�킪�n�j�R���X�̎v���o�i�F�_��I�Ȏ���̎��j
�T�t�����E�݁A������܌�b�сA���C�X�E�L��������T�����@�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁@�����`���l�i�G�T�t�����E�݁j
�y���A�����`�A�Ẳ��i�H�Ẳ��j
���L�A���i�I�|�[���E�N���[�̐H��j
雞�A�}�сA����i�J��ʁj
�Y��i�ނ��сj�A�����q杁A�k�H��l��i�K���[���h���b�v�j
�m�U���Z�́n
�̏W�s�����t�k�S�l
�m�V���o��n
��W�s�z���t�k50�叴�l
�m�W���U���n
���e���O�Y�A���x�X�N�i�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�j
�o���i�k�ߕS��j
1 �����͂ǂ��ɂ��邩�H�A2 �o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�A103 �\�͎c���Ȍ��A104 �Â��V�t�A105 �l�̑O�ŁA106
�����̈��A107 ���_�̂��Ƃ��\�\�����i�y���F��j
�m�X���Βk�n
�ѓ��k��Ƃ̑Θb�����I�t�̌�䊁i�s�����C�J�t1975�N12���Վ��������j
�i��t�j
�o�T�i���o�Ə����j
�g�����N��
���
������u��y�[�W���^�e�O�Z���A���R����k�s�l�̈�i�g�v�őg�ނƁA��296�y�[�W�ɂȂ�B�ȏ�͈��̎v�l�����������킯�����A �m���o�����ҁn ��m��ˎ闝���ҁn�i�U���I�W�s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�t�̎��т�����j�ƕ���ŁA�m���Y���P���ҁn��m���}�����ށ��ҁn�́s�g�����t���ǂ�� �݂����i�̐l�Ȃ�A�m�c��m���ҁn��m�F�V���F���ҁn�A�m�y���F���ҁn����������Ɗ������j�B��|���肪���Ȃ��ė\�z�����ɂ��������ɁA�����݂� �傫���B
�k�NjL�l
�ےJ�ˈ�E�����E�O�Y��m�s���w�S�W�𗧂�������t�i���Y�t�H�A2006�j�́q���E���w�S�W�r�Ɓq���{���w�S�W�r��2�т��琬
��B��҂͌�肨�낵�ŁA2006�N�ɂȂ��ꂽ�C�k���낤�B���́q�����h�A�v�����^���A���w�̖��r�̐߂ŁA��ыł͂���Ȉ����悤���B�i�s���w�S
�W�𗧂�������k���t���Ɂl�t���Y�t�H�A2010�N2��10���A��l�l�`��l�܃y�[�W�j
�\�\�k���i��̓���L�l���a�̎������n�̍�Ƃ��ǂ����邩�B���F��A�Ԗ�e�A���}�Òj�c�c�B�����P���A�Ñ��E���A ��蒷���Y�B
�ےJ�@���̂ւ�݂�Ȃ� �߂悤��B
�����@��ыłƂ���蒷 ���Y�Ƃ��A�ނ�͂ق�Ƃɕ��͉���ł��ˁB
�\�\����ł��邱�Ƃ𐽎����Ǝv���Ă���ӂ�������܂��B���}�Òj�����͂�����Ƃǂ��ł��傤�B
�O�Y�@���}�Òj�Ɋւ��� ���A�l�͂��ЂƂ��A���Ă����ӂ��ɂ͎v��Ȃ��B
�ےJ�@�u����W�v�ɓ��� ���炢���ł��傤�B
�}�����[�̑n�ƎҁA�Óc�肪���Ɏ��Ɏ����Ōh���������l�i�}������S19���̑�������őS�W���o�Ă���j�̍�i�́A�R�{�P�s�����ł� ���A���ǗY �i���e�Ə�����҂a���{�s��ыŕ��w���ځt���тɐG�ꂽ���z�����߂���e�W�s�̓��̋q�t������j�Ƃ��������̎m������]������Ă���A�}���́u�� ���v�ł͈䕚����Ƃ̓�l�W�ł���i���͒Z�я����q�ė�r�̂܂������Ƃ��Ƃ����ɑł��ꂽ�j�B�ےJ�E�����E�O�Y�̎O�l�ɂ��s���w�S�W�𗧂�������t�Ɖ� ��ƎR�{�̓�l�ɂ��q�V�E���{�S�W�𗧂�������r�̊����Ă��r�ׂ�ƁA�ˋ�̕��w�S�W�̕Ҏ[�������ɋ�����������̂��������ł���B�{�e�͂���ւ̎��� �����m�I�}�[�W���n�ł���B���Ȃ݂ɁA�C�k�̖{���ɋg�����͓o�ꂵ�Ȃ����i���e���O�Y�͓o�ꂷ��j�A�q���{���w�S�W�����Ĉꗗ�r�̖���W�A��79���q�� �㎍�W�r�Ɏ��^�����ƍl���Ă������낤�B���ڎ��т́A�s�Õ��t�s�m���t�s�T�t�����E�݁t�s��ʁt�Ȃǂ̎��W����A�W�����܂ޏ��^���тƂ������Ƃ��� ���B
�g�����̉̏W�s�����t�i����70���L�ԁj�͘a�c�z�q�s�҂Ƃ��āA�ӂ���̌������L�O���ׂ�1959�N5��9���A���ƔłŊ��s���ꂽ�B���e�͋g���̍ŏ��̒����ł���s�����G�߁t�i����ɁA1940�j�́q���́r�Ȃ�тɁq蜾蠃��r�i�Z��44�������2��j�Ɠ����ŁA�V���Ɂq���Ƃ����r���t���ꂽ�B�g���͌�N�A���z�ɂ��������Ă���B
�@�K��I���̏W�w�����G�߁x�́k�c�c�l�㔼�͒Z�̎l�\����u蜾蠃��v�Ɩ��Â����B�L���������܂������A蜾蠃�̓X�K���ƌP�݁A�n�`�̈��B���t�W�̂Ȃ��Ɂu�X�K�����g���v�Ƃ����ؗ�ȕ\�����������悤�Ɏv���B��������肵�����̂��A���݂̏��̏W�w�����x�ł���B�i�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A����y�[�W�B���o�́s���㎍�蒟�t1975�N9�����j
�g���͑剪�M�Ɂu���Ƃ̕\��́u蜾蠃��v�Ƃ������ǁA�������Ȃ��āw�����x�ɂ����v�i�s�����C�J�t1973�N9�����A��l���y�[�W�j�Ɖ���̗��R������Ă��邪�A�ق�Ƃ��ɂ������낤���B�q蜾蠃��r�͎��̏W�s�����G�߁t�̘a�̂̕W�肾�������A�P�Ƃ̉̏W�̏����́s�����t���Ƃ����m���鍪�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�{�e�ł͂��̗R���ė���Ƃ�����l�@����B�u�����v�������E�`��̒n���u���Ս�v�Ɉ˂�Ƃ�����������B�ڍׂ͌�q���邪�A���͂���������m�肵�����B�g����1950�N��O���A�Ƃ������Ƃ͂̂��Ɏ��W�s�Õ��t�i1955�j�ƂȂ鎍�т��������ł������������̂悤�ɐU��Ԃ��Ă���B���z�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́q�R�@���ϒn���̎��Ӂr�Ő��e�̎��q�R�̗�i�C���E�����[���A���j�r�������Ă���A����������̂��B�Ȃ��A���o�́s���e���O�Y�@���Ǝ��_�k��6���l�t�t�^�q�l�ƍ�i�r�i�}�����[�A1975�N10��31���j�ŁA����́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�B�y�@�z���͎��̒��L�ł���B
�@����́A�����W�Ƃ�����s�ߑ�̋��b�t�̂Ȃ��̈�сq�R�̗�i�C���E�����[���A���j�r�̈�߂ł��邪�A���ɂƂ��āA�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���i�ł���B������ܔN�O�y��o�s������Ƃ������t�̊��s�����炷���1969�N�A���z�̎��M�����炷���1970�N�z�̏H�̏��߂��낾�����B���e�搶�͏o��������̐��M�W�s������Ƃ������t�ɏ������邽�߁A���Ђ��ꂽ�B�S��\���ɃT�C�������܂���Ƃ������Ɏ�ɂ��Ȃ����ƁA���e�搶�͋���ꂽ�B�����ċ}�Ɏv�����ꂽ�悤�ɁA�O�c�ɋC�ɓ��������݉������邩��s�����Ɖ�c�j�Y�Ǝ����^�N�V�[�ɂ̂����B�c���w�߂��ō~���ƁA��ʂ�ɖʂ��Đ^�����X�\���������B����͕����ʂ荕���Ƃ����𑠁y2014�N�̎��_�ő��݂��m�F�ł��Ȃ��z�ł������B�܂��l������Ƃ����̂ɁA���D���̋q���K���ɓ����Ă���̂������������������������ɂ��������B���̌X�����됼�e�搶�͏����U�����悤�ƌ���ꂽ�B
�@��c�j�Y�͂��т��ѐ搶�Ə����s��U�������Ă������A���������Ȃ܂Ȃ����ɂƂ��ẮA���������搶�Ƃ̂���������͏��߂Ă������B���Ս��y�����s�`��O�c4���ځE����1���ڂ̋��B��̖������Վ����`��O�c4-8-34�A����z�A�ɎM�q���y�`��O�c4���ځE����2���ڂ̋��z������A�����h�q�̕��y���������`��O�c4-7-29�z�����Ă���A�ׂ������̍�y�H����z���̂ڂ�ƁA���ϒn���y�ʖP�����`��O�c4-11-19�z�������Ă����B�^�����h��ꂽ�n������̊�͐Ԃ�����|�������āA�ނ���������������A���ł����̗d�C��Y�킹�Ă���B
�@���͓�\���N�O�̂��Ƃ�z���o���Ă����B���̒n�����܂̉��̊␣�Ƃ����ƂɁA�Ⴂ��Ƌg�c���j�Ɖ��h���Ă����̂��y�g����1951�N�A���Ս�̋߂��ɉ��h���A��ԑ����̕����Ɍ��j�ƏZ�z�B�Ǝ�͎l�\�܁A�Z�̌�Ƃ���ŁA�����Ԃ������ꂽ�قƊ�����Ă����B�~�̐[��ɁA�e�q�O�l�̐Q������Ȃ���A���͕֏��ւ���������̂��B�������͑䏊���o������ɂ��Ă����B���傤�ǂ����ɂ͌{�����������āA�^�Ă͕��m�ӂ�n�̏L���ɕ������B�_�o���Ȍ��j�͂��Ƃɂ��₪�����B�ނ͎q���̂����A�̕a�C�������Ƃ��ŁA���������ꂽ�������āA�s���҂̎�������̂������B��Ƃ�������n�̌����ɁA�܂��n�R���O�V���~���y1947�N3���A�u�`��O�c�L�����v�ɓ]���z���Z��ł������A�s�v�c�Ȃ��Ƃɗ�����Ă���̂������Ƃ͂Ȃ������B
�@�߂��ɜh�q�̕揈���������̂Łu�{���m�ӂ�n�̍���ׂ�͎O�V���~���t�v�Ɠ�l�͏����B�����������p�y���{�����꒬�ɊJ�����]�ˍ��ɗאڂ��āA�����h�q���N����蘐���m���J���Ă����z�́u�~������ׂ�͉����y�E�q��v�̃p���f�B�[�ł���B�F�l�����́A���Ƌg�c���j�Ƃ̋��������͈�N�������Ȃ����낤�ƌ��������A���a��\��N�̉āA�ނ��y���ŔN��̕w�l�ƐS������܂ő������B
�@���̍ג����������玄�̎��W�s�Õ��t�͐��ꂽ�B
�@��x�����ϒn���̑O��ʂ�̂��A�����������Ă����킪�F�g�c���j���A�����͉��������z���o���Ă����B�i���O�A����`��O�Z�y�[�W�j
 �@
�@ �@
�@
���Վ��̎R��i���j�ƎR��O�Ɉ��u����Ă��鐅�q�n���i���j�F���Վ��́u���a�O�N�i1617�j�L�O�����É~�������ɋ��Չ@���J�n�A�k���l�i���N�i1630�j�O�c�Ɉڂ�A�������N�i1652�j���n�Ɍ����A�͂��߉@���𐅌��@�Ə̂����i�O�N�i1774�j���@���ɉ��߂��B�{���̋��Պω��ɂ�苛�Ս�̒n�����ł��Ă���v�i�����s�`������ҁs�`��j�k�㊪�l�t�����s�`������A1960�N3��15���A�O��O�y�[�W�j�B�Ȃ�����͈��p�҂̕�L�i�ȉ����j�B���Պϐ�����F���i�E�j�k�o�T�F���Պϐ�����F���Ƌ��Վ��i�O�c�R ���Վ��A���s���L�ڂȂ��A�Z�y�[�W�j�l
�����s�`������ҁs�`��j�k�㊪�l�t�i�����s�`������A1960�N3��15���j�͋��Պω��̗R���ɂ��Ď��̂悤�ɋL���B
�u�O�c��̋��Ս�Ƃ����n���ɂƂ��Ă���A��y�@�O�c�R���Վ��̋��Պω��͊�̕��Ƃ��ĐM���ꂽ�B���̉��N�ɂ����Ƃ���ł́A���ɋ����Ђ��������������B�����̐l�����������A�ω��o������ł��ڂ�����]�����Ƃ����B����͊F�ł����B����ɖ@�،o��^�����āA�n�Y�Ƃ����҂������悭�ł����̂Ō����������A���̖�ɏ��͋}�����A�n�Y�͂����ւ�߂���ŁA���̏����Α��ɂ����B������l�̘V�l�����āA���͏��̕��ł��邩��Ղ��݂��Ă���Ƃ����̂ŘA��čs�Ă݂�ƁA�D�̒��͑S�ĕ����ł����B�V�l�͂��̏��͊ω��̉��g�ł��āA�������g�̕�F�ł���Ƃ��ď����������B�������Ƃ��Ĕn�Y�͕����ɓ����Ƃ����B�����{���̊ω��̖ʗւ͓��̏��炵���A�E��ɋ��̂͂����ՁA����ɓV�߂������������A�������A�㐡�̗����ł���B�J�R�@�_�����肩������炵�����̂Ƃ��Ă��邪�A�w�]�ˍ��q��x�ɂ́A���ƈɎM�q�������̒u�����ł����̂��A�����ł��炢�������Պω��Ɩ��Â������̂ƋL���Ă���B������ɂ���A�M���W�߂����Ƃ͎����ł���B�Ð���ɂ��A
�@�@���l���g������Ƃ����p
���̂������������ω����A�����ɂ����g���ɍs���Ƃ������������A�Ƃ̈ӂł���B
�@�@���Ջߏ����Ɨ�����������
�@�������̎l�V���̈�l�A�n�Ӎj���O�c�̐��܂�ł���Ƃ����`���̂���Ƃ��납��A�u�͂͂��A���O�̍ݏ��͂��̋��Պω��̋ߏ����v�Ɨ������������Ƃ̈ӁA������ɂ���A�����M�̑Ώۂ����A����̓Ő�ɂ�����Ƃ���ɁA����̐M�̎����v����ł��낤�v�i�q��l�ҁ@�ߐ��@��\�́@���ЂƐM�@��l�߁@��ʖ��O�̐M�r�A�����A��Z�l�܁`��Z�l�Z�y�[�W�j�B
�F��M�v�ďC�E���ؐM�V�B�e�s�Z��ڎO�V�������ʐ^�W�t�i���N�ЁA1981�N9��1���j�́q�Z��ڎO�V�������N���r�ɂ́A�N��͐����N�Ƃ��āu���a22�N�i���l���j�E48�v�̍��Ɂu3��17���A��A����A���B�`��O�c�L�����i���O�c�ܒ��ځj�ɗ��������v�i�����A��ܘZ�y�[�W�j�Ƃ���B�������g�́s���������̎��`�k�����Е��Ɂl�t�i�����ЁA1985�N3��25���j�ɂ͂���ɏڂ����A�����g���D�̒������|���ɓ͂����n�K�L�́u����������A�`��L�����ɗ����̂��Ă��邩��Ƃ����m�点�Ȃ�ł��B�Ƃ��Ă����Ƃ������Ƃ͂����ƑO�Ɏ莆�����Ă킩���Ă��܂������A���̌�̏������m�ꂸ�A�S�z���Ă��܂���������ł���ƉƑ��̈��ۂ��m�ꂽ�킯�ł��B�ꖇ�̃n�K�L������Ȃɂ��ꂵ���������Ƃ͂���܂���B�^�����́A�������Ă��쌴���낤�Ǝv���ċA���Ă�����ł����A�������̖����L�����ɉŁm�����n�����Ă��܂��āA�K�����������������̂ʼnƓ��Ǝq���������݂�Ȃ����g���Ă��܂����B�d���ł��Ă������̂Ō}���ɂ����Ă���āA����ƖL�����̉Ƃɗ��������܂����v�i�����A��y�[�W�j�Ƃ���B�����[�����ƂɁA�ʐ^�W�͏��a20�N��̃y�[�W�Ɂu�O�c�L��������̚����v�ȁi���a25�N����j�v�i�����A���܃y�[�W�j�Ƃ����L���v�V�����ƂƂ��Ƀ��m�N���ʐ^���f���Ă���B�N�ォ�猩�āA���̚�����̎��߂ɂ������␣�Ɓi���������Ђ�Ƃꂽ���̂��j�ŋg�����́s�Õ��t���������̂��B����Ɍ����A�s�m���t���q�~�̊G�r�i�C�E6�j�ɂ������̋L�����h�g���Ă���悤�Ɏv���B

�u�O�c�L��������̚����v�ȁi���a25�N����j�v
�o�T�F�F��M�v�ďC�E���ؐM�V�B�e�s�Z��ڎO�V�������ʐ^�W�t�i���N�ЁA1981�N9��1���A���܃y�[�W�j
�g�������z�Ɉ������q�R�̗�i�C���E�����[���A���j�r�̓����ӏ���ǂ�ł݂悤�B�S87�s�̒��قǂ�33�s�ł���B��_�̑��݂��猩�āA�g���͏��Łs�ߑ�̋��b�t�i�n���ЁA1953�N10��30���j���{�ɂ����悤���B���ڂ��ׂ��ӏ��ɉ�����t���B6�s�߁u�Ƃ̕��v�́A���J�K�M�ҁq���e���O�Y�N���r�Ɂu���a��\�ܔN�i���܁Z�j�@�\���^�܌��\���A�`��Ŕ����䒬�꒚�ڔ��\�Ԓn�ֈڂ�v�i�s��{ ���e���O�Y�S�W�k��12���l�t�}�����[�A1994�N11��20���A�O�Z�y�[�W�j�Ƃ���A���ɏ������܂ꂽ�e���͋Ζ���̌c��`�m��w����̋A�H�ɓ_�݂���B�u�]�˂̎O�����Â���̂Ȃ�Ƃ��Ƃ����^�j�̕�v�́u�]�˂ɂ�����O��������̎n�c�v�i�����s�j�A�u�O�����̃X�g���f�B���@���e�q�̂悤�Ȗ����v�i�U�����j�ٖ̈�������Α��ߍ]�̕�ŁA���Վ��̉�����M���i�`��O�c4-7-20�j�ɂ���B
���낢��E�Ƃ̂��Ƃ��l����B
�J�{�J�{�ƓD�̒��������
�q��������ēn������V�l������
���V�F�N�X�s�A��ǂ�œn������
�z������̂�
�Ԃ�Ԃ��Ƃ̕��A��
�����Ƃ�����������Ȃ��̂ɁB
�������̗��R���ˑR�킩�����B
�����o�X�̒ʂ�H���班����̍��
�̂ڂ�ƁA�������炯���B
���ɂ̓C�M���X�̕ʑ��̗���̂悤
�Ȗ傪����A�Z�E�͗m���ɉ��ʂ�
�͂��Ė���ӂ��Ă���B
���̎R���̎��X�̐��E�ɂ�
�]�˂�E�ԁu�Ђ�艺�ʁv�Ȃ�B
�Ȃɂ���|�P�b�g�Ɂu�}�N�x�X�v������
����j�͂���Ȃ��B
�u�}�N�x�X�v�̒��ł����났������
����B
���ϒn���m�������悤�������n�Ƀ����̉Ԃ���������悢�B
�̏��`�n�������ō����֓]������
�����ɂ��߂Â����ƌ�����
��낱�������h�q���o�X�̒ʂ���
�ʂ��Ă���B
�]�˂̎O�����Â���̂Ȃ�Ƃ��Ƃ���
�j�̕�����������̒��r��
���C���̈ꕔ���ł�������{�|�̒ʂ��
�����āA�₪�ĉ��݂��������
�ǂ����ւ�����������
�x�m�R�̒���ɃC�^�h���������Ă���
���Ƃ��������l�����
�ꏏ�ɔb���֍s�����e�搶��
�F���̎R�̗�m����݁n�̒����K�N�ƂȂ����B
 �@
�@
�H���@�␣�Ƃ̂������ӂ�i���j�ƍ��c�ʂ�ɖʂ���≺�i�E�j�F�ʖP����O����H���i�g�����́u�ׂ������̍�v�A�`��̈ē��Y�ɂ́u��̗����Ɏ��@�����сA���̂��т�����ł��邽�߂��̖��������炵���v�Ƃ���j�������낷�ƁA�≺�𓌐��ɑ���͍̂��c�ʂ�i���e���́u�o�X�̒ʂ�H�v�u�o�X�̒ʂ�v�j�ł���B�g�����́u�n�����܂̉��v�́A�ʖP���̗H�����ʂ́u���v�ł͂Ȃ��A�R�吳�ʂ̍�́u���v�i�������t�߂̍`��̌f���Ɂu1956�N�i���a31�N�j�����@�ŎO�c�쎛���v�ƌ����A�u�L�����v�ł͂Ȃ��j�̂悤�ɂ��ǂ߂邪�A��ˌ��Ă�A�p�[�g�A�}���V�������������Ԍ��n�Ŋ␣�Ƃ��m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
 �@
�@
�ʖP���@�n�����i���j�Ɖ��ω����n���i�E�j�F���ϒn���͎R�剡�̒n�����Ɉ��u����Ă���A�����V�b�J���[���i�x�r�[�p�E�_�[�j��ʕ��������Ă���B�ʖP���́u�c���l�N�i1599�j�����x�ɊJ�n�A���i�\��N�i1635�j���n�Ɉړ]�A�J�R�~�ށ^�����낢��h�Ċ�������������ϒn��������v�i�s�`��j�k�㊪�l�t�A�O���y�[�W�j�B�ʖP���̌Â��\�D�ɋL����Ă���Z���́u�ř��O�c�쎛���O�\��Ԓn�v�A���Ȃ킿���e���́u�����v�ł���B
�Ђ���Ƃ���Ƌg���́s�Õ��t���o�����O��1955�N�Ɂu���z�L�����̉��h���o�ė��n�̑��c�唪��ɋ߂��]�Óc�ɊԎv�i�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�j���Ĉȍ~�A���e�E��c�ƎU������܂ŎŎO�c�L�����i���݂̍`��O�c4���ځE5���ځj��K��Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B���e�̎��i���o���ڂ���1950�`53�N�̎��M���낤�j�ɏ����ꂽ�n�������A���ċg�c���j�ƂƂ��ɂ������g���̋N�������n�̂��̂������B���l�{�l�ƂƂ���20�N��ɓ��n������̂́A�ǂ�قNJ��S�[�����Ƃ��낤�B�g�����������̎�̒n������荞�ނ��Ƃ͌����ĂȂ��̂��B�u���ɂƂ��āA�Y��邱�Ƃ̂ł��Ȃ���i�ł���v�䂦��ł���B�\�\�}�����[�͋g�������Ђ���1951�N�����A���吳��O�ɋ߂��u������{���䒬9�v�ɂ������B�g���́q�a�c�F�b�Ǒz�r�ł�����u�{���X�쒬�v�i���E�퐶1�A����2�A�{��6�E7�j�Ə����Ă��邪�A���邢�͓������B�ʋɂ͓s�d�𗘗p���A�c�����i�`��œc�����͌��E���V���j�ŏ�芷���ĖL�����̉��h�ɋA���Ă����悤���i���݁A�s�d�͂Ȃ��B�����_�t�߂̂�����Ƃ���Ɂu���Ս≺�v�Ƃ����o�X�₪���邪�A�݂��ɏ�������Ă���j�B�}�����u���c��_�c���쒬2-8�v�Ɉړ]�����̂�1954�N12���̂��Ƃł���B�\�\�g���̎��ɂ�����u���ϒn���̎��Ӂv�́A�{�̕�������ɖ��܂�A���喏W���ė��Ɖ����B
��i�B�E14�j
�ӂ�Â����
�����蓽���ꂽ
�{�����̂ق̂��炢�Ȃ���
�������̂̃C�}�[�W��
�����Â�����̂̍��p
���Ȃ����r���̏L�C���������
���ƊO�̂����߂��Ȃ��Ȃ鎞
�����܂̗���
�Č{�͗������݂͂��߂�
�����������
����������w�d�݂𑝂�
�Â��Ƃ荇�͂Ȃ��Ӌ�����
�ӎu����
���肨���Ă���
��Ԃ͊����₷���ύt����Ԃ�
����̘m�̂��ւ�
��ɂ̐��������Ƃ߂�
�ւ��ނ��̂�
�m�łȂ����
���̑�n�ł��炤��
���Â܂�P������
��̈ٗl�ȕ��̂̂܂ւ�
�����Ȃ����́@�c���ł��Ȃ����̂�
���т����肢�炾����
����������̂������������ɂ��
���̂Ђǂ���Ԃ�̌��ӂ�
�����났��������
�����
��Ⴢ����G���̂₤�Ȃނ�
�����̋��Ԃ̊O�ł�
�����
�Y���̂₤��
�����疄�܂Ă䂭
����
�s���ȎЉ����
�s�����t�i1959�j�́s�����G�߁t�i1940�j�A�s�t�́t�i1941�j�A�s�Õ��t�i1955�j�A�s�m���t�i1958�j�ɑ����g������5���߂̒����ɂ��ď��̉̏W�ł���B�����̏n��́A���W�̖����@�̉�������ɂ���B���̋��������A���������u���v�����Ȃ̈�N���ł���A�������瓾����Z�F�̓V�R�����i�C���f�B�S�j�ł���A���̐F�i���F�j�ł���B�{���́u���Ձv�Ȃ�A�l�����������Ă�����A�т������Ă��B�������s���Ձt�Ƃ����̂ł́u�т��v�Ɠǂ܂�霜�ꂪ����B����A�u������������v����͋������z�N�����B����ɁA�������ɂł͂��邪�A���́s���F��寁t�Ȃ�ʁu���F�̋��v���B�����Łs�Õ��t���������ш������B�e�{�œ����A�����u�T�@�Õ��v�̂������Ƃɒu����Ă����A������e���ɂ�����s�Õ��t�̊������тł���i�����͐V���ɉ��߂��j�B
���i�B�E2�j
��͂������������ɂ���
���̂Ȃ���
����ɒu���ꂽ
��������
���̂���C���ʂ�����
�M�̂��ւ�
�Ђ����ɉ�̂���
�����
���̎M�ֈڂ�
�����ɐ��̋Q��͋��������
���̎M�̂��ڂ݂�
�ŏ��͂�����
���ɗ����Ăѓ����
�g�������M�́q�Õ��r�i�B�E2�j���e�k�Ȃɂ��̃A���\���W�[�̂��߂ɏ����ʂ��ꂽ�Ǝv�����l
�o�T�F�g�������e�u���v�R�N�����e�p���i20x20�j2�� - ���t�I�N!
�����ɂ͋�������Η�������B�����Ƃ����́u���v�A�����Ƃ������{���ɓǂ߂邪�B����͂Ƃ������A�O�\��̋g���͋��Ս�̋߂��A��ԑ����̕����ɉ�Ƌg�c���j�Ɖ��h���ās�Õ��t�̎��т������p���ł����B�l�\�œƐg�������グ��ɓ������āA�L�O�̉̏W�Ɂs�����t�Ɩ��t�����B����́A�u���̐l�����k�������j���Ă��ꂽ�܂��̊��l���l�ɂ����₩�ł��S�̂����������̂����肽���Ǝv�����B�������ɂƂ��Ă��A���̐l�����ɂƂ��Ă����U�L�O�ɂȂ���̂��B���̖����̎��������q�ɂ��悤���Ƃ��l�������A�����������قɂ����Ăӂ��킵���v���Ȃ������B�����œ�\��O����ɂ������Z�̂Ō������Ă���l�\����ɔ��̏����q�ɂ����v�i�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�Z�l�y�[�W�j���̂������B���Ս⒆���Ɉʒu���鋛�Վ��̖{���͋��Պϐ�����F�\�\�u���{���͓����ŁA�@�_��l������ɂ����̂������������̂ł���B���`�ʑ������̂��Ƃ��A�E�̎���Ղɋ��̓����̂������A���ɓV�H�߂��g�ւ����㐡����̗����ł���B�������ω��ɂ͎����̗l�ȉ��N�����`�ւ���v�i�s�ř��� �S�t�����s�ř������A1938�N3��31���A��l�Z�Z�y�[�W�k�����͐V���ɉ��߂��l�j�Ƃ��ďЉ��Ă���̂��A�O�f�́u�O�c��̋��Ս�Ƃ����n���ɂƂ��Ă���A�]�]�v�̕��͂ł���i�����������́s�ř��� �S�t���������炽�߂����́j�B��������e�Ղɍl������̂́A�z�q�v�l�����Պω��Ɍ����Ă��Ƃ����ł���B�������g�����̑z���͂͏j���̂��̂ɂ��Ă��܂��قǂɖҖ҂������̂������B���Ս�̋��Վ��̋��Պω��͂��̂܂܂̎p�œo�ꂷ�邱�Ƃ��ł����A�M�������̉��ʂŋ������p����ꂽ�i�g���̑���ɂ��v���邪�A�����ɂ͋��Ս���ӂ̓X�܂̖��ɂ����u�����v�Ƃ����āA�������p�Ƃ���w�E������j�B�M���������w��ɋ�����i���邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�����Ƃ����g���̐V���ȏo�����L�O���鏑���̕W��́A���g�̎��I�o���ƂȂ����s�Õ��t���������i�ߗׂ́j�n������u���Ձv���u�M�������v���u�����v�ƕϓ]���Č��s�̂��̂ƂȂ����B����Łu�Ձv�Ȃ�ʁu���v����v�������Ԃ̂́u�o���̗_��v�Ƃ����̎�����A�u�͗����o�łė������v�Ƃ������ł���B�����͍l�����Ȃ����낤���B�ŏ��̒����ł��鎍�̏W�ɕt�^�̂悤�ɂ��čڂ����a�̂̂ق����A�{���̊�ڂ��������т��D��Ă���ƔF�߂��䂦�́u���v�̈ꕶ�����A�ƁB�����̗��R�ɂ���āA�g���͓�\�̂���̘a�̂�����ɂ܂Ƃ߂�ɍۂ��āi���Ɋ������������Ƃ��Ă��j蜾蠃��ł͂Ȃ��A�����Ƃ���������Ȃ���������Ƃ��č̗p�����̂ł͂Ȃ����B�g���́s�����t�ȍ~�A�{�Ƃ̎���ł͂̂��Ɂs�a���`�t�i1962�j�ɂ܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ�A����܂ł́i�s�Õ��t�ł͐F�Z���A�s�m���t�ł͂�┖���A�����������j�u�P�Ǝ҂̎����v�Ƃł������ׂ����̂�˂����������m�̗̈�ɓ��ݍ���ł����B�u�P�Ǝ҂̎����v�̌��_�ł���ŏ��̒����A��������̍Ę^�E�Ċ��͂�������A�g���̐����Ƒn��A���邢�͐l���ƌ|�p�Ƃ�傫���ς���_�@�ƂȂ����B�t������A�g�������������ĉߋ��̒��q���܂Ƃ߂Ȃ������̂́A���̂Ƃ������߂Ă������B���O�Ō�̒����ƂȂ����s���܂�͂����L�t�i1990�j�͂��̑�|����ȍĉ��ƌ����悤�B�g���͓�\�ΑO��̎��̎n�܂�̌������ɎU����i�������͒��ю��Ƃ����V���Ȕ���W�]���Ă������A�a���������j�B
�k�NjL�l
���Ս�ׂĂ��āA�ӊO�ȂƂ���ŋg���Ƃ̊֘A�����������B���a���j�̒��я����s�a�@��̎��o��̉Ɓt�i�s�쐫����t1975�`1977�N�A�ځB�����s�a�@��̎��o��̉Ɓ\�\���c��k���Ō�̎����t�͊p�쏑�X�A1978�N2�����j�ɂ�������B
�@�k�c�c�l�����Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ������������������Ă��邩�Ƃ����A���ꂩ�炨�b���悤�Ƃ��Ă���A���̐��ɂ������܂��������̕���ƂȂ����A������u���o��̉Ɓv�̂���a�@��Ƃ����̂́A���z�ƎłƂ̋��ڂɂ������Ă��邩��ł���B���̕ӂ͂₽��ɍ�̑����Ƃ���ŁA���܊�̂܂��ɕ���ł���̒n�}���݂Ă��A���Ձm������n��Ƃ��ɎM�q�m�����炲�n��A�����m�߂������n��Ƃ��O���m�����n��A再]�m����������n��B�`�m�O�`�ŗL���ȓ암��m�Ȃ�Ԃ����n��̕ʂ�̓암��Ȃǂ��A�قlj�����ʂƂ���ɂ���炵���B�ق��ɐ��m�����n��A�����m�߂����n��A�V�m����n��A�z�m������n��A�K�m���ʂ��n�ⓙ�X�X�A�����ɂ��Ƃ܂��炸�����A�Ȃ��ɂ͈ÈŁm�����݁n��ȂǂƂ��������Ȗ��O�̍������B
�@�������ꂩ�炨�b���悤�Ƃ��Ă�����̍�͋��Ս�̂������ɂ���A�k�c�c�l�i�s�a�@��̎��o��̉Ɓi��j�k�p�앶�Ɂl�t�p�쏑�X�A1978�N12��20���k���ŘZ�ŁF2005�N6��15���l�A��Z�y�[�W�j
1979�N�A�s�a�@��̎��o��̉Ɓt�͎s����ē�i�Ƃ��ĉf�扻���ꂽ�B���̋r�{����|�����̂��v���q���i�s��̃y���l�[���j�ƁA�g���̐��Ԃ��Ȃ�����̗F�l�����^��i�o�ŎЂł̓����ł���A�g�����s�V�v���t�k��14���l�ɗU�������w�N�j�Ɠ��������̐l���Ȃ̂ł���B�r�{�Ɠ����^�玁��2002�N��81�ŖS���Ȃ��Ă��āi�g�����ӂ��N�����j�A������`����L���Ɂu�T���P�C�X�|�[�c�L�Ҏ��ォ��r�{����|���A�e���r�h���}��f��ɕ��L�������B��\��Ɏs����ē̉f��u�א�v�u���_�Ƃ̈ꑰ�v�A�e���r���㌀�V���[�Y�u�،͂��䎟�Y�v�Ȃǁv�i�����j���[�X�j�Ƃ���B�g���͏����Ǝu�]�����������ɂ����G��Ă��Ȃ����A���̋r�{�Ƃ͔N��炢���Ă��g���̗F�l�����^��ƌ��č����x���Ȃ��Ǝv����B�����́s�a�@��̎��o��̉Ɓt�r�{���ɂ������ĉ��a�̌����ǂ�ł���킯������A��f���̋��Ս�̂����肩��g���i�̏Z�܂��j��z�������ׂ����Ƃ��낤�B
��2012�N10������ ���k������̂���́s�����V���f �W�^���t�̋L���́A�������W�s���l�̋�t�A���W�s�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́t�i�������܁j�A�s�k�����H�m�[�g�t�i����܁j�A���я����s�ÎE�S���l�t �i�h�D�}�S���w�܁j�A���W�s�A�����J�t�i�ǔ����w�܁E���̕��w�ُ܁j�Ƒ�\�I�Ȓ���������Ă����B�����ɂ�1956�N�u���l�̑剪�M�����ƃV�������A�� �X��������𗧂��グ���B�剪����̂ق��A������s�A�g������̎��l�ƂƂ���59�N�Ɏ����u�k�i��Ɂj�v��n�������v�A�u�����Y��e���O�Y�Ȃǂ̎� �l�_���������v�Ƃ������B���͔ѓ��̑S�����ǂ�ł���킯�ł͂Ȃ��i�g���͑���ꂽ�{�͂��ׂēǂ�ł���͂��ŁA�s���㎍�ǖ{�t�̌��G�ʐ^���ς�ƁA�� ��̏��I�̈ꓙ�n�ɂ͎����ƂƂ��ɔѓ���剪�M�̎��W������ł���j�A���W�Ǝ��l�_�͂���Ȃ�ɓǂ�ł��邪�A�s�k�����H�m�[�g�t�Ɓs�ÎE�S���l�t�͖��� �������B�����̒������|����ɂ��āA�g�����Ɣѓ��k��̂��Ƃ��l���Ă݂����B
�s�k�����H�m�[�g�t�i���X�A1978�N4��30���j�͋g���́s��ʁt�a���̌_�@�i�̂ЂƂj�ɂȂ����ƍl������B�ѓ��́u���H��
�����Ɠǂ܂�
��ׂ��ł���B�����Ēm����ׂ��ł���B�����͔��H�̖��݂̂�m���Ă��āA���H���̐l�ɖ��m�̂܂܂Ȃ̂��v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�Ƃ����q���Ƃ�
���r�̈�߂́A��N�̂��딒�H�Z�̂ɖ�����ꂽ�g���ɂƂ��Ă�����̈�j�������ɈႢ�Ȃ��B�u���Ƃ��{���͓���I�ȏ��ł���A�܂����H�̈�ʂ����Ǒ̌�
���Ă��Ȃ��B���H�͂����Ƃ����ƂӂƂ���̐[�����l���Ƃ������Ƃ����ЂƂ������Ă��������B�w�@��x�̔��H�A�w�v�Џo�x�̔��H�A�w�˂̉ԁx�̔��H�ɂ�
�Ă��܂�ɂ��ڂ��͌��Ȃ������B�ނ��낻�̑��̔��H�\�\�w���̐����x��w���̗��x��w�t���b�v�E�g���b�v�x�̔��H���Љ�����������炾�v�i���O�j�Ƃ�
���Ⴂ���l��̐l�Ɍ��������b�Z�[�W�́A��������g���ɓ͂����B���͎��̂悤�ȍs���ɒ��ڂ����B�Ȃ��A�{���ō֓��g�ւ̌��y�������̂́A�p�쏑�X��
�s�Z�́t���ɘA�ځi1977�N1���`12���j�����Ƃ��̃^�C�g�����q���H�Ɩg�����߂ār���������Ƃɂ�邾�낤�B
���H�̂������҂낰�̎U���͂�������ǂނ̂ɒ�R���Ȃ��A�X�s�[�h�������ēǂ߂邪�A�g�̎U���͓ǂނ̂Ɏ��Ԃ��� ����B������ �^�ӂ͂ǂ��ɂ���̂��ƁA�^���Ȃ��炩������Ă��镔���܂œǂ݂Ƃ�Ȃ���Ǝv���ǂ܂�������B�g�̎U���́A�������������Ă���B���̂Ƃ����H �͂������҂낰���Ƃ܂��������Ƃ��ł���B�ʂ��Ă������҂낰�Ƃ͂������Ă��邱�Ƃ̕ʂ̗l�Ԃł͂Ȃ����A�Ƃ̋^�₪�N���Ă���قǂɂł���B�i�q�g�� ���H�_�r�A��O��`��l�Z�y�[�W�j
�@���́u�ē����v�͑吳���N�i�����N�j������{�͖`���̃p�E���E�N���[�́u�q�������錾�v�Ɠ����N�̎��M�ł���B�~�����w���ł́u�R�m�m�u���E�G ���C�^�[�n�v�̉^���͂͂��܂������肾�������A�p���ł̓A�|���l�[�������W�w�A���R�[���x���o�����Ƃ��Ă����B��\���I�̎�������Â����ƌ�����w�A ���R�[���x�͈���O�N�̊��s������A�w�Ԍ��x�A�w�˂̉ԁx�Ɠ��N�̊��s�Ƃ������ƂɂȂ�B�����Y�͐_�o�ǂɔY�݁A�w���ɖi����x�̎����������Ă� ���B�Ƃ��������̐��N�͂���߂ďd�v�ł���B���[���b�p����{�̋ߑ㎍�ɂƂ��Ă��A�ߑ�Z�̂ɂƂ��Ă��B�Ђ���Ƃ��Ă��̐��N����������ł���B�i�q�g �́u�ē����v�Ȃǁr�A��Z��`�ꎵ�Z�y�[�W�j
�@�ڂ��͐����鋅���Ȃǂƌ��������A���H�ɂȂ���āu�ʁv�ƌ����ׂ���������Ȃ��B�u�����j�́v�̌��т̈�s�́A�u�ʂ̌��p�͂������ĉ_�������ɒe���v �Ƃ����̂ł������B���́u�ʁv�Ƃ́u�C�i�ƍ��C�Ɨ����̐��X�v�ƌ��������Ă��悢�̂��낤�i���H�͋ʁm�A�n�A�w�X���x�̍Y�͎���j�ꂽ�� �m�A�A�A�A�A�A�n�ł������ƌ����ׂ����j�B�����������A�u�C�i�ƍ��C�Ɨ����̐��X�v�̉��Ǝ����ɍ���Ȃ��Ƃ��낤�i�Y����x�A�K�R�I�ɂ��j���Ă��܂� ���̂��j�B�������v�������͎U���̍s�����ɂ܂��܂��߂��Ȃ�A�����Ǝ��̋��E�̒肩�ł͂Ȃ��Ȃ����A�����錻�㎍��ǂނƂ����A�m�炸�m�炸�A�� ���ɈӖ��Ǝ咣�ƕ`�ʂ��ł͂Ȃ��A��͂�u�C�i�ƍ��C�Ɨ����̐��X�v�����߂Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�i�q�w���O�̖x�r�A�O�Z��`�O�Z�O�y�[�W�j
��m�b�ƌ����邩������Ȃ����A�g���̐��z�q�������܁r�̖`���u��ʁ\�\���낢��̍����E����ꂽ�܂ɁA�Ҋ���䈂̑��Ԃ�����A
�ܐF�̎�����
�炷�A���̖������B���ꂪ�{���̖�ʂ̂������炵���̂ł����A���݂ł́A�i������J�X�j���ȂǂɎg���Ă��܂��B�u���C�v�Ɓu���C�v���Ƃ����߂��A����
�Ȃ�u�ʁv�����̂������u���`�̐��E�v���A���W�w��ʁx�Ȃ̂ł��B�^���̂悤�ȕ��͂��A���͏����p�̃J�[�h�Ɉ�����āA�o��������̎��W�ɓY���A�e����
�l�����ɑ������B���N�̔ӏH�̂��Ƃł���B�^�\�\���Ƃ��܁A�����܁A���炽�܁A������������ȌÌ�̂Ђт����A���͍D�����B�����ɗގ����āA���܂�
�u���́v�̃C���[�W�����u�������܁v�����ɁA��т̎����������B���̎����łɁA�V�������W�̑薼�͌����������R�ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����
�Łl�t�}�����[�A1988�A���܃y�[�W�j�Ƃ����ӏ��ȂǁA�ѓ��́q�w���O�̖x�r�̈�߂ւ̕ԓ��ɓǂ߂�B�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�Łq������
�܁r�̎��Ɂq���H���߂���f�́r���u����Ă���̂��Ӗ��[���ł���B
�s�k�����H�m�[�g�t����́A�̏W�s���̗��t�i�A���X�A1921�j�́q�变�r�Ɂu�����猩�Ă��Ɨ��̏��|�тɂ͑N�ΐF�̓��������肻�悢�ł��B�u�̏���
�͐䂪���āA������̑��ނ�ɂ����䂪�������Ă��v�Ƃ���Ƌ�����ꂽ�i�����A���O�y�[�W�j�B�g�����̎��Ɣł̔��s���u����Ɂv�i�Z���͓����̎�
��ł���j�̓\�E�Z���V���Ɠǂނ��A���́q�变�r����q���g���̂�������Ȃ��B�ق��ɂ��q�g�́u�h�i�E�����s�v�Ȃǁr�ł̓I�N�^�r�I�E�p�X��
Renga�i�A�́j�Ɍ��y����ȂǁA�����ł̔ѓ��̖��ӎ��Ɓs�Ẳ��t�Ƃ������ɂ̈��p���т̊�����̋g���́A�����Ă����Ζ͍��ɂ�����S���G�ꂠ��
���B���ꂪ�{���̊��s���ꂽ1970�N�㖖����s��ʁt�̏��т������ꂽ1980�N�㏉�߂ɂ����Ă̂��Ƃ������B�ѓ����g�́s�k�����H�m�[�g�t�������͔�
�H��i�Ɓs��ʁt���֘A�Â������͂��₵�Ă��Ȃ��悤�����i���j�A
���ɂ͖{�����u����g�����v����������d�v�ȗv�f�̂ЂƂł���A�ł��傫�Ȍ_�@�������Ɗ�������B
�i���j�ѓ��́q���䗲�Ƃ̉������ȁr �i�s��^�_���t���}�ЁA1991�N12��10���j���@ �������������ɐV�����^�͂��������ɏo������̂����m��܂���B���䂳��̕ԐM��ǂ�ŁA�����ɘA�z�����̂́A�g�����̐��N�O�̎��W�w��ʁx�̂��Ƃ� �����B���̎��W�͐��������āA���N�̋g�����̎��̎x���҂ł���ǎ҂ł���킽���ɂ��A�Ƃ����ɂ����Ƃ���̂����i�Q�ɂ݂��Ă��܂����B�ǂ����w�T�t�� ���E�݁x��w�Ẳ��x�܂ł̋g������̎��Ƃ͂������̂ł��B���܂ɂȂ��Ďv���ɁA����͋g������̕K���̐V�����u�^�v�̑n�o�ł����āA���́u�^�v�ɂ����� �肷��Ȃ�Ƃ͓���߂Ȃ������̂ł��B
�@���́w��ʁx�́u�^�v�́A���̌��ɁA���L�V�R�̌��㎍�l�A�I�N�^�r�I�E�p�X�̒����w���x�̃X�^�C�������������A�Ƒz������܂��B���̑��ɂ����́w��ʁx �̌^�̌��^�͂���ł��傤�B�����ċg�������܂��Ⴂ�풆�̎���Ɉ��ǂ����Ƃ����A�g�k���ђ������H�Ƃ���ׂ����H�l�̒Z�̂́u�^�v���A�ǂ����Ńv���g�^ �C�v�Ƃ��ē����Ă��邩���m��܂���B�i�����A�O�`�l�y�[�W�j�ƁA �����s��ʁt�ɂȂ��߂Ȃ������Ɩ������Ă���B���̎��W���o�����������A�����Ȃɂ��r�Q���Ȃ����̂��ڂ̑O�ɂ��邱�Ƃ͂킩���Ă��A���ꂪ�ǂ��������̂� ���܂��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B��������́A���^�Ƃ������A��b�̖ʂ��傾�����B���^�͂��̌�A�ȉ��ł������������邪�A���܂��Ɍ�b�̗R���ė��� ���i�T���̈ӂł͂Ȃ��j�𗝉��������Ƃ͌�����B
�ߓ��A���я����s�ÎE�S���l�t�i�w�K�����ЁA1996�N10��30���j����肵�悤�ƃC���^�[�l�b�g�ŌÏ������������Ƃ���A��������Ɉ�
�Ă������{�i������͎s�̖{�ɐ�삯��1996�N2��25���A500������Ŏ��ƔłƂ��Ċ��s���ꂽ���́j�����₫���X����3000�~�ŏo�i����Ă����B
�O��A��������ɂ��ď�������O������A����������낤�ƍw�������B
�@��㔪��N�Z���@�M�Z��̂��₩�ɋȂ��邠����
�@���\���Ől�ԗ��ꂵ�悤�Ƃ����l�̐l��
�@������ɓd���ł���������
�@�V�l�͏��a�̃��_�j�Y���̕��w���\����l��������
�@�a�@�̂���y�n�͉͈�p�V���̒����˂̗גn�ł�������
�@���̋����{�̂̒��̎���ŁA�p�V���͒����������Ƃ���Q�菑�����o���A�y���̏h�сm�������n���܂�̓�\�O�̌R�Ċ⑺����Y�ɋ��܂�āA���� �m���ƔŁF�킢���w���ŁF��[���J���n���~�ނȂ��ƌ��ӂ��Ă���
�@�S�R�E�M�T�}�Ƃ����͎̂q������ɕ��A�ꂩ�畷�����ˎ�̖��ł����Ă����̂��A����Ƃ��A�Ђ���Ƃ��Ă���͑���V�m�����������n�A�������̂��i�����A �l�Z�`�l��y�[�W�j
�ѓ��͌ŗL����������Ă��邪�A���́u�l�v�͐��e���O�Y���B�����ł��炭�s�ÎE�S���l�t���痣��āA�s�c���Ɉِ_����\�\���e���O�Y �̎��t�i�W�p �ЁA1979�N7��10���j���ēǂ���B���Ȃ݂ɁA���ƔŁs�ÎE�S���l�t�̃W���P�b�g�́u���_�̊�i�H�j�̊G�͐V��������J�ɐ����������O�c�̎��l�i�E�m �ɂ��i��㎵�Z�N�j�v�i���ƔŁA�k���O�y�[�W�l�j�ł���B
�@���e���̂���܂ł̎���i�������łȂ������Ƃ͌����Č������Ƃ��ł��Ȃ����A���́u�ŏI�u�`�v�Ƃ����������́A�� ��߂ď����I �ł���B���������I�\���������Ă���Ƃ������Ƃ��B�����č����̏����̑������A�����̕����̂܂��荇���������̏�ΏۂƂ��Ă���Ƃ܂����������Ώۂ� ����ɂ���B���̑Ώۂ𐼘e���̎��̕��̂ő����Ă���A�Ƃ�����肻�̑Ώۂ̂����������͏㉺���E�ɁA���݂ɋ삯�ʂ��Ă���悤�Ɍ�����B
�@�����͔ۉ��Ȃ����̎G��A�G�������̂Ȃ���ʉ߂��Đ����Ă���̂ł��邪�A���̂��Ƃ������ߖʂ��Ċ������A�S�Q����̂łȂ��A�]�̂Ƃ܂ł͍s���� ���Ƃ��A���̏�Ԃ��A���ẴA�|���l�[���̒����u�n�сm�]�[���n�v�̂悤�ɂ������������̂��A���̐��e���́u�ŏI�u�`�v�ł���Ƃ��Ă����B�Â����m�Ɠ� �{��m�鎁�́A���̓����̎G�핶�������̂��݁A�������~悂����o���Ă��邩�̂悤�ł���B�i�s�c���Ɉِ_����t�A���܃y�[�W�j
15�N��ɏ������ƂɂȂ鎩�g�̒��я�����\�����Ă͂��܂����B�s�ÎE�S���l�t�͔ѓ��k��̒Ǔ����W��g�s���㎍�蒟�t2014�N
2�����ł��A
�g�c�����E�k�쓧�E�g�������E���r����炪�����]�����Ă���B����������A�����^��Y�̂悤�Ɂu�����������v�������͒������h�����ƌĂԈӐ}���悭�킩��
�Ȃ��B���́A200�N�O�̃t�����X�Ɩ����̓��{���ÎE�Ƃ����ϓ_�Ő茋���قȌ`���̗��j�����Ƃ��ēǂB�����Ɍ��炸�A�U���ɂ�����ѓ��̖z����
�����Ԃ�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��i�s�k�����H�m�[�g�t�������������j�B���������u����v��{��ɂ�������͓̂�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�����������
���̏����͋g�����̈��D����Ƃ���ł��������B���{�Βj���s��
����[�܂�����]�Ƃ̐l�X�t�i�����ɁA1975�j������A�t�����E�I�u���C�G���i�����j�́s��O�̌x���t�i�}�����[�A
1973�j������B�]�k�Ȃ���A�ѓ����{��������������͓����̏o�g�����A���e����Â������B�g���������ɖ₤�B
�g���@ �������͂ǂ��ł����A�o�g�́B
�����@����A�ڂ��͉� �Â��ƌ����ė������A�C���`�L�ł���B���܂ł��A���k���ƐM���Ă�F�l������炵���ł��ˁB���܂�͓����Ȃ�ł��B�킽���͖ڔ��̋߂��B
�g���@��������A������ ��B�ڂ��́A�������l���Ǝv���Ă��B
�����@�C���`�L���D���� ����ˁB��Õق��q���̍��Ɋo���Ă����Ŏg�����肷���ł���B���x�A���Ђ����_���������Ƃ��ɋ����ň�����ƃo�����܂�������ǂ��ˁB�����Ȃ�ł� ��B������͖̂L�ʌS�ƌ����Ă�����ł��ˁB�����{�c�c�{�̒��ł��s�O�Ȃ�ł���B
�g���@��������̑ォ�� �ł����B
�����@ �e���͉�Â̐l�Ԃł��B���ꂪ�]�˕��w�Ȃ̂ɔ��Ց����_�Ȃ�ł���B������A�q���̂Ƃ��ɂ͑��܂͂͂����ĖႦ�Ȃ����ˁB�u���Ց��̎q�����ȂI�v�Ȃ� ���I�@���Ă��������āA�~�����̂ɑ��܂��͂��Ȃ������k���l��ˁB���������X�p���^���炾���Ȃ��ɂ���܂�����B�����Ďq���̂Ƃ�����e���̐��Ƃ� ���������Ă��܂�������A��ẤB����Ő����ς�����肷��Ɖ�ÕقŃC���`�L�V�т�����ł���B�i�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g������ �k���k��l�q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�A�s�Z�́t1975�N2�����A���Z�y�[�W�j
�s�ÎE�S���l�t�ɂ́A��{���n�E�����T���Y���ÎE�����Ƃ���鍲�X�ؑ��O�Y�i��Ô˂̊��{�j���o�ꂷ��B80�y�[�W�i�u���X�ؑ��O�Y��
��Ôˎm�A��
�X�،����m����ς��n�̎O�j�Ƃ��Đ��܂�A���Z�́A�̂���Ô˗p�l�ƂȂ������{���m�Ă��났�����n�E�q��ł���B�v�j����84�y�[�W�i�u���O�Y�͌����g
�̗^���ƂȂ���������A���̉̉�ɏo�Ȃ���悤�ɂȂ����B���O�Y�͂����̉̉�̈�ŁA�F���̋��s���狏�����߂锪�c�m�I�m�͂��Ƃ��̂�n�Ɖ�A
�̐l�Ƃ��Ēm���锪�c�Ɛe�����Ȃ����B�v�j�ɂ����āA�s��8�ӏ��A���X�ؑ��O�Y�̎��тɐG�ꂽ�{���̉����ɉ��M�Ł��L������Ă���B�{���ɏ�������
������̂͂��������ŁA�����҉�������̍��X�ؑ��O�Y�ւ̊S�̐[�����F�߂���B
��ˎ闝�ɂ��A�g�����͎��g�́s���[���h���b�v�t�Ɠ����N�Ɋ��s���ꂽ�ѓ��k��̎��W�s���̊쌀�m�R���f�B�n�t�i�v���ЁA1988�j�������]�����Ă�
���i�q�g�����G�b�Z�C�I��Ҏ[���āB�r�Q
�Ɓj�B�Ȃ�s�ÎE�S���l�t�i���o�́s�O�c���{�t1994�N8���E�ċG���`95�N5���E�t�G���j�ɂ͂ǂ�Ȋ��z�����������낤�B�ѓ��̍ō��̏������Ɛ�]
������������Ȃ��B���Ȃ�������������Ȃ��B�\�z�����Ȃ��̂��B���ꂪ�ǂ��ł���A�ѓ��͋g���������Ȃ肹�ΕK����{���̑����𗊂ɈႢ�Ȃ��i�w�K
�����Ђ̕��y�ł̑����͋e�n�M�`�ŁA�s��^�_���t���e�n�̑����j�B���̂Ƃ��A���ƔŁs�ÎE�S���l�t�͂ǂ�ȑ�����g�ɂ܂Ƃ������B���Ɣłɑ����̃N���W�b
�g�͂Ȃ����A���җ����≜�t�̑g�ݕ�������A�݂������[�i�ѓ��̍ł��e�����o�ŎЂł���j�̐���ɂȂ邱�Ƃ͖��炩���B������ɂ��Ă��A�g�������e�̊G
���x�^�̒n�ɔ��k�L���]���Ďg�����Ƃ͌����ĂȂ����낤�B
����A�ѓ��k��̒����ǂݕԂ��āA�s��^�_���t���g�����Ǔ����W���������Ƃ��ĔF�������B�ѓ��ɂƂ��ās��ʁt���Ռ��I�Ȏ��W������
���Ƃ����Ȃ�
�킩��B�g���͔ѓ����s�k�����H�m�[�g�t�œ������{�[�����݂��Ƃɑł��Ԃ����̂��B�ѓ��k��́s�����V���t�Ɋ��Ǔ����q�g�����̎��r�i�`���ɉ������
�Ƃ̓d�b�ł̂��Ƃ肪�o�ꂷ��j�ŋg�����u���{�̐��ő�̎��I�˔\�������v�i�s��^�_���t�A��ꔪ�y�[�W�j�Əܗg���Ă���B�g�����������̂́A��
�̔ѓ��k��́u���I�˔\�v�������B

�ѓ��k��s�ÎE�S���l�t�i���ƔŁA1996�N2��25���j�̉�������ւ̌���E��������{��
�ƃW���P�b�g�k���{�E�����̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�݂������[�̐��삩�B����500���A�W���P�b�g�G�F���e���O�Y�l
���x�O���́s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t91���i2013�N10���j�́A�\���Ɂu�i�c�k�߁@����C���@�y���F�v��搂��Ă��āA�ژ^�f�ڂ̃��m�N���̎ʐ^�ł��M�d�ł���B���͂��˂ċg��������芪���O��C�������l�̐��e���O�Y�A�o�l�̉i�c�k�߁A�����Ƃ̓y���F�̎O�l�ƌ��Ă�������A����͒ʏ�̖ژ^�Ƃ͈Ӗ��������Ⴄ�B�u�i�c�k�߁@����C���@�y���F�v��2012�N5���ɖS���Ȃ���������������̏����������B����炪�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�̏����Ɛ������d�Ȃ��Ă���̂͋����قǂŁA���̂����������w�E���Ȃ����A�����́s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t���T�ς��Ă݂����i�����̉��s�ӏ��́^�ŕ\�������j�B

�s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t91���i2013�N10���j�̕\��
����C��
�@�i1686�j�^����C���̎��I����1927-1937�@42,000�^�v���Ё@��42�@����1500���@���t�^�r�j�[���J�o�[�t�@����������ѕM�������^�ʎ��Y���E���e���{�t
�@�i1692�j�O���O�b�@105,000�^����C���@��47�@����55���@��������@�ܕt�^����������ѕM������
�@�i1688�j��Ƃ̒��ق̕����@31,500�^����C���@��44�@���@�݂������[�@���ѕt�^����������������^���̌��p���t�B�����ɂ�������B
������^�y���F�����W
�@(2199)�^945,000�^�A�X�x�X�g�ف@����50���@��43�^38�~56cm�ꖇ�������莆�ɂ�関�Ԃ̎���W�B���l�ɑΉ����č�Ƃ��I���W�i����i������(10��)�B�ʗt�ɉ��t�A���B�z���v�w���B�ی�p�O��(�_���{�[���E��ⳕt)�ۑ���Ԃ͗ǍD�B�ڍז{���Q�ƁB
�@2199�@����܁i�y���F�����W�j�@����50���@��d���@�@�@�@�@�@�@�A�X�x�X�g�ٕҁ@��43�@945,000�^38�~56cm�ꖇ�������莆�ɂ�関�Ԃ̎���W�B�ڎ��i�A���������E�y���F�A�ѓ��k��A�r�c�����v�A��������A���[�����A�a�F�A����C���A�c������A�����ĔV�A�����G�A�쒆�����A�O�ؕx�Y�A�O�D�L��Y�A�g�����j�B���l�ɑΉ����č�Ƃ̃I���W�i����i������i10���j�B���t�A�����t���B�z���v�w���B�ی�p�O���i�_���{�[���E��ⳕt�j�ۑ���Ԃ͗ǍD�B�ʐ^8�ŎQ��
�i�c�k��
�@�i3372�j�����@31,500�^�i�c�k�߁@��44�@����70���@���t�J�o�[�t�^�ѕM�������@�G�Ɣo�嗎���̘a���\���^������������M���A�t
�@�i3356�j�i�c�k�ߏ��z�@31,500�^�_���{�[�����̔��ɖѕM�ɂĕ\��A����������������B
�ȏ�͒��҂����������֑���ꂽ�����{�������g������Ɋւ�������������A�ق��ɂ������́s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t�̎ʐ^�Ńy�[�W�ɂ́s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�������͋g���̖����̕��́i���z����L�j�ɓo�ꂷ��{�������B���ڂ������悤�B
�@�����ԔV��s���ߐ���t
�@����C���s���ƍ��Ɓk�����{�l�t
�@�s�n���̏ё��t
�@�g��O�s�����k���Łl�t
�@�x�V�ԉ��j�s�V�̘T�k��������Łl�t
�@�܊}���H�s�՚��L�t
�@�����d�M�s���ݗ́t
�@�u�����s�������z�t
�ȉ��͖ژ^�̖{���y�[�W�f�ڂ̋g���̒����B
�@844�@�T�t�����E���@�ЎR�������@�����J�o�с@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����@��51�@�@18,900�^�u�T�t�����E�k�݁l�v��p����Ⳃɉ���������������B
�@845�@����@����40���{�B�@��d�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����@��61�@�@147,000�^����R�c���B�w�͏����̊v���B�\�����͔������F�̎���z���B�{�����t�a���B�����̘a���ɖѕM���O�s�������u�����̌������͍g�t�Â鉩���̏H�@�g�����v�B�z�������A�ی�p�O���t�B�ɔ�
�@846�@���[���h���b�v�@�@���e���O�Y�}��@�����J�o�с@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����@��63�@�@21,000�^�u���[���h���b�v�v��p����Ⳃɉ���������ѕM�������B
�@847�@���܂�͂����L�@���ƔŌ���S���@�J�o�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����@��2�@�@�@21,000�^�u�ʖؓ��Ō���S���v�̓\���t�B�s�Ŗ{�Ɠ����ꂾ���{�������قȂ���݂����B�ۑ��ǍD�B
��������������̓����Ă��Ȃ�845�s��ʁt��847�s���܂�͂����L�t������Ɉ��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ����̂��A�g���̓����ł����łɂ͏����⎍��̈�߂�������邱�Ƃ͂����Ă��A���悪�L����邱�Ƃ͂܂��Ȃ����炾�B����845�́A�g�����Ə����̒��Җ{�Ɍ��悪�Ȃ��͓̂��R�����A�Ï��œ��肵���苖�̈�{�ɂ�����͂Ȃ��A�����g�����璸�Ղ����B��̖{�ł���847�i�s���܂�͂����L�k�ʖؓ��Łl�t�j������ⳂɃ}�[�L���O�y���Łu��v�����ď��������邾���ŁA����͂Ȃ������B���āA����قnj�F�W��Ǐ��X�������Ă���ɂ�������炸�A�g�����Ɖ�������̍�i�͂����Ԃ�Ɗu�����Ă���Ɗ�������B������ЂƂ��ƂŌ����͓̂�����A�q����f�́r�́u�����͂��߂āA����������������{�́A���a�l�\�N�̏t�ɏo���w�I���́x�ł������B�k�c�c�l�������W�w�I���́x�ɂ́A��т̍�i�����߂��Ă���B��������܂��o�~���̌�@���������A��̈���o�Ă��Ȃ��ƁA���͐����ȂƂ���v�����B���̂Ȃ��Łu�S����_���_�v�͎��ܒ��ŁA�r���グ�Ă���̂ɁA�ނ���S�䂩�ꂽ�B��z�̐⏥�ł���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�y�[�W�j�������悤�ɁA�g���͈���̕��Ƃ̎����������܂ł��o��ɂ������ƌ��Ă����悤���B�g�����o�������������̍ŏ��̒�����������W�s��铊��S�t�i�o��]�_�ЁA1959�j���������Ƃ��傫�������Ǝv���邪�A�q����f�́r�̍Ō�̒f�́u����ЂƂv�̑S���́u���̈��D����A����o��𐔂���������A���肪�Ȃ��B�����сu���Ӂv�S�O�\��s���A���̈�͋���A���o����ɂƂǂ߂�B�^�^��Ԃ̎��̒߂𗧂�����v�i���O�A�O�O��y�[�W�j�ł���B�q����f�́r�̔��\�����s�o�匤���t���������Ƃ����������Ă��A����̎��т����o����Ă����Ƃ����T�ɂȂ낤�B�g���̍�i���u�o��̂悤�Ȏ��v���Ƃ���A����̍�i�͂������߁u��s���̂悤�Ȕo��v���B�g�������O�q�o��̑�\�ƌ��Ă����̂́A�x�V�ԉ��j�ł������d�M�ł��Ȃ��A��������������悤�Ɏv���B
��
�����r�Y�s�F�B�̍����\�\�����r�Y��Friends Index�t�i�}�K�W���n�E�X�A1993�N9��22���j�́q��������̊��r�͔j�i�̈���]�ł���B�����͓������u�Â��A���o�������Ă���ƁA�V�ђ��ԑ吨�Ŏʂ����ʐ^�̒��ɁA���Ȃ炸�Ƃ����Ă����قLj�a���̂����l������B�V�ђ��Ԃ�F�B�Ƃ����Ȃ�A�ނ̂��Ƃ͔��F�B�Ƃł��Ăׂ����̂��낤���v�Ǝn�߂āA���́u���v�́u�P�ɏ��ɓI�Ȕے莫�ł͂Ȃ��A�ϋɓI�Ȍ`�e���̈�ʂ����v�Ƒ[�肵�A���F�B�̕M���ɉ�������������Ă���B�u�^�̔��F�B���F�B�ɂȂ邱�Ƃ͂��͂��肦�Ȃ��B����͓����Ɛ�V�I�ɑ����������̂ł����āA���̑����̈�������͂ǂ�ȗ����������Ă��Ă�������Ƃ��Ȃ����������̂炵���v�i�����A�O��l�`�O��܃y�[�W�j�Ƃ���B�����̈����u�F�B�v�i������z�N����j�̂��Ƃ����������͂����ɁA�Ȃ܂��v��ƃj���A���X�����������Ă��܂��B���̋����[���l���]�̑S���i5�y�[�W���j�����Гǂ�ł������������Ƃ��肢���A���̉ӏ������p�������B
�@����Ȃ��Ɓk���e���O�Y�̍u����ŁA���e�ɒj�Ə��ł͂ǂ������D�������₵���l�Ԃ�����������Ə��߂Ēm�������Ɓl���������ǂ�قnjゾ�낤���A�����̐��̖ؑ��m�ق̉��Ƃ�������L�Ŗ쒆�������N���̌W�̃I�[�v�j���O������A�����ł͂��߂ĉ�������ɏЉ�ꂽ�B�Љ�҂��F�V���F����ł͂Ȃ������낤���B�ق��Ɍ��J�k�K�M�l����┒�������������̂������Ă���B�I�[�v�j���O�̌�A�^�N�V�[�ɕ��悵�ē�Ɍ��������B
�@�ڂ����F�V����v�w�ƕ��сA�O�̉^�]�Ȃׂ̗ɂ͒j�̎q��A�ꂽ������������B�A���R�[���������Ă����Ԃ�n�C�ɂȂ��Ă����ڂ��͉��Ƃ������Ƃ��Ȃ��u�������������ĕςȐl�ł��ˁv�Ƃ������B�ڂ��Ƃ��Ắu�ς�����ʔ����l�ł��ˁv�قǂ̂���ł������̂����A�F�V����Ɂu�n�n�n�ςȐl���B���͂��݂̑O�ɏ���Ă���l�͉����N�̉�����v�Ƃ����āA�}�Ƀo�c�������Ȃ��Ėق肱�B
�@���̂��Ƃ��`������̂��ǂ����A���̌�u��������Ɖ����������̂ł����v�Ƃ����Ε����悤�ɂȂ����B�������ڂ��̂��Ƃ����Ƃ��ƂɂЂǂ��l��A�Ƃ����̂��B�ڂ��Ƃ��Ă͔��M���^���������A�V�h�ڂ̃o�[�E�i�W�����̑��ŏo����сA�ڂɌ����ĕs�@���ɂȂ�̂ɉ��x���o�H�킵�A�Ȃ�قǒ����D���Ȃ��Ƃ͂����������Ƃ������̂��A�Ɛl�ԐS�����w�K����v���������B
�@���̂����u�Ȃ������ȂɌ��e�𗊂ނB����ȉ���Ȃ��z�ɏ�������ȁv�Ƃ����Ă���Ƃ����b���A�ҏW�҂��畷���悤�ɂȂ����B�ڂ��̂��Ƃ������Ŕl��̂͂�����J���X�̏���Ƃ����z�ŁA�ڂ�������������؍����ł͂Ȃ��A�������A���e�𗊂ނȂƂ����̂͐����W�Q�ł͂Ȃ����A�Ɩk�C����������̊֓��ɋA�Z��������̘h���ɒj����ɂ����������Ƃ�����B
�@��������Ƃ��ڂ��Ƃ��e�����h��������Ă����ɂ́u����̓C�N���̎��i����B�����͓Ɛ�~����������Ȃ��v�B�����Ă݂�Ή�������Ƃڂ��͌��e���˗������G�����d�Ȃ��Ă���B����ȑO�Ɍ�F�W�����ʂ��Ă���B����ɘh�������������A�F�V����A�g��������A��_���䂳��R�肾�B�������A�t�������̗��j�͉�������̂ق����Â��B��������Ƃ��Ă͓c�Ɏ҂̂��ꂱ���ςȎ�m�Ɋ��肱�܂ꂽ������������Ȃ��B�i�����A�O��܁`�O��Z�y�[�W�j
����Ɂu�{�i���F�N�̏Љ�ʼni�c�k�߂�����Ђ�ς�ɖK�˂�悤�ɂȂ��āA��������̕s�����͂���ɑ������悤���v�i�����A�O�y�[�W�j�Ƃ���_�˂̉i�c�k�߂�������A�g���E�����E�����O�l�̊S���قڋ��ʂ��Ă��邱�Ƃ��킩��B���Ȃ킿�A���e���O�Y�E����C���E�y���F�E�i�c�k�߁A�h���ɒj�E�F�V���F�E��_����ł���i�������s�F�B�̍����t�ɑ���C���̊��͂Ȃ��j�B����ɂ��Ă������r�Y�́q�g��������76�̎���r�Ɓq�ӏ܁r�Ɋr�ׂ��Ƃ��A��������̋g�����_�i�l���E��i�Ƃ��Ɂj�ɂ���Ƃ���������ׂ����̂��Ȃ��̂́A�Ȃɂ䂦���낤���B�g���́q�o��\�\��������r�q����f�́r�Ɠ�т̐��z���₵�Ă���Ƃ����̂ɁB�����ɋg����Ǔ����镶�͂��Ȃ��������܂��ɁA�l�ԐS���ɕs�ē��Ȏ҂͂��������Ђ˂���肾�B
�k2020�N5��31���NjL�l
�ً}���Ԑ錾��������5�����{�A���}�����ނ��玍�сq���������̎v���o�A�ł͂Ȃ��r���f�ڂ����s����c�w��t�i1241���j�Ղ����B�ߔN�A���}������̎��ɑ���������g�����ւ̌��y�^�g��������̈��p���܂ސV��ł���B���z��F�߂����[���ɁA�����́u��i�ȊO�ł́q����c�̎��l�r�������ւ��[�����̂ł����B���̎��l���A���̎��l������c�\�\�Ƃ������������܂����B���܋g�����Ɖ�������̂��ƂׂĂ���̂ł����A����͏o�Ă��܂���ˁi�����Ƃ����̖{�Ƃ́A�o��ł����j�B�v�Ə������Ƃ���A�u�����搶�]���搶���ҏW���Ă������́u����c���w�v�P�X�X�U�N�P�O�����ŁA����������ѓ��k�ꂳ��Ƃ̑Βk�Łu���ܓǂނƁA�g���̏����̎����Ėʔ����ˁB���Ƃ͂���܂�D������Ȃ��A����Ȗ`�����Ă�悤�Ȃ̂́B�v�i�U�X�y�[�W�j�ƌ����Ă����̂��v���o���܂����B���ӊO�ł��邩������܂���B�v�Ƃ��Ԏ������������B���́s�g�����Q�l�����ژ^�t�ɂ����̋L�ڂ͂�����̂́A����̔ѓ��k��E��������k�Βk�l�q�Ƃ��Ɍ��ɂ�����̂����\�\���E��E�U���r�����ăR�s�[�����t�@�C����������Ȃ��B�S�̂��ēǂ���͍̂���}���قł̉{�����\�ɂȂ��Ă���A�Ƃ������ƂŁA�Ƃ肠��������������ӔN�̋g�����̎��i�u����g�������v�Ƃ��Ắs��ʁt�s���[���h���b�v�t�̎���j�ɂ͍m��I�łȂ��������Ƃɗ��ӂ��Ă������B��̂ɋg���̋��F�����́i�ѓ��k��������āj�u����g�������v�����ė]���Ă���悤�ŁA�ꐢ��ȏ�Ⴂ���l�������M���I�Ɍ}�����̂Ƃ͍D�ΏƂ��Ȃ��Ă���B�ǂݎ肪���A�ǂ́u�g�������v�Əo��������́A�u�����v�u�O���v�u�����v�u����v�̂ǂ̍앗��]�����邩�ɂ��Ȃ���A�����ɒl�����肾�낤�B
��N�i2013�N�j��12���ɓc�������s�� �Ɣ�]�d�t���Љ�����ƂŁA�q�g�����̑�����i�r�͂ЂƂ̐ߖڂ��}�����B�ȑO�ɂ��������悤�ɁA�莝���̋g���������̏��Ђ����� ������̂��B�����́q�g�����̑�����i�i120�j�r�͐��˓������s�l �Ȃ������t���Љ�� ���A�����\�肵�Ă���쌴��v�̖{�̂��Ƃ́A������̋g���������̏��Ђ���肷�邱�Ƃ��挈�ɂȂ�B������������䂦�A����s�q�g�����r�́u�{�v�t�ɂ� �q�g�����̑�����i�r���s����f�ڂɂȂ邪�A�ȂɂƂ����e�͂������������B
�q�g�����̑�����i�r�̋L�����ǂ̂悤�ɍ�邩�A�U�肩�����Ă݂����B�ŏ��ɂ��̃y�[�W�̐��藧�����q�ׂĂ����B2002�N11���ɖ{
�T�C�g�s�g��
���̎��̐��E�t���J�݂��ĊԂ��Ȃ��A�s�q�g�����r�́u�{�v�t�̃y�[�W���s�q�g�����r�����t�̃X�s���I�t�Ƃ��Đݒ肵���B�s�q�g�����r�����t�J�n����2
�ӌ����2003�N1���̂��Ƃ��B�g�����́i���������j�{�Ɋւ���L�����s�q�g�����r�����t�Ɏ��e���邱�Ƃ̖��������������ł���B���̋O���C������
�Ȃ���A�s�q�g�����r�����t�ł͂Ȃ��s�q�g�����r�́u�{�v�����t�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B�g�����Ɩ{�̊W�́A�g�����Ǝ��̊W�ɗ��ʂقǐ[��
�̂ł���B
���{���W�̔Y�݂͐s���Ȃ��B�����_�ŋg���������{�̃R���N�V���������S�łȂ��悤�ɁA�����̋L�����������������Ԃ��A���M�Ɠ���͖{�y�[�W�̎Ԃ̗�
�ւŁA�ΏۂƂȂ�q�g�����r�́u�{�v�������ƌ����̗��ʂŒT���E���W���Â��Ă����B���̍ہA�C���^�[�l�b�g��̏�𗧂������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B��
���������A�s�T�t�����E�݁k�����{�l�t�ȂǁA���݂��̂��̂��Ï��X�ɋ�����ꂽ�B�q�g�����̑�����i�r�̋L���쐬�̋��菊�ɂȂ�q������i�ژ^�r�́A
�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�i�v���ЁA1991�j�����́q�g���������r��҂ލہA1990�N�H�ɋg���z�q����ɍ쐬���Ă����������u����v���X�g�i���L�Ɂu���ꗿ����������
����T�����̂�1����2���ɓ������̂͑O�N�ɂ�������ł��v�Ƃ������j���x�[�X�ɁA�}�����[�i�摜�u�}�����[���g�����Ɉ˗������Č��̍T���v�Q
�Ɓj�⏑��R�c�i���j������́A�}���̕s����2�_�����������������������A�u���ɁA���̋L���i�ʐA��ł��܂����̂Łj�ł́A���L�̏o�ŎЂɂ��ꂼ��
���_���̑���{������܂��B�S���҂ɂ��������߉������v�ƁA�����ЁA�y�ЁA�v���ЁA�������[�A�Ԑ_�Ђ̒S���҂��Љ�Ă����������j�ɒ������g��
��������i�̏��������������̂ł���B���̒��S���g���Ə����̒��Җ{�����A�����s�T�t�����E�݁k�����{�l�t��
�����s�̖{�Ɠ����ŁA����ɖ{�̂��W���P�b�g�ŕ����Ă������߂ɓ����{�ł���ƋC�Â��Ȃ������̂��낤�B�����Ɠ������s���i1977�N1��15���j�ɔ�
�g�ԎɔŁs�T�t�����E�݁k�����{�l�t�i����5���j�Ƃ����Ƃ�ł��Ȃ��㕨���㈲����Ă����Ƃ������������B����ɂ��Ă��A�g���z�q����ƒ}�����[�̒W�J
�~�ꂳ��A����R�c�̑��j������̂��z���͂��������Ȃ������B�܂��A�s���㎍�ǖ{�t�ҏW���̑�������j����̌㉟�����Ȃ���A�������Ƃ���l�ł���
���Ƃ��Ă�����قǃX���[�Y�ɂ͂����Ȃ��������낤�B�L���Ċ��ӂ���B
�������Đ������̂��s�g���������t�́y������i�ژ^�z�i�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�A�O��Z�`�O�ꔪ�y�[�W�j�ŁA1941�N�́u�g�������W�s�t�́t�i��@����Ɂj�v����1990�N�́u�ܒJ���m�s�F�V���F�l�t�i�@�͏o���[
�V�Ёj�v�܂ŁA�S124�^�C�g�����f�ڂ��Ă���B���������̊ϓ_���炷��ƁA1974�N�́u�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i��Z���@���쏑�[�j�v��
1980�N�́u�g�������W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i�܌��@����R�c�j�v��2���͂��̃��X�g����O���ׂ��ł���B���F���G�i�����̂悤�ȓ\���́s�_��I��
����̎��t�͔��s�ҁE���쐬��̑����ƍl�����邵�A�s�|�[���E�N���[�̐H��t�͑����҂̕\�������Ȃ����̘̂��߁i���j���j�̑���������ł���B����2
����������122�^�C�g�������q�Ły������i�ژ^�z�̍ŏI�`�i��e�j�Ƃ���Ȃ�A�E�F�u�y�[�W�s�g���������t���q�W�@������i�ژ^�r��
���ݒʍs�̓d�q�Łq������i�ژ^�r�Ƃ������ƂɂȂ�B�d�q�łɂ́A���q�Ły������i�ژ^�z��122�^�C�g���ɁA1956�N�́u�a�c�F�b�s��t�̓��L�t�i�}
�����[�A���ܘZ�N�Z���O�Z���j�v����1984�N�́u��o���Z�s���\�\�͂邩�Ȃ��蕔�t�i�����Ёk���{���i�_�l�A��㔪�l�N��ꌎ�����j�v�܂ł�53
�^�C�g����lj����Ă���A�����_�ł͍��v175�^�C�g���ł���B
���ׂĂ͏W���A�����m�F�Ɏn�܂�B�g���������{�����ܐV���œ��肷�邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂�����A�����m�F���Ȃ킿�Ï��̒T���Ƃ������ƂɂȂ�B���̏ꍇ�̌�
���ɂ�2��ނ����āA�g���������������Ƃ������Ă�����̂Ƃ����łȂ����̂Ƃł���B��҂͌Ï��X��}���قŃu���E�W���O���邱�Ƃ���{�ŁA���̍ہA�L�[
�ɂȂ�̂͒��҂Əo�ŎЂł���B�ނ��u�g�����v�Ɓu�}�����[�v���ŏ�ʂɂ��邪�A�������������̂ňȉ��͏ڏq���Ȃ��B�O�҂́A���̏،��i���̍ł����
�̂��g�����g�̌����ł���j���珑�������쐬���A�������|����ɐ}���ُ����{��Ï���T�����邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�A��������}���ق���{�ߑ㕶�w
�فA�����ċߗׂ̌����}���فi���ňȊO�̍���̖{���������Ƃ��ȂǁA���ꂪ���ɗ��j�̗��p���قƂ�ǂ����A�����̐}���ق̂��Ƃ�����B���Ђł͂Ȃ��G��
�̗Ⴞ���A�q��́r�̏��o���f�ڂ����s���㎍�t�i����p�g���A���s�j�̓��Y���͓��{���㎍�̕��w�فi��茧�k��s�j�ʼn{�������B���ꂪ�����ɂ���A����
�Ɣ�p�̋��������茩�ɂ����܂łł���B���݂��Ȃ����̂𑶍݂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���݂�����̂��������邱�Ƃ͂ł���B���Y���Ђ��C���^�[�l�b�g��
�������邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�n�o�`�b��s���{�̌Ö{���t�Ȃǂ̌Ï��̌����T�C�g�ȊO�ɂ��A�I�[�N�V�����������[���Œʒm���Ă����T�[�r�X�����邱
�Ƃ�t�����āA��i�����B
�������苖�ɂ���Ƃ���B�ō��̃R���f�B�V�����͐V���ōw�������Ƃ��̏�Ԃ����A�O���V���i�p���t�B���j�E�сE���͖{�̂����j���E�������₷���B������
�_���ׂ��Ώۏ��Ёi�g�����̎����������j�̑тɌ��y���Ȃ����R�́A�Ί_��W�s�����t�ɐG�ꂽ�q�g�����̑�����i�i104�j�i2012�N6��
30���j�r��
�q�ׂ��B���M�̏����́A���Ђ��v������Ƃ��납��n�܂�B�T�C�Y�͖{���p���̓V�n�~���E���~�����[�g���ő���B�g���������{�́A�l�Z
��
�i188�~128�~�����[�g���������j�������ƁA�����鐳���T�C�Y�����Ȃ�����A���@���L���̂�������m���ł���B�����w�ł́A
�{�̑傫
�����O�`�̍����i�Z���`���[�g���P�ʁA�[���͐�グ�j�ŕ\������A�l�Z���̏ꍇ�A�ʏ�19�Z���`���[
�g���ƂȂ�B�g���������Ɋւ��L�ڂ̏ꍇ�A�{���p���̐��@������Ȃ����Ƃɂ͘b�ɂȂ�Ȃ��B���͑��y�[�W���B�{�̃y�[�W���͕����I��2�̔{���i1���̕\
���j�����A�{���̏ꍇ�A��������̐��{�Ȃ�8��������16�̔{���A�{������G���{���p���ƈقȂ�y�����̂̏ꍇ�͕ʒ��\�肱�݂ƂȂ�B��������͎��̗��V
�ɂȂ邪�A�O�t���t�̃V���i�����y�[�W�j���܂߂āA�����{�Ȃ�\�̕\���Ɨ��̕\���ɋ��܂ꂽ�S���̃y�[�W�����A�㐻�{�Ȃ�O�̌��Ԃ��ƌ�̌��Ԃ��ɋ���
�ꂽ�S���̃y�[�W�����A�u���y�[�W���v�Ə̂��Ă���B�����{�����Ƃ��ɕK�v�ȃy�[�W�����ƍl��������B�����w�ł͈�����ꂽ�ŏI�̃y�[�W�t�i�m���u
���j�������ăy�[�W���Ƃ��邪�A���{�E�����̊ϓ_���炷��A�d�l�ɂ����鑍�y�[�W���́u�ʒ��ʼn��y�[�W�A�{���p���ʼn��y�[�W�̍��v���y�[�W�v�łȂ��Ɛ�
�v�ł��Ȃ��B�v�́A�����̐������猴�����Č��ł��邱�ƂɈӖ�������̂��B��������K�R�I�ɓ������̂́A�e���ނ̖����Ɏn�܂�זڂ̓���ł���B����
�\���〈�Ԃ��Ɏg�p����Ă�������I�ȗp���i������t�@���V�[�y�[�p�[�j�Ȃ炻��Ȃ�̒��ו������邪�A�{���p���ƂȂ�ƌ���������肷��͓̂���B
���̂Ƃ���A���{�̍Č��̂��߂ɂ͂��ꂪ������̐S�Ȃ̂����A�c�O�Ȃ���q�g�����̑�����i�r�Ŗ{���p���̖�����Nj����邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������B
�嗪�A���̂悤�ɂ��đΏې}���̎d�l���L���B���˓������s�l�Ȃ������t�ł́u�{���̎d�l�͈ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��l�Z�y�[
�W�E�㐻
�۔w�����E�W���P�b�g�B�W���P�b�g�̐}���͉ԁi��j�Ɛ���i���j�����A��҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��v�ƂȂ�B�u�㐻�۔w�����v�͐����s�v���낤�B�u�W���P�b
�g�v�̓J�o�[�Ƃ�������g�������Ȃ����߂ŁA���ӂ͂Ȃ��B���āA�����҂̃N���W�b�g�͇@�����₻�̎��ӁA�A�ڎ��i�����Ă��{�����o���̂��Ƃ́A�Ō��
�s�j�A�B���t�₻�̎��ӁA�ɋL����邱�Ƃ������B���Җ���o�ŎЖ��قǏd�v������Ă��Ȃ����߁A�S���ҏW�҂̖��O�Ɠ��l�A�f�����Ȃ����Ƃ�����B�g����
�̑����ł��邱�Ƃ��N���W�b�g����Ă���ꍇ�A�\�Ȃ�������p���A�N���W�b�g�̋L�ډӏ����������B�\�E�e�C�̊����\�L�͌��{�̃N���W�b�g���̗p������j
���̂������A�u����v�̏ꍇ���قƂ�ǂł���A�g�������g�̕��͂ł́u����v�Ə����i���́u�����v��p���邪�A�����ł͂��̗��R���q�ׂȂ��j�B
���M�O�̏�����i�߂����ŁA�Ώې}����ǂނƂ�����{�I�ȍ�Ƃ��������Ȃ��B�Ƃ͂������̂́A���ʂȂ��Ƃ�����킯�ł͂Ȃ��B�l�Z���̕��|���Ȃ琔����
�ǂ߂邾�낤�B���̂Ƃ����ӂ���̂́A�W���{���ɖ{�̃��B�W���A�����C���[�W������悤�ȋL�q�����邩�ǂ������B�Q����ʓǁi���ǁj���Ă���łȂ��ƍ�
�ƂɂƂ肩����Ȃ������Ƃ�����ƕ������A�g���������܂ł������ǂ����킩��Ȃ��B�S���ҏW�҂Ƃ̑ł����킹�����ł��܂����\��������B������ɂ���
���A�ǎ҂͖{���̑g�ݑ̍ق�\���܂���ς��ēǂނ킯�ɂ͂����Ȃ�����A�Ō����{�����̂܂����ق��Ȃ��B���Ɍ��炸�A�g�����̍�i�����̌����
����������Ǝv���قǂ̐l�Ȃ�A�{���������ɓǂ�ŁA������̂��ɖ{���A���Ԃ��A�\���A�W���P�b�g�┟�A�i�����Ă���͋g���̎w��Ƃ͌���Ȃ����j�сA
�Ƃ�����ɁA�{������O�ցA�ӂ����ɐڂ���̂Ƃ͋t�Ɋӏ܂�i�߂Ă����̂��|�C���g���B�܂�A�O������{���܂ł͂Ȃ�ׂ����_�����킹���A�͂���
���Ȃ�A�ڎ��Ȃ�A�����Ȃ�A�S���ҏW�҂ł���o�ŎЂ̖{���g�ł̐��Ƃł���A�g���ȊO�̐l�Ԃ��w�肵���y�[�W����œ_�����킹�ēǂ݂͂��߂�̂���
���B�������ēǗ��������ʁA���҂̉F���̊�������]���ɒ��������i�K�ŁA���߂ċg���������̕\���܂��i�O���j�𖡂키�B���̂Ƃ��A��̉F���̏Փ˂���
�Ȃɂ��̂������������ĕ��͂ɂ���B��\�I�Ȉ�т��߂����p����B�q�g�����̑�����i�r�̋L�����M�̗v���͂���ɐs���悤�B

�g���������{�i�g�����̒����������j�����s���ɔr�����I�̈ꕔ
�ߔN�ł͒������Ȃ���������̒P�s�{�������g���������{�����߂����I�߂Ă��Ċ�����̂́A���܂��܂Ȓ��҂�o�ŎЂ̖{�ł���ɂ���
����炸�A��
���đ��������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�g�����{�i�I�ɏ��Əo�ŕ��̑������n�߂��̂�1950�N��ŁA�������������ň���ɂ�鏑�Ђ̉������ゾ�����B�Ō�̑���
��i�́A�c�s�o�ɂ��g�ł����p������1990�N�A�f����3�ӌ��O�̊��s�ł���B����͊�������W�s�Õ��t�i1955�j�Ɏn�܂莍�сq����r�ŏI���g
���̎����Əd�Ȃ�B�q�g�����r�Ƃ�����i���т���̎������тƑ����������B���̍ō��̒B���́A�����܂ł��Ȃ��S12���̋g�����̒P�s���W�ł���B
4�N�قǂ܂��A�q�g���� �q�k���M�l�N���r�̂� �Ɓr�� �u�s���i�t1974�N3�����Ɍf�ڂ��ꂽ�܂ܒP�s�{�ɖ����^�̐��z�q���̖ʉe�\�\���������́r�̌��e�́A�g���̎��M�Ŏs�̂̃R�N����200���l�ߗp��2�� �ɂ킽����21�s�̖{����������Ă���v�Ƃ��āA�g�������M���e�̃��m�N���R�s�[�̉摜���f���Ă������i�R�s�[�̉�����1���̂悤�Ɍ����邪�A�y��2���� ����j�B
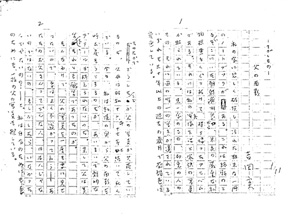 �@
�@
�q���̖ʉe�\�\���������́r�i�s���i�t1974�N3�����f�ځj�̋g�������M���e�i2�����j
�k���m�N���R�s�[�l�i���j�Ɠ��E�f�ڎ��ʁk���m�N���R�s�[�ɏ��т��Ԏ��ōZ�����L���l�i�E�j
��i���j�̉摜�͍Čf�B���e���f�ڂ�����i�E�j�̎G���s���i�t�́q���̖ʉe�r�̖{����
�@���̉Ƃɋ������j�����A���ꂽ�e���Ȉ���̃m�[�g�u�b�N������B����͏I��̂Ƃ��A�����ɂ������N�ϏB������A�� ���̌��d�Ȏ� �������������蔲���āA�����A�����A���o���ł���B����ɂ͎��̕��������ƉƑ��̎ʐ^���\���Ă���B�Z��Ƃ̂��́A�����̐l�̂��́A����ɕ�̗B��̎� �^���₳��Ă���B��������O�\�N�ȏ�̉ߋ��̍Ό��Œ����F�ɕϐF���Ă���B
�@���̂Ȃ��łǂ��������Ƃ����̎ʐ^���������Ă���̂��B����͏��a�\�Z�N�A�\���N�Ƒ����Ď���ł���B�����A���͋L���̉����畃�̖ʉe���Ăі߂����Ƃ� ��̂����A�����܂��őN���ȃf�e�[�����������Ȃ��̂��B�ʂ��ĕ��͔��j�q�A����Ƃ��X�j�ł������̂��B����Ȃ킯�ŕ��̎ʐ^����x���ȂɌ����ĂȂ��� �ŁA�Ȃ͂悭�s�R�����ĉ]���\�\���Ȃ��̂���������Ăǂ�Ȑl�A���{�l����Ȃ��̂ł͂Ȃ��́B������������A���Ȃ�������Ȃ��́H�\�\�ƁB���͎����� ���߂ɂ��A�Ȃ̂��߂ɂ��A�ꖇ�̕��̎ʐ^��T���Ă���B�i�����A�O��y�[�W�j
�ł���B�q���̖ʉe�\�\���������́r�Ƃ����ӂ��ɕW������������̂͋g���������s�U���̐������������ŁA���M���e������킩��Ƃ�
��A�g���͈�s
�߂Ɂu�\���������́\�v�Ƃ�⏬���������āA��s�߂Ɂu���̖ʉe�v��u���ă��C���̕W��Ƃ��Ă���B�����炭�G���Ђ���u���������́v�ɂ���400����
�����Ă��������A�ƈ˗����ꂽ�̂��낤�B�ӂ���C�ɂ��Ƃ߂Ă��Ȃ��������A���������ΐe���̎ʐ^���Ȃ���ŒT���Ă����ȁA���̂��Ƃł��������B�Ƃ�������
����ł͂Ȃ����낤���B���e�ƌf�ڎ����r����ƁA�s���i�t�ł͑�O�i���́u����Ȃ킯�Łv���ǂ����܂�i�����Ǔ_������j�A�u���Ȃ����������Ȃ�
�́v���u���Ȃ�������Ȃ��́v�ɂȂ��Ă���B��҂͐V���ȂÂ����ɓ��ꂵ�����߂ł���A�O�҂͎O�i�g�݂̃R�����̍s�����������߂ł���B���i��
�Ńm�[�g�̃A���o�����Љ�A���i���ł����ɕ��̎ʐ^���Ȃ��i�������ʉe�����ыN�������j�A�{���̑�O�i���Ŏ����̂��߂ɂ��A�Ȃ̂��߂ɂ����̎ʐ^��T
���Ă���\�\�Ƃ����\�����炷��A���i���Ƒ�O�i�����ЂƂɌq���Ă��܂��̂́A�����ɂ��܂����B�g�����̐��z�̌��e�͋g���Ƃɂ��قƂ�ǎc���Ă���
���悤������A�{���̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ����������������Ȃ��Ƃ��̖{���̌���͓���B�q���̖ʉe�r�ł́A���M���e���������āA�u����Ȃ킯�Łv�̂܂��ʼn�
�s���āi�Ǔ_�����������āj�A�S���ŎO�i���̓����̍\�����̂肽���B
�Ƃ��ɁA�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�i�v���ЁA1991�j�ɂ́u�o���̋L�O�ʐ^�v�Ƃ��āA�����͂g����Ƃ̏W���ʐ^���f�ڂ���Ă���B�g�����q���̖ʉe�r�����������ƁA�e�ʂ���
�肩�����������̂��낤���B�g���̔N���ⓖ���̓��L���Q�Ƃ���ƁA�����ɂ��Ă��������Ȃ��̂́A�ʐ^�̃L���v�V�����ɂ��镃�䑾�Y�A�ꂢ�ƁA�Z���v�̂�
���ɁA�o���q�i������E�̏c�Ȃ̒����̏������j�A�����F���m�ŐQ�H�����ɂ��������t�ˁi����ł����j�A�^���]�Ɩ×t�q�i���v�̉E�ׂ̓�l���낤�j�B����
���̓�l�͏f���f��������͂��̘A�ꍇ���Ɍ����邪�A�f����c���ܘY��1939�N10���Ɏ��̂����ƂŖS���Ȃ��Ă��邩��A�J���̏f��Ƃ����l���낤���B
�����◧���ʒu����A�ߗׂ̏Z���Ƃ͎v���Ȃ��B���Ⓑ�v�Ǝ����w�i�D�̎�ҁi���v�Ƃ��Ƃ̊ԁA����j�́u�J���̏f��v�̑��q�i�H�j���ꂩ�B�������X�p�͐�
�ܘY�O���̕v�A�����h�������B������ɂ��Ă��A���̐l���ɂȂ�Ƃ���グ�ł���i���ዾ�̒��g�̐l���͂���H�j�B�ʐ^�̎B�e�����́A�N���ɏƂ点�A
1941�N6�����ƍl������B�B�e�҂́A�����̂��Ƃ�����ނ��v���̎ʐ^�ƂŁA�z���������܂�������A�c�K�ʐ^�ق̏t���c�K�F��Y���̐l���������
���B

�u���o���̋L�O�ʐ^�B�g�������͂݁A�ꂢ�Ɓi�E�j�A���䑾�Y�i���j�A�Z���v�i�E����4�l
�ځj�B�v
�o�T�F�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�A
���G�k��y�[�W�l
�����t�v�̎��́A�k�����H�̒Z�̂ƕ���ŁA�Ⴋ���̋g�����̐S��͂�ŗ����Ȃ������B�g�����g�̕��͂ŐU��Ԃ낤�B�܂�1939�i���a
14�j�N�A�g
��������\�̓��L�B�u�㌎�\����^���B��g���Ɂw�l���L�x�Ɓw�J�t�̂ނ�x���͂��B�����t�v�̒Z�тƎ���ǂށv�i�s���܂�͂����L�t�A����R�c�A
1990�A���l�y�[�W�j�B���́A���z�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�ʼn̏W�s�����t���玩�������I�������Ɓu��ǂ��ĒN�̉e������������
�́A�����Ȃ��Ƃ��Z�̂̍D���Ȑl�ɂ͂킩��ł��낤�B���̂Ȃ��̂قƂ�ǂ��A�k�����H�́s�Ԋ~�t�i�˂̉ԁE�_��W�E���̗��E�����Ջ�W�Ȃǂ��珴������
�́j�A���Ⴄ�����̍��A���ǂ����s�����t�v����t�̝R��F�Z�������Ă��邩��B�k�c�c�l�����Ă݂�Ύ��͔��H�̎��ɂ͒^��Ȃ������B�Ђ�����s�˂�
�ԁt�Ɓs�_��W�t�݂̂A�˂��Ă����B���͍����t�v������ǂ�ł����B���v���ƁA����̂Ɏ��͍K�ł������̂��A�s�K�ł������̂��킩��Ȃ��B���܂�ɂ���
��ɂ��̓�l�̎��Ƃ����������āA�ʂ̂����ꂽ�̐l�֓��g��A�ʂ̂����ꂽ���l�����Y�ɏo��@��������Ă��܂����̂�����v�i�s�u�����v�Ƃ����G
�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�Z�܁`�Z�Z�y�[�W�j�B����ɁA�����i���}�Εv��j�s�����Z�L�t�ɐG��āA���ł͏t�v�̉���̕��͂Ɏ䂩��Ĉ�{�w����
���ƁA�V��ł͋���҂Ƃ��Ă̏t�v�̖����Ȃ��ꂽ���Ƃ������Ă���i���O�A�O�`�l�y�[�W�Q�Ɓj�B����I�Ȃ̂́A�̏W�s�����t�i���ƔŁA1959�j
�q���Ƃ����r�̎��̈�߂ł���B
�̏W�u�����v�͂ڂ��̏\��㔼�̍�i�ł��B���̍��A���ǂ�����g���ɂ́u�����t�v����v�A�������ɂ̖k�����H�̏W �u�Ԋ~�v�̉e����F�߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�s�����t�v����t�i�������� �s�t�v����t�j�͂��̌�s�t�v�����t�Ɖ��肳��ē����ɂ̃J�^���O�Ɏ��܂邪�A���݂͕i��̂悤���B�Ƃ��ɔ����Ђ���q�t�̎��W�r�Ƃ����S35���̑p �����o�Ă���B���̍����t�v���W�͐��e���O�Y�̕҂ɂȂ�B�g���́q���H���߂���f�́r�́u�P ���e���O�Y���̒��̔��H�v�Łu���͂����ɂ��A���e���O�Y�҂́w�k�����H���W�x�����邱�Ƃ�m��Ȃ������B���O�Y�̔ӔN�܂ŁA���̋߂��ɂ������A������ �H�ɏA�Č��̂��A���������Ƃ��Ȃ��B���̓�l�̎��l�́A�����炭�𗬂��Ȃ��������ł���B�h�ӂ��炱�̈ꊪ��҂��̂ł��낤�B���͈�{���w���āA�� �ǂ����B�ɂ������Ƃɂ����ɂ́A���O�Y�̔��H�̎��ւ̌��y���Ȃ��̂��v�i���O�A�O�Z�Z�y�[�W�j�Ə��������A���ꂪ�q�t�̎��W�r�̃V���[�Y�ŁA���e�͏t�v �Ɣ��H�̂ق��ɓ��蓡���Ɣ����Y�̌v�l���W��҂�ł���B�g�����q�t�̎��W�r�́s�����t�v���W�t�i1965�N9��1���j��ǂ��͂����肵�Ȃ� ���A���̏W�����܂��苖�ɂ���̂ŁA���p�͓������炷��i��{��1952�N�A�n���Њ��́s��{�����t�v�S���W�t���ƃN���W�b�g�ɂ���j�B

���e���O�Y�ҁs�����t�v���W�k�t�̎��W�l�t�i�����ЁA1965�N9��1���k�V���ő�7���F
1995�N4��20���l�j�̃W���P�b�g�ƒ����i���}�Εv��j�s�����Z�L�i�������̂��Ƃ��j�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1981�N10��16���j�̕\��
���Ӂm����ւ�n����m����n�̉́b�����t�v
���Ȃ����m���Ёn���������
���������ނ��g�m�݁n�ɂ����m���n�ށB
���̂̂��͂��m�����
���̂Ђ��肼�Ȃ������B
�g�����������Ƃ����ӂƂ�
���������Ȃ炶�킪�v�ЁB
���ɂ��₵������Ȃ���
����Ђ͐��m����n���A�N���ɁB
����ȂǁA�s�����G�߁t�̏��́u���邩�Ȃ��݂Â��^�Ȃ���邤�������^�̂�����肠�͂��^�킩���Ђ̂�߁v�̖{�̂̂悤�����i���̗��� �́A�t�v�Ɋr�ׂ�ƂقƂ�ǔ�߂��Ă���j�A
�f�́b�����t�v
���܂�Ђ���ΏH������
��̂���č炫�ɂ���A
�������������ĂȂ�����
��܁m�����n����邵�A�Ԃ���ʁB
�͓����薼�́q�f�́r�i�@�E14�j�́u�킪������ɂȂ�݂͂Ă��^��������ɂ����̂킭�v��z�킹��i��f�̓�т́A�t�v�̑�ꎍ�W �s�}��W�t�` ���́q���S���r�Ɍ�����A�g���́s�Õ��t�ɂ�����q�Õ��r�I�ʒu���߂��i�j�B�g���̓�s���́A���̂����ƒ����i�����炭�͏t�v�ӂ��́A���Ȏ�̂Řa�� ���̕���ɂ��j���̈ꕔ��f���������̂ł́A�Ƒz�������Ƃ��������i�s���l�Ƃ��Ă̋g�� ���t�́q�u�����g�� ���v�r�j�B�g���́q�f�́r�́A�[�łɂ����������̂������悤�ȏt�v�̂��̎��ɂ��A���������Ă���悤���B�Ƃ���ŁA���e���O�Y�ɂ͍����t�v��Ǔ��� ���q�c���̗J�T�i���́j�r�i���W�s�X�L�t���^�j�����邪�A�g���͏t�v��Ǔ����鎍�����c���Ă��Ȃ��B�Ƃ������A��N�̂���ɒ^�ǂ������ƈȊO�������邵 �Ă��炸�A�ʎ��������������肩�ł͂Ȃ��i���H�̍u���ړ��Ăɏo������ƁA���̔��H�͌��ȂŁA�Y�������Ă����Ƃ����b�͐��z�ɂ���������ǂ��j�B�� �H�̉̈ȏ�ɁA�g���̐t�̎��Ƃ��āA�ǂ����ɕ��Ă����̂��낤���B�̏W�s�����t�Ət�v���̔�r�����͍���̉ۑ肾�B
�g�����͐Ԕ����q�i1925-81�j�ɂ��ĎO�x�A���͂������Ă���B
�@�@�q���q�̈��r�i�s�Q�t1979�N1�����k����Ȃ��l�j
�@�A�q���q�Ǔ��r�i�s�Q�t1981�N6�E7�����j
�@�B�q�Ԕ����q�G�Ᏼ�r�i�s�Ԕ����q�S��W�t�x�q�Ԕ����q�m�[�g�r�A�������[�A1982�N3��1���j
�@
�́s�u�����v�Ƃ����G�t�i1980�j�Ɏ��߂�ꂽ���A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i1988�j�ł́u�ӂɂ݂��Ȃ��v�i�q���Ƃ����r�j�Ƃ��ďȂ��ꂽ�B
�u���q�̋ߍ����I�v�R�����g�́A���̒Z���i�g���̕��͖�300���j�䂦�ɏ����ꂽ���B�Ȃ��A�����́s�ӏܐԔ����q�S��t�i�������[�A1994�N3
��20���j�ɏ���112�l�̂ЂƂ�Ƃ��Ď��^����Ă���B�A�͖����s�B�B�́k����Łl�Ɏ��߂��A�A�ɂ��āu��N�̔~�J�̍��A�u�Q�v�̊��q�Ǔ����ɁA��
�͏������Ă���B����ɂ́A�W���O�x�̂ӂꂠ����Ǒz���āA�킸���l����f���Ă��邾���������B���̎��́A�����̓s���ŁA�����Ȃ��������Ƃ��A������
�����Ƃ߂Ă��������v�i�����A�O�O��y�[�W�j�Ƃ���B�g���́A�l�Ԋ��q�̋L�������������A���̂ĂćB���̂����킯�����A���̎��l�����̔o�l�Ƃ̌o�܂�Ԃ�
���q���q�Ǔ��r�͋M�d�ł���B
�@���͍��܂łɁA�Ԕ����q�Ƃ͎O�x��������Ă��Ȃ��B�w�ցx�A�w�����x�̍�҂ƍŏ��ɏo������̂́A�i�c�k�߂���� ��̎��ł��� ���B���q�͐V�����勫�����߂āA�Y�݁A畏����A�V������i�\���Ă���悤�ɁA�������B��̃o�[�̈���ŁA���͊��q�Ƃӂ��肫��ɂȂ�ƁA�u�` ����A�v�ƌ����悤�Ƃ��A���݂̂悤�ȋ����A������悤�Ɍ������B
�@���q�Ɠ�x�ڂɉ�����̂́A��W�w�Ή؏W�x�̏o�ŋL�O��̎��ł������B���҂��āA���͂��炭���߂���Ă����B�o�s���Ȏ��ɂƂ��āA��A�̗��s �ɂȂ邵�A�����A����̂��̂��D���łȂ������B�������A�w�Ή؏W�x��ʓǂ��āA���̌����Ȑ��ʂɌh�ӂ�\�������Ȃ��āA�o�Ȃ����B�剪�M���ׂɂ����B�Q �W�҂������A�܂�Ō������̂悤�ɍ��ȕ��͋C�̉�����B���R�Ȃ���A���q�Ƃ������b������@��͂Ȃ������B�킸���ȂЂƂƂ��A�ނ́u���v���Ƃ���� ����ɏ���ꂽ�A���r�[�̂悤�ȏ��ŁA���ɏA�Č�荇�������炢�������B
�@��N�̏t�A�i�c�k�ߎP���̉�_�˂̘Z�b���ōÂ��ꂽ�B��́A�O�{�̂ǂ��Ƃ����X�ŁA�S�S��s�I�Ȗ邾�����B�������ēc���Ŋς��u�����v�̑� ���������Ă���Ƃ����A�o�[���Ԃ�ցA�܁A�Z�l�̐����Ɩ�̊X�����܂悢�s�����B�����ɁA�����������������q�������B���ꂪ�O�x�ڂ̏o�����ł���A �Ō�ł������B�u�����v�̓́A���̐���������̂ł͂Ȃ������B
�@���q�����̌�ŁA�͂����u�o�匤���v�܌����̋߉r���ᒆ���ꇁ�\�܋�̂��܂�ɂ��A�Â����ׂɋ������B
�@�@�~�̊��E�̂��ƒ��������
�@���̈�傪������ے����Ă���B�����āA�u�Q�v�l�������͂����B����⇁�܋傪��߂����S�ɔ�݂�B���̈��̂悤�ɁB
�@�@�{��S�̋��Ɋ��
�@���́A�v�����O����A�w�Ή؏W�x�ɑ����V��W���A�҂��]��ł����̂ɁA���q�͂����҂ނ��ƂȂ��A�������Ă��܂����̂́A�ɂ��܂��B�i������������A ��e�̐����E�\���͂��Ă��邩���m��Ȃ��j�\�\�B
�@��A�O�N�O�ɁA�莆�Ɣ�����菭���傫�ڂ̘a���ɁA���M�������̂������B�u�嗋�J�T���Ɖ�ӂ����̖��v�̈��ł������B
�@�w�Ή؏W�x�͏G��A����ɂ��Ƃ����Ȃ����A���͍��A�����Ɉ����A�f�������Ǝv���B���q�̎��摜�̂悤�Ɍ����邩�炾�B
�@�@��T�X������͔������邩��
�@�܌������łɖ��A�������̎��͂���A������̉Ԃ͏����Ă����B
�g�������q�Ə��߂ĉ�����u�i�c�k�߂̉�v�́A1974�N1���A�_�ˁE���q���B���ŊJ���ꂽ�i�c�k�ߑS��W�s��Łt�o�ŋL�O��i���q�� ���N�ɂ��j �ł���B�u���N�قǑO�A���͋v���Ԃ�ɁA�w�_��I�Ȏ���̎��x���㈲�����B���s����ɂ݂������̎��W�́A���R�̂��ƂȂ��痝������Ȃ������B���̂悤�� �܁A���q����莆�������B���A���̎莆�͂킪�Ƃ̂��������ɁA���锤�������邱�Ƃ͏o���Ȃ��B���������ӂ͊o���Ă���B�k�����A���p�̂��߉��s�l�܂䂢 �u�̏�ɏo��Ɓ^�n�̌���^�̉e�̂��Ă��邱�Ƃ��^�ł̒����ł���k�����A���p�I���l���̎l�s�ɁA���������Ƃ������B�u�����v�Ƒ肷��l�\��s�̎��ł� ��B���͂₳�����ԕ����ꂽ�v���ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�O�O��`�O�O�O�y�[�W�j�ƇB�ɂ���̂́A�g������̔��N�l�ֈ��A�����˂� ��������{�ɑ���ԗ炾�낤�B���̂��납��T�Ǐ�ɔY�܂���Ă������q�́A1981�N3��17���A��}�d�S��e�w�߂��̓��œS�����̂̂��ߋ}�������B �����������Ɨ������Ă���g���́A���ɂȐF���ɐ��߂�ꂽ�Ǔ������́A�s�Ԕ����q�S��W�t�̞x�Ɋ��S�Ɛт�U�肩���镶�͂��悵�Ƃ����i�g���́A�� �����s���s�O���q�Y�S��W�t�x�̕���������łɎ� �߂Ă��邩��A��т���Ƃ��đ������ �}�����������낤�j�B���q�̑�\��s�Ή؏W�t�i�p�쏑�X�A1975�j����4��f����B��������q�����r�i�F�E5�j��q�킪�n�j�R���X�̎v���o�r�i�F�E 16�j�A�q�ߋ��r�i�B�E17�j�Ƃ������g�������Ƃ̐�ʉ��������������i�ł���B
�@�֎Ԃ̒�܂Ō������@�n�
�A�郉�K�[鱝�m���Ёn�����̂Ȃ��Ɏ���
���X�̂��̂ɗ���Ċz�̉�
�Ώ��m�₯�ǁn�̌������F�����Ē��n��
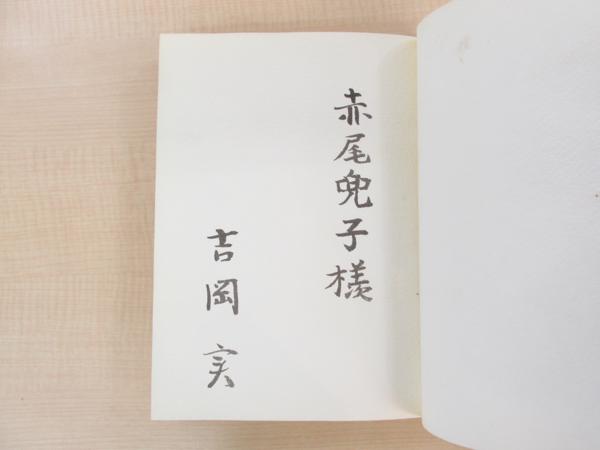
�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�i�Ԕ����q�����j�̌��提���y�[�W
�o�T�F�g�����w�_��I�Ȏ���̎��x��150�� ���菲�ʼn摕 �Ԕ����q���� -
�A�[�g�E�f�U�C���E�H�|�̌Ï� PP BOOKSTORE - ���t�I�N!
�k�NjL�l
��W�s�Ή؏W�t�o�ŋL�O��̏o�Ȏ҂̏W���ʐ^���a�c��N�Ғ��s�Ԕ����q�̐��E�k���a�o�啶�w�A���o���P�l�t�i�~�����[�A1991�N3��15���j�Ɍf�ڂ���
�Ă���A�g�����ʂ��Ă���B�ʐ^�͓����Ō��Ă��������Ƃ��āA�L���v�V�������������B
�u�u�w��
�؏W�x�o�ł��j�����q���܂���v�̋L�O�ʐ^�B�O���A�i�c�k�߁A�����d�M�A�剪�M�A�w�b�A���q�A�i�n�ɑ��Y�A�x�c��ԁA����\�O�Y�A�g�����B���
�ڍ����A��������A�������v�A���c�`���A�ޗǖ{�C��A�����ێq�A�i��l�����āj���������A�g�c����v�A�~���ҁA�{�c�����A�`����q�A�Í��a��B���̑�
�ɁA�c�Ӑ��q�A�唜�R�A�������A���숭�A�|����A��ؘZ�ђj�A�x���j�A�Ԕ������A�ѓc�I���v�A�t�؈�v�A��{����A����[�v�A��ؖL��A�ؑ��d�M�A�c����
�O�A�����A�������q�A�������A���c�͐��A�a�c��N�Ȃǁk���a50�N6���A���c�_�Ёl�v�i�����A��O�y�[�W�j�B
�B�B�����G��Ƃ͂��̂��Ƃ������̂��낤�B�L���v�V�����ɂ͂Ȃ����A��l�y�[�W�̓���̃X�i�b�v�ʐ^�i��������w�ɁA���q�������Ĉ��A���Ă���j�ł��g
���̎p���m�F�ł���B
�g�����͓�����̔o�l�Ƃ��č����d�M�i1923-83�j���ł��M�����Ă����B������̉̐l�Ƃ��ĐM�����Ă����̂́A���䗲�������悤�� �v���B������ ���ɋg���́A������i�c�k�߂��͂��߂Ƃ���o�l��o��ɂ��Ă͑����������̂��������A������̉̐l��Z�̂ɂ��Ă͂قƂ�nj���Ă��Ȃ��B�s�u�����v�� �����G�k����Łl�t�Ɏ��߂�ꂽ�̂��q���̍D���ȉ��䗲�̉́r�Ɓq��l�̉̐l�\�\�˖{�M�Y�Ɖ��䗲�r�̓�т������Ƃ����̂͏ے��I�ł���B�g���̖����s�� �U���Ɂq�Έ��̉́r�i�s���䗲�S�̏W�k�T�E�U�l�t���e���{�A�v���ЁA1987�N7���j�Ƃ������E��������i���N8��15�����́k�T�l�̕ʍ��s���䗲�_�l�t �ɍĘ^�j�B�������������ォ�ȂÂ����ɓ��ꂵ�A���p���ꂽ�s�}�j�G���X���̗��t�̒Z�̂̕\�L������Čf����B
�@�w�y�n��A�ɂ݂��x���o�ł��ꂽ���A���䗲�Əo��A��{��ꂽ�B�ȗ��A���͂��̐l���Ɖ̂ɖ������A�� ���܂Œ����� �ė����̂��B�u�݊C�̂��Ȃ��m���̔������Ăяo���Ă���d�b���܂Łv�\�\�B����N�A���R�Ɣނ͐g���B���Ă��܂����B�܂�ŕm���̔����̂悤�ɁB����ȉ��� �����ԕ炵�āA�Ԃ��Ȃ��A������i����w���I�s�x�܂ł̑S�̏W���҂܂ꂽ�B���̞x�ɁA�����ꕶ���Ă���B
�@���N��A���䗲�͉̂̐��E�ɕ��A���A���ꂩ��͈ӗ~�I�ɁA�w�A�����x���͂��߁A�����̉̏W���������Â����B�����āw�}�j�G���X���̗��x�A�w�֊��ƍD �F�x�ւƁA��̒��_�������������Ă���B�ǂ��炩�ƌ����A���́A�w�}�j�G���X���̗��x��Έ����Ă���B
�@�̒m��ˁ@�����m�����₫�ʂ܁n�ɋڂ�E�m�n�ށ@���@�̑m�ӂ�����ɂ���
�@���̂��Ƃ��ӉZ������银�q����Ђ�����ɂ��̗����ނ�
�@�~�g�͉��܂ōd���ނ痧�Ă�Ђ�₩�ɐl�͏Ђ͂��߂�
���䗲�S�̏W�̞x�Ɉꕶ�����Ƃ��邪�A�g���́q���̍D���ȉ��䗲�̉́r�́s����Z�̑�n�k��7���l�t�i�O�ꏑ�[�A1972�j�����
�f�ڂ��ꂽ��
�̂ŁA�����̑S�̏W���Ȃ킿�s���䗲�̏W�t�i�v���ЁA1972�j�̞x�Ɋ����ł͂Ȃ��B����́s���䗲�S�̏W�k�U�l�t�i�v���ЁA1987�N9��15���j
�́q���Ƃ����r�ł����U�肩�����Ă���B
�u�Ȍ��㎵�ܔN�u���s���߂���f�́E���v���u����v�ɏ����܂ł́A��̂�f�����B���̖�ܔN�̊Ԃ̒��f�ɂ���āA�킽���̉̂ɂ��Ă̍l�����́A���Ȃ�
�傫���ς����B�ǎ҂�����ǂ����킩��Ȃ��������Ŋ����Ă��邱�Ƃ��ӏ���������Ǝ��̂悤�Ȃ��ƂɂȂ낤�B
�@���ɁA�����̉̂ɋ����������Ă���鏭���̗F�l�i�N��̂��������Ȃ��j�m�Ȃ̂��߂ɏ������ƂɂȂ����B���̐l�����ɂ킩������̂�����A���Ȃ�
�u�b�L�b�V���ȑf�ނ���������A����Șb��������o���Ă��悩�����B�m���K���i���͂قƂ�ǎ��ꂾ���j�̈���Ƃ��Ĉ�Ă�ꂽ�{�����A�ق�������Ȃ����A
���������Ƃ����Ȃ������B���Y�K���i���������j�̋��������҂Ƃ��āA���̑ォ�玩���̑�܂Ő����������Ƃ��m�肵�Ă��������B
�@���ɁA��@�Ƃ��Z�@�Ƃ��ɁA��ȃX�g�C�V�Y�����ۂ���K�v�͂Ȃ��Ǝv�����B�u�A�����M�v�Ŋw�̂������悯��A�˖{�M�Y�ƈꂵ��ɊJ���u�O
�q�Z�́v�̏����@�����\�ł���B�����A�A��A�U���Ƃ̑g�����A�Ȃ�ł������̂ł����āA������Z�@�i�Ƃ��������đ債�čL�����̂ł͂Ȃ����j�ɂ��āA
�G�s�L�����A���i���y��`�ҁj�ł��肽���B���̂��߂ɂ́A�V�Y�̂�������˂ɐV�N�ɕۂ��������̂��A�Ǝv���ė����B
�@��O�ɁA��̐����I�C�f�I���M�[���玩�R�ł��肽���B����ł��āA�����Ȃ鏑�����̂��A���\����A���̐����������Ƃ������ƂɁA���o�I�ł��肽
���B
�@��l�A�̒d�Ȃ�тɌ��Ђ̎w���I�ȗ���Ƃ��������̂���́A�˂ɉ������Ă��肽���B
�@�܂����邾�낤���A���������肱�̎l�̂��Ƃ���A�w�h�����x���w�}�j�G���X���̗��x������܂ł̍�̓��@�́A�����o����Ă��邾�낤�B�������Â���
�ɂ�����A�ÓT�I��@���ӎ��I�ɂƂ���ꂽ��A�̗w���̕������������̂�A��������A�E�̎l���ڂ���o�Ă���Ƃ�����v�i�����A�܁Z���`�܁Z���y�[
�W�j�B
����̍앗�̂��������ω����A�g���͍m��I�ɎƂ߂��悤���B�Ƃ�킯�u���v�Ɓu���v�́A�g�����g��1980�N��̎���̎p���ɒʂ�����̂�����B
����̎��݂�����Z�̂ŋ������̂Ȃ�A�s��ʁt�̂悤�Ȏ��݂����㎍�ł��������͂����B����̒Z�̂ɐG�ꂽ�g���͐S�����v�����ɈႢ�Ȃ��B���̉���
���g���̎��ɂ��Č��Â��Ă���̂́A�l���m��Ƃ��肾�B
 �@
�@
�g���Έ��̉̏W�s�}�j�G���X���̗��t�i����G�ߎЁA1980�N5���k���t���L�ڂȂ��l�j�́A�˖{�M�Y�̈�A�̒����̃v���f���[�X�Œm�� ��鐭�c���� �̑����ł���i�����̉���́q���Ƃ����r�́A��������M�����˖{�Ɩ{�����o�ł�������G�ߎЂ̔��s�҂ł��鐭�c�ւ̎ӎ��Œ��߂������Ă���j�B���c���� �̑��{�����́A���Y�N���Ƌg�����̗��ɂ̒��ԂɈʒu����悤�Ɍ�����B�{���̔��ł����A�\���P�͋g���ӂ������A�}���̈����̓J�b�g�Ƃ�������i�ɋ� ���B�g���͐}�����J�b�g�Ƃ��Ďg�p����B�Ƃ��ɁA���̐l�̐}�̈ʒu�A�������Ȃ����B������ɂ��Ă��A���Җ��͂��������������Ă������낤�B�w�ƕ\���S�ɐ} ����z���邠����͐��Y�ӂ����B�g���͒ʏ�A�\���S�ɏo�ŎЂ̃}�[�N�����邾���ł���B�z���̕\���ɂ���Ƃ����������͂Ȃ����A�����ƒ��Җ���o���r�� �Ȃ��w�����̏����͒������B�g���͕\���܂��Ɍr��p���Ȃ��B�\���̐F���T�t�����̉Ԃ̒W�����Ȃ̂͋��R���낤�B����Ƃ�����̗v�]���B
�k�NjL�l
�˖{�M�Y�́q���ʋ��\�\���Y�N���_�r�i�s�f�����t�A�ǔ��V���ЁA1978�N8��14���j�ŁA���{�����`�����銿���E�������E��
����������قǑ씲�Ȉӏ��Ɖ������f�U�C�i�[�͂Ȃ��A�`�s���M�́q�a���N�r�W�r�Ɠ��l�A���̍�i�͂�����Ӗ��Ŋv���I�ł���A���m�̋ɓ_�ɋ߂Â����Ƃ�
�Ă���A�Ɛ��Y�N���̃��C�A�E�g���̗g�����B���Y�̑��{�����ɂȂ鎩���s�S��W�W�t�i�u�k�ЁA1974�j���u�����V���V�}�ƓV������}���Z�߁A�ӏ܍�i��
�̂��̂����ʐ������m���C���{�[�n�Ŕ��ɐ�Ƃ߂����߂́A�����{��Z�\���̒��ł��A�����ʂ�W���������Ă��v�i�����A�ܘZ�y�[�W�j�ƁA���̑�����
�]�����B�f�U�C�i�[�Ƃ��Ă̓ǂ݂������̑��{�ɋ��߂��̂ł���B���c�i�����͎��l�ł���A�f��Ɉꊪ�̎��W������j�����Y����w�̂́A���̑��`���_��
����ȏ�ɁA����̏���������܂ł̏����Q�ɂȂɂ������炷���A�Ƃ����N�w�������悤�Ɏv���B
�ȉ��̒Z���́A���̏H��PDF�t�@�C���Ō��J��\�肵�Ă��錻�ݎ��M���̒��ѕ]�_�s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�́q�͂������r�ł���B������ �P�Ɂs�g�� ���t�ł��悩�����̂����A������u�����ƂƂ��Ă̋g�����v�ɏœ_�����킹���ꕶ�����������̂ŁA���g���҂l�����@�Ń{�[�h���[���S�W�ɕ��i���F���� ���q���l�Ƃ��Ẵ{�[�h���[���r�ɂ��₩���āu���l�Ƃ��Ắv���������B�����Ȃ�A�{���̏����Ƃ��ď������u�q�g�����r�l�ƍ�i�v�ł���B
�@�g�����́A�f�㊧�s�̍e�{���W�s����t�������A���O�ɏ\����̎��W�����s�����B��O�́s�����G�߁t�Ɓs�t�́t�͂� ������o���O �Ɉ⏑�Ƃ��ĕ҂܂ꂽ�B������͏������낵�́s�Õ��t�ƁA���l���⏤�Ǝ��ɔ��\�������тɏ������낵���������s�m���t������Ŋ��s�B��҂��g�܂���܂��� �ɋy��ŁA���l�Ƃ��Ēn����z�����B��㎵�Z�N�́s�T�t�����E�݁t�͍������܂���܂�����\��ł���B���l�ł���Ɠ����ɏo�Ől�ł��������g���́A������ �w�Z�𑲋ƌ�A��w�����̏o�ŎЂɕ�������B��O�͏��m����`�����ꎞ�������������A���͓�A�O�̏o�ŎЂ��o�Ē}�����[�ɋΖ��B������̓|�Y���@�ɑ� �E����܂ŁA��т��ďo�ŊE�ɂ������B���̌�����l�Ƃ��āA�����ƂƂ��Ċ��A�s��ʁt�œ����L�O����܂���܁B����Z�N�Ɏ��\��ŕa�f�����B���� ���т��܂ޑS���W�Ɖ̏W�́s�g�����S���W�t�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���B
�@�g�����͕��w������Z�̂���n�߂��B���N���ɌZ���������Ƃ̍����t�˂̊������傫���B�k�����H�̉e�����ɒZ�́E�����̂��r�݁A�ق� ������ �ɁA���������̋��ɎQ�����Ĕo����������B�V���o�傩��w�ԏ��������A�x�V�ԉ��j��i�����s���́t�ɓ��e�����\���傪�f�ڂ���Ă���B���삪���߂Ċ� ���ɂȂ����̂��AJ�g�̕M���Łs���́t�֓������o�傾�����B���̌�A����C����̃s�J�\�̎���k�����q�A���삿���̃��_�j�Y�����ɐG��Ď���ɓ]���A�� �̏W�s�����G�߁t�Ǝ��W�s�t�́t�����s�B��������s����t�͏����̘a�̂��W�߂��q�`�W�r�Ɣo����W�߂��q�z���r���琬�邪�A�s�����G�߁t�ɂȂ���Ɩڂ� ��鎍�т͗p�����j��Ƃ��č폜���ꂽ�B
�@�o���O�́s����t�Ɓs�����G�߁t�s�t�́t�̓W���u�����g�����v�A�^�̎��I�o���Ƃ�������́s�Õ��t�Ɓs�m���t���u�O���g�� ���v�A���� �Ɂs�_��I�Ȏ���̎��t�Ɓs�T�t�����E�݁t���u�����g�����v�A�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t���u����g�����v�̍�i�Ƃ��āA�����ł͘_�������B���Ȃ킿�A �ŏ����̒Z���^��W�ƁA�S�\����̎��W����I�����̎��W�̊����Ɗ����̍�i�𒆐S�ɁA���l�Ƃ��Ă̋g�����̕��݂��T�ς���B
�@�g���ɂ́A�����̒Z�̂�o��A���ȊO�ɁA�U���W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i���ł���ё���Łj�A�]�`�s�y���F��t�A�s���܂�͂��� �L�t���n�߂Ƃ�����L�Ȃǂ̎U���A����ɂ͑Βk���܂ޖ����s�̒k�b������B�������K�X�Q�Ƃ��Ȃ���A�g�����̎��Ƃ����Ă������B
���łƌ����Ă͂Ȃ��A�s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�̖ڎ����f���Ă����i�m���u���͏������j�B�_����Ώۍ�i�̑I�����@�B�I���ƌ����� ����B�W��� �Ȃ������т͂�������A�g�����̎��W�̊����Ɗ����i�`���Ɩ����j�̍�i�������ɏd�v���́A�{�T�C�g�ł��Ƃ��邲�Ƃɋ������Ă����B���͖S���H���K�l�� �s�g�����A���x�X�N�t�i����R�c�A2002�j�ȍ~�A�g�����̍�i��_�������͂ɂ�����A���ɛ���������̂�����B�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t���J�� ����10�N�B���̊Ԃ̒~�ς܂��āA�{�������s�i���J�j����B
���l�Ƃ��Ă̋g�����E�ڎ�
�@�͂�����
�u�����g�����v�\�\�s����t�Ɓs�����G�߁t�Ɓs�t�́t
�@�T�@�q�`�W�r�`���̒Z�́\�\�u�����k�c�c�l�v
�@�U�@�q�`�W�r�����̐����́\�\�u���D�ʂ��k�c�c�l�v
�@�V�@�q�z���r�`���̔o��\�\�u�t�J��l�̌��t�ɉR�����v
�@�W�@�q�z���r�����̔o��\�\�u�}��l�Ԃ̋Ȃ�X�͂Â�v
�@�X�@�s�����G�߁t�����̎��с\�\�q�t�r�i�@�E1�j
�@�Y�@�s�����G�߁t�����̎��с\�\�q�����G�߂Q�r�i�@�E20�j
�@�Z�@�s�t�́t�����̎��с\�\�q�҉́r�i�A�E1�j
�@�[�@�s�t�́t�����̎��с\�\�q���̖|��r�i�A�E32�j
�@�y���z�@�u�����g�����v�\�\�s����t�Ɓs�����G�߁t�Ɓs�t�́t
�u�O���g�����v�\�\�s�Õ��t�Ɓs�m���t
�@�T�@�s�Õ��t�����̎��с\�\�q�Õ��r�i�B�E1�j
�@�U�@�s�Õ��t�����̎��с\�\�q�ߋ��r�i�B�E17�j
�@�V�@�s�m���t�����̎��с\�\�q�쌀�r�i�C�E1�j
�@�W�@�s�m���t�����̎��с\�\�q�����r�i�C�E19�j
�@�y���z�@�u�O���g�����v�\�\�s�Õ��t�Ɓs�m���t
�u�����g�����v�\�\�s�_��I�Ȏ���̎��t�Ɓs�T�t�����E�݁t
�@�T�@�s�_��I�Ȏ���̎��t�����̎��с\�\�q�}�N���R�X���X�r�i�F�E1�j
�@�U�@�s�_��I�Ȏ���̎��t�����̎��с\�\�q�R�����r�i�F�E18�j
�@�V�@�s�T�t�����E�݁t�����̎��с\�\�q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j
�@�W�@�s�T�t�����E�݁t�����̎��с\�\�q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�i�G�E31�j
�@�y���z�@�u�����g�����v�\�\�s�_��I�Ȏ���̎��t�Ɓs�T�t�����E�݁t
�u����g�����v�\�\�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t
�@�T�@�s��ʁt�����̎��с\�\�q雞�r�i�J�E1�j
�@�U�@�s��ʁt�����̎��с\�\�q�C�g�r�i�J�E19�j
�@�V�@�s���[���h���b�v�t�����̎��с\�\�q�Y��i�ނ��сj�r�i�K�E1�j
�@�W�@�s���[���h���b�v�t�����̎��с\�\�q�k�H��l��r�i�K�E19�j
�@�y���z�@�u����g�����v�\�\�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t
�@�g���������i�P�s���W�сj
�@���Ƃ���
�\�\���ѕW��̂��Ƃ̊ے������i���W�ԍ��j�͉��Ԃ߂̎��W�����A�A���r�A�����͂��̎��W�ł̌f�ڏ��������B
�g�����͐��10�N�Ԃ̑����Z�Ƃ��Ď��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j���������낵�����ƁA�s�V���W�t��s�����t�i1954�N6���n��
�`1958�N
12���I���k10���l�j��s�G�߁t�i1956�N10���n���`1958�N9���I���H�k12���l�j�Ƃ����������̓��l���ɎQ�����Ă���B�s�V���W�t�Ɓs�����t
�͓��l���������A�s�G�߁t�͍�i����������������������Ȃ��B�苖�Ɂs�V���W�t���n���������8���܂ł���̂Łi�I�����ځj�A�����Ɍf�ڂ��ꂽ��i��
�ʂ��āA�g���������������낵����G�����\�Ɉڍs��������������U�肩�����Ă݂悤�i����ȍ~�A�g���͓��l���E���Ǝ����킸�A�G�����傽�锭�\�}��
�Ƃ���j�B�����n�����̕ҏW���s�҂͍���p�O�ƒ߉��~��̂ӂ���ŁA�s���{���㎍���T�t�i�����ЁA1986�A����y�[�W�E�O�O�܃y�[�W�j�̗����̍��͂�
���Ȃ��Ă���B
����p�O�@ �����킦�������@���l�B�吳��E ��E�l�`�i1913�`�j�B�ޗnj��g��S���܂�B�{����c�s�Y�B���w���ތ�A����I���w�Z���B��ꏑ�[�ҏW���E�k�l���@�Ζ����o�Ĉ���ƁB�ޗnj��\�Ð�o�g �̎��l�쒷�����v�̌[���ɂ��ꎵ�̂��납�玍����n�߁A�u���{���d�v�ɓ��e�B�u�v�u���㎍���_�v�u�ԁv���o�āA�u���{�����h�v�ҏW���l�B���W�w��� �́x�i��14�E10�@��ꏑ�[�j�w�Ⴂ�x�i��27�E6�@���{�����h���s���j�w���y��x�i��29�E5�@���j�w����I�s�x�i��47�E1�@�فj�̂ق��A�� ���w���������Y�������݁@���Ɛ^���x�i��43�@���j������B �i�ҏW���j
�߉��~���@ �邨���ӂ䂢���@���l�B�吳�Z�E���E��Z�i1917�`�j�B�k�C�����َs���܂�B�{�����R�����Y�B��O�����w�Z���ȏC���B�����E�|�E���ƌ��������ւ� ���M�ƂɁB���w����Ƀu���E�j���O�E�L�[�c�Ȃǂɐe���݁A�O���́u�Ԑ���G���v�ɏ����Ă����̂��ŏ��ł���B���A�u���㎍�v�u���ԁv�u�V���{���l�v�Ȃ� �Ɏ�Ƃ��Ĕ��\����B���W�Ɂw�ԓ��l�x�i��32�j�w�c���ȋG�߁x�i��33�j�A�ɂb=�c=���[�C�X���w�����ǂ��ǂނ��x�i��32�j�A�]�_�W�Ɂw�s���̍� ���x�i��36�j�w�����̌����Ɨ��z�x�i��52�j������B����������ɐ�������ł������ł���B & amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; nbsp; �i����ĕv�j
�s�V���W�t�͓����T�ɂ��O�ȓ��́s���㎍�厖�T�t�ɂ��ڂ��Ă��炸�A�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B���s���́u�I�̉�v�́A�߉��~�ꂪ��ɂ� �鎍�l�̃O ���[�v�������悤���B����̎�����S�����̂�����p�O���낤���B�n�����i1955�N6��1�����s�j�̖ڎ��̃W�������ƍ�Җ����f���悤�B���͌��q�N�E�ߐ{ ���E�q��F�q�E��˕��E�����b�E�O�Y�E���J��g�Y�E�ΐ�G�E�����e�q�E����È�E��c�Éh�E�c���^�K�E�����ߎq�E�߉��~��E����p�O�B�]�_�͒߉��~ ��E����È�B�͋e���p�v�E��c�ہE�߉��~��B���]�����c���j�B�\���͊}�؎��A�J�b�g�͓S�w�����B�߉��͕ҏW���s�҂����łȂ��A������Ƃ��Ă����ʘZ �]�̊���ł���B�Ȃ��A�n�����ɓ��l����̗ނ̋L�ڂ͂Ȃ��B���Ɉ����q�ҏW��L�r�ŏЉ��Ă���e���p�v���c�ۂ́A�Q�X�g�i���B
�@�ҏW��L
���I�̉�V���W�������̂ЂƂтƂ̌䋦�͂≇���ɂ�Ă悤�₭��������܂����B
���I�̉�V���W�̃��b�g�[�Ƃ��鏊�͉������|�p�̏����������Â��邱�Ƃɂ���̂ł����A�k�c�c�l
�����̍��Ɍ��e�������e���p�v���́k�c�c�l�B��c�ێ��́k�c�c�l�B���\���G�����肢�����}�؎����́k�c�c�l�B���A�����̓s���ɂ�荡�㓌���ݏZ���l�� ���e����m�A�A�A�A�n�͒߉��̕��ւ��肢�v���܂��B�U�ւ͓�������A��ܔ��ԁi�߉��j
�� �����̂Ȃ��ׂ����Ƃ͑����B��������Ó��ʂ̎d���͌��㎍�̃p�^�[����Ƃ����������㎍�Ƃ͉����Ƃ������Ƃ̒T���ɂ���B�����ċ������f������ ���Ȃ����A�a���ē������A�e���̌��d���ē�����]�������ɍs���݂Ɍ[���サ���Ă䂭�W�c�A�s�I�̉�t�͂���������ł���B�����̔@�����ʂȃ� ���o�A�ł��邪������͗ʂƈӗ~�ɖ������l�X���ǂ��ǂ����������B
���s�I�̉�t�͒P�Ɏ��l�̏W�c�ł��邾���łȂ����̌|�p����Ƃ��𗬂��͂���A���l�̕ǎ�`��Ŕj�������B�k�c�c�l�i����j
���������s�͏\���B�i�s�V���W�t�n�����A�Z�O�y�[�W�j
�����āA���t�̂܂��Ɂq�I�̉����K��r���u����Ă���B
�@�I�̉����K��
��A����T�Z�O�Z�Z�~�O�[�҂�����Ƃ���B����͓��e���R�B
��A���e�͕ҏW���őI�t�̏�s�V���W�t�Ɍf�ڂ���B���e�͕Ԗ߂��Ȃ��B
��A����̓��D�G�Ȏ҂͓��l��ɂđI�t�̏�A���l�ɐ��E����B
��A���l�͕ʂɒ�߂�K��ɂ��B
�@�@�I�̉�ҏW��
�@�U�։��l�Z���Z�ԁ@�d�b����O�l�l�ԁi���O�j
�g���͂�������ĉ���ɂȂ�A��i��������ʁA���l�ɐ��E���ꂽ�Ǝv�����B�Ȃ�������������邩�Ƃ����ƁA��2���i1956�N1�� 1�����s�j�� �q�[�Ӂr��9���̎��W�̂Ȃ��Ɂu�g�����u�Õ��v�i���ƔŁj�v�i�����A��܃y�[�W�j�Ƃ�����肩�A�q���b�r�i�B�E15�j�Ɓq�Õ��r�i�B�E4�j��2�� ���A���т̂��ƂɁu���W�u�Õ��v���v�Ƃ����f��菑�����āA�����ɍĘ^����Ă��邩��ł���i�����A�l�l�`�l�܃y�[�W�j�B�C�ɂȂ�2�т̖{�������A �q���b�r�̑S�p�A�L��q�Õ��r�̂��ȂÂ������ꕔ��{�̎��W�s�Õ��t�ƈقȂ���̂́A����ւ̎����͂Ȃ���Ă��Ȃ��B
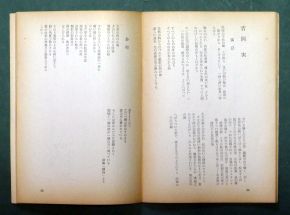
�������A����ɂ͂����ЂƂʂ̐����l������B�E�����Y�ł́s�m���t�o�ŋL�O��i1959�N1��30���j�ɂ��o�Ȃ�����X���s�� �I�̉�̎�v �����o�[�������炵���̂ł���i��2���f�ڂ̋��q�����̐��z�q�G���r�ɂ��j�B��X���g���Ɠ�����2������o�ꂵ�Ă���Ƃ�����݂�ƁA�ӂ���͓����ɓ� ����A���邢�͓��l�ɂȂ����Ƃ��l�����邪�A���̂�����ɂȂ�Ǝ������s�����Ă��āA�g������X�ƒm�荇����������Ȃ̂��A�s�V���W�t���邢�͖I�̉� �ɓ�����������Ȃ̂��A���R�Ƃ��Ȃ��B��X���s�͎���̂ق����p�֘A�̒���������A�ђˏ��X�̎G���s���㎍�t1959�N3�����́q���߁E�L�߁r�i�E�E2�j �ł͑�Ґ��i�̎ʐ^�Ƌg���̎��́u�\���v�i���ʂ̃��C�A�E�g���낤�j�����Ă���B������肩�A�s���㎍�蒟�t���N10�����Ɂq�ǐ�̃A�o���M�����h�r�� �����g�����_�����M���Ă���B�܂����������̋g�������̔����҂Ƃ����悤�B�s�Õ��t�̎��̍Ę^�Łs�V���W�t�ɓo�ꂵ���g�������A�����ɔ��\�����V����q�����r���q���r��2 �тł���B1956�N�ɔ��\�����̂��������܂�5�т�����A�g���ɂƂ��ē����������ɑ傫�ȑ��݂����������킩��B
�@1956�N���\�̋g������
�@4���@�����i�C�E2�A�s�V���W�t�k�I�̉�l3���j
�@5���@�쌀�i�C�E1�A�s���w�t�k���w�Ёl5�����k11��6���l�j
�@7���@�A�d�i�������сE6�A�s���㎍�t�k�Ώ��[�l7�����k3��6���l�j
�@11���@���i�C�E3�A�s�V���W�t�k�I�̉�l4���j
�@12���@�d���i�C�E4�A�s�����t�k���惆���C�J�l6���j
�̂��Ɂs�m���t�ƂȂ鎍�W�̏������т������āA���l���i�s�V���W�t�Ɓs�����t�j�⏤�Ǝ��i�s���w�t�Ɓs���㎍�t�j�ɗ����Ɣ��\���͂��� ���g�������A �s�V���W�t�̑�5���i1957�N5��1�����s�j�́q�ҏW��L�r�Œ߉��~�ꂪ�u�����l�����Ƃ��Ă͑�X���s���Ƌg���������ނ��ĐV���l�����ގ����}�����v �i�����A�k�\���R�l�j�ƕĂ���B��4���i��3���́q�ҏW��L�r�ł�1956�N7�����{���s�Ɨ\�����ꂽ���A���l���̂˂Ƃ��Ēx��A���ۂɂ�10���� �{���딭�s���ꂽ���j�Ɂq���r�����O��ŁA�g���͑�X�ƂƂ��ɓ��l��ނ��A�����炭�͖I�̉���މ���͗l���B�ѓ��k��ɗU���ē������s�����t���� �i���\�̕���ɂ��āA�{�i�I�Ȋ������n�߂����߂Ǝv����B�g����1957�N4���A�ɒB���v�̎����s�����C�J�t�Ɂq�m���r�i�C�E8�j���g���A���������ēo �ꂷ��̂ł���B
�k�t�L�l
��X���s�i1926-82�j��1970�N��㔼�A�����p�Д��s�̏��ЂŖ|�������S�����Ă���B�����̊����̏Љ���Q�l�ɂ��������ƁA�������L��
�i����͌����܂��͏��e�����j�B
�\�\1926�N�A���s�ɐ��܂��B�������p��w�u�t�i��勳��w�ȁE��b�f�U�C���_�j�B���{���㎍�l�����B�f�U�C���̎��ۊ����Ɠ����ɁA���`�|�p�Ɋւ�
��_����G�b�Z�C�𑽐����\�B��Ȓ���҉�����Ɉȉ�������B
�@���@��X���s��ꎍ�W�s�߂̋G�߁t�i�k���s�l�k�m�ЁA1949�j
�@���@���J�����ďC�A��X���s�ҁs�������ǂ��G���y�L�t�i�����o�ŁA1955�j
�@���@�p�쏑�X�ҁA��X���s����s���ցk�p��ʐ^���Ɂl�t�i�p�쏑�X�A1956�j
�@���@��X���s�ҁs�j���[�J�b�g�f�U�C��3000�t�i��菑�X�A1959�j
�@���@�A�[�T�[�E�z�[�L���Y�ҁA��X���s��s�A�[�g��f�B���N�^�[�̎d���t�i�_���B�b�h�ЁA1963�j
�@���@��X���s�E�͌��~�ҁs�J�b�g�E�f�U�C���E���`�[�t�t�i�_���B�b�h�ЁA1963�j
�@���@���Ì��E��X���s�ҁs�C���X�g���[�V������C���[�W�t�i�_���B�b�h�ЁA1965�j
�@���@�͌��~�E��X���s���s�f�U�C����}�l�W�����g�t�i�_�C�������h�ЁA1965�j
�@���@���{�x�m�Y�E�͌��~�E��g�~�Y��A��X���s�ҁs�J�b�g��f�U�C����A�C�f�A�t�i�����p�ЁA1966�j
�@���@���z���[�i�M���A��X���s��s�U��j���[����B�W�����\�\����|�p�Ƃ̗v��t�i�_���B�b�h�ЁA1967�j
�@���@��X���s����s��͂̃f�U�C���t�i�����p�ЁA1969�j
�@���@��X���s����s�r�A�Y���[�̃C���X�g���[�V�����t�i�����p�ЁA1970�j
�@���@��X���s����s�A�[����k�[�{�[�\�\���̃O���t�B�b�N��C���[�W�k�o���E���p�̐�l�t�i�����p�ЁA1974�j
�@���@�y�g������B�g���t����A��X���s��s�A�[����k�[�{�[��f�b�T���W�t�i�����p�ЁA1977�j
�@���@��X���s���s�f�U�C���Ɠ`���\�\���ƋZ�p�̘_����₢�����t�i�`���ƌ���ЁA1978�j
�@���@��X���s����s���\���G�����q�a���S���r�t�i�����p
�ЁA1979�j
�@���@��X���s���W�s��ÊG�t�i���w�ЁA1988�j
�����������̂𒆐S�ɁA�����ƂƂ��Ă̑�X���s�̍�i�i�̈ꕔ�j���ȉ��Ɍf����B1950�N��̍�i�́A�������g���̗F�l�������g�c���j�̂���ƂƂ��ɁA�����̋g���������ɉe����^������ �\��������B
�@���@���Ђ낵���s�^�钆�̗��K�ҁt�i����ЁA1956�j
�@���@�G�t�g�D�V�F���R���E�����O�g��ҁs�G�t�g�D�V�F���R�̎��Ǝ���t�i���a���A1963�j
�@���@�e��O���[�����E������s�x�g�i���푈�\�\�ʐ^�ƋL�^ ���j�̍����t�i�͏o���[�V�ЁA1966�j
�@���@�ɓ����E�����y�m�j�ҁs���{���w�̗��j9�\�\�ߑ�̖ڂ��߁t�i�p�쏑�X�A1968�j
�@���@�g�c����E�����y�m�j�ҁs���{���w�̗��j10�\�\�a���m�ˁt�i�p�쏑�X�A1968�j
�@���@��_�B�Y�E�����y�m�j�ҁs���{���w�̗��j11�\�\�l�Ԏ^�́t�i�p�쏑�X�A1968�j
�@���@����R���O���s�̕���̌^�k�����Łl�t�i�����n���V�ЁA1968�j�@�����t�ɂ́u���C�A�E�g�v�S���Ƃ���B
�@���@�����E�і[�Y���s�S�̑Θb�t�i���{�\�m�T�[�r�X�Z���^�[�A1968�j
�@���@�ۓc�o�d�Y�E�����o�꒘�s���{�̐S�\�\�S�̑Θb�t�i���{�\�m�T�[�r�X�Z���^�[�A1969�j
�@���@�����юi�E�����Б��Y���s�w��̌��݁\�\�S�̑Θb�t�i���{�\�m�T�[�r�X�Z���^�[�A1969�j
�@���@��c�Y���E���R�i�v���s���܂̓N�w�\�\�S�̑Θb�t�i���{�\�m���[�A1969�j
�@���@�ےÖΘa���s�V�S���t����k�Y�W���[�I���l�t�i�Y��A1972�j
�@���@���������ҁs���������l����t�i�݂����[�A1974�j
�@���@�K�[�f�����C�t�ҁs�ԂƐA�̕a�Q���S�ȁk�K�[�f���V���[�Y�l�t�i�������V���ЁA1976�j
�@���@���s�s�Q����Ғ��A�p�c���q����s�����ʎu�t�i�V�l�������ЁA1977�j
�@���@��X���s���s�f�U�C���Ɠ`���\�\���ƋZ�p�̘_����₢�����t�i�`���ƌ���ЁA1978�j
�@���@����e�ܘY�E�����쎡�Y�E���V���E�����ܘY���s���{�̌|�k 1�\�\�̕���P�t�i���Y�o�ŁA1978�j
�@���@�Ԗ��͑��Y�E�쑽���ΘY�E�]��U�ƌ����E��c����Y���s���{�̌|�k 5�\�\�V�h�E�V�����E�쌀�t�i���Y�o�ŁA1978�j
�@���@���㏼�V���E��R���l�E�Y�ӌH�q�E�֓��Г�Y�E���c�f�����s���{�̌|�k 6�\�\�f��t�i���Y�o�ŁA1979�j
�@���@���쒉���E�����֓V���E��֒��ԍ�E��������E�k�⒘�s���{�̌|�k 7�\�\�G�|�t�i���Y�o�ŁA1979�j
�@���@�ʏ����s�t�Ɛ푈�\�\����풆�h�̎�L�t�i���a���A1980�j
�g�����̏����̓������ѕ��́A�ŋ߂܂Ŏ���5�����Ƃ���Ă����B�s���Ɋے�������U���āA�s�g���� �����s�U���W ���o�ꗗ�t�̋L�ڂ����B���̂����A�C�� �D�͎v���Ђ̌��㎍���ɔŁs��ˎ闝���W�t�i1996�j�Ɠ��s���L�O�玍�W�t�i2002�j�́q���l�_�E��i�_�r�Ŏ�y�ɓǂނ��Ƃ��ł���B
�@������o��̈�ϑt�@�����d�M��W�s���{�C�R�t�сi1979�N9��30���A�������[���j112
�A���k�q�݂��r�́c�c�l�@�ѓ��k��Z�яW�s�O�̕���t�сi1980�N11��25���A����R�c���j123
�B���k���͖S���t�����d�M�́c�c�l�@�ĐΔԖ��W�s���g���|���e�B�b�N�t�сi1985�N7��25���A�q�r�Њ��j170
�C���k���f�m�G���}���n�i�c���̌��j�Ɓc�c�l�@��ˎ闝���W�s�����t�сi1985�N10��27���A����R�c���j171
�D���k�s����K�t�Ɓs�[���t�́c�c�l�@���L�O�玍�W�s�~���a�t�сi1987�N8��30���A�v���Њ��j187
���N�i2013�N�j��3���A����1�����g���̎��M�����ѕ��̃��X�g�ɉ�������B�A�ƇB�̊ԂɂȂ�B
���P�Ƃ̎��@�����p�V�̏W�s�����t�сi1981�N10��10���A���q�����[���j�\
�@�u������Ԃ��閲�Ȃ�ΒP�Ƃ̎�����͂�ĉԂт��H�ށv
�\�\�Ȃ������̈�A�����p�V�̎������̂悤�ɁA������B�Q���痣��A�Ƃ�ňłɘȂށA���̉e�B
�@���̉̐l�́A�����Əh�}�́u�ԁm����n�v��Y���A�݂�����́u�_�m����n�v���ԕ����A�w�����x�ꊪ���r�݂������B

�����p�V�̏W�s�����t�i���q�����[�A1981�N10��10���j�̔��Ƒсk���F�g�����l
�����͎��l�E�g���������M�����ѕ��ł����āA�}�����[�ŋƖ���A���M�����ł��낤�S�����Ђ̑ѕ��i���ꂪ����Ƃ��āj�Ƃ͐��i���ق� ����B������ �̑ѕ��̎��M���ȒP�������͂��͂Ȃ����A��������̏ꍇ�́A���e���ʂ̑��ǂɂ�����炸�A��J���Ȃ��珑�����悤���B��ˎ闝�̐��z�q�킽���̏������W�� ����r�����̊Ԃ̎����`���Ă���̂ŁA��Ⓑ�������Ă݂悤�B
�@�k���W�w�����x�́l�{���͂��łɈ���ɓ���A����͌��܂����Ƃ������̂́A�ЂƂ�����肪�c�����B�т��ǂ����� ���ł���B���̂��Ƃ�����R�c�Őq�˂�ꂽ�Ƃ��A���͑т̂��ƂȂǂ܂������l���Ă��Ȃ��������牽���v�������A�g������Ƒ��k���Ă݂܂��Ɠ������̂��� ���B
�q�\������@�A�a�J�s�n�o�ŋg�������Ƃ�����āA�w�����x�̑т̂��Ƃ𑊒k����B�ѕ��̎��M���������ꂽ �̂Łw�����x�O�Z�����n������r�@ ���̓��A���͏����͂Ȃ��Ă��\��Ȃ��̂ʼn��������Ă��������Ȃ��ł��傤���Ƌg������ɂ��肢�����B�����v�����Ȃ��������ʂ̏o�����ŁA�g�����̑ѕ��� �͂Ȃ��A�g���������������̂ł���炵���ѕ��Ƃ������̂ɁA�t�C�̓��荬�����������o������������̂����A�g������͂�������́u�����v�Ǝ~�߂��炵 ���B��������Ɓu������v�Ɠ������A���ꂩ���l�ł��炭�L�ɂ��Ęb�����Ă����L��������B
�q�\���\�Z���@�����A���k��V���m�A�[���B�g����������ѕ��̌��e�����������B�������A�r�܁A����R�c�ɓ͂� ��B�r���A�g������d�b�őѕ��̌��A�ύX�̘A������B���W�̂��߂̍�Ƃ̂��ׂĂ���������r�@���ǁA������ꂽ�ѕ��͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B
���f�m�G���}���n�i�c���̌��j�ƐH���m�A���}���n�i�m���o���j�Ɉ˂��āA���G�ɐD�萬���ꂽ�A�A�쎍�тƂ����� ���B�i���t�̉N�����j���甭�����Ă���̂ɁA�S�ʓI���ł̊뜜�����낤���B�������A���̎��т́i���j�ɂ͂��炫�����Ă���i���u�j������B�@ ���e��������Ƃ��A���łɁu�g�����v�Ƃ����������͂�����ƋL����Ă��āA���͂��̌�D�ӂɊ��ӂ����B�u���f�m�G���}���n�v�u�H���m�A���}���n�v�u�� �t�̉N�����v�u�S�ʓI���Łv�Ȃǂ̌��t�́w�����x�̎��傩��̈��p�ł���B�Ƃ͂����A���e�����������Ă���A�킸���Ԃقǂ̊ԂɁA�Ō�̈ꕶ�̂ЂƂ� �̌����߂����āA��ې[���Ȑ܂��������B
�@�g������͍ŏ��A�u���̎��т́i���j�ɂ͂��炫�����Ă���i��j������v�Ə������炵���B�����A�g������ɂƂ��āu��v�Ƃ������t�͎��̌��t�ł����āA �U���̂���ł͂Ȃ������B�����グ�Ă���������炵���A�u��v����ŏ����āA�������e��������Ƃ��ɂ́u�i���j�ɂ͂��炫�����Ă�����̂�����v�Ƃ� �����͂ɂȂ��Ă����B���ɂ́A���ꂪ�g������̌��t�炵����ʞB������s��ł���悤�Ɏv�����̂ŁA�u���́v���́u��v�̕��������Ǝv���Ɛi�����A�u ���A�l�����܂�Ă���g������́u�������ˁv�ƌ����čĂь��́u��v�Ƃ������t���������܂ꂽ�B
�@���̌��e�������āA���͏���R�c�Ɍ��������̂����A�����ɋg������d�b������A�u��v�ł͂Ȃ��u���u�v�ɂ��悤�Ƃ����A�����������B���̐��ɂ͐捏 �̖����͂�������Ȃ��A�A�铹������g������͂��̈������Ƃ߂Ă����ƍl���Ă���ꂽ�̂��ȂƎ��͎v�����B
�@���s��A�g�����̏�������������Ă��鏬�ш�Y������A�g�������P�s���W�ɑѕ������̂͂��ꂪ�͂��߂Ăł͂Ȃ����Ƃ����A���������������B����R�c �̑��j�����́u�g������̏����ꂽ���̂ɒ���������̂�����A�ߍ��̎Ⴂ�l�́\�\�v�Ƌ���ꂽ�B�o���オ�����{�����������ɑ����Ă���A������A�� ��Ȃ̂��A�y���F�������}�ւʼn���̂��Ԃ��ׂ̒Е����͂����A�������B
�@���̂悤�ɂ��Ď��̍ŏ��́u�����v�́A���Ɋ��������B�i�s�g�����̏ё��t�A�W���v�����A2004�N4��15���A�ꔪ�`���y�[�W�j
�Ō�̈ꕶ�u�������A���̎��т́i���j�ɂ͂��炫�����Ă���i���u�j������v�́u�i��j�����́��i��j���i���u�j�v�ƎO�]�����킯��
�i���e�����Ă��Ȃ��̂ŁA�p�[�����͖��m�F�j�B���Ȃ݂ɁA
�k�c�c�l
���f�m�G���}���n�A�H���m�A���}���n
���ɂ͂��炫����
�S�ʓI���ł�����
�k�c�c�l
�Ƃ�����������̒����ɂ����сq���̏ё��r�̖����ɂ́u�i���́A�L�����Ə����̂���uLes
Georgiques�̕��ցv�Ɓu�|��Ɓ^���邢�͈��p�v�A���̂悤�ɑ肳���ӂ��̘_�l����C�ӂ̕��߂����o���A���閬���ɂ���čĂэ\�z����B��
���āA�����B������Y�ށm�A�A�n���̂͂��������N�ł���̂��H�v�i�s��ˎ闝���W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1996�N9��1���A���Z�y�[�W�j�ƒ����Ă�
��B���сq�\�L�̐��r�ɂ́u��̒��̐��@���̂Ȃ��Ɂ@�i���́j���u�̂Ȃ��Ɂv�Ɓu���t�̉N�����m�����݂ǂ��n�v�Ƃ������傪����B�g���̑ѕ��̎�v�ȕ�
���́A�܂�������˂̎�������������̂������B���̏�˂̎��т͖L��́u�_�l����C�ӂ̕��߂����o���A���閬���ɂ���čĂэ\�z�v�������̂��Ƃ����B��
���������肩�����g���́u���̌��t�v�ł���i��j�ł͂Ȃ��A�i���u�j�Ƃ����u�U���̌��t�v�Ɏ��ʂ������B��ˎ闝�́q�킽���̏������W�̂���r�́A�ѕ���
���������ȁA�������d�v�ȎU���Ɍ������g�����̎p���������ɕ`���Ă���B
�L�����qLes Georgiques��
���ց\�\un
dess(e)in�r�i���o�́s�����K�N�t�n�����A1982�N6���j�ɂ�������i�o�T�͖L�����s���҂Ɓi���Ắj�Y�p�t�A�}�����[�A1986�N11��
28���A��Z�y�[�W�j�B
�@���ׂẮA��́u��ʁm�Z�[�k�n�v����n�܂�ȑO�ɁA��̈��p�A���Ȃ킿��̔�������n�܂��Ă����B�n�܂� ���n�܂�̒�����n�܂������Ƃ͌����ĂȂ����A���ꂩ����Ȃ����낤�B���̈��p�i�G�O�[���O�j�ɂ͂����ǂ܂��\�\
�������̕��y�A�G�߁m�Z�]���n�A���m�\���n�A�F�A�ŁA���A���f�m�G���}���n�A�H���m�A���}���n�A�����A���فA �^���A�x���A���ׂĂ����������Ă����Ƃ����@�B�A�����̍��ɂ͂��炫������̂ł���B
�i-�i�E���\�[�i�w�����x�j
���́u���f�A�H���v�́A�W����=�W���b�N�E���\�[�́s�����t�́q��㊪�r�Ɂu�����ΐ��_�������݂��������I�g�D�A������Ȃ�Ƃ����� ���_�̏����� �Ȃ�悤�ɓ����������Ȃ�A�ǂ�Ȃɗ����̂���܂����~���A�����̔������ӂ����邱�Ƃ��I�@�C��A�G�߁A���A�F�A�ŁA���A���f�A�H���A�����A�Î�A�^ ���A�x���A�����������ׂĂ������̓��̂̋@�\�ɂ͂��炫�����A���������Ă����̍��ɂ͂��炫������B����炷�ׂẮA���������R�Ɏx�z���Ă� �鏔��������̍����ɂ����ē������邽�߂́A�قƂ�NJm���Ȗ����̎肪�������Ă���v�i�K�����v��j�Ɠo�ꂷ��B�u���������p�v�̒T���̗��ɏI��� �͂���̂��낤���B
�k�NjL�l
�N���[�h�E�V�����̑��s�_�k���t�́A�������s����31�N���2012�N2���A�F��v�̖�Ŕ����Ђ��犧�s���ꂽ�B�u�w��ʁx�A���������Ƃ킵���_�k���\�\�B�v�i������b�q�j
�k2013�N8��31���NjL�l
�u���͖S���t�����d�M�́k�c�c�l�v�ƉĐΔԖ��W�s���g���|���e�B�b�N�t�i�q�r�ЁA1985�j�ɑѕ������g�������A���҂́sBan'ya/�E�F�u���u���O�t���q�R�O�N�O�̋g�����̂͂����r�ɑ���W�s��L�t�i�Òn�ЁA1983�j�ւ̗�摜�Ō��J����Ă���B���ʂ�^�����Ă��������B
�w�؏�L�x���Ȃ���A�����\�グ��̂��x��܂������Ƃ��A���l�т������܂��B����͓ǂގ��@���A�l���Ă�������̂��ƁB���āA�{����ǂ��A�[�����x�����ڂ��܂����B�ߗ��̎��̔o��̍�i�ŁA����قǁA��鄎u���Ɛ��n�x���A���˂��Ȃ��������́A�H�ꂾ�Ǝv���܂��B�]�_���������邱�ƂȂ���A���ꂩ��́A���ւ̐��i��]�݂܂��B
�܌��l���@�@�@��
����Ŏ��̋�W�ɑѕ��𗊂܂Ȃ��@�͂Ȃ����낤�B�Ȃ��A�g���́q�d�M�ƒ�q�r�́q�S�@�r���̏j���r�ʼnĐΔԖ�̋�ƂɐG��āu���߂āA��W�w��L�x�Ɉ˂�A����������z�Ŋ����̂���ǂ��o���i��m�����̂��v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O��܃y�[�W�j�Ə����Ă���B�g�����₵���A�ł��Ⴂ����̔o�l�ւ̌��y���Ǝv����B
���l���s�r�n�k��l�t�S6�������s���ꂽ�̂�1947�N9������1948�N6���܂łŁA�g���������́s�k�t�i�S10���A1959�N8������1962�N9���܂Łj�Ɗr�ׂĂ������Ƃ͌����Ȃ����A�s�r�n�t�̖��͐�㎍�̑�\�I�ȃG�R���Ƃ��Č��`���ꂽ�B�s�r�n�t�h�̎��l�ŋg���ƍł��e���������̂́A�O�D�L��Y���낤�B�O�D�͓y���F�́u���͓��̎t�v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A��l�y�[�W�j�ł���A�g���Ƃ͈Í�������ʂ����m�F�ł��������B�O�D�Ɏ����Őe���������̂͂����炭�c�����ꂩ�k�����Y�ŁA���c�O�Y�E���ˉ�v�i��l�Ƃ��g���Ɠ��N���܂�j������ɑ����A����M�v�i�g���̖����s�U���Ɉ��쎍�W�ւ̌��y������j�E�g�{�����i�g���ҏW�́s�����܁t�ɋg�{�̎����_���f�ڂ���Ă���j�ɑ��Čh�ӂ͂Ƃ������A�e���̏������Ă������͒肩�łȂ��B�،��F��i�s�A���\���W�[�R��t�Ɂq�r���r���̂����j������ˑ��Ƃ̐ړ_�͕s�����B
�g�������Ɓs�r�n�t�h�̎����l����Ƃ��������v���o�����̂́A�k�����Y�̋g���]�ł���B�k���́s���㎍�蒟�t1978�N10�����q���W�E��㎍��10�с\�\�lj��Ɠ��c�r�Łu�ނ̏o���Ă���c�����A���I�Ȃ��́A�����A�X�����Ƃ��A�Â����̂��炵�����������Ƃ��A�����������̂̃C���[�W�́A���Ƃ̋g�������\������悤�ɔ��ɋ�J���ď����Ă�Ǝv���܂���B�����ǂ��̈�тƂ������ƂŁk�q�����r���l�o�����Ӗ����l����ƁA�ǂ�ȂɌ��ꐢ�E���A���ۂ̐��E���ƌ����Ă��A������Ɩ{�����o�Ă�Ƃ�������������ˁB�k�c�c�l�����A�k�s�m���t�́l���t�̎g��������Y���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�O�D�L��Y�Ɠc������̉e���������Ƃ������Ȃ����ȂƂ����C�����܂����ˁB�Ƃ��ɎO�D�̎��������Ƃ��ڂ����ǂ�ł��Ȃ����ȂƂ����C�����܂����ˁv�i�����A��Z�l�y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�O�D�̑�ꎍ�W�s���l�t�i��J���X�A1949�j�Ƌg���̎�����̑�ꎍ�W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�Ƃ̊W�͏ڍׂɌ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�s���l�t�Ɠc���̑�ꎍ�W�s�l��̓��Ɩ�t�i�����n���ЁA1956�j�̊W���𖾂��҂����B
�g���̐��z�q�c������E�f�́r�i���o�́s�����C�J�t1973�N5�����j�ɋ���A��l��1959�N4��17���A�}�����[�̓����̏Љ�ŏo������i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꔪ�O�y�[�W�Q�Ɓj�B���̒}���̓����̂r�Ƃ��������́A��̂���Ȃ̂��낤���B�g���̐��z�͎l�̒f�͂��琬��B���Ɋے�������t���ƁA�@�͓c���Ƃ̏o��Ƃ��̏�ƂȂ����i���X�f�~�A���̏���l�Ƃ̃G�s�\�[�h�A�A�͏�������s�l��̓��Ɩ�t����̂����A�Ȃ����߂�����Ɍ������̏��������������Ɓi1961�N3��6���̓��L�ɋ���A�g���̕��ɓc�������������́u�j�b�J�̃u���b�N�����y�����Ă��ꂽ��������̋L�O�ɁI�v�j�A�B�́q�ɂԂ��S�r�S�т̈��p�Ə��N����̉�z�A�C�́s�̎v�z�t�i�v���ЁA1967�j���߂���^���A�Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B�C�͂������B
�@������A�c������Ə��쒬�̃V���R�[�O�����Ńr�[��������ł����Ƃ��A����͍��x�A�q���E���R�r�Ƃ������W���o���Ɖ]�����B���͈�u�A���A�q���C���R�r�����Ԃ���ȑ�̎��W���Ǝv�����B����q���E���R�r���ƙ�X��B�ނɂ͉�S�̕\��炵���A�������낤�����肩�������B���͓��S�����Ă����B�����������炻�̍��A�s�ې��Ȑ�������߂āA���N�̂��߂ɔނ͖�����J���āA�`������ł������߂�������Ȃ��B�����ĂЂ����ɁA���E���R��r�����Ă����̂��낤�B���ꂩ�炾���Ԃ����āA�V�������W�����ɏo���B����́s�̎v�z�t�ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�ꔪ�Z�y�[�W�j
�A���R�[���Ŏ�����̂�`�Ŗ��₷�c����z������Ƃ��낪�A��������ꂸ���������B�����Č���̂��炵���B���̒f�͂́A�g����1967�N6��20���̓��L�u���h���I�œc������ƃr�[���B�c���ɏZ�ݐ`���̂݁A�̓��̖ʉe�����H�@��H��敂̈̑傳��M�S�Ɍ�錒�N�Ȃ闲��v�i���O�A��O�y�[�W�j��z�N������i�s�̎v�z�t�͓��N9��1�����s�j�B������ɂ��Ă��A�{�т͋g�������l�ɂ��ď��������͂̂Ȃ��ŏo�F�̂��̂ł���B��ˎ闝�Ҏ[�́s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�t�i�v���ЁA2006�j�ɍ̂��Ă��Ȃ��̂��ɂ��܂��B�Ƃ��ɁA�g���ƎO�D��}���̂��y���F�Ȃ�A�g���Ɠc����}���̂͐��e���O�Y�ł���B�V�q�r��͐��e�́sAmbarvalia�t�Ɓs���l���ւ炸�t�����߂����ɖ{�̉���œc���̎��сq���C�����b�h�̉Ď��r�Ɍ��y���āA���̑O��25�s�����������A���́s�V�N�̎莆�t�i�y�ЁA1973�j�Ɏ��߂�ꂽ�q�D�F��俁r�ɒ��ڂ������B
�D�F��俁\�\���O�Y�搶�Ɂb�c������
67�N�̓~����
68�N�̏��Ă܂�
�ڂ��́u�h�i���[�v�Ńr�[��������ł���
���̋㎞����o�[�ɂ�肩������
�h�C�c���O�̃r�[��������ł����
���N�̕w�l������Ԃ������Ȃ���
�X�ɓ����Ă���
�ڂ��ƂȂ��Ńr�[�������肵�����̂�
�A�����J���E�t�b�g�{�[���̃X�R�A�E�{�[�h��
�Ԗ͗l�̕ǂɂԂ炳�����Ă���
���l�����̂��ł���炵�Ă���
��������1939�N�n�ƂƎ�I�ɓ����Ă���
���̖k�Ē������̑�w���Ȃ�
�V�܁m���ɂ��n�̂ق���
1939�N��W�EH�E�I�[�f����
�j���[���[�N�̌\��ԊX��
�u�D�ƃG���X�v�̃E�C�X�L�[������ł����u���v��
���́u���v�͔R���ĔR���ĔR������
���E�͊D�ɂȂ���
�u�h�i���[�v�̖��
�A�����J�̕E�̎��l�⒆���̖S���҂�����
�ڂ��͂ނ�݂Ɋ��t�������̂�
���E���D�ɂȂ�����������
�ڂ���͂������������t���g��Ȃ��Ă�����
�o�ϗp��Ɛ����I����Ƃ�
��͂����܂������čs���̂�����
���Ɛ_���܂͎��ӂ�����Ă�������̂ł���
���N�̏t
�ڂ��́u�h�i���[�v�ɂӂ���Ɠ����čs����
�ڂ��ɂƂ��Ă͎O�N�Ԃ肾��
�u�h�i���[�v�̂��₶�ɂƂ��Ă͂�����̂��Ƃ�
�E�̎��l��S���҂����͂������Ȃ���
�X�R�A�E�{�[�h�����ău�����N�̂܂܂�
���҂����҂����Ȃ��Ƃ�
���������҂�����
���₶�̕����ʂ͂��̂�����
����
�r�[���ɂ͂���������
�������炻���Əo�čs������
�M���V���̕���
�o�b�J�X�̌��ƃj���t�̐V�����܂���������Ă���
�����������݂�
�u�D�F��俁v�Ƃ����������̕���
���o�́A�������_�Ђ̋G�������s�����t��29���i1972�N8���̂��̍��͐��e���O�Y�̑����W�ŁA������11�ю��߂��Ă���j�B�ނ��c���́A���e�́q俁r�i�sAmbarvalia�t�����j�܂��Ă���B
俁b���e���O�Y
�R�N�E�e�[�����݂͂��ڂ炵�����K�U���
���邪�M���V���̒����͉����̉�������B
�u�D�F�̓��v�Ƃ��Ӄo�[�֍s�Ă݂��܂ցB
�o�R�X�̌��ƃj���t�̐V�����܂����������
�Í��̕s�ł̐������A���ӂ�
�ԗւ̂₤�ɑ傫�ȃq�����Ƌ��ɌO��B
�c���̌����͋g���ɏՌ���^�����Ǝv�����B����Ƃ����̂��A�������ɍڂ����g���̎����q��q�r�i�F�E15�j�ɂ͂����������o�̎��ʂɌ����ł���|�̎������Ȃ������̂ɁA��N�̋g���͂��̓_���߂����Ċ�ȂقǍ������Ă���̂��B�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́q�V�@�u�Ẳ��v�r�ɂ�������B
�@���͂������e�搶�ɕ����鎍�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����B�Ȃ����Ƃ����ƁA������Z�A���N�قǑO�A�u�����v�̐��e���O�Y���W���ɁA�q��q�r�Ƃ����Z�����������Č����Ă����B�����l����Ƃ��낪�����āA���͓�N�Ԃقǎ�����~�߂Ă����B����Ȑ��_��Ԃ̂Ȃ��ŏ��������Ȃ̂ŁA���W�s�_��I�Ȏ���̎��t��҂ނƂ��A�搶�ւ̌����ł��鎌�����A�폜���Ă��܂����̂ł������B�͂����āA�搶�͂��̂��ƂɋC�Â���Ă����邩�ǂ����͒m��Ȃ��B�������A���͐S�ꂵ�������Ă����B�����ԑO�Ɋ��s���ꂽ���W�s����t�̂Ȃ��ɁA�q���V�L���r�Ƃ����Z����������B�搶�����̂��߂ɏ����Ă�������������ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A��O�Z�y�[�W�j
���͂��˂Ă���g���̍����̌�����ʂ肩�˂Ă������A���e������c���������鍜�@�ɁA�܂�c���́u��q�v�Ԃ�ɁA�V���b�N�����̂ł͂Ȃ����B����ł́A���e���O�Y�搶�̒�q���Ȃǂƌ��������̂ł͂Ȃ��B�c���̎��݂Ȉ��p�i�ނ��늷���D�فj�ɔ䂵�āA�g���̈��p�͍��������Ă���Ƃ������A���`�Ɉ��p����t���āi������2��ށj�A�����邨����Ƃ����������ł���B
�k�c�c�l
�q�i���Ƃ͍��̌��݂̂��Ɓr
�k�c�c�l
�u�֏��͂ǂ����Đ_��I��
�@�������ɂ���̂��v
�k�c�c�l
�g���͂���ȑO�A�s�o��]�_�t�n���\���N�L�O�S�����̍u���Łu�������A�����ɂ���������F����A�V������ƂƂ����̂́A��������Ȃ��āA�����Ɉӗ~�I�ɁA���Ƃ��A���̌��Ă����u�~�]�v�Ƃ����f��ƁA����Ƃ����т��悤�Ƃ��A���������l���ŁA����Ă���������Ǝv����Ł\�\�A�l�́A�o��͔o�傩��w���A���̂��̂���w��łق����Ɓ\�\�A���͎�����w���A��������̂���w��łق����ƁA���������ӂ��Ɏv���܂��̂ŁA�F������A���ꂩ��A�悢��i�������ĉ�����悤�ɁA���肢���܂��v�i�s�o��]�_�t78���A1968�N3���A��l�y�[�W�j�ƌ���Ă���B���������쎍�@���f���Ă������l�������������̏Ռ��͂��A�c���̌����ɂ͂������B�������璆���g�������́u���p�v���n�܂�B1969�N12���Ɂu�c������ҏW�̋G�������u�s�s�v�Ɉ˗�����āu�R�����v����������A�v���Ƃ��날�莍�\���邱�Ƃ��b���~�߂�v�i�q�k�g�����l�N���r�j�̂́A�^�ɋ��R�ł͂Ȃ������B
�k�t�L�l
�g���Ɠc���̏o��̒���҂Ɋւ��ẮA�ʂ̐�������B�s�c������S���W�t�i�v���ЁA2000�N8��26���j�̓c��q�N��ҁq�N���r�ɋ���u���܋�N�i���a�O�\�l�N�j �O�\�Z���^�k�c�c�l�l���A�ѓ��k��̈������킹�ɂ��A�_�c���쒬�̃R�[�q�[�X�f�~�A���ŋg�����ɉ�v�i�����A��l�܌܃y�[�W�j�ł���B����҂����قȂ���̂́A���邢�͓������̂��Ƃ��B��l��ւB
������11��
�@��c�j�Y�q�n���J�r�A�A�ѓ��k��q���b�\�[�Ɛ��e����̖X�q�r�A�B���萴��Y�q���e���O�Y�搶�r�A�C��������qCredo�\�\���e���O�Y�����Ɂr�A�D����S���q����i���r�A�E�c���@�����q�q���l�Ȃ肹�\�\���e���O�Y���ɕ����r�A�F���c�q���q�q�H�̎��l�\�\���e���O�Y�搶�Ɂr�A�G�c������q�D�F��俁\�\���e���O�Y�搶�ցr�A�H����C���q���H���̂���R���[�W�����\�\���e���O�Y���Ɂr�A�I����l�Y�q�S���̖̉��\�\���e���O�Y���Ɂr�A�J�g�����q��q�r�B�ȏ�A�f�ڏ��B
�g�����ɂƂ��āA�A���h���E�W�C�h�i1869-1951�j�̓��C�i�[�E�}���A�E�����P�i1875-1926�j�ƑɂȂ鑶�݂������B�g ���̎��ƎU���ɂ͂�������B
�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����i�q�ʕ��̏I��r�D�E2�B���o�́s������t9���A1959�N6���j
�� �鏭���ւ̗��ɔY�݁A�E���������ꂵ�����痣�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ�������\�̐t�B�k�c�c�l�����P�̎��ƃW�C�h�̏����Ȃǂ����̍��̖����̏��Ƃ� ���悤���B�i�q�Ǐ����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���y�[�W�B���o�́s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8���j
�܂��A���̂���̓Ǐ��X���������U�肩�����Ă���B
��Z����̎��́A�����̕����ŁA�����̖|�w���A�ǂ݂������Ă������̂ł���B�Ƃ��Ƀt�����X�̏������D�݁A �W�����W���E�T ���h�w�J�t�̂ނ�x��X�^���_�[���w�p�����̑m�@�x�����ăA���h���E�W�C�h�̏���i�ł������B�i�q�����w�����Z�L�x�r�A���O�A�O�y�[�W�B���o�́s���� �W���[�i���t1982�N3��26�����j�g���̌������ꂽ���L�␏�z�𑍍�����ƁA�u�A���h���E�W�C�h�̏���i�v�͎��̂悤���ƍl������i�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�Q �Ɓj�B�̊��s���Ɍf����B
1939�i���a14�j�N�́u�O���^���i�� ���s���j�@�w����� ��x�ǂ߂ǂނ��������A������߂�B�w�ł̗́x�ǂݏI��B���́w���P�^�C�X�x�B�v�i�q���܂�͂����L�r�A���O�A��O�y�[�W�j�ɘf�킳��Ă͂����Ȃ��B�� ��A�{�i�I�Ɏ��������͂��߂��g�����ł��䂩�ꂽ�̂́A�u�����_�����v�i�������I�s���i���F�_�\�\�u�����L���v�̐����ƃ{�[�h���[���t�A���M���A2008 �N10��30���A���Z�y�[�W�j����s�������t�������ɈႢ�Ȃ��B�������ɁA�g���X�g�C�̋Y�ȁs�ł̗́t��A�i�g�[���E�t�����X�̏����s���P�^�C�X�t�� �ǂސl�ԂɂƂ��āA�s�������t�͓���������낤�B�W�C�h�̏���̂����s�w���ҁt�i1902�j�A�s��t�i1909�j�A�s�c�������y�t �i1919�j�A�s���̊w�Z�E���x�G���t�i1929�E1930�j�́A��҂ɂ�镪�ނɏ]���Ε���m���V�n�ł���B�s�p�����[�h�t�i1895�j��s�@�����̔� ���t�i1913�j�Ƃ��������Ԍ��m�\�`�n�i�s���w�ك��x�[�����a�厫�T�t�ɂ́u�W�b�h�����Ȃ̒��ԓI�v�f���܂�A�̕��h�������A�u����v�A�u�����v�� ��ʂ��邽�ߗp�������́v�Ƃ���j���������Ă��Ȃ��̂͋����[���B����9�N��A1948�N3��16���̓��L�ɂ́u�W�C�h�s�@�����̔����t�Ǘ��B������x�� ��ł݂悤�v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j�Ɠo�ꂷ��B�����炭���̐ΐ�~��̊�g���ɔŁi��g���X�A 1928�j�Ɠ��l�ɁA�W�C�h�B��̏����m���}���n�ł���s�������t�i��҂͂̂��Ɂs��������t�Ɖ��肵���j���A���g�̎���͍����Ă��ă����P�́s�� �_���t���Ĕ��������g���ɓǗ����邢�͍ēǂ������Ȃ������Ƃ͍l���ɂ����B���������ϓ_���炱�̒��я������ēǂ��Ă݂��i�R���`�Y��s��������k�V���� �Ɂl�t�V���ЁA1969�N2��15���j�B
��Ƃ����܂萳�m�ɐl����`�ʂ��悤�Ƃ���ƁA�Ƃ����ǎ҂̑z���͂������邩���ɁA�������Ă��̔��I��W���錋�� �ɂȂ�B���� ��ǎ҂ɁA�D������ɐl����z���������ق��������A�Ɣށk�G�h�D���[���l�͍l�����B�ނ͂��ꂩ�珑�����Ƃ��Ă��鏬���̂��Ƃ��l���Ă����B����́A���܂� �ŏ��������̂Ƃ͎��Ă������Ȃ����̂ɂȂ�͂��������B�w����m�ɂ����ˁn�����x�A���̑肪�������ǂ����A����ɂ͎��M�����ĂȂ������B�\���������� �͂܂��������ȁB�ǎ҂�ނ낤�Ƃ��Ắs�ߊ��t�\���A����͂������ɋ��ȏK�����B������ނ��͂��Ȃ����낤���A�����āA��҂͂���ɂ�����c�c�� ��ɁA���̑�ڂ��������������A�ނɂ͎��M�����ĂȂ������B�ނ́A�����ƑO����A���̍�i�̂��Ƃ���l���Â��Ă����B�����A�܂���s����A�����Ă͂� �Ȃ��B���̂����A�ނ͈���̃m�[�g�ɁA�S�o�����Ƃ��v�����Ȃǂ����낢�돑������ł������̂������B
�@�ނ́A�X�[�c�E�P�[�X�̂Ȃ�����A���̂��߂̃m�[�g����肾�����B�����āA���N�M���|�P�b�g���炾�����B�ނ͏����B
�@�@�@��������A���ɏ����{���̂��̂łȂ�������v�f���������邱�ƁB�k�c�c�l�i�����A��Z��y�[�W�j
�u��������A���ɏ����{���̂��̂łȂ�������v�f���������邱�Ɓv�Ƃ����咣���A�W�C�h�̏����s��������t�̓o��l���ł��鏬���� �G�h�D���[�� ���A���ꂩ�珑�����Ƃ��Ă��鏬���w��������x�Ɋւ���S�o����v���������낢�돑������ł������m�[�g�ɍ��܂��ɋL���ꂽ�͋�ł��邱�Ƃ͒��ڂ��� ��B�쒆�l�����鏬���Ƃ����ꂩ�珑���͂��́A�W�C�h�̎��݂��鏬���s��������t�Ɠ���̍�i�w��������x�̑n��m�[�g�ɖ��߂��܂ꂽ�咣�A�Ƃ����� ��ῂނ悤�ȓ���q�\���ɂ́A�t�B�N�V�����ɑ�����ȐM���ƁA����ɂ�������炸�A���邢�͂���䂦�ɁA�T�d�ɂȂ炴������Ȃ��W�C�h�̎��M�ԓx���� ����Ă���B�g���̎��сq�ʕ��̏I��r�͂ǂ����B
�˂Ɏ��ʐl�̂܂��ɂ���H�т̒��̂Ȃ���
�����ӎ��̊O�ʂł͂������
�E���̌��̗�
���̐^�V�����������̊��т̐[�w��
���I�Ɣ������肩����
���ʐl�̗c�N���̏ё�������
�k�c�c�l
���Ɣ��̔��̌���瀎������N�̎�����]������
�k�c�c�l
���B�ˑ��ւ̓��M�Ɖ��@
�k�c�c�l
�I�y���ق̋ɍʐF�̕���̗\���̉̎肽��
�k�c�c�l
�K���{�̔�ւ̉��ߊ�
�A�i�x���̌��̐O�̐G�}
�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����
�g���l���̈łŎ��ł���
�k�c�c�l
�[���Ȏ��̋��|�̓`����
�k�c�c�l
�����̐l�ނ̎��E���ɂȂ�˂Ȃ�ʖ����̎�
�����ȗ����ނ̊��ݍ��������̒Ⴂ�p��
������鎀�E���ĉ�����鎀
�k�c�c�l
�����ʐl�̔����̓����}
�ё��̏��N�͖͕킷�邾�낤
��l�̏K���̂ʂꂽ�H�т����炷����
���݂�鏌���̊g����
���̎��ɂ́u���v�ƁA��ҋg���̗������v�킹��ɂ܂��ŗL�����i�u���B�ˑ��v�u�I�y���فv�u�K���{�v�u�A�i�x���v�j�ƕ��|�̗p
��i�u���I��
���v�j������݂���Ă���B�����Ď��т̂قڒ����Ɉʒu����u�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����v�Ƃ����茾�B�����ŋg�������̎����W���
������u�i���v�Ɓu���_�v�̗p������悤�B�Ȃ��u�i���Ɂv�́A�ΏۂƂ��Ȃ������B
�E�i���̐S�Ɠ��̈��L(�q�����r�C�E19)
�E�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����i�q�ʕ��̏I��r�D�E2�j
�E�i�����Ȃ���Ύ��i���Ɂi�q�́r�D�E9�j
�E�ꂽ�J���o�X�������Ɖi���łȂ��ł���i�q�n�E�t�̊G�r�E�E5�j
�E�i���ۑ����\�Ȃ�i�q�Â��ȉƁr�E�E16�j
�E�̌��z���Ƃ����Ă��i���i�q�}�N���R�X���X�r�F�E1�j
�E�i���̈�p�b���������I�i�q�������r�F�E10�j
�E�i���̖��Â̂Ȃ��Łi�q�_��I�Ȏ���̎��r�F�E11�j
�E�S�_�������肻�߂̉i����I�i�q�ẲƁr�F�E13�j
�E�q�i���Ƃ͍��̌��݂̂��Ɓr�i�q��q�r�i�F�E15�j
�E�����Ă��鎞�͉i���̉ԉł̎��̂悤�Ɂi�q���C�X�E�L��������T�����@�\�\�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�G�E11�j
�E�u���̂��i���̃X�y�N�g���v�i�q���̖��{�r�H�E9�j
�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ꂪ�i���ł����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Ɂi�q�V���r�J�E9�j
�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킪�i�i���̕�j�̐�������`����i�q�C�g�r�J�E19�j
�q�i���̒��Q�r�i�������сE19�j
�E�B��Ƃ��ĉi���̍��u���悶�̂ڂ�炭��������i�q�g��i���Ɏ~��r�������сE10�j
�E�̑����鏭���̂͂邩�Ȃ鎋�_�Łi�q���e�j�i�O�m�[�����j�r�G�E27�j
�u�i���v�́u���_�v�̕����玍��������ق������Ƃ͓�������B���₱���́u�i���̎��_�v�������B�ނ���u�͂邩�Ȃ鎋�_�v�Ƃ����A�� ���̂͂��ꂩ ��̂悤�Ȏ���̂ق�������ɋ߂��B�ł́u���Ձv�͂ǂ����B���́q�|�[���E�N���[�̐H��r�̎��傪�A�B��̗p��ł���B���l�̕����ł���ȏ�A�L�̋��Ղ� ���āu���Ղ���v����̂̓J�����A�C�������肦�Ȃ��B���ꂳ���u�ł��Ȃ��v�B�e�[�u���N���X�ŕ���ꂽ��������猩��A�V�ɋ킯�����邱�Ƃ��n�ɐ��邱 �Ƃ��ł��Ȃ������\�\�B
���l�̔�ƍ�����̋��͒���
���Ղ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̎s��
�Ƃ�̂����ꂽ�z�̒f�R
�L�������ƌ��グ��
�Â������������Ă��邨���݂�
�����㢂͗����Ă���i�q�|�[���E�N���[�̐H��r�I�E1�A11-16�s�߁j
�u�i���̎��_�́k�����l������Ղ����v�ƈ�ʉ����Ă݂�ƁA���̎���̓��ق����悭�킩��B���ꂪ�u�i���̎��_����k�����l����Ղ� ��v�Ȃ�A�� ��Ȃ�ɕ��ӂ͒ʂ邵�A���������₷���B�����A�悭�l���Ă݂�u�i���̎��_�v�������琶�܂��͂����Ȃ��A���ꂪ�����������琶�܂����̂Ȃ�A�W�C�h �̏����ł��낤�������P�̎��W�ł��낤���A���̂��Ƃ���Ղ��邽�߂̎��_�̑���ɂȂ肤��B�l���Ȃɂ���؎��ɋ��߂�Ȃ�A���ꂪ�ǂ�Ȃ��̂ł���K���� �Ȃɂ�����Ă����B���@��͍����鎍�l�ɂ́A�����璼�ړ�����̂͂ނ��돭�Ȃ�������������Ȃ��B�Ƃ��ɁA�W�C�h�́s�������t���M�����̓��L���� �����Ă���B�s�������̓��L�t�i����Ŋ��s�́s�������t�Ɠ���1926�N�j�ł���B�M��́A��O�ɖx����{��ŋ������ŃW�C�h�S�W�i1934�j�A ��،��Y��Ō��ݎДŃA���h���E�W�C�h�S�W�i1934�j�ƒP�s�{�i�����ЁA1935�j������A���ɖx����ŐV���ДŃA���h���E�W�C�h�S�W�i1951�j�A ��ؖ�ŒP�s�{�i�O�}���[�A1952�j�A�p�앶�Ɂi�p�쏑�X�A1954�j�A�p�쏑�X�ŃW�C�h�S�W�i1957�j�Ȃǂ�����B�g���̎���u�W�C�h�k�c�c�l�� ���v���{�����Ƃ��āA�s�������̓��L�t�������Ă݂悤�B���p���́s�A���h���E�W�C�h�S�W�k��15���l�t�i�V���ЁA1951�N8��31���j�̖x����{ ��B�Ȃ��A�����͐�����V���ɉ��߁A���̎��_�͊J�����B�J��Ԃ��L���i�T�U�X�Ȃǁj�͂Ђ炪�Ȃ⊿���ɒu���������B�����́i�@�j�̐����͓����ł̌f�ڃy�[ �W�B
�@�Ƃ���ŁA���̎d�����ݗ��̏����̃^�C�v�ɋ߂Â��悤�Ƃ�����邾���A����͑������̂̂₤���B�Ɠ����ɂ܂��A �l���꒩�A�� �̎d���ς�Ȃ��̂ɂ��悤�ƕ������߂��ւ�����A�����m���Ӂn�̏�������͑�����������Ďd���ӂ₤�ɂ��v�͂��B�l�����̎d�����A���̉����Ƃ��ގ� ���Ȃ����̂ł��邱�Ƃ�F�߂Ă��ȏ�A�i�R������͂ނ���l�̖]�ނƂ���Ȃ̂��j�����ꂵ��ŁA�b�̋̈��ʊW�ⓝ������߂��肷��K�v�����邾�炤 ���H�@���x�l���̗p����`�����ȂĂ���Ȃ�A�p�ĊԐڂɂ��ꓙ�̂��Ƃ̔�]���֏o����̂ł͂Ȃ����炤���B���ƂւA���t�J�f�B�I���A���X�̏o�������� �̋Ɍ��э��͂��悤�Ǝ��݂Ď��s����₤�Ɏd�g��A���p�̐l���A���ʂȎd���A���v�ȉ�b�Ȃǂ�p�Ђ���A�܂��A�����̒��̂��܂��܂ȏo�������A�� ���Ĉ�̋��`����Ȃ��m�A�A�n�₤�ɍ��グ���肷�邱�Ƃɂ�āB�i17�j
�@�l�́A�}���^���E�f���E�K�[���̕���́A���̋L�q�I�ȑԓx�����҂��B�������āA�N�N�Ε��݂𑱂��A�ނ̏����ƂƂ��Ă̒́A���ׂ悤�Ƃ��鎖 ������������m���n�܂Đ^���ʂ���Ƃ��o���B�����͈�������ɕK����x�͗̐擪�ɗ��Ă��̌��𗁂т�̂����A�����ޓ����݂̐��́A�@���Ȃ� �ꍇ�ɂ������Č������邱�Ƃ��Ȃ��B�����ɂ͂܂��A�e���Ȃ���A���߂��Ȃ��B����́A���łɁA�g���X�g�C��ǂ�Ŗl�̋C�ɂȂ鏈�����B�ޓ��̓p�m���} ����Ă��̂����A�|�p�͊G������ɂ���B�ŏ��ɐ�ÁA������������𒍂������̊p�x�������m�A�A�n���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ�āA������A�e �����肳���킯���B�e�e�̂��̂̎p�́A���̉e�ɘ߂Ă������߂Ĉ����̂��B
�@���čs���l���́A�w�ォ�炾�������ώ@�o���Ȃ��Ə��m���邱�ƁB
�@���̍�𗧔h�Ȃ��̂ɏ����グ��ɂ́A���ꂪ�����̈ꐢ���̏����ł���A�܂��Ō�̒��q�ł���ƁA��Î����ŐM���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�́A����� ���A���������A����ɒ������ނ��肾�B�i20�j
�@�w�̍�i�̑Θb�̌�Ă��_�́A�ނ̍쒆�l������ɁA�ǎ҂ׂ̈߂ɂ��̂��]�Ă��_�ɂ���B��҂��A�ޓ��ɖ����̐��������ς˂Ă��_�ɂ���B�쒆 �l�����A���̑���Ɍ��Ă����������̂��]�͂ʂ₤�ɒ��ӂ���̂�����B�i22�j
�@�l�ɂƂĂ̖��́A�s�@���ɂ��Đ������邩�H�t�ł͂Ȃ��A�s�@���ɂ��ĕs���ɂ��邩�m�A�A�A�A�A�A�n�H�t�ɂ���̂��B
�@���łɋv�����A�l�́A�����ɑ���ᔻ�̑i�ׂ́A�T�i�@�ŏ��Č�����S�Z�ł��B�l�́A�ēǂ����ׂ߂ɂ����M�͂Ƃ�Ȃ��B�i28�j
�@���̍�i�����������čs����ɖl�������邱�̔��ȍ���́A�Ƃ�����A���̏��Ɋ܂܂�Ă�鍪�{�I�Ȍ��ׂ̓��R�Ȍ��ʂ����m��Ȃ��̂��B�k�c�c�l���i �ɉ]�ӂƁA���̍�i�ɂ́A�l�̓w�͂��W�������ׂ����S������Ȃ��B�ȉ~�`�̂₤�Ȃ��̂ŁA���̍�i�́A��̏œ_�̎��͂ɕ��ɍ�p�������̂��B�܂�A ����ɂ��ẮA�o�����A�����A�O�E�̎��ہA���̈���ɂ��ẮA���ꓙ�̎������ޗ��Ƃ��č�i��n�삵�悤�Ƃ��鏬���Ƃ̓w�͂�����̂��B���̌�̂��� �����́A�d�v�Ȏ��ł��āA���ꂪ�V�������S���`������̂ŁA����̒��������āA�z���̐��E�ɂ���������肱�ތ��ʂɂȂ�B�v����ɁA���̏����� ���З����̋L���������Ă�邱�̎蒟�́A�S�������̂����ɗ�������ŁA�ǎ҂ɂƂĂ͐����܌�墁m���邳�n�����Ƃł��炤���A���܂͂��ɁA�������ɂ� �ďd�v�ȋ��������グ�錈�S���B�i30�j
�@�l�̏����́A���ɖ��ȋ�ɁA�t�ɔ��W���čs���B���R�́A���݂̍s�ׂ̓��@�ƂȂ鎖���Ŋ��ɉߋ��̎��ɋN���Ă�āA�]�͂˂Ȃ�Ȃ������A���ꂱ��ƁA �₦���l�Ɍ����邩�炾�B������A�V�����͂́A���������ɏ���ǂ��ĉ��͂�̂ł͂Ȃ��ɁA�ŏ��l�����͂��Ǝv�Ă���̂��A�Q�����ւƒǂЂ�� �ċt�ɉ��͂�̂��B�i37�j
�@�l�ɂ́A�������g�̖��ŁA�����̍l��\��������A�쒆�l���ɂ��̂��]�͂�������A�͂邩�ɗe�Ղ��B��ɁA���̍쒆�l�����A�l�ƈقȂ鐫���ł���A�� ��قLj�w�e�Ղ��B�l�́A���Ă܂��A���t�J�f�B�I�̓Ɣ��y�уA���b�T�̓��L�ȏ�ɗǂ����̂��A�܂��e�Ղɏ��������̂��m��Ȃ��B����������Ȃ���A�l�� ������Y��Ă��B�l�͕ʂȐl�ԂɂȂĂ��B�k�c�c�l���S�Ɏ��Ȃ�Y�p����̋��n�ɂ܂ŁA���ȝe���������i�߂邱�Ƃ�����B�i45�j
�@�w�������x�̕��͂́A�l�̒��ӂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̍�i�́A�\�ʓI�ȋ�����A�@�q�͐�Ɏ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̊�p�Ȋ�p�t�̂₤�ȘA�� �ɁA�u���̕ϓN���Ȃ�����Ȃ����v�Ƌ�����₤�ȁA�ɂ߂ĕ����R�R�����@�Ō���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i49�j
�@���̏����́A���łɈ����ꂽ���̉����̏�ɁA���̑����\�����܂��Ƃ��鏊�ɁA�������B�]�͂A����́A�s�f�̏o���ł���˂Ȃ�Ȃ��B�܂�A�e�e �̏͂́A���ꂼ��A�ǎ҂̐S�ɑ��ĐV���������o������̂ł���A������ł���A������^�ւ���̂ł���A�������͂ł���A���ł���Ȃ���Ȃ� ��Ȃ��B�R���ǎ҂́A�W�m������݁n����ꂽ�̂₤�ɁA�l���痣��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B�������l�̎茳�ɂ܂����Ж߂ė���u�D�������̂₤�ɁA�ǎ� ���l�ɐn���ė��邱�Ƃ��l�͋��܂Ȃ��S�Z���B�i50�j
�@�l���V�����n������悤�Ǝv�ӂ̂́A�����ĐV�����l�Ԃ�`���x���ׂ߂ł͂Ȃ��A���͂��ꓙ�̐l�Ԃ����͂��V������@�ׂ̈߂��B���̌��ɏ������鏬�� �́A���˂ɏI�锤���B����������Ď�肪�������������߂ł͂Ȃ��A���� �J�닂�ݐs���Ȃ��Ɖ]�ӊ�����^�ӂׂ����B�J��A����Ƃ͔��ɁA���̊g���A���̗֊s�ّ̓����̂��̂ɂ�ďI��������₤�ɂ���̂��B���ɓZ�m�� �Ƃ܂�n�������肵�Ă͂����Ȃ��A����͔J��A�U��U��ɂȂ�A����Ȃ�������Ȃ��c�c�B�i57�j
�����P�̎��������́s���_���t���瑽����ێ悵���悤�ɁA�g���̓W�C�h�̏��������s�������̓��L�t���瑽�����w�̂ł͂Ȃ� ���B�u�b�̋� �̈��ʊW�ⓝ������߂�K�v�͂Ȃ��v�\�\�u�|�p�͊G������ɂ���v�\�\�u�쒆�l���͂��̑���Ɍ������Ă��̂������v�\�\�u�ēǂ���邽�߂ɂ������M�� �Ȃ��v�\�\�u��̏œ_�̎��͂ɕ��ɍ�p��������i�v�\�\�u���ȋ�ɋt�ɔ��W���Ă��������v�\�\�u���S�Ȏ��ȖY�p�A���ȕ����v�\�\�u�ɂ߂ĕ��R�Ȏ�@�� ��邱�Ɓv�\�\�u�s�f�̏o���B������A������^������́A�������́A���v�\�\�u�l�Ԃ����킷�V������@�v�Ɓu���˂ȏI���v�B�����́q�ʕ��̏I��r �ɒ��ړI�ȉe����^�����ȏ�ɁA�q�킽���̍쎍�@�H�r�Ɏ���g���̎��@�����{����b�B�����A�Ǝ��ɂ͎v����B
�g�����͎��쎍�т̎����ɑ��ĉ��^�I�������B��O�I�ɁA�s�k�t4���i1959�N11���j���\���q���̕a�C�r�i�D�E11�j�Ɓs�����C�J�t1972�N
10���Վ����������\���q�^�R�r�i�G�E2�j��
�́A��i����ɂ܂���Ҏ��g�ɂ���N�̎U�����c����Ă���B�s���㎍�t1958�N6�������\���q��́r�i�C�E13�j�Ɍ��y�����q�킽���̍쎍�@�H�r
�i���o�́s���̖{2�k���̋Z�@�l�t�A�}�����[�A1967�j�ƕ���ŁA�H���ȋL�^�ł���B�q��i�m�[�g�k�q���̕a�C�r�l�r�Ɓq�k�q�^�R�r�l�����r�́A��
������S���������B
�@���a�O�\�l�N�\�ꌎ�O���̒����V���̂����L���w�r���}�́k�u�l�N�r�i�K���k�v�l�x�����ނ����B���Ȃ�������� �K�̐l������ ���邱�Ƃɔߒɂ����ڂ���B�����͋L���𒉎��Ɏʂ��A���Ɣ����͂ڂ��̋��\�ł���B�����̍ޗ������ƂɈ�т̎������������Ƃ́A�ڂ��̎����U�ɂ����ď� �߂Ă̂��Ƃł���B�i���{���|�Ƌ���ҁs���{���W 1961-1�t�A�����ЁA1961�N7��5���A��Z���y�[�W�j
�@�q�^�R�r�Ƃ������́A���̒�������̌��̂Ȃ��ł����������̂ł���B�Ȃ��Ȃ炱�̎��̔��z�\�\�Ƃ��������̔����́A�e���r�̎��R�Ȋw�f�悩�瓾���� ��ł���B���R�ς��^�R�̐��Ԃɋ��������ڂ��A��}���ŁA���肠�킹�̎��Ƀ������Ƃ낤�Ƃ������A�u���ɉ߂�����f���ƃi���[�V�����Ȃ̂ŁA�ŏ����̎��� �������ł���B���̖̂{�Ń^�R�̂��Ƃׂ邱�Ƃ��Ȃ��A���Ƃ͎��̑z���́i�n���́j�ň�C�ɏ����グ���B�����炱�̎��́A�Ȋw�I�ɂ͐��m�ł͂Ȃ��B ���������ɂƂ��ẮA���A���e�B�̂����i�ɂȂ����Ƃ������������������ꖕ�̕s�����������B
�@��㎵��N�́u�����C�J�\�k���I�����㎍�́l�����v�ɔ��\�����B���c�����q�^�R�r���������낢�����ƁA�]������Ă���̂�l�ÂĂɕ����āA���͂܂� �͂悩�����ƈ��g�������̂ł���B�i�s�����t41���q����S�l�ꎍ���I�����r�A1977�N12���A��Z�Z�`��Z��y�[�W�j
�g�����ނ�������s�����V���k�����l�t1959�N11��3���t �k��26503���l3�ʂ̃R�����L���q�����ւӂ₷�\�\�r���}�́u�N�r�i�K���v�r��ǂ����݂ň����B���s�ӏ��́^�ŕ\�������B
�u���C�R�[�i�r���}�̃J�����j�n���̒��j�̐�����тɂ́A���E�̊����������l���Z��ł���B�����ɂ̓p�_�����Ƃ����A�J���� ���̈��B�^ ���́A�܁A�Z���납��V���`���E�̗ւ���ɂ͂߁A�傫���Ȃ�ɂ�āA��ւ̐����ӂ₵�Ă䂭�B���ɂ̓A�S����������܂Ŏ�ւ��d�˂�B�^��ւ̒� �̓J���łȂ��A��{�̒����V���`���E�̖_�ł���B��������ς��ɂ܂����A���Ɋ����A����ɗ����ɂ͋�̗ւ��͂߂�B��ςȏd���ł���B�^�������� �N���͕s���R�炵���A�����ƂɂȂɂ������Ă��E���Ȃ��B�̂��Ўキ�A�������B�����Ƃ���̓y���M�����݂����ŁA�ނ���A�����܂�������������B�^���� �قǔ��l�Ƃ���邩�炾�Ƃ��A�����]�������邽�߂��Ƃ��A���R�͂��낢�낢���邪�A�Ȃ���ւ����邩�A�������w��̂������Ă���̂Łc�c�x�Ƃ����� ���ʼn����m��Ȃ������B�^���{�͂��̈��K���~�߂����悤�Ƃ��Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ������ڂ͂Ȃ��炵���B����ł���l�A��l�A��ւ����Ȃ����������B������ �����̓J�\���b�N�ɑ����A��ɏ\�������Ă���B�s�v�c�ɐ���M�̂��̎R���ɃJ�\���b�N���悭�����Ă����B�^��ւ��͂߂���A�ւ��ӂ₷�ɂ͓��ʂ̋Z�p ������B���̂��ߓ���A�O�̕����Ɉ�l�̇��Z�t��������A���������Ď�ւ̒��߂�����Ă���B���܂��ܒ��߂̂��ߎ�ւ��O�����Ƃ���������҂̘b �ɂ��ƁA���ɏĂ��Ȃ��A�����A�����k�[���Ƃ��o���A���ɕs�C���������Ƃ����B���ʐ^�̓��C�R�[�����Z�X�N�����ŊێR�x�ǒ��B�e�^�i�����O�[������ �R�o���R�b�N�x�ǒ��j�v�B
�g���̎���i���o�ƍĘ^���Ȃ킿�O�f�s���{���W 1961-1�t�̖{���͓��`�j�ƋL���Ƃ̑Ή������悤�B�q���̕a�C�r�͎���Ǝ���̊Ԃ��S�p�A�L�̎U�����^�����A�X�I�ɑS�p�A�L�̏��ʼn��s���āA�� ���̕K�v��A�s���Ƀ��C�i�[��t�����B�c�c�̂��Ƃ̐Ԏ��\�L���L���̖{���ł���B
01 ����V���L���Ŏ��̂��Ƃ����߂Ēm�����c�c
�q�����ւӂ₷�\�\�r���}�́u�N�r�i�K���v�r
02 ���܂ł��r���}�̃J�����j�n���ɓ��l���Z��ł���Ƃ̂����c�c
���C�R�[�i�r���}�̃J�����j�n���̒��j�̐�����тɂ́A���E�̊����������l���Z��ł���B
03 �ʐ^���ڂ��Ă���̂ł��Â������c�c��
�^�̓��C�R�[�����Z�X�N�����ŊێR�x�ǒ��B�e
04 ���ׂĂ̏�����ւ��͂�
05 ���������ȗc���������Ă����c�c���́A
�܁A�Z���납��V���`���E�̗ւ���ɂ͂߁A
06 �����ł͍ߐl�łȂ����l���������d���g�Ƃ����c�c
�����قǔ��l�Ƃ���邩�炾�Ƃ��A�����]�������邽�߂��Ƃ��A
07 �ڂ��͎v�����������N�̍�
08 �O���̒n���������T�Ō������Ƃ�
09 �ޏ������͑̂̐����Ɠ����ɐ^�J�̗ւ������Ƃӂ₵�c�c
�傫���Ȃ�ɂ�āA��ւ̐����ӂ₵�Ă䂭�B
10 ��������������܂ŏd�˂��c�c���ɂ�
�A�S����������܂Ŏ�ւ��d�˂�B
11 �ł��l�Ԃ̎�ɂ����������邩��
12 �����̌`�Ԃ��ӂ݊O���Ȃ��g�Ŏ~�߂�
13 ����ȏ㒷��������댯��
14 ���E�ςƓ��������ɕω�����
15 ���͎��ʂ��낤
16 �ڂ��͑z���͂��Ƃڂ�������
17 �ޏ������̌����̖�̈ł܂ł݂Ƃ����Ȃ�
18 �^�J�̗ւƗւ̂��������Ƃ����a��
19 ���̖��@���̗₽�������₫��������
20 ���̒j�̓������h����
21 ���̖����̎����≘���ł܂�
22 �̂Ȃ��ɔޏ������͒��މP
23 �Ƃ�����ڂ��ɂ͕ʂ̂��Ƃ��C�����肾
24 ���܂��ܔޏ��������a�C�ɂȂ����ꍇ��
25 �O�̕����Ɉ�l�̎�ւ̋Z�t������炵���c�c
���̂��ߓ���A�O�̕����Ɉ�l�̇��Z�t��������A
26 ���̏��͒�̑傫�Ȏ��ɂ����ğ��������ׂ�
27 ��ԏ�̗ւ���O���Ă���
28 �����̎}�ɂ�����
29 �Ō�̑傫�ȗւ��������Ƃ��������̑����������k���o�`���Ę^�`�F�Ƃ��������W�`�F�i�g���j�l
30 �Z�t�͂��̂Ƃ��͂��߂��c�c���܂��ܒ���
�̂��ߎ�ւ��O�����Ƃ���������҂̘b�ɂ��ƁA
31 ���ɓ��������Ƃ��Ȃ������c�c���ɏĂ���
���A
32 ����������̕����c�c�����A������
33 �����̏��荂���ʂ����Ɠ˂��o�������Ɏv�킸�f�b���c�c
�k�[���Ƃ��o���A���ɕs�C���������Ƃ����B
34 �蓖�����Ƃ炸�X�ւ������k���o�`���Ę^�`�F�����ł��遨���W�`�F�i�g���j�l
01-06�͋L���ɂقڑΉ��A07-08�͉�z�A09-10�ɂ͗��҂��d�˂��킳��Ă���B11-15�͂����܂ł�O��Ƃ������������A14���i
�فm�W���t�n���o������}�f�ɂȂ�Ƃ���A�݂��ƂȎ�j�������B16-22�͋g���Ȃ�ł͂̎���A�Ƃ��Ɂu�̂Ȃ��ɒ��މP�v�Ƃ����Úg�����炵���B
23-24�̕a�C�i�W�肪�q���̕a�C�r�ł��邱�Ƃ�z���o�����j���ɏՍނɂ��āA30-33�ōĂыL���ɖ߂�B29��34�̏��o�`����эĘ^�`�u�Ƃ�
���v�u�����ł���v�����W�ō폜���ꂽ�̂́A�Ή�����V���L�������݂��Ȃ����Ƃ̖�����������邽�߂ł͂Ȃ��B�q���̕a�C�r�Ƃ����U����������Κg��
�����܂�Ƃ��č����o���̂ɁA���̓`���`������G���ƂȂ邩��ł���B�`�����u�����v���̂��Ƃ���A�t�Ɂu�J���v���ƁB���ꂪ�G���f�B���O�̎�����
�Ӗ��ł���B�q��i�m�[�g�k�q���̕a�C�r�l�r�͍Ę^���тɕt����Ă����B�g�����X���X�ƂȂ����V���̓��t�܂Ŗ��炩�ɂ��Ă���ȏ�A���тƋL����ǂ�
����ׂĂ�����Ă��܂�Ȃ��\�\���ȁA�ނ��낻�����Ăق����Ƃ�����҂̈ӋC���݂������Ɋ�������B�Ƃ�����s�m���t�i1958�j��appendix
�ƎƂ�ꂪ���ȁs�a���`�t�i1962�j�ŁA�g���́u�����̍ޗ������ƂɁv���������Ƃ����V������@���p����g�ɂ����B�����āA����͔N���o�邲��
�Ɍ����ɂȂ��Ă����B���͖{�т��g�������ɂ�������p�̗��[�i���������p����Ȃ��j�A�y���ɉ�������g�������������������т��ƂƂ炦�����B
�q�^�R�r�͐V���L���ł͂Ȃ��A�e���r�̎��R�Ȋw�f�悩��z�Ă���B�����r�Y�����́q�ӏ܁r�Łu�k�c�c�l�e�����B�W�����Ō����^�R�� ��ځE�r���� �f�����_�@�ɂȂ��Ă���ƍ�҂͂������A���̉f���̂��Ȃ�v���~�e�B���ȕ`�ʂ��܂̎U���`�����ŁA���������œ�̍s��������������Ƃ����T���h �C�b�`�\�����A���̍�i�̓����ł���B�k�c�c�l�u����͉ߋ��̂��Ƃ����m��Ȃ��v�Ƃ����^�R�̌�ځE�r���ɏے������h���_�ɂނ����āA�u�Ẳ��v�Ƃ��� ��������u�j�����v�Ƃ����Ȃ܂Ȃ܂������R���N�����Ă���A�Ƃ��ǂ߂�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A���l�`���� �y�[�W�j�Ə����Ă���Ƃ���A�g���̉�z�I�Ȕ����͑O�f�q�k�q�^�R�r�l�����r�̓��e�ƈ�v����B�����ł�����x�����A�u�e���r�̎��R�Ȋw�f��v�́u�u�� �ɉ߂�����f���ƃi���[�V�����v�Łu�ŏ����̎������v�u���Ƃ͎��̑z���́i�n���́j�ň�C�ɏ����グ���v���сq�^�R�r�B�q�^�R�r���f�ڂ��ꂽ�s�����C �J�t1972�N10���Վ��������̌��e���������킩��Ȃ����A�g���̎��M�̏�Ԃ��炷��A�q���̕a�C�r�قǂłȂ��ɂ���A�Ђƌ������O�ɏ��� �����Ă����Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�B�Վ��������̔����������m�ɂ͂킩��Ȃ��B���t�̔��s�����u10��25���v������A�ʏ��10�����i�������u10��1 ���v�j��11�����i�u11��1���v�j�̊ԁA�����11�����ɋ߂�����ɈႢ�Ȃ��B�����ŁA�q�^�R�r�̃X���X��T�����ׂ�1972�N9���́s�����V���k���� �kNo.615�l�t�̃e���r�ԑg���Œ��ׂĂ݂�ƁA�͂����Ă���炵�������ԑg���������B9��13���i���j23��15������45���܂ł�30���ԁA�m�g�j �e���r�́u�L�^�f��u�l���铮�������v���蒆���A�i�k���m�g�j�`�[�t�A�i�E���T�[�̒����ӈꎁ���l�v�i�����A�l�O���y�[�W�j�����ꂾ�B�������́q�L�^�f ��u�l���铮�������v�r���A�g�����u�e�����B�W�����Ō����^�R�̌�ځE�r���̉f���v���Ƃ���ƁA�Ȃ���R���A����������9��14���i�j�̓��L���s�y ���F��t�i�}�����[�A1987�j�Ɍf�����Ă���B
�@��A�J�̒��������N�����z�[���֍s���B�ʖ쉩�s�̑�����E�����o�h���������́u���{�~�v���ς�B���䂢���� ��ɕ~���� ��ꂽ�ڂ늗�c�̂����ŁA�ʖ쉩�s���̂��������B��ŖȂ��ނ���A���ɂ��킦�A�����ƂȂ鎞�A�Ț���܂ł����C�g�ɏƂ炵�o����A���I�ɐ�ɂ���̂��B �I���ċ߂��̋i���X�ŏj�t�B����C���A����Y�A�푺�G�O�A��쐟�q�A�����A���Ԏ������Ē����Ă����B�i�����A���`�ܔ��y�[�W�j
����ɂ��̗�15���i���j�͌h�V�̓��ŏj���B�����炭���̓��A�u��}���ŁA���肠�킹�̎��Ƀ������Ɓv�����u�ŏ����̎������v���Ƃ� �q�^�R�r���u�� �C�ɏ����グ�v��ꂽ�A�Ǝ��͐�������B�m�g�j�̃A�[�J�C�u�Ɂq�L�^�f��u�l���铮�������v�r�̃r�f�I�ł�����Ύ��Ԃ͂͂����肷��̂����A�C���^�[�l�b �g�Œ��ׂ�������ł͕s���������B�g�����f�ڎ������u�����C�J�\���I�����v�Ə�������܂��Ă���̂́A�������m�F�����ɋL���ŏ��������߂��낤�i�s����C ���̎��I���� 1927�`1937�t��A�z������̂������[���j�B�u���c�����q�^�R�r���������낢�����ƁA�]������Ă���̂�l�ÂĂɕ����āA���͂܂��͂悩������ ���g�������̂ł���v�́A����l���ās�����C�J�t�̕ҏW�l�E�O�Y��m����Ă������Ǝv����B�����i1972�N10���j�A���c�͋g�����ҏW����}�� ���[�̂o�q���s�����܁t�Ɂq�����G�k�r��A�ڒ����������A�g���ɖʂƌ������Č������̂ł͂Ȃ��A�Ƃ����킯���B���e���O�Y�Ɂs�m���t�]���Ȃ��̂Ɠ��l�A�� �c���ɖ{�i�I�ȋg�����_�i���N�G�X�g�ł���Ȃ�s�T�t�����E�݁t�ɂ��āj���Ȃ��̂́A���������������c�O�ł���B
�k�t�L�l
�m�g�j�A�[�J�C�u�X�̕ۑ��ԑg������������q�f�W�^����}�� �l���铮�������r�i����e���r�A2002�N2��2����
���j���q�b�g����B�ԑg���J���C�u�����[�܂ŏo�����˂Ό���ꂸ�A�����ł���B

�M�Ղ͊ԈႢ�Ȃ��g�����̎��M�ł���B20���l�߁~30�s�̌��e�p������ �сq�i���̒��Q�r�̐������e�� ���̂Ɠ����Ɍ�����B�������Ƃ���A�ӔN�̋g�����҈䋪���������Ĉ��p�������e�p�����B�g���ɂ��X���p�p�����̕\�����́u�g�̏�\���v�B�I�[�N �V�����̎ʐ^�ƎO���q�Y��W�s�g�̏�t�i�������[�A1988�N12��25���j���Ƃ炵�āA�g���̌��e���e�L�X�g�f�[�^�ɋN�����Ă݂悤�B��̍s���̊ے��� ���͍�Ɨp�̉��ԍ��A�s���̊������́s�g�̏�t�f�ڃy�[�W�ł���B
�O���q�Y�@�g�̏�@�\���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g����
�@���Ƃ̋�W�͂��ςݓ��𐂂�� ��
�A�����݂̓~�̟N�����K�� ��
�B�k�s���l
�C�k�s���l
�D�k�s���l
�E�k�s���l
�F�n����肠�������ꂵ�䂵���� �Z��
�GꝂ��t�m�������Ɖ]���m�������Ӂn�������� ����
�H�s�D�̏��đ����������̉� ���Z
�I�c���m��������n�̐̐Ԏq��~�� ����
�J�҂ƂȂ��V�̒n�ق∬�� ���
�K��峂���锤�̖��߂���߂� ��Z��
�g�����O���q�Y�̔o��ɐG�ꂽ���i����܂ށj�́A���̂ӂ����m���Ă���B�ЂƂ́s�o�匤���t1977�N11�����́q�O���q�Y�\ ��r�i���̐� �͖����s�j�A���܂ЂƂ́s�O���q�Y�S��W�t�i�������[�A1982�N3��1���j�x�́q�O���q�Y���Ᏼ�r�B�q�O���q�Y���Ᏼ�r�Ɍ�����u�ȑO�A�O���q�Y�̏G ��A�����I��ŁA�G��������ɒZ�����̂��A���͏��������Ƃ�����B�c�O�Ȃ���A���̐ؔ������t����Ȃ��̂ŁA�Q�Ƃ����ɁA�S��Ƃ�ǂݕԂ����i������W �w�����x���܂ށj�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�O�Z�y�[�W�j�̇��G��������ɏ������Z�����̇����q�O���q�Y�\��r���� ���B����͎O���̋�W�s�܂ڂ낵����t�i�o��]�_�ЁA1966�j����\����A�s�^�_�t�i�[��ЁA1973�j�����\�O��A�s�̒��t�i�R�[�x�u�b�N�X�A 1977�j����\������́B���Ɂq�\��r�Ɓq���Ᏼ�r�ɂƂ��ɍ̂��Ă���d���\�����f����B�g���̂��C�ɓ���̋�ł���B
�����ߗ���V���̏����Ђ炭���� �s�܂ڂ낵����t
���N����s�J�\�̐̂Ȃ��ɕa�� �s�܂ڂ낵����t
�����킪�F�������B �s�܂ڂ낵����t
�������ɒ��̔R���s���� �s�܂ڂ낵����t
���l�X���l�݂Â���d�C���� �s�܂ڂ낵����t
���a���֔n�̉�����[���� �s�^�_�t
��̌��a�̌���肵�Â��Ȃ� �s�^�_�t
��ł̂��̘T��A����� �s�^�_�t
��k�Ɋ��ݏo���\�y�Ƃ͂̏H �s�^�_�t
�ǂƂɓ���Ȃ��ނ��̂����낷���� �s�^�_�t
�f���̂��͏G�ˉĉ� �s�̒��t
�ނ����т�傫���Ȃ肵��̎R �s�̒��t
�`���́q�O���q�Y ��̏�\���r�ɖ߂낤�B�q�g �����N���k������2�Łl�r�� ���g����1989�N7���A�u�����v���U�z�e���ł̎O���q�Y�s�g�̏�t�́k��23��l��┏�܂��j����ɏo�ȁv���Ă��邩��A���҂��瑡��ꂽ��W�� �Ǘ���A����ł��t����������\�����Ԃ��Ƃ͂��₷�������ɈႢ�Ȃ��B�������A���̐�傪������Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���Ƃ��Ȃ��B�v�Ă��Ă��Ă����� �����Ȃ��̂ŁA�s�g�̏�t����|�����ҏW�҂̏@�c��������ɁA��傪�ǂ����ɔ��\����Ă��Ȃ��������������������Ƃɂ����B�@�c����͋g���̋�W�s�z���t �́q���r�������Ă��āA���̌��ɂ��Ďf���̂ɍł��ӂ��킵�����ł���B�@�c����̓d�b�ɂ��ƁA�G���̓��W�I�Ȃ��̂��܂߂āq�g�̏�\���r���� �����ɔ��\���ꂽ�`�Ղ��Ȃ������łȂ��A�O���q�Y�v�l�̍F�q��������̌��e�ɂ��Ă͂������Ȃ������A�Ƃ̂��Ƃ��B���e�͊p��������Ȃ̂�����A���҂Ɏ� �n�����߂ɏ����ꂽ�̂��낤���A�͂����Ă��ꂪ�O���q�Y�{�l�̎�ɓn�������̂��A�@�c����ɂ����f�������˂�l�q�������B��W���炨�C�ɓ���̋�����e �p���ɏ����ʂ��č�҂Ɍ��悷��̂́A�g�����̍�҂ւ̌h���ł���A��i�ւ̌h�ӂ��낤�i���̐ق�⽍��u�g�����v�̉���ɂ����A���Ԃ� �Ɏ��сq�i���̒��Q�r�̐������e�����������炢���j�B�Ƃ��Ɂq�g�̏�\���r�̕s���̎l��B�`�E�́A��Z�y�[�W����Z�Z�y�[�W�܂ł̋�\��̒������� ���ɈႢ�Ȃ��B���̒��Ŏ����䂩�ꂽ����������Ă݂悤�B
���Ɏ�����ꏂ̝ɝɂ�N�U �q���a�\���N�r
���i���Ǝ~�܂��U�q���v���� �q���a�\��N�r
��������������݂ꂤ�������͂�� �q���a�\��N�r
�i���郂̕ʂ��m��ʏH �q���a�Z�\�N�r
���ۙZ�̂��ƎO�b�◜�̉� �q���a�Z�\��N�r
��ӏ���蓯���ɂ�����_������ �q���a�Z�\��N�r
�C���鐅�͂邩�Ȃ������ �q���a�Z�\��N�r
��W�̕\�L�͐������j�I���������Ȃ̂ŁAShift JIS�ŕ\���ł���̂��̂͐����P�����B��q�̂悤�ɁA�g�����͎O���q�Y�̋�Ɋւ��ē�x�i�q�g�̏�\���r���܂߂�ΎO�x�j�M�������Ă���킯�� ���A�O�����g���̎��ɐG�ꂽ���͂͂Ȃ��悤���B�������A�����O�S�i�O���͓n粔���юO�S�̖剺�j�̋�Ƃ���āA�݂��̎d���Ɍh�ӂ��Ă������Ƃ� �^����e��Ȃ��B�g���̂��̏\������A�����������̂��ƂŌ���̂��ӂ��킵���B
�@�x�C�Y�͂قƂ�Lj�삲�Ƃɔ��W���Ă䂭�����Ƃł������B���R�ɂ� ���Ȃ�Ƃ������͂ނ���A�Ȃ�炩�̐V�������W�̕������T�肠�Ă���܂ŁA���̈���݂����̂��ӎ��I�ɗ}���悤�Ƃ���^�̏����Ƃł������B�i���� �����j
�g�����̐�O��2���̎��W�A�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j�Ɓs�t铁t�i���A1941�j�����Ƃ��A�K�����������ɏo�����̂��k�� ���q�ł���B �����g���x���������������A������{�I�ɂ��̍l���ɕς��͂Ȃ��B�g���{�l�����̉e�������Ă��邱�Ƃ���`���āA�g���̐l�ƍ�i���Љ���Z���ɏƂ� ���܂ł��Ȃ��A���łɒ���ƂȂ��Ă���B����������ɂЂ����Ƃ�Ȃ��d�v�Ȑl���Ƃ��āA�x�C�Y���킷��킯�ɂ͂����Ȃ��B�g�����ɂƂ��Ă̖x�C�Y�\�\�Ђ� �͋g���̐��̎��Ɍ���I�ȉe����^���������P�ւ̓�����Ƃ��āA�����Ă����ЂƂ́s���Ƒ��t�ɑ�\����鏃�����{�̒S����Ƃ��āB�g���͐��z�q�Ǐ� ���r�Ɠ�\�̂Ƃ��̓��L�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���̂̕��ł́A��g���ɂ́w�����o��W�x�w�t�v����x�Ɖ������ɂ̔��H�́w�Ԋ~�x��^�ǂ����Ƃ����Ă��悢���� ���B�����ēǂ� �����ł͂�������Ȃ��Ȃ��āA�Z�̂��������肵���B���A�����̋L�O�Ƃ��Ĉ�������A���̏W�w�����x�ɂ́A���H�͕�̉̎l�\�����߂��Ă���B�k�� ���q�ƃs�J�\�A���ꂩ�獶�삿���̎��ɂӂ�āA���^�I�Ȃ��̂֓]�ڂ��Ă������̂ł���B���鏭���ւ̗��ɔY�݁A�E���������ꂵ�����痣�E���Ȃ���� �Ȃ�Ȃ�������\�̐t�B�x�C�Y�̕��͂���A���Ԃ��P���킽���Ȃ�ɔ��������̂ł͂Ȃ��������B�������̐��������X�ɍs���A�����J�X��́w���� �P���W�x�����߂��Ƃ��̊������A�����Y����Ȃ��B�����P�̎��ƃW�C�h�̏����Ȃǂ����̍��̖����̏��Ƃ����悤���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�} �����[�A1988�A�ܘZ�`���y�[�W�j
�@�k���O��N�l������\�O��
�@�[�l������A�x�߂��Ή��̌c�����̉Ƃɂ䂫�A�A��o���Đ�����֏o��B�s�E�̒r�Ń{�[�g�V�сB���Ⓧ�F���Q���傫�ȗt�̒��Ɍ�����B�����V�_�� ��ʂ�A�Ö{���Łw���H���S�W�x�����߂�B�L���H�̐��ˉ��Ń\�[�_���▨����H�ׂ��B�c�����̂�����B�c�����ŕʂꂽ�B�Ï��ژ^�Œ��������A�x�C�Y�w�� �Ƒ��x�i�]��Łj���͂��Ă����B�i�s���܂�͂����L�t�A����R�c�A1990�A�Z���`�Z��y�[�W�j
�]�쏑�[�Łs���Ƒ��t��1932�N2���̊��s�B���L�ɂ���悤�ɁA�g���͂����Ό���{��ژ^�������Ă��āi�����̐��z�q�f�͎O�ƈ� �т̎��r�ɂ� �u���̍��A�K���ō���̂����₩�Ȏ��̖{�̌Ï��ژ^���o���ẮA�ʐM�̔�������̓X���������v�Ƃ���A�k�����q���W�͂����œ��肵�Ă���j�A�{�������� ���čw�������̂̈�����낤�B�g����1939�N6��18���i���j�j�Ɠ���28���̓��L�ɂ́u���B�������̐��������X�ŁA���]�̊����J�X��w�����P�� �W�x���B��~���\�K�B������܉~�Ȃ̂ł炢�Ƃ���B�v�A�u��A�w�������ʁx��ǂށB�v�i�s���܂�͂����L�t�A�܁Z�y�[�W�A�O�y�[�W�j�Ƃ���B�O�� �́s�����P���W�t�����t�̊��s���i6��10���j��8����ɓ��肵�Ē^�ǂ����g���́A�����P�ւƓ������x�C�Y�̑�\��s�������ʁt�̂����炭�͌���{ �i1938�N�̖�c���[�Łj�����̍��g�̂Ȃ��œǂi����ɂ����Ƃ���ŁA���x�߂���㆓ǂ��������낤�j�B�J�c�����́q�x�C�Y�Ƃ̉��m���ɂ��n�r�ɂ�� �A�x�������P�ɐe���݂͂��߂��̂�1934�i���a9�j�N���납��ŁA�u���̔N�A�ނ��ҏW�Ɍg������������l�G���u�l�G�v�̑n��������O�������āA�u�}�� �e�E���I���b�c�E�u���b�Q�̎�L�v���ڂ��A���N�ɂ́u�l�G�v����{�ōŏ��́u�����P�����v���Ƃ��ĕҏW�����v�i�s濹���̖x�C�Y�\�\���̐���������T ��t�A�\�����[�A1997�N7��15���A��l�O�y�[�W�j�Ƃ���B�g�����x�C�Y�o�R�Ń����P��m�����̂́A���A���^�C���ł͂Ȃ������炭��ǂ����낤���A�� ���̎G����ʂ��Ă������ɈႢ�Ȃ��B�����Ƃ��A�J�c�ɂ��u�x�C�Y�̒P�s�{�͂͂��߂̍��͂قƂ�ǂ�����o�łŁA����ꂽ�ǎ҂�����ɂ��邱�Ƃ��ł� �Ȃ������B�킸���ɕ��y�łƂ��Ă��������L���ǎ҂ɓǂ܂ꂽ�Ǝv����̂́A���a�ܔN�ɉ����Ђ���o���w�s��p�ȓV�g�x�i�V�s���w�p���j�ƁA���a�\��N �i���O�Z�N�j�ɖ�c���[����o���G�b�Z�C�W�w�ς̎蓅�x�A���y�Łw���Ƒ��x���炢�ŁA��͂蕶�Y�G���ł̓ǎ҂���ŁA�P�s�{�œǂވ�ʓǎ҂͂܂������� �Ȃ������Ǝv����v�i���O�A��O�Z�y�[�W�j����A�q�����P�G�L�r�����߂��s�ς̎蓅�t�i��c���[�A1936�j�������\�����̂Ă���Ȃ��B�����A�g���� �x�̂ǂ̔łɂ���ă����P�ɐe�������d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A��n�Ɍg���������̖{�̂Ȃ��ɖv���̋��ꂪ����|�A�����P�́s���_���t�� �����Ă��āA���ꂪ�펞���̋g�����̎��̋��菊�ɂȂ����Ƃ����e���̓����ł���B�g���ƃ����P�̊W���߂����ẮA�����q�g�����ƃ����P�r�ɏ������̂ŁA��������B
�E�����P�̖{�i�I�ȉe���͐��10�N���o�����W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�Ɏ����Ă悤�₭����ꂽ�B
�E�펞���̒��� �嗤�ŁA�����Đ��Ԃ��Ȃ������Ŏ��g�̎���͍����Ă����g�����A�����P�́s���_���t�͗슴�ɗ���Ȃ��u��d���̐��_�v�Ōە������B�Ⴋ���ɒ����Ƃ� �Ă����g�����{������ɂ����̂́A���邢�̓��_���ւ̊S���傾������������Ȃ��B���������ʂƂ��āA���_���́u�����v�����A����ɂ̓����P�́u���v�� ����͂邩�ɑ傫�Ȃ��̂������炵�����̕]�`�́A�g���̎��I�o���𑣂��ƂƂȂ����̂ł���B
�E�g���������P����w�̂́A�����́u���v�ƑΛ����鎍���_�̂��肩���������B�푈������ŏ��ǂ���\���N���o�āA�s�����P���W�t���܂��s���_���t�Ƃ� ���ɋg�����̎��I�o�������������Ƃ����悤�B
�E�s��ʁt�i1983�j�A�s���[���h���b�v�t�i1988�j�Ƒ���������ьQ�������͂��߂钼�O�A�g�����̓����P�̎v�z�I���k�_�������s�h�D�C�m�̔߉́t�� �R���ׂ��A��x��20���I�㔼�ɂ�����u�������e�[�}�̒��ю��v��t�ł悤�Ƃ����̂������B
�s�t铁t�̌�b�ɔ��H�A�k���ƕ���Ŗx����{�Ɩx�C�Y�̉e��������Ǝw�E�����͎̂푺�G�O�������i�q�g�����̂��߂̊o�����r�j�B�����A �����x�C�Y�� ��i����z�N����̂͋g���̎��̈��ł���B����͉̍e�q�`�W�r�A�s�����G�߁t�́q蜾蠃��r�A�̏W�s�����t�̂�����ɂ������邪�A�ł��������_�Ǝv���� �s���܂�͂����L�t��1939�N9��7���i�ؗj���j�ɂ��̉̂������L����Ă���̂��ǂ��l��������̂��B�g�����y���ɍs�����`�Ղ͑O��̓��L�̋L�ڂ� �����Ȃ��B����ŁA�����ɋ��Â����Ƃ����؋����Ȃ��B�莝���̎�������͕s���Ƃ��邵���Ȃ��B���́A���͓����ɂ������g�������̒n�̊O���l�̖���z�� ���ɒ蒅������i���ƍl����B���邢�͖x�C�Y�ƃ��m���[���ւ̋g���̃I�}�[�W�����ƁB
�@�₪�Č����̟�̒�����w�̍����Ⴂ�O���w�l������Ԃ������Ȃ��玄�̕��߂Â��ė���̂����͔F�߂��B���͂� �Ƃ����̐l �Ɍ��o�����Ȃ��₤�Ɏv���B�������̓����̑傫�ȍ��̖{�ɐg���ē��������Ă��ƁA����Ԃ̒����爟���F�̖є����������̎������̊�����Ăɂ� ��Ƃ����B�������ނ荞�܂�āA�ɂ���Ƃ����B���A����Ԃ������Ă���̎Ⴂ��͎��̕��ւ͌����������Ȃ��ŁA���̑O��ʂ�߂��čs���B������� ���Ă�邤���A�ӂƂ��̉s�����炩�牽���������������Ƃ�����炵�����̏��̎Ⴂ���������̖ʉe���������̂₤�ɕ���ŗ������ɂȂ��B�\�\�x�C �Y�q���������r���̋g�����x�C�Y�̐��E���牓�����������Ƃ��A���̉e���͎v��ʏ��Ŏp�����킷�B�s�G�߁t1958�N7�����ɔ��\���ꂽ�q���Ƒ��r�i�C�E14�j������ ���B���̎��́s�m���t�Ɏ��^���ꂽ��i���A������Ō�ɎG���ɔ��\���ꂽ���тł���i���M�͏������낵�́q�����r�̕������Ɓj�B���тɓo�ꂷ��V�����j ���v�����e�́A�ꖺ�̕v�ł��蕃�ł���V�����j�ŁA��e�̊��ʑ���̎Ⴂ�j�ƑΔ䂳��Ă���B
�Ė�䂭���������̉���������߂�e���藎���t�Ȃ肯��i�y���j�\�\�g����
���Ƒ��b�g�����������X������
�����̂���[�ׂ�������
�R��������̖Ǝւ̉ƌn��f�ׂ�
������ꖺ
��e�̓T��Ȕ��ƐQ�Ԓ��̖��Ԃ�
��l�̘V�����j���i�߂��낷
���ݍ������F�����̔n�̕��A�̏I��
�ꖺ�̐S���Ђ���Ȃ̉���
�ނ炪��ڂ��ӂ�̐��{���
��݂�����V�����j
������ނ��̕v
��H�̕��e
�����̖��͂����܂����T�̑�������
��̂��낢�Ђ܂��̎��̗��̂Ȃ���
���̂̏����̒ɂ݂𒍂�
���ׂẲƍ��Ƒ��z����̖�����炬���
��e�͊C�̂����Ŋ��ʂ�
�Ⴂ�j�̂����̓������݂ɂ䂭
������ƌҊԂɊ����Ȃ���
���e�͐��Ȃ�������̌�������
�ӂ����X�R�̓˒[��������
����̓L���X�g���ɂ����鐹�Ƒ��i�c���C�G�X�ƕ�}���A�A�����Z�t�̎O�l�̉Ƒ��j�ł͂Ȃ��B�ނ��A�x�C�Y�̓���́u���}���i���я� ���j�̖͌^�݂� ���ȒZ�я����v�i���i���F�j�ɂ͎��Ă������Ȃ��B�L���X�g���I�ł��A�x�C�Y�ӂ��ł��Ȃ����Ƒ��B�ނ��둭�ɂ܂݂ꂽ�A���̋ɒv�̉Ƒ��Ƃ����ׂ����낤�B �����r�Y�́q���Ƒ��r�̊ӏ܂Łu�ꂢ�ɂ���Ĕ����Ƒ��Ɠǂ߂����B���̂��납��Љ���ɂȂ��Ă�������Ƒ������ɂȂ��Ă���B�������A���̕���Ƒ� �͎����ȓ��{�̕��y�ɂӂ��킵���Ȃ��A�������炩��Ƒs��ɕ���B�k�c�c�l�Ƒ����\��������̂��j���i�v�A���A���q�j�Ə����i�ȁA��A���j���Ƃ��� ��A��҂̎����͂����ς珗���A�ȁA��A���̋����A�����܂����̂ق��֒�����A�j���A�v�A���͎コ�A�݂��߂����炵�����\���A���q�I�Ȃ��͕̂�e�̏ �̑Ώۂɂ����Ȃ�Ȃ��v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A�O�O�`�O�l�y�[�W�j�Ə����B�u���̖Ǝւ̉ƌn�v�͐��m�̖�͂̐}���̂悤 �Łi�͂����Ă���������͂����݂���̂��s�������j�A���̂܂܂��̕��ꖺ�̉Ƒ��̗���������Ă���B���т̈�Ƃ������܂ł��u���Ƒ��v�Ȃ�A�����Ɍ����� ����̂̓C�G�X�E�L���X�g�ɑΉ�����c���ł���i�x�̒Z�тɕ�Ɩ��A�����đ��q�ɑ��������҂͓o�ꂷ�邪�A���͑��݂��Ȃ��j�B�傢�Ȃ��ʂƂ��Ă̒j�� �̑��݁A���邢�͕s�݁B�q���Ƒ��r�����߂����W�s�m���t��ǂ҂ɂƂ��Ă������ɑz�N�����̂́A���̎��������\�\�q�r���r�i�C�E15�j�́u�~���̎� ���v�ł���A�q�����r�i�C�E19�j�́u�����v�\�\���B�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t���N�̑I�ɂȂ�̂��킩��Ȃ����i�g�����A�������A����Ƃ����҂� ���c�ɂ�邩�j�A�s�m���t����̏��^���q�q�́r�q�m���r�q�ār�q��́r�q���Ƒ��r�q�����r��6�тŁA�������q���Ƒ��r�̂��ƂɁq�����r���u����Ă���̂� �܂��ƂɈӖ��[���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�����ŋg�����ƒ}�����[�Ŗx�C�Y�S�W�ɂ��ċL���Ă������B�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�Ɍf�ڂ����q�g���������r�̑�����i�̖ژ^�쐬�ɂ������āA�}�����[�W�̎����͒W�J�~�ꂳ��̎��ς킹���B���� �u'90.11.28�v�Ƃ������̊m�F�������R�s�[�̌��{�́A�����̃J�[�h�i�ق�A5���T�C�Y�����A�R�s�[�Ŋg��E�k������Ă��邩������Ȃ��j�ł� ��B
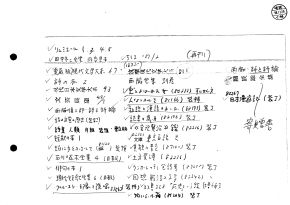
�}�����[���g�����Ɉ˗������Č��̍T���k�����̃R�s�[�ɏ��т��������L���������m�N���R�s�[�l
�ꕔ�̎G����S�W�̃^�C�g���̓S����i�c�����j�����A�قƂ�ǂ����M�ŁA�}�����[���g���Ɉ˗������Č���3�i�ɂ킽���ċL����Ă���B �S���҂��˗� �̂��тɋL�������炵���A�M�Ղ͂܂��܂��ł���B��������Ȃ��Ȃ��Ă��Ƃ��痓�O�ɏ������`�Ղ�����i�㕔��2�s�j�B���̂��ߕK���������s���ł͂Ȃ����A �ȉ��ɂ�����T���̏��Ԃǂ���ɋN�����Ă݂�B�e���́i�ԍ��j�Ɓy���\�N���z�́A���p�҂��X�I�ɕt�����B�}���ݎЎ���i1951-78�j�̈Č��͎��l�g �����ɑ��Ă̂��́A���БގЌ�̈Č��̓t���[�����X�Ƃ��Ă̎d���ł���B�e�Č��ɑ�������L�ڂ��s�q�g �����r�́u�{�v�t�E�s�g�����N���t�E�s�g ���������t�ɂ���̂Ōɉ�����Ȃ����A5���̐����� ISBN�R�[�h�̏����L���B�i3�j�Ɓi17�j�́s�g���������t�ɋL�����悤�ɓ����e�B�i7�j�Ɓi31�j�͏d����������Ȃ��B
| �i1�j�����~�G�[�� 1.3.4.5�y1985.9, 1986.3, 6, 9�z | ||
| �i2�j�c���~��S�W ���e���{�y1984.11�z | �i16�j������ '87/2�y1987.2�z | |
| �i3�j�����Ō��㕶�w��n 67�y�����F1967.12�z | �i17�j�}�����㕶�w��n ��1�y1981.12�z | �i31�j���e�E���Ǝ��_�y1975.10�z |
| �i4�j���̖{ 2�y�����F1967.11�z | �i18�j���e�S�W �ʊ��y1983.7�z | �i32�j�x�C�Y�S�W�y1977.5-1980.10�z |
| �i5�j������{���w��n 93�y�����F1973.4�z | �i19�j�e�Ƃ�ꂽ���i80233�j�������y1983.10�z | �i33�j82267 ���{���V�L�i�����j�y1989.6�z |
| �i6�j���|�W�] 49/7�y1974.7�z | �i20�j�l�Ȃ������i81166�j����y1983.10�z | |
| �i7�j���e���O�Y�E���Ǝ��_�y1975.10�z | �i21�j�a��Ɗ���̂������i82193�j�����y1985.6�z | |
| �i8�j���̎��o�̗��j�i���B�j�y1979.2�z | �i22�j�Ǐ��̍Ό��i82196�j�����y1985.6�z | |
| �i9�j���W �l�� ���� ����E���y�ŁV�y1979.6, 11�z | �i23�j�s�{���t�Ӂi82216�j�����y1986.9�z | |
| �i10�j�Z�̖̂{ 1�y1979.10�z | �i24�j02101 ���� �����S�b �V�y1986.12�z | |
| �i11�j���Ɏ���������āi81120�j����y1980.3�z | �i25�j���e�̐�i87100�j�����y1987.1�z | |
| �i12�j�ΐ��ؑS�W 4�i����j�y1980.3�z | �i26�j�y���F��i82236�j�y1987.9�z | |
| �i13�j�o��̖{ 1�y1980.4�z | �i27�j�E���K���b�e�B�S���W�i83088�j�����y1988.1�z | |
| �i14�j����Z�̑S�W 6�i����j�y1981.3�z | �i28�j��z ���̕��w�i82242�j�V�y1988.4�z | |
| �i15�j�v���[�X�g�E��ۂƉB�g 83563�i����j�y1982.8�z | �i29�j�o�� 328 �u�����v�Ƃ����G�k����l�y1988.9�z | |
| �i30�j�����ӏ����i81264�j�����y1988.11�z |
�����Ŗ��ɂȂ�̂́i32�j�ŁA�S����ɂ��u�x�C�Y�S�W�v�ɂ́i����j�Ƃ��i�����j�Ƃ���L���Ȃ��A�g�����{���Ƃǂ������������ ���킩��� ���B������i�̖ژ^�쐬�̍�Ɠr���ŋ^��Ɏv���ĒW�J����Ɋm�F�����Ƃ���A���Ƃ̂��Ƃ������B�����͂����ċC�ɂƂ߂Ȃ��������A���̂��Ƃ̈Ӗ����� �߂čl���Ă݂����B�i7�j�́s���e���O�Y ���Ǝ��_ �Y�t����̐��z�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�ł���i�i�c�k�߂̎�Ɏ�����̌��e�˗��ɑ���Ԏ����x�ꂽ���Ƃ��k�߈���1975�N8��31���t���ȂŘl�т� �g���́u���e���O�Y�s���Ǝ��_�t����̒����� ������Ƃ������肠�킹������̂ł��B���̍\�z���o�����A�܂��\�ܖ��Ƃ����������܂�ď��߂ĂƂ������ׂ������ɁA�������남�낵�Ă���Ƃ���ł��v�Ƌ� ���𖾂����Ă���j�B���e���O�Y�S�W�͋g�����������������A�s���e���O�Y ���Ǝ��_�t�V���[�Y�̑��������ꂩ�\������Ă��炸�A���̈�ۂł͋g���������ł͂Ȃ��C������B�g���͎��l�Ƃ��Ă��̈Č��Ɋւ�����̂�����A���M�����f �ڂ����s�Y�t�����{�Ƃ��ĎƂ����������낤�B����5�����苖�ɒu���Ă������������g���́A����𐏑z�̌��e���M���Ƃ̑��E���Ȃɂ��Ŋ��Ă������ �̂ł͂Ȃ����B���̂����肪�is7�j�̎��Ԃ̂悤�ȋC������B���l�ɁA�i32�j�̊��s�J�n���_�ł܂��}���ɍݐЂ��Ă����g���́A���̌�̓t���[�����X�� �Ȃ��Ėx�C�Y�S�W�ɂȂ�炩�̌`�Ŋ֗^�����\�\�����̎菕��������Ȃ�A�f�ނ̋ᖡ�Ɉ���Ȃ肵���\�\���߁A�����̂ł͂Ȃ����B�������x�C�Y �S�W�͖{�����Ɂu���^���@���V���v�ƃN���W�b�g������A��1������ɂ́u�{�S�W�̑���҂͉����V�����ł����A���E�\���E���̊G������V���ɕ`���Ă����� �������̂ł��v�A���f���1978�N5���̑�6������ɂ́u����̑����̂��d���ł́A�\���̔������̐��̏o�����Ɏ���܂Ō������`�F�b�N���d�˂Ă������� �܂����v�Ƃ��邩��A�����҂������V���ł��邱�Ƃ͓����Ȃ��B�����Ȃ��A�ӂ��u���v�ƌ���Ȃ����A�x�C�Y�S�W���w�ǂ����������g�������Ђ̏o�ŕ� �Ȃ̂ŎГ��̔������Ŕ������A�Ƃ��l�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B������ɂ��Ă��s�x�C�Y�S�W�k�S8���E�ʊ�2���l�t���g���̎���̏��˂ɕ����Ƃł��낤�B ���Ȃ݂ɓ��S�W�́A��13�{����R���N�[���ŗD�G�܁i�S�W����j����܂��Ă���B
�x�C�Y�̒����̑��{�ɂ��ẮA�y������ɕ��ْ��E�員�q�s�́q�x�C�Y�̏������{�r�i�s�ߌ���̃u�b�N�f�U�C���l
I�\�\�����ɂƂ��Ă̔��t��������p��w ���p�فE�}���فA2012�N10��22���j���ڂ����B�ȉ��A�員�_�����s������w�}���فb�}���قɂ��āb���s���b�}���̕��i������w�}���ًI�v�j�b1���t��
�q�������{�\�\�]�쏑�[�Ɩ�c���[�r�i���M�Җ��̋L�ڂȂ��j���肪����ɂ��Ėx�̒����̑��{�ɂ��čl���Ă݂����B�Ώۂ��g�����Ï��ژ^�Œ��������]�쏑
�[�Łs���Ƒ��t�ƁA�g�����ǂs�������ʁt���c���[�ł̂���Ƒz�肵�āA2���ɍi��B�S�i���`�́q�����r�ɂ��A�s���Ƒ��t�Ɓs�������ʁt�͎��̂�
�Ƃ��ł���B
3�@���Ƒ��^ ���a���N��\�����s�^�]�� ���[�i�����s�O�a�J������\���Ԓn�A�]�쐳�V�j���s�^����ҁ@����q���Y�^�a�U�ό^���i12.5�~16.5cm�j���\��������J�o�[ ���\���� �@�{�����\�O�Ł@�艿��~�i��\��܁Z�j�A��~�\�K�i��܈�\�܁Z�Z�j�^�ܕS�����芧�s�i�z�O�ǎ������ҏ����S�\���i��\��܁Z�j�A�ؒY�����O�S�\ ���i��܈�\�܁Z�Z�j�j�^���^���i��������j �܁^���Ƒ����i�s�x�C�Y�S�W�k�ʊ���l�t�}�����[�A1980�N10��25���A�l�l��`�l�l��y�[�W�j
15�@���������^ ���a�\�O�N�l���\�����s�^��c���[�i�����s�����������\�l�Ԓn�A��c���O�j���s�^����ҁ@�����ہ^�`�T���w�m���R�[�l���\�����e�k�}�}�l�����@�{���S�� �\�ܕŁ@�艿��~�^�ܕS�����芧�s�^���^�������� ���^�@���� ��^�@�t ��O�^�@�������ʎl��^�@�~ ����^�@���̂����̒J ��Z��i���O�A�l�l�Z�y�[�W�j
�����Œ��ڂ������̂́s���Ƒ��t�̂a�U�ό^���i12.5�~16.5cm�j�Ƃ����T�C�Y���B�苖�ɂ�����{�ߑ㕶�w
�قɂ�閼�������S�W
�́s���Ƒ��t�͂a�U���̓V�n���J�b�g����A������Ɛ����l�܂����������B���́s�g���������t�͖{���y�[�W�̎d�オ��V�n�~���E�̐��@
������A
�s���Ƒ��t�̂���𑪂��157�~118mm�ŁA�g������
�W�s�����G�߁t��172�~
121mm�͋ߎ��l�Ƃ�����B�s�����G�߁t�̖{���p���͏o����O�ɂ����g���ւ̗F�l����������S�ʂ���������i�g�����t���[�n���h�ŗp����I�������킯��
�͂Ȃ���������j�A�P���Ȕ�r�͂ł��Ȃ����̂́A���W���a�U�ό^���ɂ����w�i�Ɂs���Ƒ��t���܂������e�����Ă��Ȃ������Ƃ͂����܂��B��������Ȃɂ��
���A���W�̑��{�ɂ����ċg�����{���ɔ͂������؋����s���Ƒ��t�̃t�����X���ł���B���������a���ܒԂ��̑��{������t�����X���ɂ���K�v���ǂ��ɂ����
�����̂��B�����Ȃ�Ӗ��ł����������i�u���v�̂悤�ȟ������ЂƂg���Ă��Ȃ��j�őg�܂ꂽ�s���Ƒ��t�ɑ��āA�s�����G�߁t�̕\���́i�����炭�g
���̎�ɂȂ�j�ѕM�����A����́s�����G�߁t���g���́u�⏑�v���������Ƃ��l����Δ[���������B�u�\���ȊO�͏����Ȃ��̏������B�k�c�c�l�����̋ǎ��Ɏ���
�̊����̂Ƃ肠�킹�͋C�i�ɂ��ӂ��B�t�����X���v�i�員�q�s�A�O�f���A�Z�Z�O�y�[�W�j�́s���Ƒ��t�ɋg���������������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B����s��
�����ʁt�Ƃ̊W�́s���Ƒ��t�Ɓs�����G�߁t�قǒ��ڂł͂Ȃ����A��N�̌���łɂ�����g���������̍��@�ɉe����^���Ă���B���y�Łi�Ƃ�킯�����j�ɂ�
����p���\���̗̍p���A�Ⴂ����ɏo�������s�������ʁt�ɕ����Ƃ��낪�傫���B
�ѓN�v�����q�ߌ���̃u�b
�N�f�U�C���l I�r��
�w�E���Ă���悤�ɁA�x�C�Y���g����������{������肽�����Ă����B�員�q�s�́q�x�C�Y�̏������{�r�����̂悤�Ɍ���ł���B�\�\�u�x�v�l�̓����ō�����
�̎��Ɏc���Ă���̂́A�u��l�͂�����������������A�ق�Ƃ��͖{���ɂȂ肽�������悤�ł���v�Ƃ������t�ł������B�����Ō����Ă���{���Ƃ́A�{��
�邱�ƁA�����ȏo�ŎЂ�������
�������Ӗ������ł���B�^�����̏�����
�����̑��肽���悤�ɑ���A�F�B
�̏����������̍D�݂�F�B�̍D�݂ɍ����悤�ɑ���B���������l���𑗂ꂽ��ǂ�Ȃɂ悢���낤���A�Ɩx�����ɕ`���Ă�����������Ȃ��v���̈ꕔ�́A���Љ�
���Ă����悤�Ȍ����ȏ����ƂȂ��āA���������ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��낤���v�i�O�f���A�Z���܃y�[�W�j�B
�u�����ł�����Ɠy�n�̘b�����Ă݂�����ł�����ǂ��A�������̐��e����̘b�Ɉ���������ƁA�c������Ƙb���Ă��āA��l�Ƃ��ӌ����� �v�����̂́A ���_�j�Y���Ƃ����͖̂k���Ɠ����̉����ɏo��Ƃ�����ł���B�k���Ƃ����̂͐V��������ĂˁB���ꂩ�牺���Ƃ����̂́A�x�C�Y����g�����ɂ�����܂łƂ� ���b�ɂȂ����킯�B���{�̃��_�j�X�g�͑�������o�Ă���B����͂ǂ����Ă��A���ɕs�v�c���Ƃ�����ł���B�ނ̐��ɂ��ƁA�����Ƃ��F���̗͂��y�� �������Ƃ��낾�ƌ����ȁc�c�v�Ƃ͔ѓ��k��̔��������i�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������k���k��l�q�����������錻��̎��\�\�� �k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�A�s�Z�́t1975�N2�����A�Z��y�[�W�j�A�k���E�V���̃��_�j�X�g�͑���C���E���e���O�Y�ŁA�����̉����� �i�x�C�Y�E�g�����Ɍ���j�{���ł���B�O�҂͑[���āA�����̉����ɏo�郂�_�j�Y���Ƃ͂Ȃɂ��B����͓�₾�B���Ȃ��Ƃ�20���I�S�ʂɂ킽����{�Ɖ��� �̌|�p������ɓ���Ȃ���A�e�Ղɉ����Ȃ��B�m���ɉ������܂ꋤ�ʂ̋C���Ƃ����̂͂���B��N�̋g����15�ΔN���̖x�ɓ����i�����������A�x�͓����E�� ����y���ɂ������j�̏����ƂƂ��Đe���݂��o�����̂��������낤�B��������́A���������ł͂����Ă��A���̕��w�ɐe�t�����g�����_�j�X�g�̓�����ޗ��R �ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����Ȃ�̓��I�ȕK�R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Č����̑ΏۂƂȂ�e�L�X�g�̖�肪����B�x�C�Y�́A�{�e�ŐG�ꂽ�}�����[�őS�W�ȑO�ɂ� �V���ЂƊp�쏑�X���猳�ł╁�y�łƂ������`�ʼn��x���S�W���o�Ă��āA�����̊�b�ƂȂ镶���Ɏ������Ȃ��B�����A�g�����͑S�W�͂��납�����s�̎U���̏W�� �������s����Ă��Ȃ��B�g�����Ɩx�C�Y�Ƃ������͓I�Ȏ��ɂ�������炸�A�����̉����ƃ��_�j�Y���^���_�j�X�g�Ƃ����ϓ_���痼�҂�_����ɂӂ��킵���� ���ɂȂ��Ƃ����̂����݁A2013�N�Ƃ������ƂɂȂ낤���B�ƌ����������ł̂��Ƃ����A���a�O���̃��_�j�Y�����w�Ɠ����̉����A�Ƃ�킯�͐[���� �W�ɂ���i�x�̒Z�сq�����فr�́A��`���ċ����[���j�B����͋g�����Ɛ̊W��T������@������������B
�k�t�L�l
�V���Ђ̕ҏW�҂������J�c�����͌��Ŗx�C�Y�S�W�̑��{�ɂ��āA�x�̒�q�ł��镟�i���F�����������ɏo���āA���̂悤�ɏ����Ă���B�Ȃ��A�s��z ���̕��w�t�͋g��
���̑����ɂȂ�B
���i����͑�ςȋÂ萫�ŁA�{�̕ҏW��{����Ɉُ�Ȃ܂ł̏�M���������B�����̒���̕ҏW��{����ɂ��̏�M���� ������������ �Ȃ��A�w�x�C�Y�S�W�x�̕ҏW�Ɍg������܂ɂ����̏�M�͈⊶�Ȃ��������ꂽ�B���̑S�W�ł́A���o�A�{���̈ٓ��Ȃǂ�F����̋r���œ���A���{�͔w��A��� ���܁k�}�}�l�A�ʎ��A�z�܁k�}�}�l�\������ɂ���Ƃ������Ȃ��̂ł��������A���������D�݂���łɎ咣���ď���Ȃ������͕̂��i����ł������B�x�C�Y �́w���E�x���X�̋U��x�w���Ƒ��x�w�������ʁx���̏��Ŗ{�́A������s�A�P�A���łȂǂ̗]���������k���ȕҏW�ƁA���^�ŕ��i�̍������{�ɓ��F�̂���� ��{�����A�{�Ɉ����̐[�����i����́A����Ȗx�C�Y�ɂӂ��킵���S�W����邱�Ƃɗ͂������������̂Ǝv����B�i�q�x�C�Y�Ƃ̉��m���ɂ��n�r�A�O�f���A�� �l�Z�`��l��y�[�W�j
�@�V���Ђ́w�x�C�Y�S�W�x�͏��a��\��N�O���ɑ�ꊪ�����s���ꂽ�B�e���E�w��E�ʎ����\���E��玆�m����҂��n���A�z�������Ƃ������ȑ��{�ŁA���o ���E�{���Z�قȂǂ��F����̋r���œ���Ƃ����^�j��̖{�������B�艿�͐�~�B�����̒P�s�{����A�O�S�~�̂���ł���B�^�ҏW�ψ��ł́A�_���������{����� �_�o���Ȑl���������A�r����F����ɂ����F����A���ȑ��{�Ȃǂ��咣���ď���Ȃ������͕̂��i���F���������B���͎������w�҂ɂȂ��Ă���O��N�j���� ���A�ŏ��w�x�C�Y�S�W�x�̒S�����������A���i����̏�M�ƎЂ̕��j�Ƃ̒����ɐ������܂����悤���B�i�J�c�����q���i���F�\�\�l�����|�p�ł��邩�̂悤�ɐ� ����r�A�s��z ���̕��w�t�A�}�����[�A1988�N4��25���A�ꎵ�y�[�W�j
���V�������ɂ́s�V�t2011�N8�����̉i�c�k�ߓ��W�܂��āA�u������͒����́q�g�����Ɖi�c�k�߁r�������˂Ȃ�Ȃ��v�Ɠ��� ���q�ҏW��L�r�� ���������̂́A�܂��������Ă��Ȃ��B�{�i�I�Ș_�l���M�̏�����ƂƂ��āA���̂قǎ��Ɛ��̋g�������s�i�c�k����\�\�q�莆�r�Ɓq���r�Ɉ˂�t����悵�A ���삵���B���쌠�d���闧�ꂩ��A�g�������M�����{���i���Ȃ␏�z�j�A����k�߂̔o��������Ɍf�ڂ���킯�ɂ����Ȃ��̂ŁA�s�g���������s�U���W ���o�ꗗ�t�Ɠ����悤�ɁA���̍�ƂɂȂ��ڎ��E�� �o�ꗗ�E�Ҏ҂��Ƃ����� �f�ڂ��悤�B�Ȃ��s�i�c�k����t�ɂ́A�e�{���̖����ɏ��o�Ȃǂ̏����֘A�̏����L���Ă���A�d�����}���āq���o�ꗗ�r��݂��Ă��Ȃ��B�{���̑g�̍قɂ� ���Ắq�Ҏ҂��Ƃ����r�ɏڏq�������A�Ŗʂ̗l�q���킩��悤�ɁA���́q�i�c�k�߂Ƌg�����\�\�w�k�ߕS��x�Ƃ��̌�r�Ƌg���̏��ȁE���z���f�ڂ������J�� ���f����B
 �@
�@
���ш�Y�q�i�c�k�߂Ƌg�����\�\�w�k�ߕS��x�Ƃ��̌�r�̌��J���i���j�Ƌg�����̏��ȁk�E
�y�[�W�l�Ɛ��z�k���y�[�W�l���f�ڂ������J���i�E�j
�k�s�i
�c�k����t���L�l
�q�i�c�k�߈��g�������ȁr�̒�{�́A����
���s�Ս��t�f�ڕ����A����
���P�H���w�ىi�c�k�ߕ��ɏ����̋g�������Ȃ�\�킵�A���Ȃ̖{���͍Z�����Ȃ������B�������ɏ��o���⍷�o�X�ǂ̏���̏����L�����B
���z����͕\�L�̗���ꂵ�A���p���͌��{�ƏƂ炵�čZ�������B�Ȃ������s�̐��z�ȂǂŁA�킩��₷���悤�ɕҎ҂��W��������ӏ�������B�W��̌�
��͕������̏��o�̏��ɋL�����B
�i�c�k�߂Ƌg�����\�\�w�k�ߕS��x�Ƃ��̌�@���ш�Y vii
�����Z�O�N�ꌎ��Z���@�i�c�k�߈��͂��� �O
�����Z�O
�N�ꌎ��Z���@�i�c�k�߈� �l
�����Z�O
�N�l�������@�i�c�k�߈� ��
�����Z�O
�N�Z���ꎵ���@�i�c�k�߈� ��
�����Z�l
�N�O���@�i�c�k�߈��������� ��
�����Z��
�N��Z���ꎵ���@�i�c�k�߈� ��
�����Z��
�N�O������@�i�c�k�߈��͂��� ��
�����Z��
�N�O�������@�i�c�k�߈����� ��Z
�����Z��
�N�l�������@�i�c�k�߈� ���
���k���Z
���N�l�܌��O�Z���@�i�c�k�߈����� ��O
�����Z��
�N�Z��������@�i�c�k�߈��͂��� ��l
�����Z��
�N�����������@�i�c�k�߈��͂��� ���
�����Z��
�N��Z����O������@�i�c�k�߈��͂��� ���
�����Z��
�N��ꌎ��O������@�i�c�k�߈��͂��� ��Z
�����Z��
�N��ꌎ��l������@�i�c�k�߈��͂��� �ꎵ
�����Z��
�N�ꌎ�l���@�i�c�k�߈��͂��� �ꔪ
�����Z��
�N�㌎��O������@�i�c�k�߈��͂����i���̈�j ���
�����Z��
�N�㌎��O������@�i�c�k�߈��͂����i���̓�j ��Z
�����Z��
�N��������@�i�c�k�߈����B�͂����i���̈�j ���
�����Z��
�N��������@�i�c�k�߈��͂����i���̓�j ���
�����Z��
�N���������@�i�c�k�߈��͂��� ��O
�����Z��
�N�㌎�����@�i�c�k�߈��͂��� ��O
�����Z��
�N�㌎��O���@�i�c�k�߈����B���� ��l
���L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�� ��Z
����㎵�Z
�N�܌�����@�i�c�k�߈��͂��� �O�Z
����㎵�Z
�N�㌎��������@�i�c�k�߈��͂��� �O��
����㎵�Z
�N�㌎��O���@�i�c�k�߈������������� �O��
����㎵��
�N�O����O������@�i�c�k�߈��͂��� �O��
�i�c�k�߂Ƃ̏o� �O�l
�q�ΘŁr�Ɓq�������_���r �O��
����㎵��
�N������������@�i�c�k�߈��͂��� �l��
�i�c�k�ߋ�W�s��ʁt����叴 �l�O
����㎵��
�N�㌎�ꎵ���@�i�c�k�߈� �l��
�o�� �l��
����㎵��
�N�l���Z������@�i�c�k�߈��͂��� �Z�l
����㎵��
�N�k�܌����l�@�i�c�k�߈� �Z��
����㎵��
�N������ܓ�����@�i�c�k�߈��͂��� �Z��
����㎵��
�N������O������@�i�c�k�߈��͂��� �Z�Z
�s�E�Łt�O�� �Z��
�i�c�k�ߋ�W�s�E�Łt����叴 ���Z
����㎵��
�N����@�i�c�k�߈� ����
�k�ߏG�叴 ���O
����㔪�Z
�N�܌������@�i�c�k�߈� ���Z
����㔪�Z
�N�Z����ܓ�����@�i�c�k�߈��͂��� ����
�i�c�k�ߋ�W�s���́t�\�叴 ����
����㔪��
�N�O����Z���@�i�c�k�߈� ���l
�i�c�k�ߋ�W�s�E�c�t���D�叴 ���Z
�܌��̋�\�\�k�߂̋傩�� ����
����㔪�O
�N�܌��l������@�i�c�k�߈��͂��� ���
����㔪�l
�N�ꌎ��Z���@�i�c�k�߈� ��O
�i�c�k�ߋ�W�s�����t���u�叴 ��l
����㔪�l
�N�����Z���@�i�c�k�߈� ��Z
�k�ߑe�` �㔪
����㔪��
�N�ꌎ��l���@�i�c�k�߈� ��Z�O
����㔪��
�N�����@�i�c�k�߈��͂��� ��Z�l
����㔪�Z
�N�܌��ꔪ���@�i�c�k�߈� ��Z�l
����㔪�Z
�N��Z�������@�i�c�k�߈� ��Z�Z
����㔪�Z
�N��Z����Z���@�i�c�k�߈����� ��Z��
����㔪�Z
�N��Z����Z���@�i�c�k�߈� ��Z��
�k�ߎO�\�� ���Z
�k�߁��K���@�\��� ���Z
����㔪��
�N�Z����Z���@�i�c�k�߈� ��ꔪ
����㔪��
�N��Z����������@�i�c�k�߈��͂��� ���Z
����㔪��
�N��ꌎ��������@�i�c�k�߈��͂��� ����
����㔪��
�N�㌎�����@�i�c�k�߈� ����
����㔪��
�N�ꌎ������@�i�c�k�߈� ����
�k�ߋ�W�w�l���x�\����� ���l
����㔪��
�N�O����Z���@�i�c�k�߈� ���
�i�t�^�j�k�ߕS��\�\�g������ ����
�Ҏ҂��Ƃ��� ��l�l
�u�i �c�k�߂���ˑR�A�莆�������B�k�c�c�l���̂Ƃ� ���玄�ƍk�߂���̕��ʂ��͂��܂�B�����\�N�A���͉i�c�k�߂ɂ����莆�������Ă����悤�Ɏv���B���ɂƂ��Ď莆���������Ƃ́A���ʂقǂ炢��ƂƂ����� �̂�����B�Ȃ�Ƃ������Ƃ��낤���A���͍����Ɏ���܂ŁA�킪�Ȃɂ����t�̂͂����������Ă��Ȃ��B�v �\�\�g����
�@���l�̋g�����i1919-90�j���o�l�̉i�c�k�߁i1900-97�j�ɑ����̎莆�������Ă������Ƃ́A�k�ߎ�ɂ̔o���s�Ս��t�ɋg��
����̗��Ȃ�
���Ă����Όf�ڂ���Ă������Ƃ�������炩�ł���B�g���ɕ]�`�s�y���F��t�̈ꏑ������A���z�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�̘A�삪�������A�k�߂Ƃ̐e��
�ȊW��\�킷��i���܂Ƃ܂��Ă��Ȃ����Ƃ��A���͂��˂��ˎc�O�Ɏv���Ă����B
�@����Ƃ��g�������Ȃ̕Ҏ[���v�������āA�܂��z�N�����̂��k�߂Ɉ��Ă����Ȃ̑��݂������B�g�������Ȃ́s�Ս��t�ւ̌f�ڂ͈��Z�O�N�̈�Z�Z������
�����Ǝv���邪�A�g�����q�i�c�k�߂Ƃ̏o��r�i�{���A�O�l�y�[�W�j�ɏ����Ă���悤�ɁA�k�ߋ�W�s�o�D��t�𒍕��w���������Z�Z�N���납�當�ʂ��n
�܂��Ă���B�g�����S���Ȃ�O�N�̈�㔪��N�O���ɂ́q������\�c�����ā\�r�Ƃ��ās�Ս��t�ɍŌ�̌f�ڂ����Ă���B
�@����Z�N�H�ɁA�P�H���w�قŁq����ɗV�� �o�l
�i�c�k�߂̐��E�r�W���J����A�s�Ս��t���f�ڂ̋g�������Ȃ��W�����ꂽ�B��_�W�H��k�Ђœ|���c�����甭�@���ꂽ�M�d�Ȏ����̈ꕔ�������B���͓�Z
�Z�ܔN�Ɏ����Ă悤�₭�A�k�߂̍���ł���i�c�k�߂̉�̑�\�ł�����q�炳��Ɂs�Ս��t�Ɍf�ڂ���Ă��Ȃ����Ȃɂ��ċ����Ă����������Ƃɂ����B���q
���炲�{�l���̋g�����͂����O�ʂ̃R�s�[���A����ɑ����ĕP�H���w�ق̊w�|���̕��̎��ς킹�āA���فE�i�c�k�ߕ��ɏ����̋g�����̉i�c�k�߈��̏���
�O�\��ʂ̃R�s�[�������肢���������B�������̐V�����̏o���ɋ��|���삵�����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���q����̎莆�̈ꕔ�������B
�@�u�P�H���w�ق���������i�c�k�߈��Ă̋g�������ȎO�\��ʂ��w�|���̒|�A�T�q���R�s�[���đ����Ă���܂����̂ł��͂��v���܂��B�^�����͂�����
���A��_��k�Ђœ|���i�c�k�ߑ���@��o���ꂽ���̂ł��B�^�k�߉����g��������̏��Ȃ������ɑ�ɕۑ����Ă�����������厖�Ȏ����L�^�ł������
���B�v�i��Z�Z�ܔN�Z�������t�j
�@�@�@�@�@��
�@�ȏ�́A��Z�Z�ܔN���������Ƃ������z���ꂽ���s��������Ɨp�^�C�g���s�i�c�k�߈��g�������ȏW�t�̂��߂ɏ����������q�Ҏ҂��Ƃ����r�ł���B���̂�
�뎄�́s�i�c�k�߈��g�������ȏW�t���q���Y��ԑp��2�r�Ƃ��ē��p���̑��e�s�g���������s�U���W�t�i���Y��ԁA�����N�g�ŗ��A�����s�j�Ɠ����̍ق�
�g�݂�����ׂ��A�g�����k�߂Ɉ��Ă����Ȃ��e�L�X�g�G�f�B�^�œ��͂��Ă���A�c�s�o�\�t�g�iAdobe PageMaker
6.5J�j��p���āA�{���͂ǂ��ɂ��`�𐮂����B���ꂪ���u�����ɂ��������o�܂͂͂����良���Ă��Ȃ����A�����炭�������������낤�B�u�V�т̎��Ԃ͏I
������v�������́u���͂܂����̎��ł͂Ȃ��v�B�����A���Ȃ킿��Z�Z�ܔN�����̃T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�̒���X�V������Ɓq�g�����ƃW�F�C���Y�E�W��
�C�X�r�A�q�g�����̑�����i�r�i���c�j�T��W�s�����Ă����t�̏Љ�j�Ȃǂ�����A�q�ҏW��L�r�ɂ́u�V���Ɉ�сA�g�����̖����s�U���������B�肵��
�q�܌��̋�\�\�k�߂̋傩��r�v�Ƃ��u�g�������Ζ�������R��������X�A�������[�Ȃǂ̏o�ŎЂɂ��Ă��A������ׂ����������Ă��珑�������Ǝv���v��
�ǂƂ���B�i�c�k�߈��g�������Ȃ��Y��ȍ��q�ɂ܂Ƃ߂邱�Ɓi�ނ��A�ǎ҂͎�����l�ł���j�����A�����̋g�������̈��D�҂Ɍ����ĐV���ȋL����������
�Â��邱�Ƃ�D�悵�����̂��낤�B�����āA���̑I���͐����������Ǝv���B
�@��Z���N�l���A���m�̏��V�������Ɏ��s�V�t�̉i�c�k�ߓ��W���i���N�������s�j�Ɂq�i�c�k�߂Ƌg�����r�������Ăق����Ƃ������[���������������B
�����������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���M�̂Ƃ��ɏd���̂��s�i�c�k�߈��g�������ȏW�t�̃v�����g�A�E�g�������B�Ƃ����PageMaker�̃t�@�C���͓�
�Z��Z�N�ĂɃp�\�R�������v���[�X�����ہA�V�����@�B�Ƀ\�t�g���C���X�g�[���ł����A�����������Ă��邤���ɌÂ��@�B�͓d��������Ȃ��Ȃ�A���̂c�s�o��
���ɖ߂��č�Ƃ��邱�Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ����iPageMaker��6.5J�̎���7.0J���ŐV�łɂ��čŏI�Łj�B��Z���N�܌��AAdobe
InDesign
CS6�Ƃ����c�s�o�\�t�g�������B�����킢�Ȃ��ƂɁs�i�c�k�߈��g�������ȏW�t�̃t�@�C���͐V�����@�B�ɕۑ����Ă������̂ŁA�悤�₭�����ɂ��ׂĂ�
�V�������Ői�߂鏀���i���̌��e�Ƒg�ŗp�c�[���j���������B
�@���̂Ƃ��Ђ�߂����̂��s�i�c�k����\�\�q�莆�r�Ɓq���r�Ɉ˂�t�̍\�z�ł���B�g�����k�߂Ɉ��Ă����Ȃ�N�㏇�ɕ��ׂ����̂��x�[�X�ɂ��āA�����
�����ցs�u�����v�Ƃ����G�t�⓯�k����Łl�ɋg�������^�����k�߂Ɍ��y�����U���͂������A�g���ɂ��k�ߋ�̐�i�����Ɂs�Ս��t�Ɍf�ڂ��ꂽ�j��D�肱
��ł����B�s�V�t�ɏ������q�i�c�k�߂Ƌg�����r�́A���ɂ����Ċ����ɐ�����B�S�̂̍��i�͂���ł����Ƃ��āA�ǂ�ȔŖʂɂ��邩����肾�B�Ҏ[�̗v���Ƃ�
�u�Ȃɂ��v�Ɠ����ɂ�����u�ǂ��v�����邩�A�����炾�B
�@�q���Y��ԑp���r�i�����܂ł��Ȃ����z�̏������j�̂Ƃ��ɂ́A�W�J�~�ꂳ��ҏW�́q�}���p���r�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t���Q�Ƃ����B����ɕ��
��PageMaker�́s�i�c�k�߈��g�������ȏW�t��InDesign�ɕϊ�����ƁA�t�H���g���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�g�̍ق������B�����͗��p�Ȃ�
�l�����ɐV�K�ɍ\�z���Ȃ����ׂ����A�ƌ�����B�z�������ׂ��̂��A������܂��W�J����ҏW�́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�ł���B����������
�l�Z���ł͂Ȃ��`�T���ɂ��āA�ǂ����Ă��{���i���z����j��10�|�A���Ȃ�9�|�őg�݂��������B�����ŎQ�Ƃ��ׂ��{�́A���ؒ��h����ҏW�́s�u�����v��
�����G�t�i�v���ЁA��㔪�Z�j�ł���B�����́u�{���V���V���ȁ@10�|�O�㎚�l��܍s�g���Łv�i�s�g���������t�j�ŁA�{���E�m���u���E���͂���P���A
���Ȃ�9�|�g�͓����́q���Ƃ����r�ɕ키���Ƃɂ����B���Ȃ킿�A�������낵�́s�y���F��t�ɑ���u���R���[�W���s�i�c�k����t�̓��e���A�ŏ��̎U���W
�s�u�����v�Ƃ����G�t�̑̍قɐ��邱�Ƃɂ����킯���B
�@�@�@�@�@��
�@�s�u�����v�Ƃ����G�t�̋g�����́q���Ƃ����r�i�킸���\�O�s�����A�Ȃɂ��ėv�����́j�Ɋr�ׂāA�Ȃ��Ȃ��Ə����Ă��܂����B�Ō�ɂȂ������A�{����
�g�����i�c�k�߂Ɉ��Ă����Ȃƍk�߂Ɍ��y�������́A�Ȃ�тɂ���ƕs���̍k�ߋ�̐�����߂Ă���B�g�����Ҏ[�ɂȂ�s�k�ߕS��t�́q�o���r���g���̒���
�Ƃ��Ė{���ɁA�����̖{�̂��Ȃ��I��W�q�k�ߕS��r�͕t�^�Ƃ��Ė{�������Ɍf�ڂ����B���̓����A�i�c�k�߂��g�����Ɉ��Ă����ȂƂƂ��Ɂs�g�����E�i�c�k
�߉������ȏW�t���҂܂�邱�Ƃ����҂��A�{����������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��Z���N�܌��O���
�k�NjL�l
�s�k�ߕS��t����|�����n�ӈ�l�����̂悤�ɏ����Ă���B�u����A�ԑ��k�r��l���u�k�ߕS��v�̖{���ɗp�����ꍆ��������
����Ȃ��Ƃ����Ă������A���̊����͌����̊����ō��͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�̂͌����A�����A�G�p�A�z�n�A��c�Ɖ]�����������[�J�[�������āA�����̌`��c
���̓��̔䗦���قȂ��Ă����B�������𑵂���ɂ͏�C���p���犈���������͎����A�����邵���Ȃ��A��C�̊����ɂ����Ƃ��߂��̂������̊����������v�i�q�։ԏ��ǁr�A
�s�ł���f����2.0�t�A2011�N6��6���j�B�����ɂ��Ắu�����͕�^�����ς��Ɣ����ɏc���̓����̔䗦���قȂ�B�܂������̉��̖ʐς�����
�ɈقȂ�B�����̊��������ɂ͂����Ƃ��C�ɓ������B�Ȃɂ����A��^�����@�B�̐��x���Ⴄ�B���x���Ⴆ�G�b�W���V���[�v�ł���v�i�q�N�䔦�Y����̂��ƂȂǁr�A���O�A2008�N8��12���j�Ƃ���B�s�k��
�S��t����ɂ��Ă܂�������̂́A�v���̂ق��y�����ƂƁA�ꍆ�����ɂ��k�ߔo��̈��|�I�ȑ��݊��ł���B�z�n���c�Ɋr�ׂāA�����Ɋւ�����͂قƂ�
�ǂȂ��ɓ������B�����̊������^�ɂ��Ă��ڂ����m�肽���Ǝv���B
2000�N12��31���i�O���I�Ō�̓��ł���j�Ɋ��s�����s�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�i���Y��ԁj�Ɏ����ꂽ�k������ 3�Łl���쐬�����̂ŁAPDF�t�@�C�������J����B�ȉ��ɓ����̂��Ƃ����q���J�ɍۂ��ār�Ǝd�l��^���āA�s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t�̏Љ�� �ウ��B
�s�g�����S���ѕW ������k������3�Łl�t���J�ɍۂ������@�s�g�����S���ѕW��� ���k������3�Łl�t�@2012/11/30 �@�yPDF�t�@�C���z�@846KB
�s�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�Ŗ{�����̏��łɒǕ₵���q�����r�i���єԍ�137�j�ȍ~�A�q�C�̏́r�i35�j�A�q�f�́r�i174�j�A�q��ɂār �i191�j�A�q�����r�i138�j�A�q�G�̂Ȃ��̏��r�i40�j��5�т̖������т������i��������S���W�����^�j�B�����������Ƃ������āA�苖�̕ҎҖ{�� ������v����Ԏ��▢�����т̏����������tⳂŌ��ꂵ�����肳�܂�悵�Ă���B�����͏��o���ڂ́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i262�j�̒T���� ���������_�Ŗ{�����k������3�Łl���㈲�������ł������A�Ƃ肠���������_�ʼn������A���J����B������㉟�������v��������������̂ŁA�������� ���B
���ɁA2008�N11������2011�N11���ɂ����āA�s�����G�߁t����s���[���h���b�v�t�܂ł̋g�����̑S���W�Ɏ��^���ꂽ���� �̖{���Z�ق��s�g�����̎��̐��E�\�\���l�E�����Ƌg�����̍�i�Ɛl���̌����t�ihttp: //members.jcom.home.ne.jp/ikoba/�j�y�NjL�F 2017�N2������uhttp://ikoba.d.dooo.jp/�v�ɕύX�z�Ɍf�ڂ������ƁB�ڍׂ͓��T�C�g�́q�g�������W�{���Z�قɂ��ār�ɏ��� ���A���̒����ŋg���̎���ꂪ���o�Ə��ł̂������ōł����������Ƃ��킩�����B����܂��āA��e����s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j��⊮�� �鎑���Ƃ��āA�g���̘a�́i�Z�̂Ɛ����́j�E�o��E���т��܂ޑS���Ƃ̏��o�`�\���ɍژ^�����s�g�����̑S���Ɓt���쐬���ł���i�����p�̂��߁A���J�� �\��͂Ȃ��j�B���́s�S���Ɓt�ɑΉ������A�ڍׂȏ��o�����L���������̉����V�ł��s���ɂȂ����B
�� ��ɁA�{������d�q�t�@�C�������邱�ƂŁA�p�ɂȉ�����Ƃɑς��A�����̌��\���e�ՂɂȂ邱�ƁB����́s���㎍�ǖ{�\�\�����ŋg�����t�i�v���ЁA 1991�j�Ɍf�ڂ����q�g���������r�̕s���̉�����ړI�Ƃ��ăE�F�u�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t���J�݂������@�ɓ������B�����Ƃ��d�q�t�@�C����html �ŋL�q����Ȃ�A�{�����̍��q�̂̎��ʂ̐������ێ����邱�Ƃ͓���B�����ّ̈̎���r�ɂ��ӂ肪�ȕ\���̂ق��A�{���̏��̂�T�C�Y�ȂǁA���C�A�E�g �ʂ̐��x�͖]�ނׂ����Ȃ��B���������Ɋӂ݂āA�����DTP�\�t�gAdobe InDesign�Ńy�[�W�A�b�v�������̂�PDF�t�@�C��������̂��œK���Ɣ��f�����B����E���{�������Ȃ����̂́A�k������2�Łl�Ɠ��l�A������̔ʼn� �Ƃ��Ēʗp���鎆�ʂ�ڕW�ɐ��삵���B
�� �O�ɁA���������Ӑ}����������c�[���̈����Ɋ���Ă������ƁB���́s�g�����̎��̐��E�t�����߂�Adobe GoLive�ŃI�[�T�����O���Ă������A���݂̓t���[�\�t�g��KompoZer�ō�Ƃ��Ă���BKompoZer�͂킪�T�C�g�ɂ͂܂��\�����Ȃ��A������ �s�̃\�t�g�̕K�v��F�߂Ȃ��B�������A���ɂƂ��Ĉ�����̓E�F�u�y�[�W�قǃV���v���ł͂Ȃ��B�s�g�����S���ѕW������t���ł́AMacintosh�̃��[ �h�v���Z�b�TEGWORD�őg�݁ALaserWriter�Ńv�����g�A�E�g�������̂��k�����āA���ʃR�s�[�����B�{���̓����E�~���ƒ��S�V�b�N�̘a��2�� �̂ŁA�W�̖{���p����A��6���{�ȂǁA���܌��Ă�����Ȃ�ɔ������B�k������2�Łl�ɂ͐�����̃N���W�b�g���Ȃ����AAdobe PageMaker�őg��ŁA������͌y��������B������ɂ��Ă��A���܂̎��Ɂk������2�Łl�Ɠ����̌��ʂ��E�F�u�y�[�W�ŏグ�邱�Ƃ͕s�\�ł���B
InDesign �̋@�\���K������Ӗ������˂āA�s�g�����̑S���Ɓt�ɐ悾���ās�g�����S���W�t�̍Č����I�Ɏ��݂��B���ň���Ō�̑����搂�ꂽ���̏����̑g�ł��� �w�Ԃׂ��_�͑����B�g�p�����̑I���Ƒg�̍فB�W���莫�E�����܂��̍s�h���ƍs�ԁA����炪�y�[�W�̍Ō�ɗ����Ƃ��̏������@�B����̖{���ł́s��ʁt ���^�̊K�i��̎������i�Ƃ�킯���ʗނ��܂ނƂ��̒������@�j�B����A�{�����̂ɑI���˖����̂ŕ\���ł��Ȃ�Unicode�̊����i����͖������ŁA ���̂�MingLiU-ExB��PMingLiU�ɕς��ĉ��u�����Ă���j�B�Ƃ��ɁA�s��̖`���\�\�f�U�C���̓���t�i�I�ɚ������X�A2005�j�̒��� �Ƃ��Ă��m����O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�̏��c�s������́A�q�����g�݁��A�C�f���e�B�e�B�r�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
���ꂩ�炠����G�����Ă��āA��T�ԏW�����čׂ����������܂����B�����A�ؑ��T�����S������Ă��� �w�n�C�t�@�b�V�� ���x�͋C�ɂȂ�G���ł����B�ł��A�^���悤�Ƃ��Ă��^�����Ȃ��ǂ���������ł��B������A�ǂ��������̂��g���Ă��āA�ǂ������g�ݕ�������Ă��邩�� ���A���s�̃��C�A�E�g�╶���g�݂͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ��O��I�Ɍ������Ă�������ł��B����������߂n�[�h���͂����Ɖ�����B���̍�Ƃ͂���Ă��� �Ă悩�����ȂƁA���ł��v���܂��ˁB�i����s�E�����^�I�sAdobe InDesign�@�����g�݂̊�{�Ǝ��H�t�A�������V���ЁA2010�N1��29���A���`�O�Z�y�[�W�j���ɂƂ��Ă� �g�ł̌����́A���͂ƍl�@�����ł͕s�[�����B���ۂɑg��ŁA�w�肵�����̂��ǂ̂悤�ɑg�݂����邩�������Ȃ��ƁA�ł��d�v�ȕ����݂͂��Ă��Ȃ��B�ו��̈� �����͂����đS�̂ɂǂ̂悤�ȕϗe�������炷���B�����̌���ɗ��������Ƃ́A������������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B�g�������̖{���̍Z�ف\�\����̈ꎚ�ꎚ ���ƍ����Č��e�������̏�Ԃ͂��l�@���邱�Ɓ\�\���܂������������B�g���͎��т����M���邾���łȂ��A�s�t�́t���������ׂĂ̒P�s���W�̖{���� �Ƃ��Đ���҂Ƃ��čZ�����A�i�s�|�[���E�N���[�̐H��t�ȊO�́j�S�P�s���W�̖{���g���w�肵�A����ɂ͑��{���������B�ڂɌ����邷�ׂĂ��w�肵�āA12�� �̎��W���������B���l�E�����Ƌg�����̍�i�̌����Ƃ́A���̑��̂�ǂ邱�Ƃ��ƕЎ����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�@2012�N11��30��
���ш�Y
�s�g�����S���ѕW������k������3�Łl�t�@���ш�Y�Ҏ[�A���Y��Ԋ��B A5���E�{��64�y�[�W���g�E2�F���B�����ጾ�A���іژ^�A�����{���k�S286�сi�}�����[�Łs�g�����S���W�t�����^��5�т�Ǖ�j�̎��єԍ��E���ѕW ��E����E��݂��ȁE�S���W�f�ڃm���u���A���і{���`��1�s�A���ѐߐ��E����̖{���s���E���o�}�̂̏ڍ��E�����^�P�s���W���邢�͕ω��z���������сA ���l�l�A�����o�����f�ځB�i2012�N11��30���APDF�t�@�C�����J�j
�k�t�L�l
���t�̕\�������A�����_�ł͈ȉ��́u�k�c�c�l�v������������͌l���̂��ߌf�����Ȃ����ڂł���B������Ƃ��Ċ��s����ۂɂ͐����ɋL�ڂ��邱�ƂɂȂ�
���B
�g�����S���ѕW������k���� ��3�Łl
1995�N5��31��
���Ō���36���iA��6���EB��30���j���s
2000�N12��31���@�k������2�Łl����120���iA��20���EB��100���j���s
2012�N11��30���@�k������3�ŁlPDF�t�@�C�����J
�Ё@��
�k�c�c�l�~�i�ŕʁj
�Ҏ[�� ���ш�Y�i���₵�E�����낤�j
���s�� ���Y���
�k�c�i�Z���j�c�l
�X�֔ԍ��@�k�c�c�l
�d�b�ԍ��@�k�c�c�l
�X�U�ց@�k�c�c�l
�g�@�� ���낾���i�g���E�������j
�o�@�� �g���E������
���@�� ���낾���i�g���E�������j
�Ł@�� ���ш�Y
���{���̎d�l
A5�������i210�~148mm�j�E���J�����g�E�{��64�y�[�W2�F�i�X�~�E���F�A�J�j�E�\��4�y�[�W4�F
��Adobe InDesign CS6�̐ݒ�
�m�����n
�E�{�������˖��� Pro R�i�����E�����E�@11Q�j+Adobe Caslon Pro
Regular�i�p���E�A���r�A�����@11Q�@���������E�����䗦�e105%�j�@������11H�@�s����17H�@42���l��42�s�@�V�n�^���E�����@�i����
���E�܂�Ԃ��������Ȃ��^�s�����p�^�Ԃ牺���Ȃ��^�s���̋�_�͑S�p�h���^�����ŏ��l�l��
�E�m���u���i�m�h�j��Adobe Caslon Pro Regular�@14Q
�E���i��������13H�����j��Adobe Caslon Pro Regular+���˖��� Pro R�@13Q
�E���o���i2�s�h���j�����˖��� Pro M�@16Q
�E�����i2�s�h���j�����˖��� Pro M�iC15+M100+Y100�k���F�A�J�l�j�@16Q
�m�ژ^�ipp.10-16�j�n�m���t���L���ip.64�j���n
�E�{�������˖��� Pro R�@10Q�@������10H�@�s����16H�@46���l�߁E24���l����44�s�@
�V�A�L16.5mm�^���E����
�E���o���i2�s�h���j�����˖��� Pro R�@11Q
�剪�����E���쌪�E���X�؊��E���J�Y���E�ԓc���P���ӔC�ҏW�����s�S�W�E���㕶�w�̔����t�̑�13���i�{�Y���сA1969�N2��10 ���j�́s���� ��Ԃ̒T���t�Ƃ����E�܂����W��ŁA���͂��܂ł��Ƃ��ǂ���Ɏ��i2004�N�Ɂu�V���Łv���o���j�B�{���͋g�����s�Õ��t�i1955�j����i�Õ��^�Õ� �^�Õ��^�Õ��^���^�~�̉́^�Ă̊G�^�]�́^�҉́^���b�^���̏ё��^�ߋ��j�����^���Ă���B

�s�����Ԃ̒T���k�S�W�E���㕶�w�̔����E��13���l�t�i�{�Y���сA1969�N2��10���j
�̔��Ƌg�����u�Õ��v�̔��y�[�W�k���{�F���Ì��l
����Ƃ����̓y�[�W�ɖڂ����炵�Ȃ���A���Ȃ��ƂɋC�Â����B��̂ɋg���́A����̎��ɐU�艼���i�쑺�ۜ��Ɉ˂�u�ǂ݂�����Ǝv ���銿���� �t������A���ʂȓǂݕ������銿���E�����Q�ɕt������v����j�Ƃ��Ẵ��r�͕t���Ȃ��B�Ƃ��낪�s�����Ԃ̒T���t�́s�Õ��t�ł́u���m�����n��v�u��A �m�̂ǁn�v�u���m�͂���n�v�u�u���m����n�v�u��m�ނ��n�сv�u��m���т����n�����v�u��m�˂��n����v�u�O�m�͂��n��Ă���v�u�V�m���n���v�u�� �m�܂��n���ł���v�u���m�悾��n�v�u�`�R�m����n�v�u�Ám�܂Ȃ���n�v�u�E�C�m���肭�n�v�Ƃ���B�����Ƃ��u���Ȃ��Ɓv�Ƃ����̂́A���r���̂��� �ł͂Ȃ��B�����̐U�艼���́s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�i�}�����[�A1967�N12��10���j�Ɏ��^���ꂽ�s�Õ��t�S�т̐U�艼���Ƃ܂��������� �ŁA�����炭�g���́s�����Ԃ̒T���t�̌f�ڌ��e�Ƃ��ās���㎍�W�t�́s�Õ��t���w�肵���̂��낤�B�Ę^�ɍۂ��čŐV�̊��{���e�L�X�g�ɂ��邱�Ǝ��́A�� ��̕s�v�c���Ȃ��B���͂����q�g�������W�s�Õ��t�{���Z�فr�� �u�s���㎍�W�k���㕶�w�� �n67�l�t�́s�Õ��t�Ƀp�����r��t�����̂��N�Ȃ̂��킩��Ȃ����A���@����ɁA�k���㕶�w��n�l�̕ҏW���ł͂Ȃ����낤���B�g�����p�ӂ����{�����e�̓� �NJ����ɕҏW�����ǂ݂��Ȃ�U��A�g��������𗹏������A�Ƃ��������肪����ɋ߂��悤�Ɏv���v�Ə��������A�������̍l���ɕς��͂Ȃ��B�u���Ȃ��Ɓv�� �����̂́A���^���тɁu��m���т����n�����v�i2�ӏ�����j�̂ق��Ɂu���т��������v��2�ӏ����邱�Ƃ��B�������A�\�L�̕s������������Ă����̂ł͂� ���B����ɂ����āA��ɍł��ӂ��킵���\�L��Nj�����͎̂��l�Ƃ��ē��R�̉c�ׂł���B���́u��m���т����n�����^���т��������v�����g�����̈����u�� ��v�Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����_�ɒx�܂��Ȃ���C�Â����̂��B
�g���@ ���x�S���W���Z�����Ă��Ȃ���A�Ȃ� �Ƃ���ǂ���i����ł��邩�A�Ɗ�������ł���B���ɂ͈��邽�̂������Ȃ�������Ȃ���Ȃ����A�Ƃ������������̍����Ă�����ł��B�����̎� �͎���ŏ��������Ă����Ȃ����A�����Ƒ��ȂȂ܂Ȃ܂������̂������Ă���K�v�������Ȃ����A�����������̂���͂�h�{�������Ȃ����낤 ���A�ƁB�ڂ����g���ł��t�H�����łȂ��āA���炩���Ȃ肽���A�����������Ƃ����ӎ��������āA�w�Â��ȉƁx�͂����������̂ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B�� ���A��������ł��Ȃ邩���킩��Ȃ��B�V��N���u��v�Ǝw�E�����̂͂��܂��Ǝv���܂��B
�i�g�����E����N�v�k�Βk�l�q�͌ЂƂ������E�ցr�A�s���㎍�蒟�t1967�N10�����q���W���g�����̐��E�r�A�l�y�[�W�j
�⁁����A�ǂ�Ȏ��������Ă��������Ƃ��l���ł����B
�����w�m���x�Ȃǂł͈��̎�����g���Ă��܂����B����́A���t�Ƃ��Ă͂킩��₷���A���e�͂悭�킩��Ȃ����́A���ǂ������ă]�b�Ƃ�����́A�������� �Ƃ��������̂��ł�����Ǝv���܂��B
�⁁�w�Â��ȉƁx�́H
��������ɋ߂����̂ł��B
�i�����r�Y�q�g��������76�̎���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�N9��1���A��l�܃y�[�W�j
�����Ȃ��ƂɎ��͂��́u�i���́j����v�����ꂾ�Ƃ���v���āA�Ȃ�̋^��������Ȃ������B�����Ƃ������v�킹�邾���̗��R�͂� ��B���Ƃ��� �s�g�������W�k���㎍����14�l�t�́s�m���t�̏��^���т�������i�����^�d���^�`���^�m���^�P���^�ā^�Ō`�^��́^���Ƒ��^�r���^�����^�����j�ŁA�� �́A�Е������������̍s�u�i���́j����v�̌֎��łȂ��ĂȂ낤�B�������g�����̍ŏ��̑n�삪�Z�̂ł��������Ƃɑz�����������A���ꂪ�a ��ł��邱�Ƃ̉\���ɋC�Â��Ă�����ׂ��������B�p��������悤�B
�E�q�́i�A�E10�j
���Ԃ��삵�������Ă䂭�i��1�s�j
�E ���鑒�Ȃ̒f�z�\�\�q��n�ɂār�i�A�E23�j
�ߐ��͚삵���i��1�s�j
�E �t�̇U�i�A�E27�j
�k�c�c�l�^�삵�������̔畆���������ɂȂ�ȁ^�k�c�c�l�i��6�s�j
�E �~�̉́i�B�E8�j
�~�̖閾���̚삵�������̂Ȃ��Ɂi��40�s�j
�E �]�́i�B�E11�j
�H�̖̎����삵���i��23�s�j
�E �҉́i�B�E12�j
���̂悤�ɂ��т����������炰�̂��������̂ڂ��Ă䂭�̂��i��13�s�j
�E ���̏ё��i�B�E16�j
���т����������̔r���̂Ȃ��Łi��38�s�j
�E �āi�C�E10�j
�삵�������N�̋��̗��́i��17�s�j
�E ���������i�C�E16�j
���т��������i�v�L���̔g�i��6����j
�E �����i�C�E19�j
�o���Y�ޚ삵�������̖�̏j�Ձi��157�s�j
���̚삵�����̈ł���i��163�s�j
�E �ʕ��̏I��i�D�E2�j
�_�����Ȑ��̂��т��������D���ցi��15�s�j
�E�A��i�D�E6�j
���l�̂��т��������������ĂɌ����ʁi��23����j
�E �́i�D�E9�j
���ނȂ�Ή�����삵���m�̑��i��8�s�j
�E �ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�j
ⴂ̂悤�Ȕ����̂��т����������Ɓi��4�s�j
�E ��`�i�D�E19�j
��̔g�̉��̂��т��������}�т̋��i��27����j
�E �s�ł̌`�ԁi�G�E16�j
�ł��t����ꂽ�삵���B�Ɓi��18�s�j
�E ��i�H�E21�j
���͂��т��������u�ށi��10�s�j
�E 雞�i�J�E1�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�삵���U��������́i��36�s�j
�Ȃ��ł����ڂ����̂��q雞�r�ŁA���o���Ɂu�U��������́v�������̂��A�s��ʁt�ł́u�삵���U��������́v�Ɖ��߂�ꂽ�B���o���̕W ��q�ɂ�� ��r�������́q雞�r�ɕύX���ꂽ�̂Ɠ��������̎����ł���A�u�삵���v���u�������v�ł͗p���Ȃ��Ȃ��B�u�ڂ����g���ł��t�H�����łȂ��āA���炩���� �肽���A�����������Ƃ����ӎ��������āA�k�c�c�l�B�ł��A��������ł��Ȃ邩���킩��Ȃ��v�Ɨ\�z�����Ƃ���A�g���͂������Ƃ����Ƃ��́u����v�̎g�p�� �S�O���Ȃ������B�����炭����⍂���Ɍ��������A���Ȃ킿�v���ДŁs�g�������W�t�i1967�j���܂Ƃ߂邱�Ƃł���܂ł̎��Ƃ�U�肩�����������肩 ��A�g���́u��m���т����n�����^���т��������v�ɑ�\�����a��ɂ��u�i���́j����v�̎g�p�āA�u�����́v�Ȃǂ̂�茩���ꂽ�^���Ȃꂽ�� ���Ŋ���ɂ�鋭�ʂƂ͕ʗl�̌��ʂ��o�����Ƃ����̂ł͂Ȃ����B�u���t�Ƃ��Ă͂킩��₷���A���e�͂悭�킩��Ȃ����́A���ǂ������ă]�b�Ƃ�����́A �������܂Ƃ��������́v��ڎw���āB�s�Â��ȉƁt�i1968�j�Ɓs�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�̓W�ɂ���炪�܂������o�ꂵ�Ȃ��̂́A����� �鎍����g�p���Ȃ��Ŏ������邱�Ƃ��ǂ��܂ʼn\���Ƃ����A����܂ł̎��Ƃ̊ϓ_���炷��Ήʊ��ȁA���Ȃނ��떳�d�Ȏ��݂̌��ʂƎƂ邱�Ƃ��ł� ��B�������A����̈���I�ȋ֎~���K�������ڎw���Ƃ���̎������邱�ƂɌ��т��Ȃ��ƌ����A�g���͌��R�Ƃ��Ă����|���B�O���͕�����邽�߂ɑ��� ����B�g�����ɂƂ��āA����Ƃ̊W�͂��̂悤�Ȃ��̂ł������ƍl������B
�g�����͎�N�̂����ƒ����Ƃ������A�c�O�Ȃ��獡���܂Ŏ���̒����͂������G������J����Ă��炸�A�g�����ǂ̂悤�Ȕ��p��i �� ���̂������킩��Ȃ��i�������A���ʂ�f�ނɗp�����I�u�W�F�͂���j�B���l�⏬���Ƃɂ͊G���悭����҂������A�Ȃ��ł��A���}���Œm����̂��s�S�ԕ��t �i������1979�N�j�̖؉��ۑ��Y�i1885-1945�j�Ɓs�ߑ����S�ԕ��t�i������1981�N�j�̕��i���F�i1918-79�j�ł���B���i�̏����́A�� �g�̏����s���̉ԁt�i1954�j�ɂ��Ȃ�ŕt�������Ɩۑ��Y�̕S�ԕ��ɂ��₩���Ă���B�g���͖ۑ��Y�ɂ����i�ɂ����y���Ă��Ȃ����A�������l�̕S�ԕ� �ɃT�t�������o�ꂷ��i���i���̏����̓��������W�s�a���`�t������Ƃ������A�����B�y2016�N12��31���NjL�F�̂��ɓ���B�q�g�����ƕ��i���F�r���Q�Ƃ̂��ƁB�z�s�a���`�t���s�̒� �O�A���i�͋v���Ԃ�̎��q���݂���̒��߁r���s���Y�t1962�N5�����ɔ��\���Ă���j�B
 �@
�@
�؉��ۑ��Y��q�T�t�����r
�i���j�F�؉��ۑ��Y�i�O�쐽�Y�ҁj�s�V�ҕS�ԕ��S�I�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2007�N1��16���j�ƕ��i���F��q�T�t�����r
�i�E�j�F���i���F�敶�W�s�ߑ����S�ԕ��k�㊪�l�t�i�������_�ЁA1981�N5��25���j
�ۑ��Y��̑Ό��y�[�W�\�\�؉��ۑ��Y�i�O�쐽�Y�ҁj�s�V�ҕS�ԕ��S�I�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2007�N1��16���A�ꎵ���y�[�W�j
�\�\�̕��������B�Ȃ��A872���̌��F�ł��a�S��2���Ɏ��߂������s�S�ԕ��t��4�N��A1983�N�����V����ܘY�I�s�S�ԕ��S�I�t�ɂ�74�ԂƂ��āq�T�t
�����r�����^�������B
87�@ �T�t����
���a���N�O�����ܓ��@���j��
�@�@�m���L�n�O�����ܓ��@��
�@���A�ɂ������������B�k�c�l�A�����ɂ܂͂�B�R��Ƃ܂��̂݉Ԃ����A�i���ɍg���̔~�ԁj�B�O���߁k�c�l���K�B����k���̎��_�l�ߊϓI�̘b������B
�@��A���l����ʐ����i�R��A����A������A�����m�k�l�n�j
�������P�̓�T�Ԍ�A�ۑ��Y�͂Ȃɂ�z���Ȃ���G�M�𑖂点���̂��낤���B�O�쐽�Y�́q����r�Łu�����ĎO���\���i�y�j�̔ӂɓ�����
��P�Ƃ����J
�^�X�g���t�B������B�{�����В��̑��c�Ǝ��ӂ͐h�����ē��Ƃꂽ���A��w�̈�ǂ͏Ă����B�u��R���A�����A�k�h�C�c��o�ł́l��]���F�Ă����B�k�{���l
�x�@�A��������₯���B�v���̂悤�ȋɌ��I���ɂ����ĐA���ʐ��͂������ɖ����ł����āA�\����I���߂̂����傤����O�����l���̎R��m����
�����n�܂ł̎l�\���Ԃ͈ꖇ����삪�Ȃ��v�i�����A����`���O�y�[�W�j�Ə����Ă���B�����܂ł��Ȃ��A��R���͋g����1934�N�i���a9
�N�j����1938�N�i���a13�N�j�܂ŋ߂���w���̏o�ŎЂł���B
�\�\���̍Ȃ̕��1930�N�i���a5�N�j�A�{�����܂�̋�P�̌��҂����A��
���X�J�C�c���[�͌������Ȃ��ƌ����Ă���B�펞���A�����S���{�Ђ̏��ŕČR�̔����@�ƈ������������{�R�̔�s�@���瑀�c�m���E�o�������̂́A�p��
�V���[�g���J�������̂܂ܒė�����̂�ڌ��������炾�B�ߏ��̐l�l�́A���ʂƒm��z�c������ė����n�_�֑������Ƃ����B���̓����ɐ�����ƕ����w��
�i���Ȃ݂ɋg�����̐��܂�́u�����s�{���撆�m���ƕ����v�j�A�����X�J�C�c���[�̊J�Ƃɍ��킹�ĂƂ����傤�X�J�C�c���[�w�Ɖ��̂����B�\�\
1979
�N3���A�؉��ۑ��Y�s�S�ԕ��t�̊��s���L�O���ĊۑP�œW��������ꂽ�B���i���F�̕v�l��q�́s�ߑ����S�ԕ��k�����l�t�i�������_�ЁA1981�N7��25
���j�́q���Ƃ����r�Ɂu���̓����߂��ɁA���F�̕��͂��A�傫�ȃp�l���ɂȂ��Čf�����Ă����v�i�����A��Z���y�[�W�j�Ə����Ă���B�u�B�ӂ̕����ɂ��
�Z���S�o���������̎ʐ������A�ꖇ�܂��ꖇ�ƌ��čs���Ƃ��A�������͔ނ��Ђ����ɂ��̖��̉��̒����͔R�����������ɂȂ����Ƃ�m�āA�Ō�̖���
�����ɑ�ď�M�̈���X�����̂ł͂Ȃ����̂��ƁA���z�����������Ȃ�̂ł���v�Ə��������i���F���̐l�����N�ĂɖS���Ȃ�Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����Í���
�낤�B���ɁA���i��q�T�t�����r�̕����\�\���i���F�敶�W�s�ߑ����S�ԕ��k�㊪�l�t�i�������_�ЁA1981�N5��25���A���y�[�W�j�\�\���N�����B
�T�t���� Crocus sativus L. �i����߉ȁj
�\���\����ɃN���[�J�X�ƃT�t�����̋��������͐��͔|�ɂ����͒�ɐA��@���̒��̈��������̋��ŊJ���͂��߂��̂ŏ����Ȕ��ɓ���Ċ���ɒu������ �����͂�����J�����̂ōQ�Ăě�������
17/11/1976
���ǂ��p��X�p�C�X�Ƃ��ėp����T�t�����͔ӏH�ɍ炭����A���̎����̃X�P�b�`�ɓo�ꂷ�邱�ƂɂȂ�̕s�v�c���Ȃ����A�g���̎��W �s�T�t�����E �݁t��1976�N9��30���ɔ��s����Ă���A���i�̓T�t�������ʐ����Ȃ���g���̐V����z�N���Ȃ��������낤���i�g�������i�Ɍ��{�������肩�ł͂Ȃ� ���A�����^��Y�͓ǂ�ł���j�B���i�͂��̔N�A�}�����[���璘�������o���Ă��Ȃ����̂́A�����Y�S�W�Ɠ�x�߂̒����֑S�W�i��������g���������j�̓� �e���{�ɐ��E�����Ă���B��l�̊ԂŒ��ڂ��Ƃ�͂Ȃ��������낤���A�ӏH�̓����̋�̂��ƁA�n���C���݂����Y�Ƃ���W�����F�̃T�t�������ԊJ������ ��z������ƁA�S������ꂷ��B
�k2015�N12��31���NjL�E2016�N12��31���C���l
2015�N12�����{�A�a�J�E�{�v��̒������X�Œ����^��Y�Ɉ��Ă����W�s�T�t�����E�݁t�i���提���{�j�������B���Ɍo�N�ω����قƂ�nj����Ȃ��ɔ��{
�ł���B�قڃn�K�L��̃x�[�W���F�̃J�[�h�Ƀu���[�u���b�N�̃y�������ŋg�������M�̃��b�Z�[�W���L����Ă���B
�u��������Y�l�^���̂��сA�����̎��W�𐄂��Ă����������肪�Ƃ������܂��B�x����Ȃ���A���点�Ă��������܂��B�^�k��㎵�Z�N�l�\��\����^�g
�����v
��
�������ʂŁA����Ƃ͕ʂɍ��c�@�l���������w�U����̋ޒ�p�Z��������ł������i����ɁA1976�N9��30���̊��s����ɂ͒��҂̋g�����獂�����ܑI
�l�ψ��̒����Ɍ��{���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��j�B���܂̑I�l�Ώۂ̎��W���ǂ̂悤�ɒ��B���ꂽ���킩��Ȃ����A����͒����^��Y���I�l��̓���
�i1976�N12��20���j�A���i�����E�s���J�u���̋{�v�j�œǂ�{�ł͂Ȃ��悤���B�g���́A�������u�����̏��ւ͗��Ă��Ȃ��v�Ƃł��������̂��A
�������܂̎������߂��v���Ђ̏��c�v�Y�����肩�畷�����̂��낤���B���������w�i�܂őz�������鋻���[�����提���{�ł���B���Ȃ݂ɒ������X�̌�
�����i��21,600�~�B
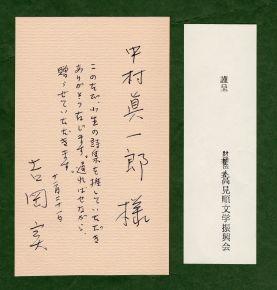
�������ܑI�l�ψ��E�����^��Y�Ɍ��������W�s�T�t�����E�݁t�ɓY����ꂽ�g�������M�̃��b�Z�[�W�J�[�h�ƍ��c�@�l���������w�U
����̋ޒ�p�Z��
�g�����̎��𑁂�����]��������]�ƂɎc��m�i1927-89�j������B���̍ŏ��ɂ��čő�̌��т́s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�̕҂���щ�����B�c�̋g���_�ŁA�����������Ă���ł����������̕��͂́q�����̖�S��r�i���{�Ǐ��V���A1958�N6��30���j�����A����́q�����r�i�C�E19�j���\����̎��]�ł���i�̂��V���Њ��s���Y�N��1959�t�ɍĘ^�j�B�g���̎��W�s�m���t�����惆���C�J����1958�N11���Ɋ��s������A���s�l�̈ɒB���v���s�����C�J�t1959�N1�����Ɏc�̎��W�]���f�ڂ����̂́q�����r�̎��]���Â������炾���A�g����܂̗]��������ās�g�������W�t�Ɏc���N�p�����̂́A�ɒB�̍єz�ł���i���Ȃ݂ɁA�c�́s�m���t�̏o�ŋL�O��ɂ��Q�����Ă���j�B�s�g�������W�t�̊����Ɏ��߂�ꂽ����q���I����ɂ��Ă̎O�̒f�́r�́A�ЂƂɂ͎����̐���������A�c�́u���I����v�_�܂��Ȃ��Ɨ������ɂ����i�����́u�f�́v�Ȃǂƍ\�����A�{���̎c�炵�����Əq�ׂĂق��������j�B�����Ɠ�������Ɏ��M���ꂽ���{�̌��㎍�֘A�̃G�b�Z�C�����߂��s���I����t�i�����ЁA1968�N5��20���j�ɂ��Ȃ���A���̂������T���Ă݂悤�B�����̑ѕ��Ɂu�g�E�Y�E���H�����㎍�l�Ɏ��錾�ꐢ�E�ٖ̋��ȉ𖾁v�Ƃ���悤�ɁA�����̎c�̎�v�ȊS�͋ߌ��㎍�l�̌���̉𖾂ɂ������B���������u���I����v�͉p���poetic language�i���I�\���j�̒���ŁA�c��������̗p�����w�i�ɂ͂���Ȃ�̔z���������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�u���I����v���s���I����t�ɍŏ��ɓo�ꂷ��̂́q����r�̎��̕��ɂ����Ăł���B�i�@�j���̐����́s���I����t�̌f�ڃy�[�W�m���u���B
�@���{�̋ߑ㎍�̃��[���b�p�I�u�����l�����ꍇ�A�w�C�����x�ȉ��̖��W�́A�܂��Ƀ��[���b�p���Ɠ��{���̂������ɁA�s�v�ȁA����A�ނ���L�Q�ȊɏՒn�т����肾�����B�����ł́A���[���b�p�̎��I������A���{�̎��I�������������A�U��̎��I���ꂪ���s���Ă���̂ł���B�i39�j
�u���I����v���A���I�\���Ȃ��������C���Ƃǂ��Ⴄ�̂��͂킩��Ȃ��B�q����r�̎��ɒu���ꂽ�G�b�Z�C�q���Ə����̂������Łr�ɂ͂�������B
�k�c�c�l���@�����[�ɂ��A���͂ł��邩����A�u�������E�v�k�c�c�l���牓�������āA����I�Ȑ��E�Ƃَ͈��́A�ʂ̑z���I���E���`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�\����䂦�ɁA���I����́A�ЂƂЂƂ̌��t�Ƃ��ẮA���Ƃ��A����I���k����g���Ƃ��Ă��A���ꂪ����i���\������u�Ԃɂ́A���͂����I�ȋ@�\�������āA�z���I���E�ɕ�d����Ƃ����̂ł���B�i41-42�j
�@�t���[�x�[���ƂƂ��ɁA�����͏I�����Ƃ����G���I�b�g���A�܂����͏I�����Ƃ����E�C���X�����A�Ƃ��ɐ��m�Ȕ��f�Ȃ̂��낤�B�ӂ���Ƃ��A�w�{���@���[�v�l�x�̍�҂̗��ɁA�����́A�Ƃ����������w�I���E���\�z���Ă��鎍�I�����crisis��F���������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�i45�j
�@��͂�A�ڂ��͉C���ƎU���̂������A�܂�A���I����Ə����I����̝p�Ԃɗ����Ă݂�K�v������B�i46�j
����ƉC�����u���I����v�ŁA�U���������I����Ȃ̂��B�ǂ����A�����ł��Ȃ��炵���B
�@����Ȃ�A������i�����̓Ƒn�����ւ肤��̂͂Ȃɂ��B�ڂ��͂��łɏ����I����Ƃ��������������I����ɑΔ䂵�ėp�����B�����āA����ɂڂ��͎U���ƉC���Ƃ����ÓT�I�ȑΔ���ꉞ�l���̊O�ɂ����Ă���B
�@ �����I����͂˂ɂӂ��̋ɂ����B�ЂƂ͓���I�Ȍ������E�ł���A�����ЂƂ͑z���I���E�ł���B���傤�ǁA�ȉ~�̌`�Ԃ��ӂ��̒��S�_�̋����ɂ���Č��肳���悤�ɁA�����I����͂��̂ӂ��̋ɂւ̌������ӎ����Ȃ���A���ɑ��l�ȏ�����i�݂����Ă����B������x���Ƃ��Ă݂�Ȃ�A�ق����œ_�����A�ӂ��̋��̏Ɩ��ɂ���āA�͂��߂Ă��̑S�e�𖾂炩�ɂ��镨�̂̂悤�ɁA�������E�Ƒz�����E�̗�������Ǝ˂��āA�悤�₭���w�����l��������̂��B�]���ď����I����͂��̂ӂ��̋ɂƂ̊֘A���˂ɕێ����Ȃ�������A���̋@�\�����������ƂɂȂ�B
�@����ɑ��āA���I����͂�����ڑ��ȓ��퐫����������������Ă��A���Ȃ炸�A����͌������E�ɔw�������āA�܂�������ɑz���I���E��ڎw���B�����ł͈��������������}�`�����������̂��B�i48�j
�����ł悤�₭�u���I����v�̒�`�炵�����̂��o�ꂷ��B�u������ڑ��ȓ��퐫����������������Ă��A���Ȃ炸�A����͌������E�ɔw�������āA�܂�������ɑz���I���E��ڎw���v�\�\����͂킩��B�������A�����I����̑ȉ~�̌`�Ԃ����O�ɒ���Ă��邽�߁A�u���I����v���~�m�A�n�ł͂Ȃ��āu���������������}�`�v���Ə�����Ă������͒ǂ����Ȃ��B����Ɏc�́u�����I����Ƃ̓��V�ł���v�i50�j�ƒf�肷��B
�@���V�͂ЂƂ̉^���ł���B����́A���Ƃ��Ă����Ζ������̂悤�ɁA�����̔ޕ����疳���̔ޕ��ւƉ^�s���Ă䂭�B���̗���ɂ�闥���������A���V�̃��V����{�����Ƃ����Ă����B
�@�������A���V�͌��t�ŏ������B����͏����Ƃ��O�Ϗ�́A�ڂ�����������I�ȏ�ɂ����ėp���錾�t�ƂȂ��ς�͂Ȃ��B�]���ē���I�Ȍ��t���l�ɁA���Ȃ炸�Ӗ������B�܂�A�L���Ƃ��Ă̐E�����ʂ�����̂ł���B�������A���̌��t���ЂƂ��у��V�̗���̂Ȃ��ɐg�𓊂���ƁA�����ɂ́A����I�Ȃ��̂Əs�ʂ����錾��I���E�������B�����A�����I����͌������E���痣�E���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B���R�Ӗ��̏d�ׂ�w���킴������Ȃ��B�K���Ȃ��ƂɁA����I���E�͑��`��F�߂�B���I����̐��E���A������`�I�ł͂��邪�A�����ł͑��`���͂ЂƂ̉ߓn�I�Ȓi�K�Ȃ̂��B���`�̋ǖʂ������āA����i�͂ЂƂ��Ȃ݂ɈӖ��������Ȃ��u�Ԃ���������B�i51�j
�����́u�k���I����̐��E�ɂ����Ắl���`�̋ǖʂ������āA����i�͂ЂƂ��Ȃ݂ɈӖ��������Ȃ��u�Ԃ���������v�͂����炭��́u���������������}�`�v�ɑΉ�����̂��낤���A���̐����������傽����e�Ƃ���̂����̃G�b�Z�C�̊�ڂł͂Ȃ������̂��B�����A���̐����͓ǎ҂ɂ͗^�����Ȃ��B�q���Ə����̂������Łr�͎��Ɉ����i���œ��˂ɏI���B
�@���_���������B���������`������������A����������A�ӂ��̋ɂ�������Ȃ�������A�����͖łт����Ȃ���A�ϖe���邱�Ƃ��Ȃ��B���邢�́A�����z����������ȂǂƂ������Ƃ��ł���͂����Ȃ��B�����āA�ӂ��̋ɂ̘A����ۏ��A������i����i���炵�߂�̂́A�˂Ƀ��V�̉^���ł���B�i51�j
�����Ə����I����ɂ��Ă͈ꉞ�����ł����Ƃ��āA���Ɓu���I����v�ɂ��Ă͎c�������[�����āA�ǎ҂́u����i�͂ЂƂ��Ȃ݂ɈӖ��������Ȃ��u�Ԃ���������v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��A��|���肷��^����ꂸ�ɕ��肾�����B���������u��l���q�����ЂƂ��Ȃ݂Ɂk������Ɂl�����v���{���̗p�@�ł���悤�ɁA�u�k���V�Ɓl����i�͂ЂƂ��Ȃ݂ɈӖ��������Ȃ��u�Ԃ���������v�Ƃ�����ɁA�����Ȃ菬���I����Ȃ背�V�Ȃ�����ēǂ����Ƃ���ƁA�����͑��`�I�ł͂����Ă��A����i�������ł���悤�Ɂu���`�̋ǖʂ������āA�k�c�c�l�Ӗ��������Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��A�ƋK�肳��Ă���i�܂����u���`�̋ǖʂ������āA����i�́k���`�̋ǖʂƁl�ЂƂ��Ȃ݂ɈӖ��������Ȃ��u�Ԃ���������v�ȂǂƂ��������̂ł͂Ȃ��낤�j�B�p��̑I���Ɨp�@���̂��c�̘_�|�𗠐�B�ǎ҂̓��̂Ȃ��ł́A�c�����̂����G�b�Z�C�Ƃ�����蕨�ɏ���Ăǂ����ֈړ����悤�Ƃ��邽�тɁA�i�s�����ɗ����ӂ�����Ȃɂ��̂��ɏՓ˂���B���_���������B�c�͂����i�q���Ə����̂������Łr�j�ŏ����I����̐����i��ǂł͂Ȃ��j�ɂ͐����������A�u���I����v�̉�ǂ͂�����̐����ɂ����s�����B
�@���Ƃ��A�g�����̎���i���܂��ɂ��āA�����ɂ͘A�̂ɒʂ���A�z�̎��I���ʂ�����ȂǂƂ������悤�Ȃ��Ƃ���������y�_���`�X�����Ⴂ�O�q���l�̂������ŗ��s���Ă���炵�����A���������ǂ���������Ȃ̂��낤���B�Ȃ�قǘA�̂ɂ͂���߂Ď��R�ȃC���[�W�̘A�z���삪�F�߂��邱�Ƃ͂�������������Ȃ����A�A�̘̂A�̂���䂦��͂���ȃC���[�W�Ƃ������B���Ȃ��̂ɂ���̂ł͂Ȃ��B�ڂ��ɂ͘A�̂��B���������ɂ̎��I���ʂ��ǂ����Ă������]���ł��Ȃ����A�A�̂̓Ƒn��������Ƃ���A���łɐ����̖����Ǐ�ɂ����Z�̂̎��I����̂������������̕��G�ɂ��Ĕ���Ȗ��Ƃ����O�I�Ȃ��̂ɂ�����邱�Ƃɂ���āA���̐�������낤���Ėh���Ƃ߂����Ƃł͂Ȃ����B�����A���̂��߂Ɍ���̓��ʂƊO�E�̃o�����X�͂����ꋎ��A���I����Ƃ��Ă͏\�S�������悤�ɂ݂���B�g���̏ꍇ�͎���͂܂������ΏƓI���B�ނ̎��I����̗R�������Ƃ߂�Ƃ���A�ǂ����Ă����O�Z�N�O��́A���̂��܂ƂȂ��Ă͍����I�Ƃ�Ԃ����Ȃ����I����̎����ɂ܂ł����̂ڂ�Ȃ���Ȃ�ʁB����͌���̂ЂƂ̌`���̑��ł̒���ɂ���Ă����B�`���ւ̐M���͂��������A�`�����̂��̂͂܂����ꂦ�Ȃ��B�����V�����`���ւ̗\���݂͂Ȃ����Ă���B�����A�`���͒��ۂƂȂ�A�T�O�ƂȂ��Ď��l�����̓��]���x�z���A�ނ�̖a���������I����͊O�E�������Ȃ��āA�Ђ������������蓹�͂Ȃ������B���ʂ��݂߂邵���Ȃ�����͂��傤�ǃo�x���̓��̍H�l�����̂���̂悤�ɁA���ɂ͌��ꂻ�̂��̂�۔F���A�����Ȃ����ƂɂȂ�͓̂��R�̓��s�����낤�B�����A�g���͂��́A���܂�ɓ��ʓI�ŁA�����I�Ȍ���̂Ȃ��ɍ����̓��{�̎��̖�����ǂ݂Ƃ�A���̂�̎���q�����B
�@�A�̂̎��l���������I����̕ێ������̌���̊O�I�����ɂЂ���������Ă���̂ɑ��āA�g���͔ނ̕����Ȍ���Ɍ`����^���邽�߂ɂ͂��̓��ʂɋ��邵���Ȃ��̂ł���B�����ċg���͌����ɂ��̋���Ɋ����Â��A�ގ��g�́A�����ē����ɂڂ������̐V�������I����̌`����n�肾������B�C���[�W�̘A�z����ȂǂƂ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă݂Ă��A���F�g���̕s���̌���̕\����Ȃł�ɂ����Ȃ��B
�@�g���̎��ƘA�̗̂ޔ�͍D���Ƃ̊ՂԂ��ɂ͂ӂ��킵���g�s�b�N��������Ȃ����A���{�̎��̌���ɂ��Ă͂����������J������Ƃ���͂Ȃ��B�i100-101�j
�{���U���́q���H�ˌ��r�i���o�́s�Z�́t1964�N4�����j�ɑ}�܂ꂽ�A�u���I����v�q�ɋg������_�������ł���B�c�́s�g�������W�t�̉�������̒��q�ł����ׂ��������B����ނ���A�q���I����ɂ��Ă̎O�̒f�́r�ւ̕s�������̔��H�_�ɐ��\�s�̋g���_�����������邱�ƂȂ����Ƃ����������������B�c�͌�N�A���̖����q���I����\�\����N�v���肪����Ɂr�i���o�́s�u�� ���w�k��3���l�t�A��g���X�A1976�N2���j�������āA�g�����_�q���l�̉^���_�o�ɂ��ār�i���o�́s���{�E�t1977�N8�����j�ȂǂƂƂ��ɁA�s���I����t�ɑ������_�W�s���㎍���]�t�Ɏ��߂Ă���B�����́q�f�́r�Ɠ����ɁA���邢�͂��̂܂��ɓ����ɂ��Ȃ���A�c�̋g���_�̒��j�ƂȂ�u���I����v�Ƃ����T�O�ɂ��Ă̗����������Ȃ��̂��B���Ȃ킿�q���I����\�\����N�v���肪����Ɂr�̎��̈�߂́A�P�s�{�s���I����t�̖`���ɐ������Ă�����ׂ������������B
�@����i�ɂ����錾�t�̋@�\���A���ꂪ���������N����|�G�W�[�̋����̂��Ȃ��ɐg�������āA�Nj삵�Ă䂯�A���ǁA���t�̂ЂƂЂƂ������Ă�����퐫����̗��E�A�����āA��i��ǂ݂����A����ɁA���̍�i�S�̂�ǂ݂������Ă݂�Ƃ��A�����ɗp����ꂽ���t�̌Q��́A�������ɁA���邢�͐܂�d�Ȃ�A���邢�͈�������Ȃ���A�ЂƂ̏��F�����`�Â����āA�����̓���I�Ȃ������܂�����ɑ��āA�c�R���雦�������֎�����̂ł���B���������������ƛ��������A�ǂ������������ŕ\����������̂��A���ꂪ�ڂ��̕��S����Ƃ��낾�����B
�@���{��̂��肪�����ŁA����Ɏ��ɂ����錾�t�Ƃ��������������Ă��A����͒P���ɂ��Ȃ�A�����ɂ��Ȃ�B����͂���ł����B����ƌ����A���A���邢�́A��A�O��̌����̂ł����Ȃ����A���̌��t�Ȃ�A�����Ɨ����I�Ȋg����������āA��i���\������S���̌��t������܂�����̂ł���B�������A���̌��t�̌Q�ꂪ�A��������������ێ����Ȃ���A���̑��̂ɂ����āA����I�ȏ�ւ̛���������ɔ�߂Ă��鎖����w�����Ȃ��܂ł��A���߂ĈÎ��ł����Ă����ɂ́A���̌��t�ł́A���܂�ɂ���X�����B�ǂ����Ă��A�V�����p����l���邵���Ȃ��B�������āA����Ƃ̎v���ŁA�ڂ��͎��I����Ƃ��������������͂��߂��B���d�͊o��̏ゾ�������A���܂��A�Ȃ��A���̖��l�Ȋ��o�䂦�ɁA���̌������͂ł��邩����T�ނ悤�ɂ��Ă���B
�@���łɁA�����ЂƂŖ����b��⑫���Ă����Ȃ�A���I����Ƃ������������g�����Ƃ����Ƃ��A�A�̗i��҂Ƃ������A�g�t�̖��������Ă��ꂽ�̂�poetic language�Ƃ����p�ꂾ�����B���̌��������V�����p�@�ŁA���Ƃ��Ƃ͓��{��́u����v�ɓ���poetic diction�Ƃ������t���\�㐢�I�����̃��}���h�u���ȍ~���X�ɂ�����A�����I�ɓ����Ď��R���^�̊m���ƂƂ��ɁA���S�Ȕp��ɂȂ����̂Ǝ��������āA�o�ꂵ�����̂ł���B�܂�A���O�Z�N�����肩��A�ڂڂ��ɂ���A�����ɂȂ��Ă����p��ŁA�����ł����T�ɂ͐����ɍ̗p����Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ����ŁA���G���͂��ł����@�ł���B
�@�b����Z�ɒ[�܂��Č����Apoetic language�Ȃ�A���邢�́A���̂��Ɠ�\�N���炢���Ēǂ�������悤�ɂ��ďo�Ă���lang[u]age poetique�Ƃ����t�����X��ɂ��Ă��A�܂��A���ʂ̖��ł���u���I����v�Ƃ������{��ɂ��Ă��A���ꂼ��̌���ɂ����鑽���̐��d�Ȉ�a�����������ĂȂ�����A�ق��ɁA����Ƃ��������K�Ȍ��t���Ȃ��܂܁A���w�p��Ƃ��Ċ��p����Ă���̂́A���R���^����̂Ƃ��錻�㎍���Ђ낭�s���Ă��邽�߂ł���B�܂�A���̌��㎍�𖡂킢�A���̖��͂����ЂƂƂ��ɐ������������߂ɂ́A�ǂ����Ă��u���I����v�Ƃ������t���A��Ԃӂ��킵������ł���B�i�s���㎍���]�t�A�W�p�ЁA1982�N2��10���A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
���Ȃ݂Ɂu���I����v�Ȃ錾���܂킵�́A�g�����̎��͂������A���͂ɂ��k�b�ɂ��o�Ă��Ȃ��B
�g�����͉i�c�k�߂̎��i���̏ꍇ�A�o��j������������̂͂�������A���V�����u�ӂ���Ƃ������̐��H�Ȃǔ��p���D�����������Ƃ��A���܂����������R��������Ȃ��Ƃ��v���Ă��܂��v�Ƃ����Ƃ���A���������D����_�ł��[���Ȃ����Ă����B�g�����k�߂Ɉ��Ă�1987�N6��10���t���ȂɁu�u�i�c�k�߂̓��v����A���x��P���ɂȂ�܂��ˁB�����������Ƃꂽ���ƂƎv���܂��B����A�k�ߓƉ��Ƒ���Y�ƕ����A�����ł����B�����A������L�ł��ʂꂵ�Ă���A��؈ꖯ�ƃG���b�N�E�Z�����h����āA���s�֏o���̂ł��B�V����i���L�q���a�a�ŁA������̗���߂Ȃ���A�r�[�����L�q��H�ׁA�߂��̃t�����\���ł������e�B�_����͒����̕ӂ����������ȍ�������`�������̂ł��B���̍��~�̏�ɂ��낪���Ă���A�S���}���قǂ̓S���̐^���ȗ�������܂����B������܂�ŁA�̌��̂悤�ɂȂ��Ă��āA���߂ł������Ȃ̂ŋ��߂܂����B�ꉞ�A��������̂��̂Ƃ̂��Ƃł����A�ǂ�Ȃ��̂ł��傤���B���x�̗��̂悫�v���o�Ƃ��āA��ɂ������ł��v�i�q�t�������r�A�s�Ս��t428���A1987�N7���A�Z�y�[�W�j�Ƃ���B���́u������܂�ŁA�̌��̂悤�ɂȂ��Ă��āv�Ƃ����������炵���B�������g�����ƍ����������Ȃ�A�Ȃɂ�[���Ă���ˎ闝�́q�����r�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�k�c�c�l�w���邩�A�����邩���ċg���Ƃɉ^�э��܂ꂽ�炵�������́A�����̚���A�����Ε��A�퐶�y��A�ÒO�g���P�A��������̌Ր}�A�����̌Ղ̗ڗ����F�A�k��H�D�R�l��D���D�M�Ȃǂł���B�܂��A�D�܂����v��ꂽ�Ƃ��ڂ������A�v�������q�A���B�̏���A�����̍��A�͈䊰���Y�̏������璆���ɂ����Ă̍�i�̂������A�����ĉ~�ȂǁB�������A�D�R�l��D���D�M�͋`���A�a�c�F�b�̈�i�ł���̂ŁA�{�l�����߂��̂́A�����ނ˗����̂��̂���Ƃ������ƂɂȂ�B�������A�����ł͔��߂̐l�X�ɂ��I�ȗϗ��ς̔��f�Ƃ��Ĕ������肪���ꂽ�Ƃ����̂ɁA�ނ�������ꂽ�炵���̂��A�؍H�i��Ε��A����Ȃǖ��炩�ɖT���̂��̂���ł��邱�ƁA����ɂ͏����̗����̏Ă����Ƃ��Ă����ЂƂ��������̂��A�����ł͂Ȃ��ɗڗ����F�A���{���������A�����炭�͑N�₩�Ȑ́A�����ė����Ƃ�������̂Ȃ��ł́A�ǂ��炩�ƌ����ƒ������H���ȕi�ł���͂��̏��i�����Ƃ����̂́A��͂��Ȃ��Ƃł��邾�낤�B���@�x���A�����́u�����݂̐F�v�ƌĂu���v�ɋg�����͔������Ȃ������̂ł��낤���H�i�s�g�����̏ё��t�A�W���v�����A2004�N4��15���A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
����ɁA�g�����ɂƂ��č����͂Ȃ������Ƃ�������ɑ��ẮA
�@���ۂɂ��t���������Ă���ԂɁA�g�����獜�������b�́A�v���o�b��ʂɂ��āA��x�����������Ƃ��Ȃ������B����͋��ŁA���͂����ʁm���傭�n�B�u���犿�̂���܂ŁA���҂𑒂��Ƃ��Ɍ��Ɋ܂܂������̂炵�����A���̕��K���̂ɊS���o�����g������́A���Ƃ������t���̂�����̎��̂Ȃ��Ŏg���Ă���B���{��������Ă���Ƃ��ɁA�Ƃ���Ô��p�X�ŋ��R�Ɍ������A���̏�ōw�����̂��Ƃ����B�������ɁA���̋��ʂ̍��𗯂߂Ă���Ƃ����A���̋ʂ̂��Ƃ����Ȃ���A�g������͂����������ӋC�ł��������A����͍�������������l�ԂȂ�N�ł������悤�Ȃ��̂ł��邩��A�g������̓��肳�ꂽ��䂪���Ƃ���ɋM�d�Ȃ��̂��Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B�^�����A��ォ�獡���Ɏ���܂ŁA�����ł͒��d������A���{�ł͎�e����邱�Ƃ̂Ȃ������u�ʁv�ɋg�������䂩�ꂽ�Ƃ������Ƃ́A���������ے��I�ł���B�ʂ̋��A�u���₩�Ȃӂ���݁v��������A������b�q���u�ۂ����Ə����ȓ��̂����Α��v�ƌ�闛���Ε��d�d���͂�L����\�ʁA���邢�́A�ނ�����m�A�A�A�A�n�Ƃ������́B�^�����炭�A�����ł���Ȃ�A�g�����ɂƂ��Ă��ꂪ�����ł���K�v�͂Ȃ������̂��B�ނ������̂��̂��D�̂́A�u����̌`���v�i�R��Y�j�Ƃ��Ă̗������̂��̂��������ł͂Ȃ��ۂ��ւ̕Ύ�����ł͂Ȃ������̂��B�i���O�A��Z��`���Z�y�[�W�j
�Ɛ��肵�Ă���B���͍����ɈÂ��āA���̐���̉ۂ�_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A�ЂƂ����^��Ɏv���_������B�u���v�ɂ��Ăł���B��ˎ闝�ɔ�r���ċg�����Ɩʒk����@��̂͂邩�ɏ��Ȃ����������A�����炭��������ɁA���������b���������������Ƃ�����B�q�g�����Ƃ̒k�b�i1�j�r����A1989�N5��4���̒k�b�����������B
�\�\�u���m�Ô��p���O���ŋ��\���������̂��A�߂�������������B�����ă��A���ȂB�X�̎�l�͓S���ƌ��������ǁA��ɋ������t���Ă���������\���낤�B���\�́A�Γc�p��Y�s�����Y�̕�t�œǂ����B���V�����Ɠ������X�ŁA�����r�Y�����ʂ̂��B�v
�ʒk�̂Ƃ��A���\�ƌ����Ă����ɂ͔���Ȃ������B�m��Ȃ��Ƃ͂����茾�����̂��悩�����̂�������Ȃ��B�g������͑f�l����ɂ��܂₩�Ȑ��������Ă��ꂽ�B���ꂪ��f��˕��Ɠ������̂��w���̂��Ƃ���A�u���\�m����n�v�ł����āA�u���m����n�v�ł͂Ȃ��B�g�������ɋ��\�͓o�ꂷ�邪�i�q�C�g�r�J�E19�j�A���͓o�ꂵ�Ȃ����Ƃ��T�ɂȂ邾�낤�B����ŋg���́A�����Ƃ��������Ô��p�Ƃ������ق�����������ɂ��āA���z���c���Ă���B
�u��v�Ƃ��������F�̕\���̐}�^������A�킪�Ƃɓ͂����B����́A���É듩�����A���̒��l�v�c�F�̏߈��̋����i���A�܁X�ɓW�����A���̈⓿���Â�ł̍s���ł���炵���B����͑�l��ڂ̍Â̐}�^�ł���B�݉��̏N�W�i�́A�V���A�������̕������p�A�G�����b��A����A���H�i�A�@�B���Ԕh�̍�i�A�ÕM�A�n�ւ���A��a�Õ��o�y�i�܂ŁA�c��Ȃ��̂��������B�i���Ȃ݂ɁA��N�̉āA����G�Y�w�݉��E�v�c�F�x�����s���ꂽ�B���]�v�������̂Ȃ̂ŁA��C�ɓǂ݊��������B�j�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�l�l�y�[�W�j
���z�q�J�@�c��u�L�}�v�r�i���o�́s�ڂ̊�t1982�N7�����j�̈�߂ł���B���p������͂킩��ɂ������A���̐}�^�i�Ƃ����ɂ͂��܂�ɗ��h�ŁA�}�œ\�荞�݂���͔��p���̕��i������������Ă���j�A�k���Ûܕҁl�s��\�\�v�c�݉��t�i���É듩���A1980�N10��1���j�ɓ`�J�@�c��M�́q�L�}�r���f�ڂ���Ă���B�g���́u���āA�u�L�}�v�ł��邪�A��u�A���͗�C�ɂ������v���ł������B�q���x����ɂ��ƁA�u�z�̂܂邢���_�ƐK���݂̂��������L���A�w���܂�߁A��̊�����Ђ炢�ėx��B�������ꂾ���̊G�ł��邪�A�I�g����C�i�������悢�A�厩�R�̐_�C���z��������B�v�Ƃ���B���ɂ́A�����̐F�ʂ��A���̑傫�����킩��Ȃ��B�����V�n�͈Â��A�F���̒��S�ɐ_��I�Ȕ������̂����݂��A�ċz���Ă���̂��B�����I�ȑ傫���ȂǁA�ǂ��ł��悢�B�܂��ɁA�u�厩�R�̐_�C���v�ƌ����Ă��悭�A�厩�R���̂��̂́u�����v�ɐG�ꂽ�A�ƌ����Ă��ԈႢ�ł͂Ȃ����낤�B�}�S�̔L�̊G�́A���̑O�ł͏��ł��邩������Ȃ��B�^�������̓����A���́u�L�}�v��q�݂������̂��ƁA����Ă���v�i���O�A�O�l�l�`�O�l�܃y�[�W�j�Ƒ����Ă���B�|�[���E�f�C���B�X�̃A�N������q�L�ƃ����S�r�i1977�j���������Ă������l�̖ʖږ��@������̂�����B
 �@
�@
���p�����́u�q���x����v���s��\�\�v�c�݉��t�Ɍ����Ȃ��͈̂�̂ǂ��������Ƃ��낤�B�������Ɋ����̐��Û܁q���������r�ɑ����āA�q���̏Љ�q�v�c�݉��\�\���̒����̋��n�r�����߂��Ă��āA�����ɂ͋g�������z�ɏ������T���̕��A���Ȃ킿�u�݉��̏N�W�i�́A�����ɂ����ĂقƂ�njڂ݂��邱�Ƃ̂Ȃ�������a�Õ��o�y�̍l�Êw�I��i���͂��߁A�V���A�������̘ŋ����p�A�G�����b��A�������̂̒���A���G�A���H�i�A�@�B���Ԕh�̏���i�A�ÕM�A�T�іn�ցA����ɂ͒�������y�Q�m�炭�낤�n�̔��@�i�A�v����A�Ñ�I���G���g�̈╨�ɂ����ł���v�i�����A�k���y�[�W�l�j�͂�����̂́A����ɑ������镶�͂͂��납�A�J�@�c����q�L�}�r���o�Ă��Ȃ��B�g���͉q���́q�L�}�r�̉�����ǂ��œǂ̂��낤���B��ł���B���āA���́q�L�}�r�ɐG�ꂽ�ߔN�̕��͂ɁA�|�c���u�q�J�@�c��\�\�����V�q�̑f��r������B
�@����ɂ��Ă��A���̔L�͂����҂ł͂Ȃ��B��ʂ���Ђ��Ɠ`����Ă��鋰�낵���܂ł̑��݊��E�G���C�L�\�\�`�J�@�c��M�Ƃ����邱�̔L�́A�u�c��̔L�v�ł����낤���u�L�̍c��v�Ȃ̂��B����ȋC������B
�@����҂̗��ꂩ�炱�̊G����������̂́A�����̑v�������Ƃ̎t�\�̈�Ƃ��Ă�����{��Ƃ̏���~�쎁�B
�@�u�������悭����ƁA��{��{�̖т����ɒO�O�Ɍ����ɕ`���Ă���B��ςȕ`�ʗ́B��������悤�ȋ���ȈЌ��������A�G�̂܂��ɂ́A����҂ɗL�������킳�ʐ_���ȋ�C���Y���Ă���v
�@�k�c�c�l
�@ ���̔L�́A�吳���N�̓����݉Ƃ̔��藧�Ėژ^�ɁA���ˉƑ��i�u�l���L�m���₱���˂��n�v�Ƃ��čڂ��Ă���B���̌�A�ߑ���{�̑�\�I����҂ő�R���N�^�[�̉v�c�݉��̔鑠����Ƃ���ƂȂ����i�݉��̌Ô��p���W���߂���D�G��̖����̌��M�A���]�́A��ɂƂ肠�����J�@�c��M�u�����}�v���������A���ꂪ��̎����������j�B�i���{�o�ϐV���Еҁs���̋��l�����\�\�V�ˁA���̉ؗ�Ȃ��Y�t�A���{�o�ϐV���ЁA2000�N4��21���A��㔪�y�[�W�j
�q�L�}�r�i�v����@���{���F�@22.8�~27.2cm�@�l���j���J���[�}�łœ����Ɏ��߂��Ă���B���W�ɑ��āA���̂��ٗl�ɑ傫���āi�ǂ����Ă��A�̖т��ӂ����炵�Ă��邽�߂Ƃ͎v���Ȃ��j�A�Ȃ�Ƃ��s�C���ȍc��L�ł���B�g���͐�Ɉ��p�����q�J�@�c��u�L�}�v�r�̑O�̏��ł��������Ă���B�u���鎞�A��Ƃ̒����ĔV�ƁA�G�̘b�Ȃǂ����Ă�����A�u�߂���A����ȂɏՌ����������G�͂Ȃ������v�ƌ������B���̊G�Ƃ́A�`�J�@�c��M�́u�L�}�v�ł���Ƃ̂��Ƃ������B�É�̐��E�̂��Ƃ��A���͂Ƃ��ɒm���Ă���킯�ł͂Ȃ��B������A�J�@�Ƃ����u�����}�v�Ǝv���Ă�������A�u�L�}�v�����̐��ɑ��݂���ƕ����āA�S������������̂��B��Ƃ͋߂������ɁA�u�L�}�v�̌f�ڂ��ꂽ�}�^��T���o���đ���Ɩ��Ă��ꂽ�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�O�l�l�y�[�W�j����������A���ꂪ�O�f�́s��t�Ȃ̂��낤�B���{�ɓ`������B��̋J�@�^�M�Ƃ����q�����}�r�Ɋr�ׂĒm���Ă��Ȃ��q�L�}�r�����A�g���Ȃ炸�Ƃ����́u�L�̍c��v��q�݂����Ȃ�ł͂Ȃ����B
�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������̍��k��q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r �i�s�Z�́t 1975�N2�����j�́q����̉̐l�Ƃ��̎��Ӂr�Ƃ����߂ŁA��������́u��狋�́w�Ñ㊴���W�x���悩��������ǂ��A����Ȃ��̂ł����Ȃ��v�ƑO�o�u�v�� �u����Z�̂̃g�b�v�v�ƌĂ�Ő�^���Ă���B������ċg�����́u�ǂ݂����ˁB�ނ̉̏W�Ƃ����͎̂�ɓ���Ȃ��̂ˁB�k�c�c�l�̐l�O�o�u�v��m��Ȃ��� ���ˁA�ڂ������́A����ł��܂��܂��������̏W�����܂���ɓ���Ȃ��ĂˁB���Гǂ݂����ˁv�Ɖ����Ă���B���̂��ƁA�ѓ��k�ꂪ�����L�́q�J�G�r�\��� �̎^����ƁA�g���͐V�l�̒Z�̂ɂ͐G�ꂸ�ɁA������o���B
�g���@ �{�A��́w�R���ȁx�ł������A�� ��ǂނƁA����ς�푈���w�̈�̋ɒv���Ǝv����B�푈���w�A���낢�날��ł���B��������������A�L�^����������A�o������邩�ȁc�c���J��f������ ���A�����Ǝv�����ǂˁB��͂�{����̂���͌��삾�ˁB������ׂ��̏W���Ǝv����B���Гǂ�ŗ~�����ł��ˁB�i�����A���܃y�[�W�j
���ڂ��ׂ������ł���B�����E�ѓ�������̐l�ɂ��Ďv�����܂܌���Ă���̂ɑ��āA�g���͋{�A��i1912-86�j�́s�R���ȁt ���u�푈���w �̈�̋ɒv���v�Ə̗g���Ă��邩�炾�B�s����Z�̑S�W10�k���a21�N�`24�N�l�t�i�}�����[�A1980�N6��25���j�ɂ́s�R���ȁt���S�ю��^����� ����B�����M���ɂ�邻�̏����������u�w�R�����m�� ������ ���n�x�@��O�̏W�B���a��l�N�Z����Z���A�Ìa�Д��s�B�艿��Z�Z�~�B�̍فE�a�U�������A�J�o�[�L�B�u���v�i�G�s�O�����j�꒚�A�ڎ��Z�ŁA�{���ꔪ�Z�ŁA �u��L�v�ܕŁA�u����L�v���ŁA����\�L�B�܍�������ŎO��g�B�̐��O���l��v�i�����A�l�����y�[�W�j�ł���B���k��̂�����1975�N�����A���쌪�E �剪�����E�����͑��Y�E�J�����E�]���~�ҁs�푈���w�S�W�k�ʊ��l�t�i�����V���ЁA1972�j�ɂ́q�R���� ���r�����^����Ă��邪�A�s�R���ȁt�̊��{�͏����ȊO�A�܂��Ȃ������悤���B�g�����ǂ̂������炭�������낤�B����Ȃ�A�g�����b����]�����͓̂��� �ł��Ȃ�ł��Ȃ��āA�O�o�u�v�̉̏W����ɓ���ɂ����\�\��ɓ���ɂ��������Гǂ݂����\�\���Гǂ�łق�����ɓ���ɂ����̏W�Ɂs�R���ȁt������\�\�� �����悤�ɘA�z�̎�����{�ʂ��Ă����Ƃ�������B�Ȃ��A������F�́s�{�A��W1�t�i��g���X�A1989�j�́q��L�r�ɂ́A1949�N4��15����500�� ����o�ŁA���y�ł����N6��20���ɓ��Ђ��犧�s���ꂽ�A�Ƃ���B�g�������ɖ߂�A�푈���w�ɊY������̏W�͂Ȃɂ��s�R���ȁt�Ɍ���Ȃ��B�����́u���� �ǂ�ŗ~�����v�ɗ͓_��u�����I���ƍl����ׂ����i�g���͂��̍��k��ȊO�ŋ{�A��ɐG��Ă��Ȃ��j�B�s����Z�̑S�W�t�Łs�R���ȁt��ǂ�ł݂悤�i�����A ���r�͊��������j�B
���ɖ{���t�W���߂Ă��ʑ���͂Â��Ĕw�X��T��
�܂ǂ�߂��ǂɔM�����藈�Ėʉe�����悳���
�t���̎邨�Ƃ�ւ�����藓�ɗ��̍����،���
���ق����͌�������Ȃ��Ђ��Ԃ�ɐ�Ў��ɂ����l�̗F
����ǂ�̂������������ւɈ��Q�Ė��̂ڂ�ׂ������̎R
�ΉƏ���������쉺����ّ�����ֈ߂ɂ��ċR���������
�Ə��ɒ��̐�墂��W�点�ĖC�˂̔n�̌��̑��t
�ÒJ�ɍ��Ă��䂫���n�v�ւΒ����ʂ��Ɋ�荇�Ђ��n
�قƂ�ǂɖʕς��킪�����r�n����ĕ��ꂵ�@���z��
�X�J�Ɉ�邠�肫���R���̂����������ĉ_�܂��铹
�����݂͉i�v�ɂ�����ޗ[����̈ǂɍg�����͖�����
���ɗ[�ɔ��H�搶�ÂтO�N�͉߂��ʊ����嗤��
�����ɉ��Ђĉ߂�����т�����ė������Ȃ��ɗr�̌Q
�Â��Ȃ�߂��݉m���ʐΒ�ɗ�₫�܌��̌��˂���
�����̋�߂����[�Ă��̊������ɕ��͐��݂�
�ڂ̉����@�E�݂ɗт��舽�鎞�͉J�~�舽�鎞�͖v�z�˂�
���̗t���݂݂ɏƂ�ΉJ�߂���醔n�ƒ뒹�ƈꏊ�ɗV��
��Ăɐi������e�J�����㑱�q���n�d�ʐM����
�z�Ӊ��o�����n���l����Ȃ�䂫�������ĂȂ�
����r�ꂵ���̖��c�ɍg�̉_�Ђ���[�x�����邵
���̗[�ׂ����낪������F�����̎x�ߒn���}��ǂɓ\���
����肼��d�̑������ނ���������炬�̌�������
������Ȃ������̋��U��Ђ�������̂��ǂ�ɐς�
�[�ׂ��݂ǂ�Ȃ���̂��낤�����������̂���
����ꂵ���肫�ƌ��͂˂ǂ������Ђɓ���Ηܗ����
����锼�ɖڊo�߂�����~�������̕����͎R���̋o���ɂ��炸
��X�Ɏx�ߋ������Ȃ��N���ڒn�}�ɂ��ǂ�č����q�˂䂭
���ɋN�����������Ɩ�̂��̂ɐg����ލ����Ƃ��łɂ��łɈق�
�O�f�s�푈���w�S�W�k�ʊ��l�t�́A������Y�ȁA�Z�́E�o��̂ق��A���L��R�́A����i�c�͐��A�s�̂炭��t�j�Ȃǂ����^���Ă���B�ȉ� �ɔo��̖ڎ� ���f����B�قƂ�ǂ����^�̂Ȃ��ɂ����āA�s�����푈�t�i�u�V���w���{�x�o�嗓���v�ƒ��L����Ă��邩��A���ꎩ�́A���o�ł���j�ƁA�g�����G�ꂽ���J ��f����W�s�C�ԁt�i�O�ȓ��A1939�j�̂ӂ������́u���v�ƂȂ��Ă��Ȃ��B
���J��f���i1907-46�j�́s�C�ԁt�ɂ͎��̂悤�ȋ傪������B�s���� ����o���n�k��3���l���a13�N�`���a15�N�t�i�p�쏑�X�A1981�j�ł́A���l���q�ɂ�铯��W�́q���r��X���Y�́q��i����r���f���̋�������Ă� �邪�A�����Ă���ɂ͖ڂ��҂�A�n�d���������g�����Ƃ̊֘A�őI�B
�킪�n�����Âނƕ���͖�@��
�����͔n��艺��Ă��邭�Ȃ�
�싞����ɂ��Ē��̑��̂��������
�n�䂩����͂����Ă��������Ȃ�
�ނ������n�̂ɂقЂ̉ݎԂł䂭
�n�d��̊��C�e�̔�������
�������������̒��ɉ������镺
�R�����|���y���R�����̉����ƏZ��
�Ă��Ԃƌ��ɂЂ���ƕ����Ɍ���
�\�\�킽������\��ŁA���F�֏o�����āA�E��̕����������A�قڌ܃��N�ɘj���Ă��������B���̂Ȃ��ł킸���ɁA���L����Ǝ������ �m�[�g���c���� ���̂����A�Z�̂�o�����������B�L���ɂ̂���̂́A���̂������ł���B�u���̑��̂�Â��Ɍ����ē~�ؗ��v�B�i�q�����d�M�E�U�炵�����r�A�s�u�� ���v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����y�[�W�j
�g�����͉�������ɂ��đ���������Ă��Ȃ��B�c���ꂽ�f�ГI�ȏ،��́A���z�q�Ǐ����r�ɂ�����u���̂ق��A���́u�S�v�A���V��� �Z�сA�Ƃ�� ���u�M�̒��v�A�ו��́u�����ߍ��v�A����Y�́u�t�Տ��v�A�N���́u�ፑ�v�A����́u�@�B�v�ȂǓ��ɍD���ȏ����ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k���� �Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ܘZ�y�[�W�j��������A�s���܂�͂����L�t�ɂ�����u�k���a�\�l�N�i���O��j�l�Z����\�Z���^�w�@�B�x�ēǁv��u������\ �l���^���Q�̂��ƁA�w���ցx��ǂށB�ؗ�ȕ��͂ɐ����v�i�����A����R�c�A1990�A�O�y�[�W�E�Z�Z�y�[�W�j��������A�q�f�ЁE���L���r�ɂ�����u�k�� �a��\��N�l�O����\�l���@�k�c�c�l��������s�Q���t��݂������v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��Z�Z�y�[�W�j��������A�q�� �L�@���l�Z�N�r�ɂ�����u�l���O���@�k�c�c�l��A��������s�@�B�t��ǂށv�i�s�邵����t6���A1990�N5��31���A�O�O�y�[�W�j�������肷��悤 �ɁA�����̏�����ǂƂ����L�ڂɂƂǂ܂�B�����A�����̏������i�����炭�͂��̂��ׂĂ��j�ēǎO�ǂ��Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl����B��̂Ɂs���܂�͂� ���L�t�̐N�g�����͓����������x�O�x�ƌJ�肩�����ǂ�ł��邪�A1939�N�Ɂu�ēǁv���Ă���q�@�B�r�ȂǁA���Ԃ��Ȃ�1946�N�ɂ��ǂ�ł���B �g���̓ǂq�@�B�r������̃G�f�B�V�������s�������A��O�ł́s�Q���k���a����I�W�i1�j�l�t�i�V���ЁA1939�N5��24���j�����s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�� ���������Ă������B���ꂪ�������Ƃ���A���s��Ђƌ��ő������ēǂ��Ă������ƂɂȂ�B������ɂ��Ă��A�����ւ̔M���Ԃ�����������ɑ���B

��������s���ցk�������Ɂi��@��l�\��сj�l�t�i�����ЁA
1929�N2��3���j�Ɖ�������s�Q���k���a����I�W�i1�j�l�t
�i�V���ЁA1939�N5��24���A�����F�L�����n�j�̕\��
��������̖��͏�f�̓��L�ȍ~�A�q�Ǐ����r�ɂ����o�ꂵ�Ȃ����A�g���͐�����т��Ďx�����Ă������̂Ǝv����B�g�����E������ ���E�߉ϑ��Y�E �ѓ��k��E�g�������k���k��l�q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�́q�O���R�I�v�E��オ���O�ɂԂ������r�Ƃ� ���߂Ŕѓ��k��ɂ�������Ă��邩�炾�B
�g���@ ���˂Ȃ��Ƃ�������ǂ��A��������� �O���Ǝ��Ă����Ȃ�������B�������������������B��������͂ڂ��̍D���ȍ�ƂȂ��ǁA���ܕs���ɕ]�����Ⴂ�킯��B�����ǁA�l����l�`�� ���Ƃ��������c�c��͂艡���Ƃ����̂͑�ւ�ȍ�Ƃ��Ǝv���̂�B�ӂ����ѓ��˂Ȃ��Ƃ�����ǂ��A�����ƎO���Ƃ����͎̂��Ă����Ȃ����Ƃ����̂��A ���v���̂ˁB
�ѓ��@������A�������� �Ӗ��ŁA��������������Ă���悤�ɁA�O���������炭��������Ă����Ȃ����B��͂艡������[�ł���A���{�́B������A�O�����N���Ƃ� ���̂͂킩���ǂ��B
�g���@����ς胊�A�� �e�B�������̂ق��Ɏ����ė����ق���������ŁA�����鋕�\�I�ɂ������Ƃ����A�V�������������낤�Ƃ����ꍇ�́A�����̔ߌ��������āA�O���̔ߌ������� ��Ȃ����Ƃ����C������̂ˁB�i�s�Z�́t1975�N2�����A���Z�y�[�W�j
��������i1898-1947�j�̎O�̏����A���сs���ցt�i1923�N5�����\�j�A�Z�сq�@�B�r�i1930�N9�����\�j�A���сs�Q ���t�i1930 �N11���`12���A1932�N5���`11���A�ځj��ǂ�ł݂悤�B���L�̋L�q�����Ă���ƁA�g�����ǂł��낤���{�͑O�f�ʐ^�̓�������A�{���̈��p�� �͏o���[�Łs��������S�W�t�i1955-56�j�ɋ���A�����͐V���ɉ��߂��B
�@�u�ږ�Ă͔��G�̕Њ�̕��֔w���������B�������āA�����Â��߂̕R�����A���̘e�ɉ�����іڂ������قǂ��ƁA�ޏ��̈߂́A
�t�����ꂽ���̂₤�ȗ��ׂ̂āA�ޏ��̊��炩�Ȍ�����є�̏��爂藎�����B
�@
����̑傫���J���ꂽ��̊�ɂ́A���j�̕������߂̕��ցA�Âɓ����~���ޏ��̍��̋Ȑ����A�����������̌����������߂ɁA���F�̓��ƂȂĕ���
�����Ȃ���Ԓd�̏�ʼnH�@���߂̋��т�����ɂ��̉����猻���Ă䂭�̂��f�Ă�B�������āA���G�̓����ʈ�̊�ɂ́A�ޏ��̓��[�̍��܂肪�A����
�̓��̌��ɋY��锵�̓��̂₤�ɔ�������̂��f�Ă�B�ږ�Ă͗��̂������ςւ��V�����߂̈�[�ŁA���j�̕������w��ЂȂ��畔���̒��������B
�@�u����B���̕�������ɗ^�ւ�B��͍����ɒ�܂炤�B�v
�@�ޏ��͐Âɔ���̖T�ߊ���B�������āA�w�ɉ�炤�Ƃ���߂̓�̒[�����Ɏ����Ȃ���A�ނ̋��g�������Ĕ��𓊂����B
�@�u����B��͖�n��̈߂��D�ށB���͌�̂��߂Ɏ��̗^�ւ��߂����ׁB�v
�@����͔ږ�Ă����l�߂Ȃ���A���̈߂̒[����ɂƂ��B�x�тɐ�����߂��ނ̊�́A陂̒��Ŕޏ��̈߂̎˂錦�̌�����Ĕ��g�F�ɉh���Ă�B������
�����d�a�Y�̎��̂����G�̘r��爂ē|��鉹�������B���G�̎w�͐��ꉺ������̐�ŁA���𝪂���\�C�̎\�̂₤�ɓ����o���ƁA�ނ̐g�̂͋��тɍr�r����
�ċz�������Ȃ��玟��ɔږ�Ă̕��X���Ă����B�v�\�\�s���ցt�\��
�u���͎��͋�B�̑��D������o�ė����̂����ӂƓr���̋D�Ԃ̒��ň�l�̕w�l�Ɉ����̂����̐����̏��߂Ȃ̂��B�w�l�͂����\���܂� �ɂȂĂ�� ��l�Ɏ��Ȃ�Ƃ��Ȃ���Ύq�����Ȃ��̂ŁA�����̐e�ʂ̏��Ŏb�����ɂȂĂ��牺�h���ł��n�߂�̂��Ɖ]�ӁB����Ȃ玄���E�ł���������Ȃ��̉��h �֖��ɂȂ肽���Ə�k�̂���ʼn]�ӂƁA����ł͎����̂��ꂩ��s���e�ʂ֎����Ƃ��Ă����̎d������`�͂Ȃ����Ƃ����߂Ă��ꂽ�B�����܂��ǂ��� �邠�ĂƂĂ��Ȃ��Ƃ������A�ЂƂ͂��̕w�l�̏�i�Ȍ��t��p��M�p����C�ɂȂĂ��̂܂܂ӂ��ƕw�l�ƈꏏ�ɂ����̎d����֗��ꍞ��ŗ����̂ł���B ����ƁA�����̎d���͏��߂͌����ڂ͊y���������i���J���͂����q����D�Ă����Ɖ]�ӂ��ƂɋC�������B����ō����͏o�悤�����͏o�悤�Ǝv�Ă� �邤���ɁA�ӂƍ����h����������ɂ͂���ł͂ЂƂ����̎d���̋}����S���o������ł���ɂ��悤�Ɖ]�ӋC�ɂ��Ȃė��āA�����Ŋ댯�Ȏd���ɋ߂Â����� �ɋ������������ƂƂߏo�����B�Ƃ��낪���ƈꏏ�ɓ����Ă�邱���̐E�l�̌y���́A�������̉Ƃ̎d���̔閧�𓐂݂ɔ����ė����ǂ����̊Ԏ҂��Ǝv�Ѝ��� ���̂��B�ނ͎�l�̍N�̎��Ƃ̗Ƃ��痈�Ă��j�Ȃ̂ʼn����ɂł����R�����������ɂ��ꂾ����Ƃ����ŁA�悭���钉���ȉ��l�ɂȂ肷�܂��Ă݂邱�Ƃ� ���y�Ȃ̂��B�v�\�\�q�@�B�r
�@�u���͎莆��ǂݏI���B�����܂ʼn]�Ђ킯���]�ċ��������o���ė��Ă��ޓލ]�ɁA���̗��R�����ĕ����ĂĂ�̂ł��炤�B����
���l�����炤
�Ɠ{�炤�Ǝ̂ĂĂ����Ă��ǂ����̂��A�킴�킴��l�Ɏg�Ђ������āA�������������������������Ă旈�������ȐS������ɂ����͂炸�A����������Ƃ܂�A��
������炩���Ǝv�Ж��Ă�鎩�����v�ւA���Ƃւ�����̂���m�H�Ǝ����̓�l�ł��炤�Ǝv�͂���Ȃ��̂����B
�@�������A����ɂ��Ă��A���͂������瑡��ꂽ�ʂЂ𒆂ɁA�������Ə�����ւ̐S�̋ꂵ�݂����������Ă�鎩���̈Ӓn���Ȃ��ɋC�����āA���ꂪ��
��قǕn�������̂̐S���ƁA�j������܂܂�����Ƃ��ē����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ����B
�@�ނ͖�ɂȂ�܂ł������ĉƂ���O�֏o�Ȃ������A�ޓލ]�ɂ��Ăė�ƈꏏ�ɖ�Ђ��̂�Ԃ��莆�������Ă���A������o���Ƃ��o���܂��Ƃ������A����
���ւ��܂Ѝ���ŊO�֏o�Ă����B�������A�ނ͂܂��ޓލ]���������z���ǂ�قǂ���̂����Ă�Ȃ��̂��B���炭���Ƃ��ӎ��͂��ł��炤���A�������
���z���ӊO�ɏ������̂ł����Ȃ�A�����������˂��Ԃ����Ƃ��̓ޓލ]�̍��ނ̎d������ɂ������A����͂�����ƍ��܂Ŏv�Ă��������������ƁA�v
�͂ʊ�т��Ƃ���X�p�œ��˂Ɋ����o�����B����ǂ��A�Ԃ��Ȃ��������̗��֏o�āA�݂͊ɓY�ĉ��Ă��������ɁA�Ђ��Ђ��Ɩ������쐅�̏�ɗ����Ƃ���
������Ă�����̉�����ɂ����B����ƁA�S�͋}�ɂ�����Ɛ܂�āA�J�J�Ƃ����C�����̋��ɖ������ė��n�߂��B�ނ͉݂͊��L�ݍ��܂܁A�����ɂۂ�
��Ƃ�����{���Ă�銦�ނ��ȍY�Ɍ����Ă��ƁA�܂�ł��̊�O�̕��i�Ƃ͔��ɁA�����ٍ��̗��悫�Ō������Ƃ̂���Q���̕��i���ۂ���Ɠ��̒�
�ɕ�����ė���̂����B�ނ͂��̑O�ŁA�����x�߂̓V�q�ЂƂ肪�o�邱�Ƃ������ꂽ�Ƃ��ӑ嗝�̗��̒����̌����̏���A����g�ɂȂēn�Ă݂���
�̂��Ă̍��Ȉꍏ�̖����A���̂킪�g�ɂЂ�����ׂĂ͂��Ȃ��v�Џo������Ȃ����B�v�\�\�s�Q���t
�Ƃ��Ă������l�Ԃ����������̂Ƃ͎v���Ȃ��A�ٗl�ȋْ����ɖ��������͂ł���B�������u�꒼�Ƃ̏����Ɋw���Ƃ͂悭�m����B�g�� ���܂����M�N ����1934�N�i�\�܍j�Ɂu�u�꒼�Ƃ̍�i��ǂށv�ƋL���Ă��邵�A��\�̓��L�ɂ́s�a���t��ǂ݊��������Ə����Ă���B�����Ƃ����������ƁA������ �����ӗ~�͌��������̂̎��ۂɏ������Ƃ̂Ȃ������g����P���Ɋr�ׂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����̏����͗͋Z�Ŏu��̃��A���Y�������̌��O�ɒE�o���悤�Ƃ��� �ۂ��z���I�ȕ��́\�\�O�т̂Ȃ��ł́s���ցt�ɂ����čł��������\�\�̉c�݂ł���A�����ɑ�ނ�������̐g�ӂɍ̂�Ȃ��Ƃ������ʍ��̊��s�������B�g�� ���̏ꍇ�A���̐��z�ɂ͎u��̏����̃��A���Y���̉e�������ĂƂ��i����́q�˒�ɂār�Ƃ����u���I�U���v�ɂ����Ă����Ă͂܂�j�B�g�������̉����]���� �Ƃ߂�Ɓu�l����l�`�̂��Ƃ���������ւ�ȍ�Ɓv�ŁA�u���\�I�ɂ������Ƃ����A�V�������������낤�Ƃ����Ƃ���ɉ����̔ߌ�������v�ƂȂ낤�B�ѓ� �́A�������͐�[�ł����āA�O�������N���͂킩��Ȃ��Ƃ��������ɑ��ẮA���A���e�B�̂����[�̕��ɕ�������Ƃ��Ă���悤���i�g���̈��ǂ����� �[��i���s�ፑ�t���������Ƃ�z���o�����j�B�s���قǂȂ������������̍�i����O�̑�\�����Ȃ̂͂킩��Ƃ��āA���̍��k��Ɍ��炸�A�g���ɐ��� ��[��i�ւ̌��y���Ȃ��̂͂ǂ��������Ƃ��낤�B���������g���́q���������r��q�Иr�r��ǂ܂Ȃ������̂��낤���B�ǂ܂Ȃ������͂����Ȃ��B��[�����\ �I�ɂ������V���������͎��g�̎��̐��E�ɂ��܂�ɗאڂ��Ă��āA�Α��I�ȑ��݂Ƃ��ĂƂ炦���Ȃ������̂��낤���B����Ƃ������ɂ�����[�̃��A���e�B�� ���߂��Ă��āA���͂⋕�\�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł��Ȃ��قLj�̉����Ă���Ɗ�����ꂽ�̂��B�����ɂ����鋕�\�ƃ��A���e�B�Ƃ����ݒ�Ƃ͕ʂ́A���҂̍�i�� ���͂��o�Ȃ���Ή����������Ȃ������܂�ł���悤�Ɏv����B�Ō�ɁA�g�����G��Ă��Ȃ����������̑�\��A������̎��l�E�����~�q�i1898- 1965�j�̎U������z�N������V���o�̕��͂̈�߂��f����B
�@�u�����ꂽ�嗝�̎O�ʋ��ɕ�܂ꂽ���̒��ŁA�i�|���I���ƃ��C�U�Ƃ͖��Â�M�߂����A���S�������B���ӐF�ʂ̐�e���A����
���Ȃ��狾�ʂŏՌ������B
�@�u�É��A���C�����͂���ꂽ�̂ł������܂��B�É��A�������Ȃ���܂��B�v
�@
�������A�i�|���I���̘r�͔ޏ��̎�ɗ��܂�����B�ޏ��̔��͋��F�̉Q�������Ă��炫��ƜɂւĂ�B�i�|���I���̎c�E���̓��C�U�����~���Α��~���قǓ{
��Ƌ��ɍV�i�����B�ނ͕Ў�ɔޏ��̓������̂₤�Ɋ��������B�\�\������B�]�̓R���V�J�̕����̑��q�ł���B�]�̓t�����X�̋M����łڂ����B�]�͑S��
�E�̋M����łڂ��ł��炤�B������B�n�v�X�u���O�̏��B�]�͍��M�ƎႳ���ւ���̓��̂ɁA�����̕a�Ђ�A����Ă��ł��炤�B
�@���C�U�̓i�|���I���Ɉ��������Ă��߂����B��l�̑��Ђ́A�g���R�̍����̓��Ђ��e��ƎT���U�炵�Ȃ���A�Q��̕��߂Â��čs���B�j�����߂��
���B�y���V���̎��̖͗l�͎b���j�������̏�ŁA������˂��グ����x���ɒ����ėh��Ă�B
�@�u�É��A���C�������߂Ȃ���܂��B���̓W���Z�t�B�k���܂ւ������\���ł������܂����B�v
�@�j���̊Ԃ���痂�����{�̎肪���т�ƁA���̏�ɂ͂ݏo�Ă���𒆂ֈ������荞�B
�@�u�É��A�����͐Âɂ��x�݂Ȃ���܂��B�É��͂����ЂȂ��ꂽ�̂ł������܂��B�v
�@�y���V���̎��̖͗l�͒��܂��B�����̗����͂ЂƂ�~���̖T�Ō������̏�̎��g�̎p�����l�߂Ă�B����ƁA�ˑR�A����j���̐�����A���F�̃��C�U
���A���������Ԃ̂₤�ɓ]����o�����B��������ʼnԊJ�����B�j���͒��܂��B���C�U�͈����ꂽ�Q�߂̐������I�͂Ȍ����o���ē|��Ă�B�ޏ�
�͎b�����̏ォ��N����炤�Ƃ��Ȃ����B�~�������ꂽ�ޏ��̋����́A�g�ł��܂ܑ嗝�̏��̏�֓����o���ꂽ�B
�@�ޏ��͑Q���N�����ƁA���߂��j��܂ŔG�炵�Ȃ�������o�����B�ޏ��̒������́A�ޏ��̋�ɂȑ��Ղ��������j���̉�����J�T�ɌJ��o����ĉg����
�����B
�@�i�|���I���̕����̏d�X�����j���́A���̂܂������̂₤�ɖ����܂œ����Ȃ����B�v�\�\�q�i�|���I���Ɠc���r�l
�C���^�[�l�b�g�ŋg��������������Ƃ��ɂ́u�g�����@���v�Ƃ��u�g�����@���l�v�Ǝw�肷�邱�Ƃ������B�����܂ł��Ȃ����Ǝ��l�ɖ��W �̋g�������� ��ׂ��r�����������炾���A�Ƃ��ɂ͂킴�Ɓu�g�����v��u�g�����v�Ŏ����Ă݂邱�Ƃ�����B���ꂱ�ꂵ�Ă��邤���ɁA����A����Ȃ��̂܂ł���̂��Ɗ��S ������ꂽ�T�C�g�ɏo������B������s������ ���T���Ɩ��O�����L���O | �����A���O�A�����A�c���̕��z�ƗR���t�ŁA ���������u�g�����v�ׂĂ݂��B
�d�b���̌f�ڌ��������ƂɊY������l���i���ۂ̐l���ł͂���܂���j��T���܂��B��ʓI�ɐ��ю�̖��O���f�ڂ���� ���܂��̂ŁA�����̖��O�⍡�ǂ��̂��q�l�̒��������O�Ȃǂ͂��܂�Y�����Ȃ��Ǝv���܂��B
�Ƃ������ӏ����̂��ƂɁu�g�� ������̓��������̐l���͑S���� 106�l�v�ƕ\������āA�k�C�����牫��܂ł�47�n��̐l���Ƒ��l�����o�Ă���i�u�g�����v�ׂ���u�g�� ������̓��������̐l���͑S���� 11�l�v�Əo���j�B�C���^�[�l�b�g��̋g������g�����ɂ́A�����d�b���Ɍf�ڂ���Ă���������̏�L�ڂ���Ă���\��������킯���B�g���͑S���� ���������̑�151�ʁA�g�����͋g�����̂Ȃ��ő�6�ʂƂ̂��Ƃ��B�����s������ƁA1,031,223�l�̑��l���ɑ��ċg������6�l�ł���B100���l ������6�l�������̂����Ȃ��̂��悭�킩��Ȃ����A�l���̑�������12�ʁi4�l�j�܂ł̒n��������Ă݂�B
�@�k�C�� 8�l�d�b���Ɍf�ڂ���Ă��Ȃ��u�g��������v�̐l���Ȃnj��������Ȃ�����A���̐�������ɂ��邵���Ȃ����A���������ꐔ�ł���e�n��� �u�d�b���̌f�� �����v���Ⴄ�B����ɂ��Ă��A���̐l���͊��o�I�ɂ��݂Â炢�B�����ŁA47�s���{���e�n��̔䗦�i�u�g�� ������̓��������̐l���v÷�u�d�b���̌f�ڌ����v�܂肱���Ō����u���l���v�j���A���{�̑��l��128,057,352�l �i2010�N�̍� ���������j�ɐ�߂�u�g��������v�ɒu�������Ă݂悤�B���ʂ�1,000�l�ȏ�̏��16�n��Ɍ������B
�@������ 3,152�l�������̐l�������{�̑��l���Ɠ�����������A����3,152�l���̋g�����������ɂ���Ƃ�������ɂȂ�B��́A�l���̑��������e�n�� ��12�ʂ܂� �ɂ͂���قǒn��I�ȕ�͂Ȃ��������A������͒�������{�ɑ������ʂƂȂ����B���͂Ƃ��������͐e���t����̂��ӂ����낤����A�����{�̋g������� ��������E�����{�̋g������̂ق����u���v�i�~�m���Ɠǂނ̂��}�R�g�Ɠǂނ̂��A�����Ȃ�~�m����������Ȃ��j�Ɩ������邱�Ƃ������Ƃ͌��������ł���B ���āA�ЂƂ��܂̖��O����ł͐\����Ȃ��̂Łu���ш�Y�v���������Ă݂�ƁA�u���� ��Y����̓��������̐l���͑S���� 510�l�v�Əo���B���̂��������s��43�l�B���Ȃ݂Ɏ��͓d�b���Ɍf�ڂ��Ă��Ȃ�����A�����ɂ͊܂܂�Ȃ��B�u���O���r�m�r�i�\�[�V�����E�l�b�g���[�L�� �O�E�T�[�r�X�j�����Ȃ��B�g�������̓ǎ҂ɓ`���������Ƃ����E�F�u�T�C�g�ɔ��\���邾���ŁA�u���O��r�m�r�Ƃ͌W��肽���Ȃ��̂��B
�g�����͐��܂ꂪ1919�N�A�吳8�N�ŁA�S���Ȃ����̂�1990�N�A����2�N�ł���B���̐��U�ɂ͏��a�̎���62�N���܂�i���a���N �Ɠ�64�N�� �Ƃ���7���ԁj���܂�܂�܂܂�A���̈ꐶ�̓\�r�G�g�Љ��`���a���A�M�̒a���i1922�N�j�����́i1991�N�j�܂łƂقڏd�Ȃ�B�E�B�L�y�f�B�A�� �f�ڂ���1919�N���܂�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȑl��������B�a�����͊������āA���X�g�̈ꕔ���f����B
�@�i�E�c�E�T�����W���[�̎���c�[�`�v�A����Ƃ���Ȃ��������A�o�l�����q�����̎O�������݂Ȃ̂͐S�����B�g�����������Ȃ�A���N2012�N�̒a ����4��15����93���}�����킯���B�g�����S���Ȃ���1990�N�̕��̎҂͂ǂ����낤�B�������E�B�L�y�f�B�A�̃��X�g�̈ꕔ���f����B
�@�L�[�X�E�w�����O�i���[�^�[���H�엲�s�A�w���҂��n糋ŗY�A�W���Y�h���}�[���A�[�g�E�u���C�L�[�� �O�����g�����Ɛ��f�N��������B���̎O�l�Ƃ������������̂����Ȃ��̂���r���邷�ׂ��Ȃ����A�g���̎��W�Ɠn糂̉����i�Ƃ�킯��x�ɂ킽���ē��{ �t�B���n�[���j�[�����y�c���w�������V�x���E�X�̌����ȑS�W�j�A�u���C�L�[�̃A���o���i�Ƃ�킯���g���������W���Y�E���b�Z���W���[�Y���`�̍�i�j�� �ɋ��銴�o��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������́A�����㐫�ȂǂƂ������̂ł͂Ȃ��B���̎O�l�̃p�t�H�[�}�[�Ƃ��Ă̐��U�ƍ�i�ɑz����v�����Ƃ��A�g���� �Ǝ��̂ނ��т����Ƃ炵�����ɈႢ�Ȃ��A�ƍl���邩�炾�B
�q�g�����́u�u���v�Ɣo��I�]�r�� ���p�����q���z�\�\�o��]�_�܌���܂ŁE�o�ߕ� �ƑI��]�r�i�s�o��]�_�t72���A1967�N9���j��ǂނƁA�g������������̐V�l�̔o����ǂ��I��������������B�����ȍ~�̔o��Ɋւ��ẮA�� �o�l�ւ̎U���I�Ȍ��y�݂͂�����̂́A�ߑ�o��I�̂悤�Ȍ`�ł܂Ƃ܂������͂͑��݂��Ȃ��B���������ɁA�ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�E�g�����̘A�ڍ��k ��q����o������r�i�s�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l���� I�`XII�t�A�������[�A1980�N5��1���`1981�N4��20���j������A�g���̖����ȍ~�̔o��ς����l����Ă���B�@�c�����̎肪�������Ǝv���� �s�����d�M�S�W�k��3���l�t�i�������[�A1985�N8��8���j�����̍��k��q����o������r�ɋ����Ĉ��p����f���A��ւ̋g���̃R�����g������ꍇ�A �\�\�̌�Ɉ������i�q�K�́u��H�q�v�́A���o�A�ڂ́u���H�q�v�ɖ߂����j�B�Ȃ��A�{�e�����Ɉ��p��̍Z�ق��f�����B
�@�����q�K
�E�{���̏\�l�ܖ{������ʂׂ�
�@�\�\���́k�����l�O�\�O�N�Ƃ����ƁA���̋�ł��ˁB�k���p��l���̎����ŁA�o�����߂Ă����Ƃ��������Ȃ��Ȃ��Ă����ˁB�o��͂Ȃ��Ȃ��Ă������� ���ˁB
�E���肱���̗��t��S���m�Ƃ���Ă�n
�@�\�\�����ł�����Ǝq�K�̏����̔o����A���ꂪ�I��ł�������B�����I���Ǝv�����ǁB�k���p��l
�E���͂ꂳ����Ղ�爂铔�撎
�E������Ԃɉ_�������Y�ԁm���݂Ȃւ��n
�@�\�\����Ȃ̂͂܂��ɐV�����������Ǝv���B�k���p��l
�E�~�͂���m�����n�ɂԂ牺��ϔ�����
�@�\�\����Ȃ͕̂����B�ڂ�����O�͔m�Ԃ��킩��Ȃ��ĕ�����ӓ|����������悭�킩��̂ˁB���܁A���͎�ϓI�ȍ앗�̔m�Ԃ̕��������Ƃ����Ǝv���� ��B
�E�̂�L��v�ӂ��܁T�ɗ��Ђ킽��
�@�\�\��������낢�傪����B����͑剪�ɂ�����ƕ����������ǁB�k���p��l�Ȃ�āA����͂�����ƍŌオ�������낢�ȁB�u���Ђ킽��v �ƁB
�E���蔫�ɔ�����儁m�����݁n����
�@�\�\����A�ƂĂ������Ǝv���ˁB
�E�����܂��␙����̉����
�E���͂��x�z��鎞�H�̕�
�@�\�\���ԂƋ�Ԃ������ɑ������Ă���݂����ōD���ȋ傾��B
�E���̂�����ɂ��͂�߂�����
�@�\�\���̂���ȂV�����Ǝv���̂�B�k���p��l����͉̂ɂ�������Ƃ��������Ȋ����Ȃ��ǁA�ƂĂ������傾�Ǝv���̂ˁB
�E���僁m�Ƃ�ځn�}�g�ɉ_���Ȃ��肯��
�@�\�\����͂܂��ɕ����ł���ˁB
�E�}�ɑ�̐Â�����
�@�\�\���ꂩ�������D���Ȃ̂́A�ڂ����g���������܂�ŁA�q���̂���ւ�������イ�s���Ă������ǁA����͐��r��ŁA�k���p��l���� �Ȃ̗���̖�̏�i���o�Ă���B
�E���H�q�ɋ��N�̖������ʂ���
�@�\�\������������낭�Ĕ����Ă�����ł��B���U�ɐ�傮�炢������̂��ȁB�����������m��Ȃ����ǁA�ڂ����ǂȂ��ł������ɂ����傪���邵�A���� �����q��Ɍ�˂��Ƃ��ɂȂ����Ă����Ǝv����ł���ˁB�@�͓��Ɍ��
�E�t���⓹�W���\�l�N�Ȃ�
�@�\�\���͕Ɍ�˂͍��x�ǂ̂ˁB�����ǎ��R����Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ��̂ˁB���R���Ȃ�A���Ƃ�R���Ȃ̂ق��������Ƃ����ȁB�������剪������ ���u�Ԃ��ցv�̋�A���̑O��̂Ƃ���ɂ��Ƃ����傪��������ňꉞ�����Ă݂܂��ƁA�k���p��l�Ȃ�Ă����̂�����ˁB
�E�l�ܖ{�̖_�Y�c�鎬������
�@�\�\���ꂩ��D���ȋ�́k���p��l
�E�t�������c�̏�̍��Ȃ��_
�E�͍��m���͂قˁn�̉ԂɏW��ڍ�����
�@�\�\���ꂩ�玟�̈���������B�k���p��l���̑O��ɂ��Ƃ����傪����B���������܂�o�l�Ƃ��āA������ڂ��݂����ȑf�l���ǂ�ŁA�������낭�Ȃ� �Ȃ��Ƃ��������������ł��ˁB�@���l���q
�E�~��墐m���̖ʁm�����n���ы��炸
�@�\�\���Ƃ����q�̋�Ȃ��ǁk���p��l�͋�����ˁB
�E�H��墂ςƂƂ�ł͖�����
�@�\�\����͔��Ɏa�V�Ȃ̂ˁB
�E�����܂��俍炫���葐�̒�
�@�\�\�Ƃ��A���͂͋��q�̋�Ɋ������B�������́u�Ԃ��ցv��ȂƓ�������Ȃ̂ɂˁB�����͗������Ƃ��đo���Ə̂���Ă����낤���ǁA������ƍ� ����������Ȃ��낤���Ƃ����̂������B
�E���R�ɓ��̓��肽��͖삩��
�@�\�\�����O�\�O�N�Ȃ��ǁA��N�L���ɂȂ����k���p��l���������̂�����̂ˁB����Ȃ̎q�K�Ƃ�����S�R�]�����Ȃ������̂��ȁB
�E�ˈ�t������Ȃ��痎���ɂ���
�@�\�\����ɂ��������āk���p��l������ˁB���܂͗L���ȋ�Ȃ��ǁB
�E���T�q�m�����˂ނ��n���m�Ȃ����n�ł̐[������
�@�\�\�Ȃ�āA�������傪������Ă���ˁB���܂̉�X�͑f�l�łȂɂ��Ɍ�˂�����Ă���킯����Ȃ��B�������q�ϓI�ɂ݂Ă����ʂ��ċ��q��������Ă� ��B
�E�R�����̉Ƃ��o���l�����֗��肯��
�@�\�\�吳��N����́k���p��l����͂�����ƈٗl�ȉr�݂Ԃ肾��B�g�ɂ����������Ƃ炦�����̉̂������ˁB
�E�C�l╂ɂ��艺�����Ă�L�ւ��ɍ݂�
�@�\�\����Ȃǂ��ł����ˁB�k���p��l����Ȃ̂����������݂��͌����ł����B��X���㎍�͐V�������Ƃ���肽���킯�ˁB�ŁA��S���Ă�����ǁB ���ꂪ�吳�Z�N�̋�B�@�ѓc���
�E���肻�߂ɓ��Ă�����̒�
�@�\�\��│̂ڂ��̍D���ȋ��I���ǁB�k���p��l
�E�ԕn��ӂ����Ƃ��������Ђɂ���
�@�\�\�k���p��l�������낢�Ǝv���ˁB
�E���̘I�A�R�e�𐳂�����
�@�\�\�L���ȋ�ɂȂ����Ⴄ���ǁk���p��l��������͑�\�삾�Ǝv�����ǁA�S�m�����ˁn�Œ���悤�Ȕo�l�ł��ˁB������ƌ����߂����Ȃ����� ���B
�E���a���Ē܂��������Ή�����
�@�\�\���}���`�b�N�ȋ�A�����ς������B�k���p��l
�E������ЂƂɂ͂��ɂ����̂ڂ��@�O�c����
�E���m����n�͂�Ă݂Â����R�͑��V�m����n�ɓ���
�@�\�\�R�������Ă䂭�悤�Ȃ������낳������܂��ˁB
�E���������̐��̐�������₩��
�@�\�\����A���������Ȃ��B����ɐ��炩�ɂȂ�ˁB�@���ΓC
�E������ɖ�e�̐����ꋏ��
�@�\�\�����ɍ����ȋ傪����܂��ˁB�k���p��l
�E������ň�R�̘I���������@����S��
�E���{�̊�Ԃ�Ď��͂ꂯ��
�@�\�\����A����ɂȂ����Ⴄ�̂��ȁB�S��́B�k���p��l����ς肢����ł��傤�B
�E�t����Ԃ�������ӌ�
�@�\�\�Ƃ����̂����邯�ǁA����܂肽���������ƂȂ��H�@�n�Ӑ��b
�E�����܂Ĕ�������俁m���݂�n����
�@�\�\����A����͂��ꂩ�B���ȋ�ł��ˁB�k���p��l�@�����H���q
�E���炭�Ɗ����̖�͂Ƃ̓܂�
�@�\�\�ڂ��ɂƂ��āA�g�Ɂw�Ԍ��x�Ɓw���炽�܁x����������悤�ɁA�H���q�͂���ς�w�����x�Ȃ̂ˁB�ڂ��Ȃ��Ƃɖ{�����܂�Łu�����v�Ƃ����� �͎q���̂��납��A���m�����y�n�Ɩ������Ă��邩��A���̕����͂܂��ɊG�̂悤�Ɍ������B�k���p��l
�E�����Ⓧ���߂����c�ׂ��@����f�\
�E�����䂭�_�����Ă͋�m����n�Ȃ肫
�@�\�\�f�\�̋�ŁA������ƎO�傮�炢�����Ă݂܂��傤�B�k���p��l
�E�����ւ̈�l���肫�Ē�ʂ�
�@�\�\�ӊO�ɁA���������̍D���Ȃ̂ˁB
�E�H�ׂĂ�鋍�̌�������̉�
�E�[����͂邩�̈�H������
�@�\�\����Ȃ́A������ƍD���ˁB
�E����䂭��Ƃ����܂�̉Ԑ���
�@�\�\���������̂͂��̂�������炩�ȁA�������Ƃ�������������̂ˁB������A�ڂ��͑f�\�����������m��Ȃ��������ǁA���ꂾ���ɓǂ�ł݂����Ɗ� ���͂��܂��ˁB�@���g���
�E�Ȃ����������m���傭���n�̉J�⟸�ϑ�
�@�\�\������A���̗L���ȋ�A�k���p��l����͂������ˁB���̋�͎c�閼�傾�Ǝv���B�܂��ɍ��݂���ǂ�ł��銴�������̂������������낢�킯�ˁB�@�������H
�E�R���挩��Ή��ɐႪ�~��
�@�\�\�ق��̂��������e�����Ђ���Ƃ�����Ă����Ȃ����ȁB�ڂ��͂��̍�i�͔o��Ƃ��čۗ����Ă��邯�ǁA���̈�s�Ƃ����ꍇ�A�|��������� ���A�����~�q�������B�����瑋�H�Ȃ͂ނ���k���p��l���������̂��ڂ��͐�i���Ǝv����B�@�����O�S
�E�����K�o���Ɗ����C������
�@�\�\�����O�S�̗�́k���p��l����Ȃ��F�V���F�ɂ��Ă�ςɂ��ꂽ�B����Ȃ̂��Ȃ�Ŗ��傾�Ȃ�Č������ǁA���j�I�ȉ��l�ł��ˁB�@�Γc�g��
�E��������E���������`��
�E����łĂΏ\�O�錎�ّ���
�@�\�\�Ƃ��A���܂ɂȂ�ƁA�����ނ̈ӋC���݂Ƃ������̊ӏ܂͈Ⴄ���ǂˁB
�E����̍��̔ޕ��̌�������
�@�\�\���������͉̂i���ɐ����̂тĂ�����������̂�ˁB�@�������
�E���˂Ζ앪�����Ă���Α��ւ�
�@�\�\�ϔO�傩�m��ǂ��B�k���p��l����A����ς��ڂ��̂Ȃ��ɐ����Ă�̂ˁB����͐l�Ԃ̐������̈�̎������Ǝv����B�����Ă���A�l�� �����Ă���ȁB�u��_�v��茅�Ⴂ�ɍD���ȍ�i���B
���k��̐Ȃł̔���������A��b�̗���ɂ���Ă͋g���̈Ӑ}�ǂ������I�ł������^��͎c��B�����A�����̂قƂ�ǂ��e�[�}�ɉ��� �Ď��O�ɑI�� �ꂽ��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���̍ہA�q�q�K�ɂ�����o��ƒZ�́r�̐߂ɂ�����g�������̂悤�ɁA�u�����������Ƃ͌����Ȃ��́B�ڂ��͎q�K�̒Z�͓̂ǂ� �łȂ��̂�B�o�傾���č��x�܂��߂ɓǂ����ŁA�Z�̂ŝR��I�Ȏ�ϓI�Ȃ��͉̂���������Ȃ����B�����ł��Ȃ��̂�����B����������i�������� �Ȃ����낤���Ƒz��������ǁv�i�����A�O�O��y�[�W�j�ƁA���߂ďn�ǂ����͎̂q�K�̂ق��͕Ɍ�˂Ƒf�\���炢�ŁA�Ђ���ǂݐe����A�g���̎��X�� ��₵�����낤�傪�������ꂽ���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�Ƃ�킯����3�傪�����[���B
�����܂��俍炫���葐�̒� ���l���q
�����܂Ĕ�������係��� �n�Ӑ��b
����䂭��Ƃ����܂�̉Ԑ��� ����f�\
���J�̍�������̂悤�ɎU�邳�܂́u����䂭�v�������Ă��A�����܂��č炭���Ԃɂ���قǂ܂Ŕ�������̂͂ǂ��������Ƃ��낤�B�q�� ���r�i�C�E 19�j�́u���j�Ƃ̕�n��係ŕ������v�Ɏn�܂�A�u������Ԃ̃X�~���v�i�q������G�r�E�E15�j�A�u�ނ炳���̃X�~�����炭�v�i�q�t�H�[�N�\���O�r �F�E7�j�A�u���_�̐��F�̃X�~���̐|�����߂āv�i�q��q�r�F�E15�j�A�u�ԍ炭�X�~���̕�n�Łv�i�q�킪�n�j�R���X�̎v���o�r�F�E16�j�Ƃ��������傪�A �O�����璆���ɂ����Ă̋g�������i�Ƃ�킯���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�j�ɓo�ꂷ��͕̂�����Ȃ����������A����ɂ��킸���Ȃ���o�ꂷ��B���p��O��̋g �������ɂ��A����Ƃ����ăq���g�ɂȂ肻���Ȃ��̂͌�������Ȃ��B�Ïk�����Ԃ̎p�ɔo��`���������\�\�ȂǂƂ������Ƃ����肻���ɂȂ��B�����͑f���� ���ǂ��āA��i�����B係̎��ɒ��ڂ������̂́A
�����܂��␙�؋���̉���� �����q�K
���R�ɓ��̓��肽��͖삩�� ���l���q
���͂�Ă݂Â����R�͑��V�ɓ��� �O�c����
������ɖ�e�̐����ꋏ�� ���ΓC
�����̉��̏��R�̒��ւ̓��ۂ͂Ȃɂ����̂��B�u����r�q�̉�������q�T�C�������m���₯�n�r�Ɋ�v�ƌ����̂���q�T�C�����g�E���邢�͍��r �i�G�E25�j�̑O����Ǎ��݂ň����B
�����̎R�̐��k��^���̂��炾�͋̂悤�ɈÂ��^�����̕��Ƃ��ꂿ�����^�Ƃ��Ɏ�����q���Ɓ^��e�͂����p �������ā^ �����Ă䂭�悤���^�₽�������̉����ց^���o��ƌ��������o�����^���̂ق��������̂��́^���C�^�����^�艱�����j�^�ȉَq�^����߂ē���I�Ȗ����� ���]����^���ʂ��ꂷ��Ɂ^�Ԏ���s�@�͂Ƃǂ܂�^��̕S���͔��Ă���^�ł̋u�ց^�̂ڂ�Ⴂ�����������Ƃ�����^��҂̔����������������^�q�Ҍ��s�\�r �Ȍ��t�����߂Ă���悤���^�k�c�c�l
���́u���k����v�ɂ��āu�ł̋u�ւ̂ڂ�Ⴂ���v�����A�����̍����ɂ��Ď��i�o��ƌ����Ă��������j�̒a���̕ʖ��ł͂Ȃ��������B�� ���͌��ɂ܂� �ꂽ�Y���ł���A�Ȃɂ��̂ɂ��Ҍ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����t�̂��Ԃ��Ȃł���B�g���͂��������A�����̔鋫��o��ɋ��߂Ă����̂�������Ȃ��B���邢�́A ���̔鋫�ɒʂ��鏬���ȗ̔����B
�g������1951�i���a26�j�N4���A�}�����[�ɓ��Ђ������A���Ђ̌o�܂��L�������͂͂Ȃ��B����A5�N�O��1946�N1��15���i�Ηj�j�̓��L��
�@���A�����P�s�}���e�̎�L�t�������ǂށB�����l�\���o�B�ߌ�A�k�Ζ���̍������[�́l�����k�m�́l���Əo�ŋ���֍s���B��R������̐�y�̕S�����o���Ƃ�����B��������̐N�w�Z�̐搶����߁A�}�����[�ɓ��Ђ����Ƃ̂��ƁB�[���Ƃ����̂ɂ����̐��̒J�͈Â��A�j�R���C���̏�ɂ���߂��~�̐��͗�߂����B�i�q���L�@���l�Z�N�r�A�s�邵����t5���A1990�N1��31���A�O�O�y�[�W�j
�Ƃ���A�g���̏��������͂ɒ}�����[���o�ꂵ���ŏ����Ǝv����B�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r��1951�N�̂�����ɂ́u���m�������ߎl���A�ҏW���ɋ߂�S�����o�̌��Y���Œ}�����[�ɓ��ЁB�В��Óc��A�ږ�P��g���A���؏��O�A�������v�B�V���́w���w���S�W�x��S���B�T��}���ژ^��w��t�S�W�x�̓��e���{����葕���A���{�܂Ŏ肪�������Řa�c�F�b�Ɛe�����Ȃ�v�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A����O�y�[�W�j�Ƃ��邩��A�S������ĐV���̗v���Ƃ��Đ���ꂽ���̂��B�����ŕS���ɂ��ďq�ׂ�B�u�S�����o�v��NDL-OPAC�Ō�������ƁA�u�����^�[�m�i�S�����o��j�s�܂̖��t�i�n���ЁA1948�N6��30���j�Ɓs���t�Z�̑I�\�\�Ⴋ�l�X�̂��߂́t�i�Ð쏑�[�A1985�N5��15���j��2�����q�b�g���邪�A�̏W���i�W�͂Ȃ��B�S���́A�a�c�F�b���M�́s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j�ɓo�ꂷ��B��ыł̏����ɋ����Ă͂��邪�A�Ўj�Ƃ��ď�����Ă���̂ŁA�a�c�̕M�ɂȂ�S�������邱�Ƃɂ��悤�B
�@�k��ыł̒Z�я����l�u������[�v�̂Ȃ��ŁA�R�c�V�l�����Z�����āA�čZ�́A������ō����w�Z�̋��t�����Ă���l�������Ɍ��邱�ƂɂȂ��Ă���Ə�ыłɌ����̂��A�}�����[�̎��̂��A�Óc�̋����̎��ƂɈڂ��Ă�������ł���B���̍����w�Z�͌��ŁA�����A���쑺�̐N�w�Z�̋��t�����Ă����S�����o�̂��Ƃł���B
�@�����l�\�N����̕S�����o�́A���{���w�A���{���Z�ŁA�P��g����Óc��̓��ł������B���{���Z����A���s��w�̓N�w�Ȃɂ͂������B�S���͑��n�ȕ��˂�Z�̂̐���Ŏ����Ă����B�����̐�y���ؐԕF�A���c����ɂ���������A�S���͕��w���Ђɂ͔ᔻ�I�ŁA�̒d�ł͎��R�ȗ�����Ƃ����B
�@�S�����o�͑�w��N�̂Ƃ��A�����^���ɂ͂���A�ߕ߂��ꂽ�̂��A�����œ]���𐾂��A�A�����āA�Z�̂̐��E�ɖv�������B���������o���̂��ߋߌ����Ȃ��������߂ł���B���{���Z�Ńh�C�c�������������茫�O�Y�̐��b�ŁA����O�̓�R���ɓ������̂́A���a��N�̖��ł������B�S���́A��R���ɘZ�N�߂��߂����A�Óc�肪�}�����[���͂��߂����a�\�ܔN�ɂ́A��˔����Y��ɂ́w����Ȋw�����x�Ƃ����G���s���Ă����������X�ŕҏW�̎d�������Ă����B
�@���̌Óc�肪�o�ŎЂ��͂��߂����Ƃ��������͂��������A�S���́A�������ȂɖK�˂Ȃ������B���N�A�S���́A�X��̐����ƈӌ������킸�A���߂ċA���A�l���̐V�w�����珬��N�w�Z�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă����B
�@��ɓߌS���쑺�́A�Óc��̋������}���S�}���n���Ɨאڂ��Ă���̂ŁA����N�w�Z�́A�����������̑g�����ɂȂ��Ă����B
�@���a��\�N�̉Ă̈�����A����w�O�̕S�����o�̉��h�ցA�ˑR�A�Óc�肪�K�˂ė����B
�u�����ł͎d���ɂȂ�Ȃ��̂ł�����ň�����Ă��邪�A�Z�������Ă����l���Ȃ��B�N�ɗ��ށv
�@�Óc����ɂ��ė����̂́k��ыł̍�i�W�l�w�ė�x�̍Z�����ł������B�S���́A�������͂��߂ɒ}�����[�̍Z�������邱�ƂɂȂ����B�i�����A��Z��`��Z�l�y�[�W�j
1907�N���܂�̕S���͂��傤�Njg��������N���Łi�a�c��1906�N���܂�j�A��R���\�������X�\�}�����[�ƁA�g���ƋΖ�����������o�Ől�����A��f�̋g�����L�ł͐������X�ňꏏ���������Ƃ͓ǂ݂Ƃ�Ȃ��B�s���t�Z�̑I�t�́q���Ƃ����r��65�Ō�����ނ����Ƃ��邩��i�����A�O��Z�y�[�W�Q�Ɓj�A�}�����[��ގЂ����̂�1972�N���납�i�s�}�����[�̎O�\�N�t�́q�Ј��ꗗ�\�i�l�\�܁k1970�l�N�Z���\�������݁j�r�ɂ́u�ЗF�v�Ƃ���j�B�s�����C�J�t�̋g�������W��������ɏo�Ől�Ƃ��Ă̋g���̎v���o�������Ă����Ă����悩�����̂����A�c�O�Ȃ��炻���������͂͌�������Ȃ��B���Ȃ݂ɒ}���I���Łs�}�����[�̎O�\�N�t�i2011�N3��15���A���l�y�[�W�j�ɂ͌��ł����N���Ȏʐ^�ŁA39�i�g�����L�ɓo�ꂷ��1946�N����j�̕S���̏ё����f�ڂ���Ă���B�g���́A�}�����[�ɓ��ЊԂ��Ȃ�������q�a�c�F�b�Ǒz�r�ɂ��������B
�@���͏��a��\�Z�N�ɁA�}�����[�ɓ����āA�V���́s���w���S�W�t���A��y�̈�l�ƒS�������B�������Ԃł���A���Ԃɗ]�T�����������߁A�}���ژ^�����邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B���܂��܂��̏o�������肪�悩�����̂ŁA���̌l�S�W�s��t�S�W�t�̓��e���{������悤�Ɍ���ꂽ�B
�@���͂��̎��A�͂��߂Ęa�c�F�b�Ȃ�l�Əo������̂��B�������������������A���e���{�������Ƃ��Ă͗��h�Ȃ��̂��o�����B���ꑢ�{�܂ŁA���͎肪����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������т��������̂݁A�G�k�����肵�āA�e�����Ȃ��āA��t�����̑��ɁA�s��Ƃ����t�Ɓs�\�a�c�t�s���D�L�t�Ȃǂ̏����������Ă��邱�Ƃ�m�����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꎵ�܁`�ꎵ�Z�y�[�W�j
��̂ɏ��Ђ̑g�Ŏw��́A�\���E���ނ͕ʂɂ��āA�{�������ڎ��A�ڎ��������t�̂ق�������B�����̏��̂�T�C�Y�A������A�s�Ԃ̃A�L�ȂǁA���Ă��ׂ��v�f���}�����邩��ł���B�܂��Đ}���ژ^�̂悤�Ȕ̑����́A���̎ʐ^�̂悤�ɏc�g�Ɖ��g�̍��݂������āA��قǂ̃x�e�����łȂ���Ύ�ɕ����Ȃ��㕨���B��ʓI�ȏ��Ђ����͂邩�ɓ���B��������5�N���A�g���͂��̊ԂɊ����ɂ��g�Ŏw��̋Z�p�����S�ɏK���������̂Ƃ݂���B
 �@
�@ �@
�@
�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t�̕\���i���j�Ɠ��E���ʁk��Z�`�ꎵ�y�[�W�l�i�E�j
�}���ژ^�̎d�l�́A�ꔪ�Z�~��~�����[�g���E���Ԃ��E�\��4�y�[�W�{��32�y�[�W�i�\���͕ʎ��ŕ\���P�E�S�̂݃X�~���b����2�F�A�{���X�~1�F�̊��ň���j�B�\���̗v�f�͂��ׂāA�{���̊�{�Ŗʓ��ɔz�u����Ă���B���e���炢���āA�Ƃ�����Ό����Ȃ肪���ȂƂ�����A�\�������g�ɂ��ăJ�b�g�ƐF�ʂŕω������Ă���̂��������B�ژ^�̐}����S�ьf�ڂ���͔̂ώG�Ȃ̂ŁA�e�y�[�W����ŏ��ƍŌ�̒��Җ��i��Җ��j�s�����k���l�l�t���i�`�j�Ō���œE����B�Ȃ��y�@�z�͖ژ^�̃m���u���B���������̓}�}�A�����͐V���ɓ��ꂵ���B
�y�\���P�z�}���ژ^�^1951�N6���^�k���B�W���A���F�A���̃J�b�g�Ɗw�I�F�ʂ̑g�ݍ��킹�l�^�}�����[
�y�\���Q�z
���ҏ��H���āE�u�꒼�ƁE���{�L���E���{�\���E���J�F�g�Y�E���q���V���E�a�ғN�Y�E�J��O�O�E������q�E��������Y�E�C�엲�s�킪�t�킪�F�t�k�ߊ��l�`��㗊�L�s���V�A�̖��w�t�k�ߊ��l
�y1�z�N�w�E�v�z�E�@���k�S27�^�C�g���l
�c�ӌ��s�����N�w�̋}���t�`�c�ӌ��s�J���g�̖ړI�_�t
�y2�z
�c�ӌ��s���@�����C�̌|�p�N�w�t�`�a�ғN�Y�s�����t
�y3�z
�w�[�Q���i�����h���j�s�N�w�̌n�t�`�T�������E�}�C�������`�i���ѓo��j�s����Q�N�w�҂̐��U�t
�y4�z
�哇�N���s����敪�̐��������t�`�u���N�n���g�i���r�Y��j�s���E�j�I�l�@�t
�y5�z
���c�i���s�����ɉ�����ߑ�v�҂̍��܁t�`�A�E�O�X�`�k�X�i���K���v��j�s�\�����L�A�E�̐��t
�y6�z
�G�b�N�n���g�i�����M���j�s�_�̈Ԃ߂̏��t�`�����ӎO�s�l�������̌����t
�y7�z�]�_�k�S13�^�C�g���l
���쌪�s���蓡���t�`���؏��O�s�O�ؐ��t
�y8�z
���؏��O�s����j�ւ̎��݁t�`�ђB�v�s���j�̕���t
�y9�z���j�E�I�s�E�����k�S5�^�C�g���l
���u��i�⑺�E��j�s���t�^�l���V�L�t�`�Γc�p��Y�s�͓�����l�t
�y10�z�����w�E�������w�k�S6�^�C�g���l
��Ԍ��C�s���ߐV���t�`�������s���ꋳ��w�̍\�z�t
�y11�z
�g��K���Y�s�m�ᎄ�L�k�S4���l�t�`�y�������s���t�W�����k�S20���l�t
�y12�z���p�E���M�E�����k�S5�^�C�g���l
���������Y�s��ێ�`�̎v�z�ƌ|�p�t�`�{�{�����E�{�{�S���q�s�\��N�̎莆�t
�y13�z���w�k�S38�^�C�g���l
�����G�G���i�C�엲��j�s�Njq�t�`�V���~�b�\�[�i��˕x�Y��j�s�e���j�t
�y14�z
�������i�����v��j�s�J�������t�`�V�F�C�N�X�s�A�I�W�i����D�v��j�s���~�I�ƃW�����G�b�g�t
�y15�z
�l�����@���i����������j�s���Ɛl���t�`�W�C�h�i�C�엲�ق�������j�s�H�̒f�z�t
�y16-17�z
�C�엲�E�������Y�E��ؐM���Y�ďC�s���@�����C�S�W�k�S25���l�t
�y18�z
�s���w�u���k�S6���l�t�`�Q�I���M�E�i�͐��D����j�s��\���t
�y19�z
���т����q�s�������ӏ��t�`�Ŗ��َO�s���� ���̓��܂Łt
�y20�z
�X���O�s�Ӓn�t�`�����ցs���ˁt
�y21�z
�F��_�����s���蓡�����W�k�����Łl�t�`�s�����֑S�W�k�S3���l�t
�y22�z
�s�䕚����I�W�k�S9���l�t
�y23�z
�s����d���I�W�k�S10���l�t
�y24�z�s���w���S�W�k�S100���l�t
���퐶�q�s1 �A���v�X�̎R�̉����t�`�g�c�b�q���Y�s3 �A���N���E�g���̏����t
�y25�z
�g�c����s4 �������̎��W�t�`�ؖ��C�s9 �������̉̏W�t
�y26�z
���O���s10 ���I�̘b�t�`�F��_��s15 �\���N�Y���L�t
�y27�z
���c����s16 �̑�Ȑ��w�҂����t�`���c��`�s21 �ۂƂ̂��������t
�y28�z
�P��g���s22 �吳����I�t�`��ސL�s27 ���ꐼ�m�j �����t
�y29�z
�g�c�G�a�E���q�N�E�ʋ{��Y�s28 �������̉̋ȏW�t�`�O�D�B���s33 �������̋�W�t
�y30�z
�哇�ו��s34 �V���̘b�t�`�J��O�O�s39 ���_�I�t
�y31�z
���{��������s40 ���Ƃ͉����t�`�����M���Y�s45 �����J�[���̂����Ђ��t
�y32�z
��������s�}���R�E�|�[�����s�L�t�`�k���Җ��Ȃ��l�s�E�q�t
�y�\���R�z�䒍���ɂ���
�y�\���S�z�kCHIKUMA�̑�̃}�[�N�l
���łɉ��x�����������Ƃ����A�����Ƃ��Ď��Ђ̏o�ŕ��ɑ����҂Ƃ��ĎЈ��̖��O���N���W�b�g����邱�Ƃ͂Ȃ�����A���Ђ���1951�N����ˊ�ގЂ���1978�N�܂ł̒}�����[�̏o�ŕ��͋g���������̉\��������ƍl���Ȃ��ƁA�����Ƃ����˂Ȃ��B�����Ƃ��A��ŐG�ꂽ190�^�C�g���i�������́u�ߊ��v�ŁA�Ō�́s�E�q�k���w���S�W�l�t�̂悤�Ɋ��s����Ȃ��������̂�����j���܂ށs�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t�f�ڐ}���́A�N��m�N���m���W�[�n�I�ɂ����ċg���̑����ł͂��肦�Ȃ�����A�Ώۂ���O���Ă������낤�B���I��̊�b�ƂȂ�̂́A���Łs�}�����[�̎O�\�N�t�̊��������q���Д��s�}�����ژ^�r�i���@���a15�N6��18���^���@���a45�N6��18���j�ł����āi������ŃJ�E���g����ƁA�g���̓��ЈȑO�Ɋ��s���ꂽ���Ђ͖�250�^�C�g���j�A�}���I���ł̊��������q�N���i1940-1970�j�r�͖ԗ����Ɍ�����B1970�N�ȍ~�͑n��50���N���L�O�����s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j���i�i�ɏڂ������e���ւ邪�A�f�ڂ����s���łȂ����߁A�q������i�ژ^�r�̃f�[�^�Ɠ˂����킹�Â炢�̂���_���B�n��70���N�i2010�N������ɓ��������j�̍��q�̐}�����ژ^���Ȃ��̂́A�c�O�疜�ƌ��������납�ł���B
�k�NjL�l
�u�����^�[�m�i�S�����o��j�s�܂̖��t�i�n���ЁA1948�j�́A�s�����̎������꒲�i�s���t�W�t�ɐe����҂̑f�{����������Ă���j�Ŏ����ɂ������A�u�w���N�̖��@�̂̂Ԃ��x�̍�҂̃����w���ŁA�{�i�I�v�i�_�{�P�v�q�q�ǂ��̕��w�̐V�����\1945-1960�r�j�Ƃ����]�ɂ���悤�ɁA���ܓǂ�ł��y���߂�݂��ƂȂ��̂��B������ɂ����͕̂{���s���}���ُ����̏��łŁA���Ԃ��Ɂu�F���Y�l�^�S�����o�v�ƃy�������̌��提��������B���\���Ɂu�������ݗL��^����L��v�Ɛ}���ق̒��ӏ������\���Ă���Ƃ���A�{���ɂ͐̃{�[���y���ł��Ȃ�̉ӏ��ɏ������݂�����B���ꂪ�ǂ����Ă��ǎ҂̂��̂ł͂Ȃ��B�o�Ŏґ��̐l�Ԃ̎�ɂȂ���̂ƒf�肵�Ă����Ǝv���B����ǂ��납�A������V���ɉ��߂Ĉ����A
�E���Ă���ǂ́A�Z���搶�͌ˁk�i�����j�����l�̕����Ă����т܂����B�i��Z�y�[�W�j
�E���̓��������l�̕G�ɂ̂��A���m�ق���n����ւ܂Ђ�����قǂ̑�ꍂ��A��A�m�̂ǁn�ƕ@�k�ł��������痧�āl�Ė��Ă�܂��B�i����`���O�y�[�W�j
�E�����Ńs�`�����|�`�����͏M�Ɏl�̎ԗւ��敍���A�c�r���c�r���͐X����Z�C�̌F���Ăт����āA�k�i�����j���O�m�܂ցn�l�j�m�Âȁn���Ђ��Ă݂�Ȃ��J�����J�������܂ʼn^��ł��ꂽ��A�傫�Ȑ��I�m���₤���n����َ̉q����Â�炤�Ɩ��܂����B�i���O�y�[�W�j
������ƁA��Ҏ��g�̏������݂Ƃ��v���邪�A�啔�����߂�Ǔ_��ꎚ�̕M�Ղł̓T���v�������Ȃ��āA�����̕����Ɣ�r���Â炢�B�ȉ��ɓ����̏����Ɓk��m忄�ɗ��n�l�̒����ӏ����ʐ^�Ōf����B���ɂ͂��ꂪ�����l�Ԃ̕M�Ղ��ǂ����Ӓ�ł��Ȃ��B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�u�����^�[�m�i�S�����o��j�s�܂̖��t�i�n���ЁA1948�N6��30���A�����F���R���j�k�{���s���}���ُ����{�l�\���i���j�Ɠ����E���Ԃ��̏����i���j�Ɠ����E�{���O�Z�y�[�W�ւ̏������݁i�E�j
���̖{�̗��������Ă݂�ƁA�@1948�N�̔��s���牓���Ȃ������ɖ�ҁE�S�����o���烁�[���P�̖�҂Ƃ��Ēm����F���Y�Ɍ��悳��A�A�����Ȃ闝�R���s���Ȃ���A�S���i�ɋ߂��o�Ŏґ��̐l�ԁH�j���{���ɒ������{���A�B�����Ȃ鎖��s���Ȃ���A��肠���ߔN�ɕ{���s���}���قɓ������i�����Ȃ������ɁA�h�b�^�O���\���Ă���j�B�M�L�p���M�Ղ̌o�N�ω��̋����A�@�ƇA�͂ǂ��l���Ă����̏��Ԃł������肦�Ȃ��B�Ƃ���ƁA��x���悵���{�����߂��āi�H�j�������{�������ƂɂȂ�B����Ƃ���҂��Ï��X�Ō����������{���߂��āA�������������Ő}���قɊ������B�������A�̈���Ȃ����A�Ï��X�̃��x���̍��Ղ��Ȃ��B���ꂪ�{���ɖ�Ҏ��g�ɂ������{�Ȃ�A�{�̂ǂ����ɗR�����L����Ă��Ă��������炢�ŁA�s�܂̖��t��|������ۂ̋M�d�ȃe�L�X�g�ɂȂ邱�Ƃ͊m�������A�^���͕s�����B����}���ق̎q�ǂ���������������{�����ɂ���{�Ƃ��r�ׂĂ݂�A���������͂����肵�����Ƃ��킩�邩������Ȃ��B
�k2021�N7��31���NjL�l
�}�����[�ɂ�����g���������{�����邽�߂ɁA���̂Ƃ���߂��̌����}���ق���}���{���肾���Ă���B�����ɂ����̂́A�������Y�́s�S�[���L�[�̐��U�t�i1973�N9��25���j�A�e��8�|2�i�g584�y�[�W�̑���ł���B���҂́q���Ƃ����r�ɂ�������i�����ɂ́u��㎵�O�N���ā^���ҁv�j�B
�@����͂ǂ������̖{�́u�J�Ԃ̎���v�Ɏ��Ă���B�����A���C�́A��]�A���y�A�f�J�_���A���Ȗ����A���S�A�\�́c�c�Ƒ��l�Ȑl�ԍs�ׂ̉��s����Z�b�N�X���w�̗��s�܂ŁB�u�J�Ԃ̎���v�̏��߂ɃS�[���L�[�̖v���������₩��A���̏I��ɂ͂ӂ����т��̃J���E�o�b�N���Җ]���ꂽ�B�l�͂��܂ł��J�Ԃ��Ă͂����Ȃ��̂��B�����͂܂����̏��a�����̂悤�ɃS�[���L�[�ɂ���Čە�����鎞�������������Ȃ��B
�@�k�c�c�l
�@�I��ɁA����Ǝx����ɂ��܂�Ȃ������}�����[�̊W�ҁ\�\�S�����o���A�����T���̐ϔN�̂����ӂɊ��ӂ���ƂƂ��ɁA�w�Ⴋ�S�[���L�[�x������������Ă����b�ɂȂ����ҏW���̑吼�����Ɍ��������\���グ��B
�@�k�c�c�l�i�����A���܃y�[�W�j
�������Y�́s�Ⴋ�S�[���L�[�t�i1968�N12��20���j�͎l�Z��282�y�[�W�B�q���Ƃ����r�Ɂu�I��ɁA�����̏ǒ����猃����A����ɂ��܂��܂Ȃ��s�͂ɂ����������}�����[�̕S�����o���ɐS���炨���\�グ��B�v�i�����A��y�[�W�j�Ƃ���B�u���a�����̃S�[���L�[�v�ŕ��w�ɊJ�Ⴕ���g���ł͂��邪�i���������ɂ��s�ǂ��t��s��t�̘N�ǁj�A�s�S�[���L�[�̐��U�t�͎Г������ł���ɂ��Ă��i�����҂̃N���W�b�g�Ȃ��j�A�g���̎�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��悤���B�����T�́A�����ł̓`�F�[�z�t��i�̖|��҂Ƃ��Ē����B�S�����o�͖{���̒S���҂ł͂Ȃ��A�ҏW���̑吼���̏�i�Ƃ��ďo�Ŋ��𐄐i�����A�Ƃ����������낤���B
�g������1959�N5���A���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�ő�9��g���܁i�����̖��̂́u�g�܁v�j����܂������A���̂��ƂɊւ��ċ����قljǖقŁA���ЂƂ��Ċ��s���ꂽ�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�ł��s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i���A1987�j�ł����܂̎�܂Ɍ��y���Ă��炸�A�����s�̎U���œ�x�G��Ă��邾�����B
���ܔ��N���W�w�m���x���s�B���܋�N�܌��A�a�c�z�q�ƌ����B����g��܁B�i�q���`�r�A�s������{�����W�听 11�t�A�����n���ЁA1960�N9��10���A�O��Z�y�[�W�j�܂ɑ��Ĝ��W�Ƃ��Ă����ʂ͂��邾�낤�B�������A�Ȃɂ�����9��g���܂ɂ܂��u�����v����������C�����A���̒��قɓ����Ă��Ȃ������Ƃ͂����܂��B����S���ɐG��g�����u�g�������v�ɂ��ď������̂́A���̔ӔN�A1980�N��̂��Ƃł���B�u���a�O�\�l�N�@���܋�N�@�l�\�^���t�A�w�m���x����g���܂ɐ�����邪���ނ���B�������F�l��ɏ��߂��A�܂���i������u�g�������v�N����A����S���̐��m��m��j�v�i�q�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��O��y�[�W�j�B�����āq�S���f�́\�\�u�g�������v�ق��r��
�k���a�O�\�l�N�l�O���O�\���@�،��F�ꂩ��d�b�A���㎍�l����ɓ���ӎu���邩�ƑŐf������B����g�܂������炵���B�����Ƃ��A�l�������ĖႤ�B�ǂ����C�ɓ���ʂ̂ł��Ƃ��B�^�O���O�\����@�ɒB���v�A������s����B���㎍�l����ɓ����āA�g�܂���Ƃ̂��ƁB�F��Ɋ��ӂ��邪�|�ӂ����B�^�k�c�c�l�^�l�������@���㎍�l�������߂Ăg�܂���悤�ɂƌ����Ă���B������A�ɒB���v�ւ܂��m�点��B���̐܁A�����̎��l�p���̈���Ƃ��ās�g�������W�t���o�����ƌ���B�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�N9��1���A����`���Z�y�[�W�j�B
�@�u�g�������v�ƈ�����ꐡ�Ƃ������Ƃ��u���d�v�ŋN�����B���́w�m���x�̎��܂��߂����āA�u�������v���V���Ђ�W�҂ȂǂɁA�z��ꂽ�̂��B�����Ԍ�Ŏ��͒m�����̂����\�\����̑I�l�ψ���̐ȂɁA����S�����x��ė��āA�u�I���́w�m���x�Ɉ�[������v�ƌ������炵���B�܂��[���̒i�K�ɓ����Ă��Ȃ����Ȃ̂ŁA�ꕔ�̐l����A����́u���O�����v�ł���A�ᔽ���Ƃ������ƂɂȂ����B���ꂪ�����̔��[�ɂȂ����悤���B�����A���́u�����C�J�v���ӂɂ���A�����̎��d�Ƃ́A������悵�Ă����B���́u�����v�𑼐l���̂悤�ɊO�����璭�߂Ă����B�i�s����S�� ���鑒���k���㎍�ǖ{�l�t�A�v���ЁA1989�N3��1���A��Z�`���y�[�W�j
���e�����Ă��Ȃ��̂Œf���ł��Ȃ����A����u�\�\�u�g�������v�ق��v��t�����͕̂ҏW���ŁA�g�����^�C�g���ɏ������̂́u�S���f�́v�����������낤�B����ɂ��Ă��A�����́u�@�v�̑����͐q��ł͂Ȃ��B�g���͂ӂ���A���̂悤�ȕ��͂������ď����Ȃ��B������A�ЂƂ́A��A�����Ă���̂́A���̌��ɐG��邱�Ƃ����C�łȂ��������ł���B�܂̎�Òc�̂ł�����{���㎍�l��i�����́u���㎍�l��v�B�g�����q�f�ЁE���L���r�Łu���㎍�l����v�Ə����Ă���̂͌��j�̃E�F�u�y�[�W�s�g�������@�\�\���̌o�߂ƌ��� | ���{���㎍�l��t�Ɏ����̂���܂����ڂ��Ă���B���Ђœ������e���f�ڂ��Ă���̂����c�����Y�E�ےn��q���{���㎍�l��Z�Z�N�j�r�i���{���㎍�l��ҁs�����E����̎�2010�t�A�w�����E����̎�2010�x���s�ψ�����{���㎍�l��A2010�j�����A����ɂ��ƁA���Ƃ̔��[�͋g�����������悤�ȑ���S���̎��O�����ł͂Ȃ��A�����S���E�،��F��̑I���^���ƎƂ�ꂩ�˂Ȃ��s�ׁi�I�l�ψ���W�̃n�K�L�ɋg�����E�������a�E��̂�q�̎O���W�̖����L����Ă����j�ɂ������B����ɂ��Ă��،��ɂ��Ă����ӂ͂Ȃ��A�P�ɂg�܂ɂ́s�m���t���ӂ��킵���i�������ق����܂܂ɂ���A�s�m���t�ɂg�܂����^���邱�Ƃ����㎍�l��ɂƂ��Ĕ����t���j�Ƃł��l�����̂ł͂Ȃ����B�Ȑ܂����������̂́A�ŏI�̖��L���E�P�L���[�̌��ʂ́s�m���t���ő���7�[�A�ȉ��A�k�쑽��q���W�s���t��5�[�A�s�g�{�������W�t��1�[�������B����M�v�ҏW����́s�g�{�������W�k�����̎��l�o��3�l�t�i���惆���C�J�A1958�j�͂Ƃ������A����ɂ��k�쑽��q�̑�ꎍ�W�s���t��N���ǂނ��낤�B�����͍�������}���قɂ����{�ߑ㕶�w�قɂ���������Ă��Ȃ��̂ŁA�q���{�̌Ö{���r�Ō������ČÏ�����肵���B�Ȃ��k�쑽��q�̒�����CiNii Books�Ō��������Ƃ���Y����͂Ȃ��AWebcat Plus�ŎR�{�a�v�ҁs���㏭�N���W�k�V���{���N�������w�S�W40�l�t�i�|�v���ЁA1961�j���q�b�g�����i�{���͖����j�B

�k�쑽��q���W�s���t�i���ԎЁA1958�N12��29���j�̎d�l�́A��O�Z�~��Z�O�~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�����E�R�Œ��Ԃ��E����ݕ\�����ꑕ�B�ѕ��i�\�P�Ɏ��ꗲ�O�Y�E�c������E���c�~�A�\�S�ɑ���S���E�O�D�B���E����l�Y�j�B��F����̔��̗��Ɂu�f�b�T���@�ѕ��^���B�@�����C�v�̃N���W�b�g�B�����̂��Ƃɐ��e���O�Y�́q���r�i4�y�[�W�j�A�[���{���q�q�k��v�l�r�i3�y�[�W�j�A�ѕ��̃f�b�T���i1�y�[�W�j�B�q���\�\�����̕s���r�̔��̂��Ƃ���{�����n�܂�B�ܐC�̓d���^���^�E�o�̂˂����^�Ό��^���^�i���^�y�̒�R�^�f�R�^�C�̊�^�r�C�^��^��^�ΌY�^�����^���t�i�{���A���v34�y�[�W�j�B�ѕ��̃f�b�T���i1�y�[�W�j�B�q��r�Ƃ��Ĉ䕚����i2�y�[�W�j�A����\�O�Y�i2�y�[�W�j�A���������i1�y�[�W�j�A�c�����]�i1�y�[�W�j�A��]���Y�i3�y�[�W�j�B�q���Ƃ����r���k��~�F�i2�y�[�W�j�A����q�i1�y�[�W�j�B�q�ڎ��r�i2�y�[�W�j�A�����ɍĂсu�f�b�T���@�ѕ��^���B�@�����C�v�̃N���W�b�g�B��F����̉��t�i1�y�[�W�j�B�{�̂ƕʂɂ`�T��10�y�[�W�́s�k�쑽��q�𗝉����邽�߂Ɂi�e�E���Ɛ��E�̌��t�j�t�Ƃ������ݍ��ݍ��q���t���B�{�̂́q���r�q��r�q�f�b�T���r�q���B�r�̐l�����N���W�b�g����Ă��铯���q�\���̉����ɁA�{���̊T�v���L����Ă���̂ň����B�u�a�T�ό`��^���C�㎿���S�ҁC�t�����X���ɔ���{�C�艿355�~�i�����j��32�v�B�u�a�T�ό`��^���v�u�㎿���S�ҁv�͂����Ƃ��āA�u�ɔ���{�v���ǂ��������Ȃ��Ƃ��āA���̎�ɂ��Ă���Ï����������Ƃ���A�f���āu�t�����X���v�ł͂Ȃ��B�P�Ȃ钆�Ԃ��ł���B���ݍ��ݍ��q�s�k�쑽��q�𗝉����邽�߂Ɂi�e�E���Ɛ��E�̌��t�j�t�ɂ́A�����܁i�㔎�A����a�@���j�Ɏn�܂�N�䏟���i���l�^�u���ԁv���l�j�ɏI���51�l�̐��E�̌��t���f�ڂ���Ă���B�W��������͔̂ςɊ����Ȃ��̂ŁA�����������Ŏ��M�Җ��̂f����i�f�ڏ��B�����͌����j�B
�����܁^�c������^�l�ƕ��q�^���c�~�^�V����q�^�O�D�B���^����l�Y�^����S���^�k�����q�^���ꗲ�O�Y�^�������Y�^�씎�^���q�����^�U���L��Y�^�ѓc�S���^���{�E�^�d�w���U�^����C�F�^�����C�^�����V�g�^�����ρ^�،��F��^�O��ӂ����^��їQ�v�^�y�����d�^��������^�˒J�W�O�^���C�i��^�A���\�V���^�ѓ����^�����ʎ}�^�ēc����Y�^�F��p�r�^���я��^�˓c�`���^���c�����Y�^������Y�^�F��邁^�^�ǐm�^�{��F���^���]�����Y�^��J�`�j�^�O�D�L��Y�^�����O�F�^�L�V�S�^���R�s�ܘY�^�]���F���^���c�u�Îq�^�e�R�����^�����C�v�^�N�䏟��
���E�̌��t�̂Ȃ�����A��9��g���܂̑I�l�ψ��߂�����A����A�،��̎O�l�̌��㎍�l����ƁA�I�l�ɂ͊ւ���Ă��Ȃ������_�j�Y�����̏d���ł���k���̕]�����悤�B
���@����l�Y�i���l�j
�@�V���y�����B�G���̎��̒��ɂ���A���Ǝ��̎d����A�ł��邾�����������ɂ����̂́A�����P���ƁA�}���Z���E���C�����͏����܂������A�k�쑽��q����̎d����Ƃ��ė������̂͒N�Ȃ̂ł��傤�B
�@����q����̓I���t�F�̂悤�ɁA���̋������R�ɏo���肷��B���̗l�q���������ɁA���鎞�́A�ƂĂ��V�N�Ȓm�o��^���܂��B�i�s�k�쑽��q�𗝉����邽�߂Ɂi�e�E���Ɛ��E�̌��t�j�t�A��`��y�[�W�j
���@����S���i���l�j
�@���C���ʼn��g�Ȃ�������̖��́A���A���e�B�ɗ��ł�����Ă�邽�߂ɓ˔�łȂ��܂��Ƃ��ł���B
�@���̉\���Ƃ��ӂ��̂͌v��m��Ȃ��B�i���O�A��y�[�W�j
���@�k�����q�i���l�j
�@���̎��W�́A�����̓�̗��R����A���w�I�ƐւƂ��Ẳ��l�������������̂ł��B
�@ ���̈�́A�u���ԁv���i���Ԏ咣���Ă����l�I�E���A���Y���̗��_�����Ƀt���N�V�u���ɓ�������āA�U�����Ƃ��ẴX�^�C�����������Ă���_�ł��B���̂��Ƃ́A���̎��W�̑S��i�����ꂼ��ϐ��̂����i�ƂȂ��Ă��邱�Ƃł������ł���܂��B���ꂩ�瑼�̈�̗��R�͂��̒��̊Ȍ��Œe�͐��ɕx���I�z���͂̓Ǝ����ɂ�������̂ł����A�P���őf�p�ȕ\���̂Ȃ��ɔ����ȃt�B�N�V���������U�C�N�̂悤�ɍ\�����Ă���̂͋ɂ߂Ŗ��͂ł��B�i���O�A��y�[�W�j
���I���͂������W�@�،��F��i���l�j
�@�k�쑽��q���̂��̎��W�̖��͂̂ЂƂ́A���B�W�����̑N�����ɂ���܂��B���̃��B�W�����͓��̂Ȃ��Ƀ��������ɂ��肠�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A����߂Ď��R�ɓ������i�Ƃ��Ă��܂����Ă��܂��B�����Ă���ɒ��ڂ��ׂ����Ƃ́A���̓������i�̂Ȃ��ł́A�Ȃɂ����K�������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B���̂��߂ɁA�ǎ҂͂��̑N���ȃ��B�W���������߂��Ƃ��A�����Ɏ��l�̓��I�h���}�����肠��ƌ������Ă��܂��킯�ł��B
�@���͂��̊���̎��̂Ȃ��ɁA�A���@���M�����h�f��̃V�i���I�Ɠ����̂��̂������Ƃ������Ƃ��������܂��悤�B����̓J���A�łȂ��A���m�g�I���Ő��삳��˂Ȃ�܂���B
�@�Ȃ��Ȃ�A���̂悤�ȃ��B�W�������J���A�ōČ�������悤�Ȏ�r�����f���Ƃ́A�c�O�Ȃ���܂��ǂ��ɂ����Ȃ�����ł��B�����Ă���͌��㎍�l�̂Ȃ��Ƃ��˂Ȃ�ʓ����I�Ȏd���̂ЂƂł�����܂��B�i���O�A�l�y�[�W�j
�������́i���l�j���s���t�ѕ��S���̎��ԎЂ̕ҏW�҂̊ԈႢ�ł͂Ȃ����Ɩڂ��^���悤�ȕ����̃I���p���[�h�����A���ꂪ�s���ԁt�̎�ɎҁE�k��~�F�ւ̈��A���ƍl����Η����ł��Ȃ��ł��Ȃ��B�����������ւ̗��Ȃǁi�ǂ����猩�Ă��������j�A⸒�ɔ邷�ׂ������̂��̂ł����āA������Ƃ��Ƃ��ƍ��q�ɂ܂Ƃ߂Ăǂ����悤�Ƃ����̂��B�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j���o���������̋g�����ɂ͂܂��s�����C�J�t���ӂ̒m�F�����Ȃ������ɂ���A�Ō��̎Ў�E�ɒB���v�͈Ⴄ�B�u���E�̌��t�v���˗��ł���u�e�E�̏����v�������낤�B�s�m���t�́A���і{���̂ق��͖ڎ��Ƒn����ԁA���o�ꗗ�ƒ����ژ^�A���t�����ŁA�ѕ��������㏑�����Ȃ��i�g���ƈɒB�ȊO�Ő���Ɋւ�����̂́A���̎ʐ^���B�e�����ޗnj��ꍂ�����ЂƂ�j�B���ꂪ�����Ƃ������̂��낤�B���ʓI�Ɏ����̔��[��p�ӂ����،��F��́A�����s���w�t�̕ҏW�҂ł����������A16�N��A���{���㎍�l��ɂ��Ă̕��͂łg���܂Ƃg�����������̂悤�ɑ��������B
���a��\�Z�N�A�����̖^���̌㉇�ɂ���āA���㎍�l��Ɏ��l�܂��݂����A���̑���́u���ԁv�̎��l�A�a���F���̎��W�w�f�w�x�ƌ��肵���B���̎��l�܂́A�����ԁA�㉇�҂����炩�ɂ���Ȃ��������A���̃C�j�V�@�����Ƃ��Ăg���܂ƌĂ�邱�ƂɂȂ����B�g���܂͐V�l�܂��A���J�܂����̐��i���s���m���������A���a�O�\��N�k��їQ�v�́q���{���㎍�l��O�\�N�j�r�i��o�j�ɋ���u���a�O�\�ܔN�ꌎ�\�ܓ��v�i�ܘZ�y�[�W�j�ł���l�A������g���������_�@�Ƃ��āA�u�g���ܑI�l��v����߂��u���̏܂͐V�l�̂����ꂽ���W���L���Љ�ɐ������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v���ƂƂȂ����B�g�������Ƃ́A���a�O�\�l�N�x�̂g���܂��߂����āA���̐��i���B���ȂƂ��납��A��h�ɕ���Ę_�����s��ꂽ���̂ŁA�����̓����A�������Ȃǂ�������āA�W���[�i���Y���̘b��ƂȂ��������ł���B���̎����́A���E�����S���̎��C�A�����̖k��~�F�������̒E�ނɂ���ďI�~����ł��A���㎍�l��͐V�����A���{���㎍�l��Ɩ���ς��A�g���ܑI�l���݂��ĐV���������B���̂Ƃ��A�g���܂̌㉇�҂g���͒����Ԃ̃��F�[�����Ƃ�A�f�������킵���B�g���Ƃ́A���Ẵv�����^���A���l��̈ψ���������Y���A���A���ƉƂƂȂ�A�V���l�琬�̂��߂ɏ܋���������̂ł������B�i�s���{�̎��̗���k���{�̎��l�t�A�ق�Տo�ŁA1975�N12��1���A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j
�g���܂͑n�ݓ�������V�l�܂ł����āA���J�܂ł͂Ȃ��B�u�g���܂͐V�l�܂��A���J�܂����̐��i���s���m���������v�ɁA�،��̒ɗ�Ȕ����ǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ս�E�c�����E�O�Y�m�҂́s���{���㎍���T�t�i�����ЁA1986�j�ƈ������Y�E�剪�M�E�������ďC�A��ˏ���E��������E������q�E�V���G�E�����P�E���Y�ÁE�{��^�f���E�a�c�����҂́s���㎍�厖�T�t�i�O�ȓ��A2008�j�̖k�쑽��q�i����E���I�A���Ɠc�ȑ��I�������͓c�ȉ���q�j�̍����������ƂŁA�k���i�̏Љ�ɑウ��i���M�́A�s���{���㎍���T�t�����䏟���A�s���㎍�厖�T�t���R������j�B
�k�쑽�I�@�������� �����@���l�B�����l�܁E�܁E���`�i1912- �j�B�{���c�ȁm������n���I�B���������n�S���܂�B�k��~�F�v�l�B�w���x�i��34�@���ԎЁj�́A�ɂ߂ē���g�ӓI�Ȏ��ۂ��������ċS�C���閲���I�Ȏ��I�����̐��E��n�����Ă���B�l�I=���A���Y�����̈ꐬ�ʂ��������̂Ƃ��Ă̕]���Ă���B�ق��Ɂw���̞��m�����͂��n�x�i��53�@���j������B�u���ԁv���l�B�u���[���b�p�̌����v�i�u���ԁv��40�E���`41�E7�j�ɂ��A����k��~�F��܁B�i�s���{���㎍���T�t�j
�k�쑽�I�q��������E�����r�@�����E�܁E���`
�@���������n�S���܂�B����q�Ƃ��\�L�B�{���A�c�ȁm������n����q�B�k��~�F�v�l�B���l�i��29�j�N�A�u���ԁv���l�ƂȂ�B��ꎍ�W�w���x�i�ܔ��E���@���ԎЁj�͕a���Ō������o��Ԃ������̂ŁA���ƌ����A���Ǝ��̊Ԃ���s�������앗�́A�u�w���ԁx���i���Ԏ咣���Ă����l�I�E���A���Y���̗��_�����Ƀt���N�V�u���ɓ�������āA�U�����Ƃ��ẴX�^�C�����������Ă���v�i�t�^�����q�E�k�����q�̐��E�̎��j�Ƃ����B�u���[���b�p�̌����v�ő���k��~�F�܁A�u�������ꂳ��Ǝ��̎q�v�ق��ő�Z�܂���܁B�ق��Ɏ��W�w���̎V�m�����͂��n�x�i�����E��@���ԎЁj������B�i�s���㎍�厖�T�t�j
�k��̖v�N�����A����r�V�́q�g�������Ɩk�쑽�I�r�i�s�k�����l���R�l�t24���A2009�N10���j�́A�쑊�n�s�ݏZ�̎��l�E�ᏼ�䑾�Y�̒����ɋ���A�u�����\�O�k2001�l�N����Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̓_�ɂ��Ă͍���̒����ɘւ������v�i�����A����y�[�W�j�Ƃ��Ă���B12�ΔN���������k��̕v�E�~�F�ƁA�k����7�ΔN���������g�����́A�Ƃ���1990�N4���E5���Ƒ��O�サ�ĖS���Ȃ��Ă���B�g�����ɖk�쑽�I����іk��~�F�ɐG�ꂽ���͂͂Ȃ��B
�k2019�N12��31���NjL�l
�s���㎍�蒟�t1959�N7�����i�n����2���j�̕ʒ��ڎ��̂��Ƃ̕ʍ��������G�̓��m�N��1�������A�k�܃y�[�W�l�́q���l���f�U�C������r�͒����ǑT�B�e�̐��e���O�Y�i���ӁE�ҏW���̒Z���q�킪���@�r��t���j�A�k�Z�y�[�W�l���q���W�E���㎍�l��r�ł���B�q���W�E���㎍�l��r�̃e�[�}�͂ӂ��B�ЂƂ́u����o�����V�������v�Ƃ����A�����V���E�k���r�j�B�e�̌��㎍�l��V�������E�k��~�F�̃X�P�[�g�p�i�Z���̃^�C�g���́q�킪���N�@�r�j�B�����ЂƂ́u�܌��̎��ՃX�i�b�v�v�͍��c�V�B�e��4�_�̑g�ʐ^�ŁA�@�������A�A�����Ґ����Ɍh�ӂ�]����k��~�F���A�����ćB�ƇC�ɂ��̔N4���Ɂs�m���t�ő�9��g�܂���܂����g�������o�ꂷ��B���T�̃L���v�V�����ƂƂ��Ɍf���悤�i�Ȃ������́A�q�g�����ƕ��w�܁r�ɋL�����悤�ɁA�u5��27��18:00�`�u�܌��̎��Ձv���@�m���n�����E�ԍ�u������كz�[���v�v�ł���j�B��g���Y�Ƙb�����ދg���ׂ̗ŁA���ނ��k��~�F�̎p����ۓI���B
 �@
�@
�u�B�@��ҋg�������Ƃ��̐l������镽�ѕq�F���v�i���j�Ɓu�C�@���e��B��O����k��A�g���A��g���Y���A�v�i�E�j�k�o�T�F�s���㎍�蒟�t1959�N7�����A�k�Z�y�[�W�l�l
��9��g���܂̑I�l�ψ��͎���15���B����������㎍�l��̊����ł���B�����ρA������Y�A�ɓ��M�g�A�������A��їQ�v�A�k��~�F�A�،��F��i���������j�A����S���A�����V�g�A�y�����d�i���������j�A�����O�F�A���e���O�Y�i�������j�A�O�D�L��Y�A����l�Y�A�R�{���Y�B��їQ�v�́q���{���㎍�l��O�\�N�j�r�ɂ́u����g���܂́A�����Ɋe�V���A�G���ɒʒm����Ɠ����ɁA���O�̖ɏ]���āA�u���w�v�܌����Ɏ������ǂ���̑I�l�o�߂ƁA�e�I�l�ψ������z�����M���邱�ƂɂȂ����B�������A�\�l���k�����ς͕a�C�̂��ߌ��ȁl�̑I�l�ψ����A���z���������̂́A������Y�A�������A��їQ�v�A�k��~�F�A�����V�g�A�y�����d�A����l�Y�A�����O�F�̔����ł������B����̑I�l���@�́A���L���A�P�L���[�ł��������A�]���ʂ�I�l�ψ����ꂼ��̌����ɏ]���Č��߂���ׂ����̂ł������B�u���w�v�Ɂu�I�]���z�v�����������ƂŁA���R�Ȃ��瓊�[���W���������B�Ƃ��낪�A��ʂɂȂ����k�쑽��q�w���x�ɓ��[�������̂̒��ɁA�������������̂�����̂ł͂Ȃ����ƁA�����傪�m�F�o���Ȃ��܂܂ɁA�������݊Ԃɋ^�S�ËS���A�܂��A���d�W���[�i���Y�������m�ȍ������Ȃ��̂ɉ����L���𗬂��A��肪�Ђ낪���čs�����v�i���{���㎍�l��ҁs�����E����̎��t�A�u�k�ЁA1981�N6��20���A�ܓ�y�[�W�j�Ƃ���B�s���w�t1959�N5�����́q���㎍�l��g�ܑF�t�ψ����z�r�ŋg�����Ɍ��y�����͈̂����E��сE�k��E�����E�y���E����E������7���ŁA���e�̊��z��������Ȃ������̂͂��������������c�O���B���e�ɂ́s���t�����́q���r�ł͂Ȃ��A�s�m���t�̊��z�������I�@����r�V�͑O�f���Łu���e���O�Y�͌�⎍�W��ǂ�ł��Ȃ��Ƃ����s���ȗ��R�Łk�I�l���l�����������A��a�̑I���������̂����m��Ȃ��v�i�����A��Z��y�[�W�j�Ɛ������Ă���B����Ȃ��肩�c�t�ŏX���Ȃ��́u�g�������v�i�������V�l�܂̑I�l�ł͂Ȃ����j�́A���e���O�Y�ɂ��s�m���t�]�̔��\�Ƃ�����ڈ���̋@���D�����B��9��g����҂̋g�����̑����猩���Ƃ��A���͂��̈�_�ɐs���悤�B�����N���������㎍�l��̖^�����́A���̂��Ƃ����ł��ӂ߂ɒl����B
| �@�s�����G�߁t | �����������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j |
| �A�s�t�́t | �����������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �B�s�Õ��t | �����������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �C�s�m���t | �����V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �D�s�a���`�t | �����V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �E�s�Â��ȉƁt | �V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �F�s�_��I�Ȏ���̎��t | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �G�s�T�t�����E�݁t | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �H�s�Ẳ��t | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �I�s�|�[���E�N���[�̐H��t | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �J�s��ʁt | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
| �K�s���[���h���b�v�t | �V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j |
�m�k�P�x�����r�����Q�R���l�͏����x���r�̈ٓǂ͂��قǏd�v�łȂ��Ɣ��f�����ꍇ�A���̕\�����폜���Đ��������
���[�����o��
���т��t�H�[�N�̐��
��C�̌ς��߂��߂�
����͈�҂̂ɂ���
�k�\��������
������₽��
�ċz�ǂN����
�ʂꂽ�[�����ł܂�
���N�������`���
�悲�ꂽ�H��̒���
����
���t�ւ����ȁk�P�x�r�Q���R���l��
�Ȃ���Ă��܁k�P�Ӂ��x�r�Q�R���l
�m���͏����ƂȂ�A�Z�ق̖{���́u�����Ȃ^���āv�u���܂Ӂ^���v�Ƃ����i�Ђ炪�Ȃ̝X�����̕����^�����j�Ƌ������^�V���Ȃ̑���ɋA������B���Ȃ킿�A�q�҉́r�ɂ͌�N�̋g�����ɂ�鎍��ւ̎����͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B���������e�L�X�g�f�[�^�̃n���h�����O�ɂ́A�\�Ȃ�����e�L�X�g�t�@�C���ɂ����{�����œK���B�J�肩�������A�{���̓d�q�e�L�X�g�̊�{�̓e�L�X�g�t�@�C���ł���B���o�`�ł���ŏI�`�ł���A���т̓lj��E�����̏o���_�͒�{�̊m��ł���A�{���̍���ł���B����{�ɂ��߁E����̎��l�̖{���Z�ق͂����Ă��̏ꍇ�A�ٓ��ӏ�������E�������L�^�̋L�q�Ȃ̂ŁA�{���̓lj����r�E���͂ɂ͒ʏ�̕��͂ɖ߂��A�܂���e�L�X�g�Ɉٓǂ�Ɠ�����K�v������B��҂̑n���I�Ȏ����ɓ����������͂ł́A��L���A�A�\�L�̌n�̕ύX�ɔ��������≼���̉��ςȂǁA�m�C�Y�ƂȂ�v�f���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������{�ōŏ�����s�Ȃ��ƂȂ�ƁA�{�����������邾���ň�d���ɂȂ��Ă��܂��B������ꂽ�e�L�X�g�f�[�^����K�v�ɉ����Ė{�����쐬���邱�Ƃ́A����{����̍�ƂɊr�ׂĂ͂邩�ɊȒP�����A�ԈႢ�����Ȃ��B�������K�v�Ƃ���{���i���Ƃ��u��҂̑n���I�Ȏ����v���Ǝv����ٓǂ�Ɠ������{���j�����݂ɂ��肾�����Ƃ��ł���\�\���ꂪ��i���e�L�X�g�f�[�^�����邱�Ƃ̍ő�̗��_�ł���B����̍����������\�Ȃ��Ƃ͌����܂ł��Ȃ��i����e�L�X�g�Ƃ̔�r�E�ƍ����l����ƁA�v�����g�A�E�g���̏��̂́u�l�r�����v�Ȃǂ̌Œ�s�b�`�t�H���g���x�X�g���j�B���̂悤�ɍZ�ق̖{�����ł��Ă���A�x���������邱�Ƃ͗e�Ղł���B���Ď��́A�{�T�C�g�ŗ��z�{�ɂ�����s�m���t�{���ɂ��ĉ�����������B
�k�c�c�l
���t�ւ����ȁk�P�Q���R���l��
�Ȃ���Ă��܁k�P�Ӂ��Q�R���l
�����_�ł͎c�O�Ȃ���A�g�������W�{���Z�ق̓E�F�u�y�[�W�Ȃ�ł͂̎g������̖ʂ��l������Ă��Ȃ��B�k�P�`���l�̈ٓ����܂��j�A�Ȏ��і{���̃e�L�X�g�f�[�^�Ƃ����f�ނɂ����Ȃ��B����������́A�g�����̑S12���W���\������262�т̈���e�L�X�g��d�q�e�L�X�g�ɓ]�ʂ����ŏ��̂��̂ł���B�s�g�����S���W�t��15�N�O���łɁu�Ō�̊��ň���v�ƌ���ꂽ�i�������łɂ�鏑�Ђ́A����R�c�Ȃǂ��������̔Ō��̏o�ŕ��Ƃ��āA�����ł��V�����o����Ă���j�B���܂�w�p�ŕҏW�́A���ň���ǂ��납����e�L�X�g�ł���Ȃ��A�d�q�e�L�X�g�ɐ芷������B�d�q�e�L�X�g�̖��_�Ɨ����͖{�e�ł��̂���܂����w�E�����B���o�́s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1957�N4�����k2��4���l�O���`�l��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|22�s1�i�g�A9��84�s�B�Ȃ��A�ߕ\���̃A���r�A������[�}�����̈ʒu�́A�Q��������A�R���V�c�L�A�S���O�������肾���A�{�e�ł͓V�c�L�ɓ��ꂵ�A�����̕\�����e�Ɉٓ����Ȃ����߁A�P���܂߂čZ�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������i�ȉ����j�B
�@�v�E�l�E�T�b�J���[�̍�i�̕ҏW�ɒ����Ԍg��������ƂƁA�u���B�N�g���A�������̏����v�ւ̐V���ȊS�Ƃ��A���ɂ����̕�����v���������B����́A�s�\�Ȗ��̂悤�Ȓ�Ă̊j�ƂȂ���̂ł���A���B�N�g���A�������̃f�W�^���E�A�[�J�C�u�̍\�z��̌n�I�ɍs�����߂̂��̂��B�܂��A�����̑����̂܂܂̏��Ŗ{�̉摜����n�܂�B�����āA�f�W�^�������ꂽ�I���W�i���̃e�L�X�g���܂܂�A����ɉ����āA��_�ȕҏW�҂ɂ���ĕ҂܂ꂽ�V�����e�L�X�g�ƁA�o�ł��̑��̗��j�I�Ȓ��߂��^������B���͑z������B�ŏ��̃z�[���y�[�W���A���s��~�����n�����Ƃ��������ɂւ̔��Ɠ����������ʂ����A���p�҂͂�����ʂ��āA���@�[�`�����ȏ����̂Ȃ��ւƓ����Ă����̂ł���B���˂̃G���A�́A�܂�Ŗ{���̂悤�ȏ���������ł���A�N���b�N��ŁA�N�㏇�i���̏ꍇ�A���Ƃ��Ύ��͈ꔪ�܋�N�Ɋ��s���ꂽ�������ׂĂ����邱�Ƃ��ł���j�A���Җ��A���t�@�x�b�g���A���ł̒l�i���A�`�����ȂǂŔz�������Ƃ��ł���i���Ƃ��A���V�����O�Ŕ������ꂽ�{�������A�O�Z�V�����O�Ŕ������ꂽ�O���{�����Ƌ�ʂ��邱�Ƃ��ł���j�B���͖����Ă���A���̃��@�[�`�����ȏ��˂̂Ȃ��ɁA�p���b�V���A�e�C���[�A�E���t�A���b�c�h���t�A�T�h���[�A�}�N���[���Ƃ������R���N�V�����ɏW�߂�ꂽ��������̂ƂȂ�A����ǂ��납�{�h���[�A����A�u���e�B�b�V���E���C�u�����[�̏�������̂ƂȂ邱�Ƃ��B�����āA�L�[�{�[�h�𑀍삷�邾���ŁA���̏��˂���D���Ȗ{�����o���ēǂ߂�̂��B����Ƀe�L�X�g�ׁA���s�m�p�������n�e�L�X�g��ˌ��m�ׂ�����n���A���j�E�e�L�X�m�ɂ��Ă̒���ǂ݁A����ȉӏ����璷���[�h�܂��̓o�b�N�O���E���h���[�h�ɉA�n�C�p�[�����N���\�\�D���ȂƂ���ł����̂����\�\�f��║��ł̋r�F�A�|��A���̑��֘A���鏑�]��R�����g�Ɍ����ē\�邱�Ƃ��ł���B�i�q��6�́@�d�q�e�L�X�g�̂��߂��߂����������r�A�����A��Z�܁`��Z�Z�y�[�W�j���͂��́u�s�\�Ȗ��̂悤�ȁv�f�W�^���A�[�J�C�u���A�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�Ɍf�ڂ��镶�͂��܂Ƃ߂�ۂ̏��i���q�����A�C���^�[�l�b�g�����Ƃ��j�����̓��e�����łȂ��A�擾����߂Ƃ������s�ׂ܂Ŋ܂�ŕ�I�ɍ\�z�������́A�Ƃ����ӂ��ɗ��������B
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�g�����̎��̏W�i���������{�̕\�L�́u���W�v�j�s�����G�߁t��1940�N10��10���A����ɂ��Ȃ킿�g���̎���s���ɂ��Ď���ŏo�ł��ꂽ�B�g���ŏ��̒����ł���A20�т̎���i���琬��q�����G�߁r��1�т̘a�̍�i�q蜾蠃�k�X�K���l��r�i�Z��44��ѐ�����2��j�̓\���ŁA���ׂĂ��������낵�ł���B�Ȃ��A�����ɖڎ��͂Ȃ��B�a�̍�i�̍Z�ق͂��ł��q�g�����̏W�s�����t�{���Z�فr�ōs�Ȃ����̂ŁA�{�Z�قł�20�т̎���i��ΏۂƂ��A�O ���M���e�`�A�P ���̏W�s�����G�߁t�f�ڌ`�A�Q �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����Q�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A���̏W�s�����G�߁t�e���т̏��o�`�{�������̌�ǂ��ω����������ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�́A�P�����Q�܂ł̈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ͊����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A�s�{�ӂȂ��烆�j�R�[�h�ɂ��u蠟�v�̑���ɃV�t�gJIS�́u�X�v���g�p���Ă���_�����ȉ��������������B�ŏ��Ɂs�����G�߁t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O ���M���e�F2011�N11�����_�Ŗ����B�����͋����A���Ȃ͋������i�X�����͕����j�ŏ����ꂽ���̂ƍl������B�P���Q�ł́q���������r�i�@�E10�j��3�s�߂������̕\�������A�P�̋����̓E�F�u��Ő��m�ɍČ��ł��Ȃ��̂Ōf�ڂ������킹�A�V���ŕ\�������i���������āu���k�P�[���Q���l���A���́k�P䱁��Q�s�l�̓����Łv�ȂǂƂ��Ȃ��j�B�P�����Q�܂ł̕ύX�ӏ����T�ς���Ɓ\�\�Q�͋g�����̟f�㊧�s������A��������V���ւ̕ύX�͐��z�i��o�̉��Q�Ɓj�ɋg�������p�����Ƃ��̕\�L�ɕ�������\�\�A���M�⊧�s�����̐V���E�G���̕\�L��ɉ��������̂Ƃ����悤�B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�@�@��̐��q��������F�̏Ɏq�t�œd�����̂�
�@�@�@���ڂ���
��20���Ő܂�Ԃ��Ă��邩��A���e��20���l�ŏ�����Ă�����������Ȃ��B
�P ���̏W�s�����G�߁t�i����Ɂk�����s�{����X����m�\�O�@���쌓���s�ҋg�����l�A1940�N10��10���j�F�{�������������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|20���l�i�s���͍ő��Łj14�s1�i�g�B������̖P�ѓ��i�����s���{���抝�꒬��m�O�j�Ɋւ��ẮA�ѓN�v�����q�����G�߁r���ڂ����B
�Q �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A10�|20���l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���P ���̏W�s�����G�߁t�B
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�k�O�t�l�y�[�W�l�A�{��9�|1�i�g�A4�s�B���т̕��q�����G�߁r�Ƙa�̂̕��q蜾蠃��r���琬��s�����G�߁t�S�̂ɂ����鏘�̒Z�́B�̂��̉̏W�s�����t�i1959�j�ɂ́A���_����肳�����`�Ŏ��߂��Ă���i�q�s�g�����S���W�t������i�r�Q�Ɓj�B���邩�Ȃ��݂Â�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�O�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A10�s�B�g���̐��z�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B���͒��̋r��݂�݂�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�l�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A7�s�B�g���̐��z�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B���ˊ�̌ߑO�㎞�\��
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�܃y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A8�s�B�g���̐��z�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�����̓����ł�1�s�߂�2�s�߁A7�s�߂�8�s�߂����ꂼ��ꕶ���������n�߂��Ă��邪�A����ꂩ��A���s���i�����̏��o��s�u�����v�Ƃ����G�t�ł́A���p���̎����Q�E�s�A�L���k����Łl�Ƃ��قȂ��Ă���j�B�@�ւ̕���ግ��ɘ��߂����̐�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�Z�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�g���̐��z�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B�����̐������墂��Ԃ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A5�s�B���[��
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�����ւ��ꂽ������������
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A4�s�B�ӎȂɍ���䂭���ق̂����
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��Z�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A5�s�B�̂��肵��{�̊������̂ɂ��݂�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�X�َq�͂Ƃ���
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�g���̐��z�q�V�������ւ̖ڊo�߁r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1975�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B�s�u�����v�Ƃ����G�t�Ɠ��k����Łl�����̓����ł́u���]�ԋ����I��v�ƂȂ��Ă��邪�A����ꂩ��A���s���i�����̏��o�ł́u�����v�j�B���]�ԋ����I�肪�Փ˂���
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��O�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�m�M�ɏt�̉Ⴊ�Ƃ܂萇����
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��l�`��܃y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A19�s�B�P�ł͖{�т������J���ɂ܂������i�ƂȂ��Ă���B�Ԃт�̂��ւɎ���ł��w�̂��Ƃ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��Z�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�^���̉e�։ԕ������ڂ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�ꎵ�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A2�s�B�킪������ɂȂ�݂͂Ă�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�ꔪ�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B�O��̐����̂ɓ������`�����̂��Ă���B�쉺��M�̓��ɂ�������ނ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A3�s�B�����̂���ɂ�����ƈ����݂킭�ߌ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��Z�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A5�s�B�|埂����Č�����Ԃ�
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A6�s�B���҂͔������|�Ɏw���Y��
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j���y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A7�s�B���̒�q��
���o�͎��W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j��O�y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A9�s�B�g���̐��z�q�킪�������W�s�t�́t�r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1978�N9�����j�ɐV���������őS�s���p����Ă���B�����̋�㢂̒���
�@�����@�k�c�c�l�ڂ��̎苖�ɂ́A�g���������ɍs���Ƃ��ɂ��������W�Ƃ����̂��ȁA���邢�͉̏W�ƌĂق��������̂��A���ꂪ�����ł���B������݂�Ƃڂ��́A����ς�܂��܂����������������ǂ��A���̂Ƃ��A�g�����������������Ȗ{���A�Ȃ��o���C�ɂȂ������Ƃ����悤�Șb���Ă݂�ƁA�����������Ƃ������킩���Ă���Ǝv����ł���B�������s�����G�߁t�����L���Ă����̂́A�x�V�ԉ��j�Ɉ��Ă���{�������̖ڂɗ��܂������R�ɂ��B�g���́A��シ�łɋM�d�������s�t铁t���������ł��낤���Ԃ̎��l�����ɂ����s�����G�߁t�������邱�Ƃ͂��납�A�掦���邱�Ƃ��A����b��ɂ��邱�Ƃ����Ȃ��������낤�B����Ƃ����̂��A�s�����G�߁t�̎��́A���W�̕ҏW��Ɉ��̋��珢�W�ŌR���̐��E�������܌����g���ɂƂ��Ă͏K��ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ���������ł���B��n�ŎƂ����s�t铁t�ƈقȂ�A����i����Ɂj�ɖ߂��Č��̐����𑱂����g���́A���W�̈�����i�s���邳�Ȃ��ł��u���₱��͈Ⴄ�B�����̏����������̂͂���ł͂Ȃ��v�Ƃ������Ȃ鐺�����͂����B��������������Č����ɓ��݂������̂́A�⏑�Ƃ��āu���W�ߏ��O�Ɏ��W��҂ߑs�ȓ����̋C���v�i�q�莆�ɂ��ւār�j�ɒ�������������ɉ߂��Ȃ��B����͐l�ԂƂ��Ă͋����Ă��A���l�Ƃ��Ă͋����Ȃ��s�ׂ������̂��낤�B���O�̋g�����s�����G�߁t����킸��6�т𐏑z�ŏЉ�������Ł\�\������q�t�r�Ɓq�ār��������������łɁq�H�r�q�~�r����I����Ƃ����A�����ɂ���Ă͓������Ȏ��M�ԓx�Ł\�\���ɍĊ����邱�Ƃ��Ȃ������w�i�ɂ́A������������������B�������A��Ҏ��g�̕]���Ƌg�������ɂ�����s�����G�߁t�̈Ӌ`�Ƃ͕ʂ��̂ł���B��������ꂩ�猩�Ă��������B�ŏ��Ɂs�����G�߁t�̎��̏����ꂽ���������A�S�я������낵�̂��ߎ��W�̖{�����琄�����邵���Ȃ��B�܂��͎��ӏ��Ƃ��āA1939�i���a14�j�N�A1940�i���a15�j�N�����̋g�������̂��肳�܂��s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j�ɒT�邱�Ƃ���n�߂����i�y�@�z���̗j���͏��т̕�L�j�B
�@�g���@�Ȃ����̂�����A����́B�w�t�́x����Ȃ��ł���B
�@�����@�������܂��ˁB��������̒Z�̂��ڂ��Ă���{�ŁA���������a�\�ܔN�̔��s�������B
�@�g���@�w�����G�߁x�Ƃ����̂���������ł����ǁA����H
�@�����@����A����B���̖{�Ɂu�莆�ɂ����āv�Ƃ����p�ݍ��݂̕��͂������āA�o�ł̂������������Ă������B
�@�g���@����ɂ���́H�@����͂����Ԃ�s�v�c���ȁB�i�j
���a�\�l�N�i���O��j1938�N�āA��R����ސE�����g���́A�ŏ��̒����܂ł̂قړ�N�Ԃ�����̂��߂̎��s�P�\���ԂƂ��āA����܂łɎ����߂Ă����Z�́E�o�傩�猻�㎍�ւƑ傫���J�[�u������B���L�̋L�q�ŋ����[���̂́A���������v�l�������̂��ƂɊׂ�̂�����邩�̂悤�Ɏ��z�ɂӂ�������A��������݂��肷��p�����A�����ŏd�v�Ȃ̂�1939�N5��31���́u���W���ɂ䂭�O�ɏo�������Ǝv���v�ł���B�g���͂��̂Ƃ��܂łɂǂ̂��炢�����������߂Ă����̂��B���N���́u���×ށA���e�̐����B�c�t�Ȏ��A�́A�o���ǂ݂������v�́A�c�t�Ȏ���j�������̂��A����Ƃ������̂��鎍���c�����̂��B�g�������������Ă���̂�m�����˕��t�i�������X�Ɠ����̏o�ŎЁj�̐ΐ��q�Ɓu�ǂ����ɔ��\���Ă���́v�u�������߂Ă��邾���v�u�܂��A�ق�Ƃ̕���̂ˁv�Ƃ������Ƃ肪������1940�N2��6���̎��_�ŁA�I�����߂�悤�ɂ��Đ��������͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B�s�g�����S���W�t�̔��ɂ́s�����G�� 1940�t�ƋL����Ă��邪�A����͋g���̐��̎��W�������ł���悤�Ȑ�����Ԃł͂Ȃ��A���s�N���ƂƂ炦��ׂ��ł͂Ȃ����i���Ɂs�����G�߁t�̊��{�ɂ́u�c�I��Z�Z�Z�N�^���܂�͂��Łv�i�����A�k�O�t��y�[�W�l�j�Ƃ��邾���ŁA�g�����g�͐�����ԂL���Ă��Ȃ��j�B��̓��L�̈��p�ɂ͓o�ꂵ�Ȃ����A�����̋g���̓Ǐ��o���œ��L���ׂ����s�����P���W�t���s���삿�����W�t�Ƃ̏o��ł���B
�@�l����\�ܓ��y�z
�@�Ƃ̓܂�B�������q�w�Z�����ɍs���B���z�ɂӂ���B�K���V���̏��Z�т�ǂށB�i�O�Z�y�[�W�j
�@�܌��O�\����y���z
�@�w�A�h���t�x�A�w�t�v����x��ǂށB��A�K���ɖv���B���W���ɂ䂭�O�ɏo�������Ǝv���B�i�l�Z�`�l���y�[�W�j
�@�\�ꌎ�Z���y���z�@
�@��������݂邪�A�s���B��������̕��ӂł͈���ł������A��`���ė~�����炵���̂��B�������������Ă��܂��B�k�c�c�l�i���܃y�[�W�j
�@�\��\����y���z�@
�@���×ށA���e�̐����B�c�t�Ȏ��A�́A�o���ǂ݂������B��A�m���@�[���X�w���ԁx�B�i��Z�O�y�[�W�j
���a�\�ܔN�i���l�Z�j
�@�ꌎ����y�z�@
�@���B���A�G�ς��H�ׂ��B����̂��l����B��x���A�Z�Ə��q���̎x�߂��Ή��֍s�����B�i��Z��y�[�W�j
�@�ꌎ��\�O���y�z�@
�@�����痚�����������B��߂Ď���ɂӂ������B�k�c�c�l�i����y�[�W�j
�@�l���y���z�@
�@�Z�v�w�̌����O���N�L�O���B����Ȃ̂������j���̍����ɂ����̂��B���ƌZ�͗t�q����ċT�̓��ɍs���A�����͐Â��ɂȂ�B��͎O�ڒʂ�܂ŁA���̍D���̊C�ۂ��ɏo��B����ɂӂ���B�ǂɌ����������c�k���́u��l�v�̔ʼn�̉��ŁB�k�c�c�l�i����y�[�W�j
�@�Z���y�z�@
�܁B�������������X�͕��Ă����B�Ö{���ňꎞ�Ԃقǎ��Ԃ��Ԃ��Ė߂�B�L���̒��֎q�ɐΐ쏗�j���ڂ��肵�Ă����B�������̐l�Ɍ��������Ė���ē���B�����킩���Ăӂ���ł��������ށB���j�͎��������Ă���̂�m�����悤���B�ǂ����ɔ��\���Ă���́B�������߂Ă��邾���B�܂��A�ق�Ƃ̕���̂˂ƁA���Ȃ��Ƃ������āA�A�����B����{�������A�ǂ����ƃQ�����͂��B�����A���ї������o���A������A�����̈��������B�O�͉��O�Ⴊ�~���Ă����B�i��O�Z�`��O��y�[�W�j
�@�O���Z���y���z�@
�@���A�����̑���{����֍s���B�O�K�̏o���Z�����ɒʂ����B�k�c�c�l�锪���߂��܂ł��������B��A���z�ɂӂ���B�k�c�c�l�i��O��y�[�W�j
| �t | �i�@�E1�j | �y4�z |
| �� |
�i�@�E2�j |
�y4�z |
| �H |
�i�@�E3�j |
�y3.5�z |
| �~ |
�i�@�E4�j |
�y4�z |
| �V�q�̉� |
�i�@�E5�j |
�y2�z |
| ���̏Ɏq |
�i�@�E6�j |
�y3.5�z |
| �Ό� |
�i�@�E7�j |
�y3.5�z |
| ����ЂƂ� |
�i�@�E8�j |
�y1�z |
| ���� |
�i�@�E9�j |
�y2�z |
| �������� |
�i�@�E10�j |
�y4�z |
| �b�� |
�i�@�E11�j |
�y4�z |
| �ʎт����b |
�i�@�E12�j |
�y2.5�z |
| ���� |
�i�@�E13�j |
�y4�z |
| �f�� |
�i�@�E14�j |
�y1�z |
| �������� |
�i�@�E15�j |
�y1�z |
| �˂̉� |
�i�@�E16�j |
�y2�z |
| �ljَq |
�i�@�E17�j |
�y4�z |
| �a�� |
�i�@�E18�j |
�y3.5�z |
| �����G�߂P |
�i�@�E19�j |
�y3.5�z |
| �����G�߂Q |
�i�@�E20�j |
�y3.5�z |
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�O ���M���e�F2011�N10�����݁A�����B�g�������M�́s�t铁t�e�{�i���W����p���e�j�̏ڍׂ͕s�������A�g���̐��z�q�R���̃A���o���r�i���o�͒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t82���A1967�N5��20���j�Ɂu�킽���̑�Ȃ��́\�\�Ƃ����e�[�}�ŏ������Ƃ��������Ă��܂������A�����l���Ă݂�Ƃނ��������̂ō������B�k�c�c�l�ʂȕ��ł́A���W�s�Õ��t�̌��e�i����͏������̂ɁA�B��̌��e�̎c���Ă�����́j�B����ɓ�\�ΑO��̓��L�B���m�[�g�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l�܃y�[�W�j�Ƃ���Ƃ��������ƁA�����炭�e�{�͏Ď����A�u��\�ΑO��́k�c�c�l���m�[�g�v�Ɂs�t铁t�֘A�̑��e����������\�����c��Ɛ��������B�s�t铁t�͑S32�сA�s�t�́t���S32�т̎���i�����߂�B�Ƃ��낪�A���҂ɂ��Ď��W�Ҏ҂̋g���́A���̎U���ɂ����Ď��т̐����˂�33�Ƃ��A��x��32�тƏ����Ă��Ȃ��B����͂��������Ȃ����B
�P ���W�s�t铁t�����i����Ɂk�����s�{����X����̈�O�g�����@���s�ҋg�����l�A1941�N12��10���j�F�{�������������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍��i�s���͍ő��Łj17�s1�i�g�B�\���q�T�@�ߑO�r�i16�сj�q�U�@�ߌ�r�i16�сj�̋敪����B
�x �s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���k�Z�ق̒�{�ɂ͏����ƌ��Ȃ�����{���g�p�����l�j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|18�s1�i�g�B�{�������Ɂq�T �t�́i1940�`1941�j�r�Ƃ��Ĉȉ���12�т��f�ڂ���Ă���B�q�҉́r�i01�j�E�q�����r�i02�j�E�q�q�́r�i03�j�E�q�����������}�r�i04�j�E�q�Y�ꂽ���J�̝R��r�i05�j�E�q���i�r�i06�j�E�q�Ԓx�����̉́r�i07�j�E�q�t�̇T�r�i08�j�E�q�t�̇U�r�i09�j�E�q�ߐ��r�i10�j�E�q����Ȑ��r�i11�j�E�q�����ʖ�\�\�����������N�̓��̉S�r�i12�j�B�����ɂ������T�E�U�̋敪�͂Ȃ��B
�r �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B�{�������Ɂq�U�b�t�́@1940�`41�r�Ƃ����x�Ɠ���12�т��f�ڂ��ꂽ�i�T�E�U�̋敪�Ȃ��j�B
�Q ���W�s�t�́t�Ċ��i���쏑�[�q�p���n���鋛No.2�r�A1971�N9��10���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�a��̝X�����͕����A�J�^�J�i�E�O����̝X�����͏����j�g�p�A�܍�17�s1�i�g�B32�т��ׂĂ��f�ځi�T�E�U�̋敪�Ȃ��j�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l19�s1�i�g�B32�т��ׂĂ��f�ځi�T�E�U�̋敪�Ȃ��j�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q���W�s�t�́t�Ċ��ł���B
�i�`�j�w�t�́x�ɂ͒��������Ȏ��юO�\�O�A���ƔŕS���B�ڂ��́A�������ォ�玝������������������Ă���ANo.�����B�i�q���W�E�m�I�g�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�B���o�F�s���w�t1959�N4�����j�ȏオ�A�g�������s�t�́t�̍�i���ɐG�ꂽ���ׂĂł���B�i�b�j�́u�@�v���́i�`�j�̈��p����������I�ɂ͎O���A�����܂Ŋm�M�������ď����Ă��邩��ɂ́A����Ȃ�̍���������ɈႢ�Ȃ��B�����〈�ł����s�t铁t�͋g���Ƒ��{�i������77�Ԗ{�ł͂Ȃ�70�Ԗ{�ŁA�����Ȃǂ̏�������͂Ȃ��j�ƁA�g�����s�Õ��t���s�̔��N�قǂ܂���1955�N1��6���ɑ��c�唪���i�s�Õ��t�̔��s�l�j�Ɍ������ԊO�{�i���L�ԁj�̓�����������A33�т߂̎��̍��Ղ͂ǂ��ɂ������ł��Ȃ������B����Ƃ������v�Ă��Ȃ��܂܁A�Ȃɂ��Ȃ��s�t铁t�́q�ڎ��r�����Ă��邤���ɁA���邱�ƂɋC�Â����B�Ō�̎��q������桁q�����������N�̓��̉S�r�r�̂��ƂɈ�s�A�L�����āA�q���Ƃ����q���ї��E�r�c�s�V�r�r�Ƃ���B���̎ʐ^�ł킩��悤�ɁA���̓�s�Ƃ��O�̍s�Ɋr�ׂ�Ƃ��Ȃ蒷���B�g���́i�`�j�����M����ہA�uNo.�����v�̖ڎ��Ŏ��т̐����J�E���g����Ƃ��ɁA�q�ߑO�̕��r16�тɑ����āq�ߌ�̕��r���q���Ƃ����q���ї��E�r�c�s�V�r�r���܂߂�17�тƌ���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B��s�A�L������̂ŁA���Ȃ�ꂵ�����ł͂��邪�A�ǂ�������ȋC������B
�i�a�j�⏑�̂���ŁA����܂łɏ��������юO�\�O���s�t�́t�ꊪ�ɕ҂B�i�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�A���A�Z���y�[�W�B���o�F�s�Z�̌����t1959�N8�����j
�i�b�j�u�k�c�c�l�s�t�́t�ɂ͒��������Ȏ��юO�\�O�A���ƔŕS���B�ڂ��́A�������ォ�玝������������������Ă���ANo.�����v�Ƃ���B�^���̃����C�J�łɁs�t�́t�����߂鎞�A�O�\�O�т���\��т�I�B�k�c�c�l�����č����܂Łu���v�̂܂ܓ��P����Ă��Ă���B�^����ǁA�p���q�n���鋛�r�ɓ����ɂ�����A�v�������ĕ������邱�Ƃɂ����B�悩�ꂠ������A���ꂪ�^�̎p�ł��邩�炾�B�i�q�o���r�A���o�F�s�t�́k�p���n���鋛No.2�l�t�A���쏑�[�A1971�N9��10���A�k�l�܃y�[�W�l�j
�i�c�j�s�t�́t�͎O�\�O�т���A�\��т�������ʂɌ��\���Ă��邪�A�s�����G�߁t�͂܂���т��A���̂悤�ȈӖ��ł͊���������Ă��Ȃ��B�k�c�c�l���́k�s�t�́t�́l������}�b�́A�����Ώ�������A����Ă����̂ŁA���肩���������͂Ȃ��B�s�t�́t����A�܂����\���Ă��Ȃ������O�тقǏЉ�āA�ӂ߂��ʂ������Ǝv���B�i�q�킪�������W�s�t�́t�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A���Z�`�����y�[�W�B���o�F�s���㎍�蒟�t1978�N9�����j
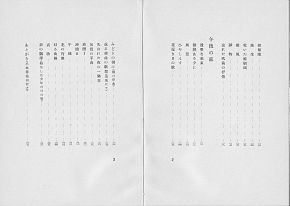
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A14�s�B�k���l�ɓ��W�i01�j�B�m�k�P�x�����r�����Q�R���l�͏���
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�l�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A6�s�B�ܐ��������
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�܃y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�w���҂̎��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�g���̐��z�q���֕������O�̎��r�i���o�F�s����̊�t1961�N11�����j�ɑS�s���p����Ă���B�@�@�@�@�@�q�����t�q�Ɂr
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A9�s�B�k���l�ɓ��W�i02�j�B����Ղ̎��̉��Ԃ���
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A9�s�B���̎M��@���k�P���́��Q�R����l��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A9�s�B�a���̓��E��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A12�s�B�t�̃p�Z���̓��k�P�����Q�R���l�܂�
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A4�s�B�Ίp���̘X�C���k�P�����Q�R���l���
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�k���l�ɓ��W�i03�j�B���Ԃ��삵�������Ă䂭
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��O�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A12�s�B�������Ł@�a�߂鏗�́@���������
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��l�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A4�s�B�g���̐��z�q�킪�������W�s�t�́t�r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1978�N9�����j�ɑS�s���p����Ă���B��ق��X�����鑁��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��܃y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A13�s�B�k���l�ɓ��W�i04�j�B�Ԃ�s�X�g����
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A6�s�B�g���̐��z�q�킪�������W�s�t�́t�r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1978�N9�����j�ɑS�s���p����Ă���B�D�F�̊��ʂ̒��Ɂk�P�����Q�R���l�鐯������
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�ꎵ�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A4�s�B�g���̐��z�q�킪�������W�s�t�́t�r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1978�N9�����j�ɑS�s���p����Ă���B�A���́k�P���Q�z���R��l�˂ނ�
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�ꔪ�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�k���l�ɓ��W�i05�j�B�r���̔n�Ԃ��ʁk�P�x�r�Q���R���l�Ă䂭
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A5�s�B�_�̑��ՂX���Ă䂭
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A9�s�B�a�Ԃ̂͂邩�Ȃ�u
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��O�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�k���l�ɓ��W�i06�j�B���̓��ɗ[�̓����Ƃ���
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��l�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�ߑO�̏��~�@�͘Z�K�ɒ�܂�
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��܃y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�k���l�ɓ��W�i07�j�B��i�k�P�x�r㢁��Q�ށ��R㢁l�̂Ȃ��Œ����܂Ƃ����Ď���
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j��Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A13�s�B�@�@�@�@�@�q���̏��ȁr
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A12�s�B�@�@�@�@�@�q��n�ɂār
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A8�s�B���o�W��u���͂ꂽ��̈�ُ́v�B�������k�P�Q���R���l�Ă䂭�����A
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j���y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�����߂�ɂЂ낪�锒���_
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�k���l�ɓ��W�i08�j�B�����̗��ɂ݂ǂ�̎ւ̉e�����
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O��y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A11�s�B�k���l�ɓ��W�i09�j�B���̎w�����ɂ����镨�̂��n����
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O��y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�k���l�ɓ��W�i10�j�B�������֑̉��v���݂����˂�
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�O�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�����m�Ɏq�w�A�c�}��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�l�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A10�s�B�k���l�ɓ��W�i11�j�B���]������邭��������䓁���_��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�܃y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A8�s�B�є�ɂ��k�P�����Q�R���l�܁k�P�Q���R���l��
���o�͎��W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�O�Z�y�[�W�A�{���܍�1�i�g�A12�s�B���o�W��́u������桁v�i�x�E�r�ł̕W��́u�����ʖ�v�j�B�k���l�ɓ��W�i12�j�B�@�@�@�@�@�q�����������N�̓��̉S�r
���̎w�����ɂ����镨铂��n�����Ȃ��g���́A�s�t铁t�ł��s�����G�߁t�ł��u�X�v�͎g�p���Ă��邪�A�u�T�v��u�U�v�͎g���Ă��Ȃ��B
����������D������~�X���j���k��
���ݐς��ꂽ���݂��u�Ԃ̉f���Ɛ�
�\���錌�t���X���Ōv�ʂ���}��
����d�t�݂͂ǂ���X�q�����t��
���К삵���_���̔畆�����ɂȂ��
����A�����ւ��ڂ�Y�ꂽ�Ɣ�
�����ؗ�ȉ����ɂ����܂��Ȃ��n��
�ւ���Ă���q������G�����ɂ߂�
��ꂽ�����Ŏx�֊��������o�Ă䂭
����醔n�������Ȃ����ꂷ�鐅�̏�
| # |
�W�� | ���l�� | �s�� | ������ | ���l |
| 1 |
�����i�A�E5�j | 12 |
9 |
108 |
|
| 2 |
���i�A�E15�j | 7 |
4 |
28 |
|
| 3 |
�Ԓx�����̉��i�A�E21�j | 16 |
10 |
158 |
�i�ŏI�s��14���j |
| 4 |
�t�̇T�i�A�E26�j | 15 |
11 |
165 |
|
| 5 |
�t�̇U�i�A�E27�j | 16 |
11 |
176 |
|
| 6 |
�ߐ��i�A�E28�j | 14 |
10 |
140 |
|
| 7 |
����Ȑ��i�A�E30�j | 16 |
10 |
160 |
|
| 8 |
�����i�A�E31�j | 8 |
8 |
64 |
|
| 9 |
���̖|���i�A�E32�j | 16 |
12 |
192 |
�@�ؗF�g�����Z�͌䏢�ɜ䂶�A���ݑ嗤�Ɋ��Ă��B���W�ߏ����Ƒ�W����{�����s�̈�����B�ɏ����ėE�����r�ɏ���B���B�͌��ҟǛ{�ɍˁA���A��������`�̎��͖{�c�̂Ƃ���[���������Ȃ��B�n�Ă��̔C�ɂ��炸�Ƃ͎v�����A�o������ؗF�̖��ɔw���̂��s�{�ӂƁA�m�n�ɕڑłāA�Q��䢂ɏ㈲����^�тƂȂ��B�q���Ƃ����r�ɓo�ꂷ�鏬��Ђ́A�{�����t����킩��悤�ɑ���{���������Ђ̒S���ҁB�g�������Z��������˔����Y�s��������̗��ꂩ��t�i�������X�A1940�N3��25���j�A�k�C�������s�k�C���̌���`���t�i���{����o�ŎЁA1940�N3��30���j�̉��t�ɂ�����̖����L����Ă���B�s���܂�͂����L�t�̓ǎ҂ɂ͐e���������F���m�̍����t�˂́A�g���w�ɓ��������Ƃɂ��Ĕo�l�B�����m�͂͐������X�̎В��ŁA�g����1939�N���ɖ����F���m��ނ��ė�40�N2���ɓ����X�ɓ��Ќ�A1941�N�Ăɏo������܂Ő����̂��Ƃŏ��Ђ̕ҏW�Ɍg������B���ї��͐����̒m�l�̉��ŁA�g���Əo����������͊J���قɋΖ��B�ҏW�҂��B�r�c�s�V���s���܂�͂����L�t�̒r�c�s�F�Ɠ���l���Ȃ�A�g���ƍ����t�˂̔o�咇�ԁB�g�����q�n����ԁr������������t�q�̏����ɏڂ����Ƃ��������ƁA��R������̓����Ǝv�����B��p�ʂ͂����炭�g���̌Z�̒��v���Ǘ����A����ʂł͓�R���E�����F���m�E�������X�A�e����̒m�Ȃ����W�����g���̎��W�s�t铁t�́A���s�̌o�܂�����ɂ��Ă����ɏ�������҂́u��e�W�v���Ȃ���ł���B�s�t铁t�̑����͖ڎ����Ɂu���Ҏ����v�Ƃ��邩��g�����ł����Ƃ��āA���т̖{���g���w�肵���̂͒N���B���̖�ɂ͂��Ƃœ����邱�Ƃɂ��āA���̍s���i�ŏ���4�s�A�ő���14�s�j�ƍs�Ԃ̊W���r���Ă݂悤�B�Ȃ�32�т̂����q�n����ԁr�͌�������A�q�����́r�́u���́v�Ƃ������o������̂��߁A���і{�������̑g�łƑ̍ق��قȂ�̂ŁA�����̑ΏۂƂ��Ȃ������B�u���т̖{���s���E���і{���̕��E�s�ԁi�{�������̔{���j�v�𑪂������l���f����B
�@�{���̓��e�̝̍����ɔz��͈�ؒ��҂̎w���ɜn�ЁA���͒��҂̎��`�y���̎w��ɌW��f�ނ�p�ЂāA�V�Ɏ��B�̍l�Ă�����ցA�䗗�̒ʂ�̂��̂ɂ�������ł���B�D�쉓���A�Z���E�����Ȃǂ҂ɍZ�{���Ă���ӎ����o�҂��A���҂̊�]�ɕ��͂Ȃ�����笕��������ł��炤�B�n�Ė{���W�ɂ���椎ҏ��������J�߂��y������A���ׂĒ��҂̎蕿�ł���A�䎶������y������A��؎��B�̓���Ȃ����߂ł���B
�@�Ȃٖ{�����s�ɏA���Ĉ���Ȃ�ʌ䏕�͂�������ЁE�����t�ˁE�����m�͂̎O���Ɍ������X��\�ギ�鎟��ł���B
�@�@���a�\�Z�N�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���с@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�c�s�V
| ���т̖{���s�� | ���і{���̕�[mm] |
�s�ԁi�{�������̔{���j |
| 4 |
37 |
��{�i2.0�j |
| 5 |
48 |
��{�i2.0�j |
| 6 |
45 |
�S�p�l���i1.25�j |
| 8 |
55 |
�S�p�i1.0�j |
| 9 |
62 |
�S�p�i1.0�j |
| 10 |
69 |
�S�p�i1.0�j |
| 11 |
68 |
�l���i0.75�j |
| 12 | 64 |
�i0.5�j |
| 13 |
70 |
�i0.5�j |
| 14 |
75 |
�i0.5�j |
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�g�����s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j��1940�i���a15�j�N2��16���i���j��2��21���i���j�Ɂs��������̗��ꂩ ��t�Ɋւ���L �q������B���Ȃ킿�u������A��˔����Y�w��������̗��ꂩ��x�̍Z���ɂ͂��ށv�Ɓu�C��������Ȃ����������X�֍s���B�w��������̗��ꂩ��x�̃Q�����I ���ǂށv�i�����A��O�l�E��O�Z�y�[�W�j�ł���B�s�g�������y�����E��i�� �����k���t�l�t�̓��Y���ڂ���ās��������̗��ꂩ��t�̐����Ƃ���B
�s��������̗��ꂩ��t �i�������X�A1940�N3��25���j�k259 -799�l�������̓��L�ɓo�ꂷ���s�k�C���̌���Ɠ` ���t�\�\ �������͖k�C�����ҁs�k�C���̌���`���t�i���{����o�ŎЁA1940�N3��30���j�ł́A�����g�����Ζ����Ă����������X�͐����ЂƂ��č��q�ɓO���Ă� �邪�A�s��������̗��ꂩ��t�͐������X�����s�����B�{���̎d�l�́A��Z���~��l���~�����[�g���i����j�E�O���Z�y�[�W�i�O�t��l �y�[�W�E�{ ���O���Z�y�[�W�E���t�꒚�k�����l�j�ŁA�����ł��Q�ł������ߔ��̗L���E���{�d�l�͕s���B�ȉ��ɁA�{���̊T�v���L���B���p���̊����͐V���ɉ��߁i�x�莚�� ��̎��_�͓��̎��_�ɉ��ρj�A���ȂÂ����͌����̃}�}�Ƃ����B
�� ��S���w�ҁE��˔����Y�k1893-1985�l�̒���B�g���́u������A��˔����Y�w��������̗��ꂩ��x�̍Z���ɂ͂��ށB�ǂ݂Ȃ��犴�������ڂ����v�� �����Ă���B��˂̂ق��A������Y�E�����E�����O�Y�E���|�③�E�_�ߎs�q�E�ː��I�X�E�v�z�������E�q���y�O�E���c�۔V���E�������O�Y�E��������Y�E�H�m �ܘY�E�q��x���Y�E���Ђ낵�E�O�؈����E�R��������E�R�c�킩�E�g�c�F���̒���W���o�Ă���w�p����W���C�u�����[�́s��˔����Y����W�k�S7���l�t�� ��6���Ƃ��Ĕ����牜�t�܂ł������Ŏ��^�A��������Ă���i�w�p�o�ʼn�A2008�N2��25���j�B�����������B
�@�킽�����́A�����Ɂw�����Z�p�Ƌ��當���x�Ȃ钘�q�ɂ����Ė�������Ȃ��͂�݂������A����͒P�Ȃ��ڂɂ��� ���A���ꂪ�@ ���Ȃ闧��̋�����Ӗ����������\���ɉ𖾂��邱�Ƃ��ł��Ȃ����B�������j�N�͓��ɂ��̖�������Ȃ�p��ɑ��A���̈Ӌ`�����₵�A��������̗���� ���ɂ��邱�Ƃ�v�����ꂽ�B�킽�����͉����̋@��ɂ��̐ӔC���ʂ������Ǝv�Ă�Ƃ���A���܂��ܐ������X�吼���m�͌N���狳��Ɋւ��钘�q�̏o�ł� ���ꂽ�̂ŁA������@��ɂ킽�����̗���𖾂��ɂ��Č������ƍl�ւ����A����ɂ��ďn�����M����̗]�T���^�ւ�ꂸ�A�{��������܂ŎG����V���ɔ��\�� ���_����㕂߂����̂ɂȂĂ��܂Ёk���ђ��F�{���ɏ��o�̋L�^�͌f�ڂ���Ă��Ȃ��l�A��������̗��_��̌n�ɂ��Ă͈ꌾ���G��邱�Ƃ��ł��Ȃ������� �͐r���\�Ȃ��B�������{������Ɂw��������̗��ꂩ��x�Ƒ肵������ɂ́A���̗��ꂾ���͖��Ăɂ��Ă����˂Ȃ�ʁB�� �q�ڎ��r�k��@�c�c�@��@�c�c�@�͌��{�ł͂��ꂼ��Ɨ�������s�����A���s�ӏ����ΐ��i�^�j�ɑւ��Ēǂ����݂ŕ\�������B�܂��m���u���͏ȗ������l
�@�킽����������܂œ��{�̋���ɂ��čl�ւ����Ƃ́A�@���ɂ������̗͂ɂ�ĉv�X���Ƃ̘�����łɂ��A���F�����̌c���i���邱�Ƃ��ł��邩 �Ƃ��ӂ��Ƃł����B���̒������݊��ɂ�����d�v����Ƃ��ĔF�߂��Ă�鐶�Y�͂̊g�[�Ƃ��J���͂̊m�ۂƂ����ӂ��Ƃ������̐����͂{���邱�ƂȂ��� �͒B����ꂸ�A�����̌c���͍����̐����͂������ɂ��邱�Ƃɂ�đ��i����A���Ƃ̘���͂���ɂ�ĉv�X�łȂ��̂ƂȂ�̂ł���B�v����ɖ�������� ���ꂩ��l�ւ��鏫���̋���́A�����̐����͂{���邽�߂ɐV���������Z�p�����A�V�������݂̊�b�ƂȂ鋳�當���̔��W�ɂ�č����̐��������V ���邱�Ƃł���B�i�{���A��`�O�y�[�W�j
���́@���玡���̖{�`�� ���t�k���̎ʐ^�Q�Ɓl
�� �@���w�̍��V�^��@�����Ƌ����^�O�@������v�ւ̔F�����́@�V�����̋��琭��
�� �@�������ƍ������^��@�V��������Ɠ��������́^�O�@��������̎O������O�́@���{����̍Č�
�� �@�����V�l���̑n���^��@���{�̋��當���^�O�@������v�̍��{���^�l�@����̊w�Z���^�܁@���痧�n�̖��^�Z�@����v�V�̖ڕW�^���@��������Ƌ���� �w�^����l�́@��������̐���
�� �@���琭��ƎЉ��^��@�E�Ɠ����ƌv�拳��^�O�@�E�Ƌ���ƐE�Ǝw���^�l�@�l�I�����̗��p�����^�܁@�`������Ə��̖����́@�����ی싳��̕K�v
�� �@�n�������̋�����^��@���_���㎙�̋���^�O�@�����s�҂̖h�~�^�l�@�s�Ǐ��N�̋�����Z�́@������b����̌���
�� �@�����w�Z�Ăɂ��ā^��@��������Ɨc������^�O�@�ە�ɕK�v�Ȃ�f�{�^�l�@���ȉ����̖��^�܁@���ȏ����̌����^�Z�@�t�͋���̉��v�掵�́@�N��O����̊m��
�� �@����I�N��̖��^��@��O����̑̌n�^�O�@�N����̑g�D���^�l�@�Y�Ɛ���ƐN����^�܁@���N�̕ی엧�@�^�Z�@�����w�Z�̉��v�^���@���w�����p�~ �̖���攪�́@��w����̖��
�� �@���ƂƑ�w�^��@��w����̉��v�^�O�@�Y���ꂽ���w�̎g���^�l�@��w�ƐN�����^�܁@��w���Ƃ��Ă̋��{�^�Z�@�w���͂��鋳��^���@�V��������Ƒ�w �̍đg�D
���a�\�ܔN�O����\�����
���a�\�ܔN�O����\�ܓ����s
�@��������̗��ꂩ��
�@�@�@�@�@�艿�@����~���E�K
�@�@�@��
����ҁ@��˔����Y
���s�ҁ@�����m��
�@�@�@�����s�_�c�揬�쒬��m����_�c�r��
����ҁ@�����
�@�@�@�����s������s�J���꒬��m���
�@�@�@��
���s���@�������X
�@�@�@�����s�_�c�揬�쒬��m����_�c�r��
�@�@�@�@�@�d�b�_�c�i25�j�l�܌܁E�l�ܘZ
�@�@�@�@�@�U�֒�������������Z�l���Z�l
����{���������Ј�� �k�����͉E���獶�ւ̉��g�l

�{���q���r�ɓo�ꂷ�闯�����j�i1898-1977�j�͎Љ�犈���ƁE����Ȋw�����҂ŁA�������X����s��������_�t�i1940�N7 ��31���j�� �o���Ă��邩��A�����m�͂͏�˂ɂ������ɂ��߂������Ǝv����B�g����1939�i���a14�j�N11��5���̓��L�Ɂu�����m�͂���莆�������B���o�� �Ђ��n�߂��ƌ����B�w�Ҕ��̐l���Ǝv�����v�Ə����Ă���B�����́s��������_�t�́q���r�̏I���̕����������B�����̋g�������L�͖����s�����A�����̍Z�� �̎�`�������Ă������B
�@�ȂفA���́A���́u��������_�v������i��ŏo�ł���ӎu�ƗE�C�������Ȃ����̂ł��邪�A�������X�����m�͎��� �Ȃ邷���� �ɂ�āA�Ђɏo�ł��邱�ƂɂȂ��̂ł���B���̂��߂ɁA���e�̐�����͂����x�ꂪ���ɂȂāA����̖��f�������Ă��܂��B�܂��A�Z���ɓ��� �́A���ɖȖ��Ȓ��ӂ�Ղ����B�������X�ɑ��Đ[�ӂ��鎟��ł���B
�@�@���a�\�ܔN��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ȋw������������ǂɉ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ҁi�����A�O�y�[�W�j
�g�����s��������̗��ꂩ��t���u�ǂ݂Ȃ��犴�������ڂ����v�̂͂ǂ̂悤�ȓ_�������̂��낤���B�����A�����ǂ�ŋ������䂩���͎̂��悤�ȉӏ��ł�
��B
�u�l
�I�����̋���I�J���ɂ͋Z�p���炱���d��Ȗ�ڂ��ʂ����̂ŁA���w��N�w�̔@����ʕ����I���{�͉��y��̑��Ɠ��l�ɋ���ɂ����郊�N���G�[�V�����Ƃ��Ď�
����̗��Ɋw��ōs�����Ƃ��ł���̂ł��邪�A�Z�p�̋���͓��Ɋw�Z�Ƃ��ӓ���̑g�D�I����@�ւȂ����Ă͌��ʂ�[�ߓ��Ȃ��̂ł���B���݂̔@���@���w
���̋���Ȃ�A�}���قłȂ�A���a�I�łȂ�w�K���邱�Ƃ��ł���̂ł��āA���ɑ�w�̔@���ݔ���K�v�Ƃ͂��Ȃ��̂ł���B�N�̋���ɂ��Ă����ɂ�
�̓_�ɒ��ӂ��ċZ�p�������Ƃ���g�D�I����@�ւ��������A����ɂ�ĐN��O�̐E�\������s�ӂ��Ƃ����Ƃ̕K�v�Ƃ��鍑������̊����ł���Ƃ��ւ��
�ł���B�ȏ�̔@�����n���猩��A���w�Z�͍����w�Z�̏�������łȂ��A���ꎩ�g��̊�������ł���A�i��ō����������Ƃ�����͍̂L���N��O
����\�͂̂�����̂�I�����ċ�����{���ׂ��ŁA���݂̂₤�ɍ����̐�勳�炪�\�͖{�ʂł͂Ȃ����͖{�ʂł��邱�Ƃ͋��玑�{��`�̕��K�ł���A�l�I����
�̋���I�J���Ƃ��Ă͌����č��Ƃ̂��߂ɉx�Ԃׂ����Ƃł͂Ȃ��̂ł���v�i�q��O�́@���{����̍Č��r�́q�O�@������v�̍��{���r�A�{���A���l�`����
�y�[�W�j�B
�u���w��N�w�̔@����ʕ����I���{�́k�c�c�l�Љ���̗��Ɋw��ōs�����Ƃ��ł���v�Ƃ�����߂ɂ́A�g�������̌��I�ɋ��������̂ł͂���܂����B������
���g���ɂƂ��Ắu�Љ���v�̎��Ԃ́A���̌�̒鍑���R����ѐ����{�Ƃ����ߍ�����܂�Ȃ����̂ł��������B
�s��������̗��ꂩ��t�ɒ��҂̂��Ƃ������Ȃ��͎̂c�O�����A���ɍĊ����ꂽ��˂́s�����Z�p�Ƌ��當���t�i�ݗ��t�A1946�N6��5���j�́q���r�ɂ�
������B�u�킽�����͏��a�\��N�Z���\�O���ˑR�����̖��߂ɂ�Đ��c�J���ɗ��u����A���N�܌��\�O���Q�����R�̐g�ƂȂ��B�����̗��R�͂킽����������
���Y��`��M�ċ���^�����s���Ƃ��ӌ��^�ł����B�����Ă��̏؋��Ƃ��Ă�����ꂽ���̂́A��g�u���u����Ȋw�v�ƎG���u����v���тɁu����w��
�T�v�Ɏ��M�������_���ł���A���q�Ƃ��Ă͌����ق�芧�s�����u�����Z�p�Ƌ��當���v�Ɓu�c�����狳��_�v�k�������́u�c������_�v�l���тɐ������X���
���s�����u����k�}�}�l����̗��ꂩ��v�ł����v�i�����A�O�y�[�W�j�B���g�̒���������L�E��A���Ă���̂́A�苖�ɂȂ����ߋL���ɗ����ď��������炾
�낤�B�ɂ�������炸�s��������̗��ꂩ��t�������Ă���̂́A��˂������̒���ɂȂ݂Ȃ݂Ȃ�ʎ����Ƃ���𗠏��������т����p����ۂ��Ă�������
���ƍl�������B
���̋g���͏�˔����Y�i�̒����j�ɂ��āA�Ȃɂ��G��Ă��Ȃ��B�Γc�g���Ƃ̊֘A�ŁA�������X�̂��������_�c�r���Ɍ��y�����ȊO�́B�u���a�\�l�A�ܔN��
��A���͒W�H���̓��_�c�r���̈ꎺ�ɂ���A�����ȏo�ŎЂɋ߂Ă����B�����̊K�i��֏��̑O�ł��ꂿ�����A���Ȃ����̘a���p�̑傫�ȐN�̎p�ɐS�䂩��
���B����������ł悭�ꏏ�ɂȂ�A�n���ؔ��s���̖�����A���ꂪ�Γc�g�����ƕ������v�i�s�o��t1970�N11�����A�Z��y�[�W�j�B���A�g��������
�w�E�ɏڂ��������m�͂Ɗւ�������Ԃ��Z���\�\�g����1945�i���a20�j�N12���A�������X�̎В������͎҂đn�����������[�ɓ��ЁA��1946�N8
���A�������[��ގЁ\�\�A���̌�͒}�����[�Ə�˂̕t���������قƂ�ǂȂ��������Ƃɂ���邾�낤�B
�k2014�N1��31���NjL�l
��˔����Y�ɂ́A�q������v�̊��̉��Ɂr�i1980�N2��7���A�m�g�j����e���r�s�킽���̎����`�t�ŕ����j
�Ƃ����^������������B���͂b�c�i�m�g�j�T�[�r�X�Z���^�[���s�E���Д����A2012�N5��22���j�ŏ�˂̘b�����B�\�z���ꂽ���Ƃ����A�g�����
�����X�ւ̌��y�͂Ȃ������B���b�c�i�s�m�g�j�킽���̎����` 11�k����E�@�� 2�l�t�j�̃p�b�P�[�W�ł�
�u�����Ԃ���^���Əo��A�ΘJ��`���琶����`�ɓ]��
��
�c���̌O�����u���R�ł��邱�Ɓv������ς̊�ƂȂ����B���厞��u���B�S���w�v���������A�q�ǂ��ɑ��鋻�����������B��Q�̓��k�Ɩk�C���Ő�����
����^���Əo��A���̉^���ƍ����������ƂŒe���������A���́u����Ȋw�v��W�Ԃ����B�v
�ƏЉ��Ă���B��˂̌����ɂ́A�ǂ��ƂȂ��������Q���o�g�̑�]���O�Y�Ɏ������̂��������B�ۂ������ዾ�����������e�����̈�ۂ����߂Ă���B
�������s���w�ق��l����\�\���w�يw�����̂��߂̃G�X�L�X�t�i�y�ЁA2011�N2��28���j��ǂB�ѕ��Ɂu�m�I�c�ׂ̕ۑ��ƌp�� �^���w�҂̈� �e�A���o���A���ŁA��i���A���w�҂̑�������`���镶�w��Y�ɂǂ��Ώ����ׂ����B���̂��߂ɕ��w�ق͉������ׂ����B���w�ق̗��O�A�{�݂���^�c�̎����ɂ� ����܂ł̂���������n���I�A�ԗ��I�A��̓I�Ɍ������A�Ȏ@�����킪���ŏ��߂Ă̕��w�٘_�B�}����������l�тƂɕK�g�̏��v�Ƃ���悤�ɁA���݂̂Ƃ� �땶�w�ق��l���邽�߂̗B��̏����Ƃ����Ă������낤�B�{���ɋg�����ւ̌��y�͌����Ȃ����A�{�T�C�g�s�g �����̎��̐��E�t��W�J���Ă������߂̑n���ɖ����Ă���B�ȉ��ł͖{���ɑ����āA����ׂ��q�g�������w�فr���\�\�ЂƂ̎v�l������ ���ā\�\�\�z���Ă݂悤�B�Ȃ����q�̓s����A�{���̍��ڂ��ƂɌ��o���Ɓia�j���̋L����t���A���s�ӏ����^�ŕ\�킵���B

�������s���w�ق��l����\�\���w�يw�����̂��߂̃G�X�L�X�t�i�y�ЁA2011�N2��28
���j�̃W���P�b�g
�i1�j�y���w�ق̐}���ٓI�@�\�ɂ��āz
�@���w�ق̖{���̎g���́A���w�����A���Ȃ킿�A�ia�j���M���e�A�ib�j���o���A �ic�j���Ŗ{�A�id�j���Ȃ��o������̊��{�A�ie�j���L�A�if�j���ȁA�ig�j�n��m�[�g�A�ih�j��������{���̑��̑����A����Ɂii�j�����������Ђ낭�� �W�A�ۑ��A�������A�����ғ��̉{���ɋ����邱�Ƃɂ���B����߂Č���ꂽ�����̓ǎ҂̂��߂̐}���ٓI�@�\���ʂ������Ƃ��{���A���w�ق̖����ł���B���� ��A�������������ɈӋ`��F�߂�Ďu�ƁA�����̓����Ȃ���ΐ��藧�����Ȃ��B���{�ߑ㕶�w�ق̂����ł���A�������̍�ƁA�w�ҁA�o�ŎГ��̎x���ƍD�� �ɂ���āA����܂ňێ�����Ă����Ƃ����Ă悢�B�o�啶�w�فA���{���㎍�̕��w�ٓ����A�����ނˁA���������}���ٓI�@�\�𒆐S�Ƃ��镶�w�قł���B�i��� �y�[�W�j
�g�����̏ꍇ�A���W�́i1-a�j���M ���e�͓��{�ߑ㕶�w�ق��� ������B�s�Õ��t�i1955�j�̍e�{�ȊO�ɑ��݂��Ȃ��Ǝv����B��O�̓W�A�@�s�����G�߁t�i1940�j�ƇA�s�t�́t�i1941�j�̓��M���e�͂����� ����ЂŏĎ����A�C�s�m���t�i1958�j�ȍ~���ׂĂ̎��W�̌��e�͗z�q�v�l�̏ɂȂ���̂�����ł���i���z���܂ގU���́A�g�����̎��M���e�Ǝv��� ��j�B�i1-b�j���o�����q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�������S���� �̔��\�}�̂Ƃ��̖{�����������Ă���B�ނ��A�V���ɖ����s���т̔��������\���͎c���Ă���B�i1-c�j���Ŗ{�́s�Õ��t�ȍ~�͊e�n�̐}���ق╶�w�� ���������鎍�W���������A���ƔŁi�Ƃ�킯�����̂��́j�͕��������Ȃ��H���̂��߁A�������ƂȂ��Ă���B�i1-d�j���Ȃ��o������̊��{�̑�\�͉���ނ��́s�g �������W�t�ŁA�����_�ł̍ŏI���{�́s�g�����S���W�t�i1996�j�ł���B�i1-e�j�� �L�͐��O�Ō�̏��Ёs���܂�͂����L�t �i1990�j��M���ɁA�G���⏑�ЂɌf�ڂ��ꂽ���̂�����������B�i1-f�j�� ���͉i�c�k�߈��̂��̂��k�߂̎�Ɏ��s�Ս��t�ɐ����f�ڂ���Ă������A���ȏW�̂悤�ɂ܂Ƃ܂������̂͂܂��Ȃ��B�i1-g�j�n��m�[�g�ɗނ��鎑���̑��݂͌��݂Ɏ���� �Ŋm�F����Ă��Ȃ��B�i1-h�j��������{���̑��̑����� �s���̓_���������A���˂�w�i�ɂ����ё��ʐ^�����瑠���̈ꕔ���M����B�������̎��{������������A�g���͑����ɏ������݂����Ȃ������悤���B�i1- i�j�������� �g�����̐��O�Ɉ���A�f��Ɏl�������邪�A����̃��m�O���t�����H���K�l�̑������ɂ��܂��B���{�ߑ㕶�w�قɂ͋g�����̒���20�����͂��߁A�s�����t ��s�k�t�Ƃ��������l�����̑����A�������̋g�������̏��o�f�ڎ�������A�o�啶�w�قɂ͋g���̔o�咇�Ԃ̋M�d�ȋ�W������B�������{���㎍�̕��w�ق����� ����q��́r�i�C�E13�j�̏��o���ł���s���㎍�t�����E�k��܂ŒT���ɂ������̂́A�����̌f�ڍ������{�ߑ㕶�w�قł���������}���قł������������� ��ł���B
�i2�j�y���w�҂̌����A���w�҂̌����ɂ��āz
�@�^�ɕ��w�҂���������̂ł���A�܂��A�ia�j���̕��w�҂̎������Ђ� �����W�A�ۑ��A��������A�Ƃ������{���̕��w�ق̊��������S�ƂȂ�˂Ȃ�܂��B���̏�ŁA�ib�j���̕��w�҂Ɋւ��錤���]�_�ނ��Ђ낭���W�A�ۑ��A���� ����B��������w�قɋ��߂���{���̊����ł���B���̏�ŁA�ic�j���s���̔��s�ł��낤�B�k�c�c�l�^���Ɍl���w�҂̋L�O�ق̂����A���w�ق͂��̕��w �Ҍ����̃��b�J�Ƃ������ׂ��A�����֍s�����ׂĂ̌����������������Ă���{�݂ł����Ăق����B�������邱�Ƃɂ���āA�͂��߂Ă��̕��w�҂̌����̊�b�� ������̂��A�Ǝ��͍l����B �i��O�y�[�W�j
�i2-a�j���̕��w�҂̎����́A �g�����̏ꍇ�͂܂��S�W���o�Ă��Ȃ�����A���s���͌̒P�s�{����ёS���W�A�����s���͏��o�����Ƃ������ƂɂȂ�B�i2-b�j���̕��w�҂Ɋւ��錤���]�_���͂܂��i1- i�j�����A���ЂɎ��^���ꂽ�A���邢�͎G����V���Ɍf�ڂ��ꂽ���̈ȊO�ɂ��A�C���^�[�l�b�g�����Ō��J����Ă��镶��������������B�s�g�����Q�l�����ژ^�t�͎��}�̂ɔ��\���ꂽ�����]�_�ނɌ��肵 �č̘^���Ă��邪�A�l�b�g��̏d�v�ȕ��͂Ɋւ��Ă͂��́s�q�g�����r�����t�ق��Ō��y����悤�ɂ��Ă���B�i2-c�j���s���̔��s�� �ŏ��ɑz�������Ԋ��́A���݁A�P�H���w�ىi�c�k�ߕ��ɂ���������g�����̉i�c�k�߈����ȁi�k�߂���̗��Ȃ����������ȏW����܂����j�ł���A�g���� �k�b��Βk�E���k��ȂǁA�G�N���`���[���ɂ��炴����̂̏W���ł���i���͂����̕ҏW���قڏI���Ă���j�B��҂͂����ς玩���̎��̋�ɂ��Č������ �̂�����A���������D�܂Ȃ������g���̏،��Ƃ��Ă��M�d�ł���B�Ȃ��A�����s�̎U���i������ҏW���������Ă���j�́i2-a�j���̕��w�҂̎����Ƃ��Ă� ����g�����S�W�Ɏ��^���ׂ����̂ł���B
�i3�j�y�����ɂ̏d�v���ɂ��āz
�@���w�ق̌����̐v���˗����A���邢�͌��傷������A�ǂ��������i�̕��w�قƂ��� ���Ƃ������O�����m�łȂ���A�{��̑����v�҂ɕK�v������掦�ł��Ȃ��B�ia�j�����̎��W�A�ۑ��A�����ғ��̉{���A���p�𒆐S�Ƃ���}���ٓI�@�\���A �ib�j�[�ցA���y�A�������̂��߂̓W���𒆐S�Ƃ��锎���ٓI�@�\���A�ic�j���w�����A���w�����̒��j�I�@�\���B�����̂��ׂĂ����˂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂� ����A�����̊Ԃ̌��˂������ǂ����邩�B�����������Ƃ��[���������A�n���I�����A�~�n�̏����A�������\�Z�A������J�ٌ�̈ێ��E�Ǘ��̔�p�܂ōl���� �Ă͂��߂āA�v�҂ɒ掦������������܂�̂��Ƃ����Ă悢�B�^����ł��Ȃ��A���͕��w�قɂ���������ɂ̏d�v���͂����ɋ������Ă�������������Ƃ����� �Ƃ͂Ȃ��ƍl���Ă���B�W�����S�̔����ٓI�@�\��ړI�Ƃ��镶�w�قł����Ă��A�����i�������Ȃ��W���͂��肦�Ȃ��B���������߂�����ɂƂ������舵���E ���������w�ي����̊�Ղł���B�i�O�l�`�O�܃y�[�W�j
���ۂɋg�������w�ق����Ă�ƂȂ�A������v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����̓E�F�u�T�C�g��̉ˋ�̋�ԂƂ������ƂŁA������ɂ͐[�� �肵�Ȃ��B�������A�i3-a�j�{���A���p�𒆐S�Ƃ���} ���ٓI�@�\�A�i3-b�j�W�� �𒆐S�Ƃ��锎���ٓI�@�\�A�i3-c�j�� �w�����A���w�����̒��j�I�@�\�A �̂ǂ���d�����邩�͌��肷��K�v������B���́s�g�����̎��̐��E�t�����J����ɂ������āA�T�C�g�̊T�v���u���ш�Y�������E���q�E�쐬����A���l�E���� �Ƌg�����̐l�ƍ�i����������y�[�W�B�g�����̒����������ʂ���⊮���A�ӏ܂ƌ����Ɏ�����B�N���E�����E�Q�l�����ژ^�ق��v�ƋL�����B�ʌ�����A���� �ЂƂ肪���M�ҁE�ҏW�ҁE����҂ł��邱�ƁB�g�����̎��l�Ƒ����Ƃ̗��ʂ��������邱�ƁB���A���Ȑ��E�̋g���̒����ɑ��āA���@�[�`�����Ȏw�W�Ƃ��Ă� ��ɍ�p���邱�ƁB��̓I�Ȍf�ڍ��ڂƂ��ẮA�g�����N���i����͋g���z�q����҂̔N����]�ڂ��邱�Ƃ��ł����j�E�g���������E�g�����Q�l�����ژ^�ł��� ���Ɓ\�\�����͂ǂ��炩�Ƃ����i3-a�j�ɋ߂��A�g�������w�ق̃X�g�b�N�ɑ�������B����A�s�g�����̎��̐��E�t�̐^�̖ړI���i3-b�j�̋g������i ���[�ցA���y�A�����A������ ����ƕ\����̂̊W�ɂ���i3-c�j���w�����A���w�� ���ł��邱�Ƃ͕�����Ȃ��B����̓t���[�Ƃ��������A�˂ɐV�����g�������̒Ƃ����悤���B���͓����ɂ��ꂪ�A�g������ ��̗�Ƃ���V�����������@�ł��邱�Ƃ�����Ă���B
�i4�j�y���W���ׂ����w�����A�Ƃ�킯�}���ɂ��āz
���w�قƂ͕��w���������W�A�ۑ����A�����ғ��̉{���ɋ�����{�݂� ���邱�Ƃ��A���̑��`�I�ȑ��݈Ӌ`�ł���B�R���N�V�����̂Ȃ����p�ق��W���z�[���ɂ����Ȃ��̂Ɠ��l�A���w�����̂Ȃ��A���邢�͖R�������w�ق͂��̖��� �l���Ȃ��B�^���w�����Ƃ́ia�j�}���A�ib�j�G���A�ic�j���e�A�id�j�n��m�[�g�A�ie�j�����̗ށA�if�j���L�A�ig�j���ȁA�ih�j���M�̏���A�ii�j�� ����������A�ij�j�M�L��̓���̐g�̉��i���������B���{�ߑ㕶�w�قł́A�}���A�G���������A���e���̑�����ʎ����Ƃ��ł���B�����̐����ɂ��A ���W�A�����A�ۊǁA���p���ɈႢ������A��������l�Ɏ�舵�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�^����̕��w�҂̋L�O�ق̂����A���W���ׂ��}���Ƃ��ẮA���̕��w�҂� ���s�����ik�j�P�s�{�̂��ׂāA����ɐ��O�A����Ɋ��s���ꂽ�il�j�S�W�A�im�j�I�W�A�in�j���ɔŁA����ɂ��̕��w�҂̍�i�����^����Ă���io�j���w �S�W�A�ip�j�A���\���W�[���ӂ��݁A���̕��w�҂Ɋւ���iq�j�������A�ir�j�]�_�A�is�j��z���̓`�L�I�����ƂȂ�}���܂łӂ��ށB�i�l�Z�`�l���y�[�W�j
�i4-d�j�n��m�[�g�� �i1-g�j�Łu���݂Ɏ���܂Ŋm�F����Ă��Ȃ��v�Ə��������A�悭�l����Ă݂�·K�s���[���h���b�v�t�i1988�j�̖ڎ��̏��Ă�����ɑ��������悤�ɁA �ق��ɂ��܂����݂��邩������Ȃ��B�i4-e�j������ �́A���g�̉ƌn���n�}�ɂ܂Ƃ߂悤�Ƃ����i�����炭�͖������́j���ꂪ��ۂɎc���Ă���B�i4-f�j���L�́A �g�������������Ă����ƍl�������̂͂قƂ�nj��\����Ă���̂ł͂Ȃ����B�������s���܂�͂����L�t�����s�����u�����I�ȓ���́u���E���L�v�͏��ł� ��͂��ł���v�Ƃ����q���Ƃ����r�̕��������̂܂Ƃ߂Ă������̂��ǂ����B�L�s����t�i2002�j�̌��{�����ł�Ƃꂽ�悤�ɁA�u���E���L�v������ ����̂ł͂Ȃ����B�i4-i�j�������������́A �g�������w�ق̔��p�ٓI�E�����ٓI�����Ƃ��āA�W���ɂ͍œK�ł���i�g���̟f��ɂ́A�T��̃R���N�V�������W�����ꂽ�j�B�s�T�t�����E�݁t�̃W���P�b�g�� ��̂悤�ɂ��łɐl��ɓn����������ꓰ�ɉ����A������s�ςł��낤�B�s�g�����Q�l�����ژ^�t�́i4-q�j�������A�i4-r�j�]�_�A�i4-s�j��z���̓`�L�I�������ЂƂ�����ɂ��Ă��� ���A����͍ו��������ق���������������Ȃ��B�ɉ���t�����Ƃ͖����Ƃ��Ă��A���y����Ă����i�����L���邱�Ƃ́A�g���������ɑ傢�ɖ𗧂� �낤�B���l���s�g���������t�́i4-l�j�S�W�A�i4-m�j�I�W�A�i4-n�j���ɔ��A�i4-o�j���w�S�W�A�i4-p�j�A���\���W�[�ɍĘ^���ꂽ��i���݂ȁq��v�� �i���^���ژ^�r�ɂ܂Ƃ߂Ă��邪�A�������������ׂ����B
�i5�j�y���Ŗ{�Ƃ��̈Ӌ`�ɂ��āz
�@�l���w�҂̋L�O�قł���A�n�敶�w�قł���A�ΏۂƂ��镶�w�҂Ɋւ�����W���� �����Ƃ��āA���ɐ}���A���ƂɁia�j���Ŗ{������B���Ŗ{���W�̈Ӗ��́A���z�{�Ƃ̔�r�ɂ��ib�j���ȉߒ��T���̎����ł��邱�Ƃɂ��邪�A���Ȃɂ� �Ă͌��e�Ƃ̊W�Ō�ɍl���邱�ƂƂ���B�k�c�c�l�^�����A���Ŗ{���������Ƒ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ώ��ł̕����ł̐�����肪�����A�����͓��{�� �㕶�w�ق̐E���A��ɐ_�ސ�ߑ㕶�w�ق̎����ǒ����Ƃ߂��q�a�j���狳����ꂽ���Ƃ����A����̏��Ŗ{���r�������Ȃ���A�^�̏��Ŗ{���m��ł� �Ȃ������Ƃ����B������g��Ŕł����A����@�ɂ����Ĉ�����Ă����ԁA�����̖{�̂����A�����Ί����̒E�����яo�����݂��邻���ł���B�܂��A�k �쑾�ꂳ��̒����ɂ��A�����t���犧�s���ꂽ���������Y�w�q�b�q���x�̏��ő����ɂ͌�A�����������ƍ�҂�����Ă��邪�A���̌㏙�X�ɒ������ꂽ�� �̂́A�攪���Ƒ����Ƃ̊ԂŖ��炩�ɉ��ł���Ă���Ƃ����B�^������A���t��M�����ď��łƂ��߂��ނ��Ƃ̊댯�A���ő����ɂ��肪���Ȍ�A���l������ �������͏��Ŗ{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�l���`�l��y�[�W�j
�g������12���̒P�s���W�́i5-a�j��
�Ŗ{�̏��������͎���
�Ƃ���B�@100���A�A100���A�B200���A�C400���A�D400���A�E270���A�F700���A�G�s���i6���Ōv9,000���j�A�H1,000���A
�I800���A�J2,000���A�K1500���B�s�����������ĕ��ς���A1���������670���ɂȂ�B���̍�i�̂��e���͂ɔ䂵�āA�����̏��Ȃ��ɋ�
���B�ŏ��́s�����G�߁t�����ƔłŊ��s�����Ƃ��A�g���͂��łɏo�ŎЂ̕ҏW�҂������i�����̋Ɩ��͂܂����Ă��Ȃ������悤���j�B�o�łɐ��ʂ����l�Ԃ���
������Ȃ�Ƃ����Ⴊ�A�����12���̎��W�ł���B�i5-b�j��
�ȉߒ��T���̎����̖ʂ���́A�s�v�ȍs�A�L�����������H�s�Ẳ��t�i1979�j�ȊO�A�{���ɒv���I�����r�͌�������Ȃ��B����
�ȏ�Ɍ����Ȃ̂������̐ݒ�ŁA�Ƃ�킯�s�Õ��t��200���A�E�s�Â��ȉƁt�i1968�j��270���ɂ͐��������B
�i6�j�y�����Ǘ��ɕK�v�ȏ��ё���ɂ��āz
�@���ꂽ�������ǂ��������A�Ǘ����邩�́A�p�[�\�i���E�R�� �s���[�^�i�ȉ�����Ɂu�R���s���[�^�v�Ƃ����j�𗘗p���Ă�������ƁA�菑���ŏ������Ă�������ƂŁA���@���܂�ňႤ����ǂ��A�Ǘ����ׂ����̖{ ���ɈႢ������킯�ł͂Ȃ��B���w�ق��Ǘ����ׂ����́A�L�x�ł������قǖ]�܂������A�J�́A��p���ɂ�莩����x�����邱�Ƃ͎~�ނ����Ȃ��B�܂��A ���w�ق݂̍���ɂ���Ăǂ�قǏڍׂȏ����Ǘ����邩���Ⴄ��������Ȃ��B�^�}���ł���A�ia�j���Җ��A�ib�j�薼�A�ic�j�o�ŎЖ��A�id�j�o�ŔN�� ���A�ie�j�ҁA�if�j�⑰�̏Z���E�����A�ig�j���ŁE�Ĕł̕ʂȂǂ͍Œ���K�v�ȊǗ�����A�ih�j�����E�땶�̕M�ҁA�ii�j����Җ��A�ij�j�扽 �����̍������Ǘ����Ă����������ł���B�^�k�c�c�l�^���͏������Ƃ��đ���Җ����L�q���Ă����ׂ����ƍl���Ă���B�����ɂ��A�}���Ƃ͓��e���Ȃ� ���͂ƊO�����鑕��Ƃ̑�����i�ł���B����͎���Ƌ��Ɏ���قɂ��A����҂̌��ɂ���Ă�����قɂ���B����͓W�ς̑ΏۂƂ��Ȃ邵�A�����̑Ώ� �Ƃ��Ȃ�͂��ł���B�������̈�Ƃ��đ���Җ����L�q���A����҂���̌������\�Ȃ悤�ɂ������Ǝ��͍l���Ă���B�i����`���O�y�[�W�j
�i6-h�j�����E�땶�̕M����
��W��̏W�ł͏d�v�ȏ������ł���B�g�����@�c������W�s���t�i1985�j�Ɋ��q�w���x�̔o�l�ւ̊��ҁr�́A�o�啶�w�ق́u���E��ژ^�v�Ō���
���Ĕ����������̂��B�i6-i�j����Җ���
�ʏ�A���̗���ڎ��̍Ō�A�������͉��t�ɋL�ڂ���Ă���A�i6-a�j��
�Җ���
�悤�ɔ���W���P�b�g�A�\���E�{���ɋL����邱�Ƃ͂Ȃ��B����ɂ܂��A�o�ŎЂ̎Ј������������ꍇ�A�ҏW�҂Ɠ��l�A�N���W�b�g����Ȃ��̂��ӂ��ł���
�i�}�����[�ݐВ��̋g�����������������j�B�_�ސ�ߑ㕶�w�ق̎��������́u�������ځv�Ɂu����E�}��Җ��i�}���̂݁j�v���w�肷�邱�Ƃ��ł���B������
�u�g�����v�Ɠ��͂���Ǝ���41�����q�b�g����i�k �l���́A�}���̐����L���j�B
1. �����������@
�����@����
�Ё@1960.5.1�@�kK02/5013�l
2. ��W
�@�`�̉��@�O�D�B�����@�}�����[�@1976.6.30(��51)�@�k�~��/�J2�l
3. �K���X��
�� (���W)�@��蕶�Y���@�������[�@1983.7.15(��58)�@�kK02/0833�l
4. �M��Ɠ]
���@�l���c���F���@�V���Ё@1987.9.25(��62)�@2���@�k����/�L1�l
5. ���̂̑�
�q�@�����r�Y���@���X�@1978.2.20��(��53)�@�k�^�J78/�L1�l
6. ������s
���W�@������s���@�v���Ё@1970.12.1�@�kb�l
7. ���l�̌��@
�����r�Y���@���X�@1977.8.20(��52)�@�k�^�J78/�V1�l
8. ���Ɣ�]
�@A�@�c�����꒘�@�v���Ё@1976.9.25�@3�Ł@�k�^��8/1-1�l
9. ���Ɣ�]
�@B�@�c�����꒘�@�v���Ё@1977.5.25�@4���@�k�^��8/1-2�l
10. ���Ɣ�
�]�@C�@�c�����꒘�@�v���Ё@1976.9.1�@3�Ł@�k�^��8/1-3�l
11. ���Ɣ�
�]�@D�@�c�����꒘�@�v���Ё@1977.6.1�@3���@�k�^��8/1-4�l
12. ���Ɣ�
�]�@E�@�c�����꒘�@�v���Ё@1978.10.15�@�k�^��8/1-5�l
13. �F�V��
�F�l�@�ޒJ���m���@�͏o���[�V�Ё@1990.2.20�@�k918/�V�u7/1�l
14. ���@
�F�V���F���@�����Ё@1981.11.9�@�k�V�u7/�V1�l
15. ���W
�l���@���e���O�Y���@����[��]�@�}�����[�@1979.6.20(��54)�@�k�j�V14/�V5�l
16. ���Ƃ�
�����@�����r�Y���@���X�@1978.10.10(��53)�@�k�^�J78/�Z2�l
17. �����V
�g�S�W�@1�@�����V�g���@����Ł@�y�Ё@1982.7.15�@�k�^�J43/1-1�l
18. �����V
�g�S�W�@2�@�����V�g���@����Ł@�y�Ё@1982.3.15�@�k�^�J43/1-2�l
19. �����V
�g�S�W�@3�@�����V�g���@����Ł@�y�Ё@1982.5.15�@�k�^�J43/1-3�l
20.
�����V�g�S�W�@4�@�����V�g���@����Ł@�y�Ё@1982.8.15�@�k�^�J43/1-4�l
21. �����d
�M�S��W�@�����d�M���@���Ё@1972.3.7(��47)�@�kK03/1745�l
22. �����d�M�S�W�@1�@
�����d�M���@�������[�@1985.7.8(��60)�@�k�^�J65/1-1�l
23. �����d�M�S�W�@2�@
�����d�M���@�������[�@1985.7.8(��60)�@�k�^�J65/1-2�l
24. �����d�M�S�W�@3
�@�����d�M���@�������[�@1985.8.8(��60)�@�k�^�J65/1-3�l
25. ���Ɏ�
�@���@�쌴��v���@���u���|�\�g�@1981.12.10(��56)�@�k�m�n/�^1-1�l
26. ���Ɏ�
�@���@�쌴��v���@���u���|�\�g�@1981.12.10(��56)�@�k�m�n/�^1-2�l
27. �Ǐ���
�Ό��@�|�����q���@�}�����[�@1985.6.30(��60)�@�k�^�P49/�g1�l
28. ���̉��@
�ےJ�ˈ꒘�@�������X�@1987.9.16(��62)�@2���@�k�}��11/�g1�l
29. ���e��
�O�Y�@�ϗe�̓`���@�V�q�r�꒘�@�ԗj�Ё@1979.9.25�@�k918/�j�V14/2�l
30. ���{��
���㏬���@�c��m���@�W�p�Ё@1980.5.10�@�k�V�m6/�j1�l
31. ������
���Y���̑��@�߉ϑ��Y���@���X�@1976.4.20(��51)�@2���@�k�i�J95/�n2�l
32. ���W�@
�S���т̂̂��@�O�D�B�����@�}�����[�@1975.7.30(��50)�@�k�~��/�q2�l
33. ��
�D�@���Ɏ�[��]�@�}�����[�@1957.6.20�@�kK03/1898�l
34. ��⸂�
�Ԏ]�@�]�X���F���@����@���Ё@1971.5.1�@�k�G��2/�z1�l
35. �{�̎�
���@�z��p���q�咘�@���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��@1979.1.10�@�kS06/020/32�l
36. �{�̎����@�z
��p���q�咘�@���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��@1980.7.10�@4���@�k020/6�l
37. ���ӂ�
�� (���W)�@���ѕq�F���@�̒��Ё@1988.6.1�@�kK02/4440�l
38. �s�{��
�����t���@�V�V�ޓ�Y���@�}�����[�@1986.9.30(���a61)�@�k�A�}4/�~3�l
39. �₳��
�����t (���W)�@�Ί_��@�Ԑ_�Ё@1984.4.21�@�kK02/0706�l
40. ��̉��@
�������Y���@����R�c�@1988.6.10�@�k�A��13/��1�l
41. �����@
�Ί_��@�Ԑ_�Ё@1979.5.9�@�kK02/0707�l
���{�ߑ㕶�w�ق̏��������ł́u�t���[���[�h�v�Ɂu����@�g�����v�Ɠ��͂���ƁA��f�́u31. �����Y���̑��v�̂ق��A�s��{��
�ϑ��Y��
�W�t�Ɓs�ٗ�Ձk����Łl�t�̌v3�����q�b�g����B����}���ق�NDL-OPAC�͂������������Җ����̘^���Ă��Ȃ�����A�_�ސ�ߑ㕶�w�ق̎���������
�M�d�ł���B�Ƃ���ŁA�����Ƃ������ꍇ�͏��Ђ̊O���i����W���P�b�g�A�\���A�{���j���w�����Ƃ͖��Ȃ��Ƃ��āA�ڎ��≜�t�A�{���g�͊܂܂��̂��܂�
��Ȃ��̂��B�u�u�b�N�f�U�C���v��u���{�v�Ƃ̈Ⴂ�͂��̂�����ɂ���悤�Ɏv�����A�g���������ł́u����v�Ƃ����N���W�b�g�������A����͏��Ђ̊O����
���肷��̂��ӂ��킵���낤�B�g���͂����ΐ��z�Ɂu���{����͉]�]�v�Ə����Ă���A����͊O���ɉ����Ėڎ���{���g���i�ҏW�҂Ƌ������āj�S����������
�ƍl������B
�i7�j�y�������̃R���s���[�^���p�ɂ��āz
�@����������������A�R���s���[�^�𗘗p����Ƃ��́A�������� ���͈͂�x�ő���A�����̃L�[���[�h�ɂ��A���Җ��A�薼���̏������͒����Ɍ����������Ƃ��ł���B�����Ǘ��p�̏��{���҂ɒ��ׂ�������� ���Ē��邱�Ƃ��e�Ղł���B�䒠�A�ژ^�A�J�[�h���쐬����K�v���Ȃ��B�R���s���[�^�̓������ȗ͉��ɑ傢�ɖ𗧂��Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�^�������A�ia�j �������w�������̑����ژ^�f�[�^�x�[�X�iNACSIS-CAT, NC�j�����������A�e��̃f�[�^�x�[�X���ɂ��łɓ��͂���Ă�����̓_�E�����[�h���A���w�ٓƎ��̏��������[����A���ׂĂ�������͂���K�v�͂� ���B����ɉ����āA���̑����f�[�^�x�[�X�Ɏ��^����Ă��Ȃ��}���A�G���ɂ��ĐV���ɓ��͂���Α����킯�ł���B�^�������A�R���s���[�^�𗘗p���邱�� �ɂ͑傫�Ȋ��v������ł��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���͂͏��F�l�Ԃ̎��Ƃł���B�l�Ԃ̍�Ƃɂ͂˂ɊԈႢ�����邱�Ƃ͔����������B�� �U�ԈႦ��Ό������͂���߂ē���B����A�䒠�A�ژ^�A�J�[�h��������쐬���A���邢�͓]�L����s�x�A���̐}���A�G���ɐڂ��邱�ƂɂȂ邩��A���̂��� ��A���قɂǂ̂悤�Ȏ������V���Ɏ�������邱�ƂɂȂ������A�Ȃǂɏڂ����m���������ƂɂȂ�A���l���̎��Ƃ��o�Ă����ԂɊԈႢ�ɋC�t�����Ƃ��� ��B�R���s���[�^�Ŋȕւɂ��܂���A������肷�邱�Ƃ͂ł��Ă��A�m�����̌��ɂȂ��ĐE���̐g�ɂ��킯�ł͂Ȃ��B�܂��A�����̏��ɂ����ƁA�ǂ� ���Ă���g�ɂȂ肪���ŁA���ꂼ��̊قɓK�������ނ���̑̌n��z���͓̂���B���̂��߂ɂ͂�قǎ��o�I�Ȏp����K�v�Ƃ��邾�낤�B�i���O�`���l�y�[ �W�j
�i7-a�j�������w�������̑�����
�^�f�[�^�x�[�X�͓��Y����
���ǂ̋@�ցi�{�݁j�ɏ�������Ă��邩�킩���Ă��肪�������A���������ʂ����Ȃ�����B���Җ����g�����Ńq�b�g����̂�6���A�������P���͂킸��
��3���ł���B������ɂ��Ă��A�f�[�^�x�[�X�̏����͎��̖ژ^���i���{�ߑ㕶�w�قł͂܂��g�p�ł���j�Ɠ���Ɉ����āA�������炽�ǂ�����������m�F
���Ȃ���ΉL�ۂ݂ɂł��Ȃ��B�ŋ߁A�C���^�[�l�b�g��̂��鏑���i�}���ق�OPAC�ł͂Ȃ��j�ŏo�ŎЂ������ЂɂȂ��Ă����̂ŁA���̊��ň���Œm��ꂽ
�V�܂̈��������ʏ����o���̂��Ǝv���āA���{�̉��t��������A������������ЂŁA�Ō��͕ʂ̏o�ŎЂ������B�����܂�Ɉ�����Ɣ��s������肿�����邱��
������̂ő傫�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A���͂����l�Ԃ����t��ǂ݂܂��������̂��낤�B���̂��Ƃ����炢�܂ǂ����t�Ɉ�������L�ڂ���̂͂�߂Ăق�������
�����A�o�ŎЂɂ��Ă݂�Α������ɏ������s�����N���������A�������s�����N����������2�s�ɂ������̂�������Ȃ��B�����{�T�C�g�ɏ��Ђ̔��s�N�����܂ŏ�
���̂́A�����������������Ƃ��m�F���邽�߂ł�����i�������A�{�����̋g�����̒����͔N�������̊ȗ��\���j�B
�i8�j�y���M�����Ɋւ����͂��ׂ����������ɂ��āz
�@�����������ʎ����Ƃ��ł�����M�����̐���������̂͏��ЁA �G���ƈ���āA�������̂��̂����{�I�f�[�^�����s���Ȃ�������������ł���B�����������Ē��������̎����������Ă��A����͌����[���邱�ƂƂ��A�� ���ɑ䒠�̋L���A�J�[�h���쐬�A���邢�̓R���s���[�^���͂̍�Ƃ͐i�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�^���͂��ׂ������������A���łɏЉ�����w�ِE�����C�u���̋L �q������p����ƁA���{�ߑ㕶�w�قł͈ȉ��̂悤�Ȏ�������͂��Ă���B�^�u�ia�j���ʁA�ib�j���@�A�ic�j�����A�id�j�w���E�E����N�����A �ie�j���M�E����̔N�����A�if�j�����̏�ԁA�ig�j�z�ˏꏊ�Ȃǂ͊e���ނɋ��ʂ���v���A���̑��K�v�ȏ��Ƃ��āA�l����W�ڂɗ��Ă���̂Ǝ�����W�� �ɗ��Ă���̂̓��ɕ�����A�l����W�ڂɗ��Ă�����A�^�@�ih�j���e�\�^�C�g���A���e�E���e�̕ʁA���M�E���[�v���E�������e�E���M�E���M�Ȃǂ̕ʁA�� �e�p���̎��l�߁A�M�L��A���o�E���łɊւ��鏑���I�f�[�^�A�N�������i������j�����\�ł�����̎|�^�A�ii�j���ȁ\�������́��������ȂƂ��A���M���t �i���L���t���D�悵���L�̏ꍇ�͏���j��t�L�A���M�n�A�����E�t���E�G�t���̕ʁA��ⳁE�����E�r���Ȃǂ̕ʁA�����̗L���A���e�̗v��A��M�l�͕⏕�J�[�h �i�R���s���[�^�̏ꍇ�̓L�[���[�h�Ƃ��ē��́j�ɂ��^�B�ij�j���L�\���ɏ�����Ă��邩�i���L���A�m�[�g�Ȃǁj�A�M�L��A�����\�i���ɂ��j�E�����\�� �ʁ^�ȉ��͍��ڂ݂̂�����A�C�ik�j���M�����A�D�il�j�M�n�A�E�im�j����A�F�in�j�G��A�����A�G�io�j�ؔ��A�H�ip�j������A�I�iq�j�����A�J �ir�j�ʐ^�A�K�is�j��i�A�L�it�j���̑��̔@���ł���B�^�������������A���ނ��꒩��[�łł��Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�e���w�ق����s���낵�Ċe���� ���@���m��������A�����������͕��w�يԂŋ��L���ׂ����Ǝ��͍l����B�i�����`�����y�[�W�j
�g�����̓��M���������W�s�Õ��t�e�{���Ɍ����Ă݂悤�B�i8-a�j������1���B�{���͑S����39���i���̂����y���̓\����2���j�B�i8-b�j���@�͓V�n265�~���E184�~�����[�g���B�i8-c�j������͓��{�ߑ㕶�w�فB�i8-d�j�w���E�E����N�����́A���m�ɂ͂킩��Ȃ����A���ɒ������Ɉ��Ă��z�q�v�l�̏��Ȃ�2002�N4��18���t�Ȃ̂ŁA2002�N4���Ƃ���B�i8-e�j���M�E����̔N�����́A�e�{�̍ŏ��̔����e�Ɂu�g�������W�^�Õ��^1955.5.5�v�ƎO�s���������Ă��邩��A1955�N5��5���Ƃ��Ă����B�Ȃ��A���t�́u���a�O�\�N������\�����v�ƈ������Ă��邪�A�e�{�́u���a�O�\�N�����O�\������s�v�ł���B�i8-f�j�����̏���́A�ܒԂ��̌��e�̔w�����ł������������{�ŁA�g�����g�����i�v�I�ȕۑ���ڎw�������Ƃ͊m���ł���B�i8-g�j�z�ˏꏊ�͕s�������A���ʎ����Ƃ��Ĉ�ʎ����i�}���E�G���j�Ƃ͕ʒu�ɂ��Ă���̂��낤�B�����ł́i8-t�j���̑��Ƃ��Ĉ����Ă������A�������e�͂��ꎩ�̂��g�����̍�i������A���{�Ƒɂ������̓W���͋g�������w�ق̗v�f�Ƃ��Č������Ȃ��i�g�������Âԉ�ł́A����R�c�̊��s���̑������e���z���̂����W�����ꂽ�j�B�^�甎���J�b�g��`�����s�Õ��t�̑������e���������邩�͕s���i�e�{�s�Õ��t�Ƃ�������ɕۑ�����Ă͂��Ȃ������j�B
�i9�j�y���W�̃e�[�}�ɂ��āz
�@��ݓW���~�߁A���邢�͏�ݓW�̂��߂̃X�y�[�X��啝�ɏk������ƁA���W�����S�� �Ȃ�̂ŁA�L�x�ȓW���������K�v������B�ia�j�ΏۂƂ��镶�w�҂̖�����@�艺���Ď��X�ɑ������Ԃ������ēW�����Ă������Ƃ����͈��Ƃ��čl���Ă� ��B�^��i���ƂłȂ��Ă��A�֓��g�ɂ��Ă����A�w�Ԍ��x�w���炽�܁x�̎���A�w���V�x�w���x�̎���A�w�Ƃ����сx�̎���A�w�����x�w�ōg�x�w�� �_�x�̎���A�w�����x�w�����R�x�̎���A�w�������x�̎���A�Ƃ����悤�ȁib�j����敪�ɂ���āA���ꂼ��̎���̖g�̉̋����ӂ��߂��W�����l����� ��ł��낤�B�^�܂��A�Z�̂Ƃ͕ʂɁA�u�g�̐��M�v�u�g�Ɩ��t�W�v�Ȃ����u�g�Ɗ`�{�l���C�v�u�g�ƈ�Ɓv�Ƃ������ic�j�e�[�}�œW������悷�邱�� ���l�����邵�A�u�g�̌̋��Ɖ̋��v�u�g�̑؉��̌��v�u�g�Ɖi��ӂ��q�v�Ȃ����u�g�̏����W�v�Ƃ������������肤��ł��낤�B�i���l�y�[ �W�j
�i9-a�j�ΏۂƂ��镶�w�҂̖����� �������ƂɂȂ�A�g���̏ꍇ�A�s�m���t�A�G�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�A�J�s��ʁt�i1983�j�̎O���W�͊O���Ȃ��B�i9-b�j����敪�� ����Ƃ��낾���A1945�N�܂ŁA1955�N����1970�N�܂ŁA1972�N����1980�N�܂ŁA1981�N����f�N��1990�N�܂ŁA�����Ɂu�����v �u�O���v�u�����v�u����v�Ƃ������B�u�O���v�u�����v�u����v���\���鎍�W���O�f�́s�m���t�s�T�t�����E�݁t�s��ʁt�ł���B�i9-c�j�e�[�}�œW��������Ƃ́A�܂��Ɏ������� �s�q�g�����r�����t�ł���Ă��邱�ƂŁA�q�g�����̉����r�q�g�����Ɖ����r�́A�����E�����E�l���ƁA���ꂱ��������硂��Ȃ��B�g�����S�W�ɂ����鎖�� ���E�����E�l���̊e�����������ɑ������邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�i10�j�y���������̌��\�ɂ��āz
�@���w�ق̎������鎑���͌����ғ��̉{���ɋ����邱�Ƃ����ł͑���Ȃ��B�����͌��\ ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���\���Ȃ���A�����͎������Ă���ɂЂƂ����B�^���\�ɂ́A�]���͕��w�ق����s���Ă���ia�j�ٕ�A�j���[�X�A�I�v���̑��̊��s�� �Ɍf�ڂ��邱�Ƃ��ʏ�ł��������A������A�����̊��s���Ɍf�ڂ��Č��\����K�v�����邯��ǂ��A���݂ł́A���킹�āA�ib�j�C���^�[�l�b�g�������Č� �\���邱�Ƃ��A���s���̔z�z�ȏ�ɑ����̐l�X�ɒ��ڂ����@������̂ŁA�C���^�[�l�b�g�̗��p���l����K�v������B�^�����A���s���Ɍf�ڂ���ɂ��A �C���^�[�l�b�g�𗘗p����ɂ��A����ɐ旧���āA�ic�j�����̖|�����K�v�ł���B�������A���M������|�����A���s���Ɍf�ڂ��邱�Ƃ͌����ėe�ՂȂ��Ƃł� �Ȃ��B���Ƃ��A�������̕M�����̏��Ȃ�lj����āA�|�����āA�f�ڂ���ɂ́A��������M�ғ��L�̏��̓���ǂ݉����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����ɂ͓��R�A�n ���A�m���A�o���A�\�͓����K�v�ł���B����ɁA���Ƃ��A�����̐��쎞������肷�邽�߂ɂ́A�����̓��e�A�����̗p���̎�ޓ��A�l�X�ȏ��琄�肵�Ȃ� ��Ȃ�Ȃ��B���̕��w��i�A���ȓ��Ɋւ�����ӂ̎����m��Ȃ���A�����̓��e������Ȃ����Ƃ��������A���w�҂��ǂ��������e�p�����g�p���Ă������� �m�邱�Ƃ����쎞���̐���ɖ𗧂̂ł���B�i�ꔪ��y�[�W�j
�i10-a�j�ٕ�A�j���[�X�A�I�v�� �̑��̊��s���͓��Y���w�ق�K���҂ɂ͓��肵�₷�����A�������̂��i10-b�j�C���^�[�l�b�g�����������\�A���Ƃ��� PDF�Ō��������ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�{���̌��J�������A�ڎ������ł��[���ɗL�����낤�B�i10-c�j�����̖|���� �K�{�ŁA�ʐ^�ł͌����̑��݂𗠕t���邽�߂̕⑫�ɂƂǂ߂�ׂ����i�Z�����K�v�ɂȂ�ꍇ�����邾�낤�j�B�����ɁA���w�҂̋Ɛт̊T�ρA���Y�����̗����� �S�̂ɂ����邻�̈ʒu�Â��A�������Ȍ��ɂ܂Ƃ߂������������Ȃ��B����������b�I�ȍ�Ƃ̗ݐς��܂��ď��߂āA�g�����S�W���g�������w�ق��\�ɂȂ�� �l����B
�k�NjL�l
�k2013�N5��31���NjL�l
�x�䌛��Y�s���܂��������A�̕��͖@�k�����ܐV���l�t�i�}�����[�A2011�N9��10���j�́A�����W�߂ƌ��e���M�̗v�������̂悤�Ɏw�E����B
�@���S�ȃI���W�i�����߂������Ƃ���ƁA���Ƃ��A���Ӗ��Ɏ����W�߂������肷��B
�@��N�ސE��A�悵�A���܂�m�� ��Ă��Ȃ����y�̈̐l�ɂ��āA����o�ł̖{���ЂƂ����グ�悤�ł͂Ȃ����Ɓk�c�c�l����������������������Ă��܂����s�́u�܂��A�������R���v ���[�g���悤�A������Ǝ������W�߂�v�Ƃ������������Ă��܂����Ƃł��ˁB�������W�ߏo������������́A�܂��A�{�������܂���B�����Ȃ������A�Ƃ��� ���v�ɂ͂܂��Ă�̂����������̖�肾���ǁA�������W�߂đS�̑�������ŁA���̑S�̂��������Ƃ��Ă���A���̓��̓����������Ȃ�ł��ˁB
�@�k�c�c�l�I���W�i���Ȃ�āA��������̐V�������_�������������̂��B
�@������u�̐l�ɂ��ĂȂɂ����������v�Ƃ������Ă�����A�����ȂW�߂ĂȂ��ŁA�����ɏ����Ȃ����B�����W�߂Ă鎞�ԂŁA�������B�{�������̂ɑ厖�� �̂́A�Ƃɂ����u�O�i�ޗ́v�ł����āA�����̐l�̑S�̑����������Ƃł͂Ȃ��B����ȂƂ���ɃI���W�i���͑��݂��Ȃ��B���Ȃ����������������u�Ȃɂ���� �̃|�C���g�v���A���̐l��I�����|�����˔j���Ƃ��āA�Ƃɂ����O��I�ɉs��������ł��������Ȃ��B�����W�߂͂��Ƃ���B�S�e����悤�Ƃ��� �ȁB�ЂƂ̑��ʂ��������Ώ\���ł��B�i�q�Ƃɂ����O�i�ޗ́r�A�����A��l�܁`��l�Z�y�[�W�j
�u�{�������̂ɑ厖�Ȃ̂́A�Ƃɂ����u�O�i�ޗ́v�ł����āA�����̐l�̑S�̑����������Ƃł͂Ȃ��v�B����͎����ŁA�s���|�C���g�ŏ� ���͂��߂āA ����Ȃ��i�Ċm�F�������j����������Ώ��������Ƃŕ⋭�i�������͊m�F�j�̂��߂ɓ��肷��B��������V���ɔ����������̂�����Ȃ�A�܂��ʂ̃^�C�g���ŕ� �͂����������B�u�����فv�̌`���Ƃ�̂͂��̌��ʂł����āA�ړI�ł͂Ȃ��B�ړI�́A�������Ƃ��ꎩ�̂ɂ���B
�k2016�N10��31���NjL�l
�g�����̎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�������������B1963�N8�����s�A���q����
�ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�����ꂾ�B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�i���W�s�Â��ȉƁt���^�j�̊Ԃ�
�́A�Ђ炪�Ȃ̑����i�u���v�^�u�v�j�̕\�L�������āA����Ɉٓ��͂Ȃ��B
�g���������W�s�Õ��t��1955�N8��20���A���Ɣł��Ȃ킿�g���̎���ŏo�ł��ꂽ��O���W�ɂ��Đ�㏉�̎��W�ŁA17�т��ׂĂ��������낵�ł���B�{�Z�قł́A�O ���M���e�`�A�P ���W�s�Õ��t�f�ڌ`�A�Q�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�f�ڌ`�A�R�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�f�ڌ`�A�S�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�i�O�̈ꕔ�͉��Ō��y�j�����S�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�Õ��t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ�����ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�́A�P�����S�܂ł̈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ͊����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A�s�{�ӂȂ��烆�j�R�[�h�ɂ��u瀆�v�̑���ɃV�t�gJIS�́u���v���g�p���Ă���_�����ȉ��������������B�ŏ��Ɂs�Õ��t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O ���M���e�F�g�������M�́s�Õ��t�e�{�i���W����p���e�j�́A�g���̟f��A�z�q�v�l�ɂ���ē����E�ڍ��̓��{�ߑ㕶�w�قɊ��ꂽ�B�e�{�̊T�v���܂Ƃ߂��٘_�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�̋L�ڂ��玍�т̕W��Ɩ{���Ɋւ��镔�������ɐ��肱���A�K���������M���e�̓��e���ׂĂf�������̂ł͂Ȃ��B�Ȃ��A����N�v�q������v�Ǝ��r�ɂ͋g���̒k�Ƃ��āu�w�Õ��x�́A�����̋߂Ă�o�ŎЂɏo���肵�Ă���ǂ���̈�����ɁA����ň��Ă�����B�����͓����L�����ɂ�āA������V�����ɂȂ���ł��܂Ă�̂ŁA�Z���͎Г��̍Z�{���̃��F�e�����̗F�l�ɓ��Ɍ��Ă���āA��肪�o��̂�h�����B�������A���������ł͌�肪�����Ȃ����炤�B����ŁA���Ƀ����C�J���玍�W���o�������ɂ́A���e�̒i�K����V�����ŏ������v�i�ےJ�ˈ�ҁs������v��ᔻ����k���{��̐��E16�l�t�A�������_�ЁA1983�A��y�[�W�j�Ƃ���B�����Ɋւ��ẮA�P�̋����̓E�F�u��Ő��m�ɍČ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�f�ڂ������킹���i�Q�l�܂łɁA�Z�ق̂��Ƃ��������сq�Õ��r�̋����g�p�`���f�����j�B�P�̋������Q�ȍ~�͐V���g�p�ɕ��j�]�����ꂽ���߁A�ύX�i�������A戾���߁A�N�����A㊁���A㣁��ʁA�ց��j�ɘR�ꂽ�ꍇ�́A�Z�ق̑ΏۂƂ��Ĉٓ����f�����B�Q�ȍ~�A�P�ł͎g�p����Ȃ����������̔����L���̓��̎��_�i�X�j���g�p����Ă���B���ȂɊւ��ẮA�S17�т�ʂ��āA�������������V���ȂÂ����ɕύX���ꂽ�ӏ���106�A�Ђ炪�Ȃ̑����������i�j���珬���i���j�ɕύX���ꂽ�ӏ���39����A�J�^�J�i�̝X�����͂��ׂď����ł���B�P�����S�܂ł̎����ӏ����T�ς���Ɓ\�\�����ꕔ�̃T�u�X�^���e�B�u�ȕύX�������\�\���M�⊧�s�����̐V���E�G���̕\�L��ɉ��������̂Ƃ����悤�B���т̐ߔԍ��̐����̈ʒu�i�������j�͍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������E�s�ǂ�͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�����̎��������s�g�����S���W�t�̂���ɏ������B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�P ���W�s�Õ��t�i���ƔŁk�����s���n��쒬�l�̘Z��@���s�ґ��c�唪�l�A1955�N8��20���j�F�{�������������i�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�30���l�����24���l�E25���l11�s1�i�g�B�\���q�T�@�Õ��r�q�U�@�]�́r�̋敪����B
�Q�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|30���l�����24���l�E25���l18�s1�i�g�B�T�E�U�̋敪�Ȃ��B���ł̉��t�ł����Ă�����ɂ���ĔŖʂ��قȂ�_�Ɋւ��ẮA�k�NjL�l���Q�Ƃ��ꂽ���B
�R�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B�T�E�U�̋敪�Ȃ��B
�S�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l19�s1�i�g�B�T�E�U�̋敪�Ȃ��B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���R�s�g�������W�t�B
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�Z�`���y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A21�s�B�s�Õ��t�̖`���͏����ȗ��A��т��Ă��́q�Õ��r�ŁA�g�����̎�ɂȂ�e�{�ł��ŏ��̍�i�Ƃ��Đ��{����Ă��邪�A���ɏq�ׂ�悤�ɁA������ɓn�����i�K�ł͖{���т́q�Õ��r�A��̓�Ԃ߂ɒu����Ă����B�g���͎��W�̍Z���i�K�̂��鎞�_�ŁA�q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�����������тɂӂ��킵���ƒf���������̂ł���i�e�{�ł̑��s�́u��̊�̍d���ʂ̓����Łv�Ƃ������̂��A���M�Łu���v�ꕶ�������Ă���j�B��̊�̍d���ʂ̓���
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j��Z�`���y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A13�s�B�e�{�ł́A���s���u��݁k�������́u�v�A���߂́u�y�v�u�q�v�ǂ��炩���ɏ����ď㏑�����Ă���l�̋��v�Ƃ������̂�Ԑ��ŏ����Ă���i���̎ʐ^�Q�Ɓj�B�e�{�œ����A�����u�T�@�Õ��v�̂������Ƃɒu����Ă����q�Õ��k��͂������������ɂ���l�r�����A������e���ɂ�����s�Õ��t�̊������т������i�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�Q�Ɓj�B��͂��k�P�Q�R���S���l�����������ɂ���
�g�������W�s�Õ��t�e�{�́q�Õ��r�i�B�E2�j�`���k�s���{�ߑ㕶�w�فt��189������l
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j���`��O�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A15�s�B���̂Ȃ��r�̓���
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j��l�`��Z�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A21�s�B�䏊�̉��ꂽ��
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�ꔪ�`���y�[�W�A�{���܍�30���l11�s1�i�g�A9�s���B�g�����s�Õ��t��ҏW���铖�����āA�����炭���m�[�g�ɏ���������������т��ƂɌ��e�p���ɐ��������i�K�ł͎��т̏��Ԃ͌��܂��Ă��炸�A���W�̍\�������肵�Ă��牔�M�Œʂ��m���u�����L���������̂Ǝv����B���̎��_�ł́u14�v�u15�v�ƃm���u�����L�����A���{�́s�Õ��t�̂ǂ��ɂ������Ȃ��q���y�r�Ƃ������т����݂����͂����B�e�{�́q���鐢�E�r�ɉ��M�����m���u���̂Ȃ����Ƃ�T�Ƃ��āA�q���鐢�E�r�͂��́q���y�r�ɑւ��V���e�ƍl������i�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�Q�Ɓj�B�����̂Ȃ��Ł@�Ăт�������@�����������@�₪�ė���������@���k�P���Q�R�S�ځl���Ƃ���@�����낢���`�̂ނ�@�܂�Ȃ߂����̂��Ƃ����̂̂ނ炪��J�I�X�@���̊g�傳�ꂽᰂ̉����猻�k�P�́��Q�R�S��l���@�ڂ������̌`���@�җ�Ȋ��̂Ȃ����@�ڂ������̕@�@�����邽�߂̚q�f�����肩�k�P�ց��Q�R�S���l���@�ڂ������̈�A�@�������~�̓��ɂ͂��������炳��ā@���k�P�����Q�R�S�X�l�T���[�߂Ă䂭�@�ڂ������̎��@���̈Â����ւ������ǁk�P�Ё��Q�R�S���l���k�P�ց��Q�R�S���l����@�������k�P�ց��Q�R�S���l�k�P�Q�R���S���l�Ă䂭�@�ڂ������̐�@���܁@�����̎M�̊C�ɒ��݂�����@���̂��ꂽ���̐��E�@���̑O�ɂ��ā@�ڂ������̓ˑR����ɂȁk�P�Q�R���S���l���������韵�����炷
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j��Z�`���y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A16�s�B�J�̂ʂ炵���m�̐Q������
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j���`��O�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A12�s�B�g����1949�N8��1���̓��L�Ɂu����ꏊ�ɂ��闑�قǂ��т������̂͂Ȃ��悤�ȋC������B���ꂩ��o���邩����q���r�����ɂ������т������Ă݂����Ǝv���v�Ə����Ă���B�_���s�݂̎�
�g�������W�s�Õ��t�e�{�́q���r�i�B�E7�j�`���k�s���{�ߑ㕶�w�فt��190������l
�u�����Ă����̂̉e���Ȃ��^���̏L�Ђ��̂ڂ�ʁv�Ɠǂ߂�
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j��l�`�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A40�s�B�g���̐��z�q���֕������O�̎��r�Ɉ˂�A���܂��͂s�͒r�c�F�q�ł���B�@�@�@�@�@�k�P�q���Ɂr���Q�R�S�s�Ɂl
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�O�Z�`�O��y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A28�s�B���`�⟲�֑D�����̉Ă�
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�O�l�`�O�Z�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A28�s�B�{���т́A�e�{�̒i�K�ł͖ڎ��E�{���Ƃ��q�N�[�g�[�̕��i�r�Ƃ����薼�������i�u�N�[�g�[�v�ɂ��Ă��q��ƃN�[�g�Ǝ��q�͎ʁr�̏��o�r�A�q�����V�A���E�N�[�g�[�Ɠ�т̋g�������r������q���сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�]�߁r�Q�Ƃ̂��Ɓj�B���́q�N�[�g�[�̕��i�r���Z���̂��鎞�_�Łq���i�r�ɕς�����킯�ł���B�̎���
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�O���`�l��y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A34�s�B�ڂ��ɂ͊g���肪�K�v��
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�l��`�l�Z�y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A37�s�B�킽���������l�ł���
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�l���`�܁Z�y�[�W�A�{���܍�24���l�E25���l11�s1�i�g�A21�s�B�{���͎l���`�l��y�[�W��24���l�ŁA�܁Z�y�[�W��25���l�Ő܂�Ԃ��Ă���B�{���̎l���`�l��y�[�W�ȊO��25���l�Ő܂�Ԃ��Ă��邱�Ƃ���A24���l�͑g�ŏ�̕s����ƍl������B����@���͏n���@��܂܌͂��
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�ܓ�`�܌܃y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A35�s�B�ӂ�Â����
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�ܘZ�`�܋�y�[�W�A�{���܍�25���l11�s1�i�g�A18�s�B���M���e�����Ɂu���܌܁E�O�E�܁D�v�ƍe�{���B��A�E�e���炵���L�q������i�q�g�����ƃt�����V�X�E�x�[�R���r�Q�Ɓj�B�����̐�C��墁@�ƂяI��@�k�P�Q��R�S���l���n���̗ނ́@���݂̈Â��肩��@���Ƃ����肵�ā@��i�Ɛ[�����E�֒��݂䂫
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�Z�Z�`�Z�܃y�[�W�A�{���܍�11�s1�i�g�A7��40�s�B�e�{�ł͍ŏ��̑薼���q�J���炵�̌��r�ł���A�����ɁA���邢�͌���q���̏ё��r�ƕ��肪�t�����A�ŏI�I�Ɂq���̏ё��r�ƂȂ����B�u�J���炵�̌��v�͖{���Ɍ����鎍�傾���A�q���̏ё��r�ɂ͉����y�Ȃ��B�q�J���炵�̌��\�\���̏ё��r�ɂ����Ƃ���œ��f�ł���B�@�@�@1
���o�͎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j�Z�Z�`�Z��y�[�W�A�{���܍�25���l11�s1�i�g�A30�s�B�g���͐��z�q���q�f�z�r�ɖ{�т���9�s���p�������ƁA�u����͎��́q�ߋ��r�Ƃ������̈�߂ł��邪���̊���Ȍ`�̋����ߋ��m�A�A�n�̏ے��Ƃ��đ��^�������ƂɁA���͎����������Ă����v�Ə����Ă���B���̒j�͂܁k�P�Á��Q�R�S���l�ق������т��痿���߂𐂂炷
�Ε��b�g�������̌�A�g���̒P�s���W�̖{���\�L�́A�s�m���t�i1958�j�ȍ~�͂��Ȃ�����������V���ȂɁA�s�Â��ȉƁt�i1968�j�ȍ~�͊�������������V���ɕς���Ă����킯�����A��{�I�Ɋ����ɓǂ݂��Ȃ̃��r�͕t���Ȃ��B�Ƃ��낪�����Ɂs�Õ��t�S�т����^�����s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�i�}�����[�A1967�N12��10���j�������āA���̖{�����ς烋�r�Ȃ̂ł���B���r���������{���̊����E���Ȃ̕\�L�́A��q�����ӏ��������āA�R�́s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�Ƃ܂��������ꂾ����A�s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�̌��e�́s�g�������W�t�̍Z�����^�ӗ����i�������͂��̓��e�p�̌��e�j��������������Ȃ��B����Ƃ����̂��A�g�����i�c�k�߂Ɉ��Ă�1967�N3��1���t�̂͂����Ɂu�S���W�k�v���ДŁs�g�������W�t�̂��Ɓl���Z���ƂȂ�A�l���ɂ͊��s�����Ǝv���܂��B���̂��݂ɑ҂��Ă��ĉ������v�i�P�H���w�ىi�c�k�ߕ��ɏ����j�Ƃ��邩�炾�B���Ɂs���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�f�ڌ` �� �s�g�������W�t�f�ڌ`�ŁA�ς烋�r�̂��鎍���������B
������̍d���ʂ�����
�����₩���������Ă���
�H�̂�������
��◜��Ԃ����̗�
���ꂼ���
�����Ȃ��܂܂��p����
�����
�ЂƂ��~����
�傢�Ȃ����قւ������Ă䂭
�߂��߂��̍ł��[���Ƃ���֎���
�j�͂����ނ�ɂ悱���͂�
���̂܂͂��
�߂���沂��ȕ�ࣂ̎���
��������ꏂ̂܂ւ�
�̂₤��ᢂ��Ȃ�
�����̂������̗̂ނ�
���悢��d�݂����ւ�
�[�����̂Ȃ���
���̖�̘�ۂ̗���
�Ƃ���
�傫�������ނ�
���m�����n��� �� ����́@�q�Õ��r�i�B�E2�j�s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�́s�Õ��t�����ɂ́u�i���Ł@���a�O�\�N�����A���k�}�}�l�ƔŁj�v�i�����A�l��O�y�[�W�j�ƒ��L�����邪�A�Z�ق�����킩��悤�ɁA�{�����P�̏��ł��Č��������̂ł͂Ȃ��B�R�ɂς烋�r���{�������̖{���́A���s�̎������炢���Ă��R���S�̊ԂɈʒu���Ă���B�O�q�����悤�ɁA�`���́u���m�����n��� �� ����́v�Ɓu��n���̗ނ� �� �����n���̗ނ́v�i�q���b�r�B�E15�j�͊����̕ύX�R�ꂾ�낤�B����ɓ����ɂ͒�{�E�Z�����j�E���ӂ��L����Ă��Ȃ��B����A�̂��Ɂs�m���t��S�ю��^�����s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�A1973�N4��5���j�͎��т̊����Ƀ��r�͂Ȃ��i���Łs�m���t�ɂ��Ȃ��j�A���L�Ɂu�i���Ł@���a�O�\�O�N�\�ꌎ��\���A�����C�J���j�^�ҏW�����@�{���W�͎v���ДŁw�g�������W�x�ɂ��v�i�����A�Z�y�[�W�j�ƁA�ȒP�Ȃ��珑���ƒ�{���L����Ă���B�s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�́s�Õ��t�ɂς烋�r��t�����̂��N�Ȃ̂��킩��Ȃ����A���@����ɁA�k���㕶�w��n�l�̕ҏW���ł͂Ȃ����낤���B�g�����p�ӂ����{�����e�̓�NJ����ɕҏW�����ǂ݂��Ȃ�U��A�g��������𗹏������A�Ƃ��������肪����ɋ߂��悤�Ɏv���B�����������Ƃ����������߁A�s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�́s�Õ��t�{���͍���̍Z�قɑg�݂���邱�Ƃ������A�Q�l�����Ƃ��Ă����Ɍf�����B
�ڂ���̈�A�m�̂ǁn �� �ڂ���̈�A�@�q�Õ��r�i�B�E3�j
���m�͂���n�ƂƂ��ɌX���������� �� ���ƂƂ��ɌX���������ց@�q�Õ��r�i�B�E3�j
�ڂ������̓ˑR����ɂȂ��������韵�m�悾��n�����炷 �� �ڂ������̓ˑR����ɂȂ��������韵�����炷�@�q���鐢�E�r�i�B�E5�j
���̖�̋�̉₩�ł��т����u���m����n �� ���̖�̋�̉₩�ł��т����u�� �q�~�̉́r�i�B�E8�j
�j�̈���Ȏ��Ɏ���ꂽ��m�ނ��n�� �� �j�̈���Ȏ��Ɏ���ꂽ��� �q�~�̉́r�i�B�E8�j
�~�̖閾���̚�m���т����n���������̂Ȃ��� �� �~�̖閾���̚삵�������̂Ȃ��� �q�~�̉́r�i�B�E8�j
���m�Ƃ��n�̗ɑD�̊����j���� �� ���̗ɑD�̊����j����@�q�Ă̊G�r�i�B�E9�j
���ɂ͞��m�Ƃ��n����̃o���̖��m��n�� �� ���ɂ͞�����̃o���̖��� �q���i�r�i�B�E10�j
����͟��m���n����ł��܂� �� ����͟�����ł��܂��@�q���i�r�i�B�E10�j
����₩�Ȑ��̋�����m�˂��n���� �� ����₩�Ȑ��̋�������� �q�]�́r�i�B�E11�j
���ܓ܂ĊO�m�͂��n��Ă��� �� ���ܓ܂ĊO��Ă���@�q�]�́r�i�B�E11�j
�H�̖̎�����m���т����n���� �� �H�̖̎����삵���@�q�]�́r�i�B�E11�j
����V�m���n���Ⴂ�b�ւ� �� ����V���Ⴂ�b�ւƁ@�q�]�́r�i�B�E11�j
����炷�ׂĂ��ׁm�܂��n���ł��� �� ����炷�ׂĂ��ׂ��ł���@�q�҉́r�i�B�E12�j
�͂ꂽ�}�̏�Ɂ@���炭�͌��ۂ̏d�݂�欁m�����܁n���� �� �͂ꂽ�}�̏�Ɂ@���炭�͌��ۂ̏d�݂�欂���@�q�W�����O���r�i�B�E13�j
���̗���@���̘f�m�܂ǁn�킵�@���̋��Ё@���͂Ƃԁ@���f�ɉ����Â���_ �� ���̗���@���̘f�킵�@���̋��Ё@���͂Ƃԁ@���f�ɉ����Â���_ �q�W�����O���r�i�B�E13�j
�ٌ`�̗����ӂ���@�����G��̗�����Ԃ��������Ɂ@塡�m���n�߂Ă䂭 �� �ٌ`�̗����ӂ���@�����G��̗�����Ԃ���������塡�߂Ă䂭 �q�W�����O���r�i�B�E13�j
�̍���ᎁ@�̉��@㠈��m�����n�̉ԁ@���� �� �̍���ᎁ@�̉��@㠈��̉ԁ@���� �q�W�����O���r�i�B�E13�j
�킸���ȋɒn�̔����Ɂ@���m���n���ԁ@���������@����Ȃ���̖�����m����n�炩�ȉ�̑��� �� �킸���ȋɒn�̔����Ɂ@�����ԁ@���������@����Ȃ���̖�����炩�ȉ�̑��� �q�W�����O���r�i�B�E13�j
�����蓽�m�����n���ꂽ �� �����蓽���ꂽ�@�q��r�i�B�E14�j
��Ⴢ����G���m�����n�̂悤�Ȃނ� �� ��Ⴢ����G���̂悤�Ȃނ�@�q��r�i�B�E14�j
�n���̒[���@���ꂽ�@�Â�Ŗ`���@�����ȏ��Ɓ@�����̟��m�悾��n�@�Ƃ��ɖĂ̐K�̌��@�_�Z�ȍg�̍������@�`�R�m����n���Ám�܂Ȃ���n���ق��߂Ă䂭���\�\�����ʂ́@�������A�̊C �� �n���̒[���@���ꂽ�@�Â�Ŗ`���@�����ȏ��Ɓ@�����̟��@�Ƃ��ɖĂ̐K�̌��@�_�Z�ȍg�̍������@�`�R���Â��ق��߂Ă䂭���\�\�����ʂ́@�������A�̊C�@�q���b�r�i�B�E15�j
�E�C�m���肭�n�ɂ����� �� �E�C�ɂ����ā@�q�ߋ��r�i�B�E17�j
| �\�� | �F | �g�������W / �g������, �c��m�ҏW��� |
| �V���[�Y | �F | �����̎��l�o�� = Poetes d'aujourd'hui ; 5 |
| �o�Ŏ� | �F | �����C�J |
| �o�Œn | �F | ���� |
| �o�ŔN | �F | 1959 |
| �o�ŔN���� | �F | ���a34.8 |
| ���ʁE�傫�� | �F | 148p, �}��1�� ; 17cm |
| ���L | �F | �\�� : �l�c�ɒÎq |
| ���ҕW�� | �F | �g��, ��(1919-) |
| ���ҕW�� | �F | �c, ��m(1927-1989) |
| �Q��ID | �F | BA65593014 |
�@�w�g�������W�x�i�u�����̎��l�o���v��܊��A���t�̔��s���͏��a�O�l�N������Z���j�͎O���������Ă���A���t�̔��s�N�����͓��������A���쎞�����S���قȂ�悤���B����ʂ̔�r�i��Z�ܕŎQ�Ɓk���u���ň���Ŏ��^��������ꍇ�A�ʖ{�̔Ŗʂ̑傫�����r���āA�傫�����قȂ�A�������ق�����Ɉ�����ꂽ�{���Ɣ��f�ł���v�l�j�Ȃǂ���A���̂悤�ȏ����낤�Ɛ����ł���B�c���x�s���惆���C�J�̖{�t�̊��s���L�O���ĊJ�Â��ꂽ�q���惆���C�J�̖{�r�W�i�����Ï����2�K�M�������[�A2009�N10���j�ɂ�����W���{�̃L���v�V�����ɂ͂����������B�\�\�u�T�w�g�������W�x�c��m�ҁ@���a34�N8�����s�@�����t�̔��s�N������ウ�Ȃ���������B�����ɂ͉��t���Ɂu�����̎��l�o���v4�_�E�u�C�O�̎��l�o���v5�_�k1958�N1��10�����s�v�����F�[�����W�t�A1958�N1��15�����s�A�����E�~�V���I���W�t�A1958�N8��10�����s���l�E�V���[�����W�t�A1958�N8��10�����s�J�~���O�Y���W�t�A1959�N3��31�����s�S�b�g�t���[�g�E�x�����W�t�l�̏o�ō��m����B�w�m���x�сi�D�F�㎿�����j���͌���{�A����ɂ��̌�̑�������i���t�̌r�ɏ�����j�B�^�W���P�b�g��E�l�c�ɒÎq�@�W���{�͏����ŁA�w���㎍�S�W�x���̍L���`���V1�t���v�\�\�����܂��āA�ȉ��̍Z�قł��Q����L�y1�z�y2�z�ŕ\������ƂƂ��ɁA�y3�z���ו������āA1���߂̕x�{���g���ɏ����{���y3a�z�A2���߂̍�{��T�����{���y3b�z�A3���߂̖ؑ��Ò������{���y3c�z�ƌĂԂ��Ƃɂ���B���Ȃ킿�y3a�z�́y1�z�Ɠ���������A�y3b�z�́y2�z�Ɠ��������A�y3c�z�͂���Ɍ����Ƃ������ƂɂȂ�B�����Łs�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�����{�́q�Õ��r�i�B�E4�j�̖��̉ӏ����f���悤�B
�E����ځi���a�O�l�N�������s�j�c�c�x�{���g���ɏ����{�B���t���Ɂu�����̎��l�o���v��l���܂ł̃��C���i�b�v���L���ꂽ���X�g�i�L���j�k1957�N3��10�����s�R�{���Y���W�t�A1957�N8��30�����s�������j���W�t�A1958�N1��10�����s�g�{�������W�t�A1958�N6��1�����s���c�O�Y���W�t�l���f�ڂ���Ă���B�k������{�l
�E����ځi���a�O�l�N��������O�ܔN��Z���܂ł̊Ԃɐ���B�{���Ɠ��łł��鍑��}���ٖ{�́A��Z��łɋL�����悤�Ɂk���q�����C�J�̏o�ŕ��̍���}���قւ̔[�{�r�u35�E10�E17�i18���j�c�c�g�������W�v�l�A���a�O�ܔN��Z���ꎵ���ɁA��O�������̔��s���̏o�ŕ��ꔪ�����܂Ƃ߂Ĕ[�{���ꂽ�����̈���Ƃ��Ď�����Ă���B���������Ė{�����A�[�{�����̓��t�܂ł̊��Ԃ̂����̂ǂ����̎��_�Ő��삳�ꂽ���̂ƍl������j�c�c��{��T�����{�B��������}���ٖ{�Ɠ��ŁB���t���̑o���L���Ȃ��B�k�����{�l
�E�O���ځi���a�O�Z�N�ɐ���H�j�c�c�ؑ��Ò������{�B�{���̔ł��k�݁A����{�i�����j�ł���B�u���d�ɍő�̔g��𓊂������̎��W�u�m���v�S�ю��^�I�v�Ƃ��������B�g�����玍�l�ؑ��ɂ��Ăď��a�O���N�Ɋ������́B�k����Ɍ����{�l�i�����A��ꔪ�y�[�W�j
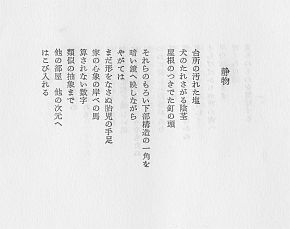
���̎苖�ɂ͖{���k�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�l�̏��łƎv����Ï��ƁA�����Ǝv����Ï��Ƃ�1��������B���҂̊O���͂܂����������Łi��������҂������t���Ă����\��������j�A���t�����ꂾ���A�O�҂̉��t�������Ȃ̂ɑ��āA��҂̉��t�̗��́k�����̎��l�o���l4���Ɓk�C�O�̎��l�o���l5���̍L���ɂȂ��Ă���B���ꂪ������̈Ⴂ�ł���B�{�����A�悭����ƑO�҂̌�A����҂Œ�������Ă���i����͂ނ���t�ŁA��A�̂�������u���Łv�A��������Ă�������u�����v�ƌĂ�ł���̂����j�B��f����2008�N11���A�����q�g�������W�s�m���t�{���Z�فr�ɏ��������͂ŁA����ɑ����Ď��^���W�s�m���t�̌�A�Ȃǂ̑g�ŏ�̕s���4�قǎw�E���Ă���B�������A�����܂ŋL���Ă����悤�ɁA�u���Łv�Ɓu�����v����肿�������L�q�䂦�Ɍ��ł���B����Ă����ɁA�u���ł͉��t�����k�����̎��l�o���l4���Ɓk�C�O�̎��l�o���l5���̍L���ɂȂ��Ă���{�ŁA�����͉��t�������̖{�ł���v�ƒ�������B�����Ƃ��A��肿������ɂ͎�肿�����邾���̗��R���������B�y1�z�͑g�œI�ɑP�{�ŁA����䂦���Ă̎��́y2�z�̌�A�𐳂����̂��y1�z���Ɛ��������킯���B
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�A�C���X�A�A�I�C�A�A�I�L�A�A�J�V�A�A�A�P�r�A�A�U�~�A�A�U���A�A�A�W�T�C�A�A�X�e���x�A�A�X�i���A�A�X�p���K�X�A�A�Z�r�A�A�l���l�A �A�����A�A ���A�A���e���i���A�C�O�T�A�C�^�h���A�C�`�C�A�C�`�S�A�C�`�W�N�A�C�`�n�c�A�C�g�X�M�A�C�k�K���A�C���J�K�~�A�E�C�L���E�A�E�R���U�N���A�E�Y�m�V���Q�A �E�c�M�A�E�b�R���R�E�A�E�c�{�O�T�A�E�h�A�E���A�E���o�`�\�E�A�E���C�A�G�]�}�c�A�G���h�E�A�I�I�}�c���C�O�T�A�I�L�i�O�T�A�I�V���C�o�i�A�I�j�Q�V�A�I �j�����A�I���_�J�A�I���U�T�`���@�A�J�G�f�A�K�K�C���A�J�J���A�A�J�L�c�o�^�A�J�V�A�J�^�N���A�J�c���A�K�}�A�J���A�J���X�E���A�J���}�c�A�J�����A�J�� �]�E�A�J���i�A�L�C�`�S�A�L�`�K�C�i �X�r�A�L�r�A�L�~�J�Q�\�E�A�L�����{�N�A�L���E�J�A�L���E���A�L���A�L���|�E�Q�A�N�T���^�A�N�`�i�V�A�N�}�U�T�A�O�~�A�N���v�g�����A�A�N���~�A�N���X�A �N���b�J�X�A�N���}�c�A�N�����W�A�N���A�P�[���A�P���L�A�R�E�]�A�R�P�����A�R�u�V�A�S�{�E�A�R�k�J�O�T�A�S�}�A�R���c�K�A�R���M�A�T�C�J�`�A�T�N���A�T �N���\�E�A�T�N�����{�A�T�T�Q�A�T�c�L�A�T�{�e���A�T���W���A�T���I�K�Z�A�T���g���C�o���A�T���m�R�V�J�P�A�V�R�^���}�c�A�W�V�o ���A�V�h�P�A�V�m�U�T�A�V�o�A�V���J�o�A�V���l�A�I�C�A�V���K�A�V���N�i�Q�A�V�����s�j�I���A�W���Y�_�}�A�X�C�Z���A�X�M�A�X�M�S�P�A�X�M�i�A�X�Y�J�P�m �L�A�X�Y���m�J�^�r���A�X�Y���m�e�b�|�E�A�X�Y�����A�X�~���A�Z�L�`�N�A�Z���A�Z�����[�A�[���}�C�A�^�[�j�b�v�A�^�P�A�^�f�A�^�}�i�A�^�}�l�M�A�^���m �L�A�^���|�|�A�`�K���A�`�S�����A�`�V���A�`���A�`���{�q�o�A�`���[�E���b�v�A�c�o�C�����A�c�o�L�A�c���N�T�A�c���N�T�A�c���K�l�\�E�A�h�C�c�g�E�q�A�g �h�}�c�A�i�X�^�V���A�j���A�j���W���A�l�M�A�l�Y�R�A�l�R���i�M�A�m�o���A�n�C�r���N�V���A�n�C�}�c�A�n�N�T���`�h���A�n�R���i�M�A�t���A�n�^���L���E�A �o�i�i�A�n�i���T�C�A�n�}�i�V�A�o���A�o���N�X�}�c�A�n���m�L�A�q�J�Q�m�J �Y���A�q�i�Q�V�A�q�m�L�A�q���V���X�A�t�L�A�t�W�A�v�������A�t���b�v�X�A�w���I�g���[�v�A�z�E�i�A�z�E�����\�E�A�z�^���J�Y���A�{�^���A�z�b�v�A�}�O�m ���A�A�}�_�A�}�`���A�}�c�A�}���A�~�Y�A�~�Y�L�A�~�Y�o�V���E�A�~���E�K�A���X�J���A���E�Z���S�P�A���~�A�����R�V�A���h���M�A���}�c�c�W�A���}�u�L�A�� �L�i�A���L���i�M�A���b�J�A�����A�����M�A���C���b�N�A�����A�����Q�\�E�A�����Q�c�c�W�A�����r
�ȏ�A202��B���Ȃ��݂̂��̂��������A���߂ĕ����悤�Ȃ��̂�����i���Ƃ��A�X�e���x�A���X�J���j�B���ɂ͋g�������ɓo�ꂷ��A ���̉���E�� �^���f�ڂ��鏀�����\�͂��Ȃ��̂ŁA�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�̖{������A�������E���ɂƂǂ߂�i�������тɁq�G�̂Ȃ��̏��r��Ǖ₵ ���j�B�L�ڂ́A�g�����L�����A�����Əo�T�B�������тɕ�����o�ꂷ��ꍇ���A����o�ꂵ�Ȃ��ꍇ�Ɠ���Ɉ������B�����A���Ōď̂��قȂ�ꍇ���A���� ���͂��Ȃ��i�E�H�[�^�[�������ƃX�C�J�^���Z�^���Z�A�Ђ������Ɛ��@�^���@�͕ʂɂ����j�B�����E���T�ނɌf�ڂ���Ă����͖��Ȃ����A������V�i�Q�V �͂ǂ��������̂��B��҂������ŏ����Ύx��㠈��ƂȂ낤���A�g������㠈����瑢�ꂵ���\�����̂Ă���Ȃ��B����āA�ʏ�̎��T��}�ӗނɌf�ڂ���Ă��� �������ƃV�i�Q�V�̂ӂ��͍̘^�������킹���B�ŗL�̕i��łȂ���Ȃǂ��̂�Ȃ������B���������A�A���A�m�i�ȏ�A30��j�A���i19��j�A�������� �^�ʎ��i�v14��j�A��i10��j�Ȃǂł���i���Ȃ݂Ɂu�����v�͑S���咆�A25��o�ꂷ��j�B�܂������F�Ƃ��ēo�ꂷ��A�����̂�Ȃ������B�������� �i13��j�^���F�i4��j�A�炢��^��F�^�o���F�i�ȏ�A�e4��j�^�K�N�F�i2��j�Ȃǂł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
��L�f�ډ�3��ȏ�̐A���𑽂����ɋ����Ă݂悤�i��������\�L�̏ꍇ�A�����ނ˂Ђ炪�ȁ^�J�^�J�i�^�����̏��ŗj�B�Ԃǂ��^
�u�h�E�^����
�i15��j�A���^�b�i12��j�A���i11��j�A�X�C�J�^���Z�^���Z�A���A��^�o���^�K�N�i�ȏ�A10��j�A���������^�C�`�W�N�^���ԉʁA���A��^��
���S�^�ь�i�ȏ�A9��j�A������^�U�N���^�Ξց^�ўցi8��j�A���^�ǁA�X�~���^俁A�|�A�S���i�ȏ�A7��j�A�Ƃ����낱���^�g�E�����R�V�A�n�^��
�L���E�^�b�U�ǁA���i�ȏ�A6��j�A�A�l���l�A���A������^�T�N���^���A���S�^�r���A�������^�X�X�L�A�ɂ�^�j���W���A�~�J���^�����i�ȏ�A5��j�A
�I���[���^�I���[�u�A�I�����W�A�L���x�c�A�L���E���^�ӉZ�A�X�M�^���A�^�}�l�M�^�ʔK�A�c�^�^�ӁA�K�A���ׁA���A�ȁi�ȏ�A4��j�A�����݁^�A�U�~�^�H�A
�����A�C�`�S�^䕁A�����A�J�V���^���^�ށm������n�A�I�A�����^�H�q�^㠈��A�R���N�A�T�{�e���A���Ⴊ�����^�W���K�C���A���@�^���@�A�Ƃ�����^�~�Z�A��
�S���^���S���A�g�}�g�A�֎q�A�ɂ�^�j���^�B�A�@�A�p�Z���A�o�i�i�A�Ђ܂��A�ւ��܁A�g�t�A�����Q�^�@�i�ȏ�A3��j�B�����S����58��̐A���̂�
���A����29�킪���������A�ʎ����q���H�p�ɂȂ����肷����̂Ȃ̂͒��ڂɒl����B�A���A�A���Y�A�C�`�S�A�C�`�W�N�A�I���[�u�A�I�����W�A�L���x
�c�A�L���E���A�N���A�U�N���A�W���K�C���A�X�C�J�A�^�}�l�M�A�g�E�K���A�g�E�����R�V�A�g�}�g�A�i�V�A�i�X�A�j���A�j���W���A�l�M�A�p�Z���A�n�^���L��
�E�A�o�i�i�A�u�h�E�A�~�J���A���M�A�����A�����S�B�Ԃ炵���Ԃ͎���10��B�A�U�~�A�A�l���l�A�P�V�A�X�C�����A�X�~���A�n�X�A�o���A�q�}�����A�����A��
���Q�B�炵���͎���5��B�C�g�X�M�A�J�V���A�X�M�A�}�c�A���i�M�B��������Ȃɂ����_�߂������Ƃ����������͓̂�����A�Õ���̑Ώۂɂӂ��킵����
�̂������Ƃ������Ƃ͌�����B�u��◜��Ԃǂ��̗ށv�i�q�Õ��r�B�E1�j�B�H�̂������̂ɑ�\�����g�����̐A���́A�ڂŐH�ׂ��邱�Ƃ�~���Ă�
��B
�k�t�L�l
���c�P�v
�s�����̃C�[�n�g�[�u�A�����t�ɂ́q�Q�l�����r�i�����A�k���܃y�[�W�l�j�Ƃ��Ď��̏��ځ\�\���t�@�����X�u�b�N�i�Q�l�}���ށj�ƃe�L�X�g�i�{���j�\�\��
��
�����Ă���B�Y������ł��낤���ڂɁA��������}���ق̏���NDL-OPAC�������N�����Ă݂��i�����́k�@�l�͏��т̕�L�A�������̏��ڂ̃����N�͊�
�������j�B�ׂ������Ƃ����A�q�Q�l�����r��搂���
��A�W��̕\�L�ɐ��m�������̂͂������̂��ƁA�����⎖�T�̗ނł����Ă��ҎҖ��E�Ŏ��E���s�N���f����ׂ��ł���B
�q��V�k���{�l�A���}���i�k���فj
���L�S�ȑ厖�T�A�����i���w�فj
�k�}���l�A���ώ@���T�i�n�l���فj
�k�}���l���؎����i�����[�j
�p�ĕ��w�A���������i�y�R�[�j
�Ԃ̍Ύ��L�k�J���[�Łl�i�W���Ёj
�V�C�{���S�W�i�}�����[�j
�Z�{�{���S�W�i�}�����[�j
�{����b���T�i�������Ёj
�N���{���`�i�������Ɂj
����厫�T�i���w�فj
�L�����i��g���X�j
�势�a���T�i��C�فj
�����k��l�厫�T�i�������Ёj
�s�g���������t�́q�V�@��v��i���^���ژ^�r��Z�Z���N �k������Z�N�l�̋L�ڂ������B�uJapanese Love Songs�i���{�̗��́j�k�^�������l�@���]�\�v���m�F���ѐ^���A�A���g�T�N�\�t�H���F�N���[�h�E�h�D�����O���@��Z�Z���N����@BIS�@���ǎ�̏��i�����j�k�약��Y��Ȃ�Dashu no sho, for voice and alto saxophone�i2003�j�̉̎��l�@�����C�i�[�m�[�c�kDashu no sho (The Helmsman's Book), ...�l�@���ǎ�̏��k1�E5�E6�߁l�����̃��[�}���\�L����щp��v
���C�i�[�m�[�c�kDashu no sho (The Helmsman's Book), ...�l��a�Ă݂�B�u�q�ǎ�̏��r�́A�약��Y�i1953-�j�̍�i�̓y��Ƃ��ėp����ꂽ�g�����i1919-90�j�ɂ��V�������A���X�����ŁA�������Ǝ����Ɏ���Ȃ����z�̗v�f�Ƃ�N�₩�Ɏ����Ă���B���т͂�����l�̃V�������A���X�g���l�ł������C���ɕ������Ă��邪�A����͕����O�̐��_�I���Ƃ݂Ȃ����i�����͍�ȉƂƂ��Ă̌o���̏����ɑ����̑���̎������y�ɂ��Ă���j�B�약��Y�͓����Y�p��w�ƃp�������������y�@�ō�Ȃ��w�сA���Q�e�B�A�h�i�g�[�j�A�G�g���F�V���A�t�@�[�j�z�E�̉��Ŋw�B1990�N����͓����Y�p��w�����ł���A���݁A��Ȃƃs�A�j�X�g�Ƃ��Ă̌o���ɐ�O���Ă���B���̋ƐёS�̂ɂ��A�T���g���[���y�܂ƌ|�p�I�������Ȋw��b�܂���܁v�i�sJapanese Love Songs�t�A�u�b�N���b�g�A�Z�`���y�[�W�j�B�b�c�ł̓g���b�N11���약��i�ŁA�N���W�b�g�ɁuNODAIRA, ICHIRO (b. 1953)�^DASHU NO SHO for voice and alto saxophone�i2003�j�iLemoire�j 9' 35�^Text: adapted from a poem by Minoru Yoshioka�^Commissioned by Claude Delangle�v�Ƃ���B�u�b�N���b�g�ɉ̎��i���[�}���\�L�̌����Ɖp��k��Җ��̋L�ڂȂ��A�������u�b�N���b�g�S�̂̉p��҂�Andrew Barnett�l�j���ژ^����Ă���̂ŁA���[�}���\�L�������ɖ߂��Ĉ��p����i�u�b�N���b�g�ɐߔԍ��͂Ȃ��j�B
| 1 | |
| �J�� | The rain |
| �Ă̐�l���̞��̏�ɍ~�� | falls on the prickles of the summer cactus |
| ����͈�̃X�^�C���� | that is a certain style |
| �K�[�g���[�h�E�X�^�C����͌���� | Ms Gertrude Stein reported, |
| �u�l�Ԃ̎��̏[������ | �eThe flower basket, |
| �@�@�@���� | swollen with the deaths of people, |
| �ǂ����Ă���ق� | why is it such |
| �@�@�@�@�@�@ �@�@�y���e��Ȃ̂��H�v | a lightweight container?�f |
| ����𗼎�Ŏx���� | holding it in both hands |
| ����݂Ђ炢�ċ߂Â���� | and bringing one's wide-open eyes closer to it |
| �u������������������ | �egradually shutting in the light |
| ����t�Ɉł�����߂��肷��v | or on the contrary shutting in the darkness�f |
| ����͋ߐ��̐_�b�Ƃ������ | one might say that it is a modern-day myth |
| 5 | |
| �l�͎��R�Ȏ���������Ă��� | Man possesses two free hands |
| ����䂦�� | and thus |
| �s���R���K�N�̓����ɗ}���� | carefully holds the hampered head of roses |
| �u�ق��� | �esilently |
| �����Ă����Ă��܂����v | walked away�f |
| ����͌`�Ԋw�� | morphologically speaking |
| ����߂Ď��ȓ����I���� | this is extremely self-contradictory |
| �փ����[�E���A�͖��̉��܂�S�ő��� | Henry Moore sculpts the queen of the dreams in iron |
| ���̂悤�ȓ��� | the interior like the flame |
| �I�����W�̂Ȃ��̍��j�� | obsidian within the orange |
| ���ꂪ���� | there is the island |
| ���C�����[�h���� | the helmsman and the octopus |
| �ǎ�Ƒ� | conduct the blue sea |
| 6 | |
| �Ȃ��閾���̐����Q�̓t�B�����̂悤�� | Why, at dawn, does the group of sacred images fade |
| �D�F�ɒ���ł���̂� | into the grey, like in a film? |
| �u�߂����̂̐��������v�̏H | autumn of �ea possession beyond the crystal�f |
| �����������N�̍��̂�����܂� | around the waist of an adolescent writing a poem |
| �����g������� | the white waves break |
| �����͊C�݂ɏo������ | the keel emerges on the beach |

�sJapanese Love Songs�i���{�̗��́j�t�iBIS-CD-1630�A2008�N12���j�̃u�b�N���b�g�\��
�q�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�͂��ĊO����ɖꂽ���Ƃ��Ȃ��͂�������A���Ƃ͂����M�d�Ȗ|��ł���B�약�́q�ǎ�̏��r�̋ȂƂb�c�̉��t�ɂ��Ă����A���ꂪ���ɂ͓�ł���B���ѐ^���̃��]�\�v���m�ƃN���[�h�E�h�D�����O���̃A���g�T�N�\�t�H���ɂ��̂Ɖ��t�́A�▭�̊|���������݂���B���т̉̂́i�̎������{��ł��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂����j�A��͂�̎������A�[�e�B�L�����[�V�����𖡂키�ׂ����̂��Ɗ�������B�h�D�����O���̃T�b�N�X�͂����Ƃ�Ƃ���������ۂ��A�c���ɋ삯�߂���A�W���Y�̍r�r�����Ƃ͕ʂ́A���̊y�킪�{�������Ă���䂩���������Ă���B���y�S�ʂɋ����������Ȃ������g�������A���̌��㉹�y���Ăǂ��v�������B�ق��Ď��U�������낤���A����Ƃ������炪�\�z�����Ȃ��������Ƃ����������낤���B�u���Ă݂��������B
�g���������W�s���[���h���b�v�t��1988�N11��25���ɏ���R�c���犧�s���ꂽ�B1984�N12������1988�N9���܂łɔ��\���ꂽ����19��i�����߂�i�Ȃ��A�q�����q杁r�ɕω��z�����ꂽ�q���ȁr��1984�N9���ɁA�������q���N�@���邢�͏H�r��10���ɔ��\����Ă���j�B�{�e�ł́A�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���f�ڌ`�A�Q �s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�f�ڌ`�A�R�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����R�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s���[���h���b�v�t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���i���{���Č����邽�߁A�u〽�v�Ȃǂ̃��j�R�[�h�������g�����ӏ�������j�B�Ȃ��A�������V���̖{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs���[���h���b�v�t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�F�����炭�z�q�v�l�̎�ɂȂ鎍�W�f�ڗp���e���e�ƂƂ���2011�N4���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������B���т̐ߔԍ��̐����̈ʒu�i�������j�͍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������E�s�ǂ�͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�{���O�̌����⎌���A�{����̒��L�̎��������s�g�����S���W�t�̂���ɏ������B�Ƃ���ŁA�g���́s���[���h���b�v�t�̎��т̕W��A�����A�{���A���L�Ő���ނ̊��ʂ��g�p���Ă���B��̓I�ɂ͈ȉ��̘Z��ނł���B�g�p�p�x���ɁA
�P ���o�G���E�V���F�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B�{���̕\���͊�{�I�ɐV���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�Ȃ̂ŁA���L�Ȃ��ꍇ�͂����\�킷�B
�Q �s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�N11��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A12�|13�s1�i�g�i�������q������ܒf�����сr�̂܍�15�s1�i�g�j�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q�s���[���h���b�v�t�B
| �p�[ ���� | �i�@�j | 296 �ӏ� |
| �ꊇ�� | �u�@�v | 149�ӏ� |
| �T�b | �k�@�l | 114�ӏ� |
| ��d�ꊇ�� |
�w�@�x | 2�ӏ� |
| ��d�p�[���� | ((�@)) | 1�ӏ� |
| �R���� | �q�@�r | 1�ӏ� |
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1986�N12���Վ��������k18��14���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A62�s�B�k���Ȃ�w偁l
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1985�N7��26���k35760���l���ʁA�{��7.5�|3�i�g�A30�s�B���o�E�G�u���[�����v�B��ʐ^�ƂƂ��ɁA���g�Łu�悵�����E�݂̂�@1919�N�A�������܂�B�V�������A���X�e�B�b�N�ȃC���[�W�ɂ��ӂꂽ���W�w�m���x�ő�9��g���܁B�����Ɂw�T�t�����E�݁x�i�������܁j�A�w�q�����r�Ƃ����G�x�A�w��ʁx�i����܁j�ȂǁB�v�ƏЉ����B�{���q���o�ꗗ�\�\�r�ɂ́u�i����j�v�ƋL����Ă���B�u�e������������v
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1985�N1��5���k39054���l�l�ʁA�{���V������1�{�G��1�i�g�A31�s�B���o�u�ʐ^�E���X�ؐ��a�v�B�`���ɂ��L�����悤�ɁA���e���e�𒉎��ɍČ��������߂��낤�A���̂قƂ�ǂ̎��тƈقȂ�s���̋N�������ꊇ�ʁi�u�j�ƃp�[�����i�i�j���V�̃��C���̏㕔�ɑg�܂�Ă���B�����ł͎������̈ٓ������o�`�ɑ�������Ƃ��ċL�ڂ������A�ŏ���1�s�߂��ꊇ�ʂƕ����i�u�c�j�̊ԂƍŏI��31�s�߂��ꊇ�ʂƕ����i�u�^�j�̊Ԃ�������V�̃��C���Ɖ��肷��ƁA9�s�߁i�ڂ��͗V�s�̂����ƘH�����ǂ�j�A20�s�߁i����鉺����i���j�j�A29�s�߁i���g���@�����_���j�̊e����́A�ꎚ�����ł͂Ȃ��V�c�L�Ƃ������ƂɂȂ�B�u�c���͎R�֎Ċ���ɂ䂫
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1984�N12���Վ��������k16��14���l��Z�`��Z�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A�k1 �āl�k2 �H�l�k3 �~�l�k4 �t�l83�s�B���o���L�Ɂu���i1�j�͕ʍ��u�w�l���_�v�A�i2�j�́u�p�������j���[�X�v�ɔ��\�������̂ł���B�v�Ƃ���悤�Ɂq���N�@���邢�͏H�r�i�s�ʍ��w�l���_�t�k�������_�Ёl1984�N10���k�H�E5��4���l�O���O�y�[�W�A14�s�j���q���ȁr�i�sMainichi Daily News�t�k�����V���Ёl1984�N9��17���k22128���l��ʂ́q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�A20�s�A���[�}���\�L�qShookyoku�r��Roger Pulvers�ɂ��p��qA Short Piece of Music�r��t���j�̂��ꂼ��S�s��ω��z���B�k1 �āl�́q���N�@���邢�͏H�r���`�Ƃ��āA�k2 �H�l�́q���ȁr���a�Ƃ��āA�q�����q杁r�{���Ƃ̈ٓ����L�����B�@�@�@1�@��
���o�́q���W�r�p���t���b�g�k�؉�L�l1985�N9��17���A�{��16��17�s1�i�g�A32�s�B�\���ɖ`����4�s��3�{�A�L�̒Ǎ��E���g�ŋL����Ă���B���т̖{���p���͔��t���B�{���q���o�ꗗ�\�\�r�ɂ́u�i����j�v�ƋL����Ă���B�u���m���̎��͂ǂ������
���o�́s�l�J�V�����l�`���t�k���p�o�ŎЊ��l1985�N6��10���A��Z�y�[�W�A�{��13��3�i�g�A4��52�s�B�Ό��y�[�W�S�ʂɐl�`��`�����l�J�V�����̓��ʼn���f�ځB�Ȃ��A���o44�s�߁i�ߐH�Z���K�v�ł���v�j��45�s�߁i�g������H�ׂ���͗҂����j�̊Ԃɍs�A�L�͂Ȃ��B�@�@�@�@�@�i�l�`�͔�������j�k�P�i�i�V�j���Q�R�\�\�\�l�l�J�V����
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�l1986�N1�����k40��1���l��y�[�W�A�{��9�|1�i�g�k�R�����q���̎��r�l�A20�s�B�J�b�g�F�i�C�B�_�`��K�𑀍삵��
���o�́s�C���t�k�������X�l1986�N1�����k5��1���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A5��78�s�B���o�����y�[�W�q���M�҈ꗗ�r�Ɂu�g�����i�悵�����@�݂̂�j�����N����B�����u�m���v�v�Ƃ���B�@�@�@1
���o�͔~�؉p�����ʼn�W�s���X�̘f���t�k�M�������[�v�`�t�H�������l1986�N12��3���A1�i�g�A39�s�B�s���̋N�������ꊇ�ʁi�u�j�͓V�̃��C���̏㕔�ɑg�܂�Ă��邪�A�`���ŏq�ׂ����R�ɂ���āA�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꖖ�̉f��ق̉Ă̏I��
���o�́s�K�t�k����R�c�l1985�N4���k2���l�l�`��y�[�W�A�{��9�|21�s1�i�g�A5��80�s�B�Ȃ��A�Q�Œ��L�̃A�X�e���X�N�i���j��90�x�X���Č�A����Ă���B�@�@�@1
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1986�N8�����k29��8���l�O�Z�`�O��y�[�W�A�{���܍�22�s1�i�g�A35�s�B�{���q���o�ꗗ�\�\�r�ɂ́u�i����j�v�ƋL����Ă���B�u���̎�
���o�́s�V���t�k�V���Ёl1986�N6�����k83��6���l���Z�`��O�Z�y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A�k�T �����̔ߖl�k�U ���\�b�h�l�k�V �e�L�X�g�l�k�W �̉��lj��l�k�X �i����̂̍̏W�j�l�k�Y �҉́l�k�Z ���ƐΕ��l�k�[ ���ߐS���l196�s�B���o�W��̑O�Ɂu���ю��\�\�y���F�Ǔ��v�Ƃ���B���̎ʐ^�͒������g�������M�̈���p���e�ɂ������邪�A�������g�ŏ�̎w����Ȃ��A���ۂɎg�p���ꂽ���̂��ǂ����킩��Ȃ��B���M���e�̕W�肩��{��13�s�߂܂ł��l�Ƃ��āA�����ās���[���h���b�v�t�ɐ旧���Ċ��s���ꂽ�s�y���F��t�i�}�����[�A1987�N9��30���j�f�ڌ`�i�S�сj���g�Ƃ��āA���Ƃ̈ٓ����L�����B�@�@�@�@�@�q�_�̌���ՏI���Ă���r�k�l�i�S�p�A�L�j���P�i�O�{�A�L�j���g�i��{�A�L�j���Q�R�\�\�\�l�y���F�k�l�n�]���G�l
�q������ܒf�����сr�`���̋g�������M���e�@�o�T�F���o���ďC�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���A�k���y�[�W�l�j
���o�́s�C���t�k�������X�l1987�N11�����k6��11���l�ꔪ�`���y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A3��63�s�B���o�����y�[�W�q���M�҈ꗗ�r�Ɂu�g�����i�悵�����@�݂̂�j�����N����B�����u�Z�ʁv�v�Ƃ���B�@�@�@1
���o�́s�G���Ԑ_�t�k�Ԑ_�Ёl1987�N8���k1��2���l��l�`��܃y�[�W�A�{��10�|19�s1�i�g�A34�s�B�������̎���������
���o�́s�V���t�k�V���Ёl1988�N5�����k85��5���i�ʊ�1000���j�l�Z�`�O�y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A4��75�s�B�@�@�@1
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�l1988�N1�����k42��1���l��y�[�W�A�{��9�|1�i�g�k�R�����q���̎��r�l�A20�s�B���o�W��́A�{���ł́u((��m�A�W���[���n))�v�A�ڎ��ł́u�i�A�W���[���j��v�B�J�b�g�F�������F�B�Î_���ς��i��m�A�W���[���n�j�̉���
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1988�N6���Վ��������k20��7���l�l���`�O�y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A6��107�s�B���o�Ɏ����u�F�V���F�������сv�Ȃ��B�s���̋N�����̊��ʁA���Ȃ킿�p�[�����i�i�j�E�T�b�i�k�j�E�ꊇ�ʁi�u�j���V�̃��C���̏㕔�ɑg�܂�Ă��邪�A�`���ŏq�ׂ����R�ɂ���āA�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�@�@�@�@�@�F�V���F��������
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1987�N12��28���k40120���l�l�ʁA�{���V������1�{�G��1�i�g�A35�s�B���o�W��u���������v�A���o�u�ʐ^�E���X�ؐ��a�v�A�܂��u�悵�����E�݂̂��@�����N�A�������܂�B��Ȏ��W�Ɂu�Õ��v�u�m���v�u�T�t�����E�݁v�ȂǁB�ߊ����Ɂu�y���F��v�B�v�ƏЉ����B�i�X�����炵���悤�ȓ~�j
���o�́s�������_���|���W�t�k�������_�Ёl1988�N9���k�H�G�E5��3���l�����`����y�[�W�A�{��10�|22�s1�i�g�A4��74�s�B���o�����u�i��㔪���E���E���j�v�B���o�����́q�ҏW��L�r�Ɂu���k�H��l�Ƃ������t���C���[�W�B�g�������̎��͌䎩�g���Ō�́A�ƌ������i�ł��B�v�i�d�k�]�㖞���l�j�Ƃ���B�s���̋N�����̊��ʁA���Ȃ킿�T�b�i�k�j�E�p�[�����i�i�j���V�̃��C���̏㕔�ɑg�܂�Ă��邪�A�`���ŏq�ׂ����R�ɂ���āA�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�@�@�@1
Shookyoku / Yoshioka Minoru�y02�z�@�q�킾�݁r�i�K�E3�j�Ɋւ��ẮA�s���̊��ʗނƎ���̎������Ƃ̊W���킩��悤�ɁA���o�`���f����i�ǂ݂��ȁ����r�͊����j�B
Me no mae de
"Hitotsu no ishi ga
kuuchuu de tokeuse temo
o d o r o k a n a i
Zessei no bijin ga iru
higasa o kurukuru mawashi yuuhi no naka ni
Boku wa shoonen dakara
arayuru shooku ni
gimonfu o utsu
"Kanojo no shootai" o miyo
yanagi no ha no kage kara arawareta yuurei?
soretomo Afurodiitee no matsuei?
Ima mo tsubame ga tobikai
keshi no hana ga sakimidare
Konoyo ka anoyo ka handan dekinai
"Kaaten no
Reesuori ni tsutsumareru"
sonraku kara shootakuchi made
"Shinu hito wa kakeasi da"
sudeni aki no hajimari
A Short Piece of Music / by Minoru Yoshioka
I see an unrivalled beauty
"who would remain calm
even if a rock
melted into thin air"
before her very eyes
twirling her parasol into the setting sun
as I am a boy
I question
each and every chapter and verse
let's look at her "true form"
a ghost from the shade of the willows?
or a descendant of Aphrodite?
the swallows fly past once again
the mustard flowers bloom like crazy
"people whose time is up don't stand still!"
enveloped in the curtain's
lace
stretching from the village to the swamp
so that no one can tell if it's this world or that
autumn is upon us now
�\ translated by Roger Pulvers
�u�c���͎R�֎Ċ���ɂ䂫�y03�z�@�q���[���h���b�v�r�i�K�E10�j�Ɋւ��ẮA�q�g�����ƃi�{�R�t�r�Q�ƁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̏��}�ƂƂ���
�@�@�J�̕��֗����Ă䂫
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c��͐����ɂ䂫
�i�M�j�ŕY���o��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�U��ԁ@����
�u������̕��Q�ł���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ͌��҂̂��Ƃ�
�@�ڂ��͗V�s�̂����ƘH�����ǂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������₩��
�u���F�̋T�������Ă����n�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�錩�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������炱�̐��߂�
�u��т������ꂽ
�@�@�@�@�@�@�@�@���̋r������
�@�@�@�@�@�@�@�@�֎q�̐܂ꂽ�r�������v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�u�ԍ炭�̉��ɖ��鏗�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킪���̂ӂƂ�����������
�@����鉺����i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂ǂ�̖Ԃ̖ڂ��Ђ낰��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�n���s�j
�@�@�@�@�@�����Ȃ݁@�i�����j�@����
�u�킾�݂̔ޕ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���Ɂi�E�j�̂��Ɂv
�u��͑D�̔��̂悤�ɔ�����
�@�@�@�@�@�@�@���ƕ����v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s��ł���
�@���g���@�����_���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂��������Ɓi���j�łȂ�
�u�^�g�̑��ނ�グ��v

�����킽���������l�X�ƈ���āA���Ƃ�������m���n���ɂ������Ǝv���Ă���B
���Ɓm�ЂƁn��l�Ɉفm���Ɓn�Ȃ�āA�H��m���傭�ځn���M�m�����Ɓn�ԁB
���Ոى��l�m��\�O�n�A���M�H��m��\�l�n�B
��\�l�@���M�H���@�u�H�v�͗{���̈Ӗ��ŁA�u�H��m���傭�ځn�v�͗{����A���Ȃ킿����̂��ƁB�u��v�͖��ɑ���{�������B�u�H��v�ŁA�����Ӗ�����B
�i�I���M�v�s�V�q�k��g���Ɂl�t��g���X�A2008�N12��16���A��Z�`��Z�y�[�W�j
| �W��i�f�ڏ��j | �������� | ���\�� | �ߐ� | �s�� | �� |
| �����i�J�m�v�X�j�i�K�E8�j | 01 | �y08�z | 5 | 78 | 131 |
| �J�^�o�~�̉Ԃ̂悤�Ɂi�K�E2�j | 02 | �y05�z | 30 | 50 | |
| �킾�݁i�K�E3�j | 03 | �y02�z | 31 | 52 | |
| �����q杁i�K�E4�j | 04 | �y01�z | 4 | 83 | 139 |
| �H�̗̕��i�K�E5�j | 05 | �y06�z | 32 | 54 | |
| ���ׁi�K�E6�j | 06 | �y04�z | 4 | 52 | 87 |
| ����i�K�E7�j | 07 | �y07�z | 20 | 34 | |
| �Y��i�ނ��сj�i�K�E1�j | 08 | �y12�z | 62 | 104 | |
| �▋�i�K�E9�j | 09 | �y11�z | 39 | 65 | |
| ���[���h���b�v�i�K�E10�j | 10 | �y03�z | 5 | 80 | 134 |
| ���i�i�K�E11�j | 11 | �y10�z | 35 | 59 | |
| ((��m�A�W���[���n))�i�K�E16�j | 12 | �y16�z | 20 | 34 | |
| ������ܒf�����сi�K�E12�j | 13 | �y09�z | 8 | 196 | 329 |
| ���i�K�E14�j | 14 | �y13�z | 34 | 57 | |
| ���@�i�K�E13�j | 15 | �y14�z | 3 | 63 | 106 |
| �ӏ��i�K�E15�j | 16 | �y17�z | 4 | 75 | 126 |
| ��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�i�K�E17�j | 17 | �y18�z | 6 | 107 | 180 |
| ���������i�K�E18�j | 18 | �y15�z | 35 | 59 | |
| ���v | 1072 | ||||
| ���� | 59.6 |
| �W��i�f�ڏ��j | �������� | ���\�� | �ߐ� | �s�� | �� |
| �Y��i�ނ��сj�i�K�E1�j | 08 | �y12�z | 62 | 102 | |
| �J�^�o�~�̉Ԃ̂悤�Ɂi�K�E2�j | 02 | �y05�z | 29 | 48 | |
| �킾�݁i�K�E3�j | 03 | �y02�z | 32 | 53 | |
| �����q杁i�K�E4�j | 04 | �y01�z | 4 | 83 | 137 |
| �H�̗̕��i�K�E5�j | 05 | �y06�z | 32 | 53 | |
| ���ׁi�K�E6�j | 06 | �y04�z | 4 | 50 | 83 |
| ����i�K�E7�j | 07 | �y07�z | 20 | 33 | |
| �����i�J�m�v�X�j�i�K�E8�j | 01 | �y08�z | 5 | 78 | 129 |
| �▋�i�K�E9�j | 09 | �y11�z | 39 | 64 | |
| ���[���h���b�v�i�K�E10�j | 10 | �y03�z | 5 | 80 | 132 |
| ���i�i�K�E11�j | 11 | �y10�z | 36 | 59 | |
| ������ܒf�����сi�K�E12�j | 13 | �y09�z | 8 | 196 | 324 |
| ���@�i�K�E13�j | 15 | �y14�z | 3 | 64 | 106 |
| ���i�K�E14�j | 14 | �y13�z | 34 | 56 | |
| �ӏ��i�K�E15�j | 16 | �y17�z | 4 | 74 | 122 |
| ��i�A�W���[���j�i�K�E16�j | 12 | �y16�z | 20 | 33 | |
| ��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�i�K�E17�j | 17 | �y18�z | 6 | 112 | 185 |
| �F�i�K�E18�j | 18 | �y15�z | 35 | 58 | |
| �k�H��l��i�K�E19�j | �\ | �y19�z | 4 | 74 | 122 |
| ���v | 1150 | ||||
| ���� | 60.5 |
| �Y�� | �u�����C�J�v�Վ�������㔪�Z�E�k��ꁨ���l |
| �J�^�o�~�̉Ԃ̂悤�� | �u�����V���v��㔪�܁E���E��Z�[���i����j |
| �킾�� | �u�����V���v��㔪�܁E��E�ܗ[�� |
| �����q� | �u�����C�J�v�Վ�������㔪�l�E�k��ꁨ���l |
| �H�̗̕� | ���W�p���t���b�g�@��㔪�܁E��E�ꎵ�i����j |
| ���� | �w�l�J�V�����@�l�`���x��㔪�܁E�Z�k�i�i�V�j���E��Z�l |
| ��� | �u���w�E�v��㔪�Z�E�� |
| ���� | �u�C���v��㔪�Z�E�� |
| �▋ | �~�؉p�����ʼn�W�w���X�̘f���x��㔪�Z�E�k�と���E�O�l |
| ���[���h���b�v | �u�K�v�Q�@��㔪�܁E�l |
| ���i | �u���㎍�蒟�v��㔪�Z�E���i����j |
| ������ܒf������ | �u�V���v��㔪�Z�E�Z |
| ���@ | �u�C���v��㔪���E��� |
| ���� | �u�Ԑ_�v�Q���@��㔪���E�� |
| �ӏ� | �u�V���v��㔪���E�܁i�獆�L�O���j |
| �� | �u���w�E�v��㔪���E�� |
| ��L | �u�����C�J�v�Վ��������k�����E��ꁨ�����E�Z�l |
| �F | �u�����V���v��㔪���E���E�[�� |
| �k�H��l�� | �u�������_�k�i�i�V�j�����|���W�l�v��㔪���E�k��Z���|����E�H�l�� |
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�g������1948�i���a23�j�N7��2���i���j���j�̓��L�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���i�^�͌����j�B
�������
�@�q���q�r
�@�g���M�q����̂�����^�啧���܂̒�ɂ��ā^�ׂ�Ƃ������ׂ�^�Ă̎��̂����Ł^�Ђ܂Ȏʐ^�����ЂƂ�^���Ƃ���ނ�Ă����^�Ԃ�����o�Ȃ���^�Â����Ǝv�����i�g������e�q�����i���l���N�E�ė�j�r�A�邵����ʍ��s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����t�A1996�N11��30���A����R�c�A���y�[�W�j
�����̋g���́A1946�i���a21�j�N8���ɍ������[��ގЂ��i���Ђ͑O�N��12���j�A��ɓ��Ђ����߂������^��̐s�͂œ��N10���ɓ��m���֓��Ќ�A���Ђ̕ҏW�ɏ]�����Ă����B�����Ƃ��A�g���M�q�̖{�͓��m������o�Ă��Ȃ��B���̂�����̎����剪�M�Ƃ̑Βk�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t1973�N9�����j�ł̋g����������܂Ƃ߂悤�B���m���i���s�ҁFꝈ�`�Y�k�����s������ؔҒ��O�m�l�l�j�Ɨ������A��m�o�ł̎O�Ђ͎Ж������قȂ���̂̓����o�ŎЂŁA���m���͊w�p�I�Ȗ{���o���Ă���A�g���̓J�����i�K�c���F��j�s���{�剤���u�t����c���j�s���ޔ_����b�t��S�������B�������̕��͑�O�I�Ȗ{�̔Ō��ŁA�g���M�q�́s���̊K���t�Ⓑ�J��L�̍�i���o���Ă����Ƃ����B���я����s���̊K���t�́A1936�i���a11�j�N4��11������9��19���ɂ����ās�ǔ��V���t�ɘA�ڂ��ꂽ�̂����o�B���N10��15���ɂ͑����������f��s���̊K���t�i�ēF��t���j�����J����Ă���B�g���̐l�C���炢���ē��R�A���Љ�����Ă�����ׂ��ŁA�s�t�z�����{�������ɖژ^�i���j�t�Ɉ˂�A�q���{�������Ɂr�́u449?�v�Ƃ��āu1937.12.?�v�Ɋ��s����Ă���i���̏����͌��{�����j�B�A�ڂ���12�N���1948�i���a23�j�N2��15���A�s���̊K���t�͏�q�呢�̑����ŗ���������Ăъ��s���ꂽ�i��������}���ُ����̃}�C�N���t�B�b�V���͍Ċ��{�́u�O�Łv�ŁA���N7��30�����s�B�����͋��E���j�B�g���������q�ɋg���M�q��K�˂��̂�����7���������킯�ŁA�����Ȃ�v���������̂��A�`���̈��p����͂킩��Ȃ��B�����A12��21���̓��L�Ɂu���E������s�{�����W�t�����炤�v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���O�y�[�W�j�Ƃ���A�������̕ҏW�҂Ƃ��ċ��E�������́u�O�Łv�̌��ŖK�₵���\�����ے�ł��Ȃ��B���s��25�N�o�����剪�Ƃ̑Βk�ŁA�����܂ŋ����ċg���̒����ɐG��Ă���̂�����A�s���̊K���t�̕ҏW�S���ł����Ȃ���A����Ȃ�̊ւ�肪�����Ă��������Ȃ��i�g�����������ŒJ���Z�Y�̖����S�����ďo�ł����o�܂��q�g�����ҏW�̒J���Z�Y����r���Q�Ƃ��ꂽ���j�B
 �@
�@ �@
�@�@
�g���M�q�s���̊K���k3�Łl�t�i�������A1948�N7��30���A�����F���E���j�̉��t�Ɩ{���k��������}���ُ����̃}�C�N���t�B�b�V���l�i���ӂ��j�A�����E���Łi���A���N2��15���A�����F��q�呢�j�̖{���ƕ\���i�E�ӂ��j
�����Ŏ��_��ς��āA�g���M�q�i1896-1973�j��1948�N��̔o��i�S��j������p����B�{���́s�g���M�q�S�W�k��12���l�t�i�����V���ЁA1976�N1��15���j�ɋ���A�s�g���M�q��W�t�i�������p�A1974�N3��30���j���Q�Ƃ����B�u墒��̗��̐����m�����сn��ӉZ���݁v�i�g���́q���J�̎p������r�i�H�E14�j�́u�w墒�����^�H�ׂ����̃T�o�̎ς����^���o���x�^���������{�̉ā^�����Ƃ���������₷���^���A�m�݂Ȃ�n�I�v��z�킹��j�̌オ���ɂ́u�Ȍ�Z�A���A�����Ɠ���J�n�ȗ����߂ċx�݁B�������M�ɒǂ�ꂽ�B�㌎�����Ăѓ���v�ƌ�����B�g���̂��̔N�̏����̘A�ڂ�1������12���܂ł��s����t�A4������10���܂ł��s���̋L�t�A�����ĒZ�т�6�{���M���Ă��邪�A����őO��̔N�Ɋr�ׂĎ��M�ʂ��ɒ[�ɑ����킯�ł͂Ȃ��̂�������������B������x�̂́A�o��ɒ����ׂ����Ԃ����Ȃ������������낤���B�ڍׂ͕s���Ȃ���A����1948�N�̂����܂��̋�u�킪�S���킯���ɐ���łv�i�O�����́u���鎞�v�j���Ȃɂ�����Ă���悤���B�Ƃ���ŁA�ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�E�g�������ҁs�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l�t�̑�12���q���l�o��W�r�i�������[�A1981�N3��20���j�ɁA�r��s��q�̊ӏ܂ɂ��q�g���M�q�r�����ڂ���Ă���B���̍Ō�̊ӏ܋�A�g���́u�H�����Â肵���̊�R�́v�i1950�N�j�́A�g���́u�H����w�̂����݂���g�W�v�i1948�N�j��z�킹��B�������A�Ȃɂ����g���Ƌg���̓�l���ڋ߂����̂́A�x�c�ؕ��i1897-1923�j�̔o��ɂ����Ăł���B�g���̐��z�q��z�̔o��r�́u�P�@�x�c�ؕ��ƎO���R�F�q�̋�v�i���o�F�s�����V���t1976�N7��4���j����A�ؕ��ւ̌��y�������B
�@�ĂɂȂ�ƁA�s�v�c�Ɍ������ďo��o�傪����B����͎�����\����Ɉ��u�����A�x�c�ؕ��̈��ł���B
�@�@�����ė��鎙��֎q�̉�
�@���̂܂�ŁA������̂悤�ȏ�̐��E����A���̏��N�̓��X����݂�����B���̐��܂������{������`�͂ǂԔ̒��������B������A�Ƃ�ڂ⏬����߂�ɂ́A�������~�̎O���_�Ђ����˗l�i���c�����j�֍s�����B���܂ɉ����g�M��x�̂�����܂ŏo�������B�܂������ɂ͉֎q�̉Ԃ��炭����������B
�@���܂ɂ��Ďv���ƁA���͖ؕ��̔o�傻�̂��̂����A�����Ȃ��Ŋw�Z�ɂ��s�����A����͂��邽�ƌR�l�߂ŁA�������o�����Ƃ�����ߎS�ȋ��U�ɁA�S�䂩�ꂽ�̂����m��Ȃ��B
�@���A����̗F�V�䐺���҂́s�x�c�ؕ��S�W�t�ɂ���āA�L�����ɒm����悤�ɂȂ����Ǝv���B�������A���̐S�̂Ȃ��ɐ����c�����傪����B���߂Ē��ׂČ��āA�ꎚ�����Ȃ��o���Ă����̂͂��ꂵ���B�܂�����������Ƃ������ׂ����̂��B
�@�@���Ɍ���Ύ����Ȃ�����~�ؕ�
�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�܁`��O�Z�y�[�W�j
�Ⴂ�g�����ؕ���ǂ̂͐V�䐺���ҁs��{�ؕ���W�t�i�𗖎ЁA1938�j�������낤���B�g���̕��͂́s��̂ʂ������ہ\�\�J�D�̔o�l�����t�i�V���ЁA1964�N7��5���j�Ɏ��߂�ꂽ�q�n��ɏ���\�\�q�x�c�ؕ��r�r�i���o�F�s�����V���t1963�N8�����j�ŁA�u�������ꂱ��\�\�\��O�N�O�̂��Ƃ������B�����ӂƎ�ɂ����o���̂Ȃ��̐��M���ň�l�̔����̔o�l�̂��Ƃ��`�����ƒm�����B�^���̂ЂƂ̖��́q�x�c�ؕ��r�������B�Ȃ����͂��̔o�l�̖��Ƃ��̋�����܂Œm��Ȃ������̂��A���Ԃ�̂����疜�ɋ����͂��������Ȃ����v�i�����A�O�܃y�[�W�j�Ƃ����̂���������������A�g�����g���ɖؕ��̋��������̂łȂ����Ƃ͊m�����B�����炭�ʒk���ɂ��o��̘b��͏o�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�u�~�̐��֒֍��Y�A�c�K�t���A�r�c�s�F��Ƌ�s�B�k�c�c�l���̍��A�e�����o�咇�ԂƗ��ꂱ�ꂩ��͎��������čs�������ƌ��Ӂv��1949�N�́q�g�����N���r�i�g���z�q�ҁj�ɂ��邩�炾�B�������ɂ����������������Ƃ����M�����f�I���ꂽ�̂����̎����ł���B���Ȃ݂ɋg�������������̂����A��҂́q�n��ɏ���r�̖`���ɓo�ꂷ��B�g���͐�̈��p�ɑ����Ă��������Ă���B
�@�\�\�Ƃ���������ƒx�܂��Ȃ��玄�͂��̕x�c�ؕ���Y�꓾�ʔo�l�Ƃ��Ċo�����B�����͂��̐l�̂��Ƃׂ����Ɗ���Ă����B������W��T���Ă���łȂ̂���ɓ���Ȃ������B
�@���߂āA���̋�肾���ł��������ƌ����O�͐_�Ђ֍s���ċ���������Ƃ���Ƃ��������ꂪ�Ȃ��Ȃ�������Ȃ������B�L���ȁi�[����c�����߂���̐_�Ȃ�j�̕�䑴�p�̂₻�̑��̔�炵�����̂͂��������ɂ��������A����̐N�o�l�������ؕ��̂͌�����Ȃ��̂Ŏd���Ȃ��Ж�����K���ƁA���ւɎႢ�����o���āA�킴�킴�ē����ĉ��������B
�@����͂Ȃ�ƁA�_�Ђ����Ƃ����̉E���̖؉A�̉��ɂ������̂��A���������������͂�����ʂ�߂��ĎГa�̕��ւ܂�������ɐi��ł��܂����̂������B���R�̕\�Ɂi���Ɍ���Ύ����Ȃ�����~�ؕ��j�Ƃ���c�c�c�O�Ȃ��玄�̏���ȁi�D�݁j�ɏ]�����̋�͔��K�̐��U���\���ŕ����l�ɂ��܂�t�m�n��������C�������B�ߎS�ȍŌ�𐋂����l�Ǝv�������ɁA�������Ă��́i�����Ȃ������j�Ƃ������������C�Ȃ������c�c�B�T�̔��̖ؕW�Ɂi�x�c�ؕ����j�ƋL����āA��̕����͉P�c���Q�̕M�Ƃ����ď����������肵���A�Ȃɂ����Q�̕M�Ղ������Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A���͖ؕ��̕����Ō����������̂��B�������͂��̋��̑O�ɂ��炭�����Ă����B�t���̕�F�̂��܂鋫���ɂ͌w�ł�l�e���Ȃ�����Ƃ��Ă����B�A�肩����Ƃ��Ƃ�ǂ��ė����ቜ���u��W������܂������A��������ł����炨�Ԃ��ɂȂ��ĉ������v�ƍ����o���ꂽ�B�ق�Ƃ��ɂ��肪���������I
�@�ƂA���ē��̉��ł��̋�W���Ђ��Ƃ��Ƃ���Ɩؕ��̐��U�̋��m�邱�Ƃ��o�����B�����čK���ɂ����̍D���ȋ傪�͂Ȃт�̎U���Ă���悤�ɁA�ǂ̕łɂ��������B
�@�@�@�叼�ɂЂ��Ǝq�V�Ԓ��̌�
�@�@�@���������ɒu���ė[�M����
�@�@�@�����тĉ��Ɏq������_�y���q
�@�@�@���锄�ׂ������Ă䂫���Ђ���
�@�@�@�g�Џ��̑��Ŋ��@�m�Ӂn�����ꂩ��
�@�ؕ��̐���Ĉ���������吳�̖{����������~��������̉����̍J�̏�ƋG�����Ȃ�Ƃ݂��݂������Y���\�������̝R��Z���ł��낤�c�c����͔o��Ƃ��ĕ]����̂łȂ��A���̍D���ȋ�Ƃ��Ċ������Ď���B
�@���ɒ���ꂽ���̋���A����ɑO�������i�S���l�X�Ɍ��āj�Ƃ���̂���W�Œm��Ɣ[�����������B
�@���̋�W�͂��܂����\�ܔN�O�̏��a�\�O�N���ŐV�䐺���҂Ƃ������B
�i�s��̂ʂ������ہ\�\�J�D�̔o�l�����t�A�O�܁`�O���y�[�W�j
�s�Õ��t���������Ƃ��Ă��鎍�l�E�g�����Ə����Ƃɂ��Ĕo�l�̋g���M�q�����3�N�߂̉ĂɁi�����炭�͋Ɩ���̘A���Łj�ʒk���A�݂��ɒm�邱�ƂȂ������̔o�l�E�x�c�ؕ����߈����A�̂��ɂ���͂Ɏc�������Ƃ͋����[���i�g���͂ނ��g������ǂɈႢ�Ȃ��j�B�g�����g���̔o��ɂ��ď����Ă��Ȃ��͎̂c�O�����A�q��z�̔o��r�ɖؕ�����肠�������Ƃŏ[����������Ă���悤�Ɏv���B����ɂ��Ă��g���̕��͂̉^�т́A�g���̐��z�̂���ɂȂ�Ǝ��Ă��邱�Ƃ��B
�k�t�L�l
�v�ۋԍƕҁs�t�z�����X���s�}�����ژ^�i1879�N�`1988�N�j�t�i�t�z�����X�A1991�N6��30���j�́u���a12�N�i1937�j�v�ɂ͎��̂悤�ɂ��邪�A�u�K�i�v�́u�K���v�̌�A���Ǝv����i�����A�O���y�[�W�j�B
�@���F12�@�@�����F���{�������Ɂ@���̊K�i�@�@���E��E�ҎҁF�g���M�q�@�@���^�F�e���@�@�ŁF424�@�@���i�~�j�F0.55
�g���������W�s��ʁt��1983�N10��20���ɏ���R�c���犧�s���ꂽ�B1981�N����83�N�܂łɔ��\���ꂽ����19��i�����߂�i�Ȃ��A�q�H�v���r�ɕω��z�����ꂽ�q�f�z�r��1978�N11���ɔ��\����Ă���j�B�{�e�ł́A�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���f�ڌ`�A�Q �s��ʁt�i����R�c�A1983�j�f�ڌ`�A�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����R�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s��ʁt�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���i�������Č����邽�߁A�u䱱�v�Ȃǂ̃��j�R�[�h�������g�����ӏ�������j�B�Ȃ��A�������V���̖{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs��ʁt�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�F�����炭�z�q�v�l�̎�ɂȂ鎍�W�f�ڗp���e���e�ƂƂ���2011�N2���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������B���т̐ߔԍ��̐����̈ʒu�i�������j�͍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������E�s�ǂ�͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�{���O�̌����⎌���A�{����̒��L�̎��������s�g�����S���W�t�̂���ɏ������B�Ƃ���ŁA�g���́s��ʁt�̎��т̖{������ђ��L�Ő���ނ̊��ʂ��g�p���Ă���B��̓I�ɂ͈ȉ��̘Z��ނł���B�g�p�p�x���ɁA
�P ���o�G���E�V���F�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B�{���̕\���́q����r�ȊO�A��{�I�ɐV���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�Ȃ̂ŁA���L�Ȃ��ꍇ�͂����\�킷�B
�Q �s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A12�|15�s1�i�g�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q �s��ʁt�B
| �p�[���� | �i�@�j | 256�ӏ� |
| �ꊇ�� | �u�@�v | 63�ӏ� |
| ��d�p�[���� | ((�@)) | 14�ӏ� |
| �T�b | �k�@�l | 1�ӏ� |
| �R���� | �q�@�r | 1�ӏ� |
| ��d�ꊇ�� | �w�@�x | 1�ӏ� |
���o�́s�����V���t�k�����V�������{�Ёl1981�N1��3���k34131���l��ܖʁA�{��7.5�|13�s3�i�g�A39�s�B���o�W��u�ɂ�Ƃ�v�B���̏��̂ނ����̓��̏o
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1981�N9�����k24��9���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A35�s�B���o�W��u�G�m����n�̐��v�B�u�S�͊Ձm�����n���ɂ��ā@�ڂ���������v
���o�́q���z�V���[�Y30�\�\���z���l��V���[�Y�U�r�́s�Ă̏��t�k���}�Ёl1982�N5��25���A���y�[�W�A�{��24��������1�i�g�A23�s�i���F�͎�j�B���o�����u�q�Ă̏��r�ɂ悹��v�B�k�P�������ڂ��V�т̎q���������Q�R�i�g���j�l
���o�́s���{�o�ϐV���t�k���{�o�ϐV���Ёl1982�N3��7���E14���E21���E28���k34638����l�ʁE34645����l�ʁE34652����l�ʁE34658����l�ʁl�A�ڂ́q�O���̎��T�`�W�r�A�{��7.5�|1�i�g�A27�s�E29�s�E29�s�E29�s�B���o�W��u�n�̗�i�t�̓`���P�j�v�u���̖��i�t�̓`���Q�j�v�u�̘T�i�t�̓`���R�j�v�u��m�����n�̉i�t�̓`���S�j�v�B�@�@�@�T�@�n�̗�
���o�́q��|�Εv�W�r�p���t���b�g�k�؉�L�l1982�N3��27���A�k��y�[�W�l�A�{��14��1�i�g24�s�i�q��|�Εv�W�Ǝ��сq�NJ|�r�r�Q�Ɓj�B�k�P�������Q�R���l�����͗V��ł���
���o�́q�l�D�G�����X�g�C�P�����̃_�_�W�\MAX ERNST, DADA in KOLN 1919/FIAT MODES PEREAT ARS�r�p���t���b�g�k���J��L�l1982�N12��8���A�k�l�`�܃y�[�W�l�A�{��10�|1�i���g�A31�s�B���o�W��u�s�����邢���X�v�B���J��L�̍��J�a�F�́q���Ƃ����r�Ɂu�J�^���O�ɂ͂l�E�G�����X�g�ɋ����S���������̎��l�g�������碊s���@���邢�͐��X��Ƒ肷�鎍�����̓W����̂��߂ɂ������������B����L�̓W����J�^���O�͍����24���𐔂��邪�C�����ڂ�͎̂n�߂Ăł���B�܂��e�L�X�g�͖{�]�M�v����ɂ��肢������e�����������B���̎��ƃe�L�X�g�ɂ��C���̓W����͈�w�̂ӂ���݂ƌ����𑝂����ƂƂȂ����B���Ӑ\���グ�鎟��ł���v�i�k�\���R�l�j�Ə����Ă���B�Ȃ��A�k�|�p�͖łт�Ƃ��^���s�͉h����l�̊��ʂ́A���o�ł͔��k�L�̓�d�T�b�i〘�@〙�̗��[�����Ă���j�������B�@�@�@�@�@�k�P�}�b�N�X�E�G�����X�g FIAT MODES PEREAT ARS�W�Ɋā��Q�R�}�b�N�X�E�G�����X�g�Δʼn�W�Ɋāl
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1981�N11���Վ��������k13��14���l��Z�`��܃y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A110�s�B���o���ɐ߂̐����͂Ȃ��A��s�A�L�B�@�@�@�k�P�i�i�V�j���Q�R1�l
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1982�N12���Վ��������k14��13���l�`�O�Z�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A39�s�B4�s�߂���11�s�߂܂ŁA�q�f�z�r�i�sCURIEUX�\�\�����t�k�������l1978�N11���k4���l�A��y�[�W�j�S�s��ω��z���i�q�f�z�r���o�`���`�Ƃ��āA�q�H�v���r�{���Ƃ̈ٓ����L�����j�B�����̎��������͓̂�d�p�[������⦅�@⦆��������̌`�����A�V�t�gJIS�ł͕\���ł��Ȃ��̂ŁA���p�p�[�������ӂ��d�˂�((�@))�ő�p�����i�ȉ��A���j�B���̉Ă̏I���
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1982�N8��16���k38200���l�l�ʁA�{���V������1�{�G��3�i�g�A39�s�B���o�u�ʐ^�E���X�ؐ��a�v�B��雞�m�����ȁn�̚e����
���o�́s�C���t�k�������X�l1982�N4�����k1��4���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A2��80�s�B���o�W��u�Z�ʁv�B���o�����y�[�W�q���M�҈ꗗ�r�Ɂu�g�����i�悵�����@�݂̂�j�����N����B�����u�m���v�u�T�t�����E�݁v�v�Ƃ���B�@�@�@1
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1983�N1�����k26��1���l��l�`��܃y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A40�s�B���̎q�����܂ꂽ
���o�́s�C���t�k�������X�l1982�N10�����k1��10���l�ꔪ�`���y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A75�s�B���o�\���ɕW��E���M�Җ��ƂƂ��ɖ{����14�s�߂��f�ځi�ꔪ�y�[�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�l�̎�������ɂ܂����v�܂ŁA���s�ӏ����^�ŕ\�킷�Ǎ��\�L�j�B���o�����y�[�W�q���M�҈ꗗ�r�Ɂu�g�����i�悵�����@�݂̂�j�����N����B�����u�m���v�u�T�t�����E�݁v�v�Ƃ���B���̂Ƃ���Ă̍��~��
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1982�N7�����k14��7���l�l�Z�`�l��y�[�W�q�Ǔ������e���O�Y�r�A�{��9�|21�s1�i�g�A3��58�s�B���o�͒��L�u�����͂͐��e���O�Y�w���w�x��菴�o�����B�^�Ȃ����̌��ł��A���p�����u�͋�v������B�v�̂��ƂɁu�i��㔪��E�Z�E��Z�@�ʖ�̓��j�v�Ƃ���B�u2�v�̃q���[�^���E���b�E���E�����ނ��̎l��́A�P�̃S�`�b�N�̂��Q�R�ł͖����̂ɉ��߂�ꂽ�B�u2�v�̉��s�ӏ����^�Ŏ����A�P�́u����̐��E�͈�̗��h�ȉ��̏ے��̐��^�E�ł��邩��A�u�q���[�^���v�Ƃ������^�͂����ɂ����̂́u���b�m����n�v���悭�ے����^�Ă���悤�Ɏv����B����������͓��^�{�l�����ł����āA���{���m��Ȃ��l�^�ɂ͂��̉��͉����u���v�̂悤�Ȉ�ۂ��^�^���邩���m��Ȃ��B���Ƀt�����X��^�̃O���h�igourde�j=�Z�\=�̓t�����X����^�m��Ȃ��l�ɂ́A���̉��͂ނ���u�����ށ^���v���悭�ے�����Ǝv�������m��Ȃ��B�v���Q�R�̉��s�ӏ��ƈقȂ�A8�s�߈ȍ~��18���l���g�̎��Ԃ����Ă���B�@�@�@�@�@�Ǔ��E���e���O�Y�搶
���o�́s����t�k�W�p�Ёl1983�N1�����k5��1���l�`�O��y�[�W�A�{��10�|18�s1�i�g�A4��68�s�B�@�@�@1
���o�́s�������܁t�k�������܂̉�l1983�N2���k�~�E8���l��`�܃y�[�W�A�{���܍�15�s1�i�g�A51�s�B�ڎ��E�{���̏����́u�g�����v�B�n�\���ꂷ���
���o�́s�Ԑ_�t�k�Ԑ_�Ёl1983�N9���k�H�E3��3���l��`�O�y�[�W�A�{���܍�17�s1�i�g�A30�s�B�킽�����q���ł�������
���o�́s�����t�k����ь牮�l1983�N6���k�āE10���l��Z�`���y�[�W�A�{��12�|15�s1�i�g�A4��67�s�B���o�W��̑O�Ɂu�Ǔ����v�Ƃ���B�����̋����g�p�ƂЂ炪�Ȃ̝X�����̕����g�p�́A���̌f�ڎ��т����Ă��s�����t���̕ҏW���j���ƍl������̂ŁA��A�́k�P�i�����j���Q�R�i�V���j�l�Ɓk�P�i�X�����̕����j���Q�R�i�X�����̏����j�l�͖{�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�@�@�@�@�@�i���t��@���̒��莩��̖��傹��j�@�h���ɒj
���o�́s���j�ƎЉ�t�k���u���|�[�g�l1983�N5���k2���l��ܔ��`��Z�O�y�[�W�A�{��9�|18�s1�i�g�A4��72�s�B�@�@�@1
���o�́s�C�t�k�������_�Ёl1983�N6�����k15��6���l���`��܃y�[�W�A�{��9�|26�s1�i�g�A4��84�s�B�@�@�@1
�u�����낤�͏����y03�z�@�q����r����{�I�ɓV�c�L�̎��ł���B��s��͂����u��^��^��^���^���^���^���v�̃J���O�����͏��o�`�̕����Ռ��I�ŁA�s��ʁt���^�ł͑��̎���ɂ܂���Č��E����Ă���B���邢�́A�s��ʁt���^�ɂ��邱�ƂŏՌ���}�����Ƃ����ׂ����B�{�тɂ������ās��ʁt�́u��肪���m�ɂȁv�����悤�Ɏv����B�Ȃ���́u䱱���v�͒����Ñ�̒n���s�R�C�o�t�́q���R�o�r�Ɂu�x���o���C�k�c�c�l������䱱���i�x������������o�āA�k�c�c�l��̒���䱱���m���悤�����n�������j�v�ƌ����A�u�����m��Ԃ��ǂ�n�v�́q���R�o�r�q�k�R�o�r�ɓo�ꂷ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@���I�͂������čs���v
��̏�Ȃ����ނ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�����łЂƂ�̏��������Ђ˂���
�n��_
�C�i���i�̖��̂������ǂ���̈ł���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ȃ鋛�̂悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���ҁv��u���ҁv�����݂��Ƃ��ꂽ
�u�ԐړI�i��ԁj���E�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ���m�A�A�A�n��A�Ō`���������
��������
�@�@�@�@�@�u�����G�̂Ȃ��̒��v�ł��肦�Ă�
�@�@�@�@�@�u�����G�̂Ȃ��̏��v�ł���Ƃ͂�����Ȃ�
�e�[�u���̒[�Ƀ��[�\�N��R�₵
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���A����H�ׂ鏗�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r��Ԃ鍰�̒j�͗҂���
��̐Ώ��̏���͂��܂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�˂��݉ԉ͏����c�c�v
�w��ʁx�ɂ����錾�ꓹ�f�̌��t�U��B���̉��͂́w��ʁx�S�т��т��B�������A�w��ʁx�����̎��т��ׂĂ����݂݂���悤�Ȍ`�Ŕ��\���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B�g���������w��ʁx�ɂ�����K�i��̘A���`���̗p�����͈̂�㔪��N�O���̂��ƂƐ��肳��邪�A�����ł͈�㔪��N�Ă̕ʍ��u���z�v���Ɍf�ڂ��ꂽ���o�u�e�G�v���Љ�����Ǝv���B�w��ʁx�ɂ�����u�e�G�v����e�Ɣ�r���āA���̕ϗe���m�F���Ă������������B�i�s����D�t��6���q�g�������W�r�A1984�N7��1���A�l�l�y�[�W�j�O�f�Z�قŁu���̕ϗe���m�F���v���킯�����A�ʏ�̎���̎����ɉ����Ď������ɂ��ύX���{����Ă��āA�C���̑S�e�͗e�Ղɂ��݂������i���o�Ŏ���̖�����20���l�̃��C���ɐڂ���s���܂����邪�A���ꂪ���e�i�K�̂��̂��A�g�Ŏ��̍Z���ɂ����ς����߂������j�B�g���̏C���̂����A����̒�������ԂŁA����̈ʒu�w��i���������̈ړ��j��ōČ����āA���o�`�i�̍Ę^�j�ւ̎������摜�Ōf����B

| �W�� | ���\�� | �ߐ� | �s�� | �� |
| 雞�i�J�E1�j | �y01�z | 39 | 69 | |
| �G�̐��i�J�E2�j | �y02�z | 35 | 62 | |
| �� ��i�J�E7�j | �y03�z | 110 | 194 | |
| �NJ|�i�J�E5�j | �y04�z | 24 | 42 | |
| �� �}�сi�J�E4�j | �y05�z | 4 | 114 | 201 |
| �� �ʁi�J�E10�j | �y06�z | 2 | 80 | 141 |
| �e�G�i�J�E3�j | �y07�z | 23 | 40 | |
| �� �́i�J�E13�j | �y08�z | 3 | 58 | 102 |
| �V���i�J�E9�j | �y09�z | 39 | 69 | |
| �� �����i�J�E12�j | �y10�z | 75 | 132 | |
| �s���i�J�E6�j | �y11�z | 31 | 55 | |
| �H�v���i�J�E8�j | �y12�z | 39 | 69 | |
| �t�v���i�J�E11�j | �y13�z | 40 | 70 | |
| �� �I�i�J�E14�j | �y14�z | 4 | 68 | 120 |
| �����i�J�E15�j | �y15�z | 51 | 90 | |
| �H ���i�J�E18�j | �y16�z | 4 | 72 | 127 |
| �� �C�g�i�J�E19�j | �y17�z | 4 | 84 | 148 |
| �� ��i�J�E17�j | �y18�z | 4 | 67 | 118 |
| ����i�J�E16�j | �y19�z | 30 | 53 | |
| ���v | 1079 | |||
| ���� | 56.8 | 100 |
| �W��i�f�ڏ��j | ���\�� | �ߐ� | �s�� | �� |
| 雞�i�J�E1�j | �y01�z | 40 | 70 | |
| �G�̐��i�J�E2�j | �y02�z | 35 | 61 | |
| �e�G�i�J�E3�j | �y07�z | 24 | 42 | |
| �� �}�сi�J�E4�j | �y05�z | 4 | 116 | 202 |
| �NJ|�i�J�E5�j | �y04�z | 24 | 42 | |
| �s���i�J�E6�j | �y11�z | 33 | 58 | |
| �� ��i�J�E7�j | �y03�z | 8 | 112 | 195 |
| �H�v���i�J�E8�j | �y12�z | 39 | 68 | |
| �V���i�J�E9�j | �y09�z | 39 | 68 | |
| �� �ʁi�J�E10�j | �y06�z | 2 | 80 | 140 |
| �t�v���i�J�E11�j | �y13�z | 41 | 72 | |
| �� �����i�J�E12�j | �y10�z | 75 | 131 | |
| �� �́i�J�E13�j | �y08�z | 3 | 58 | 101 |
| �� �I�i�J�E14�j | �y14�z | 4 | 68 | 119 |
| �����i�J�E15�j | �y15�z | 51 | 89 | |
| ����i�J�E16�j | �y19�z | 30 | 52 | |
| �� ��i�J�E17�j | �y18�z | 4 | 67 | 117 |
| �H ���i�J�E18�j | �y16�z | 4 | 72 | 126 |
| �� �C�g�i�J�E19�j | �y17�z | 4 | 84 | 147 |
| ���v | 1088 | |||
| ���� | 57.3 | 100 |
| 雞 | �u�����V���v��㔪��N�ꌎ�O���i����A����u�ɂ�Ƃ�v�j |
| �G�̐� | �u���㎍�蒟�v��㔪��N�㌎�� |
| �e�G | �k�u���z�v�ʍ������z�V���[�Y�u�Ă̏��v�l��㔪��N�k�č����܌��l |
| �}�� | �u���{�o�ϐV���v��㔪��N�O�������A��l���A�����A���i����A����u�t�̓`���v�j |
| �NJ| | ��|�Εv�W�ē���E�؉�L�E��㔪��N�O���� |
| �s�� | �}�b�N�X�E�G�����X�g�Δʼn�W�p���t���b�g�E���J��L�E��㔪��N��k�i�i�V�j�������l |
| ���� | �u�����C�J�v�k�ʍ����Ց��l���㎍�̎����E��㔪��N��ꌎ |
| �H�v�� | �u�����C�J�v�k�ʍ����Ց��l���㎍�̎����E��㔪��N��� |
| �V�� | �u�����V���v��㔪��N������Z���[�� |
| ��� | �u�C���v��㔪��N�l���� |
| �t�v�� | �u���㎍�蒟�v��㔪�O�N�ꌎ�� |
| ������ | �u�C���v��㔪��N�k�と��Z�l���� |
| ���� | �u�����C�J�v��㔪��N������ |
| �ØI | �u����v��㔪�O�N�ꌎ�� |
| ���� | �u�������܁v��㔪�O�N�k������A�~���l |
| ���� | �u�Ԑ_�v��㔪�O�N�k�i�i�V�j���㌎�A�l�H�� |
| ���� | �u�����v��㔪�O�N�k�āA���Z���A�āE�l���Z�� |
| �H�� | �u���j�ƎЉ�v��㔪�O�N�k�t�A���܌��A��l�� |
| �C�g | �u�C�v��㔪�O�N�k�܁��Z�l���� |
�k2019�N1��31���NjL�l
2019�N1���A���t�I�N�I�ɋg�����̍����N�父�n�K�L�i1980�N12��16���k18�]24�l�a�J�Ǐ���j���o�i���ꂽ�B�肵�āq�g���� �����M���M �^�M �t���������N�� �����w�E���{���X�x�������͕挊�ɂ܂������ē�Y�����遟�w�m���xH������l���x�P�b�g�r�B�c�O�Ȃ��狣�藎�Ƃ����Ƃ��ł��Ȃ��������A���сq雞�r�̐����ɂ������d�v�ȏ،����܂ޓ��e�Ȃ̂ŁA�����̎ʐ^���f���A�g�������������ʂ��N�����Ă݂�B
![�����N�父�g�������ȁi1980�N12��16���k18�]24�l�a�J�Ǐ���n�K�L�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l](image/ymshokan_takahashi_niwatori_1.jpg)
�����N�父�g�������ȁi1980�N12��16���k18�]24�l�a�J�Ǐ���n�K�L�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l
���킽�������N�̐��A���������������ł����B�ߓ�
�͐V���s�E���{���X�t���A���肪�Ƃ������܂��B
���āA���������V�������O���i�H�j�̂��߂̎���
�������Ă��܂����A�x�P�b�g�̎���̈�s���ؗp
�������܂����B�u�������͕挊�ɂ܂������ē�Y
������v�Ɋ����������߂ł��B���p�̒���
�t���k�����́��悤�Ǝv�����́l�ł����A�u�Î��L�v�u���}�сv�̈�s��
�g���Ă���A����k�i�i�V�j����l������ƁA�����m�A�A�n�ɂȂ�
�̂ŁA�k�i�i�V�j�����ׂāl��߂܂����B���k�����ȁl���̂قǁA���肢����
���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�ܓ��@�@�@��
���̔N��11���ɏo�������̐V���s�E���{���X�t�i�����Ёj�́A�g�����Ɍ��y�����q�z���͂����ʂƂ��r��q�I��Ɏn�߂���r���܂ށB��f�����́k���i�������ꂽ���̎����킩��Ȃ��j���ȁl�ȊO�̐����o���͍s�Ԃɏ�����Ă���A��x�i�Ō�܂Łj���������ƁA�����ꂽ���̂Ǝv�����B���͖{�e�q�g�������W�s��ʁt�{���Z�فr��2011�N2���ɔ��\�������ƁA�s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�i���Y��ԁA2013�N9��28���j�́q�u����g�����v�\�\�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t�r�̏͂ŁA�s��ʁt�̊������сq雞�r�i�J�E1�j�Ɗ������сq�C�g�r�i�J�E19�j�ɂ��ď����Ă���B�O�҂̈�߂��A���̒����ƈ����B
�@���̈��p�u�퐢�̒������W�߂Ė����߂�v�́s�Î��L�t�̓V�̊≮�ː_�b�ɂ���u�퐢�̒������W�߂Ė����߂āv���痈�Ă���B�������A�g�������M���ɐڂ����̂́s�Î��L�t���̂��̂ł͂Ȃ��A����F��s�\��x�l�t�́q�{�Ɋւ���`���r��������������Ȃ��B�����ɂ́u�j���c�g���܂��j���g���͒�Ɏ�������̖����B�k�c�c�l�u�_�㊪�v��w�Î��L�x�ɁA�V�Ƒ�_����Ă�̎��A���S���̐_�A�퐢�̒������ڂߌ݂��ɒ������߂��ƌ���B�{���钷�H���A�퐢�̒����Ƃ͌{�������B�v�i���S�j�Ƃ���B�{�т̔��\�}�̂͑S�����̐V�N���������|���ŁA�g���̎��A�g�s�~�V��Ɖ͖쑽�b�q�̐��z�Ƃ�����肠�킹�������B�g���ɑ��ď\��x�̎����A�Ƃ����˗����������͕s�������A�єN�ɂ��Ȃ�Ńj���g���̎���ݒ肵�����_�ŁA�s�\��x�l�t�̏����͔��Ζ��ꂽ�悤�Ȃ��̂ł���B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@���̈��p�u�j�����͉����Ő���Ă���v�͉i������̃t���C�U�[�s�����ٌ̕�l�t�́u�j�����������̑����U�߂ɂ����Ă���Ƃ��A�Ȃ͂����Ɏc���Ă���j�Ɗ��ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B�v�i���U�j�ɂ�낤�B
�@��O�̈��p�u�������͕挊�ɂ܂������ē�Y������v�̓x�P�b�g�̋Y�ȁs�S�h�[��҂��Ȃ���t�̃|�b�c�H�̑䎌�u�ǂ����A�������͕�ɂ܂������Ă��Y�����Ă���悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A�v�ƃE���W�[�~���̑䎌�u��ɂ܂������Ă̓�Y�B�v�i���V�j�ɂ��B
�@�\��x�ɂ��Ȃ�i�Ɍ�����s�Î��L�t���邢�͓���F��ƃt���C�U�[�ƃx�P�b�g�B�����������ꂪ�g�������ɂ����邱�̑g�݂��킹��\�z�������낤�B�����قǂ��̖G�肪�s�T�t�����E�݁t�Ɍ�����ƌ��������A����͂��Ƃ̈��ł���\�\�x�P�b�g�́q�����`�r�i�H�E10�j�ɂ��̖��𒐋L�̂����A�͋�������ꂽ���\�\�A�s��ʁt��s���[���h���b�v�t�������ꂽ���Ƃ����炻��������̂ł����āA���Ȃ��Ƃ���㔪�Z�N�̎��_�ł����\���ł����̂́A���̋g�����܂߂Ă���ЂƂ肢�Ȃ������B
�i���S�j����F��s�\��x�l�t�̈��p�́s�\��x�l�i���j�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1994�N1��17���j�A���l�y�[�W�ɂ�������A�U�艼���͏ȗ������B�g�����{���ɐG�ꂽ�Ƃ���A�ёq�ƕ��Z���s�\��x�l�i�P�`�R�j�k���m���Ɂl�t�i���}�ЁA1972�`73�j���낤�B
�k�c�c�l
�i���U�j�i�E�f�E�t���[�U�[�i�i������j�s�����ٌ̕�l�t�i�s���E���{�S�W�k19�l�t�A���}�ЁA1962�N12��24���j�A�l�Z�Z�y�[�W�B�s�����ٌ̕�l�tThe Devil's Advocate�́A�͂��߁s�T�C�L�X�E�^�X�N�tPsyke's Task�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B�s�T�C�L�X�E�^�X�N�\�\���M�ƎЉ�x�t�̊�g���ɔł�1939�N6��15���������A�����̋g�����V���œǂL�^�͂Ȃ��B
�i���V�j�����M��E�����N�狤��s�x�P�b�g�Y�ȑS�W�k�P�l�t�i�����ЁA1967�N10��20���j�A�ꔪ��A�ꔪ�O�y�[�W�B
�Ȃ��Ȃ��Ƌ��e���������̂́A���������������E���E��O�̈��p�̏o�T���ꉞ�͐��������Ƃ����������������炾�B����ɂ��Ă��A���p�ɒ���t���Ȃ��Ƃ����g���̏q���́A���M�ɒl����i�̂��ɂ͕t����ꍇ���������j�B��s���鑼�҂̕��������тɈ����āA���������̃X���X�𖾂����Ȃ��̂́A���т̓��ۂ��߂̑�_�Ȑ헪�ł���B�u���p�̒���t���v�āu����������ƁA�����m�A�A�n�ɂȂ�̂Łv�u��߂܂����v�ƍ����ɘR�炵�Ă���̂́A�g���Ȃ�́i��㵂ɏ[�����j���g�̕��@�̊J���ł͂Ȃ��������B����ɂĂ��A����͏d�v�ȏ،��������B���o�q�ɂ�Ƃ�r�i�s�����V���t1981�N1��3���j�́A���^������N�́u�s��ʁt���^�v�ł͂Ȃ��V�c�L�̍s�����������A�s�Î��L�t��s���}�сt����̈��p�ƓT���̕��@���̗p�����A�����Ȃ�ΌÐF��тт����_�j�Y�����̑��삾�����B��������A�g�����́u����v���n�܂�B
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�ɖ����^�́q�G�̂Ȃ��̏��r�Ƒ肷��18�s�̖������т������B�f�ڎ��͈ꖇ��㉔��s�́s�ʍ��ꖇ��㉁t��4���q�Ԓ������̐��E�\�\�V��^�m��E���{��I�r�i1981�N10��1���j�ŁA�ڎ��́u��l�́@���v�ɂ́u�q���r�g�����@�J��r���Y�v�Ƒ薼�����ō�Җ������ڂ��Ă��Ȃ��i�J���i�́q�����ЂƂ̂����r�j�B�ڎ��̍��݂��������C�A�E�g����l�����E�������̂́A�������������܂��i�C���^�[�l�b�g�̌Ï����Ŗ{���̑��݂�m��A�g�������̍Ę^�ł��邱�Ƃ��o��̂����A�s���_�Œ��������Ƃ��떢�����т������̂ɂ͋������j�B�e�y�[�W�ɂ͔Еz�����G��Ǝ��̋�i�V�삨��ѕ��̎҂̊����\��i�̈��p�j����肠�킳��Ă��āA�q�G�̂Ȃ��̏��r�̒��L�ɂ́u�{���̂��߂̏������낵�^���悵���� �݂̂�i�����\�@�j�����@���l�@�g���܁@�������܁@��㎍�̌|�p�����`�I�Ȏ��̕s�C���Ȗ��͂���������B�V���[�����A���X���̊G��̔������ɋ߂��ʔ����̂����сB�v�i�������j�Ƃ���A���т̏㕔�Ɂu���c�p���Y�@�������@�U���@���G�v���J���[�Ōf�ڂ���Ă���B�q�Ԓ������̐��E�r�S�̂̍\�����猩�āA�g�����̎��ƌ��c�p���Y�i1920-�@�j�̊G�̎�肠�킹�ɕK�R��������Ƃ͎v���Ȃ��B���Ȃ킿�A�g�������c�̊G�����Ď����������킯�ł��A���c���g���̎���ǂ�ŊG��`�����킯�ł��Ȃ��A�ҏW�҂̎�ɂ���ė��҂������y�[�W�ɔz���ꂽ�̂ɂ����܂��B���q�◇�w�ӂƂ��錷�c�̊G���̂������킯�ł͂Ȃ����A���L�́u�V���[�����A���X���̊G��̔������ɋ߂��ʔ����̂����сv�Ƃ͂����͂Ȃꂽ�敗�ƌ��킴������Ȃ��B�����Ƃ��A�g�����̍D�ފG��Ƌg�����̎�������v����Ƃ͌���Ȃ��B�g���́s�ꖇ��㉁t1982�N5�����́q���i�̂���G�b�Z�C�r�ɐ��z�q�@�B�u�e���}�v�r���Ă��āi���̍��̓����̑��̒��҂͕��c�����E�Ί_���E�R�c����E�{�e�r�O�j�A������́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�Ɏ��^����Ă���B

�G�̂Ȃ��̏��b�g����
�u�����낤�͏���
���I�͂������čs���v
��̏�Ȃ����ނ�
�����łЂƂ�̏��������Ђ˂���
�n��_
�C�i���i�̖��̂������ǂ���̈ł���
�����Ȃ鋛�̂悤��
�u���ҁv��u���ҁv�����݂��Ƃ��ꂽ
�u�ԐړI�i��ԁj���E�v
�ɂ���m�A�A�A�n��A�Ō`���������
��������
�u�����G�̂Ȃ��̒��v�ł��肦�Ă�
�u�����G�̂Ȃ��̏��v�ł���Ƃ͂�����Ȃ�
�e�[�u���̒[�Ƀ��[�\�N��R�₵
�h���A����H�ׂ鏗�����
�r��Ԃ鍰�̒j�͗҂���
��̐Ώ��̏���͂��܂���
�u�˂��݉ԉ͏����c�c�v
�q�G�̂Ȃ��̏��r���\��1981�N�A�x�M�����̋g����1���Ɂq雞�r�i�J�E1�j�A9���Ɂq�G�̐��r�i�J�E2�j�A11���Ɂq����r�i�J�E7�j�Ƃ����A�̂��́s��ʁt���\�����鎍�т\���͂��߂Ă���B�������{�т͂����Ɠ��l�A�s��ʁt���^�ł͂Ȃ��A���^��\�L�́s�Ẳ��t�i1979�j�ɍł��߂��B�܂��A�ȑO��Ȍ�̎��тƂ̗ގ����������킹�鎍�傪�U������_�ŁA1981�N���\�̑���3�тƂ͑傫���قȂ�B�e����Ƌ߂���������c�c�ɑ����Čf���A�o�T���L���i�s��ʁt���^�̎������͏ȗ������j�B
�u�����낤�͏����c�c�i�����낤�͏����i�q�k�H��l��r�K�E19�A72�s�j
���I�͂������čs���v�c�c�ւ͂������Ă䂭�j�i���O�A73�s�j
��̏�Ȃ����ނ�c�c��̏�Ȃ����ނ�Ɂc�c�B�i���O�A74�s�j
�����łЂƂ�̏��������Ђ˂����c�c�ЂƂ�̏��������Ђ˂����i�q�����q杁r�K�E4�A70�s�j
�n��_�c�c���ɂ����̒n��_���i�q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�G�E31�A111�s�j
�C�i���i�̖��̂������ǂ���̈ł���c�c�C�i���i�@�C�V���^���@���B�[�i�X�i���O�A133�s�j�A�i��j�̂������ǂ���́^�i�[���j���i�q�����q杁r�K�E4�A2-3�s�j
�����Ȃ鋛�̂悤�Ɂc�c�����ȓ����������i�q�Ẳ��r�H�E20�A43�s�j
�u���ҁv��u���ҁv�����݂��Ƃ��ꂽ�c�c�i���ҁj���^�i���ҁj���^�Y�݂��Ƃ����i�q�����q杁r�K�E4�A72-74�s�j
�u�ԐړI�i��ԁj���E�v�c�c�u�ԐړI�Ȑ��E�v�i�q�Ẳ��r�H�E20�A39�s�j
�ɂ���m�A�A�A�n��A�Ō`���������c�c�k�ɂ���l�Ɓk�A���l�𗁂тāi�q�k�H��l��r�K�E19�A65�s�j
��������
�u�����G�̂Ȃ��̒��v�ł��肦�Ă��c�c�G�̂Ȃ��̔n����������ށi�q�O�d�t�r�F�E17�A33�s�j
�u�����G�̂Ȃ��̏��v�ł���Ƃ͂�����Ȃ��c�c�킽���̊G�̂Ȃ��̐X�̓��ցi���O�A45�s�j
�e�[�u���̒[�Ƀ��[�\�N��R�₵�c�c���[�\�N�����Ă��e�[�u���Ɂi�q�Ẳ��r�H�E20�A40�s�j
�h���A����H�ׂ鏗������c�c�l�N�^�����̎��́i���O�A41�s�j
�r��Ԃ鍰�̒j�͗҂����c�c�킽���̍r�Ԃ鍰�新��i�q�r�́r�H�E23�A31�s�j
��̐Ώ��̏���͂��܂��c�c���l�͒n���͂��܂��i�q����r�J�E7�A75�s�j
�u�˂��݉ԉ͏����c�c�v�c�c�u�˂��݉ԉ������܂��^�S���������܂��v�i�q����杁r�H�E17�A7-8�s�j
�q�G�̂Ȃ��̏��r���\�O�̎��тɁq�O�d�t�r�i�F�E17�j�A�q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�i�G�E31�j�A�q����杁r�i�H�E17�j�A�q�Ẳ��r�i�H�E20�j�A�q�r�́r�i�H�E23�j�A�قړ������ɔ��\���ꂽ���тɁq����r�i�J�E7�j�A���\��̎��тɁq�����q杁r�i�K�E4�j�A�q�k�H��l��r�i�K�E19�j������B��O�O���[�v�̎��тƖ{�т̊W�͂킩��₷���B�g���̏ꍇ�A�V���Ɏ��������Ȃ��玍��ɋl�܂����Ƃ��A�ߋ��̎���̈�߂�q���邱�Ƃ͂܂܂������B�q�H�v���r�i�J�E8�j�ɕω��z�����ꂽ�q�f�z�r�i�sCURIEUX�\�\�����t4���A1978�N11���j�Ȃǂ�����ŁA�q�f�z�r�͎��W�Ɏ��^���ꂸ�A�V���Ȏ��q�H�v���r�̎̐ƂȂ����B���l�Ɂq�G�̂Ȃ��̏��r����q�k�H��l��r�����܂�A�O�҂͌�҂̎̐ƂȂ����B����͂����B�����A�u���[�\�N�����Ă��e�[�u���Ɂ^�l�N�^�����̎��́v�i�q�Ẳ��r�j�Ɓu�e�[�u���̒[�Ƀ��[�\�N��R�₵�^�h���A����H�ׂ鏗������v�i�q�G�̂Ȃ��̏��r�j�̊W�͂ǂ��l�����炢���̂��B����������I�ɉ��߂���ɂ́A�q�G�̂Ȃ��̏��r�̑S����͔��\���ꂽ1981�N�ɏ������낳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�u�G�̂Ȃ��̏��v�Ƃ����e�[�}�ɍ��v����������q�Ẳ��r�̎̐ƂȂ������т̏��āi�������͒�e�ɂ�����r���̏�ԁj��������ʂ������̂������A�Ƃł�����ȊO�Ȃ��B�ނ��A����͑z���ł���B�������A�q�G�̂Ȃ��̏��r���s��ʁt�i1983�j�Ɏ��^����Ȃ������͎̂����ł���A���̖`����3�s���g�����Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�̊������сq�k�H��l��r�̍Ō�̎��s�u�i�����낤�͏����^�ւ͂������Ă䂭�j�^��̏�Ȃ����ނ�Ɂc�c�B�v�ɍĐ��������Ƃ��A�܂������ł���B�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j����ŔӔN�̋g�������܂Ł\�\�u����g�������v�̑S����܂ށ\�\�����h���ɂ��郂�U�C�N�͗l�̈�сB�q�G�̂Ȃ��̏��r�������]���Ă݂����B
�g���������W�s�|�[���E�N���[�̐H��t��1980�N5��9���ɎR�c�k��̏���R�c����850������Ŋ��s���ꂽ�i6��9����800�����s���ꂽ�u�ĔŁv�̔��s�҂͗�؈ꖯ�j�B1957�N����1980�N�܂łɔ��\���ꂽ�E�⎍��21��i�����߂�B�{�e�ł́A�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���E���Ќf�ڌ`�A�Q �s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j�f�ڌ`�A�R�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����R�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B�Ȃ��A�������V���̖{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs�|�[���E�N���[�̐H��t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�F�����炭�z�q�v�l�̎�ɂȂ鎍�W�f�ڗp���e���e�ƂƂ���2010�N12���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������B���т̐ߔԍ��̃��[�}��������уA�X�e���X�N�̈ʒu�i�������j�͍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������i�s�h���̓��[�}�����E�A�X�e���X�N�Ƃ��s�g�����S���W�t�ł͓�s���������A������Z�ق̑ΏۊO�Ƃ����j�B�s�g�����S���W�t�Ő���N����u1959�`1980�v�ƋL���Ă���̂́A�ȉ��̋L�ڂ�������炩�Ȃ悤�ɁA�u1957�`1980�v���������B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�P ���o�G���E�V���E���ЁF�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B�{���̕\���͊�{�I�ɐV���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�Ȃ̂ŁA���L�Ȃ��ꍇ�͂����\�킷�B
�Q �s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A���ł�1980�N5��9���k�Z�ق̒�{�ɂ͍ŏI�����{�ł���1980�N6��9�����s�́u�ĔŁv���g�p�����l�j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍��k�U�����^�̕����ł�19���l��20���l�l10�s1�i�g�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|�k�U�����^�̕����ł�19���l��20���l�l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q �s�|�[���E�N���[�̐H��t�B
�s�|�[���E�N���[�̐H��t���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s�������t�k���s�����l�f�ڔN�����i���j�k�i���j���l�j
�|�[���E�N���[�̐H���i�I�E1�A37�s�A�s���㎍�t�k�Ώ��[�l1957�N5�����k4��4���l�j
�T�[�J�X�i�I�E2�A45�s�A�s������`�t�k���z�Ёl1958�N9���k15���l�j
���C���b�N�E�K�[�f���i�I�E3�A40�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1958�N12���k10���l�j
�����i�I�E4�A17�s�A�s�����V���t�k�����V�������{�Ёl1959�N7��26���k26404���l�j
����i�I�E5�A11�s���A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1959�N9��28���k29776���l�j
���L�i�I�E6�A30�s�A�s���w�t�k���w�Ёl1960�N1�����k15��1���l�j
���i�I�E7�A13�s�A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1961�N10��5���k30512���l�j
�ӏt�i�I�E8�A4�s�A�s�����ԗ����t�k�����ؓ���l1962�N6�����k26���l�j
���Ƒ��ׂ݂̊��i�I�E9�A22�s�A�s�Ԓցt�k�������o�ŕ��l1962�N6���k7�����E13��6���l�j
�㌎�i�I�E10�A23�s�A�s�k�C���V���k�[���l�t�k�k�C���V���Ёl1964�N9��7���k7930���l�j
�Ƒ��i�I�E11�A10�s�A�s���Y�t�H�t�k���Y�t�H�l1966�N3�����k44��3���l�j
�t�̊G�i�I�E12�A13�s�A�s��̐V���t�k�ǔ��V���Ёl1967�N2��5���k32455���l�j
�X�C�J�E���o�I�ȉ��i�I�E13�A15�s�A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1968�N8��19���k33015���l�j
�ԁE�ό`�i�I�E14�A�U��18�s�A�s�����ȑ����t�k�����o�ŕ��l1966�N5���k53���l�j
翉��i�I�E15�A26�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�l1969�N12�����k23��12���l�j
�I�s�i�I�E16�A18�s�A�s���t�k���{��ʌ��Ёl1977�N8�����k51��8���l�j
�e�̋��i�I�E17�A11�s�A�R�{���q��I�t�Z�b�g�ʼn�W�Q�s�⋾�\�\MIRRORING�t�k�A�g���G�R�{���l1976�N12��5���j
���k�i�I�E18�A5�s�A�q�ЎR���W�r�p���t���b�g�k������Ɂl1979�N9��10���j
�l�H�ԉ��i�I�E19�A�����4�߂ɕ�����40�s���A����O�l�W�L�O�sALICE IN FLOWERLAND�\�\�Ԃ̍��̃A���X�t�k���������R�����l1976�N2��4���j
���i�I�E20�A20�s�A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1980�N1��25���k37177���l�j
�c�O�~�i�I�E21�A29�s�A�s���t�k�����s���l1980�N3�����k100���l�j
�ǓƂȐS�ɂȂ��݂̕������o�́s���㎍�t�k�Ώ��[�l1957�N5�����k4��4���l���y�[�W�A�{��9�|23�s2�i�g�A37�s�B
�����ȊX�ɂ͏����ȉΎ����������o�́s������`�t�k���z�Ёl1958�N9���k15���l�O�Z�`�O�O�y�[�W�A�{���܍�12�s1�i�g�A45�s�B���M�Җ��̌�Ɂu�����N�����ɐ���B�}�����[�Ζ��B���W�w�Õ��x�B�v�Ƃ���B
�@�@�@�k�P�o���[�q���C���c�N�E�K�[�f���r��聨�Q�R�i�g���j�l���o�́s�����t�k���惆���C�J�l1958�N12���k10���l�ꔪ�y�[�W�A�{��8�|23�s2�i�g�A40�s�B
�j�͕s���Ȃ��̂����������o�́s�����V���t�k�����V�������{�Ёl1959�N7��26���k26404���l�ꎵ�ʁA�{���V��������{�G���A17�s�B���o�W��u�q�́v�A���o�u���@���H�m�݂Ȃ݂������n��m�͂��߁n�v�B�{���̌�Ɂu�i�u�����v���l�j�v�Ƃ���B
�ꂪ���邤�����������N�́@����ӂ����܂܁@�����鋛�̌��ց@�牺���Ƃ����߂���@���͕����l��̓��������k�P�i�x�^�j���Q�R�i�S�p�A�L�j�l�M�̏�ʼn��ȏ����̗̔����k�P�����Q�R���l���@���L������Ȃ���@���łɘX�̌������������@��K�őg���Ă��V�̂֒u���@�����̉Ƒ��̂��т������@�Ẳʕ��̂Ȃ��̎�q�����V����@�ނ炪���m�̌���������邽�߂ɂ́@�ꂢ�S�Ő���̉^�������肩�����˂Ȃ�ʁ@���̑̌n�������ł܂����o�́s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1959�N9��28���k29776���l�l�ʁq���ƃf�b�T���r�A�{���V��������{�G��19���l1�i�g�A10�s���B���o�u���@���R�m����܁n�����m�܂������n�v�B
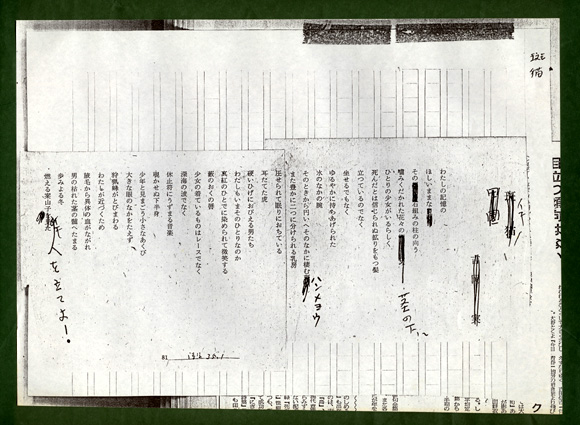
���сq���L�r���o�`�ւ̋g�����̎����k�g���Ƒ��X�N���b�v�u�b�N�̃��m�N���R�s�[�l
�킽���̋L�������o�́s���w�t�k���w�Ёl1960�N1�����k15��1���l����y�[�W�A�{��9�|18�s2�i�g�A30�s�i�q���сq���L�r�̎����e�r�Q�Ɓj�B
�ē��}���������o�́s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1961�N10��5���k30512���l�ܖʁA�{���V��������{�G��1�i�g�A13�s�A����l�Y�q���㎍�̂킩��ɂ����\�\����͐��_�����̗���ƂƂ��ɂ���r�̕����Ɍr�݂͂Ōf�ځB
���o�́s�����ԗ����t�k�����ؓ���l1962�N6�����k26���l��y�[�W�q�l�s���r�A�{��16���S�`�b�N1�i�g�A4�s�B���o�u�G�E�x���K���v�A���o���q�����̂��Ƃ����r�k�������l��t���B
�����̂��Ƃ���
�Ȃ������A�Ȃɂ�����A�Y�܂����B�l�X�͎��X����Ȍo��������B�����ōl���Ă��悭�킩��Ȃ��B�������A�����̂Ƃǂ��Ȃ������̂��̂łȂ藧���Ă���̂��A�l�ԁA���Ƃɕ��G�Ȍ���́A�l�Ԃ��B���̗����̒�ɉ����Â��ĉ��[�����E�A�����֒��ς̃]���f��X�������̂��A���㎍�̖����̈���B���̎��ɂ͔ӏt�̔Y�܂������G���e�B�b�N�Ȑ������̂Ƃ��Č����ɐ����ǂ肳��Ă���B
���l�g�����́A�Ɠ��ȓ�̓����I���\�͂ƒ��ϗ͂Ō���̍Ő[���̃h���}�^���钴������`�I���l�̑��l�ҁB�g��ҁB����x���K���́A����l�̐S�ە��i���_��Ő������ꂽ���̃J���o�X�̏�ŝR��钨�B�ȍ앗�̑�����ƁB�u������v�����B
�ڂ��͐Ԗʂ���
���ɂʂꂽ���Ƃ̂Ȃ��k�P�����Q壁��R�u�l�F�̌����̂ڂ�Ƃ�
�Â��b�����ׂ��čs���@�ڂ��̉ԉł̌�p�����Ȃ���
����̑��֖߂肽�����Ă���g��������
���o�́s�Ԓցt�k�������o�ŕ��l1962�N6���k7�����E13��6���l�܃y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A22�s�B���o�u��E�e�c�a�v�B
�J��̎�{
�t����Ăɂ�����
������陂���j�����̒�����
�ڂ������a�l�̂ЂƂ�̏������~���Ƃ�
�^�����Ȃ����ԂƓ����̓�
�����̂ڂ��Ȃ�����
�ڂ������������̂Ƃ�
�c���̔��������ƐM����
�s�ł̕s�K�E�s�ł̈�
�������ʉ��̔w�i
����͐��̉��Ō��̂悤�ɍ���
�ЂƂ̑�q����n���̎��͂܂�
�����ɕ��k�P�����Q�R���l�Ă���
���܂ڂ��ɖ{���̗���߂���
������C�a�̂ЂƂł��^�g�ɋP���Ƃ�
�ڂ��̋L���̍Ȃ͊D�F�̒����Ȃ̕z�Ƃ��Ă����
�����̂Ђ߂₩�Ȃ�����
���肩����������x�сk�P�I���Q�R�i�g���j�l
����͂ڂ������K�N�F�̖�
�Y�܂�������̗⊴�̂�����
�����̋r�������������Ƃ��Ƃ�
�@���I�ȉ��Ƒ��ׂ݂̊�
��I�����������o�́s�k�C���V���k�[���l�t�k�k�C���V���Ёl1964�N9��7���k7930���l�ܖʁA�{���V��������{�G��1�i�g�A23�s�B���M�Җ��̌�Ɂu�i���㎍�l�����j�Ƃ���B���o�u���@�c�Ȏi�N�m�����낵�낤�n�v�B
�ڂ��͐��܂�����o�́s���Y�t�H�t�k���Y�t�H�l1966�N3�����k44��3���l�����y�[�W�A�{��8�|1�i�g�k�R�����l�A10�s�B��Җ��́u�g�����v�B
���k�P�m�Ȃ��n���Q�R�i�g���j�l�̔������o�́s��̐V���t�k�ǔ��V���Ёl1967�N2��5���k32455���l�ꔪ�ʁA�{��7.5�|1�i�g�A13�s�B�{���̌�Ɂu�吳���N�������܂�A�}�����[������B���a�O�\�l�N���W�u�m���v�ő���g����܁B���{���㎍�l����A�k�̉�l�B�v�Ƃ���B
�X�C�J���������o�́s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1968�N8��19���k33015���l���ʁq�����̂����r�A�{���V��������{�G��1�i�g�A15�s�B���o�u�ʐ^�E���{���U�L�ҁv�B
�@�@�@�T���o�́s�����ȑ����t�k�����o�ŕ��l1966�N5���k53���l�O��y�[�W�A�{��9�|�k�����F�S�`�b�N�A���ȁE�J�i�F�A���`�b�N�l11�s2�i�g�A�U��18�s�B
�킽���̍D���ȏ퓅��k�P�̈��p���Q�R�i�g���j�l���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�l1969�N12�����k23��12���l��y�[�W�A�{��9�|13�s2�i�g�A26�s�B���o�W��u�w�A�[�v�B�J�b�g����B
�ӓ��̂悤�����o�́s���t�k���{��ʌ��Ёl1977�N8�����k51��8���l��l�Z�y�[�W�q�����̎��r�A�{��20���S�`�b�N1�i�g�A18�s�B���o�ʐ^�L���v�V�����u���[���i����j'76�u���v�ʐ^�R���e�X�g�ŗD�G��i�@�J�����@�O☐����v�B
�ϔO���܂��邽�߂����o�͎R�{���q��I�t�Z�b�g�ʼn�W�Q�s�⋾�\�\MIRRORING�t�k�A�g���G�R�{���l1976�N12��5���A�Z�y�[�W�A�{��12��1�i�g�A11�s�B
�ؑ��̌Â����w�Z�̕֏��̈Â�������o�́q�ЎR���W�r�p���t���b�g�k������Ɂl1979�N9��10���A�k��`�O�y�[�W�l�A�{��7�|1�i�g�A5�s�B���o���W��Ȃ��B���o�ɊG�E�ЎR���u�u���������X�v��� 1969�v�i�q�g�����ƕЎR���r�Q�Ɓj�B���M�Җ��̌�Ɂu�i���l�j�v�Ƃ���B
�k�P�i�V�c�L�j���Q�R�i�ꎚ�T�Q�j�l�_�Ƃ̔[���ɐl�X�͂ǂ����čŏ��ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�@���̑�n�Ő�����l�ԂȂ�k�P�A���Q�R�i�g���A�L�j�l�����������Ƃ����R�ȓ����ł���k�P�B���Q�R�i�g���j�l���o�͑���O�l�W�L�O�sALICE IN FLOWERLAND�\�\�Ԃ̍��̃A���X�t�k���������R�����l1976�N2��4���A��Z�l�`��Z���y�[�W�A�{��12�|25���l13�s1�i�g�A�����3�߂ɕ�����34�s���B
�u���̎�̂����ɏ�����o�́s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1980�N1��25���k37177���l��ʁA�{��7.5�|1�i�g�A20�s�B
�������̏��ׂ̍���̂����킫�������o�́s���t�k�����s���l1980�N3�����k100���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|17�s1�i�g�A29�s�B
�g�����͒P�s���W�̏����ɂ��Ƃ�����t���Ȃ������B��O�́s�����G�߁t�i1940�j�ɑ}�݂��܂ꂽ�q�莆�ɂ��ւār�Ɓs�|�[���E�N���[�̐H��t�̂��Ƃ��������A�q���Ƃ����r�Ƃ����W��͌����Ȃ��B
�@���̏����W�́A���܂ł̎��W�Ɏ��^����Ȃ�������i�Ő������Ă���B�����Ă݂�A�E��W�ł���B�q�|�[���E�N���[�̐H��r�A�q�T�[�J�X�r�A�q���C���b�N�E�K�[�f���r�̎O�т͓��R�A���W�s�a���`�t�ɓ���ׂ����̂ł��������A�앗�������قȂ�ƍl���A�����������̂ł���B�ق��̎��т́A���i�ł���A�܂��Â��t�قł��邽�߁A�ǂ��ɂ��Ę^���Ȃ����������ł���B
�@����R�c�E�R�c�k�ꎁ�̍��]�ɕ����A��\���N�ɘj�鏬���т�T���o���Ă��āA�G�R�ƕ҂��̂ɂ����Ȃ��B�x������v���ł��邪�A�����Ƃ̉i���𗬂��琶�ꂽ�L�O�{�Ƃ������Ƃł������������������Ǝv���B
�@�q���r�A�q�c�O�~�r�̓�т́A���݂̎����̍�i�ł���B�������炭�����������Ƃ��A�܂��Ď��W�ꊪ�𐢂ɖ₤���Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����ČJ�����A���������邱�Ƃɂ����B
�@�@�@��㔪�Z�E�O�E���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���@��
�g���̋敪���Ȃ����Ă݂�ƁA�S21�т͎��̂悤�ɂȂ�B�\�\�s�g�����S���W�t�i1996�j�́u�|�[���E�N���[�̐H�� 1959-80�v�ɕ���āA���\�������炷��ǂ̎��W�ɓ��邩�A��L�����i�q�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t���r�Q�Ɓj�B
�|�[���E�N���[�̐H��\�\�u�m�� 1956-58�v
�T�[�J�X�\�\�u�m�� 1956-58�v
���C���b�N�E�K�[�f���\�\�u�a���` 1959-62�v
�@�@�@��
���́\�\�u�a���` 1959-62�v
���\�\�u�a���` 1959-62�v
���L�\�\�u�a���` 1959-62�v
���\�\�u�a���` 1959-62�v
�ӏt�\�\�u�a���` 1959-62�v
���Ƒ��ׂ݂̊Ł\�\�u�a���` 1959-62�v
�㌎�\�\�u�Â��ȉ� 1962-66�v
�Ƒ��\�\�u�Â��ȉ� 1962-66�v
�t�̊G�\�\�u�_��I�Ȏ���̎� 1967-1972�v
�X�C�J�E���o�I�ȉā\�\�u�_��I�Ȏ���̎� 1967-1972�v
�ԁE�ό`�\�\�u�Â��ȉ� 1962-66�v
翉́\�\�u�_��I�Ȏ���̎� 1967-1972�v
�I�s�\�\�u�Ẳ� 1976-79�v
�e�̋��\�\�u�Ẳ� 1976-79�v
���k�\�\�u�Ẳ� 1976-79�v
�l�H�ԉ��\�\�u�T�t�����E�� 1972-76�v
�@�@�@��
���\�\�u�|�[���E�N���[�̐H�� 1959-80�v
�c�O�~�\�\�u�|�[���E�N���[�̐H�� 1959-80�v
���������ƁA�����Ɂu�a���`
1959-62�v�̂��둽���̎��т����������A�@���ɂ킩��B�܂��A�V���Ђ���̎��M�˗��ɉ����ď��������т��������B�����͂g��܂̉e�����傫���낤�B�V���Ђɂ����Ƃ���ŁA��ƈȊO�Ɏ�������ƂȂ�ƁA�܂̎�҂Ƃ����͈̂��芴���Q�ł���B�ŏ��̎O�сA�Ō�̓�шȊO���u���i�ł���A�܂��Â��t�قł���v�Ƃ����f�ẮA�g�����ɂ��ē�\�s�O��̐V�����ʂł͐L�ѐL�тƕ��i�̖`�����ł��Ȃ��������Ƃ���Ă���B���W�ł���������ӏ��������̂́q�l�H�ԉ��r�i�I�E19�j�����A��Ǔ_������ăA�L�Ƃ���@�B�I�ȑ[�u���قƂ�ǂŁA�Ӗ��Ɋւ������́u���ʂ܂ŕ��k�P�с��Q�R���l����Ă���v�Ɓu����Ȃ�k�P�쁨�Q�R�i�g���j�l�C�`�S�������āv���炢���B���ۂ̎���ꂪ�����̂́q�w�A�[�r���߁q翉́r�i�I�E15�j�ł���B���т̏��o�`�{���ɂǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���͑O�f�Z�قɂ���Ă��ǂ�邪�A�u���e�v�̓x�������������̂Łi�g�����q���^��i���o�L�^�r�Łu�i���e����j�v�Ƃ����͖̂{�т̂݁j�A���o�`�Ǝ��W���^�`�̑o�����f����B
�w�A�[�b�k���o�`�l
�킽���̍D���ȏ퓅��̈��p
�w�A�[�̉��̉ʎ�
�w�A�[
�����ł͋��|���n���ς߂�
�w�A�[�̉����̉��Őg������������l
�͖̂����֓���
�w�A�[�@���݂ɂ����������
�ł����Ŗ��n�ȃC�`�S��������
�������炻�̑S�̂�������܂�
�b�h��I
�����ɂ͂ǂ�Ȍ`�Ԃ̎ւ��Ԃ�����o��
���邢�͍����ނ��
�ԍ炭��̋z�Ղ������邩�H
�w�A�[�̗[��
�܂��ɗ҂����h�����J����@����
�җ��l�����鐅�H���瓹�H��
��ӂ�M�@�����
���ꂩ�畃����̗c���͎��o��
�V�����q
�w�A�[
���ɂ킽���Ɋm�F�ł���̂͂ȂɁH
�X�Ƃ͂����Ȃ�ʒu���瑪��悢�̂���
�w�A�[�̉��łȂ���������Ԃ̉���
���̂悤�ɐV�N��
����Ό���قǑ傫��
�킽���̗��l�@�������I
翉��b�k���W���^�`�l
�킽���̍D���ȏ퓅��
�w�A�[
�w�A�[�̐X
�����ł͂ӂ炿���o���ς߂�
�ʑ��̉��Őg���������鉳��
�͖̂����ɓ���
���݂ɂ����������
�삸���̐��
�������炻�̑S�̂�������܂�
�b�h��I
�����ɂ͂ǂ�Ȑ�c�̈��삪���яo��H
�w�A�[�̗[��
�܂��ɗ҂����h�����J����@��
���l�͋���
���H���瓹�H��
��ӂ�M�@�����
��̒�����������
�V�Ă��鉳��
�w�A�[
�킽���Ɋm�F�ł���̂͂ȂɁH
���i�Ƃ͂����Ȃ�ʒu���瑪��悢�̂�
�Γ��̉��łȂ���������Ԃ̉���
���̂悤�ɐV�N��
�w�A�[
����Ό���قǑ傫��
�킽���̗��l�@���e
| �|�[���E�N���[�̐H�� | �k�����C�J�Łw�g�������W�x���܋�N���u���㎍�v�����N�܌����l |
| �T�[�J�X | �k���E���u������`�v���ܔ��N�㌎�i�\�܍��j�l |
| ���C���b�N�E�K�[�f�� | �k���E���u�����v���ܔ��N�\�i�\���j�l |
| ���� | �u�����V���v���܋�N������Z���i����j |
| ��� | �u��̐V���k�i�i�V�j���i�[���j�l�v���܋�N�㌎�� |
| ���L | �u���w�v���Z�Z�N�ꌎ�� |
| �� | �u��̐V���k�i�i�V�j���i�[���j�l�v���Z��N�\���ܓ� |
| �ӏt | �u�k�i�i�V�j�������ԁl�����v���Z��N�Z���� |
| ���Ƒ��ׂ݂̊� | �u�Ԓցv���Z��N������ |
| �㌎ | �u�k�C���V���k�i�i�V�j���i�[���j�v���Z�l�N�㌎���� |
| �Ƒ� | �u���Y�t�H�v���Z�Z�N�O���� |
| �t�̊G | �u��̐V���v���Z���N�ܓ� |
| �X�C�J�E���o�I�ȉ� | �u��̐V���k�i�i�V�j���i�[���j�v���Z���N�����\��� |
| �ԁE�ό` | �u�k�i�i�V�j�������ȁl�����v���Z�Z�N�܌� �k�����\�O���l |
| 翉� | �u���{�E�v���Z��N�\���i���e����j |
| �I�s | �u���v��㎵���N������ |
| �e�̋� | �A�g���G�R�{�u�⋾�v��㎵�Z�N�k�㌎������\�ܓ��l |
| ���k | �ЎR���W�ē���@��㎵��N�k�������㌎�\���l |
| �l �H�ԉ� | ��������i�W�w�Ԃ̍��̃A���X�x��㎵�Z�N�l�� |
| �� | �u��̐V���k�i�i�V�j���i�[���j�v ��㔪�Z�N�ꌎ��ܓ� |
| �c�O�~ | �u���v��㔪�Z�N�O���� |
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�O �G���p���e���e�`�F2010�N11���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������i�q���܂�͂����L�r�̌��ɂȂ����u���E���L�v�́A�����͂����炭�����A���Ȃ͋������A���Ȃ킿1940�N10�����́s�����G�߁t�ɑ}�����ꂽ�q�莆�ɂ��ւār�Ɠ��l�̕\�L�ŏ����ꂽ���j�B����ɂȂ�̂ōZ�ق̑ΏۂƂ͂��Ȃ��������A�e�{���ł̌��o���̓��t�̕\���͎��̂Ƃ���B
�P�G���s���㎍�蒟�t1980�N10�����f�ڌ`�F�{���̕\���͐V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�B�����A���`�Z��y�[�W�B8�|20���l27�s3�i�g�B
�Q ���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�N9��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�B�����A��܈�`��Z�l�y�[�W�B13��44���l19�s�g�B
�R �s���܂�͂����L�k��Ԃ�ǂ邵����P�l�t�i����R�c�A���ő����F1990�N4��15���A�����F1996�N3��15���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�B�����A�k���l�`����y�[�W�B9�|25���l15�s�g�B�Ȃ��A�{�Z�ق̒�{�ɂ͑������g�p�����B
�P�F�V�c�L�Ō��o���̓��t�i�����́j�A�ꎚ�A�L�œ��L�̖{���i�����́j�B�{�Z�قł́A���₷���ƃX�y�[�X�����Ă��āA���o���̓��t���Q�̑̍قɕ�����i�������A�S�`�b�N�̂��{�[���h�̂ɂ��Ă��Ȃ��j�B�g���͏����A���L�{���〈�o���̓��t�ɑ����āi�@�j���ɗj�����L�ڂ��Ă��邪�A�Q�l�̂��߁A�{�Z�قł͂��ׂĂ̌��o���̓��t�ɑ����āy�@�z���ɗj�����L�����B�܂��A�{���̖��炩�Ȍ�L�E��A�́k�끨���l�̌`�ōZ�����Ă���B
�Q�F�ꎚ���Q�Ō��o���̓��t�i�S�`�b�N�́j�A�ꎚ�A�L�œ��L�̖{���i�����́j�B
�R�F��s�Ō��o���̓��t�i���L�̖{�����|�C���g���������S�`�b�N�́j���ꎚ���グ�����c�L�őg�݁A���s���Ĉꎚ���Q�œ��L�̖{���i�����́j�B
�@���́u���܂�͂����L�v�́A���̈ꕔ����㔪�Z�N�́u���㎍�蒟�v�\�����́u�g�������W�v�ɂ悹�����̂ŁA���̂� ���ɕt�L���Ă���B�\�\��O�́u���L�v ������������܂ʂ���Ďc�����B����������a�\�O�\�\�ܔN�̂��̂ł���B�璷�ȋL�q���Ȗ��ɂ��A�����Ɏ��^����B��������ׂ͂Ȃ��B���x�����䂦�A ���A���͂Ȃǂ̍�i����邱�Ƃ��o���Ȃ��B�t�قȓ�\�́u���L�v���Ȃ��āA���̔C���ʂ��\�\�ƁB�����I�����������Ȃ���A�q���Ƃ����r���p���t���[�Y���悤�B
�@�ŋߊ��s����͂��߂��A����R�c�̏����q�u�邵����v�ɁA��i�E���͂����߂�ꂽ���A�x�M���Ȃ̂ŁA�u���܂�͂����L�v�̕��ŁA���̂��߁m�A�A�n���� ������ �v�����B�ȗ���������߂āu���I�����v���E���o���āA�}�����Ă䂭�����A�v�킸���M������A���\�]���̌��e�ɐ����Ă��܂����B�A�ڂ��Ă����N�͂����邾�� ������A�������P�s�{�ɂ��܂��傤�A�Ƃ������ƂɂȂ����B�������u��Ԃ�ǂ邵����v�ŏ��̈���ƂȂ�Ƃ����B�ʉf�䂢�����ꂵ�����Ƃ��B�w���܂�͂��� �L�x���s�̋ŁA�����I�ȓ���́u���E���L�v�͏��ł���͂��ł���B
�@�m�ɗ��鏗�̎q�ɁA���߂̂���́u���Z����v�ƌ���ꂽ�B�j�̎q�ɂ͂����������Ɏv��ꂽ�B�₪�ďK���Ɏ�M �����A�Â� �� �ۂ����Ă��ƁA�u�搶�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�i1938�N11��14���A��Z�y�[�W�j�����܂��Ɉ������͖̂{���̍Ō�̕��́B���������l���̏o�����ꂪ�u��ׂ͂Ȃ��v����قlj�������̂킴�ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B�i3�j�́u���I�� ���v�̑}�������́A���ꎩ�̋����[�����̂����A�Ɏw�E���Ȃ��̂ŁA�ǎ҂͂�낵���Z�قɂ��ꂽ���B�Ȃ��A�R�� �폜���ꂽ1939�N9��5���̐V���L���̈ꕔ��5�����s��6���t�s���������V���k�[���l�t�Ɍ�����i����������Ɓu���E���L�v�ɂ͐V���̐蔲�����\�t ����Ă�����������Ȃ��j�B��19����20�܂ł̋g�������L�ɂ́A�����⏼��c�A��x���ȂǏ��߂ĖK�ꂽ�y�n���Ïk�����M�v�ŕ`����Ă���B�o��Œb ����ꂽ���R�`�ʂ��{���ɍʂ��Y���Ă���B�g���̓��L�́s���܂�͂����L�t�̂̂��A1946�N1���`4������1948�N6���`7���������\���ꂽ�B�O�� �͐��O�Ō�̍�i�A��҂͈��ł���B
�������ю������ɗ��Ă���B�����ŏ��w������悭�^������������̂��B�i1939�N3��25���A���y�[�W�j
���������ԘV�����A����������Ƃ߁m�A�A�A�n����߂����邱�ƁB�i4��6���A��܃y�[�W�j
�@�g���̂悤�ɂ����肷�鏭�����i�a�q�B���̎q�������u���Z����v�ƌ������̂́B���ꂳ���āA��������m�������点��Ƃ̂��ƁB���w�Z�̐i�w�̕��� �� �邽�߂炵���B�k�c�c�l��A�ƂɊ��ƁA���͑��ς炸��̏�ɂ����ƁA�������Q�����Ă����B�i4��19���A�y�[�W�j
�锪���߂��A���S���ɂق�������ɍs���A�A��ɉƂɊ��B���̂ނ������畃�̐Q����������B�i4��27���A�O��y�[�W�j
�[��B��������Ǝl�J�����֍s���B�A�p�[�g�n�E�X�E�n�}��K�ꂽ���A�֓����i�ʼn�Ɓj����͕s�݂ʼn��l�Ƌq�����������B�i5��5���A�O�܃y�[�W�j
�@�����ւ䂭�ƁA�Ћr�̂Ȃ��l�������B�x�ߎ��ςŁA�������Ȃƒ��������B�������Ɍ��o���̂���炾�B�i6��30���A�l�y�[�W�j
���V�̉���ŁA���Ԃ����Ɖ�B�O�l�Œ��������̂��Ƃ���b��ɂȂ�B�i7��12���A���y�[�W�j
�ߌ�x���U���ɏo��B���싴���킽��A�ю������ɒ����B���w���̍��A�������^����̏ꏊ�������̂�z���o���B�i7��14���A���y�[�W�j
�@�U������߂�ƁA���������̗\�K�̂��ƂŁA�F�����������ƌ������̌��t�ɂт�����B��\�O���̔����B�[��̊X�𑖂��Ė{���������w�Z�Ɍ����B�Z��̂Ƃ� �� �ŁA���Ԃ����������u�����I�����������v�B���R�ƈÂ�����߂����B�i7��20���A�܋�y�[�W�j
�Z�ƋT�̓��ɍs���B�\�N�Ԃ�̂��Ƃ����m��Ȃ��B���r���������j�Ƃ܂�������B�̋ߏ��ɂ����V����ƌ����l�������B�v���������푈�̘b�����ꂽ�B��A ���V�̂Ƃ���֍s���A������ۂ݂Ȃ���A���������\���u���̓��e�������Ė���Ĉ��S����B�i7��23���A�Z�Z�y�[�W�j
�@���B�\�ꎞ�߂��A�l�J�̍֓�������̂Ƃ���֗V�тɍs���B�s�݂Ȃ̂ʼn�����Ƃ�����ׂ�B�₵�n�u���B�ꎞ�ԂقǂŖ߂�A��K�̃A�g���G�Ŗ��G�A�f�b�T ������ �����ĖႤ�B���x�A��ȂɌܓ_�o�i�����Ƃ̂��ƁB���̌b�܂�Ȃ���ƂɍK�^����B��ʂ�܂ő�����B�i8��30���A����y�[�W�j
���̌�������A���͋߂����߂邱�ƂɂȂ����B�����\���~������Ȃ��Ȃ�̂����B�Ƃ�����������������ň���S���B�i1940�N3��6���A��O��`��l �Z �y�[�W�j
�y�����h�����d�l�����z����ɂ��Ύl���C�M���X�����@���̓E�C���w�����X�n�[�t�G���y�уu�����X�r���c�e�����̗v �`���P�����A�E�C���w�����X�n�[�t�G�� �߂� �̃V���c�N�w�������H�߂��Ńh�C�c�퓬�͈�ǂ͔��e���܂Ƃ��Ɏđ呹�Q���A�u�����X�r���c�e���ɉ��Ă��퓬�͈�ǂɑ�Ȃ鑹�Q��^�ւ��A�E��P�� �D�܂�����ʓV��̉��ɍs�͂ꂽ���A�G��R�͋t�P���A���˖C�����A�p�R���͎�̑��Q��ւ�
�y�����h���l���������z�p�����{�͎l���C�M���X��R�����͐��k�h�C�c�̌R�`�E�C���w�����X�n�[�t�G���ɒ������̃h�C�c�͑��������Ɣ��\����
�y�����h���l���������z�p��R���������͎l���k�C�ɗՂރh�C�c���̌R�`�E�C���w�����X�n�[�t�G����勓�P���A���`�������̃h�C�c�͑��ɑ�������s �� �����E�̐��ʂɊւ����Ȃ͎l���鎟�̔@�����\�����u�p��R�̏d���������͎l���E�C���w�����X�n�[�t�G���R�`�ɒ������̃h�C�c�͑��ɑ���s���� �� �̔����Ŕ��e���͒��ڃh�C�c�R�͂ɖ�������͓͊�ǂɑ呹�Q��^�ւ��v
�p�@�܋@���Ă���y�x���������d�l�����z�l����̃��a�I�����ɂ��Ύl���\��@��萬��C�M���X�����������E�C���w�����X�n�[�t�G���A�N�c�N�X�n�[�t�G�� �Ȃǂ̗v�`���P���������̔��e�𓊉��������A��Q�͌y���ʼnp�͏\��@�̓��܋@�N�c�N�X�n�[�t�G���� �߂Ŏ˗����ꂽ�ƁA�ȂىE�͐��z���ȗ��ŏ��̑ΓƌR���s���ł���A�ŏ��̋�P�ł���
�����ʂ���4�i�������o�����E���u��������ɐ�@�v�u�{�i�I���̎����^�ƃ\���������Ō�����v�u���L��s�s�ח��^��������\�[�ɋ� �Â��v�ŁA�g ����9��1���̃h�C�c�R�̃|�[�����h�N�U�ɂ�����E���J�n���āA�����̋L�������^���邱�Ƃ��P�q���܂�͂����L�r���I���悤�Ƃ����͔̂[ ���ł���B���̂Ƃ��u�u����n�d ����l��܋g�����v�Ƃ������v�Ƃ������L�̍Ō�̈ꕶ�͐V���L���Ƃ��ĉ����A�g���̂��̌�̉^�����Î����ď[���Ȍ��ʂ������Ă���B�����A�R�s���܂�͂����L�t�Ƃ����q�� �܂�͂����L�r�Ƃقړ��ʂ́A�ȍ~�̓��L�{���������i�ɂȂ�ƁA�����ł̐V���L���̈��p�͂����ɂ��d���B�g�����s���܂�͂��� �L�t�ł����̋L�����폜�����w�i�ɂ́A����������������Ă����̂ł͂Ȃ����B�܂��A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�Ƃ̈Ⴂ��ł��o���� �������Ƃ������Ƃ����낤�B
����5���Ɂs�}�������S�W�k�S5���l�t�i�}�����[�A1989-2010�j���ŏI��z�{�̑�1���q���E�C�W�`���[���r�������Ċ��������B ���͑S�W�̊� ����S�҂��ɂ��Ă������A���҂͊O�ꂽ�B�{�т�ʍ��́q���E�����r�̓��e�ɕs�����������킯�ł͂Ȃ��B �ɓ��T��Y��s鍎q�ꝱ�t�̏������L�ڂ���Ă��Ȃ���������ł���B�����Ƃ��M��S�W�ɖM��̖ԗ��I�����͕K�{�ł͂Ȃ�����A���̕s���͌����Ⴂ���� ���B�g�����́q�u���\�I���сv�G���r�́q�R �w鍎q�ꝱ�x�r�ɂ��������Ă���i���o�́s�G�������~�G�[���t5���A1986�N9���j�B
�@���m�̐l���瑡��ꂽ�w鍎q�ꝱ�x�ŁA���͏��߂āA���̓���Ȃ鎍�т�ǂƂ������A�����̂������B�����̂��ƂȂ̂��A�� ���T��Y��� �����q�� �́A���s�N�������s�������L����ĂȂ��̂ŁA�킩��Ȃ��B���ڂ낰�Ȃ�����A�ٗl�ȏ��@�Ɓu���̖����}�v�ɋ��Q�������̂������B���͍��A�u�ڍׂȃm�[�g�v �̕t�����A�H�R���v��́w鍎q�ꝱ�x��ǂ݁A�����u����v�ɔ��\���ꂽ�A�]�������ǂ݁A�Ȃ�Ƃ���ǂ̎肪�����݂͂����Ǝv���Ă���B
�@���ŋ߂̂��ƁA�����L�ŁA�F�V�F��ƍs���������B���́w鍎q�ꝱ�x�ɂ́A�u���I�C���[�W�v���F�Z���o�Ă���悤�Ɏv���ƌ�������A�u����͂����ł� ��v�Ƃ��Ƃ��Ȃ��ɓ�����B�������ɁA�u�F���S�́v�𓊉e����ƈ�����A���̎��тɂ͓��R�̂��Ƃ����m��Ȃ��ƁA���Ȃ�ɔ[�������B�i�s�u�����v�Ƃ��� �G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z���y�[�W�j
�s�g��
�����y�����E��i�������k���t�l�t��
�����������Ƃ����A�ɓ��T��Y��s鍎q�ꝱ�t�͏����������ڂ̓�̈�����Ȃ̂ł���i����������ƁA�G�����\�̔������q��������Ȃ��j�B�����Ȃ��ɓ��T��
�Y��ɂ�����邩�ƌ����A���ꂪ�g���́s��ʁt���`�̃X���X�Ƃ��ĂȂ�炩�̉e����^���Ă��邾
�낤���Ƃ��m��������ł���B�������g���{�l�́i�n��Ƃɂ͂悭���邱�Ƃ����j�A�}��������ǂ̂́s��ʁt���`�����ゾ�ƌ���Ă��邩��A����
�s���t���������ƂŐ^�Ƀ}�������Əo
������I�N�^�r�I�E�p�X�Ɠ��l�̎�������ɓ����Ă����ƌ��邱�Ƃ��ł���i�q�g
�����ƃI�N�^�r
�I�E�p�X�r�Q�Ɓj�B�ɓ��ɂ��͍���̒T���ɘւƂ��āA�g�����������ق��̖M������Ă݂�
���B
�H�R���v��s鍎q�ꝱ�t�i�v���ЁA1972�N11���j�́A��E����F�V���̌���100�������ł����A�����B1984�N12��1����
���Ђ�������Łs鍎q�ꝱ�t���o�Ă��āA������͌��₷���B�Ȃ��A1966�N��50���������ꂽ�i������Ƃ̂��Ƃ�����A���ꂪ�{���̌��^���i��
�������
���j�B�]������́A�����s����t34���i1986�N3���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�B�{���y�[�W�̕W��q�[�q�̈ꝱ�͌����ęF���r���܂��r�́q鍎q�́c�c�r�̌�A��
�낤�B�\���E�ڎ��̕W��͂Ƃ��Ɂq鍎q�ꝱ�r�ŁA�\���ɂ́u��ԂƑ��ƉC�����d�w�I�ɂ���݂������@�̋ɒv��₤���̍�v�Ǝ�傪����B
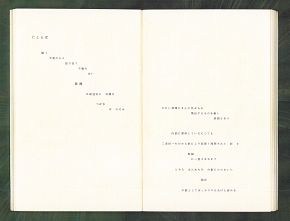 �@
�@![�]������q鍎q�ꝱ�r�i�����s����t34���A1986�N3���j�̇V�ʌ��J���k���m�N���R�s�[�l](image/ucdd_ebara.jpg)
�sUN COUP DE DES�t�i��\�I�ȖM��́q鍎q�ꝱ�r�������́q�̈�U��r�ŁA�ߔN�͌� �҂��D���j�� �H�R���g�łȂ��ꂽ�����͌��������Ȃ��B�����Ƃ��H�R���qUn Coup de Des�r�̖�Ƙ_��A�ڂ������o���s���{���w�����t�i24���A1966�N10���E27���A1967�N7���j�͍��J���E���g�ł���A���y�[�W�ɕ����̌����A �E�y�[�W�ɖM���̖Ƃ������o�̑̍ق��s鍎q�ꝱ�t�̃x�[�X�ɂ��������Ƃ͊m�������B�s�}�������S�W�k��1���l�t���q�� �̈�U��r������������̍��J���E���g �ŁA�����Ɠ����s�̕��������̗p����Ă���̂́A���́u���قȌ`�Ԃɂ�鎍��i�v�i�q�}��r�A���� �ʍ��A���y�[�W�j���v������K�R���낤�B�{�т̏��o�́s�R�X���|���X�t1897�N5�����B���̌�A�����ȉ揤�A���u�����[�Y�E���H���[�������h���̑}�G ��Y����200������̎���W�� ���s����悵���B�}�������̎��ɂ���Ė����ɏI��������ؖ{�s鍎q�ꝱ�t�ł���B
���̐V�ł̂��߂Ƀ}�������͕��ᎆ�̑唻�m�[�g�u�b�N���g���āA�����̔z�u�̑��A�]���̕��A���ꂼ��̊����k�f�B�h�����̃^�C�v �t�F�C�X������ ��i�ɂӂ� �킵���Ƃ����}�������̔��f�ɂ��ƂÂ��āA����̓t�B���}��=�f�B�h������ƌ��܂����l�̑傫�����ނȂǂ��ɏ���������p�̊��t���`�m�}�P�c �g�n���݂�������肠�����B�i�����O�̉��E�����q�̈�U��r�́u���H���[���ɂ�鍋�ؖ{���s�v��v�A�s�}�������S�W�k��1�� �ʍ��l�t�A�Z�O��y�[�W�j
���̃}�P�b�g�́A�}�������^���������A���q�N�v��s�̈�U��͒f���ċ��R��p���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�\�\���e�ƍZ�����@ �t�����\���[�Y�E�������ɂ��o�łƍl�@�t�i�s�H�ЁA2009�N3��25���j�ɃJ���[�̃t�@�N�V�~���ł��f�����Ă��āA�e�ՂɌ��邱�Ƃ��ł� ��B���ꂪ�����[���B�s�}�������S�W�k��1���l�t�̐� ���O�ɂ����E�����q�̈�U��r�́u�|��ɂ��āv�ɂ́u���̂ɂ��ĐG���A�������}���͖̂��������A�C�^���b�N�͎̂Α̂Ƃ��A�܂��}���������� �i���ł����� �p�� �Ă���啶�������őg�܂ꂽ��́A�����́E�C�^���b�N�̂̂��ꂼ��u�׃S�`�b�N�v�Ƃ����B�܂����{�ꊈ���̎�ނ̐�������A�����ŋ����̂��ߒP��̖`���� �݂�啶���Ƃ���ꍇ�́A���Ƃ̈Ⴂ��\���ł��Ȃ��������̂�����v�i���� �ʍ��A�Z�O�y�[�W�j�Ə�����Ă���B����́A���̂ƒԂ���}�g���N�X�ɂ��čl����Ƃ킩��₷���B�������Ă݂悤�B
�����̃��}���́i����p��ł͗��́j�@���@�M��̖�����
�����̃C�^���b�N�́@���@�M��̎Α�
�@�E�Z
���t�̂��鏑�́i���}���̂ƃC�^���b�N�́j��������̏��́i��
���́j�̐��́����̂ƎΑ̂ɒu������������
�����̑啶�������őg�܂ꂽ��@���@�M��ł́u�׃S�`�b�N�v
�@�E��
���ł͒Ԃ�̃��x��������A�M���ɑ������鏑�̂����݂�
��킯�ł͂Ȃ�
�@�E�u�����́k�c�c�l�́k�c�c�l�u�׃S�`�b�N�v�v�͑g�ŏ㖵�����邩��A���́����̂́u�׃S�`�b�N�v�i��
�Α̂́u�׃S�`�b�N�v�j�ɓǂݑւ�����
�@�E���ۂ̔Ŗʂ́A�׃S�`�b�N�ł͂Ȃ��A���`�b�N���x�̃E�G�C�g�̑������i���́����̂ƎΆj���p�����Ă���
�q�̈�U��r�̖�҂��̂�Ȃ������悤�ɁA�����E�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̈Ӑ}�I�Ȏg���킯�⊇�ʗނ̎g�p���̑����Ȃ��ƂȂ�A���́�
���́^�ΆA
�����̃Z���t�i�a���̗���j�^�����̃T���Z���t���S�`�b�N�i�a���̗Ȃ��j�̑Δ�ƁA�����̑召��g�݂��킹�����������\���@�\�\�O�f�}�������^������
�{�̖�ҁE���q�N�v�ɂ��u�g�p����銈���́A�啶������ŏ��̏������܂ő傫�����قȂ�l��ނƁA�����̑������Ⴄ���ނ́A���v��ނ̃��[�}����
�́B����ɑ傫���A�������قȂ�l��ނ̃C�^���b�N���̂̌v���ނ̊�������g����Ă���v
�i�q���Ƃ����r�A�����A���܃y�[�W�j�\�\�́A�{�т̂悤�ȋH�L�Ȃ�L���̎U����g��Ƃ��鎍�̖|��̏ꍇ�A�[���ɗL���ł���B
�����ŏH�R��ƍ]����A����
����������p������
�̂����Ahtml�t�@�C���ōČ�����ɂ͋Z�p�I�ȍ�������B���]�̈��Ƃ��āA����̔z�u�i�����Q�j��s�A�L�A�����̑傫���E���̂̂��ׂĂ��L�����Z��
�����f�̃e�L�X�g��
���āA�SXI�ʂ̂����V�܂ł�3���J���������i���J���̋����\�\�Ŏ������j�B�ǎ҂͂ǂ����S�т����ꂼ��̌��T�i������j�ł��ǂ݂������������B
�H�R���v��b鍎q�ꝱ
鍎q�ꝱ
�\�\
������
���Ƃ��@�i���I�Ȋ��@�ɂ�����
��������Ƃ�
��j�̒ꂩ��
�\�\
���Ƃ���
�X��
�V�W�̂���
�{�苶��
�s����
����
�[��
�͐�]�I�Ɂ@�H����
��
�́@�̂��݂̂Ȃ����Ă̂܂��ɕ������
���o������̂����
�g��������
�����ɗv�Ă���ɂ��Ă�
��ґ���̂����锿�ɂ���[���������ꂽ�@�e�@��
����
�Ɉ�v������܂�
������@�܂�������@�̌��ɂ����ނ���
�D��
�̊k�Ƃ��Ăۂ���������������[�݂�
�]������b鍎q�ꝱ
鍎q�̈ꝱ��
�\�\
������
��j�D�̒ꂩ��
�i����
���܂��܂ȏɓ�����ꂽ���ł���
�\�\
�Ⴆ��
���m�ӂ��n��
����
��]�I�ɕ��m������n�Ȃ�
�Ο��m�悱�Ȃ݁n�̂�����
�����A����
���䂽��
�{��
���̗���
���ё��ˁ@�O�ɓ|��
���������韷�m�Ȃ݁n�ʂɂ��Ԃ���
���m��n�����g�Q�����
�Ԃ��g�̔��Ł@�[����
�����������߂��Ă����e
�ꌽ���瑼���ւƌX�m�����n��
�����قǂ�
����J���[����
�[����ɏk�߂�̂�
�����O��b�̈�U��
�̈�U��
�\�\
�f���Ă��ꂪ
���Ƃ��@�i���̏ɂ�����
��������ɂ���
��j�̒ꂩ��
�\�\
���邢��
���Ȃ킿
�q��m��ʐ[�݁r��
���X��
�Â܂�
�����肭�邢��
��]�I�Ȃ܂ł�
����Ȃ�X����
���̂���
���̗��̌X���̂��Ƃ�
�O�����ā@���Ă𗧂��グ�鍢��ɂ�藎��������
�����Ĕg�̕��o��
����𐅖ʂɐ闃
�͂邩�����Ɂ@�v��
�[�݂ւƖ������ꂽ�S����@���̑���̔��ɂ����
������t��
��v��������
�傫�������J�����[�݁@���̂܂�
�D�̂Ƃ���
�E�܂����ւƌX��
�g�����́s��ʁt�i1983�j��s���[���h���b�v�t�i1988�j�ł͖{�����̂ɖ��������g�p���Ȃ��������A�ꊇ�ʈȊO�ɂ����܂��܂Ȋ�
��
�ނ𑽗p���āA
�����̏��̂�p����̂Ɠ����̌��ʂ��������B�g�����Ɩ��Ƃ���������O���i�������V���Ɍf�ڂ��鏑�ЍL���j�̎w��̓}�P�b�g���̂��̂ł���B��������
��Ƃ�����̕��������g�����}�������̂悤�ȔŖʂɂ��Ȃ������̂́A���̎�̎w�����
�тɎ�
�����ވӎv���Ȃ���������ƍl����ق��Ȃ��B�s��ʁt���`���z���̂ق��ÓT�I�Ȃ������܂��������Ă���̂́A�}���������z�肵���u���ꂼ
��̊����̑傫�����ށv
�̎g�p�ɂ͎��~�߂����������߂ł���B�s��ʁt���`�͋g�������Ɂs鍎q�ꝱ�t�̏��@�����̂܂ܓK�p�������̂ł͂Ȃ��B�g����
�̗p�����̂́A�K�i��̎������ɂ��A���ꎩ�͎̂���̐��I�ȓW�J�i�������O�������u������j�ƁA���l�ȏ��̂ɑ��鑽�l�Ȋ��ʗނ̎g�p�������B
�Ō�ɁA�A���x�[���E�e�B�{�[�f�ƃM�B�E�~�V���[�����ꂼ��
�̃}�������_�Łs鍎q�ꝱ�t�ɐG�ꂽ�ӏ�
����������B
�w鍎q��U��x�́k�c�c�l�����̕ł̓��O�ɂ������l�̒P�Ɛ��ւƐ��E���Ҍ�����B�����ɂ͋��R�̓�����_�X�ƘA�˂ċH�L�Ȃ�L�� ���L����� ���A������ �s�\�ȉi���̕ŁA���Ԃ̊O�ɋ��̓B�ŗ��߂�ꂽ�������Î�����ȊO�̉��l�������Ȃ��B�i�`�E�e�B�{�[�f�A�c���~��E���叇�N��s�}�������_�t�A���ώɁA 1991�N10��25���A�O��l�y�[�W�j
�}�������͂ЂƂ̊m�F����o�������B����́A�Z������ɑ����̗]���m�A�A�n�Ɉ͂܂�Ă���A�Ƃ������Ƃł���B���̗]�����A��i�̂܂��ɔz�u���ꂽ�� �ق̂悤�ȗ]�����A�v�l��Ӗ��̗v�����̂��̂ɂ��������āA�y�[�W�̏�ɎU��������m�A�A�A�A�A�n���Ƃɂ���āA�����Ƃ��܂����p���Ă��悢�̂ł͂Ȃ� ���B�i�M�B�E�~�V���[�A�c�����a��s�X�e�t�@�k�E�}�������t�A�����ЁA1993�N3��30���A��O�Z�y�[�W�j
�O�҂́q�킽���̍쎍�@�H�r�̈�߂Ƃ����Ă��ʗp�����������A��҂́s��ʁt���`�̔��z����������̂Ƃ��ǂ߂�B����g�������́A�� �^�̖ʂ����Ƃ��Ă��i�s鍎q�ꝱ�t��20���I�����ō��̍�i���Ƃ���I�N �^�r�I�E�p�X�o�R�Łj�}�������Ɋ����Ă��邱�Ƃ͋^���Ȃ��B���Ȃ݂Ɂq�u���\�I���сv�G���r�́q�R �w鍎q�ꝱ�x�r�̒��O���Ȃ킿 �q�Q ���̎��r�̖����ɂ́A�p�X�Ɓs鍎q�ꝱ�t�̂��Ƃ�������Ă���B�ɓ��T��Y��s鍎q�ꝱ�t�ɂ��̕ӂ̎���𑤖ʂ���Ƃ炷���e���L����Ă��� �\��������ȏ�A�T���𑱂� �����B
�k�t�L�l�@���ɂƂ��Ă��܊S������͉̂��l���̉�ƂŁA�Ȃ��ł��t�����V�X�E�x�[�R������ԋC�ɂȂ��Ă���B�o���e���X�����������A�Ȃ�Ƃ����Ă��x�[�R���͕s���ȉ�Ƃł���B������ȁA���ꂽ��������̂��������ꂢ�ȐF�̃p�b�N�ɕ������߂��G���A�Ȃ��`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B����[�̌`���݂Șc��ł��܂��Ă���̂��u���ꂪ�G���v�ƒ�o���Ă���Ƃ��낪�A��͂苰�낵���B�O���g�G�m�g���v�e�B�b�N�n�͕lj�̂悤�ȑ��ʂŁA�����������Ƃ͉�W���ς������ł͕�����Ȃ��B
�@ �x�[�R�����킴�킴����`�����Ƃ����Ƃ͎v���Ȃ��B��͂�A���R�ɕ`�������Ƃ������Ƃ��炱�������敗�ɂȂ����̂��낤�B�������\�߂��͂������A�Ƃ�����������l�̂킯�ŁA�����Ƃ̃x�[�R�����Ȃ����̂悤�ȊG��`�����̂��A��͐s���Ȃ��B��i�̉�����͓��R����̂��낤���A���{�ł͂܂��ژ^�����Ȃ��悤���B���Y���P�ɂ��A�W���E�h�D���[�Y���w���o�̘_���x�̑�Ńx�[�R���_�������Ă���Ƃ����i�̂��ɎR�p����s���o�̘_���\�\��ƃt�����V�X�E�x�[�R���_�t�A�@����w�o�ŋǁA2004�N9��25���j�B�\�\�l�����ԂƂ���A����͏�ɁA��ɂ݂͂���������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��́A���ׂĂ̌��i�����������A��Y�⊴�o���������킷��́A���������͂ɏP��ꂽ����ł���B���ꂱ�����u���|���͂ނ��닩�т��悭�v�Ǝ咣���邱�ƂŃx�[�R�����������Ƃ��Ă��邱�Ƃł���i�q�W�@�͂��悭���Ɓr�A�����A�ܘZ�y�[�W�j�B�\�\
�@�x�[�R���ȊO�ŊS������̂́A�o���e���X�ƓS�ւ��B�S�ւ͂����ւ�ȉ�Ƃ��Ǝv���B�S�ւƃo���e���X�����̎��̐��E�ɂ��܂�����Ǝv�����A�����ɂ̓x�[�R�����܂߂��O�l�������ł��Ȃ���������Ȃ�����A�Ƃ肠�����x�[�R������ԋ߂��Ƃ���ɂ���Ƃ�����i���͂܂��A�o���e���X�̌Z�ł�����N���\�t�X�L�[�̊G�Ɏ䂩��Ă���B�s�K�t�ɔ��\�����q���[���h���b�v�r�̓N���\�t�X�L�[�ƃi�{�R�t�́s�������t�ɐG������ď����������j�B
�@������ȃC���[�W�������̊G�̘g�ɕ����߂Ă���x�[�R���̊G�����̂܂ܕ����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�x�[�R���ɂ��Ă��ƈ�A��т͏����āA���̎��W�s���[���h���b�v�t���\���������Ǝv���Ă���B
��f�́A�g���������Y���P�E��������Ƃ̓C�k�i�Θb��]�j�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t1987�N11�����j�Ńt�����V�X�E�x�[�R���ɂ��Č������������ɁA�����������t�ӂ��ɂ܂Ƃ߂����̂ŁA�g�������M�������͂ł͂Ȃ��i����͋g�����U���Ńx�[�R���Ɍ��y�������Ƃ��Ȃ����߂̋���̍�ŁA���ӂ͂Ȃ��j�B����A�g���̓o���e���X�ɑ��Ắq���\�I�ȑ��`��Ƃ����r�i���o��1986�N6���́s�G�������~�G�[���t4���j�̈�߂ŃI�}�[�W��������Ă���B�����[�����ƂɁA�Ƃ���20���I�̋�ۉ�̋����ł������t�����V�X�E�x�[�R���i1909-92�j�ƃo���e���X�i1908-2001�j�͖ʎ����������B�x�[�R���͂���C���^�����[�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
�@�l�`�k���~�V�F���E�A���V�����{�[�l�@�t�����V�X�E�x�C�R���A�O��͌����Ƃ̘b�ɂȂ�܂����B���Ȃ��̓o���e���X�ɉ�������Ƃ�����Ǝv���܂��B�ނ̊G�̐��E�͂��Ȃ��ɂƂ��Ă܂����������̂��̂ł����A����Ƃ��A���̋t�ɁA�ނ̍�i�ɂ͂��Ȃ�������������̂�����܂����H
�@�e�a�k���t�����V�X�E�x�C�R���l�@�ނ̊G�ɂ͊��S����Ƃ�������������邯��ǁA�ł��A�ނ��l�����͂��݂��ɂ܂�������������Ă���Ǝv���B�ނ̕��i�͂����Ǝv���B���ɑ�D���Ȃ��̂��Q�A�R������B�ł��A�ނ̍�i�ň�ԍD���Ȃ̂́A�����Ԑ̂̃p������̊G�ŁA��O�̂��̂����ǁA���@�[�W������������āA�������s�X�H�t�Ƃ����^�C�g���������B�l�̋L���ł́A�Е��̃��@�[�W�����̕���������������X�H�ɐl�Ԃ��������āA����ɁA��̃��@�[�W�����̍앗���܂�ň������Ȃ����ȁB��̃��@�[�W�����̕�������������萳�m�ŁA����薾�m�ŁB�����Ƃ��D�����ȁB�k�c�c�l
�����Œ��ڂ������̂́u���Ȃ��̓o���e���X�ɉ�������Ƃ�����Ǝv���܂��v�ɕt���ꂽ�\������ɂ����B�u1977�N�Ƀx�C�R���̓��[�}�ɒZ���؍݂��A���n�̃��B�����E���f�B�`�ŁA�C�U�x���E���[�X�\�[���̒������Ńo���e���X�ɉ���Ă���B���y����Ă���ނ́s�X�H�t�̓�̃��@�[�W�����̂����A�l���̏��Ȃ�����1929�N�A�l���������A�������`���������m�ȕ���1933�N�̍�B�x�C�R���͂��̑Βk�̂悤�Ƀo���e���X��������x�]�����Ă��邪�A����A�o���e���X�̓x�C�R���̎���A�x�C�R���ɂ��Ă����q�ׂĂ���B����ăx�C�R���Ƃ�������Ȑl�Ԃ������B�̑�ȉ�Ƃ��������A�ł��ނ̍�i�͍D���ł͂Ȃ������B�G�ł́A�Ȃ̊����}�����邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Ȃ𗥂��邱�Ƃ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�i�w�t�B�K���x1995�N7���j�v�B�i�~�V�F���E�A���V�����{�[�A�\�������s�t�����V�X�E�x�C�R�� �Βk�t�A�O���ЁA1998�N1��25���A�܁Z�y�[�W�j�B�g�����̓o���e���X�ɂ��Ă͕��͂��₵�Ȃ���A�Ȃ��x�[�R���ɂ��Ă͓C�k�Ō��y���������������̂��B����͍l�@�ɒl�����肾�B�����A�����͍T���悤�B�ЂƂ�����̂́A�g���ɂƂ��ăx�[�R���́u���\�I�ȑ��`��Ɓv�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł���B

�x�[�R�������̑�\��Ɂq�G��r�i1946�j������B���́u�G��v�Ƌg�����̎��сq���b�r�i�B�E15�A�E�e�͂����炭1955�N3��5���j�́A�ǂ��炪�ǂ���̑}���G�Ƃ��������Ƃ����Ȃ��A���ߐ��������Ă���B�g�����x�[�R���ɂ��ĎU���ŏ����ƂȂ�A�q���b�r�̑��݂�����Ēʂ�킯�ɂ͂����Ȃ��B�x�[�R���̊G�����邱�Ƃ́A����̎��т���邱�ƂƓ��l�ɍ���B����A�g�����x�[�R���̂��Ƃ����ŏ��������Ȃ�A�Ƃ������{���q���i�r�i�K�E11�j���B����36�s�̎��т̓x�[�R���̓`�L�����܂����A�g�����ɂ��q�t�����V�X�E�x�[�R����r�ł���B
�u���̎��^�쌴�ɕ����~���^����`�����Ƃ��Ă����v�^����Ȃ̂Ɂ^�i��Ɓj�͂Ȃ����^�����Ɓi����j��`���Ă���^�������̎��^���������́^�i�S�I�m�����^���n�ȋ�ԁj��z�N���Ă�����^�����炭�^�u�j������^�O���琂��閨�v�^��`���Ă��������m��Ȃ��^�����́i�n��j�ł́^�u�������ƂƁ^�����Ȃ����ƂƂ��������v�^�t���[�c�p�[���[�̈֎q�Ɂ^�i��Ɓj�͙~��Ȃ��璭�߂Ă���^���H�̊X�H���^�i�����̉ʕ��j��������^�i���N�j���ʂ�^�i�͑��j�ɂ̂����ā^�i���ҁj���ʂ��čs���^�u�������������^����Â���v�^�i���u�m��������n�j�̉��Ł^�u��Ōċz����v�^�킪�i��Ɓj�́^�u���̂Ƃ������n�����Ă���^�i���e�j�̗E�p��`�����Ƃ��Ă����v�^�i��̐瑐���c�c�j�^�i��̐瑐�����̉����c�c�j�^�����āi�S�I�m�����^���n�ȋ�ԁj�Ɂ^�u�L���̂܂����^�i�����j�v�^��`���Ă���悤��
��ɒǍ��̌`�ň������q���i�r�́s���㎍�蒟�t1986�N8�����A���Ȃ킿���̓C�k��1�N�ȏ�O�ɔ��\����Ă��邩��A�g�������ꂩ�珑�������ƌ����Ă������̂́A�C�k�̗�1988�N5���A�s�V���t�ʍ�1000�����\�́q�ӏ��r�i�K�E15�j�Ɍ��������ƍl������B���Ɂq�ӏ��r�̑�1�߂��f����B�u����㌎q�̃}���g�𒅂��^�k�@���l�l�̏ё����ˁI�v�̓x�[�R���́q�x���X�P�X�̖@���C���m�Z���g�\���̏ё��ɂ��K��r�i1953�j�܂��Ă���ɈႢ�Ȃ��B
��͔����܂�
�@�@�@�@�@�@���ɂȂ��o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃J�[�e�����J����
�i�O�E�͂܂�ł����܂Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V���̂悤���j
����㌎q�̃}���g�𒅂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�@���l�l�̏ё����ˁI
��͂Ȃ��Ƃ����ĕ�Ƃ֖߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɕ�܂ꂽ
�@�@�@�@�@�@�@�@�k�������l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂悤�ȋ�����
�i������G���
�@�@�@�@�@�@�@�@����ь����Ă���j
�ƔF������
�@�@�@�@�@�k�z�O�l���܂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ǂ݂Ƃ蓾�ʂ��́j
�ڂ������ݕ`������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�G��l�Ȃ���̂�
�i�[�z�̂Ȃ��̊��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��邩���m��Ȃ�

�t�����V�X�E�x�[�R���q�x���X�P�X�̖@���C���m�Z���g�\���̏ё��ɂ��K��r�i1953�j
�Ō�ɁA�x�[�R���̂��Ƃ��琶�܂ꂽ����������悤�B�W����}�^�A���������ߑ���p�ٕҁs�t�����V�X�E�x�[�R���t�i�����V���A1983�j�̋����q�f�C���B�b�h�E�V�����F�X�^�[�Ƃ̃e���r�E�C���^�r���[����̔����i1975�j�r�́u���͕����̌��̕������Ă��܂����B�ˑR�ɁA���ꂾ�I�@�l���͂���Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ𗹉����܂����v�܂����̂��A�q�Y��i�ނ��сj�r�i�K�E1�A���o�́s�����C�J�t1986�N12���Վ��������j�̎��̎���ł���B�����́s��ʁt���`��4�s�����A�Ǎ��ň����B
�ܓ��̋��Ł^�u���̕������ā^�ˑR�^�����Ɂi�l���j������Ƌ��v
�����g������ƍŌ�ɘb�����̂�1989�N12��20���̂��Ƃ��B�x���M�[�̉�ƃ|�[���E�f�����H�[�ɂ��Đq�˂�ƁA�u�k�̊ہk���������ߑ���p�فl�̃f�����H�[�W�͊ς����A�u��̉�Ɓv���Ƃ킩���Ă��܂��āB�O�͍D������������ǁB���܍D���Ȃ̂́A�o���e���X�ƃN���\�t�X�L�[�ƃx�[�R�����v�Ƃ������ƂŁA�S�ւ̖��͏o�Ȃ������悤�Ɏv���B���p�ƎO�l�����������z�q���\�I�ȑ��`��Ƃ����r�̈�l�Ƃ��ăo���e���X�ɃI�}�[�W����������i���̓�l�̓n���X�E�x�����[���Ǝl�J�V�����j�A�S���Ȃ锼�N�قǑO�܂ŁA�t�����V�X�E�x�[�R���͋g�����̔]��������Ȃ������B
�s���܂�͂����L�t�̏��a15�N2��14���i���j�Ɂs�k�C���̌���`���t�Ɋւ���L�q������i�����A��O��y�[�W�j�B�����ł��s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�̓��Y���ڂ��������B
�k�C�����ҁs�k�C���̌���`���t�i���{����o�� �ЁA1940�N3��30���j�k764-112�l
�g���́u���������e�́w�k�C���̌���Ɠ`���x�̐����ɖv������B�o����ƁA�V�c�É��Ɍ��シ��Ƃ̂��Ɓv�Ə����Ă���B���s�ҁF�k�C���A�������B��� �҂͏���Ёi�����s������s�J���꒬�꒚�ڏ\��Ԓn�j�A����͑���{���������ЂŁA���N���s�̋g�������W�s�t�́t�i����ɁA1941�N12��10���j�� ����ҁE������Ɠ����ł���B�������F�x�M���B
�� �L���̏����s�k�C���̌���Ɠ`���t�͍ŏI�I�Ɂs�k�C���̌���`���t�ƂȂ����B�{���`���̌��o�������s�k�C���̌���E�`���t�����A�ق��͔��̔w�E���A�{�̂� �\���̔w�E���A�{���i�ȏ�͏��������j�A���t�Ƃ����ׂās�k�C���̌���`���t�ƂȂ��Ă���B����́s�k�C���̌���Ɠ`���t����L�E��A�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A working title�Ƃ���Ή�������i���L�̏��e���쐬�����Ƃ��A�g���̎苖�ɓ����͂Ȃ������͂����j�B�s���܂�͂����L�t�̂��̌�̋L�q�����Ă����ƁA3�� 6���i���j�Ɏ��̂悤�ɂ���B���Ȃ݂ɂ��̓��́A�����L�ɓo�ꂷ��Ō�̓��B
�@���A������ ����{����֍s���B�O�K�̏o���Z�����ɒʂ����B�K���X����̎����͖��邢������B�������̎��ŁA�G���ЁA�o�ŎЂ̘A�����Q����ǂ�A�W�̐l�Ƒō� ����������B���߁A�l�K�̐H���ł��y���ɂȂ�B�[���܂Ő�������ƍZ���ɖv������B����Ђ����X�A�ō����ɂ����B�锪���߂��܂ł��������B��A���z�� �ӂ���B���̌�������A���͋߂����߂邱�ƂɂȂ����B�����\���~������Ȃ��Ȃ�̂����A�Ƃ�����������������ň���S���B�i�����A��O��`��l�Z�y�[ �W�j
���̒m���Ă���1980�N��̑���{����̏o���Z�����ƂقƂ�Ǔ����Ȃ̂ɋ������A�� �L�ɂ����Γo�ꂷ�����҂́u����Ђ���v�͉c�ƒS���҂������̂��낤���B��㊧�s�̏��Ђ̉��t�ł���������B���L�̑O�O���A3��4���i���j�ɂ́u�[ ���A�x���v�l����B�ΐ쏗�j�Ǝd���̑ō��������Ă���悤���B��������͖��S�ŁA�Q���ǂ݂ɔM�����Ă���B�v�l�͉������Ă��b�������Ă��Ȃ��B���炿�� ������������B�ΐ쏗�j��U���ċA���Ă������B�Z���ɂ��g������Ȃ��v�i�����A��O��y�[�W�j�Ƃ���A�����Ƃ��s�k�C���̌���`���t�̍Z����Ƃ����� �Ǝv����B�����A���̏��̂ǂ���T���Ă��A���s���g�����Ζ����Ă����������X�̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�����炭�В��̐����m�͂��u�ҏW�v���_�N�V�����v�Ƃ� �Đ���𐿂��������Č��������̂ł͂Ȃ����B�s���܂�͂����L�t��ǂނ�����A�g���ɖk�C�����Ƃ̃R�l�N�V�������������`�Ղ͌�������Ȃ��̂ł���B �s�k�C���̌���`���t�̍\���̊T�����ȉ��ɋL���i�����͌f�ڋL���̊J�n�`�I���m���u���ŁA�O�t�͋L�����Ƃɕʃm���u���B�����͐V���ɉ��߂��j�B
�q���r�i�k�C���������E�˒ˋ��Y�j�@��`�O
�q�����}�Łr�@�k���m�N�����G�ʐ^�A�����l
�q�k�C���̌���`�����z�}�r�@�k�܍��n�}��t�A�����l
�q�ڎ��r�@��`���
�q�}���}�ŋy�����}�Ŗڎ��r�@��`���q�� ��x���r�@��`�O�^�q�n���x���r�@�l�`�O��^�q�w�R�x���r�@�l�Z�`����^�q��u�x���r�@����`��Z�Z�^�q��m�x���r�@��Z���`��Z���^�q���x���r�@��Z ��`����^�q���G�x���r�@����`���Z�^�q�@�J�x���r�@��ꎵ�`����^�q�ԑ��x���r�@���O�`��O�Z�^�q�_�U�x���r�@��O��`��O�܁^�q�����x���r �@��O�Z�`��l�Z�^�q�\���x���r�@��l���`��O�^�q���H���x���r�@��l�`��ܔ��^�q�����x���r�@��܋�`��Z�܁^�q�D�y�s�r�@��Z�܁`��Z���^�q���� �s�r�@��Z���`�ꔪ�Z�^�q���M�s�r�@�ꔪ�Z�`���Z�^�q�����s�r�@���Z�`���l�^�q���H�s�r�@���l�`��Z��^�q�эL�s�r�@��Z��`��Z�O�^�q����s�r �@�Ȃ�
���t�@�k��Z�܁l
�u���a�\�ܔN�O����\�ܓ�����^���a�\�ܔN�O���O�\�����s�^�k�C���̌���`���@�\�S����\�^�ꕔ�@����~�\�K
�\�\�\�\�\�\�\�\
�� �ҁ@�k�C�����^���s�ҁ@�D�y�s�k��𐼌ܒ��ڈ�Ԓn�@�k�C���A�������@��\�� �吼����^����ҁ@�����s������s�J���꒬�꒚�ڏ\��Ԓn�@����Ё^���s���@�D�y�s���𐼈꒚�ڔ��Ԓn�@���{����o�ŎЁ^�������@�D�y�s���𐼎O���� �Z�Ԓn�@������Еx�M���@�d�b��\�Z�Z��Z�^����{���������Ј���v
�@
�k�C�����ҁs�k�C���̌���`���t�i���{����o�ŎЁA1940�N3��30���j�̉��t �i���j�A���E�{���i�E�j
���̂͂����ނˊȌ��Ȍ��㕶�i���ÐF������j�����A�Ȃ��ɂ͐X�L�O�s�� ���ӏ����t�� �v�킹��悤�Ȉ�i������A�Ƃ����ΖJ�߂������낤���B���Ȃ��Ƃ��u�����R�Ȃ����������������A�ȂĎ��lj������̋��y�����V�߁A���j�T�̈ꏕ����� �K�r�Ȃ�v�i�k�C���������E�˒ˋ��Y�q���r�A��y�[�W�j�Ƃ����ړI�͒B�������A�����̂ɂ�鋽�y�j�{�ł���B�{���ł͍Ō�ɓo�ꂷ��q�эL�s�r�̑S�� ���A���{�̑g�̍ق��Ȃ�ׂ��������Ę^����i�����͋������g�p�����j�B
�@�@�@�@�@�@��A�s�i��A�s�������j
��A���Ã`���}�g�[��ㅂ͂�B��
�@ ���N�\�������_�y�l�ԂɝDू��N��A�\���y�l�͑�s�����B���̌�Ăљ_�y�l�ԂɝDू��N��A���x�͓����y�l���s�R�����B�����đދp�ɕ���A���̋̂� �ߕ��s�����R�Ȃ炸�A���̕��Óy�l�{�Z���߂̏�����A�ɉH�̒����l�ĔV��H���A�ꎞ�𗽂��ŋ����B�Ƃ��낪�Ԃ��Ȃ��w�ʖ��O�ʂ�����đޘH���� �ЁA�I�ɓ����y�l�͏����ɐg�𓊂��A�M������҂����ɂɏ���B���҂��̏���y�l��Ń`���}�g�[���i�����B�������s�������Ƃ��ӈӋ`�ŁA���ɓy�l���͚��� �ɉ˂���ꂽ��A�s�̐��[�̔����A�`���}�g�[�����i���ċ���B�i�����l�\�N�\�\�ܓ�ᢍs�\���j��O�y��l�Łj�A�����̋��͑吳�\�N�����̏����� �āA�����𓌐��ɐ�㔂������ߜE�₳��č��͂Ȃ��B�ȂٔV�Ǝ��ʂ���A��̙B��������B
�� �̕��Õʂ̃`�z�}�g�[�Ƃ��Ӗ��̋N��́A�̋��H��k���̕��̜��҂ǂ������X�̛����𗩂߂Ę҂āA������Z�\�l���A���̏��̊����ƂĐH�ċ����Ƃ���� �̎҂ɍU�ߗ��Ă��A���ɔ�э���œM�ꂽ�Ƃ��납��A�`�z�}�Ƃ��Ӝ����Ƃ��ӈӖ��̖��������B�i�����l�\�N�O����\�������ÏU���c�E���i�a�����c���� �Y���̋g�c�ܒ����Ɉ˂�j
�吳�ܔN�\�ꌎ�O�����ÃA�C�k�����O�O���g�c�ܒ����̈�߂ɁA�u�̎��V�s�`�����i���̓��������̒n���j�̓G�O��Z�\�l���U�Ę҂����A���g�J�`���˔\ �҂ɂ���V�j�����A�\��l�͂��̏��ɒǍ��߂��ēM�����A���̈�l�͐h�����ăV�s�`�����ɓق����ւ���B�\��̉��˂����邩��A�Ђ�ւ�Ƃ� �Ӎl�Ń`�z�}���i����Ɏ����B�g�E�͏��̈Ό�ł���B
�吳�ܔN�\�ꌎ�O�����ÃA�C�k�̎句�ŁA�����V�c���R���ꡔq�n���A���̓�Ȃɖm���ď��K��n������Ƃ����B�V�A�C�k�͈�ꎂɏ��̖��`�z�}�̕s�g�����ւ� �̂ŃJ���C�g�E�Ɖ��i���邱�ƂɂȂ��Ƃ��ӂ��Ƃł���i�g�c�܍e�{�\�����_������揂̈�߁j�@ �Ȃٌ����`�z�}�g�E���̓J���C�g�E�i�_�����j�Ƃ��Ēm���T����́A��Ƃ��ě�A�s�������\�O�Ԓn�i�J�������Y�틋�o�n�j������\�ܔԒn�i�p���V���{�Z �����n�j�Ɍׂ�A���ڔ����闑�`�̏��ƁA�����̓�������\��Ԓn�̍ג���檞�t�`�ŁA�ؑ��̑p���������Ƃ̏������ɉ߂��Ȃ��B�R�������ɟ��Ε��߂͈�� �̌ΐ��n�ł��āA�����ɟk�镚�Õʁm�t�V�R�x�c�n�i�E��̋`�j�̎����ʂ�A�o�����̍ۂ͏��������㔂��ğ�䩂Ƃ����Ώ��ƂȂ�A���̌`���ߑ����邱 �Ƃ��o�҂Ȃ����₤�Ɏv�͂��B���̌㕍�߂̓y�n�̊J���T��笂Ď���ɐ�������A���ɍ����̏�Ԃ�悷��Ɏ����̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�ȏ��A�s�g�c�܋L�^�ɂ��j
 �@
�@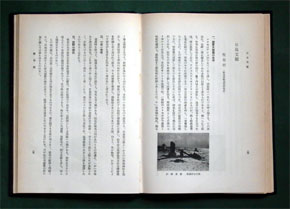
�k�C�����ҁs�k�C���̌���`���t�i���{����o�ŎЁA1940�N3��30���j�̔��ƕ\��
�i���j�A���E�{���y�[�W�i�E�j
�{
���̎d�l�́A���Z�~��܁Z�~�����[�g���E��l���y�[�W�E�㐻�z���i�����͏��������A���������j�E�@�B���B�{���̊�{�g��9�|�E53
���l�~16�s�E�s�Ԍ�
���B�c�g���������A�m���u���͓������B�{�����̎ʐ^�i�ڎ��ł́u�����}�Łv�j��90�_�ɏ��A�������̎ʐ^�ɂ̓^�C�g���̂ق��Ɂu���a�\�l�N�\�ꌎ��
�\�����^�Ìy�v�ǎi�ߕ����{�ρv�Ƃ������L�ڂ�����B
�s�k�C���̌���`���t�̑����҂͂͂����ċg�������낤���B���ꂪ�ǂ����悭�킩��Ȃ��B�Ƃ����̂��A�w�p���ɏ�����̍فi�e���E�㐻�E�����j�̖{���́A��
�������{�Ɏ茘���܂Ƃ߂���ۂŁA�ҏW�ҁE����ғƎ��̔z�u�m���C�A�E�g�n���f���Ȃ��̂��B�����̏������́A�N���W�b�g���Ȃ����̖̂k�C���������E�˒�
���Y�������ŁA�g���̏��̉\���͂Ȃ��B�v���Ɍ��e�����A�O�t�i�q���r�q�����}�Łr�q�k�C���̌���`�����z�}�r�q�ڎ��r�q�}���}�ŋy�����}�Ŗڎ��r�j�E
�ʐ^���܂ޖ{���E��t�i���t�j�̎w��A�����čZ�����g�����̒S���������̂ł͂Ȃ����i�{�̂���є��̑����͒N���ʐl�A���Ƃ��ΎВ��E�����m�͂̉\������
��j�B��Ƃ͈̔͂����Ȃ����ς����Ă��A���e�����͋g���̒S���ł���A400���l���e�p����430���̂����������̎��M�҂̏������낵���ɂ߂ĒZ���ԂŊ�
�s���邠����A�����̎d���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������N�x���[�i�Ƃ͂����A���e�����ɖv�����Ă���킸��1�ӌ����Ŋ����Ƃ����̂͋��ٓI�ȃX�s�[�h
�ł���A�����ē���20�̋g�����̏��ЕҏW�҂Ƃ��Ă̗͗ʂ�������݂�ׂ��ł���B
�k�t�L�l
���i���F�̖����̒��я����Ɂs���̗ցt������i���₷���ł́s���i���F�S�W�k��12���l�t�A�V���ЁA1987�j�B����ɂȂ����k�C���̉ˋ�̊X�u���m��
�т���n�v�ɁA���i���I���̈�~���߂������эL�m���тЂ�n�����e���Ă��邱�Ƃ͑����Ȃ��B�s���̗ցt�Ɍ���`���I�ȋL�q�͂Ȃ����A�ꌩ��Ⴂ�ȃA�C�k
��[�J���ւ̌��y�͐펞���̓��{�i�l�j�𑊑Ή����鎋�_�Ƃ��ĕs���ł���B���i�����̒��т������ۂɁs�k�C���̌���`���t���Q�Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ�������
�낤���B
�g �������Ⴂ����ɒ����Ƃ������Ƃ́A�{�l�����т��я��������k�b�ł����y���Ă���̂ŁA�悭�m����B�������̗��`������ɐG��Ă��邪�A�g�����M �́q���`�r���́u�����Ƃ݂ĉʂ����B�v�i�s������{�����W�听 11�t�A�����n���ЁA1960�N9��10���A�k�O��Z�y�[�W�l�j�����̗��[���낤�B�㑱�̗��`�ɂ�
�Ƃ���i�s�q�g�����r�l�ƍ�i�t�Q �Ɓj�B�����Ƃ̖����j��āA�@�㏑�o�œ�R���Ζ��A�A �������Ɗw�Z�i��ԁj�ʊw�A�B���w�����ǐ��ǁA���O�Ȃ��瓯���i�s����`�ŁA�Z�́E�o��E���Ȃǂ̕��w��i�̑n��͂��̌�̂��ƂɂȂ�B���l�E�����Ƃ� ���Ă̋g�����́A���ʂ̃I�u�W�F�� �����Β����͂��납���\���ꂽ�`�ł͊G����c���Ă��炸�A���`��i�𐧍삵���`�Ղ͂Ȃ��i���������A���p�������A�����ȊO�ɂ��������c�����Ƃ����_�ŋ��� �������C���Ƃ͂������قȂ�j�B�����Ƃ̖��ׂ͒����܂ܕ��シ�邱�Ƃ��Ȃ������̂��B���܈�x�A�g���̒k�b����T���Ă݂悤�B
���`�ւ̊�]�͎����������Ƃʼn��������A�Ƃ����̂��g���̏o�������_�ł���B�ł́A���z�Ȃǂ̎U���ɓo�ꂷ��u�����v�u�����Ɓv�͂ǂ� ���낤���B�� ���A�W���̐����́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�̃m���u���B
�� �p���ɂ͍��������Y�i1883-1956�j�AAuguste Rodin�i1840-1917�j�A����a�Y�i1930- �j�Ƃ����ŗL�������������Ă��āA���h���I�̒�������x�o�ꂷ��B���ڂ��ׂ��̓��_�������A���_���̒�����i�ɑ��ċg���͑z���̂ق���W�ł���B������ �������i�Ɓj�ւ̋��������s���_���t�ɐG�ꂽ�g�� �́A�v�������������P�̂��ƂɎ䂫�� ���Ă������B���ꂪ�A��O������ɂ����Ă̋g�����̋O�Ղ������B���Ȃ݂ɓ����́A�g���������̍ۂɌg�����O���̂����̈���ł���B
�@ ���āA�����P�́w���_���x�ł��邪�A�������_���ւ̎��l�̏����ȍ����A�����ɌX�|���Ă��������́A�����̏��ł���B�������A���ɂƂ��ẮA���_���̈̑傳 �́A�ǂ��ł��悩�����B�����ȋ�Ԃ֒����܂ꂽ�悤�ȁA�����P�̌��t�\�\���̂̍��A�����A���B�߂̊ØI���ɋ�̍�����̂ڂ��čs���A�d���݂̂��������̂� ���ɖ[�Ȃ��`�ہ\�\�Ƃ����悤�ȉA�e�[�����I���̂ɁA���͖�����ꂽ�B�i�q�����P�w���_���x�\�\���̈���r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A 1988�A���y�[�W�j
�����P�́s���_���t�ɊJ�Ⴕ�ās�Õ��t�i1955�j���������g�����A���������Y�̒����ɂǂꂾ���������ꂽ���͕s���Ƃ����ق��Ȃ��i�} �����[�ȑO�� �Ζ���E���m���̎В���Ɋ������ۂɁA�s���������Y���W�t��Y��Ȃ������g���ł͂��邪�j�B�Ō�Ɏ��т����悤�B
�ނ��ȊO�ɂ������Ƃ͎��тɓo�ꂵ�Ă��āA
��Jean Arp�i1887-1966�j�ALouise Nevelson�i1900-88�j�AHenry Moore�i1898-1986�j�AHenri Laurens�i1885-1954�j�Ȃǂ����݂̍�Ƃ��B�������A�Ȃ�Ƃ����Ă��q�`�͕s���̉s�p�������c�c�r�̑莫�u����̏��L�҂͗J�D�Ƌ����ɐS�� �I�܂��v�̍�ҁE�ѓc�P���i1923-2006�j���킷��킯�ɂ͂����Ȃ��B�O�f�u�w�Ẳ��x�̎��т̑����́A�e�����k�c�c�l�����Ɓk�c�c�l�����̌� �t���A���p���Ă����Ă���v�̒����Ƃ͔ѓc���w���̂�����B�ѓc�͕��M�ɗD��A�q�q��[�G�j�O�}]�r�Ɍ����ā\�\�g�����r�ŋg���������u�C���E��g�E �Úg�E�z���E���o�E�����ėd��������̓��̂܂ł��t���̊�@�ɎN���Ď����Nj����Ă������́A�����g�����̂�̎��@�������������Ƃ��ł��Ȃ��Ɩ������Ă��� ���̎��@�̔�߂�ꂽ���e�B�[�t�́A�u���E�̓�v�ɂ��Ă̌����ł������v�i�s�����̎v�z�t�A���X�A1995�N10��20���A�O�Z��y�[�W�j�Ɗ��j�� ���B�������A��l���k����܂́A�����������③�`��i�ɂ��Ă̘b�肪���������̂ł͂���܂����B�����ɂ��Ė���āA�ѓc���嗪���̂悤�ɋg���� ������Ƒz�����邱�Ƃ͋�����邾�낤�B
�@�������G��ƈق�|�p�ł��邱�Ƃ��͂����莦�� �ЂƂ́A���ꂪ��ʂƂ�������̓����ʂɎ��Ȃ����肵�Ȃ������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�����Ƃ��ĎO�����̗��̂ł���A�l�͂��̎��͂��� ��������A����Ɏ��G�ꂽ��A�Ƃ��ɂ́A���̉������������������B���z�Ǝ��Ă���̂͂��̓_�ł���B�^�܂��A����́A�E�u�����Y�E�S�E���E���̑��� ���錻���̕�����f�ނƂ��āA����ڐ��`���邱�Ƃ����i���o�����B���̂��Ƃ���A�����͂��łɁu��i�v�ł���Ɠ����ɁA�����̋�Ԃɒu����Ă� ����E�Q��E�C�E�d�C�X�^���h�ȂǂƓ����́u�����v�Ƃ��ċ�Ԃɑ��݂���B�^����ɁA�u�G��v�����̃C���[�W����������҂ɋ������鐫�������̂ɑ��A �u�����v�́A����҂ɂȂɂЂƂ������Ȃ��Ƃ�������B���̂��Ƃ͒��������̂Ƃ��đ��݂����ʂ����邱�Ƃ���Ă���B�i�ѓc�P���s�����Ɓ\�\�n���� �̏o���k��g�V���l�t�A��g���X�A1991�N5��20���A�O�l�y�[�W�j
�@���[�A����\���I�̐l�Ԃ���ޓI���ʂɊ���������� �́A�s�J�\��W���R���b�e�B�̍�i�̎������������̂����m��Ȃ��B����ɂ��Ă��A�����̎����A�����Ĉ��p�m�A�A�n���烀�[�A�͎����̃C���[�W��y������ �Ƃ���܂ʼn^��ł���B�����̂Ƃ��낪�A���[�A�̈̑傳�ł���B�^���p����ҁA���p�ł���҂͖����ɂ��邪�A���p�̒n�_����A���p�̊j�����[���A�傫 ���A�ЂƂ̓Ƒn�̃C���[�W�ւ܂ʼn^�����A��Ă����邱�Ƃ̂ł���҂́A���łɕ��}�ł͂Ȃ��B�i���O�A���l�`���܃y�[�W�j
�@�G�o�͎v�l�␄�ʂщz���āA�������̂��̖̂{����`����B�G�o��}��Ƃ���Ƃ��A�����̕\�w�Ɠ����Ƃ͋�ʂł��ʑS�̂Ƃ��� �ꋓ�ɔF�m�� ��A�c�������B�ꋓ�ɔF�m�����Ƃ����A�G�o�̂��̒��B���A���ڐ��A�����������̐��̊�w�𐬂����̂��B�i���O�A��O��y�[�W�j
�g ��������]���āA����ɂ�钤���A�ƌĂԌ���������B��������́A����̓W�J���䂫�N�������e��̉��ʂɂ��̂ł��Ȃ���A�܂��Ă⊇�ʗނ���绂��� �s��ʁt���^�̎��o��̒i���ɂ��̂ł��Ȃ��B�G��̂��C���[�W�������A���Ȃ킿�u���E�ꂷ�鎖���̕���萫�v��˂��āA�����̎����u��̕��̂� ���ċ�Ԃɒu����v�i���O�A�O�܃y�[�W�j���������炵�߂邱�ƁB���ꂪ�ӔN�́A�Ƃ�킯�s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�̎��т��т��g�����̎p ���ł���B�g���͂��̂悤�ɂ��āA�����Ƃ����Ƃ��鏉�u���I�ȏ���̂��������������̂ł���B
���W�̂悤��
�@�@�@�@�@�@�i�S�̒����́j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̓����ɂ����Ȃ݂̗���
�ł�����܂�
�@�@�@�@�@�@�ڂ��͎v�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u������鎆�̏��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f�b�T������v
�i�q�H�̗̕��r�K�E5�A�����j
�g���������W�s�Ẳ��t��1979�N10��30���ɐy�Ђ��犧�s���ꂽ�B����i28�т����߁A���W���s��ɔ��\���ꂽ�q�~���̓����r�i1979�N11���j�Ɓq�u�Ɣ�������v�r�i1979�N12���j��2�т������āA�q�y���r�i1976�N8���j����q���̐��̉ār�i1979�N8���j�܂ł̑S26�т��{���W�ȑO�ɎG���E�V���E���ЁA���邢�̓z�[���ǖʂɔ��\����Ă���B�Ȃ��A�q�~���̓����r�Ɓq�u�Ɣ�������v�r2�т̌��e�́A���W���s�ɐ旧���Ċe�}�̂Ɍf�ڂ��\�肳��Ă����ƍl�����邽�߁A�e�}�̌f�ڌ`�����o�Ƃ��Ĉ����B�{�e�ł́A�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���E���Ќf�ڌ`�A�Q �s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j�f�ڌ`�A�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����R�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�Ẳ��t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B�Ȃ��A�������V���̖{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs�Ẳ��t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�F���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ���2010�N6���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������B
�P ���o�G���E�V���E���ЁF�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B�{���̕\���͊�{�I�ɐV���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�Ȃ̂ŁA���L�Ȃ��ꍇ�͂����\�킷�B
�Q �s�Ẳ��t�i�y�ЁA���ł�1979�N10��30���k�Z�ق̒�{�ɂ͍ŏI�����{�ł���1980�N2��15�����s�́u��Łv���g�p�����l�j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|�k�U�����^�̕����ł�22���l�l14�s1�i�g�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|�k�U�����^�̕����ł�22���l�l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q �s�Ẳ��t�B
���т̐ߔԍ��̃A���r�A�����E���[�}��������уA�X�e���X�N�̈ʒu�i�������j�͍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������i�莫�⎌���E���L�̎��������s�g�����S���W�t�ɍ��킹���j�B�P�s���W�ɂ́k�Q1976�`1979�l�Ɛ�����Ԃ̕\��������B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�s�Ẳ��t���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s�������t�k���s�����l�f�ڔN�����i���j�k�i���j���l�j
�y���i�H�E1�A31�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1976�N8�����k19��9���l�j
�����i�H�E2�A34�s�A�s�V���t�k�V���Ёl1976�N12�����k73��12���l�j
���i�H�E3�A40�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1978�N7�����k10��8���l�j
�q���̋V���i�H�E4�A56�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1976�N10�����k15��10���l�j
�ٖM�i�H�E5�A31�s�A�q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�i�؉�L�A1977�N5��31���j
�����i�H�E6�A5��86�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1977�N11�����k16��11���l�j
�Ӊ��i�H�E7�A22�s�A�s���s�ʐM�t�k���s�ʐM�l1977�N10�����k164���l�j
���i�H�E8�A66�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1976�N11���Վ��������k8��13���l�j
���̖��{�i�H�E9�A6��100�s�A�s�r�c�����v20�N�̑S�e�t�A���p�o�ŎЁA1977�N11��3���j
�����`�i�H�E10�A63�s�A�s�C�t�k�������_�Ёl1977�N5�����k9��5���l�j
�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�A�V��52�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1978�N4�����k21��4���l�j
���E���邢�͉��i�H�E12�A35�s�A�s�J�C�G�t�k�~���Ёl1978�N8�����k1��2���l�j
�����i�H�E13�A38�s�A�s�����̈�Q�t�k�C���Ёl1976�N12���k�~�E2���l�j
���J�̎p�������i�H�E14�A8��126�s�A�s�C�t�k�������_�Ёl1978�N5�����k10��5���l�j
���i�H�E15�A17�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�l1978�N1�����k32��1���l�j
�D���̎O�̒[�z�i�H�E16�A����3�߂��]����74�s�A�s�G�s�X�e�[���[�t�k�����o�ŎЁl1978�N11�����k4��10���l�j
������i�H�E17�A5��84�s�A�s�C�t�k�������_�Ёl1979�N5�����k11��5���l�j
�g���i�H�E18�A6��67�s�A�s�V���t�k�����Ёl1977�N8�����k24��8����292���l�j
����ȏt�̗��i�H�E19�A43�s�A�s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1977�N1��17���k1889���l�j
�Ẳ��i�H�E20�A�Y��120�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1978�N10�����k17��10���l�j
���i�H�E21�A12�s�A�s�X�����̎��݁t�k�n���S���c�������_�{�O�w�z�[���ǖʁA�p���t�����X�l1979�N6���`8���j�A���̃A���\���W�[�s�n���S�̃I���t�F�t�i�I�[�f�X�N�A1981�N4���k���t�L�ڂȂ��l�j�ɍĘ^
���̃A�X�e���X�N�i�H�E22�A��������58�s�A1978�N3��20�����̋��q���`�ʼn�W�sLE REVE D'ALICE�\�\�A���X�̖��t�i�p�쏑�X�j�o�ňē��J�^���O 1978�N2���j
�r���i�H�E23�A37�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1979�N7�����k11��9���l�j
���̐��̉��i�H�E24�A20�s�A�s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1979�N8��20���k33641���l�j
���q�A���i�H�E25�A40�s�A�s���̌���t�k�u���̌���v�Ɂl1979�N3���k9���l�j
��̊G�i�H�E26�A17�s�A�s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1979�N1��5���k13124���l�j
�u�Ɣ�������v�i�H�E27�A55�s�A�s���������\�\����C���Ɂt�A�u���������v���s��A1979�N12��10���j
�~���̓����i�H�E28�A6��85�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1979�N11���Վ��������k11��14���l�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1976�N8�����k19��9���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A31�s�B�g���͐��z�q���ƏҊ��r�́u�Q�@�Ҋ��v�Ŗ{�т����p���āA����̔w�i�ɐG��Ă���B
���͂�������p����
���l�̌��t�ł����p���ꂽ���̂�
���łɉ�������
�u�A���̑S�̂͗n����
�k�P�i��ꉺ�j���Q�R�i�܉��j�l���̉��k�P�Q�����R竉�l�̉�������
�k�P�i��O���j���Q�R�i��j�l�ԁX�͐��܂��v
���ċߐ��̏��A���w�҂͂��̂悤�ɏ�����
�D�F�̐�̂ӂ��ɗ���炭
�S��̉ԏҊ��͂܂��
���̐܂ꂽ���̂悤�ȉԕق𐂂炷
���V��̊y���̂Ȃ���
���͕s�����n�Ƃ����H�ׂ��̂���
������܂�鏬����{��
�����Ėϑz�����肩����
�V������o���̂悤��
�ؔn�ɂ܂�����
������ɂ���
�u�l�Ԃ̑S�̂͗n����v
�����鎞�_�Œn�̏�ɉ�����邩
�@�@�@�@�@�@���̏�ɉ������Ԃ�
����Ό���قǔ����Ȃ�
�u�M���D�̈ꐷ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���v
����͉i���ɉ^���ł��ʂ������
���̐��ɂ܂��p������s�˂�l������Ƃ�����
���́k�P�����Q�R�S�l�l�ԓI�Ȑl�̔w���
�V������Z��͒ʂ�
��̂Ȃ���ɂ܂�����
���̔g�ɏ��
��m�G�j�O�}�n
���͍݂�
���o�́s�V���t�k�V���Ёl1976�N12�����k73��12���l��l�Z�`��l���y�[�W�A�{��9�|21�s1�i�g�A34�s�B�J�b�g�F�����G�q�B
�o�̂Ȃ���
�u�Ђ��������
�k�P�i�����j���Q�R�i�����j�l�Ȃ��炦��悤�Ɂv
��l�̏��͌��������Ă���
�|�`�͗l�̕~���̏��
�i�������Ƃ��ɉ߂����߂�
�C�ӂ̋����͂��������
�N��̍����鏗��������悹�Ă���̂�
�����炩�ɔ�F�̈�{�̖ю��ł�����
�q�y��m�t���[�Y�n�r�ł͂Ȃ�
����͌����Ȃ���
�؈���ʂ�
�X����ʂ���
�u���͖łт邩
�k�P�i�����j���Q�R�i�����j�l�܂��͕ω�����v
�k�P�i�i�V�j���Q�R���́l�n���
�������Ă���̂�
������l�̎Ⴂ���̏�������
�q�j�m�R�A�n�r����
�ю��̋ʂ̂悤�ȕ�����
�Ђ��̊Ԃʼn�]����
�G�ꂽ�芣������
����͊O������k�����Ă䂫
�₪�đ��ނ��
�ւ̂��Ƃ�������
��l�̏��́q�����r�Ƃ����T�O����
�Ƃ��͂Ȃ����
�u���܂ł͏ۉ�̂悤��
�k�P�i�����j���Q�R�i��j�l�Î~���Ă���v
������������
��l�̏��̂���͕̂����̓�
�Ƃ�������
���̉��͒���������ʂ��Ă䂭
��I�̂悤�ɂ����v����
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1978�N7�����k10��8���l���`��O�y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A39�s�B
�u��C�̖I���u�[���Ɣ�т܂���Ă���v
���V�̎�k�P���́��Q�R���l
�k�P�܂Ђ�܁��Q�R�i�g���j�l
��R���z��
���P�������ĉ���������Ă���
�k�P�i�i�V�j���Q�R�S���悤�Ɂl
�킽���̍D���ȃA���X�C�X�g
�@�@�@�@�@�@�@���s�X���Y��
�@�@�@�@�@�@�@�k�P��̐����Q�R�i�g���j�l
�ɑ����̏@����Ƃ�
�u�������k�P�~���Q�R�I�l�̒�������ĕ��ށv
�k�P�������Q�R��l�̂��߂�
�V�l�����̉Ԃ�O�i��
�`������
�u���킵�̂悤�ɂ₹��
��e�v
���琶�܂ꂽ
�^�[�N���[�Y�̂悤�ȁk�P�i�Ǎ��j���Q�R�i���s�j�l�����̂��߂�
�������̎�l�͎��̔n����߁k�P�i���s�j���Q�R�i�Ǎ��j�l
������k�P�i�Ǎ��j���Q�R�i���s�j�l�\�O��
�Ƃ̉��������Ă���
�u�l���̂Ȃ��ɂ���
�p�тɂӂݖ����v
�k�P�i�i�V�j���Q�R�j�Ɓl
�Ȏq�͏���
�������̗t�ł������ނ��Ă���
�܂�Ŗn�G�̂悤��
���Ȃ݂Ȋ��p�傾��
�u�܂͕S����
�o���̊Ԃɗ�����v
��������ނ���
�S�����̂悢�҂�
�Ԕт�H��
�����h�̉����������܌���
������
�u���l�͖��̉����}���v
���k�P�����Q�R�i�g���j�l�_�̊O��
�����났�͖�
�u�ׂ��d������v
�ΖȂ≔��
�݂낭�ڂ��͑n���Ă͂��Ȃ�
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1976�N10�����k15��10���l��Z���`�ꎵ��y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A56�s�B�{���J�b�g�F�쒆�����B
�킽���̓`���[�N�ō��ɕ`��
����̕��̑��Ǝw
���ꂩ��o�i�i��ςޏM���c�c
��͈��̒��ɂ̂��čs��
�q�˂��Ă��邾�낤���H�@�A�X�^���e�̖�
�u���H�ɗ������ׂ鏗�v
�u�h���C�A�C�X�̔��������v
�M�тł͌��̕@�������Ȃ��Ȃ�
��̖є�p��z���o��
�ΐقNj����Ȃ錊�̂��������́m�A�A�n
�킽���͉d���łȂ����݂̎p��
���̕��̂悤�ɗ����Ă����̂����m��Ȃ�
���炪�˂̓��ŔF������
�q���r�̂Ȃ��ɂ͌��������������̂���݂���
����������␅
���͑r���̈�
�u�C�R�����̂悤�ɑ��ڂ��炽��Ă���v
�l�͂��̂悤�ȔM���鏗��Y��Ȃ�
�킽���͉t��̂��̂˂���
��̋C�z�̂��߂����ԉʂ̖�����
�A���}�W���͉��ꂽ���̂Ȃ��Ł@���炾���܂�߂�
���F�̏ۉ�̋ʂ̂悤�ɗ҂�������
�Z�́u�ȕz�ƎO���̉H�ł���܂����S���v
�ł���ꂽ�P�ʃt�H�����@�S�˂Ŕ���čs����
�ΊW�@�����Ԃ��͔�����
�킽���̖�䰂��y��
���r���̂�����̌҂���̈ł�
���䏤�l�����E�|�E�Ӟ���ɗ���
�����Ύo�̐����юp�������܌���
�u����ɉԍ~�艹�y�������@�썁�l���ɌO���v
�u�V�l���@�H�Ȃ����̂��Ƃ��Ɂ@�オ���Ƃ���Έ߂Ȃ��v
�̊����́q�H�߁r�I�Ȑ����̏t�ł�����
���͒ўւ�H�I���
�u�k�P���e���Q�R�o�n�ƃo�P�c�l�𗼎�ɂ����ĊX���o���v
���̌�����Â鎮�̖��͉��k�P�H���Q�R�i�g���j�l�@���̗t�̘I
���͒n��ɋA��Ȃ�
�����`���ɂ���
�u���̏�����������q�͔���
�悭��������v
�傫�ȓ~�Z�ɂ܂����閺����������
�킽���͕��G�ȍ\���̂��̂͌�����
�P���Ȃ��̂�
���̌��𗁂тĂ悭������
�k�P�P�V���Q�R���l�̉Ԃ̂����ŔԐl�v�w�����Q���Ă���
�킽���̋��߂Ă���̂�
�k�P�u�������j�v���Q�R�i�g���j�l�s�D�̕�Ȃ̂��k�P�H���Q�R�i�g���j�l
�u�l�Ԃ̎�̉����琶�܂��v
�S�y�̏��g���͔����̋�����
�J�[�f�B�i��
�����鏗���F�̂悤�Ɍy�₩�ɏ��̎}�ɂƂ܂�
�Ђ��̔g�����̂��̂�
�u���łȂ��ɂ���ė{����^�����Ă���v
�T���S�F�̍Ւd��
�u���E���܂̂Ȃ��ɖ߂�v
���܂Łk�P�i�i�V�j���Q�R�i�S�p�A�L�j�l�҂Ă悢�̂��낤���k�P�H���Q�R�i�g���j�l
�킽���̊�͂܂����J�̏�Ԃ̂܂܂ł���
���o�́q�w���}���E�Z���G���g�W�r�p���t���b�g�i�؉�L�A1977�N5��31���j�A�k�O�y�[�W�l�A�{��15��16�s2�i�g�A31�s�B�Ȃ����o��25�s�߁u���v�������i�r���A�ł͂Ȃ��u��v�j�ň���Ă���̂́A���e�̎��`�𒉎��ɍČ��������߂ƍl������̂ŁA�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B�s��z�t�Ę^�y�[�W�̊G�́A�Z���G���g�́q�W��r�Ɓq�y�e���t�r�i1976�j�B�����ɖ{�т��u1974�N�W�p���t���b�g���v�Ƃ���̂͌��B
�q�ٖM�r�i���o�`�j�̍Ę^�@�o�T�F�s��z�t��19���k���W�����z�̔��l�i�y���g���H�[�A1986�N10��17���A����`���O�y�[�W�j
�@�@�@�@�k�P�i�i�V�j���Q�R�փ��}���E�l�Z���G���g�̊G�ɂ悹��
�����̔Ԑl��ⴂ������ŋA���Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ�Ƃ������
�킸���ɘm�˂̂Ȃ��ɑ��݂���
�Ɓk�P�����Q�R�n�l��
�q���͓����҂ɋ߂Â��r
�s���l�͗��𗹂��ċ������ɓ���
�̕ǂ̋T��͐[��
�O�̋�̂悤��
��l�̘V�l�̎�̂Ȃ���
�v�l�̂ʂ�����
�̎�
��̎�t�������ނ�
���̂ƂȂ�̏��͔�����
���[�Ƙr�����Ă���
�e�[�u���̉��͈Â����ނ�
�k�P���́��Q�R�i�g���j�l���ʂ����Ԃ���
�܂��͖ڂ�������
�~������@���Ɩ�
�k�P���ꁨ�Q�R���l�͂��łɒ��̖e���̂���
�≖�̈ꗱ�����
�q�H�@�l�r�̖M�֔�ї���
���܂́k�P�Qꡁ��R�y�l���ɂȂ����ԍ炭�y�n
���I
�͎}�ɂ͋��̍����������Ă��k�P�遨�Q�R���l
�����̂Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�����̎q��S��������
�@�@�u�b�艮�̑O��
�@�@�@�@�@��m����l�ɂȂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��l�ɂȂ���
�@�@�@��̓����牌���̂ڂ����v
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1977�N11�����k16��11���l��Z�l�`��Z��y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A5��93�s�B�{���J�b�g�F�������ǁB�g���͋�����b�q�Ƃ̑Βk�ň��p���ɂ��āu���b�q��`�����u�����v���A�N�̌��t�����ł́A���܂������Ȃ��̂ŁA���͔ѓc�P���̃G�b�Z�C���������ؗp���Ă���B�����A�ڂ��������Ă��������̂́A������̎��т����傩��͂Ƃ��ĂȂ���B����݂͂�ȑΏۂɂȂ����l�̃G�b�Z�C����Ƃ��Ċ��ʂɂ���āA��������ɂ����Ă��Ă���v�ƌ���Ă���B����̒Z�я����q���r�i���o�F�s���|�W�]�t1978�N�~�k1���l�A�P�s�{�F�s�P��W�t�}�����[�A1979�j�ł͑莫�Ɂq�����r����܍s������Ă���i���o�ɂ͂Ȃ��j�A�{���ɂ��u�킽���́u���Y�v�̏\�ꌎ���̋g�����̎���ǂ�ł��āv�Ƃ����L�q������B����ɂ́q�����r�i���o�F�s���Y�t1980�N1�����A�P�s�{�F�s������鐅�t�W�p�ЁA1981�j�Ƒ肷��Z�я���������B
�@�@�@�@�q���̛̂s�ޖ��͂��ɑ��l������߂Ă���r�@������b�q
�@�@�@1
�u�₽���X�[�v�̓������K���X��
��̕\�ʂ�
���������H�̓܂�v
�̉�
�킽���͌`����I������
���ɂ��镃��
�e�̊��Ɏ��߂�
�q����̏����r�k�P�i�i�V�j���Q�R�́l�ЂƂ�
�i�i�C
�얳�I
���݂͂����@���݂�����
���q�Œn��֖߂�
�����ēǏ���
�g����������ߌ�
�@�@�@2
�u�Ñ�̐_���̂܂Ƃ�
���߂̎��v
�̂悤�ȓ��p�V����q���[���E�W�F���[�r
���Ȃ킿�~�Y�N���Q�̂ނ�
�����̎q�G�t�B��
�܂��������B�����ƂȂ�
�|���v
�[���̔g�Ԃ�
�u�����q�̓����̂悤�ȏ_����
�ۂ��N���̐��E�v
����
�ϔO��s��
�킽���͖����߂����ĉj��
�u���Ƃ��Ă̖��v
�Y���䂭�q���[���E�W�F���[�r
�����Ȃ����
�����
���_�G�A
�@�@�@3
�u�k�P���҂����҂̍��֔��с��Q�R�i�g���j�l�k�P�i���s�j���Q�R�i�Ǎ��j�l
���ҁi�j�j�ҁi���j�̍��ĂѕԂ��v
����������
���y�k�P�m���Y���n���Q�R�i�g���j�l
�̕�
�V�䂩�琅���|�^�|�^�������
�킽���̓t���C�p����Ȃ���v��
�u�l�͓��̂ɂ���Č������
�����Ō����v
���������щz��
�q�Ɣ��r�Ɓq�f�Ёr�����c����
�����̒j�����͎���ł䂭
�u�D�w�͐^��������
�w�i�ɂ́k�P�i�Ǎ��j���Q�R�i���s�j�l��̑ۂނ�����ꂱ���ׁv
����͊G�ł���̂��낤���H
�u�̐��E����������҂͎����v
�킽���͎��ɂ̔����̂Ȃ���
�m�[�g������
�k�P�u���ƌ���Ȃ��悤�ȁ��Q�R�i�g���j�l
�k�P�q���r��M�p���Ȃ��v���Q�R�i�g���j�l
�k�P�܂��āq���r�͂Ȃ����炾���Q�R�i�g���j�l
�k�P�u�S�̒��ɂ��������悤�̂Ȃ����Q�R�i�g���j�l
�k�P��������Ȃ���Q�R�i�g���j�l
�k�P���̕��������Q�R�i�g���j�l
�k�P�킽���͔��ɋ߂Â��遨�Q�R�i�g���j�l
�@�@�@4
�킽���͂ʂ邢���M�ɂ���
�p�������������Ă䂭�̂�
�����Ȃ���
�u����鐅�̖ʂ̒��
�̂悤��
���̑��݂����킾������v
�G�S���E�V�[����
���U�Ə͋��z���o��
�u�l�͉Ă̐����
�H�̎�����������v
�܂�ł��̉Ƃ�
����̂悤��
�����炳�߂����
�k�P�������Q�R�����l��
���t��
�݂��������Ă���
�����킦���
�����̉Ԃ̂͂邩����
�킽���͊ዅ�ɓ_�H����k�P�i�i�V�j���Q�R�Ă��l��
�@�@�@5
�u�Ȃ��킽���͉�����͂��Ȃ�
�H���̏u�Ԃ�
������ꂽ�̂��낤�v
���l�̖��̂Ȃ���
�u�����Ă���ȏ�N�����v
�킽���̎��ȔF����
�����Ă݂��
�u���̊ϏƂɏI��Ƃ������̂��Ȃ��v
�悤�ɏH����~��
�u�����̕��q�̊Ԃ�ʉ߂���v
�M���҂������
��y��
��
���̂Ȃ��̉f��͗������\�\
�킽���͋��S�n��
��邢������
�~�̗��̃V���G�b�g�߂�
���o�́s���s�ʐM�t�k���s�ʐM�l1977�N10�����k164���l�́q�\���̎��r���`��y�[�W�A�{��18�p22�s1�i�g�A22�s�B�ʐ^�F�ޗnj��ꍂ�B
�Ă�����Ȃ�
��e�̓v���[�c�̃X�J�[�g��
�Ђ�Ђ�g��������
���ʂ��Y��
����������I�̉���
���ɔ��������q���Y��
�́k�P�����Q�R�C�l���̒���
���ꂱ���l�Ԃ��s���k�P��]�I�ȁ��Q�R�i�g���j�l�V�Y�k�P�i�i�V�j���Q�R�̈�l
�J�ɑł���
���z�͒��݂䂫
���R����
���e�͐��k�P��Q�R���l�̑��𐂂炷
��̕R�̂悤��
�u���̂͂��������͂���
��������v
�M�̒��
�߂����J�i�����̖�
�ł̏H�Ƃ����炶
�I�̍b���k�P�i�i�V�j���Q�R��l
�I�̟{
�u���G�Ȃ��̂����P���Ȃ��̂�
�悭�P���悭��������v
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1976�N11���Վ��������k8��13���l���`��܃y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A65�s�B���p����Ɋւ��Ă��q�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�u�̏������悤��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�̓��ށv
�k�P�����Q�R�i�g���j�l�H�ׂȂ���
���璆�N�̒j�͑��k����
�L�邱�Ƃ��疳�����Ƃ܂�
���E���E���E��E���E��
�u����ȉC���͂��肩����
�Ă͂����Ȃ��v
���������Ɉ������Ƃ��K�v��
�䂦�ɋ�C������p����
�u�s�A�m���t�̂悤��
�k�P�i��ꉺ�j���Q�R�i��j�l�����k�̂�����։��v
���̓~�̖��
�u�������ĕ����Ă��Ȃ�����̐��v
�X����������@�Ă��肪����
������̊K�i���~��
�n�シ�ꂷ�����
����
�u�ꖇ�̎������܂��[���̂�������
�K���������Ă��Ȃ��v
�k�P�����Q�R���l��ߑ㎍�l�͒f������
�u�W���X�p�[�E�W���[���Y�̍�i�ɂ͂���
����E�l�@����E�C��
�����̊���������v
���q�I��
��̒�����g�ݗ��Ă�
�p��Ɨp�����˂�
���Y���s����g�ݗ��Ă�
����ɂ����
�u���݂̓��H�M�������Ƃ͂��Ȃ�ق�v
�������̂�����
����͎��R�Ȃ��Ƃł�����
���Ԃ�[��������
���璆�N�̒j�͏����ŏƂ炳���
�u�傫�Ȏ\����C
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̕ǂ��璊���o���v
�����͐���邾�낤��
賂̉H�̋P���X�̋�́\�\
���Ɋ������ꂽ
�̊�
���ꂪ�₪�āk�P�Q�����R�M�l��n�֒u����鎞
������Y�}���o����
�u�k�P�J���J���ƃQ�^���Q�R���Ƃ͔������ې�����l
�k�P�͌Z��ł���̂��H���Q�R�Ɠ����Ɉ������ې�����l�v
����͍l���R�[�q�[���̂�
�u�J�������l�X��
�k�P�i��ꉺ�j���Q�R�i��j�l���Y�̂悤�Ȋ�v
�k�P�����Q�R�i�g���j�l���邩������Ȃ�
�g�߂̖����Ă��鏈��
�C���ӁI
�P���Ȍ`�ƐF�����肩����
�_�̕�k�P�i�i�V�j���Q�R������l
�����̎R�k�P�i�i�V�j���Q�R������l
������Ȃ���
���璆�N�̒j�͌|�p�l����M�Ȃ�
�u�f�ނ͖Ƌ����v
�̉Ώe���������
���e����
������s����
���E���E���E��E���E��
�k�P��Ɓ��Q�R����イ�ǁl�̊�͎���k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i���s�j�l�Ă��䂭���e���k�P�i�i�V�j���Q�R�\�\�l
��C�͍d���₽��
�u�r�̐��ʂ�
�@�@�@�@�@�@�@�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v
���̂͂��܂�c�c
�@�@�k�P�Q�����R���l�@���p��͎�ɁA�G�Y���E�p�E���h�k�P�i�i�V�j���Q�R�i�V�q�r���j�l�A�ѓ��k��̏͋���ؗp�����k�P�Q�i�i�V�j���R�B�l
���o�́s�r�c�����v20�N�̑S�e�t�i���p�o�ŎЁA1977�N11��3���j��ꔪ�`����y�[�W�A�{��16�p35�s2�i�g�A6��100�s�B�Ȃ����ؐT��҂̒r�c�����v���I��W�s�z���̂悤�Ɂ\�\�W�l�̎��l�ɂ��I�}�[�W���t�i�����ЁA1983�N5��25���j�ɍĘ^���ꂽ�ہA�v7�s�������Ă���̂́A���e�ɂ������o�̃m�h����4�s��3�s�̃R�s�[�~�X�������ƍl������B
�@�@�@�@�@�@�q�ڂ͎��Ƌ��ɐÎ~����r�k�P�\�\���Q�i��{�A�L�j���R�i�S�p�A�L�j�l�r�c�����v
�@�@�@1
�u�T�̖���
�V����͂��Ă���T�\����
�살�炵�̔����v
���̈����̕\�ʂ�
�u���������
�����ā@���_�̂悤�ȐF�ʁv
�ɂƂ�܂����
�킽���͈炿������
�@�@�@2
���B��
���P�Ƃ�
��V
�Â��I���h���̕���
���ƌ�
�u�n�Ԃłق�������Ԃ�Ȃ���
�x�ߊX��ʂ肷����v
�����Ă˂������
�炭�u��
�E�H�[�^�[��������H�ׂȂ���
�킽���͒��N���őł�
���҂̂悤��
���҂̂悤��
�u�ˑR�}���z�[���ɗ�����v
���̎���������
�킽���͏��N�ɂȂ����̂�
�����܂�
��ɂ��݂̐S��������
�ۓ����Ă���
�u���܂��܂���
���������ł���̂�
�s�v�c�ł͂Ȃ��v
�ƂȂ�̒��
�s�ׂ��闼�e����
���ʂ��Ԃ��R���c�c
�@�@�@3
�u���܂ꂽ��͂��������H�v
�����̗����ɂ���
�������Ȃ��悤�Ł@������
���̊�
�ċz����X�̉���
�Ă͏I�邾�낤
�u�`���ꂽ��͂������Ȃ��v
���̊�͍�����
�u���݂�̊�͕����Ă䂭�v
���Ă̑��ނ��
�J�}�L���̌�����݂߂Ȃ���
�u���R�̈Â��ɐڋ߂��Ă���v
�@�@�@4
�킽���͉��҂ɂȂ����̂��H
�u�����Ȃ�������֏���
�K���X������
�y��ނ��R����v
����Ȋ�ւ������������蓾�邾�낤���k�P�H���Q�R�i�g���j�l
�֊�ɂ��Ⴊ�݂Ȃ���
�O�̏���
�킽���͓����̃t�P���ӂ肻����
������ϔO������
�̔g
���̉��̌�
�u���ɓ|���ꂽ
���A�v
���j���͉J
�u�킽���͌C�E�l�ɂȂ肽�������v
���G��
���G��
���������n���g��
�����̏������C���͂��ė���
���̖��H���\�\
�@�@�@5
�|���j
�X�v�����^�[
�v�����^�[
��͊J�����ςȂ�
�ɂ݂̊��o�����邩����
�킽���͎�ɒ������Ă��镨��M����
�ؒf���ꂽ���ł�
�l�^�Ⓓ�^
���ׂĂʉ���
�u���̂��i���̃X�y�N�g���v
�������C�Ǝ��͗����̂֊Ҍ�����
�܂��܂�������������
�p���̏�ɓH�炷
�F���⊴��̊O��
�����炢�܂ł�
�u���̂͗��̂܂܂̕��̂ł���
���Ƃ�ۗ�����Ă���v
�^���|
�w��
���[���[
��
�@�@�@6
�킽���͕s�ӂ̏M�ɂ̂�
��������������
�����̏W�ɏo������
���{�ł�
���͎���ł���
���Ƒ����������
�V�[�g�����Ԃ����X�t�B���N�X
�킽���͍U������
�u�d�C�h������|�S�̎O�p���Ȃǂ�
������g����
����������
�����������肷��v
�k�P�i�i�V�j���Q�R�������l�I���_�̂͂邩����
�������ނ���X�t�B���N�X�̏���
���o�́s�C�t�k�������_�Ёl1977�N5�����k9��5���l�O�Z�`�O��y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A62�s�B���p����Ɋւ��Ă��q�g�����ƃT�~���G���E�x�P�b�g�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�A�l���l�̍炭���
�킽���͍l����
�Ŏ�Ƃ����E�Ƃ̈Ӗ��ƌ`����
�Ď����铃�̂Ȃ���
������������ɒ����L�̔��̂�������
����悤�ɈÂ�
�����̒����Ƃт܂��
�킽���͎��ȓ��ꎋ���邽�߂�
�߂������邱�Ƃ͂Ȃ�
�u�z���͎͂���
�@�@�@�@�@�@�@�@�z������v
�]�����ł��܂��܂̔푢��������
�����≲������
�ǐ_�̉���
�Y��̎Y�k���킭
�u�Ԏ��͂ɂ������ގ��̃K���X��
�o����墎���̂悤�Ȋ���������v
�ʂ̕\���������
����͑����Z��
���̓X�Y����̂悤�ɂӂ����
���ʊ�B�̐��̂悤�ɒn�_���w���Ă���
�u�c���͂����Ԃ���
�L�����������Ȃ߂Đ�������v
������
������������
���ƎE�Ӂ@�����@���Ł@��
�q�L�ד]�ρr
����k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i���s�j�l����Ȃ���̎�
�u����
�s���S�Ȑ��̊����ł���v
�Ǝ������肷��N�l�̉Ƃ�
�u����ƍ����������ށv
���N�͌����Ȃ�����_��g�̂Ɋ�������
��Ɣg�̊Ԃ�
��剻����
�킽���͐푈���u������܂�
�����n���߂�
�͂Ȃ₩�ȉԂ̂�����U���
��˂̊��Ԃ̉���������
����Ƃ�ɏ]����
�u�ዅ�̓����̎֕����d�����L�яk�݂��ɂ����Ȃ�v
���͂������Ȃ�
���̗[��̋Ս��̐�����
�g���V�l�͍s��
���̐��̔g�̂�������
�S���䂾�˂�
���p�Y�Ƃ���
�u���̂߂̂Ȃ���̍��̔@��
�����ȕ\�w���炵�߂�v
���@���
�Y�ꂽ�ו���
�����̖��͌҂̊Ԃ���
�Ԃ�����R�𐂂炵
�l�̎q��U�f�����
�u�G��Ă������ꂾ��
�e���Ȃ������v
�N�͔[��������Ă����������
�q���̒n�r�ƌĂ�
�����͍������
���𓊂���
���𓊂���
�u����������Ă��Ȃ����i���W�J���Ă���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�P�b�g�k�P�E���Q�R�i�����N���j�A�l�y���F�Ȃǂ̏͋�����p�����k�P�Q�i�i�V�j���R�B�l
�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�j
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1978�N4�����k21��4���l���`��l�y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A�V��52�s�B
�@�@�@�@�@�@�q����̏��L�҂͗J�D�Ƌ����ɐS��I�܂��r�k�P�i��{�A�L�j���Q�R�i�S�p�A�L�j�l�ѓc�P��
�@�@�@�T
�}�̏�ŏ������`�b�`�Ɩ�
�u���݂�����̂�
��������v
���t�̃Q���}���̐X�̂Ȃ���
�킽���́q�������m�A�m�j���n�r���u����
�u�`�ʂƂ������̂����Ă�������
���Ԃ��Ƃ肱�ށv
���Ƃ���
�u���ڂ����@��
�y�⏬�Ȃɓ����
���̔�����
�y�̌`���o����v
�J�ɑł���
���ł��Ă䂭�l�p������
�����Ă킽���̓A�����E���[�����X��
���t���v���o��
�q�l�͂������ӎ���\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��r
�Ђ��Ђ��Ɨ����
�n����
�u��̑���
�y�̒�����
�����݂�
�n��Ɍ�����v
�����ĕ��ɂ���琁�����
�@�@�@�U
�u�l�͓����ɓ�ȏ��
���_��
���݂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v
�킽���͓��̂��������Ȃ��
���������
�G�̂��ւ䂭
�u�畆�݂����Ȃ��́@���݂����Ȃ��́v
�ł���͕����Ă���
�����̉���
�킽���͌���⎀���߂��Ɋ�������
�B��ԗ�
�����̂��ւ䂭
�Ȃ��Ȃ�
�َ��I�ɖ��
�u�n���S�̌����֎q�ɖق���
�����Ă��鏗�v
�̂悤��
�l�����݂���
�����X���̂���鉹�������Ă��邩�炾
�J�m��
�J�m��
�u���������悤�̂Ȃ���������Ȃ��
���̕������@���݂̐S��
���ɋ߂Â���v
�Ӎ�������
���䂷��j�͌�������
�@�@�@�V
�u�`�͕s���̉s�p������
�F�͗₽��������v
���o�́s�J�C�G�t�k�~���Ёl1978�N8�����k1��2���l��l�`��܃y�[�W�A�{��9�|21�s1�i�g�A35�s�B
�u�܂̌��̓��̂���
��҂ʼn߂��鎞
���E�͂�������ς��Ă����v
�킽���̒܂���܂Ɖ���
�������̓����
���N���̔\�͂����Ȃ���
���炾�𔒂��h��
�������h��̂����ꂽ�����������
���̏�ɐQ��
�u�}�������݂��ڂ�
���v
�ɓh���Ă��炤��
�ӎ��ƌ��t�̊W�̂悤��
�s���ł��e����
�u�g�𓊂����߂�
�l�^����������o����v
���̊C��
�u�ŐS����M�点�Ă���
�l�e������v
����͗��l�����m��Ȃ�
���܂���
�u���̉�����l����
�o����
���v
�ł��邩���m��Ȃ�
���h�̓�����k���Ȃ���
�킽���͉���
�u�\�w���E�v
�������ǂ��܂ł����ʂ���Ȃ�
�킽���ɂ͊��m�ł���
�u���ɑŕ������ꂽ
�l�Ԃ̗��́v
���������т�
�u�f�ʂɕK���ōۗ��ҁv
�����\�\
���o�́s�����̈�Q�t�k�C���Ёl1976�N12���k�~�E2���l�q���W���b Imaginary Beings�r�l�Z�`�l��y�[�W�A�{��9�|30�s1�i�g�A38�s�B
��ʂ��
�u�����̂����藧�v
�X�����I���X�܂ł���
�Ⴂ���͏�����
�u�s���ȕ��i�v��
�쉈�����s���Ζ؈��̂��邫�݂�̌̋�
�u���̍����甖�Łv�܂�
�u�����v�Ŗ��Ȃ��炦
�C���̎�l�͈�̎��������������
�u���|���������P������ɂ�
���������|�ɔ��t���Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ��v
���̓X�̉��͂܂��
�u�l���A�̓��A�̂悤��
�傫�Ȋ��L�̌`�����Ă���v
�������M��
�b�Ɏ����d����ɂ�
��C����[�C�܂ł�
�F�Ƃ�ǂ�̏��i���k�P⍁��Q�R���l��ł���
�Ⴂ���͂���������
�ΐF�̔�̃u�[�c�ɋr������
�C���̎�l�͖�����
�u�炢�Ă���b�U�ǂ̊ԂŁv
�v���[�c�@�v���[�c�ƂԂ₭
�u����@�͂���Ȃ���k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i���s�j�l�ł��f�U�C���͂��ꂪ������
�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ�������v
�u�Ȃ�Ƃ����₵�傤�v
���ׂ̍��̂����悤
�u�e�ō��܂ꂽ��v�̑O��
�u�S�C�v���͂�����
�u�Ⴂ����V��ƐQ������v
�n���郍�[�\�N�̎�M�̂�����
�C���̎�l�͍�������
���h��̚h�ڂ���傤��傤�Ƌ�������
�����̂��݂�̐��n
�k�P�X�����I���X�́u�Ƌ����v�̑f�ނŏo�������Q�R�i�g���j�l
�k�P�i�i�V�j���Q�R�����́l���s�̂Ȃ����ʂ̐��E�k�P�i�i�V�j���Q�R���l
���ɉ���
����������Ɗg����
���o�́s�C�t�k�������_�Ёl1978�N5�����k10��5���l�O��`�O���y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A8��126�s�B
�g���z�q�v�l�̎�ɂȂ�q���J�̎p������r�̎G���f�ڗp���e���e�i�o�T�F�ʉp�����X�j
�����ɁuNo. 26501 �g�������e�^9�� ���i:450,000�~�^�w���J�̎p������x�@�y��640���l�\�苤���@�n����@�u���W�Ẳ��v(��54.10�@�y�Њ�)�����v�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�u�ڂ��̓E�j�Ƃ��i�}�R�Ƃ��q�g�f�Ƃ�����
�@�@�@�@�@�@�������Ƃ炦�����̂�
�@�@�@�@�@�@�����͂���瞙�瓮���Ɏ��Ă���v
�@�@�@�@�@�@�k�P�i��Z���j���Q�R�i�ꔪ���j�l�ѓ��k��
�@�@�@1
�u�X�i�K�j�������@����
�Ђ���ł��錊�v
��`��
���˓��C���݂ň����
�ڂ��͎q���̎�����
�u�����Ƃ��Ă���
�A������
�����������
���ɂ����₷���畆�̂Ȃ��̂��炩������
�ΎR
���瓮��
���ԁv
�ւ̎�����������
�u��͗��̔��g�̂悤��
�ڂ�����ł���
���̂Ȃ���
�ڂ��͓����Ă����v
���Ȓ��S�I�ȓ���ӎ��̊O��
���̎ւ͂䂭
���Ƃ̌아�̂悤��
�@�@�@2
�ڂ��́q�댯�Ȏv�z�r�Ƃ������̂�
������������������̂��Ǝv��
��ɂ͏t�̎���
�u�}�O���b�g��
���
����y������ł���v
�@�@�@3
�u�ڂ��̎��̃C���[�W�ɔ�ׂ�v
�Ɠ��{�̊C�͈Â�����
���̂Ȃ���
���ԓ��X��
�₵������
�g
�Q
��
��
�~���Ȃ�
�����Ȃ�
��
���̌���
�K���X�˂̌�����
�C�l�����݂���
���̕��G�ȓ����̍\����
��������
�����炭�q���E�r�̓�����݂̂�
�B�����m�A�A�n�ɕC�G����
�@�@�@4
�u�Ȃ��ڂ���
���J�����D����̂��낤�H�v
����͂�������
���̓��̂��v�킹��
�T��̓�����
�e��
�ڂ��͏��ׂ̍�������
�w��̐��璹��
�N�̊�̐Â���
���ʂ����������x
�@�@�@5
�Ă̂���ꍏ
�u���j���C���[�W��
�t�P�����v
��Ƃ��������
�܂錩���ɂȂ鎀�҂���
�u���g�������ɂ��ꂽ
�s�A�m���D�̉���
�[������ł����v
�������ꂽ
����y�n���悭�L�����邽�߂�
�ڂ��͊C�݂����
�C�\�M���`���N��q�g�f�̂���
���i�Ɋ��҂��Ă͂Ȃ�Ȃ�
�����͋����Ă���
�u��x�����ꂽ���t�͏����ȁI�v
�g�̂܂�肩��
�M�L���ЂÂ���
������
�S�N�O�Ɍ����j�̂悤��
�ڂ��͏ĉΔ���n�֓˂������
�����͐���
�@�@�@6
�u���l�Ƃ����ό����͉����Ȃ����H�v
�[���j�E���̔��ɒ���������
���|��
��̉��ɗ��j
�u���ׂĂ͔�Ȃ��v
�ڂ���̓���
�G���̂�������
���Ƃ��������ł��Ȃ�
�u���̏�ԁm�G�^�E�_�[���n�v
�����ɂ���@�������
���t��⏬��
�G�b�N�X�����ɓ��������
��������
��
���[���͂��肱��ōs��
�ڂ��͕ǂ⒌��
�����Ԃ������肵��
���Ɍ�����
墎�莆���т�т���Ȃ���
��C��墂��Ƃ炦�Ă���
��������̎l�s��
�፷���̐[���₳����
�
����
�邪�����
��̐��ɐڋ߂���
�@�@�@7
�ڂ��͍��ɂ̋�������
���̑��B�Ȃ̈�l�̒j���v���o��
�u�q���z�̋{�a�r�Ƃ����ٌ`�̓��́@�O�\���N����
���ā@�V�����@���Ƃ����X�֔z�B�v���@���X�̎d
���̓r���@���Ђ낢�@�����ς�Ō��Ă�����
�ł���v
�����ɐl�͏Z�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ�
�����h��Ȃ��
�����͂̐l�X�̖�
�V�l�͓��X���Ђ낤�Ƃ����q���@�r�������
�u���͈̐�̌��ꂾ�����v
����͗슴�̉́k�P�i�i�V�j���Q�R�������l
���E�ւ̒ʘH�̕W����������Ȃ�
���̓�
�ڂ���͂��̑��݂�����ӂ�
���Ԃɂ������Ă��
���낤�낵�Ă���
�����͉����H
�@�@�@8
�w墒�����
�H�ׂ����̃T�o�̎ς���
���o���x
���������{�̉�
�����Ƃ���������₷��
���A�m�݂Ȃ�n�I
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�l1978�N1�����k32��1���l��y�[�W�A�{��9�|1�i�g�k�R�����q���̎��r�l�A17�s�B�J�b�g�F�ɒ�V���Y�B�Ȃ����ł�2�s�߂�
�@�@�u�܂��Čς̂��炾�̂������͓�
�ƋN�������ꊇ�ʂ��t���Ă����i���ꊇ�ʂ̓i�V�j�B
�l�̐S�̂������͓�
�܂��Čς̂��炾�̂������͓�
���k�P�Ɓ��Q�R��l��������̉Ԃ̖݂�
�킪�S�̌ς�������
�a�˂�
㩂ɂƂ���Ď��ɍs��
�l�̊�
���ɂ͈ꖇ�̖��g�����킦
�ޕ��́k�P�B�ꁨ�Q�R����l�Ƃ֓���
����̓S�V�b�N��̖�
�u���P�̒��
�t�m����C��
�������̍������������v
���邢���݂��璭�߂��
�u�l�Ԃɉ������ς̉e��
�����Ƃƒܐ���ۂ߂ĕ����悤�ɕ����v
�t�̖���ނ炳���F�ɐ��߂�
���o�́s�G�s�X�e�[���[�t�k�����o�ŎЁl1978�N11�����k4��10���l��l���`��O�y�[�W�A�{��10�|14�s1�i�g�A����3�߂��]����74�s�B���p����Ɋւ��Ă��q�g�����̑�����i�i49�j�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�@�@�@�@�@�@�u�C�}�[�W���͂�����������
�@�@�@�@�@�@�������܂�������
�@�@�@�@�@�@�Ӗ��������Ƃ���v�@�@�@�@�k�P�{��~���Q�R�i�g���j�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P�i�i�V�j���Q�R�{��~�l
�@�@�@��
�u�i���̐ςݘm�����F�ł���j�̂�
���ɂ��������邩�炾�v
���H�̋����ˌ��̉���
�u�d������y�݂�
��n�I�Ȃ��̂���
��C�I�Ȃ��̂ցv
���͔��̃f�B�X�N�[�������݂�
�u��Ԃ̂Ȃ���
�J�����
�����ЂƂ̋�ԁv
����͂���߂ĞB���Ȏ��Ԃ��o��
���ꂽ��
�u�����邱�Ƃ������ꂽ
�i��ԁj�ł���v
�k���̂قƂ��
��ӂ˂����̉Ԃ��Ȃ���
���͈��鐼���̉�Ƃ̂��Ƃ��v��
�q�����Ό�������̂�
�����ł���
�����r
�@�@�@��
�u�����͎����Ɏ��Ă���v
���F�̃e�[�u���E�N���X
�̏�ɍ݂�
���C�^�[�i�k�P���F���Q�R��l�j
�D�M�i�����̋z����j
���ہi��j
���M�i�����S���j
�u���邱�Ƃ͓����ɒE������
������
���̂я�点��v
�����ł͂ЂƂ͐^�Ɍ��Ă͂��Ȃ�
�\�ʁm�A�A�n
�\�ʓI�m�A�A�A�n
�\�ʉ��m�A�A�A�n����
�����̓���i��
���ɂ͂��ꂼ��̎��̂�
���p�Ɏv����
�u�������ǂ��Łk�P���Ȃ����Q�R�i�g���j�l
�k�P�i�i�V�j���Q�R���Ȃ��l�Ƃ���ł��邩�炾�v
�������ċ������Ă���̂�
�u�t�ɑ��݂͉�������
�s�݂̂���߂��v
���ɍ���w�l��
�u�I�ꂽ�r�v
�@�@�@��
�u���̗~�]�̃��[�^�[�͓Ɛg�҂̋@�B��
�Ō�́i�����Ƃ�
�ˋN�����j�����ł���v
�ւ��Ă��Ă���
�ւ���
������
��p���ꂽ�K���X��
�������ł�
�q���������i�܂��͑܁j�̂Ȃ��ɛs�܂�Ă���悤��
���ׂƂ�����O�̂Ȃ��Ɂi�L���E��i�j��
�s�܂�Ă���r
�����܂���̃G�[�e���̑w����
�܂��₩��
�����ۂ�ƕX�̖��ŕ�܂ꂽ
�u�ԉłƂ���
�V�������[�^�[���o������v
�����ɉH��������
���R�@�ւ̂��炭�������
�q�d���@������́@�͂̂�������
���r
������
�u�߂Â����Ƃ̂ł��Ȃ�
���̏����ȊO�ʂ�
�P���v
����͈��⎀��
���g�ł͂Ȃ��̂��k�P�H���Q�R�i�g���j�l
���̎��_����
�u�P���̑Η���������
�j��
�̑Η��ƂȂ��Ă���v
���o�́s�C�t�k�������_�Ёl1979�N5�����k11��5���l�O��`�O�܃y�[�W�A�{��9�|26�s1�i�g�A5��83�s�B���łł́u1�v��16�s�߂�17�s�߂̊ԁA�u4�v��15�s�߂�16�s�߂̊ԁi���o�ł͂�������y�[�W�̃m�h�ɂ������Ă���j��1�s�A�L�����������A��Łi����ђ������Łk���t�����łŖ{������ł̂��́l�j�ŏC�����ꂽ�B���p����Ɋւ��Ă��q�g�����̑�����i�i49�j�r�́k�NjL�l���Q�Ƃ̂��ƁB
�@
2012�N2���AYahoo! JAPAN�̃I�[�N�V�����ɏo�i���ꂽ�q�g�������e�u����杁v�A�y�����A640���~5���A���W�w�Ẳ��x�����r�̉摜�i���i�̐����Ɂu�E�㕔���z�b�`�L�X��5���~�߂Ă���܂��B���e�p���̒����Ő܂ꂠ��B�v�j
�@�@�@1
��҂ŋ킯��
�������s���̏��N���������Ƃ�����
��������
�X����͌�ނ��Ă䂫
�q�e�̐r�ɕς������
���N��@���݂͗��ɂȂ낤�Ƃ��Ă���
�k�P�i�i�V�j���Q�R�u�l�˂��݉ԉ������܂��
�S���������܂��k�P�i�i�V�j���Q�R�v�l
�Ă̗[�ׂ̍���̂Ȃ���
�k�P�u���Q�R�q�l���t�̂����k�P�v���Q�R�r�l
�u���L���̖��̂Ђ�����k�P�����Q�R���l
���������̊w�X���ʂ���
������
�������ɂƂ�
���݂̊D�F�̋l�݂̕��͉J�����̂���
�����̂悤�ɋu�̕��֔��
���Ƃ��ł��Ȃ�
�x���`�̏�ł����ꗋ�J�ɑł����
�@�@�@2
�u���҂͉�������̂ł���v
�ƌ�����҂̌��t�͐�����
���N��@���݂�
�u�����͂Ђ��傤�ɕ��G���܂���
�l�́v
�ł���Ɠ�����
�u��q�ɂ͂�ꂽ
�������F���ɕ����N���v
�r�r�r�[�b�@�r�r�b�Ɩ�
���N��@���݂�
�u���̌���
���⌊�̒��a���v����v
�m�M�X�̂悤�Ȃ��̂�
���∤���v��
�@�@�@3
�����I������
�q�X��̗v�f�r���n���点��o��
�[�����܂���
���N��@���݂�
�u��ւ̉Ԃ̓����������悤��
������ǂށv
�����ăm�[�g���Ƃ���
�@�w�����X�̕��̓[�E�X�@��͔����������_�k�P�i���s�j���Q�R�i�Ǎ��j�l�̃}�C�A
�@�@�@�ٕ�Z�A�|���[���i���_���[�g�[�̎q�j
�@�|���X�Ə���H�y�j�A�̎q���G���X�i�N�s�k�P�i���s�j���Q�R�i�Ǎ��j�l�h�[�j
�@�k�P�i�j���Q�R�i�ꉺ�j�l�k�P�i�i�V�j���Q�R�q�l�G���X�k�P�i�i�V�j���Q�R�r�l
�@�_�X�͂��ׂĐ��₾�I
�@�@�@4
���N��@���݂̓��Ȃ�
�o���̂̂���
����̂̂���
�u���̖ڂƕ@�̊Ԃ���
���܂ꂢ�Â�v
�����n���̑o�������J��
�ϋÂ�̂悤�Ȃ��̂�f��
�u�w偂̎q���U��v
�悤�ɖ����͏��ł�
�u�}�^�̖�������̖X�v
�̉������ǂ��čs����
���̉��̉����̂Ȃ���
�u�e�͂����ƌX����
���|���ɂȂ�v
�T�C�����g�f��̂悤��
���̂͂܂ǂ��
���i���܂ǂ��ł���
�q�������k�P�l�́��Q�R�͗l�l�r
�̗��ɉ��|���ɂȂ���
��
���
��֒e�����݂���
�@�@�@5
�u�ᎀ������l�̈ꐶ�v
�Ȃ�Ζ��z��
�낤������������
�V�k�Ƌ��ɘL�����킯�ʂ���
���Ӂ@�k�̕��@����
���N��@���݂͑�u����������
�������̕���G�f��
��������
�͂邩�Ȃ鎂�q���̉���
������H�����̂���
�����]���̗����n�܂�
�u��F�̏�������
���F�̎����ցv
���N��@���݂̓S���C���͂����܂�
�q�����Ԃ̐��E�r
���s���s��
�k�P�i�i�V�j���Q�R�c�c�c�l
�u�m��ʂ��Ƃ̈�����݂�I�v
���o�́s�V���t�k�����Ёl1977�N8�����k24��8����292���l��Z�`��O�y�[�W�A�{��12�p21�s1�i�g�A6��66�s�A�}��́q�����Ǎ�r�i1975�N�A�ڍ�����j�k�ʐ^�F���p���l�ƈ���r�q�́q�ЂƂ����r�i1976�N�A�A�X�x�X�g�فj�k�ʐ^�F�R�����v�l�̕���ʐ^�e1�_���f�ځB
�@�@�@�@�@�@�}��b�̂��߂̑f�`�̎�
�@�@�@1
�������̎R���ӂ���肵��
�܂��������݊���
���̎��_���炷�ł�
�킽���̓��̂́q���̎��́r�ɋߎ�����
����o��g�q
�k�P�i�i�V�j���Q�R���ǂ̂Ђ���̂Ȃ��ցl
�@�@�@2
����g�҂͒ʂ肷����
�����Ă䂭���ƏM
�������Ă䂭�e
�^���̖���
��̖���肳��ɔw�M�I��
������ꂽ���̂قƂ�
�t�̎E�C����Ǝ蕀��
�킽���͒O�c�Ɏ�
�ЂƂ̐l�i������
�S���̉Ԃ͊J�Ԃ�
������L�̗����ق���
���̂�������́c�c
�@�@�@3
�������
�g�̂�ㆂ���
�~��ɂ܂�����ϋ{�̐l
�u�킽���͕��̂Ȃ�����
������o�����v
�l�Ԃ͉������Ă��悢
�@�@�@�������Ă��悢
�u���܂��܂Ȉّw�������蔲���v
�܂��܂��Ɓq�Í��̐����r�̌�����p������
�r�Ƃ̎���
�Ղ͏�������
�g�҂͗��g���ꖇ�̕z�ŕ�܂��
�����ĉi����
�u�ԉł�҂Ԗ��̂悤��
���k�P�ځ��Q�R�сl���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�@�@�@4
������@���䂩��~���
�����ʁ@��
������@�n����~���
�����ʁ@���R
������@������~���
�����ʁ@��
�@�@�@5
�u�J�̂悤��
�T��̓��̂���������
���ɂ�����
�킽���̓��̂͏��X�Ɍ��x��ቺ������
���Ɉł̂����ɏ���������k�P�i�i�V�j���Q�R�v�l
�܍߂��̂��̂�
�ϔO�Ɖ������낤
�A�X�g����
�A���x�X�N
�A���[�o�̂��Ƃ��k�P�v���Q�R�i�g���j�l
�@�@�@6
�����́q��ۂ̐H���r��ۂ�
�u���̓������Ƃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�킽���͕�������v
���̗��ɐ��E������
�����E�ɂ͒|�k�P�M���Q�����R�M�l�ƌ��̌��ꂪ����
�퓅��i�̔�V�Ƃ�
�u�j�����̓��̂��ؗp����
���\������v
�킽���͑S�����炵���̂ɂȂ�
���̂�Y���
�u���̂͂����Ȃ�
�q�\�ʁr�����L���Ă��Ȃ��k�P�i�i�V�j���Q�R�v�l
�����̐l�����̒f�ʂ߂邾����
���́q�\���r�Ƃ��Ă�
�����̎���������
�u�����X�̂悤�ɗ₽���������ށv
�k�P�킽���́q�㎚�r��遨�Q�R�����Ɍċz����l�͂��Ȃ��l
�k�P�����Ɍċz����l�͂��Ȃ����Q�R�킽���́q�㎚�r���l
���o�́s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1977�N1��17���k1889���l��ʁA�{��9�|22�s2�i�g�A43�s�B�J�b�g�F����v���q�B���o�͊�ʐ^��80���]��̗����i��L�E��A����j���f����B
���Ƃ낤��������������
��̉���
�u�k�P�i�ꕶ�����P�j���Q�R�n�l�ꂩ��ӂ�����
�n�k�P�i�ꕶ�����P�j���Q�R�\�l�֏o��v
�ւ�w�
���ꂩ��܂̂悤�Ȑ��H
�l�͂킽���𗷐l�ƌĂԂ��Ƃ͂Ȃ�
�܂��Ďq�����ƌ�������
�l�����̐��ɂ͂��Ȃ�
���ׂ̍���ɂނ��t�̖��
�u�����Ɋ�����
�H���v
�o�ƂƂ��ɍs��
�u�l�̈߁@��̔�v
�T�����Ƃ߂�
�p����n��
���ɓ����Ă͓��̏��
�ǂ̋T�������
�����ɏƂ炳���
�u�ɂ͉��̍��Ղ��Ȃ�
�D�F�̕ǂ͔N��L��`���Ă͂��Ȃ��v
���Ȃ����ɗ҂�������n
���͈��������͂��悮
�u��ƒn���߂���
���̈�s�v
�̂��Ƃ���
���������̏�ɕ�����ł���
���̐���~���r��
�c������ǖʂ�����
���܂�Ắ@�����䂭
�A�̂Ȃ���
���݂�����̂��R��
���݂�����̂���������
�l�͒P���Ȏv�l���D��
�l�͒P���ȃt���[�Y�����肩����
�A�͐��ɐ�������
�������킽����o��͗������낤
���F�̑��|�̉Ƃ���
�ΊD��̒�����]�ގ�
�u�畆�������Ă���v
�Ƃ������ނ���
�u�����畆���Ă���v
���̏o������
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1978�N10�����k17��10���l���Z�`���Z�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A�U��120�s�B�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u�V�@�u�Ẳ��v�v�Ŗ{�ѐ���̌o�܂���z���Ă���B
�@�@�@�@�@�@���e���O�Y�搶��
�@�@�@�k�P�i�i�V�j���Q�R�T�l
���ނ���
�u�t���𑖂�L�L�v
��ǂ�����
�����̈�l�̐N������Ƃ�����
����͂킽�������m��Ȃ�
�ЂƂтƂ�
�u�������֍s���ē���
�@�@�@�@�@�@�i���ˁj�v
�Ƃ̂̂�����
�킽���́u�Y�z�ҁv������
�^���̖�
�C�^�h���̖݂�ʂ�
���ǂ�Â�㢂̒��ɏo��
���̕ӂ�ŐΊD������ł���
���ƌ{����
��͉B�҂̏���ǂ�
�q��̉��֎w���������
����
��������Ε��̌`���ω�����r
�킽���̊ϔO�̔g�Ԃ�
�u�܂邢���v
�͕Y��
���I�Ȃ��ƂƂł����Ƃ̏I��
�u���̃����v�̉���
�Ƃ��ǂ�
�����l�����ށv
�@�@�@�k�P2���Q�R�U�l
�u���̐��E�ł�
�l�Ԃ��Ԃ����
�����O�E���ɂ����Ȃ��v
�ƔF������
��z�̂�����
�u���̌���̂悤��
�䓁�ňÍ��ȗь���ނ��Ă���
�j�v
��`���l�Ԃ�����
����͂킽���ɗގ������҂�
�}�b�`�_�̐�ɂ���
����
�u�ԐړI�Ȑ��E�v
���[�\�N�������e�[�u����
�l�N�^�����̎���
���܂�������
�����ȓ���������
���؏W�ꊪ��������
�@�@�@�����q���Ă�ɂ����r�Ƃ���
�k�P�i�O���j���Q�R�i�V�c�L�j�l���������܂�Ă���
�u�Ȃɂ���T�O�Ƃ������
��̑��݂ɂ͑��݂ł��邪
�Ŕ̂悤�ɂ�
�悭�����Ȃ��v
�@�@�@�k�P3���Q�R�V�l
�ݕӂɃL���|�E�Q�̉Ԃ��炫
�ڎ撎�͎G�ؗт��o��
���l�ւ�������ꂽ
�ЂƂ܂݂̉�
�u�͉i����
���̉��𗧂ĂȂ��v
��̐��̊��
����₩��
�����Б���������
�u���_�̕��v
��������p��������
�u�|�|�C�v
�킽���͂�����
�u�����쌴�ł��Ⴊ�ށv
�R���������
���ꂩ��͎ア�l�Ԃ̈�l�Ƃ���
�R���֓�����
�u�����ɂ�
�J���V�J�̂₳�������
�K�N�̂悤��
�Ⴊ����v
�����}
�����ƍ�������
�v��
�v�l����
�q���ɂ�����̂�
��ɂ�����̂��������Ƃ��r
�@�@�@�k�P4���Q�R�W�l
�u�킽���̎��̐��E��
�k�P�M���Q�����R�M�l�̒�����̑��̂悤��
���N������C�e�̈ꔭ�Ŕj�ł��邩���m��Ȃ��v
�@�@�@�k�P5���Q�R�X�l
���Z�̎�q��d��
�����Đ��Z���̂��̂����
���Z���������Z��������l������
���n�̊O��
��Ƃ͌`����I�ȊG�����`���Ȃ�
�@�@�@���ƐF�ʂ̔�����
�@�@�@�s�����Șg��
�@�@�@�_��
�@�@�@�G�ꂽ�g�`�̎������\�����Ȃ�
�����ނ肽��
�Ă̓����ƂڂƂڍs����
�u��w�̂��̌Ղ̂悤��
�K�v
���킽���͐S�ɕ`��
�u�ӉZ�̉Ԃ͂��݂��˂ނ��Ă���
�Ƃ��ɂ��炢�Ă���v
�������̗���
���̈Â����
���܂��₵��H�ׂĂ���n�̉e������
�@�@�@�u�҂����Ƃ������̂�
�@�@�@�n�ォ�痈��v
�@�@�@�k�P6���Q�R�Y�l
�w�I�Ȃ��̂���̍\���Ȃ�
�u�Ȑ��̂��ɂႮ�ɂ��
�o���Ă���̂�
�\���ł���v
�{�[�����̂Ȃ���
�킽���͐j����R������
�����čŌ��
����̂��鍜������
���ꂪ�����̍��ł���̂��l�Ԃ̍��ł���̂�
�ЂƂтƂ�₤���Ƃ͂Ȃ�
�u�����̏I��͎��̏I��v
�Ƃ����悤��
�킽���͌�������Ă����Ԏ�
�܂�����ɂ����
�Đ������҂ł���
���Ȃ̊i�����L��
���Ȃ킿
�@�@�@�u��͌����߂�����
�@�@�@�����̉Ƃ̓����߂����v
�� �o�́s�X�����̎��݁t�k�n���S���c�������_�{�O�w�z�[���ǖʁA�p���t�����X�A1979�N6���`8���́u�����v�l�ŁA�c��130�~����165cm�̊z���f����ꂽ�B���̌�A���̃A���\���W�[�s�n���S�̃I���t�F�t�i�I�[�f�X�N�A1981�N4���k���t�L�ڂȂ��l�A����2000���j�ɍĘ^���ꂽ�i��l�`��܃y�[�W�A�{��12�|11�s1�i�g�A12�s�j�B�{�Z�قɂ͍Ę^�`���f�����B�s�X�����̎��݁t�̎����I�Ȋ��҂ł���ѓ��k��͓����q�܂������r�ŁA��O���̍�҂̂ЂƂ萴����s�́u������O�`����F�̘g�ŁA����ɐڑ����Đԕ�����F�̘g������A���̓����̓����F�̃K���X�ɁA�������ŏc��������Ă���B�������肵�����́B�K���X�̗�����壌������Ɩ����Ă���A���̕������N���ɕ����т������Ă���v�i�����A��`��Z�y�[�W�j�Ƃ������͂��Љ�Ă���B
�u���R�E�͐l�Ԃ̑��E��肷����Ă���k�P�i�i�V�j���Q�R�v�l
��Ȃ̑���܂����̖ʂ�
�u�قƂ��鐅���́v
������ǂ镃��
�s���̂�����̂Ȃ���
�ꂪ���ނ��̂�
�ق������F�̐l�Ԃł���Ȃ�c�c
�u���邱�Ƃ́@�������Ɓv
�����ڂ̂̉��_�̉���
���͂��т��������k�P�Q壁��R�u�l��
���Ȃ�����
�u�����ꂩ���H��ł���v
���o��1978�N3��20�����s�̋��q���`�ʼn�W�sLE REVE D'ALICE�\�\�A���X�̖��t�i�p�쏑�X�A�����99���j�̏o�ňē��J�^���O�i���A1978�N2���j�k��`�O�y�[�W�l�A�{��16�|26�s3�i�g�A��������60�s�B�̂��Ɂs���q���`�A���X�̉�L�t�i���p�o�ŎЁA1979�N7��10���j�k�����V�ő�1���i1993�N6��15���j�����łƓ����e�L�X�g�l�ɍĘ^���ꂽ�i���Z�`����y�[�W�A�{��13�p1�i�g�A��������58�s�j�B�Ę^�`�͏��o�`�����s�Ẳ��t���^�`�ɋ߂��A�s�Ẳ��t���^�`�ƈقȂ�̂͏I��肩��6�s�߂́u����v�i���o�`�Ɠ����j�A�����́u���@�A�X�e���X�N�@���̂��Ɓv��2�ӏ��B
�@
�q���̃A�X�e���X�N�r�i���o�j�@�o�T�F1978�N3��20�����s�̋��q���`�ʼn�W�sLE REVE D'ALICE�\�\�A���X�̖��t�i�p�쏑�X�A�����99���j�̏o�ňē��J�^���O�i���A1978�N2���j�k��`�O�y�[�W�l�i���j�Ɠ��J�^���O�̕\���ƃJ�^���O�����߂�m���Ƃ����݁n �k���C�A�E�g�́A�l�J�V�����l�`�W�s�����Ɖߋ��̃C���t�i�؉�L�Ac1973�k�N10��27���l�j��S�������ߖ{���O���l�i�E�j
�@�@�@�@�@�@�k�P�\�\���Q�R�i�g���j�l���q���`�̊G�ɂ悹�āk�P�\�\���Q�R�i�g���j�l
�@�@�@��
�k�P�Ǐ����鏭�����Q�R�i�g���j�l
�k�P����͂킽���̍D���ȍ\�}�ł��遨�Q�R�i�g���j�l
�k�P���ƂɁ��Q�R�i�g���j�l���̕�����
�[�g�̃\�t�@����̎M�ŏ[��
�n墂��Ƃт܂��
��ł������ɂ悢
�q�V�g�I�m�A���W�G���c�N�n�ȃA���X�r�̂悤�Ɂk�P�i�i�V�j���Q�R�܂����l
�k�P�܂������Q�R�i�g���j�l�Ǐ����鏭����
�����I��
�킽���͊ώ@����
�֎q��Α��̏�Łk�P�i�i�V�j���Q�R�́l�Ȃ�
�����͌Z�̂Ђ��ɍ�������
�k�P�E���Q�R���l��ɖ{���������Ă���
�u���j�ƂƂ��ɌÂ�
�����ȂقǏ�����
�s��I�ȂقNJÔ��Ȃ�v
���F�̃������X��
�Y���[�X�����肳����
���҂������ɂ���
�����̍���������E�肪��������
����ł���ǂ���
�@�@�@����
�����͉͖��̂Ȃ����
�I���[�u�̗t�A�̉���������Ȃ�
�u�̊^�͖�
���F�̂Ȃ߂����͔����v
���{�̖��H���߂���
�M�����C�̂������߂�
�E�ߎ�����E�o���Ă���
���l�̐N�k�P�i�i�V�j���Q�R��l
���݂����ꂽ�M�ɂ̂���
���Y�}�̏�����������
�傫�Ȕ�����
�����ɏ������Ȃ锠��
�J����@�J����
����
�����̖M��
�������s��
�␅�v�[�����j��
���߂鍕�l�̐N
�U�E���[�N���E�g������
�Ȕ��̂Ȃ���
�G�i�����̂悤�ȗ����Ɖ���
�k�P�������Q�R��l��
�@�@�@������
��|���̉ԁk�P�炭���Q�R�U��l���k�P�i�i�V�j���Q�R�ׁl��
�k�P�Ǐ����遨�Q�R�ю���҂ށl����
����͂킽���̑z������q����Ȑ���r�ł���
�W�b�p�[�̓�����
�����̗��̓��[�͂�������Ă���
��炻�����
�������̂�����
���Ԃ��̓e���܂�Ő��q�̂悤��
��̎���܂���
�������܂ɕ���ł���
��炩�Ȓ�
���̂Ɓk�P���쁨�Q�R�썰�l�̂悤��
��������
�k�P�u���Q�R�i�g���j�l�q��ƍ��r
�k�P�i�i�V�j���Q�R�u�l����͋߂���
�������Ă���悤��
����߂ĉ����ւ������Ă���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P�i�i�V�j���Q�R���@�A�X�e���X�N������p���`�̂��Ɓl
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1979�N7�����k11��9���l���`��O�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A37�s�B
�u���̐F�������J�͑ł��Â���v
�살�炵��
��͂Ȃ���Ȃ���
�@�@���ɌՏ�
�@�@���̗����B��
�Ԃ݂�
�ނ炳���̎������͂������߂ɂ���
���̐��ɉ���
���̓�͎ς�����
�ᒌ�͗���
�u���Ȃ��Ƃ������݂�H�ׂ���v
��͂ނ����D�F�ȌR���ɕ����ꂽ��
�@�@��������_��
�u�q���͐A���Ɠ����悤��
�z�̂Ȃ��ň�v
�Ƃ������ۂ�����
�������킽���͂��܂ł�
�u�Ԃ̒��ɂ����܂��Ă���
�J�̌���v
�d���̊V�q��
�m�̎R��
��͍~��Â���
���܂ǂ̉�D�̎��͂��܂����
�Ȃ߂����̂悤��
�o�čs�����̐�
�@�@�M�s���Ί݈ڂ�
�@�@������
�u���͌��t���Ȃ���
���t�͓��̂��������Ƃ�v
��Ƃ𗹂���
�킽���̍r�Ԃ鍰�新��
�����̊��c�̏��
�u���ɐÂ��Ȃ��n���ȁv
�ꌾ�̎��d�̂��Ƃ�
�t���̂��Ȃ���
���݂���
�@�@�̉��̔�
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1979�N8��20���k33641���l�O�ʁA�{��7.5�|1�i�g�A20�s�B�،��ؔŁF���ьh���B���p����Ɋւ��Ă��q�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�u�E�q�͕����Đ��тɓ���v
�̏��q�̐��炩��
����
�u���l�����Ɍ����Ă���v
�Ɖr�Ñ�̚���l�̈�傪�D����
�����I�ȏt���v�킹��
�u���̉Ԃ�
�����琼�ւƍ炫�ق���ԁv
�悤�Ɉڂ�
�ς鎩�R��ϗ��ς�����
���̐���
�߂���߂��Ă͂��邩
�u��т��������ɔL���������܂�v
�܂������X����
�u���̉Ă�����C�݂�
���F���C����������
���v
�̗���ϑz����
�u�Â���̂Ȃ���
���F�͌�������߂�v
�� �o�́s���̌���t�k�u���̌���v�Ɂl1979�N3���k9���l�Z�`���y�[�W�A�{��16�p26�s1�i�g�A41�s�B�ڎ��ł͌������u����Y�̕����q���E�A���փ��`�[�i��r�Ɋāv�Ƃ���A��A����Ă��Ȃ��B�Ȃ��A���o�ł͋N�������ꊇ�ʁi�u�j�����ׂĖ{���̓V������ɓ˂��o�đg�܂�Ă��邪�A�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B
�@�@�@�@�@�@����Y�́k�P�����Q�R���l���q���E�A���փ��`�[�i��r�Ɋ�
�l�m�ꂸ��̑��̏��
�u�q���Y�݂��Ƃ�
�V�k�v
�̂悤�ɑ�҂��Ђ炭
���P�A���w���`�[�i�̞�F�̏��̊g����
�u��������̂�
���������Ȃ����̂�
�ꏏ�Ɍ�����v
���߂̕��u�����̈ł̂Ȃ���
�u�h���Ă�����́v
�k�P���̂ɏh���Ă��遨�Q�R�i�g���j�l
���ł����炯�̎q����������
�u�_�̂悤�ɍd������
���L�v
��������łɂȂ�
�ւ��Ă�ꂽ��n
�����łЂƂ͐^�Ɍ���Ă��Ȃ�
�Ƃǂ̂܂�
�u��傩���C��
�z������v
���h��̘V�l�͋���
�u�M������̂�
���̃L���x�c�������k�P�I���Q�R�I�l�v
�ӂ炿�ȐU���̗V��
�ƈ��������
���w�̍g���}���g�̓�����
���炴�炵��
�u�G�o�I��ԁv
���d���͖��ł�
����������̂�������
�h
�ÌC
���q�A�������̂悤�Ȃ���
�u�E�������
��������v
�����Ȃ鐢�E���z��
�ԏ���������X�q�̉e�̉���
�u�J���ꂽ
�����̂悤��
�l�Ԃ̓��́i���邢�͍��j�v
�����V������
���o�́s�����V���k�[���l�t�k�����V�������{�Ёl1979�N1��5���k13124���l���ʁA�{���V������1�{�G��1�i�g�A17�s�B�Ȃ�10�s�߂́u�i�����j�v�́A���r���s�Ԃɑg�܂Ȃ��V���Ɠ��̓ǂ݉����\�L�ŁA���̌��e�ɂ͂Ȃ��i�V���Ђ��Ǝ��ɕt�����j�U�艼���̉\���������B
�ݕӂɋ߂�
���������₪����
���̂������ŋ��v����������n�ɒu��
�����x�����Ă���悤��
�킽�������ɂ͌�����
����̓A���h�����[�E���C�G�X�̑f�`������
�u�����͑��݂�ӎ��̒n��ɑ�
�C�}�[�W���̒n��ƌĂԂׂ����̂�������Ȃ��v
�������ɈÊ��F�̔G�ꂽ�₪����
�l�͏����@�ފƂƟD�k�P�i�����j���Q�R�i�g���j�l���u���ꂽ�܂܂�
�����ɂ͋��k�P���Q�R���j�l�͂Ȃ�
�ł��悹�@�����������Ă䂭�@�g�̉���������
��Ƃ̊����������G��
�킽���͂��̂悤�ɔF�����S�Ђ��ꂽ
�Ƃɖ߂��Č�肠������
��ɒu���ꂽ���̂͂�������
�q�e�r�Ɓq���r�������ƍȂ͌����Â���
���o�́s���������\�\����C���Ɂt�i�u���������v���s��A1979�N12��10���j��Z��`��Z�܃y�[�W�A�{��14�|17�s1�i�g�A55�s�B
�@�@�@�@�@�@�u�����̂Ȃ��ɔ�т��ނ͍̂����v�k�P�i�x�^�j���Q�i�O�{�A�L�j���R�i��{�A�L�j�l����C��
�H�����
�I���[���̎��̂Ԃ炳����
�����ɊJ���ꂽ
�u�����̑��v
���݂�
�u���ǂ̑��������܂ǁv
���݂�
������̉B��Ƃ��o���
�D���̂͂邩���
�u�v
�͗҂���
��Â�Ȃ�܂�
�u��
�Ɣ�������v
�킽����
�u�����̎R���v
���̂ڂ��čs���҂��ЂƂ肢��悤��
�u��l�̒��̕s���e�v
��T���Ă���̂��낤��
�邪��������
��ՂɂԂ�����̂�����
�V�[�j���@�V�[�j���@�V�[�j��
�܂��
�u�䓁�̕X����v
�̂悤�ɉs������
�L���Ƌ�k�P�Q㣁��R�ʁl
�ǂ�����n��
�ǂ��ŏI��̂�
��䂵���킽���̖�
��䂵��
�u�Ƃ�������
���Ƃ��������v
���Ƃ͂������
�q���r�Ɓq���r�Ƃ�������������������
�u�^�R�̂悤�Ȃ����̎�Łv
�ł��邱�ƂȂ��
�������̕�����������
�s�ɂ�������͗���
����
�X������
�u���������͒m�炸��
�����Ƃ�v
���̐����i���������鎞
�킽�����P���̂�
�I������ł͂Ȃ�
�u���̑剹���̂���
�Y�߁v
��䂵���������̎o�̂����ނ�
�u�����ɐ�����
���f�v
��ڂɗ���
�킽���͔F�������炽�ɂ�
�u�ނ��됶����
�A���o�C�̂Ȃ���
�����݂��������ƂɂȂ�v
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1979�N11���Վ��������k11��14���l�O�l�`�O��y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A6��85�s�B�Ȃ��R�́A�莫�̍�Җ��u�剪�@�M�v�̔z�u���u�k�c�c�l�g���ł���v�̂��ƑS�p�A�L�ɂ��������A����1�s�����s�ړ������Ă���B
�@�@�@�@�@�@�u����Ƃ������̂͌ő�
�@�@�@�@�@�@���ł���Ɠ����ɔg���ł���v�k�P�Q�i��{�A�L�j���R�i�S�p�A�L�j�l�剪�k�P�i���p�A�L�j���Q�R�i�S�p�A�L�j�l�M
�@�@�@1
�u��Ƃ����Ɍ��т��Ă���v
�q���̍�
����̂قƂ��
�n���E�}���^�E�t�i��ނ�
�ڂ��͉��҂��ʂ炷
���̕��
�ʂ�ʂ邵�Ă���
�d����
�k�P�́��Q�R���l���ɕ߂�
�u���݂Ƃ��Ă̎��R�ł͂Ȃ�
�����Ƃ��Ă�
���R�v
���̂��̂�m����
�@�@�@2
�u�q���͋����ɐ�������v
�̉莞
���юR�������
�u�Ƃт������ė���
�v
�ڂ��͊Ԃ��Ȃ�
�A�f�m�C�h�̎�p�����
�ނ��Ƃ���ł̂��Ȃ�
�u�����ɋ���ȏ�����������Ă���
���Ƃ�z������v
�@�@�@3
�u�~���̒��͐Â܂肩����v
�L�͎��ɂ䂫
������ɂ䂫
������ɂ��Ă��҂����H��
������������
�l������ł䂭
�u�����̖[
�݂����Ȃ������v
�@�@�@4
�I�����Ƃǂ�
���R���z��
�����Â炨��̌a���~��Ă���
�u�܂��ׂȂ����
����������v
���ꂪ�͂��
�ϔO�̓��e�����Ƃ߂�
�u�����ːJ�v
���̕����͔�����
������������ނ���@��
�u���ƌ�����
���ԁv
�ɐ��݂���
�u�c�N�l�C���R���v
���̂͂邩��Ɍ���
�u�Ⴆ�Ⴆ�Ƃ���
���v
�ڂ����V�l�������炱�̂悤�ɂԂ₭
�u���t�̕�����̂�
�l���߂�Ɛl����
���̂��Ƃ��v
�@�@�@5
�u�����ƍz���̗�������������
�킫�����Ă���
�n�\�v
�����ł̐����͂炢
�u�q��̐H���ł�
�ނ��{�����Ƃ͏o���Ȃ��v
�ڂ��̂͂炩���
�Ђ�����v�l��
�u���قɕ�������\�́v
�������킦��
�����͊��L�̂悤�Ȑl������
�u�₦�������n���v
���̋����߂����̂���
����䂦��
�u���炾�̂Ȃ��ɂ˂�
�t�H�������o�������Ȃ��`��
���ݏo�����v
���̂܂��ɎU������
�����◑�q
�i���t�j
�������̋�ۂ�
ⴂ�͂�����������
���������点��
���~�I
���������ꖇ�̐���
�@�@�@6
�u����ʂ���
������Ɓv
����ڂ��͗��ɏo��
�����̒������������Ƃ����
�i�_�ŐM���j����
��������
�u�X�͂��n����
���E�̍^�����͂��܂�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��㎵��E�ꁛ�E��j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���̎��W�����s���ꂽ1979�N�����͑O�̎��W�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�Ƃ̗ގ��ɂ���ڂ����������i�g�������������o���тƂ��Ē�o�������Ƃ͋^���Ȃ��j�A�g���̂��̌�̓W�J��m���Ă��鎞�_���炷��A���́s��ʁt�i1983�j�ƒʂ��鎍�����s�Ẳ��t�Ɍ��ē��R�ł���B���́u�����g�����v����߂����邱�̎��W�ɁA�g�����ӔN�̎����̖G����������Ǝv���B�s��ʁt����肵���s�Ẳ��t�̓�����v��Ȃ�A���e�ʂł͐_�b�▯�ԓ`���ւ̌��y�A�`���ʂł͈��p����Ɏ{���ꂽ�K�i��̎���������������i�u�����`���ɂ��Ɓ^�u���̏�����������q�͔��Ł^�悭��������v�^�傫�ȓ~�Z�ɂ܂����閺����������v�̈��p����ȂǁA�����ɂ��t���C�U�[�́s���}�сt����̂悤�����A�o�T���ڂ炩�ɂ��Ȃ��j�B�����r�Y���q�ӏ܁r�Łu�ǎ҂Ƃ��Ă͈��p�̌��T��T��������悵�A���p�`���n�̕��Ɨn�������Ă���������ނ��悵�A���̍�i�k���W�����́q�y���r�l�������������R�ȓǂ݂����̊��߂Ƃ��Ƃ��v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��O��y�[�W�j�Ə������悤�ɁA�����������Ȃ�̓ǂ݂̑ԓx�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�s�Ẳ��t�̕��̂œ����I�Ȃ̂��A����̌J��Ԃ��ł���B�g���͌�̃��x���Ɋւ��ẮA������b�q�Ƃ̑Βk�Łu�����łڂ��̔閧�����J����Β����܂ł̍�i�́A���Ƃ��u���v���o�����x�Ɓu���v�͏o�Ȃ����A�u���v���o�Ă������x�Ɓu���v�͏o�Ă��Ȃ��Ƃ����悤�ɁA���ׂĈ�ŗ��Ă���A�������̂��J��Ԃ��Ȃ��̂����F�Ȃ́B�����炭�F���ł���B���o�Ă����炻��͂����o�Ă��Ȃ��v�i�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A�㔪�y�[�W�j�ƌ���Ă���B����A����̃��x���ł́i��I�ȗp�@���܂߂āj���Ȃ莩�R�ɌJ��Ԃ���W�J���Ă���B
�����鎞�_�Œn�̏�ɉ�����邩
�@�@�@�@�@�@���̏�ɉ������Ԃ��i�q�y���r�H�E1�j�@�@�@�@�@��m����l�ɂȂ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��l�ɂȂ����i�q�ٖM�r�H�E5�j���@���i�q�����`�r�H�E10�j
���𓊂���
���𓊂���i���O�j�J�m��
�J�m���i�q�`�͕s���̉s�p�������c�c�r�H�E11�j�ւ��Ă��Ă���
�ւ���
���Ă���i�q�D���̎O�̒[�z�r�H�E16�j�l�Ԃ͉������Ă��悢
�@�@�@�������Ă��悢�i�q�g�ҁr�H�E18�j�J����@�J����i�q���̃A�X�e���X�N�r�H�E22�j
�s�Ẳ��t�ł͎���ɂ�����u���p�v��u�ŗL�����v��u�K�i��\�L�v�̉e�ɉB�ꂪ�������A���������X�^�C���͋g�������̂���ʂ������Ă��āA�����ɒl����B
���z�q�u�z���͎͂��@�z������v�r�i���o�F�s���㎍�蒟�t1977�N5�����j�͎��_�̑̍ق����Ƃ��Ă��Ȃ����̂́A�����̋g���̎���ɑ���p����������d�v�ȕ��͂ł���B�g���͂����Łu���鎞������A���������Ȃ���A���͎��Ȃ̑z���͂̌͊��������Ƃ��������B���܂ł͖L���ȃC���[�W�̗N�o�ɁA���x�Ƃ��̒蒅�ւ̗}���ɐ��_���W������A���͂���Ȃ�̎��̐����ɗ�����B���������̍��͑��l�̌��t�̈��p�ƁA�f�ޓI�����A�n���A�l����}�����Ȃ�����Ȃ郊�A���e�B�̊m�������݂Ă���̂ł���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���l�y�[�W�j�Ə����Ă���B�k�b�ł����т��ѐS���f�I�����悤�ɁA�s�T�t�����E�݁t�Ɋr�ׂ�u�z���͂̌͊��v�\�\�ƌ��������u�z���͂̌����v���낤�\�\�͔ے�ł��Ȃ��B�������u�z���͂�����̂́A�^�̑n���������炷�z���͈ȊO�ɂȂ����낤����v�i���O�j�Ƃ������ӂ̂��ƁA�g�����͂�������A���̐^�Ă̋ɒn���疢���̎����E�ւ̓o�����J�n����B�₪�ās��ʁt�Ƃ����u����g�����v�̋��p�����킷���낤�B
�k�t�L�l
�{���W�̒P�s�{�̊����i���t�Ό��y�[�W�j�Ɍf�ڂ���Ă���q���o�����ꗗ�r�ɂ́A��������肪����B���łɊe���т̖{���O�ɏڍׂȏ��o�L�^���f�����̂ŁA�����ł́q���o�����ꗗ�r�ƌ��T���Z���������ʂ�{���̍Z�قƓ��l�̏����ŋL���A��L�E��A�𐳂��Ă������B
| �����o�����ꗗ | |
| �y�� | �u���㎍�蒟�v�@1976�E8 |
| ���� | �u�V���v�@1976�E12 |
| �� | �u�����C�J�v�@1978�E7 |
| �q���̋V�� | �u���Y�v�@1976�E10 |
| �ٖM | �u�w���}���E�Z���G���g�W�v�@1977�E5 |
| ���� | �u���Y�v�@1977�E11 |
| �Ӊ� | �u���s�ʐM�v�@1977�E10 |
| �� | �u�����C�J�v�@1976�E11������ |
| ���̖��{ | �w�r�c�����v20�N�̑S�e�x�@1977�E11 |
| �����` | �u�C�v�@1977�E5 |
| �`�͕s���̉s�p�������c�c | �u���㎍�蒟�v�@1978�E4 |
| ���E���邢�͉� | �u�J�C�G�v�@1978�E8 |
| ���� | �u�����̈�Q�v�@1976�E12 |
| ���J�̎p������ | �u�C�v�@1978�E5 |
| �� | �u���w�E�v�@1978�E1 |
| �D���̎O�̒[�z | �u�G�s�X�e�[���[�v�@1978�E11 |
| ����� | �u�C�v�@1979�E5 |
| �g�� | �u�V���v�@1977�E8 |
| ����ȏt�̗� | �u�k�i�i�V�j�����{�l�Ǐ��V���v�@1977�E1�E17 |
| �Ẳ� | �u���Y�v�@1978�E10 |
| �� | �u�X�����̎��݁v�@1979�E6�k�i�i�V�j���`8�l |
| ���̃A�X�e���X�N | �k�u���q���`�A���X�̉�L�v�@1979�E7�����q���`�ʼn�W�wLE REVE D'ALICE�\�\�A���X�̖��x�o�ňē��J�^���O�@1978�E2�l |
| �r�� | �u�����C�J�v�@1979�E7 |
| ���̐��̉� | �u�����V���v�@1979�E8�E20 |
| ���q�A�� | �u���̌���v��㍆�@1979�E3 |
| ��̊G | �u�����V���k�i�i�V�j���[���l�v�@1979�E1�E5 |
| �u�Ɣ�������v | �w���������x�@1979�E12 |
| �~���̓��� | �u�����C�J�v�@ 1979�E11�k�i�i�V�j���Վ��l������ |
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�H���K�l�i1961.6.10.-2010.4.29.�j�ɕ���
�g �������s�Ȃ����Βk����k��́A�܂���{�ɂ܂Ƃ߂��Ă��Ȃ��B���O�ɏo�ł���Ȃ������̂͋g�����g�̈ӌ��ɂ�낤���i���������̕ҏW�҂������為������ �Ɋ�悵���j�A���ЂƂ���y�Ȍ`�œǂ݂������̂��B����́A�g�������o�Ȃ����Βk�E���k��̊ȒP�Ȍf�ڋL�^�ƋL���̏����o����E���邱�ƂŁi�����ŋL �ځj�A�ˋ�̏����s�g�����Βk�E���k��W�t���T�ς��悤�B�Ȃ��A�o�Ȏ҂��̂��̂��u�Βk�v�A�O���̂��̂��u�C�k�v�A�����葽�����̂��u���k��v�Ƌ� �����āA�N�㏇�ɕ��ׂ��B�\�\���ш�Y�q�g�����̑Βk�E���k��W�r�i2004�N3��31���j
2010�N5��31���ŁA�g�������S���Ȃ��Ă��傤��20�N�ɂȂ�B1996�N�ɉ̏W�s�����t���܂��s�g�����S��
�W�t���A2003�N�ɑS��W�ɑ��������s�z
���t�����s����A�C���Ɋւ��邩����g������i�̌����͂قڏI������
�i�ق��ɉ̏W�s�`�W�t�Ƌ�W�s�z���t
�����߂��s��
��t��2002�N�ɏ������Ȃ��犧�s����Ă���j�B�U����1996�N�̒Ǔ����W�s���̂������
���������Ă����t�Ɉ�e�q�����i���l���N�E�ė�j�r�����\���ꂾ���ŁA���̌�͐��O���\�̖�
���s�U���̏��Љ����i�W���Ȃ��B����͋g�����i�̏����j����������҂ɂƂ��ėR�R�������ԂŁA���Ђ̌`�łȂ��ƒP�s�{�����̎U���ɑΉ������s�g�������y�����E��i�������k���
�t�l�t��ł��Ȃ��B�g���������M�E���\�����U�������̏�Ԃ�����A��
���ł̒k�b�L����Βk����{�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂͂����������Ȃ��Ƃ͂����A����炪�g���������ɂƂ��ĕs���̏d�v�����ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B
����A���́q�g�����̑Βk�E���k��W�r�ɍڂ������X�g�ɁA�g�����P�Ƃ̒k�b��C���^�r���[�������āA�s�g���������s�U���W�t�ɑΉ�����`�Łs�g�����g�[�L���O�t��Ҏ[�����B��
�ċg���Ƃɂ͓y���F�̎G���A��
�q�a�߂镑�P�r��ʼn��Ԃ��������q���������i����͋g�����s�a�߂镑�P�t��
���{�E������S������ۂɁA�ҏW��������ꂽ���̂�������Ȃ��j�B�s�g�����g�[�L���O�t�͂��̍��q�Ɠ������_�ŁA�ȕւȌ`���Ƃ���g�����̔�����
�\�Ȃ�����W�ς��āA�f��20�N�������ăf�W�^���f�[�^���������̂ł���B�����html�t�@�C���ɂ����̂́A�E�F�u�y�[�W�Ƃ��Č��J���邱�Ƃ��ړI��
�͂Ȃ��i���쌠��̖����N���A���Ă��Ȃ��̂ŁA����ł͌��J�ł��Ȃ��j�A�Œ���̃��C�A�E�g���{�����s�g�����̎��̐��E�t��
�Q�Ɖӏ��Ƀ����N��ݒ肷�邱�ƂƁA�V�t�g�i�h�r�̃e�L�X�g�ŕ\���ł��Ȃ����������j�R�[�h�ŕ\�����邱�Ƃ��ړI�������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�T�E1 �k�k�b�l�q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S����� �^���Ձr�i�s�o��]�_�t78���A 1968�N3���j
�@�T�E2 �k�k�l�q�����ƍ��ׁ\�\��a�����ƐV������Ƃ����r�i�s�f ��|�p�t1969�N3�����j
�@�T�E3 ���}������q�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�\�\��������܂� �g�������ɕ����r�i�s�T���Ǐ� �l�t1169���A1977�N2��21���j�̋g�����̔���
�@�T�E4 �k�C���^�r���[�l�q�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���r�i�s�� �㎍�蒟�t1978�N3���� �q���W���e���r���ǂ����邩�r�j
�@�T�E5 �i�q�j�q��Ԑ��̕��́\�\���̐��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�i�v ���Њ��j���o���g�������r�i�s�� �{�Ǐ��V���t2065���A1980�N7��14���j�̋g�����̔���
�@�T�E6 �k�k�b�l�q�����{�̈��V�ˁr�i�s�_�u ���E�m�[�e�[�V�����t1985�N7��23���q�y���F ���[�f�B���O�r�j
�@�T�E7 �q�k�����V�g�����Ɋւ���k�b�l�r�i�s�� ���V���t1987�N6��6���j
�@�U�E1 �k�g�����E�V��ޓ�Y�̑Βk�l�q�V�t�Βk�r�i�s�� �㎍�t1963�N1�����j
�@�U�E2 �k�g�����E����N�v�̑Βk�l�q�͌ЂƂ������E�ցr�i�s�� �㎍�蒟�t1967�N10�����q���W�� �g�����̐��E�r�j
�@�U�E3 �����r�Y�q�g��������76�̎���r�i�s�g �������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�N9�� 1���j
�@�U�E4 �k�g�����E�剪�M�̑Θb�l�q���`�̐��E����r�i�s�� ���C�J�t1973�N9�����q���W���g�� ���r�j
�@�U�E5 �k�g�����E�ѓ��k��̑Θb�l�q���I�t�̌�䊁r�i�s�� ���C�J�t1975�N12���Վ��������q�� �i�����W ���㎍�̎��� 1975�r�j
�@�U�E6 �k������b�q�E�g�����̑Βk�l�q��̌��t�\�\�t�B�N�V���� �ƌ����̍����ցr�i�s���㎍�� ���t1980�N10�����q���W���g�����r�j
�@�V�E1 �k�S��V�閾�E���{�R�ʕ��E�g�����̍��k��l�q�ǎ҂Ɩ{�̌��� ���\�\�o�ōL���͂ǂ�����ׂ����r�i�s�� ���V���t1961�N2��4���k�T��589���l�j
�@�V�E2 �k���Y���P�E��������E�g�����i�Q�X�g�j�̑Θb��]�l�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t1987�N11�����j
�@�W�E1 �k���q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�g�����E�������q�̍��k��l�q����o��]�_�ܑI�l���k��r�i�s�o��]�_�t25���A1963�N2���j
�@�W�E2 �k������Y�E���ˉ�v�E�g��O�E���C�i��E�H�J�L�E�����ρE�g�����E����l�Y�E����S���̍��k��l�q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�i�s���w�t1963�N7�����q���W���g���܁r�j
�@�W�E3 �k�g�����E�����؍K�j�E���q�����E�����d�M�E���c�Îq�̍��k��l�q����o�偁���̒f�ʁr�i�s��t1972�N10�����j
�@�W�E4 �k�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������̍��k��l�q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�i�s�Z�́t1975�N2�����j
�@�W�E5 �k�g�����E�ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�̍��k��l�q�v�z�Ȃ�����̎��l�r�i�s���㎍�蒟�t1975�N5�����q���W����؎u�Y�NVS�g�������r�j
�@�W�E6 �k�ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�E�g�����̘A�ڍ��k��l�q����o������r�i�s�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l�t�������[�E���� I�`XII�A1980�N5��1���`1981�N4��20���j
�@�W�E7 �k���q�W�E�����d�M�E�g�����E�O���q�Y�E�����r�Y�E�i�c�k�߁E��ؘZ�ђj�E���c�q���q�E�j�M�q�E�߉��P�v�E�Í��a��E��������E�������q�E�ѓ����q�E�����O���q�E���×��E��ؔ��E��ˏ~�v�E����o�X�q�E�Ԕ����q�̍��k��l�q�V���|�W���E�� �i�c�k�߂̐��E�r�i�s�o��t1980�N9�����j
�@�W�E8 �k�g�����E�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�̍��k��l�q��ނȂ����I���݁\�\���e���O�Y�Ǔ����k��r�i�s���㎍�蒟�t1982�N7�����j
�@�W�E9 �k�I�N�^�r�I��p�X�E�g�����E�剪�M�E�a��F��E�g�������̓��ʍ��k��l�q����Ǝn���r�i�s���㎍�蒟�t1985�N1�����j
�k�����o���Ȃ��l
�k�b�{���i400���l���e�p����12���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�o��]�_�t�k�o��]�_�Ёl1968�N3���k10��3����78���l21�`24�y�[�W�B�ҏW�l�E�����d�M�́q���Ƃ����r�Ɂu���H�̑S�����ɂ�����A �������H�E�剪�M�E�g������̏����̒k�b���f�ڂ����B�o���邾���A�����̐��܂̊������c�������Ǝv���A�^�������܂܂��A�قƂ�ǎ����ꂸ�ɔ��\�����v �i�����A�k�l��y�[�W�l�j�Ƃ���i�q�g �����́u�u���v�Ɣo��I�]�r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�k�����o���Ȃ��l
�k�{���i400���l���e�p����8���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�f��|�p�t�k�f��|�p�Ёl1969�N3�����k17��3����259���l92�`93�y�[�W�B�q�����̍�Ƙ_�r�̃R�[�i�[�ɁA��؎u�Y�N���M�́q���̕� �����߁\�\���������u��K�v���v�u�فv�r�ƂƂ��Ɍf�ڂ��ꂽ�B�����ɂ͍����c�E�y���F�E��唪�E�R�{�W��̍��k��q�Z�b�N�X�ƌ|�p�\�\���{�r�d�w�f��� ���r���f�ڂ���Ă���B
�V�����`����͍�����\�\�u���邱�Ɓv���瑽���̗{�����z��
�������d���ȑ��^���\�\�E�l�̎�d���̂悤�Ɏd�グ��
�����ɂ��ӗ~�R�₷�\�\���Ă̇������̌����Ƈ��R���̌���
�����{���i400���l���e�p����4���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�͏��}������q�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�\�\��������܂̋g�������ɕ����r�i�s�T���Ǐ��l�t1977�N2��21���k1169���l1�ʁB�g������ ��ʐ^�Ɓs�T�t�����E�݁t�̔��ʐ^�A�e1�_�f�ځB�{���̋g�������i�{���S�̂�15���~330�s����92�s���j�̂f�����B�̂��ɏ��} ������s���߂̕��w�� �\�\27�l�́q�n��H�[�r���k��p��102�l�t�i�发�فA1982�N8��15���j�ɍĘ^���ꂽ�̂ŁA�ƍ����čZ�������y���o�`���Ę^�`�z�B
�k�����o���Ȃ��l
�C���^�r���[�{���i400���l���e�p����14���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c���o�́s���㎍�蒟�t �k�v���Ёl1978�N3�����k21��3���l�q���W���e���r���ǂ��� �邩�r115�`118�y�[�W�i�u���l�́q��r�v���̈�тŁA�ڎ��ɂ́q�u�e���r���߂���15�̎���v�ւ̉r�Ƃ���j�B �W��̎��Ɂu�C���^�r���[�E�ҏW���v�ƃN���W�b�g����Ă���i�ҏW�l�͎R�����P�j�B�g�����̓e���r�ԑg�ɏo�����Ȃ��������A1994�N5��15�����f�� �m�g�j����e���r�s���j���p�فt�́q���z�̉����\�\�F�V���F�̉F���r�ŁA�y���F�̍��ʎ����F�V�ƂƂ��Ɋ��̒��̓y���ɕʂ��������V�[�������ꂽ�i�q�g �����̎����o�����i1�j�r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�k�����o���Ȃ��l
�����{���i400���l���e�p����2���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́i�q�j�q��Ԑ��̕��́\�\���̐��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�i�v���Њ��j���o���g�������r�i�s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1980�N7��14�� �k2065���l�j2�ʂ̃R�����q��r�B�g�����̊�ʐ^1�_�f�ځB�u�@�v�t���̋g���̔����i���������ł킩��ɂ����ӏ��͒n�̕����������j�����ׂČf�����B �Ȃ��{�����Ɂu�A���A�g�������g���u�Z�M�I���݁v�ƌĂԑ��c�唪���Ƒg��Łu�G�{�v������v��͂���v�ƌ����邪�A���́u�G�{�v�͎������Ȃ������B
�k�����o���Ȃ��l
�k�b�{���i400���l���e�p����1���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c���o�́s�_�u���E�m�[ �e�[�V�����t�k���[�E�s�[�E���[�l1985�N7��23���k2���l �q�y���F���[�f�B���O�r71�`72�y�[�W�B���o���̔Ō��ɖ��߂Ă����W�ŁA���͎�ނɓ��s����K�^�Ɍb�܂ꂽ�i�ڍׂ��q�� �ȂÂ��̐��\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i���́j�\�\�Ǔ��g�����r�́u�Z����Z���i�j�v���Q �Ƃ̂��Ɓj�B���̐Ȃŋg������y���F�ɂ��Љ���Ă����悤�Ɋ��߂�ꂽ�B�Ђƌ���A���̓A�X�x�X�g�ق̈ꎺ�œy���F��撊P�ɐڂ����B
�k�����o���Ȃ��l
�k�b�{���i400���l���e�p����1���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�����V���t�k�����V�������{�Ёl1987�N6��6���k39917���l23�ʁB����́q���l�A�g�������̘b�r�ŁA�{���L���q�Ɍ��̃_�_�C�X�g���l�^ �����V�g���������r�̂��Ƃɕt����ꂽ�R�����g�B�g���Ə����̐蔲���ɂ́A�g���{�l�̎�Łu�����V���@���a�Z�\��N�Z���Z���i�y�j�v�ƃ�������������B �g���͒Ǔ����q�_�K�o�W�W���M�a����A���悤�Ȃ�r�i�s�����C�J�t1987�N7�����j�������Ă���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�k�����o���Ȃ��l
�Βk�{���i400���l���e�p����7���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�t�k�ђˏ��X�l1963�N1�����k10��1����121���l�q���W���V�t�Βk�r40�`41�y�[�W�B�S����18�{�̑Βk�̊�G��́A�@���q�� ���E��̂�q�A�A�x�m�����E���r�v�A�B�y�M�[�t�R�E��c�G�A�C�Ί_���E�R�c���O�A�D�R�{���Y�E�@���߁A�E�������O�E�J��r���Y�A�F���c��v�E�֍� �O�A�G�����ρE�V��a�]�A�H����È�E�ѓ��k��A�I�������ȁE�����m�]�q�A�J�����O�E�剪�M�A�K���c�q�q�E�����q�A�L��c�q�Y�E�E�i�[�\�A�M�O�D�L�� �Y�E�������A�N�������a�E��]���O�A�O���J�엳���E���R�C�i�A�P�g�����E�V��ޓ�Y�A�Q����M�v�E�g��O�B�g���E�V��Βk�ɂ́A�o�Ȏ҂̊�ʐ^�e1�_���f �ځB�g�����͊�{�I�ɑΒk�Łi���g�́j���ȊO���e�[�}�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������A�{�т͂��̍ŏ��̑Βk�ł���Ȃ���A�f�ڎ����g�������W�łȂ��_�����M���� ��B
�����������ƂƎ��_����������
��i�̕ω��ɂ���
�g�����̎��̏o��
�g�����̎��̌��t
��i�ƌ����Ƃ̂�������
�����̏�Ԃ��珑���n�߂�
�Βk�{���i400���l���e�p����37���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1967�N10�����k10��10���l�q���W���g�����̐��E�r52�`61�y�[�W�B�o�Ȏ҂̃c�[�V���b�g�u�Βk���̓���N�v �i���j�A�g�����i�E�j�����v�Ɗ�ʐ^�e1�_���f�ځB�ҏW�l�E���ؒ��h�́q�ҏW���^���G�\�\���Z���N�Z���`�����r�́u8��23���i���j�v�Ɂu�[���A�V�h�̔n��u�ŋg�����E����N�v�Βk�B�g������͂悭����ׂ��Ă���A���������܂��_ ���Â��Ă܂Ƃ߂Ȃ��� �i�s�����v�i�s���㎍�蒟�t2010�N2�����A159�y�[�W�j�Ƃ���B
�l�Ԃɂ���
���{����ѓ��{�l�ɂ���
���퐶���ɂ���
�����ɂ���
�V�N����ю��ɂ���
���ɂ���
�E�l�ɂ���
�_�ɂ���
���w�Ƃ̏o�
����ւ̓��@
�푈�̌��ɂ���
����̂��߂ɏ�����
��㎍�Ǝ����̎�
�O�q�ɂ���
���{��ɂ���
�Z�b�N�X�ɂ���
����̎��̕���
�����̌v��
���̐V���������
���łɂ��������܂�
�{���i400���l���e�p����25���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�͍����r�Y���M�̃C���^�r���[�`���ɂ�鎍�l�_�q�g��������76�̎���r�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�N9��1���A 138�`146�y�[�W�j�B�g���͎��M�q�N���r��1968�N�̍��Ɂu�āA�k�c�c�l�������p�[���[�ŁA�����r�Y�̃C���^�����[����i�u�g��������76�̎� ��v�j�B�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�N1��20���A233�y�[�W�j�Ə����Ă���B�q�g��������76�̎���r�͕��o���ďC�s���㎍ �ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�Ɂq�g�����G�b�Z�C�E�C���^�r���[�r�Ƃ��čĘ^���ꂽ�B��{�ɂ͏��o���̂����B�{���͍Ę^�`�ɏƂ炵�ď����� �u�@�v���w�@�x�ɁA�N��̍˂��ɒ��������A�Z���̕\���͂��Ȃ������B
�g�����O�j�����߂�
���N���̏����Q
�����o�ꂷ��
�o�傩��̒E�o
���܂��܂ȏo����
�����ł��邱�Ƃ��K�v��
�X�g���b�v�̉F��
���꒤���̌���
�U���̗����
�ŗL�����̐��E�ցk�q�ڎ��r�ł́u�ŗL�����̖��f�v�l
������Ȃ��E�炷��k���E�u����Ȃ��E�炷��v�l
�Θb�{���i400���l���e�p����66���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N9�����k5��10���l�q���W���g�����r142�`158�y�[�W�́u�Θb�v�B�o�Ȏ҂̊�ʐ^�e8�_���f�ځB���o�`���� ���폜���āA�s�V�I�g�������W�k�V�I�E���㎍����110�l�t�i�v���ЁA1978�j�Ɓs���E�g�������W�k���㎍����129�l�t�i���A1995�j�Ɏ��^�B�g�� �́u�O��₷�q�́w���̎ʐ^�x�v�ɂ��Đ��z�q�Ǐ����r�ł������Ă��邪�A�O��₷�q���Ɂs���̎ʐ^�t�͌�������Ȃ��i�s�g���� ���y�����E��i�������k���t�l�t�́q�O��ȁr���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�u�k�v�̎���
�ɒB���v�́u�����C�J�v
�u�m���v�̎���
�u�_��I�Ȏ���̎��v
�u�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́v�Ɓu�V�N�̎莆�v
�^�c�ƃV�������A���X��
�u���{��A�v�̖��
�\���Ƃ��Ă̖g
���q�����Ɛ��e���O�Y
70�N��̎��l����
���I�t�H������
�w���q�V�S�x
�w���X�B�Ɓx
�Θb�{���i400���l���e�p����80���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N12���Վ��������k7��12���l�q��i�����W ���㎍�̎��� 1975�r192�`221�y�[�W�B�g���͓������Ɏ��сq���܂�����r�i�G�E30�j���Ă���B�ѓ������ɂ�����ʓW�q���q����̒����r�i������������ �فj�̉���͏��a50�N10��7���`11��24�������A���́u�Θb�v�̎��{���͕s���B
�̌��Ƒz����
�o��E�Z�̂ƌ��㎍
���p���ɂ���
�J��Ԃ��������
�����I�Ȍ��t
�ڂ̐l
�ۂ��Đ��Â܂�̂���
��ؐV�������̂͂Ȃ�
�u��́v�ւ̎u��
�Βk�{���i400���l���e�p����95���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1980�N10�����k23��10���l�q���W���g�����r90�`111�y�[�W�B�o�Ȏ҂̊�ʐ^�e1�_���f�ځi�g���E����Ƃ��A �w�ɉ������͂���ł���j�B�g���̎ʐ^�́s���㎍�蒟�t1990�N7�����́q�Ǔ��A�g�����r�̔��y�[�W�ɗ��p���ꂽ�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���ɂɕ�������\�\���ʂ̂���L���A�Ȃ��L��
�h���I�Ȕz���@�\�\�\�f��Ɏ������@�I�Ȑ��i
�V���͕`�����\�\�o�ŎЁ@�t�F�e�B�V�Y���j��
�Ǐ��l���͂ӂ���\�\�̔������𗘗p������
�\���̏��]�����\�\���j�I�ǎ҂����ނ���
�V���͌��������ā\�\�����I�Ȃo�q�ŋ��͂�
���k��{���i400���l���e�p����31���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�����V���t�k�����V���Ёl1961�N2��4���k�T��589���l2�`3�ʁB�o�Ȏ҂̊�ʐ^�e1�_���f�ځB�L�����Ɉ݂͂Łu�o�Ȏҁv�Ƃ��āu�����V�� �����{�Џo�ŋƖ��������@�S��V�閾���^���_�ЎВ��@���{�R�ʕ����^�}�����[��`�ے��@�g�������^�i�������j�v�Ƃ���B�̂��ɗS��V�͐Ό�����ƂƂ��ɁA �X�c����ҁs�O�i�����G��W�t�i�������A1972�j�̑I��S�������i�q�X �c���ᎁ�������r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�k�����o���Ȃ��l
��i�ƑΘb��]�{���i400���l���e�p����42���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1987�N11�����k19��12����256���l249�`�i�C�k��252�`�j261�y�[�W�B�g���̓��L�́q�A���P�[�g�u�����āA�W���P���́c�c�v�r�i�s�i�فt4���q�����٘^�a�r�A1983�N10���j�ŁA�u���̂Ƃ���A�ăo�e���Ă���B���v���Ԃ�ŏē����X�g�����u�́v�̗�����H�ׂ��������A�����������C�ɂȂ�B�Ȃ̍D���Ȃl�w�r���R�e�̃y���y���ŁA�R�[�q�[��T�����B�́m�肫�n�������̂Łu�Ԑ_�v�̂��߂̏����т��A��C�ɏ����͂��߂�B�������A�s���v�i�����A11�y�[�W�j�Ȃǂƌ�����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�n���m�Ύq
���{�퐶
���c���j
�O��O��
�|�{���i
�u����
�Ăѓn���m�Ύq
�����P��
�n���m�Ύq�ƒ|�{���i
����_�i
�剪��i
�Ƃɂ����i�낤
����ł͂ǂ�����
���k��{���i400���l���e�p����69���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�o��]�_�t�k�o��]�_�Ёl1963�N2���k5��1����25���l8�`29�y�[�W�B�f�ڎ��̖`���Ɂu�o��]�_��ᢕ\�^���I �Y�c�҂Ȃ��^����� �ف[�����E�ہ[����� ���c���j�^ �E���� ���{�\���^ �N�̉� �O��O���^ �������̉S �n���m�Ύq�^�I�O���� �]���]�^ �Ԍ����� �剪��i�^ �~�c���^ ���i�C�� �����P���^ �ς��Ă���p���� �u�����^ ���Ղ�� �|�{���i�^ ���̐� �����Βj�^ �����F�^ ����_�i�^�R���� ���䗲�@���q�����@�~�c�G�v�@��{���g�@�����d�M�@�i�c�k�߁@�g�����^��� �o��]�_�Ёv�A�����āq�o��]�_�܉���܍�i�r4���4���́q��܂̌��t�r���f�ځB���k��L���̍ŏ��ƍŌ�̌��J����������18�y�[�W�ɂ킽��A3�i�g�{ ���̏�i��9���́q�o��]�_�ܑI�O����r�̏Љ�ɏ[�ĂĂ���B���̂Ƃ��̑I�]���_�@�ƂȂ����Ǝv�����u�����Ƌg�����̊W�ɂ��ẮA�q�g �����̖����s���т��r���Q�Ƃ̂��ƁB
�I�l�o��
���k��{���i400���l���e�p����21���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c���o�́s���w�t�k���w �Ёl1963�N7�����k18��7����196���l�q���W���g���܁r 46�`51�y�[�W�B���̍��k������ƂɁA�����q�g���ܑI�l�ψ��E�g�����r���������B����N�v�́s�����Q���n���X���̓��t �̊G�͗����ɂ����̂����A 1960�N��̋g���������ōł��������N�p���ꂽ�̂������̃J�b�g�������B�������A�����̊G�Ɍ��炸�A�g���Ɏ���W�ƌĂׂ钘���͂Ȃ��B
�o��Ƃ̏o�
�Z�̂�����Ƃ��������������
�w�O���\�N�x�̂���
���͓I�Ȏʐ^
�����܂������R
�����鎩�R���͂܂�Ȃ�
�{�L���u�����[�̕s��
���݂Ƃǂ܂��Č���
�o�d�͂�������
���Ђ̎�Ɏ�
��i���������߂̊����H
�s�Îq��L�t
�q�́i���W�w�t�́x���j
�����؍K�j���̍�i�i�u'72�Z�̔N�Ӂv���j
���q�������̍�i�i�u'72�o�匤���N�Ӂv���j
�����d�M���̍�i�i�w�����d�M�S��W�x���j
���k��{���i400���l���e�p����84���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s��t�k��o���l1972�N10�����k9��10����100���l12�`35�y�[�W�B�^�C�g���y�[�W�ɏo�Ȏ҂̊�ʐ^�e1�_�f�ڂ̂ق��A���c�������Q �X�g�o�Ȏ҂̍�i�Љ�̃R�����Ɋ�ʐ^�����ꂼ��1�_�f�ځB�g���͓��c�Îq��W�s��k����o��p��18�l�t�i�p�쏑�X�A1984�N10��20���j����W �����s�o��t1985�N6�����Ɂu�o���̔��e�ɑ�̕X�肯��v���f���āA�q�u��v�߂������r�Ƃ������z�������Ă���i�q�ҏW�� �L 39�r�Q�Ɓj�B
���{��̎��l�E���e���O�Y����
������|�̉�
�o���E�ߋ��E�C��܂𑖂�
����̉̐l�Ƃ��̎���
�O���R�I�v�E��オ���O�ɂԂ�����
���k��{���i400���l���e�p����112���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�Z�́t�k�p�쏑�X�l1975�N2�����k22��2���l58�`87�y�[�W�B�^�C�g���y�[�W�ɏo�Ȏҁi�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g���� ���j�̊�ʐ^�e1�_���f�ځB�����o���̏�ɏo�Ȏ҂̊�ʐ^�i�{���ł́��ŕ\���j���J�b�g�I�ɔz�u���Ă���i�f�ڏ��ɔѓ��E�g���E�g���E�߉ρE�����j�B���k �`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�̂�������́A��c�O�l��E����O�F�E�n�ꂠ���q�E���c�C��E�ЎR����E�O�q���w�I�ӔC�Ƃ��Ă̍����̉́r�B
�g�̎��l��؎u�Y�N
��̓I�����𗹉�����
�U���ɑ���N���Ȉӎ�
���킢���l�A�����Ȏ��l
���g�����\�����x�点��
���ɂ�����U�����Ƃ͉���
��т̒��ю��ւ̖�
���k��{���i400���l���e�p����57���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1975�N5�����k18��5���l�q���W����؎u�Y�NVS�g�������r116�`129�y�[�W�B�^�C�g���y�[�W�ɏo�Ȏ҂̊�ʐ^ �e1�_�f�ځB�ҏW�l�E���ؒ��h�́q�ҏW�m�[�g�r�Ɂu�k�c�c�l���̓�l�̎��l�͌��㎍�̓�̋ɓ_���������݂ł���Ȃ���A�܂������炳�܂ɋ��ʂ����n���� �ʒu���Ă���悤�Ɏv����v�i�����A238�y�[�W�j�Ə����Ă���B�� ���g�������s���̎莆�t�i���� �X�A1974�j�̑��{�́A���[�����ɂ��B
�����q�K�̏ꍇ
�q�K�ɂ�����m�Ԃƕ���
�q�K�ɂ�����o��ƒZ��
�E���Ȑl�̗E���Ȃӂ�܂�
�q�K�̏����̉���Ȃ�
�q�K�̘A��ے�̈Ӗ�
�o�傾���łȂ������q�K
�Ăюq�K�̉���
�q�K��Z���^�ɐ�O����������
�Z�ʖ��V�������q�K
�O�l�O�l�̎�
�Ɍ�˂Ƌ��q
�y�Ɍ�˂̉���Ȃǁ��i�g���j�z
�Ɍ�˂������Ă����q�K
�����錩�ǂ���̂����ƂȂ���
���q�̕��@
���q�̔o�啜�A�̌���
�Ɍ�˂̖����S��`
�Ɍ�˂̔ߌ�
���ł���o��A�g�̂ł���o��
��│̔o��
�����Ƃ����l
�ΓC�̖���Ȃ�
�S��̌�����
�]�˂��q�o�l���b
�C���e���o�l�l�r�̓o��
�o�d�O�����ꂽ�l�r
�����̔o�d�E�̒d�E���d
�o�����X���Ƃ������q
�l�l�̐}���A�l�l�̋��ʓ_
����I�ȐV�N��
�f�\�̕��@
���̓��F
��q����ĂȂ��o�l
���݂ɂ����V���o��̎���
�y�V���o��^���Ɛ푈���i�g���j�z
�y����̓����ƒZ�́E�o��̊W���i�g���j�z
�y����ւ̔��R�̑�֕��H���i�g���j�z
���@�ӎ��̓���
�y�u�����Ė�v�̈Ӗ����i�g���j�z
��^���d���V���o��
�V���o��Ǝ��R���o��
���Q�̎��l
���Ƃ��A�R����
�y�V���o��Ǝ��R���o��̋��ʐ����i�g���j�z
���c�j�̖���
�g���ɂ���
��終Ɓu�o�v
��終̈�̑̎�
��終Ƒ��c�j�̊�H
��O�̏����A���̏���
�鏗�Ɛԉ��j
�y�鏗�Ƌv���E�����q���l�s�Ƌv���z
�y�E���q�Ȃǁ��i�g���j�z
��O�̔o��E���̔o��
�y���o�l�ɂ����ʂ��c�c���i�g���j�z
�y�o��`���ւ̏�M���c�c���i�g���j�z
���厩�����߂�����
�������ɂ���Ɓc�c
�q�A�ڍ��k��r�@�@�@�A�@�B�@�C�@�D�@�E�@�F�@�G�@�H�@�I�@�J�@�K
���k��{���i400���l���e�p����215���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l�t�������[�A1980�N5��1���`1981�N4��20���A�q���� I�`XII�r��3�`8�y�[�W�i�������q���� XI�r��5�`7�y�[�W�j�B�@�ɏo�Ȏ҂̎ʐ^�u�����剪�M�A�ѓc�����A�g�����A�����d�M�v���A�B�Ɏq�K�E���q�E�Ɍ�˂̒Z���̎ʐ^�u�����q�K�A���q�A�� ��˂̕M�ցi�o�啶�w�ّ��j�v���f�ځB��{�ɂ͑��̖{���ɕ���ď��o�`�q�A�ڍ��k�� ����o������r���̂�A�s�����d�M�S�W�k��3���l�t�i�������[�A1985�N8��8���A330�`384�y�[�W�j�����̍Ę^�`�q����o������r�ɏƂ炵�� ���o�`�̌�L�E��A�i�\�L�ύX���܂ށj���Z�������y���o�`���Ę^�`�z�i�Ҏ҂ɂ��Z���́k�@�l�ŕ\���j�B�Ȃ��A�������Ȃǂ̑̍ق̕ύX�͍Z�����Ȃ������B�q�s�ӏ܌���o ��S�W�l�t���r���Q�Ƃ��ꂽ���B
�͂��߂�
�u�Q�߉ށv�̋�ɂ���
�}���s��̋�
�u�ߊC�Ɂc�v�̋�
���ݑ��G���`�V�Y��
�u���̐��Ɂv�̋�
�G��Ƃ�������
�u���E������v�̋�
�d�w�I�ȓǂ݂���
���_�̎��݂�
��d�̎��摜
���͂Ƃ��Ă̖���
�i�c�k�ߓ�\��
���k��{���i400���l���e�p����80���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s�o��t�k�p�쏑�X�l1980�N9�����k29��10����371���l168�`195�y�[�W�B�^�C�g���̂��ƂɎ��̂悤�ɏo�Ȏ҂̃N���W�b�g������B �u���q�W�i�Ս��j�@�����d�M�i�o��]�_�j�@�g�����i���l�j�@�O���q�Y�i�V�T�E�o��]�_�j�@�����r�Y�i���l�j�@�i�c�k�߁i�Ս��j�@��ؘZ�ђj�i�ԗj�E�V�T�j �@���c�q���q�i���l�j�@�j�M�q�i�����j�@�߉��P�v�i���l�j�@�Í��a��i��Ɓj�@��������i��Ɓj�@�������q�i�o��]�_�j�@�ѓ����q�i��j�@�����O���q�i�� �炬�E�����j�@���×��i�o�l�j�@��ؔ��i���l�j�@��ˏ~�v�i�o��]�_�j�@����o�X�q�i�n�\�j�@�Ԕ����q�i�Q�j�v�B�g�����s���́t����I�\��́s�� ���t351���i1980�N7���j�Ɂq�w���́x�\�叴�r�Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B���̉~��̕]�肪�������̂�1980�N5��14���A�_�ˁE�Z�b���ŊJ���ꂽ �q�P���E�i�c�k�߂̓��r�ɂ����Ăł���B
�l����Ɛ��n
���e���O�Y�Ƃ̏o�
�v�l�ƕ\���̉ߒ�
���W�ɂ�����鎍�I���E�̓W�J
�ꗬ�Ƃ��ẴC���[�W�Ɖ���
���ɂ�����\�z���ꂽ����
���k��{���i400���l���e�p����72���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1982�N7�����k25��7���l24�`41�y�[�W�B�^�C�g���̌�ɏo�Ȏ҂̊�ʐ^�e1�_�A�{�����ɐ��e���O�Y�̃X�i�b�v�� �^3�_�i����1�_�́u����J�ɂāE1979�v�j�A���e�Ƌ��q�����̃c�[�V���b�g�u���q�����ƁE1969�N����v���f�ځB���̋L���͈����L��E���J�K�M�E�R �{���ҁs��z�̐��e���O�Y�t�i�c��`�m�O�c���w���C�u�����[�A1984�j�Ɏ��^���ꂽ�B�܂��A�s���㎍�蒟�t2009�N10�����k52��10���l�́q���W ���q�����Ɛ��e���O�Y�\�\�n��50���N�L�O �����E���㎍�蒟�r�ɏ��o�̌�A�𐳂��āA�����̍قōČf�ڂ��ꂽ�B
���{���Ƃ̏o�
�`�����ƌ��㎍
�c�̃A�����J
�|��Ǝ�
�u�j���G���Ɖf��
�A�W�A�ւ̎��_
���k��{���i400���l���e�p����82���j�͏ȗ�
�ҎҒ��c�c ���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1985�N1�����k28��1���l38�`58�y�[�W�B�^�C�g���y�[�W�Ƀp�X�Ƌg���E�剪�E�a��E�g���́A�{�����Ɂu�I�N�^�r �I��p�X�v�Ɓu�p�X�v�ȁv�̎ʐ^�A�v4�_���f�ځB�ҏW��L�i�ҏW�l�E����ǐ��j�Ɂu�����̍��k��͋}篌��܂��������̒��ł̉ߖ��ȃX�P�W���[�������s �Ȃ�ꂽ�B���l�Ƙb�������Ƃ����̂̓p�X�����g�̋�����]�ł��炩���ߏ������ꂽ�g������̉p��A����̎��т�ǂݍ��݁A���Ă����p���͎��l�̐^������ �v�킸�ɂ͂����Ȃ������v�i�����A232�y�[�W�j�Ƃ���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
1960�N��
�@�V�E1 �k�S ��V�閾�E���{�R�ʕ��E�g�����̍��k��l�q�ǎ҂Ɩ{�̌��т� �\�\�o�ōL���͂ǂ�����ׂ����r�i�s�����V���t�k�����V���Ёl1961�N2��4���k�T��589���l2�`3�ʁj�\�\���k��{����400 ���l���e�p�� ��31��
�@�U�E1 �k�g �����E�V��ޓ�Y�̑Βk�l�q�V�t�Βk�r�i�s���㎍�t�k�� �ˏ��X�l1963�N1�����k10��1����121���l�q���W���V�t�Βk�r40�`41�y�[�W�j�\�\�Βk�{����400���l���e�p����7��
�@�W�E1 �k�� �q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�g�����E�������q�̍��k ��l�q����o��]�_�ܑI�l���k��r�i�s�o��]�_�t�k�o��]�_�Ёl1963�N2���k5��1����25���l8�`29�y�[�W�j�\�\���k��{ ����400�� �l���e�p����69��
�@�W�E2 �k�� ����Y�E���ˉ�v�E�g��O�E���C�i��E�H�J�L�E�����ρE�g�����E ����l�Y�E����S���̍��k��l�q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�i�s���w�t�k���w�Ёl1963�N7�����k18��7���� 196���l �q���W���g���܁r46�`51�y�[�W�j�\�\���k��{����400���l���e�p����21��
�@�U�E2 �k�g �����E����N�v�̑Βk�l�q�͌ЂƂ������E�ցr�i�s���㎍ �蒟�t�k�v���Ёl1967�N10�����k10��10���l�q���W���g�����̐��E�r52�`61�y�[�W�j�\�\�Βk�{����400���l���e�p����37��
�@�T�E1 �k�k �b�l�q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S����� �^���Ձr�i�s�o ��]�_�t�k�o��]�_�Ёl1968�N3���k10��3����78���l21�`24�y�[�W�j�\�\�k�b�{����400���l���e�p����12��
�@�U�E3 �� ���r�Y�q�g��������76�̎���r�i�s�g�������W�k���㎍�� ��14�l�t�v���ЁA1968�N9��1���A138�`146�y�[�W�j�\�\�{����400���l���e�p����25��
�@�T�E2 �k�k�l �q�����ƍ��ׁ\�\��a�����ƐV������Ƃ����r�i�s�f�� �|�p�t�k�f��|�p�Ёl1969�N3�����k17��3����259���l92�`93�y�[�W�j�\�\�k�{����400���l���e�p����8��
1970�N��
�@�W�E3 �k�g �����E�����؍K�j�E���q�����E�����d�M�E���c�Îq�̍��k��l�q�� ��o�偁���̒f�ʁr�i�s��t�k��o���l1972�N10�����k9��10����100���l12�`35�y�[�W�j�\�\���k��{����400���l ���e�p���� 84��
�@�U�E4 �k�g �����E�剪�M�̑Θb�l�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t �k�y�Ёl1973�N9�����k5��10���l�q���W���g�����r142�`158�y�[�W�j�\�\�Θb�{����400���l���e�p����66��
�@�W�E4 �k�g �����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������̍��k��l�q���� �������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�i�s�Z�́t�k�p�쏑�X�l1975�N2�����k22��2���l 58�`87�y�[�W�j �\�\���k��{����400���l���e�p����112��
�@�W�E5 �k�g �����E�ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�̍��k��l�q�v�z�Ȃ����� �̎��l�r�i�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1975�N5�����k18��5���l�q���W����؎u�Y�NVS�g�������r116�`129�y�[�W�j�\�\�� �k��{���� 400���l���e�p����57��
�@�U�E5 �k�g �����E�ѓ��k��̑Θb�l�q���I�t�̌�䊁r�i�s�����C �J�t�k�y�Ёl1975�N12���Վ��������k7��12���l�q��i�����W ���㎍�̎��� 1975�r192�`221�y�[�W�j�\�\�Θb�{����400���l���e�p����80��
�@�T�E3 �� �}������q�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�\�\��������܂̋g���� ���ɕ����r�i�s�T���Ǐ��l�t1977�N2��21���k1169���l1�ʁj�̋g�����̔����\�\�����{����400���l���e�p����4��
�@�T�E4 �k�C ���^�r���[�l�q�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���r�i�s�� �㎍�蒟�t�k�v���Ёl1978�N3�����k21��3���l�q���W���e���r���ǂ����邩�r115�`118�y�[�W�j�\�\�C���^�r���[�{����400���l���e�p���� 14��
1980�N��
�@�W�E6 �k�� �c�����E�剪�M�E�����d�M�E�g�����̘A�ڍ��k��l�q����o����� ��r�i�s�ӏ܌���o��S�W�k�S12���l�t�������[�A1980�N5��1���`1981�N4��20���A�q���� I�`XII�r��3�`8�y�[�W�i�������q���� XI�r��5�`7�y�[�W�j�j�\�\���k��{����400���l���e�p����215��
�@�T�E5 �i�q�j �q��Ԑ��̕��́\�\���̐��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�i�v���� ���j���o���g�������r�i�s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1980�N7��14���k2065���l�j2�ʂ̋g�����̔����\�\�����{���� 400���l���e �p����2��
�@�W�E7 �k�� �q�W�E�����d�M�E�g�����E�O���q�Y�E�����r�Y�E�i�c�k�߁E��ؘZ �ђj�E���c�q���q�E�j�M�q�E�߉��P�v�E�Í��a��E��������E�������q�E�ѓ����q�E�����O���q�E���×��E��ؔ��E��ˏ~�v�E����o�X�q�E�Ԕ����q�̍��k��l �q�V���|�W���E�� �i�c�k�߂̐��E�r�i�s�o��t�k�p�쏑�X�l1980�N9�����k29��10����371���l168�`195�y�[�W�j�\�\ ���k��{���� 400���l���e�p����80��
�@�U�E6 �k�� ����b�q�E�g�����̑Βk�l�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ��� �̍����ցr�i�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1980�N10�����k23��10���l�q���W���g�����r90�`111�y�[�W�j�\�\�Βk�{���� 400���l���e�p ����95��
�@�W�E8 �k�g �����E�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�̍��k��l�q��ނ� �����I���݁\�\���e���O�Y�Ǔ����k��r�i�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1982�N7�����k25��7���l24�`41�y�[�W�j�\�\���k��{�� ��400���l ���e�p����72��
�@�W�E9 �k�I �N�^�r�I��p�X�E�g�����E�剪�M�E�a��F��E�g�������̓��ʍ��k ��l�q����Ǝn���r�i�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1985�N1�����k28��1���l38�`58�y�[�W�j�\�\���k��{����400���l���e�p ����82��
�@�T�E6 �k�k �b�l�q�����{�̈��V�ˁr�i�s�_�u���E�m�[�e�[�V�� ���t�k���[�E�s�[�E���[�l1985�N7��23���k2���l�q�y���F���[�f�B���O�r71�`72�y�[�W�j�\�\�k�b�{����400���l���e�p����1��
�@�T�E7 �q�k�� ���V�g�����Ɋւ���k�b�l�r�i�s�����V���t�k�����V�� �����{�Ёl1987�N6��6���k39917���l23�ʁj�\�\�k�b�{����400���l���e�p����1��
�@�V�E2 �k���Y���P�E��������E�g�����i�Q�X�g�j�̑Θb��]�l�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t�k�y�Ёl1987�N11�����k19��12����256���l249�`�i�C�k��252�`�j261�y�[�W�j�\�\�Θb��]�{����400���l���e�p����42��
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
����������͏��߂ĂŁA���̐������Ƃ��ēC�k�A�Βk�A�u������Ȃ� ��`�ł���܂��B�\�\�g�����q�V���|�W���E�� �i�c�k�߂̐��E�r�i1980 �N5��14���́q�P���E�i�c�k�߂̓��r�ɂāj
�@�z
���w�E���C�X�E�{���w�X�i�ؑ��Ĉ��j�s�{���w�X�A�I�����t�i���敗���K�N�A1987�N11��10���j�́q��҂��Ƃ����r�Ɂu����̓{���w�X�̍u�����W��
�����̂Ȃ̂ŁA�w�{���w�X�u���W�x�Ƃ��������l�����̂����A�����Ŏ���̍l�������A�Ƃ����Ӗ����������Ǝv���A�����Č��������̂܂܂������ȏ���
���w�{���w�X�A�I�����x�Ƃ����v�i�����A�ꎵ�Z�y�[�W�j�Ƃ���B�Ҏ҂́s�g�����g�[�L���O�t���ڂ̕�����T�����Ă��邠�����A���́u�i�s���̈Č�
�iwork in
progress�j�v���q�G�N���`���[���ɂ��炴����́r�ƌĂ�ł������A�܂����s�g�����̃G�N���`���[���ɂ��炴����́t�Ƒ肷��킯�ɂ��������A����
�̂悤�ȕW��ɂȂ����B���͒��҈ȊO�̐l�Ԃ���������ɋÂ����薼��t���邱�Ƃɂ͔�������A���̂Ȃ���Ȃ����Ȃ��A�����Č����Ζ����z�ȃ^�C�g���ɖ�
��������B
�@�k�b�E�C���^�r���[7�сA�Βk6�сA�C�k2�сA���k��9�т̍��v24�т��A�u�g��������������Ɓv�̂��ׂĂƂ��Ă����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B���̂����̉��т�
�́A�s�g�����̎��̐��E�t�̋L���Ɉ��p���邽�߁A�ȑO�Ƀe�L�X�g�f�[�^�����Ă������A�����̋L���i�Ƃ�킯���k��j�͍��߂ăe�L�X�g�f�[�^�������B��
���̑唼�͔N�����o���R�s�[���e�̂��߁A�n�b�q��Ƃ͍��������߂��B���w�I�Ɏ�肱�摜�������Ƃ��ĔF������Ȃ����߁A���̂ɂ���Ă͉��\�s����
�Ń^�C�v���ē��͂��邵���Ȃ��������̂�����B�������A�����J��ƌ����͓̂�����Ȃ��B�莫�Ɉ������g��������M����Ȃ�A�ǂ����Ă��f��肫��Ȃ���
���˗��ɉ��������ʂ������24�тł���A���̋M�d���ɂ����ċg�����M�����������͂ɗ����̂ł͂Ȃ�����ł���B
�@���������A2010�N3���ɂn�b�q�ɂ����́A4���ɑg�Łihtml�t�@�C�����j�A5���ɕ����Z������ѓ���m�F�������B�E�F�u�y�[�W�̐���i�����
�A�b�v���[�h���Ȃ�����A���m�ɂ�html�t�@�C���̍쐬�j�ɂ͈���E���{�̍H�����Ȃ����߁A�t�@�C�������̎��_�ō�ƏI���ƂȂ�B����͂����Ȃ����
���Ȋ��o���B������Â��肪��{�ɂȂ��Ă��鎄�̂悤�Ȑl�Ԃɂ́A�d�q�I�ȕ����̍쐬�́u�s���ȗ��l�v�̂悤�Ŏ艞�����Ȃ��B�s�g���������s�U���W ���o�ꗗ�t�\�\
�s�g���������s�U���W�t�̖{���͂c�s�o�őg����u�ʼn����삻�̂��́v�������\�\�ɑ����āA���̂悤�Ȍ`�ŋg�����̍�i���܂Ƃ߂�ꂽ���Ƃ͊������B��
���I�ɂ́A�s�g�����S�W�t�́q�k�b�E�Βk�E���k��r�Ƃ��ās�g�����g�[�L���O�t�̓��e����������邱�Ƃ����҂������B
�@�@�g�����f���\�N�̓�Z��Z�N�܌��O����@�����E���n�ɂ�
���ш�Y
�������W�s�Â��ȉƁt�܂ł����߂��s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�͊��s�����̋g���́u���̑S���W�v�������B���m�Ɍ����A��O��i�́s�t�́t�i����ɁA1941�j���珴�^��12�т����ŁA�s�����G�߁t�i���A1940�j�͍̂��Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A�g���͂��̂Ƃ��܂Ő��z���Łs�����G�߁t�Ɍ��y�������Ƃ����Ȃ������i�P�j�B�������A�s�����G�߁t�́u�c�t�E���d�ŁA���I�Ȕ������Ɍ����Ă���v�i�q�킪�������W�s�t�́t�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�j�Ƃ���g���̎��ȕ]�����z�ʂǂ���Ƃ�̂̓i�C�[�u�ɉ߂���B���́A�g�����s�����G�߁t���������W�ƔF�߂Ȃ������ő�̗��R�́A���l�Ɂu�G���v�i���O�j�Ƃ܂Ō��킹�����W�S�ׂ̂�X�^�C���̌��@�ɂ���̂ł����āA��ш�т̎��̗ǂ���������肾�����킯�ł͂Ȃ��ƍl����B�u�킪������ɂȂ�݂͂Ă��^��������ɂ����̂킭�v�i�q�f�́r�@�E14�A�S�сj�ȂǁA�����̓ǎ҂̈��u�����т��낤�B�꒲���Z�̗R���ł��邱�Ƃ͂��̎��̔��_�ł�������A�u�c�t�E���d�v����͉����B
�g�������������ȑO�Ɋ���e�����w�`���͘a�̂ł���B�a�̂͗������Ȃ��ߓ��e���l���邾���ł悭�A���̂悤�ɂ̓X�^�C�����l������K�v���Ȃ������B���ꂪ���R���������͂��߂��ۂ�5���E7���̗��Ƃ���Ⰲ��O��āA��т̎���̒������s�������ӂɂȂ�B�����́u���ӂȈ�сv�𑩂˂ĂЂƂ̃X�^�C�����\�z����ɂ́A��т́u���v���������ƂƂ͕ʂ́A����́u���W�v�����ϓ_���K�v�ɂȂ�B�����������܂Ƃ߂��̂��s�����G�߁t�ŁA���W���`�����鎍���������̂��s�t�́t���Ƃ����̂��g���̎������������낤�B�W�Ƃ��������낵�A�����W��m�炳�ꂽ���Ƃ̒Z���Ԃ̕ҏW��ƂȂ���A�g���͂��̈�N�Ŏ��������̐l���玍�l�ւƕϖe�𐋂����B�z���s�����G�߁t���\�����鎍�ɂ͎�{�����������B�Z�̂��玍�Ɉڂ�������̋g���͎��Ȃ̃X�^�C�������݂����˂Ă��āA�蓖���肵�����u����́v�Ɗ������X�^�C�������݂��B���̂Ȃ��ɂ́A����Z�̂������̂��̂�����A�k�����q�⍶�삿�����ӎ�����������U������B�g���̍ŏ��̒����A���̏W�s�����G�߁t�́q�t�r�q�ār�q�H�r�q�~�r�Ƃ����l�̖`�����т���q�H�r�����悤�B
�H�b�g����
�@�ւ̕���ግ��ɘ��߂����̐�
�@�@�@�Ɏq�ǂ̒��ł͂�����Ɩ̗t������
������q�̂ӂ��𑖂�l�Ԃ̓Q�̂Ђт�
�@�@�����֒w偂������͂��@�@�@�����C���̂����ɍL���C�����̂ڂ�
�@�@�@�@�@�ݓ��Ŏq�����d�������킵���@�H�������炫�炫����点
�@�@�@�܂����肱�ڂ�
�������ƍs�A�L����g�����W�J�͏[���ɗ����Ă���B�����̖ڂ��炷��ƁA���̏��@�̓��_�j�Y���̕��Ɠ����ɁA���邢�͂���ȏ�ɘa�̂̎U�炵������z�N������i�����ās��ʁt���ł͂Ȃ��j�B�g���͂Ȃ�����𑼂�3�сq�t�r�q�ār�q�~�r�̂悤��
�ւ̕���ግ��ɘ��߂����̐�
�Ɏq�ǂ̒��ł͂�����Ɩ̗t������
������q�̂ӂ��𑖂�l�Ԃ̓Q�̂Ђт�
�����֒w偂������͂�
�����C���̂����ɍL���C�����̂ڂ�
�ݓ��Ŏq�����d�������킵��
�H�������炫�炫����点
�܂����肱�ڂ�
�Ƃ��Ȃ������̂��B�q�t�r�q�ār�q�H�r�q�~�r�œ���I�ȃX�^�C����Nj������̂Ȃ�A����3�тƓ����ɂ���悩�����B�q�H�r�����ɂ���̂́A��{�ɂ������_�j�Y���̏��@�Ƙa�̂̎U�炵�����̍����ł���A��������e���鎍�l�̓�d���ł���B����߂����̂����������ɔz�u���Ȃ���A����S�̂����������Ђ���Ǝ��������G�͋g�������߂��u�������������v�i�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�Z���y�[�W�j�Ƃ͔����ɂ���Ă���B����́A�����̌���Z�́A�g�������ǂ��Ă�܂Ȃ������s�Ԋ~�t�̖k�����H���v�킹��B�g�����̘a�͉̂̏W�ȊO�̂���ȂƂ���ɂ������Ă����B����A����̏������т͎��̂悤�Ȃ��̂��B
�@���A�Ɣ��K�N�Ƃ����a�����\������Ƃ��̂��鐇���������т����B�@���̂Ȃ��ɂُ͈�ɐ������ɖ���n���֒��˂����̂悤�ɋ��ՂȒe��������B�@�c�ɂ͓y���̂悤�ɔ����������̊����ɂ��̂̂����͐��m�Ȃ̂Ŋ������̂ɏ[���Ȉ��͂����B�@���ׂẲ����镨���Ɠ����ɂ��̐������ӎu�ɑ����Ă����̂�����H�@��������]�������̂悤�ɍז��Ȕ]����������B�@����ȋ��ʂɂ͖����̐_�l���������Ă���B�@���̏u�Ԃ̕����͉Ԃ̂��Ƃ��Y��ł���B�@���ӂ�閳�p���������ĉԂ̈ӎu�������ĐV���z�p��������ޗt���F�̍A���������z�t�̓�̊�͋`��ł���B�@�����Ĕނ̐������������ɖ��@���ɕω�������̂��ӎ����Ă���B�@�ЂƂ����̉����̌����͏����̔������˂��Ƃ������܂��B�@�����I�Ȃ�ߑO������B
�s���I�����t�̓�Ԃ߂ɒu���ꂽ�qETAMINES NARRATIVES�r�́u�P�v�i���o�́q�R���r22���A1927�N�j�ł���B�S����11�̎���i�Ǔ_�͂Ȃ��A�Z���e���X�Ƃ��Ď������Ă���j�͋g���̂���ɔ�ׂĂ��Ȃ蒷���B�܂��A�O��̎���Ƃ̊ւ��͋g���̂���Ɠ��l�A�\�Ȃ�����Ⴍ�ݒ肳��Ă���B�ɂ�������炸�V���^�b�N�X�͌����ɍ�p���Ă��āA������V���b�t�����Ă���i�Ƃ��Đ������邩�Ƃ����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�g���̏������W�̕W����2�т���B����1�т�
�����G�߂P�b�g����
���̒�q��
���ʂ������G���
�邪�ዾ�������Ă̂ڂĂ䂭
�t���̉��̗ւ̒��ŏ��B�͖ł�
�d���ɔ��_���ӂ���
���J�����]����֎q�̏��
�ڂ̐Ԃ�������C�����Ă
�ł���B�qETAMINES NARRATIVES�r�ɕ킦�Ή��s�ӏ��͂����ƌ���A�u���̒�q����ʂ������G���邪�ዾ�������Ă̂ڂĂ䂭�@�t���̉��̗ւ̒��ŏ��B�͖łѓd���ɔ��_���ӂ���@���J�����]����֎q�̏�ɖڂ̐Ԃ�������C�����Ă�v��3�Z���e���X�ɁA����1�т́q�����G�߂Q�r�l�ɃA�����W����u�����̋�㢂̒��ɐ������Ă������Ǝl���̉����@���L�̎��̂悤�ɓ����Ă��������̏�ɓ��j�����|��Ă��Â܂�@���q�����ɖc��ނƗ��͐��ւȂ��ꚿ�ɂ͉Ԃ̉e������Ђ낰�ČX���@�����݂������j�������炵���݂�ᰂ�����̎�����f���o���@����������啂����Ԃ��Ƃт߂���v��5�Z���e���X�ɂȂ�B����́u���A�Ɣ��K�N�Ƃ����a�����\������Ƃ��̂��鐇���������т����v�ɑ��A�g���́u���q�����ɖc��ނƗ��͐��ւȂ��ꚿ�ɂ͉Ԃ̉e������Ђ낰�ČX���v�ƁA���҂̌�@�̗ގ����āA������ɂ͝R����ۂ���Ă���B�u�����Ȃ�A�R���N���[�g�̕ǂɗ⍓�ɂ��G�ꂽ�o���̉Ԃ̒ɂ܂������v�i�q�~�ς��肤���r�A���O�j�ƌĂт��킷���̎���͔������B�g���́s���I�����t�̂͂��߂ɒu���ꂽ��i�ɐG��āA�����炭���S�����������낤�B�u�ԃC�E���R�m���K�I�~�j�Փ˃X���X�H�j�v�i����C���qLINES�r�j�\�\�u�ڂ̐Ԃ�������C�����Ă�v�i�g�����q�����G�߂P�r�j�B
�g�����s�����G�߁t�ɏ��߂Č��y�����̂�1972�N�A���k��ō����d�M�Ɏw�E����Ăł����i�Q�j�B������s����C���̎��I���� 1927�`1937�t���܂Ƃ߂�̂ɎO�\�N���������悤�ɁA�g�����s�����G�߁t�����������Ƃ�F�߂�܂łɎO�\�N�ȏォ�������B�g��������ɕ������q�ǎ�̏��r�̔��\�����̗���74�N�B���̕����͒P�Ȃ���R���낤���B�O���悤�ɁA�q�ǎ�̏��r�́s���I�����t�����i�̕W��⎍����قƂ�ǂ��̂܂ܗ��p���Ă����i�R�j�B�g�����͌��掍�ɂ����āA�����Ƃ��Ď��l�̎U������͋�����p���Ă��A������͎�������p���Ȃ����Ƃ�g��ɂ��Ă����i�S�j�B����̎��i�̕W��j�����p�������Ƃ́A�g���ɂƂ��ās���I�����t�͌����̎��l�̎���i�ł͂Ȃ��A���j��̐l���̗��j�I�ȍ�ł���Ƃ������Ƃ������Ă���̂��낤���B�\�\�{��~��Ǔ������q�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�̏ꍇ�ƂƂ��ɁA����̉ۑ�Ƃ������B
����i�ɂ�������p�Ƃ́A���l�̏͋�����g�̎���ɂ��邱�Ƃł���B���̏o�������邽�߂Ɂu�@�v���͂��߂Ƃ�����p���Ŋ����āA���傪�A�����Ă������Ґ����ۗ�������B����͂���Ƃ��āA�O�\�N�ȏ�O�̎����̎���͂ǂ��܂ł����Ă������̂��̂ł��葼�l�̏͋�łȂ��A�Ɩ����ł��邾�낤���B������s���I�����t�ɓY�t�����q����C���̎��I����1927�\1937�Y�������r���u���̂Ȃ��̂ЂƂ�̑��l�����̂悤�ȕW���I�����v�Ǝn�߂Ă���̂́A�܂��Ƃɏے��I�ł���B�g��������̎��I�������瓾�����̂́A�O�\�N�A�l�\�N�O�̎���́A���Ă͂����ł������ɂ���A���͂⎩�g�̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ����F���������B���̂Ƃ����߂āA�g�����Ƃ����N���O�\�N�O�ɏ������������I�Ȏ���́A�g�����ɂƂ��đ��l�̏͋�ƂȂ�B
1970�N��́u�����g�������v�́A�ŗL�����i�l���j�̓����Ƒ��l�̏͋�̈��p�Ƃ����`�ŁA�����ς畁�ʖ����Ǝ��O�̎���ŒԂ�ꂽ�s�Õ��t����s�_��I�Ȏ���̎��t�܂ł́u�O���g�������v�Ɩ��炩�ȑΏƂ��Ȃ��B����͊g��c���𑱂����s�_��I�Ȏ���̎��t�̎���̊O����A�q�킽���̍쎍�@�H�r�i1967�j�ő��������������̋����琬�鎍�w���ЂƂЂƂ��Ԃ����Ƃɂ���Ĕ������āA���g�̎��̓]����}�����̂ł���B�������A�g�����̎��̓����ɂ����T�邱�Ƃ͓���ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A��������܂ŋg�����̎��ɂ��Ę_�������Ƃ̂قƂ�ǂ�����ɓ����邩�炾�i�s�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁t�Q�Ɓj�B�����Ŋ��]���āA���т̒����ɒ��ڂ��Ă݂悤�B�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�̊e���W�̎��і{���̃y�[�W�������т̐��Ŋ��������́A��т�����̕��σy�[�W�����ȉ��̕\�ł���i���ڂ͎��W�ԍ��E���W���E���s�N�j�B
| �@�����G�߁i1940�j | 0.8 |
| �A�t�́i1941�j | 0.9 |
| �B���i1955�j | 1.8 |
| �C�m���i1958�j | 2.5 |
| �D�a���`�i1962�j | 1.9 |
| �E�Â��ȉƁi1968�j | 2.8 |
| �F�_��I�Ȏ���̎��i1974�j | 3.8 |
| �G�T�t�����E�݁i1976�j | 4.1 |
| �H�Ẳ��i1979�j | 3.5 |
| �I�|�[���E�N���[�̐H��i1980�j | 1.5 |
| �J��ʁi1983�j | 3.7 |
| �K���[���h���b�v�i1988�j | 3.9 |
����炷�ׂĂς���Έ�т̃y�[�W����2.6�ƂȂ�B���Ȃ킿�A���l�̑傫�����̂͒����A���������̂͒Z���B��O�̇@�ƇA��1�����A���́u�O���g�������v�̂����B�`�E�͂ق�2�`3�O��A�F�`�K�i�F�́u�O���v�A�G�ƇH�́u�����v�A�J�ƇK�́u����v�Ɏ��߂����j���ق�4�O��Ȃ̂́A�����Ŏ��@�̑傫�ȓ]�������������Ƃ��i�I��22�N�Ԃɂ킽��E�⎍�W�̂��߁A�ق��ƌX�����قȂ�j�B�]���̗v���͂������l�����邪�A���̕M���́u���鎞������A���������Ȃ���A���͎��Ȃ̑z���͂̌͊��������Ƃ��������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�j�Ə����A�k�b�ł����т��ѐG�ꂽ�u�z���͂̌͊��v�ł���B���\���|�Ƃ���g�������ɂ����āA�z���͂̌͊��͍�i�̑��S�Ɋւ���厖�������i���ƂЂƂ�����Ȃ�A�u���ю��v�ւ̓��ۂł���j�B�������A�g���̑S�L�����A��ʂ��āu���v�Ƃ����`���Łu�G�v��`�������Ƃ����u���`�ւ̊�]�v�i�q�킽���̍쎍�@�H�r�A���O�A����y�[�W�j�͓����Ȃ������B�g�������̋N������s�����G�߁t�̑O�ɑ����̃s�J�\���i�T�j������A�s�T�t�����E�݁t�̑O�Ɂs����C���̎��I���� 1927�`1937�t���������B�����炭�s���[���h���b�v�t�̌�́A�s�R���N�V��������C���t���ӊ��̋g�������������ɈႢ�Ȃ��B�����A�g������x�͎��݂�����C���S�W�̌����I�ȓW�J�A�s�R���N�V��������C���k�S13���E�ʊ��l�t�i�݂������[�A1991-98�j�O�Ɍ��邱�Ƃ͂Ȃ��A�u�������e�[�}�̒��ю��v�i�q�ŋߊS�̂���e�[�}�r�A�s������{���M�ґ厖�T77/82 ��l���i�Ё`��j�t�A���O�A�\�V�G�[�c�A1984�N8��25���j��������邱�Ƃ��Ȃ������B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�i�P�j�@�g�����s�����G�߁t�ɍŏ��Ɍ��y�����̂́A�i�Q�j�Ɉ��������k��q����o�偁���̒f�ʁr�i�s��t1972�N10�����j�ɂ����Ăł���B���̌�A1973�N9���̑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r��A1975�N9���́q�V�������ւ̖ڊo�߁r�A1976�N10���́q�ԉ��j�厄���r�A1978�N9���́q�킪�������W�s�t�́t�r�A1980�N1���́q��̎��W�̂͂��܂Łr�Ƃ��������z�ŁA���W�ɐG�ꂽ�莍�т����p�����肵�Ă���B�����ās�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�́q���Ƃ����r�Ɂu��\���N�Ԃɘj��G���̐��X��ʓǂ��āA�C�Â������Ƃ́A�������W�s�t�́t�ɂ܂��A�s�����G�߁t��s�����t�ɏA�Ă̌��y�̑������Ƃ��B�܂����ɒm���邱�Ƃ��Ȃ����������A���ւ̖v�������A�K�R�I�ɏ�������ӂ̐����ɂ��������Ă��܂����킯�ł���v�i�����A�O�Z��y�[�W�j���Ō�ƂȂ����i�������q���Ƃ����r�̏��o��1980�N���̓������Łj�B���҂ɂ�錾�y�́A�����d�M�́q�g�����Ɣo��`���r�i�s�����C�J�t1973�N9�����j�������Ě���Ƃ��邪�A�����͂����Ŏ�������p���Ă��Ȃ��B
�i�Q�j�@�g�����E�����؍K�j�E���q�����E�����d�M�E���c�Îq�̍��k��q����o�偁���̒f�ʁr�́q�o��Ƃ̏o��r�Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ肪����B�����͎������珑���������Ă��Ȃ��B
�@�����@�k�c�c�l�ڂ��̎苖�ɂ́A�g���������ɍs���Ƃ��ɂ��������W�Ƃ����̂��ȁA���邢�͉̏W�ƌĂق��������̂��A���ꂪ�����ł���B������݂�Ƃڂ��́A����ς�܂��܂����������������ǂ��A���̂Ƃ��A�g�����������������Ȗ{���A�Ȃ��o���C�ɂȂ������A�Ƃ����悤�Șb���Ă݂�ƁA�����������Ƃ������킩���Ă���Ǝv����ł���B
�@�g���@�Ȃ����̂�����A����́B�w�t�́x����Ȃ��ł���B
�@�����@�������܂��ˁB��������̒Z�̂��ڂ��Ă���{�ŁA���������a�\�ܔN�̔��s�������B
�@�g���@�w�����G�߁x�Ƃ����̂���������ł����ǁA����H
�@�����@����A����B���̖{�Ɂu�莆�ɂ����āv�Ƃ����p�ݍ��݂̕��͂������āA�o�ł̂������������Ă������B
�@�g���@����ɂ���́H�@����͂����Ԃ�s�v�c���ȁB�i�j�i�s��t1972�N10�����A���`��O�y�[�W�j
�i�R�j�@���}������s���߂̕��w���\�\27�l�́q�n��H�[�r���k��p��102�l�t�i�发�فA1982�N8��15���j�ɂ͋g�����̔����u�����̑z���͂����ł͂Ȃ��āA�p�E���h�Ȃ̗�ɂ�����悤�ɁA���l�̌��t�������Əc���ɗ��p���ċC�y�ɏ����Ă����Ă�������Ȃ����A�Ƃ����C�ɂȂ�����ł��B�����ʂ�̈��p������܂����ǁA������������A�t�̂��Ƃ���������ŁA�����Ԃ��ɍ����悤�ɂ���ς���������Ă܂��v�i�q�g�����u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�r�A�����A��Z��y�[�W�j���L����Ă���i���o�́q�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�\�\��������܂̋g�������ɕ����r�A�s�T���Ǐ��l�t1169���A1977�N2��21���j�B
�i�S�j�@�g�����͋�����b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�Łu���p���v���Ď��̂悤�Ɍ���Ă���B
�����@���̊��ʂ͉��ł��傤�ˁB�ŏ��͂��������p�ł��邱�Ƃ����邽�߂Ɏg���������Ƃ����̂���Ȃ��Ǝv����ł����ǂˁB
�g���@�S�`�ł������킯�Ȃ��ǁA�ŏ��͓��`�I�ɂЂƂ̌��t�ł��邱�Ƃ��������߂Ɏg�����̂�����ǁB�k�c�c�l�����A�ڂ��������Ă��������̂́A������̎��т����傩��͂Ƃ��ĂȂ���B����݂͂�ȑΏۂɂȂ����l�̃G�b�Z�C����Ƃ��Ċ��ʂɂ���āA��������ɂ����Ă��Ă���B��������̗�O�́A�������ɕ������u�Ɣ�������v�����͂ǂ����Ă��A�������́u���t�v�����ō��Ȃ��Ȃ��āA���傪��A�O�͂����Ă���B�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�y�[�W�j
�͒Ǔ����q�u�Ɣ�������v�r�i�H�E27�j�����łȂ��A���掍�q�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�ł������������Ǝv����B
�i�T�j�@�g�����͐��z�ŘZ��ɂ킽���āu�s�J�\�̎��v�Ɍ��y���Ă���B�@�u���̍��A�֓������̎l�J�̃A�p�[�g�ŁA�s�J�\�̎������A���������B����́u�݂Â�v���Ȃɂ����낤�v�i1959�N8���j�B�A�u���X�̏K������݂����o��ł��Z�̂ł������ł����A���p�G���ł݂��s�J�\�̎��ɐG������Ď��ֈڍs�����v�i1962�N1���j�B�B�u�k�����q�ƃs�J�\�A���ꂩ�獶�삿���̎��ɂӂ�āA���^�I�Ȃ��̂֓]�ڂ��Ă������̂ł���v�i1968�N4���j�B�C�u�����s�J�\�̊G�Ǝ��������̂́A�������\���A���̂���̂��Ƃ��v�i1982�N3���j�B�D�u�k�����H�̒Z�̂⍲���t�v�̎��ɖ������Ă����A���N���̎��͋��R�ɓǂs�J�\�Ɩk�����ʂ̎��ɂ���āA�ʂ̎��̐��E������̂�m�����v�i1983�N4���j�B�E�u�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łw�݂���x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������v�i1984�N1���j�B����C����ɂ��Ƃ����L�q���o�ꂷ��͇̂E���ŏ��ŁA����ȑO�̂��鎞�_�ł��ꂪ����́q���������s�J�\�r���������Ƃ�m�����킯���B�T���́s�ߑ�|�p�k���p�I���l�t�i���p�o�ŎЁA1962�j�̉\�����������A����͏��o�q���������s�J�\�r�i1937�j�Ȍ���s�J�\�̎��ɂ��т��ѐG��Ă��邩��i�q���������s�J�\�r�̓����Ă���s�ߑ�|�p�t�̍Ċ���O�����܂߁A1949�N�ȗ���3�x�ɂ킽��q�s�J�\�̎��r��1973�N�́q�u�s�J�\�̎��v�]�k�r������j�A�g�������A�Ȃɂɋ������̂��f��ł��Ȃ��B
�g�����̎��сq�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�́s���㎍�蒟�t1974�N10���Վ��������q����C���r�ɔ��\���ꂽ�B�O����q�_��r�i�������сE20�j������́s�]���ɏ��� �Q�t�i�݂������[�A1982�N7��1���j���ł������Q�Ƃ��Ă����悤�ɁA�{�т��˂��Ă���̂́s����C���̎��I���� 1927�`1937�t�i�v���ЁA���ŁF1967�N12��1���A�k���ŁF1971�N12��15���j�Ɓs�]���ɏ����t�i�݂������[�A1966�N5��30���j�ł���B���Ɍf���鍀�ڂ́A���g�����̎���c�c�T���Ǝv�������C���́q�W��r��͋�y�@�z���͂��́q�W��r�i�o�T���̂Ȃ����̂́s����C���̎��I�����t����ŁA�����͓����ɂ�����f�ڃm���u���j�ł���B
���Ă̐�l���̞��̏�ɍ~��c�c�q��l���Z��r�y�q��l���Z��r�l�Z�z
���u�l�Ԃ̎��̏[������^�@�@�@���Ắc�c�q���Ăɏ[������l�Ԃ̎��r�y�q���Ăɏ[������l�Ԃ̎��r�Z�Z�z
���u�����������������߁^����t�Ɉł�����߂��肷��v�c�c�����Č����������������߂���t�Ɉł��Ƃ����߂��肷��D�y�q�h���I�ȓ����p�\�\���[�����Ɂr�A�s�]���ɏ����t�A�y�[�W�A���o�F���[�����W�A���L�A1960�N5���z
���n��̐��E�K���{�I�c�c�q�n��̐��r�y�q�n��̐��r���l�z
���u�܌��̃X�t�B���N�X�v���c�c�q�܌��̃X�t�B���N�X�r�y�q�܌��̃X�t�B���N�X�r��l�Z�z
�����ƍ��Ɓc�c�s���ƍ��Ɓt�y�s���ƍ��Ɓ\�\���^���k���q�P�l�t�A����R�c�A1973�N2��25���z
���u���͊��S�Ȃ���̂����킦�Ĕ�ԁv�c�c��������ˑR���̂悤�Ȓ����ʔK�̂悤�Ɋ��S�Ȃ��̂������Ĕ�т������B�y�qTEXTE EVANGELIQUE�r�Z�l�z
���u�ޏ��͖��m�̉���Ȃ��ނ�^��f���ŐV�̌����́v�c�c�ޏ��͖��m�̉���Ȃ��ނ��f���ŐV�̌���铁A����̎v�t���ł���B�y�q�������ɂ����鑾�z���ւ̌��J��r��Z��z
���u���H�̂Ƃ�����͂��܂�v�c�c�q���H�̂Ƃ�����n�܂�r�y�q���H�̂Ƃ�����n�܂�\�\�r�c�����v�Ɂr�A�s�]���ɏ����t�A����y�[�W�A���o�F�r�c�����v���ʼn�W�A���{����L�A1963�N9���z
���u�B���Ȋ��Ɖ����Ƃ́^��������㫂߂悤�Ƃ��Ă���v�c�c�o�T����
���u�ق��ā^�����Ă����Ă��܂����v�c�c�o�T����
���u�߂����̂̐��������v�̏H�c�c�o�T����
�{�т̖�1�N��ɏ����ꂽ�u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�ƕ���̂���q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�ɔ�ׂāA�u�@�v�Ŋ���ꂽ�͋�̏��Ȃ��̂��������B�������A�n�̎��傪���ׂċg���ɂ����̂��Ƃ����ۏ��Ȃ��B���Ƃ��u�n��̐��E�K���{�I�v�̎��s�u���݂̋���ȐO�����ǂ��s���̐l�͑��݂��邾�낤���v����}���E���C�̖��ʑ��q�V����̎����Ɂ\�\���l�����r�i1932-34�j��z�N���Ȃ��ł���͍̂���ł���A�̂��ɛܒJ���m���u����C���̃}���E���C�ւ̋����Ƌ����͍��Ԃ����v�i�s���ꂽ���\�\����C���Ɠ��{�̃A�[�e�B�X�g�����t�A���}�ЁA2004�N12��5���A�l�Z�y�[�W�j�Ə����悤�ɁA�g��������̃}���E���C�Ɋ鋻���Ƌ����߂������ƌ���ׂ����B�܂���T�߂�1�s�߁u�l�͎��R�Ȏ���������Ă���v�́u���R�Ȏ�v���A����̏��Ă���|�[���E�G�����A�[���̎���W�s���R�Ȏ�t�i�}���E���C�Ƌ����A1937�j�Ɉ˂��Ă��邱�Ƃ����炩���B�����܂��āq�ǎ�̏��r���g��������Ɣނ̋�������A�[�e�B�X�g�����ɕ����������ƂƂ炦��Ȃ�A����ɓo�ꂷ��B��̃A�[�e�B�X�g�ł���փ����[�E���A���A����Ƃ����C���̔g���̂ЂƂɉ߂��Ȃ��Ǝv���Ă���B�u�փ����[�E���A�͖��̉��܂�S�ő���^���̂悤�ȓ��ʁ^�I�����W�̂Ȃ��̍��j�^���ꂪ�����^���C�����[�h����^�ǎ�Ƒ��v�����̎U���q�փ����[�E���[�A�̒����r���Q�Ƃ��ēǂ܂˂Ȃ�ʓ����͂Ȃ��B�g�����������ꂽ���A�́u�ǎ�Ƒ��v�Ƃ����^����l�����邽�߂ɃA�R���K�C�̊L�k���ɍ������ꂽ�ٕ��̂��Ƃ����݂ł���B�v���Έ��p��������̍�i�̕W���͋傱���A�g���ɂƂ��Ắu���j�v�ł���u���v�ł���A�C���s���C�ɐ��ޑǎ�ɂ��đ��ł��낤�Ƃ���ӎu���Ƃ��Ɏ��҂Ƃ��đ�����������邱�Ƃ��A�{�т̊�ڂł������B���̂Ƃ��A�g�������тɌ�������p�����̕W��E�͋傷�ׂĂ��ŏ��Ɂi�����������āj���ׂāA���̊Ԃ����g�̎���Ŗ��߂Ă����Ď��т������Ă������Ƃ͎v���Ȃ��B���і������̏��o�`�Ǝ��W���^�`�����悤�i�q�ǎ�̏��r�S�̂̈ٓ����q�g�������W�s�T�t�����E�݁t�{���Z�فr�Q�Ɓj�B
�@�@�@�T
�l�͎��R�Ȏ���������Ă���
����䂦��
�s���R���K�N�̓����ɗ}����
�u�ق���
�k�i�ꉺ�j���i�V�c�L�j�l�����Ă����Ă��܂����v
����͌`�Ԋw��
����߂Ď��ȓ����I����
�փ����[�E���A�͖��̉��܂�S�ő���
���̂悤�ȓ���
�I�����W�̂Ȃ��̍��j��
���ꂪ����
���C�����[�h����
�ǎ�Ƒ�
�k�i�i�V�j���@�@�@�U�k�ߔԍ��l�l
�Ȃ��閾���̐����Q�̓t�B�����̂悤��
�D�F�ɒ���ł���̂�
�k�i�i�V�j���u�߂����̂̐��������v�̏H�l
�����������N�̍��̂�����܂�
�����g��������
�k�������l���͊C�݂ɏo������
�����̎��͖{����14�s�߈ȍ~��V���Ȑ߂ɂ������ƂƁA�u�u�߂����̂̐��������v�̏H�v�Ƃ��������}���������Ƃł���B�����ɂ́A������Ȃ߂炩�Ɍq���ł����̂ł͂Ȃ��A���߉����Ċ�̂悤�ɂ���������̎����A�˂Ă����Ƃ������j�����ĂƂ��B����̏͋�i�̂悤�Ɍ�����u�@�v�Ŋ���ꂽ�͋�j�͋g���̎��z��f������̂Ƃ��āA�܂�u�փ����[�E���A�v�����傫�Ȉٕ������ׂ������Ă���B���̐����͑��҂̂��Ƃi�̂悤�Ɍ�������́j������邱�Ƃɂ���ē]�Q�����̂ł����āA�d�w�������̂ł͂Ȃ��B�߂̋敪������Ԃ̒f����㉟�����錋�ʂɂȂ��Ă���B�g���́u�`�Ԃ͒P���Ɍ����Ă��A����Ȏ��Ԃ̉�H���������\�����K�R�I�ɗv�������B�\���I�ɘA�q�����Ȃ���A�\�m�ł��ʒf������肩�������G�����\�ʒ��͂�����v�Ƃ������g�̍쎍�@�̗��O�͂��̂܂܂ɁA��̓I�ȓW�J��@��傫���ς����̂ł���B�q�ǎ�̏��r�͈��p���ł���Ɠ����Ɂu�e�����|�p�Ƃ����̏ё����A���������ŕ`���悤�ɂȂ����v�i�q�O�̑z���o�̎��r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A���Z�y�[�W�j���掍�̑��������̈�тł���B���p�̎�@�����̎��W�s�Ẳ��t�i1979�j�Ő��n����ȑO�̍�i�����ɁA���i���m�ɂ́u���I�����v�j�ƎU���́q����C���r���ۓۂ݂��悤�Ƃ���g���̕s�G�Ƃ������鎎�݂��A�w���ʐ^������悤�ɓ����ł���B
�g�����Ƒ���C�����߂��钍�ڂ��ׂ����k�����B���Ñ��Y�E�ѓ��k��E�剪�M�E�����O�q����C���̑��݁r�i�s���㎍�蒟�t1968�N10�����j�ŁA�s�R���N�V��������C�� �ʊ��t�i�݂������[�A1998�N7��24���j��1�y�[�W���́q����C���Ƌg�����r�͂����炭���҂��r�����B��̕����ł���B
�剪�@�k�c�c�l�������̃C���[�W�̎��́A���Ƃ��Ή_������Ȃ����Ј�Ђ��������ꂢ�Ȍ��ɂ������Ă���݂����Ȋ���������B�y���ē����ŁA���������ՂɌ����Ƃ߂Ă���Ƃ�������������B�k�c�c�l�����������̂������Ă���������I���l�́A��㎍�l�̂Ȃ��ł͂܂��S�R�o�Ă��Ȃ��Ǝv���B
�ѓ��@�����������Ƃ��݂����Ȋ���������̂͋g�������ȁB���{�I�ɂ͌��������ԁB
�剪�@�����ˁB�����A�������̐^���ɐ���킽�����Ƃ���͋g�����ɂ͂Ȃ��B
�ѓ��@����͂Ȃ��B�ނ���t�݂����Ȃ��̂��B
�剪�@�g�����͈Â����F�̐��E�ւ�����ł����B
�����@�w����C���̎��I�����x�̍ŏ��̂ق��̍�i�́A�����g�����̏����̍�i���v�킹��ˁB
�ѓ��@�g���̈ӎ��Ƃ��Ă͖k�����q�̂��Ƃ����ɂ���낤����ǁA�k�����q�Ɏ��Ȃ��Đe�ʂ̂�������Ɏ��Ă��܂����i�j�B��l�Ƃ����炾���܂Ŏ��Ă��邵�A���j�I�A�ϗ��I�łȂ��Ƃ�������Ă��邪�i�j�A�����F�������S�R�Ⴄ�B
�剪�@���W�̍ŏ��ɏo�Ă���uLINES�v�Ƃ��uETAMINES NARRATIVES�v��ǂ�ł���ƁA�˔�ȘA�z�����ǁA�u���E�j���O�̎��ɂ����A�u���ׂĐ��͂��Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����A���������������A�͂邩�ɓ����ɂ��Ċ������đ��z�̌����W�X�Ƃ��т������悤�Ȋ���������B�k�c�c�l�u���E�j���O�̎���̂��̂Ƃ͂������S�R�Ⴄ����ǂ��B�g�����ɂȂ�Ƃ����Ɛ��E���Â���ǂ�ł����Ƃ���ŏ����Ă���B
�ѓ��@���Ƃ��u���ܔ��l���������Ƃ���ł���v�Ƃ��u�ޏ��̍A�̋@�B������v�Ƃ������s���E���Ă݂Ă��A�A�b�Ƌ����悤�Ȉ��Ɠ��̃��[���A������B
�����@����͂���܂��ˁB
�剪�@���[���A�͐�������B
�ѓ��@�����ƈ�����ӂ��ɋ��S�ɓǂ�A���������Ă��܂�Ȃ��悤�ȂƂ��낪���邾�낤�ȁB
�剪�@�g�����ɂ͐�̃C���[�W�͂��܂�Ȃ��ˁA���͂������ǁB���̐����A�ڂ��̊�����̂́A�n�ʂ��琶���Ă����ٗl�Ȃ��̂ȂȁB�������͂�������Ȃ��āA�n���͉F����Ԃ̂Ȃ��ɓ����o���ꂽ���̂Ƃ��Ă̑�n�Ƃ����������B�k�c�c�l�i�����A����܁`����Z�y�[�W�j
�ȏ���܂Ƃ߂�A�@�g���̎��͑���̎����Â����]���������̂ŁA�A���҂͗��j�I�E�ϗ��I�łȂ��_�A���I�Ń��[���A�̂���_�����ʂ���B����ɕt��������A�B���邱�Ƃ��J�����鐢�E���u��̃X�^�C���v�i�q�ǎ�̏��r�j�Œ蒅�����̂����҂̎���i�Ƃ������ƂɂȂ낤�B���������̌��鏈�i�Ώہj�͂��Ȃ�u�����Ă��āA�g���͂����Ό������Õ��Ɏ������i�u�l�Ԃ̎��̏[������^���Ắ^�ǂ����Ă���قǁ^�y���e��Ȃ̂��H�v�^����𗼎�Ŏx���ā^����݂Ђ炢�ċ߂Â���^�u�����������������߁^����t�Ɉł�����߂��肷��v�j�A����͎���ɏՌ��I�ȃ��A���e�B��t�^����Ɠ����ɁA���݂��邱�Ƃ̂����܂��������Ȃ��`�����Ƃɒʂ���B�����ɑ���̎��Ƃ̌���I�ȈႢ������B���ꂪ����Ƌg�����܂ޓǎ҂ɂƂ��Ă͂����肷��̂�1960�N�㖖�ɂȂ�������ł���B����Ƌg���̎����r����ۂɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�s����C���̎��I�����t�Ɓs�����G�߁t�i1940�j�Ɓs�t�́t�i1941�j�Ƃ�����O�̎��Ƃ�Δ䂷�邩�A�s����C���̎��I�����t�Ɓs�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�Ƃ����قړ����Ɋ��s���ꂽ�u�S���W�v�őΔ䂷�邩�A�Ƃ����_�ł���B���k��̑剪�Ɣѓ��͌�҂́A���Â͑O�҂̗���Ŕ������Ă��邽�߁A�c�_�����݂��킸�ɗ���Ă����Ă��܂����̂͐ɂ��܂��B
LINES�b����C��
�ԃC�E���R�m���K�I�~�j�Փ˃X���X�H�j
�烒�q�\�}�Z�e�C���g
�����i�����m�����f
�ԃK�d�^�N
�Ճn���������n
�N�����l�b�g�m�ϖヒ�X��
�^��L�j�C���C�e�C���[���_��
�X�j�ύX�V�e�����_�����K���m�X�j���������V�e�C��
�����T�L�m�Ɏq�����N���N�T�Z�i�K��
�K�N�m���A�j���V�e
�{�e�B�`�F���m���N����b�^�L���K
�����b�L�m�ԏ��j�c������
�ޏ��m���q�n�������N�X�z�h�C
�s���I�����t�͖ڎ��������ɒu����Ă��āA���̎��̌��J���͔��B�ŏ��̖{���Ƃ��ēo�ꂷ��s�����E�����J�^�J�i�\�L�́qLINES�r�i���o�́s�R���t21���A1927�N6���j���s�����G�߁t��s�t�́t�ɂ������Ƃ��Ă���a���͂Ȃ��B�{�т͋g�������ɊJ�Ⴓ�����q���������s�J�\�r�i1937�j��10�N���旧���A�ނ��̂��Ɓs�t�́t�ɐ�s����̂����A��O�̋g��������̎��т�ǂ�ł������͂͂�����Ƃ��Ȃ��B�g���̊��������邩���蓖���̈��ǎ��̕M�����s���Y�Ę_�t�ŁA�s�R���t��s���Ǝ��_�t�Ȃǂ̏��o����T�����Ă܂ő�����ɐG�ꂽ�\���͒Ⴂ�B
�Ԃ̏ё��i�A�E29�j�b�g����
�����m�Ɏq�w�A�c�}��
���m���J���ԕ��K�×��V�e
�ߑO���m�����^�`�n�����j�i��
�p�����m�X���g�r�T��
���M�m���E�i���n�܃��e
�p�k�m�_�K�����R��
�����m�ԃj�J�G�b�e���N
�Õ��i����ԃm���_�`�m����
��G���ƃm�ꃂ�����j����
��K���g������
�J�^�J�i�\�L���qLINES�r��q�n���n�����r�i���o��1928�N11���́s�R���t34���A1929�N9���́s���Ǝ��_�t��5���ɓ]�ځj���痈�Ă���̂��A�g�������܂��܂ȃX�^�C���ɒ��킵����{���痈�Ă���̂��f��ł��Ȃ��i�{�тɐ�s����J�^�J�i�\�L��i�����݂������낤���Ƃ͋^���Ȃ��j�B���a���N�i2�N����12�N�܂Łj�̑�����Ə����g�����������Ă��邱�Ƃɑ����̐l���C�Â����̂́A��ɏq�ׂ��悤��1960�N��ɓ����Ă���ł���B�s�k�t���l�i�Ƃ�킯�g�����Ɣѓ��k��A�剪�M�j���犉�]����Ă�������́u��O�̑S���W�v�i����ɂ��q����C���̎��I����1927�`1937�Y�������r�j���z�̖ڂ��݂��̂�1967�N12���ł���A�g���́s�t�́t���i�������q�Ԃ̏ё��r�͎��^����Ă��Ȃ��j���܂ށu�S���W�v�������v���Ђ��犧�s���ꂽ�̂��A��������N��10���������B�g���́s����C���̎��I���� 1927�`1937�t���ǂ��ǂ̂��B
�k����C�����W�́c�c�l�b�g����
�@����C�����W�́q�k�r�O���[�v�ҏW�ɂ���āA�q�k�p���r���W�Ƃ��Ċ��s����锤�ł������B����͉i���ɑS�e�����킳�Ȃ����̎��W�\�\������ڂ��炪�݂��������A�S�䂭�܂Œ^�ǂ���������ł���B�������s�K�ɂ��ĈɒB���v�̎��ɂ���č��܂����B����܂łɑ���C�����W�͊��s���O�ɂ����s�^�ɂ݂܂��O�x�l�x���̋@�����ꂽ�Ƃ�����B���܂܂ŁA�f�ГI�ɍĘ^�������j�I���тɁA�킸���ɂڂ���͊������₵�Ă����B
�@���������ɏ��c�v�Y���̎��O�ɂ���āA�s����C���̎��I�����t�����s�����B�͂��߂Ă��̑S�����̂ɂ����ɂӂ���鎞�������̂ł���B�i�s����C���̎��I���� 1927�`1937�t���e���{�A�v���ЁA�k1967�N11��1���l�j
�u���܂܂ŁA�f�ГI�ɍĘ^�������j�I���тɁA�킸���ɂڂ���͊������₵�Ă����v�Ɓu�͂��߂Ă��̑S�����̂ɂ����ɂӂ���鎞�������v�̓́A�g�����s���I�����t�ȑO�ɑ���̎��̑S�e�ɐG��Ă��Ȃ����������łȂ��A���a���N�̔��\���ɂ����ɐڂ���@��Ȃ��������낤�Ƃ��������������B�O�f���k��ɂ��A�ѓ���������ɐG�ꂽ�̂͑n�����Ɂi�s���{���l�S�W�k��6���l�t�n���ЁA1952�j�ŁA�g���ɂ����Ƃ���ő卷�Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���������̂���g�������菊�ɂ��Ă����̂͐��e���O�Y�ł����āA����C���ł͂Ȃ������B����́s����C���̎��I�����t�����̌�̋g�������ɂǂ̂悤�ȉe����^�����̂����l���Ă݂悤�B
�g�����ɂƂ��đ���C���Ƃ͒N�������̂��B����͑傢�Ȃ��ł���B����Ɠ�����̖k�����q�i1902-78�j�́s�����G�߁t��s�t�́t�Ƃ������g���̎��I�o����p�ӂ������A����̎t�ł����������e���O�Y�i1894-1982�j�́s�Õ��t�Ɏn�܂�g���̐��̃L�����A�S������݂������B����C���i1903-79�j�͎��l�E���p�]�_�ƁE���`��ƂƂ���邪�A�s����C���̎��I���� 1927�`1937�t��M���Ƃ��鎍��i�͂����킸���ł���A��N�A���p�]�_�̕M������Ȃ��Ȃ����A�h���[�C���O�Ȃǂ̑��`��i���c�����B�����������₢�����̂͑���̂����������ʓI�Ȋ����̂ǂ���g�����d���������Ƃ������ƂƂ��Ⴄ�B�g�����N����E���Ă݂悤�B
���O���N�i���a�\��N�j �\����
�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łu�݂Â�v�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������B���Z���N�i���a�l�\��N�j �l�\����
�\���A�k�c�c�l����C���̒a�����Ɓw���I�����x�̊��s���j����̌�A���e���O�Y�ɗU���Ĕѓ��k��A�剪�M�Ɛ��e�Ƃ�K��B��㎵�l�N�i���a�l�\��N�j �\�܍�
�H�A�������̑���C�����K�ˁw�葢�茿���W�x��Z�߂�悤�˗�����B��㎵���N�i���a�\�O�N�j �\���
�ݐE��\���N���A�\�ꌎ�\�ܓ��ˊ�ގЁB��V�q��L�̑���C���ƃW���A���E�~���̎���W�q�~���̐��Ƌ��Ɂr�W����֍s���B��㎵��N�i���a�\�l�N�j �Z�\��
��������A����C�������B����Ƃ�A�l�ɃI���[�u�̎}��������B�k�c�c�l�\���A���W�w�Ẳ��x�y�Ђ�芧�s�B����Ƃ�K��⍜���K�N�ƃ`���R���[�g�w�Ẳ��x�������A���q�v�l����I���[�u�̎���Ղ��B�\�A����C���ɕ������i�W�w���������x�ɒǓ����u�Ɣ�������v�\�B��㔪�Z�N�i���a�\�ܔN�j �Z�\���
�Z���A�k�c�c�l������قő���C�����Âԉ�B
�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�̔N���i�g���z�q�ҁj�ɓo�ꂷ�����C�������邩����A�������琼�e��k����������ȑ��݂������������Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A�ق�Ƃ��ɂ������낤���B�g���̎��I�]����������������̃s�J�\���ɂ��Ă��q�����g�������Ɩk�����q�E���삿���r�ŐG�ꂽ���A�g���̎��I�I���ɂ�����i�̏͋�j�����������Ă���̂��B�S���Ȃ锼�N�قǂ܂��ɔ��\���ꂽ�A�Ōォ���Ԃ߂̎��сq�_��r�i�������сE20�A�s��t1989�N10�����j�����ꂾ�B���������̒��L�ɂ́u������C�����̂ق��̏͋�����p���Ă���B�v�Ƃ��邪�A�����ɓo�ꂷ��i�@�j��k�@�l�Ŋ���ꂽ���p��E���p�����A�g�����ł������Q�Ƃ����ł��낤����́s�]���ɏ��� �Q�t�i�݂������[�A1982�N7��1���j�̃e�N�X�g�Əƍ������̂��ȉ��ł���i���ڂ́A���g�����̎���c�c����C���̃e�N�X�g�A�y�@�z���͓����́s�]���ɏ��� �Q�t�ɂ�����W��A�f�ڃy�[�W�m���u���k�������l�E���s���k�A���r�A�����l�j�B�Ȃ��n�̎���u�g�ɐ����^�C���̑��Ձv�����p���Ɠ���Ɉ������B
���i�Ƃ�Ƃ�Ɩ��肱�ށ^�k�q�_�l�ł͂Ȃ��j�c�c�o�T����
���i�ߒ��Ԃ��������Ă䂭�^�������̊��߂̏����j�c�c�o�T����
���k�J��̑�[�����т�]�l�c�c�o�T����
���i���Â̋������z���j�c�c�o�T����
���i���̗��^���b�̍��j�c�c���̗��A���b�̍������܂�K���ł��낤�B�y�Ò���L�A����E13�z
���k�C�f�A�̐��E�l�c�c�{�т���ɁA�F�V���F�Ǔ����т́q�x���r(�������сE18)�Ɂu�ǂ�Ȃ��̂̏�ɂ��^�~�܂邱�Ƃ͋�����Ȃ��v�^�k�C�f�A�̐��E�l�v�Ƃ���B
���i�����ꂽ�^�k���t�l�́^�k���l�̂悤�Ɏc�邾�낤���H�j�c�c�o�T����
���k���ցl�c�c�ّ��E��䶗�������@���𒆐S�ɁA�邭�͂Ȃ₮���\�̐��E������W�낰�Ă���̂ɑ��āA�����E��䶗��͈×̊�̂Ȃ��Ɍ��ցm�K�i�����n�ƌĂ�锒�F�~�����`�t�Ƃ��āA����������������E�Ɉ��k���Ă���A�⌵�ł��Ĕ�ނ����ʗH��Ƃł��������E���Ƃ�����A�{���̋ύt����O��Ď����䂫����B�y����ւ̓����A���O�E5-8�z
���k�����ނ�l�c�c�o�T����
���i�x�ߐl�͔L�̊�Ł^���Ԃ�ǂށj�c�c�o�T���ځi��q�j
���g�ɐ����^�C���̑��Ձc�c�ł���g�ɐ���鐡�O�́A�C���̑��ՁB�y�_�̎��ʁ@�f�r�ϑz�҂̎�e�A�ꎵ��E3�z
���k�D��[�ǂ낮��]�l�c�c�o�T����
���k��l�c�c�o�T����
���k�����}�@�l�c�c�{�т���ɁA�O�f�q�x���r�Ɂu�k�����}�@�l�v�Ƃ���B
���k�_��l�c�c�o�T����
���i�����܂��Y������j�c�c�����܂��Y�����鍏��̉^���������̂��B�y�_�̎��ʁ@�f�r�ϑz�҂̎�e�A�ꎵ�܁E7�z
���i����������Ȃ��U��j�c�c�o�T����
���k���t�l�c�c�o�T����
���k���k�l�c�c�o�T����
���k�L���l�c�c�o�T����
���k����[���ɂ�]�l�c�c�o�T����
���i�R������@��������j�c�c�o�T����
���k���C�l�c�c�o�T����
���k�ωʕ�[�R���|�[�g]�l�c�c�o�T����
���i�@�̂ڂ݁^��̂��ڂ݁j�c�c��̂��ڂ݂ƉԂ̂ڂ݂̔߂��������ǂ����o�������B�y�N���}�g�|�C�G�}�]�A���Z�E5-6�z�^���̂Ƃ����͂ӂƁu�@�̂ڂ݂ƚ�̂��ڂ݁v�Ƃ������{��̌�C�������v�������̂����A�����ɂ͉p���k�ga sad and droll meeting of the curve of a vase and its prolonged-into-bud of loto�m�}�}�ns�h�AA divagation upon invisible monuments: �^Tribute to CHROMATOPOIEMA: The work of Junzaburo Nishiwaki & Yoshikuni Iida�A�i�������g�j�l��E2-3�l�ɂ����������͂Ȃ��B�y���Ԏv�ď��A�O���E7-8�z
���i���́k�����l�͂܂��^���S�Ɂk�n��l�Ɂ^�~�藧���Ă��Ȃ��j�c�c�o�T����
�o�T���ڂ̎���̂����ǂꂪ�u����C���̏͋�v���͂����肵�Ȃ��B���邢�́s�]���ɏ��� �Q�t�ȊO�̑���̏�������̈��p�����邩������Ȃ����A�o�T�̒T���͂����܂łɂ��悤�B�i�@�j��k�@�l�Ŋ���ꂽ�͋�����̂�������낤���{�[�h���[���i�u�i�x�ߐl�͔L�̊�Ł^���Ԃ�ǂށj�v�͎U�����s�p���̗J�T�t�̈�߂ŁA�g���͂�����F�V���F�̃G�b�Z�C������p�����Ǝv�����j���낤���A���T���U�����낤���U�������낤�����Ȃ��A�Ƃ����̂��ӔN�̋g�������������n������A�o�T���ڂ̎���̓T���{���邱�Ƃ͂����������̎�ɗ]��B���Ă����ŁA����C���Ƌg�����̍�i���\�̗��j���ӂ肩�����āA���҂̊W�ׂ��|����Ƃ������B
�ӔN�̋g�����߂����āA�R�c�k�ꎁ���狻���[���b�����B����C���̟f��\�\����̏͋�����̂܂ܕW��Ɉ������q�u�Ɣ�������v�r�i�Q�j�̂��Ƃ��\�\�A�g���ɑ���̋z�掆������Ď��т����M���Ă��炨���ƈ˗��������A���܂Ōo���Ă����������A�z�掆�͑�����q�v�l�̂��ƂɕԂ��ꂽ�Ƃ����̂ł���B���̋z�掆�́A�ܒJ���m�s���ꂽ���\�\����C���Ɠ��{�̃A�[�e�B�X�g�����t�i���}�ЁA2004�N12��5���j�́q����C�������T�r�́u�z�掆�v�̍���
�@���ʂ�����������݂����A�z�掆�ɕ`�������̂��Ƃ��ɈӖ��Ԃ����B���̋z�����ފG���C���N�̂ɂ��݂���A���L�̃I�[�g�}�e�B�b�N�Ȍ��ʂ����܂��B�u�A�z�̕Њ���̂ق��ɁA�s�ׂ̏؋��������A����Ƃ��]��s�ׂ��A�߂₨����ׂ��B�̂Ă�ɔE�т��A���͂���ŎO���̖{���������v�i�u�肪�悫�A�悫����v�j�Ƃ����B�i�����A���O�`���l�y�[�W�j
�Ƃ��邻�ꂾ�낤�B���т������������Ă���A����C���̐��ʂƕ������g�������̎���W���a��������������Ȃ��B�������A�g�����N�̊G��ł��ꒊ�ۓI�ȍ앗���D�Ƃ͎v���Ȃ��B�g���������ɋ�ۉ�����������́q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�̈�߁A�u�����������ԉ߂������A�ЎR���͈ꖇ�̊G�������Č���ꂽ�B����͒n�̓D�ɖ������A�̐؊���َ��炵�����̂̌`�Ԃł���B���͂��̎�������ʂ���Ƃ�O�ɁA���f�����B���̊G�����Ԃ��Ɏg���A���̏������邠�̉Ă̗т̊G���J�o�[�ɂ���Ƃ�����Ă����A�ȉ����Ė�����v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�l�y�[�W�j��ǂ߂Ώ[�����낤�B����C���̋z�掆���܂��ɁA���т̎��M�ɓ�a�����i���邢�́A���f�����j���Ƃ͑z���ɂ������Ȃ��B���͂����ő���̋z�掆�̐}�ł������ւ��ɁA���́q�肪�悫�A�悫����r���i�ܒJ���̑O����܂ތ`�Łj���p�������B����Ƃ����̂��A�����܂��̒i���́u�L���v���q�_��r�́u�k�L���l�v�̃X���X�Ɏv���ĂȂ�Ȃ����炾�B
�@�u���[�̃C���N�����̐F�ʂɑ��A�����g���͂��߂�B�ѕM�͖��p�A�X�|���W�g�p�B���N�M�͐܂�A�f�y�������߂Ȋ����܂ŁB�C���N���y���J���Ȃǂ̃h���[�C���O�E�C���N�p����B
�@�����̂�҂��ăy�[�W���߂���̂����ǂ������A�z�掆���g���B��C�ɋz�����邱�Ƃ��ڑO�̍s�ׂɘA��������������B
�@�������u�Ԃ̒蒅���A���̐F�ʂɈ��̗}�������ʂށB�ӂƁA�G��̏����̂ЂƂ�@���Ă���̂��A�����̕~�����܂����ł���̂��c�Ǝv�����Ƃ�����B�������Ԃ��B���@�������ɂ͂Ȃ���������B
�@���ʂ���C���N�Ɛ��̑啔�����z�����z�掆�������Ɛ��k�}�}�l�ς��A���݁m�A�A�n���͂��߂�B�A�z�̕Њ���̂ق��ɁA�s�ׂ̏؋��������B����Ƃ��]��s�ׂ��A�߂₨����ׂ��B
�@�̂Ă�ɔE�т��A���͂���ŎO���̖{���������B����ɂ��A�����̐������Ɉ�x���������Ȃ��������O���Y��Ă���B�u�}�e�B�A�X�E�O�����[�l�E�@���g�̎���ꂽ���L�A�܂��͉�Ƃ̃n���h�u�b�N�v�gBLOTTING PAPER IS SOMETHING. ET CETERA�h���̑�͎��O�i�����x�E�n�E�̎�ɓn�����B�j
�@�肻�̂��̂��A�l�Ԃ̋��L�s�ׂ̋L���B�����ɐl�͉^���܂ł��ǂށB�i�s�]���ɏ��� �Q�t�A��Z���`��Z��y�[�W�B���o�́s�G���g�����\�j�b�N�t2���k�t�l�A1974�N4���j
�g�������Ȃ��y�I�����ɏ��������ɑ���C���̐��ʉ���邱�Ƃ͉\�ł��A�u�����ɐG�����ꂽ�g�����v�͌����I�ɕs���ɏI��炴������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������B���������̕s����͋g���ɕ����ڂƂ��Ďc��A���ꂪ�ق�10�N�̍Ό����o�āq�_��r�����������ƍl������B�o��G�����玍�т��˗����ꂽ�g���́A�Ȃɂ��̂��������i�R�j�Łq�Ƃ茾�̌`���Ł\�\�g�����Ɂr�i�����Ɂu�~�@����e���^�m�@�얖�́^���@�ڗ��̖�̐[�݁v�Ƃ����A�N���X�e�B�b�N�̋傪����j�����߂��s�]���ɏ��� �Q�t����Ɏ���Ăς�ς�ƌ��Ă��邤���ɁA�̓��̑���ɑ��镉��ԍς��邩�̂悤�Ɏ����Ԃ�͂��߂�A�Ƃ��̎��т̂��������ɑ���̏͋傪���߂��܂�Ă䂭�B�k����l�ɂ͋z�掆���~���߂��A�u�����܂��Y������v�Ƃ�����ɓI�ȏ͋���܂ށq�_�̎��ʁ@�f�r�ϑz�҂̎�e�\�\���[�����q�����[�\�Սݕ��ʂɂ��ār�ƂƂ��Ɂr����A�W��͎����Ɓq�_��r�ɗ��������c�c�B�s�J�\�̎��i�S�j����[�������g���̎��I���U�̂����ɁA���������q����C���r�̂�����i��z���������Ȃ�B���̌�̋g���͂킸���Ɂq����r�i�������сE21�j�������ŁA�s�����G�߁t�ȗ������I�ɂ킽�鎍��̕M�𝦂����̂ł���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�@�@�@�g������
����A�A�����I
������ׂ�����
�h�点�邱�̎�i
�S�C�u�₩��
�T�t�����E�݂̂Ђ邳�����i�s�R���N�V��������C�� �T�@�]���ɏ��� �U�t�A�݂������[�A1994�N5��25���A��Z�Z�y�[�W�j
�u�A�����v�́q�ٗ�Ձr�i�G�E19�j�Ɍ�����l���ŁA������b�q�Ƃ̋g���̑Βk�Ɉ˂�A�G�h�K�[�E�A�����E�|�[���܂܂��B�����т́u�l�͐�����̂��߂Ɂ^���l�̂��₪��d��������^�����̍l���y�ʛ@�q���������ā^�A�����^�w�L�ފw�̎���x���ł���������v�́A���쐳�g�ҁq�|�I�N���r�́u�ꔪ�O��N�@�O�\���^�N�̏��߁A���ȏ��p�Ɂw�L�ފw�̎�����x�iThe Conchologist's First Book�j���o�Łv�i��������E���i���F�E�g�c����ҁs�|�I�S�W ��R���k�V���Łl�t�A�����n���ЁA1970�N1��20���A���O�y�[�W�B�����͓����n���V�ЁA1963�N12��20���j�ɂł��˂������̂��낤�B�t������A�����ɂ͋g�c�����q�o���i�}���W�i���A�j�r�����߂��Ă���B�q�Ƃ茾�̌`���Ł\�\�g�����Ɂr�́gMARGINALIA�h�Ɖ����̕W���t�����s�]���ɏ����t�̑��҂Ɏ��߂��Ă���A���́u������������̋i�����Ł^���͂₯�ɃG�R�[�̊D��@���Ȃ���^���Ȃ��Ɨ��O�m�A�A�n�Ƃ����b�������Ă����v�Ƃ����s��z���A�|�[�Ƒ���Ƌg���Ƃ����V���Ȏ�肪�����т������Ă���B
�i�Q�j�@�q�u�Ɣ�������v�r�̕W��́q�T���E�t�����V�X�ƂƂ��Ɂr�i���o�F�T���E�t�����V�X�W�qBlue balls�r�A���L�A1961�N5���j�́u�A�A���ɂ͂��������Ɣ�������ȊO�Ɏ肪�Ȃ��̂��B�v�i�s�]���ɏ����t�A�݂������[�A1966�N5��30���A�O���y�[�W�j�A�������莫�́u�����̂Ȃ��ɔ�т��ނ͍̂����v�́q�͂��߂Ɂr�i���o�F�R�c���N�q���ʼn�W�A��V�q��L�A1961�N7���j�́u�����̂Ȃ��ɔ�т��ނ͍̂����B�v�i���O�A�l��y�[�W�j����̂��Ă���B
�i�R�j�@�_�ҁi���ш�Y�j�͂��낾���̕M���ŁA���p�ƓT���̌�������\�z���q���E���̃e�[�}�r�����ɏ������낵����W�s���씼���kTREE-SPIRIT: SEMI-LATTICE�l�t�i���Y��ԁA1989�N9��15���j�����s�i�Ċ��j���Ă��邪�A�����̏����{�i�{�v���̃o�C���_�[�d�l�j�͓��N4��15���̋g�����̒a�����ɐ��a70�N���j���Č�����ꂽ�B�u���씼���v�Ɓu�i���̗��^���b�̍��j�v�Ƃ�������Ɋւ�肪����̂��́A�u�����тꂽ�B
�i�S�j�@�q�����g�������Ɩk�����q�E���삿���r�ŋ����Ă��Ȃ������̃s�J�\�̎��͂̂ЂƂ�
�@����俐F�̌����v����ᰋ����̓��А������Łm�y�G�W�n�Ɉꔭ�����ӎ��͏��ӂقƂ���K�N�F�Ȕ����e�̒��̃J�i���������F�̒W�F�̉e�̒��̋��Ȕ��̒��̂ЂƂ����̗����̎肪�e�̂����Ŏ�ɉe�������C�̔����K�N�F��囈�̍��������������{�̓B�����Ȃ����X�̍���̋���̑��͂����̌��̏����͓��P���Î��߂���̒��̎w�������̔��������̒��̂Ђ��葾�z�͉ΉԎU��T��鑾�z���̂Ђ���ƂĂ��������z����ɔ������z�i�s�݂Â�t385���A1937�N3���A�k�{���̊����͐V���ɉ��߂��l�j
������B�����̎��͂Ɛ�O�̋g�������i�s�����G�߁t�s�t�́t�j�Ƃ̏ڍׂȔ�r�����́A����̉ۑ�Ƃ������B
�g���������W�s�T�t�����E�݁t��1976�N9��30���ɐy�Ђ��犧�s���ꂽ�B����i31�т����߁A�q�t�r�i1972�N4���j����q���N�r�i1976�N5���j�܂ł̑S�т��{���W�ȑO�ɎG���E�V���E���ЁA���邢�͉w�̃z�[���ǖʂɔ��\����Ă���B�{�e�ł́A�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���E���Ќf�ڌ`�A�Q �s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�f�ڌ`�A�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����R�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�T�t�����E�݁t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A���j�R�[�h�ɂ��u禱�v��u瀆�v��u蠟�v�̑���ɁA�s�{�ӂȂ���V�t�gJIS�́u���v��u���v��u�X�v���g�p���Ă���_�����ȉ��������������B�Ȃ��A�������V���̖{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs�T�t�����E�݁t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���E���Ќf�ڗp���e���e�F���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ���2010�N1���̎��_�Ŗ��������A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������B
�P ���o�G���E�V���E���ЁF�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B�{���̕\�����q���N�r�ȊO�A��{�I�ɐV���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�Ȃ̂ŁA���L�Ȃ��ꍇ�͂����\�킷�B
�Q �s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA���ł�1976�N9��30���k�Z�ق̒�{�ɂ͍ŏI�����{�ł���1979�N10��30�����s�́u�Z�Łv���g�p�����l�j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|�k�U�����^�ł�23���l��25���l�l14�s1�i�g�B
�R �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|�k�U�����^�ł�23���l��25���l�l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q �s�T�t�����E�݁t�B
�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����̕\�L�́A�ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ɍ��킹�ď����ɓ��ꂵ���B���т̐ߔԍ��̃A���r�A�����E���[�}��������уA�X�e���X�N�̈ʒu�i�������j�́s�g�����S���W�t�ɕ���ĎO�������ɓ��ꂵ�A�������͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������i�����⒐�L�̎��������s�g�����S���W�t�ɍ��킹���j�B�{���W�̕W��u�T�t�����E�݁v�́s�g�����S���W�t�ł́k�R�T�t�����E�݁@1972-76�l�ƂȂ��Ă��āA�����O�t�ɂ͌����k�Q�R�j�E�l�E�x�Ɍ����l������A�P�s���W�ł͂��̑Ό��y�[�W�Ɂk�Q1972�`1976�l�ƓƗ����Đ�����Ԃ̕\��������B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�s�T�t�����E�݁t���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s�������t�k���s�����l�f�ڔN�����i���j�k�i���j���l�j
�T�t�����E���i�G�E1�A42�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1973�N7�����k16��7���l�j
�^�R�i�G�E2�A����3�߂��]����34�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1972�N10���Վ��������k4��12���l�j
�q���V���X���͐����i�G�E3�A40�s�A�s���i�t�k�I�X��l1972�N6�����k13��6���l�j
�t�i�G�E4�A125�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1972�N4�����k4��4���l�j
�}�_���E���C���̎q���i�G�E5�A42�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N1���k5��1���l�j
����ȓ~�̗��i�G�E6�A85�s�A�s�������_�t�k�������_�Ёl1972�N7�����k87��7���l�j
�s�N�j�b�N�i�G�E7�A33�s�A�s�|�p�����t�k�|�p�����Ёl1973�N7�����k26��7���l�j
������܌�b���i�G�E8�A4��87�s�A�s���p�蒟�t�k���p�o�ŎЁl1973�N2�����k364���l�j
�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�i�G�E9�A23�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�l1973�N11�����k27��11���l�j
���a�i�G�E10�A19�s�A�s��̐V���t�k�ǔ��V���Ёl1974�N3��24���k35051���l�j
���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�A�k�킪�A���X�ւ̐ڋ���43�s�l�k�����`���������14�߂ɕ����T����чU��66�s���l109�s�A�s�ʍ����㎍�蒟�@���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�t�k�v���Ёl1972�N6���k1��2���l�j
�w�A���X�x����i�G�E12�A76�s�A�s�A���X�̊G�{�\�\�A���X�̕s�v�c�Ȑ��E�t�k�q�_�Њ��l1973�N5��1���j
����̔ӎ`�i�G�E13�A34�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1974�N4�����k17��4���l�j
�c���i�G�E14�A12��134�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N9�����k5��10���l�j
���]�Ԃ̏�̔L�i�G�E15�A18�s�q�����O�j�W�r�p���t���b�g�k�؉�L�l1974�N4��13���j
�s�ł̌`���i�G�E16�A20�s�A�s�ʍ������V���t�k�V���Ёl1974�N7���k�ċG�E26��3���l�j
�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�A�����5�߂ɕ�����85�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N11���k5��13���l�j
�G���i�G�E18�A30�s�A�s���i�t�k�I�X��l1974�N5�����k15��5���l�j
�ٗ���i�G�E19�A8��161�s�A�s�ٗ�Ձt�k����R�c���q�����낵�ɂ��p���@���q3�r�l1974�N4��25���j
�����i�G�E20�A29�s�A�s�G���o��t�k�������@�l1973�N10���k1���l�j
���f�A���E������Ƒ��i�G�E21�A75�s�A�s���|�W�]�t�k�}�����[�l1974�N7���k�āE6���l�j
�ǎ�̏��i�G�E22�A6��76�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1974�N10���Վ��������k17��11���l�j
�����i�G�E23�A28�s�A�s��t�k��o���l1974�N10�����k11��10���l�j
�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�A5��89�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1974�N12���Վ��������k6��15���l�j
�T�C�����g�E���邢�͍��i�G�E25�A41�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1975�N1�����k18��1���l�j
����ȉĂ̗��i�G�E26�A6��72�s�A�s�V���t�k�����Ёl1975�N7�����k22��7���l�j
���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�A5��79�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N9�����k7��8���l�j
�J�J�V�i�G�E28�A15�s�A�s���t�k���{��ʌ��Ёl1975�N9�����k49��10���l�j
���N�i�G�E29�A6��52�s�A�s�����t�k����ь牮�l1976�N5���k�t�E1���l�j
���܂������i�G�E30�A�X��90�s�A�s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N12���Վ��������k7��12���l�j
����ȓ��ʂ̏H�̗��i�G�E31�A7��145�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1975�N11�����k14��11���l�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1973�N7�����k16��7���l��Z�`�y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A42�s�A�ڎ��̍�Җ��́u�g�����v�B���o�u�{���J�b�g�E�i�C�v�B
�N���^�̈��鉤�{�̕ǂ�
�u�T�t�����E�݁v��
�Ă��ؗ�ȕlj悪���邻����
�����ł́@���N���l����ɂȂ���
�T�t������E��ł���
��̊Ԃɂ͕ɂ��g�������܂��͗l�����肩�������X
���������ɂ͂�����p���������Ȃ�
���N�̊z�Ɂ@���������z����������
���`�̉�������ł���
���ꂽ���N�̐K���[���̖���
�˂��o�����Ƃ�
�����́@��s�̃T�t�����̉Ԃ̍��t�̂��������F�߂�
�g������@�����O�p�g
���Ɏa�ꂽ
���������̎�����ł��낤
�ڂ��Ƃ������N�̈Ő[�����肱��
�Ήp�̂悤�Ȋ�̏��
�t�̉ʎ��Ƌ��ō\�����ꂽ
�A���`���{���h�̏ё���̂悤��
���s���Ă䂭�@���ׂĂ�
�\�ʂ���
�����̔������k�P���灨�Q�R�炪�l�����������
�G�[�Q�C�̉��̐M�Ǝ�����
�Ȃ߂��ꂽ���̃g���\
���悮���������
�ʂꂽ���N�̌����x������̂�
����̑��҂ł���̂�
���̂������ꂽ�A�s�ł���̂�
�勾�̂Ȃ��ɂ���͂���
�\�ӕ����̂悤��
�[�Ă͉����~��������߂Ă���
������g
���F�̊��L�̓������߂���߂���
�w�́x�͂��܂��
�T�t�����̉Ԃ̒W����
�����҂�����Ƃ�����
���N�͊�I�����������
�����鉼���̂Ȃ�����M���̎p���S���
�����͍����炭�@��炸
���ׂ��炸
�j�����̖��M���\�\
�V�W��g���z������܂ł�
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1972�N10���Վ��������k4��12���l���`��l�y�[�W�A�{��10�|25���l1�i�g�A����3�߂��]����34�s�B
�@�@�@��
���ւ��ĂČĂт�����
�₳�����^�R�̕�e�͑����܂�����
�T���S�̒I�ɂ��ꂳ������
��������
�t�W�c�{�̐M�[���E��
�т��肵���ݗ��𑗂肱�܂�Ƃ���
���̂��ɑD���̎r�̂�
���\�I�ɉ�������Ă���Ƃ���
���_����ł�
���ꂩ��͂��߂�
�^�R�̕�e�͂Ƃ�݂��������l�̂悤��
����������
�@�@�@��
�^�R�̐��B�͂ƂĂ����ꂽ�t�H�[����������@����͔G��ėꂽ�P�̂悤�ȓ��̎U���ɂ������@�^�R�̃I�X�̎��̑��͐���������ށ@�����Ďc���ꂽ������ׂ�̈�̑��������̊튯�̖�ڂ�����@������ƌ���Ɓ@�C�̕R�̂悤�ɂ݂��ڂ炵���@�^�R�̃��X�̏����ȍE��T�����߂ē��肱�ށ@���ꂪ��ڂƂ����邾�낤���@���͋N�����ĂȂ����@�����Ȑ��E�ł͉x�т��Ȃ��ː��͏I��@�������Ƀ^�R�̃��X�݂̂Ђ炩�ꂽ�Ⴊ����@����ɂ͔Đ_�_�I�Ȉ��ӂ���������@��ق���^�R�̃��X�͊C�̒�̐̑��ւ������A���čs���@��\�����̓����ȗ��ނ��߂Ɂ@���ꂩ���H��Ԃ̂܂܁@�u�h�E�̖[�̂悤�ɂ��ꂳ�������܂̗��Q�ց@�K���ɖA�𐁂��Â���@����͌ċz�ɕK�v�Ȏ_�f�𑗂邽�߂��@��炮�C���̂����Ł@�^�R�̕�e�͂�����x�̔r���ŕ�������ւƑւ�
�@�@�@��
�ЂƂ�̏��������z�����炤�܂��悤��
���Ɛ�����^�R�͏o�������̂�
�����̒��ۊG��
���͍��ɂ���Ė��܂�
�L�͓����Ő�����
����͉ߋ��̂��Ƃ����m��Ȃ�
�Ẳ�����j����������
���o�́s���i�t�k�I�X��l1972�N6�����k13��6���l�ܓ�`�܌܃y�[�W�A�{��9�|12�s1�i�g�A43�s�B
�~���N���̂ނƂ�����j�͂����l����
���W�G�[�^�[�̂Ȃ���
�����B�ꂷ��
�q���V���X�̃����T�L�̂ނ炪���
�����鏗���Ƃ肩����ł�
����k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
��Ԕ�s�@
�����牺�������A���ǂ�����
����j�͗e�ς̂���k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
���̂����Ƃ߂čs��
������
�����̒n���G�}�k�P�i�i�V�j���Q�R�݂̍�Ƃ���l
��q����
�ۏĂ��̑�����
���P���闋�b���v�������������݂�
�k�P������p�̂Ȃ��́��Q�R�n���͎��n���q���l
�k�P��̗p���������Q�R�i�g���j�l
�₽���[���[�̂Ȃ����
���̂܂��k�P�i�i�V�j���Q�R�Ɂl
�M���V�A�ߌ��̕����K���
�o�C�L���̂���
�k�P���Q�R���}�����l�E���M�̓��[�̂ӂ���ޏ��āk�P���Ăт��遨�Q�R�ɂ́l
�����ɖ𗧂��̂��ق���
�k�P���R�E���v�\�f�B�[���Q�R���Ƃ��ΐl�ɂ͎�����l
���₩�ɂƂ����̎R
�₪�Ĕ����f�[�k�P�i�i�V�j���Q�R������l
���Y�̎������ڂ��̔w��͈Â��k�P���H���Q�R�i�g���j�l
�����k�P墁��Q�����R墁l�̃p�C�̎M
�����Ńt�B�����ɂ��Ԃ���i���[�V���������I
���݂�ɂƂ��Đ푈�̌��Ƃ͉����H
�݂邩�����Ȃ��~�J�Q��
����͍��łȂ�
�����̏��֖߂镨�̉e
���̃~�X�e���[����������
�����闇�̔��l
���̉���������ʂ���
�܂����낢����
�Ǘ��l�͂�����܂т炩�ɂ͂��Ȃ�
�~�V�䂩���͓��̖��k�P�i�i�V�j���Q�R���̂сl
�����͂˂�
�~�����E
�����ł݂����猩�邱�Ƃ�
�����I
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1972�N4�����k4��4���l���`�ꎵ�y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A135�s�A�ڎ��Ɂu�A�����v�Ƃ���B
���b�v�̖_�̗��Ă����Ă���
���̋N���̂Ȃ�Ɖ�������
�f�p�[�g�̐��ʏ���
�q���I�Ȗ؈��̝R�
�҂��҂���������������
������
�����̒p�����k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�[���r�ւ�����I
�������Ȃ��D��
�|���w�������̉��������
�ߋ��̊튯�̃��J�j�Y�����Ղ�
������
�������āk�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
��F�̈߂͂Ȃт�
���Z�������܂�
�Ƃ��ɂ̓o�P�c�����������
�y����
��@�̕ϑ������݂Ă͎U���I��
�M�Łk�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�w�̉��̑w�����߂�
�A��
�J���e���̔������Ȑ��E��
��i���̂͌��̋C�̖R���������͂��
���ꂾ����l�ނ��V���J��������
���܂̍��l�̉S�k�P�i�i�V�j���Q�R�������l
�v�l�͈ڂ�
�����嗤�̃R�X�`�[�����͏I��
�k�P�f���|�[���Q�R���ꂽ�z�͂Ȃт��l
�k�P�i�i�V�j���Q�R���܁l�e�ŏe�Ō������
���ׂĂ̍d���̕��Ƃ܂��͑S����
���@���t
����ɂ��Č��̂͂ނ�������
��H������Ƃ�����
���ݓI�k�P�i�i�V�j���Q�R�ȋl��
�k�P���ꂽ�z���Q�R�i�g���j�l
�����Ō������Ă͂����Ȃ�
��������K�w�ƉΐH���́k�P�������Q�R�������l
���̊O�I�ȏՓˁk�P�́��Q�R�Ɓl���k�P�i�i�V�j���Q�R���l�@�̊W��
�₤���Ƃ��ł��邩�H
�����͔�傷��H�`������
�}���z�[���̃t�^���ЂƉ�肷��
��l�̐��̓s�s
����͈��p�ӂ�
���p�ӂ��Ȃ����Ƃɂ����
�킢�͂����
�₪�đۂނ����Ί�k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ�����őS�p�A�L�j�l
�P�C
���炿��`���k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�����̉��k�P�i�i�V�j���Q�R�ɂ́l
�ǂ��������������̐Ԃ�V
������
�S�����
�S����܂��͂߂Ă��݂���
�Đ��ł��Ȃ���
����
���̊Ô炩�Ԃ�
�k�P�炯��A�l���l���Q�R�i�g���j�l
�\���ォ��ŗL�����̗��p�����
�e�܂��e
���d�A�[�X��
�O�O��ۓI
�i�߂�ꂽ�f�Y�f���[�i
�����ȗ��̊G�n�̏����o�Y�}
�k�P�i�i�V�j���Q�R�炯��A�l���l�l
�J�����ςȂ��̃J�����E���[�N
��K���o����
�J�[�e���̂�����
������ǎ҂���������
�ł���]�Ƃ͉ΎR�Ɖƒ{�̉^�������
��҂�T���ɒJ��
�Ӗ��ƃ��A���e�B�Ƃ͕ʂ̂��̂�
�Ȏ@����
�P���ȃ^�C���@���p�ȃX�^�C��
�o���̗r���̂Ȃ���o��
�����̋łɂ�
�������܂́k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�܂ɂ��܂���̂�����
�ЂƂ̗��j�E�ЂƂ̔�g�E�ЂƂ̌I
���f�ȕ���
�V�k�̂������ȐH�ו���
�\���_�Ƃ��Ă܂Ȃ�
��҂̎��̊O�ꂽ�Ƃ���Ł@���߂đ����璭�߂悤��
�̉Ԕ��k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�́l
�Ȃ܂Ȃ܂����v�w�Q�k�P�i�i�V�j���Q�R���l
�C���w�I�ɍl���Ă��ŗǂłȂ�
�A�����j�A�̓���
���ׂ��炭���S�̍E���J������
���|�����͍Ă�
�Α~�_�ő����̂��̂�˂�
��i�c�ׂƂ͂��̂悤�Ȃ��̂̔ޕ��k�P�i�i�V�j���Q�R�́l
���̎R
�c�����������ւ܂��
�����đ������Ƃ�
�������Ɓk�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ�����őS�p�A�L�j�l
������邱��
�ߎ����݂̂��݂�����
�ω��ł͂Ȃ�
�n�T�~���V�͏�������
���ł₩�ȏt�k�P�i�i�V�j���Q�R�̐�܂Łl
�����͗V�s����
�ڂމ������Ă̂Ȃ��ɂȂɂ�
�u���v�́k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�݂邩�H
����I�Ȃ��̂̂Ȃ����E��
�����͂ǂ��̂���
��������邱�Ƃ̖@�x
����G���^�C���̓��݂���
���ێ�
�܂���킵�����X
�
���A�X�`���[���̔��k�P�i�i�V�j���Q�R�͐ς܂��l
���̂ւ����肪�K�v��
�Ȃ܂��͕̂���
�n�^���L���E�̂悤��
�n�ォ������čs���f��
�����̃v�[��
�ꎚ�̈�
��i�̏I�͂͑����̏ꍇ�p�^�[�����̌X���k�P�i�i�V�j���Q�R������l
�ӎ��̂��邤���ɒ��ӂ���
����ɂ������
�l�H�I�슴
���܂�g�̉�
���̂̋�
�����������Ȃ킿����
�₪�o��
�j�K�����h�镽��
���ނ��Ƃ��ł��Ȃ���҂̎p���͂��߂Č������I
�����a�ւ̓���
�����̒鍑
���ꂪ���邢�͏o���̋���
�������������i�̏I��̓~������
�X�Y���K�̑������܂��
�����͂����ǂނ��Ƃ��\���낤���H
�n�A�n�A����x��
�\�\
�t
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P�i�A�����s�S�y���t�̈ꕔ�j���Q�R�i�g���j�l
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N1���k5��1���l��Z�`�ꎵ�y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A42�s�B
�}�_���E���C���̎q����
���l�͌��Ȃ�
�������q���̑̑�����Ƃ����
������
���̂��тڂ���͎��ɂ����Ȃ�
������}�_���E���C���͂�����l��
�����ɗ���
���u���V��l�Y�~�߂��
���܂ɂ͗���o���\�E�R�E����ɂƂ�
�����͒����琰��Ă��邽��
�}�_���E���C���͎q���ɑ̑��̗��K��������
���̃}�_���E���C���͔�����
�ł��ƂĂ������Ȃ��ו��������Ă���
�ĂȂ炢���̂���
��̂ӂ����}�_���E���C���͕����Ă�����
�����납�炤���납�炻��͏o�Ă���
�`����I�ɕ\�������
�u������
�k�P�i�܉��j���Q�R�i�V�c�L�j�l���͎̂��̊�Łk�P�i�ǂ����݁j���Q�R�i���s�j�l���߂���I�v
���`�̏W���łȂ肽��
�������镔�������̂܂ܑS�̂Ƃ���������
�c�Ɍ��̐�����Ȃ���
���̖��[������ł���悤�Ɍ������
��g�Ƃ���
���鋛�ɂ͖т��͂��Ă��Ȃ���
����l�ɂ͖т��͂��Ă���
����͖��ĂȐ����̓����䂦��
�����ł��₷�����_������
�������}�_���E���C���̏��L����Ƃ���
�ނ���n�����悤�Ɗ���Ă���퐶���Ƃ�
���[���}���̂Ȃ�
�q���Ɠ��]�����z���Ȃ̂�
�ԕ��̂Ȃ���I�̂����܂��t�����Ȃ�
����ꂽ��̔���
�ڂ���̗����Ă��鐅�̏�������čs��
�}�_���E���C���͂����������
���̓���𑼐l�͖��Ȃ��łق���
����͉߂����u���e�v�����m��Ȃ���
�̑��̂ł��Ȃ������́u�q���v�����m��Ȃ�
�}�_���E���C���͏H���D��������
�g�t��������ʂ���
���o�́s�������_�t�k�������_�Ёl1972�N7�����k87��7���l�O�`�O�O��y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A85�s�B
�|�̉߂��k�P�����Q�R��l�������z���o�̂��߂�
�Ȃ܂��k�P�̂��̂��́��Q�R�i�g���j�l��H�ׂ�
��l�̂̂킽���̗�����
�Γc�E���c�т��Ȃ���o��
�~�Y�J�L�������q���悳���
�����͂��łɓ�����̂悤��
�˂Ȃ炸�@���̏o������
�U�N���E�C�`�W�N�̎��̂����Ȃ�̔ޕ��Ƃ�
�����̂��Ƃł���̂�
�Y�I�Ȑ����̓��[�����߂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�X�g�b�L���O�E�X���b�p�E�R���Z�b�g��
�k�P�i�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�͂܂�Ă���v
�i�t�^�����L���o���F��
�q���H�M�r�̒n�����܂悢�s��
�܂������Ă��Ȃ�
���y�̓����������߂�����̂悤�Ȑ��g�����̂�
�����ɋ�z�͂Ȃ��댯�Ȑ���������
�������̐��͔R��
�Ă̐��͂Ȃ��ꂽ
������ꂽ���ې痢�̉��̓����s����
�ʂ���@�ʂ���
�L�@�I�ɍs������
�L�߂̎�{�ց\�\��
�Ðl�̉]����s�E�e���\�N�̖��x������X
�����\�\�I���h�����u��j��
�u������������v
����͒��ۊϔO�ł���
�l�������ɂ���Ďl���֓S�_��˂����܂��
���鍕�т̖�̃{�f�[�ɐG��
���̑傢�Ȃ鎀�̉e�̏d�����Ƃ������
�ߓx�̋��\��
���͌������̂��̂ł͂Ȃ���
�₢�͂��߂�
�h�����炳���ȑO��
�h�h�b�Ƃ����̂ڂ���C��
���ތR�͂̃X�J�[�g���܂錩��
���������̗��j�ƒ����c�����͐�ׂ�
��l�̂̂킽���E���Ȃ킿���m���݂�͐���
�J�T�T�M�̂����߂Ƃ�
��͍̚��̂��Ă��ȓG���͎�����
����ł������S���̉��ɐ��݂���
���ʂ̊i�q�̂Ȃ���
�����Ă���n���`�̐��X������
�Ӗ������y�₩�Ȍ아�������l
���Ȃ����
�ւƉ��̊Ԃ�
�m�������ޗ҂����s�ׂ��̂��̂̂Â�
���ꂩ��̍Ό��̉~���ӂ��ǂ錌�Ђ̓��̂�
�����߂̐��Z��R�E�����������z��
�O�l�̂̂킽���E�ނ�͈����������Ђ�����
�䍂���肵���̗t�̕��Ǒz����
�ނ����k�P�d�d���Q�R�c�c�l���J�f�ɋ����������s��
�h���̖݂̂ǂ��Ԃ�����
���������C�X�g�[���̋u����
�G��ǂ�ʂ�ʂ���
�q���r�́q��r���킳���o���ׂ�
��l�̂̂킽���͂Ȃ�
����̏��n���čs���̂��낤
����������ϔO�̂�������
�s�v�̕��������ł�
�����
�����̉��ꂽ���̑���
�������Ɏ}�ׂ̍��Ƃ����
�i�i�t�V�̂���Ȉړ�������
��l�̂̂킽���E�N��̎��ω��̉^���������
�����Ă����Ԃ̃s���N�F���N�₩��
���̍����͕��̌`�Ԃ̌Œ�ϔO������
�P�����X��
���ꂱ������Ȉ�l�̂̂킽���̐������ɋ߂�
���g���Ă�C�ӂ�
�M�w�l�̒��}�X�N����K�̏��
�p�ЊD�~�������̗����I����
�O�l�̂̂킽���E�ނ炪����̂͑ދ��ȕҕ��f��
�������ɂ�
�ۑ����ׂ������Ȃ�
�����̕X�Ђ̂悤��
�����邠�܂�ɑ����̂���
�n���Ɩ��Ə���
��Ȃ�_�͕s�^�̒����������ꂸ
���̃R�[�q�[���̂ނƂ�
�Y�b�Y�b
�����|�p�̓y��̂��ׂ�
���炵�����̖̌Q��炭�ԁX
���炵�����������
�����̂₳������Ȑ�����F�߂�
���o�́s�|�p�����t�k�|�p�����Ёl1973�N7�����k26��7���l�k��l�Z�`��l��y�[�W�l�A�{��12�|20�s1�i�g�A32�s�B
�܂�Łk�P�n���ׂ�́��Q�R�i�g���j�l���y�̂悤��
�k�P�i�i�V�j���Q�R�A�W�T�C�̉Ԃ̐F�͕ς�l
�ߋ��̃J�e�h�����̂悤��
�����́u�̑�Ȉ��ƈ��v�k�P�����Q�R�̎���͏I�邾�낤�l
�[�āk�P��F�m���恨�Q�R�̗т̂Ȃ��Łl
�E���W�[�~���E�i�{�R�t�͋L�q����
�������鏭���̎肩��r�ց@����ɓ͂��Ȃ��Ƃ����
���͗҂����L���̂悤��
�p���Z�����߂�
�e�̖т̓����ɂ�
�m����D���j��`���ƂƂ̂���
�R�e��n�T�~��
�����悭���[����Ă���
���̉Ƃł͏���������ׂ�����
����ׂ�Ȃ�������
�����C���������Ɂk�P�r���Q�R�`�V�����l�ւ䂭
���̏�ɒu��������Ăɂ�
���܂��Ă�������{���̓���
������Ƃ�܂���̐��X������
���ꂪ�s�N�j�b�N�̂��̂���
�����ޏ���
���邸�钾�ޒ��N�j�̖���
���ޒE���сk�P�i�i�V�j���Q�R�̂܂܁l
�Ԑl�����ۂ�������
���������݂ɂ����肱�Ȃ�������
�l����ւ����͂Ȃ���
�k�P�u�����̎���v�͏I�邩������Ȃ����Q�R�͂Ƃǂ܂�l
�����鎇�̕����k�P�i�i�V�j���Q�R�I�l�̉���
�V�����[�𗁂т�ꖺ��
�������Ɂk�P���遨�Q�R���āl
�����́u�Úg�v�ɋ߂����݂ł���
�փA�[�s���̎R���k�P�i�i�V�j���Q�R�͂邩�l
�k�P�e���Q�R���l���Ƃщz����
���o�́s���p�蒟�t�k���p�o�ŎЁl1973�N2�����k364���l��܈�`��ܓ�y�[�W�A�{��8�|24�s3�i�g�A4��87�s�B
�@�@�@�@�q�n�����Ŕ҂������Ȃ�r�y���@�F
�@�@�@�P
�킽���͌������b�I
�����̂��݂̕��p���߂�����
��l�̘V�k�̂��낦������̂����̎w��
�����܂�
���ʂ͂����������ė���
���ꂪ�₪�Đ����ɂȂ����Ƃ�
�݂����̂�
�Ȃ��������
������L���������
��̐��͂��łɂȂ�
�����͎T�����
�D��Ȗ��̂��Ɛ��悤�ȓ��v��
�ϔO�̘g����O���
�߂̕����
���ꂩ�畑���ւƌi�F��ւ�
�u�Ԏq�̖j�ɂӂ��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�Ԃ̖ڂ���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�킽���͉���`���悢�̂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�J���C�̐o
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���тꂽ�֎q�̐K
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���̋z�o�����z���o��������
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l����Ƃ����ۂ��ꂽ��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���v
�함�ւ̂Ȃ��ܓ���
�𗹂��邽�߂�
�u�킽���͐Q���ɂ܂イ�����������v
�@�@�@�Q
�����
�勘���肫
�_�Ɋ������
����z��g�������肫
�̂�����̔��������D��
�^�ȂŃt�N�t�N����܂ꂽ�o�̑������ǂ���
�u��ɍs���ΐ���@���ɂ������
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���l�`�v
�����Ă̂��҂��Ȃ�Ȃ�
�u���Ԃɂ�����̂����́v
�₪�Ė�����
�u�S�n����H�ׂė�����o�čs���悤�Ȃ̂��w�Ɓx���邢�́w���k�{���x�v
�����炻�Ή��̏\��Ԗڂ̖��q��
���łȂ�
�u�L���J�N�V�Ɏ��𗧂Ă�v
�܂�
��͒P���䂦�ɒ^���I��
���I�����肨�낷�悤��
�ؕ��m�R�}�C�n�҂ݐE�l�̉S��������
�@�@�@�R
�u�����^�R�̐e�������ӂ���̂����߂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l��Ő���Ă��铹�[�ŌZ�����N��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���肷���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�N���b�Ƃ܂邭�Ȃ钎������v
�g������������邱��
�u���͂��̒��ł��炾�̐��@���v��v
���ꂪ�����鉼����
�������
���������}���l����
�킽���͐����̐l
�여��̐��Z��
���l�ƈꏏ�ɋ�
�vጂ��炯�̐^�钆�̐l���͂���H
���C���o��
�˔ɂ̂�����
���̓���������j��������
���V�̉���
�C�{�C�{�̌ӉZ���Ȃ��Ă���
�@����̂悤��
�@�@�@�S
���C���͂����܂�
�ԉł͖߂�
�V�q�Ɛ�̐��E����
�|�^�|�^�킽�����Y�ނ��߂�
�����̒��֓���
�u�����Ȃ����̂Ɠ����Ă���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���̂̔��������v
�킽���͎���悭����o�邾�낤���H
�u���Ȃ�p�x����T��ҁv
�ƂȂ�ׂ�
�Ȃ���������
����̎ς��鉹����
���܂����Ԃ����n�����������藧��������
��������Ƃ���
�Ւd�ƊD�̏�
����͂����펯�I�Ȍ`���ł͂Ȃ���
�u���̕��܂��p�`���ƂԂ��v
�قǎ��R���̂�
�킽���̖��݂��ɕK�v�Ȃ̂�
���̔���ƃR�[���^�[���̈��L�ł���
�h���̃��[���A���Ƃ���
�u�X�M�i�����ޘV�l�̊{���O����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�������o��v
�@�@�@�@�@�@�k�P�i�����E�����j���Q�R�i�g���j�l
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�l1973�N11�����k27��11���l��y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A23�s�A�ڎ��Ɂu���̎��v�Ƃ���B
����������͍���������l
���̃^���̖ɂ����Ă䂫
�����͂̂ڂ�
���̕挴��
�S�H�̃c�O�~��H���҂��l
���ꂪ�`�����邨�Ƃ�����̈Â��S
����ɂȂ�Ȃ�
��������Ƃ�ł���
���O�r�[�{�[�����X�J�[�g�̂Ȃ���
���˂�����͉B�����܂܂�
�Ȃ̂Ŋ�h�̔L��
���ʂ𑖂�J�ɂʂ��
�H�S�̂悤��
�������Ƃ͑P�ӂ̗������Ă���
���r�J�������X��
�݂Ȃ����܂�����
�ł͋L�O�ʐ^���Ƃ�܂���
��ւނ�����
�ɂ�������ĉ�����
�ł����܂��f�邾�낤��
�����łɂڂ���
�n���C���ݒn���̉��n��
�R���N�̖Ɓk�P���Ɓ��Q�R�Ƃ��l�ɐ������Ă���
���o�́s��̐V���t�k�ǔ��V���Ёl1974�N3��24���k35051���l��O�ʁA�{��8�|1�i�g�A20�s�A�u�G�b�`���O�E�o�����v�B
���̏�Ɏx�ߕ��̏㔼�g���̂�����
��l�̒j���F���Ă���
���g�ݍ�����
�����̒܂͉��F���ؕЂ̂悤��
�������̖ѕz�̉��Ɂk�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
��������Ă�����̂�
���̍Ȃ����m��Ȃ�
�傫�Ȍ��̂Ȃ��ŋ�����҂�
�^�̉Ԃ��Ƃ���ǂ���ɐ��߂�
��т��������县�̑��҂�
�������犪���Ă���
������Ȃ鐺
�x�ߕ��̒j�̐��́k�P�Qꡁ��R�y�l���Ȃ�ł֊g���Ă���悤��
���⍁�̖�͂�����
��k�P�i�i�V�j���Q�R�h��l�̑������̕���
�������������邭
�j�Ə��̂܂��͒�~���Ă���̂�
��]���Ă�����i�c���̎�
�悭�����
��l�̒j���������
���C�X�E�L��������T�����@�i�G�E11�j
���o�́s�ʍ����㎍�蒟�@���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�t�k�v���Ёl1972�N6���k1��2���l����`��Z�l�y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁�43�s�l�k�����`���������14�߂ɕ����T����чU��66�s���l109�s�A���ɁuPhoto by Lewis Carroll / Poem & Montage by Minoru Yoshioka�v�Ƃ���i�q�g�����̃��C�A�E�g�i2�j�r�Q�Ɓj�B�ڎ��̕W��͒P�Ɂu�L��������T�����@�v�B
�O�l�̏���
�A���X�E�}�[�h�b�N
�A���X�E�W�F�[���E�h���L��
�A���X�E�R���X�^���k�P�E�X���Q�R�X�E�l�E�F�X�g�}�R�b�g
�ޏ���̊�͉������Ă���̂��H
�ޕ��ɂ�������q
�̂т��肿�k�P�����Q�R���l�肷��J�^�c����
����Ƃ���}�[�K���b�g�̉��Ɓk�P�F���Q�R���l�̉Ԃ̒��
�ޏ���̋r�͈͂܂�Ă���
�ǂ�����k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l����͓��̂悤�ɂ̂������Ƃ��ł��邩�H
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�����k�P�A���Q�R�i�g���A�L�j�l���̎q�̉ԕق������������
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�܂���オ���Ă�����k�P�A���Q�R�i�g���A�L�j�l�����Ƃ���͂Ȃ����ˁm���n�v
�ޏ���̐S�͂��݂̂Ȃ̏��
���]�ԂŒʂ�
�`�[�Y�̃`�F�V���B�̐X
�X����M�U�M�U�̋��́k�P�����Q�R�n�l�Ŕ҂���j���D��
���̂Ȃ��͋��łȂ�
�������ꂽ����
���j�Ƃ̕��̎��̂Ƀj�X��������
���̉��̐��E����
������殂݂̂ǂ�̐���������
��l�̏�����߂���
�Ȃ�܂���������
�����Ă��鎞�͉i���̉ԉł̎��̂悤��
�Ƃ��ǂ��Ђ炩���
����i�q
���M���Ȃ߂Ȃ���
�킪�����A���X�E���k�P�b���Q�R�i�g���j�l�f��
���݂͂������Ɏl�Ԗڂɐ��킽���Ă���
����͉��̂ɂ����Ȃ�
�q���r�̊O�ɂ���
�����鏭���̂Ȃ��̂����ЂƂ�̏����I
���݂͂��̂̏��ʂ炸��
�D�Ɖ��̍Ō�ɂ���
����ł��Ă��݂͔G��Ă���
�J���̂���
�j�����֍s�B���
���̉H�̌�
�`������悤�łȂ�
���������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̔ƍ�
�嗝�̓��ʂ�B��
�A�C���X�E�g���ȁE�H�E�A���X
���k�P�b���Q�R�i�g���j�l�f���I
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����C�X�E�L�������k�P�s���Q�R�q�l���̍��̃A���X�k�P�t���Q�R�r�l���c��������
�@�@�@�T
�h�k�P�b�O���Q�R�W�l�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�k�P�A���Q�R�w�l�����G�b�^�k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@����Q���̂Ȃ��͊��L�O��
�@�@�@��
���W���[�W�E�}�N�h�i���h�͂Ђ����̂��@���������[�̐O�́@�C�`�W�N�̏`�ł悲���@�w�l�X�̉�����c�^�̗t��点��p��@���ɕ���ā@���̑����̂��
�@�@�@��
�A�O�l�X�E�t�������X�E�v���C�X�͍�������̑傫�Ȑl�`������@�����̂���������ٔ����̎p�������l�`���@�킽���̍߂��āI�@�Ȃ̉��������Ă��邱�Ƃ�
�@�@�@��
�G���U�x�X�E�k�P�q���[�X�B���Q�R�n�b�Z�l�[�@�悢������Ƃ��ςȖ��@���o�[�E�k�P�q���[�X�B���Q�R�n�b�Z�l�[�����̖��@���̃\�t�@�[�։�������ā@�ߌ�͕��҂@��͈�҂�҂@��͕���҂@���҂����@�킽���͑҂@����������Ղ�҂�
�@�@�@��
�����A�C���[���E�E�B���\���E�g�b�h��@���ɐ����ꂽ���̒���������̖������@���낵�����Ƃɖ̊�����邵�Ă���@����ł���@�����Ă���@�@���Ȃ�̌҂��@���q�ւ������ČZ�̎��݂�����
�@�@�@��
�����猩����G�t�C�[�E�~���G�k�P�X���Q�R�[�l�@���ƕ�Ɓk�P�����Q�R���l�����̑������т����̂��k�P�i�x�^�j���Q�R�i�S�p�A�L�j�l�ォ��̂������悤�ȋC������
�@�@�@��
�t�t�t���t�����N�����v�l�̖�����Ɏ��Ă���@���ނ��o���̂Ȃ��̃��[�Y�@�q��S�͎����ʼnS���̂�@�o���新��Ȃ���I
�@�@�@��
�}���k�P�i�i�V�j���Q�R���l�A�E�z���C�g�̔����}�������낪���Ă䂭�@�~��Ƃ��낪���邾�낤���@�����x�X�E�p���X�̑��d�Ȗ�Ŏ~��@������������ďf�������߂�����
�@�@�@��
�}�k�P�h���[�k���Q�R�f���C���l�E�L���T�����E�p�[�l���@���������D���@�����т��D���@���炪�D��
�@�@�@��
�b�E�o�[�J�[�q�t�̖����C�͈֎q�̏�֗����Ă���@�C�̂܂܁@���̘T�S�̜����@�\��k�P�ˁ��Q�R�l�ɂȂ������т����
�@�@�@��
�����[�N���X�}�X�@�a�߂��@�a�߂鎵�ʒ��̐��@�킽���̓��k�P�i�i�V�j���Q�R�A�l���[�E�}�N�h�i���h�@�W���[�W�E�}�N�h�i���h�̖��@�������܂��Ǝo�@�������������炢
�@�@�@��
�G���E���j�A�k�P�[���Q�R�E�l�E�C���A���Y�@�L�����ق����ő|���@�ǂ��܂ł��ǂ��܂ł��Â��Ɓ@�����͍����́u�����v�ƂЂƂ��Ɖ]����
�@�@�@��
�k�P��C�������Q�R��ȍٔ����l�f���}�����̖��O���C�X�E�f���}���@�̊K�i�̈�ԉ����ޏ��̌e���̐��E�@�d���傫�ȒȂŐԂ��J�j���ꌂ������@�����鏗�̐S�ɂ����Â�
�@�@�@��
���͌|�p�ƃA�[�T�[�E�q���[�Y�@����ꂽ���̃A�O�l�X�@�E�T�M�̂悤�ɖт̂��镞�𒅂ā@���������������Ȃ�@�t����Ă܂Ł@�L�d�^�̒I�̉��̏��g�����̗�
�@�@�@�U
�e�j�k�P�X���Q�R�\�l���v�l�̖ÃA�O�l�X�E�O���C�X�E�E�F���h�͐Ԃ���n���Ђƃ}���g�𒅂��@�n�̂�����ɗc���F�������Ăԁ@�k�P�R�[�g�D�X����i�Ձ��Q�R�N���t�g�q�t�l�ق̎g�p�l�̖��k�P�N���t�g�E���N�g���[���Q�R�i�S�p�A�L�j�w���́u�R�[�c�v�l�@�����̖��G���U�x�X�E�k�P�q���Z�C���Q�R�n�b�Z�[�l�@�|�p�Ƃ̖��k�P�A���Q�R�G�l�~�C�E�q���[�Y�@�s�E�a�k�P�i�i�V�j���Q�R�E�l�X�g�����O���m�̖Ã]�[�C�@�W���[�W�E�}�N�h�i���h�̖��@�������܂��Ƃ����Ȃ��k�P�C�����Q�R�A�C���l�[�k�P�l���Q�R���l�@���̎o���A���[�@�k�P�s���[���Q�R�p�l�g�j�k�P�B���Q�R�i�g���j�l�[�̋���k�P�i�i�V�j���Q�R�q�l�t�̖��x�A�g���X�E�փ��k�P���C���Q�R���[�l�@�G�����E�e���C�̖������}���I���ƃt�������X�@���|���m���̖��t���[�����X�E�r�b�J�[�X�e�X�@�s���k�P�b�V���Q�R�[�W�l�[���m�̑����k�P�J���Q�R�P�C�l�e�B�[�E�u���C�k�P�k���Q�R���l�@�W���k�P�[���Q�R�i�g���j�l���E�~���k�P�G�X���Q�R�[�l�̖����A���@�N�����{�k�P�k���Q�R�[���l����k�P�i�Ձ��Q�R�q�t�l�̖��k�P�_�C���Q�R�f�B�l���t�i�E�G���X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��Ă����̂͒N�H�@����x�߂̖��́k�P�����Q�R���l�������A���N�T���h���E�L�b�`������@���Ƃ��̃N�V�C�[�@���������݂ɍs���ā@�ŏ��Ɍ����̂͂Ȃ�Ȃ́H�@���̋�����Ƃ��k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l�M�𑆂��_�v�@����߂����̉��̖ԁ@�������Ă�@�x�߂̃E�O�C�X�͂ǂ�Ȗ��������邩�H�@�y���V���͗l�̔��̔��̏�Ł@���݂�N�V�C�[��@��̂قƂ�Łk�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l�Ō�Ɍ������̂͂Ȃ�Ȃ́H�k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i��{�A�L�j�l���Ȃ����g�̓��́@���̉e�ɐS������悤�Ł@�Ȃ��悤�Ɍ�����@�Ȃ܂߂��������c�������H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂�Ȃł��ꂩ��L���������������T���̂�@����͕�тŊ����ꂽ�H��Q�̂Ȃ��Ł@�����ԑ����������l����I
���o�́s�A���X�̊G�{�\�\�A���X�̕s�v�c�Ȑ��E�t�k�q�_�Њ��l1973�N5��1���A���`��l�y�[�W�A�{���܍�28���l28�s1�i�g�A76�s�A�ڎ��ɂ���u�A���X���̂��߂̃A���X�H�[�@Alice workshop for the hunting of Alice�v���̈�сB
����͂�������̕a�l�̖����������Ȃ����Ȃ��
�q�ދp���Ă䂭����⌌�̏o�����r
�킵����҂�����R��̈�т��т͈��u�ł���
�����@���������̈�l�̘V�k�������Ɏ���
�@
���ꂱ��e�j�X�����̎���������
�J�����Ǝ��Ă邾���̕��������ĐX�܂ōs��
�܂������e�ރ{�[����Nj�����@��������킵�������邩
�ނ��������j���̊Ԃɐ�����@�J���t�����[�@��
�@
���̐��ɒɂނ��̂��͂����Ă��邩
�킵���f�@����̂͋��̒��̊��҂̊�������
������ꂸ�@���L���Ȃ�
�ł�����@���̕\�ʂɂƂǂ܂�I�����W�̂悤��
�@
����̎ʐ^�@�R�_�b�N�̌ܕC�̔L�̎ʐ^�@�D���̎ʐ^�@�Ԃ�V
�̎ʐ^�@�ė�������s�@�̎ʐ^�@�������̎ʐ^�@�R��̎ʐ^�@
���D�̃k�[�h�ʐ^�@�`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\��������
�B�����A���X�̎ʐ^
�@
�q�Î~����䓁�⋛�@���݂��闋�Ⓧ�r
�q�X��R�̓��������B�̒��̓����r
�q������l�̏������������Ă���r
�q���̂قƂ�̓��S���ƉJ�r�k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l�������킵�͚n�D����
�@
�����Ɠ��[�u����͂������ɐ؊J����v
���ꂪ�I������͂̂����肠�����n���@�肩������
�������o��@�����ɐ�����̂��o��
���̂Ƃ��͊Ō�w���Ă�ŕ�т����邮�銪������
�@
�ł͂��̂悤��
�ł͂��̂悤���A��
�Ƃ͂������̂�
�Ƃ͂������̂̌���
�@
�u�������Ȃ₩�ɂ�������v�Ƃ�������l�̏���
���̂̂т₩�ȑڂ�����@���̂Ȃ���
���̓I�ȕ��͉z������@���������ʂ͑���Ȃ�
�I���[�u�����ڂ��̔w��͈Â��@���ƎR�r
�@
�n�������܂��߁@�͂������܂��߁@��ق������܂��߁@�R�͂�
�����܂��߁@���H�������܂��߁@�Q�[���������܂��߁@���v��
�����܂��߁@���������܂��߁@����������܂��߁@��������
�܂���
�@
�ނ����O���̖���ł���Ƃ̂����ʂ�z�N����
�����̕�������
����͑��ނ�̈���̂悤�Ɍ�����@���
�����E�A���X�͓�����
�@
�w���x�ɂ͎��̂��h�肱�߂��Ă��܂�����
�킩��܂���i�O�C�̔L�j
�w���x�ɂ͍���������܂�����
�킩��܂���i�Ђ܂��̉ԁj
�@
�w���x�͉��ŏo���Ă��܂�����
�킩��܂���i�S���̂悤�Ȃ��́j
�w���x�͉����͂�ł��܂�����
�킩��܂���i��c�̉ƌn�j
�@
�w���x�͍��������Ă����ɍ݂�܂���
�킩��܂���i���ƒ��j
�w���x�͂ł͂ǂ��ɑ��݂���̂ł���
�킩��܂���i�i���ɕی�F�j
�@
������ׂ���p������
������ׂ��a���Ȃ��Ƃ���
������ׂ������
������ׂ����̂���
�@
�킵�̒m���Ƃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u������l�̃A���X�͏\���ɂȂ��Ă��@�p��̔���ɐK��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�ڑł���@����Ƃ��̓Y�b�N�̑܂ɋl�߂��ā@�V��ɒ݂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�����@���������̃A���X�E�~���[���C�c�c�v
�@
����ɂ��Ă��킵�͔`�������@�܂ƃy�`�R�[�g�̓�����
�Ȃ܂߂����������Q�̉H���ꂷ��@�Ô��ȋG�߂̏I��
�������[���ޏ���̔畆������@���Ɖ����z��
��͉Ɖ��𐁂��グ��@��̌��ꏭ���悢����
�@
�����������������
��F�̈߂��܂Ƃ�����m���̌`������
�Ď�����Ƃ���������l�����߂�
�킵�͏��Ί�����V����j�@�×̕ǎ��̉Ƃɂ���
�@
���˂Γs�@�������M���V�A�ߌ��̌����ǂ���
���̕�����Ƃǂ��@�L���k�P�o���Q�R�p�l�����̐�
�����鏭���̓����牺�͍g����Ȃ�
���i�ȃn���J�`�����L���邱�Ƃ�F�����@����@���t�I
�@
�Ă̋�̐F�����鎞
�킵�����l�����炽�܂ɂ͌`����I�ȉ���������
�����@���������̈�l�̏����́w�x��Ǒz����
���܂��鉮���̏�̐l�@����͓������m�ꂸ�H
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1974�N4�����k17��4���l���`��y�[�W�A�{��9�|1�i�g�A35�s�B
�q���Y�[�����@�̒���������
�����̖��
���������̂���傫���Ȃ�
�傫�����̂��珬�����Ȃ�
�������E�֏Ɖ�����
���̂��l�@��
�r�X�P�b�g������
�킽���͒��֎q�ɂȂ��Ȃ��ƐQ��
���[���F�̕���
�����܂���̐A����������
�����͂܂�����
�u�������߂̉����v��
�p���\����������
�Ñヌ�f�B�[�̗d�����ɗU����
���߂̎��k�P�i�i�V�j���Q�R�l�l
�u�J���ɂ�
�q�����l�̑������ށv
�@�ׂȍ\���́k�P���E���Q�R���{�l���痈��
�킽���͑z����̗��l�k�P�i�i�V�j���Q�R�̂ЂƂ�l
���ܗ���ɂ�����̂�
�ł����Ə_������
���ꂼ�������
���܂������镨�����ə�����
���炭���ʂƂ��܂Ł\�\
���̋łɑ�ȐS��
�i���ɂʂꂴ��k�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
���̓��Ȃ�T
�����������
�R�̒���킽���ꂽ
���Ȃ鐅�@�̍炭�قƂ�ցk�P�i���s�j���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�������낤
陂��͂₵����l�̗F��
�����̎Ⴂ���̂���ނ�Ă���
���̏�ł����₩��
�H�ׁk�P�遨�Q�R��l
�k�P�i�i�V�j���Q�R�u��ɂ͖��V�̐��v�l
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N9�����k5��10���l�Z�Z�`�Z���y�[�W�A�{��9�|24�s1�i�g�A12��134�s�B�ڎ��ɂ́u�����v�Ƃ���B
�@�@�@1
���̃G�v�����̂�����
�킽���͐��܂ꂽ
�Ƃ�������
�u��ԊT�O�Ƃ͉����v
�ƂȂ�̐l���₤
����͂�������
�u���͈ÈłŌ�����̂��v
���ʂɂ�������������
�L�m�R�ނɋߎ����Ă���
���̊̑��Ő͈炿
�킽���͑��̏�֒u���ꂽ
�����`�́q���t�r�̊ǂ��z���Ă���̂�
���|�[�������킽���łȂ�
�o�b�^�̈�킾����
�@�@�@2
�u�����ɐ����t�����܂���@�����݂���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�y�͕����Ă��邩��v
�G�i�����h��̋��̓��W�͂܂���
�ΉP�̏��
��̖����邱���
�V�l�����͋A���čs��
�h�Ղ�
�u�킪�q��@�킪����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���̂����邻����I�v
�B�̎R�ŕ�͉S���Ă���
�@�@�@3
���͖ҏb��X�^�C���̏����D��
�����p�����Ă��t���C�p���̐K��@���Ȃ���
�ԑ܊p�������ɓ˂��o���Ă���
����͑�@����͑��̊O��
�G��Ă���@����܂���ւ̂悤��
�V�����Ό��̂悤�ɂ���͊���
���܂ŗp������
�@�@�@4
���ƃs���N�ɐ��߂�ꂽ���@�̖��������
�킽���͗V��ł���
���̖̌Q��
���炴�炵�����̎���H�ׂĂ�
�u�����Ȍő́v�����߂�
�s����殂��~��
����l�@�����ߐl
�q��̂Ђ��̂�����
�킽���͒T���Ă���̂�
���ꂽ�т̂Ȃ��̖�e��
�[�������̉���
����������������������������
�u�ԉŁv
�킽���̈�ԍD���ȁq�ϔO�r�I
�@�@�@5
�n����M�ɂ̂��Ă���Ă���
�����I�Љ��
�ނ̂��߂ɉ̂��S����l�̏��������炵��
���j�ƂȂ猟������
�X�t�B���N�X�Ɂu�Z��v���������ǂ���
�����₻��́u�o���v�ł͂Ȃ�������
���̊�ȑ����n�݂����ɐ������ގp��
�n��̑e���O�|�̂�����
�e�j�X�C�̏����͖�����
�@�@�@6
�X���肪���̃e���g�̂܂���������߂�
���҂ւ̗�߂����
���ꂽ���ƃV���c�ɂ����܂��
�����̐e�����݂܂���
���M�@�E�T�M�@�L�W�@�E�V�@�u�^�@�E�}
�u���ׂĂ̌��͂��ĂĂ͂����Ȃ���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���͎ς߂��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�ς߂�قǂ��܂��Ȃ�v
�@�@�@7
���ꂪ����̓��̂�����
��C�̖C�g���������߂�
���━���o���肳���ɓ�������
�ዅ�╺�m�̎�o��
���ꂩ�疡�̔Z���X�[�v������
�l�ނ�삦��I
���{�n�̗r��������
�݂���n�[�g�̋u�߂Ă䂭
�܂Ȕ̏�ɍ݂�
�J���ꂽ��
�@�@�@8
���̖����������߂�ޕ�����
���͂̂ڂ�
�E�H�[�^�[�q���V���X�͍炭
����ɂ��c�N����͂���
���̂Śg�����
������u����v�ɕt��
���F�̃Z���C�̂悤�Ȃ���
�킽���͂��������
�����̃}�C�X�^�[�ɂȂ邱�Ƃ�
��̏�̉Ƃ�
�\�[�Z�[�W������
�u��i�v������V�E���u������
�ǂ��������Ƃ�
����͂ނ�Ȏp�����������Ƃ���
�@�@�@9
��n�Ő���̒f�ʂ�
����ꂽ�n�}�̂悤�Ɍ�����
�w�b�g�ƃ��[�h�̗₽���������
�����w�b�h�̕��̓^�}�l�M������A��
�������o���[�h���S����̃��[�u�͉����
���ꂱ���j�Ə��Ƃ����̂̎O�ʈ�̂�
��͓B�t���ɂ��ꂽ
�߂���߂����\�̒n�̏���
�@�@�@10
�킽���͕a�C����
�����ǂ̂Ȃ����䂫������
�̐S�������q��
���炴����̏��������߂�
�������߁@�l�߂��q���r��T��
���₩�Ȑ�̂قƂ��
�̉��ɗ{���Ă���J�j��G�r��߂�
�M�I��
�Ƃ��ǂ��ӂ�ނ�
�u�ƂĂ��d��Ȏ������v
�����̂Ȃ��ɉ���������
�����̂Ȃ��ɉ������ł�
�����̂Ȃ��ɉ������c��
�����̔�̂Ȃ��ɂ͖[�������
�@�@�@11
�Ӗ��Ȃ����A���e�B�u�����
�O���I�I���i��
�a�̉����䂭���l����
������L�̂悤��
���Ɩ��Â�����͔̂��y����
����ꂽ��r�̂ւ��
�t�̒����Ђ�������
�u�����ɂ���@���̉ԁ@�n�L�@�~�̖_
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���@�����̑��@�D�@�Ɨ�v
���Ƃ�����炪�����̋߂��ɂȂ�������
�u����v�̐����͂Ȃ������낤
�͂邩�Ȃ���̑��̉���@�߂�I
�@�@�@12
��z����������
���킽��R����
�Ƃ����낱���̖тɕ�܂�
�]�o�����������Ƃ�
��l�ɂȂ��ā@�킽���͎v���o����
�u�q�A�[�g�r�͑ދ�����v
�}��߂��Ă���嗋��̊k�̂悤��
���̐��̓����͉������ɂȂ���
���Ď����Ȃ��h��
�u�z���ł�����̂́@�z���ł��Ȃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���̂��q�������o�r������c�c�v
�킽���͂��܁u�Ǔ����v�����q����k�P�i�i�V�j���Q�R�l
���Ɍ����Ă���
�e�[�u���̒j�̂悤��
���o�́q�����O�j�W�u���N�����v�r�p���t���b�g�k�؉�L�l1974�N4��13���A�{��10�|18�s1�i�g�A18�s�B�s��z�t�Ę^�y�[�W�̊G�́A�����O�j�́q���]�Ԃ̏�̔L�r�i�T�C���̔N���́u�k19�l71�v�j�B
�q���]�Ԃ̏�̔L�r�i���o�`�j�̍Ę^�@�o�T�F�s��z�t��19���k���W�����z�̔��l�i�y���g���H�[�A1986�N10��17���A��l�y�[�W�j
�@�@�@�@�k�P�}�c�C�E�L�~�I�̊G�ɂ悹�ā��Q�R�g���l
�ł̖����������
���̎��]��
�k�P�i�i�V�j���Q�R���́l�������Ԃ̌o�߂̂�����
���l�͎��ɐ₦
��̎ԗւ̂��₩�Ȏ��]�̎��̒��S����
�݂ǂ�̐A�����ɖ���
���������̂�
�����
�������
�����Ȉ��̎��]��
���̍����̂悤�ȏ敨�̏��
��҂��Ђ炭�L������
�Ƃ�����
����͂����鏭�N������O�ɂ��z���͂̐��E��
�k�P�Úg���Q�R�֗~�l�I��
�����̊X������Ă䂭
������ނ��̏���
�ނ�������k�P�����Q�R�|���l�l������
���o�́s�ʍ������V���t�k�V���Ёl1974�N7���k�ċG�E26��3���l��l�`��܃y�[�W�A�{��9�|12�s1�i�g�k�R�����l�A20�s�B���o�u�{���J�b�g�E���c�ەv�v�B
�킽���ɕK�v�Ȃ̂̓~�J���̔�łȂ�
�u�s�ł̌`�ԁv��
�����ׂ��j�����g����
�͂邩�Ȃ�n���̏ۂ̍��i�ׂ�
����͑@�ׂȍ\��������
�э��̂悤�ȗ̖����͂��
�ԉňߏւ̓����Ɏ��Ă���
�Εǂ̖��H���s��
���̂������Ƃ��炢���Ƃ�����
�哤�܂̉��ɂ̓l�Y�~������
�q�ɂ̗����킽��
�킽���͌�����n������
�����v�l���Ȃ���
���j�Ƃ͑�̂Ȃ��ŏ���������
�u�k�P�݁��Q�R���l���v�̕ꂾ�ƍl����
�u�k�P�݁��Q�R���l���v�̂Ȃ��ɂ͕��͑��݂��Ȃ�
�킽�����S���狁�߂Ă���̂�
�ł��t����ꂽ�삵���B��
�������������
�u�s�ł̏����v���̂���
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1973�N11���k5��13���l�܁Z�`�l�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�i�U�����^��23���l�j�A�����5�߂ɕ�����85�s�A�ڎ��Ɂu�L�̎��ɂ�钷�ю��v�Ƃ���B
�킽���̕����Ɉꖇ�̏����ȊG���|���Ă���
�������̊G�������l�͂��Ȃ�
���̊G��`������Ƃ����Č����Ƃ͂����Ȃ�
�����}�`�G�[����������������
�l�͂���ł�
�u���݂̏�������G��
���L�̈ł̃x�[���̌�����
���݂��邾���ł͂Ȃ����v
�Ɣ��₷��
�d���Ȃ����狤������ȂƂƂ���
�킽���͂��̎O�C�̔L�̂��ނ낷��G�����
�ł��邾���ÓT�I�ȕ`�ʂŎ��݂悤��
�킪�Ƃ̔̕ǂ�����
�B��̊G�̎��ӂ�����Ȃ���
�������I�ȕ����ꂽ�t�H�[�T�C�h�Ƃ̓�������̂���
�@�@�@��
�킽���͂��Ă̈���Ă̗[��
��l�̏��̑ٓ���������ʂ����
���݂���X�Ɛ�̏�y��������̂ł͂Ȃ����ƍl����
���K�̉~���̖��H�����
��y�̉�ƃ��[�����E�u���W�I�̕`��
���������M�w�l�̏ё��߂Ă���
�K�N�^�̑傫�ȖX�q�����Ԃ�����
���������W�F���[�̏�
��x�ߑ���S�̂ɂ��Ԃ�����
������������g��I��ɏo���Ă���
���������ʂ��ނ��Ƃ�
�\���҂�T��������
�V�����g���[�̕Έ��}
�o�b�N�𗬂��͉̂��y�łȂ����
�{�a�̉�L��뉀�̕����̖��ł���̂��낤
�����ꂽ�_�Ɩт̂Ȃ���
�E�n�ɂ������ꂽ���Ηނ��̂�������
���I�Ȍ����̂Ƃ͂Ȃɂ�
���n�����܂悤�T���҂����̍�
���̐^�g�̃f�e�[������
�O�C�̔L�����܂ꂽ
�@�@�@��
�킽���̓\�t�@�[�ɍ���Ȃ���
����̃J���o�X�̘g����o��
��Ƃ̎�����ޔL������
����͎O�̑��ʂɂ����܂�Ă��Ȃ�
��̐��E�ł͂Ȃ����낤���H
�̎R�̑O�ɐl�������~��̂�
�������鎞��
���ׂ̏����̋����͒������ꂽ�悤�ɈÂ�
���̉����E���ꂽ�̂����
�ޏ��͗��r�Ɉ�C���̔L������Ă���
�E���̔L�͒��F�łƂĂ��삦��
�ł����̂悤�ɌX�ނ�
�����炨�̂��ƍ����̍��Ɣ��̂Ԃ��̔L�͔w���܂邭����
������Ă���͎̂��ԑтłȂ�
�O���[�̃J�[�e���̂Ђ��̂悤��
�R�łЂ����ڂ��Ă��Ȃ��̂�
�V��̕��ւ������Ă��邩�炾
�ߌ��̏����ɂ͂ӂ�ނ��^�̐��ʂ��Ȃ�
���F�̃X�J�[�g�̍����悶����
�˂���֒��̔�Ԃ̂����Â���
�����炤����։���čՒd�̋���
���������đ�E�����������L�̑��݂�m��Ȃ�
�V�Y�̉^�������肩������
�Î~�����u�Ԃ𑨂�
����Ȃ߂��莨��~�����̊D�F�̔L
�ӎ��Ɩ��ӎ��̒��ԂɈʂ���
�L�̒��ق͋�����
�@�@�@��
�G�X�L���[�͂ǂ����ĔL��`���Ȃ��̂��낤�@���J�i�_�E�G�X�L���[�W������Ȃ���@�킽���ƍȂ͂ӂ����Ɏv�����@�����̓��m�N���[���̂����炵�Ƌ��ł���@���������ނ��o���ā@�X�̎R�̒��Ɂ@���̂悤�ɋP���Ă��邹�������@���̂ق��͂ӂ��낤�̊G���肾�����@�n���ɖ��鋛�̗t��������ā@���̂���H���Ђ낰�Ă����@���̊�͏��̋����̕\������@�Â��Ԃ̌Q���̂Ȃ��Ł@�܂ꂽ����~���Ă���@������H�̑傫�Ȃӂ��낤���݂߂Ă���Ɓ@�₪�ĔL�ɕϖe����悤�Ɂ@�킽���ƍȂɂ͎v�����@�����̃G�X�L���[�̍��ɂ́@���Ƃ͎q���ƌ������Z��ł��Ȃ��̂��낤
�@�@�@��
�u�ΐH�����������Ƃ����Ƃ͂킽�������̏K���ɂ͂Ȃ��v
�R����H�ԂƂ�̂Ȃ���
�����鉤�Ɖ��܂̑����ߏ�̗��j��
�����̊^�҂̃x�b�h�̋r�̉���
������O�C�̔L�̐_�b���\�\�l�͒m���Ă��邾�낤��
�u�����ł͒܂��Ƃ��Ȃ��@�����̒����ق�����v
������L��ǂ��͂����
�u�L�͂��炢��@�����ĕ����Ă��@���ɂႮ�ɂႵ��
�x�����Ȃ���ł����́v
�Ñ��聏G���l�͂��̂悤�Ȍ��t���₵�Ă���
���o�́s���i�t�k�I�X��l1974�N5�����k15��5���l�l�`�܌܃y�[�W�A�{��10�|19�s1�i�g�A29�s�B���o�u�J�b�g�E���Ԋ��v�B
��Ƃ��e�[�u����`���Ƃ�
�ŏ��ɊD�F�̕�����
�S�̂Ȃ��ɓh��
�u����Ƃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l����Ƃ��邱�Ƃ��v
����ɂ����
�Ă̐��ꂽ�B��䰓�
�̖�ؗނ��X�g�C�b�N�ȉe��������
�Z���̌ߌ��
���ނ��ςȂ���
���悢�捂�݂֎���
���̉�����
�����̎w������
���̌`���o�Ă���
�����Ńe�[�u���͑O���X��
���͒�֖߂�
�M�̏�œ����
���m���́q�ԁr�͎����̒��S�ɂȂ�
�����H�ׂ�q����
�����̌�������
�������ɊO�ς͂����܂��ɂȂ�
�k�P�i�i�V�j���Q�R�n��Łl
�u�����̌�����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���͐������Ȃ��v
�Ӟ��҂���ӓ�����
�����̊������݂��Ȃ��Ȃ�
������
������̔w�i��
�������̋L���Ɓk�P���t���Q�R���K�l�ɕ�������
�ł֗��o����
���o�́s�ٗ�Ձt�k����R�c���q�����낵�ɂ��p���@���q3�r�l1974�N4��25���A�l�`�ꔪ�y�[�W�A�{���܍�13�s1�i�g�A8��161�s�B
�@�@�@�P
���͍��܂Ɍ�����
��
�Ă̔g�̊鏈��
��e���ĂԂ悤��
�g���z���
��̂悢�������Ђ��Ƃ�
�A����
���݂����q�����⏬�푰�̍D�ޓ��F�̓�
�q���́r
�I�p�[���̑�̂Ȃ��̔��e�̖�
���ޚނɓ����Ă���
��
�����߂Â���
�܂��j��������炷
�V�N�ȋ��̖ڂ̂悤��
����҂�
�A����
�ߌ��Ƃ͉����̂Ȃ��̉���
�@�@�@�Q
�J�̓���
���݂��݂ƕ����X�֕v��l�̐���
�ׂ�ׂ�Ɛ����鎍�l��l�̖�
�A����
���݂͔�������
��`�̌��̉��ɐ�������
��Ƃ̍�������
�p�����܂悢�����A�I�R���c�N��
�ނ̒T�����̂�
�ނ̐����т̂Ȃ��ɂ͂Ȃ��̂�
�}��̎�����W���V�̐��E�����Ăт���
�댯�Ȑ��E��ʂ�
�����̂����߂Ă���
���z�@���K���X�̔j�Ё@�����Đ��n�u���V
�l������������������
���ɋA���Ă���
���̂̒�
�@�@�@�R
�A����
�����ɂ͕K�v�Ȃ��̂����肷����
�K�v�Ȃ��̂���
���K�v�Ȃ��̂�I��
����͂������ɕK�v���ƍl����
�����ɂ͕s�p�̂��̂����肷����
�s�p�̂��̂���
���s�p�̂��̂�I��
����͂������ɕs�p���ƍl����
�����Ă������s�p�̂��̂���
�K�v�Ȃ��̂������
���Ƃ���
�u���_�̊O���v�̂悤�Ȃ��̂�
�@�@�@�S
�A����
�u�`�������ŏ��ɐH�ׂ�
�k�P�i�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�͎̂��l�v
�ł�
�u�ŏ��Ɍ��������͉̂ƒ{
�k�P�i�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�Ԑl�̍ȁv
���܂��t�̑��z���P���Ȃ��
�ނ�͂Ƃ��ɊC���𐅓H�̂悤��
��]��
�Y��������
�܂��
���݂�̉��J�̉Ƃ���
�Ȃ߂������ꍑ��T���悤��
���ւ̗����Â���
�����Ă݂�Α�q���݁r�Ə̂���
�����́q���Ԃ̉��r�̉���
�ۂ�����G�ꂽ�E��
���o����
���┽�ɏ��ł����
�A����
�Ȃ߂����͉����ւ䂭
�l�̒ʂ�ʌǐ�̓��ւ������ړ�����
�H�܂ł�
���▨�I�͉₢�ł���
���鍂����ۂ���
�Ԋ��̂قƂ��
�@�@�@�T
�e�[�}�͂��炩���ߐݒ�ł���
�����������̉^����
�є�̂Ȃ��̍��̂悤�ɍ����Ď����Ȃ�
���h���̓��ʼn�̉ߎ��̓_�̍�
�������̂����ʂ̐l�Ȃ�
�܂���̂͒N�H
�悶����ɉi���ɔ�����
�A����
���ʂ̕��m�̑傫�Ȍ����̂����Ă����
�Ԃ��ʂ�ʂ�̐�ł͂Ȃ���
���̉��[���ł̊�ɂ�
�S�̋ʂ��˂��o�Ă���
�A����
������
�A�C�ȌZ��ƂƂ���
�������ʏ��I
�₪�Ă����̓s�s�ɐႪ�~��
�̂ł���������
�o�����������
����悤�Ɏv����̂�
��������͂����ĉ�������
��Ɋ����
�t�̔������H�Ƃяo�����낤
�A����
�������������͂Ȃ���
�S�V�b�N�����̔��̒��S�̍����ڂ�
�̎}�������G��Ă���
�@�@�@�U
�������̂͑���
�����Ȃ����̂͑�����
�Ƃ����̂͐^�������m��Ȃ�
�������̂���
�����Ȃ����̂�
�`�Ԃ�ւ�
�����ւ�
�F�ʂ�ւ�����
�A����
���݂̖锼�̍�Ƃ�
�݂��߂ȌӉZ�̂���Ȃ�ɂ�Ȃ�
�Ȃ̕s�K�Ȃ鐶�U��
����������ɂ����
�֎q�̉Ԃ͂����ނ炳���ɍ炭
���g�͔Z�����Ă���ĉ�����
����ɂ�
����Ȃ�́k�P�q���Q�R�i�g���j�l�����k�P�r���Q�R�i�g���j�l������܂��䂦
�u�n�̂��������������v��
�Ȃ��̂���
�A����
���݂͍s���s��
�X�镃�e�̓y�n��
�@�@�@�V
�l�͐�����̂��߂�
���l�̂��₪��d��������
�����̍l���y�ʛ@�q����������
�A����
�w�L�ފw�̎���x���ł���������
���������Ȃ��L
�����Ă���������Ȃ��̂��Y��
�T���S�F�̖�
�p�Y���琸�_�ُ�҂܂ł܂邲�ƛs��
�������L�̌���
�߂ȕ��͂�Y���ׂ�
�A����
�����͊O���𒅂�
���̊X�֏o��
��C�̂������܂�L��T���Ɂc�c
�͂����ɂȂ�
�I�F�̖ѐ[������
�G���I
�@�@�@�W
�@�̗t�̂�����
�ق��ڂ��Ɛ����̂т�l
�e�̎����邷
���Ƃ���삷��l
�����̂Ȃ��̗��z�I�Ȑ������ł͂Ȃ���
�܂��ɈӖ�������
�����̐����I�c�ׂ���҂�
�����ɓ|���
������ΐ̉���
�A����
���݂͓n��������낤
�勘�̐n�̋P���ϔO�̐��E����
�u�e�Ɏ��Ă���v
���̕����̂����߂�
�Ŏւ̂Ƃ���܂������s��
�����ɂ͉��s������
�A����
���݂Ƃ�����
���܂������݂悤��
�u�R��̐���v���\�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P1974�E2�E14���Q�R�i�g���j�l
���o�́s�G���o��t�k�������@�l1973�N10���k1���l�Z�Z�`�Z���y�[�W�A�{���܍�17�s1�i�g�A29�s�A�ڎ��Ɂu�k���Ґȁl�^���v�̂��ƁA�u��㎍�̌��R�ň�т��Ď����̗Ő��������ĕ���ʍ���v�Ƃ���B
����͓`���ɂ���
�J�̂Ȃ���
�����������Ă��铮���̂悤��
�q���r����������W�߂�
�R���֑����Ă䂭
�g�F�̓����̔�傷��n�[�g�̉e
����˂��o��
�w������������
�������ׂĂ���҂̂悤��
�����ǂ̋��ɗ���
�������ɔG�ꂽ�璣��̈֎q�̂悤��
���炾�𒆐S�Ő܂���
�т⍜���e�[�u���̉��֒u��
���т������̕���
�����������Ă䂭
�q�����r�Ƃ�
���������Ȃ낤��
���łɁq�ʁr����������g�݂���
�Y�z�̂̎q�����
���ܒ����j���킽��Ƃ��낾
���̉��͈��͍��������m��Ȃ�
�킽�������̔F���̂����݂�
��͕R���Ђ�����
�������͐���
���̂Ƃ���ň��]����
�₪�ĖA�Ŗ��܂��Ă䂭
��������
���������
�ЂƂ́q�́r���I�点��
���o�́s���|�W�]�t�k�}�����[�l1974�N7���k�āE6���l��Z�`��O�y�[�W�A�{��9�|21�s1�i�g�A75�s�B
�킪�Ƒ��͂ǂ�����
���̍g�@�n���̓���������
�G�[�e���͂Ƃǂ�����
����ł��Ȃ����M�ł��Ȃ�
����ł��Ă�������͏Ă����
���f�A��
�͂邩�Ȃ鐯�̌����͂�
�����V�W�~�̐�����
���̒��Ԃ�
���z�������т܂�
�g�̌`���������҂��j��
���f�A��
�킽���͂Ȃ������̋��̔[���ɂ˂�
�Ȃ��Ȃ��ƌ��
�����牽�܂�
�`����̖��ɂȂ�
�ӂ��ӂ��������̂̏��
�Q�邱�Ƃ̑�Ȃ��Ƃ��Q�O�ɐ���
���̕�����
���[�u�F�̃X���b�p���ʂ���
�n��ɗ��Ƃ�
���R�̗t�̖��̂قƂ�
�킪���͉������̂܂܉������
���̂��߂łȂ�
�����邽�߂�
��q��ۑ�����
���f�A��
�T�閅�̕����z��
�₪�ė��������C�g�̂悤�ɔ��
���z�G������悤��
��͍��̑S�ꐫ���x����
����j���̂悤�Ȃ���
��͂����܂ł���
�u���_�̍i�E�v�͍s���Ă����
���q���{�[�g�ɏ����
�������������ɂ���
�����E�l������
�V�W�̉��͕s�ł̈łł��낤��
�Ƃɂ������̉���
�Ύ��{���Ĉ�ƒc�R����
�^�����
����̓u�c�u�c�A�ӂ��A���̂��炾�Ƌr
�Z�����̎��k�P�A���Q�R�E�l���{
�����͌��t�ŏo���Ă���炵��
�������ƕϐF����
���f�A��
�����ő嗝�̓y�䂪�������
�킪��͋L�O���ƂȂ�
�킽���͂��̂悤�ȗ�E��������
���ʂ����Ԃ����Z�Ȃ�Ώ��邾�낤
��A�̑O�ɗ���
�l�Êw�҂̂悤��
�͂ł����Ė����̉��������o��
�Ȃŕ�܂ꂽ�����Ƃ���
���ܒ��֎q�̏��
�₯�ǂ����o���Ƃт�����Ƃ�
������Ղ̔�͔�����
�������킪�Ƒ���
�킽���̗��l�����ɂȂ邱�Ƃ��̂���ł���
�l�̉~�����܂��Ȃ�����
�킽���̐l���̉��t��
�����ȓ�����������Ă���
���n�̕�����������
���ꂪ���蒅���Ƃ���
���f�A��
���͂�������Ă���
�l�͉�����n��Ȃ���Ȃ�Ȃ�
�ꂪ����Ƃ�����
��ɂ͌������܂��Ă����
��Ɣ�̒���ꂽ�y�n�ɂ�
���l�̋��߂Ă���
���[���S���̉Ԃ��炭
���ꂪ�q�̓I�����ł͂Ȃ���
���̂������ȁ@���݂�͂炩��͕��V����
���f�A��
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1974�N10���Վ��������k17��11���l�����`���y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A5��75�s�B
�@�@�@�@����C������
�@�@�@�P
�J��
�Ă̐�l���̞��̏�ɍ~��
����͈�̃X�^�C����
�K�[�g���[�h�E�X�^�C����͌����
�u�l�Ԃ̎��̏[������
�k�P�i�����j���Q�R�i�O���j�l����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�ǂ����Ă���ق�
�@�@�@�@�@�@�@�@�y���e��Ȃ̂��H�v
����𗼎�Ŏx����
����݂Ђ炢�ċ߂Â����
�u�����������������߁k�P���聨�Q�R�i�g���j�l
�k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R����l�t�Ɉł�����߂��肷��v
����͋ߐ��̐_�b�Ƃ������
�@�@�@�Q
�����߂��̉f��ق�
����͊ϑ�����
�n��̐��E�K���{�I
���݂̋���ȐO�����ǂ��s���̐l�͑��݂��邾�낤��
���݂���������H�ׂĂ���Ƃ�����
����͕s�v�c�Ȏ��Ԃł���
���݂̉����E�̂Ȃ���
�����������Ă䂭�Y����������
�]���@��@�r�����@��
�̗ւ������ɋ߂��g�傳���
���̉��ɂ�����̂�
�B��̃������A��
�u�܌��̃X�t�B���N�X�v��
�@�@�@�R
����q��r�͍l����
�q��r�͉G���ƒ������[������
������
�q�o�r�͓����Ɉ�́k�P�Q壁��R�u�l��
�����Ă���ɂ����Ȃ�
�����̋�ɂ̂Ȃ���
���ƍ���
�u���͊��S�Ȃ���̂����킦�Ĕ�ԁv
��������ł�
���͕s���S�Ȃ���̂����킦�ĉj��
���A��̏t��
����q��r�͂���������
�q�o�r�Ƃ����ď̂̐l��
�u�ޏ��͖��m�̉���Ȃ��ނ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l��f���ŐV�̌����́v
�ΉԂ̂Ȃ���
�͗t�̂Ȃ���
�@�@�@�S
�u���H�̂Ƃ�����͂��܂�v
�\���s�ׂ̂Ȃ��ɂ�
����̊Ⴊ�z������������
�X�g���x���[�W���[�X
�̂悤��
�F�ł����ĐF�łȂ�
�ƍߎ҂̎����o���o������
�L���x�c�̐c�̂悤��
�`�ł����Č`�łȂ�
���Â��悤�̂Ȃ�����
�u�B���Ȋ��Ɖ����Ƃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l��������㫂߂悤�Ƃ��Ă���v
���ƌ��t��
�L���̐��E�ɂ��c�c
�@�@�@�T
�l�͎��R�Ȏ���������Ă���
����䂦��
�s���R���K�N�̓����ɗ}����
�u�ق���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�����Ă����Ă��܂����v
����͌`�Ԋw��
����߂Ď��ȓ����I����
�փ����[�E���A�͖��̉��܂�S�ő���
���̂悤�ȓ���
�I�����W�̂Ȃ��̍��j��
���ꂪ����
���C�����[�h����
�ǎ�Ƒ�
�k�P�i�i�V�j���Q�R�@�@�@�U�k�ߔԍ��l�l
�Ȃ��閾���̐����Q�̓t�B�����̂悤��
�D�F�ɒ���ł���̂�
�k�P�i�i�V�j���Q�R�u�߂����̂̐��������v�̏H�l
�����������N�̍��̂�����܂�
�����g��������
�k�P�����Q�R���l���͊C�݂ɏo������
���o�́s��t�k��o���l1974�N10�����k11��10���l�ꔪ�`���y�[�W�A�{���܍��A�L17�s1�i�g�A28�s�B
�����������N�̊G�̎���
�q�a�߂鏭���r
�Ƃ����̂�����
�킽�������̊G��
�����o������
�����ɔ�߂�ꂽ�k�P�́��Q�R���l�����o������
�u�ƂĂ��d��Ȃ��Ƃ��v
�ƍl����
�p�Z���̗̗t��
���̒[�ɂ��킦��
�����玟�ւ�
�����ȕ~���̓����͗l�̏��
���т͂˂Ă䂭
�u�����͂˂Ɏ��̂ł���v
�Ƃ����̂�
�ƒ{���l�̕�����
�������ł�
�u�Q��̋r�̂܂��ɑ���������v
�����ǂɔ��������f��
�e�[�u���̏�ŃL�m�R��
�������ς�H�ׂĂ���Ƒ���
�킽���͑z������
�₪�Ė���������
�����̋���ȉ��̂Ȃ���
�閾��������
���ꂩ��ؘm��
�H�ׂ�n���������
�X���R�Ԃ̏��
�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1974�N12���Վ��������k6��15���l�l�Z�`�܈�y�[�W�A�{��10�|26�s1�i�g�A5��89�s�B
�@�@�@�P
�u�ߐ[�����͉j�����p���܂������Ă���v
����͕a�l�̂��킲�Ƃ�
�����̉j��
�C�Ƃ͔Ď��R�I��
���ׂĂ̔g�͉~�̂Ȃ���
�ԗւ̂悤�ɉ���Ă���
�]���̊Ԃ̃n�[�g�̂悤��
���̏�̗��̂悤��
���܂��M���V�A�̖�͉͂���
�D������]�܂��
�����I�ȗ��n��
�Ȃ��f�R�Ɉ�̃����S���P������
��������k�P�遨�Q�R���l�u��n�̎��v���݂�
�@�@�@�Q
�҂������̂Ƃǂ낭
�����̓s�s�l�X�͏W�܂�
�T���S�⍻������
�Ƃ��ɂ͔����j�I��
����⎀�ɕ���I�Ԃ�
�������߂�҂ƂƂ���
�u������͒n�ɑ�������v
�Ƃ����̂ɂȂ���
�l�͓��ɑ�������
�ƂĂ��Ȃ��傫�ȁq�E���{���X�ցr��
�s�p�ӂɂ��Y��
�ꖇ�̌��ɕ�܂��
�����́q���z���m�]���l���V���^�[���n�r����
�����ɂ͐Ԃ��O���X���݂��т�
�u�������������t�����Ȃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�����������ċz�𑽂��v
�l�͐�����ׂ���
�@�@�@�R
�u�Z�C�̉����ʂ�]��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l��ň�������
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�m�}�b�g�ɉ���v
���ꂱ���{���ə����鐸�_�Ȃ̂�
���ꂩ�瓮�����ʂ�����
�Əo�l
���̓����i�g���@��p���Ɓ@���̎��Á@���ځ@�ق���j
�Ȃǂł��邩��
���������v�[���Ō�����
�����̔����̐K
�����T�L�F�̒��̂Ƃ�
�Ă̏I���
�u�]���l���V���^�[���̑剉���������Ă���v
�l��@�ו����^�������
�l��@����^��
�l��@�S���^��
�@�@�@�S
��Ƃ������邽�߂ɂ�
�u�l�̐�̒n�сv���K�v��
�u�Ȃɂ䂦�Ƀe�[�u���ɂ͎l�̋r
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�n�Ɏl�̋r�v
�Ɩ₤���Ƃ͖`����
�킽���̕��
�l�̓��[������
�������q��������{������
���̒��
�T�{�e�����͔|����
�i�Ԃ��������Q��̂��́@�������̂悤�ȉ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�~���q�̋G�߁j
���̏�̘I
������ĂтȂ���
�u�n��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�����ĊC��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�V�L�^��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�B�����鏗�v
���̂������Ԃ̗̈�ł�
�K�Ɗ�̋�������
�̑�Ȃ����
�`����̕����S����
�u���E�ɂ͎G���Ƃ킽���Ƃ��Ԃ�v
�������݂��Ȃ��̂�����
�@�@�@�T
���̍�������
��҂ŏ��y�Ǝt�������Ă���
�q�L�K�G����j�݂킯��
�u���S���鍰�v�͋C����
�~�̒n�����z��
�p�Ȃ���p����o�q����
�D�Ɂu���̍����v���͂��܂��
���ɂɂ͓e�̐_
�X�ɂ͂߂��������C�I��
�͂邩�ɏ����͉e�G�̂悤�Ɍ���
�����݂͊𗣂��
俐F�̒����Ă���
�����Ȃ鉘���̏��
�D�Ȃ�₪�Ē��ނ��낤
�\���҃]���l���V���^�[���͊肤��
�F���M�Ŏ��ɕ`���ꂽ�G�Ȃ��
���݂₩��
�Y�p����邱�Ƃ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P���@�]���l���V���^�[���́u�����ҁv�Ɓ^������ْ[�̘V�l��ƁB�J�b�R�́^���̈��p��́A���W����ژ^���^�p�����B���Q���]���l���V���^�[���́u�����ҁv�Ƃ�����ْ[�̘V�l��ƁB�^���p��́A���W����ژ^���ؗp�����B���R���]���l���V���^�[���́u�����ҁv�Ƃ�����ْ[�́^�V�l��ƁB���p��́A���W����ژ^���ؗp�����B�i�^�����s�ӏ��j�l
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1975�N1�����k18��1���l��Z�`���y�[�W�A�{��9�|25�s1�i�g�A41�s�B
�@�@�@�@����r�q�̉�������q�T�C�������m���₯�n�r�Ɋ�
�����̎R�̐��k��
���̂��炾�͋̂悤�ɈÂ�
�����̕��Ƃ��ꂿ����
�Ƃ��Ɏ�����q����
��e�͂����p��������
�����Ă䂭�悤��
�₽�������̉�����
���o��ƌ��������o�����
���̂ق��������̂���
���C
����
�艱�����j
�ȉَq
����߂ē���I�Ȗ��������]����
���ʂ��ꂷ���
�Ԏ���s�@�͂Ƃǂ܂�
��̕S���͔��Ă���
�ł̋u��
�̂ڂ�Ⴂ�����������Ƃ�����
��҂̔���������������
�q�Ҍ��s�\�r�Ȍ��t�����߂Ă���悤��
���@�̐ΊK�̉���
���g�͉��ꂽ�m�ŕ�����
���������
�悱��������
��ɂ�����ꂽ�݂�
�l�͂����l�Ƃ��ꂿ����
�����̂����炬��
���͂����ΐ^�g�̉��Ƒ�������
�ʗ��̓��X
�q���r�߂��T�C�����͖�Ђт�
���Ђ̐��E�Ƃ�
�i�����̏I��̔�g�ł͂Ȃ��̂�
���͂������ɂ���ĉ��
���ꂽ�ł̂Ȃ���
�Ⴂ�����@�ق��ʂ���������Ƃ�
���̂͂ق�с@��́q�͑��r�Ɋ҂�
�T�[�����s���N
�T�C�����g
���̔�
�����Ől�͊���Ƃ������Ƃ��k�P�k�S�p�A�L�l���т��������݁��Q�R�i�g���j�l��
���o�́s�V���t�k�����Ёl1975�N7�����k22��7���l�ܔ��`�Z��y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A6��72�s�A�\���Ɂu���@�g�����@����ȉĂ̗��v�Ƃ���B
�@�@�@�P
�M���o�[�g���݂͑P�ǂ�����
���v�̗����������Ȃ���
�݂�I����꒚�������Ƃ�o����
���֏o��
�@�@�@�Q
�킽���͗F�l������
�M���o�[�g���݂̍D���ȏ퓅������p����
�u�l�Ԃ̑̂͂���߂ēʉ�������v
�����Ă������̎��͂�
���݂͉��Â��Ă���
�h�����J���̃{�f�[���v��悤��
�����ɂȂ���
�M���o�[�g���݂�
�[���̊X����k�P�i�i�V�j���Q�R���Ă�l��
�@�@�@�R
���X�O���[���̔ޕ���
�z�Ղ̉ԍ炭���ƕ�𗧂�����
�M���o�[�g���݂�
����ƃ_�C�������h�̓s�s����
�Ǖ����ꂽ�̂�
����͂܂��
�u���ɉ^��Ă䂭���v
�̂悤�Ɏ��R�Ȃ��ƂȂ̂�
�M���o�[�g���݂̊Ⴉ��
�܂̂����ɉ��F���������o��
�����͂ǂ����H
�u�i���ɓD�܂݂�̎R�r�̑��v
�̍���
�}�b�`������Ƒ傫�Ȑ�������
�@�@�@�S
�u�����̂ɍ����Ă��Ȃ�
�Ǝ�̂܂��ɓ˂��ς���
�����o��v
������M���o�[�g���݂�
���ɂ����������m�̐���������͉̂��肾
�z�Ǝ葫��
�u�ǂ��炪�����@�ǂ��炪�Z�����v
���܂ł��l����
�ЂȂ����̍炭
�쌴�ɍ�����
�@�@�@�T
�d���E�l�̎d���ɂ�
�����I�Ȗʂ����Ԃ�ɂ���
�u���͂ǂ��Ő������ނ̂��H�v
�M���o�[�g���݂͂���Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���
���_�[�X�̐j�����ɂ��킦��
���ꂩ��Â��d������
����ȕz�n�����ŃW���L�W���L�ْf����
���̑e���ѐD���̉���
����������������
�ӎ�����▶
�������͓��̂�����
�M���o�[�g���݂̃f�b�T���͐��m��
�������ĂĘr�⋹�̐����Ȃ���
�������ɑڂ̂Ƃ���Ńe�[�v��\��
�Ă̓�����̒��
�܂�Ő��H�ו��̂悤��
���C���o��
����������
�@�@�@�U
�킽���͗F�l������
�M���o�[�g���݂̎d���̎d�����݂Ƃǂ���
�u�肫���܂ꂽ
���E
�z�n�̐،��Ɛ،���D������
�ł��邾������ɂ��Ă̂���
�ړI������
����ł���݂���Ȃ����̂��˂��ς��ďo����
�J�i�e�R�Œ@��
�т�т炵���]���Ȃ��̂�
�Ђœ\�����
���R����͓������B����
�����Ȍ`��
�n�����܂ł��肠����
������菇�悭�G�炵��
���n���Ђ��ς�Ȃ���
�M���A�C�������܂�ׂ�Ȃ�������v
���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N9�����k7��8���l��Z�l�`��Z���y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A5��79�s�B
�g����1975�N8��31���t�̉i�c�k�߈����ȂŁu�ҏ��̉Ă������ŏI��\���̔����̍Ō�̖�A����Ƃ��Ԏ����o����悤�ɂȂ�܂����B�V��W�s��ʁt���ꑁ���A�n�ӈ�l�N��ʂ��Ē����Ȃ���A�����\�グ���ɂ������Ƃ�[������ђv���܂��B���x���̂���A�����C�J�㌎���q�a�F�\���[�g�s�A�̐��_�r�Ƃ������W���̌����������Ă��܂����B�����ċ������S�g�����Ղ��Ă�������ł��v�Ə����Ă���B
�@�@�@�@�F�V���F�̃~�N���R�X���X
�@�@�@�P
�u�����͏�������
�͂��Ȃ���������ǂ�
������x�Ǝp�����킵�͂��Ȃ�����
�����ďo�Ă���
�₢�Ȃ�
�����͂������܌`�Ԃ�
�Ȃ������v
����͂Ƃ�킯���J�̂͂�������
�킽���͊ϔO�Ǝ��݂�
�˂Ɉ�v����
�q�̂Ƃ��Ă̏��������߂Ă����
���̓����ɂ͂����ΖȂ��߂��Ă���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�f���^�̓D�y�̂Ȃ���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�Ԃ��炩����Ƃ���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�傢�Ȃ錴���̔��@�m���[�^�X�n�v
�����͌��t�傷�邱�Ƃ��Ȃ�
�@�@�@�Q
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�킽���͗c�N����@�����[�E�~���N�Ƃ����~���N��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�k�P�Q㣁��R�ʁl�̃��b�e���Ɂ@���̎q�������[�E�~���N�́k�P�Q㣁��R�ʁl����k�P�i�i�V�j���Q�R���l
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�k�P�����Q�R�i�g���j�l�Ă���p�̕`����Ă���v
���́k�P�Q㣁��R�ʁl������Ă��鉮�~�̏��̎q�߂Ȃ���
�킽���͐��vጂɜ���Ă���
�ǂ�₳�₦��ǂ����̂Ȃ�
�c�ɂ̓��X
�̑����鏭���̂͂邩�Ȃ鎋�_��
�킽�����⏬��
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�����ƐA���̒��ԂɈʒu����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�L�k�⍜��X�蒎�v
�����ΊD���̐��E��
�ʉߋV�������݂�
�@�@�@�R
���t���������
�_�b��������Ƃ��������܂�
�߂������̂�
��C����
�u�����{�X�̗�v
�킽���̒����ł�
�u�����{�X�Ȃ���̂̎��̂��@�܂�ʼn_������
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�悤�ɂ����܂������Ƃ��ā@���Â����������v
�킽���̍D���Ȗ��֕�d���铹��
�����u���I
�u�A�p�b�`���̃V���[�}���́@�����{�X����]���k�P�i�i�V�j���Q�R���āl
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�k�P���ā��Q�R�i�g���j�l�s���g�ɂȂ�����@������\������v
��������
�����ɂ͎�ق����Y���Ȃ�
�u�����{�X�Ƃ́k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�i�x�^�j�l�q���̊ߋ�ȊO�̉����ł��Ȃ��v
�f�p�ȚX�萺���Ă���
�u���̓Ɗy�v
�����m��Ȃ�
�@�@�@�S
�킽���̖��݂铮���ނƂ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�s�����m�t�G�j�c�N�X�n�@��p�b�m�E�j�R���j�X�n�@���厁m�T���}���h���n�v
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�Ƃ��ɒ��d������̂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�t�b�v���v
�k�P�킽�������̑ΏۂƂȂ蓾�Ȃ����́��Q�R�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�Ɩ��Ȃ���l
�k�P��������V�g�܂ł̂����鑶�݂Ɂ��Q�R�����̂Ȃ��Łl
�k�P�ϐg����\���������Q�R�n���̐�����������l
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�t�b�v���v
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u������̕��̂̑��ւƋ߂Â���v
�}�������
�T�b�^�̓���q�𑽐����܂���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�t�b�v���v
��x��������Ƃɂ��Ă͓�x��邱�Ƃ͂Ȃ�
��x�s�Ȃ������Ƃɂ��Ă͓�x�s�Ȃ����Ƃ͂Ȃ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�t�b�v���͕꒹�����ʂ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���̎r�̂̏�ɂ̂���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�����̏ꏊ��T�����߂�v
�̂Ȃ���
���̂Ȃ���
���͓y�̂Ȃ����\�\
�@�@�@�T
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�l�Ԃ̑z���͂́@���镨�̂����̑傫���̂܂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���܂��Ă��邱�ƂɁ@�������Ȃ����̂̂悤�ł���v
����Ɠ�����
�D���̖ڂ��g�債
�������k��������
�킽�������l�ނƂ������̂�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�u�ŏ��̎��v����
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�ŏ��̃Z�R���h����яo���Ĉȗ�
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l����܂Ő_���s�N�ƍl�����Ă���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���R�̎���
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l�_�̎��Ԃ����ɐ₦
�k�P�i�ꉺ�j���Q�R�i�V�c�L�j�l���͂��x�ƕ������邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����e�j�������v�̂���
���o�́s���t�k���{��ʌ��Ёl1975�N9�����k49��10���l��Z�Z�y�[�W�k�Ό��̓�Z��y�[�W�͌�o�J���[�ʐ^�l�A�{��20��1�i�g�A15�s�A�u�����̈ĎR�q�@'74�u���v�ʐ^�R���e�X�g���I��i�@�J�����@�͌����O�v�B
�V�W�~�̉��̏o��
���c�̎��k�P�����Q�R�́l����Ă͐���
�j�Ə��̉���������
�u������������Ă���ҁv
�̐��ޏ��ł�
���̌Q��������ς�
�r㼂̂悤�ȎR�̕��ւ䂭
�u�ċ�
�@���̎ς�
��сv
�̐H���͏I��
���݂�ׂ��l�݂͂Ȃւ��ܒI�̉��ɏW��
���̑����ł͌���ƂƂ���
�ډB���̛����̂Ȃ���
�Ԃ�V�����܂��
���o�́s�����t�k����ь牮�l1976�N5���k�t�E1���l��`�Z�y�[�W�A�{���͋����V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A12�|15�s1�i�g�A6��53�s�B�����̋����g�p�ƂЂ炪�Ȃ̝X�����̕����g�p�́A���̌f�ڎ��т����Ă��s�����t���̕ҏW���j���ƍl������̂ŁA��A�́k�P�i�����j���Q�R�i�V���j�l�Ɓk�P�i�X�����̕����j���Q�R�i�X�����̏����j�l�͖{�Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������B
�@�@�@�P
���▨�I�̂悤��
��������
�킽���͏��N����������
�����̕��ʂ�������
�䂭�L�c�l�Ǝ�l�ɉ��������l�������悤��
���ӂ̉Ԃ͕W�I�̂悤�ɂ��̂̂�
���N�̓����͔G���
�t�͂�����̔삦����̑����G��
�@�@�@�Q
�u�킽���̓����Ȍo���̒����Ɂv
�����ł͉�Ԃ��ʔK�₶�Ⴊ�����̂�����
���u�h�E�̖[�����
���̖������
������̂��ׂĂ������
�n�K�֍~��Ă���
�ϔO�̑�j���������
�@�@�@�R
���R�͂�����ł���
���N�̂����Ȉł̂Ȃ��ɂ�
���̂悤�Ȃ���
���`�̂悤�Ȃ���
����炪���݂���
�u�j���̐ؒf�ʂ��琶����b�U�ǁv
���̂�ɂ���
�_�v�̖�������
�킽���͔M���n�̕��𗁂т�
�@�@�@�S
���̂Ȃ��Ő�������
�Ղ�����悤��
���N�͋T�b�̂̂Ȃ���
���X��������
���������܂Ȃ�
�璹�Ƃ�������
�}�Ă̂Ȃ��ɂ����Ă�ł��Ȃ�
�O�͂Ђ܂��̉Ԃ̌X���Ă��I��
�@�@�@�T
�o����@���݂�͂ǂ�����
���ō\������Ă���̂�
���ł�
�u�킽���̍��͏��̍��ɓ���
���̌�����X�~�����炭�v
�Z���@���݂��
����X�~�����Ă��ق�ڂ�
�@�@�@�U
��̂Ȃ��Ő����肠��
�������͑��z���肠����
����_������悤�Ɏv��ꂽ
��I�̉���
�V�R���R�̂��̂�
�l�X�͑���������`�����Ƃ����ł��Ȃ�
�������N�k�P�́��Q�R��l�T�k�P�����Q�R���l
�������̔ޕ���
�Ƃ������̉ʎ����k�P�c�c���Q�R�\�\�l
�k�P���������ł́��Q�R�i�g���j�l
�������̂������Â��Ă���
�u��Ȗ�Ȑl�Ԃ��Β��ɓ����
���̎����ׂ��������Ă��������Ƃ���v
���������t�̖�������
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1975�N12���Վ��������k7��12���l��Z�`��܃y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A�X��90�s�B
�@�@�@�@�k�������h�s����t�̈�ێ���
�@�@�@�T
���łɏH
���]�Ԃ̃`���[�u�̂悤�Ȃ��̂�
�S�g��������
�J�̂Ȃ��ɗ�����
�n�����邶�Ɏ₵��
�m�ƓD�Ő����������E��
�J���ꂽ�����݂�
����b�̍��Ђ�
�l�X���B�����邽�߂ɓ������ꂽ
���ꂽ������
��������ӂ肩������
�ٓ��̂��炭���
�������Ȃ���
��������Ă���҂�����
��Œ@���ꂽ���͂͊זv����
����
�
�B�̕�͂Ȃт�
�܂�ŃS���̕`��
�g���̔����N���o������
�n�ɓ��͈��
�q����m�C�X�g���[���n�r�̂͂��܂�
�@�@�@�U
�����̒��
���������܂�
�����Ă薾�H����������
���̉֎q����߂�����
�Q����b��`������
���낤�낷�邠�܂��̎q������
�u�����ɉe�𗎂���
�����v�v
�����ɂ����̉Ԃ�����
������q�ɂ����܂��
����d��
���������̐���������
�V���[�}���͖k���u����
�͂���̑����̎R��
����ߐ�͍~��
�l�X�͍��h��̎������
�ΑŐ�ł����킹�Ă�
�Ύ�����
���̂��������
�������m�A�}���K���n�̈ł̂Ȃ����\�\
�@�@�@�V
���t�`�������鎕���̓�������
�@�@�@��
���R�[���܂����ʂ������B
�@�@�@��
���a���l���ɂȂ���R������
�@�@�@��
�Ⴈ��ȏo�n�R�����B������
�@�@�@��
�r�_��{���M�߂���
�@�@�@��
�����ԉΉ���Ȃ�����ꂯ��
�@�@�@��
�����т̎����������䂭��킪�ނ���
�@�@�@�W
����{�������@�߂��q�̂ӂ����
��̖쌴�����܂悢�䂭
���q�̌ܐl�̎p�������邩
������̂悤��
���̗t�Ŏ������ꂽ�܂܋���
�u�L���g�����H�ׂ����v
���͕̂�����
�d���͋ɓ_�܂ł�����
���傹��q���̍ݏ��r�͖����̂��낤���H
���͎������������L����
�������̍����N���I�\�[�g�ۂ�����
�P���ς߂Ė��
�Ђ����M�̕ӂ�������ɔ߂���
���̑����ł̐q�ːl
�i��Ɩ��̒��ԁj��
�␢�̔����N�͐錾����
�ϔO����邽�߂�
�y����
���������
�q�^�X�J�����C�a�r�֒��߂�I
�@�@�@�X
���̗��̔g��
����������̂łȂ�
�������̐��g�̒j����������
�������ꂽ�����̔g
�[���`�����
���݂֑̊ł��悹��A����
�Ԃ̍���}�@
���_�I�ȏ��͐l�`������
�u�ؖс@�n���R�@�˕��@���Ȃǂ�
�`���������
�X���@�Ƃ��ɂ̓������X��v
���݂����Ƃ��K�v�Ƃ���
����ȓ������������@�葫���Ƃ肩��
�����̉�ł͍s��ꂽ
�p�������q�̈Â��Ћ��ł�
�q����m�C�X�g���[���n�r�̏I��\�\
���܂�@��������
����������N��
�`���[�u�̔n�͓���̂܂܂ł���
�������ꂽ����
�������m�A�}���K���n�Ƃ��čĂі��v����
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1975�N11�����k14��11���l���l�`��O��y�[�W�A�{��9�|23�s1�i�g�A7��145�s�B���o�u�{���J�b�g�^�g���p�Y�v�B
�g����1975�N8��31���t�̉i�c�k�߈����ȂŁu�k�c�c�l�ߓ��A�q�Ս��r�O�S���L�O���֎��M����Ƃ̑��B�̎莆���Ȃ���A�����܂Ŗ����ȕԎ����o���������Ă���܂����B����́A���e���O�Y�s���Ǝ��_�t����̒�����������Ƃ������肠�킹������̂ł��B���̍\�z���o�����A�܂��\�ܖ��Ƃ����������܂�ď��߂ĂƂ������ׂ������ɁA�������남�낵�Ă���Ƃ���ł��B���̏�A�^��邭�i��������łɓ�J���O�Ɉ˗����ꂽ���́j���镶�|���ɒ������������˂Ȃ�܂���B�����́A������e����������ƁA�ǂ����Ă��C���U���Ă��܂��䂫�܂���v�Ə����Ă���B
�@�@�@�P
���Ȃ闷�Ƃ͕��̉�H���߂���
���̂������߂���]����
�˂�����炵�̖铹���s��
�u�ڊo�߂Ė��݂�l�v
�E���܂̏L���X�̓��X
���҂͋���ɂ͂��݂�
���҂̓T���O���X�������ċx������
�o�C�I�����`�̏������߂�
������҂͂Ƃ��ɏ��N�̂悤��
�]�|����
���m�g���c�v�n�@���V��ԁm�g���c�v�n
��������̂�����@�����Ȃ����̂�����
����������̂�����
���̒��Ԃɕ�����̂�����
�]�|���铹���t
�]�|����t���X�R
�]�|���錾��
�]�|���錚�z��
���ׂĉߏ�Ȃ���
��s�̃A�l���l�̂ق���
�@�@�@�Q
�D�P��͂����̂悤��
�ˑR����Ă���ߌ��̐��퐫
�u���v�̔畆�������ꂵ�߂���
���Ɂu���v�̗�����~�߂�
�����̘p�ɟ���
��̗�������
�����������݂̊j������ۂɂȂ���
��̐l��
��̉��~�ւ̂˂����Ƃ�
�������Ă����₭
���ɂ������悢�q��S
������҂͓��@�ق�E���Ŗ��邾�낤��
�J�ɂʂ�đ邪�Ƃ�
�@�@�@�R
�u���i
����͂��鍰��
��Ԃł���v
������҂̒n���
���܂�c����̂Ƃ�������
����܂߂̉Ԃ�
�̂ɂ����ۂ���܂铯�ʂ̈ł���
���ꂷ��t���[��
����k������t���[���@�t���[��
�t���[���̓����ɗ}������
�u���̓��̂̓V�R�̕x�͎���ꂽ�v
�����炩��
�A���~�j���E���ƃK���X�̔햌�Â����
�����̂̓V�䂩��
�������͂��߂��Ԃ������͕��V����
�{�H�l�͋����@��t������
������҂݂͂������
�����`�̍��̂����߂ĕ���
�݂��т��̌������ւ������܂��
�q�[�X�̑��ނ��ʂ�
�Y�^�̒r���߂���@�����̂悤��
���^�̉Ԓd���߂���@�␅�̂悤��
�����Ă����̗�����҂�
�|�����ɉ���
���ӂ�Ő��̌͂ꂽ����
�튯�m�I���K���n�̂��Ƃ�
��������������
�u�����̏�ɂ����Ȃ��v
�@�@�@�S
�u���R�Ɛ��_�̂����܂��ȋ��E�Ɉʒu����
�c���Ƃ������݂ɂ�
��������V�g�܂ł�
�����鑶�݂ɕϐg������\��������v
����ꂪ�m���Ă���
�אl�̗c���͂��炩���葫������
��������@�A���Ȃ����Ă���
���������̎����Ƃ��Ă�
�����܂��܂������u�c���v�͕Y�������݂Ă���̂�
���I�Ȑ퓬���o����
���łȉƂ̃x�b�h�֖߂��Ă���
�u�c���v�͎o���ɂ݂Ƃ���
�S�y�̂̂���ڂ��ɉ���
���͒n�������������މp�Y�ɂȂ�
�@�@�@�T
����ꂪ�u�A�h�j�X�v�ƌď̂��Ă�����̂�
���Ƃ̎Y���ɂ����Ȃ�
���������I�Ȑ����������
����ꗷ����҂̑�����݂�
���e�̂������Ƃ�
�`����ƂƂ̂��Ă��閲�́u�A�h�j�X�v�̂ЂƂ�
�������͕�e�̖D���Ă��邤�Ԃ��ɕ�܂ꂽ
�e�̂����ނ�
�[���j��
����ꂪ�u���B�[�i�X�v�ƌď̂��Ă�����̂�
���Ƃ̍��p�ɂ����Ȃ�
�H�̖�͔Җ_��̋r
��q��̔w������̂���
�֎q�ɍ�����
������҂͍l����
�@�@�@�U
������
�߂Â��Ă���
�@�B���ώ����d�|���Ă���
���ڂ����C���̊ǂ����̋@�B�͏������ɂʂ�
�n�C�X�s�[�h�ő@�ۂ�a��
�����ĉԖ͗l���������ƐD��Ȃ���
��C����̕��̂���
����͐��l�p�̖ؔ�
�Ƃ�����������
�܂��͒e�͂���^�C��
�Ǝv�����̎肴��肪����
��I�ȕ��͋C��
��e���̂������߂Αَ����m�F�ł��邩������Ȃ�
�����ƌ�����ւ���
���܂݂�̊点������̗F
������҂̊፷���ɂ�
���V�т̂��Ƃ̏��������z�����
�C�i���i
�C�V���^��
�����̐��E�ɉ��̂�
���ɂ����̒n��_��
�ӁI
�@�@�@�V
�u�p�������w���̂悤�Ȋ����g����
���̂ق����炽��˂�ɋl�ߍ���
���_�������v
�푰�̏Z�ޏ������߂�
���������X�͒n�тɓ�����
�����̒T���̏I�肩�������
������҂͌������邾�낤
�A�t���f�B�[�e�[�̉��g����
�����鏗�_����
�u�K���X�̕ǂɂւ��Ă��Ă���
���o�i���E�j�v�̔ޕ�
�����q�Ꮧ���f�B�j�r���o������
�@
�@�w��������������
�@�Ȃ̓������m�n�g�n�̂��Ƃ�
�@�Ȃ̕��݂͂����˂��锞�̂܂����k�P�k���s���ēl���Q�R�i�ǂ����݁j�l
�@�@�S���Ԃ����Ă����߂邪���Ƃ�
�@�Ȃ���͏ۉ�̂₮��̂��Ƃ�
�@�Ȃ̐O�͐Ξւ̔��ЂɎ�����
�@�Ȃ̔��@�̖т͕����̂��Ƃ�
�@�Ȃ̐g�̏�͞��L�̎��ɓ�����
�@�����̑�Ȃ邩�ȁx
�@
�C�i���i�@�C�V���^���@���B�[�i�X
���̐��̍�������
��̖A���͂���
���Ȃ�X�̏��̏��
��j�Ɓq�Ꮧ���f�B�j�r�̍������s��ꂽ
����F�̕s��`�̂��̂̂܂��킢�Ƃ�
���������������������������
�����𗁂т�����
���������Ă䂫
���ȓ��ꐫ�𐬏A����
�u�����͖{���Ɏ��Ȃ̐g�̂̂Ȃ��Ɏ��܂���
����̂��낤���H�v
������҂͂킪�S�ɖ₤
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�P1975�E9�E22���Q�R�i�g���j�l
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�Z�قł��P���o���Q�P�s���W�E�R�S���W�̔�r�ΏƂɏI�n�������A�P�s���W�E�S���W���q���C�X�E�L��������T�����@�r�̖{���ɂ͍Z�����ׂ�����4�ӏ�������̂ŁA�ȉ��Ɍf����B�܂��k�����`���l�T�̑�1�ߏ��o�`�����l�߁i25���j�ǂ���ɍČ�����B
�h�b�O�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�A�����G�b
�^�@�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@��
��Q���̂Ȃ��͊��L�O��
����ɏC�������������߁A�P�s���W�E�S���W�i������25���l�j�Ƃ��A���̂悤�ɂȂ��Ă���B
�h�W�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�w�����G�b�^
�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@����Q
���̂Ȃ��͊��L�O��
����̈Ӗ����炢���Ă��C���[�W���炢���Ă��A�u�w�����G�b�^�v�̂��Ƃ́i���Ƃ��Ƃ������j�S�p�A�L���������킯�ɂ͂����Ȃ��B�܂肱����
�h�W�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�w�����G�b�^
�@�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@����
�Q���̂Ȃ��͊��L�O��
�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�s���̑S�p�A�L�͏ȗ������A�Ƃ������͐��藧���Ȃ��B�P�s���W�E�S���W�́q�^�R�r��2�߂̎U�����^�i25���l�j�ɁA�S�p�A�L���s���ɗ��Ă��鏈��2�ӏ����邩��ł���B�Ȃ��A�s���̑S�p�A�L�����������@�Ƃ��āA�O�̍s�Ŏ��Ԃ�������1��������Ƃ����g�ł̒������@�����邪�A�s�T�t�����E�݁t�ł͍̂��Ă��Ȃ��B����ɍZ�����K�v�ȕʂ̃p�^�[��������̂ŋ����悤�B�������k�����`���l�U�̌㔼�A���o�`��r����������B
�k�c�c�l�~���G�X�̖����A���@�N�����{�k����i�Ղ̖�
�_�C���t�i�E�G���X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��Ă����̂͒N�H�@����x�߂�
���̕��������A���N�T���h���E�L�b�`������@���Ƃ���
�N�V�C�[�@���������݂ɍs���ā@�ŏ��Ɍ����̂͂Ȃ��
�́H�@���̋�����Ƃ��@�M�𑆂��_�v�@����߂����
�̉��̖ԁ@�������Ă�@�x�߂̃E�O�C�X�͂ǂ�Ȗ���
�����邩�H�@�y���V���͗l�̔��̔��̏�Ł@���݂�N
�V�C�[��@��̂قƂ�Ł@�Ō�Ɍ������̂͂Ȃ�Ȃ́H
�@���Ȃ����g�̓��́@���̉e�ɐS������悤�Ł@�Ȃ���
���Ɍ�����@�Ȃ܂߂��������c�������H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂�Ȃł���
����L���������������T���̂�@����͕�тŊ�����
���H��Q�̂Ȃ��Ł@�����ԑ����������l����I
html�t�@�C���̉��g�\���ł킩��ɂ�����A�e�L�X�g�t�@�C���ɕϊ����ďc�g�\���ɂ���Ƃ͂����肷��̂����A�u�x��Ă����̂͒N�H�v�̏�̃A�L�́u��Z���v�Ƃ����Œ�l�ł͂Ȃ��B�O�s�́u�_�C���t�i�E�G���X�v�{�i�S�p�A�L�j�{�i���s�k��萳�m�ɂ́A1�s���p����i�߂邱�Ƃ��Ӗ�����uLF��Line Feed�v�Ƃ��Ẳ��s�l�j���鑊�ΓI�Ȉʒu�W����������ǂ݂Ƃ�Ȃ���A��i�̈Ӑ}���������Ȃ����ƂɂȂ�B���́u�Ȃ܂߂��������c�������H�v�Ɓu�݂�Ȃł��ꂩ��L���������������T���̂�v�̊Ԃ̉��s�ӏ������f�ł���B�Ō��9�s���琬��u���b�N�̏I���̂ق��A�P�s���W�E�S���W��
��̂قƂ�ōŌ�Ɍ������̂͂Ȃ�Ȃ́H�������Ȃ����g�̓���
�Ǝ���̊Ԃœ�{�A�L�ɂȂ��Ă���͇̂T�́u�w�����G�b�^�v�̏ꍇ�Ɠ��l�A�S�p�A�L�łȂ���Ȃ�Ȃ��i���o�ɂ͉��s�ӏ��������ĕ���킵�����Ƃ͕���킵�����j�B��L�́k�����`���l�U�̍Z�����ʂ��܂Ƃ߂��
�[�̖����A���@�N�����{�[������q�t�̖��f�B���t�i�E
�G���X
�@�@�@�@�x��Ă����̂͒N�H�@����x�߂̖��̕�������
�A���N�T���h���E�L�b�`������@���Ƃ��̃N�V�C�[�@��
�������݂ɍs���ā@�ŏ��Ɍ����̂͂Ȃ�Ȃ́H�@���̋�
����Ƃ��M�𑆂��_�v�@����߂����̉��̖ԁ@����
���Ă�@�x�߂̃E�O�C�X�͂ǂ�Ȗ��������邩�H�@�y
���V���͗l�̔��̔��̏�Ł@���݂�N�V�C�[��@���
�قƂ�ōŌ�Ɍ������̂͂Ȃ�Ȃ́H�@���Ȃ����g�̓�
�́@���̉e�ɐS������悤�Ł@�Ȃ��悤�Ɍ�����@�Ȃ�
�߂��������c�������H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂�Ȃł��ꂩ��L����������
�����T���̂�@����͕�тŊ����ꂽ�H��Q�̂Ȃ���
�@�����ԑ����������l����I
�ƂȂ�B�q���C�X�E�L��������T�����@�r�́k�����`���l�̔@���4�ӏ��́A����ׂ��s�g�����S�W�t�ɂ��̎��сi�g�������̂Ȃ��ŋ��w�̌���ł���j�����^����ۂɂ́A���Ў��M���̎��݂��������`�ɉ��߂Ă��炢�����B
�k�t�L�l
�{���W�̒P�s�{�̊����i���t�Ό��y�[�W�j�Ɍf�ڂ���Ă���q���o�����ꗗ�r�ɂ́A�c�O�Ȃ��炢������肪����B���łɊe���т̖{���O�ɏڍׂȏ��o�L�^���f�����̂ŁA�����ł́q���o�����ꗗ�r�ƌ��T���Z���������ʂ�{���̍Z�قƓ��l�̏����ŋL���A��L�E��A�𐳂��Ă������B
| �����o�����ꗗ | |
| �T�t�����E�� | �u���㎍�蒟�v1973. 7. |
| �^�R | �u�����C�J�v1972. �k11��10�l�@�Ց� |
| �q���V���X���͐��� | �u���i�v1972.�k7��6�l. |
| �t | �u�����C�J�v1972. 4. |
| �}�_���k�i�i�V�j���E�l���C���̎q�� | �u�����C�J�v1973. 1. |
| ����ȓ~�̗� | �u�������_�v1972. 7. |
| �s�N�j�b�N | �u�|�p�����v1973. 7. |
| ������܌�b�� | �u���p�蒟�v1973. 2. |
| �킪�Ƃ̋L�O�ʐ^ | �u���w�E�v1973. 11. |
| ���a | �u�ǔ��V���v1974. 3.�k�i�i�V�j��24.�l |
| ���C�X�E�L��������T�����@ | �u�k�i�i�V�j���ʍ��l���㎍�蒟�v1972.6�@�k�Ց����i�g���j�l |
| �k�i�i�V�j���w�l�A���X�k�i�i�V�j���x�l��k�i�i�V�j����l | �w�A���X�̊G�{�x1973. 5�@�q�_�� |
| ����̔ӎ` | �u���㎍�蒟�v1974. 4. |
| �c�� | �u�����C�J�v1973. 9. |
| ���]�Ԃ̏�̔L | �u�����O�j�W�v�p���t���b�g�@1974. 4. |
| �s�ł̌`�� | �u�ʍ������V���v1974. �ċG�� |
| �t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L | �u�����C�J�v1973. 11. |
| �G�� | �u���i�v1974. 5. |
| �ٗ�� | �w�ٗ�Ձx1974. 4�@����R�c |
| ���� | �u�G���o��v197�k4. �H��3. 10�@1���l |
| ���f�A���E������Ƒ� | �u���|�W�]�v1974. �āk�i�i�V�j���@6���l |
| �ǎ�̏� | �u���㎍�蒟�v1974. 10�@�Ց� |
| ���� | �u��v1974. 10. |
| �]���l���V���^�[���̑D | �u�����C�J�v1974. 12�@�Ց� |
| �T�C�����g�E���邢�͍� | �u���㎍�蒟�v1975. 1. |
| ����ȉĂ̗� | �u�V���v1975. 7. |
| ���e�j | �u�����C�J�v1975. 9. |
| �J�J�V | �u���v1975. 9. |
| ���N | �u�����v1976. �t�k�i�i�V�j���@1���l |
| ���܂����� | �u�����C�J�v1975. 12�@�Ց� |
| ����ȓ��ʂ̏H�̗� | �u���|�v1975. 11. |
���\�}�̖��┭�\�N���������ƁA�����T������҂��~�X���[�h���Ă��܂��B�}�̖��̊����̐V���^�����̕ʂ��厖�Ȃ��Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ����i�����ɂ��ǂ���ۂɎx�Ⴊ�Ȃ��̂ŁA�k�t�L�l�ł͍Z�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������j�A�ސ��������Ȃ����������_�������m�ł��肽���A�Ƃ��������̔O�����߂Čf����B
�k2019�N1��31���NjL�l�����N�父�g�������ȁi1976�N4��13���t�����j�̂���
2019�N1�����߁A���t�I�N�I�ɋg�����������N��Ɉ��Ă����ȁi�����ƃn�K�L�e1�_�j���o�i���ꂽ�B�n�K�L�͋��藎�Ƃ������A�����͈킵���i3���~�������_�őނ����j�B���̕����ɂ͋g�����q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�G�E11�j�̍Z�{�������Ɉ˗��������Ƃ�������Ă����̂�����A����ł��Ȃ��͎̂c�O�������A�Ȃǂƒ��C�ɍ\����킯�ɂ͂Ȃ��B���������Ȃ肻���ɍs���܂��ɁA���m�F���Ă������B�q���C�X�E�L��������T�����@�r�̏��o�{���̐l���E�n���́A�P�s���W�Ɏ��߂���ۂɑS�ʓI�Ɍ�������Ă���B�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�ɂ����Ă�
�@�A���X�E�R���X�^���E�X�E�F�X�g�}�R�b�g�@���@�A���X�E�R���X�^���X�E�E�F�X�g�}�R�b�g
�@�킪�����A���X�E���b�f���@���@�킪�����A���X�E���f��
�@���b�f���I�@���@���f���I
�ƌy�����������A�k�����`���l�ɂ����Ă�
�@�h�b�O�\���@���@�h�W�\��
�@�A�����G�b�^�@���@�w�����G�b�^
�@�G���U�x�X�E�q���[�X�B�[�@���@�G���U�x�X�E�n�b�Z�[
�@���o�[�E�q���[�X�B�[�@���@���o�[�E�n�b�Z�[
�@�G�t�C�[�E�~���G�X�@���@�G�t�C�[�E�~���G�[
�@�}���A�E�z���C�g�@���@�}�����A�E�z���C�g
�@�}�h���[�k�E�L���T�����E�p�[�l���@���@�}�f���C���E�L���T�����E�p�[�l��
�@�����[�E�}�N�h�i���h�@���@���A���[�E�}�N�h�i���h
�@�G���E���j�A�[�E�C���A���Y�@���@�G���E���j�A�E�E�C���A���Y
�@��C�����@���@��ȍٔ���
�@�e�j�X���@���@�e�j�\��
�@�R�[�g�D�X����i�Պق̎g�p�l�̖��N���t�g�E���N�g���[�@���@�N���t�g�q�t�ق̎g�p�l�̖��@�w���́u�R�[�c�v
�@�G���U�x�X�E�q���Z�C�@���@�G���U�x�X�E�n�b�Z�[
�@�A�~�C�E�q���[�Y�@���@�G�~�C�E�q���[�Y
�@�C���[�l�@���@�A�C���[��
�@�s���[�g�j�B�[�@���@�p�g�j�[
�@�x�A�g���X�E�փ����C�@���@�x�A�g���X�E�փ����[
�@�s���b�V�[�@���@�s���[�W�[
�@�J�e�B�[�E�u���C�k�@���@�P�C�e�B�[�E�u���C��
�@�W���[���E�~���G�X�@���@�W�����E�~���[
�@�N�����{�k�@���@�N�����{�[��
�@�_�C���t�i�E�G���X�@���@�f�B���t�i�E�G���X
�Ƒ啝�ɏC������Ă���i�킩��₷���悤�Ɏ����̌��ʂ����Ă݂��j�B���o���̌��e�쐬�ɂ������ĉ����Ԃ�̐l�����J�^�J�i�\�L����ہA�O����ɕs�ē��ȋg���͌�w�Ɋ��\�Ȑg�߂Ȑl���ɗ��͂����i���ɂ͋�̓I�Ȃ���l�����z�������Ԃ��A�m���Ȃ��̂Ŏ����͋L���Ȃ��j�B���̐l�͂����炭�t�����X��̑f�{��ς��߂ł��낤�A�A���X���͂��߂Ƃ���C�M���X�l�̖��O���t�����X��ӂ��ɓǂ݂Ƃ��ăJ�^�J�i�ɂ��Ď������Ǝv�����B���o��ǂl�Ԃ��l���̕\�L�ɋ^�������ċg���ɓ`�����Ƃ���A����̓��C�X�E�L�������_���������A���Ă͕ҏW�҂������푺�G�O�ł����Ă����������Ȃ��i�g���́s�푺�G�O�̃��r�����g�X�t�̐��E���q��y�I�h���Ɖ��b�Ɓr�ŁA�u���̈�ې[���̈���̏����\�\�s�i���Z���X���l�̏ё��t���Ȃ�������A���̃A���X���т��Ȃ킿�q���C�X�E�L��������T�����@�r�����݂̂悤�Ȍ`�ŁA�܂Ƃ܂������ǂ����^�킵���B�����͂܂��A���C�X�E�L�������ւ̌��y�͂قƂ�ǂȂ��A���͎킳��̏������`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\���̗��`�q�ǂ���̏����U���ҁr���A�B��̎Q�l�����Ƃ������̂ł���v�Ə����Ă���j�B�����A�g�����q���C�X�E�L��������T�����@�r�����W�Ɏ��߂�ɂ������čZ�{���˗������̂́A�C�M���X���w�̑דl�E�����N��ł���i���o�f�ڍ��́s�ʍ����㎍�蒟�t�́A�����̑S�ʓI�ȏ����E���͂ɂ���Đ������j�A���̏؍��ƂȂ�̂����̏��Ȃ������B�����̎ʐ^���f���悤�B
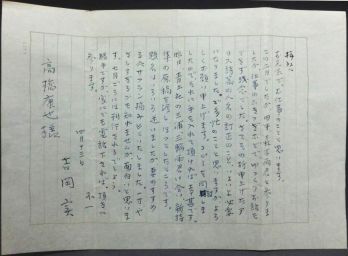
�g�����������N��Ɉ��Ă������̕��ʁi1976�N4��13���t�j�k�o�T�F���t�I�N�I�l
�O�̂��߂ɁA�g�����������N��Ɉ��Ă�1976�N4��13���t�̕����̕��ʂ��N�����Ă������B�Ȃ��A���t�I�N�I�o�i���̃^�C�g���́q�g���� �����M���M �^�M ���ȁ������N�� �����w�T�t�����E�݁x ��������܁��w�m���xH������l���A���X���� �x�P�b�g ���C�X�L�������r�ŁA���̐����ɂ́u���C�X�E�L�������A�T�~���G���E�x�P�b�g�A�V�F�C�N�X�s�A�Ȃǂ̌����Œm���A�p�����CBE�M�͂���͂����A�����N��̋����i���\�^���㎍�̂ЂƂ̓��B�_�Ƃ����w�m���x�Ȃǂ̍�i�ŁA���ō��̎��l�̈�l�ɐ�������A�g�����B�^����̂��i�́A�g�����́A���M���Ȃł��B�^�����N��ֈ��Ă�ꂽ���̂ŁA�������܂���܂��邱�ƂɂȂ�A�w�T�t�����E�݁x�̂��ƂȂǂ��L����Ă��āA�����[���ł��v�Ƃ���B
�q�[
�����C�ŁA���d���̂��ƂƎv���܂��B
���̓ł������A�c���A�X�{�_�N�ƎQ���
�������A�d���̂Ђ����ȂǂŁA������肨�b��
�ł����c�O�ł����B���Ă��̐ܐ\�グ���A
���X���т̐l���̒����̂��ƁA���悢��K�v
�ɂȂ�܂����B�����Z�̂��ƂƎv���܂����A���
�������肢�\�グ�܂��B�R�s�[������
�����̂ŁA����Ɏ�����Ē�����K�r�ł��B
����A�y�Ђ̎O�Y�A�O�֙_�N�ɉ�A�V��
�W�̌��e��n���A�ق��Ƃ����Ƃ���ł��B
�薼�͂��낢������܂������A�Ȃ̂�����
��s�T�t�����E�݁t�Ƃ������܂����B�ꐡ�A��
���������邩���m��܂��A�ʔ����Ǝv����
���B��������ɂ͊��s�����ł��傤�B
����ł����A�Ƃɂł��d�b������A������
�Q��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l���\�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g ���@��
�@�����N��l
�g�����̐��z�q�u�z���͎͂��@�z������v�r�i���o�́s���㎍�蒟�t1977�N5�����q���̖��E���̈��r�j�`���́u���鑁�t�̒��A���͏��p�������āA�߂��̍����N�炳��̉Ƃ�K�₵���B�����͔��R�Ƃ��약��Ƃ����������n���̗אڂ����ՐÂȂƂ���ł���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�j������1976�N2���̂��ƂȂ̂��킩��Ȃ����A�����Ƃ͋g���Ɠ����ڍ���t��ɂ���B���������āA��������A������������g���͎����Ȃ�k���ŖK�₵���ɈႢ�Ȃ��B�����ŁA�����̐l���ɒ����Ă����B�u�c���A�X�{�_�N�v�͒}�����[�̕ҏW�ҁA�c�������Y�E�X�{���F�Ǝv�����B�u�y�Ђ̎O�Y�A�O�֙_�N�v�́A�����s����v�z�t�ҏW���������O�Y��m�Əo�ŕ��̎O�֗����B���ʂɂ��A1976�N4��12���i���j���ł���j�Ɂs�T�t�����E�݁t�̌��e�i�����炭�z�q�v�l�������菑���̂���j���o�ŎЂ̕ҏW�S���E����S���ɓn�����̂�����A���̂Ƃ��́q���C�X�E�L��������T�����@�r�̐l����n���̕\�L�͏��o���̈�����ƂقƂ�Ǔ������������낤�B���̌�A���W�̍Z�������Z�E�čZ�Ɛi��ł���������i�K�ŁA�����̍Z�{�̐��ʂf�����Ԏ���������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�����������Ȃ��A��ɏq�ׂ��q���C�X�E�L��������T�����@�r�́k�����`���l�ʼn��߂�ׂ�4�ӏ��́A�l���E�n���̏C����Ƃɕ���āA�{������ׂ��p���牓�������Ă������̂ł͂���܂����B���W�̊��s���A�\�����ꂽ7��������ۂɏo��9�����܂ł��ꂱ�̂́A�`�����낵���˗������ЎR���̑��悪�Ȃ��Ȃ��d�オ��Ȃ��������Ƃɂ���낤���i���z�q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�Q�Ɓj�A�{���̍Z���܂ŁA�\�z�ȏ�Ɏ��Ԃ������������߂��Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B������������̗����̎�����������킹�鏑�Ȃ��A�g���������Ɉ��Ă�1976�N4��13���t�̂��̕����������̂ł���B
��
�q���C�X�E�L��������T�����@�r�̏��o����ҏW�����K���Εv�́A�����N���Ǔ������q�L�������E�L�����N�^�[�̎�����r�i����猕ҁs�v���o�͐g�Ɏc��\�\�����N��Ǒz�^�t�������_���Əo�ŁA2004�N5��30���j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�u�ʍ����㎍�蒟�v��2���u���C�X�E�L�������v���̕ҏW�ɂƂ肩�����Ă���1972�N�t�ɂڂ��͏��߂č����N�炳��ɂ�����邱�Ƃ��ł����B���l�E�g��������̂��������������߂ɂ��o��������B
�@�u���C�X�E�L�������v�̓��W���́A1969�N�A�ڂ��������u���㎍�蒟�v�̕ҏW�҂Ƃ��Ď푺�G�O����̘A�ڃG�b�Z�C�u�i���Z���X���l�̏ё��v��S�����Ă���Ƃ��A���C�X�E�L�������̎v�������Ȃ���ʂ�m���Ă���A�����͂ƔO������ɂȂ��Ă����B�₪�āu�ʍ����㎍�蒟�v�̕ҏW�Ɏ��g�ނ悤�ɂȂ�A���̑�ꍆ�Ƃ��āu�ԁv����ҏW���A����Ȃ�ɕ]���邱�Ƃ��ł����̂ŁA��Ɍ��Ẵ��C�X�E�L���������W���Ă��邱�Ƃ��ł����B
�@�E�\�̂悤�ȃz���g�̘b�Ȃ̂����A�����̓��C�X�E�L�������Ƃ����Ă��A���́w�s�v�c�̍��̃A���X�x�̍�҂ł��邱�Ƃ����A�s���Ƃ���l�����Ȃ������̂ŁA���͑�_�Ȋ���Ă������̂ł���B���l�����̂Ȃ��ł́A�ڂ����M�����Ă����A����C��������͂��߁A������������V��ޓ�Y����A��쐟�q�����ɐ��������^�����Ă�����Ă������A���傤�ǂ��̍��u���炭���������Ȃ��v�ƌ������Ă����g��������ɂ��A�ق��Ȃ�ʃA���X�ł���L������������ƁA���肢���ɍs�����B���̂Ƃ��������B�g�����Ζ����Ă����}�����[�Ń��C�X�E�L�������S�W�̊�悪�i��ł���A���̒��S�ɍ����N�炳��Ƃ����p���w�҂����邱�ƁA�Ȃ��Ȃ��̐l�Ȃ̂ň�x����đ��k���Ă݂�Ƃ����A�h�o�C�X�������������̂ł���B
�@�k�c�c�l
�@���Ȃ݂ɂ��̂Ƃ��g��������́A�u���C�X�E�L��������T�����@�v�Ƃ���������Ă��ꂽ�̂����A����̓L�������B�e�̏����ʐ^�����Ȃ���Ƃ�������̍�i�ŁA�����ЂƂ�ЂƂ�̖��O���d�v�ȈӖ��������Ă����B�����ŐT�d�������Ă���������������ɔ����ƕ\�L���m�F���A������g��������ɂ��͂������B���̎��_�ō�������́A�g����i�ɂقƂ�ǃG�L�T�C�e�B���O�Ȋ��҂�����Ă����悤�ł���B�i�����A��l�܁`��l�Z�y�[�W�j
�u�}�����[�Ői��ł������C�X�E�L�������S�W�̊��v�͓��̖ڂ��݂Ȃ������B�Ƃ͂����A1977�N12��20���A�����N��E��菇�V����Łs���C�X�E�L���������W�\�\�s�v�c�̍��̌��t�����t�\�\�`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\�����N��13�̎��ɏ�����������n�߂āA��́w�A���X�x���꤁w�X�i�[�N���x�A�w�V�����B�[�ƃu���[�m�x�Ȃǎ�v��i����q���r��E�݂Ƃ��ĕ҂ݏグ���g�s�v�c�̍��h�̃A���\���W�[�i���ɔŗ��\���j�\�\���ق��Ȃ�ʒ}������o�Ă���̂́A���ɏI������S�W�̂Ȃ���ɈႢ�Ȃ��B�Ȃ��A�O�f�g�����ȂɌ�����c�������Y�́s���C�X�E�L���������W�t���ł́A�X�{���F�͂��̏��łɁs�s�v�c�̍��̃A���X�t�̌����������A����E�����𐄝Ȃ������ɔł̒S���҂ł���i�����́q���Ƃ����r�łӂ���́u�@�m�ƔM�ӂƔE�ρv�Ɋ��ӂ�����Ă���j�B���ɔł́A�s���T�Ώ� ���C�X�E�L���������W�k�����ܕ��Ɂl�t�i1989�N4��25���j�Ƃ��āA�W���P�b�g��e���y�[�W�ɃL�������B�e�̏����̎ʐ^��Y���Ċ��s���ꂽ�B����́A�q���C�X�E�L��������T�����@�r�̏��o�ŁA�L�������̎ʐ^���ނɎ��ƃ����^�[�W���݂̂Ȃ炸���C�A�E�g�܂Ŏ�|�����g�����c�������Ƃ��낤�B
��
�A���X���т��߂���g�����ƍ����N��̂��Ƃ�̂Ȃ��ōł��d�v�Ȃ̂́A�����܂ł��Ȃ������́q�g�������A���X���ɏo������Ƃ��r�i���o�́s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�A�̂������N��s�m���Z���X��S�t�A�����ЁA1977�j�ł���B���o�͂����n�܂��Ă���B�i�����A�㔪�`���y�[�W�j
�@�g�������͂܂��N�]�ɂ킽��قڊ��S�Ȓ��ق��A�ŋ߁A���т́u�A���X���v�ɂ���Ĕj�����悤�Ɍ�����i�w�ʍ����㎍�蒟��Q���x�́u���C�X�E�L��������T�����@�v����сw�A���X�̊G�{�x�́u�w�A���X�x���v�j�B���̈��ǎ҂������ĂЂ����Ɏ��C���A�����܂��ܓ����Ɂm�A�A�A�A�A�A�A�n���C�X�E�L�������ɖ������Ă����ڂ��Ƃ��ẮA���̂��Ƃ͓�d�̈Ӗ��ő傫�Ȋ�тł���A�����ł������B
�@�k�c�c�l
�@�g�����Ɓu�A���X�v�Ƃ̈����ɂ��ẮA���͂��łɕ�����Ȃ������������̂�����A�ڂ��̂������͂قƂ�Nj~���������ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v���Ђ̌��㎍���ɂ́u�g�������W�v�i���Z���j�̊����Ɏ��߂�ꂽ�����r�Y���Ƃ̑Θb�̏I��߂��ŁA�����g���،����Ă����̂��I
�@�⁁�ŋߊ��������{�́H
�@�����u�ӂ����ȍ��̃A���X�v
�����Œ��ڂ��ׂ��́u�v���Ђ̌��㎍���ɂ́u�g�������W�v�i���Z���j�v�Ƃ����o�T�̖����ł���B
�@�k�c�c�l�u�ŋߊ��������{�́w�ӂ����ȍ��̃A���X�x���v�Ƃ����A���́u�ŋ߁v�Ƃ͌����ɂ��Ȃ̂��B�c�c
�@�����Ȃ�ƁA���̂��𖾂�������̐��m�����n�̐l�ԂƂ��ẮA���̂�n��ꗬ�̐l�Ԃ����܂��āA�b��Ȃ������Ȃ��ł͂����Ȃ��Ȃ�B��N�O�p���Ńx�P�b�m�ɉ���Ď��₵���Ƃ��A�u����A�ǂ������킯�����̓L�������Ɏ䂩�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��̂ł��v�Ƃ����������Ԃ��Ă��āA�W���C�X��{���w�X�̏ꍇ���v������ׂA�u����ς�v�ƍ��_���Ȃ�����A������������i�H�j�����o��������B�g�����Ƃ̈�Ȃ��������ĉ�����Ƃ����u�����C�J�v�ҏW���̐\���o�ɁA���ǁA�ڂ��͂��̂̂��Ȃ��牞�����̂ł������B���ۂɂ́u�A���X�v�ȊO�̂����܂̘b�ɉԂ��炢�Ă��܂����̂����A�ȉ����A�e�[�v�������Ȃ���v���g�����̘b�̂����̕����ł���B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j
���̎苖�ɁA�g�����������N��Ɉ��Ă��s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA�u��㎵��N�㌎�\�ܓ���Z���v�j������i2019�N1���A�a�J�̒������X�ōw���j�B�{���ɂ́u�����N��l�@1973, 7, 24�^�g�����v�ƌ��提�������������̓u���[�u���b�N�C���N�i�o�N�ω��ŐF�����ʂ��ɂ����j�̃|�[���y���ŋL����Ă���B����1973�N7��24���i�Ηj���j�́A�u�g�����Ƃ̈�Ȃ��������ĉ�����Ƃ����u�����C�J�v�ҏW���̐\���o�ɁA���ǁA�ڂ��͂��̂̂��Ȃ��牞�����v�ʒk�̂��̓��������̂ł͂���܂����B���܁u�g���������N��Ɉ��Ă��v�Ə��������A���̖{�͋g�����������m�A�A�A�n���̂ł͂Ȃ��A���������Q������{�ɂ��肠�킹�̕M�L��ŋL�������̂Ǝv�����i�ѕM�k�M�y���l�͏����āA�g�����{�i�I�Ɍ��提������ۂɗp�����̂́A���܂��ău���[�u���b�N�C���L�̃p�[�J�[�����N�M�������j�B�����܂ŋg���̏����{�����Ȃ��炸���Ă������A�|�[���y���ɂ�邻��͏��߂Ăł���B
 �@
�@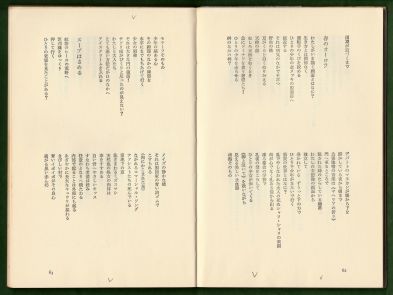
�g�����������N��Ɉ��Ă��s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA�u��㎵��N�㌎�\�ܓ���Z���v�j�̖{���i���j�Ɠ����́q�t�̃I�[�����r�̌��J���y�[�W�i�E�j
�@�����A�����ցw�A���X�x������킯�ł����A�����A�w�Â��ȉƁx�ł��u�����v������Ȃɉ�����o�Ă��܂����k���ɖ{�Ő����Ă��Z��A�ق��ɂ��u�����v��u�o�v�u���v�Ȃǂ�����l�B�����A�����G���e�B�V�Y�����c�c������A���Ƃ��ƈ����l�ԂȂȁB���l�̃X�g���b�v�͌����邯�ǁA�����̂͌����Ȃ��B��]�Ƃ�������ȁB�ւ��A�L�������͎ŋ��D���������́B�X�g���b�v����������A�����ƌ����낤�ˁB�i�����A��Z��y�[�W�j
���̌��提������̍����N�狌���{�ɂ́u�w�Â��ȉƁx�ł��u�����v������Ȃɉ�����o�Ă��܂����k���ɖ{�Ő����Ă��Z��A�ق��ɂ��u�����v��u�o�v�u���v�Ȃǂ�����l�v�ɑ�������2�i�g�̖{���̏㉺�̗��O�ɁA���M�����Łu�u�v���̃`�F�b�N���������܂�Ă���B�g���Ƃ̑Θb�̂��ƁA�u�b�̂����v�ɒ����邽�߂ɍ��������V�Ɋ��肵�����̂ɈႢ�Ȃ��B�����ɂ͂ق��ɂ���Ƃ������������݂͂Ȃ����A�q�m���r�i�C�E8�j�̕W��y�[�W�ɁA�J�i�_�E�g�����g�̏��X�̂��̂Ǝv�������V�[�g�i1990�N9��7���j������ł���B�����������x�����ɂ����̂Ȃ�A���̔N��5��31���ɖS���Ȃ����g�������Â�ŁA�q�m���r���ēǂ����Ƃ��̂��̂��B���Ȃ݂ɁA�����N��͓��N6���̋g���̑��V�ɂ́A2���Ɂu���������t���a�@�ɂāv���u�x����p�v�i�������E�͍��ˈ�Y�쐬�q�����N�� �N���r�A�s�v���o�͐g�Ɏc��t�A��Z�Z�y�[�W�j�̕a���{���Ă������߁A�o�Ȃł��Ȃ������悤���B�Ǔ������˗����ē��R�̎v���Ђ́s���㎍�蒟�t��y�Ђ́s�����C�J�t�ɂ��A�����Ă��̑��̔}�̂ɂ������̕��������Ȃ��̂͂�����������ɂ�邩��ł͂Ȃ����B���̍����N�炪�Ђ��Ƃ����g���������q�m���r�������Ƃ���A�����m��҂ɂƂ��Ċ��S���ЂƂ����ł���B�����g���̖{�ōŏ��ɍw�������̂́s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA�u��㎵�O�N�\�ꌎ����掵���v�j�ŁA����������̑�w�̐����ɂ����Ă������B
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�ɖ����^�̖����s���т�1�сA���������B�s���{�̌Ö{���t�͎����ł��p�ɂɎg���Ï��T�C�g�����A�����̂��߂̃c�[���Ƃ��Ă����p�ł���̂͂��肪�����B����A�g�����W�̏��Ђ��u���E�Y���Ă����Ƃ���A���m�E�������s�̉i�y������u�������z�^�u�����k�}�}�l�A�o��]�_�ЁA���S�S�A�P���^����P�Q�O�������d�M�����A�g���������i����ⳓ��j�v��6,000�~�ŏo�i����Ă����i�{���̑��݂͂��̂Ƃ����߂Ēm�������A���̌�A��������}���ق̏����{�\�\���҂�����ꂽ��{�ŁA�u�k���a�l44. 6.18�v�̎������\�\�����������j�B�Ƃ��Ɂu�g���������v�Ƃ����A�����Ɏv���o�����̂����̎��тł���B�ٕҁs�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�i���Y��ԁA2000�j�̓����̍�����A�������т̔ԍ������ς��Ĉ����i�����̖}��͊����j�B
135�@�����i���債�j�m�\�\�n
���邽��z�N������
3�s�����c���j��i�W�s���ꂤ���q�C�L�\�\The Verses of the St. Scarabeus�t�i�o��]�_�Њ��j1969�N5��15�����������сE13
�s�������z�t�́q�����r�̃f�[�^���s���ꂤ���q�C�L�t�i����120���j�̂���Ɠ����`���ɐ����āA����ׂ��s�g�����S���ѕW������t�ɑ��₷����̂��߂ɁA���e�����Ă������i���єԍ��́ub�v��135�̎��ɑ}�����邽�߂̉��̂��̂ŁA����������ɂ͐��K�̔ԍ��ɕt�����������j�B
135b�@�����i���債�j�m�\�\�n
���n�֔��������ނ͋A��
2�s���u�����咟�s�������z�t�i�o��]�_�Њ��j1969�N6��1�����������сE14
�q�����r�͂킸��2�s�́A�����������Ɉ��A�I�Ȏ��тł��邪�i�V��I�ł͂Ȃ��j�A���́u���n�֔��������ނ͋A��v�͒��ڂɒl����B�s�������z�t���s��1969�N�A�g���͂̂��̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�̍�i�Q�������Ă���A�u���n�v������2�тɓo�ꂷ��̂��B
���n�ɐԂ��^�R���郉���W�F���[�^�R����t���A�i�q���͂Ȃ����F�Ȃ̂��H�r�F�E12�j
���n�ɐԂ����̂܂���߂āi�q�킪�n�j�R���X�̎v���o�r�F�E16�j
����͉���A1990�N�A���U�Ō�̍�i�ƂȂ����q����r�i�������сE21�j�̖`���͂������B
�����̂Ƃ���^�@�@�@�@�@�@�k���n[�����炳��]�l�̍��~��
����炪�P�Ȃ���̃��x���ɗ��܂�Ƃ����Ȃ�A�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�̍Ō����߂�����q����ȓ��ʂ̏H�̗��r�i�G�E31�j�̌����ɋ߂��⏥�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�C�i���i�@�C�V���^���@���B�[�i�X
���̐��̍�������
��̖A���͂���
���Ȃ�X�̏��̏��
��j�Ɓq�Ꮧ���f�B�j�r�̍������s��ꂽ
����F�̕s��`�̂��̂̂܂��킢�Ƃ�
���������������������������
�����𗁂т�����
���������Ă䂫
���ȓ��ꐫ�𐬏A����
2003�N�̎u�����̟f��A��Аm���E��ˏ~�v�E���c���j�ҁs�u�����S��W�t�i�����q�C�ЁA2004�N2��22���j������75���Ŋ��s���ꂽ�i�s�������z�t�̋g���́q�����r���Ę^����Ă���j�B�S��W�́q���Ƃ����r�i���L���������s�l�ł������Аm���̃y���ɂȂ邩�j���u�����̔o��ɐG�ꂽ�g���̔����������Ă���̂ŁA�f����i�v���̌��T�́s�o��]�_�t1963�N2�����̋��q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�g�����E�������q�q����o��]�_�ܑI�l���k��r�j�B
�@�k�c�c�l�u���чT�v�ɘ^�����u�ς��Ă�ً������v�ɂ��āA���������̂����������Ă��������B���̈�A�͏��a�O�\���N�ɕ�W���ꂽ����o��]�_�܂ɉ��������̂ł���B���ʂ́u�I�O����v�ł��������A���l�̑I�l�ψ��k���q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�g�����A���䗲�E�i�c�k�߁l�̂����̋g�����́A�������ʂɐ������i���E�e�I�҂͎O����I�o�j�B�ȉ��́A���̑I�l���k��̔����̈ꕔ�v��ł���^�u���̎u���������B����͖l�ɂ͂�����Ǝ�ɕ����Ȃ��v�i�_�c�G�v�j�B�u�Q�e���m�i���q���������j�ƌ�����Q�e���m������ǁA�O�ꂵ�Ă���B���̖ʔ���������B����ɑO�q�o��Ȃǂƌ������Ƃ������Ȃ�A�����܂œO�ꂵ�����������v�i�g�����j�B�u��Ԃꂩ�Ԃꂶ��Ȃ����v�i��{���g�j�B�u����Ŗl�Ȃ�Ɏ����������B������ʔ����Ǝv�����v�i�g���j�u���̃p�^�[�����Ƃ��܂��R�͏����Ȃ��ł��傤�B����ɁA���܂�J��Ԃ��ƕ@�ɂ���Ȃ����v�i�����d�M�j�B�u���������_�͂���v�i�g���j�B�u�\���̖��ł��ˁv�i��{�j�B�u�����̃p�^�[���������Ȃ��ŁA���R�ƌ��悤�^�����k�}�}�l�ŏ����Ă���A�����́A���������A����Ύ�ɕ����Ȃ��悤�Ȋ����ł��A�p�^�[���������ď����Ă���_�ŁA�l�́A���̐l�������ɍ��������܂��B���́A���̃p�^�[���̂��ƂŁA���̕ʂȃp�^�[����W�J���邱�Ƃ��o���邩�A���̔\�͂����邩�ǂ����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�q�˔\���Q�r�Ƃ����}�[�N��l�͂��Ă������ǁA����́A�Ȃ܂Ȃ��̍˔\�ł͓���ł��傤�ˁv�i�����j�B�i�����A�l���`�l��O�y�[�W�j
���҂͏����s�������z�t�́q��L�r�i1969�N4��26���̓��t������j�̈�߂ŁA�u���́A�����b�g�̂悤�ȏ��咟���A�t�����鍂���d�M���A���i����g�������̌��t�ŏ��蓾�����Ƃ́A�킽���ɂƂ��āA�S���̍K���ł���B�[�����ӂ��鎟��ł���v�i�����A�l�O�y�[�W�j�ƁA�����q�����\�\�����܂��A�ނ͇��r�Ƌg���q�����r�ɗ��s�����Ă���B�Q�l�܂łɖ{�����t�̋L�ڂ�^����B
�k���C�@�֎Ԃ��ۂ�������i�\���j�l
���@���@���@�z
�i����P�Q�O���j
���a44�N6��1��
���@�ҁ@�@�@�u���m���܁n�@���m�����n�i���j
���s�ҁ@�@�@�����d�M
����ҁ@�@�@�����P�v
��
���s��
�o��]�_��
�����s�F�J��㌴3����4��13��
�d�b�E����(03)467-0941
�Љ��Q�O�O�~
����ŋg���������O�ɔ��\�������́A�v285�тɂȂ����B���Ȃ킿�s�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�f�ڂ�281�тɁA���̌㔭�����ꂽ�q�g�����̖����s���O�т��r��3�сA�����č����1�тł���B�����Ȃ�ƁA�����d�M������o��]�_�Њ��s�̋�W�ɋg���������͂⎍���܂��ق��ɂ����邩������Ȃ��A�ƍl�������Ȃ�B�����ō�������}���ق�NDL-OPAC�Łu�o�Ŏҁv�Ɂu�o��]�_�Ёv�Ǝw�肵�Č������Ă݂��23�����q�b�g�����B����23���̔o��]�_�Ж{�̍ŏ����Ηj���i�W�s�Ηj�t�i1960�N7��1���j�ŁA���҂͖ڎ����ɁA��Аm���E�剪��i�E�匴�e���J�Y�E������E��������E���c��v�E�������j�E�u�����E�����d�M�E���c���j�E���C�����j�E�������q�E��c���E�����Βj�E��������15���ł���B15���̒��҂̂Ȃ��ɂ͋g�����̐��z�ł�����݂̖��������������Ă���A���̂��������n�߂ɒT������̂��̂悤���B
�i���j�u������W�s�W�t�i�쐣���X�A1958�N2��8���j�̉��t�̒��Җ��ɂ́u�u���m���܁n���m���Ƃ��n�v�ƃ��r���U���Ă���i����1971�N2��1���A�o��]�_�Њ��̋�W�s�D㣎ԃl���t�̂���ɂ̓��r�Ȃ��j�B�{�����t�́u���m�����n�v�́A�����d�M�m�����̂ԁn�̔o�������d�M�m�W���E�V���n�ɕ�������̂��B
�g�������s�Â��ȉƁt�͒P�s�{�Ƃ���1968�N�Ɏv���Ђ��犧�s���ꂽ�B�������A�����͑O�N1967�N�v���Њ��s�́s�g�������W�t�Ɂu�S�b�Â��ȉ�1962�\66�v�̕W��Ŗ������W�Ƃ��đS�ю��^����Ă��邩��A���W�Ƃ��Ă̌��\�͂�����̂ق��������B�s�Â��ȉƁt��16�т����߁A�q���߁E�L�߁r�i1959�N3���j����q������G�r�i1967�N2���j�܂ł̑S�т��{���W�ȑO�ɎG���ɔ��\����Ă���B�{�e�ł́A�O �G���f�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���f�ڌ`�A�Q �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�f�ڌ`�A�R ���W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�f�ڌ`�A�S �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����S�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B��q�̂悤���Q���R�̖{���͓���g�łȂ̂ŁA�u�Q���R�v �Ƃ܂Ƃ߂ĕ\�������B����ɂ��A�g�������W�s�Â��ȉƁt�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A���j�R�[�h�ɂ��u蠟�v��u禱�v�̑���ɁA�s�{�ӂȂ���V�t�gJIS�́u�X�v��u���v���g�p���Ă���_�����ȉ��������������B�Ȃ��A�V�����̗p�����{���̐V���ȊO�̊����́A�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�ŕ\���\�Ȃ�����A�Z�قƂ��Ă�����ژ^�����B���߂Ɂs�Â��ȉƁt�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���f�ڗp���e���e�F���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ��ɁA2016�N10���̎��_�Ŗ����B����R�c�̑��j������Ɉ˂�A�g�����̎��W�f�ڗp���e���e�́A���o�̐�ʂ��Ȃǂł͂Ȃ��A�z�q�v�l���g���{�l������̂���Ƃ����B�����A�{���͂����ł͂Ȃ������B�z�q�v�l�́u�k���W�s�Â��ȉƁt�́l���o�������킩��Ȃ����R�́A�킽�����k�v���ДŁs�g�������W�t�i1967�j�Ɂl�����\����t���ĒԂ��Ă������̂��A�k�g�����l���̂܂��W���Ɏg�������炾�Ǝv���܂��B���a43�N�k1968�N�l��3���Ƀ}���V���������߁A���̑O�A���N�́A��1�l�ŒT������Ă��������ŁA���W�̂��߂̏������L�����Ȃ��̂ł��v�i���ш�Y�����ȁj�Ƃӂ肩�����Ă���B�q���o�ꗗ�r�̂Ȃ��v���ДŁs�g�������W�t�̐��삪��s�������߁A�{���A���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ��ɏ�����������鏉�o�k�����l�ꗗ�̃f�[�^�������������̂Ƒz����B
�P ���o�G���F�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B
�Q �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B
�R ���W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�N7��23���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B�{���Ɍf�ڂ̖{�����Q�́s�g�������W�t�̑g�ł𗬗p���Ă��邽�߁A���҂̊ԂɈٓ��͂Ȃ��B
�S�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���Q �s�g�������W�t�B
�s�Â��ȉƁt�̎G���f�ڗp���e���e�͊����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������i��o�q�X�[�v�͂��߂�r���e�̎ʐ^�łƉ�����Q�Ƃ��ꂽ���j�B�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����́A�ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�ŏ����ɓ��ꂳ�ꂽ���Ƃ�����A�{�Z�قł͏��o�`������ƈقȂ�ꍇ���s�g�����S���W�t�ɍ��킹�ď����\�L�Ƃ����B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�s�Â��ȉƁt���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s�����t�k���s�����l�f�ڔN���i���j�k�i���j���l�j
���̂��߂̃g���̎����i�E�E1�A39�s�A�s�k�t�k�k�̉�l1962�N9���k10���l�j
���߁E�L���i�E�E2�A�����4�߂ɕ�����48�s�A�s���㎍�t�k�ђˏ��X�l1959�N3�����k6��3���l�j���o�u�ʐ^�E��Ґ��i�A�\���E��X���s�v
�����i�E�E3�A10�s�A�s���p�蒟�t�k���p�o�ŎЁl1963�N2�����k216���l�j���o�u�G�E���R�����v
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G�����i�E�E4�A47�s�A�s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A���s�҂͏o��O���l1963�N8���k2��9���l�j
�n�E�t�̊G�i�E�E5�A20�s���A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1963�N1�����k2��1���l�j
�������i�E�E6�A29�s�A�s�X���t�k�X���O�ω�l1964�N7�����k16��7���l�j
�؍��i�E�E7�A25�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1964�N4�����k7��4���l�j
���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�A28�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1965�N3�����k8��3���l�j
�₳�������Ζ��i�E�E9�A71�s�A�s�����t�k�������_�Ёl1965�N11���k�H�G�E19���l�j
�t�̃I�[�����i�E�E10�A41�s�A�s���i�t�k�I�X��l1966�N3�����k7��3���l�j
�X�[�v�͂��߂��i�E�E11�A37�s�A�s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl1966�N5�����k1��1���l�j
���I�ȗ��S�i�E�E12�A95�s�A�s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl1967�N1�����k2��1���l�j
�q�����i�E�E13�A51�s�A�s����t1966�N10���k15���l�j
�ǓƂȃI�[�g�o�C�i�E�E14�A102�s�A�s�O�c���w�t�k�O�c���w��l1966�N11�����k53��4���l�j
������G�i�E�E15�A42�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1967�N2�����k10��2���l�j
�Â��ȉ��i�E�E16�A52�s�A�s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1966�N4�����k9��4���l�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���o�́s�k�t�k�k�̉�l1962�N9���k10���l��`�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�20�s1�i�g�A39�s�B
����܂ł͕��ʂ̃T�C�Y
���������邩��s���ɉƂ̂��ׂẲƋ�x���ω�����
���Y���ɂ̂��ā@�Â����j���̕��̂Ȃ���
���y�̓��[�����X�N
���o�I�ɑ傫�ȃR�b�v�@�傫�Ȏ��u���V
�V��܂łƂǂ��m���_���X
���������ς��̃e�[�u��
�Ƒ��l�l�������g�}�g
���E�m�����傫���Ĕg������Ђ֏o��ꂸ
�Z�E�C���傫���ă��Z������
���E���o�т��傫���ăL��������
��E�傫�ȗe��̎����͂��тŔ��Ă������
���ɓd�b��������
�g����̂悤�ɑ傫�Ȑ������̕s���Ȏd��������
�Z�͏���s�܂��߂��������
�d�b�@�̈�
���͉ΎR���̂悤�Ȑ����֏��̂ӂ���
���l�̖����Ă�
��͂ǂ����Ă��邩�@��͍Ö����̉��ɂ���
���̊O�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��@���Ō�����
��������钩���珇���ɃT�C�Y���������Ȃ�
�����ȋ��@�����ȐQ��
�����ȃp���@�ϔO�̂悤��
���s�킽���͋Q���Ă����t
�Z�s�����������̂��낤�@���̑��̊O��
�@�@�Ύ���n�k����Ȃ��@�ʂ̏o������
�@�@�ڂ������̍߂���Ȃ��t
�[�邩��n���̏�̂ق�т̋Z�p
�����ނ���
�����ނ�����
�����ނ���
����̎��[�͉�]���Ă���m���_���X�̒�
�Z���̓����K�̏�ɍ�����
�J���ӂ��Ă���
�ӂ���ރX�|���W�̐��E
�Z�s�Ƃɂ����ʂ�Ȃ��Ƃ���@�ǂ������邾�낤�t
�Z�����������関���̌`��
������H
������c�o���̖���
���o�́s���㎍�t�k�ђˏ��X�l1959�N3�����k6��3���l��O�`�ꔪ�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|1�i�g�A48�s�A�u�ʐ^�E��Ґ��i�A�\���E��X���s�v�B�{�т́s�Â��ȉƁt�Ɏ��^�����܂��A�c��m�ҏW�E����s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�́q�W�������сr�Ɏ��߂��Ă���A���̖{���͏��o�G���f�ڌ`�̉��ʼnӏ����A�X�e���X�N�ɕύX�i���Ȃ킿�k�i���Łj���@�@�@���l�j�����ق��́A�������ꕶ�����߂��i17�s�߁u�Ȃ݂����܂����Ȃ̂ʂꂽ�k�끨軀�l�͍��̓����K�F�v�j�����ł���B
�����͂Ƃ��ǂ�����
�ނ��ق����j�̐S�̎S���̖��H�̊��̖�
���Ă̌����]������
�o�X�P�b�g�̂Ȃ��̑傫�ȊI�̂��₵���ȍs��
�d�݂̂���ѕz���
�e��Ƃ������̃I���K�X���X
���N�����̐S�����̂��������
���ꂼ��u��
�������d�������܂��
���k�P�����Q���R�S���l��̕��芹
�َ��͎�܂��ʂ����낤
�k�P�i���Łj���Q���R�����S�@�@�@���l
�����͒n�����֓���
�D�����ȂƎq�͌���Łk�P���Q���R�S�́l��������
���킪�݂���܂�
�����͒����Ό����ǓƂȕǂk�P�����Q���R�S�Łl��
�s��̋L���̂��肩����
�Ȃ݂����܂����Ȃ̂ʂꂽ�k�P�끨�Q���R�S軀�l�͍��̓����K�F
�ނ͂�����̂悤�ɓ��@����
��l�̔��������`�̏����̃g���\�̓�
����߂Â������
�ׂ����̐j��
���ꂪ�ւ��`�Â���
�����͖��̖�������͂����
�ƍ߂̋N����
�l�̐S�̍זE�̉ԉ�
����͐^�̔ƍ߂ɂ͕s�v�̂��̂����m�ꂸ
�k�P�i���Łj���Q���R�����S�@�@�@���l
���\�ȗe�^�҂͓��̘g�̂Ȃ���
�Жڂ������Ă���
������̊�̖��͍���ڂ̂��ɂ����
����ꂽ�����킵���[�k�P�����Q���R�����S���l
���̎��]�Ԃ̂���܂��
�H������E�ӂ�
�s�����疞���̎q���ւ̎���
�����̒E��
���̕��A�̂������
���]�Ԃ̂���܂��
������X��
�������
���]���閜�؋��̐l
���߂̗e�^�҂͖얖��
�����̊���Ƃ�
�q���S����łڂ���
�j�C����
�k�P�i���Łj���Q���R�����S�@�@�@���l
�X�g�b�v
�i����
�������ꂽ�j���̂��߂�
�\�Ȃ��
���߂��L�߂��Ȃ�
���o�́s���p�蒟�t�k���p�o�ŎЁl1963�N2�����k216���l���܃y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A8�|1�i�g�A10�s�A�u�G�E���R�����v�B
�킽���͔�����
�����邽�߂ɂ����ɂ���
�킽���͓��Ӂ@�X�X�L�̖݂̂Ȃ���
�킽���͕������@����
���a�l�̏����̎x�ߕ��̂�������
�����₫�����錌�̐�
�킽���͂���ɂ���苩��
�M���������t
�����������˖C��ւ̂ڂ�j
�킽���ȊO�ɂȂ��Ɠ�����
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G�����i�E�E4�j
���o�́s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A���s�҂͏o��O���l1963�N8���k2��9���l��`�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̑����ƃJ�^�J�i�̝X���͏����j�g�p�A8�|21���l1�i�g�A47�s�A�J�b�g�i�N���W�b�g�Ȃ��j�B�q�ڎ��r�Ɩ{���y�[�W���Ɂu��e�v�Ƃ���B�s�C���t�̕ҏW�҂ł��蓯�l��\�ł�����q�������q�ҏW��L�r�Ɂu�g��������̐V��������������B�N�Ԃǂ��ɂ���i�������Ă��Ȃ��̂ŁA�g���t�@���̑����o�d�ւ̗ǂ��v���[���g�ł���͂��B�v�Ə����Ă���B
���̋��͂��������j��
�������炾�S�̂ɒ���o����
�����⒆���̐펀�҂̔��̖т�
�Â��肩��@�Â���܂łȂт�����
���̏�̐�������Ō���̂́H
������т�ꂽ�����̋�����
���ӂ����č��l�֑�C���������܂�
���N�̒j����l�Ő푈���͂��߂邾�낤
�����o��܂ł�
���̒j�͂ӂƂ����H��ɂȂ邾�낤
����悭�s����
���j�I�Ȋy����������H
�����ꂽ���@�����ꂽ�I
�ԖڂƗ�
��̂��闤�n����
���̌R�͂̊��z���Ȃ��ꂽ���ւ���
���������j�Ə��̂��悢�_��̈�
�킽���͏j�Ղ��Ă�肽���Ǝv��
��ƂȂ�Δ�����������
�葫���瓷�܂Ŗ_�̂悤��
�܂�����
�����͂�������܂ŗ������Ă���
�����Â���@���͊^�̂Ƃт܂�鐅���̂Ȃ���
���܈���̕��݂����
�������̌҂܂ł̕S���̏�
�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯��
���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S��
�s���S�ȔR�Ă�
�~���N�E�[���[�Ɨ₽����
��Ƃ̍��M�����I��
�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv��
�H����~�ւ����Ē��Ӑ[��
�R�͂͑S���~�����
�Ƃ��ɂ͉~������
��؉��̂���i���ւ����ݏՓ˂���
�������ꂽ�j���W���E�L���x�c
�킽���͑���E���˂錩���l�Ƃ���
�����N�̂ނ�@���̂�����������
�������A�X�p���K�X
��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv��
�ɕ`���ꂽ�Ⴂ�ւ̋�Y�̓��̂͂���
�^�łȂ��Ȃ�g���镽��
�Ƃ�����̉J�ɂʂ炳��邾�낤
�܂��`����Ȃ��G���@�G�����L����ׂ��ׂ��R
�e�[�u���̌����ɎR�ԁ@�X��b���̗�
�킽���ɂ���炪�����Ȃ�
�^�g�ȐF�̎������̂���ł���
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1963�N1�����k2��1���l���`��O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A10�|25���l1�i�g�A22�s���B
�킽���͂��̂Ƃ����n��̎Ő��ɂ˂ā@�~�����̔n�����Ă���@���˂�̂������I�@��������ɂ킽���̉Ƃ̌˒I�̂Ȃ��Ɂ@�n������ł���Ɗm�F������@�ǂ�قǂ킽�����x���邱�Ƃ��@�킽���͑������̃X�|���W�������n���\�𗼎�ŗ}����@����͖�܂ő����@�s�f�̐l����������݂ā@�����҂̎��R����낤�Ǝv���@�˒I���炱�낪�肾����ނƌ��܂݂�̃n���h���@�I��ɍE�̂�������S�̓��̓������v��@���ɑł���ĐL�k�x��������n�̎�@����͂킽���ɂƂ��Ă͉߂����킢�̐S�̊������@���ꂪ���̎�Ƒ����������������k�P�Ƃ����Q���R�S���l�̂킽���̂��ǂ낫�@�����S�̂悤�ɔ�������ꂽ���̉��Ł@�אl�݂�Ȃ̈���݂���@��k�P�i�i�V�j���Q���R�S���l�ꂽ�J���o�X�������Ɖi���łȂ��ł���@��������n�̕��ց@�킽���͌������Ě����@�s�l�Ԃ̍K���͊e�l�̐����̂��́t�@���͒��S�̉�����X�J�[�g������@�s���N�ƃO���[�̂��₩�ȃJ�[�u���M�̓��A���čs���@�킽���͂���ɂ������Ȃ��̂��@���͎��n�Ȃ̂��@�J�̂Ȃ��ł��܂ł����˂�@���Ă킽�������Ō����~�����̔n�Ȃ̂��@���������炵�������������邵���i�c���̎��@�킽���͎����q�Ŏ����݂����@�������肨�Ƃ����낤�@���E�͂����]���Ȃ��̂�����@�킽���ɗ]���Ȏd����^����
���o�́s�X���t�k�X���O�ω�l1964�N7�����k16��7���l��l�`��܃y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|25�s1�i�g�A29�s�B���M�Җ��̌�Ɂu�i���{���㎍�l�����j�v�Ƃ���B
�킽�������Ăт��܂��Ƃ�����
���т������B�I���b�g�F�̊Ô炩�炾
����͂������茩�����������
�Ƃ���ǂ���Ă̂������̖̂[����
�������Ɉ�Ȃ𑖂点��
�����̃h�[���̉��͂��炩���n�̌�
�k�P�S��������肤�������Q���R�S���ڂ��ꗱ�̉����l
�킽�������Ăт��܂��Ƃ�
���Z�̔��Ō��͋P����
���܁@���܂Ƃ͂����Ȃ�R�̐��
�召�̗r�������g�̖т�������
�킽�������̕����
��ԂŐ��߂�ꂽ
�n�}�̏��
�����������Â����E�̈�̏���
�����ł킽�������̕�͒�����������������
�͂łȂ��S�łǂ��܂ł�����
���m�N���[���̓ÎR
�����͒@���Ƃ���łȂ���
�킽�������̎����镃�߂鐹�n
�˂�
��Y�̓��E�M����
�킽�������̕�͐��������玟�̂��̂�����
�����v�̌���
�E���܂̂Ȃ��ŐF��ς�����F��
�Z���t�@���ŕ�܂ꂽ
����
���ꂪ�킽�������E��\���I�̂킽������
�X�s�[�h�������Đ����Ȃ����
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1964�N4�����k7��4���l���`��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͏����j�g�p�A�܍�1�i�g�A25�s�B
�킽���͂����l����
�h�A�̃m�u�̂��炩�����|
�؍݂Ƃ͂ȂɁH
�Ύ��̂Ȃ��ł͂���傫�Ȋy������Ă���
�킽���͕s���̂��̂�
�����肵�Ȃ����낤
���ꂪ�X��Ȃ�
�킽���͏��̍����������Ċ����čs��
�~���������~
�����錻��������
��H��߂�\�[�Z�[�W������
����͐V�����ϔO��
���y���L�h��̃|���v�ւ킽���͐ڋ߂���
�㉺�ɂ������Ȃ����Ƃ�
�������Ȃ�@���ւ��ڂ���
������킽���͊����H����������
����S�̃K���X�̔j�Ђ̍ו��܂Ō�����
��̔������[��
���ꂱ�����ڂ���
�������瑱������������
�҂����z�e���̗������o�Ȃ���
�킽���͍l����
�J�P�̂Ȃ��̏����Ȉ���
�������鎩���Ԃ̃n���h��
�k�P���ׂā��Q���R�S�i�g���j�l���֍��ւƂ�����
���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1965�N3�����k8��3���l��Z�`���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�15�s1�i�g�A28�s�B�ڎ��ł̕W��́u���E���邢�̓��B�N�g���[�v�B
�����̖A�̂Ȃ���
������������]����
���̂�����𑖂�}���\���I��
��@���B�N�g���[
�҂��ꂽ���̏o��Ƃ���
����̃S�[���H
�V�l�͔��肷�閰�����܂�
�ӂ����щ���Ă���
���̔�����
���ׂ�Ȃ���
�V�l�͎��l�̔\�͂������킦��
�����₩����
��֏L�����]
��@���B�N�g���[
�V�l�̌�
����͋Z�p�I�ɂ��傫��
�S���z�[�X�ł��ꂢ�ɐ���
���炩����
���̂����������炭�͌���k�P�i�i�V�j���Q���R�S�I�l
���l���y���Ȃ��Ă����]
�V�l�͏������̂Ȃ��܂������グ��
���F�̃^���|�|�̖��
��@���B�N�g���[
�k�P�Q���R壁��S�u�l�����̐S����
�U�q���߂�Ƃ�����
�J�^�c�����̂��炫�炵���ʘH���Ƃ���
���悤�Ȃ�
��@���B�N�g���[
���o�́s�����t�k�������_�Ёl1965�N11���k�H�G�E19���l���`��܃y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A20��19�s1�i�g�A71�s�B
�Ă͂͂����Ȃ��肽���Ȃ���
�`�����[�͂����v��
�܂��ď����̂��Ԗт̌��̂܂���
��肽���Ȃ��ƍl����
�~���N�̂ݐl�`�̕��̂悤��
����炵���J���������킹���
�����t�`�����[�͖���
�①�ɂ̔��������ӂ��Ă������Ǝv��
����͂����ȏ��h�Ԃ̏��̂悤��
�����������ȓ��������Ă���
�L�ւ�鋛������łȂ��
�R�J�E�R�[���̃r���̓K�`�K�`��
�`�����[�̋��߂Ă�₽������
�������s��`�ȗ�
���ď��N�������L�����Ȃ�
�ނ̋L�^�͐X�ѕ��Ώ\�l��
�O�\��˂̃`�����[�͔ߖ�����
���̂����ɕ�Ɩ����J�����̂悤��
�������
�i���ɐV�����푈�ʐ^
���ꂩ���d�̂Ȃ��̊��Ԃ̉��~
�E�̂͂��Ă��邱�Ƃ���l�Ȃ�
�`�����[�͐|�̒��̑�l
�J�}�X�ɋ����C���V�̓Ő��̂Ȃ�����
����Ă��邱�Ƃ��߂Ȃ�
�`�����[�̑̏d�͗�
���͔R����A�����J�l�Y�~�̔�
�k�P�Q���R㊁��S��l�̉~
���邮�����Ă����
����͓d�C�������_�I�Ȃ���
�`�����[�̎S�͔���͂��ꂽ�E�T�M�̂悤��
���̐l�̌��h��̐l�ވ�����݂͂�����
�������G��
���O������
�����łȂ��S�̓I����
���̐l�̊ώ@�ł��Ȃ�
���X�̐�
�`�����[�̓����錀
�ЂƂ̓S�̒����瑼�̒���
�A�����J�̍��w�C������
�V�i�̂����ꂽ�t�J�̐��n�̊C��
������`�����[�������邩�H
���̐l�̐S�̓}�b�`���C����قǔM���Ȃ�
�������������̌ߌ�ł�
�₳�������Ζ��`�����[�E�R���f����
�悾��͔M����������
�����錻���̐X�т͉��Y�ނ��т������Ƃ˂�
�^�o�R�E�t�B���^�[�E�Z�����C�h�̔�
�`�����[�̓���͂ǂ��������
������������Ă�����퐫����
����퐫�փI�N�^�A�u���ւ�
�p���|�p
�`�����[�̔����Ǝ�`�̏������낤���H
�T�[�X�E�L���j�I���̑��̐l�̕����ꂩ��
�Ƃ���������Ԃ߂̖�̉Β�
�`�����[�͓����邱�Ƃ����ۂ���
�ނ���K���
�ނ���Î~
��̃Z�~�̏o���̂�邢��
���邱�Ƃ��ւ���
������x�т̍����}�X
�������ڂ�̏��ƒ����������ƍs�Ȃ�
����������
�����Ȃт��ޕ��̉ԉňߑ�
�`�����[�͓��̒��̉�
�����闃�@���Ȃ̉������Ă���
�s�O�o�̂Ƃ��́@�J������킷��Ȃ��t
�@�s�O�o�̂Ƃ��́@�J������킷��Ȃ��t
�₳�����j�`�����[�E�R���f��
�T�b�̂Ȃ��ւ̐���
�J�����߂Â��܂�
���o�́s���i�t�k�I�X��l1966�N3�����k7��3���l�ܓ�`�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|23�s1�i�g�A41�s�B
�킽�������ܕ`����ʂƂ͂ȂɁH
�������Ƃ͊W�Ȃ�
�^�]��̂��т��i�߂�
�ЂƂ�̏��N�̋����b�L�̒E���т�
�ڋ߂���
����͕a�C�̂Ȃ��Łk�P���������Q���R�S�����l
�쐶�̓�
�Ă�����Ɣ����ʂ肩����
�V�g�̊�
�ނ��됳�ʂ��ނ��Ƃ�
�}�Ƀh�[�i�c��H���V�k�����I
�ЂƂ�̏��N�𑖂点��
���̂Ȃ��̖��H
�f�p�[�g�̃}�k�J���������牺��
�n�����Ă���邩�璩�܂�
���Q�n�k�P�恨�Q���R�S�сl�̉��y�́s�}�w���A�̋F��t
��֎���Ƃ����
�Ƃ��ꂽ�o�̂��炵�Ă����}�k�P�恨�Q���R�S�сl
�킽���̖��z���̉�ʂ���
�Ɨ�����
������Ă���@���k�P�[���Q���R�S���l���Ɖ��̕���
�ЂƂ�ŏ��N���܂����ōs��
�����̐��E�Ƃ͂ȂɁH
���ł₵�Ȃ�ꂽ��l�̎��ʃV�����E�V�����̊y��
�����S�łȂ��E���铛����o��
����s��̊w�Z��
�E���̕�����낵��
�ЂƂ�̏����������Ă���
�s���拃���āt���̂��Ȃ���
������������~����
�a�M���̂���
���`�[�t���̂���
���N�̎Ȃ���S
���̍ו��̂Ȃ��̍ו���
�����ɂ܂ł��������čs��
�����̉J�P
����͑傫�ȁk�P�����Q���R�S�~�l�̕����I
�T�\�������҂���Ɣ������̂������Ȃ��H
�킽���Ƒ�l����
�ƂĂ��������@�������̂Ȃ���
�A�C�X�N���[��������

�g���z�q�v�l�̎�ɂȂ�q�X�[�v�͂��߂�r�̎G���f�ڗp���e���e�i�o�T�FYahoo!�I�[�N�V�����j
���̎G���f�ڗp���e���e�Œ��ڂ��ׂ��́A�ҏW�҂��L�������Ǝv�����Ԏ��ɂ��w��ł���B�ʐ^�̉𑜓x���Ⴍ�Ĕ��ǂ��ɂ������A�w��͌��e�̏�����ɑ��Ď{����Ă���悤�Ɍ�����B�o�T��Yahoo!�I�[�N�V�����̃N���W�b�g�u�g�������e �X�[�v�͂��߂鑐�䌴�e�p��(32�~20)3�����v�́u����v�͐������́u����Ɂv�ł���B
���o�́s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl1966�N5�����k1��1���l��Z�`���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�21�s1�i�g�A37�s�B�ҏW�S���҂̂ЂƂ萴����s�͏��o�������́q��L�r�Ɂu�n�����́A����i�̏����W�ƂȂ����̂ŁA��l��łƂ��������ȏ����ł��肢�������A�������e�������������Ɋ��ӂ������v�Ə����Ă���B
�g���̃q�[�X�̍r���
�Ŋ��@���������
�����čs��
�ЂƂ�̘V�k���������Ƃ�����H
�m�C�Y�̐Â��ȋ�
����͐��}�Ƃ̐����S����
��������
�q���ɂ����܂ꂽ���r
�Ȃ����R�}�[�V�����E�\���O
�t�@�V�X�g�����̎���ł���
���n�ł̉�
�j���܂��~�Y�X�}�V
�V�R�F�̏����̓��̂�
���������߂�
�������ւ₳�����L�b�X
���Ȃ킿�V�k�͛K��
�C�ӂ̂ƂȂ�։������
�����ŋN�邱�Ƃ͊O���ɂ��N��
�����₩�ɒ���ȃL���E�����̂��
��������
���C�{�C�{�����̗ǐS
�ɂ��鍕���Ԃ�V
���ሤ�������������̂��H
�����ގ҂Ɩ߂�҂�
�����ɒʂ�
�z�b�g�E�R�[�i�[�ŘV�k�̔�����
�����s�X�g��
���݂���~��������ʂ���
�A���v�̓��`�̐�
���ʂ��̂��Ȃ��Ƃ���
�Ȃ����l�тƂ͍��M������
�r�̂Ȃ��̏�w���Ƃ���
���֕��ԃR���N�̐�
���ނ��̂�ς���
�ЂƂ�̘V�k�̉P����
�������낤���܂�
���߂��X�[�v�͓��F�̖���
���o�́s���Ɣ�]�t�k���X�Ёl1967�N1�����k2��1���l��Z�`��O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�13�s2�i�g�A95�s�B
�E�l�҂̂����ȃX�g���x���[�W���[�X
�ƂĂ��Ԃ�����
�K���X�̊�֒������I
������鍰�̉ԕ���
���݂��������ʂ́k�P�����Q���R�S�́l�����
�����̒�d�̓d�Ԃ́k�P�����Q���R�����S���l�l�̕悪
���Ȃ₩�ɂ��݂�����
���������ĔY�܂�����I
�G���x�[�^�[�̏��
�������i�ߎE���ׂ��_���~����
�X�g���[�ł����܂킷��
�����߂��čs��
�[�Ă̋�̃X�g���x���[�W���[�X��
���݂̕�̌��łȂ����
�����̖��̐A�������������̉t
�ڂ��͎E�l�҂�
���ɂ������Ă���L
�d�q�I���K�������Ă���ߌ��
��������傩��o�鐅�q
�ڂ������q��
���݂����������ȔL�̕��Ǝq�{
����炪���e���͂�������
�X�̏��
�\�[�Z�[�W�̍H���
�ڂ��̕��̖���̐�̉���
�ڂ��̒�͒s���œ~�̂��т����X���s��
�s�����ɂ͂�������̏�������t
����ӂ���I
�����錚�z���̗�����
���ׂ鍻�̂Ђт����������
�����܂��f�R���[�V�����P�[�L
���R��̈�A���܂�
���݂�̃��b�p��̊ǂ��܂�
�^�C���̗�����
���ӂ��T���S��
���ӂ�镺���̐�
�h������@���Ă�I�@�Ă̖��
��ԃt�H�[�N
�H��
�����̂悢�e�b�|�[����
�̑S�J��
�ڂ����E�����^�]��
���݂炪�E���������f�U�C�i�[
����炪�E�����~�X�E�V�i
�e�[�u���̉~���܂��
����ł���H�̖�
���R�ȏ�Ԃŏ�ނ��X�v�[��
�Ƃ�����O
�f��̃t�k�P�C���Q���R�S�B�l�����̂Ȃ���
�Ƃ�����ƍَ҂�
��p�̋���Ȉݑ܂̏�
���Ԃ�������
�n������čs��
���ւ̈��@���ւ̈�
������錢�ւ̈�
�؍��ւ̕����I�Ȍ��̈�
����\������Վ��j���[�X������
�ڂ����E�l�҂ɂȂ���
������k�P�H�����Q���R�S�Ǐ��l����
�����z�k�P�����Q���R�S�i�g���j�l�������̗܂̋�
�i�b�g�E�L���O�R�[���̉S
����y����
�_��ȃu���[��F��
���k�P�̗̈�����Q���R�S�i�g���j�l
�ڂ��̕s�ς�����
������
���݂������Ύ����݂��т�
���łɁk�P�������Q���R�S�P�V�l�̔��܂�
����l�Ƃ��Ă�
���ʂ����l�Ȃ�
�c���̃}�k�J�����ڂ��͕������낤�H
�����̋�����邲�Ɩ邲�Ƃ�
���݂��ڂ����E���ɂ���
�����₭�A�̂Ȃ���̂Ȃ�����
�X�g���x���[�W���[�X��
�Â��@�̏�
�\�t�@�[�̊D�F��������
����炪���݂���E���ɂ���
�ڂ��֔̕邪
���݂����̋֒ʂ��钩�܂���
�����̐Ζ��������݂���
�����ւȂ���ł�͂ƃj���g��
�q���͈���Ă͂����Ȃ�
�ނ��됶��Ă͂Ȃ����������
�Ȃ��v�����������Ƃ�
�ԉ�����
�ł̋�
�邻��Ƃ��^��
�ڂ���̏I��̍��}�H
�����v�̂�������
�Y���b�k�P�v���Q���R�S�j�l
�����͗l�̂������͗t
�ڂ��͋C������Ȃ��Ő����Ă���
���݂����E������
�K���X�̊�̂��������̂悤��
���o�́s����t1966�N10���k15���l�O��`�l��y�[�W�u�Q�X�g��i�v�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|22�s1�i�g�A51�s�A�ڎ��ł̕W��́u�Ђ�߁v�B
�q�����͊C�̂Ȃ��ʼnj��
�M��
����ނ��
�߂����邽��
�҂��҂����������̐�
�L����ނ�
��܂ł����܂�
�V�k��������Ƃقق���
���ꂪ���}�Ȃ�
���ʂׂ����H
������ׂ����H
�g�̉���
�V�k�̍������~��čs��
���̐Ԃɉ�����
����]
�q�����̗��ʂ�
�����������炩�ɂȂ�
�₽���M��
�k����삩��
�Ђ��悹����
��̊Ⴊ�Ђ炩���
�q����
�M��鏭�N�̂������闇�̋r
�ƂĂ��K�\�����L��
�ː��̂Ȃ���
����C�J
���ԃX�g���[�E�n�b�g
���ԗ�
�N�����ʂ̂��낤�H
���̊����̉Ԃ̌��̏o
�Â��g�E�t�̔���
�S�̂Ƃ��Ă͗ڂ̂ӂ����y���\�i
�ʂ��鉩�F������
�ʂ���}�k�J���̎葫
�Y���R���j���N
�ӂ����ѕY��
�����̂Ȃ��ւ���������d�k�P�����Q���R�S���l
�͂����茩�����I
���h�v����
���ɂ����Ȃ������z�[�X��
�Ђ������čs��
�����C�ݐ�
�q������
���ʂȐ��n���E��
�����̌����Ђ炫
�����̖т��͂₵
���悢�悠���܂��Ȍ`����
���̓���̃G���`�b�N�Ȍ��̉���
�����܂��ȐS����
���̂Ƃ�
�������Ƃ��Ă͐���
���o�́s�O�c���w�t�k�O�c���w��l1966�N11�����k53��4���l�O�܁`�O��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|21�s1�i�g�A102�s�B
�C�݂̍��n��菭���������ʂ�
�������
�~�`�̃R���N���[�g�̏��H
����͌��F�̃q�g�f�̂悤��
����
�N�̐Ԃ��}�t���[
���S�~���ґR�Ɖ�]����
�K�w�̑��ʔ�����
�t�̏I��֊���ړ��I
�悲�ꂽ�l�̉����̌�����
�₪�ė[��ꂾ
�@�B�̖_�ő��삳��鍰�̒��S��
���̃I�[�g�o�C�������Ă���
��T�C�N���̃X�s�[�h��
��T�C�N���̂Ȃ���
���݂���
�~�̖������I
�ǓƂȃI�[�g�o�C�̗���
�����h���̂Ȃ�܂�������
�~�̖��H��
�Ȃ��ꂱ�މ��F���A�l���l
���鐅
�q���������A�X�s���������r
����ԗ�
�����ʂ��钹
�܂����C�ق��ʂ��
���ꂩ�珈�����̃V�����_�[��
���݂��Ă���̂��킩��H
�@�B�����邳�т����W�����m����
����ԗւ̉��̂܂����o�i�i
�����₭�G���W���̈�
����Ƃ��͌�����
����p�l��
����ׂ邵��ׂ�K�\�����̌�
����ׂ�Ȃ����ق̓d�C
����C��
���[�^�[�̓�����
���炩���^�g�̌��̓O���X����
�����w�����b�g�����Ԃ�
�ƂĂ����̂����ՓˁH
�ׂ����ނ肪�o��
���삽���̗��p���c
���̂͂邩����
�l����̕���̑�
���̓��̏��
�ǂ݂�����
�E�̐�
�x�r�[�̎��S�@�o����
�ݎؑΏƕ\
�@���̕��ᎆ�̔ޕ���
��܂���郌���Q�̉�
�����Ē_�`
�������������l��������������
�C�܂���ȔL���͂��
������̂�����
������̂̑��̂��̂�����
�L����̂悤��
�X�^���h�̐��T�{�e���̂Ƃ��̊G
�������܂̃T�\������
�������Ђ炫
�����`�̈�A
���łɂȂ��O������A�����ڂ��
�K���K��������Ȃ���
�ς܂�Ă䂭�r�[���́k�P�Q���R㣁��S�ʁl
�S���@�����
�j���̔ߖk�P�I���Q���R�S�i�g���j�l
���Ԃɉ�����
�}���h�����̕��։�����
�I�[�g�o�C�������Ă���ł�
���̓}�����o�⑾��
�܂��ԗւ֔�����������
�S���̃^�C���̏۔琫��������
�悤����ɔj��ł��Ȃ����
�č\���ł��Ȃ�
��Ԃ�\�z����
�J�ɂʂ��I�[�g�o�C
�O�b�h�o�C
��b�̂Ȃ��̒��߂�ꂽ�o���u
���N�̍������������Ȃ�
�����̒E���Ȃɂӂꂽ���Ȃ�
�ǓƂȃI�[�g�o�C�̃T�h��
���݂��鐸�_�E������㵒p�x
���ԂƂ͂ǂ�Ȕ����H
���S�~�̔�������
��~���锼�~�̓����x
�o�Ă����Ȃ��J�j
�C�݂ւ�����߂Â��ȁI
����S��
������֖߂���
������̋ł܂ʼn��n���h����
�����������z����
���g�v
�牺�쌌�I
���X�s�[�h�ŏo�Ă䂭�K���X
���������ς��ɂ��ܓ����Ă���C�J
���̃I�i�j�Y����
�~�]�̃��[�^�[�̓�����
�z�b�g�E�P�[�L���Ԃ���
���V�l�v��
�킯�̂킩��ʘA����
�e���e���e���c�c�c
�ǓƂȃI�[�g�o�C������
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1967�N2�����k10��2���l�`���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͏����j�g�p�A�܍�1�i�g�A42�s�B
���鐶��
������Ԃ̃X�~��
��܂��ꂽ������̂��͂���
����o�T�~�E����o�T�~
����͖�̑�����
�����̖A�̏㏸����̂��ώ@����
������䍂����
�����^�C���̏�ł�
�l�����Ȃ����l����
���̎��̂Ȃ��̖I
�J�ӂ閃
�ڂ����N���C���������Ƃ�������
�ЂƂ�̏���������
����͂ڂ�����\�˂̂Ƃ�
���Ȃ����V�i�̏����Ɏ��Ă���
�삦��Ɠ����ɂ₹�钱
�Ђ낪��Ɠ����ɂڂ܂��
�����ł����H
�ڂ��̑z���K�P��
�C�ւ�����ōs���r��
����ꂽ���ƍ߂̐������I
�c�����畗�C�����炢��
���R�ȏ�Ԃ�
�ڂ��̊G�����܂��H
�a�C�̎q���̎牺�̂Ȃ�
�Đ����I�Ȗ�̂Ȃ���
���̏o��
�u���[�̋�
�R���N�̖̂Ȃ����т̓���
�J�P�������V�i�̕ꖺ
�������r���l���炵�čs��
������܂錩��
�����Œ��
���m�̂����Ȃ�
���ꂱ��������������̊G
������������̃r����E�j
������������́k�P�~�~���Q���R�S���l
�����߁k�P�����Q���R�S���l�R���I
�������������
���̉E����������
�Ζ�ɂ��痁���܂ł���
������G
���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1966�N4�����k9��4���l�O���`�l�Z�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�21�s1�i�g�A52�s�B
�p�Z���̗t�݂̂ǂ��
���肠�������`
�ڂ������ɍȂ����邱�Ƃ͍K��
�Ƌ���ł���j
����͗m���̂Ȃ��ɂ���Ƃ����킯�ł͂Ȃ�
�Ȃ����_�������߂�
�����|�̊��̐߁X���Ƃ�ł���
�N���A�Q�n�̈ł̋�����
�M��Ă���悤�Ɍ�����
�A���I�l��
�ȂƂ͂ȂɁH
���̐H�ׂĂ���I�̏��
�}�}���[�h�̒��S
���ꂼ��̕v�́s�����ɍ����͎n�܂�t
�H���͎n�܂�
�l�����ނ̂Ȃ��֚�
�������[��
���̏��
�g�@�̐ォ�猩����
�����̏��̐�͒�������
�܂�܂�Ƃ���
�ЂƂ̏\���˂։����č~��čs��
�ł̓j�b�L�͂ǂ�Ȓn�ォ��
�͂���Ă���H
������O��
���B�N�g���A�̃J�G���܂ʼnJ�łʂ炷
�q����l��擪�ɂ���
����Ă���̂�
�t�́k�P�����Q���R�S���l�I
���ꂪ�ق�Ƃ̝R��I�Ȃ̂��H
��̂����Ȃ钌
���̖т̕`�ʂł��Ȃ��Z���q
�X�Ɠ������Ă���
�W�܂钹��
����ނ��ɍ����ו�������
�G�̂Ȃ��̋�Y
���ǁ@�ȂƂ̓o���b�N�|�p�̉ԏ���
�قƂ��邱�Ƃ��o����H
�����̐��ʂ�
�Ăѐ���������c�^�̗t�������邩�ˁI
�@���I�ȃX�e���h�O���X��
�i���ۑ����\�Ȃ��
�܂䂭�J��
�U��s���ʂ̂Ȃ���
�唞�̎�q
���炩���ߎ���˂Ȃ�Ȃ�
�v�����������
�����h��̏����ȊG
�X�M�̖̌����ɂ���
����Ȃ���Ȃ���čs���n�ƕ�����
���E�̐Â���
��������l�A������
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�s�Â��ȉƁt�́q�@�r�Ɓs�@�t�����p�����Ɏg�p���Ă���i�R���ʂ͂����ł͉�b��Ȗ��A�����̂��߂̂��̂ŁA�ʏ�̍����́u�@�v��w�@�x�ɓ�����j�B�{�Z�قł��S�ɕ���āq�@�r�Ɓs�@�t�ɓ��ꂵ�����A�Q���R�ɂ͂����ɉ����ā��@���Ɓ�@�₪���݂��Ă��āA���������i�Ȃ����@���Ɓ�@��́u�������v�łv�o�ϊ�����邪�A�{���A�c�g�p�̖ł͂Ȃ��j�B2��ނ̖����݂��鎖�Ԃ��u�Ӑ}�I�Ȏg���킯�v�Ƃ��鍪���͌�������Ȃ��A�u�Z����̕s����v�Ƃ����̂��S�̗��ꂾ�낤�B���̂悤�ȍ������P�̖������p�������ʂƂ��l������̂ŁA�P���Q���R����������ׂĂ݂�ƁA�q�₳�������Ζ��r�ȊO�̂��ׂĂ̏ꍇ���P���Q���R�͓������A�܂�q�@�r���s�@�t���A���@������@����A���o�`�Ǝ��W�f�ڌ`�������������̂ł���B�Z�ق̖{���ɂ�����������ƔώG����܂�Ȃ��̂ŁA�ȉ��ɎR���ʁ^���w�L���̕s�������o�ꂷ�鎍�傾�����o���āA�P���Q���R�A�S�̈ٓ����ƍ����Čf����B
���̂��߂̃g���̎����i�E�E1�j
���k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�킽���͋Q���Ă����k�P�Q���R��S�t�l
�Z�k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�����������̂��낤�@���̑��̊O��
�@�@�k�c�c�l
�@�@�ڂ������̍߂���Ȃ��k�P�Q���R��S�t�l
�Z�k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�Ƃɂ����ʂ�Ȃ��Ƃ���@�ǂ������邾�낤�k�P�Q���R��S�t�l�n�E�t�̊G�i�E�E5�j
�s�l�Ԃ̍K���͊e�l�̐����̂��́t�₳�������Ζ��i�E�E9�j
�k�P�s���Q���R�ၨ�S�s�l�O�o�̂Ƃ��́@�J������킷��Ȃ��k�P�t���Q���R��S�t�l
�@ �k�P�s���Q���R�ၨ�S�s�l�O�o�̂Ƃ��́@�J������킷��Ȃ��k�P�t���Q���R��S�t�l�t�̃I�[�����i�E�E10�j
���Q�n�т̉��y�́k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�}�w���A�̋F��k�P�Q���R��S�t�l
�k�P�Q���R�ၨ�S�s�l���拃���āk�P�Q���R��S�t�l���̂��Ȃ����X�[�v�͂��߂��i�E�E11�j
�k�P�Q���R�����S�q�l���ɂ����܂ꂽ���k�P�Q���R�����S�r�l���I�ȗ��S�i�E�E12�j
�k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�����ɂ͂�������̏�������k�P�Q���R��S�t�l�ǓƂȃI�[�g�o�C�i�E�E14�j
�q���������A�X�s���������r�Â��ȉ��i�E�E16�j
���ꂼ��̕v�́k�P�Q���R�ၨ�S�s�l�����ɍ����͎n�܂�k�P�Q���R��S�t�l
���̂��Ƃ��w�������̂́A�s�g�������W�t�����́s�Â��ȉƁt�̓��e�p���e�͗z�q�v�l���M�ʂ������̂ł͂Ȃ��A���o�G���Ɍf�ڂ��ꂽ������������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^���ł���B�e�ł���A�q�@�r�Ɓ��@���A�s�@�t�Ɓ�@��̍��������g�ł��������Ă��A�Z�����ɓ��ꂵ�₷���B����ɑ��āA����������e�p���e���ƁA�ӎ��I�Ɏg�p�������w�肵�Ȃ�������A��s����g�łɈ��������ē������Č����邱�ƂɂȂ肪���ł���B�R���ʂƐ��w�L���̕s�����̍��A�Ƃ����g�ŏ�̍��ׂȒ]�т��A�t���I�Ɏ��W���e�p���e�����݂��Ȃ��������Ƃ��ؖ������Ƃ����悤���B
��
�g�����͎��Ɉ����q�O�̑z���o�̎��r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���j�Łs�Â��ȉƁt�Ɍ��y���Ă���i�����ɂ́s�Â��ȉƁt����q������r1�т����^�j�B�g���͓����Łq�Â��ȉƁr��S�s���p�������ƁA����������B
�@���̎��т́A���̕��Y���̂悤�Ȃ��̂������B�u���E�H�̊G�v�͂��łɏo���A���̖�́A�u�C���Əȗ��v�ɖv�����Ă����B�[��ꎞ����A���Ɋ��������B�ق��Ƃ��A���ł�����ĖႨ���ƁA�ׂ�̕�����`���ƁA�Ȃ̎p�������Ȃ��B�����A�����֍s�����̂��낤���B���܂łɂȂ����ƂȂ̂ŁA�s���ɂ���ꂽ�B���͏��݂Ȃ��܂܁A���e�p���Ɍ����Ă����B����ނ���S����߁A�C���܂���킷�ׂ��A�����L�q�̕��@�Ŏ��������͂��߂��悤�Ȃ��̂������B
�@���ꂩ��A�ꎞ�Ԃقǂ��āA�Ȃ��A���ė����B���x���̎��A���̎����A�u��������l�A���Ă���v�̈�s�ŁA�������Ă���̂��B�u�܂��b����ˁA�i��������l�A���Ă���j�Ȃ�āv�A�Ȃ͏Ƃꂩ�����ɁA�{���Č������B�C�����ɁA�a�J�܂ő���L���A�X������Ă����Ƃ̂��ƁB�܂��A����ɔM�����Ă��鎄�̎p���A�����A���������ς��Ɋg����A�ƂĂ����ɋ����Ȃ��Ƃ��A�����̂������B�u�Â��ȉƁv�́A���̍�i�̒��ł��A�Z���ԂŐ��������ٗ�̎��тł���B���a�l�\�O�N�̉āA�ق��ɏ\�ܕт̎������߁A���W�w�Â��ȉƁx�͊��s���ꂽ�B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j
�q�Â��ȉƁr�����W�̃^�C�g���|�G���ƂȂ������Ƃ���́A�u�����L�q�̕��@�Ŏ������v�������A�܂�s�m���t�i1958�j�̑ɂ��s�����Ƃ���ӎv���ǂ݂Ƃ��B����A���^�̖ʂɖڂ�]����A�U�����^�̎��т́s�m���t�ł�19�ђ�9�сi�g���̎��W���ő��j���������A�s�Â��ȉƁt�ł�16�ђ�����1�тł���B�����r�Y���O�f���́q�ӏ܁r�Ŏw�E���Ă���悤�ɁA�s�a���`�t�i1962�j����s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�܂ł��u���́E���z�@�v�́u�ߓn���\���N�v�i���O�A�l��y�[�W�j�Ȃ�A����͓����ɎU�����^��i�������Ă����ߒ��ł��������i�U�����^�̎��т́s�_��I�Ȏ���̎��t�ł��ɂȂ��Ȃ�j�B�g�����U�����^���o�čĂт����ɖ߂����Ƃ��A�Ɛg�҂̖��z�����߂����̋�`�̔��ɑ���z���͏����Ă����B�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�ɏ��R����U�����^��i�͂Ȃ����A�q�^�R�r�i�G�E2�j�O���̒���������q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�G�E11�j�́k�����`���l�i�Ƃ�킯�U�j�A�q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�i�G�E17�j��4�߂߂Ȃǂɂ��̍��x�ȉ^�p��������B1981�N�ȍ~�́A������s��ʁt���^�̊K�i��̍s�����������S�ƂȂ�A�U�����^�̍�i�͋g�������̕\���䂩�������B�s�Â��ȉƁt���u�����g�������v�̏I���ƌ��鏊�Ȃł���B
�k�t�L�l
�s�y���F��t�́q���L�r1968�N8��31���ɂ͊}��b�̕������ς����ƁA���i���ł̏����̐ȂɎv���Ђ��玍�W�s�Â��ȉƁt�̌��{���͂������Ƃ��A������9��28���ɂ͑���Y�E�y���F�E����x�q�̕������ς����ƁA���{�����X�Őe�����l�����Ɂs�Â��ȉƁt��z�������Ƃ�������Ă���B���ۂɁs�Â��ȉƁt���ł����̂́A���t�̔��s���i1968�N7��23���j����1�ӌ��ȏ�ゾ�����悤���B
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�v���Д��s�̌������s���㎍�蒟�t�͍��N2009�N�A�n��50���N���}���A6���ɂ͋L�O�̓��W�����҂܂ꂽ�B�g���������т�U�������G���͐������邪�A�����͂����炭�ő��f�ډ��ւ�B���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j���������낵���g���́A�s�V���W�t�s�����t�s�G�߁t�Ƃ����������̓��l���ɎQ�����邢���ۂ��i�O�͓��l���������s�G�߁t�͍�i�����������j�A�s�����C�J�t�s���w�t�s���㎍�t�Ȃǂ̑��������ɂ����͓I�Ɏ��т\���A�������܂Ƃ߂��̂����W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�ł���B1959�N6�����s�́s���㎍�蒟�t�n�����i�Ō��͐���Ёj���\�̎��тƂ���ɕt�����U���ȍ~�A�f����O�N1989�N3���̌��J�K�M�ւ̒����܂ŁA�g���������ɔ��\�������сE�U���A�A���P�[�g�A�C���^�r���[�E�Βk�E���k������o�̔��\���Ɍf����B
1959�i���a34�j�N
6���@�x�����i�������сE7�j�A���l�̃m�I�g�i�����j
11���@�̂̎���ȂƐS�̎���l�Ɓi�����j1961�i���a36�j�N
2���@�A���P�[�g�u�Z��N�x�Ɋ��҂���V�l�v�i�����j1964�i���a39�j�N
4���@�؍݁i�E�E7�j1965�i���a40�j�N
3���@���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j1966�i���N41�j�N
4���@�Â��ȉƁi�E�E16�j1967�i���a42�j�N
2���@������G�i�E�E15�j
10���q���W�E�g�����̐��E�r�@���́i�F�E3�j�A�͌ЂƂ������E�ցk����N�v�Ƃ̑Βk�l�i�����j
12���@�ѓ��k��u��������́v�E���i�����j1968�i���a43�j�N
4���@�����������W�����������̎��i�s�u�����v�Ƃ����G�t�j
11���@�J�i�F�E9�j1969�i���a44�j�N
10���@�킪�n�j�R���X�̎v���o�i�F�E16�j1972�i���a47�j�N
6���@���C�X�E�L��������T�����@�\�\�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�k�����`���l�i�G�E11�j�k�s�ʍ����㎍�蒟�@���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�t�l1973�i���a48�j�N
7���@�T�t�����E�݁i�G�E1�j1974�i���a49�j�N
4���@����̔ӎ`�i�G�E13�j
10���k�Վ��������l�@�ǎ�̏��i�G�E22�j1975�i���a50�j�N
1���@�T�C�����g�E���邢�͍��i�G�E25�j
5���@�v�z�Ȃ�����̎��l�k�ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�Ƃ̍��k��l�i�����j
9���@�V�������ւ̖ڊo�߁\�\�k�����ʁw�������W�x�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�j1976�i���a51�j�N
8���@�y���i�H�E1�j1977�i���a52�j�N
2���@���A�k��������܁l�i�����j
5���@�u�z���͎͂��@�z������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�j1978�i���a53�j�N
3���@�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���k�C���^�r���[�l�i�����j
4���@�`�͕s���̉s�p�������c�c�i�H�E11�j
9���@�킪�������W�w�t�́x�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�j1979�i���a54�j�N
2���@���z�k�������ܔ��\�l�i�����j1980�i���a55�j�N
2���@���z�k��\�����ܔ��\�l�i�����j
10���q���W�E�g�����r�@���܂�͂����L�����a�\�O�N�i���O���j�A���a�\�l�N�i���O��j�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�s���܂�͂����L�t�j�A��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցk������b�q�Ƃ̑Βk�l�i�����j1981�i���a56�j�N
2���@���z�k��\������ܔ��\�l�i�����j
5���@���ƏҊ��i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�j
9���@�G�̐��i�J�E2�j1982�i���a57�j�N
7���@��ނȂ����I���݁k�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�Ƃ̐��e���O�Y�Ǔ����k��l�i�����j1983�i���a58�j�N
1���@�t�v���i�J�E11�j1984�i���a59�j�N
6���@���ρi�������сE16�j1985�i���a60�j�N
1���@����Ǝn���k�I�N�^�r�I��p�X�E�剪�M�E�a��F��E�g�������Ƃ̍��k��l�i�����j1986�i���a61�j�N
2���@���_�̂��Ƃ��\�\�����i�s�y���F��t�j
8���@���i�i�K�E11�j1987�i���a62�j�N
9���@�x���i�������сE18�j1989�i���a64�^�������j�N
3���@�u�P�l�v���������Ȃ��ցi�����j
��f�̏��o��i�̓������q�ׂ�u���т�60�N��v�\�u���z��70�N��v�\�u�Βk�E���k���80�N��v�ƂȂ낤���B���o�̂ق��ɂ��A���}�̔��\�̎��т����N�P��̂悤�ɔN���́q���㎍�N�Ӂr�ɍĘ^���ꂽ���A�g���̐l���ƍ�i�Ɍ��y�������͂����O������80�ы߂��f�ڂ���Ă��āA�g�����Ɓs���㎍�蒟�t�̉��͐�ʂ��̂�����B���������Ȃ��ŁA1967�N�̑S���W�I�ȁs�g�������W�t��80�N�̏��̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i��������v���Њ��j�ɍ��킹�����W���̑��݂͓��M�����B�����̏��Ђ�G�����W���̑����I�Ȃ��肩���́A�y�Ђ́s�����C�J�t�g�������W���i1973�N9���j���s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j��p�ӂ����̂Ƃ͑ΏƓI�ŁA�����[���B
 �@
�@
�s���㎍�蒟�t1967�N10�����i���j�Ɠ��E1980�N10�����i�E�j
�s���㎍�蒟�t�͑n���i�g���������d�œ��p��\�킵�Ă��������ɓ������j�ȗ��A�g���̟f������������B��ɂ��Ė���̎����ł���i�����ɂ��̔����I�ԁA�����Ǝv���Ђ�S���Â������c�v�Y���Ɨ��̕ҏW�҂̑���ȍv�������������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��j�B���Ȃ݂Ɂs���㎍�蒟�t�i�s�ʍ����㎍�蒟�t���܂ށj�ɏ��o�̋g��������20�т𐔂��A�s�����C�J�t�k�y�Ёl��19�т����炭���}���ăg�b�v�ł���A�S����284�т�7���ɑ�������B�������͎��̐��ł͂Ȃ��A�����g���������\����q�T�t�����E�݁r��т��f�ڂ��������Ƃ��āA�s���㎍�蒟�t���i���L�����邾�낤�B
�k�NjL�l
�s�����C�J�t�k�y�Ёl�ɏ��o�̋g������19�т͈ȉ��̂Ƃ���B�x�M������1970�N��̍�i�͐��܂����Ƃ��������悤���Ȃ��A�s�T�t�����E�݁t���y�Ђ���o���̂�������B
1969�i���a44�j�N
8���@�ẲƁi�F�E13�j1972�i���a47�j�N
4���@�t�i�G�E4�j
11���k�Վ��������l�@�^�R�i�G�E2�j1973�i���a48�j�N
1���@�}�_���E���C���̎q���i�G�E5�j
9���q���W�E�g�����r�@�c���i�G�E14�j
11���@�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�j1974�i���a49�j�N
12���k�Վ��������l�@�]���l���V���^�[���̑D�i�G�E24�j1975�i���a50�j�N
9���@���e�j�i�O�m�[�����j�i�G�E27�j
12���k�Վ��������l�@���܂�����i�G�E30�j1976�i���a51�j�N
11���k�Վ��������l�@���i�H�E8�j1978�i���a53�j�N
7���@��i�H�E3�j1979�i���a54�j�N
7���@�r�́i�H�E23�j
11���k�Վ��������l�@�~���̓����i�H�E28�j1981�i���a56�j�N
11���k�Վ��������l�@����i�J�E7�j1982�i���a57�j�N
7���@���́i�J�E13�j
12���k�Վ��������l�@�H�v���i�J�E8�j1984�i���a59�j�N
12���k�Վ��������l�@�����q杁i�K�E4�j1986�i���a61�j�N
12���k�Վ��������l�@�Y��i�ނ��сj�i�K�E1�j1988�i���a63�j�N
6���k�Վ��������l�@��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�i�K�E17�j
���Ȃ݂Ɂs�����C�J�t�k���惆���C�J�l�Ɍf�ڂ��ꂽ�g�������́q�m���r�i�C�E8�A1957�N4���j�A�q�����r�i�C�E19�A1958�N7���j�A�q�́r�i�D�E9�A1959�N10���j�A�q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE10�A1960�N6���j�A�q�ߔ��r�i�D�E16�A1961�N1���j��5�тŁA��������N1�т����\����Ă���B�u�G���q�����C�J�r�ʊ��\�O���̂����A���͌ܕт̎��\���Ă���B����͑����Ƃ͌����Ȃ����A�܂����Ȃ��Ƃ������Ȃ��v�i�q�u�����v�Ƃ����G�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�Z��y�[�W�j�B
�g�������s��ʁt���s���i1983�N10���j�ɒE�e�����q�k���M�l�N���r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��
20���j�ɂ��āA���͂��Ď��̂悤�ɏ������B
�u�q�N���r�͗B��A�g�������M�̔N���B�q�g�����ڍהN���r�i�s�����C�J�t1973�N9�����q���W���g�����r�j����{�ɂ��A������ꂽ�ӏ܋L�^���[����
�Ă���B400���l���e�p�����Z�Ŗ�22���B1984�N1��31���t�����V���[���́q��g���g�r�́u������l�͂��������}�l�ł������āA��낵���B���̔N
���A����҂ɒʂ����Ƃ܂ŏ����Ă����āA���ꂪ���Ƃǂ�ȊW������H�@�Ƃ��������Ȃ邪�A����ς�V���[���ȊW������̂ł��낤�B�^���㎍���ЂƂ���
�̐l�C�����߂����߂ɁA�g�����Ȃ�����Ғʂ��܂Ŋ܂߂����`�������������Ƃ���]���Ă������v�i��ʁq�V���[���ȊW�r�j�ƕ]�����B�u����Ғʂ���
�Ŋ܂߂����`�����v�͏�����Ȃ��������A�̂��́s�y���F��t�͂��̕]���ӎ����Ă��邩�v�i�q�g
�����̔N���r�A�O��̂Ȃ�����l�����Ĉꕔ���ς����j�B
�g���̎��т�z�q�v�l�����邱�Ƃ͍L���m����Ƃ��낾���A�U���Ɋւ��Ă͕v�l�����e�ɖڂ�ʂ����Ƃ͂����Ă��A�������邱�Ƃ͂Ȃ������悤���B����
�݂Ɂs���i�t1974�N3�����Ɍf�ڂ��ꂽ�܂ܒP�s�{�ɖ����^�̐��z�q���̖ʉe�\�\���������́r�̌��e�́A�g���̎��M�Ŏs�̂̃R�N����200���l�ߗp��2
���ɂ킽����21�s�̖{����������Ă���B
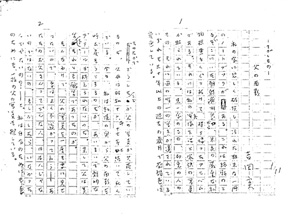
�q���̖ʉe�\�\���������́r�i�s���i�t1974�N3�����f�ځj�̋g�������M���e�i2�����j
�k���m�N���R�s�[�l
�q�k���M�l�N���r�́A�g�����g�̐��z����L���\�[�X�Ɏ��M�������̂Ǝv����B�t�ɂ��̋L�q�����Ƃɐ��z�����Ĕ��\�����̂��A���Ɉ��� �q���a�l�\�� �N�r�̌㔼�̋L�ڂ�W�J�����q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�i���o�F�s��t1988�N2�����j�ł���B�q�k���M�l�N���r�́s�y���F��t�ȑO�ł͍� ���̕��́i�������낵�j���������߂��A�������̌�L�E��A���c�����ƂƂȂ����B�ȉ��ɁA�ŗL�����𒆐S�ɖ��ӏ����Z������`�Łu�뎚��{�l�̊��Ⴂ�v �i�z�q�v�l�j���f���邪�A������V���ŕ\�킵���w���w�E�x�Ȃǂ͎w�E���Ȃ������i�{�T�C�g�ł́s���{�E�t��s���Y�t�ƕ\�L�j�B
�@���a�\��N�@���O���N �\����
�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łw�݁k�����Ál��x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������B�@���a�\�l�N�@���O��N ��\��
�d���ɋ^��������A��R����ގЁB�����F���m�i������j�։������A�q�������ɏK����������B�k����͑O�N�A���a�\�O�i���O���j�N�̂��Ƃł���l�@���a�O�\�l�N�@���܋�N �l�\��
���惆���C�J�́u�����̎��l�k�p���o�l���v�̈���Ƃ��āA�w�g�������W�x�����s�B�@���a�l�\��N�@���Z���N �l�\����
�āA�_�c�̋i���X����ŁA������b�q�Ə��߂ĉ�B�\��A���ɏ܌��ɂȂ藈�ЁB�k�āA���i�g���j�l���c�J���̋i���X�@��ŁA�X�仂Ɖ�A���` �w�L���̊G�x�o�ł̑��k������B�@���a�l�\���N�@��㎵�O�N �\�l��
�H�A�w�����C�J�x�Łu�g�����v���W�����s�B����̎O�\�O����̖@�����A�����^�����ł��ƂȂށB�k�H�A���i�g���j�l�}�����[�̑n���ҁA�Óc��}���B�k�c�c�l �k�t�����āl�A�w�����x�����ł�[��p����芧�s�B�@���a�l�\��N�@��㎵�l�N �\�܍�
�H�A�R�`���߉��s�ԓc�֍s���B�u�k�������h�v���������u����v���ς�B�����̈Í������h���Q������B�H���R�����R�r���Y�ƎQ�w����B�k����͗��N�A���a�� �\�i��㎵�܁j�N�u�H�v�̂��Ƃł���B�s�y���F��t�́q50 �u����v�r���Q�Ƃ̂��Ɓl�@���a�\��N�@��㎵�Z�N �\����
�t�A�p���w���C���b�N�E�K�[�f���x�i�����h����ҁj�V�J�S�������[�k�i�i�V�j���v���X�l��芧�s�����B�@���a�\�Z�N�@��㔪��N �Z�\���
���u����v���w�����C�J�x�k�ʍ����Վ������l�i���㎍�̎����j�ɔ��\�B�@���a�\���N�@��㔪��N �Z�\�O��
�k�����U���l�u���e���O�Y�A���x�X�N�i�Ǔ��j�v���w�V���x�������ɔ��\�B�@���a�\���N�@��㔪�O�N �Z�\�l��
�F�V�k�끨���l�F�A�O�D�L��Y�A�푺�G�O�A�r�c�����v�A�߉��P�v�̂�������v�l�����B�k�c�c�l������ق́u�k������l���C�����Âԉ�v�ŁA�����ĔV�A�r�c ���Y�A����F���A���[�����A�ޒJ���m��ƒk����B
�k�t�L�l
�g�����̌������L�Ɓq�k���M�l�N���r���������e�������Ă������A��g����������B
�k���a��\�O�N�l��\����@�o�ɕٓ������Ďł̍s�{�W��̂Ƃ���ւ䂫�A�ꏏ�ɐ� �֏o��B ���b�N���őS���ɂ����������[�������݂ċ��Q�A�����o�^�t���C�B�V���[�N���[���ƃR�R�A�B�ٓ������ĐH���B�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍���� 14�l�t�A�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j
�F�l�Ɛ֍s���A���b�N���őS���ɂ����������[�����̗x������ċ��Q����B�i�q���a��\�O�N�@ ���l���N ��\��r�j
�g���́q����f�́r�i���o�F�s�o�匤���t1983�N7�����j�ŃW�v�V�[�E���[�Y�i1934-67�j�ɐG��āu�����[�����A��ȋ��q�A�L �e�B���c�Ȃ� �̖��͂���X�g���b�p�[�����̂����ł��A�W�v�V�[�E���[�Y�͓��{�l����̂������̂ƁA���\�������Ȃ��Ă����B�܂��鏈�Ƀo�^�t���C��t���Ă���������� ��B���͐̏����Ȍ���m����n�ŁA�͂��߂ăW�v�V�[�E���[�Y�̗x��Ƃ��̔������g���܂Ԃ����A���������̂������B�q�����Ă����c�J�͎O�̔M�����I�� �ƁA���s�����N���̒m�l�������ƕ���ߊ��A�ԑ���������̂ŁA���͂������ɂƂ�ꂽ�B���ꂩ�炵�炭��A�m�l�͎��E���Ă��܂����v�i�s�u�����v �Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O���y�[�W�j�Ə����Ă���B����ȂǓ��L�̋L�q�����Ƃɖc��܂������̂ɈႢ�Ȃ��B���́u�N���̒m�l�v�� �u�s�{�W��v�\�\�q�k���M�l�N���r�ł́u�F�l�v�\�\�Ƃǂ������W�Ȃ̂��낤���B�q�f�ЁE���L���r�́q�k���a��\��N�l �\����\�ܓ��r�ɂ� �u�u�J��V���v�̍Z���͎����܂ł�����B�N���u�����̒n�����ɏZ�ލs�{�W��������˂�B���x�[�H�̎��Ȃ̂ŁA����t�̔ނ̂��₵���Ȏ藿����H���B�N���u �ł̓_���X������Ă���̂��낤�A���y�������Ă���B�R���i���z���A�ǓƂȒj�����v�i�O�o�A���Z�y�[�W�j�ƌ�����̂����B
�k2009�N10��31���NjL�l
�}�����s�ӂ�ނ��Ή������������t�i�V���ЁA1988�N11��15���j��ǂ�ł�����A�u������y���v�Ɋւ��镶�͂��������i�q�f��فu������y���v��
���Ȃ炸�㎞�I�f�A�̕s�v�c�r�j�B
�����̎O�̌���k������y���A�ׂ�̏�Ձm�Ƃ���n���i���x�فj�A���ׂ̗�̋����m�����䂤�n�فi���ݐ� �����|�j�l�ɂ́A��K������n��L���Ō���ŁA��̑����œ��ꗿ���A�O�ق̉��m���n������������V�X�e�����������B���N�̐t�@���ɂ́A�u�O �ً��ʁv�Ƃ��Đe���܂ꂽ�B�i�����A��܃y�[�W�j
�����ǂ�A�E�F�u��̎ʐ^�������肷��ƁA�g���́u�N���u�����v�͓�����y���i1913�N�J�ƁE1991�N���A�䓌���1�� �ڂɂ������m ����̉f��فB�ʖ��A�����N���u�E�����N���u�j�Ƃ����C�����Ă��邪�A�c�O�Ȃ��ƂɁu�n�����v�̋L�q���Ȃ��B�g���̓��L����́A61�N�O�̓y�j�� ��A�����l�߂��d���ɔ�ꂫ���āA�̂܂ܗF�l�̏Z�ތ����i���ꂪ�ӂ��̏Z���łȂ����Ƃ͊m�����j��K�˂��Ɛg�҂̎p��������ł���B
���l�̉��c���Y�͎����s���ԂƋ�ԁt�i���ԂƋ�Ԃ̉�j36���i1996�N1���j����45���i2000�N7���j�ɂ����āA9��ɂ킽�� �āq�g���� �_�r��A�ڂ����i38���͋x�ځj�B�s���ԂƋ�ԁt46���i2001�N1���j�́q�Ǔ��E���c���Y���r�ɂ��A����2000�N7��11���ɖS���Ȃ��Ă���A �q�g�����_�r�͂����炭����1��Ŋ����̗\�肾�����炵���B���̖����̒��ѕ]�_�i400���l���e�p���Ŗ�390���j���A���̌㏑�ЂƂ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�`�� �͂Ȃ��A�����L���m���Ă���Ƃ͌����������i���Ɏ����A���㐸��̃E�F�u�T�C�g�̏Љ�Œm�����j�B����A��������}���ُ����́s���ԂƋ�ԁt���{ �������̂ŁA���c���Y�q�g�����_�r�̊T�v�����B�e��̕W��������ŕ\�L�i�k�@�l���̃��[�}�����T�`�X�́A�� ���ɂȂ��������̂����т�������j�F���o���A�m�@�n���ɍ����Ɣ��s�N���A�f�ڃy�[�W������ŁA����ɍs�����߂āA�{�����Ɉ��p���ꂽ�g�����̍�i�������� �Ōf�����B
�g�����_�k�T�l�F�̏W�@�����^���W�@�t�� �m36���A1996�N1���A51-63�n
�� �i�B�E14�j�A�o��u�ԃg���{�v�u�Ί_�́v�u�������v�u�H����v�A�Z�́u���Ấv�u��Ƃт��v�u�y�K���v�A�҉́i�A�E1�j�A�q�́i�A�E10�j�A���i�i�A�E 19�j�A�t�̇T�i�A�E26�j�A�t�̇U�i�A�E27�j�A�ߐ��i�A�E28�j�A�Z�́u��Ԃꂽ��v�u���o�́v�u���͂ꂵ�v�A��́i�C�E13�j
�g�����_�k�U�l�F���W�u���v��� �m37���A1996�N7���A70-87�n
�o ��u���M����v�u�䂭�t��v�u���~��v�u�~�̓��́v�A�~�̉́i�B�E8�j�A�Õ��i�B�E1�j�A�Õ��i�B�E2�j�A�Õ��i�B�E3�j�A��i�B�E14�j�A���i�B�E 7�j�A��́i�C�E13�j�A�]�́i�B�E11�j�A�Õ��i�B�E4�j�A���̏ё��i�B�E16�j�A���i�B�E6�j�A�Ă̊G�i�B�E9�j�A�ߋ��i�B�E17�j
�g�����_�k�V�l�F���W�u�m���v��� �m39���A1997�N7���A59-73�n
�m���i�C�E8�j�A�����i�C�E2�j�A���Ƒ��i�C�E14�j�A�r�� �i�C�E15�j�A�����i�C�E19�j
�g�����_�k�W�l�F�q��́r �q���W�@�a���`�r �a���`�i�T�j�i�U�j �m40���A1998�N1���A87-100�n
��́i�C�E13�j�A�쌀�i�C�E1�j�A�V�l��i�D�E1�j�A���� �i�D�E3�j�A�a���`�T�i�D�E4�j�A�a���`�U�i�D�E5�j�A�́i�D�E9�j�A�c�Ɂi�D�E10�j�A�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�j�A���̕a�C�i�D�E 11�j�A�~�̋x�Ɂi�D�E12�j�A�C���Əȗ��i�D�E22�j
�g�����_�k�X�l�F�q�Â��ȉƁr �m41���A1998�N7���A71-83�n
���i�D�E17�j�A��`�i�D�E19�j�A�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G�� ��i�E�E4�j�A�n�E�t�̊G�i�E�E5�j�A�؍݁i�E�E�V�j�A�� ����i�E�E6�j�A���\�\���̓��B�N�g���[�i�E�E8�j�A�₳�������Ζ��i�E�E9�j�A���E�H�̊G�i�D�E21�j�A���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j�A�ǓƂȃI�[�g �o�C�i�E�E14�j
�g�����_�i�Y�j�F�u�_��I�Ȏ���̎��v�� �m42���A1999�N1���A79-88�n
�_ ��I�Ȏ���̎��i�F�E11�j�A�����́i�D�E15�j�A���i�D�E17�j�A��`�i�D�E19�j�A���E�H�̊G�i�D�E21�j�A���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j�A���� �i�E�E3�j�A���I�ȗ��S�i�E�E12�j�A������G�i�E�E15�j�A�F�ʂ̓����i�F�E4�j�A�����i�F�E5�j�A�������i�F�E10�j�A���āi�F�E8�j
�g�����_�i�Z�j�F�k���o���i�V�l �m43���A1999�N7���A92-99�n
�ቹ�i�F�E14�j�A���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j�A�킪�n�j�R ���X�̎v���o�i�F�E16�j�A�R�����i�F�E18�j�A�q�́i�C�E7�j�A�����͂ǂ��ɂ��邩�H�\�\�y���F�̔�V�ɂ悹�āi�F�E6�j�A�t�i�G�E4�j
�g�����_�i�[�j�F�u�T�t�����E�݁v �m44���A2000�N1���A101-111�n
�T�t�����E�݁i�G�E1�j�A�D���̎O�̒[�z�i�H�E16�j�A�t �i�G�E4�j
�g�����_�i�\�j�F�u�T�t�����E�݁v�Ȍ� �m45���A2000�N7���A104-112�n
�t�i�G�E4�j�A�^�R�i�G�E2�j�A�}�_���E���C���̎q���i�G�E 5�j�A�킪�n�j�R���X�̎v���o�i�F�E16�j�A�w�A���X�x���i�G�E12�j�A�ǎ�̏��\�\����C�����Ɂi�G�E22�j�A���e�j�i�O�m�[�����j�\�\�F�V���F�̃~ �N���R�X���X�i�G�E27�j
�g�����ŏ����̔o��E�Z�̂��玍�W�s�T�t�����E�݁t�i1976�j���Ȃ킿���������Ƃ���́u�����g�����v�܂ł����n��Œǂ��āA�e���� �̓������Ƃ� ����X�^�C���́A�ʉ�F�́s�~�Ɨ��`�\�\�g�����m�[�g�t�i�v���ЁA1975�j��ߎR�T�i�́s���l�ɂ��āt�i�l�Ώ��ЁA1998�j�Ɠ����ł���B�܂��� �����ȏ��q���@�Ƃ����悤���A�N���I�ȗ\�蒲�a�̓W�J�ɑ������d����댯������B���c���Y�̋g�����_�͂ǂ����낤���B���W�s�Â��ȉƁt��_�����k�X�l�� �ꕔ�������Ă݂�B
�k�c�c�l���W�w�Â��ȉƁx�͌����ĕ��ÂȎ��Ƃ͉]���Ȃ��B����S�����Ă̎��ł���B�ό`�����B�ɓ������܂�āA���l�͎l�ꔪ�ꂵ �Ă���B
���̏�̐�������Ō���̂́@�H
���j�I�Ȋy����������@�H�@���̓�s�̋^�╶�͎��l���S�̓��h�����������ɂ��邱�Ƃ�����Ă���B����͌l�ɊW�Ȃ��n�߂��A�l�̎��ŕ�����B
�킽���͏j�Ղ��Ă�肽���Ǝv��
�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv����Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂𗬂��Ǝv��
�e�[�u���̌����ɎR���ƕX��b���̗�
�킽���͂���炪�����Ȃ�
�^�g�ȐF�̎�����]��ł��� �q�͎ʁr�@���̉��ЂƂS���J�����Ƃ��Ȃ��\���B����炵��������̂͐l�Ԃ����t�Ƃ��đ��݂��Ă��鎞�����ł���B�q�N�[�g�̊G����r�Ƃ� �������k�}�}�l�ɂ������ȋ������A���c�Ȏ��̂̕��m�������A�ǂ���Ƃ��Ă��A���̂͐������̂Ƃ��Ă䂳�Ԃ�U�����Ă���B
�������̌҂܂ł̕S���̏�^�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯���^���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S�́^�s���S�ȔR�Ắ^�~���N�[ ���[�Ɨ₽�����q�͎ʁr
�@ �����ɂ͂Ђ��ނ��ɉ����u���ւƎ������̍�������߂Ă���B�푈�Ɣw�������̒����̗��j�́A�����Ă����b�ł͂Ȃ��A�����̕��ꂩ�玀���ς����k�}�}�l�N ������B�l�͎���I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A�I��������B���̍�i�����łȂ��A����Ȍ�̌X���Ƃ��Ēʏ́k�}�}�l�������p�ɂɎg���n�߂�B���A�I�A��C�A�R �́A�j���W���A�L���x�c�A�ցA�b���@���X�G�R�Ƃ������i�ł���B�k�c�c�l�i�s���ԂƋ�ԁt��41���A1998�N7���A���l�`���܃y�[�W�j
����́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i���o���ځj��_�����ӏ������A�Ɠ��̌����܂킵�ōʂ�ꂽ���c�̉��߂̓��ۂ͖��Ȃ��B������ �ڂ������� �́A�����o�T�ł���B�q�͎ʁr�Ɍ��炸�A���c�������܂ł̖{�_�ň������g�������̓T���͂����炭�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�����A�����ł̖{���� �u�e�[�u���̌����ɎR�ԁ@�X��b���̗��v�ł���q�͎ʁr��45�s�̎��傪�A���c���ł́u�e�[�u���̌����ɎR���ƕX��b���̗��v�ƂȂ��Ă���̂́A���o�`�� ���������߂��낤���B�����͎v���Ȃ��B�N���W�b�g�̂Ȃ����Ƃɂ���邪�A�q�g�����_�r�̓W�J���̂��̂����o�`�̓o��������Ȃ��̂��B��f�����̋g�������� ���p�ɂ́A�]�L�~�X�Ǝv�����Ƃ��낪6�ӏ��i�u���̏�̐�������Ō���̂��@�H�v�u���j�I�Ȋy�����������@�H�v�A �u��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂������Ǝv���v�A�u�킽��������炪�����Ȃ��v �u�^�g�ȐF�̎������]��ł���v�A�u�~���N�[���[ �Ɨ₽�����v�̉������j������B�����������͂������ہA����̈ꎚ�������낻���ɂ��Ȃ��p�������߂���B�ׂ������Ƃ������悤�����A�����ŗׂ肠���� ���Ȃ��������ׂ����p��1�s��ׂ������A��f���p�ɂ͂Ȃ��u�a���`�v�ɂ������Ắi��̗��������͍̂T���邪�j�A�������\�L�̕������Ȃ��قǂ��B �g���������������Ȃ�Ǝv�����낤�B�����������҂�ҏW���͂����ƍZ�������̂��B
�\�\�\�\
�ȉ��ł́q�͎ʁr�̏��o���߂���ŋ߂̏��q�ׂ�B����A�苖�̋g�����������������Ă����Ƃ���A�V��ޓ�Y�E���c���F�E���c�O �k�C�k�l�q���]�`���ɂ�錻�㎍�l11�l�_�U�\�\�g�����_�r�i�s���㎍�蒟�t1964�N2�����j��
���c�@�R��Ƃ������ƂɊ֘A���ĕ⑫���邪�u���w�v�̂Ȃ��̇��ڂ��͉�Ƃ����燁�Ƃ����� �t�������������ׂȂ���u�͎ʁv�̂Ȃ���
�@�����N�̂ނ�@���̂�����������
�@�������A�X�p���K�X
�@��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv��
�Ƃ����Ƃ�����I�[�o�[���b�v�����ǂނƂˁA�g�����������̂��߂ɗ܂��Ȃ����̂��Ȃ��Ǝv��������ĂˁB�������ȁB�����Ɨ⍓�ł����Ăق����� �ɂˁB�D�����l�͂�͂�₳�����Ȃ��Ă䂭�����Ȃ��낤���B�i�����A�O��y�[�W�j
�Ƃ������������߂ēǂ�ŁA���c�O�ɂ��q�͎ʁr�̈��p�͏��o���炾�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����l�����ӂ��ɗN�����������B���W�s�Â��� �Ɓt �i1968�j�ɂ͐���N��Ƃ��āu1962-66�v�ƕ\������Ă��āA�i1959�N3�����\�́q���߁E�L�߁r���O�Ƃ���j�m����1962�N9�����\�� �q���̂��߂̃g���̎��݁r����1967�N2�����\�i�E�e��1966�N�����j�́q������G�r�܂ł́A�q�͎ʁr�������S�т����W���^�O�ɎG���f�ڂ���Ă���B ���������āA�ٕ��s�g�����N���k��i �сl�t��
���Z���i���a�l��j�N �l���`�l���@�k�c�c�l�^�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����i�E�E4�A�l���s�j���o���ځk�����̔N��Z���܂łɔ��\���l191
�ƋL�ڂ������o�N�����i�s�Â��ȉƁt�͒P�s���W�ɐ�삯�āA1967�N10�����̎v���ДŁs�g�������W�t�ɑS�ю��^���ꂽ�j�A��f�C�k ���s�Ȃ�ꂽ �ł��낤1963�N���������Ƃ��ׂ��J�肠���邱�Ƃ́A���W�̐���N��u1962-66�v�Ƃ����v���Ă܂��ƂɍD�s���ł���B���Ƃ���A���o�T���̏��a �́s�m���t�i1958�j�Ɓs�a���`�t�i1962�j�ŋg���������f�ڂ������Ƃ����������s����1962�N����66�N�܂ł̃o�b�N�i���o�[������݂Ԃ��� ���ׂĂ������Ƃ�������Ȃ��B�����ł��������s���w�t�ɓ�����Ȃ����Ă݂����A�\�z���Ă������ƂƂ͂����A��U�肾�����B�����A�˖{�M�Y���q���l�ɂ� �ār�i1959�N7�����j�Ƃ������͂ŁA���삿���̎��q���̕E�r�� �̗g���Ă���̂����߂ēǂނ��Ƃ��ł����̂́A�\�����Ȃ����n�������B
�k�t�L�l
���c���Y�́q�g�����_�r�A�ڒ��O�́s���ԂƋ�ԁt35���i1995�N7���j�Ɏ��q���؍Ձr�\���Ă���B�U���ł́A31���i1993�N7���j�Ɍ��c���q
���W�s�V�h�E���Y�̍��t�i层̉�A1992�j�̏��]�A32���i1994�N1���j�ɐ쐙�q�v���W�s�F�����t�i���w�ЁA1993�j�̒����̏��]�A34��
�i1994�N12���j�ɏ��È���Y��i�ɂ��ẴG�b�Z�C�\���Ă���B�����̒Ǔ����Ɉ˂�A���c�ɂ�18�т��琬��s�����t�i���c���Y�A1989�N
8��15���j�Ƃ���250������̎��W�����邪�A�q�g�����_�r�̘A�ڒ��͎��\���Ă��Ȃ�����A���́q���؍Ձr���Ō�̎���i��������Ȃ��B�Ǎ��ň��p
���悤�B
���؍Ձb���c���Y
�̂�����́^�݂��Ɂ^���̐�����ǂ������^�ǂ��z���˂Ȃ�Ȃ������^�����@���Ȃ܂������u���̂ڂ�߂�
�� �̂��߁^���͐�N���A��葬���o�����ā^�����I��������Â����^�X�ɐ�N���͂邩�����^�l�ނ̐�X�ɑҕ����Ă����^�n��Ɂ^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�� �Ɂ^��̊ԂɎ葫�����������Ă����^�i�����b�݁^���n�̂Ȃ��Ɂ^�������G�����葱�����^���C�[���^�⏧�̃N���[�^�[�Ɂ^�����̒B��H������^�����̈��� �̂�D��
���̂Ɛ₦�����^���C�ɂƂ�c����ā^�͂ꂽ�r�@�L���̏��w�Ɂ^���E�̒������͍A���ł��^����̍Ղ�֑͋���Ƃ��ā^���̂������� ��^�ӂɂ���܂ꂽ�o���́^�ʎ��͏��n�ɗ����^������D�͂�^�G�Z�̔R����^�Ɏ���N���Ă���
�� �N�𑫎~�߂���^���ꂩ���́^��N����肷�邽�߁^�݂����������ߊ�������́^�Ñw���ォ��^����Â��^�������ނ�ǂ��z���^���b��ǂ��� �����^���A�l�ނ�ǂ������Ă���̂��^���w���I�ɖ��܂������́^�@��Ԃ���A���ݏグ��ꂽ�^���c����^����ȃv�����g���𐁂������Ă���^�������� �����̐��E�^�S�W������栂��n�߂����肾�^�n���n�܂��Ĉȗ��̔ɉh�ƕn���^�n���n�܂��Ĉȗ��̊i�����^�n����Ă��
�I��肩��l�߂̎���́u��栁v�́u���Q�v�̌�肾�낤���A���ׂČ����̃}�}�ł���B�{�т͋g���́q���r�i�B�E6�j�܂������� ���B���Ȃ݂ɉ��c�́q�g�����_�k�U�l�r�œ��������p���Ă���B
�k2016�N10��31���NjL�l
�g�����̎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�������������B1963�N8�����s�A���q�����ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A
���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�����ꂾ�B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�i���W�s�Â��ȉƁt���^�j�̊Ԃɂ́A�Ђ炪�Ȃ̑����i�u���v�^�u�v�j�̕\�L����
���āA����Ɉٓ��͂Ȃ��B
�g�����̎��сq�����r�i�C�E18�j�͎��W�s�m���t�i1958�j�ɂ����ĈِF�́A�̂��镨��ӂ��̍�i�ł���B�g����������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�Łu�����@�ł��A�A���X�̎��̎��͂킽���͊����������ȁB���Č����������A���Ə����̏o�Ă��鎍���y��������D���łˁB�u�����v�Ƃ������ˁB�^�g���@����͈ӊO�Ȑl�ɍD����Ă�̂ˁB����́A�W���[�t�E�P�b�Z���́w����x�Ƃ����������ڂ��͐�O����ǂ�ł��邩��ˁB�f��̉e���ł͂Ȃ��v�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A���Z�y�[�W�j�ƌ���Ă���悤�ɁA���̎����D�ސl�͑����B�y���F�̕\���́u�����ɂ��v�Ǝv�킹�邵�A�V�V�ޓ�Y�̓��W�I�̋g�������W�ԑg�Ŗ{�т�N�ǂ��Ă���B����A�����́s����t�i�����sBelle de Jour�t��1929�N���s�j�͍����A���C�X�E�u�j���G���ēA�J�g���[�k�E�h�k�[���剉�̃t�����X�f���s����t�i1967�j�̌���Ƃ��Ēm���邪�A�ނ��f��Ƃ͕ʌ̓Ɨ�������i�ł���B�g�����u��O����ǂ�ł���v�͖̂x����{��̒��я����s����t�i��ꏑ�[�A1932�N6��15���j�ɈႢ�Ȃ��B���݁A�{�������܂茩�Ȃ��̂́A��v�ۋv�Y�ҁq��ꏑ�[���s�}���ژ^�r���L���u�i�Z����\����������Q���闝�R�ɂ�蔭���֎~�j�v�i�ђB�v�E���c���l�E�z��p���q��Ғ��s��ꏑ�[ ���J�얤�V�g�t�A���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1984�A��y�[�W�j�Ƃ����[�u���e���������̂��B���Ȃ݂ɁA��������}���ق͖{���̑�ꏑ�[�ł��������Ă��Ȃ��B
 �@
�@
�W���Z�t�E�P�b�Z���i�x����{��j�s����t�i��ꏑ�[�A1932�N6��15���j�̕\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�g���́s���܂�͂����L�t�i1990�j�́u���a�\�l�N�i���O��j�v�ɂ́u�܌���\����^�P�b�Z���w����x�B�k�c�c�l�v�i�����A�l��y�[�W�j�ƌ����邪�A�{���������肵���̂��낤�B��Ɋ����J�X���s�����P���W�t�i��ꏑ�[�A1939�N6��10���j�����s�����̓���18���ɓ��肵�Ă���g�������A�s����t��V���Ŕ��֑O�ɍw���������Ƃ́A13�Ƃ��������̋g���̔N����l����A�܂��Ȃ��������낤�i���L�́s����t�́A�s�w�����v�l�Ƒ����B�t�̂Ƃ��̂悤�ɁA�o����O�ɔN���̗F�l����ؗ��������̂��j�B����Ȃ�A1958�N8��8���ɋg�����q�����r��E�e�����Ƃ��A��ꏑ�[�Łi�������͌�o�̑��̔Łj���苖�ɒu���Ď��삵�����낤���B���̉\���͒Ⴂ�Ǝv���B�g������ЂłقƂ�ǂ̑����������Ă���_�͓x�O�����Ă��A�q�����r�́u�T���̎��w�v�����ƂɎ��M�����ɂ��Ă͐�����������B��f�̑Βk������A�L���̂Ȃ��ɂ���s����t�̏���l���̐l��������|����ɁA�z���͂̕����܂ܑn�삵���l�q������������B�����Łs����t�̖M�����X�g�ɂ��Ă������B
3.����6.�ɂ����Ă̔łŋg�����ēǂ��Ă��ĕs�v�c�͂Ȃ����A���́s����t�Ɋւ��錾�y���Ȃ��̂ŁA�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B�����ŁA1.�̖{�M���玍�сq�����r�Ƃ̑Ή�������������q�v�����I�O�r��S�����p����B�ł킸��2�y�[�W�ƒZ���Ȃ�����A�s����t�̃��C�g���`�[�t�Ƃ��ĕs���Ȉ�߂ł����i���j�B����ɑ����āq�����r�`���̂P��Ǎ��Ōf����B
�@���̍����m��n�ɂȂ��Z�����B�k�́A�����̎������̎��֍s���̂ɁA�����L����ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����B�ޏ��͂��̓r����ދ����āA�������킯�Ēʂ邱�Ƃɂ��Ă�B���钩�ޏ��́A�L���̒��قǂ܂ŗ��āA�����~�܂��B�L���̂����̏��ɁA�����֒ʂ���ˌ������āA���ꂪ���x�J�m���n�����Ƃ��낾���B��l�̉��ǍH��������o�ė����B�g��m�����n�̒Ⴂ�A���ڂ����j�����B�ނ̖ڂȂ������A�܂���ʁm�܂��n�̊Ԃ��k��āA�����̂��ւɒ����ꂽ�B�s�f�͂��̕|�m�����n���Ȃ��Z�����C�k���A���̎��͕|����Ȃ��āA���Ƃ����肵���B
�@���̐g�U���j�����S�������B�ނ͑f��������������āA���āA����ŃZ�����B�k��������B�ޏ��͐g�߁m�݂����n�ɁA���z�Ɛ��͂̓��Ђ��������B�E�m�Ђ��n�̐�������̐O���ޏ��̎����Ă����B�ޏ��͒�R�����B
�@�E�H�͖ق肱���ē����I�ɏċ����B�ނ̗���͒����̉��ŁA��͂炩���ޏ��̓��̂ʼn��B�}�ɃZ�����B�k����R���Ȃ��Ȃ��B�ޏ��͍d�����āA�܂��ɂȂ��B�j�͔ޏ������ɂ˂����āA���̂܂܉������Ă��ɋ��m���n�Ă��܂��B
�@�ƒ닳�t�m�K���A�l�X�n���A�|��Ă��Z�����B�k���������B�Ɛl�́A�ޏ������ē]���̂Ǝv���B�ޏ��������M�����B�i�����A�܁`�Z�y�[�W�j
�Z�˂����낷�^�ڂ��ɂ͏�l�̏K�����Ȃ��^���_�܂œS�̔��͂��ɂ���^�X��ʂ�K�X�ǍH�v�����R�݂ċL������^���̂Ȃ��ɓ��ꂽ��l�̒j�^�֊�ɂ܂�����ڂ���������炤�^�������ׂ鏭���͂�����ނ��^�X�q���܂Ԃ������Ԃ�K�X�ǍH�v�̒Ƃ̈ꌂ�ށ^�����̓��𐅓��Ő�킹���^�������݂̂Ȃ��Ƃ��Ă���������^�c���܂̎���^��l�̏��̊��̉Ă�m��ʁ^�����������͋킯���ނ��낤�^�ڂ��̔��̉Ɓ^���ʂ̖@�����������b�^�̓����̒���������낤�^����܂ŋx�Ƃ��^��������Q��܂ŎȔn�𑖂点�^�y���L��h����^���łɉ����̈Â�
�s����t�Ɨގ��̎���͈ȉ��̐߂ɂ݂͂��Ȃ��B�����őz�N����̂́q�f�ЁE���L���r�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�́u�k���a��\�O�N�l�O���O�\���@�m�タ����Ă����B���A�Z�ƈꏏ�ɖ��`���炫���̂��B���̏����ꂴ�鏬���s���͓��̗t�t�̗c����������������傫���Ȃ�A�����ꐡ�������B���w�Z�̃o���[�̑I��v�i�����A����y�[�W�j�Ƃ����L�q�ł���B�u���̗t�v�Ƃ��Ă̗c�����s����t�̏���l���ƌ��������Ƃ��A�q�����r�̏����I���E����ق����A�Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B����ɒ��ڂ��ׂ��́A�g�������̎����������낵�������Ƃ��A���o�̕Ė{���q�����@���āA8��29���ɑ��E���Ă���_�ł���i�g���͂��Ďo�̍K�������U��\���������̂悤�Ɂu�J�̖���݂���ʉƂɂƂ��䂭�^���̂����Ƃ̂Ȃ��������͂��v�Ɖr�����j�B1958�i���a33�j�N�̂��̊Ԃ̓��L���A��i�̎��M�ɐG�ꂽ�����ƂƂ��Ɉ����i���O�A��ꎵ�`����y�[�W�j�B
�k���a�O�\�O�N�l�Z���\�O���@�o���a�C�Ƃ̘A���A�r���O�S�~�ꔠ�����Č����ɂ䂭�B�O�N�Ԃ肩�B�o�����サ�Ă���̂ɋ����B�Z�L�Y�C�J���G�X�炵���B
�Z���\�ܓ��@�����C�J�������o���B���ю��q�����r�f�ځB���s�삩���m��ʂ��A�Ǝ��Ȗ���Ǝ�������B�݂�������j���B
������\�����@�o�A�G�i�P�J�̓��啪�@�ɓ��@�B
�����ܓ��@���啪�@�֎o���������B�ƂƂ͉_�D�̍��A���ꂢ�ȃx�b�h�ɂ˂Ă����B�v���܂������ʂƂ̂��ƁB
���������@������Z�k�W���[�X�������Ďo�̌����B�L���͂�������̊��҂ƕt�Y�l�����B���ٗl�ȏL������B
���������@�q�����r�o���B����Ŏ��W�s�m���t�̏\��ъ����B�k�c�c�l
����40�̔N�ɕ��r�����B�㔼���͕a�ƂƂ��ɂ��������U���������A���@����2�T�Ԃقǂł̎��͎��ɂƂ��Ắu�}���v�ł���A���ɓ��ɐ��サ�Ă������܂�����̂͊��������������B���͕a���ɕ���������Ă���A���ƁA���l�G���ɏ������̕��͂��Ђ����珑���Â����B���̂Ƃ��̎����̐S�����琄���ʂ�̂����A�g�����́q�����r���������ƂŎo�̉����A����ɂ͂��̍ċN���F�O���Ă����̂ł͂Ȃ��������i�g���͕���̎��̒m�点���n�ŎƂ��Ă���j�B�a���łЂƂ�키�҂Ɩ����ɋ������邽�߂̔�V�Ƃ��Ă̎��M�B���܂̂��̎d�������Ƃ��邱�Ƃ��ł���A�a�l�͕K����������B���̂Ƃ��A�����҂̔]���͂ӂ���ɂ������ĕ�������B���ʁA���̈ӎ��Ɩ��ӎ������������ɗނ����Ȃ���i���o������B���ꂪ���́A�s�m���t�ōŌ�Ɋ������݂����т̗����ł���B�������낵�̎��сq�����r�͂U��99�s���琬��A���W�̍Ōォ��2�Ԃ߂ɒu���ꂽ�B��i�̕���ݒ�́q�m���r�i�C�E8�j��q�����r�i�C�E19�j�Ɋr�ׂ�Ɛ����I�ł���B���̂��߁A�u�ڂ��v�͋g���ł���Ɠǂ����Ƃ���A�ł��Ȃ��͂Ȃ��B�����A�Ɛg����́u��ȗ����V�Y�v�i�q�k���M�l�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j���ޗ��ɂ��Ă���ӂ���������B�������ۂ̂Ƃ���A���̓����͂ǂ��Ȃ̂��낤�i��Ɉ������P������킩��悤�ɁA�g���͖{�тł͎����ȗ�����Ȃǂ��āA�Ӑ}�I�ɓ���̎�̂�B���ɂ��Ă��邽�߁A�l���W���킩��ɂ����j�B�����ł͂����T�邽�߂̕���Ƃ��āA�{�т��U���ɂ��Ă݂�B�g��������v��Ƃ����̂���Ȃ��̂����A����I�ȓW�J�̒ǐՂƂ������Ƃł������������������B
�Q�@���@�̍炭�āA�����͕ω����Ă���B�Ԋ�����܂ɍ����`���ڂ��͂��߂�Ƃ��A�ڂ��̕@�т̖݂��Ƃ���ʂ���B�I��㢂��y�����ɂ��̂̂������B�ڂ��͂����Ȃ�ω��A������҂��Ă���̂��B
�R�@�r���ɂ����ꂽ���������̂̏����ڂ��̊��e�ȓ���̉��ɍ݂�B���̌��̗��̉��Ȃ������̐��_���ڂ��̓��𑨂���B���͕a��ȕv�łȂ���Ζ��܂����邪��S����v���E���Ă����炵���B�l�łȂ���A���傤�������B
�S�@�ڂ��͔퍐�𗠐�B�퍐�͂��ׂĔ�������ɂӂ��킵���q������B�ڂ��͖@��ɂꂱ�܂�A�퍐�Ƃ��č����̎҂����ɂƂ�܂���A�ƍߐl�̗�����������������B�ڂ��ٌ̕�l�͍Ȏq�Ɨ��e�̂��߂ɉƂ}���B�s�^�Ȏ҂͐j���ŗ{���A�Â����ɂ���B
�T�@���̕v�̊C�`�Z�t�́A�o�ڍH��A��ĊC�֍s���B�o�ڍH�͂��ɂ̌`�ɕ����B�v�ׂ݂͊ŕ��������B���͐H�����͂���ł��ĉj���B�M�����̏��͐l�̐S�����L�ɕω������A�₦�����˂܂�点��B�O�l�̐H���͊댯���B�C�͎��j�łӂ������B
�U�@�ڂ��͐��@�̉Ԃ��Ăт̂����^�]�����s��ꂸ�^���E�̏��������R�̂��ׂĂ�������Ă��Ȃ��^�^�����܂��^�Ԃ̐[����������������������݂̂�^�ڂ��͎����ƕs�K�ȏ����~�ς��ׂ��^���̑ڂ֎���ׂ̂�^�r���͖�ɕ���₷���`�ƐF�����^���܂������Ԃ�����Ɗ���^���ꂩ���̂ڂ��͂܂��߂ȐX�Ԃ��^�����ނ�̂ЂȂ���Ă悤�ƌ��ӂ���^���ׂ����\�̐��ɕω��������̐����^�@���━���̂Ƃǂ��ʏ����Ł^�ڑ��Ȃ�����H�����玀�炳��^�ڂ��������U�߂Ă�����������̏�^���̑��̔���������������^�����͋P�����́^����������́^���̔��̏�ɑꂪ�������ē���^�ڂ��͗�Âɖ@�T�̉������̂���ށ^���Ăڂ��͏��ɂ͑�ς������^�ߐ[�����͋��点�悤�^�K�X�ǍH�v�ɏт��q����ē��̏����������𔗂�̂��^�ڂ��͋v�����҂�
�������ɍŌ�̂U�͗v��s�\�ŁA�Ǎ��Ō����������ق��Ȃ��B�u���ׂ����\�̐��ɕω��������̐����v�͒��ڂ̎��傾�B���h��Y�s�����̖쒹�t�i�����V���o�ŋǁA1981�j�ɂ́A�\�i�c���ڃN�C�i�Ȃ̐����j�͓����n���ł͗����܂��͉Ē��ŁA������E���c��E�r�쉈���̎��n�A�x�k�c�ł͂܂����Ȃ�̐���������Ƃ���B1950�N�㖖�ɂ����ӂ̑��p�ŃN�����Ɩ��u�\�̏��v�������ꂽ�͂����i�ЂȂ͐��܂�Ă����ɕ������Ƃ��ł���Ƃ����j�B�Ƃ���Łu�ڂ��v�̐E�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂��낤�B�@���������ɋ߂�ٌ�m���K�����B���ꂪ�S�Łu�퍐�v�Ɠ��ꂩ���B�u�ڂ��v�̓o�ꂵ�Ȃ��T�ł́A�ƍ߂̔w�i�ƂȂ����O�p�W���ق̂߂������B�����U�̍ŏ��ŁA�S�ƂT�̃V�[�������ۂɂ͋N�����Ă��炸�A�{�Ղ̂܂ǂ�݂ɂ�����o�����������Ƃ킩��悤�ɏ�����Ă���B���̂Ƃ��R�̖�����2�s�u�l�łȂ���Εʂ̂��́^���̑傫�Ȃ��傤�������h���Ă����̂��v�́A�O�̎��W�s�Õ��t�i1955�j�{���́q�ߋ��r�i�B�E17�j�ɓo�ꂷ��u�Ԃ����v�Ɓu���̒j�v�̓^����f�i�����Ȃ���A�u���v�̉ߋ���������B����Ȃ�ʁu���@�̉ԁv�\�\��y��z�N������\�\�����Ă����u�ڂ��v�́A���Ǖv���������i�E�Q�����H�j�r���̏��Ƃ̌����f�����āA���̏����i�݂̂Ȃ炸�K�X�ǍH�v�Ƃ̊Ԃɂł������̎q���j�Ƃ̌�����҂̂��B�q�����r�́s����t�̃Z�����B�k�̕��ꂩ�牓���u��������l�̒j���A���g�̐V���z����杂������B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�s����t�M���X�g�́u7.�R�荄���Y��i�O�}���[�A1971�N5��31���j�v�̏d�ł̖�ҁq���Ƃ����r�ɂ́u��������A�s����t��V���ɖ|��ɂ�����A���̊w������ɓǂA�x���搶�̖|����A�����N�����o�āA���߂ĎQ�Ƃ����Ă������������Ƃ����̋@��Ɍ��������\���グ�����B�k�c�c�l�^�Ȃ��A���͂��̖|��ł́A�ł��邾������̎Ⴂ�l�����ɓǂ݂₷�����̂ɂ������Ƃ����z�������āA�����Č��ꂩ�痣��āA�����ɑ������P�������肵����������B�^�k�c�c�l�^��㎵�O�N�ꌎ��\�l���@�d�ł̋@��Ɂ^��ҁv�i�s����t�A�O�}���[�A1973�N2��20���A��l���`��l��E��܁Z�y�[�W�j�Ƃ���B�ŏ��̖x����{��ق�40�N�o�������_�ł̎R�荄���Y����f���āA�u�ł��邾������̎Ⴂ�l�����ɓǂ݂₷�����̂ɂ������Ƃ����v��҂̔z���������������B�x����Ɠ��l�A�`���́q�v�����[�O�r�S���i�����A���y�[�W�j�ł���B
�@�������������Z�u���[�k�́A�����̕��������̕����ɍs���̂ɁA�����L����ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ޏ��͂��ꂪ����ŁA���������Ēʂ����B���钩�̂��ƁA�Z�u���[�k�͘L���̒��قǂ܂ŗ��āA�v�킸�����Ƃ߂��B���傤�ǂ��̏ꏊ�ɁA�����ɒʂ���h�A�������āA���ꂪ�J�����Ƃ��낾�����B��l�̉��ǍH��������o�ė����B���炾�͏��������A��������Ƃ��Ă����B�ނ̎������A�������F�̂܂���ʖсm�܂��n��ʂ��āA�����̏�ɒ����ꂽ�B�ӂ���͕��|�m�����n���Ȃ��Z�u���[�k���A���̎��͂��킭�Ȃ��āA���Ƃ����肵���B
�@���̓��삪�j�����S�������B�ނ͂����������������킵�A���ꂩ��A����ŃZ�u���[�k���������B�ޏ��͐g�߂ɁA�K�X�ƒj�̐��͓I�ȓ����������B�Ђ��m�A�A�n���悭�����Ă��Ȃ��O���ޏ��̎����Ă����B�ޏ��͂��������B
�@�E�l�͖ق��āA�����I�ɏ��Ă����B�ނ̗���͔ޏ��̕��̉��ŁA���̂��炩�����̂ł܂킵�Ă����B�}�ɁA�Z�u���[�k�͂��炪���̂���߂��B�ޏ��͍d�����A�܂����m�����n�ɂȂ����B�j�͔ޏ������m�䂩�n�̏�ɂ˂����A�������Ă��ɗ��������Ă������B
�@�Ɛ��w���A���m�䂩�n�ɓ|��Ă���Z�u���[�k���������B�Ƃ̎҂����͔ޏ������ׂ��ē]�Ǝv�����B�ޏ��������v�����B
�R�荄���Y�搶�́A2021�N3��11���ɖS���Ȃ�ꂽ�B103�������i�q�R�荄���Y���������r�j�B
�{ �Z�قł́A�g�����́q蜾蠃�k�X�K���l��r�̒Z�́E�����́i�ȉ��u���o�v�Ƃ����j���� �W�s�����t�̒Z�́E�����́i�ȉ��u��e�v �Ƃ����j���r�E�Z���������ʂ��� ���Ɏ����i�T�j�B�܂��q蜾蠃�k�X�K���l��r�ɂ́A5��������Đ��`�i�̍e�q�`�W�r�j�����݂���̂ŁA�T�̖{���Z�قɑ����ćU�Ƃ��Đ��`�̎����E�{�� ���f�����B�������U�͇T�Ƃ̈ٓ����������߁A�Z�ق̌`���Ƃ炸�ɕ��L�Ƃ����B
�}��
�P�@
��{�ɂ́A���o�F���W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�A��e�F�̏W�s�����t�i���ƔŁA1959�N5��9���j�A���`�F�e�{���W�s����t
�i�ʖؓ��A2002�N5��31���j��p�����B�s�����t�͏����̂̂��ɁA�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�N9��1���j�A�s�����k�V��
�Łl�t�i�[��p���ЁA1973�N8��28���j�A�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�ƎO�̖{�������邪�A�{�Z�قł͊��������B
�Q�@�s���̃A���r�A�����́A����̍Z�قɓ������ď��т����ɕt������Ɨp�̍�i�ԍ��ł���B
�R�@00�Ԃ̒Z�̂́A��e�ł͉̏W�́q���́r�ł��邽�߁A01�Ԃ̒��O�i�Ό��y�[�W�j�ɒu����Ă���B����A���o
�ł͎��W�s�����G�߁t�S��
�́q���́r�ɂȂ��Ă���A00�Ԃ�01�ԂƂ́q�����G�߁r���\������20�̎��тŊu�Ă��Ă���B
�S�@���o�̒Z�́i01�ԁ`44�ԁj�̉��s�k�u�^�v�ŕ\�L�l�͒�e�ł͂��ׂĒǍ��ɕύX���ꂽ���A�ώG�ɂȂ邽�ߖ{
�Z�قł́k�^���i�Ǎ��j�l
�̕\�����ȗ������B00�Ԃ����45�ԁE46�Ԃ̖{���́A���o����e�ʼn��s�Ɉٓ��͂Ȃ��B
�T�@�u//�v�́A�����̂��Ƃ̉��s��\�킷�B
�U�@�g�p�����́A���o�F�����A��e�F�V���ŁA�{�Z�قł͌����Ƃ��ĐV���ɓ��ꂵ�����A��e�ł����o�Ɠ������̂��g
�p����Ă���ꍇ�͂����
�̂����i01�ԁu�݁v�A07�ԁE41�ԁu���v�A13�ԁu���v�A16�ԁu�N�v�A38�ԁu㊁v�A45�ԁu�ցv�Ȃǁj�B
�T �̏W�s�����t�{���Z���k�q蜾蠃�k�X�K���l��r���s�����t�l�^�U ���`�i�̍e�q�`�W�r�j
00 ����//���邩�Ȃ��݁k�Á��l���^�ȁk�������l��邤�������^�̂��k�������l��肠�͂��^�킩���Ђ̂��
�U �A�e��//���邩�Ȃ����𗬂��A���̉e��肠�͂��Ⴋ���̖� ��01 �䂫����̏����������Ă��肩�˂��^�����ݓ��ɏt���䂭�߂�
�U �X�p���//�䂫����̏��m�ЂƁn���ӂċ��肩�˂������ܓ��ɏt�͂��ɂ��� ��02 �g�Ƃǂ�⍪�z�ے�����^�M���Ђ���Ă͂��ɂ���
�U ����//�g�Ƃǂ�⍪�z�ے�����ΏM���Ђ���Ă͂��ɂ���03 �t���Ɏl���̒��̕�������^���Ə��͋u�������䂭
�U �u//�t���Ɏl���̒��̕������茢�Ə��͋u�������䂭04 ��Ԃꂽ�鎆���D�͑��̒��^�[�ď��ā^�q�炩�ւ�䂭
�U ��݂�//��Ԃꂽ�鎆���D�͑��̒��^�[�ď��ā^�q�����ւ�䂭05 ���݂���//���͐����͂낯���t�����݁^�����������݂����Ȃ肯��
�U ���͐����͂낯���t�����݂��������������Ȃ肯��06 ���݂����͉��Ȃ�^���Ɂ^�����Ђ����w�̓��[�́^���ꂽ�邢��
�U �s��//���݂����͉��Ȃ�^���Ɂ^�����Ђ����w�̓��[�́^���ꂽ�邢��07 ��̉�̂߂��铕��̂ЂƂƂ���^�߂��肵�D�̓X�[�h�̏���
�U ���v���//��̉�̂߂��铕��̂ЂƂƂ���߂��肵�D�̓X�y�[�h�̏��� ��08 ���E�����Â��ɂ˂ނ鍻�̏�^�o�i�i�̔�̊�������ߌ�
�U �k�i���`�i�V�j�l09 ���o�̖тɗ[���̂킽�鍠�^�D�Ԃ͉w�ւƃJ�[�u���Ă䂭
�U �x��//���o�̖тɗ[���̂킽�鍠�D�Ԃ͉w�ւƃJ�[�u���Ă䂭10 �O�̂��������킫���^��������̐����ނ��^�����܂ق�����
�U �O�̂��������킫����������̐����ނ�拃���܂ق�����11 �H�炭���ЂƂ����ɐ���ɂ���^���`�̎R�̏H�ӂ��݂�
�U �H�H//�H�炭���ЂƂ����ɐ���ɂ��薭�`�̎R�̏H�ӂ��݂�12 �H�Ђ炭���W�̗]����ӂ��݁^�a�̂������ƂӂƂ����ɂ���
�U �H�̂���//�H�Ђ炭���W�̗]����ӂ��a�̂������ƂӂƂ����ɂ��� ��13 ��`�����//����̈ꐺ�e���Ă悬��䂭�^����̋��ɓ��̂Ƃڂ肽��
�U ��`��//����̈ꐺ���ĂĂ悬��䂭����̋��ɓ��̂Ƃڂ肽��14 ���Ɏq�Ɋ����e�̂��͂����^��P�����~�ƂȂ邩��
�U ���Ɏq�Ɋ����e�̂��͂�����P�����~�ƂȂ邩��15 �꒹�̗[�����̐��قƂ�^�b�̉Ԃ����킽�k��䂭���錩��l
�U �꒹�̗[�����̐��قƂ��b�̉Ԃ����킽�錩��16 �D�M��伂̂��ނ��炬����^���N�����ւÂ�t�̂ЂƂƂ�
�U �D�M��伂̂��ނ��炬������������ւÂ�t�̂ЂƂƂ�17 �\���ӉƂ̔��ǐ��߂������^��Ԃ̉Ԃ̉e���Ă��
�U �t�̉e//�\���ӉƂ̔��ǐ��߂�������Ԃ̉Ԃ̉e���Ă��18 �[���鋾�̏�́^�`���R���[�g�̂��������̂��Ɓ^�Ă͂������
�U ����//�[�Ђ��鋾�̏�̃`���R���[�g�̂��������̂��ƉĂ͂������ ��19 �莆�����������ʖтӂ�Ӗ�^�ǂɋ����̉e���Â��Ȃ�
�U �莆�����������ʖтӂ�Ӗ�ǂɋ����̉e���Â��Ȃ� ��20 ��k�i����j���i�E��90�x�]�|�j�l���H��Â����Ԃ̂��Â�����^���̑��̕ӂ��T���̂Ƃ�
�U �䂭�H��Â����Ԃ̂��邵�Â����̑��̕ӂ��T���̂Ƃ�21 ���D//��̉w�̎��v�̐j�̂������̂��^�ӂƂ݂����Ƃ̂��͂����Ȃ���
�U ���D//��̉w�̎��v�̐j�̂������̂��ӂƂ݂����Ƃ̂��͂����Ȃ���22 �ᕗ��^������܂̓J�Ƃق��^������锼��Y���ɂ���
�U ����ܓJ//�ᕗ�⏗���̓J����������锼�̒Y���ɂ���23 �~��//�����Ђ��������n�Ԃ����^�w�̗����k�l�����ނ�
�U �k��//�����Ђ��������n�Ԃ����w�̗����ɖk�l�����ނ�24 �����̒��̏Ɏq�ɏH�̉�́^�������݂����J�ӂ肻�߁k�ȁ��ʁl
�U �k�i���`�i�V�j�l25 �k�i�i�V�j���o��//�l�J�̖���݂���ʉƂɂƂ��䂭�^���̂����Ƃ̂Ȃ��������͂��
�U �k�i���`�i�V�j�l26 �y���//�Ė�䂭���������̉�����^�����߂�e���藎���t�Ȃ肯��
�U �y���//�Ė�䂭���������̉���������߂�e���藎���t�Ȃ肯�� ��27 �H�����ā^�k�i2���A�L�j���i�g���c���j�l�ь�̍��莕�ɂ��݂�^�k�i4���A�L�j���i�g���c���j�l�����������݂��^�k�i1���A�L�j���i�g���c���j�l���m�� ���߂�
�U ����//�H茂��ā^�@�@��̍��莕�ɂ��݂�^�@�@�@�@�@���������݂��^�@���m�肻�߂� ��28 ���͂ꂵ���]�Ɂ^����������D�̗[�M�́^�����Â���
�U ����//���͂ꂵ���]�ɔ���������M�̗[�M�̉����Â���29 ���L�̂����Ђ��悬�鏪�̒��^�Ɛl�͎���͂߂��Ă䂭
�U ��̃p���g�}�C��//���L�̉e�Ђ��悬�鏪�̒��Ɛl�͎�����͂߂��Ă䂭30 ���ə~��w�ŏɎq�Ɏ��Ȃǂ����^���̏t�J�ЂƂ̗�����
�U �t�J//���ə~��^�w�ŏɎq�Ɏ��Ȃǂ����^���̏t�J�^�l�̗����� ��31 ���L���H//��̊X��f���̏������Ƃ߂䂭�^���������M�G���Ȃ���������
�U �k�i���`�i�V�j�l32 �Z�p�̉��M�̉e��ӂ��ā^�n�ǒ��߂���H�ƂȂ�ʂ�
�U ���H//�Z�p�̉��M�̉e��ӂ��Ĕn�ǒ��߂���H�ƂȂ�ʂ� ��33 �y�K����ւ��ǂ���e�Ɂ^�܂͂�q���[���f�̉�
�U �y�K����ւ��ǂ���e�ɂ܂͂�q���[���f�̉�34 �܂����ނ��낲����̂Ђ˂������^��q�����邭墂̂Ƃт
�U �t�̐�//�܂����ނ��낲����̂Ђ˂�������q�����邭墂̂Ƃт35 嗋��̐G�p�ʂ߂ʂ߂Ƒ��ɂ̂с^���R���̉J���ǂꂽ��
�U 嗋��̐G�p��͂炩�����ɂ̂ї��R���̉J�͐��ꂽ��36 ���Â̒j��╂Ŕ��肠�邭�^�������ɓ��̕�ꂻ�߂�
�U �k�i���`�i�V�j�l37 �l�Ȃ̓���̍g�̂ɂ���䂭�^��̂��݂���̐Q���邵������
�U ���݂���//�l�Ȃ̓���̍g�̂ɂ���䂭��̂��݂���̐Q�ꂵ������38 ㊂Ƃт������̘r�����݂ā^�������k�i�i�V�j���́l�ӂ���钩�Ȃ�
�U �Ă̒�//��Ƃт������̘r�����݂Đ������ӂ���钩�Ȃ�39 ���ӏD��//�݂݂�͂Ȃ����^����Ђ̂Ђ��Ђ��^�Ƃ�����Ȃ����^�����̂�ӂ���
�U �H�݂̂Ái���D����j//���݂�Ȃ����D�Ђ̗₦�₦�ƐS�Ȃ����H�̗[����40 ���܂�^���Ђ��k�T�����l�Κe���^�L���C���͊X�ɏ����
�U �s//���܂���Ⴍ�Κe���A�h�o���[���͊X�ɏ����41 �@���J���ނ鑋�ׂɓ����Ƃ����^�Ԃ��������͎蓅���ʂ�
�U �������//�@���J���ނ鑋�ׂɓ����Ƃ����Ԃ��������͎蓅���ʂ�42 �o�X�̏��ԏ��́^�Ђ�߂���X�J�[�g�̉e�Ɂ^�Ă������X
�U �o�X�̏��ԏ��̂Ђ�߂���X�J�[�g�̉e�ɉĂ������X43 �Ák�i�S�p�A�L�j���i�g���c���j�l�t�q���ꂵ����//�X�̉�݂̐ӂ���ތ����́^����̍��ɉJ���Â��Ȃ�
�U �ю�����//���X�̉�݂̐ӂ���ތ����̍���̍��ɉJ���Â��Ȃ� ��44 �l�v�l��//�l�Ȃ̖j�̂قĂ�����Ȃ�����^�Ԃ͂��Âق�[���Ƃق�
�U �t��//�l�Ȃ̖j�̂قĂ�����Ȃ�����Ԃ͂��Âق�[���Ƃق�45 �k���`�R �i�����̓��j�������̓��^���`�R�l//�ւӂ������̎q���⡂�������ށ^�ԋ˂ɕ���[�R����̂���
�U �߂������//�M�ӂ������̎q���⡂�������މԋ˂ɕ���[�R����̂���46 ���̂������߂ɒ��̂˂ނ�t����^�ق̂ڂ̂ƐV�����鍁�̂������߂ɂ���
�U �����i�L�����j�\�\�i�����́j///���̂������߂ɒ��̂˂ނ�t����ق̂ڂ̂ƐV�����鍁�̂������߂ɂ���
�V �s���܂�͂����L�t�f�ڌ`
�U ���`�i�̍e�q�`�W�r�j�Ł����t����11��i��i�ԍ�00�E01�E07�E12�E18�E19�E26�E27�E30�E32�E43�j�́A�\�L�������ɈقȂ�ꍇ �����邪�A�s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�N4��15���j�ɓo�ꂷ��B�ȉ��ɓ����̖{���������A����ɑ����Čf�ڃm���u�����A�i�@�j���ɓ��L�̔N �����𗪋L����B��̏��o�E��e����ѐ��`�Ɓs���܂�͂����L�t�f�ڌ`���r��������A���L�Ɖ̍e�̊ԁA�̍e�Ǝ��W�Ɖ̏W�̊Ԃɂ����āA��i���ǂ̂� ���ɐ������Ă������������ǂ邱�Ƃ��ł��邾�낤�B
43 ���X�̉�݂̐ӂ���ތ����̍���̍��ɉJ���Â��Ȃ�i�×t�q���ꂵ���Ɂj ��22�i1939�E3�E25�j
30 ���ə~��w�ŏɎq�Ɏ��Ȃǂ������̏t�J�ЂƂ̗����� ��29�i1939�E4�E22�j
18 �[���鋾�̏�̃`���R���[�g�̂��������̂��ƉĂ͂������ ��40�i1939�E5�E15�j
01 �䂫����̏����������Ă��肩�˂������ܓ��ɏt���䂭�߂� ��62�i1939�E7�E29�j
32 �Z�p�̉��M�̂�����ӂ��Ĕn�ǒ��߂���H�ƂȂ�߂� ��71�i1939�E9�E4�j
00 ���邩�Ȃ����𗬂��A���̉e��肠�͂��Ⴋ���̖� ��72�i1939�E9�E4�j
26 �Ė�䂭���������̉���������߂�e���藎���t�Ȃ肯��i�y���j ��72�i1939�E9�E7�j
27 �H茂��ā^�@�@�ь�̍��莕�ɂ��݂�^�@�@�@�@���������݂��^�@���m�肻�߂� ��73�i1939�E9�E10�j
12 �H�Ђ炭���W�̗]����ӂ��a�̂������ƂӂƂ����ɂ��� ��77�i1939�E9�E28�j
19 �莆���������̂܂тӂ�Ӗ�ǂɋ����̉e���Â��Ȃ� ��92�i1939�E11�E24�j
07 ��̉�̂߂��铕��̂ЂƂƂ���߂��肵�D�̓X�y�[�h�̏��� ��96�i1939�E12�E7�j
�q�g�����̒Z�́r�� �q�ׂ��悤�ɁA1938�N����40�N�̏��߂ɂ����ċg���̍�����a�̂́A�q�`�W�r�̕W��̂��ƁA�Z��200��E������9��̌v209��𐔂���B�������� ����1�E�Z��44�E������2���̂�����҂̐S������{�Z�ق�ʂ��ĉ��߂Ċ������B�Ȃ��A00�Ԃ́q���́r��39�Ԃ̒Z�̂̎����ɐG�ꂽ�q�s�g �����S���W�t������i�r�i�q�u������H��v�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i12�j�\�\�q���͂Ȃ����F�Ȃ̂��H�r�r�́q�U ���Ɛ��r�j���A�����Ă�������������Ƃ��肪�����B
�g �����̎��ɂ́A�o�T�E���Җ��̕\���̂Ȃ����p�傪�������܂܂��B�T����p�����쎍�@�̋N���́A���W�s�a���`�t�i1962�j���M���́q���̕a�C�r �i�D�E11�j��q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE10�j�܂ők�邱�Ƃ��ł��邪�A����͍Ō�̎��W�ƂȂ����s���[���h���b�v�t�i1988�j�́q�▋�r�i�K�E 9�j�ŋg�������p�����X���X�������A�����Ď��т̔��\�}�̂ł���~�؉p�����ʼn�W�s���X�̘f���t�ɂ��čl�@���悤�B�܂��q�▋�r�̒�e���f����i����s ���̐����̓��C�i�[�j�B
�▋�b�g����
01 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꖖ�̉f��ق̉Ă̏I��
02 �u�X�N���[���̋��̂ق���
03 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃɂ��
04 �k�炵�����̂���������v
05 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����K�u���G��������
06 �������ڂ��ɂ͂��ꂪ
07 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���Z��H�������v�̂悤�Ɍ�����
08 �u���ׂẮi���j��
09 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�z������i�j�v
10 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Ȃ��킽�ꎞ
11 ��߂�E��
12 �@�@�@�@�@���ɂȂ����K�u���G����
13 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�l�̂̂����Ƃ�
14 �s���I�ȁi�튯�j���g������v
15 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������҂�҂�
16 �@�@�@�@�@�i���j���������悤��
17 �ڂ��ɂ͌�����
18 �@�@�@�@�@�@�@�u���������ƂȂ��ĂقƂ���v
19 �@�@�@�i�A�E���j
20 �@�@�@�@�@�@�@�u�Â��Ă̂Ȃ��ɍ݂�
21 �@�@�@�@�@�@�@�@�}�b�V�����[���v
22 ����𐔂��@�����
23 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�z�n�m�e�C�V���n�j�y�[�p�[��
24 �ڂ��͐������Ă���
25 �@�@�@�@�@�@�@�@�@���̗t�╂�̕Y��
26 �i���ꂽ�݁j����
27 �@�@�@�@�@�@�@�@�{�[�g�������o��
28 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ڂ��͗瑕�̈�l�̒j
29 �^�钆�݂̂����݂̏��
30 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�͂����t��
31 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂��Ȃ����t���v
32 �ڂ��͎��ʂ���
33 �@�@�@�@�@�@�@�s���̊�����点��
34 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���x�̕\�ʁj
35 �u�y�����ƍ���������
36 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�ݍ��킳�ꂽ�v
37 �@�@�@�@�i�f���j�ɂ�
38 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�X�N���[���̂悤��
39 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̏����t���Ă���v
�q�▋�r��02�`05�s�̓T���́A�l���c���F�s�f��͂��������S�ɂȂ�k�������Ɂl�t�i�}�����[�A1986�N5��30���j�̎��̉ӏ� ���낤�i�� ���A���y�[�W�j�B
�@���m���[�����͂��߂ĉf��ɐG�ꂽ�̂́A�ꔪ�㎵�N�A����K�u���G���ɘA����ăp���̃f���t�F�C�G���S�ݓX��K�ꂽ�Ƃ����� ���B
�@�u�������������~���Ƃ����A�ӂ�͂����^���ÂɂȂ����B�|��ׂ��@�B���A�Èł𐦂܂������ė�������̌����قƂ��点���B�X�N���[���̏�� �́A���ɂ͉����Ȃ������ς�킩��ʉf����������B���������ꂪ�݂�ȁA����ł̓s�A�m�̔��t�ƁA��������ł͈����̋@�B��������h���h���Ƃ����� �����Ă����̂��B���͂���m�����n�܂�̔ߖ��L�[�b�Əグ���B�i�c�c�j���̉f��͑傫�ȉ͂��ʂ������̂ŁA�X�N���[���̋��̕��ɂ́A�����k�m�� �Ɂn�炵�����̂��������A�ƃK�u���G���͌����̂������v �i���{�W���w�W�����E���m���[�����`�x�E�݂������[�j
�l ���c���������Ă���̂́A�W�����E���m���[���i1894-1979�j�̎��`�i�sMA VIE ET MES FILMS�t�A1974�A�M���1977�j�̑�2�̏́q�f���t�F�C�G���S�ݓX�r�̖����ŁA�����Ȃ��02�`05�s�̓T�����l���c�{�ł͂Ȃ����m���[���{ ���������Ƃ��l������B��f���p���Ŏl���c�����ȗ������i�c�c�j�������ŕ₦�A�ȉ��̂悤�ɂȂ�B
�� ���Ȃ��Ă͂�������A��o����葼�͂Ȃ������B�������̃}���^�E�N���X�̃L���b�L���b�Ɖ�鉹���A��ɂȂ��Ă݂�A���̏�Ȃ��������y�ƂȂ��Ď��̎��� �����ł��낤�ȂǂƂ́A�v���Ă��݂Ȃ������B�����̎��ɂ́A�J�����Ɖf�ʋ@�ɂƂ��ĕK�v�s���Ȃ��̕��i�A����Ȃ��ɂ͉f�悻�̂��̂����Ă��蓾�Ȃ����� �ɂȂ��Ă��܂����̕��i�̏d�v���̓T�b�p���킩��Ȃ������̂ł���B
�@�Ƃ����킯�ŁA���̋����m�A�C�h���n�u�f��v�Ǝ����g�Ƃ̍ŏ��̏o��́A���S�Ȏ��s�ɏI�����̂ł������B�K�u���G���́A�����܂��܂Ńz�[���ɂ����� �������̂��A������Ɍ��ɂ������Ă����B�i���{�W���s�W�����E���m���[�����`�t�A�݂������[�A1977�N7��5���A���y�[�W�j
�� �����r����ɁA�g�����������̂́u����K�u���G���v��������l���c���ƂƂ�̂����ɓK���Ă���B�����炭�����������Ƃ��낤�B�~�؉p�����ʼn�W�̂��߂� 40�s�̎����˗�����Ă����g���́A�l���c������f����߂���V�����A���̎v�l�ɐg���䂾�˂āu�ꖖ�̉f��ق̉Ă̏I��v�Ƃ������s���������� �����̂��B�j���ɏƂ点�A�u����K�u���G���v�̓W�����̐���̏]���K�u���G���ŁA���I�[�M���X�g�E���m���[���i1841-1919�j�̊G�̃��f�������� ���A�c���̃W�����ɂƂ��āu������P�����m�͂��n��ړx�������v�i���O�A�l��y�[�W�j���ł���B�����A�q�▋�r�ɕ����m���[���ӔN�̗��w������ �邱�Ƃ́A�u���X�̘f���v�łc�b�R�~�b�N�́s�f�C���[�E�v���l�b�g�V���t��z�N���闝�R���Ȃ��ȏ�ɁA���p�ƌ����ׂ����B13�`14�s�ŋg���́A���m���[ �����܂߂��������Ƃ��`�����Ƃ̂ł��Ȃ��������ʂ�蒅�����B����́i�G��ł͂Ȃ��j�ꖖ�̉f��قŊς�ꂽ�f�悾�Ƃ����̂��{�т̊�ł���A���� �܂ł��Ȃ����̎x���̂ƂȂ����̂��u�▋���X�N���[���v�ł���B���ċg���́s��ʁt�i1983�j�Ɓs�T�t�����E�݁t�i1976�j��
�u��͌��̔���v�Ƃ����@�]�ˌ��ꂪ�Ȃ�����
�����X���@�������邱�Ƃ��Ȃ��@�����̉��@�@�u���݂�����̂̓����v���̂���
�@�@�ꖖ�̉f��ق�
�@�@���͘V����
�@�@���͛s��
�@�@�u�K���{�͓S�̐�ԁv���Ƃ킽���͎]���i�q�G�̐��r�J�E2�j�����߂��̉f��ق�
����͊ϑ�����
�n��̐��E�K���{�I�i�q�ǎ�̏��r�G�E22�j
�� �������B�g�����̑S284�т̎���i�ŁA�u�f��v�u�f��فv���o�ꂷ��7�ђ�2�тɃO���^�E�K���{�i1905-90�j��������̂��ǂ��l����悢�� ���B�W�����E���m���[���́A�c�E�v�E�O���t�B�X��i�̃N���[�Y�A�b�v�͋��قł���A�����A���E�M�b�V���A�����[�E�s�b�N�t�H�[�h�A�O���^�E�K���{�̂���� �f���Ƃ��Đ��U�A�]���ɏĂ�����ꂽ�ƌ���Ă���i�O�f���A�l�y�[�W�j�B�W�������25�ΔN���̋g���ɂƂ��āA����͏������قȂ�B�N���[�Y�A�b�v�� �͂Ȃ��A���̂Ƃ��ẴK���{�B
�@�W���Z�t�E�t�H���E�X�^���o�[�O�̖���u�Q���̓V�g�v�ň��� �`�ɂȂ����}���[�l�E�f�B�g���b�q�́u�����b�R�v�u�Ԓ��w27�v�ŁA�������𖣗����A���ꂩ��l�\�ܔN��̌��݂܂ł��A�����̐l�X�Ɉ�����A�^�ɃX�N���[ ���̏����ł���Â��Ă���B����ɂЂ������A������l�̐_��̏����O���^�E�K���{�́A���܂�悢��i�Ɍb�܂�Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B�����̓`���I �f��u��тȂ��X�v�Ƃ��u���́k�́��Ɓl�����v�́A�ǂ����Ă����ɂ͌���@��Ȃ������B�킸���Ɂu�ʂ�ꂵ�����v�u�O�����h�E�z�e���v�u�A���i�E�J�� �j�[�i�v�u�֕P�v�u�N���X�`�i�����v���炢�Ȃ��̂ŁA���̂Ȃ��ɐ[����ۂ��̂����Ă���̂́A���Ԓ���`�����u�}�^�n���v�ł������B�f�B�g���b�q�́u�Ԓ� �w27�v�ƑɂȂ��Ă���̂��ʔ����B��i�Ƃ��ẮA�u�}�^�n���v�̂ق����ʑ��I�ł��邪�A�������̕���ŋ���ȕ����̑O�Ń}�^�n�����G�L�]�`�b�N�ȋF�� �̕��������Ȃ���A�Ō�Ɉꎅ�܂Ƃ�ʎp�ԂɂȂ�B���̈Ó]�̈�u�̖����B�_���Ȃ�J���{�̐^�������̂������܌����Ƃ܂ǂ��Ńn�b�Ƒ����̂��̂ł� ��B�i�q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꎵ�`�ꔪ�y�[�W�j
�I
���W�i���̓��ʼn�W�s���X�̘f���t�i�M�������[�v�`�t�H�����A1986�N12��3���j�͒N�ł��ς�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA�~�؉p�����z��W�s�Ō�̊y���t
�i�������s��A1992�N9��20���j�ɂ��A�q���X�̘f���r��6�y�[�W�ɂ킽����11��i���f�ڂ���Ă���B���Ȃ킿�qArmour in
Space�r�A�q���̏M�r�A�q�f���r�A�q�����`�r�A�qRecital�r�A�q�]���r�A�q���H�r�A�q���r�A�qFortune
Teller�r�A�q���y�r�A�qMagic�r�ł���B��i�̊G���͓����Ŋm�F���������Ƃ��āA�q�f���r�i17.5�~22.5
���]�`���g
1986�j���u�u���Z��H�������v�v�i07�s�j�́A�q�]���r�i17.5�~22.5 ���]�`���g
1986�j���u�i���ꂽ�݁j����^�{�[�g�������o���^�ڂ��͗瑕�̈�l�̒j�v�i26�`28�s�j�̃X���X�ł��邱�Ƃ͌��₷���B�g���̎��т������s���[���h
���b�v�t��s�g�����S���W�t�i1996�j�œǂނƂ��ɂ͂킩��Ȃ����A���o�́s���X�̘f���t�œǂ߂A�����̎��傪�~�ؔʼn�ւ̎]�ł��邱�Ƃ͂܂����
�Ȃ��B�ʼn�Ǝ]�Ƃ���͂Ȃ���āA�]���]�����ɂȂ����Ƃ��A�g���́u�T����p�����쎍�@�v�́u���p���v�ւƎp��ς���B���̂Ƃ��A���p�͈��p���u�@�v��
�L���ƊW�Ȃ����肩�A���p�����̏͋傪�g�����g�̎�ɂȂ邱�Ƃ��[���ɍl������B�u�g���@�ڂ��̒��ł��A��
���͎����ō���Ď����Ŋ�
�ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p�������
���ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁv�i������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A
�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�y�[�W�j�B
�Ƃ��ɁA01�s�͋g�����̎��ł�����сA�����������`���s�ł���B���������@�E�A�E�B�̂悤�Ɋȗ�������Ɓi�q��|�Εv�W�Ǝ��сq�NJ|�r�r��
�Q�Ƃ��ꂽ���j�A02�F�@�A03�F�A�A04�F�@�A05�F�A�ŁA01���A���́s��ʁt���`�̑�1�s�������ł���悤�ɂ́u�V�����������Ȃ��v�ł͎n�܂炸
�ɁA03�F�A�ƕ��s���Ă���̂́A���̍s�����Ƃ���}�����ꂽ���Ƃ��������킹��B�g���́u�u���݂�����̂̓����v���̂��́v�i�q�G�̐��r�j�̘k�𑖂�
���邽�߂ɁA�W��q�▋�r�Ɓu�X�N���[���v�i02�s�j�̊Ԃɂ���12���������u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꖖ�̉f��ق̉Ă̏I��v��u���āA����i��
���j�A����i�ʼn�j�A�f�ʁi�f��j�̊e�s�ׂ��x���̏�̖����̏��ƌ��т����̂ł���B
�k�NjL�l
�s�Ō�̊y���t�̈��y�[�W�ɂ́q�▋�r���Ę^����Ă���A������
�m���o�w���X�̘f���^�~�؉p�����ʼn�W�x��㔪�Z�N�n
�� �钐�L�����邪�A�Ę^���ꂽ�e�L�X�g�͏��o�`�ł͂Ȃ��s���[���h���b�v�t�����̒�e�`�ł���B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�̊Ԃ̈ٓ���2�ӏ��B�ύX�́u���� �Ȃ��킽��m�A�A�A�A�n���v�i10�s�߁j�̖T�_����肳��A4�������肾�����u�͂��Ȃ����t���v�v�i31�s�߁j��30�s�߂Ɠ����������ɑ������i�������j �����ŁA���ւ̎����͂Ȃ��B
�g �����̎��сq�NJ|�r�i�J�E5�j�́A��|�Εv�̌W�i�؉�L�A1982�N3��27���`4��10���j�̃p���t���b�g�ɔ��\���ꂽ�B��|���̍ŏ��̒����s�A�� �X�g�s�A�t�i���E�V���t���A��E��|�Εv�A�p�����ɁA2000�N5��25���j�́q���ҏЉ�r�ɂ��A���̌W�̓O���[�v�W�����������̓W����ŁA���� ��A����L�ł̌W��1986�A90�A91�A95�A98�N�A��W��1984�A86�A87�A90�A93�A94�A95�A96�A98�N�ƁA���N�̂悤�ɊJ����� ����B��|���͐؉�L�Ƃ̏o������āu�|��̐搶�̏Љ�ł��B���͋��s�s���|�傾�����̂ł����k��|����1979�N�̑��Ɓl�A���̍��O�c���搶 �������ŗ��Ă���ꂽ��ł��B���̑O�c�搶�͐؉�L�ƈȑO���炨�t���������L�����̂ŏЉ�Ē������̂ł����A�؉�L�͏Љ����{�I�ɂ͎Ȃ��炵 ����ł���ˁB����ł���i�����Ă�������Ƃ���A�C�ɓ����Ă�������l�Ȃ�ł��B���ꂩ��ł��ː؉�L�Ƃ̕t�������́v�i�q�A�[ �g��g�߂ɁI�m ���u�E�A�[�c �n�X�y�V�����E�C���^�r���[�r�j �Ɠ����Ă���i���Ȃ݂ɁA�g���̖������сq�X�����x���O�̉́r�G�����\���̃C���X�g�͑O�c���ł���j�B�g�����ŏ��̌W�ȑO�ɑ�|���̍�i��m���Ă��� ���s�������A�؉�L�̎��M�˗����đ�|�G����i���߂āj�ς����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �c�O�Ȃ���A��|�Εv��W�͖{�e���M�̎��_�ő��݂��Ȃ��̂ŁA�O�f�s�A���X�g�s�A�t�A�O�����Z��i�V���t����j�s�Ԃ�����k�G�{�O�����̐X 6�l�t�i�p�����ɁA2005�j�A�sTAROT�m�^���b�g�n�t�i�����E���R�C�i�A��E��|�Εv�A�s�G�E�u�b�N�X�A2005�j�Ȃǂ̏��Ђ�A��|�����g���쐬 ����E�F�u�T�C�g�sSecrets of Plant Worms House�k�~�����z�ق̔閧�l�t�� ��������ق��Ȃ��B�� ��������āA�{�e�ł́q�NJ|�r�Ƒ�|�G��̑Ή��͂����đF�������A���т̏��o�`�ƒ�e�`���r���A�����ĕW��́u�NJ|�v���ǂ��ǂނ��ɂ��čl���Ă݂� ���B�܂����o�`���������B
�NJ|�k���o�`�l�b�g����
���������͗V��ł���
�@�@�P���V�т���@�������V�т�
�@�@�@�@�@����|�Ŏւ�����
�Ƃ��߂�����
�@�@�@�@�@�@�@�@���̐��͉����Ŗ�����
�u�I���p���X�v������ꂽ
�@�@�@�@�@�@�@�����ނ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�̓�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���������
�����͔����̎s�ꂩ�牓��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ�ٓ�������
�����ɂ͞�F�̌��������Ă���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ܒi�̐Βi�����Ă���
�@�@�H���̔����V�l�ɕ�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͒p�����Ԕ���G�炷
���̕����։���
�ނ炳���F�Ɏ�����
��l�̉������V��ł���悤��
�@�@��������̃o�P�c�̒���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���B�@�����@���ʁ@�E��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂̋��������������
�t�̂ЂƂƂ�
�@�@�@�܂�Ŕ������NJ|�m�^�s�X�g���[�n���D���Ă䂭�悤��
�����̉�����������������ė���
�������i�j�����A��������ŕ\�킷�ƁA���o�`�̖`��3�s�͂����Ȃ�B
��������������������
������������������������������
��������������������������
�� �̎������߂�ꂽ�s��ʁt�i1983�j�̊K�i��̎��`�A�q�������܁r�̌����S���u���Ƃ̉�������u�y���v�̂悤�ɎU��߂��A�����Ă݂�u�� ���v�̂悤�Ȃ��́v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��㎵�y�[�W�j�Ɋ��ꂽ�ڂɂ́A���o�`�̎������͂Ȃ�Ƃ���A�Ƃ��������r ���[�ɉf��B�g���͎��W�ł͎���̃��j�b�g�����̂悤�ɓ��ꂵ�Ă��邩�炾�B
��������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�� �X�I�ɍŏ��̎�����@�A���̎�����A�A��O�̎�����B�A��l�̎�����B�i���ꂪ�Ȃ��ꍇ������j�A��܂̎�����C�ƕ\�킹�A�@�͓V�c�L�Ŏn�܂�i��1 �s�j�A�A�͇@�̕��������̋�Ɏn�܂�i��2�s�j�A�B�͇@�ƇA�̕��������̋�Ɏn�܂�i��3�s�E��4�s�j�A�C�͇@�ƇA�ƇB�̕��������̋�Ɏn �܂��Ă���i��5�s�j�B�\�\�ȏ�̂�������A����`���E�����̊��ʗނ͔��p�ɃJ�E���g�B���́A������s��ʁt���`���q�NJ|�k���o�`�l�r�ł͌��i�Ɏ��� �Ă��Ȃ��̂��B�{�e�ł́A���o�`���e�i���W���^�j�`�ƍZ������ɂ������āA�������̈ٓ����ȗ������邽�߁A���̂悤�ɕ\�킷���Ƃɂ���B�o���̊ԂŎ��� ���ɕύX�̂Ȃ��ꍇ�́A����̊ے��������m�@�n�Ŋ���i�m�@�n�A�m�A�n���j�B����A�ύX�̂���i�܂�����̌��ʁA��L�́s��ʁt���`�ƂȂ����j�ꍇ �́A����̊ے��������y�@�z�Ŋ���i�y�@�z�A�y�A�z���j�B��������ƁA�ٓ��͈ȉ��̂悤�ɂȂ�i�s���̐����̓��C�i�[�j�B
�NJ|�k���o�`����e�`�l
01 �k���������l�����͗V��ł���m�@�n
02 �@�@�P���V�т���@�������V�тցy�A�z
03 �@�@�@�@�@����|�Ŏւ����݁y�@�z
04 �Ƃ��߂����ԁy�A�z
05 �@�@�@�@�@�@�@�@���̐��͉����Ŗ�����y�B�z
06 �u�I���p���X�v������ꂽ�m�@�n
07 �@�@�@�@�@�@�k�����ނ聨�S�����l�y�A�z
08 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�̓��y�B�z
09 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�g��������܁��E�߁l�y�C�z
10 �����͔����̎s�ꂩ�牓���m�@�n
11 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ�ٓ�������k�i�i�V�j�����l�m�A�n
12 �����ɂ͞�F�̌��������Ă���m�@�n
13 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�܁��\�Z�l�i�̐Βi�����Ă���y�A�z
14 �@�@�H���̔����V�l�ɕ�����y�@�z
15 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�k��������l�̖��l�͒p�����Ԕ���G�炷�y�A�z
16 ���̕����։��m�@�n
17 �k�ނ炳���F���͂Ȃ�����l�Ɏ����߁y�A�z
18 ��l�́k���������l���V��ł���悤���m�@�n
19 �@�@��������̃o�P�c�̒��ցk�i�i�V�j�����݂Ɂl�y�@�z
20 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���B�k�i�S�p�A�L�j����l�����k�i�S�p�A�L�j����l���ʁk�i�S�p�A�L�j�E�߁��i�g���j�l�y�A�z
21 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�ҁ��l�l�́k���������l�����������y�A�z
22 �t�̂ЂƂƂ��m�@�n
23 �@�@�@�܂�Ŕ������NJ|�m�^�s�X�g���[�n���D���Ă䂭�悤�Ɂy�A�z
24 �k�i�i�V�j�����ʂ́l�����̉�����������������ė���m�@�n
�`��5�s�̎�����������ƁA���o�`���@�E�A�E�B�i�O�q�̂悤�ɁA����3�s�͂قځA�ł����Ċ��S�A�ł͂Ȃ��j�E�@�E�A�Ȃ̂ɑ��āA��e�`���@�E�A�E�@�E�A�E�B�Ȃ̂́A���ӂ��炢���Ă������Ȏ����ł���B���̕ύX�ł́A17�s�߂́u�k�ނ炳���F���͂Ȃ�����l�Ɏ����߁v�������[���B���̏C���́q�H�v���r�i�J�E8�j4�`11�s�Ƃ��ď��o������g�݂��܂ꂽ�q�f�z�r�i�sCURIEUX�\�\�����t4���A1978�N11���j�̑�1�s�u�ނ炳���F�Ɏ����߂����v��D�悷�邽�߂̑[�u���낤�B�g���́s��ʁt��҂ނƂ��A�͂��߂Ă��̗ގ��ɋC�Â��ĕύX�����ƍl������B�����炭�q�NJ|�k���o�`�l�r�Ɂu�ނ炳���F�Ɏ����߁^��l�̉������V��ł���悤���v�Ə������邵�����_�ł́A�q�f�z�r�̖`���s��Y��Ă����̂��낤�B�t�Ɍ����A�u�ނ炳���F�Ɏ����߁i�����j�v�Ƃ������傪�擱���鐅���҂̃C���[�W�́A�g���ɂƂ���ė���Ȃ��I�u�Z�b�V�����������̂ł���B���ɁA���o�̈�����ɋg���������ꂽ��Ԃ��Č����Čf���邪�A���Ǝ������̕ύX�w�������݂��Ă��āA�V���ɐ����������������قǂ̔ώG���ł���A��������d�オ���z�肷�邱�Ƃ͓���B���W�p�̌��e�쐬�̍ۂ́A��̂��Ƃ��A�g���̎������i���M���Ɠ��l�j�z�q�v�l���������Ƃ��낤�B
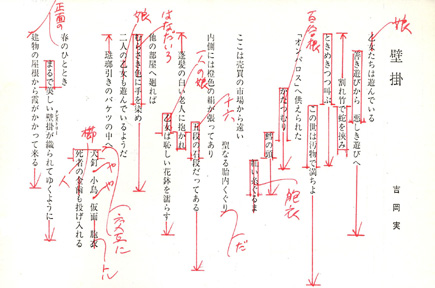
�g�����̎����k���o�`����e�`�l�����ш�Y���Ԏ��ōČ��������сq�NJ|�r�i�q��|�Εv�W�r
�p���t���b�g�A�؉�L�A
1982�N3��27���j
���̕W��́u�NJ|�v�����A���і{���i�Ōォ��2�s�߁j�ł́u�^�s�X�g���[�v�ƃ��r���U���Ă���̂ŁA�q�NJ|�m�^�s�X�g���[�n�r�Ɠǂ݂����Ȃ�B�������Ȃ���A�s��ʁt���\������ق��̎��т����ׂĊ����\�L�Ł\�\��O�͍ŏ����̎��сq�G�̐��r�i�J�E2�j�̂݁\�\�A�ǂ݂��a�ꂩ����ł��邱�Ƃ����Ă���ƁA�u���ׂ����v�Ɠǂނׂ����Ǝv����B����Đٕҁs�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�i���Y��ԁA2000�j�ł��u���ׂ����v�Ɠǂ�ł������B���̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�ł̋g����������A�q�����i�J�m�v�X�j�r�q��i�A�W���[���j�r�q��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�r�̂��Ƃ��A�q�NJ|�i�^�s�X�g���[�j�r�Ƃ�����������Ȃ����B
�k�NjL�l
�؉�L�̓W����̃p���t���b�g�ɔ��\���ꂽ�g�����̎���4�сB���ꂼ��́u�G�ɂ悹�āv������A������s�T�t�����E�݁t�i1976�j����s���[���h���b�v�t�܂ł�4���W��1�т����߂��Ă���B�Ȃ��A�Z���G���g�́q�ٖM�r�Ə��́q�O�����i�[���̓e�r�́A�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����t�i����R�c�A1996�j�́q�g�����̏����ȕ����r�ɃJ���[�Ő}�ł��f�ڂ���Ă���B
�g���������W�s�a���`�t��1962�N9��9���A�Ȃ̋g���z�q�s�l�Ƃ��đ���ɂ��犧�s���ꂽ�B�������Ō��́u����Ɂv�̕\���̓t�����X���̕\�S�Ƌ@�B���̕\�P�����Łi���̕\�S�ɂ͑��������ꂽ�uSSS�v�A�uSohSenSha�v�̗���������j�A���܂��≜�t�ɂ͂Ȃ��B�����͎v���ЁB���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�łg���܂���܌㏉�̎��W�Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�s�a���`�t�́A22�т����߁A�q�V�l��r�i1959�N1���j����q�C���Əȗ��r�i1962�N3���j�Ɏ���S�т��{���W�ȑO�ɎG����V���ɔ��\����Ă���i�q�g�����N���k��i�сl�i�s�a���`�t������ԁj�r�Q�Ɓj�B���̍Z�قł́A�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���E�V���f�ڌ`�A�Q ���W�s�a���`�t�f�ڌ`�A�R �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�f�ڌ`�A�S �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�P�����S�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�a���`�t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���A���ǂ邱�Ƃ��ł���B�{�e�͈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ́A�����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A���j�R�[�h�ɂ��u瀆�v��u禱�v�̑���ɁA�s�{�ӂȂ���V�t�gJIS�́u���v��u���v���g�p���Ă���_��ȉ��������������B�ŏ��Ɂs�a���`�t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���E�V���f�ڗp���e���e�F�q���w�r�̎ʐ^�ł������āA���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ��ɁA2009�N3���̎��_�Ŗ����B
�P ���o�G���E�V���F�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B
�Q ���W�s�a���`�t�i����ɁA1962�N9��9���j�F�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l13�s1�i�g�B
�R �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B
�S �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���R �s�g�������W�t�B
�s�a���`�t�̌��e�́s�m���t�Ɠ��l�A�����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������i��o�q���w�r���e�̎ʐ^�łƂ��̉�����Q�Ƃ��ꂽ���j�B�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����́A�ŏI�`�����߂��S���W�ŏ����ɓ��ꂳ�ꂽ���Ƃ�����A���o�`������ƈقȂ�ꍇ���S���W�ɍ��킹�ď����\�L�Ƃ����B�Ȃ��q�V�l��r�Ɓq�ʕ��̏I��r��2�т́s�a���`�t�Ɏ��^�����܂��A�c��m�ҏW�E����s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�Ɂq�W�������сr�Ƃ��Ď��߂��Ă���B�����ɂ�����2�т̖{���́A���o�G���f�ڌ`�Ƃ����W�s�a���`�t�f�ڌ`�Ƃ������ɈقȂ�̂ŁA�s�g�������W�t�f�ڌ`���x�Ƃ��āA�P�E�x�E�Q�̏��ōZ�����Ĉٓ����f�����B��{�x�̑g���̊T���͎��̂Ƃ���B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
�x �s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l18�s1�i�g�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�s�a���`�t���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s���E�����t�k���s�����l�f�ڔN���i���j�k�i���j���l�j
�V�l���i�D�E1�A46�s�A�s�G����]�t�k����Ёl1959�N1���k�t�G�E2���l�j
�ʕ��̏I���i�D�E2�A57�s�A�s������t�k���̉�l1959�N6���k9���l�j
�����i�D�E3�A24�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N8���k1���l�j
�a���`�T�i�D�E4�A12�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N9���k2���l�j
�a���`�U�i�D�E5�A13�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N3���k7���l�j
�A���i�D�E6�A35�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�j
���w�i�D�E7�A19�s���A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�j
�ҕ����鏗�i�D�E8�A19�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N10���k3���l�j
���i�D�E9�A70�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1959�N10�����k4��10���i38���j�l�j
�c���i�D�E10�A25�s�A�s������t�k���̉�l1959�N12���k10���l�j
���̕a�C�i�D�E11�A22�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N11���k4���l�j
�~�̋x���i�D�E12�A14�s���A�s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1960�N3��7���k1043���l�j
���̂��肠�����i�D�E13�A22�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N5���k8���l�j
�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�A35�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1960�N11�����k14��11���l�j
�������i�D�E15�A25�s�A�s���i�t�k�I�X��l1961�N2�����k2��2���l�j
�ߔ��i�D�E16�A39�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1961�N1�����k6��1���i52���j�l�j
����i�D�E17�A20�s�A�s�ߑ㕶�w�t�k�ߑ㕶�w�Ёl1961�N1�����k16��1���l�j
����鏗�\�\�~���̊G�����i�D�E18�A26�s�A�s���w�t�k���w�Ёl1961�N5�����k16��6���l�j
��`�i�D�E19�A19�s���A�s�����t�k���w�O���[�v�����l1961�N7���k9���l�j
����ɂ��i�D�E20�A33�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1961�N10�����k15��10���l�j
���E�H�̊G�i�D�E21�A23�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l�j
�C���Əȗ��i�D�E22�A26�s���A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���o�́s�G����]�t�k����Ёl1959�N1���k�t�G�E2���l��`��O�Z�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͕����j�g�p�A�܍�15�s1�i�g�A47�s�B
���т������̗c���ƃy���J����
�V�l���A�����
�a�l�̉��҂Ƃ��Ď��ʎ��̂���
���̓����ƐS�̌Ǘ������m�F����
�X�̖̑S�̂����Ŕ҂�
�o���邾���������
�H��D��g����
���ꂪ�Q���̉����猩����
�ρk�P�݁��x�Q�R�S�i�g���j�l���܂ꂽ�̂͌�����������
���Ɣx���̌̍����
�V�l�͏o�Ă䂭
��̉����瑱���[���g�̂��˂�֏��
���т̍Ȃ����Ԃ��ɂ���
�������[�̓őf��
�l�̐S�����킪�����݂���
���炰�̑̂��܂��Ă���
�V�l�͕����Ȃ���
��
��
��x�͎����V�����̌�������
���Ԃ̂͂��ꂽ���E���z�����k�P�i�i�V�j���x�Q�R�S�́l
��k�P�x�Q�i�i�V�j���R�S���l��ʋ��̕��͂�����������
���������k��
���̂������������͂�������
�G���`�b�N�ł���
��V�������V�l�炳��
�K�[�[�̌��̂Ȃ܂߂�������
�V�l�͉�z����
���m�ɂ����Ȃ�Αn������̂�
�ݑ܂��N���́k�P�Ȃ����x�Q�R�S���߁l��
���̂Ȃ������̖��
�͂����Ȃ�Ñ�̚e��������
���ƍ��̑Γ��̎s��
�����ď��ɂ̉��̒��S�ɍ���
���҂̐S���̊��
�����Ȍ��������k�P�i�i�V�j���x�Q�R�S�悤�Ƃ��l��
�k�P�ʂẮ��x�Q�R�S�i�g���j�l
�ނȂ���������ꂽ
╂̂��Ƃ�����
�݂��Ƃȗ��̗x�q��������
�s���Ȗт̐��E��
�����̎�l���䓁���Ђ�߂���
�V�l�̑哪����k�P�x�と�Q�R�S���l����
�p�̂߂���
���������҂Ƃ���
�c���ƃy���J���̎��_�Ƃ���
���l�ɂ͎ז��ɂȂ�ʏ��ֈڂ����
���o�́s������t�k���̉�l1959�N6���k9���l��O�`��Z�y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|19�s1�i�g�A57�s�B
�˂Ɏ��ʐl�̂܂��ɂ���H�т̒��̂Ȃ���
�����ӎ��̊O�ʂł͂������
�E���̌��̗�
���̐^�V�����������̊��т̐[�w��
���I�Ɣ������肩����
���ʐl�̗c�N���̏ё�������
�܂ꂽ�َq�̊Ԃ�������
��̏�̂䂦�ɉ�������
�Ɗy�̉��X�s�[�h�Ŏ����Ă䂭���M�̎���
㵒p�̃Z�b�N�X�ŌC�������
�c���̂܂邢����Ԃ��ւ̕��̂ƂƂ���
��،^�̕��̐S���I�|�Y������
���Ɣ��̔��̌���瀎������N�̎�����]������
�閧�ʐ^��
�_�����Ȑ��̂��т��������D����
���n�Ȉǂ���
�����悢���̂���̂��ڂ݂�
�s��܂�̏��N���̒x�����̎n�܂�
�炢��̖������]�o�ɋ��炳��
�邢�ꂫ�̂��������f��̗⊴�Ő�ɂ���
���ւ̉�蓹
���B�ˑ��ւ̓��M�Ɖ��@
�Ƃ��������Y
�܂��ʂ̏����ւ̂₳�����ܟB
���R�ƍ^���͂��������N�̐g�̏�����肠����
�㐢�̍����̂Ȃ���
���̖��q�ƌZ�̖��͂ȉƂ̒����������
�I�y���ق̋ɍʐF�̕���̗\���̉̎肽��
���ۂŐ�����쌀���҂���
�K���{�̔�ւ̉��ߊ�
�A�i�k�P�x�E���Q�R�S�i�g���j�l�x���̌��̐O�̐G�}
�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����
�g���l���̈łŎ��ł���
�ƒ{�̑����̏L����������
���e�������N�̐��_���X�̉͂����������
���łɔc�������������̉^�s��
�[���Ȏ��̋��|�̓`����
�ɂ鏬���̔��̐��ւ̏W�ς̓{��
���N�͌ǓƂ̌��������ɂ�
���̌ł��p���o�����͂��߂�
�����������v�̔��[����I���܂ł���������
����������̐푈
��C�̎ԗւ̂ЂƉ�肷�鎞
���Ӗ��Ɍ��̂ӂ����鎞
�����̐l�ނ̎��E���ɂȂ�˂Ȃ�ʖ����̎�
�����ȗ����ނ̊��ݍ��������̒Ⴂ�p��
������鎀�E���ĉ�����鎀
�Ñ�̖�O�~�`����̑��z�̉��̏X���ȏ��p���
��l�����̏��N�͚L����߂�
����̕����̐��E��
�R�b�v�̗��̂Ȃ���
�܂��ɋt�k�P�i�i�V�j���x�Q�R�S���l�܂�
������
�����ʐl�̔����̓����}
�ё��̏��N�͖͕킷�邾�낤
��l�̏K���̂ʂꂽ�H�т����炷����
���݂�鏌���̊g����
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N8���k1���l���`��y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|25���l1�i�g�A26�s���B
�ڂ��͉�������@�̂��ނƂ���łȂ��@���ޏp���Ȃ��@���j�̕ϑJ�ƌl�̎d���̓�d�����̖�ɂ܂���ā@�ڂ��͉�������@�g����̉ԂƁ@�����̋�����߂�ႂ̓f�����n�����̐��@����͂ڂ������̌��ۂ��낤���@������������������������@�l����ΐ̂̋L���̂Ȃ��̐����̂Ƃ�����̓��[��`���Ȃ���@�����͂ڂ���̓���̏K���@���Ă̐��E�̕֊킪�W�߂���@�ڂ��̉����͂ڂ��̐��_�����݂������@���l�̑����̐S�֓`�B����@�Q���̑�O�̗Ƃ点�Ă䂭�@���̂Ƃ�����Q���ׂ�V��j���̂ނ�@���̂����₩�Ȑ��@���̂����炵���葫�̉^���@�����̐����Ă���؋��̔r���̈��@�N�������̈ʒu�@�ڂ��͂ǂ����������������Ƃ��납��@���ڊD�����Ԃ�@��s�I�ȐH�������邽�߁@�n�⌢�̌o�������Ȃ��ł��낤�@���m�Ȍ`����̉���������@�͂Ȃ��ނ��됶���邱�Ƃ�F����@�ɂ݂̓����Ƃ���@���̊i���̏I��̋�Ԃ��ނ��铃���݂�@�ڂ��̎����ׂ����̖̂�Ђт��}���̌��̂Ȃ���̍��܂鎞�@�ڂ��͉�������@�k�����X�̓y�n�Ɂ@���܂���̐₦������̉��Ɂ@�i�v�ɐS�̓����̌_�@�̒���f�@�ڂ��͖Y�����@�ڂ��͐l�ƕ���Y���@���݂̂Ȃ��ɂ߂��肠������F������@����ȉ�������ߑ�̏X���Ȃ����܂�Ö���Ԃ��ʂ��@������قȈÂ�������ւ���@���S�Ɏ��R�̌��̐ڐG�����肩�����@��\���I�̒�Ɂ@�ڂ��́k�P�Q�����R�S���l���̂Ƃ��Č��N�Ȓj�̈�l�ɂȂ�@�܁k�P�����Q�R�S���l������H���͂��߂�@�����ɐV�����W�E�Θb���͂��܂�
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N9���k2���l�l�`�܃y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|25���l1�i�g�A13�s���A�W��́u�a���`�P�v�B
��̂܂������ꂻ��͂܂����ł���@�����Ȃ����̑��鏬���ȕ�����͒j�ł���@���̊O�̒n�Ɏ��˂Ȃ��l�X���߂��߂��̕n���Ȏ��㢂��݁@墂��ނ炪�点�@���Ɵ����Ł@��l�̒j�Ə��ɐQ���̎���^����@�邪�s���p�����Ȃ�@���̐l�͏�̉��֒��ށ@�Ύ��͌��𗁂с@��̎q�{�ֈڂ�R����@���͂������̉��Ƃ��Ď��Ȃ̎}�ւ肳���苩�ԁ@���𐅂��@��͓�̐K��ⴂŐڂ��ꂽ��̉����ɕς�@���̐��E�֓����Ă䂭�@���͒��������牱�̂Ȃ��L�`�̎���@�J���ɂ�����M���S��ł�������@���܂ꂽ�m�̖ڂ����̐��̐���Ƃ���k�P�����Q�R�S���l�@����炷�ׂĂ��A�C�ȏ��˂��h���@���ꂪ�����ł���@���K�ł���@���͂ӂ����̒��������������悱������@��͏�q�̓����śs�݂���
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N3���k7���l��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�܍�25���l1�i�g�A14�s���A�W��́u�a���`�Q�v�B�g����1960�i���a35�j�N3��9���̓��L�Ɂu���ł����q�a���`�Q�r�݂�B�܂��悵�A�z�q�ɏ��Ă�����āA�q�k�r�֑���v�Ə����Ă���B
�킽���̐����Ă��鍡�@�킽���͐G���Ă���̂��@����͂����Ԃ�ߋ��̔N���̈��Ɨr���̐����ɗ}����ꂽ�܂܁@�����ȑ܂ł̈�͂��̗��Ƃ��ā@�����ɂ˂ނ�@�����������ł킽���͎����̑��̒܂����@�킽���̐M�͂��ꂩ�獂�܂�@���[�ɂ��肩�������H���̌Ō`�̎��@�킽���͂��̂��ђ������ꐫ�̊Â��q�f���@�����������痧��������邩���m��Ȃ��@�����Ԃ��������Ǝv���Ȃ���@���̎p�Ł@���Ȃނ��뗇�ȑO�̂낤�����̌`�Ł@�����̓��e��O�㍶�E�̕ǂɉf�������@���ꂪ���ꂪ���łȂ����́@�������̂̉H��^�����ʂ��́@�ď́E���@�ď́E��̖��݂Ă���ȑY���̎ҁ@��̍�����Ȃ̂Ȃ��̌��̃A�[�`��������o��@�������ꂽ�G�L�X�@�ؑ��̎�s�ň�s���̂Â�̂ӂ��Ђ炭�l���@�^�Ȃ����Ԃ�V�k���������Ă���
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�q�u���w�v���l�сk�q�A��r�q���w�r�q�m���r�q�r���r�q�P���r�l�r���Z�`����y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|1�i�g�A35�s�A�u�J�b�g�E�Ɍ��ʕv�v�B
����֒���������
���܂܂Œ���ł������̗�
���������ɓ�������
墂ɂƂщ���
�Ô��ȗ��l�����̎����̏����킽��
���R�t�ł�ꂽ�̗t�̉��y�Ɋ�������
�炢��ɋP��
���ʂ͎��C���Ȃ���
���̗�
�܂�ׂ�Ȃ��]��
��p�̐����̓���������
�p�Y�̈ÎE���ꂽ����̎s��ʂ�ʂ�
���̑O��
���낢�₷���������̑ڂ�
���̗��͕����߂Ă䂭
�^�����Ȃ�����̎x�z��
������Ȃ��Â������Ȃ���
���ł₩�Ő��_�̌���������ꂽ����
�邲�ƂɘA�q�����肩�������l��̊�Ɛ�̗���
���̒��]�Ɉ��Ǝ��̋��������肦�悤��
�������̗������̗����̂肱����
�������Ȃ��@�Ђǂ��ϗe
���l�̂��т��������������ĂɌ�����
���N�Ȓj���̎����J����鎞�܂�
�A���Ђ����̗�
�ϔO�̐��E�Q�Ԃ�ł��Ȃ��̂��낤��
���炩���C�̑��̕~���̂���
�����܂����ʉ߂�������
�����Ȃ����̗�
�����̂Ȃ��ފ݂�T��
���M�̂Ȃ�����
���߂Ȃ炵�炭
�⌌�ȓ��̗��֍S�������
�k�P�z���Q�R�S�ނ��l��ꂽ���̗�
�����܂����Ȃ��V�̂�
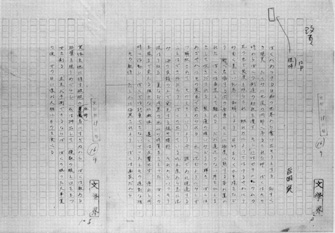
�g���z�q�v�l�̎�ɂȂ�q���w�r�̎G���f�ڗp���e���e�i�q�g�����̎��e�q���w�r�r�Q�Ɓj
�o�T�F�ؐ����i�ۏ����v�ďC�j�s�ߑ㎍�l�E�̐l���M���e�W�t�i�������o�ŁA2002�N6��10���A��Z�O�y�[�W�j
�G���f�ڗp���e���e�Œ��ڂ��ׂ��́A1�s�̎��l�߂ł���B32���~20�s�̌��e�p�����A�s����4���A�L�ŏ����������s����2���A�L�Ő܂肩����26���l�߂ŏ�����Ă���A�Q�E�R�E�S���ׂĂ̊��{��27���l�߂Ƃ́A�킸��1�����̈Ⴂ�����A�قȂ��Ă���i�U�����^�͂���26���̂ق��ɁA20���E22���E24���E25���E27���őg�܂�Ă��邪�A���e�̎��l�߂����o�`�̎��l�߂Ɠ��������͕s���j�B�p���p��́A�{�e�̏��߂ł��G�ꂽ�悤�Ɋ����͐V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͂Ђ炪�ȁE�J�^�i�J�Ƃ������j�ŁA���ʓI�ɖ{���e�̕\�L�@�́A�u瀆�v���܂߂āA�S�́s�g�����S���W�t�f�ڌ`�Ɗ��S�Ɉ�v���Ă���B
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�q�u���w�v���l�сk�q�A��r�q���w�r�q�m���r�q�r���r�q�P���r�l�r����y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|26���l1�i�g�A20�s���A�u�J�b�g�E�Ɍ��ʕv�v�B
�ڂ��������锒�s�̐��E����D���o�����Ƃ���@�邷�ׂ������@�����݂ɖє�̓����݂֒邳�ꂽ���@�ڂ��͂��̎�����ڂ��̑n���̏��������@�����ɂ̓[���j���E���̉Ԃ̐F�Ŋ��x���Ƃ炳��@�G����ɂ���Ă͂��₩�ɂ���ނ����������[�@�a�����悤�@�ړI���Ȃ������������ǂ�@���N�Ղ�����̑S�g�@�����ɋɓx�ɏn����䕂��u���ꂽ�@�ڂ��͔ے肵�ė����@�������߂̂Ȃ��݂��ЂƂ܂����Đ����������@���Ƒ��̈Â��݂ǂ�̋P���@�ڂ��͂����₩�ɂ��̊��F�Ő��߂���@���֒��ނ悤�ɏ������������ā@���̂Ƃ��Ƃ�����荡�@�N�ł���k�P�������Q�R�S�����l���邱�Ƃ͂ł��ʂ��낤�@�ڂ��̗����Ă���h���x����}�ɒ��݁@�C�̊L�ނ̏�Ŕ�������ڂ⍘���@���ꂩ�炢�������g�͂��˂�@�ĂȂ��⊦�̕X�R�̓��������Ƃ����@�ڂ��̎咣�܂ŕς��鋭�͂ȑg�D�́@�����͔��������@��~�Ɠ����ɕ������@�ڂ��ł͌v�ʂł��Ȃ��}�b�X�Ƃ��̉ߏ�ȉA�@���̊��ҁ@�������ɕ��̂���悤�@�ڂ��͉�Ƃ�����@���̂𑼂Ɉڂ��j���̎{�p�҂ɂ����ʂ���@�ڂ��͐����錌�ǂ�߂��炵�@���͉��o���ā@�����̊�ƌ���������n��@�������\���ł���Ȃ�@�ڂ��̖������厖�Ƃ̌�@���̔���������_�ɂ��̂�H�ׂ�
�k2010�N8��31���NjL�l
�؏��X�i�����s������x�j���q���w�r�̎��e���s���{�̌Ö{���t�ɏo�i���Ă����B�u�g�������e�@�摜����^�g�����A1�^�u���w�v�@�y����640���l���@���ŗL�@2���^�؏��X�@�@105,000�~�v�B�����N�摜�������i��f�ʐ^�Ƃ͕ʃJ�b�g�B�F�������Ă��Ȃ����A�J���[�Ȃ̂Ōf����j�B
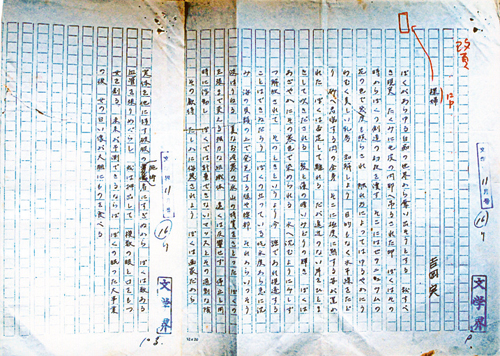
�g�������e�q���w�r�i�o�T�F�؏��X�j
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N10���k3���l�Z�`���y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|27���l1�i�g�A19�s���B
�����Ղ�Ɛ��҂݂ɂ����v���I�[�o�[�@����̗����ɂ͋ʔK���g�����@�ޏ��͂��Ԃ�̂��炾���牽��҂݂����̂����ꂽ���̂ł͂Ȃ��@�傫�ȋ܂̓^�[�g���l�b�N�̕ς�^�@�ޏ��͍��̗͂ň�l�̒j���������Ƃ����@�W���[�W�[�Ńs���N�Ȃ�ނ���_�ɂ�����@���z�̖Ԗڂ̂Ȃ���䕂��Ԃ����x�̓��X�@�j�̏Z�����ǂ��֍T�������v���������@�H������u���[�@�O���[�ȂǂŖ͗l��ς��@�������S���҂݂ɂ��ā@�j���Ɛg�҂̌��͊��̖т��ʂ炷�Ɓ@��k�P�Q�R�P���S���l���O�ɂ��炵���d��Ȍ����@�������͎O�\�W���̓��F�̕z���͂��ĉ��ɂȂ�@����ɂȂ�ʂ���@�j�̕����ւ͔L�����ʂ�ʔ閧����������@���͐ܕԂ���[���@�j�Ƃ��̉Ă͔g�̉��ց@���ׂ������Ƃ��Y����ʁ@�P���ȃ������X�҂݂ł������肳���悤�@�j�̓��k�P�g���Q�R�S�e�l�E���E��E�s��Ȏo���@�h���X�E���[���łȂ���Ώ��Ɏd���ʁ@�������̃V���G�b�g�@�j�͕n��������D�F�ȕlj��`���@�����������Ĕޏ�������Ƃ��R�R�A�F�̃X���b�N�X���������Ɓ@�V�ٖD�t�ɂ���ꂽ�@�����~�������ڂɂȂ�@�D�̒�̊L�̗₽�����肪�Ƃǂ��@�ޏ��̊�ɓ���j�͔ޏ��ɂƂ��ďۉ�F�̋��`�̃n���K�[���@�{���Ɏ��ʂȂ�Z�[�^�[��E�������Ɣޏ��͍l����
���o�́s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1959�N10�����k4��10���i38���j�l��l�`�y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|21�s1�i�g�A70�s�A�莫�́u���獡��Ƃ������̎��^���̉����̔n�̕�������A�s���^���S�ɂ��ā^�J�̒n�ɔq�삵���^�q���}�m�̎������r�v�B
�킽�������̍���Ƃ������̎�
���̓��Ƃ����J�Ət
���������Ȏ��@�̋��������ʂ��ɂ�����
��q���䂭��Ȃ��~�����̂Ɗ�����
���̉��ɏW��r�̋�Ԃ�
�Ȃ�܂�����̂Ȃ��������
�ӂ��Ȃ�ΌY������Ď����L
���ނȂ�Ή�����삵���m�̑�
�킽�������͎̔ւƂ��ɕ���ŐQ��
�ɂ�����݂Ȃ��痬���
�吨�̐l�̔���
�܂��͂܂�Ȃ鑞���ƕ�
�킽�������̔畆�̂߂������Ƃ�
�������̋\�ނ��ʏ��Ƃ���
��Ǝ�@���ƒ�����
�˂ɂ݂͂����I�����W
���̉ʓ��̔G��ɓ��k�P�с��Q�R�S�i�g���j�l�����
����m��ʈ�
�ϔO����s�ׂ�
�Ó]���鑾�z���̎��͔���
�킽�������̕X��S�g�ɗ�����ꂽ
�Ԃ͎��ʂ��̂̎��i
���炭�͍��C������₪�Ă͒������˂���
�َ��̐Q��
��ꂽ�ւ̗��@����
�a���ꂽ�A�т̎���
���Ԃ���ѕz��
����o�@�̂т�A����
�ނ炪��I�̐j�����̓��֑ł�
�ہ@��
��������̂�
�킽�������̏��������ʂ�
�d�p�͂Ȃ��̂�
�p���Ƌ����̂ق��ɂ�
�����ȘQ��̕������錶�̂��܂��肽��
�@�I�̐��E�ɕ����߂�ꂽ
�킽�������̌�{�̒�
���l�̂��킪�����q�����W��
����@�߂������@�۔�a
�����̊�̖��͂�����
�嗝�̒��̂�������̂���
�֗~�̈߂����X�ƒ��߂�C�a
�킽�������ɔ���邾�낤��
�ؔ��Ȃ�������
���߂ӂ����[���̕��i�̉ʂ�
�x��e�����ĕn��{��
����ȊO�̂Ȃɂ��^�����悤
�Ƃ��ɗ��̔�
���ƂƂ͂������
����������̂ނȂ������ł���
�������ސ��H�̐���
���̋z�Ղ̖M��
�Â��߂̂Ȃ�������
�킽�������͈��݂Â���
�ߑ㑕���̓����̂����ӂ���
�ꂽ�e��������邷
���̍��g�̌��̏o
�킽��������������
�ᖡ����Ƃ炳���
�킽�������̗������������ꏊ
�˂ɊD����̖Ȗт���点��
�킽�������̐S�Ɠ��̉A��
�킽�������̔��ʓ���
�˂������̂˂��݂��C���܂킹��
�\�������
��l�̒j�Ƃ��ė������ݏグ
��l�̏��Ƃ��Đ���������
�����̊G��ɂ��܂ǂ��Đ������
�i�����Ȃ���Ύ��i����
�W����ꂽ���y
���o�́s������t�k���̉�l1959�N12���k10���l�Z�Z�`�Z���y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|1�i�g�A26�s�B
�[���ł����т����肩����
�H��̌����l
�ɂ̂����Ƃ��������䗠
�O����ܐ�x��
�ނ炪�锒�����`�ɕ���
��������ʁk�P���Q�R�S�G�l������
���ˏo���s���̔n
�ނ炳������ɏƖ������
�R�S����H�ׂɂ䂭
�q���̋�����
����Y�������̂Ȃ�܂�������
�߂��������ꂽ��
�r�̂̔����ɂ͐[��������������
�j�̐H���I��������������
��҂т炫�̐��������
���ʂ̔n
���ȂȂ��Ȃ���
�O����ܐ�x��
��x�̔{�̘Z���̒ܐ�x��
�q�����@�����Ȃ����u��
�Ȃ܂�����������ւނ炪��
����@���J�@�X�e�b�L��@����
����I�ɂƂ܂�
�ÓT���̌����Ƃ���
�ɂ��H���n
�k�P���R�ɐS�̔^�����������Q�R�S�i�g���j�l
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N11���k4���l�Z�`���y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A�܍�25���l1�i�g�A24�s���B�g�������N���A�t�@�C���ɕۑ����Ă����V���̐蔲���ɁA�{�т̃X���X�Ǝv�����L��������i�q�q���̕a�C�r�̃X���X�r�Q�Ɓj�B
����V���L���Ŏ��̂��Ƃ����߂Ēm�����@���܂ł��r���}�̃J�����j�n���ɓ��l���Z��ł���Ƃ̂��Ɓ@�ʐ^���ڂ��Ă���̂ł��Â������@���ׂĂ̏�����ւ��͂߁@���������ȗc���������Ă���@�����ł͍ߐl�łȂ����l���������d���g�Ƃ��ā@�ڂ��͎v�����������N�̍��@�O���̒n���������T�Ō������Ƃ��@�ޏ������͑̂̐����Ɠ����ɐ^�J�̗ւ������Ƃӂ₵�@��������������܂ŏd�˂�@�ł��l�Ԃ̎�ɂ����������邩��@�����̌`�Ԃ��ӂ݊O���Ȃ��g�Ŏ~�߂�@����ȏ㒷��������댯���@���E�ςƓ��������ɕω�����@���͎��ʂ��낤�@�ڂ��͑z���͂��Ƃڂ�������@�ޏ������̌����̖�̈ł܂ł݂Ƃ����Ȃ��@�^�J�̗ւƗւ̂��������Ƃ����a�݁@���̖��@���̗₽�������₫���������@���̒j�̓������h�����@���̖����̎����≘���ł܂�@�̂Ȃ��ɔޏ������͒��މP�@�Ƃ�����ڂ��ɂ͕ʂ̂��Ƃ��C�����肾�@���܂��ܔޏ��������a�C�ɂȂ����ꍇ���@�O�̕����Ɉ�l�̎�ւ̋Z�t������炵���@���̏��͒�̑傫�Ȏ��ɂ����ğ��������ׂ�@��ԏ�̗ւ���O���Ă����@�����̎}�ɂ�����@�Ō�̑傫�ȗւ��������Ƃ��������̑����������k�P�Ƃ������Q�R�S�i�g���j�l�@�Z�t�͂��̂Ƃ��͂��߂ā@���ɓ��������Ƃ��Ȃ�����@����������̕����@�����̏��荂���ʂ����Ɠ˂��o�������Ɏv�킸�f�b���@�蓖�����Ƃ炸�X�ւ������k�P�����ł��遨�Q�R�S�i�g���j�l
���o�́s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1960�N3��7���k1043���l1�ʁA�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�V���p������{�i���p�j22���l1�i�g�A18�s���B�g����1960�i���a35�j�N2��27���̓��L�Ɂu���сq�~�̋x�Ɂr�o���v�Ə����Ă���B
�����ł͊D�F�̔n�ƊD�F�łȂ��n�Ƃ����ꂿ�����@�D�F�̔n���Ă炵���т��������ꂳ����@�ʂ̔n�͈×̉��Ȃ̂��낤�͂�������������@�������̂��Ă��݂�������]����т̗��̂ɂ܂ō��܂��ā@�����ɂ͂��ꂪ������@���S�ȉ~�̂ӂ�����@�Ƃ��ǂ��͂ݏo����̂��I�����W�F�Ɍ���@���S�͂������Ԃ��o�߂����̂ō����@���ӂɂ�������Ƃ��ꂳ�̂���������p�b�̂悤�ɋ��낵���@�����͎��g�̑ڂɔM�𗁂т�@�܂����ꂿ�����Ă���n�����@�s�G���łȂ��Ԃ��X�q�̒j�́@�������C�Â���������l�ł͂Ȃ��@������������Ă��鋤�Ƃ̂͂ɂ��݂̐S�@�e���g�̒ꂪ�[���Ȃ�Ȃ�قǂ������@�n�̕��ւ����Â��@���߂��邽�߂ɔ��ɍג����_���ӂ肨�낷�@�d�����Ђ�������X�̊Ŕ̕��ց@����͏[��������Ə����͎v���@�D�F�̖Ĕn�̂���Ȃ肵�����Ɂk�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�S�i�x�^�j�l�ٕ��킪�h��������@���݂̂������~�̋x�ɂ��I��ƂƂ���
���o�́s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N5���k8���l��`�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�܍�20���l1�i�g�A29�s���B
���̂Ȃ���͎~��@���̑S�ʂ̍d���ʂ̏�����ׂ�@���Ƌ��@�������܂����X�J�[�g�̂Ȃ��̗ŏ���ꂽ�r�@���炢���̊��ڂ�����肠�����Ă��鐅�@�Ƃ��ǂ������܂����ā@��C���z���ɋ����z���O�ɋ������傫�Ȋ���o���@�o���Ă���̂łȂ���@���̔��̔��g���o�n�ł��������Ă���s����Ȍ����@���̂��낢�Ȑ��̔g�𑼂̋����Ƃт�����@�邩�璩�ւׂ̍��o���@��F�Ƃނ炳���F�͏��̍D���ȐF�@���̔w�������܂ł���݂���ł���x���̐F�@�j�ƈ��̊�@�@�����������o�߂����畅��ؐ����ԁ@���傤�Nj��̊�̂Ȃ��ɒ��݂Ȃ��珗�͖���@���̏��̔��k�P�Ɓ��Q�R�S�́l�т̑��Ł@�Ăь��N�̂ɂȂ鋛�@���肠���鐅�@���肠������@�M����̔ߖ��@�������܂̎��@�������܂ɍ~��J�����炭�@�����z�n�Œ��߂悤�@���̉��̗��n�@�����̂Ɍ�������䂭�@�Ύ��ƍ������ނ�@�������ł͂Ȃ����͘m�łȂł��@���͕X�̊p�ʼn������ā@���������ʁ@�Ռ��̂Â����F���@��ȉƂ̖]��ł��郁���f�C�����܂ꂽ�@�[������������ʂ��k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�S�i�x�^�j�l�Ăт��肠�����Ă��鐅�@���̒��S�̉J�P�̒�������@�S������j���@���������j�̐g�ւ������@��g�̕��i�֑D��u���@�Q��������������ƂŁ@�������肠����@�P�Ȃ�O�`�ł͂Ȃ��@���k�P�Q㢁��R�S�ށl�ɂ��т������n�������߂���@���[�͎�����̏��Ƌ��@���̕ώ�����ޕ��@�ǂ��܂ł��A�����鐅�̂��肠����
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1960�N11�����k14��11���l��Z��`��Z�O�y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|23�s1�i�g�A35�s�B
�k���I�ȔZ���̂�����邱��
�킽���̓x���`�ɍ������ğ�������
�v���g�j�b�N�Ȉ��т��̂���
ⴂ̂悤�Ȕ����̂��т�����������
�����ɂ͊ϔO�̌ǓƂȌ����̂Ԃ�̂ЂƗh��
�����炾��ł����s�o�ɂ���
�����낵���������
����͓��̗̂֊s�ł͂Ȃ�
�ޏ��̓��݂���v���Y���������������璯�܂��Ă���
�ޏ��̘r��ڂ����ł݂Ă͎��炾
�Ȃł��肳���Ƒދ�����
�ӂ����ю��ȏȎ@���������
�킽���͍��݂���Â����������ׂ�Â���
���܂ɂ͂��܂������Ƃł͂Ȃ��i����
�ޏ��͕���������̂�
�锼�͂悭����
�X���̂Ȃ���
���z���̏��
�͂��炢���Ȃ�
�킽���̐H�ׂ����̐��Z�̏�ɂ܂�����
�����������獡��͏o���
�ޏ��̓f���P�[�g�ȋV�����s���ɂ������̂��낤
���l�̏�̐��ǂ��鉹�y
�g�����������鏈�����̉�
�v�[���̒��̋�
������ޏ��̓��̂����S���ł����
�����ɂ�����L�O��̓y��̑嗝���H�Ⴄ
�킽���͌����ɐV�����ǂ��ʂ�
�킽���̋@�\�͂ł͖��m�ɑ������Ȃ���
�W�I�̂悤�ȉ~���Ȃ�ׂ�
�ޏ��̏ё���`��
���炭�킽���͕ʂ�Ă��悤
���̐l�ɂƂ��Ă��ޏ��͕K�v������
�ޏ��͐ߓx�������ē�����Ă���
�k�P�����̃h���}�́��Q�R�S�^�V�����l��U�}�̏��
���o�́s���i�t�k�I�X��l1961�N2�����k2��2���l�ꔪ�`���y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A8�|�i�A�L�j1�i�g�A25�s�B
�ڂ��͒m���Ă���
�Ă̔������_�ւ̕��݂�
����ނ�����O�̂��炭
�������̒�����Ȃ��Ă���
�ǂ̈�����ЂƂ�����������
�����ɗ����ĉ~�݂�����
�ڂ��͋���Ă���̂�
�l�Ȃ͂��ׂė��ł������Ƃ���
�L����c������Y��Ă͂��Ȃ��̂�����
��_�Ȏl�̒��͍��Ȃ�
�ӂ��ꂸ�ɏ�������Ȃ�
�J�ɂʂ�Ă���
��������n�͏o�����čs��
�ڂ��͑��l�̐Q���̐�������܂݂�
�܂ꂽ�D�̊C���Ƃ���
���݂֎��X�Əd���߂���
�����̂Ђ������͉��𗧂Ă�
�ׂ�������܂��
�����鉨
���̂��Ȃт��t
�ڂ��͂���ȑ�l�ɂȂ��Ă�
���Ƃ������ɂӂ��
�Ђ������Ƃ����Ђ��������J��
�~������܂ł�
���Ȗv���̉ߒ��𗹂邽�߂�
���o�́s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1961�N1�����k6��1���i52���j�l�ܘZ�`���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|1�i�g�A39�s�B
�����݂̉�����
�킽�������̔畆�̃n�A���j�C
�킽�������̎l�p����������
�n�c���獡�ɂ�����܂�
�����݂��mᝐ�
�v�w������
�Ԃ�V������
�������������ΊC�֏o��
�������������
���邷�ׂ�̍g
�Ԃ�V�͗͂����������͘V�l������
�Ύ��̍\�������q�̐��E
�Ȃ݂̑b���銢�̋�
�V�l�͔���
��������
�V�l�͎������炵�ęꂭ
�Ɩ�Ƒ������͉���
���̔�������߂�����
���H�̍��͍��̊�̒�
�V�l�͗͂���������
�X�s�[�h��������
���炩�ȑۂ̏�ł�
�����[�邿����
�҂��҂��̊��`�̌�
�@�I�ł��ꂢ�ɐ���݂₤��
���̔������J�[�������������
���~�̓��ׂ̂�
�������邽�߂�
��������܂��Â�
�D�Ɛ����܂��ׂ��|��҂݂���
����̖�̂悤�ȕ�
�����ł킽�������͌���
�鍳�̏�������������@��
�Ղ�炷�܂̎�̂Ƃ���
����V��
��邽����
�킽�������͉Ƃɓ���
��C�̂ނ��ł��E������
�������̔\�ʂ̓`���̂�����
���o�́s�ߑ㕶�w�t�k�ߑ㕶�w�Ёl1961�N1�����k16��1���l��Z�Z�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|1�i�g�A20�s�B
��̉��ɂ˂ނ�B
�l������I
���D���̗��́k�P�x���Q�R�S�@�l����
�q���ƍ������Í������̈���
���݂Ă��锼���I���O�̎�
�����݂�����ΉP�̂Ђт�
�l�тƂ̎��ʂ̊i�q
�ڂ��̎��ɂ��ꂪ�i����
�����l���̋�̉���
�݂������̊C�̔g��
�ڂ����M���������Ƃ��ꂪ�j��
�Ȃ������o��
�g�}�g�̎R��������
�k�P�`�����Q�R�S�����l�̎��̖��
�������������čs����
�ڂ��͎��ʂ�薳�S�ɂȂ낤
���⓹��̂������
���u�����ǂ낭�قǂ҂�ƒ����Ă���
�M������I
���̖т̉��ɂ�������
����鏗�\�\�~���̊G�����i�D�E18�j
���o�́s���w�t�k���w�Ёl1961�N5�����k16��6���l�l�Z�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|2�i�g�A26�s�B
���R�̔z�F�̗≩�̂��₩��
��l�̏������܂��
��{�̕R��g�������Ȃ���
�ڂ��̐S�ɉ̉~��`��
���̏��̍����獶�E�ɓ˂��ł�
�_�̗��[�ɂƂ܂钹
����͂����q���̂悤�ɚL��
����������t������܂�
���ɐ^��������
���킷��
�ł̋��
����Ẳ��̊C�ɂ��܂�
�e�킪���k�P�ف��Q�R�S�E�l��ς���
���̓��e�����肩���������F����
�����Ȃ�
�����Ȕ���
�X�y�C���̓���
���j�̑��̒��̌�
�Ă݂�������
���̖��́k�P�����Q�R�S�]�l���̂Ȃ���
������������
�ڂ��͌��������Ă��邩���m���
�����ɂ݂����C�g�̒n���
�����]������
��Ԕ������w�l�X��
�ӂ����ё��z�����ʂɋP���Ȃ��
���o�́s�����t�k���w�O���[�v�����l1961�N7���k9���l�Z�Z�`�Z���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�܍�24���l1�i�g�A22�s���A�����Ɂu1961�E4�E14�v�B
�ڂ��̓��̂̉������Â��@���������⏗�̔����̒��ց@�����I�̗n�����̑��̊ԁ@�ڂ��͎咣�ł��邾�낤���@�ڂ��̔F���̂��߂ɑD���ԓ��i�݁@�����̓����Ŕ��������炰���M�̂��߂Ɋ������@�܂�ڂ��̈������̂��������g�F�ɐ��߂�܂Ł@���ׂĂ̈ǂ��͏n���Ȃ����낤�@�Ȃ��������݁@�ڂ����ڎw���`�̑S�i���������ɂ������@���t�͔O����ɂ����@��������܂������ɏW��@�����̘p�̒��S�ց@���y����������@�ڂ��̖���������̍j�������Ȃ�@�ڂ��̏��͏[���ڋ����@�T�̍b�̉��Ł@�����₳������������Ƃ�����@���邢�������`�A�����̂��@�i���̏�ɎM�����u����ā@���ڂ܂�̉��ǂ̉Ɓ@�ڂ��ɂ͐V�����q�Ղ��Ȃ��@�ڂ��̐S���ς����Ƒ��l����������@�ڂ��͐Ö��̂Ȃ��ŕς����̂��@���ꂩ��������͂��܂鈫�u�ƐZ���@�ڂ��̐������Ȃ܂Ȃ܂���������@��̔g�̉��̂��т��������}�т̋��@�������Ƃǂ��k�P�����Q�R�S���l��Ȃ����邽�߂Ɂ@�ڂ��͍����݂��������낤�@���n�̉J�Ɨr�̓����͂ލ���@�����ĉƋ�̎R���R�����@�������������O�ꂽ�s�@�����Ƃ���Ɂ@����悭�Ȃɂ��c��Ȃɂ��c��Ȃ��̂��H�@�M�^�[�̓��������炷�`�ց@�ڂ��͋߁k�P�����Q�R�S�Ál��
���o�́s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1961�N10�����k15��10���l���Z�`��y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|1�i�g�A33�s�B�g���͖{�т́q��i�m�[�g�r�Ɂu�u����ɂāv�́A���Ɍ��ӂ����ڂ��͂��߂������̍�i�ŁA�����ւ��V�����Ȃ��珑�����L��������B���́A�ꌾ�ł����A�푈�̂��߂ɁA�t������������l�̒j�̐S�̎p�ł���v�i�s���{���W�P�X�U�Q�t�A�����ЁA1962�N12��15���A��Z�l�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�@�@�����͂����q�ق����������̋ꂵ�݁\�\�r
������艌���~��
�����X�q�̉���
�������ꂽ�R�͂̐S�����܂�
�^�Ԃȃx�b�k�P�g���Q�R�S�h�l�̕����z�������
��̒��̖�����̋���
�ڂ��ɂ͍����ꂾ������������ꂸ
�R���N���[�g�̖A�́k�P�����Q�R�S�E�l���������Ȃ�
���̔b�U�ǂ����ׂ鏭�N�����Ȃ�������
���̉h���̌��Ɩ閾���̐�����j������
�ڂ��͓����������
���}���`�b�N�Ș]�̂�������g��
�Y�k�̂悤�ɗ����
��i��i���܂�C���s��
���ɂ���q�{������
�傫�ȃ����Y���삩��k�։��
������x��������������̊P��
�������ɂ������ꂽ�����d��
�ĂȂ������֏��̉��̈łʼn��͉������
�ڂ��̍��̑e������Ȃ�
����͐����āk�P�i�i�V�j���Q�R�S���l�邽�߂̌��
����ɃR�X���X���炭���F�Ɣ�
���Ԃ�������܂�
�ڂ��̔\�͂��ۏႳ���
��d�ɂ��}�т������ꂽ��
���̉������̓��w
���N�̔����䂦�@�����Ȃ��含���Ȃ�
�ڂ��̌��݂͉��ƍ��̂��邱�Ƃ�
�Ⴂ�I�ł͂ւ��܂���Ȃ�
��������ʂ̐F��
�ʂ̕��i�����u�����Ƃ�����
�`�[�N�ނ̑D�̒�ɉԉł����悤��
��������������
�|�[�Y��ς��邱�ƂȂ�
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l��l�Z�`��l��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A10�|1�i�g�A23�s�B�g���́q�O�̑z���o�̎��r�Ɂu�u���E�H�̊G�v�́A���p�G���Ō����A�V�������A���X���̏�����ƃ��I�m�[���E�t�B�j�̊G���ނɂ������̂��B�����Ă݂�A���t�Ŗ͎ʂ����悤�Ȃ��̂ł���B��C�̗������߂锖���̏��ŁA�������Ă���u�킪�A�t���f�B�[�e�[�v�ƁA�����ĉ������Ă��悢�B�u�킽���͂������ł���H�v�ƁA�v�炵�A��]���Ă���̂��v�Ə����Ă���B
�@
������s�ҁs�C���ւ���t�i���w�ЁA1971�N4��12���j�̔��ƕ\���k�����F���q���`�l�i���j�Ɠ����i�����`����y�[�W�j�f�ڂ̋g�������M�q���E�H�̊G�r�i�E�j
���������ɂЂƂ肢��
���[�̉�������
���a�ⓔ�S���Ɠ����悤��
���֒���
���n�̓����̂�����{�������
���̂₳�����a�C����������
�����Ȃ��т̂Ђ��ɐG��Ă���
��Ȑ[�݂ɗ���
������ꂽ��I��
�킽���͂������ł���H
���������̌�
�a�̂ЂƉ�肷��ꃁ�[�g�����a�̔n�̓��W
���ꂪ���J����č��֑��Ƃ�
�킽���͔ۂł�����F���ł���
���ł��B���Ȑl�Ԃ̎������肩������
���͂������ׂ݂���ׂ݂ւ�
�킽���̔A�⌌����������܂�
�������o�łȂ���ΗՏ��I��
���͂ʂꂽ���̖т����ڂ��
����������������֎�����������
�Ȃ�̘c�݂��Ȃ�
�����ɐ�����
���ҋחނ̉H�т�爂�Â���
���o�́s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l��l��`��l�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|26���l1�i�g�A27�s���B
�����͗l�ɗp����ꂽ�炵���@�킽���̓���̂Ƃ��Ă̐l�ԁ@���������͎M�̒��S�łƂ���@�Ƃ����������Ǝ��R�ȓ��o�ւ̈��@����͂��ł��k�P�ڂ����Q�R�S�킽���l�̍l���Ă���@�x�߂̗c���̐H�ׂ镨��z��������@�X�R�̉ƂŕH�̎����ς����ց@���̐����̓��Ȃ����������������������@�����܂�������������������@�┧�֊J���������j�Ⓑ�����̂Ђ��������@�����ł͏����ȕ����Ɛn���������I��@�_�C�i�~�b�N�Ȍ��̏o�܂Ł@���Ɋ��܂ꂽ�Ђ�߂����������@�ܐl�̏��̗D��ȗV�Y�̂����Ɂ@�g�̗͂�������@���̂��݂₩�Ȕ��̈ړ������Ƃ�@�킽���͎w�E�ł��邩�H�@�ƍs�҂̎��傫�Ȗ͗l�@���̑N���ȐԂ⍕�̎Ȃ��Ƃ���܂��n�}�̏���@�����������l�@���������������@�������������������킷�@�O������c����ꂽ�x�̂Ȃ��̕a�C�@�₪�Ė{���I�ɓ��̂Ȃ����E����������H�@�̂悤�ȐÂ��Ȓ����̐[���G�a�̑��荂�܂�܂Ł@������莀���̊������ꂽ�����x�b�h�Ō���@���ꂪ�킽���̊ł���@�̑�Ȏ��݂Ƃ����悤�@�V�����ǂ���H����`�̍ז�����O���@���Ȃ킿���̏��̏�֏��@�l���̕��ʂ���L�`�ȕ����̘R��������܂Ł@���̏�؋��I�@���̂܂����f�U�C�����킽���͎��Ȃɋ��e����@������߂̗₽�������@���ʂłʂ�ꂽ���E�̂����߂�ꂽ���̎��i�@�T�C�Y�̗�@���E���̎��ȓ����@�����̂Ȃ��P�זE�̑��݂����������鎞�@�ЂƂ̊��̈ӎu�����傫�����]����@�킽���͔��f�ł���@���肠�܂��̎R�����݂Ȃ���@�����ɂ��@�݂��ƂȘV�l�ւƏC��������т��@�����ȗ��R�łȂ��@���łȑ����̏�Q�����Ƃ�k�P�̂����Q�R�S���l���@�}�Ă̂悤�ɔ������ȗ������@���傷��ׂ�
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�g������1980�N4��28���̓��t�����s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�́q���Ƃ����r�Łu����ɂ��Ă��A�s�a���`�t��s�_��I�Ȏ���̎��t�A���ꂩ��s�T�t�����E�݁t�Ȃǂ̎��W�̐����̋L�^���Ȃ��̂́A���ɂ��čl����Ύc�O�Ȃ��Ƃł���v�i�����A�O�l�l�`�O�l�܃y�[�W�j�Ə������B���̌�s�T�t�����E�݁t�ɂ͐G��Ȃ��������i1979�N���\�́q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr������j�A���Ɉ����q�O�̑z���o�̎��r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�j�Łs�a���`�t�Ɍ��y�����i�Ȃ������̖{���ɂ́s�a���`�t����q�a���`�T�r�q�a���`�U�r�q�c�Ɂr��3�т��A�q�O�̑z���o�̎��r�ɂ͈��p�̌`�Łq���E�H�̊G�r�S�s�����^����Ă���j�B
�@���́u���E�H�̊G�v�́A���a�O�\���N�́w���|�x������ꍆ�i�O�����j�֔��\�������̂��B����܂ł̌ܔN�ԁA�w���|�x�͋x����Ԃł������B���s���̉͏o���[�͂������A�ҏW�ӔC�҂̍�{��T���A�w���|�x�����ɂ͕��X�Ȃ�Ȃ����ӂƔM����Ȃ��Ď���i�߂Ă����B���������˗����ꂽ�̂́A�O�̔N�̏\�ꌎ�����낾�����悤�Ɏv���B�Ȃɂ���A��\��N�O�̂��Ƃł���B���͂��̍D���ɉ�����ɁA�ӂ��킵����i�������Ȃ���ƁA�C�������B���ꂪ�������čЂ����A���ؓ����߂��Ă��A���͂Ȃ��Ȃ��o���Ȃ������B�܂��Ζ���̐�`�W�̎d�����A���Z������߁A���͐g�S�Ƃ��ɔ�J���Ă����B�N�̐��̊X�͍Q���������߂��Ă������B�c�Ɣ�����ҏW�S���҂ɂȂ����N�͗��`�ł��т��сA����̒c�n�̂킪�ƂɍÑ��Ɍ���ꂽ�B
�@���͐����̋x�������ׂĔ�₵�āA��т̎����ǂ��ɂ������グ���B�{���Ȃ��̒������т��]�܂����̂ł��낤���A�C�͂��������A��т̏��i�ɕ����Ă��܂����̂������B���Ȃ݂ɂ�����̎��́A�u�C���Əȗ��v�Ƃ����U���`�̂��̂ł���B���̔N�̏H�Ɋ��s�����A���W�w�a���`�x�̖����ɂ��̓�т����߂Ă���B�i�����A��Z��`��Z��y�[�W�j
�s�a���`�t��22�ђ��A2�쓯���ɔ��\�Ƃ����P�[�X���ӂ�����B�q�A��r�q���w�r�ƁA�q���E�H�̊G�r�q�C���Əȗ��r�ł���B�u�{���Ȃ��̒������т��]�܂����̂ł��낤���A�C�͂��������A��т̏��i�ɕ����Ă��܂����v�Ƃ������́A�q�A��r�Ɓq���w�r�ɂ����Ă͂܂邩�i�q�A��r�q���w�r�̌�ɑ����āq�m���r�q�r���r�q�P���r���Ę^����Ă���̂́A�������낵���т̍s�����������Ă��Ή��ł���o�b�t�@�[�̈Ӗ����������ɈႢ�Ȃ��j�B�g����܌�̋g���́A���|�W���[�i���Y�����肩�A�n���Ԃ��Ȃ��s�k�t�̗v���ɂ����l�Ƃ��ĉ����Ȃ���Ȃ炸�A�s�a���`�t�̐�����Ԓ��A�̂��ɏE�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j�Ɏ��߂����i�i6�сj�����łȂ��A���O�����s�ɏI��������сi4�сj�⎟�̎��W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�ɉꂽ2�т����\���Ă���i�ŐV�́q���̂��߂̃g���̎��݁r�́s�a���`�t�̊��s�Ɠ������j�B���ǁA�g���́s�m���t������Ɋ����������i4�сj���������̎��i12�сj���̂Ăās�a���`�t��҂B�z�������炷�Ȃ�A�g�������ɂ�����Œ������q�g��i���Ɏ~��r���{���̊����Ɏ��߂��Ă�����i���傤�ǁs�m���t�ɂ�����q�����r�̂悤�Ɂj�A���W�s�a���`�t�͍��Ƃ͂�قLj�����A���j�[�N�ȍ�i�W�ɂȂ������Ƃ��낤�B
�k�t�L�l
�����O��1958�N�ɍ�Ȃ����q�����G��\�\���I�m�[���E�t�B�j�[�ɂ��i����Ǝ����I�[�P�X�g���̂��߂́j�r�\�\3���\���̎��Ɖ��y���琬��m�g�j���W�I�����ԑg�q���t�Ɖ��y�̂��߂�3�̌`�ہr�̑�1���\�\�̉����ŁA�H�R�M����̎��q�����G��r�̘N�ǂ�������B�S9�߂��琬�邱�̏H�R�̎��̖`��2�߂��A���Ȃ��b�c�Ɏ��^����Ă���s�����O�S�W ��1�� �nj��y�ȁt�i���w�فA2002�N12��10���j�̉������������B
��́@��b�̎�X����
�a�������₽�������
��𒋂ɕς���@��e�̗܂�
�Ԃ������̂Ȃ��Ɂ@����B��
���������ł�ꂽ饁m���Ă��݁n����
���ɐ������~�]���ɂ���
�邪�ɂ����@�@���܂��̂����ЂƂ̈��̃C�}�[�W����
�@�@���܂����ސ_��ȍ�����
�@�@�̂Ȃ��ɖ����Ă���邾�i�����A��l�y�[�W�j
�����ɂ̓t�B�j�[�́q���E�̉ʂār�̃��m�N���ʐ^���f�ڂ���Ă���A���̐����Ɂu���̃t�B�j�[�̊G�́A�H�R���C���X�s���[�V�����������́v�i���O�A��܃y�[�W�j�Ƃ���Ƃ��������ƁA�t�B�j��́q���E�̉ʂār�i�q�I���r�Ƃ��j�͋g�����̎��q���E�H�̊G�r�����łȂ��A�H�R�M���̎��q�����G��r�i�ƁA������������O�̋ȁq�����G��\�\���I�m�[���E�t�B�j�[�ɂ��r�j�ɂ��슴��^�����G��Ƃ������ƂɂȂ�B
�g�����N���k��i�сl�i�s�a���`�t������ԁj
�@�@1959�N����1962�N���܂łɔ��\�̎��т݂̂��i�q�g�����N���k��i�сl�r�̋L�q���ꕔ���߂��j
��1959�i���a34�j�N 39�`40��
1���@�V�l���i�D�E1�A46�s�A�s�G����]�t�k����Ёl1959�N1���k�t�G�E2���l�j
3���@���߁E�L�߁i�E�E2�A�����4�߂ɕ�����48�s�A�s���㎍�t�k�ђˏ��X�l1959�N3�����k6��3���l�j
6���@�x�����i�������сE7�A12�s���A�s���㎍�蒟�t�k����Ёl1959�N6�����k1���l�j�A�ʕ��̏I���i�D�E2�A57�s�A�s������t�k���̉�l1959�N6���k9���l�j
7���@���́i�I�E4�A17�s�A�s�����V���t�k�����V�������{�Ёl1959�N7��26���k26404���l�j
8���@�����i�D�E3�A24�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N8���k1���l�j
9���@�a���`�T�i�D�E4�A12�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N9���k2���l�j�A���i�I�E5�A11�s���A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl9��28���k29776���l�j
10���@�ҕ����鏗�i�D�E8�A19�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N10���k3���l�j�A���i�D�E9�A70�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1959�N10�����k4��10���i38���j�l�j�A��ȁi�������сE8�A14�s���A�s�ߑ㎍�t1959�N10���k27���l�j
11���@�A���i�D�E6�A35�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�j�A���w�i�D�E7�A19�s���A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1959�N11�����k13��11���l�j�A���̕a�C�i�D�E11�A22�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1959�N11���k4���l�j
12���@�c���i�D�E10�A25�s�A�s������t�k���̉�l1959�N12���k10���l�j
��1960�i���a35�j�N 40�`41��
1���@���L�i�I�E6�A30�s�A�s���w�t�k���w�Ёl1960�N1�����k15��1���l�j
2���@���́i�������сE9�A35�s�A�s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N2���k6���l�j
3���@�a���`�U�i�D�E5�A13�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N3���k7���l�j�A7���@�~�̋x���i�D�E12�A14�s���A�s���{�Ǐ��V���t�k���{�o�ŋ���l1960�N3��7���k1043���l�j
5���@���̂��肠�����i�D�E13�A22�s���A�s�k�t�k���惆���C�J�l1960�N5���k8���l�j
6���@�g��i���Ɏ~��i�������сE10�A11��257�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1960�N6�����k5��6���l�j
11���@�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�A35�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1960�N11�����k14��11���l�j
��1961�i���a36�j�N 41�`42��
1���@�ߔ��i�D�E16�A39�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1961�N1�����k6��1���i52���j�l�j�A����i�D�E17�A20�s�A�s�ߑ㕶�w�t�k�ߑ㕶�w�Ёl1961�N1�����k16��1���l�j
2���@�������i�D�E15�A25�s�A�s���i�t�k�I�X��l1961�N2�����k2��2���l�j
5���@����鏗�\�\�~���̊G�����i�D�E18�A26�s�A�s���w�t�k���w�Ёl1961�N5�����k16��6���l�j
7���@��`�i�D�E19�A19�s���A�s�����t�k���w�O���[�v�����l1961�N7���k9���l�j
10���@����ɂ��i�D�E20�A33�s�A�s���{�E�t�k���Y�t�H�V�Ёl1961�N10�����k15��10���l�j�A���i�I�E7�A13�s�A�s��̐V���k�[���l�t�k�ǔ��V���Ёl1961�N10��5���k30512���l�j
��1962�i���a37�j�N 42�`43��
3���@���E�H�̊G�i�D�E21�A23�s�A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l�j�A�C���Əȗ��i�D�E22�A26�s���A�s���Y�t�k�͏o���[�V�Ёl1962�N3�����k1��1���l�j
6���@�ӏt�i�I�E8�A4�s�A�s�����ԗ����t�k�����ؓ���l1962�N6�����k26���l�j�A���Ƒ��ׂ݂̊Łi�I�E9�A22�s�A�s�Ԓցt�k�������o�ŕ��l1962�N6���k7�����E13��6���l�j
9���@���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�A39�s�A�s�k�t�k�k�̉�l1962�N9���k10���l�j
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
�g�����̎��W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�́A�ЎR���̑���ɂ���Ď��т̖��͂��ő���ɔ��������\�\�����������Ȃ�A�g���� �����ɂȂ�P �s���W�ɐe���҂ɂƂ��āA�ЎR�̊G�Ɛ�͂Ȃ��ās�T�t�����E�݁t��z�������ׂ邱�Ƃ͓���B�u�A���O���|�p�v�ɒ^�M���Ă���1960�N�㖖�A�g�� �͉�W�s���������X�t�i�����ЁA1969�N12��10���j�ŕЎR���Əo������B
�@�Âт��ؑ��̏��w�Z�̕֏���Z���w�i�ɂ��āA���N�����̖��ƌ������A�Ô��ɁA�܂��c���ɕ`�����A�ЎR���̉�W �s���������X�t�����āA���͏Ռ������������̂������B���Y�{���̐�����𐂂炵�āA�Z�������j�̎q��V���������炾�Ɋ������āA���A���鏗�̎q�� �p�Ԃ����Ă���ƁA�q�j���k�����k�r�ƌĂԂ̂��ӂ��킵������̕��͋C������͐F�Z���s���������X�t�̂Ȃ��ɕY���Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k���� �Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�O�y�[�W�j
���́q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�̏��o�́s���{�E�t1979�N9���������A�g���͓��N9��10���������̉�L�E������ɂŎn�܂����ЎR ���W�̓�� �܂胊�[�t���b�g�̈ē����5�s�̎��i���o���ɕW��Ȃ��A�薼�́q���k�r�͎��W�s�|�[���E�N���[�̐H��t���^���ɕt����ꂽ�j���Ă���B
�ؑ��̌Â����w�Z�̕֏��̈Â���Ł^�����k�͔�т��������������^�����`���҂�����Ȃ�@����͌Ղ̘�ʂ����Ԃ����_�^ �j���k�͉Ă̍Z����e���g���Ȃ���@�����܂��^���Y�{���̊Ԃ���@�𐂂炵�@�i����
 �@
�@
�ЎR���W�ē���i������ɁA�k1979�N9���l�j�̊O�ʁi���j�Ɠ��E���ʁi�E�j
�����t�q�́u�w���������X�x�ɏ[�������������́A��������`�j���ꂽ���N�⏭�������̐���A���т��������r���s�ׂ̂��̎p�Ԃɂ��܂� �āA�d�������� ���l�X�Ȍ��p�̒��ɂ����A��������B�����܂�}�����܂�Ă���v�ƌ����Ђ́q�o�ňē��r�ɏ������i���L�͂Ȃ����A1978�N���납�j�B���͂��̕����珼 �Y���P�́q���p������\�\�w�T�t�����E�݁x�̈ʒu�r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�j��z�N�����ɂ͂����Ȃ��̂����A�s�T�t�����E�݁t�̃W���P�b�g�̊G�i�q�u����v1973�r�B���W���s�����g���̏����ŁA �s���㎍�ǖ{�t�̌��G�ʐ^�ɋg���ƂƂ��Ɏʂ��Ă���j�̏����͓�l�Ƃ��K�������Ă�����̂́A���N�͑S���i���̊G�̏��N���܂߂āj�K�������Ă��Ȃ��B
��
�g�����́s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j���Ō�̎��W�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɯ��ꂽ�i�������Ƃ����́u�q���r�A�q�c�O �~�r�̓�т́A ���݂̎����̍�i�ł���B�������炭�����������Ƃ��A�܂��Ď��W�ꊪ�𐢂ɖ₤���Ƃ��Ȃ��̂ŁA�����ČJ�����A���������邱�Ƃɂ����v�Ƃ��������́A ���̂悤�ɓǂ܂��ׂ����j�B�ޘH��f���߂Ɋ��s�����E�⎍�W�̕\���Ɣ��Ɂs���������X�t�̊�����i�i�ʒ��{���̎��̌r�݂͂�����A����W�̌��G���j�� �g���Ă��邱�Ƃɂ́A�s�T�t�����E�݁t�̑����ɑ��鎩���ȏ�ɁA�ЎR���̊G�ւ̈������������B�g�����͕ЎR���̉��M������߂̂悤�Ɏ��W�ɓZ�킹�邱�� �ŁA�s�T�t�����E�݁t�ɑ�\����鎩�g�̒����܂ł���߂��������̂ł���B

�ЎR����W�s���������X�t�i�����ЁA1978�N2��30�k�}�}�l���j�̔��Ɗ����̊G�k�����F
�R���[�q�l
�k�t�L�l
�g�����̐��z�ɂ͓��L�̋L�q��f�ɂ������̂������邪�A�����ɍD�̗Ⴊ����B���߂��q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�̍ŏI�i���A�����u��㎵��N�Z���\�����v
�́q���L�r���B�q���L�r�Ɍ�N�̎肪�����Ă��Ȃ��Ƃ����ۏ͂Ȃ����A�g�����̕��͍�@�̗v��������ɂ͏[�����낤�B
�@ ���N�̘Z���̈�[�A���ƍȂ͑���c�̓������ق֍s�����B�Í������E�̗d���x�����q�̓ƕ��q���W�B�A�r�����邽�߂ł������B�����̓Ԃ̂��ƁA��K�̋i�� ���ŁA�������́A����Y�⒆�������ƕ���̊��z��b���������B���ς����Ƃ������^�Ȗx�����q��Ō}�����B���炭���āA���m��ʎႢ�����ɐ������� ��ꂽ�B���ꂪ�ЎR�v�l�ł���A�x�����q�Ƌ��ɁA�}��b�剺�ł���̂��A��Ƃ������̂ł���B�v�l�ƋA��H���낢��b���������A�ЎR���͏H����J���W �̂��߂ɁA���q�����̏ё�������ŕ`���Ă��邻�����B���͂���ł͐F�C���Ȃ��Ǝv�����̂ŁA������̏ё��Ƃ��Ⴂ���̊�ȂA�`���Ă��܂��ƕ��� ����A����������`�[�t�ɂ����G��`���Ă��܂����A���ꂪ�D�w����łƌ����āA�قق��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A ��Z�܁`��Z�Z�y�[�W�j
�@ �[���A�z�q�Ƒ���c�̓������ق֍s���B���������ŁA�x�����q�̓ƕ��q���W�B�A�r���ς�B��[���u���Ȃ��A��̐�@������Ă��邾���ŁA�����ӂ��o��B �ޏ��͐F�ʂ̂��������[�u����d�ɂ��܂Ƃ��B���̐��͂��������ɗāA�܂���A���̂悤�Ɍ������B�������܂�p�Ԃ�����܂�ɋN�����A�C���邭�x�邾 �����B���̐��̐l�łȂ��A�������d���̂��Ƃ��B�����̓Ԃł������B��K�̋i�����ŁA����Y�A���������Ƃ��낢�ŎG�k�B���ς����Ƃ������^�Ȗx���� �q��Ō}����B
�@�A��݂��A�ˑR�A�Ⴂ�����ɐ�����������B�Ȃ�ƁA���ꂪ�ЎR���v�l�ł���A�x�����q�ƂƂ��Ɋ}��b�剺�ł���̂��A��Ƃ������̂ł������B������ ������߁A���������Ă���Ƃ̂��ƁB�ЎR���͏H����J���W�̂��߂ɁA�c�����q�����̏ё�������ŕ`���Ă��邻�����B���͂���ł͐F�C���Ȃ��Ǝv������ �ŁA������̏ё��Ƃ��Ⴂ���̊�ȂA�`���Ă��܂��ƕ�������A����������`�[�t�ɂ����G��`���Ă��܂����A���ꂪ�D�w����łƌ����āA�قق� �B�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A���l�`���܃y�[�W�j
�g���z�q�ҁs�N���t�́q��㎵��N�i���a�\�l�N�j�Z�\�r�̘Z���ɂ́A�u�x�����q�G���Q���^���c�����q���W�B�A�r���ς�v�i�s�g���� �S���W�t�A�}�����[�A1996�A���Z��y�[�W�j�Ƃ���B
1959�N6���A�l�Z�̋g�����͎���̗c���N���ɍނ��̂������сq�ʕ��̏I��r�i�D�E2�j�Ɂu�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����v�Ə����āA���U��ʂ��Ă�����x�A���g�̎���Ɏ��l�̖������B���̒���A�g���͏��߂ă����P�́s���_���t�Ɍ��y�����i�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�A���o�́s�Z�̌����t1959�N8�����j�B
�@���a�\�Z�N�̉āA���͏o�����邱�ƂɂȂ����B�����P�́s���_���t�Ɩ��t�W�Ɓs�Ԋ~�t���Ƃڂ������̎������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�Z���y�[�W�j
����ɏ��o���Ɂu�R������ƃ����P�v�ƌ��o�����t�����Ă����q�Ǐ����r�i�s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8�����j�ł͊����J�X��s�����P���W�t�������Ă���B
�k�c�c�l�x�C�Y�̕��͂���A���Ԃ��P���킽���Ȃ�ɔ��������̂ł͂Ȃ��������B�������̐��������X�ɍs���A�����J�X��́w�����P���W�x�����߂��Ƃ��̊������A�����Y����Ȃ��B�����P�̎��ƃW�C�h�̏����Ȃǂ����̍��̖����̏��Ƃ����悤���B
�@���a�\�Z�N�������疞�F�֏o�����A���N�ϏB���ŏI����}����܂ł́A�l�N�Z�����A�킽���͉ʂ��Ăǂ�Ȗ{��ǂ��A���̑������L�����Ă��Ȃ��B�R���̔ߎS�ȓ��X�̒��ŁA�Ђ����ɓ��L�Ǝ��������Ȃ���A�܂ɂӂ�āA��g���ɂ̃����P�́w���_���x��ǂ�ł����B���������̎��A�킽���͂����X�ɂ̐Q�m�̒��ցA���A�����̖|�������̂��B�Q�[�e�́w�e�a�́x�����̐����������i�̈�������B
�@�����P�́w���_���x�̎�d���̐��_���A���̂킽���̎���֑傫���e�����Ă���Ƃ�����B�Y�̎��A�g�̒Z�̂����͂��߂āA�ނ��ڂ�悤�ɓǂ��̂��B�x���o��䂦�A���̈����͍��ł��[���B�i���O�A���y�[�W�j
�g���́q���܂�͂����L�r�i���o�́s���㎍�蒟�t1980�N10�����j�Ɂu�k���a�\�l�N�l�Z���\�����@�������̐��������X�ŁA���]�̊����J�X��w�����P���W�x���v�i���O�A��܋�y�[�W�j�ƐV������̊��S�������Ă�����̂́A�����P�̖{�i�I�ȉe���͐��10�N���o�����W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�Ɏ����Ă悤�₭����ꂽ�B���̊Ԃ̎����m��ɂ́A�g���́q�����P�w���_���x�\�\���̈���r�i���o�́s�����V���k�[���l�t1982�N4��19���j��ǂނɔ@���͂Ȃ��B
�@���͒������ƁA�V�������̕�����͍����Ă����B�����ϔO�ł́A���ȍ�i�������܂�Ȃ����炾�B���͍ĂсA��g���ɂ̃����P�w���_���x�i����������j����ɓ���A�ǂ݂͂��߂��B�����Ă���[�������B�u�Ăсv�Ƃ́A�ȉ��̌o�܂�����������ł���B����͏��a�\�Z�N�̉āA���͖��F�֏o�������B�g�т������ꂽ�A�킸���Ȏ����̂Ȃ��ɁA�����̏����������čs�����B�|�́A�Q�[�e�w�e�a�́x�ƃ����P�w���_���x�̓���ł��������A�R���̓��������̂Ƃ�������A���̓���͖v������Ă��܂����B
�@�����P�̎���w�}���e�̎�L�x�����ǂ��Ă������A�[�������āA����̂����ł́A�e�����Ȃ������B�܂����͖{�C�ŁA�����������Ƃ��A�l���Ă͂��Ȃ������悤���B�V�Y����悤�ɁA���������̎����A��������������ɂ����Ȃ��B�����̎������߂��A���̏������W�w�t�́x���m�Ȃ̎�ŁA�o�ł��ꂽ�̂́A�哌���푈�̎n�܂����N�̓~�ł������B
�@���āA�����P�́w���_���x�ł��邪�A�������_���ւ̎��l�̏����ȍ����A�����ɌX�|���Ă��������́A�����̏��ł���B�������A���ɂƂ��ẮA���_���̈̑傳�́A�ǂ��ł��悩�����B�����ȋ�Ԃ֒����܂ꂽ�悤�ȁA�����P�̌��t�\�\���̂̍��A�����A���B�߂̊ØI���ɋ�̍�����̂ڂ��čs���A�d���݂̂��������̂悤�ɖ[�Ȃ��`�ہ\�\�Ƃ����悤�ȉA�e�[�����I���̂ɁA���͖�����ꂽ�B���̐ɂ������͂��̈ӎu�������B���͂��̐̏�����ǂ��肵�đ��̕��֍s�����Ƃ��ł��Ȃ��B���͂��̐ɐg���A���߂炢�A�Ƃǂ܂�A���̐̒��ɏZ�ނ̂ł���B
�@ ���_���̑嗝�̌Q�����A���q�������̂ق�̈�߂����A�������݂��Ƃɑ������A�܂��Ɉ�т̎��ł���B�w���_���x�ꊪ�́A�����P�����_���̐��_�ƒ������]�����Ȃ���A���Ȃ́u���_�v��W�J���Ă���悤�ɁA���ɂ͎v��ꂽ�B�����^�̌[�������ƁA������͎̂��̏͋�ł���B
����������̐����ƂȂ蓾�邩�ۂ��́A�������Ĉ̑�ȗ��O�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�ЂƂ������������O�����̎�d�����A����I�Ȉ�����̂��A�ЂƂ̂Ƃ���ɍŌ�܂łƂǂ܂鈽����̂���邩�ۂ��ɂ������Ă���̂ł��B
�@ ���̌��t�͂����炭�A���_���̌��t�ł���Ɠ����ɁA�܂������P�̗��O�Ƃ����Ă��悢�̂��낤�B���͈�̕������w�����ꂽ�v���������B���ꂩ��́A���������Ƃ��͂Ƃ߂āA�E�l���함������悤�ɁA�u�슴�ɗ��邱�ƂȂ��v�A��d���𑱂��Ă����̂ł���B�����̎��т��A���W�w�Õ��x�ւƐ������Ă������̂ł������B�i���O�A���`���y�[�W�j
�g���͂��̂��ƁA�q�Õ��r�i�B�E2�j��S�s�����ē�������߂������Ă���B�u��̊�̍d���ʂ̓��Łv�Ǝn�܂�q�Õ��r�i�B�E1�j�łȂ����Ƃɋ������������邩������Ȃ��B�����A�������낵�́s�Õ��t�̈���p���e�쐬�̎��_�ł��́u��͂��������������ɂ���v���������тł��������Ƃ��ڂ݂�Ȃ�i�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�Q�Ɓj�A�{�삱�������P�́s���_���t�Ɋw�g�����u�V�������̕�����͍����v�����ʂ́A�����炭�͍ŏ��̈�т������B�����ŏ����I�Ȃ��Ƃ��q�ׂ�A�����P�́s���_���t�͋g���̏o�����O�̏��a16�i1941�j�N6��10�����Ŕ��s�ŁA1960�N9�����s��9���ʼn��Łi����j����Ă���B��f����ǂނ�����A�o���O�ɐV���{���A������ɓ����̈�{���w�������͗l���B������Ɂq�����P�w���_���x�\�\���̈���r�Ɉ��p����Ă���͉��Łi����j��̂���ł���A�g���͖{�����p�̂��߂ɐV���ɓ�������肵�����̂Ǝv�����B���ł�����A�g�������F�̒n�Ŗ����ɂЂ��Ƃ������ł̖���A������V���ɉ��߂Ĉ����B�i�@�j���͌f�ڃm���u���B
���̂̍��A�����A���B�߂̊ØI���ɋ�̍�����o��s���A�d�����������̂₤�ɖ[�Ȃ��`�ہB�i42�j
���̐Ɏ˂����͂��̈ӎu�����ӁB���͍��̐̏��f�ʂ肵�đ��̕��֍s�����Ƃ��o���Ȃ��B���͍��̐��v����A�O��ЁA�~�܂�A���̐̒��ɏZ�܂ӂ̂ł���B�i73�j
����������̐����ƂȂ蓾�邩�ۂ��͌����Ĉ̑�ȑz�O�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�l���������ӕ������̎�d�����A����I�Ȉ��镨���A�l�̂Ƃ���ɍŌ�܂Ŏ~�܂鈽�镨����邩�ۂ��ɂ����Ă��̂ł���܂��B�i87�j
�������炾���ł��s�Õ��t�Ɏ���g���̑����𐄑����邱�Ƃ͉\�����A�����P�́s���_���t�ɂ͋����[���͋傪�����Ă���B���Łi����j�{������p����B
�@���iDinge�j
�@���̌��t���������������Ɂi�������ł��傤���j�A����Î₪�N����܂��B���̂܂��ɂ���Î�B���ׂẲ^���������܂�A�֊s�ƂȂ�A�����ĉߋ��Ɩ����̎������̉i������̂��̂����̉~�����A���ꂪ��Ԃł��A���֒ǂ��߂�ꂽ���iDinge�j�̈̑�Ȓ��Âł���܂��B�i79�j
�펞���̒����嗤�ŁA�����Đ��Ԃ��Ȃ������Ŏ��g�̎���͍����Ă����g�����A�����P�́s���_���t�͗슴�ɗ���Ȃ��u��d���̐��_�v�Ōە������B�Ⴋ���ɒ����Ƃ݂Ă����g�����{������ɂ����̂́A���邢�̓��_���ւ̊S���傾������������Ȃ��B���������ʂƂ��āA���_���́u�����v�����A����ɂ̓����P�́u���v�����͂邩�ɑ傫�Ȃ��̂������炵�����̕]�`�́A�g���̎��I�o���𑣂��ƂƂȂ����̂ł���B

�����P�i����������j�s���_���k��g���Ɂl�t�i��g���X�j�̏��Łi1941�N6��10���j�Ɠ��E���Łi1974�N10��20����22���j
����ł́A�����P�́u���v�͂ǂ��������̂��낤���B�g�����́q��Ə��r�i���o�́s�C���[�W�̖`��3 �����t�A�͏o���[�V�ЁA1978�N8���j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@������\���눤�ǂ������̂ɁA�����J�X��́s�����P���W�t������B���̂Ȃ��́A�����ȁq�H�r�Ƃ��������D���������B�茳�ɂ��̖{���Ȃ��̂ŁA��������������B
�@�@�̗t���U��A�����Ƃ��납��̂悤�ɎU��A
�@�@�ǂ�����̗y���ȉ����~�͂�Ă䂭�悤�ɁB
�@�@�̗t�͔ۂނ悤�Ȑg�U��ŎU���Ă���B�@�@�����Ė�X�A�d����n��
�@�@���X�̊Ԃ���⛌�̒��֗����Ă䂭�B�@�@�������݂͂ȗ�����B�����ɂ��邱�̎��������A
�@�@�������đ��̐l�X�����邪�����B�����͂��ׂĂɂ���B�@�@�������̗���������Ȃ������₩��
�@�@���̎�Ɏ~�߂Ă��l�̂ЂƂ�����B�@ ���������͂��߂��҂ɁA�ŏ��Ɏv�������͓I�ȃ��`�[�t�́q��r�ł���Ǝv���B���������́A�����P�̂��̎���ǂ��A�q��r�̎����������Ƃ�f�O�����悤�Ɏv���B����ƂƂ��ɁA���Ɂq��r��q���r�������������̂���������悤�Ɋ����Ă�������ł�����B�q��r��q���r�̓��݂���ے����ɂ����ꂩ�����āA���Ղɐ���������i������ƁA���͂�肫��Ȃ��C���ɂȂ�B�i���O�A���܁`���Z�y�[�W�j
���������̖�͂����炭�s�����P���W�k�u�k�Е��Ɂl�t�i�u�k�ЁA1977�j���邢�͓����́s�����P���W�k���E���w���C�u�����[�l�t�i�u�k�ЁA1972�j�����A�g���͂Ȃ��s���{�̎���28 �W�t�i�������_�ЁA1969�j�̊����J�X��q�����P�����r�������Ȃ������̂��낤�i�s���{�̎���27 ���㎍�W�t�ɂ͋g���̎�4�т����^����Ă���j�B���W�̐���K�g�́q�ӏ܁r�ɂ�������B�u�J�X�̖�́A���d���Ă������Ȃ����A�^���Ȍ꒲�������A���M����Ƃ��낪�Ȃ������ɁA�������Č����̐^�V�����f�ʂ�������Ƃ��낪�����B����͂��ƂɁA���́u�H�v�ɂ����Ă����ł���B//�u�H�v�iHerbst�j�͈��Z��N�̏��H�Ƀp���ŏ����ꂽ���́B�������돑���ꂽ�u�H�̓��v�ƂƂ��Ɂw�`�ێ��W�x�̂Ȃ��ł����Ƃ������ꂽ���ɑ�����ƂƂ��ɁA�����Ƃ��|�s�����[�Ȏ��ł���v�i�����A��`�Z�y�[�W�j�B�����J�X��s�����P���W�t�i��ꏑ�[�A1939�N6��10���j����q�H�r���f����B
�t��������A��������̂₤�ɗ�����A
���̉��������͂��₤�ɁA
����ے肷��g�U�ŗ�����B�������ďd���n�͖�X��
�����鐯�̒�����⛌�֗�����B��X�͂��ׂė�����B���̎��������B
���̂��̂��䗗�B���ׂĂɗ���������B��������l���A���̗�����
���Ȃ��₳��������Ŏx�ւ�҂��B
�J�X��́s�����P�����t��2008�N4���A��g���ɂɓ����ēǂ݂₷���Ȃ������A�g�������M����30�N�O�͓��肵�ɂ����������낤�B�s���_���t�̖�ҁE���������̂��Ȃꂽ�C�ɓ������̂�������Ȃ��B�ǂ���ɂ��Ă��A�q��Ə��r�̍���ɂ���̂��J�X��̃����P���ɑ���h���ł���A�g���������P����w�̂́A�����́u���v�ƑΛ����鎍���_�̂��肩���������B�푈������ŏ��ǂ���\���N���o�āA�s�����P���W�t���܂��s���_���t�ƂƂ��ɋg�����̎��I�o�������������Ƃ����悤�B

�����J�X��s�����P���W�t�i��ꏑ�[�A1939�N6��10���j�Ɠ��s�����P�����k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2008�N4��16���j
�g������O�ɓǂs�}���e�t�́A�x�C�Y��ɂ�邻�̒f�͂���R����́s�}���e�̎�L�t�i�����ЁA1939�j���낤���A�����炭��ЂŏĎ����A���Ɉ������̓��L�ɏo�Ă���s�}���e�t�́A1946�N1��20�����Ŕ��s�̖]���s�b��̊�g���ɔłł͂Ȃ����낤���B
�k���l�Z�N�l�ꌎ�\�ܓ��@���A�����P�s�}���e�̎�L�t�������ǂށB�i�q���L�@���l�Z�N�r�A�s�邵����t5���A1990�A�O�O�y�[�W�j
�k���a��\�l�N�l�\�ꌎ�\�����@�k�c�c�l�����P�s�}���e�̎�L�t�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j
�O�҂͐V�����w������A��҂͉��x�߂��ɓǂ݂��������Ƃ����B�苖�́s�}���e�̎�L�k��g���Ɂl�t�̎O�Ŗ{�i1974�N3��30���F25���j����A �g���̋Ր��ɐG�ꂽ�ł��낤�ӏ��������B
�@���ł͒m��ׂ̂��Ȃ��̋��̉Ƃ��v���ɂ��āA�l�͈ȑO�͎����܂�����Ȃł͂Ȃ������ɂ������Ȃ��ƍl����B���̂���͂�������A�ʎ��̎���߂Ă���悤�ɁA�����̓����Ɏ����߂Ă���̂��ӎ����āi�܂��́A�����āj�����ɂ������Ȃ��B�i14�j
�@�l�͋��|�ɑ��Ď�i���u�����B���܂ŐQ���ɏ������Ƃɂ����B�i20�j
�@����ڂ��ł������Ă��鍡�A�l�͎d�����n�߂Ȃ��Ă͂ƍl����B�l�͓�\���ɂȂ邪�A�܂��قƂ�ǎd���炵���d�������Ă͂��Ȃ��B�i22�j
�Y��Ă������|���c�炸��݂������Ă����B�k�c�c�l�Q�߂̏����ȃ{�^�����l�̓������傫���͂Ȃ����A�傫���ďd���͂Ȃ����Ƃ����s���A�i66�j
�@���̐Â����̂Ȃ��ɉ��y�����������ɂ����낤���B���܂łɂ��������ɂ����������Ă͂��Ȃ������낤���B�i131�j
�ށk���W�����E�h�E�f�B���l���f�����̋��̌ǓƂ̂Ȃ��ŁA����o����������̒j�̂��Ƃ�s�v�c�ɂ������m��A�ՏI�̏����璵�ˋN���āA���̒j�̎炠�₤���j������̂ł������B�i169�j
�����̕����ɂ͏h�̂Ȃ��L���邲�ƂɖK��A�������Ђ����Ɉ��������A�����̏�Ŗ���̂ł���B�i212�j
�@ ���̉��ɂЂƂ肷����Ă���ނ́A�����������Ƃ��ґz���F�����Ȃ��瑋�O�̃x���`�̏�ɉʕ������M��F�߂�B�ނ͖��ӎ��ɂ��̎M����������A�����O�̃e�[�u���֒u���B�ނ̐����͂��̊��������ʕ����ǂ̂悤�ɂƂ�܂��Ă���̂��낤�A�Ɣނ͋�z����B�����������̂̂܂��ɂ́A��������Ȃ��������E����ɏ㏸�����܂�̂ł���B�i237�j
![�����P�i�]���s�b��j�s�}���e�̎�L�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1974�N3��30���F25���j�ƃ����P�i��˕x�Y��j�s�h�D�C�m�̔߉́k���l�t�i���A1974�N2��20���F17���j](image/rodin03.jpg)
�����P�i�]���s�b��j�s�}���e�̎�L�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1974�N3��30���F25���j�ƃ����P�i��˕x�Y��j�s�h�D�C�m�̔߉́k���l�t�i���A1974�N2��20���F17���j
�g�������Ō�Ɍ��y���������P�̍�i�́s�h�D�C�m�̔߉́t�������i�����J�X��s�����P���W�t�ɂ́A�s�����P�����t�ɒlj�����`�ŁA�q�h�D�C�m�߉́r�̑��E��l�E�攪�߉̂���ڂ���Ă���j�B
�̓����P�̎v�z�I���k�_�������s�h�D�C�m�̔߉́t�ɑR���ׂ��A��x��20���I�㔼�ɂ�����u�������e�[�}�̒��ю��v��t�ł悤�Ƃ����̂������B�����@�g������͂������A�����Ǝ��l�ł��Ȃ��Ă������Ƃ���������Ă����ł���B���̊ԉ�������́A����ς莍���������Ƃ����邩���m��Ȃ����Ă���������Ă��āA���̎����Ɗ��������������ł����ǁB
�g���@ ���g���Ă��܂����ˁB�����炠�̎����b�q�Ɍ������̂́A����͂������G�z�Ȃ��ƂȂ��ǁA�����P�́w�h�D�C�m�̔߉́x��͕킵�����̂��ڂ��ɂł����炢���ȁA�Ƃ�����]���������킯�B�����A�ڂ��Ȃ@���I�ɔY�݂������Ȃ��ł���A���@���ŁB�����ǃ����P�̂����������ɂ͂����Ƃ��[���͂����Ă����Ȃ����Ǝv���ĂˁB�ƂĂ������������݂̂�����̂͂ł��Ȃ����ǁA��������������������w�h�D�C�m�̔߉́x�̖͕�I�Ȃ��̂ł�����Ă݂����Ȃƍl���Ă��邯��ǁc�c�B�k�c�c�l�����x��ŁA���������l�����܂Ƃ܂�A��������������������Ă݂����Ƃ����C�������S�R�����Ă���킯�ł͂Ȃ��\�\�B�i������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�܃y�[�W�j
�q�g�����̑�����i�i62�j�r�ŋg���������́s���̖{ �U ���̋Z�@�t�i�}�����[�A1967�j���Љ�āA�����Ɏ��ڂ��ꂽ�g���̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�ɐG�ꂽ�B�����ł͖`�������̔ے莫�𒆐S�ɋg���̍쎍�@�ɑ����{�p�����q�ׂ����A����́q�킽���̍쎍�@�H�r�̎l�̌f�ڌ`�̊Ԃ̈ٓ��ׂ��B���ʂ�v����ɁA�P�F�s���̖{�t�i���o�j�̖{���͂قڂ��̂܂��Q�F�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�Ɏ��^����A��e�����ׂ���̓������R�F�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�̖{���́A���O�Ō�̔łƂȂ����S�F�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�Ɍ����ێ�����Ă���B�{�Z�قł��S�̖{�����ŏI�`�ƌ��āA�P�`�S�Ԃňٓ��̂���Z���e���X�̂������i�f�㊧�s���T�F�s�g�����U�����k���̐X���Ɂl�t�i�v���ЁA2006�j�̖{�����S�Ɠ��`�j�B�Ȃ��A�P�`�T�̍Z�����͖����B�ŏ��Ɂq�킽���̍쎍�@�H�r�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O�F�s���̖{ �U ���̋Z�@�t�̈���p���e�́A2008�N12�����ݖ����B
�P�F�s���̖{ �U ���̋Z�@�t�i�}�����[�A1967�N11��20���A����`��Z�܃y�[�W�j�f�ڌ`�́A�{��9�|44���l17�s1�i�g�A129�s�i�s�͍s���ɎZ�����Ȃ��j�B�ȉ����A�{���\�L�͊�{�I�Ɋ����͐V���́A���Ȃ͌��ォ�ȂÂ����ŝX�����͎̂ĉ����B
�Q�F�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�N9��1���A��Z�Z�`��Z�܃y�[�W�j�f�ڌ`�́A�{��8�|25���l18�s2�i�g�A205�s�B
�R�F�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�N7��1���A��O�Z�`��l�Z�y�[�W�j�f�ڌ`�́A�{��10�|39���l15�s1�i�g�A148�s�B
�S�F�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�N9��25���A�����`��l�y�[ �W�j�f�ڌ`�́A�{��13��44���l19�s1�i�g�A136�s�B
�T�F�s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�k���̐X���Ɂl�t�i�v���ЁA2006�N3��1���A����`�����y�[�W�j�f�ڌ`�́A�{��13.5��41���l15�s1�i�g�A141�s�B

�s���̖{�t�i�}�����[�A1967�j�A�s�g�������W�t�i�v���ЁA1968�j�A�s�u�����v�Ƃ����G�t�i���A1980�j�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�A�s�g�����U�����t�i�v���ЁA2006�j
�q�킽���̍쎍�@�H�r��400���l��12���ŁA�e�f�ڌ`�Ƃ��^���Ɏ��сq��́r�i�C�E13�j�S�сA���̂܂���8�i���̕��́A���̂��Ƃɓ�����8�i���̕��͂Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B����܂��āA���т��������͂̊e�i���Ɂi01�j����i16�j�܂ł̔ԍ���U��A�{���̈ٓ��ӏ����������߂̃A�h���X�Ƃ���B�����̎��̂�r�̑̍ق̑���ȂǁA�ׂ��Ȃ��̂���������Ȉٓ��͎���10�ӏ��ł���B
1. �i03�j����G�悪������k�P�Q�A���R�S�B�l���̂��z�������k�P�Q�A���R�S�B�l�T�̍b�̌ł������ɂӂ��B
2. �i05�j���ȁk�P�Q[��������]���R�S�i�g���j�l�͈ꌩ�A��i���Ƃ����s�ׂł��邪�A�����ɁA�펯�I�ɁA���Ȃ��̂ɉ�������댯������B
3. �i06�j����ɂł����̂Ȃ��Ŏg�����ƂŁA�D���Ȃ̂ƌ��k�P�Q�i�i�V�j���R�S���l�Ȃ̂�����B
4. �i08�j����́A���k�P�Q�����R�S�i�g���j�l����́A��ɂӂ������́A�d�ʂ�����A��Ԃ��߂���́A���݁\�\���Ӑ}���Ă�������ł���B
5. �i�q��́r�j���F�����́k�P�Q�����R�S���l������˂�
6. �i�q��́r�j�k�J�Ɠ��k�P�Q�|���R�S�~�l�̏Փ����܂�������
7. �i09�j�k�P�i1�����Q�j���Q�R�i�V�c�L�j���S�i1
�����Q�j�l�����ɁA�u��́v�Ƃ�����т�����B
8. �i09�j���̓��́A�k�P�Q�R�������S�A�l�����B
9. �i11�j�u�Z�̂������̏����ȓ��v�Ƃ́A�ނ�̓����������킯�Łk�P�Q�i�i�V�j���R�S�́l�Ȃ����A���̒������߂𒅂Ă���̂ŁA����������B
10. �i12�j����͌��ł��邪�A�킽���ɂƂ��āA���a�H���釁�͇��W�V���N���釁�łȂ���Ȃ�Ȃ��k�P���A���Q�R�S�B�l���k�P�i�i�V�j���Q�R�S�Łl
�͕ʂɇ��a�H[�G�W�L]���釁�ł悢�Ǝv���Ă���B
�ȏ�̈ٓ��̓����Ɣw�i�ɂ��čl���Ă݂悤�B
1.�Ǔ_2�ӏ�����_�ɕύX�����̂́A���������`�Ŏ~�߂ĒZ����A�˂������i03�j�́u�ӎ��̂Ȃ���k�c�c�l���~���邱�Ɓv�̎��Ԃɉ����Ă���A�Ɣ��f�������߂��낤�B
2.�u���������v�Ƃ����ǂ݉������g�����t�����Ƃ͍l���ɂ����B�f�ڎ��Ɂs���̖{�t�̕ҏW�����t�������̂��B�����炭�i03�j�́u��[����]�v�����l���낤�B
3. �u���v���u����v�Ɠǂ܂��̂����������ꂩ�B
4.�u���݁v���u��ɂӂ������́v���u�d�ʂ�����A��Ԃ��߂���́v�Ƃ������i������A�ŏI�`�́u������́v�ł͂Ȃ��A���o�Ɓk���㎍���Ɂl�́u��������́v���̂肽���B�u������́v���ƁA�u���镨�v�Ƃ��Ă̑ΏۂȂ̂��A�u����ҁv�Ƃ��Ă̎�̂Ȃ̂��A�Ӗ��Ɖf���̗��ʂő��肪������B���ꂪ�g���̎���ꂩ�A�g�ŏ�̎�Ⴂ�������Ƃ��낾�B���Ȃ݂��R�́q���L���\�\���Z���r�̏����o���u�Z����\���v�i��l�y�[�W�j���S�ł͒E�����Ă���i��O�y�[�W�j�A�S�̍Z����Ƃ��S�ǂł͂Ȃ��������Ƃ��������킹��B
5��6. �q��́r�̊���2�ӏ��̕ύX�́A�c���Ă���������V���ɓ��ꂵ���[�u�i�Ȃ��q�g�������W�s�m���t�{���Z�فr�́q��́r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
7. �Q�œV�c�L�ƂȂ����̂́A�����炭�g�ŏ�̎�Ⴂ�ł���i�P�̓��Y�ӏ������傤�ǃy�[�W�̍ŏI�s�ŁA1�����Q�ł��邱�Ƃ��킩��ɂ����j�A�S�ŋ��ɕ����Ă��邱�Ƃ�����A�g���ɂ������ł͂Ȃ��Ǝv����B�\�\���S�ōZ�{�@�\�������Ă���̂�ڂ̓�����ɂ���ƁA��قǂ̌��ɔ����邪�A4.�́u���k�P�Q�����R�S�i�g���j�l����́v���g���̎����̂悤�ɂ��v���Ă��āA�{�������A�Y�܂����Ƃ���ł���B
8. �u�ԁv�ł͂Ȃ��u�A�v�ł��邱�Ƃm�ɂ��������B�i12�j�Ɂu���̋A�荋�J�ɂ����A�v�Ƃ���B
9. �Ӗ����炢���Ă��A�꒲���炢���Ă��A�Ó��Ȏ����B
10. �u�c�c���A�c�c���A�c�c�B�v�Ɛڑ������́u���v���d�Ȃ邱�Ƃ����������ꂾ�낤�B
�����ł�����x�U�肩����ƁA�g���ɂ������i�������͑g�ŏ�̉��ρj�̂Ȃ������i���́A�O�����i01�j�`�i02�j�A�i04�j�A�i07�j�ŁA�㔼���i10�j�A�i13�j�`�i16�j�ł���B�Ƃ���ŁA�i01�j�`�i16�j�̖{���S�̂���d�v�Ȓi�����ЂƂI�ԂƂ���A�����̐l���i08�j��������ɈႢ�Ȃ��B�剪�M�͋g���Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�Łi08�j��N�ǂ��Ă���̂ŁA���̔����������B
�剪�@���݂������Ă镶�͂łˁA�g�����̎��I�錾�݂����Ȃ��̂Ƃ��āA�����������ȕ��͂������B�}�����[�́w���̖{�x�ɍڂ��Ă�w�킽���̍쎍�@�H�x�B����̂Ȃ��ŁA�u����l�́A�킽���̎����G�搫������A���͒����I�ł���Ƃ����B����ł킽���͂悢�Ǝv���v�Ƃ����Ƃ��납��n�܂��߂ˁA�����͂����A���ɂ��Ăǂ��v�������Ă���ꂽ�Ƃ��A���݂͈��Ă��������蔲���ēn�������������ˁB���Ƃ����̂��ƂÂ��āA�u���Ƃ��Ƃ킽���͒����Ƃւ̖�������������A���`�ւ̊�]�͂悢�̂ł���B���͊���̓f�I�A���R�ւ̓����Ɍ����āA�����Ⴋ�ɂ��悤�ɁA�Ȃ���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B����́A��������́A��ɂӂ������́A�d�ʂ�����A��Ԃ��߂���́A���݁\�\���Ӑ}���Ă�������ł���B������`�Ԃ͒P���Ɍ����Ă��A����Ȏ��Ԃ̉�H���������\�����K�R�I�ɗv�������v�B���̂�����͎��Ɍ����ȎU�����ˁA���ꂩ��u�\���I�ɘA�q�����Ȃ���A�\�m�ł��ʒf������肩�������G�����\�ʒ��͂�����v�Ƃ����A�������f���������ǂˁB�u������킽�������̓s�J�\�̏��̊�̂悤�ɁA��������̂��Ɍ��镡��������Ƃ��K�v���B���S�Ƃ͂܂��Ɉ�_������ǁA�������̎x�_�����蕡���̒��S���ړ�����k�u���v�̌�A�l�āA���̑��B�Ɖ�]���v��̂��B�Î��E�Î��A�ڂ₯����������������e�����˂���āA���F�����g����v�B�܂��ɋg���̍ō��̎U�����ł���B���_�Ƃ��āA�킸���ꖇ�����炢�̕��͂����ǂ��B�i�s�����C�J�t1973�N9�����A��ܘZ�y�[�W�j
�Βk�̌��e��Z�����o�Ȏ҂��`�F�b�N����͓̂��R������i�ҏW����Z���҂͘N�ǂ��ꂽ�u�@�v���̌������P���������Q�Ŋm�F�������낤�j�A�g���͑剪�̔����́u����́A��������́A��ɂӂ������́A�d�ʂ�����A��Ԃ��߂���́A���݁\�\���Ӑ}���Ă�������ł���v��ڂɂ��Ă����͂����B�܂�A���̎��_�Łu��������́v�̓X���[�������B�����Ƃ��A�����玩�������������͂ł��A�Βk����̘N�Ǔ��e�Ɏ�����邱�Ƃ͂��Ȃ����낤����A����������ċg�����u��������́v��e�F�����ƒf�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B������ɂ��Ă������́A���҂��܂߂��N�ɂƂ��Ă�1973�N�̉Ă܂ł́u��������́v�������̂��B���ꂪ1980�N�̋g�����̐��z�W�Łu������́v�ƂȂ����̂́A�����Ȃ闝�R�ɂ��̂��B��Ƃ����ق��Ȃ��B
�q�킽���̍쎍�@�H�r�͋g���̎��_�Ƃ��Ă͗B��̕��͂����A���l�̎�|�͂���ȑO�A����N�v�Ƃ̑Βk�q�͌ЂƂ������E�ցr�i�s���㎍�蒟�t1967�N10�����j�Ō��ɂ���Ă���B���Βk�ł̋g���̔����i�c�Ɨ��L����j�Ƃ���ɑΉ������S�� �{���i�i����ԍ��\������j���ȉ��Ɍf����B
�c�@�ڂ��͎��ɂ��Ă̕��@�Ƃ����Ƃ��ɂ��Č��Ȃ����A��肽���Ȃ��Ƃ������A�ڂ��͎��ɂ��Ę_���I�Ɍ��Ȃ��B�k�c�c�l�����玩���̎��ȂA�͂�������Ȃ���ł���B
�i01�j�@�킽���ɍ쎍�@�Ƃ�������̂��ʂ��Ă��邾�낤���A�r���^�₾�Ǝv���Ă���B�����Ȃ�Ӑ}�ƕ��@�������Ď�������݂���悢�̂��A���܂��悭�킩��Ȃ��B�c�@���Ƃ������͈̂�ʂɏ����Ă݂āA���ꂩ���[�͂�]�Ɍ����_�ŏ����āA�����珑���āA������g�ݓ���Ă����ĉʂ��Ăł��邩�ǂ�����������ǁA���ǂł��Ȃ������B�ӎ��I�ɂ͂ł��Ȃ��B
�i08�j�@������킽�������̓s�J�\�̏��̊�̂悤�ɁA��������̂��Ɍ��镡��������Ƃ��K�v���B�c�@�k�c�c�l�ڂ��̂Ȃ��Ɍ`�Ԃ̂���悤�Ȃ��̂͊m���ɂ����ł���B�\�ʒ��͂�₦�������Ă�����̂���͂�����Ă���킯���B���ꂪ��͂�ڂ������߂Ă�����̂ȂˁB
�i08�j�@�\���I�ɘA�q�����Ȃ���A�\�m�ł��ʒf������肩�������G�����\�ʒ��͂�����B�c�@�ڂ����q���̍��A���R�Ɩ������̂͒����Ƃł��ˁB�����Ȏ���Œ����Ƃ��ʖڂɂȂ�A �G�������ʖڂŁA����Ŏ��������Ă��܂����B�����ꍇ�ɂ��A��ɂƂ����̂��~�����B
�i08�j�@����l�́A�킽���̎����G�搫������A���͒����I�ł���Ƃ����B����ł킽���͂悢�Ǝv���B���Ƃ��Ƃ킽���͒����Ƃւ̖�������������A���`�� �̊�]�͂悢�̂ł���B�c�@�N�ɂ����t�̈Ӗ��Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B�ڂ��̎��ɂ́A�H��ɂ͂��邩������Ȃ� ����ǁA�u�ށv�Ƃ��u���݁v�Ƃ��u���܂��v�Ƃ��A���������ϓ_���o�Ă��Ȃ��B
�i07�j�@���ꂩ��A�u���݁v�Ƃ��u���Ȃ��v�Ƃ��Ăт������l�̂��g���Ď��̍\���G�ɂ�����@���Ƃ��Ă��Ȃ��B�u���݁v�u���Ȃ��v�Ƃ́A�_�ł���A �Љ�ł���A�����ē��e�A���l�A�����Ė��m�̐l�ł���A���̂����܂������A�킽���ɂ͂ǂ����Ă��[���ł��Ȃ���������ł���B�c�@���ꂩ��A�ڂ������Ɏg���Ă��Ȃ����t�́u���t�v�Ƃ��u�����v�Ƃ��u�����v�Ƃ��u���v �Ƃ��A�{�ɂȂ�����͈̂ӎ��I�Ɏg��Ȃ��ł��ˁB�g�����Ƃɑς����Ȃ��B����͂ǂ��������Ƃ��킩��Ȃ����ǁB
�i06�j�@����ɂł����̂Ȃ��Ŏg�����ƂŁA�D���Ȃ̂ƌ����Ȃ̂�����B�킽���̏ꍇ�A�g��ʕ���������������B�Ⴆ�u�����v�u���v�u�Łv�u���t�v �u�����v�B����ň�̐��i���ǂ݂Ƃ��Ǝv���B�����́A�{�A�V���A�G���ނɊW�������t�ł���B���_�I�Ɍ������Ă���̂��B���́u�����v�E�u���t�v�� ����䂦�ɁA���ڂɂ킽���͎��Ȃ̎��̒��Ɏ������܂Ȃ��̂ł���B�c�@�ڂ��͎蒠�͂������������Ȃ���ł���B���ꂩ��v�����ď����Ƃ��A������C���X �s���[�V�����͐M���Ȃ���ł��B��͂�A���͏����ׂ����Ƃ����p������n�߂�B
�i03�j�@������킽���͎蒟�����������Ȃ��B�i���X�ŁA�X�p�ŁA�ӂ��ɑf�������Ǝv���鎍��Ȃ�Ӑ}����[����]��ł��킽���͏������߂��肵�Ȃ��B�� ��͖Y���ɂ܂����邱�Ƃɂ��Ă���B�킽���ɂƂ��Ė{���ɕK�v�ł�������A����͍Ăь�����ɈႢ�Ȃ��ƐM���Ă���B�c�@ �ܘ_���Ȃ͂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����ǁA�Ⴆ���n�ł����Ă��A���Y���̂Ȃ�����o�Ă������t�����߂Ă͂����Ȃ����A���̂܂ܐ��������ق������������Ƃ������̂� �Ȃ��Ȃ����Ƃ�������������܂��ˁB�̂ł��o��ł����ł��A�悭���Ȃ��d�˂�l�͂��邯�ǁA�ڂ��Ƃ��Ă͂����������@�͂Ƃ�Ȃ��B���͗�Â���Ȃ� �āA���鋶�C�̏�Ԃ̂Ȃ��łł���킯�ŁA������Âɔ��f���Đ����������܂�Ȃ��ł���B�܂��Č�N�����ꂽ��S�R�ʖڂ��Ǝv���܂��B
�i05�j�@�킽���͎��Ȃ̂Ȃ��ňꉞ�o�������т͂ł��邾��������Ȃ����Ƃɂ��Ă���B���Ȃ͈ꌩ�A��i���Ƃ����s�ׂł��邪�A�����ɁA�펯�I �ɁA���Ȃ��̂ɉ�������댯������B���鍬�ׂ��琶�܂ꂽ���I�ȃ��Y���ƃG�l���M�[���p�����鈫��p������ڂ����炾�B�ߋ��̍�i�ɂ������������ ��Ƃ�����ǐS�I�ȑԓx�ƌ��镾�K�����ɂ���B�킽���̒m�邩��������̗Ⴊ�����Ǝv���B���Ȃ͖{���A���������Ă���������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ�����B ����������͏K��̂����ɁA�������Ȃ����ɂ��ׂ��ł���A�܂����\���ׂ����̂ł͂Ȃ��̂ł���B���\�������҂͈��������ēǎ҂ɂ������悭��i���䂾 �˂邪�킽���͂����Ȃ��Ƃ��悢�Ǝv���Ă���B�c�@������A�ڂ��̏ꍇ�́u�����v�̓e�[�}������������ǂ��A���Ƃ͂��܂�e�[�}�Ȃ��Ŕ� ���̏�ԂŎn�߂�B
�i02�j�@�킽���͎��������ꍇ�A�e�[�}�₻�̍\���E�\�������炩���ߍl���Ȃ��B������Ԃ��킽���ɂƂ��āA�ł����������ɂ悢��Ȃ̂��B
�Βk�ł̋g���̔����i�y���F�́u���x�v����{�̌ÓT���w�ւ̌��y������j�����ׂāq�킽���̍쎍�@�H�r�œW�J����Ă��邩�Ƃ����A�� �ł���B
�g���@������A�V���[���Ƃ����Ƃ������邱�Ƃ����邯�ǁA�ڂ��̓��A�����Ǝv�����A���A �k���l �e�B���Ȃ���Αʖڂ��Ǝv���Ă���B��s��s�Ō���A���A���Ȃ��Ƃ��������Ȃ��B�u�R�b�v���l�����ށv�Ȃ�Ă��Ƃ͏����Ȃ��B������`�ł���Ă����ƁA �ڂ��͎v���Ă��܂��B���藧���Ƃ��������@���炠���������ɂȂ��Ă��Ă��A���łȂ��āA������`���Ă������ł��B������A��s��s���͂��Ă݂�A�� ��Ȃɓ��˂Ȃ��Ƃ͏����Ă��Ȃ��ł���B�ӎ��I�ɂ�������Ȃ��̂��Ȃ��ɂ͂��邯��ǂ��A���A���e�B�̂�����̂̐ςݏd�˂�w�߂Ă���Ă���킯�ł��B�� ���͖�������l�Ԃł͂Ȃ��Ǝ����Ŏv���Ă��܂��B�����ŐU�肩�����Ă݂āA��͂��̓��^�Ƃ��������L�ɋ߂����̂ɂڂ��̂Ȃ��ł͂Ȃ��Ă��܂���B���e �搶�̂��̍��̎���������L�ł���Ɠ����悤�ɁA�ڂ����U�肩�����Ă݂āA���̎��セ�̎���̓��^�ɋ߂����̂ɂȂ��Ă��܂��ˁA���l���猩����킩��Ȃ� �Ǝv�����ǁB�i�s���㎍�蒟�t1967�N10�����A�Z�Z�y�[�W�j
�u�ӎ��I�ɂ�������Ȃ��́v�́i12�j�́u�a�H[�W�V���N]����v��i14�j�́u���S�̉_���Y�ދŁv�̎�����z�킹�邪�A�����̎��� �u���̎��セ�̎���̓��^�ɋ߂����́v���Ƃ������M�́A�g�����ɂƂ��Ắu���A���e�B�v�̎��㐫�ƂƂ��ɁA�X���ɒl����B
�k�t�L�l
�����h����̉p���sLilac Garden:
Poems of
Minoru Yoshioka�t�iChicago Review Press�A1976�j������J. Thomas
Rimer�qIntroduction�r�����́u����́A��������́A��ɂӂ������́A�d�ʂ�����A��Ԃ��߂���́A���݁\�\���Ӑ}���Ă��������
����v�����p������B
Poetry is planned to be something visible, something you can touch, that has weight, that occupies space -- that has actuality.�i�����Axiii�y�[�W�j
���Ɂu�gWhat Is the Way That I Write Poetry?�h�iwatashi no sakushiho?�j, Yoshioka Minoru shishu, No. 14 in the series Gendaishi bunko published by Shichosha, Tokyo�v�Ƃ���Ƃ���A��{���Q�F�s�g�������W�k���㎍�� ��14�l�t�i�v���ЁA1968�j�ŁA�usomething visible����������́v�ƂȂ��Ă���B
�g���������W�s�m���t�͂��傤��50�N�O��1958�N��11��20���A�ɒB���v�̏��惆���C�J���犧�s���ꂽ�B20���I�㔼�E���a����̓��{���\���鎍�W�Ƃ����Ă������낤�B�s�m���t�͑S19�т��琬��B����5�т��������낵�ŁA�{���ȑO�ɎG���ɔ��\���ꂽ���т́q�����r�i1956�N4���j����q���Ƒ��r�i1958�N7���j�Ɏ���14�т𐔂���B�{�Z�قł́A�O �G���f�ڗp���e���e�`�A�P ���o�G���f�ڌ`�A�Q ���W�s�m���t�f�ڌ`�A�R�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�f�ڌ`�A�S �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�f�ڌ`�̂����A�G���f�ڂ�14�т��P�����S�܂ł́A�������낵��5�т��Q�����S�܂ł̎�����Z�������{���Ƃ��̍Z�ق��f�����B����ɂ��A�g�������W�s�m���t�e���т̏��o�`�{���ɂ��̌�ǂ̂悤�Ɏ����ꂽ�����ǂ邱�Ƃ��ł���i������̍Z�����������Ȃ��͎̂c�O�����j�B�{�e�́A�P�����S�܂ł̈����ׂ̍��ȍ��فi��̓I�ɂ͊����̎��̂̈Ⴂ�j���w�E���邱�Ƃ����ł͂Ȃ��̂ŁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��銿���͂����D�悵���B���̂��߁A���j�R�[�h�ɂ��u瀆�v��u蠟�v��u禱�v�̑���ɁA�s�{�ӂȂ���V�t�gJIS�́u���v��u�X�v��u���v���g�p���Ă���_�����ȉ��������������B�ŏ��Ɂs�m���t�e�{���̋L�q�E�g���̊T�����L���B
�O �G���f�ڗp���e���e�F���W�f�ڗp���e���e�ƂƂ��ɁA2008�N11���̎��_�Ŗ����B����N�v�q������v�Ǝ��r�ɂ́u�g������̏ꍇ�́A��������i��ŁA�w�m���x�ȍ~�́u���ォ�ȂÂ����v�ɐ�ււ��v�i�ےJ�ˈ�ҁs������v��ᔻ����k���{��̐��E16�l�t�A�������_�ЁA1983�A��y�[�W�j�Ƃ���B
�P ���o�G���F���W�ɏ��o�̏������낵���܂߂āA�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����B
�Q ���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�F�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�B
�R �s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l14�s1�i�g�B
�S �s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A10�|27���l19�s1�i�g�B�Ȃ��s�g�����S���W�t�̒�{���R �s�g�������W�t�B
�̐S�́s�m���t�̌��e�����A�����͂����炭�V���A���Ȃ͐V���ȁi�X�����͏������Ȃ킿�̂ĉ����j�ŏ����ꂽ�ƍl������i���̕\�L�X�^�C���́A�g���̔ӔN�Ɏ���܂ŕς��Ȃ��j�B�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͍ŏI�`�����߂��S���W�ŏ����ɓ��ꂳ�ꂽ���Ƃ�����A���o�`������ƈقȂ�ꍇ���S���W�ɍ��킹�ď����\�L�Ƃ����B���o�G���f�ڌ`�̂Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̕\���́A�e���т̖{���O�ɋL�ڂ����g���̊T���Ɋ�Â��āA�Č�[�����@�[�X]���邱�Ƃ��ł���B�Ȃ��q�g�������W�{���Z�قɂ��ār���Q�Ƃ̂��ƁB
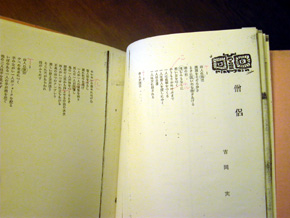
�g�����̎��������ш�Y���Ԏ��ōČ��������W�s�m���t�̃t�@�C���k�S���o���т̃��m�N���R�s�[�l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�s�m���t���эז�
�@�@���ѕW��i���W�ԍ��E�f�ڏ��A���і{���s���A���o�s�����t�k���s�����l�f�ڔN���i���j�k�i���j���l�j
�쌀�i�C�E1�A21�s���A�s���w�t�k���w�Ёl1956�N5�����k11��6���l�j
�����i�C�E2�A16�s���A�s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N4���k3���l�j
���i�C�E3�A13�s���A�s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N11���k4���l�j
�d���i�C�E4�A20�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1956�N12���k6���l�j
�`���i�C�E5�A11�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���k���M��1956�N�l�j
�~�̊G�i�C�E6�A21�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���k���M��1956�N�l�j
�q���i�C�E7�A27�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1957�N3���k7���l�j
�m���i�C�E8�A�X��84�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1957�N4�����k2��4���l�j
�P���i�C�E9�A22�s���A�s�����t�k���惆���C�J�l1957�N6���k8���l�j
���i�C�E10�A32�s�A�s�G�߁t�k�Ёl1957�N10���k11�����E7���l�j
�Ō`�i�C�E11�A24�s���A�s���㎍�t�k����p�g���A�l1957�N10�����k4��10���l�j
���i�C�E12�A20�s���A�s���w�t�k���w�Ёl1958�N5�����k13��6���l�j
����i�C�E13�A39�s�A�s���㎍�t�k����p�g���A�l1958�N6�����k5��6���l�j
���Ƒ��i�C�E14�A21�s�A�s�G�߁t�k�Ёl1958�N7�����k11���l�j
�r���i�C�E15�A29�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1958�N7���k9���l�j
���������i�C�E16�A19�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���k���M��1958�N�l�j
�l���i�C�E17�A28�s�A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���k���M��1958�N�l�j
�����i�C�E18�A�U��99�s�A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���k���M��1958�N�l�j
�����i�C�E19�A�[��189�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1958�N7�����k3��7���i22���j�l�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���o�́s���w�t�k���w�Ёl1956�N5�����k11��6���l�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|23���l15�s2�i�g�A25�s���B
�䏊�̋��Ł@�w����ꂽ�������я��@������݂̊ɋ߂��@�����Ă�����l�̒j���������������@���Ɉ�C�̖X�q�����Ԃ����L���̂��ā@�j�͎���ł䂭�Ȃ̂��߂Ɍ����ق�@�H���Ƌ����艟�Ԃ����ɏo�Ă䂭�@���̓����ӂ����Q��̋r�ƏY��ށ@�j���L���Ȃ���ȁk�P�Q�����R�S�Łl�邽�߁@�L�̈�A���畒����ɂ˂��݂̎p�͗n���@���ʂ̌��������@�������������������X�̎��@�₪�Đ�����Ԃ�@�����ȕ����֒j�ƎΎ��̊�̔L���Ăі߂��@�����������Ƃ͂Ȃ��@���������F�̑O�Œj�̓O���X�Ɏ��𒍂��@�L�͉������𑖂��Ă����̂�����@������̒j�͒E�т���L���˂炤�@���S�ȗ��̔L�̂܂Ԃ����ɒj�͊���ӂ���@���̖�̑����̂������͂ǂ���@���Ȃ̔��̂�����������̂Ŏ˂������@�j�͂����ނ�ɔL�̎l���������@���̔g�̎�̖v����͉̂��F�𑝂����o�^�[�̚�@�댯�Ȕ|�{�ɖ�������k�P�遨�Q�R�S�i�S�p�A�L�j�l��҂�陂����j�͊����Ȃ����@�v�킸�L�̓O���X���ӂ��@���̎��������ɒj�͋~��ꂽ�̂��낤�@������̂Ȃ��̎w�̓A�~�[�o�̍V�i���~�߁@�l�Ԃ̎�ɑމ������̂�����@���̂����j�Ђ̊Ԃ���P�������Ȃ������@�d�������x�������Ȃ����̂��낤�@�j�͂���������܂킵�@����ł��Ƌ�ɂƂ�܂���Ă����̂ɋ����@���ꂩ��͏����ʕ����@���������}�ɑ�Ɏ戵���@��v�Ȕ�̑܂���@�j�͓�x�ƌ�����
���o�́s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N4���k3���l�O��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͕����j�g�p�A8�|24���l16�s2�i�g�A18�s���B
�킽���͒m��Ȃ����Ƃ́@���̐l�ɍ����ʁ@�܂����̐l�̐�������p�̂܂�������ʁ@�킽���͂����S�̗̂͂̂��܂�@�Z�����łӂ�悤�Ƃ�����@�����Ă��镨�Ȃ�@�������܂Ő̏�ʼn����@������镨�Ȃ�Ƃт̂�@��]���镨�Ȃ��Ō����@�킽���̍������ɋ���ł���܂Ł@�����ė҂����o�Ă䂭��⌌�ǂ̗�ɒʘH������@���ꂪ���Ȃ��̂Ȃ��ɓ˂��߂��@�\�S�Ȃ��Ȃ₩���Ɨ₽����X����܂ł킽���͂���ڂ��Â悭�҂̂��@�H�ו��Ȃ�f���@�ނ�e��̒���ł������k�P�f���Q�R�S�e�l�[�u���̉��̈Â̂����Ɂ@���X�Ƌ��ƒ��̎��肨�Ƃ��Ȃ���@�𗧂��ƕs�v�̕��ނ���@�����ԈႢ�͂��蓾��̂��@���̎��͉H�тƂ��낱�̖A��@���@���̃K���X�̊O�̏o���������悤�Ƃ���@�q���̓�Ƃт��@�ЂƂ̖�މ��˂̃}�b�X���@�ʂĂ͖ؗ��̑w�ɂ˂ނ���̋��тŁ@�킽���͑���o���@��l�̗��̌`�����ā@�K���ƔE�ς�������������Ƃ��ā@�J�ɂʂ�Ă䂭�@�����ł̂��̎����͑��̐l�ɍ�������
���o�́s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N11���k4���l�l��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A8�|24���l16�s2�i�g�A14�s���B
�k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�S�i�V�c�L�j�l���֏��@�j�͊�p�ł݂���@�b�⋛�̑傫�ȋ|�Ȃ�̍��Ђ̗ށ@���]���Ȃ��瑾�z���N�����@���낢���̂����܂̎��k�}�@���X�ɐ����ɂȂ��Ă䂭�j�̊�݂̊́@�s�p�I�Ȍ��̏o���@�Y��悤�@���Ђ��傤�ȑN���x�Ł@�C���̗�������@����Ȏ��ǂ����ĉ��y��������Ȃ��̂��낤�@���ꂪ�s�����̌ʂ��`�Â���Ƃ��@�j�̂Ȃ������������葫���킸���ɂ������@���̂��щ��̒[����@���̖ʐς����k�P���Q�R�S�i�g���j�l�܂肾���@�����͂������ɖ����̗����̑����@��ї����ʌ��̒������̂��߂Ɂ@�j�̂������Ɋg�傳���@�͂��������ɔ����ꂽ���̑S�ʁ@�ǂ���T���Ă��`�������̐l�Ԃ̒܂̍��ЂƂ�������ʁ@�I�т͂��Ȃ��@���̃A�g���X�@�j�͂₹���ٓ�����@�����̐��ƌ������ڂ肾���@�≏�̂ɉ����Č�������~�̔g�����ׂ葱����
���o�́s�����t�k���惆���C�J�l1956�N12���k6���l���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|13�s2�i�g�A20�s�B
�חg�n�͉J��
�ʔK�Ɛ^���̂Ȃ���
���̒j�͂����d���܂̉��ɂ���
���Ԃ͖Ӗڂ̎҂���
�D���炨�낷�ׂ̗�
���ׂČ`�����ɂ������̂�
�����ɂ����ł䂭
���肠�܂�A���̗�
�͂������Ɗ���
��݂��璊���o���ꂽ
��̒����ǂ�ʂ�ʂ�
���肱����
���̒j�͊��S�ɓ�v���ꂽ
�����K���̊�͊ώ@������܂���
�����Ă����S�{�̉��˂����n����p������
���̒j�͂��������ʼnƘH����
�Ƃ�̐H����ۂ�
���ȓV�̂�Q���Ɏ������ނ���
�L���V���c�̔w������
���̒j�͐�ɕ��s���ꂽ
�k�P���ܘZ�E��E��܁��Q�R�S�i�g���j�l
���o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j��Z�`�ꎵ�y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�A11�s���B���M��1956�N�B
�֎q�̏ォ��@���т���Ă䂭�@�L�̖т̂Ȃ�����@���߂̂��Ƃ����@��ʂ��ɂȂ�@�Ԃ̐[���Ђ��Ɂ@�z�����܂ꂽ�@�N�ł������߂Ă̂��Ƃ��Ƌ����@�ؐ��̎l�̋r�@�������炭��s���@�����̋��ŋ}�ɒ�~���@�֎q�͓`�������ꂽ�@������m��ʒj�@���Ԃ����ѕz���猻���@�֎q�ɂ���������@���ʂ���M�ƏL�C���ʂ��Ȃ���@���ɂȂ���ǂ�����߂��ɂ�����o���@�}������ʃS���̏�ԂŁ@������͂��߁@���������߂Ă̂������܂��@���̂̌ۓ��@���y�̐L�k�@��̂��߁@���̒j�͋v�����O����@�L�Ɗ���Ȃ�ׁ@�ǂɂ����܂ꂽ�܂܁@�Â��Ȃ��Ă䂫�@�������낵�Ă䂫�@������ԍۂŁ@�Ύ����Ƌ���
���o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�ꔪ�`���y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�A21�s���B���M��1956�N�B
���l�ɂ͌����Ȃ����̂��@�������ڂ��̕����ɂ���@���Ƃ��x�b�h�̋r�ƕǂƂ̊ԂɁ@��T�ԑO����ڂ����ʂ������C���u����Ă���@�ЂƂ͂�����Đ܂�@�Е��͗����Ă���ɂ����Ȃ��@�ڂ��̋L���̂����т��̉J�̂Ȃ��ł̂ݔG��@�ڂ��̈��Ȃ̃x�b�h�̉��ł̂݊����@�Ђт���@���h�̏���l�͂�����̗��R�ł����@�ڂ��̕��������Ƃ���ʁ@�L���q���Y�݂ɂ��鎞���@�т̑������̔�������������@�邩�璩�֏���l�͍���ⴂ����������@�ڂ��͕a�C�ɂȂ肫��@�ѕz�̉��ł��т̐^�������Ă���@����l�͗��ɐ��ސl�@�X���b�p���͂��@���̂��߂��@�₩���̊C�̎������ЂƂł̊J�̒��������Ƃ炸�@�{�[�����ɘZ�C�̐��ꂽ�L���߂ďo�Ă䂭�@�ڂ��͖�����o��������������@���ꂪ��ԑ厖�ȓ��ۂ��@����l�͒E�߂��@��֒��Z�C�̔L�̎q�̑̉��ƒe�͂���݂����点�@�������瓒�������k�Q�o���R�S���l���@�ڂ��ɂ͊댯���@�����������K�i�̓r���́@�ڂ��͌�����@�ǂɗ��Ă������@���E������Ƃ̃J���o�X���@�ڂ��̎����̂����Ł@���ꂾ�������ɑς��悤�@����l���\���̂�F�̒n�k����@���̊G���ڂ����܂����Ă����B��̂��̂�������ʁ@�n������Ƃł������j�������ɕ`�����@�{��̍\�}�@�Ƃ����Ɉ��͂������Ɂ@�������[�݂���@�₽��ɂ̂肾�����Ƃ���@���ނ����̃g���\����
���o�́s�����t�k���惆���C�J�l1957�N3���k7���l��y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|15�s2�i�g�A27�s�B
���ɂ���
�킽�������������邽�ߗ��ɂȂ�
����̂ƂȂ��
����ʔn���ꂾ��
�����̐��Ɠ��鐯�̊p��
�����鏗�̓��̂Ɠ����d����
�����镨�����
���̒���͂�����
�Ȃ߂�����ނ��ł̗x��
�킽���������₭��肽�Ă�
�H�т̂Ȃ�����S���̋�
���e���Ė邾�܂���Ȋl����
�͂ꂽ�m�ƈ�����̉_�̂�������
������Ɉړ������������ނ���
�����ɂƂ�����
�����猎����������
��������
�H���ɂȂ�ʎl�̑ڂ̓����₫
�����ɂȂ�ʃ����������ڂ�
�����̎�l�͍s���s��
�}�_���͐S������
�q���͊X�̊w�Z�̕֏��̂Ȃ�
�ɂ��₩�ȉ^��
�킽�����������ɒ�����
�킽���������̂܂�
�Ύ��Ɠ����ɏ��������
�����̊X�̐l�X���������ɂ���
���o�́s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1957�N4�����k2��4���l�O���`�l��y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|22�s1�i�g�A�X��84�s�B�Ȃ��A�ߕ\���̃A���r�A������[�}�����̈ʒu�́A�Q��������A�R���V�c�L�A�S���O�������肾���A�{�e�ł͓V�c�L�ɓ��ꂵ�A�����̕\�����e�Ɉٓ����Ȃ����߁A�P���܂߂čZ�ق̑ΏۂƂ��Ȃ������i�ȉ����j�B
�P
�l�l�̑m��
�뉀�����������
�Ƃ��ɍ����z������������
�_�̌`
�����݂��Ȃ���
�Ⴂ����@��
�k�P�����Q�R�S���l�����肪���k�P�����Q�R�S�i�g���j�l�Ԃ܂�
��l�͐H��������
��l�͍ߐl��T���ɂ䂭
��l�͎���
��l�͏��ɎE�����
�Q
�l�l�̑m��
�߂��߂��̖��߂ɂ͂���
���l�`�����낵
���ɖċ����f��
��l����l�̓�������
����l���F����
���̈�l����������Ƃ�
�[��̐l�����牟�k�P�i�i�V�j���Q�R�S���l�悹�镪�̍^��
�l�l�����������ɗ���������
�s��̎l�̃A���u����
�������ǂƓV�䒣��
�����Ɍ���������
�J���ӂ肾��
�R
�l�l�̑m��
�[�ׂ̐H��ɂ�
��̂Ȃ�����l���t�H�[�N��z��
���ڂ̂����l�̎肪���𒍂�
���̓�l�͎��������
�����̔L��
�����̏��ɂ����Ȃ���
�����ɗ����̃{�f�[�����
�k�P�[�с��Q�R�S�ѐ[�l�������l�̎肪����グ��
���͍����ق߂����
���͌��ɎN��������
��l�͖O�H�̂��ߔ��
��l�͑n���̂��߂₹�ق���
�S
�l�l�̑m��
���̋�s�ɏo������
��l�͐X�֒��̎p�ł��肤�ǂ��}���ɂ䂭
��l�͐���̎p�ŏ����̌҂��̂����ɂ䂭
��l�͊X����n�̎p�ŎE�k�P�肭���Q�R�S�C�l�̊���ς�ł���
��l�͎���ł���̂ŏ�������
�l�l�ꏏ�ɂ��ę����Ȃ�
�T
�l�l�̑m��
���Ŏ�q��d��
���̈�l�������
�q�����\�ɕ���������
������������̊�̕�e�̌���
�ނ��D�̑��z�߂�
���ɍ����u�����R�ɏ��
�O�l������������
����l��
���̂��炷�̐[����A�̒��Ő����o��
�U
�l�l�̑m��
��˂̂܂��ɂ�����
���͎R�r�̉A�k�P�̂����Q�R�S�X�l
����ʌ��o��
�O�l������ł��ڂ肾��
�C���̑傫���̃V�[�c
����l�������Ŋ����ɂ䂭
�J�̂Ȃ��̓��̏��
�V
�l�l�̑m��
��l�͎��@�̗R���Ǝl�l�̗���������
��l�͐��E�̉Ԃ̏����B�̐���������
��l�͉��ƕ��Ɛ�Ԃ̗��j������
��l�͎���ł���̂�
���̎҂ɂ������
�O�l�̋L�^�������ɕ���
�W
�l�l�̑m��
��l�͖͌̒n�ɐ�l�̂����������Y��
��l�͉��ƌ��̂Ȃ��C�ɐ�l�̂������������Ȃ���
��l�͎ւƂԂǂ��̗��܂锉�̏��
������Ґ�l�̑��k�P�i�S�p�A�L�j���Q�R�S�i�x�^�j�l������Ґ�l�̊�̍t�ʂ̓������̂ɋ���
��l�͎���ł��ĂȂ��a�C
�Ε��̌����ŊP������
�X
�l�l�̑m��
�ł������̂Ƃ�ł��o��
���U���n���Ȃ��̂�
���E����i��������
����苤�ɚo��
�����
�l�l�̍��͓~�̖̑����̂܂�
��̂���鎞��܂Ŏ���ł���
���o�́s�����t�k���惆���C�J�l1957�N6���k8���l�O�Z�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|25���l15�s2�i�g�A24�s���B
�x�������ꂸ�ɂ��̒j�͎��@���k�P�ꁨ�Q�R�S骶�l���̂������邵���ˋN�����j�Ɂ@�Ȃ͑����݂����������@��̂��ɐオ�߂��������₭�̂Ł@���[�̂䂽���ȏ��ł���Ȃɂ͂������ʁ@�H������Ƃ��ȊO�́@�����������ɂ���܂@�ނ���Ȃ��Ƃ�����@���ƂɏA�Q����Ƃ��@�A���̉Ԃ����ʕ��������������@���̒j�͂����̑��̂��ƂɂЂ��ς��ā@�n�ɕ����Ă䂭�A�S�Ȍ`�Ԃ��Ƃ�@���������Ȃɂ͂���͂ǂ��ł��悢�@���������������g����Ł@�ǂ̌����Ɏ����Ă��錢�ɉa��^����@���̋U���S����Ȃ����Ȃ��Ȃ��̂��@���Ԃ�̔������������L�������Ő�����Ԃ�@�����Ă��邱�Ƃ��͂��䂢�@�������Ԃ�̎֕����Â̗�����[���̂с@�j�̕����܂�镔���֓˂��߂�����@���ڂ͂���@�p�َ̑���s�߂邩��@���͒j�̐g�̂܂��̂�����₫�@���点����킹��@���ꂩ�炳���̊Ô��ȑ���͂ł��ʁ@�j�͐����邽�߂ɂ́@���Ȃ̔L��o����ӂ鉮������Ăі߂��ā@�|���d���܂˂Ȃ�ʂƍl����@�����I�Ȏ����łȂ��@���������Ɏd���Ă����@�ŏ��̖�͐Q��ł������߂ā@�M���҂̍D�ތ����̂ڂ炷�@���̏��̎p���Ɨt�̉��ɑ��Â����̔��n��㵒p���@���Ƃ�������ׂ��吺���������@�Ă�������Ȃ̕R�����炵�ā@�j�͐l�Ԃł���؋��̂䂦�Ɏ��ʂ̂��@���͌��̌������킪���@�����g�͔L�̖тɕ���ꂽ�܂܁@���̋�������@�������ꊦ���ւƑ���ꂽ
���o�́s�G�߁t�k�Ёl1957�N10���k11�����E7���l�Z��`�Z�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�J�^�J�i�̝X�����͕����j�g�p�A9�|19�s1�i�g�A32�s�B
�k�P�i�x�E�v �Ɂj���Q�R�S�x�E�v�Ɂl
�X�т��̐H���̗ނ��݂ĕ���
�����������т͊Â��挱�̉Ă��P����
�얞�Ƒ��͒��˂܂��
�ڂ��͒p���ׂ������Ȑ��Z�����j
�^�C���^�̗[���̊C�݂ɂ���
�ԂƊD�F�̎Ȃ������e���g�̓�����T��
�ڂ��Ɠ����s��̏�������
�������
�a���`�̍��i�̂����Ƀ^�I��������
�݂��߂ȃV�X�e���̍��Ɍ���������
�ڂ��͋h����肾
���̐����҂��Ԃ߂�s�����̑��̖тk�P�Q�����R�S�Łl
�ڂ��̐��_�̉���g�������Ă䂭
���N�ڂ���`�������
��̍��̏
�ԋ߁k�P�����Q�R�S�i�g���j�l�ɂ݂�ʎ��̃t�H����
�삵�������N�̋��̗���
���̂����O�ς�����k���Ă䂭�X
�ڂ��̗��J�{�\���ڂ��̊Ⴉ��
�S�Ă̐����֓`����
���p�̗��n�������킹��
�ڂ��͏���G�o��
�q���p�̕��܂���֏��X�ɂ͂߂���
���܂����ڂ��͏�
�S�̔��̌X�ނ��x������
�ڂ��̃v���C�h���ӂ�
�ڂ��̓����Ƒ�]���N���Â���
���Ȃ̉Ă̊C
�ł̔̊C
�Ⴂ�i�̉���
�ڂ��͐��L��������
���Ȃ̌������ɏo��
���o�́s���㎍�t�k����p�g���A�l1957�N10�����k4��10���l�O�l�`�O�܃y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|25���l18�s1�i�g�A26�s���B
�ڂ��̕Ό��͑����̐l�����܂炷�@�Ƃ��ɐA���̌s�Ƃ����s�֒�k�P�����Q�n���R�S���l�Ă�@�،�����W�J�����@�ߌ��I�Ȃ�F�̈炽�ʉƑ���������@�����̂܂��@���������邱�Ƃ̂ł��ʁ@�������̒j���@�������Ȍ�ڂ̂Ђт��@�ԕ��͕ǂ�Q��������@�����ƌł����炴��̗��ɋ߂��@����䂦�q���͊ߋ�̎Ԃ̐��E�𑖂�ʁ@�V�я�͕�̎q�{�@�����̂ւ��܂̒I�̉��@�����Ŋ���@�ڂ��͂��������c�����o��@�ڂ��̐M���́@���͌Ō`�ł����悭����˂Ȃ�ʂƍl����@���Ă�����ꂽ���֓����ɔ���ڂ��ƈ�C�̂Ƃ�ڂ̕���@�ڂ��͗]�����Ȃ��@�����j���O�p�̑S�g���ʂ��@�i�Ⴂ�̓���R�Ԃ̕X�̐���w�����@��������炩���^�����炢���@�ł��H�@�ł��J�Ȃ痼��ň�������@���݂Ɉ�́k�P�Q㢁��R�S�ށl���R��@�l���M�����ʂقǁ@�ڂ��͜����Ƃ��ĊX�ɓ���@�U�����ꂽ���@�̊O���̐Ε���@���@���ꂱ���㓙�̗V�Y���@�a�@�ւ䂭�Ⴂ�K�w�̂��Ƃ�����@�������̂ڂ�̎Ȗڂ����S�����@�ׂ�����`���Ă䂫�@���܂�ł��Ȃ����ׂ��ׂ̒��_�Ł@��������������@��҂̏������@�������ł����Ύ��̗[���@��q�₤���������畆���̂��@�܂̒��g�̓����ނ��k�P�����Q�R�S���l�ɂ䂭�@�ʂ邢��q�̂���ۂۂ̎��͂́@�ɂ݂����Ăނ�����@���b�������ȃ����j���O���ӂ�����@�ڂ��͐^�̌Ō`���݂āk�P�����Q�Ł��R�S���l����@���낢�����[�̊ǂ������ތ��̑e�����ӔC�ȌR�������������@�����łڂ��͊X���o��@�����ڂ���X��l�E���镨�ɑւ���@������ڂ��͂˂ɏ킸�@���悤�Ȃ�����Ȃ�
���o�́s���w�t�k���w�Ёl1958�N5�����k13��6���l�O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|20���l16�s2�i�g�A26�s���B
������悤������@���ꂪ�ڂ��̍D�݂̎����@�a���̖ѕz�̐[���Ђ��ɋ��܂�@�ڂ��͔E�ςÂ悭�҂@�����łȂ����łȂ��@���̏��Ղ̋P�����@���܂͎l���@�I�̍����������@���������ԕ��̐ς܂�Ă䂭�畆���Ɂ@�F��̖��H�̌����߂Â��@�ڂ��̍ӂ�����ڍ��͉i���Չɂ̂䂦�Ɂ@���̉��y���@�ӎ����k�P�i�x�^�j���Q�R�S���i�S�p�A�L�j�l���͐�������d���Ắ@������Ƃ��ā@���тꂽ�c�����i�̈�ꑂ�������@��̘m�̎R�֑}�����܂ꂽ�܂܁@��\�̂����т��������@��H�̂��炷���ї�������@���т��юo�͌������ɂ��ā@�ׂ̊��҂̈����̊������]�����@�ڂ��̉������̓���@���Ắ@�ꎞ�I�ɂ�������̎��̔�����U�v����̂��@�˂ɓ���뉀����ށ@�����̒߂�Ō�w�̂ނ���@�ڂ��͏X������ڋ߂����@�s���Ȏ����Ɠ����̖�������ق𝘝a���@���ɂ͂�������i�̏L����k���@�����܂��Đ��̍������ʂ��@�k�P���Q�R�S�Q�l���̎����ڂ����P���@�����̈ߕ��̊ϔO�͂����ā@�s���ȓ������Ɓ@�����c������M���Ă����炭���̌`�Ł@�ڂ��͕G�����@�ʓ|�͂ǂ̐��E�ł��N��@���яo�����S�˂̏�Ł@�ЂÂ��̓��ƍ��̖��C���͂��܂镥�ł��@�����͊��}��ā@���������X�̏���������ė���@�ِ��̋��Ȃ݂ɔ��܂łʂ炵�@�ڂ��͐�����C�Ɉ��݊���
���o�́s���㎍�t�k����p�g���A�l1958�N6�����k5��6���l���`��O�y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A9�|20�s1�i�g�A39�s�B�{�ю��M�̏́A�g���̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�ɏڂ����B
�x�߂̒j�͑���n�́k�P���́��Q�R�S�i�g���j�l���Ŗ���
�Z�̂������̏����ȓ���
�n�̉A�s�ɂ҂����艈�킹��
�Ƃ��ɂ͂���ɒ݂肳����
�~�̊���ꂽ���Ԃ��܂̍��k�P�����Q�R�S��l�̒n�`��
�r�����Ȃ���̂�z����
�x�߂̒j�͓ł̋P���������炵
��̎葫�Ŕ삦���n�̓��̂����яグ
�����ɂ˂�����߂̍炫�݂��ꂽ
�u�˂������Ă䂭
���傫�Ȗ��^�����߂�
��������ΐ���Ƃщz����
�n�̎��̊Ԃ�
�x�߂̒j�͍I�݂ɉa�H����
���̔M���������������Ō��ւ͂��т���
���l�ɂ͐M�����ʌ|����
���Q�〈�����̉c�݂łȂ�
����͓V���̍��������ς�s�����V�Ƃ�����
����n�̌㎈�̟B����k�P�i�i�V�j���Q�R�S�������l
�k�P���������Q�R�S�i�g���j�l�������������̑���
�x�߂̒j�͐l�n��̂̊����ӂ�
�͂��������J���ꂽ�n�̊�̖���ʂ�
�Ԗڂ̏����E���ꂽ�y�̉ƁE�k���̗ŕ�܂ꂽ�l
���F�����̗�������˂�
�x�߂̒j�͕a���̗��j��
�n�͏Z�݂��ė���ʎ�l�̂��ߑ���Â�
���ɂ������Ē�������݂�
�܂��ɔ��Ă��鎞
�Ō�̕����̂�����
���Ԕn���\���
�x�߂̒j�͊Ԕ�����ꂸ
�k�J�Ɠ��k�P�Q�|���R�S�~�l�̏Փ����܂�������
�w�̕�����Ȃ��߂Ƃ�
�푰�̔ɉh�𐬏A����
��ׂȎ����ƈ̑�ȗ\����
���S�̉_���Y�ދ�
�x�߂̒j�͂��̂�̂��Â���
���̎�s�E�G��
�A�S�ȌY���������Ɍ���
���o�́s�G�߁t�k�Ёl1958�N7�����k11���l���`��O�y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|16�s1�i�g�A21�s�B
�������X������
�����̂���[�ׂ�������
�R��������̖Ǝւ̉ƌn��f�ׂ�
������ꖺ
��e�̓T��Ȕ��ƐQ�Ԓ��̖��Ԃ�
��l�̘V�����j���i�߂��낷
���ݍ������F�����̔n�̕��A�̏I��
�ꖺ�̐S���Ђ���Ȃ̉���
�ނ炪��ڂ��ӂ�̐��{���
��݂�����V�����j
������ނ��̕v
��H�̕��e
�����̖��͂����܂����T�̑�������
��̂��낢�Ђ܂��̎��̗��̂Ȃ���
���̂̏����̒ɂ݂𒍂�
���ׂẲƍ��Ƒ��z����̖�����炬���
��e�͊C�̂����Ŋ��ʂ�
�Ⴂ�j�̂����̓������݂ɂ䂭
������ƌҊԂɊ����Ȃ���
���e�͐��Ȃ�������̌�������
�ӂ����X�R�̓˒[��������
���o�́s�����t�k���惆���C�J�l1958�N7���k9���l���`��y�[�W�A�{���V���V���Ȏg�p�A9�|17�s1�i�g�A29�s�B
�ڂ��������肽���̂͋�`�̉�
�����ň�Ă����˂Ȃ�ʉ~���̎���
���Z�Ȃ��킢�ɑ������ׂ�
�����̍Ȃ��N���Ă͂����Ȃ�
�S�y�̓��̂��Ԓf�Ȃ��ω������邽�߂�
�u�N�ƃG�[�e���̑ޒ�
�����̑e���z�̉��Ŗ钋�̕ʂȂ����˂�
�ڂ��͐ΒY�̓��鏰�ɂ͂�����
�����̚M�����Â���
�Q��ƈ��������������炵�Ȃ�����
�ڂ��̘r�͂́k�P�Q�R�����S���l�O�ɍ݂�
���̂��������ł������鎀��
����͌��h�ɕC�G����ߌ�
�ڂ��̍��̒��ޏ�̑S�i����
�������������A���Ƃ��ė�������
���l�̌o�c�����Ԃ����X�ɖ���
�����鎀���̉~��
���̂��ׂ��ׂ̂܂������
�ڂ��͕��e�̐����o����
��e�͐H�����̂��܂����炷��
�₪�ĉ~���̎����͚L��
��Ƃ̑����Ƃ���
�o�Ƃ����̑�����P�̂��Ƃ����Ԃ鎞
�ڂ��̉ƌn�͒����������Ȃ����낤��
�V�����˂��݂̌`�[������
�ڂ��痼�e�̓X�g�[�u�̂Ȃ��̈ł�
�Z�݂������m���
����
�~���̎������r���ɕ����鎞�܂�
���o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�ܔ��`�܋�y�[�W�A�{�������V���Ȏg�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�A19�s���B���M��1958�N�B
�V���d�͐H��������Â��ċ���@�h�A�̊O�ɏo���Ƃ������ނ���[�f���̋��̂z���Ƃ���@���������̃Y�{���̐����F���̂����@�D���̂҂��҂��������̋��Ɂ@�Q��̒j���͂��Ȃ��ނ��̂悤���@���т��������i�v�L���̔g�@���h�̂͂������ŘV���d�͎��ʂ��낤�@�������z���ٖ̈M�֗����ׂ��@�t���̂͂����X�v�[���ɂ܂�����@���肾�������̗ށ@�o�̂��Ȃ₩�ȓ���Ł@�V���d�͂����������܂ꂽ��ւƂшڂ�@���悤�Ȃ�@���_�̌Q�O�@�܂̓���@���̊C�@�ォ�猩��Ƃ悭�����ł���@�Ύ��̃����h���}�@���J�̌ǓƂȋV���̏I��@�V���d�͘B�B��������ʼn����H����ۂ�@���̌�̒��Q����������ƒN���Ȃ���悤�@���҂����̏K����N���n�m���邩�@�V���d���N����͂��݂ŋ��t��������@�]����ʐς�T���@�S�Ȃ炸�����Q�����̂��@�C�̂Ȃ��ő傫�ȉ������Ă�@�V���d�͐��U�͂��߂Ă̑e���������@���̂����̎��吨�̋q�����ɂނ��@���₤�₵���ӂ���@���ꂩ��̒����������邽�߂ɂ́@��a��㵒p���E�Ԃ@�����҂Ƃ��ĘV���d�͔삦���薧�Β��ɓ���@���炭���т̔������܂Ԃ���������@��M�̉��ɉ�荞�ތ��@�����͍s�V�̈�����ꂩ���m���
���o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�Z�Z�`�Z��y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�A28�s�B���M��1958�N�B
�����͐l�̔��g�Ƌ��ɍ��̎�{�֒���
���X�ɂ��ǂ����ĝ˂��
���F���n�̂��Ă��݂̉��ł��������������̌��Ƒ��z
����������܌���
���E�̗��n�̐l�̔����̓{��̊��
�]�V�Ȃ����邠�Ɣ����̐l�̐S
���ׂĂ̏����̎q�{��@��
���m�̔����͂��炩�������͕a�C�Ōł܂�
������������
���@���Ȃ����͎���
�R�����a�̎R�Ɖ����̒���
�C�ւƂ����߂�ꂽ���q���͋����Ȃ����
�����ɞ��Ƃ�̂�Ŕ���ꂽ
�R�͂̉���������
���ɑ��B���鉲�k�Q�y���R�a���S�y�l�̏d�݂ł����ނ�
�g�̒�����
��̉��k�Q�y���R�a���S�y�l�̕��͂���������
���̐l������
�����N������������
���҂̐����̂���̕��m���͂��܂���C��ł�
�X�R�ɏ������Ђт����Ȃ���
�[�f���̃v�����N�g���̂ނ�ɐ��߂�ꂽ���j��
���̂��L�����邽��
���E�̎c��̔����̐l�̍������֏��
���Œg���Ƃ�
��������������܌���
���E�̗��n�̐l�̔����̓{��̊��
�]�V�Ȃ����邠�Ɣ����̐l�̐S
���o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�Z�l�`���O�y�[�W�A�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�A�U��99�s�B�g���͓��N8��8���̓��L�Ɂu�q�����r�o���B����Ŏ��W�s�m���t�̏\��ъ����v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�Ə����Ă���B
�P
�Z�˂����낷
�ڂ��ɂ͏�l�̏K�����Ȃ�
���_�܂œS�̔��͂��ɂ���
�X��ʂ�K�X�ǍH�v�����R�݂ċL������
���̂Ȃ��ɓ��ꂽ��l�̒j
�֊�ɂ܂�����ڂ���������炤
�������ׂ鏭���͂�����ނ�
�X�q���܂Ԃ������Ԃ�K�X�ǍH�v�̒Ƃ̈ꌂ��
�����̓��𐅓��Ő�킹��
�������݂̂Ȃ��Ƃ��Ă���������
�c���܂̎���
��l�̏��̊��̉Ă�m���
�����������͋킯���ނ��낤
�ڂ��̔��̉�
���ʂ̖@�����������b�^�̓����̒���������낤
����܂ŋx�Ƃ�
��������Q��܂ŎȔn�𑖂点
�y���L��h����
���łɉ����̈Â�
�Q
�������̐��̏�Ő��@���炭
�����G��̂͂��܂�
������̉��ŏ����͕ω����Ă���
�Ԃ̐A���̊�����
���т̎p�Ԃ̕s�����ȑ܂ɍ����`���ڂ��͂��߂�
�ڂ��̕@�т̖݂��J�łʂꂽ�����Ƃ���ʂ���̂͂���ȂƂ�
�I�̂�������ׂ̍��
�t�̂𗭂߂�ł̂Ȃ���
�y�����ɂ��̂̂�����
�ڂ��͂����Ȃ�ω�
�����Ȃ������҂��Ă���̂�
�R
�ڂ��̖���̝B�ʂ��߂̂��̂悤�Ɋ��炩�ɂȂ�
�����ɋ�������������l�̏�
�r���ɂ����ꂽ���������̂̏���������炢��
���͑g�݂�����ꂽ�r���Ƃ���
�ڂ��̊��e�ȓ���̉��ɍ݂�
������g�����ꂽ�㔼�g
��Ɍ��̗��̉��Ȃ������̐��_
�������ڂ��̓��𑨂���
����u�Ԃ͏Ƃ炷
�@����Ƃ��돗�͐l���E���Ă����炵��
�����a��ȕv�łȂ����
���Ⴊ�����̖��܂����邪��S����v
�l�łȂ���Εʂ̂���
���̑傫�Ȃ��傤�������h���Ă����̂�
�S
�i�N�̌o������ڂ��͔퍐�𗠐�
�퍐�͂˂ɋ~���ʐ��i��������
�ނ�͂��ׂĔ�������ɂӂ��킵���q������
�Ⴆ�ڂ����Ƌ�����@��ɂꂱ�܂�
�퍐�Ƃ��č����̎҂����ɂƂ�܂����
�@�q�킽���̍Ȃ͋a�̐��E�֔��n�����
�@�n������́@�����₭���`�̍����̑܁r�ƌ�����
�l�X�̐S���Q��
����łڂ����ƍߐl�̗�����������������
�ڂ��ٌ̕�l�͍Ȏq�Ɨ��e�̂��߉Ƃ}��
�K�̑܂ɂ�������k�����ߎ����̂����{�̎�������ĉJ�̒��֓���
�s�^�Ȏ҂͐j���ŗ{���Â����ɂ���
�T
���̕v�͘V���ȊC�`�Z�t
�o�ڍH��A��Ė����C�֍s��
�����N�����C�̉��ł͂��炭�̂�
�^���̌����ɓ���Ƃ�
�o�ڍH�͂����܂����ɂ̌`�ɕ���
���g�̖т��P����
�[���ȔS�͂Ƌꖡ�̂���A�𐁂����ڂ�
�Ƃ��낫��킸��
�v�ׂ݂͊ŕ�����������
�j�D�ƖԂ̔j��ڂ���
����������
���Ȃ킿�Z�t�̍Ȃ��H�����͂���ł��ĉj��
�M�����̏��͐l�̐S�G�Ȋ��L�ɕω�����
�����ɗ₦�����˂܂킷
���̌�ł̎O�l�̐H���͊댯��
�M��t�H�[�N���A�C�ɂ�����
���ނ◑�͐H��������
��ؗނ͂܂����̂���
�C�͎��j�łӂ������
�U
�ڂ��͐��@�̉Ԃ��Ăт̂���
�]�����s��ꂸ
���E�̏��������R�̂��ׂĂ�������Ă��Ȃ�
�^�����܂��
�Ԃ̐[����������������������݂̂�
�ڂ��͎����ƕs�K�ȏ����~�ς��ׂ�
���̑ڂ֎���ׂ̂�
�r���͖�ɕ���₷���`�ƐF������
���܂������Ԃ�����Ɗ���
���ꂩ���̂ڂ��͂܂��߂ȐX�Ԃ�
�����ނ�̂ЂȂ���Ă悤�ƌ��ӂ���
���ׂ����\�̐��ɕω��������̐���
�@���━���̂Ƃǂ��ʏ�����
�ڑ��Ȃ�����H�����玀�炳��
�ڂ��������U�߂Ă�����������̏�
���̑��̔��������������
�����͋P������
�����������
���̔��̏�ɑꂪ�������ē���
�ڂ��͗�Âɖ@�T�̉������̂����
���Ăڂ��͏��ɂ͑�ς�����
�ߐ[�����͋��点�悤
�K�X�ǍH�v�ɏт��q����ē��̏����������𔗂�̂�
�ڂ��͋v�����҂�
���o�́s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1958�N7�����k3��7���i22���j�l�`�O���y�[�W�A�{���V���V���ȁi�Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|22�s1�i�g�A�[��189�s�B�Ȃ��A�{�ю��M�̏Ɋւ��Ă��q���сq�����r�̐�����r���Q�Ƃ��ꂽ���B
�T
�傫�Ȃ悾�ꂩ���̏�Ɏ����͂���
����̓G�ł��Ȃ�
�����ł��Ȃ�
�����͕s�V�̉ƌn���������H��
�����l�ނ��݂����Ƃ�����l�ނ̂̂��ꂽ�L���̌t��
�i���̐S�Ɠ��̈��L
��x�͕�e�̋��Ǝq�{�Ɉꂽ
���������̊��̉ʕ�
����ɂ��D��ꂸ��
���e�Ƌ��ɓ����m�ł܂��
�n���̉~�̒��̐V������
�����ȏd�݂̂Ȃ��̌��ł��\
��������������
�����͕��e�̋`��̂��̂łȂ�
��e�̈����̌ՂłȂ�
�����͗c���̌Z��łȂ�
�Ԃǂ��ۂ̎��@��
���̓��鐢�I�����ŏ��W����
�V�����l�i
�����ȋ��|�̍v��
�ق��ҁE�ق����ҁE�����
�݂��Ƃȓ��ꐫ�̃t�B��������]����
�����͊��̉��̒��łȂ�
�����̓D�̐��̉��łȂ�
��������������鑤�ɂ���
�U
�͖���ٍ̈���
��e�͎����̂��炾���
�����̎c�E�ȉ��̖��߂�
�S���̍��ʼn��{��g�グ��
�ق̂��̎g���̏I��
��e�̗܂̈�Ă��y�n��
�n�̂Ђ��߂ɂƂ����߂���
�����̂ނ�͋���
�^���͉Ɨ��̉x�Ԃ�������̎�
��͖̌Ɉ�l�̕�e��^����
�͖��B������̕�������e���ɒ݂���
�S���͖̌͂��߂��S���̕���
�����̋�Ɏq�{�̌��R
���E�̕�e�̂͂�������͌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�Ύ���
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ɕ���
�@�@����������ɗ����^�����k�P�i�O�s�ƃV���]���G�j���Q�R�S�i����ɑS�p���Q�j�l
�V
�����͋��R������
���E���̐Q�䂪
�s�V�悭�V�l����l���悹���a�ނ̂�
�����X�̎�����
���V�l�Ǝ��ɂ݂������
�͂������Ă䂭������
��Ɠ��̐ς܂ꂽ
�����ݑ܂����������
�Ƃ��ǂ��S�C�̓��悪��������
�ߖ�������
�V�l�̏��F��
�������k�P�Ɓ��Q�R�S�i�g���j�l�R���������͂���
�����痁����
���P�̗��l�E�v�w�����̐Q���
������̗��R�Ŏ����͚L��
�Z�b�N�X�����L���Ȃ��̂�
�̂��Ƃ��p����
�����Ȃ�Ό���̋�
���炩�Ȍ��̐Q��
���̔��́k�P�����Q�R�y���S���l�������̏ꏊ�ɏZ�߂�
�����͘V������e�̑r���̂�݂�
���肩�����ЂƂ�̗��s��
���炠�炵���̔����
���̑��B�@�f��̌��h
�ł���Ώ��ł̒m�����܂Ȃ�
���܁k�P�i�i�V�j���Q�R�S�́l��㌎q�̌C�ɓ��܂��X�̋G��
�����̕����͂���߂�
���ڂ���̉Ԃ�����
�����͐��E���̎�����V�l�Ɠ�����
�W
�����̔���ƕa�C�ɂ���
���ׂĂ̈�҂͒��ق���
���ƊC�Ȃ݂̂Ȃ��Ƃ��k�P�x���Q�R�S���l�炷�b�̒���
��e�̓��[�͂ǂ��̒n���k�P�Q�i�i�V�j���R�S���l�ɂ����������
�s���ȕ��y�Ɩ\�͂̉����ɂ��������
�����ɂ̂�����
�����̋ꂢ������
����̂��̎����͎�p�̊�̉������܂悤
�H�̉ʕ����k�P�R���Q�R�S�́l�֔��т�����
���l�̘V�ԂȎZ�p���a�C������
�����̒܂͊O���ւ̂т�
����s�ޓ����ւ����܂�
�����̕a�C�̌o�߂�
�H���ƕ��̋���̊W��
�����̈�r�����ǂ�
�Ō�͖��̏ɉ��ŏ�����
�����͈�҂̋L�^�ɂ̂���̂łȂ�
���j�Ƃ̕�n��係ŕ������
�X
�X�т��̐��E�̎�{��
��e�͎�����w�����ď��炷��
�@
�@�ӂ��ꂽ������̏��R
�@��̂Ȃ��n�̒��̂Ƃ���܂���̐w�n
�@�������ꂽ�����̂ق����҂�������Ă��ꂽ����
�@���̏��ł̕��m�Ǝ����̍���
�@�R�͖͂C�����炭���̑������Ԃ�
�@�Εv�̎���܂����ފC�X��
�@
�����̉x�ԕ��i��
��������e�̈��͂��₢
�����̎�ɂ���S���̊ߋ���Ƃ肠����
�����ɂ͐�����������
�������₪����͔̂�����
�����̐a�m�i���̐H��֒p���𔘂�
���̂����Ȃ����鍑�̖�͂��������݂���
�����̔��𐂂炵
���͂��̓���I�o����
�J���߂�
�����E�E���ꂽ���E�̓��̂̐J���߂�
���̗J�k�P�Q�R�T���S�T�l�Ȃ���Ƃ炵�߂�
��������ɂ̂��܂艘�����Ȃ����܂�
ⴂ̉����낢����
�嗝�̎���
�S���̍�������
�����̐X�̎������܂��̍��̎���
���̂Ƃ�
������e�͉Ă̐�̎��̒n��
�قȂ�G�l���M�[��
�قȂ鋃������
����̓{��̗��j������
�Y
�����̍D���ȗV��
�ނ炪����
�k�P��X���Q�R�S�X��l�̊C�֖Ԃ�����
��C�Ƌ��ɒ���ōs�����j�k�P�B���Q�R�S�����l�̏d���k�P���������Q�R�S�Ίہl���Ђт�����
�������̍��ƈł��z���Ă������F�ʂł�����
���҂̂��߂Ȃ���S���Ďd�����ł���
���Ƌ���̗ނ̞g���͂���
��v���P�Ń{�f�[������݂���
�͖̗��n�œ�x�ڂ̕�������Ȃ������Ă���
���������̂�����̗�
���߂̎��̂��݂��������̓��X
���̖鉾�͑ދ����ƐÂ��ȍ��͂Ԃ₭
�����ɂ͂��ꂪ������
������x������Ԃ��\�Ȃ�����g���悤
�����̂Ȃ�Ȃ�ł����n
��e�͂���Ȋ�������Ď�`�킸
�����̂͌����ł��Ȃ���
�j�D�̉ƂłǂȂ肾��
�����͐����������咣�ł��Ȃ�
��e�̖ڂ̓͂��ʏ��ɗ���
�k�P�����Q�R�S�X�l�����܂܉��炷��
��������
�`���̋O�Ղ̊C
�Z
��e�̂˂ނ�����
�������������
�ʂĂ�
�k�P�i�i�V�j���Q�R�S�t�́l���̊C�߂���
���҂̂���ނ��̊�̏�ŗ������
�����玟�ւ�
���˕�������
���J���ꂽ�o�����߂�
������l�̎o�łȂ������̎o��
�g�̍��ɌĂ��
�A�C�Ș@���������čs��
�ڂ̒�������߂�
�����̊C��
�o���s��
�o���Y�ޚ삵�������̖�̏j��
�P������������Ђ炫
�Ñ�̖��J�n��
�����͌��邾�낤
�����̕��ؐ}��
�����ꂽ��̈��
���̚삵�����̈ł���
���X�ɔ����̎��������܂�o��
�[
�����������ďW���e����
����p�s�E���锼������
���������̑r���̂������Ђ�������
�܂�ɂ͏����̌��܂ł�
����ɂȂ�܂ō����֓����Ă䂭
���̂�����ׂ�̕�e������
���ق����߂��đ�������C�ʂֈړ�����
�����玟�֍����т̏@���I�ȂȂ���
�G�Ȃ����̌������i�ǂ邽�߂�
����������������ʂ悤�ɂ��₷
�q��S�ƈ����̂��肩������
�����łǂ����Ă��̕����̕��s�̉̂������ł��悤
�Ƃǂ낭���̂悤��
�L���ȍ����悶��
�Ō�ɔ����̂���߂̕�e�������X�͂ɕ���
�K����l�̎����������Ă�؋���
�߂��߂������̗����\��@��
���̂͂������ŚL������
���̉i���̓�V�ȗ��̖�������悤
�����߂�ꂽ�r���̐��E��
�s���~�b�h�̒��_���킸���Ɍ�����
����قǏW���Ă͂��߂�
�S���̕�e�̂����܂����̂Ȃ���
�����炵���N��
�����̐��������߂���
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���W�s�m���t�̍ŏI�`�����߂��s�g�����S���W�t�͟f�㊧�s�����A���҂̐��O�ɂ͑O�f���̂ق��ɁA�c��m�ҏW�E����s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�A�s������{�����W�听11�t�i�����n���ЁA1960�j�A�s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�A1973�j�ɑS�т����^����Ă���B���҂̖{���̈ٓ����q������{�����W�听�Łs�m���t�{���̂��Ɓr���q�g�����̑�����i�i60�j�r�Ŋm�F����������̂ŁA�����ł́s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�����̖{���ɂ��ĐG��悤�B���s�������炢���āA�{���̒�{���Q ���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����Ŗ{�����x�Ƃ��āA�`���̍Z�قƓ����菇���Q�Ƃ̍Z�����s�Ȃ��A���̂��鎍�т̂ݓ��Y�ӏ����f���ăR�����g��t�����B�Ȃ��i�@�j���̐����́A�s�����̎��͉��s�߂����A�U�����^�̎��͂����߂̎��傩��\�킷�B��{�̊T���͎��̂Ƃ���B
�Q ���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�F�{�������V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A�܍�27���l13�s1�i�g�B
�x �s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�F�{���V���V���ȁi�Ђ炪�Ȃ̝X�����͕����A�J�^�J�i�̝X�����͏����j�g�p�A9�|27���l18�s1�i�g�B
���i�C�E10�j
�@�@�Q�x�E�v�Ɂ��x�E�v�Ɂi�����j
�@�@�@�@���ō���Łu�x�v���E�������P����A���B
�Ō`�i�C�E11�j
�@�@�Ƃ��ɐA���̌s�Ƃ����s�֒�k�Q�n���x���l�Ă�i2�j
�@�@�@�@��A�𐳂������́B
����i�C�E13�j
�@�@�x���F�����̗�������˂��i24�j
�@�@�@�@�u�����v�Ƃ���ׂ��Ƃ���B
�����i�C�E18�j
�@�@�Q�n������́@�����₭���`�̍����̑܁r�ƌ����遨�x�n������̂����₭���`�̍����̑܁r�ƌ�����i51�j
�@�@�@�@�S�p�A�L�ł���ׂ��Ƃ���B
�����i�C�E19�j
�@�@��e�̓��[�͂ǂ��̒n���k�Q�i�i�V�j���x���l�ɂ���������ʁi75�j
�@�@�@�@�R�ȍ~�̖{���Ɉ�������邱�ƂɂȂ�A�{���ɂ�����B��̎����B
�@�@�x�Ō�ɔ����̂���߂̕�e�������X�͂�⍂ԁi179�j
�@�@�@�@�u���ԁv�Ƃ���ׂ��Ƃ���B
���̎苖�ɂ͖{���̏��łƎv����Ï��ƁA�����Ǝv����Ï��Ƃ�1��������B���҂̊O���͂܂����������Łi��������҂������t���Ă����\��������j�A���t�����ꂾ���A�O�҂̉��t�������Ȃ̂ɑ��āA��҂̉��t�̗��́k�����̎��l�o���l4���Ɓk�C�O�̎��l�o���l5���̍L���ɂȂ��Ă���B���ꂪ������̈Ⴂ�ł���B�{�����A�悭����ƑO�҂̌�A����҂Œ�������Ă���i����͂ނ���t�ŁA��A�̂�������u���Łv�A��������Ă�������u�����v�ƌĂ�ł���̂����j�B�y2011�N7��31���NjL�F���́u���Łv�Ɓu�����v���߂��鐄���͌��ł������B�ڂ������q�g�������W�s�Õ��t�{���Z�فr�́k�NjL�l���Q�Ƃ��ꂽ���B�z������s�m���t�̃y�[�W�Ŏ����ƁA�u�A�S�ȁv�́u�A�v�i�㔪�y�[�W�j�Ɓu�����́v�́u���v�i���Z�y�[�W�j�����ɓ]�|���Ă��āA�����炭�����̃E�L�̂��߁u���v���X�y�[�X�i��Z�l�y�[�W�j�ɂȂ��Ă���B���ꂾ���ł͂Ȃ��B��Z�y�[�W�̖{���g�őS�́i���сq�ār�̑O���j����1�������A��ɏオ���Ă���i�m���u���̈ʒu���犷�Z���āA���{��̂���ł͂Ȃ��j�B�������҂ł͏C������Ă���B���������q�ār���C�������̂�����O�f�̌��������������悤�Ȃ��̂́A������͂��̂܂܂ł���i���t�y�[�W�Ɂu�[�{�v�̈�̂��鍑������}���ُ����{�k911.56-Y929y-S�l�́A��A�̏�Ԃ��猩�āu���Łv�̈�{�����A�q�ār�̌����́u�x�E�v�Ɂv�Ɩ��Ȃ��B��������Z�y�[�W�̑g�ł�1���������A��ɏオ���Ă���j�B�ł́u���Łv�͂ǂ����悤���Ȃ����̂��Ƃ����ƁA���ꂪ�����ł��Ȃ��B�{���p���́u�����v�������o���L�[�ŁA�������K�x�ɐH������ł������͂���Ȃ�ɔ��������A�m�h�̊J�����悢�B�{�����u���Łv�̎��ނŁu�����v�̖{����������悩�����̂ɁB
 �@
�@
�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�́u���Łv�i���j�Ɠ��u�����v�i�E�j�̓������J���i��Z�`���y�[�W�j
�{�W�����ɂ͋g���́q���W�E�m�I�g�r�����߂��Ă���̂ŁA�s�m���t�ɐG�ꂽ�i���������A���҂ɂ�����Ƃ��Ă���ɗD����̂�m��Ȃ��B
�u���W�w�m���x�́A���ܔ��N�̏\�ꌎ�A�����C�J����l�S�����s�B���ܘZ�N����ܔ��N�܂ł̎��\��т����^�B����㇀�|�[���E�N���[�̐H�쇁�k�i�I�E1�j�l�����C���b�N�E�K�[�f�����k�i�I�E3�j�l�����������B�ڂ��ɂƂċL�O���ׂ��������m�����k�i�C�E8�j�l�̓o�[�E�G�X�J���S�Ŕѓ��k��ƈ���ł��鎞���z����C�ɏ������B���������k�i�C�E19�j�l�͂ڂ��Ȃ�ɎЉ�ɎQ�����悤�Ǝ��݂��ŏ��̍�i�Ƃ�����B�ɒB���v�̂����߂��Ȃ�����A�܂��n���Ȃ����낤�B������s�������A�ڂ��̂��Ƃ����Ɛg�����Őg�������_���Ƃ��邵���B�剪�M�A��c�G�͗��������B���܋�N�A�l�\�Ō��������v�i�{���A��l���y�[�W�j�B
�g�������̂��Ƃ����i���o�́s���w�t1959�N4�����k����s�t�́E�Õ��E�m���t�l�j�Ɏ��W�̉���Ɓs�k�t�̒��Ԃ����ւ̈��A�������������A�ŐV���W���s�m���t���������ƂɊ��S���o����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�g�����N���k��i�сl�i�s�m���t������ԁj
�@�@1956�`58�N���\�̎��т݂̂��i�q�g�����N���k��i�сl�r�̋L�q���ꕔ���߂��j
�s�g�������W�t�́q�������сr�ɂ́A�O�f�q���W�E�m�I�g�r�̊�����i�̃��X�g�ɒlj����Ȃ���Ȃ�Ȃ��q�T�[�J�X�r�i�I�E2�j���܂ގ��т�3�тƂ����ڂ���Ă���\�\�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j�ɂ����^�B���Łs�m���t�ɕ\�����ꂽ������ԁu1956�`1958�v�̎��т́A�q�A�d�r�i�������сE6�j�������Ă��ׂĖ{�W�œǂނ��Ƃ��ł���B
��1956�i���a31�j�N 36�`37��
4���@�����i�C�E2�A16�s���A�s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N4���k3���l�j
5���@�쌀�i�C�E1�A21�s���A�s���w�t�k���w�Ёl1956�N5�����k11��6���l�j
7���@�A�d�i�������сE6�A19�s���A�s���㎍�t�k�Ώ��[�l1956�N7�����k3��6���l�j
11���@���i�C�E3�A13�s���A�s�V���W�t�k�I�̉�l1956�N11���k4���l�j
12���@�d���i�C�E4�A20�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1956�N12���k6���l�j
���̔N�k���M���s���l�@�`���i�C�E5�A11�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���j�A�~�̊G�i�C�E6�A21�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���j
��1957�i���a32�j�N 37�`38��
3���@�q���i�C�E7�A27�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1957�N3���k7���l�j
4���@�m���i�C�E8�A�X��84�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1957�N4�����k2��4���l�j
5���@�|�[���E�N���[�̐H��i�I�E1�A37�s�A�s���㎍�t�k�Ώ��[�l1957�N5�����k4��4���l�j
6���@�P���i�C�E9�A22�s���A�s�����t�k���惆���C�J�l1957�N6���k8���l�j
10���@�Ō`�i�C�E11�A24�s���A�s���㎍�t�k����p�g���A�l1957�N10�����k4��10���l�j�A���i�C�E10�A32�s�A�s�G�߁t�k�Ёl1957�N10���k11�����E7���l�j
��1958�i���a33�j�N 38�`39��
5���@���i�C�E12�A20�s���A�s���w�t�k���w�Ёl1958�N5�����k13��6���l�j
6���@����i�C�E13�A39�s�A�s���㎍�t�k����p�g���A�l1958�N6�����k5��6���l�j
7���@�����i�C�E19�A�[��189�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1958�N7�����k3��7���i22���j�l�j�A�r���i�C�E15�A29�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1958�N7���k9���l�j�A���Ƒ��i�C�E14�A21�s�A�s�G�߁t�k�Ёl1958�N7�����k11���l�j
9���@�T�[�J�X�i�I�E2�A45�s�A�s������`�t�k���z�Ёl1958�N9���k15���l
11���@���������i�C�E16�A19�s���A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���j�A�l���i�C�E17�A28�s�A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���j�A�����i�C�E18�A�U��99�s�A���W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���j
12���@���C���b�N�E�K�[�f���i�I�E3�A40�s�A�s�����t�k���惆���C�J�l1958�N12���k10���l�j
�k2019�N4��15���NjL�l
�g�����̐��a100���N�i2019�N4��15���j���L�O���āA�q�g�����S���сk���o�`�l�r�i���ш�Y �ҁj�k�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��[293]�y�[�W�l��V�K�y�[�W�Ƃ��ăA�b�v�����B�������A�{�T�C�g�ł́s�q�g�����r�����t�̈ꍀ�ڂƂ����ʒu�Â��̂��߁A�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͌f�o���Ȃ��B
���ʉ�Ƃ̐R���g�i1920-1994�j�͏��߂Ă̐��M�W�s�����������ł��t�i�R���g�A1991�N10��1���j�ł�����ӏ��A�g�����ɐG��Ă���B
�@���B�̖��a�@�Ŏ��͋g�����Ƃ����₳�����l�ɉ�����B�ނ͎����G��`���Ă����Ƃ����ƁA�����͎��l�ł������Ƃ����A����ȗ��ƂĂ��ӋC�������Ă悭�b���������B
�@�₪�Ď��͌㑗����Ė��É��ɖ߂�A���鎞���܂��ܒ����r���̏��X�ɗ������A�ӂƔނɖ{�낤�Ǝv�����B�����œ�A�O�����A�X���ɖ��B�̕a�@�֑����Ăق����ƌ����ƁA�펞���ł��̎葱�����ƂĂ��ʓ|���ƌ����B����Ƃ�����l�̏��X�����ƂĂ��D�ӓI�ȑԓx�ł��������Ă��ꂽ���A�����萔�Ȃ��Ƃł������낤�B
�@����ȗ��A���͉�W�Ȃǂ��悭�����ɂ��̓X�ɗ�����������A���̂����ޏ��Ƀf�[�g��\�����ނ悤�ɂȂ����B
�@������܂��f���ɇ��n�C���ƕԎ������Ă���A���̌�����܂苑�ۂ��ꂽ���Ƃ��Ȃ��A��������ɂ͂������̗��ꂪ�Ȃ������ς����Ă����̂ŁA�Ƃ��Ƃ��ޏ��ƌ��������A����ɂ��܂ł��肪�����A��Y���Ă���B
�@�j�ł����ł�����̐\���o�����ۂ��鎞�́A������Ƃ��̉��܂ł������Ă䂭����m�ꂸ�A�����v���Ƈ��m�I���Ƃ������t�͉���ɂȂ錾�t�Ȃ̂����Ǝv�����肷��B�i�q���n�C���Ƃ��������r�A�����A���܁`���Z�y�[�W�j
����A�g���͐R���g�ɂ��āA���L�ł��������Ă���i���n��Ŕԍ���U��j�B
�D�@�k���a�O�\�l�N�l�\���\�O���@���{����R���g�㋞����B�~�тłƂB�Ƃɂ�Ă��ėz�q�Љ�B�ꕔ���Ȃ̂ŏx�䑑�ɏh���Ƃ蔑�߂�B�i�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j
�E�@�k���a�O�\�ܔN�l�Z���ܓ��@�������Β�A�哿�����@�̒�����A�L�����։����ӕ�F�ƑΛ�����B�ێ��A�V�����A���R������Ĕ���B��A���{�̐R���g�̉Ƃ֔���B
�k���l�Z�������@�j���{���ς�B�����傫�ȏ�q�ƍ���B����ۓI���B���֏o�A�@�P�������̂ʂꂽ�Ε��ƍ����B���{�֖߂��q������삿���Ƃ��悤�Ȃ�B��s��Ԃɂ̂�B�i���O�A���l�y�[�W�j
�R�͗c���E������琭�g�ɉ������Ă��邩��A���L�́u�R����v�ɒ��ڂ���ƁA
�@�@�k���l�Z�N�l�O���O�\����i���j�j�@�ߌ�A�����N�Ə��̓��{���p�W���ςɍs���B���{��̊�킷����̂ɋ����B���M�s�ʂ̐R����̊G��������B�������ŏZ�������B�i�q���L�@���l�Z�N�r�A�s�邵����t6���A1990�A�O�O�y�[�W�j
�C �@�k���a��\�l�N�l�\���\����@����I�����������˂ď��ւ䂭�B���R�A��I����I�̒��ɐR����̊G�����A�������ŏZ�����B���F�̌R���a�@�Œ��悭�邵����J���̐������v���o�����B���P�Ƃԏt���B�i�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j
�R�̐��M�Ɠ������Ƃ�������Ă��邪�A��l���R���a�@�ɂ������R�͏o�Ă��Ȃ��B����Ɂs�y���F��t�i�}�����[�A1987�j�́u���s�ցu�o���`���X�W�v���A�y���F�Ɗςɍs����������A��K�͂ȁu�S�֓W�v���Â����ƁA���{�ݏZ�̋����F�l���畷���Ă����v�i�����A���l�y�[�W�j�̋��F�͐R�ɈႢ�Ȃ��B���̂Ƃ��g���́A�u�����s����A��������̓y����U�킸�Ɂu���͂ЂƂ�ł����s�֍s�����Ƃɂ��߂�v�i���O�A���܃y�[�W�j�ƋL���Ă��邾���ŁA�R�Ƃ�������ɕx���S�֓W���ς����ǂ����͂킩��Ȃ��B�����R���g�i����j�ɒ��ڂ���̂́A�g�����s�Õ��t���܂Ƃ߂�Ɏ��鎞���ɂ��̑��݂��傫�������̂ł͂Ȃ����ƍl���邩��ł���B��̋g���͂��̎��̌`���ɂ������đ����̊G��i�������͑��^�j��i����[�����Ă��邪�A�����ʼn�Ƃ̑��݂������ł��Ȃ��B�̂��s�Õ��t���������낵���������g�c���j�Ɠ������Ă������Ƃ͋g�����G��Ă��邪�A�R�̑��݂���i�̐����Ɗ֘A�����ď��������Ƃ͂Ȃ��B���L�C�̂����O�ɂ͎��̋L�ڂ�����B
�A�@�k���a��\�l�N�l��������@����ꏊ�ɂ��闑�قǂ��т������̂͂Ȃ��悤�ȋC������B���ꂩ��o���邩����q���r�����ɂ������т������Ă݂����Ǝv���B�i�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1968�A���Z�y�[�W�j
�B�@�k���l�����\����@�l����|�[���E�N���[�̊G�̂���q�݂Â�r�����B���n�̑f�p�Ȗ��Ɨ҂����̒ꂩ����݂ł�R��B��߂����m�����ތ��z�̌����ȁB�d���̂����܁A�܂��˂ǂ��̒��Ń|�[���E�N���[�̊G���݂���A�]�`����ށB�N���[�̂悤�Ȏ������������Ǝv�����B�i���O�j
���������S������Ă��������A�d���̊W�ł��낤���A�g���́u����I�����������˂ď��ւ䂭�v�B��I��͒��삪�F�J��ꂽ���ƌ��������c�̂�����A���܂��܂��̓W����Łu�R����̊G�����v���̂��낤�B�푈���I�����4�N�B�g���͂��łɁA���m���ōK�c���F�̖���c���j�s���ޔ_����b�t�A�J���Z�Y�̒��і����̕ҏW��S�����Ă����B�����͂���Ȃ�Ɉ��肵�āA����ĊJ�̈ӗ~���V�܂��Ă��������ł���B���N�t�A�֍��Y�E�c�K�t���E�r�c�s�F��ƂƂ��ɂ����~�̐��ւ̋�s���Ō�ɁA�e�����o�咇�ԂƂ�����i���̂��������t���͂ǂ����Ă����̂��낤�H�j�A����͎��������Ă��������ƌ��ӂ��Ă���B�N��l������炤�F���Ȃ���ԂŎ�������݂���i�̑薼�́A�Õ��ɂ��q�����r�B�g���͂ł�������̎��т̎ʂ������s�i�������͐��{�j�̐R����ɑ����Ă���B�펞���̖��F�Ō݂��ɉ�ƂƎ��l�Ɩ���肠���Ĉȗ��̋��F�ɁB
�q�����r�i�����\���сj�F11�s�i�����ɂ��10�s�j�B�����Ɂu�q��l�A��A��\�r�v�A�ے������Łu28�v�i�ʂɔ����ے������Łu45�v�j�A����Ɂu�i����֓�l�A�\�A��\����j�v�A�ے������Łu�\�܁v�Ƃ���A1949�N9��20���E�e�ƌ�����B����u���Ȃт��^�̂����͂��ꂳ����v���q���i�r�i�B�E10�j�ɗ��p����Ă���B���ёS�̂ɑ傫���u�~�v���t����Ă���B
�q�ہ[��E����[�̉́q���͐�̃J���o�X�r�r�i�����\���сj�F20�s�B�����Ɂu�q��l�A��A��O�r�v�A�ے������Łu29�v�i�ʂɔ����ے������Łu46�v�j�A����Ɋے������Łu�\�Z�v�Ƃ���B1949�N9��23���E�e�ƌ�����B
�\�\�����炭���a24�i1949�j�N�̏t�ɋg�����C�����V���Ɏ��������͂��߂Ă��甼�N�A�@�A�A�A�c�Ɗے������Ŕԍ���t����29�т��a�����Ă����B���̌�̂��鎞�_�i�s�Õ��t�ҏW�̑O�i�K���j�Ŏ�̑I�����s�Ȃ�ꂽ���ʁA���2�т��܂ޏ\�Z�т��̂��A13�т��̂Ă�ꂽ�B�q�����r�͍̂�ꂽ�\�Z�т̂ЂƂ����A���̌�i�����炭�ŔӔN�Ɂj�A��i�Ƃ��Ă͖�������ӎu�������ꂽ�B�ɂ�������炸�A���e���̂��͈̂₳�ꂽ�I�@���������s�Õ��t�Ɏn�܂���g�������̊J蓂��L�O���邩�̂悤�ɁB���邢�́u�i����֓�l�A�\�A��\����j�v�Ƃ��郁���䂦�ɁB�\�\�Ǝ��͑z������B
�R�̐��M�W�s�����������ł��t�̎d�l�́A���O�~��l���~�����[�g���E����y�[�W�i���G�Ɍ����t�\���j�E�㐻�p�\���i���E�w�Ƃ��z�j�E�@�B���B����500���B�ʐ^������킩��Ƃ���A�{�����g���́s��ʁt�i����R�c�A1983�j�܂��Ă��邱�Ƃ́\�\�Ƃ�킯���̓\���ӂƌp�\���ɂ����ā\�\���炩�ł���B�s��ʁt��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��R�́A��F�E�g���ɑ���Ǔ��̈ӂł��낤���B
 �@
�@ �@
�@
�R���g�s�����������ł��t�i�R���g�A1991�N10��1���j�̔��ƕ\���i���j�Ƌg�����s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j�̔��ƕ\���i���j�A�g�����R�Ɉ��Ă��s��ʁt�̏����p�J�[�h�i�E�j
�k2009�N3��31���NjL�l
�{�e�����ǂ݂����������R���g�̂��q����쎁����A���a24�i1949�j�N�����̐��g�̋��Z�n�ɂ��ă��[�������傤���������B���݁A�ł��ڍׂȁq�R���g�N���r�ɂ́u1948�N�i���a23�N�j28�@���s�s���G����w�Z�𑲋Ɓ^1950�N�i���a25�N�j30�@���Ɍ��������i�����{�s���j���k���w�Z���p�����ƂȂ�v�i�R���g��i�W�s���t�S�i�t�A�R���A�k2000�l�A��Z���y�[�W�j�Ƃ����āA���a24�N�̏H�ǂ��ɏZ��ł�������|����ɂȂ�L�ڂ͂Ȃ��B��쎁�́A�������g�͂��łɌ������Ă��āA������q���a�����Ă���A���s���R�ɂ��������Ƃ̓V�Ղ痿���u�~���v�߂��̐�N���ɉ��h���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ɛ������Ă���B�g�����́q�D���Ȃ��̐������r�Ɂu���s������ł���_���A�n���̗��̂�����̗[�܂���v�i�}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t90���A1968�N7��31���j�ƋL�����悤�ɁA���̒����������D��ł�������A���s�ɂ�������ƐR����ɐV��̎��e�𑗂邱�Ƃ͂����₩�Ȋ�т��������낤�B
�k2018�N12��31���NjL�l
�g�������R���g�ɑ��������W�s��ʁt�ɓY�t����Ă������낤�����p�J�[�h�i�V�n��Z��~���E����~�����[�g���j���I�[�N�V�����ŗ��D�����̂ŁA�ʐ^���f����B�Ȃ��J�[�h�̗��ʂ́A�g���̎��M�ɂȂ鎍�W���s�̈ē��B2008�N10��31���̖{���̖����ɁA�R���g������u�s��ʁt��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��v�Ə��������A�����p�J�[�h�̏o���ł��ꂪ���t����ꂽ�B
�s�� �㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�̖ڎ��͕ʒ��ω��܂�̒��ʂ����A���̊O�ʂ͋g�����̏ё��ƕM�Ղ̎ʐ^�ō\������Ă���B�M�Ղɂ͖ѕM�ɂ��q�g�����̏��r ��3�_�܂܂�Ă��āA�����ɂ͂����̂ق����G��1�_�A�{������1�_�̌v5�_�A�g���̏��̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B�����ɔԍ���t���ĕ����ɋN�����Ă݂� �i���s�́^�ŕ\�������j�B
�� �̂����g�����̎��т́A1���q���\�\���̓��B�N�g���[�r�i�E�E8�j�̖`���A3���q���r�i�B�E7�j�̑S���A4���q���̏ё��r�i�B�E16�j��1�߂̑S���ŁA�� ���͉��s�ӏ�������e�����������̂́i�s�̓r���Ő܂�Ԃ����Ƃ���������߂��j�A����Ɉٓ��͂Ȃ��A����̎���ѕM�ŏ������D���B2��5�͎���� �Ȃ����A2�ɂ��Ă͌�q����B5�Ɋւ��ẮA�i�c�k�߂��q�g������̏��\�\�Ǔ��ɂ����ār�i���o�́s�Ս��t1990�N7�����j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@ �f��̈��s��J�̖�̐������ȁt�́A���a�Z�\��N�l���ɉ��ώɂ��甭�s�̋�W�A�w�K���x�Ɏ��߂Ă���A���́s�t�̋��̂Ȃ��ł��A�����[�����X�Ȉ� ��i�i��_���ɋ�����ł���B���N�Z���\���ɁA���Ɍ�����قōÂ����ꂽ�s�Ď��i�c�k�߂̓��t�́A����Y���̕����s���@�t��������āA�Q��҈ꓯ�� �H���̋��ɗ��ܓI���ق�U�����H�L�̈�ۂ͖Y���B���������s�L���t�ɁA���͌f��̋g��������̊��|����������̂ł���B�ꖇ�����荗�a���S��31�Z�� �`�~43�Z���`��̎����̕����ɁA���̎��l�̍����I�Ȑe�ؐS�����݂��߂Ȃ���A���͂��̏j�ӂɗ܂����̂ł������B�k�c�c�l
�@�Ƃ���Ōf��̋g������̏������A�I�قz�����A�Ђ����猵�l�f�p�ȁA���Ƃ������C���ł��낤�B���ꌾ�ŁA�g������́s�l���t���@���Ă����Ȃ� �A�s���`�t�̓����A���ɓK�Ȍ��t�͌�����Ȃ��̂��B���͂��̈�t���Q[����]�ĂĎ��o���āA���܂Ŏ��ǂ����߂Ă����z���ɁA�^�g�̖��|���� �}�b�g�ɔ[�߁A���ւ̎��̍e�Ɨp�̊��̐^���̕ǂɌf�����B�i�O�f���A����y�[�W�j
�s��
�㎍�ǖ{�t�̓�ܔ��y�[�W�ɂ�5���V�n70�~���E50�~�����[�g���̎ʐ^�Ōf�����Ă��邩��A�������L���@�Ɋg�債�čk�߂�����
�悤�Ɋz������A�g
�����̏��̕��͋C�𖡂키���Ƃ͂ł��邾�낤�B�������A���������ŏd���������͍̂k�߂ɂ��q�NjL�r�̇C�̈�߂ł���B
�u���̂������̓��L�̏��X�ŏo����ڂ��ׂ�����������B����͂��̎��l���A���̎���ɁA�悸�s���m�t�ɓ��菕��I�Ȏd���ɏA���Ă������Ƃł���B�m����
����菭�N�����ŁA�ނ�̏K�������ĉ���Ƀ}�����Ă�����肵�āA�ނ�ɐe���܂�čs�������ƂȂǁB�������Ď��l���g����K��Տ��Ȃǂ��C���Ȃ���A
�����������u��K�v�ɏ����𓊂��ās�܂��ŁA���X�ꋉ�ɏ��i���Ȃ��t�ƋL���Ă��鏈���ʔ����ǂ߂��B���̑O�Ɂs�K���ɖv�����t�Ƃ����Z�͂�����������
�肷��v�i���O�A��܋�y�[�W�j�B
�k�߂��g���̏��ɐG���ȏ�A�s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j�Ɍ��y����͕̂K�R�����A�k�߂̎w�E�ǂ���A�g���̏��̍��@�͂��̏��m�ł̏��莞
��ɔ|��ꂽ���̂Ǝv�����i�{�e�������s���܂�͂����L�t�ɂ�����
���Ɋւ���L�q��E
���āA��̒���t�����j�B
���āA2�́u�Ώ�͉Ԍ�^���U�����t�v�ł���B����́u�̏�ɉԂ��͂��Č�A���U�������炱��t�v�Ƃ����T��ŁA�i�n�ɑ��Y�i1923-96�j���D���
���|�����i�s�T�������t1999�N12��15���������A�s�i�n�ɑ��Y����̎莆�\�\�w�X�����䂭�x�̗F�l�����ցt�A�����V���ЁA�q�����O���r�A�r�k��O
�y�[�W�l�Q�Ɓj�B�i�n�̏����C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂�ƁA�����炦�ނ��Ɂq���[��Ï����D��2008
�����ÓT��r�Ɂu�i�n�ɑ��Y���z�^�Ώ�͉Ԍ�c�^��ʁ^���D�Œቿ�i�F
15�v�Ƃ��Ď��̉摜���f�ڂ���Ă����B��������������A�g�����̏��ƕ��ׂĂ݂悤�B
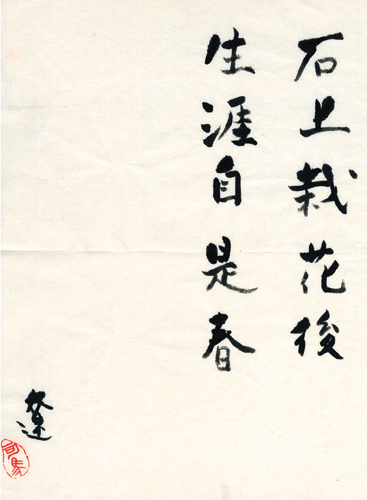 �@
�@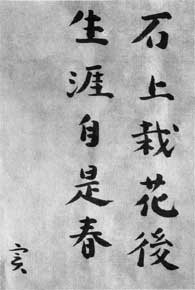
�i�n�ɑ��Y���z�k�o�T�F�q���[��Ï����D��2008 �����ÓT��r�l�i���j�Ƌg�������k�o�T�F�s��
�㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�A�v���ЁA1991�l�i�E�j
�o ���Ƃ��������ꂽ�̂��킩��Ȃ����A���������ǂ��炩���ǂ��炩�����ď��������̂悤�Ɏ��Ă���i�Ƃ�킯�u�́v�̎��j�B����Ƃ��A������{��Տ����� ���ʂ��낤���B�g���̏����Ԃ�́A3�E4�E5�Ƃ���قLj���Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�i�n�̕��́A�ΐ��k�s������100�l�̎��k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA 1998�j�܈�y�[�W�Ɏ��ڂ̃��[�����X�ȁu�N�q�L���v�Ƃ͂����Ԃ����Č�����B���́u���v�Ƃ��́u�U�v�̂����͂قƂ�Ǔ��������A�u�v�̑��� �́u�y�������ɓ���݂����Ă���v�i�����A�܁Z�y�[�W�j����������ɏ��̎p�����\���������߂ɁA�ӂ���̊��|���痣��Ă��܂����悤���B�ꌩ����Ǝi�n �́u�z���̏��v�i�����A�l��y�[�W�j�Ɍ����Ȃ��̂́A�������T��Ƃ����āA���i�����݂𐳂��ĕM�����������Ƃɂ��̂��B�Ƃ���ŁA�u�Ώ�͉Ԍ�c�v�� �܂ޏ�f�̋g���̏��ɂ͂ǂ���悳��Ă��Ȃ��B�g�����g��⽍������݂Ȃ�������������Ȃ����A�������L���Ă��Ȃ������͂��͂Ȃ��̂ɁB�s�����G�߁t ��s�t�́t�̉��t�ɓ悳�ꂽ�u�g�����v�̔�����i����Ƃ��������������j����Ŏ���ꂽ�Ƃ��Ă��A�X�c����͋g���Ɏ����̈�����Ɓq�ւ̎��Ӂr �i�s�����ցk���t���Ɂl�t�A���Y�t�H�A1995�A�ꔪ�Z�y�[�W�Q�Ɓj�ɏ����Ă��邵�A�g���ɉ������������l�������͂����B�g���́s�u�����v�Ƃ����G�k�� ��Łl�t�i�}�����[�A1988�j�ł�⽍��͂������A���ɂ��ĂقƂ�nj���Ă��Ȃ��B�����ċ�����A�ȉ���9�т����ւ̌��y�̌����镶�͂ƌ����悤 ���B
�����ŁA�s�g���������s�U���W�t���� ���Y�ӏ��������āA���ɑ���g���̍l�����T�ς��Ă� �悤�i���p���ŏ����ɂ��邽�߁A�O��̕��͂������������̂����邪�A���p�����ŏȗ������ꍇ�̂݁k�c�c�l�ƒ����ł��邱�Ƃ�\�������j�B
�i1�j��o���\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t163���i1963�N5��1���j
����Ət�炵���Ȃ�܂����B�����C�ŏ���̎d���ɐ��i����Ă��邱�ƂƎ@���܂��B���������k�߂̏����~�����Ǝv���Ă��܂��������肢����̂�������
�����Ǝv���Ă��܂Ă��܂����B���̓W������Â����Ƃ́u�Ս��v�Œm���Ă��܂������A�Ђ��Ă��������Ȃ����낤�Ƃ�����߂Ă����Ƃ������㉇����ɂ�
��Ώ���i����ɓ���Ƃ̂��Ƒ����\���݂܂����B�{���Ȃ珑��W�ɎQ��S�䂭�܂łɖn�ւ������Ɍ������̂ł����d���̂��ߍs���܂���B���炵����ł���
�܂��悤�ɁB
�i2�j��o���\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t166���i1963�N8��1���j
�@�J���ЂƂ₷�݁A������A�O���Ă炵���Ȃ�܂����B��T�̓��j���A�Q���̂Ȃ��ŁA�M�d�ȏ���i�q�܂����B���炵���n�ցA�߂Â��Č��A���������Č�
�Ă��̂���ł���܂��B�K���ȑ傫���Ȃ̂��A���������Ȃ̂łƂĂ�����悢�̂ł��B�����A���o�ɂ��炵�����Ȃ��̂ŁA���I�̒��ɑ����Ă��܂��B�k�߂���
�̖{�ӂɂ��ނ��s�ׂƂ͒m��Ȃ���B�Ԏ��������ꂽ���Ƃ�����т��܂��B
�Z���\������
�@�ǐL�B
�@��A���������䐷������̂ł��傤�B�Q��Ȃ������̂��c�O�Ɏv���܂��B���čŋ߁A��{���g����A�r�߂����
�@�S���ɍ�������̉Ԃ�����
�̒Z�����������܂����B�܂������\�グ�ĂȂ��̂ŁA����ɂ��莆�������܂��B
�i3�j�D���Ȃ��̐������@�}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t90���i1968�N7��
31���j�q���̍D���Ȃ��́r
�@���b�L���E�A�u���W�b�g�E�o���h�[�A���Ƃ��ӁA�f��A���F�A����ׂ��A�y���F�̕����A���炱�A�����A�̂�A���\�Y�̃e���g�ŋ��A���哴�A�L�����݂̂�
���A�����A�a�J�{�v��̓g�b�v�̃R�[�q�[�B�k�c�c�l�n�Ղ��݂�̂����̂����B�k�߂̏��B�k�c�c�l�����B
�i4�j���L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�́@�s�Ս��t235���i1969�N11��1���j
�Z���\�O���@�I�ɍ����T�����ŁA�n�đO�̂�������������S�����Ɖ�B�k�ߓW�̂��߂̂�������҂ɂȂ��Ē����ׂ��B�����Ƃ��ċ�W�A���̎ʐ^���݂���B
�q�����r�̓��݂āA����͖{�����A�������̂������Ă��ꂽ�\�\������B�ق��Ƃ��Ĕ��\���ŃR�[�q�[���̂ށB�[���B
�����\�����@���z�e���ōk�߂���Ɖ�B�V���ł������̂�������ƕʂ�A�k�Y�a�̊C���ւ䂭�B���B�A���C�A���O���̏��Ȃnj����Ă��������B�����߂�
�ƌ{���̂Ђ�߂��B�k�߂���͒��N�̑f�p�ȉԂ̊G�ɐ���������B������̂��_�O�̒����i���Ĉꍏ�A�`���I�ȉ��R�J�̈ꕝ��q���B���̑O�ɂЂ������k�߁A
�����Ƃ��ɕ�R�A�����ƂȂ�B�h��∤�̐_�i�Ƃ����B�S���C�B��b���̎����ԂŐ_�c�֖߂�B���؈�v�̓��ۂ��݂₰�ɁB
�i5�j�t�䏑���\�\�i�c�k�߈��@�s�Ս��t300���i1975�N11��10���j
���āA�����̏���ȁu�莆�Ƌ叴�v���Œ����Č��h�ł��B����A�܂��n�ӈ�l�N�������A�u�s���v�̊z�������Ă��Ă���܂����B���̍��h�̔��������̊z
�ɁA�����k�ߏ������A���ւɌ����܂�����A���܂܂ŏ����Ă������A�A�o�e�B�̐F�ʓ��ʼn�Ǝ����ς��āA���������͋C�ɂȂ�܂����B
�i6�j�������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t351���i1980�N7��1���j
�@�P���̉�ɎQ���ł��Ă悩�����Ǝv���܂�[�B]�S�̂��������f��������[�ł����B����ɁA����W���������܂����B�_�˂Ƃ����y�n�ɂ��e���݂��o���A�܂�
�Q�肽���Ȃ�܂����B�o������A���̏H�ɂł��A�k�߂���̂���ɎQ��A�납�̊G����ɂ��������̂ł��B
�i7�j���q�Ǔ��@�s�Q�t1981�N6�E7�����i1981�N6��28���j
�@���q�Ɠ�x�ڂɉ�����̂́A��W�w�Ή؏W�x�̏o�ŋL�O��̎��ł������B�k�c�c�l�킸���ȂЂƂƂ��A�ނ́u���v���Ƃ���ǂ���ɏ���ꂽ�A���r�[�̂悤��
���ŁA���ɏA�Č�荇�������炢�������B
�@��N�̏t�A�i�c�k�ߎP���̉�_�˂̘Z�b���ōÂ��ꂽ�B��́A�O�{�̂ǂ��Ƃ����X�ŁA�S�S��s�I�Ȗ邾�����B�������ēc���Ŋς��u�����v�̑�
���������Ă���Ƃ����A�o�[���Ԃ�ցA�܁A�Z�l�̐����Ɩ�̊X�����܂悢�s�����B�����ɁA�����������������q�������B���ꂪ�O�x�ڂ̏o�����ł���A
�Ō�ł������B�u�����v�̓́A���̐���������̂ł͂Ȃ������B
�@�k�c�c�l
�@��A�O�N�O�ɁA�莆�Ɣ�����菭���傫�ڂ̘a���ɁA���M�������̂������B�u�嗋�J�T���Ɖ�ӂ����̖��v�̈��ł������B
�i8�j�A���P�[�g�u�����āA�W���P���́c�c�v�@�s�i�فt4���i1983�N10��20���j�q����
�٘^�a�r
�i�c�k�߂́u�����}�v���A���Ԃ̕ǂɊ|����B����܂ł́A���̎����ɋ}�������A�킪�F�����d�M�𓉂݁u���^���͂́^�C�Ɓ^��䮂̉ԁv�̐��M���f���Ă���
���B�b���q��A�R���v��A�₷�炩�ɐ�������B
�i9�j�N���@�s����̎��l�P�@�g�����t�i1984�N1��20���A�������_�Њ��j
�@���a���N�@���O��N �\�O�@
�{���������w�Z�ɓ��w�B����`�̓�������X���̎l�������ֈڂ�B��K�ɐ�Z�̍��������i���Ɩ����q�j�̉e���ŁA���w�ɐe���ށB
�@���a�\�l�N�@���O��N ��\�@
�d���ɋ^��������A��R����ގЁB�����F���m�i������j�։������A�q�������ɏK����������B�{��������Œ�����������B
�@���a�\�ܔN�@��㔪�Z�N �Z�\��@
�āA�k�c�c�l�O�z�{�X�ŁA�NJ��W���ς�B�V��啗�B
�@���a�\���N�@��㔪�O�N �Z�\�l�@
���āA�������������قŁu�O�@��t�Ɩ������p�W�v���ς�B���哶�q�����i���������j�̘Z��ɖ�������B
�i10�j�t��������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t397���i1984�N9��1���j
���̓x�̓c���K�₩�炾���ԓ��������A���܂��남���\���グ��̂��A�C���Ђ��܂��B�ǂ����������������B�y���F������O����ʂ��āA���ł���܂�
���B�k�c�c�l�{���́A�k�߂���Ƃ�����肨�b�������������̂ł����A�y�����Ⴂ�F�l���l���A�h�ɑ҂����Ă������̂ł�����B�����Ȃ��炠�̏��ւ͂�
�났�܂��B���ւ́u�ԍg�v�̓́A�f�������Ǝv���܂����B
�i11�j�i�c�k�ߏ���W�s���t����W�@�s�Ս��t417���i1986�N7��1���j����q�i�c�k��
����W�E���@����W�q���r�r
���̂��сA�����ȁw�i�c�k�ߏ���W�E���x���o���܂������Ƃ��A���j���\�グ�܂��B�悸�Ȃɂ������������Ƃ́A���������́u�s���v���ŏ��Ɍf�ڂ���Ă���
����ł��B���h�Ƃ����Ă͖��ł����A���ł��܂��B�u�����v�̖��i��_�����܂��k�ߗl�̎茳�ɂ���̂�m��A���S�������܂����B��i�Ə����҂����т���
���̂��݁A����ƑI�ꂽ�k�ߗl�̂���S���������肵�Ă���܂��B���R�Ȃ���A�����ҕs���ŁA���X�̏G�삪����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�́A�c����
�����Ă����A����Ȑԋ��A���ꂪ�Ȃ��͎̂c�O�ł��B��������ԂɐS�䂩�ꂽ�̂́A�u�H�ɏ��_���v�ł��B�傫�����킩��܂��A�V�n�����ς��ɑ��݂��Ă�
��悤�Ɍ����܂��B�������q����鑠�Ƃ����̂��A�߂ł������Ƃł��B�{���ɂ���Ԃ����Ă��̂���ł���܂��B
�i12�j�t��������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t422���i1987�N1��1���j
���̂��т͂��莆�ƍk�ߒZ����q�Ċ����������܂����B�S�����l�̊���������ꂽ�Ƃ̂��ƁA�܂��Ȃ�Ɣ�������������ꂽ���Ƃł��傤���B�ō��̂�
���{���Ǝv���܂����B���āA�������Z���ɂ́A�s�ł̖���u�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�v�����M����Ă���A�i���X�D���̏����ɂ͉����̂��̂ł��B���Ă�
�P���̉�̐܂ɒ������Z���̕M�����A��x�I�ł���Ȃ�A����ɂ͔��B�̕��C�������܂��B�����ɁA�����Ε��̘e�ɒu���āA���X���߂Ă���܂��B�{���ɂ���
���Ƃ������܂��B
�i13�j�_�K�o�W�W���M�a����A���悤�Ȃ��@�s�����C�J�t1987�N7�����i1987�N7��1
���j�q�Ǔ��������V�g�r
�@���a�l�\���N�̓~�A�����炭���߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���鍂���V�g����W�����{���̖���L�ōÂ���Ă��܂��B�����āA��c�j�Y�ƈꏏ�ɁA���̐ق��F�����]
���o�i�������܂����B���̐܂萅�n��́u�H�����v��Ђ��Ė�����̂ł����A����͉��l�̈����ӂ�����i���ƌ�Œm��܂����B
�i14�j�t��������\�\�i�c�k�߈����ȁ@�s�Ս��t428���i1987�N7��1���j
���莆�ɂ��ƁA�����̒t�قȕM�ɂȂ�u�K���\���v���A���Œ������ꂵ���v���܂��B���̂����A���h�Ȋz�ɓ�����A�c���̈���ɁA����ꂽ�Ƃ̂�
�ƁA�ʉf�䂢����ł��B�q�����܂����A�Ñ㉩�y�痿�ōʂ�ꂽ���ȕ����܁B�����ɂ͂Ȃ����A���q�̂悤�Ɍ����܂��B�ނ����l�l���瑡��ꂽ�A�Ñ�
�����ꂽ�z�ɂ҂���������āA�����Ε��̂킫�ɒ������Ă���܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂��B�������̂ŁA�u�i�c�k�߂̓��v����A���x��P���ɂȂ��
���ˁB�����������Ƃꂽ���ƂƎv���܂��B����A�k�ߓƉ��Ƒ���Y�ƕ����A�����ł����B
�g
�����̖����̎U���ɉi�c�k�߈��Ă̏��Ȃ��������߂���ł͂Ȃ��낤���A�k�߁i1900-97�j�⍂���d�M�i1923-83�j�A�Ԕ����q�i1925-
81�j�Ƃ�����������̔o�l�̏��ւ̌��y���唼�Ȃ̂ɋ��������B�ق��ɂ͋�C�k�O�@��t�l�i774-835�j�A���댘�k���R�J�l�i1045-
1105�j�A��x�i1394-1481�j�A���d�k���O���l�i1497-1573�j�A���B�i1685-1768�j�A�NJ��i1758-1831�j�A������b
�k�������C�l�i1828-1905�j�A�����V�g�i1901-87�j�A��c�j�Y�i1914-90�j���o�ꂷ��B�܂��A��f�i14�j�ƍk�߂́q�g������̏��r
��Δ䂳���Ă݂�Ƌ����[���B�i14�j�Ɠ������ɂ͋g���̑I��q�k�߁��K��
�\���r�������Ōf�ڂ���Ă��āA��l�傪�u��J�̖�̐������ȁv�ł���A�攪�傪�u�T�L��܂��o�ė������˂̉ԁv�����炾�B���O�q���Ƃ̈��L��
�i1916-85�j�𓉂k�߂̋���A�g���͂ǂ�Ȏ�ŏ������̂��B�����̎苖�ɂ͋��q��҂ɂ��i�c�k�ߏ����i�W�s�D�t�i�i�c�k�߂̉�A
1999�j������B�u�k�c�c�l����A�k�ߐ��a�S�N���L�O����Ӗ��ŁA�O����W�u���v�̂قƂ�ǂ̍�i���Ę^���A����Ȍ�̍�i�Ə����K�쎞��̍�i����
���A�k�ߏ�������قږԗ��ł���`�ŕҏW�����v�i�����A��l���y�[�W�j�ƕҎ҂��q��L�r�ɏ����悤�ɁA�s�D�t�͉i�c�k�ߑS����W�̎�������Ă���i���Ȃ�
�ɁA�k�߂̂قƂ�ǂ̏���ɂ́u�c���v�̎镶�悳��Ă���j�B�s���̂���������������Ă����t�i����R�c�A1996�j�Ɂq�����}�r���ڂ��Ă���悤
�ɁA�g���������̍�i���{���Ɋ܂܂�Ă���̂��낤���A�����͐S�Â��Ƀy�[�W���J��ɂ����͂Ȃ��B
�g�����͏��̌W���J�������Ƃ��Ȃ��A���̏����L���m���Ă���Ƃ������������i�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��A�������F���u�~
�̓��̋Â�^���ׂȂ�ւ̖e�v���X�䏑�X����o�i����Ă�����x���j�B�����A����������g���́u���v��������̂́A���̑����ɂ����Ăł���B�ΐ��k
�́u�k���́l��̂́A�����������i�n��[���݂���]�j�̑��ɂł͂Ȃ��A�n��[���݂���]�ɂ���Ďp��ς���ꂽ���A�܂�͗]���̑��ɂ���A���̖n�ՂƗ]
���Ƃ̋��E�ł���u��[����]�v���A�����ʂ�u�ۗ��v����ł���B�k�c�c�l���������ɂ��炳���u�ہv���A�\���ł���J�o�[�ł��葢�{�ł���B���̈�
���ł͑�����܂������ɂ�������́u���v�ł���ƌ�����̂ł���v�i�s�����w�ԁ\�\�Z�@�Ǝ��H�k�����ܐV���l�t�A�}�����[�A1997�N4��20���A���
�Z�y�[�W�j�Ɗ��j�������A���́u�ہv�Ə����̊W�́A�Ƃ�킯�g�������ɂ����ē��Ă͂܂�悤�Ɏv����B�u�ۗ����v�̗L�����A�g����������}�S�̋g����
�������番�����Ă���̂��B�g���̑����Ə��Ђ̐V���L���u�O���v�̊֘A���w�E�����P�c�����́A�g���̏��ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�g�������|�����M�Ղ�����ƁA�܂��ɏ��N���������悤�ȗ��V�Ȟ����ŏ�����Ă���i���łȂ���A�g���͏\��̂���A����m�̎�`���Ŏq�ǂ������ɏK
���������Ă����j�B�����j�I�ɂ݂�A�����̊������ł���A�����̉���������Ղ�̂�����邻��ł͂Ȃ��A����ȑO�̏��̂Ƃ��Ă̐������ɂ����鎞
��̌��N�I�Ȃ�������f�i��������̂ł���B�M�ՂقǏ�����̐l�ƂȂ�𐳒��ɉf���o���̂��̂͂Ȃ��B���̕M�ՂƓ��l�ɁA�g���̑���͐܂�ڐ������u����
�̍�@�v�Ɋт���Ă���̂��v�i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A���܃y�[�W�j�B
�P�c����͏���ʂ��ċg�����́u����p�v�i���O�j������Ă���킯�����A���͂���ɉ����āu���Ɣo��v�̑��݂������������Ǝv���B��㺔V�i307?-
365?�j�ӂ��̞����̕M�Ղ��āA�u�������Ɓ��n�邱�Ɓv�Ƃ������_���g�����l�������ł��낤���Ƃ��B�g���͍����ł������w���̂���A�̂��́u���Ɓv
�����t�˂ɂ���ĕ��w�ɊJ�Ⴕ�A�����̓�R����ޓX���Ă���́A1�N4�����قǍ����̖����F���m�i�ނ������܂��傶�キ�A�Ɠǂނ̂��낤�j����`���A�c
�K�t���⍲����ƂƂ��ɋ��ɗ�B����A�Z�̂͂܂������̓Ɗw�ł���B���Ƃقǂ��悤�ɁA�g���́u���v�́u�o��v�ƂƂ��ɂ������B�g�����̕\���s�ׂ�
�u�����o��v�Ɓu���i�Z�́j�v�Ɓu�����v�̎O�ʈ�̂Ƃ��ĂƂ炦�Ȃ������Ƃɂ���āA���܂ł́u���v�Ɓu�����v�̓Η�����͌����Ȃ��������̂�������
���Ȃ����낤���B
�s���܂�͂����L�t�ɂ����鏑�Ɋւ���L�q�i���j
�����a13�N�i1938�j
9��5���y���z�@�k�y�@�z���̗j���͕]�҂ɂ���L�l
��������������������̉Ƃɐg����B�k�c�c�l�C�܂܂ɕ�
�����Ȃ���A���m����`�����ƂɂȂ����B
11��14���y���z
�m�ɗ��鏗�̎q�ɁA���߂̂���́u���Z����v�ƌ���ꂽ�B�j�̎q�ɂ͂����������Ɏv��ꂽ�B�₪�ďK���Ɏ�M�����A�Â���ۂ����Ă��ƁA�u��
���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�ߌォ��[���܂łɁA��S�l�ʗ���悤���B
�����a14�N�i1939�j
4��18���i�Ηj�j
������A�ۑ�̔����Z���̐����������B
5��2���y�z
����Տ��B
5��10���y���z
�[���A�t�˂���i�����j������t�m�搶�̂Ƃ���ցB�k�c�c�l
��A褚������Տ��B
5��18���y�z
���z�m��Տ��B
5��31���y���z
��A�K���ɖv���B
6��22���y�z
�[���܂Ŏq�������̏K�����݂�B�k�c�c�l��A�u�㐬�{�Ґ���v��
�Տ�����B
7��14���y���z
���A�T�̓�����߂�A�Տ��ɂ͂��ށB
8��7���y���z
�u���M����v�ɁA�킪��i���f�o����Ă���B�덆�u���ہv��
�Ȃ��Ă����B
8��25���y���z
��x���A�ᒠ�ɓ����ĐQ�Ȃ���A�t�˂���Ƙb�������B������������m�䂦�A���̉Ƃ��o���ق����悢���낤�B���̋���Ȃ̂�����B�F����ɂ��悤��
�v���B
11��1���y���z
��A���k�̌��ӑ܂Ɏ�̈���������A������ꂽ�B
11��2���y�z
�[���A�����������u��K�v�͂��B�܂��ŁA���X�ꋉ�ɏ��i
���Ȃ��B
12��19���i�Ηj�j
����͑���鵶�k�A�l���B�搶�ƏK������̔̊Ԃ�|�����A�[�H�����܂��A�o������B
12��27���y���z
�k�˓c�l�h�q����A�{�i�I�ɏ����ɂ͂��݁A���K���̐搶�ɂȂ�����ƁA����ꂽ�B
12��31���y���z
����������ŁA�����F���m���o�邱�ƂɌ��߂��B�ˑR�̂��ƂŁA���͂߂��炵���{��A��܂œ��������B�Z�͉�������Ȃ������B�t�˂���ɑ��āA�킪�Ƃ̂�
��Ȃ���������������Ă͂炢�B�䂦�Ɉ�A�ӂ���̊Ԃ̐��_�I�Ȃ䂫���������A�b���Ă͂��Ȃ��̂��B�q���̍�����̉i���𗬂ł���B�g�ӂ����Ă�
�鍠�A�t�ː搶�͐V�N���}���鏀���ɗ]�O���Ȃ������B
�����a15�N�i1940�j
1��18���y�z
�ߌ����A��K�Ńm�[�g�ɒZ�̂������Ă���ƁA�ꂪ�t�˂���̌��`�B�َ݉q�̈ɐ����̎q�������̂ŁA��`���ɍs���B��������A���k�̏K���̓Y���
���ė~�����Ƃ̂��ƁB�[���߂��܂łɏI��B�����x�݁A�����A�铿������𑗂��āA���w�܂ōs���B
1��21���i���j�j
����c�̑S�����Łu���N�̒��v������B�߂��̈˓c����E�h�q�v�Ȃ������˂��B�����A�o��̒��ԂȂ̂ŁA�b��͂��Ȃ��B
1��24���y���z
��A�t�ː搶�Ə��a���q���Ɗw�Z�֍s���B��O��u��鵶�k�A�l���v�̂ǂ��B
2��3���y�y�z
�\�ꎞ����v���Ԃ�ŁA�����F���m�������ˁA�t�˂���ƉΔ��ɂ�����y�����A�o��A�Z�̘̂b�B�ߌォ��_�c�̎������֍s���B������������A��̕����̈��������ɖv������B
2��6���y�z
�����A���ї������o���A������A�����̈��������B
�s���܂�͂����L�t�ɂ����鏑�Ɋւ���L�q�i���j ��
�� �������k�t�ˁl�i���Ƃ� ���ケ���k������傤�l�j�@�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t1973�N9�����j�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B�������͋g�������� �N���̂悤�����A���N���͖��ځB
�g���@ �k�c�c�l�ڂ��́A�����t�˂Ƃ������Ƃ̉e���ŕ��w���͂��߂��킯���B�ނ͐����̕n�����_�Ƃ̐l�ŁA�ǂ��������Ă����ƍ����v�z�̎��傾�����悤�Ɏv���B�� ���̓�K�łق��ڂ��ƕM�k������Ă��킯�A����������Ȃ���ˁB����͂܂��s�v�c�ȉ��łˁB�����Ԃ����͓���`�̓����ɏZ��ł����A���z������ ���Ԃ��đ傫�ȉƂ����肽���A�����Ɠ���ւ��Ă���Ƃ����Ă����킯����B�����A��K�ɍ����Ƃ����l�����h�����Ă��邪�A�ł����炨��ł����̂� �ܒu���Ă���Ă���Ƃ����������������킯�B����ŁA���������͐e�q�O�l������K����Ԃ���A�܂���̏Z�߂��ŁA���m�����B���̉Ƃ��X���̎O���� ���ŁA�ڂ��͂�������o�����A����͂����Ŏ��B�������Ƃ��B���̍����t�˂Ƃ����l�̕����ցA�ڂ��͏��N���サ������イ�o���肵�Ă����B�ނ͕��w�N ������A�悭�{��ǂ�ł��ꂽ�B���ꂪ�S�[���L�[�́w�ǂ��x��w��x�ȂŁA���܂ł���ۂɎc���Ă���B
�剪�@�\�O���炢�̂Ƃ��ˁB�ނ͉����炢���ȁB
�g���@���ܘZ�\�܁A�Z�̐l���Ǝv���B
�剪�@����A�����O�\�߂������킯���B
�g���@���̐l�̉e���ŕ��w�ɖڐ��߂āA���ꂩ���R���ւ����āA���܂��܂��������o�ŎЂɂ������߂ɖ{����� �����ɓǂB������A�� ���ɂ͒N���t�����Ă̂͂Ȃ��킯���B�i��l�Z�`��l���y�[�W�j
�� �����i�� �����Ȃ�A558-638�j�@�����̏��ƁB���q�E�q�_����r�B
�� ��t�m�i�� ������ �����悤�A����29�k1896�l-���a38�k1963�l�j�@�_�ސ쌧���{�ꐶ�B���͖A�ʍ��ɓE�V�S�E����������B�吳2�k1913�l�N�A�����t�� �Ɏt���B��5�k1916�l�N�A����c��w���ƁB�������������ɂ��A�G���s��K�t�s�����B�ד������@�����R�����B���A���{�������p�@�̑n���ɎQ �悵�����R�����Ƃ��ē��@�̔��W�Ɋ�^�����B���W�ɏ������Q������ƂƂ��ɐR���������߂��B�u�����Ȍ�̌ÓT���A�������鏑�d�̒��ŏt�m�͂킪����� ����ߐ��Ɏ���L�͂ȗ̈�ɂ킽��w���ɋy�сA���̂ق��A��a�G��G���A����ɕ��[�l��Ȃǔ����������ĕ������A�������Ȃ̊e�̂��I�݂ɂ��Ȃ��a�l�\���� �Ƃ��āA���L���ׂ����݂ł���v�i�ÒJ���j�B5��10���̗l�q�́A�t�m���s��K�t�ɔ��\�����G�L�ɋL����Ă���̂ň��p����B�����ɂ́u��̐l�X�v�Ƃ��� �����ō����t�˂̖��͌����Ȃ����A��5��3���ɓo�ꂷ��B
���\���@�������B�ꎞ�Ԓ��Q�Čm�ÂɎ悩����A���b�ɂȂ��l�X�� ���������A�y�ւ��猥����R�͂��A�� �͗�̐l�X�W�܂�ˌÍ���ÕM�̘b�Ɏ����̗L������\�ꎞ���߂��B�i����t�m�s�t�m�G�L�k��2���l�t�A����t�m�搶��ƌ�����A�k1985�l�A��l �܃y�[�W�j
���O���@�t�ˌN�G�t�����������A�����n���̌Â��̂𗊂̂�������Șb�A�L����̑��݂ł���A�������V�炵���������F�ɘe���Ɍ���A�k�c�c�l �i���O�A��l�O�y�[�W�j
�s�t �m�G�L�k�S4���l�t�͏��a60�k1985�l�N���t�m�̓�\�O����ɓ����邱�Ƃ���A����t�m�搶��ƌ���������E���s�������́B���{�̃t�H�g�R�s�[��� �Ԃ����{�������������Ĕ��ǂɋ�J���邪�A�{�����獲���t�˂̎��т𖾂炩�ɂ��邽�߂̎�|���肪�����邩������Ȃ��B
褚 �����i���� ������傤�A596-658�j�@�����̏��ƁB��q�哃�������r�B
�� �z�m�i���� �悤�����A557-641�j�@�����̏��ƁB���q�㐬�{�Ґ���r�B
�� ���{�Ґ���i���� ���������イ�ꂢ����߂��j�@�����B���̒��6�k632�l�N�̌���B���@�̒��|�ɂ����鰒�������A���z�m���������B�u���@�̋ɑ��v��`���錆��B24 �s�E�e�s50���B蟐��ȗٟ����Ɍ�������B���{�ł͏��a���珬���w�Z�̋��ȏ��̎�{�Ɏ�������A�㐢�ɑ���ȉe����^�����B
��
�M�����i��
���ق����傳���j�@���ƁE⽍��Ƃ̍������i����39�k1906�l�N-����4�k1992�l�N�j���ҏW���A���g����ɂ���M�ؘ��i���s���ܔԒ����Ԓn�j
�����s�������������G���B�₳��Ă���̂͏��a11�k1936�l�N�̑�3�����珺�a15�k1940�l�N�̑�7���܂łŁA�ŏ��̕����������Ă���B���͕�
�������S�Ԉ䑺���܂�B�{���͗ѕ��q�A�����A�ƁE���E�������B���k��w�ɏ��L�Ƃ��ċΖ������B�吳14�k1925�l�N�A���֓]���A�t�̍����V�i��
��4�k1871�l�N-���a8�k1933�l�N�j���S���Ȃ������N�A�M�ؘ�����ɂ��A�劲�Ƃ��ās���M����t��ҏW�E���s�����B
�s���M����t���a14�k1939�l�N7�����i��6����7���j�ɂ́A�q��E�Z�����сr�́u�K��v�l���Ɂi�n���Ȃ��Łj���ۂ̖��O������B�M�ؘl�E
�y��ؒJ�ɂ�铯���u���Ӂv�l���̐R���]�Ɂu�����ہ@�U���v�i��Z�y�[�W�j�Ƃ���A��i�͌f�o����Ă��Ȃ��B��8�����i��6����8���j�ɂ́A�q�K����I�r
�Ɂu�T�[�Ԗؐ[�k�팚�̌܌������q�j�R����T�@�r�̑�l��l�^�l�@���ې��v�i��y�[�W�A���̎ʐ^�Q�Ɓj���f�o����Ă���A�g�������L�ɏ������̂͂��̂���
�ɈႢ�Ȃ��i����͂����Ɓu���ہv�͒N���t�����덆�Ȃ̂��낤�j�B�����q��E�������сr�́u�K��v����сu���Ӂv�l���ɂ��ꂼ��i�n���Ȃ��Łj����
�Ƃ���A�u�K��v�l���̋y��ؒJ�̐R���]�Ɂu�����ہ@��ϗǂ��Ȃ��ė����v�i�ꔪ�y�[�W�j�ƌ����A�g���̐��i������������B�Ȃ��A�����u�K��v���E�E��
�I�E�ꋉ�̐R���]�͑���t�m�i�M�ؘl�ɂ͖���A�˂Ă��Ȃ��j�������Ă���A�g���͍����t�˂Ƃ��̎t�E����t�m�̂Ȃ���Ō��́s���M����t�̐����Y
��������̂��B���Ƃ���A�g���ɔ��ۂƖ��t�����̂͏t�m���Ƃ͍l�����Ȃ����낤���B
 �@
�@ �@
�@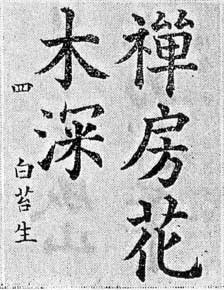
�s���M����t�i�M�ؘ��A���a14�k1939�l�N8�����j�̕\���i���j�Ɠ����f�ڂ̋g�����̏�
�k�ʼn���̉E�����߁l��
�y�[�W�i���j�Ƃ��̃A�b�v�i�E�j�k����������m�N���R�s�[�l
��
�K�i��
�Ȃ炢�j�@����t�m�̏��������G���B�����B�吳14�k1925�l�N�ɑn�������l�G���s�t�m�t�i�����A��j�����a5�k1930�l�N�Ɂs��K�t�Ɖ���B
���a18�k1943�l�N�ɐ펞�������A���̌�ꎞ�x���������A���a38�k1963�l�N�ɟf����܂őa�J��̓Ȗ،������s�Ŕ��s�𑱂����B
�k2010
�N4��30���NjL�l�g�����E�����؍K�j�E���q�����E�����d�M�E���c�Îq�k���k��l�q����o�偁���̒f�ʁr�i�s��t1972�N10�����k9��10���ʊ�
100���l�j�ŁA�g���͎��̂悤�Ɍ���Ă���B�u���ꂪ�\���A��̂Ƃ��ɂ��������ǁA����ς茆�삾�Ǝv����B�u�Ί_�̑ۂ̂͂��ꂵ������
�ȁv���Ă����̂ˁB����͂��܂ł����□�ɂȂ�Ȃ��A�����傾�Ǝv���B����́u��K�v�Ƃ����G���ɓ��e��������A����ɍڂ�����ł����ǁA����Ŏ��M��
���킯���B���ꂪ��������Ȃ����ȁA�c���Ă�̂Łc�c�B�v�i�����A���y�[�W�j�B�f�ڎ��͖��������A���ł͂Ȃ��o��𓊍e�������Ƃ���́A�s��K�t���̂��̂ւ̐e�t������������B��
����ɂ��Ă��A���Ɣo����߂���g���̐l���ɂ͏d�Ȃ�Ƃ��낪�����A�g
���Ɂu���ہv�̍���t�����̂͑���
�t�m�Ɏv���Ă���B
�� �A��̕����̈��������@ �������X�i�В��͐��A�g�����Ζ������������[���������ƂɂȂ鐼���m�́j�n�Ƃ̈��A��ł��邩��ɂ́A���R�n�����낤�B�\�\�]�҂̗��e�͂Ƃ��ɏ��a���N �̐��܂ꂾ���A���܂�������͖ѕM�ŏ������B�ߐ�i���͓S���Ȃ̂����S�A��͐V���E���n�̑�����j�ł�����������Ƃ������Ƃŏd�ꂽ�B
�g �������W�s�m���t��1958�N11��20���ɏ��惆���C�J�������400���̒P�s�{�Ƃ��ďo�ł��ꂽ���ƁA1�N���o�����Ďc��m�ҏW�E����s�g�������W �k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�ɑS�т����^����邱�ƂōL���ǂ܂ꂽ�i�푺�G�O�͂������{���Łs�Õ��t���}����܂œǂj�B�s�m ���t�͂��̗�1960�N�A�����n���Ђɂ��u�����E�吳�E���a��㎍�W�v�̑p���s������{�����W�听�t�̑�11���ɑS�ю��^����āA������b�q�̂悤�ȔN �Ⴂ�ǎ҂��l���������Ƃ��q�g�����́q���`�r�r�� �������B�����ł͂����ĐG��Ȃ��������A ������{�����W�听�Łs�m���t�̖{���ɂ͏��Ȃ���ʖ�肪����̂ŁA�����ł͂�����w�E���悤�B���эŏI�y�[�W�́q�����r�{���̂��ƂɁA��s�A�L�Œ�{�� �ւ��鎟�̋L�q������B
�@���w�m���x�͈��ܔ��N�\�ꌎ��\���A���惆���C�J���s�ɋ������B�i�����A�O�O��y�[�W�j
���Łs�m���t�ƌ�����{�����W�听�ł̖{�����Z���������ʂ��ȉ��Ɂ\�\���ł́u�������Ԃ�̎֕����Â̗�����[���̂сv�i�q�P���r�C�E 9�j�������� �O�ꔪ�y�[�W��i�Łu�������Ԃ�̕����Â̗�����[���̂сv�ƂȂ��Ă����Ԃ����̂悤�ɗ��L���ā\�\�f����B
��
���̂ق��ɂ��A�U�����^�́q���������r�i�C�E16�j�̑S�p�A�L���x�^�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪��ӏ��A�q�����r�̎����Q���s�����Ă���Ƃ��낪��ӏ���
�邪�A��f��11���܂߂ĕs��ɕt���Ƃ��Ă��A1�E3�E4�E6�E7�E8�͒ʓǂ��Ă������Ɍ�A�Ƃ͂킩��Ȃ������ɁA�g�����ɂ������Ƃ��v��ꂩ��
���A���ł���B���������Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����̂��B�{�W�̌��e���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������s�������A�s�m���t�̒P�s�{���̂��̂łȂ��������Ƃ͊m
�����낤�B�s�m���t�̌����łȂ������̂Ȃ猴�e�͂ǂ̂悤�Ȍ`�Ԃ������̂��A���ꂱ��z������̂����悭�킩��Ȃ��B1980�N��̏��߁A���������ȏo��
�ЂŕҏW�̌��K�����n�߂�����A�������ł͂܂��Ă��\�\�Ă��p���Ɍ����𖧒������ċ@�B�̃��[���[���ɒʂ��Ɗ������Đ���悪�������ł邠�́u��
�^�v�\�\�Ō��e�̕��ʂ��Ƃ��Ă����B�ނ���p�������������炾���A�g�p�����i�̏L���ɕ��������̂ł���B�Ă��͍����̃t�H�g�R�s�[�i�����́u�[
���b�N�X�v�ƌĂԌ�m�������j�̂悤�Ȕ��ˌ��ł͂Ȃ����ߌ����g������A�{�Ȃǂ̍��q�͕��ʂł��Ȃ��B����͂Ƃ������A���e�����ł������ʂ�������������
�Ɖ��肵�悤�i���ł͋������őg�܂�Ă��邪�A�{���ł͐V�����ɂȂ��Ă���A������V���œ��ꂵ���菑���̌��e���쐬���ꂽ�\���͔ے�ł��Ȃ��j�B
���ň���ł͕��I�S���҂��������ꕶ���ꕶ���E�����߁A�`�̂悭�����ʂ̊���������đI��ł��܂����Ƃ�����B���ꂪ�ꕶ����A�̎�Ȍ������B�{�����t��
�́u������@���r�Ёv�Ƃ���A���݂̓I�t�Z�b�g������S�̓��Ђ��A�����̏��Ј���̑唼�������������悤�Ɋ��ł���ԂŁA�g�ō�Ƃ�����������Ă����͂�
���B�o�ŎЂ̍Z���S���҂����e�ƏƂ炵���킹�čZ�����ɐԎ����L������킯�����A1�E3�E4�E6�E7�E8�̂悤�Ȍ��́A���e���e�����ł̌��������̕���
�ł��邩����A�ʏ�̍Z�������Ă���N���肦�Ȃ��B�g�����̎��̏ꍇ�A���̓��قȃV���^�b�N�X�䂦�A���e�̒i�K�Ŏʂ��܂�������Ɓi��A�����W�̌㔼�A
���Ȗ����̐��тɂ����܂��Ă���̂́A���ʂ�Z���������l�Ԃ̏W���͂������Ă������ʂł͂Ȃ����j�A���̌�L���f�ǂݒi�K�ł̋^��o���Ō����E���������
���Ƃ͂܂��Ȃ����낤�B�����������Ƃ��l�����킹��ƁA�g���͌�����{�����W�听�ł̒��ҍZ�����i�������낵�́q���`�r�������āj�����炭���Ă��Ȃ�����
�̂ł͂���܂����B�p���ւ̏��Łs�m���t�̑S�ю��^�Ƃ�������I�Ȋ�Ă��A��L�̂悤�����r�Ȃ����ʂɏI��������Ƃ́A�܂��ƂɎc�O���ƌ��킴�����
�Ȃ��B
�s������{�����W�听11�t��1960�N9��10���ɓ����n���Ђ��珉�ł����s���ꂽ���ƁA�����n���V�Ђ���d�ł��o�Ă���i�����n���Ђ̃T�C�g�Ɍf�ڂ�
������q�����n
���Ёb�N���r��
�́u1961�N�i���a36�N�j9���A�����n���Г|�Y�v�A�u1962�N�i���a37�N�j1��18���A�����n���V�ЂƂ��čăX�^�[�g�v�Ƃ���j�B�苖�̓����n��
�V�Дł̈�{�́A���ł̓\�����@�B���ɕς���Ă���1965�N4��30�����s�́u4�Łv�����i���ł���ʎZ�����u4���{�v���낤�j�A��Ŏw�E�������̉�
���͂��ׂď��łƓ���ŁA�e�L�X�g�͕s���Ȃ܂܂ł���B������2���{�E3���{�̔Ō��������n���Ё^�����n���V�Ђ̂�����ł����Ă��A�s�m���t�̖{��������
�Ɠ���ł��낤���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B
�g �����͂����Α\�V�̒n�����ۂɕ��������ƁA����𐏑z�ɏ����Ă���B����́q�{���������E�G�r�Ɓq�����ؒʍ�r���e�L�X�g�ɁA�{���Ɠ�����T�K���Ă݂� ���B��������s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�Ɏ��߂�ꂽ�{���������A��v�Ȏ����ɂ̓����N���Ē���ʐ^��t���B�܂��q�{���� �����E�G�r�B���o�́s���t1978�N12�����q���W�E�����\�\���̖��͂��Ĕ�������r�́q�������̓����@MY TOKYO STORY�r���̈�сB
�{���������E�G�b�g����
�@�H�̂�����̌ߌ�A�����n���S�̓����ō~��A�ؒʍ����̂ڂ� ���B�V���X�P�Ƃ��������������������ɂ����āA�Ȃ������B�́\�\�Ƃ��� �Ă��A������ �����w�Z�𑲋Ƃ��āA�{���������ɂ�������w������R���ɕ���� �s�����A���a��N����ɂ́A�܂���̉��Ɉ�l��l�̗�����V�����āA�Ԃ̂��Ƃ������Ă������̂��B�� ���̃}���V������ �����Ă���ӂ�́A���@�̐Ε��������Ă����B����̂Ȃ��z�e���̊p�� �Ȃ��āA������ ���V�_�����Q�肵���B�~�̉Ԃ̍炭���́A�l�łɂ��₩�����A�ӂ���͗҂����B�₪�ē�R���̑O�ɗ��Ă����B���F�̓�A�O�l�͂������� ����͂��� ���A�q�˂邱�Ƃ͂�߂āA�ׂ��ُˉ@�̋����ɓ������B��l�����Ɏ���� ���߂������ȂǁA���͂悭�傫���N�X�m�L�̎��̉��ɗ��������̂������B
�@�ՍϏ@�V��[�Ă�]�R�ُˉ@�́A�t���̋ǂ̕揊�Ƃ��Đ��ɒm���Ă���B���͎l�\�N�Ԃ�ŁA�l�C�̂Ȃ���n������A�ǂ̕��T�������ꐡ������� �������B�ؗ��̉��̂ق��Ŏd�������Ă���Ή�����ɁA������Ă���Ƃ킩�����B�Z�ݍ��݂Ŏl�N�Ԃ��߂��ɂ��Ȃ���A���͈�x�����Q������ĂȂ����Ƃ�m�� ���B
�@�t���̋ǂ̕��͗��h�Ƃ��������A���ɂ͈ٗl�Ɏv��ꂽ�B���̌d�� �������ǂ������̂��낤���A�傫�Ȋ�� ��ɔ��p�̑䂪�����āA���̘@��ɋ��̂��̂�A�܂����̏�̘@��ɒj���̂悤�Ȑ������Ă���̂������B��ꏉ�߂���̉��ŁA��������炭���߂Ė�� �o���B�ʂ���ւ��Ă��������Ƃ����X�ɓ����ăR�[�q�[�����B�X���͗� ���̏ĕ��̎M��₪�т�����Ɛς܂�A�n �ځA���A�\�y�Ȃǂ̖؍H�i���u����Ă����B�q�ɂ̂Ȃ��ɂ���悤�Ȋ�ȕ��͋C���������B���ɋq�������������Ȃ��̂ŁA���͕������̂��Ƃ��A�Ƃ�Ƃ� ���Ȃ��z���o�����肵���B�@��R���̏o�ŕ��̂Ȃ��ł��A�����E��{�P�Y�����́s���ȏ��t�S�O���{�́A �Ƃ�킯�����Ƃ���Ă����B ���ꂾ���ɐV�w�����Ƃ����A�₦���������Ă����B���͎g������Ƃ��āA�����Z���Q���������āA����w������ ������ �s�������̂��B�������������A�Ԏ��̃Q����Ԃ��Ă����A�����őe��ɂ��������鏕�����N���X�̒j�������B�悭�����Ȃ�ӂ肩�܂�ʊw���^�C�v�Ƃ� ���̂��낤���B���鎞�A���̐l�������ǂ�t���X�R�Ȃǂ̊킪�����ς��u���ꂽ�A���֗I�R�Ə��ւ���̂����āA���͋������B�����܂��l�Ԗ����ӂ��p�ɐS �ł��ꂽ�B���̐l����N���t���d�Y���m�ł���B
�@�Ⴂ�j����O�\�l�قǂ��A���̊�h ���������Ă���X�ł́A�Ď����Ƃ��āA�ޖ������̔�����Ƃ����V�l����Ƃ��Ă����B�����[���ɏo���Ă���̂ŁA�������͔�[�A]����ƉA����@�����B ��������Ȃ������C�̂Ȃ��l�ŁA�������������Ă����B��A�d�����I��Έꉞ���R�Ȏ��Ԃ����Ă����A�O�o��ɍs����ƋA�X���Ԃ��L�����Ȃ���A�V�тɂ� �o���Ȃ������B����������Ǘ����Ă����B
�@���͂悭�s�E�̒r�̂قƂ���� ��L���H�֍s�����B����������̐l���� �ŁA���₩�Ȗ�X���̂��������̂͊y�����B�A��ɂ����咬�߂����m�Ԋ��� �����i���ŁA�������݂̂Ȃ�����������o��G����ǂ肵���B
�@�Â��ؒʍ����肫��ƁA�����₫���]�m��������B�����ł͖��ӂ̂悤 �ɁA���A�ꍂ�̐搶��w�����������̍� �Ⴕ�Ă����B����l�����ɂ͉��̂Ȃ����E�������B���͓X�ɖ߂�A�A�X���Ԃ���������āA�Q�����̂ł���B
�@�{���������Ƃ����n���́A���͂Ȃ��B�i�����A�O���`�l�Z�y�[�W�j
 �@�ؒʍ�F�����V���{��w�ɂ��Đؒʍ�̌������́u�����̃}��
�V�����v�i����3����30��4����6�̊ԁj
�@�ؒʍ�F�����V���{��w�ɂ��Đؒʍ�̌������́u�����̃}��
�V�����v�i����3����30��4����6�̊ԁj �@ �V���X�P�F�u���ꍇ�̓X�v�i�����擒��3-31-5
YUSHIMA3315�r���j
�@ �V���X�P�F�u���ꍇ�̓X�v�i�����擒��3-31-5
YUSHIMA3315�r���j �@��R���r���F������Г�R���̓r����1�K�i�����擒��4-1
-11�j
�@��R���r���F������Г�R���̓r����1�K�i�����擒��4-1
-11�j �@
�����@�m�فF�����@�뉀�̖k���͖�����ɐڂ���i�����s�䓌��r�V�[1-3-45�j
�@
�����@�m�فF�����@�뉀�̖k���͖�����ɐڂ���i�����s�䓌��r�V�[1-3-45�j �@�ُˉ@�̎R��F�ُˉ@�͒ʏ́E�k�k��[���炽���ł�]�i����
�擒��4-1-8�j
�@�ُˉ@�̎R��F�ُˉ@�͒ʏ́E�k�k��[���炽���ł�]�i����
�擒��4-1-8�j �@�ُˉ@�̃N�X�m�L�F�R����������č��艜���ނ�����
�@�ُˉ@�̃N�X�m�L�F�R����������č��艜���ނ����� �@ �t���ǂ̕�F�ُˉ@�̉��܂������ɐ��ؗ��Ɉ͂܂�Ă���
�@ �t���ǂ̕�F�ُˉ@�̉��܂������ɐ��ؗ��Ɉ͂܂�Ă��� �@
��������������������F��R������͐M�������Ό������i����2-31-17�j
�@
��������������������F��R������͐M�������Ό������i����2-31-17�j �@
�]�m���F�����V���{�Ɠ�R���̂Ȃ��قǂɂ���i�����擒��2-31-23�j
�@
�]�m���F�����V���{�Ɠ�R���̂Ȃ��قǂɂ���i�����擒��2-31-23�j�����āA��f����4�N��ɓ�����`�����q�����ؒʍ�r�B���o�́s���������{ 22 ���w�̔w�i�t�i���E�����ЁA1982�N�k�����L�ڂȂ��l�j�́q�q�k�C���E���k�E�֓��E�����r�Y���̂��܂����r���̈�сB
�����ؒʍ�b�g����
�@���͔ӏt�̗[���������A�����V�_�������˂��B�� ���́A�ؒʍ��� ���̂����A���̓����j�����̂ڂ����B���������̕ӂ�ɁA�ӔN���v�ۓc�����Y�� �Z��ł����ƁA�����B��Ƃ͂����Ă��A�O�\���i�̐Βi�ł���B��A�O�l�̎q�����V��ł����B
�@�@�~�炭�ⓒ���̎Г��t�@���q
�u�j��v�̗R�����������W���̖����ɁA���̈�傪�f���Ă������B�~�̉Ԃ̍��́A�����̐l�œ��₩�ł��邪�A���͋����ɐl�e���� �������B�БO�� ���Ԃ̈͂��ɁA�������̋F������߂��A�삵���G�n�������Ă����B
�@〽�k�̋L���l�����ʂ�@�v���o��
�@�@���ӎ�ł́@�S�ӋC
�@�@�m��┒�~�@�ʊ_��
�@�@�c���l�́@�e�@�t�@�L�����u�����̔��~�v�̑��߂ł���B���̗̉w �Ȃ́A�Ԃ��w�w�n �}�x���f�扻���ꂽ���̎��̂ł������B���͂Ƃ��ɋ��Ԃ̔M�S�ȓǎ҂ł͂Ȃ��̂ŁA�w���쐹�x�Ƃ��w����x���炢�����ǂ�ł��Ȃ��B ������A�w�w �n�}�x�Ƃ����A�ŋ���f��Ō����u�����̋����v�̈��ʂ����A�S�ɂ��� �Ȃ��B�������A�u�����v�Ƃ����ꏊ�́A ���ɂƂ��āA��ۂ̐[���y�n�Ȃ̂������B�̂̕���ł͂Ȃ����u�����ʂ�Ύv���o���v���Ƃ�����B
�@���a��N�̏t�A�����������w�Z�𑲋Ƃ���Ƃ� ���A�{���������� �݂����A��w����m���֕���ɍs�����B�X�œ����҂́A���d�����̒����ɑO �|���p�Ȃ̂ł����������͋������B�u���m ����v�Ƃ������t���A�܂������Ă��鎞�ゾ�����B���͖����̂悤�ɁA���]�ԂŁA���g����{�̔z�B�̂��߁A�� �ʍ��� �̂ڂ�~�肵���B�܂�����Ƃ��͖���x���A���l�̕��y�ƉԂɔ�������ς�ŁA�}���z�̍�������āA���w�֍s�����B�A��͋�ɂȂ����ב�Ɍ��ɐQ�āA �~��ɂ܂������������A�Â��ؒʍ���̂ڂ����B����ȂƂ��A���͗���������A�o�������̂ł���B
�@������W���z���o������B�O�A�l�N�̒P���ȓX�������Ɍ�����A��l�������� �o������B�����̐l�C���� �������A��m���Y�w�Ⴂ�l�x�̍]�g�b�q�̂悤�ɁA�u�������v�̗d������ ���ǂ��Ȃ����Ђ߂Ă���B���Ɏv������ ��҂�����悤���������A�����͎��ɂ��D�ӂ��������B
�@����́A�����_���� �t�̍�̖邾�����B��������Q���܂ŁA���䂪���сA�Q�w�q�����Ă����B���H�A�Ȉ��A�R���S�C�A��āA���ł�A�ǂ�ǂ�āi���D�ݏāj�A�������� ���A�����͂�������A�����ɂ������Ȃ����̂��B��������̐��ʊ�ɁA���]�������M���������ɑ���܂���Ă���A�҂���������������B�l���݂̂Ȃ��� �����āA���_�y�̕�����ςĂ���A�����Ƃ�̐N�̎p���A���͌��Ă��܂����B�����𒅂������͑�l�тāA�Ƃ��ɔ����������B�@���͋������o�āA���Ȃ��ސؒʍ���~�肽�B�Q�W�a�̐Ί_�̉��ɁA�� �����V���������Ă���̂ɋC�Â� ���B
�@�@��ӂ����ɁA
�@�@��̈ꎞ���ɐؒʂ̍����肵���\�\
�@�@�߂Ȃ���ȁB�@�ΐ��w�߂����ߋ�x�̈��ł���B�������ɂ��Ɓ\�\�����A��͖{���|���̊�V���i���E�V�䗝���X�j�̓�K�ɊԎ��Ă� ���B�����Ĉ�� �ܐl��{�����߂ɁA�����V���ɍZ���W�Ƃ��ċΖ����A��ӂ����ɖ�������B�\�\��N�O�Ɍ��Ă��Ƃ���B���łɁA�u�� ��v�� �̂ڂ���̖�͕�����Ă����B�������L���H�܂ŕ����A�r�V�[���@�ʈ��� ������B�X���O���w��x�̂Ȃ��ɁA�����Ώo�Ă��鋼�����ł���B�] �˖���������̓X�ł���炵���B�����߂��ɁA�@�̑����s�E�r������B�i�O �f���A��Z���`��y�[�W�j
 �@�����V���{�̒j��F�����w����ؒʍ��w�ɂ��Đi��Ԃ̎�
�O���E��
�@�����V���{�̒j��F�����w����ؒʍ��w�ɂ��Đi��Ԃ̎�
�O���E�� �@�ΐ��̉̔�F�ؒ�
��̓����V���{���
�@�ΐ��̉̔�F�ؒ�
��̓����V���{���  �@�����V���{�̏���F�u����̂Ȃ��z�e���̊p���ȁv��Ƃ���
�@�����V���{�̏���F�u����̂Ȃ��z�e���̊p���ȁv��Ƃ���
 �@�@�ʈ��F���r�V�[�����ʂ�i�䓌����2-8-7�j
�@�@�ʈ��F���r�V�[�����ʂ�i�䓌����2-8-7�j �@�s�E�r�F�Ă̘@�r�͐��ʂ������Ȃ��قǗt�ŕ�����i�䓌��
������2���ځj
�@�s�E�r�F�Ă̘@�r�͐��ʂ������Ȃ��قǗt�ŕ�����i�䓌��
������2���ځj�{
�e�������ɂ������ē�x�A�{���E������������B�ŏ��͓����w�ʼn��Ԃ��āA�t���ʂ�̓쑤��{���O���ډw�i��]�ː��j�ւƐؒʍ��o�����B��x�ڂ͖{���O��
�ډw�i�ۃm�����j�ʼn��Ԃ��āA�t���ʂ�̖k��������Đؒʍ������A������ς��Ė����������A�g�����̑��Ղ����ǂ����B
��f�̒��ň������i�n�ɑ��Y�s�{���E�G�\�\�X�����䂭
37�k�������Ɂl�t�i�����V���ЁA1996�N7��1���j�́A�{���ⓒ�����U��̂ɕK�g�̈���ł���B������̒n�}������Ȃ����B

����j�ҁs�����꒚�ڂƕ��߂̍��̎��t�i�k�����s�{����l�����꒚�ڒ���A1935�j�ɓ���
���܂�Ă����q�����旪�}�r
�̖{���E�������Ӂk���L�͂Ȃ����A���n��Ƃ����L�ڂ����邩��1947�N�ȍ~�̍쐬���l
�� ���A�g�����Ɩ{�������т��Ă���̂́A�n���S�̓s�c��]�ː��E�{���O���ډw�̕ǖʂɓW�����ꂽ�u���̕ǁv�ł���i�A���\���W�[�̃^�C�g���� �gCROSSING HEARTS�h�j�B2000�N12���̑�]�ː��J�ʎ��̐V���L���ɂ��A�n��1�K���D���R���R�[�X���ʂɐݒu����Ă��郌���[�t�́A�c��2���[�g�� �~�� ��10���[�g���B���㎍�l48�l�̎����G�b�`���O��������9�Z���`���[�g ���̍ג����A���~��16�������Ă���B �A���\���W�[�͏��эN�v�E������w�����̔��Ăɂ�茚�z�Ƃ̑��G�q�炪�f�U�C���������̂ŁA���̑I�l�ψ��͏��эN�v�ƐV��L���E������Y�E���[�E�쑺 ��a�v�E�璆������6�l�B�g���͏ォ��4���߂ɁA�u��������悤������@���ꂪ�ڂ��̍D�݂̎����@�a���̖ѕz�̐[���Ђ��ɋ��܂�@�ڂ��͔E�ςÂ悭�҂@ �����łȂ����łȂ��@���̏��Ղ̋P�����@���܂͎l���@�I�̍����������^�g�����u�v�i'58�j�v�ƁA���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j����q�� ���r�i�C�E12�j�`����8���傪�f�����Ă���B�����������㎍�ɐΑ���̎���ȂǕs�����������A���̂Ƃ���u���̕ǁv���g�������B��̃��j�������g�ł� ��B
![�s�c��]�ː��E�{���O���ډw�̕ǖʂɓW�����ꂽ���㎍48��i](image/sinokabe_48.jpg) �@
�@![�s�c��]�ː��E�{���O���ډw�̕ǖʂɓW�����ꂽ�g�������сq�r�̈ꕔ](image/sinokabe_ym.jpg)
�s�c��]�ː��E�{���O���ډw�̕ǖʂɓW�����ꂽ���㎍48��i�i���j�Ƃ��̋g�������сq��
���r�̈ꕔ�i�E�j
�g�����͐��z�q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�i���o�́s���{�E�t1979�N9�����j�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B�u�\�N�قǑO�A���̓A���O���|�p�̐��E�ɓM��Ă����B������Í������̎n�c�y���F�◼����L�̊}��b�̓Ǝ��ȑn���̕���ɐS�����Ă������A�܂��͌���H�����̂���g�e���g�̓ƍَғ��\�Y�̎ŋ��̋ɍʐF�̙��̐��E�������܌��Ă����B�܂��ٍ˂��`�t�́q�˂����r�Ȃǂ̖����A�ѐÈ�̝R���ɒ��ڂ��Ă������̂��B���̂悤�Ȏ��A���͈�l�̉�Ƃ̍�i��m�����̂ł���B�����Њ��̉�W�s���������X�t�̕ЎR���ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z��y�[�W�j�B
�g���́s�y���F��t�i�}�����[�A1987�j�ł͓��L��^����`�ł��`�t�Ƃ̏o��������Ă���B�u�q���L�r�@��㎵�Z�N�㌎�O�\���^�m�A�m�A�ŋ�����b�q�̗[�ׁB�͂��߂͊}��b�Ƃ��������̘N�ǁB�l�J�V�����̋�������S�B�s���l�`�̂悤�ȉ��Ȕ��b�q�̗x��́A���h��̉��ʂ����ɂ��킦�����X�g����ۓI���B���@���킫�̃��j�R�[���ŏj�t�B�V�V�ޓ�Y�A�}��v�ȁA���R���O�Y�����āA�u�˂����v�̖���Ƃ��`�t�Ə��߂ĉ�B�₫���A���ߓ����ŃW���t�B�[�Y��t�B�\�����U��v�i�q25�@���h��̉��ʁr�A�l�O�y�[�W�j�B
�̂��Ɂs�_��I�Ȏ���̎��t�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��鎍���������ł���1960�N�㖖�A�g���͂��̖���A�Ƃ�킯�q�˂����r����N��Ȉ�ۂ����Ǝv�����B���\�Y��V�V�ޓ�Y�ɂ͂��`�t�_�����邩��A�q�˂����r�̕]���͂��������F�l����������`��������낤���i�g���͖ʒk�̐܁A�u�ǂ�Ȗ{��ǂ�ł�́H�v�Ɛu���̂���Ƃ����j�A���y�O���́s�J���C�`�t�𔒐������̖��ɑ����Ă����Ƃ�������A�q�˂����r�����o�́s�K���t�������q���`�t���W�r�i1968�N6���j�œǂ�ł��Ă����������Ȃ��B�܂��A���̂���}�����[�ł͒ߌ��r��E�������j�E�k�m�v�ҁq���㖟��k��1���l�r�̃V���[�Y�����s����Ă��āA��12���s���`�t�W�t�i1970�N2��25���j���g�߂ɂ������͂�������A�����́s�_��I�Ȏ���̎��t�Ɠ����̂��������̍�i�Ƃ��Ď�e���Ă������낤�B
�q���`�t�r�u���I�O���t�B�[�r�Ɉ˂��āq�˂����r�̂��炷�����L���A�u�C�ӂɉj���ɗ��ă����N���Q�ɘr�����܂ꂽ�ُ�Ȋ�t���̏��N�́A��҂��������āA�����̐��E��f�r���B�����́A�����������ԋ����̒��ł���A�H��킫�ł���A���H��ł���B���̊ԁA�X�p�i�������N�j�A���C�@�֎Ԃ��^�]����L�c�l�ʂ̏��N�A�����Y�������V�k��ɉ�s�𗝂ɖ�������b�������B�悤�₭�w�l�Ȃ̏���ɂ߂����A�t�g���̒��Ł��~���������p�����V���c���s����B��p�ɐ����������N�̍��r�ɂ́A���ǂ��Ȃ��l�W������ꂽ�܂܂ł���v�i���`�t�E�����W�s���`�t����p�k��l�t�A���C�Y�o�ŁA1993�N9��9���A��y�[�W�j�ƂȂ�B
�������璼���ɑz���N�������̂́q���ār�i�F�E8�j��q�_��I�Ȏ���̎��r�i�F�E11�j�̎��s�ł���B���͂����̎��̕]�߂��������A���̈�Ԃ̖��͂́i��ƌ����Ă��������Ƃ����j�A�]�߂ł͂��܂��d���Ƃ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��s����s�ւ́u�킽��v�Ƃł������ׂ������̌ċz�ł���A�s�_��I�Ȏ���̎��t�̂���́A�g�����g�̂ق��̂ǂ̎���̍�i�����q�˂����r�Ƃ̗މ�������������B���������͂����u��ʂ��Ƃ̃g�r�����܂��v�ƕ]�������i�q���������̐�����w�˂����E�g���ԁx���`�t�r�j�A1960�N�㖖�̋g���͎��傲�Ƃ̃g�r���Ⴆ�킽���Ă���A�ƌ��������B

�s�K���t�������q���`�t���W�r�i1968�N6���j�̕\���k�o�T�F�u���O�q�b�n�l�ƃK������r�l
��c�ޏ����s�y���F ���̐g�́t�i���{�����o�ŋ���A2008�N2��25���j���o���B600�y�[�W�ɂȂ�Ȃ�Ƃ���A�����_�ōł����ׂȓy���F�̕]�`�ł���B�Y�тƌĂԂɂӂ��킵���Ӑg�̍삾�B�g�����́u�k���Z���N�l�A��������̎��W�w�`����{�x�������Ґ��܂���܂��A�j����J���ꂽ�B���̐Ȃɂ͑����̎��l�Ƌ��ɓy����������A�y���Ǝ��l�̋g�����͏o��A���̌�A�ڋ߂��Ă䂭�v�i�{���A��O�O�y�[�W�j�ŏ��߂Ė{���ɓo�ꂷ��B�ȉ��A�����Ɂs�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j����̈��p�̌`�ŁA�{���ɂ͋g���̏،��������o�ꂷ��B�{���̋L�q�͂قƂ�NJԑR����Ƃ���̂Ȃ��s�y���F ���̐g�́t�����A�ɂ��ނ炭�͂��̎�̏��ЂɕK�v�s���Ȑl�������������B�����Łu�g�����v�̍����������A���삵���̂ňȉ��Ɍf����i�{���͐l�������Ƃ��ďE��Ȃ����A�s�y���F��t�̏o�T�\��������y�[�W�́A�u�g���v�̖����Ȃ��Ă��u�s�y���F��t����̈��p�v�ƋL�����j�B
�g����
5, 233, 235-236, 238-239, 258, 271-272, 295-296, 308,
(309-310�F�s�y���F��t����̈��p�j, 315, 343, (344�F�s�y���F��t����̈��p�j, 353, 356, 388, 401,
405, 415, 419, 423-426, 438, 471, 473, 482-483, 512-514, 516-518,
522-523, 531-532, 535-536, 548-549, (550�F�s�y���F��t����̈��p�j, 555-557, 566,
569, (570�F�s�y���F��t����̈��p�j, 571, (572-573�F�s�y���F��t����̈��p�j, 574-576
�����ɂ�6�y�[�W�ɂ킽���āq�y���F���N���r���f�ڂ���Ă���B�{���Ǘ���Ɂs�y���F��t��ǂ݂��������̂ŁA�g�����ς��y����i�N��������������āA�k�@�l���Ɂs�y���F��t�L�ڂ̔N������t�����i�j���͕]�҂ɂ��j�B
�{���ɂ͌������Ԃ��L����Ă���̂ŁA�g���̊ϗ��������Ȃ̂��y���Ȃ̂��Ȃǂƌ��Ă����ƁA����͐s���Ȃ��B�{���ɂ͂����y����i�̍u�]���L����Ă���A�g���́s�y���F��t�ƑΏƂ��ēǂނƈӖ��[���B���������悤�B��L7�́s��ฑ哥�ӌ����k�x��q�t�[�s�[�Ɛ�������̂��߂̏\�ܓ��ԁl�t�q�Â��ȉƁr�ɂ��āA��c���Ƌg���͂��ꂼ�ꂱ�������B
�q�Â��ȉƁr�́A���̓��e���s�l�G�̂��߂̓�\���Ӂt���瑽���̃V�[������čč\�������悤�ȍ�i�ł��������Ƃ���A����܂ł��܂�]������Ă��Ȃ������B�������A�q�v�杁r�Ɠ��l�ɓy���̂��炾�̓������̂��̂ɒ��ڂ��邱�ƂŁA�y�����s�l�G�̂��߂̓�\���Ӂt�ȗ������Ă���V���Ȑg�̂ւ̎��݂𗝉����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�i�{���A�l���y�[�W�j
�k�c�c�l�u�Â��ȉƁv��т��ς�B�O���ԋ߂��A�ْ����������镑�䂾�����B�\�\������|�p�Ƃɂ͂��Ă̎��Ȃ̍�i���A���p���A�ό`���A���B���Ă䂭�Ƃ����A�c�ׂ�����B���̍�i�ɂ����ꂪ����悤�Ɏv��ꂽ�B�i�s�y���F��t�A����`����y�[�W�j
1962�N���܂�̈�c���́A�y���F�̕�����ςĂ��Ȃ��B���P�̍�Ƃ��āA�����蓾�邠����f�����������ēy���F�̐g�̂ɔ��낤�Ƃ����c���̔�]�̍���ɂ́A�x��҂̎���������B�u���ĘZ�Z�N��̓y���́A�F�V���F�炩��t�����X�ْ̈[���w��v�z���z�����A����C���炩��V�������A���X���̕��@���Q�Ƃ��A���邢�͓�����̋�C����}���N�X��`�I�v�z���ʂ蔲���A���{�̐����ߑ㉻�ւ̃A���`�e�[�[��͋����A�\�͓I�ɑ̌������v�i�{���A�܌O�y�[�W�j����u�g�̂��v�l���A��邱�ƂƁA�x��A�㉉���邱�Ƃ̊Ԃɂ́A�[���f�₪����v�i�{���A�܌l�y�[�W�j�܂ł̂ӂ��̒i���A700���ケ���{���̔����ł���A�y���̐g�̂̓��B�_���w�E����ƂƂ��ɂ��̌��E�P���Ă���B�������̈�߂́A�s���o�̕����Ƃ̕]�`�Ɏd�g�܂ꂽ�|�낵���������u�ł͂Ȃ����B�͂����āA�y���̐g�̂͋�O�������̂��A����Ƃ���ゾ�����̂��B������x�镑�x�����҂ɂ��{���́A�g������������̕��w�҂ɂ��A�y���̕���̋q�Ȃ���̋L�^�A�y���̐g�̂��O������ς��]�`�ł���̂ƁA�܂��Ƃɂ����đN�₩�ȑΏƂ��Ȃ��Ă���B
�s�y���F ���̐g�́t�ɂ́A�����́q��v�Q�l�����r�ɋ������Ă��Ȃ�����������ӂ�Ɉ��p������߂��Ă��āA�g�������̃X���X�Ƒz����y���F�̂��Ƃ\�\�F�V���F�ɂ��C���^�����[�q���̂̈ł��ނ���c�c�r�i�s�W�]�t1968�N7�����j�\�\���o�ꂷ��B���Ȃ݂ɁA�{���ɂ͋g�������ւ̌��y�͂����Ă��A����̈��p�͂Ȃ��B
���^�ȂŃt�N�t�N����܂ꂽ�o�̑������ǂ��āi�q������܌�b�сr�G�E8�j�c�c�v����ɐ^�Ȃł���悤�ȁA�ӂ��ӂ����������Ƃ����̂����{���x�ł�����ˁB�i�{���A��Z���y�[�W�B�O�f���A��Z�l�y�[�W�j
�ȉ��͋g�����Ɠy���F�̒��q�ɂ��Ăł���B�������͂��łɋL�������Ƃ����邪�A�����ł܂Ƃ߂ās�y���F��t�̌�L�E��A���Z�{�E�Z�����Ă������B�\���́A�끨���i�y�[�W���E�s���j�B
�g�������s�y���F��t�ň��p�������Ɓi50�����ɁA����r�q�A�V�V�ޓ�Y�A�ѓ��k��A�r�c���Y�A�r�c�����v�A�s���A�ܒJ���m�A�F��M��A����c�\��A�剪�M�A����Y�A���c�l�A�}��b�A��������A���\�Y�A���g�a�q�A�S�i�����A���c���j�A�ؔ��a�}�A�F�V���F�A�����W�A���������A��؈ꖯ�A��؎u�Y�N�A�����r�Y�A����C���A�c������A�c�����A�J��W��A�푺�G�O�A�߉��P�v�A�o���T�O�A������Y�A�i�c�k�߁A�����ĔV�A�����G�A���������A�j�[�`�F�A�H�i�����A���J�Y���A�y���F�A�Ñ�r���A�]�p���A���R�r���Y�A���Ԏ��A�O���R�I�v�A���J�E�v�A�O�D�L��Y�A�����Y�q�A��쐟�q�A���ؒ��h�A�g�������A�g���v�M�A�ق��j�̕��͂͑薼��o�T��������Ă��Ȃ����߁A��L��2��9�ȊO�A���T�ɓ������čZ���ł��Ă��Ȃ��B���������������B
�Ȃ��q49�u�����Ǎ�v�r�Ɋ}��b�����c�́q�����Ǎ�r�����`���V������p����Ă���u��ҕs�ځv�̉̂́A�R�����m�O�Y�A�吳6�N�̍�q��{�_�́r���낤�B
����A�s�y���F��t�Ɉ����ꂽ�y���̕��͂̏o�T�ׂĂ��邤���ɁA�ʔ������ƂɋC�������B�g�����莫�Ɍf���A�����̑ѕ��ɂ��̂��ėL���ɂȂ����u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���\�\�y���F�v�i�����A�k��y�[�W�l�j�Ɠ���̏͋傪�y���̕��͒��Ɍ�������Ȃ��̂ł���B�ߎ��������̂Ȃ�A�ӂ�����B
���̂������œ˂������Ă��鎀�͎̂��B�̂��̂ŁA�ޕ��Ȃ���͓̂��̂̒��ɂ���B�i�q���̂ɒ��߂�ꂽ���̊w�r�A�y���F�s���e�̐�t�A�}�����[�A1987�N1��21���A�Z���y�[�W�B���o��1969�N�j
�x��Ƃ͖��|���œ˂����������̂ł���ƒ�`���Ă��悢���̂ł���B�i�q�l����������悤�Ȃ��炾�̓��ꊷ�����A���B�̐�c����`����Ă���B�r�A���O�A�����y�[�W�B���o�́q�����l�r�i�A���ەҁs�`���Ƒn���k�`���ƌ���12�l�t�A�{�Y���сA1971�j�A�̂�1975�N�Ɂq�l����������悤�Ȃ��炾�̓��ꊷ�����A���B�̐�c����`����Ă���B�r�Ɖ��肵�čČf�k�s���e�̐�t�́q���o����ю�̒��r�ł͌�҂����o�Ƃ��Ă���l�j
�s���͓y���F��_�����q���]�哥�Ӂr�Łu�y�������āu�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���v�Ƃ��������Ƃ��v���o�����ɂ͂����Ȃ��v�i�s�����̃R�X�����W�[�t�A�������[�A1983�N7��5���A�ꎵ�O�y�[�W�B���o��1973�N�j�Ə����Ă���B�m���̍\���P�����s�y���F��t�̎��M���A�莫�Ɍf���邽�߂̓y���̕����Ɋւ��錈��I�ȕ�����T���Ă����g�����A������s�앶�Ɍ��o���đ����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂����̐����ł���B
�k�NjL�l
�g�������y���F�́q�a�߂镑�P�r�̎G���A�ڂ�蔲���āA�ŒԂ��Ċȑf�ȍ��q�ɂ��Ă������Ƃ͈ȑO�ɂ��������i�����炭�g���Ɏ萻�{�̎�͂Ȃ������낤�j�B���́q�a�߂镑�P�r�̏��o�̓R�s�[�����苖�ɂȂ����߁A�{���ɕs�ւ������B�����@��Ȃ̂ŁA��䂦��s�f�W�^���Z�p�Ǝ萻�{�t�i����w��o�ŕ��A2007�j���Q�l�ɂ��Ȃ���A���̃R�s�[��ܖ{�Ɏd���ĂĂ݂��B
 �@
�@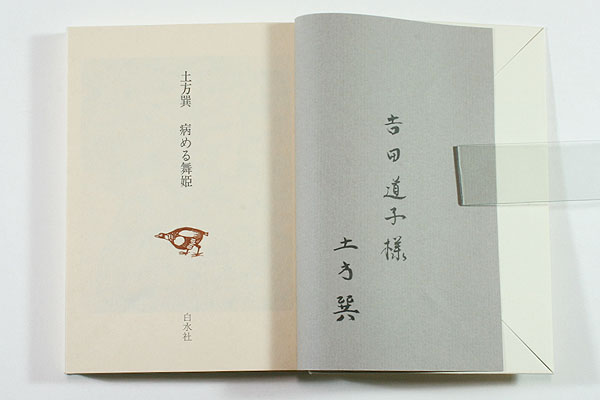
�y���F�q�a�߂镑�P�r�̎G���A�ځi�s�V���t1977�N4�����`1978�N3�����k1977�N11������1978�N2�����͋x�ځl�j�̃R�s�[�����ш�Y���ܖ{�Ɏd���Ă����́i���j�Ɠy���F�s�a�߂镑�P�t�i�����ЁA1983�j�̌�����蒘�ҏ����{�kYahoo!�I�[�N�V�����̉摜�l�i�E�j
�k2008�N7��31���NjL�l
�q�g�����Ɠy���F�r�����ǂ݂����������^����h���烁�[�������傤���������B�^������͓y���F���S���Ȃ�2�N�O���납��A�X�x�X�g�ق̕����u�K��ɎQ�����Ă����A�y���Ō�̒�q�ł���B
�u���k�̕���v��̂S�v�̃��X�g�V�[���͖�ʂ������ďI�����܂����B�i�Q�������������̈���ڂ͘a�I�k�R�I�v�l���A�R�������Ă���ʂ����ꂸ�A���Œ@���Ė�ʂ͊���܂����j�^�y�����S���Ȃ������ƁA�g�����u��ʁv�Ƃ������W�\���Ă������Ƃ�m��A����́A�u�Â��ȉƁv�Ƒ薼�͂��Ȃ���������ǂ��B�薼��������Ă�����u��ʁv�Ƃ������ɂȂ������䂾�����A�����A�ǂ�ł݂����Ǝv���Ă��܂����B
��������^��������x�q���������������̂Ȃ��̈���s�G���n�������t�n�����q���W�E������r�i�O���I�o���ЁA1969�N5���j�Ɂq�E�l�����o����r�Ƃ����y���F�̒k�b�i����ҁE�O�c���q�j���f�ڂ���Ă��āA���̓y�������ɂ���u�k�c�c�l���̕����̊�{�`�̒��ɂ́u�����͖������ł������Ă��鎀�̂��v���Ă����錾������܂�����v�i�����A�Z�l�y�[�W�j�Ƃ�����߂��u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���\�\�y���F�v�̃X���X�ł͂Ȃ����Ƃ̂��w�E�������������B���������^�����瑗��ꂽ�R�s�[��ǂ�ł݂�ƁA�y���̂��̐錾����f�s�앶�i���o��1973�N8��15���A�A�X�x�X�g�ٔ��s�̐V���s���]�哥�Ӂt���������j�Ɉ�����Ē蒅���A����i��j���g�����̖ڂɂƂ܂������Ƃ͋^���Ȃ��悤�Ɏv����B�y���͂��̕����̃e�[�[���A���M�������Ȃ��������̂́A���g�̌����甭���Ă����̂ł���B�Ƃ���ŁA�����[���̂͂��ꂾ���ł͂Ȃ������B���̒k�b�̂����܂��ŁA���������҂��Ǝv�����Ɩ���āA�y���͓����Ă���B
�y���@����ς��Ȃ��j�A�҂����āB�����玄�A�~�������͕K����ɓ���܂�����B�K����ɓ���Ă��邵�A����������Ȃ������B�ł����玄�A���ɃI���W�i���Ȏd���A���̓��e�������̐l���ǂ��������ł���������������Ă������Ƃ����܂���B
�@���̐e�������h���Ă��鎍�l�ɋg�����Ƃ����j�����Ă��Ȃ��͂ǂ��������Ɏ������̂��ĕ�������A���[�������ɍs��������ɏ������Ă�����ł���B�����A���Ă��āu�ł����v���ē����Ă���Ƃˁu�ł�����v�B�����������ɃX�b�Ɗ�����킹��B���̃X�y�[�X�A���B�ł����特�y�Ȃ特�y�������A�ŋ��Ȃ�ŋ��������A�S�����̓��̂̂悤�ȋC�������ł��ˁB�k�c�c�l�i�����A�Z���y�[�W�j
����ɂ��āA���ċg�����͓y���F�ɂ��̂悤�Ɍ���Ă����̂��B
�g�����͐��Ԃ��Ȃ��J���Z�Y�i1921-81�j�̖����ҏW���ďo�ł��Ă��邪�A�����܂ł��̏ڍׂ��킩��Ȃ������B���҂̏،����� �ƂɁA�J���� �抧�s�̌o�܂����ǂ��Ă݂悤�B
�܂��A�g�����J���̂��Ƃ��q�f�ЁE���L���r�ɏ������B�\�\
�k���a��\��N�l�㌎�\����@����Ƃ̒J���Z�Y�N�Ƌ}�ɐe�����Ȃ�B�ނɁA���̎��W�s�t�́t��݂��Ă������A��
���Ԃ��ɂ��āA�ƂĂ�����
�����Ƃ����B�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��Z��y�[�W�j
�����ǂ剪�M�ɖ���āA�g���͓����Ă���B�\�\
�剪�@�J���Z�Y����̖������L�ɂۂ����Əo�Ă���ˁB
�g���@
�J���Z�Y�Ƃ̏o�����͂����������ƁB�������k���m���i�g����1946�N10������1951�N�ɒ}�����[�ɓ��Ђ���܂ŋΖ������j�̕ʖ��̏o�ŎЂŁA���E��
�����̋g���M�q�s���̊K���t�i�O�ŁF1948�N7��30���j�Ȃǂ��o�Łl�͏���������Ă����ǖ������낤����Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ����B����Ŗ���
�Ƃ�T�����킯���B�ŁA���܂��܋����ʐM���ǂ����ŏo�����J���Z�Y�́w�V���W�c�C�`���E�x�Ƃ��������������ƂĂ��f�������ȁB���̖���Ƃ�T������
�Ă�ŁA�J���Z�Y�����n���ǂ����̉Ƃ֖K�˂Ă������B�ނ͂��̍��b���a�݂Ń[�C�[�C���Ă��悤�Ɏv���B�����̘Z�Y����Əo�������̂͂��̎�����B
�剪�@�J�����T���V���̕\����`���A���������ӂ��ɂȂ邸���ƑO�ł���B
�g���@
�����ƑO�B�قƂ�Ljꕔ�ɂ����m���Ȃ�����Ƃ�������Ȃ����B�����A�������i�C�[�u�Ȃ��������`���Ă�����A������������āA�ŘZ�Y����̂Ƃ�
�ɉ�ɂ����ė���ŁA�����炭����������悤�ɋL�����Ă�B����ŘZ�Y����Ƃ͂��̌���e�����������ǁA���ǁA���������Ԃꂩ�����āA���߂Ē}
���ւ������ƂɂȂ��āA����ŘZ�Y����Ƃ̉�����Ă����Ⴄ�킯�ˁB�i�s�����C�J�t1973�N9�����A��܁Z�`��܈�y�[�W�j
�s�����C�J�t�̓������i�g�������W�j�Ɋ��J���Z�Y�́q�g������̊�r�ɂ͂�������B�\�\
�@�傫����A����ƒ�m��Ȃ��v���߂��Ƃł������悤�Ȋ�A�k�c�c�l�������킴�킴�ڂ��̕`�����}���K���Ă��˂��Ɍ��Ă��ꂽ�B�^�k�c�c�l�^���킢��
�Ȃ��}���K��������������Ȃ���������킴�킴�Љ�Ė{�ɂ��Ă����܂łɂ߂�ǂ����݂Ă��ꂽ�g������ł��B�^�k�c�c�l�ڂ��͔���̕a���ł��肩����
�g������̂��ꂽ���W��ǂ݂������܂����B�^����͂����ւ��A�����ɂЂт��S�̎��ł���܂����B�^�k�c�c�l�^�g��������Łu�܂��A��������Ȃ�
���v���t���Ȃ���y�����Ă��ꂽ���X�g�����Ƃ��̋g������̑傫�Ȋ�A�������߂�̂�������Ȃ��A�ڂ��ɂ͉���Ȃ���́A�₳����[�A�A�A�A]�Ɠ�����
����������[�A�A�A]���ڂ��̐S�ɂ���܂����B�^�ł������ɂȂ��Ă��̋g������̉����[�������̂悤�Ȃ��̂ɑς��Ďv�l�������A�u���t���v���m�̐�
�̘B���p�t�ɂ����Ă��鐶�����ƁA���̑傫�Ȋ�̏G�˓I�ȉ���Ȃ������A����ƂȂ������ė����悤�Ɏv���܂����A����͂ڂ��̓ƒf�I�ȋg������̑��ł��B
�k�c�c�l�i�����A���Z�y�[�W�j
�J���͂���ɗ����N�A�q�킽���̊G�̐��E�r�ł��������Ă���B�\�\
����Ԑ�ɒP�s�{���o���܂����B���a��\��N���ɉ������q�������̖{���o�ł��Ă����l�����܂��ďo���܂������A�����̖{���o�ł��Ă��ꂽ�l�͍��͈�
���l�ł��B�^��������I��̏Ă��ƂŁA���Q�̎��Ȃǂ����ǂ��Ă���܂����̂Ŗ{�]�ł���܂��B�i�J���Z�Y��W�s�������̊G�{�t�A�V���ЁA1975�N5��
15���A���Z�`��ꎵ�y�[�W�j
�g �������́w�V���W�c�C�`���E�x�́A�J���Ƒ�|��Y�̋����A�\���̏������s�p������[�}������ SHINJITSU ICHIRO KUN[�V���W�c�C�`���[�N��]�t�i����ЁA1947�N7��5���j���w���̂��낤�B�����͍���H�Q�{�ŁA�J�����g���q�T���V���f���r�Łu���̏Ă����� �ŁA���Q�̎�[��]�������ǂA�ڂ��̂����̃x�X�g�Z���[�w�V���W�c�C�`���[�N���x�p�����胍�[�}���}���K�P�s�{�ƁA�w�J���������Y�x�̒P�s�{�������� �̕��A�����艺�����B����������a��\��N����A���s�������̂ł��B���̏Ă����Ƃɂł��Ă����o���b�N���Ă̓X�ŗ���Ԃ����āA�d�C�p���Ċ�Ńp���Ȃ� �Ă��Ȃ��珑�����}���K�ł��B������̂���́A�}���K�̌��e���ł͐H�ׂ��܂���ł�������A�o���b�N�̏��X�̃`���V�\�\���َq�Ƃ��A�A���~�c�Ƃ��A �X�Ȃǂ̍L���\�\�̎d�������Ȃ��炩�������̂ł����v�i�s�T���V���t1975�N10��2�����A���l�y�[�W�j�ƈ˗����Ă��邭�炢���B�s�V���W�c�C�`���[ �N���t�̏��e�́s�J���Z�Y ���a�̑z���o�k�Ƃ�ڂ̖{�l�t�i�V���ЁA2006�j�Ɍ�����B�����́q���N���r�ɂ́u���a21�N�i24- 25�j�^ �����������b���������ցB�u����v���ɂS�R�}����u�^����Y�N�v��A�ځv�A�u���a23�N�i26-27�j�^����{ �w�J���������Y�x�w���̒n�� ��x���}���K�̗F�Ђ�芧�s�v�i�����A���܃y�[�W�j�Ƃ��邪�A���Ԃ��Ȃ�����������o���i�H�j�g�����ҏW�̊̐S��2���́A���̏��������킩��Ȃ��B�� ��Ƃ��A�s�}���K �J���������Y�t���s�� �`���}���K ���̒n����t�� ����Ȃ̂��B�J���̔N���⏑���������璭�߂Ă��Ă����������Ȃ��̂ŁA����������ɔ@���͂Ȃ���NDL-OPAC�Ō�������ƁA�s���̒n����t�����̍� �ێq�ǂ��}���قɏ�������Ă����B�Ȃ��A��f���ł�2���Ƃ����s�����u�}���K�̗F�Ёv�Ƃ���Ă��邪�A�}�^�s��̉��̎q�ǂ������q1945�`1949�r�t �i�j�`�}�C�A2001�j�ɂ��A�s�J���������Y�t�̔��s���́u����̗F�Ёv�Ƃ���B
 �@
�@ �@
�@
�J
���Z�Y�s�}���K
�J���������Y�t�i����̗F�ЁA1948�N1��10���j�̕\���i���j�Ɠ��E���ʁi���j�k�摜�̏o�T�͂����������c��w�u��̉��̎q�ǂ�����
�q1945�`1949�r�W�v���{�ψ���ҁs��̉��̎q�ǂ������q1945�`1949�r�\�\�����[�����h��w�����E�v�����Q���Ɂu����R���N�V�����v�ɒT
��t�i�j�`�}�C�A2001�N5��12���j�A��O�l�y�[�W�l�ƒJ���Z�Y�s��`���}���K
���̒n����t�i�}���K�̗F�ЁA1948�N10��10���j�̉��t�k���m�N���R�s�[�l�i�E�j
�s�J���������Y�t�œ����I��
�̂��A�R�}�ԍ��̏����Ԃ�ł���B�J���ɂ�1941�N�i�g���̎��W�s�t�́t�Ɠ������I�j����́q�n�}�x�m�R�r�Ƃ����J���[14�y�[�W�A55�R�}�̖��悪
�����āi�s�J���Z�Y�W���� �ʊ�
���k�V�����Ɂl�t�A�V���ЁA1982�A�����j�A���̃R�}�ԍ����قƂ�Ǔ����Ȃ̂ł���i�s���̒n����t�ɂ͂Ȃ��j�B���g�̎萻�{�Ǝv�����q�n�}�x�m�R�r��
�\���ɂ́u�n�}�x�m�R�^���a�\�Z�N��v�ƋL������A�u���Đ푈�̂͂��܂�^�n���C���̍��^�̏K��G�{�v�ƌ�N�̒NjL�i�H�j������B���Əo�ł́s�J������
���Y�t�Ɓs���̒n����t���u�}���K�v�ł���̂ɑ��āA�q�n�}�x�m�R�r���u�G�{�v���咣���Ă���̂́A�J��������̓��������d���������߂��낤�B
���ێq�ǂ��}���قɂ͖���̗F�Ђ̊��s����1����������Ă���B���˖Εv�s�ڂ�����܂�
�L�������̖`���t�i1948�N8��20���j������ŁA���e�E�\���Ƃ��J������̑����ɂ��y�Ȃ��B���ɁA�����Ă����炭�Ō�ɁA�J���Z�Y�́s��`���}��
�K
���̒n����t�i�}���K�̗F�ЁA1948�N10��10���j������B�����͑S96�y�[�W�A2�F�������ʓI�Ɏg�p�������N�����̃X�g�[���[�̈���ŁA�h�}���炭
��T����n������u�h���Z�������m�v�̈��s�ɑ������A�J������̌���ł���i�O�f�s���a�̑z���o�t�ɂ́A�^�C�g�����s�h���Z�����t�ƕς��ĒJ�����萻��
�W���P�b�g����������{���f�ڂ���Ă���j�B�ҏW�ҁE�g�������A�J���Z�Y�́s���̒n����t�Ė{�]�������ɈႢ�Ȃ��B
��i�E�j�̉摜�ł͂킩��ɂ������A���[�Ɂu���s���@�}���K�̗F�Ё^�����s������ؔҒ��^�����H�ƃr�����������v�Ƃ����āA���N8������10���̊Ԃɗ���
���i�Z���͋g�����߂Ă������m���Ɠ����j�̕ʉ�Ђ��u����̗F�Ёv����u�}���K�̗F�Ёv�ɕ\����ύX�����Ǝv�����B�s�L�������̖`���t�Ɓs���̒n��
��t�̉��t�ɂ́A�Ƃ��Ɂu�[�{�v�u23.11.20�v�ƃX�^���v���悵�Ă���i�O�҂͔��s��3�����A��҂�1�������A�o�߂��Ă���j�B���̈ǂ̋@�ւ�
���̂����f����ޗ������̎��ɂ͂Ȃ����A�g���́q�f�ЁE���L���r��1948�N12��10���u�f�g�p�̔[�{�W�ɌĂт�����B���s�ォ�Ȃ肽���Ĕ[�{����
�̂ŁA�܂��������B���̖{�𖾒��܂łɑS���������ʂƁA�����̏����ɂ���Ƃ��ǂ������v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����
�y�[�W�j�Ƃ����L�q�ƏƂ炵���킹��ƁA�����[�����̂�����B
�q�g�����Ƌg�c���j�r�ŋg�c�� �j�̑}�G������Љ�����A���̌�ɒm�肦����i�� �܂ވꗗ�����s���Ɍf����B�i�����́���͌��G��}�G���A����̓J�b�g���܂ޑ�����i��\�킷�j
�g �����̕��͂ɂ���悤�ɁA�g�c���j��1954�N�̉Ă������͏H�ɔN��̏����ƐS����������A���N�̍�i�̑����ɂ͒ɂ܂������̂�������B�g�c�͂����̏� �Ђ̑�����}�G�𐧍삵�Ȃ���A������ʓ��̎��g�̎���z���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���ƁB����A��f�ꗗ�Ɠ���1950�N�i�����Ɍ����1952�N�j���� 1954�N �ɂ����Ă̋g���̑�����i�́A�킸���Ɏ���2�_�ł���B
����
�Ƃ��g���͒}�����[�̎Ј�����������A���Ђ̏o�ŕ��ɂ̓N���W�b�g����Ă��Ȃ��i��L2�_�ɂ������҂Ƃ��Ė��O�͋������Ă��Ȃ��j�B���������āA��L�ȊO
�ɂ����̎����̑��������݂���\���͎̂Ă���Ȃ����A�g�c���j�̑����ɕC�G����_���͂Ȃ��Ǝv����B�ނ��낻�������Č������������Ƃ��͂Ȃ�ׂ��g�c
�Ɉ˗����āA�����炭�t���[�����X�������g�c���j�̖��O���ł��邾���N���W�b�g�����̂ł͂Ȃ����B���̌�A�g�c�͍u�k�Ђ⒩���V���ЂƂ������A�}�����[��
�O�̔Ō��̏o�ŕ����肪���Ă������킯�ŁA�g�����u�����ƁE�g�c���j�v�̒a������ɈႢ�Ȃ��B�ł͋g�����͓����Ȃɂ����Ă����̂��B��́s�Õ��t�i��
�ƔŁA1955�j�̎��e�������Â��Ă����̂ł���B�g���́q�a�c�F�b�Ǒz�r�i���o�́s�V���t1978�N7�����j�͂����n�܂��Ă���B
�u���͏��a��\�Z�N�ɁA�}�����[�ɓ����āA�V���́s���w���S�W�t���A��y�̈�l�ƒS�������B�������Ԃł���A���Ԃɗ]�T�����������߁A�}���ژ^������
���Ƃ𖽂���ꂽ�B���܂��܂��̏o�������肪�悩�����̂ŁA���̌l�S�W�s��t�S�W�t�̓��e���{������悤�Ɍ���ꂽ�B�^���͂��̎��A�͂��߂Ęa�c�F�b
�Ȃ�l�Əo������̂��B�������������������A���e���{�������Ƃ��Ă͗��h�Ȃ��̂��o�����B���ꑢ�{�܂ŁA���͎肪����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�������т���
�����̂݁A�G�k�����肵�āA�e�����Ȃ��āA��t�����̑��ɁA�s��Ƃ����t�Ɓs�\�a�c�t�s���D�L�t�Ȃǂ̏����������Ă��邱�Ƃ�m�����B�^�a�c�F�b�͑���
����A���̂Ȃ��ɁA���z���鍰�ƐE�l�C������������A��Ȓj�Ǝv���Ă����炵���B���̂���A���͖��z�L�����̉��h�ŁA�Ђ����Ɏ��������Ă����B���̃f
�r���[��Ƃ������ׂ��A���W�s�Õ��t�͂����Ő��܂ꂽ�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꎵ�܁`�ꎵ�Z�y�[�W�j�B
�����̋g���́s���w���S�W�t�̑}�G���g�c���j�����Ɉ˗����A�a�c�F�b�Ɓs��t�S�W�t�̓��e���{���쐬���A���S�W�̑������{��S�����A�g�c�Ɠ������̉�
�h�łЂƂ莍�������Ă����B���˂Ȃ悤�����A���͋g�������g�c���j�̑��������邱�Ƃ��瑕�����n�߂��̂ł͂Ȃ����Ƒz������B�g���̐�O��2���A���̏W
�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j�Ǝ��W�s�t�́t�i���A1941�j�́A���҂�����̎��̃m�[�g�̕\���ɕM�ŏ����𐴏������悤�ȁA�����̉����Ƃ���������
�ʂ����Ȃ��B����͏��������������ł��邱�ƂƂ͖��W�ł���B�e�v�f�̑����I�ȕz�u�������Ă���̂��B
 �@
�@
���c�~�s���Ɛ��Ёt�i�}�����[�A1953�N7��5���j�̖{���ƃW���P�b�g�k�����F�g�c��
�j�l�i���j�ƈ����s����Ɩ�
���̊ԁt�i�����V���ЁA1954�N4��10���j�̖{���ƃW���P�b�g�k�����F�g�c���j�A�莚�F�����ыg�l�i�E�j

���c�~�s���Ɛ��Ёt�ƈ����s����Ɩ����̊ԁt�̕\���k�����F�g�c���j�l
�����ɋg�c���j������2��������B���c�~�̒Z�я����W�s���Ɛ��Ёt�ƈ����̒��я����s����Ɩ����̊ԁt�ł���B���҂̎d�l���ȒP�� �\�ɂ܂Ƃ� ��B
| ���� | ���^ | ���{ | �y�[�W�� | �W���P�b�g | �\�� | �{�� | �艿 |
| ���Ɛ��� | �l�Z�� | �㐻�E�����E�۔w | �O��l�y�[�W | 4/0�F | 1�F | 2/0�F | 290�~ |
| ����Ɩ����̊� | �l�Z�� | �㐻�E�����E�۔w | �l��l�y�[�W | 4/0�F | 2�F | 2/0�F | 320�~ |
�����̕��|���ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��̍قł���B�����q�g �����Ƌg�c���j�r�� �u������̎d���Ɍg����Ďl�A�ܔN�B�g�c���j�͎��g�̑����X�^�C���̊���������܂��ɐ��������̂Ǝv�����v�Ə��������A���̋L�q�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���Ȃ��Ƃ�����2���́A�G��ǂ����鑕���Ƃɂ�錩���Ȏd���ł���B�g���͉�Ƃ̗D�ꂽ���������āA�Zᘂ������Ȃ��������낤���B���n�ɕ����ƃJ�b�g��z �����g�c�̕\���́A�g���������̍��@�Ƃ��܂�ɂ悭���Ă���B�g�c�̎������Ō�̓���̂悤�ɂ��ās�Õ��t�̎��т������������g���́A�^�甎�̍ז��� ���̊G�āA���W���ЂƂ̂܂��������^��i�ɂ��肠�����i�g�����́s�Õ��t���g�c���j�̊G�ŏ��肽�������̂ł͂���܂����j�B���l�Ƃ��ẮA������ �����ƂƂ��Ă̋g�����̕����ɁA�g�c���j�̑��݂Ƃ��̍�i���G��Ă���B�G��`�����A�`���������g�p�����A�C�S�̒m�ꂽ�`����̃J�b�g�Ɩ������������Ŕ� ��W���P�b�g�E�\���E�{�����\������g�����������A�����炭���̎�������ق������̂Ǝv����B
�k2010�N8��31����
�L�l
����A�ѓN�v���珬�R���s�����Ȓ��t�i�}�����[�A1954�N4��15���j�̏��e�i�W���P�b�g�E�\���E�{���j�̃J���[�R�s�[�����傤���������B7��21
����
�т���̃u���Odaily-sumus���q��
���Ȓ��r��
�����L�����A�b�v����Ă����̂ŁA�u�s�����Ȓ��t�̃W���P�b�g�i�ł���ˁj�ʐ^���q���ł����̂͂��肪���������ł��B�\�������������Ƃ��Ȃ��������̂ŁB
�q�g�c���j�̑�����i�r�ŋg�����ƌ��j�̂��Ƃ����������Ƃ�����̂ŁA���ǂ���������K���ł��B���̈����A�����ɂ��Ǝv���܂����v�ƃR�����g������
����A�т���u�g�c���j�Ƃ����l�͂���������Ƃ�������ł��ˁB�\���͕��������A���ɏ����ȂĂ�Ƃ����̐��悪����A�g���D�݂̃��C�A�E�g���Ǝv���
�܂��v�Ƃ��Ԏ����������������A�ߓ��̏��e�b���ƂȂ����̂ł���B

���R���s�����Ȓ��t�i�}�����[�A1954�N4��15���j�̃W���P�b�g�i�\�P�E�w�E�\�S�j�k��
���ѓN�v���l
 �@
�@
���E�{���i���j�Ɠ��E�\���i�E�j�k������̉摜���ѓN�v���l
�o���r�ň͂�ꂽ���t�i�����A�k��㎵�y�[�W�l�j���N�����Ă������i�����͐V���ɉ��߂��j�B
�u�����Ȓ�
�艿�@��S���\�~�^�n���艿�@��S��\�~
���a��\��N�l���\�ܓ� ���s
�m�u���v�̌���n
���ҁ@���R���^���s�ҁ@�Óc��^����ҁ@�����e�Y�^���s���@������В}�����[�^�����s������䒬��^�d�b���ΐ�i92�j�܈�E��Z���^�U�֓�����Z��
�Z���^�������{���������Ј�����{�v
����ҁE������{���͋g�����́s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̂���Ɠ����ŁA������Ɋւ��ẮA����N�v�q������v�Ǝ��r���`����g�����̌��Ɂu�w�Õ��x
�́A�����̋߂Ă�o�ŎЂɏo���肵�Ă���ǂ���̈�����ɁA����ň��Ă�����v�i�ےJ�ˈ�ҁs���{��̐��E 16 ������v��
�ᔻ����t�A�������_�ЁA1983�A��y�[�W�j�Ƃ���B
�g�����́q���r�i�H�E8�A���o��1976�N11���j�̖����Ɂu���@���p��͎�ɁA�G�Y���E�p�E���h�i�V�q�r���j�A�ѓ��k��̏͋���ؗp�����v�Ə����Ă���B�����т̈��p����ȉ��Ɍf����i�s���̐����̓��C�i�[�j�B
01 �u�̏������悤��
02 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�̓��ށv07 �u����ȉC���͂��肩����
08 �Ă͂����Ȃ��v11 �u�s�A�m���t�̂悤��
12 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����k�̂�����։��v14 �u�������ĕ����Ă��Ȃ�����̐��v
19 �u�ꖇ�̎������܂��[���̂�������
20 �K���������Ă��Ȃ��v22 �u�W���X�p�[�E�W���[���Y�̍�i�ɂ͂���
23 ����E�l�@����E�C��
24 �����̊���������v30 �u���݂̓��H�M�������Ƃ͂��Ȃ�ق�v
35 �u�傫�Ȏ\����C
36 �@�@�@�@�@�@�@�@�@����̕ǂ��璊���o���v43 �u���Ƃ͔������ې�����
44 �Ɠ����Ɉ������ې�����v46 �u�J�������l�X��
47 �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�̂悤�Ȋ�v56 �u�f�ނ͖Ƌ����v
64 �u�r�̐��ʂ�
65 �@�@�@�@�@�@�@�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v
���́u�p�E���h�v�͐V�q�r���s�G�Y���E�p�E���h���W�t�i�p�쏑�X�A1976�N9��30���j���낤����A��f�̈��p����ɒT���Ă݂�B
�W���_�̃��F�[������ɂ܂Ƃ���
�@�@�@�@����ɕY���̗t�̂悤�ɋ���ׂ��L���e�[��
�̏������悤�ȑ����ȓ��{�b�e�B�`�F����Z���C�I�������m���Ă���
�@�@�@�@�@�@���F���X�P�X�������ċ^��Ȃ��������̂�
���������u�����g�̊��F�̓���
�@�@�@�@�@�@���[�x���X�ƃ����_���X�̂Ȃ܂̓��Ɏ����Ă��܂����i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j
�`���ɑΉ����邱��́A�p�E���h�̑�\��s����[�L�����g�[�Y]�t�k�攪�\�я��l�̓߂ŁA�g���́q���r�S66�s���h���C�u����ɂ������āA�����ȏ��o�����Ă���B
�@���ۂ�������邱�ƁB�悢�U���ł��łɂ���Ă��邱�Ƃ�����ȉC���ł��肩�����Ă͂����Ȃ��B�i�����A�O�l��y�[�W�j
����͎��_�q�C�}�W�Y���r���́q����r�̈�߁B������C�����āA���t���C���i�g�����g�A�قƂ�Ǘp���Ȃ������j���ւ�����e�ɕς��Ă���B�܂�11�́u�s�A�m���t�̂悤�Ɂv�́A�����O�l��y�[�W�́u�܂��́A���ʂ̃s�A�m�̋��t�����y�̋Z�I�ɂ��₷�̂Ə��Ȃ��Ƃ��������x�̓w�͂����̋Z�I�ɕ���Ȃ��ł��A���Ƃ̋C�ɓ��邱�Ƃ����Ȃ������ɂł���Ǝv��Ȃ����Ɓv�ɋ��邩�B
���B�������Ă������Ȃ��i�C�`���Q�[���̐��݂����ɁB�i�����A��l�Z�y�[�W�j
�g�����s���сk���\�сl�t��nightingale�i����e��[�T���i�L�h��]�A�w���FLuscinia megarhynchos�j ���u����v�ƕύX�����̂́A�l���ƂƂ���̂�������[�u���낤�B�����܂ł͏������������A���̒��ו��������̂�19�ȍ~�̏o�T���킩��Ȃ��B�����̂��ׂĂ��ѓ��k��̏͋傾�Ƃ͎v���Ȃ��̂����B�ނ���ӊO�������̂́A�ʂ̎��сq���̐��̉ār�i�H�E24�A���o��1979�N8���j�Ɂu�p�E���h�i�V�q�r���j�̏͋�v���ؗp����Ă��邱�Ƃ��B������̎��ɂ͒����t����Ă��Ȃ��̂��B
01 �u�E�q�͕����Đ��тɓ���v�c�c�E�q�͕����ā^�@�_�̂킫���^���тɓ���^�쉺��������Ă��Ƃɏo���i�s���сk��\�O�сl�t�A�����A���Z�y�[�W�j
04 �u���l�����Ɍ����Ă���v
07 �u���̉Ԃ�
08 �����琼�ւƍ炫�ق���ԁv�c�c�u�ǂ̉Ԃ́^�����琼�ւƍ炫�ق���ԁ^�킽���͂��ꂪ�U��Ȃ��悤�ɂƂ߂��v�i�s���сk��\�O�сl�t�A�����A���܃y�[�W�j13 �u��т��������ɔL���������܂�v�c�c��т��������ɔL���������܂�i�s���сk��O�\��сl�t�A�����A��Z�l�y�[�W�j
15 �u���̉Ă�����C�݂�
16 ���F���C����������
17 ���v19 �u�Â���̂Ȃ���
20 ���F�͌�������߂�v�c�c�u�Â���̂Ȃ��ŋ��F�́^��������߂�v�c�c�i�s���сk��\���сl�t�A�����A��l��y�[�W�j
�g���̓p�E���h�́s���сt����s��6�s��f�������āA�S20�s�̎��т݂������̂ł���B�q���̐��̉ār�͋g�����ɂ��A���p�̋����G�Y���E�p�E���h�ւ���̂Ƃ݂�ׂ����낤�B
�u�g���@�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB�k�c�c�l�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ����ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���v�i������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�r�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A��Z�y�[�W�j�B
�g�������ɂ����Ă͈��p���̂��鎍��ł����҂̏͋�̎ؗp�Ƃ͌��炸�A�g�������g�̕��������p���Ŋ����ă��A���e�B��Nj����Ă���ꍇ�����邩��A�o�T�T������ؓ�ł͂����Ȃ��B
�O�D�L��Y�i1920-92�j�́q�g�����̎��r�i�s�����t18���̐��M�q���̍D���Ȏ��r�A1960�N6���j�ŁA�`���Ɂq��́r�i�C�E13�j�������Ă��������Ă���B
�@ �ނ̎������ɃV���b�N��^�����̂́A�ނ̎��I�{�\�̋��x�ȍ��������A���̎��I�{�\�ɋ����i��������ŁA���̋��x�Ȏ��I�{�\�ɂ���đ�����ꂽ���ꂪ�A�����̗l���́A��邬�Ȃ��\���ƂȂ��ĊJ�����Ă��邩��ł���B�����ɂ͒m�I�V�Y�̋ȐR�����͟|���Ȃ��B�ނ̌��ꂪ��邬�Ȃ��\���ƂȂ��Ĕ���̂́A�ނ̃��e�B�t�̔c���̋��ł��ɂ��̂ŁA����̓��_�j�Y���̒m�I�ߑ��̐R�����ɂ����̂ł͂Ȃ��B�ނ̒m���́A���삷�錾������I����ɘB�������A�蒅�����A��т̎��Ƃ��ċK�����铭���ɂ����Ă���B�i�����A��Z�y�[�W�j�B
����͎O�D���s�m���t��ǂ�Łi�����炭���҂��瑡���āj�A�g���ƈ�x�������b���������Ƃŏ��������̂����A����������Ƌg���́q�킽���̍쎍�@�H�r�i1967�N���\�j�͎O�D�̂��̕��͂܂��ď����ꂽ�̂�������Ȃ��B��f���p�͌��_�̕��������A���̑O�Ɏ��̈�߂����邩�炾�B
�@ �g���̎����A���_�j�X�g�̉e������o�����Ȃ���A�����e�Ȓm�I�V�Y�ɂ�������Ȃ������̂́A�|�G�W�C�����I�{�\�̐[���Ƃ���ő����Ă�������ŁA�ނ��������������A���ɂ��Č��̂����߂炤�̂́A�ނ̎��I�{�\���A�������ɂ͎���i�ȊO�ɂȂ��Ƃ������ƁA���̔��z�Փ����m���̌��̂Ƃǂ��Ȃ��Ƃ���ɍ��������Ƃ�m���Ă���A����������A���_��胁�`�G��M��������Ȃ����Ƃ�����Ă��邩��ł���B�^�ނ��u����ہv�ƌ�������A�u�����ɕ����̎��������L����v�ƌ����̂��A����͔ނ̎��w���_�Ƃ������A�ނ��݂�����̃��`�G�ɑ��鎩�o���甭�����ޓƎ��̕��@�_�Ȃ̂ł���B�i���O�j
�u����ہv�͂��̌���O�D���g��������_����ۂ̃L�[���[�h�ƂȂ邪�A�O�D���g���̘b�����̂悤�ɗv�����ƂŁA�t�ɋg���͎��g�̔������Ċm�F���āA�̂��Ɂq�킽���̍쎍�@�H�r�����M�����̂ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɁA���́q�g�����̎��r�͋g���Ƃ̃X�N���b�v�u�b�N�ɓ\���Ă����������ŁA�����ǂg��������ۑ��������Ƃ̈Ӗ��͑傫���B
�g���ɂ́s�O�D�L��Y���W 1946�`1971�t�i�T�����I�A1975�N2��15���j�̞x�q�l�ƍ�i�r�Ɋ��q��ȓ��̂��Ɓ\�\�O�D�L��Y�r�Ƃ������z������B�b�̓s����A�{���i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����`��Z��y�[�W�j�̒i���ɔԍ���U���Đ������邪�A����͂ǂ����Ă��g���ƎO���R�I�v�̃j�A�~�X�����������͂Łi�D�`�E�j�A�O�D�L��Y�ɂ��Ă̂��́i�B�A�H�j�Ƃ͎v���Ȃ��i�O�l�̔w��ɍ��}���g�̉��l�̂悤�ɗ����͂�����̂��A�y���F�ł���j�B����ȉ�Ԃ��ʗp����̂��g�����O�D�Ɛe������������ŁA����͍Ō�̒i����ǂ߂킩��B����A�g�����O�D�̎��ɐG�ꂽ�q���z�r�i�s���㎍�蒟�t1979�N2�����q�������ܔ��\�r�j�ɂ́A�u����M�v�k�s�h���s�t�l�A�����ρk�s���t�t�l�Ƃ͂܂��ʎ�́A���n���������֓��B�����A�O�D�L��Y�s�ђ������t���A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����W���ƁA���͎v���Ă���v�i�����A��Z�Z�y�[�W�j�Ƃ���B
�i���������͂����ăX�E�F���E�w�f�B�������j
���v�E�m�[��
�͂邩�ɒ��������̌ۓ�
���̐��̐���[���̂�]�c�c
�q���̒lj��r����
�s�ђ������t�i���X�A1978�N5��30���j�́q���̒lj��r�̈�߂́A�g���̒��ю��q�g��i���Ɏ~��r���v�킹��B
�ҁb�O�D�L��Y
�����ق̂߂����K���X�̂ނ�����
���̏����Ȑ��̍҂�
���N�̒��ق���������
�����ɂ��[�����Ă݂������@���傹��
�Ȃܐg�̓��̂̂�������m�肦�ʎړx�Ȃ�
�O��N�ł��ܖ��N�ł���������Ȃ����\�\�d�������̑ٓ�����h�����Ĕ���������
�ق��Ƃ��ā@�����Ƃ��Ȃ����͒���
��ӂ��̃r���̉���Ŗi���Ă��錢�̐���
�R���N���[�g�̒f�R��
������̒[�ւ䂫
������̒[�ւ���
�g���̂肾���Ĉł̖D�ڂ����ݗ悤��
�i���Ă���̂��낤
�i�u���v�Ƃ͂Ђ����傤�ɂ���ȏ�̉��ł���̂��j
���܂ł����܂ł��������悤�ɖi���Ă���
���̐����đ��������́c�c
�q�ҁr�̂��ƂɎO�D�̑�ꎍ�W�s���l�t�i��J���X�A1949�j�̊������сq���l�r��g���́q���̏ё��r�i�B�E16�j�������K�v�͂���܂��B�k�����Y�́u�����A�k�s�m���t�́l���t�̎g��������Y���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�k�c�c�l�Ƃ��ɎO�D�̎��������Ƃ��ڂ����ǂ�ł��Ȃ����ȂƂ����C�����܂����ˁv�i�s���㎍�蒟�t1978�N10�����A��Z�l�y�[�W�j�ƁA�g�����ƎO�D���̗މ����w�E���Ă��邪�A�O�D�L��Y�̑��݂��g�������Ɗւ���Ă���̂́A�g�����y���F�̎O�D�_�q�����̐l�r�i�s�O�D�L��Y���W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1970�j�̏͋�����p���āA�q������܌�b�сr�i�G�E8�j�����M�����Ƃ��Ɏn�܂�i�莫�́q�n�����Ŕ҂������Ȃ�r�́A�y���F�̌����ł́u���͎O�D���������x�ɁA�n�����ň��������Ȃ�v�ł���j�B�y���͎O�D���u���͓��̎t�v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A��l�y�[�W�j�Ƌ��A���̌�����т̎U���q�a�߂镑�P�r�i�s�V���t�A�ځA1977-78�j������������A�g���́u���p���v�ɎO�D�̏͋傪���ڌ����Ȃ��Ă��A���̑��݂͖��������Ȃ��B���ꂾ���ɁA�g�����O�D�L��Y�̕��Ƃɂ��đ��������Ȃ������͎̂c�O�ł���B�g���ƎO�D�̌�V�͋g���̎��܂ő����A�Ƃ��ɐ��e���O�Y��y���F������������́A�s�y���F��t�ɏڂ����i�O�f�q��ȓ��̂��Ɓ\�\�O�D�L��Y�r�́A�����ł́q20 �X�y�[�X�J�v�Z���̗[�ׁ\�\��ȓ��̂��Ɓr�Ɖ��肳��Ă���j�B
�g�����͒k�b�q�����ƍ��ׁr�i�s�f��|�p�t1969�N3�����́q�����̍�Ƙ_�r���j�ŁA�u��a�����ƐV������Ƃ����v�i�k�b�̕���j�ɂ��ďc���Ɍ���Ă���B�g���̉f��_�Ƃ��Ă����������e�����A�Ƃ���ǂ���Ɏ��g�̎���ɂ��Ă̌��y������A���ɂƂ��Ă͂ނ��낻�ꂪ�M�d�ł���B���������ϓ_����k�b�̔������������Ă݂悤�i�{���̌�A�͒��������j�B
�@���Ƃ��ƁA�ڂ��Ƃ����l�Ԃ͔�]�Ƃ����s�����͂ł��̂����܂���B�y���݂Ō����Ⴄ�Ƃ��A���Ƃ��������ɂ����炷���̂����邩�Ƃ����C�����Ō����Ⴄ�B
����Ȃ����炢���Ƃ������Ƃ͂Ȃ�����ǁA����Ȃ����̂����Ƃ����l�͍D���Ȃ�ł��B�l�Ԃ̍l�����̒��ʼn���Ȃ��̂����l�Ƃ����̂͐������ƂŁA�ڂ����N�ɂ�����Ȃ������A�L���łȂ��āA���}�Ȍ���ō�肽���B�ł������Ă��܂��킯�ˁA�܂������Ă��܂��킯�ˁB�f�悾�ƁA����_����Ȃ����̂������Ȃ����Ƃ����C������B
�@�ڂ��́A���̐V�����f���ƂƂ����̂͒m��Ȃ�����ǁA���Ƃ��Ύ������ꍇ�A�ڂ��̏ꍇ�͐悪����Ȃ��B�n������܂��n��A�ǂ��Ŋ�������̂��ȁA�������A�����Ň��ƂȂ�킯�ł����A�f��̏ꍇ�̓V�i���I�Ƃ�������ňꉞ�̍\�}�Ƃ������A�i�s�w��������B���̏�őn��V�������z�Ȃ�A�C���[�W�B��������̂ł͂Ȃ����ȁB
�����ł͐V������������Ă��Ă��A�f��ł͂��܂�ÏL���̂͌������A�����������Ԃ����܂������ė~�����Ǝv���B�������o�T�o�T���ĕ��G�Ȏv�l��D�荞�܂��ƍ����Ă��܂����Ƃ�����B�~�߂Ċӏ܂ł��Ȃ����E������B
�Ƃɂ��������̂悤�ȏ��s���I�l�Ԃ́A������x�����̂����䂤�G���`�b�N�Ȃ��̂��B�낤�Ƃ��Ă���l�Ԃɋ�������B�܂��߂ȍl�����ƕs�����ȍl�����ꏏ�ɓ����Ă���B�ᏼ��i�ł����A�]���ɂȂ����u�Ƃ��ꂽ���߁v���u���̕��Q�v�̕����D�����B�R�J���j�̂��炵���������ƁI�@�Ă��Ȃ���ʂ̍����B���肤�邱�ƂȂ�ł���B�|�p�Â����ݒ�����Ă��Ȃ��ȁB���Ă��Ȃ��āA�������[�݂�����B
���\���ꂽ�Ƃ������̂́A���Ɋւ��Ă����ƁA�����ł�����Ȃ����̂������ł����A�N���ڂ���⑫���Ă悭�݂Ă����l������̂ł͂Ȃ����Ƃ悭�v���B�f�悾���Ă������Ǝv���B�����ɂ����ĉ���Ȃ��Ƃ��낪����A�����厖�ɂ��Ă�����ł��傤�B���������ӂ��ɂ��č�҂͎��M�������Ă����A�|�p��i�͂��ׂċ~�ς���āA�悭�Ȃ��Ă����B�i�s�f��|�p�t1969�N3�����A���`��O�y�[�W�j
�Ōォ��ӂ��߂�ǂ߂킩��悤�ɁA�g���͂��̒k�b�Ő��z�q���}���E�|���m�f��G���r�i���o�́s�G�������~�G�[���t1���A1985�N9���j�́q�P�u�َ��������鎞�v�r�ɑ���������e�𒆐S�Ɍ���Ă���B�Ƃ��ɁA���̐��z�Ō��y����Ă���f��͑S����20�{�B�����̏G����d�������邽�߂ɁA�g���͂����������{�̃��}���E�|���m�f����ς��̂��낤���B�i����͒k�b�ł����y������i�j
�P �u�َ��������鎞�v
�Q �u�����˂��ݏ��m�v�E�u�F��o���v
�R �u��������E�G�ꂽ�~��v
�S �u�l�ȏW�c�\�s�v�������v
�g�����k�b�Ō��y���Ă����i�̂����A���z����쐬������L���X�g�ɂȂ�6������Ɍf����B
�ȏ��26��i�̂Ȃ��Ŏ����ς��̂́A�킸���Ɏᏼ�F��́s�َ��������鎞�t�i�ᏼ�v���_�N�V�����A1966�N7���j�������i������1990�N�ɑ嗤���[����o���q���l�f�挆��S�W�r�Ƃ����r�f�I�e�[�v�Łj�B�����Ƃ������̉f��̌��J�����͂܂������w���ŁA�f��قŊς���͂����Ȃ��������B�g���́q�P�u�َ��������鎞�v�r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�������̍��A�u�s���N�f��v�̔��e�ɓ���Ȃ��A��̍�i���A���͏ꖖ�̃s���N�f��قŊςĂ���B����́A�ᏼ�F��́u�َ��������鎞�v�ł���A��a�����́u����̋G�߁v�ł���B�Ƃ��ɁA�u�َ��v�ɂ͏Ռ��������̂������B�R�J���j�̕�����u�j�v���u���v�𗇂ɂ��āA�x�b�h���������A���ւ����ɔ������B�����āA�Ђ�����u���v�̓��̂��A�ځi�x���g�H�j�Œ@���Â���̂��B���̔����I�ȍs�ׂ�����߂āA�ɖ��ł��邽�߁A���Ԃ͎~��A���̔ߖ�������Ԃ�c�ȉ�����B�ː����Ȃ���A��ق����܂ꂽ�A�e�̉f���̐��E�B�u�َ��������鎞�v�́A�ꐡ�A�ނ��݂Ȃ���i�ł���B�u�j�v���R�J�a�j���ƁA���ƂŔ��������A�u���v�ɕ������̂͂����Ȃ鏗�D���A���܂��m��Ȃ��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܈�y�[�W�j
�O�f�r�f�I�̃p�b�P�[�W�ł́A���̏��u���J�v�͎u���݂͂�B�s���{�f��f�[�^�x�[�X�t�ɋ���A��a�����́s����̋G�߁t�i�ᏼ�v���_�N�V�����A1966�N12���j�ɂ��o�����Ă���B

�ᏼ�F��ē�i�s�َ��������鎞�t�i�ᏼ�v���_�N�V�����A1966�j�ɂ�����u���݂͂�
���e���O�Y�̎��ƎU���̑I�W�s���e���O�Y�R���N�V�����k�S6���l�t�i�c��`�m��w�o�ʼn�j��2007�N
��6������11���ɂ����Ċ��s���ꂽ�i�ŏI���̐��M�W�ɂ́u��z�̐��e���O�Y�v�Ƃ��ċg�����́q���e���O�Y�A���x�X�N�k�i�Ǔ��j�l�r�����^����Ă���j�B
���Ă̑I�W�s���e���O�Y
���Ǝ��_�k�S6���l�t�i�}�����[�A1975�j�����W�i���Ƃ����s�X
�L�t���s�߉́t�j
�Ƃقړ������̎��_�i���Ƃ����s���{�t�j
���ЂƂ̊��ɂ܂Ƃ߂Ă����̂ɑ��A�V�q�r��҂ɂȂ鍡��̂���͎��W�i2���j�E�|�W�E�]�_�W�i2���j�E���M�W�ƁA�W�������ʂɐ��e�̕��ƂI��
�����e�ƂȂ��Ă���B
�g�������e���ǂ����Ă������́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�\�\�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j��s�g�����U�����k���̐X���Ɂl�t�i�v
���ЁA2006�j�őS�т�ǂ߂�\�\���Y�قɌ���Ă���A�����Œ�������K�v�͂Ȃ��낤�B�O�̂��߂ɕt������A�q��q�r�i�s�_��I�Ȏ���̎��t�j�A�q��
�̉��r�i�s�Ẳ��t�j�A�q���́r�i�s��ʁt�j�A�q�i���̒��Q�r�i�������сj��4���т����e�ɕ������Ă���i�g�����̈��p�͋�ɓo�ꂷ�鐼�e���̏o�T�T��
�͍���̉ۑ�Ƃ������j�B
����A���e���g�����ǂ����Ă������͂킩��ɂ����B���Ȃ��Ƃ����l�E�g�����ɐG�ꂽ�P�Ƃ̕��͂͂Ȃ��悤���i���e�̎��тɁs����t�����́q���V�L���r����
�邪�A�s�g�����Q�l�����ژ^�t�ɂ͐��e���g���ɂ���
�����������Ƃ��ċL�ڂ��Ă��Ȃ��j�B�����œ�����p����������Ȃ��̂����A�ȉ��Ɂs��{
���e���O�Y�S�W�k��12���l�t�i�}�����[�A1994�N11��20���j�̌��J�K�M�q���e���O�Y�N���r�i�u���a�\���N�i��㔪�O�j�v�ȍ~�͐V�q�r��q�N����
��r�j����A�g�����o�ꂷ�鍀��ς��}�킸�����Ă݂�i�Ȃ��g���Ɠ��i�����̑��̐l���͊��������j�B
���Ȃ݂ɐ��e�̔N���Ɋւ��āA�g���͎��M�N���u���a�\���N
��㔪��N
�Z�\�O�v�̍��Ɂu�ӏH�A�_�c�̃��h���I�ŁA��c�j�Y�A���J�K�M�A�V�q�r��A�]�X���F��ƏW�܂�A�u���e���O�Y�N���v�̊m�F������v�i�s�g�����k����̎�
�l1�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���A���e�f����s���e���O�Y�S�W�t�Ɗւ�肪�[���������Ƃ��������킹��B
���a�l�\��N�i���Z���j ���\�l��
�@�\�����A����C�����͂މ�ɏo�ȁi���h�B�̒��j�B���̉�̋A�H�A�g�����k�c�c�l������ɏ����A�Ɉ����k����B���a�l�\�O�N�i���Z���j ���\�܍�
�@�O���\�l���A�k�c�c�l���̍����T���}�����[��K�ˁA�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�Ɛ_�ے��E�G�����ݕ����B���a�l�\�l�N�i���Z��j ���\�Z��
�@�O����\�Z���A�}�����[�w���e���O�Y�S�W�x�̊��s���肵�A����u��G�v�ɂāk�c�c�l�g�����k�c�c�l�ƕҏW�ō����̉�����B���a�l�\�ܔN�i��㎵�Z�j ���\����
�@�O���\�����A�_�c�u�����v�ɂđS�W�ō����̉���J���B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB
�@�O����\�����A�ԍ�u��t�v�ɂāA�S�W�ō����̉���J���B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB���a�l�\�Z�N�i��㎵��j ���\����
�@�O���O���A�w���e���O�Y�S�W�x��ꊪ�����A�_�c�T���ɂďj���A�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB
�@�l�������A�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�ƕS�����ɗV�ԁB
�@�܌���\�Z���A�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�Ɗ��q�ɗV�сA�������v�l�ƍ��k�B���a�l�\���N�i��㎵��j ���\���
�@�����A�u�����v��\�㍆�A���e���O�Y���W�������s�i��i�u�j���ؒf�v����e�B�q�����r�k�c�c�l�g�����k���́q��q�r�i�F�E15�j�l�k�c�c�l�j�B���a�l�\���N�i��㎵�O�j ���\��
�@��\���A�S�W�����j�������h���\���ɂčs���B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB���a�l�\��N�i��㎵�l�j ���\���
�@�l���\����A�`�@�@�ɂď��O�Y��A���Ղ̖n�G��W�����A�V�ԁB�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�Q���B���a�\�N�i��㎵�܁j ���\���
�@�Z���\�����A�E�w���Ǝ��_�x�k�}�����[�Łw���e���O�Y ���Ǝ��_�x�S�Z���l���s�̉������l��ŊJ�����B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB
�@�w���k���e���O�Y���Ǝ��_�l�Y�x�\���O�\����@�l�܌ܕŁ@���w����x�w�������сx�A���_�w�����G�b�Z�C�x���A�w�䓁�Ɨь�x���B�N�����J�K�M�B�t�^�g�� ���u���e���O�Y�A���x�X�N�v���a�\��N�i��㎵���j ���\�l��
�@�\��\�����A�a�J�u��`�ǂ����v�Łk�c�c�l�g�����k�c�c�l�ƖY�N��B���a�\�l�N�i��㎵��j ���\�Z��
�@�Z���A���W�w�l�ށx�����s�B���O�Y�͋g�����Ɍ����āu���ꂪ�ڂ��̍Ō�̎��W�ł��v�ƌ�����B
�@�Z���\����A���W�w�l�ށx�̌��{�o���A�g�����k�c�c�l�Ƒ�X�ؔ����k���i�ňԘJ����J���B
�@�Z����\����A�a�J�u��`�ǂ����v�Łw�l�ށx�̏o�ŏj���B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB
�@�\���A�g�����w�Ẳ��x�̑����`���B�k���q�Ẳ��r�i�H�E20�j�����ځl
�@�w�l�ށx���@�Z����\���@�}�����[�@���E��cm�~��l�E��cm�@��㎵�Ł@�����@������S���@�艿�l�܁Z�Z�~�@�t�^�p���t���b �g�@�k�c�c�l�g�����u�s�l�ށt�o���v�k�c�c�l
�@�w��̖���x���@�\�ꌎ�O�\���@�ԗj�Ё@���E�Ocm�~���E��cm�@�����@���ґ}���t�@��Z��Ł@����g�����@�艿�Z�Z �~
�@�u���㎍�ǖ{�X�@���e���O�Y�v�i�v���Ёj�����s�i�k�c�c�l�g�����u���e���O�Y�A���x�X�N�v�k�c�c�l�j�B���a�\�Z�N�i��㔪��j ���\����
�@�ꌎ��\���A�w��{���e���O�Y�S���W�x���s�B����Œa���j���̉���J���B�k�c�c�l�g�����k�c�c�l�o�ȁB
�@�\�ꌎ�������O�\���܂Őԍ�̑������p�قŁu���e���O�Y�̊G��v�Ƒ肵�ēW����J�����B�k�c�c�l�����A�k�c�c�l�g�����v�ȁk�c�c�l����A�Εv�Ȃ� �����Ő��e�Ƃɍs���A�x���܂Œk�B���ꂪ�u���͉��֍~��Ă��ĊF����ɂ����A���ׂ����v�Ƃ����A��K���珇�O�Y���~��Ă�����A�̂ɐk�������Ē����ɉ� ��B���a�\���N�i��㔪��j ���\���
�@�v��G���Ǔ����W�y�ъW�L���͍��L�̒ʂ�ł���B
�@�u���㎍�蒟�v�������i�k�c�c�l���k��u��ނȂ����I���݁v�g�����k�c�c�l�j
�@�u�����C�J�v�������i�k�c�c�l�g�����u���́v�k�i�J�E13�j�l�k�c�c�l�j
�@�ق��ɒǓ����̌f�ڂ��ꂽ���̈ȉ��̂Ƃ���B
�@�k�c�c�l�g�����u���e���O�Y�A���x�X�N�k�i�Ǔ��j�l�v�i�u�V���v�������j���a�Z�\�O�N�i��㔪���j
�@�Z���\���A�ԍ�̑�����قɂāu���e���O�Y���Âԉ�v��Z�����J�ÁB���N�l�́k�c�c�l�g�����B�������N�i��㔪��j
�@�O���O�\����A���e�W�k��o�l�I�[�v�j���O�ɂ́k�c�c�l�g�������̑��������o�Ȃ����B
�@�l���������܌��\�l���܂ŁA�V���s���p�قŁu�i���̗��l���e���O�Y�@���E�G��E���̎��Ӂv�W���J�ÁB����҈�Z�l��Z�l�B�W����J�^���O���s�B���e �́A�k�c�c�l�i�����E�����j�k�c�c�l�g�����k���́q�i���̒��Q�r�i�������сj�l�k�c�c�l������N�i����Z�j
�@�܌��O�\����A�g���������B
���e���O�Y�N���ł́A�g�����}���̎Ј��Ƃ��đ������肪�������e�S�W��s�l�ށt�֘A�̋L�ڂ��������ƂɋC�����B�g�������z�ɋL������
����������
�i����͂ނ���t�ŁA�N���Ҏ[�҂��g��������̘^�����\���������j�B�Ȃ��g���ɂ́q���e���O�Y�A���x�X�N�r�ȊO�ɁA�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t����
�́q���L���r�A�q�Ǐ����r�A�q�w�v��ヷ���X���M�x�̂��Ɓr�A�q�o��r�A�q��ȓ��̂��Ɓr�A�q�ǓƂ̉́r�A�q��̎��W�̂͂��܂Łr�A
�q�y���Ȃ�́r�A�q�����d�M�f�z�r�A�q���H���߂���f�́r�A�q�������܁r�i�ȏ�A���\���j�ɐ��e�܂��͐��e���ւ̌��y������B
����A���l�Ƃ��Ă͐��e���O�Y���W����Ǔ����ւ̊�e���ڂɂ��B�ŏ��̖�ɖ߂�A���e���O�Y�ɂƂ��Ă̋g�������l����ɁA�u����������v�}�����[�̕ҏW
�ҁE�����ƁA�Ƃ����̂�������߂������̂ł͂���܂����B���ƕ\���ɐ��e�̑��������������s���[���h���b�v�t���o�������Ƃ̋g���ɑ��h���鎍�l�ɂ�
�Đu���@����������A�\�z�ɔ����ĒN�̖��O���o�Ă��Ȃ������B���e���O�Y�́H�@�Ɛ���������ƁA���e�Ɍ��炸�ǂ�Ȏ��l�̉e���i�Ƃ��Ԃ����͂����j
���U�肷�ĂĐi��ł����A�Ƃ����C�T������ɂ��ꂽ�B���̂Ƃ��g���̔]���ɂ́s����ꂽ���t�Ƃ��s�߉́t�Ƃ��قȂ�A���g�́u���ю��v�\�\����͓y���F��
���𓉂q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�̎�@����I�ɓW�J�������̂ɂȂ����͂����\�\�̗\�����Q�����Ă��Ȃ��������낤���B
�g �����̐��z�q�w�ɑr���r�́s���{�E�t1985�N9�����́q���̕��i�r�Ƃ����A�����R�����ɔ��\���ꂽ�i�g���̉��18���~23�s �~3�i�A���Ȃ킿 1242���̖{���X�y�[�X�j�B�̂��Ɂs�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�A��`��y�[�W�j�Ɏ��߂���ہA�قڎO���̓��800 �����ɏk�߂�ꂽ�B�g���̐��z�ł͒������P�[�X�ƌ�����B��e�����̎���Z�́u����̈ꐺ�e���Ă悬��䂭����̋��ɓ��̂Ƃڂ肽��v�̂܂��ɂ������� �u���w�l�N���̍��A�h�b�W�{�[���̂�肷������A���͘]�����ɂȂ����B��`�ǂ����̋߂��̎���f�Ï��֒ʂ����߂ɁA���̋��������Ή����������̂��� ���B�v�����ꂽ�̂́A�Z�̂��������Ă邽�߂̑[�u�Ǝv����B�����ׂ��́A����3�i�߂̕��͑S�̂��폜���ꂽ���Ƃ��B
�@���̈��́A��\����r���̂ŁA�u��`�����v�Ǝ���������B
�@���͋v���Ԃ�ŁA��`���ɂ��Q�肵�āA�֍s�����B��Ƃ��������Ɠ��₩�����A���i�͗҂����B����̓����̉E�p�ɁA�A�I�m�Ƃ����ߋ�X������B�c�� ���A���e�ɂ���Ă̊ω��l�Q��̋A��ɁA���܂��Ă��̓X�̑O�ŁA���������������ŁA���������̂��B�͉Ƃ�������ē�\�����炸�̋����Ȃ̂ŁA�� �N����͂悭�Ƃ�ŁA�V�тɗ������̂������B�f��X�̎G�����悻�ɁA���I�̂���Z�\�r�ɂ́A��A���j���ł����B
�@���a�Z�N�ɁA�����f�p�[�g���J�X����ƁA�����̈��������͂������āA�W�܂������̂������B�X�|�[�c�����h���o���A���[���[�X�P�[�g�ꂳ�������Ă����B
�@�q���Ȃ��A�Ђ����肵�����Д���̃K���X�P�[�X�̒��ɁA�O���̎ʐ^�W�������A�J���ꂽ�łɁA�Ⴂ���̗��̂����߂��A���͂��炭�B�t���ɂȂ��Ă� �܂����B�i�s���{�E�t1985�N9�����A���Z�y�[�W�j
�� �����J�b�g�������Ƃŕ��ӂ��ʂ�ɂ����Ȃ����̂��낤�A�u���w�l�N���̍��A�k�c�c�l�v�̂ЂƂ܂��̕��́u�k�����Ȃ�A���i�g���j�l�܂������֍s �k���� �����������l�A�e�������āA��`�����킽�k��������A��`���ɂ��Q��������l�B�v�Ǝ肪�����ꂽ�B�����[���̂́A�q���̂���̋L�q���s���܂�͂����L�t �i����R�c�A1990�j�̏��a13�i1938�j�N9��2���ɂقƂ�Ǔ����`�Ō����邱�Ƃ��i���o�́s���㎍�蒟�t1980�N10���������A���o����я��� �^�́k����Łl�ł�9��1���̂��ƂɂȂ��Ă���j�B�k����Łl�ł́q���܂�͂����L�r��D�悵�āA���o�q�w�ɑr���r�̋L�q�����������B
�@ ������B�Ă�Ղ�̎O��ׂ̗�̊ߋ�ɂ́A�������Ⴊ���Ă���B�q���̂��낱�̓X�̑O�ŁA�[���}�C�d�|�̍����Ⓛ��~�������āA��������点���� �̂��B�Ђ傤����r�̎��̉��ŁA�����̗V�j�������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�A��܈�y�[�W�j
�g
������1919�N�A�����s�{���撆�V���ƕ����i���݂̓����s�n�c��ƕ�2���ڂ��j�ɐ��܂�A4�̂Ƃ��A���̒n�Ŋ֓���k�Ђɑ��������B�k�Ќ�ɓ]������
�{���擌��`�̓�������A�����q�포�w�Z�i����8�i1875�j�N�J�Z�j���ƌ�A�{����X��2-13�i���E�n�c��{��2-18���邢��2-19�A���̏W
�s�����G�߁t�⎍�W�s�t�́t�̔��s���E����ɂ̏��ݒn�j�̎l�������ֈڂ�A22�̂Ƃ��ɂ��̉Ƃ���o�������B
�u���N������߂��������̕ӂ�́A�ƕ����ς��Ă͂����肵�Ȃ��B�x�V���̔��X�ɂȂ��Ă��鏈�̂悤�Ɏv��ꂽ�B�v�̂x�V�����ǔ��V���Ȃ�A���M������
�ƕ��̔����A�{���̔����i��������n�c��ƕ�3-10-12�j�Ɏv���邪�A�O�q�̓���`�ł͂Ȃ��A�ꏊ�����ł��Ȃ��B�g�����̏��N����𐏑z�q���̐���
�ꂽ�y�n�r��q���������̍Ղ�r�ŎÂ��Ƃ́A�X����
�U��ɔ@���͂Ȃ��B
��
�c�唪�̃G�b�Z�C�q�J�����I���̊�r�̈�߂Ɂu���k�b�ɖڂ����J���Đ^���ɕ������S����̂��g���������B�|�҃����c�͌���ł���ƌ��܂�����A��o����
���S��������ߖɋ߂����ʼn̂����肵�Ă����v�i�s�����C�J�t1973�N9�����A�����y�[�W�j�Ƃ���B2005�N��11���A���c�唪����E�\�l�q����v��
�ɂ��ڂɂ��������Ƃ��ɁA�q�|�҃����c�r�Ɓq���S�������r�ɂ��Đu���Ă݂��B�Ȃɂ����̐��܂ꂽ���a30�N�O��̂��ƂȂ̂ŁA�����������������Ȃ���
���B
�܂��q�|�҃����c�r�́A�������\�쎌�E�Éꐭ�j��Ȃ́q�Q�C�V���E�����c�r�i1952�N5��31���^���E8��1�������j���Ɣ��������B�_�y��͂�q
�i1931-95�j���X�^�[�_���ɂ̂��������́A�����~�̗w�̔������ƁA���Ȃ����߂��ŋ߂̂b�c�̃��C�i�[�m�[�c�ɂ͂���B
���Ȃ��̃��[�h�Ł@���c������^�`�[�N�_���X�́@�Ȃ�܂����^�݂���鐞[����]���@�͂��������ꂵ�^�|�҃����c�́@�v���o���� �c
��ɂ͎O�����@�����~�A��^���ɏd�����@����[�܂�������]�^����Ȃ���悩�����@����̂��Ȃ��^���ꂪ��J�́@�͂��߂ł��傤��
���Ȃ��̂�����@�������ꂵ���Ɂ^�ۂ琌������@�x������^����͂��߂ā@������Ăˁ^�ǂ����ꏏ�ɂ�@���点�ʐg��[���� ��]
�C����������߁@�A������́^�X���ė܂́@�ʂ�J�^���������Ă�@�V����[����Ȃ��Ȃ�]���^���̐h�����@�g�ɂ��݂�̂�
�i�s�������\�S�W�k��9���l�t�A�������s��A1996�N4��30���A�O�`�O���y�[�W�j
����1952�N�ɑ�q�b�g���Ă����]���`�G�~�i1937-82�j�́q�e�l�V�[�E�����c�r�ɑR���č��ꂽ�Ȃ��Ƃ������A��敨�ł��� ���Ƃ������� ���Ȃ��Ȃ��Ȃ��̉��Ȃł���B

�_�y��͂�q�q�Q�C�V���E�����c�r�i�R�����r�A�A1952�j
�o�T�Fhttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r39585774
�� ���q���S�������r�́A���c���狳���Ă����������u�������܂Ŗт��������^��冋o�锪�S���v�Ƃ����̎�����|����ɁA�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă� ���B�����̉S�炵���A��e�͂Ȃ��悤���B�Ȃ��猒��̂k�o�s�t�́t�i�J���[�h�X�R�[�v�A1974�j�����́q���S�������r����̓]�ڂ������B
�� ����͋�g�ˎ��@���ꏑ�@�̉����~�@����͌��\����̈䌴���߂��̐l�́@�\�l���̂��̒��Ł@���������ƉS��ꂵ�@���S�������̕���@�����̍D���Ȓ��Ȃ� �с@�������܂Ŗт̂͂����@�Ƃ����낱���锪�S���@���������S�����Ă����Ȃ�@���Ƃ��������̋g����Ɓ@���ւ����킹���ł��悤�Ɂ@���ꂪ���̐�� �����@��c�̃����ɉ����ā@�p�b�ƔR���o���Ύ��̌��@�l�m��܂��Ǝv�����Ɂ@�V�m��n�m��l�̒m��@�ׂ̂ƂȂ�̂��̂ƂȂ�@�ƂȂ�̃o�o�@�[�Ɍ��� �����ā@���i�����ĕߔ�����@��i��ɂ͌��s�l�@��i�������Ă����a�@���݂��̂悤�Ȏ�����ā@�\���グ�܂����s�l�@���̐��܂ꂽ���̔N�́@�Ђ� ���Ђ̂Ƃ��Ђ̂����܁@���������̎��[�Ł@����ł����Ɛ\���܂��@�\�l�Ƃ����Ώ�������\�܂ƌ���������Ɂ@�S���S��͘S�̒��@�S���S�邪�������Ȃ�@ ���̔n�ɏ悹���ā@���������n��͓��{���@�g�����Y�O�̌������Ƃɂ�@���ꂪ���S���̐F���@�ڂ��Ƃς�����F���Ł@�����Ƃ���Ȃ�����@���̎����ق�� �����@�g����ق��͖������Ȃ��@�l�����ꂽ�V�傳���@��������̃������Ŏv���o���@��m�̓y�l�̖������@�o�i�i�̔�ނ���C���o���@�܂��ĉ�X�}�l�̓Z ���Y�������̂������͂Ȃ��@�ĂȂĂȗ��̕���@���a�̌��܂Ŗ����c���@���S�������̕���
���c�唪�́i�Ƃ������Ƃ͋g�����́j�������߂��A�Ȃ��猒��̋Ȃ������Ă��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������Ȃ����A�ӂ��͓����ł͂���܂�
���i�Ȃ��炳
��̒����̈�ۂ���A�����v���j�B
�g���̌�����I���ŁA�}�����[�̕ҏW�҂��g���Ɂq���S�������r���̂��悤���������A���c����ƂƂ��ɋg���̐e����߂��\�l�q����́u�������ʼn̂��S
����Ȃ�����v�Ǝ~�߂��������B�q���S�������r�́A�������F�߂�g���̏\���Ԃ������̂ł���B
�k�t�L�l
�]�ː에���̒Z�сq���G�Ɨ�����j�r�ɁA�̏\��K��w�i�ɂ��āu�`�����炭��v���o�ꂷ��B���̂��炭�艮�̕v�w���m�ꐺ�����킹�āA�ڂŔ��q�����
�Ȃ���̂��Ă���q���S�������r���u���炭��߁v���B�����̂��炭��߂�m��l�ɂ��A�Õ��Ȉ��D��тт������ŁA��Ђ̉���Ȃǂŗ]���ɔ�I����҂�
�����Ƃ����B����q������ݍu�߁r�ɂ́A�j���u�Ӟ��������v��z���������߂ɔ`�����炭���^�����ʂ��łĂ��邪�A�����ł��炭��߁i�H�j�����Ƃ�
�ł���B
�g�����́s�A���r�A���i�C�g�t�A�s����镨��t�ɂ��ē�x�����Ă���B�܂��͎��I�U���q�˒�ɂār�i���o�́s���㎍�t1962�N1�����j�̈�߁B
�@�c�͐H����҂��Ă��Ă��ꂽ�B�Ñ�̎ϕt�ɁA������тƂ������ŁA�������肵���B�c�̎d���͏����ɂ����Ă���炵���A�r�[�����A�O�{�̂B�������̑V�̏�Ɍ܁A�Z���d������}�G���u����Ă����B���̕���̓A���r�A���i�C�g�����A�q���p�̎G���ɂ��ẮA��σG���`�b�N�ȑ}�G�������B����ő��v�A�Ƃ���̂��ȂƎv�����B�c�ɂ��킹��A���܂łɊ�肪�����̂ŁA�����`�������������炵���B���͊G�ł���A�ʐ^�ł��ꏗ�̗��̂�����Ǝh�������̂��B�F�l�̕`�����q���̂��߂̑}�G�ł������������Ȃ�A�Q���邵�������Ȃ��Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l��`�܁Z�y�[�W�j
�����āA���z�q�Ǐ����r�i���o�́s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8���j�ɂ����鏬�w�Z����̑z���o�B
�@�܂Ƃ܂��Ē������̂�ǂ̂́A�������_�Дł́w����镨��x�ʂ��낤�B�~�~�~�������āA�������G���`�b�N�ȕ`�ʂɑ�ϋ��������悤�Ɏv���B�i���O�A�ܘZ�y�[�W�j
�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�ł��������悤�ɁA���̒������_�Дł̏����́s����镨��t�ł͂Ȃ��s�����t�ŁA�g���͋L���ɗ����Đ��z�����M�����̂ł��낤�B��҂ɂ��q���r�i��ґ�\�͑��s�ꂾ���A���M�Җ��͂Ȃ��j�ɂ�������B
�u���{�ł��A�������N�ɉi��G���Ƃ��Ӑl�̖�ŁA�u�J������A�\�镨��v�Ƒ肵�ďЉ��Ĉȗ��A�\�w�ɂ��܂��{�����s����Ă�邪�A���ׂđO�L�̕s���S�ȏ���{�k���C���łȂǁl���X�ɏ������̂ł���B�ŋߏo�����́T���ł́A�u���E���b��n�v���̓����ԔV���y�э������Ɋ��s��s�̐X�c�������A���ʋ��ɒf�R������Ă͂�邪�A���Â���O�L���C���łɂ�����̂ł���A�]�ă��C���ł̒Z���̑啔���P���Ă��̂͌ȁk�}�}�l�ނȂ��v�i�s�����k��1���l�t�A�������_�ЁA1929�N12��25���A�k�O�t�l�O�y�[�W�j�B
���̓����ԔV��́s�����t����̑�1���i���O�j�Ɋ��q�S���E����r��
�@�����A���r�����i�C�g�ł�����܂��Ƃ��Ӓ������q�����邾�炤���A�u�V�����v�āu�i�����v���u���v���E�ɂ��A���̘_���ƌ����ϗ��Ƃ��K�����āA����������肠�Ђ܂��ē����}�a�c�N�����h�𔒓��̂��ƂɐU��̂ł���B�ނ���ؕ|�ɑςւ��邱�̖������̓a�������̖��c��̜}�ы����炸�A�N���o�ė\�k�킽�����l������o�A�g��������u�������A���̕��͐��݂ɂ�Â�͂���ĉʂ����d���ЁA�������̎�����{���̋��߂ɉ����ă��C���{��S�ċ͂��ɗ~���̈ꕔ���Ԃ߂���������B
�Ə����āA�������_�ДŁs�����t����{�Ƃ����o�[�g���łɌh�ӂ�\���Ă���B
�������Ɋ��s��ł̐X�c������s���镨��k�S4���l�t�͖��������A1927�N�ɃA���X���犧�s���ꂽ������҂ɂ�鏑�����낵�s�A���r����b�k���{�������Ɂl�t�i1982�N�ɖ������y��畜���ł��o�Ă���j�́q�ጾ�r�ɞH���A�{���͍������Ɋ��s��ł���q��������8�т�I��Łi��9�сq�A���E�o�o�r�̓o�[�g���łɂ��j�A�Ȃ�ׂ��킩��₷�����̂ɏ����Ȃ��������̂ŁA�q���ɂӂ��킵���Ȃ��A�������킵���Ƃ���͉��삵�Ă���B�ޏ��Ƃ͈قȂ�A���{�l�̎����I�����āA���{�̎����̂��߂ɏ����Ȃ��������̂ł���A�]�]�B�{���Ɏ��߂�̂́A�ȉ���9�тł���B�q���[�i�����Ɗw�҃d�[�o���̘b�r�q�n�T���Ɣn���̘b�r�q�Ⴂ���q�Ƒ�H�̘b�r�q�A���E�G�E�f�B�[���̘b�r�q�Ђ傤����҃n�T���̘b�r�q���w�d�����b�h�̘b�r�q�n�ǂ�ڂ��r�q�G�X�E�V���a�o�[�h�̍q�C杁r�q�A���E�o�o�Ǝl�\�l�̓����r�B���̐X�c�����s�A���r����b�t�����ォ�ȂÂ����ɉ��߂āA���肵���s�A���r�A���i�C�g�k���w���S�W63�l�t�i�}�����[�A1955�j�̕\���G�E���G�E�}�G��S�����Ă���̂��A�O�f�q�˒�ɂār�́u�c�v���Ƒ��c�唪�ł���i�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�Q�Ɓj�B
 �@
�@ �@
�@
�X�c�����s�A���r�A���i�C�g�k���w���S�W63�l�t�i�}�����[�A1955�N2��5���j�̕\���i���j�k�����F�ɓc叕�l�A���G�i���j�Ƒ}�G�i�E�j�k�G�͂���������c�唪�l
�`���Ɉ��������͂�ǂ݂������܂ł��Ȃ��A�g�����s�A���r�A���i�C�g�t�ɃG���`�b�N�Ȃ��̂����т��Ă��邱�Ƃ͌��₷���B��������������A�������_�ДŊ����́q�V���[���A�[�����Z��̘b�r�̈�߂������Ă݂悤�i�����̑����r�͔���ɂ��Ȃ����j�B
�@����Ȃ킯�ŁA�����Z���̎�ɏo������̂��������V���[�E�U�}�[���͋��Ԃ��o�āA�V�����ቺ���Չ����i�q���̑O�֍����B�����āA�l�m�ꂸ�Ȃ̗���߂��ݒV���Ȃ���Y�ދ�����̂₤�ȓf����f���Ă�B���T���̎��I�@�O���ɒʂ���閧�̒n�����̔����p�c�ƊJ���ꒆ���猻��ė����̂́A��\�l�̓z��Ɏ����ꂽ�����قǔ������Z���̔܂ł����B���ƗD�U�Ƌϐ��Ɠ�̂Ȃ����炵���̉��g�Ƃ����ӂׂ����܂́A�₢���Ƃ�����C���Ћ��߂Ȃ���A㷗r�̂₤�Ș@�����^��ŗ����B�����ŃV���[�E�U�}�[���͑�����g��ނ��A���ӂ��猩���Ȃ����₤�ɗp�S���Ȃ���A��s�̗l�q��`�������Ă�B�ꓯ�͔`���Ă����̂���₤�ȂǁT�͖��ɂ��v�͂��A���̊i�q���̂�������ʂāA��̑傫���r�̐^���ɐ݂ւ�ꂽ�����̑��܂ł����ƁA�݂�Ȉ�Ăɒ�����E�����B���T�A���̂����̏\�l�͌�{�̕w�l�����ŁA���̏\�l�͒j�̔��l�z��ł͂Ȃ����B���ꂩ��j�Ə������X��l�ÁT�g�ɂȂĕ��ꂽ�B���U��l��c���ꂽ���܂́A�u�킽���̂Ƃ��ւ����ŁA�T�C�[�h�l�I�v�Ƒ吺�ŋ��B����ƁA��l���q�炵�����g�̂�痂������l���A������ނ��o��������M���M�������Ȃ���A�����̒������o���ė����B�Ȃ�Ƃ��Ӗ��C���Ȍ��i���炤�B�����č��l�͖T�ᖳ�l�ɉ��܂̕��ɋ߂Â��~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~����𓊂����������A�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�B�ƌ��邤���ɁA���l�́~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�~�A�{�^���E���{�^���ɓZ�Ђ��₤�ɁA����ݍ��Ēn�ʂ̏�ɓ|�ꂽ�B�\�l�̓z����݂Ȃ���ɕ�ā~�~�~�~�~�~�~�~�A�~�~�~�~�~�A�~�~�~�~�~�~�A�~�~�~�~�~�~�~�A�~�~�~�~�~�~���ʂׂ��Ƃ������Ȃ����B������ꂩ�T�鍠�ɂȂāA�j�̓z��͂₤�₭���������痣�ꂽ�B��̍��l�����܂̑�����ނ����B�z��B�͂��Ƃ̏����Ɋ҂�A���������݂Ȓ����𒅂��B���U���l�����͂��̂܁T�����̉��[���p�������Ă��܂��B���ꂩ��ꓯ�͋{�a�̒��ɂ͂���A�n�����̔��͌��̂₤�ɕ��ꂽ�B�i�s�����k��1���l�t�A�������_�ЁA1929�N12��25���A�܁`�Z�y�[�W�j
�����Ɋւ��āA��҂͑O�f�q���r�Łu���X�ɏo�ė���j���Ԃ̘I���ȕ`�ʂ́A�k�c�c�l���s���{���x���l�����āA��炩����������A�\������͂炰���肵���Ƃ��������Ƃ��ӂ��Ƃ�ȏ����Ē��������v�i�k�O�t�l�܃y�[�W�j�ƃG�N�X�L���[�Y�����Ă���B��f���p���̕����Ɠ����ӏ����A��N�̑�ꐳ�j��s�o�[�g���� ����镨��k��1���l�t�i�}�����[�E�����ܕ��ɁA2003�N10��8���j����������A���Ɍ��킹��u�{�^���v�̚g�̕�����قǃn�C�e���V�������B
������̍��l�͑�_�s�G�ɂ��܂ɋ߂Â��āA�r�����̎�ɂ܂������B�܂������悤�ɒj���Ђ��Ƃ��肩�����������B���ɁA�j�͍r�X�����ڕ�[�����Â�]���A�܂�Ń{�^���E[����]���{�^�������߂�悤�ɁA�����̋r��̋r�ɂ���݂��A�n��ɂ����|���āA�����y���B�^�ق��̓z�ꂽ�������ǂ���ɓ����܂˂����A������ނ����~�������B�ڕ����A���i���A����[�Ƃ�]���A�ӂ��������Ȃǂ��āA���͂Ă�Ƃ��݂��Ȃ��������k�c�c�l�i�����A�l���y�[�W�j
�g�����̎��Ɂs�A���r�A���i�C�g�t�ӂ��ƌ��������ߓ��ӂ��ȏ�ʂ������Ȃ̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă����ю��q�g��i���Ɏ~��r�i���o�́s�����C�J�t1960�N6�����j�����A�Y����Ȃ��̂��q�V�l��r�i���o�́s��]�t1959�N5���k�t�G�E2���l�j�ł���B���W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j�̖`�����������q�V�l��r�̏I���O���̈�قǂ��������B�\�\�ȗ����������ɂ́u��ʋ��̕��͂������������^���������k���^���̂������������͂������ā^�G���`�b�N�ł���v�Ƃ��������������B
�k�c�c�l
�V�l�͉�z����
���m�ɂ����Ȃ�Αn������̂�
�ݑ܂��N���̂��߂�
���̂Ȃ������̖��
�͂����Ȃ�Ñ�̚e��������
���ƍ��̑Γ��̎s��
�����ď��ɂ̉��̒��S�ɍ���
���҂̐S���̊��
�����Ȍ��������悤�Ƃ���
�ނȂ���������ꂽ
╂̂��Ƃ�����
�݂��Ƃȗ��̗x�q��������
�s���Ȗт̐��E��
�����̎�l���䓁���Ђ�߂���
�V�l�̑哪���肠����
�p�̂߂���
���������҂Ƃ���
�c���ƃy���J���̎��_�Ƃ���
���l�ɂ͎ז��ɂȂ�ʏ��ֈڂ����
�g�������ɓ����I�ȃG���`�b�N�ȑ��ʂ́A�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�ȍ~�Ƃ�킯�����ɂȂ��Ă���B�q�|���m�����G���r�Ɍ����鏺�a20�N��㔼�́u�|���m�����v�u�ɗނ���O�����w�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܌܃y�[�W�j�̎�e�ƂƂ��ɁA��N����́s�A���r�A���i�C�g�t�A�s����镨��t�̉e���������ł��Ȃ��悤�Ɏv����B
�k2013�N6��30���NjL�l
���c�p���s�A���r�A���E�i�C�g�Ɠ��{�l�t�i��g���X�A2012�N9��27���j�Œm�肦�����Ƃ�NjL����B�X�c���������s���镨��t�̏����͎��̂Ƃ���i���c���͌��T�̕\�L�d���ċ��������g�p���Ă��邪�\�\���g�̕��͐V�����E�V���������\�\�A�V�����ɉ��߂Ĉ������B�V�A���A���͂������A���̃\���n�̋������͕\���ł����A�V�����݂��͂ނ��낢���ꂩ�̑̌n��D�悷������̂������߂ł���j�B�����́i�@�j���̐����͓����̌f�ڃm���u���B
�E�X�c������w���镨��x���E�����ϑ�A�e���ю��\�\�A�S�l���A�������Ɋ��s��A����ܔN�㌎�\���N�l���B�i155�j�q��O�́@�������w�r�́u�S�@�q���{�������Ɂr�Ɓq���w���S�W�r�v�ɐX�c�����́s�A���r����b�t�̉�肪����B���͊��������B
�k�c�c�l���i���a��j�N�ɂ̓A���X�́q���{�������Ɂr�ƁA�����ЁE���Y�t�H�Ђ́q���w���S�W�r�Ƃ������p�����a������B��ʂɁA����ȁq���Ɂr�͒m���l�ƒ�ɁA�����I�ȁq�S�W�r�͈�ʉƒ�ɕ��y�����ƌ����Ă���B���̓�p���ɂ��A���ꂼ��X�c�����́w�A���r����b�x�i���N�㌎�j�Ƌe�r���i�ꔪ�����\���l���N�j�́w�A���r����b�W�x�i���N�l���j�����߂�ꂽ�B
�@�Ȃ��ł��X�c�����́A��ɂ��G�ꂽ�ʂ�A���C���őS��i����܁\�N�j�̎d���ɐ��N�Ԃɘj���ď]�����Ă����̂ŁA�w�A���r����b�x�͂��̗]�H�̈�Ƃ����i�D�ł������낤�B�����ł̓��C���ł���A�u���[�i�����Ɗw�҃d�[�o���̘b�v�u�n�T���Ɣn���̘b�v�u�Ⴂ���q�Ƒ�H�̘b�v�u�A���E�G�E�f�B�[���̘b�v�u�Ђ悤����҃n�T���̘b�v�u���w�d�����b�h�̘b�v�u�n�ǂ�ڂ��v�u�G�X�E�V���a�o�[�h�̍q�C杁m������������n�v�̍��v���b��I�яo���čĘb���A����Ƀ��C���łɂ͂Ȃ��u�A���E�o�o�Ǝl�\�l�m�����䂤�ɂ�n�̓����v���o�[�g���Łi�u�o�[�g���E�N���u�Łv�j�������Ă���B���̂����A�u�Ђ悤����҃n�T���̘b�v�Ɓu�n�ǂ�ڂ��v�́A��ɐG�ꂽ�w�Ԃ����x�f�ڂ́u�̂҂Ɖ��l�v����сu�n�ǂ�ڂ��v���قڂ��̂܂ܗ��p���Ă���B������I�̂́A��҂̌����Ăɂ��A�k�����͉��s���Ĉ��p�l�w�A���r����b�m���n�x�Ȃ���̂́A���������̂��߂ɍ��ꂽ���̂ł͂Ȃ��̂ŁA���낢��ȓ_�Ŏ����̓ǂݕ��ɓK���Ȃ��̂������B�ŁA���ꂾ��������b�̒��ł��A�{���Ɏ����ɓǂ܂��č����x�ւȂ��Ǝv�͂��̂́A�܂Â��̏��Ɏ��^������̘b�����Ȃ��́i�㗪�j�@�i�u�ጾ�v��\��Łj�k�����A���p�I���l�����炾�Ƃ����B�����āA�]���̖̑������u���m�l���I�����āA���m�l�����m�̎����̂��߂ɏ������������̂����̂܂ܖ|��������͏���v���Ă���̂ɑ��A�{���́u�ŏ����玄�m�킽�����n���I��ŁA���������������Ƃ��ӈꎖ�v�ɓ���������ƕt��������B�������ɖ{���́A�����̞~�����玩�R�ɂȂ�����҂��A���b�̓��e������̌��t�ɂ���Č�蒼�����Ƃ����ς�����B�܂��A�u�Ⴂ���q�Ƒ�H�̘b�v�u�A���E�G�E�f�B�[���̘b�v�ȂǁA�قƂ�Lj�ʂɂ͒m���Ă��Ȃ��n���Ȍ��l�D�݂̘b��I���ł����̂��A���C���őS��Ƃ����o���̗��ł������������炱���ł��낤�B����Ŕނ́A�u�q���ɂ͌������Ȃ��A��l�́u���镨��m�A���r�A���i�C�c�n�v�v���w���镨��i�����сj�x�i���E��O���w�S�W58�A�����ЁA���O��N�ꌎ�j�ɂ܂Ƃ߁A���ɒ[�̂������ŋύt������Ă���B
�@�Ȃ��A�w�A���r����b�x�ɂ́A�o�[�g���Łi�u�o�[�g���E�N���u�Łv�j�����̃o�b�e�� John D. Batten�i�ꔪ�Z�Z�\���O��N�j����Ɋ�Â��[��ȎO�i�ꔪ���\�����N�j�̃J���[���G�u���[�i�����Ɗw�҃d�[�o���̘b�v�k�c�c�l����_�A���C���ł̃n�[���F�C�̌���Ɉˋ������P�F�}�G����_�k�c�c�l�A��Ƃ��Ǝ��ɕ`�����Ǝv�����P�F�}�G����_���^����Ă���B�i151-152�j
���̋L�q�����ǂ�ł��A�X�c�̖⒘�����ςĂ��Ȃ��l�Ԃɂ����z�N�����鐸�k�Ȍ������ł���i��f�����A�k�c�c�l�ŗ������I���̓�ӏ��́A�Ή�����}�Ŕԍ��j�B�c�g�݂̊����ɒu���ꂽ�q��L�r�͉��x���n�NJ㖡�����B�S�������p�������U�f�ɂ����邪�A��ӏ����������B
��Z�Z�O�N�ȍ~�A�قږ��N����A�����������߂Ď����̏N�W�ƒ������s�Ȃ��A���̌��ʂ��I�v�ɂ܂Ƃ߂��Ƃ𑱂������̂́A�Ȃ��ׂ����������o���A�V���Ȏ�肪���X�ƕ��サ�Ă������߁A����܂ň�ʂ�I����̂ɏ\�N��̔N�����������Ă��܂����B�����������b�W���̂�����Ȃ̂ŁA�S��̈��ʓǂ��A�|��̎���]�����邾���ň�Ă�ׂ����N���������قǂł���B�S�̂Ƃ��Č���A�����͎v���������Ȃ�����������ɂȂ����i�D�ł���B�i782�j
�@����A�������������̐��Ƃł�����o�ϑ�w�̒M�{�ƗY�������A�����ɂ�����w�A���r�A���E�i�C�g�x�ɂ��Č������ʂ\���Ă����邱�Ƃ����R�m�����̂��A���ɂƂ��Ă͑傫�Ȏh���ɂȂ����B�N���S������Ȃ��ł��낤�Ǝv���Ă�������ɁA�D�ꂽ��B������͉̂����̗�݂ƂȂ���̂ł���B�M�{���͂��ׂĂ̕����ɂ��āA�����ɓ�����Ȃ����艽�����_�������Ȃ��Ƃ������i�Ȏ��؎�`�����H���Ă����A���̎p���͎��ɂƂ��Ă��A�y���Ȃ��猩�K�������\�\�Â߂��������t���g���A�������^�������\�\���̂Ɏv��ꂽ�B�i783�j
�������_�ДŁs�����k�S12���l�t�Ɓs�g�����S���W�t����Ă����ēǂނׂ��Ƃ��������B
�t�����X�̉�ƃ����V�A���E�N�[�g�[�i1904�`77�j�̊G���g�����̎�2�тƊւ���Ă��邱�Ƃɂ��ď����B�ȑO�q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�� �G�ꂽ���A�������낵�̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�Ɏ��߂�ꂽ���сq���i�r�i�B�E10�j�́A����p���e���e�{�̒i�K�ł͖ڎ��E�{���Ƃ��q�N�[�g�[ �̕��i�r�Ƃ����薼�������B�q�N�[�g�[�̕��i�r���Z���̂��鎞�_�Łq���i�r�ɕς�����킯�����A�g���͂��A�����Ȃ闝�R�ʼn��肵���̂��낤���B�Ȃɂ͂� ������q���i�r��ǂ�ł݂悤�B
���i�b�g����
�̎���
���݂��݂܂�
�����̂̎��̒�����
�D��C�݂�ق̒�܂Ŕɂ����
���ɂ͞�����̃o���̖���
�̏o�����̂肱��
���̉��ӂ����̗��^�̊k�̂ӂ��܂�
�Ƃ肩���݂����Ǝx����
����͟�����ł��܂���
���[�̂Ȃ����E�̕ς�͂Ă�������
�����J�ɂ����ނ����E
��Ȃ̌��ɂЂƂƂ��f�����
�䏊�����̂�ŕ����{����
�p���E�l�̉����Ȃ�~��̎�ɂ����ς�
���Ȃт��^�̋r�͂��ꂳ����
����߂Â�
���ɐÂ��ɂȂ�����
�̎�X�����k��Ă���
�����̒n��
�u���L���̋T�̎葫��
��̂ЂƂ�ꂪ�����钬�̉Ƃ̓�
��e��������
��̒��ɐH�����������
���������̗t��
��������ꂾ���I���������
���F�Ɍ͂�Ă䂭
�����╗�i�̉���
�Ƒ��͒c�R����
�����Y����f�i�������߂����邪�A�q���i�r�Ƃ�����ŏ[���ʗp����B���ꂪ�q�N�[�g�[�̕��i�r���ƁA��s����Ȃɂ��i���ꂪ�Ȃ� �ł��邩��� ��Ȃ��j�����̂Ȃ��́u���i�v���Ȃ������悤�ɉf��B��������s���ɒu���ꂽ�u�́v�u���Ȃт��v�u�́v�u���F�Ɂv�Ƃ��������肪��̓I�ȓT����z���� ���邾���łȂ��A�q�N�[�g�[�̕��i�r�̎��A�����́A�o���̖��A�{�����A�^�A�T�A���������Ȃǂ̓��A�����A���ꂱ���G�ɕ`�����悤�Ɏ��܂��Ă��܂��āA�g�� �����Ȃ�ł͂̃h���C�u���Ɍ����銶�݂��c��B��N�A�g����������b�q�Ɂu������A�ӎ��I�ɗ��̎��������ꍇ�͗������o�邯�ǁA�����̎��̏ꍇ�́A �u�K�N�v�Ȃ�u�K�N�v�ł�������A���ꂪ��x�o��������o�Ă��Ȃ��͂��v�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A�㔪�y�[�W�j�ƌ�������Ƃ��v���o�����B ���̂悤�ɁA�q���i�r���q�N�[�g�[�̕��i�r���Ǝ��̈�ۂ������ɕς���Ă��邪�A����́A21���I�̌��݂̓ǎ҂������̎������\���ꂽ�����I�O�̓ǎ҂� �ق������������̂ł͂���܂����B�����A�قƂ�ǖY���ꂽ���̂����ƃN�[�g�[�����A��߂Ȕ��p���T�ł͂����Љ��Ă���B
�N�[�g�[�@���V�A���@Lucien Coutaud�i1904�`�j�k���E��l�K�[�������[�k�ɉƋ�E�l�̎q�Ƃ��Đ���B�j�[���̔��p�w�Z�Ɋw��A�p���ɏo�ē�A�O�̌������ɒʂ��B���� ���N������i�\���o�������A���̌�C�^���A�ɗV�сA�������l�b�T���X�A���Ƀs�G���E�f���E�t�����`�F�X�J�Ɋ��������Ɠ`������B�A����̓V���[�� ���A���X���̍�i�\���Ă��邪�A�l��N���͎�Ƃ��ăT�����E�h�I�g���k�y�уe���C�����[�ɏo�i�A�l�ܔN�ɂ̓T�����E�h�E���G�̐ݗ��ɎQ�������B���̓� ���́A�j�Ǝh��z�킹��悤�Ȑ��ƌ`�̑g���킹�ɂ��l�̂���́A���̔߈��̏�Ɩ������s�v�c�Ȍ������ƂȂ��āA�����ɔ����Ă���B�ŋ߂̔ނ̓^�s �X�g���[�̉��G�A���z�����A�o���G�̑��u�ȂǁA�������p�̕��ʂɂ��A���̑��˂Ԃ�����Ă���B���݁A�t�����X�̒�����ƒ��A�ł����ڂ�����l�ł� ��B�i�Ö�k���Y�l�j�i����Ēj�E�R�c�q�O�Y�ҁs���m���p���T�t�A�������A1954�N11��30���A��㔪�`����y�[�W�j
�N�[�g�[�A �����V�A���@Lucien Coutaud�@1904.12.13�\�@�@�t�����X�̉�ƁB�K�[�������[�k�ɐ��ꂽ�B�����ɂ̓V�������A���X�����̍�i��`���Ă��邪�A�^���ɂ͎Q���� �Ȃ������B1943�N�̃T�����E�h�E���[�̐ݗ��҂̈�l�B�Ƃ��̐������悤�Ȏl���������̐l�̂�����̍r�����ގ��𑽂��`���B���قȑ������� ���т����z�I�敗�Ńf�U�C���A���G�A���z�����A������p�ł�����B��\��Ɂw�̃X�J�[�g�x�i1945�A�p���A�����ߑ���p�فj������B�i�s�V�����E���p ���T�t�A�V���ЁA1985�N2��20���A�l�y�[�W�j
�N�[�g�[�@Lucien COUTAUD
1904�`77.�@�t�����X
�앧���[�k�ɉƋ�E�l�̎q�Ƃ��Đ��܂��B�j�[�����p�w�Z�A�����Ńp�����p�H�|�w�Z�Ɋw�ԁ@'28���̍�����i�\�B���̌�C�^���A�ɗV�w�A������ �l�b�T���X�Ɋ��������Ƃ�����B�A����V���[�����A���X���ِ̈F��ƂƂ��Ēm����@'42�`��Ƃ��āA�T�����E�h�[�g���k�ƃT�����E�f�E�`���C�����[ �ɏo�i�@'45�T�����E�h�E���̐ݗ��ɎQ��B�ȗ���C�ψ��@'64�`�p�����p�w�Z�ʼn�Ȏ�C�����߂��B���ʉ�̑��A�ʼn�͂������A�lj�A�^�s�X�g ���[�A���z�����A�I�y���̕���f�U�C���ȂǑ������p�ɂ����˂Ԃ���@'67�p���s�G���ܑ���ܑ����^�J���[�G�b�`���O�A�r�������A�h���C�|�C���g�A �A�N�A�`���g�Ȃǂ���g�����Z�Z��̓��ʼn�𐧍�B�i�����N�Y�s�ʼn掖�T�t�A�������ЁA1985�N9��18���A���O���y�[�W�j
�g�������s�Õ��t���\�����鎍�т��������ł���1950�N��O���A�����V�A���E�N�[�g�[�͂킪�����p�E�Œ��ڂ���Ă����A�����炭��
�݂ł͑z���ł��Ȃ����炢�ɁB
�N�[�g�[�̍�i���킪���ɖ{�i�I�ɏЉ�ꂽ�̂́A�s�݂Â�t558���i1952�N2���j��6�_�̐}�łƂӂ��̕��͂��ŏ��̂悤���i�q��ƃN�[�g�Ǝ��q�͎ʁr�̏��o�r��
�}�ł̃R�s�[���f���Ă���̂ł����������������j�B�����f�ڂ̘a�c��v�q�����V�A���E�N�[�g�I�r�Ɖ��{�����ɂ���Ƃ̃A�g���G�K��L�͂Ƃ��ɒP�s�{�s�t
�����X�̎Ⴋ��ƒB�t�Ɏ��^�A��l�̋����Ƃ��ē��N6���Ɋ��s����Ă���i���G�ɃJ���[1�_�ƃ��m�N��2�_�̃N�[�g�[��i���f�ځj�B�a�c�͖{���Łu�����V
�A���E�N�[�g�I�̌|�p�������ɂ͒����I�A�킯�Ă��S�V�b�N�̌|�p�Ƌߎ����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��v�i�s�t�����X�̎Ⴋ��ƒB�t�A���p�o�ŎЁA
1952�N6��20���A�l��y�[�W�j�\�\�u�ߑ�̃X�t�B���N�X�͌`����̖�̒����U������v�i���O�A�l�O�y�[�W�j�Ə����Ă���B
��1953�N1���ɂ͏��̌W���_�ސ쌧���ߑ���p�قŊJ����A4�y�[�W�̃��[�t���b�g�Ȃ���ژ^�����s���ꂽ�i�g�������W���ς��L�^�͂Ȃ����A�ςĂ���
������������j�B���̌W���āA�s�݂Â�t570���i1953�N2���j�ɂ�29�_�̐}�łƂƂ��Ɂi����2�_�̓J���[�j�A�y�����́q�����V�A���E
�N�[�g�[�ɂ��ār���f�ڂ��ꂽ�i�����́s���[���b�p�̌�����p�t�A�����V���ЁA1953�N7��20���Ɏ��^�j�B�u�����V�A���E�N�[�g�[�̂���
vacuum�k�^��l�̉�ʂ͂ǂ��ł��낤���B���̖���ЂƂ��т������āA�����̂悤�ɓ����ŗH�ÂȏƖ��𗁂т����ׂĂ̂��̂́A���Ƃ�������D���A��
�����̂悤�ɁA�N�[�g�[�̐��E�̌`�Əے��Ƃɕό`����Ă��܂��v�i�����A��Z�Z�y�[�W�j�B
���N�����́s���p�蒟�t�̓N�[�g�[�̐}�ł�17�_�f���i����2�_�̓J���[�j�A����C�����q�N�g�I�r�Łu�����炭�N�g�I�̓t���C�h�̐��I�̌Õ��ŗD���
���Ӊ�ƂƂ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���v�i�����A1953�N2�����A��Z�y�[�W�j�Ə����A�����������q�n�����̐_��\�\�����V�A���E�N�g�[�W�̈�ہr
�Łu���z�̐��E������قǃ��A���ɕ\�����邽�߂ɂ́A�����������A���Y���̊�ՂƗD�ꂽ���^�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�ނ̉s���f�b�T���A����t�H������
���т����A�\���̖��x�͍����]������˂Ȃ�܂���v�i���O�A��܃y�[�W�j�Ə������B
����ɗ���1954�N�ɂ́A���p�S�W�ɊG���i���f�ڂ��ꂽ�B�s���E���p�S�W
27�k���m��\���I�U�l�t�i���}�ЁA1954�N6��30���j��1�_�i�}�ʼn���͋g��펡�j�ƁA���E�s��ҁs���㐢�E���p�S�W�k��9���l�t�i�͏o���[�A
1954�N8��25���j��8�_������ł���B�g�����q�k�N�[�g�[�́l���i�r�������ɂ������ĎQ�Ƃ����̂́A���̑唻�i�a�S�̓V�n��j�́s���㐢�E���W
�k��9���l�t�������Ǝv����B���̗��R�͒ǂ��ďq�ׂ邪�A�܂��͖{���̏Љ���ȒP�ɂ��Ă������B�s���㐢�E���p�S�W�t�͔~�����O�Y�E�u�꒼�ƁE�����ɑ�
�Y�E���ҏ��H���āE����\���Y�Ƃ������d�����ďC�҂ɖ���A�˂Ă��邪�A�{�������ۂɂ܂Ƃ߂��̂́A�ȉ��Ɏ��^��ƂƂƂ��Ɍf����i�@�j���̉�����M�҂�
�����낤�B
�O�����[���i��v�ۑׁj�^�^���M�[�i�c�ߌ��O�j�^�N�[�g�[�i���厛���p�j�^�s�j�����i�x�i�y��j�^�}���V�����i�Ö���Y�j�^�����W���i�a�c��v�j�^�}�l�V
�G�i�A������j�^�~�m�[�i�v�c�`�M�j�^�r���b�t�F�i�����ɑ��Y�j�^�N���[���F�i�{�c�d�Y�j
10�l�W�̂Ȃ��ɂ����āA���̍앗���ЂƂ��Ƃł����u�_�o���ȃ_���v�Ƃł��ĂԂׂ��N�[�g�[�́A�ِF�̉�ƂƂ�����ۂ������B���^���ꂽ�N�[�g�[��i��
�}�ł͈ȉ��̂Ƃ���ł���i���[�}�����̔ԍ��͈��p�҂��t�������́j�B
���F�Łi�J���[�j
�@�T�q�g���A�m���̖������\Les desmoiselles Trianon�r1951
�@�U�q�Ⴂ���A���A���u���\Jeunes loirarbres�r1952
�O�����B�A�i���m�N���j
�@�V�q���C���̑z���o�\Souvenir rhenan�r1930
�@�W�q�̍L��Ɛ��_�\Trois nuages bleus sur la place verte�r1944
�@�X�q��̃p���^�с\Porteuse du pain dans la nuit�r1945
�@�Y�q�z���o�\Souvenir�r1949
�@�Z�q�E��ɊD�F�̒j��������\A droite, l'homme gris fonce parait�r1952
�@�[�q�C�݂̃G���e�B�R�}�W�[�\Plage de l'Eroticomagie�r1954
���̐}�ł́A�O�f�s�݂Â�t��s���p�蒟�t�A�f�ڕ������^�����P�s�{�ɓY����ꂽ�ǂ̃N�[�g�[�̐}�ł����A�g���́q�k�N�[�g�[�́l���i�r�̎���ƘA����
�Ă���悤�ɂ݂���i�����Ƃ����q��v�}�̂Ɍf�ڂ��ꂽ�N�[�g�[��
�i�̐}�ňꗗ�r���Ɍf�����j�B
�܂��J���[��2�_�̂����U�́u�̎��́^���݂��݂܂Ł^�����̂̎��̒�����^�D��C�݂�ق̒�܂Ŕɂ�����v�A�T�́u���ɂ͞�����̃o���̖��́^��
�̏o�����̂肱���^���̉��ӂ����̗��^�̊k�̂ӂ��܂Ł^�Ƃ肩���݂����Ǝx����^����͟�����ł��܂����^���[�̂Ȃ����E�̕ς�͂Ă��������v�Ƃ����A��
�т̖`�������ɑΉ�����B
 �@
�@
�T�q�g���A�m���̖������\Les desmoiselles
Trianon�r1951�i���j�ƇU�q�Ⴂ���A���A���u���\Jeunes loirarbres�r1952�i�E�j
�o�T�F���E�s��ҁs���㐢�E���p�S�W�k��9���l�t�i�͏o���[�A1954�N8��25���A�}��5�`6�j
����A���m�N��6�_�̂����A�W�́u���ɐÂ��ɂȂ�����^�̎�X�����k��Ă���^�����̒n���v�ɁA�X�́u��Ȃ̌��ɂЂƂƂ��f�����
�^�䏊������
��ŕ����{�����^�p���E�l�̉����Ȃ�~��̎�ɂ����ς��^���Ȃт��^�̋r�͂��ꂳ����v�ɁA�Z�́u��e��������v�ɁA�[�́u�����╗�i�̉��Ł^�Ƒ��͒c
�R����v�ɑΉ�����悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ��B�\�\�ȂǂƉ��Ɍ����̂��A���m�N���}�ł̃N�[�g�[��i�ɂȂɂ��`����Ă��邩���ʂ��ɂ����̂ɉ����āA�g��
�̎��傪��ɂ������ĈӖ������ǂ�ɂ�������ł���B
�X����чZ�́A���Ƌg���̎��傪�ĉ����Ă���_�ɒ��ڂ������B����́A�̂��̃X�^���`�b�`�̉��Ɓq�����r�i�C�E19�j�̊W����肵�Ă��悤�B����
��̐}�łƎ��s�����S�Ƀ}�b�`���Ȃ��Ă��A�N�[�g�[��i�Ƌg����������W�̂悤�ɊςāA�ǂގ��R�͍����̂����Ɏc����Ă���B
 �@
�@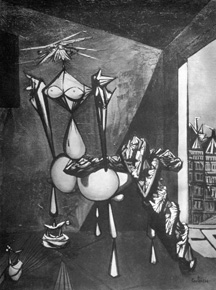
�W�q�̍L��Ɛ��_�\Trois nuages bleus sur la place
verte�r1944�i���j�ƇX�q��̃p���^�с\Porteuse du pain dans la nuit�r1945�i�E�j
�o�T�F���E�s��ҁs���㐢�E���p�S�W�k��9���l�t�i�͏o���[�A1954�N8��25���A�}��15�`16�j
�\�\�{�S�W�̑����͌��O�B���M�ɉ����鑢�{�v�E���C�A�E�g�����i�̃f�B���N�V�����j���낤�B�q����r�ȉ��̖{���̓X�~�Ǝ���2�F���� �ŁA�����X�~�Ǝ��i�m���u���̂݁j�ɂ�����́s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1967�j�̃X���X�̂ЂƂ��B�\�\
 �@
�@
�Z�q�E��ɊD�F�̒j��������\A droite, l'homme gris
fonce
parait�r1952�i���j�Ƈ[�q�C�݂̃G���e�B�R�}�W�[�\Plage de l'Eroticomagie�r1954�i�E�j
�o�T�F���E�s��ҁs���㐢�E���p�S�W�k��9���l�t�i�͏o���[�A1954�N8��25���A�}��18�`19�j
�������R�������߁A���W�̕W����s�Õ��t�ƌ��߂����_���ǂ��܂ők��邩��߂��������A���e���e�̎��܂Ƃ߂͒x���Ƃ�1955�N�̏t �Ǝv���� �i�������Ȃ������e�{�̔����e�Ɂu�g�������W�^�Õ��^1955.5.5�v�ƎO�s�ʼn���������Ă���j�B�g���͏e���e���ђP�ʂŕғ��E�폜���邱�Ƃ� ��荷���ւ�����A���т̏��Ԃ����ւ����肵�āA���W�̍\����͍����Ă���B���������Ȃ��ŁA���W���s�Õ��t�Ɩ��Â�����₽�����Ɂu�Õ���v��z�N �����邽�߁A�W�߂�ꂽ�e���т͈�l�ɊG��I�Ȍ��̂��ƂŒ��߂���i�g������������������̂́A����̕M�Ղ𗣂ꂽ���Z�Q���őS�т����킽�����Ƃ����� ���j�B���ꂪ�A�g�����{�т��q�N�[�g�[�̕��i�r�̂܂܂Ƃ��Ȃ����������ł���B���z���鍰���茘���Z��ŗ��ł�����g���́u�敗�v���A�N�[�g�[�̂���Ɠ� ���������ɂ������B�g���́A���̏o�����Ɂu�T���ƈ��p�v�̕��@�ɂ���߂ċ߂��n�_�ɗ����Ȃ���A�N�[�g�[�̐}�ł����ЂƂ̌����Ƃ��Č���A�����Ȃ�� �u����̎��z�v���`��4�т́q�Õ��r����悵���B���̂Ƃ��q���i�r�͂���̂��̂ł��Ȃ��A�g�����g�̂��̂ƍ�҂͔F�������B���߂Ɂq���i�r�i�܂� �q�k�N�[�g�[�́��g���́l���i�r�j�Ɖ��肵���̂��B�u�w�Õ��x�͈��܌ܔN�A��S������o�ł����B������Ƃ��W���Ђ炭�悤�Ȋ��҂ƕs���̗��Łv �i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�j�B���́u������Ɓv�ɂ́A�����Ȃ��Ƃ̌ŗL�������悯���������B
��
�u�����v�y�сu�T�t�����E�݁v�̓�т́A�܂�Ƃ���G��ɂ���Ĉ����o���ꂽ���A�G��ɜ߈˂��ꂽ���A���Ă͂� �̋��n����荞���ƌ���������̂ł����āA���̈�_�ɋ����āA�������G����Î����邱�Ƃ��琬�����u����鏗�\�\�~���̊G����v�A������s���p�G�� �Ō����A�V�������A���X���̏�����ƃ��I�[���E�t�B�j�̊G���ނɂ����t�Ɩ������ꂽ���Ƃ��L��u���E�H�̊G�v��u�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����v�Ƃ����� �ނ́A�G���`�ʂ������A�~���������A���߂������Ƃ́A�ǂ����W���������قɂ��Ă���炵���̂ł���B�i�H���K�l�q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�A�s�g�� ���A���x�X�N�t�A����R�c�A2002�A���y�[�W�j
��
�g�����͎��Ɉ��������q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G ����r�i�E�E4�j���A���W�s�a�� �`�t�i����ɁA1962�j�\�\�H�����Ɍ�����q����鏗�\�\�~���̊G����r�i�D�E18�j�Ɓq���E�H�̊G�r�i�D�E21�j�����^����Ă���\�\���s��� 1963�N��������64�N�ɏ������Ǝv�������A�q�͎ʁr�̔��\�}�́i���o�f�ڎ����j�͂܂��킩���Ă��Ȃ��B���Ȃ݂Ɂq���E�H�̊G�r�̓T���A�t�B�j�́q���E �̏I���r�i1948�j�́A�N�[�g�[�́q�E�肩��D�F�̒j���������r�i1952�j�ƂƂ��ɁA�O�o�s���E���p�S�W 27�k���m��\���I�U�l�t�Ƀt�B�j�̍�i�Ƃ��Ă͂������A�O���r�A�łƂ��Čf�ڂ���Ă���B
�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����b�g����
���̋��͂��������j�� 1
�������炾�S�̂ɒ���o���� 2
�����⒆���̐펀�҂̔��̖т� 3
�Â��肩��@�Â���܂łȂт����� 4
���̏�̐�������Ō���̂́H 5
������т�ꂽ�����̋����� 6
���ӂ����č��l�֑�C���������܂� 7
���N�̒j����l�Ő푈���͂��߂邾�낤 8
�����o��܂ł� 9
���̒j�͂ӂƂ����H��ɂȂ邾�낤 10
����悭�s���� 11
���j�I�Ȋy����������H 12
�����ꂽ���@�����ꂽ�I 13
�ԖڂƗ� 14
��̂��闤�n���� 15
���̌R�͂̊��z���Ȃ��ꂽ���ւ��� 16
���������j�Ə��̂��悢�_��̈� 17
�킽���͏j�Ղ��Ă�肽���Ǝv�� 18
��ƂȂ�Δ����������� 19
�葫���瓷�܂Ŗ_�̂悤�� 20
�܂����� 21
�����͂�������܂ŗ������Ă��� 22
�����Â���@���͊^�̂Ƃт܂�鐅���̂Ȃ��� 23
���܈���̕��݂���� 24
�������̌҂܂ł̕S���̏� 25
�ԔS�y�w�̂��₩�ȋu�ւ̋킯�� 26
���邱�Ɓ@�����Ă��钆�S�� 27
�s���S�ȔR�Ă� 28
�~���N�E�[���[�Ɨ₽���� 29
��Ƃ̍��M�����I�� 30
�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv�� 31
�H����~�ւ����Ē��Ӑ[�� 32
�R�͂͑S���~����� 33
�Ƃ��ɂ͉~������ 34
��؉��̂���i���ւ����ݏՓ˂��� 35
�������ꂽ�j���W���E�L���x�c 36
�킽���͑���E���˂錩���l�Ƃ��� 37
�����N�̂ނ�@���̂����������� 38
�������A�X�p���K�X 39
��Ƃ͔ނ�̂��߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv�� 40
�ɕ`���ꂽ�Ⴂ�ւ̋�Y�̓��̂͂��� 41
�^�łȂ��Ȃ�g���镽�� 42
�Ƃ�����̉J�ɂʂ炳��邾�낤 43
�܂��`����Ȃ��G���@�G�����L����ׂ��ׂ��R 44
�e�[�u���̌����ɎR�ԁ@�X��b���̗� 45
�킽���ɂ���炪�����Ȃ� 46
�^�g�ȐF�̎������̂���ł��� 47
1963�N3��20������29���܂Łq�����V�A���E�N�[�g�I�V��W�r�����W��������L�ŊJ���ꂽ�B�N�[�g�[�Ƃ�30�N���̗F�l�E�����o
�C���A�V��W
��10�N�O�ɏ��яG�Y�Ƃ�������Ƀt�����X�̃N�[�g�[�̉Ƃɍs�����A�Ɓq�F������藈��\�\�����V�A���E�N�[�g�I�̂��Ɓr�ɏ����Ă���B�u�ނ̉�z�̏��
���т̕\�������ƃg�Q�g�Q�̐l��������ꂽ�̂����̎��n�߂Č����B���邭�ނ��냍�}���`�b�N�ȉ悾�����̂��A���݂̔ނ̉�z�Ƀg�Q�g�Q�̋R�m�̂悤��
�j�Ⓑ���X�J�[�g���͂����g�Q�g�Q�̋M�w�l���o�ꂵ�n�߂��̂��A�푈��10�N�Ԃ̏��Y�Ƃ����������Ƃ������A�ǂ����悤�Ə��肾���A���͂ނ����J�̌���
�ƌ������B�^�k�c�c�l�^���яG�Y�N�͔ނ̃A�g���G�֏�����A�Ƃ��ɐH������ꂽ���u����͖{���̂��ˁv�Ǝ��Ɍ�����̂�Y��Ȃ��B�ނ̉敗�͍D�ނ��̂�
���낤���A�܂����̈ӂ�\����l�����邾�낤�B���A�l�Ԃ͖{���̂����A�r���{���̂��Ǝ��͐M���Ă���v�i�s�݂Â�t�ʍ�699�A1963�N5���A����
�y�[�W�j�B
�H���K�l�̎w�E�̂悤�Ɂq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���u�G���`�ʂ������A�~���������A���߂������v�Ȃ�A�g���͂��������ǂ́u�N�[�g�̊G�v����{��
���\�z�����̂ł��낤���B�W����ɍ��킹�Ċ��s���ꂽ�}�^�s�N�[�g�I�V��W�t�i�k������L�E�����V���Ёl�Ac1963�N3���j���傽�鎑���Ƃ���
�\�\1990�N�A�t�����X�ŊJ���ꂽ�N�[�g�[�W�̃J�^���O�sAtelier Lucien Coutaud�i1904-1977�j�t�iEtude
Gros Delettrez�A1990�j��⏕�I�Ɏg�p���ā\�\�l�@���Ă݂悤�B
�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�Ɓs�N�[�g�I�V��W�t�ɂ́A��́q���i�r�ƃN�[�g�[����i�قǔZ���ȊW�݂͂��Ȃ��B�G���Ǝ���ɂ͊֘A�𗠕t�������
���قƂ�ǂȂ��A�B��q11.
�ԕz�̂Ђ��̒��ɑ��z���ގႢ�ً��k�̓����m�r�Ɓu��ƂȂ�Δ������������^�葫���瓷�܂Ŗ_�̂悤�Ɂ^�܂����ā^�����͂�������܂ŗ������Ă�
���v�i19�`22�s�j�����Ă�����x���B�V��W�S��̐}�ł��}�^�Ɍf�ڂ���Ă���킯�ł͂Ȃ����i55�_��36�_�f�ځj�A�}�ʼn����ĉf�����i���玍�傪
�a�������ꂽ�̂łȂ����Ƃ͊m�����B�̂Ȃ����ɉ��𗧂Ă�悤�ȁA���̕����t����s�ׂ̈Ӗ�����Ƃ���͂Ȃɂ��B
���������q��v�}�̂Ɍf�ڂ��ꂽ�N�[�g�[��i�̐}�ňꗗ�r��
����Ȃ܂łɃN�[�g�[��i�̃^�C�g�����������̂́A�g�����W����������i�}�Łj�Őڂ����\���̂����i���c�邭�܂Ȃ��������Ƃ��ړI�����A�g�����ς�
�������ł��낤��i�Ƌg���̎���ɋ��R�Ƃ͎v���Ȃ��ގ������݂���B���Ȃ킿�u�����N�̂ނ�@���̂������������^�������A�X�p���K�X�^��Ƃ͔ނ�̂�
�߂ɗ܂��Ȃ����Ǝv���v�i38�`40�s�j�ƁqLA LETTRE, OU
AUTOPORTRAIT�k�莆�A���͎��摜�l�r�i1942�j���B�N�[�g�[�̍�i���sAtelier
Lucien Coutaud�i1904-1977�j�t�iEtude Gros Delettrez�A1990�j�̕\����
�Ȃ��Ă��āA�\���͌���̍����O���̓���x���c���ăg���~���O����Ă��邪�A��ʂ̉E���ɂ̓A�X�p���K�X�ɕϐg�������N�i�H�j��������ł͂Ȃ����B���̌�
���Ƃ��łȂ���A�q�莆�A���͎��摜�r�͂��ē��{�ŊJ���ꂽ�W�����o�ł��ꂽ������i�}�Łj�ɂȂ��A�g�����ǂ����Ŋς��̂��Ƃ�����A���̓T���͕s
���ƌ��������Ȃ��B�Ƃ����킯�ŁA�c�O�Ȃ���u���̓N�[�g�̊G����v�̏o���̒T���͑ł����炴������Ȃ��B�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���o�̒����Ƃ�
���ɁA����̉ۑ�Ƃ��Ă������B
�g�����́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r���s�g�����k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�́s�Â��ȉƁt���^���т̂ЂƂɑI��ł���A�����W�̂Ȃ�
�ł����M�삾�����ɈႢ�Ȃ��B���̎��т̕W��u�͎ʁv�͂Ȃɂ��Ӗ�����̂��B���ꎫ�T�ɋ���A�u�͎ʁv��
�܂˂Ă������ƁB�܂��A���̂����Ƃ������́B�u�����͎ʂ���v
�Ƃ���A�ᕶ�͂܂��ɋg���̑薼�Ɠ����p�@���B����A�p�a���T�ɂ�
a copy; a reproduction; a facsimile
�͎ʂ���@copy; reproduce
�Ƃ���B�����A�g�����ƃ����V�A���E�N�[�g�[�Ƃ̊W�����Ă��������́A������u�R�s�[�v�ł͂Ȃ��u�p�X�e�B�V���v�i�v���[�X�g�� ������u�^ �I�ᔻ�v�ƌĂ悤�Ɂj�Ɠǂ݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł́q�N�[�g�[�̕��i�r�����肼���āq���i�r�Ƃ����g�����A���̂��т͂Ȃ��q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�� �G����r�ƕ���ɉ�Ƃ̖����L�����̂��B�����̂悤�����A�s�Õ��t�Ɓs�m���t�̎��тɗ���������K�v������B�N�[�g�[�I���т��q���i�r�Ɓq�͎ʁ\�\���� �N�[�g�̊G����r�ɂƂǂ܂�Ȃ�����ɁA�g�����̎��@�̔閧������Ǝv���邩�炾�B1956�N11���ɎG���ɔ��\����A���W�s�m���t�Ɏ��߂�ꂽ�q���r �i�C�E3�j�Ƃ����A�����̋g�������p�����U�����^�̈�т����A������s�����̎��ɂ��Ă݂�Ɓq���i�r�Ƃ̗ގ����ۗ����Ă���B
���֏��
�j�͊�p�ł݂���
�b�⋛�̑傫�ȋ|�Ȃ�̍��Ђ̗�
���]���Ȃ��瑾�z���N����
���낢���̂����܂̎��k�}
���X�ɐ����ɂȂ��Ă䂭�j�̊�݂̊�
�s�p�I�Ȍ��̏o��
�Y��悤
���Ђ��傤�ȑN���x��
�C���̗�������
����Ȏ��ǂ����ĉ��y��������Ȃ��̂��낤
���ꂪ�s�����̌ʂ��`�Â���Ƃ�
�j�̂Ȃ������������葫���킸���ɂ�����
���̂��щ��̒[����
���̖ʐς����܂肾��
�����͂������ɖ����̗����̑���
��ї����ʌ��̒������̂��߂�
�j�̂������Ɋg�傳���
�͂��������ɔ����ꂽ���̑S��
�ǂ���T���Ă��`�������̐l�Ԃ̒܂̍��ЂƂ��������
�I�т͂��Ȃ�
���̃A�g���X
�j�͂₹���ٓ�����
�����̐��ƌ������ڂ肾��
�≏�̂ɉ����Č�������~�̔g�����ׂ葱����
�����ǂ�ł��A���W�s�m���t�ɂ�����g���������V�A���E�N�[�g�[�ɑ������w��ł��邱�Ƃ���������悤�B�t�Ɍ����A�N�[�g�[���牓 �����ꂽ���� ���������炱���A�͂��߂āu�N�[�g�̊G����v�Ə������邱�Ƃ��\�ɂȂ����̂ł����ā\�\�u��Ƃ̍��M�����I��^�킽���͌��݂����т������ゾ�Ǝv���v �i30�`31�s�j�\�\�A���傪��ʂƎ��悤�����܂����{�т̌��Ƃ͂Ȃ�̊W���Ȃ��A�q���i�r��q���r��y���ȃG�R�[�Ƃ��ĕ���ɂ��̉�Ƃ̖����i������ ���͊��ӂ̋C�������߂āj�L�����̂��B
��
�Ō�ɋ^�₪�c��BLucien Coutaud�̃J�^�J�i�\�L�ł���B�����q��v�}�� �Ɍf�ڂ��ꂽ�N�[�g�[��i�̐}�ňꗗ�r������ �킩��悤�ɁA�u�N�[�g�[�v�i�S�ʓI�Ɍ�����j�Ɓu�N�[�g�I�v�i�Ƃ�킯�����ɑ����j�̑o����������̂́A�g���������悤�ȁu�N�[�g�v�������Ȃ��̂� �ǂ������킯���낤�B�������čő�̓�ł���B
�y�����z ��v�}�̂Ɍf�ڂ��ꂽ�N�[�g�[��i�̐}�ňꗗ
�}�ň�������́u���F�Łv�̓J���[�A�u�O���r���Łv�̓��m�N���A���L�Ȃ� �}�Łi�����͓ʔŁj�̓��m�N���ł���B �N�[�g�[��i�Ɗ֘A�����̍ژ^�ɓ�����A�����͈ꕔ�̐l���������ĐV���ɓ��ꂵ�A���ȂÂ����͌����̃}�}�Ƃ����B�Ȃ��A�ꗗ���ɂ������ĕ\�L��̑̍ق� ���邽�߁A�K�X��Ԃ����B
���s�݂Â�t�i�ʍ�512�A1948�N6 ���j
���s�݂Â�t�i�ʍ�558�A1952�N2 ���j�q�N�[�g�I�̍�i�r
���a�c��v�E���{�����s�t�����X�̎Ⴋ��� �B�t�i���p�o�ŎЁA1952�N6��20���j
���s�݂Â�t�i�ʍ�563�A1952�N7 ���j�q���{���۔��p�W���W�r
���s���p�蒟�t�i1952�N7�����j
���s�N�[�g�[�W�ژ^�t�i�_�ސ쌧���ߑ�� �p�فAc1953�N1���j�k�� ���F1��1���`2��22���l
���s���p�蒟�t�i1953�N2�����j�k�� �i�ʐ^�͂��ׂăN�[�g�[�W�� ���ނ������́l
���s�|�p�V���t�i1953�N2�����j�q�N�[ �g�[�W �I�t�Z�b�g�r
���s�݂Â�t�i�ʍ�570�A1953�N2 ���j�k��i�͂��ׂăN�[�g�[�� �W�ɏo�i�������́l
���y�����s���[���b�p�̌�����p�t�i���� �V���ЁA1953�N7��20���j
���s���E���p�S�W27�k���m��\���I�U�l�t �i���}�ЁA1954�N6��30���j
���~�����O�Y�E�u�꒼�ƁE�����ɑ��Y�E���� ���H���āE����\���Y�ďC�A���E�s��ҁs���� ���E���p�S�W�k��9���l�t�i�͏o���[�A1954�N8��25���j
���s�N�[�g�[�V��W�t�i�k������L�E�����V ���Ёl�Ac1963�N3���j�k�� ���W����F3��20���`29���A���W����F4��9���`14���l
���s�O�ʁt�i�ʍ�161�A1963�N4���j
���s�O�ʁt�i�ʍ�162�A1963�N5���j
���s�݂Â�t�i�ʍ�699�A1963�N5 ���j
���sAtelier Lucien Coutaud�i1904-1977�j�t�iEtude Gros Delettrez�A1990�j
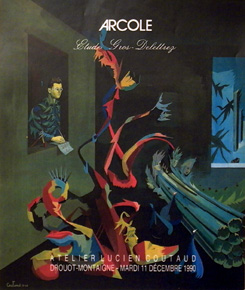
�sAtelier Lucien Coutaud�i1904-1977�j�t�iEtude
Gros
Delettrez�A1990�j�̕\��
�k����́qLA LETTRE, OU AUTOPORTRAIT�r�i1942�j�l
�k2011�N6��30���NjL�l
�N�[�g�[�Ɩʎ��̂��������{�l�͂�肠�������悤���B�����͌|�p�W�҂��낤���A�ѐF�̕ς�����Ƃ���ŁA�i���p���Ō��q�����w�̌����𑱂�������N�q
�i1909-80�j������B���̐��M�Ɂs�p�����z�\�\��E�݂��[��E�ǁE���������t�i�݂������[�A1973�N6��21���j������A�q�V
�ꎵ���I�̌����s�r�����߂��Ă���B�薼����͂킩��Ȃ����A�q�����V�A���E�N�[�g�[����̏��ҏ�\�\�ꎵ���I�̌����s�r�Ƃł����t���������e���B�V��
�m�E�h�E�x���W�����b�N�̒����̑}�G��S�������N�[�g�[���珵���ꂽ�o�ŋL�O�p�[�e�B�[�ɂ܂��o�������A舒B�ȕM�ŏ��������͂��i���F�ɂ����g������
�R���Ղʼn������̂��A�s�V���m�E�h�E�x���W�����b�N�t�̃p���f�B�������j�B�N�[�g�[���u�V���m�E�h�E�x���W�����b�N Cyrano de
Bergerac �̏������gVoyage dans la
lune�h�i�w���̐��E���s�x�j�̑}��Ƃ��ăI���W�i���̔ʼn�����v�i�����A���Z�y�[�W�j�������̍��ؔł́A�����z�q�ꎵ���I�̌����s�r���s�݂�
���t1971�N7�����Ɍf�ځi�����Ɂu��㎵��N�܌���\�O���L�v�Ƃ���j���������N�ɁAClub du livre Philippe Lebaud
�������325���Ŋ��s����Ă���B�����z�ɋg�������Ƃ̊֘A���M�킹��L�q�͂Ȃ��̂ŁA�s�p�����z�t�́q�U
�t�����X�̘_���Ɠ��{�̘_���r�̈�߂��������B
�k�c�c�l���{�̊w��ɍs�����t�����X�l�����́A�������ē��{�ɂ���t�����X�l�𗊂�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��āA��S���Ȃ� ������{�ł� �����̎���̒T�����y����ł���̂ł������B�k�c�c�l���{�ł��W����𐔉�Ђ炢���t�����X�l�̉�Ƃ̃N�[�g�[���ȂǁA�����܂������Ȃ����߂ɊX�̊p�X�� �߂ڂ������������₭�X�P�b�`���āA����𗊂�ɓ��������ƌ����Ă����B���Ȃ݂ɁA�����́A�����̗̐����ŁA�P�����P�����������Ă�����i �̔������Ƃ��A��炶�����V��̎肳���̌^�݂̂��Ƃ��Ƃ��A���݂����̎��̔��p���Ƃ��������̂ɉs���ώ@�����ċA���ė������A�����������͎����̔� ���ŁA�������ē��{�ɂ���t�����X�l�̎���肽���̂ł͂Ȃ������B�i�����A���܁`���Z�y�[�W�j��N�A����N�q�͟f���ĊԂ��Ȃ��N�[�g�[��Ǔ����āA�s���E�p�����z�\�\��E�ꂢ���Eゔ���[��t�i�݂������[�A1977�N9��5���j�̌��G�ɃN�[�g�[�� �O���b�V���q�������� Crepscule 1975�r���J���[�ŁA�����Ɂq���ɑウ�ā\�\�����V�A���E�N�[�g�[ Lucien Coutaud ���𓉂ށr���f���Ă���B
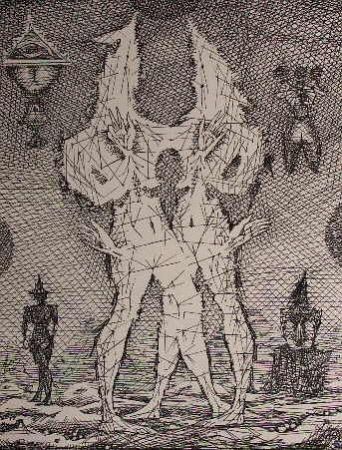
�k2016�N10��31���NjL�l
�g�����̎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�������������B1963�N8�����s�A���q�����ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A
���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�����ꂾ�B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�i���W�s�Â��ȉƁt���^�j�̊Ԃɂ́A�Ђ炪�Ȃ̑����i�u���v�^�u�v�j�̕\�L����
���āA����Ɉٓ��͂Ȃ��B
�s�u�� ���v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�͋g�����̎U���̏W�听�ł���B�����ӂ���g���̕��͂�ǂނ̂����̖{�ł���A�傢�ɏd�Ă���B�g�� �͖{�����}���p���ɓ���Ƃ����āA�U���W�̌���łɂ�����肾�����ł��낤�B���ꂾ���ɁA��A��Z������Ȃǂ����r���ɂ��܂��B���̏������ݗp�̓��� ����A�{�����Z�����ׂ��ӏ������������Ă݂悤�B�Ȃ����p���̂ӂ肪�Ȃ͂����ł͎�肠���Ȃ��B�i�@�j���̐����̓m���u���E�s���ŁA�s�A�L�̓J�E���g�� �Ă��Ȃ��B
�����⒘�Җ����s�g�������y�����E��i�������k��� �t�l�t���Q�Ƃ��ꂽ���B���o�ꗗ�́A ���������ۂ̌����̏����s�g���������s�U���W ���o�ꗗ�t�́� ��Ɓ���ɋL�ڂ��Ă���̂ŁA���������������������Ƃ��肪�����B���̏������ݗp�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�́A��I�����W�̌u���}�[�J�[�A�� �̃{�[���y���A�����M�̋L���ł����ς����B���߂ĊO�������ł��Y��ɁA�ƕ����p�̏�v�Ȍ����Ŏ萻�̃u�b�N�J�o�[��������i���ӂ͒}���p���̐V���ē���� ��ʂ��ē\�������́j�B�����20�N�߂������̌o�߂ƂƂ��ɎC��āA���܂ł͎ʐ^�̂悤�Ȃ��肳�܂��B

�������ݗp�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�̒��ʂƎ萻�̃u�b�N�J
�o�[
�g�����ɂƂ����F�V���F�Ƃ͒N�������̂��B�g�������F�V���F�Əo������̂́A1960�N4��6���i�g���̂��̓��̓��L���F�V���o�ꂷ��j�ȑO�ŁA�g���̌��ɂ����F�V���}�����[�ɖ{���ɂ����̂����Ζʂ炵���i���t�͕s�������A1950�N�㖖���j�B�g���͏o��ƑO�サ�ās�m���t�i1958�j���Ă��āA�F�V�̎��l�g�����ɑ���]���͂��̎��W�ɏI�n����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�F�V�̉���q������{���w�ɂ�����u���̒Nj��v�r�\�\���o��1968�N2���́s�S�W�E���㕶�w�̔���9�t�i�{�Y���сj�\�\�ɂ����鉼�Ȃ�����A
�g�����̎��́A�l�Ԃ̂�����A�тƃR�~���j�P�[�V������}���Ȃ���A�ǓƂ́A�s�ς́A�l�N���t�B���A�́A�������Ȃ��玍�l�ɂƂ��čł��{���I�ȁA���ȂƐ��E�Ƃ̊W�̉��y[�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A]�ɂЂ����玷�����Ă���悤�Ɍ�����B�i�s�F�V���F�S�W�k��9���l�t�A�͏o���[�V�ЁA1994�N2��12���A�ꎵ�l�y�[�W�j
����肱���邱�ƂŁA�g���͂��̖L���ȁu�����v���`�������B���̈Ӗ��Łs�T�t�����E�݁t�Ɂu�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�Ǝ����̂����q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j�����^����Ă���̂͋��R�ł͂Ȃ��B������b�q�́q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�ɂ��u�F�V���F�v�ȂƉ��N���O�l�J�V�����̐l�`�W�ňꏏ�ɂȂ������A�{�C�Ő^�ʖڂɍ��̂Ƃ���A������F�V������ԋC�ɓ����Ă��邩��ˁA�ƌ����A�F�V���F���A���̂Ƃ���[�A�A�A�A�A]�A�����A�Ƒ�������v�i�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A���l�y�[�W�j���������A�g�����N���ɏƂ炷�Ƃ����1973�N10���̂��ƂŁA�F�V�́s�ӓ��̒��̐��E�t�i1974�j�Ɓs�T�t�����E�݁t�i1976�j�̊W�𗠏������Ă���B

�g�������F�V���F�i�s�l�J�V���� �l�`���t�̏o�ŋL�O��ɂāB�R�E�u���b�N�A1985�N5��31���j
�o�T�F�s�V���|�ǖ{ �F�V���F�t�i�͏o���[�V�ЁA1993�N4��25���A���G�q�F�V���F�A���o���r�k���y�[�W�l�j
��
�g�������F�V���F�i1928�`87�j�̕��ɍ��ł��낤����́A�Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�Ɏ��߂��q��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�\�\�F�V���F�������сr�i�K�E17�j�́u�R�v�ł���B
���̌����z�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�C�̒�։��~����
�@�@�@�@�@�k��L�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ킿�i�L�����E�t�@���^�X�}�j
�u���̐��g����
�@�@�@�@�@�@�@����̓ˋN���S���Ŏl�{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂�Ŏl���b
�̂悤�ɐ����Ă���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�p���́k����l���܂ʂ���
������ꂽ�k���݁l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�_�b�̉��b�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȃ����
�i�L�����E�t�@���^�X�}�j
��
�o���T�O�s�F�V���F�̎莆�t�i�����V���ЁA1997�N6��1���j�ɂ́A1963�N������F�V�̌�F�W����������߂�����B�㔼�ɋg�����o�ꂷ��B
�@ �y���F�͕����ƁA��������͔o�l�����l�A�r�c�����v�͉�ƁA�x�����b�q�͎��l�A���{�����͉��o�ƁA���R�r���Y�̓C���h�w�ҁA���[�����͉�ƁA�쒆��������ƁA���������͎��l�B�����Ă��̋Ȏ҂��낢�̋q�������A�Â��Ɋ��҂���[�A�A�A�A�A�A�A]�Ƃ����▭�Ȗ������Ȃ���������̖�쐟�q�́A�G�˂̃h�C�c���w�҂������B���̂���̂ɁA�����������ăA�[�`�X�g�����v�����Ȃ��B
�@���̐l�����ɁA�₪�ăh�C�c���w�̎푺�G�O�A�t�����X���w�̛ܒJ���m�A�l�`��Ǝl�J�V�����A��Ƌ��q���`�A���l�����r�Y�A���������l�g�����A�o�D�����o�Ɠ��\�Y�炪�����B���ۂ͒������A���ʊi�Ȃ̂�����v���Ђ̐Έ䋱��A�A�[�g�f�B���N�^�[�̖x�����ꂾ�B�i�����A��ꎵ�y�[�W�j
���������A�]�p���B�e�̋L�O�ʐ^�̊�G���z�N�����B����́s�A�T�q�J�����t1972�N2�����́q�k�A�ځi��j�\�A�l������� ���l�r�̈�_�ŁA�q��������o�ŋL�O��@���a46�N11��27���@�V�h�ԉ��_�Ёr�Ƃ�����̌��J���ʐ^���i��̑ΏۂƂȂ����{�͌��㎍���ɔŁs����������W�t���s�j�����@�M�i�t���j�B���̃L���v�V�����Ƃ�������u�o�ȎҎ����i���s���j�v�������B
����i�q�@���䐟�q�@����N�v�@�l�J�V�����@����o�@�����O�Îq�@�F�V���q�@���ā@����x�q�@�ޒJ���m�@���R�r���Y�@����Y�@��c�Γ��@����C���@���v�ی��T�@�]�����g�@�g�����@��m�G�@�����@��������@���c�C�@����@�N�@�T�R�ށ@����L�@�O�c���u�@�F�V���F�@�u�����@�������j�@�y���F�@��_�B��@�g�{���V�@�����x�M�@��쐟�q�@�r�c�����v�@�E�c�ʜ\�@���������@�g���N�O�@�������@���\�Y�@���J�K�M�@������@����p�v�@�썇���O�@��c�N��@�����ʍ]�@�吼�a�j�@�N�F�v�@�|���b���@�����N��@�����W��@�ɓ��r�Y�@�������@�k���L�q�@�o���T�O�@�͒J���F�@�쒆�����@�哇��q�@�J��W��@�X���z�@���R���O�Y�@�ї��l�@�k��K�v�@�����ĔV�@�{���m�@�F�V�F��@�����T�v�@�푺�G�O�@���ؒ��h�@���엲�@�ŎR���Y�@�R�{���q��@�֓��T���@��c�O�u�@��Z�����Y�@�˓c�O�q�@�ؑ��p��@��֏G�I�@�O�p���@�{��s���@���я��u�@��J����@���c�K�Y�@�{�i���F�@�����H�@�]�p���@�������i�����A����`���O�y�[�W�j
�]����͎������Ɂu�o�ȎґS���̋��͂łł����L�O�ʐ^�ł���B��F���u�I���ЂƂ�Ƃ̂������Ǝv���Ă����̂Ɂv�Ƌ��ł�قǍL���B�ْ���������ꂽ��u���B�����ʐ^�ŁA���̏ё��ʐ^�_���炷��Ύד��Ƃ������ƂɂȂ邪�A���Ƃ��ɂ�����ɂȂ����X�i�b�v�E�t�H�g�O���t�B�[�́A�L�O�ʐ^�ւ̉��p�ł���B�v�i�����A���Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B�g���̌������č��ׂ͎���̉�������A�E�ׂ͑���C���B���ዾ���F�V�͓y���F�Ɨׂ荇�킹�ŁA�����Ȃ���ł���B����������ɂ��A���̎ʐ^�ɂ́i��f�u�o�ȎҎ����i���s���j�v�ɂ͂Ȃ��j���[�����A��L�V�A�g�������̏������ʂ��Ă���Ƃ������Ƃ�����A�܂����Y�����̂��Ƃ���G��ł���B�Ȃ����̎ʐ^�́A�ܒJ���m�i�ďC�E���j�s�F�V���F ���z���p�فt�i���}�ЁA2007�j�₻����Ę^�����ܒJ���m�s�F�V���F�_�R���N�V�����V�\�\�F�V���F ���z���p�ف^�F�V���F�Ɓu���v�̒��ԁt�i�א��o�ŁA2018�j�ł����邱�Ƃ��ł���B
��
�F�V���F�ɂƂ��ċg�����͒N�������̂��B�F�V���q�v�l�́u�F�V�͋g������̎��������]�����Ă��āA�g������̂ق����N��͏ゾ�����̂ł����A���̊W�͐e�����C�S�̒m�ꂽ�F�l�Ƃ��������ł����B�v�i�s�F�V���F�Ƃ̓��X�t�A�����ЁA2005�N4��30���A��O��y�[�W�j�ȏ�̕]��m��Ȃ��B
�k2019�N12��31���NjL�l
�����d�M�A�F�V���F�A�y���F�瑽�ʂȍ˔\�Ƃ̌�V�̓��X�������ɋL������������̓��L�q�����̎� �W�ȍ~�\�\1960�i���a35�N�j�`1974�i���a49�N�j�r�i�s���������i��W�V�\�\���������L�E�G�b�Z�C�E��V�^�t�A����A���X�A2016�N7��16���j�ɏ�f�̏o�ŋL�O��̗l�q���^����Ă���̂ŁA���p����B�Ȃ��A���L�{���͊����ɐ������g�p���Ă��邪�A�C���^�[�l�b�g��ł͂��ׂĂ��Č��ł���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�g�������g�����v�̂悤�ɐV���ɉ��߂��B�������A�{�l�̗p�@�d���Đl���E�����͌����̂Ƃ���Ƃ����B���������́A�̂ĉ����̎g�p���܂߂āA�����̃}�}�B
�k1971�i���a46�N�j�l�\�ꌎ��\����
�@�u�r����v�u�V�q��ԁv�u�q�̃������v�u�j�����@�M�i�v�u��铊��S�v�u����������W�v�̏o�ŋL�O��B�V�h�ԉ��_�ЂɁu���ɒJ�v���o���B�ߌ���A�i����������Ă��ꂽ���J�K�M�������ɗ��Ă���đō����B�����A�ԉ��_�В��B���É�����T�R�܁A�u�����A�Q�n���牖�����j�̊炪������B����C���������t�̉������Ƃ��Ă����B�S�l�ʂ��Ƃ��Әb�A�������B
�@��́u���j�R���v�B���������ƃe�[�u���̏�ŗx���Ă�ē]���B���e���O�Y�������̉���ς܂��Ă��痈�Ă����B�u�i�W���v�ɍs�������͂��Ȃ����B���Z�����A�ɓ����Y�N�ɑ����Đ����ɋA��B�i��\�����L�j�i�����A���܃y�[�W�j
�o�ŋL�O��̑ΏۂƂȂ�����������̒����́A�s����������W�t�s�j�����@�M�i�t���܂ށA1969�N����1971�N�ɂ����Ċ��s���ꂽ�ȉ���6���ł���B
�@�@�s�r����t�i�v���ЁA1969�N12��30���j�͑�W�B
�@�@�s�q�̃������t�i���ʎЁA1970�N10��15���j�͑�l��W�B
�@�@�s�V�q��ԁt�i�O�ꏑ�[�A1970�N11��15���j�͑��]�_�W�B
�@�@�s��铊��S�k����Łl�t�i�����ɁA1971�N8��16���j��1959�N���̑���W�̌���ŁB
�@�@�s�j�����@�M�i�t�i�K�N�\���ЁA1971�N8��20���j�͑�O���W�B
�@�@�s����������W�k���㎍����45�l�t�i�v���ЁA1971�N10��20���j�͂��̎��_�ł̑�����W�ɂ��đ������W�B�s���������i��W�V�t�́k���́^����N�O�l�q�������r�ɂ́u�A���@���M�����h������̐����ƌ��������v�i�����A�ܓ�܃y�[�W�j�Ƃ���B�Ȃ��g���́A�{���ɐ��z�q�o��r�����M���Ă���B
�k2020�N7��31���NjL�l
���������V�^�s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�N10��19���j�́q�_�S��lj��r�̔����i�Ό��y�[�W�͌��̏W���ʐ^�j�Ɂq�Ɖe�F���ꗗ�i�\�����j�r���f�ڂ���Ă���B�ɂ��ނ炭�́A�l�����\�[�g����Ă��邽�ߎʐ^�̐l���Ƃ̏ƍ�������B���������́q�Ɖe�F���ꗗ�i�\�����j�r�A��������{�l�i���邢�́A���łƕ��ɔł̕ҏW�S�����ł����l�E�n糈�l�\�\�n糂͕��ɔŊ����̉���q�����̓��X�r�ł́u�g�����v�Ə����Ă��āq�Ɖe�F���ꗗ�i�\�����j�r�̕\�L�ƈ�v���邪�A����������u�g�����v�Ə�������A���M�ғ���̂��߂̔��f�ޗ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��\�\���A����Ƃ��A�w�K�����Ђ̕ҏW�������c�G�����j�����������������̂Ǝv����̂ŁA��L�̐l���Ƃ̏d�����ꂸ�A�ʐ^�ƂƂ��Ɍf����B
���R���O�Y�@�r�c�����v�@�ɓ��r�Y�@��_�B��@����N�v�@�ܒJ���m�@���v�ی��T�@�哇�l�q�@�吼�a�j�@����Y�@��֏G�I�@����o�@�����W��@���J�K�M�@��������@�T�R�܁@�썇���O�@�͒J���F�@��m�G�@���\�Y�@�k��K�v�@�k���L�q�@�ؑ��p��@�E�c�ʜ\�@�N�F�v�@�֓��T���@�������j�@�������@�ŎR���Y�@�F�V�F��@�F�V���F�@�F�V���q�@������@�u���k�`�����l�@���������@�{�i���F�@���ā@�]�����g�@����x�q�@�����N��@����C���@�|���b���@�J��W��@�푺�G�O�@��Z�����Y�@�o���T�O�@�˓c�O�q�@�����O�Îq�@����p�v�@�����ʍ]�@�����T�v�@�����ĔV�@�����H�@�����x�M�@��c�Γ��@��c�N��@��c�O�u�@�쒆�����@�ї��l�@�y���F�@���䐟�q�@����@�N�@�]�p���@�O�c���u�@����L�@���c�C�@���c�K�Y�@���я��u�@���R�r���Y�@����i�q�@���엲�@�O�p���@�{��s���@�{���m�@�X���z�@��쐟�q�@���ؒ��h�@�������@��J����@�R�{���q��@�g�����@�g���N�O�@�g�{���V�@�l�J�V�����@�����@��������l�i�����A���Z�y�[�W�j
![�u���a46�N11���A�V�h�ԉ��_�Ђł̏o�ŋL�O��B�i�B�e�E�]�p���j�v](image/katoikuya_kai_3.jpg)
�u���a46�N11���A�V�h�ԉ��_�Ђł̏o�ŋL�O��B�i�B�e�E�]�p���j�v�@�o�T�F���������V�^�s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�N10��19���A�k��ꎵ�y�[�W�l�j�B�g�����͑O����2��߂̉E����8�l�߁i���ׂ���������j�B�Ȃ��A�o�T�̈قȂ邱�̏W���ʐ^���q�g�����Ɖ�������\�\�ӂ���̓��L�𒆐S�Ɂr�̂����܂��ɂ��f�ڂ����B
�g�����͉�Ƌg�c���j�i���N���ځj�ɂ��āA�q���e���O�Y�A���x�X�N�@�R�@���ϒn���̎��Ӂr�i���o�́s���e���O�Y�@���Ǝ��_�k��6���t �^�l�t�A�}�����[�A1975�N10��31���j�ł��������Ă���B
�@���͓�\���N�O�̂��Ƃ�z���o���Ă����B���̒n�����܂̉��̊␣�Ƃ����ƂɁA�Ⴂ��Ƌg�c���j�Ɖ��h���Ă����� ���B�Ǝ�͎l�\ �܁A�Z�̌�Ƃ���ŁA�����Ԃ������ꂽ�قƊ�����Ă����B�~�̐[��ɁA�e�q�O�l�̐Q������Ȃ���A���͕֏��ւ���������̂��B�������͑䏊���o������� ���Ă����B���傤�ǂ����ɂ͌{�����������āA�^�Ă͕�[�ӂ�]�̏L���ɕ������B�_�o���Ȍ��j�͂��Ƃɂ��₪�����B�ނ͎q���̂����A�̕a�C�������Ƃ� �ŁA���������ꂽ�������āA�s���҂̎�������̂������B��Ƃ�������n�̌����ɁA�܂��n�R�ȎO�V���~�����Z��ł������A�s�v�c�Ȃ��Ƃɗ�����Ă��� �̂������Ƃ͂Ȃ������B
�@�߂��ɜh�q�̕揈���������̂Łu�{��[�ӂ�]�̍���ׂ�͎O�V���~���t�v�Ɠ�l�͏����B�������͑��p�́u�~������ׂ�͉����y�E�q��v�̃p�� �f�B�[�ł���B�F�l�����́A���Ƌg�c���j�Ƃ̋��������͈�N�������Ȃ����낤�ƌ��������A���a��\��N�̉āA�ނ��y���ŔN��̕w�l�ƐS������܂ő��� ���B
�@���̍ג����������玄�̎��W�s�Õ��t�͐��ꂽ�B
�@��x�����ϒn���̑O��ʂ�̂��A�����������Ă����킪�F�g�c���j���A�����͉��������z���o���Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A 1988�A����`��O�Z�y�[�W�j
���̂�����̂��Ƃ͋g�����M�̔N���Ɂu���a��\��N�@���l�N �O�\�܍^�H�A�y���ŁA�����̉�Ƌg�c���j���N��̏��ƐS���B�唪�ƌ��j�̒�ƂƂ��ɁA�⍜���}���ɍs���B���C�~�ō�����݁A���̊Ԃֈ��u���A���̏h �Ɉꔑ����B���j�̎����_�@�ɁA���ꂽ�����s�E�h�Ɗ�ȗ����V�Y�v�i�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j�Ƃ���B�ނ�� ���S�ɂ������c�唪������u���̍��k���a��Z�N�㖖�l���̉Ƃɂ͂����ȋ������B���̌�y�̊G�`���g�c���j�A�ނ��g���Ƃ͋��ʂ̗F�l�ƂȂ����̂����A ���̒j�������ɂ��Đ����Ȍ̂ɐS���Ƃ�������ɂ��Ă͔���������`���Ƃ��Ď��B�̑O���狎���Ă������B�g���Ǝ�����Ɍ��j�̒�ƎO�l�Ōy���̌x�@�֍��� �����ɍs�������Ƃ��������v�i�q�J�����I���̊�r�A�s�����C�J�t1973�N9�����A�����y�[�W�j�Ə����Ă���i�g���͑��c�������܂ŋg�c�̂��Ƃ��� ���������Ȃ������j�B���܁u��Ɓv�g�c���j�̑��Ղ����ǂ邾���̗p�ӂ��Ȃ��̂ŁA�u�}�G��ƁE�����Ɓv�g�c���j�ɂ��ďq�ׂ����BOPAC�Ȃǂ̏����Œ� �ׂ�ƁA�g�c�͈ȉ��̐}���̑}�G�����S�����Ă��邱�Ƃ��킩��i�����4�^�C�g����1962�`63�N�A�O�������߁k�V�ŏ��w���S�W�l�Ƃ��ďo�ł��� ���j�B
�H�c���X�́k���ǂ��G���Ɂl�ɂ͑��c����ɊG��`���Ă��邩��A��y�̋g�c���Љ�����̂��낤�B�}�����[�́k���w���S�W�l�̒S���� �W�҂͋g���ł���i���z�q�a�c�F�b�Ǒz�r�̖`���Q�Ɓj�B�k���w���S�W�l�̃J���[�̌��G��m�N���̑}�G�͊m���ȋZ�ʂŕ`����Ă�����̂́A���ꂪ�ق�Ƃ� �ɋg�c���`�������������E���A�ƂȂ�^�₾�B
 �@
�@ �@
�@
�������n�s���Ƃ̊w�Z�k���w���S�W16�l�t�i�}�����[�A1955�N11��30���ĔŁj�k��
�G�F�g�c���j�l�i���j�Ɗۉ����s�ƂȂ��q�k���w���S�W54�l�t�i�}�����[�A1954�N8��31���j�\���k�����F�ɓc叕�l�i���j�Ɠ��A���ʁk�}�G�F�g�c��
�j�l�i�E�j
����A������i�Ƃ��Ă͏��R���̑��n��W�s����E�Ёt�i�}�����[�A1953�j�⑱���s�����Ȓ��t�i���A1954�j�A�����E�݂̂�s�� �̕����t �i���A1953�j�A�c�{�ՕF�s�K�̉Ԃ������t�i���A1954�j�A���c�ɑ��Y�s�����t�i���j�Ȃǂ����邪�A�g���͕ҏW�S���ł͂Ȃ��Ǝv����B�ʐ^�Ō��� �s����E�Ёt�͊G�`���̑����ŁA����Ƃ����������͂Ȃ��i�{���Ƀ~���[�̊G���̐����z���Ă���j�B�s�����t�̃W���P�b�g�͎O�p�`�E�H�`�����`�[�t�ɂ��� �w�͗l�����A����Ƃĕ`������ʂ̋��Ƃ���Ƀ��^�����O�̕�����u���Ă݂��Ƃ������͐@���Ȃ��B������̎d���Ɍg����Ďl�A�ܔN�B�g�c���j�͎��g �̑����X�^�C���̊���������܂��ɐ��������̂Ǝv�����B
 �@
�@
���R���s����E�Ёt�i�}�����[�A1953�N6��10���j�W���P�b�g�k�Q�����т̌f�ډ摜�l
�i���j�ƕ��c�ɑ��Y�s�����t�i���A1954�N6��30���j�{���ƃW���P�b�g�i�E�j�k�Ƃ��ɑ����F�g�c���j�l
�g�����ɂƂ��ċg�c���j�Ƃ͒N�������̂��B���̎��܂ő��|��4�N�ԑ��������������́A�g���ɉ�Ƃ̂Ȃ邩���������ɈႢ�Ȃ��i�g�c �̊G���i�� �ς��Ȃ����̂��낤���j�B�g���̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�ɂ́u��Ƃ̐S�ۂׂ݂̊̔n�v�i�q�Õ��r�B�E4�j�Ƃ������傪����A����Ɂs�m���t �i���惆���C�J�A1958�j�ɂ͎��̂悤�Ȍ���I�Ȏ��傪����B
�k�c�c�l�@�ڂ��͌�����@�ǂɗ��Ă������@���E������Ƃ̃J���o�X���@�ڂ��̎����̂����Ł@���ꂾ�������ɑς��� ���@����l�� �\���̂�F�̒n�k����@���̊G���ڂ����܂����Ă����B��̂��̂�������ʁ@�n������Ƃł������j�������ɕ`�����@�{��̍\�}�@�Ƃ����Ɉ��͂������Ɂ@ �������[�݂���@�₽��ɂ̂肾�����Ƃ���@���ނ����̃g���\�����i�q�~�̊G�r�C�E6�j
���ɂ́q�~�̊G�r�́u���E������Ƃ̃J���o�X�v���A�g�������g�c���j�̒Ǔ��̂��߂Ɏ��ŕ`�����G�Ɍ����Ă��������Ȃ��B�g�c�̂��ǂ��� �Ղ�ǂ��悤�ɂ��āA���g���ꂵ�����̓��ɓ��݂܂�����������A�҂����g�����A��������g�����������̂��s�m���t�������B
���сq���L�r�i�I�E6�j�̐蔲���́A�g�����̎肪��������ԂŃX�N���b�v�u�b�N�ɓ\�t����Ă���B����͂��������������B�q���L�r�ȊO�̎��т́ASCRAP BOOK�i�i�ԁF�R���N�g S-101�j�AMEIKANDO TOKYO����SCRAP BOOK�i�i�ԁFKING NO.140�j�̑o���Ƃ��A�i��Ɏ��W���^�̍ۂɎ肪�����Ă���ꍇ���j�X�N���b�v�u�b�N��ł͂܂������������݂��Ȃ����炾�B����ɁA���Ɍf�����ʐ^�i�q�����ԍ�11�E12�E13�̐蔲����\�t�������J���y�[�W�r�̎����ԍ�13���L�����Ƃ���j������킩��悤�ɁA���̎��т��X�N���b�v�u�b�N�̗p���ɂ����ɓ\�t����Ă���̂ɑ��āA�q���L�r�̐蔲���͒��ړ\���Ă��Ȃ��B��������͎��̂悤�Ȍo�܂��z�肳���B
�g���́A�@����ɂ̖�����̌��e�p���i32���~20�s�l�j�ɁA��i�g�̏��o�����ɐ��Ė{�����A������悤�ɓ\��A�A���̐蔲���Ƀy���ŏC������������A�B���e�p���̗]���ȂƂ�������Ő�A�C���̌��e�p�����c�ɓ�܂肵�āAKING NO.140�̑䎆�ɃZ���n���e�[�v�œ\������i�ϐF���ăR�s�[�ł͍���������j�B�g���́q���L�r���s���w�t�i1960�N1�����j�ɔ��\��̂��鎞�_�Ł\�\�����炭�͎��W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j�Ɏ��^���邽�߂̑O��ƂƂ��ā\�\�A�܂ł��s�Ȃ��Ȃ���A�Ȃ�炩�̗��R�ł�������W�p���e�ɂ��Ȃ������i�g���͎��сq���L�r�����W�s�a���`�t�ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��Ɣ��f�������߁A���^�������킹���̂ɑ���Ȃ��j�B����ɕ�����h���ׂ��A�����KING NO.140�̎���12�̏���ɓ\��A20�N�߂��Ό����o�ďE�⎍�W��҂ލہA�u���L�v�Ə������tⳂ�\������B�����悻�ȏ�̂悤�Ȃ��Ƃ����������B
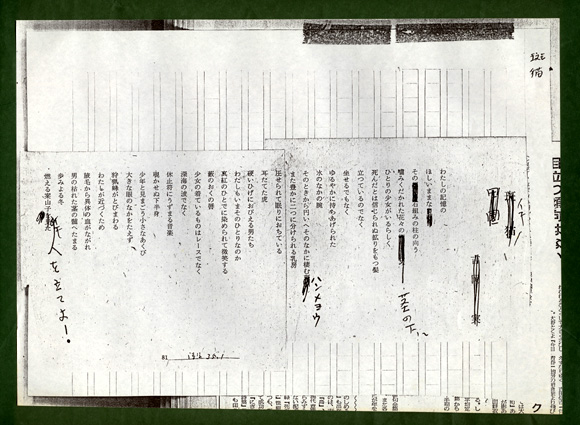
���сq���L�r���o�`�ւ̋g�����̎����k�g���Ƒ��X�N���b�v�u�b�N�̃��m�N���R�s�[�l
���сq���L�r���o�`�ւ̋g���̎����i��f�ʐ^�j��ǂ݉����āA�����ōČ����Ă݂�B
���L�k���c�������L�l�k�g�������i�g���j�l
�킽���̋L����
�ق����܂܂ȁk��Ԗځ��i�g���j�l
���́k�z���́��i�g���j�l�Αg�݂̒��̌���
���݂������ꂽ�ԁX�́k�C���̋ɂ݁��s�̉��Ɂl
�ЂƂ�̏���������炵��
���Ƃ͐M�����ʊg�������
���Ă���̂łȂ�
������ł��Ȃ�
���₩�Ɏ���������ꂽ
���̂Ȃ��̘r
���̂Ƃ�����~���ւ��̂Ȃ��ɐ��ށk���L���n�������E�l
�܂��L���ɓ�ɕ���������[
�������Ė���ɂ����Ă���
��������
�d���Ђ��ɂ��т���j����
�킽�������܂��̂ЂƂ�Ȃ̂�
�^�g�̂ЂƂłɐ��߂��Ĕ�����
�M�̂����̐O
�����̒��Ă�����̂̓��[�X�łȂ�
�[�C�̔g�łȂ�
�x�~���ɂ����܂鉹�y
�`�����ʉ����g
���N�ƌ��܂��������Ȃ�����
�傫�Ȋ�̂Ȃ���������
��I���Ƃт܂��
�킽�����߂Â�����
���т���ّ̂̌����Ȃ���
�j�̌͂ꂽ�s�̐��ւ��܂�
���݂��~
�R����ĎR�q�k���������𗧂Ă�I���������l
���ɁA���W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j���^�`�A���Ȃ킿��e���f����i�s���̃��C�i�[�͈��p�ҁj�B
���L01 �킽���̋L����
02 �ق����܂܂�
03 ���̐Αg�݂̒��̌���
04 ���݂������ꂽ�ԁX�̌s�̉���
05 �ЂƂ�̏���������炵��
06 ���Ƃ͐M�����ʊg�������
07 �����Ă���̂łȂ�
08 ������ł��Ȃ�
09 ���₩�Ɏ���������ꂽ
10 ���̂Ȃ��̘r
11 ���̂Ƃ�����~���ւ��̂Ȃ��ɐ��ރn���~���E
12 �܂��L���ɓ�ɕ���������[
13 �������Ė���ɂ����Ă���
14 ��������
15 �d���Ђ��ɂ��т���j����
16 �킽�������܂��̂ЂƂ�Ȃ̂�
17 �^�g�̂ЂƂłɐ��߂��Ĕ�����
18 ���̂����̐O
19 �����̒��Ă�����̂̓��[�X�łȂ�
20 �[�C�̔g�łȂ�
21 �x�~���ɂ����܂鉹�y
22 �`�����ʉ����g
23 ���N�ƌ��܂��������Ȃ�����
24 �傫�Ȋ�̂Ȃ���������
25 ��I���Ƃт܂��
26 �킽�����߂Â�����
27 ���т���ّ̂̌����Ȃ���
28 �j�̌͂ꂽ�s�̐��ւ��܂�
29 ���݂��~
30 �R����ĎR�q������
�����`�ƒ�e���r����ƁA���s�߁u���k�����l�Ă���̂łȂ��v�A���s�߁u���̂Ƃ�����~���ւ��̂Ȃ��ɐ��ށk�n�������E���n���~���E�l�v�A�ꔪ�s�߁u�k�M�����l�̂����̐O�v���ٓ��ӏ������A�����������̏C���Ƃ��������A���W�Ҏ[�ɂ�����\�L��̓���i�V���E�V���ȁj�Ƃ݂Ȃ����B�苖�ɂ���T���͌����̃��m�N���R�s�[�̂��߁A�������݂̃C���N�̐F�����ʂł��Ȃ��̂��c�O�����A���L�̎�����������ɂ����鎞�ԓI�Ȑ��ڂ��l�@���Ă݂悤�B
�܂��A�薼�ł���B�q���L�r���q�c���r�ɕς����̂́A�����炭�{���̎����Ɠ��������낤�B�g�������̑薼���K�������u�������ł��Ȃ����̂łȂ����Ƃ��s���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁t�ł��q�ׂ����A���̎����q�c���r�Ƒ肷��̂͂������������̂悤�Ɏv����i���ꂩ����ʂ��A�q�c���r��1973�N9�����\��12��134�s�̎��̑薼�Ƃ��āA����I���ŏI�I�ɓo�ꂷ��j�B����ŁA�{�т̑薼���q�c���r�Ȃ���ɂȂ�Ȃ��������s�߁u���̂Ƃ�����~���ւ��̂Ȃ��ɐ��ށk���L���n�������E�^�n���~���E�l�v�́A��x�͖��������q���L�r���C�L�ɂ��ď��Ă̑薼�ɖ߂������߁A�J�^�J�i�Ɗ�����l�̕\�L�����ї����A��e����������̂܂܈��������Ă���B�Ƃ���Łu���L�v�́A�����܂ł��Ȃ������ڔ��L�Ȃɑ����鍩���̑��̂����A�����̕\�L����͔��͗l�̔L�̎p������������邩��s�v�c���B
�{���ւ̎����ł����ڂ����̂́A�O�Z�s�߁u�R����ĎR�q�k���������𗧂Ă�I�l�v�ł���B���̎�̊��Q���̗p�@�͑������s�a���`�t�i1962�j�Ɍ����Ă���A�����W�ւ̎��^��\�肵�������A�Ƃ������̐����͓I�O��ł͂Ȃ��B���������o�`�̖����̎d�����A���͓h��Ԃ��Ȃ̂ɑ��āA����������{���̌��������Ȃ̂͂Ȃ����B����ꂪ����̂��̂ł��������߂̂悤�ł����邵�A�C�����e�Ɏ��M�����ĂȂ��������߂̂悤�ł�����i��Łu�C�L�v�Ə����ď��o�`�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ��d������A��҂ƂȂ낤�j�B���̂�����̂��Ƃ����Ă���ƁA�O�Z�s�߂̎����i�C������т��̒����k�߂��l�j�̂ǂꂪ���W�s�a���`�t�����̂��̂��A�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j���^���O�̂��̂��A�y�y�ɔ��f�ł��Ȃ��B����ȏ�q���L�r�̖{���ɂ��Č�邱�Ƃ́A�z�q�v�l�̎�ɂȂ邾�낤���W���e�p���e�ł����Ȃ����������B
��Ƃ̍������ꎁ���q�f�ڎ��r�Ƒ肵�ăR�����������Ă���B�u�����ł���A�G�b�Z�C�ł���A���͂������A�K���f�ڎ��i���j�������Ă���B��������͒��J�ɐ蔲���āA�X�N���b�v�ɂ܂Ƃ߂Ă���B�^�k�c�c�l���ۂ̂Ƃ���A���̍�Ƃ���͂ǂ�����Ă���̂��낤���B���Ǝ҂�`[�̂�]�����ł���Ƃ���Ȃ�A������������Ԃ̋����ł���v�i�s���{�o�ϐV���k�[���l�t�A2007�N2��28���A19�ʁA�q�v�����i�[�h�r���j�B�m���ɑn��Ƃ��X�N���b�v�ɂ��đ̌��I�Ɍ�������͂͏��Ȃ��悤���B�g���������Ƃ̎��͂Ƃ����A������蔲���ăX�N���b�v����̂͐V���L�������ŁA�G���͌�����ۑ����邩�A�a�S���̃R�s�[�ɂƂ��ēt�@�C���ɒԂ���B�������́q�f�ڎ��r�Ȃ�A�܂��V�����ʁi5�E6�ʂ�19�E20�ʂ�1���j�������ʂ��Ĉꎞ���u����B�ēǂ��ĂȂ��ۑ����鎑���������J�b�^�[�Ő蔲���A�u�e�[�}�F�@�@�@�@�@�@�v�A�u���{�o�ϐV��2007�N�i����19�N�j�@���@���i�@�j�@�ʁv�Ȃǂƃv�����g�����`�S�̔��̂ɌЂÂ����āA�e�[�}�Əo�T���菑������B�������Ăł����X�N���b�v�V�[�g�i���Ȃ̂Ńu�b�N�ɂȂ�Ȃ��j�́A�����ς���p���̓T���Ƃ��Ďg�p����B
���āA�q�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i1�j�r�ɑ����āA�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�ł���B�O����w�\�����ʂ����ʐ^�̂����AMEIKANDO TOKYO���́qSCRAP BOOK�r�i�i�ԁFKING NO.140�j�̓��e���Љ�悤�B�ȉ��Ɏ����ԍ��A�\�t������̍�Җ��i�g�����̏ꍇ�͏ȗ����A�W���������L�j�ƕW��\�\�z�q�v�l�̎�ɂȂ�o�T�����\�\���l������ꍇ�͔��l�A�̏��ɋL���B
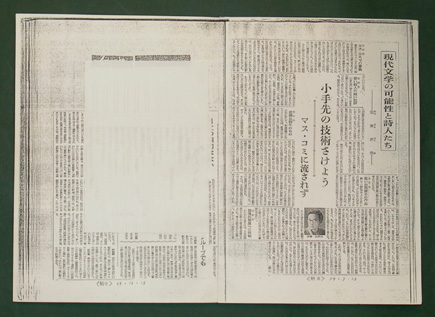
�����ԍ�11�E12�E13�̐蔲����\�t�������J���y�[�W�k�g���Ƒ��X�N���b�v�u�b�N�̃��m�N���R�s�[�l
�����̂Ȃ��ōł������[���̂́A�����ԍ�13�̎��сq���L�r�i�I�E6�j���B���̐蔲�������A����i����ёO��j�̃X�N���b�v�u�b�N�ŗB��A�g�����̎肪�����Ă��鎍�Ȃ̂ł���B�\�\�Ə������Ƃ���ŁA�q���L�r�{���̓��e�ɂ��Ă͍e�����߂ďڏq�������B
�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�́q�g���������r�����M����ɓ������āA�����ł��d�������̂͗z�q�v�l���炨�肵���g�����̃X�N���b�v�u�b�N�������B���̎ʐ^�͂����̔w�\�����ʂ������̂����A����͍�����2�Ԃ߂́qSCRAP BOOK�r�i�i�ԁF�R���N�g S-101�j�̓��e���Љ�悤�B�ǂ̃y�[�W���V����G���̐蔲����1�A2�_�\�t���������ӂ��̏�ԂŁA�����ւ̏������݂͈�Ȃ��B

�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�ƃN���A�t�@�C���u�b�N�i�g���Ƒ��j
�ȉ��Ɏ����ԍ��A�\�t������̍�Җ��i�g�����̏ꍇ�͏ȗ����A�W���������L�j�ƕW��\�\�z�q�v�l�̎�ɂȂ�o�T�����\�\���l������ꍇ�͔��l�A�̏��ɋL���B

�����ԍ�9�E10�E11�̐蔲����\�t�������J���y�[�W�k�g���Ƒ��X�N���b�v�u�b�N�̃��m�N���R�s�[�l
�X
�N���b�v�u�b�N�͍��J���ŁA�S����15�y�[�W�ɂ킽���Ĉ�������\�t����Ă���B����̎��т�2�сA���������z��4�сA���҂ɂ�錾�y�i�g�����_�j��8�сA�Ƃ�������ɂȂ��Ă���B1969�N12������1973�N6���܂ł�3�N���̍�i�╶�͂�ǂ�ł����ƁA����1970�N�㏉�߂̋g�����́u���فv�̓䂪�����邩������Ȃ��\�\����ȗ\�������������鎑���ł���B
�z�������܂܁A�����[���_��������B���䕶�̌�ɁA�����߂��鐏�z2�т�������Ă��邱�ƁB��{�������̎����ɏW�����Ă��邱�Ɓi��{���s�]���̋N���t��2006�N�ɔ��n�Ђ��犧�s���ꂽ�j�B�s�����C�J�t�i�y�Ёj��2�M���Ă��邱�Ɓi���ꂪ1973�N�́q�g�������W�r���Ɍq����A����ɂ�1976�N�́s�T�t�����E�݁t�Ɍ����������j�B��A�Ƃ�������s���㎍�蒟�t�i�v���Ёj�ւ̊�e���Ȃ����ƁB�tⳂ̕t����3��̂����q�w�A�[�r�i�q翉́r�Ɖ���j�́s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�ɁA�q�����_���r�́s�u�����v�Ƃ����G�t�i1980�j�Ɏ��^���ꂽ����A�q���M�r����҂₻�̑���łɂ͎��߂��Ȃ��������ƁB�g���̑��������߂Ė{�i�I�ɘ_�������c�����o�ꂵ�����ƁB
�Ȃ��A�����ԍ�11�̐����N�Y�̌������͌f�ڎ��ł́i���l�j�ƂȂ��Ă��邪�A�s�����C�J�t�̔��s���E�y�Ђ̎В����̐l�ł���A��Ɂs�T�t�����E�݁t�̔��s�҂ƂȂ�l���ł���B

���{�Βj�s������Ƃ̐l�X�t�i�����ɁA1975�N7��30���j�̕ی�p�T�b�N�ƕ\��
���{�Βj�̒��я����s������[�܂�����]�Ƃ̐l�X�t�i�����ɁA1975�N7��30���j��ǂB����1000���B�\�������ΐF�i�}�[�u �����ɔZ�� �v�́u�p���v�j�����A�z�̓\���A���Ԃ��A�{���A�O���̏������߁A�ƍ��œ��ꂵ���ӏ��͏��J�Y���̒������v�킹��B�������A���J�̂��ꂪ��Ɋp�w�������̂� ���āA�{���͊۔w�ł���B�\����V�n�Ŋ������i�{�[���̕ی�p�T�b�N�ɂ͒��҂́q���Ƃ����r�����ӓ\�肳��Ă��邪�A��������قȂ�̂Ŗ{���́q���� �����r����ꕶ�������B
�@���̍�i�́A���܂���A���\�N���O�̂��̂ł���A�ŏ��Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��A�u�ߑ㕶�w�v�ł��������A���̂Ƃ��� ��A�A�ڂȂ��� �Œ��₷��^���ɂ���A���ꂩ��\��N�̌�A�u��k�v�Ɍ܉�ɂ킽���āA�ēx�f�ڂ��ꂽ���Ƃɂ���āA�����̂����ŁA�悤�₭�������݂�ɂ����邪�A�u�� �㕶�w�v����u��k�v�Ɍf�ڂ����\��N�Ԃ̂������ɂ��A�u��k�v�ł̌f�ڂ�������āA�����ɂ�����܂ŁA���x���{�ɂ����@��ɂ߂��肠���Ȃ���A�z�� �ڂ��݂钼�O�ŁA�ł̂Ȃ��ɏ����Ă�������i�ł��邱�ƂɁA�Ȃɂ�����A���킵���^���I�Ȃ��̂������Ă��������ɁA���̂��сA�g�������A�����ɂ̐������� ���̂��s�͂ɂ���āA�{�ɂ���邱�Ƃɂ��܂������Ƃ����邱�ƂȂ���A���̍�i�̍�҂Ƃ��āA���̍�i�ɂ܂Ƃ����ꂽ�^���I�ȊW���A�����ŁA�悤�� ���f���邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�B�i�{���A�k���܃y�[�W�l�j
�s������Ƃ̐l�X�t�͍��{�̏�����ŁA�s�ߑ㕶�w�t1955�N4�����E6�����E7�����Ɉꕔ�f�ڂŒ���B�s��k�t1967�N3��������
7�����ɂ���
�ĘA�ځA���������B�g�����͍��{�Βj�Ɍ��y���Ă��Ȃ��̂ŁA�u���s�́v����̓I�ɂǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��킩��Ȃ��B�����A�g���́s��k�t1968�N10������
�����q���ār�i�F�E8�j�\���Ă���A1973�N6���ɂ͖����Ɋ��̉i�c�k�ߑS��W�s��Łt�ɐ��z�q�q�ΘŁr�Ɓq�������_���r�r�i�P�s�{�����^�j����
�Ă��邩��A���Ắs��k�t�ҏW�ҁE�������ǂ���Ɂs������Ƃ̐l�X�t�𐄏��������Ƃ͑傢�ɂ��肤��i�����őz�N����̂́A1967�N�A�g�����s���
�C���̎��I����
1927�`1937�t���e���{�Ɋ�����̕��͂ł���j�B�����s������Ƃ̐l�X�t�̑��݂�m�����̂́A�������s�܂����˂��ɂ��镶�w�̂��߂Ɂt�i�}����
�[�A1986�N6��25���j�ɂ���Ă������B��������͂��������Ă���B
�u�k�c�c�l����͈��܌ܔN�̐^�~�ɁA�F�l�̎莆�ŏЉ��āA�l�l�̒j�̎q�̉ƒ닳�t�ɂȂ�ׂ��A��҂ł���킽�����A���̒�������Ȃ���r�����
�̖�����Ƃ�K�˂�Ƃ��납��͂��܁v��A�u�`���̂Ƃ���ōC���炯�̃{�����b���̂悤�ɐg�̂Ɋ��������O���炢�̒j�̎q�Ɂu�킽���v�������Ȃ�w��
���݂����Ƃ���Ƃ��A�l�l�Z�킪�O��I�Ɍ��������߂邭����A���ꂩ�牺�j�オ��̎�l�����Ȃ̞X�юq�̏]�Z�ŁA�O���ɂ���\�������Ɏ莆���������
�����������Ō����A�L���X�g�J�������Ƃɂ���ĉi���̍��������G�w�G�W�����X�i������{���̑n��j�̑}�b�A�����čŌ�̎q�������l�l�ɂ�
�鉼�ʌ��̏�ʂȂǂ́A���܂ł��N��Ɋo���Ă���v�i�����A��l��y�[�W�j�B�����̖{������A���{�̕��̂ɓ����I�ȉӏ����������B
�@�킽���́A���̃J�[�e���̉����猻��ꂽ�A�A�C�ȈÂ����̕ǂɂ�����ꂽ�G��ق��Č��l�߂��B
�@�Â��Ȃ��ɂ��d��������A���������Ƃ�����͂܂�ł��̏�[�Ђ�]�̊�����蔲���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���قǁA�Ȃ�Ƃ������ʑN�₩�ȁA��M���Y�� �����܂łɌ������������A�^�����Ƃ����Ă����B�������A��l�̘b�ɂ�鑾�z�̔M�̂悤�ȁA���C���Ȍ���͉����ɂ��������Ȃ������B�����A�Ȃ�ƂȂ����� �G����g�̖т��悾���̂��o�����̂́A�Ԏq�̂悤�Ɋ��X���������Ƃ��A�L�������Ȋz�ɂ����^���ȁA����ł��Č��̂悤�ɏ_�炩�Ȕ��̉����A�����ɂ��� �悤���͋C���A���ɓ�������Ă����A���̗m��Ƃ����q���ɂ������肾�������Ƃł���B�����āA���ꂪ�A�t�ɁA�킽�����z�����ނ悤�ɁA����A����ɖ����� ��Ă������f�ɂǂ��ɂ��R����p���Ȃ������B�i�{���A����y�[�W�j
��Ɉ������q���Ƃ����r�قǂł͂Ȃ����A���߂̃Z���e���X��A�˂��S�������M�v�́A�g�����̎U���Ƒɂɂ���B�t�����E�I�u���C�G���� �s��O�̌x ���t�i�}�����[�A1973�j���������������A�g���̍D�ޏ����͂����Ղ��ς�������킢�̂��̂������A�s������Ƃ̐l�X�t�����̗�ɘR��Ȃ��B���͉��h���� ����j���������Ƃ��̂悤�ȒE�͊��ƂƂ��ɁA�{����ǂ݂������̂������B
�k2014�N9��30���NjL�l
����ǐl�����q�����͏���������Ȃ�r�i�s�S�����ǁ@�~��t����ǂށi26�j�t�j
�ō��{�Βj�ɐG��Ă���B1956�N�A�~�肪�s�����V���t�ɘA�ڂ��������s�ނ����t�i�p�쏑�X�A1957�j�̓o��l���E�w���w���Y�́s������Ƃ̐l�X�t
�̒��҂����f�����Ƃ����B���쎁�ɂ��A�w���́u�������𖼏���ē���c��̑\�����ق̂߂����N�Ƃ��ēo�ꂷ��v�B�܂��A�ٕ��ɐG��āu�w�l�k�}�}�l
�Ƃ̐l�X�x���ڂ����Љ���E�F�u�y�[�W���������B���e������A�\���Ƀ}�[�u������p���A�Z�ɐ��߂�ꂽ�v��w�Ɍp�����n���Ȗ{�ł���B���Ő畔�B�Â�
�����{�͊��s�҂̖�������Ȃ�قǂȁA�Ǝv�����B�����ċ����[���̂́A���̏o�łɎ��l�̋g�������s�͂����Ƃ����������L����Ă���B�g�����Ƃr�E�m�k�}
�}�l�Ƃǂ̂悤�Ȍ𗬂��������̂��낤�B�Ƃ������r�E�m�͂��̌�����܂����A�����������Ċ������A���h�Ȗ{�܂ŏo���Ă����Ƃ����̂ɂ͋������B�w�l�Ƃ̐l
�X�x����ɓ���ēǂ�ł݂����Ǝv���v�Ƃ������Ă���B�s�ނ����t�͐V���ДŔ~��t���S�W��܊��i1973�j�Ɏ��^����Ă���i8�|2�i�g��310�y�[
�W�̒��сj�B�`����`�������������A���{�Βj�́s������Ƃ̐l�X�t�Ƃ͎��Ă������Ȃ��M�v�Łu����������Ȃ�v�l����`���Ă���B
��������30�N�O�A�g�����͎��W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�ő�7�����܂���܂����B���̂Ƃ��́q���A�r���ȉ��Ɉ����i�P�s�{�����^�j�B
�@��Ƃ̒����^��Y���Ƃ́A�ʎ���������x�ł��邪�A���̑I�l�ψ��݂͂�ȁA�e�����F�l�ł���A�܂����䂽���Ȏ��l�ł���B���̂悤�Ȑl�����ɁA�s�T�t�����E�݁t���F�߂�ꂽ���Ƃ��A���ɂ͂Ȃɂ������ꂵ���B
�@��N�O�̔ѓ��k��N�́s�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́t�̎����̓��A�F�l�̈�l�Ƃ��Ď��͈��A��������ꂽ�B���̎��A�����ꎄ�����̏܂��������̂��ƁA��k�߂����Č��������̂ł���B���ꂪ�����̂��ƂɂȂ����̂��A�s�v�c�Ȉ������Ǝv�����B
�@�q�������܁r���̎�҂́A��������O�r�̂Ђ炯���Ⴂ���l�����ł��������A���̂悤�ȔN�z�̎҂�������̂͏��߂Ăł���B����ł��̏܂̑Ώۂ̕����Ђ낪�����̂́A�悢���Ƃ��Ǝv���B
�@�����̂Ƃ���A���̎l�N�ԁA���������Â��Ă����̂ŁA���e�������C���ł���B�i�s���㎍�蒟�t1977�N2�����q�掵�����ܔ��\�r�A����y�[�W�j
���̖����ɋL����Ă���u�\��\�l���v�Ƃ������t�́A1976�N�̃N���X�}�X�C���Ƃ������ƂɂȂ�i���Ȃ݂ɂ��̂Ƃ��̑I�l�ψ��́A�����^��Y��M���ɓc������A�R�{���Y�A�剪�M�A����N�v�j�B���N1��28���A�ԍ�v�����X�z�e���ōs�Ȃ�ꂽ�������ܑ��掮�̗l�q���A�g���́q����̖�r�i�s�����V���k�[���l�t1977�N2��8���j�ɏ����Ă���B���ł̈��A�ɂ��Ă̒i�������ƁA
�u���͈��A�̂Ȃ��ŁA�ЂƂ��������Ė�����B����͎�����̍��蕨�ɂ���c������̑I�]�ɂ��Ă��B���̖`���ɁA
�@�g�����́A�ڂ����،h���鎍�l�ł���B�،h�Ƃ��������A�ؕ|�ɋ߂��B�����m�푈�̂͂��܂�O����A�ނ͒鍑���R�̋S�R���ŁA�n�̌P��ɂ����Ă̓x�e�����������Ƃ����c�c
�@ �����ǂ�ŁA���R�Ƃ����B�ވꗬ�̃��[���A�̂���Ȃ̂����m��Ȃ����A���͂��̍��A�ꓙ���ł������B�S�R���Ƃ����C���[�W�͉f��q�n����i���Ɂr�̃A�[�l�X�g�E�{�[�O�i�C���ł��낤�B���͏_��ȏ��W���ł���A�d���n�Ƃ͒S�����A�m�n�����܂������Ȃ������ł������B���傹�̂悤�ȕ����ɂ́A�������ւ̓]���ɂ��]���̉^�����҂��Ă����B���͍ϏB���Ŕs���m�����̂��B���ɂ����|�c�_���ޒ��ł���\�\���̂悤�Ȃ悯���Ȃ��Ƃ����̂œ��R���̈��A�͂��܂��Ȃ������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l�O�y�[�W�j�B
�����ł��܂������Ȃ��������A���킴�킴���͂ɂ��Ďc���Ƃ́A�����Ȃ�S���ł��낤���B�g���͓c�������Ƃ������܂��郆�[���A�����邪�i�q�c������E�f�́r������ꂽ���j�A����͒P�Ȃ郆�[���A�ł͂Ȃ��B�c���͑I�]�q�ؕ|�����������l�r�Łu���ƃG���X�̓��Ȃ�W���A�ނقǓ����I[�A�A�A]�ɋߑ���{��őn���������l���A�ڂ��͂ق��ɒm��Ȃ��v�i�O�o���A����y�[�W�j�ƌ��_�Â��Ă��āA�g�����u���R�Ƃ����v�ӏ��͑O�U��ɉ߂��Ȃ��B���p�����q����̖�r�㔼�̕K�v�ȏ�Ƃ��v���錪���́A�g���̑���{�鍑���R�ւ̉ߏ�Ȕ����ł͂Ȃ��낤���B�Ƃ����Ă��A�ނ��R���ł̊K�����ꓙ�����A�ޒ����A�R�����A���m�����������Ƃ����̂Ƃ͈Ⴄ�B�g�������̔w�i�ɑ����m�푈������_���i���O�Ɂj�咣�����̂��A���掮�̃X�s�[�`�ł���A�����^�����q����̖�r�������B�g���́s�T�t�����E�݁t���e�[�}�I�ɓǂ܂�邱�Ƃ�v�������̂��B
�q����̖�r��7�N��ɔ��\�́q�u��ܑO��v�̑z���o�r�i�s���t2���A1984�j�ɂ��q�g�����̃��C�A�E�g�i3�j�r�ŐG�ꂽ�B�����ɂ����鎮�ł̈��A�́A�������Ɗx���a�c�F�b�̘b��ɏI�n���Ă���A���\�}�́i�s���\�\���������w�U������t�j�ւ̔z�����M����B�q����̖�r�ɏ����ꂽ���A�́A�푈�̏��Ղ��g�����琶�U�����邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ���Ă���悤�Ɏv����B
�g ������1967�N10��1���A�v���Ђ���s�g�������W�t�����s�����B�������W�s�Â��ȉƁt�܂ł����߂��A�����ɂ�����S���W�ł���B�g���͒P�s���W�Ɋւ� �Ă͂����ΐ����̋L�^�������Ƃǂ߂Ă��邪�A�{���ւ̌��y�͂��́q���Ƃ����r�ȊO�A�����Ȃ��B�����K���Ȃ��ƂɁA�i�c�k�߂Ɉ��Ă����ȂɁs�g������ �W�t�ɐG�ꂽ�ӏ�������̂ŁA�����ǂ��Ă݂悤�B�ŏ���1967�N3��1���̂͂����ł���B�Ȃ��A�����̎��͉̂\�Ȃ����茴���̍Č���S�������B
�t�A�O������ɂȂ�܂����B�k�ߗl�ɂ͂��������邵�ł����B�����̕��ׂт������ꂩ��͂Ȃ���ł��傤�B�ߓ��̈�� �̉�ł́A�F �F�Ƃ��A�ѓ��k��A�� �������A�x�������q�i�͂��߂Ă̏o��j�Ɖ�A�����ɂ͒��������̂�����[�ł����B�S���W���Z���ƂȂ�A�l���ɂ͊��s�����Ǝv���܂��B���̂��݂ɑ҂� �Ă��ĉ������B��Ђ̎d�����A�L�������A�ҏW���Ɉڂ�܂����A�L�Ӌ`�Ȃ鏑�����o���čs�������Ǝv���Ă��܂��B ���悤�Ȃ�@�@�@�@���B
�s�g�������W�t���u�l���ɂ͊��s�����Ǝv���܂��v�Ƃ���A�{���Z����A�ӂ���������Ώo�łł���ƍl����̂͂������R�ł���B���� ���A���ꂪ���� �������́u�ӂ��̑����v�ł���Ȃ�A�����B���͑O�M��1�T�Ԍ�A3��8���̕����ł���B
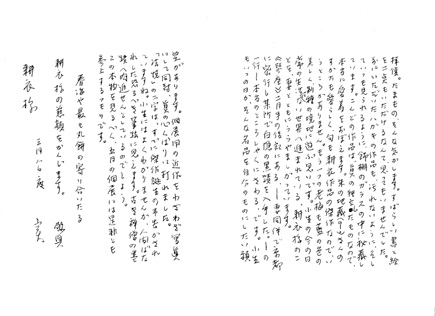
�i�c�k�߈��g�������ȁi1967�N3��8���j
�P�H���w�فi�i�c�k�ߕ��Ɂj����
�q���B���܂��́A����ȋC�����܂��B���炵�����ƊG���_������������Ȃ�āA�v���Ă����܂���ł����B�O�ɂ��� �������n�K�L �̍�i���A����Ȃ��悤 �ɁA�����Ă���������悤�ɁA���I�̃K���X�̒��ɔ��U���Ă��܂��B����ǂ̍�i�́A���̓Ɨ��������̂Ȃ̂ŁA�{���Ɉ��������ڂ��܂��B��̒n�U�i�H�j ����̂����������炵���A����k�ߍ�i�̌���Ȃ̂ŁA�����Ƃ��낪����܂���B������̘V�~�����̐F�̔������A�ʎ�̋��n�ɗV�Ԏv���ł��B�����̍��̓� ��̐����ɂȂ����E�i�܂�Ă���A�k�ߗl�̂��Ƃ��A�ȂƂƂ��ɂ����܂������Ă��܂��B
�s�Ս��t���̌�L�ɂ���A�\�\�ȓ����ŋ��s�ɖ��s���^���Ŕ��B�̖n�ւ���肵���B�\�\�̈�s�\�\�{���̂Ƃ��낵�Ⴍ�ɂ����A�ł��B���������̓� ���A����Ȗ��i�������̂��̂ɂ�������]������܂��B�W�p�̋ߍ���킴�킴�����ɂ��ē����A���̐S����ɑł�܂����B
�u�@�x�v�̓́A���łɌ���a���̗\��������Ă��܂��ˁB�����ɂ͂悭�킩��܂��A�l�ԂȂꂵ������ׂ��M�ՂɎv���܂��B�Â��T�m�̖n�ւ֓����� ��Ƃ��Ă���̂ł��傤�B
���̖{��������ׂ��A�܌��̌W�ɂ͐���Ƃ��Q�シ�����ł��B
�@�@�t�C��ł��݂ۖ̊�荇������
�k�ߗl�̎�������܂��B�@�@�@�@�h��
�O��������@�@�@�@��
�k�ߗl
�k �߂��珑�ƊG���_����ꂽ�̂́A�L������ҏW�ւ̈ٓ��j���A�S���W���s�̗\�j�A���邢�͂��̗��������˂Ă̂��Ƃ��낤���B�k�߂┒�B�̏��ւ̖v������� �Ē��ڂ��ׂ��{��̂��ƁA4��8���t�̏��ȁi�s�Ս��t207���ɔ������f�ڂ���Ă���j�A���̔N�Ǝv����5��30���t�̕����A6��28������̂͂������� �݂��邪�A��������s�g�������W�t�ɂ͐G��Ă��Ȃ����߁A�i�s��Ԃ��M�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����8��2������̂͂����ł���B
�����̓��X�A���������邵�ł����B���J�̐܁A�����ɂł����������\�グ��ׂ��ł������A�������̂��ƂƐM���A���炢 �����܂����B �u�k�ߋ�W�v���̂����ǂ� �ł���܂��B���āA�u�Ս��v�������̌W���W�̋L���ƂĂ��ʔ����A���Ƃɂ킪�u�����}�v�ɂӂꂽ���͂������A�����ɂȂ�܂��B�S���W�ǂ���甪���ɂ͏o�� ����邱�ƂƎv���܂��B���܂��炭���҂����B��
�u�k �ߋ�W�v�́A6��28���ɍk�߂��瑡��ꂽ���I��W�s�i�c�k�ߋ�W�k���o���ƃV���[�Y�P�l�t�i�u�C���v���o��̉�A1967�N3��20���j�̂��ƁB 8�����߂̎��_�Łu�����ɂ͏o�ł���邱�ƂƎv���܂��v�Ƃ���A�s�g�������W�t���v�f�ǂ���i�s���Ȃ��������Ƃ�����������B�Ō�͊��s���10��23�� ����̂͂��������A���̂܂��ɍk�߂́q�g������̎��r�i�s�����C�J�t1973�N9�����j��������B�u�g�����璸�����u�g�������W�v�i�v���Ёj�̒W���F �̔��ɂ́A�u�����鉨�^���̂��Ȃт��t�v�̓�s���A�y���Ŋ��|����A1967�C10�C14�Ɠ����܂ŁA���L����Ă���B��������ƁA���̈������A���� �ė��V�Ȟ����ŁA�f���Ɋm�Ə�����Ă���v�i�����A��y�[�W�j�B
�H���B�����̎��W�A��낱��ł��������Ė{���ɂ��ꂵ���v���܂��B��O���琔���ē�\�N�A�Ƃɂ��������Ȃ���A�悭 ����Ă����� �v���܂��B�k�߂���̍�� �N���ɔ�ׂ�킯�ɂ́A�����܂��B�����㋞�����Ƃ̂��ƁA���̏�A�M�d�ȁu���Áv������������Ƃ͌��Ăł��B�ĉ�̓��������炽�̂��݂ɂ��Ă��� ���B�����I�̍k�ߕS��́A������˂ƐS�ɂ��߂Ă��܂����A�����������Ԃ��������B���A�厚�����|���ꂽ�Ƃ̂��ƁA���������̂ł��ˁB�����A�������B�� ����A������t�����ĉ������B�@�@�@�@��
�u�� �O���琔���ē�\�N�v�́u��\�ܔN�v�̏�������܂肩�A�����Ȃ���ΌR���ɂ������Ԃ����������̂��B�u���Áv�͍k�߂̑���W�s���Át�i�{���w�ЁA 1934�N11��11���j�̂��ƁB���̋H������Ƃ����āA�u�����I�̍k�ߕS��́A������˂ƐS�ɂ��߂Ă��܂��v�ƌ��ӂ��V���ɂ��Ă���̂��ڂ� �����B�u�k�ߕS��v���g�����ҁs�k�ߕS��t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�N6��21���j�Ƃ��Č�������܂łɁA���̌�\�N�߂���v����B�o�łƂ́A�i������ �ӎu�̕ʖ��ł��������B
�@ �g�����͍ŏ��Ɍ�����������w�����G�߁x�ȑO�ɁA���W�w����x����e�{�Ƃ��Ĉ₵�Ă���B���́w����x�ɂ��āA�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�u���`�̐��E����v�ʼn̏W�ł��邩�̂��Ƃ��Ɍ��y�������x�ŁA�ڍׂȓ��e�𖾂炩�ɂ��Ȃ��������A�f��\��N���o����Z�Z��N�Ɂw���W�@����x�Ƃ��ċg���z�q�v�l�̎�ŏ��������o�ł��ꂽ�B���Ɉ����͎̂����E�F�u�T�C�g�w�g�����̎��̐��E�x�̋g���������ɏ������w����x���ł���B
�@���W�w����x�́A���W�w�����G�߁x�i����ɁA1940�j�ȑO�̋g�����̍ŏ����̘a�́i�Z�̂Ɛ����́j�Ɣo������߂Ă��邪�A���т͎��ڂ���Ă��Ȃ��B�g���z�q�͂��̊Ԃ̎�����w����x�́u�o���v�Ŏ��̂悤�ɋL���B�u�k�w����x�́l���ɂȂ������̂́A�Ⴂ�g�������A�a�T�Łk���l�̌��e�p���Ƀy���Ő������������̂ŁA�Ԃ��N���X�̌��\���Ő��{���A�w�ɉ������Łu���W�@����@�g�����v�ƍ������������Ă���܂����B��i�ɕt���ꂽ���t����A���a�\�O�N����\�ܔN���߂ɂ����ď����ꂽ���̂Ǝv���܂��B�j����Ă�ꂽ�y�[�W����\���قǂ���܂������A�c����Ă��镔���ɂ͉��M�ŏC���̎��݂��Ȃ���Ă��āA�̐l���������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B���̏W�������肾�����悤�ŁA���߂̓��Œ��f����Ă��܂��v�i1�j�B
�@���M���W�w����x�������@�c�����́A��W�w�z���x�i����R�c�A2003�j�́u���v�ɂ��������Ă���B�u�w����x�́A�g���̕���悾������R��������̂a�T�����e�p���i12���~19�s�j�ɍ�i��O�O�Ƀy���������A�Ԃ��z�\���Ő��{�A�w�ɂ͉������Łu���W�@����@�g�����v�ƍ��̔�����������B�����̉������������Ă���A���̂��ƂɎ��M�̉̏W�e�u�`�W�v�Ƌ�W�e�u�z���v�������v�B�u���̊����̔j��ꂽ���y�[�W���ɂ͉����L����Ă����̂ł��낤���B�͂�����Ɓu���W�@����v�ƍ��Ă��邱�Ƃ��v���A�����ɂ͎���i��������Ă����ƍl���邱�Ƃ����R�ł���B�����Ĉ₳�ꂽ�Z�̂�o�傩�炻�̐���N�����l����A���炭���̎��Q�́A�ŏ��̎��W�w�����G�߁x�ɂȂ����ƌ��Ă悢�̂ł͂Ȃ����낤���v�i2�j�B
�@���������Ă��Ȃ��̂łȂ�Ƃ������Ȃ����A�ӂ��̏،����画�f���邩����A���M���W�w����x�ɂ́u����v�̕W��̂��ƂɁi��́u�����G�߁v���\������j���т̂��������A�u�`�W�v�̕W��̂��ƂɁi��́u蜾蠃��v���\������j�a�̂��A�u�z���v�̕W��̂��ƂɁi��N�̋�W�w�z���x���\������j�o�傪���^����Ă����Ǝv����B�����̎��̋�����߂��w���W�@����x�͂��̂܂܂̌`�ł͊��s���ꂸ�A���̂����߂ċg���ŏ��̒���ƂȂ����w���W�@�����G�߁x�͉i�����ƒ��҂���͏������W�ƌ��Ȃ��ꂸ�A�g���́w����x��ɏ����ꂽ�ł��낤���т��������߂��w���W�@�t�́x��������̏������W�Ƃ��Ă����B���Ȃ킿�A���̋�̎O�ʈ�̂����A�̂��ЂƂЂƂU�邢���Ƃ��Ă������Ō�Ɂu���v�ɂ��ǂ�����̂��A�g�����Ə����́w���W�x�Ƃ̊W�������̂ł���B
�@ �g�����ŏ��Ɏ����߂��W�������͒Z�̂��������A�Z�̂���߂Ĕo��ցA�o���p���Ď��ւƒi�K�I�ɐi��ł������킯�ł͂Ȃ��B�\������\�ɂ����Ă̓��L�̂��������ɂ͎���̔o���Z�̂�����߂��Ă���A����ւ̌��y���U�������B���̈��O��i���a�\�l�j�N�܌��O�\����ɂ́u���W���ɂ䂭�O�ɏo�������Ǝv���v�A�㌎�\����ɂ́u�̏W�w蜾蠃���x���o�������Ǝv���v�A�\�ꌎ�\����ɂ́u���ɂ͂��ށB������W�w�z���x��҂݂����Ǝv���v�i3�j�Ƃ���A������O�ɂ����g���́A���̏����₷���Ƃɑz����y���Ă���B�S��Z�������߂��u�`�W�v�����悤�B�����̈��́A�O�s�����̂������̂��ΐ��ӂ��ŁA�g���炵���͉M���ׂ����Ȃ��B�Ƃ���Łu�`�W�v�ɂ͂̂��̉̏W�w�����x�ɂقƂ�ǂȂ������i�W��ɋ߂��j���A�����Ƃ��Ă���B���Ɉ����͈̂�O�Z��߂́u�����v�ł���B
��ɂȂ肫��ʂȂ�݂�����
���|���ɒ������̂Ă���i4�j
�@ ����́u�`�W�v�ł͗�O�I�ȉ̕��ŁA���ɂ́w�����G�߁x�̎����\�����Ă���悤�Ɏv����B����܂ł̒Z�̂̌��łȕ��̂ɋT�������悤�Ɍ�����̂ł���B�����A�g�����ǂ̂悤�ɒZ�̂��玍�ֈڍs���Ă��������́A�u�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁv�i���܋�N���\�j�ɏڂ����B
�@���͏\�܍���\��܂ŁA�s�˂̉ԁt�̐��E�ɂ����B�k���p��͏ȗ��l�̊��\�ƕ��͋C���������B����ɂÂ��ās�_��W�t�́k���p�l��͏ȗ��l�̖쐫�Ɛ������Ƃɋ��Q�����B�₪�ās���̗��t�̂����́q�����Ջ�W�r�́k���p�O��͏ȗ��l�̂�����͒W�ȏ�q�̐��E�ɓ����Ă����̂ŁA���͂����Œ�����B���̋��߂���̂͊������������łȂ����낤���ƍl�����B�V�����h����~�����B�����Ȃ�A�R���N���[�g�̕ǂɗ⍓�ɂ��G�ꂽ�o���̉Ԃ̒ɂ܂������B���͑O�썲���Y��Ό����̐V�Z�̂��݂��āA���߂炢���Ȃ��^�����B�������r���[�ȋC�����Ă�߂��B���̍��A�֓������̎l�J�̃A�p�[�g�ŁA�s�J�\�̎������A���������B����́u�݂Â�v���Ȃɂ����낤�B�k�c�c�l�^�Z�̂�������A���m�̊��o�ƃC�}�[�W�����Ăѓ����ɐ�D�̎��^�������̂��B���ꂪ�������h�̎��ł��邱�Ƃ�����Ƃ킩�����B�Ȃ��Ȃ�A���͗B��l�̗F���Ȃ��A�܂������肳����ł��̂������Â��Ă����̂�����B�����Ă킪���̍�i��T�����B�s���삿�����W�t�A�k�����q���W�s���̃A���o���t�̓�������ꂩ��Ȍサ�炭�͈��ǂ̏��ƂȂ����B�i5�j
�@ �g�����̎��I�]�������ė]���Ƃ��낪�Ȃ��B�k�����H�̒Z�̂�I�̏W�w�Ԋ~�x�ň��ǂ����g���́A�\���҂Ƃ��ĐV�Z�̂ɋ������������̂́A���́u���v�͒Z���^���w�Ɏ��܂���̂ł͂Ȃ��Ȃ�������B���̂Ƃ��G�}�̂悤�ɋ@�\�����̂��s�J�\�̎��i����C�����u���������s�J�\�v�Ŗ�o�������́j�ł���A���̒����ȉ�Ƃ́u������S����˂̒��őłe�����̒ʂ�̂�����̂��U�܂̒��ŗ��̔����������v��u�g�����Ŗ��������������Ƃ��������j�Ŕނ̓d���̈ߏւ�D�ӓ����v�i6�j�Ȃǂ̎���ɐG��āA�Ɨ͂Ŗk�����q�ƍ��삿���������B�g���͖k���́w�~�����W�x�̂܂������V�����\���ɖ������A�w���̃A���o���x��T�����߂ēǂ�ł���B�g�����g�́u�k������͕킵�͂��߂��̂ł���v�Ə����Ă��邪�A���ɂ���������Ă݂悤�B
�@�@VIN�b�k�����q�H���A�����w�ɂ����ւāA�����Ɏq�ǂŌ����z�Ă��ƁA�₪�Ĕ]���������Ȃ�A�^��F�ɂȂ�A���ڂŌv��Ɣw���̕�����j��Ă��܂��B�i7�j
�@�@���������b�g����
���]�ԋ����I�肪�Փ˂���
�Ė����̓��[�̘L�֔S�t���ӂ��o����̐��q��������F�̏Ɏq�t�œd�����݂̂��ڂ���
�X�Βn�т���~���^�X�q�ւȂ��ꂱ��
�ꖇ�̕��ƖƉԎǂ����̋q���Ȃ�p�̉��ϕi�X�ɂ͂����i8�j
�@ ���̔��z�ɂ����ċg�����k������w���̂͊m���ɑ����A�w�~�����W�x�Ɓw���̃A���o���x�����^���b�̕�ɂƂ��čŏ����̋g�������̋N���܂̖�ڂ��ʂ��������Ƃ��^���Ȃ��B�����A�u���������v�̎��_�̐芷���A����������Ύ���Ԃ̒f��ɂ́A���̂���g�����e���V���o��̌ċz�ɋ߂����̂�����������B���тƘa�̂�����Ɏ��߂��w�����G�߁x�́A���u�t�v�u�āv�u�H�v�u�~�v��u�f�́v�Ȃǂ�������炩�Ȃ悤�ɁA�X�^�C���̌��{���ł���A�g���́u�킪�������W�s�t�́t�v�i��㎵���N���\�j�Ɂu���̈�сk�u�����G�߂Q�v�l�����Ă��A�c�t�E���d�ŁA���I�Ȕ������Ɍ����Ă���B���̂�����\�т̕��̂ɓ���Ȃ��A�܂��ɎG���ł���B�킸����N���Ƃ̍�i�ł͂��邪�A�s�t�́t�ɂ́A�ϐ��̔��Ƃ���Ȃ�̃X�^�C��������ƍl���Ă���̂ŁA���̏������W�́A�s�t�́t�Ƃ������ƂɂȂ�v�i9�j�Ɯ�������z�����L���Ă���B
�@ �g�������ɂ�����w���삿�����W�x�̉e���͂ǂ����낤���B���͂��́u�R���N���[�g�̕ǂɗ⍓�ɂ��G�ꂽ�o���̉Ԃ̒ɂ܂����v�ɁA���O�Ɉꊪ�̎��W���������ƂȂ�������聏G��������i�w�����G�߁x�́u�a���v�Ƃ�����тȂǁA���ΔN���̎��l�ւ̒Ǔ����ɂ����v����j�B�ِF��u�ʎт����b�v�ɂ́A�k���̎��u��w�L�����z�v�Ɠ����ɁA����̎��u��b�v�̃��~�j�b�T���X������B��������͊O���I�ȗގ��ɂ����Ȃ��B�⍓���ȊO�E�ɔۉ��Ȃ����ʂ�����ꂽ�҂ւ̋����ɂ́A�������T��������̎p���d�˂��킳��Ă��悤�B����̎��сu�O�t�ȁv�ɒ������A�����Ȃ����̂����悤�Ƃ���ӎu�́A�g���Ɂu�ڂ̋��x�v�Ƃł������ׂ����̂�A�������B����́w�����G�߁x��w�t�́x�ł͌��݉������A���F�Ŕn���g���ĉ߂������펞�����o�āA���\�N���{���Đ��������W�w�Õ��x�ʼnԊJ�����B����̎��̎��͋g���̎��u�ߋ��v��z�N�����邪�A����ȏ�Ɏ��W�w�Õ��x�Ɏn�܂�^�̋g����������肵�Ă���B�g�����܂��u���҂̖ځv����݉������Ƃ����悤�B
�@�@����陁b���삿�������l���������B�l�{�̎w�Ղ����āA
�\�\����Ɍ{�������Ȃ����B�����ł����z�͂Ԃ�Ă��B
���Â˂Ă�����̋�̊Ŏ�B
�������삯�r�ł䂭�̂��B
�ނ�͐������Ȃ�������S���̒��Ŏ�Ă��B
�h�J�̗��̂₤�ȊO�̐��E�ɐG��邽�߂Ɉ�C�̉�ƂȂđ��ɓ˂�������B
���̒�����颂�����������߂���̂���߂�Ȃ�Ύ���͊�ւ̏�Œ��т�����B
���͎��̊k��E���B�i10�j
�@ ����A�g�����e������̖k�����q�̎��ɂ����������̂͌�������Ȃ��B�k���̎�������̎��ƕ������̂����A���҂̎��_�̗L���ł���B�������W�w���̃A���o���x�͋g���́w�����G�߁x�Ɠ��l�A���܂��܂ȃX�^�C���ŏ[�������Ă���iPOESIE DE THEATRE�̈�сu�l�`�ƃs�X�g���ƕ��D�v���g���ӔN�́w��ʁx�̊K�i��̎��^�����Ă���̂ɂ��Ӗڂ�������j�B�w�t�́x�́w�~�����W�x�ɔ͂����ŁA���W�Ƃ��Ă̓���̂��u�����Ă���B���U�A���W�ɑ��ĕ����Â������̎p�������A�g�����k���̎����I�ȏ������W����w�ő�̂��̂��낤�B
���p����
�i1�j�@�g�������W�w����x�A�ʖؓ��A2002
�i2�j�@�g������W�w�z���x�A����R�c�A2003
�i3�j�@�g�����w���܂�͂����L�x�A����R�c�A1990
�i4�j�@�i1�j�ɓ���
�i5�j�@�g�����w�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�x�A�}�����[�A1988
�i6�j�@����C���u���������s�J�\�v�A�w�݂Â�x1937�N3���i�ʊ�385���j
�i7�j�@�k�����q�w�~�����W�x�A�{�����X�A1933
�i8�j�@�g�������W�w�����G�߁x�A����ɁA1940
�i9�j�@�i5�j�ɓ���
�i10�j�@�w���삿�����W�x�A���X�ЁA1936
�k�t�L�l
��f��2006�N�āA���ۍ��a�q����̕ҏW����p�����s[Five]
Factorial�t�iFactorial Press���j�ɔ��\�����g�����_�qMinoru Yoshioka's Early Poems, in Light of Katue Kitasono and Chika Sagawa�r�iYu Nakai�ESawako Nakayasu�����ɂ��p��j�̌����q�����g�������Ɩk�����q�E���삿���r�ł���B���q�̕K�v��A���W�s����t������s�g�����̎��̐��E�t��������Ă��邱�Ƃ��������������������B�����{�T�C�g�Ɏ��M����ꍇ�A�g�����̕��͂Ƃ̌��˂����Łs�@�t��q�@�r���g�p���Ă��邪�A�{�e�ł͈�ʓI�ȁw�@�x�Ɓu�@�v���g���Ă���A�i���`���̈ꎚ�������܂߂āA���e�̂܂܂Ƃ����B�����̌f�ڂɂ������ẮA���M�̋@���^����ꂽ���ۂ���̗ȉ����B�L���Đ[�����ӂ���B
�k2010�N11��30���NjL�l
���V��u�s�k�����q�̎��t�i�v���ЁA2010�N8��1���j�Ɏ��̋L�q������B�u�k�����q�͎��W�Ƀe�[�}�̊��������Ƃ߂�X��������A��W�ȍ~�͐ݒ肵���e�[�}�̂��Ƃɏ����ꂽ�����������W�ɂ܂Ƃ߂邱�ƂŖړI�̏C���Ƃ����B�w���̃A���o���x�́A�O�N���Ƃ������Ԃ̌��肪����Ƃ͂��������̃X�^�C�����l�߂��A���\���W�[�ŁA�܂��p���k�����t���X�́q����̌|�p�Ɣ�]�p���r�l�Ƃ���������t�H�[�}�b�g��{�����[�����ŏ����猈�߂��Ă������ƂȂǂ��u�S�ʓI�v�ł͂Ȃ��Ƃ����s���ɂȂ���A�܂����̕s���͌�N�̎��Ҏ����ւ̍S�D�ɒ������Ă������悤�ɂ��݂���v�i�q�u�}�`���v��ǂށr�A�����A�Z�O�y�[�W�j�B�g���́s�����G�߁t�́A�S�ʂɖ�����p���Ȃǂ̌���v���͂��������̂́u���Ҏ����v�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��A���܂��܂ȃX�^�C���̓����̌����͂ق��ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�s���̃A���o���t�́u�����Ȃ��Ƃ��l�̕��w�̑S�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����k����38�N��̏������W��ڂɑ���u�S�ʓI�ɔ��f���Ă��Ȃ��Ƃ����s���́A���@�̕s���ł͂Ȃ��O�a�̕s���ł͂Ȃ��������v�i���O�j�A�Ƃ������V���̎w�E�͉s���B�g���������̏������W�Ɂu�O�a�̕s���v���o�������ʁA�s�t�́t�����܂ꂽ�悤�Ɏv����B
1977�N5���A�g�����͎��сq�����`�r�i�H�E10�j���s�C�t�ɁA���z�q�u�z���͎͂��@�z������v�r���s���㎍�蒟�t�́q���̖��E���̈��r���ɔ��\�����B���҂ɓo�ꂷ��̂��A�T�~���G���E�x�P�b�g�́u�z���͎͂��@�z������v�i�����N���j�Ƃ����͋�ł���B���z�̖`���͂������B
�@���鑁�t�̒��A���͏��p�������āA�߂��̍����N�炳��̉Ƃ�K�₵���B�k�c�c�l�b��͓��R���C�X�E�L�������ƃT�~���G���E�x�P�b�g�̂��ƂɂȂ����B���́q�A���X���сr�𐔕я����Ă���̂ŁA���C�X�E�L�������͐g�߂ȑ��݂ł��������A�T�~���G���E�x�P�b�g�́A��ȕ\���ɂȂ邪�u�߂��ĉ������݁v�̍�Ƃł���B�����Ƃ��S�������Ă��āA�����̃x�P�b�g�̏������茳�ɒu���Ȃ���A���܂��ɒʓǂ��Ă��Ȃ��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�j
�u�����̃x�P�b�g�̏����v�́A�����M���s�����C�t�i�����ЁA1969�j�A�����N���s�}���E���͎��ʁt�i���j�A�������Y��s���Â����ʂ��́t�i�����ЁA1970�j�A��������s�}�[�t�B�t�i�����ЁA1971�j�A�����N���s���b�g�t�i���j�A�����M���s�����^�����V�G�ƃJ�~�G�t�i���j�A��������s�R�葹�̞��������t�i�����ЁA1972�j�A�ЎR���E�����M��E�����N���s�Z�ҏW�t�i���j�A�ЎR����s���̎���t�i���j�̂ǂꂩ���낤���B�܂��u���p�v���d������݂Ȃ�A����͋g���������ҏW���߂Ă����s�����܁t�̌��e�Ƃ肾������������Ȃ��B������95���i1977�N3���j�ɁA�����N��́q�A���X�ƃh���E�L�z�[�e�r�i�u���\���邢�͖��̓���q�H[�`���C�j�[�Y�E�{�c�N�X]�I�\�����߂��锭�z�v�Ƃ����h���I�Ȉ�߂�������j���f�ڂ���Ă��邩�炾�B�q�u�z���͎͂��@�z������v�r�̌㔼��������B
�@�����N��́s�r�E�x�P�b�g�t���ŗǂ̓��发���Ƃ̐��]�ł���B���͊X�ł����T������������Ȃ�����ƁA�N�炳��ɖ��S�����B�A�鎞�ӂƒ�߂�ƍ�̂͂邩�ޕ��̐�ɁA�����x�m���P���Ă����B�^�u�z���͎͂��@�z������v�^�s�r�E�x�P�b�g�t��ǂ�ł��āA���̌��t���������B�܂��ƕ|�����ꌾ�ł���Ǝv���B�k�c�c�l�����N�炪�A�u���낵����Ɓv�Ƃ����x�P�b�g�̏�����A���͂��ꂩ��ǂ�ł������Ǝv���Ă���B�i���O�A���l�y�[�W�j
�s�r�E�x�P�b�g�t�i�w�����̕\�L�j�͐����ɂ́s�T�~���G���E�x�P�b�g�k�����̃C�M���X�E�A�����J���w3�l�t�i�����Џo�ŁA1971�N2��25���j�ŁA�u�z���͎͂��@�z������v�̏͋�͓�����Z�y�[�W�ƈ�l�l�y�[�W�Ɍ�����B��������҂ŗ�L���Ă���u�u�z���͎͂��@�z������v�eImagination morte imaginez�f�A�u�r�[���v�eBing�f�A�u�~���̒��Łv�eDans le cylindre�f�v�̂����A�u�~���̒��Łv�͋g���̎��сq�~���̓����r�i�H�E28�j�Ƃ��W�����肻�������A�l��y�[�W�ɏo�Ă���u�������̍s��[�}�g���c�N�X]�k���邢�͕��[�}�g���c�N�X]�l�v�́s���[���h���b�v�t�����́q�Y��i�ނ��сj�r�i�K�E1�j�̈ꎍ���p�ӂ�����������Ȃ��B�g�������̌�A�u�x�P�b�g�̏���v��ǂ��͐��z�ɏ�����Ȃ��������A�����N��̒����s�r�E�x�P�b�g�t���g�������Ɛ[���ւ��������Ƃ́A�܂�����Ȃ��B
�q���̖��O�r������������ɂ́A�g�������ɓo�ꂷ�钹�̖��O�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B���������S���W���Ђ��Ƃ��̂�����A�u���v��u�����v�Ƃ���������̎�łȂ����̂��܂߂邱�Ƃɂ���B
����A�Ώۂɂ�����i���͓��i���ѓ��A�a�̈�j������A��L�̈��l���͎l�܃p�[�Z���g�߂��B����̎��тł͓��ȏ�o�ꂷ��ꍇ������o�ꂷ��ꍇ�������Ɉ������̂ŁA�ǂ̎�ނ�����������ꂽ���P���Ɍ����Ȃ����A�O�шȏ�ɓo�ꂷ���ނ������Ă����i�\�L�͂������`���̂����j�B�u��A������A�C���A�F�A�A���A�J�i�����A���A���A���炷�A��A�E���A�i�����j�A���A�T���A��A�璹�A�c�O�~�A���A�߁A�A�i���j�A�{�A�����A���A�t�N���E�A�Č{�v�B
�ȏォ�猩���Ă���̂́A�i1�j�{�i13��j�A���i10��j�A��i5��j�Ȃǐg�߂Ȏ�ނ��������Ɓi2�j�E���A���A���ʒ��A�F�Ȃǂɓ��ʂȑz�������߂��Ă���炵�����Ɓi3�j�s�m���t�́u���炷�v�������A���Ȃɂ��\�L�́s�Â��ȉƁt�Ɏn�܂邱�Ɓi4�j�s��ʁt�ł͂قƂ�ǂ̎��сi�S19�ђ�17�сj�ɒ����o�ꂷ�邱�Ɓi5�j����̎��тɌÌ�ɂ�钹�̖��������邱�Ɓi6�j�q�g��i���Ɏ~��r�A�q����r�A�q������ܒf�����сr�Ƃ����������ɑ����̎�ނ̒�����������Ă��邱�ƁA�Ȃǂł���B
�g�����U���ł��ꂾ���M�S�ɏ������_���}�C���R�����тɓo�ꂵ�Ȃ��̂͋����[���B�\�\�u���ɂ͌l�I�Ȏ���͎������݂����Ȃ��̂ł��v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��l�܃y�[�W�j�B�q���̖��O�r�ł͋g�������̕W��Ƃ��āq�c�O�~�r�i�I�E21�j�A�q雞�k�j���g���l�r�i�J�E1�j�A�q�s���r�i�J�E6�j������������A�����Ɂq����r�i�J�E17�j�Ɓq�F�r�i�K�E18�j�������Ă������B���̖��O��W��ɂ����т�����g�������ɏW�����Ă��鎖���́A���̒����哰���ƊW������̂�������Ȃ����A�͂����肵�����Ƃ͂킩��Ȃ��B
�g�������g���Ă����蔲���p�N���A�t�@�C���ɁA���M�Łu�i�����j�v�ƃ������������A�G�������̂܂ܐ�Ƃ���2�t�i4�y�[�W�j�̋L���������Ă���B�蔲���͖`���̎��t�������Ă���A�W��E���M�Җ��͂킩��Ȃ��B�����Ƃ������̏����o���u������|�v�̈�߂Ɂu���̒�{�쒹�L�̍Z���v�]�]�Ƃ��邱�Ƃ���A�����哰�i1895-1984�j���ӔN�ɏ��������͂ƒm���B���|�̌o�܂������B
�@���|�̒��ŕ��ς�Ȃ��̂���������B����͊��q�̕���������Ƃ����l���擪�ɗ����đ����Ă�������A�}�`���A�̒T���c�̂��A�ߋ��\�ܔN�Ԃ̓��j���Ƃɍs�Ȃ����T���U��Ō��������ʎZ�S��\���ƂȂ����B���Ă͂�����O�ڕ����̐����`�̂ւ�ɁA�S���������ŏ������ׂĂق����Ƃ̂��ƁB�^�k�c�c�l����Ȋ��|���n�߂Ă̂��ƂȂ̂ŁA��Q�l�܂łɂ����ɋ�����B���݂̊w��g���Ă���E�F�g���A���̕��ޏ��ł��邪�A�Ȗ��͂����ɕ��ׂĂ����B�i�f�ڎ��s���A��l�`��܃y�[�W�j
�����Ĉ����̒��̖��O������ł���킯�����i���ɂ͂ӂ肪�Ȃ��Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ����̂������j�A�g�����苖�ɒu���Ă������������̂͂��̋������̒��̖��O�ɈႢ����܂��B�ȉ��ɁA�V�t�gJIS�̃e�L�X�g�Ƃ��ĕ\���ł��Ȃ������̓��j�R�[�h������}�����āA�Ǎ��Ōf�ڂ��Ă݂�i�V�t�gJIS�ɂ��鋌�����͎g�p�����j�B�Ȃ��u鸊�v�͌����ł�焊��Ɂu���v�A�܂��u���E�U�ɂ���Ắu�K鳸�璹�v�Ɓu�K鳸�v�ŕ\���ł��Ȃ����߂͌ː��Ɂu���v�������B���i�Q�^�j�́u���v�̕����}�Ɂu���v�ŁA�苖�̊��a���T��j�R�[�h�������T�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B�����Ō�̎O��u�g���^�����^�������v�ɂ́A�p�Ŋ����āu�Ăʂ������쐶���������́v�ƋL���Ă���B
����^��g���^鸊鷉�^�H��鸊鷉�^��鸊鷉�^�ԋ�鸊鷉�^��鸊鷉�^�吅�㒹�^�͉L�^�C�L�^�P�L�^�܈ʍ�^���܈ʁ^���^���^����^����^����^����^�Γ����i�^���j�^�y���^�����^�ъ��^�꒹���^�������^�{�A���^�����H���^�銛�^�����^�j�����^�_�q�H���^�C�H���^��H���^�L�^���p��^�^����^�W�^鵟�^鵊���i���H�j�^���^�����V�^�G�^�����{�^賁^�\�^���Z�^�s���i�y�Z�j�^���璹�^�K鳸�璹�^���璹�^�ڑ�璹�^��ڑ�璹�^�����^��V�^�v���^�c�v���^�����Z�^�c�N�^�_���Z�^�����c�N�^�P�G�Z�^�G�Z�^�_�Z�^���_�Z�^�����H�Z�^���H�Z�^�O���Z�^���Z�^�݊��Z�^�����^���Z�^���Z�^���Z�^����Z�^�����Z�^���Z�^���{�Z�^�唽�{�Z�^����Z�^�����Z�^�����Z�^�c�Z�^��n�Z�^�ԋݕh���Z�^�S�����^�w�����^��w�����^�h���^�����^���^�C�L�^�O�䉨�^�{�������h�^���h�^�����h�^賔��^�Δ��^�\��i���ߐS���j�^�s���^�����^�m�C�^�����ؓe�^��ؗt�ؓe�i鵂鶹�j�^�Ηt�ؓe�^���^����i��꒹�j�^�P�J���^�R�Ő��^���Ő��^�Ő��^�Ŗ@�m�^�Α�ؒ��^�ԑ�ؒ��^��ԑ�ؒ��^����ؒ��^�_���^�������^���^���ԉ��^�≍�^���T���^���T���^�w���T���^�֒ǁ^�c鷚�^�R����^�J�^�E�^���E�^�͉G�^�[�]�^��^���^���ڗ��i��j�^�ڗ��O�^���O�i���O�j�^���J���^�����^���I�^���I�^�ԕ��^�����^�I�i���n�j�^�M�J�^��^���ѐ^�ڍ�峋�^�ڈ�峋�^���i峋�^�e�Ձ^����i�ቺ�j�^���O�^��ڗ��^�L�O�^�ڈ��O�^���L�O�^�O�����^�����^�����^�����^�R���^�l�\���^�\���^�J�᎙�^�j���^����с^�j�ԁ^���j�ԁ^�����^���D�i�䐝�j�^���D�^���с^�͌��S�^�^�S�i�������j�^���^�^�^�K鳸�^���^�������^���^�������^�����^�����i�|�q�j�^��a�F�i�����j�^�{����i���Ƃ��炷�j�^�{����i�Ȃ݂��炷�j
�@���l��
���i�h�o�g�j�^�g���^�����^������
�������Z�Z��̂����A�g���������ɏ��������͉���ނ��邾�낤���i�W��ł́q�c�O�~�r�Ɓq�s���r���z�������ԁj�B�g���́s��ʁt�i����R�c�A1983�j�̎��т������Ă���1980�N��̏��߁A�����̒��̖��O��O�ɂ��āA�q雞�k�j���g���l�r�ɑ����V���Ȏ��т��\�z���Ă����̂�������Ȃ��B

�g�����̎��M�Łu�i�����j�v�ƃ����������ꂽ�G���̐蔲���i�g���Ƒ��̃��m�N���R�s�[�j
�g�����͏\�ォ��Z�̂�ǂ݁A�܂��r�ނ��ƂŎ��I�o���𐋂����B�����ł͋g���ƒZ�̂̊W���T�ς��悤�B���߂ɁA�g�������M�q�N���r �i�s�g�����k�� ��̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�j����A�Z�̊֘A�̎��������o����B
�@1934�i���a9�j�N�@15�^���H�́w�˂̉ԁx��͕킵���Z�̂����͂��߂�B
�A1940�i���a15�j�N�@21�^�H�A���̏W�w�����G�߁x���ƔŕS�����s�B
�B1941�i���a16�j�N�@22�^���F�֏o���B��g���ɂ́w���t�W�x�A�k�c�c�l�������ɂ̔��H�w�Ԋ~�x�k�c�c�l�����܂Ɏ��ߌg����B
�C1946�i���a21�j�N�@27�^�w����壁x�ꊪ�����m��Ȃ������A�֓��g�̂��̑��̉̏W�w�Ԍ��x�w���炽�܁x�ɐG��A��������B
�D1959�i���a34�j�N�@40�^�܌�����A�a�c�z�q�ƌ����B�L�O�ɁA���̏W�w�����x������A��I���̏o�Ȏ҂֔z��B
�E1973�i���a48�j�N�@54�^�t���A�w�����x�����ł�[��p����芧�s�B
�@�̂��ƁA1938�N����40�N�̏��߂ɂ����ď����ꂽ�a�̂́A�q�`�W�r�̑�̂��ƁA�e�{�̎��W�s����t�i�o�ł�2002�N�A�ʖؓ��j
�ɂ܂Ƃ߂��
���B�̐��͒Z��200��E������9��̍��킹��209��B
�A�́s�����G�߁t�Ɏ��^���ꂽ�a�̂̑�́q蜾蠃�k�X�K���l��r�B�Z��44��i�����u���E�����Â��ɂ˂ނ鍻�̏�^�o�i�i�̔�̊�������ߌ�v�u�����̒���
�Ɏq�ɏH�̉�́^�������݂����J�ӂ肻�߂ȁv�u�J�̖���݂���ʉƂɂƂ��䂭�^���̂����Ƃ̂Ȃ��������͂��v�u��̊X��f���̏������Ƃ߂䂭�^������
���M�G���Ȃ��������āv�u���Â̒j��╂Ŕ��肠�邭�^�������ɓ��̕�ꂻ�߂ʁv��5��́q�`�W�r�Ɍf�ڂ���Ă��炸�A�ߍ�Ǝv����j����ѐ�����2
�琬��B
�B�Ɋւ��ẮA�g���̐��z�q�s�Ԋ~�t��r�ɏڂ����B
�C�̍֓��g�ɂ́A�g���͖k�����H�قnj��y���Ă��Ȃ��B
�D�́s�����t�́s�����G�߁t�́q���́r�Ɓq蜾蠃�k�X�K���l��r�S�т���я������낵�́q���Ƃ����r�����߂�B2�`4�s�ŕ\�L����Ă����q蜾蠃�k�X�K���l
��r�̒Z�̂́A���^�ɍۂ��Ă��ׂ�1�s�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B����̈ٓ����ȉ��Ɍf����B
�꒹�̗[�����̐��قƂ�k���s���Ǎ��l�b�̉Ԃ����킽�k��䂭���錩��l
�����̒��̏Ɏq�ɏH�̉�́k���s���Ǎ��l�������݂����J�ӂ肻�߁k�ȁ��ʁl
�u�J�̖���݂���ʉƂɂƂ��䂭�k���s���Ǎ��l���̂����Ƃ̂Ȃ��������͂��v�Ɏ����u�o�Ɂv��lj�
��
��A�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j���ڂ́s�����t�܂ŁA���Ȃ⊿���̕\�L��̒����������āA��{�I�Ɏ���̕ύX�͂Ȃ��i��������o1968�N��
��1973�N�łł́u���L�̂����Ђ��悬�鏪�̒��Ɛl�͎���k���l�͂߂��Ă䂭�v�Ɓu���v�������Ă���j�B���̏W�̔w�i�ɂ��ẮA���z�q�~�ς��肤��
�\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�ɏڂ����B
�E�́u�V���Łv�i1973�N8��28�����j�ȑO�ɁA�s�����t�́s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�Ɂq���Ƃ����r���܂߂đS�эĘ^����
����B
�@�@�@�@�@��
�����ŁA�g�����Z�̂̏o���Ƃ������ׂ��q�`�W�r�����̈������Ă݂悤�B
�@�@�~���
�����
��C��墂��ɂ���
���̂ʂ����蓐�ވ��ꂳ
�����ɂ��ΐ��ӂ��ŁA�g�����炵���͂��������ׂ����Ȃ��B�q�`�W�r�ɂ́s�����t�ɂ͂قƂ�ǂȂ��������A�f�ډ̂̂悤�Ɍ����Ƃ��� �t���B���� �����̂�11��߂�136��߂̓����u�����v�A������137��߂́u�钷�v�ł���B
�����ʖ�̒����戣�����拾���Ƃ�ċ��Ƃ������i11�j��ɂȂ肫��ʂȂ�݂�����
���|���ɒ������̂Ă��i136�j�����ʖ�̒����戣������d�Ԓʂ�ɖ����̂���i137�j
11��߂�137��߂̏�̋傪���`�Ȃ̂�
�Ӑ}�I�ł��낤���A136��߂́q�`�W�r�ł͗�O�I�ȕ��̂ŁA���ɂ͂��ꂪ�s�����G�߁t�̎����\�����Ă���悤��
�v����B����܂ł̒Z�̂̌��łȕ��̂ɋT�������悤�Ɍ�����̂��B���̈��́A�܂��ɋg�����Z�̂��玍�ֈڍs����Ƃ����ۂ̃h�L�������g���낤�B����
�䂦�q蜾蠃�k�X�K���l��r�͋g�����̔����̉̂ł���A�����o�łł���ɂ�������炸�s�����G�߁t�̒Z�̂́A���тɊr�ׂĂ����낵���܂ł̊����x�������Ă�
��B����܂���A�g�����̒Z�̂Ɂu���̐�v�͂��͂△���ɓ����������B
�@�@�@�@�@��
�̏W�s�����t�����4�s���a�ݗt�W
���l�\�\���a�\��N�`�\�l�N�t�i�u�k�ЁA1979�N8��28���j�́q���������̉́r���́q�X�p�Łr�ɑI������Ă���B����������a14�N�̍�ŁA�Ę^�ł�
���邪�A�g���������O�Ō�ɔ��\�����Z�̂��낤�B
���܂���Ђ����Κe���L���C���͊X�ɏ����
�X�̉�݂̐ӂ���ތ����̍���̍��ɉJ���Â��Ȃ�
�݂Â݂�Ȃ�������Ђ̂Ђ��т��Ƃ�����Ȃ���邠���̂�ӂ���
�H�Ђ炭���W�̗]����[���]�ӂ��a�̂������ƂӂƂ����ɂ���
���Ɉ��������4��̏��o�`�i�q�`�W�r�f�ځj������ƁA�g�����Ꮡ���̉̂ɂǂ̂悤�Ɏ����ꂽ���i���邢�͓���Ȃ��������j�������� ����B
�@�@�s
���܂���Ⴍ�Κe���A�h�o���[���͊X�ɏ����
�@�@�ю�����
���X�̉�݂̐ӂ���ތ����̍���̍��ɉJ���Â��Ȃ�
�@�@�H�݂̂Ái���D����j
���݂�Ȃ����D�Ђ̗₦�₦�ƐS�Ȃ����H�̗[����
�@�@�H�̂���
�H�Ђ炭���W�̗]����ӂ��a�̂������ƂӂƂ����ɂ���
�q�`�W�r�Ɓs���a�ݗt�W�t�̊Ԃɂ́A40�N���̍Ό�������Ă���B�g�����̒Z�̂́A���̔o��Ƃ͈قȂ�A�{�i�I�Ȏ���̊J�n�ƂƂ��ɕ� �ꂽ�B�� ��́A�g�������̌��I�ȕϖe�̚��O�ɂ����āA��捂Ȏp�����ɂƂǂ߂�B
�g�����ɂƂ��č��삿���i1911�`1936�j�́A�k�����q�i1902�`1978�j�ƂƂ��ɏd�v�Ȏ��l�ł���B�����A���M�́q�N���r�Ɂu���a�\��N�@���O���N�@�@�\���^�m�l�֓����i�ʼn�Ɓj��Ō����s�J�\�̎��i�����炭����C����Łw�݂��k�Ál��x�Ɍf�ڂ��ꂽ�u���������s�J�\�v�j�Ɍ[������B�Ȍ�A�k�����ʎ��W�w���̃A���o���x�Ɓw���삿�����W�x�Ȃǂ�ǂށv�i�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O�Z�y�[�W�j�Ə����Ă�����̂́A�k���Ɋr�ׂ�ƂقƂ�nj��y���Ă��炸�A���̓�ӏ�������������Ȃ��i�l�͂ق�Ƃ��ɑ�Ȃ��̂ɂ��Č�������Ƃ͌���Ȃ����j�B
�u�Z�̂�������A���m�̊��o�ƃC�}�[�W�����Ăѓ����ɐ�D�̎��^�������̂��B���ꂪ�������h�̎��ł��邱�Ƃ�����Ƃ킩�����B�Ȃ��Ȃ�A���͗B��l�̗F���Ȃ��A�܂������肳����ł��̂������Â��Ă����̂�����B�����Ă킪���̍�i��T�����B�s���삿�����W�t�A�k�����q���W�s���̃A���o���t�̓�������ꂩ��Ȍサ�炭�͈��ǂ̏��ƂȂ����v�i�q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�Z���y�[�W�j�B
�u�k���a�\�l�N�l������\�����@���j���Ǝv���Ă�����A�{���͎O�j�炵���B������Œ��ׂĖ������u�O�j�v�������B�w���삿�����W�x�͂��v�i�q���܂�͂����L�r�A���O�A��Z��y�[�W�j�B
�O�҂́q�N���r�̋L�q�̌��ɂȂ��Ă��镶�́B�ł́A��҂̋g���̂��Ƃɓ͂����s���삿�����W�t�Ƃ͂ǂ�ȏ����������̂��B
���삿�����W
���a�\��N�\�ꌎ��\���@���X�Д��s�i���s�ҁ@�X�J�ρj�@���y�ŁE�����ŁE���s�ŕ����O�S�\������
���y�Ł@�O�S������i�L�Ԗ��j�@�l�Z���܍��\�����ԑ��@�����@�{���㎿���\��|�C���g�����g�@�m���u�����y�[�W��Z��@�ڎ����y�[�W�@�{����܋�y�[�W�@�u���W�̂��Ƃցv�i�S�c�@���j�Z�y�[�W�@�u���삿�����W�o�����v�i���s�ҁj��y�[�W�@�u���`�v��y�[�W�@�ʒ��}��i�l�t�j�E����@�O�ݐߎq�@�艿��~
�����Ł@�l�\�ܕ�����i�L�ԓ��j�@���^�E�{���g�ŁE�}��E���拤�ɕ��y�łɓ����@�p�w�p�\���㐻�@�����{�[�������@�{���������m�q���@�艿�O�~
���s�Łi�����j�@�ܕ�����i�L�ԓ��j�@�̍فE�{���p�����ɓ����łɓ����@�O�ݐߎq���M�f�b�T���}���t���@�艿�\�~
�i�q�����r�A�s���삿���S���W�t�A�X�J�ЁA1983�N11��27���A��܈�y�[�W�j
�g���������肵���͕̂��y�ł������ł̂ǂ��炩���낤�B������ɂ��Ă��A���Ɉ�������̎U���q���̊�ł����Ȃ�r�i���o�́s�J�C�G�t7���A1934�N5���j�͎��^����Ă��Ȃ��B
�u��Ƃ̎d���Ǝ��l�̂���Ƃ͔��Ɏ��Ă��Ǝv�ӁB���̏؋��ɊG������Ƃ����т��B�F�ʂ́A���̓��`�C�t�ɂ�����\�}�A�A�e�̂������炷���͋C�A������ԂƂ̐ڐG�_�����߂�\�}�A����Ȓ��ӂ����āA���ʂ��l�ւč\�����ꂽ�����������邾�炤���B�����Ă��͂��̏�̈ꐡ�����v�Еt���Ŏ��������Ă��ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ�������B����ł悢�ꍇ������B��������Ȏ��͊��ɖłтĂ��B���ՂȐ����̒Z�����̂ł����v�i�s���삿���S���W�t�A��Z���y�[�W�j�B
�g�������o���Łq���̊�ł����Ȃ�r�ɐG�ꂽ���͒肩�łȂ����A���͂��̈�߂Ɏ��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̎��@�Ƌ��ʂ�����̂�������B���̈�ۂ����邩�̂悤�ɁA���삿���ɂ́q����陁r�i���o�́s���삿�����W�t�j�Ƃ����A�g�����́q�ߋ��r���v�킹�鎍�т�����B
����陁b���삿�������l���������B�l�{�̎w�Ղ����āA
�\�\����Ɍ{�������Ȃ����B�����ł����z�͂Ԃ�Ă��B
���Â˂Ă�����̋�̊Ŏ�B
�������삯�r�ł䂭�̂��B
�ނ�͐������Ȃ�������S���̒��Ŏ�Ă��B
�h�J�̗��̂₤�ȊO�̐��E�ɐG��邽�߂Ɉ�C�̉�ƂȂđ��ɓ˂�������B
���̒�����颂�����������߂���̂���߂�Ȃ�Ύ���͊�ւ̏�Œ��т�����B���͎��̊k��E���B
����͐�ɓI�ł���B�q����陁r�����e�����q���̉Ɓr�ɂ͂��́u���͎��̊k��E���v�Ƃ������傪�������A�q���̉Ɓr������̑�\��Ƃ��Đ��������ɂ͎^�������˂�B
�Ƃ���ŁA���삿���̎��Ƃ��ǂ��Ƃ炦���炢���̂��낤���B�V��L���́q�����̂Ȃ��ƕs�v�c�Ȏ��R���\�\�������_�j�Y���̏������l�����Ɩk�����q�r�Łu���̃��_�j�Y�����̏��������k�]�ԏ͎q�A��������A�R���x���q��l�̃C���[�W���\�w�I�ł���̂ɔ�ׂāA����̎��͂��B�g�I�ł���A���z�ɂ͕��y�I�ȃ��A���e�B������B�ޏ��̌��t�͏I�n�ޏ����g�̌��t�ł���A����ȊO�̒N�̂��̂ł��Ȃ������v�i�s���㎍�蒟�t2002�N11�����A�Z�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B����̑S��i����́A���̒Z�����U��m��ʎ҂ł����A���̗\�������ׂĂ̎��т��x�[���̂悤�ɕ����Ă���̂������邾�낤�B
�ŏ��Ɉ������g���̓��L�̌ːВ��ׂ́A�������̏��߂ɍT��������������O�ɂ��Ă̂��Ƃ̂悤���B���̂悤�ȓ����ɁA��\�̋g�����ǂ݂ӂ������̂��s���삿�����W�t�ł���A�����J�X��́s�����P���W�t�������B
�s�g�����U�����t�i�v���ЁA2006�j��ǂ�ł�����q�x�V�ԉ��j��W�s�َ��t�̂��Ɓr���ڂ��Ă����̂ŁA�Ҏ҂̏�ˎ闝��������̏� �]�i���o�� �s�o��t1962�N1�����̏��]���j��厖�ɂ��Ă��邱�Ƃ��킩���Ċ����������B�{���͊ȒP�ɓǂ߂�̂�����A�����ł͋g�����ƕx�V�ԉ��j�i�������͐V�� �o��j�ɂ��čl���Ă݂����B�g���́q�x�V�ԉ��j��W�s�َ��t�̂��Ɓr���u�ԉ��j�Ƃ̏o�����肽���v�i�����A���O�y�[�W�j�Ǝn�߂Ă��邪�A�����s�� �U���q�ԉ��j�厄���r�i�s�x�V�ԉ��j�S��W�t�̞x�Ɍf�ځj�ł��u�ԉ��j�Ƃ̏o��v���珑���������Ă���B�`���̒i���͂������B
�@���͏o�����鎞�A�Z�ɓ�̎��𗊂B����͏������߂����т̏o�łƁA�����̖{���Ēu�����Ƃł������B���� �����̖{�� �薼��Y��Ă��܂������A���������Ȃ��̈�����x�V�ԉ��j�́s�V�̘T�t�ł������B���w�E�|�p�ɊS�̂Ȃ������Z�ɂƂ��ẮA����Ȍ���{�����߂邷�ׂ�m �炸�A�s�V�̘T�t�͐��Ɏ��̎茳�ɂ͓͂��Ȃ������B�������A�Z�͎��̗F�l�����Ƌ�J���āA���W�s�t�́t���Ă��ꂽ�̂ł������B�i���A����ь牮�A 1976�N12��10���A�O�y�[�W�j
�O�̂��߂ɒ�����A�s�V�̘T�t�i���͔��s���A1941�N8��1���j�͕x�V�ԉ��j�i1902�`62�j�̑���W�ŁA1951�N�ɂ͑��� �����ł��V�� �T���s���r��_�R�l�̑��{�ŁA����200���Ċ�����Ă���B�g���́q�ԉ��j�厄���r�̑�2�i���ŁA�s�t�́t���������W�s�����G�߁t�Ɠ��l�A�ԉ��j�Ɍ� �{���Ă���͂����A�Ə����Ă����3�i���ɂ��������B
�@���������Ȏ��������Ă������́A�V�����߂����o��G���q���́r�ɐS�䂩��A�Ƃ��ǂ��w���ēǂ�ł������̂ł���B ����ނ�ɓ� �債�āA�����I���Ă���̂��A�Ȃ������v���o�ł���B���쑐���ЎR���j�̋�����A���͐S����u�֎U�邠�T�Ȃ܂ʂ邫���̉Ύ��v�u�ԕ��̓��@���͓� �[���������肫�v�Ȃǂ̐ԉ��j�̋�������Ă����悤�Ɏv���B
�����őz�N�����̂��A�g�������сq�����������}�r�i�A�E13�j�̉p��ҁE�����h�����Ɉ��Ă����ȁi1974�N10��10���t�j�̈�� �u�k�q������ �����}�r�́l�u���K�v����͏����̑���ł͂���܂��A�����ɂ͂���܂���ˁB��O�̃��_�j�Y���o�傠����Ɏg��ꂽ�悤�Ɏv���܂��B�u�R�E�J�C�v�Ɠ� �݂܂��B�����Ă݂�A���{�̓����̃z�e���I�Ȍ܁A�Z�K�ʂ̊����ł��B��O�̓��{�ɂ́A���݂����ɏ\�K�A��\�K�͂Ȃ���������ł��B�������A�A�����J�ł� �܁A�Z�K�ł͖��ł��傤�ˁB���܂������܂��v�i�sLilac Garden�t�AChicago Review Press�A1976�Aiv�y�[�W�j�ł���B�g���͐V���o��̌�b�Ŏ��W�s�t�́t���������̂��B���āA�q�ԉ��j�厄���r�̖{���͎��̂悤�Ɂu���]�v�ɐG�� �����ƁA�ԉ��j�̑S�傩��s�V�̘T�t16��A�s�ւ̓J�t10��A�s�َ��t6��A�q�E��r9����������q�ԉ��j�厄���r�i���͑S�̂̕W��Ɠ����j�ŏI����� ����B���̎����ɂ́A�O�f������2���������B
�@���a�O�\�ܔN����A�����d�M�Əo�����A���k���l���{�s�V�̘T�t�Ɓs�ւ̓J�t�����āA�͂��߂Đԉ��j�̑S�e����� ���邱�Ƃ��o �����̂ł������B���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A��W�s�َ��t�̏��]�������͂߂ɂȂ��Ă��܂����B����́A�s�V�̘T�t�����u���鎄�ɂƂ��ẮA�炢���Ƃł������B
�@�ӔN�̐ԉ��j�͎��ւ̎u�����悭�A�o��Ƃ������A��s���Ƃł��̂��ׂ����̂��肾�B���ɂ͂ǂ����Ă��A��i�̊ϔO�I�}�@�������Č����āA���ɂ̏� �����߂����͂������Ă��Ȃ��B�����炭�a���̐ԉ��j�����]�������Ǝv���ƁA�S�ꂵ��������ł���B�s�َ��t�͂��̂܂܁A�ԉ��j�̈�e��W�ɂȂ��Ă��܂� ���B
�g�����́A1965�N�Ɋ��s���ꂽ�s��{�E�x�V�ԉ��j��W�t�i��{�E�x�V�ԉ��j��W���s��j�ł́A��W�o�ł̔��N�l�i�����d�M�瑼�S 30���j�̈�l�ƂȂ��Ă���B
�ȑO�A�q�g�����̘b�����r�̖`���Ɂu�g�����́A�N�lj��u���Ȃǂ̌��J�̐Ȃɏo�邱�Ƃ��Ȃ���������A���̘b�Ԃ��m��l�͌����Ă��悤�v�Ə������B���Ɉ����q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S�����^���Ձr�́A���O��O�ɂ����g���̘b���Ԃ�܂œ`����M�d�ȋL�^�ł���A�u���ɏ�������̂ƎƂ��Ă悩�낤�B�����͎G��4�y�[�W���̂��߁A�����ꕔ���Љ��B
�@���c���j����́A������ςɍ˔\�̂���l�ŁA����ł����S�̂��A��ς����ꂽ���Ȃ�ŁA���͂������Ԃɐ�������ł����ǁA��������Ƃ��A���������h�ɋ߂��Ȃ��āA�����o��Ƃ���Ȃ��Ă��A��s���Ƃ������A���ł�������Ȃ����B����́A������Ǝ��̕��ֈ����ς��Ă݂����悤�Ȑl�Ȃ�ł����ǁA�܂��o��ɂ����Ƃ��ĈِF�����ƂƁ\�\�B�܂���������Ȃǂ�����܂����A������ِF�����Ƃł��傤�B
�@�k�c�c�l
�@�������A�����ɂ���������F����A�V������ƂƂ����̂́A��������Ȃ��āk�����Ɏ蒟��u���Ė�����o�߂�������������A��s�������肷��̂ł͂Ȃ��āl�A�����Ɉӗ~�I�ɁA���Ƃ��A���̌��Ă����u�~�]�v�Ƃ����f��ƁA����Ƃ����т��悤�Ƃ��A���������l���ŁA����Ă���������Ǝv����Ł\�\�A�l�́A�o��͔o�傩��w���A���̂��̂���w��łق����Ɓ\�\�A���͎�����w���A��������̂���w��łق����ƁA���������ӂ��Ɏv���܂��̂ŁA�F������A���ꂩ��A�悢��i�������ĉ�����悤�ɁA���肢���܂��B�i�s�o��]�_�t78���A1968�N3���A��O�`��l�y�[�W�j
�s�o��]�_�t�͕ҏW�l�E�����d�M�A���s�l�E�������q�̔N8�y�[�X�̎G���B�����́q���Ƃ����r�Ɂu���H�̑S�����ɂ�����A�������H�E�剪�M�E�g������̏����̒k�b���f�ڂ����B�o���邾���A�����̐��܂̊������c�������Ǝv���A�^�������܂܂��A�قƂ�ǎ����ꂸ�ɔ��\�����v�i�����A�k�l��y�[�W�l�j�Ə����Ă���B�R���́u�u���v�O�ɍς�ł����B�����Ȃ�ƁA�g���̑I��]���ǂ݂����Ȃ�̂͐l��Ƃ������̂ŁA���ɓ���72���i1967�N9���j�́q���z�\�\�o��]�_�܌���܂ŁE�o�ߕƑI��]�r���f����i�k�@�l���͍�i���B�܂����p�����̋���A�����{���̋�ɏƂ炵�čZ�������j�B
�@���c�@���j�@�R�_ �k�q���ꂤ���q�C�L�r�l
�@�����i�̒��ł́A�ł����I�ŁA�S��̗������낢�A��̐��E������B�ꐡ�A��������̒����̎�����������B�ЂƂ��ƂŁA�����A�܂��ɁA���邽�̊��G�B
�@�@���ɂ�������ނ��Ӑ��v�������ӂ���
�@�@�������肩������@凁k[�����͂܂���]�l���͂�
�@�@���Ȃ�k�@���A�l�R���ЂƂӂ���̂��Ђ���
�@�@�����܂��ق났�Ɏ��������邠�ӂނ�
�@�@���炷���F���{���������̂Ă��炪��
�@�@���߂��邠�܂����˂��݂ӂȂ����
�Ȃǂ͏G��Ǝv���B
�@�͌����f�j�@�P�_ �k�q�����r�l
�@�ÓT�h�̕��i������B
�@�@�C�̏ꏊ�ɏt�̊C�݂�ȕ�����
�@�@�����␅�k�́����l�˂̏H�̐�
�@�@�ŘV���Ă��������Ƒ�����ɂ���
�@�����@�P���@�P�_�k�q�p�́r�l
�@���������삵�Ă���B
�@�@������@�䂭�������݁@�Ȃ���䂫
�@�@���ς��@�h�q�������ӂȂ�����
�@�@����荨��ށ@�����ɂȂ�ԔK�V��
�@���R�b�q�j�@�P�_ �k�q��i���\�|�^�~�A�j�r�l
�@�ϔO�I�ŁA����E����̗��C�ɂȂ�B�����ƌ������𒍂����ƁB
�@�@�����̕��m�ԕ������̎�s
�@�@�p�����R����A���ƂȂ�R�n
�@�@�ۉ傿�݂ɉ���S�����j�䂭
�O�̉��Ⴀ��ɂ���Đ����B
�@�ق��ɁA����i�Îq�����ɂÂ��Ǝv���B
�@�@���Ƃ��炠�Ƃ��猎��̎莆�j������ �k�q�������r�l
�@�@�ڂ̔z�肽���Ȃ�ʂ��̂����ނ�
�@�ȉ��A������q��
�@�@���^�̂�������^����݂̐S�d�}
�@�����
�@�@�����͂ЂƂ̕a�C�S������
�@�������Y��
�@�@���V�Ƀ[�u���悩��ĕꂪ�Q��
�@�Óc���V��
�@�@�ꍡ���Â�������͂�
�@�l�{�s��
�@�@�~���̌��̌����������Ȃ��Țe��
�@�@�Ĉł݂̒苴�킽�錢�͏ł���
�@�O���F�q��
�@�@�������т��X�Ɍ�����k���ȁ���l�т��� �k�q�����r�l
�@�剪��i��
�@�@��������
�@�@�t���O��
�@�@�������� �k�q��䃒����r�l
�Ȃǂ̑f���ȍ�i�ɐS�䂩�ꂽ�B�i�����A�O�Z�`�O��y�[�W�j
�g���������c���j��i�W�s���ꂤ���q�C�L�\�\The Verses of the St. Scarabeus�t�i�o��]�_�ЁA1969�j�Ɂq�����r���Ă���̂��A���̑I��]���@�����Ǝv����B�ȍ~�A�g���͋�W�̊��z�����i�c�k�߂́s�Ս��t�Ȃǐe�����厏�ɏ����Ă�����̂́A�o��̑I�]�͎c���Ă��Ȃ��B
�s�� ����{�����W�听11�t�i�����n���ЁA1960�N9��10���j�ɂ͋g�����̎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j���S�ю��^����Ă���B�ق��ɒJ��r�� �Y�s��\�����N�̌ǓƁt�i�n���ЁA1952�j�A�R�{���Y�s���s�҂̋F��̉S�t�i���惆���C�J�A1954�j�A���J�열���s�p�E���E�̒߁t�i���惆���C�J�A 1957�j�A�J���s�J��厍�W�t�i�����ЁA1960�j�A�֍��O�s�G�̏h��t�i�����ЁA1953�j�A���c��v�s�s���ƗV���t�i�ђˏ��X�A1959�j�A�ѓ� �k��s���l�̋�t�i���惆���C�J�A1953�j�A��c�G�s�ƍفt�i���惆���C�J�A1956�j�Ƃ�����1950�N��̖������鎍�W�����^����Ă���A������b �q���{�W�Łs�m���t�ɐG�ꂽ�Ƃǂ����ɏ����Ă����B�����ŏ��Ɂs�m���t��ǂ̂́s�g�������W�k���y�Łl�t�i�v���ЁA1970�j�ł��������A8�|2�i�g 22�y�[�W���߂�s������{�����W�听11�t�Łs�m���t�ɐG��Ă�����A�܂��ʂ̈�ۂ���������������Ȃ��B�{�W�̔������ɂ́A�e���l�ɂ��450���� ���́q���`�r���������낳��Ă���B�g���́q���`�r�͌�N�́q�N���r�i�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�j�ɘA�Ȃ鎩�M�N���̐��F�����A �P�s�{�ɂ͎��^����Ă��Ȃ��B
�����N�����{���̐E�l�̉Ƃɐ����B���䑾�Y�A�ꂢ�ƔӔN�̎q�B�o�E�Z�̎O�l�Z��B�����q�포�w�Z�ɓ��w�B���� ���납��悭 �Z���p�j�B�`�����o ���V�т̈���̊����B�ƂɈ���̖{���Ȃ��A�F�����̖{��ǂ݂�����B�{���������w�Z���ƌ�A�㏑�o�œ�R���ɕ���B�Y�w�l�Ȑ}�����݂ăV���b�N��������B ��͏��Ɗw�Z�֒ʂ��B�����Ƃ݂ĉʂ����B���ƍ����t�˂̉e���Ŕo��Z�̂����݂�B���l��N�ďo���B���W�w�t�́x����o�ŁB�x�E�m�Ƃ̗���������� �ŁB���B�����̌R���ՂŁA�V���m�E�h�E�x���W�����b�N���쌀�����ď㉉�A�t�c���̋t�ɂӂ�]���B�ϏB���ŏI��B���ꂷ�łɖS���B�Ƃ莍������B���� ��N�}�����[�ɓ��ЍL����S���B���܌ܔN���W�w�Õ��x����o�ŁB�s�E�h�Ƃ̎l�N�Ԃ̗����ɏI�~���B�ѓ��k���m��A�w�����x�ɓ���B�͂��߂Ď��l������ �������B���ܔ��N���W�w�m���x���s�B���܋�N�܌��A�a�c�z�q�ƌ����B����g��܁B�u�k�v���l�B�w�g�������W�x�����C�J��芧�s�B�i�s������{�� ���W�听11�t�A�k�O��Z�y�[�W�l�j
�{
�W��18�s�̒Z���Ȃ���A�̂��ɂ��낢��Ȑ��z�ŏ�����邱�ƂɂȂ鎖�����A���V�ɂ����s�Ȃ��ɋL����Ă���i�ǎ҂͂�낵���s�u�����v�Ƃ����G�k����
�Łl�t�̕��͂ɓ������Ă݂�ꂽ���j�B���Ƃقǂ��悤�ɁA�{�W�͂��̌�́q�g�����r�����Ă���̂����A����ɗ�炸�����[���̂��g�������i�Ƃ�킯
�s�m���t�ɂ�����j�̕]���ł���B����M�v�������́q����r�������Ă���̂ŁA�g���ɐG�ꂽ�����������B
�u�g�����́w�m���x�́A���a�O�\�O�N�Ɋ��s����A�O�\�l�N�x�̏܂����^���ꂽ���W�ł���B������Ƃ����_�ł́A�J���Ɣ�r�����g�����A���̂悤�ȏ܂�
�����Ƃ́A��N�x�̎��d�ɂƂ��Ĉ�ٕ̈ςł������ƌ����Ă悢�B�^�������A����������ŏX���ŁA��\���I�̃X�L�����_���̂��ׂĂ��܂ނƂ����邻
�̃��j�[�N�ȃC���[�W�́A�ǎ҂̑z���͂ւ̈��̒���Ƃ��āA�����D��̊�Ō}����ꂽ�B���@�Ƃ��ẮA���y�����ꂽ�V���[�����A���X���̎�������Ă�
��B��͂�A�u�����v�Ɓu�m���v����\��ł���B�،��F��́u�ނ̎��̂������낳�͎���̕��ʌ����ł͂Ȃ��A���̍\�z�̎����m�������Ƃ���ɂ���B������
��{�̃��x�b�g�̎��͊w�I�i�Í��I�j�Ӗ���������Ɨe�ՂɎ��̑S�̂����������Ƃ��ł���̂ł���B�����ɂ͈Í��̔��w�A���x�Ȓm�I�Q�C���ɐڂ��������
������v�ƌ����A������́u���̑̎��I�Ȍ���̔S���������Ɠ��̂��Č����Ȃ������q�����̔��w�r���Ȃ��Ă���v�ƕ]���Ă���v�i���O�A�O�O��y�[
�W�j�B
�g���́q���`�r�́s���㎍��n3�t�i�v���ЁA1967�N3��1���j�́q�����r�Ƃ��āA���̂悤�Ɍ`�����߂Čf�ڂ���Ă���B
�����N�A�����{���ɐ��܂��B���䑾�Y�E�ꂢ�ƁB���N�����Z���p�j����B�����̐����̐l�����t�ˎ��̉e ���������ĒZ �́E�o�������B���H�A �t�v�A���Ƃ����ǁB�������w�Z���o�āA�㏑�o�œ�R���ɕ���B�����t�q�Əo��B���l��N�������B�֏o���B�\���������m�푈�u���B�\���B���W�s�t �́t���s�B���l�ܔN�����\�ܓ��I��B���N�ϏB�����A��B���ꂷ�łɎ����B�͂��߂āA�Y�A�g�A���q��ǂށB���c�唪�v�Ȃ�m��B�����̉�Ƃs�E�x �̎��E���_�@�ɁA�s�E�h�Əo��B���܌ܔN�s�Õ��t���s�B������u�k�v�O���[�v�y�����C�J���ӂ̎��l������m��B���ܔ��N�s�m���t���s�B�g�܂��� ���B���܋�N�t�A�a�c�z�q�ƌ����B���Z��N�s�a���`�t���s�B�}�����[�Ζ��B�i�����A���l�y�[�W�j
���́q�����r�́A���N�H���s�̑S���W�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�ɂقڂ��̂܂܂̌`�ŗ��p����邱�ƂɂȂ�B������A�̕��� �́A�����܂� �̋g�����̓`�L�I�����Ƃ��āA���ɎQ�Ƃ��ׂ��d�v�����ł���B

�^�甎�����ɂȂ�s������{�����W�听11�t�i�����n���ЁA1960�N9��10���j�̖{�̂�
��
���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�̑�V���̑O���́A�g�������e���Z�̔o��ɂ��Ă̕��͂Ő�߂��Ă���B�薼�� �Ώۍ�Ɩ���t�L���Čf���悤�B
���l�ɂ��āA�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�̑��╔������A�Z�̔o��ɂ��Ă̕��͂�������B
��ǁA�o��E�o�l�ւ̌��y���������Ƃɋ��������B�Ԃ��Ɍ���A����͏���59�ђ�8�сA�����86�ђ�15�т𐔂���B�g������ �Ƃ��Ĕo��� �ӏܕ��́A���Ƃقǂ��悤�ɑ�ȕ��삾�����̂ł���B1976�N7���A�g���́s�����V���t�ɘA�ڂ����q��z�̔o��r�̑�3��q�g���̎O��r�̈�߂ɂ��� �������B
�@���͘Z�N�O�ɁA����o��G������u�g���̈��v�Ƃ����e�[�}�̏��������߂��āA���̋�������Ă���B�@�@�����ƑѓZ���o�Â�S���g
�@ ���̂Ƃ��̕��͂�v��Ɓ\�\�u���a�\�l�A�ܔN����A���͒W�H���̓��_�c�r���̈ꎺ�ɂ���A�����ȏo�ŎЂɋ߂Ă����B�����̊K�i��֏��̑O�ł��ꂿ�� ���A���Ȃ����ʼn��ʂ��̑傫�ȐN�̎p�ɐS�䂩�ꂽ�B����������ł悭�ꏏ�ɂȂ�A�����Ȗ�����̌�����A���̑呫�̐l���Γc�g���ł��邱�Ƃ�m�����B �g���͂��łɁA�o�d�̋P����V���ł������B���͂̂��Ɏ��W�s�t�́t�ƂȂ������������Ȏ��т������Ă������Ȃ̂ŁA�g���ւ͋߂Â��Ȃ������B�������g�̔g�� �������܌����A���̎����Ƃ��Ă��̈�傪�Y����Ȃ��B�����܂��t�̊X���v�����R�𒅂ĕ����Ă����B�v�\�\�Ƃ���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�} �����[�A1988�A��O��`��l�Z�y�[�W�j
�g���͂��́u�g���̈��v�Ƃ����e�[�}�̏����q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�����̂悤�ɏ����Ă����B���Ȃ݂Ɂu�����Ɓv�̋�͔g���̋�W �s���t�i�꞊���[�A1943�j�Ɏ��߂��Ă���B
�@�����ƛ�㕂��o�Â�S���g�@���a�\�l�A�ܔN����A���͒W�H���̓��_�c�r���̈ꎺ�ɂ���A�����ȏo�ŎЂɋ߂� �����B�����̊K�i��֏��̑O�ł��ꂿ�����A���Ȃ����̘a���p�̑傫�ȐN�̎p�ɐS�䂩�ꂽ�B����������ł悭�ꏏ�ɂȂ�A�n���ؔ��s���̖�����A���� ���Γc�g�����ƕ������B�����Ȗ�����́A��������t�ꎁ�̖������Ǝv���B���łɔg���͔o�d�̋P���鐯�ł����B���͔g���߂Â����Ƃ����Ȃ����B �����Ȃ���o����̂āA���͂Ђ����ɒ��������Ȏ�������݂�������B
�@�����͂��ƂŁA���W�w�t�́x�ɂȂ�͂��ł����B�����g���̋�����ɂ���悤�ɂȂ��̂́A���ł���B
�@�S���Ƃ��݂킽���Ƃ��w�ɖ��x�ꊪ���⏥���Ǝv���B�������A��\���E���̔g���̐��g�̎p���A�����Ԍ������ɂ͂Ȃɂ����A��Ԏ����̂���`���Ƃ��āA ���̈�傪�Y����Ȃ��B��\��̎����܂��܂�ɂ͒����𒅂āA�t�̊X������Ă����B�i�s�o��t1970�N11�����q�Γc�g�����W�i�S�W�����L�O�j�r�A �Z��y�[�W�j
�q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�̊����x�������ĒႢ�킯�ł͂Ȃ��B�������g���́A�o������U���Ƃ��Ă͝R��I�ɉ߂���Ɣ��f�����̂ł͂� ��܂����B�� �̂��߁A�ق��̕����ׂ͍������荞��ł���ɂ�������炸�A�u���ʂ��v��u���̑呫�̐l�v��u�v�����R�v�Ƃ������o���������������������ƍl������ �i�s���t�ɂ́u�Ŏ�t�킪�呫�����Ȃ��ޓ��v�Ȃ�傪����j�B�g�������U���ɂǂ�قǐS���𒍂������A�����������Ƃ̂ł���D��ƌ����悤�B
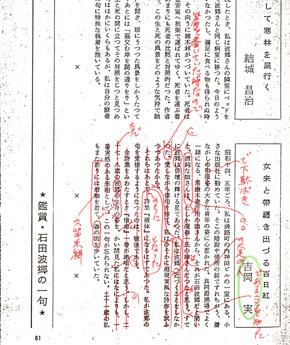
�g�����q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�i�s�o��t1970�N11�����j�̎���
�k�Ԏ��͏��ш�Y���q�ӏ܁E�Γc�g���̈��r�Ɏ�����āq�g���̎O��r�Ƃ��Ă݂����́l
�g�����͂قƂ�lj��y���Ȃ������悤���i�����A�g���̐��z�ɂ͉��y�̘b�肪����߂ď��Ȃ��j�B�z�q�v�l�ɂ��A�N�����E�H�[�N�} �������� ���Ƃ����Ƃ���A�����ɃC���t�H�����O���Ă��܂����������B�Ȃ��̂����₾�����̂��A���̌��Ɉٕ�������̂����₾�����̂��͒肩�łȂ����B����� ���A�g���̎��тɂ͎��̂悤�Ȏ��傪����B
���y�̓��[�����X�N�i�q���̂��߂̃g���̎��݁r�E�E1�j���Q�n�т̉��y�́s�}�w���A�̋F��t�i�q�t�̃I�[�����r�E�E10�j
�s���拃���āt���̂��Ȃ���i���O�j�i�b�g�E�L���O�R�[���̉S�i�q���I�ȗ��S�r�E�E12�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j�[�i�E�V�����̉S���D���i�q���ׁr�K�E6�j
�@�@�@�@�i��̐瑐�����̉����c�c�j�i�q���i�r�K�E11�j
�q���[
�����X�N�iHumoresque�j�r�̓h���H���U�[�N�̃s�A�m�ȁB�s�}�w���A�̋F��t�̓}�w���A�E�W���N�\���̂��Ƃ���́q��̋F��iThe
Lord's Prayer�j�r���B�r���[�E�z���f�C���̂��Ă���q���拃���Ă�����iWillow Weep for
Me�j�r�͏����쎌��ȉƃA���E���l�����K�[�V���C���ɕ������ȁB�i�b�g�g�L���O�h�R�[���̉S�́q�A���t�H�Q�b�^�u���iUnforgettable�j�r��
���肩�B�j�[�i�E�V�����̉S�̓K�[�V���C����Ȃ́q�A�C�E�����E���[�E�|�[�M�[�iI Love You,
Porgy�j�r���B���́q��̐瑐�r�͗����`�̉̎��Œm����A�C�������h���w�B�����̊y�Ȃɋg�����͂��A�ǂ��ŐG�ꂽ�̂��낤���B
�q��̐瑐�r�ɂ͏��w�Z���̂Őe�����낤�i�q���[�����X�N�r�������炭����ɏ�����j�B�u�j�[�i�E�V�����̉S�v�͎l�J�V�����ɕ��������тɏo�Ă����
������A�w�i�͐����ł���B�ł́A�s�}�w���A�̋F��t�Ɓs���拃���āt�͂ǂ����B�}�w���A���`�̖�ҁE���V�K�v���́u���{�̃t�@�����}�w���A��m�邫����
���ƂȂ����̂��A�u�^�Ă̖�̃W���Y�v�Ƃ����f��i���݂̓r�f�I������Ă���j�ł���B���̉f��͈��ܔ��N�ɍs��ꂽ�j���[�E�|�[�g�E�W���Y�E�t�F�X
�e�B���@���̋L�^�f��ŁA���̒��Ń}�w���A�͍Ō�ɏo�����A���̗͋����̂Œ��O��[���������Ă���v�i�}�w���A�E�W���N�\���A�d�E�l�E���C���[�s�}�w��
�A�E�W���N�\�����`�\�\�S�X�y���̏����t�A�ʗ��ЁA1994�A��܁Z�y�[�W�j�Ə����Ă���A�g����1960�N���{���J�̂��̉f����ς��̂ł͂Ȃ����B�g��
���S�X�y���̂k�o������A�W���Y�i���ɏo���肷��}�͑z�����ɂ����̂��B�\�\���Ȃ݂ɁA�����ɂ́u�}�w���A�Ɠ����悤�Ƀx�b�V�[�E�X�~�X�̉e����F�Z
�����W���Y�E�V���K�[�̃r���[�E�z���f�B�[�v�i��O���y�[�W�j�Ƃ����L�q��������B
�g�����ƃW���Y�I�@���܂ŋg������_�������͂ŃW���Y�̕����������L�����Ȃ����A�����������炻��͂ЂƂ̃��m�O���t��v������V���Ȏ��_�Ȃ̂�������
�Ȃ��B�{�e�̕��Ă����m�点�������}�����ނ���̃��[���Ɂu�w�Â��ȉƁx��w�_��I�Ȏ���̎��x��ǂ�ł���ƁA�ӂƃR���g���[�����v���o�����Ƃ���
��܂��B�ӔN�̃R���g���[�����A�����̍D���Ȃ��̂����i�}�C�E�t�F�C���@���b�g�E�V���O�X�j���������c�߂��肵�Ē����Ԑ��������Ă����i�ƁA��������
�g���̎���������Ǝ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����肵�܂��v�Ƃ���̂́A�����\��������B�Ƃ��ɁA�O�f�̃V���K�[�����݂͂ȍ��l�ł���B�g���̎��т���
�u���l�v�̓o�ꂷ�鎍��������Ă݂�B
�l�����Ȃ����l�����i�q������G�r�E�E15�j�^���C�̂Ȃ��̍��l�i�q�}�N���R�X���X�r�F�E1�j
���l�Ƌ����i�q�_��I�Ȏ���̎��r�F�E11�j
���܂̍��l�̉S�������i�q�t�r�G�E4�j
���l�̐N��i�q���̃A�X�e���X�N�\�\���q���`�̊G�ɂ悹�ār�H�E22�j
���߂鍕�l�̐N�i���O�j���l�̎��̂Ȃ��ցi�q�t�̊G�r�I�E12�j
�q�t�r�́u��i���̂͌��̋C�̖R���������͂�ށ^���ꂾ����l�ނ��V���J��������^���܂̍��l�̉S�������^�v�l�͈ڂ�v�͋�̓I�ȉ̎�
���z�肳���
����悤�����A�T���̎藧�Ă��Ȃ��B
���������͗]�k�ł���B�g�W���Y�E�h�����E�̃V�F�C�N�X�s�A�h�A�A�[�g�E�u���C�L�[�͋g�����Ɛ��f�N���܂����������Ȃ̂��i�u���C�L�[��1919�N10
��11�����A1990�N10��16���f�j�B�ޕ��̃A���o���������̎��W�ƕ����Ď�e����̂��A�W���Y�E�~���[�W�b�N�Ƃ̗��݂ŁA�ꋻ�ł͂��낤�B
�k2006�N3��31���NjL�l
�r�f�I�Łs�^�Ă̖�̃W���Y�iJazz on a Summer's
Day�j�t���ς��B����t�����u�k�u�X�E�B�[�g�E�W���[�W�A�E�u���E���v���̂��L���ȁl���̃V�[�������ŁA�A�j�^�k�E�I�f�C�l�̓W���Y�̂ЂƂ̓`����
�Ȃ��Ă��܂����v�i�a�c���E����t���s�|�[�g���C�g�E�C���E�W���Y�k�V�����Ɂl�t�A�V���ЁA2004�A�ꔪ�l�y�[�W�j�Ə������f��ł���B�}�w���A�E�W��
�N�\���́A���̃A�j�^��C�E�A�[���X�g�����O���������āi�ƌ����̂��ς����j�A�Ƃ���Ƃ��Ă���B�ޏ��̉̐��́A����͂��������ȊO�ɂȂ��B�g���̎���
�u���Q�n�т̉��y�́s�}�w���A�̋F��t�v�́A�u�V������ƂƂ����̂́A�k�c�c�l���Ƃ��A���̌��Ă����u�~�]�v�Ƃ����f��ƁA����Ƃ����т��悤�Ƃ��A
���������l���ŁA����Ă���������Ǝv����Ł\�\�v�i�q�g�����́u�u
���v�Ɣo��I�]�r�Q
�Ɓj�ƌ�������l�̕��@�̎��H���̂��̂ł͂Ȃ����B
�g
�����́q�i�c�k�߂Ƃ̏o��r�i1971�N���\�j�ōk�߂Ƃ̎莆�̂��Ƃ�ɂ��ď����Ă���B�u�i�c�k�߂���ˑR�A�莆�������B����ɂ́A�w�o�D
��x�̒����ɋ��k�������ƁA�����|�����Ƃ���āA���]�������̂ł͂Ȃ����ƁB����Ɏ��W�w�m���x�̍�҂̖��͂��łɒm���Ă����ƁB���̂Ƃ����玄�ƍk��
����̕��ʂ��͂��܂�B�����\�N�A���͉i�c�k�߂����Ɏ莆�������Ă����悤�Ɏv���B���ɂƂ��Ď莆���������Ƃ́A���ʂقǂ炢��ƂƂ�����̂�����B��
��Ƃ������Ƃ��낤���A���͍����Ɏ���܂ŁA�킪�Ȃɂ����t�̂͂����������Ă��Ȃ��v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z��
�y�[�W�j�B
�g���ƍk�߂Ƃ̕��ʂ́A��܋�W�s�o�D��t�i�Ս��o���A1960�j�̒������@�Ɏn�܂����B�u���͂Ȃ�Ƃ��Ă��w���яW�x�ȑO�̍k�ߔo���ǂ݂������̂�
�Ǝv�������A���X���̋@��Ȃ������B���ꂩ��ܔN��A��������R�ɐ_�ːV���̏����ȏЉ�L���ŁA�i�c�k�ߊҗ��W�w�o�D��x���o���̂�m��A������S�~
�������Ē��������v�i���O�A��Z��y�[�W�j�B
�i�c�k�߂͔o�厏�s�Ս��t�i�Ս��o���A1949-1997�j����ɂ��A���Ƃ��k�߂Ɉ��Ă����Ȃ͐��������Ɍf�ڂ��ꂽ�B�g�����̏��Ȃ��ŏ��ɍڂ����̂�
1963�N2���A160���́q��o��r���Ǝv����B�ȗ��A1989�N4����447���q������r�܂ŁA��20�ʂ̍k�߈����Ȃ��s�Ս��t�Ɍf�ڂ���Ă���B
���̔��������Ɍf����1987�N1���A422���́q�t�������r�̎莆�ł���B
�@�q���@���̂��т͂��莆�ƍk�ߒZ����q�Ċ����������܂����B�S�����l�̊���������ꂽ�Ƃ̂��ƁA�܂��Ȃ�Ɣ� ������������ ����ꂽ���Ƃł��傤���B �ō��̂����{���Ǝv���܂����B���āA�������Z���ɂ́A�s�ł̖���u�R�[�q�X�i���ɍ݂�H�̉J�v�����M����Ă���A�i���X�D���̏����ɂ͉����̂��̂ł��B ���Ă̎P���̉�̐܂ɒ������Z���̕M�����A��x�I�ł���Ȃ�A����ɂ͔��B�̕��C�������܂��B�����ɁA�����Ε��̘e�ɒu���āA���X���߂Ă���܂��B�{ ���ɂ��肪�Ƃ������܂��B����͋v���Ԃ�ŁA�J���~���Ă��܂��A�H�̉J���B�~�̖K�ꂪ�����Ƃ̂��ƁB���ꂮ������g��ɁB
�h�@��@
�@�\�\�Z��
�� �������́u�\�\�Z���v�͎莆�̕��ʂ�����@������悤�ɁA�u�\����\�Z���v�̌�A�B�����Ȃ́A��_��k�Ђœ|���c������@��o����A�P�H���w �قɊ��ꂽ�i�c�k�ߕ��ɂ̏����i�ł���B�����̈����ʂɂ͍k�߂̎��Łu�t��^������^�V�N���ցv�u61.10.30.�v�u���{�^�Z���̂��Ɓv�u�� �ۑ��v�Ƃ������M�ɂ�郁��������������B
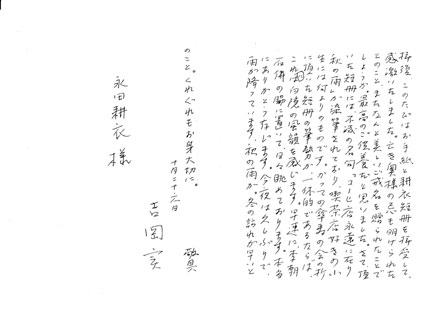
�i�c�k�߈��g�������ȁi1986�N10��26���j
�P�H���w�فi�i�c�k�ߕ��Ɂj����
�g��������{���g�Ɉ��Ă��t�����A�ʉp���H�Q�{����275���s���{�̕M�Ձ\�\������Ƃ��瑺��t���܂Łt�i�ʉp�����X�A2004�N5��25���j�̈ꔪ���y�[�W�Ɏʐ^�łŌf�ڂ���Ă���B���ǂ������ʂ��ȉ��ɋN�����Ă݂悤�B
�q�[�A�����C�ł��d���̂��ƂƎv���܂��B�����ɁA�k�ߒZ�����Ƃǂ����������Ȃ���A�����\���̂��A�����ւ���Đ\�����܂���B���d�b�ł��Ǝv�����̂ł����A���������Ƒ����A�莆�����������悤�Ƃ��Ă��邤���ɁA���ɖ��C�͏�ԂɂȂ�A�����Ɏ���܂����B����邵�������B�M�d�Ȃ��́A�{���ɂ��肪�Ƃ������܂����B���x�̏���W�̈�_��Ђ��Ă����������̂ŁA������ɓ�_���U���邱�Ƃ��ł��Ă��ꂵ���Ƃ���ł��B�h��
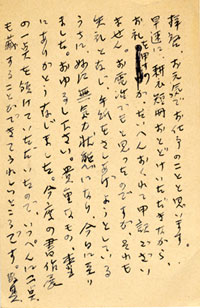
��{���g���g�������ȁi���a38�N6��18���j
�o�T�F�ʉp���H�Q�{����275���s���{�̕M�Ձ\�\������Ƃ��瑺��t���܂Łt�i�ʉp�����X�A2004�N5��25���A�ꔪ���y�[�W�j
�ʉp���H�Q�{���ڂɂ́u1014�@�g�����t���@�ꖇ�@��܁A�Z�Z�Z�~�^��{���g���@���a38�N6��18���@�y��10�s�v�Ƃ���A�����炭1963�N6��18������̂��̂Ǝv����B�����̍k�ߒZ�����Ȃɂ��C�ɂȂ�Ƃ��낾���A�g���̍k�߈����Ȃɂ��ꂪ������Ă���B
�@�J���ЂƂ₷�݁A������A�O���Ă炵���Ȃ�܂����B��T�̓��j���A�Q���̂Ȃ��ŁA�M�d�ȏ���i�q�܂����B���炵���n�ցA�߂Â��Č��A���������Č��Ă��̂���ł���܂��B�K���ȑ傫���Ȃ̂��A���������Ȃ̂łƂĂ�����悢�̂ł��B�����A���o�ɂ��炵�����Ȃ��̂ŁA���I�̒��ɑ����Ă��܂��B�k�߂���̖{�ӂɂ��ނ��s�ׂƂ͒m��Ȃ���B�Ԏ��������ꂽ���Ƃ�����т��܂��B
�Z���\������
�@�ǐL�B
�@��A���������䐷������̂ł��傤�B�Q��Ȃ������̂��c�O�Ɏv���܂��B���čŋ߁A��{���g����A�k�߂����
�@�S���ɍ�������̉Ԃ�����
�̒Z�����������܂����B�܂������\�グ�ĂȂ��̂ŁA����ɂ��莆�������܂��B�����A���N�̊ԂȂɂ����Ă��܂���B�k�߂���̂��d���Ԃ�ɒp�������B
�k�߈����Ȃ́s�Ս��t166���i1963�N8���j�́q��o��r���ɍڂ������́B�u��T�̓��j���v�͂����炭6��9�����낤�i�u�Z���\�����v�����j�ł���j�B��{���g���g���ɍk�ߒZ����͂����o�܂͕s�������A�O�N��1962�N9��10���ɐԍ�̈��ŊJ���ꂽ����o��]�_�ܑI�l���k��i���̏o�Ȏ҂͋��q�����E�_�c�G�v�E�����d�M�E�������q�j�̐Ȃłł��A�k�߂̖n�ւ��߂��銽�k���������̂��낤�B�f�ڗt���́A�g���Ɠ�{���g�Ƃ̌𗬂��M�d�ȏ،��ł���B
�k2020�N12��31���NjL�l
�~�����[�́k���a�o�啶�w�A���o���l�͏��a�o��ׂ�ɂ͊��D�̃V���[�Y�ŁA���͒������q�Ғ��́s�����d�M�̐��E�t�i1991�j�����ǂ������̂��B���̇M�́A�I��Y�Ғ��s��{���g�̐��E�t�i1991�N5��15���j�B�Ҏ҂ɂ��q��{���g���N���r����A�����[���N��E����i�����A��Z�܁`��Z���y�[�W�j�B
�吳11�N�i�����j
12��19���A���h�O�Y�A���_�̒��j�Ƃ��āA���s����k�l�A�����u���݁v�ɐ��܂�B
���a19�N�i���l�l�j22��
12���A���K�m���ƂȂ�֓��R�֓]���A�\�������֔z������B
���a20�N�i���l�܁j23��
�����s�ɂďI����}���B�����B�ɒO�O���F��K���B10���A���쑐��𒆐S�ɎO���F�A�j�M�q��Ɓu�܂�߂�v�����B�����d�M�́u�Q�v�ɎQ���B
���a21�N�i���l�Z�j24��
4���A�����Ɂu���z�n�v�n���A�����B6���A�哇���Y�A����q�Y��Ɓu�c��o��v�n���B11���A�u�܂�߂�v�n���A���l�ƂȂ�B
���a23�N�i���l���j26��
4���A�卂���w�Z�̍��ꋳ�t�ƂȂ�B9���A�c���`�m��w���w�������ȂɊw�m���w�B�u�Q�v���U��́u�����v�ɋ���A���s�^�������݂�B
���a24�N�i���l��j27��
1���A�u�ΎR�n�v���l�B�x��ԉ��j��B4���A�R�w�@�u�t�ƂȂ�B
���a26�N�i���܈�j29��
1���A�㋞�B�u���݁v�����X��\�B6���A������W�w�B�ԐA���x�i�B�ԐA�����s��j���B
���a28�N�i���O�j31��
3���A����o�勦�����ƂȂ�B�o���o�Łu��玕���v�n�݁B
���a31�N�i���ܘZ�j34��
1���A���쑐������B12���A����i��܁B���ݑ�\������ƂȂ�B
���a33�N�i���ܔ��j36��
3���A�u�o��]�_�v�n���A���l�ƂȂ�B
���a36�N�i���Z��j39��
����o�勦���B�����̐ӔC�������E��B�o���w��ψ��ƂȂ�B
���a37�N�i���Z��j40��
1���A�u�ǔ��V���v�S���Ŕo�d�I�҂ƂȂ�B3���A���w�@��w��w�@�C�m�ے��C���B10���A�w�Γc�g���x�i�����Ёj���B
���a38�N�i���Z�O�j41��
6���A���{���|�Ƌ������ƂȂ�B�ꒃ�܂菬���w���o��I�҂ƂȂ�B
�q��{���g���N���r�ł́A�i�c�k�߂Ƃ̐ړ_�������Ȃ����A�����d�M�A���쑐��A�x��ԉ��j�A�Γc�g���Ƃ������g�������ǂ݁A�e���o�l�����̖����������Ă���B�g���ɂƂ��ē�{���g�i1922�`1988�j�́A�s�B�ԐA���t�̔o�l�ł���Ɠ����ɁA�����u���݁v�̎傾�����̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�g���͂����ʼn�������Əo��A�y���F�Ɖ^���I�ɏo������̂�����B
�� �ˎ闝�҂̋g�����U���I�W�s�˒�ɂāt���v���Ђ́q���̐X���Ɂr�̈���Ƃ��Ċ��s�����̂��L�O���āA�W���q�˒�ɂār�i��2400���j�̍Z�ق��L���B ����͕]�߂̑O�i��Ƃł��邪�A�{�т̕]�߂͍e�����߂čs�Ȃ������B�Ȃ��A�g�������M���e�i�G�����e���e�j�͖����ł���B
�����o�F �q�˒�ɂār���o�́A�ђˏ��X���s�̎G���s���㎍�t1962�N1�����i��9����1���j�́q���l�̎U���r���Ɍf�ڂ��ꂽ�i8�|25���l& times;21�s��i�g�E�r�� �݁A�l���`�܁Z�y�[�W�j�B�ڎ��ɂ͉��g�Łu48�@�g�����@�����l�̎U���E�˒�ɂāv�Ƃ���A�q�ҏW�m�[�g�r�Ɂu���ė��s�̂��́A�V�N������̊��ɂ� �āA����Ƃӂ�Ă������B��́A��k��l�ʂ̂悤�ȎU����i����тÂf�ڂ��Ă������Ƃɂ����B���̃g�b�v�o�b�^�[�͋g�����ł���v�i�����A��Z�� �y�[�W�j�ƌ�����B
�@�����F�s�g�������W�t�i�v���ЁE���㎍����14�A1968�N9��1���j�́q�������т���r
�̍Ō�Ɍf�ڂ��ꂽ�i8�|25���l�~18�s��i�g�A����`���O�y�[�W�j�B�ڎ��ł͈�s�̂����u���˒�ɂāv�ƃA�X�e���X�N������
��A���̑O�ɒu���ꂽ
�s�����̎��Q�i�̂��Ɏ��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�Ɏ��^�j�Ƌ�ʂ���A�{���͉��ŋN�����ƂȂ��Ă���i�O�̎��Q�͒Ǎ��݁j�B
�@�y�Z�فz������@�ł̎����
���o�����Ђ炪�Ȃ̏������g�p���Ă��Ȃ��������߁u���Ă����v��u����Ȃ����낤���v�������Ƃ��낪�A�����ł́u�����Ă����v�u����Ȃ����낤���v�Ə�
���ɓ��ꂳ�ꂽ�B�g���ɂ��\�L�⎚���̎����́A�u�j�K�e�v���u�ɂ��āv�ɁA�u�S�C�v���u�S���v�ɁA�̓�ӏ��B�ł��傫�ȕύX�́A���{�ł͖����́u��
�ɐ^�̌��f������A���̋���݂肳���āA���̞B���Ȗʖe���݂�̂����A���͎����̐S���D�Ԃ̎��Ԃւ��肽�Ă��B�v�̌�ɁA��s�āu�ł��㉺���犚��
�������̋��̗��j�ւЂ��k�́l�悤�Ɋ�����̔��̖т�����Ă���B�v�Ə��o���ɂ������i�����폜�����_�ł���B
�A�Ċ��F
�g�������z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�N7��1���j�́A���������̋L�Ȃǂ��W�߂��q�T�r�i�ڎ��ł́q�R���̃A���o���r�̂��Ɓu���v�ŋ��
��āq�˒�ɂār����т�������j�̍Ō�Ɏ��^���ꂽ�i10�|39���l�~15�s�g�A�����`����y�[�W�j�B�����ł͖����Ȃ��玍��i��
���Ĉʒu�Â����Ă�
���{�т́A����ȍ~�u���z���U���v�̈����ƂȂ�B
�@�y�Z�فz�@����A�ł̎����
�E�V�N�ȋ��k�́����l�H�ׂ����ĖႦ���A�������͂���������H�킳��ėJ�T�ɂȂ��Ă����B
�E�k��l�́��������Ɂl���N�̒j���Ƃ肢���B
�E���̂����Z��ł���ꏊ�A���̂Ȃ��Ȃ�đ���m��Ȃ���߂����k�Ł��Ɓl�Â�����Ȃ����낤���B
�E���͂��̒j�̂�����ɒu���ꂽ�k�i�i�V�j���傫�ȁl�o�P�c���̂������B
�E����������u���ꂽ�k�i�i�V�j�����߂ɁA�l�ނ�グ��ꂽ�����ȎG�����S���g���������̂ł͂Ȃ����Ǝ��͋^�����B
�E�c�̎d���͏����ɂ����Ă���炵���A�r�[�����k�i�i�V�j���A�l�O�{�̂B
�E�������̑V�̏�Ɍ܁k�i�i�V�j���A�l�Z���k�A���g���l�d������}�G���u����Ă����B
�E���̕���̓A���r�k�����A�l���i�C�g�����A�q���p�̎G���ɂ��ẮA��σG���`�b�N�ȑ}�G�������B
�E�c�͂܂���k�i�i�V�j���A�l�O���؍݂���炵�����A���͖����͋A��˂Ȃ�Ȃ��̂��B
�E�����ڂ��́k�i�i�V�j������l�o�P�c���u����Ă��邩�炾�B
�B�O���F�g�����s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�E�}���p��328�A1988�N9��
25���j�ł͍Ċ��Ɠ��l�A�q�T�r�̖�����
�f�ڂ���Ă���i13��44���l�~19�s�g�A�l���`�܈�y�[�W�j�B�g���������O�Ɋ��s�����Ō�̔łł���B
�@�y�Z�فz�A����B�ł̎����
�E���k�Ɂ��i�g���j�l�́k�A���i�g���j�l�G�ł���A�ʐ^�ł��ꏗ�̗��̂�����Ǝh�k�������l�����̂��B
�������̍Ę^�F ���o���ďC�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�ɍĘ^����Ă���̂͏����̃e�N�X�g�����A���̍̑��ɂ͖�肪����B���j�I�Ӌ`���d��Ȃ珉�o�`�����A�u�� �e�v���߂����Ȃ�{�����쎞�ɓ��肵����ŏI�e�N�X�g�ł���O�����{�ɂ��ׂ��������B�Ȃ��A�{���ɂ͑�{���q�������ꂽ��\�\�u�˒�ɂāv�ɂ��ār �i���o�́s���{�Ǐ��V���t1971�N1��1�����f�ڍe�Ɏ肪�����Ă���j�����^����Ă���A����́u�k�c�c�l���z�̋��̖ʖe�����悤�Ƃ����q���r�̌Ǔ� ���A�S���D�Ԃ̎��Ԃɂ��肽�Ă��Ƒł����鎞�A�\���ҁE�g�����̌��f�́q�����r���ꂽ��̃C���W����ЂƂ̌`�Ԕ���n��o���Ɠ����ɁA�\�����E�� ��A�������̂悤�ɂЂ��グ�Ă䂭�i�������ɋA���Ă����j�\���҂̂��̌��E�����s�܂��Ă��܂����Ƃ��v����v�i�����A��Z�O�y�[�W�j�ƌ��_�Â��Ă���B

��{���q�������ꂽ��\�\�g�����u�˒�ɂāv�r���o�̐蔲���k�g���Ƒ��X�N���b�v�u�b�N�̃R�s�[�l
�{ �т́ABurton Watson�ҁE�����h����ɂ��p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�kthe third volume in the Floating World Modern Poets Series�l�t�iChicago Review Press�A1976�j�ɁqOn the Jetty�r�Ƃ��ĉp��Ă���i�����A��Z�O�`��Z�܃y�[�W�j�B���s�������琄���āA��{�͏������Ǝv����B�`�����u�����Ƃ������тꂽ�����Ɏ��� �c�Ƃ��Ă����B�v���gI was with D in a desolate fishing village called Sajima.�h�Ɩ�Ă��邱�Ƃ���A�����̓T�W�}���Ƃ킩��i��҂͋^��̉ӏ��������Β��҂ɖ₢���킹�Ă���A�����ɂ����҂̈ӌ������f���Ă� �悤�j�B�Ƃ���ŁA���̋�������̓I�ɂǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ��B�啔�̒n�����T�ɂ��Y������n���͂Ȃ��A�O�Y���������i���{��s�j�̍���[�T�W�}]���Ƃ��v ���邪�A����ł͌��ߎ�������B
�k2006�N4��30���NjL�l
�`���ŐG�ꂽ��ˎ闝�҂̋g�����U���I�W�́A�������s�˒�ɂāt����s�g�����U�����t�ɕς���āA����3���Ɋ��s���ꂽ�B�{���ɂ��q�˒�ɂār�����^����
������A�Z�ق�NjL���Ă����B
�C�l���F�g�����s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�t�i�v���ЁE���̐X����E06�A2006�N
3��1���j�ł͍Ċ��E�O���Ɠ��l�A
�q�T�r�̖����Ɍf�ڂ���Ă���i13.5��41���l�~15�s�g�A��܁`���y�[�W�j�B�����܂ł��Ȃ��A�g���f�㏉�߂Ă̔łł���B
�@�y�Z�فz�B����C�ł̎����
�Ȃ�
�s�g�����U�����t�ŇB�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�ƈٓ��̂���ӏ��́A�g�������O�̏�������{�ɂ���Ă���͂�������i�ȑO�A���s�҂̏��c�v�Y����
�Ƃ��b����������A��{�ɂ��Ă����������j�A����ꂪ�Ȃ����Ƃ́A�B�ƇC�̖{�����{�т̍ŏI�`�ł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B
�ȑO�A�s�͌����f�j�S��W�t �i���ȎЁA2003�j�ɂ��ď� �������A�����ɐ旧�S��ƂƂ��ās�͌����f�j��W�t�i���ȎЁA1997�j������B�����؍K�j����̏��]�i���{�o�ϐV���j�Ŗ{���̊��s��m�������A�g�߂� ���X�ɂȂ��A���ȎЂɒ������ē��肵���B�{���ɂ́q�͌����f�j�^�����r�Ƃ������y�[�W�̋��݂��݂��t�����Ă���A�g�����́q���f�j�̔��w�r���������� ����B�����A�������ڂ����̂́u�g�����E�i�c�k�߁u�w�����x�̏\��v�k�c�c�l�i����1987��15�E16�������w�����x���W�����ȎЁj�v�Ƃ����L�q���� ���B���Y����o�啶�w�قق��ŒT��������������Ă��炸�A�͌���������ς킹���ās���ȁt���̃R�s�[�����傤���������B�g���́s�����t���玟�̏\���I�� �ł���i�s���ȁt15�E16���A1987�N11��1���A�܃y�[�W�j�B
�N���܂���͂ɓM����ߖ�
���̂��ɂւ�挴�̒��d�M����
�~係��̐��l�ܓ����ꂽ����
�V�����������݂Ė������͂���
�ĂӂĂӂ�V��㮍�[���₭]�悬���
ꔂ��ȓE�݂Ē��ނ�B�̉�
儒��ǂ̎}������Ȃ肫
����݂����ꂵ���̉�
���قނ炳������[���ق���]�����N�S����
�j�̉Ԃ݂Ȑ����߂����₵����
�͌�����͓����́q�����^�r�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�~���~��
�@�g���������u�����̏\��v�e�͂��B�\��̂Ȃ��Ɂu㮍��v�̋叴�o������݂�B���̏��M�Ɂu�c�����т������X�A�M�Z�ɂ͂�����肠��܂��B�u�k�߂� ���v�ɂ́A���A�����ŁA���b���o�����A�c�O�ł����B���āu�����\��v�����ɓ����������܂��B��ǂ��āA�O�\�Z��𒊏o���A�قڈꂩ����ɁA�ēǂ��Ă��̏\ ���I�т܂����B��������G�Ⴞ�Ǝv���܂��B�̂Ă����������f���܂��B
�@�����Ђɂ�鎀����ݔ����Ę�[��]
�@���̝ꈢ�C���̈�w�����ӂ��
�@��̖����Ɋ��q��ꂵ��X��
�@�̋��⍡���������₭��͌K��
�@�t�[���ӂƒ��k���₵����
�@����E�ӓV�Ɉ����B����
�@�����͏������w�y���F��x���A���̓�\����ɍZ���ɂ������A�������ق��Ƃ��Ă���Ƃ���ł��v�Ƃ���B�i�����A��O�y�[�W�j
�u�\��̂Ȃ��Ɂu㮍��v�̋叴�o������݂�v�́A�͌����s���ȁt�A�O�ƈꔑ����̌Ζk�̗��̋A�r�A�Ԓ��Łu�k���܂��܁u㮍��v�̘b �ɋy�ԁB�w�� ���x�̋�u�ĂӂĂӂ�V��㮍��悬��v�́A�o���Ă��Ǝv�ӂ̂����N���J�߂Ȃ��˂ƁA�ЂƂ莩�]���ċA��v�i���O�j�ƁA���̑O�̓��^�ɂ���̂��� ���́B�g�����s�y���F��t�i�}�����[�A1987�j���u���̓�\����ɍZ���ɂ������v���͔̂������낤���i���Ȃ݂Ɂs�y���F��t�̊��s�͋㌎�O�Z���j�B�� �̂悤�Ƀ��C���̋L���͂�������A�n��̕��䗠���_�Ԍ��邱�Ƃ̂ł���̂��A���J���ꂽ�g�������Ȃ̑�햡�ł���B

�s�͌����f�j��W�t�i���ȎЁA1997�N9��15���j ���Ɩ{�̏�̋��݂���
���ċg�����̎���u���܂Ƃт����鏭���̔��z�́^�x���ŗ�́^�K���ʂ��Ō���v�i�q�ቹ�r�F�E14�j�ƁA�W�F�C���Y�E�W���C�X�s�� ���V�[�Y�t�� �q�k13 �i�E�V�J�A�l�r�̈�߂��r�������Ƃ����邪�i�q�u�u �����R �̂�̃i�E�V�J�A�v�r�j�A �����ň��p������{�͊ےJ�ˈ�E�i����E�����Y���s�����V�[�Y �U�k���E���w�S�W �U-14�l�t�͏o���[�V�ЁA1964�j�������B�g�������̖Łs�����V�[�Y�t�Ɂi���߂āj�G�ꂽ�\���͋ɂ߂č����B�����ċg�����q�k13 �i�E�V�J�A�l�r�Ɋ��҂������낤���Ƃ��z���ɓ�Ȃ��\�\�Ƃ����̂����̎�|�������B�Ƃ��ɋg���́A�W���C�X�Ɋւ��ċ�̓I�ɂȂɂ������̂����Ă��Ȃ��B �B��̗�O���s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j��1939�N5��23���u�w�V�S����`���w�x�����o���ēǂށB�Ȃ�Ƃ��w�����V�C�Y�x��ǂ܂�� �������A��Ŏ~�߂�v�i�����A�l��y�[�W�j�Ƃ����L�ڂł���B���́s�����V�C�Y�t�́s�V�S����`���w�t�̒��҂ł���ɓ����ق���́s�����V�C�Y. �O,��ҁt�i��ꏑ�[�A1931�E1934�j���낤�i�����Ƃ��s�����V�C�Y�t�͂��̌�̓��L�ɂ͓o�ꂵ�Ȃ�����A�g�����ʓǂ������ǂ����s�����j�B�s���� �V�[�Y�t�̖M�Ɋւ��ẮA�������̐V���s���a���N�́w�����V�[�Y�x�t�i�݂������[�A2005�N6��16���j��ǂނɔ@���͂Ȃ��B���͂����Ŗx����{ �́q���S�Ɣ��r�i1925�N���\�j�\�\�s�����V�[�Y�t�̓��I�Ɣ��̎�@����{�ɏЉ���ŏ��̕����\�\�ɏ��߂ĐG��Ĉ�������B����́q���S�Ɣ��r������ �Ȃ��炱�������B
�@���̌`���k���I�Ɣ��̂��Ɓl�ɂ��A�u��ꓙ�̐S���ł����[�����ɑ��̊ԋN������v�O���\�\������ꓙ�̈ӎ��� �ɐ���ď��� �邻�̏����̎v�O�\�\�� ���E���}��������̂܂܂ɁA�R�����葁���\�����邱�Ƃ̏o����\�������ʂɕ��w�ɗ^������v�B����́A����ɂ���č�Ƃ��A�u�l�S�̉���ɂ܂ʼn��� �čs�āA�����ɗN���o�邠����v�O���A�ӎ��̊������ʈȑO�ɂ��̂���̂܂܂̎p�ɕ߂ւ邱�Ƃ��\�Ȃ炵�߂�₤�Ȍ`���v�ł���B�i�����A�Z�� �y�[�W�j
�g
���͗B��̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�i1967�N���\�j�Ɂu�������ӎ��̂Ȃ���͒N�̒��ɂł��L���ɗ����B������~���邱�Ƃ�����A���Ȃ킿������
��s��s�ɒ蒅�����邱�Ƃ��B���������C���[�W�����̂܂܂����ǂ邱�Ƃ���ł���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�����y�[�W�j
�Ə����Ă���B�g������O�ɖx����{�����ǂ��Ă������Ƃ́s���܂�͂����L�t���Ђ��Ƃ��Ζ��炩�ł���A���сq�ʕ��̏I��r�i�D�E2�j�́u���I�Ɣ�������
�������v��q�O�d�t�r�i�F�E17�j�́u���̖�̃��[���}���v��q���́\�\�Ǔ��E���e���O�Y�搶�r�i�J�E13�j�́u�]���̈ӎ��̗������v�Ȃǂ̎����z
�N����ƁA�g���́A�Ƃ�킯�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�̋g���́A�x���́q���S�Ɣ��r�ɕ���āu�ӎ��̂Ȃ���v�����Ȃ̎��@�̏d�v�ȗv�f
�Ƃ��Ă���悤�Ɏv�����̂ł���B���̂Ƃ����@�́A���̋Z�@�ł�����͎��l�̐��E�ςł���B
�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�Ɏ��^����
���߁s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ�鏑����
��i�������ĊԂ��Ȃ����A�s���a���N�́w�����V�[�Y�x�t�ɓo�ꂷ�鏑���Ƌg���́u���a���N�́v�Ǐ��X���͂��Ȃ�d�Ȃ��Ă���B
����炪�s�����V�C�Y�t�ȊO�őo���ɓo�ꂷ���ȏ����ł���B����Ɋւ��č��́A���炽�߂č��ڂ�݂��ďڏq�������q�g�����ƃ��_�j�Y ���r���A���� �O�̖ʂ���l���邤���ł܂��Ƃɋ����[���A�Ƃ��������Ă������B
1958�N�A39�̋g�����́q�r�i�C�E12�j�A�q��́r�i�C�E13�j�̂��ƁA���ю��q�����r�i�C�E19�A�[��189�s�A�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1958�N7�����j�\�����B���сq�����r�̐���ߒ����߂����āA�g���͎U���q�u�����v�Ƃ����G�r�i�s�����C�J�t�k�y�Ёl1971�N12�����j�������Ă��邪�A����ȑO�ɂ��q�����r���Ę^�����ۂɕt�������͂ŐU�肩�����Ă���B���́q��i�m�[�g�r�̑S���������B
�@�u�����v�ɂ͐���̋�Y�ƁA�ЂƂ�̏��ւ̈���[�߂��v���o������B����͈��ܔ��N������\�O���̖邾�B��Ƃn�̉ƂɁu�����v�̉������������āA�ޏ��Ƌ��ɔ������B�ڂ������~�̏������Łu�����v�̊������߂������B�ޏ��͂n�̉Ƒ��ƃA�g���G�ŗV��ł����B�ނ���ҋ@���Ă���̂��B���̈�����o����Ɣޏ����Ăя����̂B���M�����̌��e�ő��l�ɂ͔��ǂł��ʂ悤�Ȃ��̂��A�ޏ��͗v�̂悭�܂Ƃ߂��B�����̖�܂łɍŏI�̈�����̂����݂̂ɂȂ����B�ޏ��̏��������c�ɂ���āA�����̎����݂邱�ƂɈ��̐��y���Ɨ�Â����ۂĂ��B���ꂩ���T�ԂقNjꂵ�݁A�㌎�Z���̋łɍŏI�̗����ł����B�ꐇ�����Ȃ����������܂��疰��Ȃ��B���ĂȂ������ƍV���̂����Ɍ{�̖��̂����B�����Ă����ޏ������ɂ��Ȃ��̂������䂩�����B�ޏ����Ђ��ς�������Ă���Ȃ�������A�u�����v�͂����Ƃڂ��̎�����������A�ʂ̂��̂ɂȂ��Ă����낤�B�i���{���|�Ƌ���ҁs���{���W�t�A���惆���C�J�A1960�N1��10���A����y�[�W�j
�q�u�����v�Ƃ����G�r�ƕ����Ă����ǂ߂A�g�����ǂ̂悤�ȏŁq�����r�����������ԑR���鏊�͂Ȃ����A�ǂ��ɂ���Ɏv����_������B�u���ܔ��N������\�O���v�Ɓu�㌎�Z���v�Ƃ������t�ł���B�����͋g���̋L���Ⴂ���A��L���邢�͌�A�ł͂Ȃ��낤���B���ɓE����1958�i���a33�j�N�́q�f�ЁE���L���r�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�j�̋L�q�Ɓq��i�m�[�g�r�̓��t����������̂��i�ȉ��A�y�@�z���̗j���͏��т̕�L�j�B
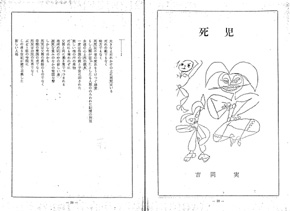
���сq�����r���o�i�s�����C�J�t�k���惆���C�J�l1958�N7�����j�`�����J��
���L�̋L�q��s�����C�J�t�́q�����r�f�ڍ��̔��s�������Ă���A�u���ܔ��N������\�O���v��1958�N5��23���i���j���j�A�u�㌎�Z���v��6��6���i���j���j������ł͂Ȃ����B
�ł͂��̓��t�͂Ȃɂ��B���͎��W�s�m���t�̏e�쐬�̓����������Ɛ�������i�z�q�v�l�k���p�����́u�x�E�v�v�ł���l�̃y���ɂȂ������e�p�́s�m���t�e������ɐ��{����Ă���j�B���̐����𗠏������邩�̂悤�ɁA�u�����l���y���j�z�@�s�Õ��t�v���{�܍��ł���B������A�ԎO���B�x�E�v�ɍ��B�唪�A�k��ɐԂ�v�i���O�A��ꔪ�y�[�W�j�Ƃ���B���łɁq��́r��q�m���r�i�C�E8�j�A�q�����r�Ȃǁs�m���t�̎傽�鎍�т��G���ɔ��\���Ă����g���́A�q���������r�i�C�E16�j�A�q�l���r�i�C�E17�j�A�q�����r�i�C�E18�j�̏������낵���т��܂Ƃ߂�ׂ��A���W�s�Õ��t�����{�삵�A�s�m���t����̗�݂ɂ����Ƃ������Ƃ͑傢�ɂ��肦��B
����u�㌎�Z���v�͂Ƃ����A��1959�N�u�㌎�Z���@���j�@�����玍������A�ߌ�q�́r�����B���������C�J�֓n�����Ɓv�i���O�A���Z�y�[�W�j�Ƃ���A�q�́r�i�D�E9�j�́q�����r�̗��N�A�����s�����C�J�t��10�����Ɍf�ڂ���Ă��邩��A���̂�����̋L�^������݂���āq��i�m�[�g�r�̓��t�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�g������ƈ�Έ�ōŌ�ɂ��b�������̂́A1989�N12��20���ł���B�i���X�g�b�v�E�a�J�w�O�X�̓��������E��̐ȂŁA13������ 14��20�� �܂Ŗʒk�����B���̐܂̃���������̂ŁA�q�g�����Ƃ̒k�b�i1�j�r�� �����悤�ɍĘ^���Ă� �����B
�\�\15�����玩��߂��̎���҂ɍs���\��ŁA���͒��ڍ��̕a�@�Ŏ��Â��Ă���A�����ԑ������i2�L���H�j�Ƃ̂� �ƁB���v�̃R�[�g�ɑ����l�̃Z�[�^�[�Ƃ� �������B�\�\ ������܂܈��p���Ȃ��悤�ɁA��2���i���t�͏��Łj�̒����{�s�Ẳ��t�����������B���Ԃ����i���́A���Ό��y�[�W�ɏ����̂����D���Ƃ��j�ɂ͗z�q�v�l�ւ� �������������ՁB50���̂���2���������ς�o���Ă��āA���̂܂����̌������L�����Ă��܂����R�B�����{�͒ߎR�����ˎ��ɂ��B�y�Ђ̒S�������q���� 杁r�̍s�A�L���ԈႦ���̂����A�������킹�͒S�����Ɨz�q�v�l���B�g������͑f�ǂݍZ���B�u�Q���͏��Z�čZ�Ɠǂ��ǁA�C�Â��Ȃ������v�B���̎��͏��� �����悤�A�Ƃ��������B������⽍��i�u�������Ă�ˁv�j�ƃX�J���x�i�t���R���K�V�̌`�������̒����ŁA��p�I�ȃG�W�v�g�̖��|�i�j������������B�g �����_��2���i�ߎR���Ə�ˎ��ɓn�������Ɓj�B
�s�T�t�����E�݁t��6����9000���B�s�Ẳ��t�͏�����1000���A��L�́q����杁r����������̂�2���B�s�Â��ȉƁt�̏��o�L �^�͐蔲�� �ׂ�킩��͂��B�L�ڂ��Ȃ��̂́A�S���W���ɏo��������B���o�����͂ڂ�����������Ȃ��B
�� �W��҂ނƂ��A���̏��Ԃ͊��⊴���݂����Ȃ��̂Ō��߂�B�s���[���h���b�v�t�́q�Y��i�ނ��сj�r�͍��L�����D�����D�����ƌ����Ă����̂ŁA�����ƌ�� �������k���̖ڎ����e�Q�Ɓl�̂��g�b�v�ɂ����Ă����i�Ō�ɒu�����т͌��܂��Ă����j�B����u�k���Ȃ�w偁l�v�̓}�������i�o�T�́s�����C�J�t���W���̒N ���̕��́j����B
���W�s���[���h���b�v�t�ڎ����e�̃��m�N���R�s�[�i�����e�̃C���J�G�̎w���E�s���͐� ���j�L����ꎁ�͎Ⴂ�̂ɐɂ��������B�ڂ��̎��ɂ��Ă͏����Ă��Ȃ����낤�B
�� ��R�c����2����3���Ɂs���܂�͂����L�t�����s����\��B�ŏ��A�G���p�Ɍ��e�����߂�ꂽ���A���ʂ��炢���Ė{�ɂ��悤�Ƃ������ƂɁB�V���[�Y�̑�1�� �z�{�B�s�K�t���I����Đg�y�ɂȂ��������Ƒ��ɂ́A�u����̌������Ƃ����ɁA��肽�����Ƃ����v�ƁB��������́s���q�t�p���������� �悩�������ǁB
�s�����~�G�[���t�́q�|���m�r�̃R�����݂����ȕ��͂́A�̂т̂тƂ��Ă��Ėʔ���������������Ȃ��B�u�`�N�v�Ƃ͒W�J�~�ꎁ�Ȃ�B
��ш�т̎��͂��������Ȃ���Ȃ����B���ꂩ��͒��ю����U�����B�Ƃ��ׂ��̏��������ĂȂ����B1989�N�̎���́q�_��r �Ɓq����r �i�Ɓq�i���̒��Q�r�H�j�B
�����̋ߍ�͐X�L�O�A�푺�G�O�̂��́B���X�̂͂ڂ�����Ȃ��B�s���܂�͂����L�t�̓V���[�Y�{�Ȃ̂ŁA�����͂��Ȃ��B�� �J���m���s�F�V���F�l�t�̑������i�s���B�s�F�V���F�S�W�t��400�`500�y�[�W�œ�\�����ɂȂ邾�낤�B���ɔłł��������o�Ă��� ����A���܂� ����Ȃ����B�q�� ����ԁr���F�V���Ƃ̏o��̋L�q�͎����ƈႤ�B�����ƌÂ��i�������̊��Ⴂ���낤�A�ƕԓ��j�B�}���ɖ{���ɗ����̂��ŏ����ȁB
�k�����̋g�����_�́l�ǂ̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�̂��킩��Ȃ��B�����ꂽ���̂��Q�Ƃ��Ă��邤���Ɂu���{�v���ł�������̂ł͂Ȃ����B �Ƃ������A�� �������ǂݎ��͖̂ʔ����B
�s�� �ʁt�X�^�C���̓}��������ǂޑO����B�p�E���h�Ƃ��A�����J�̎��l������Ă邵�B���E�I�ɂ݂Ă����W�S�̂ł���Ă�̂͒������̂ł͂Ȃ����B�G���b�N�E�Z �����h���̉p��sKusudama�t��1990�N�ɂ͊��s���B�J�i�_�̗F�l�Əo�ŎЂ��H�@�Z�����h������ӂ��������₵�Ă���̂ɂ͎Q�����B���̓��{ ��łȂ�Č����̂��S�����ׂ������Ŏg���Ă���킯����Ȃ����A���ꂱ��[���l���Ȃ��łς��Ƃ�����Ⴄ����B
���Y���P���̋g�����_�A�s���㎍�蒟�t�ł��s�����C�J�t�ł��A�ڂł��Ȃ������R�B�Ώۂ����e���O�Y������Ȃ�������������Ȃ� ���B
����C���S�W�A���ɂ݂������[����o�邱�ƂɁB���p�o�ŎЂ��}�����A����S�W�̔Ō��Ƃ��Ă͂悭�Ȃ��B�݂�����������B�剪�E ����E������ ������̒�q���ҏW�ψ��Łi���e�������Ă���Ζ��_�E�Ȃ낤���j�B
�˖{�M�Y�̉̏W�́s�����y�t���x�X�g�B�m�肠�����s����`���t����{�������Ă����i�ǂ����˖{���͋g���Ɍ��{���Ă��Ȃ��悤 ���j�B�ԍ������ �̏W�i�s���́t�Ȃ�ށj�͔������тꂽ�B�i�\�\�����̖{�œǂ݂܂����H�j�Ö{�ŒT�����炢����B
�� ���~�q�͓ǂB��O���ȁB�s�R���仁t��s������_�t�B�ނ̓V�������A���X�g�ł͂Ȃ��B�k�����q�Ƃ͐��O���ɉ��Ȃ������B���鎞���A�k���ƍ��삿�� ���������ł悩�����B�ق��ɋߓ����A�t�R�s�v�A��{�C���Ȃǂ��ǂ���ǁB���͂�����؉��[�������āB�Y�⏇�O�Y����P��ǂ�ł���A �����Ɂs�Õ��t�̂悤�Ȏ��������͂��߂��킯�ł͂Ȃ����B���h���Ă��邾������ʖڂ��B�������g�̓Ƒn�I�Ȃ��̂��Ȃ���B����e�����āB��������� ��ǂ�ς�邵�B
�s�Õ��t�͉�Ђ�60���قǔ��ꂽ�B�܂����������Ȏ҂̎��W����������A�������Ă���̂�100�����炢���B�c�����X�Łs�Õ��t�� �������̂͐� ���B�s�m���t�͑厖�ɂ��ꂽ����A�������Y��Ȃ̂���������܂������������A�����͏��������ɂ��Ƃ��܂��傤�B
�\�\�s�m���t�i�ɔ��łȂ����ߏ��������j�Ɓs�a���`�t�A�s�_��I�Ȏ���̎��k���y�Łl�t�Ɍ��提�����Ă��������B�u�l�̖{������A ���s����ƍ� ��ˁv�ƃp�[�J�[�̍��ŁB
�k�̊ہk�ߑ���p�فl�̃f�����H�[�W�͊ς����A�u��̉�Ɓv���Ƃ킩���Ă��܂��āB�O�͍D������������ǁB���܍D���Ȃ̂́A�o�� �`���X�ƃN���\ �E�X�L�ƃx�[�R�����B�q���E�H�̊G�r�͂��́k�����g���_�ň��p�����l�t�B�j�̊G�B�s�݂Â�t�Ŋς��̂��ȁB
�k�b�����������C�g���Ȃ���A�g������̌����������������l�����S���Ă���̂��ւ����Ȃ��B
���͐��O�̋g�����Ɛ�����قǂ�����������Ƃ��Ȃ��B�c�O�Ȃ��ƂɁA�g������ƈ�Έ�ł��b�������̂͂킸��2��ł���B���̂����A 1989�N5�� 4����14������16���߂��܂ŁA�a�J�E������̋i���X�g�b�v�Řb�������������܂̃���������̂ŁA�Ę^���Ă������B
�\�\�n�K�L�����������A5��3��13���ɓd�b���ė����������B�z�q�v�l�̐�����Ⴕ���̂ɋ����i�킪���� �Ⴂ�̂��j�B�\�\�������Ă��炤�ׂ��A�P�s���W�𒆐S��6���A���Q����B�@�g�������W�i�v���ДŁj�A�_��I�Ȏ���̎��i���쏑�[�Łj�B�Ẳ��C ���[���h���b �v�D�u�����v�Ƃ����G�i�v���ДŁj�E�y���F��B
70�Ƃ͂����A�a�����Ȃ�đ��I�Ɍ�������Ȃ�����B���낾����W�s���씼���t�� ���傤�ǂ��ǁi����Ȍ��t������� �����āj�A�Ȃ��Ȃ��ǂ�����A200�����炢�����đ�������B�s�i�فt�s����D�t�̏�����ĐΔԖ�A����_�i��������ɁB
����⽍��� �����Ȃ����A�Ⴂ����B���ł͐��e���O�Y�̂��̂��ǂ��B���݂������Ƃ�����B����S����i�c�k�߂ƂȂ�Ƃ����v��������B��[�N���ȂA����炵 �����炢�̂����邯�ǁB���Ƃ͎u�꒼�ƁB���e����̐F����2�������Ă��āA�����鏈�ɏ����Ă���B�}�����[�̉��x�߂��̕��w�S�W�̌��G�̂��߂̎�ւ��A�� �W�S���̐l������肤�����B���ƁA�O�����������̂��߂̂�����ǂ�����B
�i�V���s�ł̐��e�W�k��o�l�̘b�̂��Ɓj���e����ȊO�ł͂Ȃɂ�ǂނ́H�\�\�Y�ł��B
�Y�A���e�A�ڂ��Ɨ��Ă�A����ς�B�\�\�������ƕ��i���F�B
���������Ă����B�\�\�ŋ߂͑�]���O�Y�B
���̐l�͍l�������������肵�Ă��邩��B
�G�́A�{�̂��߂̃J�b�g���`���Ȃ��B�i�c�͂̊G�拳���œ߉ϑ��Y�ȂƏK�������ǁA�����ɂ�߂Ă��܂����B�����̈˗��́u�J ���@�[�͎� �Łv�Ƃ��w�肪�����āB�J���[���̂͋��ȂB
�s���[ ���h���b�v�t�̑���́A���e����10�N���炢�O�ɖ�����J�b�g���q���E���ꎁ�Ɏg�킹�Ă��炨���ƁB���̉��F�̓\��O��́A��������R�c����̔��� �������W�̑ю��B������݂̕\���̕z�͂������ޗ��������B1500���ł����ƌ������̂ŁA1000���ł�1200���ł����邾���ŗǂ���A�ƁB�R �c�Ƒ��k���Ė{��12�|�g�ŁA�q�f�����сr����10�|�ŁB�s��ʁt��2000���ŁA�T�C�Y���傫����������e�ό`�ō̂�邾���傫�����悤�Ƃ����B�\���z �͔w�ɂ����g���Ȃ��������ǁB�s��ʁt�̕\���̎��F�̎��̓C�^���A���B���{�ŊςāA�R�c�Ɋm�ۂ��Ă����Ă���Ɛ�ɗ��B
�����͓ǂ܂Ȃ��B
�� ���������̂́A�@��肪�u��O�̕��m�v�Ƃ��Ă̐�킴�镺�m�B�t�B�N�V�����̂���U���������H�@�A�������́A�Z�����̂��܂��ю��A�̂ǂ��炩�B�q�� �̂���̘b�͂��łɂ��낢�돑��������A���������B�F�V���F���Ƃ��u�������́i�u�����V����s���`�����݂����Ɂj�B�����ق����ǂ��v�u�������A�������v�B ���͎q���̂���̂��Ƃ�����������ӔN�̏������������A�ƌ����F�l�����邯��ǁB
�s�y���g�n�E�X�t�����}�ɂȂ��Ȃ����݂����B�\�\�o�Ō��̍u�k�Ђ̎В����Ђ̕��j�ɏ������Ƃ̂��ƁB
���m�Ô��p���O���ŋ��\���������̂��A�߂�������������B�����ă��A���ȂB�X�̎�l�͓S���ƌ��������ǁA��ɋ������t���Ă� ��������\�� �낤�B���\�́A�Γc�p��Y�s�����Y�̕�t�œǂ����B���V�����Ɠ������X�ŁA�����r�Y�����ʂ̂��B
�\�\16���߂��A�P�O�X�̑O�܂œ�������~��Ă��ĕʂ��B�ْ��̂��܂�A�ُ�ɔ���B�S�g�ɂ킽���J���Ȃ�B
�� ���ȉ���͉����Ȃ����A�ŏ��́u�n�K�L�����������v�́A���N4��25���Ɋςɂ������s�i���̗��l ���e���O�Y ���E�G��E���̎��Ӂt�W�i�V���s���p�فj�̊��z���������G�t���ɑ���ԐM�B���W���ꌔ�ɂ́A���e���g���́s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j�̂��߂ɕ`���� ���悪�g���Ă���B
 �@
�@
�s�i���̗��l ���e���O�Y
���E�G��E���̎��Ӂt�W�i�V���s���p�فA1989�N4��1���`5��14���j
���ꌔ�Ɛ}�^�̕\��
�g�����̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�͊����̏͂ɑ��╪���܂Ƃ߂Ď��ڂ��Ă���A���̍Ō�Ɂq�u���\�I���сv�G���r�i���o��1986�N9���́s�G�������~�G�[���t5���j��u���Ă���B���Ȃ킿���z�W�{���̕�������ł���B�����ł́q�u���\�I���сv�G���r�́q�Q ���̎��r���肪����ɁA�g�����ƃI�N�^�r�I�E�p�X�ɂ��čl���Ă݂����B
�@���͂��炭�O����A���L�V�R�̎��l�I�N�^�r�I�E�p�X�̍�i��ǂ�ł���B�U���́w�|�ƒG�Ձx�̎��_�I�ȃG�Z�[���悢���A�����C���[�W���N���ł��炵���B���āu���̎��v�Ƃ����Ȃ����|�[���E�G�����A�[���̃G���`�b�N�Ȏ��т�z�����ׂ�B�������������Ȃ��̂ŁA�p�X�̎�����I�B���́u��̂��炾�v�͒Z�����̂����A��̓T�^���Ǝv���B
�@�k�c�c�l
�@��N�O�̏H�A�I�N�^�r�I�E�p�X�v�Ȃ����������B���͐��l�̎��l�Ƌ��ɏ�����āA��[���k�������Ƃ��������B�c�O�Ȃ���A�p�X�̎��͂܂��l�\�]�т�����o����Ă��Ȃ��B�������A����������i�A�G��ŁA����ȖɈ˂��āA�p�X�̎��Ƃ̕З������������B���͂��̂��Ƃ�`���A�Ƃ��ɒ����u���v�Ɋ��������ƌ������B�p�X���͔����Ȃ���A��ϋ�S������i�ŁA�u���E��䶗��v�ƃ}�������́w鍎q�ꝱ�x�ɐG�����ꂽ���̂ł���ƁA�������B���������u��]����L���v�̂Ȃ��ŁA�p�X�́w鍎q�ꝱ�x���ɘ_���Ă���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�O�Z�܁`�O�Z���y�[�W�j
�u���\�I���сv�ŗ�؎u�Y�N�┒�������A�˂��ߐ����ɓ���C���̎��Ɍ��y�����g���́A�u���̎��v�ɂ��čl�@���͂��߂��Ƃ���ŁA�Ȃ����G�����A�[���ł͂Ȃ��p�X�̎��������Ă���B�������s�G�����A�[�����W�t���苖�ɂȂ��Ƃ����̂͌����ɉ߂��܂��B�p�X�v�ȂƊ��k�����g���ɂƂ��āA�u���̎��v�̓p�X�̎��łȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B��́q�Q ���̎��r�̈��p�Œ������������́A�p�X�̎��сq��̂��炾�r�S���Ƃ��́u�i�K���ꔎ��j�v�Ƃ����N���W�b�g�ł���B
�g���ƃp�X�̊W��`���镶�͂ɁA�ѓ��k��́q�p�X�čl�r������B�u�S�F�g�����̎��W�w��ʁx�i�p�X�̗����������l�N�̊��s�j�́A���̊����̊K�i��̑g�ݕ����炵�Ă��p�X�́w���x��A�z�����邪�A�����Ƃ��ċg���́A�p�X�́w���x�ւ̊S���킽���Ɍ�������Ƃ��������B�u�w���x�ˁB�p�X�́w���x������ˁv�B�g���͌����Ď��͓I�Ɍ��Ȃ��B���ꂾ���ŏ[��������^���Ȃ̂��v�i�s���㎍���Ⴉ��������t�݂������[�A1994�A��܌܃y�[�W�B���������W�s��ʁt��1983�N10���̊��j�B�����ǂނƁA�g���̓p�X�́q���r�ɐG������ās��ʁt�̎��`���̑������悤�Ɏ��邪�A���͂����������G���������낤�B�g�����u���͂��炭�O����A���L�V�R�̎��l�I�N�^�r�I�E�p�X�̍�i��ǂ�ł���v�Ə����u���炭�O�v�����Ȃ̂����m�ɂ͂킩��Ȃ����A�g�����s��ʁt�̎��`���u���Ƃ̉�������u�y���v�̂悤�ɎU��߂��A�����Ă݂�u�����v�̂悤�Ȃ��́v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A��㎵�y�[�W�j�ƒ�`����Ƃ��A�q���r�͂��̐��F�̂ЂƂł͂��낤���A���z�̌��̂��ׂĂł͂Ȃ��悤�Ɏv����B

�I�N�^�r�I�E�p�X�q���r�k�ے���l�i�c��m�ҁs���E�̕��w37�k���㎍�W�l�t�A�W�p�ЁA1979�N2��20���j�`���̕���
�����M����s�|�ƒG�Ձk���e���A�����J���w�p��12�l�t�i�������s��j��1980�N1���ɏo�Ă��邪�i���������q��]����L���r���o�́s�C�t1978�N3�����j�A�g������������ǂ̂������R�Ƃ��Ȃ��B�͂����肵�Ă���̂́A�I�N�^�r�I�E�p�X�A�剪�M�A�a��F��A�g�������A�����ċg�����o�Ȃ������k���1984�N10��30���Ƃ������t�ł���i���ی𗬊���̏����ŗ��������p�X�Ƃ̍��k��B�ʖ�͖�J�����j�B�g���͂���ȑO����p�X�̍�i�ɐe����ł����ɂ���A���߂Ă��̕��ƂɐG��Ȃ��������Ƃł��낤�B���k��q����Ǝn���r�ŁA�g���̓p�X�Ǝ��̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���B
�g���@�Ƃ��낪�p�X����̎��͔��Ɏc�O�Ȃ���A���{�ɂ͌\�т��炢������Ă��Ȃ���ł��B�ŁA�l�͒Z�������ɁA�D���Ȃ̂͂��������ł�����ǂ��A�����ǁA���Ƃ����Ă��u���v�Ƃ������̉ߌ��Ȕ��������͂ǂ�����o�Ă����낤���ƁB�Ƃɂ����A�|��œǂ�ł����̂��������炵���ł��B
�p�X�@�i���S�[���Ɂj��ςł����B����͓�������B�܁A���ۂ̂Ƃ���A���Ȃ�Č����Ă��炷�珑������̂��Ⴀ��܂��B���Ԃ̌`�͔��ɕ��G�ł�����ǂ��A��͂艹�y�̉e��������܂��B�����ĂƂ�킯�֑ɗ��̉e���������B��ŕ���������ł����A�֑ɗ������t�ō�낤�Ƃ��Ă���ł��B�l�̃p�[�g�ɂ킩��Ă��āc�c�B��ԓI�Ȏ������݂��̂ł��B
�g���@���{�ł́w���z�̐x�͖�Ă��Ȃ�����ł�����ˁA�l�Ȃ͓ǂ߂Ȃ���ł����ǁA�܂����ꂩ��{���Ƀp�X����̎������{�ŏo��悤�ɂȂ�Ǝv����ł���B����ŁA�U���͂��������������̂��o�ł���Ă邵�A�p�X����͍K���ȕ����Ǝv���܂��B�F������ł��B�Ƃɂ����A�w�|�ƒG�Ձx�A���ꂩ��w�傢�Ȃ镶�@�w�҂̉��x����ς悢�Ǝv���ĂˁA�킽���͂�������A���Y���ɏ悹���ēǂ݂܂����B�i�s���㎍�蒟�t1985�N1�����A�l���`�l��y�[�W�j
���̂��ƁA�������j��s�傢�Ȃ镶�@�w�҂̉��t�i�V���ЁA1977�j���߂����āA�Ō����瓯���̖|��̈˗������������A���ԓI�ȗ��R�Œf������a��F�オ�ɔے�I�Ȍ������I����ꖋ�����������ƁA�p�X�̒����q���r�ɂ��Ė₤�Ă���B
�a���@�p�X����́u�u�����R�v�Ƃ�����i�ɂ́A�}�������̉e���͂������܂��B
�p�X�@�������܂��B�}�������̃G�s�O���t���g���Ă܂��B�����}�������������̂͂��������������ł��B��ɓǂ�ł͂�����ł����ǐ[���͕������Ă��Ȃ������B�ŁA���̂������ƕ������Ă��āA����Ӗ��ł̓}�������������u�u�����R�v�ւƓ������B�i���O�A�l��y�[�W�j
�g�����u�c�O�Ȃ���A�p�X�̎��͂܂��l�\�]�т�����o����Ă��Ȃ��B�������A����������i�A�G��ŁA����ȖɈ˂��āA�p�X�̎��Ƃ̕З������������B���͂��̂��Ƃ�`���A�Ƃ��ɒ����u���v�Ɋ��������ƌ������B�p�X���͔����Ȃ���A��ϋ�S������i�ŁA�u���E��䶗��v�ƃ}�������́w鍎q�ꝱ�x�ɐG�����ꂽ���̂ł���ƁA�������v�Ə������̂́A���k��̈��p�����܂��Ă̂��Ƃ��낤�B���ɂ͋g�����p�X�̎����ق�Ƃ��Ɂu�[�����������v�̂́A1983�N�́s��ʁt���s�̂��ƁA1984�N�̃p�X�̗����O�̂悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�����������_���܂߂āA�s��ʁt���`�̐����Ɋւ��Ă͍e�����߂ďq�ׂ����B�������R�ƁA�g�����u���\�I���сv�́q�R �w鍎q�ꝱ�x�r�ŐG��Ă���}�������A�i���푽�l�Ȉ��p���ɂ��Ắj�]�X���F�̓������̎��сA�����ĂȂɂ����g�����g�́q雞�k�j���g���l�r���o�`�Ǝ��W���^�`���r��������K�v������A�ƍ��͊����Ă���B
�g�����ǂu�l�\�]�сv�Ȃ����u�\�т��炢�v�̃p�X�̖͂ǂꂾ�낤���B�܂��q��̂��炾�r�Ɓq���r���܂ގc��m�ҁs���E�̕��w37�k���㎍�W�l�t�i�W�p�ЁA1979�N2��20���j��6�т���������B�g���̑������Ƀp�X�̖M�W�͏o�Ă��Ȃ�����A�G���ژ^�œ����̖���������ƁA�@�����r����q�I�N�^�r�I�E�p�X�����r�i�s���w�t1966�N1�����j��12�сA�A�ے���q��\���W���O�\��сr�i�s�C�t1978�N3�����j��31�сA�B�ے���q�I�N�^�r�I�E�p�X�����r�i�s���㎍�蒟�t1980�N9�����j��27�сA�Ȃǂ��������B���������Ă���ƁA�@�ƇB�A����Ɂk���㎍�W�l�̍��v45�т̂悤���i�g�����s�C�t1978�N3�����̃I�N�^�r�I�E�p�X���W��ǂ�ł��Ȃ��Ƃ͍l���ɂ������j�B
�܂��A�ۏ����v�ďC�A�ؐ������W�E����́s�ߑ㎍�l�E�̐l���M���e�W�t�i�������o�ŁA2002�N6��10���j����A�g �����̎��e�q���w�r�̉����S�����p����i�����A��Z�O�y�[�W�j�B
�@�g���@���i�����`����Z�j�@���̎��e�́A���a�O�\�l�N�\�ꌎ���ɍڂ���ꂽ�g���́u���w�E���l�сv�̒��́u���w�v�ł���B������N�A�w���w�E�x�Ɏ��グ�� �ꂽ���̖ڎ����o���́A
�@�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@���w �@�P�� �@�m��
�@�A�� �@�r�� �@���ِF�V�s���l�̖���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g����
�@�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�ł������B�����ď\�łɘj���Č����������Ă��邪�A�����ɂ́A���u�m���v�u�r���v�u�P���v�͎��W�w�m���x�ɂ�臁�Ƃ���B
�@�������̌ケ�̎��l���听���Ă̎��T�ł́A�����͌Â��A��O���������̖{���������w�Z���ƌ�A���H�A��A�t�v�A�Y��̎��Ɋ�������B
�@�Z�̂���n�߁A���a�\�Z�N���W�ߏ���A�⏑�̂���Ŏ��W�w�t�́x���܂Ƃ߂�B�푈���n�d���Ƃ��Ė��B���ړ��A�ϏB���Ŕs����}�����B
�@���͒}�����[�ɓ��ЁA�O�\��N�w�Õ��x�����s�B�O�\�O�N�ɏo�����̂��A������������ɋL����Ă���Ə������w�m���x�i��33�j�������B���Ɏ��W���� �u�m���v�͌���ƌ����A���̔N�̂g���܂ɋP���B
�@���́w���w�E�x�̌f�ڂɁA�u���w�v�͏������낳�ꂽ���̂������̂ł���B
�؎��̉���ɂ́A�������̌�肪����B�Ƃ�킯�u������N�A�w���w�E�x�Ɏ��グ��ꂽ���̖ڎ����o���́A�v�̍s�ɂ͒E��������
�āA�����炭
�u������N�A�v�̂��ƂɌ��e����̌o�܂��Ԃ��Ă����̂ł͂���܂����B���̈ꕶ�����{����̊�ڂ��Ȃ����ł��낤�Ɂi�ނ��s���{�E�t�f�ڔN�́A���̑O
�s�ɂ���Ƃ��菺�a34�N�ł���j�B����Ɂu�u�m���v�u�r���v�u�P���v�͎��W�w�m���x�ɂ��v�̌����́u�ɂ��v�ł͂Ȃ��u���v�i�����A����y�[�W�B
�����͋����́j�ł���B�g�������������͔̂��H�A��̎��ł͂Ȃ��Z�̂����A�Y�̎���ǂ̂͐�O�ł͂Ȃ����ł���B���W�s�Õ��t�����s����
�̂͏��a31�N�ł͂Ȃ�30�N�ł���A���W�s�m���t���g���܂���܂����̂͏��a33�N�ł͂Ȃ���34�N�̑�9��ł���B�������ׂ��Ȏ�����F��N��̑���
�ȂǁA�ق�Ƃ��͂ǂ��ł��悢�̂��i������ׂ������ɓ�����Δ������鎖���ł���j�B
�̐S�Ȃ̂́A�f�ڂ����̂��g�����̎��M���e�ł��邱�Ƃ��B�ڍׂ͈ȉ��ŏq�ׂ邪�A�c�O�Ȃ��Ƃɖ{���̎ʐ^�ł́q���w�r�͋g�����̎��M�ł͂Ȃ��A�g���z�q�v
�l�̎�ɂȂ���̂��B����Ƃ����̂��g���́s�m���t�ȍ~�A��т��Ď��e�̏�z�q�v�l�ɔC���Ă�������A�����I�ɋg�������т̎��M�̓��e�p���e�͑��݂�
�Ȃ��̂��i���z�Ȃǂ̎U���̌��e�́A���̌���łȂ��j�B
���тɂ�����g�����̕M�Ղ�����̂ɂ������߂ȕ����́A���o���ďC�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�i�v���ЁA1991�j�ł���B�������̌��G�ɂ́q���w�r���M��1959�N����̎��e���Ȃ��A��r���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�܂�������s�ҁs�C���ւ���
�k���M�ɂ�鎌�؏W�l�t�i���w�ЁA1971�j�ɂ́A���сq���E�H�̊G�r�i���\�́s���Y�t1962�N3�����j�̎��M���e���f�ڂ���Ă��邪�A������s���Y�t
�p�̓��e���e�ł͂Ȃ��B�s�C���ւ���t�̊��̂��߂ɐ�p�̗p���ɐV���Ɂi�o�őO�N��1970�N�ɂł��j�����������ꂽ���̂ŁA����u���v�ł���A����
�܂������̑ΏۂɂȂ�Ȃ��B
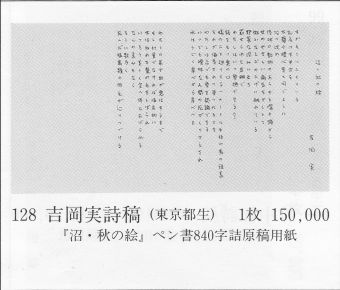
���؏��X�́s�ߑ㎍�l�M�ՓW�t�i�����X�Ï����O�K�W����A1999�N11��26���`12��
25���j�}�^�Ɍf�ڂ��ꂽ�g�������M���e
���͑O�f�s���㎍�ǖ{�t�́q�g���������r�����M����ɂ������āA�z�q�v�l���瑽���̋M�d�Ȏ������ؗ��������A���̂Ƃ��g�����̎��M���e���قƂ�Ǒ��݂��� �����ƂɋC�Â����B�O�̂��߂Ɏؗ������̃R�s�[�ׂȂ����Ă݂����A�g�������M�̓��e���e�͈�_���܂܂�Ă��Ȃ������B�ȉ��ɁA���苖�ɂ��鎍�e�֘A �̎����̊T�v�������B
 �@
�@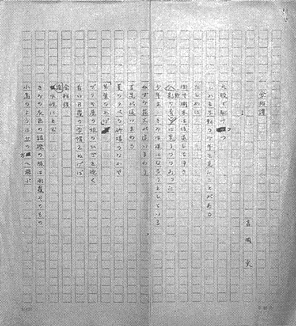
�q����r�i�s���{�E�t1990�N1�����f�ځj�̓��e�p���e�k��1�t�̃R�s�[�l�i���j�Ɓq����
杁r�i�s�C�t1979�N5�����f�ځj�̓��e�p���e�k��1�t�̎ʐ^�Ł��s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t59���i2003�N2���j����l�i�E�j�i��������g���z�q�v�l
�̕M�Ձj
�����̎��e�̕M�Ղ��Ԃ��Ɍ����������ʁA�q���w�r�̓��e���e�͗z�q�v�l�̏e�Ɣ��f�ł���B�ł͂��̎��e�ɉ��l���Ȃ����Ƃ��� �ƁA�Ƃ�ł��� ���A�傢�ɂ���̂��B���܁u�e�v�Ə��������A�����[����������ӏ�����B�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j���ƈ�O�y�[�W�̂����납��4�s�� �ɂ���u�{�p�ҁv���A�ŏ��u�J���ҁv�Ə�����Ă����������Ă���̂��i�����̕M�Ղ��z�q�v�l�j�B�܂����̎ʐ^�ł̂������ŁA���o�u��������v�͌�A�ł� �Ȃ��A���e�ǂ��肾�Ƃ������Ƃ��킩��i���W�ł́u��������v�j�B�ق��ɂ��A�e�͐V���E�V���Ȃŏ�����Ă��邪�A���o���͋������g�p���X�����ɏ����� ���Ȃ��g���Ă��Ȃ��A�Ȃǂ̂��Ƃ��ǂ݂Ƃ��B�����Ȃ��g�����̓��e���e�̌��J�ɂ́A�傫�ȈӋ`���F�߂���B�����A�������s�ߑ㎍�l�E�̐l���M���e�W�t �ł���ȏ�A�{���̏ꍇ�͋g�����̎��M�łȂ��Ƃ�����_�����Ȃ̂ł���i�Ȃ��A�g���̎��e�ɂ��Ă��q�q�g ��i���Ɏ~��r�{���̂��Ɓr���q�g�������W�s�� ���t�e�{�r���Q�Ƃ��ꂽ���j�B
�k2005�N5��31���NjL�l
���x�O���́s�ΐ_�䏑�ьÏ��ژ^�t59���i2003�N2���j�ɋg�����̎��e�q����杁r�i�H�E17�A5��84�s�A�s�C�t�k�������_�Ёl1979�N5����
�k11��5���l�j��1�t���ʐ^�łŏЉ��Ă���̂ŁA�q����r�ƕ��ׂď�Ɍf�ڂ��Ă݂�B���ژ^�̖{���y�[�W�ɂ́u1678�@�g����
���M���e�@
�u����杁v�@640���l�p��5�������B�y�����B�@�ʐ^6�ŎQ�Ɓ@120,000�v�Ƃ���A�g�����̎��M�Ƃ�搂���
���Ȃ��B
�s�ו��S�W�k��29���l�t�i��g���X�A1995�j�́q�Q�l�сr�ɉi��ו��q�ljԗ]���r�����߂��Ă���B����Ɂq�S�F�s�썶�c���N�lj��L�r�Ƃ���悤�ɁA�u�w�f��������x���{����̏��o�ł��邪�A�s�썶�c���Ƃ̌�F����L���畂���яオ�点��Ƃ�����̓Ǝ��̎��݁v�i�������F�q��L�r�A�����A�l�O��y�[�W�j�ł���B���o�͏��a16�i1941�j�N4����5���́s�������_�t�ŁA�̂���g���X�ő�ꎟ�s�ו��S�W�k��29���l�t�i1974�j�Ɏ��^���ꂽ�B�吳6�i1917�j�N12��9�����珺�a15�i1940�j�N4��10���܂ł̓��L�̏��^���琬��q�ljԗ]���r�̂͂������́A���ǂɒl����B
�s�썶�c���N����䭂ƍ��������ӔN���߂ĈljԂƂȂ��ʁB�ljԎq�����Ă�葁������N�̌����͉߂�����B�����������_�Ђ̕ҏS�L�җ���ĈljԎq�I�O�̂��߂ɗ]�����L�̒����q�Ɋւ���L���̏��^�����ށB�ljԎq�̒m�F�ɂ��Y�d�̖��Ƃ��Ƃ�蛖���Ƃ����B�R��ǂ��]�������N�̌�V������ȂęG�z�̍߂��ڂ����͂�T���܂܂ɗ]����������ʂ��邱�ƁT�͂Ȃ��ʁB���a�h���Γו��V�l���B�i�s�ו��S�W�k��29���l�t�A��g���X�A1995�A���y�[�W�j
�g�����̂��Ƃ�������A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�o�ł̌o�܂Ɋւ���ӏ��������B
�@���̓y���F�̈╶�W�w���e�̐�x�̊��s�����ɎQ�悵�A�o�ŎЂ��}�����[�Ɍ��܂�A���ׂ̉����肽�B��N�̏t�̂��Ƃł���B���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A�ݎЎ���̌�y�̒W�J�~�ꂪ�V�тɗ��āA�������܂łɓy���F�֕��������тƁA�U���A����Ɏ�̏������̕��͂������āA�����Ȗ{������܂��傤�A�ƌ����̂������B���ނ��ɂ��킹�A�B���ȕԎ��������̂������Ȃ������B��Ђ̐����Ȋ��ɂ̂��Ă��܂����̂ł���B
�@�u�y���F�Ƃ͉��ҁH�v�N���������v���Ă���ɂ������Ȃ��B���̐l���Ɠ�\�N�̌𗬂�������̂́A���ɂ͂��́u��̓V�ˁv���A�\�S�ɑ����邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�����Ŏ��͎����́u���L�v�𒆐S�ɐ����A�y���F�̎��ӂ̗F�l�A�m�Ȃ̏،����S��A�����ĕ����Ƃ�⼌��I�Ȍ��t���A�K�X�}������A�\�������݂��B�i�����A��l�Z�`��l��y�[�W�j
���镶�l���A�ꎞ����悵������l�ƂƂ��ɉ߂����������̋L�^�������ĒǑP���邱�Ƃ��A�������т��т���Ƃ͎v���Ȃ��B���������̂��Ƃ�����ǂނ�����A�g�����s�y���F��t�̍\�����l����ɂ������ĉו��́q�ljԗ]���r��z�N�����`�Ղ͂Ȃ��B�g���͏��a16�N�̏t�܂���������Ă��炸�A���o����ǂދ@��͂������B�������A���ꂪ�����I�߂���́s�y���F��t�Ɍ��т��������f����ޗ��͂Ȃ��B�����͂�͂�A���W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j�ȍ~���悢���s�ɂȂ����u���p�v�Ɉ˂�|�p�Ƃ̏ё��̋��ɂ̎p������ׂ����낤�B�ł���Ȃ�A�q�ljԗ]���r�Ɓs�y���F��t�̗މ����߂łA���ꂼ��ɓǂ߂Ώ[���Ȃ̂�������Ȃ��B
��
���A�F�{��̋߂�������Ă�����A���܂��܉X��[���܂��]���������B���̂����Ƃɐݒu���ꂽ�F�{�s�ɂ��ē��ɂ́u���ˎ���ɂ͍��̎s�����̈ʒu
�Ɍ�X���������Ƃ��납���X���Ɩ��Â���ꂽ���A�����ȍ~�͒P�ɉX���Ɖ��߂�ꂽ�B�^���a�ɓ����Ă�����āX���C���s���A���݂̋��͏��a�\���N�ɉ�
�ւ���ꂽ�v�ƌ�����B
�����ʼnX���Ƃ����A���c��ɉ˂��鋴�Ƃ��Ēm����B���ẲX��1���ځi���E�n�c��{��1���ځj�Ɛ��O3���ځi���E�䓌�摠�O3���ځj�ƂɈʒu
���A����152���[�g���B�L�������͎ԓ���16.6���[�g���A������3.7���[�g���A�v22���[�g���B�S�����ʐς�3,344�������[�g���B����͎̖��
��p���A�����͍|��ɝi���ŁA�S���̏d�ʂ�2,016.334�g���ł���B
�X���������ېV��ŏ��̋��Ƃ��ĉː݂��ꂽ�̂́A����7�i1874�j�N10���̂��ƂŁi�����˂�����ȑO�́u��X[����܂�]�̓n���v�ł������j�A����
20�N��̉˂������̂��ƁA�H�ʓd�Ԃ𑖂点�邽�߁A����34�i1901�j�N9���ɏC�U���ēS���ɂȂ����B���̌�A�吳12�i1923�j�N�̊֓���k�Ђ�
�������Ď��������߁A�吳15�i1926�j�N7���A�����ɒ��肵�ď��a4�i1929�j�N9���Ɍ��݂̋������������B�ϐk�ω\������Ƃ��A�s�s�̔��ϖ�
���l�����āA3�A�̃A�[�`�`�̋��ɂ����Ƃ����B�ȏ�͎�Ɂs�n�c��j�t�i�����s�n�c������ҏW���s�A1959�N3��15���j�ɋ��������A��������킩���
���ɁA�s�����G�߁t��s�t�́t������������g�������n�����X���́A���݂��˂��鋴�ł���B
 �@
�@
���O���猩���[�i�̉X���i���j�Ɩ{�����猩����i�̉X���i�E�j
��
��L��Ɂq�X���r�Ƃ����Z�я���������B���a20�N��㔼�A�w���ŋ��ŋ������������𓌌���a�@�Ɍ������b�ŁA����������߂�����B�g�������s�Õ��t�̎�
�т��������ł�������̏�i���B�u�l�e�̂Ȃ��X���̉����A�S㊂Ōq�������B���D���O�z�A�g�D�ɉg����ď�čs���B�G�ꂽ�D�̂�������Ƌ���Ɍ���
���̂́A�����ɑ������Â��̂���炤���B��g�͐�������X�Ɍ������A�D�̉����ɔ����ӂ��U���v�i����L��s�~�t�A�W�p�ЁA1980�A�����y�[
�W�j�B
�Ƃ���ŁA�g���́s���܂�͂����L�t�̉X���́A��O�̒n���E�����s�{����X���ɗR������B�s�n�c��̒n���t�Ƃ����E�F�u�y�[�W�ɂ́u�{���v�̐����Ɂu���a
5�N�ɂ͕t�߂̒��X���������X���ƂȂ������A���a41�N�ɁA�u�X�v�����p�����ɂȂ��Z���\���̋K�i����R��Ă��܂��A�̖̂��O�k�{���l����������o������
�ɂ����v�Ƃ���A�g�����Z��ł����X��2���ڂ́A���݂̖{��2���ڂ̈ꕔ�̂悤���i�אڂ���k���̓���`���A�쑤�̐Ό����͌��݂�����`�ƐΌ��ŁA������
�ς��͂Ȃ��j�B
�N���̂�����A�X�����B�e�ɍs�������łɁA�{��2���ڂ�����Ă݂��B�{���͐�̐�ЂŏĂ�������Ă��邩��A�g������炵������̊X���͂��������ׂ�
���Ȃ����A�Ȃɂ����������̓��̓����������ɂ͂������B�u�����s�{����X���v�ɂ��ẮA������e�����߂ď��������B
��ȉƂ̏��X�r��������A�g�������ɂ��̋Ȃ̉�����y���Ȃǂ̎����������肢���������̂ŁA�Љ�悤�B2004�N9��25���A���݂��g���t�H�j�[�z�[�����z�[���Łq��11���ȉƓ�l�W�r�i��ÁE���ی|�p�A���j���J����A�����a�F���Ə��X���̍�i�����t���ꂽ�B�̋ȁq����̔ӎ`�r�͂��̒��̈�Ȃł���B�q��ȉƓ�l�W�r�̈����������p����B�q�v���O�����r�ɂ͂�������B
�u���X�r���^����̔ӎ`�i�u�T�t�����E�݁v���j�i2002�j ���F�g����
Le diner sur l'Herbe�iDe �sCueillir des Safrans�t�j
pour Chant et Piano -Poem par YOSHIOKA Minoru
�q�\�v���m�r���荁�q �q�s�A�m�r���Ì[�q�v
�̐S�̉̋Ȃ����A�����炭�����̃I�[�f�B�G���X�^���ŁA���t���Ԃ͖�6��50�b�B�ӂ���̋Ȃ��K���̂Ȃ����ɂ́A�����ւ�V�N���Ռ��I�ɋ������B�v���O�����ɂ́u�̎��v�Ƃ��ċg�����́q����̔ӎ`�r�i�G�E13�j�S����������Ă��邪�A�قƂ�ǂ̒��O�ɂ͏��߂Ėڂɂ��鎍�тł��������낤�B���X����́q��ȉƂ���̃��b�Z�[�W�r�ɂ��������Ă���B
�u������̔ӎ`�i�u�T�t�����E�݁v���j�i2002�j ���F�g����
�@���̍�i�͋g�����̌��z�I�Ȏ��ɍ�Ȃ����A���ɂƂ���4��ڂ̉̋Ȃł���B�g�����̎��ɂ͉ߋ��̎��̈��p�������U������邪�A���̎��͍�i���̂��}�l�̊G��u����̒��H�v���_�@�Ƃ��Ă���A�S�̂�ʂ��ĐZ������ے���`���̃������R���[����ۓI�ȍ�i�ł���B�̋Ȃ̍�Ȃɂ́A���ɉ��y����Y�킹��d���ƁA���y�Ɏ���t���]�킹��d���Ƃ����낤�B���́A���F�����[�k���u�悸���y���v�ƌ������̂ɕ���āA�u�悸���t�i�p���[���j���v�ƌ��킸�ɂ���Ȃ��B���̉̋Ȃ��܂��A�ŏ��Ƀp���[��������B�u����̔ӎ`�v�̖L���Ȍ��t��O�ɍ�Ȃ���ɓ����Ď��͓r���ɕ�ꂽ���̂́A�₪�Ď��̃C�}�[�W���Ɂu������āv���y���p�������Ă������B�v
�q����̔ӎ`�r�̏�����2002�N5��28���A��8��21���I���{�̋Ȃ̒����A�\�v���m�E���R�T���A�s�A�m�E����a��ł���B�Ȃ����N10��8���A��16��O���[�v�V���{�̋ȉ��t��œ�x�߂̍ĉ����s�Ȃ�ꂽ�i���]�\�v���m�E��x�T���A�s�A�m�E���|���q�q�j�B
�����̉��y���ł��̉̋Ȃ����Ƃ̂��Ȃ�Ȃ��������́A�J�Z�b�g�e�[�v�̉����ɐ[���g���䂾�˂邱�ƂŁA�g�������̂����ЂƂ̂���悤��̌������̂������B

���X�r����Ȃ̊y���̖`���i�̋ȁq����̔ӎ`�r�Ɓq���́r�j
���X����͋g�����́q���́r�A���������3�̎��i���W�s�I���Ɖ����t���j�ɍ�Ȃ��������Ɗy���������������B�̋ȁq���́r��1994�N�̍�ȁi�����͓��N10��8���A�����Y�p��w���t�R���A�\�v���m�E�匴��P�A�s�A�m�E�Βˉ��G�j�B��������̕���1999�N�̍�ȁi�����͓��N10��3���A��11��O���[�v�V���{�̋ȉ��t��A�o���g���E�����z��A�s�A�m�E�����F��j�ł���B
�̋ȁq���́r�͉��t���Ԃ͖�5��35�b�B���X����̓��[���Łu�w������̋Ȃł�����A���͂��������Ȃ����낤�E�E�Ɖ]���t�ق������������Ɍ�����̂ł��v�ƌ������Ă��邪�A�̏��ƘN�u�Ƃ̑Δ䂪�X�������O�ȁq���́r���q����̔ӎ`�r�Ɗr�ׂāu�t�فv�Ƃ����͓̂���Ȃ����낤�B�q���́r�ɂ́q���́r�̓Ǝ��������݂���B������ɂ��Ă��A���̂悤�Ɂq���́r�����߂����W�s�_��I�Ȏ���̎��t�̕]�߂������Â��Ă���҂ɂ́A���������̂Ȃ����蕨�ł���B
�� �{�ŗB��̉��C��^�����s���ׁt�ɋ��鎍�l�̖ؑ��N�炳��A�g�������̒��������f�ڂ��������s���{���㎍�I�t�i�Γ�l���o�ŎЁE������сA 1987�N7���k�ȑ̎��͓��{��̊����ɉ��߂��l�j���ؗ��ł����̂ŁA����������ɓ��{����ؑ�����̖��Q�Ƃ��Ȃ���A�g�������̒��������Љ� ���悤�B

�����s���{���㎍�I�t�i�Γ�l���o�ŎЁA1987�j�Ɩؑ��N���s������
������{���I�t�i���ƔŁA1997�j
�� �����s������ ������{���I�t�i���ƔŁA1997�N3��1���j�́q��҂��Ƃ����r�ŏ����Ă���悤�ɁA�{���́s���{�̎��� 27 ���㎍�W�t�i�������_�ЁA1970�N3��15���j���{�Ƃ������̊C���ł炵���A�g�����O�̊��s�ł͂��邪��҂���ɂ������^��ł���B�s�g���������t�� �L�ڂ����Ƃ���A��{����́q���i�r�i���W�s�t�́t�j�A�q�Õ��r�i���W�s�Õ��t�������сj�A�q�q�́r�i���W�s�m���t�j�̎O�т���ڂ���Ă�����̂́A�l�� �߂́q���w�r�i���W�s�a���`�t�j�͏��̗��Ƃ����G���e�B�V�Y���䂦���A�{���ɂ͌����Ȃ��B���͊ȑ̎��ɕs�ē��Ȃ̂����A���݂Ɂq�Õ��r�̒������i�s���{ ���㎍�I�t�A���y�[�W�j��������{��̊����Ɂu�|���v���āA���Ɍf���Ă݂�B
�Õ��b�����k�ȑ̎��͓��{��̊����ɉ��߂��l�闠�I��M�\�w
�X���o����
�H�V�I����
�ߍ�䙉ʗ��q����
�e��
�ȕs���I�p�ԑ��ڈ�N
��������
�������a�~
�����Y�̓I���y
�e����B�Ő[�w
���ʎ���
�L���[����࣓I����
���ʓI�j���Q�ݘI��
�ʌ��ߎ��l�I�厕
��ېΓ����n�|�����C
�ߍ�����
�ݐ[���I��M��
�ݖ�I���i��
���R���Y��������
��
�S�s�ݐ����͈�
�����̎��ʂ��炾���ł��A�g�������̐�捂ȉ��y��
�Y���łĂ��鋻���[����ł���B
�Ƃ����s�q�g�����r�l�ƍ�i�t��
�]�ڂ������җ����̓��{���͂������i[�@]���͖ؑ�����ɂ���L�j�B�u�g�����i�����`[����Z]�j�^�����N�������܂�B���ď��Ɗw�Z�Ɋw
�сA���ތ�A�������̏o�ŎЂŎd���������B���ݒ}�����[�ŐE�ɂ���[��㎵���N�ސE]�B�w�����x�w��[�k]�x�Ȃǂ̎����̓��l�ł���B���W�Ɂw�t�́x
�i���l��j[����ɁA�g����]�A�w�Õ��x�i���܌܁j[���Ɣ�]�A�w�m���x�i���ܔ��A�g���܊l���j[���惆���C�J]�A�w�Â��ȉƁx�i���Z���j[�v��
��]�A����щ̏W�w�����x[���܋�A���Ɣ�]�Ȃǂ�����v�i�ؑ��N���A�O�f���A��l�܃y�[�W�j�B
�ؑ�����ɂ͂�������A�����T�Җ�Ɉ˂�s�������
���{��㖼���S�ƏW�t�i���ƔŁA1997�j�Ƃ����A�����삩�珬��p���܂ł����߂�����̖����邪�A�g�����̎��͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B
�g�����͎��сq�s�N�j�b�N�r�i�G�E7�j�̖{���Ǝ��сq���[���h���b�v�r�i�K�E10�j�̒��L�ŁA��x�ɂ킽���ăE���W�[�~���E�i�{�R�t�i1899-1977�j�Ɍ��y���Ă���B���Ȃ킿���̓�ӏ��A
�[�Ă̗т̂Ȃ���
�E���W�[�~���E�i�{�R�t�͋L�q����
�������鏭���̎肩��r�ց@����ɓ͂��Ȃ��Ƃ�������薼�Ǝ�̏͋���i�{�R�t�w�������x�i�x�m��`�V��j����ؗp�B
�ł���B�q�s�N�j�b�N�r�͋g�������̒������\����s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�ɁA�q���[���h���b�v�r�̓^�C�g���|�G���Ƃ��ĔӔN�́s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�ɁA���ꂼ����߂��Ă���B�g���̒����������ɂ����Ă��A�i�{�R�t�Ƃ����⏕���������čl���Ă݂邱�Ƃ��L�����낤�B�����ł͑f�`�̂��߂̍ޗ��𑵂��邱�Ƃɂ���B
������b�q�́q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�ɏ����Ă���B�u�g������Ƃ̎G�k�̂Ȃ��ł́A���ł��u�����ŋ߂������낢�{�͂Ȃ��H�@�����Ă�v�Ƃ���������邱�ƂɂȂ��Ă���̂����A���̎�������������A�w�����[�^�x�͂�����ǂ݂ł��傤���A�i�{�R�t���ŋ߂܂Ƃ߂ēǂA�Ǝo�������A����k�N�v�l����́w�Z�o�X�`�����E�i�C�g�̐��U�x�͎��ɖʔ��������������ƌ����A�������͂���ɂ��Ȃ����A����͈��ڂ܂��̂���悤�ȉA�S�Ŋ��m�ȏ����ł���A�ƒN���������̂����A�g������̔����͈Ⴄ�B�^�i�{�R�t�H�@�����A�w�����[�^�x�ˁB�O�Ɉ�x�ǂ݂���������ǁA����͖��Ƃ�ł��Ȃ���������H�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A���Z�`��ꎵ�y�[�W�j�B���āA��������}���قɂ́A���̘Z�̃i�{�R�t�s�����[�^�t����������Ă���B
�@�s�����[�^�k��E���l�t�A�͏o���[�V�ЁA1959�N4��20��
�A�s�����[�^�t�A�͏o���[�V�ЁE�͏o�y�[�p�[�o�b�N�X�A1962�N7��15��
�B�s�l�Ԃ̕��w ��28�t�A�͏o���[�A1967�N7��25��
�C�s�����[�^�k����Łl�t�A�͏o���[�V�ЁE�G�g�����W�F�̕��w�A1974�N9��30��
�D�s�����[�^�t�A�͏o���[�V�ЁE�͏o�C�O�����I15�k�C�̐V���Łl�A1977�N12��15��
�E�s�����[�^�t�A�V���ЁE�V�����ɁA1980�N4��25��
�g�����ǂ̔łŁs�����[�^�t���u�ǂ݂������v���A�m����؋��͂Ȃ��B�����A�푺�G�O�̃��C�X�E�L�������_�i�q�ǂ���̏����U���ҁr�A�s�i���Z���X���l�̏ё��t�A�|�����X�A1969�j�ɂ���s�����[�^�t�ւ̌��y��ǂ��Ƃ͊m��������A�B�s�l�Ԃ̕��w ��28�t�����肪�i�{�R�t�Ƃ̏o���������Ȃ��B�������ȑO�ɋg�����s�����[�^�t��ǂ݂��������Ƃ͂��肦��B�ȂǂƂ����Ă܂��������������������A�@1959�N�̍ŏ��̑�v�ۍN�Y���`���Č��Ȃ������A�ƍl����ق����s���R���ƌ������ق��������B�Ƃ���ŁA�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�̌��G�ɁA����Ǝv�������˂�w�ɂ����g���̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B���́A�O�����w�̕��ɖ{�����߂��I�ɁsO��̕���t��s�킪�����̗d���t�����N�t�ȂǂƂƂ��ɁA�s�����Ɠ{��t�ׂ̗�ɇE�s�����[�^�t�i��v�ۍN�Y��j��������̂��B�g���͂͂����Ă��̕��ɖ{��ʓǂ������낤���B

�q�u���[���h���b�v�v�r���o���i�s�������̎��t1989�N4�����j�̎��ʁk���m�N���R�s�[�l
���W�s���[���h���b�v�t���o������̋g���Ɂq�u���[���h���b�v�v�r�Ƃ�����́A�P�s�{�����^�̐��M������i���k�d�͂����s����o�q���s�������̎��t�ɁA�������M�q���t�̐�r�Ƃ��Čf�ڂ��ꂽ���̂����A�K���ɂ����o������̑I�őO�f�s���㎍�ǖ{�t�Ɏ��߂��Ă���j�B���������͂������B
�@�w�����[�^�x�̍�҃E���W�[�~���E�i�{�R�t�̑�\��ɁA�u��ނȂ�����F���̍\�z�v�ƈ����钷�я����w�������x������B�ꎍ�l�̋�S��\��s�̎��т̓���A���̗F�l���u�𖾁v�Ɓu���߁v�����݂�Ƃ����\���ł���B�i�s�������̎��t1989�N4�����A�O�y�[�W�j
�g���ɂƂ��āq�s�N�j�b�N�r���s�����[�^�t�̃i�{�R�t�������Ȃ�A�q���[���h���b�v�r�͌����܂ł��Ȃ��s�������t�̃i�{�R�t�ł���B���M�q�u���[���h���b�v�v�r�͂��������Ă���B
�@���͂��܂��܂��̎��т�ǂ�ŁA�u���[���h���b�v�v�Ƃ������t�ɁA�S�䂩�ꂽ�B�����ł́u������v�Ɩ�o����Ă���B�k�c�c�l���͂��̌��t�ɐG������āA���\�]�s�̎����������B�i���O�j
���݁A���ɔł����肵�₷���s�������t�����i�x�m��`�V��A�}�����[�E�����ܕ��ɁA2003�j�A�g�����˂����̂͂��̌��ɂȂ����s�}�����E���{��n 81 �{���w�X �i�{�R�t�t�i�}�����[�A1984�N7��5���j�����́s�������t�ł���B�g�����u�G���v�����u�ꎍ�l�̋�S��\��s�̎��сv�̖{���i��Z��`��Z��s�j���A�����ƂƂ��ɕx�m��`�V������B
�i���������́m�A�A�n���������Ȗ��Ȃ��̎��тɂ͉���
������I�m���[���h���b�v�n�ȑ薼���K�v���B�����Ă���A�E�C���I �w�������x���j
�iBut this transparent thingum does require
Some moondrop title. Help me, Will ! Pale Fire.�j
�i�����A��O���y�[�W�j
�u�E�C���v�Ƃ́u�E�B���A���E�V�F�C�N�X�s�A�̂��Ɓv�i�j���B�g���̐��O�Ō�̎��W�̃^�C�g���|�G�����A�i�{�R�t�̏����s�������t���̃W�����E�t�����V�X�E�V�F�C�h�̏��������q�������r�̎��傩��a�������̂��B�u���_����т����c���Ȃ������g���́u���͎�����n��Ȃ��v�ƌ���Ă����v�i���ш�Y�q�q�g�����r��T�����@�\�\�N���E�������쐬���Ȃ���r�A�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�O�y�[�W�j�̂�����A�u�薼�v���i�i�{�R�t�̑n�삵���ˋ�̎��l�̎��т���Ƃ͂����j�u�ؗp�v�����Ƃ��������́A�����₨�낻���ɂł��Ȃ��B�����炭�����ɁA������u����g�������v�̖�肪�W��Ă���B�����@�����A���сq���[���h���b�v�r�̎���Ƃ��Ĉ��p���ꂽ�u��̏͋�v�����Ɍf���悤�B
�k�c�c�l�邪��C�p�^�p�^���𗧂ĂĔ��ł����k�c�c�l�i���O�A��Z�Z�y�[�W�j�H��Ƃ̏o��͉������ꂽ�m�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�n�B�i���O�A�O�Z�Z�y�[�W�j
����Ȃ���̐������U�����ށB�i���O�A�O�Z��y�[�W�j
�x�m��`�V�́q����r�ł��������Ă���B�u�����ɖ�o�����w�������x�i���Z��N�j�́w�����[�^�x�k���܌ܔN�A���ܔ��N�l�ɂÂ��Ċ��s���ꂽ�����ł���B�O��Ƃ͂��܂��܂̋ǖʂŖ����ȍ��ق��F�߂���ɂ�����A���w�ւ̏�M���x���Ƃ���_�ŁA����͖��炩�Ɂw�����[�^�x�Ɛ������������i�ł���v�i���O�A�O���y�[�W�j�B�܂������A�g�������̒�����������v���悤�ȕ]���ł͂Ȃ��낤���B�V�F�C�h�̎��q�������r�̒��ߎ҂����āu�k�c�c�l�G�b�Z�C�W�⎍�W�\�\���邢�́A�����A���Ҏ��\�\�̕\��ɁA�ߋ��̑����Ƃ�����������i���炻�̂܂܂Ƃ�������𐘂���Ƃ����A�������̂�������Ă������������v�i���O�A�O��O�y�[�W�j�Ƃ܂Ō��킵�߂��E���W�[�~���E�i�{�R�t�ɁA�g�����̉p�W�Ǝ��сq���[���h���b�v�r��ǂ܂����������B
�k2017�N9��30���NjL�l
�O��E��́u���̉��f�I���㎍�]�v���q���p���߂�����̃A�N�`���A���e�B�[�ɂ��ā\����g�����_�i���̂Q�j�r�ɁA��ŐG��Ă��Ȃ��g�������q���[���h���b�v�r�i�K�E10�j�̎���̃X���X���f�ڂ���Ă���B�O��̘_�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�c�щ���ⴂ�����
���̋Ȃ����G��w�v
�Ƃ������傪�u�k�c�c�l���̃V�F�C�h���ґz���k�q�������r�l��313�s�ڂɂ���A�u�c�щ���ⴂ������̋Ȃ���趖�w�v�Ƃ������t���g���͈��p���Ă���v�Ƃ��������̎w�E�Ɏn�܂�A�g���̍쎍�@��z�����A�ꊇ�ʁi�u�@�v�j���߂����čl�@���A�u���p�v����s�ׂ̈Ӗ���₤�Ă��āA�X���ɒl����B�O��̂��̘_�l��������Ƃ��Č�������邱�Ƃ����҂���B
�k2021�N5��31���NjL�l
�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t���k2021�N5��31���t�L�l�́s�����[�^�k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1980�N4��25���j�ŐG�ꂽ��ҁE��v�ۍN�Y�i1905�`1987�j�����M�����q����r�́u�w�����[�^�x�̍�҃E���W�[�~���E�i�{�R�t�́A���̏��̊����ɂ݂����珑���Ă���B�v�i�����A�l�����y�[�W�j�Ǝn�܂�B5�y�[�W�ƒZ���Ȃ���A���̉���łɕt���ꂽ�q����r�́A�͂̂��������D�����̂��B�Ƃ���œ����̖`���u�w�����[�^�x�̍�҃E���W�[�~���E�i�{�R�t�v�́A�g���̐��z�q�u���[���h���b�v�v�r�̏��������Ƃ܂����������Ȃ̂ł���B�V�����ɔł̏����{���͒m�炸�A�g�����{���̖�ҁq����r��ǂ��Ƃ͋^����e��Ȃ��B
�s���㎍�蒟�t�ҏW���ɂ��C���^�r���[�L���q�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���r�́u13�v�ŁA�g�����͎��̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���B
�@�ł́A�ꎞ�Ԃ́k�e���r�l�ԑg�̐�����˗����ꂽ��A�ǂ����������̂����܂����B
�@���ɂ����Ȃ��B
�@�i�����ɂ����Ȃ����Ƃ����ӂ��Ȕԑg�����킯�ł����B�j
�@����A�ڂ��ɂ�����D��S�́A���Ȃ��͂蕶�͂̐��E�łˁB�f�������Ƃ��̐���͂��������������Ȃ��B����́A���e�k���O�Y�l����Ɂu���͑��l�����v���Ă���������������������ǁA�I���͂���ς臀�f���Ƃ��Ȃ�Ƃ��͑��l����ꇁ���Ă��������ˁB�����������Ɩ���Ă��A�ڂ��͉��ɂ��Ȃ��̂�A�܂��ɂ����ȂB�I���̒��ɂ͂���Ă݂������Ƃ��Ă̂́A�ӂ��̓���̒��łȂ�ɂ��Ȃ��̂�B���Ԃɂ́A�ς���̂́A�G��̓W�����A�̕���A�X�g���b�v�A��ˁA�Í������ƁA��������̂�����ł���B����͑S���A�ς������͎����ł������Ɋςɂ����킯�ˁB�Q�W�̒��̈�l�Ƃ��Ċς��ŁA�Â��ɑ��݂��Ă������̂ˁB������A�����������肩������̂����̂́A���͂̐��E�������ȁB�i�s���㎍�蒟�t1978�N3�����A��ꔪ�y�[�W�j
���U�A�l�O�Ŏ����N�ǂ��邱�Ƃ������Ȃ������g���ɂ��Ă݂�A���R�Ƃ������ׂ������ł���B�p�t�H�[�}���X�ɏd����u���Ȃ��l�ԂɂƂ��āA�e���r�ԑg�̐���ɂȂɂقǂ̉��l�����낤�B���ꂩ����ʂ��A�g�����̉f�������͊F���ɋ߂��B���̒m��B��̂���́A����l�N�܌���ܓ����f�̂m�g�j����e���r�s���j���p�فt�́q���z�̉����\�\�F�V���F�̉F���r���B�F�V���y���F�̍��ʎ��ň��A����܂��i�F�V�͑��V�ψ����߂��j�A���̒��̓y���ɕʂ��������V�[���ɋg�����o�ꂷ��̂ł���i�A�X�x�X�g�ق̊W�҂��B�����L�^�p�r�f�I�Ƃ��ڂ����A�v���V���b�g�ł͂Ȃ��j�B�����ŋg���͓y���̎���Ɍ������ď����������āA�o�C�o�C�Ƃ����ӂ��ɏ����U���Ă����炵�Ă���B
�g�����{�l���o�ꂵ�Ȃ������o�����͂���������B����̓e���r�ԑg���s�b�N�A�b�v����i�ȉ��̎O�_�Ƃ��r�f�I�^�悵�Ă��邪�A���쌠�̊ϓ_����f���E�����̃A�b�v���[�h�͂��Ȃ��j�B
�@����l�N�O����Z���A�m�g�j�e���r�s�i�C�g�W���[�i���t�́q���W�فr�̃R�[�i�[�ŃC�b�Z�[���`�̘N�ǁA���{��q�̉��y�i�s�A�m�j�ɂ��q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j����l���b�ɂ킽���ĕ��f����A�ԑg�L���X�^�[�̏@���w�ҁE���c�T�����u�Z�b�N�X�̃v���Z�X�����Ԃɂ��ǂ��Ă����āA�Ō�ɉʂĂ�Ƃ�������̃C���[�W�Ō���Ă���̂��Ǝv���B���Ǝ��͂����������߂������Ă��邩��A�Ȃɂ��S�䂩���̂ł͂Ȃ����v�i�v��j�ƃR�����g�����B
�A����Z�N������A�m�g�j����e���r�s���j���p�فt���q�����̃��[�g�s�A�\�\�������{�����߂ār����f���A�g���̒������Љ���i�q�g�����̓����{�r�Q�Ɓj�B�Ƃ��ɁA�g���͑O�f�q�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���r�ł��D���Ȕԑg�́H�@�Ɩ���āu�u���j���p�فv�͂��Ǝ��Ă�悤�ɂ��Ă�v�i���O�A���Z�y�[�W�j�Ɠ����Ă����B
�B��Z�Z��N�܌������A�˂��ߐ���̂m�g�j�l�ԍu���s���t�̗́E���̗́t�i�m�g�j����e���r�j�̑攪��q���ɕ����R�g�o�A��������o���R�g�o�\�\�����a�Ƌg�����r�ł˂��߂��g��������������A�ޗlj����q���q�Õ��r�i�B�E1�j�Ɓq�m���r�i�C�E8�A�u�ċ��v���u�����v�ƌ�L�E��ǂ��Ă���̂��ɂ��܂��j��N�ǂ����B�g���̓������A��㎵�l�N�̂m�g�j���W�I�s���|����t��������ꂽ�B
�u�����Ƃ��͂����Ӗ��ŋ��C�ɂȂ��Ă�킯��B�o�Ă������t���ł��厖�ɂ��āA�ۑ����Ă��������ƁB����������������Ⴄ�Əo�ė��Ȃ��킯�ˁB�v�i�e���b�v����j
�g�����̍쎍�@�̐����Ƃ����Ă����������e�ł���B
�k2007�N4��30���NjL�l
�m�g�j����e���r�̔ԑg�s���j���p�فt�́q���z�̉����\�\�F�V���F�̉F���r�͘^�悵�Ď苖�ɂ��邪�A����A�y���F�̉f�����C���^�[�l�b�g�Ō������Ă�����qYouTube - Broadcast Yourself.�r�T�C�g���qYouTube- /\/\/\/\/My fav�F�V���F���y���F��tatsuhiko shibusawa/tatsumi hijikata�r�Ƃ����^�C�g���ŁA���f���ꂽ�y���F�̑��V�̃r�f�I�����A�b�v����Ă����i����c�\��B�e�ɂ��y���F1972�N�̕����q�v�杁r�̋L�^�f�����A��q������p��i�̂ЂƂƂ��Ċς���j�B

���̒��̓y���F�ɕʂ���������F�V���F�i���j�Ƌg�����i�E�j
�o�T�FYouTube
- /\/\/\/\/My fav�F�V���F���y���F��tatsuhiko shibusawa/tatsumi hijikata
�q���z�̉����\�\�F�V���F�̉F���r�i45���j�̊T�����L���Ă����B�ē����l�J�V�����i�l�`��Ɓj�A�i���[�V����������j�Y�i�o�D�j�A�i����֓��G�v�i�A�i�E���T�[�j�Ɛ^�싿�q�i���D�j�A�ʐ^�𑊓c���i�ʐ^�Ɓj���S���B�ԑg�́A���f���Ƀ��t�g�E�t�H�[�����i�����S�ݓX�r�܁j�ŊJ�Â���Ă����s�F�V���F�W�t�ƘA�����Ă���A���C�����F�V���D���p��i�̏Љ�ƁA�F�V�Ɛe���������l�l�̃C���^�r���[�ō\������Ă���B�o�ꂷ��̂̓X�����x���N*�A�f�����H�[*�A�N���i�b�n*�A�A���`���{���h*�A�]���l���V���^�[���A�G�����X�g*�A�{�b�X�A�x�����[��*�A���������A���q���`�A�y���F�A�V���[�l�E�}���e�B�[�j*�A�s�G���E�f�B�E�R�V��*�A�������*�A�l�J�V�����Ƃ�����l���̍�Ƃ̔��p��i�ŁA����̋�l�̓R���e���|�����[�A�[�g���Ӑ}�I�ɏ������ܒJ���m�ҁs�F�V���F��z���p�فt�i���}�ЁA1993�j�ɍ̂��Ă���A�g�����D��Ƃ������܂܂��B�C���^�r���C�[�͛ܒJ���m�i�t�����X���w�ҁj�A���q���`�i��Ɓj�A�r�c�����v�i��ƁE�ʼn�Ɓj�A�F�V���q�i�v�l�j�A�r���I�i�h�C�c���w�ҁj�̊e���ŁA�r�c����͖S�F�E�y���F�Ƃ̑z���o������Ă���B
�q���z�̉����\�\�F�V���F�̉F���r��37���߂������肪�y���F�̑��V�̃r�f�I�ŁA�F�V�ƂƂ��ɋg�����킸���Ȃ���o�ꂷ��i�S��3��26�b�́qYouTube�r�łł́A2��24�b�߂�����̐��b�ԁj�B�u�e���r�����������F�V����̋M�d�ȉf���ł��v�ƃi���[�V���������Ԃ��邪�A���̃r�f�I�͂܂��A��x���e���r�ɏo�����Ȃ������g�������Ƃ炦�������炭�͗B��̉f���ł���B
�F
�V���F�́q�|���m�O���t�B�[���߂���f�́r�ɂ��������Ă���B�u���̍D���ȃ|���m�O���t�B�[�̏�����B���Ȃ킿�I�[�u���E�r�A�Y���[�́w�E�F�k�X�ƃ^���z
�C�U�[�̕���x�A�k�c�c�l���ꂩ��g��������ɋ�����ēǂT�f�B�E�u���b�P�C�Y�i���̓s�G�[���E�}�b�R�������j�́w�A���X�̐l���w�Z�x���X�B������
���悭�������|���m�O���t�B�[�ł��邽�߂ɁA�|�p��i���ꂷ��ɋ߂Â������̂ƌ������Ƃ��ł��邾�낤�B�v�i�s�F�V���F�S�W17�t�A�͏o���[�V�ЁA
1994�A���y�[�W�j
�������㎵���N�̏��o�œǂ�ňȗ��A�Ȃ�Ƃ����ās�A���X�̐l���w�Z�t��ǂ�ł݂����Ǝv�������̂́A���������ɋ@��Ȃ������B�傫�Ȑ}���قɂ�����
����Ă��Ȃ���������ł���B������A�W�J�~�ꂳ��Ƃ̎G�k�̂���A�s�A���X�̐l���w�Z�t��ǂ݂����̂���������Ȃ��āc�c�Ƃ��ڂ����Ƃ���A�}�����[
���F�V�̒S���ҏW�҂ł��������W�J����́A�F�V�v�l�ɐq�˂Ă݂���A�Ƃ��Ƃ��Ȃ��Ɍ���ꂽ�B�ꑽ���ĂƂĂ�����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��������A�悤�₭�O�N
�܂��A�������[�Łs�A���X�̐l���w�Z�t����肵���B�P�s�{�ł͂Ȃ��A�s��权N���u�t�̗Վ��������������B

�s��权N���u�k�Վ��������l�t
�T�f�B�E�u���b�P�C�Y�s�A���X�̐l���w�Z�t�i��ȐV��A�����[�A1953�N12��20���j�\��
��
���A�g�����́q�|���m�����G���r�ɂ��������Ă���B�u���̏��a��\�Z�N���A�����k�|���m�����l�ɗނ���O�����w���ԊJ�����Ƃ��A��ĂɊ��s����n�߂�
�̂ł���B�w�K�~�A�j�x�A�w��k�푈�x�A�w�a�̕����ꔶ�x�A�w�W�����A���̐t�x�A�w�g���[�E���u�x�����āw�o���J���푈�x�Ȃǂł������B���͈�ʂ肻��
����w���āA�ǂ�ł���B�قƂ�ǂ������Ɠ����ɁA�֎~���������悤���B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܌܃y�[�W�j
�g���́s�A���X�̐l���w�Z�t�������Ɠ����悤�ɂ��čw�ǂ����̂��낤���B�g�����ƃ|���m�����̊W�͋����[�����̂����邪�A����͂Ƃ������A��㎵�O�N
���\�̎��сq�w�A���X�x���r�i�G�E12�j�Ɏ��̎��傪�����邱�Ƃ����̐S�ȓ_�ł���B
�킵�̒m���Ƃ�
�u������l�̃A���X�͏\���ɂȂ��Ă��@�p��̔���ɐK��
�ڑł���@����Ƃ��̓Y�b�N�̑܂ɋl�߂��ā@�V��ɒ݂�
�����@���������̃A���X�E�~���[���C�c�c�v
�T�f�B�E�u���b�P�C�Y�̃|���m�����̎�l���̖��́u�A���X�E�~���[���C�v�B�s�A���X�̐l���w�Z�t�́A��Z�Z��N�Ɋw�K�����Ђ���s�G�[ ���E�}�b�R�� �������Ƃ��āA�����O���̉����t���Ė|������Ă��邩��A�����̂�������͂�����ɂ��ꂽ���B
���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�ȑO�ɋg���������\��������т�J�g�̕M���Ŕ��\��������т��A�A�����R���i�ߕ��i�f�g�p�j�����W �����G������ �������ꂽ�B�E�F�u�T�C�g�s�� �̊��G���L����� �f�[�^�x�[�X�t�́A ��������}���ٌ����������ʼn{���E�������\�ȁs���{��̊����{�G���i�����[�����h��w�}���كS�[�h���E�v�E�v�����Q���ɏ����j1945�N�`1949�N �i���a20�N�`���a24�N�j�\�\�}�C�N���t�B�b�V���Łt�����̂��߂̉���I�ȃc�[�������A���M�ҁ��u�g�����v�Ō�������ƎO���A�q�b�g����B���̌��ʂɎ� �͋������B�g�����̖��m�̎���т��܂܂�Ă�������ł���B�������ʂ̋L���^�C�g���ɔԍ���t���Ĉ����B
�@�i�{���j����ҁF�i�ڎ��j�s�k�F������
�A�f��
�B���F�C�̏�
�@
�̎���сq�s�k�r�Ɓq�������r�́s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�ɂ����^����Ă���A���ŏ��̋g�������Ƃ��Ēm���Ă���i�P�s���W�ɖ����^��
����A�g���͌������L�Ō��y���Ă��邩��A��т͌㐢�Ɏc�����肾�������낤�j�B�������A�ƇB�́s�g�����S���W�t�ɖ����^�ł�����肩�A�����܂ł���
���݂���m���Ă��Ȃ��������тł���i�ٕҁs�g�����S���ѕW������t�ɂ����f�ځj�B�܌����ɍ�������}���قʼn{���ł����̂ŁA�T�����q�ׂ悤�B
���т̌f�ڍ��𗪋L����ƁA�@���s�V�v���k��14���l�t1947
�N9���̑�2���A�A�́s���Y�t1948�N8�����A�B�́s��[���Ȃǂ�]�t1947�N9�����B�@�A�Ƃ��A����}���قɂ͎G���̌��{����������Ă���B�}�C�N
�������ꂽ�����̓u���E�Y����ɂ͕s�ւ���܂�Ȃ�����A�����Ƃ��G���ەʎ��ō��{�̃y�[�W��T�d�ɂ߂����Ă������B����Ɓs���Y�t1948�N7�������
�J�g�̎��q��ɂār���f�ڂ���Ă���ł͂Ȃ����B�q�g�����̔o���r��
�uJ�g�v�ɂ�
�čl�@�����Ƃ��A�o���ケ�̖����g��ꂽ�`�Ղ͂Ȃ��Ƃ����W�J�ɂȂ������A���A���������тɂ��̕M�����p�����Ă����Ƃ͗\�z�̊O���B�����ܕт��f��
���̊��L�ɏ]���ĔN�㏇�ɕ��ׂȂ����ƁA���̂悤�ɂȂ�B�ȉ��A���p���̂��ȂÂ����̓}�}�A�����͐V���ɓ��ꂵ���B�����������ƐV���Ől���ɗL�ӂ̍�����
��ꍇ�A�������g�p����i�q�u�g�����v����u�g�����v�ցr�Q
�Ɓj�B
�i1�j1947�N9�����s���t�̋g�����q�C�̏́r
�i2�j1947�N9���A�s�V�v���t2���̋g�����q�s�k�r�q�������r
�i3�j1948�N7�����s���Y�t��J�g�q��ɂār
�i4�j1948�N8�����s���Y�t�̋g�����q�f�́r
�s���t
��1946�N8���n���̔_�ѐ��Y�W�̐��G���ŁA1948�N7������́s���Y�t�Ɖ���A�������p������1949�N10���܂Ŕ��s���ꂽ�A�ƍ���}���ق�
�G���ژ^�ɂ͂���B��������A������Г��m���i�����s������ؔҒ��O�m�l
�����H�ƃr���j����o�Ă���B�c�O�Ȃ���{�T�C�g�̃R���Z�v�g��A�g�����̖����s���͑S�т����p�ł��Ȃ��̂ŁA�e���тɂ��ĊȒP�ɐ������悤�B�i1�j��
�q�C�̏́r�͝R��ŁA�s�Õ��t�Ȍ�̋g�����v�킹����̂͊F���ƌ����Ă悢�B�����ėޗ��T���A��N�̒Z�́u��Ԃꂽ�鎆���D�͑��̒��[�ď��Ďq�炩
�ւ�䂭�v�i�s�g�����S���W�t�A���܋�y�[�W�j�̃g�[���ɋ߂��B�i2�j�̖{���́s�g�����S���W�t�ł��ǂ݂������������B���͂�����A�g������O�̎��W�s�t
�́t�i����ɁA1941�j�̍앗���Ӑ}�I�ɔ������āA�����ɐ��̎���́u�����v�Ƃ��Đ�������i���ƍl����B�i3�j�́q��ɂār���Ђ炪�Ȃ����ŋL����
�Ă���̂́A��Ô���̉̏W�s���W�t�i�n���ЁA1940�j����̉e�����낤���A���z�͔����Y�́q�Q�W�̒������߂ĕ����r������ɋ߂��B�i4�j�́q�f
�́r�̉r�V���ɂ́A��͂�Y�̎��W�s�X���t�i��ꏑ�[�A1934�j��z�킹����̂�����i���̂Ƃ��A�g���͂܂����e���O�Y���Əo����Ă��Ȃ��j�B�s��
�Y�t�f�ڂ̓�тɊւ��ẮA�a�����́i3�j����厞�̍��ŁA�������́i4�j��{���Ŕ��\���Ă���_�������[���B
�g���������̎��������������̗l�q�́q�f�ЁE���L���r�ɏڂ������A1948�N12��10���̋g���̓��L�Ɂu�f�g�p�̔[�{�W�ɌĂт�����B���s�ォ��
�肽���Ĕ[�{�����̂ŁA�܂��������B���̖{�𖾒��܂łɑS���������ʂƁA�����̏����ɂ���Ƃ��ǂ������B�k�c�c�l�v�i�s�g�������W�t�A�v���ЁE���㎍��
��14�A1968�A����y�[�W�j�Ƃ���A�����̏o�ŎЂƂf�g�p�̂��Ƃ��m�邱�Ƃ��ł���B���ɁA�g���̋Ζ���Ɋւ���L�q���g���z�q�ҁq�N���r����
��������i�s�g�����S���W�t�A�����`����O�y�[�W�j�B
���l�ܔN�i���a��\�N�j ��\�Z��
�\�A�������X�̎В������͎҂đn�����������[�ɓ��ЁB���l�Z�N�i���a��\��N�j ��\����
�ҏW�̎d���ő����Ԏq�A�ؓc�����A���n�F�l�Y�A��������Ɍ��e������˗��B�����̓����^��ɗU���āu�V�v���v�ɓ���B��R������̐�y�S�����o��� 琁B�����A�������[��ގЁB�\���A��Ɏ��߂������^��̐s�͂œ��m���֓��ЁB���l���N�i���a��\��N�j ��\����
�u�V�v���v�ɓ�т̎����f�ڂ���A���߂Ă̌��e���܁Z�~��Ⴄ�B���܈�N�i���a��\�Z�N�j �O�\���
���m�������ߎl���A�ҏW���ɋ߂�S�����o�̌��Y���Œ}�����[�ɓ��ЁB
�i1�j
�́s���t1947�N9�����́q�ҏW��L�r�ŁA�ҏW���̓����^��Ǝv�����r�E�g�����̂悤�ɏ����ċg����D�ꂽ���l�Ƃ��Č��������B�u����q�˂������B�{
���̕��|���͂��̐�����A���邽���A�C�Ɛ��Y�ɂ��Ȃ��̂��ڂ��ė������A�����Ă���ɊW�̖������̂�����̂ł͂Ȃ��낤���A�Ɖ]���C������B
���̖��ɏA�āA�ǎ҂̎v���������ė~�����B����ȎG�������ɕ��|���͓��Ɋy�������̂ɂ������B�ꗬ�����V�l�����߂āA���̐��ʂ������Ă��Ȃ����ɁA
�{���͐�Ɂu�����D�v�̋g�g�N�A�u�Ζ�̐l�X�v�̊ێR�|�H�𑗂��B�{�������́u�C�̏́v�g�����A��������̐��������l�X�ł���B���̓_���|����
�䌨���Ēp���Ȃ��v�i�����A�ܘZ�y�[�W�j�B�u�����^��v�́A�̂��̋r�{�ƁE�����^�玁�ł��낤�B�܂��u�g�g�N�v�͗������[�В��E���씎�k�����E�Ђ�ށl
�̕M�����A�Ƌg���͑剪�M�Ƃ̑Θb�Ō���Ă���B
�g���͂����Łu�k�c�c�l���m���Ƃ����̂͊w�p�I�Ȗ{���o���Ă����킯���B������K�c���F�̃J�����́w���{�剤���u�x�Ƃ��A���e�͂킩��Ȃ��Ă��ҏW�S����
���čK�c����̂Ƃ��֍s���Ă��킯�B���ꂩ����c�k���j�l����́w���ޔ_����b�x�Ƃ����̂�������v�i�s�����C�J�t�A1973�N9�����A��܁Z�y�[�W�j��
�U�肩�����Ă��邪�A���m�������s���Ă������G���̖���A�����Ɏ��\�������ƂȂǂ����тɂ��o���Ă��Ȃ��B�i�g���͂��̑Θb�Łu�k�����^��́l����
�̓T���P�C�̌|�\�L�҂Ƃ��Ĉꗬ�̐l���Ǝv�����ǁA�����A�����o�̊C�R���𒅂����w�N�������v�i���O�A��l��y�[�W�j�ƌ���Ă���B��N�A�����͋g����
���ď������邵�Ă��Ȃ��悤�����A�g�����]��u�����������Ǝv���̂́A�ЂƂ莄�����ł͂Ȃ����낤�B�j
�g�����̖����s���q�C�̏́r�q��ɂār�q�f�́r�O�т͂�������C��`���Ă��邪�A���ꂪ�s���t�s���Y�t�Ƃ����u����ȎG���v�̐��i���炫�Ă��邱�Ƃ́A��
����v���Ȃ��B�����̔��s���̓��m���́A�O�f�N���������悤�ɋg���̋Ζ���ł���B�������ׂ�������A�����̎��̍�҂Ƃ��ĈȊO�A�g�����i�����
J�g�j�̖��͌������A�����Ƃ̊ւ��͕s�����B�����A�����Ԏq��ؓc�����A�g���M�q�Ƃ��������M�Ƃ��q�����Ȑ��M�r���Ă���Ƃ��납��A��ҏW�҂�
���Ă����̒��҂�S�������\���͑傫���B�܂������Ƃ��A�ߌ���̒Z�̔o�傩��C�␅�Y�Ɋ֘A�����i�����A�R�����Ɍf�ڂ��Ă���B����ȂǁA�Z��
�^���w�ɏڂ����҂̑��݂������Ă͂��߂č쐬�ł�����̂��B����ɁA�g�������ǂ��Ă����c���~�W�s�R���t�i��ꏑ�[�A1935�j����q�~������r��
�q�R�����r���s���Y�t�ɍČf�ڂ���Ă���̂́A�g���̑I�ɊԈႢ����܂��B������ɂ��Ă����̎����A���Ȃ킿���W�s�Õ��t�ɂ�����܂ł̐��̋g�����̕�
�w�I�O�Ղ́A�قƂ�ǂ킩���Ă��Ȃ��B�������ꂽ�����s���O�т͂�����𖾂��邽�߂̍ł��d�v�Ȏ�|����ł���A���̖����s���тƕ����ās�g�����S
�W�t�́q�����s���сr�Ƃ������`�ł̌�������܂��B
�ȏオ�g�����i�����J�g�j�̖����s���тɂ��Ăł���B�������Ȃ���A�V�����͂������蒲�ׂĂ݂���̂ŁA�s���Y�t1949�N2�����ɂ͋g�����̕ϖ�
�Ǝv�����u�t�C�~���v�Ɓu�u�m�g�v�̖��ŁA�o��O��E�Z�̓�f�ڂ���Ă���B�薼�E��Җ��̋L�ڂ��ڎ��ɂ�����̂́A�f�ڃy�[�W��C�A�E�g���猩
�āA�����炭�������e�ł��낤�B����䂦�A�ǂ����猩�Ă��ϖ��Ƃ킩�鏐���ɂ������̂Ǝv����B�u�u�m�g�v�́u�g�����v�̊����̃A�i�O�������i�q�g�����̔o���r�Q�Ɓj�B���ɂ��̓������o���ʂƂƂ�
�Ɍf����B
 �@
�@
�u�m�g�q���t�r�i���j�Ət�C�~���q���T�~���r�i�E�j�̏��o���ʁi��������s���Y�t
1949�N2�����j
���T�~���b�t�C�~�����~��
�Ŕ��ϔY�̈ӂȂ��g�~��
�ڂ݂ɂ�����Ԃ̑����~��
�ӂ邫���炩�̏Ƃ邵�Â����t�b�u�m�g
�����炬�݂̂Âɂ��Â߂�
�����̂����������т�
���Ȃ����肯���t��݂Ȃ�����
�Ђ���g�݂��
�͂邯�����̂�
���Ђ��Ƃ�����
�g�����̑��̕��͂��������ƂŁA���̓�삪�g���̕M�ɂȂ邱�Ƃ̖T�Ƃ���B�܂��q�f�ЁE���L���r�A�����Ď��W�s�t�́t�Ɖ̏W�s�����t
���^�̉C����
�i�ł���B
�u�k���a��\�l�N�l�ꌎ�O�\���@���j�@�~�̐���s�B���Y�A�t���A�s�F�炽���B���~�A�g�~�A���~���������B
�@�@�@���~��ӂ邫���炩�̔g���Ă�v�i�s�g�������W�t�A���O�y�[�W�j
�u������@�����悬��@���f��
�Ԃ�������ʁ@�N�悢�����Ɂv�i�q�����́r�A�E11�j
�u���ӏD��
�݂݂�͂Ȃ���
����Ђ̂Ђ��Ђ�
�Ƃ�����Ȃ����
�����̂�ӂ���v�i�s�����G�߁t�A����ɁA1940�A�Z�܃y�[�W�j
���Ă���ŋg���������O�ɔ��\�������́A�v�l�тɂȂ����B��т��f�ڂ����s�g�����S���ѕW������k������2�Łl�t�i���Y��ԁA2000�j�Ɠ�����
�قɂ��đO�f���т\���ɋL�^���邱�ƂŁA���̏Љ���I���悤�i���������єԍ�34b�́ub�v��34�̎��ɑ}�����邽�߂̉��̂��̂ŁA����������ɂ�
���K�̔ԍ��ɕt�����������B�s�g�����S���W�t�f�ڃm���u���͋L�����u�\�\�v�ŕ\�L�j�B������
�ԍ���t�������ās�g�����S���ѕW������t���������@��́s�g�����S�W�t���o��܂łȂ����낤����A���������������̕��͂��̕������v�����g���Ċ�
�p����������Ƃ��肪�����i�q�s�k�r�Ɓq�������r�͍Ę^�ł���j�B
34b�@�C�̏��i���݂̂��傤�j[�\�\]
�n�����ā@���т����Ȃ���
16�s���s���t�i���m���j1947�N9�����i2��9���j���������сE1200�@�s�k�i�͂��ڂ��j[717]
�_�̏����Ђ炩�ꂽ��
6�s���s�V�v���k��14���l�t�i�����Ёj1947�N9���i1��2���j���������сE2161�@�������i�������傤���j[717-718]
�@�@���m���v�j
7�s���s�V�v���k��14���l�t�i�����Ёj1947�N9���i1��2���j���������сE3186b�@��ɂ��i�Ȃ����ɂāj[�\�\]
�Ђ���̂Ȃ������킽���͂��邢�Ă
12�s���s���Y�t�i���m���j1948�N7�����i3��7���j���������сE4
�������́uJ�g�v�B170b�@�f���i���傤�j[�\�\]
�i���ɏM�̋���䂭
9�s���s���Y�t�i���m���j1948�N8�����i3��8���j���������сE5
��̖{���ł͐G��Ȃ��������A�s�V�v���k��14���l�t�̕ҏW���͓���݊w���̒���p�v�ł���B����́s�V�v���t�̍��ɂ��āq����p�v ���ʃC���^ �r���[�\�\�w�����ِ����L�x����w���߂̒Z�̎j�x�̎���ցr�i������E�R���R�I�l�j�ŁA�����q�ׂĂ���B
�����@ �u����v�Ƃ����G��������܂��ĂˁB����͎�`�咣�������ďW�܂�����ł����A�u�V�v���v�̏ꍇ�͂���Ȃ��ƂƊW�Ȃ��āc�c�B�����w�Z�̐e�F�ɁA����@ ���Ƃ����A�̂��ɖ����V���̐��������ɂȂ����j�����āA���̋��R���݂��˂āA���Ƃ������Ă�낤�Ɛe������ɘb���Ă��ꂽ��ł��ˁB����͂��Ƃŕ������b �����ǁA�����ʼnƂ������炢�̋������̐e�����o���Ă���ĂˁA�u�V�v���v���͂��߂��킯�ł��B
�R���@���̎��̓��l���g�s�~�V��A�֛��A���씎�A�����Q��ł��ˁB�n�����ł́A���䂳��͐����lj�Ƃ����y�� �l�[�����g���Ă��܂� ���c�c�B�i����p�v�s��{ ���߂̒Z�̎j�t�A���C�Y�o�ŁA1993�A��ܔ��y�[�W�j
����́s�V�v���t�̑n�����ő��Ɏ����珬�����A�܍��ŎO���R�I�v���玍����������b�͂��Ă��邪�A�g���ɂ͌��y���Ă��Ȃ��B���͒���p �v�̔M�S�ȓ� �҂ł͂Ȃ��̂ŁA�g�����ɂ��ď��������͂��̏W�s�����k�V���Łl�t�ѕ��� �ق��ɂ���̂��A�ڂ炩�ɂ� �Ȃ��B
�k2004�N9��30���NjL�l
���̌�A�s�֛��S��i�t�i�������[�A1982�j�����́q����\�\���C�̊��r�Œ���p�v���s�V�v���t�̐����ɐG��Ă���̂��݂����B�����ɂ́u���́u�V�v
���v�͂Ђǂ��ϑ��I�Ȃ��̂ŁA�k�c�c�l����i�̒������A�g�����A�O���R�I�v��������ׂē��l�ł͂Ȃ������B���̑���e�Ƃɂ͑����̌��e�����x��������
�ŁA�g����������i�ŋ�����������̂͂��̂Ƃ������߂Ă��Ɖ�ڂ��Ă���v�i�����A�O�l��y�[�W�j�Ƃ���B
�g �����͏������������B�����ژ^�����J�����Ύ��Ԃ͂͂����肵�悤���A�g���̐��M��ǂނ����ł��[������������B�����̐��M�q�u�R�r�̉́v�����{�Ȃǁr�� ���������͂������B�u�����̋H�Q���ɂ��ď����Ƃ̂��Ƃ����A�ʂɂ����������̂͂Ȃ��B������������̏������W�u�R�r�̉́v�ɂ͈ꐡ�����}�b�߂������̂� ����B�v�i�}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t32���A1958�N4��30���A�Z�y�[�W�k�����́u�x�E�l�v�l�j

�q�u�R�r�̉́v�����{�Ȃǁr�i�}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t32���A1958
�N4��30���j�̏��o����
�� ��ܘZ�N����A�M���o�W���̃Y�{�������肾�����{�[�i�X�Łs�R�r�̉́t�̏������ɔ��{���w�������o�܂��A���̋Â�ʕM�v�ŕ`�����Z���ł���i������ ���s�u�����v�Ƃ����G�t�̂ǂ����ɂ��A���̂��鎞���A�����ȏ������W�E�̏W�E��W������W�߂Ă����A�Ƃ������j�B���o���ɂ́q���M�u�{�̂͂Ȃ��v�r �Ƃ��邩��A�}���̎Ј��������{�ɂ��ď����Ă����̂��낤�B���āA���́q�u�R�r�̉́v�����{�Ȃǁr�̖����Ɏ��̋H�Q�{���������Ă���B
�@���̑��A�߂ڂ������̂́A�x�C�Y�������u���Ƒ��v�]��ŁB�ē��g�u���炽�܁v���Ŗ{�B�����Y�u�L�v���� �{�B�����ԔV�� �u���ߐ���v���Ŗ{�B�x�C �Y�u�������ʁv��c�ŁB�g�c���u�̉��̏��v�B�u��[���ɋ�W�v�ʑ��ДŁB�R�����q�u���`�v�u�����v�B�u�������c�j��W�v�������[�ŁB�Ȃǂł���B�i�� �O�j
�̏W�ɑ����W�̗D���ȂǁA���낢��Ȃ��Ƃ��v�������ԁB�x�C�Y�E�֓��g�E�����Y�E�g�c���E��[���ɁE�R�����q�E�������c�j �́A�g���̂� ���̐��M�ɂ��o�ꂷ�邪�A�����ԔV��̖���������̂͒������B�����A�Ȃɂ�����������Ƌg�����̎�肠�킹���ʔ����B
�k���a��\��N�l�㌎�\����@�Γc�m�A�l�N����B�s�������玍�W�t���o�� �ƌ�����B���������ċ��l���̒��ł� �ށB�s���Ɨ��Ȃ��̂͂ǂ��������Ƃ��B���ǂ̂��ƁB�i�s�g�������W�t�A�v���ЁE���㎍����14�A1968�A��Z��y�[�W�j
�q�� �L���r�́s�������玍�W�t�͂��̔N�������̑n���I���ł����A�g���͋�N��A���̏������W�ɓZ�Z�~�𓊂���قǂɂ́u�s���Ɨ��Ȃ��v������]�����Ă��� �̂ł���i���㎍���ɂ̔ѓ��k��̍�i�_�q�g�����̎��r�ȊO�A���҂̎����r���Ă������v�����Ȃ��j�B�����g���������̋H�Q������A�Ȃɂ�����V�� �����̂������Ă���C������B
�g�����͎��g�̐������A�����ɂ́u�g�����v�A���̌�͈�т��āu�g�����v�Ə������邵���i�{�T�C�g�ł́u�g�����v�ƕ\�L�j�B���̂�����̌o�܂������̒��Җ����璲�ׂĂ݂悤�B
�@�����G���i1940�N10���A����Ɂj�@�g����
�A�t���i1941�N12���A����Ɂj�@�g����
�B�Õ��i1955�N8���A���ƔŁj�@�g����
�C�m���i1958�N11���A���惆���C�J�j�@�g����
G�����i1959�N5���A���ƔŁj�@�g����
�i1�j�g�������W�i1959�N8���A���惆���C�J�j�@�g����
�D�a���`�i1962�N9���A����Ɂj�@�g����
�i2�j�g�������W�i1967�N10���A�v���Ёj�@�g����
�E�Â��ȉ��i1968�N7���A�v���Ёj�@�g����
G�s�����t�ɂ͂��ƂŐG���Ƃ��āA�P�s���W�Ō����·D�s�a���`�t�܂ł��u�g�����v�A�E�s�Â��ȉƁt�ȍ~�͂��ׂĂ��u�g�����v�ł���B����́A���Ȃ�̊m�x�ŗ��R�𐄒�ł���B���W�s�Â��ȉƁt�́i2�j�s�g�������W�t�̖{���𗬗p���Ă���A���́s�g�������W�t���V���V���Ȃőg�܂�Ă���̂��B����ƍ��킹�邽�߂ɁA���Җ����V���́u�g�����v�Ƃ����̂��낤�B����͂����Ƃ��āA�i1�j�s�g�������W�t�̖{�����V���V���Ȃł���Ȃ���A���Җ����u�g�����v�Ȃ̂͂ǂ������킯���낤�B���������A�s�g�������W�t�i�A�����^�A�B�ƇC��S�ю��^�j�̐����̕\�L�ɂ͈ɒB���v�̈ӌ����������̂ł͂Ȃ����B����A�̏W�s�����t�i����͈ɒB���v�j�͋g�����̈ӌ��������̂ł͂���܂����B���Ȃ݂Ɂs�����t�̉��t�ɂ͊ۂɁu���v�̎��̌��悳��Ă���i������s���܂�͂����L�k�ʖؓ��Łl�t�̈�Ɠ����j�B�����Ō��邩������܁Z�N�㖖����u�g�����v���o�ꂵ�A���Z���N�́A�����Ƃ��Ă͑S���W�ł���s�g�������W�t�ȍ~�A���S�Ɂu�g�����v�ƂȂ����̂ł���B
�����͂ǂ����B����͂��x��ē��l�ɕω������Ǝv����B�����̎ʐ^�͐����F�Y���Ɍ��悳�ꂽ�s�g�������W�t�̏��������A�u�g�����v�Ƃ���i�u1967.9.28�v�Ƃ������t�͉��t�̊��s���̑O�ł���A���҂ւ̌��{�n���̓����牓���Ȃ����낤�j�B�ʐ^�Œ��ڂ������̂��u�l�v�̋������B�킪�g��U�肩�����Ă��A�����̐����͎莆�̈����Ɋr�ׂĒ��J�ɏ����B���̋C���������́u�l�v�̋����ɕ\���Ă���B�����S����p���u�g�����v�ɂ��������̂ł͂Ȃ����B������㔪�Z�N��ɏ������Ă����������{�ɂ́A�y�������ѕM�������킸�A���ׂāu�g�����v�Ƃ���B�g�����̏����{�͉\�Ȃ������Ɏ��悤�ɂ��Ă��邪�A������������u�g�����v����u�g�����v�֕ς�����̂��A�m���Ȃ��Ƃ͂܂��킩��Ȃ��B�����ꂱ�̗��ŕł���A�Ǝv���Ă���B
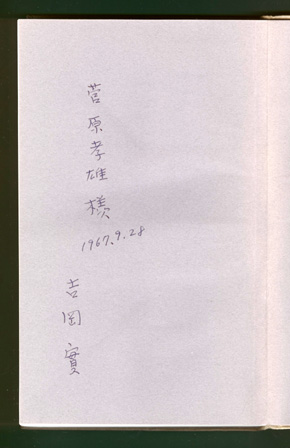 �@
�@
�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j�̌��Ԃ��ւ̏����i���j�Ɓs�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j�̏���ⳁk�n�K�L��l�i�E�j
�k2008�N1��31���NjL�l
�n�ӈ�l�����sdespera�f���t�́q��l�@���t���ȁr�i2006�N11��11���j�Ɂu���s�Ǝv���������������̔×��ɁA���f����C�����ɂ�����ꂽ�̂��o���Ă���B����ŋg��������̂悤�ɁA���Ȏ���͎v���o�������Ȃ��Ƃ���ɋ�����������e�肾�����ЂƂ����炵���B�g������̕Ғ����u�k�ߕS��v���㈲�����܂́A���̎������ꂩ��͗����ɂ��Ă���Ɨ��܂ꂽ�B�ЂƂ͂��܂��܂Ȑl���𑗂�A������Ƃ₩�����������͎��ɂ͂Ȃ��A�]�܂�邪�܂܂̏�����̂��ҏW�҂̖��߂ł���v�Ə����Ă���B�s�k�ߕS��t�i�Ҏ[�Җ��̕\���́u�g�����v�j��1976�N�̊��s�ŁA��L�̎��̐��Ɩ������Ȃ��B
�g�����͎��������܂�����Z�̂��A�����Ŕo�������Ă����B���N��ł����A�\��㔼���������ɂ�����B�����̒Z�̂́q蜾蠃�k�X�K���l��r�i���W�s�����G�߁t�����A�̂��̉̏W�s�����t�j�A�o��́q�z���r�i���W�s����t�����A�̂���W�s�z���t�j�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���B��҂̖��O�́A�Z�̂ł͖{���̋g�������A�o��ł͂ӂ��̉덆���p����ꂽ�B��҂Ɋ֘A����ӏ����s���܂�͂����L�t��������i�\�\�ȉ��͏��т̃R�����g�j�B
�k���a�\�l�N�i���O��j�l�܌�����
�u���́v�ɂ���ނ�ɏo�����傪�f�����Ă���A�����B�k�c�c�l�i�O�܃y�[�W�j
�@�\�\��Җ���J�g�B
�����O��
�k�c�c�l�u���́v�������Ɉ��o��B�k�c�c�l�i�܌܃y�[�W�j
�@�\�\�������AJ�g���`�B
�\�ꌎ��\�O��
�@
��ɂȂ��ĉJ�B�t�˂���Ɨ���O������X�u���W���֍s���B���������̐Ȃ��B����������u��鵶�k�A�l���v�̂߂�߂�A�����A������A��߁A�t���A���b�A�s�F�A�l�G�j�i�����j�ƏW���B�R�[�q�[�A�T���h�C�b�`���Ƃ�Ȃ���A�ݑI�ƂȂ�B���ʁA�т�ɂȂ肪������B�k�c�c�l�i���y�[�W�j
�\���
�k�c�c�l�u���́v�͂��B�O��̂��Ă���B�i��܃y�[�W�j
�@�\�\�s���́t����ɂ�J�g���`�ŁA�O��ł͂Ȃ���傪�f�ڂ���Ă���B
�\�\����i�Ηj�j
�@����͑���鵶�k�A�l���B�k�c�c�l�ݑI�̌��ʁA�ō��\���_�ŁA�l�G�j���Ȃ̏\��_�B�k�c�c�l�i��Z��y�[�W�j
�k���a�\�ܔN�i���l�Z�j�l�ꌎ�\�O��
�@���A����c�̏�����߂����Â������̂͂邩��ɁA���_᫁X�����ԎR��������B�k�c�c�l�i���Z�`��ꎵ�y�[�W�j
�ꌎ��\�l��
�@��A�t�ː搶�Ə��a���q���Ɗw�Z�֍s���B��O��u��鵶�k�A�l���v�̂ǂ��B�k�c�c�l�ݑI�̌��ʁA��\�l�_�Ŏl�G�j���ō��_���Ƃ�B�\�ꎞ�U��B�i����y�[�W�j
��\���
�k�c�c�l��A���̉������B�R�[�q�[���ŁA�J���[���C�X�ƃR�[�q�[�B�����A�t���A�s�F�A���邽���B�ݑI�̌��ʁA�l�ʂƂӂ��Ȃ������B�\�ꎞ�U��B�i��O�Z�y�[�W�j
�@�\�\���O�̋L�ڂȂ����A�l�G�j��p�����ł��낤�B
���ɁA�@�c�������s�z���t�̊����ɕt�����q���r����A���̊Ԃ̎���Ɋ֘A����ӏ��������B
�@�g���́A���a�\�l�N�O��������\�ܔN���ɂ����A�V���o��e�����O�̐V���o��n���u���́v��J�g�̃y���l�[���łقږ����i14�N4�A6�A11�����ɂ͋g����i�̌f�ڂȂ��j��𓊂��Ă����B�i��Z�l�y�[�W�j�@ �܂��Ȃ��A�g��������J�g�̋�́A���a�\�ܔN���u�X��ʁv���I�́q�H�J�̒�E���Ȃ�������߂�r�i�u�E��v�Ɍ�o�j���Ō�Ɂu���́v���炢�����������B�\�ܔN�\�l���ɂ͓����ɂ��V���o��l�̑ߕ߁i����o�厖���j���n�܂�B�g�����g���\�ܔN���ĂɗՎ����W�̂��ߖڍ��勴���n�d���ɓ����A���̂Ƃ��⏑�Ƃ��ėF�l�����ɑ����Ă������̂��A�w����x�����̒Z�̂��܂ޏK�쎍�W�e�w�����G�߁x�i�̂�����S�����j�ł������B������I���Ĉꃖ���]�ŏ��W�����ɂȂ�A�\�Z�N�܌����́u���́v�ɖ{���ň��o�ꂷ�邪�A�u���́v�������ŏI���B�\�Z�N�����ɏo���A�Ȍ�A�o��͑S�������Ȃ��Ȃ�B�i���O�`���l�y�[�W�j
�@ �q���N�Ɓk�t�̌ς̜�ĂȂ�l�r�́u���́v���a�\�Z�N�܌����i�I�����j�́u���͍�i�v���I�B�\�Z�N�ɂȂ�ƐV���o�僊�[�_�[�i�̓��쑐��͎w���I���ꂩ�玩�l���ށA���̍��́u���͍�i�v�͈��Z�ցA�ЎR���j�A���J�Ӛ�A�x�V�ԉ��j�̋��I�������B����̓���͖{���g�����B����ł͉��܁q���Ȃ�r�Ƃ��邪��A�ƌ��Ē����B�O��̓��I��q�H�J�́r�Ƃ̊ԂɈ�N�]�̋�����B���̌�u���́v�͎G�������߂ő����ƕ����u���߁v�ƂȂ邪�A�g����i�͌����Ȃ��B�i���Z�y�[�W�j
�g���������a��l�N�����Z�N�ɂ����āA�ǂ���ɗ��Łs���́t�ɋ�𓊂����Ƃ��̍�Җ���J�g�i�u�����E�˂������v�������́u�����E�˂����v�Ɠǂ�ł����j�ł���A�������ƍ����t�˂����Ƃ̋��ŗp�������͎l�G�j���i��ܔN���̎��W�s�����G�߁t�Ɨ��N���s�t�́t�̍�Җ��͂�������g�����j�B�l�G�j�͏t�ďH�~�l�̋G�߂̂ق��ɁA�����q�K�ɑ���h�ӂ����߂��Ă��邩�i�����Ƃ��A�g�����q�q�K�ɂ�����o��ƒZ�́r�ȑO�Ɏq�K��M�S�ɓǂ`�Ղ͂Ȃ����j�B����Ɂu���E���E���v���u��E���E���E���v�Ǝ������ō\������Ă���̂ɂ́A���R�ȏ�̂��̂�������B����AJ�g���ǂ̂悤�Ȍo�܂ŋg�����̔o��̍��ƂȂ������͂������A�{�l�͌�N���̖����珑�����邵�Ă��Ȃ��B�ȉ��AJ�g�Ɋւ��čl�@����B
���Y��Ԃ̌����l�Ŏ��l�̖ؑ��N�炳��̂������Ɉ˂�AJ�g�̒�����̔����́u�A�C�j���`�[�A�オ���ĉ������ďオ��v�B������ł͐��Ɏg���鎚�����܂��Ă���A���̏ꍇ�͔J�Ƌg�����B᫂́u�����B����̐F�v�ň����͂Ȃ����A���ɂ͎g���Ȃ��B�J�́u���Â��B�����B�Ȃv�Ɣ��ӂ�\�킷����������A�u�ǂ����čK���ɂȂ�悤���v�ł͖��O�Ƃ��Ăӂ��킵���Ȃ��B�ܔN�O�̒������s�̂���A�k���̃K�C�h����J�g�ɂ��Đq�˂�Ɓu���O�ɂ͗ǂ��Ȃ��v�Ƃ̓����������A���ɂ��Ďv��������w���Ă����̂��낤�B
�ł͂Ȃ��g�����A�o���ɒ����l�̂悤�Ȑ������̗p����Ɏ������̂��B��̐��Ɣ�����悤�����A�����Q���s�势�a���T�t�Ɉ˂�u�J�g�i�l�C�L�c�j�v�ɂ́A�����₩�ł悢�A�̈ӂ�����B�g���́u�ǂ����čK���ɂȂ�悤���v�ł͂Ȃ��u�����₩�ł悢�v�J�g��I�͂����B�Ȃ��J�g�͏��R����u�덆�v�ƍl����ׂ��ł͂Ȃ����B�����l�̐����ƍl�����̂����������̂��B����ɕt�����킦��AJ�g�͋g�����Ƃ��������̃A�i�O�����i�u�g���g�v�u����᫁v�u�����J�v�j�ō\������Ă���Ɛ������邱�Ƃ����\���A�Ǝ��͍l���Ă���B
��N�̎��Ƙa�̂ɂ͏����Ƃ��������p�ӂ��Ȃ���A�o��ɂ͂��ɐ��O�A�����̌`��^���邱�Ƃ̂Ȃ������g�����B�����m�푈�̎n�܂钼�O�A��x�܂ň⏑�Ƃ��Ă̎��W�����s���A���g�̐��̍��Ղ��̂������Ƃ����g�����B�g���͂������������Ƃ͕ʂ̐����悤�Ƃ��āAJ�g�̋�A�l�G�j�̋���Y�݂������悤�Ɏv����B
�k�t�L�l
�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�����́q�g�����A���o���r�Ɂu�P�X�R�X�N���A�o�咇�Ԃ����ƁB�v�i���y�[�W�j�ƃL���v�V�����̕t�����W���ʐ^���f�ڂ���Ă���B�����p�̋g���͍őO��ŕG������č��������Ă���A��͂�őO��̒j���D��̂��̂���ɂ��Ă���B����Â炷�ƁA�ǂ��ɂ��u�b���o����v�Ƃ����������ǂ߂�B�Ƃ���A�g���́s���܂�͂����L�t�ɂ��锒鵶�k�A�l���ƕʂ̋��ɂ��W����Ă������ƂɂȂ邪�A�b���o����ɂ��Ă͂܂��Ȃɂ��킩��Ȃ��B
�k2005�N2��28���NjL�l
�t���c�K�F��Y�̈��W�s���n���t�i�k���s�ҁE���s�V��l�A1952�N9��21���j�́q�ҏS��L�r�̈�߂ɁA�Ҏ҂ł��鏼�]��O�Y�i�o�l�̒֍��Y�j�����������Ă���B�u���Ղ�T���l�Ɉ����Ђ낢�W�߂��傪����������A����������������̋��̖͂����̏W��҂����v�i�����A�O��y�[�W�k�����́u���v�������l�j�B�u�������v���O�f�u�b���o����v���w���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂��B����A�֍��Y�̑���W�s�~���k�ߑp���l�t�i�������p�A1974�N9��15���j�̒��ҁq���Ƃ����r�̈�߂ɂ͂�������B�u���a�\�ܔN�c�K�t����l�Ɏ�قǂ��Ĕn���ɓ���A�����H�N�q�搶�Ɋw�ԁv�i�����A����y�[�W�j�B�b���o����������H�N�q��W�s�b���t�i�͏o���[�A1939�j�ɂ�閽���ł��邱�Ƃ��A�܂������Ȃ��B�֍��Y��W�s�~���t�́q���n���@���a�\�Z�N�`���a��\���N�r����A�c�K�t�����b���o����Ɋ֘A�������������B
�@�@�c�K�t���v�l�����@�O��
�@���ޒ|�[����͂˂Ēʖ閾����
�@�G���[��ɖv����ӑ���
�@�t��ɐc�܂œ��āT���E��
�@�k�c�c�l
�@�@���Ȃ�S�ւ�c�K�t����
�@�ĕz�c��y�ɕ~���Ę̂яZ�ނ�
�@���n���ЂƂ�[�M�̂��̂��Ƃ�
�@�@�����o�����U
�@���n���Ƃ���ʖ�X�ƂȂ�ɂ���
�@�@�c�K�t�����H����\�z����@�l��
�@����\������Ƃ��Â��Ɍ��Ђ��I����
�@��_�����Ђ낲��⏑���Ȃ�
�@�H�_�̉��̂��Â��������Ă����
�@�I����M���������u���v�`����
�@�k�c�c�l
�@�@�t����T�k�}�}�l��
�@�t�����ⓤ���̔������ɂ̂�
�@�k�c�c�l
�@�@�t���O���
�@�e������������ɌN�����
�{��W�̕ҔN�̂̕ҏW�ɏƂ点�A�b���o������U�͏t�����H�̏��a26�N9��21�����O�Ɛ��肳���B�u�c�K�t�����A�S���Ȃ̂��Ƃ�ǂ��悤�ɁA�������E�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A��l��y�[�W�j����܂��A�����Ɂi�H�j�����b���o��������U�����̂ł͂���܂����i�����̔o��G���ׂ�A�b���o����Ɋւ���ڂ������Ƃ��킩�邩������Ȃ��j�B1949�i���a24�j�N���s�g�����N���t�ɂ́u�~�̐��֒֍��Y�A�c�K�t���A�r�c�s�F��Ƌ�s�v�ƁA�b���o�����O�f��鵶�k�A�l���̃����o�[�Ƃ̂Ȃ�����f�킹��L�q������B
�k2017�N12��31���NjL�l
�ߓ��A�֍��Y�s�~���t���C���^�[�l�b�g�Ō������āA�F�엲�ۈ��̌��提������������W���w�������B�F�엲�ۂ͓��{��W�̒��������̐l�����A���҂Ƃ̊W�͕s�ځB�����@�����A�ȉ��ɖ{���ڎ��Ɍ����鍀�ځE�M�Җ���������B
����c�c�c�c�c�c�c�c�c�Γc�g��
�k���ҏё��ʐ^�l
���c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�Β˗F��
�_�c��
�@�@���n��
�@�@�~�@�
�@�@�@��
�@�@������
����䶗�
�@�@�ʁ@��
�@�@���@��
�@�@�u�@��
�@�@�~�@��
��c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�ΐ�j�Y
���Ƃ����c�c�c�c�c�c�c�֍��Y
�֍��Y�i����43�N�k1910�N�l���j�́q���Ƃ����r�Ɂu���̏��W�Ŏ����̐ܖڂƂȂ����B���㉽���Ȃ邩�͕���Ȃ��B���邪�܁T�̎��R�ɂ܂����鎖�ɂ���v�i�{���A����y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A�����͂��̈�������̂悤���B�g���́q��z�̔o��\�\�S�@�t���Ƃ��̗F�r�Łu���Y�͍��ł��A�s��̂Ƃ��₳��m�A�A�A�A�A�n�ł���B�����{���̈㏑�o�ŎЂ̏Z�ݍ��ݓX���ł��������A�҂����Ȃ�Ƃ悭���L���H�̖�X��������B�����ĉƋƂ𗹂������Ƃ܂ŁA���E�̎葊�������Ă������Y�������˂�B�ނ͂ɂ�������āA�V�ዾ���ɒu���A�����߂��̔m�ԊقփR�[�q�[�����݂ɗU���Ă��ꂽ�B�^�k�c�c�l�^����O�\�]�N�A�֍��Y�̏�����W�s�~���t�����ɏo���B�u�~��������̂Ă��������ȁv�Ɓu�ጩ�T���U�炷�����v�ɏے������悤�ɁA�����߂����e�������r��ł���v�i���o�́s�����V���t1976�N7��25���A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A��l��`��l��y�[�W�j�Ə����āA�����4��������Ă���B
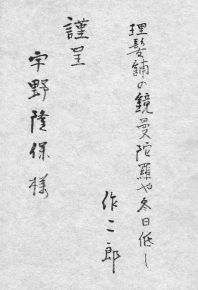
�֍��Y��W�s�~���k�ߑp���l�t�i�������p�A1974�N9��15���j�ɕt���ꂽ���M��E�����E�������̋��ݍ���
�g�����Ƒ���l�Y�̂��Ƃ����������͂��Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ��B�C���^�[�l�b�g�Łu�g�����~����l�Y�v�Ō������Ă݂Ă��A����炵�����̂͌�������Ȃ��B�ŋ߁A����̎���ǂ݂Ȃ����āA�v���̂ق��g���́s�Õ��t��s�m���t�ɋ߂����̂��������i�����ꂽ�������炢���Θb�͋t�Ȃ̂����j�B�g��������̎��ɐG�ꂽ���͂͂Ȃ��悤�����A����͋g���ɂ��Ă������̕��͂��c���Ă���B�q�g�܂��������g�����́u�m���v�r�i�����V���[���A1959�N5��19���j�ɂ���Ȉ�߂�����B
�u���́w�m���x�Ƃ������W�́A���オ�̍ق悭�������Ă��邠����X���̗v�f���A���̎��Ƃ������̂����A�����ɂ����o���ꂽ���J�Ǝc���̃C���[�W�̏Ռ��͂́A���炵�����̂ł������B�������@�Ƃ��ẮA��������`�̎��@���̗p���Ă��邩��A��ʂ̓ǎ҂ɂƂ��ẮA�Ђǂ������ɂ������̂ł���ɂ������Ȃ��B����Ό��㎍�̉\���Ɗ댯���̋Ɍ�����x�ɂ������悤�Ȏ����I��i�����A�����g���܂��̂��̂��A���ɂ܂Ƃ܂��������ȋ@�\��`�̍�i�ɗ^��������A���������������̂���V�����G�l���M�[�ɗ^����������A�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�v�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�A��y�[�W�j
���삪�����Ŏ���I�l�ψ��߂�g���܂̑I�l�ɑ��ĝ����I�Ȍ�����p���Ă���̂́A������u�g�������v�܂��Ă��邽�߂����A����������Ђ��ēǂނƁA���̕]����͑���̗��ꂪ�g���ɋ߂����Ƃ���������B�������A�g���Ƒ��������I�ɕ����̂͂��́u���@�v�ł����āA���삩�猩��g���̎��@�͒�������`�̂���Ƃ������ƂɂȂ�B
����́q�V���������Շ�����ԁr�i���{�o�ϐV���A1967�N12��18���j�ł����̂悤�ɏ����Ă���B
�u�g�������W�i�v���ЁE��A���Z�Z�~�j�́A�����W�ɐV������i�u�Â��ȉƁv�������Ă���B�ނ̎��̎��́A���J�ƍ߂ɂ܂݂ꂽ����̃X�L�����_�������A���̎��I���^�����h�I�Ȏ�@�ɂ䂾�˂Ă���B���Ď��W�u�m���v����Ƃ��A���̈ٗl�Ȏ��I�l���ɂ��ǂ낢�����A����ŁA�͂����Ă��̓��قȎ��I��Ԃ��A�ǂ��܂Ŏ�����������ꂤ�邩�Ƃ����A�����̊뜜�i�����j�����������ꂽ���̂ł���B���������̌㎍�W�u�a���`�v���ւĂ��́u�Â��ȉƁv�ɂ�����z���͂̐V�N�x�ɂ́A���������̐����������Ȃ��B����́A���̑O�q�����[�����݂̔F���͂ɗR�����Ă��邩��ł��낤�B�g���Ƀu���g�����������h�̊拭�i���傤�j�Ȃ���聁���v���������Ƃ́A�����Ďv�����ł͂Ȃ��B�v
����ɂ��Ă݂�u�g���Ƀu���g�����v�������v�͎̂��R��������Ȃ����A����Ƌg�������ʂɒu���ē��������猩��Ȃ�A��͂��قƌ���˂Ȃ�Ȃ��B����͑���̎�����V������`�������`�Ƃ������t�ŕ��������Ȃ��̂Ɠ����ŁA���҂͂��́u�����Ȏ����v�i����͂����炭�A�����������邱�Ƃɑ���搧�U���̈Ӗ������j�����L���邱�Ƃɂ���āA���O�߂��n�_�ɗ����Ă���B���̎����g���́q���b�r�i���W�s�Õ��t�����j�Ɠǂ݂���ׂĂ������������B
�����̃I���t�F�b����l�Y�����ɖʂ���
���̕��������̂��ꖋ�̂܂���ʂ�Ƃ�
�ڂ��̍��͖��ɂȂ���ł�������Ȃ��������̂�
�ӂ����Ȝ��炳�łȂ��ł���
����������
���������菝���悤���Ȃ������炯��
�����̂��̂ɂȂ��Ă��܂����e������
�����߂��䩂�
Ⴢꂽ����͗l���Ђ낰�Ă���̂��S�т̌��e�Ƃ�
�i����῝�Ƃ������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ�
�������ɂ����Ƌٖ���
�����̗[�f���Ƃ����悤�Ȃ���
���̍g���F�̂��Ȃт��̒�����
���̋C�̂����������Ȓ���
�܂��˜��n�ɒ����R���Ă���̂�
�܂��ƂȂ�����ꂳ��
�X���ɂ��炳��Ă���
�g�������s�|�[���E�N���[�̐H��t���܂Ƃ߂ċx�M���̈�㔪�Z�N�����A�s��{ ����l�Y�S���W�t���}�����[���犧�s���ꂽ�i�g���̑����Ȃ̂��낤���j�B�g���͂����ǂƂǂ��ɂ������Ă��Ȃ����A�n�ǂ����̂ł͂���܂����B���̌�̋g���́A���g�̏����⑺��̎����牓������āA�̂��́s��ʁt�̐��E�ւƒ������Ă����̂ł���B

�s��{ ����l�Y�S���W�t�i�}�����[�A1980�N8��25���j �i�{�[�����E�\���ƕ\��
�O��A�b�v�������낾����W�s���씼���t�֘A�̎�����T���Ă�����A�g������Ɉ��Ă����Ȃ̍T�����o�Ă����B������Ȃɂ��̉����� ����Ȃ��� ��A�ȉ��ɍĘ^���悤�B
�@���t�������肪�Ƃ��������܂����B���̂��Ƃ���������v�ۂ̔o�啶�w�قł���q�_��r��q�ǂ��A�i���̗��^�� �b�̍��j���� �łȂ��A�{�[�h���[���̎U �����̎�������A�����܂����B���̐[�ǂ݂łȂ���A�t���C�U�[�̍ł��Ô��ȕ��������f����Ă���Ǝv���܂������A�i�����܂��Y������j�̌������̑O �ł́A�����ďd�v�Ȃ��Ƃł͂���܂��܂��B�@�ْ��k���낾����W�s���씼���t�l�ɑ��ĉ��l�����炲�Ԏ������������܂����B�O���q�Y���A�]�������A�����Y�q���A��ˏ~�v ���A����È� ���A�Ԕ��b�Ȏ��A��t�^�|���ȂǁB�F�l��m�l�͂Ȃ��Ȃ���������Ă���悤�ł��B
�@���āA��ɂ����܂����]�߁k�u�� ����ԁv�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i3�j�\�\�q���́r�l �����͂����܂��B��N���l���Ă���ƒ����������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����A���ׂȂ���ו��𖡂키�y���݂���͂Ȃ��Ȃ��������܂���B�����Ⴂ�̓_����� ���ł�����A�������˂������������܂��B�s�_��I�Ȏ���̎��t�S�т��قȂ����X�^�C���Ř_���Ă݂����A�Ƃ����̂����ʂ̖ڕW�ł��B
�@�܂����ڂɂ������@�����Ɗy���݂ɂ��Ă���܂��B���̂Ƃ��܂łɂ͂Ȃ�Ƃ����d�グ�����v���Ă���܂��B�����Ȃ�� ���B���̂�� �ɂȂ����Ă��������B�����Ȃ��炷�炵����i��҂��Ă��܂��B
�@��㔪��E�\��E��
���ш�Y
�@�g�����l
�u�s�_��I�Ȏ���̎��t�S�т��قȂ����X�^�C���Ř_���Ă݂����v�Ƃ���������A�����猩��Ƃ����h�����A�g������̑z���o�̂��߂ɂ��� �Ă��̂܂܌f �ڂ��邱�Ƃɂ����B�O������i�g�������Âԉ�ł������ڂɂ��������j���A�]�������A���쎁�����łɋS�Ђɓ����Ă���B
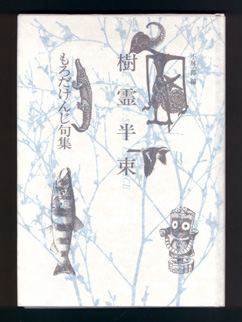
���낾����W�s���씼���t �W���P�b�g�i���Y��ԁA1989�N9��15���j
��
���ɂ��f�肵�Ă����ƁA���낾���͎��̒Z���^���w���M���̕M���ŁA��W�s���씼���t�i���Y��ԁA1989�j�͋g�����ɕ������Ă���B�����Ƃ��A����
�Ȃ茣������̒P�s�{�ɂ���̂͂��߂��ꂽ�B�v�o�o�͂��R�s�[���������{�́A���P��F�����X�g�A���Ȃ������݂������Y��ԓ��l�ւƓ����ɁA�g�������
���鋰�邨���肵�����̂��i���̕ӂ̌o�܂́A�{�������Ƃ����ɂ��������j�B�ǂ��ɂ����ዾ�ɓK�����炵
���A�u�R�s�[�{����Ȃ��āA������
�ł������炿���ƈ�������{�ɂ���v�Ƃ����߂����������B�����̋������傤�������������R�ł���B�E��A��W�������������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
���́s�g�����̎��̐��E�t�ł��u���낾����W�s���씼���t�v�����x���o�ꂷ��̂ŁA�v�������đS�����f�ڂ��邱�Ƃɂ����B���Ƃ���i�Ƃ��Đ��ɖ₤
�킯�ł͂Ȃ��A�T�C�g�쐬�҂̑��N�ɘj���ĕς��ʊS�݂̍菈�������ɉ߂��Ȃ��B���������āA�o��ӏ��ɂ̓����N���ĕʃy�[�W���J���悤�ɂ������A
�g�b�v�y�[�W�́q�ڎ��r�ɂ͋L�ڂ��Ȃ������B

�����ÒÁs�V�� �v�����@���X笕M�t�i�哌�o�ŎЁA1970�N3��15���j�̔��k�����F�����ÒÁl�Ɠ��s�v��ヷ���X笕M�t�i�����o�ŁA1947�N8��20���j�̕\���k�G�F�؉��ۑ��Y�l
�g�����́q�w�v��ヷ���X���M�x�̂��Ɓr�i���o�́s���Y�t���Z��N�܌����A����q�������@�����ÒÒ��w�v��ヷ���X笕M�x�r�j�������n�߂Ă���B
�@�����ÒÁw�v��ヷ���X���M�x���o�ł��ꂽ�̂́A���a��\��N������\����k�}�}�l�ł���B���������ɋ߂��������҂̂��̖{���A�ǂ��������@�Ŏ�ɓ���A�����Ď��͓ǂ̂��낤���B���܋L�������ǂ��Ă݂�ƁA���a��\�O�N���I��߂����낾�Ǝv���B���͏��p�œ����o�Ŋ�����ЂɊW����m�l�������˂��B���̂�����ɁA�ǂ�ł��ǂ݂������̂����������A�O�������čs���Ƃ���ꂽ�B�r��ł����A���������ς܂ꂽ�ԕi���炵���{�̒�����A�O���̂������{��I�B����́A�w�v��ヷ���X���M�x�ł���A���̓���́A���e���O�Y���W�w���ނ��肠�x�Ɓw���l���ւ炸�x�ł������B���͋��R���̂Ƃ����e���Əo�������B�����āA���_�̂��܂�Ȃ����̎����_�͂��̓���̋L�O��I��i�ɑN��ȏՌ����������Ƃ�����B�������ʂ̈���A�����ÒẤw�v��ヷ���X���M�x�́A���̓��̂̋Q�����������������߂Ă��ꂽ�̂ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�`��܃y�[�W�j
���g�̓����̓��L�̈�߂Ɩ{���̈��p���܂ފȒP�ȏЉ�̂��ƁA�g���͂����܂Ƃ߂Ă���B
�@���҂̂��Ƃɂ��A�H�ו��̂��Ƃ���ɏI�n�����Ƃ̂��Ƃ����A�����ɂ͈߂�Z�╗�����A�����Ēn���C�������̗��]�A���j�܂ł����₩�ɟ���ł���A���j�[�N�Ȑ��z�W�Ƃ����邾�낤�B���͔��������{�̍Ċ���҂��Ă���B�i���O�A��܃y�[�W�B��A�͈��p�҂��������j
�g���̕��͂����\���ꂽ����㎵�Z�N�̎O���A�s�V�� �v�����@���X笕M�t���哌�o�ŎЂ��犧�s���ꂽ�B���҂̑����ÒẤq���r�i�����͐����������B��A�͈��p�҂��������j�ɂ��������Ă���B�i�����A��`�O�y�[�W�j
�@�w�v��ヷ���X笕M�x�Ƒ肵���������͂��߂Đ��ɏo�����̂́A�푈����̏��a��\��N�����A���͑��݂��ʓ����o�Ŋ�����Ђ���ł����B���ЂŁA��c�F���Y�����ҏS���Ă���ꂽ�w�Y��閒���x�ƁA���ݏo�ŊE�ɗY���㓡�Ύ����̐�N�^���Y���́w���E���x�Ƃɍڂ��ė����v�����@���X�W�̏������W�߂����̂ł���B���̐����������z��������̂��ƂƂāA�e���Ȏ��ɂa�Z����S��\��ł̏��������A�\���͂킪�ԕ�̓I�ł����؉��ۑ��Y�i���c���Y�j�搶�̕M�ɐ���A���������W�ʂ̉��M����Ȃď����Ă�B
�@���҂͓������o�ĂفU���̌�A��g��̓s���ɂ��A�i���R�̓����ė��������B�]�ē����Ɋւ��鐢�̔�]�ɂ��ĂقƂ�ǒm�鏊���Ȃ������A�ŋ߂ɓ���A���啧��������㋆��Y�����G���w���Y�x�i���a�l�\�O�N�������j�́u�������@�v���ɓ������u���@�v���ĉ�����A�X�ɍ�N�l����\�����̒����V���w�|���u�����Љ�v�ɁA��Ƌe�r�d�O�Y���������������Ă�����|�𑼂���m�炳��A���Â�ɂ��ӊO�Ȋ�т��o�����B
�@�k�c�c�l
�@�Ō�ɁA���㍑�����x�ւ̔��R�̂��̏������s�����哌�o�ŎЂ̏�ɁA�{�������S�Ƃ��Ă݂̂ɏI��ʂ��ƂS�O���ğ[�܂Ȃ��B�@�@���a�l�\�ܔN�ꌎ
�����ÒÁ@
�Ȃ�ƁA�g�������s���Y�t���a�l�l�N�܌����́q�������@�r�Ɂs�v��ヷ���X笕M�t�̂��Ƃ��������O�N�̔����ɓ����G���̓������ɓ����{����㋆��Y�ɂ���Ď�肠�����A�������a�l�l�N�̎l�����i�Ƃ����A�g�������G���Ɍf�ڂ��ꂽ�̂Ƃقړ����j�̐V���ɓ����{�i��������Z�N�ȏ���O�ɏo�ł��ꂽ�����j����肠������Ƃ����A���낵���܂ł̋��R�B�����̍Ċ��͂��̂悤�Ɋe���ʂ���Җ]����Ă����킯�����A�ɂ��ނ炭�͋g���̊��҂���u���������{�v�ƂȂ肦�Ȃ������悤���B���҂̃X�P�b�`��ɂ͊���Ԃ�ɂ��Ă��A���Ԃ��͉����ŁA�m�h�ł��˂��Ă��邵�A�S���������Ƃ���ŁA�����͒��҂����ׂ��ł͂Ȃ������i�g���ɑ����������������I�j�B���̓_�A�ۑ��Y�̑��Ԃ��\���������Ă��錳�ł́A���^�Ȕ�������X���Ă���B�Ï��X�Ō���������߂̌��ł́A���e���O�Y���W�ƕ��ׂĂ��炦��悤�A��ˎ闝����ɑ������B
�k2004�N7��31���NjL�l
���̌�A�����ÒẤs�b�����w�U���t�i�����ЁA1956�N9��25���j�Ɓs�b�����w�A���o���t�i�����V���ЁA1969�N1��20���j�������B�s�b�����w�A���o���t�̖{���ʐ^�͒��҂̎B�e�ł����āA�����̊G�S�͂����Ɋ������ꂽ�B�A���o�����u�A���O���̃��B�I�����v�i�q���r�j�ȏ�̂��̂ɂ��Ă���̂́A�p���̕��w�^���w�̃p���ɑ��鈤��䂦�ł��낤�B�Ƃ��Ɂs�b�����w�U���t�̖{���͐��������������A��O�N��́s�b�����w�A���o���t�́q��r�����u���������ЁA���튿���v�őg�ł���Ă�����̂́A�{���́u�[�ނȂ��V���x�ɏ]�ӂ��ƁT�����B�⊶�̋ɂ݂ł���B�v�i�q��r�j�ƁA�V���V���ȑg�݂ł��邱�Ƃ̕s�{�ӂ��������Ă���B��������Ɉ��p�����q���r�Łs�V�� �v�����@���X笕M�t�i�����܂ł��Ȃ��A�{���������������g�݁j���u���㍑�����x�ւ̔��R�́v���ƌĂw�i�ɂ́A������������������B
�g�����̊��ɖk�����H���I�̏W�s�Ԋ~�t���[�߂�ꂽ���Ƃ͏ے��I�ł���B���w�I�o�������ہA�Z�̂ւ̈����ƂƂ��ɕK�����������ɏo�� �Ă����{���A ���̍Ŋ��������������炾�B�g���͉��x���U���Ŕ��H�̒Z�̂ɐG��Ă���A���p�����̂��������i���O����A������Z��j�B�����ł͊p�x��ς��āA�s�Ԋ~�t ���g�������̌�b�ɗ^�����e�������Ă݂����i�p�[�������̐����́s�Ԋ~�t�̃m���u���j�B
�s�˂̉ԁt�i5�j
�q�����r�i26�j
�Ƃ肩�ւ锖�m�������n�����m���邩��n���݂ǂ�̂Ђ�т낵��ɍ��͏o�ł��i77�j
����Ɨ[���肭��Ώ�P���̋���[�������n��������������������i104�j
�q����r�i110�j
�q���q���r�i117�j
�������̌{�m�Ƃ�n������͂��Ƃ���ɂ����ӂ�͂��Â��̌{�m�Ƃ�n���i120�j
���d�@�m�_�C�i���n�̉��������������Y���ʂ��̂��̐���������Ђɂ���i145�j
�����Ԃ镓�m���Ԃ�n�����ɖڂނ�͐[�ނ炳���̎�[���тȂ��n�̊��i156�j
���悩���Ɏq�����V��ł���冋o�m�������낱���n�͂��ɐ^�g�m�܂��n�Ȗт�h��Ă��i214�j
�̏W���̕W��́A�g�����̎��сq�˂̉ԁr�q�����r�q����r�q�����q杁r�Ɠ������A�߂����̂��B�g���̎���͌Ɏw�E���Ȃ����A�̏W �s�����t�ȊO�� ����b�┭�z�̓_�Ŕ��H�Z�̂���̉e���͑傫�������悤���B�s�Ԋ~�t�͍L���ǂ܂�Ă���A���a�O�i���j�N��Z���O�Z�������Њ��̏��ł̂��ƁA��N�� �̏��a�܁i���O�Z�j�N�㌎���ɂ͑��������ɖ{�ɂȂ��Ă���i�������ɁE���Z��сj�B
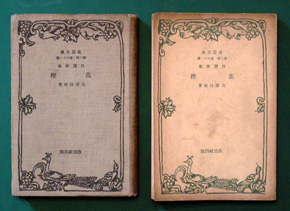
�k�����H���I�̏W�s�Ԋ~�t��26���i�����ЁE�������ɁA1933�N7��12���j�Ƒ�29��
�i���A1936�N5��27���j�̕\��
���̂����Ă���s�Ԋ~�t�̈���͕z���ŏ��a���N�������́u��\�Z�Łv�A��������͎����ŏ��a���N�܌����́u����Łv�B�g������������ �Ă����̂͂� �Ԃ�z�����낤�B�g���͂��̎����Ƃ��Ă̖{�ɂ��āA�q�s�Ԋ~�t��r�i���o�́s�R�X���X�t1972�N11�����j�ɂ��������Ă���B
�@���͍ϏB�����畜�������B�Č��Ǝ�̎����������āA�p�Ђ̓����֖߂����B�ܔN�O�ɏo��Ƃ������Ă��������̂� ��������� ���������B�ꂪ����ɂƓn���Ă��ꂽ����V�̈�{�̔��Ɣ��H�́s�Ԋ~�t����ł������B�r�����瑡��ꂽ�̂��A���O���N�㌎��\����ł��邩��A���ɎO �\�l�N�̍Ό����o�Ă���B�킪�Ƃɂ��鏑���̂�����ԌÂ����̂ł��낤�B���łɁA�{�łȂ����ۂƂ����ׂ���������Ȃ��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k���� �Łl�t�A�}�����[�A1988�A���y�[�W�j
 �@
�@
�g�����ҏW�́s�����܁t105���i�}�����[�A1978�N1���j�̕\���i���j�Ɠ��E�����V�g�q�Ɋނ̑T�m�B�r�`���y�[�W�i�E�j
�N���ɂ��ƁA�g�����͈�㎵��N�ꌎ�A�s�����܁t�i���Z��N�܌��n���̒}�����[�̂o�q���j�̕ҏW��C�ƂȂ�A��㎵���N�i�g���͂��̔N��ꌎ�ɒ}����ގЁj�����̈��ꍆ�܂œ�����S�����A��y��m�Ȃɂ������̌��e���˗����Ă���B����͋�Z�����܂�̂��̂Ȃ�����A��������Ă݂����B�Ƃ���ŁA�g���̍����V�g�ւ̒����q�_�K�o�W�W���M�a����A���悤�Ȃ�r�i�P�s�{�����^�j�̈�߂ɂ�������B
�@�����ҏW�Ɍg������o�q���u�����܁v�ɁA�����V�g����́u�Ɋނ̑T�m�B�v���f�ڂ����Ē����܂����B�T�@�̖���`���镶�͂͂����V�N�ŁA���ɂ��悫���ƂȂ�܂����B����ɖ����̂悤�ɂ��������A���ق̂��ĂȂ����A�G�k�Ɏ��Ԃ��Y��A�����������Ƃ���������܂����B�i�s�����C�J�t�A1987�N7�����A�l�O�y�[�W�j
�����V�g�q�Ɋނ̑T�m�B�r�̘A�ڂ��n�܂�����Z�܍��i��㎵���N�ꌎ�j�̃��C���i�b�v���������B�ڎ������������Ă݂悤�B
�c�O�Ȃ��瓖���́s�����܁t�ɂ͕ҏW��L���Ȃ��A�ҏW�ҁE�g�����̐��̐������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���̖ڎ������ׂĂ�����Ă��悤�i�ЂƂ��L����A�g���̎����q�e�̋��r�i�I�E17�j�͈�㎵�Z�N�A�R�{���q��̃I�t�Z�b�g�ʼn�W�s�⋾�t�Ɋ�ꂽ��i�ł���j�B�N���W�b�g�͂Ȃ����̂́A�g�����g�����t��S�������\��������B���̓����A�g�����ҏW�́s�����܁t�S����ǔj���������̂��B
�C���^�[�l�b�g�Łu�g�����v���������Ă���ƁA�Ƃ��ǂ������炪�\�z�����Ă��Ȃ������y�[�W�ɏo����Ƃ�����B���Ƃ��Γ�Z�Z��N�� �ꌎ���sLogged tree under 1610�t�̎��̋L���B
�u����͝f�v����Ȃ��v�@�v�Ă����֗^�̒j��
�� �N�����`�l�����a���i�k���N�j�ɂ��v�ėT�����Փ����i52�j���f�v�Ɋ֗^�����Ƃ���铌���s���ݏZ�̍ݓ����N�l�j�����l���܂łɁA�����ʐM�̎�� �Ɂu����͝f�v����Ȃ��v�u���͘b���鎞������Ȃ��B�����͂͂����肷��v�ȂǂƘb�����B�k�c�c�l�ΐ쌧�x�̒��ׂȂǂł́A���̒j���͈�㎵�Z�\�����N ����A�u�g�����v�Ɩ����l������d�b�ŌĂяo����u�����͖k���N�H����̃L�����B���͂��Ȃ��Ɓi�k���N�ɋA�������j������̂��߂ɂȂ�Ȃ��v�Ƌ����� ���B�k�c�c�l
�u�k���N�H����̃L���v���u�g�����v���x������㎵�Z�A�����N�Ƃ����ƁA���l�E�g�����́s�T�t�����E�݁t�ō������܂���܂��A���̊W �ŐV������ ���Ɏ�肠������@������������i�q�g �����Q�l�����ژ^�r�Q �Ɓj�B���{�l�̖��O�Ƃ��āA���A���e�B���������Ƃ������Ƃ��B���ɋ�����̂́A���̉f��ɓo�ꂷ��u�g�����v�ł���B���̃y�[�W���s���t�B�����O���t�B�t�B
���@�w�h���~�t�@���̌��͑����x�i�k19�l85�j
�u�� ���Ƃ����܂����A�g������v�Ƃ����ɂ߂��̖��䎌�ƂƂ��ɁA����f��̃f�B�[�o�A�����ˎq�����߂ēo�ꂷ��B�u�g�����v�i���������j������o���h�̒��� �ȉ��t�������J�Z�b�g�v���[���[�����肵�߂āu�c�Ɂv����o�Ă����H�q�i�����j�́A��w�Ƃ������m�̐��E��T�����邤���Ɂu���v���ǂ����ɒu���Y��A�S ���w�����̕��R�i�ɒO�\�O�j���Nj�����u�Ɍ��I�p�������ψفv�̎����ɁA���̖��C�ɋP���g�̂���邱�ƂɂȂ�B�k�c�c�l
�� �㔪�l�N�A�g�����͑O�N�Ɋ��s�������W�s��ʁt�œ����L�O����܂���܂��Ă���B���������́u�g�����v�͂��悻�s��ʁt�̎��l�Ǝ����Ƃ���͂Ȃ����A���� ���̎��l�E�g�����ւ̃I�}�[�W���������̂�������Ȃ��B�g������Ɂs�h���~�t�@���̌��͑����t�ɂ��Đu���Ă����悩�����B
�k2003�N10��31���NjL�l
���̌�A���ē�i�́s�n���̌x�����t�i1992�j�ɐz�K���N������Ƃ���́u�g�����v���o�ꂷ�邱�Ƃ�m�����B�܂���i�͊ςĂ��Ȃ����A����ē�
���m�M�Ƈ��ł���B

�u���C�|�[���̎���ŗx�閺�����v�k�G���̐蔲���̂��߁A�o�T�s�ځl
��㔪�Z�N��̋g������k�������ł��낤�����̂ЂƂɁA�t���C�U�[�s���}�сt�i�i������A��g���ɁA���ł�1966�`67�N���j������B�g���̎��сq�}�сr��q�ØI�r���ڍׂɘ_����ɂ͕ʍe��v����̂ŁA�����ł͎��W�s��ʁt��s���[���h���b�v�t�̎���̃X���X�Ǝv������������i�������͊����A�A���r�A�����̓y�[�W���j�B
�E�o�C�G�����̃��C���n���A���邢�͂܂��w�b�Z���̔_���́A��r���r��܂����ꍇ�ɁA�֎q�̋r�ɕ��������}�т����邻���ł���B�i��E114�j
�E�^����������˂�����@�����肵�ăM���[�Ɩ�����B�i��E277�j
�E�u�܌��̎��v���u�܌��̖_�v�i��E279�j
�E���ɂ��̉����Ɍ��������A��オ�H�т̖[�ł����Ă�������썰���͂������ނƁA��������ɗނ�����̂̒f�Ђ̂悤�Ȍ`�������썰��⥂ŎƂ߂���B�i��E85�j
�E���J�P�X�ɔx�a�킹�ĕ������B�i�l�E126�j
�g���̎���͌Ɏw�E���Ȃ����A�s���}�сt�̂��������Ɂu����g�����v�̐��E�ƒʂ�����̂�F�߂��ɂ͂����Ȃ��B���Ƃ��H�@�i���̗��^���b�̍��j�I
�܌��̎��܌��̖_�ɓ]���₷���i���낾����W�s���씼���t�A���Y��ԁA1989�A��Z�y�[�W�j
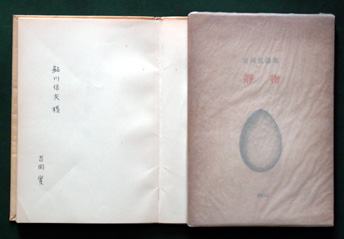
�g����������M�v�Ɍ��������W�s�Õ��t���� ���Ԃ��Ɣ�
���̎����A�����E�ڍ��̓��{�ߑ㕶�w�قŁA�g���������W�s�Õ��t�̍e�{�i���W����p���e�j���{������@��Ɍb�܂ꂽ�B�����ł͈ٕ��̏ڍׂɐG��Ȃ����i�e�{�͏e�����A���s���ꂽ���W�s�Õ��t�ƈقȂ鎚����������j�A�S�т��������낵�䂦�̓���������̂ŁA�T�����L�����Ƃɂ���B�����e�{�̑��݂�m�����̂́A��㔪�Z�N�A�g���̐��z�q�R���̃A���o���r�Ɉ˂��Ă������B
�@�킽���̑�Ȃ��́\�\�Ƃ����e�[�}�ŏ������Ƃ��������Ă��܂������A�����l���Ă݂�Ƃނ��������̂ō������B�k�c�c�l�ʂȕ��ł́A���W�s�Õ��t�̌��e�i����͏������̂ɁA�B��̌��e�̎c���Ă�����́j�B����ɓ�\�ΑO��̓��L�B���m�[�g�B�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�A�v���ЁA1980�A���l�y�[�W�B���o�͒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t82���A1967�N5��20���j
�e�{�̎����������̂́s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�ŔN���E������S�����邱�Ƃ����܂�A�ďC�̕��o������A�ҏW�̑�������j����Ƌg���z�q���������ɖK�˂�����Z�N�������Ǝv���B�������܂����ւ�Ȏ������ƋC�Â������̂́A���܂�̏d�v���ɂƂ��Ă��肾���E�C�͂Ȃ������B���̂Ƃ��͂��ꂪ�����ɂ���ƒm���������ŁA�y�[�W���J���Ă����Ȃ��i�������s�m���t�̍e�{������͂������A�z�q�������\�`���������̂�������Ȃ��j�B�ȗ��A�s�Õ��t�̂��Ƃ��l���邽�тɂ����ƍe�{��z�������Ȃ��ł͂Ȃ��������A��N�A�ɂ킩�ɂ��̑��݂��N���[�Y�A�b�v���ꂽ�B�e�{���s���{�ߑ㕶�w�فt�ŏЉ�ꂽ�̂ł���B�u�n���l�Z���N�L�O���W�v�̍��k��q���w�ق̍���̉ۑ�r�i�o�Ȃ͒������E����玟�E�\��L��j�ŁA�ٗ������ɂ��Ď��l�̒������������������Ă���B
�����@ ����́A���|�}���̏o�ŎЂ������I�ɒ��Ղ�����A���҂��Ɏ҂̂��ӎv�Ŋ��Ă�������V���̐}���G���������āA�Â����̂ɂ��ẮA�A���邢�͊�����Ă�������̂�҂����Ƃ����p���ł��ˁB�����ŁA���l�̌��e�������Ƃق����A���̎��l�����ɂ͂��肢����Β��Ղł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���t���āA�S������̕��X�ɐ�����������A���ŏ����Ă����������̂ł��B�^���Ƃ��A�g�����́u�Õ��v�Ƃ������W�̌��e�̑S�҂{�������̂��g���v�l���璸���܂������A�J��r���Y�A�ѓ��k�ꂻ�̑��̕��X��������Ղ��܂����B�i�s���{�ߑ㕶�w�فt��189���A2002�N9��15���A��y�[�W�j
�u�g�����́u�Õ��v�Ƃ������W�̌��e�̑S�҂{�������́v�́A����ɂ��̒��ʂ̈�y�[�W���ʐ^�łŌf�����Ă���B�L���v�V�����ɂ́u���N�l���A�v�l���炲�����������g�����u�Õ��v���e�v�Ƃ���B�e�{�̑��݂�m���ē�O�N��̓�Z�Z�O�N���������A�悤�₭�Ζʂ��邱�Ƃ��������̂ł���B
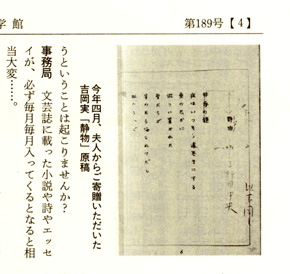
�g�������W�s�Õ��t�e�{�k�s���{�ߑ㕶�w�فt��189������l
�e�{�̊T�v�Ɉڂ낤�B�O���͏ۉ�F�̃N���X���ŁA�p�w�̏����{�i�V�n��Z�܁~���E�ꔪ�l�~�����[�g���j�B�W�蓙�͋L����Ă��Ȃ��B���Ԃ��͕\���Ɠ��n�F�ŁA�\�����̌Г��ꕔ���ɕϐF��������B�{���̑O���Z�����F�̕ʒ��i�������̋L�ڂ͂Ȃ��j�ŋ���ł���̂́A�����������͕ی�̂��߂��B���ɗz�q�v�l���������Ɉ��Ă����ȁi��Z�Z��N�l���ꔪ���t�j�ɂ�����悤�ɁA�e�{�͈���p�̓��e���e��ܒԂ��ɂ��āA�w�����ł������Ă���i���e���͌��J����ԂŁA�E�[��ŒԂ������Ղ�����j�B
�{���͑S���ŎO�㒚�B���̂����y���i�������O�Ɂu�y�}�����[�E���e�p���z�v�Ƃ����Z���l�߁E��Z�s�A���F�̓O���[�j�̓\��������A����͌ォ������e�i�u�g�������W�v�Ɓu�U�@�]�́v�j��}���������߁B�q�~�̉́r�ɁA�i���o�����O�i����������e��̌�A�����ɑł������́j���l���Ƒ��ܒ������Ⴆ�ĒԂ���Ƃ�������������B�ܒԂ����̌��e�p���̃T�C�Y�͓V�n��Z�Z�~���E�ꎵ���~�����[�g���A��Z���l�߁E��Z�s�i�����㕔�ɋ����A�����Ɂu�}�����[�v�̖�����j�ŁA���F�̓O���[�B�y���A�l�Z�Z���l�ߌ��e�p���Ƃ��A�����̋Ζ���̂��̂��낤�B
�M�L�p��͇@�u���[�u���b�N�C���N�E�y���k�i1�j�ӂ��̔Z���Ɓi2�j�Z�����́l�A�A�ԃC���N�E�y���A�B���M�k�i1�j�ׂ����̂Ɓi2�j�������́l�A�C�ԉ��M�A��4��ށB�@�́i1�j�u���[�u���b�N�C���N�͖{���ɗp�����A�i2�j�Z���u���[�u���b�N�C���N�́A���e�p���̊e�y�[�W�������ɋL���ꂽ�m���u���A�ڎ����e�A�ꕔ�̖{�����M�⎚��̏C���ɗp�����Ă���B�A�̐ԃC���N�E�y���͑g�ŗp�w��Ɏg���Ă���A�ȏ�̇@�ƇA�͋g�����̎�ɂȂ�B�B�͂ǂ�����m���u���p�ŁA�i1�j�ׂ̍����M�����͌��e�p���̒ǂ����A�i2�j�̑������M�����͑O�f�y�������m���u���̏C���p�i���e�p���Ɗ��{�̃m���u���̊W�͌�q����j�B�C�̐ԉ��M�����́A�A�Ƃ͕ʂ̑g�Ŏw��p�B
�M�L�̏�Ԃ���̎ʐ^�Ő������悤�B�܂���s�A�L�œ�s�߂̘Z�}�X�߂���薼�́u�Õ��v�A��s�����Ďl�s�߂̎O�}�X�߂���{�����n�܂�X�^�C���͑S���тƂ����ʂŁA��L�@�́i1�j�B�薼�Ɂu12p�k�|�C���g�l�v�Ɗ����̑傫�����A�u4�s�v�h���Ƒ薼�̍s�h�����w�肵���̂��A�B����Ƃ͕ʂɑ薼�̎��������u3�����Q�v�A�薼�̍s�h�����u3�s�ڒ����v�A���̑g�̍ق��u�ȉ������v�A�ƇC�ŋL�������͈̂�������낤�i���������{�ł͋g���̎w��ǂ���A�薼�͎l�s�h�������ɂȂ��Ă���j�B
�ʐ^�ł̍e�{�͎��̓�_�ł܂��Ƃɋ����[���B�܂��A���s���u��݁k�������́u�v�A���߂́u�y�v�u�q�v�ǂ��炩���ɏ����ď㏑�����Ă���l�̋��v�Ƃ������̂�Ԑ��ŏ����Ă���_�B���ꂾ���ł��Ռ��I�����A���̃i���o�����O��l����������ɓn�������_�Ńi���o�����O��O���̒����u�T�@�Õ��v�̂������Ƃɒu����Ă��������ɁA�����͋��|����i�y�������A���M�����̃m���u���Ƃ��i���o�����O�Ɠ��������������j�B���Ȃ킿�q�Õ��k��͂��������������ɂ���l�r�����A�s�Õ��t�̊������т������̂��B�薼�̑g�̍قŁu�ȉ������v�Ƃ���̂����̃i���o�����O��l�������Ȃ̂��A������e���̊�����i���{�т��������Ƃ𗠕t����B������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̖`���͏����ȗ��A��т��āq�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�ł���A�e�{�ł��ŏ��̍�i�Ƃ��Đ��{���Ă���i�i���o�����O��O���̂��ƁA�܁E�Z�E�l�E���c�c�Ƒ����Ă���j�B�g���͎��W�̍Z���i�K�̂��鎞�_�ŁA�q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�����������тɂӂ��킵���Ƃ����f���������̂��i���s�́u��̊�̍d���ʂ̓����Łv�Ƃ������̂��A���M�Łu���v�ꕶ�������Ă���j�B�������A�Z�����֘A�͌��݂܂Ō��\����Ă��Ȃ��̂ŁA����ȏ�̂��Ƃ͂킩��Ȃ��B
������ɂ��Ă��A���W����p���e�{�����͈̂��܌ܔN�Ɏ��W�����s���ꂽ���Ƃ̂��Ƃ��낤�i�s�Õ��t�̊v���{�𐧍삵�������A�A�C�{���[�̃N���X���g����������i�̌����邱�낪�肪����ƂȂ낤�j�B���Y���P�́q�n�܂�Ƃ��̏��Ł\�\�g�����w�Õ��x�r�ł��������Ă���B
�������A�����Ŏn�܂�Ƃ����̂́A�قƂ�Nj������̂悤�ɏo�����������̋N���̖͑��ł���ɂ������A���̈�s�k�u��̊�̍d���ʂ̓��Łv�̂��Ɓl����������Ƃ��납�玢�]�̂��ׂĂ�����o�����Ƃ����悤�Ȑ^���̎��ԓI�N�_���������Â����Ă���킯�ł͂Ȃ��B��҂����ۂɂ��̈�s�ł����Ĕނ̏������W�������o�����̂��ǂ����͐��m�ɂ͂킩��Ȃ��B���������ł͂Ȃ��̂��낤���A������ꂪ���W�̑��s�Ƃ��ēǂތ��t�̘A�Ȃ�ɂ����Ƃ���ŁA�܂��M���������������̌��t�����̂܂܂̂������Ŏc����Ă���̂ł��Ȃ��A��ɂȂ��Ă̑R��ׂ����M�E�����E�폜���o�������ōŏI�I�ɏ����̖`�������邱�ƂɂȂ����̂��낤�B�i�s�G�s�X�e�[���[�U�t1���A1985�N8���A�l�ܓ�y�[�W�j
�e�{�������ɏ������ł��낤���Y�̋���ׂ��d��ł���B���ɁA�s�Õ��t���{�̃m���u���Ɠ��e�̑Ή��\���f���悤�i���{�ߑ㕶�w�قɂ͋g�����������Ɍ�������{����������Ă���j�B�{���́A��Z�y�[�W��܂̎l�ܕ��Ɣ��y�[�W��ܕ��̌v�ܐ܁A����y�[�W���琬���Ă���B
�m���u�� ���e �W�蓙 �u�m���u���v���́i�@�j�ň͂��������͊��{�ł͉B���m���u��
�ʒ��E�\ �k�{���l �g�������W�@�Õ�
�ʒ��E�� �k���l
(1) �k�����l �g�������W
2�`3 �k�ڎ��l ���W �Õ� �ڎ�
�i4�j �k���l
�i5�j �k�����l �T�@��
6�`8 �q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r
�i9�j �k���l
10�`11 �q�Õ��k��͂��������������ɂ���l�r
12�`13 �q�Õ��k���̂Ȃ��r�̓��́l�r
14�`16 �q�Õ��k�䏊�̉��ꂽ���l�r
�i17�j �k���l
18�`19 �q���鐢�E�r
20�`21 �q���r
22�`23 �q���r
24�`28 �q�~�̉́r
�i29�j �k���l
30�`32 �q�Ă̊G�r
�i33�j �k���l
34�`36 �q���i�r
�i37�j �k�����l �U�@�]��
38�`41 �q�]�́r
42�`46 �q�҉́r
�i47�j �k���l
48�`50 �q�W�����O���r
�i51�j �k���l
52�`55 �q��r
56�`59 �q���b�r
60�`65 �q���̏ё��r
66�`69 �q�ߋ��r
�i70�j �k�{���ŏI�y�[�W�l ���W�@�L
�i71�j �k���t�l
�i72�j �k���l
�m���u���ɂ��đ�v�������B�e�{�ɋL���ꂽ�m���u���ɂ͓�̑��ʂ�����B���́A�q�Õ��k��͂��������������ɂ���l�r�́u2�v�Ɏn�܂�q�ߋ��r�́u67�v�ɏI���i�������q���鐢�E�r�ɂ͋L����Ă��Ȃ��j���e�p�����̂��̂̒��t���ŁA�B�́i1�j�ׂ����M�ŏ�����Ă���B���͊��{�̉��y�[�W�߂ɑ������邩�Ƃ������̂ŁA�O�q�̊������ъ֘A�������Ė{���ŏI�y�[�W�u���W�@�L�v�́u72�v�܂ŁA���{�̃m���u���i�{���j�ɂȂ�ׂ��������@�́i2�j�Z���u���[�u���b�N�C���N�E�y���ő��̃m���u����ɏd�˂ď�����Ă���i���R�A�y�������̂ق����ڗ��j�B�Ƃ��낪�q���b�r�Ō�̃i���o�����O��O�꒚�́A���e���ǂ����܂ꂽ���߂ɑΉ�����{�����Ȃ��Ȃ�A���y�[�W�̃m���u���Ƃ����M�Łu�~�v���āA�E���ɂ͂���Ɂu�i�N�i���v�Ɖ��M�������Ă���B����ȍ~�i�q���̏ё��r���牜�t�܂Łj�́A�B�́i2�j�������M�őO�L�̃m���u���i�ׂ����M�{�y���j�����ĐV���ɋL�����������{���ƂȂ�B�ȏ�̂��Ƃ��琄�肳���̂́A�����炭���m�[�g�i�u�킽���̑�Ȃ��́v�I�j�ɏ���������������т��ƂɌ��e�p���ɐ��������i�K�ł͎��т̏��Ԃ͌��܂��Ă��炸�A���W�̍\�������肵�Ă��牔�M�Œʂ��m���u�����L�������i���̎��_�ł́u14�v�u15�v�ƋL�����q���y�r�Ƃ������т����݂������̂Ǝv����j�B���{�v�ɂ������āA���y�[�W���Z�o���邽�߂ɂ����ꂼ��̎��т̌��e���ʂƃm���u�������ߍ���ł������i�U�����^�̎��l�߂��w�肵���̂����̂Ƃ����낤�j�B���̂܂ܐώZ����ƑS�̂Ŏ��l�y�[�W�ɂȂ��Ă��܂��A����i���Łj��{�̓s����A�D�܂����Ȃ��B��y�[�W���ǂ����ō팸���邽�߂ɁA�g�̍ق����Ă��邱�Ƃœ����͌܃y�[�W���i���J���N����������A���ۂ͘Z�y�[�W���j�������q���b�r���l�y�[�W�Ɏ��߂��B����ȂƂ���ł͂Ȃ����낤���B�Ȃ��A��q����u�ڎ��v���e�ɂ̓m���u���ɑ������鐔�����L�ڂ���Ă��Ȃ��B
����Ȓ��q�ŏ����Ă����ƍی����Ȃ�����A���т̑薼���߂���b��Ƒ��{�Ɋւ��郁���ɐG��ďI���ɂ���B�ŏ��ɖڎ����e�i�i���o�����O��j���Ę^���邪�A�ڎ��͖{���̎��т����ׂĐ����āA���e�ԍۂɋN�e�����ƍl������i��������V���E�����̋�ʂ͖������A����p�̎w������������j�B
���W�Õ��ڎ�
�T�@�Õ��k�ʏ�̍s�ɋL���l
�Õ�
�Õ�
�Õ�
�Õ�
�k���適���y�l���E
��
��
�~�̉�
�Ă̊G
�N�[�g�[�̕��i
�U�@�]�́k�ォ��s�ԂɋL���l
�]��
��k�y���Ŗ������āA���M�œ��Ɂu�~�v��l
�҉�
�W�����O��
��
���b
���̏ё�
�ߋ��k���e�p���̗��O�A���Ȃ킿���s�߂ɋL���l
�U���\���͖ڎ����e��̃v�����Ǝv�������i�{���ɂ͍ŏ��A�O���y�[�W���k���l�ɂ���w�肪�������̂�������Ă���A�ォ��}�������y���u�U�@�]�́v�ɂ͖{�����A�B��i���o�����O���ł���Ă��Ȃ��j�A�q���鐢�E�r���q���y�r�ɑւ�錴�e�ł��邱�Ɓi�O�q�̂悤�Ɂq���鐢�E�r�ɉ��M�����m���u���̂Ȃ����Ƃ��T�j�A�q���i�r���q�N�[�g�[�̕��i�r���������Ɓi�{���̕W����q�N�[�g�[�̕��i�r�B�u�N�[�g�[�v�ɂ��Ă��q��ƃN�[�g�Ǝ��q�͎ʁr�̏��o�r�Q�Ɓj�A����ɖ{�����e�̂ǂ��ɂ��Ȃ��q��r�Ƃ������т����݂����炵�����ƁA�̎O�_�ɒ��ڂ������B�薼�֘A�ł����ЂƂB�Y�сq���̏ё��r�́A�{�����e�ł͍ŏ��̑薼���q�J���炵�̌��r�ł���A�����ɁA���邢�͌���q���̏ё��r�ƕ��肪�t�����A�ŏI�I�Ɂq���̏ё��r�ƂȂ����B�u�J���炵�̌��v�͖{���Ɍ����鎍�傾���A�q���̏ё��r�ɂ͉����y�Ȃ��B�q�J���炵�̌��\�\���̏ё��r�ɂ����Ƃ���œ��f�ł���B
���{�Ɋւ��郁���́A�e�{�̍ŏ��̒��i�i���o�����O���Ȃ��Ƃ�����݂�ƁA������ɓn��Ȃ��������e�j�̃E���i��q����u�����e�v�̎��̖ʁj�ɑ��߂̉��M�ŏc�ɏ�����Ă��邪�A�����ɑ��菑���Ƃ͂����A�g�����̎��Ɍ����Ȃ��B���e���炢���āA�g���ȊO�̐l�Ԃ��������Ƃ͎v���Ȃ��̂����B�ȉ��ɂ��̃�����^���邪�A�����̏C���ƁA�u�m���u���v�ւ́u9�|�C�^���b�N�v�Ƃ����NjL�A�y�[�W��̃m���u���ʒu�̐}�����A�ォ��ԉ��M�ŏ�����Ă���i�����Œ��L����A���{�́u�V�A���J�b�g�v�ł͂Ȃ��B�ق��͋L�ڂ̂Ƃ���d�オ���Ă��邩��A���{�����͈�����{�k�������{���������Ёl�̒S���҂��L�������ƍl�����Ȃ����Ȃ��j�B
�a�U���V�A���J�b�g
�{���܍����ԃx�^
�s�ԑS�p�A�L
��Łk�\�s���\��s�d���l
�����y�����Ȏg
�e���т͕K�����J���ŏ��܂�B
�S�Łk���l������Łl
�m���u���Œ������C�^���b�N
�Ō�Ɏ��W�̎��M�E���s�����ɂ��āB�s�Õ��t�͋g�������q���W�E�m�I�g�r�Łu���W�w�Õ��x�́A���l��N���玵�N�Ԃ̍�i�\���т����߂Ă���B�ڂ��ɂ͈�l�̎���������F���Ȃ��A���\����@�ւ����Ȃ������B�t�ɂ����A�F�����炸�A���\�̏�����߂��A�����Ŕ[���ł��鎍�����邱�Ƃ̂ݍl���Ă����B�w�Õ��x�͈��܌ܔN�A��S������o�ł����B������Ƃ��W���Ђ炭�悤�Ȋ��҂ƕs���̗��ŁB���m�̐�y�A�m�Ȃɔz�����B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���O�y�[�W�j�Ə������悤�ɁA���l��N����܌ܔN�܂ł̑��|�����N�Ԃ̎��т��琬��i�q���b�r�̖����ɂ́u���܌܁E�O�E�܁D�v�ƍe�{���B��A�E�e���炵���L�q������j�B�e�{�̍ŏ��̒��i�i���o�����O�Ȃ��j�I���e�́A�u�g�������W�^�Õ��^1955.5.5�v�ƎO�s�ɉ��������Ďl�p���r�݂͂��������e�����A�Ԃő傫���u�~�v�����Ă���i���{�̖{���͕ʒ��ŁA�V���v���Ɂu�g�������W�@�Õ��v�Əc�g�j�B����A���t�̌��e�ɂ́u���a�O�\�N�����O�\������s�v�Ƃ���i���{�̉��t�́u���a�O�\�N������\�����v�j�B�����𑍍����āA�̎��т����A�ǂ̂悤�ȏ��Ԃŏ����ꂽ�����܂߂��s�Õ��t�e�{�̒����E�����́A����͐G��Ȃ������{���̈ٓ��̏ڍׂƂ������āA����ׂ��s�g�����S�W�t�Ɋ��҂������B
�k2011�N8��31���NjL�l
�Q�l�܂łɁA���t���O���M���e�`���P���W�s�Õ��t�f�ڌ`���A�Z�ق���Čf����i�q�g�������W�s�Õ��t�{���Z�فr�Q�Ɓj�B
�O���M���e�`�F�c���B�V���Ō��e�������i15���~5�s�{6����81���j�B
�g�������W�Õ��E���ƌ����S��
�E���a�O�\�N�����O�\������s�E
�Љ���S�~�E����ґ����e�Y�E��
�����{�������{���������ЁE��
�s�ґ��c�唪�E�����s���n��쒬
�l�̘Z��
�O���P �Z�فF�����̉��M�E�C���̂����A���s�ӏ��̕ύX�͊��������B
�g�������W�Õ��E���ƌ���k�O�i�i�V�j���P�Łl��S��
�k�O�E���P�i�g���j�l���a�O�\�N�k�O�����P���l���k�O�O�\�ꁨ�P��\�l���k�O���s���P���l�E
�k�O�i�ꕶ���s���j���O�P�Ёl����S�~�E����ґ����e�Y�E��
�����{�������{���������ЁE��
�s�ґ��c�唪�E�����s���n��쒬
�l�̘Z��k�O�i�i�V�j���P�E�l
�P ���W�s�Õ��t�f�ڌ`�F�c�g�B�����g�p�i12�|�x�^�A16���~5�s��80���A���g�j�B
�g�������W�Ε��E���ƌ���œ�S��
���a�O�\�N������\�����E�ЙJ��S
���E����ґ����e�Y�E������{����
���{����������ЁEᢍs�ґ��c�唪
�E�����s���n���쒬�l�̘Z��E
�g�������������Ɍ��������W�s�Õ��t�ɑ}�܂�Ă��������i124�~��80mm�j
�e�{�̕\�L�łƂ�킯�ڂɂ��̂��u���j�I�����Â��Ёv�Ɓu���ォ�ȂÂ����v�̈ٓ��ł���B���̊Ԃ̎����`����g�����̏،�������̂ŁA�ȉ��Ɉ����B����N�v�́q������v�Ǝ��r�Ƃ������ŁA�������W�s�@����Ƃ��s�t�i���惆���C�J�A1955�j���Ȃ��u���ォ�ȂÂ����v�ƂȂ��Ă��܂��������߂����߂ɂ��������Ă���B
�@���ɁA��͂莍�l�̋g�����Ɂk�����C�J���玍�W���㈲����ɂ������āA�ɒB���v���牼���Â����Ɋւ��ĉ��������Ȃ��������A�l��Ѝ��͂����B�g������́A���Ɠ����N�ɁA���ƔłŎ��W�w�Õ��x�i���j�I�����Â��Ёj���o���A���̎��W�w�m���x�i���ォ�ȂÂ����j�́A�����C�J������ܔ��N�ɏo���B���̂܂����̔N�ɂ́A���������C�J����w�g�������W�x���o�邪�A�����ɂ́A�w�Õ��x�݂̂Ȃ炸�A��O�̎��W�́w�t�́x�܂ł����A�\�L���u���ォ�ȂÂ����v�ɕςւĎ��^����Ă��B�g������̓��́\�\�A
�@�u�w�Õ��x�́A�����̋߂Ă�o�ŎЂɏo���肵�Ă���ǂ���̈�����ɁA����ň��Ă�����B�����͓����L�����ɂ�āA������V�����ɂȂ���ł��܂Ă�̂ŁA�Z���͎Г��̍Z�{���̃��F�e�����̗F�l�ɓ��Ɍ��Ă���āA��肪�o��̂�h�����B�������A���������ł͌�肪�����Ȃ����炤�B����ŁA���Ƀ����C�J���玍�W���o�������ɂ́A���e�̒i�K����V�����ŏ������B�v
�@�܂�A�g������̏ꍇ�́A��������i��ŁA�w�m���x�ȍ~�́u���ォ�ȂÂ����v�ɐ�ււ��킯�ł��邩��A���ʂ̖��̖T�ɂ͕K�������Ȃ�Ȃ��B�i�ےJ�ˈ�ҁs���{��̐��E 16 ������v��ᔻ����t�A�������_�ЁA1983�A��y�[�W�j
�k2010�N6��30���NjL�l
�{���ŐG�ꂽ�s���{�ߑ㕶�w�فt�̎��̍��i��190���A2002�N11���j�ɋg���z�q�q���W�w�Õ��x�̂��Ɓ\�\�e�{�̊ɂ������ār���f�ڂ���Ă���B�����ɂ́u�w�Õ��x�̔��s�҂ɂȂ��Ă��银��Ɓk���c�唪���l�͏��a��\�Z�N�A�g�����w���w���S�W�x�̊G���˗������̂����Őe�����Ȃ����F�l�ŁA�}�G���������߂ɂƂ����C�ӂ̒�h�ɓ��h���āw�Õ��x�̌��e�������t�����������Ƃ���ɒm�����v�i�����A���y�[�W�j�Ƃ��������[���L�q������B�g�����q�˒�ɂār�ɏ������悤�ȏ��Łs�Õ��t�����W�Ƃ��Đ��܂ꂽ�ƍl����ƁA�q�˒�ɂār�͂��������d�v�Ȉ�тƂ������ƂɂȂ�B����������Ɓu����k�q�˒�ɂār�l�́A�̂́u���㎍�v�́u���l�̎U���v�Ƃ������ŁA���z�I�Ȃ��̂����߂Ă����̂Ł\�\�v�i������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�̋g�������A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����A���y�[�W�j�Ƃ����˗��������ɁA�g���͎��g�̎��I�o���̔w�i�����̌��z�I�ȎU����i�ɏ�������ł����̂�������Ȃ��B���̂Ƃ��q�˒�ɂār�`���́u���͕ʂɂ��˂Ȃ�ʎd�����Ȃ��̂ŁA�k�c�c�l�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l���y�[�W�j�Ƃ����ݒ�́A�u�Ɩ���̎d���v�Ɠǂ݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�s�Õ��t�̐��삱���A���̋g���������Ēʂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�d���v����������ł���B
�k2011�N7��31���NjL�l
���W�s�Õ��t�i���ƔŁj�ɂ��ė��L���悤�BNACSIS Webcat�Łs�Õ��t����������ƁA�������Ă���͓̂��{�ߑ㕶�w�ق����ł���B���ق̏��������ŕ\�������s�Õ��t�͉��̂Ƃ��肾���A�u�o�ŔN�����v�́u���a30.8.20�v���������B
| �\�� | �F | �� : �g�������W / �g������ |
| �o�Ŏ� | �F | ���c�唪 |
| �o�Œn | �F | ���� |
| �o�ŔN | �F | 1955 |
| �o�ŔN���� | �F | ���a30.7.20 |
| ���ʁE�傫�� | �F | 69p ; 19cm |
| ���L | �F | ���ƌ����200�� |
| ���ҕW�� | �F | �g��, ��(1919-) |
| �Q��ID | �F | BA91424557 |
| �ʒu�L�� | �����L�� | ����ID | ������ |
|---|---|---|---|
| T | ||ּ53||1 | BS047429 | �{�� |
�� �����͂��āu��Z���I�㔼�A���a����̋g�����̎��̈Ӌ`�͂Ȃɂ��B�����̎��l�Ƃ��Ă͒������قƂ�Ǔ��{��ɂ���Ă̂ݕ��w�I�ȑf�{��ς݁A��n�ɋ�� ������A�Ăѕ��}�ȋߐl�Ƃ��ē����ɐ�������Ԃɏ����ꂽ���̈Ӌ`�͂Ȃɂ��B�킽���ɂ͂��̍�i�̐������l�̐_�b�ƌ���̐_�b�Ƃ��W�Â��悤�Ƃ��� �ʊ��Ȏ��݁A�Ӑg�̗͋ƂɎv����B�g�����Z�̂���o�����o��Ɏ����߂��̂����Ɍ��������̂́A������{�̕��͂Łu���v���\���Əؖ����邽�߂̕K�R�� �������悤�ȋC��������v�i���o�� �ďC�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�A�O�y�[�W�j�Ə����܂����B
�� �́u��Z���I�㔼�A���a������\���鎍�l�v�Ƃ����̂́A�吳���̔����Y�A���a�O���̐��e���O�Y��O���ɒu���Ă̂��Ƃł��B�Y�̎����𐼘e�ƎO�D �B���������悤�ɁA���e�̎����������̂��g���Ɠc������ł����B�����ł́A�S���Ȃ����g���E�c���ɑ����̒J��r���Y���������O���Ɂu���a��� �̎��l�v���\�����邱�Ƃ��\���ƍl���܂��B�g���̍ł��Â����F�ł���ѓ��k��͋g�����u���ő�̎��l�v�Ƃ܂Ō����Ă��܂��B
�킽�������ɖ������Ĉȗ��A�g�����̎��͂˂ɍō���Ɉʂ�����̂ł����B�ӔN�̐��N�ԁA�����i���́u���{��ɂ����فv�I�j�� �݂��������l �Ɖ��x�����b������@��̎��Ă����Ƃ��A���͂��肪�����v���������܂��B
�g�����Ɋւ���ł��_�j�ȏ����s�g�����A ���x�X�N�t�� �������H���K�l����́A�g�����I�q�[���[�ɂȂ��炦�܂����B�킽�����قړ����ł��i�������A���y�͋g�����̎���͈͊O�ł����j�B�g������Ƃ킽���� ���傤�ǎO�܂��Ⴄ���N�ł��B�e�q�̔N�����i�ɂ܂��������������邱�Ƃ̂Ȃ����͂Ƃ́A��͂萦�����̂ł��B���N�O�Ɏ��킽���̕�͋g�����̎� ��ǂ�Łu�C�F�������v�ƌ����܂������A����Ӗ��ł���͐������Ǝv���܂��B�l�ԑ��݂́A���̔��C�������܂Ŋ��ʂ����H�L�̎��l���g�������ƍl���܂��B
�g�����̎��I�o�������ۂɖY��ĂȂ�Ȃ����l�ɁA�k�����q������B�ȉ��ɁA�g�����s�k�����q�S���W�t�̞x�Ɋ��q�f�͎O�ƈ�т̎��r���玍�сq���l�̔����ё��r���A�����ł���k�����q���W�s�ł����t�i���|�Ę_�ЁA1941�j�ƍZ�����Ȃ�����������āA��l�̐�B���Âڂ��i�����̌�Ɉ��p���т̑薼���L�����j�B�Ȃ��q���l�̔����ё��r�͑S�сs�ł����t�̈��p���琬��B�g���́u���W�s�ł����t�Ɏ��߂�ꂽ��\�ܕђ��̏\�Z�т̎�����A��s����l�s�قǂ̏͋���A���o���ĒԂ荇�������̂ł���B�����Ă݂�A�킽���̓��Ȃ�i�k�����q���j�ł���v�i�s�k�����q�S���W �x�t�A���ώɁA1983�A��y�[�W�j�Ə����Ă���B
���l�̔����ё�1�@�k�q�C���N�̎ցr�l
�_���̖��Ă���̂���
���N�B�͓J�𐁂�
�₪�đӂ��Đ��̒��ɓ���Ђ���2�@�k�q�����h�N�g�����r�l
�l�̉e�������̎��̂₤�ɂ��˂�3�@�k�q�꒼���̓��r�l
��Z���̓����������ł���
���ɏo��
�����T�������g�̏�����邫4�@�k�q�x�ɂ̃o�K�e���r�l
�˂��ꂽ�֎q�ɂ�����
�p�C���A�b�k�c�l�v����H�k��l��5�@�k�q���M�̐����r�l
���@�����ɂ�
�ő��Ȃɂ��Ȃ�6�@�k�q�ߑO�̏ё��r�l
�ÓT�ɋ߂�
�t�̂�k��l���Ȑl��
���H��
�v�ЂƂƂ���7�@�k�q�����ȃI�u�a�G�r�l
�y���L�̉���
���P�b�k�c�l�g
����Ђ̓g�����N8�@�k�q�q���V���X�̋G�߁r�l
���k�y�l�����ዾ������
���̃~���N������9�@�k�q���������r�l
�͂ꂽ���̉��̎K�т����]�k���l�Ԃɂ����ꂽ10�@�k�q�������̃J�X�P�c�g�r�l
���ׂ̍��F��11�@�k�q���邢�h���A���r�l
�ӓ��̔������̖j��
氓���Z���Ƃ�12�@�k�q�������L�����h���r�l
��������L�̏��13�@�k�q���̃��P�c�g�r�l
�삦���v�l�͐i�܂�14�@�k�q�D�̃u���I�`�r�l
�v�l�̕\�ʂ��L���k���l�x�c�̂₤�ɏk���15�@�k�q�����ȃO���e�X�N�r�l
����͏[���ɑދ��ł���16�@�k�q�����h�N�g�����r�l
�����Ȃ�d���ɖn��h��17�@�k�q�A�R�C�e�X�̉́r�l
���̎��͋T�̂₤�ɐS���Â�����
�l�͋T�̑��̌`���������ō����̏d����ʂ�
�����ɐ_�̏d�������ʂ��k�l�Ă
�����[���̂́u9�v�ŁA�u�����ԁv�i�k���j���u���]�ԁv�i�g���j�֕ω����Ă���B�����P�Ȃ鏑�������ԈႢ�ƌ��邩�A�Ӑ}�I�ȉ��ςƌ��邩����Ƃ��낾���A���́u���]�ԁv�͂����ɂ��g���ɂӂ��킵���B�q���l�̔����ё��r���g������̎��тƌ�����́A�����A�������Ȃ��ꂽ�i�i�c�k�߂�M���Ƃ���j��W����̓E�^�Ɠ���Ɉ����ׂ����A�Ƃ����̂����̍l���ł���B�g�����̎���ƌĂ�邽�߂ɂ́A���̂悤�ɏ����Ă��炢�����Ƃ��낾�B
���l�̔����ё��\�\�k�����q�s�ł����t�̏͋���S���
�_���̖��Ă����̂���
���N�B�͓J�𐁂�
�₪�đӂ��Đ��̒��ɓ���Ђ���
�l�̉e�������̎��̂悤�ɂ��˂�
��Z���̓����������ł���
���ɏo��
�����T�������g�̏�����邫
�˂��ꂽ�֎q�ɂ�����
�p�C���A�b�v����H��
���@�����ɂ�
�ő��Ȃɂ��Ȃ�
�ÓT�ɋ߂�
�t�̂悤�Ȑl��
���H��
�v���ƂƂ���
�y���L�̉���
���P�b�g
���邢�̓g�����N
�������ዾ������
���̃~���N������
�͂ꂽ���̉��̎K�т����]�Ԃɂ����ꂽ
���ׂ̍��F��
�ӓ��̔������̖j��
氓���Z���Ƃ�
��������L�̏��
�삦���v�l�͐i�܂�
�v�l�̕\�ʂ��L���x�c�̂悤�ɏk���
����͏[���ɑދ��ł���
�����Ȃ�d���ɖn��h��
���̎��͋T�̂悤�ɐS���Â�����
�l�͋T�̑��̌`���������ō����̏d����ʂ�
�����ɐ_�̏d�������ʂ��Ă���
�k�����q�̂悤�ȁA�g�����̂悤�ȁA�i����Ɍ����ΐ��e���O�Y�̂悤�ȁj�s�v�c�Ȏ��s�ł͂Ȃ��낤���B
1963�N�A�g�����͓��{���㎍�l��g���܂̑I�l�ψ��߂Ă���B���̗l�q���s���w�t�́q�g���ܓ��W�r�Ō��Ă݂悤�B�q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�́A������Y�ψ��̎��̔����Ŏn�܂��Ă���i���ȂÂ����̓}�}�B�Ǔ_��K�X�A������j�B
�u�k�c�c�l�I�l�͎O����\����ɂЂƂ܂�������ƁA�g���ܑI�l�ψ��̗����̉�����āA����S���̕S�O�̃A���P�[�g�����܂��āA���̂Ȃ������ɂ�Ĕ��l�̕��̎��W��I�т܂������A�g���ܑI�l�ψ������̉���A����͎O����\�����ɊJ���܂����B��ɂ�āA����Ɉψ��̑I����̎��W������ɉ����\���ɂȂ�܂����B����ɏo�Ȃ����ψ��́A����k�S���l�ψ������A�g��k�O�l�A�H�J�k�L�l�A���C�k�i��l�A�����A����k�l�Y�l�A�g���k���l�B���Ȃ����̂́A�O�D�L��Y�A�����ρA���ˉ�v�A������ł������A���ˁA�����̓�l����͂��ꂼ�ꕶ���ɂ�ĘA��������܂����B���̂Ƃ��Ɍ��Ǒ�ꎟ�R���Ƃ����悤�Ȍ`���ƂāA�Ō�Ɏl�̎��W�A�А����q�w���܂��̔j��͊C�̂悤�Ɂx�A���Ǘ����q�́w�ꏊ�x�A����N�v�́w�����Q���n���X�k���l�̓��x�A�R�{���q�́w����x�̎l�����A�Ō�̂���ǂ̐R���ɂ����邱�ƂɂȂ�܂����B�^���̓��͂��ꂾ���ŏI�āA�������S�ψ������̍�i���悭�ǂ�ł������ƂɂȂ�܂��āA�l�������ߌ�Z������g�~�[�O�����ōŏI�R���ɂ͂���܂����B���̊Ԋe�������낢��ӌ����Ȃ�ׂē��c���܂������A�Ȃ��Ȃ��l���W�Ƃ��咣�����āA�������������̂ł����A�Ō�ɍ��Ǘ����q�́w�ꏊ�x�Ɍ��肵�܂����B����ł́A���̎��W���ӂ��߂Ċe�ψ��Ɋ��z���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��悤�B�v�i�s���w�t1963�N7�����A�l�Z�y�[�W�j
�ȉ��A���ˁA�g��A���C�A�H�J�A�����e�ψ��̂��Ƃɋg�����������A����A�������ψ��A����ψ����������B���̋g��������^����B
�g���@ �ڂ��́A�l���̎��W��ǂ�ł݂܂������A�ŏ��A�R�{���q����́w����x�������]�����ēǂ킯�ł�����ǂ��A�������ǂ݂������Ă݂܂��ƁA���ɗ��\�ʼnf�������Ȃ������ɂ��Ƃ�������Ă����悤�Ȕj�ꂩ�Ԃ�̂Ƃ��낪����܂��B�ڂ����A�V���̎��l�͔��ɑ�ł����A��Ă����Ƃ����C��������̂ł����A�ނ�C�Ȑl�ŁA�ɒ[�ɂ����Ύ�����߂邱�Ƃ����蓾�邵�A���������Ӗ��ŎR�{��������O���܂��āA���_�I�ɂ͓���N�̎��W�Ƃ������܂����B���̎��W�́A�ŏ��̂��뎄�A�R���g���ƁA���������l���ł݂Ă���܂������A�悭�ǂ�ł݂܂��Ƃ܂�����Ȃ����Ȃ̂ł��B���łȂ���Ώ����Ȃ����т�������Ƃ������A�y���ȃ��[���A��������Ă��܂��B�ق�Ƃ��̈Ӗ��̃��[���A������͓̂���N�̎�����Ԃł��B�ꂢ���[���A�ł��邩���킩��܂���ǂ��I�n���̂��������Ă���B����N�̈ȑO�ɏ��������͋ꂵ��ł����Ă��܂������A���̎��W�͂��̂��݂Ȃ��珑���Ă��܂��B���́A�ꂵ��ŏ����̂�������ł�����ǂ��A�y����ŏ����A�ł������̂̊����x�������Ƃ������̂�����܂��B���������������N�͏����Ă���̂��Ƃ������܂��B����N���ǂ��������E��`���Ă���̂��͂���킩��Ȃ�����ǂ��A����ǂ̌��ɂȂ����W�̂Ȃ��ł͂��ʂ��Ă���Ƃ����ē���N�𐄂��܂����B���̂��ɂ́A�А�����̎��W��荂�ǂ���̕��������I�Ȃ��Ƃ����Ă����ł����Ƃ������܂����B����ǂ��A���̎��W���悭�ǂނƖ����������āA������i�ƈ�����i�����݂ɓ��Ă��邭�炢�̎��W�ŁA���ꊴ�Ɍ����Ă��܂��B�������A���̍D�݂ɂ������������o�āA���ɂȂ낤�Ƃ��Ă���̂ŁA��͂�吨���炢�Đ����Ă��܂����B�ے肷�邱�Ƃ��Ȃ��̂ŁA���͍��ǂ���Ō��\���Ƃ������܂��B�А�����̎��́A���̍l�����炢���܂��Ƃ悭����Ȃ����Ȃ̂ł��B�Ȃɂ������ł��悤����ǂ��A���Ƃӂ��̏����̎��Ƃ����Ƃ�܂���B���Ƃ̑I�т������A��������������悤�ɊϔO�����ɏo����Ă������낳���S�R�Ȃ��悤�ɂ������܂��B�O���̕������x�Ȃ�ł�����ǂ��A�㔼�̒��q�͗����Ă���悤�Ȋ����ł����B�i���O�A�l��`�܁Z�y�[�W�j
�g�����́s�m���t���g���܂���܂��邱�ƂŐ��ɏo���킯�ŁA���̑I�l�ψ��̎d������ɂ��Ă����Ǝv����B�u���[���A�����鎍�v�u�y����ŏ������v�u���W�̓��ꊴ�v�u�������̂��鎍�v������ɁA�����̋g���̎��ς����������鋻���[���I�]�ł���B
�l����Z���A����p�ꂳ��q���̐�F�A�g�����r�Ƃ������[���������������B���䂳��̂������āA�ȉ��Ɏ��Ƃ̂��Ƃ��^����B
�g�������������Ă��āA���їl�̂g�o�������܂����B
�����g��������Ɛ�F�������W�ŁA�Ƃɂ͋g��������̎��W����������܂��B���̕�����N�����ɖS���Ȃ�A���̑����͂��̂܂c����Ă��܂����A���ɂ͋g��������̎��͓���łقƂ�Ǔǂ��Ƃ͂���܂���B���̐e�F�������g��������̖{�́A���̎v���o�Ƌ��ɂ��ꂩ�����ɕۑ����Ă䂫�܂��B
���������������������Ă��ꂽ��A�g�����Ɋւ���ڍׂȃf�[�^���L�������їl�̂g�o�����āA������������Ƃ��낤�Ǝv���Ǝc�O�łȂ�܂���B
����A�g������W�s�z���t�����l�̗z�q����S�����ɑ��悳��A�����A���̕��O�ɋ����܂����B�i�g�����������������R�ł��j��������A�������ǂ�ł݂悤�Ǝv���܂��B
���[�������肪�Ƃ��������܂����B�s�g�����̎��̐��E�t���������������A���k�������܂��B���䂳�܂̂�����i�����O�͂Ȃ�Ƃ��������̂ł��傤�j �Ƌg��������F�ł������B�g������͐펞���̂��Ƃ��قƂ�Ǐ����̂����Ă��܂���B���͗z�q�v�l����g������̌R���蒫�̑��݂����������܂������A������̓��e�͒m��悵������܂���B�ł��̂ŁA������̐���ȂǁA����������������Ƃ��肪���������܂��B
���̏��I�����炽�߂Ē��ׂĂ݂܂����B�g�����璸������������̎��W������������܂����B�V�������W���o�邽�тɒ����Ă����悤�ŁA�g������͐��O�A�u���O�ɂ͉��̎��͂킩��Ȃ����낤���A��������l�ł����o�邼�v�ƌy���������Ă����ƁA���͏��Ă��܂����B
���́A����ˈ�Ɛ\���܂��B�吳8�N6���A�����͖{���̐��܂�ł��B���Ƌg������Ƃ̂��t���������ǂ̂悤�Ɏn�܂����̂��A���͕����Ă��܂��A���܂ꂽ�N�Əꏊ���߂������̂ŁA�R���ňӋC�����������̂ł��傤���B�g�����S���Ȃ�܂ŁA���Ƃ͐e�F�Ƃ��Ă��t�������������悤�ł��B���͏��������c���Ă��Ȃ��̂ŁA���ƂȂ��Ă͉������ׂ悤������܂���B
�m���A�g���������������a��\�N�㏉�߂̓��L�ɁA���Ƃ̌𗬂�������ƍڂ��Ă����悤�ȋL��������̂ł����A���A���̖{��������܂���B��シ���̓��L���������Ǝv���̂ł����A�@���ł��傤���B
�g��������̏ˌ��������߂Â��Ă��܂������A������ɕ��Ƒ����̐^�����ɕ�Q��ɍs�����̂����������v���o���܂��B
�g�����̏��a��l�N�̓��L�B�u�܌�����@�����Ǝl�c�̍ˈ�̉Ƃ֍s���B�ނ̕��͂��Ȑl�������B�ՏI�̏��ŁA�ˈ�ɖ����Ƃɂ��Ȃ��Ŏd�������Ă�Ɖ]�����Ƃ����B�����S�������B�ނ͐V�������l���o���A�Y��ł���B�O�l�Ő֏o��B�R��������v���o���B�V���֊O�o�̎��A�悭�O�l�ŗV��A���l������H������B���܂ɂ͊Â����̉��̎O�g��ŐH�������������̂��B�A���W�k�}�}�l�F���X�ŃR�[�q�[�B�v�i�s�g�������W�t�A�v���ЁE���㎍����14�A1968�A���l�y�[�W�j�\�\���́u�ˈ�v��������ł͂Ȃ��ł��傤���B�u�����v���ǂȂ����킩��܂��A��͂�R������̐e�F�ł��傤���B�g������́A���L�ɐe�����҂̐����Ȃ��Ė������L���Ȃ�����܂����B����āA�����u�ˈ�v����̐������܂ł킩��܂���ł����B���������܂ŁA�M�d�ȏ،��������܂����B
���̑c���͏��a24�N4��17���ɖS���Ȃ�܂����B�����A���͎l�c�ŃZ�����C�h�̎d�������Ă��܂����B���L�͂��̎��A��������ƈꏏ�ɕ����Ԃ߂ɗ���ꂽ���̂��Ƃ�������Ă���̂ł��傤�B
��������́A�R����������̎��ł��B���̐�F�̈�l���Ǝv���܂����A���a14�N11��13���́u���܂�����L�v�ɎR����������ƋL����Ă���̂ŁA�g������Ƃ͌Â�����̗F�l�����������m��܂���B
���̕��ƎR������́A�g�����S���Ȃ���܂Őe�������t���������Ă��܂����B���D���������悤�ŁA�悭�O�l�W�܂��ăA���a�F���X�֍s������A�H���������肵�Ċy����ł��܂����B�g�����S���Ȃ�����A�c���ꂽ���ƎR���������ԋC�������Ă����̂��v���o���܂��B���̎R��������S���Ȃ��܂����B
����p�ꂳ�猩���g�����́u�Z�����C�h�ߋ��ɐ������A�S�����k����ˈ�l�̖���̐e�F�v�Ƃ������ƂɂȂ�B

���сq���̕a�C�r�̃X���X�Ǝv�����蔲���i�s�����V���k�����l�t1959�N11��3��
�t�k��26503���l3�ʁj�k�g���Ƒ��̃t�@�C������̃R�s�[�l
�g�������N���A�t�@�C���ɕۑ����Ă����蔲���ɁA�����q�� �����̕a�C�r�i�D�E11�A���o�F�s�k�t4���A1959�N11���j�̃X���X�Ǝv�������̈�t������B�L���S �̂��N�����Ă݂悤�B
�����ւӂ₷�\�\�r���}�́u�N�r�i�K���v�@���C�R�[�i�r���}�̃J�����j�n���̒��j�̐�����тɂ́A���E�̊����������l���Z��ł���B�����ɂ̓p�_�����Ƃ����A�J �������̈� ��B
�@���́A�܁A�Z���납��V���`���E�̗ւ���ɂ͂߁A�傫���Ȃ�ɂ�āA��ւ̐����ӂ₵�Ă䂭�B���ɂ̓A�S����������܂Ŏ�ւ��d�˂�B
�@��ւ̒��̓J���łȂ��A��{�̒����V���`���E�̖_�ł���B��������ς��ɂ܂����A���Ɋ����A����ɗ����ɂ͋�̗ւ��͂߂�B��ςȏd���ł���B
�@�������ɋN���͕s���R�炵���A�����ƂɂȂɂ������Ă��E���Ȃ��B�̂��Ўキ�A�������B�����Ƃ���̓y���M�����݂����ŁA�ނ���A�����܂�������������B
�@�����قǔ��l�Ƃ���邩�炾�Ƃ��A�����]�������邽�߂��Ƃ��A���R�͂��낢�낢���邪�A�Ȃ���ւ����邩�A�������w��̂������Ă���� �Łc�c�x�Ƃ��������ʼn����m��Ȃ������B
�@���{�͂��̈��K���~�߂����悤�Ƃ��Ă��邪�A�Ȃ��Ȃ������ڂ͂Ȃ��炵���B����ł���l�A��l�A��ւ����Ȃ����������B�����������̓J�\���b�N�ɑ� ���A��ɏ\�������Ă���B�s�v�c�ɐ���M�̂��̎R���ɃJ�\���b�N���悭�����Ă����B
�@��ւ��͂߂���A�ւ��ӂ₷�ɂ͓��ʂ̋Z�p������B���̂��ߓ���A�O�̕����Ɉ�l�̇��Z�t��������A���������Ď�ւ̒��߂�����Ă���B���܂� �ܒ��߂̂��ߎ�ւ��O�����Ƃ���������҂̘b�ɂ��ƁA���ɏĂ��Ȃ��A�����A�����k�[���Ƃ��o���A���ɕs�C���������Ƃ����B���� �^�̓��C�R�[ �����Z�X�N�����ŊێR�x�ǒ��B�e
�i�����O�[�����ێR�o���R�b�N�x�ǒ��j
KING ���́uCLEAR FILE�v�kNo.122�^B�T-S�^�l�ɓ����Ă������̐蔲���́A�V�n167�~���E85mm�B�q�e���^�C�v�r�Ƃ������S���炷�� �ƁA�V���̃R�������B �o�T�̋L�ڂ͂Ȃ������B���̃t�@�C���ɂ���ق��̋L���͈�㔪�Z�N��̂��̂���������A�O�͕ʂ̂Ƃ���ɕۊǂ���Ă����̂��낤�B�̂��̎��сq�T�t�����E �݁r�i�G�E1�j���A����ȋ�ɔ��z���ꂽ�̂�������Ȃ��B
�k2012�N3��31���NjL�l
���̂قǔ������ās�g���������t�́q�V�@��v��i���^���ژ^�r�Ɍf�����悤�ɁA���{���|�Ƌ�����s���{���W 1961-1�t�i��
���ЁA1961�N7��5���j�Ɂq���̕a�C�r���Ę^���ꂽ�ہA��҂ɂ��q��i�m�[�g�r���V���ɕt���ꂽ�B���ɂƂ��Ē������Ɩ��ڂ������q���̕a
�C�r�̃X���X�i�o�T�j���A�g�����g�ɂ���Ă����Ŗ�������Ă���i�ڂ��������Ȃ�s�����V���k�����l�t1959�N11��3���t�k��26503���l3�ʂł�
��j�B�����Ă��܂��������Ȃ����̂����\�\��������}���قœ������{�����ās�����V���t�k���ł̃R�s�[���Ƃ�̂ɗv�����͎̂O�Z���قǁ\�\�o�T�̒T��
�ɂ́A�{�e����������������킩��悤�ɁA9�N�߂����������B�g�����q��i�m�[�g�k���̕a�C�l�r�̑S����^����B
�@���a�O�\�l�N�\�ꌎ�O���̒����V���̂����L���w�r���}�́k�u�l�N�r�i�K���k�v�l�x�����ނ����B���Ȃ�������� �K�̐l������ ���邱�Ƃɔߒɂ����ڂ���B�����͋L���𒉎��Ɏʂ��A���Ɣ����͂ڂ��̋��\�ł���B�����̍ޗ������ƂɈ�т̎������������Ƃ́A�ڂ��̎����U�ɂ����ď� �߂Ă̂��Ƃł���B�i�s���{���W 1961-1�t�A��Z���y�[�W�j
�����N�ɏ��������̈�߂��Ę^����B
�k���ю��q�g��i���Ɏ~��r�́l���o�ɂ͖{����ɒ��L�Ƃ��āu�i�{�e��蔪�\�s���폜���āk��l��Z�Z�N�܌����� �m�g�j���� ���j�v�i�s�����C�J�t�A 1960�N6�����A�O�y�[�W�j�Ƃ��������A���{�ł͏Ȃ���Ă���B��Z�Z�s���甪�Z�s��������ƈꔪ�Z�s�ƂȂ�A�Ⴆ�q���ār�Ƃ�����قǍ����Ȃ��� �邪�A�c�O�Ȃ���폜�ł̌`�Ԃ͒��ׂ��Ȃ������B�O�ȏ�̐߂ł̍��v�����Z�s�̑g�݂��킹���l�����Ȃ��͂Ȃ����A�킽���ɂ͂ǂ����S�̂ɉe�����o�� ���悤�ɁA�e���ŝS�悤�Ɏv����B�t�Ɍ����A����͗v��\�ȍ�i�������̂��B���������q�g��i���Ɏ~��r�������āA�g�����Ɋȗ��Łi��Ҏ��g�� ��ɂ����̂ł����Ă��j�̑��݂������������肦�邾�낤���B���̒����̍Ō�́A�����čő�̓����́A�S���łƍ폜�ł̓��̖{�������݂����i�͂����j�� �����_�ɂ���B�i���Y��ԉ��21�q�u���𑖂点�āv�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i7�j�@���сq���ār�r�A1992�A��O�y�[�W�j
�u�ȗ��Łv�̑��݂�[�肵�ď���Ɍ��_�Â��Ă���̂������h�����A�u�ꔪ�Z�s�v�́q�g��i���Ɏ~��r�́A���̕������������Ƃ��C������ �������B���� �֓���N�v����́q�u�g��i���Ɏ~��v�̎v���o�r������ꂽ�B���́q�t�L�r�S���������B
�����̘^���Ɓu�����C�J�v���̃e�N�X�g�Ƃ��ׂĂ݂�ƁA�����ɂ�1�`11�͔̏ԍ��Ǝ���Z�\��s������A�܂��l �J���ɏ����� ���̉��ς�����B�g���� �́A���̖{�Ԙ^���ɗ�������ċ�����̂�����A�����̍폜����ς́A��҂̏��F�̏�łȂ��ꂽ�Ɣ��f���Ă悢���낤�B�������A�v���ДŁw�g�������W�x �ł̌`�ł́A�E�̍폜����ς͍̂��Ă��Ȃ��āA����Ƃ͕ʂɌ܃J���ٕ̈�������B�i�s�g�����S���W �t�^�t�A�}�����[�A1996�A�Z�y�[�W�j
�u�� ��Z�\��s�v�Ƃ���A����Ɂu�͔ԍ��v�̈��s���𑫂��Ă��A����s�ɂ����Ȃ�Ȃ��B����s�͔��Z�s�ł͂Ȃ��B�����A�܂��܂������Ă킩��Ȃ��Ȃ����B�� ��͉����������Č�����ȊO�ɂȂ��ƁA�s�g�����S���W�t�̕Ҏ҂ł��������ɂ������������āA�����̘^�����J�Z�b�g�e�[�v�Ƀ_�r���O���Ă����� �����B�Z���̌��ʁA�悤�₭�u���Z�s�v�̓䂪�Ƃ����̂ł���B
�����Łq�g��i���Ɏ~��r�e�e�𗪋L���Ă������B
�����A�����Ă��Ȃ����A�A���E�� ���e�p���e�ł����낤����A�ȉ��̘_�|�ɉe���͂Ȃ��B�g�������ҏW�҂� �ɒB���v�����L�Ƃ��āu�i�{�e��蔪�\�s���폜���Ĉ��Z�Z�N�܌������m�g�j�������j�v�ƌ��e�A�ɏ������� ���A�܂��s�����C�J�t�ɂ� �q�g��i���Ɏ~��r���f�ڂ���Ă��Ȃ�����A�u�{�e��蔪�\�s���폜���āv�́A�E�̎��ʂł͂Ȃ����e�p���e�p���� �̏�Ԃ��w�����낤�i���� �݂Ɂs�����C�J�t�ł͈�s�O�Z���l�߂őg�܂�Ă���A�܂肩�����œ�s�ɘj�鎍��O�ӏ����܂�ŁA����Z�Z�s�A����̐�����j�B�s�����m�F���邽�߂� �́A�A�i�܂��E�j����s�����l�߂ŏ�����Ă��������m�肽���B�܂��C�́A �z�q�v�l���A������ �ɐV���ɏ��������������̂�������Ȃ��B�g���Ƃɕۑ�����Ă��邩������Ȃ������̌��e�����邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ�����A�g���̌��e�̏������������邱�� ���甗���Ă݂悤�B�Ȃ��A�G���I�̒�{�ł���B

���ш�Y���⽍��u�g�����v�@�k���낾����W�s���씼���t�A
���Y��ԁA1989�A���y�[�W�ɉ���l
�\�\���̃y�[�W�擪�����сq�i���̒��Q�r�̐������e�́A ⽍��̂��Ԃ��ɋg�����炿�傤�����������̂��B�V���s���p�ق́s�i���̗��l ���e���O�Y ���E�G��E���̎��Ӂt�W�ɏo�i�����̂Ɠ������̂��킴�킴�����Ă����������i���͂�u���e�v�ł͂Ȃ��y�������́u���v�ł���j�B���̌��e�p���͒҈䋪���� ���炢���������Ǝf�����B�\�\
�c�O�Ȃ��玄�́A�g�������M�̎��e���قƂ�nj������Ƃ��Ȃ��B�����Ŏʐ^�łő��e�ׂĂ݂� �ƁA�O�~��Z�s�Ƃ����u����Ɂv�̖�����̓������e�p���ɁA�㉺�ɃA�L������ď����Ă��邱�Ƃ������Ɣ���i�s���㎍�ǖ{�\�\�� ���� �g�����t���G�Ȃǂ��Q�Ɓj�B�������A�q�g��i���Ɏ~��r�͂��̓����p���ɂł͂Ȃ��A�s�̂̓�Z���l�߂̌��e�p���ɏ����ꂽ�̂ł͂Ȃ����B�������W�͈�ܕ� �ԂƂ������Ԃ̐����A�u�l�Z�Z���l�ߌ��e�p���ʼn����v�Ƃ������M�˗��������Ƒz������邩��ł���B�q�g��i���Ɏ~��r����Z���l�߂̌��e�p���i�g���� ���M���R�N�����̃y���k20���~10�s�l�ɏ������肵�Ă���j�ɏ������낳�ꂽ�Ɖ��肵�Ă݂�B�߂��O�s�h���ɂ���ƁA�l�Z�Z���l�� �œ�Z���ɂȂ�B�E�i�� �̏ꍇ�A�A�̑ւ��j���C�i�̑ւ��̃��W�I�����^���̕������j��t���� �킹��Ƃǂ����낤�A�݂��ƂɁu���Z�s�v���傤�Ǎ� ������Ă���ł͂Ȃ����i�������A����̎n�܂�͈ꎚ�����ŁA�����ɂ͈�㎚�l�߁B��s�ɘj�����ꍇ�A���̍s�͓V�c�L���j�B�ȉ��ɁA�A�� ���C�� ���ɍۂ��č폜���ꂽ�s�������f����B
�� �����ǂ́u�߁v�ɑ����邩���L���B1�`7�ԁ��u2�v�A8�`13�ԁ��u2�v�A14�`34�ԁ��u4�v�k���Ȃ킿�u4�v�S�̂��폜�l�A35�`56�ԁ��u5�v�A 57�`65�ԁ��u5�v�A66�`67�ԁ��u6�v�A68�`69�ԁ��u8�v�A70�`72�ԁ��u8�v�A73�`76�ԁ��u9�v�A77�ԁ��u9�v�A78�`80�ԁ� �u11�v�B
�A�i�܂��E�j�����C�� �̎����Ŗڗ��̂́A������w�E���Ă� ��A�߂̐����̍폜���i�����ł́A�����␅���A�����̌��ʉ��Ȃǂŋ���\�킵�Ă����j�B��ӏ��́u����ꁨ�킽�������v�͑S�̂̓���̂��߂Ǝv��� ��B����́u�܂��l�J���ɏ����Ȍ��̉��ς�����v�Ƃ����̂́A���̓_���B
����́u����Z�\��s������v�́A���1�`80�Ԃ��E�� �s�����C�J�t�f�ڍe�Ő����Ȃ����ƁA��Z���l�߂̌��e���O�Z���l�߂̎��ʂɂȂ邱�Ƃɂ���ĘZ��̎���ƂȂ�̂ŁA������Ԃ�ʗl�Ɍ����Ă���Ǝv��� ��B�ŏ��Ɏ����z�������u�ꔪ�Z�s�v�́q�g��i���Ɏ~��r�͑��݂��Ȃ������̂��B�u����Ƃ͕ʂɌ܃J���ٕ̈�������v�͓��肵�ɂ����B�\�L�̖��Ƃ����� �̂ŁA��������ǎ҂��E���G�̊Ԃ̈ٓ��ׂ�̂���낵�����Ǝv���B
���͈����N�Ɂu�g���� �{���P�s���W�ɓ���Ȃ������̂́A�����ăw�f�B�����⑺�k�́s�����A�W���T���L�t�l�Ɉˋ���������ł͂Ȃ��A��i�̍\�������̋g�����S��ƑΗ�����u�� ���̂����{���v�Ő������Ă�������ł͂���܂����v�i�`���̈��p�ɓ����j�Ə������B�������̌����������K�v�͂Ȃ��ƍl���邪�A���͂��̒��ю����A������ ���N�ǔł��D�����i���ɁA�p�\�R���̃f�X�N�g�b�v�ŃT�E���h�t�@�C�����Đ����Ȃ���A����������Ă���j�B
*1 �@�u�k���a�O�\�ܔN�l�l���\�ܓ��@�l�\��� �̒a�����B�q�g��i���Ɏ~��r��\�Ɋ����B�z�q�ɏ��Ă��炤�B�v�i�s�g�������W�t�A�v���ЁE���㎍����14�A1968�A���O�y�[�W�j
*2 �@�u�k���a�O�\�ܔN�l�܌��\���@�锪���A�J �̒����m�g�j�܂ŕ����B�������W�q�g��i���Ɏ~��r�̖{�Ԙ^���B���o�������j�A���D��R�����B�v�i���O�A���l�y�[�W�j

�w�f�B���s�����A�W���T���L�t�i�⑺�E��A�n�����ɁA1953�N9��30���j�\��
�k�g�������ˋ��������{���l
�g �������q�g��i���Ɏ~��r�����M����ɂ������Ĉˋ������Ǝv���銧�{�͊⑺�E��ɂ��w�f�B�����s�����A�W���T���L�t�i�n���ЁE�n������ D78�A1953�N9��30���j�ł���i�ڍׂ́A�O�f�q�u���𑖂点�āv�r�A��y�[�W�ȍ~���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�ȉ��ɁA�g�����ƌĉ�����{���������B���� �́i�@�j���̐����͈��p���̌f�ڃm���u���ł���B
���̓��C�X�����E�x�C�̓����J���h�� ��A���ӂ̃`�F���b�N�i�S�������j�E�Ӗ����E�p�k�̐H���̖��k�E�Ζ��E�p���E�^���J���i�u�����j�E�I���E�K�E�}���i�}�J���j�j�E���܁E���E�ځE�p�k�p�� ��E���E���ہA���������̕K�v�i���߂ė����B�k�c�c�l�ŋߐ����Ԏ����t�˔M�Ƒ�C���ɑ��݂���o�̗ʂƂ̊Ԃ̖��ڂȊW������D�@��𑨂����B �i18�j
���̓��[�����͎������������r���A����x�l�̋��Z���l�͔n�鏒�Ƀ`�[�Y�����Q�����A���̖�͔ޓ��Ɖ������ ������Z�^�[���i�W�C�U�[�\�\���̌��y��j�ƃO�A�[�����i���^�̒G�Ձj�̉��t�ɑł��������A���̓y���̊y��͂��₩�Ȓ��q�őt��������������A�� �����������R���[���Ă߂����y�ł͂��������B�k�c�c�l�ŋ߂̎s����̂��Ƃł��������f�H���Ɉ��j�����o�O�ɐH�������ɂ����A�����ߔ�����ĕڑł��ꂽ��A �����w���Ŕ�������s��̒���������ĕ������A�i21�j
�F���t�͕a�l�̉�����镔���ɓ���Ζ������v�̔R����鉋�ɂ����ƌ�����A�����Ĕޓ��͂��̕w�l�ɂ͈��삪�߂��Ă���Ɛ錾����B ���ۂ���n �ߕa�l�̗F�l���͕����̓��O�ɏW��A�i24�j
�� ���č������f�̏����̂��߂Ƀ}�����E�o�V�C�ɑ؍ݒ����̓^�N���E�}�J�������ɖ��ꂽ�p�ЂɏA���Ă̘b���o�����Ƃ��ł����B�^����͂������\�ɂȂ�V�l ���b���Č��ꂽ�̂ł������B��X���^�N���E�}�J���̗��������f����v��������Ă���ƕ����Ă��̘V�l�͂킴�킴���̏h�ɐq�˂ė����B���̘V�l���܂��Ⴂ�� �̂��Ƃł����������ł��邪�A�R�[�^������A�N�E�X�E�ɗ��������j��m���Ă����A�ނ͗������ɓ�������}�炸���Ñ�̓s�s�̔p�Ђɍs�������������ő����� �x�ߌB���U�����Ă���̂����o�����A����͎��G����ۂ⍚���ɂ��Đo�̔@�����ꗎ���ĐՂ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ̂��Ƃł���B�܂����j�̓A�N�T�N�E �}�������o�����ė������ɓ�����R�ɓs�s�Ղɍs������A�p�Ђ̒��ɑ����̋���݂̎U�݂��Ă���̂����o���A�ł��邾�������ɔP�����タ�傤�ǎ������� �Ă����܂ɂ���ς��U�ߍ���ŁA�����A�낤�Ƃ���Ƃǂ�����Ƃ��Ȃ��R�L�̑�Q������Ė�肩�����ė����̂ŁA���|�̂��܂�܊p�̊l���𓊂��̂Ăē��� �A�����B��ɗE�C���ۂ��čĂєp�Ђ�q�˂Ă݂������ɍĂт��̏ꏊ�����o�����Ƃ��ł����A���̐_��̓s�s�Ղ͗����̒��ɉi���Ɏp�������Ă��܂��Ă����B �i28�j
�����̌���͌����Čy�̂���ɕ�������ׂ����̂ł��Ȃ���܂����Ղɂ��ׂ����̂ł��Ȃ��B�k�c�c�l�������̔ޕ� �ɋN�����鍻�u�̂Ȃ��炩�Ȍ`��������Ȃ��C�����f���A���Ă��������ʂ��̂ɂȂ����B���u���z���Ĕޏ��ɂ͕��̔@�����ق̒��ɍł��Â������ɂ��A�L�^�� ���A�����ċL�ڂ���Ȃ��������m�̓��ۂ̒n�A�����č��⎩�����ŏ��̑��Ղ��ׂ��n����������Ă���̂ł������B�i30�j
�C�X�����ƃ��N�u�́k�c�c�l�J���K���b�N�ňꓪ�Z�|���h�\�y���X�̊����Ŕ����̗��h���p�k����ɓ���邱�Ƃɐ��������B�i31�j
�A�N�E�c���͑傫�Ȕ������p�k�ŏd���S�̐������̍j�����Ă������̂�����A���������f���I���ĊԂ��Ȃ��ɓx�̔�J����˂�� ���܂����B �k�c�c�l�����̑S���ɂ͊e�e�����Ƙm�Ƃ��l�߂��Ƃ�����ꂽ�B�i32�j
�ꔪ��ܔN�l���\���̓����P�b�g�̔N��L�ɋL�ڂ����ɑ�����ł����������m��Ȃ��B��Ƃ�����A������Ƃ̉����Ɖ]�������͌Q �W�Ŗ���A�� �X��s�̏o�������������B�i37�j
�Q�W�̌��X�ɂ��鉏�N�̈����\���̒��ɗB����̖�o���j�����Č��ꂽ�̂́A�����p�k�ɐi�s�𖽂������A��x�l�̋��Z���l�����\�� �̓��K�i�^�� �Ɏl�p���E�̋��x�߂̐��K�j�����̓��̏�ŎT���āA�u�䖳���Ɂv�Ɖ]�������Ƃł������B�i37-38�j
�鋳�t���n�l�X�͂��łɃ��C���b�N�Ŏ��Ƌ��Ƀ^�N���E�}�J�����f�����݂����͂Ȃ��Ɛ\�o�Ă����B�i38�j
�A�W���̔������t�������ĉ䓙�̎��͂ɖK��ė����̂��A�k�c�c�l���̏u�Ԃ���z���鎞���͏�ɑ���̍s�i���v���o�����ɂ͂����� ���̂ł���B �i39�j
�� ���Ԍ��X�͑S���̉ו����p�k���牺���A�p�k���~�`�Ɍq���A�G��܂邱�Ƃɂ���ċN��r�̖�Ⴢ�h���悤�ɂ����B�������ēԂ��藧�����Ă�������� �b�����R�ɋ�܂��邽�߂ɍj�������������B�����̉ו��Ɠ�����i�����X�̃L�����v�͈��R��ӂ̊G��ł������A�����Ă��̌��i�͂���瑍�ׂĂ����̂��̂� �Ɖ]�����Ƃ��l���鎞�A���ɂ���Ȃ���������^����̂ł������B�k�c�c�l�������ĉ�X�̃L�����v�̌��i�͑S���ꖇ�̖q�̓I�ȊG�ł������B�i42�j
�����k�������L�����v�𐁂��炵��C�͐o����ς��Ɋ܂݁A�e���g�̋ɂ����߈ȊO�̎��E�͊D�F�ɞN�O�Ɖ���ł����B�i43-44�j
�� ���̋u���̓�A�O�Ő������^��ł����p�k���]���K���Ȃ��Ƃɂ͋��ɑO�r�������݂̂Ŏ��͍ςB����ł��Ȃ���X�͓]���p�k�̔w����ו������� ���Ă�薔�Ăѐςގ萔�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�p�k�͌�r�𐧓��@�Ƃ��Ďg�p���Ă���߂čI�݂ɍ��̌X�Ζʂ��~�肽�B���傤�ǐ��߂ɉ�X�͍������u �ɕ��Ă߂��A�߂ނȂ����̍��u�̊Ԃ�E���邽�߂ɖk���Ɉꎞ�i�H��ς����B�k�c�c�l�k�����͏I�������Â����B��͊D�F�ɓ܂�A�ςɗ₽�������B �i44�j
���̋߂��ɂ͌͂ꂽ���k�������{�������щ�X�͂��̎}�ʼn�R�����A�܂��p�k�ɂ��b�̗t�������ɗ^�����B�k�c�c�l�� �̋u�˂̊ԂɎ��������n�������̂ł����Ɉ�˂��@���攼�ɂ��Đ��ɒB�����A�k�c�c�l�o�͗r�т̔@���_�����A�����ē�A�O�̏ꏊ�ł��p�k�̕G��v�� ����[���Ƃ�����������B���X�p�k�̒��̉��ʼn��𗧂Ăĕ���锖���������̊k�����n�̕��R�ȕ����Ɋg�����Ă���ꏊ���������B�k�c�c�l��O�L�����v�ɂ��� �Ă���̔@����l�̒j�͈�˂��@�������A�Z��ȏ�@�艺���邱�Ƃ��ł������͂Ȃ��o�Ă��Ȃ������B�i45�j
���ƌ{�͏�ɐ��� �S���Ĉ�˂��@��̂�������Ă����B�k�c�c�l�����`�͂��̕����ɂ̓G�V���E�R�[���i�̌j�Ə̂���Ă���傫�Ȍ�����Ɖ]�����B�R���ގ��g���A �܂��ނ̒m���Ă��鉽�l�����̌��������Ƃ͂Ȃ��A�����ނ͂��̑��݂����ɂ��Ă��������̂��Ƃł������̂ŁA���̐��͂������̒��x�̊m������L������̂� �����Ȃ������B�i46�j
��\�ꖉ������i��ɋ��R������ɂԂ������A���̓J�V���ɂ��̐��𖡂���Č���悤�ɖ������Ƃ��낪�A�������Ŕނ́u�� �̂悤�Ɋ� ���v�Ƌ��B49�j
�r�̍ŏ��̈ꓪ�������œj�E���A���Ƌ����͌��ɗ^�����B�i50�j
��X�͎���ɖ��m�̑卹���ɂ���������������B�i51�j
�����Ő�[����y�ѓ쐼�Ɍ����Ă���Ǘ��������u�̏�ɍ����̃L�����v�邱�Ƃɂ����B�i54�j
�e���g�����O�������O�~�̉��Ɉ�D������̒�����嶂�����̂����������A���̓Œ��͐��Ƃ��r�炳�ꂽ�̂ł��̋���ׂ������ �����Ɩ\��� ������B�k�c�c�l���̓��̍s�H�͑����ł��������A���̑����ɂ͂���߂đ�����殒J�Ə���Ƃ����݂��Ă����B�i55�j
�Ώ��ƎR�Ƃ̊Ԃ�D���ĉ�X�͐悸����ڂ����Đi��A���̎R�̎x�����I�邽�߂ɖk�����ɐi�H��ς����B�i55-56�j
�邪�{�̏��������ɐ��Ă������A�����e�̎ˌ��ɋ����Ĕ�ы������B�i56�j
���ɕ�����B��̉��͉���q�̒Ⴂ�X��Ə��̈�C�A��C�̊^�̖����Ɨy���ޕ��̋���Ă��̋��тƂ����Ď��X�b�̒����狿�� �p�k�̗�̉� �݂̂ł������B�k�c�c�l�Ȍ��T�Ԏ��̐S�͂������̒n��̊y���̎v���o�ɔ�Ԃ̂𐧂����Ȃ������B�i57�j
���̒j�͂��̒n���ɉ��̍̎�ɗ��Ă����̂ŎR���ɂ͑��ʂ̉�������Ƃ̂��Ƃł������B�i58�j
���̕ӂ��Ō�Ƃ��ĉ�X�͂��͂�V�N�Ȑ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�ł��낤�A�i59�j
�ꓯ�͂��̍��u�����[�}���E�N���i���ނׂ����j�Ƃ��`�����E�N���i�傫�����j�Ƃ��܂��C�O�C�Y�E�N���i�������j�Ƃ��ĂсA���̒��� ���Ƃ��x���X �i�����H�j�Ə̂����B�i61�j
�u�i�߁A�i�߁v�ƍ����̕����������A�u�i�߁A�i�߁v���p�k�̗邪�����Ă����B�ړI�n�ɒB���邽�߂ɂ͐�x��������s���A��������� �͈���ł��� ������B�k�c�c�l����������ς̒��̈ꓪ���]�݂̂ł������A�i63�j
��A�O�̖������邪�e���g�̒��̓����߂����Ĕ�т܂���Ă����A�i65�j
�J�����@����嗋��̔@���̂�̂�Ɛi�ނ݂̂ł������B��X�͍��u�̒��ɓo�邲�ƂɎl�������n���̂ł��������A������̕��������Ă� �������l�̒P ���Ȕߊς��ׂ����߁\�\���݂ɓ�������鍻�u�\�\�ݕӂȂ���g�̑�m�E���ׂȉ����ł�����ꂽ�R���\�\�݂̂ł������B�i68�j
�������Ȍ��̃����_�b�V���Ɨr�͊����̂��߂Ɏ��ɂ������Ă����̂Ő���^�����B�����_�b�V���͐��̉������u�Ԃ͑S���̋��C�� �悤�ɂȂ� ���B�i69�j
��ʂɂ��̔S�y�̒n�\�͓�����D�̍b�̒��x�̖ʐς��z���邱�Ƃ͂Ȃ��A�₦�邱�ƂȂ��A���I�ɐϑw�^���𑱂��Ă��鍻�u�͔S�y�� �n�\�ɍ���� ���A������X���ɂ���B�i70�j
���̒��Ȍ��p�k�ɂ͈�H�̐����^�����Ȃ��Ȃ����B�i71�j
���u���z���ĉ�X�͐i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ������A�����ĕ�n�ւ̑���̔@���p�k�̗�̔߂����ȉ��Ƌ��ɐi�ނ̂ł������B�i76�j
�����Ĕޕ��̕X�ɕ��ꂽ���Ȃ�R�̕X���n�����A�����Ă��̍|�̔@�����X�͂��痬��o�ł��̎R���ɖA�𗧂Ăė��ꉺ��₽���� ���̔@������ ��t����ɗ^����B�i77�j
���̐��͉����Ɠ��l�ɊŎ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i83�j
�ޓ����B��Ƃ��ĕ��݁A���̋r�͐k���A�����͗͂Ȃ����ꉺ��A���@�͊J���Ă����B�i91-92�j
�����đ�O���p�k���������A���̏b���܂����̓Ɠ��l�ɍ������̋�ɂɖ������ꂽ����㩂̒��Ɏ��c���ꂽ�̂ł������B�i92�j
��H�̏������T�����J�����@���̎��͂���Ĕ�ы������A�����čĂщ�X�̊�]����߂������̂ł������B�i96�j
�Ƃ��낪�A�[���ɂȂ��ăJ�����@���𗦂��Ă����J�V���ƃ��n���b�g�E�V���[�Ƃ���H���c�炸����œۂ�ł��܂������Ƃ������B �i97- 98�j
�� �̏Z�Ƃ̌������͊Â���������J���K�N�Ǝ������ԂƂɏ[������A����̏��a�ɂ͑嗝�ΕЂ����߂��Ă���A�����Ē�̒����ɂ͐����̂悤�Ȑ���X�� �����嗝�̐��Ղ������āA���̒��S����͕������@�ׂȐ����Ɛ����Ƃݐ�����C���ɑ����Ă����B�i104-105�j
�C�X�����Ƒ��̎ҒB���p�k�̔A�����Ɉ�t���߂Ă���ɐ|�łƍ����������ăR�b�v�ɒ����A�@���܂�ł��̊���ȍ����������ݍ��� ���B�k�c�c�l ���炭����Ƒ��̎O�l�͋��낵����ɂ��q�f���Â��A���Ƃ��Ƃ��n�ɓ|�ꕚ�����B�i108�j
�ނ̐g�̂͑S���͂���Ė؈ɔT�̔@���ׂ�A�ނ̓��F�̊�݂̂��ނ̒��Ŋ����ł����C��ۂ��Ă��镔���ł������B�i111- 112�j
���Ƃ����������鍩���̔@���������Ă����͂��̓�ւ�蔲����A�ƌ��S���ł߂��̂ł������B�i115�j
�܂��y��������]��ŃR�[�^���͂̐X�̕����������q�r�l��⾉ł������͂��܂����ƔM�S�ɑ{�����߂��B�i116�j
���͍��⎄�̗ǐS�Ɠ���ɋP�����ȊO�ɂ͉����̔����������ʂ̂��A�����ǐS�Ɛ��݂̂����̌�������́A�����Ēm�蓾��B��̂��̂� ����A������ �ǐS�Ɛ��Ƃ͎���������ł���r�����̉e�̒J�ł͂Ȃ��Ɖ]���z�O�����ɐ������B�i124�j
���͏��̕����g���A�������Ƃ��Ė��K�v�ȏꍇ�ɂ͕���ɂ������ł������B�i129�j
�� ��ɗ����Ȃ����߂ɂ͈ӎu�̗͂��|�S�̔@���ɂ���K�v���������B�k�c�c�l���̕����͗₽���閶�ɑS������Ă���B�k�c�c�l��ƈ��̑p�B�k�c�c�l�݂͊� �����߂��܂ōs�����������A�����퉹�ɋ�������Ĕ�ї�����������̔@����ы������B���������ɂ��A�����Ď��̏u�ԂɎ��͐V�N�ȗ₽�����\�\���������\�\ �ɏ[�����ꂽ������������̍ۂɗ����Ă����B�i130�j
�������ޑO�Ɏ��͖����v�����A���̎��A�����l�\��B�k�c�c�l����������o�����őP�Ŕ��̎��\�\���̃M���V���̐_�X�̔����\�\�Ƃ� ���ǂ����̐� �̔��������Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B�i131�j
������䩔��Ƃ��Ĕޕ��ɔ��݁A�l���̔ߒɁA�S��Ȃlj]�����͎̂��ɂƂ��Ă��̎��͑S���o���ɂ��l���Ȃ��̂悤�Ɏv��ꂽ�B �i132�j
�X �G�[�f���̎��̌C�͊��S�Ȗh���C�ň�H�̐����ʂ��Ȃ��B���͌C�Ɉ�ς������[�����A�J�V�������߂ē��������Ԃ����B���炭�A�W���嗤�����f������A��l�� ���������S�ɋ~�����C�������̂́A���̎��̌C��������C�����n�߂Ă̂��Ƃł������ɈႢ�Ȃ��B�^���͖������̏_���������͏��̏�ɓ��e���Ă����̂ŁA ���n�ɍ����ꂽ���Ղ�H��͕̂ʒi����ł͂Ȃ������B�i133-134�j
�\�\
�� ���ł́A�l�Ԃ̈ӎu�������̋���ȗ͂��A���l�ɂ��̋��\���𐪕������Ȃ��B����ׂ��^�N���E�}�J���������n��̐X�����ۂ��x�z����_�̖��ɂ����āu���̒n �܂ŗ���A����Ǎ��n���i�ޖ܂�A���n�ɂ����ēւ炵���Ȃ�g��A�i���Ɏ~��v�Ɛ錾���Ă���̂ł���B�i250�j
�����p���̌J�肩�����L���͂��̂܂܍Č��ł��Ȃ����߁A������Ђ炪�Ȃ�
�J�����B�܂��A�ӂ肪�Ȃ��Ȃ����B
�����p�����́k�c�c�l�͒������A�^�͉��s��\�킷�B
�������́q�O�ҁ@�^�N���E�}�J���̉��f�i���́\�\��\�́j�r�̖ڎ����f����B
�������܂��̈��p���́A�ŏI�́i�q��ҁ@���v�E�m�[���ցi��\�Z�́\�\�� ��\�́j�r�́q���\�́@�ړ����郍 �v�E�m�[���r�j�̍Ō�̈ꕶ�ł���B
�g�����́A�N�lj��u���Ȃǂ̌��J�̐Ȃɏo�邱�Ƃ��Ȃ���������A���̘b�Ԃ��m��l�͌����Ă��悤�B�����ɖ�����w���l��̖Y�N��i1984�N12��9���A�����E���k��j�ł̃X�s�[�`�̘^��������̂ŁA�����̃e�[�v����N�����Ă݂悤�B
�i��҂́u�����͖��厍�l��̂��߂킴�킴�����ł��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B����ł����q�̌��Ƃ������ƂŁA����k�N�v�l�搶�Ƌg��������ɂЂƂ��Ƃ����肢���܂��v�̌���̂��ƁA����Ō}����ꂽ�g���͈ꕪ�O�Z�b�قǃX�s�[�`�����Ă���B
�u���厍�l��Ȃ�Ă���W�Ȃ��ł�����ǁi�j�B���܂��܉��������āA���厍�l��̂Ȃ��́s����D�t���ڂ��̓��W������Ă���āA����͂����ւ�ɁA����z���ȏ�ɂ������ǂ��̂��ł��Ă���B���̂����������k����l����ɉ���Č�������A�w����͂ƂĂ��ǂ����̂��ł��Ă���x�ƁB�ڂ����g���v���Ă�����ǁA����ς����́A���ƂɎႢ���l��Ȃ����炭�����v���Ă���Ǝv���܂����ǁA�Ȃ��Ȃ���`�������Ȃ���ŁA����܂蔄��ĂȂ���Ȃ����Ǝv�����ǁB
�܂��A���厍�l��ǂ��́A���W���悤�Ƃ��܂��Ƃ��܂�Ȃ���ł����ǁA�s����D�t�͏����̖ړI��B�����āA�\���A�ǂ����W�ł���Ă������������ƁB
�݂Ȃ��������A�Љ�l�ɂȂ�ƁA���ǂ��閲���j��Ă������Ⴄ�Ƃ������Ƃ̂ق��������Ǝv���܂��B���������ۂǐS�����߂Ȃ��ƁA���̂������Ă������Ƃ͂ł��Ȃ���ŁA�݂Ȃ��Ƃ��Ă͕����������Ƃ��A�����ɂ���l�͎v���Ă���Ǝv����ł����ǁA�܂������͂���ۂǕ����������āA������āB�����������̂��������Ƃ��Ĉ��ł��v�����ȏ�́A���u���т��Ăق����ƁB���ꂪ�S�\���ł��B�v
����ɏ������Ă��Ȃ������������̐ȂɘA�Ȃ����̂���ƌ��������Ȃ����i����ɂ̓��O���Ŕѓ��k�ꂳ��́q�A�|���l�[���r�u���ɍs�����j�A�g���̃X�s�[�`�̌�i�͊̂ɖ��������̂��B
���ɂƂ��āA�Ȃ�Ƃ����������g�����̘b�����ł���B�kMP3�t�@�C���Ŗ�880KB�l
���Z���N�́q�g�����N���r�ɁA���͈�ɑ����āu���s���v�̂���Ŏ��̊e�����L�ڂ����B
�s�s�v�c�̍��̃A���X�t��n���X�E�x�����[���s�l�`�ʐ^�W�t�ɖ�������B�x�����b�q�┒�������̎������ǁB��X�؏㌴�̍��� �d�M������߂ĖK��B�\�������q�����˂��ݏ��m�r�q�F��o���r�A�_��C���́q��������E�G�ꂽ�~��r�A�c���o�q�l�ȏW�c�\�s�v�������r�Ȃǂ̓������}�� �|���m�f����ς�B�F�V���F�Ɍ��ʂ�B���ʂ͎q���̂��납��u�B�l�v�����̂���r�O�������B�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�A���Z�y�[�W�j
�u���ʂ�v�̍��́A���̔N�̈ꌎ�ɉ���������F�V�@��K�₵���Ƃ��̂��Ƃ��ƌ�ɂ킩�������A���ʂɂȂ݂Ȃ݂Ȃ�ʎ��M�������Ă����F�V���g�� �̋Z�ɁA�u�S���S���A�܂��ɐ_�Z�ƌĂԂɂӂ��킵�����́v�i�q�g�����̒f�́r�A���O�A��Z�܃y�[�W�j�ƒE�X�����悤�ɁA������Δ�I�ɋy�B��㔪�Z �N�A�q���㎍�I�u�W�F�W�r�Ɂu�W�̂Ȃ��Ԃ��ؔ��ɓ��������h��̌��ʂ��o�i�v�i�q�g�����N���r�A���O�A�O�Z�Z�y�[�W�j�����g����i���ς����A�I�u�W�F�͔� ���i���������A�}�^���Ȃ������ȓW��������B���̃I�u�W�F�́A�g���̌��ʂɊ�z���Ȃ����Đ��܂�Ȃ��������낤���A���ɂ͂��ꂪ�u��i�v�Ƃ������� �ǐ�̒j���̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�q�J�r�i�F�E9�j�́u�V�샋�C�Y�E�j�[���F���X���v��W���[�t�E�R�[�l���̃��~�j�T���X�i���ӎ��I�L���j�������Ă��� �悤���B
�k2006�N9��30���NjL�l
�q���㎍�I�u�W�F�W�r�i1980�N7��10���i�j�`15���i�j�^AM10:00�\PM6:00�^�V�h�E�I�ɚ�����L�k�c�c�l�^�v���Ёk�c�c�l�j�̈ē�
�n�K�L�ɋg�����̌��ʍ�i�������������́i�̃��m�N���R�s�[�j���o�Ă����̂ŁA�X�L�����摜���f����B�}�ł͂킩��ɂ������A�ؔ��̏����i����mm�ׂ̍�
�l�p���f�ʁj�ɂׂ͍����M�U�M�U�̎R�^�����܂�Ă��āA�g�������H�����̂������̖ؔ��������������̂��͕s�����B�����̕������R�s�[�œǂ݂Â炢�̂ŁA��
���ɋN�����Ă����B
�o�i��i�i�j
�k�c�l��25cm�@�k���l��12cm�@�k�����l��5cm�@�k���o���A�ォ��l�Ђ��^�����h�������܁^�ʂ̐^�ォ��o�������ʂ�ꂽ�Ђ�������܂��Ă���B�^�Ԃ��h�����ؔ�

�q���㎍�I�u�W�F�W�r�i�V�h�E�I�ɚ�����L�A1980�N7���j�̈ē��n�K�L�ɋg������i�������������́i���m�N���R�s�[�j
�g�����̏����̎��W�i���Ȃ킿�s�����G�߁t����s�Â��ȉƁt�܂Łj��̏W�s�����t�A���s�ٗ�Ձt�ɑт͂Ȃ��B�����ł́A�������ȊO�� ���ӂ��̑ѕ���^���āA���̕ϑJ�����ǂ��Ă݂悤�B
���ł̊��s���ł����ƁA�̏W�s�����k�V���Łl�t�� ��ɂȂ�B�u����p�v���]�@�Ђ���Ɨ₽��������̊��G�Ŗ����ʂ��ꂽ�g�������̎��Ƃ��̌��t�ɁA��������ƒW���w�䂪�c����Ă���Ȃ�A���ꂪ�Z�̂� ����Ȃ�A���͑f�l�T��̂悤�Ɋg�勾����ɂ��A���炭���̎w��߂Ă������B�v�i�\�P�j�B�킽���͂��̕]��ǂނ��тɁA�Ȃ��������Y�̒Z�� �Ǝ���A�z���Ă��܂��B
������
�惆���C�J��
�s�g�������W�t��
���A�����ɂ��苖�ɑт̌������Ȃ��B�g���Ƒ��{�ɂ͑т����������A���e�ł����̑��݂��m�F���Ă͂��邪�A�����܂őѕt���̌Ï��ɏo��������Ƃ��Ȃ��B���s
�҂̈ɒB���v���q�g�����ٕ��r�Łu���W�w�m���x�͈���c�炸���ꂽ�B�ڂ��͂��łɑO���W�w�t�́x�w�Õ��x���������w�g�������W�x�s���Ă������A����
�������܂��ł��d�˂��c�c�B�v�i�s���l�����\�\�����C�J���t�A���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1971�A��O�l�y�[�W�j�Ə���������i�ȍ~�j�ɕt���Ă���
�̂��낤���i�������A���t�ɓ�����̕\���͂Ȃ��j�B
�k2004�N9��30���NjL�E2014�N7��31���C���i�ѕ������j�l
�Ȃ��Ȃ�������q�ނ��Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA��ނ����ʑ[�u�Ƃ��ď��e�i�ʐ^�Łj����ѕ����N�����Ă݂�B
�u���d�ɍő�̔g��𓊂������̎��W
�m�m�����n���@�S�ю��^�I
���e�@��P���W �t�́@��Q���W �Õ��@��R���W �m���@�������яW
�����C�J�Łv�i�\�P�E�S���j
�u�g�܁u�m���v�S�ю��^�v�i�w�E�S���j
�u300�~�v�i�\�S�E�S���j

�uNo. 42492 �g�������W �����̎��l�o��5�v�̕\�P�Ɣw�i�o�T�F�ʉp�����X�j
�g���� 1�� ���i: 22,000�~�^���Ł@���V�~�@�O�����V�~�@�܍��J�o�[��єw�����P�^���惆���C�J ��34
�v���Ђ��s�g�������W�k��
�y�Łl�t�̑�l���͈�㎵���N�l
����Z���̔��s�ŁA���łɂ͂����炭�Ȃ������т��t���Ă���i��㎵���N�ꌎ��Z�����s�̑�O���ɂ��t���Ă�����������Ȃ��j�B�u����������l�v
�i�w�j�A�u�g�����i����������l�j�̌܍��̎��W��ԗ��v�Ƃ����^�C�g���Łu�Ǝ��Ȋ��̔��𐂂炵�A�S�t���̈�ࣖ��c�Ȍ��z�B���Ȃ���A���Q��
���w�ɍʂ�ꂽ���Ԓn����W�J���钘�҂̏������W�w�t�́x�y�сw�Õ��x�w�m���x�w�a���`�x�w�Â��ȉƁx�S�сB�v���\�P�̕��͂��B�\�S�́u�ނ̎��́A����
�Ƃ�������A���邢�͋ɒ[�ɋ߂�����A����l�Ԃ����Ă��鎋�_����o�Ă���B�ނ͌���l�ł���B�G���l�ł���B�c�c�ނ̎��́A����œ���Ɍ����Ă��A��
�Ր����ɒ[�ɋ��߂�B�v�i�ѓ��k��j�́A���㎍���ɔŁs�g�������W�t�̍�i�_�Ƃ��ď����ꂽ���͂���B
�˖{�M�Y���s���{�Ǐ��V���t���Z���N��ꌎ�Z�����Ɋ��s�g�������W�t�i�s�g�������W�k���y�Łl�t�̌��Łj���]��������B�u��������Ɏ���I�Ȕw�i��
��Ҍl�̎��I�ȓ��@�����낤�Ƃ���܂��ƁA���Ƃ�莄�ɋ����͖����B���ׂĔ��Q�̔��w������Ƃ��āA�ǎ҂Ԓn���ɗU���A���͉Ղޖ��ł���A���̒�
�R�������ʑ��݊������A�g�����𑼂Ƃ킩���̂��B�����̎��т́A���炭��Ҏ��g�����\���A�֒m���Ȃ������A���͂�~�ϕs�\�̐��E�����A�����ɔ��g��Z
���āA�S�t���̈�ࣖ��c�Ȍ��z�����ȑ��B������̂��B�v�i�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�A�v���ЁA1991�A����y�[�W�j�B�܂��s�m���t�̈�ۂ̔Z�����Z�Z�N�㖖�Ȃ�Ƃ������A���łɁs�T�t�����E�݁t���o�Ă����㎵���N�ɂ���
�ѕ����ƁA�ǎ҂͈�a�����o�����̂ł͂���܂����B
���쏑�[���s�_��I�Ȏ� ��̎��k����Łl�t�̑тɂ͏� ������Ȃ����A�s�_��I�Ȏ���̎��k���y �Łl�t�ɂ́u�g���@���^1967�`72�N���W�^�u�}�N���R�X���X�v�u�O�d�t�v�u�R�����v�����^�^����R�c�v�i�\�P�j�Ƃ���A�����̎G ���̍L���ɂ��A�q�O�d�t�r����̎��傪�g�p����Ă����B
�g���{�ɑѕt������ԂƂȂ�̂́A���W�s�T�t�����E�݁t��
�����Ě���Ƃ���B�u�g�����^�y�Ёv�i�w�j�A�����āu�����̂Ђт��`����I�n���v�Ƃ����^�C�g���Łu�����ɂ��č��M�A���m�ɂ��Č��l�ȈÍ��̏j�Ղ��Î�
���A���ƃG���X�̍��ׂ��镗�i��ʂ��āA���㎍�ɐV�����ʑ�������҂��A���I࣏n�̒��_�ŕ����̐V���W�v���\�P�̕��͂��B�\�S�ɂ͓��Ђ̐V���W�V
���[�Y�̏��ڈ�Z�����������Ă���B
�g�����́q���L���\�\���Z���r�̎����O���ɂ�������B�u�k�c�c�l�l���E�q�W�J�^�̊���ɂ��ēT��A���C�Z�c�ɂ��č��M�A�R�b�P�C�ɂ��Č��l�Ȃ�Í��̏j
�ՁB�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�`��l�y�[�W�j�B�������āA�g�����y���F�̈Í������s�`����w�t��]�������t�́A�͂�
�Ȃ����g�����g�̎����E�̌`�e�Ƃ��Đl�����Y�t���Ă������ƂɂȂ�B
�s�T�t�����E�݁t�͍�������܌�́u�O�Łv�i1977�N1��15�����s�j�ł́A�w�̒��Җ��̘e�Ɂu��������܁v�Ɠ���A�\�S�͎��̎l���̕]�ɍ�����
�������B
���ےJ�ˈꎁ�]�i�����V���u�e�Ȃ܂��v�j
���N������y�����W�͋g�����́w�T�t�����E�݁x�������B�w�Õ��x��w�m���x�̂���̖��f�������Ɩ��̔Z�����̂ɂȂ��č��o����Ă��āA���Ȑ����S�n �ɂȂ�̂��B
���剪�M���]�i�����V���u���|���]�v�j
���̑S�̂́A���т��тƂ��˂�Ȃ���A�s�v�c�ȑz�����E�̊C�◤�n�A�L�⏭�������̂���i�F��ʂ蔲���A�͂Ă͋ÑR�Ƌ����̐��E�ɐg�����炷�Ƃ���܂� �s���Ă���悤�ɂ݂���B
������N�v���]�i�ǔ��V���j
�g�����̍�i�j�̏�ł��܂���㎍�j�ɂ����Ă��A���M����Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�Ȏ��W�ƌ����悤�B
���������Y���]�i�����V���j
���̎��l��ǂނƁA�ǎ҂́A���ꂪ�ǂ�قnj��z�I�ȍ�i�ł����Ă��A���Ƃ���̋Î�����������邱�Ƃ͂Ȃ��B�u�ނ�������|���l������v�Ƃ����Ō�̈�s �̂悤�ɁA�C�}�[�W���͌������猩���ė���̂��B
�s�Ẳ��t�� �u�s�T�t�����E�݁t�Ȍ�́^�ŐV���сv�i�w�j�A�����āu���Ȃ������⌵�l�Ȃ�l�Ԋ쌀�̔ޕ��ɁA���ƃG���X�̍�������Í��̏j�Ջ�Ԃ��Î��߁A�����̐��� �n�Â���V��������W��n�o���āA���㎍�ɖ����̐V�̓y������̐V���W�B�v���\�P�̕��͂��B�s�Ẳ��t�́s�T�t�����E�݁t�ƌZ��̂悤�ɂ悭���� ���W�����A�ѕ��ɂ�����͌�����B���̎��W�ɂ�����u���p�v���A�u�����̐���n�Â���V��������W�v�ƋK�肵�Ă���_���ڂɂ��B
�s�|�[���E�N���[�̐H ��t�̕\�P�ɂ́u���� �_�̗����玍�l�̏��ɗ��Ƃ��ꂽ�R��̏����Ȑ����v�Ƃ���B�o�Ō��̏���R�c�̃T�C�g�ł́A����Ɂu��\���N�ɘj�莍�l��⸒�ɔ�߂��Ă������掍���� �\��̎�ʂ̎��тɂ��E�⎍�W�v�Ƒ����B
���z�W�s�u�����v�Ƃ���
�G�t�͔w�Ɂu�S���z
�W�v�A�\�P�́u�Җ]�v�����S�G�b�Z�C�W!!�v
�Ƃ����^�C�g���Łu���قȎ��I���E���\�z���Â��Ē��ڂ���钘�҂��A1955�N���猻�݂܂Ő܁X�ɏ������G�b�Z�C�̂��ׂĂ����^��������I���s�B���E�Z
�́E�o��̐l�ƍ�i�_���玩��E�g�ӁE���ȂǂɊւ��āA�s�����������߁A����Ȃ������ȕ��̂ŒԂ�A�l���������肳������B�v�Ƃ���A�\�S�ɂ͕W�蕶
�̖����̈�߂������ꂽ�B
�s�u�����v�Ƃ����G
�k����Łl�t��
�w�Ɂu�S�U���W����32�сv�A�\�P�Ɂu�����{���ł̐��������̋L�A�o����O�ɏ������W��҂ނ��ƁA������߂��邳�܂��܁A���H�ȂLj��ǂ����Z�̔o��ɂ�
�āA���e���O�Y�͂��ߎ��l�Ƃ̌𗬋L���X�A�ɓx�ɋÏk���ꂽ���̂ɂ��A�w�T�t�����E�݁x�̎��l�����P���̎U���W�B80�N�łɍ���V���ɑ�T���Ƃ���32
�т�lj���������ŁB�v�Ƃ���B
���z�W�A�G�b�Z�C�W�A�U���W�c�c�B�g�����g�͂������u�U���v�ƌĂԂ��Ƃ��D�B
�s��ʁt�̔w�� �u�V���W�v�B�\�P�ɂ́u�g�����\�\��[�����h�炬�����̂ڂ鎍�����V�������̂ƂȂ��ċ삯����A����ɕՍ݂��錶���̒n��_��ł��@���A�ӓׂ��錴 ��������炳�܂ɂ���\�\�V���W�v�Ƃ���B���͂�A�s��ʁt��ǂ݂��Ǝ��̕]�ƌ����ׂ����낤�B
�s�y���F��\�\�q���L�r�� �q���p�r�Ɉ˂�t�� �т̓g���[�V���O�y�[�p�[�̂悤�ȍގ��ŁA�w�́u�������Ǔ��сv�B�\�P�́u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���\�\�y���F�v�̂��ƂɁu�O�q���l�ƈÍ��� ���Ƃ̓�\�N�ɂ킽��H�L�Ȍ𗬂����������Ǔ��сv�Ƃ���B���ɒ}�����[�́s�V���ē��t�i1987�N10���j��������B�u�u�����Ƃ͖������œ˂����� �����̂ł���\�\�y���F�v���̏o����猍��܂œ�\�N�A�O�q���l�ƈÍ������Ƃ̌𗬂����ݏo�������A���l�̓��L�A�������̗F�l�E�W�҂̏،����R���[ �W�����A�u������܌�b�сv�𒆎d��ɁA����u������ܒf�����сv�Ɏ��ʂ��Ă������Ǔ��сB���Ҏ����B�v
�s���[���h���b�v�t�� �w�ɂ��u�V���W�v�Ƃ��邪�A�\�P�͏��������G�ŁA�Z���O���[�ɋg���̎��q���i�r����A���傫�߂̕����Łu���H�̊X�H���^�i�����̉ʕ��j��������^�i�� �N�j���ʂ�^�i�͑��j�ɂ̂���ꂽ�^�i���ҁj���ʂ��čs���v�������ň�����i���W�ł͎l�s�߂��u�̂����āv�j�A���͔��k�L�Łu�o���e���X�A�N���\�E �X�L�[�A�x�[�R����̍�i�ɐ��E���鎍��\�\�G��̓�����踠�k���K�l�����̂������Ђ�����A��ʂ̒�ɐg����߂���̂�����h���Ԃ�A��z�̔w��ɂ����� �Ƃ̉F������炬�������鎍�ьQ�v�Ƃ���B�g���{�l�̂悭�Ȃ����Ȃ��������Ŏw��Ƃ�����B
�s���܂�͂����L�t�� �\�P�Ɂu������̉��� ������䊂ƂȂ��Ĝf�r�����l�^�g�����^�Ⴋ���̋L�^�v�A�\�S�Ɂu1938�\40�N�A����̋���̒��Ɋ��R�ƃj���A�h�~�����̎�������˂��A����̂̑n�o�� �Ǐ��ɏ�O�̌ۓ��������������_�̋L�^�v�Ƃ���B
�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�̔w�́u�Ǔ��@�g�����v�A�\�P�́u���ȐN�Ƃƕϖe���J��Ԃ��A�W���������A������āA�N�₩�Ȍ�䊂���������ő� �̎��l�A�g�����B���̐������@�ɁA�c���ꂽ��ȃe�N�X�g�ɐV���ȉ�ǂ����݁A���̐g�̐����܂߂āA�g�[�^���Ȏ��l�̎p���ڂ�ɂ���B�v�Ƃ���B
�s�g�����S���W�t�� �w�u���V�L���́^���V�I�J�̂悤�ȁ^���v�͐��e���O�Y�̎��q���V�L���r�i���W�s����t�����j�̈�߂ŁA�\�P�́u�g���� 1919-1990�^�S��280�сv�ƃV���v�����B�u280�сv�Ƃ����̂͂킽���́s�g�����S���ѕW������t���Q�Ƃ��Ă̂��Ƃ��낤���A�S���W�Ɏ��^���� �����̐��𑫂��Ă����Ɓu280�v�ɑ���Ȃ��i�ŏ��ɒP�ƂŔ��\����āA�̂��ɕʂ̎��тɌJ�肱�܂ꂽ��i���O�т��邱�Ƃɂ��j�B�ѕ��̕ѐ��́A������ �����̂��炢�A�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B
�s�z���t�̑ѕ����q��W�s�z���t �����s�����i2003�N4��18���E�e�j�r�Ɉ����Ă���B
�s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�t��
�w�ɂ́u�V���@���̐X���Ɂ@
E06�v�ƃV���[�Y������������Ă���B�\�P�͔��n�ɃW���P�b�g�Ɠ������F�Łu���̐X���ɐV���I�v�A���F�x�^�ɔ��k�L�Łu�������I�ȃ��A���Y���^���҂͒Z
���G�b�Z�C�������̂�����Ⴕ���ƌ����邪�A���̕��͖͂��i�ƕ]����Ă����B�o�������������A�����R�I�ȑ��e��ттĂ���B���`����쎍�@�ɂ܂�
����́A���e��̐l���_�܂ł����^�B�������ˎ闝�v�A�����ăV���[�Y���A�艿�A�W�������i�G�b�Z�[�j�B�\�S�ɂ́u�i�{�����j�v�Ƃ��āq�킽���̍쎍
�@�H�r�̈�߂�������Ă���B
���܂܂łɂ����x��������ɏ��������A�g�����̎����q��
�ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o���킩��Ȃ��B
�g���͊����\�̎��т͏��o�L�^�����W�����Ɍf�ڂ��Ă��邪�A���́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�����^�������W�s�Â��ȉƁt�i1968�j�́A�P�Ƃ̎��W��
�O�A�����̑S���W�Ƃ������ׂ��v���Д��s�g�������W�t�i1967�j
�ɐ�Ɏ��߂�ꂽ���Ƃ������āA�q���o�ꗗ�r���ڂ��Ă��Ȃ��B�ӔN�̋g������Ɂu���W�s�Â��ȉƁt�̏��o���킩��Ȃ��āc�c�v�Ƃ��ڂ����Ƃ���A�L������
�ǂ��Ē��ׂĂ����������炵���B�f��Ɏ��W�̊Ԃ��烁�����o�Ă������A�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�̃f�[�^�͏�����Ă��Ȃ������A�Ɨz�q�v�l���炤��
�������B�܂��A�z�q����́u���o�������킩��Ȃ����R�́A�킽���������\����t���ĒԂ��Ă������̂��A���̂܂��W���Ɏg�������炾�Ǝv���܂��k��
�W�̂��߂̓��e���e�́A��ʂ��Ȃǂł͂Ȃ��A�z�q�v�l���g���{�l������̂���Ƃ����A�Ə���R�c�̑��j����
�炨���������l�B���a43�N��3���Ƀ}���V���������߁A���̑O�A���N�́A��1�l�ŒT������Ă��������ŁA���W�̂��߂̏������L�����Ȃ��̂ł��v��
���ւ�������������B
�N�[�g�̓t�����X�̉�� Lucien Coutaud
�i1904�`77�j�ŁA�N�[�g�[�^�N�[�g�I�Ƃ������B1963�i���a38�j�N�ɗ������A�����Ƒ��ŌW���J���Ă��邩��A�q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G��
��r�͂��̂��Ǝ��M�E���\���ꂽ�̂��Ǝv�����A�f�ڎ��������킩��Ȃ��B���̃T�C�g�������̂����ŁA���o�i���邢�͎��W�ȑO�̔N�ӓ��ւ̍Ę^�j����������
��A���Ђ��m�点���������B���݁A�g�����̎���ђ��A�����ЂƂA���o�k�`�l�̂킩��Ȃ��̂����́q�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�Ȃ̂ł���B

�N�[�g�̊G�@�k���l�C�̌����i1950�j�Ɓk�E��l�g���A�m���̕P�B�i1951�j�k�o�T�F�s�݂Â�t558���i1952�N2���j�̃��m�N���R�s�[�l
�k2016�N10��31���NjL�l
�g�����̎��сq�͎ʁ\�\���̓N�[�g�̊G����r�i�E�E4�j�̏��o�������������B1963�N8�����s�A���q�����ҏW�̔o�哯�l���s�C���t�k���s���̋L�ڂȂ��A
���s�҂͏o��O���l9���k2��9���l�����ꂾ�B���Ȃ݂ɁA���o�`�ƒ�e�`�i���W�s�Â��ȉƁt���^�j�̊Ԃɂ́A�Ђ炪�Ȃ̑����i�u���v�^�u�v�j�̕\�L����
���āA����Ɉٓ��͂Ȃ��B
�g�����̔N���ɂ��āA�ȒP�ȉ����L���B�g�����̔N���́A�ߋ��Ɏ����i1�j�����i5�j�̌܂��������Ă���B
�i1�j�@�k�\�\�l�q�g�����ڍהN���r�i�s�����C�J�t��㎵�O�N�㌎���E���W���g�����j
�i2�j�@�g�����q�N���r�i�s�g�����t�A�������_�ЁE����̎��l1�A��㔪�l�N�ꌎ�j
�i3�j�@�k�\�\�l�q�g�������N���r�i�s���㎍�蒟�t����Z�N�������E�Ǔ����W�����ʂ� �g�����j
�i4�j�@���ш�Y�q�g�����N���r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA�����N�l���j
�i5�j�@�g���z�q�q�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A����Z�N�O���j
�����͕W��Ɂu�N���v��搂������͂ŁA���N���I�Ȃ��̂͂���ȑO�ɂ��g�������g�ɂ���ď�����Ă��邪�i1960�N���q���`�r�ق��j�A�u���`�I�Ȃ��̂��܂����������ł��Ȃ��B�܂��A�N���I�Ȃ��̂�����ώG���ɂ��ς����Ȃ��v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���܃y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�N���Ə̂��邱�Ƃ̂ł���̂��i1�j�������Ě���Ƃ���B
�i1�j�ɂ͕ҎҖ��������Ȃ����A���W���̕ҏW�l�E�O�Y��m���i����ѕҏW���j�ɂ����̂Ǝv����B�����A�����s�̋g�����̕��́i�����炭�g������̒j�̈��p���܂݁A����ȍ~�̋g�����N���̌X�����K�肵���J��B���ʂ͎l�S���l���e�p�����Z�Ŗ�13���B
�i2�j�͗B��A�g�������M�̔N���B�i1�j����{�ɂ��A������ꂽ�ӏ܋L�^���[�����Ă���B��22���B��㔪�l�N�ꌎ�O����t�s�����V���k�[���l�t�́q��g���g�r�́u������l�͂��������}�l�ł������āA��낵���B���̔N���A����҂ɒʂ����Ƃ܂ŏ����Ă����āA���ꂪ���Ƃǂ�ȊW������H�@�Ƃ��������Ȃ邪�A����ς�V���[���ȊW������̂ł��낤�B�^���㎍���ЂƂ���̐l�C�����߂����߂ɁA�g�����Ȃ�����Ғʂ��܂Ŋ܂߂����`�������������Ƃ���]���Ă������B�v�i��ʁq�V���[���ȊW�r�j�ƕ]�����B�u����Ғʂ��܂Ŋ܂߂����`�����v�͏�����Ȃ��������A�̂��́s�y���F��t�͂��̕]���ӎ����Ă��邩�B
�i3�j�͈���Z�N�܌��̎��l������A�����ɕ҂܂ꂽ�B�f�ڎ��̕ҏW�E���s�l�̏��c�v�Y������ѕҏW���ɂ����̂Ǝv����B��6���B
�i4�j�́q�g���������r�q�Q�l�����ژ^�r�ƂƂ��Ɂq�g���������r���`������B�g���̖����̎U�����܂ޏ���������҂܂ꂽ�ł����ׂȓ��e�B�`�L�I�����ƍ�i���o�Ƃ��琬��B��83���B�{�q�g���������r�̑��тƂ��āq�g���������\�\�u���㎍�ǖ{�v�ŁE���r�i�s���㎍�蒟�t����ܔN���E���W���g�����ēǁj������B
�i5�j�͂���܂ł̔N���̐��ʂ���̑I�����A�g�߂ɂ������҂Ȃ�ł͂̎������������M�d�ȓ��e�B��42���B�Ȃ��A�{�T�C�g���q�g�����N���r�ɂ͂����i5�j�̍e���f�ڂ��Ă���B
�{�T�C�g�̍쐬�҂Ƃ��āA�g���z�q������͂��߂Ƃ����L�̊e�N���̕Ҏ[�ҁA���\�}�̂̕ҏW�҂Ɏӈӂ�\����B
�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~�@�~
���ш�Y�Ҏ[�q�g�����N���r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�j�̉�����2���k2012�N8��31���NjL�l
�g�����̓`�L�I�����̔N���Ƃ��āA�{�T�C�g�ɂ��q�g�����N���r�Ƃ�����ŋg���z�q����҂ɂȂ�q�N���r�i�s�g�����S���W�t�����j��]�ڂ��Ă���B�i4�j�ٕ̐ҁq�g�����N���r�͋g�����f������1991�N�̎��_�ōő���̓w�͂��X���č쐬�������̂����A�����̖ڂ��炷��i��R�͂Ƃ������j�ʼn߂���������肪�U�������B���̂��߂ɁA������������g���Q�Ƃ���̂ɕs�ւ������Ă���B����A������Ƃ��ĉ�������@��͂܂��Ȃ����낤����A�u�k�Е��|���ɂ́q�N���r�Ɍ�����̍ق���ĐV���ɑg�����ł��APDF�t�@�C���Ō��J���邱�Ƃɂ����B�ǎ҂͂�낵���{������Ȃ�A�_�E�����[�h����Ȃ�A�v�����g�A�E�g����Ȃ肵�āA�{�N�������p����Ƃ��B
�����ł��l�т��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�q�g�����N���r�̔��\��A�{�T�C�g���J�݂���2002�N����܂ł̖�10�N�Ԃ́A�C�����ׂ��ӏ����������邽�тɌ��{�ɐԎ����L�����ĉ�����Ƃɔ����Ă������A�J�m���Ƃ��ċg���z�q�ҁq�g�����N���r��{�T�C�g�Ɍ��J���Ĉȍ~�́A�p���I�ȃt�H���[��ӂ��Ă���B���̂��߁A�����{�T�C�g�ɏ������L���̂قƂ�ǂ͉����ŔN���ɔ��f����Ă��Ȃ��i�L���������̂ɐ�S�����A�Ƃ������͂���Ŏ��t�������̂��j�B����͂����āu����Łv�Ƃ͂����ɁA�莝���̍ޗ����܂Ƃ߂邱�ƂŁA�Ƃ肠�����q�g�����N���r�́k������2�Łl�Ƃ����B
�Ȃ��A���Łq�g�����N���r�̍�i���o�̍��ڂ́A�{�T�C�g�ٕ̐��q�g�����N���k��i�сl�r�ɍŐV�����f���Ă���̂ŁA������������������������B�{�q�g�����N���k������2�Łl�r�́AA6���i���ɖ{�T�C�Y�j�Ŗ{��42�y�[�W�A���e���ʂ͎l�S���l���e�p�����Z�Ŗ�80���ł���B���Łi��83���j���������Ă���̂́A��i���o�̍��ڂ������������Ƃɂ��B�`�L�I�����Ɍ���A���łɏ�L�́q�g���������\�\�u���㎍�ǖ{�v�ŁE���r���������Ă���̂ŁA���ʂ͂��Ȃ葝���Ă���B
���@���ш�Y�Ҏ[�q�g�����N���k������2�Łl�r�i2012�N8��31���APDF�t�@�C���k��700KB�l���J�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�k2021�N5��31���NjL�l
���̃y�[�W�i�q�g�����r�����j�́A�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t��index����g�b�v�y�[�W�������A�ŏ��̃y�[�W�i���Ȃ킿�{���m�ق����n�j�ł���A�Ҏ҂��{�T�C�g�ōł��͓_��u���y�[�W�ł�����B2002�N11���̃T�C�g�J�݈ȗ��A��x���x�ڂ��Ă��Ȃ����Ƃ�����A����͂��킩�肢�������悤�B�����Ƃ����̂��߂ɁA�ЂƂ̃t�@�C���Ƃ��Ă͐q��łȂ����ʂƂȂ��āA�{���ɕs�ւ𗈂��悤�ɂȂ����͈̂⊶�ł���B�q�g�����S���сk���o�`�l�i2019�N4��30���j�r�͓�������`�S���c�ʒu�����300�y�[�W�߂��ɂȂ邱�Ƃ��z�肳�ꂽ�̂Łi400���l�ߌ��e�p���Ȃ�900���������j�A�쐬������ʃy�[�W�Ɏd���Ă����A����A����ɑ����s�q�g�����r�����t�f�ڂ̋L�����s�q�g�����r�����k���O�l�t�Ƃ��Đ蕪���邱�Ƃɂ����B�^�C�g���́u�q�g�����r�����_02�v�B�ڍׂ��k���O�l�y�[�W�̖`���ɋL�����Ƃ���ł���B
���āA��������͗]�k�B���͖{�T�C�g�̂��߂ɒ����E���M�A�^�c�E�Ǘ�����l�ōs���Ă���B�N�����������낤���A�T�C�g�����ɓ������Ď����̐����E���p�ɂ͂˂Ђ��듪��ɂ߂Ă���B�����E���T�ނ͕ʂɂ��Ă��A�g�����̒���i�ꎟ�����j�A�g�����Ɋւ��镶���i�����j�A���̑��A�g�̎���ɒu���Ă��������{��G���Ȃǂ̈�����A�R�s�[�́i���̍��i�����͕ς��Ȃ��ɂ��Ă��j�����E���M���̃e�[�}�ɂ���Ă��܂��܂ɕω�����B��{�I�ɂ��������t���[�̎����͋߂��̐}���ق����āA��Ƃ��I���Ύ苖�Ɏc��Ȃ��悤�ɂ��Ă���B�o�ϓI�ȗv����������邪�A�Ȃɂ�����ԓI�Ȑ��傫���B����c�Ō���w�������Ă�����{�ΗY�i1913�`1983�j�́A�u�`�̍��Ԃɐ��Ԕ��ӂ��Ɍ������B�_����|��̃^�X�N�����܂��āA��ƂŎg����������ɎR�Ɛ��������������˂ɖ߂���̂������̂Ƃ����A�ƁB�搶�̂��̊��S�͐g�ɐ��݂�B�����A�g�����Ɋւ��镶���i�̈ꕔ�j��������鏑�I�̎ʐ^���f���邱�ƂŁA2021�N5���Ƃ������_�łЂƂ̋�肪�����L�O�Ƃ��悤�B

2021�N5��17���̋g�����֘A�����̏��I�i�قƂ�ǂ̎����Ɏ萻�̃^�C�g����\�������炪�|�����Ă���j �k������T�����L���A�g�����S���W�A�R�s�[��v�����g�A�E�g�̃t�@�C���A�g�������W�k���㎍���Ɂl�A�g�����k����̎��l�l�A�y���F��A�g�������W�k���㎍���Ɂl�ƐV�I�g�������W�k���㎍���Ɂl�A�g���������s�U���W�i�����j�A���܂�͂����L�A�g�����̏ё��A�g�����A���x�X�N�A�}�����[ ���ꂩ��̎l�\�N�A�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�A�����C�J�i1973�N9�����j�A���㎍�蒟�i1990�N7�����j�A���㎍�ǖ{ �g�����A���̂���������������Ă����ALilac Garden�i�R�s�[�̃t�@�C���j�l
�q�g�����r�����@��
| �����N�̓g�b�v�y�[�W�s�g�����̎��̐��E�t�ɐݒ肵�Ă��������B | ||||
| ���ӌ��E�����z�Ȃǂ̃��[����ikoba@jcom.home.ne.jp�܂ŁB | ||||
| Copyright © 2002-2021 Kobayashi Ichiro. All Rights Reserved. | ||||
|
�{�E�F�u�T�C�g�̑S�����邢�͈ꕔ�𗘗p�i�R�s�[�Ȃǁj����ꍇ�́A
���쌠�@��̗�O�������āA���쌠�҂���я��ш�Y�̋������K�v�ł��B |
||||
![[Brought to you by LaCoocan]](image/ym_hanga_03_A.jpg)