
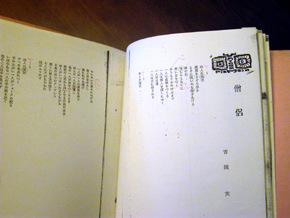
吉岡実詩集収録詩篇および未刊詩篇〔初出形〕ファイル(小林一郎が吉岡実全詩286篇の初出コピーに定稿化のための作者の手入れを赤字で記入・再現)――当初のままのフラットファイルは右から①〜⑥と左端の未刊詩篇分だけで、⑦と⑧はリングファイルに、⑨〜⑫はクリアファイルに、それぞれ入れかえて収容(左)と④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉(右)
最終更新日 2019年4月30日

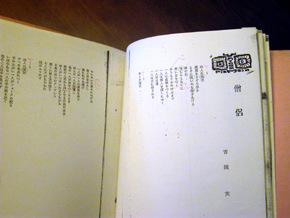
吉岡実詩集収録詩篇および未刊詩篇〔初出形〕ファイル(小林一郎が吉岡実全詩286篇の初出コピーに定稿化のための作者の手入れを赤字で記入・再現)――当初のままのフラットファイルは右から①〜⑥と左端の未刊詩篇分だけで、⑦と⑧はリングファイルに、⑨〜⑫はクリアファイルに、それぞれ入れかえて収容(左)と④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉(右)
【1950年代】 1955(昭和30)年
1956(昭和31)年
1957(昭和32)年
1958(昭和33)年
1959(昭和34)年
【1960年代】 1960(昭和35)年
1961(昭和36)年
1962(昭和37)年
1963(昭和38)年
1964(昭和39)年
1965(昭和40)年
1966(昭和41)年
1967(昭和42)年
1968(昭和43)年
1969(昭和44)年
【1970年代】 1970(昭和45)年
1972(昭和47)年
1973(昭和48)年
1974(昭和49)年
1975(昭和50)年
1976(昭和51)年
1977(昭和52)年
1978(昭和53)年
1979(昭和54)年
【1980年代】 1980(昭和55)年
1981(昭和56)年
1982(昭和57)年
1983(昭和58)年
1984(昭和59)年
1985(昭和60)年
1986(昭和61)年
1987(昭和62)年
1988(昭和63)年
1989(昭和64/平成元)年
【1990年代】 1990(平成2)年
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2019年4月15日は、吉岡実が生誕して100周年の記念すべき日である。私は本サイト《吉岡実の詩の世界――詩人・装丁家吉岡実の作品と人物の研究》でも祝意をこめた企画を用意したいと思い、吉岡が生前、活字にして発表した全詩作品286篇の〔初出形〕を発表順に掲載することにした。本サイトの冒頭ページ《〈吉岡実〉を語る》では、すでに詩歌集《昏睡季節》(1940)から詩集《ムーンドロップ》(1988)までの全刊行詩集収録の詩篇、および未刊詩篇を本文校異の形で掲げている。だがそれらは、新聞・雑誌などに掲載された〔初出形〕と単行詩集もしくは全詩集に収められた〔定稿形〕を併記したテキストを単行詩集の刊行順・収録順に並べたものだった。今回の〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉では、吉岡が個個に詩篇を公表した順序どおりに、その〔初出形〕を配列した。私を含む読者は、1940(昭和15)年の〈序歌〉(①・0)から1990(平成2)年の〈沙庭〉(未刊詩篇・21)までを通読することで、吉岡実の半世紀に亘る詩的営為を時系列的にたどることができる。人によっては、自分が生まれた当時発表された詩篇を読むこともできよう。
ここで、吉岡実詩を数量的に把握しておきたい。吉岡実は生前に12冊の単行詩集を刊行した。そこに収められた詩篇の総数262。これ以外に、新聞や雑誌に発表したものの、単行詩集には収録しなかった未刊詩篇が21篇ある。このうち《吉岡実詩集》(思潮社、1967)に再録された〈波よ永遠に止れ〉を含む15篇が、単行詩集に収録の262篇とともに《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)に収められている。その総数277篇。これに《吉岡実全詩集》に未収録の未刊詩篇6篇(これらは《吉岡実全詩集》刊行の1996年時点で未発見)を加えた283篇が、吉岡が生前に完成させた全詩篇となる。《吉岡実全詩集》を増補改訂するなら、この283篇とすべきだろう。ときに、当初は単体で発表されながら、作品としては消滅した詩篇がある。〈秋思賦〉に1篇、〈聖童子譚〉に2篇、本篇に変改吸収されたのだ。これによって、吉岡実が生前に発表した詩篇の数は286篇に増える。この286篇が今回、本稿〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉において対象とした詩篇の総数である。ちなみに、このほかに手稿のまま遺された未発表詩が2篇あり、さらに北園克衛の詩集からの引用詩句だけで構成された詩が1篇ある(私はこの〈詩人の白き肖像〉を吉岡の創作とは見なさなかった)。生前発表の286篇にこれら3篇を加えるなら、289篇となる。これが今日までに判明している吉岡実詩のすべてである。
ところで、吉岡が永年勤務した筑摩書房は今日までに《太宰治全集》を十数度にわたって刊行している。さまざまな編纂方法の全集が存在するのは、それだけ読者の需要があるからだが、《初出 太宰治全集〔全12巻・別巻1〕》(1989年6月〜1992年4月)は、収録した作品を「すべて初出誌・紙を底本とした初めての全集。作品の配列は作者の執筆脱稿年月日順。全巻に詳細な作品生成過程を述べた解題と綿密な校異を収載」とある(同全集の編纂・解題は山内祥史)。〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉はこの《初出 太宰治全集》の吉岡実版ともいえるが、作品の配列は「作者の執筆脱稿年月日順」ではない。本稿で採用した作品の配列は、発表紙・誌、書籍などに記載された奥付発行日の順である(同日の場合、脱稿が早かったと思われる詩篇を先に掲げた)。それというのも、作者の日記や書簡などにその制作の状況が記されたごく一部を除き、吉岡実詩の大半は執筆脱稿年月日が特定できないからである。
本稿では詩篇を通覧できるよう、詩篇本文に先立ち、1940年から1990年までの各年(発表詩篇のある年に限る)を見出しに立て、その年に発表された作品を
詩篇標題(詩集番号・掲載順、詩篇本文行数)
で立項して、標題にリンクを張り、詩篇本文と関連づけた(索引を兼ねる〈詩篇目次〉として、50音順に並べた標題を最初に掲げた)。各詩集本文の〔初出形〕と〔定稿形〕の異同に関しては、
①吉岡実詩歌集《昏睡季節》本文校異
②吉岡実詩集《液体》本文校異
③吉岡実詩集《静物》本文校異
④吉岡実詩集《僧侶》本文校異
⑤吉岡実詩集《紡錘形》本文校異
⑥吉岡実詩集《静かな家》本文校異
⑦吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》本文校異
⑧吉岡実詩集《サフラン摘み》本文校異
⑨吉岡実詩集《夏の宴》本文校異
⑩吉岡実詩集《ポール・クレーの食卓》本文校異
⑪吉岡実詩集《薬玉》本文校異
⑫吉岡実詩集《ムーンドロップ》本文校異
を、また各詩篇の詳細に関しては、吉岡実詩の総覧として最新版の《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第4版〕》を参照されたい。この《吉岡実全詩篇標題索引》はまだ冊子体の印刷物が存在しないため、本サイトからダウンロードしてプリントアウトされることをお奨めする(本稿の末尾に、付録として《吉岡実全詩篇標題索引》の〈目録〉を小さく掲げた)。なお、12冊の詩集それぞれの表記(漢字の旧字/新字、ひらがな・カタカナの旧仮名/新かな、同じくひらがな・カタカナの拗促音の並字/小字)の詳細は、〈吉岡実詩集本文校異について〉を参照されたい。これを要するに、各詩集を表記の面から区分した次の表の4種([A]〜[D])となる。私は、①と②を吉岡実詩の「初期」、③〜⑥を「前期」、⑦〜⑨を「中期」、⑪と⑫を「後期」と称している。
| 区分 | 詩集(制作年) | 漢字の旧/新 | かな・カナの旧/新 | かなの拗促音の並/小 | カナの拗促音の並/小 |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | ①詩歌集《昏睡季節》(1940) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | ―― |
| ②詩集《液體》(1941) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | 小字 | |
| ③詩集《静物》(1949-55) | 旧字 | 旧仮名 | 並字 | 小字 | |
| [B] | ④詩集《僧侶》(1956-58) | 旧字 | 新かな | 並字 | 小字 |
| ⑤詩集《紡錘形》(1959-62) | 旧字 | 新かな | 並字 | 小字 | |
| [C] | ⑥詩集《静かな家》(1962-66) | 新字 | 新かな | 並字 | 小字 |
| [D] | ⑦詩集《神秘的な時代の詩》(1967-72) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 |
| ⑧詩集《サフラン摘み》(1972-76) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |
| ⑨詩集《夏の宴》(1976-79) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |
| ⑩拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(1957-80) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |
| ⑪詩集《薬玉》(1981-83) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 | |
| ⑫詩集《ムーンドロップ》(1984-88) | 新字 | 新かな | 小字 | 小字 |
細かなことだが、詩篇標題と詩篇本文との間に置かれた〈詞書〉や〈題辞〉・〈献辞〉、本文の後に置かれた〈註記〉(散文と見なして追い込んだ)や擱筆日と思われる〈年月日〉は、原則として本文よりも小さな文字で表示し、字下げは本文活字の何倍に相当するかを計測して、地揃えと思しいものも天からの字下げとした。本文中の節を示すアラビア数字(一桁のものは全角で、二桁にわたるものは半角で表示)や時計数字(ローマ数字)、アステリスク(*)の字下げも本文活字の整数倍とした。
〔初出形〕はその9割以上が活版印刷による組版だが、使用漢字の字体・字形を含めて、ウェブページ上で完全に再現することはもとより不可能である。個個の作品の(目次における標題・作者名)―標題―作者名―本文前の文言―詩篇本文―本文後の文言―(編集後記)、という流れ=詩篇の構造が把握できれば充分だろう。
最後に、《吉岡実全詩集》の補完資料たる①〜⑫の各詩集の本文校異とともに、この〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉が吉岡実詩の味読、研究の一助となることを願ってやまない。
吉岡実生誕100年の2019年4月15日 東京・練馬にて 編者 小林一郎
>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
〈詩篇目次〉には、〔定稿形〕を対象とした拙編《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第4版〕》(文藝空間、2017年1月31日)の内容を転用した。記載項目は次のとおり。
詩篇番号 詩篇標題――副題(よみがな)〔同じ標題で複数の詩篇が存在する〈哀歌〉〈序詩〉〈静物〉〈断章〉〈夏〉〈挽歌〉〈風景〉〈牧歌〉の8タイトルには、冒頭の詩句を補記した〕[《吉岡実全詩集》掲載ノンブル]〔未掲載の場合は[―]と表示した〕
記載項目の「詩篇標題――副題」は初出時のそれであって、〔定稿形〕で改題された詩篇(全部で14篇ある)には「15 ((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(アジュール)[699-700]」のようにその旨を註記し、〔定稿形〕の標題にリンクを張って当該詩篇を呼びだすようにした。
1 哀歌(あいか)〔毛皮にうずまつて〕[53]
2 哀歌(あいか)〔それは或は風説だろう〕[721-723]
3 哀歌(あいか)〔わたしの世界は 小さな峠の茶屋で〕[611-614]
4 青い柱はどこにあるか?(あおいはしらはどこにあるか)[249-252]
5 「青と発音する」(あおとはつおんする)[524-527]
6 秋(あき)[9-10]
7 秋の前奏曲(あきのぜんそうきょく)[31]
8 秋の領分(あきのりょうぶん)[653-655]
9 悪趣味な内面の秋の旅(あくしゅみなないめんのあきのたび)[423-431]
10 悪趣味な夏の旅(あくしゅみななつのたび)[402-407]
11 悪趣味な春の旅(あくしゅみなはるのたび)[501-503]
12 悪趣味な冬の旅(あくしゅみなふゆのたび)[322-326]
13 曙(あけぼの)[455-458]
14 朝の硝子(あさのがらす)[12]
15 ((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(アジュール)[699-700]
16 亜麻(あま)[730]
17 あまがつ頌(あまがつしょう)[417-423]
18 編物する女(あみものするおんな)[154-155]
19 雨(あめ)[263-266]
20 『アリス』狩り(アリスがり)[345-350]
21 或る世界(あるせかい)[62]
22 或る葬曲の断想(あるそうきょくのだんそう)[45]
23 あるひとへ(あるひとへ)[13]
24 杏菓子(あんずがし)[20]
25 田舎(いなか)[159-160]
26 犬の肖像(いぬのしょうぞう)[82-85]
27 衣鉢(いはつ)[169-171]
28 異邦(いほう)[445-447]
29 異霊祭(いれいさい)[371-380]
30 陰画(いんが)[150-152]
31 陰謀(いんぼう)[718-719]
32 失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(うしなわれたよるのいちがくしょう)[46]
33 美しい旅(うつくしいたび)[118-119]
34 馬・春の絵(うま はるのえ)[194-195]
35 海の章(うみのしょう)[―]
36 永遠の昼寝(えいえんのひるね)[733-734]
37 詠歌(えいか)[516-518]
38 液体Ⅰ(えきたいいち)[48]
39 液体Ⅱ(えきたいに)[49]
40 絵のなかの女(えのなかのおんな)[―]
41 絵本(えほん)[33]
42 臙脂(えんじ)[15-16]
43 円筒の内側(えんとうのうちがわ)[527-532]
44 遅い恋(おそいこい)[719-720]
45 苧環(おだまき)(おだまき)[692-694]
46 織物の三つの端布(おりもののみっつのはぎれ)[486-490]
47 絵画(かいが)[369-371]
48 回復(かいふく)[111-112]
49 カカシ(カカシ)[412-413]
50 影絵(かげえ)[574-575]
51 影の鏡(かげのかがみ)[558-559]
52 過去(かこ)[85-87]
53 かささぎ → 鵲(かささぎ)[707-709]
54 家族(かぞく)[551]
55 形は不安の鋭角を持ち……(かたちはふあんのえいかくをもち)[469-472]
56 カタバミの花のように(カタバミのはなのように)[644-646]
57 郭公あるいは駙い森(かっこうあるいはあおいもり) → 郭公(かっこう)[584-586]
58 葛飾哀歌(かつしかあいか)[18-19]
59 寿星(カノプス)(カノプス)[660-665]
60 壁掛(かべかけ)[583-584]
61 狩られる女――ミロの絵から(かられるおんな ミロのえから)[173-174]
62 乾いた婚姻図(かわいたこんいんず)[37]
63 感傷(かんしょう)[121-127]
64 甘露(かんろ)[615-619]
65 樹(き)[63-64]
66 喜劇(きげき)[91-92]
67 寄港(きこう)[174-175]
68 紀行(きこう)[557-558]
69 狐(きつね)[485-486]
70 銀鮫(キメラ・ファンタスマ)(キメラファンタスマ)[700-707]
71 休息(きゅうそく)[731-733]
72 求肥(ぎゅうひ)[622-624]
73 霧(きり)[546-547]
74 桐の花(きりのはな)[19]
75 金柑譚(きんかんたん)[491-496]
76 銀幕(ぎんまく)[665-667]
77 苦力(クーリー)[112-114]
78 寓話(ぐうわ)[80-82]
79 九月(くがつ)[549-550]
80 草の迷宮(くさのめいきゅう)[459-465]
81 薬玉(くすだま)[599-603]
82 果物の終り(くだもののおわり)[143-146]
83 示影針(グノーモン)(グノーモン)[407-412]
84 首長族の病気(くびながぞくのびょうき)[161-162]
85 雲井(くもい)[735-738]
86 劇のためのト書の試み(げきのためのトがきのこころみ)[185-187]
87 下痢(げり)[147-148]
88 幻場(げんじょう)[474-476]
89 恋する絵(こいするえ)[224-226]
90 珈琲(コーヒー)[190-191]
91 告白(こくはく)[92-93]
92 固形(こけい)[109-110]
93 午睡(ごすい)[50]
94 東風(こち)[619-622]
95 孤独(こどく)[34]
96 孤独なオートバイ(こどくなオートバイ)[218-223]
97 子供の儀礼(こどものぎれい)[441-445]
98 この世の夏(このよのなつ)[518-519]
99 コレラ(コレラ)[296-301]
100 昏睡季節1(こんすいきせついち)[21]
101 昏睡季節2(こんすいきせつに)[22]
102 崑崙(こんろん)[255-263]
103 サーカス(サーカス)[537-539]
104 歳月(さいげつ)[12-13]
105 サイレント・あるいは鮭(サイレント あるいはさけ)[400-402]
106 沙庭(さにわ)[738-739]
107 サフラン摘み(サフランつみ)[305-307]
108 猿(さる)[562-563]
109 讃歌(さんか)[72-73]
110 三重奏(さんじゅうそう)[292-295]
111 塩と藻の岸べで(しおとものきしべで)[548-549]
112 色彩の内部(しきさいのないぶ)[244-246]
113 仕事(しごと)[94-95]
114 死児(しじ)[127-138]
115 使者(ししゃ)[496-500]
116 静かな家(しずかないえ)[226-229]
117 七月(しちがつ)[14]
118 失題(しつだい)[32]
119 自転車の上の猫(じてんしゃのうえのねこ)[361-362]
120 島(しま)[93-94]
121 ジャングル(ジャングル)[76-78]
122 秋思賦(しゅうしふ)[594-596]
123 修正と省略(しゅうせいとしょうりゃく)[179-181]
124 呪婚歌(じゅこんか)[155-159]
125 受難(じゅなん)[171-172]
126 竪[しゆ]の声
→ 竪の声(しゅのこえ)[571-574]
127 春思賦(しゅんしふ)[604-606]
128 巡礼(じゅんれい)[587-594]
●130 小曲(しょうきょく)[―]
131 少女(しょうじょ)[247-249]
132 少年(しょうねん)[413-417]
●133 少年 あるいは秋(しょうねん あるいはあき)[―]
134 蒸発(じょうはつ)[30-31]
135 〔食母〕頌(しょくぼしょう)[709-714]
136 叙景(じょけい)[673-675]
137 序詩(じょし)〔うんすんかるたを想起させる〕[―]
138 序詩(じょし)〔白地へ白く白鳥類は帰る〕[―]
139 人工花園(じんこうかえん)[560-562]
140 神秘的な時代の詩(しんぴてきなじだいのし)[268-274]
141 スイカ・視覚的な夏(スイカ しかくてきななつ)[553]
142 睡蓮(すいれん)[688-691]
143 スープはさめる(スープはさめる)[207-209]
144 スワンベルグの歌(スワンベルグのうた)[725-727]
145 聖あんま語彙篇(せいあんまごいへん)[329-334]
146 聖あんま断腸詩篇(せいあんまだんちょうしへん)[675-687]
147 青海波(せいがいは)[633-638]
148 聖家族(せいかぞく)[115-116]
150 聖少女(せいしょうじょ)[267-268]
151 生誕(せいたん)[336-337]
153 聖童子譚(せいどうじたん)[648-653]
154 静物(せいぶつ)〔鵞鳥の頸ねむく〕[38-39]
155 静物(せいぶつ)〔夜の器の硬い面の内で〕[57-58]
156 静物(せいぶつ)〔夜はいつそう遠巻きにする〕[58-59]
157 静物(せいぶつ)〔酒のない瓶の内の〕[59-60]
158 静物(せいぶつ)〔台所の汚れた塩〕[60-61]
159 聖母頌(せいぼしょう)[195-197]
160 蝉(せみ)[439-441]
161 草上の晩餐(そうじょうのばんさん)[351-352]
162 相聞歌(そうもんか)[35-36]
163 僧侶(そうりょ)[100-105]
164 即興詩(そっきょうし)[717-718]
165 ゾンネンシュターンの船(ゾンネンシュターンのふね)[394-399]
166 滞在(たいざい)[197-198]
167 タコ(タコ)[307-309]
168 舵手の書(だしゅのしょ)[387-392]
169 卵(たまご)[64]
170 垂乳根(たらちね)[606-610]
171 単純(たんじゅん)[106-107]
172 誕生(たんじょう)[36]
173 断章(だんしょう)〔わがこころになやみはてず〕[18]
174 断章(だんしょう)〔永劫に舟の去りゆく〕[―]
●175 断想(だんそう)[―]
176 父・あるいは夏(ちち あるいはなつ)[472-474]
177 朝餐(ちょうさん)[28-29]
178 鎮魂歌(ちんこんか)[167-168]
179 ツグミ(ツグミ)[564-565]
180 低音(ていおん)[278-279]
181 弟子(でし)[280-280]
182 田園(でんえん)[353-361]
183 天竺(てんじく)[597-599]
184 伝説(でんせつ)[96]
185 灯台にて(とうだいにて)[176-178]
186 動物(どうぶつ)[381-382]
187 透明な花束(とうめいなはなたば)[40]
188 溶ける花(とけるはな)[29-30]
189 灯る曲線(ともるきょくせん)[52]
190 内的な恋唄(ないてきなこいうた)[210-215]
191 汀にて(なぎさにて)[―]
192 謎の絵(なぞのえ)[522-523]
193 夏(なつ)〔注射器の午前九時十二分〕[9]
194 夏(なつ)〔蝋びきの食物の類をみて歩く〕[107-109]
195 夏から秋まで(なつからあきまで)[237-240]
196 夏の家(なつのいえ)[276-278]
197 夏の宴(なつのうたげ)[503-510]
198 夏の絵(なつのえ)[68-69]
199 波よ永遠に止れ(なみよえいえんにとまれ)[740-755]
200 にわとり → 雞(にわとり)[569-571]
201 沼・秋の絵(ぬま あきのえ)[178-179]
202 野(の)[511]
203 葉(は)[312-319]
204 灰色の手套(はいいろのしゅとう)[47]
205 敗北(はいぼく)[717]
206 白昼消息(はくちゅうしょうそく)[14-15]
207 薄荷(はっか)[655-658]
208 花遅き日の歌(はなおそきひのうた)[43]
209 花の肖像(はなのしょうぞう)[51]
210 花冷えの夜に(はなびえのよるに)[28]
211 花・変形(はな へんけい)[554-555]
212 春(はる)[8]
213 春の絵(はるのえ)[552]
214 春のオーロラ(はるのオーロラ)[205-207]
149 春の伝説(はるのでんせつ) → 青枝篇(せいしへん)[576-582]
215 挽歌(ばんか)〔洋燈は消え〕[27]
216 挽歌(ばんか)〔わたしが水死人であり〕[74-76]
217 晩夏(ばんか)[453-454]
218 晩春(ばんしゅん)[547]
219 晩鐘(ばんしょう)[694-698]
220 斑猫(はんみょう)[544-546]
221 ピクニック(ピクニック)[327-328]
222 人質(ひとじち)[119-121]
224 微熱ある夕に(びねつあるゆうに)[40-41]
225 微風(びふう)[38]
226 白夜(びゃくや)[392-393]
227 ひやしんす(ひやしんす)[42]
228 ヒヤシンス或は水柱(ヒヤシンスあるいはみずばしら)[310-312]
229 白狐(びゃっこ)[727-729]
230 病室(びょうしつ)[20-21]
231 ヒラメ(ヒラメ)[215-218]
232 風景(ふうけい)〔猿の頭に夕の灯がともり〕[41-42]
233 風景(ふうけい)〔緑の樹は〕[70-71]
234 フォーク・ソング → フォークソング(フォークソング)[252-255]
235 フォーサイド家の猫(フォーサイドけのねこ)[364-369]
236 不滅の形態(ふめつのけいたい)[363-364]
237 冬(ふゆ)[10-11]
238 冬の歌(ふゆのうた)[65-67]
239 冬の絵(ふゆのえ)[97-98]
240 冬の休暇(ふゆのきゅうか)[162-163]
241 冬の森(ふゆのもり)[724-725]
223 ヘアー(ヘアー) → 鄙歌(ひなうた)[555-557]
242 部屋(へや)[437-438]
243 紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(ぼうすいけいいち)[148-149]
244 紡錘形2 → 紡錘形Ⅱ(ぼうすいけいに)[149-150]
245 蓬莱(ほうらい)[628-633]
246 放埒(ほうらつ)[17-18]
247 ポール・クレーの食卓(ポールクレーのしょくたく)[535-537]
248 牧歌(ぼっか)〔歯車が夥しくおちてゆく〕[34-35]
249 牧歌(ぼっか)〔村にきて〕[98-100]
129 牧歌(ぼっか)〔男は不足なものをさがす〕 → 唱歌[542-543]
250 マクロコスモス(マクロコスモス)[233-236]
251 マダム・レインの子供(マダムレインのこども)[319-321]
252 巫女――あるいは省察(みこ あるいはせいさつ)[165-167]
253 水鏡(みずかがみ)[447-453]
254 水のもりあがり(みずのもりあがり)[163-164]
255 蜜はなぜ黄色なのか?(みつはなぜきいろなのか)[274-276]
256 みどりの朝に(みどりのあさに)[44]
257 ムーンドロップ(ムーンドロップ)[668-673]
258 無罪・有罪(むざい ゆうざい)[187-190]
259 産霊(むすび)(むすび)[641-644]
260 メデアム・夢見る家族(メデアム ゆめみるかぞく)[383-387]
261 面紗せる会話(めんしゃせるかいわ)[16-17]
262 模写――或はクートの絵から(もしゃ あるいはクートのえから)[191-194]
263 喪服(もふく)[116-118]
264 桃――或はヴィクトリー(もも あるいはヴィクトリー)[199-200]
265 夜会(やかい)[543-544]
266 夜曲(やきょく)[720-721]
267 やさしい放火魔(やさしいほうかま)[201-204]
268 遊子の歌(ゆうしのうた)[11]
269 雪(ゆき)[78-80]
270 雪解(ゆきげ)[659-660]
271 夢のアステリスク(ゆめのアステリスク)[512-515]
272 夢の飜譯 → 夢の翻訳(ゆめのほんやく)[54]
273 雷雨の姿を見よ(らいうのすがたをみよ)[477-484]
274 ライラック・ガーデン(ライラックガーデン)[540-542]
275 楽園(らくえん)[435-436]
276 落雁(らくがん)[624-628]
277 裸子植物(らししょくぶつ)[520-522]
278 螺旋形(らせんけい)[465-468]
279 裸婦(らふ)[152-153]
280 立体(りったい)[240-244]
281 ルイス・キャロルを探す方法(ルイスキャロルをさがすほうほう)――〔わがアリスへの接近(わがアリスへのせっきん)〕〔少女伝説(しょうじょでんせつ)〕[337-345]
282 老人頌(ろうじんしょう)[141-143]
283 わが馬ニコルスの思い出(わがうまニコルスのおもいで)[282-291]
284 わが家の記念写真(わがやのきねんしゃしん)[334-335]
285 忘れた吹笛の抒情(わすれたすいてきのじょじょう)[39]
286 わだつみ(わだつみ)[646-648]
152 〔標題なし〕 → 生徒(せいと)[559]
以上、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――詩篇目次〉
>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10月10日
序歌(①・0、4行)
春(①・1、10行)
夏(①・2、7行)
秋(①・3、8行)
冬(①・4、6行)
遊子の歌(①・5、5行)
朝の硝子(①・6、6行)
歳月(①・7、4行)
あるひとへ(①・8、5行)
七月(①・9、6行)
白昼消息(①・10、6行)
臙脂(①・11、6行)
面紗せる会話(①・12、19行)
放埒(①・13、6行)
断章(①・14、2行)
葛飾哀歌(①・15、6行)
桐の花(①・16、3行)
杏菓子(①・17、5行)
病室(①・18、6行)
昏睡季節1(①・19、7行)
昏睡季節2(①・20、9行)
12月10日
〔午前の部〕
挽歌(②・1、14行)
花冷えの夜に(②・2、6行)
朝餐(②・3、11行)
溶ける花(②・4、10行)
蒸発(②・5、9行)
秋の前奏曲(②・6、9行)
失題(②・7、9行)
絵本(②・8、12行)
孤独(②・9、4行)
牧歌(②・10、11行)
相聞歌(②・11、12行)
誕生(②・12、4行)
乾いた婚姻図(②・13、13行)
微風(②・14、6行)
静物(②・15、4行)
忘れた吹笛の抒情(②・16、11行)
〔午後の部〕
透明な花束(②・17、5行)
微熱ある夕に(②・18、9行)
風景(②・19、10行)
ひやしんす(②・20、10行)
花遅き日の歌(②・21、10行)
みどりの朝に(②・22、13行)
或る葬曲の断想(②・23、12行)
失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(②・24、8行)
灰色の手套(②・25、11行)
液体Ⅰ(②・26、11行)
液体Ⅱ(②・27、11行)
午睡(②・28、10行)
花の肖像(②・29、10行)
灯る曲線(②・30、10行)
哀歌(②・31、8行)
夢の飜譯 → 夢の翻訳(②・32、12行)
9月
海の章(未刊詩篇・1、16行)
敗北(未刊詩篇・2、6行)
即興詩(未刊詩篇・3、7行)
7月
汀にて(未刊詩篇・4、12行)
8月
断章(未刊詩篇・5、9行)
8月20日
〔Ⅰ 静物〕
静物(③・1、21行)
静物(③・2、13行)
静物(③・3、15行)
静物(③・4、21行)
或る世界(③・5、9行分)
樹(③・6、16行)
卵(③・7、12行)
冬の歌(③・8、40行)
夏の絵(③・9、28行)
風景(③・10、28行)
〔Ⅱ 讃歌〕
讃歌(③・11、34行)
挽歌(③・12、37行)
ジャングル(③・13、21行)
雪(③・14、35行)
寓話(③・15、18行)
犬の肖像(③・16、7節40行)
過去(③・17、30行)
4月
告白(④・2、18行分)
5月
喜劇(④・1、25行分)
7月
陰謀(未刊詩篇・6、19行分)
11月
島(④・3、14行分)
12月
仕事(④・4、20行)
3月
牧歌(④・7、27行)
4月
僧侶(④・8、9節84行)
5月
ポール・クレーの食卓(⑩・1、37行)
6月
単純(④・9、24行分)
10月
固形(④・11、26行分)
夏(④・10、32行)
5月
回復(④・12、26行分)
6月
苦力(④・13、39行)
7月
死児(④・19、Ⅷ節189行)
喪服(④・15、29行)
聖家族(④・14、21行)
9月
サーカス(⑩・2、45行)
11月20日
伝説(④・5、11行分)
冬の絵(④・6、21行分)
美しい旅(④・16、19行分)
人質(④・17、28行)
感傷(④・18、6節99行)
12月
ライラック・ガーデン(⑩・3、40行)
1月
老人頌(⑤・1、47行)
3月
無罪・有罪(⑥・2、48行)
6月
遅い恋(未刊詩篇・7、12行分)
果物の終り(⑤・2、57行)
7月
牧歌 → 唱歌(⑩・4、17行)
8月
下痢(⑤・3、26行分)
9月
紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(⑤・4、13行分)
夜会(⑩・5、10行分)
10月
編物する女(⑤・8、19行分)
呪婚歌(⑤・9、70行)
夜曲(未刊詩篇・8、14行分)
11月
陰画(⑤・6、35行)
裸婦(⑤・7、20行分)
首長族の病気(⑤・11、24行分)
12月
田舎(⑤・10、26行)
1月
斑猫(⑩・6、30行)
2月
哀歌(未刊詩篇・9、35行)
3月
紡錘形2 → 紡錘形Ⅱ(⑤・5、14行分)
冬の休暇(⑤・12、18行分)
5月
水のもりあがり(⑤・13、29行分)
6月
波よ永遠に止れ(未刊詩篇・10、11節257行)
11月
巫女――あるいは省察(⑤・14、35行)
1月
衣鉢(⑤・16、39行)
受難(⑤・17、20行)
2月
鎮魂歌(⑤・15、25行)
5月
狩られる女――ミロの絵から(⑤・18、26行)
7月
寄港(⑤・19、22行分)
10月
灯台にて(⑤・20、33行)
霧(⑩・7、13行)
3月
沼・秋の絵(⑤・21、23行)
修正と省略(⑤・22、27行分)
6月
晩春(⑩・8、4行)
塩と藻の岸べで(⑩・9、22行)
9月
劇のためのト書の試み(⑥・1、39行)
1月
馬・春の絵(⑥・5、22行分)
2月
珈琲(⑥・3、10行)
8月
模写――或はクートの絵から(⑥・4、47行)
4月
滞在(⑥・7、25行)
7月
聖母頌(⑥・6、29行)
9月
九月(⑩・10、23行)
1月
冬の森(未刊詩篇・11、14行)
3月
桃――或はヴィクトリー(⑥・8、28行)
11月
やさしい放火魔(⑥・9、71行)
3月
春のオーロラ(⑥・10、41行)
家族(⑩・11、10行)
4月
静かな家(⑥・16、52行)
5月
スープはさめる(⑥・11、37行)
花・変形(⑩・14、Ⅱ節18行)
10月
ヒラメ(⑥・13、51行)
11月
孤独なオートバイ(⑥・14、102行)
1月
内的な恋唄(⑥・12、95行)
2月
恋する絵(⑥・15、42行)
春の絵(⑩・12、13行)
7月
青い柱はどこにあるか?(⑦・6、51行)
8月
夏から秋まで(⑦・2、64行)
10月
立体(⑦・3、61行)
11月
マクロコスモス(⑦・1、70行)
7月
フォーク・ソング → フォークソング(⑦・7、45行)
8月
色彩の内部(⑦・4、43行)
スイカ・視覚的な夏(⑩・13、15行)
10月
神秘的な時代の詩(⑦・11、103行)
崑崙(⑦・8、150行)
11月
雨(⑦・9、66行)
1月
少女(⑦・5、45行)
2月
スワンベルグの歌(未刊詩篇・12、34行)
3月
三重奏(⑦・17、71行)
4月
蜜はなぜ黄色なのか?(⑦・12、30行)
5月
序詩(未刊詩篇・13、3行)
6月
序詩(未刊詩篇・14、2行)
8月
夏の家(⑦・13、39行)
10月
わが馬ニコルスの思い出(⑦・16、*印で5節に分かつ163行)
11月
聖少女(⑦・10、22行)
12月
ヘアー → 鄙歌(⑩・15、26行)
コレラ(⑦・18、97行)
3月
低音(⑦・14、23行)
4月
葉(⑧・4、135行)
6月
ヒヤシンス或は水柱(⑧・3、43行)
ルイス・キャロルを探す方法(⑧・11、〔わがアリスへの接近=43行〕〔少女伝説=*印で14節に分かつⅠとⅡの66行分〕109行)
7月
悪趣味な冬の旅(⑧・6、85行)
8月
弟子(⑦・15、44行)
10月
タコ(⑧・2、*印が3節を従える34行)
1月
マダム・レインの子供(⑧・5、42行)
2月
聖あんま語彙篇(⑧・8、4節87行)
5月
『アリス』狩り(⑧・12、76行)
7月
サフラン摘み(⑧・1、42行)
ピクニック(⑧・7、32行)
9月
田園(⑧・14、12節134行)
10月
動物(⑧・20、29行)
11月
わが家の記念写真(⑧・9、23行)
フォーサイド家の猫(⑧・17、*印で5節に分かつ85行)
3月
生誕(⑧・10、20行)
4月
草上の晩餐(⑧・13、35行)
自転車の上の猫(⑧・15、18行)
異霊祭(⑧・19、8節161行)
5月
絵画(⑧・18、29行)
7月
メデアム・夢見る家族(⑧・21、75行)
不滅の形態(⑧・16、20行)
10月
舵手の書(⑧・22、5節75行)
白夜(⑧・23、28行)
12月
ゾンネンシュターンの船(⑧・24、5節89行)
1月
サイレント・あるいは鮭(⑧・25、41行)
7月
悪趣味な夏の旅(⑧・26、6節72行)
9月
示影針(グノーモン)(⑧・27、5節79行)
カカシ(⑧・28、15行)
11月
悪趣味な内面の秋の旅(⑧・31、7節145行)
12月
あまがつ頌(⑧・30、Ⅴ節90行)
2月
人工花園(⑩・19、*印で4節に分かつ34行分)
5月
少年(⑧・29、6節53行)
8月
楽園(⑨・1、31行)
10月
子供の儀礼(⑨・4、56行)
11月
曙(⑨・8、65行)
12月
部屋(⑨・2、34行)
幻場(⑨・13、38行)
影の鏡(⑩・17、11行)
1月
悪趣味な春の旅(⑨・19、43行)
5月
螺旋形(⑨・10、62行)
異邦(⑨・5、31行)
8月
使者(⑨・18、6節66行)
紀行(⑩・16、18行)
10月
晩夏(⑨・7、22行)
11月
水鏡(⑨・6、5節93行)
草の迷宮(⑨・9、6節100行)
1月
狐(⑨・15、17行)
2月
夢のアステリスク(⑨・22、***節60行)
4月
形は不安の鋭角を持ち……(⑨・11、Ⅲ節52行)
5月
雷雨の姿を見よ(⑨・14、8節126行)
7月
蝉(⑨・3、39行)
8月
父・あるいは夏(⑨・12、35行)
10月
夏の宴(⑨・20、6節120行)
11月
織物の三つの端布(⑨・16、*印が3節を従える74行)
●断想(変改吸収詩篇・1、8行)
1月
謎の絵(⑨・26、17行)
3月
裸子植物(⑨・25、41行)
5月
金柑譚(⑨・17、5節83行)
6月
野(⑨・21、12行)
7月
詠歌(⑨・23、37行)
8月
この世の夏(⑨・24、20行)
9月
〔標題なし〕 → 生徒(⑩・18、5行)
11月
円筒の内側(⑨・28、6節85行)
12月
「青と発音する」(⑨・27、55行)
1月
猿(⑩・20、20行)
3月
ツグミ(⑩・21、29行)
1月
にわとり → 雞(⑪・1、39行)
9月
竪[しゆ]の声 → 竪の声(⑪・2、35行)
10月
絵のなかの女(未刊詩篇・15、18行)
11月
巡礼(⑪・7、8節110行)
3月
壁掛(⑪・5、24行)
春の伝説 → 青枝篇(⑪・4、〔地の霊(春の伝説1)=27行〕〔水の夢(春の伝説2)=29行〕〔火の狼(春の伝説3)=29行〕〔空[くう]の華(春の伝説4)=29行〕114行)
4月
薬玉(⑪・10、2節80行)
5月
影絵(⑪・3、23行)
7月
哀歌(⑪・13、3節58行)
8月
天竺(⑪・9、39行)
10月
垂乳根(⑪・12、75行)
12月
郭公あるいは駙い森 → 郭公(⑪・6、31行)
秋思賦(⑪・8、39行)
1月
春思賦(⑪・11、40行)
甘露(⑪・14、4節68行)
2月
東風(⑪・15、51行)
5月
蓬莱(⑪・18、4節72行)
6月
青海波(⑪・19、4節84行)
落雁(⑪・17、4節67行)
9月
求肥(⑪・16、30行)
6月
白狐(未刊詩篇・16、42行)
9月
●小曲(変改吸収詩篇・2、20行)
10月
●少年 あるいは秋(変改吸収詩篇・3、14行)
12月
聖童子譚(⑫・4、〔1 夏=14行〕〔2 秋=21行〕〔3 冬=13行〕〔4 春=35行〕83行)
1月
わだつみ(⑫・3、31行)
4月
ムーンドロップ(⑫・10、5節80行)
6月
薄荷(⑫・6、4節52行)
7月
カタバミの花のように(⑫・2、30行)
9月
秋の領分(⑫・5、32行)
1月
雪解(⑫・7、20行)
寿星(カノプス)(⑫・8、5節78行)
5月
亜麻(未刊詩篇・17、10行)
6月
聖あんま断腸詩篇(⑫・12、〔Ⅰ 物質の悲鳴=23行〕〔Ⅱ メソッド=26行〕〔Ⅲ テキスト=12行〕〔Ⅳ 故園追憶=40行〕〔Ⅴ (衰弱体の採集)=41行〕〔Ⅵ 挽歌=31行〕〔Ⅶ 像と石文=15行〕〔Ⅷ 慈悲心鳥=8行〕196行)
8月
叙景(⑫・11、35行)
12月
銀幕(⑫・9、39行)
産霊(むすび)(⑫・1、62行)
8月
苧環(おだまき)(⑫・14、34行)
9月
休息(未刊詩篇・18、38行)
11月
睡蓮(⑫・13、3節63行)
12月
かささぎ → 鵲(⑫・18、35行)
1月
((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(⑫・16、20行)
5月
晩鐘(⑫・15、4節75行)
6月
銀鮫(キメラ・ファンタスマ)(⑫・17、6節107行)
9月
〔食母〕頌(⑫・19、4節74行)
4月
永遠の昼寝(未刊詩篇・19、25行)
10月
雲井(未刊詩篇・20、3節47行)
1月
沙庭(未刊詩篇・21、20行)
以上、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――1940(昭和15)年〜1990(平成2)年〉
>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10月10日
序歌(①・0、4行)
春(①・1、10行)
夏(①・2、7行)
秋(①・3、8行)
冬(①・4、6行)
遊子の歌(①・5、5行)
朝の硝子(①・6、6行)
歳月(①・7、4行)
あるひとへ(①・8、5行)
七月(①・9、6行)
白昼消息(①・10、6行)
臙脂(①・11、6行)
面紗せる会話(①・12、19行)
放埒(①・13、6行)
断章(①・14、2行)
葛飾哀歌(①・15、6行)
桐の花(①・16、3行)
杏菓子(①・17、5行)
病室(①・18、6行)
昏睡季節1(①・19、7行)
昏睡季節2(①・20、9行)
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)〔前付四ページ〕、本文旧仮名使用、9ポ1段組、4行。詩篇の部〈昏睡季節〉と和歌の部〈蜾蠃鈔〉から成る《昏睡季節》全体にかかる序の短歌(〈《吉岡実全詩集》巻頭作品〉参照)。
あるかなくみづを
ながるるうたかた
のかげよりあはき
わかきひのゆめ
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、10行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。
朝は蝶の脚へ銀貨を吊す
感湿性植物の茎の内部で
釦のとれた婚礼が始まる
蝋燐寸の臭ひに微睡む空気よ
白い手套が南方に垂れ
造花に翳つてゆく倦怠
檣壁へ逆さまに体温を貼り
卓子の汚点で曇天を吸ひとる
停車場の鏡に鱗形の夢を忘れ
尖塔へ喪はれた童貞と星を飾る
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、7行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。
注射器の午前九時十二分
露台の女の透明な胸奥に
麦藁蜻蛉の眼球の砕粉がちる
虹の輪を廻して鼻毛のふちを
鮑貝かぶつた懶惰な狩猟者達がゆく
氷菓子の断面に太陽が溶け
鶏が甃の上の黄色い精虫をついばむ
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)五ページ、本文旧字新かな使用、9ポ1段組、8行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字新かなで全行引用されている。《「死児」という絵〔増補版〕》所収の同文では1行めと2行め、7行めと8行めがそれぞれ一文字分高く始められているが、手入れか誤植か不明(同文の初出や《「死児」という絵》では、引用詩の字下ゲ・行アキが〔増補版〕とも異なっている)。
蛇の腹の瘡痕に仄めく昼の星
硝子管の中ではしきりと木の葉がちる
白い卓子のふちを走る柩車の轍のひびき
瞳膜へ蜘蛛が巣をはる
遠い靴下のさきに広告気球がのぼる
鋪道で子供が電球をこわした
秋が窓からきらきら光らせ
爪をきりこぼす
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)六ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。
亜鉛の錘が雪の蠅をつぶす
褐色な牡蠣の液汁が街を蔽ひ
時計の針は北へ折れ曲る
赤馬の鼻孔に夜行列車が到着した
地殻と粗い舌へ蝋燭の焔ゆらぎ
娼婦の骨盤に羽をひろげて鴉が下りる
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)七ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、5行。
朝夕の
襟飾がおもたくて
私は乳房のふくらみに
羊を飼ひ
草笛を吹く
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)八ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。
裏がへされた微風が掌から
林檎の花の明るさに澪れる
山脈を旋回する反射鏡の光に
揺籃のみどり児は小便を匂はす
黒い犬は皿の上の朝をなめる
樹脂が流れゆく雲に粘りつく
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)九ページ、本文旧字使用、9ポ1段組、4行。
盲縞に昏れゆく眼瞼のうらで
切断される蜥蜴の尾の悲しさよ
色褪せた風の間を冷たく静かに
透明な時間が流れてゆく
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一〇ページ、本文旧字使用、9ポ1段組、5行。
のこりし一本の巻煙草のにがみよ
たそがれてゆく窓掛と犬の遠吠え
まちわびて吹くけむりの輪のなか
いつしかに新月のきらめけれども
むなしくもああきみはきたらずや
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一一ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。
氷菓子はとけて
銀の匙をつたはり
爪の紅へにじみゆく
淡い夏の夕
鏡の中の女の捲毛に
風がひとすぢゆれてる
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一二ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、6行。吉岡の随想〈新しい詩への目覚め〉(初出:《現代詩手帖》1975年9月号)に新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)で全行引用されている。《「死児」という絵》と同〔増補版〕所収の同文では「自転車競争選手」となっているが、手入れか誤植か不明(同文の初出では「競走」)。
自転車競走選手が衝突する
夏蜜柑の内房の廊へ粘液がふき出す
頸の青い子供が燻銀色の硝子杯で電流をのみこぼした
傾斜地帯から円錐型帽子へながれこむ
一枚の風と約束と花蕊と
女の客が曲り角の化粧品店にはいつた
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一三ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。
洋皿に春の蚊がとまり睡い日
鍵盤のなみへ薔薇や夢がただよひ
石鹸の泡から果実がうれて出る
糸で吊るされた水母に金矢を刺し
頸飾をかけて令嬢は結婚した
手巾のうすくよごれた都会の憂愁
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一四〜一五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、19行。《昏睡季節》では、本篇だけ見開きにまたがる作品となっている。
花びらのうへに死んでゐる指のあとを
見ると あたし泣けるの
銀の針で その背後を失つた哀れな人を
女のやはらかな耳朶から
ほりだしたいの
硝子のやうにたのしい触手をもつ
あたしたちよ あなたの泪が靴の裏で
汚れるわ 十字架の蔭に 鼻孔をひろ
げる喪服の男のことなんか ぬれてゐる
樹液の香を唇にぬつて 忘れなさいな
紅の茸は湖のほとりに 咲いてゐるわよ
蒼黝い幹の疣に 夕ぐれを巻き
つけ 黄色の布と
距離のない春の光線を
明日の虹の流れへ すててきて
あきらめるわ
空をとべない風より 草むらに
墜ちてくる星を拾つて 掌の上にのせて
あたためませう
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、6行。
真昼の影へ花粉がこぼれ
白い液体の底に指環はしづむ
肥つた紳士は皮膚の上を彷徨ひ
夢の女を探す……靴あとのこして
室内には夜の空気がふくらみ
螺線階段を青い虫の這ひあがる
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一七ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、2行。
わがこころになやみはてず
あをぞらにくものわく
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一八ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。三首の旋頭歌に等しい形式を採っている。
川下る舟の灯にかかる青けむり
家々もはやあたたかき夕餉なるらし
古き橋わたりゆきつつ娼婦たたずむ
おくれ毛のあせし油香匂ほし風ふく
赤き星ひとつきらめき犬吠ゆる土手
草ゆれてゆくひともなく遠くつづけり
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)一九ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、3行。
白紙のうらにうつすらと哀しみわく午後
私は鉛筆の芯を尖らしては折る
雨あがりの窓べに桐の花がひとつおちた
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二〇ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、5行。
蛞蝓が這つて光つた空間を
落下傘で一滴の乳酪がおりてきた
草色の山脈は煽風機で歪曲する
噴水へ刺繍された午の月
忘れた衣装の女が杏菓子をたべる
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二一ページ、本文旧字旧仮名使用、9ポ1段組、6行。
患者は白い窓掛に指紋を忘れ
朝の水銀にいのちを計られる
昼間の隙の青空で風船玉ふくらみ
再び失はれた追憶が雲に乗る
圧搾器から今日も葡萄の汁と
夕暮がしたたりそめる
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、7行。
水の梯子を
迷彩を失つた季候や
夜が眼鏡をかけてのぼつてゆく
葉巻の煙の輪の中で女達は滅び
電球に斑点がふえる
物憂く廻転する椅子の上に
目の赤い魚が一匹乾いてゐた
初出は詩集《昏睡季節》(草蝉舎、1940年10月10日)二三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、9行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に新字旧仮名で全行引用されている。
牛乳の空罎の中に
睡眠してゐる光線と四月の音響
牡猫の耳のやうに透けてうすく
砂の上に日曜日が倒れてうづまる
麺麭が風に膨らむと卵は水へながれ
堊には花の影が手をひろげて傾く
眠り薬を嚥みすぎた男が口を尖らし
銅貨や皺くちやの紙幣を吐き出す
夜を牽いて蝙蝠が弔花をとびめぐる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12月10日
〔午前の部〕
挽歌(②・1、14行)
花冷えの夜に(②・2、6行)
朝餐(②・3、11行)
溶ける花(②・4、10行)
蒸発(②・5、9行)
秋の前奏曲(②・6、9行)
失題(②・7、9行)
絵本(②・8、12行)
孤独(②・9、4行)
牧歌(②・10、11行)
相聞歌(②・11、12行)
誕生(②・12、4行)
乾いた婚姻図(②・13、13行)
微風(②・14、6行)
静物(②・15、4行)
忘れた吹笛の抒情(②・16、11行)
〔午後の部〕
透明な花束(②・17、5行)
微熱ある夕に(②・18、9行)
風景(②・19、10行)
ひやしんす(②・20、10行)
花遅き日の歌(②・21、10行)
みどりの朝に(②・22、13行)
或る葬曲の断想(②・23、12行)
失はれた夜の一樂章 → 失われた夜の一楽章(②・24、8行)
灰色の手套(②・25、11行)
液体Ⅰ(②・26、11行)
液体Ⅱ(②・27、11行)
午睡(②・28、10行)
花の肖像(②・29、10行)
灯る曲線(②・30、10行)
哀歌(②・31、8行)
夢の飜譯 → 夢の翻訳(②・32、12行)
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、14行。〔抄〕に入集(01)。――流布本として定評のある《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》(思潮社、1968年9月1日)には詩集《液體》全32篇のうちの12篇が抄録されている。それ自体、作者によるある時期における提示のしかただったことを考慮して、これらが抄録された詩篇である旨を「〔抄〕に入集」と記した。〔抄〕の本文は新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用――。
洋燈は消え
頭骸をつき出る
銹びたフォークの尖に
一匹の狐がめざめた
それは医者のにぎる
北十字星よりも
距離を冷たく
呼吸管へ起伏し
ぬれた夕刊紙でつつまれ
少年たちは饒舌に
よごれた食器の中で
翼を焚き
落葉へかさなつて
ながれてしまふ
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、6行。
涙線がきれて
遠い窓の灯がきえる
夜は苑いつぱいに噴水して
白い繃帯をといてしまふ
注射針のさきで呼吸してる星よ
花は冷えてねむれなかつた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)五ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。
指揮者の手に
遅刻した春の山脈つらなり
林の館へ曲る
朝の洋燈の芯と
湖がめくれて
髪毛の植物性油が匂ふ
街には白い封筒が一枚
静にながれてゆく
莨の口からやがて
ふえると帽子に
鳥が卵をうみにくる
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)六ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、10行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に全行引用(本文新字新かな使用)されている。〈中村葉子に〉
春の葉脈に神々が膨脹してゐる
金貨の見える丘よ
聖書の上で海盤車がひかる
扉をひらくと青空が一枚
浴室の石鹸の泡にぬれる
風見鳥は夜へまはり
少年たちは白い皮膚へ沈んでゆく
天使の頸のあたりに漂着する
穴のある靴下と蝶
猫の唾液で花が溶けてゐた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)七ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。〔抄〕に入集(02)。
聖母祭の樹の下を発車する
脳髄の午睡へ沙漠をはさむ
温室で鸚鵡の金属性の嘴の
重量が遠い女の乳房に沈み
手袋に飛行機は入らぬとて
メロンの輪切うすく仰ぐと
透ける少年と犬の舌の冷い
不眠性も終らない中に舶来
の手帛でつつまれてしまふ
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、9行。
朝の皿を拭きをはり
蜻蛉たちがつながつてとんでゆく
いくら麺麭をふくらせても
故郷のない私の尖つた咽喉骨
折れたとらんぷよりつめたい
角の洗濯屋の子供の瞳
影とひかりの間から
鳥打帽子ななめにかぶり
爪をみがいて秋がやつてきた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)九ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。
病犬の瞳孔を
無数の砲弾が通過する
卵巣に仙人掌の花が萎え
皿に毛虫が繁殖してゐる
灰色の魚骨の隙間で
歪んだ太陽が氷結しながら
手品師の汗臭い襯衣へ墜ち
死産児の蹠より
敗戦した艦隊が出てゆく
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、12行。
春のパセリの匂ふまど
眼帯をはづす朝です
異人さんの子供の青い靴下
寺院の鐘が聞える
みじかいおまへの手紙と
貝がらのやうな雲と
犬は絵本もよめません
卵焼きのだいすきな叔母様
体温器はしづかにねむり
蝶がとほりすぎる
インキのついた指
明日は雨がふるでせう
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、4行。
対角線の蝋燭くづれて
花びら白紙をこえゆく
死せる魚族の鱗に蔽はれ
月蝕の館でわれひとり眠る
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一二ページ、本文旧字使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(03)。
歯車が夥しくおちてゆく
神の掌より
杳なところ波があがる
笛を吹けよ
雨にぬれた青い葦の葉
羊たちはのびたり縮んだり
癈園への道が見えなくなる
洋燈の内側を拭き
重つてくる蝶の翅をめくる
遅刻した短剣が月へ刺さり
花びらがしきりに溢れた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一三ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、12行。
白い橋で 病める女の あしうらに
かくされた 一枚の骨牌を やぶき
羊をつれて 私は秋の鏡を
さまよひ 霧の隙間に 木曜日の
靴下を吊れば かなしみは
とほく 林檎のなかに忘れた
夜光時計のやうに 冷たい
花つぶす 爪に啼く鳥よ
繃帯のかなたを ああ 泪と
あなたの朝の汽船がゆく
反歌
横顔を 魚族よぎれば 胸廓の
花くづほれぬ 君よいづこに
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、4行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字旧かな(ひらがなの拗促音は並字)使用)されている。
母胎が氷結する早晨
濁つた血液の坩堝より
爬虫類に蔽はれた太陽へ
一頭の青く濡れた馬かけのぼる
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一五ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、13行。〔抄〕に入集(04)。
花やピストルも
いつしか枯葉の下になり
カレンダアのごとく
葬送の列へ滑り
皿の上に夢は冷えゆく
高階の夜の婚礼も
女の手鏡にばかし
華麗にたちのぼり
男たちは癈園に
競売人の抱へてる
蒸溜水盤から
音もなくこぼれて
やがて乾いてしまふ
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、6行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字旧かな(ひらがなの拗促音は並字)使用)されている。
灰色の括弧の中にゐる星たちよ
僕はひとりぼつちで誕生日を祝ひ
円頂塔の雲を手袋でなでたりする
幼いころ失つた緑の矢が戻つてきた
その晩から彼女の胸ふかくに
一羽の透明な鳩が見えはじめた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一七ページ、本文旧字使用、五号1段組、4行。吉岡の随想〈わが処女詩集《液体》〉(初出:《現代詩手帖》1978年9月号)に全行引用(本文新字使用)されている。
鵞鳥の頸ねむく
異人墓地へ曲り
午後の鼓膜から
女飛行士が下る
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)一八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(05)。
喪服の馬車が通つてゆく
吹笛へ雨はふり
くすりびんのなかで
孔雀をひらいてはこつそり
水脈をかぞへをはると
ねむくなる僕は
たえず螢どもを匙でとらへる
柔かい巣の上にできた斜塔へのぼり
青い樹木の年輪をぬけだし
灯る聖水盤の下をさまよふ
ああ獅子の首を索めて
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二一ページ、本文旧字(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、5行。
神の足跡へ傾斜してゆく
花と魚族の婚姻図
商館区の紳士は洋杖で
垂れさがつた女体をたたき
窓帷にすばやく蛇をみつける
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二二ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、9行。
紡車のはるかなる丘
片道切符をちぎると
南風の街々から
果液がながれあふれて
昏れてゆく搖籃に
いひそびれたことばが重く
噴水へ突然こわれた椅子おち
眼球は月と共に溶解し
鏡に微熱がある
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二三ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(06)。
猿の頭に夕の灯がともり
肺管へまひおちる花びら
露台の夫人の指のあひだに
ふるさとの泉があふれ
麦稈帽子いつぱいこもる慕愁
単音よりも遠いひとよ
眠りのほとりに
布のやうに僕の一枚の皮膚がしづむと
青いけむりがたち
砂丘の尖つた寺院の鐘が聞える
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二四ページ、本文旧字旧仮名(カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、10行。
午前の昇降機は六階に停まる
温室咲きのヒヤシンス
半休日の交換手の耳から
こぼれでる蜜蜂たち
罅のある巡査の眼鏡をうり
まよひやすいシャボンの泡すくふ
一本の試験管となり
火の音にふと母性をしたひ
楡の木の下で旅装する
風船玉のしぼまぬうちに
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(07)。
薬品罎のなかで朝をまとうた牝鹿の
薔薇色のやはらかい咽喉のあたりを
流浪する女たちは天鵞絨の傷のやう
にやさしく私のねがひを羽毛襟巻へ
飼つてゐる金魚の呼吸のひとこまに
秘めたころ退屈な水分の多量な妖し
い土曜日の指輪の内側の匂へる華麗
な路へ曲つてゆく婚礼自動車を追ふ
死んだ鳥をかついだ男が急に煙草の
灰へくづれると街燈がともつた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、13行。〈朝の序曲〉
四月の鏡から柔かい卵が浮び上る
おもひだせない手帛の縁の頭文字
朝の時計のなかで
水脈がしづかにゆれてゐる
化粧室の鍵がみつからない奥様よ
栗鼠が虹をとびこえます
新鮮な電報をやぶりきると
旅客機の音が聞える
莨をすこし吸ひすぎました
塑像はまだ濕つてゐませう
重役の頭を一直線に上昇する
縞ズボンのポケットから
折目のない青空が出てくる
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二七ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、12行。〈墓地にて〉
午睡は夥しく
花あんずのやうに冷え
白い距離を走る
そこに炎える手紙を
南へむけてたらすと
抹殺された夜の傷口がしきり
蔦の窓を搖曳し
濫ふれる水も
あきらめることなく昏れ
旅びとは風船の周囲をめぐり
やつと死の旗をみつける
数字に扮装した甲虫の中に
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二八ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、8行。
遠ざかつてゆく青い水泡
脣は蝙蝠となり
北側の硝子が粉砕される
さようなら
左の爪に傷ついた月の出よ
すつかり乾いた眼球の底で
喪の日に燐寸が燃えつきる
銀行員の肋骨で山鳩が啼いた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)二九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、11行。
いちめんにひろがる白い雲
なんべんも色鉛筆をなめました
やつとみつかつたお母さんの写真
あんずの花はよく匂ひますね
十字架のたそがれるころ
麦酒がこぼれて
私は旗のやうにひとり
ああ遠いみづうみにしづんだ
豆売娘のやさしい肩掛よ
墓地への道はながかつた
太陽を蔽うてる灰色の手套の下
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(08)。
水晶の粒にみどりの蛇の影がゆら
ゆらふるへてゐたと思ふまに手紙
が配達されたので網膜が冷たくな
りながら湖へひろがり眠る女の明
るいトルソを蔽うて隅の方より南
の街へ燬け縮んでゆく赤い風船玉
がとびだす脳髄のうちで粉砕され
た秋のガラス類が唾液に溶解はじ
めるほのかな音は菩提樹の葉をつ
たはりテラスの石卓にわすれた朝
の月を羽毛のやうに濡らしてゐた
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号1段組、11行。〔抄〕に入集(09)。
その指ききにあらゆる物体が溶化し
て虚空に剥奪される神々は軽く震揺
し累積された存在が瞬間の映像と接
触する血液が氷下で計量され枝を離
れる二重奏はみどりの帽子に均衡を
失ひ夥しい両側の皮膚が透になりな
がら植物類へこぼれ忘れた約束と薄
明を華麗な王冠にうけまもなく地図
へおりてくる子供らを季節風にめく
られた金属で支へ換気筒を出てゆく
朝の驢馬を音もなく粉砕する水の上
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(10)。
水平線へ体温計をつみかさねる
腕の青い血管のひとすぢにふる
さとの霧ふかい提燈を失ひさぼ
てんの〓に傷ついた卵巣を金貨 〓:草冠に「剌」。定稿では「莿」。
で覆うて逃亡する冷たい蜘蛛の
息に翳る病院の廊下の硝子に映
つた女の胸廓に花葩がちりつく
すと蝋燭は消え噴水があがつた
り洋籠がひらくと鱗がふつてく
る電球のなかに夕の木琴が鳴る
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三三ページ、本文旧字旧仮名(カタカナ〔ただし和語〕の拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。
温室ノ硝子ヘアツマル
女ノ耳カラ花粉ガ氾濫シテ
午前中ノ小鳥タチハ透明ニナリ
角砂糖ノ街ヲトビサル
鉛筆ノヤウナ風ハ折レテ
駱駝ノ雲ガ眠ルコロ
亜麻ノ花ニカヘツテユク
古風ナ乳母車ノワダチノ音ヨ
冷エル眸ノ底モ斑ラニユレ
鈴ガ鳴ルト昏レル
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、10行。〔抄〕に入集(11)。
廻転扉をゆるくおしたら剃刀が雲を
切りおとしてしまふたくさんの神経
をのぼつたりおりたりする春の蛇に
冷えてゆく異国女の脂肪がぬれてる
希臘風の客間の灯る鏡の瞬間にふと
銀の匙を失つた夢を緬羊の瞳の中で
歯磨粉と混乱させては青銅の首をか
ぎりなく溶ける花にうかべ月よりも
上昇する音符に試験飛行士が衝突す
ると皿がわれて葡萄の種子がひかる
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号1段組、8行。
毛皮にうづまつて
みづうみはねむり
手帖の白い頁から
春のくらげらわき
一匙の雲啜るまも
わすれられぬひと
冷えた眸のそこに
花とともに溶ける
初出は詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)三六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号1段組、12行。〔抄〕に入集(12)。〈紛失した少年の日の唄〉
金魚が紛失する午後の音譜線を走る
少年は蝋にまみれながらも牧師様の
帽子をこまかくちぎり暖かい卵をさ
かんにぬけ星とぬれた植物の隙間へ
のぼつてゆく伯爵夫人の扇をとらう
と手をのばしたら山羊の乳液があふ
れだし緑の周囲がまるく縮んだかと
思ふとたちまち旅行証明書と平行す
る夏の雲よりもはやく待避駅が映る
女医の水晶の眼鏡へ蛾がおちて間な
くシャボン玉が湧きふりかへる風に
葡萄が灯り首輪のない犬がもうきた
以上の32篇は、書きおろしの詩集《液體》(草蝉舎、1941年12月10日)に掲載。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
初出は《漁》(東洋堂)1947年9月号〔2巻9号〕一ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、10ポ四分アキ20行1段組、16行。《吉岡実全詩集》に未収録。
貧しくて さびしくなつたら
海へ行こう
晴れた日の海へ行こう
でつかい魚たちが跳ね上り
どこにも金の波があふれている
午後の風をはらんだ白帆は
お母さんの乳房のようにやさしい
はるか遠くで 入道雲も微笑している
けつしてひとりぼつちを
さびしがるな そこらの岩かげに
蟹が泡を吹いて居眠りしているし
まかれた花びらみたいに鴎もとんでいる
そして夕焼の浜べで
ぬれたばらいろの貝がらをひろい
童謡を唄つてかえろう
灯のともつた 家にかえろう
初出は《新思潮〔第14次〕》(玄文社)1947年9月〔1巻2号〕の〈詩二篇〉二四ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号二分アキ11行1段組、6行。
神の掌がひらかれたが
影になる方向には
灰色の波が重り
歪んだ帽子へ消えると
蛇や百足虫が這ひ出し
私の骨が残つた
初出は《新思潮〔第14次〕》(玄文社)1947年9月(1巻2号)の〈詩二篇〉二五ページ、本文旧字(カタカナ〔ただし和語〕の拗促音は並字)使用、五号二分アキ11行1段組、7行。《吉岡実全詩集》で第一行が詞書/献辞のように組まれているのは誤り。
私ノ時計ニ
蝶ガトビコンダ
スルト銀ノぜんまいヤ花ヤ
牛酪ヤ私ノ夢ガ
溢レダシ
イツペンニ
夏ノ窓ハ明ケテシマツタ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
初出は《水産》〔本号より《漁》を改題〕(東洋堂)1948年7月号〔3巻7号〕二六〜二七ページ、本文旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ15行1段組〔コラム〕、12行。作者名は「皚寧吉」。《吉岡実全詩集》に未収録。
ひぐれのなぎさをわたしはあるいてゐた
なにかをもとめてあるいてゐた
わたしのゆくさきにだれかのあしあとがのこつてゐた
てんてんとわたしのかなしみよりはるかにふかくすなにしづんでゐた
いくらわたしがついきゆうしてもあしあとはつづいてゐた
だれがこんなさびしいものをのこしていつたのか
すなはかすかにかわいてつめたかつた
かいそうのまつわつたいわのあたりにもまだつづいてゐた
とほくないだうみのうへをかもめがひとつとんでゐた
にさんどなきながらさつてしまつた
わたしはわたしのまへをゆくひとをもとめてあるきつづけた
つきがのぼるとばかにそのひとがこひしくてならなかつた
初出は《水産》(東洋堂)1948年8月号〔3巻8号〕一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号二分アキ11行1段組、9行。目次に記載なし。漁船と蟹の挿絵(クレジットなし)が詩篇を囲む。《吉岡実全詩集》に未収録。
永劫に舟の去りゆく
落日の海に魂のふるさとを求め
われ浮腫混沌の方角より
憔悴せる手をさしのばす
ああわが懊悩の手
清楚無限の波に洗はれ
ふたたび無垢の血よみがへり
はるかなる回帰線を越え
白鳥のいのちをつかまんとす
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8月20日
〔Ⅰ 静物〕
静物(③・1、21行)
静物(③・2、13行)
静物(③・3、15行)
静物(③・4、21行)
或る世界(③・5、9行分))
樹(③・6、16行)
卵(③・7、12行)
冬の歌(③・8、40行)
夏の絵(③・9、28行)
風景(③・10、28行)
〔Ⅱ 讃歌〕
讃歌(③・11、34行)
挽歌(③・12、37行)
ジャングル(③・13、21行))
雪(③・14、35行)
寓話(③・15、18行)
犬の肖像(③・16、7節40行))
過去(③・17、30行)
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六〜八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、21行。《静物》の冒頭は初刊以来、一貫してこの〈静物〉で、吉岡実の手になる稿本でも最初の作品として製本されているが、次に述べるように、印刷所に渡った段階では本篇は〈静物〉連作の二番めに置かれていた。吉岡は詩集の校正段階のある時点で、〈静物〔夜の器の硬い面の内で〕〉こそ巻頭詩篇にふさわしいと断を下したのである(稿本での第一行は「夜の器の硬い面の内側で」とあったのを、鉛筆で「側」一文字を抹消してある)。
夜の器の硬い面の内で
あざやかさを増してくる
秋のくだもの
りんごや梨やぶだうの類
それぞれは
かさなつたままの姿勢で
眠りへ
ひとつの諧調へ
大いなる音楽へと沿うてゆく
めいめいの最も深いところへ至り
核はおもむろによこたはる
そのまはりを
めぐる豊かな腐爛の時間
いま死者の歯のまへで
石のやうに発しない
それらのくだものの類は
いよいよ重みを加へる
深い器のなかで
この夜の仮象の裡で
ときに
大きくかたむく
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一〇〜一一ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、13行。稿本では、第一行が「非在〔もしくは「非存」、二文字めは「土」「子」どちらかを先に書いて上書きしている〕の鏡」とあったのを赤線で消してある(写真参照)。稿本で当初、中扉「Ⅰ 静物」のすぐあとに置かれていた〈静物〔夜はいつそう遠巻きにする〕〉こそ、印刷入稿時における《静物》の巻頭詩篇だった(〈吉岡実詩集《静物》稿本〉参照)。
吉岡実詩集《静物》稿本の〈静物〉(③・2)冒頭 出典:《日本近代文学館》第189号(2002年9月)
夜はいつそう遠巻きにする
魚のなかに
仮りに置かれた
骨たちが
星のある海をぬけだし
皿のうへで
ひそかに解体する
灯りは
他の皿へ移る
そこに生の飢餓は享けつがれる
その皿のくぼみに
最初はかげを
次に卵を呼び入れる
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一二〜一三ページ、本文旧字使用、五号11行1段組、15行。酒のない瓶の内の
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一四〜一六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、21行。
台所の汚れた塩
犬のたれさがる陰茎
屋根のつきでた釘の頭
それらのもろい下部構造の一角を
暗い鏡へ映しながら
やがては
まだ形をなさぬ胎児の手足
画家の心象の岸べの馬
計算されない数字
類似の抽象まで
他の部屋 他の次元へ
はこび入れる
それらの異質のものを同じ高さで
同じ角度で静止させる
夜の仕事の華麗なる狡猾さである
しかし
重すぎるので
ただ一個の卵はそのまま
窓の卓に置かれてゐる
そこには夜のみだらな狼藉もなく
煌煌と一個の卵が一個の月へ向つてゐる
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)一八〜一九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号30字詰11行1段組、9行分。吉岡が《静物》を編集する当たって、おそらく詩ノートに書いた下書きを一篇ごとに原稿用紙に清書した段階では詩篇の順番は決まっておらず、詩集の構成が決定してから鉛筆で通しノンブルを記入したものと思われる。この時点では「14」「15」とノンブルを記した、刊本の《静物》のどこにも見えない〈音楽〉という詩篇が存在したはずだ。稿本の〈或る世界〉に鉛筆書きノンブルのないことを傍証として、〈或る世界〉はその〈音楽〉に替わる新原稿と考えられる(〈吉岡実詩集《静物》稿本〉参照)。
薄明のなかで 呼びおこされ うごきだし やがて立ちあがり 喚ばうとする 黄いろい原形のむれ つまりなめくじのごときもののむらがるカオス その拡大された皺の下から現はれる ぼくたちの形相 猛烈な汗のながれる ぼくたちの鼻 生きるための嘔吐をくりかへす ぼくたちの咽喉 しかも冬の日にはげしくさらされて 日日亀裂を深めてゆく ぼくたちの歯 その暗い奥へたえず追ひかへされ 巻きかへつてゆく ぼくたちの舌 いま 落日の皿の海に沈みかける 脂のきれた骨の世界 その前にきて ぼくたちの突然巨大になつた口が凍る涎をたらす
樹(③・6)初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二〇〜二一ページ、本文旧字旧仮名使用、五号11行1段組、16行。
雨のぬらした藁の寝床から
若い女は鮮明な姿態で起き上る
そのかたちについて
樹も起き上る
まぶしい太陽の下で
羞恥の斑が花のやうに
女のかくれた幹をながれる
うづくまる裸の樹
その渇く内部
やがてまた地から
充分な樹液が注がれ滑らかになる
さへぎるもののない野へ
しなやかな姿勢で
根の瘤から
いまはじめて樹は
男のやうに立ち上る
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二二〜二三ページ、本文旧字旧仮名使用、五号11行1段組、12行。吉岡は1949(昭和24)年8月1日の日記に「或る場所にある卵ほどさびしいものはないような気がする。これから出来るかぎり〈卵〉を主題にした詩篇を書いてみたいと思う。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一一六ページ)と書いている。
吉岡実詩集《静物》稿本の〈卵〉冒頭(「いきてゐるものの影もなく/死の臭ひものぼらぬ」と読める) 出典:《日本近代文学館》第190号(2002年11月)
神も不在の時
いきてゐるものの影もなく
死の臭ひものぼらぬ
深い虚脱の夏の正午
密集した圏内から
雲のごときものを引き裂き
粘質のものを氾濫させ
森閑とした場所に
うまれたものがある
ひとつの生を暗示したものがある
塵と光りにみがかれた
一個の卵が大地を占めてゐる
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)二四〜二八ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号11行1段組、40行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に依れば、tまたはTは池田友子である。
〈tに〉
その夜の空の華やかでさびしい殷賑
塵のなかから離れ
いくつかの星は沈む
大きな氷る器のなかに
われわれにどうして反響が聴かれようか
この愛のないところには
多くの屋根
太陽に育ちゆくこともない
われわれの石の屋根
冬の狭い窓は
男の固い心臓の上に
切れた紐の端をたらす
ここには多くのものは戻らない
猫や風の叫びの他には
きしむベットで男はうつむく
まるで汚れた藁の奥に
死を凌駕するもの
結び目のないもの
法外な愛の充足を
手でさがすかのやうに
やがてすべての窓はひらかれなくなるだらう
小さな風景一つ映しはしないだらう
その吹きさらされた外を
沈んでいつた多くの星
それに蹤いていつた多くのミニッツ
それらは一度は通つていつたかも知れぬ
その眠らぬ男の眼や
皮膚のなかを
ひとりの女の愛を求める
男の淫らな歯に囚はれた咽び
枯れた野の木の根には
限りなく春へ捧げられる地の液が注がれるのに
あふれることもない
ただ深さだけを示すひとつの海の秩序がたもたれる
その男の暗い眼のなかで
いまはじめて
多くの沈んだ星はぬれ
徐徐に光りだす
大きな器をとりまく
冬の夜明けの夥しい反響のなかに
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三〇〜三二ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、28行。
商港や浚渫船もこの夏は
狂信的な緑の儀式へ参加する
同時に
マストはにぎやかに梢となり
鳥の斑のある卵をいくつもかかへる
大きな葉を風は
船長の帽子へ投げ入れる
さかさまにひつくりかへつた船長の股に木の実が熟れる
前進せよ沖へ
緑の波の中へ
波も緑のモザイクの葉
停止せよ
棘の緑に船の旗も破られる
緑の祝日は
太陽すらのぞかせぬ
小便する船乗りの犬
それも緑のとげへ
縦横にみどりの毛糸でひつかかつてゐる
すこしほどくと枯れだす
船は上陸した
横たはる
大きな樹木になつて
根にかかへる千の石をおとし
枝枝の間から
千の鳥を
沖の波にかこまれた
みづみづしい桃のなる
島へ帰らせる
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三四〜三六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、28行。本篇は、稿本の段階では目次・本文とも〈クートーの風景〉という題名だった(「クートー」については〈画家クートと詩〈模写〉の初出〉、〈リュシアン・クートーと二篇の吉岡実詩〉および〈詩篇〈模写――或はクートの絵から〉評釈〉を参照のこと)。その〈クートーの風景〉が校正のある時点で〈風景〉に変わったわけである。
緑の樹は
すみずみまで
けものの歯の中から
船や海岸や館の庭まで繁りつくす
つひには棘ばかりのバラの蔓は
石の出窓をのりこえ
女の奥ふかくの卵型の殻のふちまで
とりかこみそつと支へる
それは泛かんでしまつた
発端のない世界の変りはてたすがた
注ぐ雨にかたむく世界
稲妻の光にひととき映されて
台所をこのんで歩く鶏たち
パン職人の旺盛なる欲情の手にいつぱい
黄なびた蛙の脚はたれさがり
それへ近づく
非常に静かになつた空
緑の弱弱しく洩れてくる
落日の地方
ブリキ製の亀の手足や
首のひとゆれが見える町の家の灯
母親が現はれる
器の中に食物が捧げられ
いちじくの葉に
美しくわれだす露が示される
黄色に枯れてゆく
事物や風景の下で
家族は団欒する
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)三八〜四一ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、34行。
ぼくには拡がりが必要だ
さわやかな水の響が希はれる
ある夕べの部屋で
女の肖像をみつける
ぼくはその不倫にとまどふ
別の意味で感動しようとする
物の混同の機能を証明できないか
きはめて貧しい食堂の隅
詮索する
女の死
いまはじめてぼくのうちで女は死んだのだ
枠から遠ざかる
肖像の中の女の眼
その女の髪の中で
輝いた星は
いま曇つて外れてゐる
残酷な生存の世界から
全人類が眠つた後
ぼくは一本の縄の端の円で
新しい世界
夜明けの釘をさがす
反映する空へ正確にちかづく
秋の木の実が夥しい
ぼくの飢ゑ
ぼくの渇きが現はれる
地上を這ふ朝のランプ
その新鮮な啓示の卓の卵
何ものにも容れられてない
ぼくの純粋なる振動
火 河 人間をこえ
全身の露をはらひおとし
りりしくも
卵を啖ふ若い獣へと
ぼくは大きく転身する
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)四二〜四六ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、37行。
わたしが水死人であり
ひとつの個の
くづれてゆく時間の袋であるといふことを
今だれが確証するだらう
永い沈みの時
永い旅の末
太陽もなく
夕焼の雲もとばず
まちかどの恋びとのささやきも聴かない
かたちのないわたしの口がつぶやく
むなしいわたしの声の泡
かたちのないわたしの眼がみる
星のやうにおびただしいくらげのしづしづのぼつてゆくのを
かすかに点じられた
微粒のくらげの眼
沈んでゆくわたしの荷を
いつせいに一瞥する
それにはおそろしく沈黙の年月があるやうに思はれた
わたしの死の証人たち
それはくらげのむれなのか
やたらにわたしの恥部をなぜる
海の藻の類の触手なのか
わたしをうけ入れるために
ひとつの場所を設定する
もつと深く
もつとはるかな暗みへ置かれる
水平な岩であるのか
地上から届けられた荷
すつかり中味をぬきとられた袋の周辺では
おほくの世界
おほくの過去と未来
おほくの生の過剰と貧困
それらすべてを跨いでくる
ひとつの死の大きさ
そのしずかな全体
腐れかかつた半身をひきずつて
幾千種の魚が游泳する
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)四八〜五〇ページ、本文旧字旧仮名使用、五号24字詰・25字詰11行1段組、21行。本文は四八〜四九ページが24字詰で、五〇ページが25字詰で折り返してある。本書の四八〜四九ページ以外は25字詰で折り返してあることから、24字詰は組版上の不統一と考えられる。
木が茂る 実は熟れる 茂るまま枯れる
沈黙の中で 或は形而上の外で 実がおちる
枯れた枝の上に しばらくは幻象の重みが谺する
また茂る 永遠にくりかへす 無償のみどり
黄色の視線 まれには深紅の微点 ここには
生の乱費 生の惑はし 生の脅威 鳥はとぶ 反映に炎えつづける雲
渇く天の井戸 切実なる死の庇護 夏がすぎて秋へ 蛇がはひまはる
肉体の到達の場がない のたうつ寸秒が 滅びが美に価する
異形の卵がふえる それら雑種の卵が空間をしづかに填めてゆく
すべてに死のみごもる季節
木の根の瘤 石の下 罌粟の花 落日
あまりにも繁殖する世界 別にもう一つの世界が輝くならば
あまりにも暗い きのこの密生する地の屋根
雨また雨のふりそそぐ 河のながれ
猛獣はたちまち交尾し 終る 喝釆のない田舎芝居の舞台の裡で 叫ぶ
午睡の岩は千丈も裂かれる 神の手も血ぬれて
突然の死と空間の恍惚たる交感状態 夜でも昼でもなく
皮といふ皮がむかれて垂れさがる風景
その間からのぞく 青青とした遠方
他になにものも示されない 見えぬ
わづかな極地の薄明に 泛かぶ 結晶する牙 生れながらの未だ浄らかな牙の他は
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)五二〜五五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号11行1段組、35行。
ふりつづく雪に
すつかり匿された
鶏小屋のほのぐらいなかで
いきもののイマージュ
生きつづけるものの差恥
かなしい排泄の臭気がただよふ
内と外のけじめがなくなる時
しじまの裡で
牝鶏は卵をうみはじめる
雪よりも炎えた
白い卵が一層重みを増し
暗い照り合はない辺境から
意志を発して
ずりおちてくる
空間は感じやすい均衡をやぶり
きんいろの藁のうへに
苦痛の生をうけとめる
へこむものが
藁でなければ
この大地であらうか
しづまり輝きだす
一個の異様な物体のまへで
見えないもの 把握できないものに
おびえたりいらだつたり
叫喚するものたちがたしかにゐる
このひどい雪ぶりの向ふで
たじろぎ遠ざかる
それら
麻痺した烏賊のやうなむれ
薄明の金網の外では
次第に
塑像のやうに
下から埋まつてゆく
樹や
不安な社会がある
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)五六〜五九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号25字詰11行1段組、18行。自筆原稿末尾に「一九五五・三・五.」と稿本中唯一、脱稿日らしき記述がある(〈吉岡実とフランシス・ベーコン〉参照)。
肉屋の千匹の蠅 とび終り 包丁刃物の類は 仮設の暗がりから あとずさりして 一段と深い世界へ沈みゆき
慰めのない 真夏の仕事場 凍る肉の重い柱 さかさにつるされる 完全に浄められた空間 すでに人間のはげしい咀嚼の音もとほざかり
今この店先の調理台のうへに 尾もない頭もない 一つの肉の原型 魅せられたやうに よこたはつて
すべてのものの耳がゆれ立ち
すべてのものの舌が巻かれる時
苦痛の鉤からはづれた凝脂の肉の神
虚しい過去 生の真昼の空を夢みようとする
甘い太陽とみどりの草 臓腑の中で輝く 河
と星屑 角の間へぼうぼう風をとばし 疾走
する四肢の下で みだれる夕焼の雲 小鳥の
脱糞 金の藁の中で つねに反芻される 自
我のエクスタシイ
地平の端を 汚れた鼻づらで冒す 兇悪な笑
ひと 混淆の涎 ときに牝の尻の穴 柔媚な
紅の座を嚊ぎつけ 嫣然と眦をほそめてゆく
時――ああ果は 滂沱たる放尿の海
主人の猫ものぞかぬ 化石めいた深夜のホリゾント すなはち店先の部厚い矩形の処刑台をきしませ 裂かれた肉の衣装のかげから 触発されたもの 突然立ち上りよみがへり みるみる形成されだす 裸の牡牛の像
へばりついた梁で 夜あけまでみぶるひする 肉屋の千匹の蠅
初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六〇〜六五ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号11行1段組、7節40行。稿本では最初の題名が〈雨ざらしの犬〉であり、同時に、あるいは後日〈犬の肖像〉と副題が付けられ、最終的に〈犬の肖像〉となった。「雨ざらしの犬」は本文に見える詩句だが、〈犬の肖像〉には遠く及ばない。〈雨ざらしの犬――犬の肖像〉にしたところで同断である。
1
或る時わたしは帰つてくるだらう2
多くのもの3
いまわたしのまなびたいことは4
きはめて自然な路傍の受胎にはじまり5
たとへば結晶する月の全面へ血の爪をかけるほどの6
わたしは犬の鼻をなめねばならぬ7
その犬の舌から全世界の飢ゑが呼ばれる初出は詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)六六〜六九ページ、本文旧字旧仮名(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号25字詰11行1段組、30行。吉岡は随想〈誓子断想〉(初出:《山口誓子全集〔第9巻月報〕》、明治書院、1977年8月25日)に本篇から9行引用(本文新字新かな)したあと、「これは私の〈過去〉という詩の一節であるがこの奇怪な形の魚を過去[、、]の象徴として造型したことに、私は自負をもっていた。」と書いている。
その男はまづほそいくびから料理衣を垂らす
その男には意志がないやうに過去もない
鋭利な刃物を片手にさげて歩き出す
その男のみひらかれた眼の隅へ走りすぎる蟻の一列
刃物の両面で照らされては床の塵の類はざわざわしはじめる
もし料理されるものが
一個の便器であつても恐らく
その物体は絶叫するだらう
ただちに窓から太陽へ血をながすだらう
いまその男をしづかに待受けるもの
その男に欠けた
過去を与へるもの
台のうへにうごかぬ赤えひが置かれて在る
斑のある大きなぬるぬるの背中
尾は深く地階へまで垂れてゐるやうだ
その向ふは冬の雨の屋根ばかり
その男はすばやく料理衣のうでをまくり
赤えひの生身の腹へ刃物を突き入れる
手応へがない
殺戮において
反応のないことは
手がよごれないといふことは恐しいことなのだ
だがその男は少しづつ力を入れて膜のやうな空間をひき裂いてゆく
吐きだされるもののない暗い深度
ときどき現はれてはうすれてゆく星
仕事が終るとその男はかべから帽子をはづし
戸口から出る
今まで帽子でかくされた部分
恐怖からまもられた釘の個所
そこから充分な時の重さと円みをもつた血がおもむろにながれだす
以上の17篇は、書きおろしの詩集《静物》(私家版、1955年8月20日)に掲載。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4月
告白(④・2、18行分)
5月
喜劇(④・1、25行分)
7月
陰謀(未刊詩篇・6、19行分)
11月
島(④・3、14行分)
12月
仕事(④・4、20行)
初出は《新詩集》(蜂の会)1956年4月〔3号〕三一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は並字)使用、8ポ24字詰16行2段組、18行分。
わたしは知らないことは 他の人に告げぬ また他の人の声が造る石膏のまわりを歩かぬ わたしはただ全体の力のあつまる 短い斧でふれようとあせる 立つている物なら たおれるまで石の上で押す 横たわる物ならとびのる 回転する物なら手で捲く わたしの黒い肉に喰い込んでくるまで そして淋しく出てゆく蛾や血管の列に通路を譲る それが女なら眼のなかに突き戻す 十全なしなやかさと冷たい湖を湛えるまでわたしはしんぼうづよく待つのだ 食べ物なら吐く 壜や容器の沈んでいつたデーブルの下の暗のうちに 次々と魚と鳥の首を切りおとしながら 役立つ物と不要の物を分類する だが間違いはあり得るのだ その時は羽毛とうろこの泡を拭き 窓のガラスの外の出来事を見ようとする 子供の縄とびを ひとつの夜を生む煙突のマツスを 果ては木理の層にねむる樹の叫びで わたしは走り出す 一人の裸の形をして 習練と忍耐を具現した黒い像として 雨にぬれてゆく ここでのこの事実は他の人に告げられる
喜劇(④・1)初出は《詩学》(詩学社)1956年5月号〔11巻6号〕五三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ23字詰15行2段組、25行分、目次での作者名は「吉岡實」。
台所の隅で 背中を裂かれた卵が泛び上る 長い夜の岸に近く 眠つていた一人の男が立ちあがつた 肩に一匹の帽子をかぶつた猫をのせて 男は死んでゆく妻のために穴をほる 食物と金をつんだ手押車が反対に出てゆく その道筋をふさぐ寝台の脚と什器類 男が哭きながらなぜるため 猫の咽喉から葡萄状にねずみの姿は溶け 正面の月を消す 遠くから向きをかえる森の樹 やがて雪をかぶり 小さな部屋へ男と斜視の眼の猫を呼び戻す だが歩くことはない 元から煖炉の前で男はグラスに酒を注ぎ 猫は屋根裏を走つていたのだから 寒がりの男は脱毛する猫をねらう 完全な裸の猫のまぶしさに男は眼をふせる その夜の窓をのぞく鳥はどれも 死んだ妻の髪のかたちをするので射ち落す 男はおもむろに猫の四肢を解く その波の手の没するのは黄色を増したバターの壺 危険な培養に魅了される医者の髯をつけ男は汗をながす 思わず猫はグラスを砕く その時たしかに男は救われたのだろう 噴霧器のなかの指はアミーバの昂進を止め 人間の手に退化したのだから そのうえ破片の間から輝く血をながした 重い物を支えたくなつたのだろう 男はあたりを見まわし 鋏や固い家具にとりまかれていたのに驚く それからは傷つかぬ部分 足や顔や性器を急に大切に取扱う 丈夫な皮の袋から 男は二度と現われぬ
陰謀(未刊詩篇・6)初出は《現代詩》(緑書房)1956年7月号〔3巻6号〕四八〜四九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ26字詰19行1段組〔コラム〕、19行分。
百匹の猫には百匹の敵がいる ある一匹の心やさしい猫がベンチの片隅で新聞をよんでいると見なれぬ手の折れた猫が並んで新聞をよみはじめる 帽子をかぶった心やさしい猫はスポーツの記事がよみたいと思っているのだが 隣の猫が戦争の悲惨なニュースをよむように指図する 心やさしい猫は美しい妻に贈物がしたいのだ 化粧品の広告がみたいと思う 折れた手で隣の猫がにやにや笑いながら 軍艦の沈没してゆく場面の写真を示すので 香水罎の類を彼方に眺め 自分も溺死する水兵の服をきて海中に沈んでしまう もちろん隣の猫は別の軍艦の甲板で折れた手を振っている 心やさしい猫は公園を出てレストランに向う 手の折れた猫がおくれたわびをいいながら 同じ食卓の前に腰かける 心やさしい猫は明日の仕事のため栄養分のあるものを注文する 手の折れた猫はもう自分が注文しといたからだいじょうぶだという 陰謀は食事に関係が多い 湯気の立つスープのかわりに 落下傘の包が食卓の上に置かれる 心やさしい猫は空腹のままそれを身につけてとびおりる たちまち十字砲火を浴び戦死する 折れた手で猫は雨でぬれた半旗を垂らし戸口から入ってしまう
一九五六・五・二十一
島(④・3)初出は《新詩集》(蜂の会)1956年11月〔4号〕四九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、8ポ24字詰16行2段組、14行分。
島へ上り 男は岩角でみつける 獣や魚の大きな弓なりの骨片の類 自転しながら太陽が晒した くろい蛸のあたまの収縮図 徐々に水平になつてゆく男の眼の岸は 鋭角的な月の出だ 忘れよう 今ひじような鮮明度で 海鳥の卵が迫る こんな時どうして音楽が聴かれないのだろう それが不眠性の弧を形づくるとき 男のなげだした遠い手足がわずかにうごく そのたび下の端から 島の面積が狭ばまりだす ここはたしかに明日の落日の巣だ 飛び立たぬ幻の鳥たちのために 男のかたわらに拡大される はげしく光に曝された卵の全面 どこを探しても冒険ずきの人間の爪の痕ひとつ見あたらぬ 選びはしない このアトラス 男はやせた胎内から 少しの声と血をしぼりだす 絶縁体に沿うて向う側を冬の波がすべり続ける
仕事(④・4)初出は《今日》(書肆ユリイカ)1956年12月〔6号〕八ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ13行2段組、20行。
荷揚地は雨だ
玉葱と真昼のなかで
その男はいつも重い袋の下にいた
仲間は盲目の者ばかり
船からおろす荷の類
すべて形が女にちかいので
愉快にかついでゆく
ありあまる植物の力
はげしい空腹と渇き
やみから抽き出された
一つの長い管を通りぬけ
坐りこんだ臓物
その男は完全に馴致された
だが習性の眼は観察をあやまたぬ
見えていた百本の煙突が陸地から姿を消す
その男はいそぎ足で家路へ向う
独りの食事を摂り
卑猥な天体を寝床に持ちこむため
臭いシャツの背中を星が裂く
その男は川に平行された
一九五六・九・一五
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
牧歌(④・7、27行)
4月
僧侶(④・8、9節84行)
5月
ポール・クレーの食卓(⑩・1、37行)
6月
単純(④・9、24行分)
10月
固形(④・11、26行分)
夏(④・10、32行)
初出は《今日》(書肆ユリイカ)1957年3月〔7号〕九ページ、本文新字新かな使用、9ポ15行2段組、27行。
村にきて
わたしたち恋をするため裸になる
停る川のとなりで
眠らぬ馬をつれだす
飼槽の水と凍る星の角に
かさばる女の胴体と同じ重さの
こわれる物を搬ぶ
桶の底をはいつくす
なめくじやむかでの踊り
わたしたちすばやく狩りたてる
羽毛のない鳥やゴムの魚
朝啼いて夜だまる可憐な獲物を
枯れた藁と茜いろの雲のあいだで
しきりに移動したえず噛むもの
小屋にとじこめ
窓から月を押しだし
火をおこす
食物にならぬ四つの腿の肉をやき
飲料にならぬレモンをしぼる
小屋の主人は行方不明
マダムは心中未遂
子供は街の学校の便所のなか
にぎやかな運命
わたしたちここに停るもの
わたしたち裸のまま
火事と同時に消えるもの
多勢の街の人々が煙を見にくる
初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1957年4月号〔2巻4号〕三七〜四一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、9節84行。標題は二号活字で「僧侶」と印刷されたが(目次は9ポで「僧侶」)、本則は新字のため「僧侶」を採った(印刷所の二号活字に新字の「僧」がなかったと見るのである)。カット:浜田伊都子。(本稿冒頭の〈④の吉岡実詩集《僧侶》〔初出形〕ファイルの詩篇〈僧侶〉〉参照)
1
四人の僧侶
庭園をそぞろ歩き
ときに黒い布を巻きあげる
棒の形
憎しみもなしに
若い女を叩く
かうもりが叫けぶまで
一人は食事をつくる
一人は罪人を探しにゆく
一人は自涜
一人は女に殺される
2
四人の僧侶
めいめいの務めにはげむ
聖人形をおろし
磔に牝牛を掲げ
一人が一人の頭髪を剃り
死んだ一人が祈祷し
他の一人が棺をつくるとき
深夜の人里から押よせる分娩の洪水
四人がいつせいに立ちあがる
不具の四つのアンブレラ
美しい壁と天井張り
そこに穴があらわれ
雨がふりだす
3
四人の僧侶
夕べの食卓につく
手のながい一人がフォークを配る
いぼのある一人の手が酒を注ぐ
他の二人は手を見せず
今日の猫と
未来の女にさわりながら
同時に両方のボデーを具えた
深毛い像を二人の手が造り上げる
肉は骨を緊めるもの
肉は血に晒されるもの
二人は飽食のため肥り
二人は創造のためやせほそり
4
四人の僧侶
朝の苦行に出かける
一人は森へ鳥の姿でかりうどを迎えにゆく
一人は川へ魚の姿で女中の股をのぞきにゆく
一人は街から馬の姿で殺りくの器具を積んでくる
一人は死んでいるので鐘をうつ
四人一緒にかつて哄笑しない
5
四人の僧侶
畑で種子を播く
中の一人が誤つて
子供の臀に蕪を供える
驚愕した陶器の顔の母親の口が
赭い泥の太陽を沈めた
非常に高いブランコに乗り
三人が合唱している
死んだ一人は
巣のからすの深い咽喉の中で声を出す
6
四人の僧侶
井戸のまわりにかがむ
洗濯物は山羊の陰のう
洗いきれぬ月経帯
三人がかりでしぼりだす
気球の大きさのシーツ
死んだ一人がかついで干しにゆく
雨のなかの塔の上に
7
四人の僧侶
一人は寺院の由来と四人の来歴を書く
一人は世界の花の女王達の生活を書く
一人は猿と斧と戦車の歴史を書く
一人は死んでいるので
他の者にかくれて
三人の記録をつぎつぎに焚く
8
四人の僧侶9
四人の僧侶
固い胸当のとりでを出る
生涯収穫がないので
世界より一段高い所で
首をつり共に嗤う
されば
四人の骨は冬の木の太さのまま
縄のきれる時代まで死んでいる
初出は《現代詩》(緑書房)1957年5月号〔4巻4号〕二一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行2段組、37行。
孤独な心になじみの物は
一度はすべて固い光の形を解いて
人の住まぬ暗い家にはいり
尊大な金属のかげに
いきいきとした像をむすび
ささやかに屯する
このせまい室内のおくでは
フォークはなえた草のように生え
唇をうしなったグラスは宙にかたむき
にがい酒はながれる
腸詰の皮と骨ばかりの魚は沈む
俯瞰することのできない水の市に
とりのこされた布の断崖
猫がちらりと見上げる
暗い光線をだいているおもみで
からの罎は立っている
卓の上に棲みついて独り
だれだって立っているということがさびしくなる
しぜんにほそいくびになる
招かれないので
朝から晩まで戸口の隅に
つぼまったまま滴をたらしている雨傘
卓のまわりは椅子が寄り
皿や器が集ってくる
そのなかには無益にも食いあらされた皿もある
そにもまして哀しいのは汚れない皿
棚のうえに重り重り
そのまま夜はバターの下でひびかない
こころなごむ宴も終りちかく
母のふくらむ腹をした
塩の壺のなかから
声がでてくる
応えがないのでまたもとのところへ戻る
永遠に拭く人の現われぬ食卓
四方から囲こむ
白いかべはたった今
海をのんだのかひっそりとして
初出は《今日》(書肆ユリイカ)1957年6月〔8号〕三〇ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ25字詰15行2段組、24行分。
警戒もされずにその男は死んだ 尾底骨のいちじるしく突起した男に 妻は憎しみしかもたず 眼のわりに舌がつめたくかがやくので 乳房のゆたかな女である妻にはたえられぬ 食事するとき以外は うごきが非常にかんまんだ むしろないといえる ことに就寝するとき 植物の花をつけぬ部分を感じさせ その男はくもの巣のいとにひつぱられて 地に伏してゆく陰惨な形態をとる しかし死んだ妻にはそれはどうでもよい ただ毎日たえず波うつ手で 壁の向うに飼つている犬に餌を与える その偽証が心から妻を死なせないのだ じぶんの美質をうけつぐ猫が屋根で雪をかぶり 生きていることがはがゆい もしじぶんの蛇腹が暗の裡から充分のび 男の歩きまわる部屋へ突き戻せたら 勝目はある 石膏の胎児を孕めるから 犬は男の身のまわりのせわをやき 困らせたり笑わせる それからさきの甘美な操作はできぬ 男は生きるためには 死んだ妻の猫を塵ばかりふる屋根から呼び戻して 芸を仕込まねばならぬと考える 世俗的な事柄でなく 美しい女に仕立てあげ 最初の夜は寝台であたためて 溺死者の好む月をのぼらす 裸の女の姿勢と葉の下に息づく桃の半熟の羞恥を えとくさせるべく大声をだした 夏がきた稲妻の紐をたらして 男は人間である証拠のゆえに死ぬのか 頭は犬の血をさわがせ 下半身は猫の毛に蔽われたまま 汗の強国から 肌寒い一寒村へと葬られた
初出は《現代詩》(書肆パトリア)1957年10月号〔4巻10号〕三四〜三五ページ、本文新字新かな使用、9ポ25字詰18行1段組、26行分。
ぼくの偏見は多くの人をこまらす ときに植物の茎という茎へ剃刀を当てる 切口から展開される 悲劇的なばら色の育たぬ家族を見つける 水ものまず 光も咥えることのできぬ 薄い膜の男女 かすかな交接のひびき 花粉は壁や寝具を汚す さわると固いざらざらの粒に近い それゆえ子供は玩具の車の世界を走らぬ 遊び場は母の子宮 日蔭のへちまの棚の下 そこで滑る ぼくはすたすた田園を出る ぼくの信条は 物は固形ですわりよくあらねばならぬと考える 立てかけられた斧へ同時に迫るぼくと一匹のとんぼの複眼 ぼくは余す所なく ランニング姿の全身を写し 段違いの虹や山嶽の氷の錐を背負う あらゆるやわらかい蛙がきらいだ 固い羽 固い雨なら両手で愛撫する 試みに一つの罎を蹴る 人が信ぜられぬほど ぼくは恍惚として街に入る 攻撃された寺院の外側の石塀を叩く これこそ上等の遊戯だ 病院へゆく若い姙婦のあとをつける だんだん坂をのぼり石の縞目が中心へ向き 細い線を描いてゆき がまんできないすべすべの頂点で 白い腹を見せる 医者の笑う時だ 鐘が乱打される火事の夕刻 鉗子やうごく鋏が皮膚をのばし 袋の中身の頭をむかいにゆく ぬるい種子のたんぽぽの周囲は 痛みをつけてむしられる 脂肪が清潔なランニングをふきつける ぼくは真の固形をみてあせる もろい下の躰の管をすすむ血の粗い無責任な軍隊を見すごす そこでぼくは街を出る 風がぼくを氷る人・滑る物に替える だからぼくはつねに笑わず さようならもしない
初出は《季節》(二元社)1957年10月〔11月号・7号〕六二〜六三ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は並字)使用、9ポ19行1段組、32行。吉岡の随想〈女へ捧げた三つの詩〉(初出:《現代の眼》1961年11月号)に依れば、Y・Wはのちの妻、和田陽子である。
(Y・W に)
蝋びきの食物の類をみて歩く
女たちの腋毛は甘い先験の夏を輝かせ
肥満家族は跳ねまわる
ぼくは恥ずべき小さな西瓜をもつ男
タイヤ型の夕方の海岸にきて
赤と灰色の縞をつけたテントの入口を探す
ぼくと同じ不具性の女を求め
一廻り二廻り
紡錘形の骨格のうえにタオルを巻き
みじめなシステムの砂に穴をあける
ぼくは吃るばかりだ
次の水死者を慰める不揃いの藻の毛を撫ぜ
ぼくの精神の塩を波が引いてゆく
毎年ぼくを冒涜する夏
夜の砂の情事
間近かにみる果実のフオルム
夥しい未成年の魚の裸体
そのうえ外観から収縮してゆく氷
ぼくの凌辱本能がぼくの眼から
全ての生物へ伝染し
実用の陸地を見失わせる
ぼくは女を触覚し
子供用の浮袋を首へ徐々にはめこむ
いまこそぼくは笑う
心の帆の傾むく支柱へ向き
ぼくのプライドを砕き
ぼくの肉声と大脳を晒しつづける
内省の夏の海
暁の板の海
違い段の沖へ
ぼくは生臭い風を受け
自己の血を狩りに出る
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5月
回復(④・12、26行分)
6月
苦力(④・13、39行)
7月
死児(④・19、Ⅷ節189行)
喪服(④・15、29行)
聖家族(④・14、21行)
9月
サーカス(⑩・2、45行)
11月20日
伝説(④・5、11行分)
冬の絵(④・6、21行分)
美しい旅(④・16、19行分)
人質(④・17、28行)
感傷(④・18、6節99行)
12月
ライラック・ガーデン(⑩・3、40行)
初出は《詩学》(詩学社)1958年5月号〔13巻6号〕五三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ20字詰16行2段組、26行分。
らつきようを噛る それがぼくの好みの時だ 病棟の毛布の深いひだに挟まれ ぼくは忍耐づよく待つ 治癒でなく死でなく 物の消耗の輝きを いまは四月 蜂の腰がうごく うず高く花粉の積まれてゆく皮膚や野に 色情の末路の月が近づく ぼくの砕けた大腿骨は永い閑暇のゆえに 血の音楽を聴き 燐質化或は精分を放電しては 黒い杖として さびれた田園風景の一齣を見せる 一つの藁の山へ挿し込まれたまま 交媾のさけびもあげず 二羽のからすを飛び立たせる たびたび姉は見舞いにきて 隣の患者の悪性の患部を讃美し ぼくの下向きの頭を叩いては 一時的にもざくろの実の爆発を誘致するのだ つねに凍る庭園を歩む 多くの鶴や看護婦のむれより ぼくは醜い女を接近させ 不粋な辞書と肉感の夢を持つ母胎を攪拌し 次にはげしい薬品の臭いを嗅ぐ たちまち再生の香油をぬられ 慚次の死がぼくを襲う 既製の衣服の観念はうばわれて 不快な動物だと 女が幼時から信じてきたらくだの形で ぼくは膝をつく 面倒はどの世界でも起る 搬び出される担架の上で 糊づけの肉と骨の摩擦がはじまる払暁だ 渇きは眼を媒介して 解けだす氷の沼から漲つて来る 胎生の魚なみに尾までぬらし ぼくは水を一気に飲み干す
初出は《現代詩》(書肆パトリア)1958年6月号〔5巻6号〕九二〜九三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ20行1段組、39行。本篇執筆の状況は、吉岡の詩論〈わたしの作詩法?〉(初出:《詩の本〔Ⅱ 詩の技法〕》、筑摩書房、1967年11月20日)に詳しい。同文での詩句の本文は、新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用。
支那の男は走る馬の腹の下で眠る
瓜のかたちの小さな頭を
馬の陰茎にぴつたり沿わせて
ときにはそれに吊りさがり
冬の刈られた槍ぶすまの高梁の地形を
排泄しながらのり越える
支那の男は毒の輝く涎をたらし
縄の手足で肥えた馬の胴体を結び上げ
満月にねじあやめの咲きみだれた
丘陵を去つてゆく
より大きな命運を求めて
朝がくれば川をとび越える
馬の耳の間で
支那の男は巧みに餌食する
粟の熱い粥をゆつくり匙で口へはこびこむ
世人には信じられぬ芸当だ
利害や見世物の営みでなく
それは天性の魂がもつぱら行う密儀といえる
走る馬の後肢の檻から
たえず吹きだされる尾の束で
支那の男は人馬一体の汗をふく
はげしく見開かれた馬の眼の膜を通じ
赤目の小児・崩れた土の家・楊柳の緑で包まれた柩
黄色い砂の竜巻を一瞥し
支那の男は病患の歴史を憎む
馬は住みついて離れぬ主人のため走りつづけ
死にかかつて跳躍を試みる
まさに飛翔する時
最後の放屁のこだま
浮ぶ馬の臀を裂く
支那の男は間髪を入れず
徒労と肉慾の衝動をまつちさせ
背の方から妻をめとり
種族の繁栄を成就した
零細な事物と偉大な予感を
万朶の雲が産む暁
支那の男はおのれを侮蔑しつづける
禁制の首都・敵へ
陰惨な刑罰を加えに向う
初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1958年7月号〔3巻7号(22号)〕二八〜三八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、Ⅷ節189行。なお、本篇執筆の状況に関しては〈詩篇〈死児〉の制作日〉を参照されたい。
Ⅰ
大きなよだれかけの上に死児はいる
だれの敵でもなく
味方でもなく
死児は不老の家系をうけつぐ幽霊
もし人類が在ったとしたら人類ののろわれた記憶の荆冠
永遠の心と肉の悪臭
一度は母親の鏡と子宮に印された
美しい魂の汗の果物
だれにも奪われずに
父親と共に働き藁でつつまれる
地球の円の中の新しい歯
誠実な重みのなかの堅固な臀
しかし今日から
死児は父親の義眼のものでなく
母親の愛撫の虎でなく
死児は幼児の兄弟でなく
ぶどう菌の寺院に
この凍る世紀が鐘で召集した
新しい人格
純粋な恐怖の貢物
裁く者・裁かれる者・見る者
みごとな同一性のフィルムが回転する
死児は棺の炎の中でなく
埋葬の泥の星の下でなく
生けるわれわれを見る側にいる
Ⅱ
枯木ばかりの異国で
母親は死児のからだを洗う
中世の残忍な王の命令だ
全部の骨で王宮を組上げる
ほのおの使役の終り
母親の涙の育てた土地を
馬のひずめにとじこめられて
死児のむれは去る
真昼は家来の悦ぶごうもんの時
一つの枯木に一人の母親を与える
枯木が殖えればその分だけ母親が木に吊られる
百万の枯木はよろめき百万の母を裂く
八月の空に子宮の懸崖
世界の母親のはげしい眼は見る
山火事を
同時に聞く
それを消しに来る大洪水を
Ⅲ
死児は偶然見つける
世界中の寝台が
行儀よく老人を一人ずつ乗せて軋むのを
ゆるんだ数々の蛇口から
回虫が老人と死にみきりをつけ
はいだしてゆく方向に
野菜と肉の積まれた
働く胃袋が透視される
ときどき鉄砲の筒先が向けられて
悲鳴も聞えた
老人の浄福を祈り
ゆっくりと山へ血を持ちはこび
頂から浴せる
因襲の恋人・夫婦たちの寝台に
ただ一つの理由で死児は哭く
セックスを所有しないので
回虫のごとく恥じる
いうなれば交情の暁
やわらかな絹の寝台
麦の畑の涼しい蔭の場所に住めぬ
死児は老いた母親の喪服のやみで
くりかえすひとりの乱行を
あらあらしい石の発芽を
禁制の増殖 断種の光栄
できれば消滅の知識をまなぶ
いま緑の繻子の靴に踏まれる森の季候
去勢の噴水はきらめく
かぼちゃの花ざかり
死児は世界中の死せる老人と同衾する
Ⅳ
死児の発育と病気について
すべての医者は沈黙した
蜜と海綿のみなもとを凅らす獣の跳梁
母親の乳房はどこの地平にも見あたらぬ
不順な風土と暴力の下着にかくされて
無理にのぞけば
硫黄の苦い結晶体
それ故この時世は呪術の岩の下をさまよう
秋の果物を山へ搬びすぎた
商人の老獪な算術が病気をつくる
死児の爪は外部へのびず
夢を孕む内部へうずまく
死児の病気の経過は
食物と父の怯懦の関係で
悪化の一途をたどり
最後は霧の硝煙で消える
死児は医者の記録にのこるのでなく
歴史家の墓地の菫で物語られる
Ⅴ
蝋びきの世界の首府を
母親は死児を背負って巡礼する
砕かれたもぐらの将軍
首のない馬の腸のとぐろまく夜の陣地
姦淫された少女のほそい股が見せる焼かれた屋根
朝の沼での兵士と死んだ魚の婚礼
軍艦は砲塔からくもの巣をかぶり
火夫の歯や爪が刻む海へ傾く
死児の悦ぶ風景だ
しかし母親の愛はすばやい
死児の手にする惨劇の玩具をとりあげる
死児には正しきしつけを
もしいやがるものは罰せよ
白昼の紳士淑女の食卓へ恥部を曝せ
夜戦のすきなあらゆる国の紋章を引裂いた高みから
死児の髪を垂らし
或はつるつるの頭を露出する
辱しめよ
死んだ父・殺された同胞の肉体の辱しめと
魂の憂欝なばらを照らしめよ
死児が苦痛のあまり汚物をながすまで
箒の黄いろい死児
大理石の死児
鉄線の黒い死児
金髪の森の死児あまたの砂の死児
そのとき
賢い母親は夏の蝉の樹木の地に
異なるエネルギーで
異なる泣き声で
同一の怒りの歴史をつくる
Ⅵ
死児の好きな遊び
むらがって
瑚珊の海へ網を入れる
大砲と共に沈んで行った男達の重いこうがんをひびかせる
女たちの砂と闇を吸ってる肛門も色彩でかざる
死んだ者のためなら安心して仕事ができる
塩と金具の類の枷をはずし
丈夫な膠でボデーをくるみあげ
枯木の陸地で二度目の奉公をかなえさせてやるんだ
ざくざく採れる金銀の鱗
さめの歯のかみあう恍惚の日々
水の夜伽は退屈だと静かな骨はつぶやく
死児にはそれが聴える
もう一度月から網を可能なかぎり拡げよう
死んだものならなんでも収穫
母親はいやな顔を見せて手伝わず
死んだものは交換できないと
破船の家でどなりだす
死児は声が小さく主張できない
母親の目の届かぬ所に来て
凍ったまま横臥する
かたわらに
伝説の軌跡の海
Ⅶ
母親のねむった後
死児が床を這い廻る
果ては
嵐の海を埋めつくす
死者のうわむきの顔の上で立ち上り
次から次へと
跳ね歩く死児
凌辱された姉を求めて
ただ一人の姉でなく多くの姉の
波の魂に呼ばれて
陰気な蓮華をかざして行く
腿の柱をきよめに
混血の海へ
姉が孕み
姉が産む夥しい死児の夜の祝祭
輝く王道をきりひらき
古代の未開地で
死児は見るだろう
未来の分娩図を
引き裂かれた母の稲妻
その夥しい血の闇から
次々に白髪の死児が生まれ出る
Ⅷ
死児をだいて集る母親たち
或る廃都・或る半球から
おしきせの喪服のすそをひきずって
まれには償いの犬までつれ
定員になるまで沙漠へ入ってゆく
他のおしゃべりの母親たちは
沈黙を求められて村落から海面へ移動する
次から次へ黒い帯の宗教的なながれ
隈なくこの現世を司どるために
死児が生きかえらぬようにあやす
子守唄と悪夢のくりかえしで
骨肉でどうしてこの文明の腐敗の歌を合唱できよう
とどろく雷のように
豊かな腰をよじり
最後に半数のやもめの母親たちが氷河に並ぶ
必ず一人の死児をだいてる証拠に
めいめい死児の裸の臀を叩く
そのはげしさで哭いた時
この永い報復の難儀な旅の夜も明けよう
しきつめられた喪服の世界に
ピラミッドの頂点がわずかに見える
これほど集ってはじめて
全部の母親のさかまく髪のなかに
あたらしい空が起り
実数の星座が染められる
初出は《今日》(書肆ユリイカ)1958年7月〔9号〕八〜九ページ、本文新字新かな使用、9ポ17行1段組、29行。
ぼくが今つくりたいのは矩形の家
そこで育てあげねばならぬ円筒の死児
勝算なき戦いに遭遇すべく
仮眠の妻を起してはさいなむ
粘土の肉体を間断なく変化させるために
勃起とエーテルの退潮
湿性の粗い布の下で夜昼の別なくこねる
ぼくは石炭の凍る床にはいつくばい
死児の哺乳をつづける
浪費と愛をうけつけず発育しないもの
ぼくの腕力の埓外に在り
正体も見せず固くかさばる死児
それは光栄に匹敵する悲劇
ぼくの魂の沈む城の全景を占め
美しいメモリアルとして立ちつくす
他人の経営する空間を徐々に埋め
せり上る死児の円筒
そのすべすべのまわりを歩く
ぼくは父親の声も出さず
母親は食事ものぞまず横臥する
やがて円筒の死児は哭く
一家の族長として
塵とくもの巣を頭から傘のごとくかぶる時
ぼくの家系は秩序をうしなうだろうか
老いたねずみの形骸を発光させ
ぼくら両親はストーブのなかの闇に
住みつくかも知れぬ
或は
円筒の死児が喪服に覆われる時まで
初出は《季節》(二元社)1958年7月号〔11号〕二二〜二三ページ、本文新字新かな使用、9ポ16行1段組、21行。
美しい氷を刻み
八月のある夕べがえらばれる
由緒ある樅の木と蛇の家系を断つべく
微笑する母娘
母親の典雅な肌と寝間着の幕間で
一人の老いた男を絞めころす
かみ合う黄色い歯の馬の放尿の終り
母娘の心をひき裂く稲妻の下で
むらがるぼうふらの水府より
よみがえる老いた男
うしろむきの夫
大食の父親
初潮の娘はすさまじい狼の足を見せ
庭のくろいひまわりの実の粒のなかに
肉体の処女の痛みを注ぐ
すべての家財と太陽が一つの夜をうらぎる日
母親は海のそこで姦通し
若い男のたこの頭を挟みにゆく
しきりと股間に汗をながし
父親は聖なる金冠歯の口をあけ
砕けた氷山の突端をかじる
小さな街には小さな火事があり初出は《實存主義》(理想社)1958年9月〔15号〕三〇〜三三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号12行1段組、45行。執筆者名の後に「一九一九年東京に生る。筑摩書房勤務。詩集『静物』。」とある。
初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)一六〜一七ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号27字詰13行1段組、11行分。執筆は1956年。
椅子の上から 跳びおりてゆく 猫の毛のなかの跣足 刹那のことだが 大写しになり 花の深いひだに 吸いこまれた 誰でもが初めてのことだと驚く 木製の四つの脚 床をしばらく跛行し 部屋の隅で急に停止し 椅子は伝説化された 事件を知らぬ男 かぶつた毛布から現われ 椅子にこしかける 流通する熱と臭気をぬきながら 肛門につながる管をけんめいにたぐり出す 抑えきれぬゴムの状態で かさばりはじめ 部屋中を占めてのたうちまわる ものの鼓動 快楽の伸縮 夜のため その男は久しい前から 猫と顔をならべ 管にかこまれたまま 暗くなつてゆき 息をころしてゆき 消える間際で 火事だと叫んだ
初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)一八〜一九ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号27字詰13行1段組、21行分。執筆は1956年。
他人には見えないものが いくつかぼくの部屋にある たとえばベッドの脚と壁との間に 一週間前からぼくがぬいだ長靴が置かれている ひとつはたおれて折れ 片方は立つているにすぎない ぼくの記憶のあいびきの雨のなかでのみ濡れ ぼくの悪癖のベッドの下でのみ乾き ひびわれる 下宿の女主人はただ一つの理由でしか ぼくの部屋をおとずれぬ 猫が子を産みにくる時だ 毛の太い束の尾が床をこする 夜から朝へ女主人は黒い箒をうごかす ぼくは病気になりきり 毛布の下でえびの真似をしている 女主人は陸に棲む人 スリッパをはき 藻のゆらめき 岩かげの海の湿つたひとでの開閉の兆しもさとらず ボール函に六匹の生れた猫をつめて出てゆく ぼくは夜へ向く出窓を少しあける それが一番大事な日課だ 女主人は脱衣し 川へ沈んだ六匹の猫の子の体温と弾力をよみがえらせ 浴槽から湯水を溢れ出す ぼくには危険だ 上も下もある階段の途中は ぼくは見つける 壁に立てかけた 自殺した画家のカンバスを ぼくの持物のうちで それだけが光に耐えよう 女主人の臀部のばら色の地震から その絵がぼくをまもつてくれる唯一のものかもしれぬ 貧しい画家であつた男が存分に描いた 怒りの構図 とおくに或はちかくに 落ちこんだ深みから やたらにのりだそうとする 困憊した石のトルソたち
初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)五八〜五九ページ、本文旧字新かな使用、五号27字詰13行1段組、19行分。執筆は1958年。
老給仕は食器をかたづけて去る ドアの外に出たというよりむしろ夕映えの球体へ吸いとられる おしきせのズボンの青い染色をのこす 船室のぴかぴかした床の隅に 寝台の男女はさなだむしのようだ おびただしいナプキンの波 動揺のはげしさで老給仕は死ぬだろう 美しい鉱物の異邦へ旅立つべく 鍍金のはげたスプーンにまたがる 腐りだす肉や野菜の類 経木のしなやかな動作で 老給仕はぎざぎざ刻まれた空へとび移る さようなら 棍棒の群衆 袋の日常 函の海 上から見るとよく理解できる 火事のメロドラマ 雷雨の孤独な儀式の終り 老給仕は錬達した手つきで温い食事を摂る その後の昼寝が長すぎると誰がなじれよう 死んだ者たちの習慣を誰が熟知するか 老給仕が起きるはずみで金釦がちぎれ 転がる面積を探す 心ならずも復讐したのだ 海のなかで大きな音をたてる 老給仕は生涯はじめての粗相をした 藻のかげの死んだ大勢の客たちにむき うやうやしく陳謝する これからの長い夢を見るためには 違和も羞恥も忍ぶんだ 成功者として老給仕は肥え太り密石亭に入る しばらく金毛の美女をまぶしく感じる 酒樽の下に廻り込む月 ここは行儀の悪い墓場かも知れぬ
初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)六〇〜六二ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号27字詰13行1段組、28行。執筆は1958年。
建物は人の半身と共に沙の首府へ沈み
次々におどり上つて斃れる
黄色い馬のたてがみの奥でだき合う半分ずつの月と太陽
それをかいま見る
世界の陸地の人の半分の怒りの眼と
余儀なく眠るあと半分の人の心
すべての女性の子宮を叩く
兵士の半分はやわらかく半分は病気で固まる
反応も示さず
耳鼻もない鳩は死ぬ
燃える秣の山と伽藍の頂で
海へとじこめられた女子供は泣きながら仰ぐ
同時に棘とばらのつるで縛られた
軍艦の下腹を見る
遂に増殖する牡蠣の重みでかたむく
波の底を這い廻る
一個の牡蠣の浮力しか持たぬ
骨の人質たち
長い年月を毎日かかさず
死者の生きのこりの兵士をはげまし大砲を打つ
氷山に少しずつひびを入れながら
夕映えのプランクトンのむれに染められた歴史と
肉体を記憶するため
世界の残りの半分の人の骨が島へ上り
焚火で暖をとる
今日それをかいま見る
世界の陸地の人の半分の怒りの眼と
余儀なく眠るあと半分の人の心
初出は詩集《僧侶》(書肆ユリイカ、1958年11月20日)六四〜七三ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号27字詰13行1段組、6節99行。吉岡は1958(昭和33)年8月8日の日記に「〈感傷〉出来。これで詩集《僧侶》の十九篇完成。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一一九ページ)と書いている。
1
鎧戸をおろす
ぼくには常人の習慣がない
精神まで鉄の板が囲いにくる
街を通るガス管工夫が偶然みて記憶する
箱のなかに匿れた一人の男
便器にまたがるぼくをあざわらう
桃をたべる少女はうしろむき
帽子をまぶかくかぶるガス管工夫の槌の一撃を憎む
少女の桃を水道で洗わせず
狭い蜜のみなもとを涸していつたから
幼い袋の時代
大人の女の汗の夏を知らぬ
少女もいつかは駈けこむだろう
ぼくの箱の家
正面の法律事務所の畸型の入口の柱を抱くだろう
それまで休業だ
屋根から寝台まで縞馬を走らせ
ペンキを塗り廻る
すでに伽藍の暗さ
2
金魚鉢の水の上で睡蓮が咲く
悪い季候のはじまり
薄い皮の下で少女は変化している
花の植物の冠から
えびの姿態の不透明な袋に黒い汁を移しはじめる
ぼくの鼻毛の茂みを雨でぬれた鳥がとおりぬけるのはそんなとき
棚のあらゆる口の細い罎
液体を溜める闇のなかで
痒走感におののきだす
ぼくはいかなる変化
いかなる交換を待つているのか
3
ぼくの眠りの截面がめのうのように滑らかになる
そこに居合せたただ一人の女
喪服にいつわられた美しい肢体の女が昨日からいる
今は組みあげられた脚線として
ぼくの寛容な肉情の下に在る
朝から使役された上半身
殊に肩の裏の可憐なそばかすの星雲
恐しくぼくの頭を捉える
或る瞬間は照らす
察するところ女は人を殺してきたらしい
もし病弱な夫でなければ
じやがいもの麻袋をかるがる担ぐ情夫
人でなければ別のもの
頭の大きなさんしよううおを刺してきたのだ
4
永年の経験からぼくは被告を裏切る
被告はつねに救えぬ性格をもつから
彼らはすべて罰せられるにふさわしい陳述をする
例えばぼくが家具化した法廷につれこまれ
被告として黒服の者たちにとりまかれる
〈わたしの妻は蟻の世界へ売渡される
溶けるもの かがやく裸形の砂糖の袋〉と口走る
人々の心証を害し
それでぼくも犯罪人の両肩を見せ下獄する
ぼくの弁護人は妻子と両親のため家へ急ぐ
尻の袋にぎつしり殻粒をつめ脂がのつた鶏の首をさげて雨の中へ入る
不運な者は針金で養われ暗い所にいる
5
女の夫は老練な海港技師
熔接工を連れて毎日海へ行く
長い年月を海の下ではたらくので
真昼の光線に当るとき
熔接工はたちまちかにの形に歩き
総身の毛を輝かせ
充分な粘力と苦味のある泡を吹きこぼす
ところきらわずに
夫は岸べで焚火をたくばかり
破船と網の破れ目から
女が現われる
すなわち技師の妻が食物をはこんできて泳ぐ
熱い砂の床は人の心を複雑な巻貝に変化させ
同時に冷えた魚を跳ねまわす
その後での三人の食事は危険だ
皿やフォークが陰気にうごく
肉類や卵は食いつくされ
野菜類はつつましくのこる
海は死んだ男でふさがれる
6
ぼくは睡蓮の花を再びのぞく
転換が行われず
世界の女を巻く紐のすべてが解かれていない
蛙も挟まれる
花の深所から金髪が吹きだされるのを夢みる
ぼくは自分と不幸な女を救済すべく
女の腿へ手をのべる
喪服は夜に紛れやすい形と色を持つ
あまつさえ時間がくると滑る
それから先のぼくはまじめな森番だ
くさむらのひなを育てようと決意する
水べを渉る鷭の声に変化した女の声を聴く
法律や煤煙のとどかぬ小屋で
卑俗なあらゆる食物から死守され
ぼくだけが攻めている美しい歯の城
その他の美しい武器をうばう
落日は輝くもの
おえつするもの
女の髪の上に滝が懸けられて凍る
ぼくは冷静に法典の黄金文体をよむ
さてぼくは女には大変つくした
罪深い女は去らせよう
ガス管工夫に肖た子をつれて桃の少女が結婚を迫るのを
ぼくは久しく待つんだ
初出は《今日》(書肆ユリイカ)1958年12月〔10号〕一八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ23行2段組、40行。
バレー〈ライラツク・ガーデン〉より
紫のいろは夜のみつぎもの
すべての音楽が沈みやすいように
すこしずつ泡だちながら
庭から星を消す
それはまわりのライラックの花咲く頃
石の像はささやかれる
嫉妬にも愛にも
抽象的な倦怠をかたどる
欠けた耳をたれたまま
そのかげから
美しい妻はいざなわれる
心をぬれた鳥がかけぬけ
不倫の腰帯 橙色の男のうでのなかで
純粋な恋の跳躍
ただいちどしかできない角度
かんらんの枝のおもみで女は支えられる
喜ばしい罪の肌着のひと裂き
なやましい絹の足がまじわるとき
髯の男この舘の主はとびだしてどなる
かけだす犬 ランプをまもる猫たち
髯の男は欲情の大きな輪をひろげてゆく
花と破綻の中心に
おのれの情人たる緑の着物の女をよこたえる
咲きそびれたライラック以外の花の
めざめる声をききながら
下男は玩具の猿の踊り
女中は玩具の蛇の踊り
ライラックの花のしげみで
まっちをするな
夜鶯を鳴かすな
舘のろうそくのひかりを蠱惑する海辺の風を
ことごとくまねきいれる
ひだの多い美しい妻の裳で
愛をいつわる女の乳房のふかさを石にきざみ
秋の海の反響はかすかになってゆく
いまは人物も不在の庭の空を
夜鶯も鳴き過ぎる
他の種の花も匂いだす
狂ってのぼる黄色い月は
近ずく朝のみつぎもの
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
老人頌(⑤・1、47行)
3月
無罪・有罪(⑥・2、48行)
6月
遅い恋(未刊詩篇・7、12行分)
果物の終り(⑤・2、57行)
7月
牧歌 → 唱歌(⑩・4、17行)
8月
下痢(⑤・3、26行分)
9月
紡錘形1 → 紡錘形Ⅰ(⑤・4、13行分)
夜会(⑩・5、10行分)
10月
編物する女(⑤・8、19行分)
呪婚歌(⑤・9、70行)
夜曲(未刊詩篇・8、14行分)
11月
陰画(⑤・6、35行)
裸婦(⑤・7、20行分)
首長族の病気(⑤・11、24行分)
12月
田舎(⑤・10、26行)
初出は《季刊批評》(現代社)1959年1月〔春季・2号〕一二七〜一三〇ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は並字)使用、五号15行1段組、47行。
さびしい裸の幼児とペリカンを
老人が連れている
病人の王者として死ぬ時のため
肉の徳性と心の孤立化を確認する
森の木の全体を鋸で挽き
出来るだけゆつくり
幽霊船を組立てる
それが寝巻の下から見えた
積み込まれたのは欠けた歯ばかり
痔と肺患の故国より
老人は出てゆく
皮の下から続く深い波のうねりへ乗り
多毛の妻をうつぶせにする
黒い乳房の毒素で
人の心もさわがしくみだれ
くらげの体も曇つている
老人は腹蔵なく笑う
ばんざい
ばんざい
一度は死も新しい体験だから
蝶番のはずれた境界を越える夜
裂れぬ魚の腹はたえず発光し
たえず収縮し
そのうえ恐しく圧力を加えて
エロチツクであり
礼儀正しい老人を眠らさぬ
ガーゼの月のなまめかしさで
老人は回想する
正確にいうならば創造するのだ
胃袋と膀胱のなかに
交代のない沙漠の夜を
はいえなや禿鷹の啼きごえを
星と沙の対等の市を
そして小舎の炎の中心に坐り
王者の心臓の器で
豪奢な血を沸騰させる
果ては
むなしく伏せられた
笊のごとき存在
みごとな裸の踊子も現われぬ
不安な毛の世界で
床屋の主人が剃刀をひらめかせ
老人の大頭を剃り上げる
石膏のつめたさ
美しい死者として
幼児とペリカンの守護神として
他人には邪魔にならぬ所へ移される
初出は《現代詩》(飯塚書店)1959年3月号〔6巻3号〕一三〜一八ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組、48行、「写真・大辻清司、構成・大森忠行」。本篇は《静かな家》に収録されるまえ、篠田一士編集・解説《吉岡實詩集〔今日の詩人双書5〕》(書肆ユリイカ、1959年8月10日)の〈Ⅳ未刊詩篇〉に収められており、その本文は〔初出形〕の改頁箇所をアステリスクに変更(すなわち〔(改頁)→ *〕)したほかは、漢字を一文字改めた(17行め「なみだぐましく妻のぬれた〔躯→軀〕は今はレンガ色」)だけである。
判事はときどき歩く
彼が裁いた男の心の惨劇の迷路の葛の茂り
初夏の月が望遠する
バスケットのなかの大きな蟹のあやしげな行為
重みのある毛布を裂く
馥郁とした血のオルガスムス
少年少女の心中死体が導火される
それぞれ瞬間
美しい電流が生まれる
幻灯画の仏手柑
胎児は手袋をぬぐだろう
(改頁)
判事は地下道へ入る
優しい妻と子は劇場で笑劇を見る
兇器がみつかるまで
判事は長い歳月を孤独な壁を撫ぜる
不具の記憶のくりかえし
なみだぐましく妻のぬれた躯は今はレンガ色
彼はもぐらのように洞察した
一人の美しい裸形の少女のトルソの二叉
眼を近づければ兇器
細い線の針金
それが輪を形づくる
判事は霧の密室からはい上る
犯罪の起源は
人の心の細胞の花火
兇器は真の犯罪には不要のものかも知れず
(改頁)
無能な容疑者は肉の枠のなかに
片目をあけている
もう一つの眼の夢は桜んぼのつるつるにさわり
閉じられた物狂わしい深淵
空走る一つの自転車のからまわり
食事から殺意へ
不安から満腹の子供への呪咀
逃走の脱糞
愛の放尿のこころみ
自転車のからまわり
窓から街へ
光から暗へ
送転する万華鏡の人
無罪の容疑者は野末で
両方の眼をとじ
子供全部を滅ぼした
祝砲を聞いた
(改頁)
ストップ
永遠に
彫刻された男女のために
可能ならば
無罪も有罪もなく
初出は《現代詩手帖》(世代社)1959年6月創刊号〔2巻6号〕六六〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ27字詰14行1段組、12行分。標題はゴチック体で「遲い恋」と印刷されたが(目次も旧字の「遲」)、本則は新字であるため「遅い恋」を採った。吉岡による約400字の散文〈詩人のノオト〉を付し、その末尾に「(よしおか・みのる氏は大正八年、東京生。詩集「僧侶」で本年度現代詩人会H賞を受賞。この五月には長い独身生活から足を洗うとのこと。現、筑摩書房広告部次長。)」とある(〈《現代詩手帖》創刊号のこと〉参照)。
ガリ氏の上半身は裸だ むしろ枯木の存在にちかく がらす板のむこうで 女医先生が手を器用にうごかしてのぞきこむ ガリ氏の尖つた内部を いささかガリ氏は羞しいのだ 少しばかり女医先生がすきなので 自分が人間の器官をうしなつて 深い根に支えられてない 黄昏の物体であり 鳥の巣ほどの夢もかかえず みずみずしい四月の葉に飾られてないことが いつそう内部をはたらきのないものにする だが光のなかで人間は真実の恋ができようか 女医先生はたしかに職業の恋をしはじめる つめたい手と眼で ガリ氏の患部を愛撫しながら そしてふたりだけの 暗い場所を甘い髪の匂いでみたす 盲目の世界で記録されたカルテは永遠に判読されぬだろう 世のすべての恋人たちの手紙のように
初出は《同時代》(黒の会)1959年6月〔9号〕二三〜二六ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ19行1段組、57行。
つねに死ぬ人のまわりにある羽毛の潮のながれ
けばだつ意識の外面ではじかれる
孔雀の血の粒
その真新しいくちばしの喚びの深層で
内的独白をくりかえす
死ぬ人の幼年期の肖像を見た
つまれた菓子の間を疾走し
母の情事のゆえに下痢する
独楽の廻るスピードで失われてゆく微熱の時間
羞恥のセックスで靴下を穿く
幼女のまるいくるぶしへの侮蔑とともに
紋切型の父の心理的倒産があり
黒と白の斑の犬の轢死が少年の視線を転化する
秘密写真へ
柔かい曲線のおびただしい泥沼へ
未熟な杏から
すわりよい梨のしりのくぼみに
都会うまれの少年期の遅い恋の始まり
ばらいろの繭を持つ従姉に教育され
るいれきのある肥った叔母の冷感で戦慄する
肉への廻り道
霧隠才蔵への入信と改宗
とかげの磔刑
また別の少女へのやさしい折檻
反抗と洪水はたえず少年の身の丈をせりあげる
後世の砂漠のなかに
父の無智と兄の無力な家の柱を回避する
オペラ館の極彩色の舞台の予言の歌手たち
仮象で生きる喜劇役者たち
ガルボの秘蹟の遠近感
アナ・ベラの絹の唇の触媒
永遠の視点はジイドとリルケの書から俯瞰される
トンネルの闇で死滅した
家畜の臓物の臭いをかぎつけ
投影した少年の精神が氷の河を引き入れる
ついでに把握しがたい月の運行を
充分な死の恐怖の伝承と
繁る小麦の畑の生への集積の怒り
少年は孤独の肩をあらわにし
物の固い角を経験しはじめた
消えたランプの発端から終焉までを告発する
発生する癌の戦争
大砲の車輪のひと廻りする時
無意味に穴のふさがる時
多くの人類の死・猿にならねばならぬ無声の死
下等な両棲類の噛み合う快感の低い姿勢
横たわる死・だんじて横たわる死
古代の野外円形劇場の太陽の下の醜悪な消却作業
一人だけの少年は哭きわめく
粥状の物質の世界で
コップの嵐のなかで
まさに逆まだ
偶像は
いま死ぬ人の半生の透視図
肖像の少年は模倣するだろう
大人の習慣のぬれた羽毛をたらす死を
歩みよる曙光の拡がり
初出は《朝日新聞》(朝日新聞東京本社)1959年7月26日〔26404号〕一七面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、新聞活字一倍扁平、17行。「え 南大路[みなみおおじ]一[はじめ]」。本文の後に「(「今日」同人)」とある。
男は不足なものをさがす
夏の植物が少年たちと絡みあう
薄明の世界から出る
ある愛の生きながらえている邦へ
古代の氷山を背景にして
こわれた軍艦がひもで岸につながれる
雨と光熱のありあまる港
異端の音楽を聴く
男は見なければならぬ
他の人がひとりもいない真昼の首都
窓わくの奥のうごかない海のなかで
おぼれるリボンの輝き
すべての毛をぬぎさった
ひとりの少女をめざめさせるため
男は小声で祈り
シナの墨でぬられたフカの腹を裂く
美しい汗の夜のはじまり
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年8月〔1号〕八〜九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25字詰1段組、26行分。
ぼくは下痢する のぞむところでなく 拒む術もなく 歴史の変遷と個人の仕事の二重うつしの夜にまぎれて ぼくは下痢する 紅いろの花と 薄明の空をそめる痰の吐かれる地下室の水 それはぼくだけの現象だろうか 今日もそれをする昨日もしたんだ 考えれば昔の記憶のなかの青い膚のとうがんの内房を覗きながら 下痢はぼくらの日常の習慣 洗いたての世界の便器が集められる ぼくの下痢はぼくの精神を飲みくだし 他人の多くの心へ伝達され 飢えの大衆の糧を腐らせてゆく そのときから寝そべる老若男女のむれ そのささやかな声 そのいじらしい手足の運動 それらの生きている証拠の排泄の愛 誰もが流木の位置 ぼくはどこかもう少し高いところから 直接灰をかぶる 被虐的な食事をするため 馬や犬の経験もしないであろう 滑稽な形而上の下痢をする 力なくむしろ生きることを認証する 痛みの導くところ 雷の格闘の終りの空間に聳える塔をみる ぼくの死すべき肉体の鳴りひびく殉教の血のながれの高まる時 ぼくは下痢する 耕される傾斜の土地に 汲まれる泉の絶えざる岩や石の下に 永久に心の内乱の契機の腸を断つ ぼくは忘れられる ぼくは人と物を忘れる 仮設のなかにめぐりあった交友だから 寒冷な下痢する近代の醜悪なかがまる催眠状態をぬけ 回復する驚異な暗が次元を替える 中心に自然の光の接触をくりかえす 二十世紀の庭に ぼくは綜合体として健康な男の一人になる まじ梨から食いはじめる ここに新しい関係・対話がはじまる
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年9月〔2号〕四〜五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25字詰1段組、13行分。
首のまがった母それはまだ女であり 見えない骨の走る小さな父それは男であり 窓の外の地に死ねない人々がめいめいの貧相な手で罎をつみ 蠅をむらがらせ 哄笑と泪声で 二人の男と女に寝床の時を与える 夜が鋭い角をもつならば 他の人は畳の下へ沈む 火事は血を浴び 母の子宮へ移りつつ燃える 父はもうつるつるの猿として自己の枝へつりさがり叫ぶ 水を水を 母は鍋の尻と箒で接がれた一つの化物に変り 襖の世界へ入ってゆく 父は朝早くから桶のなかへ鍬形の手を涵し 労働にたえる熱い鉄を打ちすえる 刻まれた鑪の目が万の錐の尖をとがらす それらすべてが陰気な畳を突き刺す それが生活であり 金銭であり 父はふいごの著しく長い腹をよこたえる 母は障子の内側で孕みつつある
初出は《讀賣新聞〔夕刊〕》(読売新聞社)1959年9月28日〔29776号〕四面〈詩とデッサン〉、本文新字新かな使用、新聞活字一倍扁平19字詰1段組、10行分。「え 加山[かやま]又造[またぞう]」。
母が今夜うんだ卵をだく少年は 眼をふせたまま 死せる魚の口へ 首から下をとじこめられる 父は文明人種の特質を発揮し舟板の上で可憐な少女の緑の髪を解く 口臭を放ちながら ついでに蝋の結晶した星を 定規で組立てた天体へ置く 魔性の家族のさびしい夜会 夏の果物のなかの種子も浮遊する 彼らが未知の現実を会得するためには 苦い心で水銀の運動をくりかえさねばならぬ 夢の体系を失う暁まで
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年10月〔3号〕六〜七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ27字詰1段組、19行分。
たっぷりと畝編みにしたプルオーバー 今夜の料理には玉葱を使おう 彼女はじぶんのからだから何を編みだすのかしれたものではない 大きな衿はタートルネックの変り型 彼女は砂の力で一人の男を愛そうとした ジャージーでピンクなら彼も大胆にさわれる 太陽の網目のなかの苺をつぶす愉悦の日々 男の住所をどこへ控えたか思いだそう 秋だからブルー グレーなどで模様を変え 袖口をゴム編みにして 男が独身者の血は冠の毛をぬらすと 二ケ月前にもらした重大な口説 裏うちは三十糎幅の同色の布をはって横になる しわにならぬから 男の部屋へは猫しか通わぬ秘密をかぎつける 裾は折返しを深く 男とこの夏は波の下へ すべったことが忘れられぬ 単純なメリヤス編みですっきりさせよう 男の肉身・父・母・不具な姉を呪い ドレス・ヤーンでなければ上手に仕上らぬ 長い胴のシルエット 男は貧しいから好色な壁画を描く たくしあげて彼女が着るときココア色のスラックスが似合うと 老裁縫師にいわれた もう冬だからやぼになる 船の底の貝の冷たい光りがとどく 彼女の眼に入る男は彼女にとって象牙色の魚形のハンガーだ 本当に死ぬならばセーターを脱ぎたいと彼女は考える
初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1959年10月号〔4巻10号(38号)〕二四〜二七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、70行。
われら今夜というこの時
この黄教の馬の放中せる陰茎を
中心にして
雨の地に拝跪した
〈ラマ僧の呪祷より〉
わたしたちの今夜というこの時
この日という雨と春
おごそかな寺院の偶像を骨ぬきにした後
卓子をゆくりなく円いものと感じて
その下に集る脚の空間に
なやましい川のながれを見た
ふれるならば刑罰されて死んだ犬猫
つかむならば炎える夥しい藁の束
わたしたちは斜の板へともに並んで寝て
にんじんを噛みながら流れる
大勢の人の微笑
またはまれなる憎悪と風
わたしたちの皮膚のつめたいことを
たがいの欺むかぬ証しとせよ
手と手 腸と腸から
つねにはみだすオレンジ
その果肉の濡れに導びかれて
測り知れぬ愛
観念から行為へ
暗転する太陽その次は薄明
わたしたちの氷る全身に浴せられた
花は死ぬものの嫉妬
しばらくは香気を放ちやがては窒息をねがう
黙示の寝床
われた蛇の卵 麦粒
紡がれた陰毛の糸車
かぶさる毛布類
つもる塵 のびる植物勢
むらがる蜂の針を女の肉へ打つ
否 否
加えるものは
わたしたちの小部屋を彩る
謀術はないのか
パンと牛乳のほかには
純粋な浪費の舞踏する幻のかまきりたち
如露の世界に閉じこめられた
わたしたちの後宮の庭
他人のさわがしい子供が集る
ちんば めっかち 象皮病
それらの眼の油はたぎり
大理石の柱のかげからのぞく
禁欲の衣を次々と沈める海溝
わたしたちに飛躍があるだろうか
華美なさかだち
慈悲ふかい骸骨の抱擁の果に
富を抛棄して貧を養う
それ以外のなにが与えられよう
ともに裸の秤
共犯とはかかる状況
かかる矜りのむなしい愛であり
つきすすむ水路の星座
その吸盤の邦で
甘い罪のながい涎を
わたしたちは飲みつづけた
近代装飾の洞穴のおくふかく
裂かれた兎を耳からつるす
この高揚の月の出
わたしたちも同時に
吟味され照らされる
わたしたちの立ちあがった場所
つねに灰いろの綿毛を舞い上らせて
わたしたちの心と肉の陰画
わたしたちの半面頭に
ねずみ泣きのねずみを二匹棲まわせて
予言される
一人の男として煉瓦をつみ上げ
一人の女として水をかき廻す
悪夢の絵具にくまどられて生きると
永遠がなければ次永遠に
蓋せられた音楽
初出は《近代詩猟》(発行所の記載なし)1959年10月(27冊)六ページ、本文新字新かな使用、14ポ24字詰18行1段組、14行分。末尾の「一九五八・八・四」は、吉岡陽子さんに依れば「一九五九・八・四」が正しい。
夜それも初夏の夜 ぼくは召使としてつつましく坐る それであらゆる型態の蛾をとらえる ほそい朝鮮服の妻のためにだ ぼくが喜色滿面でかざす 蛾のかたじしの胴体は尻へつぼまり 豹の緊張した野性を誇示する 妻の眼のなかでそれに応えて おののく植物の生臭いひとなぜの風 いうまでもない 妻の心はいやおうもなく 蛾の鋭い歯で肉食される 花粉と汗をながす妻の全身を白磁のシーツで陰蔽した 下品な召使のしたごころから 蛾の翅の蝋のにぶい光から 鳥籠には粘土の鳥 まわりには全部まぶたをとざした家具類 ぼくと瀕死の妻は同一の管で 同時に水を吸いあげる 囁く泡のながれ その夢みる裝飾帯 暁ちかく二人の間に赤ん坊が泣きながら割りこむ そんな幻覚を映して氷山が滑り込んでくる
一九五八・八・四
初出は《文學界》(文藝春秋新社)1959年11月号〔13巻11号〕〈「裸婦」他四篇〔〈陰画〉〈裸婦〉〈僧侶〉〈喪服〉〈単純〉〕〉一二〇〜一二一ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、35行、「カット・伊原通夫」。
光りへ抽きだされ
いままで沈んでいた卵の類
いつせいに動きだす
蠅にとび廻られ
甘美な恋人たちの死相の沼をわたり
偶然奏でられた木の葉の音楽に感応して
ばらいろに輝く
半面は磁気を発しながら
卵の類
まんべんなく転る
呪術の生活の逃避所から
英雄の暗殺された武器の市を通りぬけ
鏡の前へ
うつろいやすい女たちの腿を
一つ一つの卵は閉じこめてゆく
疑いもない眠りの支配だ
かぎりなく暗い水をながす
あでやかで精神の交合をうばわれた浴室
夜ごとに連繋をくりかえす死人らの眼と舌の羅列
この眺望に愛と死の共存がありえようか
いくつかの卵が他の卵をのりこえる
符合しない ひどい変容
死人のおびただしい口が明瞭に見えぬ
健康な男女の歯が開かれる時まで
陰をひく卵の類
観念の世界へ寝返りできないのだろうか
やわらかい海の藻の敷物のうえ
すさまじい通過を見せる
軸もない卵の類
策略のない彼岸を探す
光熱のない平面
だめならしばらく
冷血な肉の裡へ拘留される
毟られた卵の類
たちまち仮借ない天体を頂く
初出は《文學界》(文藝春秋新社)1959年11月号〔13巻11号〕〈「裸婦」他四篇〔〈陰画〉〈裸婦〉〈僧侶〉〈喪服〉〈単純〉〕〉一二二ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ26字詰1段組、20行分、「カット・伊原通夫」。雑誌掲載用入稿原稿(写真参照)で注目すべきは、1行の字詰めである。32字×20行の原稿用紙を、行頭は4字アキで書きおこし行末は2字アキで折りかえす26字詰めで書かれており、詩集《紡錘形》(草蝉舎、1962年9月9日)・《吉岡実詩集》(思潮社、1967年10月1日)・《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996年3月25日)、すべての刊本の27字詰めとは、わずか1文字の違いだが、異なっている(散文詩型はこの26字のほかに、20字・22字・24字・25字・27字で組まれているが、これらの原稿の字詰めが〔初出形〕の字詰めと等しいかは不明)。〈裸婦〉の詩句の表記は、漢字が新字、かなが新かな(拗促音はひらがな・カタナカとも小字)で、結果的に本入稿原稿の表記法は(「瀆」の字を含めて)《吉岡実全詩集》掲載形と完全に一致している。このことから、1950年代末までには吉岡実詩の晩年までの表記法(漢字は当用漢字・常用漢字を使い、そこにない表外字は、「涜」といったいわゆる拡張新字体は用いず、いわゆる康熙字典体の「瀆」を使用する、というもの)が定まったと考えられる。
吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈裸婦〉の雑誌掲載用入稿原稿(〈吉岡実の詩稿〈裸婦〉〉参照) 出典:青木正美(保昌正夫監修)《近代詩人・歌人自筆原稿集》(東京堂出版、2002年6月10日、二〇三ページ)青木書店が〈裸婦〉の詩稿を《日本の古本屋》に出品していた。すなわち、「吉岡実詩稿 画像あり/吉岡実、1/「裸婦」 ペン書640字詰完 裏打有 2枚/青木書店 105,000円」。上掲写真とは別カットで、色調補正もされていないが、カラーなので参考までに掲げる。
青木書店(東京都葛飾区堀切)が《日本の古本屋》に出品していた吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈裸婦〉の雑誌掲載用入稿原稿 出典:青木書店
ぼくがあらゆる白痴の世界から奪い出そうとする 秘すべき現実 たくみに毛皮の内部へ吊るされた卵 ぼくはその時からぼくの創造の初夜を涜す そこにはゼラニュウムの花の色で幾度も照らされ 触れ方によつてはゆるやかにうわむく美しい乳房 和解しよう 目的もなく水平線をたどり 砂へ君臨する肉の全身 そこに極度に熟する苺が置かれた ぼくは否定して離れる だが遠近のない岸をひとまきして吹きだされる 髪と藻の暗いみどりの輝き ぼくはあざやかにその寒色で染められる 水へ沈むように少しずつ解放されて そのときというより今 誰であれ視透することはできぬだろう ぼくの立つている吃水度から急に沈み 海の貝類の上で発光する腿や腰部 それからいつそう波はうねる 夏なお冷寒の氷山の特質をさとつた ぼくの主張まで変える強力な組織体 遠くは反響せず 停止と同時に浮動し ぼくでは計量できないマッスとその過剰な陰 その歓待 たしかに侮蔑されよう ぼくは画家だから 実体を他に移す破服の施術者にすぎぬから ぼくは数ある血管を張りめぐらし 或は押出して 複数の眼と口をもつ女を創る 未来が予測できるならば ぼくの眠つた大事業の後 女の白い像が大胆にものを食べる
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1959年11月〔4号〕六〜七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号25字詰1段組、24行分。吉岡実がクリアファイルに保存していた新聞の切り抜きに、本篇のスルスと思しい記事がある(〈〈首長族の病気〉のスルス〉参照)。
或る新聞記事で首長族のことを改めて知った いまでもビルマのカレンニ地方に二千人も住んでいるとのこと 写眞も載っているのでつくづく見た すべての女が首輪をはめ いたいけな幼女も立っている ここでは罪人でなく美人の矜持を重い枷として ぼくは思いだした少年の頃 外国の地理風俗事典で見たことを 彼女たちは体の成長と同じに眞鍮の輪をつぎつぎとふやし あごをつきあげるまで重ねる でも人間の首にも制限があるから それらの形態をふみ外さない枠で止める それ以上長くしたら危險だ 鹿・狐と同じ動物に変化する 或は死ぬだろう ぼくは想像力がとぼしいから 彼女たちの交合の夜の闇までみとおせない 眞鍮の輪と輪のかちかちという軋み その無機質の冷たいささやきがたえず 首長族の男の肉性を刺戟し その満月の狩を唾や汚物でまつる 火のなかに彼女たちは沈む臼 ともあれぼくには別のことが気がかりだ たまたま彼女たちが病気になった場合だ 三つの部落に一人の首輪の技師がいるらしい 首長族の女は庭の大きな樹にしばられて泪をうかべる 一番上の輪から外していく それを木の枝にかける 最後の大きな輪をかけたときさしもの太い生木も裂けたという 技師はそのときはじめて 日に当ったこともなく湿り 白く長い軟体物が 自分の丈より高くぬうっと突き出た実感に思わず吐瀉し 手当料をとらず森へかけこんだそうである
初出は《同時代》(黒の会)1959年12月〔10号〕六六〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組、26行。
納屋であくびをくりかえす
幽霊の見物人
にんじん畑のうっとうしい舞台裏
三つ廻れる爪先踊り
むらがる白鳥を扇形に分け
一つしか廻れぬ偏平足で
跳ね出る夜行性の馬
むらさきいろに照明されて
山へ心臓を食べにゆく
子供の泣き声
川底を漂う肌着のなやましい挑発
めかくしされた魚
屍体の白鳥には深いおじぎをさせ
男の食肉的ずうずうしさで
大股びらきの洗濯女を抱えた
覆面の馬
いななきながら
三つ廻れる爪先踊り
一度の倍の六つ廻りの爪先踊り
子供が鼻血をながす瞬間
なまぐさい蝶が柵へむらがる
拍手 口笛 ステッキを叩く音
発作的にとまり
古典美の権化として
にんじんを食う馬
自然に心の膿も見えた
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
斑猫(⑩・6、30行)
2月
哀歌(未刊詩篇・9、35行)
3月
紡錘形2 → 紡錘形Ⅱ(⑤・5、14行分)
冬の休暇(⑤・12、18行分)
5月
水のもりあがり(⑤・13、29行分)
6月
波よ永遠に止れ(未刊詩篇・10、11節257行)
11月
巫女――あるいは省察(⑤・14、35行)
初出は《詩学》(詩学社)1960年1月号〔15巻1号〕八一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ18行2段組、30行(〈詩篇〈斑猫〉の手入れ稿〉参照)。
詩篇〈斑猫〉〔初出形〕への吉岡実の手入れ 出典:吉岡家蔵スクラップブック〔モノクロコピー〕
わたしの記憶の
ほしいままなる網目
その想像の石組みの柱の向う
噛みくだかれた花々の修羅の極み
ひとりの少女がいるらしく
死んだとは信じられぬ拡りをもつ髪
立つているのでなく
坐せるでもなく
ゆるやかに持ちあげられた
水のなかの腕
そのときから円いへそのなかに棲む斑猫
また豊かに二つに分けられる乳房
圧せられて眠りにおちている
耳たてた虎
硬いひげにおびえる男たち
わたしもいまそのひとりなのか
真紅のひとでに染められて微笑する
藪のおくの唇
少女の着ているものはレースでなく
深海の波でなく
休止符にうずまる音楽
覗かせぬ下半身
少年と見まごう小さなあくび
大きな眼のなかをたえず
狩猟蜂がとびまわる
わたしが近づくため
腋毛から異体の血がながれ
男の枯れた茎の髄へたまる
歩みよる冬
燃える案山子を見た
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1960年2月〔6号〕八〜九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は並字)使用、五号21行1段組、35行。
それは或は風説だろう
ぼくと向きあつた妻が魚の腸を
のりこえ
ぼくを不浄な庖丁で刺す
キヤベツ・ジヤガイモに看視され
ぼくは瀕死の客
スープの湯気の束の間の命
テーブルの上に
レモンの美しい膚があらわれ
正面から血を浴びる
妻よこころせよ
それがぼくの自尊心
ぼくの空腹が他人の便秘に
通ずる油ぎつた岸べ
そこから他国へながれる川
料理された鶏の首と
ぼくの頭が藁で結ばれて
月下の水面を滑る
前世を
ぼくは耐え忍ぶ
爼と胎児を
錐と姙婦をすり替える
ぼくの無償の詐術
髣髴と浮び上る
岩の頂で番のあざらしを凍らす
愛の復讐の記念像
陸の難破者をして仰がせる
ぼくの不倫・ぼくの殉教精神
麦畑へ火事を導びく
ついでにけしの畑
灯る人家を望み
ぼくと密通した人妻の
幼女のマヌカンを
ぼくは抱くだろう
糸杉の狂える夜ごと夜ごとを
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1960年3月〔7号〕二ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号25字詰1段組、14行分。吉岡は1960(昭和35)年3月9日の日記に「昨夜できた〈紡錘形2〉を朝みる。まずよし、陽子に浄書してもらって、〈鰐〉へ送る」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一二一ページ)と書いている。
わたしの生きている今 わたしは触つているのだ それはずいぶん過去の年月の愛と羊水の水圧に抑えられたまま 小さな袋での一囲いの卵として 水平にねむり 立つた勢いでわたしは自分の足の爪を噛んだ わたしの信仰はそれから高まる 朝夕にくりかえされる食物の固形の時 わたしはそのたび聴いた母性の甘い嘔吐を もしかしたら立ちあがれるかも知れない ずいぶん狭い伽藍だと思いながら 裸の姿で いなむしろ裸以前のろうそくの形で 自分の投影を前後左右の壁に映しだす これがこれが犬でないもの 鳥けものの羽を与えられぬもの 呼称・父 呼称・母の夢みてる可憐な塑造の者 夜の香料薬科のなかの血のアーチをくぐり出る 召命されたエキス 木造の首都で一市民のつづらのふたひらく四月 真綿をかぶり老婆が沐浴している
初出は《日本読書新聞》(日本出版協会)1960年3月7日〔1043号〕一面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、新聞用活字一倍(正角)22字詰1段組、18行分。吉岡は1960(昭和35)年2月27日の日記に「詩篇〈冬の休暇〉出来。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一二一ページ)と書いている。
そこでは灰色の馬と灰色でない馬とがすれちがう 灰色の馬が牝らしく毛が長く垂れさがり 別の馬は暗緑の牡なのだろうはげしく躍動する たがいのたてがみも尾も回転する毛の立体にまで高まつて 少女にはそれが見える 完全な円のふちから ときどきはみ出るものがオレンジ色に光り 中心はもう時間が経過したので黒い 或晩にお父さんとお母さんがのぞかせた一角獣のように恐ろしく 少女は自身の腿に熱を浴びる まだすれちがつている馬たち ピエロでない赤い帽子の男は 少女が気づいた時から人ではなく だれもが持つている共犯のはにかみの心 テントの底が深くなればなるほどゆつくり 馬の方へちかづく 命令するために非常に細長い棒をふりおろす 電光もひきあげる街の看板の方へ 今夜は充分泣けると少女は思う 灰色の牝馬のすんなりした腹に 異父弟が宿つたから このみじかい冬の休暇が終るとともに
初出は《鰐》(書肆ユリイカ)1960年5月〔8号〕二〜三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号20字詰1段組、29行分。
水のながれは止る その全面の硬い量の上をすべる 女と魚 たえずまくれるスカートのなかの鱗で飾られた脚 くらい鏡の割目からもりあがつてくる水 ときどき血もまじえて 空気を吸いに魚が想像外に恐しく大きな顔を出す 嗤つているのでなければ 絹の肌の半身を出刃でくすぐられている不安定な口つき 女のもろい曲線の波を他の魚がとびこえる 夜から朝への細い出口 ばら色とむらさき色は女の好きな色 魚の背骨をいつまでも包みこんでいる休息の色 核と愛の危機 もうすこし経過したら腐る滞水時間 ちようど魚の眼のなかに沈みながら女は眠り その女の髪と毛の巣で 再び健康体になる魚 もりあがる水 もりあがる肉 溺れる蝉の悲鳴を聞く さかさまの樹木 さかさまに降る雨をしばらく 未建築地で眺めよう 水の下の陸地 水晶体に結晶されゆく 火事と黒いけむり さだかではなく女は藁でなでられ 魚は氷の角で押えられて 美しい離別 衝撃のつづく小宇宙 作曲家の望んでいるメロデイがうまれた 深い水をくぐりぬけ 再びもりあがつてくる水 その中心の雨傘の宙がえり 心中する男女 しばしば魚が男の身替りをする 受身の風景へ船を置き 寝台を準備したあとで 水がもりあがる 単なる外形ではなく 酒罎にさびしい砂地が閉じこめられる 死骸は実物大の女と魚 音の変質する彼方 どこまでも連続する水のもりあがり
波よ永遠に止れ(未刊詩篇・10)初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1960年6月号〔5巻6号〕四八〜五三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ30字詰25行2段組、11節257行。目次での標題は「波よ永遠に止まれ」。「カット真鍋博」。吉岡は1960(昭和35)年4月15日の日記に「四十一歳の誕生日。〈波よ永遠に止れ〉夜十二時に完成。陽子に浄書してもらう。」、同じく5月10日の日記に「夜八時、雨の中をNHKまで歩く。放送詩集〈波よ永遠に止れ〉の本番録音。演出遠藤利男、声優若山弦蔵。」(〈断片・日記抄〉、《吉岡実詩集〔現代詩文庫14〕》、思潮社、1968年9月1日、一二三ページ、一二四ページ)と書いている。《吉岡実詩集》(思潮社、1967年10月1日)に改稿再録(三一四〜三三五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ27字詰14行1段組)。典拠となったヘディンの訳書や「八十行を削除」した放送詩集用の原稿に関しては、〈〈波よ永遠に止れ〉本文のこと〉を参照されたい。
ヘディン〈中央アジア探検記〉より
1
わたしは 二人の従者と一人の宣教師とともに
四頭馬車で砂漠の入口に着いた
ここからわたしの夢がはじまる
わたしにだけ見えて
ほかの三人の男には見ることのできない夢
幾世紀もの間 砂にうずもれた
伝説の王 眠りの女王の生活の歴史
もしかしたらわたしだけの幻覚だろうか
死んだ都のステンドグラスの寺院の窓から
ながれ出る河のながれ ともにながれる時のながれ
朝は凍りつき 夜あらゆるいきものの
骨を沈めているヤルカンド河のつめたいながれ
2
翌朝 わたしは従者の一人を呼んだ
わたしはその男を毛皮の男と名づける
けものの皮をはぐのがその男の神聖な職業だったから
毛皮の男はヤルカンドへ八頭のらくだと斧を求めに行った
もう一人の従者は近くの支那人の市場から水と麦粉蜂蜜麻袋などの必要品を買って戻る
その男をわたしは女中と呼ぶ
彼は回教徒のタブーを冒し 日の出前に物を食ったため
刑罰をうけ不具にされ
もう男ではないのだから
ロバの背にのせられたまま
女のような泣き声をあげたのを救けた
女中はサルト人にさそわれると
白楊の木の茂みへ
ときには聖なる墓地をよごしに行く
祈祷師の太鼓のなりやむ暁まで
悪霊のおどりをおどるのだ
宣教師には仕事はない 彼は昼は汗をかき
夕方はたらふく羊の肉を食い
夜は祈祷師の残り酒をのんでは吐く
わたしは気象の観測と
ゴブラン織のような地図をひろげる
その地図から
黄塵が湧きあがり われわれの貧しいキャラバンをつつむ
その地図の別の方角 緑色に塗られた印のところから
羚羊が現われ 泉がわきあふれ 甲虫がとびまわる
その地図の褐色にいろどられた丘や草原から
太陽が野兎や われわれの耳を照らす
双眼鏡の視界のかぎり 涯ない砂の原
あの雪のように汚れてないふくらみを見よ
そこにわたし以外の者の足跡があってはならない
生きる人間・死せる人間のものであれ
最初の遠征者・わたしの軀の重みを支える
わたしの足跡でなければならない
点々とつづき点々と消えまたつづく
わたしの生命の証しでなければならない
狼が吠えている
狼があらゆる闖入者を拒んでいる
わたしの願望のために
砂と星の領域を守って立っているのが見える
かたむく月 かたむく月
わたしも宣教師も
女中もひとりねの眠りにおちるだろう
毛皮の男はいつ戻るか
舟の竜骨のようなたくましいその男を
わたしは信頼して待つ
明日という朝 あさってという朝
3
タクラ・マカン砂漠を横断するキャラバンがあるときいて
わたしの宿を一人の老人がおとずれた
このからすのようなだみ声の老人
彼はわたしの目的を探りにきたのかも知れぬ
突然 流沙の中に永遠に姿を消した
死の都の財宝を
わたしたちが発見にきたのだと思っているのだろうか
老人は語るのである
若い頃の恐ろしい体験を
悪霊がいまなお廃墟の周囲にとどまり
黄金探求者たちを死にみちびく
みずみずしい果物一つ盛られてない皿
あざやかな満月の皿
そのまえで渇きながら黄金探求者は死んでゆく
半身は砂にうずもれ
あとの半身はつめたい金銀の器具におおわれて
山猫のむれが鳴く
じゃこうねずみのむれが鳴く
はじめは山猫がその人形のような餌食をみつける
次にじゃこうねずみのするどい歯が噛む
骨のなかの肉を
肉のなかの骨を
砂のなかの髪の毛を
暗のなかの食事はしずかに行われる
砂のうえの食事はしずかに終る
それから幾百年後に
別の黄金探求者たちは財宝のかわりに
別のものをみつけ出すだろう
奇妙な色と形をしたたくさんの支那ぐつが散乱しているのを
手にとろうとするとき
支那ぐつはたちまち塵のごとくくずれ
あとかたもなくなってしまう
……………………
老人が語りおわるころ珍しく雨がきた
わたしはこの口碑・伝説を一笑に附すことはできない
だがわたしの危険な旅行は中止されぬだろう
わたしには水平線の彼方に
美しく起伏する砂丘の鼓動が魂にひびいてくる
わたしのロマンチックな仮説が未知の世界
未知の空間へ記録されるかもしれない
もし不幸な運命がわたしの立っている砂の上
この砂の下へしのびよらなければ
4
わたしはここ数日
輻射熱と大気のなかにある塵の量と
温度の密接な関係を調査して暮す
宣教師は
すさまじい砂嵐の吹かぬかぎり
印度の金融商人の夜のみだらな酒宴によばれる
踊る女のへそにはめた虎眼石が輝く
深くて戻るすべのない闇
わたしはいまだかつて宣教師が祈りをあげているのも
土民の病人の看護する姿もみとめない
彼も一度は心をこめて祈る時がくる
みずからが突然の死にくびられる時
滴れない桃のしずく
滴れない梨のしずく
土民のかきならすジイザーという楽器を
女中が天幕の入口で奏でている
刑罰をうけた人間の魂がもつメランコリイ
水槽のなかの水が少しずつ泡だつような夜だ
5
毛皮の男が戻ってきた 八頭のらくだをつれて
それぞれのらくだの背につまれた乾草の匂いは甘く
わたしは緑地地帯の涼しい水が快く回想される
パンを焼くマラル・バシイの村の景物とともに
毛皮の男は白楊樹の太い幹へ
斧を一撃うちこむとその下へ寝る 生きづいている毛皮
大小さまざまならくだを円形につなぐ
蘆を気ままに食べるのをみながら
わたしは一箇の絵を観賞しているやすらぎをおぼえる
女中は恋人にふたたび会えたようなはしゃぎ
毛皮の男のために食事の準備をする
卵を割り マカロニを妙め
一羽の鶏の首を斧で断つ
わたしにはこれらのこともまた牧歌的な絵だ
何も始ってはいない 灯をめぐる幾つかの大きな蛾
どうどうめぐりをくりかえす迷える蛾
それすらわたしたちの運命の暗示とは考えられぬ
わたしは生きて目的を果すであろう
天幕の入口からただちに砂漠へつづいている行程
これから幾日かわが愛すべき砂
わが憎むべき砂
未知の森 未知の空
未知の河 未知の水平線
未知の世界を進むためには
たがいに頼らなければならないわたしたちいきものたち
6
砂漠の年代記に記載されるべき日
わたしたちは出発する
門出を祝福する数十枚の支那の青銅銭が空へまかれた
わたしはらくだの背に乗りながら
コンパスを未知の方向へ確信のうちにのばす
宣教師は病気だといつわって去った
彼は今 屋根に集る群集の一人として見送るだろうか
遠ざかる屋根 遠ざかる人
遠ざかる泉
アジヤの美しい春だ
荒涼とした砂漠へ向う
わたしたち悲劇のキャラバンの鈴がひびく
八頭のらくだのつけている鉄の舌をもつ鈴
みちびきの鈴よ 弔いの鈴よ
不吉であれ 幸運であれ わたしたちはどこまでも
ともに旅するであろう
アジヤの美しい春を
7
北東風は終日吹きつづけ
空には星のかわりに砂がながれる
すべての植物類が影をひそめるころ
わたしたちは巨大な砂丘の迷宮にとじこめられた
滑る砂 らくだの足を沈める砂
水槽を積んだ背高らくだがころんだ
十五呎もある斜面で荷をおろしてらくだを休ませ
飼料の蘆の葉を与える
わたしたちは少量の水でのどをうるおしニッキを噛む
黒い綿毛のような雲の彼方に旧い河床を発見した
毛皮の男が先頭のらくだの上で叫んだ
北方に一時進路を変えよ
わたしのらくだが続く 女中のらくだが続く
荷物を積んだ五頭のらくだが続く しんがりを犬がおりる
再び砂丘が十呎の高さで疲れたキャラバンをとりかこむ
落日の波形の影がすべての砂丘の頂きを走る
やっと平坦な塵の上に出る 羊毛のようなやわらかい塵
ときたまらくだの蹄にふみくだかれる塩の結晶の不気味な音
わたしたちが野営地につく前に夜がきた
毛皮の男と女中が井戸を掘り
そのまわりを犬と鶏が深い関心をよせて見守る
井戸をほること そしていのちの水を得ること
これがわたしたちの金科玉条
生きること 三人の人間 八頭のらくだ 一匹の犬 これら生きものがいきること
今夜は水が得られるであろうか 蜜のように甘い水が
明日は復活祭だ
8
わたしたちは未踏の大砂漠にさしかかりつつある
こころよい西の微風 青空の反射にかがやくあざみの花
エシル・コールとよばれる「緑の湖」はどこにあるのか
毛皮の男も女中も知らない まぼろしの湖よ
ここで羊の最後の一頭を屠殺し 祝福された食事をする
血と屑肉は犬に与えた
翌日の真昼 天幕を取り外したら 敷物の下から
一吋半のさそりがとびでたのに驚く
今日は美しい溪谷と沼沢地を踏破し北東方へ進路を変えた
鷹が舞っている ライフルで撃つ 鷹は孤立した山へ去った
午後の沼の岸べは蛙の鳴き声 雁の叫び
わたしにとって長くない地上の楽園となろう
毛皮の男と女中は水浴びから戻らない
わたしは妻と子のための手紙を書く
妻と子のすきなタマリスクの花の匂いをこめて
とどかないかも知れない故に深い愛のことばを告げる
9
この人間の棲まぬ果で一人の男に出会う
塩を求め山中へ入って行く孤独な 塩採取人が地上での最後の人間
新鮮な水を得ることのできる最後の土地
魅惑の溪谷を発って十数日を経た
砂丘は粘土の地表へ砂を灌ぎ灌ぎ はるか南西へ拡っている
黒い蝸牛にも似たキャラバン
わたしたちはすすむ すすむ 目的地を指し
千度も千歩を行く
岸べなき砂の大洋[おおうみ] 黄色い大波 熱い水脈
犬と羊が狂気のごとく水槽に近寄る
女中も狂気のごとく渇きをうったえて哭く
千の針に刺された朝の太陽 盲いて行くわたしたちの心臓
なめる黄金の水 水のなかの黄金の舌
この夕刻以後らくだには一滴の水も与えてやれぬだろう
見あげる砂の頂きにはわたしたちの荘厳なる墓地
雲のなかに消える
死んだ二頭のらくだのため
いまわしくも生きのこるわたしたちのため
蹌踉として永遠の砂丘をよじのぼるらくだたちよ
葬列の鈴を美しく鳴らせ
彼方の氷にとざされたる父なる山よ
そのゆたかな氷と雪を溶せ
女中は最後の一滴の水まで盗み行方をくらます
10
それから幾日後 一羽の鶺鴒がとんできて希望をめざめさせる
毛皮の男はらくだの尿を酢と砂糖をまぜてのんだゆえ
恐しい嘔吐のため瀕死の状態にいた
わたしは水槽を持って死のキャラバンを離れる
目印のカンテラが砂の表面をしずかにしずかに照す
まどろみと幻想のうちに水晶の水とライラックの匂いをかぐ
たえずはいずり歩く わたしはミイラの末裔
コータン河の森の方向に
羊飼のかがりびでも見えぬであろうか
いまこの沈黙の夜がキャラバンの最後の場面なのか
否否わたしにはみちづれがある
頭上の星 鋼鉄の精神 鋤の柄の杖
東南の方角が霧に巻かれているのが見えた
次に灌木と葦のくさむら
ついに河岸にたどりついた時
わたしの跫音に鴨がとび立ち しばらくして水音が聴える
新鮮でつめたい美しい水
鴨がこの水の上に憩うていたのすら非常な冒涜に思われた
わたしは脈搏を計りそれからのんだギリシャの神々の美酒を
未来は茫漠として微笑む人生の悲惨な行事が空白になる一瞬
わたしは裸も同然で何一つ水を入れるものがない
混乱のなかの天の啓示
わたしは防水靴にいっぱい水を充たし
月光の林のなかを死につつあるキャラバンの方へ戻って行く
聖なる靴 一人の生命を救った この創造主 靴屋に幸いあれ
11
わたしは故国への帰路につく
ゆれる船 かたむく帆柱 さらば陸地よ さらば砂漠よ
「そこでは、人間の意志も水流の巨大な力も、同様にその狂暴
さを征服し得ない。恐るべきタクラ・マカン砂漠が地上の森羅
万象を支配する神の名において宣言する。《この地まで来れ、
されどこの地より進むなかれ この地において汝らほこらしげ
なる波よ 永遠に止れ》」
(本稿より八十行を削除して九六〇年五月一一日NHKより放送)
初出は《文學界》(文藝春秋新社)1960年11月号〔14巻11号〕一〇一〜一〇三ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、35行。
北欧的な濃霧のうすれるころ
わたしはベンチに腰かけて洟をかむ
プラトニックな逢びきのため
箒のような白髪のおびただしい樹木と
そこには観念の孤独な公園のぶらんこのひと揺り
見たらだれでもが不覚にも笑う
おそろしく肥つた女
それは肉体の輪郭ではなく
彼女の内在するプリズムが着物を下から脹ましている
彼女の腕や腿を肉眼でみては失礼だ
なでたりさわると退屈する
ふたたび自己省察をこころみ
わたしは高みから暗い滑り台をすべりつづける
いまにはじまつたことではなく永遠に
彼女は歩きすぎるので
夜半はよく坐る
氷柱のなかに
建築物の上に
はじらいもなく
わたしの食べかけの西瓜の上にまたがる
もしかしたら今夜は出会えぬ
彼女はデリケートな儀式を行いにいつたのだろう
死人の上の石をどける音楽
波がもちあげる処女性の夏
プールの跳板の空中で
肥つた彼女の胴体が中心部でずれる
同時にあらゆる記念碑の土台の大理石が食違う
わたしは謙虚に新しい壁をぬり
わたしの機能力では明確に捉えられないが
標的のような円をならべて
彼女の肖像を描く
しばらくわたしは別れていよう
他の人にとつても彼女は必要だから
彼女は節度をもつて導かれている
生命のドラマの解剖図の上へ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
衣鉢(⑤・16、39行)
受難(⑤・17、20行)
2月
鎮魂歌(⑤・15、25行)
5月
狩られる女――ミロの絵から(⑤・18、26行)
7月
寄港(⑤・19、22行分)
10月
灯台にて(⑤・20、33行)
霧(⑩・7、13行)
初出は《ユリイカ》(書肆ユリイカ)1961年1月号〔6巻1号(52号)〕五六〜五七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、39行。
たたみの黄いろ
わたしたちの皮膚のハアモニイ
わたしたちの四角い腰が坐る
始祖から今にいたるまで
たたみの疥癬性
夫婦が這う
赤ん坊が這う
もう少し這えば海へ出る
ざるをかざせば
さるすべりの紅
赤ん坊は力つきそこから先は老人が這う
火事の構造する障子の世界
つなみの礎石する瓦の空
老人は這う
黒い胴巻
老人は耳をたらして呟く
家紋と太い柱は遠い
げんげの畠を去るつめたい水
飲食の国は魂の岩の中
老人は力つき骨が這う
スピードがおちる
やわらかな苔の上では
もう夕暮ちかく
ぴかぴかの鎌形の月
如露できれいに洗うしらみやうじ
骨の美しいカーヴをくつきりと
初冬の道のべで
顕彰するために
ここからまたつづく
泥と水をまぜ細い竹を編みこんだ
囚れの矢来のような壁
そこでわたしたちは見る
夜叉の女たちが茶釜を叩き
琴を鳴らす爪の受菜のときを
走る天井
停るたたみ
わたしたちは家に入る
一匹のむかでを殺すため
泣き笑いの能面の伝統のうちに
初出は《近代文学》(近代文学社)1961年1月号〔16巻1号〕一〇〇ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ1段組、20行。
雪の下にねむる釘
考えられる!
造船所の裏の堀割で
子供と昆虫が暗号だけの愛を
試みている半世紀も前の事
憎しみは鋏や石臼のひびき
人びとの死面の格子
ぼくの次にだれが吠える
リンネルの空の下で
みせかけの海の波へ
ぼくが溺死したあとだれが泳ぐ
なぜ月が出る
トマトの山を半分かくし
伝統の受難の野に
もう少し歩いて行けば
ぼくは死ぬより無関心になろう
拷問道具のうしろに
砂丘がおどろくほどぴんと張つている
信じられる!
髪の毛の下にうごく櫛
初出は《風景》(悠々会)1961年2月号〔2巻2号〕一八〜一九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、8ポ二分アキ1段組、25行。
ぼくは知っている
夏の美しい雲への歩みを
夜をむかえる前のしばらく
いくつもの柱がつらなっている
どの一つもがひとかかえもあり
垂直に立って円みをもち
ぼくは恐れているのだ
人妻はすべて裸であったという
記憶を幼時から忘れてはいないのだから
大胆な四つの柱は今なお
砕かれずに上も下もなく
雨にぬれている
そこから馬は出発して行き
ぼくは他人の寝室の青空をかいまみる
折れた櫂の海もともに
高みへ次々と重く閉められて
王室のひきだしは音を立てる
細い首を挟まれて
死せる鴎
髪のたなびく春
ぼくはこんな大人になっても
柱という柱にふれる
ひきだしというひきだしを開く
冬がくるまでに
自己没入の過程を了るために
初出は《詩学》(詩学社)1961年5月号〔16巻6号〕四六ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、9ポ2段組、26行。
偶然の配色の緑や黄のもやから
一人の女が生まれる
一本の紐を波うたせながら
ぼくの心に火の円を描く
その女の腰から左右に突きでる
棒の両端にとまる鳥
それはいつも子供のように哭く
すつかり肉付が了るまで
月に真横を見せ
挑戦する
闇の空に
野菜籠の下の海にもまた
容器が世異を変える
その内容が腐りかかつた茶色から
黒くなる
小さな半島
スペインの内乱
歴史の霜の中の血
夏みかんを狩る
その蜜の頭髄のながれ
もしかしたら
ぼくは見すごしているかも知れぬ
驚愕にみちた砲身の地より
方向転換して
飛ぶ美しい婦人帽を
ふたたび太陽が正面に輝くならば
初出は《秩序》(文学グループ秩序)1961年7月〔9号〕六六〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、五号24字詰1段組、22行分。
ぼくの肉体の延長がつづく うごき廻る火や女の尾冠の頂へ 旧世紀の溶ける雪の束の間 ぼくは主張できるだろうか ぼくの認識のために船が赤道へ進み 下着の内側で美しいくらげが熱のために干される つまりぼくの愛が鴎のくちばしを紅色に染めるまで すべての杏やりんごは熟さないだろう 綿が屋根を包み ぼくが目指す港の全景をしずかにかくす 唾液は念入りにたれる 帆柱からまつすぐに集り 薄明の湾の中心へ 音楽が命ぜられる ぼくの眠りを縛る幾条かの綱が太くなり ぼくの笑いは充分卑屈だ 亀の甲の下で もしやさしい女がいるとしたら 明るい旋風が港へ帰つたのだ 絞首台の上に皿や野菜が置かれて 末つぼまりの鉛管の家 ぼくには新しい航跡がない ぼくの心が変つたと他人がいつたら ぼくは静脈のなかで変つたのだ それからゆつくりはじまる悪疫と浸水 ぼくの生理がなまなましく感じる 夜の波の下のおびただしい繃帯の魚 賠償をとどこうりなくするために ぼくは今日みつけだすだろう 陸地の雨と羊の頭を囲む柵を そして家具の山が燃え上り 鎖骨がゆつくり外れた市 狭いところに 首尾よくなにが残りなにが残らないのか? ギターの内臓をさらす港へ ぼくは近ずく
1961・4・14
初出は《文學界》(文藝春秋新社)1961年10月号〔15巻10号〕一二六〜一二七ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組、33行。吉岡は本篇の〈作品ノート〉に「「灯台にて」は、詩に倦怠をおぼえはじめた時期の作品で、たいへん難儀をしながら書いた記憶がある。主題は、一言でいえば、戦争のために、青春期を失った一人の男の心の姿である。」(《日本詩集1962》、国文社、1962年12月15日、二〇四ページ)と書いている。
教授はいう〈異つた生き方の苦しみ――〉
ゆつくり煙が止る
道化帽子の下で
分割された軍艦の心臓部まで
真赤なベットの覆い布がたれる
鷹の中の迷える石の魚雷
ぼくには今それだけしか感じられず
コンクリートの泡の穴しか見えない
裸の巴旦杏をたべる少年時がなかつたんだ
女の栄光の血と夜明けの水域も泳がずに
ぼくは灯台をさがす
ロマンチックな肋のいかだを組み
産婆のように冷笑して
一段一段高まる海を行く
両極から子宮を挟む
大きなレンズが南から北へ廻る
もう一度聞きたい陸からの咳を
さかさにかざされた懐中電灯
夏なお寒い便所の下の闇で鴎は汚される
ぼくの魂の粗相じやない
それは生きてるための誤解
中庭にコスモスが咲く桃色と白
投網が閉じられるまで
ぼくの能力が保障される
二重にも繃帯を捲かれた塔
その艶消しの内陣
中年の薄明ゆえ宗教もなく悟性もなく
ぼくの現在は何と合体することか
低い棚ではへちまがつらなる
そこから別の色彩
別の風景が装置されるとしたら
チーク材の船の底に花嫁が死んだように
美しく生きている
ポーズを変えることなく
案内図がある初出は《讀賣新聞〔夕刊〕》(読売新聞社)1961年10月5日〔30512号〕五面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、新聞活字一倍扁平1段組、13行、村野四郎〈現代詩のわかりにくさ――それは精神文化の流れとともにある〉の文中に罫囲みで掲載。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
沼・秋の絵(⑤・21、23行)
修正と省略(⑤・22、27行分)
6月
晩春(⑩・8、4行)
塩と藻の岸べで(⑩・9、22行)
9月
劇のためのト書の試み(⑥・1、39行)
初出は《文藝》(河出書房新社)1962年3月号〔1巻1号〕二四〇〜二四一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、10ポ1段組、23行。吉岡は自作についての随想〈三つの想い出の詩〉に本篇を全行引用して(本文のひらがなの拗促音は小字)、「「沼・秋の絵」は、美術雑誌で見た、シュルレアリスムの女流画家レオノール・フィニの絵を題材にしたものだ。いってみれば、言葉で模写したようなものである。霊気の立ちこめる薄明の沼で、水浴している「わがアフロディーテー」と、解して下さってもよい。「わたしはいつ愛撫できる?」と、思慕し、願望しているのだ。」(《吉岡実〔現代の詩人1〕》中央公論社、1984年1月20日、二〇二ページ)と書いている。
女がそこにひとりいる
乳房の下半分を
太藺や灯心草と同じように
沼へ沈め
陸地の動物のあらゆる嘴や蹄から
女のやさしい病気をかくして
微小なえびのひげに触れている
野蛮な深みに立ち
罰せられた岩棚で
わたしはいつ愛撫できる?
鋸をもつ魚の口
蟻のひと廻りする一メートル半径の馬の頭蓋
それが侮辱されて骨へ代るとき
わたしは否でも愛を認識できる
いつでも曖昧な人間の死がくりかえされ
水はうごく岸べから岸べへと
わたしの尿や血が悪化するまで
もし幻覚でなければ臨床的に
女はぬれた髪の毛をしぼられ
いつそう美しく空へ持ちあげられる
なんの歪みもなく
そこに数多く
死んだ猛禽類の羽毛が辷りつづける
初出は《文藝》(河出書房新社)1962年3月号〔1巻1号〕二四二〜二四三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ26字詰1段組、27行分。吉岡は自作についての随想〈三つの想い出の詩〉に「私は正月の休日をすべて費やして、二篇の詩をどうにか書き上げた。本来なら一つの長い詩篇が望ましいのであろうが、気力が続かず、二篇の小品に分けてしまったのだった。〔……〕「沼・秋の絵」はすでに出来、その夜は、「修正と省略」に没頭していた。深夜一時ごろ、遂に完成した。」(《吉岡実〔現代の詩人1〕》中央公論社、1984年1月20日、二〇二・二〇六ページ)と書いている。
装飾模様に用いられたらしい わたしの統一体としての人間 いちじくは皿の中心でとがる といつたずつと自然な内腔への愛 それはいつでもぼくの考えている 支那の幼児の食べる物を想像させる 氷山の家で菱の実が煮られる夜へ その生命の内なる青い骨が分ちがたく見える すさまじいお伽噺をきかせよ 岩肌へ開示される歴史や長い竜のひげが垂れる そこでは小さな文明と刃傷沙汰が終り ダイナミックな月の出まで 砂に噛まれたひらめをうごかす 五人の女の優雅な遊戯のうちに 波の力を感じる そのすみやかな帆の移動をさとる わたしは指摘できるか? 犯行者の持つ大きな模様 その鮮明な赤や黒の縞がとぐろまく地図の上を 向き合つた人 向き合つた動物 笑えば恐しく長い歯を現わす 外部から把えられた肺のなかの病気 やがて本質的に肉のない世界を見つけられる? 板のような静かな直線の深い竪溝の走り高まるまで ゆつくり死んだ女の完成された肩をベッドで見る それがわたしの希いであり 偉大な試みといえよう 新しい壁から食肉主義の細密画を外し すなわち主題の女の上へ乗る 四方の平面から豊饒な葡萄の漏水があるまで この情況証拠! このつつましいデザインをわたしは自己に許容する あきらめの冷たい響き 水彩でぬられた世界のうすめられた血の実景 サイズの零 多孔質の自己陶酔 秩序のない単細胞の存在がうたがわれる時 ひとつの器具の意志がより大きく自転する わたしは判断できる ありあまる野菜の山を噛みながら 見方によれば みごとな老人へと修正される喜びを 正当な理由でなく 堅固な俗世の障害物をとりのぞき 図案のように美しく省略される 増大するべく
初出は《いけ花龍生》(龍生華道会)1962年6月号〔26号〕二ページ〈四行詩〉、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、16級ゴチック1段組、4行。「絵・堀内規次」、初出時〈理解のいとぐち〉〔無署名〕を付す。
理解のいとぐち
なぜだか、なにかしら、悩ましい。人々は時々そんな経験をする。理屈で考えてもよくわからない。しかし、理屈のとどかない多くのものでなり立っているのが、人間、ことに複雑な現代の、人間だ。その理屈の底に横わる暗くて奥深い世界、そこへ直観のゾンデやメスをいれるのが、現代詩の役割の一つだ。この詩には晩春の悩ましさがエロティックな生きものとして見事に生けどりされている。
詩人吉岡実は、独特な軟体動物的官能力と直観力で現代の最深部のドラマを造型する超現実主義的詩人の第一人者。H賞受賞者。画家堀内規次は、現代人の心象風景を柔軟で洗煉された感受性のカンバスの上で抒情する暢達な作風の第一線作家。「同時代」所属。
ぼくは赤面する
水にぬれたことのない肉色の月がのぼるとき
暗い甲板をすべって行く ぼくの花嫁の後姿を見ながら
水母の巣へ戻りたがっている波を感じる
初出は《花椿》(資生堂出版部)1962年6月〔7月号・13巻6号〕五ページ、本文新字新かな使用、9ポ1段組、22行。「画・脇田和」。
雨後の首府
春から夏にかけて
多くの髯を剃る男たちの中から
ぼくが半病人のひとりの少女を救うとき
洪水をながれる花と動物の頭
よろよろのぼる稲妻を見る
ぼくも少女もそのとき
幼児の発言を聞いたと信じる
不滅の不幸・不滅の愛
うごかぬ化石の背景
それは星の下で絹のように黒く
ひとつの卓子から地球の周囲まで
同時に蔽うている
いまぼくに本当の恋情がめざめ
あらゆる海溝のひとでが真紅に輝くとき
ぼくの記憶の妻は灰色の長い縞の布としてたれる
少女のひめやかなあくび
くりかえす生きる悦び!
それはぼくをつつむ薔薇色の繭
悩ましい水母の冷感のうちで
少女の脚が恐しく長いとさとる
宗教的な塩と藻の岸べで
初出は《鰐》(鰐の会)1962年9月〔10号〕二〜三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号20行1段組、39行。
それまでは普通のサイズ
ある日ある夜から不当に家のすべての家具調度が変化する
リズムにのつて 暗い月曜日の風のなかで
音楽はユーモレスク
視覚的に大きなコップ 大きな歯ブラシ
天井までとどく洋服ダンス
部屋いつぱいのテーブル
家族四人が匿れるトマト
父・洋服が大きくて波うち会社へ出られず
兄・靴が大きくてラセン巻き
妹・月経帯が大きくてキララいろ
母・大きな容器の持ちはこびで疲れてたおれる
父に電話がかかる
拡声器のように大きな声が父の不正な仕事をあばく
兄は女を孕ます罪をあばかれる
電話機の闇
妹は火山口のような水洗便所のふちで
恋人の名を呼ぶ
母はどうしているか 母は催眠錠の下にいる
塀の外はどうなつているのか 洗濯物で見えぬ
ある日ある朝から順調にサイズが小さくなる
小さな鏡 小さな寝台
小さなパン 観念のような
妹《わたしは飢えているわ》
兄《何があつたのだろう この窓の外で
火事や地震じやない 別の出来事が
ぼくたちの罪じやない》
夕暮から地平の上のほろびの技術
かたむく灯
かたむく煙突
かたむく家
父母の死骸は回転している洋服ダンスの中
兄妹はレンガの上に腰かけ
雨がふつている
ふくらむスポンジの世界
兄《とにかくぬれないところ どこがあるだろう》
兄妹立ちあがる未来の形で
聞える?
恋するツバメの鳴き声
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
馬・春の絵(⑥・5、22行分)
2月
珈琲(⑥・3、10行)
8月
模写――或はクートの絵から(⑥・4、47行)
初出は《文藝》(河出書房新社)1963年1月号〔2巻1号〕一二〜一三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、10ポ25字詰1段組、22行分。
わたしはそのとき競馬場の芝生にねて 円柱球の馬を見ている 一二回跳ねるのを見た! もしかりにわたしの家の戸棚のなかに 馬が死んでいると確認したら どれほどわたしを悦ばせることか わたしは早速そのスポンジ化した馬の臀を両手で抑える それは夜まで続く 不惑の人生をかえりみて 少数者の自由を守ろうと思う 戸棚からころがりだす酒壜と血まみれのハンドル 終りに孔のたくさんある鉄の筒の胴廻りを計る 水に打たれて伸縮度を加える馬の首 それはわたしにとつては過ぎた戦いの心の患部だ それが女の首と太さが同等だつたときのわたしのおどろき リンゴのように半分噛られた星の下で 隣人みんなの哀れみを受ける 裂れたカンバスよりもつと永遠でない闇から 愛撫する馬の腹へ わたしは口をつけて囁く 《人間の幸福は各個人の生得のもの》 女は蹄鉄の下からスカートをつける ピンクとグレーのゆるやかなカーブの藪の道へ帰つて行く わたしはだれにも聞けないのだ 女は死んだ馬なのか 雨のなかでいまでも跳ねる かつてわたしが光で見た円柱球の馬なのか 朝がきたらしいああいちじるしいナツメの実 わたしは歯刷子で歯をみがき それを取りおとすだろう 世界はいつも余分なものをつくり わたしに余分な仕事を与える
初出は《美術手帖》(美術出版社)1963年2月号〔216号〕七五ページ、本文新字新かな使用、8ポ1段組、10行、「絵・加山又造」。
わたしは発見し
答えるためにそこにいる
わたしは得意 ススキの茂みのなかで
わたしは聞くより 見る
半病人の少女の支那服のすそから
かがやき現われる血の石
わたしはそれにさわり叫ぶ
熱い珈琲を一杯
高い高い高射砲台へのぼる男
わたし以外にないと答える
初出は《海程》(発行所の記載なし、発行者は出沢三太)1963年8月〔2巻9号〕二〜三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ21字詰1段組、47行、カット(クレジットなし)。目次と本文ページ柱に「寄稿」とある。《海程》の編集者であり同人代表である金子兜太が〈編集後記〉に「吉岡実さんの新作をいただいた。約半年間どこにも作品をだしていないので、吉岡ファンの多い俳壇への良きプレゼントであるはず。」と書いている(本篇〔初出形〕確認までの経緯は〈詩篇〈模写――或はクートの絵から〉初出発見記〉参照)。
沼の魚はすいすい泳ぐ
骨をからだ全体に張り出して
犬藻や中世の戦死者の髪の毛を
暗がりから 暗がりまでなびかせて
頭の上の尖った骨で光るのは?
もちろんくびられた女王の金髪だ
今晩だって砂浜へ大砲をすえたまま
中年の男が一人で戦争をはじめるだろう
日が出るまでに
その男はふとった幽霊になるだろう
首尾よく行けば
歴史的な楽園が見える?
干された蛸 干された蟹
網目と裂け目
雪のある陸地から
この軍艦の幾艘もつながれた島へくる
着飾った男と女のよりよい神秘の愛
わたしは祝祭してやりたいと思う
画家ならば美しい着物を
手足から胴まで棒のように
まきつけて
生命力が失われるまで立たせておく
昼より暗い空 或は蛙のとびまわる水草のなかへ
いま一歩の歩みが大切だ
死んだ少女の股までの百合の丈
赤粘土層のゆるやかな丘への駈け足
見ること 見えている中心は
不完全な燃焼の
ミルク・ゼリーと冷たい鉢
画家の高熱期も終り
わたしは現在をさびしい時代だと思う
秋から冬へかけて注意深く
軍艦は全部円を廻る
ときには円を割る
野菜園のある段畑へすすみ衝突して
くだかれたニンジン・キャベツ
わたしは走る・跳ねる見物人として
死んだ少年のむれ そのいたいたしい
美しいアスパラガス
画家は彼らのために涙をながすと思う
石に描かれた若い蛇の苦悩の肉体はいま
膿でなくなり拡がる平面
ときおりの雨にぬらされるだろう
まだ描かれない絵が 絵が所有する細い細い紐
テーブルの向うに山嶽 氷る甲虫の卵
わたしにそれらが見えない
真紅な色の持続をのぞんでいる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4月
滞在(⑥・7、25行)
7月
聖母頌(⑥・6、29行)
9月
九月(⑩・10、23行)
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1964年4月号〔7巻4号〕八〜九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号1段組、25行。
わたしはいつも考える
ドアのノブのやわらかい恐怖
滞在とはなに?
火事のなかではぜる大きな楽器を見ている
わたしは不可視のものを
笑ったりしないだろう
それが氷上なら
わたしは女の腰をかかえて滑って行く
円が回避する円
あらゆる現実を分割して
回路を戻るソーセージがある
それは新しい観念だ
青いペンキ塗りのポンプへわたしは接近する
上下にうごかないことが
死を語るなら 死へも接する
だからわたしは寒い食事がすきだ
凍る心のガラスの破片の細部まで見せる
鯛の美しい擬態
それこそ注目せよ
そこから続く長い長い橋
淋しいホテルの裏口を出ながら
わたしは考える
雨傘のなかの小さな愛を
疾走する自動車のハンドル
すべて左へ左へときられる
初出は《郵政》(郵政弘済会)1964年7月号〔16巻7号〕一四〜一五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ25行1段組、29行。執筆者名の後に「(日本現代詩人会会員)」とある。
わたしたち再びうまれるとしたら
さびしいヴィオレット色の甘皮からだ
それはいじるより見る方が美しい
ところどころ夏のくだものの房をつけ
しずかに稲妻を走らせる
亜鉛のドームの下はやわらかい馬の口
鉄がゆっくりうごく
わたしたち再びうまれるとき
西瓜の畑で月は輝くか
いま いまとはいかなる紐の切れ目
大小の羊が下半身の毛を刈られる
わたしたちの母を匿すんだ
青や赤で染められた
地図の上に
分割されつつある暗い世界の一つの小屋
そこでわたしたちの母は長い髪をかきあげる
力でなく心でどこまでも高く
モノクロームの禿山
そこは叩くところでないんだ
わたしたちの死せる父を埋める聖地
つねに
苦悩の虹・熱い滝
わたしたちの母は誠実だから次のものを見る
ランプの光に
殺虫剤のなかで色を変える染色体
セロファンで包まれた
乳歯
それがわたしたち・二十世紀のわたしたち
スピードを加えて水がながれる
岩棚が見える初出は《北海道新聞〔夕刊〕》(北海道新聞社)1964年9月7日〔7930号〕五面、本文新字新かな使用、新聞活字一倍扁平1段組、23行。執筆者名の後に「(現代詩人会会員)」とある。「え 田畔司朗[たぐろしろう]」。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
冬の森(未刊詩篇・11、14行)
3月
桃――或はヴィクトリー(⑥・8、28行)
11月
やさしい放火魔(⑥・9、71行)
初出は《朝日新聞〔夕刊〕》(朝日新聞東京本社)1965年1月5日〔28377号〕五面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、新聞活字一倍扁平17行1段組〔コラム〕、14行。絵「待つ・海老原喜之助」。
そのところに月は満ち
マスクした枯木の梢が楕円形に
ひとりの幼児を囲んでいる
火花の記憶のなかに
ささげられた食物の世界
この青みがかった幼児の内海で
肉をかぶっていく骨が見える
フクロウの金環の爪でさかれた
母の口は暗く
それは名づけようもない過去
未来とは羊歯のかたち?
鉤のウサギの血を吸う雪?
幼児は問いつづけ
ついに大声になる
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1965年3月号〔8巻3号〕二〇〜二一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字、カタカナの拗促音は小字)使用、五号15行1段組、28行。目次での標題は「桃・あるいはヴィクトリー」。
水中の泡のなかで
桃がゆつくり回転する
そのうしろを走るマラソン選手
わ ヴィクトリー
挽かれた肉の出るところ
金門のゴール?
老人は拍手する眠つたまま
ふたたび回つてくる
桃の半球を
すべりながら
老人は死人の能力をたくわえる
かがやかしく
大便臭い入江
わ ヴィクトリー
老人の口
それは技術的にも大きく
ゴムホースできれいに洗浄される
やわらかい歯
そのうごきをしばらくは見よ
他人の痒くなつていく脳
老人は笑いかつ血のない袋をもち上げる
黄色のタンポポの野に
わ ヴィクトリー
螢光灯の心臓へ
振子が戻るとしたら
カタツムリのきらきらした通路をとおる
さようなら
わ ヴィクトリー
初出は《無限》(政治公論社)1965年11月〔秋季・19号〕二二〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、20級19行1段組、71行。
夏ははげ頭なんか刈りたくないと
チャリーはいつも思う
まして少女のうぶ毛の口のまわりを
剃りたくないと考える
ミルクのみ人形の腹のように
いやらしい雨期をおもわせるんだ
理髪師チャリーは毎日
冷蔵庫の白い肌をふいていたいと思う
それはすきな消防車の鐘のように
爆発しそうな内臓をしている
猫へやる魚が死んでならび
コカ・コーラのビンはガチガチ鳴る
チャリーの求めてる冷たい水と
凍った不定形な涙
かつて少年だった記憶もなく
彼の記録は森林放火十四回
三十二才のチャリーは悲鳴をあげ
血のうえに母と妹をカモメのように
飛ばせている
永劫に新しい戦争写真
それから停電のなかの滑車の下降
髭のはえていることが大人なら
チャリーは酢の中の大人
カマスに喰われるイワシの毒性のない肉質
肥っていることが罪なら
チャリーの体重は零
頭は燃えるアメリカネズミの尾
火繩の円
ぐるぐる廻っているんだ
それは電気よりも精神的なもの
チャリーの呪う心は皮をはがれたウサギのように
他の人の厚塗りの人類愛からはみだして
けいれんする絵画
公衆を冷笑する
患部でなく全体的患部
他の人の観察できない
蜜蝋の赤
チャリーの逃げる劇
ひとつの鉄の柱から他の柱へ
アメリカの高層気流から
シナのさかれたフカの水墨の海へ
逃げるチャリーが見えるか?
他の人の心はマッチが擦られるほど熱くない
しかし今日この午後でも
やさしい放火魔チャリー・コルデンの
よだれは熱くしたたる
あらゆる現実の森林は火を産むさびしいしとねだ
タバコ・フィルター・セルロイドの函
チャリーの道具はどれも小さく
だれもが持っている日常性から
非日常性へオクタアブが替る
廃物芸術
チャリーの反商業主義の勝利だろうか?
サース・キャニオンの他の人の物干場から
とおく見える慰めの夜の火柱
チャリーは逃げることを拒否する
むしろ訪れる
むしろ静止
岩のセミの出来のわるい眼
見ることを禁じよ
生きる悦びの黒い枝々
牛乳しぼりの女と鳥がゆっくりと行なう
美しい死方
煙たなびく彼方の花嫁衣装
チャリーは頭の中の火
もえる翼 自己の火を消している
《外出のときは 雨具をおわすれなく》
《外出のときは 雨具をおわすれなく》
やさしい男チャリー・コルデン
亀甲のなかへの精射
雨期が近づくまで
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
春のオーロラ(⑥・10、41行)
家族(⑩・11、10行)
4月
静かな家(⑥・16、52行)
5月
スープはさめる(⑥・11、37行)
花・変形(⑩・14、Ⅱ節18行)
10月
ヒラメ(⑥・13、51行)
11月
孤独なオートバイ(⑥・14、102行)
初出は《風景》(悠々会)1966年3月号〔7巻3号〕五二〜五三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、41行。作者名は「吉岡實」。
わたしがいま描く画面とはなに?
生き方とは関係なく
運転手のくびを絞める
ひとりの少年の金メッキの脱腸帯へ
接近する
それは病気のなかでうごく
野生の桃
夏がくると白くぬりかえる
天使の顔
むしろ正面をむくとき
急にドーナツを食う老婆たち!
ひとりの少年を走らせる
桝のなかの桝?
デパートのマヌカンが腰から下を
溶かしている夜から朝まで
公害地帶の音楽は《マヘリアの祈り》
門へ至るところで
犯された姉のたらしている繃帶
わたしの未想像の画面から
独立して
巻かれている ずーっと下の方で
ひとりで少年がまたいで行く
黒麦の世界とはなに?
乳でやしなわれた大人の死ぬシャリ・シャリの楽園
肉が心でなく孔ある筒から出る
凍る都会の学校で
孔雀の母をころして
ひとりの少女が歩いてくる
《柳よ泣いて》を歌いながら
見える美しい止血器
病熱そのもの
モチーフそのもの
少年の縞ある心
その細部のなかの細部を
水平にまでもちあげて行く
少女の雨傘
それは大きな圓の復活!
サソリ座がぴくりと反ったのが見えない?
わたしと大人たち
とても悪い方法だが口のなかへ
アイスクリームを入れる
ぼくは生まれる初出は《文藝春秋》(文藝春秋)1966年3月号〔44巻3号〕八七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、8ポ1段組〔コラム〕、10行。作者名は「吉岡實」。
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1966年4月号〔9巻4号〕三八〜四〇ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号21行1段組、52行。吉岡は自作についての随想〈三つの想い出の詩〉で本篇を全行引用して、作品成立の背景を記している。
パセリの葉のみどりの
もりあがった形
ぼくたちに妻があることは幸せ
と叫んでいる男
それは洋服のなかにいるというわけではない
なおも酸性を求めて
高い青竹の幹の節々をとんでいる
クロアゲハの闇の金粉に
溺れているように見える
植物的人間
妻とはなに?
その食べている棚の上の
ママレードの中心
それぞれの夫の《ここに砂漠は始まる》
食事は始まる
詰りつつある壜のなかへ壜
しかも夕暮
息の上の
紅蓮の舌から見える
下る坂の鐘の舌は中世風に
まるまるとして
ひとつの十字架へ沿って降りて行く
ではニッキはどんな地上から
はこばれてくる?
愛する唇へ
ヴィクトリアのカエルまで雨でぬらす
子供二人を先頭にして
やってくるのだ
春の風!
これがほんとの抒情的なのか?
母のうちなる柱
その毛の描写できない六拍子
森と同化している
集まる鳥の
うわむきに黒い細分化した
蹠のなかの苦悩
結局 妻とはバロック芸術の花飾り
ほとばしることが出来る?
建物の正面へ
再び生きかえるツタの葉が見えるかね!
宗教的なステンドグラスの
永遠保存が可能ならば
まばゆく開け
散り行く量のなかに
大麦の種子
あらかじめ受け入れねばならない
夫が刷画をする
絹を裂く朱塗りの小さな絵
スギの木の向うにある
川をながれながれて行く馬と兵隊の
世界の静かさ
女中が一人帰ってくる
初出は《詩と批評》(昭森社)1966年5月号〔1巻1号〕二〇〜二一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号21行1段組、37行。編集担当者のひとり清岡卓行は初出誌巻末の〈後記〉に「創刊号は、詩作品の小特集となったので、一人二頁という窮屈な条件でお願いしたが、快く御寄稿下さった諸氏に感謝したい。」と書いている。 この雑誌掲載用入稿原稿(写真参照)で注目すべきは、編集者が記入したと思しい赤字による指定である。写真の解像度が低くて判読しにくいが、指定は原稿の小字や約物に対して施されているように見える。なお、出典のYahoo!オークションのクレジット「吉岡実詩稿 スープはさめる草蝉原稿用紙(32×20)3枚完」の「草蝉」は正しくは「草蝉舎」である。
吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈スープはさめる〉の雑誌掲載用入稿原稿 出典:Yahoo!オークション
紅紫のヒースの荒野へ
芝刈機をゆっくり
押してゆく
ひとりの老婆を見たことがある?
ノイズの静かな暁
それは製図家の青い消ゴムで
こすられる
〈肉にかこまれた星〉
ながれるコマーシャル・ソング
ファシストたちの死んでいる
沼地での夏
泳ぎまわるミズスマシ
天然色の処女の肉体は
事をすすめる
白い骨へやさしいキッス
すなわち老婆は姙み
任意のとなりへ横たわる
内部で起ることは外部にも起る
あざやかに長大なキュウリが採れる
さびしい村で
青いイボイボがその良心
痛がる黒い赤ん坊
じゃ愛が正しかったのか?
すすむ者と戻る者の
同時に通る
ホット・コーナーで老婆の発する
消音ピストル
存在する円をくぐりぬける
アルプの乳形の石
死ぬものがないときは
なかんずく人びとは高熱をだす
腕のなかの情婦もともに
水へ浮ぶコルクの栓
挟むものを変えよ
ひとりの老婆の臼歯の
生えそろう時まで
さめたスープは桃色の膜を張る
Ⅰ初出は《いけばな草月》(草月出版部)1966年5月〔53号〕三二ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ〔漢字:ゴチック、ひらがな・カタカナ:アンチック〕11行2段組、Ⅱ節18行。
初出は《凶区》(発行所の記載なし)1966年10月〔15号〕三九〜四一ページ「ゲスト作品」、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、51行、目次での標題は「ひらめ」。
ヒラメは海のなかで泳ぐ
信仰
たわむれに
捕えられるため
ぴくぴくうごく砂の浅瀬
貝がら類で
首までうずまる
老婆がちょっとほほえんだ
あれが合図なら
死ぬべきか?
生くるべきか?
波の下へ
老婆の腰巻が降りて行く
矢印の赤に沿って
反回転
ヒラメの両面が
すこしずつ滑らかになる
冷たく熱く
北から南から
ひきよせられて
二つの眼がひらかれる
ヒラメ
溺れる少年のばたばたする裸の脚
とてもガソリン臭い
射精のなかを
走るイカ
浮ぶストロー・ハット
浮ぶ涙
誰が死ぬのだろう?
この干潮の花の月の出
暗いトウフの半面
全体としては裂け目のふかいペルソナ
ぬげる黄色い水着
ぬけるマヌカンの手足
漂うコンニャク
ふたたび漂う
腰巻のなかへつきつける懐中電灯
はっきり見えた!
消防夫たち
役にたたない長いホースを
ひきずって行く
乾く海岸線
ヒラメは
平面な水墨世界で
ある種の口をひらき
ある種の毛をはやし
いよいよあいまいな形へ向う
岬の灯台のエロチックな光の下で
あいまいな心自体
そのとき
おそくとも夏は逝く
初出は《三田文学》(三田文学会)1966年11月号〔53巻4号〕三五〜三九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ21行1段組、102行。
海岸の砂地より少し高い平面を
廻っている
円形のコンクリートの床?
それは原色のヒトデのように
夏へ向う
青年の赤いマフラー
同心円が猛然と回転する
姙婦の多量発生の
春の終りへ感情移入!
よごれた個人の下着の見える
やがて夕暮れだ
機械の棒で操作される魂の中心を
一台のオートバイが走っている
一サイクルのスピードで
一サイクルのなかに
試みられる
円の癒着性!
孤独なオートバイの裸体
合成塗料のなやましい匂い
円の迷路へ
なだれこむ黄色いアネモネ
高鳴る水
〈くださいアスピリンを二錠〉
走る車輪
筒をぬける鳥
まず換気弁がぬれる
それから処女性のシリンダーが
潜在しているのがわかる?
機械がつくるさびしい関係を告知せよ
走る車輪の下のまだ青いバナナ
ささやくエンジンの愛
あるときは見える
検眼パネル
しゃべるしゃべるガソリンの口
しゃべらない沈黙の電気
走る気体
モーターの内部で
やわらかい真紅の絹はグラスをつつむ
白いヘルメットをかぶり
とてもたのしい衝突?
細いけむりが出る
精霊たちの裂かれるパンツ
そのはるか下を
四つんばいの父母の像
つるつるの頭の上で
読みあげる
孔の数
ベビーの死亡 出生率
貸借対照表
宗教の方眼紙の彼方へ
ばらまかれるレンゲの花
そして胆汁
抱きあった恋人たちが立ちさり
気まぐれな猫がはらみ
あるものが来る
あるものの他のものが見え
記号や畝のように
スタンドの青いサボテンのとげの絵
さかさまのサソリの鋏
ゆっくりひらき
切られる矩形の咽喉
すでにない前方から泡がこぼれる
ガラガラくずれながら
積まれてゆくビールの罐
全部叩かれる
男女の悲鳴!
水車に沿って
マンドリンの腹へ沿って
オートバイが走っている闇へ
次はマリンバや太鼓
まわる車輪へ白髪が発生し
ゴムのタイヤの象皮性を見せよ
ようするに破壊でもなければ
再構成でもない
空間を予想する
雨にぬれるオートバイ
グッドバイ
野獣のなかの締められたバルブ
少年の腰をだきたくなる
少女の脱脂綿にふれたくなる
孤独なオートバイのサドル
試みられる精神・金属の羞恥度
時間とはどんな白線?
同心円の反復から
停止する半円の透明度
出ていかないカニ
海岸へだれも近づくな!
走る心で
うしろへ戻って
ある日の暁まで廻るハンドルへ
美しい血が循環する
寒暖計
皮下溢血!
超スピードで出てゆくガラス
月光いっぱいにいま入ってくるイカ
女のオナニズムの
欲望のモーターの内部で
ホット・ケーキがつぶれるんだ
葬儀人夫の
わけのわからぬ連祷唱
テンテンテン………
孤独なオートバイが走る
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
内的な恋唄(⑥・12、95行)
2月
恋する絵(⑥・15、42行)
春の絵(⑩・12、13行)
7月
青い柱はどこにあるか?(⑦・6、51行)
8月
夏から秋まで(⑦・2、64行)
10月
立体(⑦・3、61行)
11月
マクロコスモス(⑦・1、70行)
初出は《詩と批評》(昭森社)1967年1月号〔2巻1号〕二〇〜二三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号13行2段組、95行。
殺人者のすきなストロベリージュース
とても赤くって
ガラスの器へ注がれる!
注がれる魂の花文字
きみたちが死ぬのが喜ばしい
かれらの停電の電車の函詰の墓が
しなやかにきみたちと
だき合って悩ましい夜!
エレベーターの上で
少女を絞め殺すべき契約を欲する
ストローでかきまわすんだ
うすめられて行く
夕焼の空のストロベリージュースを
きみの母の血でなければ
かれらの妹の植物化した直腸の液
ぼくは殺人者で
死にたがっている猫
電子オルガンが鳴っている午後を
黄金の肛門から出る水子
ぼくが水子で
きみたちが多淫な猫の腹と子宮
かれらが爆弾をはれつさせるんだ
氷の上へ
ソーセージの工場へ
ぼくの父の麻薬の舌の下へ
ぼくの弟は痴漢で冬のさびしい森を行く
《そこにはたくさんの女がいる》
眼をふせよ!
あらゆる建築物の裏側で
すべる砂のひびきが聞えるんだ
うずまくデコレーションケーキ
女騎手の咽喉がつまる
きみらのラッパ状の管もつまる
タイルの浴室へ
あふれるサンゴ樹
あふれる兵隊の星
ドラムを叩いてよ! 夏の夜を
飛ぶフォーク
食肉
匂いのつよいテッポーユリ
の全開期
ぼくが殺した運転手
きみらが殺した服飾デザイナー
かれらが殺したミス・シナ
テーブルの円をまわり
沈んでくる秋の霧
自然な状態で上むくスプーン
とじられる唇
映画のフイルムのなかで
とじられる独裁者の
手術の巨大な胃袋の傷
時間をかけて
溶かされて行く
女への愛 樹木への愛
交尾する犬への愛
蛮国への物質的な血の愛
今夜十時から臨時ニュースがある
ぼくが殺人者になった
喜ばしい食事時だ
水を吸いあげる母の涙の魚
ナット・キングコールの唄
教会音楽風な
神秘なブルー一色の
矢印の緑の一日
ぼくの不倫がつくる
麦畑へ
きみたちが火事をみちびく
ついでにけしの畑まで
灯る人家を焼き
密通した人妻の
幼女のマヌカンをぼくは抱くだろう?
糸杉の狂える夜ごと夜ごとを
きみがぼくを殺しにくる
ささやく泡のながれのなかから
ストロベリージュースの
甘い鼻の上
ソファーの灰色をけばだて
かれらがきみらを殺しにくる
ぼくの便秘が
きみたちの空腹へ通ずる朝まだき
かれらの石油くさい岸から
他国へながれでる河とニワトリ
子供は育ってはいけない
むしろ生れてはなお罰せられるんだ
妻が夫をうけ入れるとき
花火が凍る
闇の空
夜それとも真昼
ぼくらの終りの合図?
水時計のうごく水
漂う秒計
唐草模様のうごく枯葉
ぼくは気も狂わないで生きている
きみたち・かれらも
ガラスの器のうごく蜜のように
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1967年2月号〔10巻2号〕二八〜二九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号1段組、42行。
造る生活
造られる花のスミレ
ばらまかれたあるものをはさむ
洗濯バサミ・洗濯バサミ
それは夜の続きで
水中の泡の上昇するのを観察する
恋する丈高い魚
白いタイルの上では
考えられない黒人たち
その歯のなかの蜂
雨ふる麻
ぼくがクワイがすきだといったら
ひとりの少女が笑った
それはぼくが二十才のとき
死なせたシナの少女に似ている
肥えると同時にやせる蝶
ひろがると同時につぼまる網
ごぞんじですか?
ぼくの想像妊娠美
海へすすんで行く屍体
造られた塩と罪の清潔感!
幼時から風呂がきらいだ
自然な状態で
ぼくの絵を見ませんか?
病気の子供の首から下のない
汎性愛的な夜のなかの
日の出を
ブルーの空がつつむ
コルクの木のながい林の道を
雨傘さしたシナの母娘
美しい脚を四つたらして行く
下からまる見え
そこで停る
東洋のさざなみ
これこそうすももいろの絵
うすももいろのビンやウニ
うすももいろのミミ
すすめ龍騎兵!
うすももいろの
矢印の右往左往する
火薬庫から浴室まである
恋する絵
梨[なし]の畑で初出は《讀賣新聞》(読売新聞社)1967年2月5日〔32455号〕一八面、本文新字新かな使用、7.5ポ1段組、13行。本文の後に「大正八年東京生まれ、筑摩書房取締役。昭和三十四年詩集「僧侶」で第九回H氏賞受賞。日本現代詩人会員、鰐の会同人。」とある。
初出は高井富子舞踏公演〈形而情学〉チラシ1967年7月3日、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、12ポ1段組、51行。吉岡は自作についての随想〈三つの想い出の詩〉に本篇を全行引用して、「飯島耕一の紹介で、土方巽を知り、初めて暗黒舞踏の「ゲスラー・テル群〔論〕」を、草月会館で観て、衝撃を受けた。〔……〕以来、私は親しい芸術家たちの肖像を、数多く詩で描くようになった。それだけに、最初のこの詩は思い出深いものがある。」(《吉岡実〔現代の詩人1〕》中央公論社、1984年1月20日、二一〇ページ)と書き、《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》の冒頭〈1 青い柱はどこにあるか?〉にも全行を引用して、「この一篇は土方巽の求めに応えて書いたものである。〔……〕或る日、奇妙なポスターが送られて来た。舞踏公演「形而情学」のもので、中央に朱塗りのタバコとビー玉が入った函が付いている。そして別の紙袋の中には、加藤郁乎の詩と「青い柱はどこにあるか?」がインディアン・ペーパーに印刷されていた。」(同書、筑摩書房、1987年9月30日、六〜七ページ)と書いている。なお、本篇以降の詩集《神秘的な時代の詩》(湯川書房、1974年10月20日)収録の各詩篇の引用詩句については《吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈》を参照されたい。
闇夜が好き
母が好き
つとに死んだカンガルーの
吊り袋のなかをのぞけ
テル・テルの子供
ニッポンの死装束が白ならばなおさら
青い柱を負って歩き給え
円の四分の一の
スイカのある世界まで
駈け足で
ときには
バラ色の海綿体へ
沈みつつ
犬の四つ足で踊ること
かがまること
凍ること
天井の便器のはるか下で
ハンス・ベルメールの人形を抱き
骨になること
それが闇夜が好きなぼくたちの
暁の半分死
ある海を行き
ある陸を行き
ラッパのなかの井桁を吹き
むらさき野を行き
ふたたび闇夜を行く
美しき猫の分娩
そのしている夢
そのうえしてない行為
ぼくたちはどうしている?
すべてに同化する
末梢循環の恥毛性存在!
消えなん横雲の空
鋼鉄のビル・ビルの春
ビー玉の都市
そこにサクラは散るや
散らずや
赤い映像とは肉体の終り
ガニ股の父が好き
心中した姉が好き
古典的な死の隈取
闇夜が好き
かがり火が見えるから
大群衆が踊り狂っているんだ
亜硫酸ガス
濃霧
予定のない予定?
黄いろの矢印に沿って
柱に沿って
形而上的な肛門を見せ
ひとりの男が跳ねあがる
一九六七・五・一五
この作品は吉岡 実氏が土方 巽におくったものです
初出は《文学者》(文学者発行所)1967年8月号〔10巻8号〕二〇〜二三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ17行1段組、64行。
池 田 満 寿 夫
銅版画展目録より
レインちゃん 黄色い舌をして
素敵なソプラノの花嫁
それはなんですか
何にする非生物
花のクチナシ
木の机の下で
観念する
夏
聖なる川の楽園に死す
足なえの夏
鏡のうちの青
はずむブルーの球
カメがかむカヤツリグサ
四つ手の網のうえで
S字型のマス
わたしは食べたくない
姉妹と関係したくない夢
わたしはネコを抱く疑問符の人
すべてのものを満喫したくない
あらゆる壁を剃る
血を剃る
ころびたい愛
曲りたい矢印!
水からさきの水
道からさきの道
涙からさきの眼のランデブー
影からさきの影
具体的な物
賛成!
庭をよこぎる
メタフィジックな牛乳配達自転車
あるいは蛾
レインちゃんおしっこをして行きな!
横たわる人とみつめる人の
前で
ミシンのように
はずかしい
花嫁の領地を占める
ビタミン青空
母なるミカンの房
レインちゃんこぼしちゃだめよ!
赤いセーターをぬぐ
日まで
オムレツをつくる男
オムレツらしきものをつくる男
はずかしいオムレツをつくり
急ぐ人
ホタルの闇で
肉の入らない記念碑をなでる
秋ならススキがなびく
レインちゃん 靴下のまま
そこで何をみがくの
つかのまの亀甲体?
吊天井の恐しい花嫁のスカート
円を縮小する方へ
すすむ矢印
沼へ沈みゆけ
老婆の乳母車群
めずらしくむらさき色の
渟る矢印
電気ウナギを釣っている
男と同時に見える?
両側へ紐をたらしつつある
神祕的な靴が――
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1967年10月号〔10巻10号〕六二〜六五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号21行1段組、61行。編集人・八木忠栄の〈1967年 日録〉の「8月28日(月) 晴・雨」に「筑摩書房へ行き、吉岡実から詩2編〔註:「立体」「青い柱はどこにあるか?」〕もらう。」(《「現代詩手帖」編集長日録 1965-1969》思潮社、2011年9月15日、一〇三ページ)とある。
真夏の午後でも
彼らは紳士だから
室内を歩き廻らないだろう?
フロックコートの正装で
立っている
次のドアをひらいたら
ネズミの死骸が少しずつなだれこむ
にちがいない今日の在り方
別のドアを出て行く
ふとった蝶
ひげのはえた紳士が
蓄音機の把手をぐるぐる廻すんだ
暑い夏を暑くするために
ギイギイ音をたてる
なお想起せよ!
破瓜・分娩音
彼らは紳士だから
フロックコートのズボンをぬいで
出窓の端から投網をくりかえすんだ
ずるずるひろがる
暗い網の底から
錯誤の未来性
両の乳房をつきだして
花嫁があらわれる!
十字の紅い割れ目
彼らは停ったままの腕で
蓄音機のラッパを抱く
真鍮の花
相談する瞑想する
喋らずうごかず
意思が次の波を呼ぶだろうか?
伝達のない世界へ
テーブルの上で
化石の鳥が化石のリンゴの囲りをとぶ
化石の鏡がやわらかい出来たてのパンを映す
化石の矢がやわらかい子供の首を刺しているか?
そんな時はすぎる
彼らの泥の瞳
彼らの飼っている泥のライオン
泥の書棚
それは可塑物?
夏の暖炉で燃える敷物の道
彼ら汗をたらしながら
心を凍らすべく
一つのカンバスに描くんだ
花嫁のほしいままなる曲線を
走る矢印
オレンジ色に燃え
ながれる中心から
同時に縦から横まで
秘密のよろこびの声を明らかにする
内視の肉を輝かせよ!
内耳の霊の秋
その向うを
漂う湖
朝鮮アサガオの雨の朝がくる
彼らは紳士だから
フロックコートの正装のまま
存在するために
共同幻想体として
スイートな金魚鉢を支える
初出は《三田新聞》(三田新聞学会)1967年11月22日〔1146号(創刊50周年記念号)〕九面、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平35行1段組、70行、「イラスト/廣瀬俊恵」。――略歴の記載あるも、誤記・誤植多く引くに値せず。
石の建築物といっても永遠
ではない二階から上は
紫の窓
なでられている
ビーナスの尻が見え
戸棚のパイナップルのザラザラの皮が
精神を支配する
洗濯屋が汚れたワイシャツを
もってくる正午
四階に住んでいる
画家と犬はなんだろう?
白塗りの星條旗の下で
叩かれている犬
写真に撮られるべく
ハンバーグを食う
タライのなかの黒人
ぼくらの現況の雨の葺原から
暁の丘に至るまで
シナの娘が大鎌を振って行く
馬のながい陰茎の岸べ
かくすハハコグサ
タケニグサ
自慰観音
心はつめたく地は熱い今日
だんだんと殖える
水のなかのトンボの印
八月の暑い恋びとたちの
コルクのセンを咬む愛
ではどうしよう?
肥大漢のぼくらの姉妹
双生児を生みに行く
長いボール紙の筒があるかね?
それを廻って
ぼくらの肥大の子供は遊ぶんだ
ダンダン畑から採る
輪切りのパイナップル
食べる桃色の人食人種
考える口が見える時まで
だんだんにふとるぼくら肥大漢の兄弟
キリコの木の頭の点線の十字へ
赤い布をかぶせて
白夜の白衣の父なる医者
椅子の上へすわる
異物分娩開始!
たまたまクロブタが鳴く
今夜だれか死にましたか?
スズカケのシームレス靴下の下で
答えて下さい
人のしてないことを
考える人
人のしているあらゆる行為を
善なる悪なる共同幻想
燃えやすい耳
夏のキノコ
鳴けよブルーカナリヤ
空とぶ黒色の
終りの矢印
想像する
紅潮する戦車
そのなかのかずかずのスワン
ヨードチンキの臭う夜を
印刷された死体の極彩色
明くれば涼しい風景を眺めよ!
ぼくらの豊饒な草むら・枯むぐら
粘菌性のマクロコスモス
千紫萬紅の高千穂の峯をふりかえり
鳥肌の世界を反省する
棒高跳選手
バーを越えるとき
不條理な鉄の処女を感じる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7月
フォーク・ソング → フォークソング(⑦・7、45行)
8月
色彩の内部(⑦・4、43行)
スイカ・視覚的な夏(⑩・13、15行)
10月
神秘的な時代の詩(⑦・11、103行)
崑崙(⑦・8、150行)
11月
雨(⑦・9、66行)
初出は《同時代》(黒の会)1968年7月〔23号〕四二〜四四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ18行1段組、45行。目次での標題は「フォークソング」。
むらさきのスミレが咲く
マダム・トラコーマはすきな形の
舟をみつける
その下は水でなく
ダイナミックに煮える粥のような波
たよれる
たよりになる棒とは?
どれほどの太さと長さを持っている人
ももいろのビニール製品の
たくさん垂れている
向う側とはどんな凹面? 突起態!
どんな赤ん坊が産まれているのかね?
梨籠のなかの甘いビラン体
カルシュウム乳
もしくは釘
ナチスの制服の人型の空胴の青空を見よ
つるべうちにうたれた
兎のそよぐ春風の毛の下で
国家治安のために
花嫁たちがたれながしのまま
双生児をうむ
ながれる舟のなかに
発泡状の球体群
空は暗い菱形に見え
バロック風なナベから
立ち上る
雄鶏
よく見れば
鉄製器具の寄せ集めでつくられた
危機の蝶番の結合
赤塗りのトウモロコシの
とさかをなびかせよ!
復讐とは
ねじること
それぞれの夕闇へ
コウモリをとばさんとする
処女の子宮をふさがんとする
灯る内装芸術
タクシー乗場から軍艦の丸窓まで
夜目にもしるく
金色の矢印をつける!
この前兆的なる
内的構図の終りか?
動くインテリア
ヒバリがしきりと鳴きのぼるとき
初出は《the high school life》(MAC)1968年8月〔15号〕一〇面〔コラム〈えるまふろじっとのうた〉〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平1段組、43行。
ピンクの空間へ
ダイビングする四頭馬車
方向指示の黄色の
矢印のとどかぬ世界で
鳴く夏のフクロウ
まぶしい眼
網のようにひろがる円
その中心へ近づく
幼児の便器
母より恥ずかしく
看護婦の白衣のなかにつつまれる
わたしたちの知っている
傷ついた馬
長い年月の腸
はかない花
みじかいホウタイ
笑ってはいけないかね?
まして泣いては
肉屋が来る時代!
注射器の針が
刺しているわたしたちの
あらゆるところ
あらゆる孔のある皮
精神
かがやく鏡
あえぐ葦
にくにくしい肉体
走ってはいけない?
解剖図のある暗い部屋から
グリーンを走る
手足のない水着類の干してある
クスノキの下まで
生きているとはどんなこと?
恋にこだわり
はねる水
吐く闇
はるかな白骨
すべての事物を想い出せ!
そして今
クジャク尾のうしろへ廻って
喚起する
なまなましい藍いろの
表現愛
スイカを割る初出は《讀賣新聞〔夕刊〕》(読売新聞社)1968年8月19日〔33015号〕七面〈八月のうた〉、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、新聞活字一倍扁平1段組、15行。「写真・橋本彰禧記者」。
初出は《季刊藝術》(季刊藝術出版)1968年10月〔秋・2巻4号〕一一六〜一一九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ27行1段組、103行。吉岡は1968年10月10日の日記に「〈季刊芸術〉七号届く。「神秘的な時代の詩」掲載。」(《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》、筑摩書房、1987年9月30日、二四ページ)と書いている。
走っている電車のなかで
白昼いそいそと
わたしたちは見るんだ
いくつもの白塗り頭のマネキンたち
なめられるアメの棒
青と赤のウズマキの上昇する
アンモニヤ
密教芸術
妄想してはいけないかね?
両手をつく青年たち
さかだちの母なる獣
だんだん垂れる
トイレットペーパーの王道
夜は見えないから
乳色の矢印にみちびかれ
肉のようなものが甲羅のなかへ
入って行く
それは天然の美
よみがえるメロディ
シナの枕はどうしてあんなに長いのか?
神秘的なほど重く
よこたわる
弓張月
マタニティ・ドレスをひらひらさせて
老婆のむれ
ミシンの針のように進んで行く
どこか?
どこへ
わたしたちの自意識自滅の
闇の砂漠の三千世界
ここから恥入るべき
現代の凱旋門
すばやくすき透る
チェリー・ピンクのありあけの
静かに成長する
美しき夫人の
かがやく鐘乳洞
しみじみとさわり
しみじみと仰ぎみよ!
金属の含有する方形の気孔類
そこにいかがわしい十二変態のサナギ
腐るものから腐らぬものへ
変らぬものから変るものへ
着色マッチをすりつつ
恥らう楕円のなかの裂け目で
黄金をみつけるか?
死の塩の商人
ふとることを恐れる
ももいろの飛行機
ももいろの影
トラコーマの眼
密通
密着美人
燐光塗料のかつらをかぶり
マリリン・モンローの肉体はちぢんだ!
殺到する覗く人たち
わたしたちの言語のなかで
腐るもの・変るもの
永遠の明暗のなかで
痛むもの!
くびれた存在の痔
広告用ビーナス
天竺牡丹
やがて六月へ
自動車の中でそよぐ脚
公園の石獅子
記念写真ですかこれは?
ニンジンを抱いて
死んで行く
黒人と恐龍
それは夢かまぼろしか?
群衆の中の腰巻きの海軍旗
口にくわえた鎖の女
芸術的胃下垂
おお陳腐!
今日 生卵の黄味のゼリーの表面に
一篇の詩が印刷される!
未生児のむらさきの眼も
わたしたちのテープの走り込んで行く
小さな鉄のボックス
出る音楽
出る木の芽
出るオバケ
血の出るテープ一万呎をなびかせて
は寝る姙娠可能の少年たち
いかがわしい蘭のからまる少女たち
夜景をまわる夜警たち
その市松模様
暑い夏がくるまで
蛇行セレモニイ
黒くなるべき孔雀
白くなるべきポスター
いつ赤くなる?
フライパンの上でマカロニの孔
すべての肉はアルミ箔で包まれた!
河へながされる汚水の
野菜類
じゃ終りかね?
金看板
来たるべき絵画
来たるべき時
わたしたちの有罪期の
半跏思惟像!
初出は《南北》(南北社)1968年10月号〔3巻10号〕六〜一三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ四分アキ20行1段組、150行、目次には「長詩」とある。
では未経験的なピンクの空間へ
ダイビングする
四頭馬車の喪服ずくめ
さかさまになる
四つに分けられた馬の頭は見えず
きみは驚き
ぼくは悲しい顔を剃り
きみの彼女はふとる
墜ちるにはふさわしい水面
ぼくの彼女が笑う月
じゃだれがトップで死ぬんだろう
母の恥しい腹のなかにいる
ぼくかしら?
妻の詰った子宮から出てくるきみかね?
ほんとうのことを云うべきだ
生まれるより先に死ぬべき同行者・同義語
きみの彼女が父の尻の孔の奥まで戻る
これは一種の自負であって
生でなく死でもなく
赤いネオンの透明なはかない消滅法
車輪がとんで行く
めもさめる型式美
とざす障子の桟に巣食う鳥
来るべき潜水艦が丘を越えて
迷宮入り
忘れられているのではないだろうか?
ぼくの彼女の主知的に
あまもる唇
類型の多い死ではないかね
贋金
先頭をだれが行く
ぼくの足の赤い鼻緒のゲタ
きみの胸のエンドマーク
きみの彼女のタワーのようなヘアー
ぼくの彼女のアミタイツの脚
たりない人体
四つの部分で真の人間は出来ていないだろう
すくなくも一万部分の集積
あるいは九個のフラスコのミカン水
ビニールのような耐久性と劣情を示せよ
在るべき時間とは
在らざる愛のこころ
在るべき空間とは
在らざる光線銃
ここはどこか?
ここは深くも浅くもない軟着感!
ぼくの彼女が至りつく
冬のフトンの果て
まっすぐ歩いて
くびれた母型を認識し
似たような荷物をみつける
なにが入っているかもわからぬ観念
歯型
電子音楽
ムラサキ
未来の
愛
ではきみの彼女の運命とは
それは生まれる
むなしい稼業から
もり上ってくる
非情緒的な廃品同様
むしろなんでもなくなりつつある
周辺をかこんで
イチジクの葉
かくすラクダのコブの相似性
同円のスリ鉢叩いて
日常言語の床屋の白い布を裂く
記号の罐
開かれる開かれる
自在に無意味に赤い床から天井へ
横断する横断する
電気芝刈り機
ニクロム線の庭
静電気
そのもののウェーブで
カメをくすぐる彼女たち
玉鳴るソロバン
ハプニング
ハッピー
はるさめ
煙突掃除用ブラシがススでなく
幼児をこするものへ
変化する
壁を掻く老人たちとうとう壁をつきぬけて
けむりを出す
魂と秋
女は自身の手でなにを変える?
虹彩の遊び場で
女はもろもろの疑似割れ目を表現し
毛のはえた裁ちバサミで
紙テープを切る
そしてダンス
そして銃殺シーン
そしてそして想い出を想い出す
まるくまるく
ハリネズミを追いつめ
恍惚たる少年の藍をあびて
水槽では血気の尻
さめるサメ肌をふるわせる
共謀的彼女たち
めざすメザシの
目をつらぬく矢印
死への
橋がかり
金切声
さらにとどろくぼくらの白骨期
真鍮の棒で砕かれる
あるところへ戻ったら
形が変り色が変る
物が物をのむときは闇
吐くときは光るか?
彼女らはすべて見えずと反対のバラのトゲをつかむ
これが芸術だ
それは偶然の自律自慰!
肉色をしていることが
罪悪ならば
ぼくたちになにができる?
藁の上で
肉色の幽霊と化して
にもかかわらず
そのうしろに眠るきみの彼女の螢光体
なめるなぐさめで
分裂するきみの水色の舌
ハンバーグをつくる
ハリボテのハンバーグをつくる
そしてぼくの彼女はヌード
清掃車がくる
起伏がくる
水葬の夜明け
ももいろの回虫の環境
ももいろの夢
凍結がある
そこでぼくらは行く
写真のなかで永遠に
首を吊られている人の下を
真夏の反現場性の海の輝く
金輪
サイコロ
過去からカブトガニの内部は
はたして
うごいているのかゼリーのように
ピンクから白色の世界へ
むしろ次から次へと変革している
そうしてうずまき模様の
ののののの
のたれ死を承認せよ
ノオ
今日ぼくたちにも存在しないだろう?
崑崙!
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1968年11月号〔11巻11号〕三二〜三五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号20行1段組、66行。編集人・八木忠栄の〈1968年 日録〉の「10月7日(月) 曇・雨」に「筑摩書房近くの喫茶店で吉岡実と会い、詩「雨」をもらう。このところ調子が悪かったというが、とてもいい作品だ。「いつも題名に困るんだ」と吉岡さん。」(《「現代詩手帖」編集長日録 1965-1969》思潮社、2011年9月15日、一七一ページ)とある。
それはたとえば
老嬢ルイズ・ニーヴェルスンの
スイ星の球のつまった
箱をさがすように
レインコートの黄色の美人がすきだよ
だからトウモロコシ畑のうしろへ
廻って
赤毛のやさしい愛撫から
少年がぞろぞろ出る
こんなにノビのきく夢
ビニールの紐がどこにある?
知覚できる具体的メカニックの世界から
ひとつの堅牢な白い箱をしばりあげよ!
踏台のように
他によりかかる映像がないので
中世の女のように
しゃべらず
黄色のレインコートをぬぎ
それにほそい脚を
かける
あまがける!
箱の下はいまなお血生臭い戦いの世界?
或は老人たちのあそんでいる砂場?
それともススキの茂る情死の腐爛期
どうでもいい日々
肩から乳房までさらして
その女は大きく股をひらくんだよ!
では灰かぐら
箱は水面へ泛びあがり
なによりも流れる
罪ぶかい行為とは空間を穿つこと
関係のない物体や言葉を
同次元へ置くこと
であればこの白昼のなかで
ザクロの粒々の
果肉がはじき返えされるんだ
太陽から遠く
金属の小さな柱の森へ
たのしんでいる鳩
たのしんで叩くピアノ
たのしんで突つく浴室の孔
老人になる日まで永遠に
にがにがしくスパイとして
具体性のある物をつくり
肉色の箱を担いで歩く
それの内側は金色の塗料ですみずみまでぬられ
回復できない肉体の周囲
パラシュートの兵士は宙吊り
女の帽子が風でとぶ
その単位
その恍惚の夜は
同時にくるか同時に戻る
トーテムの上で泣く幼児の声を聞く
火をくぐる美しい女の腰
建築物の空間の
あらゆる余白を横切るものはなに?
それは音楽?
それは暴力的な甘い蜜?
痛みまで感じる
黒髪のゆたかなカーブを見よ!
はみだしたものはくびれ
平らな面は割れ
秋のあかつきがくる
箱は黒色の角を緊張させたままぬれる
いつからと問うことはなく
雨のなかに
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
少女(⑦・5、45行)
2月
スワンベルグの歌(未刊詩篇・12、34行)
3月
三重奏(⑦・17、71行)
4月
蜜はなぜ黄色なのか?(⑦・12、30行)
5月
序詩(未刊詩篇・13、3行)
6月
序詩(未刊詩篇・14、2行)
8月
夏の家(⑦・13、39行)
10月
わが馬ニコルスの思い出(⑦・16、*印で5節に分かつ163行)
11月
聖少女(⑦・10、22行)
12月
ヘアー → 鄙歌(⑩・15、26行)
コレラ(⑦・18、97行)
初出は《血と薔薇》(天声出版)1969年1月〔2号〕一四〜一五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、45行。
客観的状況で
塩がほしいのよ!
ぬれたハイヒールをさかさまにして
その尖筒をなめるとき
晩夏の街にはどんなモモイロの少女がいるのか?
言葉を犯罪的に使って
紅色の闇へ
イタリア貂を狩りに出る
ぼくたちにとって
死はとりとめもなく
自動ドアを入る
肉をラセン巻きにするガードル
まばゆい丘の上で
馬の交尾
その影のしていることが
暁の彫刻?
血豆の大理石
マンダラ模様の千羽鶴
そこから少女は成長するんだよ
樹と外套でかこわれて
少女の夢のはらみ方
すきなエクレヤ
ブルガリヤ人の男根
きわどいレールを
バクシンする蒸気機関車が正面から
入ってくる!
呻きの乳色の霧
まるで虎刈りの老人がきたのよ!
ほそいほそい靴下をぬぎながら
口をふさいで
血の波紋の少なくない世界へ
毛の捕虫器かざし
モモイロの柵に
だんだんよりかかる
だんだん裂ける
蜜房はなぜいつまでも黄色く苦く
夕陽のように
一つのゲームの終り
浴室で裸になって
今宵から花嫁たらんとする
心なき少女の自己誘拐
ぼくたちにとっていかなる痛みのビラン体であるのか?
声する恋の夕暮れの
家のなかで顔を巻く包帯をとけ!
格子が見える
初出は《婦人公論》(中央公論社)1969年2月号〔54巻2号〕の〈MY POESY まい・ぽえじい・2〉〔PETIT PETIT(プチプチ)のコーナー、二二○〜二二一ページ〕、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、8ポ20行1段組、34行。「イラスト・前田常作」(スミ・アカの2色刷)。註記「※スワンベルグ〔以下なし〕」。のち、《ユリイカ》(青土社)1973年9月号〔5巻10号〕の〈吉岡実新詩集 神秘的な時代の詩・抄〉に改稿再録(一六八〜一六九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ26行2段組)、末尾「注記/詩集『神秘的な時代の詩』は、ここに掲載された作品のほかに、すでに思潮社版『現代詩文庫14・吉岡実詩集』に収められている「マクロコスモス」「フォーク・ソング」「夏から秋まで」「立体」および、現代詩手帖に発表された「わが馬ニコルスの思い出」などを含み、湯川書房より刊行される予定である。」
ものの成熟について
ひとは考えるべきだ!
桃が籠のなかで
甘いビラン状になるとき
老人司祭の死の舌が必要か?
ひとりの男と女の恋
暁の熱い舟をつくり
そこでももいろの花火をかぶる
それらはきっと
すすまず浮かばず
聖なる母の毛のかたまりをすべる
星も輝かない
ももいろの氷の世界
ももいろの中年
ゆがんだ弓なりの
やがて美しい五月が来るだろう
緑の布の上に
両側から吊される
なよなよとした双曲線の乳房
青空の孔から
ああなやましく
想起せよ
花模様の一角獣
水をたらす
ビニールの漏斗で
ももいろの電話機の声
それから深夜
それからレモン
それから涙
暗い靴下をはいて
さびしい少年が来るんだ!
遠景の円柱を廻って
包帯のなかの処女性を
求めて・・・・・
※スワンベルグ
初出は《本の手帖》(昭森社)1969年2・3月号〔9巻2号〕七〇〜七三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、71行。
わたしは自分の描いた絵を
見てもらいたいので
女友だちを家につれてくる
その女友だちはバカにして笑つた
わたしの絵は観測というものでなく
むしろ昆虫群
わたしは女友だちに絵の構造を説明すべく
本物を見せる
それはピンクの長方形
やわらかくなると同時に
寒ざむとキララ色の袋に収まる
その繩文模様
この夜のムーヴマン
だから愛とは熱く
油絵具のなかにたむろして
出る骨をくるむ
女友だちは絵よりも蝋化した
観念がすきだといつて
わたしのベッドを塗り変える
それがヴァイオレットなら
ヴァイオレットの乳房
鉄の歯のようなものを
によきによき生やす
絵としてわたしが描いた心
低い空でも処女は犯せるか!
鉄砲ユリの奥は深く
わたしの絵はぬれることを知らない
表面というものがない
闇を所有しているわけでもないから
すくなくともわたしには持ち歩くことができる
おそらく女友だちには
それはできぬだろう
絵のなかの馬がそれを拒む
母が息子を拒み
息子が父を拒み
サボテンが露を拒むように板の下を
日と河がながれる
わたしは淋しいことは絵に告げ
死にたいときは
絵のうしろを歩く
そのときはきまつて
暴風雨がくる
女友だちは明日は帰つてゆくだろう
彼女の行手に立ちはだかる
わたしの絵のなかの森の道へ
女友だちが手をひく
娘のような妹は悪霊だな!
こちらをふりかえつて
鼻血をたらす
わたしは便所へかけこみたい感じだ
彼女たちの前で
なぜわたしの描いたものを絵といつたのか!
それはすみからすみまで肉化
されたものであつて
輝やくバクテリアではなかつたか?
細い管と太い管で編まれた
長い長い人生のトンネルかもしれず
光学的には暗く
建築的にはもろく
自然的にも不自然で赤く
わたしが無意識的に模倣している
女友だちのこれから
作りつつある再生芸術だろうか?
彼女たちが午餐をすませて
水着で泳ぐのを
わたしは見に行くんだ
女友だちの娘のような妹の
孕んだ腹を裂くよ
夏とはそんな一日であることを
感謝しながら
みずみずしい帚を買つてくる
初出は《郵政》(郵政弘済会)1969年4月号〔21巻4号〕一四〜一五ページ〔コラム〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ1段組、30行。目次での標題は「蜜はなぜ黄色なのか」。執筆者名の後に「(現代詩人会会員)」とある。
蜜はなぜ黄色なのか?
永遠に
瞑想的でなく
愛することでもなく
虎のように
フォルムを所有する
秋の青空はあくまで疾走し
眼と眼は暗く
向きあった男と女の立体感覚!
内臓へまでとどく
四つの腕の様式美
求めている唇のよだれ
それらのただれ
紅葉の錦
いま近づけば発火する?
格子を出てゆく金蠅
かくてモノトーンの夜を
なまめかしい水槽で
恋する幽霊
水の回転する泡の苦界の
男声・女声
ながながと哭[な]く老婆
ながながと鳴くウグイス
白地に赤く
燃えるランジェリー
燃えるフロア
コカコーラの罎[びん]のうしろの沖を
走るあらゆる船は静止し
蜜のような物質で
徐々に包まれる
初出は寺田澄史作品集《がれうた航海記――The Verses of the St. Scarabeus》(俳句評論社)1969年5月15日、〔八〜九〕ページ、本文新字使用、9ポ1段組1行アキ、3行。作者名は「吉岡實」。《吉岡実全詩集》に未収録。
うんすんかるたを想起させる
和洋折衷の精神と色彩をもつ
微小にして壮大な浪漫の世界
初出は志摩聰句帖《白鳥幻想》(俳句評論社)1969年6月1日、八ページ、本文新字使用、9ポ四分アキ1段組1行アキ、2行。対向の九ページにイラスト、「飾画 大沢一佐志」。《吉岡実全詩集》に未収録。
白地へ白く白鳥類は帰る
ありあけの美しき紫肉祭
初出は《ユリイカ》(青土社)1969年8月号〔1巻2号〕七六〜七七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、39行。
森のアオバの下に来て
双頭の美女と逢びき首びき
考えてもみて下さい
花飾りの下着の太い胴廻り
そのなかで落下蝋石!
それはよいともわるいともいえない
子供の描く絵
露のつらなるはずかしい
夏の男と女
すべる多面体
狭い入江の奥へ至る
笹鳴る夕べ
わたしはアンチ・ロマンに食傷して
そぞろに思う
トリカブトの毒
スダレ・ふうりんの夢
入日の都市では
棒こそかりそめの永違よ!
ブルーの髪をなびかせて
とびあがる
モッブのおさげの女生徒たちを押えて
球なす汗の陰蔽だ!
長い地下道を通過する
貨車や
影の火薬
もしくは仕度の了った死体?
南が曇れば北上する
暑い日
花嫁のかつらをかぶって
泳ぐ人
今を時めく
双頭の老婆を
正面から抱く人
ミスティックな水の音
ミモザは茂り
暗い菊形のパラシュートで
淋しい家の梁から
わたしはほそいほそいランニング姿で
おりるんだ!
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1969年10月号〔12巻10号〕三六〜四三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、*印で5節に分かつ163行。編集人・八木忠栄の〈1969年 日録〉の「8月25日(月) 曇」に「筑摩書房へ行き、吉岡実から詩「わが馬ニコルスの思い出」をもらう。170行を越す力作。」(《「現代詩手帖」編集長日録 1965-1969》思潮社、2011年9月15日、二四四ページ)とある。
花咲くスミレの墓地で
わが馬ニコルスは快心の脱糞する
それからかるがると
あらゆる死体をとび越えた
その荒野に
言葉が必要か?
それとも主題なき愛の労働がのぞましいか?
そこには底なく
負目のみの
蝋の道の続きだ
夏の嘆きのふかい沼地
紫紅の下着の
女生徒たちのハイキングの賑わいよ!
白いストッキングに覆われた
かたい両腿の跳ねるたび
わが馬ニコルスは呼吸を止め
歓喜し
熱い鉄の蹄鉄をはめて
ずーっと遠景まで
シナゲシを越え
水晶を砕く
死都の一部が見えるよ!
わが馬ニコルスのキララで包まれた陰頭が青空へせり上る
痛みの金櫛でこすられて
自立し
転調する
地獄より暗い地上で
一度は見たい桃いろの植物群
そのなかへ
時間錯誤にかかわりなく
群衆を匿せよ!
そして瞑想
擂鉢をする疑問符の人
白地に赤く死のまる染めて
みにくい未来へ
わが馬ニコルスはギャロップ!
*
雨にぬれて恐ろしい緑の
葉はちぢれる
そのさきのつるつるした赤くほそい根だよ!
この田園の悪夢とは
わが馬ニコルスがニンジンを食うとき
だれも近づくな!
病人・幼児・鶏・姙婦を憎む
あらゆる個の
虚像・銅像
藪があればそのいばらの果へ
蹴りあげるんだよ!
自負の白塗りの柵をとび
ねはりの綱で囚われるときまで
黒雲千里
まれなる涼しい雷雨のゆうべの
できごと
*
刺された父が窓までゆき
刺された母が窓までゆき
それはフォルムでは
ない
それは起源ではなく
まして成就ではない
なによりもまず
あらゆる戦いの認識の変形
芸術・手術・忍術
はねる血の父
はこばれる凾の母
カシの木の生えた森のような室内
そこでカタツムリを発見し
ゆがめられた金の道のべで
わが馬ニコルスは死病の疝痛をこらえる
冬ごもりの廃屋で
誠実な兄弟たち
弱々しく
燐光塗料の書物を読みあげる
他界の闇の
ナイトテーブルをまわり
少女の腹部をあつかましくも求めて
水位へ出る
老人十字軍
ともに浮遊する
わが馬ニコルスのゴムのようなおとがいを愛撫せよ!
母の半欠け乳房のように
*
ピンク色のハマムギを成長させる
荒野の納屋で
わが馬ニコルス
水をねながら飲む
浮いている藁の下の方に
恋する幽霊たち
或はナメクジの類
潜水艦に類似した
わが馬ニコルスのまるまるとした尻を見よ!
それに乗る人がこの世にいるか?
寒い冷たい人
砲弾とともにとぶ淋しい人
横から眺めれば
先祖ごろし
血の雲がたなびく少年の夢
絹につつまれた
姉妹のくろい種子が
ひざの間で
白水でぬれて
消毒飛行
ツバキの花びら散らし
正面を占める
わが馬ニコルスの笑う歯の薄明よ!
すべからく
皮一重の腐り方への悦び
トカゲの湿った心で
宗教的物質と
やわらかい肉も食べる
その同時性こそ女の弾性だよ!
もしも楽園があるとしたら
それは紫色の
葦毛が脱けおちる
わが馬ニコルスの虹のような
股がまたぐ
独身者の燃える棘冠
或は濡れるシャツのプライベートな
その汚辱
その辻便所の孤独から
内的建築を求めて
ずーっと近景まで乗り入れる
斑点のある戦車
貨車への接続詞・終止符。
単語のつながる末尾の
赤い毛のかつらの下の大砲
その投影
その三角又は四角形
その装飾をつきぬけて
黒と白の格子
テーブルに坐って
母娘が比喩的に語る
生まれる子供の意味を伝えよ!
一つの言語から生まれる
生死の観念の在り方
彼方の水へ
泳ぐ百人の子供
彼方の塔へ
のぼる百人の子供
彼方の砂へ
もぐる百人の子供
彼岸の彼方の白布へ
つつまれる百人の子供
その一人の子供だけでも欲しいわよ!
血のように燃えて
わたしたちの分裂のくらがりに
遍在する
つねに黒い手袋をした子供が――
要するに客観的状況を
断罪してよ!
暁の叙事詩の直立性を押しわけ
母娘の子宮を絞めて
恍惚の子供が泳ぎ出る
そんな広域な
ネハン
の湾
*
すえながく生きつづける仮想の敵
ブランコのりの子供たち
わが馬ニコルスが荷車に積まれて
行った河と時を記憶せよ!
空鳴りの肉色の鉄橋の弧のかたちを破壊し
消滅する
わが馬ニコルスの水色の大きな瞳孔の
ふたたびまばたくまで
潜在的世界には
犯罪的な言葉が屹立する
初出は《小説新潮》(新潮社)1969年11月号〔23巻11号〕一七六〜一七七ページ〔コラム〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ13行1段組、22行。この雑誌掲載用入稿原稿(写真参照)で注目すべきは、編集者が記入したと思しい赤字による指定である。指定は原稿の改頁の箇所(10行めと11行めの間)に施されているほか、12行めを2行に分けて新たな行を二下から起こすよう記されている(これは「改行」というより、詩句をコラムの天地に収めるための「折り返し」だろう)。誌面もこれらの指定どおりに組まれているが(吉岡実詩集《神秘的な時代の詩》評釈〈「紅血の少女」〉の〈Ⅰ 〈聖少女〉評釈〉参照)、本校異では原稿の形を尊重して「ぼくら仮想の老人の遙かな白骨のアーチをくぐり」を1行として扱った。
吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈聖少女〉の雑誌掲載用入稿原稿 出典:森井書店
少女こそぼくらの仮想の敵だよ!
夏草へながながとねて
ブルーの毛の股をつつましく見せる
あいまいな愛のかたち
中身は何で出来ているのか?
プラスチック
紅血の少女は大きな西瓜をまたぎ
あらゆる肉のなかにある
永遠の一角獣をさがすんだ!
地下鉄に乗り
哺乳ビンを持って
ぼくら仮想の老人の遙かな白骨のアーチをくぐり
冬ごもる棲家へ
ハンス・ベルメールの人形
その球体の少女の腹部と
関節に関係をつけ
ねじるねじる
茂るススキ・かるかや
天気がよくなるにしたがって
サソリ座が出る
言葉の次に
他人殺しの弟が生まれるよ!
初出は《文學界》(文藝春秋)1969年12月号〔23巻12号〕九ページ、本文新字新かな使用、9ポ13行2段組〔コラム〈扉の詩〉〕、26行。カット:宮崎進。詩集fの〈収録作品初出記録〉には「(改稿改題)」(同書、八七ページ)とある。
わたしの好きな常套句の引用
ヘアーの下の果実
ヘアー
そこでは恐怖の麩を煮つめて
ヘアーの黄金の下で身もだえする恋人
枯木のかげへ入り
ヘアー かみにくい皮を噛み
固い函で未熟なイチゴをかこむ
部分からその全体が現われるまで
甲冑を洗え!
そこにはどんな形態の蛇が赤い舌を出す
あるいは砂かむりで
花咲く母の吸盤が見えるか?
ヘアーの夕焼
まさに淋しいドラムカンを叩く旅
股旅人が来る水路から道路へ
雪ふる舟 来る車
それから父離れの幼児は死出の
天翔ける種子
ヘアー
次にわたしに確認できるのはなに?
傾斜とはいかなる位置から測ればよいのかね
ヘアーの下でなく疾走する車の下で
塩のように新鮮に
見れば見るほど大きい
わたしの恋人 反処女!
初出は《都市》(都市出版社)1969年12月〔1号〕五〇〜五一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ25行2段組、97行。
戦争を考える
子供連れの男はルーマニア展へゆけ!
女中がめくるめく
下着の三色スミレの群落を見よう
翼ある毒物
肉のような絵が描かれて
あまねく拡がる霧の空
センニンカズラの葉が延びるのを刈るベランダの老人の
そのまわりから近代性を超え
未来へ至る
押し石が一つ欲しいよ
生理的な花咲く乙女
腸チフスで休校の庭は
棺のかたちの
人びとが列をつくるに快適な
オルガンを演奏する
兵士の断たれた手
それを見物する人たちがどこにいるのだろう?
ニンニクの肉房のように
忘却されている
火事のように地で燃えて
夜は単純な言葉を喋れ
ぼくの胸の上で灰色の猫がこうばこする
サクランボが七、八個赤い台所を通り
反自動的な書き方による詩の試み
愛の不在をたしかめ
手は手袋をはめ罠をはめ針金の上の骨をつまむ
それは流れそれは口をあける
その毛織物の下で
生まれる鉱物
人びとは誰のためにそれを鍛えるのか?
海鳥のように飛ばし
モグラのように恐怖の汗をかかせる
苔むす火薬庫の日の出
変りやすい書割り
靴屋・肉屋・パン屋・花屋そして管理人
必要な品を持って
夕焼の入江から歩いてくる
或は這って
反対に帰ってゆく
犬や洋服屋の針だらけのボデーがある
言語幻滅の治世に
水間という空間等価の世界があるとしたら
水中銃を撃て!
とぶ飛魚
やわらかな魚雷の内部の真珠母類
波にもまれる母親と赤ん坊
冷血・れいろうたる血
過去は王冠のギザギザに傷つく心
そこでカキフライを食べてあくびだよ
高層温室で眠るべくエレベーターで昇る
みにくい花嫁花婿
同時にブドウが熟れる
まず大切なのは水の飲み方
船の帆を墨染にする
海の上のコレラに罹らぬために
裸になって蝶のように
ゼンマイの口でしずしず水を吸うんだよ!
またはプラスチックの管で
かこまれてあらゆる廊下を走れ
球体からながれる藍の水
窓から今度は
セメント樽がおろされる
ぼくは詩句を書きながら
それを見ていればよいのだろうか?
〈金魚鉢をかかえて駈ける騎兵隊〉
途中でとまった
自動車のつぶれた屋根で鳴く牝鶏たち
その卵の黄色い内部の霊媒を
たしかめて
コーヒーをのんで庭へ出て
明るい透明な巨人のゴムの木を〓る 〓:木偏に「戈」。定稿では「伐」。
そんな土の遊びをつづける
悪い私生活
雪ふる紐の首都
ぼくが詩を書き終えるために今夜の状態はどうか
浴槽のなかで虎みたいに重い
シャワーの下で妻は甲冑のなかにいる
あまりにも水が熱く
貝のなかの舌というものは乾く
モモイロのその舌がいくつにも裂けるよ
死声と雷の双曲線で
移動するネズミだ数量支配のネズミ産の潜在的
血の彫刻を仰げ
とうもろこしの堅い粒々で下痢する
ぼくたちはどんなデザインの勲章をつけて
廃校近い朝の運動場を駈け廻り
迷路・退路を進み
雨のアメリカのジャングルジムへ
しめなわを張り
いかなる幽霊の姿勢で
全員で吊りさがればよいのか?
男女の区別はなくなってほそくほそくなる
春きたりなば
離魂
これから何処へ
浮遊せんとする!!
〈一九六九・一〇・五〉
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
低音(⑦・14、23行)
初出は《風景》(悠々会)1970年3月号〔11巻3号〕五八〜五九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ16行1段組、23行。
ブランコのりの少女がひとり
辻公園にいる
とわたしは想像し
肉体と紐を使って
苦い荷をはこぶんだよ
方解石
漆
いまとびあがる少女の薄布の
支離滅裂の
尻を大写しで見よ!
その移動することだま?
発光する水晶でなければ
それはプラスチック
木の球
花嫁
みずみずしく
防疫人が調べる
輝かしい孔類
それは点になるまでコイルで巻かれて
青空へ至るんだ!
母恋うる声
向うを老人や草刈機が通り
わたしが通る
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4月
葉(⑧・4、135行)
6月
ヒヤシンス或は水柱(⑧・3、43行)
ルイス・キャロルを探す方法(⑧・11、〔わがアリスへの接近=43行〕〔少女伝説=*印で14節に分かつⅠとⅡの66行分〕109行)
7月
悪趣味な冬の旅(⑧・6、85行)
8月
弟子(⑦・15、44行)
10月
タコ(⑧・2、*印が3節を従える34行)
初出は《ユリイカ》(青土社)1972年4月号〔4巻4号〕一二〜一七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、135行。目次に「連祷詩」とある。
モップの棒の立てかけてある
その起源のなんと遠いこと
デパートの洗面所の
衛生的な木蔭の抒情詩
ぴかぴかした床がすきだ
だから
われわれの恥しい
擬似排便を見よ!
かたちなき灰玉
掃除婦こそこの黄金時代の
過去の器官のメカニズムを衝く
聖女勢
かくして
緋色の衣はなびき
乳兄妹がうまる
ときにはバケツ抱き父を抱き
土離れ
手法の変則を試みては散文的に
舟で
層の下の層を求めて
湖へ帰る
カンテンの半透明な世界へ
作品自体は血の気の乏しい夢をはらむ
それだから人類をシンカンさせる
浮袋の黒人の唄
思考は移る
旧き大陸のコスチーム劇は終り
デンポー
鋲打銃で撃たれる
すべての硬質の物とまたは全汚物
肉 言葉
それについて語るのはむずかしい
回路があるとしたら
潜在的に
洗われた布
ここで見失ってはいけない
沐浴せる姙婦と火食鳥の声を
その外的な衝突の消法の関係を
問うことができるか?
われわれは肥大する菱形をもち
マンホールのフタをひと廻りする
非人称性の都市
それは一つを用意し
二つを用意しないことによって
戦いはおわり
やがて苔むす消火器
臼砲
ちらちら覗く
反橋の下
どれもこれも水虫頭の赤ん坊
流せ水
心あらば
ゴム手袋をはめてつかみだす
再生できない魂
言語
その甘皮かぶり
咲けよアネモネ
構造上から固有名詞の乱用を避け
影また影
放電アースで
ググ具象的
絞められたデズデモーナ
中世以来の絵馬の処女出産図
開きっぱなしのカメラ・ワーク
大尻を出して
カーテンのかげの
あらゆる読者を驚かせる
でも批評家は火山と家畜の運命を語る
作者を探しに谷へ
意味とリアリティとは別のものか
省察せよ
単純なタイル 多角なスタイル
バラの羊水のながれ出る
われわれの暁には
さかさまの
袋にたまるものがある
ひとつの歴史・ひとつの比喩・ひとつの栗
質素な物質
老婆のしずかな食べ方を
表現論としてまなぶ
作者の主題の外れたところで 改めて窓から眺めようか
菜の花畑
なまなましい夫婦群
修辞学的に考えても最良でない
アンモニアの匂い
すべからく中心の孔を開示せよ
清掃聖父は再び
火掻棒で多くのものを突く
作品営為とはそのようなものの彼方
籾の山
幼児が向う側へまわり
そして造物母を犯す
書くこと
書かれること
近似性のみずみずしさ
変化ではなく
ハサミムシは消失する
あでやかな春
われわれは遊行する
芹つむ乙女の籠のなかになにか
「問題」は
在るか?
決定的なもののない世界像
ここはどこのこと
汚染されることの法悦
走る扁平タイヤの内在する
抽象死
まぎらわしい日々
罅
発泡スチロールの函
そのへだたりが必要だ
なまものは腐る
ハタンキョウのように
地上から消えて行く映画
青い水のプール
一字の愛
作品の終章は多くの場合パターン化の傾向
意識のあるうちに注意せよ
それにかかわる
人工的霊感
高まる波の夏
ものの具
装飾性をすなわち消せ
岩が出る
ニガリが宿る平面
歩むことができない作者の姿をはじめて見つけた!
下水溝への入口
書物の帝国
それがあるいは出口の金門
もしかしたら作品の終りの冬がくる
スズメガの太い胴まわり
われわれはこれを読むことが可能だろうか?
ハアハアする肺魚
――
葉
(連祷詩《粘土説》の一部)
初出は《風景》(悠々会)1972年6月号〔13巻6号〕五二〜五五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ12行1段組、43行。
ミルクをのむときわれら男はいつも考える
ラジエーターのなかに
見え隠れする
ヒヤシンスのムラサキのむらがる花
恋せる女をとりかこんでは
飛上る
夜間飛行機
だから下を向く輸卵管が見え
われら男は容積のある
物体をもとめて行く
何方へ
未完の地獄絵図
礼拜して
丸焼けの窓から
来襲する雷獣を久しいあいだ夢みて
数ある用のなかの
一つの用をたす
冷たいゼリーのながれる
幹のまわり
ギリシア悲劇の父が訪れる
バイキンのついた
夜具・ヤギの乳房のふくらむ初夏が再びくる
すぐに役立つものがほしい
乱軍・ラプソディー
ゆるやかにとける雪の山
やがて抜歯デー
ユズの実をしぼる母の背後は暗いか?
交わる蠅のパイの皿
そこでフィルムにかぶさるナレーション聞け!
きみらにとって戦争体験とは何か?
みるかげもないミカゲ石
それは今でなく
末世の松へ戻る物の影
そのミステリー小説がすき
死せる裸体美人
藻の下をくぐりぬける
まっくろいもの
管理人はそれをつまびらかにはしない
円天井から上は豆の蔓
鱒がはねる
ミリュウ
ここでみずから見ることを
水柱!
初出は《別冊現代詩手帖 ルイス・キャロル――アリスの不思議な国あるいはノンセンスの迷宮》(思潮社)1972年6月〔1巻2号〕一五七〜一六四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ25字詰25行1段組、〔わがアリスへの接近=43行〕〔少女伝説=*印で14節に分かつⅠおよびⅡの66行分〕109行、扉に「Photo by Lewis Carroll / Poem & Montage by Minoru Yoshioka」とある(〈吉岡実のレイアウト(2)〉参照)。目次の標題は単に「キャロルを探す方法」。
三人の少女
アリス・マードック
アリス・ジェーン・ドンキン
アリス・コンスタン・スウェストマコット
彼女らの眼は何を見ているのか?
彼方にかかる縄梯子
のびたりちじんだりするカタツムリ
刈りとられるマーガレットの黄と色の花の庭で
彼女らの脚は囲まれている
どこから それは筒のようにのぞくことが
できるか?
「ただ、この子の花弁がもうちょっと
まくれ上がっていたら、いうところはないんだがね[*]」
彼女らの心はものみなの上を
自転車で通る
チーズのチェシャ州の森
氷塊をギザギザの鋸の刄で挽く大男が好き
鞄のなかは鏡でなく
肉化された下着
歴史家の父の死体にニスをかけて
床の下の世界から
旅する谿のみどりの水をくぐる
一人の少女を捕えよ
なやましく長い髪
眠っている時は永遠の花嫁の歯のように
ときどきひらかれる
言語格子
鉛筆をなめながら
わが少女アリス・リッデル
きみはたしかに四番目に浅瀬をわたってくる
それは仮称にすぎない
〈数〉の外にいて
あらゆる少女のなかのただひとりの召女!
きみはものの上を通らずに
灰と焔の最後にきた
それでいてきみは濡れている
雨そのもの
ニラ畑へ行隠れの
鳩の羽の血
形があるようでなく
ただ見つけ出さなければならない浄福の犯罪
大理石の内面を截れ
アイリス・紅い縞・秋・アリス
リッデル!
*ルイス・キャロル《鏡の国のアリス》岡田忠軒訳より
Ⅰ
ドッグソン家の姉妹ルイザ マーガレット アンリエッタ 緑蔭へ走りこむ馬 読書をつづける盛装の三人 見よ寝巻のなかは巻貝三個
*
父ジョージ・マクドナルドはひげをのばし 長女リリーの唇は イチジクの汁でよごれる 婦人帽の下からツタの葉を茂らせる継母 父に抱れて 鳥の巣を採る弟
*
アグネス・フロレンス・プライスは今日も一つの大きな人形を抱く 中世のかつらをつけた裁判官の姿をした人形を わたしの罪を罰して! 縞の下着をつけていることを
*
エリザベス・ヒュースィー よい名それとも変な名 ロバー・ヒュースィー教授の娘 絹のソファーへ横たわって 午後は母を待つ 母は医者を待つ 夜は父を待つ 母を待つ父を わたしは待つ 絹を傷つける虎を待つ
*
ああアイリーン・ウィルソン・トッドよ 風に吹かれたあの長い髪が庭の木を巻く 恐ろしいことに木の幹がつるつるしている 死んでいる木 生きている木 叩くなら木の股を 大梯子へあがって兄の首を吊すこと
*
窓から見えるエフイー・ミレエス 父と母と妹がこの窓から飛びおりるのを上からのぞいたような気がする
*
フフフ笑うフランクリン夫人の娘時代に似ている うつむくバラのなかのローズ 子守唄は自分で唄うのよ バラよ眠るなかれ!
*
マリア・ホワイトの白いマリがころがってゆく 止るところがあるだろうか ランベス・パレスの荘重な門で止る 恐しい顔をして叔父が門を閉めたから
*
マドリーヌ・キャサリン・パーネル 水兵服が好き 水浴びが好き 横顔が好き
*
C・バーカー牧師の娘メイは椅子の上へ立っている 靴のまま この狼藉の恍惚 十二才になったら飛びおりる
*
メリークリスマス 病める雪 病める七面鳥の声 わたしはメリー・マクドナルド ジョージ・マクドナルドの娘 うずくまる母と姉 鮭の燻製がきらい
*
エラ・モニアーウイリアムズ 廊下をほうきで掃く どこまでもどこまでも暗い家 教授は今朝は「寒い」とひとこと云った
*
主任判事デンマン卿の娘グレイス・デンマン 石の階段の一番下が彼女の憩いの世界 重い大きな鎚で赤いカニを一撃したら 恋する女の心にちかづく
*
父は芸術家アーサー・ヒューズ つくられたものアグネス ウサギのように毛のある服を着て おしっこしたくなる 春から夏まで キヅタの棚の下の召使たちの恋
Ⅱ
テニスン夫人の姪アグネス・グレイス・ウェルドは赤い乗馬頭巾とマントを着け 馬のうしろに幼い友だちを呼ぶ コートゥス教区司祭館の使用人の娘クロフト・レクトリー 教授の娘エリザベス・ヒュセイ 芸術家の娘アミイ・ヒューズ T・Bストロング博士の姪ゾーイ ジョージ・マクドナルドの娘 髪がうまくとかせないイレーネ その姉メアリー ピュートニィーの教区師の娘ベアトリス・へンレイ エレン・テリイの妹たちマリオンとフロレンス リポン僧正の娘フローレンス・ビッカーステス ピュッシー博士の孫娘カティー・ブライヌ ジョーン・ミレエスの娘メアリ クランボヌ教区司祭の娘ダインフナ・エリス
遅れてきたのは誰? あら支那の娘の紛装したアレクサンドラ・キッチンだわ いとしのクシイー けさ水汲みに行って 最初に見たのはなんなの? 串の魚それとも 舟を漕ぐ農夫 蝶を捕える青空の下の網 聞かせてよ 支那のウグイスはどんな鳴き方をするか? ペルシャ模様の八個の箱の上で 夢みるクシイーよ 川のほとりで 最後に見たものはなんなの? あなた自身の肉体 その影に心があるようで ないように見える なまめかしくも幼い聖痕?
みんなでこれからキャロルおじさんを探すのよ それは包帯で巻かれた幽霊群のなかで 副葬花束を持った人だわ!
初出は《中央公論》(中央公論社)1972年7月号〔87巻7号〕三二八〜三三一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、85行。
酢の過ぎし悪しき想い出のために
なますのすのものを食べて
一人称のわたしの旅立ち
火田・水田帯をながれ出る
ミズカキをつけた子孫よさらば
ここはすでに透視画のように
つねならず 月の出を見た
ザクロ・イチジクの実のすずなりの彼方とは
何処のことであるのか
可塑的な聖性の乳房を求めて
「ストッキング・スリッパ・コルセットが
堆まれている」
ナフタリン臭いバラ色の
〈共食信仰〉の地をさまよい行く
まだ見えてこない
音楽の内部をうずめる肉柱のような生暖いものは
そこに空想はなく危険な生活がある
もろもろの洗濯物は燃え
夏の水はながれた
伏せられた柄杓千里の下の道を行けば
通ずる 通ずる
有機的に行き暮れる
有罪の首府へ――と
古人の云う包茎・テンソクの愉悦する日々
おお――オンドル装置を破壊せよ
「料理がつくられる」
それは抽象観念である
人民たちによって四肢へ鉄棒を突きこまれて
いる黒毛の野豚のボデーに触れ
その大いなる死の影の重いことを恐れる
過度の虚構は
或は現実そのものではないか
問いはじめよ
ドラが鳴らされる以前に
ドドッとたちのぼる蒸気と
沈む軍艦のスカートがまる見え
物質合成の歴史と長いツララは先細り
二人称のわたし・すなわち兵士きみらは逝く
カササギのかすめとぶ
雪の塹壕のすてきな敵を囲周して
だれでもがもつ心臓の奥に潜在する
正面の格子のなかに
飾られている馬蹄形の星々がある
胡麻よりも軽やかな護符をもつ死人
さながらに
蛇と桶の間で
藁をきざむ淋しい行為そのもののつづく
それからの歳月の円をふちどる血糊の道のり
いつも斜めの水瓜やコウリャン畑を越え
三人称のわたし・彼らは悪しき足をひきずり
丈高かりし麻の葉の母を追想する
むかし‥‥ムカデに驚きし乙女を夢孕む
ドロの木のみどり芽ぶく日は
美しきメイストームの丘から
濡れ壁を通りぬけて
〈詩〉の〈語〉いわさず嗤うべき
一人称のわたしはなぜ
生皮の上を渡って行くのだろう
数多くある観念のうちから
不要の物をえらんでは
生木を裂く
肌着の汚れた女の側に
たしかに枝の細いところで
ナナフシのいんさんな移動を見た
二人称のわたし・君らの七変化の運命だそれは
生きている空間のピンク色より鮮やかに
その昆虫は負の形態の固定観念を示し
輝く徐々に
これこそ悪趣味な一人称のわたしの生き方に近い
白波立てる海辺で
貴婦人の蝶マスクせる尻の上で
廃墟灰掻き歩きの旅も終った
三人称のわたし・彼らが見るのは退屈な編物映画
今ここには
保存すべき物がない
水槽の氷片のように
消えるあまりに多くのもの
地理と枕と書物
つらなる雲は不運の兆しかもしれず
朝のコーヒーをのむとき
ズッズッ
ずれる芸術の土台のすべて
すばらしい梨の木の群れ咲く花々
すばらしい巣ごもりの
父娘のやさしく野蛮な生命を認める
初出は《無限》(政治公論社)1972年8月〔29号〕三八〜三九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、20級22行1段組、44行。吉岡は「〔……〕今から六、七年ほど前、「無限」の西脇順三郎特集号に、〈弟子〉という短い詩を書いて献げていた。当時考えるところがあって、私は二年間ほど詩作を止めていた。そんな精神状態のなかで書いた詩なので、詩集《神秘的な時代の詩》を編むとき、先生への献詩である詞書を、削除してしまったのであった。」(〈西脇順三郎アラベスク〉の「7 「夏の宴」」、初出:《東京新聞〔夕刊〕》1978年10月24日)と書いているが、印刷に付された本篇に西脇への「献詩である詞書」はない。同誌の目次には〈献詩〉の見出しの下に、会田綱雄から村野四郎までの10名の詩篇の標題(献辞がある場合、2倍ダーシでつないで表示)に続けて、吉岡作品が〈弟子〉とだけ記されている。
それは違った意味に使われる
言葉
笊のように
晩夏へ向うよ
淡黄色
見えなくなったら
ハツラツとして
眼薬をさす男
砂かぶりの丘をゆき
職業を意識する
この世に歌があるだろうか
たとうれば
草上の露命
〈永遠とは今の現在のこと〉
だから心は重く
死んだカモのように
岸べに寄る
われわれには切ない
私生活があって
紐のすべてが濡れているように
円にかこまれる
紺染のはるかなるアザミ
花瓣的な奥深いものを信仰というのか
われわれは明晰でありうるか
疫神の午後
紅藻類のなかで娘をみつけて抱く
力ない血祭
どこから起伏せるなやましい大理石
吹きながしのチリメンの鮮緑色群
たたずめばスルメの足
過ぎれば燐
戻れば雪の嶺が見え
わずかに
夢みる鋸歯の海を
ラジィカルに泳ぐ
老人をたたえよ
そして箴言集をみよ
「便所はどうして神秘的に
高い処にあるのだ」
女神の水色のスミレの酢を求めて
梯子をよじのぼる唯一の弟子
さて簀子は乾いた!
春は曙
牛乳屋が来る
初出は《ユリイカ》(青土社)1972年10月臨時増刊号〔4巻12号〕一二〜一四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ25字詰1段組、*印が3節を従える34行。
*
火をへだてて呼びかける
やさしいタコの母親は藻をまさぐり
サンゴの棚にたれさがって
下を向く
フジツボの信仰深い孔へ
青びかりした累卵を送りこまんとする
そのそばに船長の屍体が
官能的に横たわっているときは
八点鐘を打つ
それからはじめて
タコの母親はとりみだした恋人のように
動く岩を抱く
*
タコの生殖はとても呪われたフォームを見せる それは濡れて裂かれた傘のような肉の散乱にちかい タコのオスの七つの足は水を抱きこむ そして残されたごく先細りの一つの足がくだの器官の役目をする ちょっと見ると 靴の紐のようにみすぼらしく タコのメスの小さな孔を探し求めて入りこむ これが交接といえるだろうか 水は起伏してながれる 透明な世界では悦びもなく射精は終る すぐそばにタコのメスのみひらかれた眼がある それには汎神論的な悪意が感じられる 受胎せるタコのメスは海の底の石の巣へゆっくり帰って行く 二十万粒の透明な卵を生むために それから絶食状態のまま ブドウの房のようにたれさがった袋の卵群へ 必死に泡を吹きつづける それは呼吸に必要な酸素を送るためだ ゆらぐ海草のかげで タコの母親はただ一度の排卵で腐る肉質へと替る
*
ひとりの女が悪い想像からうまれるように
塩と水からタコは出現したのだ
漆黒の抽象絵画
砂は砂によって埋まり
貝は内部で生きる
それは過去のことかも知れない
夏の沖から泳ぐ女がくる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
マダム・レインの子供(⑧・5、42行)
2月
聖あんま語彙篇(⑧・8、4節87行)
5月
『アリス』狩り(⑧・12、76行)
7月
サフラン摘み(⑧・1、42行)
ピクニック(⑧・7、32行)
9月
田園(⑧・14、12節134行)
10月
動物(⑧・20、29行)
11月
わが家の記念写真(⑧・9、23行)
フォーサイド家の猫(⑧・17、*印で5節に分かつ85行)
初出は《ユリイカ》(青土社)1973年1月〔5巻1号〕一六〜一七ページ、本文新字新かな(ひらがな拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、42行。
マダム・レインの子供を
他人は見ない
恐しい子供の体操するところを
見たら
そのたびぼくらは死にたくなる
だからマダム・レインはいつも一人で
買物に来る
歯ブラシやネズミ捕りを
たまには卵やバンソウコウを手にとる
今日は朝から晴れているため
マダム・レインは子供に体操の練習をさせる
裸のマダム・レインは美しい
でもとても見られない細部を持っている
夏ならいいのだが
雪のふる夜をマダム・レインは分娩していたんだ
うしろからうしろからそれは出てくる
形而上的に表現すれば
「しばしば
肉体は死の器で受け留められる!」
球形の集結でなりたち
成長する部分がそのまま全体といえばいえる
縦に血の線がつらなって
その末端が泛んでいるように見えるんだ
比喩として
或る魚には毛がはえていないが
或る人には毛がはえている
それは明瞭な生物の特性ゆえに
かつ死滅しやすい欠点がある
しかしマダム・レインの所有せんとする
むしろ創造しようと希っている被生命とは
ムーヴマンのない
子供と頭脳が理想美なのだ
花粉のなかを蜂のうずまく春たけなわ
縛られた一個の箱が
ぼくらの流している水の上を去って行く
マダム・レインはそれを見送る
その内情を他人は問わないでほしい
それは過ぎた「父親」かも知れないし
体操のできない未来の「子供」かも知れない
マダム・レインは秋が好きだから
紅葉をくぐりぬける
初出は《美術手帖》(美術出版社)1973年2月号〔364号〕一五一〜一五二ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ24行3段組、4節87行。
〈馬を鋸で挽きたくなる〉土方 巽
1
わたしは見たんだぞッ!
薄明のたつみの方角をめざして
一人の老婆のそろえた両手のさきの指の
高さまで
水面はもちあがって来る
それがやがて水平になったとき
みせものの
なつかしい風情だ
うさん臭さうしろ暗さ
具体性はすでになく
金粉は撒かれる
優雅な命のこと切れるような日没の
観念の枠から外れる
関節の平野へ
言語から舞踏へと景色を替え
「赤子の頬にふれる
網の目から
わたしは何を覗けばよいのか
カモイの塵
くびれた茄子の尻
蛸の吸出しが吸い出したもの
それとも抽象された線
愛」
器物へのなかま入り
を了えるために
「わたしは寝床にまんじゅうを引き入れる」
2
往古より
大鋸ありき
棒に巻かれて
いる布や紅い糸ありき
火のついた母の半白髪が好き
真綿でフクフクくるまれた姉の足をたどって
「上に行けば精霊 下にあるもの
が人形」
そしてのっぴきならない
「中間にあるものが肉体」
やがて明け方
「ゴハンを食べて裏から出て行くようなのが『家』あるいは『東北本線』」
だからそば屋の十一番目の末子は
飴でなく
「キンカクシに歯を立てる」
つまり
夜は単調ゆえに耽美的だ
生姜をすりおろすように
木舞[コマイ]編み職人の唄が聞える
3
「歯槽膿漏の親父がおふくろのおしめを
川で洗っている道端 で兄が石を起し
たりすると
クルッとまるくなる虫がいる」
身丈を小さくすること
「物囲いの中でからだの寸法を計る」
これがいわゆる仮埋葬
割箸を裂きつつ
煉獄舞踏図を考える
わたしは水虫の人
川流れの西瓜を
死人と一緒に喰う
疱瘡だらけの真夜中の人物はだれ?
湯気が出る
戸板にのせられて
鮭の頭をかじる男が見える
炎天の下で
イボイボの胡瓜がなっている
宗教画のように
4
長靴をはいたまま
花嫁は戻る
碍子と雪の世界から
ポタポタわたしを産むために
押入の中へ入る
「動かないものと動いている
ものの半分半分」
わたしは首尾よく生れ出るだろうか?
「聖なる角度を手探る者」
となるべく
なぜか恐しい
堕し薬の煮える音響だ
麻袋をかぶった馬が立ちあがり立ちあがり
招魂せんとする
祭壇と灰の床
これはごく常識的な形式ではないか
「魚の浮袋をパチンとつぶす」
ほど自然自体だ
わたしの夢みる軟骨に必要なのは
物の発情とコールタールの悪臭である
蘇生のユーモアもともに
「スギナを噛む老人の顎を外せば
火が吹き出る」
(正月・七草)
初出は《アリスの絵本――アリスの不思議な世界》(牧神社)1973年5月1日、二一〜二四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号28字詰28行1段組、76行、目次にある「アリス狩りのためのアリス工房 Alice workshop for the hunting of Alice」中の一篇。
それはたくさんの病人の夢を研究しなけりゃならん
〈退却してゆく臓器や血の出る肛門〉
わしも医者だから抒情詩の一篇や二篇は暗誦できる
今宵 生き損じの一人の老婆も無事に死んだし
かれこれテニス試合の時刻がくる
カメラと持てるだけの物を持って森まで行く
まっ白い弾むボールを追究する 悪寒するわしが見えるか
むきあった男女の間に生える カリフラワー 粉
この世に痛むものがはたしてあるか
わしが診察するのは鏡の中の患者の患部だけ
手も汚れず 悪臭もなく
でも疲れるんだ 鏡の表面にとどまるオレンジのように
父母の写真 コダックの五匹の猫の写真 船腹の写真 赤ん坊
の写真 墜落した飛行機の写真 結婚式の写真 騎手の写真
女優のヌード写真 チャールズ・ラトウィジ・ドジソン教授が
撮ったアリスの写真
〈静止せる剃刀や魚 潜在せる雷や桃〉
〈森や山の動物よりも檻の中の動物〉
〈ただ一人の少女が走り回っている〉
〈沼のほとりの燈心草と雨〉 それらをわしは嗜好する
血豆と乳房「それはただちに切開する」
それが終ったら力のかぎりあらゆる岩地を掘りかえせよ
何かが出る 何かに成るものが出る
そのときは看護婦を呼んで包帯をぐるぐる巻かせる
ではこのように
ではこのように鵞鳥
とはいうものの
とはいうものの月光
「髪をしなやかにしたいわ」といった一人の少女
そののびやかな腿を内包する 鏡のなかで
立体的な物は越えられる しかし平面は走れない
オリーブをしぼる母の背後は暗い 夜具と山羊
馬をすすましめ 河をすすましめ 受胎をすすましめ 軍艦を
すすましめ 飲食をすすましめ ゲームをすすましめ 時計を
すすましめ 矢印をすすましめ 物語をすすましめ 死をすす
ましめ
むかし外国の漫画でよんだことのある場面を想起せよ
長い石の塀が立つ
それは草むらの一隅のように見える法廷で
声女・アリスは答える
『塀』には死体が塗りこめられていましたか
わかりません(三匹の猫)
『塀』には高さがありましたか
わかりません(ひまわりの花)
『塀』は何で出来ていましたか
わかりません(心臓のようなもの)
『塀』は何を囲んでいましたか
わかりません(先祖の家系)
『塀』は今も立ってそこに在りますか
わかりません(時と鳥)
『塀』はではどこに存在するのですか
わかりません(永遠に保護色)
しかるべく手術をせん
しかるべく病巣なきときは
しかるべく印をつけ
しかるべく肉体を罰せん
わしの知っとる
「もう一人のアリスは十八歳になっても 継母の伯母に尻を
鞭打たれ あるときはズックの袋に詰められて 天井に吊る
される 美しき受難のアリス・ミューレイ……」
それにしてもわしは覗きたい 袋とペチコートの内側を
なまめかしい少女群の羽離れする 甘美な季節の終り
かくも深く彼女らの皮膚を穿ち 水と塩を吸い
夜は火と煙を吹き上げる 謎の言語少女よいずこ
上向き下向き横向き
緋色の衣をまとった大僧正の形をして
焼死せんとする恋しき人を求める
わしは消火器をもつ老たる男 暗緑の壁紙の家にいる
死ねば都 ここがギリシア悲劇の見せどころ
西の方からとどく キンバラ鳥の声
あらゆる少女の胴から下は紅くれない
下品なハンカチを所有することを認識し 洗濯せよ 言葉!
夏の空の色あせる時
わしも詩人だからたまには形而上的な怪我をするんだ
今宵 書き損じの一人の少女の『非像』を追想する
落涙する屋根の上の人 それは汝かも知れず?
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1973年7月号〔16巻7号〕二六〜二七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25行1段組、42行、目次での作者名は「吉岡實」。本文カット:司修。
クレタの或る王宮の壁に
「サフラン摘み」と
呼ばれる華麗な壁画があるそうだ
そこでは 少年が四つんばいになって
サフランを摘んでいる
岩の間には碧い波がうずまき模様をくりかえす日々
だがわれわれにはうしろ姿しか見えない
少年の額に もしも太陽が差したら
星形の塩が浮んでくる
割れた少年の尻が夕暮れの岬で
突き出されるとき
われわれは 一茎のサフランの花の香液のしたたりを認める
波が来る 白い三角波
次に斬首された
美しい猿の首が飾られるであろう
目をとじた少年の闇深く入りこんだ
石英のような顔の上に
春の果実と魚で構成された
アルチンボルドの肖像画のように
腐敗してゆく すべては
表面から
処女の肌もあがらいがたき夜の
エーゲ海の下の信仰と呪咀に
なめされた猿のトルソ
そよぐ死せる青い毛
ぬれた少年の肩が支えるものは
乳母の太股であるのか
猿のかくされた陰茎であるのか
大鏡のなかにそれはうつる
表意文字のように
夕焼は遠い円柱から染めてくる
消える波
褐色の巻貝の内部をめぐりめぐり
『歌』はうまれる
サフランの花の淡い紫
招く者があるとしたら
少年は岩棚をかけおりて
数ある仮死のなかから溺死の姿を藉りる
われわれは今しばらく 語らず
語るべからず
泳ぐ猿の迷信を――
天蓋を波が越える日までは
初出は《芸術生活》(芸術生活社)1973年7月号〔26巻7号〕〔一四〇〜一四一ページ〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、12ポ20行1段組、32行。
まるで地すべりの音楽のように
過去のカテドラルのように
われわれの「偉大な悪と愛」を
夕焼を認知せよ
ウラジーミル・ナボコフは記述する
水浴せる少女の手から脚へ さらに届かないところへ
口は淋しく記号のような
パンセを求める
兎の毛の内部には
洋服を縫う針や形をととのえる
コテやハサミが
秩序よく収納されている
この家では女中がしゃべったり
しゃべらなかったり
長い靴下を干しに池へゆく
草の上に置かれる一個の籠には
うまく焼き上った鶏冠の肉と
それをとりまく野菜の数々がある
これがピクニックのたのしみ
すすむ少女
ずるずる沈む中年男の夢枕
ゆるむ脱腸帯
番人が柄杓を持って
青い水を汲みにきたりこなかったり
考えを替える川はながれ
「理性の時代」は終るかもしれない
死垂る紫の葡萄の下で
シャワーを浴びる母娘を
遠巻きにする
われわれは「暗喩」に近い存在である
へアーピンの山を
兎がとび越える
初出は《ユリイカ》(青土社)1973年9月号〔5巻10号〕〈特集=吉岡実〉六〇〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、12節134行。目次には「長詩」とある。
1
洗濯女のエプロンのかげで
わたしは生まれた
ということ
「空間概念とは何か」
となりの人が問う
それはたしかに
「星は暗闇で光るものだ」
水面にうかんだ微生物よりも
キノコ類に近似している
父の肝臓で石は育ち
わたしは草の上へ置かれた
長方形の〈言葉〉の管を吸っているのは
青いポールを持つわたしでなく
バッタの一種だった
2
「すぐに据え付けられますよ おかみさん
土は腐っているから」
エナメル塗りの牛の頭蓋はまつられる
石臼の上に
夜の明けるころは
老人たちは帰って行く
揺籃へ
「わが子よ わが犬よ
たのしく暮そうよ!」
釘の山で母は唄っている
3
父は猛獣狩スタイルの女が好き
いつもパンを焼くフライパンの尻を叩きながら
赤袋角をあらわに突き出していた
それは滞り それは窓の外で
濡れている ぜんまいや蛇のように
新しい石鹸のようにそれは滑り
朝まで用がある
4
白とピンクに染められた寺院の門をくぐり
わたしは遊んでいた
梨の木の群と
ざらざらした梨の実を食べては
「純粋な固体」を求めて
不安な谿を降る
坐る人 歩く罪人
子守のひざのうえで
わたしは探しているのだ
狩られた毛のなかの野兎を
深い傷口の奥に
もしかしたら甘い蜜がかもされている
「花嫁」
わたしの一番好きな〈観念〉!
5
馬具屋が舟にのってやってくる
反詩的社会から
彼のために歌を唄う一人の少女が憎らしい
歴史家なら検討する
スフィンクスに「兄弟」がいたかどうか
もしやそれは「姉妹」ではなかったか
その奇妙な像が馬みたいに水を飲む姿を
馬具屋の粗い前掛のかげで
テニス靴の少女は夢見る
6
氷売りが絹のテントのまわりを歩く正午は
死者への礼節が大切だ
汚れた鳩とシャツにかこまれて
肉屋の親方がみまかる
ヤギ ウサギ キジ ウシ ブタ ウマ
「すべての血はすててはいけないぞ
血は煮つめれば
煮つめるほどうまくなる」
7
それがわれらの肉体をつくり
大砲の砲身をあたためる
煙や煤が出るよりさきに筒口から
眼球や兵士の手首が出る
それから味の濃いスープが溢れる
人類よ肥えよ!
資本系の羊歯が茂って
岸からハートの丘を埋めてゆく
まな板の上に在る
開かれた卵
8
沼の霧がたちこめる彼方から
日はのぼり
ウォーターヒヤシンスは咲く
だれにも幼年時代はある
文体で喩えれば
あらゆる「言語」に付く
金色のセンイのようなもの
わたしはあこがれる
肉屋のマイスターになることを
岩の上の家で
ソーセージをつくり
「作品」をつくる天職を志向する
どういうことか
それはむりな姿勢をたもつことだよ
9
大刃で切る肉の断面は
失われた地図のように見える
ヘットとラードの冷たい肌ざわり
白きヘッドの父はタマネギ畑から帰り
哀しきバラードを唄う母のローブは汚れる
これこそ男と女とけものの三位一体の
舌は釘付けにされた
めくるめく官能の地の床に
10
わたしは病気がち
白い壁のなかをゆききする
緑の心臓をもつ子供
発育ざかりの少女を求めて
さしずめ 詰めた〈時〉を探す
ゆるやかな川のほとりで
石の下に養われているカニやエビを捕え
信仰的に
ときどきふりむく
「とても重大な事柄だ」
何かのなかに何かが生じ
何かのなかに何かが滅し
何かのなかに何かが残る
蜜柑の皮のなかには房が九つある
11
意味なきリアリティを併置すれば
前世紀的風景だ
秣の下をゆく旅人たち
肥った猫のように
酒と名づけるものは発酵する
こわれた大瓶のへりで
春の蝶がひげを巻く
「そこにある 豆の花 馬鍬 樫の棒
炎 くもの巣 灰 家霊」
たとえばそれらがわれわれの近くになかったら
「父母」の生活はなかったろう
はるかなる梁の巣の燕よ 戻れ!
12
回想を改葬せよ
浅瀬をわたる騎兵隊
とうもろこしの毛に包まれ
従姉がいったことばを
大人になって わたしは思い出した
「〈アート〉は退屈だわ」
枝を戻ってくる蝸牛の殻のように
この世の内部は艶消しになって
いて視えない宿命
「想像できるものは 想像できない
ものより〈生理感覚〉がある……」
わたしはいま「追悼詩」を叙述する
水に向っている
テーブルの男のように
初出は《季刊俳句》(中央書院)1973年10月〔1号〕六六〜六七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号17行1段組、29行、目次には「〔招待席〕/詩」のあと、「戦後詩の懸崖で一貫して至高の稜線を持して崩れぬ高峰」とある。
それは伝聞によると
雨のなかで
しかも生きている動物のようだ
〈線〉をたくさん集めて
崖下へ走ってゆく
紅色の動物の肥大するハートの影
耳を突き出し
背中をかくして
草をたべている犀のように
白い壁の隅に立ち
たしかに濡れた皮張りの椅子のようだ
からだを中心で折って
毛や骨をテーブルの下へ置き
さびしい巣の方へ
ゆっくり歩いてゆく
〈動物〉とは
いったいなんだろうか
すでに〈面〉をたくさん組みこみ
綺想体の子をつれて
いま長い綱をわたるところだ
その下は或は砂漠かも知れない
わたしたちの認識のしきみを超え
夜は紐をひきずり
死んだ動物は声を発し
跳板のところで一回転して
やがて泡で埋まってゆく
足を見せ
眼をかくし
ひとつの〈歌〉を終らせる
初出は《文學界》(文藝春秋)1973年11月号〔27巻11号〕九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ1段組〔コラム〈扉の詩〉〕、23行。
おかあさんは腰巻きする人
首つりのタモの木にそってゆき
朝日はのぼる
島の墓原で
百羽のツグミを食う猛き人
それが義理あるおとうさんの暗き心
いやになるなあ
公園からとんでくる
ラグビーボールをスカートのなかへ
おねえさんは隠したままだ
なので寄宿の猫は
沼面を走る雨にぬれる
幽鬼のように
いもうとは善意の旅をしている
星ビカリする夜々を
みなさん揃いましたか
では記念写真をとりますよ
青空へむかって
にっこり笑って下さい
でもうまく映るだろうか
時すでにぼくは
地中海沿岸地方の奥地で
コルクの木と共とに成長している
初出は《ユリイカ》(青土社)1973年11月〔5巻13号〕五〇〜五四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組(散文詩型は23字詰)、*印で5節に分かつ85行、目次に「猫の主題による長篇詩」とある。
わたしの部屋に一枚の小さな絵が掛けてある
だがこの絵を見た人はいない
この絵を描いた画家だって見たとはいえない
ただマチエールを造っただけだから
人はそれでは
「きみの所持する絵は
万有の闇のベールの向うに
存在するだけではないか」
と反問する
仕方ないから共存する妻とともに
わたしはその三匹の猫のたむろする絵を語る
できるだけ古典的な描写で試みようか
わが家の板の壁を飾る
唯一の絵の周辺を歩きながら
反現世的な閉ざされたフォーサイド家の内部を解体する
*
わたしはかつての或る夏の夕方
一人の女の胎内をくぐりぬけると
潜在する森と雪の浄土圏があるのではないかと考えた
高階の円塔の迷路を廻り
逸楽の画家ローラン・ブリジオの描く
着飾った貴婦人の肖像を眺めていた
薔薇型の大きな帽子をかぶった女
薄いランジェリーの女
印度衣装を全体にかぶった女
いずれも下半身を露わに出している
肉性が正面をむくとき
予言者を狼狽させる
シンメトリーの偏愛図
バックを流れるのは音楽でなければ
宮殿の回廊や庭園の噴水の霧であるのだろう
巻かれた雲と毛のなかに
窪地にかくされた小石類をのぞかせる
可視的な月光体とはなにか
聖地をさまよう探索者たちの魂
その真紅のデテールから
三匹の猫がうまれた
*
わたしはソファーに坐りながら
頭上のカンバスの枠から出る
画家の手を噛む猫を見る
これは三つの側面にかこまれていない
一つの世界ではないだろうか?
緑の山の前に人が立ち止るのは
母を恋うる時だ
窓べの少女の金髪は彫刻されたように暗く
父の王が殺されたのを悟り
彼女は両腕に一匹ずつの猫を抱いている
右側の猫は茶色でとても肥えて
固い枕のように傾むく
だからおのずと左側の黒と白のぶちの猫は背をまるくする
押されているのは時間帯でなく
グレーのカーテンのひだのようだ
紐でひきしぼられていないのに
天井の方へたぐられているからだ
悲劇の少女にはふりむく真の正面がない
水色のスカートの腰をよじって
ねぐらへ鳥の飛ぶのを仰ぎつづける
だからうしろへ廻って祭壇の隅に
こうばこして大髭をうごかす猫の存在を知らない
遊戯の運動をくりかえしつつ
静止する一瞬間を捉え
手をなめたり耳を掻くその灰色の猫
意識と無意識の中間に位する
猫の沈黙は恐しい
*
エスキモーはどうして猫を描かないのだろう 昨夜カナダ・エスキモー展を巡りながら わたしと妻はふしぎに思った 多くはモノクロームのあざらしと魚である 白い歯をむき出して 氷の山の頂に 星のように輝いているせいうち そのほかはふくろうの絵ばかりだった 地中に眠る魚の葉骨を咥えて 斑のある羽をひろげている母喰鳥 その眼は女の驚きの表情だった 暗い花の群生のなかで 折れた翼を敷いている もう一羽の大きなふくろうをみつめていると やがて猫に変貌するように わたしと妻には思えた 薄明のエスキモーの国には あとは子供と犬しか住んでいないのだろう
*
「火食鳥を撃ちおとすことはわたしたちの習慣にはない」
燃える羽ぶとんのなかで
死せる王と王妃の装飾過剰の歴史と
黄金の蛙股のベッドの脚の下で
恋する三匹の猫の神話を――人は知っているだろうか
「黄金では爪がとげない 太い木の柱がほしいよ」
声する猫を追いはらって
「猫はきらいよ だって抱いても ぐにゃぐにゃして
支柱がないんですもの」
古代の閨秀詩人はそのような言葉を遺している
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
生誕(⑧・10、20行)
4月
草上の晩餐(⑧・13、35行)
自転車の上の猫(⑧・15、18行)
異霊祭(⑧・19、8節161行)
5月
絵画(⑧・18、29行)
7月
メデアム・夢見る家族(⑧・21、75行)
不滅の形態(⑧・16、20行)
10月
舵手の書(⑧・22、5節75行)
白夜(⑧・23、28行)
12月
ゾンネンシュターンの船(⑧・24、5節89行)
初出は《讀賣新聞》(読売新聞社)1974年3月24日〔35051号〕二三面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、8ポ1段組、20行。「エッチング・出岡実」。
横板の上に支那服の上半身をのぞかせ
一人の男が祈っている
手を組み合せて
半数の爪は黄色い木片のようだ
かたわらの毛布の下に
横たわっているものが
その妻かも知れない
大きな口のなかで鋸歯を挽く
膿の花をところどころに染めて
包帯がその琺瑯質の太股を
遠くから巻いてくる
傷つく母なる声
支那服の男の裾は遙かなる闇へ拡っているようだ
竜や香華の紋章をつけた
朱の太い柱の方へ
そこだけが明るく
男と女のまわりは停止しているのに
回転している壺やナツメの実
よく見れば
一人の男が生れつつある
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1974年4月号〔17巻4号〕八〜九ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組、35行。
ヒンズー教寺院の庭を巡り歩く
多くの夜は
小さいものから大きくなる
大きいものから小さくなる
現実世界へ照応する
肉体を考察し
ビスケットを噛り
わたしは長椅子にながながと寝る
モーヴ色の部屋
たちまち謎の植物が成長し
ここはまさしく
「生き埋めの王国」だ
パラソルをさした
古代レディーの妖しい笑に誘われる
慈悲の詩
「雨期には
ヒルが人の足を噛む」
繊細な構造の世界から来る
わたしは想像上の旅人
いま両手にあるものは
固い物と柔かい物
それぞれを持ち
あまつさえ腐る物を口に咥える
恐らく死ぬときまで――
その暁に大切な心は
永遠にぬれざる
死の内なる亀
恩寵があれば
紐の張りわたされた
聖なる水蓮の咲くほとりへ
着くだろう
髯をはやした二人の友と
半裸の若い女のたわむれている
草の上でささやかに
食べる
初出は〈松井喜三男展「少年少女」〉パンフレット(青木画廊)1974年4月13日、本文新字新かな使用、10ポ18行1段組、18行。《夜想》再録ページの絵は、松井喜三男(1947〜81)の〈自転車の上の猫〉(サインの年号は「〔19〕71」)。
詩篇〈自転車の上の猫〉〔初出形〕の再録 出典:《夜想》第19号〔特集★幻想の扉〕(ペヨトル工房、1986年10月17日、九四ページ)
マツイ・キミオの絵によせて
闇の夜を疾走する
一台の自転車
長い時間の経過のうちに
乗る人は死に絶え
二つの車輪のゆるやかな自転の軸の中心から
みどりの植物が繁茂する
美しい肉体を
一周し
走りつづける
旧式な一台の自転車
その拷問具のような乗物の上で
大股をひらく猫がいる
としたら
それはあらゆる少年が眠る前にもつ想像力の世界だ
暗喩的に
薄明の街を歩いてゆく
うしろむきの少女
むこうから犬が来る
初出は吉岡実《異霊祭》(書肆山田〔書下ろしによる叢書 草子3〕)1974年4月25日、四〜一八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号13行1段組、8節161行。
1
朝は砂袋に見える
岬
夏の波の寄せる処で
母親を呼ぶように
紅い布を裂き
趣味のよい書物をひもとく
アラン
きみが叙述した矮小種族の好む虹色の二字
〈肉体〉
オパールの滝のなかの美貌の妹
沈む壜に入っている
玉
死を近づける
また破裂をもたらす
新鮮な魚の目のように
何を待つ
アラン
悲劇とは仮死のなかの仮生
2
雨の日に
しみじみと歩く郵便夫一人の生活
べんべんと生きる詩人一人の夢
アラン
きみは発見する
鉤形の月の下に棲息する
画家の魂をもつ鳥
叢をさまよい歩くアオコヤツクリ
彼の探すものは
彼の生活帯のなかにはないのだ
枝や木の実やワラジムシの世界から翔びたち
危険な世界を通り
青いものをあつめてくる
青い布 青いガラスの破片 そして青いハブラシ
人里から青い王冠を咥えて
巣に帰ってくる
聖領の鳥
3
アラン
われわれには必要なものがありすぎる
必要なものから
より必要なものを選び
それはたしかに必要だと考える
われわれには不用のものがありすぎる
不用のものから
より不用のものを選び
それはたしかに不用だと考える
そしてたえず不用のものから
必要なものをつくるんだ
たとえば
「精神の外傷」のようなものを
4
アラン
「蛋白質を最初に食べる
のは死人」
では
「最初に口をきくのは家畜
番人の妻」
たまたま春の太陽が輝くならば
彼らはともに海原を水滴のように
回転し
漂ってすすむ
まるで
きみらの汚辱の家から
なめくじが母国を探すように
星への旅をつづける
いってみれば滞る〈現在〉と称する
われわれの〈時間の塩〉の下で
ぽっかり濡れた孔が
現出する
いや反対に消滅するんだ
アラン
なめくじは遠くへゆく
人の通わぬ孤絶の島へゆっくり移動する
秋までは
蝶や蜜蜂は華やいでいる
或る高さを保って
花冠のほとりに
5
テーマはあらかじめ設定できる
しかし生物の運命は
毛皮のなかの痕のように昏くて視えない
ルドンの銅版画の過失の点の黒
鐘をつくのが仮面の人なら
涙するのは誰?
よじれる縄に永遠に縛られる
アラン
仮面の兵士の大きな口をのぞいてごらん
赤いぬるぬるの舌ではなくて
その奥深い闇の器には
鉄の玉が突き出ている
アラン
酩酊せよ
陰気な兄弟とともに
聞こえぬ鐘!
やがてわれわれの都市に雪が降る
のでおごそかに
出口が閉ざされて
いるように思われるのだ
内側から力を入れて押したら
二つに割れて
春の鳩が数羽とび出すだろう
アラン
くすぐったくはないか
ゴシック装飾の扉の中心の合せ目に
木の枝が少し触れている
6
続くものは続き
続かないものは続かず
というのは真理かも知れない
続くものから
続かないものへ
形態を替え
言語を替え
色彩を替えたら
アラン
きみの夜半の作業は
みじめな胡瓜のうらなりにつらなる
妻の不幸なる生涯を
美しい物語につくるんだ
茄子の花はうすむらさきに咲く
口紅は濃くしてやって下さい
死顔には
それなりの〈生命〉がありますゆえ
「馬のかたちをした煙」に
妻をのせて
アラン
きみは行き行く
氷る父親の土地へ
7
人は生活費のために
他人のいやがる仕事をする
われわれの考え及ばぬ奸智さをもって
アラン
『貝類学の手引』をでっちあげる
内部しかない貝
そしてたえず巨大なものを産む
サンゴ色の膜
英雄から精神異常者までまるごと孕む
恐しい貝の研究
罪な分析を忘れるべく
アラン
われわれは外套を着て
酒の街へ出る
一匹のうずくまる猫を探しに……
はだしになる
栗色の毛深い処女
エリ!
8
蓮の葉のかげで
ほそぼそと生きのびる人
兎の耳をつるす
国家を守護する人
われわれのなかの理想的な生き方ではないか
まさに意味ある誤解
それらの世俗的営為せる者は
仰向けに倒れる
石があれば石の下に
アラン
きみは渡り歩くだろう
大鋸の刃の輝く観念の世界から
「影に似ている」
その物自体を求めて
毒蛇のとぐろまく道を行く
そこには奥行がある
アラン
きみとわれわれは
いましばし試みようか
「山上の石けり」を――
1974・2・14
初出は《風景》(悠々会)1974年5月号〔15巻5号〕五四〜五五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ19行1段組、29行。「カット・風間完」。
画家がテーブルを描くとき
最初に灰色の物質を
心のなかに塗る
「見るとは
眼をとじることだ」
それによって
籠の洗われた韮や莢豆
緑の野菜類がストイックな影を加える
六月の午後は
肉類を煮ながら
いよいよ高みへ至る
大鍋の下から
女中の指を噛む
炎の形が出てくる
そこでテーブルは前方へ傾き
犬は庭へ戻る
皿の上で内包され
西洋李の〈赤〉は実相の中心になる
それを食べる子供の
黄金の口を見よ
しだいに外観はあいまいになり
「われわれの見得る
物は数すくない」
胡椒挽きや胡桃割り
それらの器具しか存在しなくなる
だから
厚盛りの背景は
いくつもの記号と言葉に分割され
闇へ流出する
初出は《文芸展望》(筑摩書房)1974年7月〔夏・6号〕一〇〜一三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、75行。
わが家族はつどい来る
その紅蓮地獄の内部を見よ
エーテルはとどこおり
寒冷でもなく白熱でもなく
それでいてあらゆる肉は焼き上る
メデアム
はるかなる星の光が届く
黒いシジミの水桶へ
その中間に
仮想物質がびまんし
波の形をした死者が泳ぐ
メデアム
わたしはなつかしき故郷の納屋にねて
ながながと語る
何から何まで
形而上の問題になる
ふかふかした物体の上に
寝ることの大切なことを群衆に説き
足の方から
モーブ色のスリッパをぬいで
地上に落とす
自然の葉の茂る泉のほとり
わが父は燕尾服のまま横たわる
死のためでなく
生きるために
種子を保存する
メデアム
亀裂せる妹の腹を越え
やがて翼をつけた砲身のように飛ぶ
仮想敵がいるようだ
母は魂の全一性を支えて
いる針金のようなもの
空はあくまでも青く
「美神の絞殺」は行われているんだ
入子風ボートに乗って
いそいそ葬式にきた
屋根職人がつくる
天蓋の下は不滅の闇であろうか
とにかく大鍋の下で
火種を養って一家団欒せよ
運ばれてくる
それはブツブツ泡ふく鵞鳥のからだと脚
セロリの七、八本
料理は言葉で出来ているらしく
時がたつと変色する
メデアム
そこで大理石の土台が据えられ
わが母は記念柱となる
わたしはそのような霊界がすきだ
仮面をかぶった兄ならば笑えるだろう
岩窟の前に立ち
考古学者のように
力でもって万物の化石を引き出す
綿で包まれた炎もともに
いま長椅子の上へ
やけどした姉がとびあがるとき
死せる虎の皮は美しい
もちろんわが家族は
わたしの恋人が裸になることをのぞんでいる
四つの円柱がまもなく立つ
わたしの人生の恩師も
小さな入口から入ってくる
両刃の斧をかかえて
これが到り着くところ
メデアム
水はいつも流れている
人は横梁を渡らなければならない
底があるとしたら
底には血がたまっているんだ
縄と皮の張られた土地には
旅人の求めている
筒深い百合の花が咲く
これが牧歌的生活ではないか
たのしきかな 夢みるはらからは浮遊する
メデアム
初出は《別冊小説新潮》(新潮社)1974年7月〔夏季・26巻3号〕二四〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ12行1段組〔コラム〕、20行。「本文カット・原田維夫」。
わたしに必要なのはミカンの皮でなく
「不滅の形態」だ
長く細い針金を使って
はるかなる地下の象の骨格を調べる
それは繊細な構造をもち
毛根のような緑の夢をはらむ
花嫁衣裳の内部に似ている
石壁の迷路を行け
たのしいこともつらいこともある
大豆袋の下にはネズミが棲む
倉庫の梁をわたり
わたしは血豆を創造する
いつも思考しながら
歴史家は滝のなかで女を幻視し
「萬物」の母だと考える
「萬物」のなかには父は存在しない
わたしが心から求めているのは
打ち付けられた夥しい釘と
生皮を張った堅い板
「不滅の傷痕」そのもの
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1974年10月臨時増刊号〔17巻11号〕八八〜九一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ25行1段組、5節75行。
瀧口修造氏に
1
雨は
夏の仙人掌の棘の上に降る
それは一つのスタイルだ
ガートルード・スタイン嬢は語った
「人間の死の充満せる
花籠は
どうしてこれほど
軽い容器なのか?」
それを両手で支えて
眼をみひらいて近づければ
「光をすこしずつ閉じこめたり
逆に闇を閉じこめたりする」
これは近世の神話といえるんだ
2
砂漠近くの映画館で
われらは観測する
地上の星・ガルボ!
きみの巨大な唇をたどれる不死の人は存在するだろうか
きみがもし物を食べているとしたら
それは不思議な時間である
きみの黄金孔のなかに
たえず消えてゆく漂着物がある
肋骨 岩石 羊飼い 詩
鳶の輪が無限に近く拡大される
その下にあるものは
唯一のメモリアル
「五月のスフィンクス」だ
3
われら〈弟〉は考える
〈母〉は烏髪と長い乳房を持つ
しかし
〈姉〉は内部に一個の螢石を
匿しているにすぎない
虚無の苦痛のなかに
星と砂と
「鳥は完全なるものをくわえて飛ぶ」
だが水底では
魚は不完全なるものをくわえて泳ぐ
太陰暦の春に
われら〈弟〉はいつも見失う
〈姉〉という呼称の人を
「彼女は未知の怪奇なけむり
を吐く最新の結晶体」
火花のなかで
枯葉のなかで
4
「朝食のときからはじまる」
表現行為のなかには
われらの眼が吸う飲物がある
ストロベリージュース
のように
色であって色でない
犯罪者の歯がバリバリ噛む
キャベツの芯のように
形であって形でない
名づけようのないもの
「曖昧な危倶と憶測との
霧が立ち罩めようとしている」
声と言葉の
記号の世界にも……
5
人は自由な手を所持している
それゆえに
不自由な薔薇の頭を大切に抑えて
「黙って
歩いていってしまった」
それは形態学上
きわめて自己撞着的だと
へンリー・ムアは夢の王妃を鉄で造る
炎のような内面
オレンジのなかの黒曜石
それが島だ
青い海をリードする
舵手と蛸
なぜ夜明けの聖像群はフィルムのように
灰色に沈んでいるのか
詩を書く少年の腰のあたりまで
白い波がうち寄せ
龍骨は海岸に出現する
初出は《鷹》(鷹俳句会)1974年10月号〔11巻10号〕一八〜一九ページ、本文新字新かな使用、五号二分アキ17行1段組、28行。
たしかムンクの絵の主題に
〈病める少女〉
というのがある
わたしがその絵を
見い出した時
そこに秘められた昔が視覚化され
「とても重大なことだ」
と考えた
パセリの緑の葉を
口の端にくわえて
次から次へと
清潔な敷物の唐草模様の上を
跳びはねてゆく
「少女はつねに死体である」
というのは
家畜商人の符牒だ
寒い国では
「寝台の脚のまわりに草が生える」
白い壁に白い旗を掲げ
テーブルの上でキノコの
ごった煮を食べている家族を
わたしは想像する
やがて膜が張られて
牛乳の巨大な桶のなかに
夜明けが来る
それから切藁を
食べる馬が見えるんだ
氷れる山嶽の上に
初出は《ユリイカ》(青土社)1974年12月臨時増刊号〔6巻15号〕四六〜五一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ26行1段組、5節89行。
1
「罪深い魚は泳ぐ方角をまちがえている」
これは病人のうわごとだ
われわれの泳ぐ
海とは汎自然的で
すべての波は円環のなかを
車輪のように廻っている
肋骨の間のハートのように
巣の上の卵のように
いまだギリシアの紋章は遠い
船窓から望まれる
道徳的な陸地は
緑なす断崖に一個のリンゴを輝かせて
透視される「大地の軸」が在る
2
猛けき雷鳴のとどろく
われわれの都市へ人々は集まり
サンゴや砂を発見する
ときには反歴史的な
言語や死に方を選ぶんだ
水を求める者とともに
「うずらは地に巣をつくる」
というのになぜか
人は頭に巣をつくり
とてつもなく大きな〈ウロボロス蛇〉を
不用意にも産む
一枚の絹に包まれる
われわれの〈太陽星[ゾンネンシュターン]〉を仰げ
口許には赤いグラスをみちびき
「もうすこし言葉すくなに
もうすこし呼吸を多く」
人は生きるべきだ
3
「六匹の塩漬鯡を肋木に
鉤で引っかけ
藁マットに火を放つ」
これこそ本当に哄笑する精神なのだ
それから動物園通りを歩く
家出人
その特徴(身長 手術あと 歯の治療 いぼ ほくろ)
などであるから
室内温水プールで見つけよ
水着の美女の尻
ムラサキ色の蝶のとぶ
夏の終りに
「ゾンネンシュターンの大演説が聞えてくる」
人よ 荷物を運搬するな
人よ 手を運べ
人よ 心を運べ
4
画家が生きるためには
「四つの占領地帯」が必要だ
「なにゆえにテーブルには四つの脚
馬に四つの脚」
と問うことは冒涜だ
わたしの母は
四つの乳房を持ち
悪しき子供たちを養っている
青銅の庭で
サボテンを栽培する
(花を持った蕾状のもの 金平糖のような芽
掻き子の季節)
棘の上の露
精霊を呼びながら
「地に
空に
そして海に
新記録を
達成する女」
そのうえ時間の領域でも
尻と顔の共存せる
偉大なる乳母
形而上の母よ安心せよ
「世界には雑草とわたしとかぶら」
しか存在しないのだから
5
虹の砂漠から
大股で女軽業師が走ってくる
ヒキガエルやワニを踏みわけて
「逃亡する魂」は気高い
円の地平を越え
湾曲する湾から出航する
船に「生の合乗り」がはじまるんだ
幕舎には兎の神
森にはめしいたライオン
はるかに巡査は影絵のように見え
われわれは岸を離れる
菫色の鳥は翔けよ
無効なる汚物の上を
船ならばやがて沈むだろう
予言者ゾンネンシュターンは願うんだ
色鉛筆で紙に描かれた絵ならば
すみやかに
忘却されることを
註 ゾンネンシュターンは「幻視者」といわれる異端の老人画家。カッコの中の引用句は、同展覧会目録より借用した。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
サイレント・あるいは鮭(⑧・25、41行)
7月
悪趣味な夏の旅(⑧・26、6節72行)
9月
示影針(グノーモン)(⑧・27、5節79行)
カカシ(⑧・28、15行)
11月
悪趣味な内面の秋の旅(⑧・31、7節145行)
12月
あまがつ頌(⑧・30、Ⅴ節90行)
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1975年1月号〔18巻1号〕一〇〜一一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ25行1段組、41行。
芦川羊子の演舞する〈サイレン鮭[じやけ]〉に寄せる
薄明の山の川を遡る
鮭のからだは空胴のように暗く
多くの物とすれちがう
ときに死せる子供と
母親はかがんだ姿勢をして
入ってゆくようだ
冷たい半肉の伽藍へ
時経ると血が噴き出される
そのほかもろもろのもの
水垢
小骨
手桶をもつ男
綿菓子
きわめて日常的な万物が流転する
水面すれすれに
赤紙飛行機はとどまり
野の百合は飛翔する
暁の丘へ
のぼる若い女を見たことがある
二股の美しい尾をかざし
〈還元不能〉な言葉を求めているようだ
寺院の石階の下に
半身は汚れた藁で覆われて
顕現される
よこたわる鮭と
鉤にかけられた青空が在る
人はいつも人とすれちがい
水流のせせらぎを聞く
鮭はしばしば真紅の炎と遭遇する
別離の日々
〈時〉めくサイレンは鳴りひびく
塩漬の世界とは
永い旅の終りの比喩ではないのか
物はいつも物によって壊される
浄化された闇のなかで
若い女が襦袢をぬぎ湯浴するとき
肉体はほろび 一つの〈模像〉に還る
サーモンピンク
サイレント
鮭の皮
そこで人は眼をとじ口をとじ さびしい夢をみる
初出は《新劇》(白水社)1975年7月号〔22巻7号〕五八〜六一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、6節72行。。表紙に「詩 吉岡実 悪趣味な夏の旅」とある。
1
ギルバートきみは善良すぎる
時計の竜頭を巻きながら
吊り棚から一丁の鋏をとり出して
旅へ出る
2
わたしは友人だから
ギルバートきみの好きな常套句を引用する
「人間の体はきわめて凸凹がある」
そしていつもその周囲を
きみは廻りつづけている
ドラムカンのボデーを計るように
中腰になって
ギルバートきみは
夕暮れの街を歩く
3
モスグリーンの彼方へ
吸盤の花咲く妹と母を立たせて
ギルバートきみは
朝顔とダイヤモンドの都市から
追放されたのだ
それはまるで
「水に運ばれてゆく水」
のように自然なことなのだ
ギルバートきみの眼から
涙のかわりに黄色い糸屑が出る
ここはどこか?
「永遠に泥まみれの山羊の足」
の国だ
マッチをすると大きな石が現われる
4
「服が体に合っていない
と首のまわりに突っぱった
骨が出る」
だからギルバートきみは
死にかかった兵士の制服をつくるのは下手だ
布と手足と
「どちらが長く どちらが短いか」
いつまでも考える
ひなげしの咲く
野原に坐って
5
仕立職人の仕事には
非日常的な面がたぶんにある
「鹿はどこで水を飲むのか?」
ギルバートきみはそんなことを思いながら
半ダースの針を口にくわえる
それから暗い電燈をつけ
巨大な布地を鋏でジョキジョキ裁断する
その粗い毛織物の下で
事実うごきつづけている
意識や樹木や霧
もしくは肉体がある
ギルバートきみのデッサンは正確だ
紙をあてて腕や胸の線をなぞり
さいごに腿のところでテープを貼る
夏の日盛りの庭で
まるで青い食べ物のように
蒸気を出す
笑う女がいる
6
わたしは友人だから
ギルバートきみの仕事の仕上りをみとどける
「切りきざまれた
世界
布地の切口と切口を縫合せる
できるだけ平らにしてのばして
目的物を包む
それでも包みきれないものが突っぱって出たら
カナテコで叩き
びらびらした余分なものは
糊で貼りつける
当然それは内部増殖する
無理な形で
地平線までせりあがる
だから手順よく濡らして
生地をひっぱりながら
熱いアイロンをまんべんなくかける」
初出は《ユリイカ》(青土社)1975年9月号〔7巻8号〕一〇四〜一〇八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、5節79行。吉岡は1975年8月31日付の永田耕衣宛書簡で「猛暑の夏も今日で終る―この八月の最後の夜、やっとご返事が出来るようになりました。新句集《冷位》を一早く、渡辺一考君を通じて頂きながら、お礼を申上げずにいたことを深くおわび致します。丁度そのころ、ユリイカ九月号〈渋沢龍彦―ユートピアの精神〉という特集号の献詩を書いていました。そして恐しく心身を消耗していたからです。」と書いている。引用詩句に関しては〈〈示影針(グノーモン)〉と《胡桃の中の世界》〉を参照のこと。
澁澤龍彦のミクロコスモス
1
「少女は消え失せ
はしなかったけれども
もう二度と姿を現わしはしなかった
現われて出てくる
やいなや
少女はすぐさま形態を
なくした」
それはとりわけ雷雨のはげしい夜
わたしは観念と実在と
つねに一致する
客体としての少女を求めているんだ
その内部にはしばしば綿がつめられている
「デルタの泥土のなかで
花を咲かせるという
大いなる原初の白蓮[ロータス]」
少女は言葉を分泌することがない
2
「わたしは幼年時代 メリー・ミルクというミルクの
罐のレッテルに 女の子がメリー・ミルクの罐を抱
いている姿の描かれている」
その罐を抱えている屋敷の女の子を眺めながら
わたしは水疱瘡に罹っていた
どんぐりやさやえんどう豆のなる
田舎の日々
体操する少女のはるかなる視点で
わたしは矮小し
「動物と植物の中間に位置する
貝殻や骨や珊瑚虫」
それら石灰質の世界へ
通過儀式を試みる
3
漁師がやってくる
神話からもっとも遠い処まで
捕えたものは
一匹の鰈
「ロンボスの霊」
わたしの調査では
「ロンボスなるものの実体が まるで雲をつかむ
ようにあいまいもことして つくづく驚かされる」
わたしの好きな無へ奉仕する道具
螺旋志向!
「アパッチ族のシャーマンは ロンボスを回転さ
せて不死身になったり 未来を予見する」
そもそも
ここには受胎も生産もなく
「ロンボスとは 子供の玩具以外の何物でもない」
素朴な唸り声を発している
「青銅の独楽」
かも知れない
4
わたしの夢みる動物類とは
「不死鳥[フエニツクス] 一角獣[ウニコルニス] 火蜥蜴[サラマンドラ]」
とくに珍重するものは
「フップ鳥」
わたしたちの対象となり得ないもの
動物から天使までのあらゆる存在に
変身する可能性をもつ
「フップ鳥」
「女を一個の物体の側へと近づける」
媒介をして
亀甲型の入れ子を多数うませる
「フップ鳥」
一度語ったことについては二度語ることはない
一度行なったことについては二度行なうことはない
「フップ鳥は母鳥が死ぬと
その屍体を頭の上にのせて
埋葬の場所を探し求める」
火のなかを
水のなかを
或は土のなかを――
5
「人間の想像力は 或る物体が一定の大きさのまま
留まっていることに 満足しないもののようである」
それと同時に
織物の目を拡大し
生命を縮小させる
わたしたち人類というものは
「最初の時計から
最初のセコンドが飛び出して以来
それまで神聖不可侵と考えられていた
自然の時間
神の時間が死に絶え
もはや二度と復活することがなかったのである」
*示影針=日時計のこと
初出は《旅》(日本交通公社)1975年9月号〔49巻10号〕二〇〇ページ〔対向の二〇一ページは後出カラー写真〕、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、20級1段組、15行。「嵯峨野の案山子 '74「旅」写真コンテスト入選作品 カメラ 河原誠三」。
シジミの化石の出る
水田の周圍から夏は逝く
男と女の仮相をして
「夜も昼も立っている者」
の棲む処では
鳥の群も向きを変え
羊羮のような山の方へゆく
「焼魚
蓮根の煮つけ
冷飯」
の食事は終り
夢みるべく人はみなへちま棚の下に集る
この村落では言霊とともに
目隠しの屏風のなかで
赤ん坊が生まれる
初出は《文藝》(河出書房新社)1975年11月号〔14巻11号〕二二四〜二三一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、7節145行。「本文カット/吉原英雄」。吉岡は1975年8月31日付の永田耕衣宛書簡で「〔……〕過日、〈琴座〉三百号記念号へ執筆せよとの速達の手紙を頂きながら、今日まで明快な返事が出来ず困っておりました。それは、西脇順三郎《詩と詩論》月報の締切が同じころという巡りあわせがあるのです。その構想も出来ず、まず十五枚という小生うまれて初めてともいうべき枚数に、毎日おろおろしているところです。その上、運わるく(これもすでに二カ月前に依頼されたもの)ある文芸誌に長い詩を書かねばなりません。小生は、二つも原稿書きがあると、どうしても気が散ってうまくゆきません。」と書いている。
1
内なる旅とは負の回路をめぐり
霧のたちこめる入江から
ねこじゃらしの茂る道を行く
「目覚めて夢みる人」
殺虫剤の臭う街の日々
生者は苦役にはげみつつ
死者はサングラスをかけて休息する
バイオリン形の女を求めて
旅する者はときに少年のように
転倒する
旅[トリツプ] 夢遊状態[トリツプ]
こわれるものがあり こわれないものがあり
こわれつつあるものがあり
その中間に分裂するものがある
転倒する道化師
転倒するフラスコ
転倒する言語
転倒する建築物
すべて過剰なもの
一茎のアネモネのほかは
2
妊娠やはしかのように
突然やってくる悲劇の正常性
「時」の皮膚をただれしめたり
反対に「水」の流れを止める
非現実性の湾に泛ぶ
一個の梨がある
あたかも存在の核が空っぽになった
種の人間
種の下降へのねがいとは
死へ向ってささやく
耳にここちよい子守唄
旅する者は肉襦袢を脱いで眠るだろうか
雨にぬれて鷹がとぶ
3
「風景
それはある魂の
状態である」
旅する者の地上に
いまや残るものといったら
そらまめの花か
空洞体にすっぽり収まる同量の闇だけ
それすらフレーム
だんだん縮小するフレーム フレーム
フレームの内側に抑圧され
「女の肉体の天然の富は失われた」
あきらかに
アルミニュウムとガラスの被膜づくりの
立方体の天井から
発生しはじめた赤い糸屑は浮遊する
施工人は驚き 庭師も驚く
旅する者はみずからの
相似形の骨体を求めて歩く
みちびきの犬が小便をかけまわる
ヒースの草むらを通り
雄型の池をめぐる 微風のように
雌型の花壇をめぐる 冷水のように
そしてわれわれの旅する者は
倒立像に化す
霜ふる芝生の枯れた園に
器官[オルガン]のごとく
しかし其処すら
「仮泊の場にすぎない」
4
「自然と精神のあいまいな境界に位置する
幼児という存在には
動物から天使までの
あらゆる存在に変身しうる可能性がある」
われわれが知っている
隣人の幼児はやわらかい手足を持ち
泣いたり 尿をながしている
しかしその実相としては
かれらまがまがしき「幼児」は漂泊を試みているのだ
内的な戦闘を経験し
堅固な家のベッドへ戻ってくる
「幼児」は姉妹にみとられて
粘土ののっぺらぼうに化す
或は地獄をおしすすむ英雄になる
5
われわれが「アドニス」と呼称しているものは
ことばの産物にすぎない
しかし内的な衰弱を感じる
われわれ旅する者の側からみる
父親のすがたとは
形状をととのえている夢の「アドニス」のひとり
もしくは母親の縫っているうぶぎに包まれた
影のかたつむり
擬似男性
われわれが「ヴィーナス」と呼称しているものは
ことばの詐術にすぎない
秋の夜は挽棒状の脚
梯子状の背もたれのある
椅子に腰かけ
旅する者は考える
6
われわれに
近づいてくる
機械が変質を仕掛けてくる
かぼそい砲金の管や鉤状の機械は潤滑油にぬれ
ハイスピードで繊維を紡ぐ
そして花模様をゆっくりと織りながら
空気入りの物体を包む
それは正四角の木箱
といえばそう見え
または弾力あるタイヤ
と思えばその手ざわりがある
情緒的な雰囲気で
母親がのぞきこめば胎児を確認できるかもしれない
ぐっと見方を替えて
砂まみれの顔せるわれわれの友
旅する者の眼差しには
水遊びのあとの少女が夢想される
イナンナ
イシュタル
薄明の世界に遠のく
いにしえの地母神像
燐!
7
「パンヤをヘラのような器具を使って
奥のほうからたんねんに詰め込み
女神像を作る」
種族の住む処を求めて
メンルン氷河地帯に入った
われわれの探索の終りかもしれぬ
旅する者は見聞するだろう
アフロディーテーの化身たる
生ける女神を仰ぐ
「ガラスの壁にへだてられている
感覚(世界)」の彼方
おお〈雪女リディニ〉が出現する
『ああ美しきかな
なんじの瞳は鴿[ハト]のごとし
なんじの腹はつみかさねたる麦のまわりを
百合花をもてかこめるがごとし
なんじの頸は象牙のやぐらのごとし
なんじの唇は石榴の半片に似たり
なんじの髪 体毛は葡萄のごとし
なんじの身の丈は棕櫚の樹に等しく
ああ偉大なるかな』
イナンナ イシュタル ヴィーナス
この世の高き処で
雪の泡をはんらんさせ
聖なる氷の床の上で
雪男と〈雪女リディニ〉の婚姻が行われた
白一色の不定形のもののまぐわいとは
おたがいがおたがいを抱き込め
月光を浴びつつ反響し
消し去ってゆき
自己同一性を成就する
「われわれは本当に自己の身体のなかに収まって
いるのだろうか?」
旅する者はわが心に問う
1975・9・22
初出は《ユリイカ》(青土社)1975年12月臨時増刊号〔7巻12号〕二〇〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、Ⅴ節90行。
北方舞踏派《塩首》の印象詩篇
Ⅰ
すでに秋
自転車のチューブのようなもので
全身を巻かれ
雨のなかに立って
馬がいるじつに寂しく
藁と泥で盛り上った結界に
開かれた口が在る
魚や獣の骨片を
人々が隠蔽するために投げ入れた
汚れた穴から
長い杖をふりかざして
胎内のからくりを
告発しながら
這い上ってくる者がいる
杖で叩かれた周囲は陥没した
粟飯
蝗
稗の穂はなびき
まるでゴヤの描く
紅服の美少年が出現する
地に乳は溢れ
〈物語[イストワール]〉のはじまり
Ⅱ
棺桶の底で
塩をきしませ
こってり明礬をきかして
紫の茄子を染めあげた
飢餓説話を伝承せよ
うろうろするあまがつの子供たち
「月下に影を落さぬ
ランプ」
そこにさんざしの花を飾り
腰高障子にかこまれて
紙一重の
かもしかの生死を視よ
シャーマンは北方志向す
はぐろの荘厳の山へ
ざらめ雪は降る
人々は黒塗りの首をたれ
火打石を打ちあわせては
火種を取り
肉体を回収する
混合物[アマルガム]の闇のなかより――
Ⅲ
干葉汁をすする歯黒の童女かな
*
葛山麓糞袋もたぬかかし達
*
湯殿より人死にながら山を見る
*
雪おんな出刃山刀を隠したり
*
喪神川畜生舟を沈めける
*
線香花火塩首なればくずれけり
*
あけびの実たずさえゆくやわがむくろ
Ⅳ
箸二本を持ち めし碗のふちを鳴し
雪の野原をさまよいゆく
白子の五人の姿が見えるか
聖像画のように
杉の葉で呪縛されたまま叫ぶ
「キントンが食べたい」
肉体は閉ざされ
電圧は極点まであがる
しょせん〈魂の在所〉は無いのだろうか?
女は紙と鋏しか所有せず
幾粒かの黒いクレオソート丸を噛み
膠を煮つめて夜は
漬け物樽の辺を歩くじつに悲しく
この濁世での尋ね人
(霊と繭の中間)の
絶世の美少年は宣言する
観念を守るために
土石柱を
既成言語を
〈タスカロラ海溝〉へ沈めよ!
Ⅴ
紫の嵐の波は
風がつくるものでなく
数多くの生身の男たちがつくる
透視された内臓の波
ゼラチン状に
肉の岸へ打ちよせ回帰する
花の拷問図法
精神的な女は人形をつくる
「木毛 ハリコ 桐粉 鉛などで
形づくりをして
蝋絹 ときにはメリヤスを張る」
現在もっとも必要とする
うつろな頭をすげかえ 手足をとりかえ
血肉の壊滅は行われた
廃物穀物倉の暗い片隅での
〈物語[イストワール]〉の終り――
骨折り 肉たたみ
愛する美少年と
チューブの馬は同一のままである
顕示された穴へ
混合物[アマルガム]として再び埋没する
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2月
人工花園(⑩・19、*印で4節に分かつ34行分)
5月
少年(⑧・29、6節53行)
8月
楽園(⑨・1、31行)
10月
子供の儀礼(⑨・4、56行)
11月
曙(⑨・8、65行)
12月
部屋(⑨・2、34行)
幻場(⑨・13、38行)
影の鏡(⑩・17、11行)
初出は第一回三人展記念《ALICE IN FLOWERLAND――花の国のアリス》(未生流中山文甫会)1976年2月4日、一〇四〜一〇七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、12ポ25字詰13行1段組、*印で3節に分かつ34行分。
農家の納屋に人々はどうして最初に入らなければならないのか? この大地で生きる人間なら、そこがもっとも自然な入口である。
干草のつまれた上に寝ているのは、家畜じゃなくて、アリスのすてていった人形たちと赤錆のストーブ、馬鍬。では首の太い牡牛の灰色のがんじょうな姿は、どこへ行ったのだろう。とるこききょうの咲く野を越え、がまの穂や羊歯の生い茂る沼地へ行ったのかも知れない。なぜなら、人々の妄想の鏡のなかで、すでにアリスの靴や靴下そして下着まで濡れているんだ。
アナナス、アロエ、アンセリウム――この人工の楽園へ、人々はアリスより先にたどりつけるだろうか。
*
人々は枯草色の道草の迷路をたどって行くと、ものの熟れた香りでめまいを感じて立ちどまる。そしてじぶんの肉体がさかさまでないのでうしろめたくなる。なぜならば、人々は生まれて初めて、空そのものを足で踏んでいるんだ。生物学的な感触では、ビニール袋の上を歩いているようだ。見あげる天井は暗く、燕麦や大麦の穂がびっしり生えそろって、垂れている、垂れる大地。
青空に咲く花、マグノリア、とりかぶと、メリネ、グロリオサ、ブバリア。
禁欲的な時間とは、たとえていえばこんな水底をのぞく時を云うのではないだろうか。沼の岸べでは、花が花を抱き、水泡が水泡を抱きかかえて、水面まで浮び上ってくる。明滅する光と闇のなかで、人は人を抱く。
われもこう、野ごま。
*
古代の聖人の言葉にこんなのがある。
「人間というのはどうして。
のぞきが好きなのだろう」
だから人々は人生の旅の終りに、巨大なる野イチゴを見つけて、てっぺんの小さな孔から、その内部を覗くんだ。なにが見える?
アマリリス、あかのまんま。この憂き世で、だれもがアリスを見つけるとはかぎらない。
初出は《饗宴》(書肆林檎屋)1976年5月〔春・1号〕二〜六ページ、本文は旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、12ポ15行1段組、6節53行。漢字の旧字使用とひらがなの拗促音の並字使用は、他の掲載詩篇を見ても《饗宴》誌の編集方針だと考えられる。
1
蝶や蜜蜂のように
遠くへ向う
わたしは少年だつたから
草原の平面を割つて
ゆくキツネと狩人に化けた死人を見たようだ
水辺の花は標的のようにおののき
少年の頭髪は濡れる
春はうずらの肥える斑の多い季節
2
「わたしの内密な経験の貯蔵庫」
そこでは芽ぶく玉葱やじやがいものかわりに
青いブドウの房を抱え
生薬屋の娘を抱え
腐るものすべてを抱えて
地階へ降りてくる
観念の大男が見えるんだ
3
理由はいくらでもつく
少年のすきな闇のなかには
柱のようなもの
球形のようなもの
それらが存在する
「男根の切断面から生える巴旦杏」
を採りにくる
農夫の娘を見つけ
わたしは熱い地の風を浴びた
4
箱のなかで成長する
虎がいるように
少年は亀甲体のなかで
日々成長する
しかしいまなお
千鳥という鳥は
図案のなかにしか翔んでいない
外はひまわりの花の傾く夏も終り
5
姉妹よ きみらはどうして
炎で構成されているのだ
すでに
「わたしの魂は松の根に入り
その血からスミレが咲く」
兄弟よ きみらは
松やスミレを焼きほろぼす
6
眼のなかで水をつりあげ
もしくは太陽をつりあげる
水母神がいるように思われた
岩棚の奥に
天然自然のものを
人々は多く窓から覗くことしかできない
だが少年は探す
現し世の彼方に
ときじくの果実を……
そこここでは
事実ものが動きつづけている
「夜な夜な人間を火中に入れて
その死すべき部分を焼きつくそうとする」
美しい漁師の娘がいる
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1976年8月号〔19巻9号〕二〇〜二一ページ、本文新字新かな使用、9ポ23行1段組、31行。吉岡は随想〈藤と菖蒲〉(初出:《現代詩手帖》1981年5月号)の「2 菖蒲」で本篇を引用して、制作の背景に触れている。
私はそれを引用する
他人の言葉でも引用されたものは
すでに黄金化す
「植物の全体は溶ける
その恩寵の温床から
花々は生まれる」
かつて近世の女植物学者はそのように書いた
灰色の川のふちに乱れ咲く
百千の花菖蒲はまるで
翼の折れた鳥のような花弁を垂らす
悪天候の楽園のなかで
私は不可解な麩という食べものを千切り
浅瀬を游ぎまわる小魚を養う
そして妄想をくりかえし
老いたる姉妹のように
木馬にまたがる
いずれにせよ
「人間の全体は溶ける」
かかる時点で地の上に何が遺るか
水の上に何が浮ぶか
見れば見るほど微少なる
「熱い灰の一盛りと
火箸」
それは永遠に運搬できぬしろもの
この世にまだパン粉を捏ねる人がいるとしたら
その反人間的な人の背後を
老いたる兄弟は通り
川のながれにまかせて
夢の波に乗る
謎[エニグマ]
沖は在る
初出は《文藝》(河出書房新社)1976年10月号〔15巻10号〕一六八〜一七一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、56行。本文カット:野中ユリ。
わたしはチョークで黒板に描く
水腫の父の足と指
それからバナナを積む舟を……
母は愛の潮にのって行く
尋ねあてられるだろうか? アスタルテの妹
「朝食に卵をたべる女」
「ドライアイスの函を持つ女」
熱帯では犬の鼻も効かなくなる
母の毛皮姿を想い出す
洗えば洗うほど強くなる穴のあいたもの[、、]
わたしは嬰児でなく現在の姿で
鳩の糞のように落ちてきたのかも知れない
あらがねの頭で認識した
〈女〉のなかには見分けがたい流体が介在する
うごく魚や藻や水
視力喪失の愛
「靴紐が血のように太腿からたれている」
人はそのような熱する女を忘れない
わたしは液状のものを発射する
夜の気配のこめた無花果の木へ向って
アルマジロは汚れた巣のなかで からだをまるめる
褐色の象牙の玉のように淋しく光る
兄は「綿布と三枚の羽でくるまった鉄線」
でつくられた単位フォルム 担架で搬ばれて行った
火蓋 かさぶたは剥落し
わたしの薬莢は炸裂する
藍瓶をのぞく母の股ぐらの闇へ
屋台商人が塩・酢・胡椒を売りに来た
しばしば姉の水浴び姿をかいま見た
「虚空に花降り音楽聞こえ 霊香四方に薫ず」
「天人も 羽なき鳥のごとくに 上がらんとすれば衣なし」
の姦視の〈羽衣〉的な聖性の春であった
父は柘榴を食べ終ると
「拳銃を両手にさげて街を出た」
父の見る芋づる式の夢は何? 芋の葉の露
父は地上に帰らない
旧い伝説によると
「裸の女が蒔いた種子は畑で
よく成長する」
大きな冬瓜にまたがる娘たちがいる
わたしは複雑な構造のものは嫌いだ
単純なものは
月の光を浴びてよく見える
ケシの花のかげで番人夫婦が共寝していた
わたしの求めているのは
「語られる歴史」不妊の母なのか?
「人間の手の下から生まれる」
粘土の女身像は半月の空洞を持つ
カーディナル
恋する女は鵲のように軽やかに松の枝にとまる
禍いの波動そのものだ
「水でなく火によって養分を与えられている」
サンゴ色の祭壇で
「世界が袋のなかに戻る」
日まで待てばよいのだろうか?
わたしの眼はまだ未開の状態のままである
初出は《ユリイカ》(青土社)1976年11月臨時増刊号〔8巻13号〕二二〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、65行。引用詩句に関しては〈吉岡実とエズラ・パウンド〉を参照のこと。
「火の消えたような
褐色の肉類」
を食べながら
われら中年の男は相談する
有ることから無いことまで
そ・う・だ・ん・す・る
「下手な韻文はくりかえし
てはいけない」
物をじかに扱うことが必要だ
ゆえに空気枕を常用する
「ピアノ教師のように
女生徒のうしろへ廻る」
この冬の夜は
「遠すぎて聞えてこない夜鶯の声」
スリルがある てすりがある
狩猟小屋の階段を降り
地上すれすれを飛ぶ
蛾や精霊
「一枚の紙をいまも深くのぞきこむ
習性を失っていない」
ある近代詩人は断言した
「ジャスパー・ジョーンズの作品にはいつも
ある殺人 ある殺戮の
翌朝の感じがある」
叙述的に
一つの彫刻を組み立てる
用語と用語をつらねて
死刑執行書を組み立てる
それによって
「現在の肉食哺乳動物とはかなり異る」
生きものが死ぬ
それは自然なことであって
世間を納得させる
われら中年の男は松明で照らされて
「大きな蚕を一匹
漆喰の壁から抽き出す」
明日は晴れるだろうか
雉の羽の輝く森の空は――
柱に括りつけられた
木の鴨
それがやがて薮や草地へ置かれる時
一つの磔刑図が出来る
「カラカラとゲタ
は兄弟であるのか?」
われらは考えつつコーヒーをのみ
「雨乞いをする人々の
消炭のような顔」
を見るかもしれない
紅鶴の眠っている処は
火気注意!
単調な形と色をくりかえす
雲の峰
干草の山
日当りながら
われら中年の男は芸術様式を信奉しない
「素材は木と金属」
の火銃を捧げ持ち
装弾する
われらを代行して
そ・う・だ・ん・す・る
画家の眼は受像する 墜ちゆく鳥影を
空気は硬く冷たく
「池の水面は
錫箔でなければならない」
曙のはじまり……
注 引用句は主に、エズラ・パウンド、飯島耕一の章句を借用した
初出は《新潮》(新潮社)1976年12月号〔73巻12号〕一四六〜一四七ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、34行。カット:福島秀子。
塵のなかで
「ひたすら美が
ながらえるように」
二人の女は向きあっている
楯形模様の敷物の上で
永い時をともに過すために
任意の距離はたもたれる
年上の坐せる女がたぐりよせているのは
あきらかに緋色の一本の毛糸であって
〈楽句[フレーズ]〉ではない
それは光を発しながら
木蔭を通り
氷塊をぬける
「美は滅びるか
または変化する」
地上で
たぐられているのは
もう一人の若い女の所持する
〈核[コア]〉を包む
毛糸の玉のような物質だ
ひざの間で回転しつつ
濡れたり乾いたり
それは外側から縮小してゆき
やがて草むらに
蛇のごとく消える
二人の女は〈無限〉という概念から
ときはなたれて
「いまでは象牙のように
静止している」
もしかしたら
二人の女のいるのは部屋の内
というよりも
その下は潮がくぐりぬけてゆく
岩棚のようにさえ思われる
初出は《月下の一群》(海潮社)1976年12月〔冬・2号〕〈特集幻獣 Imaginary Beings〉四〇〜四一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ30行1段組、38行。
大通りに
「肉屋のそそり立つ」
スンレオロ街まできて
若い娘は消えた
「不潔な風景」の
川沿いを行けば木蔭のあるきみらの故郷
「星の刻から薄闇」まで
「盗んだ肉」で命ながらえ
靴屋の主人は一つの詩句をくちずさむ
「恐怖がわれわれを襲うからには
われわれも恐怖に反逆しないわけには行かない」
この店の奥はまるで
「ネリアの洞窟のように
大きな巻貝の形をしている」
半分沈んだ舟の
甲板に似た仕事場には
浅靴から深靴までの
色とりどりの商品が竝んでいる
若い娘はいそいそと
緑色の皮のブーツに脚を入れる
靴屋の主人は薬湯を飲み
「咲いている巴旦杏の間で」
プリーツ プリーツとつぶやく
「あら はいらないわ でもデザインはこれがいいし
なんとかならないかしら」
「なんとかしやしょう」
薄荷の香のただよう
「影で刻まれた門」の前で
「鉄靴」をはかせて
「若い娘を老提督と寝かせる」
溶けるローソクの受皿のかげで
靴屋の主人は骨化しつつ
金塗りの喇叭をりょうりょうと響かせた
月下のきみらの生地
スンレオロ街は「木と金属」の素材で出来た
奥行のない平面の世界
裏に廻れば
豆畑がえんえんと拡がる
初出は山本美智代オフセット版画集2《銀鏡――MIRRORING》(アトリエ山本)1976年12月5日、六ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、12級1段組、11行。
観念をまもるために
死や呪いとさえ手をにぎるだろう
わがアミエルの憂愁
たとえ〈鏡〉の影の世界の
できごとであったとしても
「女たちが食べたり 飲んだりする
ことが耐えられない」
この瞑想者の精神のやすらぐ
仮の宿りとは
「すべてが消えさり 分解する」
〈星布〉のなかに……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
悪趣味な春の旅(⑨・19、43行)
5月
螺旋形(⑨・10、62行)
異邦(⑨・5、31行)
8月
使者(⑨・18、6節66行)
紀行(⑩・16、18行)
10月
晩夏(⑨・7、22行)
11月
水鏡(⑨・6、5節93行)
草の迷宮(⑨・9、6節100行)
初出は《日本読書新聞》(日本出版協会)1977年1月17日〔1889号〕一面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行2段組、43行。「カット=金井久美子」。顔写真と80字余りの略歴(誤記・誤植あり)を掲げる。
樹木とろうそくが直立する
青空の下で
「(一文字欠ケ)底からふたたび
地(一文字欠ケ)へ出る」
蛇や蜘蛛
それから涙のような水滴
人はわたしを旅人と呼ぶことはない
まして子供だと言明する
人もこの世にはいない
薄荷の香りにむせつつ春の野を
「卵を半分に割って
食う」
姉とともに行く
「鼠の衣 鴉の皮」
探しもとめて
廃橋を渡り
ついに日暮れては塔の上で
壁の亀裂を見る
月光に照らされて
「石には何の痕跡もなく
灰色の壁は年代記を伝えてはいない」
さなきだに淋しい沼沢地
朝は悪しき葦はそよぐ
「空と地をめぐる
詩の一行」
のごとくに
白鳥が水の上に浮かんでいる
その水を掻く脚が
膨張する局面をつくる
生まれては 消えゆく
泡のなかに
存在するものが燃え
存在するものが凍結する
人は単調な思考を好み
人は単調なフレーズをくりかえす
泡は水に逗留する
しかしわたしら姉弟は旅立つだろう
紫色の窓掛の家から
石灰岩の頂きを望む時
「皮膚が血を覆っている」
というよりむしろ
「血が皮膚を覆っている」
日の出を見た
初出は《海》(中央公論社)1977年5月号〔9巻5号〕三〇〜三二ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、62行。引用詩句に関しては〈吉岡実とサミュエル・ベケット〉を参照のこと。
アネモネの咲く庭で
わたしは考える
看守という職業の意味と形式を
監視する塔のなかは
長いかいがらに長い貝の美体が入って
いるように暗い
ただ緑の蝶がとびまわる
わたしは自己同一視するために
近くを見ることはない
「想像力は死んだ
想像せよ」
望遠鏡でさまざまの被造物を見る
白鳥や牡牛や鯰
壁神の下で
産褥の産婆いわく
「赤児はにごった材質のガラスで
出来た蠅取り器のような感じがする」
別の表現をすれば
それは足が短く
胴はスズメ蛾のようにふくらみ
測量器械の錘のように地点を指している
「幼児はかさぶたと
キャラメルをなめて成長する」
いちご
いたちごっこ
愛と殺意 生成 消滅 無
〈有為転変〉
数珠 数珠つながりの死
「死は
不完全な生の完成である」
と歯ぎしりする哲人の家で
「しんしんと砂糖水を飲む」
少年は見えない糸を棒や身体に巻きつけて
青空と波の間で
肥大化する
わたしは戦争が勃発するまで
遠い地平を眺める
はなやかな花のさくら散る日
井戸の滑車の音も聞えず
齢をとるに従って
「眼球の内奥の蛇腹が硬化し伸び縮みしにくくなり」
周囲が見えない
この夕暮の琴座の星明り
蛭取り老人は行く
紫の水の波のうごきに
心をゆだねる
反英雄として
「肉体を分節のない一個の骨の如き
完璧な表層たらしめる」
受苦 受苦
忘れた荷物を負う
ある種の娘は股の間から
赤い腸や紐を垂らし
人の子を誘惑するんだ
「濡れてささくれだつ板に
兎をなすりつける」
青年は納豆を喰っている口元から
〈仮の地〉と呼んだ
ここは黒白空間
物を投げる
物を投げる
「血球一つ落ちていない風景が展開してくる」
*ベケット・土方巽などの章句を引用した
初出は〈ヘルマン・セリエント展〉パンフレット(青木画廊)1977年5月31日、〔三ページ〕、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、15級16行2段組、31行。なお、25行め「魚」が俗字(脚が連火ではなく「大」)で印字されているのは、原稿の字形を忠実に再現したためと考えられる。《夜想》再録ページの絵は、セリエントの〈集会〉と〈ペテン師〉(1976)。同誌に本篇が「1974年個展パンフレットより」とあるのは誤り。
詩篇〈異邦〉〔初出形〕の再録 出典:《夜想》第19号〔特集★幻想の扉〕(ペヨトル工房、1986年10月17日、七二〜七三ページ)
セリエントの絵によせて
聖堂の番人が箒をかついで帰ってくる
人も消え
にわとりも消え
わずかに藁塚のなかに存在する
火と精霊
〈死は働く者に近づく〉
行商人は旅を了えて居酒屋に入る
緑の壁の亀裂は深い
外の空のように
一人の老人の手のなかで
思考のぬけがら
の蛇
朱の酒杯をかたむけ
そのとなりの女は美しい
乳房と腕をしている
テーブルの下は暗い草むら
鳥の仮面をかぶった
まま女は目くばせする
欲しいよ 水と蜜
それはすでに鳥の貌そのもの
岩塩の一粒を咥え
〈食蓮人〉の邦へ飛び立つ
いまは遙かになった花咲く土地
血!
枯枝には魚の骨が引懸っている
月光のなかで
中世の子守唄が聞える
「鍛冶屋の前で
托鉢僧が二人になった
二人になった
二つの頭から煙がのぼった」
初出は《新劇》(白水社)1977年8月号〔24巻8号通292号〕一〇〜一三ページ、本文新字新かな使用、12級21行1段組、6節66行、笠井の〈黄泉比良坂〉(1975年、目黒公会堂)〔写真:金英沫〕と芦川羊子の〈ひとがた〉(1976年、アスベスト館)〔写真:山口晴久〕の舞台写真各1点を掲載。
笠井叡のための素描の詩
1
白い塩の山をふた廻りして
まず水を飲み干す
その時点からすでに
わたしの肉体は〈悪の死体〉に近似する
流れ出る蛭子
2
野を使者は通りすぎる
凍ってゆく水と舟
仮死してゆく兎
真昼の夢は
夜の夢よりさらに背信的だ
封ぜられた沼のほとり
猟師の殺気だつ眼と手斧を
わたしは丹田に受ける
ひとつの人格が崩れ
百合の花は開花し
両性具有の霊を受胎する
霞のかかる肉体……
3
書物を閉じ
身体を繙いて
円卓にまたがる変宮の人
「わたしは腹のなかから
両手を出した」
人間は何をしてもよい
何をしてもよい
「さまざまな異層をくぐり抜け」
まざまざと〈暗黒の水晶〉の結晶作用を視る
荒業の至福
虎は消去され
使者は裸身を一枚の布で包まれる
そして永遠に
「花嫁を待つ花婿のように
おぼえていなければならない」
4
見える 舞台から降りる
見えぬ 民
見える 地から降りる
見えぬ 自然
見える 肉から降りる
見えぬ 虹
5
「雨のような
亀裂の肉体を顕示せよ
音にさらわれ
わたしの肉体は徐々に光度を低下させて
ついに闇のうちに消えかかり
贖罪そのものの
観念と化すだろう
アストラル
アラベスク
アメーバのごとく」
6
今宵は〈印象の食物〉を摂り
「女の肉を床として
わたしは舞踏する」
足の裏に世界がある
反世界には竹藪と絹の言語がある
常套手段の秘儀とは
「男が女の肉体を借用して
虚構をつくる」
わたしは全きさらしものになり
肉体を忘れる
「肉体はいかなる
〈表面〉をも有していない
多くの人もその断面を眺めるだけだ
魂の〈表現〉としての
引潮の時刻が来る
「床が氷のように冷たく足を噛む」
わたしは〈九字〉を切る
ここに呼吸する人はいない
胡桃のように初出は《旅》(日本交通公社)1977年8月号〔51巻8号〕一四〇ページ〈今月の詩〉、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、20級ゴチック1段組、18行。写真キャプション「水納島(沖縄)'76「旅」写真コンテスト最優秀作品 カメラ 三笘正勝」。
初出は《流行通信》(流行通信)1977年10月号〔164号〕八〜九ページ〈十月の詩〉、本文新字新かな使用、18級22行1段組、22行。写真:奈良原一高。
夏きたりなば
母親はプリーツのスカートを
ひらひら波うたせつつ
水玉を産む
ごつごつした岩棚の下に
次に美しい息子を産む
緑の藻草の中に
これこそ人間が行う絶望的な遊戯
雨に打たれ
太陽は沈みゆき
砂山から
父親は水腫の足を垂らす
夜の紐のように
「肉体はいつもちぐはぐな
結びつきをする」
舟の底で
悲しきカナリヤの鳴く
暁の秋とおからじ
蟹の甲羅
栗の毬
「複雑なものよりも単純なものは
よく輝きよく成長する」
初出は《文藝》(河出書房新社)1977年11月号〔16巻11号〕二六四〜二六九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、5節93行。本文カット:中村忠良。吉岡は金井美恵子との対談〈一回性の言葉――フィクションと現実の混淆へ〉で引用詩について「美恵子を描いた「水鏡」も、君の言葉だけでは、うまくいかないので、実は飯田善国のエッセイから若干だが借用している。ただ、ぼくが言っておきたいのは、いずれの詩篇も詩句からはとってないんだよ。あれはみんな対象になった人のエッセイからとって括弧にいれて、それを詩にもってきているんだ。」(《現代詩手帖》1980年10月号、九六ページ)と語っている。金井の短篇小説〈声〉(初出:《文芸展望》1978年冬〔1月〕、単行本:《単語集》筑摩書房、1979)では題辞に〈水鏡〉から五行引かれており(初出にはない)、本文にも「わたしは「文藝」の十一月号の吉岡実の詩を読んでいて」という記述がある。金井には〈水鏡〉(初出:《文藝》1980年1月号、単行本:《くずれる水》集英社、1981)と題する短篇小説もある。
〈肉体の孕む夢はじつに多様をきわめている〉 金井美恵子
1
「冷たいスープの入ったガラスの
器の表面に
浮いた水滴の曇り」
の夏
わたしは形而上的室内で
死につつある父を
影の棺に収める
〈樹上の処女〉ひとり
ナナイ
南無!
踏みはずし 踏みこたえ
縄梯子で地上へ戻る
そして読書し
紅茶をすする午後
2
「古代の神官のまとう
寛衣の紫」
のような内湾を浮遊する〈ムーン・ジェリー〉
すなわちミズクラゲのむれ
それらの子エフィラ
また無性生殖をいとなむ
ポリプ
夕日の波間で
「白っ子の内臓のような柔かな
丸い起伏の世界」
愛や
観念を孕み
わたしは岬をめざして泳ぐ
「胚種としての無」
漂いゆく〈ムーン・ジェリー〉
透明なるもの
さらば
水神エア
3
「生者を死者の国へ搬び
死者(男)を生者(女)の国へ呼び返す」
うごく水脈
音楽[リズム]
火の粉
天井から水がポタポタ落ちる夜
わたしはフライパンを洗いながら思う
「人は肉体によって交わるより
視線で交わる」
女たちを飛び越え
〈独白〉と〈断片〉しか残さず
多くの男たちは死んでゆく
「妊婦は真横を向き
背景には一個の苔むすしゃれこうべ」
これは絵であるのだろうか?
「二元の世界を往復する者は呪われる」
わたしは歯痛の薄明のなかで
ノートを書く
「死と結ばれないような
〈性〉を信用しない」
まして〈美〉はなおさらだ
「心の中にもし癒しようのない
傷があるならば
傷の分だけ
わたしは美に近づける」
4
わたしはぬるい湯舟につかり
恥骨が白骨化してゆくのを
感じながら
「流れる水の面の底の
石のように
その存在をきわだたせる」
エゴン・シーレの
生涯と章句を想い出す
「人は夏の盛りに
秋の樹木を感得する」
まるでこの家は
水底のようだ
夢からさめればいつも
水藻や
言葉や
みじんこが舞っている
つけくわえれば
立葵の花のはるか下で
わたしは眼球に点滴される
5
「なぜわたしは蛾よりもはかない
羽音の瞬間に
魅せられたのだろう」
他人の夢のなかで
「生きている以上年を取る」
わたしの自己認識だ
いってみれば
「鏡の観照に終りというものがない」
ように秋から冬へ
「金属の分子の間を通過する」
溺死者や微生物
浄土観
湖
霧のなかの映画は了った――
わたしは居心地の
わるい処から
冬の裸木のシルエットを眺める
初出は《池田満寿夫20年の全貌》(美術出版社)1977年11月3日、一一八〜一一九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、16級35行2段組、6節100行。
〈目は時と共に静止する〉――池田満寿夫
1
「狼の鳴声や
天井をはっているサソリや
野ざらしの白骨」
その悪夢の表面を
「動きつづける線
そして 斑点のような色彩」
にとりまかれて
わたしは育ちつつあった
2
満州国
柳絮とぶ
奉天
暗いオンドルの部屋
張家口
「馬車でほこりをかぶりながら
支那街を通りすぎる」
そしてねじあやめ
咲く丘へ
ウォーターメロンを食べながら
わたしは朝鮮鴉を石で打つ
王者のように
死者のように
「突然マンホールに落ちる」
その時たしかに
わたしは少年になったのだ
見たまえ
青空にきみの心臓が浮び
鼓動している
「たまたまその
少女が裸でいるのも
不思議ではない」
となりの庭で
行為する両親たち
正面が赤く燃え……
3
「刻まれた眼はうごくか?」
頭部の両側にある
うごかないようで うごく
魚の眼
呼吸する氷の下で
夏は終るだろう
「描かれた眼はうごかない」
魚の眼は告げる
「きみらの眼は閉じられてゆく」
朝焼の草むらの
カマキリの交尾をみつめながら
「自然の暗さに接近している」
4
わたしは何者になったのか?
「音もなく岩石が宙へ昇り
ガラスが割れ
楽器類が燃える」
そんな奇蹟がいったいあり得るだろうか?
便器にしゃがみながら
三つの沼へ
わたしは頭髪のフケをふりそそぐ
見える観念がある
石の波
机の下の犬
「横に倒された
女陰」
金曜日は雨
「わたしは靴職人になりたかった」
耳濡れ
乳濡れ
武装した馬を曳き
下着の女が長靴をはいて来る
草の迷路を――
5
倒れる男
スプリンター
プリンター
眼は開きっぱなし
痛みの感覚があるかぎり
わたしは手に直結している物を信じる
切断された銅版や
人型や鳥型
すべてを平面化す
「虹のもつ永遠のスペクトル」
しかし海と樹木は立方体へ還元する
また涙も実物そっくり
用紙の上に滴らす
認識や感情の外に
だからいつまでも
「物体は裸のままの物体である
ことを保留されている」
タンポ
ヘラ
ローラー
油
6
わたしは不意の舟にのり
松脂粉末をもち
昆虫採集に出かける
迷宮では
線は死んでいる
扉と窓をあければ
シートをかぶったスフィンクス
わたしは攻撃する
「電気ドリルや鋼鉄の三角刀などの
道具を使って
傷をつけたり
穴をあけたりする」
蟹星雲のはるか下で
いぜん聳えるスフィンクスの処女
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
狐(⑨・15、17行)
2月
夢のアステリスク(⑨・22、***節60行)
4月
形は不安の鋭角を持ち……(⑨・11、Ⅲ節52行)
5月
雷雨の姿を見よ(⑨・14、8節126行)
7月
蝉(⑨・3、39行)
8月
父・あるいは夏(⑨・12、35行)
10月
夏の宴(⑨・20、6節120行)
11月
織物の三つの端布(⑨・16、*印が3節を従える74行)
断想(変改吸収詩篇・1、8行)
初出は《文學界》(文藝春秋)1978年1月号〔32巻1号〕九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ1段組〔コラム〈扉の詩〉〕、17行。カット:伊庭新太郎。
人の心のうごきは謎
まして狐のからだのうごきは謎
葛とかたくりの花の茂みで
わが心の狐を見つけよ
蟻塚や
罠にとらわれて死に行く
人の顔
口には一枚の油揚をくわえ
彼方の隠れ家へ入る
これはゴシック趣味の夢
「水甕の底に
蚯蚓が一匹と
死んだ小魚の骨が見つかった」
明るい此岸から眺めると
「人間に化けた狐の影は
かかとと爪先を丸めて浮くように歩く」
春の野をむらさき色に染めて
初出は1978年3月20日刊行の金子國義版画集《LE REVE D'ALICE――アリスの夢》(角川書店、限定版99部)の出版案内カタログ(同、1978年2月)〔二〜三ページ〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、16ポ26行3段組、***節60行。

詩篇〈夢のアステリスク〉初出掲載媒体 1978年3月20日刊行の金子國義版画集《LE REVE D'ALICE――アリスの夢》(角川書店、限定版99部)の出版案内カタログ(同、1978年2月)〔二〜三ページ〕(左)と同カタログの表紙およびカタログを収める畳紙[たとうがみ](右)
――金子國義の絵によせて――
*
読書する少女
それはわたしの好きな構図である
ことにその部屋は
深紅のソファや錫の皿で充ち
馬蠅がとびまわる
夜であればさらによい
〈天使的[アンジエリツク]なアリス〉のように
つつましく読書する少女を
彫刻的に
わたしは観察する
椅子や石像の上でなく
少女は兄のひざに腰かけて
右手に本をささげている
「歴史とともに古く
俗悪なほど純粋で
痴呆的なほど甘美なる」
桃色のメリヤスの
ズロースをずりさげて
太股をあらわにする
少女の骨化しつつある右手がしっかり
つかんでいるどくろ
**
ここは河霧のながれる
オリーブの葉陰の下かもしれない
「緑の蛙は鳴き
褐色のなめくじは這う」
冥府の迷路をめぐり
熱い蒸気のたちこめた
脱衣室から脱出してくる
黒人の青年
きみは烙印された舟板にのって
磔刑図の少女をさがす
大きな箱から
順次に小さくなる箱を
開ける 開ける
羅列から
羅刹の邦へ
橋桁を行き
冷水プールを泳ぎ
肉を沈める黒人の青年
ザウワークラウトを噛み
綿畑のなかで
エナメルのような裸像と化し
球根を頂く
***
夾竹桃の花咲く窓で
読書する少女
これはわたしの想像する〈淫らな聖画〉である
ジッパーの内側に
少女の裸の乳房はかくされている
一皮それを剥ぐと
死んだ内臓のかわりに
うぶげの兎がまるで水子のように
二つの耳を折って
さかさまに浮んでいる
浄らかな朝
肉体と精霊のように
分離する
「〈皮と骨〉
それは近くに
共存しているようで
きわめて遠くへだたっている」
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1978年4月号〔21巻4号〕二二〜二四ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、Ⅲ節52行。
〈複眼の所有者は憂愁と虚無に心を蝕ばまれる〉 飯田善國
Ⅰ
枝の上で小鳥がチッチと鳴く
「夢みられるものの
肉化する」
早春のゲルマンの森のなかで
わたしは〈無名性[アノ ニ ム]〉を志向し
「描写というものを棄てたかわりに
時間をとりこむ」
たとえば
「穴ぼこを掘り
土や小石なんかを箱に入れて
その箱を抜くと
土の形が出来る」
雨に打たれ
消滅してゆく四角い呪物
そしてわたしはアンリ・ローランスの
言葉を思い出す
〈人はいつか無意識を表現しなければならない〉
ひたひたと流れる
地下水
「野の草は
土の中から
時をみて
地上に現われる」
そして風にゆらゆら吹かれる
Ⅱ
「人は同時に二つ以上の
時点に
存在することはできない」
わたしは肉体が恋しくなると
手を汚して
絵のそばへゆく
「皮膚みたいなもの 血みたいなもの」
でそれは蔽われている
満月の下で
わたしは言霊や死を近くに感じたら
釘や車輪
彫刻のそばへゆく
なぜなら
黙示的に夜の
「地下鉄の堅い椅子に黙って
坐っている女」
のように
人生を包みこみ
紙ヤスリのすれる音をさせているからだ
カノン
カノン
「もし癒しようのない傷があるならば
傷の分だけ きみの心は
美に近づける」
胡座かいて
怪我する男は口ずさむ
Ⅲ
「形は不安の鋭角をもち
色は冷たくそれを匿す」
初出は《海》(中央公論社)1978年5月号〔10巻5号〕三二〜三八ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ25行1段組、8節126行。
吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈雷雨の姿を見よ〉の雑誌掲載用入稿原稿(出品者の説明に「No. 26501 吉岡実詩稿/9枚 価格:450,000円/『雷雨の姿を見よ』 ペン640字詰表題共完 拵帙入 「詩集夏の宴」(昭54.10 青土社刊)所収」とある) 出典:玉英堂書店
「ぼくはウニとかナマコとかヒトデといった
動物をとらえたいのだ
現実はそれら棘皮動物に似ている」
飯島耕一
1
「スナガニが砂を掘って
ひそんでいる穴」
を覗き
瀬戸内海沿岸で育った
ぼくは子供の時から
「じっとしている
植物よりも
動いているもの
じつにこわれやすい皮膚のなかのやわらかいもの
火山
棘皮動物
時間」
への執着があった
「空は卵の白身のように
ぼくを包んでおり
そのなかを
ぼくは動いていた」
自己中心的な日常意識の外へ
朝の蛇はゆく
ことばの護符のように
2
ぼくは〈危険な思想〉というものは
もしかしたら眉唾ものだと思う
野には春の七草
「マグリットの
岩も
城も軽く浮んでいる」
3
「ぼくの詩のイメージに比べる」
と日本の海は暗すぎる
そのなかに
浮ぶ島々は
寂しすぎる
波
浪
濤
無
円環もなし
線もなし
暗く
璧の向う
ガラス戸の向うに
海鼠が存在する
その複雑な内部の構造を
内視せよ
おそらく〈世界〉の難解さのみが
唯一つそれ[、、]に匹敵する
4
「なぜぼくは
雷雨を愛好するのだろう?」
それはたしかに
女の肉体を思わせる
亀裂の入った
影像
ぼくは女の細い首を抱く
『二つの青い千鳥が
君の眼の静かな
水面をかき乱す』
5
夏のある一刻
「歴史がイメージに
逆襲される」
青空といっしょに
まる見えになる死者たち
「骨組をあらわにされた
ピアノが灰の下に
深く沈んでいた」
聖化された
町や土地をよく記憶するために
ぼくは海岸を歩く
イソギンチャクやヒトデのいる
風景に期待してはならない
距離は狂っている
「一度書かれた言葉は消すな!」
身のまわりから
筆記具を片づける
そして
百年前に見た男のように
ぼくは焼火箸を地へ突き入れる
八月は逝く
6
「詩人という変光星は何をなすか?」
ゼラニウムの鉢に朝日がさす
庭を掃き
空の下に立つ男
「すべては飛ばない」
ぼくらの日月
絵をのぞきこむ
ことしか何もできない
「魂の状態[エタ・ダーム]」
そこにある あるもの
松葉杖や小石
エックス光線に透視されて
沸騰する
黒
奥深くはいりこんで行き
ぼくは壁や柱に
頭をぶっつけたりして
ついに見つける
蠅取り紙がびらびらゆれながら
一匹の蠅をとらえている
昼さがりの四行詩
眼差しの深くやさしい
蠅
汝よ
夜が来れば
一個の星に接近する
7
ぼくは紺碧の空を見ると
あの増殖癖の一人の男を思い出す
「〈理想の宮殿〉という異形の塔は 三十数年もか
けて シュヴァルという郵便配達夫が 日々の仕
事の途次 石をひろい それを積んで建てたもの
である」
ここに人は住むことはできない
もし宿るならば
反権力の人々の夢
老人は日々石をひろうという〈方法〉を会得した
「この石は一つの言語だった」
それは霊感の歌
他界への通路の標識かもしれない
死の塔
ぼくらはその存在する周辺で
時間にせきたてられ
うろうろしている
ここは何処?
8
『蠅帳から
食べかけのサバの煮つけを
取り出す』
美しい日本の夏
もっとも光を受け入れやすい
水泡[みなわ]!
初出は《ユリイカ》(青土社)1978年7月号〔10巻8号〕一二〜一三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、39行。
「一匹の蜂がブーンと飛びまわっている」
炎天の寂莫の
まひるま
野山を越え
日傘をさして乙女がやってくる
わたしの好きなアメスイスト
ラピスラズリ
蝉の声
伊太利の宗教画家は
「たえず円の中を廻って歩む」
乙女のために
天人唐草の花を前景に
描きこみ
「いわしのようにやせた
母親」
から生まれた
タークワーズのような乙女のために
染物屋の主人は紫の馬を染め
あげる十三夜
槌の音が聞えてくる
「人生のなかばにして
叢林にふみ迷う」
妻子は沼で
おおばこの葉でかえるを釣っている
まるで墨絵のようだ
つきなみな慣用句だが
「涙は百合と
バラの間に落ちる」
いおりをむすぶ
心がけのよい者は
赤飯を食べ
水浴派の乙女をかいま見る
しかし
「悪人は柳の下を急ぐ」
生け垣の外で
こおろぎは鳴く
「荷が重すぎる」
石綿や鉛で
みろくぼさつは創られてはいない
初出は《カイエ》(冬樹社)1978年8月号〔1巻2号〕二四〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、35行。
「鰤の血の頭のそばを
大股で過ぎる時
世界はすっかり変っていた」
わたしの爪は鉤爪と化し
もろもろの肉を裂く
少年期の能力をそなえつつ
からだを白く塗る
もしも塗りのこされた部分があれば
青草の上に寝て
「枝豆を噛みこぼす
女」
に塗ってもらうんだ
意識と言葉の関係のように
不可解でかつ親密に
「身を投げ込めば
人型があっさり出来る」
朝の海で
「浅瀬で心臓を溺らせている
人影を見る」
それは旅人かも知れない
たまたま
「縁の下から四つん這いで
出てきた
娘」
であるかも知れない
紫蘇の匂いを嗅ぎながら
わたしは横切る
「表層世界」
そこがどこまでも見通せるなら
わたしには感知できる
「犬に打負かされた
人間の裸体」
西日をあびて
「断面に必死で際立つ者」
父を――
初出は《文藝》(河出書房新社)1978年10月号〔17巻10号〕二二〇〜二二六ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、6節120行。吉岡は〈西脇順三郎アラベスク〉の「7 「夏の宴」」で本篇制作の経緯を回想している。
西脇順三郎先生に
草むらより
「黎明を走る臭猫」
を追かける
麻服の一人の青年がいるとしたら
それはわたしかも知れない
ひとびとに
「葡萄畑へ行って働け
(死ね)」
とののしられる
わたしは「漂布者」だった
タラの木や
イタドリの茂みを通り
鉛管や古い罎の町に出た
その辺りで石灰を噛んでいる
犬と鶏たち
夜は隠者の書を読む
〈眼の下へ指をつっこんで
見よ
そうすれば物の形が変化する〉
わたしの観念の波間を
「まるい魚」
は漂う
非現世的なことばとできごとの終り
「紫のランプの下で
ときどき
ラムネを飲む」
2
「この世界では
人間も花も岩も
同じ外界物にすぎない」
と認識して
画布のうえに
「星の光りのような
剃刀で暗黒な林檎をむいている
男」
を描く人間がいる
それはわたしに類似した者だ
マッチ棒の先にある
炎と
「間接的な世界」
ローソクをたてたテーブルに
ネクタリンの実は
いまだ見えず
蒼白な肉も見えず
詞華集一巻も見えず
ただ〈えてるにたす〉という
文字が刻まれている
「なにしろ概念というやつは
一つの存在には存在であるが
看板のようには
よく見えない」
3
岸辺にキンポウゲの花が咲き
尺取虫は雑木林を出る
死人へささげられた
ひとつまみの塩
「石は永遠に
水の音を立てない」
川の瀬の岩へ
さわやかに
女が片足をあげて
「精神の包皮」
を洗っている姿が見える
「ポポイ」
わたしはしばしば
「女が野原でしゃがむ」
抒情詩を書いた
これからは弱い人間の一人として
山中へ逃げる
「そこには
カモシカのやさしい眼や
薔薇のような
雪がある」
高い枝
もっと高い処で
思案し
思考する
〈下にあるものも
上にあるものも同じことだ〉
4
「わたしの詩の世界は
藪の中の鶯の巣のように
少年が撃つ空気銃の一発で破滅するかも知れない」
5
西瓜の種子を播く
そして西瓜そのものを作り
西瓜を持って西瓜畑を歩く人がある
砂地の外で
画家は形而上的な絵しか描かない
線と色彩の発する
不透明な枠や
棒や
濡れたトチの実しか表現しない
砂けむりたつ
夏の道をとぼとぼ行きつつ
「臥婦のあの虎のような
尻」
をわたしは心に描く
「胡瓜の花はきみがねむっている
ときにも咲いている」
染物屋の裏の
道の暗がりで
うまごやしを食べている馬の影を見よ
「淋しさというものは
地上から来る」
6
幾何学的なものも一つの構造なら
「曲線のぐにゃぐにゃに
出来ているのも
構造である」
ボール箱のなかへ
わたしは針金や紐を入れる
そして最後に
光沢のある骨を入れる
それが動物の骨であるのか人間の骨であるのか
ひとびとよ問うことはない
「生命の終りは死の終り」
というように
わたしは言語をもてあそぶ者
また言語によって
再生される者である
自己の格言を記す
すなわち
「蛾は月をめざさず
濁世の家の灯をめざす」
初出は《エピステーメー》(朝日出版社)1978年11月号〔4巻10号〕二四八〜二五三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ14行1段組、*印が3節を従える74行。引用詩句に関しては〈吉岡実の装丁作品(49)〉を参照のこと。
「イマージュはたえず事物へ
しかしまた同時に
意味へ向おうとする」 宮川淳
*
「(この積み藁が紫色である)のは
私にそう見えるからだ」
いま秋の強い射光の下で
「重さから軽みへ
大地的なものから
大気的なものへ」
私は美のディスクールを試みる
「空間のなかに
開かれる
もうひとつの空間」
それはきわめて曖昧な時間を経て
浄化された青だ
「生きることを許された
(空間)である」
渓流のほとりで
つりふねそうの花をながめ
私は或る西欧の画家のことばを思う
〈しばしば見かけるのは
空を飛んでいる
鳥だ〉
*
「ここは室内に似ている」
茶色のテーブル・クロス
の上に在る
ライター(白色)
灰皿(煙草の吸がら)
湯呑(二つ)
鉛筆(消しゴム)
「見ることは透明に脱落して
見える
ものを浮び上らせる」
ここではひとは真に見てはいない
表面[、、]
表面的[、、、]
表面化[、、、]する
それらの日常品は
私にはそれぞれの実体の
似姿に思われる
「ここがどこでもない
ところであるからだ」
私が見て共感しているのは
「逆に存在は遠ざかり
不在のきらめく」
草に坐る婦人の
「選ばれた脚」
*
「この欲望のモーターは独身者の機械の
最後の(もっとも
突起した)部分である」
へだてられている
へだて
られている
冷却されたガラス板の
向う側では
〈動物が卵(または袋)のなかに孕まれているように
混沌とした情念のなかに(記号・作品)が
孕まれている〉
うずまき状のエーテルの層から
つつましやかに
すっぽりと氷の膜で包まれた
「花嫁という
新しいモーターが出現する」
下部に羽根をつけた
内燃機関のからくりを透視せよ
〈重く つや消しの 力のこもった
音〉
がする
「近づくことのできない
この純粋な外面の
輝き」
それは悪や死の
化身ではないのか?
この時点から
「善悪の対立をこえて
男女
の対立となっている」
初出は《CURIEUX――求龍》(求龍堂)1978年11月〔4号〕、一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、15級1段組、8行。のちに全行が〈秋思賦〉(⑪・8)に変改吸収された。
むらさき色に手を染めあげ
「水没して行く 水夫」
もしもそこが秋の霧の海であるならば
へだたった処に大地が在る
葱の香 書物 古靴 塩
記憶の娼婦の美服のなかでうごいている
「牙と爪をもたぬもの」
それら仮りの世の仮の像[かたち]は今も美しく……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
謎の絵(⑨・26、17行)
3月
裸子植物(⑨・25、41行)
5月
金柑譚(⑨・17、5節83行)
6月
野(⑨・21、12行)
7月
詠歌(⑨・23、37行)
8月
この世の夏(⑨・24、20行)
9月
〔標題なし〕 → 生徒(⑩・18、5行)
11月
円筒の内側(⑨・28、6節85行)
12月
「青と発音する」(⑨・27、55行)
初出は《東京新聞〔夕刊〕》(中日新聞東京本社)1979年1月5日〔13124号〕七面、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平1段組、17行。
岸辺に近く
ごつごつした岩がある
そのかたわらで漁夫が漁具を砂地に置き
しばし休息しているように
わたしたちには見えた
それはアンドリュー・ワイエスの素描だった
「そこは存在や意識の地上に対し
イマージュの地上と呼ぶべきものかもしれない」
同じ処に暗褐色の濡れた岩がある
人は消え 釣竿と櫂(かい)が置かれたままだ
ここには仰ぐ青空はなく
打ちよせ 引きさがってゆく 波の音が聞える
画家の完成させた絵を
わたしはそのように認識し心ひかれた
家に戻って語りあったら
岩に置かれたものはたしかに
〈猟銃〉と〈斧〉だったと妻は言いつづける
初出は《肉体言語》(「肉体言語」舎)1979年3月〔9号〕六〜七ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、16級26行1段組、41行。目次では献辞が「大野一雄の舞踏〈ラ・アルへンチーナ頌〉に寄せて」とあり、誤植されていない。入稿原稿を忠実に再現したためだろう、行頭の起こしの鉤括弧(「)がすべて本文の天のラインよりも上に突き出て組まれている。
大野一雄の無踏〈ラ・アルへンチーナ頌〉に寄せて
人知れず野の草の上に
「子を産みおとす
老婆」
のように大股をひらく
舞姫アルヘンチーナの橙色の裳裾の拡がり
「見せるものと
見せたくないものを
一緒に見せる」
正午の物置小屋の闇のなかに
「宿っている肉体」
肉体に宿っている
おできだらけの子供が抱える
「棒のように硬直する
塩鱈」
仰ぐ青空もすでになく
へだてられた大地
そこでひとは真に語っていない
とどのつまり
「肛門から大気を
吸っている」
白塗りの老人は叫ぶ
「信じられるのは
このキャベツだけだ!
ふらちな振舞の遊び
と愛を受け入れよ
娼婦の紅いマントの内側は
ざらざらした
「触覚的空間」
豆電燈は明滅し
剥落するものが見える
鷲
古靴
裸子植物の胚珠のようなもの
「右もあれば
左もある」
世俗なる世界を越え
花飾りをつけた帽子の影の下に
「開かれた
干物のような
人間の肉体(あるいは魂)」
が浮遊している
初出は《海》(中央公論社)1979年5月号〔11巻5号〕三二〜三五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ26行1段組、5節83行。引用詩句に関しては〈吉岡実の装丁作品(49)〉の〔追記〕を参照のこと。
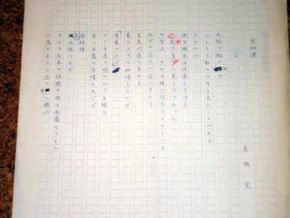
吉岡陽子夫人の手になる詩篇〈金柑譚〉の雑誌掲載用入稿原稿(吉岡実詩稿「金柑譚」、ペン書、640字×5枚、詩集『夏の宴』所収。出品者の説明に「右上部をホッチキスで5枚止めてあります。原稿用紙の中央で折れあり。」とある) 出典:Yahoo! JAPANのオークション
1
大股で駈けつつ
しかも不動の少年を見たことがある
たしかに
街や樹木は後退してゆき
〈影の青〉に変りつつあった
少年よ きみは裸になろうとしている
ねずみ花火が這いまわり
百足が這いまわる
夏の夕べの砂場のなかや
「草葉のかげ」
ブリキ屋の娘のひざを抱く
白い日覆の学帽をぬげば
金柑頭
淫水性にとむ
きみの灰色の詰襟の服は雨覆そのもの
小鳥のように丘の方へ飛ぶ
ことができない
ベンチの上でいずれ雷雨に打たれる
2
「患者は何よりも主体である」
と言う医者の言葉は正しい
少年よ きみの
「内部はひじょうに複雑骨折した
人体」
であると同時に
「障子にはられた
白紙が宇宙に風を起す」
ビビビーッ ビビッと鳴る
少年よ きみは
「物の厚さ
球や穴の直径を計る器具」
ノギスのようなもので
肉や愛を計る
3
いが栗が落ち
〈氷塊の要素〉が地からせり出す
夕かたまけて
少年よ きみは
「一輪の花の匂いをかぐように
書物を読む」
そしてノートをとった
ヘルメスの父はゼウス 母は美しい半女神のマイア
異母兄アポローン(女神レートーの子)
ポロスと女乞食ペニアの子がエロス(クピドー)
エロス
神々はすべて水銀だ!
4
少年よ きみの内なる
姉をののしり
母をののしれ
「女の目と鼻の間から
生まれいづる」
牛頭馬頭の双生児を祀り
煮凝りのようなものを吐く
「蜘蛛の子が散る」
ように万物は消滅し
「枝蛙の鳴くあたりの木々」
の奥をたどって行けば
草の下の汚洞のなかへ
「兎はぐらりと傾いて
横倒しになる」
サイレント映画のように
肉体はまどろみ
風景もまどろんでいる
〈モワレ様模〉
の裡に横倒しになった
父
野狐
手榴弾も存在する
5
「若死するも人の一生」
ならば夢想し
ろうそくかかげて
老婆と共に廊下を駈けぬけよ
今晩 北の風 晴れ
少年よ きみは大志をいだかず
もろもろの物を触診し
直立する
はるかなる獅子頭の下で
金柑を食うたのしさ
いざ転生の旅が始まる
「ばら色の初湯から
紫色の死水へ」
少年よ きみはゴム靴をはいたまま
〈無時間の世界〉
を行き行く
「知らぬことの一切を試みよ!」
初出は《街頭詩の試み》(地下鉄千代田線明治神宮前駅ホーム壁面、パレフランス提供、1979年6月〜8月の「第一期」)で、縦約130×横約165cmの額が掲げられた。その後、詩のアンソロジー《地下鉄のオルフェ》(オーデスク、1981年4月〔日付記載なし〕、限定2000部)に再録された(二四〜二五ページ、本文新字新かな使用、12ポ11行1段組、12行)。本稿には〔再録形〕を掲げた。《街頭詩の試み》の実質的な企画者である飯島耕一は《地下鉄のオルフェ》の〈まえがき〉で、第三期の作者のひとり清岡卓行の「いちばん外形が銀色の枠で、それに接続して赤葡萄酒色の枠があり、その内部の乳白色のガラス板に、詩が黒で縦書きされている。すっきりした書体。ガラス板の裏から螢光灯が照明しており、詩の文字が鮮明に浮かびあがっている。」(同書、九〜一〇ページ)という文章を紹介している。
「自然界は人間の俗界よりすぐれている
稲妻の走りまわる沼の面へ
「ほとばしる水晶体」
野をたどる父よ
行灯のあかりのなかで
母が生むものが
ほおずき色の人間であるならば……
「見ることは 驚くこと」
あけぼのの横雲の下で
青草はおびただしい螢を生む
自己か他者
「いずれかが幽霊である」
初出は《ユリイカ》(青土社)1979年7月号〔11巻9号〕二一〜二三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、37行。
「長石の色をした雨は打ちつづける」
野ざらしの
川はながれながれ
峯に虎杖
鹿の立ち隠れ
慰みに
むらさきの首長き鴨をはがいじめにせよ
かの世に遠く
うつつの鍋は煮え立ち
蚊柱は立ち
「じなっとした煎餅を食べたり」
母はむかし好色な軍曹に抱かれたり
白塩言語神変だよ
「子供は植物と同じように
陽のなかで育つ」
という現象がある
しかしわたしはいつまでも
「花の中にうずまっている
雨の光り」
電柱の碍子や
藁の山へ
雪は降りつづける
かまどの火や灰の周囲をまわって
なめくじのように
出て行く父の声
舟行けば岸移る
幾星霜
「肉は言葉をなぞり
言葉は肉のかたちをとる」
作業を了えて
わたしの荒ぶる魂よ眠れ
押入の蒲団の上は
「げに静かなる霊地かな」
一言の呪訶のごとく
春霞のかなたに
潜在する
石の下の蛤
初出は《朝日新聞〔夕刊〕》(朝日新聞東京本社)1979年8月20日〔33641号〕三面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、7.5ポ1段組、20行。木口木版:小林敬生。引用詩句に関しては〈吉岡実とエズラ・パウンド〉を参照のこと。
「孔子は歩いて杉林に入り」
の叙述の清らかさ
よりも
「美人が月に向っている」
と詠んだ古代の夭折詩人の一句が好きだ
肉感的な春を思わせる
「あんずの花は
東から西へと咲きほころぶ」
ように移り
変る自然や倫理観がある
この世に
めくるめく夏はくるか
「わびしい屋根に猫がうずくまる」
まずしい街から
「この夏もある海岸で
黄色い海水着をきる
娘」
の裸を妄想せよ
「暗がりのなかで
金色は光りをあつめる」
木造の古い小学校の便所の暗がりで初出は〈片山健個展〉パンフレット(かんらん舎)1979年9月10日、〔二〜三ページ〕、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、7ポ1段組、5行。絵・片山健「「美しい日々」より 1969」(〈吉岡実と片山健〉参照)。執筆者名の後に「(詩人)」とある。
初出は《ユリイカ》(青土社)1979年11月臨時増刊号〔11巻14号〕三四〜三九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、6節85行。引用詩句に関しては〈吉岡実の引用詩(2)――大岡信《岡倉天心》〉を参照のこと。
「言語というものは固体
粒であると同じに波動である」 大岡 信
1
「石や木とじかに結びついている」
子供の頃
狩野川のほとりで
ハヤ・マルタ・フナを釣り
ぼくは猿股をぬらす
日の暮つ方
ぬるぬるしている
硬骨魚
鯰はついに捕え
「存在としての自然ではなく
生成としての
自然」
そのものを知った
2
「子供は強引に成長する」
木の芽時
香貫山を見れば
「とびかかって来る
緑」
ぼくは間もなく
アデノイドの手術を受けるんだ
むっとする闇のかなた
「そこに巨大な女が横たわっている
ことを想像せよ」
3
「円筒の中は静まりかえり」
猫は死にゆき
鯉も死にゆき
いずれにしても淋しい秋だ
もしかしたら
人も死んでゆく
「葡萄の房
みたいなかたち」
4
露もしとどに
裏山を越え
妹がつづらおりの径を降りてくる
「涙を浮かべない眼で
事物を見よ」
言語がはらむ
観念の内容をつきとめよ
「処女陵辱」
この文字は美しい
しかし顔をそむけよ 弟
「夢と現実の
隙間」
に潜在する
「ツクネイモ山水」
そのはるか上に懸る
「冴え冴えとした
月」
ぼくが老人だったらこのようにつぶやく
「言葉の方からのみ
人生を眺めると人生は
煙のごとし」
5
「生物と鉱物の両方が騒がしく
わき立っている
地表」
そこでの生活はつらい
「尋常の食物では
彼らを養うことは出来ない」
ぼくのはらからは
ひたすら思考し
「沈黙に聞き入る能力」
をたくわえる
頭部は巻貝のような人たちだ
「冷えすぎたハム」
この興ざめたものを嚥下す
それゆえに
「からだのなかにつねに
フォルム感覚が見えない形で
生み出される」
そのまわりに散乱する
糸屑や卵子
(言葉)
もろもろの具象を
箒やはたきをかけて
舞いあがらせる
発止!
ワラ半紙一枚の聖域
6
「璧を通して
青空が見える家」
からぼくは旅に出る
桜並木の長い道がつきたところで
(点滅信号)を仰ぐ
其所から
「氷河が溶解し
世界の洪水がはじまる」
(一九七九・一○・九)
初出は《雷鳴の頸飾り――瀧口修造に》(「雷鳴の頸飾り」刊行会、1979年12月10日)一〇一〜一〇五ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、14ポ17行1段組、55行。
「青ずんだ鏡のなかに飛びこむのは今だ」瀧口修造
秋されば
オリーヴの実のぶらさがる
そこに開かれた
「黄金の窓」
が在り
「血管の走ったかまど」
も在る
うつしよの隠れ家を出るんだ
泥沼のはるか上の
「空所」
は淋しい
つれづれなるまま
「青
と発音する」
わたしの
「胸中の山水」
をのぼって行く者がひとりいるようだ
「野鼠の中の不発弾」
を探しているのだろうか
夜が明けたら
岩盤にぶつかるものがある
シーニュ シーニュ シーニュ
まるで
「剃刀の氷滑り」
のように鋭く迫る
記号と空罐
どこから始り
どこで終るのか
ゆゆしきわたしの夢
ゆゆしき
「火という文字
風という文字」
あとはつけたりに
〈愛〉と〈死〉という文字を書きそえよ
「タコのようなそいつの手で」
できることならば
もろもろの文字を抹消させよ
市にたそがれは来る
白玉
氷あずき
「美しい女は知らずに
匙をとる」
その青い骨格がもえつきる時
わたしを襲うのは
蜂や稲光りではなく
「この大音響のする
産衣」
ゆゆしき湯文字の姉のししむら
「ここに生きる
元素」
を目に留め
わたしは認識をあらたにす
「むしろ生命は
アリバイのなかに
烈しい存在を示すことになる」
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
猿(⑩・20、20行)
3月
ツグミ(⑩・21、29行)
初出は《讀賣新聞〔夕刊〕》(読売新聞社)1980年1月25日〔37177号〕九面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、7.5ポ1段組、20行。
「父の手のうえに乗る
裸の猿」
その金毛の長い手が触診する
かまどの内側はつねに
炎の快楽の夜だ
掛かった大鍋でいつまでも
煮られている豆
「似たような事が起っている」
情緒てんめんと
ぼくの姉妹たちは開腹されて
「芯にある種子を
花咲かせる」
母はと見れば
魔除けの魚の頭や
ヒイラギの葉を飾り
神棚の燈明のゆらぐはるかな闇に属し
聖化しつつある
朝がくればぼくのはらからの
「汚れた夢は
冬の太陽の光に洗われる」
初出は《蘭》(蘭発行所)1980年3月号〔100号〕二〇〜二一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ17行1段組、29行。
横向きの女の細い首のすぐわきから
跳び出してくる
犀や
ペリカン
わたしはそのような「背後のない表面」
だけのレオノール・フィニの絵が
なつかしい
「呼吸器音」が聴こえて
今朝は天人唐草の花が咲く
「忘却である空間」
たよりない煙がのぼっている
「岩盤の起伏した
曙の丘」
近づいて仰げば
あるいは淋しい虎がいる
かもしれない
わたしは羽枕をだきつつ
異国の諺を思い出す
「魚は頭から腐ってゆく」
たしかに
人も頭から燐化してゆく
「記憶である時間」
つるつる溶けるつららのつらなり
それは「聖具」のように輝き
「まるで少女期の秘密の
水脈に向って
呼び水する」
きさらぎやよい
ツグミは高い梢にとまって鳴く
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
にわとり → 雞(⑪・1、39行)
9月
竪[しゆ]の声 → 竪の声(⑪・2、35行)
10月
絵のなかの女(未刊詩篇・15、18行)
11月
巡礼(⑪・7、8節110行)
初出は《朝日新聞》(朝日新聞東京本社)1981年1月3日〔34131号〕一五面、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、7.5ポ13行3段組、39行。引用詩句に関しては〈吉岡実詩集《薬玉》本文校異〉の〔2019年1月31日追記〕を参照のこと。
松の梢のむこうの日の出
俗調の一幅の絵を仰ぎ見るようだ
ならば神話の記述の一節を
想起しようか――
「常世の長鳴鳥を集めて鳴かしめよ」
歩くにわとり
ねむるにわとり
よく観察すればその力強い姿態はまさしく
粘土と細い管と羽毛が集り
金の爪やダイナモを包んでいる
まがいもの
生者必滅の藁の地上で
もんどり打つおんどり
とき[、、]の声をあげよ
水辺の灯心草が揺れたり
ジャムの壜が揺れたり
横隔膜までぴくぴくする
母や娘のみどりの黒髪から
へアーピンも抜けおちる
仮寝の夢の苫屋に
庖丁とか樟脳を用意し
苔の上の父にはしびん[、、、]を用意せよ
冥想的な暗さ
鍛冶屋のふいご[、、、](子宮)は収縮する
菜をつつくにわとり
卵をうむにわとり
ここは恩寵の現し世だろうか
とうもろこし畑で
氷の岬で
「男たちは遠方で戦っている」
火花の明るさ
くびくくられる
めんどりのように
「女たちは墓穴にまたがって難産をする」
散乱するもの
種子や枯葉のたぐい
いま幾本かの羽毛はかるがると
護符のように
夕日のみずうみの空へ舞い上り……
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1981年9月号〔24巻9号〕二〇〜二二ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、35行。
「心は閑[しず]かにして 目を遠く見よ」
母恋いのちりめん模様の空のもとをさまよう
マッチをすると わたしの好きな 青い軟玉の
石が見える
(ぶどうの表面)
この球体は「光と半透明と闇」の
三つの層に分れている
母は冷淡で わたしと妹を追放した
黒白[あやめ]もわからぬ世界へ
父は入江の中洲で
やつめうなぎを釣っていた
「雪は犬の伯母」という 江戸諺語がなつかしい
暑い街を 犬が走ることもない 現世の夏
「夢みられるものの肉化」そのもの
場末の映画館で
父は老衰し
妹は孕み
「ガルボは鉄の戦車」だとわたしは讃え
「暗黒(肉体)は光を食って生き
光(魂)はそれ自体の内部を生きている」
この賢者の言葉も
蒸溜器か暗箱の比喩みたいだと思う
わたしは注文があれば 三脚を担いで
断崖の上に立つ
そして「すがる乙女」を撮った
野生の人参が生え やまあらしが巣をつくり
束髪の母がオルガンをひびかせている
――おかあさん あれはなんですか
――碾臼だよ
――では孔のあるところから もれているものはなに
――時間だよ
――まわりにたまっているものは
――豆のかすだよ
「竪[しゆ]ノ声」
(いまでも聴こえる母の声であろうか)
*世阿弥の伝書にある「横[おう]ノ声」(明るく外向的で太い強い声)。「竪[しゆ]ノ声」(内向的でやわらかく細かに暗い感じの声)=観世寿夫の解説
初出は《別冊一枚の繪》(一枚の繪)1981年10月〔4号〕〈花鳥風月の世界――新作/洋画・日本画選〉の〈第四章 月〉一八六ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、12級1段組、18行。註記「本誌のための書き下ろし/●よしおか みのる(一九一九― )東京 詩人 H氏賞 高見順賞 戦後詩の芸術至上主義的な詩の不気味な魅力をたたえる。シュールレアリスムの絵画の美しさに近い面白さのある一篇。」(無署名)。詩篇の上部に弦田英太郎 青い首飾り 6号 油絵」がカラーで掲載されている。《吉岡実全詩集》に未収録。
《別冊一枚の繪》第4号〈花鳥風月の世界――新作/洋画・日本画選〉(一枚の繪、1981年10月1日)掲載の吉岡実の未刊詩篇〈絵のなかの女〉のページ
「かげろうは消え
黄蜂はかえって行く」
野の丈なす草むら
そこでひとりの女が腰をひねった
地母神
イナンナの妹のかくしどころの闇から
蒼白なる魚のように
「賢者」や「愚者」がうみおとされた
「間接的(空間)世界」
にがり[、、、]や泡で形成されつつある
夏もたけて
「鳥が絵のなかの鳥」でありえても
「女が絵のなかの女」であるとはかぎらない
テーブルの端にローソクを燃やし
ドリアンを食べる女を抱く
荒らぶる魂の男は淋しい
庭の石床の上をはいまわりつつ
「ねずみ花火は消え……」
初出は《ユリイカ》(青土社)1981年11月臨時増刊号〔13巻14号〕一〇〜一五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、110行(初出時には節の数字がなく、一行アキ)。
廊下で二人の女とすれちがった
ひとりは三輪車に
跨がっている
たしかにそれはわたくしの妹
紅い本の数ページを
読んでいる
オレンジとかトマトの記述が多い
偉人の伝記である
もうひとりは肥えた
母で体重測定器へのっている
安物の服を着た内部はぐしゃぐしゃで
そこから流れ出ている
文体 死体
さなだむしもひとついる
家訓に曰く
シーツは血や汚物でよごれたことはない
永遠に 雪景色だ
荷車に大きな物をのせて
父が街を去って行くと同時に
主題が明確になる
砲煙はたなびき
モルタルで作られた
戦艦であろうか
岩山であろうか
軍隊が攻撃しつつある
光明の時
内臓までが見える
草花はちぎれ 織物はちぎれ
ぴかぴかした皿のうえに羽毛がつもる
すべての個の身体は分解し
遊魂は星形をつかむ
起りうることが起るならば
起りうることは起れ
起りえないことが起りえないならば
起りえないことは起るな
蝉しぐれのまひるま
異物を挿入された
母
母
母
穴
妹
妹
妹
雁は西へ翔ぶ
人間の(女)というものは必ずひっくり返る
ここは何処だと問えば
山海境[せんがいきよう]
桃やすももが咲きみだれ
白玉多し
鳥獣はしばしば わが名を呼び
母を呼ぶ
兵士は豕[いのこ]を好み
老人はちみもうりょうを好む
山中に谷はうがたれ
爽水は流れ 流れ 故園へ帰る
日々は過ぎ
䱱魚[さんしよううお]は残った
ならば変化自在の芸文の世界を讃えよ
妹は水浴派で泡沫をまとい
尺鳩[よぶこどり]のように
観念の仙人をさがしつづける
煙立つ
忘却である空間
さい[、、]の目に刻まれたものは何?
男性的なもの――
(火と空気)
または詩のようなもの 詩自体
女性的なもの――
(水と土)
星はきらめき
蜘蛛は自己の眼で卵をかえす
詩人は地をはいまわりつつ
荒血を頭から浴びる
わたくしは妹の出産に立ち会ったのだ
詩の降臨
今宵は涼しい風がわたり
書物はひるがえった
散文的に
さらば からくれないの紅葉のくにより
汚穢のバケツを提げ
わたくしに近似の男は橋をわたり
舟にのって
遙かなる真夜中のダマスクス……へ
大理石の世界を巡りめぐり
恥辱にまみれた
一行の詩のごとき
一匹の蚤の跳ねるのを見たり
ここで本卦がえり
洪水が来た
その暁の混沌未分から
犬や猫のむくろが出てくる
人は人をつれて消えて行くようだ
地上へ音なく降る霜
詠嘆調で叙述す
きぎす ほととぎす
袋角の雄鹿のあらあらしい声の闇
つきあたりに
なまこ色の壁が存在する
誰かがわたくしの頭のうえを杏の実で叩く (啓示的に)
不用意に使えば
人間の手の中で腐る
もしくは死ぬ
ことばと肉体の一部分
反語的に考えれば それは生きているのだ
洞窟の奥で
火焔のいただきで
今日 わたくしは何もしなかった
何もしなかった
地上で起る事は地上で終る
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3月
壁掛(⑪・5、24行)
春の伝説 → 青枝篇(⑪・4、〔地の霊(春の伝説1)=27行〕〔水の夢(春の伝説2)=29行〕〔火の狼(春の伝説3)=29行〕〔空[くう]の華(春の伝説4)=29行〕114行)
4月
薬玉(⑪・10、2節80行)
5月
影絵(⑪・3、23行)
7月
哀歌(⑪・13、3節58行)
8月
天竺⑪・9、39行)
10月
垂乳根(⑪・12、75行)
12月
郭公あるいは駙い森 → 郭公(⑪・6、31行)
秋思賦(⑪・8、39行)
初出は〈大竹茂夫展〉パンフレット(青木画廊)1982年3月27日、〔二ページ〕、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、14級1段組24行(〈大竹茂夫展と詩篇〈壁掛〉〉参照)。
乙女たちは遊んでいる
善き遊びから 悪しき遊びへ
割れ竹で蛇を挟み
ときめきつつ叫ぶ
この世は汚物で満ちよ
「オンパロス」へ供えられた
かたつむり
鱈の頭
紅い糸ぐるま
ここは売買の市場から遠い
聖なる胎内くぐり
内側には橙色の絹が張ってあり
五段の石段だってある
蓬髪の白い老人に抱かれ
乙女は恥しい花鉢を濡らす
他の部屋へ廻れば
むらさき色に手を染め
二人の乙女も遊んでいるようだ
琺瑯引きのバケツの中へ
犬釘 小鳥 仮面 胞衣
死者の金歯も投げ入れる
春のひととき
まるで美しい壁掛[タピストリー]が織られてゆくように
建物の屋根から霞がかかって来る
初出は《日本経済新聞》(日本経済新聞社)1982年3月7日・14日・21日・28日〔34638号二四面・34645号二四面・34652号二四面・34658号二四面〕連載の〈三月の詩Ⅰ〜Ⅳ〉、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、7.5ポ1段組、27行・29行・29行・29行の計114行。標題はそれぞれ「地の霊(春の伝説1)」「水の夢(春の伝説2)」「火の狼(春の伝説3)」「空[くう]の華(春の伝説4)」。引用詩句に関しては〈〈青枝篇〉と《金枝篇》あるいは《黄金の枝》〉を参照のこと。
地の霊(春の伝説1)
雨乞いの儀式とはなに
アネモネの緋色の朝
ひとりの娘が丸裸になる
そしてシキミの枝で
「砂 灰 粘土のうえに
男女の像」を描く
六根 清浄
六道 媾合
ことほぐ ことばが聞え
ツグミやセキレイも交尾する
遠方より
黒雲やトカゲが姿を見せる
干割れた大地は
荒むしろで覆われ
雨に打たれる
傘の形のような小屋のまわり
ははそ葉のそよぐ
母のおとずれる今宵
娘は双生児をうんだようだ
油煙の立ちこめる
聖域を出れば
天水桶に跳ねる
大きな鯉
他者は滅びよ
みどりの芽吹くところ
金棒をかざして
幼児が現われる
水の夢(春の伝説2)
天気のよい日には
聖なるカシワの木の間を
見えかくれする(母)
女猟師の姿がある
鹿やイタチを追っているのか
ガマの穂のゆれる沼辺に
ホウネンエビが跳ねている
そこは近いようで遠い
鬼火と藁火との境界
「言霊が成長し
石も成長する」
母恋うる夕べ
わたしは数珠玉を刈り
巫女の膝の門をくぐりぬける
青蛙を踏んだ
すでに里は暮れつつ
ひとびとは納屋のなかで
「男神の形のパンをつくり
かぼちゃの葉で包む」
土器に盛り 唱和せよ
五穀豊穣
五体満足
ラッパスイセンの咲く野の夜明け
つねに狩る者
狩られる物の関係は哀しい
枯葉とともにイノシシが穴へ落ち込む
わたしは水の面に想い描く
けがれた狩衣をことごとく脱ぐ
女身を――
火の狼(春の伝説3)
乙女がふたり
料理をつくっている
魚の腹から出てきた
銀砂子を撒くと
大地に涼しい風が起る
カーテンのゆれる向う側は
黄泉のくにか 薄荷の香がする
この世は蜜と灰で
ざらざらしている
粟や芋を煮て
笹葉のみどりを添える
神饌(みけ)で死者も蘇生するんだ
乙女ふたり
声をあげ たがいのからだを
葦や藁で叩き合い
美しい身体をからっぽにする
通過儀礼の終り
ひとは善い夢をみれば
悪い夢もみる
荒畑をめぐり 墓地をめぐり
賢者は呪詞を唱えているようだ
「よろずのこと みな えそらごと」
野苺や童話の世界より
永久追放された
野生の「幻像」がよみがえる
山河図のなかに
おお 大口真神
生木は燃えて すすけた夕日の野を
わが狼は駈けて来る
空[くう]の華(春の伝説4)
父が死んだら喜べ
金槌でとんとん顎を砕き
犬歯を口から取り外すんだ
のざらしの野を行き 山を越え
フクロネズミの巣へ その歯を投げ入れよ
マツカサの実とともに
やがて春の嵐がくる
白い幣や注連縄もゆれ
金屏風は倒れる 生れ出ずる 悲しみ
男児ならば鉄の歯を生やしている
水をはこぶ母 野兎を屠る兄
浄火を起すべく 妹は裸になる
ここはウイキョウの薫りさえする
「聖家族図」のようだ
されど時は逝き 人も逝く
此岸の仕組はまさに混沌未分
ヒナギクの花咲く地から
はるばる旅してきた少年がいる
牝牛の形の帽子をかぶり
「冥府下降」を試みつつ
石枕をして眠っている
姉を探しているようだ
雨にぬれた竹筒を覗けば 筒ぬけである
青空にはハトやスズメが飛び交い
「馬頭女神像」は畑の中に立つ
去勢山羊のむれに囲まれ
少年の裸身は汚れ 傷つく
麗わしいまひるま
「死んだ番犬は何事も気づかない」
初出は《海燕》(福武書店)1982年4月号〔1巻4号〕一六〜一九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、2節80行。標題は「藥玉」と印刷されたが(目次でも同じ)、本則は新字であるため「薬玉」を採った。巻末ページ〈執筆者一覧〉に「吉岡実(よしおか みのる)一九一九年生れ。著書「僧侶」「サフラン摘み」」とある。
1
菊の花薫る垣の内では
祝宴がはじめられているようだ
祖父が鷄の首を断ち
三尺さがって
祖母がねずみを水漬けにする
父はといえば先祖の霊をかかえ
草むす河原へ
声高に問え 母はみずからの意志で
何をかかえているか
みんなは盗み見るんだ
たしかに母は陽を浴びつつ
大睾丸を召しかかえている
萬歳三唱
満艦飾の姉は巴旦杏を噛む
その内景はきわめて単純化され
ぴくぴくと
紅門は世界へ開かれている
真鍮の一枚板へ突き当り
死にかかっているのが
優しい兄である
かげろうもゆる春の野末の暗がり
蕨手のように生えてくる
それがわが妹だ
だれだって拍手したくなる
家系の序列ととのえ
二の膳 三の膳もととのう夜
ぼくは家中をよたよたとぶ
大蚊[ががんぼ]をひそかに好む
青や黄や紅色で分割された
一族の肉体の模型図ができ上る
その至高点とは金色に輝く
神武帝御影図
鳴呼 藥玉は割られ
神聖農耕器具は塵埃にうずもれて行き……
2
「かめの中の水を鎌でさっと切り
断面止まれと叫んだ」
父もはかなくなった
狐火のまがまがしい秋
出窓から眺めれば
岩の上へ涙をたらす
海鴉一羽
振りかざされる
火縄
無限大になってゆく
円の中で
破船の腹の稜線がむっちり 見える
なみ なみ 注がれる 淫水
渦巻く波へ
沈んでゆく妊婦の腹をめぐる
くらげの内壁に静電気が起り
交感 照応 消滅
死の生臭い音がする
なむさんぼう
ぼくにはどうしても
姉であったとは断定できない
夜明けになればきっと
死人満載の菱形の陸地が発見されるだろう
熱いスープを啜り
母と妹はいそいそと
カミツレの花を摘みに出る
日常用雑貨の周辺はるかに
ボーッと白鳥の浮かぶ
紺園があり
火焔のなかで喚く男が見え
経文一帖ひらひらたたまれる
手に熱くにぎられた
虬[みずち]
金剛や言霊の泯びる処
ひえびえとした枯草を刈って
母も妹もきりぎしまで行く
猫足を見よ
冬の靄は立ちこめて来る
ぼくは日々戦っている
修辞的な意味で 書法的にも
雪の塹濠には敵が潜伏している
かも知れず
ことば
あるいは かたち
新藁のうえに
鳥の卵が数顆うみ落とされている
初出は〈太陽シリーズ30――太陽美人画シリーズⅡ〉の《夏の女》(平凡社)1982年5月25日、一一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、24級楷書体1段組、23行(刷色は朱)。
〈夏の女〉によせる
かくれんぼう遊びの子供たち
干草や枯柴のかげへ
かくれて消えてゆく
四つ辻のあたり
死馬の眼におびえ
オシロイバナの匂にむせび
少女も何かのなかに隠れる
そこは幽界のように暗く
杉皮で蔽われた小屋の奥で
煮つめられた膠[にかわ]や粥[かゆ]がある
半襟の母がまぐわっているのは
老いた父ではなく
「植物神」のように見える
月光を浴びて
青いトウモロコシが立つ
地上はるかに遠く
とどろく雷鳴で そよぐ竹むらへ
とうすみとんぼや
すだまが浮遊する
夏の終り
「紅玉石は葡萄の房をみのらせる」
美しい詩句のように
少女は「物の魂」を受胎する
初出は《ユリイカ》(青土社)1982年7月号〔14巻7号〕四六〜四九ページ〈追悼=西脇順三郎〉、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、3節58行。
追悼・西脇順三郎先生
1
わたしの世界は 小さな峠の茶屋で
トコロテンを食べて
寝ころんで
タラの木
道にすてられた茶碗のかけら
人間の性器
永遠に淋しい存在を
考える
「会陰は淋しい」
春の小川の岸をめぐれば
「万物呼応[コレスポンダンス]」
「ミソサザイは青い小枝に巣をつくり」
泥と水泡の下で
「亀の頭が甲羅の中にひきこもる」
カルマだ
脳髄の意識の流れを渉り
詩人は自己浄化せよ
風そよぐ岩のいただきに
「われ存す」
2
3
自然が結んでいる
ものを離し
離している
ものを結ぶ
「紅絹[もみ]のひだで
鯉をいけどりにする」
その時ひとは 至上の声を聞く
おお パパイ!
かやつりぐさの
彼方の
かりそめの
野原を帰る
農夫は不浄の黄金の手をもつ
「現実」の父かもしれない
崖のうえに出る
すすきの穂と月のように
「遠近関係」でなく
「連結並置」すれば
野原をはるばると行く
女は「連想」の母だろうか
汝 見とどけよ
「有であると同時に無である世界」
藪にからむボタンヅル
にわっとりが鳴く
この水車小屋の暁闇から
つぎつぎに弟や妹が生まれ出る
まれには
旅人も生まれ出る
*第二章は西脇順三郎『詩学』より抄出した。
なお他の個所でも、引用した「章句」がある。
(一九八二・六・一〇 通夜の日)
初出は《毎日新聞〔夕刊〕》(毎日新聞東京本社)1982年8月16日〔38200号〕四面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平3段組、39行。「写真・佐々木正和」。
水雞[くいな]の啼く日
桶屋はタガを担いで
「関節硬直」の村落を出る
(あれは わたしの分身か)
峠の下で
こんにゃくを串に刺す女が見え
蠅叩きでハエをころす
裸の子供が見える
(ここは まだまだ この世)
つねに油煙は立ちこめ
恋心[れんしん]の乙女もいれば
死ぬ人もまだいる
遠いようで近い不壊のくに
天竺への道
まむしやのづちの類がうようよしている
(変質した「知」の漂流物も)
曠野を越え
桶屋は円形のタガを地に置き
つるつるした白玉や
赤い腰巻の内部を夢む
生木は裂かれ
黒穂は刈られ
祭儀のはじまり
青空へひびく
山吹鉄砲のポーンという音
「円が円であるように
人間が人間である時」
やまももで肉を養い
粟と稗で骨を養う
ここは苔むす「無」の世界
「腐った木の呼びかけを聞いて
返事をしてはならない」
桶屋は汗をながしつつ
岩にタガをはめる
岩が声を発す
時まで待てよ
それが永遠であれば
永遠に
(伝承に謂[い]う 「岩の声のみに答えよ」)
初出は《海燕》(福武書店)1982年10月号〔1巻10号〕一八〜二一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、75行。表紙に標題・執筆者名とともに本文を14行近く掲載(一八ページに掲載された「人の歯ぎしりにまじっ」まで、改行箇所を/で表わす追込表記)。巻末ページ〈執筆者一覧〉に「吉岡実(よしおか みのる)一九一九年生れ。著書「僧侶」「サフラン摘み」」とある。
風のとおる夏の座敷で
祖父は死にかかっている
「捕虫器のなかの活火山」
のようにぺこぺこと震動し
細い骨をかずかず突き出す
八重むぐらへ
虻はとび かたつむりのはっている
家系の石臼の在る処
たしかにここが地上ならば
(兜羅綿)という
綿ですっかり覆われている
しばしば
「虫の葉っぱを噛む音が
人の歯ぎしりにまじって聞こえてくる」
死んだ金魚は臭い
水をはこんで妹がくる
奥襖を開ければ
ひつじぐさが咲く
裏の池の中心に
呼ばれる
庭師に符丁で呼ばれる
(七人・七鬼)
父はせつなく(切字)の用法を考え
「紙の上で尻もちをつく」
――あけぼのや七人七夢にらの露
兄は氷のう[、、、]を頭にのせ
(紙銭)や(雁木玉)をかぞえる
かぞえ終るか
望月の欠けたる夜
「湿粘地とは生と死と(白粥)が循環する
原初的な(消尽点)である」
ならば眺望せよ
遥かなる(黒繩山)
「アラヌモノハ
アルモノニオトラズ
アル」
(身毒)の園は何処
野山を越え 書物を越え
霞める滝や
観念を踏破して
見えるだろうか
電球ひとつ灯る
金殿玉楼のなかで
姉はすこやかに
卵子を生み出している
昨日も今日も
それを油紙でガサガサ包む
「生膚断ち」
「死膚断ち」
「高つ神の災」の賑わうまほろば
悪世の雨は降る
けがした頭をバリカンで刈られている
ぼくは白布をかぶせられた
「啜られている無花果の
音が聞こえなくなる」
(肉体)を借りなかった
(精神)がなかったように
(言語)を借りなかった
(精神)というものはない
金物の寿命もつきる
エコーなき(作品)の青銅体 累々
かの世へ(泥降り)して
「カボカボと泥の中を歩いて
ヒルを取って渡世する
老人もいる」
(言霊)のさきわう
消し炭色の陸を抜けて
海へ
旭日輝けば
まだまだ肉体へ奉仕する
母は浴室から戻って
まるはだかのまま
「唐辛子でまぶした
肉を食べ
絹の座布団へすわった」
初出は〈M.エルンスト,ケルンのダダ展―MAX ERNST, DADA in KOLN 1919/FIAT MODES PEREAT ARS〉パンフレット(佐谷画廊)1982年12月8日、〔四〜五ページ〕、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ1段横組、31行。佐谷画廊の佐谷和彦は〈あとがき〉に「カタログにはM・エルンストに強い関心をお持ちの詩人吉岡実さんから「郭公 あるいは青い森」と題する詩をこの展覧会のためにお寄せいただいた。当画廊の展覧会カタログは今回で24号を数えるが,詩が載るのは始めてである。またテキストは本江邦夫さんにお願いしご寄稿いただいた。この詩とテキストにより,この展覧会は一層のふくらみと厚味を増すこととなった。感謝申し上げる次第である。」(〔表紙3〕)と書いている。なお、詩集で〔芸術は滅びるとも/流行は栄えよ〕となった亀甲括弧は、〔初出形〕では白ヌキの二重亀甲(〘 〙の両端が閉じている)である。マックス・エルンスト FIAT MODES PEREAT ARS展に寄せて
帽子工場の裏へまわる
(隆起する床板)のおくに
定規や針山が見える
裸電球がぴかぴか照らす
(壁のあいだから花が生まれる)
木目のあとも
みずみずしい葉脈のように
(少女の手に掴まれた
稲妻)
郭公も啼かない 夜々
人台の下から出てくる
工場長いわく[・・・]
〘芸術は滅びるとも
流行は栄えよ〙
色とりどりの糸屑が
大地をおおいつくす日まで
(擦過する 擦過する)
一列縦隊の兵士たちがいるようだ
模造銃剣の尖から 白煙がのぼり
(きみらの包茎は脱皮する
ダイヤモンドのような多面体)
朝日を浴びて輝く
礼装用へルメットをかぶって
三角塔まで行け
やがて冬になるだろう
(振子の発端)を捉える
(眼の高さ)を揺曳する空
羽目板にかこまれて
(増殖 切断 転写)
麻袋が一つ残った
(それは三倍の大きさがある)
初出は《ユリイカ》(青土社)1982年12月臨時増刊号〔14巻13号〕二八〜三〇ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、39行。4行めから11行めまでは、本篇に先立って発表された〈断想〉(《CURIEUX――求龍》(求龍堂)1978年11月〔4号〕、一ページ)を全行、変改吸収している。なお、末尾の詩句「人間はたったひとりで焼け焦げる」を括っているのは二重パーレンで、印刷物では⦅ ⦆だが、Shift_JISでこれを表示することはできないので、半角パーレンをふたつ重ねた(( ))で代用した(以下、同じ)。
かの夏の終りに
水死した詩人の遺留品
(ワラ半紙一枚の詩)
むらさき色に手を染めあげ
「水没して行く 水夫」
もしもそこが秋の霧の海であるならば
へだたった大地が在る
葱の香 書物 古靴 塩
記憶の娼婦の美服のなかでうごいている
「牙と爪をもたぬもの」
それら仮の世の仮の象[すがた]は今も美しく……
(鉄よりも重い
真昼の水)
日向で燐寸は燃え
木綿は濡れ 灰は乾き
死者はぬくぬくと
(半醒半眠のうちにある)
千鳥が石に似た卵をうむ
川原や洞穴から
転生がはじまるか
かの詩人が好んでくちずさむ
黄金の対句?
(エデンは東方に
地獄は西方に)
今ことばと物を隔てる
(水牛の大きな像がつくられた)
盲人たちの手で
極彩色に塗られる
その浮袋のようなものの上へ
初穂を供え
初潮の娘をまたがせる
まもなく嵐が来るだろう
竹筒の墓の傾く日々
沓形斧を探し
地層を堀りつづける
一人の老人の独白を伝えよう
(九万九千の身の毛の穴)
ことごとく開き
((人間はたったひとりで焼け焦げる))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
春思賦(⑪・11、40行)
甘露(⑪・14、4節68行)
2月
東風(⑪・15、51行)
5月
蓬莱(⑪・18、4節72行)
6月
青海波(⑪・19、4節84行)
落雁(⑪・17、4節67行)
9月
求肥(⑪・16、30行)
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1983年1月号〔26巻1号〕一四〜一五ページ、本文新字新かな使用、9ポ25行1段組、40行。
女の子が生まれた
(不可解なものは何もない)
地上はつねに明るく
キリギリスが三匹死んでいる
母はトウモロコシの種子を播き
父は大木を伐り倒す
燃える夕陽のなかで
それはしばしば(絵画)に似ている
しかし(生成変化)をくりかえし
人間は(白骨)化す
(形そのものが影であり
影そのものが形である)
春の氷の割れ目に落ちて
父は溺死したようだ
もろもろの(文字)は消え
(災厄をはこび去る器)
岸べを流れ
水は流れない 日夜
((われわれの(生と死)とは
同時に存在することはない))
巴旦杏のうすむらさきの
花が裸の枝に咲けば
母はいそいそと
野ねずみをころし 腸を抜き
あまつさえ竹矢来へ(桃符)を貼る
煤はらい厄はらいせよ
煙突掃除夫が現われる
(鏡にうつる顔は
近くもなければ遠くもない)
(塔)のかなたへ
(女の影がかかると
土台石はくずれた)
雷雨が迫りつつあると
気象台の警報が聞こえる
(大事)なものを
濡らしてはならない
華やげる雨傘をひろげ
(無限)にひろげ
(葦縄でしばれた幽霊)
そのものを少女は迎え入れる
初出は《すばる》(集英社)1983年1月号〔5巻1号〕二八〜三二ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ18行1段組、4節68行。引用詩句に関しては〈〈青枝篇〉と《金枝篇》あるいは《黄金の枝》〉も参照のこと。
1
乳母が帰ってくる
(影の彼女は八つの乳房を持つ)
何かがはいっている
磁気を帯びた
その袋をのぞけ
(くろごめ 赤鯛 えびかずらの実 御幣など)
入っているかも知れない
杉皮小屋が閉じられたように
(人間はみずからを閉ざす)
(屋根からおちる霊魂を
莚で受けとめる)
祖父は眼をやみ
祖母は膣をやむ
ニワトコの花が咲くころだ
2
(眼の上に銅貨を置かれた
商人)
父は死につつある
迷宮の肛門を抜け
石化する(糞)は雨露を弾く
みはるかす夕べの空には
(毛のはえた星)
その下にとどまる(肉体)はむず痒い
うずらをわなで捕える男は唄う
(愛して死ぬ
愛して死ぬ)
皮ぐるみ 血ぐるみ
(咬噛動物)のはいまわる
みどりの森から 枯れた沼へ
母はいつまでも柳の木のかげで
(蛙をこっそりつねったり
叩いたりしてギャーと鳴かせる)
そして ちはやぶる 荒ぶる(神)を招く
(死者の名はすでに古い
秋の木葉のように)
3
(青いカケスに肺病を負わせる)
三人の美少年のひとりか
ぼくはブリキの兜をかぶり
朝の窓から外を眺める
(葦牙[あしかび])のそよぐ漣を渉りゆく
鷺足は墨の一刷け
((泡立てて水の中を通過する(時間)と煙))
消えかかる
(麗人の絹の腕)
濡れた草花におおわれ
ダヴィンチの飛行機の模型が見えた
(太陽が金箔をまき散らし
影は紫にそまる)
真昼へ生唾を吐く
姉の大口を覗けよ
(海水[うしお]のつぶたつ)
(顎は鋼刃 瞳は紅玉の輝き)
いましも荒れた地へ(五月の棒)をつき立てる
短いもの 長いもの
細いもの 太いもの
やがて(五月の樹)は繁茂するだろう
野猪も仔を生みにくる
もぞもぞと成れる(御嚢[みふくろ])
(影の皮の八つの乳房)
吸いつく 吸う 吸いあげる
吸いつくす(甘露)
4
ひとよ可能ならば
(彼岸から持ち来たる
ものに形を与えよ)
色界はすでに滅び
(一世界)のみが在った
(碾臼的装置)
(水輪)の上を
(金輪)はゆるやかに廻っている
*(引用句はおもにフレイザー《金枝篇》永橋卓介訳を借用した)
初出は《をがたま》(をがたまの会)1983年2月〔冬・8号〕二〜五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は並字・カタカナの拗促音は小字)使用、五号15行1段組、51行。目次・本文の作者名は「吉岡實」。
地表すれすれに
めぼうきの花は咲き
青いバッタは飛ぶ
村の巫女は言つた
(田園は神がつくり
都会は人がつくる)
其所から出ることはない
ぼくは高々と竹馬に乗り
(円環的時間)の中で成長する
家の白襖はいまも閉じられ
(斧で殺された者は見えず)
草をはうアシナガグモが見え
(老人星)が見えた
紗幕の向うには
((一個の(桃)はひとりの女
と同じほど生きている))
石囲いの屋敷の
(六畳間)と(八畳間)の
(間)に在る
裸庭のやみを覗け
湯浴みし(湯母[ゆおも])は弟を抱き
父を抱き
(祖霊)をしつかりと抱く
(情景世界)
午下りの(水潦[にわたずみ])
石は横たわり
(風は屍を旋回する)
ぼくは何をすればよいのだ
馬盥へ(すだま)は宿り
竹の枝へ雀はとまる
(梢は刁刁[ちようちよう]として小さくそよぐ)
兄の悪しき妄想だろうか
牝牛の腹を割く
血肉は消尽し
(生皮の内部)はぼうぼう燃えていた
穀物祭の夜のように
(浄化作用)が行われつつある
匂いスミレは匂い
(梨の木の下の地面を
ころげまわる女の影)
あれなるは懐妊せる
ぼくの母のすがたかも知れない
しばし東風は吹きめぐる
滝の上 老松 砂洲
赭岩から(息づく水)が噴き出す
(畑の畝から生まれる
女神)
ひとは(妹)と呼ぶ
はるかなる(過去) はるかなる(未来)
否
(すべてが現在だ)
初出は《歴史と社会》(リブロポート)1983年5月〔2号〕一五八〜一六三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ18行1段組、4節72行。
1
(人間が死なずにすむ
空間はないのか)
祖父はいまなお
(蓬莱郷)を探究しつつ
青菜粥をすする
風すさぶ暗い軒より
雉子の首を吊るす
家はすでに(遺構)だ
腐った木々で囲まれている
(行きつく
ところのない
時と時のあいだ)
母屋のみは明るく
紅白の縞の幕を張りめぐらす
なればこそ(霊魂)はとどまる
(柞葉[ははそば])の母の捧げ持つ
(軽いようで 重いもの
小さいようで 大きなもの)
(白木の三方)が置かれた
(歯朶 米 橙 いせえび
榧 かちぐり 昆布)
(松)のみどりが中心に立てられる
(飾られた風物詩)
ほうらい (宝来)
(飲食[おんじき])するはらからの宴も終る
(いずこにも不死の人はいない)
2
姉には(星菫)趣味がある
鷹の羽を黒髪に飾り
麦藁と矢車草で
(野兎)を編む
それは(幽界)へ通ずる
(言葉)をこえた(発光体)だ
(習習[しゆうしゆう]たる谷風)のように
川面や野づかさを越え
巨きな樟のうろへかくれる
(形代[かたしろ])
やがて(霹靂[はたたがみ]とよもす天地[あめつち])
3
(亀甲獣骨)に刻まれた文字
その最初の(文字[もんじ])は
斧でたたかう
(父)の一字ではなかろうか
暗くもなれば
明るくもなる
(社会構造)の迷路から
遙かなる処へ
父は手甲脚絆すがたで
砂鉄掘りに行って帰らず
消毒液のしばしにおう
淋しい(逆旅[はたごや])のみちづれひとり
(聖なる父)ゆえ
(女の姿と鱈の見境いがなくなる)
4
((馬に起ることは
(人間)にも起りうる))
妹はうらわかく
孕んだはらを裂かれて
死んでゆき
(人は橋上を過ぎて行く)
なれど(何者に語り得べき)――
ぼくは一篇の(鎮魂歌)を書く
(骨も見えず 肉も見えない)
(白紙の世界)をさすらいつづけ
(竹藪をぬけ出ると
そこに老婆が立っていた)
日は高く 鶴は舞い
岩根は低く 亀は這っている
(可視線の書き割り)
扇をひらくように
三葉 五葉
そして七葉の松が白砂へ連らなる
(箱庭)かもしれず
((いまは(自然)がむしろ
(不自然)に見える時である))
初出は《海》(中央公論社)1983年6月号〔15巻6号〕二二〜二五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ26行1段組、4節84行。
1
模造マホガニーの長椅子にねて
瓜や桃の実をほおばる
わが母の双面体を見よ
(やしゃとぼさつ)の二股膏薬を貼り
脚をたかだかと組みかえる
(毛は雲のごとく
血は露のごとし)
((美しければ(幻影)と
(実在)はほとんど一つとなる))
(大祓)の夜々は
(桑樹)の枡形のうろへ
(幽世[かくりよ])から
西風が吹きよせる
(よく隠れし者は
よく生くるなり)
わが父は帰るであろうか
戸口に立つ
(箒)のように顕現せよ
(星 犬 松明)
(檜扇)をばたばたあおぎ
産婆が来た
ここは(宗教的領域)
2
(木の葉の冠をした
裸の子供が
金の笏を持って現われる)
それをぼくだと認知する
(うから)も姿を見せない
(麁草[あらくさ])の世界
桑摘み乙女に抱かれ
(えびなます)で養われる
(日八日夜八夜[ひやかよやよ])
鯉の口は紅を刷き
(吐き出しても
吐き出しきれぬ)
もどかしいもの
(言葉)
(我)という概念の中の(汝)よ
((生れ 生れ 生れ
生れて(生[しよう])の始めに暗く))
(詩人)と謂われる
おぞましい(存在)と成れ
(やわたの藪)のおくで
(手負いの猪の仔)
わが姉は看取り
(歯のこぼれた鋸)のように
わが兄は松の根に隠れる
(歌垣)
麗わしい(農耕詩)の一節だ
3
((無花果をつたわり
(太陽)が地上へ降りる))
家の中には何も
(生じも滅しもしない)
唯ひとつの(葫蘆[ころ])と
(種婆[たなば])へと化身する
わが母がいるだけだ
夕べ湯文字を巻き
襦袢をまとい
(愛の裂傷)を負いつつ
まさに(再生儀礼)へ
月下はるけく
(青海波[せいがいは])
十重二十重と打ちつらなる
半円状の白い波がしら
(鱶の泳法)を試み
かつ乗り切る
(生死循環)の時間の中で
わが(永遠の母)の聖俗性を伝えよ
それは遍在するだろう
(顕世[うつしよ])に
4
((ものの(形)とは
一枚の(死衣)をかぶせられ
はじめて見えてくるものである))
箸 貝 櫛 (金蚕)
そして(蛇)
脱皮 脱皮 脱離
わたしは成長する
(棺桶の釘を抜き取り)
柊の葉をかざして
朝日さす廃屋の(かまど)へ
(火)を起す
火吹き男ひとり
それはわたしの(擬[もどき])かもしれない
(荒筵)を敷きつめるところ
(朽鶏[くだかけ])が来る
初出は《饗宴》(書肆林檎屋)1983年6月〔夏・10号〕一六〜二一ページ、本文旧字新かな(ひらがなの拗促音は並字)使用、12ポ15行1段組、4節67行(漢字の旧字使用とひらがなの拗促音の並字使用は、他の掲載詩篇と同様、《饗宴》誌の編集方針だと考えられる)。標題の前に「追悼詩」とある。(言葉よ 死の底より自らの蜜を分泌せよ) 鷲巣繁男
1
((すべて(現世)は火をつけられ
すべて(現世)は燃えひろがり))
倒壊する
淫祠邪教の(都会)
蓬頭の(死母)が全身で支える
(大梁の下で
わたしと弟は救われた)
来てみれば秋
ここは(落雁)の見える寂しい
水の上の光景だ
(西空へ裂かれた
血潮雲)
わたしは(負)の荷を担いつつ
(古き世の母親)のうるわしい
(((霊魂[プネウマ])の立ち上り))を見た
2
(迂遠なり言語空間)
振りむくな
いのこずちは茂り
(空罐山をなす)
いたる処
((見えるような(道)は
風化した(道)だ))
わたしは遊行する詩徒か
(歩めば 炎え上る身体
発すれば 炎え出ずる言葉)
ささら打ち
たたら踏み
(肉が霊にあこがれ
霊が肉をいとおしむ)
全人的な(善悪)の概念を
変容せしめ
習合する日日
丁子の樹はいま花咲き
薬油をたつぷりたくわえる
(瓦斯体より
甦れ つねに新しく
わたしの言葉)
3
粉挽き唄が聞こえる
(孤屋)の羽目板から覗け
(荒服)の人は胡坐かく
破れ畳のささくれた上に
(存在する詩)
それを待伏せしているようだ
風にとばされし
(十銭区間の赤い薄ぺらな
切符)
それは(悪霊)を退散させる
(護符)であるかもしれない
(天国もあれば まだ地獄もある)
床下の(不可触)の暗い穴
くちなわ たにぐく こおろぎ
ひむし くえびこ いきずみたま
(童の呪宝)もたむろしている
4
原義として言えば
(青年は肉体をもち
老年は知恵をもつ)
その(不可分の関係)を知れ
違和感もなく
わたしは認識する
(形而上学は
深山に無く
密室に無く
典籍に無く
凡傭なる炉辺の猫にある)
生きている限り
人等よ
(((時空)と(謎)に身をまかせよ))
初出は《花神》(花神社)1983年9月〔秋・3巻3号〕二〜三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、五号17行1段組、30行。
わたしが子供であった頃
夕空高く
(龍の頭を持つ
大きな鳥)が飛んでいた
(草は生え 花は咲き
人は死んで行く……)
兄は(器官のない身体)と化し
(石)と
(火)のあいだを
ゆききする(水)
屏風の向う側は
(紅葉[もみ]づる)
黄金の秋
(父は槲[かしわ]の枝を持ち
母は土の瓶子[へいじ]を持つ)
播殖期だ
(思考)と(言語)でなく
(肉体)をみちびき入れる
(呪詞)をとなえ
(巣出[すで]る)蟹をとらえ
(万燈)を灯せよ
(神はみのかさつけて来る)
穀霊祭の終り
雨に打たれて
家畜の影は遠ざかり
亞麻畑の朝が明けた
(牧牛女スジャーターの捧げる)
供物とはなに
白と紅の(求肥[ぎゆうひ])を
姉は受けとる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6月
白狐(未刊詩篇・16、42行)
9月
小曲(変改吸収詩篇・2、20行)
10月
少年 あるいは秋(変改吸収詩篇・3、14行)
12月
聖童子譚(⑫・4、〔1 夏=14行〕〔2 秋=21行〕〔3 冬=13行〕〔4 春=35行〕83行)
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1984年6月号〔27巻6号〕の〈特集・詩の未来へ〉三〇〜三二ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、42行。
いなりの屋根を降りる
われらは無を漂ってはいない
血のかわりに言葉を発する
金屑がとぶ
バンソウコウをすべての
抽象物に貼る
何の目的で人は生きるか
バラ色の水にうかぶネズミの死骸へ問え
喩の敍述を替える
ザクロの外側では
老人から子供までの笑い声
蚊帳を吊った川の洲へ
われらは渡る
穀物を刈るために
もしくは
領巾ふす蛇の魂をしずめに
燈火をかかげた
頭上へ絵画の枠をつくる
鋸に挽かれる十本の杉
死ぬ時に書く十行の詩
足をそろえて冷たい母
白狐
それは呼ばれた
ムシロのざらざらした世界へ
思った思おうとした
あまさかさまの日々
将棋盤の上で
美しい相のやまとは昏れよ
のどかに
蜂をリンネルで
包む学者を見たことがある
われら人生派は今も
自然を過して
意味をつくる
商人は好きな葛湯をすすり
夏の午後は入浴す
見えるさわれる
開かれる事物はどこへ
こんかい
コン・クワイ
われらの奏でる嬉遊曲
姉妹を水門の上に立たせる
*「現代詩手帖」二十五周年記念号に是非とも作品を寄せよ、との小田久郎氏の要請をこばみがたく、十余年前の自動記述的な草稿に、若干の手を加え、『薬玉』の詩篇と同じ形態をととのえ、ここに発表する。 五月九日
初出は《Mainichi Daily News》(毎日新聞社)1984年9月17日〔22128号〕九面の〈20:20――20 Poems by 20 Poets in 20 Lines〉、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、12級1段組、20行。初出時、〈Shookyoku〉〔ローマ字表記〕と〈A Short Piece of Music〉〔Roger Pulversによる英訳〕を付す。吉岡家蔵ファイルの切り抜きには、掲載紙の情報のほかに、「「聖童子譚」入れる」という吉岡自筆のメモが書かれている。のちに全行が〈聖童子譚〉(⑫・4)に変改吸収された。
眼のまえで
「一つの石が
空中で溶け失せても
驚かない」
絶世の美人がいる
日傘をくるくる廻し 夕日のなかに
ぼくは少年だから
あらゆる章句に
疑問符を打つ
「彼女の正体」を見よ
柳の葉のかげから現われた幽霊?
それともアフロディーテーの末裔?
今もツバメが飛びかい
芥子の花が咲きみだれ
この世かあの世か判断できない
「カーテンの
レース織りに包まれる」
村落から沼沢地まで
「死ぬ人は駆け足だ」
すでに秋のはじまり
初出は《別冊婦人公論》(中央公論社)1984年10月〔秋・5巻4号〕三七三ページ、本文新字新かな使用、9ポ1段組、14行。吉岡家蔵の切り抜きには、掲載誌の情報のほかに、「「聖童子譚」入れる」という吉岡自筆のメモが書かれている。のちに全行が〈聖童子譚〉(⑫・4)に変改吸収された。
ぼくは(父)を憎んでいるようだ
(母)のかくしどころの
(深淵)より
にがりや泡沫とともに
胎生の(弟)が浮かび上る
(句読点)の(点)のように
あいまいな夏の日々
鯉は腹を割かれつつ
一つの(呪文)をくりかえす
その口唇はやわらかく
今宵の(姉)のようだ
荒ぶる魂 冷えるかかと
ぼくは水鉄砲で
(実体)なきものを撃ちつづける
初出は《ユリイカ》(青土社)1984年12月臨時増刊号〔16巻14号〕一六〜二〇ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、〔1 夏〕〔2 秋〕〔3 冬〕〔4 春〕83行。本篇に先立って発表された〈小曲〉(《Mainichi Daily News》(毎日新聞社)1984年9月17日〔22128号〕九面の〈20:20――20 Poems by 20 Poets in 20 Lines〉、20行)と〈少年 あるいは秋〉(《別冊婦人公論》(中央公論社)1984年10月〔秋・5巻4号〕三七三ページ、14行)のそれぞれ全行を〔2 秋〕と〔1 夏〕に変改吸収している。
1 夏
ぼくは(父)を憎んでいるようだ
(母)のかくしどころの
(深淵)より
にがりや泡沫とともに
胎生の(弟)が浮かび上る
(句読点)の(点)のように
あいまいな夏の日々
鯉は腹を割かれつつ
一つの(呪文)をくりかえす
その口唇はやわらかく
今宵の(姉)のようだ
荒ぶる魂 冷えるかかと
ぼくは水鉄砲で
(実体)なきものを撃ちつづける
2 秋
眼のまえで
「一つの石が
空中で溶け失せても
驚かない」
絶世の美人がいる
日傘をくるくる廻し
夕日のなかに
ぼくは少年だから
あらゆる章句に
疑問符を打つ
「彼女の正体」を見よ
柳の葉のかげから現われた幽霊?
それともアフロディーテーの末裔?
今もツバメが飛びかい
芥子の花が咲きみだれ
この世かあの世か判断できない
「カーテンの
レース織りに包まれる」
村落から沼沢地まで
「死ぬ人は駆け足だ」
すでに晩秋のはじまり
3 冬
「ふくべ棚のあなたより
現われ出でる
北斗七星」
旧家の中庭の狭筵[さむしろ]で
母は詠っているようだ
〽狐は川から魚を取る
猿は木から果実を取る
みはるかす蒼海原から
父は手ぶらで帰って来る
「粟散辺土[ぞくさんへんど]」へ
隣人はいそいそと
「麦の袋を数えたり
墓碑銘を刻んだり」
4 春
かげろうは消え
土蜂はかえってゆく
野の丈なす草むらへ
待ちつづけるもの
待された(磐根[いわね])をめぐり
ざわざわする 木立の木の葉
ざわざわする (皺を持つ鏡)
それらの(霊媒化[メデイアム])
土摺り 草摺り 岩摺り
探し求めよ!
真言
炭素
卵
福袋
竪琴
「事物とことばは
同じ傷口から
血を流す」
カンノンビラキ
の金色の扉より覗け
(秩序[コスモス]を裂く)
ひとりの女が腰をひねった
陽気立つ(空桑[くうそう])のおくから
(賢者)も
(愚者)も
産みおとされる
石のごとく 蝋のごとく
漂泊の岸に
葦の葉の舟は流れ
いずこも春のひるさがり
水枕の恋しい(身削[みそ]ぎ)の母よ
ぼくはいまだ(小男[おぐな])だ
蝶や小鳥の舞いとぶ
花園を這いまわり
黄頷蛇[さとめぐり]を捕えた
*(1)は別冊「婦人公論」、(2)は「英文毎日ニュース」に発表したものである。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
わだつみ(⑫・3、31行)
4月
ムーンドロップ(⑫・10、5節80行)
6月
薄荷(⑫・6、4節52行)
7月
カタバミの花のように(⑫・2、30行)
9月
秋の領分(⑫・5、32行)
初出は《毎日新聞〔夕刊〕》(毎日新聞東京本社)1985年1月5日〔39054号〕四面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平1段組、31行。「写真・佐々木正和」。入稿原稿を忠実に再現したためだろう、行頭の起こしの括弧――鉤括弧(「)とパーレン(()――が仮定される天のラインよりも上に突き出て組まれている。すなわち、最初=1行めの鉤括弧と文字(「祖)の間と最終=31行めの鉤括弧と文字(「真)の間を結んだ線を天のラインとすると、9行め(ぼくは遊行のすえ家路をたどる)、20行め(洗われる下着や(撞木))、29行め(白波立つ 沸騰点より)の各詩句は、一字下げではなく天ツキということになる。
「祖父は山へ柴刈りにゆき
松の小枝とともに
谷の淵へ落ちてゆき
祖母は川へ洗濯にゆき
(空虚舟[うつほぶね])で漂い出る」
時じく 散る花 鳴く鳥
「死も一つの放浪である」
とは賢者のことばだ
ぼくは遊行のすえ家路をたどる
一歩二歩ゆるやかに
「金色の亀が這っている大地」
(夜見[よみ])遠見
此処からこの世を眺めよ
「包帯を巻かれた
牛の脚が見え
椅子の折れた脚が見え」
薄明がくる
「花咲く木の下に眠る女」
わが妹のふとももが見える
洗われる下着や(撞木)
みどりの網の目をひろげる
(地下茎)
さざなみ (白骨) 裂けた岩
「わだつみの彼方は
永遠に(妣[はは])のくに」
「母は船の帆のように美しく
光と風を受け」
孕んでいる
白波立つ 沸騰点より
父はいきいきと(朽木)でなく
「真紅の鯛を釣り上げる」
初出は《潭》(書肆山田)1985年4月〔2号〕四〜九ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ21行1段組、5節80行。
1
生ぬるいセルロイド色に
月は衰弱する
わたくしが気になるのは
ほかでもなく
ロベルト夫人の下着の下の梨形の
(臀部)
その全体の重み
その(共犯性)
露出する両手へ交感せよ
(不安な感じで腿を持ちあげる)
遙かな(狭間[はざま])に
(白波)が見える
「どうでもいいの
どうでも」
2
春の鶯は鳴く
雪の塚のやさしい盛上り
(むらさきの穴の収縮)
「非地上的なる
調和の世界に
呼吸している」
(物悲しげな裸像)
「土台は大きい
ほどいいの」
草地の中を
紳士たちは(水鉢)を持って廻っている
最初の一歩を踏み出してから
五年経っている
わたしはしばしば思う
彼女の所有していた物のことを
(経典)(槍)(仔鹿)(髑髏[ひとがしら])
柘榴の木の蔭で
「からだが地上から浮いている
ことに気づいていない」
ロベルト夫人
(神の模像?)
「それを覆っている
雲はみなひと雫に凝縮する」
屈辱 涙 (愛の頽落)のように
3
「星一つない夜の
青い蛾を誘い込む」
わたしはこの章句の隠喩[、、、、、]を
次のように解読する
檜垣や草花にかこまれた
(四阿[あずまや])の床机に
少年をすわらせている
ロベルト夫人は心のなかで唱える
(神秘的な花粉)を消すこと!
(青虫から
蝶への変態[メタモルフオーシス])
「そのキラキラした
一瞬が見たいのよ」
葦笛の鳴る方へ
オシドリが二羽
すいすい游いでいる
(菱形の池)
軒端にかかる
(月明り[ムーンドロツプ])
「これは出来のわるい
墨絵だわ」
4
「蛾が一匹パタパタ音を
立てて飛んでいる」
(昧爽[あかとき])
長い回廊の柱をへめぐり
「残飯桶と箒を持つ
腰の曲った雑役婦」
ペタペタ
足を引き摺りやってくる
苔むす敷石まで
「この肉色のポンプが
すきだね」
「万物が矛盾的に遍在する」
(虚空[おおぞら])の下で
(異化)された(美)
女の(霊体[アストラル])は水を飲む
「太陽にさらされて
(金の骨)が透けて見える
烏賊が欲しい」
5
わたしは(詩行[ライン])を
つらねたかったが失敗し……
「幽霊との出会いは延期された[、、、、、、、、、、、、、]」
*題名と若干の章句をナボコフ『青白い炎』(富士川義之訳)から借用。
初出は《四谷シモン 人形愛》(美術出版社)1985年6月10日、九六ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、13級3段組、4節52行。対向ページ全面に少女/人形を描いた四谷シモンの銅版画を掲載。引用詩句に関しては〈吉岡実と四谷シモン〉を参照のこと。
(人形は爆発する)四谷シモン
1
夏が過ぎ
秋が過ぎ
「造花の桜に
雪が降り
灯影がボーとにじんでいる」
池の端の(大禍時[おおまがとき])
振袖乙女の幾重もの裾の闇から
わたしは生まれた
(半月[はにわり])の美しい子孫か
「神は急に出てくるんだよ」
(非・器官的な生命)を超え
(這子[はうこ]) ひとがた
人形は人に抱かれる
(衣更忌[きさらぎ])の夜を
2
母親の印象は
裸電球の下で
白塗りの女戦士のようだ
赤い乳房が造り物に見える
「カミソリでサーとなでると
中からまた肌色の乳房が
殻をやぶって生まれてくる」
それに噛みつくから
わたしは消化不良
の子供
(唐子[からこ])の三つ折れ人形を
背負って
鈴虫の音色に聴きほれる
父親は冷酒をあおっては
(毒婦高橋お伝)をたたえ
ヴァイオリンを彈く
キー・キー・ギー
「天国がどんどん遠くなる」
3
窓まで届かない月の光
ニーナ・シモンの唄が好き
縫いぐるみの(稲羽[いなば]の素兎[しろうさぎ])が好き
「固い真鍮のベッドで
わたしは紗のような
薄い布を身にまとって寝る」
花のように
「ゆるやかな酸素に囲まれる」
少女の輝く腹部を回転させよ
アー・アー・アァー
(官能的な生命)
「人形にだって
衣食住が必要である」
揚げ物を食べた後は淋しい
この部屋の外は
「巨大な蓮池の静寂を思わせる」
4
「編み上げの黒い靴
それには犯しがたい
(聖的)な影が存在する」
(土星)が近づく
何のおしらせもなく……
初出は《朝日新聞〔夕刊〕》(朝日新聞東京本社)1985年7月26日〔35760号〕七面、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、7.5ポ3段組、30行。絵「加納光於」。顔写真とともに、横組で「よしおか・みのる 1919年、東京生まれ。シュルレアリスティックなイメージにあふれた詩集『僧侶』で第9回H氏賞。著書に『サフラン摘み』(高見順賞)、『〈死児〉という絵』、『薬玉』(歴程賞)など」と紹介がある。《ムーンドロップ》の〈初出一覧――〉には「(改作)」(同書、〔一三八ページ〕)と記されている。
「兎を抱く少女像」
これは今わたしが見ている
朱塗りの額縁に収まった
絵画[、、]なのか?
「これは絵ではない」
窓の外の崖の上で
カタバミの花はそよぎ
雲は揺曳している
「青には大きさがない
それは大きさを超えている」
夏のひるさがり
兎を抱いて少女が来る
二番煎じの
紅茶をすすり
わたしは妄想する
「事物と密着した部分へ
指を差し入れる」
蝉がジージー鳴く
竹すだれを透かして眺めよ
「肉体という
広大なる風景」
男たちが遠方の薮や川で
探しあぐねているもの[、、]を
女たちは素早く手に入れる
吹出物だらけの少女よ
「野の風は
もはや帰らぬ」
やがてきみ[、、]は身籠り
赤ん坊を産む時
「光は影からもがき出てくる」
初出は〈小沢純展〉パンフレット(青木画廊)1985年9月17日、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、16級17行1段組、32行。表紙に冒頭の4行が改行箇所=3倍アキの追込・横組で掲げられている。詩篇の本文用紙は薄葉紙。《ムーンドロップ》の〈初出一覧――〉には「(改作)」(同書、〔一三八ページ〕)と記されている。
「西洋梨の実はどっしりと
腰がすわり
(豆電球)が点滅して
入っている」
ぼくのつくった
この(作品)を見て
赤面症の從妹は言う
「死んだお母さんの肖像ね」
どこにでも見かける
「コスモスの波間」で
ぼくは瞑想する
「何ものも説明しえない
体験は夢を導く」
グロヴナー公の森を歩く
鳥は啼き 草木は茂る
(影の書割り)
「女たちの胎のなかに入っている
(火薬)を
男たちは巧みに取り出している」
吐き気がする
吐き気がする
茸採りの一人の少年は帰ってゆき
冷えたサイダーを飲む
領地の終るところ
柏の大樹の根もとをめぐり
柏の葉を食べつづける野兎
(鉄の彫刻体)
内部にさざなみの立つ
暁がくるまで
ぼくは思考し
「横たわる紙の上で
デッサンする」
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
雪解(⑫・7、20行)
寿星(カノプス)(⑫・8、5節78行)
5月
亜麻(未刊詩篇・17、10行)
6月
聖あんま断腸詩篇(⑫・12、〔Ⅰ 物質の悲鳴=23行〕〔Ⅱ メソッド=26行〕〔Ⅲ テキスト=12行〕〔Ⅳ 故園追憶=40行〕〔Ⅴ (衰弱体の採集)=41行〕〔Ⅵ 挽歌=31行〕〔Ⅶ 像と石文=15行〕〔Ⅷ 慈悲心鳥=8行〕196行)
8月
叙景(⑫・11、35行)
12月
銀幕(⑫・9、39行)
産霊(むすび)(⑫・1、62行)
初出は《文學界》(文藝春秋)1986年1月号〔40巻1号〕九ページ、本文新字新かな使用、9ポ1段組〔コラム〈扉の詩〉〕、20行。カット:司修。
雲形定規を操作して
ぼくは(何か)を描いている
それは朝日に輝く
蜘蛛の巣の糸か
茜空の下の糸杉か
今は(肉)を主題とする
(心)の問題であるから
もしかしたら沐浴する
姉の似姿かもしれない
神殿の園に咲く
スミレの花のように
「ぼくの目差しをどこまでも
吸取紙のように吸い込む」
これは描かれた絵ではなく
たえず書き替えられる
(言葉・記号)
聖俗いずれの領域にも属し
「ブリキの上を歩く虚しさ」
月光 鱗光
谷川から雪解の音がする
初出は《海燕》(福武書店)1986年1月号〔5巻1号〕一六〜一九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、5節78行。巻末ページ〈執筆者一覧〉に「吉岡実(よしおか みのる)一九一九年生れ。著書「僧侶」」とある。
1
「海山の傾斜や
岩の露出を登ったり
降りたりする」
ぼくは(化石少年)だった
(三葉虫)や(蛍石)を手にする
「この採集物はすこしも
(言葉)に似ていない」
むしろ(絵画)に似ている
テーブルの上にならべたら
妹が来てつぶやく
「お父さんのからだの(癌)のようね」
新月の夜は
母と兄は赤粥をすすり
茨垣でかこまれた
大盥のなかで
身もだえる姉がいる
2
「少女はそこに寝て
下肢をそっと閉じている」
これは(石像)ではない
ひとつの(幽態)
ぼくの構想する(作品)は
複雑な媒介が必要だ
びしょびしょに
濡れた泥の上を疾走する
「犀の写真を見ている」
夏の沼で
「沈むことに始まり
浮くことで終る」
(蓮華)や(子供)も見えた
もろもろの(印象)を
「眼の中に書きとめる」
隠喩から韻律へ
それは推移する
放物線から曲線へ
翔ぶならば鳶!
はるかに
水の上を走る稲妻
3
「萌え出ずるも
枯れるも
いずれも同じ野辺の草」
雪消えの瀬を
せかるる谷川の水の
(最初の渦巻)
「ここで時間は分岐する」
樹々は濡れ すべての(道)は濡れ
(根棲[ねずみ])はがちがち歯を鳴らす
薄明を逍遥せよ
この世とあの世を繋ぐ
(板戸一枚の山水図)
(苔衣)の者とともに
父は鉄杖を握って巡っている
墜ちるならば
(水分[みくまり])の闇へ……
鶯のように可憐に
「一つの瀑布が囀り初める」
4
「狂者ニ非ザレバ
興スコト能ハズ」
乳母から教えられた
獄死せる賢者の
(浄句)をとなえて
ぼくは(作品)を造りつつある
「この世に姿を現さない
美しい物を抱きしめたい」
一瓲の桜の花びらを浴びる
(象牙の乳房)
寿星[カノプス]のひかり
5
「ヘアードライヤーで
早くかわかしなさい」
これがぼくの(作品)の形姿?
(水車の水受板)
水をかぶったり 廻ったり
「兄の寂寞を
妹が慰める」
(ハーベスト・ムーン)
(秋の満月)
「眠れるものなら
とっくに
眠っているよ」
初出は《文藝春秋》(文藝春秋)1986年5月号〔64巻5号〕八九ページ、本文新字新かな(カタカナの拗促音は小字)使用、8ポ13行1段組〔コラム〕、10行。
「赤と緑の線で出来た
溝の中に放りこまれている」
男と女
「メリーはジョンを愛している
ジョンはメリーを愛している」
けれど内側は覗けない
絵画や音楽のように
男と女は宗教的な祭儀を行う
「一つの丘みたいなもの」
亜麻は風になびくほど成長する
初出は《新潮》(新潮社)1986年6月号〔83巻6号〕二二〇〜二三〇ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、〔Ⅰ 物質の悲鳴〕〔Ⅱ メソッド〕〔Ⅲ テキスト〕〔Ⅳ 故園追憶〕〔Ⅴ (衰弱体の採集)〕〔Ⅵ 挽歌〕〔Ⅶ 像と石文〕〔Ⅷ 慈悲心鳥〕196行。標題の前に「長篇詩――土方巽追悼」とある。吉岡は《土方巽頌――〈日記〉と〈引用〉に依る》の〈補足的で断章的な後書〉の14に「〔昭和六十一年〕四月十五日、晴。追悼詩「聖あんま断腸詩篇」ついに完成す。わが誕生日。」(同書、筑摩書房、1987年9月30日、二三九ページ)と書いている。
〈神の光を臨終している〉 土方巽
Ⅰ 物質の悲鳴
「この狂おしい
美貌の青空」
軍鶏の首をつかんでいる
「あの老婆も狼煙の一種で
あったかもしれない」
私は生きている者
そして一度は通って
みたいような(処)へ差しかかる
「物質の悲鳴が聞こえた」
小鳥の声も聞こえるなかで
「言葉が堕胎されている!」
散乱するもの
肉片 破片 記号
「人間的な言語が多量すぎる」
ゴムの鳩を抱いて
少女が立っている
この異常な明るさは
「光じゃありませんよ
もう闇ですよ」
ここは(仮の地)?
オガクズが敷かれていた
「灰柱まで
私の死への歩行が続いている」
Ⅱ メソッド
「にわとりの頸をひねり
裸電球をひねる」
男の後姿を見よ
「形や像を越え
一つの抽象的な
次元へ向っているようだ」
犬だって塀沿いに影めいて
走っている
「闇と光を交配させる」
という(行為)を私は好きだ
藁の積まれた処
「幽霊の乳を飲んでいる」
(赤児)のようなものが見える
身をかがめて
凍った(形象)を追求し
私は路上を巡りつづける
(絵画)で説明できない時は
(本能)で試みよ
「ここまでが生体で
ここからが死体だ」
蠅叩きで
冷えた畳表を叩き
「土間の消壺に近づいてゆく」
男の(裸体)を消す
炸裂するように弾ける
(星形)
Ⅲ テキスト
「葛[かづら]を被[かづき]て松の実を食み
鳥の(卵[かひご])を煮て食[くら]ひて
桑摘女は児を撫ぜ
(𨳯[まら])を吸ふ
なれば(嬭房[ちぶさ])は張り
(開[くぼ]の口)より
(神識[たましひ])を昇らせる
(奇異[あや])しき事かな
嗚呼やがては
(銅荒炭[あかがねあらすみ])の上に
(鉄丸[てちぐわん])を置きて呑み
地獄に堕ちむ」
暗黒舞踏のフェスティバル「舞踏懺悔録集成」における、講演のためのテキストをつくる時、私は『日本霊異記』を参考にした。それを拾い読みしていて、この章句を見つけた。古代から「母子相姦」の悲劇があり、それはこれからも、永遠に続くだろう。――(H)
Ⅳ 故園追憶
私は(骸骨)で生まれたのだ/弥生の曇った空の下で/こ
の秘密は父母しか知らない/ああ(骨の涼しさ)/湯気の
ような(肉体)を着せられて/初めて産声をあげる/みど
りごに成り/ブリキの匙で片栗粉を口に流しこまれる/甘
露!/だから途中から肉が付き/梨頭の子供へ変る/ほん
とうに冷えた砂枕が好き/夏のひるさがり/姉とは突然に
(家)からいなくなるものだ/
鳶が風を切って降りて来る
/草深い外の面の沼で/沈んでいる亀/畷を歩きながら死
んでいる人たち/風のさわぐ日に限って/鹿肉を売る商人
が来る/父親はそれを(神品)として大事にする/蕗の葉
や芋の葉の上に/ころがる滴玉/また道端で転んでいる老
人が多かった/私は板のささくれた面に/クレヨンで/兎
の絵を描く/ついでに(女陰)も/今朝早く水田から上っ
てくる/女を見た/私は美しい少年へと/身の丈が伸びる
/なまなましい蛇の抜け殻/
裏庭の七面鳥がホロホロと鳴
く/引き抜かれた/草のように衰弱している人の声/棚の
上から招き猫が転がり/暗い畳表へとんであがる雀/天狗
の面やおかめの面が掛けられた/粗い壁/濡れた笊/寝床
に入ると/眼をつむって/柿など啜っている/花嫁姿の人
を想う/この頃は(夢の沈澱物のような私)/
太い醤油瓶
の間に/張られた蜘蛛の巣が破れた/埃と手拭のにおいの
する/母親の肩にさわる/板の間に置かれた/茗荷は淋し
い/ニガリの効いた(時空)/どんどん色の変ってゆく/
鯖を洗っている兄/古い糊のような/臭いのする/掛け軸
の龍/
肥桶の周りを/恐るおそる駈け廻る/聖なる赤い着
物の日本の少女たち/樟脳の香気/霞んでゆき/人さらい
の懐は深く/空気で出来ているように/感じられた/村の
晩秋/雨は鮒の(精霊)に降り注ぐ/
私はいまでは(精神)
の洟をたらしている/人体の冬/燠炭のような病気の男が
/足もとの柄杓で水をかけている/(物質)か(言語)/
見よ/馬が風雪に晒されている光景/蹄鉄の火花から/
(人間)は火種を貰って来る/私は一生カルメラを焼いて
/暮したいと思ったり/この寒夜を/家のなかで沸騰する
薬缶が在る/塩鱈が出刃庖丁で切られている/(時間)/
永遠に終らないもの――
Ⅴ (衰弱体の採集)
地上にへばりついている
「金属という(身体)
凍結炭素という(身体)」
紙を漉くように
(人体)というものは光に漉かれる
「おばあさんというのは
一枚・二枚で数えるものだよ」
私が子供の頃
そう教えられた
暗いどこの家の中でも
濡れ雑巾に刺った(魚の骨)を
丹念にぬいている
老婆がいたり
痰切り飴をなめながら
「燃えている布切を
犬のからだに詰める」
老婆もいたり
衰弱した(風景)を
「影が光に息づかせている」
老婆たちは(物語)をつくり
「数えきれない
気流と呼吸のなかを
通過してきたのだ」
*
腹の赤茶けた泥鰌を
田圃で取っている
老人のからだから垂れているものは
汗や影などではなく
(紐)のようなものだった
それはまた土に滲みてゆく
「蟻の卵や蜘蛛の巣」
のようなものだった
骨も外され
五臓六腑も辺りに撒かれ
菖蒲の匂いのする
春先の泡水の流れる処で
「からだに(霞)をかけている」
*
葱の根の白さを洗っている
(雪っ原)
未練がましく(火)を起し
私は灰の上に
「火箸で(文字)を書き始めた」
Ⅵ 挽歌
箸向ふ
弟[おと]のごとき
君は旅立つ
葦原の 朝露の
遠つくに
心を痛み
別れ行きし
天雲[あまくも]の
思ひ迷[まと]はひ
夜昼しらず
また還り来ぬ
はふ蔦の
家無[いへな]みや
春鳥[はるとり]の 音[ね]のみ啼きつつ
夕まけて
野づかさを越ゆ
望月の満[た]れる
あひびきの
荒山中[あらやまなか]
君が心燃えつつ
射[い]ゆ猪鹿[しし]のごと
消[け]やすき命[いのち]
噫乎[ああ]
闇夜なす
闇夜なす
闇……
反歌
ひさかたの
天[あめ]の奥処[おくか]ゆ
日の照れば
さはに
利鎌[とかま]にさ渡る鵠[くぐひ]
Ⅶ 像と石文
「言葉から肉体が発生する」
この認識をみとめよ
雨傘をさしたまま
(無体)と化しつつある
(泥型立身像)
このささくれた(幻像)を記憶せよ
それを冒す
「血と霊と風と虫とが交合する」
森を抜けるんだ
「書く者は衰弱し
死者にかぎりなく近付く」
そのように刻まれた(石文)
現われたり 消えたり
「大暴風雨にさらされている
鹿のようなものが見えた」
Ⅷ 慈悲心鳥
菊の束で大地を叩いている者
(亡霊)ではなく
(誰?)
「骨まで染めるような
夕焼」
比喩的に言えば
(魂と炎の世界)
「慈悲心鳥がバサバサと骨の羽を拡げてくる」
・注 この作品は、おもに土方巽の言葉の引用で構成されている。また彼の友人たちの言葉も若干、補助的に使わせて貰っている。なお冒頭のエピグラムは、彼の辞世である。
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1986年8月号〔29巻8号〕三〇〜三一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号22行1段組、35行。《ムーンドロップ》の〈初出一覧――〉には「(改作)」(同書、〔一三八ページ〕)と記されている。引用詩句に関しては〈吉岡実とフランシス・ベーコン〉を参照のこと。
「あの時
野原に舞い降りる
鳥を描こうとしていた」
それなのに
(画家)はなぜか
肉屋と(肉塊)を描いている
もしあの時
凍れる肉屋の
(心的[メンタル]な空間)を想起していたら
おそらく
「泳ぐ女や
唇から垂れる蜜」
もしくは
「記号のまばたく」
(星座)を
描いていたかも知れない
(庭の干草も虫の音も……)
今この(地上)では
「動くことと
動かないこととが等しい」
フルーツパーラーの椅子に
(画家)は凭れながら
まどろんでいる
初夏の街路を
(黄金の果物)を抱えた
(少年)が通り
(模造板)にのせられて
(死者)が通って行く
「光線をたえず
送りつづける」
(蒼穹[あおぞら])の下で
「眼で呼吸する」
わが(画家)は
競走馬を調教している
(父親)を眺めているようだ
初出は梅木英治銅版画集《日々の惑星》(ギャラリープチフォルム)1986年12月3日、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、12ポ20行1段組、39行。入稿原稿を忠実に再現したためだろう、行頭の起こしの鉤括弧(「)がすべて本文の天のラインよりも上に突き出て組まれている。《ムーンドロップ》の〈初出一覧――〉に「梅木英治銅版画集『日々の惑星』一九八六・九」(同書、〔一三八ページ〕)とある「1986年9月」は、脱稿時もしくは入稿時を指すか。
場末の映画館の夏の終り
「スクリーンの隅のほうに
なにやら
鰐らしきものが見えたわ」
乳母ガブリエルが叫んだ
しかしぼくにはそれが
「西瓜を食う水兵」のように見えた
「すべての(光)を
吸収する(青)」
そんなかわたれ[、、、、]時
上衣を脱ぎ
裸になる乳母ガブリエルの
「人体のもっとも
不可視的な(器官)が紅潮する」
そこからぴんぴん
(翼)が生えたように
ぼくには見えた
「透明光線となってほとばしる」
(アウラ)
「暗い籠のなかに在る
マッシュルーム」
それを数え それを
(布地[テイシユ])ペーパーで包み
ぼくは成長してきた
葦の葉や浮木の漂う
(汚れた岸)から
ボートをこぎ出す
ぼくは礼装の一人の男
真夜中のみずうみの上で
「届く言葉と
届かない言葉を」
ぼくは識別して
不眠の眼を光らせる
(強度の表面)
「軽金属と合成樹脂で
組み合わされた」
(惑星)にも
「スクリーンのように
無数の傷が付いている」
初出は《ユリイカ》(青土社)1986年12月臨時増刊号〔18巻14号〕一六〜一九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ22行1段組、62行。引用詩句に関しては〈吉岡実とフランシス・ベーコン〉を参照のこと。
〔聖なる蜘蛛〕
風をこばみ 露にあらがう日々
「緑となった躰を
最後にひとしきり
痙攣させて……」
(紡麻[うみお])の屑のうえに
〔匿名の器のような
三つの卵をうむ〕
一つは(扇)のごとく浮遊し
一つは(書物)のごとく沈澱し
一つは(精液)のごとく消滅する
夕映えの空の下で
「見ることは一瞬にして尽きるよ」
捕虫網をかざしながら
わが少年は帰る
(祓除人形[はらい ひとがた])の流れる岸べを
限りなく溯行せよ
石船型の(都市)まで
「影のなかには
無数の知覚や記号が
胚種としてひしめいている」
舗道の隅で
「犬の糞を見て
突然
そこに(人生)があると叫んだ」
狂気の画家のように醒めて
「子供として死に
大人として再生する」
手順を模倣せよ
少年はしばしの間(生と死)の境界線に
身(魂)を置いている
〔狼と犬の間〕=黄昏どき
「裸婦はものうく
肉体をさらしている」
苦艾の匂いがする?
〔母胎[マトリクス]〕
「何かが現われるというより
何かがたえまなく
消えてゆく」
やさしい(闇)
草や苔などが繁茂し
生物が殖えてゆく
(産霊[むすび])の世界
太陽や神力の(業[わざ])を受け続ぎ
賢木[さかき]で斎[いわ]い浄めて
「言語の通用する
(日常圏[テリトリー])を排除せよ」
(紫電金線)のなかで
美しくはげしく
汚物は流れる
(白紙)の上に
〔思考を抱える主体〕
少年は物(語)を書くだろうか
「気持がいいとても」
眼の前で熟しつつある
「一つの(果実)は
(羽根 蜜 帆柱
なによりも処女性
晴雨計 歯型
スポンジの多孔質
腐敗と喪失)などの
多くの(部分)を含んでいる」
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8月
苧環(おだまき)(⑫・14、34行)
9月
休息(未刊詩篇・18、38行)
11月
睡蓮(⑫・13、3節63行)
12月
かささぎ → 鵲(⑫・18、35行)
初出は《季刊花神》(花神社)1987年8月〔1巻2号〕一四〜一五ページ、本文新字新かな使用、10ポ19行1段組、34行。
糸巻きの糸をたぐる
若い乙女の姿が見える
(中世の秋)
「人間は一つの中心から
等距離の円周に在る」
(しずのおだまきくりかえし
くりかえし……)
狭霧[さぎり]立ちのぼる
(骨の山)
「象形文字が翼を開く」ように
斑鳩[じゆずかけ]は翔び越える
(これは杉戸に描かれた泥絵)か
もしくは
(人生)に匹敵する
(物語)か
風になびく草の穂
「(生)に対し
(死)のなんと長いことだろう」
雨にぬれた瑞枝[みずえ]を
はいまわる(尺蠖[しやくとり])
「そこでは見えるものと
見えないもの
とのあいだの(敷居)がつねに動いている」
(紫の太い柱)
村落の人たちは
「見ることを
妨げられた見物人」
未明の小川で
みそぎをしている
(稚児)のつぶやきを聞け
「わたしはいつも
(石女[うまずめ])の姉を宿している」
おだまきの葉に置く
水滴のように
初出は《現代詩手帖》(思潮社)1987年9月号〔30巻9号〕の〈澁澤龍彦追悼〉一四〜一五ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、38行。
隣家の主婦がいそいそと
〔思考の腐蝕する穴〕
円天井のアトリエに
食べ物を届けに訪れる
「ゴムの浮袋のような
寝台のうえで
パオロ氏は眠っている」
この画家の視線はいずこへ
描きかけの画布を覗く
「意味のとぎれる
境界線」
硝煙のなかで
「同じ側の脚を二本
いっぺんに持ちあげている」
負傷した馬が見えた
〔透視図法〕
燃える樹木
傾く塔
ここでは遠近法を無視せよ
死んだ兵士の靴の底の
星形の鋲が迫って来る
「死体は仮の消滅で
風景に似ている」
草はぼうぼう繁茂し
水はこんこんと湧き出る
日々の運行
寝食を忘れるパオロ氏の
「あの眼は
どんなものの上にも
止まることは許されない」
〔イデアの世界〕
「女を夢みる者は
馬を夢みることはないだろう」
少女のすべすべした
「からだの表面は
未完の竹籠」
秋の過剰なる
光線を宿している
*澁澤龍彦と土方巽の言葉を引用している
初出は《海燕》(福武書店)1987年11月号〔6巻11号〕一八〜二一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、3節63行。巻末ページ〈執筆者一覧〉に「吉岡実(よしおか みのる)一九一九年生れ。著書「藥玉」」とある。
1
池面の水の襞はきらめく
日課の枝おろしを了えて
庭師エレマンは手足を洗い
〔四阿[あずまや]〕の床で午睡をむさぼる
アラビアの火焔文字のように
(神鳥は飛びながら
空中にとどまり
腟をひらき
風によって懐妊する)
これは夢かうつつか?
(芸術と非芸術は連続している)
禁欲的な存在としての
(葱のような細い脚)
「お嬢ちゃんなにかご用ですか」
「ああエレマンさん
ざくろの木の下にいる
蛇を殺して!」
日暮れても水はぬるい
むくむくと
(やわらかな泥にみちた
〔脳髄〕の内部から)
睡蓮の花が咲き出る
2
秋きたりなば
(空から雲の色を受けたり
また朝の光を受けたり)
「青葡萄ぐらいの
贅沢なかたちがほしい」
薪の山を築きながら
庭師エレマンは妄想する
衣服を脱ぐ〔ドロテア夫人〕
(視線の意のままに
変容しながら身を委ねる)
これは心を震わせる〔物語〕だ
百合 匂いあやめ 茴香
〔逸楽的〕な薬草園の辺りで
(夜蝉が鳴いている)
3
(庭園も一つの世界である)
光がつよくなれば
影もまた濃くなる
銀梅花[みると]や無花果の繁る処
「ああエレマンさん
ハーブキャンデーを持ってきて
のどがカラカラなの」
(現代において
〔絵画〕
はいかに可能か)
羞恥心なく欲望なく
(巨人と小人に前後から
襲われている
ドロテア夫人)
両腿のくぼみに
綾織りの薄い下着を絡ませる
(活人画的な不自然さ)
そこに介在する
(見える形と
見えない力)
その官能の〔微香性〕
いまも不変の〔形姿〕として
(わたしは
外から形成されている)
めくるめく〔周縁〕
(滝は光の幕を
作っているように見える)
*宇野邦一その他の章句を引用している
初出は《毎日新聞〔夕刊〕》(毎日新聞東京本社)1987年12月28日〔40120号〕四面、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、新聞活字1倍扁平1段組、35行。「写真・佐々木正和」、また「よしおか・みのる 一九一九年、東京生まれ。主な詩集に「静物」「僧侶」「サフラン摘み」など。近刊書に「土方巽頌」。」と紹介がある。
(蝋をたらしたような冬)
わたくしは仕事場で独り
ストーブにたきぎをくべて
「彼女のベッドには
枕がなく
ベッドカバーはたたまれていた」
という(物語)を
書いているのではない
「死者は透明な花嫁と
浮遊している」
という敬虔なる(絵画)を描く
(光と闇)のなかでの
(日々)
「肉体はつねに
(異物)に支えられて
生きている」
一人の画家として
「地に落ちた
女の蒼白い裸体を眺める」
わたくしは妄想するのだ
「天使たちはいったい
歯や性器を
備えているのであろうか?」
それは(想念)であって
(床に置かれた絵)ではない
「虫の入っていない
うす緑色の捕虫網のように」
この室内は淋しい
「考えもしなかった
ことを
考えている」
薬缶の湯気はながれた
雪の舞う(世界)へ
カシャカシャと鳴きながら
一羽のかささぎが飛びまわる
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(⑫・16、20行)
5月
晩鐘(⑫・15、4節75行)
6月
銀鮫(キメラ・ファンタスマ)(⑫・17、6節107行)
9月
〔食母〕頌(⑫・19、4節74行)
((青空[アジユール])) → 青空(アジュール)(⑫・16)
初出は《文學界》(文藝春秋)1988年1月号〔42巻1号〕九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ1段組〔コラム〈扉の詩〉〕、20行。目次での標題は「青(アジュール)空」。カット:犬飼直彦。
甘酸っぱい(青空[アジユール])の下で
暗い穴から這い出して
また穴へ戻る
(けいとねずみ)を観察する
ぼくは(物語)の少年のように
「生きつつあるのか
死につつあるのだ」
(影は空壜から生まれる)
冬のまひるま
(視線)と(事物)との間に在る
(半透明な膜)
濡れた流し場を透視せよ
そこの闇に焔をとじこめ
大釜で(まゆ)を煮殺す
(母親)の姿が見えた
(文脈から外れている)
(神秘の板戸)をあける
「牡蠣の殻の底に残った
幾滴かの浄水」
朝のまだ淡い(青空[アジユール])
初出は《新潮》(新潮社)1988年5月号〔85巻5号(通巻1000号)〕二八〇〜二八三ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ23行1段組、4節75行。
1
母は買物袋を
床になげ出し
窓のカーテンを開ける
(外界はまるでたえまない
浮遊物のようだ)
紫の繻子のマントを着た
〔法王様〕の肖像だね!
母はなっとくして母家へ戻る
緑に包まれた
〔金魚鉢〕
のような狭い庭
(あらゆる絵具は
空を飛び交っている)
と認識せよ
〔想念〕もまた
(読みとり得ぬもの)
ぼくが現在描きつつある
〔絵画〕なるものは
(夕陽のなかの岩塊)
であるかも知れない
2
おきなぐさが
銀毛の房をはやし
風に吹かれて
飛びちる日々
イザベルが訪れる
(意のままに発現される
衣服のなかの臀)
柔らかな羽根で包みこまれる
ビーズ玉の輝き
(砂漠で乙女とともに
悦楽に耽る者は幸いなり)
と説いている
〔賢者〕のことをぼくは想う
狂える〔力〕には
〔形〕がない
〔停滞した身体〕
〔模像〕のようなイザベル
こんどの絵はからだを掻く
〔不器用な犬〕
みたいに見えるわ!
〔昂揚せる絶望感〕
(あらゆる〔白〕は
見るたびに
柔らかく裂けて行く)
3
(覆布をとりのぞくと
その下には何もない)
という〔欠落感〕
(すべて〔絵画〕とは
不透明なるものに
依存した
〔透明〕なものなのだ)
ぼくが仕上げつつある
〔図像〕そのものは
〔不吉な不調和〕に輝く
〔黄金と紺青〕の
色彩のしとねの上で
廃棄された
(老婆の脚はからだの
残りの部分にほんとうに
根付いているわけではない)
しかしこれは
〔物語〕であって
〔絵画〕ではないだろう
4
(立ちのぼる煙
ひびく晩鐘)
恵み深い一日の終り
金雀枝の花と
サラダの匂いが
風ではこばれてくる
(父は肉を食い
母は草を食む)
ぼくは古謡をくちずさみ
(逸脱する
〔生〕の
〔波動〕をおさえている)
初出は《ユリイカ》(青土社)1988年6月臨時増刊号〔20巻7号〕四八〜五三ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、9ポ24行1段組、6節107行。入稿原稿を忠実に再現したためだろう、行頭の起こしの括弧――パーレン(()・亀甲(〔)・鉤括弧(「)――が本文の天のラインよりも上に突き出て組まれている。
1
(枕もとへ
永遠に
スープは運ばれる)
ことを疑うことなく
ぼくが〔制作〕に耽ける日夜
(何かが起る!)
「ドアを開けると
便器に女がすわっていた」
股間の金毛を露わにしたまま
仮面をかぶっている
〔美と畸形〕
あるいは〔富と貧困〕
これは〔紋切型〕の
〔物語〕であって
〔メティエ〕がそのまま
〔思想〕であるところの
〔絵画〕とはいえない
(凍てついて久しい
星の下)
ぼくは河の蘆荻の向うに
「鶴が一本脚で
立ったまま微動だにしないのを
じっと眺めていた」
2
(岩塩の立方体を
間近に見える)
ようにぼくの描いた
〔内臓の宮殿〕
まばゆく
白昼の光に照らされる
真珠 包帯 羊歯
甲殻類 パイプ 空蝉
草石蚕
書物
蟻塚
少女
そして砂漠
それらもろもろの〔物質[マテリア]〕
(肉や血や汗の臭いから
限りなく隔たっている)
ぼくは〔認識者〕
として〔世界〕を
(下からも
上からも見ない)
3
月の光を吸いこんで
深海の底へ下降した
〔銀鮫〕
すなわち(キメラ・ファンタスマ)
「その生身から
肉状の突起が全部で四本
まるで四足獣
のように生えている」
有用性の〔苦役〕をまぬがれ
解放された〔存在〕の
〔神話の怪獣〕
さながらの
(キメラ・ファンタスマ)
4
「多くの門をくぐると
自分がどこにいるのか
分らなくなる」
見えている
〔曠野〕の
〔牛と老人〕
あれらは〔暗い穴〕
そのものなのだ
ぼくは今日も
えたいの知れない
〔神殿〕や〔塔〕の周辺を
巡っているようだ
(鳥たちの鳴き声)
(女たちの笑い声)
番人は箒と塵取りで
〔排泄物〕を片づけている
すべてが(現実と
寸分変らぬ光景)
それに比較すると
〔絵画と言語〕なるものは
(何ひとつ確かなところがない)
この旅の終り
ぼくの(身体は発熱しつつあるか
もしくは凍結しつつある)
曇れる空のもと
(ヘラクレスの
〔睾丸〕のような
大きなオリーヴの実)
しばし仰ぎ見ていた
5
〔瑪瑙の断面〕
メランコリア
〔迷宮〕
(球体と直線から成る
中空の建築物)
ここは住みやすい
〔空間〕ではない
〔神の侍女〕に導かれ
ぼくは〔他人の夢〕を
夢見ている
(荷車で暗い鏡をはこぶ男)
優雅な夕べ
(二人でいる孤独)
石塀で遮断されている
〔花園〕
6
いかなる時でも
〔芸術家〕は
〔対象〕の
〔幻影〕だけで事足りるのだ
(何かが起らねばならぬ)
と絶えず考えよ
〔形而上的〕なる
〔不安〕から
それは喚起される
〔静かな鼓動〕
(砂山から
犬が首だけ突き出している)
*澁澤龍彦とその知己たちの言葉を引用している。
初出は《中央公論文芸特集》(中央公論社)1988年9月〔秋季・5巻3号〕七八〜八一ページ、本文新字新かな(ひらがな・カタカナの拗促音は小字)使用、10ポ22行1段組、4節74行。巻末の〈編集後記〉に「☆〔食母〕という言葉が拓くイメージ。吉岡実氏の詩は御自身が最後の、と言われる作品です。」(E〔江阪満か〕)とある。入稿原稿を忠実に再現したためだろう、行頭の起こしの括弧――亀甲(〔)・パーレン(()――が本文の天のラインよりも上に突き出て組まれている。
1
〔泣き女〕がめそめそと
哭きながら
行列の先導をつとめる
(鳴りひびく鈴)
それらのしんがりを行く
〔侏儒〕や〔去勢羊〕たち
(草木の影すら
見えないほの暗い
地平線)
これは〔英雄[ヒーロー]〕の〔死〕の儀式ではなく
(語りえぬもの)
〔母〕なる〔写像〕を探す
〔道〕なきみちの旅
〔分岐〕するありふれた〔処〕で
(一人の女が
〔奇妙な記号〕となる)
2
夕焼けの映える
磯辺に残された
〔斎串[いわいぐし]〕や〔馬尾藻[ほんだわら]〕
(死と思考の対立する)
波打際
(衣服もひとつの
〔言語〕である)
と仮定できるならば
それらのものを脱ぎ
(若い〔母〕は身体を洗っている)
〔霊的な空間〕をつくる
〔乳房〕と
〔臀部〕ではなく
かりそめの〔物〕が宿っている
(一つの丘みたいなもの)
〔丘〕の上へ
〔青い牛〕を連れて
〔老人〕はぜいぜい息を切らせつつ
〔道〕にそって行き
〔襞〕にそって行き
〔襞〕を超える
(老残の身の半分は液体)
〔仮寝〕の仮死の
(魂のなかに生起する)
〔死人の山〕
〔宝の山〕
迂回せよ
月の光に照らされて
あらわに見えて来る
〔膣状陥没点〕……
3
〔幽都〕より還って
〔泣き女〕が哭きやむ時
地滑りが起る
櫛 鋸 瓶 鏡 ふいごと共に
(粉々に飛び散る
〔言葉〕の稲妻)
(この世の栄光の終り)?
さるすべりの樹の周囲で
おろおろする男たち
動物ビスケットをかじる子供たち
((死ハ人生ノ
出来事デハナイ))
風に吹かれ
〔花蓮[はちす]〕の広い葉の上から
零れ落ちる
〔白露〕のように
4
(美しい緑の衝立)の蔭から
産声が聞こえる
〔にがり〕と〔泡沫〕を浴びて
〔嬰児[みどりご]〕は生まれた
(鉛に包まれた
黄金)
のごとく
〔母〕なるものに抱かれている
〔外面[とのも]〕は明るく
(かげろうは消え
蛇はかえってゆく)
野の丈なす草むらに
(一九八八・八・八)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4月
永遠の昼寝(未刊詩篇・19、25行)
10月
雲井(未刊詩篇・20、3節47行)
初出は《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》(新潟市美術館)1989年4月1日、〈西脇順三郎賛歌〉一三一ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、10ポ2段組、25行。自筆詩稿が《永遠の旅人 西脇順三郎 詩・絵画・その周辺》展(新潟市美術館、1989年4月1日〜5月14日)に展示された。
コオロギが鳴いて
(宇宙の淋しさを
告げ始める)
秋の日の野原を行く
わたしは旅人
(茶室的な岩から出る
泉を飲む)
心の淋しい時は
意識の流れに沿って
漂泊するんだ
(非常な美人の医師が来る)
赤と白の
ホウセンカの咲く
ここは故里かも知れない
聖賢の書を読み
わたしは思索にふける
(いかにして
死を諦める
ことができるか)
旅籠屋のつめたい畳で
昼寝をしたようだ
(誰かがわたしの
頭のうえを
杏の実をもって
たたいた)
初出は《鷹》(鷹俳句会)1989年10月号〔26巻10号〕四六〜四九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、五号14行1段組、3節47行。カット:内田克巳。なお、「(支那人は猫の眼で/時間を読む)」はボードレールの散文詩《パリの憂鬱》の〈時計〉からの引用で、吉岡は澁澤龍彦の文(エッセイ〈ユートピアとしての時計〉かどうかはわからないが)に依ったのに違いない(この詩句に関しては〈〈示影針(グノーモン)〉と《胡桃の中の世界》〉も参照されたい)。
1
(とろとろと眠りこむ
〔牧神〕ではなく)
森の沼のほとりで
(捕虫網をかざしてゆく
長い髪の寛衣の少女)
を見かけたような気がする
わたしは灌木の間を
〔雨後の茸[くさびら]〕を探しまわった
(明暗の境いを越え)
さまよいつづける
(樹木の霊や
鳥獣の魂)
どんなものの上にも
止まることは許されない
〔イデアの世界〕
わたしはなぜか思う
(書かれた
〔言葉〕は
〔骨〕のように残るだろうか?)
手の届かぬ高みに
〔月輪〕のように
〔かたつむり〕がいる
2
(支那人は猫の眼で
時間を読む)
狂える隠者の詩句を
わたしはくちずさむ
波に洗われる
海鳥の足跡
死者の〔泥履[どろぐつ]〕
紅い糸屑
今の世の〔空〕の
〔透視図法〕を視よ
〔雲井〕に懸かる
(虹もまた炭化する)
3
(しずこころなく散る)
〔黄葉〕や〔籾殻〕
そして〔記号〕
ここは〔沙庭[さにわ]〕かもしれない
(燃えたり 凍ったり)
する〔星辰〕の下で
〔煮果物[コンポート]〕を食べながら
(蓮のつぼみ
壺のすぼみ)
を呪文のように唱えている
(その〔少女〕はまだ
完全に〔地上〕に
降り立っていない)
*瀧口修造そのほかの章句を引用している。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1月
沙庭(未刊詩篇・21、20行)
初出は《文學界》(文藝春秋)1990年1月号〔44巻1号〕九ページ、本文新字新かな(ひらがなの拗促音は小字)使用、9ポ1段組〔コラム〈扉の詩〉〕、20行。カット:平野敬子。
吉岡陽子夫人の手になる未刊詩篇〈沙庭〉の雑誌掲載用入稿原稿〔第1葉〕には、起こしの括弧類が詩句の天の一マス上に記されている(コピーの末尾には吉岡の自筆で「1989.12月(文学界)新年号」と横書のメモがある) 出典:吉岡家蔵クリアファイル〔モノクロコピー〕
灯明のともる
〔白地[あからさま]〕の座敷で
巫女のように
〔紙衣[かみぎぬ]〕を着て姉はつぶやく
(火ねずみの
かわごろもがほしい)
祖父母は
染物用の大樽の向う側へ
〔地蔵[かくれたもの]〕
として祀られた
離れ家で父は〔屯食[おにぎり]〕をほおばり
母は〔毛糸玉〕に歯を立てる
(いつだって
人間の形を所有したこと
のない家系?)
ぼくと妹は掃除を了えて炬燵にいる
藁火のにおい
物の倒れる音
(淡雪を頭にのせ〔神様〕が
家のなかに入って来る)
以上、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――序歌(①・0)〜沙庭(未刊詩篇・21)〉
>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
本稿の〈はじめに〉で「吉岡が生前、活字にして発表した全詩作品286篇の〔初出形〕」と記した。ここには、のちに〈秋思賦〉、〈聖童子譚〉に変改吸収されることになる〈断想〉、〈小曲〉〈少年 あるいは秋〉の3篇(〈吉岡実全詩篇〔初出形〕――詩篇目次〉では詩篇番号の前に●印を付けた)が含まれるから、吉岡実が完成した詩篇の総数は283篇ということになる。このうち《吉岡実全詩集》(筑摩書房、1996)で読むことのできるのは、単行詩集収録の262篇と、単行詩集未収録の未刊詩篇の15篇、合計277篇である。したがって、全詩集帯文にある「吉岡実 1919-1990/全詩280篇」は、独立した詩篇としては同書に掲載されていない「変改吸収詩篇」の3篇を含む数であって、実際の数ではない。いまのところ、《吉岡実全詩集》未収録の未刊詩篇の6篇(全詩集未掲載の[―]と表示した分)は、初出掲載の印刷物に当たるか、それを再録した本サイトで読むしかない。また、吉岡自身が編んだ拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》(書肆山田、1980)刊行時点で、既発表ながら収録されなかった詩篇は14篇にのぼる(〈拾遺詩集《ポール・クレーの食卓》解題〉参照)。それらがいかなる理由で撰から漏れたか、詳細は不明だが、本稿を手掛かりにして接近する方法もあるかと思う(なろうことなら、私自身が究明を試みたいが)。
〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉の本文は、地下鉄千代田線明治神宮前駅ホーム壁面の《街頭詩の試み》に掲げられた〈野〉を除いて、すべて元の資料と照合した(〈野〉は再録された本文と校合した)。その際、データは作業用のhtmlのものを各年ごとのtextファイルに書き出して、各詩篇に註記した元資料に近いサイズの縦組明朝体で出力した状態で校正した。ここで本稿の吉岡実詩表示における問題点を述べておく。第一のそれは、ファイルがHTML文書であるため、縦組の原文(吉岡実詩には数篇、横組表示の〔初出形〕や〔再録形〕が存在するが、単行詩集をはじめとする自著はすべて縦組であり、原稿もおそらくはすべて縦書)を横組で表示していることだ。第二のそれは、Shift_JISのtextとして表示できない文字や記号を「数値文字参照」を使って表示したため、これをtextに書き出すとHTML文書で表示された文字・記号にならないことである(もっともtextを縦組表示すれば、第一の問題点は解決できるのだが)。すなわち赤字で示した以下の16例(複数回、登場する文字・記号もある)はtextに書き出すと「?」となってしまう。これらはいずれも吉岡実の原文を再現するための措置であり、諒とせられたい。
私自身Microsoft Wordで執筆することはないが、別解としてWord文書にして保存する手がある。まず〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉のページ全体をコピーして、Wordに貼り付ける。[レイアウト]で文字列の方向を「縦書き」にすると、わざわざ変えなくても印刷用紙が横位置になるので、ゴチックだったフォントを「MS 明朝」などの等幅明朝体に変える。私のPCの設定では458ページの文書になったが、ありがたいことに上記の赤字部分も表示されるから、読みやすいことこのうえない。本文縦組明朝体で読むときの基準はこのあたりか。本文の文字サイズは12ポで、2面付で出力すれば約8.5ポになり、両面印刷するなら用紙は115枚ですむ。これを綴れば、《吉岡実全詩集》の脇に置いておける。
以上は技術的な側面だが、それよりはるかにややこしいのは、〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉において吉岡実詩の漢字の旧字を当用漢字表(1946〜81)や常用漢字表(1981〜2010)にある漢字はそちらを表示していることだ(つまり詩篇の漢字表記の本則が「新字」とあるとき、本文で旧字が用いられていれば――新字の「灯」「妊」「蛍」ではなく、旧字の「燈」「姙」「螢」が用いられていれば、吉岡本人か陽子夫人が「燈」「姙」「螢」と原稿に書いたためそのように組まれた、と考えられる)。読者は、その間の事情をよろしくご理解いただきたい。ここで感慨にふけるならば、吉岡実詩の原典と各年ごとに分けた本文を行きつ戻りつしながらチェックに明け暮れた月日のあと、やっと校了に近づいた4月13日、仕事帰りに観た夜桜は、一生忘れないだろう。
音楽評論家の中山康樹は、《これがビートルズだ〔講談社現代新書〕》、講談社、2003年3月20日)の〈あとがき〉を「ビートルズの全公式曲二一三曲を聴いた。ビートルズをはじめて聴いてからざっと三五年は経つが、もちろん、このような聴きかたをしたのは今回が最初(で最後)だ」(二九三ページ)と始めている(*)。私はこれからさき〈吉岡実全詩篇〔初出形〕〉に何度も帰ってくるだろう。――「吉岡実の全公式詩二八三篇を読んだ。吉岡実をはじめて読んでからざっと四五年は経つが、もちろん、このような読みかたをしたのは今回が最初だ。だが、最後ではない」。
* 中山康樹は〈あとがき〉にこうも書いている。「こういった〝制覇本〟を書いていると、ごくまれに「タイヘンでしょ」と労をねぎらう声をいただく(深謝)。たしかにタイヘンではある。だが、じつはねぎらっていただくほどタイヘンではない。決してラクではないが、「タイヘンかラクか」と問われれば、楽しい、うれしいという意味において〝ラク〟なのだ。/というのも、ふだんであれば絶対にありえないような聴きかたで聴く、それによって新たなことを発見したり、さんざん聴いていたにもかかわらず、まだまだ驚きや「?」に遭遇する、逆に積年の「?」が解けるといったことがすくなくないからだ。」(同書、二九三〜二九四ページ)
本稿を深い敬意をこめて詩人・吉岡実(1919.4.15〜1990.5.31)に。

吉岡実の肖像(1980年、61歳当時) 出典:《現代詩読本――特装版 吉岡実》、思潮社、1991年4月15日、〔三二八ページ〕
>> 吉岡実全詩篇〔初出形〕(2019年4月15日) 先頭へ
●一九四〇年代
0 〔序歌〕
212 春
193 夏 〔注射器の午前九時十二分〕
6 秋
237 冬
268 遊子の歌
14 朝の硝子
104 歳月
23 あるひとへ
117 七月
206 白昼消息
42 臙脂
261 面紗せる会話
246 放埒
173 断章 〔わがこころになやみはてず〕
58 葛飾哀歌
74 桐の花
24 杏菓子
230 病室
100 昏睡季節1
101 昏睡季節2
215 挽歌 〔洋燈は消え〕
210 花冷えの夜に
177 朝餐
188 溶ける花
134 蒸発
7 秋の前奏曲
118 失題
41 絵本
95 孤独
248 牧歌 〔歯車が夥しくおちてゆく〕
162 相聞歌
172 誕生
62 乾いた婚姻図
225 微風
154 静物 〔鵞鳥の頸ねむく〕
285 忘れた吹笛の抒情
187 透明な花束
224 微熱ある夕に
232 風景 〔猿の頭に夕の灯がともり〕
227 ひやしんす
208 花遅き日の歌
256 みどりの朝に――朝の序曲
22 或る葬曲の断想――墓地にて
32 失われた夜の一楽章 ← 失はれた夜の一樂章
204 灰色の手套
38 液体Ⅰ
39 液体Ⅱ
93 午睡
209 花の肖像
189 灯る曲線
1 哀歌 〔毛皮にうずまつて〕
272 夢の翻訳――紛失した少年の日の唄 ← 夢の飜譯――紛失した少年の日の唄
35 海の章
205 敗北
164 即興詩
191 汀にて
174 断章 〔永劫に舟の去りゆく〕
●一九五〇年代
155 静物 〔夜の器の硬い面の内で〕
156 静物 〔夜はいつそう遠巻きにする〕
157 静物 〔酒のない瓶の内の〕
158 静物 〔台所の汚れた塩〕
21 或る世界
65 樹
169 卵
238 冬の歌
198 夏の絵
233 風景 〔緑の樹は〕
109 讃歌
216 挽歌 〔わたしが水死人であり〕
121 ジャングル
269 雪
78 寓話
26 犬の肖像
52 過去
91 告白
66 喜劇
31 陰謀
120 島
113 仕事
249 牧歌 〔村にきて〕
163 僧侶
247 ポール・クレーの食卓
171 単純
92 固形
194 夏 〔蝋びきの食物の類をみて歩く〕
48 回復
77 苦力
114 死児
263 喪服
148 聖家族
103 サーカス
184 伝説
239 冬の絵
33 美しい旅
222 人質
63 感傷
274 ライラック・ガーデン
282 老人頌
258 無罪・有罪
44 遅い恋
82 果物の終り
129 唱歌 ← 牧歌 〔男は不足なものをさがす〕
87 下痢
243 紡錘形Ⅰ ← 紡錘形1
265 夜会
18 編物する女
124 呪婚歌
266 夜曲
30 陰画
279 裸婦
84 首長族の病気
25 田舎
●一九六〇年代
220 斑猫
2 哀歌 〔それは或は風説だろう〕
244 紡錘形Ⅱ ← 紡錘形2
240 冬の休暇
254 水のもりあがり
199 波よ永遠に止れ
252 巫女――あるいは省察
27 衣鉢
125 受難
178 鎮魂歌
61 狩られる女――ミロの絵から
67 寄港
185 灯台にて
73 霧
201 沼・秋の絵
123 修正と省略
218 晩春
111 塩と藻の岸べで
86 劇のためのト書の試み
34 馬・春の絵
90 珈琲
262 模写――或はクートの絵から
166 滞在
159 聖母頌
79 九月
241 冬の森
264 桃――或はヴィクトリー
267 やさしい放火魔
214 春のオーロラ
54 家族
116 静かな家
143 スープはさめる
211 花・変形
231 ヒラメ
96 孤独なオートバイ
190 内的な恋唄
89 恋する絵
213 春の絵
4 青い柱はどこにあるか?
195 夏から秋まで
280 立体
250 マクロコスモス
234 フォークソング ← フォーク・ソング
112 色彩の内部
141 スイカ・視覚的な夏
140 神秘的な時代の詩
102 崑崙
19 雨
131 少女
144 スワンベルグの歌
110 三重奏
255 蜜はなぜ黄色なのか?
137 序詩 〔うんすんかるたを想起させる〕
138 序詩 〔白地へ白く白鳥類は帰る〕
196 夏の家
283 わが馬ニコルスの思い出
150 聖少女
223 鄙歌 ← ヘアー
99 コレラ
●一九七〇年代
180 低音
203 葉
228 ヒヤシンス或は水柱
281 ルイス・キャロルを探す方法
12 悪趣味な冬の旅
181 弟子
167 タコ
251 マダム・レインの子供
145 聖あんま語彙篇
20 『アリス』狩り
107 サフラン摘み
221 ピクニック
182 田園
186 動物
284 わが家の記念写真
235 フォーサイド家の猫
151 生誕
161 草上の晩餐
119 自転車の上の猫
29 異霊祭
47 絵画
260 メデアム・夢見る家族
236 不滅の形態
168 舵手の書
226 白夜
165 ゾンネンシュターンの船
105 サイレント・あるいは鮭
10 悪趣味な夏の旅
83 示影針(グノーモン)
49 カカシ
9 悪趣味な内面の秋の旅
17 あまがつ頌
139 人工花園
132 少年
275 楽園
97 子供の儀礼
13 曙
242 部屋
88 幻場
51 影の鏡
11 悪趣味な春の旅
278 螺旋形
28 異邦
115 使者
68 紀行
217 晩夏
253 水鏡
80 草の迷宮
69 狐
271 夢のアステリスク
55 形は不安の鋭角を持ち……
273 雷雨の姿を見よ
160 蝉
176 父・あるいは夏
197 夏の宴
46 織物の三つの端布
●175 断想
192 謎の絵
277 裸子植物
75 金柑譚
202 野
37 詠歌
98 この世の夏
152 生徒 ← 〔標題なし〕
43 円筒の内側
5 「青と発音する」
●一九八〇年代
108 猿
179 ツグミ
200 雞 ← にわとり
126 竪の声 ← 竪[しゆ]の声
40 絵のなかの女
128 巡礼
60 壁掛
149 青枝篇 ← 春の伝説
81 薬玉
50 影絵
3 哀歌 〔わたしの世界は 小さな峠の茶屋で〕
183 天竺
170 垂乳根
57 郭公 ← 郭公あるいは駙い森
122 秋思賦
127 春思賦
64 甘露
94 東風
245 蓬莱
147 青海波
276 落雁
72 求肥
229 白狐
●130 小曲
●133 少年 あるいは秋
153 聖童子譚
286 わだつみ
257 ムーンドロップ
207 薄荷
56 カタバミの花のように
8 秋の領分
270 雪解
59 寿星(カノプス)
16 亜麻
146 聖あんま断腸詩篇
136 叙景
76 銀幕
259 産霊(むすび)
45 苧環(おだまき)
71 休息
142 睡蓮
53 鵲 ← かささぎ
15 青空(アジュール) ← ((青空[アジユール]))
219 晩鐘
70 銀鮫(キメラ・ファンタスマ)
135 〔食母〕頌
36 永遠の昼寝
85 雲井
●一九九〇年代
106 沙庭
以上の〈付録 吉岡実全詩篇標題索引 目録〉は、《吉岡実全詩篇標題索引〔改訂第4版〕》に手を入れて掲げた。
吉岡実全詩篇〔初出形〕 了
|
|
||||
|
リンクはトップページ《吉岡実の詩の世界》に設定してください。 |
|
|||
|
ご意見・ご感想などのメールはikoba@jcom.home.ne.jpまで。 |
|
|||
|
Copyright © 2019 Kobayashi Ichiro. All Rights Reserved. |
|
|||
|
本ウェブサイトの全部あるいは一部を利用(コピーなど)する場合は、 |
|
|||
|
|
|
|
|
|