
���W�s�����G�߁t�̕\���A���W�s�t�́t�̔��A�̏W�s�����t�̕\���i��������g���Ƒ��̏����j
�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��

���W�s�����G�߁t�̕\���A���W�s�t�́t�̔��A�̏W�s�����t�̕\���i��������g���Ƒ��̏����j
�g�����̑�����i�i137�j�i2021�N8��31���j
�s�����t�f�ڂ̏o�ōL���i2021�N1��31���k2021�N8��31���NjL�l�j
�����ƁE�a�c���̂����i2020�N12��31���j
�P�c�����̋g�����_�i2020�N4��30���k2020�N10��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i136�j�i2019�N11��30���j
�q�g�����̑�����i�r�ŏ��e���f�����g���ȊO�̎�ɂȂ鑕����i�̈ꗗ�i2018�N9��30���j
�������ق�k�C���^�����[�l�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�̂����i2018�N2��28���j
�g�����̑�����i�i135�j�i2017�N11��30���j
�g�����̑�����i�i134�j�i2017�N10��31���j
�g�����̑�����i�i133�j�i2017�N9��30���j
�g�����̑�����i�i132�j�i2016�N9��30���j
�g������s�͌����f�j��W�t�i2016�N7��31���k2021�N9��30���NjL�l�j
�g�����ҁs�k�����H���̏W�t�i2016�N6��30���j
�g�����ҁs���e���O�Y���W�t�i2016�N5��31���j
�c���`�瑕����i�ژ^�Ƒ�����i�T�C�g�̂����i2016�N3��31���j
�s�����V���t�́q�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����r�i2016�N2��29���j
�Ȑ܋v���q�́q�g������̑���r�i2016�N1��31���j
�g�����̑����i��i�j���ŏ��ɘ_���������i2015�N12��31���j
�g�����̑�����i�i131�j�i2015�N6��30���j
�g�����̑�����i�i130�j�i2015�N4��30���j
�g�����̑�����i�i129�j�i2015�N3��31���j
�g�����̑�����i�i128�j�i2015�N2��28���j
�g�����̑�����i�i127�j�i2015�N1��31���j
�g�����̑�����i�i126�j�i2014�N12��31���j
�g�����̑�����i�i125�j�i2014�N11��30���j
�g�����̑�����i�i124�j�i2014�N10��31���j
�g�����̑�����i�i123�j�i2014�N5��31���j
�g�����̑�����i�i122�j�i2014�N3��31���k2018�N8��31���NjL�l�k2019�N5��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i121�j�i2014�N2��28���j
�g�����̑�����i�i120�j�i2014�N1��31���k2014�N3��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i119�j�i2013�N12��31���j
�g�����̑�����i�i118�j�i2013�N11��30���j
�g�����̑�����i�i117�j�i2013�N10��31���j
�g�����̑�����i�i116�j�i2013�N9��30���j
�g�����̑�����i�i115�j�i2013�N8��31���j
�g�����̑�����i�i114�j�i2013�N7��31���k2018�N8��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i113�j�i2013�N6��30���j
�g�����̑�����i�i112�j�i2013�N5��31���j
�g�����̑�����i�i111�j�i2013�N4��30���j
�g�����̑�����i�i110�j�i2013�N3��31���j
�g�����̑�����i�i109�j�i2013�N2��28���k2019�N11��30���NjL�l�j
���W�s�t铁t�̑g���i2013�N1��31���j
���W�s�����G�߁t�̑g���i2012�N12��31���j
�g�����̑�����i�i108�j�i2012�N10��31���j
�g�����̑�����i�i107�j�i2012�N9��30���j
�g�����̑�����i�i106�j�i2012�N8��31���j
�g�����̑�����i�i105�j�i2012�N7��31���j
�g�����̑�����i�i104�j�i2012�N6��30���j
�g�����̑�����i�i103�j�i2012�N5��31���k2018�N5��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i102�j�i2012�N4��30���j
�g�����̑�����i�i101�j�i2012�N3��31���j
�g�����̑�����i�i100�j�i2012�N2��29���j
�g�����̑�����i�i99�j�i2012�N1��31���j
�g�����̑�����i�i98�j�i2011�N12��31���j
�g�����̑�����i�i97�j�i2011�N11��30���j
�g�����̑�����i�i96�j�i2011�N10��31���j
�g�����̑�����i�i95�j�i2011�N9��30���j
�g�����̑�����i�i94�j�i2011�N8��31���k2020�N4��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i93�j�i2011�N7��31���j
�g�����̑�����i�i92�j�i2011�N6��30���j
�g�����̑�����i�i91�j�i2011�N5��31���k2021�N4��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i90�j�i2011�N4��30���j
�g�����̑�����i�i89�j�i2011�N3��31���j
�g�����̑�����i�i88�j�i2011�N2��28���j
�g�����̑�����i�i87�j�i2011�N1��31���j
�g�����̑�����i�i86�j�i2010�N12��31���j
�g�����̑�����i�i85�j�i2010�N11��30���k2018�N5��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i84�j�i2010�N10��31���j
�g�����̑�����i�i83�j�i2010�N9��30���j
�g�����̑�����i�i82�j�i2010�N8��31���j
�g�����̑�����i�i81�j�i2010�N7��31���j
�g�����̑�����i�i80�j�i2010�N6��30���k2020�N4��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i79�j�i2010�N5��31���j
�g�����̑�����i�i78�j�i2010�N4��30���j
�g�����̑�����i�i77�j�i2010�N3��31���j
�g�����ҏW�s�����܁t�S91���ڎ��ꗗ�i2010�N2��28���j
�g�����̑�����i�i76�j�i2010�N1��31���j
�g�����̑�����i�i75�j�i2009�N12��31���j
�g�����̑�����i�i74�j�i2009�N11��30���k2017�N8��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i73�j�i2009�N10��31���j
�g�����̑�����i�i72�j�i2009�N9��30���j
�g�����̑�����i�i71�j�i2009�N8��31���j
�g�����̑�����i�i70�j�i2009�N7��31���k2009�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i69�j�i2009�N6��30���j
�g�����̑�����i�i68�j�i2009�N5��31���j
�g�����̑�����i�i67�j�i2009�N4��30���j
�g�����̑�����i�i66�j�i2009�N3��31���j
�g�����̑�����i�i65�j�i2009�N2��28���j
�g�����̑�����i�i64�j�i2009�N1��31���j
�g�����̑�����i�i63�j�i2008�N12��31���j
�g�����̑�����i�i62�j�i2008�N11��30���j
�g�����̑�����i�i61�j�i2008�N10��31���k2014�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i60�j�i2008�N9��30���j
�g�����̑�����i�i59�j�i2008�N8��31���k2013�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i58�j�i2008�N7��31���j
�g�����̑�����i�i57�j�i2008�N6��30���j
�g�����̑�����i�i56�j�i2008�N5��31���j
�g�����̑�����i�i55�j�i2008�N4��30���j
�g�����̑�����i�i54�j�i2008�N3��31���k2015�N3��31���NjL�l�k2017�N10��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i53�j�i2008�N2��29���k2014�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i52�j�i2008�N1��31���j
�g�����̑�����i�i51�j�i2007�N12��31���k2013�N8��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i50�j�i2007�N11��30���j
�g�����̑�����i�i49�j�i2007�N10��31���k2008�N12��31���� �L�l�j
�g�����̑�����i�i48�j�i2007�N9��30���j
�g�����̏o�ōL���i1�j�i2007�N8��31���k2013�N4��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i47�j�i2007�N7��31���k2021�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i46�j�i2007�N6��30���j
�g�����̑�����i�i45�j�i2007�N5��31���j
�g�����̃��C�A�E�g�i4�j�i2007�N4��30���j
�g�����̑�����i�i44�j�i2007�N3��31���j
�g�����̑�����i�i43�j�i2007�N2��28���j
�g�����̑�����i�i42�j�i2007�N1��31���j
�g�����̑�����i�i41�j�i2006�N12��31���j
�g�����̑�����i�i40�j�i2006�N11��30���j
�g�����̑�����i�i39�j�i2006�N10��31���j
�g�����̑�����i�i38�j�i2006�N9��30���j
�g�����̑�����i�i37�j�i2006�N8��31���j
�g�����̑�����i�i36�j�i2006�N7��31���j
�g�����̑�����i�i35�j�i2006�N6��30���j
�g�����̑�����i�i34�j�i2006�N5��31���k2006�N6��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i33�j�i2006�N4��30���j
�g�����̑�����i�i32�j�i2006�N3��31���j
�g�����̃��C�A�E�g�i3�j�i2006�N2��28���j
�g�����̑�����i�i31�j�i2006�N1��31���j
�g�����̑�����i�i30�j�i2005�N12��31���k2011�N3��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i29�j�i2005�N11��30���k2009�N3��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i28�j�i2005�N10��31���j
�g�����̑�����i�i27�j�i2005�N9��30���j
�g�����̑�����i�i26�j�i2005�N8��31���k2005�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i25�j�i2005�N7��31���j
�g�����̑�����i�i24�j�i2005�N6��30���k2013�N12��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i23�j�i2005�N5��31���k2017�N10��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i22�j�i2005�N4��30���k2018�N1��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i21�j�i2005�N3��31���j
�g�����̑�����i�i20�j�i2005�N2��28���j
�g�����̑�����i�i19�j�i2005�N1��31���k2006�N8��31���NjL�l�k2011�N10��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i18�j�i2004�N12��31���k2019�N2��28���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i17�j�i2004�N11��30���k2006�N1��31���NjL�l�k2014�N9��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i16�j�i2004�N10��31���j
�g�����̑�����i�i15�j�i2004�N9��30���j
�g�����̑�����i�i14�j�i2004�N8��31���j
�g�����̑�����i�i13�j�i2004�N7��31���j
�g�����̑�����i�i12�j�i2004�N6��30���j
�g�����̑�����i�i11�j�i2004�N5��31���k2006�N6��30���NjL�l�k2016�N5��31���NjL�l�j
�g�����̎�|�����{�i1�j�i2004�N4��30���j
�g�����̑Βk�E���k��W�i2004�N3��31���k2010�N5��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i10�j�i2004�N2��29���k2018�N9��30������l�j
�g�������W�̊�{�Ŗ��i2004�N1��31���j
�g�����̑�����i�i9�j�i2003�N12��31���j
�g�����̑�����i�i8�j�i2003�N11��30���j
�g�����̑�����i�i7�j�i2003�N10��31���j
�g�����̑�����i�i6�j�i2003�N9��30���j
�g�����̃��C�A�E�g�i2�j�i2003�N8��31���k2004�N2��29���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i5�j�i2003�N7��31���k2021�N5��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i4�j�i2003�N5��31���k2009�N4��30���`2020�N12��31���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i3�j�i2003�N4��30���k2014�N9��30���NjL�l�j
�g�����̃��C�A�E�g�i1�j�i2003�N3��31���j
�g�����̑�����i�i2�j�i2003�N2��28���k2011�N4��30���NjL�l�j
�g�����̑�����i�i1�j�i2003�N1��31���k2013�N9��30���NjL�l�j
�g�����̓����{�i2002�N8��31���k2002�N12��18���NjL�l�j
�}�����[�ɂ�����g�����̑�����i�ɂ͂������̌n����B�傫�ȕ��ނƂ��ẮA�P�s�{������A�l�S�W������A�i���{���w�S�W�̗ނ́j�S�W���p��������B�l�S�W�ɂ��A�P�����A�܂肻�̍�Ɓi���l�ł�������A�����Ƃł�������A�]�_�Ƃł�������A���j�Ƃł�������j�I���W�i���̑��{�E����������A�k�}���S�W���ځl�̂悤�ȁA��s����P�����̌l�S�W�̊O���ꂵ���n�������B�k�S�W���ځl�ɂ��āA���͂��āu1985�N�Ɂk�����ܕ��Ɂl���n�������܂ŁA�}�����o���Ă����r�b�O�l�[���̏����Ƃ̑S�W�̗����łł���v�Ƃ��āA���O�E���E�H��E���ɂ̂�����������B���́k�S�W���ځl�Ƃ͕ʂɁA�W��́u�S�W�v��搂��Ă�����̂́A��s���鎩�Ђ̑S�W���ĕ҂����n���݂���B��̓I�ɂ��q�g�����̑�����i�i126�j�r�ŏЉ���k��5���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i1967�N4��5���`1968�N4��30���j�A�s�{�V�����S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i1967�N8��25���`1969�N8��15���j������ł���B����́s���đS�W�k�S10���l�t�i�}�����[�A1968�N5��10���`1969�N2��10���j�����̌n��́u�S�W�v�̂ЂƂ̂悤�Ɍ����邪�A�͂����Ăق�Ƃ��ɂ������B�O�����ߐM���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
 �@
�@ �@
�@
�s���Ɏ��S�W�k��6���l�t�i�}�����[�A1967�N9��2���j�̔��ƃW���P�b�g�i���j�Ɓs�{�V�����S�W�k��2���l�t�i���A1967�N8��25���j�̔��ƃW���P�b�g�i���j�Ɓs���đS�W�k��9���l�t�i���A1969�N1��10���j�̔��ƃW���P�b�g�ƕ\���i�E�j
���҂̚��h��1899�i����32�j�N8��5���A����E�������̐��܂�i��o�q���h�N���r�ŁA����Y�͉h���M�N���Ɍ�����u1900�N���܂�v���������Ȃ��Ƒނ��Ă���j�B1967�i���a42�j�N6��23���A�����E����ŕa�f�����B���N67�B���O��25���́s���h��i�W�t�i�}�����[�j������A�f��A�O�f�s���đS�W�k�S10���l�t�̂��ƁA�s���h�S�W�k�S12���l�t�i���o�ŁA1997�N4��1���`1999�N3��15���j�������āA���݂��ꂪ�ł������ȑS�W�ł���i�������A���ׂĂ̌�����i��ԗ����Ă���킯�ł͂Ȃ��j�B���o�ł̑S�W�́A����Y�i1936�`2018�j�̕ҏW�E�Z���ɂȂ�����̂��̂ŁA�ʏ�A���ݍ��݂̕ʍ��ɂ��錎�S�W�e���̖{�̊����ɑg�݂��܂�Ă��āA�͂Ȃ͂��d��B�ʍ��ɂ���͎̂�ɏ���̐���E�����̎���ɂ�邩��A��ʂ̓ǎ҂ɂ͂��̕������肪�����B���̚��h�S�W12 ����q�������r�i1999�N3���j�ɁA��͏������낵�G�b�Z�C�q�o��\�\�ҏW���I���ār���Ă���B����́A�g�c����i1908�`1984�j�̖��Ś��h�S�W�Ɏ�肩�������͂������A�u���̎��ɂ͂���Ȃɋ�J���A����Ȃɂ̂߂肱�ނƂ͖��ɂ��v��Ȃ������B�v�i�����A��l��y�[�W�j�Ǝn�܂�B
�@�����k20�N�قǂ܂��l�A���o�łł͊����̑S�W�ɁA�S�W�����^�̍�i�����W���Đ����Ƃ��Ă���ɉ����A�V���{�S�W�Ƃ��Đ��ɏo���Ă����B�������A���͂��̕����\�\�����Ɍ����Ε����őS�W�v���X���т̌`���ł͎��̑S�W�ɑ��閲�͎����ł��Ȃ��̂ł����p���A�V�ҏW�ɂ�邱�ƁA�S��i��ԗ����邱�ƁA�{���̈ٓ��L���郔�@���A���g�����邱�Ƃ������Ƃ��Ď����A�В��̉����ăX�^�[�g�����B
�@�h�̌����͔��ɒx��Ă����̂ł܂����m�ڍׂȒ���N�\�̍쐬�Ɠ`�L�̒�������n�߂��B���{�ő�̐}���قł��鍑��}���قɍ��肵�ď��ɂւ̓����������炢�A������������܂܂ŎG����������J���ĉh�̍�i�̗L�����m�F�����Ƃ𐔃J���ԑ������̂����ƂȂ��Ă͊y�����v���o�ł���B
�@�ނ��͒T���̈ꕔ�ł���A�����̐}���فA�V���ЁE�o�ŎЂ̎������A�l�̑����A�Ï��X����̍w���A�m�F���̋����ȂǂŁA�]���m���Ă�����̂̎O�{�A���ܕS�_�����W���ĕҏW�ɂ�����A�����Ƀ��@���A���g�̍쐬�ɓ������B
�@���Ƃ��ҏW���I���A���s�̒i�ɂȂ��ďo�ŊE�̏�̕ω��ő啔�̑S�W�͍���Ƃ����A�N�V�f���g�Œx���ƂȂ�A�X�Ɏ��̑劳�\�\�t�s�S����l�H���͂ƂȂ�A�����˂��o����̐��̐t�ڐA�ɂ�錀�I�Ȑ��҂Ƃ����ꖋ���͂��܂������A�K�͂��ɏk�����ċ㎵�N�l�����犧�s�ƂȂ�A���������ɐi�s���Ė{���Ŋ����ƂȂ������Ƃ���т����B�����A���̊Ԃɋg�c�搶�����E����A���ɐV�S�W����ɂ��Ă��������Ȃ����Ƃ�����܂�ĂȂ�Ȃ��B�i���O�j
�@�h�̐t�͗���̘A���ł���B�ŏ��̗��l�ł����������`���ɂ͗����A�e�F�̉�������ɂ͏o���ʂ���ē`����D���Ă���B����ɂ��ĉh�͌J��Ԃ��`���Ƃ̌���ے肷�邪�A���̔��@�����������珑�Ȃ̏o���ɂ���ĉh�̎咣�͂��낭�����ꋎ��̂ł���B
�@���̌�A��ˍ��O�i�̂����䑕�u�Ɓj�ɋ����A�ؗE���ӂ���ĔɎ��̋��ɉ��������Ĉꏏ�ɂȂ邪�A�v�͐������\�͎҂Ƃ����Ă������l�ł���A�X�ɍ����^���ɂ̂߂肱��őߕ߁E�S���E�������J��Ԃ����̂��ɓ]�����č��܂��Ă��܂��B
�@�܂��Ƃɖ��c�Ȑt�Ƃ����ق��Ȃ����A����ɒǂ��ł���������悤�ɐV�����̂Ƃ������ׂ��Ɏ��̗����������N����B����������͓����g�D�̓����Ƃ��ĐM�����A�e�����������Ă������l�̒����q�i����d���̖��j�ƒm���ĉh�͜��R�Ƃ���B�������A�h�͗�q���n���g�o�V�Đg����������B�i�����A��l��`��܁Z�y�[�W�j
���́k��12���l�̊������G�ɂ́u1934�N5���o����̍��B�����璆���q�A��l�����ĔɎ��A�h�v�Ƃ����L���v�V�����̃��m�N���ʐ^�i�C���ɂ�邹�����A���������܂߂ĂȂ��Ȃ��̔��j�����Ԃ�ŁA�Ɏ��̓A���[�L�[��f�i������j���f�ڂ���Ă���B����ɓ�����č���Y�ҁq���h�N���r���Ђ��Ƃ��ƁA�ʐ^�B�e�́u���a9�N�i1934�j��35�v�̍��Ɂu5���A�Ɏ����ێ߂ŏo������B����͑������e���ʼn^�����}���ɑޒ����A�v�����^���A��Ɠ����i���̔N2��22���ɉ��U�j���͂��ߊe�g�D�����X�ɉ��U���A�R�b�v����̂������Ƃ�m���āA���㋤�Y��`�^�������؎���������Ƃ������Ƃ����]���ł������B����㍂�c�̓V��̐ߌ������̌����鏬���Ȃ����ɋA�������A�h�͓]���ɂ��o��������A��ؔ��߂������͌���Ȃ��Œ��ق��Ă������A���̂��Ƃ��Ɏ��ɂ͍��܂Ɣs�k��ɐɎv���m�点�A�����h�������ɗ����������Ƃ����猈���ē]���Ȃǂ͂��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹����̂��������i�w�����̋��x�A�Ɏ��u�O�\�Z�N�Ԃ̓����҂Ƃ��āv�j�B�v�Ƃ���A�u���a11�N�i1936�j��37�v�̍��Ɂu5�����A�h�ɂ͈����̂悤�Ȏ������N����B�v�ƒ����q�i�d���̖��j�̕s�ς̈��i10�N�č����瑱���Ă����j�����o���A���{�����h�̓n���^�I�X���ƂŐg�����������B���̎����͒����邳��Ă������A�������������ȏ�ɉh�ɂƂ��ďd��ȈӖ��������̂Ǝv����B�N���̗��F�ɗ����A�v�ɔw�����Ƃ����n���������Ռ��͑傫���A����͋��炭��ƂƂȂ�ق��ɂ͖�����Ȃ������̂��̂ł��������ł���A�Ƃ���Ήh�̍�Ƃւ̒��ڂ̓]�g�̌_�@�́A�����ɂ������ƌ��ėǂ��悤�Ɏv���B�i�ٍe�u�B���ꂽ�^���\���h�ɂ������Ɠ]�g�̈Ӗ��v��6�E2�E15�j�v�i�����A�k�������g�l96�`98�y�[�W�j�Ƃ���B���h�̐��U�ƍ�i�ɐ��ʂ��Ă��Ȃ���A�����܂ŏ�������̂ł͂Ȃ��B�����̑S�W�ƌĂԏ��Ȃł���B�}���Łs���đS�W�k�S10���l�t�ɖ߂�A����̌��ɂȂ����s���h��i�W�k�S25���l�t�i�}�����[�A1956�N5��10���`1959�N10��10���j�̊����Ăɂ͋����[���o�܂������i���P�j�B�O�f�N������E����B
���a31�N�i1956�j��57�^5��10���A�V���ł́u���h��i�W�S15���v���}�����[����A����2�������s����A���h�u�[�������_�ɒB����B���̌���10���ɍ�i�W��14���w�G���Ƒ��x�A20���ɍ�i�W��4���w�C���x�����s�B
���a32�N�i1957�j��58�^2��15���A���h��i�W��15���w�����x�����s�B����œ����̗\��ł���15���͊������邪�A�D���Ȕ��s���̂��߁A������1���Ƃ��A�X�ɑ�2��10�������a33�N3�����犧�s����A34�N10���Ɋ�������B�i�����A�k�������g�l108�`109�y�[�W�j
�Ƃ���Łs���h��i�W�k�S25���l�t�̕��y�ŁE��2���́A���Ƃ��k��16���l�i1958�N5��15���j�̉��t���L���ɂ́A�{��i�W�k�S25���l�̏���������Ă��āA��i�ɂ́u�����\���v�Ƃ��āk��16���l����k��25���l�܂ł��A���i�ɂ́u�����\�܊��v�Ƃ��āk��1���l����k��15���l�܂ł��L����Ă���A�`���́u���h��i�W�v�Ƃ����^�C�g���̘e�ɂ͎��̂悤�ɂ���i�������o���Ƃ��A�\���܂��≜�t�ɂ����\�\�����{�E���y�Ł\�\�̌ď̂͂Ȃ��A�����Ȕŕ\���ł͂Ȃ��j�B
�����{�@�V�l�Z���@�艿��܁Z�~
���y�Ł@�V �� �Ł@�艿��O�Z�~
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
���y�Łs���h��i�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1956�N7��5���j�̕\���Ɠ��k��7���l�i���A1956�N6��5���j�̖{���i�����j�Ɓu�����Łv���k��7���l�i���A�����j�̖{���i������ӂ��߁j�ƕ��y�Łs���h��i�W�k��8���l�t�i���A1956�N6��20���j�̃W���P�b�g�i�E����ӂ��߁j�Ɓu�����Łv���k��8���l�i���A�����j�̔��ƕ\���i������E�j�k�����ł̑��{�E�����͋g�����ɂ����̂Ǝv����l
���́u�����{�v�́s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�ł́u�����Łv�ł���B�d�l�́A�ꎵ�Z�~����~�����[�g���E�e�����ϖ��Z��y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�\���i2�F���j�B�s���h��i�W�t�̈����{�^�����ł̑��{�E�����Ɋւ���N���W�b�g�́q�ڎ��r���Ɂu�������@�x���q�v�Ƃ��邾���ŁA�����Җ��̋L�ڂ��Ȃ��B����A���y�łɂ́u����E�������@�x���q�v�Ɩ��L����Ă���B���Ȃ킿�A�O�҂̑����͖x���q�ł͂Ȃ��A�}�����[�̎Г����̉\���������B���͈����{�^�����ł̑��{�E�����͋g�������Ǝv���B���h��i�W�́A�k��1���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1955�N10��15���`1956�N9��20���j���s����1956�N5�����犧�s���n�܂��Ă���B���Ɏ��S�W�́A�N���W�b�g�����Ȃ����̂̋g����������i�ƌ��Ȃ���Ă���A�\���ɏ��������X�~�n�ŁA�����E���^��i�����A�J�n�ō����Ă��鏈�́A���h��i�W�������ł���i���t�̑g�����قƂ�Ǔ��������A����͒S���ҏW�҂̎d���������ꂸ�A�T�Ƃ͂Ȃ�ɂ����j�B�������A���h��i�W�̑������̂��̋g���������S�ʂƈقȂ�_�����邱�Ƃ��w�E���Ȃ���Ό����������B���̕��̏����u���h��i�W�v�����̕����ł��邱�Ɓi����\���̔w�̏����́A���̂̂������������̂̏��������j�A�{���̏��̂������̂ł��邱�ƁA�\���̕��ɒu���ꂽ�x���q�ɂ��J�b�g���قړV�n�����ł��邱�ƁB�̂��̋g���������ł̒�Ԃ́A�����Ȃǂ̓����̖����̊����̎g�p�A�V�n����������ɔz�u�A�ł���B�������A�J�b�g�̍���ʒu�Ɋւ��ẮA�x���q�������������y�ł̕\���̂���i�V�n��������≺�j�ɍ��킹���Ƃ��l������̂ŁA�����ɝy�I�������Ă����\��������B�����̓ǎ҂̓n���f�B�ȕ��y�ł����}�������낤���A���S�ł���A�d���Ƃ������͐��^�Ȉ����{�^�����ł̑��{�E�����������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA��f�ʐ^�̔w���x���①����̂��镁�y�ł͒���旧�}���ُ����̂��̂ł���i���h�͌㔼���𒆖���{�m�����݂̂�n�ʼn߂����A�����ŖS���Ȃ����j�B
�����Ŏ��^��i�ɖڂ�]���Ă݂悤�B�s���h��i�W�k�S25���l�t��271�сA�s���đS�W�k�S10���l�t��85�тł���B���҂̊e���^�C�g���͍�i�W�k�S25���l�ł̓��C���^�C�g��������A�S�W�k�S10���l�͂��ׂĂ̍�i�̃^�C�g�������Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A �O�f�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�Ɍ�����T�v�ɑ����Čf����ƁA���̂悤�ɂȂ�i��i�W�̓��C���^�C�g���̂݁j�B�Ȃ��i�@�j���̐����͂��̊��̎��^��i���B
���h��i�W�i���y�ŁE�����Łj�@�}�G�@�x���q�@���҂��Ƃ����^�S25�� 1956�N5���\59�N10��
���y�Ł@����E�x���q�@�V�����E�J�o�[���E����t
�@�@�@�@�e��130�~
�����Ł@���Ҏ��M�������@�V�l�Z���E�㐻�E�����E����t
�@�@�@�@�e��250�~
��1�� ���̊X�E��i6�j
��2�� �`�̖̂���Ɓi4�j
��3�� ���݂͂ǂ�i13�j
��4�� �C���i3�j
��5�� ��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓi1�j
��6�� �Ȃ̍��i5�j
��7�� �������̋L�^�i4�j
��8�� �E���o�����i8�j
��9�� ��\�l�̓��i1�j
��10�� ���̉ԕ���i47�j
��11�� �݂��g�i9�j
��12�� ���i5�j
��13�� �l�ӂ̎l�G�i17�j
��14�� �G���Ƒ��i1�j
��15�� �����i3�j
��16�� �R�̒����i20�j
��17�� ���̊p�i44�j
��18�� �Ԃ����Ёi26�j
��19�� ���̎��i1�j
��20�� �Y�ꑚ�i1�j
��21�� �Ԃ̗��H�i15�j
��22�� ���Ɣg�Ɓi��j�i�\�j
��23�� ���Ɣg�Ɓi���j�i��22���ƍ��킹�āA1�j
��24�� �������̕��i19�j
��25�� �����v�i17�j
�{��i�W�́A���o�ł́s���h�S�W�k�S12���l�t�����́q�}��r�Łu�{���^��A�{�S�W���^��i�̃e�L�X�g�ɂ��Ă͎��̂悤�Ȋ�ɂ���ĐM�����ׂ��{�����߂��B�^�C �w���h��i�W�@�S25���x�i���a31�N5��10���`��34�N10��10���@�}�����[�@�ȉ��w25���{��i�W�x�Ɨ��́j�Ɏ��^���ꂽ��i�ɂ��Ă͂�����{�Ƃ��A���o�ȉ��̏��{�ƌ����ɍZ�����āA�őP�ƐM������{�����߂��B��{�����߂��ꍇ�ɂ͂��̕����ƍ�����K���{���̈ٓ��������u���@���A���g�v�̍��ɋL���Ċm�F�ł���悤�ɂ����B�^���Ȃ݂ɁA�w25���{��i�W�x�͊��s�̎��_�܂ł̒��҂̏����E�������w�E���M�L�����W���A�V���E�V�����\�L�Ŋ��s�������O�B��̍�i�W���ł���B�v�i�k��1���l�A�l���܁`�l���Z�y�[�W�j��搂��Ă���悤�ɁA���^���ꂽ��i�̐��A�K�͂��炢���Ă��A���Ґ��O�̊��s�Ƃ����_���炢���Ă��A�f��̑S�W�����ɋ���ׂ��{���̏W���ł���B���́A�}�����[���o�������h�B��́u�S�W�v�B���Ɏ��i1897�`1975�j�ƂƂ��ɁA�q����r�̏��c�؏G�Y�i1916�`2000�j����i�̑I��ɐ[���ւ�������낤���Ƃ͋^���Ȃ����A�{�S�W�ɕҏW�S���̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�����ċ�����A�}�����[�ҏW���Ƃ������ƂɂȂ낤�B
���đS�W�@�S10�� 1968�N5���\69�N2��
����@���c�؏G�Y
�l�Z���E�㐻�E�n���\���E�J�o�[���E�@�B�����E����t
�e��680�~
��1�����Ȃ̍��@�݂��g�@�����i3�j
��2�����G���Ƒ��@�����v�i2�j
��3�����M�����͂ȁ@���̎��i2�j
��4���������炭�ԁi1�j
��5�����ǂ����łȂɂ����@�E���o�����i2�j
��6������\�l�̓��@��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓi2�j
��7�����卪�̗t�@���ԁ@�Ԃ��X�e�b�L�@���@���̊X�@�������@�C�̉��@���I�O�N�@��@�L���@�����̑��@�单���@���ׂȂ��l�X�@��@�����с@�v�����m�̍Ȃ̓��L�@�r���z���ā@�����X�P�b�`�i18�j
��8�����C�@�����N�@�M���炵�@�܂Ȃ����̉́@�ܖڂ����@�ٖD���@�ӂ����с@䂁@������@�\�D�@�߂��˂Ǝ�܁@�l�ӂ̎l�G�@�a�J������@���̔w�L�@�����@�������@�����@������̏h�@�������̋L�^�@�N�ؖȁ@�V���@�U���Ɩ�ǒ��@�����i23�j
��9��������̎P�@����d�@��V�̐�@�ԁ@�́@���@��@�ɐ��̓I��̓��a�R�@�܂��͂߂ł���@�Ԃ̗��H�@�`���E���b�v�̌��z�@�������@���߂���i13�j
��10�����܂育�@�b�q�ƔL�@�\�ܖ�̌��@�`�̏����@�[��̌��t�@���邷��@���傳��̔��̉ԁ@�����̐��@���[�̉́@��̑܁@�̋g�Ƃ��Č��@�����������E�̎�@�����炲�ق��с@�`�̖̂���Ɓ@���M���̂��傤�����@�⓹�@�Ƃ����с@���̎q�@�≺��q�i19�j
�{�S�W�́A��������10���ƑO�f��i�W�̔����ɂ������Ȃ����A���^���傫���Ȃ�A�y�[�W��������325�y�[�W�ƁA��i�W��1.6�{�̃{�����[���ƂȂ����i���̂��߁A��i�W��5���́s��̂Ȃ��q�Ǝq�̂Ȃ���Ɓt�Ƒ�9���s��\�l�̓��t��{�S�W��6���ЂƂɎ��߂邱�Ƃ��\�ɂȂ����j�B���҂̑�\���ԗ����A��i�W��̔ӔN�̋ߍ���ǂ����肱�ނ����A�Ҏ[�̌��ƂȂ����B�����Ŗ`���̖�ɖ߂�A�O������͐�s���鎩�Њ��s�̚��h��i�W�̏Ă��Ȃ����̂悤�Ɍ����邪�A�S���̍\�����g�ł��V�K�́A�܂������V�����l�S�W�ł���i�{���͊��p���Ă��邪�j�B���s�J�n�̑O�N�ɖS���Ȃ������҂�Ǔ�������A�Ƃ�����ʂ����̂����Ȃ��i���Q�j�B
�s���đS�W�k�S10���l�t�̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�e�����ώO��܃y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�W���P�b�g�E�@�B���B���܂��͓\�O��i�X�~�Ǝ�F��2�F���j���܂߂āA���ׂēʔŁi�����j�ň������Ă���B�Ȃ��A���e�̌Ï��œ��肵�����E�w�̓\�O��̎�F�͓��Ă��̂��ߔ��ł��āA�قƂ�ǎ����ɋ߂��B�J�b�g�i�����̃y���ɂȂ邩�j�̃��`�[�t�̓U�N�������A���̍�i�ɃU�N���ɂ܂����̂����邩�͕s���B
�Ƃ���ŁA�g�����͚��h�ɂ��ĂȂɂ������̂����Ă��Ȃ��B���������́A��i�W��10���́s���̉ԕ���t�Ɏ��^���ꂽ��i�̕W������Ă��邤���ɁA��Ȋ������ɏP��ꂽ�B
�\�\�t���@���~�@������@�䂫��葐�@�����Ȃł����@��@����ۂہ@�l��氓��i�X�C�[�g�s�[�j�@�킷��Ȃ����@�����̉ԁ@�P��ԁ@�t�����`�E�}���S�[���h�@�Ђ߂��@���u�@�ڂ��Ԃ�@�ւт̂����͂��@�݂�܂͂͂������@���@���ԁ@���̂Ԃ����@�݂�܂�@�܂܂��̂���ʂ����@��l�Á@���Ԑ��@�|�@���@�������@���@��ԑ��@�����ԁ@�J�[�l�[�V�����@����@���ł܂�@��Ԃ����@�I���[���@�V�l�������@�ނ炳���䂭���@���@��܂قƂƂ����@���������@�R�̏h�i�݂�܂�Â݁@���ǂ��@����̂��@�����痎�t�@���j�@���ց@���t���O�i���h�s���̉ԕ���t�j
�\�\�A�i�i�X�@�A���G�@�A���Z���E���@�}�O�m���A�@�Ƃ肩�ԂƁ@�����l�@�O�����I�T�@�u�o���A�@���������@�삲�܁@�A�}�����X�@�����̂܂�܁i�g�����q�l�H�ԉ��r�j
 �@
�@
�s���đS�W�k�S10���l�t�i�}�����[�A1968�N5��10���`1969�N2��10���j�̔��̔w�ƃW���P�b�g�̔w�\���i���j�ƒ��я����s�G���Ƒ��t�̖`���y�[�W2��k�s���đS�W�k��2���l�t�i���A1968�N6��11���A���y�[�W�j�Ɠ����Łs���h��i�W�k��14���l�t�i���A1956�N5��10���A�܃y�[�W�j�l�i�E�j
�����Ŏ��_��ς��āA1967�i���a42�j�N�̒��҂̟f��A�}�����[���犧�s���ꂽ�S�W���p���ɂ�������h�W�̂������ׂĂ݂悤�B�s���h�S�W�k��12���l�t�i���o�ŁA1999�N3��15���j�̍���Y�ҁq�����ژ^�r�̋L�ڂ����B�i�����A�k�������g�l55�`58�y�[�W�j
�w���㕶�w��n39�@�Ԗ�e�@���h�@�K�c���W�x�@��43�1�10�@�}�����[�@������@�l�Z���@480�~�@����F�^�甎�@���^��i�\��\�l�̓��@�������̋L�^�@���߂���@����\�����L�Z�iP481�`487�j�@�N���\���Ɏ��iP465�`471�j�@����\���h����Ǝ��\��J���q�iP3�`4�j�@��䂳��Ƃ̗��\������q�iP4�`6�j
�w���{�Z�ѕ��w�S�W29�@���\�쎟�Y�E�{�n�ØZ�E���n�O�E���i���E���h�x�@��45�7�30�@�}�����[�@�P��g���ҁ@264�Ł@�a�U���@360�~�@����F�Ȑ܋v���q�@���^��i�\�C�̉��@���߂���@����\���c�؏G�Y�iP262�`264�j
�w������{���w��n59�@�O�c�͍L��Y�E�ɓ��i�V��E���i���E���h�W�x�@��48�5�21�@�}�����[�@458�Ł@������@�`�T���@���^��i�\�Ȃ̍��@�卪�̗t�@���i�a�\�����E�Ώ����́j�@���߂���iP291�`401�j�@���h�̕��w�\�����L�Z�iP428�`433�j�@���h�_�\������q�iP433�`437�j�@���h�N���\�\���c�ؐi�iP�k499��449�l�`453�j�@����ژ^�\���c�ؐi�E���Γ֎q�iP457�`458�j�@����90�\�l�I�Ȏv���o�\������Y�iP5,�k18��8�l�j�@�O�c�͍L��Y�E���i���E�ɓ��i�V��E���h�����ē��\�\�x�]�M�j�iP6�`7�j
�s������{���{��n59�t�ɂ͑����҂̋L�ڂ��Ȃ����A����͓����A�}���ɍݐЂ��Ă����g��������|�������̂ł���i�s������{���{��n�k�S97���E�ʍ�1�l�t���Љ���q�g�����̑�����i�i60�j�r���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�����3�����ׂĂɎ��^����Ă���̂��A�Z�т́q���߂���r�i���o�́s�Q���t1963�N11�����j���B
�@����ǂ��B
�@�̂Ȃ��@�����Ɍ����������܂܁A�V�v�w�͂��܂肱��ł����B�v���͈�Ȃ̂����A���͂�������ɏo���ĉ]�������C�͂��Ȃ��B�ق��ɂ��ꂪ����Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂�����A�������A�Ԃ��܂������k�����Ă��悢���Ȃ̂����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ȃ̂ɁA���t���o�Ă��Ȃ��B���X�A���ꂱ��Ƃ������߂����K�v���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����A�����ƗE�C���ӂ���č��̍����̂��˂Ȃ�Ȃ��悤�Ȏ��ԂɁA���߂Ē��ʂ��Ă݂�ƁA����ς肵��ǂ����悫�ɗ��B�N���炵���������𗎂��������悤�ȑ������v�́A�����̌��������т��A���ڂ�̂܂����ɊāA���������܂܂܉������ɍl������ł���l�q�����A�l���͂���ɑ����Ă���Ȃ́A�����ɖj��������܂ܕ��S�����悤�ɂ܂��������Ȃ��B����ۂǂ���ǂ��炵���B
�@�₪�ĕv���Ԃ₢���B
�@�u��������v
�@�Ȃ͈Â������ɋC���������A����������ɗ��̂���V�������B�ߔN�a�C�����̍Ȃ́A����ȂƂ��ꂻ�����炾���d�����Ȃ�̂������B�����Ȃ�g�y�ȕv���p�𑫂��Ă����̂����A���̕v�������͗�����낤�Ƃ��Ȃ��B�����Ă܂��Ԃ₭�B
�@�u���������肷��ƁA�悯�����Ȃ����v
�@�Ȃɕ����Ƃ����̂��낤���A�d�˂Ă̂Ԃ₫�ɁA�Ȃ͂ӂ��Ƃ��������̂悤�Ȃ��̂��܂ƈꂵ��ɂ��ݏグ�Ă����B�����ɂ������̂����������̂Ԃ₫�����C�͂Ȃ������̂����A�l�\�N���ꂻ���Ă������̉i���N���ɁA�������������Ƃ��Ȃ������I�Ȍ��t���A�����͂���Ȍ��t���g��Ȃ������̕v�̌�����o�Ă����̂��������������̂��B�����܂��߂ł��邾���ɁA�v�ɂ��Ă͎������̂܂܂ɂ������Ȃ��B�Ȃ͂���ŋC�������ق���A�X�C�b�`������ɗ������B
�@�u���킢�����������v
�@������ɔw�������ė܂��ӂ��Ȃ���A
�@�u�ނ̑O�ł́A��������܂����ڂ��Ȃ���ł����́B�v�����̂���������Ȃ�ח��ĂċC�x�߉]���ā\�\�v
�@�u�����͕a�C�̂��ƁA�C�����Ă��Ȃ��̂��ˁv
�@�u���Ȃ������Ȃ���B�ł��C�̂��Ȃ��ӂ�����Ă��Ȃ�������v
�@�u�Ӂ[��v
�@�u�����������Ă��A�]���Ȃ����̂ˁB�{�l��������Ǝv���Ă����ɏo���Ȃ��̂ˁv
�@�V�v�w�͂��������A�ݒ�ᇂ̂��Ƃ��v�킵���Ȃ��āA��x�߂̓��@�����Ă��閺����a�@�Ɍ������Ă����̂������B�����Ē��ɔӂɕa���̐[�܂�炵���l�q�ɋC���d�炵�Ă����B�����͎l�\��x�ɂ�������M������ƒ��˂ł��߂����肾�Ƃ����a�l�́A����ł��܂��b���Ȃ���A
�@�u�M�́A�������A�킩��Ȃ���ł��v
�ƁA���ꂳ���킩��Ζ����̋ꂵ�݂���̂�����ł����邩�̂悤�ɁA���ɂ������ɑi�����B�����Ƃ肩�˂�قǗ͂̂Ȃ����ŁA���킢���O�����ɂ������Č����ӂ��o���͂��ʂ��Ǝv���قǂ��������ɂȂ��Ă����B�����Ă��Ƃ͂����ڂ�����܂܁A���炤��̏�Ԃł���B�H�|���S�R�Ȃ��̂��ƁA���Y���Ă��閺�͂����A�����Ђ��߂āA
�@�u�������Ă����肢��̂�v
�Ƃ��Ȃ������ɂ������B
�@�u�������Ă���Ԃ��Ԃ�v
�@�u����v
�@������Ȃ��Ȃ����炨���܂��Ȃ̂����A���ꂪ�������܂��Ă���̂�����A�o������Ȃ����A�Ƃ͂����疺�ɂł��]���Ȃ��B����ɂ��Ă��A���ꂪ��\���O�ɂ͏��^�e���r����тȂ�����@�������̋C�����ȕa�l���Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B���͂������̃e���r�����錳�C�����Ȃ��A���������ӂ邦�o������A���M�Ɉӎ�����������A���炤��Ɩ�������A���̂���Ԃ��̍��Ԃ�A���ƃ����Q���ŁA�悤�₭�ۂ��Ă���̂��B�����āA���ꂪ�D�]���錩���݂͍��̂Ƃ���S�R�����Ȃ��B����ǂ��납�A��ɂƐ���͉�������炵���B
�@�u�����A�����A��Ȃ��悤�ȋC������\�\�v
�@����Ȃ��Ƃ܂ł����o�����ނɁA
�@�u�ȂɁA�����Ă�́B���ł������悭�Ȃ��ċA�����̂ɁA�Ⴂ�����A�n���Ȃ��Ƃ����Ȃ���ȁv
�@���́u���v�������ŋ߂܂œ������̕a�@�ɕa��{���Ă����̂ł���B
�l�̏͂��琬��u��v�̑S���ł���B�����̂悤�ɁA��҂ƕv�i�쒆�ł́u��Ƃ̕��쌳�q�v�Ɓu���l�̕��앶�g�v�j�̖����i�u�R�`��v�v�j�̖�������������i�ł���B
�u�R�`��v�͂��̋ߐ�̏o�ŎЂŎ����̊��𗧂Ď��W�̏o�ł��肪���Ă����B�ނ̍����܂ł̎d���̍Ō�́A�Ґ����������Ȏ��l�̍��ȑS���W�{�ł������B�����āA�͂��߂̓��@�̎��ɂ͕a���܂ł��̑傫�ȁA�d�������W����������ŁA���X�Ђ낰�Ă݂���A�Ԃ�V�̓��ɂł������悤�ɁA���S�Ԃ����\��ł������Ă����肵���B�^�u���̒��A�����������̎��W���A�o���܂�����ˁv�^����Ȃ��Ƃ��]�����肵�����Ƃ����������A���ꂩ��͂����N�̍��ł͂������W�ǂ���łȂ��Ȃ��Ă���B���X�̐V��������ɂ��Ȃ��̂��B�v�i�O�j
���͂����ǂ�Łu���̋ߐ�̏o�ŎЁv�͒}�����[���Ǝv�������A��҂̑O�f�N���i�s���h�S�W�k��12���l�t�A�k�������g�l83�`114�y�[�W�j������Ƃǂ����Ⴄ�悤���B�Ȃ������́u�i�V�j�v�͑O�f�s���㕶�w��n39�@�Ԗ�e�@���h�@�K�c���W�t�����̚��Ɏ��ɂ��q�N���r���w���B
���a32�N�i1957�j�@��58��
�@�k�c�c�l
�@2��28���A�{���̐^���Ɖ������v�̉��k���܂Ƃ܂�A���n�P���E������q�̔}�ނŌ�������B�����͉h���O��������w������̏h�x�i��24�j���o�������̕ҏW�҂ŁA���Ƃɐe�����o���肵�Ă����B�v�w�͒x�������^���̌�������Ԃ��A����ŔɎ����u���N��y���Ƃ��ɂ����ޏ��Ɨ���A�b���̊ԁA�ڂ��肷��v�i�V�j�ƋL���悤�ɋ̎v���������Ȃ������B
���a38�N�i1963�j�@��64��
�@�k�c�c�l
�@5���A�b���̔���ň����P�J�͖̉k�a�@�ɓ��@���A7���މ@�i�V�j�B
�@8��1���A�A�ڐ��M�u���̂����킹�v���u���w���̗F�v�ɘA�ځi39�N7��1���܂Ł@�S12��j
�@���̍��A����̕a�C�ɉ����A�Â̐^���̕v�������v���K���œ��@�A�傫�ȏՌ�����B
�@11���A�������v�����B�^����2�l�̎q��A��Ă��ǂ��Ă���B
�u�R�`��v�v���������v���Ƃ���ƁA�s�Q���t1963�N11�����ɍڂ����q���߂���r�͉������S���Ȃ�܂��ɒE�e���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�S���Ȃ��Ă���M���������̂łȂ����Ƃ͊m���ł����i���R�j�B�q���߂���r�̖����͂������B
�@�s��k�R�`�̒��j�̗c�t�����l�͂ЂƂ�ŗm�����ʂ��o�����B�R�`�̕�́A���Ƃ������ɂ���߂Ȃ���A
�@�u���ƂȂ������Ȃ��ƁA���������A�A��̂��₾���Ă�������Đ\���܂��ƂˁA�������āA�ЂƂ�ŁA�˂܂��A�������܂��́B�����炵���āv
�@�����Ă��đs��͂��ƂȂ����Q���ɓ����Ă������B���݂Ȃ��Ɍ��q�́A���C�Ȃ��A�e���r�̂킫�̒��ɂ������Ă���A������݂��݂��B������̖������肱��̕\�ɂ͏��|�~�̂߂ł����̉��ŁA���ƍ��ƒ��̓e���O�C�A�Ȃ�������|���Ă������܂��Ă���B���ƃn�C�J���ȎR�`�Ƃ��Ă͂������ȗ�������Ă�����̂��B��e�̍D�݂ł����낤���Ǝv���Ȃ���A����Ƃ��Ȃ����߂�����݂��B�����\�Z���B���j���B�㎇�A�F���B���s�啶���B���̂Ƃ��B���Z����\�����B�ǂ����͉ƒ�𖾂邭����B�\�\
�@����ȕ����������Ȏ��ʂɁA�k���ā��c�l�����≡�����ō��肱�܂�Ă���B�����\�Z���B����͎R�`�����@�������ł���B���ꂩ�炠�ƁA���̉Ƃł͂���݂̏�ł͓����o���Ă��Ȃ��̂��B���݂Ɉꖇ���߂���ƁA�\�����A�����B�敉�B�\�����A���ԕ��ŁB�\����A�Z���揟�ƂÂ��B
�@�����A���܂��܂̉^�����Ђ�����Əd�˂��܂܁A���̉Ƃł͖邪�����Ă��Ȃ��B���邶�̂��������A���̂܂܂ɁA�������ǂ����Ƃł����������ɁA�������������A����݂͂߂���肪�Ȃ��B�c�c
����͒����̕��ł͂Ȃ��A�����̊�Ղ��F�镶�͂������B�u�u���߂���v�́A�쒆�ɏ�����Ă���ʂ�̐l�ԊW�Ǝ����Ƃɂ��ƂÂ��Ă���A����̏d�݂����̂܂܂ɕ\�����ꂦ�Ă������ł����āA���̂䂦�ɂ܂���҂̐l�����N�߂ɂ��ʒu���\���ɂɂ��ݏo�Ă���B���`�I�ȗv�f�̂������邵�����̍�Ƃ̍�i�������Ɠǂ�ł����҂ɂƂ��āA�ӔN�ɋ߂�����̍�҂��l����ł����w��ł����������Ƃ���ɗ��Ă������Ƃ�����̂́A���S�̐[�����Ƃł���B�v�i���c�؏G�Y�q����r�A�s���đS�W�k��9���l�t�A1969�N1��10���A�O�Z���y�[�W�j�B���o���œǂ҂́A�Ȃ��Ƃ̓��߂�����܂��܂��ƌ������Ƃ��낤�B���������A���h�̍ŏ��̍�i�W�͒Z�я����q��r�����߂��s��t�i�V���ЁA1940�N3��9���j�������B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@������q�̌����҂ł��鏬�їT�q�i1941�` �j�͂��̒����s���h�k������ƕ]�`�V���[�Y12�l�t�i�V�T�ЁA2012�N5��5���j�ŁA�u�h�u�[���v�ɂ��āu�u��\�l�̓��v�u�[���ɘA������悤�Ɉ��l�N����܋�N�܂ŁA�h�̒���W�̏o�ł��������B�����ĐV���Łw���h��i�W�S��܊��x�i�}�����[�j���o�ł��ꂽ�B�������A����͐V���łł���A�l�C��Ƃł���Ȃ���A���O�ɑS�W���o�Ȃ������B�w���h�������w�S�W�S�l���x�i���Z�l�E��@�u�k�Ёj�́A���^��i�����b�Ɍ���ꂽ���ƁA�܂��w���h����W�S��Z���x�i���Z�܁E��Z�j���|�v���ЂƂ����ǂ��炩�Ƃ����Ǝ����}�����S�̏o�ŎЂ��������ƂȂǁA��ƂƂ��Ă̈������s���Ɍy���Ƃ�����ۂ���B������q�����ܔ��N�ɖ{�i�I��i�W�ł���w������q��i�W�S��܊��x�i�}�����[�j���o���A�K�c�������ܔ��N�Ɂw�K�c���S�W�S�����x�i�������_�Ёj���o���Ă���̂ɔ�ׂ�Ƒ�ςȈႢ�ŁA�����w��ƂƂ��Ă͂��s���Ƃ�����������B�Ƃ������A���܁Z�N��㔼����Z�Z�N�܂ł́A�h�̍�ƂƂ��Ă̊����̐Ⓒ���Ƃ����Ă悢���낤�B�v�i�����A���Z�`����y�[�W�j�Ə����Ă���B�s���h��i�W�t���V���łŁk�S15���l�����o�Ȃ������Ƃ����L�q�͐��m���������i���э쐬�̊����q���h���N���r�����l�̓��e�j�B�V���łƂƂ��ɔ����E�n�[�h�J���@�[�́u�����{�^�����Łv���A������15�����D�]�ɂ�10�������₵�āk�S25���l�ƂȂ��Ċ����������Ƃ́A�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t������܂ł��Ȃ��i�����ɂ͑���̌o�܂͏�����Ă��Ȃ����j�A���їT�q���{���̎��M�ɓ������āu����ȉ��b�����v�i�q�����Ɂr�A�{���A�Z�y�[�W�j�Ƃ�������Y�҂́q���h�N���r��q�����ژ^�r�̋L�ڂ̂Ƃ���ł���B�u���O�ɑS�W���o�Ȃ������v�̂͂܂��ɂ��������A�u�k�Ђɂ���|�v���Ђɂ���A���ЂƂ��ĉ\�ȁu�S�W�v�Ƃ������̑I�W��҂̂����A�����āu��ƂƂ��Ă̈������s���Ɍy���v�킯�ł͂Ȃ����낤�B�ނ���A�������邱�Ƃ̂Ȃ��������o�Ł�����Y�ɂ�铖���v�����́s���h�S�W�k�S24���H�l�t���j�i�Ɂu�d���v�S�W�������Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ����B
�i���Q�j�@����z�{�́s���đS�W�k��1���l�t�i1968�N5��10���j�̌���̖����ɁA���̂悤�ɂ���B�u�ҏW�������@���Ă��S���Ȃ��Ă���₪�Ĉ�N�ɂȂ�܂��B���̕��w�̑����Z�Ƃ������ׂ��{�S�W���ǂ��������ǂ��������܂��悤�B����z�{�͑�A�Ȍ㊪�����̔z�{�ł��B�v�i���A���y�[�W�j�B�f���N�ɖ����Ȃ��������ԂŁA�S10���̑S�W�����s����ɓ������ẮA�S��������M�̏��c�؏G�Y�Ƌٖ��ȘA�g���Ƃ����i���h��i�W�k�S25���l�Ɠ����H�j�ҏW���̑��݂��^���đ傫�������Ǝv���邪�A�S���ҏW�҂��N���������͒��ׂ����Ȃ������B�Ȃ����h�́A�}�����[����P�s�{�s���̉ԕ���t�i1953�j�A���k�V���Łl�i1955�j�A�s�����̉ԕ���k�V���Łl�t�i���N�j�A�s����̎P�t�i1954�j�A���k�V���Łl�i1955�j�A�s�G���Ƒ��t�i1956�j�A�s�Ɋy�����t�i1957�j�A���k�����Łl�i���N�j���o���Ă���B�v�̔Ɏ������W�s���D�t�i1957�N6��20���j��}�����[����o���Ă���A�����̑����͋g�����ł���i�q�g�����̑�����i�i3�j�r���Q�Ɓj�B
�i���R�j�@�q���߂���r�����߂��s���h�S�W�k��7���l�t�i���o�ŁA1998�N6��15���j�̍���Y�q���r�ɂ��̊Ԃ̌o�܂�������Ă��邩�Ɠ������Ă݂����A���ڂ���ɂ͐G��Ă��炸�A�u�������v�i�O�����Ј��A�̂��}�����[�ɕς��j�v�i�����A�l��܃y�[�W�j�Ƃ����L�ڂ��������B�s�����Ґ��S���W�t�i�}�����[�j�́A�k����Łl1000����1962�N3��10���ɒ��Ҏ����ŁA�k���y�Łl��1964�N9��30���ɏo�Ă���i������͓Ȑ܋v���q�̑������j�B�s��{ �O�D�B���S���W�t�Ɓs���e���O�Y�S���W�t��1963�N11���܂łɒ}������o�Ă��邩��A�������������v�̕ҏW���������B
2020�N��12���A�����Y�p�w���O�̍������[�̓X���ŁA���w�O���[�v���������s����G���s�����t�i���P�j�̃o�b�N�i���o�[���������B�����ɂ͋g���������сq��`�r�i�D�E19�j����1961�N7����9���͂Ȃ��������A�������̒�����1960�N7����7���i�������̓����C�J�j�ƁA���ʂƂ��čŌ�̍��ɂȂ��Ă��܂����i�Ȃ��Ȃ�A�����܂��̕��̃y�[�W�Ɂq�����@�f�ڗ\���i�r�Ƃ����\���R���������邩��j1963�N7����11���i�������͎v���Ёj���w�������B�Ƃ���ōŔӔN�̋g���́A�s�����C�J�t1989�N6�����k�Ǔ����c��m�l�́q�c��m�Ǒz�r�̖`���ŁA�s�����t�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B�Ȃ��A�g�����N���ɂ�1952�N�A33�̂Ƃ��A�u�O���A���E�O���[���w�s�Ǐ��N�x�̖�ҊےJ�ˈ�A�u�����v���l�c��m�Əo��B�v�i�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�A�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A����O�y�[�W�j�Ƃ���i��l�͂��̔N�A���R���j�Ɓs�����t��n�������j�B
�@�c��m�����Ƃ̏o����A���̂悤�ɏ����Ă���B
�@�\�\�g������Ɂk�����͂��l�߂ĉ�����̂͂����������A�����L�����������łȂ��B����́A�������ڂ������̎G���u�����v���o���͂��߂���������\�N�قǂ܂����Ǝv�����A�g������̋Ζ���̒}�����[���܂��{���̌ÐF���R���鋌�k�������l�ɐw����Ă����B�ڂ��́u�����v�̍L����Ⴂ�ɂ䂫�A���ʂ̐ӔC�҂ł���g������ɁA���낢�냌�C�A�E�g�̎w���������肵���B�Ȃ���ψА��̂����ЂƂŁA�����j���O�E�V���c�ꖇ�̏����ȏ㔼�g�����킵���ɓ������Ȃ���A����悩��|���Ă���d�b�ɂłāk�i�g���j���́l�A������Ɂu�o�k�����i�i�V�j�l�܂���A�o�k�����i�i�V�j�l�܂���v�Ƒ吺�ł�߂����ĂĂ����B����ȂɁA�Ȃ�̖{�������̂��A�ڂ��͂����Y��Ă��܂������A���邢�̓}�[�N�E�Q�C���̖{��������������Ȃ��B�\�\
�@����́A���a�O�\�Z�N�����O�\����t�́u�k���{�l�Ǐ��V���v�̃R�����́u�l���X�P�b�`�v�̖`���ł���B�����A���͍L���S���Ƃ��āA�V���A�G���Ȃǂ̍L���f�ڂ̂��߂̌�����A���e�܂ŁA��l�ł��Ȃ��Ă������̂ł���B�u�}�[�N�E�Q�C���̖{�v�Ƃ���̂́A�w�j�b�|�����L�x�̂��ƁB�����ȗ��A�����܂��x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�L���ʂ������A�Z�������X�������B�u�o���܂���A�o���܂���v�Ƌ���ł����̂́A�����炭�n���V���Ђ��Ȃ̗v���ɉ����Ă����̂��낤�B���̂悤�ȏ̂Ȃ��Ŗ����̕��w�N�̓��l���u�����v�֍L�����o���̂́A�܂������ٗ�̂��Ƃ��B�ق��ł��Ȃ��A�ےJ�ˈ�Ɉ˗����ꂽ����ł������B�i�����A�Z���`�Z���y�[�W�j
�Z�������ӏ��́A�k�g�����q�c��m�Ǒz�r���c���q�l���X�P�b�`�r�i���Q�j�l�ŁA�g���́u�o���܂���A�o���܂���v�͈Ӑ}�I�ȉ��ς�������Ȃ����A�u�����v�͋g���̎菑�����e�̕�����ǂ݂���������A�ɈႢ�Ȃ��B�����s�����t��7����11������肵���̂́A�ق��ł��Ȃ��A�O�҂̕\�Q�i�\�����j�ƌ�҂̕\�S�i���\���j�ɒ}�����[�̏o�ōL�����f�ڂ���Ă��邩��ł���B�����@�����A����2�����ǂ�ȓ��e���A�\���ɍ���ꂽ�ڎ����N�����Ă������B
�s�����t7���i1960�N7���j
�@�@�@�@�@�@�@�@���w�G��
�ҏW ���O�R�r
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\
calendrier�@�������j
�w��x�̕��̂ɂ��ā@�i����
�͏�O���Y�_�@�c��m
�V�J�S�̍�Ƃ����@�{�{�z�g
���؉��@�O�֏G�F
�s�������͎���ꂽ�i�h�j�@���R���j
�G�z�o�̊������āi�����j�@�ےJ�ˈ�
�c���ւ̎莆�@�������q
�c��m�̔�]�@�쑺��Y
���R�I�R�X���X�̉@�����q�v
�w����e�x����w�C�\�W�x�܂Ł@�X��
�S�b�g�t���[�g�E�x���@���쏺��
�@�@�@�@�@�@�@�@1960 ��
�@�@�@�@�@���w�O���[�v����
�s�����t11���i1963�N7���j
�������ā@����[�O
��ɂ��Ă̎��_�@����N�v
�o���Ȃ��h�A�@��ѐ^
ᓚЂ̕��w�@�����O
���̂��Ɓ@�i����
���閄���@�O�֏G�F
�u���F��寁v���߂��ā@���{�ꖾ
���ɖ����@�ےJ�ˈ�
�����ƊC�}�w�ҁ@�����ǗY
�����̖|��ɂ��ā@���r����
�V�������}���@���쏺��
�@�@���w�O���[�v����

 �@
�@

�s�����t7���i���w�O���[�v�����A1960�N7���j�Ɠ��E11���i���A1963�N7���j�̕\���i���̂ӂ��j�Ɓs�����t7���̕\�Q�L���k�{���y�[�W�ɁA�ےJ�ˈ�s�G�z�o�̊������āt�̉͏o���[�V�Ђ̏o�ōL��������̂�������l�Ɠ��E11���̕\�S�L���i�E�̂ӂ��j
�}�����[�̏o�ōL���̎w��������̂��g�����{�l���A�ǂ����͂����肵�Ȃ��B�������������ĕ��ׂĂ݂�ƁA�c�g�̒n�����̃��C�A�E�g�ȂǁA�g���ɂ��V���L���̎O���m�����n�ɒʂ�����̂���������B�c���ɂ́u�ڂ��́u�����v�̍L����Ⴂ�ɂ䂫�A���ʂ̐ӔC�҂ł���g������ɁA���낢�냌�C�A�E�g�̎w���������肵���B�v�Ƃ��邪�A�ނ��̂��ƁA�u���낢�냌�C�A�E�g�̎w�������v�Łs�����t�̑����w�肵���킯�ł͂Ȃ��A�����͂�͂�i�g���{�l���͑[���āj�}�����[�����w�肵���ƍl�������B�g���͎O�������łȂ��A���Ђ̏o�Ő}���̖ژ^���S�����Ă����킯������i�q�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t���邢�͕S�����o�̂��Ɓr�Q�Ɓj�A�s�����t�̂悤�Ȃ`�T���̎��ʂ��\�����邱�ƂȂǁA����̂��̂������͂����B�Ƃ���ŋg���́A�ےJ�ˈ�Ƃ̂��Ƃ����̂悤�ɏ����Ă���B
�k���a�O�\�ܔN�l�܌�����@�ےJ�ˈ�Ƃ����B�s�G�z�o�̊������āt�Ƃ��Ƃ��o�ł���邱�ƂɂȂ�B�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���O�y�[�W�j
���a�O�\�ܔN�@���Z�Z�N �l�\��@�k�c�c�l�ےJ�ˈ�Ɖ�Ћ߂��̋i���X�ʼn�A�w�G�z�o�̊������āx���o�ł���邱�Ƃ���ԁB�i�q�k�g�������M�l�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j
���̌��Ɋւ��ẮA���ĊےJ���g���ɑ������s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�\�\�ےJ�̍ŏ��̒��я����ł���\�\�̏��e���f���āA�o�ł̌o�܂ɂ��ď��������Ƃ�����B�ڂ����́A������i�q�g�����̑�����i�i4�j�r�j�������������������B
�k2021�N8��31���NjL�l
�u�O���v�̕����j�I�ȈӋ`�ɂ��āA�}���ُ��w�̍��{���́s�A�[�J�C�u�̎v�z�\�\���t��m�ɕς���d�g�݁t�i�݂������[�A2021�N1��18���j�́q���{�̃A�[�J�C�u�v�z�r�Łu�k�c�c�l�������w������悤�Ȓ��K�͈ȏ�̓s�s���ƁA�V���̕��w���⋳�{�����X���ɕ��сA��Ԃ̍�Ƃ�m���l�̑�\��ڎ�ɂƂ邱�Ƃ̂ł��鏑�X������Ƃ����A���{���L�̏o�ŗ��ʏ������܂��B����ɑΉ����āA�S�����̑��ʂɂ�����O���m�����n�L���i��ԉ��̒i�ɂW�̏c����ɂ����o�ōL�����u����銵�K�j����ʁA�O�ʈȍ~�ɂ��o�ōL�����傫���f������l�͑��̍��ɂ͂Ȃ����̂ŁA���{�ł͐V�����G�������Ђ��A�����Ċ������f�B�A�s�ꂪ�����Ă��邱�Ƃ������܂��B�����āA���̂悤�ɂ��āA�o�ŕ��͏��i�ł���Ȃ��瓯���ɃA�[�J�C�u�I�Ȗ������ʂ��������I�Ȃ��̂Ƃ��Ă̈ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��܂����B�v�i�����A��l���y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B����͂Ƃ���Ȃ������A��g���X��}�����[��݂������[�i�n�Ǝ҂ł����g�ΗY�A�Óc��A�����r�l�͂���������쌧�o�g�j�Ȃǂ̏o�ŕ����u���i�v�i�ǂ̂悤�Ȏv�z�E�M���̎�����ł��艿�ōw���ł���j�ł���A�����Ɂu�������v�ł��邱�Ƃ��A���̐�̗v�Ɉʒu����V���E�G���f�ڂ̏o�ōL���Ɍ��Ă邱�ƂŖ��炩�ɂ����B���̕����ɏƂ点�A��f�L���͌o�ϓI�Ȏx���ł���Ɠ����ɁA�}�����[�́s�����t�₻�̏�����ł��镶�w�O���[�v�����̓��l�������A�[�J�C�u�I�Ɏx�����܂��A�Ƃ��������ł��������B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@���{�ߑ㕶�w�فE���c�ؐi�ҁs���{�ߑ㕶�w�厖�T�k��5���l�t�i�u�k�ЁA1977�N11��18���k��O���F1978�N1��18���l�j�ɂ��A���|�G���s�����t�́u���a�E��`�O���E���B�G���B�S��ꍆ�B�ҏW�l���w�R�r�A���s�l���J�쐭��A�̂��[���w�B���юЁA�̂����w�O���[�v�������s�B�����ȓ��l�͎c��m�A�ےJ�ˈ�A���쏺���A�쑺��Y��̐V�i�C�s�̊O�����w�ҁB�n��ł́A�ےJ�̒��ҁw�G�z�o�̊������āx�A�G�b�Z�C�ł́A�c�̍ŏ��̕]�_�W�w����ɂāx�̏��o�A���ł́A���i���F�A�������j�A�ѓ��k��A����N�v�Ȃǂ̌��삪������B�|��ɂ��͂���������A�v���T���\���A�q���o���E�H�[�����A�s���r���G���I�b�g��̑n��A�]�_���Љ�ꂽ�B�ق��ɋ{�{�z�g�A�i�����̊�e�āA���ʂɂ͐��V�ȃ��[���b�p���w�̑����������f����Ă���B�܂����{�̋ߑ㎍�ɂ����ڂ��A���{�ꖾ�Z���w�������\���сx��X���ҁA����w�ɗǎq�����A�E���D�E��x�Ȃǂ̂��݂ŋM�d�Ȏd����ł���B���Z���ɂ́A��ꍆ����̎��M�ҕʂ̑��ڎ����f�ڂ���Ă���B�v�i���M�ҁF���c�o�A�����A��Z��y�[�W�j�ł���B
�i���Q�j�@�q�g�����̃X�N���b�v�u�b�N�i2�j�r�Łu24. �c��m�q�g�����\�\�����j���O�E�V���c�^�Z�����l���̒��̒��X���鐢�E�r�\�\�q�Ǐ��r36�E7�E31�\�\�q�l���X�P�b�`�r�R�����v�ƏЉ���c��m�̕��͂́A�g�����Ƒ��̃X�N���b�v�u�b�N�iMEIKANDO TOKYO���́qSCRAP BOOK�r�i�i�ԁFKING NO.140�j�j�ɐ蔲�����ۑ�����Ă���i�g���̎c�Ǔ����́A����������p�����̂��낤�j�B�ӔN�ł�����ʑ̂ƂȂ邱�Ƃ��������g�������A1959�N�Ɂs�m���t�łg�܂���܂����u���̐l�v�̂���́A�e��̃C���^�����[�L���Ɂi������܂܂Ɂj�|�[�g���C�g���ڂ��Ă���B�f�ڋL���̖����ɂ́u�ʐ^�͐_�c���쒬�̒}�����[�Ł��n�ӏ��K�B�e�v�Ƃ���A�e�����m�l�ɂ�鏑�����낵�̕��͂ƎB�肨�낵�̎ʐ^���琬��A�A�ڂ̐l���Љ�R�����������悤���B���́q�l���X�P�b�`�r�A���R�͂悭�킩��Ȃ����A����1970�N7��13������������b�q���M�́q�g�����\�\�u���̎��l�A�����ȁv�^�L�͔S�f���̉t�̕�݁r�ŁA�g�����̍ēo��ƂȂ��Ă���i�����Ɂu�B�e���֍��O�v�Ƃ���|�[�g���C�g�́A�͂����Ă��̂Ƃ��̎B�肨�낵���j�B���łȂ���A�C���^�[�l�b�g�Łu���{�Ǐ��V���~�l���X�P�b�`�v���������Ă݂�ƁA����������푺�G�O�̂��Ƃ��������q�z���B���p�̐�Ɂr�i1968�N5��13���j���q�b�g����i�q�푺�G�O�֘A�������X�g�r�j�B���R�����́A���Ȃ����ς����Ă�10�N�߂������Ă���̂�����A�قڔ����I�ɂ킽��s���{�Ǐ��V���t�i1937�`1984�j�ɂ����钷�����̂ЂƂ��낤�B
 �@
�@ �@
�@
�c��m�q�g�����\�\�����j���O�E�V���c�^�Z�����l���̒��̒��X���鐢�E�r�i�s���{�Ǐ��V���t1961�N7��31���j�̐蔲���i���j�Ƌ�����b�q�q�g�����\�\�u���̎��l�A�����ȁv�^�L�͔S�f���̉t�̕�݁r�i�����E1970�N7��13���j�̐蔲���i���j�k��������g���Ƒ��̃X�N���b�v�u�b�N����̃��m�N���R�s�[�l�A�s�����C�J�t1973�N9�����k���W�E�g�����l�̕\���k�G�F�R���͓�B�g���Ɍ����Ă��̂́A�ҏW�l�̎O�Y��m���A����G��Ƃ̎R�����B����Ɠ��l�A�u���̎��l�A�����ȁv�Ɗς����Ǝv�����B�l�i�E�j
�a�c���i1936�`2019�j�̒����A�s��������t��ǂ݂��������B�����Ђ̏����i1997�N12��10���j�́A�o�ł���Ă����ɓǂ�ŁA���̌�A�Œ�1��͓ǂ݂������i�ēǁj�A2006�N12��20�����́k�����t�u�b�N�X�l�͏��X�Ŗڂɂ��������ł������ɍw�ǁA�f�㊧�́k�������Ɂl�i2020�N2��25���j�ŁA���̂��юl�ǂ����B�a�c�������̍ő�̓����́A�����Ƃ��Ȃ킿�f�U�C�i�[���G���`����Ƃ����_�ɂ���B�Ƃ��������A�a�c���Ƃ����C���X�g���[�^�[�ł��傤�A�Ƃ������̂ق����傫����������Ȃ��B�{�e�ł́A���̓_���l�������A�G��`���Ȃ����������ƁE�g�����Ɣ�r���Ă݂����B�Ƃ����T���狰�k�����A���҂݂͌��ɑ���̑����ɂ��Č��y�������Ƃ͂Ȃ��悤���i�ʎ��͂��������낤���A��F�W�����قǏd�Ȃ�Ȃ��j�B���́A��[�N���ɂ��ď������q�g�����̑�����i�i135�j�r�ŁA�a�c�ɂ��s�ፑ�t�̕��̖̎ʂɐG��āA�u�a�c���ɕ���ċg�����̕��̖͎ʂ��I�������������A���̗E�C���Z����������킹�Ă��Ȃ��B�����́A�g���̏ё������a�c�{�l�̋Y������҂��邱�Ƃɂ��悤�B�v�Ɨv�]�������A���Ȃ����Ȃ������B�c�O���B

�a�c���s��������k�������Ɂl�t�i�������_�V�ЁA2020�N2��25���j�̃W���P�b�g�Ƒ� �k���\���̕��̑��Ɂu�J�o�[�@�a�c ���v�Ƃ���l
�s��������t�͌������ŏ�����Ă��āA�ǂ݂₷���B�����Ƃ��A����������悤�ɁA���ׂĘa�c�������Ă���̂�������Ȃ��B�܂����̂́A����t���̎G�����ӎ��I�Ɏ�肱��ł���B�Ƃ�����o�ꂷ����p����A�i���Ȃǂł͂Ȃ��j�n�̕��͂ł��܂��������Ă���̂ŁA������ʂ̖{�D�����e�Ղɘa�c�̐��E�ɓ����Ă�����B�{���I�ɁAillustrator���}���Ő�������l�̕��͂Ȃ̂��i���P�j�B�����[���ӏ������Ă����B�i�@�j���̐����͕��ɔł̌f�ڃy�[�W�B
��������ɂ������āA�O�̂��̂�ҏW�҂�����K�v������܂��B�^��͈˗����ł��B�k�c�c�l�^���̓�̓Q���ł��B�k�c�c�l�^���̎O�͑����{�ł��B���Ə����ăc�J�Ɠǂ݂܂��B���Ƃ����͖̂{�̌����̂��Ƃł��B�܂葩���{�Ƃ����͖̂{�̌������m�F���邽�߂ɁA�I�p�����g���ďo���オ��Ɠ����悤�Ɉ��������������{���Ă��炤���́B����͂��Ă���܂���B�^�����{�͂Ƃ肠���������̌��{�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���ۂ̖ړI�͂��ꂾ������Ȃ��A�{�̃T�C�Y�̊m�F�ɂ��Ȃ邵�A�n�[�h�J���@�[�ł悩�����̂��A�\�t�g�J���@�[�̕����悩������Ȃ����A�ƍčl����ޗ��ɂ��Ȃ�̂ŁA���{���{�Ƃ������܂��B�^�ł����ǁA�ڂ��������{���Ƃ�̂͌�����T�C�Y�����邽�߂�������Ȃ���ł��B�������ɂƂ������̊����������ɂ͑�Ȃ�ł��B�{�̑傫���������d�����A���ۂɊ��G�Ƃ��Ď����̎�ɓ`����Ă���B�܂������ɂȂ��Ă��Ȃ��A�`�����̂��̂�����ǁA���̂܂����Ȗ{�̏�ɕ������������A�f�U�C�����ꂽ�J���@�[���������āA�����Ƃ��Đ��ɏo��Ǝv���ƁA������ƃ��N���N���܂��B���̃��N���N�����f�U�C���ɂȂ���悤�ȋC�������ł��ˁB�i65-70�j
�����ƁE�������ق�́s�����C�J�t2003�N9�����k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�Łu��قǂ��\���グ���悤�ɁA�ϋv��������A��������Ƃ����d��������Ƃ����̂��傫���ł��ˁB�u�{���Ă��̂͏d���Ȃ�����v���āA�g������A�悭����������Ă܂����B�����������Ђ̑����{���o���オ��ƁA�܂��d������ŗʂ��ł���B�u���̏d�݂������v���āi�j�B�����āu�O�������Ȃ��A���ǂ��Ȃ��A���N�����Ă����I�ɒu���Ă��邳���Ȃ��{�������v�Ƌg��������������Ă����̂͊o���Ă��܂��B�v�i�����A��l�܃y�[�W�j�ƌ���Ă���B
�@���ꂩ�炱�̃V���[�Y�k�u�ےJ�ˈ��]�W�v�S�Z���i95�N�`96�N�E���Y�t�H�j�l�ł̓}�[�N�����܂����B��]�W�ɂӂ��킵���}�[�N�Ƃ����̂͂ނ��������ł����A������ƔY���Ƀ[���N���b�v���}�[�N�ɂ��܂����B�A���\���W�[��҂ގ��ɂ́A���͂����\���ꂽ�G���̐蔲���₻�̃R�s�[�Ȃǂ��N���b�v�ŗ��߂��Ƃ�����Ǝv���܂��B���邢�͔�]�������ɓ������āA�Ƃ�グ�镶�́A�Q�l�����Ȃǂ����̂悤�ɂ��Ă܂Ƃ߂邩������Ȃ��B�����ЂƂA�ےJ����͖{�ɞx����ꂽ��A�tⳂ�\�����肷�����ɕK�v�ȃy�[�W�Ƀ[���N���b�v���͂��݂܂��B���ڎ��������肵�����Ƃ�����̂ŁA���̂��Ƃ��ڂ��͒m���Ă����B����₱���ŊےJ����̔�]�W�ɂ́A�[���N���b�v����������Ȃ����Ǝv������ł��B�i90�j
�}�����[�ŋg���̌�y�����������́u��ƂȂ�A���ƂȂ�ł���`�������Ă��������܂����B���Ƃ��Ή��F���N���X��\���Ɏg�����w������{���w��n�x�i�S�㎵���A���Z���\���O�N�j�Ȃǂ������ł��ˁB���̃}�[�N���A�g�����u����Ȃ̂ǂ��H�v���Ă��`���ɂȂ����̂ł���B�v�i���O�j�ƌ���Ă���B
�@������̗��h�Ȗ{�ŁA�^�C�g���́u�ԁv�́k���w������̒S�C�̖����B�Y�l�搶�̎����g���܂����B���̎��Ƃ����̂͐搶�̃K���ł̎��ł��B�搶�̓K���ł̎��������̂��ƂĂ����܂�������ł��B�K���łłڂ������̕��W������Ă����B���C�A�E�g���������ŃZ���X���悩�����B��シ���̘b�ł���B���A�K���łƌ����Ă��Ⴂ�l�͂킩��Ȃ����ȁB���ʔłł��ˁB����p�̖��������X���̂悤�Ȃ��̂ɏ悹�ēS�M�ŃK���K���Ə����B�����̂��̕��������X���ɉ����ē_�X�Ő��B�����̏ォ�烍�[���[�ɃC���N�����č���ƁA���ɓ]�ʂ����A�Ƃ��������ł��ˁB�̂͊w�Z�ł͓�����O�̒P���Ȉ�������������B�������Ȃ݂�Ȃ���ō�����B������搶�������K���ł�����͓̂��R�̂��� �������킯�ł����A����ς�l�ɂ���Ă��܂����肪����܂��B�����搶�̓��`�����܂������B���̂��܂��͔M�S���ɂ����̂��Ƃڂ��͎v���Ă܂��B�i125-126�j
�����q�g���������̋H�Q���r�Ƒ肵�āA�g���̖����̐��M�q�u�R�r�̉́v�����{�Ȃǁr���A���o�̒}�����[�J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t32���i1958�N4��30���j�̎��ʂƂƂ��ɏЉ�����Ƃ�����B���͂��ꂪ���ʔłɂ�������������B�N���K����������킩��Ȃ����i�g���ł͂Ȃ����낤�j�A�}�����[�̎Ј��ɂ͋����̒���ŋ��������Ă����҂��������炢������A�Г��V���̎��ʂ�����̂͂���̂��̂��������낤�B�Ƃ��ɁA������w�ɓ�����1975�N�����A�A�W�r���̓K���ō��肾�����B��������Ȃɂ����A���̂��돬���Y��Ƃӂ���Ŏn�߂��������W�s���t�́A�����̏��L���铣�ʔłň�������B�̂��ɓ��l�ƂȂ����̐l�̏����S�q�͎������U�������A���߂ĉ�����Ƃ��ɖ�������Ɣʼn̏W�́A���ʔłł͂Ȃ����M�̎菑���ʼn��̊ȈՈ���������悤�Ɏv���B�s���t�͂`�T�������i�I�j�y�[�W�B�{���p���͘m�����ŁA�\���̓��U�b�N�A�ڎ��̓~���[�Y�R�b�g����F�ς��ŕʒ��ɂ����B�t�@���V�[�y�[�p�[�́A�V�h�̐��E����I�ɚ����A�h�z�b�N�ɔ����o���ɍs�����i�F�{�o�g�̏������u�j�ԃ��[�����v�ɘA��čs���Ă��ꂽ�̂́A����Ȑ܂肩�j�B���{�͑ܒԂ��ŁA�z�`�L�X�ǂ߂̕��Ԃ��̔w�ɂ́A���̐��{�e�[�v��\���Ďd�グ���B�K����́A��������Ǝ��̂ӂ��肾�B���͖ѕM�̏��������������肩���������̂́A�d�M�͏K�������Ƃ��Ȃ��B�ǂ����������̂��A�Ə����ɐu���ƁA�u������^��������v�Ƃ������Ƃ������B���v���o�������A���w������A�w���V���͂�����ʔň���ŁA���������̊G�S�����������́A�l�R�}������������i�K��������j�L��������B���̂���̃A�C�h���͂�������ˎ����i1928�`1989�j���B���̌�A�����1970�N��㔼����������A��˂��u�{�i�I�����𐋂����v���Ƃ����A�V�h�̕S�ݓX�i�ɐ��O���������j�Ŏ�芪�������Ȃ��X�y�[�X�ł�����l�A�ٖقƃT�C���y���𑖂点�Ă����˂̎p�ɏՌ������B���̐l�͂ق�Ƃ��ɂ��̒n��ɑ��݂��Ă����I�@��ɂ���ɂ�������x�̏o��������B
�@���͎R���k���v�l�搶�ŁA�R���搶�ɂ��������͂���̂ł����A�搶���g���f�U�C�i�[�Ȃ̂ŁA�����͎����ł����B�搶�����łɌ̐l�ł��B��e�W�������o����Ƃ��Ă��A��Ԓ�q��Ԓ�q�݂����Ȑl���R�قǂ���̂ŁA�ƂĂ��ڂ��̂Ƃ���ɂ͉���Ă��Ȃ��ł��傤�B�i129�j
�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��25���j�́u����ҁ@���߁v�́A����R�c�̕ҏW�ҁE���j������ł���B���͐�ɋg���̏E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�N5��9���j�ł���������|���Ă���i�N���W�b�g�͂Ȃ����j�A�g���̍���Ƃ����Ă������낤�B
�@�J���@�[�A�\���A���Ԃ��A���ƁA���낢��Ȏ��̑g�ݍ��킹���l����͖̂ʔ�����Ƃł��B�k�c�c�l�^���[�ƁA���̑g�ݍ��킹�̘b�ł����ˁB�J���@�[������̂��鎆�ɂ����ꍇ�A������Ƃ������̕\���̎肴���͂���Ȃ̂��������낤�A������J���ƁA���Ԃ��́c�c�Ƃ����ӂ��ɍl���Ă����܂��B�������Ɠ����ɐF�̂��Ƃ��l����B�v�������Ȃ���荇�킹���ʔ������ʂ��グ�邱�Ƃ����邵�A�J���@�[������܂ł̃����Z�b�g�����ނ̎��œ��ꂵ�ĐF������ς��邱�Ƃ�����Ă݂�B���邢�͐F���O���[�̔Z�W�ƌ��߂āA���̎�ނ����낢��ɂ��Ă݂�A�Ƃ��A�����Ȃ��Ƃ��ł���̂ŁA����������̊y���݂̂ЂƂȂ�ł��B�i169-170�j
��Ƃɂ��ĕ��M�ƁE�����Ƃł�����ѓN�v�́q�F�\�\�g�����̑���r�ɂ́u�k�g���{�́l���܂ЂƂ̓����A�V���̂��̂Ƃ����v���Ȃ����o�̔��I�́u�F�ʁv�ł���B���E�J�o�[�E�\���E���Ԃ��E���A�����Ė{�����B�����ЂƂЂƂ̃}�e�B�G�[���ƐF�������g���łȂ���������Č��W�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȑg�ݍ��킹�ɂȂ��Ă���B�v�i�s�Ö{�X�P�b�`���t�A�|�ЁA2002�N4��10���A��l�O�y�[�W�j�Ƃ���B
�@�ؑ���Y�w�j���[���[�N�̃t���b�N��m���Ă邩���x�i81�N�E�u�k�Ёj�͉f��ƃ~�X�e���[�����Ɋւ���E���`�N�ƃj���[���[�N���̖{�B���҂����\�肵�Ă������Ƃ��������Œ��Ă�������j���[���[�N�Ɋւ����������g���܂����B�^�w�p�ꕨ��x�i89�N�E���Y�t�H�j�͖|�ł��B�p��̓`�d�Ɋւ���{�ł�����A�p�Ă̕��w�≹�y�A�V���ȂǁA���t�ɂ܂�邳�܂��܂Ȃ��̂��A����͎����ŏW�߂āA��\��ł��Ȃ����̂͂���炵�������ŕ`���āA�R���[�W�����܂����B�i180-181�j
�g���@�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB
�����@�����ł���ˁB�����犇�ʂ̒��ɂ͂����Ă���̂����͈��p����Ȃ����̂����Ȃ肠��Ǝv���܂��B
�g���@�����Ȃ̂ˁB��������Ȃ��ƁA�����������A���e�B���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ����ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���B�i������b�q�E�g�����k�Βk�l�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W���g�����l�A��Z�y�[�W�j
�@���ɂ̎d�������鎞�̓J���@�[������S�����܂��B�\���͓���f�U�C�������A���ɖ{�ɂ͌��Ԃ��͂���܂���B���͖{���p�����g���āA�f�U�C�������ʂ̂��̂ł��B�ڂ��͕��ɖ{�̎d���������������Ă��܂����A���ɂ̏ꍇ�͑���������Ƃ͌����ɂ����āA�J���@�[��`���Ƃ��J���@�[���f�U�C������Ƃ������Ă܂��B�u�����Ƒ���v�̂Ƃ���Ō������悤�ɁA�J���@�[�A�\���A���Ԃ��A���A�Ƃ����\���܂�肷�ׂĂ��l����̂��������Ƃ���Ȃ�A���ꂩ��͂͂����킯�ł�����B�i192�j
�@�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�P�s�{���܂��o�āA���ꂪ���ɉ�����܂��B�P�s�{���ڂ������������Ƃ���ƁA���ɂ̕�������Ă���ƌ�����P�[�X�������ł��B��������̎d���ł�����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A���������܂��B�^�k�c�c�l�^�P�s�{�̑������ق��̐l������Ă���̂ɁA���ɂ̈˗����ڂ��̕��ɂ��邱�Ƃ�����܂��B����͋C�������܂��ˁB�ڂ��͂Ȃ�ׂ��P�s�{��S�������f�U�C�i�[�ɕ��ɂ����肢����Ƃ����ł���A�ƌ����悤�ɂ��Ă��܂��B���������悤�ɁA�C���[�W�����ꂳ��Ă�������������낤�Ƃ����̂����R���̈�ł��B���R���̓�́A���̃f�U�C�i�[���ʔ����Ȃ���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�����̎d�����C�ɓ����Ȃ���������ق��̐l�ɗ��̂��ȁA�Ǝv����������Ȃ�����Ȃ��ł����B�ڂ����P�s�{������āA���ɂ̃J���@�[�͕ʂ̐l�A�Ƃ������Ƃ����R����܂��B����ς�C�ɂ��܂�����ˁB���҂ɋC�ɓ����Ă��炦�Ȃ������̂��ȁA�Ƃ��B�����͍l����B�����͂����ƒP���ŁA�P�s�{�ƕ��ɂ̒S���҂�����Ă��āA���ꂼ��D���ȃf�U�C�i�[�ɗ��A�Ƃ��������̂��Ƃ�������܂��ǁB�i196-198�j
�ےJ�ˈ�s�݂݂Â��̖��t�i�������_�ЁA1985�N3��25���j�A���Ȃ킿�P�s�{�̑����͋g�����A�s�݂݂Â��̖��k�������Ɂl�t�i�������_�ЁA1988�N3��10���j�̃W���P�b�g�f�U�C���͘a�c���A�ł���i�q�g�����̑�����i�i102�j�r�Q�Ɓj�B
�@�ʐ^�͎����ŎB��܂��B�J�����͂U�~�U��35�~���������Ă܂��̂ŁB�ނ��������ʐ^�̓v���ɗ��݂܂����A���낭�炢�Ȃ�B���B�X�^�W�I�ŏƖ����āA�Ƃ����悤�Ȗʓ|�Ȃ��Ƃ͂�߂āA�d����̉���ŁA�P���g���̏�ɐ����u���ĎB��܂����B���R���ł��B���̓��̓V�C�ɂ���Đ���̉e���������肵����A�ڂ��肵����A���R�����o�Ă��āA������ʔ����ł��B���������Ă�̂ɉJ���~��ƍ���܂����ǁB�i204�j
�{�T�C�g�ɍڂ��鏑�e�́A��{�I�Ɏ����ŎB�e����B�@�ނ̓f�W�^���J�����B�Ɩ��͎��R���B�܂�̓����D���B�ȑO�͈������^���ʂ���B�邽�߂ɁA�J�������O�r�ɌŒ肵�Đ������o�����Ǝ��݂����A�J�������ĉv�����Ȃ������B���͂����ς�莝���ŎB�e����B�ǂ����Ă��^���ʂ���̏��e���v��Ƃ��́A�t���b�g�x�b�h�X�L���i�̂����b�ɂȂ�B
�@�����Ƃł���Ȑ܋v���q����́w�����b�R�v�̖{�x�i80�N�E�W�p�Е��Ɂj�A�w�����m�[�g�@���{�H�[����x�i91�N�E�W�p�Е��Ɂj�̃J���@�[�f�U�C�����������Ƃ�����܂��B�Ȑ܂��g�D�ꂽ�����Ƃ����A�����ɂ��Ă̖{�Ȃ̂ŁA�ނ����������������o���ꂽ�悤�ȋC���ł������A�Ȑ܂��`�������{�Ɋւ���X�P�b�`���f�U�C�����Ă݂܂����B�i224�j
�Ȑ܋v���q���q�g��������̑���r�Łu���͋g������̎d�������邱�Ƃ���A����҂Ƃ��Ă̓�������͂��߂��B�}�����[�̎Ј��ł���������ɖ��S�_�̎d�����������A�g������Ɍ��Ă����Ȃ������{�A�ӌ��������Ȃ������{�͐�����قǂ����Ȃ��B�N�����g������ɂق߂���ƈ��S�������A�g������̖ڂƂ����֖��ʂ�Ȃ��ƁA�ǂ��ɂ������������������B�v�i�s�����m�[�g�@���{�H�[����k�W�p�Е��Ɂl�t�A�W�p�ЁA1991�N1��25���A�l�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�@�����̒��������邱�Ƃɂ��Ď��₳��邱�Ƃ�����܂��B�����̖{�̏ꍇ�A���Ɉꏊ�����f�U�C������̂��A�Ƃ��A���e���悭�킩���Ă邩����₷�����A�Ƃ��ˁB�ǂ����ł��Ȃ��Ƃ������A�Ƃ�킯�ق��̒��҂̏ꍇ�ƈ��Ȃ���ł����ǁB�a�c�Ƃ������҂̖{��������l�̘a�c�Ƃ��������Ƃ��f�U�C������A�Ƃ����C���ł��傤���B���{�͒��҂��N�ł������Ȃ�ł��B�^����������Ⴄ���Ƃ�����Ƃ���A�����̎��ɂ͂��܂舤�z�̂Ȃ��f�U�C��������A���܂ɂ͂����������Ƃ�����A�Ƃ������Ƃł��傤���B�^������Ƃ��������Ȃ�ł����A���z���Ȃ��Ăǂ��܂ł��������Ă݂����Ȃ邱�Ƃ������āA���ꂪ�l�l�̒����ł͂��ɂ����B����Ă��Ȃ����Ǝv��ꂻ���ŕ|���A�ƌ����܂����A�����Ď�͔����ĂȂ����ǁA����������ۂ�^���₵�Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��ˁB�i235�j
�剪�M�͎��W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j�̑����ɂ��āA�q�F�B�̑���r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u���͂������Č\�ɂȂ����B���̒��d��Ƃ��Ă��̎��W���܂Ƃ߂邱�ƂɁA���ʂƂ��ĂȂ����B����ŁA�ؗF�g�����Ɏ��W�̑�����˗������B�ނ͒}�����[�Β����瑕����肪���Ă��āA�ސE��̍��͂��̐�������Ƃӂ��Ă���B�g������ɑ�����A�Ɗ���Ă���l�X�����Ȃ��Ȃ��B���͉����̈Ӗ��Ŏ��ɂƂ��ċL�O���ׂ��{�̎��ɔނɗ��ނ���ł����B�w���{�x�Ƃ������W�͂���ɋ߂��B�^�g�����͉������Ă��ꂽ�B�����Ԗ͗l�̗A�����̌������Q�ŁA�킴�킴�ّ�ɑ����^��ł���A����v�����̐}�ƂƂ��ɁA�����Ȃ��Ƃ����T���������Ă��ꂽ�B�����{���ł��邱�Ƌ^���Ȃ��Ƃ����v�����������B�^�u�����̖{�Ɏg�������ĂȂ�B�����ł���Ă݂����Ǝv�����̂łȂ����Ⴀ���v�^�g�����͂����������B�����A�����B�^���͍��܂ł��A���[�����A�F�����\�i�A�����ĔV�ȂǁA�h�����Ă�܂ʉ�Ƃ̗F�l�����ɖ{�������Ă���������Ƃ������B�������������������Ƃ�����B�g�����̑���́A�����Ƃ͂܂��ʂ̏��F�����B���͍K�����������B�v�i�s�l���C�̊D�\�\�܁X�G�L�t�A�Ԑ_�ЁA1982�N11��25���A�܌܁`�ܘZ�y�[�W�j�B
�s��������t�̍Ō�̏͂́q18 �o�[�R�[�h�ɂ��ār�B����܂ł̈��̌|�k�Ƃ͂����ĕς���āA�����ƁE�a�c�͂����ŏ��Ђ̊O������߂��铬�m�Ɖ����B�����炭�A���̏͂�ǂ�ł��炤���߂ɁA���҂͑��o���̘b���ɂ������Ȃ���I���Ă����̂��B�����Ȃ܂������I�ɏЉ��̂ł͂Ȃ��A�a�c�ɑ����āA�ǂ����ŏI�͑S�̂�ǂ�Œ��҂̈ӂ�����ł��������A�Ƃ��������B
�{��19�y�[�W�ł��G��Ă���s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�A1993�N7��15���j�́A�{�����S�y�[�W�J���[�̐}�Œ��S�̍�i�W�ŁA����Ζ{���̎o���тł����i���Q�j�B���̎o����͕ʛl�ŁA���t�y�[�W�ɂ͓����̃W���P�b�g�̕\���P��}�łƂ��Čf���A�L���v�V�����Ɂu1993�N6���E���u���|�[�g�E�a��12�ǂ�n�[�h�v�Ƃ���iChinese boxes !�j�B�ڂ̊o�߂�悤�ȟ������C�ł���B�������琄������ɁA�������s���_�ł̘a�c�̑S�����i�����߂��Ă���̂ł͂���܂����B��������A�ǂ����Ă����p���Ă����������ڂ�����B�^�C�g���͂Ȃ��āA������{�ɂ��āB
�u������̖{���肪���邱�Ƃ͑����͂Ȃ��B������̖{�͂����Ă����������A�����Ȗ{�̑���̈˗��͂��܂�Ȃ��̂��B�����������A�����̐l�̎�ɓn�鏑���ɊW����̂��ւ�����Ă鎖���ł��邪�A����ƂƂ��Ă��ґ�Ȗ{���ɂ������B�^������������̖{�̑�햡���ґɂ���킯�ł͂Ȃ��B��ɂƂ��Ă���{���ɂ��ǂ���܂ł̎菇�������������߁A���̊ԂɕK�v�ȃf�U�C���I�v�f���f�U�C�i�[������A�ǎ҂��y���܂���̂ł���B�v�i�k�m���u���Ȃ��l�j�B�u�f�U�C�i�[������A�ǎ҂��y���܂���v�u�f�U�C���I�v�f�v�����A�a�c����̗v�����낤�B
�����ɂ́A���o�����i���������Ėڎ����j�m���u�����Ȃ��B�a�c������{�́A�}�ł����Č�炵�߂�A�Ƃ����F���̋ɒv�I�@�Ȃ��{�e�̂��̒i���ł́A���u���|�[�g�Ђ̃n�E�X���[���i�p���p��j�ɍ��킹�āu����v�Ƃ������A��N�̘a�c���A�����A�u�����v����p����B

�a�c������ɂȂ镽��Дn�Y�i1900�`1986�j�̒��̏��e�@�o�T�F�s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�A1993�N7��15���j �k����Дn�Y�͘a�c���̊x���B���Ȃ킿�g�������a�c�F�b�̒���������̂Ɠ������B�l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�����i�P�s�{�j�́q���Ƃ����r�ɂ́A�{�����s�̌o�܂�{���̎d�l�E����̎w��Ȃǂ��Ԃ��Ă���i���ɔł́q���Ƃ����r�́k�����t�u�b�N�X�l�łŏ������߂�ꂽ���̂P�j�B�����q���Ƃ����r�̑O���������B
�@�ڂ��͑����̐��Ƃł͂���܂���̂ŁA�w��������x�ȂǂƂ����^�C�g���̖{���o���̂͌����܂����悤�ȋC�����܂��B����ǂ������̎d������D���Ȃ��̂ł�����A�����Ђ̘a�C������v�����������Ƃ��́A���Łu���܂��傤�v�ƌ����Ă��܂��܂����B
�@����Řa�C�������Ɍ�肨�낵�����邱�Ƃɂ����̂ł����A��ǂ��ɂ��܂肽������̂��Ƃ͂���ׂ�܂���B�f���I�ɏ������b�����āA���Lj�N������܂����B
�@����͎d���̘b�ł�����A���p�ꂪ��������o�Ă��܂��B�ҏW�҂̘a�C����ɂ͂Ȃ��݂̌��t����Ȃ̂Ŗ��͂Ȃ��̂ł����A�z�肷��ǎ҂͐��Ƃł͂Ȃ��A��ʂ̖{�D���̕��X�ł��B���̂��Ƃ��l���đ啝�ɉ��M�������ʁA��肨�낵�̕������A�������낵�̕����������Ȃ�܂����B
�@���̊Ԃ������̎d�������Ă����܂�����A�b�𑫂����肷��C�^�`������������A�܂Ƃ߂����̂���d�����镔��������Ƃ�����A���̑��������A���Ԃ͂���ɐL�т܂����B�h�������������Ă����������a�C����Ɋ��ӂ��܂��B�i�����A��y�[�W�j
�����Ђ̕ҏW�S���E�a�C���́A�g���������̑S�_�������q���{���i�_�r�V���[�Y�̒S���҂ł�����B1993�N�ɏo���s�a�c�� ����̖{�t�i���u���|�[�g�j�̃N���W�b�g�����邩����A�a�c���������������Ђ̖{�͍����N�Y�s�R���O���s���t�i1981�N12��10���j�������i�����̑���q���Ƃ����ɂ����ā\�\���܁A�Ȃ��R���O�Ȃ̂��r�ɂ��A�ҏW�S�����N�Ȃ̂�������Ă��Ȃ��j�B���Ȃ݂ɁA�s�a�c�� ����̖{�t���o�������u���|�[�g�̖{�͓����Ɉ���������Ȃ��B���������́A���̑z���ł���B�s�a�c�� ����̖{�t����ɂ����a�C����́A�e�n�M�`�Ɂs����k�`�t�i�}�����[�A1986�j������ȏ�i�������A�������肨�낵�j�A�a�c���ɂ������ɂ��ďc���Ɍ���Ă�����Ĉ���̖{�ɂ������A�ƍl�����̂ł͂Ȃ����B������߂Ă����������A�e�������������ƁE�g�����ɐu���Ă��������������₪�]�����悬�邱�Ƃ͂Ȃ��������낤���B�s��������t�́q16 �����̑����r��ǂނ��тɁA���͂����v���Ă��܂��B
�i���Q�j�@�s�a�c�� ����̖{�t�ɐ旧���āA�s����p���[�h�k�a�c���C���X�g���[�V�����W�l�t�i�����p�ЁA1982�N12��10���j�����邪�A�s��������t�ł͌��y����Ă��Ȃ��B�s����p���[�h�t�̂����܂��ɂ́A�u���̊��ł́A�{�̕\���̂��߂ɕ`�����C���X�g���[�V�������W�߂��B����F�ō��邱�Ƃ�O��Ƃ�����W�Ȃ̂ŁA���^����G������F�ŕ`�������̂���ł���B�قƂ�ǂ̏ꍇ�A��������i�K�ł���ɐF�����B�������ŏ����璅�F�����ĕ`���ꍇ���������A���������G�͂����ł͏Ȃ����B�܂��A�����Ɍf�ڂ���̂́A���悪�ڂ��̎苖�Ɏc���Ă�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����Ƃ��Ďd�オ�������̂ɂ́A�����Ă��F�����Ă��邩��ł���B����F�ŕ`�����G�Ɉ���ŐF������ꍇ�́A�F�w��Ƃ�������g���B���̈�̂������A���̃y�[�W�Ɏ������B�����͎O���F�̃p�[�Z���e�[�W�ŁA���ꂪ�J���@�[�̐F�ɂȂ�킯�ł���B�v�Ƃ����i���Ŏn�܂�2000�����܂�̖���̕��͂������āA�a�c���̑����_�͂���ɐs����i�g�����ɂ���Ɠ������̕��͂���������A�ǂ�ȂɍD���������낤�B�S����ҏW�҂́A�����炭�g���Ɏ��M���˗��������Ƃ��낤�B�����A�g���͎U���������ہA���g�����l�ƋK�肵�āA�����ɂ��Ď��M���邱�Ƃ�����ɋւ����Ƃ����v���Ȃ��j�B�a�c���́A1982�N�́s����p���[�h�t�A1993�N�́s�a�c�� ����̖{�t�A1997�N�́s��������t�A�ƒ����Ɏv���̗̈���g���A�����ƂƂ��Ă̎��Ȃ�illustrate���邱�Ƃɐ��������B
�s���ꎞ��t�i1999�j�A�s���㑕��t�i2003�j�A�s�����`�t�i2004�j�ق��A�����Ɋւ��鏑�Ђ𐔑������M���Ă���P�c�����̐V���s�q�������{�r�̕������\�\����S�\�N�̌n���t�iBook&Design�A2020�N4��25���j���o���B�ً}���Ԑ錾�̂��ƁA�Ï��X��}���ق͌����x�݂ŁA�����k���ōs���錗���ɐV�����X�͂Ȃ��i�I�j�A����͂Ƃ����{���s���{�̌Ö{���t��sAmazon�t�ŕ��F���邵���Ȃ��B�{���̊��s�́A�ѓN�v����̃u���O�i2020�N4��21���j���q�q�������{�r�̕������r�i�������ߖ{�I�j�Œm��A�sAmazon�t�ɒ��������B���������Ō����璼������Ă����̂ŁA�����̂����ǂ�������ǂ����B���̎�̖{�̏ꍇ�A���͂܂��ڎ��ƍ������n�ǂ��Ă���A�q�͂��߂Ɂr��q���Ƃ����r�ɖڂ�ʂ��āA�{���ւƐi�ށB�{�������ɂ́q��v�Q�l�����r�A�q�l�����X�g�r�i�g���̍����������s�q�g�����r�l�ƍ�i�t�Ɍf�����j�A�q���Ж������r�͂��邪�A�q�l�������r�͂Ȃ��B�����ŁA��ɂ���ċg�����̍������삷��i�ŏ��̈�s�A�s�g�������W�t�͖{���́q���Ж������r�ɂ�����́j�B
�g�������W�c�c�c�c�c�c�c�c052, 234
�g�����c�c�c�c�c�c�c�c077, 078, 080, 081, 175, 176, 177, 178, 182, 187, 291
���̂����u078, 080�v�ɊY������{���͂������B
�u�g�����i�}�����[�Ζ�����\���N�ɋy�j�̑���_�ɐڂ�������������ǂ��A�g���͎���̎p�����ڂ炩�ɂ��Ă��Ȃ��B�g���̏��������҂Ƃ��Ēm���鏬�ш�Y���A�g���͂���Βk�̏�ŁA����Ƃ������̂͂��܂ł��O���̂��Ȃ����̂��D�܂����Ƃ�������|�̔������c���Ă���݂̂ŁA�܂Ƃ܂����_�͎c���Ă��Ȃ��͂����ƁA���ɂ��ċ������Ă��ꂽ���Ƃ�����B�Ȃ��A�g���͒����V���̎�ނɉ����ē��l�̎�|�̔��������Ă���i��͎Q�Ɓj�B�v
���Ȃ݂ɁA079�͐}�łƂ��̐����̃y�[�W�Łi�{���̑g�݂��݂͂Ȃ��j�A���̉ӏ����u077-081�v�Ƃ���̂͂��߂����B����ɁA����͎�������������Ȃ����A�u077-081�v���ƁA078�i����ɂ�079�j��080�̖{�����E����݂���Ƃ��A�y�[�W���Ƃ������ŗ��������Ȃ��B�ϑ��I��������Ȃ����A�����̓A�i���O�ł͂Ȃ��A�f�W�^���ł��������B�����āA���Ɉ����u176, 177�v�̋L�q�����A�P�c�ɂ��g���_�̔����ł���B
�@���ŁA���I����̎������͂���u���ꎍ�h�v�̒S����Ƃ��Đ�㎍�ɑN��Ȍ�䊂����邵���g�����i�����`��Z�j�̑���ɒ��ڂ������B�g���͔s���Ԃ��Ȃ��l�Z�N�ɉ��n�F�l�Y�̒m�����������Ƃ��_�@�ƂȂ��đ���̌������n�߂Ă������A�܈�N���Ђ̒}�����[�ɂ����āA���Њ��s���̑���𗂌ܓ�N����p���I�Ɏ肪����悤�ɂȂ����B����͊�g���X��݂������[�Ƌ��ʂ���A�M�B�n�Ō��炵�������ȏo�ŘH������Ă��������������\���ɋz�����������ŁA�Ǝ��̍H�v���d�ˍ��킹���d�����Ƃ����悤�B�ʂɂ����ƁA������u�Г�����v�̗��O�̌p���Ɣ��W���A�}�����[�̊Ŕł��镶�w�S�W���̂𒆐S�ɋ���A�����������̂��B��㎵�Z�N��́w���e���O�Y�S�W�x�S�\�ꊪ�m���G�n�͂��̂ЂƂB��A�̎d�����]�����ĂсA��N�͑��Ђ���̈˗����ӂ����B
�@�g���͎���ɂ����Đ₦���鎩�ȍX�V������ɉۂ����B���g�̎��W�������܂߁A����ɂ����ẮA�ΏƓI�ɂ�邬�Ȃ������̔��w�����Ƃ��������Ƃ������[���B��т��čd���ȋ��������̖����̏��̂ɂ��莚�ނ�z�u���A�����ɏ����ȃJ�b�g��z���������̃X�^�C���B���E�Ώ̌`�̍\���@����Ԃł��������B�����āA�V���v��������߂Ȃ�����A�g���Ǝ��̃e�C�X�g���������B����������ƁA����ł��Ȃ��Ǝ��̎��͂����Ȃ��Ă���̂��g�����̐^�����Ȃ̂ł���B
�@�u�v����ɂˁA�ڂ��̒��ɂ͇������̂��Ȃ��{���A������݂̂Ȃ��������Ƃ����C��������{�Ƃ��Ă����v
�@�g���͑����@���đ��������Ȃ������B����ł������V���̃C���^�r���[�ɓ������ۂ̉E�̌��t�ɂ��̎p���͏W��邾�낤�i�����u�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����v��㎵�Z�N�l�����j�B
080�ŗ\������Ă����V���L�����A�����J���[���G�́q���l����̌n���̐��V�ȗ���r���s���e���O�Y�S�W�t���A���ׂĂ͂����ɋA������B�܂��ɁA�g�����������u�q�������{�r�̕������v�ɁA������ׂ������ƌ������Ƃ��ł���B
�{���́u���{�̑��{�������x���Ă�������ƁA���ҁA�ҏW�҂�̎d���ł��ǂ���{�ߑ㑕��j�̌���Łv���Ӑ}�������������āA���{�E�����ɂ͍אS�̒��ӂ������Ă���B���̂����ŁA�C�Â������Ƃ��_�B�܂��A�����̃J���[���G�i16�y�[�W�����āA���������[���j�́s������t�̒��҂��ԂƂ���̂́A�M�}���������B�����L���v�V�����������Ƃ��A�R�s�[���y�[�X�g�������ƒ����킷��邱�Ƃ�����̂ŁA�Ƃ₩���������`���ł͂Ȃ��B�����ЂƂB�����o���͊������S�`�b�N�̂ł��ȁE�J�i���A���`�b�N�̂̍��A�����A��g���X�Łs�L�����t��s���{�ÓT���{��n�t����|�������{�Ƃ̓��X�P�v�Ɉ˂�ƁA�S�`�ƃA���`�̍��A�͊���������Ȃ���������̈╗�Łi�V���̏����o���ł悭���������j�A�S�`�b�N�œ��ꂷ��̂��{�炵���B�d�q�g�ł̖{���̏ꍇ�A�������Ȃ��킯�͂Ȃ��̂ŁA���́u���A�v�͊m�M�Ƃ��낤�B�Ȃ��A���t���́m�q�������{�r�̕��������{�d�l�n�i���^�E�����E���ނ��琬��j�ɁA�����o���Ɋւ���L�ڂ͂Ȃ��B
�k2020�N10��31���NjL�l
���ƂŋC�����āA���ʂ邩�ȂƎv�����Ƃ͂܂܂��邪�A�{���̊��s���L�O�����W��������̂������̂́A���Ȃ���ɍ����������B����10�����{�A�u�g�����~����v�ŃC���^�[�l�b�g�̋L�����������Ă�����A�s�u�q�������{�r�̕������v�W – Events - Book & Design�t���������B�����ɂ́A�u���Ёw�q�������{�r�̕������@����S�\�N�̌n���x�̊��s���L�O���A�{���ŏЉ�ꂽ���Ђ̒����璘�ҏ������Ж�40�_��W���������܂��B�v�Ƃ���B����Book&Design�i�����s�䓌���2-1-14 3F�j�A�����2020�N7��24���i���j�j�`26���i���j��7��31���i���j�`8��2���i���j�ŁA12-18���I�[�v���A7��31���̂�14-20���I�[�v���B�܂���̐V�^�R���i�E�B���X�����\�h��̂��߁A�I�[�v�j���O�p�[�e�B�A�g�[�N�C�x���g�͍s�킸�A�W���݂̂̊J�ÂƂ̂��Ƃ��B���O�ɒm���Ă�����A�K����o�����āA������͑S���ݘL�\��̉P�c����ɂ��ڂɂ�����i�s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t���s���L�O����g�[�N�C�x���g�ȗ�������A���N�Ԃ肾�낤�j�A���j���̌��t�������Ă��낢�남�b���ł����̂ɁA�Ɖ���܂��B�Ȃ��A�s�u�������{�̕������v�W���I�����܂����t�ɂ́q3. ���l����ƒ��Ҏ����A�ҏW�҂ɂ�鑕��̌n���r�̃J�e�S���[�̈���Ƃ��āA������{�̂������������s���e���O�Y�S�W�t�i��2�����j�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B�W������ςĂ�������A�q�g�����N���r�ɋL�ڂ����Ƃ��낾���A�����������Ȃ��̂ŁA���̍��ɒNjL����ɂƂǂ߂�B�N���̑��e�Ȃ�A�����Ȃ낤�B�\�\2020�N7��24������8��2���ɂ����āA�P�c�����s�q�������{�r�̕������\�\����S�\�N�̌n���t�iBook&Design�A2020�N4��25���j�̊��s���L�O�����W����q�u�q�������{�r�̕������v�W�r�i�����s�䓌���Book&Design�ɂāj���J����A�q3. ���l����ƒ��Ҏ����A�ҏW�҂ɂ�鑕��̌n���r�̃J�e�S���[�̈���Ƃ��āA�����ł����y����Ă���P�c���������́s���e���O�Y�S�W�t���W�����ꂽ�B
�g�����͓��m���ɍݐЂ��Ă���1948�i���a��\�O�j�N�̓��L�ɁA���̂悤�ɏ����Ă���B�u�\�\�l���@�Ηj�@���c���j�搶�̓n���ɍs����Ă��Ȃ������B��������̃��G�����ƗV�B���ւ���̒�ɂ͉J���Ђ��т��Ƃӂ��Ă���B���ߋ߂��搶�͖߂�ꂽ�̂ʼnΔ���������Řb�������B�a���ɏ@���X�̐搶�͂₳�����C�i������B�s�_����b�t�̈�ł͑q�c��Y�̈⑰�ɑ�����Ƃ̂��ƁB�����ƂȂ������b�����������������B���G��������Ă����B�v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�B�u���G�����v�͖��c���j�i1875�`1962�j�̑����̔��}�q�B�q�c��Y�i1906�`47�j�͖����w�ҁB�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�́u���܂��܂ȏo�����v�̍��ŁA�剪�ɖ���Ă���ɏڂ�������Ă���B
�剪�@���Ƃ����̍��ɁA���c���j����Ƃ��K�c���F����Ƃ��A�����Ȑl�̂Ƃ��֍s���Ă邯�ǁA����݂͂�ȏo�ŎЂ̎Ј��Ƃ��čs���Ă�́B
�g���@�����A����͂����������Ƃ��������B�������[�̓X�|���T�[���N���X�`����������A������o�ŕ��ɃN���X�`�����̂��̂��������Ă���킯���B�킪�В��͂���Ɏア�B����ŃN���X�`�������̂��ǂ�ǂ�o���Ă����B�œ����^�炪�܂����߂āA���̎��ɂڂ������߂��k�g�����������[��ގЂ����̂�1946�N8���l�B�Ƃ��낪��C�̎���ŁA���̐E�Ƃ�T���Ȃ��Ŏ��߂�����������ς��B���̎��Ƃ̓�J�����炢���A�Z�M�̉Ƃɐ��b�ɂȂ�Ȃ������Ă�����A����ς肠���̒n���������ˁB�s���Ƃ��낪�Ȃ��āA�̓d�C�قɓ����āA�ٓ���H�����̂��o���Ă�ȁB�V�����Ȃ��玟�̐E��T���Ă���A��J�����炢�o�������A�����^�炪���łɓ��m���Ƃ��������ȏo�ŎЂɓ����Ă��āA�ڂ��ɗ��Ȃ����Ƃ�����ŁA�����̎В��ɉ�ɂ�������A�ǂ������킯���ꔭ�ŏA�E���Ă킯�k�g�������m���ɓ��Ђ����̂�1946�N10���A�ގЂ����̂�1951�N�l�B
�剪�@����͉��E�ɂ������̂����B
�g���@�����B����͓��m���A�������A��m�o�łƂ��������ȁA�O�̎Ж����������o�ŎЂȂB�������Ƃ����̂͋g���M�q���w���̊K���x�Ƃ����J��L�̖{�i���j���o���āA���ꂩ�瓌�m���Ƃ����̂͊w�p�I�Ȗ{���o���Ă����킯���B������K�c���F�̃J�����́w���{�剤���u�x�Ƃ��A���e�͂킩��Ȃ��Ă��ҏW�S���Ƃ��čK�c����̂Ƃ��֍s���Ă��킯�B���ꂩ����c����́w���ޔ_����b�x�Ƃ����̂�������B�ŁA�ڂ��͖��c����̂���֒ʂ��āA���܂����݂Ȗ��c����ɉ���Ă���킯�B�������̒m�炸�ŁA�����Ԃ���ׂ肵�����̂��B�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�A��܁Z�y�[�W�j
�����́s�_����b�t�A�Θb���́s���ޔ_����b�t�́A���c���j���s���ޔ_����b�t�i�M�Z�����A1937�j�𓌗m����1947�N�ɍĊ������s���ޔ_����b�t���w���B���m���ɂ��ŏI�Łs���ޔ_����b�k����Łl�t�Ĕł̏㊪�i1948�N9��30���j����ѓ��E�����i���N12��15���j�̎d�l�́A�ꔪ�Z�~����~�����[�g���E�㊪����y�[�W�A�����O�l�y�[�W�i�\���t�j�E�㐻�����B
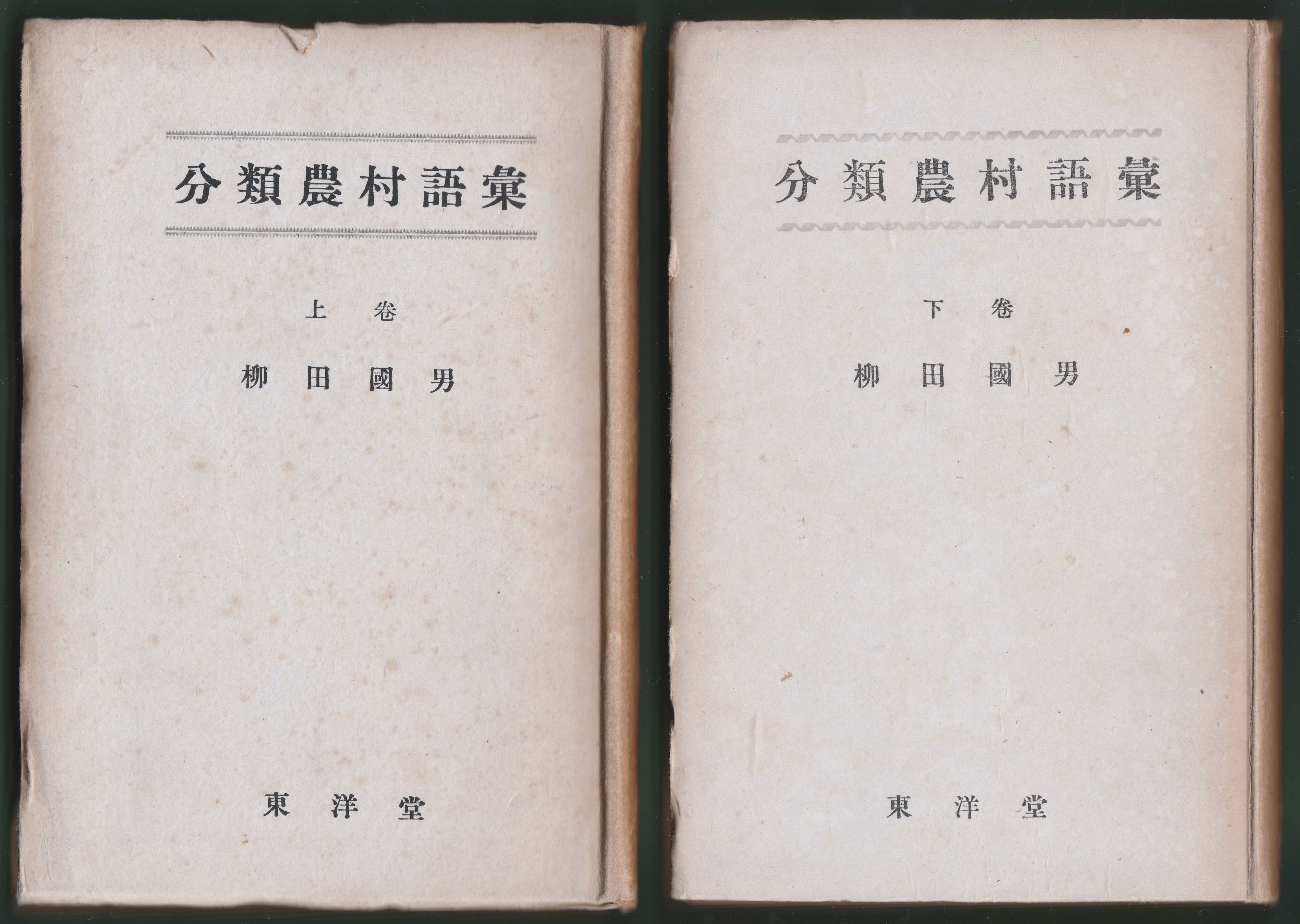 �@
�@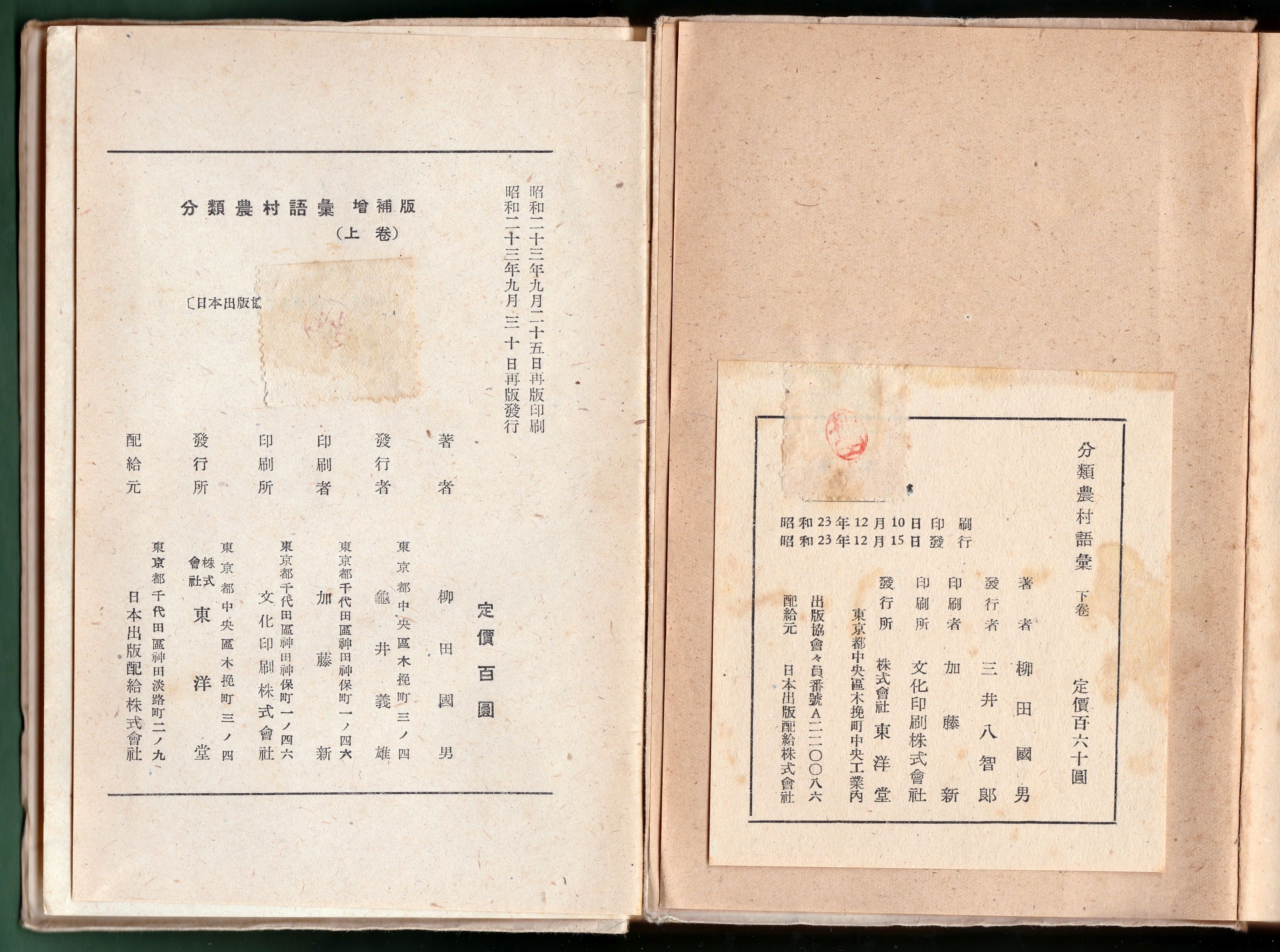
���c���j�s���ޔ_����b�k����Łl�㊪�t�i���m���A�ĔŁF1948�N9��30���j�Ɠ��E�����i1948�N12��15���j�̕\���i���j�Ɠ��E���t�i�E�j�@�㊪�E�����Ƃ������Җ��̋L�ڂ͂Ȃ��B
�s���ޔ_����b�k����Łl�㊪�t�i���m���A1947�N5��30���j�����Ɏ��߂�ꂽ���c���j�̕M�ɂȂ�q����ʼn���r�́A�s���c���j�S�W�k��22���l�t�i�}�����[�A2010�N9��25���j�̎l����`�l��Z�y�[�W�Ɏ��^����Ă���B���̕����ɂ́u���a����N�l���^���c���j�v�ƋL����Ă���A���c����q����ʼn���r�̌��e���Ƃ����̂́A�g����������Ȃ��B���c�S�W�̕ҏW�ψ��E���c�x�p�ɂ��s���ޔ_����b�t�́q���r�������B�\�\�Ȃ������㉺���́A1977�N10��30���A�������s������e��{�����s����Ă��邪�A���t�ɂ́u�������{�v�̔��s�N���������邾���ŁA���s���E���m���̖��͂Ȃ��A�����I�Ɍ��ׂ�����ƌ��킴������Ȃ��B�\�\�����ł��炩���ߒf���Ă����A���m������͏㊪�����a22�N5��30���Ɨ�23�N9��30���̓�x�A���������a23�N12��15���Ɉ�x�����o�Ă���悤�Łi��������}���ق̏����{���ȏ�ɐs����j�A�����������������3���Ƃ��A�q���r���́u�X�ɊȈՂȐ��{�v�ł͂Ȃ������B�����̊��s���㊪�̏�������1�N���ȏ�o���Ă���̂́A�㉺�����ɂ킽��q�����r���쐬����̂Ɏ�Ԃǂ������߂��B
�����c���j���w���ޔ_����b�x�́A�M�Z�����珺�a���N�i���O���j��������ɔ��s���ꂽ�B�\������ђ����ɂ���u�M�Z�����ҁv�������Ȃ�ւ��Ȃ̂��A���ł́u�����v�ɂ͂��̌��y���Ȃ��A�u����ʼn���v�Ɂu�M�Z�����̍D�ӂɂ�Đ琔�S�������s���A��Ƃ��Č����̉���ɓǂ�ł���͂��Ƃ����ׂɁA��ʂւ̔Еz�͍ŏ�����͂��Ȃ��̂ł����v�Ƃ������������邾���ł���B�������Ƃ��ĐM�Z�����V��������Ђ��������Ă���B�u�����v�Ɓu�ڎ��v�̊ԂɁA�u���̖{�̕Ҏ[�Ɋւ��ẮA���c�@�l�[����̉����ċ���B䢂ɖ��L���Ċ��ӂ̈ӂ�\����v�Ƃ����ӎ�������B
�@�u���ޔ_����b�ڎ��v�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�A��b���ނ̍��ڂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@�@�@��@��Z��
�@�@�@��@�c�ゲ�����
�@�@�@�O�@��d���ƕc���邵
�@�@�@�l�@�t�c�ł�
�@�@�@�܁@�c�n����
�@�@�@�Z�@���̎�
�@�@�@���@��|
�@�@�@���@�c�A��
�@�@�@��@�ゲ�����
�@�@��Z�@�c���
�@�@���@�c���c�~��
�@�@���@���c�A
�@�@��O�@������~��
�@�@��l�@�c�l�Ɠc�A��
�@�@��܁@�ԓc�A
�@�@��Z�@��݂čs��
�@�@�ꎵ�@����萅�܂͂�
�@�@�ꔪ�@���ǂЈ�F��
�@�@���@�ĎR�q
�@�@��Z�@�|��s��
�@�@���@���
�@�@���@�����
�@�@��O�@����
�@�@��l�@���グ��グ
�@�@��܁@��d��
�@�@��Z�@�P����U����
�@�@�@�N�v����
�@�@�@�H�Y��
�@�@���@�c����
�@�@�O�Z�@�n�_�~��
�@�@�O��@�y�n���p�̒i�K
�@�@�O��@����s���Ɩ���
�@�@�O�O�@�앨���
�@�@�O�l�@�_���
�@�@�O�܁@���n����
�@�@�O�Z�@�{�\
�@�����ɎO��łɂ킽���āu���ޔ_����b�����v���t����Ă���B
�@�w���ޔ_����b�@����Łx�́A���m������A�㊪�����a���N�i���l���j�܌��O�Z���A���������a��O�N�i���l���j��k��l�ܓ��ɔ��s���ꂽ�B����ł̊��s�ɂ������ď㊪�̊����ɒlj����ꂽ�̂��A���c���j�̏����̂���u����ʼn���v�ł���B����ɂ��Ə��ł̊��s��O�N�̂����ɒlj������������āA���c�͑���ł̕K�v�������n�߂邪�A�����Ŏ�����鎞�Ԃ��Ȃ��A�q�c��Y�ɂ܂Ƃ߂Ă��炤���Ƃɂ����̂����a��Z�N�i���l��j�t�����炾�����Ƃ����B�w�Y�ē��L�x�i�{�S�W���Z�����^�j�̏��a���N�i���l�l�j��ꌎ�O���̍��Ɂu�ߌ�q�c�N���A�u���ޔ_����b����v�e����B���m���̈ӌ������T�ɗt���A�Â��蒟�ނ�݂��ēǂ܂��ށv�Ƃ���B�����������ł̗��ʂ��������������ɑ����������A�푈�ő����������āu�Ö{�s��ł͖@�O�Ȓ��{���Ёv�ƂȂ��Ă��邽�߂ɁA���́u�o�ŊE�̍ň��̏v�ł͂�����������ł������ꂽ�̂�������Ȃ��B����ł̍Ĕł��X�ɊȈՂȐ��{�Ŕ��s���ꂽ�̂́A�㊪�����a��O�N�㌎�O�Z���A���������a��O�N���ܓ��ł���B
�@�w���ޔ_����b�x�̑q�c��Y�ɂ��Љ�Ɣ�]���A�w���ԓ`���x��O����i���a���N��Z���j�Ɍf�ڂ���Ă���B�u���ޓ��{������b�̑�O�e�Ƃ����ӂׂ����́v�Ə������̂́A���c���j�̏������u�Y��K���v�Ɓu�����K���v���āu��O���Ƃ��Ă��̕��ޔ_����b���o���v�Ƃ����̂Ɋ�Â��B
�@�u�����v�́A���̌�b�W���̎��݂��ŏ��Ɂw�_�ƌo�ό����x�Ƃ����G���Ō\�����Ɂu�n�s�v�܂ŘA�ڂ������ƂɐG��Ă���B�_�ƌo�ϊw��̋@�֎��w�_�ƌo�ό����x�ł́u�_����b�v�̘A�ڂ́A��㊪��ꍆ�i���a���N�k���O�O�l�ꌎ�j������ꊪ��ꍆ�i���a��Z�N�k���O�܁l�ꌎ�j�܂ŁA�f���I�Ɍ܉�ɂ킽���Čf�ڂ��ꂽ�B����́u�_����b�v�́u���v�������A�{�S�W���㊪�Ɏ��^����Ă���B��{�́A����ł́u����ʼn���v�Ƃ����ɍĘ^���ꂽ�u���ŕ��ޔ_����b�����v���A��O�Z���́u����W�v�Ɏ��^�����B�i�����A�����Z�`�������y�[�W�j
���R�̂��Ƃ��A�{���̌�b�̑唼�͈��Ɋ֘A����B�{���`���́q��@��Z���r�́u�^�i�I���V�v�u�^�i�h�L�v�u�^�i�t�e�v�u�l�c�P�v�u�^�i���v�u�X�a�_�n���v�u�^�i�L�v�u�^�i�C�P�T���v�u�^�l���o���q�v�u�^�i�C�P�T���q�v��10���ڂ���Ȃ�B���{�Ƃ��āu�^�i�I���V�v�̖{�����f���悤�B�i�V���ɉ��߂��j
�@�^�i�I���V�@��~��������ǂ��A�_���̎n�܂�̈ӂɗp�����B�_�����e���o���ƁA�^�i�I���V�Ɋ|����ȂǂƂ��Ӂi���h�_����j�B���Ȃǂ̗�̓^�l�I���V��c������j�Ɛ����A�d��̃^�i�I���V�Ƃ͕ʂɋ����Ă�邪�i��������W�j�B���������Ƃ��p�������̂ł��āA�g�Ђ킯�ł͂Ȃ��̂��Ǝv�ӁB�܂����̃^�i�I���V�̓��ɂ́A�ȑO���̕��������Ɍ����邱�Ƃ́A�O�͂̐U���Ŗ���d�������͓��ɓ��炸�A�����C�̂��̂������炸�A�Ⴕ����ɐG��T�Ζ������ł��܂ӂ���ƈ��ЁA�����k�S�Ȃǂɂ͓c�ɖ�����������͌����Đl�𔑂߂Ă͂Ȃ�ʁA���߂�ƕc�������~�܂�ƈ��āA�V�����ޑ��̂���i���������p���A��j���Ƃ�����M�͂��B�i�㊪�A��y�[�W�j
����A�{�������́q�O�Z�@�{�\�r�́u�g�h�R�v�u�A�g�g�v�u�R�i�T�}�v�u�V���T�}�v�u�{�{�T�}�v�u�q���K�q�R�v�u�V�W�v�u���S�v�u�P�S���X�~�v�u�C�R�v�u�C�u���v�u�c�{�~�R���v�u�t�i���X�~�v�u�`�J���O�n�v�u�I�S�J�X�v�u���J�G�R�v�u�e���R�v�u�I���v�u�w�q���}���v�u�V�P�R�v�u�r���E�V�v�u�]�E�v�u�h�L���E�v�u�d�V���v�u���c�S�v�u�g�E�g�R�r�C���v�u�m�r�v�u�R�u�V�v�u�A���h���v�u�R�o�\�_�e�v�u�����_�v�u�G�K�v�u�n�V�v�u�~�i�K�v�u���_�i�v�u�G���v�u�R�m���v�u�C���R�v�u�q�L�q���q�v�u���g�q�v�u���h�~�m�L�v�u�A�Q�X�v�u�R�{�G�v�u�R�����v�u�}�u�V�����v�u�R�e�v�u���}�A�Q�v�u�X�N���v�u�V�N�v�u�i�~�v�u���]�v�u�}�{�V�C�n�q�v�u�g�c�J�v�u�J�q�R�o�i�v�u���g�q�C�n�q�v�u���h�~�C�n�q�v�u�^�i�A�Q�v�u�R�^�}�Q�v�u�J�q�R�r�}�`�v�u�I�V���R�E�v�u�R�J�E���}�c���v�u�n�L�^�e�_���S�v�u�R�N�\�C�n�q�v�u�R�O�\�u���q�v��64���ڂ���Ȃ�B�u�V���T�}�v�̖{�����f���悤�B
�@�V���T�}�@�\���V���n�����̓I�S�n���ȂǁT�����Ӂi���������W�j�B���k�ɍO���m��ꂽ�I�V���T�}������ŁA�\�_�̈ӂł���i�����A��y�[�W�j
���݂ɁA�����́s���ޔ_����b�t�i�M�Z�����A1937�N7��1���j�ɂ�����L�ڂ�����ƁA�O�҂�
�@�^�i�I���V�@��~��������ǂ��A�_���̎n�܂�̈ӂɗp�����B�_�����e���o���ƁA�^�i�I���V�Ɋ|����ȂǂƂ��Ӂi���h�_����j�B
�Ɩ`�������ŁA�V���v���ł���B��҂ɂ������Ắu�V���T�}�v�̍��ڎ��̂��Ȃ��B���āA�q���r�́u����ł̍Ĕł��X�ɊȈՂȐ��{�Ŕ��s���ꂽ�̂́A�㊪�����a��O�N�㌎�O�Z���A���������a��O�N���ܓ��ł���v�ɒ��ڂ���ƁA�g�������L��1948�i���a��\�O�j�N12��14���̂��̓��A���c��K�����̂́s���ޔ_����b�k����Łl�����t�̍Ĕł̌��{��͂��邽�߂������悤�Ɏv����B���Ȃ݂ɁA�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�i�}�����[�A7���F1975�N7��5���k���ŁF1969�N3��15���l�j�́q�N���r�i���c�v�q�쐻�N�����̑����Q�Ƃ��ē����ҏW�����쐻�������́j�́u���a��\�O�N�i���l���j�@���\�l�v�̍��́u�ꌎ�A��u���n�߂ɍ����̍T�Ƃ��ďo�ȁB�A�_�Ж{���ݗ�����N�L�O�|�\�ՂŁu�_�ЂƐM�v���u���B�܌��A�������Њ�����Ђ̏��w���w����Ȍ��苳�ȏ��̊ďC������B�Z���A�w���͉����x���b���Ђ���A�����A�w���̂������x���V���Ђ���A�����A�w�����̘b�x����g���X����A�\�ꌎ�A�w�k���I�s�x�����ƔV���{�Ђ��炻�ꂼ�ꊧ�s�B�\�A�w�m�@����ƂȂ����B�v�i�����A�l�܁Z�y�[�W�j�ł���B����������Ƌg���͂��̓��A���{�w�m�@����ƂȂ���c�ɂ��j�����q�ׂ�ƁA�g�ӑ��Z�ƂȂ������c�ɉ������đ����Ɏ��������̂�������Ȃ��B�t������A�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�͋g�����̎�ɂȂ鑕���ŁA�����炭���̗B��̖��c���j�̒����ł���i���m���Łs���ޔ_����b�t��ҏW���������̋g���́A�܂��Ɩ��ł͑�����S�����Ă��Ȃ��j�B�g�����������s������{���{��n�k�S97���E�ʍ�1�l�t�i�}�����[�A1968�N8���`73�N9���j�̎d�l�́u�e���E�㐻�E�N���X���E�\�����v�B��10��z�{�́s���c���j�W�t�́A��ꔪ�~��l���~�����[�g���E�l�Z��y�[�W�i���̂����ʒ��̖{���ƌ��G�k���ҏё��ʐ^�l���e�꒚�j�B�{����8�|31���l�~29�s2�i�g�B�P���v�Z�ŁA400���l�ߌ��e�p��1000�����B����͐����ЁA���{�͗�ؐ��{���ł����i�����j�B
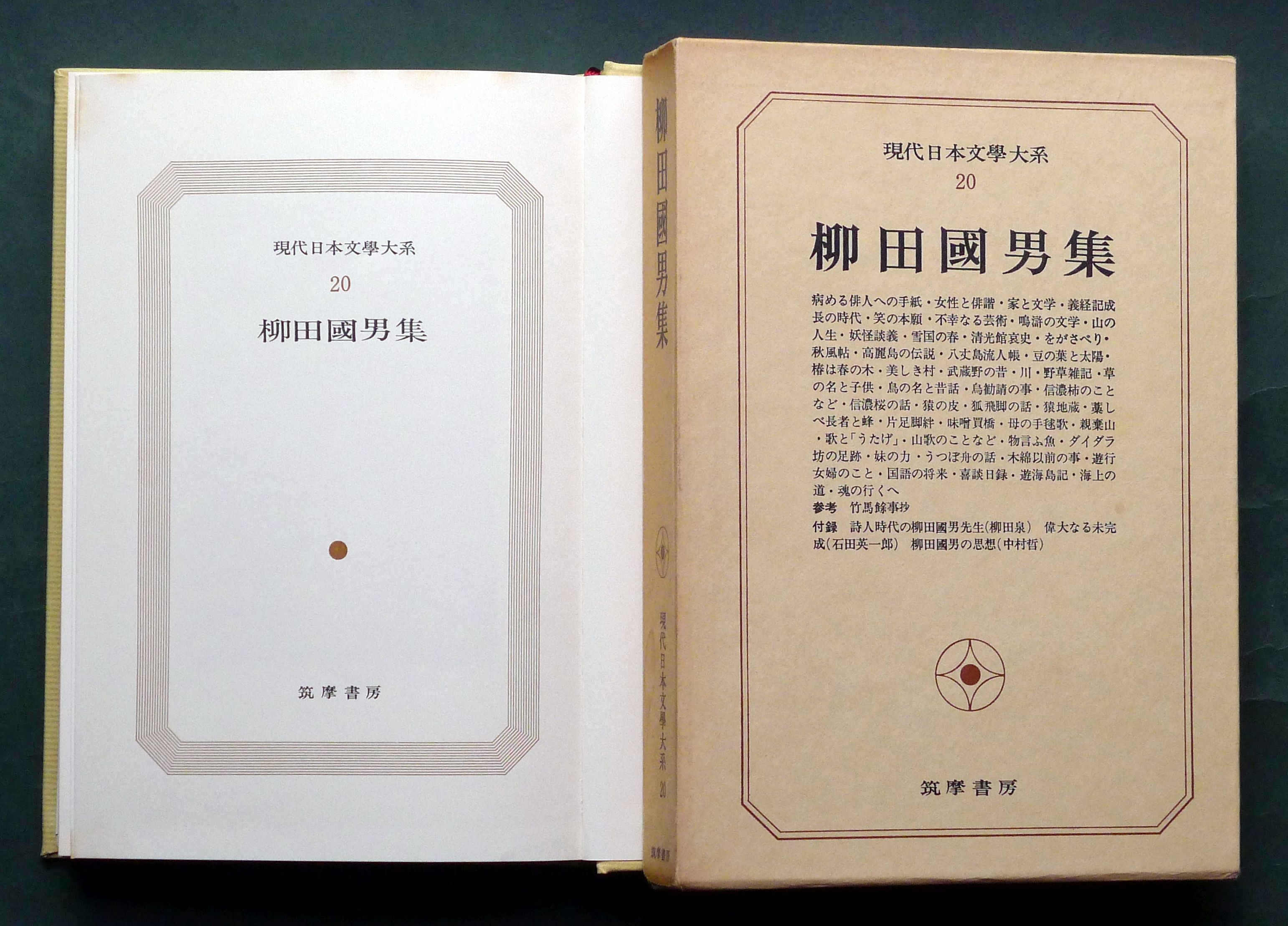
�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�i�}�����[�A7���F1975�N7��5���k���ŁF1969�N3��15���l�j�̖{���Ɠ\���k�����F�g�����l
�����ł������c�͑����̓��{���w�S�W�Ɏ��^����Ă���u��Ɓv�����A�k������{���{��n�l�͂��̐�삯�Ƃ����ׂ����̂ŁA���c���̑S�W�ł���s��{ ���c���j�W�k�S31���E�ʊ�5�l�t�i1962�N1���`71�N5���j���o�����}�����[�̖ʖږ��@������̂�����B�ӔN�̋g�����́A���c���j�́s���앨��t�i������1910�N�j�\�\�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�ɂ͎��߂��Ă��Ȃ��B����𗠕t����悤�ɁA���c���g�́s���앨��t�����܂�]�����Ă��Ȃ������Ƃ����i�������j�\�\�Ɍ��y���Ă���B
�@���͒x�܂��Ȃ���A�w�Î��L�x����c���j�w���앨��x��Γc�p��Y�w�����Y�̕�x�Ȃǂ́u�_�b�v��u���ԓ`���v�ɁA�S�䂩���悤�ɂȂ����B���̂����Ƃ��V�������W�w��ʁx�́A�����ƃt���C�U�[�w���}�сx�̌����Ɉ˂��āA�������Ă���̂��B�i�q���H���߂���f�́r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z�܃y�[�W�j
�g�������s���}�сt�ɐe���ޑf�n�́A��シ���ɒS���������c���j�s���ޔ_����b�t�i���m���j�ɂ������Ƃ����悤�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@���������s�̒��J��L�̒����Ƃ��āi���Ȃ��Ƃ��j����2�_�͊m�������A�o���Ƃ���������}���قɂ͏�������Ă��Ȃ��B�܂��AWikipedia�̒��J��L�́q��ȍ�i�r�Ƃ��������ɂ��L�ڂ��Ȃ��B
�s����̉J�t�i1947�j
�s���@�ً��{�t�i1948�j�\�\���J��L�̒Z�я����W�B�W���q���@�ً��{�r�������ɁA�q�؋�̖V�r�q�S�������r�q�]�ˏ�̌�r�q�y�킴�ܕ��q�r�q�א쌌�B���r�q�l�a��ɑ��Y�r�̑S7�т����߂�B�㐻���\���A��l�Z�y�[�W�B�\����́m�u���n�����B���{�����邩����A�g�����{���Ɋւ�����`�Ղ͂Ȃ��B�Ȃ����J��L�s���@�ً��{�t�i�������j�̔��s��1948�N12��15���́A��������c���j�s���ޔ_����b�k����Łl�����t�i���m���j�̔��s���ł�����B������͑O�҂���������A��҂���������ňقȂ���̂́A�������E���m���Ƃ����ݒn�͓����s������ؔҒ�3-4�̒����H�ƃr���Łi���s�҂͑O�҂����������Y�A��҂��O�䔪�q�Y�j�A�܂������Z���Ђł���B
�@
�@�@
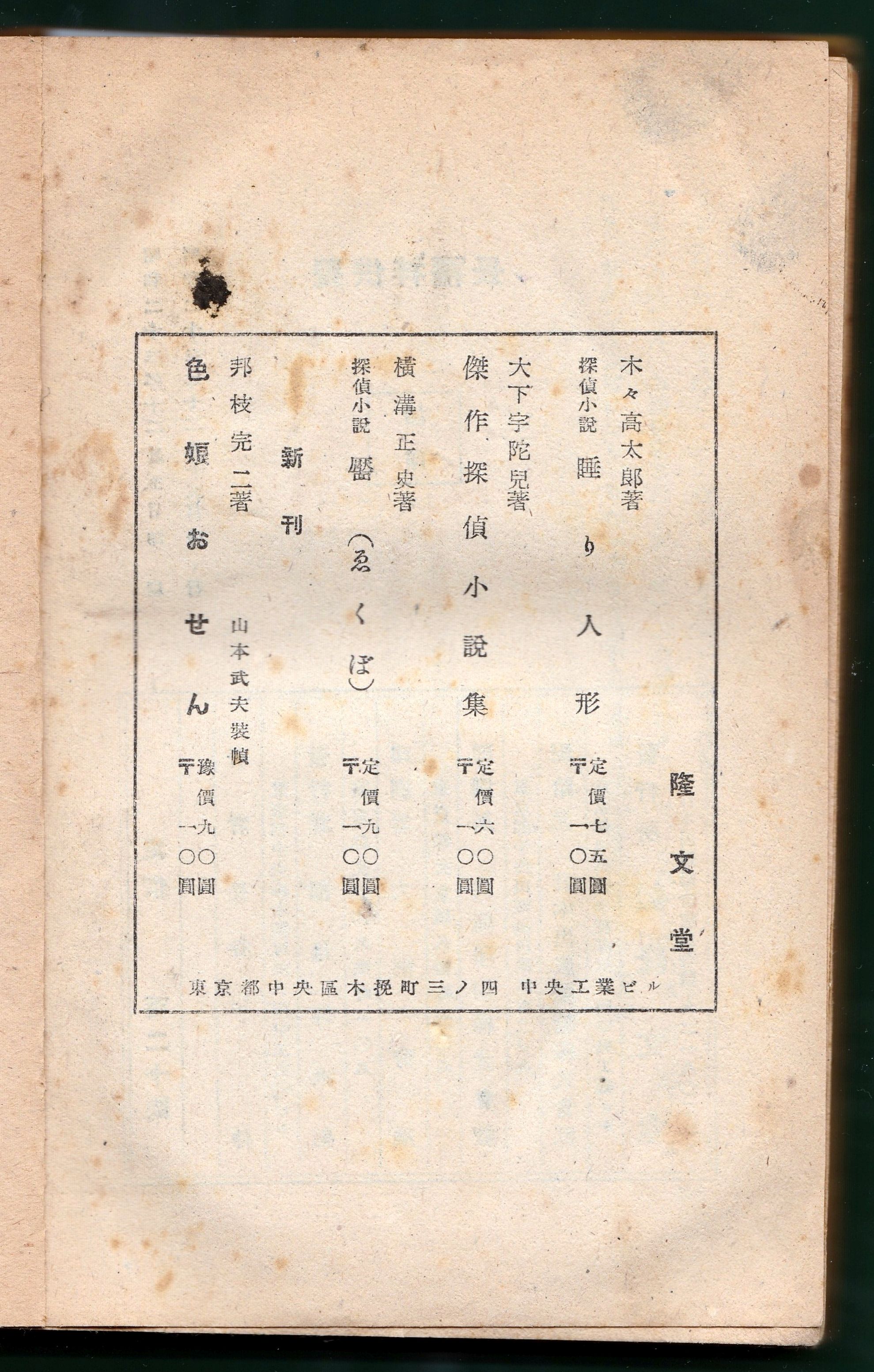
���J��L�s���@�ً��{�t�i�������A1948�N12��15���j�̕\���ɂ͌ォ��\��ꂽ���̐Ղ��Ƃ���ǂ���c���Ă���k���\���ɏ��������Łu������v�ƃT�C��������A���l��ŗL���Ȏu�������i1907�`80�j�̑���Ǝv����l�i���j�Ɠ��E�{���i���j�Ɠ��E���t���L���i�E�j
�����@�����A1945�N����1948�N�ɂ����ė����������s�������ڂ��f���Ă������B�܂��s���{�̌Ö{���t�f�ڂ́A���Ȃ킿�����̎��v��������́B�E�F�G�������āA��������������O���w��i���Ǝv���邱���̏��Ђ́A���Ђ̏o�ŕ��Ƃ������Ƃŋg�������ڂ�ʂ�����������Ȃ����A�ڍׂ͕s���ł���B
�@���}�j�Y�s�k������l���炵����t�i1945�j
�A���}�j�Y�s�h��̓�t�i1945�j
�B�X�����Y�s�k�T�㏬���l�E�l��c�t�i�k2���l1947�j
�C�y�t���s�����̋S�t�i1946�j
�D�I��e���s�k����T�㏬���l�d��̑D�t�i1947�j
�E�k�����ҁs�S���\�\���̒��̏��M�t�i1947�j
�F�t�����q�s���X�J�X�\�\�K���H���Ǝ��͂̐l�X�t�i1947�j
�G�˖{�o�s�h�{�ƕa�l�H�t�i1948�j
�H�]�n�C�s�R�̖��@������鍑�k�ĔŁl�t�i1948�j
�I��m��Y�s�k���і`�����N�����l����t�i1948�j
�J�剺�F�Ɏ��s����T�㏬���W�t�i1948�j
���͏�L����������������}���ُ����{�̃��X�g�B���������X�i���s������Ѝ]���O�m�O��A���t���L���ɂ́u��� �������v�Ƃ����\����������j�Ɨ������Ƃ̊W�͖��ڂ����A���҂͏o�ł̌X���������ԈقȂ�B�g���͑O�E�̍������[�ł̕ҏW�Ҏ���ɑ����Ԏq��S���������Ƃ����邩��A���́s���Ɍ��Ӂt�i1947�N11��15���A���s�҂͐��������Y�j�͏ڂ������ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B
�E�c���[��s���Ս��Y�ł̉���t�i1946�j
�E�\���`��s�ƒ��w��T�\�\���ۊŌ�̔錍�t�i1947�j
�E�����Ԏq�s���Ɍ��Ӂt�i1947�j
�E�\���`��s�ƒ��w��T�t�i1947�j
�E���J�����s�v����{���j�k�㊪�l�t�i1947�j
�E���J�����s�v����{���j�k�����l�t�i1947�j
�E���J�����s�v��V���{�j�k�㊪�l�t�i1947�j
�E���J�����s�v�𐼗m���j�k�S�l�t�i1947�j
�E���J�����s�V�����u���m�j�k�㊪�l�t�i1947�j
�E���J�����s�������E���j�k�S�l�t�i���������X�A1947�j
�E���q�C��s�}�C�N�]�k�k�ĔŁl�t�i1948�j
�E�g���M�q�s�k���я����l���̊K���t�i�k3�Łl1948�j
�E�M�}����s�F��������t�i1948�j
�E��㌓�Y�s�h�{�̏펯�\�\�N�ɂ��킩��h�{�wA�EB�EC�c�H�����������ւ̎w�j�k�������� 6�Łl�t�i1948�j
�g�����͗������̕ʉ�ЁE���m����1946�N10������1951�N�i3�����j�܂ł�4�N���̂������ݐЂ��Ă���B���̊Ԃ̓��m���i����ї������j�̏o�ŕ��̏ڍׂ́A����̒����E�����ɘւ������B
�i�����j�@�s���c���j�W�k������{���{��n20�l�t�̖ڎ����������ƂŁA���e�Љ�ɑウ��B�Ȃ��A�m���u���͏ȗ����A�O�t�E�{���E��t�̂܂Ƃ܂�Œǂ����B���Ȃ݂Ɏ������߂ĐG�ꂽ���c�̕��͂́A�����w�Z�̌��㍑��̋��ȏ��i�}�����[���s�j�Ɏ��^���ꂽ�q�ؖȈȑO�̎��r�����A���܍ēǂ��Ă݂�ƁA�s�����W�t�������č]�˂̐l�l�ƖؖȂ̊W���������u��v��ǂL�����Ȃ��B���ȏ��ł͏ȗ����ꂽ�̂��A�P�Ɏ����Y�ꂽ�����Ȃ̂��B
�����ʐ^�^�M��
�a�߂�o�l�ւ̎莆�^�����Ɣo�~�^�Ƃƕ��w�^�`�o�L�����̎���^�̖{��^�s�K�Ȃ�|�p�^�j���̕��w�^�R�̐l���^�d���k�`�^�ፑ�̏t�^�����و��j�^�������ׂ�^�H�����^���퓇�̓`���^���䓇���l���^���̗t�Ƒ��z�^�ւ͏t�̖^���������^������̐́^��^�쑐�G�L�^���̖��Ǝq���^���̖��Ɛ̘b�^�G�����̎��^�M�Z�`�̂��ƂȂǁ^�M�Z���̘b�^���̔�^�ϔ�r�̘b�^���n���^�m���ג��҂ƖI�^�Б��r�J�^���X�����^��̎�{�́^�e���R�^�̂Ɓu�������v�^�R�̂̂��ƂȂǁ^�����Ӌ��^�_�C�_���V�̑��Ձ^���̗́^���ڏM�̘b�^�ؖȈȑO�̎��^�V�s���w�̂��Ɓ^����̏����^��k���^�^�V�C���L�^�C��̓��^���̍s���ց^�k�Q�l�l�|�n�P����
�k�t�^�l���l����̖��c���j�搶�@���c��^�̑�Ȃ関�����@�Γc�p��Y�^���c���j�̎v�z�@�����N
�N��
�܂�����́q�ҏW��L�r�́A�k������{���{��n�l�̑�10��z�{���s���c���j�W�t�ł��邱�Ƃ�搂��Ă���A���������Ă���B�Ō�̈ꕶ�ȂǁA�s���앨��t�����^����Ă��Ȃ����Ƃ��l�����킹��ƁA�܂��Ƃɋ����[���B
�@����͕��w�S�W�Ƃ��Ăِ͈F�Ȗ��c���j�̓o��ł��B���c�w�Ƃ������j�[�N�Ȋw��̌n���������Ă����c���j��m��l�ŁA�N����A�ƕ���ԑ܂�ƌ����A����ɂ������ނ�m��l�͑����͂Ȃ��悤�ł��B�������A���̕��w�I�����������č��j�͊w��̐��E�ɑ傫�ȑ��Ղ����邵���̂ł��B���Ȃ킿�A�ނ̎d���́A����Ӗ��œ��{�l�̎��I�n���̖͂L�������@�肨���������̂Ƃ͂����Ȃ��ł��傤���B�i�����q����10�r�A���y�[�W�j
�i�������j�@�s���c���j�\�\���{�I�v�l�̉\���t�i���X�A1996�j�̒��ҁE���J���ؐl�́A�ߑ���{�l�̎��`�̔����Ƃ������c�́s�̋����\�N�t�i������1959�N�j�́q����r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�k�c�c�l�{���ɂ͐������̗F�l��m�l�Ƃ̌𗬂��L����Ă��邪�A�����ɖ��̌����Ȃ��l�тƂ�����B�k�c�c�l
�@���g�̒���ɂ��Ă��������Ƃ�������B���Ƃ������A���c�̖����w�����̎n���_�Ɉʒu�Â�����w���앨��x�̖��������Ȃ��B����̍��X�m�������n��P�m������n�ɂ��Ă����Ȃ��B���c���g�́w���앨��x�����܂�]�����Ă��Ȃ��������߂ł���B�{������͂��̂悤�ȔӔN�̖��c���g�̎��ȕ]�����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂ł���B�i���c���j�s�̋����\�N�k�u�k�Њw�p���Ɂl�t�A�u�k�ЁA2016�N11��10���A�܁Z���y�[�W�j
�q�g�����̑�����i�r�́A2018�N8�����̎��_�ŁA�V�e�E�k�NjL�l�Ƃ��Ɏ��M��Ƃ��x�~�����B2003�N1��31���́i1�j����2017�N11��30���́i135�j�܂ł̋L���́A�g��������|����������i�{�E���肵�Ȃ��玷�M���Ă��������߁A���s���ł��Ȃ���A���Җ��⏑���A�o�ŎЖ���50�����ł��Ȃ��B���́q�g�����̑�����i�r�S�̖̂ڎ��������ƂȂ�̂��s�g���������t���q�W�@������i�ژ^�r�ŁA����͑�����i�̊��s���ɕ��ׂĂ���B����A�q�g�����̑�����i�r�ɂ́A�����̓s���ŋg����������i�ȊO�̏��e���A�K�v�ŏ��������A�f���Ă���i���Ƃ��A�g�������������������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�ɑ���A����N�v�����̓����̏��ł�����ł���j�B�����͑O�L�́q�W�@������i�ژ^�r�ɏo�Ă��Ȃ������A�{����ǂ݁A���e���ς�܂ł́A���̎�|���肳���ǂޑ��ɗ^�����Ȃ��B�����ŁA���Җ���50�����i�������҂ł́A����ɏ������j�ɕ��ׂ�������p�ӂ����B�������N���b�N����ƁA�Y�����鏑�e���f�ڂ����L���ɔ�Ԃ悤�Ƀ����N�����̂ŁA�g��������������i�Ɣ�r������A���҂�ΏƂ����肵�Ȃ���{�������ǂ݂���������Ƃ��肪�����B
��
�E�����ܕ��ɔŁs�H�열�V��S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1986�N9��24���k25���F2014�N7��30���l�j�̃W���P�b�g�k�����F�������A����F�đq�ĉ��N�q�����̌܈ʂ̖ʁr�l��
�E��[�N���s��H�߁k���y�Łl�t�i�}�����[�A1952�N3��15���k�u�ܔŁv�F1952�N5��8���l�j�̕\���k���ӁE����F���ьÜl�l�Ɠ��s��H�߁E�R�̉��k������{����I�l�t�i���A1952�N9��25���j�̕\���k�����F���n�F�l�Y�l��
�E�O�D�s�Y���s���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l���蓡�������t�i�}�����[�A1983�N1��30���j�̔��ƕ\���Ɠ��E�{����
�E���������s�����P�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N7��10���j�̃W���P�b�g�ƕ\����
�E�i�c�����ďC����s�k�ւ̊G��{�܁t�i�����p�ЁA1986�N10��12���j�̖{����
�E�[����s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N10��25���j�̃W���P�b�g�ƕ\����
�E�ےJ�ˈ��s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�̖{���ƃW���P�b�g�k�����������l��
�E�g�c�����s������{���w�j�t�i�}�����[�A1980�N11��10����13���k���ŁF1965�N10��10���l�j�̖{���ƃW���P�b�g���̑�
�E�Ό�����E�S��V�閾�I�A�X�c������s�O�i�����G��W�t�i�������A1972�N7��7���j�`���ł��q�ׂ��悤�ɁA����A����I�ȋL���̃A�b�v���[�h�͊��҂ł��Ȃ����A�V���ȋg���������{��֘A���Ђ���肵���ꍇ�́A���̂Ǖ��͂Ȃ�摜�Ȃ���������āA�{�y�[�W�̕�Ԃɓw�߂����B���́A�����̏����ɂ܂܌����鏑�e�̐����s�������P�������Ǝv���A���ꂪ�u�\���v�Ȃ̂��A�u�W���P�b�g�v�i�u�J�o�[�v�̌�́u�\���v�ƕ���킵���̂Ŏg�p���Ȃ��j�Ȃ̂��A�u���v�Ȃ̂��\�\�ꍇ�ɂ���ẮA�u�@�B���v�Ȃ̂��A�u�g�����v�Ȃ̂��A�u�\���v�Ȃ̂��\�\�A���ǂ����炢�ɏ��������肾�������A�������ď��e�̃L���v�V�������ĕ��ׂĂ݂�ƁA���܂����̊�������B�܂����āA�������ł�������邱�ƂŁA���x���グ�Ă��������B
�S�~��Y�ҏW�́s�����C�J�t2003�N9�����́k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�������B���ɂƂ��ē��W�̊j�ƂȂ�L���́A�����܂ł��Ȃ��������ق�k�C���^�����[�l�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�ł���B�S�̕M�ɂȂ�ɈႢ�Ȃ������́q�ҏW��L�r�ɂ͂�������B
�@���X�ɂ�DTP�Z�@���Ƒ���̃J�^���O�����ӂ�Ă��邪�A���[�U�[�Ə���҂����̐��E�͋������B���E�����ƃC���[�W�ւƂ��₷���k������邱�ƂɁA���Ɣ�]�ƂŒ�R�ł��Ȃ����ƍl�����B�������A���w��i���܂��A���̉����\���Ƃ��Ă̏����̕������ɂ���āA���݂�ۏ���Ă����̂ł͂Ȃ��������B�d�q�ʐM�Z�p�̕��y�ɂ���āA�����͑��`�̔}�̂ł͂Ȃ��Ȃ����B���Ĉ���o�ŋZ�p�̋����ƂƂ��ɏ����Ɏ���đ����������́A���܂�d�q�������̂��肻�߂̕\���E�o�͌`�Ԃł����Ȃ����̂悤���B���͂⏑���͂ǂ̂悤�ɂ������ł͂��肦�Ȃ��B�����炱���A����͗��j�������̂ڂ��Č�����A���݂ɂ����Ď��s����˂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ�����l�Ԃ͕����̎艞���ƒ�R�Ȃ��ɐ������ɂł��Ȃ��̂�����B(j.k.)�i�����A��l�Z�y�[�W�j
���̎��_���A�s�����C�J�t�̕ҏW�������Ă̂����s�A�C�f�A idea�t367���q���W�E���{�I���^�i���w�� 1945-1969 ���E�����E�C���r�i�������V���ЁA2014�N10��10���j���s�A�C�f�A idea�t368���q���W�E���{�I���^�i���_�� 1970-1994 �ے�`�̃u�b�N�f�U�C���r�i���A2014�N12��10���j���т��Ă��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���̏o���_�ɂ��Ȃ����{���W�̖ڋʂƂ�������̂��A�g�����ƂƂ��ɒ}�����[�̏��Б�����S�����������ق�̏،��������B�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�́A����܂łɂ����́s�q�g�����r�́u�{�v�t�Ŋ��x�ƂȂ����p�E�Љ�Ă������A����͂����̋g����������i�𗣂�āA�����ł͐G��Ă��Ȃ��ӏ����������Ă��������B
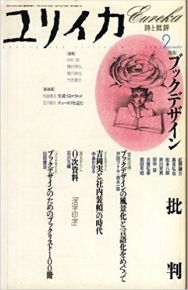
�s�����C�J�t2003�N9�����k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̕\��
�ŏ��ɁA�k���W���u�b�N�f�U�C���ᔻ�l�̒������ق�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�̌f�ڎʐ^�ɕt����ꂽ�L���v�V�������f����B������̏��Ђ��A���łɖ{�T�C�g�ɏ��e���f���A�����E���{�ɂ��Č��y�E�Љ�Ă���B
�}�����[���Љ��i�w�}�����[�̎O�\�N�x���j
�w���Ɏ��S�W�x�i��5���j��12���@�}�����[�A1968�N�A��
�w�����Y�S�W�x��1���@�}�����[�A1975�N�A��
�w������{���w��n�x��41���@�}�����[�A1972�N�A��
�g�����w�y���F��x�@�}�����[�A1987�N�A�J�o�[
�w�}�����[�̎O�\�N�x�@�}�����[�A1970�N�A��
�w�}�����[�}�����ژ^1940-1990�x�@�}�����[�A1991�N�A�J�o�[
�ȉ��A�C���^�����[�{���L���̗v����f����B�����̋�̓I������������A��茾�t���������t�ɕς����̂ŁA�ǎ҂͂��ЂƂ����{�ɂ��Ė��ǂ��ꂽ���B�i�������́i�@�j���̐����́A�����̓����f�ڃy�[�W�ł���B�Ȃ��A�C���^�����[�{���ł́u����v�̕\�L�����A�{�T�C�g�̗p���ɍ��킹�āu�����v�ƋL�����B
��
�E�������ق�̓��Г����i1966�N�j�A�}�����[�ɂ͓��ɖ{�̑��������镔�����������킯�ł͂Ȃ��A�g�����i�����̓��БO�́A�L��������`�ۂ̑O�g���̕����j�͑S�W�ҏW���ŕҏW�҂̎d���̈�Ƃ��đ��������Ă����B���̌�A�g���͂o�q���s�����܁t�i1971�N�n���j�̕ҏW�҂Ƃ��ĉc�ƕ��Ɉٓ������̂ł͂Ȃ����B�c�ƕ��ł���͂�ҏW�E����̎d�������Ă����̂��Ǝv���B
�E�������z�����ꂽ��`�ۂ̎�Ȏd���́A���Ђ̔̔����i������ˌ�����ޗ��S�ʁ\�\���X�ɒu���Ă��炤���e���{��`���V��A�V���E�G���L���̍쐬�������B�܂�A�O�i�����L���i�T�����c�j��A���Ђ⑼�Ђ̎G���֏o�e����L���̍쐬�E�Ǘ��Ȃǂł���B�G���̍L���́A���Ƃ��Ώc�O�L���i�^�e�T���j�����ƁA�����}�̂ɍ��킹�Ĕ��������Ďg�����肷�邪�A�����������̂�����Ă����B�܂��A��`�ۂɂ͓ǎҌW�̂悤�Ȗ�ڂ��������B
�E�g���́A�T�����c�����̐���ƕҏW�҂̗v�]�����܂��������Ȃ���A�]���̔������킸�A�召�̃R���g���X�g����������Ƃ����u�T�����c�̔��w�v�������āA���̂���{�̂悤�ȍL����������B�i137�`138�j
�E���l�̋g�������������Ă��邱�Ƃ́A���Ђ���܂ł͒m��Ȃ������B
�E�����̓��Г����A�}�����[�̏o�ŕ��͎Г����������������B�Г��ő�����S�����Ă����̂́A�g�����A�Ȑ܋v���q�i1967�N�ɓƗ��j�̂ق��ɂ́A��`�ۂ̋g�c���������B1970�N����̌��Ԋ��s�_����30�_�O��B�������u�S�W�̒}���v�ƌĂ�Ă����悤�ɁA���w�S�W��l�S�W�A�V���[�Y�����������B�ŏ��̌`�����������茈�߂Ă��܂��A�����͈ꂩ��l����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�Г��ł͋g���E�g�c�E������3�l�ő������Ă����B�̂��ɉ��������Y�i1972�N���Ёj�A���q�i���ДN�����ځj����������B�g���炵���A���邢�͓Ȑ܁A�g�c�炵���Ƃ��������̓�������������̂́A���͓���B��Ђ̒��ł̓����̎d���ŁA�l�̍�i�ł͂Ȃ����炾���A�g���̑����͉��ƂȂ��킩��B�s�Z�{ �{�V�����S�W�t�s�����Y�S�W�t�s���e���O�Y�S�W�t�s�����֑S�W�t�Ȃǂ��g���̑������B
�E�����̓��Ќサ�炭�́A�莚�͎ʐA���g�킸�����̐�������\�肵�Ă�������A�������ǂ��g�ނ��Ƃ������Ƃ��A�����̊�{�̂ЂƂ������B����\������ȂǑ����̕t�������������ہA���ʂ̈�����ł͂Ȃ��Ȃ������p�̏�����ꍆ�̌��o��������������Ƒ����Ă��Ȃ��̂ŁA��c��^��g���̊��������̓s�x��{�������Ă����i�g���́A���W�̖{����g�ނƂ��͓��Ɍ܍����������p���Ă����j�B�����̑莚�ɂ́A���������̂܂܂̑傫���Ŏg���̂ł͂Ȃ��A�g��E�k�����Ďg���Ă����B�R�s�[�@�̕��y�O�ŁA������ʐ^�}�ł̊g��E�k���́A�g���[�V���O�E�y�[�p�[��f�ނɂ����đΊp���������Ƃ������@����ʓI�������B�g���X�R�[�v�́A���̌ジ�����o���Ă���ݒu���ꂽ���A�g���͎g���Ă��Ȃ������Ǝv���B�����Ŕʼn��������̂ł͂Ȃ��A�����Ԃ������w�莆��ʼn����Ɏ����Ă����āA������Ƃ����ʼn����쐬���Ă�������B���̌�A���g���̎������A�Ƃ�킯���̏����E�ꍆ���g���͂��߂��B
�E�f�U�C����Ƃ̕K�{�A�C�e���́A�ʔň���̊������{���ƒ|���̐������i��ڂ̕������j�ƌv�Z�ڂŁi�d��͍����������j�A���Ƃ���������̎d���̊�{�ƂȂ鐔�l��������B�g���͒����̌v�Z�ڂ��u�ʔ��������ˁv�Ə������ŁA�g��Ȃ������B�g���ɂ͎ʐ^���g�������������܂�Ȃ��A�����|�C���g�Ő▭�ɃJ�b�g�i������e���O�Y�̊G�j����������Ă����B�܂��A�g���Ɏ菑�������͎�����Ȃ��B�����̑g�݂��D���������B
�E�}�����[�ł̋g�����̑����́A�f�U�C�����V���v���Ȕ��ʁA���{���ނ������ւ�d�����Ă������A�����͑����Ɏg����p���������Ă����B���ʂɕ\���Ɏg���鎆�Ƃ����ƁA�~���[�Y�R�b�g���A�m�s���V���A���U�b�N66�A�V�ǎ��A����т��A�F�㎿���炢�ŁA�����Ɋr�ׂđI�����͔��ɏ��Ȃ������B
�E�܂��A�F�Ƃ�ǂ�̕z��N���X�i���{�p�ɉ��H�����z�j��\���Ɏg���Ă���B������g�����ނ����Ȃ��������ʁA�z��N���X��������邱�Ƃ͏��Ȃ��炸�������B�g���͑���������Ƃ��A�^�C�g���̊������ǂ����邩�Ƃ������ƂƁA�\���̎���N���X���ǂ����邩�Ƃ������Ƃ��A�܂����ɁA�قړ����ɍl���Ă����悤�Ɏv���B�s�Z�{ �{�V�����S�W�t�����Ƃ��A�^�C�g���̐����肪�ł�������ɂ́A�F�̃A�[�g�E�J���o�X�̑����{���������B�N���X���A�A�[�g�E�J���o�X��o�N�����ȂǁA�����ŏ㓙�ȃN���X���g���Ă����B
�E�Ȃ����������̐ŁA�Y�����̉��F���c�c�ƁA�l�S�W�̏ꍇ�͓��ɓ���B�����̏ꍇ�A���łɐ�s���Ă���S�W������킯�ŁA����ɑ��ĐV�������o���Ȃ���A��肻�̍�Ƃɂӂ��킵�������ǂ���́u�J���[�v�����Ă����Ȃ�������Ȃ��B�g���́A���̈ӏ���������A�\���̎����A�F���������Ƒ厖���ƍl���Ă����悤���B
�E���{�ł́A�S�W�Ȃǂ͓��Ɏ��Ԃɑς�����̂����Ƃ����v�����A�}�����[���암�Ɛ�����ЁA���{���ȂǁA�{�Â���Ɋւ��S�X�^�b�t�����L���Ă����Ǝv���B
�E�S�W�ҏW���̋g���̊��ɂ́A�c�h�b�̎O�����̐F���{�����܂��Ȃ��āA���m�C���L�̍����\���̈���̐F���{���ƁA�����i��łɂȂ����{�́A�\���̔������p�̋��Łj���u���Ă������B����ƑO�q�̐������ƁA�{�����i�{���ځ^�����ڂƂ��j���������B
�E�g���̉s���ڂ��t�N���E���ɂȂ��炦��l�������B�V�������́A���������̂���D�����������A��������������s���܂Ȃ����ŁA�킪�ڂŌ��ɂ䂭���Ƃ����߂��Ȃ������Ǝv���Ă����B�����̑����ɂ��ẮA�}�����[�̎Ј��Ƃ��Ă̎d���A�}�����[�̖{�����d���Ƃ����l���������̂ł͂Ȃ����B�g���̋C���A�ҏW�҂̋C���A��Ђ̋C���݂����Ȃ��̂����R�ƈ�̌`�ɂ܂Ƃ܂�悤�ȁA�S�W�ł���u�}���̑S�W�v�炵���{�̌`�ɂ��̂��Ǝ��ʂ���悤�ȋ�C���������̂�������Ȃ��B�i142�`144�j
�E�g���ɗU���āA�悭�R�[�q�[�����݂ɍs�����B�����ŁA�W�����f��̂��Ƃ��ꂽ�B�y���F�����Y�̕��������A�f��s���N�}���G���o�[�g�Łt���ς�悤�A���߂�ꂽ�B
�E�����A�����A������S���爤���Ă����̂��Ǝv���B�O�q�����ɂ��Ă��A�A���_�[�O���E���h�̎ŋ���嶍��̉f��ɂ��Ă��A�u�ځv�͂��낢��Ȗ`�������邯��ǂ��A�Ō�Ɂu��v�ɂ������Ǝ��ʂ��Ă䂭�̂��A�ƂĂ��g���炵���Ɗ����Ă���B�i146�`147�j
��
�\�\�@���������Ƃ��k�i���X�ł̊��k�̂���l�A�g������͑���ɂ��Ă�����������Ă��܂������B
�����@����ɂ��ẮA���₩�Ȃ������܂��A���܂Ōo���Ă��O�������Ȃ����́A�Ό��ɌÂтȂ����́A�V���v���ŗ������Ă��邱�Ƃ��悵�Ƃ���Ă��܂����B���������Ă��܂����Ƃ����F����ŁA�C���L�̐F���͂��낢�날�邯��ǁA�������܂����ȂƋ�������������Ă��܂����B���ꂩ��A�u�`�v�Ƃ������̂���ɑ厖�ɂ���Ă��܂����ˁB�i�����A��l���y�[�W�j
��Ɍf�����ⓚ�́A�S�~��Y�ƒ������ق�ɂ��{�C���^�����[�̌���̂悤�Ȃ��̂��B���ɋg�����{�l�ɑ����Ɋւ���C���^�����[�����݂��Ƃ��Ă��A����ɗD��f�Ă������������Ƃ͎v���Ȃ��A�݂��ƂȒ��߂�����ł���B�g���������̗v���͂��̈�߂ɐs����B
�������ق�̑�����i���ȕւɒm��̂ɂ́A�`���ŐG�ꂽ�s�A�C�f�A idea�t367���E��368���ƁA�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�ɂ��̂������i�}�ŁE���͂Ƃ��ɁA�K���K�ǂł���j�B�����A�ȉ��̏Љ�ɂ�����悤�ɁA���ۂɒ�������������|�����s�}�������S�W�t����E�{���f�U�C����S�������s�̕���G���t�V���[�Y����Ɏ��ɔ@���͂Ȃ��B�����ł́A�}�����[�́i�Ƃ�킯�a���́j�S�W�́A�n���ŏa���g���������Ƃ͂܂��ʂ̖ʂ�̌�����A�i�Ƃ�킯�m���́j�h��Ő��ȑ����E���{�����邱�Ƃ��ł���B

���{���i���j�E���c�Õv�i�G�j�k�|�c�o�_�E�O�D�����E���ؐ���i����j�l�s������{���b���k���{���E���c�Õv�̉̕���G�� 1�l�t�i�|�v���ЁA2003�N10���j�̖{���y�[�W�i�m���u���Ȃ��j�k�����E�{���f�U�C���F�������ق�l
�������ق�
NAKAJIMA KAHORU 1944-
��t�����܂�B�������p��w�f�U�C���ȑ��ƌ�A�P�X�U�V�N�}�����[�ɓ��ЁB��`�����o�Đ��암�ցA�Ȍ�Q�O�O�O�N�ɑގЂ���܂œ��Ђ̎Г������S������B�ҏW���ő������|���Ă����g�����ɑ������w�сi��y�ɓȐ܋v���q�A��y�ɉ��������Y������j�A�O���f�U�C�i�[�������Ή��l�q�ɂ��e������B70�N��㔼��葼�Ђ̎d����������悤�ɂȂ�̂́A���҂������̃f�U�C�����C�ɓ���˗����ꑱ���邩��ŁA�ҖM���E�F�V���F�E�v�����F�Ȃǂ̒��삪����ɓ�����B
�@�u�{�̒��g�̊i�����������킳�Ȃ��悤�ɁA�������܂�����i�ȑ�����v�Ƃ����g�����̋������ł����Â��Č�����̂́s���@�����[�S�W�t�s�{�[�h���[���S�W�t�s�v���[�X�g�S�W�t�s�}�������S�W�t�Ƃ������S�W�̑���ł��낤�B�[�����Ɋ��\�I�Ȗ������������̂������̓Ƒn�ł���B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l�}���ł͒W�J�~��A�ԋ{���F�A���N�i�A����V�Ƃ��������r�ҏW�҂Ƃ̋��͂ȃ^�b�O�ɂ���Đ������̌��삪���܂ꂽ�B
�@�c���̂��납���ڗ��E�\�E�̕���Ȃǂ̌ÓT�|�\�ɐe���ށB���{���i���j�Ɖ��c�Õv�i�G�j�́s�̕���G���t�V���[�Y�i�|�v���Ёj�͎���c�s�o����g�����V�ߖ��D�A���؈�ࣂ̖{�����C�A�E�g�����|�I�ł���B
�@�K�[���[�E�����I�ȉ����Ɏ��������������ƕ����ňЊd���邵���Ȃ����Ȍ[���I�Ȓj�������Ђ��߂����݂̏��X�V����ɂ����āA���̒[�����ƃO���}���X���������ċg�����ƐΉ��l�q�̃n�C�u���b�h�Ƃ������ׂ�������L����̌����钆�����ق�̑���͌Ǎ��̑��݂ł���A�M�d�ł���A�������B�i�M�{���n�j�\�\�s�A�C�f�A idea�t368���q���W�E���{�I���^�i���_�� 1970-1994 �ے�`�̃u�b�N�f�U�C���r�i�������V���ЁA2014�N12��10���A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j
�������ق�i�Ȃ����܁E���ق�j
���l�l�N��t�����܂�B�������p��w�𑲋ƌ�A���Z���N�ɒ}�����[��`�ۓ��ЁB���암�Ɉٓ����A��ɑ����S�����ē�Z�Z�Z�N���ɑގЂ����B�V���v�������̂���X�P�[�����L���ȑ���p�ɒ�]������B�}������̊��{�̑����@���d�F�炩��̐M������傾�����B��\��Ɂw�}�������S�W�x�i�}�����[�j�B���݂̓t���[�Ŋ��A�@��邲�Ƃɒ}���̎d�����肪���Ă���B��Z�Z�Z�N�ɑ�O�\���u�k�Џo�ŕ����܃u�b�N�f�U�C����܁B�i�P�c�����j�\�\�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���A��Z�l�y�[�W�j
��[�N���Ƃ����s�ፑ�t�A�s�ፑ�t�Ƃ����Θa�c���́s�ϓ֔b���t�i�b�̓��W�A1977�j�ł���B�v���Ԃ�Ɂs�ϓ֔b���t��ǂ݂Ȃ������Ǝv���ď��˂�{�������A���肻���ȂƂ���ɂȂ��B�I�c����Y�͑����������闝�R�ɂ��āu�����͐V�ł��o���@�����B�܂��A�G���f�ڂ̘_����L���Ȃǂ́A��ŒP�s�{�����邱�Ƃ�����B���̍ۂɈ��p�ӏ��⏑���I�v�f�̊m�F�̂��߂ɂ��A���p�����Q�l�����͕ۑ����]�܂����v�i�q���{�l�̑����u���r�A�s�������\�\�Ȃ������͑����A�����ĎU�킷��̂��t���ێЁA2017�N7��14���A�Z�܁`�Z�Z�y�[�W�j�Ə������B�{�e�����M���邽�߂Ɏ�����Ȃ������Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�Ȃ����̂͂Ȃ��B���������Ȃ��̂ŁA�߂��̌����}���ق���肽�i���N�o������ł́s������x �ϓ֔b���t���\���j�B�s������x �ϓ֔b���t�i�i�i���N�ЁA2017�N1��25���j�́A���łɁq�w�ፑ�x�C�O�сr�Ɓq�ፑ�E70�N2�����E72�N11�����E73�N12�����E75�N2�����E77�N2�����̂Â��r���������ĕҏW���̂����A�V�e�̂����a�c�ɂ��2�т́s�ፑ�t�Y��ɂ͂��ЂƂ��G��Ă��������B
����t��
�@�́X�A�Ƃ����Ă����������\�N���炢�O�̂��ƂȂ̂�����ǁA���̂Ƃ��l�͂b62�^�@�֎Ԃ��������}�̍��Ȃɍ����Ă����B�Ƃт����芦���~�̖邾�����B
�@�@�֎Ԃ͋t�]�j�n���������߂悤�Ƃ���w���B�[���{�N�T�[�̂悤�ɃX�s�[�h���グ�A�����̃g���l���������蔲�����B�����A�܂��ፑ���A�Ɩl�͎v�����B
�@������K���X�r���Ƃ���A��̕��ɖl�����͂����B�ʂĂ��Ȃ������ꂾ�B
�@�M�����ɋD�Ԃ���~�����Ƃ���ɁA�u����������v�̃����f�B�[�����������B�������̍��Ȃɂ��鏗�̎q�������A����̂悤�ȉ��F�̌��J�������B�ޏ��͐l�ڂ��Ђ��قǂ̔��l�ł͂Ȃ���������ǁA�����낵�������̂��������������B
�@�ޏ��͗����オ���āA�l�̑O�̃K���X���𗎂Ƃ����B��̗�C�������܂�ɂȂ��ė��ꂱ�B
�@�u�w��������A�w��������v
�@�������ς��ɏ�肾���āA�A���v�X�Ń��[�f���ł��̂��݂����ɔޏ����������ԂƁA�ł̒����物�F��������J���e�����������j������Ă����B���͈ł̑ɂɂ���̂ł͂Ȃ��A���̈ꕔ�Ȃ̂��A�Ɩl�͊������B�i�����A��Z��y�[�W�j
�ےJ�ˈ�
�@�Ȃɂ����Ƃ��Ӑl�̐��ɂ��ƁA�����̒����g���l������Ƃ����͐ፑ�������ł���B���̐��͂����Ԃ�]���������B���t�ɂ͂��݂����邵�A�ނ�݂ɒP���Őꖡ���������A���킩��₷������ł����ˁB
�@���܂��ɐႪ����Ƃ��Ӗ����w�I�����������Ȃ��B�Ⴊ�~��͖̂L�N�̑O���ŁA�߂ł������̂Ȃ�ł��B����Ɉł̃g���l�����Ă܂��Ȑ��E�ɏo�Ă䂭�̂́A���̉������̉��ɂ�ē|�����̂��j�ӃJ�[�j���@���̂₤�ȁA���J�Ƃ��Ă̐��i���������A��p������p����B���ӂ܂ł��Ȃ����ӎ��̂����ɂł͂��邯��ǁB
�@�Ƃ���ł킽���̑̌������ւA�g���l������Ɛፑ�ł͂Ȃ����B�킽���̐���͎R�`��������A���̂����œ����ɂ䂩���ƋD�Ԃɏ��Ƃ��́A�ፑ����ፑ�łȂ����Ƀg���l������̂����B�����Ō��Ӑፑ�Ƃ͉z����w���̂�����ǁA�����̐l�ԂɂƂĂ�����͓����ł���B
�@�������Ă킽���Ȃ�A�g���l������Ɛፑ����Ȃ����Ƃ��A���̍��ɏo���Ƃ��A�Q�n�������Ƃ����ӂ��ƂɂȂ�B���w������͂���Ɖ������邯��ǁA�ȁ[�ɁA���܂ӂ��B�i�����A��Z���y�[�W�j
�����ےJ�̈��ǎ҂ɂ͐����s�v���낤���A�s�m���E�F�C�̐X�t�i1987�j��s���b�U�Ƃ͉����t�i1984�j�܂��������ɂ͒E�X���邵���Ȃ��B�Ƃ�킯��҂́u�Ȃɂ����Ƃ��Ӑl�v�́A�ےJ�Ɛ�[�̊W�����Î����Ă���悤�ŁA�����낵������ł���B�܂��Ɏ��|�B��[�́s�ፑ�t�́A�V�����ɔł��킪�Ƃ̂ǂ����ɂ���͂������A����܂���������Ȃ��B�����ŁA�����Y�p�w���O�̍������[�̕S�~�ψ�̒I����E�����}�����[�Łk������{���{��n�l�́s��[�N���W�t���{�Ƃ���B���Ȃ݂ɂ���́A�g�����̑����ɂȂ邨���炭�͗B��̐�[�N���̒����ł���B �s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�Ɉ˂�A�s������{���{��n�k�S97���ʍ�1�l�t�i���A1968�N8���`73�N9���j�̎d�l�́u�e���E�㐻�E�N���X���E�\�����v�B��5��z�{�̖{���̂���́A��ꔪ�~��l���~�����[�g���E�l�Z�Z�y�[�W�B�ʒ��̖{���ƌ��G�i���ҏё��ʐ^�j���e�꒚�B�{����8�|31���l�~29�s2�i�g�A�s�ፑ�t���킸��52�y�[�W�Ɏ��܂��Ă���B����͐����ЁA���{�͗�ؐ��{���Ƃ������͂ȕz�w�ŁA���ň���̒�͂�����������A�����d��̂���ꊪ�ƂȂ��Ă���B�艿��720�~�B�s�ፑ�t�̖`�������������B
�@�����̒����g���l������Ɛፑ�ł����B��̒ꂪ�����Ȃ��B�M�����ɋD�Ԃ��~�܂��B
�@�����̍��Ȃ��疺�����ė��āA�����̑O�̃K���X���𗎂����B��̗�C�����ꂱ�B���͑����ς��ɏ��o���āA�������Ԃ₤�ɁA
�@�u�w��������A�w��������B�v
�@����������Ă������ŗ����j�́A�݊��m����܂��n�ŕ@�̏�܂ŕ�݁A���ɖX�q�̖є�𐂂�Ă�B
�@��������Ȋ������Ɠ����͊O�߂�ƁA�S���̊��ɂ炵���o���c�N���R���m��܂����n�Ɋ��X�ƎU��Ă�邾���ŁA��̐F�͂����܂ōs���ʂ����Ɉłɓۂ܂�Ă�B�i�����A�O�y�[�W�j
�a�c���ɕ���ċg�����̕��̖͎ʂ��I�������������A���̗E�C���Z����������킹�Ă��Ȃ��B�����́A�g���̏ё������a�c�{�l�̋Y������҂��邱�Ƃɂ��悤�B���āA�s�ፑ�t�́s��[�N���W�k������{���{��n52�l�t�i�}�����[�A1968�N12��5���j�̊��������鏬���ŁA��[�̍�i���E���ے�����ʒu�ɒu����Ă����B���́s�ፑ�t�`���̑Ό��y�[�W�͌��G�ɂȂ��Ă��āA��[�̎�ւ����m�N���Ŗ{���p���ɍ����Ă���B
 �@
�@
�s��[�N���W�k������{���{��n52�l�t�i�}�����[�A1968�N12��5���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ����f�ڂ̒��҂̎�ցi�E�j
���͐�[�̏��ɖ��邭�Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�ʼn摜�������Ă݂��Ƃ���A���G�̏���2014�N4��12������6��1���ɂ����ĐÉ��s���p�قŊJ���ꂽ�s�����̊�\�\��[�N���Ɠ��R�@�t�W�ɏo�i���ꂽ�悤���B�����p�ق̃T�C�g���s�ߋ��̓W����t�̃y�[�W�ɂ́A���G�Ɠ��������u��[�N���s�R��щ��l�t�@���a46�i1971�j�N���v�Ƃ��Čf�����Ă��邪�A��q����悤�ɁA����N��1968�N�ŁA���G�ɂ͍ŋߍ���f�ڂ������ƂɂȂ�B���W�̐}�^�ł�����A��[���j���E���R���݁E�ē��i�i�ďC�j�A���������i�Ҏ[�E���M�j�s�����̊�\�\��[�N���Ɠ��R�@�t�i�������A 2014�N4��20���j�ɂ́A�s�R��щ��l�t���J���[�Ōf�ڂ���Ă���A���̃L���v�V�����ɂ́u149�b�s�R��щ��l�t�b��[�N���b1968�i���a43�j�N�b���R�ɑ��悵�����A�E���M���g�p�v�Ƃ���B�}�^�����́q�f�ڍ�i�ژ^�r�ɂ͂���ɏڂ����A
�@�k�}�Ŕԍ��l149�@�k��i���l�R��щ��l�b�k��Ɩ��l��[�N���b�k����N�l���Z���i���a�l�O�j�N�b�k�Z�@�^�`��l���{�n���^�ꕝ�b�k���@�i�c�~���p�j�l�Z�Z�E�Z�~�O�E�Z�b�k������l���R�Ƒ�
�Ƃ���B�����āA�Ȃɂ������R�@�́q�E���M�̂��ƂȂǁr�i1968�j�Ɂu���N�̐����A��[�N���搶����ג�������������������B�}���ŊJ���Ă݂�ƁA�̏��ŁA��́u���i��V�v�Ƃ���A������́u�R��щ��l�v�Ə�����A�u�E���M�ɂā@�ËH�����@�N���v�ƕ��L����Ă���B��������A���m��n���A�L���ŁA�i�������A�C鮂��Ă��������ȏ��̂ł���B�������A�L��C�����ň�t�ł������v�i�����A��l���y�[�W�j�Ƃ���̂��A���̏��̗������ڍׂɌ���Ă���B�s��[�N���W�t�̌��G�ɁA���́s�R��щ��l�t�̎ʐ^�ł�����t�������̂��N���킩��Ȃ��B�����A�g�����{���̎d�オ����������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���Ď���⽍����������Ă���Ƌg������ɘb�����Ƃ���A���̘b�ɂȂ�A�g������́u����⽍��������Ȃ����A�Ⴂ����B���ł͐��e���O�Y�̂��̂��ǂ��B���݂������Ƃ�����B����S����i�c�k�߂ƂȂ�Ƃ����v��������B��[�N���ȂA����炵�����炢�̂����邯�ǁB���Ƃ͎u�꒼�ƁB���e����̐F����2�������Ă��āA�����鏈�ɏ����Ă���B�}�����[�̉��x�߂��̕��w�S�W�̌��G�̂��߂̎�ւ��A�ҏW�S���̐l������肤�����B���ƁA�O�����������̂��߂̂�����ǂ�����v�i1989�N5��4���̒k�b�j�ƌ�����B��[�N���̏������L���Ă���ӂ��ł͂Ȃ��������A�h�ӂ��Ă͂����̂��낤�B���́s��[�N���W�t�̌��G�����Ȃ���A�g������[�́u����炵�����炢�́v��ւ̌����ɐڂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz�����Ă݂�B���̈���ŁA���Ґ�[���s�R��щ��l�t�����G�Ɏw�肵�Ă����̂Ȃ�A�k������{���{��n�l�̕ҏW����������ł��铌�R�ƂɃJ�����}����h�����āA�����ŎB�e�����ƍl����̂��Ó�������A���������Ȃ�g�����s�R��щ��l�t�����ۂɊς��\���͒Ⴍ�Ȃ�B���́s��[�N���W�t�̎��^��i��
�@�ፑ�E��H�߁E���l�E�\�Z�̓��L�E�����̖��l�E���������E�ɓ��̗x�q�E��E�S���E���̏Љ�l�E�������z�E�R��́E�b�E�U��ʂ���E�Ԃ̃����c�E��̏����E�ĉ�E������E�����E���͂ɂ��āE�����̊�E�����̐�
�ŁA����ɕt�^�Ƃ��Ē��J���́q�u�ɓ��̗x�q�v�_�r�A���яG�Y�́q��[�N���r�A��[�N���E�������E�ܒJ��l�ɂ��C�k�q�V���o�h����r�ƁA�ҏW���쐻�i���́F�ۏ����v�j�́q�N���r�����߂�B�{�����t�̊��s���́u1968�N12��5���v�B����O��12��3���A��[�͓��q�@�ŃX�E�F�[�f���ɔ����Ă���B�m�[�x�����w�܂̎����ɏo�Ȃ��邽�߂ł���B�����܂̒ʒm���������͓̂��N10��17��������A�s��[�N���W�t�͐�D�̃^�C�~���O�ŏ��X�ɕ����ƂɂȂ�B���Ɏ苖�ɂ��鏉�ł̔��ɂ́A�u�m�[�x�����{��܁v�Ɣ��k�L�ɂ������n�̑т�������Ă���B�Ƃ��ɁA��[�N���ƒ}�����[�̊W�œ��M�����̂́s��H�߁t������ꌏ�ł���B�a�c�F�b�̕M�ɂȂ��s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j��������B
�@���a��\���N�̒}�����[���~�����d�v�Ȗ{�̈�́A��[�N���́w��H�߁x�ł������B�u��H�߁v�̊O�Ɂu�R�̉��v�̑啔���������߂��Ă����B
�@�������v�̐s�͂ŁA�u��H�߁v���Ⴆ���Ƃ��A�Ђ͐�]��Ԃɋ߂������B�ǂ����A�Ԃ��Ȃ�A�w��H�߁x�ŏI��𗧔h�ɂ������Ƃ����Óc��̋C���ł��������B�w��H�߁x�́A��҂̊�]�ŁA����͏��ьÌa�Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�Óc��̍Ȃ������������A��̕�����L�O�ɑ���ꂽ�_�C�������h���������B����蕥���āA�Ј��̋����ɂ��Ă��͎̂l�N�O�ł������B���̍��A�܂��A���{�ŏo���Ȃ������d�C�①�ɂ��������B�O�j����������B������A����������āA�Óc��̉Ƃɂ́A�Ȃɂ��Ȃ��Ȃ��Ă����B�Ј��́A�܂�ܔN�̂������A�������{�[�i�X���Ȃ������B�����̕�����������ɒx��A�O�������܂�x�z�����܂܁A���z�̌����݂������Ȃ������B�����̎x�������́A�l����Ƃقړ��z�ɒB���Ă����B
�@�Ђ̏�Ԃ̕����Ă���S���҂́A��ʎ����Ȃ����ьÌa�Ɏ莆�������āA�Ђ̌o�c��Ԃ�����̂܂܂Ԃ��܂��A�����Ȏӗ�̂ł��Ȃ����Ƃ����O�ɘl�сA����ł����̖{�𒆐g�ɂӂ��킵���{�Ɏd�グ�������ߑ�������肢�ł��Ȃ��ł��傤���Ƃ����`�ŗ��B������A�d�b�œs���������˂�ƁA�Ìa�́A�����ɉ�A���������Ă��ꂽ�B�p���A����A���{�ƁA���ׂē��O�Ȕz���̂��ƂɁA�ԍ�����̌���łŁw��H�߁x���o��������̂́A���a��\���N�̓ł������B�w��H�߁x�́A�s���̍��ؔł̑���Ƃ�����悤�ȏo���h���ɂȂ������A����͌Óc��́u�I��𗧔h�ɂ��Ȃ���v�Ƃ����v�����A���̈���Ɍ����������߂ł���B
�@���\�肪�悲��Ȃ��悤�ɏc�ɕ���ɁA�������v�̏���������[���́s��H�߁t�͐��N�O����A��Ƃ��ď��X�ɔ��\���ꂽ���̂Łs�R�̉��t�ƂȂ��Ŏ��̍�i�̌n��̂��������łȂ����̂킪���̏����̂ЂƂ̋ɓ_���`������̂ƌ����܂��傤����������ꂽ�B���̍��ؖ{�ŁA��̍�i��ǂl�����́A�[�������������A���]�������܂����B���O���ɏo�����y�ł͓�\�����z����x�X�g�Z���[�ɂȂ����B
�@�܂��A�㌎����͂��߂��u������{����I�v�ɂ��w��H�߁E�R�̉��x���A�푁�����߂�ꂽ�B
�@�ǂ����A�Ђ��Ԃ��Ȃ�A�Ɓw��H�߁x�ɍ��Ȏ��������܂Ƃ킹���Óc��̎u��������ŁA�߂���N�̗��݂��^�����̂ł��낤���B�Ƃɂ����A���y�ł́w��H�߁x���m���̒}�����[���S�点���B�i�����A�ꔪ��`�ꔪ��y�[�W�j
�g�������}�����[�ɓ��Ђ����̂�1951�i���a26�j�N4���A�����͐V���́q���w���S�W�r��S�����A��������|����悤�ɂȂ�̂͗��N�i���Łs��H�߁t�́A���̔N2�����j����ŁA���ьÜl�Ɏ莆�ő������˗������u�Ђ̏�Ԃ̕����Ă���S���ҁv�͒��r�̗p�̐V���Ј��A�g���ł͂Ȃ��������낤�B�Ƃ���ŁA��f�̘a�c���ŋC�ɂȂ�ӏ�������B�����́u�|�p�@��܋L�O�����500���v�i��o�k�|�p�@��܋L�O�Łl���t�j�{�������Ă��Ȃ��̂����A�u���\�肪�悲��Ȃ��悤�ɏc�ɕ���v�ɒ������v��������
�@��[���́s��H�߁t�͐��N�O����A��Ƃ��ď��X�ɔ��\���ꂽ���̂Łs�R�̉��t�ƂȂ��Ŏ��̍�i�̌n��̂��������łȂ����̂킪���̏����̂ЂƂ̋ɓ_���`������̂ƌ����܂��傤�B�i�����͐V���ɉ��߂��j
�ɂ�����s�@�t�̎g�����ł���B�����͌�o�s��H�߁E�R�̉��t�̉���ł́w�@�x���g���Ă��āA�Љ�Ɍ�����s�@�t�͒������B�Ȃɂ����������̂��B�g���́s�@�t�̎g�p�͂���������Ƃ��̂�����ɕ���������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂����̐����ł���B�����Ƃ��A�g������[�ɂ��ď��������̓�ӏ��ł́s�@�t���g���Ă��Ȃ��B
���̂ق��A���́u�S�v�A���V��̒Z�сA�Ƃ�킯�u�M�̒��v�A�ו��́u�����ߍ��v�A����Y�́u�t�Տ��v�A�N���́u�ፑ�v�A����́u�@�B�v�ȂǓ��ɍD���ȏ����ł������B�i�q�Ǐ����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�ܘZ�y�[�W�j
���a�l�\���N�@��㎵��N�@�\�O�^�t�A�O�Y��m�̂����߂ŁA�w�����C�J�x�Ɏ��u�t�v�������B�Ȃƍ����̍������Ɏl�N�Ԃ�̗��s�B��[�N���K�X���E�B�i�q�k���M�l�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A��O�l�y�[�W�j
�g�����̎��Ɛ�[�́s�ፑ�t���邢�́s��H�߁t�s�R�̉��t�ɂ��ẮA�Ƃ��ɏ������邷�قǂ̂��Ƃ͂Ȃ��B����ɁA�s���Y��ԁt��8���k���W����[�N���\�\�f��20�N�l�i1992�N4��16���j�f�ڂ̋��e�q���L�^��i�A�L���^���p�\�\��[�N���Ƌg�����Ɍ���r�O���̐�[�����Ę^���悤�B�㔼�̋g�����Ɋւ��ẮA�{�T�C�g�̂��������ŏq�ׂ������Ȃ̂ŁA�ȗ�����B
�@�u����́A���̐��֔N�\�Z�̎��̏o�������A�\���̎��i�吳�ܔN�j�ɏ��������̂ł���B���A�������͂𐮂ւȂ���ʂ���Ă݂��B�����ł́A�\���̎��̂��̂��\��Ŏʂ���Ă�邱�ƂɁA�����炩����������B�܂������Ă��Ƃ��ӂ��Ƃ����ł��B�v
�@��[�N���̏��я����q���E�Ёr�̈�߂ł���B���̑����̏����ǂ݂����������ł͂Ȃ��悤�ɁA�\���̐�[�����������ł͂Ȃ������B�������O�\���N��̏����Ƃ����p���邱�Ƃŕ��͂͂ɂ킩�ɑ��e�����߂�B�\�Z�̏��N�Ə\���̐N���قȂ�悤�ɁA��[�N���Ƃ����������ʐl�̌o���ƕ��͂��q���E�Ёr�ɂȂ����ƍl�������B���邢�͂��̃R�����g�䂦�ɁA�����ł͂Ȃ����z�ƌ���ׂ����B����ƁA�}�ƒn�̊W�͋t�]���āA�`������A�����ŏ��Ɉ�������O�܂ł��ꊇ�ʂł������āA�R�����g��n�̕��Ƃ������Ȃ�B���łɌ����A�ꊇ�ʂȂ��ł��āA�R�����g���ۊ��ʂɓ�������������B
�@�q���E�Ёr�Ō��邩����A��[�̋L���̎g�������̓V���v���ŁA��b�ƍ�i�����ꊇ�ʂł����邾�����B�V���Д��s�́u���͓��L�v�Ƃ����̂́A�����Ɠ��L���̂ǂ���Ƃ����邪�A����ƂĈ��̏������B�ʔ����̂́\�\�i�_�[�V�j�Ɓc�c�i�O�_���[�_�j�̗p�@�ł���B
�@�Ȃ�Ă܂�Ȃ����Ƃ��B�\�\��͂肨�c������́A�ӂЂ���Ɋ�т̐F�������ւāA�����A�����̉����}�ւĂ��ꂳ���łȂ�Ȃ��B�@���̃_�[�V�͌\��̕M�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����낤���B�k���̂��߉�i�H�j�ɔ��˓I�ɏo�����������t��ۂ݂��݁A�����ȓI�ȃg�[���w�肩����]�Q�@�B
�@���͐l�X�̉��F����߂āA�܂������ӂ��ƂȂ����B�k�������s�l���c������̐��\�\���B�@����͐�[���\���̂Ƃ��̂��̂��낤���B�u�܂������ӂ��ƂȂ��v���s���s���̓W�J������A����ȋC�ɂȂ�B���[�_�̓R�����g�̂��ƁA�q�̋��ցr�����p����ɂ������āA�O�i���̈Ӗ��Ŏg�p���Ă���B
�@�c�c����قnjł����O�ɐ����������̂ɁA����f���̉ƂŁA���͉Ɖ��~�邱�Ƃ����m�����B�@���̑O�ɂ���i���̈ӂŁu�����A����֍s���܂����B�c�c�v�ƃR�����g�����ɏo�Ă��邩��A�܂��m�����B�i�����A��Z�`���y�[�W�j
�l�����I�Ԃ�Ɏ����̕��͂�ǂ݂������āA�����Ԃ肪�ς���Ă��Ȃ��̂ɂƂ܂ǂ����o����i�������u�����ʁv���u�ꊇ�ʁv�ɉ��߂��j�B��[�͎����̏��N���E�N���̕��͂����p����Ƃ��A�ǂ̂悤�Ɋ������̂��낤���B���l�̋^��́A�g���́s���܂�͂����L�t�ɑ��Ă������B
�k�NjL�l��[�N���s��H�߁t�P�s�{�̊e��
��[�N���s��H�߁t���s�}�����[�}�����ژ^�t�Œ��ׂ�ƁA�i���Łj�E�k���y�Łl�E�k�|�p�@��܋L�O�Łl�E�k�����Łl�E�k�V���Łl�E�k�����Łl�ƁA���ɘZ�̔ł��o�Ă���i�Ȃ���[��1952�N6��25���A�V�c������{�Y�p�@�܂����^����Ă���j�B���ژ^�̋L�ڂ������B
��H�߁@��[�N�������{�ߑ㕶�w�ق́A���̂����k���y�Łl�Ɓk�|�p�@��܋L�O�Łl���������Ă���B�k���y�Łl�͈�_�B�Y������4��15�����̍ĔŖ{�ŁA�W���P�b�g�Ȃ��A�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��i���y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t�̕����ł����A�u273�Łv���낤�j�B�k�|�p�@��܋L�O�Łl�͋g�c���ꋌ���̏��Ŗ{�ŁA�q��d���r���������Ă���B���y�[�W���́A�������u313�Łv�ŁA�ژ^�̋L�ڃf�[�^�Ɍ�肪������i���̏��{�͖����j�B�s��H�߁t�̂ق��ɂ��A�a�c�F�b���Ō�ɋ������s��H�߁E�R�̉��t���o�Ă���B����͉��n�F�l�Y�̑����ɂȂ�A�a�U���E�����̃V���[�Y�A�k������{����I�l�̏���z�{6���̂�����1���������i����́s��H�߁t���s�ɐs�͂����������v�j�B�тɂ́u�Y�p�@�܁v��搂��Ă���A�u�V�e�l�т����ށ^��f�f�扻����v�ƌ�����B�̂��ɊJ�Ԃ���g�����̑����́A��Ƃ̏��ьÜl�ł͂Ȃ��A�ʼn�Ƃ̉��n�F�l�Y�̗��������ł��邱�Ƃ�����B
�@�@�@�@����@���ьÜl
�@�@�@�@�a�U���^�㐻�E�����^322��
�@�@�@�@1952�N2��10���@580�~
��H�߁i���y�Łj�@��[�N����
�@�@�@�@����@���c�L�l�Y
�@�@�@�@�a�U���^�����E�J�o�[���^274��
�@�@�@�@1952�N3��15���@250�~
��H�߁i�|�p�@��܋L�O�Łj�@��[�N����
�@�@�@�@����500��
�@�@�@�@����@���ьÜl
�@�@�@�@�a�U���^�㐻�E�����^322��
�@�@�@�@1952�N6��10���@580�~
��H�߁i�����Łj�@��[�N����
�@�@�@�@�u��d���v������������
�@�@�@�@�a�U���^�㐻�E�����^313��
�@�@�@�@1952�N8��15���@580�~
��H�߁@��[�N����
�@�@�@�@�V�����^�����E�J�o�[���^198��
�@�@�@�@1955�N5��5���@100�~
��H�߁@��[�N����
�@�@�@�@�n�ƎO�\���N�L�O�����Łi�|�p�@��܋L�O�Łj�@����1,500��
�@�@�@�@1970�N7��20���@2,000�~
��H�߁E�R�̉��@��[�N�����v20���������Ƃ����s��H�߁k���y�Łl�t�́A�ӂ������炸�̊Ԃ�5���𐔂���B�����������āA�}�����[�������ɐ�[�́s��H�߁t���������A��[�́s��H�߁t�������ɒ}�����[�������A��������������������B
�@�@�@�@�R�̉��i�R�̉��@��̉H���j�@��H�߁i��H�߁@�X�̗[�����j
�@�@�@�@���������v
�@�@�@�@1952�N9��25���@204�Ł@200�~

��[�N���s��H�߁k���y�Łl�t�i�}�����[�A1952�N3��15���k�u�ܔŁv�F1952�N5��8���l�j�̕\���k���ӁE����F���ьÜl�l�Ɠ��s��H�߁E�R�̉��k������{����I�l�t�i���A1952�N9��25���j�̕\���k�����F���n�F�l�Y�l
����i��s���ΑS�W����t�i�p�ɁA1985�N9��25���j�́A�s�Ėڟ��ΑS�W�k�S10���l�t�i�}�����[�A1965�`66�j��s�Ėڟ��ΑS�W�i�}���S�W���ځj�k�S10���ʊ�1�l�t�i���A1971�`73�j�̑����ɂ��ď������Ƃ��A�Q�Ƃ��邽�߂ɏn�NJߖ��������A�}���ق���肽��{�������B���������č�2016�N�H�A�������k��g���㕶�Ɂl�Ɏ��^���ꂽ�̂��@�Ɉ푁���w�ǂ��āA������₵�����̂��B�ēǂ̂���A�C�ɂȂ����̂����̉ӏ��ł���B
�@���a�l�\�Z�N�l���ɏo�͂��߂��w�}���S�W���ځE�Ėڟ��ΑS�W�x�i�S��Z���ʊ���j������B���a�l�\�N�ɏo�����y�Ō^�̑S�W���l�Z���̏㐻�{�Ƃ��čĊ��������́B�����̍قŊH�열�V��A���Ɏ��A�X���O�A�{���k�{��̑S�W�ɒ}���S�W���ڔł͂Ȃ��l�A���蓡���̑S�W���o�Ă��āA�S�W�̃V���[�Y���Ƃ�������B���e�I�ɂ͏d�łƓ��������A�V���ɕʊ��u�Ėڟ��Ό����v�i�g�c����ҁj��������ꂽ�B�i����i��s���ΑS�W����k��g���㕶�Ɂl�t�A��g���X�A2016�N11��16���A���Z�y�[�W�j
�k�}���S�W���ځl�Ɋւ��ẮA�s�q�g�����r�́u�{�v�t�������͂������A�H���A�����A���O�Ɍ��y�������A���蓡���ɂ͐G��Ȃ������B�k�}���S�W���ځl�́s���蓡���S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�̊��s��1981�N����1983�N�ɂ����ĂƁA�g�������}�����[��ނ������Ƃ��������Ƃ����邪�A����炴��Ƃ���A�����̍�i�ɐH�w�������Ȃ������Ƃ����̂�������傫�ȗ��R�������B1872�i����5�j�N�A�����̒}�����ɐ��܂ꂽ�������A�}�����[�̑n�Ǝ҂ł���Óc��ɂƂ��ċɂ߂ďd�v�ȏ����肾�������Ƃ͋^���ׂ����Ȃ��B�Ⴆ�A���V���M�s��Ղ̏o�Ől �Óc��`�\�\�}�����[�n�Ǝ҂̐��U�t�i���m�o�ŁA2015�N9��28���j�ɂ́u�k�w������{���w�S�W�x�l����̔z�{���k���a��\���N�i���O�j�l������\�ܓ��Ɍ��߁A�k�Óc�l��ƉP��k�g���l�̐[���������������}�̕����w���蓡���W�x�ɔ��H�̖�������v�i�����A��܈�y�[�W�j�Ƃ���B�������́A�����̍�i�́A���W�Ǝq�������Ƀ����C�g���ꂽ���т��̏��������ǂ�ł��Ȃ��B�c��m���s�閾���O�t���̗g���Ă��镶�ɐڂ��邽�тɁA�u�ق��A�����Ȃ̂��v�Ǝv���A���������Ɏ�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ������B
�����@��Ȃ̂ŁA�s�閾���O�t�����߂��s�����S�W�t��}���ق���肾������A�O�D�s�Y�ҁs���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l���蓡�������t�i�}�����[�A1983�N1��30���j����肵���B�艿3400�~�͊��s�����ł������͂Ȃ����A���ꂾ���̓��e�̏[���A���ꂾ���̈���E���{�̊����x������ɂ��A���ň���ɂ��㐻�{�̋��ɂ̎p�ł͂Ȃ����Ɗ�������B�g�������{������ɂ����̂ł���A�K����Ύ��Ƃ����ɈႢ�Ȃ��i��q���邪�A���͌����_�Ŗ{�����g���������{�Ƃ͔F�肵�Ă��Ȃ��j�B
 �@
�@
�O�D�s�Y�ҁs���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l���蓡�������t�i�}�����[�A1983�N1��30���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�O�D�s�Y��E����s���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1981�N1��20���`1983�N1��30���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�O��Z�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\���ӁB�k�ʊ��l�̕\���͗����������̃N���X�ŁA�w�����́u���蓡���S�W�@�ʊ��v�͋��F�̔������A�Ж��͋��B���\���̃}�[�N�����B2�F���̖{���͎ʐA�I�t���B�{���͊��łŁA7�|�g�݂́q����җ����r�̃��r�A���Ȃ킿3.5�|�̂Ђ炪�Ȃ̐ꖡ���s���A�����Ȉ���ł���B������͊�����А����ЁB�z���[�o�b�N�̐��{�͎��w��̂��߁A�y�[�W���J�����{�����ɒu���Ă��J�����܂܂́A����܂������Ȑ��{�ł���B���{���͊�����АϐM���B���͕\�m�����ān�ʂɃG���{�X���H���{���Ă�����ŁA�V�n�����ꂼ��3�ӏ��A�j���i�X�e�[�v���[�j�ŗ��߂Ă���B�����Ȃ�ڒ��܂ŌЕt������Ƃ��낾�B���̕\�P�E�w�E�\�S�ɂ����Ă̓\���ӂ́A�Ȗڂ̗p���ɁA�S�̂��q�����r�ň͂��āA�p�����E�����E�����E�ҎҖ��E�o�ŎЖ��i�\�P�j�A�����E�����E�o�ŎЖ��i�w�j�A���e�̊T���E�}�[�N�E�o�ŎЖ��E�艿�EISBN�R�[�h�i�\�S�j���L���Ă���B�����͊�{�I�Ɂk�}���S�W���ځl�ɋ��ʂ��铝��t�H�[�}�b�g�ŁA���̑n�n�҂��g�����ł���̂Ȃ�A�s���蓡���S�W�k�S12���ʊ�1�l�t���g����������i���ƌ��������Ƃ��낾���A�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��A�N�̎�ɂȂ���̂��f��ł��Ȃ��B�����炭���Ԃ́A�k�}���S�W���ځl�̃t�H�[�}�b�g�ɑ����ē��Ђ̓����Ŏw�肵�����̂ł͂Ȃ����B���͂��āA�g�����}�����[�̎Ј��Ƃ��ċƖ��ő��������s�����֑S�W�k�S3���l�t�i�}�����[�A1976�j��_�����q�g�����̑�����i�i61�j�r�́k�NjL�l�ŁA
�s���������t�k�i�}�����[�A1978�N12��25���j�l�̏��e�ƒNjL���f����B�g�����͖{�����s�̔N�A���Ȃ킿1978�N11��15���ɍݐE27�N���̒}�����[���ˊ�ގЂ��Ă���A�s���������t�͎Ј��Ƃ��đ��������Ō�̈�����낤�B�������A��ЍX���@�\����̎c�������ɒǂ��Ă����g���̑���ɁA�ЂɎc������y�����̎d�������������\�����Ȃ��͂Ȃ��B�T�^�I�Ȓ}�����[�̎Г����ł���B
�Ə��������A��҂̏ꍇ�Ɠ��l�̎��Ԃ��N�����̂ł͂Ȃ����A�Ɛ�������킯���B���Ȃ킿�A���Ă����g�������A���ۂɑ��������̂͒}�����[�̌�y�Ј��������̂ł͂Ȃ����A�ƁB
���āA����́s���蓡���S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l���蓡�������t�́A����ׂ��s�g�����S�W�k�ʊ��l�g���������t��Ґ�����ۂ̎Q�l�ɂȂ�Ƒz����B��ŐG�ꂽ���i�\�S�j�Ɍ�������e�̊T�����f����i�Ȃ��A�тɂ͇T����W�܂ł̎��M�Җ����L����Ă���j�B
���蓡������
�T���_�i7�сj
�U�������]�i9�сj
�V��z�E��ہi8�сj
�W����̌����E�]�_�i13�сj
�@���蓡�������j
�@�Q�l�����ژ^
�@���蓡���N��
�T����W�܂ł͑[���Ƃ��āA�q�Q�l�����ژ^�r�i�O�D�s�Y�j�Ɓq���蓡���N���r�i�����Ύ��j�ɑ�������g�����̎Q�l�����ژ^�E�N���͂��łɐٕ҂̂��̂��{�T�C�g�ɂ��邩��A����͋g���������j�̎����ɒ��͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i���Ȃ݂Ɂq���蓡�������j�r�̎��M�҂͏\��M��j�B�����Ƃ��s�g�����S�W�t�Ɂk�}���S�W���ځl�̑̍فA�Ƃ����̂͂Ȃɂ��u�����v���݂Ă��āA�������肱�Ȃ��B�ق��̏��ł����������A�g���̑S�W�ɂ́s�����d�M�S�W�k�S3���l�t�i�������[�A1985�j��s�{��~����W�k�S3���l�t�i���p�o�ŎЁA1980�`81�j�̑����������킵���B�g�����g�́A
�⁁����Ɏc���������̂́H
���������A�����K���ɂ��g�����S�W�ł��o����A���W����̂ق��ɁA�U���W������~�����Ƃ����A�����ւ��I�Ȋ肢�͂���܂��B�i�����r�Y�q�g��������76�̎���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�A��l�Z�y�[�W�j
�ƍ����̖�ɓ����A����Ȍ�A�g���ɂ��Ă͎��q���v�̎��M������W�J���āA���̐T�܂��₩�Ȋ�݂�������ɑ���Ɛсi���z�E�]�`�E���L�Ȃǂ̎U����i�j���₵���B
�q�g�����Ƌ��q�����r�Ɂu�،��͂Ȃ����s��{ ���q�����S���W�t�i�}�����[�A1967�N6��30���j�̑������g����������������Ȃ��v�Ə������B�����Łs��{ ���q�����S���W�t����肠���āA�g���������{���������悤�B�{���̎d�l�́A��O��~��Z�O�~�����[�g���E���O�l�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�͍��̊v�A���͔��̃N���X�B�J�b�g�͉F���͑טC�j�Ƀr�j�[���̃W���P�b�g�E�\���E�{�[�����i�\���Ӂj�B�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�{���܂��̘a���i�꒚�j�ɖѕM�ɂ�鏐������B�{���̂��Ƃ̃��m�N�����G�ɋ���ˈ�j�B�e�̒��ҏё��ʐ^�B�\���t�ɉ��A����L�ԁB
 �@
�@
�s��{ ���q�����S���W�t�i�}�����[�A1967�N6��30���j�̃{�[�����Ɠ\���ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�{���ɂ��āA�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�ɂ͂�������B
�}�����[�̊��s�����S���W�Ƃ��ẮA�{���̑O�ɏ��F�G�Y�E�����Ґ��E�O�D�B���E���e���O�Y������A�{���̌�ɑ���l�Y�E�x����w�E����S���E�������E�����Y�E����d���E���������Y�Ȃǂ�����i�u��{�v���t���Ă����肢�Ȃ�������A�u�S���W�v��搂��Ă����肢�Ȃ������肷�邪�j�B�}�����[����l�S�W���o�Ă��鎍�l�i�O�D�B���E���e���O�Y�E����S���E�����Y�E����d���E���������Y�j���������ŁA���q�����̑S�W�́A���惆���C�J�E���X�Дł�5���{��1960�N����71�N�ɂ����āA�������_�Дł�15���{��1975�N����77�N�ɂ����ďo�Ă���A�}�������q�ƍł��e�����o�ŎЂƂ����킯�ł͂Ȃ������B�{���ڎ��̕W��ɁA���W�̏����N���i�@�j�ɓ���ĕt�L����i�����͐V���ɉ��߂��j�B
�@�D�̖{�i1967�j
�@IL�i1965�j
�@�����i1956�j
�@���i1955�j
�@�l�Ԃ̔ߌ��i1952�j
�@��i1948�j
�@�S�̎��̉S�i1949�j
�@�����P�i1948�j
�@�������ւ̃G���W�[�i1949�j
�@�L�i1937�j
�@�V�K�N���i1960�j
�@�H�T�̈��l�i1960�j
�@�撾�ށi1927�j
�@���̗��Q�i1926�j
�@�啅���i1960�j
�@�����˒��i1923�j
�@�������ڂꂽ�����Ђ�Ђ��߂����́i1964�j
�@�@��
�q��r�͂��̍Ō�Ɂu�����v���f���A�u���ꂩ��A���W�ɓ��Ă���̂ňӂɏ[���Ȃ����͍̂폜���āA�����ɂ����߂����̂����Ē�{�Ƃ������Ǝv�Ђ܂��B�^�Ō�ɂ��̑S�W�̕ҏW�ɂ����āA��X�����b�ɂȂ��F�ؗE�����A��c�j�Y���A���ꂩ�璘�҂��h������قǏڍׂȏ������тɔN�������Ă�������������Y���A�\���̊G�����Ă������������F�F���͑טC���Ɋ��ӂ̂��Ƃ�悰�܂��B�^�^���Z���E�l�E��O�^���q�����v�i�����A��Z�Z��y�[�W�j�ƌ���Ă���B������Y�҂́q�����r�̎��W�̍��ɂ́A���s���Ɏ��̏��ڂ�����ł���B�s���Ɂ���i���s��{ ���q�����S���W�t�Ɏ��^���ꂽ���́j�A�~��i�������Ɏ��^����Ȃ��������́j��t�L�����B�܂��A�\�\�̌�́���͐�����s�ҁs���q�������W�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1991�N11��18���j�ɏ��^���ꂽ���́i�s�L�t�͑S�ю��^�j��\���B
�@�~�@�ԓy�̉Ɓ\�\��
�@���@�����˒��\�\��
�@���@���̗��Q�\�\��
�@���@�撾�ށ\�\��
�@���@�L�\�\��
�@�~�@���F�\�\��
�@���@�����P�\�\��
�@���@��\�\��
�@���@�������ւ̃G���W�[�\�\��
�@���@�S�̎��̉S�\�\��
�@���@�l�Ԃ̔ߌ��\�\��
�@���@���\�\��
�@���@����
�@�~�@���̂₤�ȉ́i1962�j
�@���@IL�\�\��
�@���@�D�̖{
�s�ԓy�̉Ɓt�i�핶�ЁA1919�j�́A�{���̋��q�ۘa���`�Ŋ��s���ꂽ��ꎍ�W�B�s���F�t�i�̉����ɁA1946�j�́s�ԓy�̉Ɓt�̑O�A22�E23�̂Ƃ��Ɏ��M���ꂽ�������сB�s��{ ���q�����S���W�t�̍�i�̑I����z��́A���q�{�l�̎哱�ɂ����̂��낤�B���̈ӂ��Ď�����Ƃɂ��������̂��A�}�����[�̕ҏW�ҁE�F�ؗE���ł���A���Ђ̍Z���҂ł����������l�̉�c�j�Y�ł������B���q�̋��F�A��Ƃ̉F���͑טC�ɂ��J�b�g�������|�C���g�ɂ�������đ��������̂́A�{���̏����Ȃǂ��猩�āA�g�������낤�i�Z���^�[���킹���g���������̉����ł���\���́A���̂̂�������������r���̎g�p�͂ӂ���̋g���炵���Ȃ����A�c�g�̕�������r�ł͂��{���́A��N�̓V�V�ޓ�Y�s�s�{�V�����t�Ӂt�Ȃǂł�������j�B�،������Ȃ����̂́A�s��{ ���q�����S���W�t���s�g���������t�́q�W�@������i�ژ^�r�ɒlj�����䂦�B
���q�����̐���������i���Ղ���̂ɁA��g���ɔŁs���q�������W�t�͎�y�ŏd��B�����Ɍ�����s�H�T�̈��l�t�̕W�莍�т́A���q�炵����ʊÔ��ȍ앗�Ŏ��𖣗������B�����Ȃ�Ƃ������Ƃ��낤�A�s��{ ���q�����S���W�t�ɂ͂��ꂪ��������Ȃ��B�u���W�ɓ��Ă���̂ňӂɏ[���Ȃ����́v�Ƃ��āu�폜�v����Ă��܂����̂��B���̑�2�߂͂����������B
�@�@���Ƃꗧ���炵�������́A
�@�@�p���\���̗m�G�������h�n�̂Ȃ��ŔR���Ă�B
�@�@�������t�̐X�̉���
�@�@�ؘR������̂����₤���B
�@�@�������琁�������Ă��镗�́A
�@�@���m���فn�̂ɂقЂ�����B�Ԓd�̑f�]�m�W�A�X�~���n�̂ɂقЂ�����B
���͂����ǂނ��тɁA�g���́q�O�d�t�r�i�F�E17�j�̎���3�s�A
�@�@���F�����͖����͋A���Ă䂭���낤
�@�@�ޏ��̍s��ɗ����͂�����
�@�@�킽���̊G�̂Ȃ��̐X�̓���
��z�N����B�����ās�V�K�N���t�́A������W�莍�т̈�߂͋g�{�����̊�F���Ȃ��炵�߂�B
�@�@�\�\�k�c�c�l���̏����Ă��{�́A�{����Ȃ��B���e����B�����l�ނ̂��Ђ��֓�����ƉΒ������B�k�c�c�l
�s��{ ���q�����S���W�t�̏o�ōL���͐X�c����ҁs�O�i�����G��W�t�i�������A1972�j�Ɂq�n�̍\�}�r�̈��Ƃ��Čf�ڂ���Ă���B�摜���f���邪�A���i�̃{�f�B�[�R�s�[�͏������ēǂ݂ɂ������낤����A�ȉ��ɘ^����B�u�����I��]���_�ƁA����̏_��݂̋�g�ɂ���ēƎ��̂����ꂽ���I���E���\�z�������q�����B���̔����I�ɂ킽�雘��ȑS���Ƃ����������ю��W�w�D�̖{�x�������ďW�听�B���M����������Ōܔ��Z�Z�~�v�B���������������W�s�^�́t�i�}�����[�A1967�N6��25���j�̏o�ōL���ƕ���őg�ł݂̂��Ƃ��͂��Ƃ��悤���Ȃ����A�{�f�B�[�R�s�[�́A�������Ƃ̗��݂��炾�낤���A���ʂ̑̍ق��炾�낤���A�Ǔ_�i�A�j���قƂ�ǎg��Ȃ����قȕ��̂ł���B������������̂́A�ҏW�S���̌F���A��c���A�L���S���̋g�����A����Ƃ��ʂ̐�`�ۈ����B

�k�t�L�l
�ߔN�́k�����ܕ��Ɂl�́A���Ђ̊����̒P�s�{�̕��ɉ��������̖L�x�Ȏ��������������Ҏ[���╶�ɃI���W�i���ŋC��f���Ă���B��������ق��s���ȏ��œǂޖ��� ��̃����w���ق� ���k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A2017�N5��10���j�����̂ЂƂŁA���q�����̎��́q�����P�r�i�s�����P�t�j�Ɓq���炰�̉S�r�i�s�l�Ԃ̔ߌ��t�j��2�т����߂��Ă���B����2�т̖{�����s��{ ���q�����S���W�t�Ɉ˂��Ă���̂́A�{���̎��u��{�v���䂦���낤�B���Ȃ݂ɁA�����ɂɋg�����̎��͎��߂��Ă��Ȃ��B�q�m���r�i�C�E8�j��q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�����ȏ��ɍڂ���Ƃ͌���Ȃ����A���Z���Ɂq�Õ��r�i�B�E1�j��q�ߋ��r�i�B�E17�j��������͈̂����Ȃ��Ǝv���B
�q�w�G���I�b�g�x�[��� | mixi���[�U�[(id:8175386)�̓��L�r�ɁA�W��̐[����s�G���I�b�g�t�i�}�����[�A�k���s�����͌�q����l�j����肠�����Ă���B��]���O�Y�s���悤�Ȃ�A���̖{��I�t�i�u�k�ЁA2005�N9��29���j�́u�G���I�b�g�̎��W�Ƃ��Đ��܂�ď��߂Ĕ������A�����ɖ|��Ɖ�������킹���[����̖{�v�i�����A�l��y�[�W�j�Ƃ��āA�ʐ^�t���ŏЉ��Ă���̂��B���L�ɂ́u�w�G���I�b�g�x�[����i���a�O�\��N�l���\�ܓ��ĔŒ}�����[�j�A���ł����a��\��N�\����\�ܓ��A�k�w���悤�Ȃ�A���̖{��I�x�̎�l���l�Ë`�l����]���O�Y�Ƃ���A��]��1935�N����ŏ��a��\��N�ɂ͏\��B�������A�u�W���ΐF�v�́u�z�̕\���v�ł͂Ȃ����A�J�o�[�ł͂Ȃ����t�ł��B�����u�ӏܐ��E�����I�v�̈���Ƃ��ď��a��\��N�Ɋ��s���ꂽ�w�����P�x���������̃J�o�[�t�����{�̌Ö{���ɏo�Ă��邩��A�ĔŎ��ɊO�����܂߂ĕύX���ꂽ�̂ł��傤���B�^�c�O�Ȃ���k1940�N����2014�N�܂ł̒}�����[�̑���𑽐����߂��P�c�����Ғ��́l�w���e�̐X�x�Ɏ��^����Ă��܂��A����͋g�����ł͂Ȃ��낤���Ə���ɑz�����Ă��܂��v�Ə����I�������q�ׂ��Ă���B���̂����A�u���ш�Y����̃��X�g�ɂ��o�Ă��Ȃ��{�ł��B�������ɋg�����̃e�C�X�g�ł��ˁv�u�g�����̑���炵���{��������̂��y���݂̈�ł��v�Ƃ����R�����g�܂ł���ł͂Ȃ����B���̂قǐ[����s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�̍ĔŖ{�����������̂ŁA��������сk�ӏܐ��E�����I�l�V���[�Y�ɂ��ď����B�Ƃ��ɁA��f�����́u���ш�Y����̃��X�g�v�Ƃ͓��T�C�g�́s�g���������t�́q�W�@������i�ژ^�r�̂��Ƃ����A���̏��߁A1941�N�i���a16�N�j����1957�N�i���a32�N�j�܂ł��Čf����i����͖��m�F����\���j�B
1941�N �k���a16�N�l
�@�g�������W�s�t�́t�i����ɁA1941�N12��10���j
1952�N �k���a27�N�l
�@���O���A���E�O���[���i�ےJ�ˈ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A1952�N5��20���j
1953�N �k���a28�N�l
�@���c�Ǖ��E�a�c�F�b���s��t�S�W�k�S7���l�t�i�}�����[�A1953�N8��10���`1956�N6��20���j
1955�N �k���a30�N�l
�@�g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�N8��20���j
�@�k��1���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1955�N10��15���`1956�N9��20���j
1956�N �k���a31�N�l
�@�a�c�F�b�s��t�̓��L�t�i�}�����[�A1956�N6��30���j
1957�N �k���a32�N�l
�@�X���s���̖X�q�t�i�}�����[�A1957�N2��15���j
�@�a�c�F�b�s��t�̓��L�k���y�Łl�t�i�}�����[�A1957�N4��5���j
�@���Ɏ����W�s���D�t�i�}�����[�A1957�N6��20���j
�@���k��2���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1957�N10��25���`1958�N9��20���j
���Ă̂Ƃ���A�[����s�G���I�b�g�t�͋������Ă��Ȃ��B�����Łs�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�́k�ӏܐ��E�����I�l�V���[�Y�̋L�ڂ������i������3���̐����͒}�����[�Г��̐����̂��߂́u���{�ԍ��v�j�B
���ژ^�́u����v�Җ����̘^���Ă��邪�A�����ɂ͂��̃N���W�b�g���Ȃ��A�}���̎Г������������Ƃ��������킹��B�����Ȃ�Ƌg���������̉\�����łĂ���킯�ŁA�k�ӏܐ��E�����I�l�V���[�Y����������ɔ@���͂Ȃ��B
 �@
�@ �@
�@
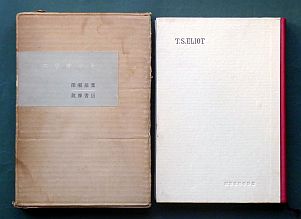
���������s�����P�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1954�N7��10���j�̃W���P�b�g�ƕ\���i���j�Ɠy�������s���t�W�k���l�t�i���A1954�N9��20���j�̃W���P�b�g�ƕ\���i���j�Ɛ[����s�G���I�b�g�k���l�t�i���A1954�N10��25���j�̃W���P�b�g�ƕ\���Ɠ����̍ĔŁi���A1957�N4��15���j�̔��ƕ\���i�E��2�_�j

 �@
�@ �@
�@
�c�����ȁs�����k�ӏܐ��E�����I�l�t�i�}�����[�A1955�N3��10���j�̃W���P�b�g�ƕ\���Ɠ����̍ĔŁi���A1957�N4��10���j�̔��ƕ\���i����2�_�j�ƌ��Έ�s���肵���̎��l�����k���l�t�i���A1956�N9��30���j�̔��ƕ\���i���j�ƍ��������s�{�[�h���[���k���l�t�i���A1956�N10��25���j�̔��ƕ\���i�E�j
1956�N�ȍ~�Ɋ��s���ꂽ���Έ�s���肵���̎��l�����t�ƍ��������s�{�[�h���[���t�i����������Łj�A�c�����ȁs�����t�Ɛ[����s�G���I�b�g�t�i��������ĔŁj�̎d�l�݂͂ȓ����ŁA�i�{�[���̋@�B���ɓ\���ӁA�{�͔̂w���N���X�ŕ��̂قڑS�ʂ����̌p���\���Ƃ����̍قł���i���@�͂��ꂼ��O�f�ژ^�́u�a�U���v���ꔪ��~���܁A�u�l�Z���v���ꔪ��~��~�����[�g���j�B����A1954�N����55�N�ɂ����Ċ��s���ꂽ���4���A����Ȃ����������s�����P�t�A�y�������s���t�W�t�A�[����s�G���I�b�g�t�\�\�����ɂ��đ�]���O�Y�́u�{�ɂ̓_�X�g�J���@�[���|�����Ă������A�Ë`�l�͂�����O���āA�����߂��炵�������z�̕\�������������ƌ����B�W���ΐF���������̂��F�āA��̂ւ�m�A�A�n���璃�F�̂��݁m�A�A�n���~��ė��Ă���c�c�v�i�O�f���A�l��y�[�W�j��50�N�ɂ킽��o�N�ω����L���Ă���\�\����ѓc�����ȁs�����t�́A�㐻�E�z���ɃW���P�b�g�Ƃ����̍قɂȂ�B���L�̋L�ڂ̂悤�ɂ��ǂ��Ă����A�s�}�����[�}�����ژ^�t�̐��4���i�a�U���j�͍ĔŎ��Ɍ��2���i�l�Z���j�Ɠ����̍قɉ��߂�ꂽ�ƍl������i�����Ƃ��A���������s�����P�t�Ɠy�������s���t�W�t��2�^�C�g���́A�ĔŖ{�������ł��Ă��Ȃ����肩�A�����I���������e�i�摜�j�����\����Ă��炸�A���ł̂܂܂ōĔł���Ȃ������̂�������Ȃ��j�B���̂悤�Ȃ��Ƃ��V���[�Y������Ȃ�Ƃ������A���s�̓r���ŋN������̂��낤���B�i�����܂ł����肾���j�u����䂫�������̂͑����̂���������A�O������V���悤�v�Ƃ������ނ̕��j�]�����}�����[�̓����łȂ��N�����̂��A�傢�Ȃ�^�₾�B�����A�����ɂƂ��čő�̖��́A�����҂̃N���W�b�g�̂Ȃ������2��̑������g�����̎�ɂȂ邩�ǂ����A�Ƃ����_�ɐs����B�Ƃ���ŁA�����̍��������s�����P�t�̉��t���Ɂu�ӏܐ��E�����I�S10���v�Ƒ肷��L��������̂ŁA�ȉ��ɘ^����i���e�Љ���Ȃ��āA�����͐V���ɉ��߂��B�s���ɕt��������͊��s���ꂽ���ڂ��A�~��͊��s����Ȃ��������ڂ�\���B�y�@�z���͏��т̕�L�j�B
�[���́s�G���I�b�g�t�́A�k�ӏܐ��E�����I�l�̂Ȃ��ł�������A�k�}���p���l�ɓ������i1968�N1��26�����B1966�N�ɐ[�����f�������߁A�����Ő[�����Y�K�j�ƂƂ��Ɏ��M��S���������c�͈�Y���q�u��L�m���Ƃ����n�v�̂��Ƃ����r�������Ă���j�B���́k�}���p���l�����AWikipedia�́q�I���r�̐����ɂ���悤�ɁA�l�Z���E�����̓��ꂳ�ꂽ�̍فE�����ŁA�u�P�s�{��I�������Ă����V���[�Y�ɂ́A�����̗����Ċ�����Ƃ����}���p�����������v�i���j�B���ɖ{�V���[�Y�����ĂȂ���������̒}�����[�́A���Ђ̏o�ŕ��𑼎Ђ̕��ɖ{�̑������ɂ���܂��ƁA���^�̍ė��p��}�邱�ƂŒ���Ȕł��k�}���p���l�̖��̉��ɍĊ������^�C�g���������i�s�q�g�����r�́u�{�v�t�Ō����A���e���O�Y�s���{�t���K�X�g���E�o�V�����[���i�a��F���j�s���݂錠���t�Ȃ��j�B�k�}���p���l�ɂ͑��Џo�ŕ���f�����������\�\�푺�G�O�̌��Łs�i���Z���X���l�̏ё��t�i�|�����X�A1969�j���s���� �i���Z���X���l�̏ё��k�}���p���l�t�i�}�����[�A1977�j���o�ās�i���Z���X���l�̏ё��k�����܊w�|���Ɂl�t�i���A1992�j�ƂȂ����̂́A���܂���̂����܂�ׂ����ɗ�������������������\�\���������A���ВP�s�{�̏ꍇ�������̂܂܁i�f�b�h�R�s�[���j�N�����̂ł͂Ȃ��A������t������Ȃǂ��ĉ��l�����߂悤�Ƃ��Ă���B�����Ƃ��s�G���I�b�g�t�̏ꍇ�A�k�ӏܐ��E�����I�l�ɂ�������������������Ă��邽�߁A�k�}���p���l�͑S�ʐV�g�݂ƂȂ����B�[���́s�G���I�b�g�t�͒��Ҏ��g�ɂ��u�{���́u�ӏܐ��E�����I�v�̈���Ƃ��āA�G���I�b�m�̏������W�̊����ɂ���w�i�E�A���t���h�E�v���[�t���b�N�̗��́x����A���сw�r�n�x�����ӂ��߂āw����Ȃ�l�X�x�ɂ�����܂ł̏\�O�т̎����A�l���A�S��\�Z�т̂Ȃ�����I��ŁA����ɓK�x�̉��߂Ɗӏ܂��{���A�G���I�b�m�̎��ɂ͂��߂Đڂ���ǎ҂����ᒆ�ɂ����āA����܂�����ł͂Ȃ������m��Ȃ����A�Ƃ�����������̓ǂ݂��̂���肠���悤�Ƃ������ŏ����ꂽ���̂ł���B�����Ƃ��G���I�b�m�̎����̑O�����̎���̑�\�I�Ȃ��͖̂w��ǎ����ꂽ����ł���B�`���͂��Ƃ��o��̂܂ւł���v�i�����ĔŖ{�A�Z�y�[�W�B�����͐V���ɉ��߂��j�B��]���O�f���ň��p���Ă���q�Q�����`�����r�{���̖�A�`����7�s�͂������B
�܂��肢�ł܂���������͉J�Ȃ����̘V���̐g�A
���m���ׁn�ɂ���椂܂��T�A�J�̍~��̂�҂Ă܂��B
���ЂƂ��т��������D�Ђ̏��ɗ��������ƂȂ�
�͂��~�肵����J�𗁂�
�d�V�ɕG�Ђ����A����т瓁�U�肩�Ԃ�
�ԂƁm�A�A�n��嚙�܂�ĝD�Ђ����Ƃ���ɂȂ��B
�킽���̉Ƃ́A�ڂ뉮�ł��A�i�s�G���I�b�g�t�ĔŖ{�A����y�[�W�j
�O�f�u�ӏܐ��E�����I �S10���v�L���ł́u�G���I�b�m�����ɂ��Ă͑��l�҂��钘�҂��A�Ƃ��Ɏ��l�O���̑�\�I������ԗ����A�ڍא����Ȏ߉���t�����B����́A�P�Ȃ�A����̈�Ɏ~�炸�A��������Ēm���鎍�l�̎v�z�̐[���Ɍ������āA�͂��߂Ă��̓�\���I�p�����d�̍ō���ɐڂ���l�ɂ����̎��z�̍�����`����v��搂��Ă���B�K���Ȃ��Ƃɂ��̊�}�͌}�����A1954�N�x�̑�6��ǔ����w�܁i���w�����܁j����܂����i�ĔŖ{�̊��s���������邩����A����܂������̒��ڂ̌_�@�ƂȂ����킯�ł͂Ȃ��悤���j�B
���Ė{��ɖ߂��āA�s�G���I�b�g�t�̍ĔŖ{�͋g�����������ۂ��B�S�~��Y�ɂ�钆�����ق�̃C���^�����[�L���q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�i�s�����C�J�t2003�N9�����j�́A�g�����肪�����S�W�E�p���ނ̑����̌����Ƃ��ĂԂׂ����e�����A���߂Ă����ŐU�肩����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�����4���ڂ��k�ӏܐ��E�����I�l�̐��4�_�i�㐻�E�z���ɃW���P�b�g�j�ƍĔł�2�^�C�g�����܂ތ��4�_�i�i�{�[���̋@�B���ɓ\���ӁA�{�͔̂w���N���X�ŕ������̌p���\���j�ɏƂ炵�Ă݂�ƁA�Ƃ�킯�i3�j�̖���������邽�߂ɓ\���ӂ��̗p�������4�_���g���������̂悤�Ɍ����ĂȂ�Ȃ��B�{���ɂ����i1�j�����|�C���g�̃J�b�g�����4�_�ɂȂ����Ƃ����邱�ƂȂ���A���4�_�̃W���P�b�g��{���̊w�͗l�͂ӂ���g�����p���Ȃ���@�ł���B�\�\�ׂ������Ƃ������4�_�̖{���̓X�~�Ɠ��F��2�F����ŁA���̓��F�͔��̓\���ӂ̐F�ƈ�v���Ă���B���Ȃ킿�s���肵���̎��l�����t���W����F�A�s�{�[�h���[���t���F�A�s�����t���I�����W�F�A�s�G���I�b�g�t���Z���D�F�ł���B�����ɏI�����4�^�C�g���i�s�Q�[�e�t�s�m��t�s�m�ԁt�s�v�[�V�L�� ���[�������g�t�t�j�ɂ��ŗL�̓��F�����肠�Ă�F�ʌv�悪�������͂������A���ƂȂ��Ă͒m��R���Ȃ��B����ɖʔ������Ƃ�����B�w�̃N���X���ŏ��́s���肵���̎��l�����t�����F�ŁA�ȉ��́s�{�[�h���[���t�s�����t�s�G���I�b�g�t��3���Ƃ������ԐF�Ȃ̂��B�ԂƐ�Δ䂳����̂͋g�������̃A�v���[�`�ŁA�ق��̏��Ŏw�E�������Ƃ����邪�i�q�g�����̑�����i�i121�j�r�Q�Ɓj�A���̂��ƂɊւ��Ď��͂�����������B�s���肵���̎��l�����t�̓��F�ɒW����F��I���_�ŁA�N���X�͂��̋t�������ĐF�ɂ����B���́s�{�[�h���[���t�̓��F�ɂ͐F��I�̂ŁA���x�͔��ɃN���X��ԐF�ɂ����B�����܂ł͂����B�Ƃ��낪���̎��́s�����t�̓��F�ɃI�����W�F��I���_�ŁA���ޒ��B���Ȃɂ��ō�����肪�����āi����Ƃ��P�Ɂs�{�[�h���[���t�̐ԐF�P���������H�j�����ĐԐF�̃N���X���g�p�����̂ł͂Ȃ����B���܂��苖�ɏW�܂����{����y�y�Ɍ��_���o�����Ƃ͊댯�����A�k�ӏܐ��E�����I�l�̖{���┟�E�\���̔w���炾���ł����܂��܂Ɍo�܂��l�����āA�����͐s���Ȃ��B�\�\
 �@
�@
�}�����[�����s�����k�ӏܐ��E�����I�l�̌��Έ�s���肵���̎��l�����t�i1956�N9��30���j�A���������s�{�[�h���[���t�i1956�N10��25���j�A�c�����ȁs�����t�i�ĔŁF1957�N4��10���j�A�[����s�G���I�b�g�t�i�ĔŁF1957�N4��15���j�\�\���Ȃ킿�A�{���ɂ����u���4�_�v�\�\�̖{���i���j�Ɠ��E���ƕ\���̔w�i�E�j
����Ɍ��4�_�̏������i1�j�S�`�b�N�̂��g���Ă���̂́A���4�_�̂���P�������߂ł����āA�g�����Ȃ�̐�����Ȃ����̂�I�������Ȃ�A���邢�͗p���邱�Ƃ��Ȃ�������������Ȃ��B���ɔ��̏��������S�`�b�N�̂����i���̃S�`�b�N�̂́A�F�x�^�̒n�ɔ��k�L�������{���Ă��邽�߁A�Ӗ��̂���p�@�ł���j�A�\���̔w��{���̏����ɖ����̂��g�����Ƃł���ɑR���Ă���B�i4�j�̌��Ԃ������A���4�_�̓N���[���F�̖{���p���n�B���4�_�͂����W���ΐF�̃t�@���V�[�y�[�p�[�n�ŁA�����炭�\���̔��Ɠ������B�����̏��_�܂���ƁA���4�_�͋g�����ȊO�́A���4�_�͋g�����ɂ��A��������}�����[�̎Г������������ƍl������B����āA�`���Ɍf�����q�W�@������i�ژ^�r�����̂悤�ɏ������������B
����̌p���\���i�w�F�N���X�A���F���j�̏㐻�{�́A1980�N��̋g���������ł͓o�ꂷ��̑����A�����X�^���_�[�h�Ƃ�������d�l�̍ق����A���ݔ������Ă��邩����k�ӏܐ��E�����I�l�����[�ł���B����ɂ܂��A����1980�N��ɑ��p�����g�����̕\�\���E�w�E���\���ɑ��ӂ�\���点��X�^�C�������ꂪ���o�ꂾ�B�Ƃ���ŁA�ɒB���v�̊��s���������͓c���x���s���惆���C�J�̖{�t�i�y�ЁA2009�j�Ŗ��炩�ɂ����悤�ɁA���̎a�V�ȑ����ō����̎����������������邪�A�g������|������t�⑾�ɂ̑S�W�Ƃ������A�����ɂ��}�����[�炵���\������̏㐻�{�ɑ��āA�����[�ɂ����鎍���̑����ɐV���ʂ�v���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����i�Ⴆ���s���̖{�k�S3���l�t�j�B���Ă��������ɂ́A�܂�����Ȃ����惆���C�J�{����w�G�b�Z���X���Ïk����Ă���B����������l���́A��͂�g������[���ĊO�ɂ���܂��B�g���́k�ӏܐ��E�����I�l�œ����艞�������ƂɁA���̎��������̃��C���������̎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�̔���A�����E�~�V���I�i���C�i���j�s�v�����[���Ƃ����j�t�i���A1959�j�̕\���Ȃǂő�_�ɐL�����Ă䂭���ƂɂȂ�B
�g�������͌����f�j�̋�ɂ��ď������ł��܂Ƃ܂������͂́q�͌����f�j�W�r�̉���q���f�j�̔��w�r�i���o�́s����o��S�W�k��5���l�t�������[�A1978�N1��5���B�Ȃ��{�e���M�҈���1999�N4��15���t�͌����f�j���ȂɁu�u���f�j�̔��w�v�́w����o��S�W�x���w�u�����v�Ƃ����G�x�i1988�N�E�}���p���j�́u���f�j�̔��w�v�̕����A���o��̕\�L����萳�m�ł��v�ƌ�����j�ł���B�g���͔��f�j�̍�i�̓��ِ����������̂ɁA�܂����f�j�̎t�ł���i�c�k�߂́u���̎�p�I�ȕ\���ɂ��A����̐Օ����D�G���ނȓ��]�̂͂��炫�̐Օ��炵����R�Ƃ������邩���ނ�������v�Ƃ����]���܂ށA����W�s�G���_�m�����䂤���n�t�i�o��]�_�ЁA1968�j�̏����̈�߂̈��p����n�߂Ă���B�g���́u�s�G���_�t��S��̂Ȃ��ł��A���̘Z��͏G��ł���A���f�j�̑S��i�̂Ȃ��̑�\��Ƃ����Ă��悢���낤�v�Ƃ��āA���̋���f����B�i���ȉ��͎Q�Ƃ̂��߂ɕX�I�ɐU�����ԍ��B�����āA��o�s�͌����f�j��W�t�f�ڌ`�Ɠ����ꍇ�́���A��`��\�L���قȂ�ꍇ�́���̂��Ƃɓ����f�ڌ`���f���A�����Ɏ��^����Ă��Ȃ��ꍇ�́~���t�����B�p�[�������̐����͓����f�ڃy�[�W�j
�@�@�O���₱����̒��͌����ꂵ�܂܁�1���i10�j
�@�@�S�g�̑啔���͐��ɗg�H��2�~
�@�@��̊��̌u���Ă̒����ԁ�3����̊���壂��Ă̒����ԁi16�j
�@�@���̗���G��č݂肵���ȁ�4�����̙_��G��č݂肵���ȁi10�j
�@�@���������͂�ւЂƂ������ʁ�5���i12�j
�@�@��e�܂ōs���Ɏl�ܐl�˂ꂯ�聞6���i17�j
����ɂ͌��ƂȂ関���s�̕��͂�����B���Ɂq�͌����f�j��W�s�G���_�t���ꏴ�r�Ɩ��t�������ȕ��ł���i���o�́s�Ս��t226���k1969�N2���l�A����q���G���_���ꏴ�r�j�B�����������B
�q���f�j�̔��w�r�Ɍ�����u�������͈�{���āA���z�����߂�ꂽ�B���̕��͂���������Ȃ��̂ŁA�����Ȃ邱�Ƃ����������͖Y�ꂽ���A������u�̔��w�v�ł���Ƃ��������Ƃ��L���Ɏc���Ă���B�Ȃ����́u�̔��w�v�ƒf�肵���̂��낤���\�\�B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�Z�y�[�W�j�́u���z�v�����ꂾ�B�g���́s�G���_�t���炳���10����f���Ă���B
�@�@�����͂ݏo���̕����ꂯ�聞7�~
�@�@��͑��̓����ʼn̕������Ȃ��灞8�~
�@�@�~�Â����͗��鑠���聞9���~�Â����͗���ЂƂ�ށi10�j
�@�@�g�̒��̂܂Â���̌u��聞10���g�̂Ȃ��̂܂Â����壎��i9�j
�@�@�g���o�łĐ������ވÂ����́�11���i13�j
�@�@�ʂ̈�͓��W�̂Ȃ��ɕ�����12���ʂ̈�͓��W�̂Ȃ��ɟ����i17�j
�@�@�c�����͉��݂��Ƃ��с�13�~
�@�@���ɗ��Ă��炭���̗��ނȂ聞14�����ɘ҂Ă��炭���̗��ނȂ�i14�j
�@�@���̐��◜�͓��ɉ͐��Ɂ�15�~
�@�@���̉e���O�ڂ����ĕ��P���ȁ�16�~
�Ƃ��ɁA�g�������͌����f�j�̋�Əo������̂�1967�N�A�����d�M���ҏW����s�o��]�_�t�̑�O��o��]�_�܁E�o�啔��̐R�����i���ɍ������H�E�����d�M�E�˖{�M�Y�E�i�c�k�߁E�O���鏗�j�Ƃ��Ăł��낤�i�g���������ɐ����Ĕo��]�_�܂̑I�l�ψ��ƂȂ����̂�1962�N8���j�B��O���i����g�����I�͎̂��c���j�q���ꂤ���q�C�L�r�i�R�_�j�ŁA�����Ő������͌����f�j�q�����r�i�P�_�j���u�ÓT�h�̕��i������v�ƕ]���āA
�@�@�C�̏ꏊ�ɏt�̊C�݂�ȕ�����
�@�@�����␅��˂̏H�̐�
�@�@�ŘV���Ă��������Ƒ�����ɂ���
�������Ă���B�Ȃ��g���́A���́s�o��]�_�t72���i1967�N9���j�́q�o��]�_�܌���܂ŁE�o�ߕƑI��]�r�ŁA
�@�����P������W�Ɂs�`�t�i�s�����@�A1994�j�A�s��ًL�t�i���A1996�j
�@���R�b�q�j����W�Ɂs�сt�i�C���ЁA1986�j�A�s���t�i�C���V�ЁA1991�j�A�s���t�i����o�勦��A1995�j
�@����i�Îq
�@������q����W�Ɂs�����t�i�[�k�ЁA1986�j
�@����
�@�������Y
�@�Óc���V
�@�l�{�s��
�@�O���F�q
�@�剪��i����W�Ɂs�剪��i�S��W�t�i�Y���H��ɁA2002�j
�̋�ɐG��Ă��邪�A���̑I�]������y�����͎̂��c���j�Ɖ͌����f�j�������낤�B���āA�q���f�j�̔��w�r�ő���W�s���m�݂n�t�i�����A�A1970�j����������͎̂���11��B
�@�@�ւ���������O�F�Â��ʁ�17���i24�j
�@�@����ł�峂̌`�����ĚL���聞18���i28�j
�@�@�����ΌN�̂Ȃ��ɍ̉ԓ��肯�聞19���i22�j
�@�@���l�Ԃ���葐�ɒ��т��ʁ�20���i26�j
�@�@���T�q���͂����₫�ċ��肵���ȁ�21����Ꝏq���͂����₫�ċ��肵���ȁi23�j
�@�@���݂�₵�����������̋���҂�����22���i30�j
�@�@�قƂƂ������֎��Ȃ莵����23���i26�j
�@�@���N��łĂ��H�̍�����24�����N��łĂ��H�̍���ᢂ��i25�j
�@�@�N���w�ɈÂ����̕��ӖH�E�݁�25���i23�j
�@�@��⎀�Ȃ˂ΌN�̘V���䂭����26���i24�j
�@�@��݂���[�ė���ċ��肵���ȁ�27����݂���[������ċ��肵���ȁi26�j
�����s�U���q�͌����f�j��W�s���t������r�i�s�Ս��t249���k1971�N3���l�A����q�q���r������r�j�ɂ͏�f�u�قƂƂ����v��23�A�u���l�ԁv��20�A�u�����ΌN�́v��19�A�u���T�q�v��21�A�u���݂�v��22�̂ق�
�@�@�X�ʋ������z�肫����Ɂ�28�~
�@�@�L�ނ��ɉ����ċ���ʁ�29���L�Ђ����ɉ����ċ���ʁi29�j
�@�@�o�y�H����z����坂ɕ������҂Ă聞30���o�Ђ�����坂ɕ������҂Ă�i27�j
�@�@�H���ɛz��ĕR�̓������ȁ�31���H���ɛz��ĕR�̂��������ȁi28�j
�������Ă���A�u��������d�C�ɖ��������i�Ǝv���܂����A���ƂɍŌ�ɒu���ꂽ�u���������v�̋�́A�⏥���Ǝv���܂��B�l�Ԃ̓��Ƃ��������̓����o���̉e���݂��āA�Ȃ����������������Ă��邩��v�i�����A��܃y�[�W�j�Ƃ���B��O��W�s腕���l�m����Ԃ��������n�t�i���ȎЁA1971�j����͎���5��B
�@�@�����߂��ĉ̍J����S�H��32���i33�j
�@�@������R�����芪�L�݂聞33�~
�@�@���ʂ∸���̂�낱�т͋����Ɂ�34�����ʂ∸���̂�낱�т͋����Ɂi42�j
�@�@�R�Ђɂ��̂�ɗ��ތ��邩�ȁ�35�~
�@�@�H����݂ȏ\��ʂ̑��̌���36���i42�j
�g���͖����s�U���q�͌����f�j��W�s腕���l�t����r�i�s�Ս��t257���k1972�N1���l�A����q�u腕���l�v����r�j�Łu������R�����芪�L�݂聞33�v������肠���āA���̂悤�ɏ����Ă���B
�ЂƂ���f�j�Ɍ��炸�A�g���������̓I�Ȉ��ɂ��Ę_�����ł��ڍׂȕ��͂̂ЂƂ����ꂾ�B�q���f�j�̔��w�r�ɑg�݂��܂�Ȃ������m���闝�R�͂킩��Ȃ����A���f�j��̕]�Ƃ��Ĉ킷��ɂ͐ɂ����͋�ł���B��l��W�s���m�Ȃ��ꂭ�����₤�n�t�i�o��]�_�ЁA1975�j����͎���6��B
�@�@���A���H�͓V�̗����聞37�����d���H�͓V�̗�����i46�j
�@�@�����Â���C�̒��V�ɂ�ā�38���i49�j
�@�@���P��������t�𒀂Ђ䂯�聞39���n�P��������t��ǂЂ䂯��i55�j
�@�@�^������ɂ͂����Ђ����Ȗс�40���i55�j
�@�@��C��ⴂ͕�ࣂ��݂聞41���i57�j
�@�@�ĂӂĂӂ␅�ɕ��������b���42���i50�j
�q���f�j�̔��w�r�͂����ŏI��邪�A�͌����f�j�ɂ͂��̂��Ƒ�܋�W�s�d���ɖ�m���肾��n�t�i�ʏ��[�A1980�j�A��Z��W�s�����m�Ăӂ��n�t�i���ȎЁA1987�j�A�q��a�u�m��܂Ƃ��n�r�i�����A1989�`1995�j�A�q�i�����m�������n�r�i�����A1987�`1996�j������B���������߂�������W�s�͌����f�j��W�t�i���ȎЁA1997�N9��15���j�͋g�����f��̊��ł���A�Ō�ɓǂ�W�́s�����t�ƂȂ�B�g�����s���ȁt15�E16���i1987�N11���j�Ɋ��q�w�����x�̏\��r�Ɏ��̋傪������B
�@�@�N���܂���͂ɓM����ߖ�43���i77�j
�@�@���̂��ɂւ�挴�̒��d�M������44�����̂������ւ�挴�̒��d�M�����i81�j
�@�@�~係��̐��l�ܓ����ꂽ���Ɂ�45���i91�j
�@�@�V�����������݂Ė������͂��ށ�46���i88�j
�@�@�ĂӂĂӂ�V��㮍��m���₭�n�悬���47���ĂӂĂӂ�V��㮍��悬��i91�j
�@�@ꔂ��ȓE�݂Ē��ނ�B�̉ԁ�48���i82�j
�@�@儒��ǂ̎}������Ȃ肫��49���i102�j
�@�@����݂����ꂵ���̉���50���i95�j
�@�@���قނ炳����虛�m���ق���n�����N�S���遞51���i104�j
�@�@�j�̉Ԃ݂Ȑ����߂����₵���Ɂ�52���i104�j
�͌��͓����́q�����^�r�ŋg���̏��Ȃ������Ă���B�����ɂ́u�k�c�c�l���āu�����\��v�����ɓ����������܂��B��ǂ��āA�O�\�Z��𒊏o���A�قڈꂩ����ɁA�ēǂ��Ă��̏\���I�т܂����B��������G�Ⴞ�Ǝv���܂��B�̂Ă����������f���܂��v�i�����A��O�y�[�W�j�Ƃ���
�@�@�����Ђɂ�鎀����ݔ����Ęҁm���n��53���i85�j
�@�@���̝ꈢ�C���̈�w�����ӂ�ށ�54���i77�j
�@�@��̖����Ɋ��q��ꂵ��X�߁�55���i89�j
�@�@�̋��⍡���������₭��͌K�⁞56���i96�j
�@�@�t�[���ӂƒ��k���₵������57���i90�j
�@�@����E�ӓV�Ɉ����B������58�����n�E�ӓV�Ɉ���誓����i96�j
6�傪������B�Ȃ��͌��ɂ́s�͌����f�j��W�t�́q�i�����r����W�s�����t�̂��ƂɌJ�肳���āA�q���݁m������n�r�i�����j���u�w�i�����x�ȍ~�̋���N�߂āA�I�̈�W�Ƃ�����́v�i�q�S���r�A�s�͌����f�j�S��W�t���ȎЁA2003�N9��23���A�ꎵ�l�y�[�W�j�Ƃ����u���v�i����W���O�Z������߂��S��W�҂͂����Ăԁj������B�Ō�ɁA���g�̊������r�݂���Ƌg�����Ǔ��������������B
�@�@���f�j����F�m�����n���ė]����铍���k�s�����t�l
�@�@������蒟�����̏Z���Ȃǁk�q���݁r�l
�k�t�L�l
�{�e�Ɉ������u�k�s�����t���l��ǂ��āA�O�\�Z��𒊏o���A�قڈꂩ����ɁA�ēǂ��Ă��̏\���I�т܂����v�Ɍ�����悤�ɁA�g���͋�W��ǂ�ŁA�܂��D���ȋ�𑽂߂ɒ��o���A�������炳��Ɏw��̐��ɂȂ�悤���I�����悤���i�u�ēǁv�̑Ώۂ��s�����t�S���Ȃ̂��A���o�����O�\�Z��Ȃ̂��͔��������j�B�Ƃ���Ŏ��͕��ɔłȂǂ̗��z�{�̏ꍇ�A�C�ɂȂ����ӏ��̂���y�[�W�̏㕔�̊p���i�m���u����������悤�Ɂj�܂��Ėڈ�Ƃ��Ă���B�E�B�L�y�f�B�A�Ɂu�{��G���Ȃǂ̂��݂�܂�Ȃ��邱�Ƃɂ���āA���������Ɋ��p���邱�ƁB�p�܂�Ƃ������v�Ƃ���u�h�b�O�C�A�iDog ears�ADog-ear�j�v�����ꂾ���A���������łȂNjH���Ȗ{�̏ꍇ�A�tⳂ�\���āA�]�L��R�s�[�Ȃǂ̍�Ƃ��I�������A�����ɔ������B�܂�A��{�I�ɏ������܂Ȃ��B�����𒆐S�Ƃ���g���������̖{������������������A��������{�͂Ȃ������B�����Ƃ��A�C�ɓ�������Ɂ�����̃`�F�b�N���قǂ����͓̂Ǐ��l�̂悭���邱�Ƃ�����A�g���������������@���Ƃ�Ȃ������Ƃ͒f���ł��Ȃ��i�U�������p����ꍇ�A�g�����T���ɂǂ�Ȉ��t�������ɂ�����ȋ������o����j�B���āq���f�j�̔��w�r�ɂ́u�k�q�͌����f�j��W�s�G���_�t���ꏴ�r���l��������Ȃ��̂ŁA�����Ȃ邱�Ƃ����������͖Y�ꂽ���A������u�̔��w�v�ł���Ƃ��������Ƃ��L���Ɏc���Ă���v�Ƃ���B����͋g������A�ł͂Ȃ����낤���B�܂�s�G���_�t�̖{�����u�̔��w�v�ɑ�\�����āA���ǂ̂Ƃ��̐����Ȃ��������Ƃɂ��邽�߂́B�q���f�j�̔��w�r�ōő��̏\�Z����������s�G���_�t����̋�Ɂu�����Ƃ����̂𑠂��ė��Â��v�u�߂����g���f�R�ɕ���𐂂炷�v���Ȃ��̂́A���̓��͂�߂Ă������A�Ƃ����ӎv�̌���ɂق��Ȃ�Ȃ��i���Ƃ����f�j���I�́s�͌����f�j��W�t�s�͌����f�j�S��W�t�Ɍ����Ȃ��̂́A���R�ł͂Ȃ����낤�j�B�ЂƂ��ёI���̂��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����A���͔@��̂悤�ɍl���āA��O�I�ɏ�f���ɔԍ���U�邱�Ƃ����Ȃ������B���̓����Z������A�g����������f�j��͍��v�Z�\��Ƃ������ƂɂȂ�B
�k2021�N9��30���NjL�l
�����V���q�s�Ђ��t�i�{���ЁA1963�N3��5���j�́A�z�c�ށs�Ђ��k���̂Ɛl�Ԃ̕����j 57�l�t�i�@����w�o�ŋǁA1986�j���q�Q�l�����r�̕M���ɋ�����R�Ɋւ�����I�Ȓ��삾���A���́q�i�����́u�Ђ��v�r�ɕR�Ɩ�ʂɂ��Ă̋����[���L�q������B
�@�f���ʐ^�ł����m�̂悤�ɁA�D�̐i�����ɂ͐i�����钼�O�ɑD�̑D��ɖ�ʁm�������܁n�Ƃ����傫�ȏ���ʂ��Ԃ牺���đD���i�����鎞�ɂ��ꂪ���āA�����疳���̐F�����U�蔵�Ȃǂ��Ƃт����B
�@���̖�ʂ�D��ɒ݂艺����ܐF�̂��ꂢ�ȁu�Ђ��v��i����ɐ��f���ĊW�҂ɂ��₤�₵��������A���ꂪ�Ȃ�Ƃ��̐��f���ꂽ�ܐF�́u�Ђ��v���A���Y�̌���ɂȂ�Ƃ�����������ɕۑ������̂ł���B
�@�܂���͋��D���������������Ė����ɊC�ɐ��܂�邱�Ƃ͈��Y�̏ے��ł����낤����A���̏j�Ɋւ���u�Ђ��v�̒��ł����Ƃ��͂Ȃ₩�Ȗ�ʂ̂�Ђ������ɂȂ�̂����ȂÂ��悤�B
�@���D�W�҂ɂ͌Â�����m���Ă��邱�Ƃł��邪�A��ʂɂ͒��炵���u�Ђ��v�̌��p�ł��낤�Ƃ����ɂƂ肠���Ă����点���邵�����ł���B�i�����A��Z��y�[�W�j
�O�H�d�H�Ɓi���D�����2018�N�ɎO�H���D������ЂƂȂ����j�̒��葢�D���ɂ͎j���ق�����B�����ɓW������Ă����i�����ōs���x�j�ؒf���Ɏg��ꂽ���͂͂����良���Ă�����̂́A�R�̕��͂��������ǂ����L�����肩�łȂ��B���̕R�����̎����Ƃ��ĊW�҂ɔz��ꂽ�̂Ȃ�A�W���ɂȂ��Ă����R�ł���B�u���{�ɂ�����i�����ł́A�܂����������s��ꂽ��A�x�j�ؒf�̋V�����s���B���̎x�j�͂����ʂƃV�����p���ȂǂɌq����Ă���A�ؒf�ƘA�����ăV�����p���Ȃǂ��D�̂ɒ@��������Ɠ����ɑD�����Ă��������O��A�����ʂ������A�����ʖ{�̂Ƃ��̎��ӂ����ʂ̎��e�[�v�E������Ȃǂ��������A�i���������i�܂��̓h�b�N�ɒ������j�i���ƂȂ�B�v�iWikipedia�q�i�����r�j�B�����ɂ��ܐF�̕R�̎p�͂Ȃ��B
�ˋ�̏����A�g�����ҁs�k�����H���̏W�t�ɂ��čl���Ă݂悤�B�g�������H�̒Z�̂Ɋւ��čŏ��ɔ��\�������͂́q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�i���o�́s�Z�̌����t1959�N8�����j�ł���B����͂����n�܂�B
�����ĒZ�̏\���Ɛ����̓��������Ă���u��ǂ��ĒN�̉e�������������́A�����Ȃ��Ƃ��Z�̂̍D���Ȑl�ɂ͂킩��ł��낤�B���̂Ȃ��̂قƂ�ǂ��A�k�����H�́s�Ԋ~�t�i�˂̉ԁE�_��W�E���̗��E�����Ջ�W�Ȃǂ��珴�������́j�A���Ⴄ�����̍��A���ǂ����s�����t�v����t�̝R��F�Z�������Ă��邩��B�k�c�c�l�ɒ[�ɔ��ӎ��̂悢���́A�N�����s�˂̉ԁt�̉̐l���H�X�|�����B�ނ���������Ƃ����悤���B�������Ƃ���Ă��������A�s�@��t��s�v�Џo�t�A����Ɂs���n�W�t�̎��l���H�ł͂Ȃ����Ƃ��B�����Ă݂�Ύ��͔��H�̎��ɂ͒^��Ȃ������B�Ђ�����s�˂̉ԁt�Ɓs�_��W�t�݂̂A�˂��Ă����v�i�����A�Z�܁`�Z�Z�y�[�W�j�Ə����B�g���������Ōf���锒�H�̒Z�͎̂��̏\���ł���B�i���ȉ��͎Q�Ƃ̂��߂ɕX�I�ɐU�����ԍ��j
�@�@�s�˂̉ԁt����
�@�@����͂ĂɉT��������̂��Ȃ��݂̂��肻�߂ʂ�Ό܌��m�����n�͂����遞1
�@�@�܂�����ޏ����̖��Ȃ�ޗ[�Ƃǂ낫�̉���������遞2
�@�@���������ƍL���������Ȃ�t�݂̂₱�̂��Ђт��̎���3
�@�@���L�����딖���Ȃ鐅��̕r�ЂƂ����H�͗��ɂ��聞4
�@�@�ǂ����݂̉Ԃ̂ɂقЂ��v�ӂƂ��݂Ĕ���N���܂Ȃ�����5
�@�@�s�_��W�t����
�@�@��m�ӂ����߁n�͑�n�̏�͕����˂����ɂ����Ƃ��낪��ɂ��聞6
�@�@�傫�Ȃ�肪����͂�Ē��ӂ����ォ�痑�����݂��邩����7
�@�@���łĂ�腖��剤����Ȃ�͖ؓ�O�{���낿��聞8
�@�@���͂̂�O�Y�O��͛��̐_��Ԃ������čՂ��Ƃ��끞9
�@�@�s���̗��t�̂����́q�����Ջ�W�r����
�@�@�꒹�̊�������̗[���˂����날�����t�����ʂ�ށ�10
�@�@���������̖�ǂ̉Ƃ����m��������n�鏒�̉ԁ�11
�@�@���悢�抦�����J�ꗈ��c�̕Ж����Ȃ�傪�܂��킽�錩�䁞12
�g�����Ƃ�킯�������͔̂��H�����̒Z�̂������B�q�~�ς��肤���r�͂����I����Ă���B
���̐��z�܂��Ă̂��Ƃ��낤�A�{�A���ɂ́s�R�X���X�t1972�N11�����q���W�E�k�����H�\�\�v��O�\���N�L�O�r�́A�g���́q�s�Ԋ~�t��r���ڂ��Ă���i�����W�̕M�҂́A�͐��D���E����l�Y�E���c���E�g���E�R�{���Y�E�k�������Y�E�ш���E�ЎR����E�c�J�s�E�{�A��ق��j�B���̐��z�́s�u�����v�Ƃ����G�t�Ɏ��^���ꂽ���i�����A���o���ɂ����锒�H�̒Z�͈̂ȉ��̂Ƃ���B
�@�@�t�̒��Ȗ����������������ƊO�m�Ɓn�̖ʁm���n�̑��ɓ��̓���[�ׁ�14
�@�@��J�̂��Ƃ����m���ȁn�����P���m�ЂƂӂ��n�ɉ߂����䂫�ɂ����Ȃ肵���ȁ�15
�@�@����͂ĂɟT���m������n������̂��Ȃ��݂̂��肻�߂ʂ�Ό܌��m�����n�͂����遞16
�@�@�����܂ł��������Ȃ����F�₠��킪�v�ӂЂƂ̏t�̂܂Ȃ�����17
�@�@���Ȃ��������ƕ�Ƃ̂ӂ��͂��瑁��Q�˂܂��ʏ��̊����Ɂ�18
�@�@����̎₵��聂̌�ڂ��߂͒��������点�đ҂ׂ��肯�聞19
�@�@賎q�����賎q�͚e���˂Ǔ��������畃�����賎q�̔�����܁�20
�@�@���������̖�ǂ̉Ƃ����m��������n�鏒�m���₪�����n�̉ԁ�21
�@�{�����܌��m�����n壙��Ђ��Ńa�L�^���X��������ӂ�a���m�ɂ����܁n�̋�����22
�@�@壔���勁m���ւ�n���Ȃ肨�Â��ÂƔE�ш��Ӗ�̔����̒���23
�@�{���L�����딖���m�������n�Ȃ鐅��̕r�ЂƂ����H�͗��ɂ��聞24
�@�@�������ɏt�̖��c�ƂȂ�ɂ��荩�z����̂���ۂۂ̉ԁ�25
�@�@��������̉ԍ炭����ΐ��̏�m�ցn�ɂ͂��Ȃ��Ă̖�����ǂ�ʁ�26
�@�{��m�ӂ����߁n�͑�n�̏�͕����˂����ɂ����Ƃ��낪����ɂ��聞27
�@�{�傫�Ȃ�肪����͂�Ē��[���ォ�痑�����݂��邩����28
�@�{���łĂ�腖��剤����Ȃ�͖ؓ�O�{���낿��聞29
�@�{���͂̂�O�Y�O��͛��̐_��Ԃ������čՂ��Ƃ��끞30
�@�@�J�ӂ�ΐ���m�݁n�Ȃ��������̐���₵�Ǝv�ւǁ�31
�@�@�꒹�m�ɂقǂ�n�̊�������̗[���˂����날�����t�����ʂ�ށ�32
�@�@���Ȃ���H���Ɍ���壈�Џ@���M���o�łď������聞33
�@�@���J�̂��܂��ɂ�����L�����Â�����Ώt�����ɂ��聞34
�{���t�����Z��́s�u�����v�Ƃ����G�t�ł͏Ȃ���Ă���B���������́q�~�ς��肤���\�\�s�����t�̂��ƂȂǁr�Ɉ�����Ă���䂦�ɁA�d����������̂��낤�B�t�Ɍ����A����炱���g���߈��̔��H�Z�̂������B�Ƃ�킯�u�����܌��m�����n�u���Ђ��Ńa�L�^���X���m���n������ӂ�a���m�ɂ����܁n�̋����v�i�s�˂̉ԁt�ł́u�����܌��m�����n�u���Ђ��Ńa�L�^���X���m���n������ӂ邽�܂��Ђ̋����v�j�͋g���̔]���ɐ[�����܂ꂽ������B�\�\�����ŗ]�k�������B�s�˂̉ԁt�͒Z�̎l�l���Ɓu���̘_�v�u�����v�Z�т����߂�B�g����������D���͎�N����̂��̂����A�s�˂̉ԁt�̕��́q���̎v�r�ɉe�����ꂽ�߂��Ȃ����Ȃ��B���Ȃ݂Ɂq���̎v�r�́u�����܌��v�̃��@���G�[�V�����Ƃ�������u���@���З�U�ԁm�����ӂ�ȁn�̓����m�Ȃ��n�ɋ����S�n��������t�̓��͂䂭�v�̂������Ƃɒu����Ă���B������K�X�A������B
���p�������́u�����ʎт̂����ɘ����ɉ��ސl�Ȃ̏D�͂����t�̑f��v�́A���̂܂܋g���̎��сq�ʎт����b�r�i�@�E12�j��z�킹��B�{��ɖ߂낤�B�\�\�ӔN�̋g�������H�̎��̂ɐG�ꂽ�q���H���߂���f�́r�i���o�́s���H�S�W�k��17���l�t����A1985�N9���j�́u�P ���e���O�Y���̒��̔��H�v�u�Q �w�˂̉ԁx�Ɓw�����x�v�u�R ���̍��b��̗[�ׁv�u�S ���u�b��m�낪��n�v�Ɓu����m�݂Ȃ��݁n�v�v���琬�邪�A���́u�Q�v�ɂ͎��̎O������Ă���B
�@�@�t�̒��Ȗ����������������ƊO�m�Ɓn�̖ʁm���n�̑��ɓ��̓���[��35
�@�@����͂ĂɟT���m������n������̂��Ȃ��݂̂��肻�߂ʂ�Ό܌��m�����n�͂����遞36
�@�@�q���V���X�����ɍ炫�ɂ���͂��߂ĐS���Ђ��߂�����37
�u�q���V���X�v�́q�s�Ԋ~�t��r�Ɍ����Ȃ��������A�O�̓�l�s�˂̉ԁt����B�u�R�v�ł́A1940�N�i���a15�N�j3���A�ۂ̓��ŎO�D�B���̎��̍��b����������˂��u����i�u�t�͓��蓡���Ɣ����Y�A�\��̖k�����H�͋}�a�Ō��ȁj�������A���H�Ƃ͐��U�܂݂��Ȃ��������Ƃ������B�����A�Ȃ�Ƃ����Ă��q���H���߂���f�́r�Œ��ڂ��ׂ��́A���āu�����Ă݂�Ύ��͔��H�̎��ɂ͒^��Ȃ������v�Ə������g�������߂Ĕ��H���ւ̌X�|��\�������u�S�v�ł���B���̑S�����f����B
�������ꂽ���͂ŋg�������y�����̂͂����̔��H�̎��̏W�����A���L��k�b�ł́s���H���S�W�t�i�A���X�A1919�j�Ɓs⹁t�i�����[�A1929�j�A�s���앗�t�i�A���X�A1934�j�A�s�Ɂt�i�����ЁA1943�j�ɐG������ŁA�s�˂̉ԁt��s�_��W�t��P�s�{�┒�H�S�W�Łi�܂�s�Ԋ~�t�ȊO�Łj�ǂƂ����`�Ղ͂Ȃ��B�Ȃ�����Ǔ��R�A�ǂ��Ƃ��낤�B�\�\�q�~�ς��肤���r�Ɉ����Ă���u��m�ӂ����߁n�͑�n�̏�͕����˂������ɂ����Ƃ��낪��ɂ�����6�v�͕s�v�c�Ȃ��ƂɁA�s�Ԋ~�t�ł͂Ȃ��A�̏W�s�_��W�t���^�`�i�������A�̏W�ł́u��n�m�������n�v�u���m����n�v�ƃ��r�������j�ł���B����q�s�Ԋ~�t��r���o�ɂ����铯�̂́A���R�̂��ƂȂ���s�Ԋ~�t���^�́u��m�ӂ����߁n�͑�n�̏�͕����˂������ɂ����Ƃ��낪����ɂ�����27�v�ł���B�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����̂��s�������A���̈ꎖ�������Ă��Ă��A�g�����s�Ԋ~�t�ȊO�̊��{�Łs�_��W�t��ǂ�ł������Ƃ͊m���ł���B�\�\��������ɂ�������炸�A���F�ŕ����ɂ��Ă���4�N�ԁA�J�肩�����ǂs�Ԋ~�t�̖{�������g���ɂƂ��Ă̔��H�Z�̂������B�g���̏��������ǂ����s�Ԋ~�t���ǂ̔ł������̂��A�c�O�Ȃ���������Ɂi���ł�1930�N9��28���j���������Ƃ����킩��Ȃ��B�g�������������H�Z�̂̓T���Ƃ��āA�s���H�S�W�k��8���l�t�i��g���X�A1985�N7��5���j�����̔��H���I�̏W�s�Ԋ~�t�i�����ЁA1928�N10��3���j�̖{�����f�ڏ��ɋ����A�g���̐��z���̕\�L�ƈقȂ�̂��Ԏ��ŕ\�������i�U�艼���̗L���Ɗ����̎��̂̑���͍Z���̑ΏۂƂ��Ȃ������j�B
�@�@�t�̒��Ȗ����������������ƊO�m�Ɓn�̖ʁm���n�̑��ɓ��̓���[�x��14�E35
�@�@��J�̂��Ƃ����m���ȁn�����P���m�ЂƂӂ��n�ɉ߂����䂫�ɂ����Ȃ肵���ȁ�15�@�@
�@�@����͂ĂɉT���m������n������̂��Ȃ��݂̂��肻�߂ʂ�Ό܌��m�����n�͂����遞1�E16�E36
�@�@�q���V���X�����ɍ炫�ɂ���͂��߂ĐS���Ђ��߂�����37
�@�@�����܂ł��������Ȃ����F�₠��킪�v�ӂЂƂ̏t�̂܂Ȃ�����17
�@�@�܂����m�����n��ޏ����̖��Ȃ�ޗ[�Ƃǂ낫�̉���������遞2
�@�@�����܌��m�����n�u���Ђ��Ńa�L�^���X���m���n������ӂ�a���m�ɂ����܁n�̋�����13�E22
�@�@�������ɏt�̖��c�ƂȂ�ɂ��荩�z�m����ԁn����m�ق��n�̂���ۂۂ̉ԁ�25
�@�@��������̉ԍ炭����ΐ��̏�m�ցn�ɂ͂��Ȃ��Ă̖�����ǂ�ʁ�26
�@�@�u����勁m���ւ�n���Ȃ肨�Â��ÂƔE�ш��Ӗ�̔����̒���23
�@�@���������ƍL���������Ȃ�t�݂̂₱�̂��Ђт��̎���3
�@�@���L�����딖���m�������n�Ȃ鐅��m����₭�n�̕r�ЂƂ����H�͗��ɂ��聞4�E24
�@�@�ǂ����݂̉Ԃ̂ɂقЂ��v�ӂƂ��݂Ĕ���N���܂Ȃ�����5
�@�@��m�ӂ����߁n�͑�n�̏�͕����˂����ɂ����Ƃ��낪����ɂ�����6�E27
�@�@�傫�Ȃ�肪����͂�Ē��[���ォ�痑�����݂��邩����7�E28
�@�@���łĂ�腖��剤����Ȃ�͖ؓ�O�{���낿��聞8�E29
�@�@���͂̂�O�Y�O��͛��̐_��Ԃ������čՂ��Ƃ��끞9�E30
�@�@�J�ӂ�ΐ����m�݂���n���Ȃ��������̐���₵�Ǝv�ւǁ�31
�@�@���Ȃ��������ƕ�Ƃ̂ӂ��͂��瑁��Q�m���n�˂܂��ʏ��̊����Ɂ�18
�@�@����̎₵���[�̌�ڂ��߂͒��������点�đ҂ׂ��肯�聞19
�@�@賎q�����賎q�͚e���˂Ǔ��������畃�����賎q�̔�����܁�20
�@�@�꒹�m�ɂقǂ�n�̊����m�������n����m���́n�̗[���˂����날�����t�����ʂ�ށ�10�E32
�@�@���������̖�ǂ̉Ƃ����m���m�����v�n������n�鏒�m���₪�����n�̉ԁ�11�E21
�@�@���Ȃ���H���Ɍ���u��Џ@���M���o�łď������聞33
�@�@����抦�����J�m�����n�ꗈ��c�̕Ж����m���Ɓn�Ȃ�傪�܂��킽�錩����12
�@�@���J�m���肠�߁n�̂��܂��ɂ�����L�����Â�����Ώt�����ɂ��聞34
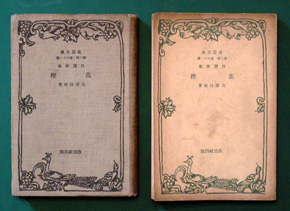
�k�����H���I�̏W�s�Ԋ~�k�������Ɂl�t�i�����ЁA1933�N7��12���k��26���l�j�Ɠ��i���A1936�N5��27���k��29���l�j�̕\��
�g�����͖k�����H�̑��̏W�s�˂̉ԁt�i���_�����X�A1913�j����̏W�s�_��W�t�i�����ɏ��[�A1915�j�Ȃǂ��������s�Ԋ~�k�������Ɂl�t�̒Z�̂ŕ��w�ɖڊo�߂��B�����čŌ�̍���s��ʁt�̔w�i�ɔ��H�̎��W�s���n�W�t�i�A���X�A1923�j��s�C�^�Ɖ_�t�i�A���X�A1929�j�����݂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�s���H�S�W�k�S39���E�ʊ�1���l�t�i��g���X�A1984�N12���`1988�N8���j�͋g�����u�x�M�v���ė���ׂ����E��͍����Ă���1980�N�㏉�߂ɂ͂܂��o�Ă��Ȃ���������A�����炭���e���O�Y�ҁs�k�����H���W�k�t�̎��W�^���{�чM�l�t�i�����ЁA1965�j�Ŕ��H�̎��ɐG��Ȃ��������Ƃ��傫���������낤�i�����́s�@��t����25�сA�s�v�Џo�t����30�сA�s�����i���� �y�����t����9�сA�s���̍Ձt����2�сA�s�^�쏴�t����6�сA�s�����m�Ɗy�t����10�сA�s���n�W�t����24�сA�s�C�^�Ɖ_�t����20�сA�s�V��t����5�сA�ȏ�131�т����߂�j�B�g�����������H�̓W�s�@��t�i�Օ��ЁA1909�j�Ɓs�v�Џo�t�i���_�����X�A1911�j�Ɍ��y���Ă��Ȃ��̂��ɂ��܂�邪�A���e���O�Y�����������悤�ɖk�����H�̎��A�i�����Đ��e�͂����҂�ł��Ȃ����j�Z�̂��ꊪ�ɕ҂Ȃ�A�����̉̏W�A����̎��W���唼���߂��̂ł͂���܂����B���������́A�g�����g�̎��̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j���玍�W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j�Ɏ���O�Ղ̑����`�ƂȂ��Ă���悤���B1990�N6���A䶔��ɕt���ꂽ�g�����̊��Ɏ��߂�ꂽ�̂́A�k�����H���I�̏W�s�Ԋ~�t�ꊪ�������B
�k�t�L�l
����ɂ��Ă����H�̑��Y�ɂ͋����B���݂ɋg���̐��܂ꂽ1919�i�吳8�j�N4���́q����N�\�r�i�s���H�S�W�k�ʊ��l�t��g���X�A1988�N8��30���A�O����y�[�W�j������ƁA���w�q����ď����r�q�������r���s�Ԃ����t�ɁA�q���N�̖ؔҁk���l�r���s�����t�ɁA�U���q�n�쓶�w�A�n�����w�I�]�r���s�Ԃ����t�ɁA�q���̐����i�܁j�r�Ɓq�s�v�c�ȗ������r���s��ρt�ɁA�k���Ø������ȁl���s�����t�ɁA�q�k�����l�]�E�I��Ɂr���s���͐��E�t�ɔ��\���Ă���B���Ȃ݂Ɂq����ď����r�͎R�c�k⩍�Ȃ̓��w��1923�N�ɔ��\�A1961�N�ɂ͂m�g�j�e���r�́s�݂�Ȃ̂����t�ԑg�J�n��4����5���ɕ������ꂽ�Ƃ����i�́F�{�j�[�W���b�N�X�A�ҋȁF�y�c�M�A�e�G�F���������j�B
�g�����͂̂��Ɂq���e���O�Y�A���x�X�N1�r�ƂȂ�q�f�Ўl�́r�i���o�́s���e���O�Y�S�W�k��7���E����l�t�}�����[�A1972�N4��28���j�������n�߂Ă���B
���{��ɂ�鐼�e�̍ŏ��̎��W�sAmbarvalia�t��1933�N�i���a8�N�j9��20���A�ł̖؎Њ��B����300���������B�g���͊��s����14�ŁA�ٕҁs�g�����N���k������Q�Łl�t��1933�N�̍��ڂ͂Ȃ��B�ł́A���W������1939�`40�N����͂ǂ����������B���N����������B
���O��N�i���a�\�l�N�j ��\��
�k�c�c�l���̔N�A�����s�����Z�L�t�A�O�D�B�����W�s�t�̖��t��ǂށB�x�c�ؕ��̋�����u�B�ɓ�����Y�s�Ԃ̉��t�A�Ñ��M�v�s�ˉB�̊G�{�t�A�O�썲���Y�s����Ȃ�t�A�֓��j�s���́t�Ȃǂ́q�V����肠�p���r�����ǁB
���l�Z�N�i���a�\�ܔN�j ��\���
�k�c�c�l���̔N�A��Ô���̏W�s���W�t�Ɏ䂩���B�a���C�Y�̎��W��ǂݎ莆�������A�s�����X�q�t��Ⴄ�B�؉��[�����W�s�c�ɂ̐H��t��ǂ݁A�Ȍ��N�Ԃ̕��ʁB�s���ꂽ�Ɓt����B
�N���ɐ��e���o�ꂷ��̂́u���l���N�i���a��\��N�j ��\���v���ŏ��ŁA�u�\�ꌎ�A�����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�A���e���O�Y���W�s���ނ��肠�t�s���l���ւ炸�t��ǂݐ��e�ɂ͔ӔN�Ɏ���܂ŌX�|����v�Ƃ���B�����Łq���e���O�Y�A���x�X�N�r�����O�ɋg�������e���W�Ɍ��y�������͂�U�肩�����Ă������B
���e���O�Y���W�Ƃ̏o�������āA�@��1947�N11���A�A��1948�N6���i�ēǂ��j�A�B��1948�N�̏I���߂�����A�C��1948�`49�N����Ƃ܂��܂��ł���B�s�g�����N���k������Q�Łl�t�ł͓��L���d�ć@���̂������A�`���Ɉ������q�f�Ўl�́r�̂ӂ��߂̒f�Ђ͂������B
�@�̓��L�̌��\����4�N��̎��M�ł���ɂ�������炸�A�g���������Łu�s���ނ��肠�t�Ɓs���l���ւ炸�t���A�����l�������ēǂ̂́A������N��̏��a��\�O�N�v�ƒf������̂͂Ȃ����A�ȑO����C�ɂȂ��Ă����B�ĂєN���������B
���l���N�i���a��\�O�N�j ��\���
�k�c�c�l�\�A�֍��Y�̏H����ɏo�ȁA�u�~�̓��̋Â�Ζ��ׂȂ�ւ̖e�v�B���߂ās�{�V�������W�t��ǂށB
���l��N�i���a��\�l�N�j �O�\��
�ꌎ�A�֍��Y�A�c�K�t���A�r�c�s�F��Ɛ���s�A�u���~��ӂ邫���炩�̔g���Ă�v�B�l���A���m���̎В��O�䔪�q�Y�ƂɊ������B���̂��뎍���������ƌ��ߐe�����o�咇�ԂƂ����ʂ��悤�Ƃ���B�k�c�c�l�Z���A������тł���B�����A�u����ꏊ�ɂ��闑�قǂ��т������̂͂Ȃ��v�A�������ɂ��������l����B�s�݂Â�t�ŃN���[�̊G�ƕ]�`�ɐG���B�㌎�A���q�ہ[��E����[�̉́@���͐�̃J���o�X�r�E�e�i�����\�j�B�����P�s���_���t���玍��Ƃ�����d���ւ̌[������B�s�����V�g�̎��W�t��ǂށB
1948�N���A���ŐV���o��ӂ��̈��āA���N���߁A���q�ɗV�ۂ̔o�~�ӂ��̋���Ō�Ɂu�����������ƌ��ߐe�����o�咇�ԂƂ����ʂ��悤�Ƃ���v�B���̎��A�N���[�̊G�A��d���ւ̌[���\�\�Ƃ������A�̂��̎��W�s�Õ��t�i1955�j�ɂ����鎍��̓������ǂ钼�ڂ̌_�@���A����̐��e���O�Y���W�Ƃ̏o��ɂ������B����䂦�A�g���͐��e���Ƃ̏o�������1948�`49�N�ł���ƌ�����B���ɂ͂��̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B
���e���O�Y�̎��W�s���ނ��肠�t�i�sAmbarvalia�t�����Ċ��{�j�Ɓs���l���ւ炸�t�͂Ƃ���1947�N8��20���A�����o�ł̊��s�B�����A�g�����D�̂́s���l���ւ炸�t�ł���B
���e���O�Y���߂���ӂ��̍��k���������B�O�҂ɏo�Ȃ������l�݂͂Ȑ��e�ɐe�t���Ă��āA���k��́q���{��̎��l�E���e���O�Y����r�̐߂ɂ͐s���Ȃ��������o���邪�A���p�͍T���悤�B�g���͉����Ċ��{�s���ނ��肠�t�������ŁsAmbarvalia�t���Ă���悤�����A��T�ɂǂ��炪�d�v���Ƃ������Ȃ��B���߂ēǂ��e���O�Y���W�ł���s���ނ��肠�t���A���̋g���̎��@�Ɏv���̂ق��傫�ȉe����^���Ă���̂��B�g�����Ō�ɐ��e�ɕ����������̎����q�i���̒��Q�r�i���o�́s�i���̗��l�@���e���O�Y�@���E�G��E���̎��Ӂt�V���s���p�فA1989�N4��1���j��25�s�̒Z����i�����A������4�s�͂������B
���̓T���́A�U�����^�́q�e��^���Εv�r�i�sAmbarvalia�t�j�ł�
�����A�s�����̎��сq�e�肽��Εv�i�����̔j��j�r�i�s���ނ��肠�t�j�́u23�v�i�S�s�j�ł�
�ƂȂ����B�Ƃ���ŁsAmbarvalia�t�́qLE MONDE ANCIEN�r�ƁqLE MONDE MODERNE�r��2���\�������A�qLE MONDE ANCIEN�r�̖`����11�т��琬��q�M���V�A�I�R��r�B���̍ŏ��́q�V�C�r�i�S�s�j��
�s���ނ��肠�t���qLE MONDE ANCIEN�r�ƁqLE MONDE MODERNE�r��2���\���ŁA�qLE MONDE ANCIEN�r�̖`����11�т��琬��q�ŗ��r�B���̍ŏ��͓������q�V�C�r��
�������B�ύX�́u���T�₭�������₭�v�Ɩ����̋�_�폜�̓�ӏ��B��O���s�̓W�i�s�����G�߁t�s�t铁t�j�ɂ����Ă��������������A�g������т��Ď��ɋ�Ǔ_��p���Ȃ��̂́A�s���ނ��肠�t�Ɓs���l���ւ炸�t�̎��w���^�������߂��ƍl������i���e���sAmbarvalia�t�́qLE MONDE ANCIEN�r�ɂ�������Ǔ_���s���ނ��肠�t�̂���ł��Ƃ��Ƃ����̂������̂́A�s���l���ւ炸�t�̏��@�ɍ��킹�����߂��낤�j�B�������ł͂Ȃ��B���e����ꎍ�W�����̑��s�ɁA�L�[�c�̒����s�G���f�B�~�I���t����glike an upturn'd gem�h��f��������������i�@�j�Ŋ��������@���A�g���́q�i���̒��Q�r��̍ŔӔN�̓сq�_��r�q����r�œ��P�����̂ł���B�����Ƃ��A�g���̈��p�����q�V�C�r�Ɍ��т����͎̂��̑n���ł͂Ȃ��B1990�N7���A�g�����̎l�\����̖@�v�̂��ƁA�_�c�̂�Ԃ��ŏ��R�r���Y���L�[�c�̎���������āq�V�C�r�ɐG�ꂽ�B���R����͋g���̈��p���Ƃ̊֘A���q�ׂ��킯�ł͂Ȃ����A���̐ȂŐ��e���ɐG���Ƃ������Ǝ��́A�g��������_�������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�͐��z�A���L�̔����A�l���_���z�Ƃ����������̑��ʂ�����i�����A�����ł͋g�����ɂ�鐼�e���O�Y���̃A���\���W�[�Ƃ��ēǂ�ł݂����B�g���������ň��������e���͈ȉ��̔��сB
�Ȃ��q���e���O�Y�A���x�X�N�r�ȊO�̐��z�ł́q�o��\�\��������r�i���o�́s����������W�k���㎍����45�l�t�v���ЁA1971�N10��20���j�Ɂq���r�i�s�X�L�t�j����9�s��������Ă���B�܂��q���H���߂���f�́r�i���o�́s���H�S�W�k��17���E����10�l�t��g���X�A1985�N9��5���j�ɂ́q�ŏI�u�`�r�i�s�L�`�̏��_�t�j����5�s�ƁA�q�쌴�̖��r�i�s�X�L�t�j����6�s��������Ă���B���́q���H���߂���f�́r�����A�l�̒f�͂́q�P�@���e���O�Y���̒��̔��H�r�͂����n�܂��Ă���B�u���͂����ɂ��A���e���O�Y�҂́w�k�����H���W�x�����邱�Ƃ�m��Ȃ������B���O�Y�̔ӔN�܂ŁA���̋߂��ɂ������A�������H�ɏA�Č��̂��A���������Ƃ��Ȃ��B���̓�l�̎��l�́A�����炭�𗬂��Ȃ��������ł���B�h�ӂ��炱�̈ꊪ��҂��̂ł��낤�B���͈�{���w���āA�ʓǂ����B�ɂ������Ƃɂ����ɂ́A���O�Y�̔��H�̎��ւ̌��y���Ȃ��̂��v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�O�Z�Z�y�[�W�j�B���͍ŏ��ɂ����ǂƂ��A�������A���e�͔��H����҂����ʼn����t���Ȃ������̂��Ǝv�������ŁA�g���̐��z�̊܈ӂɋC�Â��Ȃ������B����͎����i�g���j�ɂ͐��e���O�Y���W��҂ޗp�ӂ�����A�Ɠǂނׂ��������i���Ȃ݂Ɋp�앶�Ɂk1957�l�͎O�Y�F�V���A�V�����Ɂk1965�l�͑���l�Y�A�t�̎��W�k1967�l�͌��J�K�M�A��͑I���k1967�l�͏��C�i��A���E�̎��k1967�l�͈���M�v�A���㋳�{���Ɂk1970�l�͌��J�K�M�A�����Е��Ɂk1976�l�͔ɔ��v�A���㎍���Ɂk1979�l�͐V�q�r��A��g���Ɂk1991�l�͓߉ϑ��Y�̕҂ŁA�sAmbarvalia�t�Ɓs���l���ւ炸�t��S�ю��߂��u�k�Е��|���Ɂk1995�l�̎����I�ȕҎ҂͐V�q�r��j�B�g���͐�̐��e�Ǔ����k��ł����q�ׂĂ���B
�߉ϑ��Y�͎��W�́q����r�Łu�Ҏ҂̎����ɂ��A�wAmbarvalia�x�w���l���ւ炸�x�w�ߑ�̋��b�x�y�сw����ꂽ���x���A���e���O�Y�̎��Ƃ��\����l�̍���Ƃ��邱�Ƃ��ł���v�i�s���e���O�Y���W�k��g���Ɂl�t��g���X�A1991�N11��18���A�l�Z��y�[�W�j�ƒf���A�s�߉́t�ɂ������Ắu����ȍ�ŕ������o������Ȃ��߁A��������������Ȃ����v�i�����A�l���Z�y�[�W�j�Ƃ��Ă��邪�A����������ȁs����ꂽ���t�i1960�j����͇T�ƇW���̂��Ă���B�����ē߉ϑ��Y�́s�߉́t�ɑ���]��������ׂ��ł���B�g�����ҁs���e���O�Y���W�t�́A�g�������߂đ����������e�̎��W�s�X�L�t�i1967�j�ȍ~�̔ӔN�́s�߉́t�i1969�j�A�s����t�i1970�j�A�s�l�ށt�i1979�j������Y�������A���̍ő�̊�ڂ��s�߉́t�̎����E�ʂ����s�V�� �߉́t�Ƃ���B�����Е��ɔŎ��W�Ɂs�߉́t����V�Ɓq���Ƃ����r���̂����ɔ��v�ɂ��s�߉́t��2004�s���Ƃ�������i5���͊e400�s�����A��3��������404�s�j�A�S�̂�6����1200�s���炢�łǂ����낤�i�g���ɂ́A257�s���������ł́q�g��i���Ɏ~��r�����W�I�����p��195�s�Ɋ��肱�O��������j�B���Ȃ݂ɋg���̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j����1178�s�ŁA���̏��@�͐��e�ӔN�̎��W�ɑ������w��ł���B�s�_��I�Ȏ���̎��t�̈�сq��q�r�i���o��1972�N8���́s�����t29���j�͋g�������e�ɕ������ŏ��̎��тł���B���o�`��14�s�߂܂Ōf����B
���鐼�e�́s�߉́t�́A�U����26�s�B
���ɂ́A��ƁE��i�̃A���[�W������N�w�I��⼌��̕p�o���Ȃ�����̂ق����A���������ēǂ߂čD�܂����B���p�����s�߉́t���A�L�^�x�^�i��t����S�h���̖k�ӓc���j�̃h�W���E���o�Ă��Ȃ��ƁA�㔼�͂�����Ƃ炢�B�s�ߑ�̋��b�t���������͒W�ɂ����悤�Ȓ��q��2000�s���ێ����邱�Ƃ͍�������Ǝv����B�s����ꂽ���t�͏[�����̐��e�ɂ̂݉\�Ȋ�֓I�ƌ����Ă��������������B���̎��l�̖{�̂́q�M���V�A�I�R��r��q�����݂̈߁r�i�s�L�`�̏��_�t�j�̂悤�ȒZ���ł����ō��x�ɔ������ꂽ�B
�u�ҏW�����ҁv�c���`��i1923�`2003�j�̒����s��̎����̂�����t�����s�����V�h���[�̑�\�E���R�P�v�́A�c���̟f��A�q�u�c���`��E�{�̊w�Z�v�̐��k�Ƃ��ār�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���i���o�́s�}���V���t2003�N3��15�����j�B
�@�܂��Ȃ��A�w�c���`�瑕����i�ژ^�x���o���A��z�W�̊������Ă��邩������Ȃ��B�킽���̖��́A�����̎d���̉����Ƃ��āA�C���^�[�l�b�g��Ɂu�c���`�瑕����i�v�̃T�C�g�𗧂��グ�邱�Ƃł���B���̃T�C�g�ł́A�����A���Җ��ł̌����̂ق��A�e�{�̎��ރf�[�^�A������@�A������A���{���A�ҏW�҂Ȃǂ̃f�[�^���킩��B�����āA���ꂼ��̏��e�̉摜�����J����Ă���B�Ȃ��Ȃ��m���ĂȂ��̂��A�{�\���̐}����{���̐}���B�J�o�[��茆��Ȗ{�\������������i�c������A���߂�Ȃ����I�j�B�������A�c������̃R�������ǂ߂�B����ȃT�C�g�̎������Ă���B�i�c���`��s��̎����̂�����t�ʍ��t�^�A�V�h���[�A2007�N3��10���A��܃y�[�W�j
�u�c���`�瑕����i�v�̃T�C�g��v����ɁA�����ł���i�\�\�ȉ��͏��т̕�L�j�B
�@�����A���Җ��Ō����ł���\�\����̓L�[���[�h�ɂ�錟���Ȃ�{�̊��s���ł��܂�Ȃ����A�ڎ��ŒT���ɂ͂��ꂼ���50�����ɕ��ׂ邩�A���҂�50�����̉��ɏ�����50�����ɕ��ׂ�̂��d�낤�B
�A�e��i�́i1�j���ރf�[�^�A�i2�j������@�A�i3�j������A�i4�j���{���A�i5�j�ҏW�����킩��\�\�i3�j�i4�j�͉��t������悢���A�i1�j�i2�j�͎w�莆�ƂƂ��Ɍ�����������K�v������B�i5�j�͂��Ƃ������ɋL�ڂ��Ȃ���Ύ�ނ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�B���e�i�����W���P�b�g�����łȂ��A�{�\���̐}�����{���̐}�����j�\�\����t������ԂŎB�e���邩�A�O���ĎB�e���邩�B�c���`��s�̂̎����̂�����t�i�����V���ЁA1996�j�f�ڂ̏��e�́A�т��O���ĎB�e���Ă���B�������{�����̏��e�́A���Ԓ����������m�N���R�s�[�ł���B�ڎ����{���̑g�ł���|���Ă���{�́A���̔Ŗʂ̏��e�Ɩ{���̑g�Ńf�[�^���ڂ������B
�C���̍�i�ɂ܂�鑕���Ƃ������\�\�����Ƃ����̂��Ă�����̂��ƌ����Ă��邪�A���ꂱ���T�C�g�̕ҏW�҂̘r�̌������ł���B
���R�̍\�z�͓I�m�Ȓ���Ɋ�Â��Ă��邪�A���͂���ɉ����đ������e���w�莆���f�ڂ��Ă��炢�����Ǝv���i1979�N12���`1980�N1���A�a�J�̋i���X�s�[�R�b�N�ŊJ���ꂽ�c���`�瑕���W�ɂ́A�������e���o�i����Ă������낤���j�B�ҏW�҂ɂ�鑕����i�́A�u�b�N�f�U�C�i�[�̂悤�ɂ�������ƍ�肱���̂ł͂Ȃ����낤���A�������ł��悭�m��҂̍�i�Ƃ��ċM�d���B���Ȃ݂ɉP�c�����s���ꎞ��t�i�����ЁA1999�j�̓c���`��̍��ɂ́A�Г�������|�����ҏW�҂Ƃ��ĉԐX�����i�邵�̎蒟�Ёj�A�Ȑ܋v���q�i�}�����[�j�A�����ē��c�O�j���Y�n�a�i�͏o���[�V�Ёj�A�c���`��i��g���X�j�A�����i�������_�Ёj�A�R���o�i�V���Ёj�A�쓇���i�u�k�Ёj�A���X���i���}�Ёj�A����ɋ{�e�r�O�i�������_�Ёj�A�ԒJ�O�i���Y�t�H�j�A�ʖM�v�i���j�Ƃ������l�l�ƂƂ��ɁA�g�����i�}�����[�j�̖����������Ă���B
�Ȃ��A���R���q���������w�c���`��@�ҏW����P�P�T�l�̉�z�x�r�i�s�����V���k�[���l�t2004�N2��12���j�Łu���ܕҎ҂����̊Ԃɂ͓�̖�������B��ɂ́u�c���`�瑕�������فv�Ƃ����g�o���J�݂��A������i���X�g����芮�S�ɂ��A�J�o�[�����łȂ��A�{�\���A���ϔ��Ȃǂ̉摜�����J���邱�ƁB������́A�c�������{��ۑ����J���Ă�����w�}���ق������ق�T�����ƁB�ǂ����A���̕������Ă����Ƃ���͂Ȃ����̂��낤���H�v�Ə��������A2008�N8���`9���A��������p��w���p�����}���قœW����q�w�������Ă�ł���\�\�ҏW�����Ɠc���`��̎d���r���J����A�w�\�����J���[�ʐ^�Ōf�ڂ����}�^���o�ł��ꂽ�B�c���Ƃ�����ꂽ��1500���̓c���`�瑕���{�ƂƂ��ɁA�����̂��߂̃G�X�L�[�X�A����o�����e�i��200�_�j���W�����ꂽ�Ƃ����B�ЂƂ�̑����Ƃ̓W���Ƃ��Ă͉���I�ȍÂ��ł���A�s�ς������낤�i�c�O�Ȃ��玄�͊ςĂ��Ȃ��j�B
�g�����������Ƃł����邱�Ƃ��L���m�炵�߂��̂́s�����V���k�[���l�t1976�N4��27���t�̃R�����q������ށr�̋L���ł���i���̓��͊���������n�ق��u�l�����v�ٔ��̗L�ߔ����������킽���������ŁA������1�ʂ�10�E11�ʂɊ֘A�L�����ڂ��Ă���j�B�ȉ��ɂ��́q�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����r���N�����Ă݂邪�A���M�����L�҂̖��͋L����Ă��Ȃ��B
�@�u���ƕ��Ɩ��v�u���ˁv�Ȃǂ̍�ƁE�����ւ̐V�S�W���}�����[���犧�s�������A����̑��������l�E�g���������ʐ^���̎�ɂȂ�ƕ����ċ����l�͏��Ȃ�����܂��B�Ƃ��낪�g�����́A���͋Ζ���̒}�����[�ł��łɕS�_�]�̑�����S�����A�e�F�̎��l�E�剪�M���Ȃǁu�������h�ȑ����Ƃł��v�Ƃ����قǁB
�@���N�̂��뒤���Ƃ��u�����Ƃ��������ɁA���p�Ɩ����ł͂Ȃ��킯�����A�{�i�I�ɑ������肪�����̂͏��a�O�\�N�́w���Ɏ��S�W�x����B�ȗ��A���e���O�Y�A�{���A�����Y�Ȃǂ̌l�S�W�����X�ƒS���A�[�����F�m�}�}�n�̖Ȃނ����g�����w�����֑S�W�x�����������A���̑����ɂ͑S�̂ɒn���ȏa�������̂��̂������B
�@�u�v����ɂˁA�ڂ��̒��ɂ͇������̂��Ȃ��{��������݂̂Ȃ��������Ƃ����C��������{�Ƃ��Ă����v
�@�u����A�Y�S�W�Ȃ�����Ǝ����Ȃȁv�\�\�A�[�g�E�J���o�X�̗������������F���ڂɂ��݂�悤�ȑ��������A�u�w�L�x�ȂǍY�̏����̖{�ɂ͉��F�������̂ŁA���������D���������̂ł͂ƍl���āc�c�B�����Ă̂͊ԈႤ�ƐԂ��ۂ��Ȃ����蔒���ۂ��Ȃ����肵�āA�ނ�������v
�@�����_�͐s���Ȃ��̂����A�{�Ƃ̎��̕��́A�����l�A�ܔN�̍�i���W�߂����W�w�T�t�����E�݁x�������ɐy�Ђ���o�邻�����B�i�s�����V���k�[���l�t1976�N4��27���A7�ʁq�����r�j
�Ȃ�Ƃ����Ă������[���̂́A�}���Łu�S�_�]�̑�����S�����v�A���Ɏ��E���e���O�Y�E�{�V�����E�����Y�E�������̑S�W����|���Ă��邱�Ƃł���i���Ȃ݂ɐٕ��q�W�@������i�ژ^�r�Łs�����֑S�W�t�܂ł̒}�����[���̋g����������i���J�E���g�����Ƃ���A47�^�C�g���������j�B�}���͎Ј��ɂ�鑕���̏ꍇ�N���W�b�g���Ȃ�����A���̎w�E�͋M�d�ł���B����ƁA�g���̌������ʂ����u�����_�v�B�g���͂��̎�̕��͂������̂����Ȃ������̂ŁA���ʓI�ɂ��̒k�b���ł��d�v�Ȃ��̂̂ЂƂƂȂ����B�����̐V���W�s�T�t�����E�݁t��7�����s�\�肾�Ƃ����̂����̂����Ȃ��B���̋L���̎�ގ��i�����炭1976�N4���j�ɂ͖{�����Z�����āA�܂��ɑ����Ɏ�肩���낤�Ƃ��Ă������ł͂���܂����B���ۂɊ��s���ꂽ�̂�9���i���t�̋L�ڂ�9��30���j�ŁA�ӂ����̒x���͑��{�E�����Ŏ�Ԃǂ������߂��B������ɂ��Ă����̎��_�Œ��Ҏ����̑����v�������u�����������A�Ƃ����͖̂]冂̒Q���낤�i�s�T�t�����E�݁t�̑������߂��邢�����́A�g���̐��z�q��ƁE�ЎR���̂��Ɓr�ɏڂ����j�B

�g�����̑����i��i�j���ŏ��ɘ_�������c���F���q����ƁE�g�����r�Ɠ���1973�N�A�Ȑ܋v���q�́q�g������̑���r�i���j���s�����C�J�t9�����q���W���g�����r�ɔ��\���ꂽ�i�Ȃ��A���̓��W���ŋg�����̑����Ɍ��y�����͓̂Ȑ܋v���q�����ł���j�B�����́A�g�s�~�V��Ɓq���ϐl�ԁr�g�����͂Ƃ��Ɂu�����ׂ������Ŏ��Ă��܂��l�v�u�����ɑ��钉���������̓I�Ƃł����������Ȃ�قǂ��Ƃ����_�ŁA�悭���Ă���v�Ǝn�܂�B�Ȑ܂͋g���̑����������_����B
�@���͋g������̎d�������邱�Ƃ���A����҂Ƃ��Ă̓�������͂��߂��B�}�����[�̎Ј��ł���������ɖ��S�_�̎d�����������A�g������Ɍ��Ă����Ȃ������{�A�ӌ��������Ȃ������{�͐�����قǂ����Ȃ��B�N�����g������ɂق߂���ƈ��S�������A�g������̖ڂƂ����֖��ʂ�Ȃ��ƁA�ǂ��ɂ������������������B
�@�g������̑���ɂ��Ă͂��łɒ�]������B���̗ǂ��̓����������̂ɁA�A�}�`���A�Ƃ������t���g���Ă�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B�ނ��f�l�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B
�@����m�A�A�n���߂̃����Y���ŗǂ̏�Ԃɕۂ��Ƃ́A���ɂƂ��Ĕ��ɓw�͂̂��邱�ƂŁA�������A�v����ɂ������炵���͂��܂�Ȃ��̂��Ƃ������ƂɁA���ǂ��ǂ����������݂̉ʂɂ���ƋC���������̑��h�Ɗ��Q�A�����Ă����炩�A�]�̂����������z�Ȃ̂ł���B
�@�����Ă��܂��m�A�A�A�A�A�A�n�����Ă�����o���Ă��܂��m�A�A�A�A�A�A�n�Ƃ����`�ł̎d���́A���̏ꍇ��������͂Ȃ��B�v�Z���A���ɂ͏����@�I�ɋl�߂čs���A�\�͂̋y�Ԃ����茵���ȉ��}������A���ꂪ�����Ă���̂�҂B���������d���̂����ł͌��ѐ�Ȃ������̊��S�����A�A�}�`���A�̂����ꂽ�d���ɂ͂���B
�@�g������������A���̒��Ɉ���ł��������������������邱�Ƃ��삱�Ԃ��̂Ƃ��ẮA�g�����E�Ƒ���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ђ����Ɋ���Ă��邪�A�Ђ���Ƃ��Ă����Ȃ����Ƃ��Ă��A�g������͓����悤�ɑ�������邩�����ꂸ�A���ꂪ�q���ϐl�ԁr�̂����낵���Ƃ���ł���B�i�����A��O�l�y�[�W�j
���邽�߂̃����Y���ŗǂ̏�Ԃɕۂ��ƂŇ������Ă��܂�����o���Ă��܂������S�����A�A�}�`���A�̎d���ɂ͂���\�\�Ƃ����̂��Ȑ܂̋g���_�̍��q���B����͑����Ɍg���҂Ȃ�ł͂̊ϓ_�ŁA���瑕�����Ȃ��������낤���c�̋g���_�ɂ͂Ȃ��Ƒn�ł���B�Ƃ���œȐ܋v���q�̑�����_���čł����ׂȂ̂́A�P�c�����q�g�����E�Ȑ܋v���q�\�\�o�ŎЂ̃J���[�����������́r�i�s���ꎞ��t�����ЁA1999�N10��5���j�́u�Ȑ܋v���q�v�ł���B�����ŋg�����ƓȐ܋v���q�̑����Ɋւ���ӏ������悤�B
�@�}�����[�ɂ����ċg���̑���������p�����̂��Ȑ܋v���q�ł���i�Ȑ܂��k���l�Z���N�ɑގЌ�́A�g���͍ĂсA�@��邲�Ƃɓ��Ђ̑�����肪�����j�B
�@�k�c�c�l
�@�Ȑ܂͕ҏW���ɔz�����ꂽ���A�������������Đ��N��ɕa�C�ɂȂ���Ð����𑗂�B����̍˔\�������܂�ĕ��E������A�g���������p���������ł��ׂĂ�C�����悤�ɂȂ�B�Ȑ܂����ڎ肪������̈ȊO�ɁA�����ȉ�Ƃɑ�����˗�����悤�ȏꍇ���Ȑ܂����̌��̑����ƂȂ����B�f�U�C���ʂł́A���Z�����}�Ђ̕ҏW�҂Ƃ������Ƃ������āA���}�ЂƂȂ���̐[���������O�ɐ܂ɐG��ċ������邱�Ƃ��ł������Ƃ��悢���ɂȂ����B���ꂪ�d�オ��ƁA�K���g���Ɍ����Ĉӌ������Ƃ��Ȑ܂̏K���������Ƃ����B��x�͋g���Ɍ����Ȃ��ƋC�������������Ȃ��������炾�B�u����A������v���g���̂����̓����ŁA�u����͂��߂���v�Ƃ����悤�Ȃ������͂Ȃ������Ƃ����B�i�����A���Z�`�����[�W�j
�P�c�͐���׃G�b�Z�C�W�s�Ђ�����̋L�t�i�u�k�ЁA1978�j�Ɋ֘A���āu�Ȑ܂̎��_�́A�F���������A�ʼn�Ɠ��������ɂ��u�O�F���F�w��ł��Ȃ���f�U�C�����[���̊m���v�ł������B���̎��_��n�ł������{���́A����Z�p���炢���Ă�����߂ė��l�߂ȏ����ƂȂ��Ă���v�u�Ȑ܂̑���̖��͂́A�]�v�Ȗ��ʂ��Ȃ��A�{�Ƃ��Ă̂������̊m�����ƍL��������Ƃ���ɂ���Ǝv���B����������ƁA��{�ƂȂ鍜�i���������肵�Ă��邱�Ƃł��邪�A������Ȑ܂��}�����[�ň�������Ƃ����Ă͌��Ȃ��ł��낤�v�i�����A�����`����y�[�W�j�ƕ]���Ă���B���́u�O�F���F�w��ł��Ȃ���f�U�C�����[���̊m���v�͋g���������ɂ����ʂ��Ă���A���̍���ɂ͊��ň���̍��@������ƍl������B�P�c�̌���́u���݁A�Ȑ܂͑���̑�������ނ��Ă��܂��Ă���B�I�t�Z�b�g����ւ̈ڍs�ɂƂ��Ȃ��A���Ă̊��ň���������Ă����A�e���{���g���玸���Ă��܂������炾�B���Օi�Ƃ��Ẵm�b�y���Ƃ����u�˂ڂ��������ʁv�ɑ�������ł́A���܂▽�����茸�炷�قǂ̈ӗ~��Ɍ��o�����Ƃ��ł��Ȃ�����Ƃ����B�c�O�Ȃ��Ƃł͂��邪�A���ȂȂ܂ł̐g�̏������Ƃ����ׂ����낤�v�i�����A���l�y�[�W�j���B�g�������l�̊��S��������ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ����̂��i����͑����ł͂Ȃ����j�A����p���̏o�Ŋ��Ɂq�g�������W�r���˗����ꂽ�ہA�u�{�����I�t�Z�b�g�������������A���^��f�����v�Ǝ��ɘR�炵�����Ƃ����邩�炾�B�g�����̒����̖{���́A��{�I�Ɋ��ň���ł���B
�Ȑ܋v���q�́q�^�C�g���E�y�[�W�ɂ��ār�i�s�����m�[�g�t�n�a�o�ŁA1987�N1��23���B���o��1979�N4���j�ŁA�킪���̗m�{�ɓ��قȕʒ��{���ɂ��čl�@���Ă���B�Ȑ܂́A�z��p���q��̘a�{�́u���v���痈�Ă���Ƃ����������ׂȂ��Ȃ���A�g�c����̕��͂���|����ɁA�m�����{�p�t�����̖�������A���Ԃ��{�̈ꖇ�\����w�œ��ă������[���̔��Ƃ������̂���{�ɂ������߂ł͂Ȃ����A�Ƃ����u�b�N�f�U�C���ƃ������[���o���ɒʂ����҂Ȃ�ł͂̐����o���Ă���B�������[���̏ꍇ�A���̃y�����t�͑���t���ĒԂ����܂�邩����Ȃ����A������{�̋@�B���{�ł́A�ʒ��{���͂킸���ȌБ�Ō��Ԃ��Ɩ{���̃m�h�ɓ\���Ă��邾�����Ƃ������R����A���x���͂̒���ʒ��{���p�~�Ɏ^������B�������Ȑ܂́A�u�������v�̏ꍇ�A�{���P�Ƃł͂Ȃ��O���{�{���Ƃ��ׂ����Ǝ咣���Ă���B�����I�ȑ��{�v�z�ł���A�����͂��錩�����B�Ƃ���œȐ܂����p�����z�앶�̏o�T�́A�g���������ɂȂ��s�{�̎��Ӂt�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1979�N1��10���j�ł���B�Ȑ܂͓��R�A�g���������ƒm���Ă���͂��ŁA�q�^�C�g���E�y�[�W�ɂ��ār�ł͖������Ă��Ȃ����A�����̕ʒ��{�����ے�I�Ɍ��Ă���킯������A�㐻�{�̑����ł͕ʒ��{�����̗p���Â����g���Ɨ�����قɂ���B����͂��̂Ƃ���Ȃ̂����A�Ȑ܂����p�����g�c�́q�}���h�����X桁u�����v�r�����߂��P�s�{�́s���ˋL�t�i�������_�ЁA1973�N8��30���j�͓Ȑ܂́u���B�v�ŁA���̖{�������Ԃ��Ɠ��������̗p���ŕʒ��Ȃ̂��i�l�Z���㐻�E�p���\���̃R�[�l�����B�{���͐����������ň�����͐����Ёj�B���͂��́u�ĔŁv�{�i1974�N9��10���j���߂��̌����}���ق���肽�B�{���͌��Ԃ��Ɩ{���Ɍ��łɂȂ����Ă���A�Ԃ���\�荞�݂ɓȐ܂Ȃ�ł͂̍H�v�����炳��Ă���̂�������Ȃ����A�c�O�Ȃ���A�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ������B
�Ƃ��Ɏ��́A�t�����X���ɕʒ��{���͕s�ނ荇�����Ɗ����Ă����B�Ȑ܂�g�c�i�u�����J��Ԃ��ēǂ{�̑̍ق͖Y���Ă���͉��Ԃ��ł��㎿�̎����g�ЁA��������������������\�������{���ɂ�Ĕ炻�̑��ő��B�����������ɂ��̂܂ܔ��ɂȂ�₤�ɂȂĂ�B�v�\�\�g�c�O�f���A��O�O�y�[�W�B�����͐V���ɉ��߂��j�̂悤�Ƀt�����X�����u�����{�v�̉��Ԃ��{���ƊŘȂ�A�ꖇ�\���̊O���������Ă���Ɂu�ʒ��{�����\���v������킯�ŁA���̏d��������a�̌����������Ƒz������B�Ȑ܂́s�����m�[�g�t�́q�t�����X���r��
�@���{�́u�t�����X���v�ŋC�ɂȂ��Ă��܂�Ȃ��̂́A�قƂ�ǂ̂��̂ɕʒ��g�r���ƌ��Ԃ����͂荞�܂�Ă��邱�ƁB�Ȃ��ɂ͂��Ă��˂��ɂ��A�{�������ł�����������̂�������B������ɂ���{���̂�����O���ɂ��邱�ƂɂȂ��������A�\���̏������̐܂�Ԃ��ɂ͂��܂Ȃ��ł����̂��A�\�������ی����ɂȂ�̂ł݂��Ƃ��Ȃ��B�i�����A���Z�y�[�W�j
�Ǝʐ^�ł�Y���Ďw�E���Ă���B���ɂ��u�t�����X���v�ӂ��̎����{�����邪�A�������ɂ����B�{���Ɠ������F���Ɨ҂����̂ŁA�{���̃y�[�W�����X�~�ƐԂ̓�F���ɂ��Ă���B�\���͉����\������F�����āA�u�����{�v�̉��Ԃ��{�ɂ��₩�����i�p���͖{�������o���L�[���ЃI�t�Z�b�g�e��48.5kg�A���Ԃ������I�o���L�[�l�Z��90kg�A�\����������110kg�j�B
���q�g������̑���r�́q�g��������̑���r�Ɖ���i����ьy���̎����j�̂����A�Ȑ܂̒����s���{�H�[����t�i�~���ЁA1978�j�A�s���{�H�[����\�\�����m�[�g�k�W�p�Е��Ɂl�t�i�W�p�ЁA1991�j�A�s�������{�k��l�̖{�I�l�t�i�݂������[�A2011�j�Ɏ��^����Ă���B�g�����̑����i��i�j���ŏ��ɘ_�������͂́A���l�E���p�]�_�Ƃ̉��c���F�i1939�`97�j�́q����ƁE�g�����r���낤�B���j�I�ȈӋ`�Ɋӂ݂āA���̑S�����f����B
�@����ƁE�g�����Ƃ����Ă��A�s���Ƃ��Ȃ��l�̂ق����������Ƃ��낤�B�������Ȃ��B�g�����͎��l�ł����āA�E�\�I�ɑ�����肪���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ł���B�Ƃ͂����A�{�Â�����n�m������ł́A�ׂ����_�o�����d���Ԃ�́A�ق��ł��Ȃ�����Ƃ̂��ƂȂ݂ɑ�����B�\�\���́A���W�w�Õ��x�A�w�m���x�ȂǁA���t�̎����I�ȋ@�\�ɐg���䂾�ˁA�V�������A���X�e�B�b�N�ȃC���W��W�J�����i�Œm����B���Ȃ݂ɁA���͒}�����[�̊č����ł������Č��݂́A�G���w�����܁x�̕ҏW��S�����Ă�����B
�@�ŋ߂̑���ł́A�w���V�N�v�q���r�W���E1951�`1970�x�i�y�ЁE����S�~�j������B����́A���\�N�̂������́A�w�Ď��̉x����w�킪�o�_�E�킪�����x�Ɏ��锪�̎��W�����߁A�����Ɂw���̍\���ɂ��Ă̊o�����\�ڂ��̎���i����x�����������̂ŁA�`�T���E���O��łƂ������������̂ɂȂ��Ă���B�����͖�\�܃~���A�d���͓\�����ӂ��߂Đ��S�l�\�O�����ŁA���ꂪ�Ȃ��Ȃ����������Ȃ̂��B���͒W�����F�ŁA�{�̂͊۔w�̃N���[�X�A�����Ƃ肵�����F�ɋ��̔������B���ƕ\���ɁA�L�c�l�����C�^�`�����A�����炭���z�I�ȓ����̃p�^�[��������ق��͂���Ƃ����đ����͂Ȃ��A���x�Ă͂ނ���I�[�\�h�L�V�[������Ă���B���̓��X���鉟���o���́A���V���̌��z�_�W�w��Ԃցx�k�i���p�o�ŎЁA1971�N2��28���j�A�P�c�����ɂ��Δ��p�o�ŎЂ̕ҏW�҂ɂ��Г������l�ƍD����Ȃ��B
�@���Ԃ�g�����̂����́A�����̍�i����{�ɂ܂Ƃ߂āA����Έ��̃I�u�W�F�Ƃ��Ă��͂Ȃ����Ƃ̊y���݂���o�����āA�����̑�����肪���邱�ƂƂȂ����̂ł��낤�B���Ƃ��A�w�a���`�x�Ƃ��w�Â��ȉƁx���Ƃ肾���Ă݂�ƁA�����ɂ͋g���D�݂́A�t�����X����Ǝ��ɉ��߂����n���ȑ��ꂪ�����āA���̂��Ƃ����ł��v�킸��ɂƂ��ĕł��J�邱�Ƃł���B���l�̂��̂ł́A�w�ѓ��k�ꎍ�W�T���l�̋�x�V��ޓ�Y��]�_�W�w���̋��x�i��������T�����I�o�Łj�ȂǁA�O�҂̂悤�Ɍ��S�Ȃ��̂ƌ�҂̂悤�Ɍy���Ȃ��̂Ƃ����邪��т��Ă�������͐��������Ȃ���a�V�Ɏd�グ�Ă���_�ł���B�V���{���b�N�ȃp�^�[������g���ق��͊����̑I����z�u�̍H�v�ł܂Ƃ߂�A�����Ȃ�ΌÓT�I�ȕ\�ʏ������D�܂��悤�����A�����Ɍ��t�i�����j�����̂̂悤�ɑ�Ɉ����ԓx�́A�ڎ�����{���܂Ŋт���Ă��āA�����Ƃ̗ǐS�Ȃ�r�̗ǂ��Ƃ������Ƃ��ł���B�i�s�o�Ńj���[�X�t1973�N6����{���A��O�y�[�W�A�q�u�b�N�E�X�g���[�g�r���̃R�����q����r�j
�u�g���D�݂́A�t�����X����Ǝ��ɉ��߂����n���ȑ���v�����g�̎��W�A�u���S�ȁv�㐻�{���ѓ����W�A�u�y���ȁv�����{���V���]�_�W�A�u���X���鉟���o���v�̑S�i���j�W�����V�q���r�W���B���̎l�̃��C�������A�g���������̖{���ł���B��̋g����������i�ɑ���]�́A���́q����ƁE�g�����r�ɂقڏo������Ă���B���킭�u��т��Ă�������͐��������Ȃ���a�V�Ɏd�グ�Ă���_�v�u�V���{���b�N�ȃp�^�[������g���ق��͊����̑I����z�u�̍H�v�ł܂Ƃ߂�A�����Ȃ�ΌÓT�I�ȕ\�ʏ����v�u���t�i�����j�����̂̂悤�ɑ�Ɉ����ԓx�v�B�쌩�ł���B�������́A�������u����Ƃ̗ǐS�Ȃ�r�̗ǂ��v�Ɍ��т�������A�����ɂƂ肩����܂��ɂ��̖{�̂������܂������Ă��܂��g���̊�ɋ��Q����҂��B�Ȃ��q����ƁE�g�����r�́A�g������їz�q�v�l���肸����n�����i�����炭��1���߂́j�X�N���b�v�u�b�N�̍ŏI�y�[�W�ɐ蔲�����\���Ă���B�g�������c�̂��̕]�𑽂Ƃ������Ƃ��낤�B
�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�͊��s�O�ɗ\�Ă����̂ŁA���t���s����5��3���ɓ͂����B���̓��͍Փ��ŋx�݂Ƃ����āA���������ɂЂ��Ƃ������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�y�[�W���J���Ă��Ă����Ǝv�����̂́u018�v�̋g�c����s������{���w�j�t�������Ƃ��������B�����͋g���������{���Љ�錩�J���i����3�_�́k��1���l�k��3���l�k��4���l�����Ɏ��S�W�j�̂Ȃ���1�_�ŁA���e�����������ł���Ƃ킩��g���������{�����A�����q�W�@������i�ژ^�r�Ɍf�o����Ă��Ȃ��������������ł���B�s���e�̐X�t�������ѓN�v����̃u���O���Ɋ��s�̂��j���Ɓs������{���w�j�t�����m�̋g���������{���������Ƃ�����������ƁA���������Ȃ����Ƃɓ������b�������������B���肪�������Ƃł���B�Ƃ�������ŁA�����́s�q�g�����r�����t���s���e�̐X�t���A�s�q�g�����r�́u�{�v�t�ŋg�c����s������{���w�j�k���㕶�w��n�ʍ��l�t�i�}�����[�A1963�N9��10���A�i�j����肠����B���Ȃ݂Ɂs������{���w�j�t���̐A���̊w�͗l�́s���e�̐X�t�̕ʒ��{���k���@�� �� 1120�~790mm Y�� �����l�ɍ��FDIC199�ŁA�u�����|�C���g�̐}�āv�i�ѓN�v�q�F�\�\�g�����̑���r�j�Ƃ��Č�����ōČ�����Ă���B�т���̋g���������ւ̃I�}�[�W���ł���B

�g�c����s������{���w�j�k���㕶�w��n�ʍ��l�t�i�}�����[�A1963�N9��10���A�i�j�̔��ƕ\���A���s������{���w�j�t�i���A1980�N11��10����13���k���ŁF1965�N10��10���l�A�s�̖{�j�̖{���ƃW���P�b�g
�{���̓����̈�́A���̎����敪�ɂ���B�u��Ƃ��Ƃ��Ă݂Ă��A�\�N�Ԃ���ƂƂ��Ă̕��ώ����ɂȂ��Ă���B���Ȃ��Ƃ��A�吳����A���a�̏����܂ł͂����������H���ł������B�\�N���ĂA�ߑ��ƂƂ��ẮA�ނ���ꗬ�Ƃ����Ă����B�^���������ӂ��Ɍ��Ă����ƁA�ؓ��ꡂ́u�����_���v�A���邢�͔���g�t�̌��F�ЂȂǂ��������ꂽ������܂Łi�ꔪ�Z���\���Z�j������Ƃ��āA���ꂩ��A�����푈���͂���œ��I�푈�O��܂ŁA�܂莩�R��`���w��������܂ł̎���i�ꔪ�����\���Z�܁j������ƍl����B�����āA�����O�\��N�̎��R��`�̕��w�^���Ȍ�A�吳�\�O�A�l�N�܂ł̃v�����^���A���w��A�V���o�h�̂������Ă��鎞���܂Łi���Z�Z�\��܁j���O���A�吳�\�l�A�ܔN����I��܂Łi����Z�\�l�܁j���l���A�����āA�I�킩��Ȍ�A���̎�����܊��Ƃ����ӂ��ɋ敪���邱�Ƃ��K�����낤�Ǝv���܂��v�i�q�ߑ㕶�w�j�̎����敪�r�A�{���A�Z�y�[�W�j�B���Ȃ݂ɁA�{���̊e�����ւ̃y�[�W�z���͂������B
�@�����F13�y�[�W
�@�����F35�y�[�W
�@��O���F64�y�[�W
�@��l���F48�y�[�W
�@��܊��F31�y�[�W
�Ƃ��ɁA�{����4�N�O�ɁA�����}�����[����s������{���{�j�k������{���{�S�W �ʊ�1�l�t�i1959�N4��30���j���o�Ă���B������͒������v�q�����r�A�P��g���q�吳�r�A���쌪�q���a�r�Ƃ����z�w�ŁA�u�����v�̐��j���������ďd������܂�Ȃ��B�g�c�̖{�́y9�|45���l��18�s1�i�g�A1�y�[�W������810���i400��2.025���j�A�{���ŏI�m���u����198�A2.025�~198��400.95���z�ɑ��A�y9�|28���l��25�s2�i�g�A1�y�[�W������1400���i400��3.5���j�A�{���ŏI�m���u����476�A3.5�~476��1666���z��4�{�̃{�����[���ł���B����ɂ�������炸�A����́q���Ƃ����r�ɂ́u�ŏ����玍�E�Z�́E�o��ȂǂɌ��y���邱�Ƃ͂�����߂Ă��܂������A�|�w�E�����Ȃǂɂ��Ă����nj��y�ł��Ȃ������Ƃ��c�O�Ɏv�Ă��܂��v�i�{���A�l���Z�y�[�W�j�Ƃ����āA�O�N�Ɂs�m���t���o��������̋g�����͂Ƃ������A���e���O�Y�̓o�ꂵ�Ȃ����a�̓��{���w�j�ɂȂ��Ă���̂́A���������ǂ��������Ƃ��낤�B���̓_�A���ɂ����邢�g�c�͎����ł���B
�@�����̕����ƂƂ��ɁA���̕������߂��܂������̂�����܂��B���̎��d�́A���̎G���⎍�W�̔��s���������邵���ӂ��A����ɂ́A�r�p�����S������ɂ���Ă��邨�����Ƃ��铮���ƁA��Y�Ɣᔻ�����ɂ���đi���悤�Ƃ��铮���Ƃ��������Ă��܂��B�����̌X�����ʂ���ƁA���Ƀv�����^���A���l�n���̕����A���ɁA���Y��`�ɂ������ł����A�����ɖ������Ȃ���A�Ȃɂ��S�̂��ǂ�������߂Ĝf�r����V�����X���̝����A��O�ɁA���łɈ�Ƃ��`���������l�̎��ƍċ��A�ƂȂ�܂��B
�@�k�c�c�l
�@�������A���̕����́A�ł���\�I�ɐ��̐V�������d�̈Ӌ`�����������̂ł��B����́A�r�p�������̌����̒����狩�ꂽ�A�ߒɂȐl�ԓI�E���_�I�Ȑ��ł���A�V������]���_�̕������͂���A����̔j��I�v�f�̊m�F�Ɩ����̐�ɓI�ȗ\���ɂ���āA���㎍�ɃV���b�L���O�Ȑ��_�I�l�������������̂ł����B����́A����M�v�A�k�����Y�A�،��F��A���c�O�Y�A�c������A�O�D�L��Y��̏W�c�u�r�n�v�i���a��\��N�j�ɂ���đ�\����܂��B���̂ق��A�u���{�����h�v�u���ԁv�u����v�ȂǂɏW�܂�Ⴂ���l���������̒��ԂɊ܂߂��܂��B
�@��O�̃V���[�����A���X���̌n���́A�펞���́u�u�n�t�v�i�k�����q�j�u�f�`�k�`�v�i���e�E�k���E����l�Y�E������Y�j�Ȃǂɂ���Ė�����ۂ��܂����B�����ĎЉ��������Ă���ƁA�������Ɍ`����I�Nj��̐��_����㎍�̎��ƂȂ�͂��߂����Ƃ͔ے�ł��܂���B����l�Y�̂ق��ɁA�R�{���Y�A���䒼�A�剪�M�A�������A�������j�A��c�G�A�g�����A�J��r���Y�A������s�Ȃǂɂ��̗Ⴊ�����܂��B�i�q��܊��@�Z�@���́r�A�{���A���O�`���l�y�[�W�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ�܁~��~�����[�g���E���l�y�[�W�E�������ꑕ�E�@�B���i���͖{�������j�B���^�ȕ��͋C�͋g���̎��W�s�a���`�t�i1962�j�Ɏ��Ă���B�{����1965�N�Ɏs�̖{�i�����͋g���ł͂Ȃ����낤�j�����s����ă����O�Z���[�ƂȂ�A1982�N�ɂ͑�Q�ł��o���B�܂��s������{���w�j�k�g�c���꒘��W ���\�ꊪ�l�t�i�����ЁA1980�N3��12���j�ɂ́A�}���łɂ������q���Ƃ����r�Ɗ����̔N�\���������{�������߂�ꂽ�B����W�̂��߂̂��Ƃ����ɂ�������B�u�u������{���w�j�v�́A�}�����[�u���㕶�w��n�v�̕��^�Ƃ��āA��n�ʍ��̔i�Ƃ��ď������낵�A���a�O�\���N�㌎�\���ɏ��߂Ĕ��s�������̂ł���B�������낵�Ƃ����Ă��A��O�̎Q�l���y�єN�\�����A�����P���̗��قȂǂɉ�����㣋l�߂ɂȂ�A�ҏW�����̉������㎁�̊Ď��̂��ƂŁA���L�҂Ɂu����ׂ艺�낵�v�����̂��ŏ��ł���B�ォ���̕��͂���k��̋L���Ȃǂ��Ȃ������A���ׂĂŐ����ԂŎd�グ���ƋL�����Ă���B�̂���n�̏I����́A�Ɨ������P�s���Ƃ��Ċ��s���ꂽ�v�i�����A�O�Z�O�y�[�W�j�B�����[�������b�ł���B�Ȃ���������i1919�`90�j�\�\�q�n�̂ɂقЁr��1955�N����̊H��܂̌��ƂȂ����\�\�ɂ́A�s�킪�S�̏o�Ől�\�\�p�쌹�`�E�Óc��E�P��g���t�i�͏o���[�V�ЁA1988�j������B
�k���㕶�w��n�l�͑S69���A1963�N9���`68�N7�����B�����͐^�甎�A�l�Z���E�㐻�E�N���X���E�\�����E����t�A�e��480�~�B�����ẮA�ؓ��ꡁE��t���l���E�k�����J�W�^����g�t�E�ԏW�^�K�c�I���E�����t�W�^�X���O�W�^���y�b�ԁE�؉����]�E���A�W�^���ؓc�ƕ��E�ΐ��؏W�^�����q�K�E���l���q�E���ːߏW�^���蓡���W�i��j�^���蓡���W�i��j�^�c�R�ԑW�^���c�H���W�^���@�����W�^�Ėڟ��ΏW�i��j�^�Ėڟ��ΏW�i��j�^�k�����H�E���������Y�E�{���W�^�֓��g�E���ؐԕF�E��R�q���E��狋�W�^�i��ו��W�^�J�菁��Y�W�i��j�^�J�菁��Y�W�i��j�^���ҏ��H���ďW�^�u�꒼�ƏW�^�L�����Y�W�^�������E�v�ۓc�����Y�W�^���^�P�Y�E���퐶�q�W�^�H�열�V��W�^�R�{�L�O�W�^�����t�v�W�^�e�r���E�L�Øa�Y�W�^�F��_��E�����P���E�q��M��W�^�����Ґ��E�O���ɏW�^���F��E�����Y�E��ыŏW�^��������W�^��[�N���W�^�����Y�E�O�D�B���E���e���O�Y�W�^�����Y�E�x�C�Y�E�����֏W�^����d���W�^�t�R�Î��E���ё����E���i���W�^�{�{�S���q�E������q�W�^�Ԗ�e�E���h�E�K�c���W�^���т����q�E�~�n���q�W�^���{���̎q�E�ѕ����q�E�F����W�^���яG�Y�W�^�䕚����W�^���c�ّ��Y�E���،���E�D�c��V���W�^����m�Y�E�Ζ숯���W�^�O�H���Y�W�^�M������W�^�ΐ�B�O�W�^�ɓ����W�^���R�`�G�E�����m��W�^�i�䗴�j�E�c�{�ՕF�E�~��t���W�^�ΐ�~�W�^�������E���F��Y�E�h��Y�W�^���Ɏ��W�^��ԍG�W�^�Ŗ��َO�W�^���c�~�W�^�O���R�I�v�W�^�剪�����W�^�����W�^�x�c�P�q�E����O�V�E��������E��]���O�Y�W�^�����q�Y�E�����͑��Y�E���쏁�O�E�g�s�~�V��W�^���㖼��W�i��j�^���㖼��W�i��j�^���㖼��W�i�O�j�^���㖼��W�i�l�j�^���㎍�W�^����̏W�^�����W�B�r���G�͒k�b�q�S�W�̂��A�ō�ƂɂȂꂽ�r�Łu���Z�O�N���犧�s�J�n�����}�����[�́w���㕶�w��n�x�i�S�Z�㊪�j�́A�~�{����̑S�W��i���������Ȃ���A����ɔN�\�������������J�Ȃ���ł����B���̂��납��A���I�ȑS�W�̂������ɂȂ��Ă������̂ł��傤�ˁv�i�skotoba�t��20���A2015�N�āA�O�l�y�[�W�j�Ɩ{�S�W�ɂ��Č���Ă���B���Ȃ݂ɑ�32���̉�������W�̔N���͕ۏ����v�ҁA����͉͏�O���Y�B�����Ă͌����ɋy���A�N���E�����������{���w�p���̐��T�m�L���m���n����ɂӂ��킵���B

�s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�i�}�����[�A1967�N12��10���j�k�����F�^�甎�l�̔��ƕ\���A�s���k���{���w�S�W67�l�t�i���A1970�N11��1���j�̕\���A�s���k�}�����㕶�w��n �ʊ�1�l�t�i���A1981�N12��15���j�̔�
�g�����̎��W�s�Õ��t�i1955�j��S�ю��^�����s���㎍�W�k���㕶�w��n67�l�t�i�}�����[�A1967�N12��10���j��M���Ƃ���3�V���[�Y�͓����{���ّ̈��ł����A�����̏��e���f����B�s���㎍�W�k���{���w�S�W67�l�t�Ɓs���k�}�����㕶�w��n �ʊ�1�l�t�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ����̂́A��҂̂�������Ƃ�������́A�l�Z���Ȃ���A���n�F�l�Y�����́k������{���{�S�W�l�Ƌg���������́k������{���{��n�l�܂����݂��ƂȎd�オ��i�����͋g�����j�B�k���㕶�w��n�l�̐A���̊w�͗l�i�k���{���w�S�W�l�ł����P���ꂽ�j�͂����炭�����S���̐^�甎�̍�ŁA�s������{���w�j�t�ł����4���ׂ�360�x�ɓW�J�����̂͋g���̑n�ӂł���B
�ےJ�ˈ�̕]�_�W�s�R�����u�X�̗��t�i�}�����[�A1979�N6��30���j�́q���������҂Ƃ��ẲĖڟ��r�i���o�́s�W�]�t1969�N6�����j�Ɏ��̂悤�ȉӏ�������B
�@�����������Ă�邤���ɁA�ڂ��͐�N����S�W�́u�Ėڟ��ΏW�v�ɂ��Ă��N���ŁA����������\�ܔN�Ɂu�����̊W��v�k�C���ɐЂ��ڂ����Ƃ��ӂ��Ƃ�m���B�Ŗ����Č��ւA���̂Ƃ��ڂ��͂����ĕ��C�ł�B�����̐l�X�������̂���̂��߂��ꂱ��ƍH�v�����͓̂��R���炤���A�]�˂q�̟����F���Ⓑ�B�̐��{�̂��ߕ����Ɏ���邱�Ƃ��}�����C���͂悭����A�ȂǂƎv�������̂₤�ȋC������B�i�s�R�����u�X�̗��k�����ܕ��Ɂl�t�}�����[�A1988�N12��1���A��Z�y�[�W�j
���́u����S�W�́u�Ėڟ��ΏW�v�ɂ��Ă��N���v�Ƃ͂ǂꂩ�B��g�́s���ΑS�W�t��}���́s�Ėڟ��ΑS�W�t�ł͂Ȃ��킯������A
�̂����̂ǂꂩ���낤���i��L�̃��X�g�́A����}����NDL-OPAC�̃f�[�^���������������������A�R�ꂪ����ɂ��Ă��A�u����S�W�́u�Ėڟ��ΏW�v�v�̂���܂��͔c���ł��悤�j�B���悻���{�i�ߑ�j���w�S�W�Ƃ������ނ̑p���ŁA�Ėڟ��ΏW�̂Ȃ����̂͂Ȃ��͂����B�b���q���������҂Ƃ��ẲĖڟ��r�ɖ߂��A�s���T��t�̕s���Ȍ����́A���������������������̂��Ƃ������������Ċ���Ȃ��������i�ނ��A�������͂����Ȃ��j�A�T�ؑ叫�̎��n�����������̘_���Ƃ͕ʂ̋��瓱���������ʂ��Ƃ������ƂɂȂ�B�ےJ�̌��_�́u���́A���j�Ɨ��j���ۂƂ̂��Ђ��ɗ����Ȃ����ނ��鍑��`�̎���ɐ�������{�l�̗J�D��`���Ȃ����B���̂��Ƃ��ڂ��͐ӂ߂悤�Ƃ͂��Ȃ��B�����ڂ�����߂�̂́A���̑㏞�Ƃ��Ė������A�\�z���ꂽ�F��Ɨ���̐��b�ɂ����āA�I��߂��A�Ƃ����l���̖ʉe�������m��������n�̂Ȃ��ɖv���Ă��܂ӂ��Ƃł���B�u�����̐��_�v�Ƌꂵ�܂���ɟ��͌��ӁB�����������́A�ǓƂȈ�m���l�ł���u�搶�v�̐��_�́A��E�ƌR�l�́i���Ƃւ��ꂪ�ǂ�قǓ���ɉ�������̂ł��炤�ƁA�Ђ��悤�j�����ɂ����Ȃ����̂ɂ�āA�ڂ������̊Ⴉ��傫�����ւ����Ă��̂ł���v�i�����A�܈�y�[�W�j�B���̓��قȁs���T��t�_�ɂ��ğ��Θ_�́A�u����S�W�́u�Ėڟ��ΏW�v�ɂ��Ă��N���v�̋L�ڂɂ���Ď�N�̂��납��̓���ւ̈�a�������m�Ɉӎ������ꂽ���Ƃɒ[����B�ӔN�̊ےJ�́A�Ǐ��̐S���̈�Ƃ��āA���낢��Ȕłō�i��ǂނ��Ƃ������Ă����B�q���������҂Ƃ��ẲĖڟ��r�͂��̎��H�̏�ɐ������ƌ����悤�B
32�т̉Ėڟ��Ό����A�N���A�Q�l�����ژ^�����߂��s�Ėڟ��ΑS�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l�t�i�}�����[�A1973�N1��25���k2���F1973�N8��20���l�j������B���S���q�ҁq�N���r�́u�w������v�A�u������\�ܔN�i�ꔪ���j�@��\�Z�v�̏��A�u�l���A���Ɠ͂��o���A�k�C����u�m����ׂ��n������S���㒬�\���Ԓn��O�Y���ɈڐЁi�����֕��Ђ����̂͑吳�O�N�Z���j�B�k�C�������ƂȂ�B����͖�����\��N���������߂����z����A�����F����`����������āA�ˎ�̒��W�P�\��p���A��w���̒��W�P�\�͓�\�Z�܂łƋK�肳�ꂽ���߁A�l���H���̂��߁A�����߂̎{�s��悩��͂�����Ă����k�C���ֈڐЂ������̂ƌ�����B�Ƃ̌ːЂ́A���̌�܂��Ȃ�����S������厚��䒬�\�l�Ԓn�Ɉڂ����B��O�Y�͎O�䕨�Y�c�Ə��̌�p���l�������炵���A�ĖډƂƂ̊W�͕����łȂ����A���͕��̔z���������ƌ���Ă���B�i������ʂɂ́A��w���͕����ɊW�Ȃ����̂Ǝv���Ă����炵���A���̒����������A�����I�ȈӖ��ł̐푈�����ƌ��т���̂͑Ó��ł͂Ȃ��B�j�v�́A�Ƃ�킯�����́i�@�j���̈ꕶ�́A�ےJ�_���������̂ł���B�N���͂��̂悤�ɂ��čX�V����Ă����B
��
�}�����[�͎l�Z����2�x�A�Ėڟ��̑S�W���o���Ă���B����͐�s�����H�열�V��S�W���X���O�S�W��3�x�\�\�i1�j������㐻�{�i2�j���ꑕ�̕����{�i3�j�}���S�W���ڂƂ�������d�l�̔�����㐻�{�\�\�����ł��g���Ċ��s�����̂ɑ��āA��Ȉ�ۂ�^����B��N�̂����ܕ��ɂ��܂߂āA�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�Łs�Ėڟ��ΑS�W�t�̊T�v�����Ă݂悤�i�B�͈ꕔ�A��L�����j�B
�@�@�Ėڟ��ΑS�W�@�ďC�E��E����@�g�c����@�S10���@1965�N11���\66�N8��
�@�l�Z���E�t�����X���k���ꑕ�����{���������l�E�r�j�[���J�o�[�t
�@�A�Ėڟ��ΑS�W�@�}���S�W���ځ@�ďC�@�g�c����@�O��̔łɕʊ���������@�S10���ʊ�1�@1971�N4���\73�N1��
�@�l�Z���E�㐻�E�@�B����
�@�B�Ėڟ��ΑS�W�@�����ܕ��Ɂ@����F�g�c����@�S10���@1987�N9���\88�N7��
�@1971�N4���`1972�N1�����u�Ėڟ��ΑS�W�i�}���S�W���ځj�v���{�Ƃ���
�@�`�U���E�����E�W���P�b�g�B�{��8�|�g�B�����F�������@����F��㐟��
�@�͊H��≨�O�́i2�j�ɁA�A�͓������i3�j�ɑ�������B�i1�j�̔�����㐻�{�ɑ�������ł��Ȃ����R�́A��́s������{���w�S�W�t���͂��߂Ƃ���q�Ėڟ��ΏW�r�̔���䂫���D���������߂�������Ȃ����A�S�W�k�ʊ��l�̓��e�i�Ėڟ��Ό����A�N���A�Q�l�����ژ^�j��Z�����ŗp�ӂł��Ȃ��������߂�������Ȃ��B�����A�@���u�V���Łv��搂��Ă��Ȃ��̂́A�}���ōŏ���[�A�A�A]�Ėڟ��ΑS�W����������ŁA���ꂪ�i2�j�Ɠ��l�̌y���łł��邱�Ƃ́A�����A�}�����H��≨�O�قǂɂ͟����d�����Ă��Ȃ��������Ƃ̖T�ƂȂ�B������ɂ��Ă��A�H��Ɖ��O�̑S�W�ɑ����𑵂݂��邽�߂̎d�l�̑I��ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�@�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�O�ܘZ�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E���������B�A�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�O�Z�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\���Ӂi���ɓ��e�ꗗ�j�B�ǂ�����Г������̏�ő����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�A�͋g�����ɂ����̂Ǝv����i�@�͑��^������i�j�B
����i��s���ΑS�W����t�i�p�ɁA1985�N9��25���j�ɂ́A�@�́u�ҏW��̓��F�Ƃ��Ă�������̂́A�u���̑S�����A�S���i�A�S�]�_�y�єނ̎�����M���Ƃ��Đ��Ɏ������n��y�т���ɏ�������̂͂��ׂĎ��߁A���̌����҈ȊO�ɂ͂����ĕK�v�łȂ��Ǝv����A���Ύ��g�����\��{�ӂƂ��Ȃ��������݂̂̂���������v�i���s�̂��Ƃj�Ƃ������Ƃł��낤�B��g�ł܂��͊�g�łP�����S�W�ȊO�̂��̂ɂ͂��܂��܂ȑI���̎d�����݂�ꂽ���A�}���ł́A���Ҏ��g�����\���ׂ����������݂̂̂ɂ��ڂ����I���Ƃ����̂���̌������낤�B�^���̂��߁A���ȁA���L�A�����̏������݂Ȃǂ͓��R�͂�����Ă��邪�A��匤���ɑ����镶�w�_�A���w�]�_�A�p���w�`���_�A����Ɏ��̔o��Ȃǂ����O����邱�ƂɂȂ����B�^�{���͐V���ȂÂ����E���p�����ɂ��Ă��邪�A�p��ł��邢�͏t�z���łɂ���ׂ�ƁA�����͟��̕\�L���c���A��ǎ��Ƀ��r�����Ă���v�i�����A�ꎵ�Z�`�ꎵ��y�[�W�j�ƊȌ��E�I�m�ɋL���Ă���B

�s�Ėڟ��ΑS�W�k��7���l�t�i�}�����[�A1966�N5��25���j�̕\���A�s�Ėڟ��ΑS�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l�t�i���A1973�N1��25���k2���F1973�N8��20���l�j�̔��ƕ\���A�����ܕ��ɔŁs�Ėڟ��ΑS�W�k��2���l�t�i���A1987�N10��27���k4���F1995�N10��5���l�j�̃W���P�b�g�k�����F�������A����F��㐟���l
�����Ŋ�g���X�ł́s���ΑS�W�t�ɐG��Ă����B�R���_�́s�{���̐��Ԋw�\�\���E���O�E�H��t�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1993�N6��18���j�͑S�W�̖{���ɂ��Ẳ���I�Ș_�l���������A�����́s���ΑS�W�t���ᔻ����Ă���B�������s�S�t�ւ̌��y�͂Ȃ��B
�@��g�ł́u����Łv�i�y�т���ȍ~�̔Łj�́A�m���ɁA�X�c������ɂ���ğ��̎���قǂȂ����s���ꂽ�S�W���ł𑽏��Ƃ����ǂ��Ă͂���B��������{�I�ȍZ�����j�ɂ��Ă͑卷���Ȃ��A���s�̔ł����l�Ȗ��_������Ă���B
�@��g�ł��A���o�⏉�łɌ�����u��y�v��u�]�v�u�]�y�v�������̌������i�H�j���������Ƃ��Ƃ��u��y�v�ɓ��ꂵ�����Ƃ͂��łɏq�ׂ����A����͓��ł̐��i���ے����Ă���Ƃ����悤�B���ڒm���Ă���Z���ҒB���A���̂��߂��v���P�ӂōs�����u�����v�Ȃ̂ł��낤�B����I�ɂ����ꂪ�����ꂽ�킯�ŁA�M�҂͏\�����I�O���̉p���Ő���Ɂu�C���v���[�u�v�iimprove�j�A�܂�u�����v���ꂽ�V�F�C�N�X�s�A�̖{����f�i�Ƃ���B�����ꂽ��i�̖{���͂��Ă��Ă��������^���ɂ�����̂��B�i�����A�܋�`�Z�Z�y�[�W�j
���S�W�́A������g����ŏ��ɏo�����P�s�{�s�S�t�i1914�j��͂����O���ňٍʂ���B���́s�S�t�\�\�g�c����͉Ėڟ��ΑS�W�k��7���l�́q����r�ŁA�u���͑��ꂻ�̑���������ōl���A�x�ߌÑ�̐ΐ�����\���̈ӏ����Ƃ����B���ꂪ�̂��ɟ��ΑS�W�̑���Ƃ��ēǎ҂Ɉ�ۂÂ������̂ƂȂ����v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���\�\�����Ƒc���]�T�̑����ɂ��Ċ����ꂽ�i��g���X�A2014�N11��26���j�B���y�̐��E�ł͉ߋ��̖���̃��}�X�^�[�����Ղ��������Ȃ����A�����i�{���j�����Ȃ������Ƃ͂����Ă��A�W���P�b�g�i�����j�܂ō��Ȃ������Ƃ͋H�ł���B���ꂪ���́s�S�t�̍Ċ��i���ۂ́u��x�߁v�ł͂Ȃ��A���x�߂��̊��s�ɂȂ�킯�����j�́A�{�����������ߋ��ɂȂ��d�オ��ɂȂ��Ă���i�ѕ��Ɍ�����uKOKORO naked!�v�̓r�[�g���Y�A1970�N�́sLet It Be�t�ɑ���2003�N�̐V�ҁsLet It Be... Naked�t�܂������́j�B���ꂪ�����ɈِF���́A���������̒��L�������Ƃ��肾�B���̍��ڂ����ł��L���ɒl����B�������̑O�ɁA�c���]�ƕҏW���ɂ��q�c���]�T�u�b�N�f�U�C���@���w�S�x�@�{���̕ҏW�ɂ��ār�����悤�B�����ɂ́u��{�́A�Ėڟ��ɂ�鎩�M���e�Ƃ��A��L���Ӑ}�I�ȕ\�L�����ʂ��Â炢���̂����łȂ��A���炩�Ȍ�L�����̂܂܂Ƃ����B�܂��A�ӂ肪�Ȃɂ��Ă͎菑�����e�ɋL�ڂ��ꂽ���݂̂̂����e�ǂ���ɋL�ڂ����B�������A���ȂƊ����̎��̂ɂ��Ă͓ǂ݂₷����D�悵�A����l�N�̊�g���X�w���ΑS�W ��㊪�x�ɂ��������A�����Ƃ��Ēʍs�̎��̂��g�p�����v�i�����A�k�l�ܓ�y�[�W�l�j�Ƃ���B�����āq�\�L�E�{���g�ɂ��ār�̍��ځ\�\
����Ɂq�g�p�}�łɂ��ār�̍��ځ\�\
�������B����͌��������邵���Ȃ��s�ςł���B�O�f�R���_�s�{���̐��Ԋw�t�ƁA���̎��M���e���ʐ^�łɂ����s���M�œǂށu�V�������v�k�W�p�АV�����B�W���A���Łl�t�i�W�p�ЁA2007�j����т��́s�S�t�Ċ���ǂ݂���ׂĂ݂�ƁA�S�W�Ɍ��炸�A��i�̖{���Ƃ͂Ȃɂ����l����ۂɏd�v�ȓ_�������ڂ�ɂȂ�B���̍�i�����A���̍�Ƃ̑ΏۂƂ��čł��ӂ��킵�����̂ł���A���̂��߂̍ޗ��Ɏ������Ȃ���D�̎���̈���s�S�t�������i�s�S�t�̟��Ύ��M���e�͊�g���X�̏����j�B���́s�S�t�ł��������̂��A�����͂��̌�A�s�Ɏq�˂̒��t�i��g���X�A1915�j�����Ȃ����A�g�����͂قƂ�ǂ��ׂĂ̎���̑��{�E��������|�����̂�����A�{�����܂ޏ������\�����邠����v�f���������邱�Ƃ��s���ł���B
�g���͐��z�q�Ǐ����r�Ɂu�k�c�c�l���́u�S�v�A���V��̒Z�сA�Ƃ�킯�u�M�̒��v�A�ו��́u�����ߍ��v�A����Y�́u�t�Տ��v�A�N���́u�ፑ�v�A����́u�@�B�v�ȂǓ��ɍD���ȏ����ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�ܘZ�y�[�W�j�Ə����Ă���B�g���̌��y�����B��̟���i���s�S�t�ł��邱�Ƃ́A���̏����̖��͂Ɠ����Ă��悤�B�g���́A���i���邢�͍L�����w�ƂƂ炦��ׂ����낤�j�ɂ͓䂪�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ˂Âˌ���Ă����B
![�s���ΑS�W�k��3���l�t�i��g���X�A1994�N2��9���j�̔��ƕ\���A���s�S�t�i���A2014�N11��26���j�̔��ƕ\���k�����͟��Ƒc���]�T�l](image/soseki_2a.jpg)
�s���ΑS�W�k��3���l�t�i��g���X�A1994�N2��9���j�̔��ƕ\���A���s�S�t�i���A2014�N11��26���j�̔��ƕ\���k�����͟��Ƒc���]�T�l
�s�X���O�S�W�t�͒}�����[��3�x�A�l�Z���Ŋ��s����A�̂��ɂ����ܕ��ɔł��o���B�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�Łs�X���O�S�W�t�̊T�v�����Ă݂悤�i�C�͖ژ^���f�ڂɂ��A���т�������j�B
�@�@�X���O�S�W�@�ďC�E����@�g�c����@�S8���ʊ�1�@1959�N3���\62�N4��
�@�l�Z���E�㐻�E�z���E�@�B�����E����t
�@�A�X���O�S�W�@�O��̔łɂ��V���Ł@�S8���@1965�N4���\11��
�@�l�Z���E�t�����X���E�r�j�[���J�o�[�t�E����t
�@�B�X���O�S�W�@�}���S�W���ځ@�O��Ɠ����Ł@�S8���ʊ�1�@1971�N4���\12��
�@�l�Z���E�㐻�E�N���X���E�@�B����
�@�C�X���O�S�W�@�����ܕ��Ɂ@����F�c������q�@�S14���@1995�N6���\96�N8��
�@�`�U���E�����E�W���P�b�g�B�{��8�|�g�B�����F�������
�}���S�W���ڂ��炿���ܕ��ɂɑS�W���ڍs���������Ƃ́A���N���ɐX���O�E�Ėڟ��E�H�열�V��E���Ɏ���4�l�B���E�H��E���ɂ�3�l��2015�N���݁A�����ܕ��ɂ̍ɂ����邪�A���O�͕i��ł���B���ׂ��킯�ł͂Ȃ����A4�l�̒��ł��������o�Ă��Ȃ��̂����O�ł͂Ȃ��낤���B�Ƃ����s�H�열�V��S�W�i�V�������j�k��6���l�t�i�}�����[�A1965�N1��20���k�ĔŁF1965�N5��30���l�j�́q�X�搶�r�ɂ�������i������[�@]�͊H��S�W�ɂ�������U�艼���A�y�@�z�͊H��S�W�ƌ�o���O�S�W�ʊ��̗����ɂ���U�艼���j�B
�@���Ă̖�m��n�A�܂����ȑ�w�̊w���Ȃ肵���A�F�l�R�{��m�����܂��Ɓn�N�ƁA�ϒ��O�m�����Ă��낤�n�֎Q�肵������B�X�m����n�搶�͔����V���c�ɔ������m�̌сm�͂��܁n������ꂵ�ƋL�����B�G�m�Ђ��n�̏�ɏ������ߑ����̂����A�������y�t�����X�z�̏����A�x�߂̋Y�Ȃ̘b�Ȃǂ���ꂽ��B�b�̒��m�����n�A�����L�y�����������z�Ɣ��i�L�m�т͂��n�Ƃ��Ԉ���m���n��ꂵ�ׁA�搶�����ɂ͊Ԉ�͂�鎖�����m��A���y���ցz�Đe���݂𑝂���������B�����͍��Ám�˂Án�E�G�m�����킢�n�������炷��K�A�i��ו��m�Ȃ���ӂ��n���̓��a���ʁm�Ђ�肰���n�ɏ����ꂽ��Ɠ��������ɂ��炸��Ǝv�ӁB���̍��̐搶�͖ʁy�����z�̐F���ɏĂ��A�@���y�����z�ɂ��R�l�炵���S�n������ǁA�ތ��ȂǂƉ]�ӌ��ꂵ���͊o�����B�p�Y���q�̔O�ɖ�������䓙�ɂ́A�����Ȃ�搶�Ƃ̂ݎv�͂ꂽ��B
�@���Ėځm�Ȃ߁n�搶�̌䑒���̎��A�R�m������܁n�֏�m�������₤�n�̖�O�̓V���y�Ă�Ɓz�ɁA���߂������肵���A���~�m�����ӂ�n�̊O���ɒ��ܖX�����Ԃ肵�l�A�킪�O�֖��h�m�߂����n�������o������B���̐l�̊�̗��h�m��ρn�Ȃ鎖�A�_�ʂ���Ƃ��]�ӂׂ����A�ő��m�߂��n�ɐ��̒��ɂ����Ȃ炸�B���h������ΐX�ё��Y�m�����炤�n�Ƃ���B����A�搶�������Ǝv�Ђ����́A�����֏�֓��m�͂Ёn��ꂵ��Ȃ肫�B���̎��搶������肵�́A�����搶�̖ʁm�����n�̐F�����炴�肵�ׂȂ�ׂ��B�����搶�͗��R��ނ���A�����ʂЂ��~�߂�ꂵ���A���ɏĂ����鎖���Ȃ��肵�Ȃ�B �i�吳�\��N�����E����e�j
�{���������q�X�搶�r�́s�X���O�S�W�i�}���S�W���ځj�k�ʊ��l�t�i�}�����[�A1971�N11��5���k11���F1979�N12��20���l�j�ɂ����߂��Ă��āA������̕����U�艼�������Ȃ��B�����Ƃ������ɂ����Ɩ{���͓����ł͂Ȃ��A�H��S�W�͊������V���ŁA���O�S�W�ʊ��͋����ł���B�܂莚�ʂ͉��O�S�W�������߂����A�H��S�W���₳�����B�����A�H�삪���������e�ɋ߂��͉̂��O�S�W�ʊ��̕����낤�c�c�ȂǂƐ������d�˂Ă��Ă��d�����Ȃ��̂ŁA��g���X�ŊH�열�V��S�W�k��5���l�i1977�N12��22���j�́q�X�搶�r������ƁA�����͋����ŁA�U�艼���͂ЂƂ��Ȃ������B�����́q��L�r�ɋ���A���o��1922�N8���́s�V�����t�Վ����q�������O�X�ё��Y�r�A�����͊H��̐��M�W�s�~�E�n�E��t�i�V���ЁA1926�j�ŁA�S�W�̒�{�͏����B���������u����e�v�̕��͂ɒ��҂����܂߂ɐU�艼���������Ƃ͍l���ɂ����B�H��S�W�Ɖ��O�S�W�ʊ��̖{���ɐU�艼����t�����̂́A�Ҏ҂�ďC�҂̈ӂ����S�W�ҏW���Ƃ������ƂɂȂ낤�B�U�艼���Ȃ��ł����ɂ���A���Ȃ߂ɕt����ɂ���A���߂ɕt����ɂ���A�q�X�搶�r��т����̘b�ł͂��܂Ȃ��B�����ɂ́A�|��ɂ́A���M�ɂ́A�����\�̕��͂ɂ́c�c�ƁA���j�𗧂ĂĂ��Ƃɓ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł��V�����s�X���O�S�W�i�����ܕ��Ɂj�t�́q�ҏW�t�L�r�ɂ͂�������B
��A�{�S�W�́A��㎵��N�l������㌎�Ɋ��s���ꂽ�}���S�W���ڔŐX���O�S�W���{�Ƃ������A��\�ꊪ�u�t�@�E�X�g�v��\�́u����e�v�������|�Z�сA�y�ё�\�O���́u�ϒ��O���L�v�u���q���L�v�u���I�ޗ��v�͊�g���X�ŐX���O�S�W�ɋ������B
��A�{���\�L�́A�����Ƃ��ĕ���̍�i�ȊO�͐V�����E�V�����Â������̗p�����B
��A�{���͒��Ҋ��p�̕\�L���܂߁A�����ɏ]�����B�A���A�ǂ݂₷�����l�����A���i���́A����j�A���i���́A����j�A�����i�������j����̎w���㖼���A�ڑ������̊������Ђ炢���B�i�����ܕ��ɔŁs�X���O�S�W�k��1���l�t�}�����[�A1995�N6��22���A�k�l�l�܃y�[�W�l�j
3�x�̎l�Z���S�W�����L�����^���i�Ƃ�킯�|��j�A�V���E�V�������̗p���A�ǂ݂ɂ��������������ɒu���������킯���B���́s�X���O�S�W�i�����ܕ��Ɂj�t���i��Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤�B��v��i�͑��Ђ̕��ɂœǂ߂�ɂ��Ă��A���ꂾ���̋K�͂őn��ƁE�|��ƁE�]�_�ƁA���Ȃ킿���w�ҐX���O������n���f�B�ȑS�W�͑��ɂȂ��̂ł���B

�@�s�X���O�S�W�k��1�E8���l�t�i�}�����[�A1959�N3��15���E9��30���j�̔��ƕ\���A�A�s�X���O�S�W�i�V���Łj�k��1���l�t�i���A1965�N4��19���k12���F1970�N7��10���l�j�̕\���A�B�s�X���O�S�W�i�}���S�W���ځj�k��4���l�t�i���A1971�N11��5���j�̔��ƕ\��
�@�s�X���O�S�W�k�S8���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1959�N3��15���`1962�N4��30���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�l�~�����[�g���E�e�����ϖ�l��l�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�@�B���i�����ĂɐԎ��œ��e�ꗗ���f�ڂ��邪�A���E�\���E���Ԃ��Ƃ��܂���������d�l���H�열�V��S�W�̃X�~�����ɂ����e�ꗗ�̕����ǂ݂₷���j�B�苖�̑�1���̋g�c����q����r�ɂ́u�u�ցv�ɂ��ẮA���ꂪ�H�열�V��̒Z�сu�^�f�v�̕��{�ł͂Ȃ��܂ł��A�����炩���ʂ��Ă�����̂����Ă��邱�Ƃ݂̂��L���Ă������v�i�����A�O����y�[�W�j�Ƃ���B�H��̐��ƂȂ�ł͂̓��@���낤�B�A�s�X���O�S�W�i�V���Łj�k�S8���l�t�i�}�����[�A1965�N4��19���`11��15���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�l��l�y�[�W�E���������B�s�}�����[�}�����ژ^�t�ɂ́u�t�����X���v�Ƃ��邪�A���ꑕ�̕����{�ł���B�B�s�X���O�S�W�i�}���S�W���ځj�k�S8���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1971�N4��5���`12��10���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�l��l�y�[�W�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\���Ӂi���ɓ��e�ꗗ�j�B��������Г������̏�ő����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�@�ƇB�͋g�����ɂ����̂Ǝv����i�A�͑��^������i�j�B
��N�̂���s��t�ɐe���g���́A���Ԃ��Ȃ����L�Ɂu�ɓ�����Y�s�X���O�t��ǂށv�i1946�N1��29���j�A�u���̒��ʼn��O�́s�G�]���ցt����ށB�ꌩ�A�n�}��N����肾���s�v�c�Ɩ��͂��鏬�����v�i1947�N7��5���j�Ə����Ă���B�ɓ��̖{��1944�N���̑���{�Y�ى�u�k�ДŁB�g���͈ɓ��̒��я����s�Ԃ̉��k�V����肠�p���l�t�i����肠�E�������āA1939�j�����ǂ��Ă��邩��A���̑I�����ɓ��ւ̊S���炩���O�ւ̊S���炩�A���f�ł��Ȃ��B�s�G�]���ցt�͂ǂ̔ł��킩��Ȃ����A�������ɂ���g���ɂŁA��g�̉��O�S�W�ł͂Ȃ��悤�ȋC������B
�q�g�����̑�����i�i89�j�i2011�N3��31���j�r�Ɍf�����k��1���}�����[�Łl����k��11���}�����[�Łl�܂ł̑��Ɏ��S�W�̃��X�g�\�\�k��10���l�s���Ɏ��S�W�k�ʊ��l�t�i�}�����[�A1992�N4��24���j�f�ڂ̎R���ˎj�ҁq�����r���ɂ�����\�\�Ɂs�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�̏��lj����Ĉꗗ�\�ɂ���B�Ȃ��k��1���}�����[�Łl�͇@�̂悤�ɕ\�����A�u�k��11���}�����[�Łl���Ɏ��S�W�@�S13���@1998�N5���`1999�N5���v�͋g�����̟f��̊��s�ɂ����������B
�@���Ɏ��S�W�@�S12���E�ʊ�1���@1955�N��10���`1956�N9��
�l�Z���E�㐻�E�\�����E����t�B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��420�~�@�ʊ�480�~
�A���Ɏ��S�W�i���y�Łj�@�O��Ɠ����łɂ�邪�A��12���ɑ���@�S12���E�ʊ�1���@1957�N10���`1958�N9��
�l�Z���E�㐻�E�J�o�[���E����t�B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��290�~�@�ʊ�320�~
�B���Ɏ��S�W�i�V���Łj�@�S16���@1959�N12���`1960�N8��
����@�T�䏟��Y�@���a�U���E�t�����X���E�@�B�����B�{��8�|��i�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��160�~�@��13�E14��200�~
�C��{ ���Ɏ��S�W�@��3���ł����ɉ��ҁE���₵�����́@�S12���E�ʊ�1���@1962�N3���`1963�N3��
����@���쌒�j�@���a�U���E�㐻�E�z���E�n���\���E�@�B�����E����t�B�{��8�|��i�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��320�~
�D���Ɏ��S�W�@��1���ł����ɉ����E����@���ȏW�̂ݐV��2�i�g�@�S12���E�ʊ�1���@1967�N4���`1968�N4��
�l�Z���E�㐻�E�z�\���E�J�o�[�t�E�@�B�����E����t�B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��580�~
�E���Ɏ��S�W�i�}���S�W���ځj�@��5���łƓ��e�E�Ő��Ƃ������@�S12���E�ʊ�1���@1971�N3���`1972�N3��
�l�Z���E�㐻�E�@�B�����B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��850�~
�F���Ɏ��S�W�i�V���Łj�@�S12���@1975�N6���`1977�N11��
���@�ֈ���j�@��12���̂ݑ��n����@�Z�ٕt�@
�`�T�ό^���E�㐻�E�����E����t�B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�艿3,700�`4,600�~
�G���Ɏ��S�W�i�V���Łj�i�}���S�W���ځj�@��7���łƓ��e�E�Ő��Ƃ������@��10�E11���Ɏ�̑��₠��@�S12���@1978�N6���`1979�N5��
�l�Z���E�㐻�E�@�B�����B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B�e��2,000�~
�H���Ɏ��S�W�i�����ܕ��Ɂj�@1975�N6���`1976�N6�����u���Ɏ��S�W�i�}���S�W���ځj�v���{�Ƃ���@�S10���@1988�N8���`1989�N6��
���@�ֈ���j�@�J�o�[����@�����
�`�U���E�����E�W���P�b�g�B�{��8�|�g�B�����F�������B�艿680�`800�~
�I���o ���Ɏ��S�W�@�S12���E�ʊ�1���@1989�N6���`1992�N4��
�Ҏ[�E���@�R���ˎj�@�Z�ٕt
�`�T�ό^���E�㐻�E�N���X���E�\�����E����t�B�{��9�|�g�B�����F�N���W�b�g�Ȃ��B
�����̒}�����[�ő��Ɏ��S�W�̖{���̌n��������ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�B�Ȃ��A���͌y���ȑ���A���͊����̑�����啝�ȑ���������͉��ŁA���͓��e�E�y�[�W�����������́i�O���݂̂̕ύX�j��\���A�����́i�@�j���ɔ��^���L�����B�����Œ�����A�H���Ɏ��S�W�i�����ܕ��Ɂj�͉��t�Ό��y�[�W�Ɂu���̕��ɔőS�W�́A��㎵�ܔN�Z�������㎵�Z�N�Z���Ɋ��s���ꂽ�}���S�W���ڔő��Ɏ��S�W���{�ɂ����v�Ƃ��邪�A�������s�N�����Ԃ���͇F���Ɏ��S�W�i�V���Łj���A��������͇G���Ɏ��S�W�i�V���Łj�i�}���S�W���ځj����{�Ǝv������̂́A�����Ƃ��ɍ��v����}�����[�ő��Ɏ��S�W�͑��݂��Ȃ��B���̌����Ƃ��āA���Ƃ��·G�́k��9���l���t�Ɂu���a�\��N�\�ꌎ�\���@���ő������s�v�u���a�\�l�N��\���@���ڔő������s�v�ƁA�F�ƇG�̊��s������s���L���Ă��邽�߁A�G���̂�ׂ������F���̂������Ƃɂ��ƍl������B�Ƃ͂������̂́A�ǂ݂̂��F���G�䂦�A���̌n���̖{����V���ɑg���̂ƌ��Ȃ���B���l�ɁA�B���C�����ćD���E���@���A�̌n���̖{�����낤�B
�@���A�i�l�Z���j
�B���C�i���a�U���j
�@�@���D���E�i�l�Z���j
�F���G�i�`�T�ό^���^�l�Z���j���H�i�`�U���j
�I�i�`�T�ό^���j
���ɂ̑����̒P�s�{�������ł������悤�ɁA���|���̉����ł���l�Z���Ŏn�܂����S�W�́A�ЂƂ��т͐V�����i182�~103���邢��173�~105mm�j������傫�������悤�ȏ��a�U���̌`���Ƃ���A�Ăюl�Z���ɉ�A���A�s�{�V�����S�W�t�������ł������悤�ɁA�{���Z���ɗ͂�����ƂƂ������^���`�T���n�Ɋg�債���B�H�͕��ɖ{�܂蕁�y�łł���A�I�͏��o�`���W�߂����قȑS�W�䂦�A�{�e�Ō��y����̂̓W�������ʁE���\�N�����̒ʏ�́i�Ɖ��Ɍ����Ă����j�Ҏ[�ɂȂ�S�W�Ɍ��邪�A��̇@�B�i�D�j�F���V�@�����o���āA�����̇A�i�C�j�E�G�����̑O�̉�̗����Łi����������͌y���ȑ���j�ł��邱�Ƃ́A�ꗗ�\�̑��{�E�����≿�i�ʂ�����͂�����Ƃ���������B���̌���Ƃ���A�����҂̃N���W�b�g�̂Ȃ����̂̂����A�g����������i�͇@�A�C�D�E�F�G�ŁA�B�͋^�킵���i�B�̑����͓Ȑ܋v���q��������Ȃ��j�B
 �@
�@
�B�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�k��13���l�t�i�}�����[�A1960�N7��10���j�ƇC�s��{ ���Ɏ��S�W�k��4���l�t�i���A1962�N6��5���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ������{���i�E�j
�܂��A�B�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�k�S16���l�t�i1959�N12��15���`1960�N8��30���j�ƇC�s��{ ���Ɏ��S�W�k�S12���E�ʊ�1���l�t�i1962�N3��5���`1963�N3��15���j�̎d�l���r���悤�B��̂ɂ������a�U���Ƃ������^�ɂ�8�|2�i�g�ł��Ȃ�̌��e���������^�ł��A�p�r�Ƃ��Ắu�S�W�v���u�I�W�v�������B�{����ʓǂ���ɂ͕֗������A�w�p�I�ɂ͑��d����Ȃ��łł���B�F�����̎R���ˎj�쐻�q�����r�i�s���Ɏ��S�W�k��12���l�t�A1977�N11��30���A�ܔ���y�[�W�j����̈��p�i�����̐����͏�p�����ɉ��߂��j�ɑ����āA�d�l���f����B
�k�B�l���Ɏ��S�W�@�S�\�Z���@�}�����[��
���a�O�\�l�N�\�\�ܓ��`���a�O�\�ܔN�����O�\�����s�A�}�����[�i�����s���c��_�c���쒬��m���A�Óc��j�B���a�U���A���E�ѕt�A���G�ʐ^�e����`��t�B�{���W�|��i�g�B�艿�S�Z�\�~�`��S�~�B
�k���l��O���}�����[�őS�W�B��ꊪ�`��\�l�������ɋT�䏟��Y�u����v�����ځB
�k�C�l��{���Ɏ��S�W�@�S�\�E�ʊ��ꊪ�@�}�����[��
���a�O�\���N�O���ܓ��`���a�O�\���N�O���\�ܓ����s�A�}�����[�i�����s���c��_�c���쒬��m���A�Óc��j�B���a�U���A���E�ѕt�A���G�ʐ^�e����t�B�{���W�|��i�g�B�艿�O�S��\�~�B
�k���l��l���}�����[�őS�W�B�ʊ��̂݁A���G�ʐ^�����A�艿�l�S�\�~�B�S�\�A�e�����ɉ��쌒�j�u��E�v�����ځA�e���Ɍ���u��{���Ɏ��S�W�v��t���B
�Ŏ� �V�n�~���E�i�~�����[�g���j �e�����σy�[�W���i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j ���{�`�� ��
�B �ꎵ��~���� ��܁Z�y�[�W �t�����X���� �@�B��
�C �ꎵ�Z�~���� �O�l�l�y�[�W �㐻�E�z�� �@�B��
�B�́u�t�����X���v�ɂ��Ē�����B����́A���Ԃ��̂������ɕ\���̑����킳��ʏ�̂���ł͂Ȃ��A�g�����̏W�s�����t�i1959�j�̐��{�l���i�q�̏W�s�����t���r�̒NjL�Q���B�������A�\���ɃO���V���͊|�����Ă��Ȃ��j�Ɠ����u�����t�����X���v�Ȃ̂��i�u�����t�����X���v�Ƃ͎��̖����ŇB���ڏq����A�i1�j�ʏ�̏㐻���l�A�{���̐ܒ������Ԃ��ŋ���Ŏd�グ�ق��i2�j�\���̗p���̓V�n��40�~���قǐ܂肱�ށi3�j�����͂���ɂ����60�~���قǐ܂肩�����i4�j���̂Ƃ��܂肩�������������V�n�ɂ͂ݏo���Ȃ��悤�Ɋp����₸�炵�Ď�45�x�ɃJ�b�g���Ă����i5�j���̕\�����A�{�̂̔w�ƁA�{�̂������Ԃ��̂������̕��̏����ɌЕt������j�B�ߔN���̐��{�l���������Ȃ��̂́A�ʏ�̃t�����X���̐����Ƃ��֘A���邩������Ȃ��B�n���\�����㐻�ƕ����̒��ԓI�ȗl���ł������悤�ɁA���́u�����t�����X���v�������Ɓi�_�炩�������ŁA�`���̂���j�㐻�̒��ԓI�ȗl���̂悤�ŁA���킢�[�����̂��B
�v���A�@���A�ő��ɂ̕��Ƃ��������邱�Ƃɐ����������ƁA���L�͂ȓǎҁi�B�̑ѕ��Ɂu�Ⴂ����̐l�X�ɑ���v�Ƃ���j�邽�߂ɒ}�����[�����s�����̂��B���C�������B�����A�}���͕��ɂ��o���Ă��炸�A���C���i�b�v�̏[����}��V�����Ɂi�����̊��s���Ђ́s�ӔN�t�s�Ηz�t�s���B�����̍ȁt�s�Ìy�t�s�l�Ԏ��i�t�s���ꃁ���X�t�j��V�܂̊�g���Ɂi�������s�x�ԕS�i�E���ꃁ���X �����сt�s���B�����̍ȁE���� �����сt�j�ɑR����Ӗ������������낤�B�B�ɑ����C����́A�O��S�W�̊�����1�N���ʼn����V���ɂ��������A�z���n���\���ɂ��Ċ����Ă����߂�ȂǁA���Ɏ��̖{�Ƃ͂����炾�Ƃ�������̈ӋC���݂��`����Ă���B�g���̑����ƌ�����C�́A�B�Ɋr�ׂāA�@�B���̔����\���̐c���i�B�ɐc���͂Ȃ����j�������A���a�U���Ƃ������U��Ȕ��^�Ȃ���u��{�v�̖��ɒp���Ȃ����S�����o���Ă���B���̕��̃J�b�g�Ɣw�̊����\���������|�C���g�̐ԐF�Ȃ̂́A�@�̐F�����܂������̂��B
��
�E�F�G������܂��ɁA�}���S�W���ڂɂ��ĐG��Ă����B�S�W���ڂ́A1986�N�ɂ����ܕ��ɂ��n�������܂ŁA�}�����o���Ă����r�b�O�l�[���̏����Ƃ̑S�W�̗����łł���B
�@�X���O�S�W�k�S8���ʊ�1�l
�@�Ėڟ��ΑS�W�k�S10���ʊ�1�l
�@�H�열�V��S�W�k�S8���ʊ�1�l
�@�V���� ���Ɏ��S�W�k�S12���l
�ȏ��4�V���[�Y�����̇G���Ɏ��S�W�i�V���Łj�i�}���S�W�����j�̉��t���L���ɋL����Ă��邪�A���������ɂ����ܕ��ɂɎ��^����邱�ƂŁA���̎g�����I�����B�����̂����f�ȗ�n�܂Ŏ��߂��l�S�W�́A���Ɏ��������āA��g���X����o�Ă���i��g�ł̊e���S�W�̓������q�ׂ邱�Ƃ͖{�e�̗̈����̂ŁA�����̏����Ƃ̑S�W�ƒ}���̌l�S�W�Ƃ̔�r�͍s��Ȃ����A�����[�������Ώۂł���j�B�}���ł̉��O�A���A�H��̎l�Z���S�W�̊T�����s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�ł��ǂ�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@�X���O�S�W�@�ďC�E����@�g�c����@�S8���ʊ�1�@1959�N1���\62�N4��
�l�Z���E�㐻�E�z���E�@�B�����E����t
�A�X���O�S�W�@�O��̔łɂ��V���Ł@�S8���@1965�N4���\11��
�l�Z���E�t�����X���E�r�j�[���J�o�[�t�E����t
�B�X���O�S�W�@�}���S�W���ځ@�O��Ɠ����Ł@�S8���ʊ�1�@1971�N4���\11��
�l�Z���E�㐻�E�N���X���E�@�B����
�@�@�\�\
�@�Ėڟ��ΑS�W�@�ďC�E��E����@�g�c����@�S10���@1965�N11���\66�N8��
�l�Z���E�t�����X���E�r�j�[���J�o�[�t
�A�Ėڟ��ΑS�W�@�}���S�W���ځ@�ďC�@�g�c����@�O��̔łɕʊ���������@�S10���ʊ�1�@1971�N4���\73�N1��
�l�Z���E�㐻�E�@�B����
�@�@�\�\
�@�H�열�V��S�W�@�꒐�E����@�g�c����@�S8���ʊ�1�@1958�N2���\12��
�l�Z���E�㐻�E�@�B�����E����t
�A�H�열�V��S�W�i�V�������j�@�O��Ɠ��e�E�Ő��Ƃ������@�S8���@1964�N8���\65�N3��
�l�Z���E�t�����X���E�r�j�[���J�o�[�t�E����t
�B�H�열�V��S�W�@�}���S�W���ځ@�O��Ɠ��e�E�Ő��Ƃ������@�S8���ʊ�1�@1971�N3���\11��
�l�Z���E�㐻�E�@�B����
�X���O�S�W�́A���ɂ����Ă����{�E�����ɂ����Ă���s����H�열�V��S�W�P�������́B�Ėڟ��ΑS�W�́A�y���Łz�ɑ�������Ŏ����������̂́i�@�A�ł͂Ȃ��A�A�B�Ƃ���ΑΉ��W���͂����肷��j�A�X���O�S�W�Ɋ�s������̂Ƃ݂Ȃ���B��������g�c����Ɏ�ɂȂ�̂��ő�̓����ł���B�����E�吳�E���a�O��̕��������̑S�W�́A1970�N��ɂ����ĕ��w���̑�w���̕K�g�}���̊������������B���Ɏ��S�W���܂߁A���ڂ̑����͂قړ��ꂳ��Ă���B�Г������̏�Ƃ��đ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A���̑����́u�X���Ŕh��Ȗ{���D�������ǁA�ڂ��̍��{�́A�ƂɎ����Ă��ė��������ēǂ߂���̂ɂ������v�A�u�v����ɂˁA�ڂ��̒��ɂ͇������̂��Ȃ��{��������݂̂Ȃ��������Ƃ����C��������{�Ƃ��Ă����v�i���c�N�v�s���������Ȃ�\�\�ڂ����ҏW�Ґl���ŏo����������Ȑl�����t���w�فA2014�N9��3���A���܃y�[�W�j�Ƃ����g���̈ӌ��ɕ��������̂ƌ����悤�B
�Ƃ���ŁA�E�s���Ɏ��S�W�i�}���S�W���ځj�k��3���l�t�i1971�N5��5���j�ɋ��݂��܂ꂽ�̑����q�q�}�����[ �V���j���[�X�r�ɒ}���S�W���ڂ��ڂ��Ă���B�p���͂����u�}���S�W���ځv�̃��S�i�H�j�ƊH�열�V��S�W�k��1���l�̔��̎ʐ^���A�C�L���b�`�ɂ��āA���o���͑傪�u�S�W�̒}�������ɖ₤�l�S�W�W���v�A�����u4�l�̍�Ƃ̑S�W�𑵂����D�̋@��v�Ƃ���B��1���Ƒ�2�����u�D�]�������v�Ȃ̂��H�열�V��S�W�i�S8���E�ʊ�1�j�Ƒ��Ɏ��S�W�i�S�k22��12�l���E�ʊ�1�j�B��1�����u�D�]�������v�Ȃ̂��Ėڟ��ΑS�W�i�S10���E�ʊ�1�j�ƐX���O�S�W�i�S8���E�ʊ�1�j�B�S�̂ɂ����钐�L�Ƃ��āu���e�S�W�Ƃ��ʊ��͒艿����@��������� �������ɔ��s�@���l�Z���E�㐻�N���X���E�����@�����ώl�Z�Z�Łv�Ƃ���A�H��E���ɁE�ĖځE�X�i�̑����q�ł̕��т�50�������j��4�V���[�Y���܂Ƃ߂Đ���E�̔����Ă������Ƃ��킩��B
�S�W���ڂ����邱�ƂȂ���A1970�N��̒}�����[�́A���ɂ͍����w�Z�̌��㍑��̋��ȏ��̔Ō��Ƃ��ĉ��������B���e���O�Y�q�M���V�A�I�R��r�A�����Y�q�|�r�A�X�仁q���̖X�q�r�Ȃǂ������ǂ���ɑz�������ԁB�X���O�́q���P�r�A�Ėڟ��́q�搶�̈⏑�r�A���Ɏ��́q���ꃁ���X�r���������B�H�열�V��́q���p�r�����ȏ��œǂo�������邪�A����͒��w�Z�ŁA��͂�q������r���낤�i�u�}���̏����Ɓv�ł����A�������R���L���ւ���Ԃ������j�B����������i�ɒ}���̌l�S�W�{�ŐG��Ȃ����Ă���A����ƒm�炸�ɋg����������i�Əo����Ă����킯�����A�ꏟ�Ȑ��k�łȂ��������͐V�����ɔŁs���e���O�Y���W�t��p�앶�ɔŁs���ɖi����t����ɂ��������������B���ȏ��̎��Ƃ����A�V���̐Ό���H�ďC�E�V�����ɕҏW���ҁs�V�����Ƃ̔��\�\���ȏ��ŏo�����������Z�Z�k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA2014�N11��1���j�ɐ��e�┋���ƂƂ��ɋg���́q�Õ��r���s�g�����S���W�t������^����Ă���̂͐S���������肾�B���Z����̎��ƈقȂ�A���������q�T�t�����E�݁r��q��ʁr�̖L�`�ȋg�������̐��E�ɕ��������Ă����ǎ҂��������Ƃ��낤�B����ɂ��Ă��A�����́u�������s���A���b���������B�v�i�����A�ꔪ�܃y�[�W�j�́u���b�v�Ƃ͈�̂Ȃɂ��w���̂��A��i�͂�����̍������킩��Ȃ��B
��
�E�F�G�̎d�l�����悤�B�E�s���Ɏ��S�W�i�}���S�W���ځj�k�S12���E�ʊ�1���l�t�i1971�N3��5���`1972�N3��10���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O��~�����[�g���E�e�����ϖ�l�Z�Z�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\�O��i���ɓ��e�ꗗ���f�ځj�B�F�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�k�S12���l�t�i1975�N6��20���`1977�N11��30���j�̎d�l�́A��Z�Z�~��l���~�����[�g���E�e�����ϖ�l�����y�[�W�i���O�j�E�㐻�N���X���E�\���i���ɓ��e�ꗗ���f�ځj�B�G�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�i�}���S�W���ځj�k�S12���l�t�i1978�N6��15���`1979�N5��20���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�l��Z�y�[�W�i���O�j�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\�O��i���ɓ��e�ꗗ���f�ځj�B

�E�s���Ɏ��S�W�i�}���S�W���ځj�k��3���l�t�i1971�N5��5���j�̔��Ɣw�\���A�F�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�k��4���l�t�i1976�N1��10���j�̔��Ɣw�\���A�s���k��9���l�t�i1976�N11��10���j�̔��̔w�ƕ\���k�ȏ�A��i�l�A�G�s���Ɏ��S�W�i�V���Łj�i�}���S�W���ځj�k��3���l�t�i1978�N8��30���j�̔��̔w�A�s���k��5���l�t�i1978�N10��20���k��܍��F1983�N4��30���l�j�̔��Ɣw�\���k�ȏ�A���i�l
�E�͓����l�Z���̇D�s���Ɏ��S�W�k�S12���E�ʊ�1�l�t�i1967�N4��5���`1968�N4��30���j�̕\���Ɣ���ւ��������ł���i���Њ��̎l�Z���̒P�s�{��}���p���Ɏ��߂�̂Ɠ��H�̎�@�j�B�O�q�����悤�ɁA���s�͒}���S�W���ڂ�4�V���[�Y���A���O�E�����Ђƌ������A�H��Ɠ���������n�܂��Ă���B�����āA�}���������ɑ��ɂ��d�����Ă�����������������B
�F���G�́A���^���F�̂`�T�ό^������G�̎l�Z���ɏk�����ꂽ�̂��ő�̓����ŁA����͑S�W���ڂ̋K��l���l�Z���ł��邱�Ƃ��痈�Ă���B�F�̖{���̊�{�Ŗʂ�9�|45���l�~18�s�g�E�s��7�|�i�V�n142�~���E99�~�����[�g���ɑ����j�ŁA������`�T�ό^���̒����ɔz�u���Ă������A�G�ł��l�Z���̒����ɔz�u���Ă���B���R�A�V�n�Ə����E�m�h�̃}�[�W���͋����Ȃ���̂́A�ǂ݂Â炢�Ƃ����قǂł͂Ȃ��B�F�̔Ŗʐv�̎��_�ŐD�肱�݂��݂������̂��낤�B�@����E�܂ł̑��Ɏ��S�W�̕ҏW�S���҂͌���s���Ɏ��@�l�ƕ��w�k��E���l�t�i���u���|�[�g�A1981�N12��10���j���쌴��v�B�F�̕ҏW�S���҂��N���͂킩��Ȃ����A�g�����{���̊�{�Ŗʂ�v�����\��������B�����������̖{���̈���͐����ЁA���{�͐ϐM���i���Ђ͒������ق鑕���ɂȂ�s�}�������S�W�t����|���Ă���j�̌����Ȏd�オ��B
�G�͇E��7�N��̑S�W���ڂŁA�V���ł��o���̂͑��Ɏ������ł���B�����Ƃ��E��18�N�O�Ɋ��s���ꂽ�@�̌n���̖{������������A�F�ŐV�@�����o�����ȏ�A���ł�S�W���ڂƂ��ċ����Â���킯�ɂ͂����Ȃ��B3�N�Ƃ����A�P�s�{���當�ɖ{�ɂ���ۂ̃X�s�[�h�ɕC�G����Z���Ԃ̂����ɁA�V���ŇF�̗��ڇG���o�ꂵ�����Ȃł���B�H�����ܕ��ɂ����̐V���ł̌n���̖{���ł��邱�Ƃ͂��łɏq�ׂ��B
�}�����[�̌l�S�W�ɂ�����g���������ɂ��čl���Ă݂����B�P�s�{�E�S�W���킸�A���݂ł������Ђ̑��{�E�������t���[�����X�̃f�U�C�i�[����|����悤�ɂȂ������A�g�����}���ő������n�߂�1950�N��A��Ƃ�S�����͎̂�ɒS���ҏW�҂��f�U�C���̐S���̂���Ј������������B�g�����S�����������m����ł������S�W�́s��t�S�W�k�S7���l�t�i1953�`56�j�ŁA�����ɋ�C�̏���p���Ă���_���̂��̋g���������Ƒ傫���قȂ�B���́k��1���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���E�ʊ�1�l�t�i1955�`56�j�͋g���������̊�{�ƂȂ�����i�ŁA�����͖����̂̕`�������m���^�����O�n�ɉ��܂����B��t�A���ɂ̑S�W�Ƃ��A�g���͕ҏW�S���ł͂Ȃ������B�g���͒}���ł͐�`�L��������݁A�V���̈�ʉ��Ɍf�ڂ��鏑�Ђ̍L����A�Ђ̂o�q���s�����܁t�̕ҏW�Œm����B�܂����̖{�҂ƂƂ��ɑ��肠���āA�Ō�ɑ��{�E��������|����̂ł͂Ȃ��A�ҏW�҂̍�����u���E�v�`�I�E���o�I�ɓW�J�����ڂ��o�g���^�b�`�����_�ɂ����āA�Г��E�ЊO�̈Ⴂ��������A�����̃t���[�����X�̃u�b�N�f�U�C�i�[�Ƌ߂�����ɂ������B�������A�}�����[�ȊO�̊��s���̏ꍇ�i���̑唼�͎������������j�A���҂ƌl�I�ɐe�����ԕ��ł��邱�Ƃ������A�l�i�I�Ȍ��т������������E�ƓI�ȃu�b�N�f�U�C�i�[�Ƃ̈Ⴂ�������B�����������A�N�̎��W�ł����������킯�ł͂Ȃ����낤�B��i���ς�g���̖ڂɂ͌��������̂��������B���W�̒P�s�{�͑����Ĕ��s���������Ȃ��B�g���������������W�Ƀt�����X���������̂́A10�|��܍��Ƃ������傫�߂̊����ł������Ƒg�`�T�i�ό^�j�����y�₩�Ɏd���Ă邽�߂ł���A���{�ɉߑ�Ȕ�p�𓊓����Ȃ����߂ł����������낤�i��������̍��ؔł͂��̌���ł͂Ȃ��j�B�g�����̑�����i�ɂ́A����Ɏ��l�̎���o�łɋ߂�����������A��������ɏo�ŎЂ̏��Əo�ł̋��ɂ̎p�ł���l�S�W������B���̒��ԂɁA�l�Z���̕��|���𒆐S�Ƃ��� �P�s�{���������B�g���͐��U�ɂ킽���ĕ��ɖ{�̃u�b�N�f�U�C�������Ȃ������B���ɂ��W���P�b�g���f�U�C�����邱�Ƃ͎����̔C�ł͂Ȃ��Ƒz����߂Ă����Ǝv�����B
���ܓ���ł���}�����[���́s�H�열�V��S�W�t�́A�S�����ɕ]�_�E���L�E���M�E�I�s���������߂��S8���̂����ܕ��ɔŁi�����k1986�`87�l�A�S������6���Ɏ��߁A�̂�2����k1989�l�j�B��{�͌�o�u�}���S�W���ځv�őS�W�ł���i�������������A���^��i�͑Ή����Ă��Ȃ��j�B�H��S�W�͕��ɔł��O�Ɏl�Z����3�x�A�قȂ鑕���ŏo�Ă���B�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�̋L�ڂ���ĊT�v�������B
�@�H�열�V��S�W
�S8���ʊ�1�@1958�N2���\12��
�꒐�E����@�g�c����
�l�Z���E�㐻�E�@�B�����E����t
�e��350�~�@�ʊ�360�~
�A�H�열�V��S�W�i�V�������j
�O��Ɠ��e�E�Ő��Ƃ�����
�S8���@1964�N8���\65�N3��
�l�Z���E�t�����X���E�r�j�[���J�o�[�t�E����t
�e��380�~
�B�H�열�V��S�W�@�}���S�W����
�O��Ɠ��e�E�Ő��Ƃ�����
�S8���ʊ�1�@1971�N3���\11��
�l�Z���E�㐻�E�@�B����
�e��800�~
�C�H�열�V��S�W�i�����ܕ��Ɂj
1971�N3���`11�����u�H�열�V��S�W�i�}���S�W���ځj�v���{�Ƃ���
�S8���@1986�N9���\89�N8��
�J�o�[����@�đq�ĉ��N
�k�e������̕M�҂́A�����^��Y�A��c����A��_�B�Y�A����F�j�A�������v�A�P��g���A�g�c����A�R�{���g�B�����^��Y�q�H�앶�w�̖��́r�́u�}���S�W���ځv�ʊ������̕��l

�s�H�열�V��S�W�k��4���l�t�i�}�����[�A1958�N6��10���j�̔��Ɓs���i�V�������j�k��6���l�t�i���A1965�N 1��20���k�ĔŁF1965�N5��30���l�j�̕\���Ɓs�� �}���S�W���ځk��2���l�t�i���A1971�N4��5���k13���F1981�N4��10���l�j�̔��Ƃ����ܕ��ɔŁs���k��1���l�t�i���A1986�N9��24���k25���F2014�N7��30���l�j�̃W���P�b�g�k�����F�������A����F�đq�ĉ��N�q�����̌܈ʂ̖ʁr�l
�B���u�}���S�W���ځv�́A�ѓN�v�q�F�\�\�g�����̑���r�ɋ���Ȃ���A�g���������̓������T�ς�����ŏЉ���̂ŁA����͇@�́y���Łz�ƇA�́y�V�������z����肠����B��̊T�v�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA�@�`�B�̊H�열�V��S�W�͇@�y���Łz�̖{�������̂܂܂ɁA�O�����������߂����D���B���ŇA�y�V�������z�͏������ѐF������āA�u�t�����X���k�Ɩژ^�ɂ͂��邪�A���������Ƃ���ӂ��̂���\���������l�ŕʊ��Ȃ��v�Ƃ�����������s�{�V�����S�W�t�́y����Łz���l�A�y���Łz�̏d�������y�����ɂ����Ă������Ƃ������̂��낤�i���������A�l�Z��400�y�[�W�K�͂Ńt�����X���͖���������j�B�@�y���Łz���{��8�|23���l2�i�g�ɉ�����ɁA�Z��3�i�߂�6�|�g�̒���z�������A�J�f�~�b�N�ȑg�̍ق����������ɁA�@��B�ɂ͂ӂ��킵���Ă��A�A�ɂ��̔Ŗʂ͏d�ꂵ���B���ꂩ����ʂ��A�y���ł̂��ɂ̓��B�W���A���v�f�i�@�y���Łz�̕\���Ɠ����͓��̃J�b�g�j�Ɍy�����������銶�݂�����B�傫�ȋ^�╄��t���A�s�g���������t���q�W�@������i�ژ^�r�ɑ��^��i�Ƃ��Čf���Ă��������A�͂����ćA�y�V�������z�͋g���������Ȃ̂��낤���B���_���Ɍ����A�������̑��̍�i�Ɗr�ׂĂ��A�g���ɂ��\���͒Ⴂ�悤�Ɏv���i�������A�N���W�b�g���Ȃ��Ƃ��납��́A�}���̎Г������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��j�B�\����{���Ɍ�����g��݂͂̌r���́A�g�����ӂ����ɂ͗p���Ȃ��v�f�����A�����i�u�H�열�V��S�W�v�j�̖����̂��ׂ��̂��C�ɂȂ�B�������g����������i���A����̋����ɘւB

�s�H�열�V��S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1958�N2��20���j�̖{���y�[�W�Ɓs���k��2���l�t�i���A1958�N3��25���j�̖{���Ɓs���k��8���l�t�i���A1958�N12��25���j�Ɓs���k��4���l�t�i���A1958�N6��10���j�̕\���̕��Ɣw
�s�H�열�V��S�W�k�S8���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1958�N2��20���`12��25���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�l�~�����[�g���E�e�����ϖ�l�l�Z�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�@�B���i�����Ăɓ��e�ꗗ���f�ځj�B�苖�̑�4���́q�{�������r�́q���p���u��K���D�v�r�̐߂ɉX�����o�ꂷ��B�u����D�͑��O���̉���������A�X���^�����ɐi��ōs���B�v�Ƃ���{���ɁA�u�i3�j�X���@������\��N�ː݁B���O�\�l�N�S���ƂȂ�A�k�Ђʼn�ŁB���a�ܔN�����B�v�ƒ����t���i�����A�l�Z���y�[�W�A�l��O�y�[�W�j�B�{���ƒ��������킩��ɂȂ��Ă���A���̓_�A�����r���ł����J�����Ɏ��߂邿���ܕ��ɔŕ����̕����ǂ݂₷���B
�s�H�열�V��S�W�i�V�������j�k�S8���l�t�i�}�����[�A1964�N8��28���`1965�N3��20���j�̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�e�����ϖ�l�l�l�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�������ꑕ�B�苖�̑�6���̕]�_�q�����Y�N�r�i���E���锼�N�قǑO�ɔ��\���ꂽ���́j�ɂ́u�����N�͍����̎��l�����������炭�͖����̎��l�����ɑ傫���e����^�ւ�ł��炤�B���̖��e���͍����̎��l���������ɔ����N����Ă����̂Ƃ�ꡂ��Ɏ���قɂ���ł��炤�B�v�Ƃ���B���������x���f���āA�H�����҂͂��Ȃ��B���������A�g���̎���Ɍ�����⼌��ӂ��̌����́A�H��̕��͂���̉e�����傫���悤�Ɏv���B�g�����͊H�열�V��̍�i�ɂ��ẮA���z�q�Ǐ����r�ɂ����Ă��̑��吨�̈�����
�@�k�u��l���Ƃ́u���钩�v���A���̍�Ƃ̓�\�Z�̏�����ƒm���āA�������݂��₷���ƕs痂ɂ��v�������̂��B�k�c�c�l�R�{�L�O�̍�i�̂Ȃ��ł͋Y�Ȃ��D���ŁA�k�c�c�l�B���̂ق��A���́u�S�v�A���V��̒Z�сA�Ƃ�킯�u�M�̒��v�A�ו��́u�����ߍ��v�A����Y�́u�t�Տ��v�A�N���́u�ፑ�v�A����́u�@�B�v�ȂǓ��ɍD���ȏ����ł������B���O�́u��v�́A�����̂悤�ɖ����������ĕs�E�̒r�֎U���ɂ������̂ŁA���Ƃ̂ق������������Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ܘZ�y�[�W�j
�Ə����������̂悤���i���M�N���ɂ́A15�̍��ɓo�ꂷ��j�B�q�M�̒��r�̈��D����Ȃɂ��������������Ƃ͍T���āA�H�삪1925�i�吳14�j�N3���A�s�����t�ɔ��\���������́q�z�тƁr��������A�g���̋�W�s�z���t������i�����1939�N6��18���j�������āA���̍e���I���悤�B
�������邱����������ĊX�m�܂��n�Ȃ��߂���B
��������ɔn���m�ӂ�n�ɂЂ��钱�̂��Â����B
�i���n���͂Ȃ�锒����
���_�Ȉ�̕����͂Ƃ����q����Ɛ��E�̗ځ\�\�g�������_�r�i�s�����C�J�t1973�N9�����j�̕M�҂����A�ŏ��̒����́s�{���\�\�|�p�ƕa���k�p�g�O���t�B�o���l�t�i�����o�ŐV�ЁA1970�N2��15���j�������B�����͂̂��Ɂs�{���\�\������̋O�Ձt�i�u�k�ЁA1985�N2��10���j�ƕ�������߂ču�k�Њw�p���ɂɓ������B���́q�w�p���ɔłւ̂܂������r�ɂ�������B
�@���������́w�Z�{�{�V�����S�W�x�i��㎵�O�`�����N�A�}�����[�j�̊��s�����ɂ��āA�傫���ς��A�V����������}�����Ƃ�����B���̑S�W�̊������@�ɁA�ߔN�A�ӂ����ь������߂��錤����c�_��������ɂȂ������Ƃ́A�̂��猫���ɐe����ł������ɂ͔��ɂ��ꂵ�����Ƃł���B
�@���āA�p�g�O���t�B�o���̈���Ƃ��Ĉ�㎵�Z�N�ɏ��߂Č��������w�{���\�\�|�p�ƕa���x���A���̂��ъw�p���ɂ̈���ɓ����ɂ������āA����܂ŋ��S�W�i���Z���`�Z���N�A�}�����[�Łj�ɂ���Ă��������̃e�L�X�g���A�Z�{�S�W�ɂ���čZ������K�v���������B�����āA���̍�Ƃ��{���̓W�J�ɂȂ�炩�̒�����K�v�Ƃ���̂ł͂Ȃ����Ƃ�����Ȃ���A���̏ƍ��E�Z�����s�Ȃ����B�������A�K���Ȃ��ƂɁA�قƂ�ǒ����̕K�v���Ȃ������B�i�����A�O�y�[�W�j
���ł́q�͂��߂Ɂr�ɂ́u�k�����̐��U��N��L���ɂ��ǂ�A�`�L�I�����ƍ�i�ɑ����āA�����̑n���̐��U����̓I�ɋL�q�����l��������Ȃ���A�x���j�u�N���{���`�v�u�{���S�W�S�\�v�i�}�����[�Łj�̂悤�ȁA�Ȗ��ŐM���̂������b�I�����̏W�ς𗘗p�ł���_�A�{���̃p�g�O���t�@�[������߂Čb�܂�Ă���ƒɊ������v�i�����A�l�`�܃y�[�W�j�Ƃ���B�܂�1960�N��̖��ɋ{�V������_���悤�Ƃ����Ȃ�A�x���̔N���i��q�������A�������{����1991�N�ɒ������ɉ��j�ƂƂ��Ɉ˂�ׂ��{���́s�{�V�����S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1967�N8��25���`1969�N8��15���j�������킯�ł���B���S�W�͍��������Y�����E�莚�́s�{�V�����S�W�k�S11���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1956�N4��25���`1958�N8��15���j�̑���łŁA�����Ƃ��Ă͍ł��������ꂽ�{�V�����S�W�������B���̑���őS�W�̑������A��ɂ���ăN���W�b�g�͂Ȃ����̂́A�g�����ɂ��Г��������ƍl������B��r�̂��߂ɁA�������Ɋ��s���ꂽ�i������g���̎�ɂȂ�ƍl������j�k��5���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1967�N4��5���`1968�N4��30���j�ƂƂ��ɏ��e���f����B
 �@
�@
���Ɏ����������������A�g�������{�V�������ǂ��ǂ̂��A���̂Ƃ���悭�킩��Ȃ��i���E�������������n���Дł́s�{�����W�t��ǂ��Ƃ͊m�������j�B���o���́u�g������͋{���ɂ��āA�ǂ������ӂ��Ɏv���Ă���ł��傤���ˁv�Ƃ����₢�ɑ������N�v�̓����ɒ��ڂ��āA�剪�M�E����N�v�E�V��ޓ�Y�E���o���k���c�l�q���ȐN�Ƃƕϗe���d�˂��|�p�ƍ��\�\�w�����G�߁x����w���[���h���b�v�x�܂Łr��ǂ܂ꂽ���B
�V���@�������g�����́w�m���x�́u�������킵���v�ƌ����܂������A����͔����Y�Ƌ��ʂ��Ă�����̂��Ǝv����ł��ˁB�k�c�c�l�Ⴆ�{���Ȃ��܂�ɂ��������킵�����Ȃ����̂�����A�g������ƂȂ�����̂��Ȃ��悤�ȋC������B
�����@�ł��{���͂��������������킵������b�Ƃ��Ăł͂Ȃ��āA��̕��֖��߂��������Ȃ����ȁB
���o�@�g������͋{���ɂ��āA�ǂ������ӂ��Ɏv���Ă���ł��傤���ˁB
�����@����͈�x�����������Ƃ��Ȃ��i�j�B
�剪�@�ǂ��ƂȂ���Ȃ��������B
�����@�ł��ˁA�}�����[�̏��a�O�\��N�k�����Łl�̏㐻�{�ŏo�����S�W�����鎞�ڂ��ɂ��ꂽ�B����A�������B���Ǔǂ܂Ȃ������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��i�j�B�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�v���ЁA1991�A�O���y�[�W�j
�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�ɂ��A�s�{�V�����S�W�k�S11���ʊ�1�l�t�i�ȉ��A�y���Łz�Ə̂���j�Ƌg���������̑���őS�W�i�ȉ��A�y����Łz�Ə̂���j�̂������ɁA�����E���e�E�y�[�W���Ƃ��y���Łz�Ɠ����u���y�Łv�i1958�N7��25���`1959�N5��10���j������i�����j�B�g��������ɑ������y���Łz�͑����̍�Ə�Q�Ƃ����A�܂�Ɩ��Ŏg�p���������������̂ł͂���܂����B�{����ǂ܂Ȃ��Ă������͂ł���B�܂���11����12���A����ƕʊ������قȂ���̂́A���҂̖{���͓����łȂ̂�����B�苖�́y����Łz�́q���e���{�r���瑢�{���̑��̋L�ڂ������i���p���t���b�g�͕\���Ɨ��\�����X�~�ƃI�����W��2�F����̂`�T��12�y�[�W���̂����A�g���̃��C�A�E�g�ł͂Ȃ��悤������A�ʐ^�͂����Ɍf���Ȃ��j�B
���{�E�̍����l�Z���㐻�E�\�����z���E�����E�{���X�|��i�g���ώl�Z�Z�ŁE���G�꒚�E���ŕt�^�艿�e�����Z�Z�~�^�z�{������������z�{
�y����Łz�̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�e�����ϖ�l�Z�l�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�E�㐻�z���E�W���P�b�g�E�@�B���B���܂��͓\�O��i�X�~�ƃI�����W�F��2�F���j���܂߂āA���ׂēʔŁi�����j�ň������Ă���B�����Ły����Łz���y���Łz�A�u���y�Łv�Ɗr�ׂĂ݂悤�B�s�}�����[�}�����ژ^�t�̋L�ڂ���ĊT�v�������B
�y���Łz�{�V�����S�W�^�S11���ʊ�1�@1956�N4���\58�N8��
�u�n���m������n�\���v�́A���c�N�v�ɂ��u���{���@�Ƃ��Ă͏㐻�Ɠ����ŁA�\���ɂ����{�[�����𔖂����̂ɂ���B�㐻�̃J�b�`�����ƕ����̃\�t�g�������悭�~�b�N�X���A�ǂ݂₷���ĕ��i��������́v�i�s���������Ȃ�\�\�ڂ����ҏW�Ґl���ŏo����������Ȑl�����t���w�فA2014�N9��3���A�ꎵ��`�ꔪ�Z�y�[�W�j�B���c����|���A������낪���������s�����ܕ��w�̐X�t�i1988�`89�j�ɍ̗p����Ă���B�g���Ɓy����Łz�̊W�҂��A���̒n���\���̓����܂��đ��{�E�������������Ƃ͖��炩���B�y����Łz�́q���e���{�r�ɂ͍��������Y�̕��́i����j���u�{�S�W�̋��Łi���a31�N�j�ɂ�������ꂽ���́v�Ƃ��čĘ^����Ă��邪�A�c�O�Ȃ���y���Łz�̑��{�E�����ɂ͐G��Ă��Ȃ��B�ނ���A�̂��ɋg�����������邱�ƂɂȂ��s�Z�{ �{�V�����S�W�k�S14���i15���j�l�t�i1973�`77�j�̏o����\���������|�̐��E���ɂȂ��Ă���B�����i�Ƌ{�V���Z�j�̈ӂ�����ŁA�y���Łz���u���y�Łv�A�y����Łz�A�Z�{�S�W�A�i����ɁA���̌���j�Ƌ{�V�̌��e�����������Â����}�����[�̎��O�ɂ͈ؕ|�����ڂ���B��������S���A���p����B
����E�莚�@���������Y
�l�Z���E�㐻�E�z���E�\�����E����t
�e��420�~�@�ʊ�550�~
�u���y�Łv�{�V�����S�W�i���y�Łj�@�O��Ɠ��e�E�Ő��Ƃ������^�S11���ʊ�1�@1958�N7���\59�N5��
�l�Z���E�㐻�E�J�o�[���E����t
�e��290�~�@�ʊ�320�~
�y����Łz�{�V�����S�W�@�O��̔ł����ɑ���^�S12���ʊ�1�@1967�N8���\69�N8��
�l�Z���E�㐻�E�n���\���E�@�B�����E����t
�e��760�~�@�ʊ�1,400�~
�@�Ȃɂ���A�{�V�����̌��e�Ƃ������̂́A�܂�Ŗ��v���Ă��関���͂��敨�̂悤�ɁA�蒠��玆�Ђ��Ɏ����̂悤�ɏ����U�炳��Ă��āA���������ꂪ�c���ނ��k�}�}�l��ɏ����ꂽ��A���M���ꂽ�肵�Ă��āA���ꕁ�ʂ̐l�Ԃɂ͓ǂނ��Ƃ��o�����A�܂Ƃ܂�����т̍삩�ۂ����������̂��ɂ����悤�ȁA����Δ��Â̂悤�Ȍ`��➒�ɂ̂����Ă����̂ł���B
�@����ǂ��āA�����̏������Ƃ�����т̍�ɕ������铴�@�͂ƌ��f�͂Ƃ����̂́A�ߒ�{�V���Z����̊O�ɂȂ��A���Z����͉ɂ�����������������Â��Ђ�����Ԃ��āA���̔N���A���Z�ׂ̈ɂ��̍���Ȕ��@���Â��ė���ꂽ�B�S�b�z�̒�e�I�ł�����قǂł͂���܂��Ǝv����Z�������̐��Z����̔�ނ�₵���M��́A���ɔ��Â̔��@�����߂����A�����̋Ɛ֏W�听�̎��Ƃ����x�̑S�W�҂���ɂ܂ł��������̂ł���B
�@���̑S�W�o�ł̏d�ӂ��ďo���}�����[�͂��˂Ă��炽���Ղ莞�Ԃ������ėp�ӂɂ�����A�����Ȓ��ӂ��āA�{���̃f�B�t�B�j�`�t�Ȃ��̂Ɏd�グ�悤�Ƃ���o��ƌ����A���e���ʂ̑��K�炵�Đ��̐l����茧�Ԋ��Ɉ�N�ȏ���؍݂��āA���Z���璼�ڂ̎w���������Ă���Ƃ����L�l�ŁA�悭���鑷���⋌�ł̖ڂ���ʂ��Ƃ����悤�Ȃ�������Ȃ����͂��Ă��Ȃ��悤���B���x�������S���āA��肩�����ēǂ߂�S�W���o���邱�ƂƐM���āA���͂������̈ꎖ�����ɂ��ď������q�ׂ��B
�����͂��ꂾ���̊��҂Ǝ����������Ă������炱���A���g�̑莚�ƃJ�b�g�i�u���m����n���v�̕��������ň͂y���`���j�ŁA���O������x��������Ƃ̂Ȃ������{�V�̑S�W���������B����A�g���́i���Ɏ��S�W�ƌD����ׂ�A�Ƃ����ʂ̗v����������Ă���ɂ��Ă��j�A�l�̎�̐Ղ̂Ȃ����{�E���������Ă���B�B��̃��B�W���A���v�f�ł���ӓ��̃J�b�g���A��Ɛ������܂芴�������Ȃ��i���́A���A���ȃ^�b�`�̃J�b�g���g�����V���Ɉ˗������̂Ȃ�A���̕`����͗����ɈႢ�Ȃ����A�N���W�b�g���Ȃ����ځj�B������ɂ��Ă��A���ɂ��莚�ɑ���ɖ��������ɂ�镶���g�̏����A�M�Ղ��[���Ɋ��������J�b�g�ɑ���Ƀ��A���ȃ^�b�`�̌ӓ��̃J�b�g�A�Ƌg�����̂������j�͍����̂���Ƃ͔��̂��̂������B�����Ɍ����A�������l�Z���́y���Łz�Ɏ{���������͂��������厞��ŁA���́A�唻�̒������玍�W�s�R�r�̉́t�i���ޓ��A1934�j�قǂɂ͐������Ă��Ȃ��B�ׂ������Ƃ����A���ƕ\���̔w�����́u�{�V�����S�W�v�ŁA���̕��Ɩ{���́u�{���S�W�v�ƂȂ��Ă���i�����ł̕\�L�́A���ׂāu�{�V�v�j�B���́y����Łz���Ӑ}�����u�J�W���A�����v�i���{�E��������͂������A���s������艿�ݒ肩�������͉M����j��������x�傫�������]�������̂��s�Z�{ �{�V�����S�W�t�������B�y�[�W�Ƃ���2�����̑͐ςɌ��e�̎��Ԃ��Ƃ肱�ނ��Ƃɐ�����������́A�ЂƂ�{�V�����̑S�W�ɂƂǂ܂炸�A�}�����[�́i���邢�͂킪���́j�l�S�W�̗��j��A�ꎞ����悷��o�ŕ��ƂȂ����B���{�E�����̐����̔錍�́A���^���`�T���ɑ傫�����āA�y����Łz�̎�F�ł���I�����W�F���u�[�݂̂���[�ˁm�Ȃ�ǁn�F�v�i���c�N�v�A�O�f���A���O�y�[�W�j�̃N���X�ɐ�ւ������Ƃɂ���i�������A�y����Łz�̒n���\���̖��z�́A���ɂ̔��D�F�ɑ��A�W���F�j�B�g�����͋{�V���������̂悤�ɓǂB
 �@
�@
���e���O�Y���W�s�X�L�t�i�}�����[�A1967�N2��15���j�����̎��сq�����̉ār�̖����ɋ߂������������B�F��ȉ��̃R�����g�́A�V�q�r��i�Ɛ��e���g�j�̘J��s���e���O�Y�S�����g�W���t�i�}�����[�A1982�N9��30���j�f�ڂ̂��́B
�k�c�c�l
�u�͂�s�ɂ��Ă����낤�v�F�\�ɂ悭�g���錾�t�B
�����̖ʂ͎v�킸�\�ʂɂȂĂ���
���̉ʂĂ͂��ׂė�߂ƍ�ɏI���F�W�����E�_���̎��u���̗��v�̂�����B���Ȃ݂Ɍ�����慎h���B
���l�̗���Ղ�c�@���c�X�g���̑��̍Ղ��F�j�[�`�F�́w�c�@���g�D�X�g���x�ւ̌��y�B�����ł͐�v�҂̈ԗ쓃�������B
�s�[
���݂̂ǂ�̎ւ��̂т鉹��
�v�b�X�[
�S���̕��D�ʂ����ڂމ���
�|�E�[�F�O�́u�s�[�v�u�v�b�X�[�v�ɂ��킹�āA�|�[�̖����I�m�}�g�y�[�ɗp�������́B
�E�q��i�|�[���I���̃����P������
�l�`�₫�̌��t��
�u�b�X�[���[
�o���Ŏ������������т��F�y�ȉ��l�s�z�����k�}�}�l�w�ɂ悭�o�Ă��銵�K�B���Ȃ݂ɌS�ՕF�̌��w�S�ցm���Ȃ��n�x�i�吳��N�j�Ȃǂɂ����̂����肪�݂���B
�m�l�`�ɓB����������
���̎��O�̎R�F��
�������ȋL���̎c�肾
�܂��q���̂����̓���
���⏬�ւ�醬���►��
�V�_��R�P�̓���������
���Ɠ�������������Ƃ��낾�F�y�ȉ��O�s�z�{�[�h���[���̎��u�����Ɖ��k�R���X�|���_���X�l�v�̎��s�ւ̌��y�B�eLes parfums, les couleurs et les sons se repondent.�f���̂܂��̎O�s���p���f�B���Ӑ}���Ă���B
�{�[�h���[���̖S����Ȃ����߂�̂�
�ӂ��킵���G�L�]�e�B�b�N�̕��i��
�����̓T���\�E�W���̖�
�����̕�̂悤�ɗ��l�̂悤�ɂȂł�
�k�c�c�l
�q�����̉ār�͂��̎��W�����o�́i�������낵�́j���тŁA�V�q�́u�薼�́u�����v�́u���݁v�ɋ߂��Ӗ��Ŏg���Ă���B�w���q�x�m�k�V�ё��\��́u�����V�������݁A�l�ޔV��߂��ށB�v�v�i�����A���Z�y�[�W�j�ƒ�����B���e���͂����̒��Ȃ��ł�����Ȃ�Ɋy���߂邪�A���g�̒m�������čēǂ���̂��ʂ̖����o�āA�D���B�V�q���q���g�ƓT���\�\�͂������r�ŏq�ׂĂ���悤�ɁA���������T���̌����͂��łɃG���I�b�g��p�E���h�Ȃǂ̃��_�j�Y���̎��l�Ɍ����邪�A���{�̋ߑ㎍�ł͖{���̐��e�������Ě���Ƃ���B�������̓����s�g�����S�����g�W���t�𐬂��������̂��B���ās�X�L�t�i���C�L�Ɠǂނ̂��낤�j�ɂ́q�V���̉ār�q���l�̉ār�����Ă��́q�����̉ār�ƁA3�т̉Ă̎������߂��Ă���B�e���̖�����������A�u���̈̑�Ȃ�ߋ��͂܂��^���̂ӂ邳�ƂɂÂ��Ă���^�i���Ɋ���ԂĂ݂��܂��v�A�u�����Ă̋L���́^�H���v�A�����ď�f���p��14�s��Ɂu�������̂܂ɂ��^�܂��߂��݂͋��ɂ��܂�^�g�z�̂悤�Ɂ^�v�킸�t��u�����v�ƁA�ǂ�����Ẳ߂����Q�����̂��Ă���悤���B�sAmbarvalia�t�̉i���̉Ă������ċv�����B�N������������������̂́A���e���O�Y���̐l���낤�B�{���̎d�l�́A��Z���~��Z��~�����[�g���E��l�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�z���i�����ĕ\���Ɣw�\���Ɋv�̓\���Ӂj�E�\���B�ʒ��{���̑O�̔����ɒ��҂̃y�����������B����1200���A�\���t�Ɏ�M�ɂ��L�ԁi�����{�́u717�v�ԁj�Ɓu���v�̉���B�\���̕z�́A�F�Ƃ�����G��Ƃ����A�̂��̎��W�s�l�ށt�i�}�����[�A1979�j�������肾�B���ɂ͂��ꂪ�A�{���̑��{�E�����҂��D���������Ɏv����B�s�X�L�t�̖{���͎l����1�y�[�W��11�s�Ƃ������g�܂�A�Ђ炪�Ȃ͎̂Ă��ȁi�����j���g�p���Ă��Ȃ��B�g�����������i1968�N���s�j�́s�Â��ȉƁt�ł͂Ђ炪�Ȃ͎̂Ă��Ȃ��g�p���Ȃ��������A���̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�ł͎̂Ă��Ȏg�p�ɕ��j��]�����Ă���B
 �@
�@
���e���O�Y���W�s�X�L�t�i�}�����[�A1967�N2��15���j�̔��k�\�l�ƕ\���i���j�Ɠ����̖{���Ɣ��k���l�i�E�j
���e���O�Y���}�����[����o���������i�s������{���{�S�W�t�Ȃǂ̕��w�S�W�ނ������j�ɂ́A���̃^�C�g��������B�����́���͋g���������ł��邱�Ƃ�\���i������܂ށj�B
�����邪�A�����́s���e���O�Y�S�W�k�S10���l�t�P���������ł���B�������Č���Ɓs��L�t�ȍ~�A�g�����́s���Ǝ��_�t�Ɓs��{�@���e���O�Y�S���W�t�����������ׂĂ�S�����Ă���B����͋g���������̐��e���O�Y�{�̈���Ƃ��āA���ю��s�߉́t�i�}�����[�A1969�N12��20���j����肠����B���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�Ɏ��߂�ꂽ�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�͋g�����܂ɐG��ď��������e�W�̕��͂̏W�听�����A�ے�������U���āA�s�߉́t�Ɍ��y�����ӏ��������B�����́i�@�j���̐����͐��z�W�̌f�ڃy�[�W�B
�@���a44�N9��1��
�@���e�搶���ЁB��c�j�Y�Ɠ�Z�Z�Z�s�̎��̕ҏW�ɂ��Č��B�s�߉́t�Ƃ��������ƌ���ꂽ�̂ŁA��l�Ƃ���������B�搶�ɂ����A�\�\�Ƃ���Łs�߉́t�Ƃ͉��ł����H�@����͓y��@���ĉS�����Ƃ���B�y�l�̍�̖�̂��Ƃ��B
�@�@�@�@�@9��3��
�@���e�搶������B���s�̎��A��s����Ȃ����Ƃ��킩��A���������ɂ����Ƃ̂��ƁB�i231�j
�A���̌���A���e�搶�͌��N�Ǝ��S�Ɍb�܂�āA�w��L�x�A�w�߉́x�A�w����x�����čŌ�̎��W�w�l�ށx�܂ł̚삵����i�Q���A����������ꂽ�̂ł������B�i242�j
�B12�@�嗝�̎�
�@�@���ׂĂ̐����̉�]�̂悤��
�@�@����̉�]���V�̂ƂƂ���
�@�@�͂��肪������]���Â���
�@�@����Ȃ�Ȃ��̂�
�@�@���낪�˂̖q�l�̂ӂ��b�J��
�@�@�嗝�̂Ƃ�����܂����낿��
�@�@�킫�őS���������Ȃ�����
�@�@�o���Ă��邪�����
�@�@�ʂĂ��Ȃ��i���Ɍ�����
�@�@��������Ă���̂�
�@�@�|�|�C �i�߉̇U�j���
�@���ю��сw�߉́x���s�́A���e�搶���\�Z�̎��̏������낵��i�ł���B�������̐����ߒ��̂����ꕔ���������A�_�Ԍ����ЂƂ肾�B���I���͂ɂ́A���Q�������̂ł��������A���z�ًȂ̔����������A�]����悷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�i���ԁA�����璷�ȍ�i�Ƃ�����ۂ����c���Ă��Ȃ��������A���x�ʓǂ��Ă݂āA�F�������߂��B�Ɠ��́u���������v�ɏ��A�u���O�v�̖��x�ɐZ���̂��B���p���̂Ȃ��́u�嗝�̂Ƃ�����܂����낿�́v�̈�s�������A���͋����Ղ��ꂽ�B�����āA�z���o�������Ƃ��������B
�@��N�O�̉Ă̗[���A���͏��߂Ă̐��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�Ə����W�w�|�[���E�N���[�̐H��x�������āA���e�@�֎f�����B���z���ꂽ�����́A�����O���[���������ɓ��ꂳ��A�������B���ꂾ���搶���}�ɘV����ꂽ�悤�ɁA������B�v���Ԃ�Ȃ̂ŁA�b���͂��B�ӂƁA���I�Ɋ�ȃI�u�W�F���u����Ă���̂ɁA���͋C�Â����B�搶�ɂ����˂�ƁA�ނ����A���͖S����q�v�l���Ή��ɒ��点���A�嗝�̎ւƂ̂��Ƃ������B�ǂ����Ă��A�Ƃ��늪���ւ̋Ȑ��͂Ȃ��A�t�قȑ���ŎւƂ������A�ꂾ�B�搶�͏��Ȃ��猾��ꂽ�A�u���ꂪ���܂łɂ����Ԃ����Ă�Ō��ꂽ��v�\�\�B
�@����܂ŕs�v�c�Ȃ��Ƃ����A�搶�����q�v�l�Ǖ�̌��t���A���������Ƃ��Ȃ��B�����肩���̐e�����҂��A�����������Ǝv���B�v�l�∤�̑嗝�̎ւ��A�g���~���̏�ɏ���ꂽ�̂́A������������A�搶�̖����̎v��̕\���ł������̂��낤���B�i244�`245�j
�A�ŋ������Ă���4���́A���ׂĒ}�����[�̊��s���i��ɂ���čݎЎ���̂��̂ɃN���W�b�g�͂Ȃ����A4���Ƃ��g���������{���ƍl������j�B�B�̂悤�Ȏ����m��Ȃ��ǎ҂ɂ́A�s�߉́t�̖{�������˂�ׂ����̂��Ȃ��킯�ŁA�S�W�i�������L����̂͒�{�S�W�j��S���W�i��������{�S���W�j�ł͂Ȃ��A�����̒P�s�{�œǂ�ł݂�Ώ����̈�ۂ������邩������Ȃ��B���e���S���Ȃ��Ă����s�߉́t��ǂ݂Ȃ������g���́A�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�Ƃ̐��e���O�Y�Ǔ����k��q��ނȂ����I���݁r�i�s���㎍�蒟�t1982�N7�����j�ł�������Ă���B
�g���@�����̂��߂ɂڂ��͉��߂āw��́x�i���a�l�\�l�N�j��ǂ�B���s�����͂��܂芴�S���Ȃ��������Ǎ��x�ǂ�ł݂āw��́x�������ƊԈ�������悩������Ȃ����Ǝv���Ă�B
�剪�@�w�g�����I�E�V�ŏ�́x����邩�i�j�B
�g���@������V���w�I�ŏW���I�ɏo�ė��邩��A�V���w���n�ɒĂ�������ĈӖ����Ȃ��Ȃ��Ȃ�������Ă��B�ڂ��������Ɗ��荞�ނƂ��������������Ƃ܂Ƃ܂������̂ɂȂ��Ȃ����A�Ȃ�Ďv�����Ⴄ�B�ł��w��́x�͌��������ȁB�ѓ��k�k��l���a���̎��͐��e����̎���ǂ��Ă������ǁA���݂��݂Ƃ����Ƃ���͂���܂��ˁB�ĊO���{�I�Ȃ�ł���B
���J�@�ڂ��́w��́x�͋��Ȃ�ł���B�{���ɔ�ꂿ�Ⴄ��ł��B
�g���@���e����̊ɂ₩�ȗ���ɏ��Ȃ��Ɠǂ߂Ȃ���B�g�ɏ��Έꏏ�ɕY�����B�������荞�݂����Ȃ�~�]�͏����Ȃ����ǂˁB�i�q���W�ɂ�����鎍�I���E�̓W�J�r�A�����A�O��`�O�O�y�[�W�j
�g���@�w��́x���́w����ꂽ���x�̕��������Ǝ��͍����ł��ˁB�w��́x�́A���e����̓����ł͂��̍�����ւ̗~�����V�܂��Ă����ɂ���A�}�����[�̓��s���炢�̏������낵���Ă����˗����ď����ꂽ���̂�����A�����͖����������Ȃ����ȁB�ŏ��͈����s��������B���Ƃł����ƈ�s�����Ă炵�����ǂˁi�j�B���̗��`������ςȂ��̂��ȁB�����̍��܂Ŏ����Ă���v���o���C���[�W���������āA�������߂č������������Ă������Ƃŕs���ȓ_�����邯�ǂˁB
�����@��i�̑�h���Ŋ��ɓ��u���v���Ă����������o�Ă����ł���B�u���{�̓B�v�Ɓu���ڂ̌��z�v�i�j�B
�g���@����͂����Q�Ă��o�߂Ă��u���s�v�B���`�ȂˁA�{���ɁB�܂����e����̎�@�A���̂���Ȃ�����s�Ȃ�ď����Ȃ��ˁB�i�q�ꗬ�Ƃ��ẴC���[�W�Ɖ����r�A�����A�O�܃y�[�W�j
�܂�2000�s�i20���~20�s�̌��e�p���Ȃ�100���j���肫�̏o�Ŋ�悾�����킯�ŁA�ʏ킱�̌��e���ʂ��ƒP�s�{����ɂ͑���Ȃ��B�����A�s�߉́t�͒��ю��ł���B�ǂ�ȑ̍قł��������Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�U���Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����R���^�����Ă���B�{����3�T�ԑO�Ɋ��s���ꂽ���e�̐��M�W�s������Ƃ������t�i�}�����[�A1969�N11��28���j�̃I�[�\�h�b�N�X�ȑ̍فi10�|�E38���l�E15�s�g�j�Ɋr�ׂ�A����͖��炩���i12�|�E14�s�g�j�B�{���̎d�l�́A��ܔ��~�ꔪ�l�~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�N���X���E�W���P�b�g�E�\���ɓ\���ӁB����1200���A���ҏ�������A�\���t�Ɍ���i���j�B�l�Z�{���Ȃ����a�T���i�قڏT������j�̓\���ƁA�ѕ��ɂ���u�����̏��̏������ɂ��2000�s�̑咷�ю��v�Ɋ��҂����܂�B������{���o���A�o�o���H���ꂽ�h�H���̃W���P�b�g�ɐ��e�̊G�i���ʂɃy���p�j���J���[�ōČ�����Ă���B���̃o�N�����̕\���ɂ́A���҂ɂ��J�b�g�Ə����E���Җ������Ŕ���������Ă���B�g���̎��M��ɈႢ�Ȃ��B���Ԃ����߂���Ɣ����a���Ƀy�������Œ��҂̏���������A�{���ɂ��\���Ɠ����J�b�g���g���Ă���B�Ƃ���ŁA�唻�̐��e���W�Ŏv���o�����̂́sAmbarvalia�t�i�ł̖؎ЁA1933�j�ł���A�s����ꂽ���t�i�������_�Ёw�����x�ҏW���A1960�j�ł���B��ˎ闝�́q�{�r�ł��������Ă���B
�k�c�c�l�g������͐��e���O�Y�̎咘�̂ЂƂƖڂ���钷�ю��w����ꂽ���x���������Ă��Ȃ��̂��Ƃ����B���m�Ɍ����Ȃ�A��ɕ������ꂽ�ł̕������߂�ꂽ�Ƃ̂��ƁB���̗��R�����ł̃J�o�[�ɗp�����Ă������炪�e���ŁA�����Ƀ{���{���ɂȂ��Ă��܂�����Ƃ������̂ŁA�g������ɂ��ƕ����ł̕����u�L���C�����A�M�d���v�Ƃ������ƂɂȂ�̂����A�ނ��A���ꂾ���̓Ǝ��ŋ���Ȕ��ӎ����Ï��ƊE�Œʂ���͂��͂Ȃ��āA���łɂ͕����̘Z�{���甪�{�̒l�������Ă���B���͓���Ƃ��������Ă��邪�A�g������̈ӌ��͍m�m���ׂȁn������̂��Ǝv���B������ŕM�҂̑}�G�l�t��z����Ƃ����Â�������ł���ɂ�������炸�A����Ƃ����f�ނ͖��炩�Ɏ��s���Ă��邵�A�{���������łȂ��ʐA�̃I�t�Z�b�g����̂��ߎ��̕\�ʂɃC���N���̂������Ă���悤�ȕs���肳������B�������s�Ԃ������Ă��āA�S�̂ɑf�l�̎�ɂȂ����悤�Ȉ�ۂ������B���e���O�Y���\���閼�тł��邾���ɁA�c�O�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B�i�s�g�����̏ё��t�W���v�����A2004�N4��15���A�ܔ��y�[�W�j�Ǔ����k��ł́s����ꂽ���t�ւ̍����]�����ӂ݂�ƁA�g���͖{���ł��肤�ׂ��s����ꂽ���t�̑��������݂��Ƃ͍l�����Ȃ����낤���B���Ȃ݂Ɂs����ꂽ���t�͇W�����琬��A�S�W��96�y�[�W�B�s�߉́t�͇X���A120�y�[�W�ł���B�s�߉́t�̐��e�ɂ��q���Ƃ����r�́u���̖{�̏o�łɂ��Ă͒}�����[�̈��B�O�N��g�����N���c�j�Y�N�ɐS���犴�ӂ������v�i�����A��O�y�[�W�j�ƌ���Ă���A�������g���ł��邱�Ƃ��������킹��B
 �@
�@
���e���O�Y�s�߉́t�i�}�����[�A1969�N12��20���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ����̖{���ƃW���P�b�g�i�E�j
�g�����͏��̐��z�W�̏����ɍ̂������z�q�u�����v�Ƃ����G�r�i���o�́s�����C�J�t1971�N12�����j�������n�߂Ă���B
�@�剪�M�̌��t�ɂ��ƁA�ɒB���v�͂��łɓ`���I�l���ɂȂ����Ƃ����B���҂͒N�ł������̂悤�ɐ_��I�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��B�������A�킪�ɒB���v�͎���ł킸���\�N�ɂ��āA�������ɓ`���I�l���ɂȂ����Ƃ����Ă��悢���낤���B�ނ̈�e�W�s�����C�J���t���A�ŋ߂���p���̈���Ƃ��ĕ��k�}�}�l������A�L���Ⴂ�l�����ɓǂ܂�Ă���炵���B�\��́s���l�����\�����C�J���t�ƂȂ��Ă���B���炭�o�ŎБ��̈ӌ����낤���A���͌���̂܂܂ɂ��ė~���������Ǝv���B���̐��X�̍�Ƃ⎍�l�����Ƃ̊�ȗF��̂Ȃ��ɁA���̐t���Ă����ɒB���v�̏������A���̍�ƁE���l�_�����Ȃ��͎̂c�O�Ȃ��Ƃ��Ǝv���B
�@���ƈɒB���v�̌�F�́A����߂ĒZ�����̂������B�ӔN�̌܁A�Z�N�ɂ����Ȃ��B����Ȃ̂ɁA���̈�f�ʂ��A�u�g�����ٕ��v�Ƃ������͂ʼni���Ɏc���ꂽ�͍̂K�^�Ȃ��Ƃ��B���Ԃ�́A�q�V���r�Ɉ˗�����ď��������̂����A�����̗��R�Ŗv�ɂȂ������e�������Ǝv���B���͈�e�W�̍Z�����͂��߂Č��āA�ɒB���v�̊ώ@�̉s���̂ɋ������L��������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�Z��y�[�W�j
�s�����C�J���t�͈ɒB���v��e�W���s���u���a37�N1��16�����s�v�i���t�j�A�܂�ɒB�̈�����������Č���200�����i�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B�u���s���v�̕��������Ȃ����̂́A�u�����s�V�h��㗎��2��540�^�����C�J�^�d�b�i369�j2010�v�i�^�͌������s�ӏ��j�Ɖ��t�ɖ��L����Ă��邩��A���惆���C�J�̍Ō�̏o�ŕ��ƍl������B�苖�̈�{�͍�ʁE�����̕��r㻏��X����w�������Ï����B�Ǔ��{�Ƃ������i��A���҂Ɛe���������l�̋��������낤���A�ɒB���v�Ɠ��N�y���Ƃ����\�����ɂȂ�킯�ŁA���̂��������҂̏������⑰������������̂��B�O���Ԃ��ɂ͂a�T������܂́A�^�C�v����ɂ��ē�����ł������̂ŁA�S���������B
�@�ɒB���v���S���Ȃ�܂��Ă܂��N�o�߂��܂��������A��ƈ�e�W���ł����܂����B�F�l�ɑ��X�ƌ�����������Ȃ���A�{����ɕs���Ȃ킽���������̔�͂���A���̂悤�ɒx���������܂������ƁA�[�����l�ѐ\���グ�܂��B�ӂɂ݂��ʑ��{�ł͂���܂����A��C�e�̏エ�ǂ݂���������Ǝv���܂��B
�@�Ȃ��A����������܂����ێ�̒ʒm�����グ�܂������炵�܂������A���̖{�̔��������Ă���ɑウ�����Ă������������A�����˂Ă����ɂ��l�ѐ\���グ�܂��B
�@���Z�O�N��
�@�@�@�@�@�����s�V�h��㗎����m�l���@�����C�J��
�@�@�@�@�@�@�@�ɒB���v��e�W���s��
�ɒB���v�s�����C�J���t�i�ɒB���v��e�W���s��A1962�N1��16���j���ݍ��݂̈ē���
�ē���̕��ʂ�M����Ȃ�A���t�́u���a37�N1��16���v�͂����܂ł��ɒB�̈������O�ʂɉ������������s���ł����āA���ۂɖ{�̌`�ɂȂ����̂͗�1963�N2���̂悤���B���Ȃ݂ɉ��t�Ɉ�����E���{���̋L�ڂ͂Ȃ��B�u��v��L���Ɋ��p���邽�߁A�����ď�肢���͎g���Ȃ������Ƃ������Ƃ��B�`���́q�u�����v�Ƃ����G�r�ɖ߂낤�B�g�����́u����p���v�Ƃ́A���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��́k�G�f�B�^�[�p���l�ŁA�s���l�����\�\�����C�J���t�͂��̍ŏ��̈���A�p�����ł̓����̃W�������́u�o�Ŏ���E�o�Ŏj�v�ł���B���ł�1971�N7��20���A�苖��4����1976�N7��5�����s������A�D�]�̂����ɔł��d�˂��킯�����A2014�N���ݕi�i������̐�ł��j�B���ł̋g���������Ɋւ��ẮA�p���Ŋ�����30�y�[�W�ɂ킽��剪�M�́q����r�ɏڂ����B
�@�Ȃ��A�{�����s�ɓ����āA�����s��łƂ͎�ς�������������̂ŁA�ȉ��ɋL���B
�@��A���B�́A���łł͈ɒB���v��������؎��G�����Ƃɂ��āA�g���������B���������A�V�ł́u�G�f�B�^�[�p���v�̈���Ƃ��Ċ��s�����̂ŁA���B���p���łƂ��Ă̐V�����قǂ����ꂽ�B���Ŕ����̌��^�Ƃ��ėp����ꂽ�ɒB���v�̐؎��G�͍��͎����Ă���B�ɒB���v�͈��Z�Z�N�Ă̔��a��V�h�搼��v�ۂ̒����a�@�ɓ��@���A�\�ꌎ�Ɉꂽ��މ@�A�Z���Ԏ���ŗ×{�����̂��A�o�߂�낵���炸���b���a�@�ɍē��@���Ă܂��Ȃ����������A�����a�@���@���ɁA�S���މ@�������e�����l�X�ɂ������ŁA�؎��G������ɂ��Ď�@������߂����Ă����B�c�ɂ���ƁA�E���ɑ莚�̂悤�Ɂu�����C�J�v�Ɣ������������ɂ����l�p�����n�̕���������A���㕔�ɂ́A�u�䂤���̒���������^�J�����Ƃ��ƓH�����Ă��^�^���̑傫�ȗm�P�I�@�^�Y�v�Ǝl�s�c�����ō��ɐ��߂Ă���B���̕���������ؔ����č�������̂����ƂɂȂ��Ă���B��@���̉����ɂ́A�J�C�[���Ђ����͂₵�X�q�����Ԃ����j�̎��̕������A������A�Ў�ɗm�P���J���Ă���}������A���̉E��ɁA�\�\�ܕ��O�������Ă��鎞�v�̂��鎞�v�䂪���傱��Ƃ�����Ă���B�މ@�̏j���̂���ō�������̂ɂ����A�u�䂤���̒���������v�J������Ă��鎍��Ɛ}����I�Ƃ��낪�A�����ɂ��ɒB���v�I�����A����͌��ǁA�����̐l�X�ɔ߂��݂̂����ɔz���邱�ƂɂȂ����̂������B����̌���ƂȂ����؎��G�́A�����X�Ŏ���ꂽ�̂ŁA��e�W���s�̍ۑ��B�������g�����́A���̎�@�������ƂɃf�U�C�������̂ł���B�i�剪�M�q����r�A�ɒB���v�s���l�����\�\�����C�J���k�G�f�B�^�[�p���l�t���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1971�N7��20���A��O���`��O��y�[�W�j
�G�f�B�^�[�p���ł��i�̌��݁A��ɓ���₷���͕̂��}�Ѓ��C�u�����[�Łs���l�����\�\�����C�J���t�i���}�ЁA2005�N11��10���j�ł���B�������画��悤�ɁA��{�̓G�f�B�^�[�p���łŁA�@�����ɃJ���[�̏��e�𒆐S��8�y�[�W�̌��G���V�݂���A�A�剪�M�́q���}�Ѓ��C�u�����[�� ����r���V���ɕt����A�B�q���惆���C�J �o�ő��ژ^�r������ɐ��m�ɂȂ����B���G�̍\���͂̂��Ɂs���惆���C�J�̖{�t�i�y�ЁA2009�j���������ƂɂȂ�c���x�B�g���W�ł́s�m���t�A�s�g�������W�t�A�g���������s�L���X�����E���C�����W�t�̏��e���f�����Ă���B����ɋg�������̃A�����E�~�V���I�i���C�i���j�s�v�����[���Ƃ����j�t�������A���惆���C�J�֘A�̋g�����i�����j�{�̂��ׂĂ��B
�G�f�B�^�[�p���̓��{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ����A���}�Ѓ��C�u�����[�̕��}�Ђ��{����ɂ͒�]�̂���o�ŎЂ����A�����̔łƂ������������i���łɂ��Ȃ������j�B�������ł͂Ȃ����炻��Ȏ�Ԃ̂�������͕̂t���Ȃ��A�Ƃ����l���������낤�B�����A���̖{�ɂ���͂��Ă͂܂�Ȃ��B�Ȃ�A�q�y���F��E�l�������r�̂Ƃ��̂悤�Ɏ����Ől���������쐬����܂ł��B���Ŗ{�̖̂{���Ɓq�㏑�r��7�y�[�W����k176�l�y�[�W�܂Łi�q�ʍ��r�{����-1-�y�[�W����-22-�y�[�W�܂Łj�A�G�f�B�^�[�p���ł̖{����1�y�[�W����156�y�[�W�܂Łi�q�㏑�r�ȉ��̌�t��157�y�[�W����242�y�[�W�܂Łj�A���}�Ѓ��C�u�����[�ł̖{����9�y�[�W����166�y�[�W�܂Łi�q�㏑�r�ȉ��̌�t��167�y�[�W����261�y�[�W�܂Łj�B���̐l�������́A�K����e�ł̓ǎ҂̖��ɗ��ɈႢ�Ȃ��B�\�\�ƌv��𗧂Ă��܂ł͂悩�����̂����A�������Ƃ��鎞�Ԃ��Ȃ��B����͋g�����̓o�ꂷ��y�[�W��l�������Ƃ��Čf����̂�����t���B���̑���ɁA�g���̒����̏��������������ƁA�s�����C�J�t���Ɏ��M������i���̍�������i���������Čf����B�����̘̍^�͈͂��q�����C�J���ڎ��\�\�����C�J���ʍ��r���邢�́q���惆���C�J �o�ő��ژ^�r�A�G�f�B�^�[�p���łƕ��}�Ѓ��C�u�����[�ł̑剪�M�q����r�A�O�q�������G�i�B���m���u���Ȃ̂Łk�@�l�Ŋ������j�Ƃ�����ɁA�{�����������������̃v���������g�����i�Ȃ��A�q�ʍ��r�̃m���u���́u-2-�v�̂悤�ɕ\�L���邱�ƂŁA�{�̂̂���Ƌ�ʂ����j�B
�y�ɒB���v��e�W���s����z
�g�����c�c148�`153, -2-, -6-, -10-, -12-, -14-, -16-, -21-
�w�t�́x�c�c152
�w���x�c�c152
�w�m���x�c�c148�`152, -21-
�w�g�������W�x�c�c152, -17-�ߔ��c�c-14-
���с@�����c�c-6-
�́c�c-10-
�m���c�c-2-
�g��i���Ɏ~�܁k�}�}�l��c�c-12-
�����c�c-12-
�y�G�f�B�^�[�p�����z
�g�����c�c131�`135, 163, 168, 203, 209�`210, 234, 238�`239
�w�t�́x�c�c134
�w���x�c�c134
�w�m���x�c�c131�`134, 168
�w�g�������W�x�c�c134, 163
��i�^�ߔ��c�c203
����i�^���сE�����c�c203
����i�^�́c�c203
��i�^�m���c�c203
��i�^�g��i���Ɏ~��c�c203
��E�����c�c203
�y���}�Ѓ��C�u�����[���z
�g�����c�c140�`144, 173, 178, 216, 223�`224, 249, 253�`254
�w�t�́x�c�c143
�w���x�c�c143
�w�m���x�c�c�k3�l, 140�`143, 178
�w�g�������W�x�c�c�k7�l, 143, 174
��i�^�ߔ��c�c216
����i�^���сE�����c�c216
����i�^�́c�c216
��i�^�m���c�c216
��i�^�g��i���Ɏ~��c�c216
��E�����c�c216

�ɒB���v�s�����C�J���t�i�ɒB���v��e�W���s��A1962�N1��16���j�̔��E���G�ʐ^�Ɣ��k�\��4�l
�s�����C�J���t�́u�̈ɒB���v�������̂��������͂̑S���v�i�������q�㏑�r�A�{���k�ꎵ�Z�y�[�W�l�j�����^�����{�̂Ɓu���惆���C�J�̏o�Ŗژ^�ƎG�������C�J�̑��ڎ��v�i���O�j���f�ڂ����q�����C�J���ڎ��\�\�����C�J���ʍ��r��2�����@�B���Ɏ��߂�B�{�̂̎d�l�́A�ꎵ�Z�~��~�����[�g���E�ꔪ�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�����B�q�ʍ��r�̎d�l�́A�ꔪ�O�~����~�����[�g���E��l�y�[�W�E�����i���Ԃ��j����ݕ\���N���X���i�\��1�̃J�b�g��1956�N10���́s�����C�J�t���n�����́A�\��4�̃J�b�g��1962�N2���̓����ŏI���̕\���ʐ^�j�B�\���͑o���Ƃ������������n�i�Όn�́q�ʍ��r�\��������悤���j�B����̕z�w�͂ǂ��������̂��B���ł̑����ɂ��ẮA�{���̂ǂ��ɂ��L�ڂ��Ȃ��i�G�f�B�^�[�p���ł́u���{�E���X�P�v�v�A���}�Ѓ��C�u�����[�ł́u����c�c���_�M�v�v�j�B�ɒB���v�������ł��Ȃ������̂�����A�g�������S������̂��őP�̕������B�����́q�㏑�r�ɂ́u�k�ɒB�́l���O���s�����Ă��������v�i���O�j�ƌ����邪�A�Ō��ɏ��惆���C�J�͂��肦�Ȃ�����A�ǂ�����o�����肾�����̂��낤�B�u���N�l�̈�l�Ƃ��āv�̒������́q�㏑�r�́A�Ō�Ɂu�ҏW���s�̎��ۂɓ����Ă��ꂽ�����N�Y�A�߉ϑ��Y�A�X�J�ρA�u�k�v�̓��l�����Ɍ������ӂ���v�i���O�j�Ƃ���B��������ɒB���v�ƈ�����ʐl���������A�����I�ɕҏW��Ƃ�S�����̂͐����N�Y�i1969�N�ɐy�Ђ��N�����āA�G���s�����C�J�t���������j�ł͂Ȃ��낤���B���Ƃ���ƁA�O�f���ݍ��݂̈ē���i���ӂ��Ȃ��j�́A�����N�Y�̎��M�̂悤�ɂ��v���Ă���B�����́u�ӂɂ݂��ʑ��{�v�Ƃ́A�{���p�����m�h�̂Ƃ���Ŕg�ł��ڂł��邱�ƂƁA���̗p�����Ǝ�ł��邱�Ƃ��w�����낤�B�u�ӂɂ݂��ʑ����v�Ȃ�ʁu�ӂɂ݂��ʑ��{�v�́A�{���┟�̗p����V���ɒ��B�����A�ɕi���g�����\�����������Ă���B���̐������������Ȃ�A���惆���C�J�͎莝���̎��ނ��g�����������ƂɂȂ�B
�q�g�����ٕ��r�\�\�u�q�V���r�Ɉ˗�����ď��������̂����A�����̗��R�Ŗv�ɂȂ����v�i�O�f�j�̂́A�g�����Ƃ̗��݂䂦���낤�\�\�͂킸��6�y�[�W�̒Z�������A�ɒB�́s�����C�J���t�A�s���l�����\�\�����C�J���t�ȊO�ɁA�s�V�I�g�������W�t�i�v���ЁA1978�j�A�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�i���A1991�j�A�s���E�g�������W�t�i���A1995�j�Ƃ������֘A���ɂ��Ę^����Ă���B����Ĉ��p�͍T���邪�A�g�����͂������̂��ƁA����S���⌴�����O�Ƃ������l�l�A������s���͂��߂Ƃ���s�k�t���l�����̌����Ȑl���X�P�b�`�ɂ��Ȃ��Ă���B�g��������ɋ��Q�������Ƃ͑O�f���ɂ���Ƃ��肾�B���́q�g�����ٕ��r�̃^�C�g�����̈ɒB�ɂ��J�b�g���j���g���i���[���[�̂悤�Ɍ�����p�C�v�H������Ă���j�Ȃ̂́A�̈ӂ����R���B������܂��A�ɒB�ɂ��g���́u��f�ʁv�������B�R���͓���g���Ɍ����ĂĂ������A�ɒB�̕����悾�����B
�k�NjL�l
�g�����g�́s�����C�J���t�̑����ɂ��ĂȂɂ�����Ă��Ȃ��B�������q�f�ЁE���L���r��1961�N7��11���u�Ηj�@�[�����J�ŗ������Ȃ�B�ɒB���v�̈�e�W�̂��ƂŒ������Ɖ�B�k���l���ɒB�v�l�������҂����v�A��15���i�y�j�j�u�ɒB�v�l�s�����C�J���t�čZ�Q�������Ă���B�͂��߂āq�g�����ٕ��r�����ŁA�ɒB���v�̊ώ@�̉s���̂ɋ����v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�v���ЁA1968�A���܃y�[�W�j�Ƃ����،����c����Ă���B����Łq�f�ЁE���L���r�ɈɒB�̎��̑O��̋L�ڂ������Ȃ��̂́A���̎�����F�߂����Ȃ��A�Ƃ����g���̋C�����̕\��ɑz���ĂȂ�Ȃ��B7��11���Ɂu�������Ɖ�v�����̂́A�����̈˗������̑ł����킹�̂��߂��낤�B�������������āA�_�ے�������Łs�����C�J���t�̍čZ�Q����c�ߎq�v�l���炠���������B�ɒB�̟f�㔼�N�ł��̐i���Ȃ�A��e�W�̊��s��1962�N1���̈�����ɊԂɍ����ėǂ��肻���Ȃ��̂��B���ꂪ��1963�N2���ɒx���������R�����Ȃ̂��́A���̂Ƃ���킩��Ȃ��B

�������Y���W�s�D�� ���̉́t�͏���700����1972�N3��1���A�v���Ђ��犧�s���ꂽ�B�u�D�� ���̉́v�͎��W�̕W��Ƃ��āA���邢�͎��т̑薼�Ƃ��Ė{���ɉ��x���o�ꂷ�邪�A��s�őg�ꍇ�u�D�Ɓv�Ɓu���̉́v�̊Ԃ͊�{�I�ɔ��p�A�L�ƂȂ��Ă���B�B��A���g�̉��t�Łu���W�@�D�Ɓ@���̉́v�ƑS�p�A�L�ƂȂ��Ă��邪�A�{�e�ł́s�D�� ���̉́t��q�D�� ���̉́r�Ƃ����ӂ��ɔ��p�A�L�ŕ\�L����B�����́q���W�@�D�� ���̉́@�ڎ��r�̍Ō�Ɂu���Ō��G�@���N�Y�v�u���t���{�@����N�v�v�Ƃ���悤�ɁA�g�����͖{�����ł̑����ɂ̓^�b�`���Ă��Ȃ��B�����ċg���������ɂȂ�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N�k�������ځl�j�́A2014�N3�����݁A�����ł���B���������Ė{�e�́A�������|�Ƃ���s�q�g�����r�́u�{�v�t���M�̌�������͊O��邱�ƂɂȂ邪�A�苖�̏��Ŏ��W���q����O�����w�ٔ��s�̈������Y�W�}�^�Ɉ˂�Ȃ���i�߂邱�Ƃɂ���B�Ȃ��A���{���W�s�H�̒����E�D�Ɓ@���̉́t�i���X�ЁA1981�N3��10���j�̒��ҁq�Ċ���L�r�ɂ��A�u���W�w�D�Ɓ@���̉́x�́A��㎵��N�O���A�v���Ђ̊��s�ŁA���Z�Z���̂ق��ɓ����{��Z���A�ʐ��{��ܕ����������B�v�i�����A�k��ꎵ�y�[�W�l�j�Ƃ̂��Ƃł���B

�������Y���W�s�D�� ���̉́t�i�v���ЁA1972�N3��1���j�̔��ƕ\���k���Ō��G�F���N�Y�A���t���{�F����N�v�l
�{�����ł̎d�l�́A����~��܁Z�~�����[�g���E�㔪�y�[�W�i���N�Y�̃J���[���ʼn���ʐ^�łň�������ʒ����G�̂܂��ɂ��锖���́A�y�[�W���ɃJ�E���g���Ȃ������j�E�������ꑕ���\���E�@�B���B���Ԃ��p���͂Ȃ��A�ŏ���1�܂ƍŌ��12�܂̐ܒ��i�{���p�����������������A�ܒ��͒ʏ��16�y�[�W�ł͂Ȃ��A8�y�[�W���琬��j�ɐ݂���ꂽ�e2���́k���l�����Ԃ��̑���ɂȂ��Ă���B�܂�A�\���Ɩ{�͔̂w�����ŌЕt������Ă���B�{���̍���F�̓X�~�ł͂Ȃ��A�Z���O���[�ł���B�苖�̌Ï��͂��łɃy�[�p�[�i�C�t�œV���J����Ă������A�����̓A���I�[�v���h�������͂����B����āA�V�n���E�̓���~��܁Z�~�����[�g���͂`�T�������i���Z�~��l���~�����[�g���j�Ɠǂ݂����Ă��܂�Ȃ��B�s�D�� ���̉́t�͈����̑�W�ŁA���̐��藧���́q���ڂ������r�ɏڂ����B
�@���̎��W�Ɏ��߂��\�l�т́A�O���W�w�H�̒����x�i�����j���s��́A���ܔ��N����ŋ߂܂ł̍�i�ł���B�قڏ����ꂽ�����ɏ]�āA���̂悤�ɎG���ɔ��\���ꂽ�B
�@�k�S���т̏��o���A�u�ʒu�v�u���^�t�C�W�c�N���v�u�A���r���I�v�u�f�`�v�u�����v�u���Ɣ�]�v�u���㎍�蒟�v�̌f�ڍ��┭�\�N���̋L�ڂ�����l
�@���̎��W��҂ނɂ����ẮA��i�̔r��ƃ��C�A�E�g�́A�v���ЕҏW���̔��ؒ��h���̂��z���ɂ��A����N�v�����l���ĉ������B����l�ƁA���G���������������N�Y���ɁA�����\��������B�i�{���A���Z�`�����y�[�W�j
�{���̂��ƂɁq���ڂ������r�Ɩڎ���u���āA�Ō�ɉ��t������i�q���ڂ������r�̏��o�ꗗ����J��ƁA���W�̕��я����Č������ڎ��ɂȂ�j�B���̓W�J�́A�Ƃ���Ȃ��������҂̈�����ҏW�S���̔��A�Ҏ҂̓���ɂ��A���W���P�Ɏ��т\���ɊW�߂��ҔN�̂̋����W�ł͂Ȃ��A���m�ȈӐ}�Ɋ�Â����\�z���ł��邱�Ƃ̐錾�ł���B���͏��ߖ{�������W�̔r��i�ڎ��j���ɓǂ݁A�{�e�̎��M�ɍۂ��Ĕ��\���Ŏ��т��ēǂ��āA��x�����B
�˒I�i���o��1958�N7���́s�A���r���I�t��30���j
�@�ނ͖���˂������ĕ����̒��֏o�ė���B�����Ėl�̖T�ɍ���̂����A���̏L���ƌ�����䖝�̂ł���ǂ���ł͂Ȃ��B�ނ͈�A���ł��i�ߏグ�Ă���l�N�^�C�̌��іڂ��w��ŕ��łȂ���i�l�N�^�C�̌��іڂɐ₦�������Ă���̂������̕Ȃ����I�j�����Ƃ�Ȃ����ʼn����s���炵���ꂫ�n�߂�B�ǂ����l�̎��ɂ܂œ͂����ł͂Ȃ��̂����A�������Ă���̂��l�ɂ͂킩��B
�@�u���̂ЂƂ͂���𗠐��v
�@���ꂾ�����B���Ƃ͌J��Ԃ����B
�@�₪�āA�閈�̈ꂭ���肪�ςނƁA�ނ͂����Ɨ�����Č˒I�̒��A�čs���B
�@��̖l�͉�����낤�Ƃ��Ă���̂��H�@�˒I�̊��Ȕ˂ɂ͑傫�ȏ��O�����낵�Ă��āA����̎K�т��������A���̌˒I���������N���̊ԊJ���ꂽ���Ƃ̂Ȃ��̂́A�N�ɂł������m���b�ł͂Ȃ����B�������ނ͂��̒��ɂ���B�Ȃ��Ȃ�A�l���ނ̃l�N�^�C���i�ߏグ�āA���̏������낵���̂�����B
�@����ł����l�̏K���Ƃ����z�́A�����̎�ɕ����Ȃ����̂炵���B�ނ͑��ς炸��ɂȂ�ƕ����̒��֏o�ė��Ėl�̖T�ɍ���B���̏L���ƌ�����䖝�̂ł���ǂ���ł͂Ȃ��B�����A���ꂪ�ނ̏K�����Ƃ���A�l�ɉ����Ȃ����ׂ����낤�H
�@�Ƃ���ŁA�ނ����ɂ��錈�蕶��́u���̂ЂƁv�Ƃ́A�����Ă݂Ă��n�܂�Ȃ��A�l�̍Ȃ��B�N���m��Ȃ����̂ł����Ƃ����Ĉȗ��A�ޏ��͂ǂ���畽�t�����߂��Ȃ��Ȃ��炵���̂ŁA�l�͔ޏ����������̂��鉓�����ƂA���Ă���B�ޏ��̖��������ɐ��b���Ă��Ă���炵���B���̙{���ʂȖ����A�T�Ɉ�x�A���܂��悤�ɕ̎莆�������Ă悱���B�u���Z�l�A��S�z�͗v��܂���B�o�͂��̐����A���������悤�ł��B�ł��˒I�͂ǂ����������������Ēu���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƌ�������̂ŁA�H��I�ɋa������̂�h���̂ɋ�J���܂��v
���o��1958�N7���Ƃ����A�g�����q�����r�i�C�E19�j�A�q�r���r�i�C�E15�j�A�q���Ƒ��r�i�C�E14�j�\�������ł���B�����́q�˒I�r�͏��R����U���\�L�����i���W�ɂ͍s�����\�L�̎���11�сA�U���\�L��3�ю��߂��Ă���j�A���̎��̂Ȃ�Ƃ������Ȃ����ǂ������́A�s�m���t�̋g�������ɋ߂���������B���̎��W�̖{���̊�{�g�͌܍�30���l��13�s�����A���ۂ̃��C�A�E�g���Â��Ă���B�ʏ�͎��̑薼�����̈ʒu�i���Ƃ��ΔŖʂ̑�1�s�j�ɁA�{�������傫�߂̓������̂Ŏ����A���s���A�L������Ď��і{���̊J�n�A�Ƃ����̍ق��Ƃ�B���̏ꍇ�̃��C�A�E�g�́A�W�肪��ɓ����ʒu�ɗ��邱�Ƃɂ��A�ǂݎ�Ɏ��т̊J�n��m�点����ʂ�����B����ŁA���т̒�����1�y�[�W13�s�̝y�I���āA���Ƃ���1�s�߂Ɏ��т̕W��A4�s�Ď��і{�����n�߂�ƁA���J���N�����̍ŏ��̃y�[�W�ɂ͖{����8�s����B2�y�[�W�߂ɂ�13�s���邩��A�W��̂��錩�J���ɂ͎��і{����21�s����B�܂�A21�s�ȉ��̍�i�Ȃ�1���J���Ń��C�A�E�g�ł��A�ǂݎ���S�e��c�����₷���i���̃��C�A�E�g�ɋ����y�[�W�����J���N�����������̂́A���́A��]�ł���Ŗʂ�Nj��������ʂƎv����j�B����22�s�̏ꍇ�͂ǂ����낤�B���܂肫��Ȃ�����1�s���ӂ��߂̌��J���ɂۂ��1�s�����u����邱�ƂɂȂ�i�����g�łł͂�����u�E�B�h�E�v�ƌĂ�ŁA�֑���������j�B���̏�Ԃ���������ɂ́A�u1�s�߂ɕW��{4�s�A�L�{�{��8�s�i�ŏ��̋����y�[�W�j�A�{��13�s�i���̊�y�[�W�j�A�{��1�s�i����Ɏ��̋����y�[�W�j�A�i����ɂ��̎��̊�y�[�W�j�v�Ƃ����z�u�ɂȂ�ق��Ȃ����C�A�E�g�̊�{���j��ύX����ȊO�Ȃ��B�{���̃��C�A�E�g�ɖ߂��āA�u�ŏ��̋����y�[�W�v�ɂ����闼�ɂ̗��������A
�@�E1�s�߂ɕW��{4�s�A�L�{�{��8�s�A���q�X�r�q�����́r�ɓK�p����Ă���B�s�A�L�̖{�����m�h�ɂ�����Ȃ��悤�ɂ���ȂǁA�ق��̗v���������Ă��邪�A�W��܂��̃A�L��0�s����7�s�܂Ŏ��݂ɕω������Ď��т̍s���ɑΉ����邱�ƂŁA���ɗނ����Ȃ����W�̖{���g�ł����������B�W������݂ɔz�u���邱�̃��C�A�E�g�̕����́A���łɑ�ꎍ�W�s�H�̒����t�Ŏ��s����Ă��邩��A�{���͂��̓��P�ł���A����������I�ɊJ�������͈̂������Y���̐l���Ǝv����B�s�Õ��t�ȍ~�̐��̋g�����̒P�s���W�́A�{���̊�{�g�����炵�āA�W��̑O��ŃA�L�߂��Ă��Ȃ����߁A�E�B�h�E������i��O�̎��W�ɂ��Ă��q���W�s�����G�߁t�̑g�Łr�A�q���W�s�t铁t�̑g�Łr���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�������Y�́s�߂���̉́t�i�v���ЁA1999�j�ő掵���Y�܂���܂����B������L�O���ĊJ�Â��ꂽ�̂��O�����w�ٓ��ʊ��W �掵���Y��ғW����q�������Y�\�\�w�H�̒����x����w�߂���̉́x�܂Łr�ŁA�J�Âɍ��킹�ās�k�O�����w�ٓ��ʊ��W �掵���Y��ғW����}�^�l�������Y�\�\�w�H�̒����x����w�߂���̉́x�܂Łt�i�����Y�L�O�@���ƗƎ��̂܂��@�O�����w�فA2000�N3��4���j�����s����Ă���B���̂`�S��48�y�[�W�̐}�^�����A���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�̎�|����ƂȂ�ŏ�̎����Ȃ̂ŁA�ڂ������Ă��������B�}�^�͑傫��3���\�\�q���������r�q���W����r�q�C���^�r���[�E����ɂ��ār�\�\���琬��B�܂����������̂́A1999�N12��15���ɍs�Ȃ�ꂽ�����ւ̃C���^�r���[�ł���i����҂͕ҏW�S���̓��يw�|���A�Ó���G�j�B
�{���̊y����
�����ň�����Ď���̎��W��������Ƃ������Ƃł����B
�\�\����͎��W�ł͂Ȃ��ĒZ�ҏW�ł��B�����Ɍ����Ə��ҁB����ƒZ���Z�ҁA������O���炢���킹�āB�傫���͕��ɖ{���炢�B��\�����炢�������Ȃ����ȁB�́A������ɖ��h����@���Ă����̂�����܂����ˁB�l�̂����̋ߏ��Ɉ�����������āA�ʔ����@�B���Ȃ����Ďq�ǂ��S�Ɏv���Ă��B���傤�ǂڂ����x�w��������ɁA�F�l�̉Ƃɂ��ꂪ�������̂ł������āB�t�����炢�̑傫����������܂���A���ɔ���y�[�W����������g��ŁA����I���Ɗ������炵�Ď��̃y�[�W��g�ݒ����āA���āB�ɂ�����Ύq�ǂ��͂��낢��Ȃ��Ƃ��l���܂�����ˁB
���̂��납�瑢�{�Ƃ�����m�����Ă��n���͂��߂��̂ł��ˁB
�\�\�����āA�y���y���̎��ɂ��Ă������Ⴀ�o���o���ɂȂ邩��Ԃ��Ȃ����Ȃ�Ȃ��B�Ԃ���Ε\����t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\����t����ȏ�̓u�b�N�f�U�C���̂悤�Ȃ��̂��l���Ȃ���Ⴀ�Ȃ�Ȃ��B���������ӂ��ɂ͎v���܂�����B�l�̃u�b�N�f�U�C���̎t���́A����ɐ^�������������ł����A�k�����q�B�ƂĂ����ꂢ�ȃu�b�N�f�U�C���̎��W���o���Ă���B���ꂩ��A�{�Â���̗��_�Ƃ��ẮA�E�B���A���E�����X�́w���z�̏����x���Ă����{�������ł��B����ɂ́A�{�����Ƃ��ɂ́A�y�[�W�S�̂ɑ��ĉ��̃A�L�͂ǂꂭ�炢���ďڂ��������Ă���B�{�͌��J���œǂނ��̂�����A���E�̔Ŗʂ͂Ȃ�ׂ��^�ɊāA���J���łЂƂ̌|�p��i�ɂȂ�悤�ɍ��Ȃ����ƁB���ꂩ��A�Ŗʂ͏�Ɋ�ƁB�V�̃A�L����ԏ��������āA���������A�n�̃A�L����ԑ傫���Ȃ�悤�ɍ��Ƃ����悤�ɏ����Ă���B�������m�h�͂���Ƌ����B����Ȃ��Ƃ�͕킵�����̂ł��B�i�}�^�A��Z�y�[�W�j
�Ⴍ���Ď��W�i�����͎菑���j�����삵���o���̂��鎍�l�͑������낤�B�����A���犈�����E���Ĕł܂őg��ň������Ƃ����̂́A�؋�����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��i�g�������A�����őg�ō�Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��͂����j�B�����̓C���^�r���[�ŏ����������Ă��Ȃ����A���̏��ҏW�́q��ӂ�l�r�q�����r�q���r�����߂������g���l�i��\�Љ��G��j����E���s�́s���t�i����60���A1952�N9��10���j���낤�B�����҂̃N���W�b�g�����Ȃ����̂́A�x�C�Y�̏������{�Ɋw�������g�ɈႢ�Ȃ��B
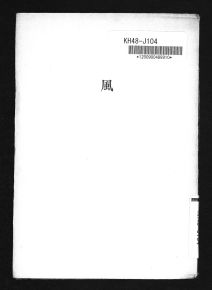
�������Y���ҏW�s���t�i�����g���l�A1952�N9��10���j�̕\���k��������}���ُ����{�̃��m�N���R�s�[�l
���Ɉ����̂́A�q���������r�́q�V���ǖ{�́w�Ԃ����сx�r�\�\�I��̗��N���s�́A���{�̗��G�Ȗx�C�Y�s�Ԃ����сt���d���ĂȂ������Ƃ������z�\�\�̈�߂ł���B
�@�����ŁA�܂��A����̖{��T�d�ɉ�̂����B�\�����͂����A���Ԃ������A�Ԃ�������āA�ǂ�������ɂ��Ă��܂��Ă���A�����̂�������܂��I�яo���A�y�[�W�̏��ɏd�˂āA�܂������̍ޗ���������g�ݏグ���̂ł���B���܂��܂ǂ�������������łǂ�����g���Ă��悢����������Ƃ��́A����̂悢����I�B�����������Ƃ����Ȃ��Ă��\��Ȃ�����A�ǂ̃y�[�W���m���u���̍���ʒu�����͏㉺���Ȃ��悤�ɋC�����āA��܂肸�A�D�j�Ǝ����g���Ă����蒼���A�͂����Ă��������〈�Ԃ���\�����i������悢����I��Łj�\����āA�������d���ɂ��Ċ��������B
�@���ꂾ���̍�ƂɈ���͂��������낤���B�����̖l�ɂ͂�����ł����Ԃ��������B�i�}�^�A���y�[�W�j
�f�ڎʐ^������ƁA�������ɓV��O�����͂ł��ڂ������i���ϒf�����Ă��Ȃ����߂ł���j�A�m���u����ʂ����Ƃ�D�悳���邠����A�����ɑ�������Ȃ�ʈ����Ƒ��w������������B�������烋�����[���ɐi�މ\�����������킯���B���́A�ĂуC���^�r���[����A�q����̍ĊJ�r�̈�߁B�{�����s�̌o�܂ƁA�g�����ւ̌��y�������[���B
�@�w�D�Ɓ@���̉́x���v���Ђ��甭�s�ɂȂ�܂����A�v���Ђ̂ق�����b�������̂ł����B
�@�\�\�����A����͎v���Ђ̊��{�ł��B���Ȃ��̎��W���o�����Ă����āA����͑�ς��ƁA�܂�����ɑ��k���āB���Ⴀ�A�l���������낤�����Ă����b�ɂȂ��āB
�@���̎��W�̔����͂����Ԃ���܂������B
�@�\�\����͂���܂����B��������]��Ȃł͂Ȃ��`�ł������݂����ł��B�Ⴆ�A�w�J�h�~�E���E�O���[���x���Ă������W������܂��ˁA���̒��ɞx�m������n�������Ă���ł��傤�B���̞x�Ɍ���������Ă��ꂽ��ł����A���ꂩ�Ɉ����̎���ǂ�ł݂���Č���ꂽ�Ƃ��A�����������x���́B��ꎍ�W�́w�H�̒����x���A�l�͂܂��������܂łƎv��Ȃ�������ł����ǁA�g�������ˁA�����Ŕ����ēǂ�łĂ���Ă��B�l�͋g������ɂ͓��������Ȃ������Ǝv����ł��B�Ƃ����̂͋g������Ă����̂͐����x���X�^�[�g�������l�ł����A�x�C�Y�Ƃ��������̌n���ł��Ȃ���������B�l�̂����郊�X�g�ɓ����Ă��Ȃ�������ł��B��������g��������́A�Ȃ�ƌÖ{���Ō�������ʔ�����������Ƃ����̂ŁA�����ēǂ�ł���Ă��B���W�̔����Ƃ����̂͏��]���o������Ƃ�����ł͂Ȃ��āA�����Ȃ��Ƃ���łǂ��`��邩�Ō��܂�܂��ˁB����ŐS�ƐS���Ȃ����Ă���A����͏\�N����\�N������������ɂ����Ɖ�𐁂��Ă���B�����v���������Ȃ�ď����Ă����Ȃ��ł��傤�B�i�}�^�A��܃y�[�W�j
�g���́s�������Y���W�k���㎍����79�l�t�i�v���ЁA1983�j�̗��\���Ɂu�Ö{���̎G���Ȃ�v�Ǝn�܂閳��̕��͂��Ă��āA�s�H�̒����t�]�]�̌��͂����Ɍ�����B
�}�^�́q���W����r�̕��Łs�D�� ���̉́t��������ꂽ��т́q���r�ł���B�Ȃ��A�g���̑����ɂȂ�������Y���W�s��̉��t�i����R�c�A1988�j�́A�����W�ɐG�ꂽ���҂̒k�b��}�^��������āA�q�g�����̑�����i�i10�j�r�ŏЉ���̂ŁA�Q�Ƃ������������B�����āA�}�^�͂��悢�揑���I�ȃy�[�W�ɂ���������B�O���y�[�W�ɂ���J���[�ɂ�鎍�W�\����̏��e�̕����}���f����B

�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�j�A�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�j�A�s�D�� ���̉́t�i�v���ЁA1972�j
�o�T�F�s�k�O�����w�ٓ��ʊ��W �掵���Y��ғW����}�^�l�������Y�\�\�w�H�̒����x����w�߂���̉́x�܂Łt�i�����Y�L�O�@���ƗƎ��̂܂��@�O�����w�فA2000�N3��4���A�O���y�[�W�j
�s�D�� ���̉́t�̏��e�́A������k�ʐ��Łl�̓\���A�k�����{�l�̖����̂����炭�͕v�w���A���ł̋@�B���ł���B�������������̂͏��ł���������A�������ɐ������邵���Ȃ��킯�����A�ׂ��Ȍv�Z���͏ȗ����āA�k�ʐ��Łl�\����236�~144�~�����[�g���i217�~160�~�����[�g���̏��ł������Ȃ�c���j�ŁA�k�����{�l�v�w���͖{�������t���̎荗�������܂����ܒ��ɓ�F����i���͐V�g�A�{�����V�g���j�̂��߁A���ł�����傫���������A�}�^�̎ʐ^�⏑���I�L�ڂ���͐����s�\�������B�}�^�ɂ͏��e�̃L���v�V�����ɊȌ��ȏ����i�����E�Ŗ��A���s�N�A���s�����A��ܗ��j�����邾���ŁA�T�C�Y��{�̗l���ȂǂɊւ���ڍ�Ȃ��͎̂c�O���B�����Ɉ����́q���M�N���r�������I�������L�͂ɂ������Ă���B���́u��㎵��N�i���a47�N�@38�j�v�Ɂu��W�w�D�Ɓ@���̉́x���v���Ђ��犧�s�B�������N�v�A���G���N�Y�B�ق��ɓ���N�v����ɂ������{�A�g��������̕ʐ��{������B�v�i�}�^�A�l��y�[�W�j�ƌ����A���ꂪ�k�ʐ��Łl�i�����N���ɂ́u�ʐ��{�v�Ƃ��邪�A�}�^�̎ʐ^�L���v�V�����̕\�L�ɏ]���j�Ɋւ��邢����ڂ����L�q�ł���B

�q�����́r���e�Ɓs�D�� ���̉́t�����{�E�ʐ��Łi�v���ЁA1973�j
�o�T�F���O�A�k�O���y�[�W�l
�}�^�Ɍf�ڂ̎ʐ^�u�q�����́r���e�Ɓs�D�� ���̉́t�����{�E�ʐ��Łi�v���ЁA1973�j�v�ɂ́A�K�^�Ȃ��Ƃɏ��łƁk�ʐ��Łl�k�����{�l���X���[�V���b�g�Ŏʂ��Ă���B��������߂����߂��Ă��邤���ɁA�����悻���̂悤�Ȃ��Ƃ��킩�����B�k�ʐ��Łl�̖{�̂̓O���V���z���ɔw�����������邾�������A���ł̔w�����P���Ă���悤���B�k�ʐ��Łl�̓\���͐��F�̗p���ɃX�~��F����A�q�����r�ň͂�����`�̂Ȃ��ɉ��g�ŎO�s�u�������Y�^�D�Ɓ@���̉́^�v���Ёv�Ƃ���B����́k�����{�l�̔��̑��ӓ\��̂��߂ɑg�łŒ��Ɉ�������悤�Ɍ�����B���́k�����{�l�̔ʼn�́A
�@�w�D�Ɓ@���̉́x�i1972�N�@�v���Ёj���s�̍ہA���G�Ƃ��āA���N�Y���ɔʼn�̐�����˗��������A��䎁�́A�u�����̂�������v�ƁA���łōʐF�̈قȂ�10���̘A��𐧍삵���B���̂�����1�������G�Ƃ��ď��Ŗ{�����s������A10���̓����{������āA1����1����������͂��ݍ��B10�_�̂����A�{�l�Ƌ�䎁�Ƒ�����肪��������N�v���A�Ō��̎v���Ђ�1���������A�c��6����̔������B�i�}�^�A�k�O���y�[�W�l�A�������g�j
�Ƃ���B�J��Ԃ��A�g���́k�ʐ��Łl�Ŕw���������ł���A���̕����k�����{�l������p���Ă���i���s�������͂����肵�Ȃ����A�}�^�ł̌f�ڏ�����́A���Ł��k�����{�l���k�ʐ��Łl�̏��������Ǝv����j�B����N�v�����̏��ł́A�����ĕ\���́u�D�v�̕������߂ɕό`�������A�f�U�C���哱�̂��̂������B�g���́k�ʐ��Łl�ł����ʏ�̖��������ɕύX�����̂ł͂Ȃ����낤���B�g�����ό`��������u�����Ƃ͎v���Ȃ��B�\�\�ȏオ�A���Ŏ��W�ƓW����}�^���琄�������邷�ׂĂł����āA�k�ʐ��Łl�̕ʐ����鏊�Ȃ͈ˑR�Ƃ��ĕs�����B�����̋@�����i���͂����ؖ]���Ă���j�A�{�e�ŏq�ׂĂ��������̓��ۂ��܂߂āA���߂ĒNjL���������肾�B
�����܂��ɁA�������Y���W�s�H�̒����E�D�Ɓ@���̉́k�����{�l�t�i���X�ЁA1981�N3��10���j�̏��e���f���悤�B��ꎍ�W�Ƒ�W�̍��{�͌���500���A�k�����{�l�͂��̂�����100���ŁA�L�ԁE���ҏ�������i���e�̈�{��72�Ԗ{�j�B�d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�㐻�p�w�p���\���i���E���A�w�E�v�j�E�i�{�[���̋@�B���ɓ\���ӁB���͖{�������B�����̃N���W�b�g�͂Ȃ����A���X�Ў哱�Ői�߂�ꂽ���̂Ǝv����B�Ȃ����ѕW��̈ʒu�́A�����W�̏��łƓ����������̂��Ă���B

�������Y���W�s�H�̒����E�D�Ɓ@���̉́k�����{�l�t�i���X�ЁA1981�N3��10���j�̔��ƕ\��
�k2018�N8��31���NjL�l
�Ă̐���̒��߂��A�������Y�����E�ғ��̂���ɖK�˂��B�g���������́s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�j�Ɠ���N�v�����́s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i���A���j�������Ă����������߂ł���B���Ƃ̋N����͂������B2017�N4���ɖS���Ȃ����剪�M����𑗂����N6��28���A������w�A�J�f�~�[�z�[���ŊJ���ꂽ�B�剪����Ƃ��ʂꂷ�邽�ߎQ�����́A�����Ŋ���Ƃ����ׂ��A���ؒ��h����Ƃ�������i�q�ҏW��L 176�r�Q�Ɓj�B�g�����Ɋւ���b����������������̎莆�ɁA�������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t���ς邱�Ƃ��ł��Ȃ��āA�Ƃ��ڂ����Ƃ���i������͓����W�̕ҏW�S���҂ł���j�A�u���A����p�[�e�B�ň������Y����ɂ�������܁A�w�D�� ���̉́x�̓����ŁA�ʐ��ł̂��Ƃŏ��т����ׂĂ��邱�Ƃ�b���܂����B��������̎茳�ɂ͂������悤�ł�����A���莆���Ă݂Ă��������v�Ƃ������[���������������B���N10�����̂��Ƃł���B������㉟�������悤�ɂ��āA��������ɓ���̎��W��q���̂����ʐ^�ɎB�点�Ă��炦�܂����ƈ˗������Ƃ���A�������B���A�ډ����̂���d���������āi2018�N5���ɐ����Ђ���o���s�w���̉x��ǂށt���낤�j�A������I���Ă���Ƃ������ƂŁA����̖K��ƂȂ����B
���҂̏،��������ƁA�s�D�� ���̉́t�̐���ɂ��Ă�����ڂ����̂́A���ؒ��h�s���l�Y���m�[�g�t�i����R�c�A1986�N8��25���j�́q�������Y�r���낤�B��Ⓑ�����A�d�v�Ȃ̂ň��p����B
�@���������y�[�X�͐l�ɂ���Ă��܂��܂ł���B�k�c�c�l
�@�t�Ƀy�[�X�̒x���l������B���Ƃ��Ώ\�l�N�Ԃɏ\�l�т̎��A�Ƃ����̂͂ǂ��l���Ă݂Ă��ُ�ȃX���[�E�y�[�X�ƌ�����B
�@���̏\�l�т�����ɂ܂Ƃ߂��̂��A�������Y�̎��W�w�D�� ���̉́x�ł������B
�@����Ɩ{���̊��t���͓���N�v�B���������������A���{�ɂ��Ă͊m�ł��錩�����������l�����A���ǂ��ł�����B���_�o�̂䂫�Ƃǂ������t�������Ă������������A�{���̍��F���n�ɃO���C�������ă\�t�g�Ȍ��ʂ��o�����B
�@�{���͂킸����Z�y�[�W����������̖{�������g���A�V���A���J�b�g�ɂ��āA�����\���͏����܂�B�������ɓ���Ă������肵�����W���ł����������B
�@��������̊�]�ŁA���G�����N�Y����ɂ��肢�����B�G�b�`���O��_�����肢�����̂����A���������C��������䂳��́u�����̂�܂��Ăˁv�Ƃ���������āA�I���W�i�����\�_�����삳�ꂽ�B
�@�������͋��삵���B�G�b�`���O�\�_��O�ɂ��āA�����Ɂu�����ł����낤�I�v�Ƃ������ƂɂȂ����B�����l�������Ȃ�������䂳��̃I���W�i���E�G�b�`���O��������ŏ\���A����͂�����I
�@�����Ȃ�A�{�����͎��t���̓����a���������B�~���o�Ă����B�G�b�`���O�̃T�C�Y�ɍ��킹�āA���䌧�̘a����������ɓ��ʒ��������B
�@�Ƃ��낪�A���D���͏��������Ƃ͂����Ȃ������B�\�z�����Ȃ���q���͂��܂����̂ł���B
�@�ł��������Ă��������a����������ɓ���A���肠���������̂�����ƁA����Ⴂ������B�����ł�����A���������Ȃ��̂ɂ͂ł��Ȃ��B�Ăјa�������������Ă��炤�B�悤�₭�����������Ă��āA�����A���x�����͂ƈӋC����Ŏ���������ɑ��肱�ށB��������I���Ĉ��S���Ă���ƁA���x�͐܂�̉ߒ��Ō���I�ȃ~�X���������B
�@�w�D�� ���̉́x�Ƃ�������ǁA�D�͐i�܂��A�̂͂Ȃ��Ȃ��������Ă��Ȃ���Ԃ���N�]���Â����B��������������������A���͗⊾�������Â����B�悤�₭�����ł��ł����������̂́A��䂳���ŖS���Ȃ�ꂽ���ゾ�����B
�@�����ł���������A����̑��A�N�̎�ɓn���������͒m��Ȃ����A�Ό��������ď����ꂽ���̑��͂����܂ł��X���[�E�y�[�X�ő��˂�ꂽ�B�i�����A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
 �@
�@ �@
�@
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̃{�[�����Ɠ\���k�|�v�����l�i���j�Ɠ��E�\���k���������ǎ��l�ƛ�k�\�\�̓|�v�����A���\�͖��Q���a���l�i���j�Ɠ��E���y�[�W�i�E�j
�i���j�{�[�����͓V�n292�~���E193�~�����[�g���ɓ\���Ӂi�w�����͏c�g�Łu�D�Ƃ��̉́@�������Y�v�j�B�\���͓�276�~178�~�����[�g���i�w�����͏c�g�Łu�������Y�@���W�@�D�Ɓ@���̉́v�j�B�Ȃ��A2014�N3��31���̋L���Łu�k�����{�l�̖����̂����炭�͕v�w���v�Ƃ���̂͌�ŁA�|�v�����̓\���̃P�[�X�A�ɑ��̂����܂�̛�i�������|�v�����\��j�A�������̌��ʂł���B
�i���j�����ĕ\���̕����g�݂͏��ł̂���Ɠ����B�w�����͖����̂Łu�������Y�@���W�@�D�Ɓ@���̉́v�i�u���W�v���̐F����A���̓X�~����j�B�\���Ƀp�[�`�����g���i�͗l�̂悤�Ɍ�����̂́A�o�N�ω��ɂ��V�~�j���d�˂Ă���A�l����܂�Ԃ��ď�݁A�t�����X���\���̂悤�Ɏd���ĂāA���G��ܒ������ށB
�i�E�j�ܒ��͓��������ǎ���1�܂�8�y�[�W�A�V�܁i�������y�[�p�[�i�C�t�Ő�Ђ炢�Ă���ǂށj�B�d�オ�萡�@�ŁA�V�n��257�~���E��164�~�����[�g���B�X�~�Ɛ�2�F����B
���p���������A���Ɍf����͈̂������Y���W�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̞x�Ɍf�ڂ��ꂽ�A���҂ɂ��q�K���ȋ��R�r�ł���B�����ɂ́u��㎵��N�\�ꌎ�v�ƁA���Ŋ��s��8�ӌ���̓��t������B
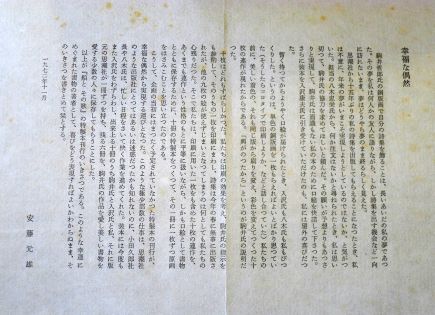
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̞x�k���������l
�x�͖{���̓��������ǎ��Ƃ͕ʂ̎����a���i�V�n210�~���E290�~�����[�g�����܂�j�ŁA�{�̂ɋ��ݍ��܂ꂽ���U��̕t�����̈����ł���B���҂ɂ��q�K���ȋ��R�r�́k�����{�l�̂��߂̏������낵�B
�@���N�Y���̓��ʼn�Ŏ����̎��W�����邱�Ƃ́A�����������̎��̖��ł����B���̖������͉��l���̗F�l�Ɍ��Ȃ���A���������W���o���@��ȂLj���ɖK��Ȃ��܂܁A���͂ǂ���疲�̂܂I��炵���������B
�@�v���Ђ���\�ܔN�Ԃ�̎��̎��W���o�ł��Ă��炦�邱�ƂɂȂ��Ƃ��A���͕s�ӂɁA�N���̖������܂����������悤�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�ƋC�������B�S���̔��ؒ��h������A���������͂Ȃ����Ɛq�˂�ꂽ�Ƃ��A���͎v���āA��䎁�̋��͂����߂Ăق����Ɨ��B���̊肢���\�z����������Ǝ������āA��䎁�͖ʎ����Ȃ����̖{�̂��߂Ɍ��G���������ĉ������B����ɑ��{�����N�v���Ɉ����Ă����������̂��A���ɂ͖]�O�̊�т����B
�@�b���҂Ă���悤�₭���G���͂���ꂽ�Ƃ��A�������؎��������т��肵���B�Ƃ����̂́A�P�F�̓��ʼn���ꖇ���炦��悢�Ƃ���v�Ă����i����������R���^�C�v�ň�����悤���A�ȂǂƘb�����Ă����j�������̑O�ɁA���������F�́A����������ł�������ς��A�ʐF��ς��Ă����\���̘A�삪���ꂽ����ł���B�u�����̂�����v�Ƃ����̂���䎁�̐��������B
�@�\���͂ǂ�����炵�����B�������͈���̌��ʂ��l���A��䎁�̎w�������Q�ނ��āA���̂����̈ꖇ������ɂ܂킵�A���W�͍��N�̏t�ɖ����ɏo�ł��ꂽ���A���̋㖇�̊G���g�������܂��ƂȂĂ��܂��͉̂��Ƃ��Ă��������̐S�c�肾���B�����Ŏ������́A����ɗp�����ꖇ�����܂߂��\���̘A����A�����܂ł��A��Ƃ������i�̂��Ƃɕ����Ɉ����Ȃ���A���������G�Ƃ��ď����ƂƂ��ɕۑ����邽�߂ɁA�\���̓����{�����āA���̈���Ɉꖇ��������͂��݂��ނ��Ƃ��v�������̂ł���B
�@�������āA���̓����ɂ͂܂����\�肳��Ă��Ȃ��������{�̊��s���A�K���ȋ��R�����������^�тƂȂ��B���̂悤�ȋɏ������̎d���́A�v���Ђ̂悤�ȏo�ŎЂɂƂĂ͂��邢�͖��f���������m��Ȃ��̂ɁA���c�v�Y�В��┪�؎��́A�Z���������������ĉ�����Ƃ�i�߂Ă��ꂽ�B���{�ɂ͍��x���܂������킸��킵�A�o�����\���̂�����䎁�Ɠ��Ǝ��A����ɔŌ��̎v���Ђ�������������A�c��Z�����A��䎁�̍�i�����������������������鏭���̐l�X�ɕۑ����Ă��炤���Ƃɂ����B
�@�ȏオ�w�D�� ���̉́x�̓����{���s�̂������ł���B���̂悤�ȍK�^�ɂ߂��܂ꂽ�����̒��҂Ƃ��āA��т��ǂ��\������悢���킩��ʂ܂܁A���̂������������Ƃ߂Ğx�Ƃ���B
�����Ď��Ɍf����̂��A�k�����{�l���t�ł���B�ʐ^���Ɠǂ݂Â炢�̂ŁA�|�����Ă݂悤�B

�������Y���W�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̉��t�y�[�W
�d�̃}�[�N�͏��ł̔���{���A���t�Ɍf�����Ă������̂Ɠ����B
���҈������Y�����s�ҏ��c�v�Y�����s��������Ўv���Ё������s�V�h��s�J
���y�����Ғ��ڏE�ޔԒn���j���������t����Ё����{���⍲���{��������
�����{����H�Ɗ�����Ё���蔋�S���E�ҔN�l���ǏE�ޓ����s���艿�Z�݉~
�k�����܂ŏc�g�B�ȉ����g�A���E�Z���^�[���킹�l
���W�@�D�� ���̉�
�@�@�@�����{
�k�d�̃}�[�N�l
���N�Y�ɂ�Ė{���̂�
�߂ɐ��삳�ꂽ�E�t��V��
�[�Y�̃I���W�i���E�G�c�`
���O����A���̚�t��Y�t
���\�E��\�\�|�v�����]��
������Ё@���\���Q���a
���@�\���E�{������������
�@��������Аΐr������
����E�����s�̂���
�{���͂��̑� �� ���ɂ�����
���́u�E�t��v�͌����̃}�}�����A�E��t�̌�L�E��A�Ƃ͍l�����Ȃ����낤���B����Ƃ����̂��A��Ō��钘�Җ{�k�ʐ��Łl�ɕt���Ă���I���W�i���E�G�b�`���O�i���ł́u�����G�v�̌���j�����̏E��t�߁\�\�Ƃ��������A�u�������͈���̌��ʂ��l���A��䎁�̎w�������Q�ނ��āA���̂����̈ꖇ������ɂ܂킵�v�i�q�K���ȋ��R�r�j���炷��A��t�߁\�\�ɓ�����悤�Ɏv���Ă��������Ȃ��̂��B�c�]�̏E�t���k�����{�l�̌��G�ƂȂ������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�ł�700���̏��ł�10���́k�����{�l�̂ق��ɁA�Ȃ�15���́k�ʐ��Łl������ꂽ�̂��B����2014�N3��31���̋L���̍Ō�Ɂu�k�ʐ��Łl�̕ʐ����鏊�Ȃ͈ˑR�Ƃ��ĕs�����B�����̋@�����i���͂����ؖ]���Ă���j�A�{�e�ŏq�ׂĂ��������̓��ۂ��܂߂āA���߂ĒNjL���������肾�v�ƁA�k�ʐ��Łl�̑��ݗ��R�m���]���E�f�[�g���n���^���悤�Ȃ��Ƃ��������B�����������́A�k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl���������������ł͂킩��Ȃ��������낤�B����A�������璼�ڂ��b���āA�͂��߂Ă��ꂪ�킩�����B������x�A���ؒ��h�q�������Y�r��ǂ�ł݂悤�B
�u�����l�������Ȃ�������䂳��̃I���W�i���E�G�b�`���O��������ŏ\���A����͂�����I�^�����Ȃ�A�{�����͎��t���̓����a���������B�~���o�Ă����B�G�b�`���O�̃T�C�Y�ɍ��킹�āA���䌧�̘a����������ɓ��ʒ��������B�^�Ƃ��낪�A���D���͏��������Ƃ͂����Ȃ������B�\�z�����Ȃ���q���͂��܂����̂ł���B�^�ł��������Ă��������a����������ɓ���A���肠���������̂�����ƁA����Ⴂ������B�����ł�����A���������Ȃ��̂ɂ͂ł��Ȃ��B�Ăјa�������������Ă��炤�B�悤�₭�����������Ă��āA�����A���x�����͂ƈӋC����Ŏ���������ɑ��肱�ށB��������I���Ĉ��S���Ă���ƁA���x�͐܂�̉ߒ��Ō���I�ȃ~�X���������B�^�w�D�� ���̉́x�Ƃ�������ǁA�D�͐i�܂��A�̂͂Ȃ��Ȃ��������Ă��Ȃ���Ԃ���N�]���Â����B��������������������A���͗⊾�������Â����B�v
���́u����Ⴂ�v�͕W��i���у^�C�g���j�E�{���E�m���u���̂����ꂩ���낤�B���Ȃ݂ɁA���łł͎��т͌��J���N�����ŁA�W��͂��̋����y�[�W�ɒu����Ă����B�k�����{�l�i�k�ʐ��Łl���j�͉���������y�[�W�ɕW��i�F�ň���j��u���A���̌��J������{�����n�܂邪�A�W��͍Z���̎w���Ō����Ȃ�A�i�g���A�L�j�ɂȂ��Ă���B����700���͂����炭���ň���̌��ō��肾�낤����A�W��y�[�W�𑝂₵����A�m���u���i������F����j��t���ւ����肵�Ă��邤���ɁA�u����Ⴂ�v���N�����̂�������Ȃ��i����Ɋւ��ẮA��������̒k�b�ł͐G����Ȃ������j�B����́u�܂�̉ߒ��Ō���I�ȃ~�X�v�Ɋւ��ẮA��������킸���ɋ����Ă��ꂽ�B�w���̓������i�]�����j���{�Łk�ʐ��Łl�����̂��ƁB
���������́A���̐����������ċL�����Ƃɂ���B�ʏ�̍��q�͕����̐ܒ����i���Łj�������Ă���A���Ԃ���\���������Ă����B���̐ܒ��̌����⏇�Ԃ��ԈႦ�Ȃ��悤�ɔw���i�e�ܒ��̔w�ɕt�����A�����Ɛܒ��̏��������������j���������̂����A���{�������Ƃ́i�ܒ��̕ς��߂ŁA��قǃm�h���J���ł����Ȃ�������j�����Ȃ��Ȃ�B�Ƃ��낪�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�̏ꍇ�A�ܒ��������炸�A�V���܂ɂȂ�8�y�[�W����1�܂�P�ɏd�˂������́A�����ɂ͏��Ђł͂Ȃ��G���̗p�ꂾ���uunbound�i�����{�j�v�Ƃł����������̂��A�Ƃɂ����ܒ��̔w���ی����̎d�l�������̂ł���B���ł��k�����{�l���A�Ƃ��Ɉ�����͎�t����ЁA���{���͊⍲���{������������A���������������������̂�������Ȃ��B���̌��ʂȂɂ��N�������B�w���̓������ܖ{���\�����i�d�オ��̏\���Ɨ\���̐����j�A�a�������̂ł���B�u����Ⴂ�v���Ȃ��ܖ{�������u�w���������Ă���v�Ƃ��������̗��R�Ŏ̂Ă�ɂ͔E�тȂ��B�k�����{�l�Ƃ͕ʗl�́A�������I���W�i���E�G�b�`���O�̓���Ȃ�����Ł��k�ʐ��Łl�Ƃ��Ă�����������Ȃ����\�\�ƍl���Ă��s�v�c�͂Ȃ��B�Ƃ��������A����܂ł̋�J���l����A�����l����������R�ł���B
���ňȊO�́k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�������Ɂq�g�����̑�����i�i122�j�r�i2014�N3��31���j�������A�Ȃ�Ƃ����ǂ������z��������Ȃ���A������͂�����Ɩ��w�����Ƃ̂ł��Ȃ������^�̗��R�����������B�g���W���Ȃ�������������A�k�ʐ��Łl�͕Z�\���������̂ł���B�܂�@���Ł��s�̖{�i700���Œ艿��1,500�~�j�A�A�k�����{�l���I���W�i���E�G�b�`���O����̌���{�i10���Œ艿��6���~�j������A�B�k�ʐ��Łl�i15���Œ艿��1���~�j��K�v�͂Ȃ������B���݂ɒ艿�ɕ������|�������㍂���Z�o����A�@105���~�A�A60���~�A�B15���~�B����{�Ƃ������ʂ̊���ł����A�B��60�����炢�����Ă��������B��������́A�ŏ����琧��̗\��ɂ͂Ȃ������B������A���S�ȍ��{���\�����~���ėN�����Ƃ���A�W�҂͎��Ԃ�V�̔z�܂ƎƂ߂āA��������q�̌`�ɂ��邵���Ȃ��ł͂Ȃ����B
���ɁA�k�ʐ��Łl���t�y�[�W�̎ʐ^���f���A�|������B
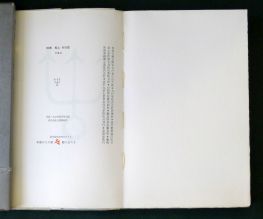
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̉��t�y�[�W�k���[�͏d���́s��̉��t�̔��l
�B���m���u�������A���̉��t�́k117�y�[�W�l�B�k�����{�l�k�ʐ��Łl�Ƃ����҂���������͈̂�Ԗ{�ŁA�k�����{�l�̉��t�ɂ́u�� �� ���v�A�k�ʐ��Łl�̉��t�ɂ́u�� �� ���v�ƕʗl�ɁA��n�ŕM��������Ă���B
���҈������Y�����s�ҏ��c�v�Y�����s��������Ўv���Ё������s�V�h��s�J
���y�����Ғ��ڏE�ޔԒn���j���������t����Ё����{���⍲���{��������
�����{����H�Ɗ�����Ё���蔋�S���E�ҔN�l���ƏE�ޓ����s���艿���݉~
�k�����܂ŏc�g�B�ȉ����g�A���E�Z���^�[���킹�l
���W�@�D�Ɓ@���̉�
�@�@�@�ʐ���
�k�d�̃}�[�N�l
�\���E�{�����������ǎ�
�@������Аΐr������
����E�ޕ����s�̂���
�{���͂��̑� �� ���ɂ�����
�k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�̉��t�ɂ��銧�s���́A�����Ƃ�1973�N4��25�������A����͂����炭�k�����{�l�̞x�̂��߂́q�K���ȋ��R�r���������u��㎵��N�\�ꌎ�v����A���t���e�ɋL����Ă������s�i�\��j���ł����āA���ۂɁk�����{�l�����������̂�1976�N11�������Ǝv����B����Ƃ����̂��A������́s���l�Y���m�[�g�t�ɂ��u�悤�₭�����Łk�}�}�l���ł����������̂́A��䂳���ŖS���Ȃ�ꂽ���ゾ�����v���A��������̒k�b�ɂ��A�悤�₭�ł����k�����{�l�����Q�����̂͋��N�Y�̑��V�̂Ƃ��������Ƃ�������A�ʼn�Ƃ��f����1976�N11��20���̂������Ƃ��낤�B�s�̖{�͂Ƃ������A��ʗ��ʂɏ��Ȃ�����{�̏ꍇ�A����̒x���ɔ������������ꗂ͂����N���肪�����B�����āA�O��͕s�������k�ʐ��Łl���قړ����Ɋ��������̂��낤�B���{���ɂ��Ă݂�A�g���u�������́k�����{�l�Ɋr�ׂāA�k�ʐ��Łl�͏������Ƃ͂����ܒ���������ʏ�̍��q�̐��{������A�芵�ꂽ��Ƃ������͂����B�����������������k�ʐ��Łl�����ł������G��Ă��Ȃ��̂́A��Y�������k�����{�l�ɋL������L����Ă��܂������ʂł͂Ȃ����낤���B������͖`���Ɉ��������[����5���قǑO�̕ʂ̃��[���ŁA���̎���ɓ�����`�Łu�ʐ��ł̑������g������ɂ��肢�����̂́A�g������̑����̂��炵���������F�����Ă����̂ŁA��������Ƒ��k���Č��߂��̂ł����v�Ə����Ă���B
 �@
�@ �@
�@
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�����{�l�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̌��G�k���N�Y�ɂ��I���W�i���E�G�b�`���O�l�i���j�Ɠ��E���у^�C�g���y�[�W�i���j�Ɠ��E�{���y�[�W�k���сq�D�� ���̉́r�̑�2�߂����4�߂ɂ����āl�i�E�j
�i���j���G�͓V�n��257�~���E��164�~�����[�g���A���Ȃ킿�a�T���ό^�B�ܒ��̎d�オ�萡�@�́A���̌��G�̗p���T�C�Y�P���Ă���B
�i���j�ܒ��͒Ԃ����Ă��炸�A���̔w�ɔw���͈������Ă��Ȃ��B
�i�E�j�{���̑g�ł́i���т̃^�C�g���������āj���ł̂���Ɠ����B��f�ʐ^��12�`13�y�[�W�̌��J���́A���ł�14�`15�y�[�W�̌��J���ɑ�������B
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̎d�l�́A����~��Z�l�~�����[�g���E���Z�y�[�W�i���N�Y�ɂ��J���[���ʼn�\�\���ł͎ʐ^�ł̕ʒ���Ԃ����݁A�k�����{�l�̓I���W�i���E�G�b�`���O�����ݍ��݁\�\�͓Y�t���Ȃ��j�E�{����F����A���I�[�v���h�E�����t�����X�����\���i�{���ƂƂ��ɓ��������ǎ��j�E�p�[�`�����g���̃_�X�g�W���P�b�g�E�\���Ɉ�����ӁE�{�[�����ɓ\���ӁB����15���i���t�ɋL�ԁj�B�艿10,000�~�B
 �@
�@ �@
�@
�������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̃{�[�����Ɠ\���i���j�Ɠ��E�\���ƌ��G�k���ł́u���Ō��G�v�Ɏg�p���ꂽ���N�Y�ɂ��I���W�i���E�G�b�`���O�l�i���j�Ɠ��E�{���y�[�W�k�E�[�͏d���̏��ł̔��l�i�E�j
�i���j�{�[�����͓V�n283�~���E184�~�����[�g���ɓ\���ӁA�\���͓�270�~169�~�����[�g���ɑ��ӂ�����B�Ȃ��A2014�N3��31���̋L���́u�k�ʐ��Łl�\����236�~144�~�����[�g���v�͌�ŁA270�~169�~�����[�g���������l�B�܂��A���L���Łu�g���́k�ʐ��Łl�Ŕw���������ł���A���̕����k�����{�l������p���Ă���k�c�c�l�B����N�v�����̏��ł́A�����ĕ\���́u�D�v�̕������߂ɕό`�������A�f�U�C���哱�̂��̂������B�g���́k�ʐ��Łl�ł����ʏ�̖��������ɕύX�����̂ł͂Ȃ����낤���B�g�����ό`��������u�����Ƃ͎v���Ȃ��v�Ƃ��������͌�ŁA�g���́k�ʐ��Łl�̕\���ɂ����ē����ɂȂ鏉�ł̂���P���Ă���B�Ȃ�A�g�������m���Ɏ�|�����̂́A���̓\�������Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤���B���҂̈������Y�i�̂��ɔѓ��k�ꎍ�W�s�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́t�����Ă���j���A���ŒS���̓���N�v���A�ҏW�S���̔��ؒ��h���A�����Ă������g���������ꂼ��Ɂk�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�̐���Ɋւ���Ă���͂�������A�N���ǂ������������Ƃ����D�����͓���̂ł͂Ȃ����B�Ⴆ�A�{�[������\���̑��ӂ̑g�ł��w�肵���̂��g���������Ƃ��Ă��A���������������Ȃ��B
�i���j�\���Ƀp�[�`�����g�����d�˂�B�{���ɏ������悤�ɁA�k�ʐ��Łl�Ɍ��G�͕t���Ȃ�����A���̈�t�͒��҉Ƒ��́u�����v�{�Ɂu���Ō��G�v�̌�����ĕۑ��������̂Ǝv�����B���������ǎ��̖{���̐��@�́A�V�n��257�~���E��164�~�����[�g���B�ܒ���1�܂�8�y�[�W�ŁA�V���܁A�����ƌr���i�n�j�������B�{���͑�120�y�[�W�B
�i�E�j�B���m���u�������A���̕W�莆�́k5�y�[�W�l�B�k7�y�[�W�l�ɑO���u�D�� ���̉́v�A�k9�y�[�W�l�Ɏ��у^�C�g���́u�D�� ���̉́v�A10�y�[�W���玍�сq�D�� ���̉́r�̖{�����n�܂�B���łŖ{���̑O�ɒu����Ă������у^�C�g���́k9�y�[�W�l�Ɉڂ������߁A���R�̂��ƂȂ��炱�̌��J�����珜����Ă���B���łł̖{���̍ŏI�m���u�����u82�v�������̂ɑ��āA�k�ʐ��Łl�ł͎��у^�C�g�����������Ă����1�y�[�W�Ă��Ƃ��납��A�u106�v���{���̍ŏI�m���u���ɂȂ����B���Ȃ킿3��24�y�[�W���A���y�[�W���Ă���B
�k�t�L�l
���������K�₵��8��5���́A���̉ĂɓT�^�I�ȍ����̈���������B�����̗ΐF�̃o�b�N���i�r�I�g�[�v�̃t�H���X�g�O���[���j�ƃf�W�^���J���������Q���āA�k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�̎ʐ^���B���Ă���ƁA�{���犾���������藎����̂ŁA�ق�Ƃ��ɗ�⊾���̂������B���ꎞ�ԂقǂŎB�e���I���A�s�H�̒����t�i�ʒu�ЁA1957�j�A�s�D�� ���̉́t�i�v���ЁA1972�j�A�s��̉��t�i����R�c�A1988�j�\�\����͋g�����̑����\�\�ɏ������Ă��������A���㎍���ɔŁs�������Y���W�t�i�v���ЁA1983�j���\���̗��𒆁A�s���̒��̍Ό��t�̔Ō����i�v���Ђł���j�������Ă��邱�Ƃ��������߂ɓ���������������ƁA�u���̋g������̕��͊����������Ȃ��v�ƌ���ꂽ�B�u�Ö{���̎G���Ȃ�͐ς̈ł���C���͈���̔����{���C���̂Ȃ��֒����o���C�ԕ�����D�܂��^�V�����C����͈������Y�̏������W�s�H�̒����t�ł������v�Ǝn�܂閳��̕��͂ł���B����܂��������ŁA���̂��Ƃ��ǂ����ɏ��������c�c�ƌ�����̂ŁA�����p�̑�w�m�[�g�ɓ\������R�s�[�������������B���[�y����ɂ̂������ނƁA�u���������A����v�Ɣ[�����ꂽ�B����͋g�����Ǔ����W���Ɋ��q������{�̖_�Y�r�ł���i�����͈�������̒P�s�{�ɂ͖����^�Ƃ̂��Ɓj�B���̍Ō�̒i���������āA�{�e���I���邱�Ƃɂ��悤�B
�@����������A�l�I�Ȃ��Ƃ������̂������Ăق����B�܂������ʎ������Ȃ���������̋g�����A������ǂ����̌Ö{���ŁA�����Ɛ̂ɏo�����܂܂Ƃ��ɖY����Ă������̎��̍ŏ��̎��W�������A������Ď����Ă��ĉ��������B���̂��ƂŒm�肠���Ă���ɂ����Ԃ��Ă��炻�̂��Ƃ��A���̂��������ꂾ���̂��Ƃ̂��߂ɁA�ǂ�Ȃقߌ��t�ɂ��܂����ė͂Â�����v���������B�����Ƃ��������Ȉ�{�̖_�Y�́A�ق�̏������ꂽ�Ƃ���ɁA����A���Ȃ艓�����ꂽ�Ƃ���Ƃ����ׂ������m��Ȃ����A������{�̖_�Y�������āA�����Ɩق��ė����Ă���B�\�\����ȋC�������B���̖_�Y�̑��݂̂��肰�Ȃ�������������܂��������B���̉e���ӂƑ~�����������܁A�g�����̎��͎��ɂƂ��āA�N�͂����ł��b���A�����ʂĂ�܂Ŗق��ė����Ă����܂��A�Ƃ����A�����̎w�}�̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����k�Ǔ����W�E���ʂ� �g�����l�A���y�[�W�j
�{�NjL���M�̂��߂ɋM�d�Ȓ��Җ{�������Ă����������������Y����ƁA���Љ�̘J���Ƃ��Ă������������ؒ��h����ɁA�S���犴�ӂ���B���肪�Ƃ��������܂����B�s�q�g�����r�́u�{�v�t�̃y�[�W��2003�N1���Ɏn�܂����q�g�����̑�����i�r�́A���s���ɕ��ׂ��s�g���������t���q������i�ژ^�r�i�S192�_�j���烊���N���Ă��邪�A�g���̎���16�_��������������i��176�_�𐔂���B�{�NjL�������āA2018�N8���̌����_�Ŕ������Ă���g��������|�������ׂĂ̑�����i�̏Љ���I���B
�k2019�N5��31���NjL�l�s�������Y���W�W���t�̂���
�s�������Y���W�W���t�i�����ЁA2019�N1��25���j���o���B�������W9�������߂��S���W�ł���B2018�N8��5���Ɉ��������Łs�D�� ���̉́t�́k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl��q���������Ƃ̎l���R�b�ŁA���������S���W���o��\�肾�Ƃ����������B���̂Ƃ����́A�Ă�����v���Ђ��犧�s�������̂Ǝv������ł����B�Ȃ��Ȃ�A��������̎��W����������|���Ă���Ō�����������B�����A�{���́s�w���̉x��ǂށk�������Ɂl�t�i2018�N5��20���j�Ō����Ȗ{����i���ɂƂ��邪�A�����镶�ɖ{�ł͂Ȃ��A�W���P�b�g�t���̃n�[�h�J���@�[�{�j���݂��������Ђ��A�O���ɗD�錩���Ȗ{�Ɏd�グ���B�Ƃ�킯�A�쑺��a�v�̉���q�����̂��̂̑��ݏؖ��Ɍ����ār���������Y�̎��Ƃ���������ƕ`���āA�{���ɉԂ�Y����i�Ⴆ�A�l�l�y�[�W�́u�����Ĉ������́A�ЂƂ̎��ɓI���i���Ă�����@�艺����ꍇ�ɂ͎U���`�����A�����I�Ȏ��Ɍ��������Ă����̊j�S���������`���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�u�p���^�N�V�X�v�k�A�h���m������w���_�[�����̎��̌�@�ɂ��ďq�ׂ��^�[���ŁA�u���Ȃ����͕��̐����̕�����Ӗ�����M���V����ŁA���̏��p�[�c���P����ɂ܂����ʗ��I�Ɍ��т��ĕ��S�̂��\�������̂ł͂Ȃ��A�����������Γ��̊W�ɂ����ĘA�Ȃ�A���s���Ă���悤�ȏ�Ԃ��w���Ƃ����v�l�I�ȍs�����`��������Ԃ悤���B�v�Ƃ����w�E�j�B����Ŏ��́A�����́q�����E���o�ꗗ�r�Ɋ��҂����̂����A������͂������������肵�Ă��āA�c�O�Ȃ���V���Ȓm���������炷���̂ł͂Ȃ������B���́s�D�� ���̉́t�̍����������B�q�g�����̑�����i�i122�j�i2014�N3��31���j�r�̖{���ł͏��o�ꗗ�̋L�ڂ��ȗ����Ă�������A�d�����邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��i�����A���l�`���܃y�[�W�B�Ȃ��A�s�������Y���W�W���t�̌f�ڃm���u���͊��������j�B
���W�w�D�Ɓ@���̉��x
���Ō��G�����N�Y�@���t���{������N�v�@����S�������ؒ��h
��㎵��N�O������@�v����
�@�D�Ɓ@���̉́i�u�ʒu�v��ꍆ�����Z��N�O���j
�@���i�u�f�`�v�܍������܋�N�j
�@���炷�i�u���^�t�B�W�b�N���v�n���������ܔ��N�����j
�@�X�i�u�ʒu�v��Z�������Z�Z�N�Z���j
�@��ǁi�u�ʒu�v�ꎵ�������܋�N�l���j
�@�J���~��i�u�ʒu�v��܍������ܔ��N�܌��j
�@����i�u�����v���������Z��N�~�j
�@��i�u�����v�㍆�����Z��N�āj
�@�˒I�i�u�A���r���I�v�O�Z�������ܔ��N�����j
�@���i�u�����v��Z�������Z��N�āj
�@�����́i�u���Ɣ�]�v���Z�Z�N����j
�@�A���i�u���㎍�蒟�v���Z���N��ꌎ���j
�@�r�i�u���㎍�蒟�v���Z��N�O�����j
�@���点�邽�߂̎��߂̉́E⍂ɔ��́i�u���㎍�蒟�v��㎵��N�ꌎ���j
���ꂾ���ł���B�k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�̋L�ڂ������Ȃ��̂́A�����������B�����A���̖{�����]�]�������ɂ����ẮB�v���Дŏ����̊��t���{��S����������N�v���A�u���W�Ɋւ��āA���ɂ͏��Ŗ{��⍋�ؖ{�n�D�͂Ȃ��A�{���̓��e�����ς��Ȃ���A�{�̑��肪�ǂ��ł��낤�ƈ�����܂�Ȃ��ƍl����ق������A����ł��A���́w�킪�o�_�E�킪�����x�ɂ��Ă����́i����Ƃ�������A�̗����Ύ��Ƃ̍���́w�����Q���n���X���̓��x�����邪�j�A���̂܂܂̎p�œǂ�ł��炢�����C�����̂Ă���Ȃ������B�{���ƒ��̃e�N�X�g�����Ȃ�A���̌�A��A��̃A���\���W�[���Ɏ��^���ꂽ���A��͂�A���̍�i�́A�����܂邲�Ƃ̂������ŎႢ�ǎ҂ɂ��͂��Ăق��������B�v�i�q���Ƃ����r�A����N�v�s�킪�o�_�E�킪�����k�����V�Łl�t�����W�A�v���ЁA2004�N7��10���A��l�y�[�W�j�Ə����Ă���B �����2���̒����\�\�s�����Q���n���X���̓��t�i1962�j�Ɓs�킪�o�_�E�킪�����t�i1968�j�\�\�͎���W�ƌĂԂׂ����삾�������i�����Ƃ��q�g�����Ɠ���N�v�r�ɏ��e���f�����j�A������2���\�\�s�D�� ���̉́t�́k�����{�l�Ɓk�ʐ��Łl�\�\�����A����ꂪ�u�����܂邲�Ƃ̂������Łv�Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����W�̍ł�����̂������B
�쌴��v�s���Ɏ��@�l�ƕ��w�k��E���l�t��1981�N12��10���A���u���|�[�g����㉺�������Ɋ��s���ꂽ�B�q���Ƃ����r�Ɏ��M�E�o�ł̌o�܂��L����Ă���̂ň����B�u���N�̈ꌎ����O���܂ŁA�����S�ݓX���́u�r�܃R�~���j�e�B�E�J���b�W�v�ɂ����āA�u���Ɏ��E���U�ƕ��w�v�Ƒ肵�ċ��قǂ���������܂����B���̂��߁A���Ɏ��̑S�����ǂݕԂ��A���̐��U�ג������̂ł����A���̇��u�`�������̖{���������������ɂȂ�܂����B�Ƃ����Ă��A����ꂽ���Ԃ̂Ȃ��ł̂����肾�����̂łȂ��Ȃ��Ɉӂ�s�������A����ɁA�����釁���ƂƇ����������ƂƂ͍��{�I�ɈႤ�s�ׂł�����A���̖{�̏�E�����v���Z�Z���́A�܂������̏������ƍl���Ă�����Ă����̂ł��v�i�{���k���l�A��O��y�[�W�j�B�쌴�ɂ͑��Ɏ��֘A�̒���Ƃ��āA�{���̑O�N���s�́s��z ���Ɏ��t�i�V���ЁA1980�j������A�{���̂��ƂɎO���A�P�s�{������B�s��z ���Ɏ��k�V���Łl�t�i�V���ЁA1998�N5��25���j�ɐV���ɕt���ꂽ���Ƃ����ɂ��A�u�}�����[��ގЂ������ƁA���́w��z ���Ɏ��x���ŏ��Ƃ��āA�w���Ɏ��@�l�ƕ��w�x�w���Ɏ��@�����Ɨ����x�w�����邱�Ƃɂ��S�����@�����E���Ɏ��x�A�����Ė{�N�A�w���Ɏ��Ɛ����x�����͏㈲�����B�܂��ق��ɁA�u���Ɏ��ƈ䕚����v�ȂNJ���̃G�b�Z�C���������v�i�q���Ɏ��f��\�N�ɍۂ��r�A�����A����y�[�W�j�̂ł���B�쌴�ɂ͒h��Y�ƍ������̓`�L�^��z�����ꂼ��ɂ��邪�A�����̒��샊�X�g�����������ł��A���ɂ͕ʊi�Ƃ��������Ȃ����݂������B

�쌴��v�s��z ���Ɏ��t�i�V���ЁA1980�N5��10���j�̃W���P�b�g�k��F���Ɏ��A�f�U�C���F�c���T��l�A�s���k11�����Łl�t�i���A1992�N8��25���j�̕\���k�f�U�C���F�c���T��l�A�s���k�V���Łl�t�i���A1998�N5��25���j�̃W���P�b�g�k����F���Ɏ��A����F�V���Б��ꎺ�l�A�쌴��v�s���Ɏ��Ɛ����t�i���A���j�̃W���P�b�g�k�B�e�F�卂���A����F�V���Б��ꎺ�l
�V���ЂŕҏW�S���҂Ƃ��đ��Ɏ��Ɛe���̂��������҂́A�}���ł͑�ꎟ�����Z���܂ő��Ɏ��S�W����|���Ă���A���ɂ̐l�ƍ�i�����ɍœK�̐l�Ԃ̂ЂƂ肾�����B�{������A�����[���ӏ��������B
�@���a��\�O�N�̎l����\���A���Ȃ킿���̓��O�ɁA������Ň��Ɩ��������w���Ɏ��S�W�x�����_���X���犧�s����܂����B�����̑S�Ɛт����̑S�W�ɂ���Ċ��������悤�Ƃ������ɂ̋���ɂ́A���łɎ��ւ̌��ӂ��ł߂��������̂��Ǝv���܂����A���̑S�W�̔��n�̕\���ɂ͒Ó��Ƃ̒߂̒�䂪���Ŕ��������Ă���܂��B�����̉Ƃ̒��ŕ\�����������l�S�W�ȂǁA�ق��ɂ͗Ⴊ�Ȃ��Ǝv���̂ł����A����͑��ɂ̋�����]�ɂ�������̂������ł��B�܂��e���̊����̌��G�ʐ^�ɂ́A���e�A���ƁA�Ìy����Ȃǂ̎ʐ^���g���ׂ��������i�߂��܂������A����ɂ����ɂ̊�]�������Ă��܂����B�i�{���k��l�A�ꎵ�y�[�W�j
�@�k���ɂ̑��n��W�w�ӔN�x�͍��q�m�܂Ȃ��n�����[����l�����̗\��ł͏\��N�O�����Ɋ��s�����\�肾�����̂ł����A���̔N�ɓ�E��Z�������u�����A���̂��ߏ��[��̎R�肪�������Ă���������\�����A���J��ɒǂ��āA���s�̎��������щ��тɂȂ��Ă��܂��܂����B�k�c�c�l�^�Z����\�ܓ��t�Łw�ӔN�x�͊��s����܂����B�e���A�A���J�b�g�A�{���ɂ͔���̖ؒY�����A�\���ɂ͔��̋ǎ����g�����ґ�Ȗ{�ł����A����͎O�}���[�k��o�����ܕ��ɔłł́A�����쏑�@�l����o���ꂽ���엲�O����̌���Ńv���[�X�g�u���Ђ��������߂āv�k�������A�w�������������߂āx�l�̑��{�ɂ͂������C�ɂ����Ă��āA���̒ʂ�ɑ����Ă����悤������]�����̂ł��B���ł̈�������͌ܕS���炢�������悤�ł����A�V�l�̏����o�łƂ��Ă��A�����ł��������ꂽ�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i���O�A����`���O�y�[�W�j
�@�w���������x�͐��̓�\�N�\����\�ܓ��ɒ}�����[���犧�s����܂������A�����͏ēy�Ɖ�����������Ȃ��A�}�����[�В��Óc��̋����̐M�B�̈ɓ߂ň������Ă��܂��B�i�{���k���l�A����y�[�W�j
�@�w���������x���������Ă܂��Ȃ��̎����Z���[�X���玵�������ɂ����āA�b�{�s�͂a29��S�@�ɂ���P���A�s�̎������Ď����A�Ό��Ƃ��S�Ă��܂����B�����A���A���É��A�_�ˁA���l�Ȃǂ̑�s�s�͂��łɏēy�Ɖ����A�a29�̍U���ڕW�͘Z�����{����n���̒����s�s�Ɉڂ�܂����B�k�c�c�l���̂悤�ȏ�̂Ȃ��ő��ɂ́A�y���Ń��[���A�ɖ������w���������x��S���������p���A���\�̐��E�ɒ������Ă����̂ł��B�^��P���Ɏ����o�����w���������x�̌��e�́A�������ɋ킯�������R���ɑ�����A���R�͒}�����[�ɂ����͂��܂����B���̏������M�B�̈ɓ߂ň�����ꂽ���Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł��B�i���O�A��y�[�W�j
�@�����A���̎��ӂɂ����l�̂Ȃ��ŁA�������ɂł����Ɏ��̎���\�����Ă����̂́A�}�����[�В��Óc�莁�ЂƂ肾�����Ǝv���܂��B�Óc��Ƒ��Ɏ��Ƃ̂��Ƃɂ��Ắw��z ���Ɏ��x�ŏ����܂������炱���ł͏Ȃ��܂����A�䕚���̕\���������A�Óc����Ƒ��ɂ���͔��t�̗F�ł����B�^�u�l�Ԏ��i�v�́A�}�����[�̎G���w�W�]�x�ɘA�ڂ���܂����B�k�c�c�l�O�������ɕM���N���A�܌��\����Ɋ��������̂ł����A���ւ̌X�̂Ȃ��ŁA���Ɏ��͍Ō�̗͂��ӂ肵�ڂ��Ă��̍�i�ɂƂ�g�݁A�Ō�̂��̂��������ŔR�Ă������̂ł��B���t�̗F�Óc��ւ́A�Ō���S�m�͂Ȃނ��n�Ƃ��āB�i���O�A����y�[�W�j
�g�����͖{���̗��N�A�쌴���s��㵂̐l�\�\��z�̌Óc��t�i���Y�t�H�A1982�N10��25���j���������Ă���i�쌴�́s��z ���Ɏ��t�͌Óc��ɏœ_�Ă��͂��q��㵂̐l�r�Ƒ肵�Ă���A�Óc����z�����s��㵂̐l�t�̏����͂���P���Ă���j�B�g���Ɩ쌴�͂��ĂƂ��ɒ}�����[�ɋΖ����Ă������A�c�O�Ȃ����l�ɂ͑���ɂ��ď��������͂��Ȃ��i���Ȃ��Ƃ��g���ɂ͂Ȃ��j�A�����̑����Ɋւ���o�܂��킩��Ȃ��B�����A�Óc���n�Ƃ����}�����[�ł��Ȃ��i���R���j�A�쌴���s�Ηz�t����|�����V���Ђł��Ȃ����Y�t�H���瓯�������s����ɂ�����A�����ł��}���F���o�����߂ɋg���������������Ă����A�ƍl���邱�Ƃ͋�����邾�낤�B����͂���ł����Ƃ��āA�{���s���Ɏ��@�l�ƕ��w�k��E���l�t���g���������ł��闝�R�͂͂����肵�Ȃ��B��ꎟ���Ɏ��S�W�̑������g�����ɂ����̂������Ƃ��������肪������\����������̂́A�g�������ɂ̕��w�ɑ傢�Ȃ鋤��������Ă������͕s���ł���B�\�\�{���q���N���r�́u���a��\��N�i���l���j�@�O�\��v�Ɂu�����\���A��\�l���w�V�v���x�n�����Ɂu���v�\�B�v�i�k���l�A����y�[�W�j�Ƃ���B�g���͓�����14���s�V�v���t�̑�2���i���N9���j�Ɂq�s�k�r�i�������сE2�j�Ɓq�������r�i�������сE3�j�\���Ă��邩��A���R�n�����i�̑��ɂ́q���r�j�͖ڂɂ��Ă��邱�Ƃ��낤�B���ɂƋg���̓����㐫������������B��̐ړ_�ł���\�\�B�����łƂ����킯�ł͂Ȃ����A�ȉ��ł͋g���ƔŌ��̃��u���|�[�g�̊W�𒆐S�Ɍ������B
�g����1983�N5���A���u���|�[�g�����s����s���j�ƎЉ�t�i��2���j�Ɏ��сq�H���r�i�J�E18�j���Ă���B���̑O�N�A1982�N12��3���̓��L�Ɂu�ߌ�x���A���u���|�[�g�̂g�Ɖ�A�G���u���j�ƎЉ�v�Ɏ��𗊂܂��B�ǂ����A�琴��̈ӂ�����ł̂��Ƃ炵���B�v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A��l��y�[�W�j�Ƃ����o�܂ň˗����ꂽ��i�ł���i�u�g�v�͓����̕ҏW�l���낤���A�s�ځj�B�Ō��̊�����Ѓ��u���|�[�g�́A�E�B�L�y�f�B�A�ɂ��u1980�N4������1998�N5���܂Ŋ��������Z�]���O���[�v�̏o�ŎЁv�ŁA�u�琴��ɂ�錨���ꂪ�傫���A��ɂ�鐼���S�ݓX�E�p���R�Ȃǂ̌o�c���X�������ƂŁA�Z�]�����p�قƕ���1998�N8���k�}�}�l�ɏo�Ŏ��Ƃ������v�Ƃ���B�܂�A�@�s���Ɏ��@�l�ƕ��w�k��E���l�t�̑����A�A�s��㵂̐l�\�\��z�̌Óc��t�̑����i���u���|�[�g�̈Č��ł͂Ȃ����j�A�B�s���j�ƎЉ�t�ւ̎��M�˗��A�����ցq�H���r���f�ځA�Ƃ�������ɂȂ�B�{���̑����̈˗������҂̖쌴�A�{���̕ҏW�ҁi�q���Ƃ����r�ɂ͌��y���Ȃ��j�A�i�Ō����u���|�[�g�̎G���́j�ҏW�l�u�g�v�i�H�j�A�Z�]���O���[�v��\�̒�A�̒N�̔��Ă��͂킩��Ȃ��B

�쌴��v�s���Ɏ��@�l�ƕ��w�k��E���l�t�i���u���|�[�g�A1981�N12��10���j�̖{���ƃW���P�b�g�A�����̉����V�Łs���Ɏ� ���U�ƕ��w�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A1998�N5��21���j�̃W���P�b�g�k�f�U�C���F���c�i�l
�{���̎d�l�͈ꔪ���~��~�����[�g���E�k��l�F���Z�y�[�W�A�k���l�F��O���y�[�W�E���������E���Ёm�����̂�n�i�����{�ŕ\���ƌ��Ԃ��̑O�������ɕ��\�܃~���قnjЂ�h���Đڒ���������@�j�E�W���P�b�g�B���t�Ɂu����\�\�g���@���v�ƃN���W�b�g������B�{���͋g������|�������Ђ̂Ȃ��ŁA�����炭�B��̏㉺���{�ł���B�ߔN�̃u�b�N�f�U�C���i�Ƃ�킯���ɖ{�̂���j�ł́A�㉺�Z�b�g�ł��邱�Ƃ��������āA������ׂ��Ƃ��ɕ\�����ꖇ�̊G�ɂȂ�悤�Ƀf�U�C��������A�Ӑ}�I�ɑ薼�⒘�Җ��̔z�u��ς��āi���̂�T�C�Y�͓����܂܁j���C�A�E�g�����肵�āA����̘A���ƍ��ق�ł��o�����Ƃ������B�g�����{���ō̗p�����̂́A�㊪�ł͐A�����ł͐ԁi����������Ȃ�W���A������u�Ȃ܁m�A�A�n�łȂ��v���F�j���X�~������⍲����F�Ƃ���A�Ƃ����~�j�}���v�������B
�c��m�s���{�̌��㏬���t�i�W�p�ЁA1980�j�Ɓs���{�̋ߑ㏬���t�i���A1988�j�̏Љ�Łu�\���z�̐ԂƐ̐F�́A�g���̎��W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�����E�ĔŁi����R�c�A1980�j�Ɠ������ꂾ�B�v�Ə��������i�q�g�����̑�����i�i12�j�r�j�A��������Ă��킩��悤�ɋg���͓����g�݂ő�������ꍇ�A�ԁ��Ƃ����W�J�����������B�������A�����r�Y�̎��_�W�O����̃N���X�́A���ԁ����ł���A�c������́s���Ɣ�]�t�V���[�Y�̑S���A�`�`�d�̃N���X�́A�F����F���ΐF�����F���b���F�������B����A�Ζ���̒}�����[�ɂ�����O���l�̑S�W�̃N���X�̐F�́A�s���e���O�Y�S�W�k�S10���l�t�i1971�`73�j���ԁA�s�Z�{
�{�V�����S�W�k�S14���i15���j�l�t�i1973�`77�j���A�s�����Y�S�W�k�S15���l�t�i1975�`78�j�����A���Ȃ킿�ԁ������ŁA�����̎O�����c���̂`�`�d�̃V���[�Y�̌܍��Ƃ͈قȂ�B�����Ƃ��O���l�̑S�W�̃��C���J���[�́A���ꂼ��̎��l�̈�ۂ�앗�̂����炵�ނ�Ƃ���Łi���e�̐ԁA�{�V�̐A�����̉��ȊO���z���ł��邾�낤���j�A���s�̏��Ԃɂ��I�����������킯�ł͂Ȃ��낤�B�܂�O���l�̑S�W�ł͂Ȃ��A����V���[�Y�⏉���E�Ĕł̑g�ݍ��킹�A�O�����`�`�d�̃V���[�Y�̐F�ʌv�悪�Q�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ŏ㊪�i��͂܂Łj�E�����i��Z�͂���j�̖ڎ��̍��ڂ����Ă݂悤�i�ׂ������Ƃ����A�㊪�́q�ڎ��r�y�[�W���̂ɂ̓m���u�����ł��Ă���A�����̂���ɂ͂Ȃ��j�B�Ȃ��A�߂́i�@�j�ɓ���Ĕԍ����ȗ����A�^�ŋ��ǂ����B
���́@�̋��Ɛ��Ɓi�ߋъҋ��^�Ƌ��Ǖ��^�Ó��Ƒf�`�^�u�v�Џo�v�̐��E�^�O�O���Z�̎O�N�ԁ^�Ìy�l�C���j
���́@�A��Ɯf�r�i���Ə��ЂƐS�������^�@�^���Ǝ���^��Ƃւ̏o���^���U�̒n���j
��O�́@�l�Ԏ��i�i�p�r�i�[�����Ł^�w�ӔN�x�Ɓw���\�̜f�r�x�^���_�a�@�Ɛ����j
��l�́@��]�ƍĐ��i����S���Ɣj���^�����Ɛ�]�̒�Ł^�]�@�j
��́@����Ɣ����i����^�u�̒��v�Ɓu�x�ԕS�i�v�^�b�{��蒬����j
��Z�́@���}���̐��E�i�O��]���^�u�퍞�ݑi�ցv�Ɓu���ꃁ���X�v�^�Ⴂ����ւ̈��^�u���̌����v�Ɓu���̕ւ�v�^���ɂ��ā^�u�V�n�����b�g�v�j
�掵�́@���w�ւ̒����i��Ȑ펞���Ł^�u���`�Ɣ��v�^�u�E��b�����v�^�w�V�ߏ������x�^�u�Ìy�v�^�u�ɕʁv�^�w���������x�j
�攪�́@��]�Ɛ�]�i�w�p���h���̙��x�^�ێ�h�錾�^�u�~�̉ԉv�Ɓu�t�̌͗t�v�j
���́@���Ɗv���i���V�Ȗ����h�m���x���^���n�^�u�Ηz�v�^�F�ӂ̍K���j
��\�́@���ւ̌X�i�u�l�Ԏ��i�v�^�u�@���䕷�v�Ɓu�O�b�h�E�o�C�v�^���̎��j
���e���ς邩����A�㊪���ʼn������Ԃł��邱�Ƃ̕K�R���͓ǂ݂Ƃ�Ȃ��B�܂�A�㉺���̐F���t�ł����Ă��A�����Ė��Ȃ��B�����ė��R��������A�\���̎��̐F�i�㉺���Ƃ��n�̓������ł���j�Ƃ̐e�a���㊪�ŗD�悵���A�Ƃ������Ƃ��낾�낤���B����𐄂��i�߂čl����A�����̕\����Ԍn�̎��ɂ��Ă��ǂ������͂������A�g���͂����܂ł��Ȃ������B
�k�NjL�l
�{���ɂ́A�����ɉ��M�������ĉ��肵���ꊪ�{�s���Ɏ� ���U�ƕ��w�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A1998�N5��21���j������B�W���P�b�g�̃f�U�C���͑��c�i�B�V���������͓����̌������\���̃^�C�g���ɖ߂������̂��B�e�͔��ɂ͐V���Ɏʐ^���f�ڂ���A�{���͌h�̂���̂ɕύX���ꂽ�i�������\�𗣂ꂽ���D�ł���j�B�q���Ƃ����r�ɂ���悤�ɁA���Ŋ��s��Ɂu���Ɏ��̑S��i�����x���ǂݕԂ��A������[�߁A�܂��A�����̎Q�l�����ɖڂ�ʂ����肵�đ��Ɏ��̎��l���ɏA���Ă̍l�@���d�˂Ă����k�c�c�l���ʂ��\���ɐ��荞�݁A�\���N�O�̒����啝�ɉ��ς����v�i�����A�l�Z���y�[�W�j���̂ł���B�Ȃ��q���Ƃ����r�����ł������L�Ɂu�{���͈�㔪��N��A���u���|�[�g��芧�s���ꂽ���̂ɉ��M�����������̂ł��B�^�i����w���Ɏ��@�l�ƕ��w�x��E���j�v�i���O�A�k�l�Z��y�[�W�l�j�Ƃ��邪�A�{�������̔��s��1981�N12��10��������A���s�N�́u��㔪��N�v�͌�A�ł���B
���˓������s�l�Ȃ������t�i�}�����[�A1983�N10��25���j�͋g���������ł͒������v���́i������A�c�ɍג������v�́j��\���܂��A���Ȃ킿�W���P�b�g��\���A����ɖ{���ɗp���Ă���B���̋L�����邩����A�B��̎g�p��ł���B�v���͎̂�ɔN���▼�h�Ȃǂ̒Z���̈�����ɗp�����A�����̖{�����̂̎嗬�������̂ł��邱�Ƃ͉��߂ďq�ׂ�܂ł��Ȃ��B�g���͏����E���Җ��E�o�ŎЖ��Ȃǂɂ��A��{�I�ɖ����̂�I��ł���i����\���܂��ł͓������������p�����j�B�{���̑v���͈̂Ӑ}�I�Ȃ��̂ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���āA�{���̖ڎ��ɂ�
�@�t�����l�@�c���r�q 3
�̂悤�ɁA�薼�ƑΏۂƂȂ����l���A�y�[�W�m���u�����L����Ă���̂ɑ��āA�{���̌��o���́u�t�����l�v�����ɂȂ��Ă���B�ȉ��A������u�t�����l�i�c���r�q�j�v�Ƃ����ӂ��ɕ\�L���āA�{���̓��e�Љ�ɑウ��B
�t�����l�i�c���r�q�j�A�̏��̐l�i�ԒJ�O�j�A�Ǘ������������L�i��������j�A�����̌a�i�������j�A�����l�i�������j�A�̉��i���{���Y�j�A��̔����i�s��[�}�j�A�������{�i���������j�A���l�i���q�����j�A�Ηz����q�i���c�Îq�E���q�j�A�u�����ӂ���v�̂ЂƂ�i���{���O�j�A�l�N�X�g�i�r�������j�A�Ԃ��l�i�r�������j�A����ɂႭ�_�C�G�b�g�i���s��j�A�i���̏��S�i�~�n���q�j�A����q�̕فi�g��K���Y�j�A�卪���낵�i�������j�A��M�̐l�i�_�ߎs�q�j�A�����̏I��i�_�ߎs�q�j�A���߂̐l�i���њF�Áj�A������̑��蕨�i���Y�N���j�A���Ⴕ��Ȕw���i�k������j�A�k���ɑz���l�i�y��P���j�A��ڂ̗J���i���g�͌������j�A�g�����N�̒��i�e�c��v�j�A�h���l�엿���i�b���j�A���O�̐l�i���їE�j�A������i����[�L���j�A�����\�t�g�i�������j�A�ꐶ�̕��i�O��ꐶ�j�A�J�̔������i���c�Ԑ��j�A���ڂ̐��m��H�i�����G�X�j�A�Ύq���߂łƂ��i�x�m�Ύq�j�A�Ύq�����܂������i�x�m�Ύq�j�A����N���i��Ďq�j�A�₵���ؗ�i���g�͌����j�A���ω��i�F����j
�������炾�Ƃ킩��ɂ������A�Ǔ����̐�߂銄���������Ƃ������i�{�����t�̑Ό��y�[�W�ɂ́u�����o�̋L�ڂ̂Ȃ����͂́u�����܁v�ɘA�ځi81�E4�`83�E4�j�������̂ł���B�v�ƒ��L�����邪�A�A�ڎ��̌���́u�Y�ꂦ�ʐl�E�l�v�������j�B���˓����`��34�l�̏ё����т̂悤�ɂ�������ƕ����߈��A���̂Ȃ��ɂ��邵���Ƃ�Ƃ��������́A�������ɓ��������ł͕\�킵�ɂ����낤�B�v���̂��鏊�Ȃ��B�Ȃ��A���҂�1973�N�ɓ��x���Đ��˓��⒮�ƂȂ������A�{���̒��Җ��͐��˓������ł���B
�@�u���̍��͂˂��A�ڂ��ނ�ƁA���炤�疲���茩�Ă˂��A�̂̂��Ƃ⍡�̂��Ƃ���������ɂȂ��āA���������m���n�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�ŋߌ������̒��ŁA�ƂĂ��C�ɂ�������̂�����܂��ĂˁB�܂�ŏ����̂悤�ŁA����͒P�Ȃ鎩���̖����A���邢�͂����ǂ����̂��Ƃ����ɏo�Ă����̂��킩��Ȃ��Ȃ�܂��ĂˁB�n�ӕ����Y����ɁA���݁A����ȏ����ǂ��Ƃ��邩�A�����A�o�����Ȃ��Ȃ�A�N���̏����ɂ���Ȃ̂����������ǂ�������ׂĂ���Ȃ����Ɨ���ł����ł����ˁB�n�ӂ�����h�C�c�܂Ŗ₢���킹�Ă��ꂽ���킩��Ȃ��Ƃ����B����͂����Ȃ�ł��v
�@���̘b�̍��Ԃ�ႂ��܂�A���t���݂̂��݁A���������ꂵ�݁Aႂ��Ƃ��Ă���܂��b���Â���Ƃ�����Ȃ̂ŁA���̘b�͂��炷��Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B����ł������ĉ��͘b���~�߂悤�Ƃ͂����Aႂ̏���������ԁA���ɍ��C�悭�P���Ƃ܂�̂�҂��Ă���A�܂������ނ�ɘb�̂Â��ɖ߂�Ƃ�����ł������B
�@�u�ǂ������킩��Ȃ����A�ꏊ�̓��[���b�p�̂ǂ����̐��ł��B�A�����J�ł͂Ȃ��ȁA���[���b�p���ĕ��i�Ȃ�ł��B�킢�̍��ԂŁA�Ԉ����������ł��B���������̑O���僒��ւ̗���Ȃ��Ă���킯�ł��B�A���y���ł��������e���ȈԈ����Ȃ�ł��B
�@�����ŁA��l���p�����܂��ďo�Ă���ƁA���̓x�ɓ����Łw�l�N�X�g�x�Ƌ��ԁB����Ǝ��̕����������Ă����B�܂����炭���ďo�Ă���ƁA�w�l�N�X�g�x�Ƌ��ԁB���̂�����B
�@�������������Ȃ�ł��Ȃ��B�����āA���悢��A�{�l�̔ԂɂȂ��ē����Ă����B���ő҂��Ă��鏗������Ȃ�A���̒j���C�₵���Ⴄ��ł��v
�@�����ł܂��A�������P���݂��͂��܂�A���͂��Ƃ��Ƃ��点���B���͉��̌ċz�������ł��x�߂悤�Ǝv���Ă������B
�@�u�܂�A���̕����́A�Ԉ��w������܂艻���݂����ɂ݂��Ƃ��Ȃ������̂ŁA�т����肵�ċC�₵����ł����v
�@�u���₢��v
�@���ׂ͍����U�����B
�@�u��������ł��B�܂肻�̏����A���̕����̖��������킯�Ȃ�ł��B���������������O�ɂ���ȁB����ŕ������C�₷���ł��B�b�͂����������̂Ȃ�ł����A�ǂ��ł��A�����݂����ł��傤�v
�@�u�ق�ƂɁA���[�p�b�T���������̒Z�я����݂����ł��ˁv
�@�u���Ȃ��A�����ǂ����œǂ��Ƃ�����܂��B�Ȃ��c�c����Ă��ƁA����͂���ς�A�ڂ��̖��̒��ŏ������n�삩�ȁc�c�ƂȂ�ƁA��ςȖ��Z�т��v
�@���������ĉ��͖{���ɓ��ӂ����ɏ�ꂽ�B
�i�q�l�N�X�g�r�A�{���A���Z�`�����y�[�W�j
�r�������͏����Ƃ�����A�b�����܂��͓̂�����O�����A������f�����˓��̕M���݂��Ƃ��i�����̂ق��ɂ��A�����ɂ͖{���̂�����Ƃ���ŐG��Ă���j�B�{���̎d�l�͈ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��l�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�����E�W���P�b�g�B�W���P�b�g�̐}���͉ԁi��j�Ɛ���i���j�����A��҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�܂��A�{�����H�̃��`�[�t��ʼn�̂悤�ɏ������āA�����ō����Ă���B�W�J�~�ꂳ��ɂ��A���F�̃T���v�����F�`�b�v�ł͂Ȃ��A���ۂ̈�����̐�[�������肵���Ƃ�������A���̗ΐF���g�����ǂ����Ō����Ď���Ă��������C�ɓ��肩������Ȃ��B
�s�l�Ȃ������t�ɂ́A�O�H���Y����ɂ��铯�l���s���w�ҁt�œ��y�Ƃ��ĎR����q�ƌ�������i�l�y�[�W�Q�Ɓj�A�Ƃ���B�R��͋g���Ƃ����̂������ҏW�҂ɂ��ď����ƁB���c�唪�s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�N7��1���j�Ɍ�����u�k�c�c�l�܂���ɏZ��ł������̎d���ŁA���N�������ɂ̒��́w��������˂ĎO�痢�x�̑}�G�̈˗��ɗ����A�����n���Ђ̎R����q�Ƃ��������ҏW�҂����܂����B���̐l���ɂ߂ă��j�[�N�Ȑl���ŁA�����悭���̉Ƃɔ��܂荞��ł����g�����Ɠ��l�A���т��щƂɗV�тɗ��Ă��܂����B�^�ޏ��̂������ŁA���Z��N�A�A���r�A���i�C�g�Z���̌��G�}�G��`�����Ă��炢�܂����v�i�����A�Z���y�[�W�j�́A�g�����q�˒�ɂār�ŐG�ꂽ�u�c�v�̑}�G�̎d���A��[�N���E��㏲��s�A���r�A���E�i�C�g�t�i�����n���ЁA1960�`61�j�̂悤���B
�{���ɂ͂��Ƃ������Ȃ��A�g�����ւ̌��y���Ȃ����A���˓��͋g�����ҏW���Ă��������́s�����܁t�i1972�N4���A��36���j�Ɂq�������Ǝ��`�̊ԁr�\�\�s��w�̗F�t�ɘA�ڂ��Ă������`�����s���������t���s���˓�������i�W�k��8���l�t�i�}�����[�A1972�N3��15���j�Ɏ��^���ď��߂Č�������ɍۂ��ď����ꂽ�\�\����e���Ă��邩��A�ʎ��͂��������B�s���������t�́A���˓�������i�W�̔ł𗬗p���āA�}�����[����1974�N1��5���ɒP�s�{�Ƃ��Ċ��s����Ă��邪�A�����i���_�c�O�̎ʐ^���O���t�B�b�N���������ԂƎ��̃W���P�b�g���j�̃N���W�b�g���Ȃ��A����̎�ɂȂ���̂��s���B������ɂ��Ă��A�}���̎Г������ł͂����Ă��A�g�����̑����ł͂Ȃ��B

�{���ɂ͕��ɔł�����B�����ܕ��ɂ�1985�N12��4���A�ꋓ20�_�őn������1�_�ł���B�����́u�J�o�[����v�͍����a�q�B���t�Ɂu����� �������v�Ƃ���A�n�������̓W���P�b�g�̃f�U�C�������삪��|�����悤���B�g�������u�b�N�f�U�C�i�[�ƌĂт������̂́A���ɖ{�̃W���P�b�g���f�U�C�����Ă��Ȃ��_�����������B�Ñ��̒}�����[�̕��ɂ������Ă��Ȃ��̂�����i�����ܕ��ɂ����ׂČ����킯�ł͂Ȃ����A���Ԃ����낤�j�A�g�������Ђ̕��ɖ{�̃W���P�b�g���f�U�C���������Ƃ͂Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���ɁA�g���������̊ےJ�ˈ��s�݂݂Â��̖��t�̒������ɔł̃W���P�b�g�f�U�C���͘a�c���ł���B�g���������̖{�̂́A�`�T���t�����X���̎��W�A�l�Z���W���P�b�g���̕��|���A�`�T���Ȃ����e���n������̌l�S�W�A�̎O�ɏW��ł��悤�B�����̕\���܂��̂قƂ�ǂ����������ƃG���u�����̂悤�ȃJ�b�g�i�������͖������������j�ō\������Ă���A���ꂪ�X�~�Ɠ��F�̂�������x�^�ň������Ă��邱�Ƃ͓��M�����B�A�~�t�Z���̐��Ŏw��ɂ��|�����킹���̂��g��Ȃ��A���ɂ�鎚�Ɖ�̓ʔň���B���ꂪ�g���������̐g�ゾ�B����������A�g�����̑�����i�͖��������ɂ�銈�ň�����̂��̂ł���B���ꂪ�P���ɂ�����ƌ��O���ꂽ�Ƃ��g�����̂����̂��A�@�B����g�����ɔ��Ƃ͈قȂ�p���ɏ����E���Җ���J�b�g�����������ӂ�\��u�\���Ӂv�̎�@�������B1980�N��A�W���P�b�g�͂������A�{�����ʐA�g�ŁE���Łi�I�t�Z�b�g�j������嗬�ƂȂ������ɖ{�ɋg����������낤�Ƃ��Ȃ������̂��A�����l����Γ��R�̂��Ƃ������B���Ȃ݂ɁA���W���܂ދg�����̖M���ɂ��P�s�{�̖{���͂��ׂĊ��ň���ł���B�s�g�����S���W�t�����ň���łȂ���Ȃ�Ȃ������̂͂��̂��߂��B
�k2014�N3��31���NjL�l
�a�c���s��������k�����t�u�b�N�X�l�t�i�����ЁA2006�N12��20���j�́q���ɂ̃J���@�[�r�̏͂ɂ�������B�u���ɂ̎d�������鎞�̓J���@�[������S�����܂��B�\���͓���f�U�C�������A���ɖ{�ɂ͌��Ԃ��͂���܂���B���͖{���p�����g���āA�f�U�C�������ʂ̂��̂ł��B�ڂ��͕��ɖ{�̎d���������������Ă��܂����A���ɂ̏ꍇ�͑���������Ƃ͌����ɂ����āA�J���@�[��`���Ƃ��J���@�[���f�U�C������Ƃ������Ă܂��B�k�c�c�l�J���@�[�A�\���A���Ԃ��A���A�Ƃ����\���܂�肷�ׂĂ��l����̂��������Ƃ���Ȃ�A���ꂩ��͂͂����킯�ł�����v�i�����A��㎵�y�[�W�j�B���ɂ̃W���P�b�g�f�U�C���͑����ɂ��炸�\�\��\�I�ȃC���X�g���[�^�[���O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�̌��������ɁA�����͂�����B�����āA�ےJ�ˈ�s�݂݂Â��̖��t���v�킹�鎟�̉ӏ��B�u�P�s�{�̑������ق��̐l������Ă���̂ɁA���ɂ̈˗����ڂ��̕��ɂ��邱�Ƃ�����܂��B����͋C�������܂��ˁB�ڂ��͂Ȃ�ׂ��P�s�{��S�������f�U�C�i�[�ɕ��ɂ����肢����Ƃ����ł���A�ƌ����悤�ɂ��Ă��܂��B�k�c�c�l�C���[�W�����ꂳ��Ă�������������낤�Ƃ����̂����R���̈�ł��B���R���̓�́A���̃f�U�C�i�[���ʔ����Ȃ���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�����̎d�����C�ɓ����Ȃ���������ق��̐l�ɗ��̂��ȁA�Ǝv����������Ȃ�����Ȃ��ł����v�i�����A��Z�l�y�[�W�j�B
�����Ƌg�����́A���ɖ{�̃W���P�b�g�f�U�C�����킪�̕��ɂ��炸�Ǝv���Ă����ӂ�������B�s�l�Ȃ������t��s�݂݂Â��̖��t�����������A����͋g���f��̕��ɉ������l���c���F�s�M��Ɠ]���t�i�����܊w�|���ɂł͑���̂����s�M��Ɠ]���E���㌒���t�Ɖ���j�Ȃǂ�����ƁA�u���ɂ̃W���P�b�g�͕ʂ̐l�Ɂv�ƌ��߂Ă����̂ł͂Ȃ����B�a�c�̎w�E�ɂ���悤�ɁA�����ƂƂ��Ęr��U���悤���Ȃ��̂ɉ����āA�ʐA���I�t�Z�b�g�Ƃ����f�U�C����������������ɍ���Ȃ������̂��B���ώɂ���I���W�i�q���㎍�l�R���N�V�����r���j�̊��̒�Ă����������̂́A�{�����ʐA���I�t�Z�b�g������˂��A�Ǝ��^��f�����|���ŔӔN�̋g�����畷�������Ƃ�����B
�q���㎍�l�R���N�V�����r�͏o�ňē��s�w�Y�o�� ���ώɂ̖{�t�i1990�N�H�j��e�폑�����Q�Ƃ���ƁA1989�N����1992�N�ɂ����đS10�������s���ꂽ�B���Җ��Ə�����������B�c������s�O���̊D�t�A���m�s���̒�`�t�A�^���́s�Ԃ���܂Łt�A���Ƃ��O�狛�s�}�C���h�E�Z�u�� ���̑��t�A���c�O�s����t�A�剪�M�s�a���Ձt�A�r��m���s���N���v�����O�t�A���Y���P�s����20�t�A��ˎ闝�s�����X�[���C��сt�A�g�������s�����̗[��A��p�b��t�B
�c������s���Ɣ�]�d�t�i�v���ЁA1978�N10��15���j�́A�q���r8�сA�q�G�T�r9�сA�q�G�U�r10�сA�q�G�V�r12�сA�q�Βk�r3�сA��5�����琬��B�Ȃɂ�[���Ă��A�ѓ��k��Ɠc���̑Βk�q�]�Z�Ƃ��Ă̕��w�r�i���o�́s�����C�J�t1973�N5�����j�́u���㎍�l�����v�Ƃ�����߂Ɍ�����g�����]��ǂ܂˂Ȃ�Ȃ��i�c�����g���̐l���Ɍ��y�����قƂ�ǗB��̕������j�B�s�r�n�t�O���[�v�̐l�����U�ɑ����āA�c�����ѓ������́s�k�t�ɘb���U��B
�c���@���Ƃ͔ѓ��̃O���[�v���B
�ѓ��@�܂��g���Ȃ�Ă̂́A�����E�l�ł��ˁB
�c���@�����E�l���ˁB����͂�͂�R�����ˁB�̂̌R�����Ă̂͑�ςȂ̂�B�����炿���Əd���ɂȂ��Ă�ł��傤�B����͋C���̂���l��B
�ѓ��@�X�s���b�g���邵�ˁB
�c���@���������ˁB
�ѓ��@���������l�������������Ă����B�w��͂Ȃ����ǁB
�c���@�����Ă��܂������̊w��ȂA�����{��w�₾����ˁB�鍑��w���o�Ă�ȏ�͑ʖڂȂ���B���Ȃ��͋�������āA�������c����w�֓��蒼���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�i�j
�ѓ��@�g������Ă͍̂ō��ɓ����l����Ȃ����ȁB�����v�z�_���͏����Ȃ����ǂ��B
�c���@����A�p���������āA�����Ȃ��������B�����Ƃꂿ�Ⴄ���́B���ꂩ��@�������ł���B�@�D���B
�ѓ��@�悵�A�����ňڂ낤�B�M�͂ǂ��ł����B
�c���@�剪���A����͂������ǂˁA��������������B�i�{���A�l�`�܃y�[�W�j
�ѓ����g�͂Ƃ������A��c�G�����s�ɐG��Ă��Ȃ��̂́A�c�������̂��ƓD����ԂɊׂ����i���ƂɂȂ��Ă���j���߂��B�Ƃ��ɁA�c���́u�g�����R�����v�́s�T�t�����E�݁t�̍������܂̑I�]�q�ؕ|�����������l�r�ɂ��o�Ă���B�S���������B
�@�g�����́A�ڂ����،h���鎍�l�ł���B�،h�Ƃ��������A�ؕ|�ɋ߂��B�����m�푈�̂͂��܂�O����A�ނ͒鍑���R�̋S�R���ŁA�n�̌P��ɂ����Ă̓x�e�����������Ƃ����B�ڂ��͔n�������ɊC�R�ɓ������̂����A�ނ̎��I���E�̌����ɂ́A�n�������Ă���B���Ȃ킿�A�ނ̎��̃p����q�͔n�Ȃ̂��B�ЂƂނ����O�A�_�c���쒬�Ɂu�f�~�A���v�Ƃ����i���X�������āA�����̃}�_�����n�Ɏ��Ă��āA���̖Ĕn���A�ނƂƂ��ɏܖ��������Ƃ��������B�ނ��R�[�q�[�����݂Ȃ���A�\�ܕ����蒭�߂������Ȃ̂����A�ޏ��̃G���X�ɂ����Ƃ肵�����Ƃ��������B�n�Ƃ����Ă��A�n�Â�̂��Ƃł͂Ȃ��B���̓��̂Ɛ��_�̉C���I�ȓ������A�n�̃{�f�B�̂悤�ɃG���`�b�N�Ȃ̂��B�h�K���`���n�Ȃ̂ł���B
�@���ƃG���X�̓��Ȃ�W���A�ނقǓ����I�m�A�A�A�n�ɋߑ���{��őn���������l���A�ڂ��͂ق��ɒm��Ȃ��B�ڂ����A�ނ̎��I���E�Ɉؕ|���������̂́A���̂��߂ł���B�i�s���㎍�蒟�t1977�N2�����A����y�[�W�j�B
�g���͂�قnjR�������S�O�������炵���A�V���ɏ��������z�i�q����̖�r�j�ł߂��炵�����_���Ă���B�u����k��f�c�����̖`���`�u�n�̌P��ɂ����Ă̓x�e�����������Ƃ����c�c�v�l��ǂ�ŁA啞�R�Ƃ����B�ވꗬ�̃��[���A�̂���Ȃ̂����m��Ȃ����A���͂��̍��A�ꓙ���ł������B�S�R���Ƃ����C���[�W�͉f��q�n����i���Ɂr�̃A�[�l�X�g�E�{�[�O�i�C���ł��낤�B���͏_��ȏ��W���ł���A�d���n�Ƃ͒S�����A�m�n�����܂������Ȃ������ł������B���傹�̂悤�ȕ����ɂ́A�������ւ̓]���ɂ��]���̉^�����҂��Ă����B���͍ϏB���Ŕs���m�����̂��B���ɂ����|�c�_���ޒ��ł���\�\���̂悤�Ȃ悯���Ȃ��Ƃ����̂œ��R���̈��A�͂��܂��Ȃ������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l�O�y�[�W�j�B�����r�Y����u�����ȃ^�C�v�k�̐l�ԁl�́H�v�Ɩ���āA�u��Ɏキ�A���ɋ����l�B�������g�A���m����A�R������������āA���������l��ɔ��R���Ă�������ł��v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��O���y�[�W�j�Ɠ����Ă���g���ɂ��Ă݂�A���������l��Ɍ�����̂͌�Ɩւ�Ƃ������S�����낤�B�u���̐l�̂܂��Ŗő��Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����ْ����o���邱�Ƃ͂��������A������b���͂��߂�܂ł̂��ƂŁA���ɏ��܂������Γ��ɋ����Ă�������i�Ɠ����Ɋ����������j�̂�����A����ƑΖʂ��Ă��Ă̋��䍂�ȑԓx�́A�Ƃ�̂��Ƃ���̂��g���̊�������Ƃ��낾�����B�������̍����ɐG�ꂽ�����ɁA�q���ɔ��������Ƃ����̂����̌o�܂������悤���B
![�c������s���Ɣ�]�d�t�i�v���ЁA1978�N10��15���j�̔��ƕ\��](image/tamura_E_1.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�d�t�i�v���ЁA1978�N10��15���j�̖{��](image/tamura_E_2.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�t�V���[�Y�̑S5���A�`�`�d�i�v���ЁA1969�`1978�j�̔w�\��](image/tamura_A-E_1.jpg)
�c������s���Ɣ�]�d�t�i�v���ЁA1978�N10��15���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i���j���s���Ɣ�]�t�V���[�Y�̑S5���A�`�`�d�̔w�\���i�E�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E�O�l�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�@�B���B�q�ڎ��r�̍Ō�̍s�Ɂu����\�\�g�����v�ƃN���W�b�g�����邪�A���E���J�b�g�̃j���g�����N�̎�ɂȂ�̂��킩��Ȃ��B�N���X�Ɣ��̐F�������b���n�B�`�`�d���A�F�E��F�E�ΐF�E���F�E�b���F�Ƃ��Ă���A�`�a�i�b�j�c�܂ł������r�Y�̎��_�W�O�����̐��F�E�ԐF�E���F�Ƌߎ��̐F�ʌv��Ȃ̂͋����[���B���̐F�����Ƃ��Ė��邷������F�͎g���Ȃ�����A�e�ȍ~�ɂ͒��F�⎇�F���o�ꂷ��\�肾������������Ȃ�
��
�s���Ɣ�]�t�S�������Ă����B�c�́s�Ⴂ�r�n�t���������ߋߍ�̎��т͂Ȃ��������A�V���[�Y���̂Ƃ���A�c������̂��̎��_�ł́q���r�Ɓq�U���r������ɂ܂Ƃ߂����킢�[���ҏW�������B�c���͖{�V���[�Y���s�r����1970�N��̑O������A�U���̘A�ڂ𐔑���������悤�ɂȂ�B���������A�{�V���[�Y�Ɏ��^���ׂ��U���͌������i�����Ă��A�ڎ��̏o�ŎЂ��P�s�{�ɂ��ďo�ł��邩��j�A�Ȃɂ������W����p�����Ɋ��s���ꂽ�B���̃X�s�[�h�͖{�V���[�Y�̊��s�y�[�X������قǂ������B�{���d���u�y�܂ŏo���v�Ƃ��������̈ӎv���Ȃ���A���̖ڂ����Ȃ�������������Ȃ��B�c���̎����A�U�����A�L�����Ɍ}������悤�ɂȂ����̂ł���B
�Ƃ���Łs���e���O�Y ���Ǝ��_�k�S6���l�t�i�}�����[�A1975�N�j�Ƃ����I�W������B�k�T�l�́A�����sAmbarvalia�t�q�g���g���̕����r�A���_���s��������`���_�t�s�V�������A���X�����w�_�t�s�ւ̂��鐢�E�i���j�t�B�c�����q���l�̕ω��Ɛ��ڂɂ��ār�Ƃ������͂��Ă���k�U�l�́A�����s���l���ւ炸�t�s���ނ��肠�t�A���_���s��������t�s���̏��i���j�t�A�Ƃ��������������B����͓����Ō��́s���e���O�Y�S�W�k�S10���l�t�i1971�`1973�j�̐��ʂ܂������̂����A�c���́s���Ɣ�]�t�V���[�Y�̕ҏW���j���Q�l�ɂ����Ƃ��l������B�ނ��A��s�S�W�Ɠ����W�������ʂ̊����āi���W�E�W�E���_�E���w�_�E���M�E�������сj�ł͐V���Ɍ�����A�Ƃ������f���������ɈႢ�Ȃ��B�����A�ЂƂ�̎U�����悭���鎍�l�́u�ω��Ɛ��ځv������̂ɁA����قǓK�����ҏW���@���Ȃ��悤�Ɏv���B��ғc������ƕҏW�Ҕ��ؒ��h�̏����ł���B���ꂩ����ʂ��A���J���v�ҏW�́s�c������S�W�k�S6���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2010�`2011�j���m���n�Ɓm�U���n�����Ɏ��^������j�P���āA�c���̎�v�ȕ��Ƃ�`����B
�c������s���Ɣ�]�c�t�i�v���ЁA1973�N5��1���k�O�ŁF1977�N6��1���l�j�́A�]�_�q�Ⴂ�r�n�r�A���l�ɂ��q���k��r�A����M�v�E���ˉ�v�́q����r�Ƃ��琬��B�P�s�{�́s�Ⴂ�r�n�t��1968�N10���A�v���Њ��B�ߔN�̊��{�ɁA�{�����{�Ƃ����u�k�Е��|���ɔŁi2007�N2��10���j������B�����̍��X�؊��Y�́q����r�ɂ́A�u�w�Ⴂ�r�n�x�͍ŏ��A�����u�����C�J�v�ɘA�ڂ��ꂽ�B�c�����ꂪ�O�\���̂Ƃ��ł���B�u�����C�J�v���a�O�\�ܔN�i���Z�Z�j����������O�\�Z�N���܂Ŏ���A�ڂ��ꂽ���A�u�����C�J�v�Ў�ł������ɒB���v�̋}���ɂ���Ē��f�����B�k�c�c�l�������I�����u�r�n�v�O���[�v���A���̓���������ɏ����Ă����悤�ɂȂ������Z�Z�N�ɁA�ǂ̂悤�ɐ�㎍�̂Ȃ��Ɉʒu�Â���̂��A��㎍�̗D�ꂽ�I���K�i�C�U�[�������ɒB���v�́A�c������̊�ɑ����āw�Ⴂ�r�n�x�̘A�ڂ���悵���̂��Ǝv����B�^�ɒB�̋}���ɂ���Ē��f���ꂽ�A�ڂ́A���a�l�\��N�i���Z�Z�j�ɂȂ��āA�u���㎍�蒟�v�i�v���Ёj�ōĊJ���ꂽ�B�A�ڂ͓��N�Z�������珺�a�l�\��N�������܂łŊ����B���̊ԁA�����̏��a�l�\��N�l�����ɁA����M�v�A�k�����Y�A���ˉ�v�A�O�D�L��Y��Ƃ̍��k��u�w�Ⴂ�r�n�x�����v���f�ڂ���Ă���B���̍��k��́A�u�����C�J�v�A�ڎ�����̓c���̃A�C�f�B�A�ł������v�i�O�l�l�`�O�l�Z�y�[�W�j�Ƃ���B�{���ł́s���Ɣ�]�t�́q��]�r���S�ʓW�J����Ă��āA�c���̎�N�́q���r�́s�r�n�t�̃����o�[�̈�l�Ƃ��čT���߂Ɉ��p����Ă��邾�����B�s�Ⴂ�r�n�t�͐������c���̎U���̒����̍ŏ��̈���ł���A���ꂪ�G���W�ł͂Ȃ������̏����������l���̐��������������ѕ]�_�ł��������Ƃ͈Ӗ��[���B�Ȃ��{���́A���J���v�ҏW�́s�c������S�W�k��1���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2010�N10��30���j�́m�U���n�ɑS�т����^����Ă���B
�@�s���E�o���t24�W�i��15�E8�����s�B�`�T�Łk���l�E28�Łj����́s�ߑ㎍�ɂ��āi2�j�t���Â��ēǂ�ł݂悤�B�����̃��_�j�X�g�̎�v�ȋ@�֎��́A�k�����q�̕ҏW�ɂ��sVOU�t�ƁA�t�R�s�v�A����l�Y�A�ߓ����A��c�ۂ̋����ҏW�ɂ��s�V�̓y�t�ŁA�O�҂͎��ɂ�����Z�p��`�̎������A�^���̖ڕW�ɂ������A��҂́A�T�^�C�A�ƃC���j�C����v����Ƃ����ߑ��`��W�Ԃ��Ă����B�������߁sVOU�t�́A�c�ɂ̒��w�Z�̉��w�����Ƃ������Ƃ���ŁA���A��i����������������A���w�̊�łȋ��t�Ɏ����Ĕ����o���Ă����̂��A���c�O�Y�Ɩ،��F��ł���A�s�V�̓y�t�͐A���n�ɂ���p�Čn�̏��V���ЂƂ����������́A���܂�p�b�Ƃ��Ȃ��p�[�e�B�������B�i�q�����v��������Ȏv�Џo�̉��Łr�A�{���A��Z�O�y�[�W�j
��`�n�\�\Love Song�b�c������
���܂��܂Ȍ`���ā@��̂₤�Ɂ@�͂����ꂽ
�u����́@�̂��炾�炤���v
�l�X�́@���k�}�}�l���M��������
�͂�M�����l�X�́@���łɌ`�ƂȂ�
�͂́@�����₤�Ɂ@�l�X�̋�����
�u���T�́@��̍L��
�����l�ւ邱�Ƃ͂Ȃ�
�̏�ɍ���
���̂߂����ɐG���v
�l�X�̌Q�ꂪ�@����̂��Ƃ��@��������
���t���Ȃ��@�ߏւ̉�����@���Ă���
����Ƃ��@�l�ɂ́@�����ʂ̂�
���U�@�̂߂����������@�M������
���ꂩ��
�͂������₤�Ɂ@�l�X�̌Q��͏������ā@�J���L��Ɂ@�~��͂��߂�
����́@�������R����
�����@�l�̊z��G�炷
�߂������y���Ǝv�ւ@���₵���@���̂͐k�ւĂ
������������@���������̂����m���
�u�͔G��Ă�̂�����v
�ӂƁ@�l�̎c�菭���q�d���@�ꂢ�Ă݂�
�J�́@�͂������I
�L��́@���炭�@����ł��܂ӂ��炤
�����@�ǂ�Ȃ��ƂɂȂĂ��@�l���̏�ɍ��k�}�}�l�Ă�邱�Ƃ͐���I
�u����͌��z����v
�悹���T�̂Ɂ@�l�̒q�d�́@�܂��ꂭ
���T�@���m��ʂ������̌������@���𗧂Ă��I
�����͕�����@����͌��t�łȂ���
�l�ɂ́@�������t�������Ȃ�
���U�@���������@�̗͂���̂₤�Ɂ@�l�̋����Ă䂭
�L�ꂩ��́@�`���ق̂��Ɍ��Ă��̂��@�]�ނ��Ƃ��o����
�l�X�́@���̖�i���D��
�Ƃ�����@�ٍ��̔����D�����`����Ɓ@�`�́@�Ղ̂₤�Ɂ@���͂�
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E�Z�y�[�W�i�苖�́u�O�Łv�{�́A�u277�v�y�[�W�Ɓu278�v�y�[�W�ɑ�������꒚�\�\���t���������Ă����ɈႢ�Ȃ��\�\�����āA��Z��~����~�����[�g���̎��t�Ɉ�����ꂽ���t���{���ŏI�́u276�v�y�[�W�Ό��̖{�����ɓ\�肱�܂�Ă���j�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�@�B���B�q�ڎ��r�̍Ō�̍s�Ɂu����\�\�g�����@���E���J�b�g�\�\�����v�ƃN���W�b�g������B
![�c������s���Ɣ�]�c�t�i�v���ЁA1973�N5��1���k�O�ŁF1977�N6��1���l�j�̔��ƕ\��](image/tamura_D_1.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�c�t�i�v���ЁA1973�N5��1���k�O�ŁF1977�N6��1���l�j�̖{��](image/tamura_D_2.jpg)
�c������s���Ɣ�]�c�t�i�v���ЁA1973�N5��1���k�O�ŁF1977�N6��1���l�j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�{�V���[�Y�̔w�̃N���X�́A���Ȃ蕝�������B�����̕\�������w����v�ɂ���Ƃ����{���̖ړI���炷��A�N���X�͔w�����č�Ƃ��₷�����肬��̋����ł����킯���B���ꂪ�ǂ�ȕ��ł���A�����ĕ\���i�\���P�j�Ƃ���\���i�\���S�j�̕��Ƃ��Č���ƁA���ƃN���X�̎��ނ̊Ԃňَ������o��B�{���̂悤�ɕ\���ɋ��ŃJ�b�g������ꍇ�i����������̊G���͉����j�A�N���X�̕����L���ƁA���̎��̍��E�����ƕ\���P�S�̂̍��E����������āA���o�I�Ɉ���������B������e�����āA�N���X�̕������߂Ă���̂�������Ȃ��B���Ȃ݂ɏ�f�̃o�b�^�́A�\���̐c�̔��̕��i�\���̍��[����N���X�̍a�܂Łj�̍��E�����ɋ�����Ă���B
�c������s���Ɣ�]�b�t�i�v���ЁA1972�N12��1���k�O�ŁF1976�N9��1���l�j�́q���r13�сA�q�A�����J����̎莆�r8�сi�Βk�Ɖ������Ȃ��܂ށj�A�q�G�T�r15�сA�q�G�U�r17�сi�J�����ɂ��C���^�����[���܂ށj�A��4�����琬��B�a�q�v�l�Ɉ��Ă��q�A�����J����̎莆�r�i���Z���N�ꌎ�\����t�j�Ɂu�ڂ��͓����ɋA��܂łɐ�s�̒������������B����͎G���ɔ��\���Ȃ��ŁA���̂܂ܒP�s�{�Ƃ��ďo���B�肵�āu�k�v�B�����邢�݂ł́u�k�v�B���̎����o����ƁA�ڂ��̒����̎d���������ł���킯���B�����������߂Ă���B�u�k�v��A�z�����錾�t�A���Ƃ��A�X�A��A�~�A����A�Ȃǂ̌��t�����������r���āu�k�v���������肾�B���Ȃ�A�Ӑ}�����͖�S�I�Ȃ̂����A�Ƃɂ����������ăN�_�P�����I�v�i�{���A���y�[�W�j�Ƃ���B����́A�̂��Ɏ��W�s�V�N�̎莆�t�i�y�ЁA1973�j�Ɏ��߂�ꂽ���сq�u�k�v�ɂ��Ẵm�[�g�r�i�s���Ɣ�]�a�t�Ɏ��^���݁j�ɂ��̍��Ղ��c���A���̒������w�����낤�B
�u�k�v�ɂ��Ẵm�[�g�b�c�������G��Ɖ��y�ɍ����Ȃ��A�Ƃ����̂́A�^�ԂȉR�Ȃ�B�ڂ����A�k�Ă̓c�ɒ��Ōo�������u���R�v�A����сu���R�v�̉�H�ƂȂ肤����́A������A����͌���Ȃ�B���E���A����ɂ�����x�A���������߂˂Ȃ�ʁB�u�k�v�̎��ɂ́A��A�X�A���A���A���l�A���̑��A�u�k�v��A�z�����߂�@�����t�i�C���j�͌��ցB
�k�āA�A�C�I���B�ɂāB���Z���N�ꌎ
�X�͊��\�\�R���錾�t�A�G���e�B�b�N�ȃ��Y���ŏ������Ɓi�������A�X�̓������������Y���Łj�B�[���A�ߜƁA�Ǘ��A�f��A�ɖk�A�ɓ_�A���_�A�̔@���p��A�t�B�[�����O�A�g�p���ׂ��炸�B
����́i������y�уA�N�Z���g�j���t���Ɋ��p�B
�����I�o���B�i���Ǝ��Ɋւ��ẮA������Ă��邱�Ɓj
�n���w�I���j�w�I�����̏N�W�B�i�����āA�N�w�I�ӎ��̔r���j
�����̌����\�\�k�����ց\�\�삩��k�ցB
K��Operation�\�\put into Operation. undergo an Operation.�@
�R���錾�t�ɂ���āA������A���₻�̂��̂��A�ǎҁi���Ȃ킿�u���v�y�сu��X�v�j�Ɍo�������߂�A�܂��܂��̐����Ȃ�B
�l�̉�U�}�\�\�L�c�h���b�O�\�\�X�H�B
�f�J���g�́A�I�����_����̋A�r�ɂ��Ă̌����B
�s�펞�ɂ�����c�L�W�f�X�������́m�A�A�n��Ō��邱�ƁB
�M���Ȃ���A���s���Ȃ��Ƃ������Ɓ\�\���s�������B
�q�A�����J����̎莆�r��ǂނƁA�uK��Operation�v�͕v�l�̎���p���w���悤���B�u�L�c�h���b�O�v�̓}�c���g�L���V�̂悤�ȁA���Ă������`�F�[���X�B�u�s�펞�ɂ�����c�L�W�f�X���v�̊܈ӂ͕s���B�Ƃ͂����A�����������m�[�g�Ȃ̂�����A��������Ă��n�܂�Ȃ��B�g�����̘A�����s�S�y���t�i�����j�́A���̈ꕔ�����сq�t�r�i�G�E4�j�ƂȂ�A���́s�T�t�����E�݁t�Ɉ������ꂽ�B�c���̒������S�s�ł���S�s�ł��c����Ă����Ȃ�A���́u�f�Ёv�͂ǂ�قǑs�ς��������낤�B�A�����s�S�y���t�ƕ���ŁA�����s�k�t�̏�����Ȃ��������Ƃ��ɂ��܂��B
���J���v�ҏW�́s�c������S�W�k��2���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2011�N2��28���j�́m�U���n�ɂ́A�q�A�����J����̎莆�\�\���Ɣ�]�b�@���r�Ƃ��āA�q�A�����J����̎莆�@���Z���N�\�`���Z���N�l���r�A�q�t�B�b�c����ƃV�����Y����̘b�r�A�q�A�����J���̗��r�A�q���̂���L�����p�X�r�A�q�A�C�I�����̌�r�A�q���C�g����r��6�т��Z���N�g����Ă���B
![�c������s���Ɣ�]�b�t�i�v���ЁA1972�N12��1���k�O�ŁF1976�N9��1���l�j�̔��ƕ\��](image/tamura_C_1.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�b�t�i�v���ЁA1972�N12��1���k�O�ŁF1976�N9��1���l�j�̖{��](image/tamura_C_2.jpg)
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E�O����y�[�W�i�苖�́u�O�Łv�{�́A�u373�v�y�[�W�Ɓu374�v�y�[�W�ɑ�������꒚�\�\���t���������Ă����ɈႢ�Ȃ��\�\�����āA��Z�Z�~���O�~�����[�g���̎��t�Ɉ�����ꂽ���t���{���ŏI�́u372�v�y�[�W�Ό��̌��Ԃ��̗V�ю��ɓ\�肱�܂�Ă���j�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�@�B���B�q�ڎ��r�̍Ō�̍s�Ɂu����\�\�g�����@���E���J�b�g�\�\�����v�ƃN���W�b�g������B���̃J�b�g���s���Ɣ�]�`�t���s���Ɣ�]�a�t�Ƃ͈قȂ�A�����炵���V���[�v�Ȑ���ł���B�g�E�����R�V�͂���܂łƓ��l�A�\���ɋ�����Ă���i��⑾�����Łj�B����̔��W��̍��F�ƃN���X�̐F�͗Όn�i�����O���[���j���B
��]�@�k�c�c�l���㎍�͖l�́A���傤�ǔ�s�@�̔��B�̒i�K�ŁA�傫�������Ȃ���Ď����Ĕ��ŗ����������肷��l�������ł��傤�A����͊��m�ŔߎS������ǂ��A�������l�Ԃ́q��т����r�Ƃ����~���̖{���̌����̂��̂������āc�c
�c���@�����A����������Ƌ�̕��ɂ�����ł����̂ˁB
��]�@���l�͂��������^�C�v���Ǝv����ł��B
�c���@�����ł���B
��]�@�����U���Ƃ́A���l���傫���������Ĕ�ڂ��Ƃ��ė�������������A��s�@�ɂ̂��Ĕ��ł������ǁA������ƌ����Ă�͂�A�傫�ȃW�F�b�g�@�̋q�ȂŐ��ł�����X�R�b�`�E�E�C�X�L�[������ł���C���ł͂����Ȃ��Ǝv����ł��B
�c���@�����ł��B
��]�@��͂�c�c
�c���@�����ł��Ȃ�������Ȃ��B
��]�@�����A������đ��c�����ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ˂ɔ�s�@���̑c��Ƃ������̂��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA��s�@���̑c��Ƃ����̂͂���������Ă��邯��ǂ��A���l�͌��ɓ�����ɐ����Ă������A���̎��l������l��͂����������̂Ƃ��Čh�ӂ��Ȃčl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂��B���������ӂ��ɍl����ƁA�܂����l�ɑ���l��̕]���Ƃ������̂��A�P�Ȃ�ǂ��������邢�͍D�݂���̂���Ƃ͏�������Ă��܂��ˁB���Ƃ��g��������l�͂������l���Ǝv���܂�����ǁA���̎��l�ɑ� �� ���܂̊ϓ_����̖l�̕]���͒Ⴂ�B����́A�g�����Ƃ������l�͂������l�����A�l�̍D���Ȏ��l�����̈�l�ł�����ǁA�������l���U����ƂƂ��ċ��낵���Ǝv�����l����Ȃ��B�����Ƃ����Ă��������C���[�W�͂���邾�낤�Ǝv���B�����Ƃ̎����Ă��Ȃ��C���[�W�A�����Ƃ������Ă��Ȃ����Y���A�����������̂������Ă��鎍�l���Ƃ����ƁA��������Ȃ����l���Ƃ����C�������ł��B�t�ɋ��낵�����l�Ƃ����Ƃǂ��������l���Ƃ����ƁA�c������Ȃ����������l�����A���Ƃ��Γ��X���a�Ƃ����Ⴂ���l�̍ŏ��̂��̂͂����ł����B���ꂪ���Ƃ��Ύc��m����Ƃ����悤�ȁA���|��]�ƂƂ��Ď��𗝉����āA�������܂���������l���A������]������̂��g�����Ƃ����悤�Ȏ��l���Ƃ���ƁA����͂�����Ǝ��l�Ə����ƂƂ̂������̓����J����]�ƂƂ��Ă͕s�K�C���Ƃ����C�����܂��ˁB�����Ƃ��t�������Ă��y�т����Ȃ��悤�ȃ��Y���������Ă���l���A�����Ƃ��������l���ƌ��Ȃ��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B�������́A���̎��Ə����Ƃ��Ȃ����Ƃ̓�Ղ������Ă����ŁA���̓�����̂��������Ƃ������ƂŁA�����̎��l�̉��l�̍����Ⴂ�������̂ł͂Ȃ��̂ł����B
�c���@����͂悭�킩��܂��B
��]�@�����Ƃ����ɑ����Ƃ��ɁA�����ƂƂ��Ă͓���ł��Ȃ��悤�ȂƂ���[���肵�Ă����Ă��鎍�l�A��������߂�C�����l�ɂ͂���킯�ł��B�i�{���A��l�Z�`��l�O�y�[�W�j
�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�̑ł����킹�ŁA�ďC�̕��o������A�ҏW�S���̎v���ЁE��������j����Ɛt��̃}���V�����ɋg���z�q�����K�˂��Ƃ��A�g���̏��I�������Ă�������B�s���㎍�ǖ{�t�̌��G�Ɏʂ��Ă��Ȃ��{�����낢�날���āi�t�����X���@���ɂ��������\�\�L���ɂ��钘�҂͏����O�A���ꂩ���P�v�̕ʖ��E��ؗ��V�\�\���������̂͂�͂�Ƃ��z���A���������������j�A�i�C�����̉��F�����̑�]���O�Y�s������Q�[���t�i�V���ЁA1979�j���������B���̔w�������������A���悳�ꂽ��{�������̂��낤���B
���J���v�ҏW�́s�c������S�W�k��1���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2010�N10��30���j�́m�U���n�ɂ́A�q��Ƃ����\�\���Ɣ�]�a�@���r�Ƃ��āq�G�T�r�́q���鉉������\�\�v�E�g�E�I�[�f���r����q�q���R���q�r�܂ł�15�т��Z���N�g����Ă���B
![�c������s���Ɣ�]�a�t�i�v���ЁA1970�N9��30���k�l�ŁF1977�N5��25���l�j�̔��ƕ\��](image/tamura_B_1.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�a�t�i�v���ЁA1970�N9��30���k�l�ŁF1977�N5��25���l�j�̖{��](image/tamura_B_2.jpg)
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E�O�ܓ�y�[�W�i�苖�́u�l�Łv�{�́A�u353�v�y�[�W�Ɓu354�v�y�[�W�ɑ�������꒚�\�\���t���������Ă����ɈႢ�Ȃ��\�\�����āA��Z�Z�~���O�~�����[�g���̎��t�Ɉ�����ꂽ���t���{���ŏI�́u352�v�y�[�W�Ό��̌��Ԃ��̗V�ю��ɓ\�肱�܂�Ă���j�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�@�B���B�q�ڎ��r�̍Ō�̍s�Ɂu����\�\�g�����v�Ƃ��邪�A���E���̋��i�L�H�j�̃J�b�g�̍�҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�����s���Ɣ�]�`�t�Ɠ��l�A�\���ɂ�������Ă���B�c�����J�b�g��`�����͂��͂Ȃ�����A�g�����ǂ�����������Ă����̂��낤���B���̕W��̍��F�ƃN���X�̐F�͐Ԍn�i�I�����W����������F�j�ł���B
�c������s���Ɣ�]�`�t�i�v���ЁA1969�N12��25���k�ĔŁF1973�N4��25���l�j�́u�c������̑S����V���[�Y�v�̑�1���Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B�Ĕł̉��t���L���ɂ́u�w�̎v�z�x�Ȍ�ɏ����ꂽ���u���̈Í��v�ȂǂX�т��͂��߁A����M�v�A���������Y�A���e���O�Y�A���q�����A�O�D�B���A����S���A�G���I�b�g��Ɋւ��銴����ǂ����_�𒆐S�Ƃ��āA�G�b�Z�C�A���^�A�C���^�����[�A���`�Ȃǂ����߁A���̗B��B�R���鎍�l�̈ʑ��̍��������߂��v�Ƃ���B�q�f�ڎ����ꗗ�r�ɂ��A����1967�N����69�N�܂ŁA��]��1955�N����69�N�܂ł̂��̂��̂��Ă���B�����A�P�s�{�ɂȂ��Ă��Ȃ����ƁA���ɏ����ꂽ��]�\�\�Ƃ������L�����ȊO�̕��́\�\��ԗ����āA��������i�ő�`����y�܂ł�26�����j�́s�c������S����W�t��ژ_�Ǝv�����B���̂�����̂��Ƃ�{���̒S���ҏW�ҁE���ؒ��h�́u�c������̎���U����Βk�����߂��w���Ɣ�]�x�Ƃ�������V���[�Y������B�X�N���b�v�u�b�N�Ɍf�ڌ��e�̐ؔ��������܂�Ɓu���N�[���A���܂�����I�v�Ɛ����������āA�ҏW�ɂƂ肩����B�����`����y�܂ŏo�����ƁA��l�Œ��肫���Ă������A�d�ŃX�g�b�v���Ă��܂����B�c������͂��̌ォ�炾�����킵�āA�A���R�[���̂ق������x�݂������v�i�s���l�Y���m�[�g�t�A����R�c�A1986�N8��25���A���Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�{���̓��e�́q���ɂ��ār7�сA�q���r9�сA�q�G�r6�сA�q���l�r8�сA�q���r1�сB�ӂ��Ɍ����A���_�E���сE���z�i�G���j�E���l�_�E���`�Ƃ������Ƃ��낾�B�g���Ɠ�����ނŏ������U���������[���B���Ȃ킿�A�����ɓ������ɍs�����z�q���̉ԁr�i���o�́s�����t1965�N8���j�͋g���̓������q���ƏҊ��r�ƁA���惆���C�J�Łs���q�����S�W�k��1���l�t�̏��]�Ƃ��ď����ꂽ�q���q�����Ƃ������l�r�i���o�́q���q�����Ƃ������l�\�\�J��������M�������Ƃ��̂��Ɓr�A�s�}���V���t�A1960�N8��27���j�͋g���̏��]�q�s痏����Ȏ��l�r�ƁA�����ēǂ݂����B�q�U�G�X�P�s�X�g�̐����ƈӌ��r�́u�Ǐ��͂��������A���I���Ȃ���A�������Ȃ��B�ނ��Œ�̃p���邽�߂ɂ�����~�X�e���[�̖|����̂���A�ގ��g�̎��W�ɂ�����܂ŁA�قڔ��\���ɂ̂ڂ鎩���̏��������A�ނ͏��L���Ă��Ȃ��B���ꂩ�ɂ���Ă��܂������A�����Ă��܂����̂ł���v�i�{���A����y�[�W�j�́A�u�c������͂���k�s�l��̓��Ɩ�t�l���˂���āA���т��ё���̎��̕����Ɍ���ꂽ�v�Ƃ���g���́q�c������E�f�́r�̋L�q��z�킹��B�g���́A�c���̍s��������������A���̈�߂܂��邩���Ēf�͂��������̂��낤�B
���J���v�ҏW�́s�c������S�W�k��1���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2010�N10��30���j�́m�U���n�ɂ́A�q���l�����\�\���Ɣ�]�`�@���r�Ƃ��Ė{������q�ڂ��̋ꂵ�݂͒P���Ȃ��̂��r�Ȃǂ̎��_�Ɓq���זE�\�\���������Y���_�r�Ȃǂ̎��l�_�A���킹��14�т��Z���N�g����Ă���B
![�c������s���Ɣ�]�`�t�i�v���ЁA1969�N12��25���k�ĔŁF1973�N4��25���l�j�̔��ƕ\��](image/tamura_A_1.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�`�t�i�v���ЁA1969�N12��25���k�ĔŁF1973�N4��25���l�j�̖{��](image/tamura_A_2.jpg) �@
�@![�c������s���Ɣ�]�`�t�i�v���ЁA1969�N12��25���k�ĔŁF1973�N4��25���l�j�̔w�k���łƍĔŁl](image/tamura_A_back_02.jpg)
�c������s���Ɣ�]�`�t�i�v���ЁA1969�N12��25���k�ĔŁF1973�N4��25���l�j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i���j�Ɠ��E�w�k���łƍĔŁl�i�E�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�@�B���B���E�{���̓��̂悤�ȃJ�b�g�i��҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��j�͕\���ɂ�������Ă��āA�s��ʁt�̃J�b�g�ƕ��͋C�����Ă���B��������w�̃N���X�̐F��ς��Ă������{�v�悾�����̂��낤���A�����r�Y�̎��_�W�O�����̂悤�ɏ��߂�����������܂��Ă����킯�ł͂Ȃ�����A������Ƃɒ��҂�S���ҏW�҂Ƒ��k���ĐF��I��ł������̂�������Ȃ��B�`�͐n�ł���B�{���̔w���������A�����}���ُ����̏��łƎ苖�̍Ĕł��r�ׂ�ƁA���炩�ɏC������Ă��邱�Ƃ��킩��B���Җ��E�����͏��ł��Ƃ���20�|�C���g�A�Ĕł͒��Җ������Ԃ�ɏ������Ԃ�ɂ��Ă���B�o�ŎЖ����������Ȃ��Ă���B�`�a�b�c�d�ƕ��Ƃ��A�w�����̑傫�������Ȃ̂͂܂����B�V���[�Y�̐i�W�ɂƂ��Ȃ��āA�w�����̃t�H�[�}�b�g����������āA�������͑������@�ɏC���������̂Ǝv����B���t�ɂ��A�{���̈���E���{�����ꂼ��A���ł����{�\�����ނƗ�ؐ��{�A�Ĕł���t����Ɗ⍲���{�i�s�g�������W�t��s�Â��ȉƁt�ɓ����j�A�O�ł��G�����p�Ɣ����Ђƕς���Ă���B���̗��R�́A�킩��Ȃ��B
�s����S�����S�i�t�i�}�����[�A1973�N5��25���j �ɂ��āA�g�����͖����̐��z�q�S���f�́r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ ����S�����鑒���t�A�v���ЁA1989�N3��1���j�ɂ��������Ă���B
�@�@�R
�@���a�O�\��N����̂��ƁB�ő��ӂ�̗����̈ꎺ�ŁA���͏��߂đ���S���Ɖ�A�e�������t�����킵���B�}�����[�̎В��Óc��Ɖ�c�j�Y�A�����k�āl�����Ꮥ�����Ȃ��Ă����B�w����S�����S�i�x�̏o�Ō���̓��j���̉�����悤�Ɏv���B���˂��ˁA�Óc��͐e�F����S���́u�{�v���o�������ƍl���Ă����B�������ҏW����c�͌����ŁA���Ƃ��В��̒�Ăł��A����͒ʂ�Ȃ��B������c�j�Y���ҏW���ɑ����Ă��Ȃ�����A���ڂɐ��i�ł��Ȃ����ǂ��������������B���]�Ȑ܂����������̂̏o�ł͌������̂ł���B���̖�A�h����ʂ����Óc��͂������������������悤���B
�@�@�T
�@�w����S�����S�i�x�̑��{�E����́A���̎肪�������̂ł���B�V���{���Ƃ��ẴJ�b�g�ɁA�u�����܂��Ⴍ���v���A�S������ɕ`�����Ă���B�v���Ԃ�ł��̖{���o���Č��āA���̖��������A���ʂ������Ă���Ǝv�����B�i�����A���y�[�W�j
�{���̓��e�זڂ͈ȉ��̂Ƃ���ł���i���̊ے������͈��p�҂��t�������́j�B
�@�@�˗��I�̉ʂĂ̍���
�@�A���z�͓����炠����
�@�B����ꂽ�I���K��
�@�C�}�����X�̉�
�@�D�x�m�R
�@�E��l�̊^
�@�F�V
�@�G��{ �^
�@�H���O��
�@�I���{����
�@�J�唒��
�@�K�x�m�R
�@�L��i
�@�M�^
�@�N���
�@�O�����͓V�C��
�@�P��S�K��
�@�Q��S�K���ȑO
�@�R�l�\���N�W�b�O�U�b�O�́\�\�E�⎍�W
�@���S�i�o��
�@���S�i�ז�
�@�������E�N��
�����̒��J��ҁq����S�������E�N���r�̋L�ڂ��ȗ������āA����̒P�s���W���T�ς���i�ے������͓��e�זڂ̂��̂��ؗp�j�B�s���S�i�t���t�ҔN�̂ō\������Ă��邱�Ƃ��킩��B
�@�Q�s�p���̚h�ځt�i�^�C�����ЁA1923�j
�@�Q�s��Ɠd���T�t�i��Ɠd���ЁA1924�j
�@�Q�s��Ɠd���U�t�i��Ɠd�����ЁA1924�j
�@�Q�s��Ɠd���V�t�i��Ɠd�����ЁA1924�j
�@�Q�s���I�Ɖԉt�i1924�j
�@�Q�s�a�`�s�s�`�t�i1924�j
�@�Q�s���t�i1924�j
�@�\�s919�t�i1925�j
�@�P�s��S�K���t�i���t�ЁA1928�j
�@�O�s�����͓V�C���t�i�k���ЁA1931�j
�@�N�s���t�i����ЁA1935�j
�@�N�s���t�i�������сA1936�j
�@�M�s�^�t�i�O�a���[�A1938�j
�@�L�s��i�t�i���_���сA1940�j
�@�\�s����ԁm���ۂn�t�i��C�E�������ǁA1942�j
�@�K�s�x�m�R�t�i���X�ЁA1943�j
�@�J�s�唒���t�i�b�����сA1944�j
�@�I�s���{�����t�i���ЁA1948�j
�@�H�s���O���t�i���q���[�A1948�j
�@�G�s��{ �^�t�i��n���[�A1948�j
�@�F�s�V�t�i�V���ЁA1951�j
�@�E�s�������z�t�i�n���ЁA1953�j�k�V��́q�������Ɗ^�r��сl
�@�@�@�@��
�@�E�s��l�̊^�t�i�������_�Ж����ҏW���A1964�j
�@�C�s�}�����X�̉�t�i�v���ЁA1966�j
�@�D�s�x�m�R�t�i�����p�ЁA1968�j
�@�B�s����ꂽ�I���K���t�i���X�ЁA1968�j
�@�A�s���z�͓����炠����t�i�퐶���[�A1970�j
�@�@�s�˗��I�̉ʂĂ̍����t�i���⏑�[�A1971�j
���z�ɂ���u���a�O�\��N�v��1964�N������A�o�Ō��肩��{�����s�܂ł�9�N�����������ƂɂȂ�B���̊Ԃɑ����6���̎��W���o���Ă���i���ȍ~�̕��j�B�q�S���f�́r�ɂ��A�g��������̎��ɍŏ��ɐG�ꂽ�̂́s����S�����W�k�n���I���l�t�i�n���ЁA1950�j�ł���B�P�s���W�����邩����A���̂��납��S���W���s����܂ł̊ԁA���̔��\�̃y�[�X�͗����Ă���悤���B����������ŊJ���邽�߂ɁA�{���̊�悪�������������̂�������Ȃ��B����ƍ��x�́A���҂������Ȏ��M�����ɓ������B�u���]�Ȑ܁v�̂ЂƂƂ͂��̂��Ƃ��������B������ɁA�����̎��l�ł���A�M��܂�Ȃ�������u�S���W�v�͂��肦�Ȃ��B�u���S�i�v�Ƃ���������Ȃ������ɂ́A�������l�Ƃ��Ă̋C�T�����߂��Ă��悤�B����́q�S�i�o���r�́q�U�r�ł��̂��ƂɐG��Ă���B�܂��A1972�N5��2���̓��t���ɂ����́q�T�r�ɂ́A�u�������č����͋g�����A�N�����k�{���̕ҏW�S���ҁl�̗��N�ƁA���ꂻ�̑��̑ō���������Ƃ���܂ł��ǂ�����v�i�{���A���ܔ��y�[�W�j�Ƃ���B
 �@
�@
�{���̎d�l�́A��l��~�ꎵ��~�����[�g���E�㔪�l�y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�͍��̊v�A���͍��̃N���X�j�E�\���E�{�[�����i�\���Ӂj�B�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�{���܂��̘a���i�꒚�j�ɖѕM�ɂ�鏐���B�{���̂��Ƃ̃��m�N�����G�ɒ��ҏё��ʐ^�A���F�ł̌��G�ɒ��҂ɂ��G���i�B9�|��i�g���܁Z�y�[�W���鎍�і{������A���̈�т����������i�s��S�K���ȑO�\�\��Ɠd�����V�t�j�B�g���́s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̑D�̎��тɌ�������ׂȂ��������A�����ɂ�����B���������̎��́A�O�f�s����S�����W�k�n���I���l�t�ɂ͓����Ă��Ȃ��B
�A�����E���c�\�E�̕��i��b����S��
����ۂł����Q���Ă���ȁ@���Â��Ȃ������������i�\�\
�����ۂ̑D�̂Ƒ�O�˒�ɂ͂��܂ꂽ�`�̓���
���c�\�E�̐l���E�މ������邢�Ă��
�ЂƂ��ЂƂ茩�Ă�Ȃ�
�މ��͔��������̂��ނ���ۂ���͂�����
���̂�̂날�邫������
�b�m�f�c�L�n�ɂ͑D�q�ƌ����l�Ƃ�
����Ԃ�┒��̃e�[�v��
����݂���ċ㌎�̑��z�ɂ���߂�
�l�X�͂͂��Ȃ�������ɕʂ�̐S�𗬂��Ă��
�����₤�Ȋ�����ӂ�͂����Ă��
���X�v�Ђ������₤�ɑ傫�Ȑ��ŌĂт����Ă݂���
�����t���Ȃ�
�l�X�͂��Ƌ����e�[�v���ɂ���
���Ă����l�̂Ȃ��l��
�ЂƂ�ڂ�
�f�c�L�̂Ă���ɂ����ꂩ���Ă��
�i�����@�D�͂������������j
���{�ɂ��ւ�����Ƃ�
�n���P�`���ӂĖl�̖������ł������̂̂Ȃ����Ƃ�
�˒�̑q�ɂ̉����ɏ����Ă����ЂƂ̃��[�}���@�a
�������n���P�`��X�q��e�[�v����͂Ȃ��
�l�͂ЂƂ�E�̍b�ɂ���
�A�����E���c�\�E�̕��i��߂�̂�
�u�}�X�g�̂Ă�`�������Ƃ���v
�ӂ邳�Ƃ̃X�e�[�V�����ŕʂ��Ƃ�
�ӂƂ݂�Ȃ����͂������t����
���ܖl�̐S�ɂ͓`�����̂��͂��
���c�\�E�̕��i���
�����@���₤�Ȃ�
���{�̐l�X��@�R��
�s����S�����S�i�t�ɏ��o�̏E�⎍�W�s�l�\���N�W�b�O�U�b�O�́t�́A�̂��Ɂs����S���S�W�t�ɑS�т����^���ꂽ�B�����Ɂs���S�i�t�̊��s�N���E���e���L�ڂ���Ă���̂ŁA�S�W��3���̕Ҏ҂ł��钆�ˉ�v�E�R�{���Y�ɂ��q���r�������B
�k�w����S�����S�i�x�^�l���a�l�\���N�܌���\�ܓ����s�@�}�����[���@�a�T�ό^���i��l��~�ꎵ��m/m�j�@�w��N���X���\�����@���ҏё��ʐ^�ꖇ�@���ҁE���F���G�ꖇ�@�ڎ��O�Ł@�{�����܌ܕŁ@�S�i�o���l�Ł@�S�i�זړ��Ł@����S�������E�N���ꔪ���Ł@�艿��Z�Z�Z�Z�~�@������Z�Z���i�s����S���S�W�k��3���l�t�A�}�����[�A1982�N4��15���A�l����y�[�W�j
���Ȃ݂Ɂs����S���S�W�k�S12���l�t�i1978�N5��30���`1984�N5��25���j�̔��E�\���E�{���ɂ́A�g�����s���S�i�t�ő���ɕ`�������u�����܂��Ⴍ���v���ĂуJ�b�g�Ƃ��Ďg���Ă���B�{�S�W�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ��A��1��z�{��1978�N5���̎��_�Œ}���ɍݐЂ��Ă����g���̑����ł���\���͂���߂č����B����̒P�s���W�s���ʁt�i1974�j�̑����ւ̕]�����F�����������߂��B
�k2018�N8��31���NjL�l
�s����S���S�W�k��3���l�t�i�}�����[�A1982�N4��15���j����肵���̂ŁA���e���f���A���킹�ē��S�W�̊T�v���L���B�@���߁E���ˉ�v�E�R�{���Y�ҁs����S���S�W�k�S12���l�t�i�}�����[�A1978�N5��30���`1984�N5��25���j�́A��1��z�{�̑�1�����s�����1978�N7���ɔŌ���������|�Y�������߁A��2���ȍ~�̊��s�͑啝�ɒx�ꂽ�B�艿��6���قǏオ�����B3�N�̃C���^�[�o�����o��1981�N�ȍ~�́A�قڊu���̃y�[�X�Ŋ��s�𑱂��āA�܂���Ȃ�ɂ��S12���������������i�g�����̎��W�ł����A�S�W���s����6�N�ԂɁu�����v�̎��W�s�Ẳ��t�A�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�A�u����v�̎��W�s��ʁt��3�����o�Ă���j�B�e���̓��e�i��3���ѕ�������p�j�Ɣ��s���A�艿���f����B
��1�������W�h �k��S�K���@�����͓V�C���@���@�唒���@���{���� ���l�@1978�N5��30���@4,800�~
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\�\�\
��5�����]�_�h �k���Ǝ��l�@�킪�����Y�l�@1981�N5��20���@7,800�~
��9�������M�h �k�̎ԁ@�킪�t�̋L ���l�@1981�N7��20���@6,900�~
��2�������W�U �k��{ �^�@�V�@�x�m�R�@�}�����X�̉�l�@1981�N9��20���@7,800�~
��6�����]�_�U �k�킪�����@�킪�ő��l�@1981�N11��30���@7,800�~
��8�����I�s �k�x�ߓ_�X�@�_�E���E�V�@��x�I�s ���l�@1982�N1��30���@7,800�~
��3�������W�V �k����ꂽ�I���K���@�l�\���N�W�b�O�U�b�O�� ���l�@1982�N4��15���@7,800�~
��7�������� �k���X�ɂ���@�^���̐l ���l�@1982�N7��5���@7,800�~
��10�������M�U �k�킪���̂����@���X���X ���l�@1982�N8��30���@7,800�~
��11�������M�V �k���̒��̗����Q ���l�@1982�N11��20���@7,800�~
��4�������W�W �k�A���������@�����@�E�⎍�с@��S�K���ȑO ���l�@1983�N1��30���@7,800�~
��12�������M�W�E���b�E�|��E���E�N�� �k����Ԃ��@�T�c�R�E���A���[�c�`�̎莆 ���l�@1984�N5��25���@8,800�~
���̔��s�o�߂����A�}�����[������S���̑S�W���s�ɂȂ݂Ȃ݂Ȃ�ʌ��ӂŗՂO�Ղɂق��Ȃ�Ȃ��B�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�̓��S�W�̋L�ڂ̖����Ɂu���j�����S16���̗\��ŏo���������C��ЍX���@�K�p�\���̂��ߒ��f�B���L�C�G�[�Ȃǂ���������12���ɍĕҊ��s�����B�v�i�����A�Z�Z��y�[�W�j�Ƃ����āA�K�͂��k������������Ȃ��������O�����������킹�邩��ł���B�ł́A�����̑S16���{�̊����Ă͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B�S�W���s�ɐ旧���e���{������ɔ@���͂Ȃ��B
 �@
�@ �@
�@
�s����S���S�W�k��3���l�t�i�}�����[�A1982�N4��15���j�̔��k�\�l�ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��k���l�i���j�Ɠ������́s����S���S�W�k�S16���l�t���e���{�i�}�����[�A1978�N4��20���j�̕\���P�ƕ\���S�i�E�j
�s����S���S�W�k�S16���l�t���e���{�i�}�����[�A1978�N4��20���j�ɂ����銪���Ă̊T�v�́A�ȉ��̂Ƃ���i���Ȃ݂�1967�N5���Ɋ`���a�v���B�e�����ё��ʐ^�́A��́s����S�����S�i�t�̌��G�Ɏg���Ă���j�B���e���{���̂��̂̎d�l�́A�a�T��12�y�[�W�E���Ԃ��A�ʎ��m�ׂ��݁n�̕\���P�`�S�̓X�~�Ɠ��F�A�I�́A�{���̓X�~�Ɠ��F�A�J�̓�F����B�\���S�ɂ́A��1���̖{�̂Ɣ��̎ߘ��Ղ̎ʐ^���f�����Ă���i�܂�A�����Ă͓��e���{�̂ł���4���ȑO�Ɋ������Ă����j�B�܂����ꂽ�{�S�W�̓����ɂ́A�u�`�T���E�㐻�E�N���X���E�\�����E���G�Q���m�}�}�n�E����W�ŁE����530�ŁE�u�����E�艿�e���s���v�ƌ�����B���G�ʐ^�ɂ́A�@���ҏё��A�A���e�⒘�҂ɂ���i�i����⎩�M���e�ށj��\�肵�Ă������B���̓��e���{�̃��C�A�E�g�����A�g�����̎�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B
��1�������W�T �k��S�K���@�����͓V�C���@���@�^�@��i�@�x�m�R�@�唒���@���{�����@���O���l
��2�������W�U �k��{ �^�@�V�@��l�̊^�@�x�m�R�@�}�����X�̉�l
��3�������W�V �k����ꂽ�I���K���@���z�͓����炠����@�˗��I�̉ʂĂ̍����@�l�\���N�W�b�O�U�b�O�́\�E�⎍�W�@���ʁl
��4�������W�W �k�S�V�@�A���������@�����@�E�⎍�с@��S�K���ȑO�i�p���̚h�ځE��Ɠd���h�U�V�E���I�ƉԉE�a�`�s�s�`�E���j�l
��5�����]�_�T �k���Ǝ��l�@�킪�����Y�l
��6�����]�_�U �k�킪�����@���R�ő��l
��7�������� �k���X�ɂ���@�^�@�V�ɓo��@�̖�@���т���ӂ̎��@�t�E�@�^���̐l�@���R�ő��̎��@���l
��8�����I�s �k�x�ߓ_�X�@�_�E���E�V�@�~������@��x�I�s�l
��9�������M�T �k�̎ԁ@�̎Ԑ��M�@�킪�t�̋L�@�킪�����̂����l
��10�������M�U �k�킪���̂����@�A�x�x�̔L���@���X���X�@�~��Ȃ����Ԃ̒����@���l
��11�������M�V �k���̒��̗����Q�@���E���̒��̗����Q�@���l
��12�������M�W�E���b�E�|�� �k�|�p���M�@�J���K���[�̎q�@������@����Ԃ��@�A�����J�v�����^�������W�@�T�c�R�E���A���[�c�`�̎莆�@����q�@���l
��13�������L�T
��14�������L�U
��15�������L�V
��16�����G�[�E�����E�N��
���W4���A�]�_2���A����1���A�I�s1���A���M4���܂ł̍\����12���{�Ɠ��������A�ȍ~�̓��L3���A�G�[�E�������Ȃ��ꂽ���D�ł���B���e���{�ɂ������12���̐��M�W�E���b�E�|��A��13���`��15���̓��L�A��16���̎G�[�E�����E�N���̏Љ�́A���ꂼ�ꎟ�̂悤�ł���B
�u���҂͎����̐��E�ɂ����Ă���ł͂Ȃ��A���Ɖ�ɂ����Ă����I�Ȑ��E�������Ă���B���̊��́A���Ɖ���߂���|�p���z���W�����Ď��߂�ƂƂ��ɁA���ׂĂ̓��b�E�|������߂�B�w�A�����J�v�����^�������W�x�́A����\�O�Y�E���������Y�Ƃ̋���ŏ��a�Z�N���B�w�T�c�R�E���A���[�c�`�̎莆�x�́A���a���N���s��قƂ�ǂ��̏��݂��m���Ȃ��������̖ł���B�v�i���M�W�E���b�E�|��j
�u��O�̓��L�͓싞�Ŏ��Ȃ�ꂽ���A���̏��a��\�O�N����̒f���I�ȓ��L���c����Ă���A���҂̕��L����F���炵�āA���̓��L�͂���߂ċM�d�ȕ��w�I�����Ƃ��āA���̉��l�����㖾�炩�ɂ���ł��낤�B�����ɗ����ɊJ����Ă���l�X�Ȏ����ւ̊ώ@�́A���҂̑n�������̌�����������킹����̂Ƃ��Ă������[�����̂�����B�����ɏ��߂Ă��̑S������������B�v�i���L�j
�u���҂́A�w�{���S�W�x�w���������Y�S�W�x�w�R���钹���W�E���O���ޗ��x�w�팩�P�g���W�x�w���؏d�g���W�x�Ȃǐ������̕Ҏ[�Ɍg���A�Ғ��������B���̊��ɂ́A�����̏����E�땶�̗ނ����߂�B�܂��ڍׂȏ����E�N���i���J��ҁj�����߂�B�v�i�G�[�E�����E�N���j
�{�e�̎��M�҂Ƃ��ẮA�����̏Ȃ��ꂽ���Ƃ��c�O���B�s����S�����S�i�t�i�}�����[�A1973�j�̒��J��ҁq�����r���p���邵���Ȃ��B�����A�S�W�e���́q���r��������Ȃ������I�������������Ă���B�q���r�ɂ����āA���^��i�̒�{�̉��t�y�[�W��ʔłɋN�����čČ����Ă���̂́A�����ɑ��錩�������������łȂ��A���t�̑g���{�Ƃ��Ă��g���ďd��B����ׂ��s�g�����S�W�t�̏����ł��̗p���Ăق��������ł���B
�s����S���S�W�k�S12���l�t�̎d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���i�`�T�������j�E�e�����ϖ�ܓ�Z�y�[�W�i�y�[�W���́s�}�����[�}�����ژ^�t���Z�o�j�k�e���ɖ{���E���G�A���҂ɂ��q���Ҋo�����r�E�Ҏ҂ɂ��q���r�l�E�㐻�N���X���E�\���E����t�B��1���k���W�h�l�i1978�N5��30���j�̑����͋g�����̎�ɂȂ�Ǝv���邪�A1981�N5��20�����s�̑�5���k�]�_�h�l�ȍ~�z�{�̎c��11�����̑����́A��1���P�����}���̎Г������i�g���ȊO�̒S���҂ɂ��j�ł͂Ȃ����낤���B����Ƃ����̂��A�g����1978�N7���̓��Ђ̓|�Y���āA���N11���ɑސE���Ă��邩�炾�B�g���͖{�S�W�ɂ��āA�q���e���O�Y�A���x�X�N�\�\�V�@�u�Ẳ��v�r�Łu���N�k1978�N�l�̉ẮA�������Ăԗ[�����قƂ�ǂȂ��A�����̂Â����X�������B���͂ӂ��ƁA������̐��e���O�Y�搶�̂��Ƃ��v�����B���������̏t����̂��ƁA�Ⴂ�ҏW�҂Ɓs����S���S�W�t�̓��e���{�̂��߂ɁA�������i���j�����肢�ɏ�����B���̐܁A�搶�͂��炾���s���ŁA����������ƌ��q�M�L�Ƃ������ƂɂȂ����B���͂���ȗ���������䖳�������Ă����̂ŁA�߂����f������C�ł����B����Ȉ�����A���̋߂Ă���o�ŎЂ��|�Y�����B�܂��ɓˑR�ł������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�܃y�[�W�j�ƐG��Ă��邪�A�����ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��B�������A�s����S�����S�i�t�̑��{�E�����ŋg��������ɕ`�������u�V���{���Ƃ��ẴJ�b�g�v���u�����܂��Ⴍ���v�i�����炭�ѕM�ł̏u���̕`�悾�낤���A�A���t�@�x�b�g�̂p�̂悤�ɂ��A�����̂悤�ɂ�������j�𗬗p���Ă��邱�Ƃ�����A�n�̕\���ɔ����ۂ������p���ł��邱�Ƃ�����A�g���̑����ł��邱�Ƃ͂܂�����Ȃ��B�����́u�Ⴂ�ҏW�ҁv�Ƃ́A2010�N�Ɂu���키������S���L�O�فv�̏���ْ��ɏA�C�����A�}���ő���S���̒S���҂������N�������낤���B�N���͂܂��A�s����S�����L�k�S7���l�t�i�v���ЁA2004�`06�j�����̐ӔC�҂߂Ă���i�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�����ł��\����{���Ɂu�����܂��Ⴍ���v���o�ꂵ�Ă���j�B��������ׂ͒���16���{�S�W�̊��̈ꕔ���A�Ō���ς��āA20�N�̂̂��Ɏ��������킯�ł���B����S���͂������A���t�̗F�E�Óc������ł��邱�Ƃ��낤�B
�i���j�s����S���S�W�t���e���{�Ɋ�ꂽ���e���O�Y�̐��E�����f����i���Ȃ݂ɁA���E�����Ă���̂͐��e�ȉ��A����ՉE�q��A���яG�Y�A�y�����A�V�h�E�R�[���}���A���ɋ薛�A�J��r���Y�A��]���O�Y�̑���8���j�B�����q����S�����ɂ��ār�́s��{ ���e���O�Y�S�W�k��12���l���M�W�Q�t�i�}�����[�A1994�N11��20���A�l�y�[�W�j�ɂ����߂��Ă���B
�u�́u�k�����{�[�����ڂ��l�v�Ŏ��̂��߂ɏW�܂肪���������ɁA����S�����́A���̎��ɂ��āu�킩�邶��Ȃ����v�ƌ����Ďx�����Ă��ꂽ���Ƃ�����B���{�̎��d�̂��Ƃ͂��܂�m��Ȃ����������A�u���̐l�͒N���H�v�ƕ����ƁA�ނ͐e�ɋ����Ă��ꂽ�B�^�ނ́A���l�̂��Ƃɍׂ����C��z��A���`�h�ł͂��邪�A�����Đl��{�点��悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B���ƂȂ����l���́A����Ō����ΐa�m�m�W�F���g���}���n�ł���B�^�N���ɒ����ɂ���A�����J�l���n�݂�������w�Ɋw�сA���̂��߂��ނ͎��ɗ����ȉp���b���B�^�ނ͂܂����o�ꂵ�������̎��l�̐��b�����Ƃ߂�����Ӗ��̑�䏊�ł���A�{���⍂�������Y���]���Љ��̂ɍv�������B�^���{�̂ǂ̎��l������e�����Ȃ������炵�����A�Ⴂ�����玍�������Â��A�Ȃɂ����܂����l�ƌ��������Ȃ��B�v�i�s����S���S�W�t���e���{�A��y�[�W�j
������9�ΔN���̐��e�̖��ɉ��������Ȍ����́A�̒��s�ǂɂ����q�M�L�̂��߂���ł͂Ȃ����낤�B���c�v�Y�́s��㎍�d���j�t�i�V���ЁA1995�N2��25���j�ɂ��A���e�͗���g���܂��߂���u�����������v�ւ̑Ή��ŁA���삩�猻�㎍�l��̊������\�\����͐��e�̑O�C�̊������������\�\�Ƃ��Ă̐ӔC���͂��������₳�ꂽ���Ƃ�����Ƃ����i�����A��܁Z�y�[�W�Q�Ɓj�B�u����Ӗ��̑�䏊�v�Ƃ��������܂킵���A���e�Ȃ�̔���Ȃ������Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�k�t�L�l
�s����S���S�W�t�̎Г��������g�����瑼�̎Ј��Ƀo�g���^�b�`���ꂽ���Ɋւ��ẮA��͂�}�����[����o�Ă���P��g���s���ܖ�k�S5���l�t���A�ŏ��́s���ܖ�t�i1965�N6��10���j�̑�����S�������Ȑ܋v���q�\�\�����҂͖��L�������A�P��̎咘�𓌋����q��w�ł̋����q�ł���Ȑ܂���|���Ȃ������͂��͂Ȃ��\�\��1967�N�ɑސE�������߁A���̌��4���i1970�`74�j���Г��ő��������i�ɈႢ�Ȃ��j���Ƃ��z�N�����B�}�����[�̎Г������̓`���ł��낤�B
���}������́q�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�\�\��������܂̋g�������ɕ����r�i�s�T���Ǐ��l�t1169���A1977�N2��21���j�͋g������ނ����Љ�L���ŁA���̔����������ĈِF�ł���i����������Ȃ�A�u�c�����ꂳ�A�������܂̑I�]�ł��̍��̂ڂ������鍑���R�̋S�R�����ƌ����Ă܂����A����͂������܂��B�ڂ��͏��w�Z�̍�����K�L�叫�ɂ͂Ȃ��Ă��ア�҂����߂͂��Ȃ��������A�R���ł���ɐl���Ȃ������肵�����Ƃ͂���܂���B���͂��J�T�ɒ���Ƃ����̂���Ԍ����łˁv�A�����A1�ʁj�B���Ђł̒n�̕��ɂ́A�����Ƌg�����ɐG���
�@��㎍�̃G�|�b�N�E���[�L���O�ł���u�m���v���l�Ƃ��Ă͂��܂�ɂ��L�������A�����Ƀ��j�[�N�ȑ���ƂƂ��Ă��m���Ă���A���ɕS�_�ȏ�̖{���肪���Ă���B��ꎟ�́w��t�S�W�x�w���Ɏ��S�W�x���͂��߂Ƃ��āw���e���O�Y�S�W�x�w�����Γ�S�W�x�A�V�����Ƃ���ł́A�w�{���S�W�x�w�����Y�S�W�x�ȂǁA�}�����[���犧�s����Ă��鑽���̑S�W�̑���͋g������̎�ɂȂ�B������s�A�ѓ��k��A����N�v����F�l�̎��W�̑���������ɂ��Ƃ܂��Ȃ��قǂ��Ă��邵�A���������̂��ё�V�����܂���܂����w�T�t�����E�݁x�̑�����݂�����̎�ɂȂ�B�T�t�����F�̕z���ɕЎR���̏��N��`�����G���������J�o�[�����A����ɃO���[�̔�����Ƃ�����̍����Ȏ��W�ł���B�i�q�g�����\�\�u���l�Ȃ�Í��̏j�Ձv�̐��E�r�A�s���߂̕��w���\�\27�l�́q�n��H�[�r���k��p���l�t�A�发�فA1982�N8��15���A��Z���y�[�W�j
�Ƃ���B�_�c���Y�E�������g�ҁs�����Γ�S�W�k�S14���l�t�i�}�����[�A1969�N4��10���`1976�N7��30���j�̑����͎Г������������߂��낤�A�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��B�����S����l������A�g���������ł��邱�Ƃ͂����킩��B�e���E�㐻�E�\������E����t���A�Ƃ����l�S�W�����̎d�l�ł���B���E�\4�̒}���̃}�[�N�ȊO�ɐ}�����Ȃ��A�����̂ɂ��W��֘A�̕��������������Ƃ���B�����鑕����r���āA�\���̕z�̑��݂��������Ă�i�\���̔w�������X�~�̐F�������j�B���G�ɒ��҂̏ё���W���ʐ^���f���A�������W��̒��Ҏ��M�̎�ւ���ɔz����B�{���i��2���j�̎d�l�́A����~��l��~�����[�g���E�������y�[�W�E�㐻�۔w�z�\���E�\������B�Ȃ��s�}�����[�}�����ژ^�t�ł̑S14���̃y�[�W���̍��v�́A���O�l�y�[�W�ł���B
 �@
�@
�Γ�����Վ��Y�i1866-1934�j�͓��m�j�w�ҁB�H��єn���m���܂Ȃ��n�i���H�c�����p�m���Ấn�s�j���܂�B�s��㒩���V���t�s��p����t�s������t�Ȃǂ̋L�҂��o�āA���s�鍑��w�����B�x�ߊw�̔��W�ɍv�������B��v�Ȓ�������^�����}���őS�W�́A1997�N12���ɑS���Z�b�g�ŕ������ꂽ�B��������V�����ɉ��߁A�e���̑��ڎ����i�ꕔ����āj�f����B
��1���@�ߐ����w�j�_�@��������@�����@�G�[�Γ�͊����E���ꕶ�����݂ɑ���B�s���R�^���t�́q�Z�捃�܋L�r�́u����@�����B��㧁B�݊C�̎j�_�B�v�̖`���͂������i�T�U�Ȃǂ̌J��Ԃ��L���́A�Ђ炪�Ȃɒu���������j�B
�����O�\��N�Ƃ��Ӎ́A�����Ȃ�Ό�ɂ͂��Ƃ����Z���ɂ߂���Ȃ肯��B�O���\����̏��Ƃ��ӂɂ́A�v�Ђ������ʗƂ��Ώo�łāA�Ⴊ���ΐ�̉��Z���́A�u�����ԂɉG�L�ƈׂ�B�Ƃ�����S�ɂ����Ėׂ֑��߂���}���ǂ��̈ꎆ���̂��炸�D���ƂȂ肵���ɂ���ɁA�S�F�C������e�ƁA�Ⴊ�c����艽�������m���n�������A�����畨����������e�{���ցA������܂̐��o�łċ~�͂�p�m���ׁn�͂Ȃ��āA���������ɂȂ����邱���A���ւ����ւ��A�⊶�Ȃ肵���B�l���ɂ͎n�߂Ďq�Ƃ��ӂ��ׂ̖��ʁA�߂ł����Ɛl�ɂ��j�͂�A������ӂ͐��̂˂̏K�͂��Ȃ߂�ǁA���̖Z�����́A�Г�ɂ��͂�ׂ������炸�B�����ĎO���m�݂��n�l���m����n�����͂�◎���m������n�Ǝv�ӊԂ��Ȃ��A�������̖����A�x�ߎO���̗��ɂ͏o�ŗ����ƂƂ��Ȃ肯��B���͌��m���Ɓn���̌Ⴊ�u�ɂāA���̂��ю��@�n�߂ē������āA���F�̎^�������A���N�̖]�𐋂���Ɏ��肽��Ȃ邪�A�H�c�Ȃ镽�F����ȂɁA�ߐ����w�j�_�̘C�������ɂ�����������]���A�����ɂ��ȂЂāA�̖S�F����߂Ė��������ƌ��Ђ���������A���m�����n��ɍ��̂̊��Ɋ��ւ��肯��B�i�{���A���y�[�W�j
�g�����Γ�S�W���n�ǂ������ǂ����͂킩��Ȃ����A�q�x�ߊG��j�r�q�G��j�G�[�r��A�[�g���ɕʍ���́q���F�ʐ^���r�Ȃǂɂ͋��������������낤�B�g���������ɂ�����w�҂̑S�W�Ƃ��āA�N���X���̓��؏��O���s�[����W�k�S2���l�t�i�}�����[�A1968�N9��25���E10��30���j���m���̑�\�Ȃ�A�z���́s�����Γ�S�W�k�S14���l�t�͘a���������͓��m���̑�\�ł���B���s��40�N���o�āA�����ћ�͂��悢��P���B
�|�����q�]�_�W�s�Ǐ��̍Ό��t�i�}�����[�A1985�N6��30���j���s����̕��́t�i���A1976�N6��10���j�ɑ������㕶�w�Ɋւ���]�_�W�ł���B�{���̎d�l�͈ꔪ���~��O��~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B���t�Ɂu����^�g���@���v�u�J�b�g�^�����@�v�ƃN���W�b�g������B�s���肾�����s����̕��́t��E���āA�Ȃ��ݐ[���g�����������߂��Ă����B�ׂ��ȃG���{�X�Ŏ������o����PP���H�ɂ���ĉ����h���N���[���n�̃W���P�b�g�ƁA���̑ю��̂Ƃ荇�킹���݂��Ƃ��B�W���P�b�g�̔��̃J�b�g�́A�̂��̏���R�c�q��Ԃ�ǂ邵����r�̃}�[�N��z�킹�邪�A�ގ��͋��R���낤�B�����Ɂu���a�Z�\�N�܌��v�Ƃ���q���Ƃ����r�ɋg���ւ̎ӎ�������B�S���������B
�@��N�قǑO�ɁA��Ƃ��Č��㕶�w�ɂ��ď��������͂������W�߂āA�}�����[����u����̕��́v���o�����B���x�v�X�ɓ��n��̐V���u�Ǐ��̍Ό��v���o���ɓ����āA���̃G�b�Z�[�W�ɕ��U���Ă������̂̒�������A��A�Ă����������͂�I��ŕ������邱�Ƃɂ����B�O�����l�A�g�������̑�����̂͊��тł���A�ҏW�̈�������[�̑���ʎq����̂����b�ɂȂ����B���̖{�̐����������ĉ������������̕��X�ɕ����ĐS����̂����\���グ�鎟��ł���B�i�{���A��l���y�[�W�j
�э_���́A�|���̕]�_�̘_������X�������₩�ŁA������̒j���̕��|�]�_�Ƃ������Ȃ₩�ȃ��S�X��a���o���A�Ǝ^����悵�Ă���i�q�w���t�ށx�͒|�����q�̍u���W�{�̔@�����t�ƌ��c�Y�b�r�j�B�ł́A���Ē}�����[�̕ҏW�҂������|���͕]�_�Ƃ����̎d�����ǂ����Ă���̂��B
�@�}�����[���ǂ������o�ŎЂł��邩��[�I�ɒm��ɂ́A�}���p��������Ƃ悢�B����͏��[�̏ے��I�Ȋ�ł���B�^���ɂƂ��ẮA���яG�Y�́u���|�]�_�v��A�������v�A�P��g���A���쌪�̎O���ɂ��A�����A�吳�A���a�̎O���̕��w�j�A���؏��O�́u�����̕��w�v�����߂�p���ł���A�֓��g�́u��̎l�\�N�v�A�g��K���Y�́u�m�ᎄ�L�v�A���A���c���Y���́u���{�̒m���l�̎v�z�v�����p���ł���B�����ɛZ�тȂ��Ƃ����̂́A�����ɖ��S�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����낤�B���ɍ��������ʒ����ɗ̖͂������Ƃ́A���̑p�����悭����Ă���B�����ɗx���ĕ����点��̂͐l�Ԃ̕s�K�ł���Ƃ������Ƃ��B�i�q�}���p���i�}�����[�Łj�r�A�{���A��l�Z�y�[�W�j�|�����g���ɐG�ꂽ���͂ɂ́q�a�c�F�b����̂��Ɓr�i�s�Q���t1977�N12�����j�Ɓq�g��������r�i�s�����܁t1990�N6�����j������B��������S�̂��������Ǔ������B�s�����C�J�t2002�N11�����́q�_�c�̐l�X�r�ɂ͂�������B�u�}�����[�ɂ́A���l�̘�c�j�Y�A�g�����A����N�v��������ꂽ�B�k�c�c�l�g�����͍L����`���Ȃ̂ŊK�͈���Ă������A���Ђ���������ꂽ�O���ɑ��ĉ����������v�i�s����̖����t�A�y�ЁA2003�N7��5���A���O�y�[�W�j�B���́u���Ёv�́A�͏o���[�ł���B
![�|�����q�]�_�W�s�Ǐ��̍Ό��t�i�}�����[�A1985�N6��30���j�̖{���ƃW���P�b�g](image/takenishi_2.jpg)
�|�����q�]�_�W�s�Ǐ��̍Ό��t�i�}�����[�A1985�N6��30���j�̖{���ƃW���P�b�g
�|�����q�]�_�W�s����̕��́t�i�}�����[�A1976�N6��10���j�́A�~�n���q����p�c���q�܂ŁA���㕶�w�Ɋւ���40�т̕]�_�����߂�B�{���̖ڎ��ɂ́A�q���͓ǖ{�r�Ƃ��̊J�n�y�[�W�A�Ƃ����ӂ��ɗ��L���Ă��邪�A�{�����̌��o���i�^�C�g���j��
�@�@���͓ǖ{�i�J�菁��Y�E��[�N���E�O���R�I�v�E�����^��Y�j
�Ƃ�����Ɏ����L���Ă���i���̏ꍇ�A�����ł͂Ȃ��e�����Ƃ̓���̒P���j�B���o���ɂ��钘�ҁE��ҁE�Ҏ҂𖼊���ƁA�ő��o���5��̉~�n���q�ŁA3��̉F���オ����ɑ����B2��͈������j�E��[�N���E�͖쑽�b�q�E�J�菁��Y�E�����P�q�E�����^��Y�E�ѕ����q��7�l�ł���B���̂����肪�Ƃ�킯�|���̈��ǂ��鏑���肾�낤�B1��́A�������E���W�E�����Y�E���؏��O�E���|���L�E�Ŗ؍D�q�E�����D�q�E�����O�Y�E�ҖM���E�p�c���q�E�O�H���Y�E������E�����t�E���i���F�E���}�Òj�E�O�c���ܘY�E�O���R�I�v�E�R����v�E�R�����E�R�c���E�R�{���g�E�g�c�G�a��22�l�i�Ȃ��ɂ́A�O�H���Y�ɂ��Ắq�ւƔ��E��H�E�}���点�̔N��r�̂悤�Ȓ�����������j�B�����́q�����r�́A50�����̍�҂̉��ɑΏۍ�i���������Ă���A���J�ȕҏW�Ԃ肾�B����Ɋr�ׂāA�{����͂���y�ł���B�{���̎d�l�͈ꔪ���~��O��~�����[�g���E��l�Z�y�[�W�E�㐻�����E�@�B���B���t�Ɂu����^�g���@���v�ƃN���W�b�g������B�d�l�͂Ƃ������A�f�ނ̑I����F�����ɂ����ЂƍH�v�����Ă��ǂ������B���E�\���E���Ԃ��E�{����ʂ��Č��Ă����ƁA�ǂ����ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂����A�S�̓I�ɒ��q���O��Ă����ۂ͔ۂ߂Ȃ��B�c�O�Ȃ���A�g���炵����ʎd���Ԃ�ƔF�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
![�|�����q�]�_�W�s����̕��́t�i�}�����[�A1976�N6��10���j�̖{���Ɣ�](image/takenishi_1.jpg)
�|�����q�]�_�W�s����̕��́t�i�}�����[�A1976�N6��10���j�̖{���Ɣ�
�@�u�}�W���l�ԁv�̒��҂̕��͂́A���{��͂����A�Ǝv�킹�镶�͂ł���B�^�p����l�̉^�p�̂����ɂ���āA�p���������A�����Ђт����A�悭����邭���Ȃ�̂����t�ł���A���{��ł���B�u�����������v�Ƃ����l�͏��Ȃ��Ȃ��B�����������̕��͂ŁA����ւ̐Ȃ���������Ă݂���̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��B����́A���łɂ������A����̂���^�p���A����I�ɓ��P������ނ悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ�����ł���B�ߋ��ɂȂ��A������ɂȂ��A����̉^�p�ɂ��Ă̐V�����悢����������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���B����́A���̐l�̂��̂̊������A�l���悤�A�������ɂ������B���Ɍ��킹��A���������e�ՂłȂ����Ƃ����łɍs�Ȃ��A�����Č��ɍs�Ȃ����鐔���Ȃ����{�l�̈�l���A�u�}�W���l�ԁv�̒��҂Ȃ̂ł���B�i�q���N�V���Ղ��E�}�W���l�ԁi�R�����j�r�A�{���A����y�[�W�j
�|�����q�͋g�����̓��L�ƔN���ɓo�ꂷ��B1960�N3��7���u�ߌ�A�|�����q�ƐH�������̃R�[�q�[�B�ޏ��̓`�[�Y���~�����Ƃ����B�ꎞ�ԂقǎG�k�B�d�����Z�����̂����Ă����v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�A1967�N3��23���u���i�~�m�َq�X�Ŕ��������Ɖ�B�O�\���̒x���B�Ȃփq���V���X�̉Ԃ����炤�B�����ނ炳���̉ԁB���ނ������B�|�����q����̓d�b�A�����������֍s���Ƃ̂��Ɓv�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�y�[�W�j�A�����Ď��M�N����1978�N�̍��u�����\����A�}�����[�|�Y�B�F�l�m�Ȃ��猩���̓d�b�E������B�c�������ɖv���B�ݐE��\���N�A�\�ꌎ�\�ܓ��A�ގЁB�k�c�c�l�|�����q����A�~���~�̔���Ⴄ�B�\��\�ܓ��A�����Ȃ��������B�҂����t���v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O�܃y�[�W�j�B
�|�����q������҂q�N���r�ɂ́A1957�N�u�l���A�}�����[�ɓ��ЁA�w������{���{�S�W�x�w�ÓT���{���w�S�W�x�Ȃǂ̕ҏW�ɏ]���v�A1962�N�u�\�A�}�����[��ގЁv�i�s�|�����q����W��܊��k���z�U�l�t�V���ЁA1996�N6��30���A�O�Z�y�[�W�j�Ƃ���B1962�N�܂ł͂Ƃ��ɒ}�����[�̓����Ƃ��āA�g�����͍L�����̎��l�A�|�����q�͕ҏW���̔�]�Ɓi�̂��ɏ����Ɓj�Ƃ��������������ɂ������킯���B���́s�|�����q����W�t�ɂ͖{���̏������L�ڂ���Ă���̂ŁA�����Ă������i�����A�l�l�y�[�W�j�B�Ȃ��A���^��i���͏ȗ������B
�@����̕��́@�@�]�_�W
�@���a�\��N�i��㎵�Z�j�Z���\���@�}�����[��
�@�l�Z���@��O���Ł@���\���@�����@�艿���Z�Z�~�@�@�@����E�g����
�@���k�c�c�l�^���Ƃ����^����
�R�{���g�́s���̎��o�̗��j�\�\�������̎��l�m�����тƁn�����t�i�}�����[�A1979�N2��25���j�́A�}�����[��1978�N6���Ɏ�����|�Y����8�ӌ���Ɋ��s���ꂽ�B1979�N6���ɓ��Ђ��犧�s���ꂽ���e���O�Y���W�s�l�ށt�̊�悪�A���e�̌����Ƃł�����p���w�҂̐V�q�r��ƒ}����ގЂ��ĊԂ��Ȃ��g�����ɂ���ē��N1���Ɏn�܂������Ƃ��l����A�{���̐���͓|�Y�O��̏��ŁA�Ȃɂ��Ƃ��Ȃ��������̂悤�ɐi�߂�ꂽ���̂Ɛ��@�����B�s���̎��o�̗��j�t�͂����Ȃ鎖����낤�Ƃ����s����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�}���̌ÓT���l�_�̑p���q���{���l�I�r�̊ďC�҂��P��g���ƂƂ��ɖ��߂��R�{���g�̎咘������ł���B���҂ɂ��q���Ƃ����r�i�u���a�\�l�N�ꌎ�l���v�̓��t�����j�́A�Ō��̌����ɂ��Ă����������M���₵�Ă��Ȃ����A���̖��Ɏ��̈�i������i�Ȃ��s���|�W�]�t�͒}�����[���s�̋G�����|�G���ŁA�g�����ҏW��S�����Ă����o�q���s�����܁t�Ɠ��l�A1978�N7���ŋx�������j�B
�@�i�N�����������̏��ɂ��Ă̊��z�́A����߂đ���ŁA���̂��Ƃ����ł���������s�������Ƃ͏o���Ȃ��B�����ł́A��������̉��b��ւ����A��t�܌��M�v�̊O�A�����̐�w�̕������ɁA���ӂ̌��t��\���q�ׂĒu�������B�܂��A�����G���u���R�v�ɍŏ��̍e�������o�������A����������Ă��̊��s������}�����[�̍���C���A���Ƃɒ��N�ɂ킽���đ����̂͂��܂��������������A������������q����ɂ���\�������B�܂���\���͈Ȍ�́A�������̜ϜȂŎG���u���|�W�]�v�ɏ��������̂����A���̑O�Ɏ��ɘA�ڂ������߁A���̐g����A�C�܂���ɑ��Đr������ł������u���R�v�ҏW�����N�ɂ��ӎ���\���q�ׂ����B�܂��A���̏��̊��s�ɂ��Ĉ��S�����ꂽ�j������N�A���B�Ɏ���k�}�}�l���ꂽ�g�������ɂ��A�S����L��̌��t�𑗂肽���B�i�����A�l��Z�`�l���y�[�W�j
�{���͍u�k�ДŁs�R�{���g�S�W�k��3���l�t�ɁA�����ɂ͂Ȃ������q�� ���̎��o�̗��j�r�\�\�s���{���������k��9���l�t�i�V���ЁA1961�j�ɔ��\�A�̂��Ɂs�`�{�l���C�t�i�V���ЁA1962�j���^�\�\�������ɐ����āA�����́q���Ƃ����r�Ɓq���p�̍����r���܂߂��S�т����߂�ꂽ�B�p�f�ł���B�ƌ�����������P�`������悤�����A�ҏW���ɂ��q���r��
�@�Ō�Ɂw���̎��o�̗��j�x�̑̍ٓ��ɂ��ďq�ׂ�B����́k���a�l�\�l�N�ɒ}�����[���甭�s���ꂽ�B�e���A�z�\���A������A�{���l���ŁA���Ɉ��p�̍������ł�����B�艿�͎l��Z�S�~�B���Ԃ��́u����r�v�͕��R��v�ł���B����͖������ĂȂ����}�����[�W�҂Ǝv����B�i�s�R�{���g�S�W�k��3���l�t�A�u�k�ЁA1983�N11��20���A�O���Z�y�[�W�j
�Ƃ���u����͖������ĂȂ��v�́A�������t�̍Ō�i�R�s�[���C�g�\���̑O�j�Ɂu���B�ҁ@�g�����v�ƌf�����Ă��邩��A���ł���B�S�W�ł͂��������P�s�{�q���Ƃ����r�́u���B�Ɏ�����ꂽ�v���u���B�Ɏ��݂��ꂽ�v�i���O�A�O�Z�Z�y�[�W�j�ƒ����Ă���̂�����A�q���r�ɂ́u����͋g�����v�Ɩ������Ă��炢���������B���̍ۂ���������ЂƂA�g���͂��̂Ƃ��u�}�����[�W�ҁv�ł͂Ȃ��B�}���̂n�a�ł͂��邪�A�����Ɍ����t���[�����X�̑����Ƃł���B�Ƃ���ŁA�R�{�́u���B�Ɏ��݂��ꂽ�k�A�A�A�A�A�A�l�v�͉����Ӗ�����̂��낤�B�g���̂ق��Ƀ��C���̑��B�҂����āA�⍲�����Ƃ������Ƃ��B����Ƃ��P�ɁA���Ԃ��G�𐧍�i���邢�͒j�������R��v�ɋC���g���������̂��Ƃ��B�ނ��A�G�͂ǂ��܂ł����Ă��u����v�ł����āu�����v�ł͂Ȃ��B
���͖{���̈ꕔ���������Ƃɍ�����o����B�ǂ����̃p���O���t�ɖ{�����\������킯�ɂ͂����Ȃ����炾�B����Ƃ����Ă͂Ȃ��A�{���Ɠ����q���̎��o�̗��j�r�Ƃ����W��̕��͂������ɒu�����R�{�̋����s�ÓT�ƌ��㕶�w�t�i�u�k�ЁA1955�N12��5���j�́q���Ƃ����r�̈ꕔ�����p�������B�u���{�̎��̎��o�̗��j�����ǂ邱�Ɓ\�\���ꂪ���̍ŏ��ɗ��Ă��v��ł����B���̎��o�̗��j�����ǂ�Ƃ������j�̂Ȃ��ɁA����⎍���̓W�J�����ۂ���A�Ō�ɋߑ�I�ȎU�������̊m���ɂ����āA�s���I�b�h���ł����͂��ł����B���̌v��́A��̂̃A�E�g���C����`���o�������ŏI���Ǝ����ł��v�Ă��邪�A�������̏������A���̍L���Ӗ��ł̎��_�̏��Ƃ��ēǂ�ʼn�����ǎ҂�������A���͂����ւ�L��Ǝv���B����ɂ܂��A����ɂ����鎍�I�ӎ��̕ϊv�ɁA�Ȃ�炩�̈Ӗ��Ŋ֘A�����Ƃ���̌���̎��_�̏��Ƃ��ēǂ�ł���������A����ɗL��Ǝv���B�ÓT�����A���w�̓`��������Ȃ���A���̊S�͂����̍����̕��w�ɂ���A���̈Ӗ��ł́u�ÓT�ƌ��㕶�w�v�ł����̂�����\�\�v�i�����A����y�[�W�j�B
�{���̎d�l�́A��ꎵ�~��l���~�����[�g���E�܁Z�l�y�[�W�E�㐻�۔w�z�\���E�\���B�ڂ̂��z�n�ɋ��������̕�������������Ɖf���錩���ȑ��{�ł���B������̃N���W�b�g�́u���Ԃ��G�@����r�@���R��v�v�ƌr���̃A�L��9�~�������Ȃ��̂͋��������B�{���ƌr���̃A�L��39�~��������̂�����B���̈ꎖ�������Ă��Ă��A�g�����S�������͕̂\���܂��i�\���E�\���E���Ԃ��E�{���j�����ŁA�{���p���ɍ���ꂽ���ʂ̎w��́u�}�����[�W�ҁv�ɂ����̂Ǝv����B

�}�����[�����̊��s�ɂȂ݂Ȃ݂Ȃ�ʗ͂𒍂����{���́A1979�N�A���ꉳ�F�́s�鍐�t�ƂƂ��ɑ�11����{���w��܂���܂����i�I�l�ψ��͑�]���O�Y�A�i�n�ɑ��Y�A�O�H���Y�A�ےJ�ˈ�j�B
�ےJ�́q�y��]�z�w��ƃG�b�Z�C�̏d�Ȃ�Ƃ���r�ŁA�i�n�ɑ��Y���{������{���w��܂ɐ��E�����A�ƌ���Ă���B�����́A����̔�]�Ƃ����\�\�R�{���g�A�������v�A���яG�Y�\�\�̈�M�����ł���Ɠ����ɁA�i�n�ɑ��Y�̏����ȏё��ɂ��Ȃ��Ă���B
�ےJ��]�̐^�����ł���B
�u�w��Ƃ����~��������������������A�����ɂ������肷���ł��ˁB�d�Ȃ�Ȃ��B����͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l����ƁA�ߑ���{���w�ł͊w�₪�y�̂���Ă����B���������C���������������āA���Ƃ��Ζ����O�\�N��̎��R��`���w�̗������ł́A�Ėڟ������ꂾ���y�̂��ꂽ�킯�ł��B�^�l��������ɐɂ����̌������̂́A���{���w��܂̂Ƃ��������ȁB��ꎟ����Ƃ��Ďi�n�ɑ��Y���R�{���g����́w���̎��o�̗��j�x���������B����������O�H���Y���A�u���������͔̂�]�Ƃ������̂����ȁB����͊w�₾�ȁB��]�Ƃ����̂͏��т̏����悤�Ȃ��̂��A����͔�]����Ȃ��v�Ƃ�������B����ɑ��Ďi�n�ɑ�Y�͏������������A�u�O�H����̂�������邨�C���͂킩��܂����A�������ǂ��ł��傤�A�O�H�����͂�������܂肢���߂��܂����ˁB���̂����ł�����]�Ƃ��o�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��ł����v�Ƃ������B�^�l�͂�����āA���̂悤�Ȃ��Ƃ��������B���яG�Y�̔�]����]�̌��^�ł���Ƃ������b�ł������A����������Ȍ�̔�]�Ƃ����яG�Y�ɂ܂���ʂ͂����ł��B���яG�Y�̕��͈͂А����悭�Ď��ꂪ�悭�āA�C������������ǁA���������������Ă���̂����͂����肵�Ȃ��B�������v��R�{���g�̕��͎͂���̂悳�Ƃ����_�ł͏��яG�Y�ɗ�邩������Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����������Ă���̂��͂悭�킩��B���������Ӗ��ŁA���яG�Y�̔�]�͖������@�̕��̂Ɏ��Ă���B�C���̂������̂Ƃ����l�����邪�A���ɂ͉��̂��Ƃ������Ă���̂��悭�킩��Ȃ��B�����ւ䂭�ƒ������v��R�{���g�̕��͂͂��������u�����͂Ȃ�����ǁA���e��`�B����\�͍͂����B���̈Ӗ��ł���͌��s���@�݂����Ȃ��̂ł���B���������b�����āA�܂����̂Ƃ��͂ނɂ��
�ɂ�ƌ��_���o�Ȃ��܂U�
���B���ǂ́w���̎��o�̗��j�x�͌��Ɏc���Ď�܂�����ł����B�^���N�������������̃p�[�e�B�[�Ŏi�n����ɉ������A�u��̏��яG�Y�͖������@�Œ������v�͌��s���@�Ƃ����b�ˁA������u���̂Ƃ��Ɏg���Ɣ��Ɏ�A�ǂ������肪�Ƃ��v�Ƃ����悤�Ȉ��A���������v�i�ےJ�ˈ�k������E����L�l�s���w�̃��b�X���t�A�V���ЁA2010�N5��10���A��ܓ�`��O�y�[�W�j�B
�g������1961�N7��12���i���j�̓��L�Ɂu�g��O����s�����t�Ĕł����炤�B���������ł悲���̂ŁA�͂��߂ăG������������B�������C���v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���܃y�[�W�j�Ƃ���i�u�G���v�͑O�N�̏t�A�҈䋪����Đl����킯�Ă���������X�̃V�����L�j�B�g���̕��͂ɋg��O�̖����o�Ă���̂͂�����ӏ������A���́q�f�ЁE���L���r�͓E�^�ŁA�ȑO�ɖʎ������������ǂ����킩��Ȃ��B�g��̏������W�s�����t�Ĕł̊��s��1957�N������A���̂Ƃ��͂܂����W�𑗂�ԕ��ł͂Ȃ������̂��낤�B�g��́q�������W�w�����x�̎v���o�r�i���o�́s���㎍�蒟�t1978�N1�����j�ɂ��������Ă���B
�@��ꎍ�W�w�����x�͓��ʍ���E�{��54�ł̂�������Ȃ��̂ŁA���ƔłƂ��āA���a32�N5��1���A��Z�Z�������s�A8��1���ɁA��܁Z�����Ĕł����B���^�ѐ��͏������܂߂�24�сB
�@���@�́A��172mm�~�c240mm�ŁA�a�T����肿����Ə����߁B�{���p����100kg���x�̔��㎿���B�\����200kg���x�̔��㎿���B�̍ق́A�u�����v�Ƃ����������ɕ��ׁA�\���̍���ɒu���������B�����w���Ɂu���W�@�����@�g��O�v�Ə����Ă���B����Ƃ������Ȃ��悤�Ȏ��ɂ������肵�����̂����A�����A�Ȃ����]�v�ȑ�����]�܂Ȃ��C�������������Ă����B
�@���Ԃ��ɂ́A�{���p������┖�ڂ̉��F���㎿�����g���A���A�V�ю��ɂ����B�ꖇ�ڂ̍�����ɁA�`���R���[�g�F�̃C���N�ŁA�c�Ɂu�g��O�v�ƍ��肱��ł���B���Ԃ��̎����ɔ������̔��������A���̎����̑�1�Łi���Łj�ɏ������A�{���̕�������⏬���߂̕����Ŏ��߁A2�Ŗڂ���{�����n�܂��Ă���B�ڎ��Ȃ���54�ŁB�Ƃ��낪24�ђ���1�сu�g���S���H�v��2�A�̒E��������̂ɋC�t���A����\��p�݂��B�u36�ł�37�ł̒��Ԃɉ��L������܂��v�Ə����A2�A�������������Ђ������Ă���B������Ĕłł͉��߂����A���ł�54�łŁA���ł̂Ƃ��ƕς��Ă��Ȃ��B
�@���\���̂ق��̌��Ԃ��̓�t���A���߂̈�t�ɉ��t��������B���t���̏㕔�Ɂu100���̂����̇��\�\�v�Ƃ������������邪�A���̔ԍ��͏�������Ȃ������B�������̇��̎����ɔԍ��������Ă�����A����͒N��������ɏ��������́B���s�҂́u��c�s�V����Z�܁@���c�M�Y��欎��̉�v�A����͎�c�s���̒������ʓ��B���ǂ��Ȃ��Ă��邩�m��Ȃ����A�����̂��₶���S�����߂ď����Ă��ꂽ���̂ŕ������������B���t�Ɂu���s�����@��Z�Z���v�Ƃ���u�i�v�Ƃ������Ă���B�Ĕł́A����̈�l�ł��钆�����ʓ��̓X��ɏ����Ă�������B�Ĕł̉��t�ɂ́u���s�����A���ň�Z�Z���@�Ĕň�܁Z���v�Ə����Ă���B�Ĕł��o�����̂œ��ӂ������炵���B�Ȃ��A�Ĕʼn��t�ɂ��u150���̂������\�\�v�����荞���A���ۂɂ͔ԍ�����������Ȃ������B
�@��p�͏��ň�Z�Z���Ɍܐ�~���g�����B�ꕔ�������50�~�B�啔���͊ɂ��Ă����A���p����100�~�ɂ����̂œ����̗X����20�~���x�S���Ă��A����ɂ���̍������������B���a32�N�����̌ܐ�~�͂킪�Ƃ̕n�R�ƌv�ł́A���Ȃ�̕��S���������A���[�a�A�ǂ��Ђ˂�o�������A�|���Əo���Ă��ꂽ�B�i�s���ւ̒ʘH�t�A�v���ЁA1980�N12��1���A���O�`���l�y�[�W�j
���W�s�����t�Ƃ���qI was born�r�����A���ɂ͋g�����́q���b�r�i�B�E15�j��z�N������q�L�^�r���Y�ꂪ�����B�q���b�r�́q�L�^�r�̑�5�A�����Ő��藧���Ă���悤�Ȏ����Ƃ�������B
�@��؈Ă̏o�������B�������ł́@���ɕς�ʒk�������ɍ炢�Ă����B
�@���肰�Ȃ��@���̖�������l�͂Ђ����Ɂ@���₵���@���͂��̕K�v���Ȃ������̂��B
�@�����@�o�͂���Ƒ��܂�@�l�͒x���҂̂悤�ɓ���B
�@�X�g�͍��܂����B���̒��͎˂��@�c�����҂͌��ʂ��̊m���������ɂ����B
�@��ӂŁ@���̖��E�����̂������B�ڗ]�̃��X���S����˂��@�S�Ƃ��]�V������Ɓ@���͊����Ȃ��G��܂����B�f����������@�N���������Ղ�@�ᑐ��Z�������Ƃ��@���̐K�̌������𑈂��ē����o�������̊���ڌ������B
�����c��������ł����B
�u�ڗ]�̃��X�v�Ƃ����A�`�e�����Ƃ��v����C���[�W�̏Փ˂������炷����̐ꖡ�A�N���Ǝᑐ�̕�F�̑Δ�A�u��𑈂��ē����o���v�Ƃ����u�������̂����Ȃ��`�ʁ\�\���������`�ʂȂ̂��낤���A�ނ��뎖���̔�����Ԃł͂Ȃ��̂��\�\�݂͂��Ƃƌ��������Ȃ��B
 �@
�@
�s�g��O���W�t�i�y�ЁA1981�N4��7���j�̔��ƕ\���Ɓs�g��O�S���W�k�V���Łl�t�i���A2004�N7��10���j�̕\���k�����F�������ق�l�i���j�Ɓs�g��O���W�t�Ɓs�g��O�S���W�k�V���Łl�t�̔��i�E�j
�s�g��O���W�t�i�y�ЁA1981�N4��7���j�̎d�l�́A��Z��~��O��~�����[�g���E�l�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�\���B�\���͋g���̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�Ɠ����悤�ȕz�������A�{���̂ق����ڂ���ł��āA��ɂ������肭�銴�����i�����d�ʂ��Ⴄ����A�P���ɔ�r�ł��Ȃ����j�B�s�g��O���W�t�́A�}���̔ʼn撲�̏����Ƃ����A�f�ނ̐F���̓W�J�Ƃ����A1�N����s���ؒ��h���W�\�\1960�`1982�t�i����R�c�A1982�N4��30���j��z�킹����̂�����B�ʐ^�́s�g��O�S���W�k�V���Łl�t�i�y�ЁA2004�N7��10���j�́A���ċg���̂��ƂŒ}�����[�̎Г�������S�������������ق�̑����B�S���W���p���\���A���g���̒}���ł̎d����f�i������B
�k2019�N11��30���NjL�l
�{�e���f�ڂ�����2014�N��1��15���A�g��O�͗�����88�i�Ď��j�ɂȂ낤�Ƃ����O���ɟf�����B���N5��15���Ɋ��s���ꂽ�s�g��O�S���W�k����V�Łl�t�i�y�ЁA�����F�������ق�j�̊����ɂ́A�u��Z��l�N�l���v�̓��t�̂���q����V�ł̂��߂̂��Ƃ����r���̋v�ۓc�ށX�q�������Ă���B�����ɂ͋g��O�ɂ��S���W�̂��Ƃ����ނ����^����Ă��āA����Ɉ˂�g���������ɂȂ�s�g��O���W�t�i�y�ЁA1981�j�̂��ƁA���̌�̎��W�Ȃǂ₵���s�g��O�S���W�t�̑�1����1994�N4���ɁA��2�������N6���ɁA��3�������N9���ɓ��Ђ��犧�s����Ă���B���̎�����f�́s�g��O�S���W�k�V���Łl�t�i���A2004�j�ŁA�g��͓����Ɂu��Z�Z�l�N�܌���Z���v�̓��t�̂���q�V���ł̂��߂̂��Ƃ����r���Ă���B�Ȃ��A�s�g��O�S���W�t�ɂ́q�̎��ꗗ�r�Ƃ����͂������āA��ȁF���c�O�Y�́q�����g�ȁw�S�̎l�G�x�r�����߂��Ă���B�Ȃ��ł��u�Ⴊ�͂������@�ӂ�Â���^��̔������@���炦�Ȃ���v�Ǝn�܂�q�i�Z�j��̓��Ɂr�͒����Ȋy�ȂŁA�������̂b�c�Œ������Ƃ��ł���B���͖{�тɕ��ׂāA�g�����q��r�i�B�E14�j��u���Ă݂����U�f�ɂ�����B
���W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�̈�����͑���{���������Ёi�����s������s�J���꒬��̈��@����ҏ���Ёj�ŁA�s�����G�߁t����������P�ѓ��i�����s���{���抝�꒬��̎O�@����Җ{�c�ӈ�Y�j�Ɋr�ׂĂ͂邩�ɑ傫�ȉ�Ђł���B��O�̂��ƂƂ͂����A�l�̎���o�ł�S��������������Ƃ͎v���Ȃ��B�g������1940�N2���̓��Ќシ���ɐ��삵���������X�̏o�ŕ��\�\��˔����Y�s��������̗��ꂩ��t�i3��25���j��k�C�������s�k�C���̌���`���t�i���{����o�ŎЁA3��30���j�\�\�ő���{����Ƃ��������n�܂������߁A�\�ɂȂ����̂��낤���B�^���͕s���ł���B�ѓN�v����́s�����G�߁t�ɐG��A�P�ѓ��ɂ��ď����Ă���B
�u���t�̈�����u�P�ѓ��v�{�c���͌�������P�ѓ�����X�i�����s��������{�����Ԓ�13-12�j�ƊW������悤�Ɏv����B�Ⴆ�A�{�c�N�玁�i�Q�n��w��w�@����w�����ȃQ�X�g�u�t�j��HP�ɂ��ƁA����1958�N�������{�����꒬���܂�A�s�\�c���͓��{���`�{����e��̕M�E�l�u�P�ѓ��i�ق����ǂ��j�v�t���Ƃ��B�܂��͕ʂ̃y�[�W�ɂ́s�吳�U�N�́u�c�ƎҐ����^�v������Ə��Ԓ��P���ڂɂ́m���n�A�Q���ڂɂ́m���n�A�X�������N�M�̖P�ѓ��c�c�t�ȂǂƂ���B���S���Ɂu�ێR�P�ѓ��v�Ƃ������X�E����X�����邪�A�g�������H���ǂ������B�v�\�\�u����Ƃ������Ƃł́A�g�p����Ă��銈�������Ȃ̂��C�ɂȂ�Ƃ��낾�B�R�s�[�̔ŖʂȂ̂Œf��͂ł��Ȃ����A�����͂��������r��Ă���B���̉̂ɂ́u�́v���l�g���Ă���Ȃ��Ɉ�����ʎ�̊������������Ă���B�����Ȉ�����ł͗L�菟���Ȃ��ƁB�v�\�\�u���͓̂����z�n���Ő�������9�|�C���g�����́i����44�N���j�Ƃقړ���̂悤���B�Ђ炪�ȂŌ����u�Ӂv�̓��̓_���E�ɂ����ƃG�r������S�J�[�u���ւ��Ⴐ�������ɂȂ��Ă���̂������I�B�G�p�Ɂ`�����Ђ́u�Ӂv�͂����悻�^�e�̃Z���^�[���킸��
�ɍ�����S�������Ɣw���L�т��ӂ��ɂȂ��Ă���B�ׂ������Ƃ����A����͌Â����̂��鏑�̂ł͂Ȃ����낤���B�g���̍D�݂����f����Ă���̂��A�P�Ȃ���R���B�v�i�q�����G�߁rdaily-sumus�@2007-09-21�j
�т���قǐ�O�̊����ɏڂ����Ȃ��̂ŁA���������̕ϑJ�����ǂ�����发���Q�ł��Ă݂�ƁA�s�t铁t�͏G�p�ɑ̂̊������g�p���Ă���悤���B����{����́A�G�p�Ɂi1876�N�n���j�Ɠ��������1935�N�ɍ������Ăł�����Ђ�����A�G�p�ɑ̂łȂ�̕s�v�c���Ȃ��̂����B�s�t铁t�́s�����G�߁t�ƈقȂ�ʏ�̗m�{�d�l�ŁA�{���͋����������A�܍�17�s�g���ň���B���{�̍\�����T�ς��邽�߁A�ȉ��ɑS�̍\�����䊄�𗪋L����B�m�@�n�Ŋ������m���u���́A�y�[�W�i���o�[��\�����Ȃ��u�B���m���u���v�ł���B
| �� |
�y�[�W |
�m���u�� | �v�f | ���� | �L�ړ��e |
| 1 |
1 |
���Ԃ�1 | �i�������j | �k�t�����X���\���̐c���l |
|
| 1 |
2 |
���Ԃ�2 | �i�������j | �k����l |
|
| 1 |
3 |
���Ԃ�3 | �i�V�ю��j | ||
| 1 |
4 |
���Ԃ�4 | �i�V�ю��j | �k���c�唪�������{�͂����Ƀy�������Ō��提���l |
|
| 1 |
5 |
�\ |
��1 | �{�� | ���W�^�t铁^����ɔ� |
| 1 |
6 |
�\ | ��2 | �i�E�����j | |
| �ʒ� |
�i1�j |
�\ | ���G1 | �ё��ʐ^ | ���ҋ߉e |
| �ʒ� | �i2�j | �\ | ���G2 | �i�E�����j | |
| 1 |
7 |
�\ | ��3 | ��� | �g�������W |
| 1 |
8 |
�\ | ��4 | �i�E�����j | |
| 2 |
9 |
1 |
�O�t1 | �ڎ�1 | ���W�@�t铁@�ڎ��^�ߑO�̕��^�k�c�c�l |
| 2 |
10 |
2 |
�O�t2 | �ڎ�2 | �k�c�c�l�^�ߌ�̕��^�k�c�c�l |
| 2 |
11 |
3 |
�O�t3 | �ڎ�3 | �k�c�c�l |
| 2 |
12 |
�m4�n |
�O�t4 | �N���W�b�g1 |
���Ҏ��� |
| 2 |
13 |
�m1�n |
��5 | ����1 | �ߑO�̕� |
| 2 |
14 |
�m2�n | ��6 | �i�E�����j | |
| 2 |
15 |
3 |
�{��1 | ����1 | �҉́^�k�c�c�l |
| 2 |
16 |
4 |
�{��2 | ����2 | �ԗ₦�̖�Ɂ^�k�c�c�l |
| 3 |
17 |
5 |
�{��3 | ����3 | ���`�^�k�c�c�l |
| 3 |
18 |
6 |
�{��4 | ����4 | �n����ԁ^�k�c�c�l |
| 3 |
19 |
7 |
�{��5 | ����5 | �����^�k�c�c�l |
| 3 |
20 |
8 |
�{��6 | ����6 | �H�̑O�t�ȁ^�k�c�c�l |
| 3 |
21 |
9 |
�{��7 | ����7 | ����^�k�c�c�l |
| 3 |
22 |
10 |
�{��8 | ����8 | �G�{�^�k�c�c�l |
| 3 |
23 |
11 |
�{��9 | ����9 | �ǓƁ^�k�c�c�l |
| 3 |
24 |
12 |
�{��10 | ����10 | �q�́^�k�c�c�l |
| 4 |
25 |
13 |
�{��11 | ����11 | �����́^�k�c�c�l |
| 4 |
26 |
14 |
�{��12 | ����12 | �a���^�k�c�c�l |
| 4 |
27 |
15 |
�{��13 | ����13 | �����������}�^�k�c�c�l |
| 4 |
28 |
16 |
�{��14 | ����14 | �����^�k�c�c�l |
| 4 |
29 |
17 |
�{��15 | ����15 | ���^�k�c�c�l |
| 4 |
30 |
18 |
�{��16 | ����16 | �Y�ꂽ���J�̝R��^�k�c�c�l |
| 4 |
31 |
�m19�n |
��7 | ����2 | �ߌ�̕� |
| 4 |
32 |
�m20�n | ��8 | �i�E�����j | |
| 5 |
33 |
21 | �{��17 | ����17 | �����ȉԑ��^�k�c�c�l |
| 5 |
34 |
22 | �{��18 | ����18 | ���M����[�Ɂ^�k�c�c�l |
| 5 |
35 |
23 | �{��19 | ����19 | ���i�^�k�c�c�l |
| 5 |
36 |
24 | �{��20 | ����20 | �Ђ₵�^�k�c�c�l |
| 5 |
37 |
25 | �{��21 | ����21 | �Ԓx�����̉́^�k�c�c�l |
| 5 |
38 |
26 | �{��22 | ����22 | �݂ǂ�̒��Ɂq���̏��ȁr�^�k�c�c�l |
| 5 |
39 |
27 | �{��23 | ����23 | ���鑒�Ȃ̒f�z�q��n�ɂār�^�k�c�c�l |
| 5 |
40 |
28 | �{��24 | ����24 | ���͂ꂽ��̈�y�́^�k�c�c�l |
| 6 |
41 |
29 | �{��25 | ����25 | �D�F�̎蓅�^�k�c�c�l |
| 6 |
42 |
30 | �{��26 | ����26 | �t�̇T�^�k�c�c�l |
| 6 |
43 |
31 | �{��27 | ����27 | �t�̇U�^�k�c�c�l |
| 6 |
44 |
32 | �{��28 | ����28 | �ߐ��^�k�c�c�l |
| 6 |
45 |
33 | �{��29 | ����29 | �Ԃ̏ё��^�k�c�c�l |
| 6 |
46 |
34 | �{��30 | ����30 | ����Ȑ��^�k�c�c�l |
| 6 |
47 |
35 | �{��31 | ����31 | ���́^�k�c�c�l |
| 6 |
48 |
36 | �{��32 | ����32 | ���̖|��q�����������N�̓��̉S�r�^�k�c�c�l |
| 7 |
49 |
37 |
��t1 | ���Ƃ��� | �k�M�҂͏��ї��E�r�c�s�V�l |
| 7 |
50 |
�m38�n |
��t2 | �N���W�b�g2 |
���W�@�t铁@�L |
| 7 |
51 |
�m39�n | ��t3 | ���t | �k�����A������E���s���A���Җ��E���s�����A�ق��l |
| 7 |
52 |
�m40�n | ��t4 | ���t���L�� | �g������i�W�^�k�c�c�l |
| 7 |
53 |
���Ԃ�5 | �i�V�ю��j | ||
| 7 |
54 |
���Ԃ�6 | �i�V�ю��j | ||
| 7 |
55 |
���Ԃ�7 | �i�������j | �k�t�����X���\���̐c���l |
|
| 7 |
56 |
���Ԃ�8 | �i�������j | �k����l |
�\���i�����t�����X���j���������{�̕����̎d�l�́A�V�n210mm�~���E148mm�i�`�T�������j�A�{��8�y�[�W�~6�܂ƕʒ�2�y�[�W�̑�50�y�[�W�B�ڎ������Ȃ������s�����G�߁t�̎��R�����I�ȍ�i�̔z��ɔ䂵�āA�S32�т��ߑO�ƌߌ�̕��ɑ�ʂ��āi�e16�сj�A�\���̔���T��B�s�t铁t��ꂽ�ɈႢ�Ȃ��k�����q���u��X�͎��܍��X�ƌ��Ƃ����̎�������W����ɂ��鎞���̓��e���Ⴕ���n�ȏꍇ�ɉ��Ă��W�����d�̐S�����ݓ��Ȃ��̂ł���v�i�s���Y�Ę_�t1942�N6�����A���y�[�W�j�ƕ]�����悤�ɁA�����ɂ����Ă͔j�i�̔����{�ƂȂ��Ă���B���т̍s���ɉ����čs�Ԃ�ς��Ė{���̔ŕ����Ȃ�ׂ����ɋ߂Â��鎎�݂��Ȃ���Ă���_�́A�s�����G�߁t�Ɠ����ł���B���Ɂu�{���s���v�Ɓu�{���s�ԁv�A�u�{�����E�i�{���̔ŕ��j�v�̊W���ꗗ�\�ɂ����B
| ���ѕW�� | �{���s�� | �{���s�� | �{���s�ԁipt���Z�j | �{�����E�i�{���̔ŕ���mm�j |
| �҉� | 14 |
�� |
5.25 |
75.6 |
| �ԗ₦�̖�� | 6 | �S�p�l�� | 13.13 | 45.2 |
| ���` | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| �n����� | 10 | �l�� | 7.88 | 61.8 |
| ���� | 9 | �S�p | 10.50 | 62.7 |
| �H�̑O�t�� | 9 | �S�p | 10.50 | 62.7 |
| ���� | 9 | �S�p | 10.50 | 62.7 |
| �G�{ | 12 | �� | 5.25 | 64.6 |
| �Ǔ� | 4 | ��{ | 21.00 | 36.9 |
| �q�� | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| ������ | 12 | �� | 5.25 | 73.0 |
| �a�� | 4 | ��{ | 21.00 | 36.9 |
| �����������} | 13 | �� | 5.25 | 70.1 |
| ���� | 6 | �S�p�l�� | 13.13 | 45.2 |
| �� | 4 | ��{ | 21.00 | 36.9 |
| �Y�ꂽ���J�̝R�� | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| �����ȉԑ� | 5 | ��{ | 21.00 | 48.0 |
| ���M����[�� | 9 | �S�p | 10.50 | 62.7 |
| ���i | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| �Ђ₵�� | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| �Ԓx�����̉� | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| �݂ǂ�̒��Ɂq���̏��ȁr | 13 | �� | 5.25 | 70.1 |
| ���鑒�Ȃ̒f�z�q��n�ɂār | 12 | �� | 5.25 | 64.6 |
| ���͂ꂽ��̈�y�� | 8 | �S�p | 10.50 | 55.3 |
| �D�F�̎蓅 | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| �t�̇T | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| �t�̇U | 11 | �l�� | 7.88 | 68.3 |
| �ߐ� | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| �Ԃ̏ё� | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| ����Ȑ� | 10 | �S�p | 10.50 | 70.1 |
| ���� | 8 | �S�p | 10.50 | 55.3 |
| ���̖|��q�����������N�̓��̉S�r | 12 | �� | 5.25 | 64. |
����i�q�c�c�r�j�̂��鎍�т͖{���s���ɕ����1�s�𑫂����s�����w��̑ΏۂƂȂ�B���l�Ɂq�����́r���u���́v�Ƃ������o����1�s���ɂȂ�B�����������s���ɑΉ�����s�ԁi�䗦�j���܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B���i���j�̂��Ƃ̐����́A�{�������܍��i10.5�|�����j��1�Ƃ����Ƃ��̖{�����E�i�{���̔ŕ��j�̔{���l�ł���B���ɍs�Ԃ�S�p�A�L�ɓ��ꂵ���ꍇ�A�ŕ��́y14�s�z��27�i�ő�j�A�y4�s�z��7�i�ŏ��j��4�{�߂��J���ɂȂ�Ƃ�����A�y14�s�z��20.5�A�y4�s�z��10��2�{���ɗ}����v���t�����Ă���B���Ȃ݂Ɂs�g�����S���W�t�͖{��10�|�A�s��7�|�œ��ꂳ��Ă���B
| �y14�s�z�E�y13�s�z�E�y12�s�z�\�\�i0.5�j�A�L | �y14�s�z��20.5�E�y13�s�z��19�E�y12�s�z��17.5 |
| �y11�s�z�\�\�l���i0.75�j�A�L | �y11�s�z��18.5 |
| �y10�s�z�E�y9�s�z�E�y8�s�z�\�\�S�p�i1.0�j�A�L | �y10�s�z��19�E�y9�s�z��17�E�y8�s�z��15 |
| �y6�s�z�\�\�S�p�l���i1.25�j�A�L | �y6�s�z��12.25 |
| �y5�s�z�E�y4�s�z�\�\��{�i2.0�j�A�L | �y5�s�z��13�E�y4�s�z��10 |
�s���Y�Ę_�t1942�N3�����E�\��2�Ό��y�[�W�f�ڂ́s�t铁t�o�ōL���̃A�b�v�k���m�N���R�s�[�l�g������W
�t�@�@�
��蟬�q��
�S������{�b���b�O���@����@���a��
�b���b�\���@���m�q�I�t�Z�c�g�ܐF��
�b���b�{���@������܁Z���G�k�m�����n�l�Ɂu�����G節�v���㈲���A�����C���Ȃ�G�X�v���������̎��ݖz���Ȃ�\���ɑ�Ď�者���Ӗڂ����߂��g�����N�͍��䏢�ɜ䂶�đ嗤�ɍ݂�B�ᓙ��著者�̈Ϛ��ɂ��ŋߍ�O�\���сA�����ɋ������ő���̔���{�ƂȂ��č]�ɖ{��������B������̖{�ł��邪�A�ނ̎��������Еz����]�������͐��웉��\�A�����\�A�����L�֑�����B �i��者���ї��A�r�c�s�V���k�}�}�l�j
�@�����s�{�����X����m�O�k�}�}�l�@�g����
�@�@�@�@�@���@�@蟬�@�@�q
���̍L������ɋg���{�l���֗^�����\���͒Ⴂ�B�����炭��l�́u�Ҏҁv�ɂ�鎷�M�E�w�肾�낤�B���W�́q���Ƃ����r�����ї��E�r�c�s�V�̗����ɂ��B�L���̕��ʂ�M����A100������́s�t铁t�̑���������250�~�Ƃ������ƂɂȂ�B���������s�̓����悤�ȑ̍ق̎��W������Δ�r�ɍœK�����A�s�t铁t���4�ӌ��O�ɏo����c�Ԏq�̑�W�s�G�̐_�t�i���q�����[�A1941�N8��10���j�̎d�l������ƁA�u�艿1�~80�K�@�l�Z���@���j�����@134�Ł@�p�w�����㐻�{�@�\���v�i���q�����[�{�@���̏W�j�Ƃ���B���蕔���͕s�������A100���Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�B
�@�E�s�G�̐_�t�F�l�Z���E�܍������E134�y�[�W�E�p�w�����㐻�{�E�\���Œ艿1�~80�K
�@�E�s�t铁t�F�`�T���E�܍������E50�y�[�W�E�����t�����X���{�E�\���Ő������2�~50�K����10�K
�g�������W�̓ˏo�����d�l�̍ق́A���҂ƕҎ҂����i�������^�̕Ҏ҂͋g���ł͂Ȃ��̂��j�����e�ɂӂ��킵�����̂�Nj��������ʂ��ƍl������B�g�����̎����I�ȏ������W�s�t铁t�́A���̑��{�����̖ʂ��������ɍl�@����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�s�����G�߁t�i1940�j����s���[���h���b�v�t�i1988�j�܂ł̋g������12���̒P�s���W�̖{���͂��ׂĊ��ň���ŁA���������������̓|�C���g�����őg�܂�Ă���i�ڍׂ��q�g�������W�̊�{�Ŗʁr���Q�Ƃ̂��Ɓj�B���̔Ŗʂ�Adobe InDesign CS6�i�ȉ��AId�Ɨ��L�j�ōČ����邱�ƂŁA�e���̑g�ł̐v���j�𖾂炩�ɂ������B���Ȃ݂�Id�́A�����T�C�Y�͂������A�|�C���g�T�C�Y�̊����ɂ�镶���g���ڍׂɎw�肷�邽�߂̊e��@�\�𓋍ڂ��Ă��āA�����g�ł̃V�~�����[�V�����Ɏg����B�g�������W�̑g�ł̍l�@�ł͎��і{���ɓ������āA�ڎ��Ȃǂ̑O�t�≜�t�Ȃǂ̌�t�̔�r�����͌���A���ׂĂ̎��W���܂Ƃ߂čs�Ȃ����肾�B
�s�����G�߁t�i����Ɂj��12���̒P�s���W���A�B��̑ܒԂ����{�i�{���p���̊O�\�m���Ƃ����ān�ɕЖʍ��肷��a���{�̈�l���j�����AId�͗m�{�i�p���̕\���Ɉ���j�d�l��DTP�\�t�g�E�F�A�Ȃ̂ŁA�ܒԂ��̎w�肪�ł��Ȃ��B����Ă����m�{�ƌ��č�Ƃ��邪�A�����̑g�̍ق�Ŗʂ̍���ʒu�Ɋւ��ė��҂ɓ��i�̍��͂Ȃ�����A��������ہA���͂Ȃ��B�\���i�t�����X�����A�����W�������́j���������{�̕����́A�V�n172mm�~���E121mm�A��80�y�[�W�B�ȉ��ɁA�I���e�\������E���\���܂ł̑S�̍\�����䊄�𗪋L����i1�y�[�W1��g�̒Z�́E�����́q蜾蠃��r�̋L�ڂ͊��������j�B�Ȃ��A�m�@�n�Ŋ������m���u���̓y�[�W�i���o�[��\�����Ȃ��u�B���m���u���v���A�������̐����͔ŖʂɈ���Ă���m���u����\�킷�B
| �v�f�m���u�� | ���� | �L�ړ��e |
| �\���m1�n | �I���e�\���k�����l | ���W�^�����G�� |
| �\���m2�n | ���Ԃ��i�������j | |
| ���Ԃ��m1�n | ���Ԃ��i�V�ю��k�I���e�l�j | |
| ���Ԃ��m2�n | ���Ԃ��i�V�ю��k�E���l�j | |
| �O�t�m1�n | ���k�I���e�l�@���� | ���W�@�����G�� |
| �O�t�m2�n | ���k�E���l�@���L | �c�I��Z�Z�Z�N�^���܂�͂��Ł^�g������ |
| �O�t�m3�n | ���� | �����͂͂� |
| �O�t�m4�n | �� | ���́^�k�c�c�l |
| �{���m1�n | ��1 | �����G�� |
| �{���m2�n | �k���l | |
| �{��3 | ����1 | �t�^�k�c�c�l |
| �{��4 | ����2 | �ā^�k�c�c�l |
| �{��5 | ����3 | �H�^�k�c�c�l |
| �{��6 | ����4 | �~�^�k�c�c�l |
| �{��7 | ����5 | �V�q�̉́^�k�c�c�l |
| �{��8 | ����6 | ���̏Ɏq�^�k�c�c�l |
| �{��9 | ����7 | �Ό��^�k�c�c�l |
| �{��10 | ����8 | ����ЂƂց^�k�c�c�l |
| �{��11 | ����9 | �����^�k�c�c�l |
| �{��12 | ����10 | ���������^�k�c�c�l |
| �{��13 | ����11 | �b���^�k�c�c�l |
| �{��14 | ����12 | �ʎт����b�^�k�c�c�l |
| �{��15 | ����12 | �i����j�k�c�c�l |
| �{��16 | ����13 | �����^�k�c�c�l |
| �{��17 | ����14 | �f�́^�k�c�c�l |
| �{��18 | ����15 | �������́^�k�c�c�l |
| �{��19 | ����16 | �˂̉ԁ^�k�c�c�l |
| �{��20 | ����17 | �ljَq�^�k�c�c�l |
| �{��21 | ����18 | �a���^�k�c�c�l |
| �{��22 | ����19 | �����G�߂P�^�k�c�c�l |
| �{��23 | ����20 | �����G�߂Q�^�k�c�c�l |
| �{���m24�n |
�k���l |
|
| �{���m25�n | ��2 | 蜾蠃�� |
| �{���m26�n | �k���l | |
| �{��27�`72 |
蜾蠃�� | �i�q蜾蠃��r�̒Z�́E�����̂͏ȗ��j |
| �{���m73�n | �k���l | |
| �{���m74�n | �{���ŏI�y�[�W | �L |
| �{���m75�n | ���t | �i������E���s���A�����E���Җ��E���s�����A�ق��j |
| �{���m76�n | �k���l | |
| ���Ԃ��m3�n | ���Ԃ��i�V�ю��k�I���e�l�j | |
| ���Ԃ��m4�n | ���Ԃ��i�V�ю��k�E���l�j | |
| �\���m3�n | ���Ԃ��i�������j | |
| �\���m4�n | �E���\���k�}�[�N�l |
�e���т̓V����Ŗʂ̂������܂ł̃A�L���u�V����imm�j�v�A��������Ŗʂ̂������O�̒[�܂ł̃A�L���u��������imm�j�v���v�������B�����𑪂�̂́A�ܒԂ��ŗp���̑傫���������ɈقȂ邽�߁A�Ŗʂ̍���ʒu���ψ�łȂ�����ł���B�{���̎��т́A���J���̉E�y�[�W�i�����y�[�W�j�ɕK���W�肪�u����Ă���B���̃y�[�W�́u�V����imm�j�v�E�u��������imm�j�v�ς���A�v��̓V����̃A�L�Ə�������̃A�L�̐��@�����肾����͂����B�����l�̕��ς́A�V����̃A�L��45mm�A��������W��i�{��2�s�h���j�܂ł̃A�L��25mm�������B
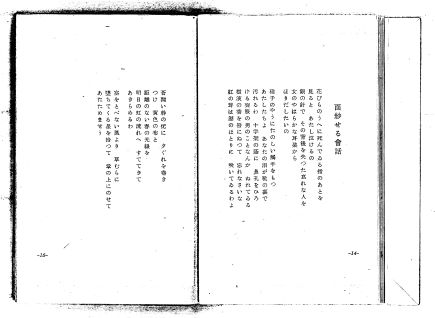 �@
�@![�q�ʎт����b�r�i�@�E12�j��]�҂�InDesign�ōČ������Ŗʁk���{�̑ܒԂ��ł͂Ȃ��m�{�d�l�̂��߁A�m�h�̃A�L���قȂ�l](image/mensha_Id.jpg)
�q�ʎт����b�r�i�@�E12�j���o�̔Ŗʁi�s�����G�߁t�A����ɁA1940�N10��10���A��l�`��܃y�[�W�j�̃��m�N���R�s�[�i���j�Ƃ����]�҂�InDesign�ōČ������Ŗ��k���{�̑ܒԂ��ł͂Ȃ��m�{�d�l�̂��߁A�m�h�̃A�L���قȂ�l�i�E�j
�T�@�{���F�����������\�L�B�W��12�|�����B�{��9�|����20���l�߁E���Ԏl���i2.25�|�j�A�L�A1�y�[�W15�s�E�s�ԓi4.5�|�j�A�L���ŏ������A�s�������Ȃ��Ƃ��͍s�Ԃ��L������Ă���B
�U�@�m���u������ђ��F�m���u���́A�n����27mm�オ�����Ƃ���ɉ��������A��������12mm���������Ƃ���ɉ��g�Łu-14-�v�̂悤�ɎΑ̂̃A���r�A�������n�C�t���i�{���p����ׂ��_�[�V�ł͂Ȃ��悤�Ɍ�����j�ŋ��ށB���͂Ȃ��B
�V�@�O�t�F�����E���L�i���s�N���E�Ŗ��E���Җ��j�E�����E�q���́r���e1�y�[�W�B�ڎ��͂Ȃ��B�O�t�̃m���u���͖{���Ƃ͕ʊ��肾���A�m���u�����L�ڂ��Ȃ��B���m���u���B
�W�@��t�F���t�B��t�ɂ��ڎ��͂Ȃ��B���t���܂߁A�S�̂�ʂ��č�i�{���ȊO�i���Ȃǁj�̃y�[�W�Ƀm���u���͋L����Ă��Ȃ��B
�{���̑g�̍ق��T�̂悤�ɋL�������A����͂����܂ŊT�v�ł���B�ŏ��̍s�ԓi4.5�|�j�A�L�őg�܂�Ă���̂́A�q�H�r�i�@�E3�j�E�q���������r�i�@�E10�j�E�q�˂̉ԁr�i�@�E16�j��3�сB��f�ʐ^�́q�ʎт����b�r�i�@�E12�j�͍s��5�|���B��{�Ŗʂ�9�|�̖{��������~���߂�Ɓu20���~15�s��300���v�̃e�L�X�g�{�b�N�X���ł���B���_��̍ő啶�����ł���B��L��4�шȊO��16���сi���ׂ�1�y�[�W�Ɏ��܂�Z����i�j�͍s�Ԃ�4.5�|��5�|�����L�߂�7�|�`11�|�ɐݒ肷�����i�s���E�������Ƃ�����j�A���e�s�������������̑���Ƃ�������ɁA1�s�A�L�͖{���̖{��1�s���̕��i�O�̍s�ԁ{�{���������{��̍s�ԁj���������g��ł���B�ȉ��ɁA�e���т̍s���i�s�A�L���s���ɃJ�E���g�j�ƍs�ԁA�s�A�L���ꗗ�\�ɂ��A�W��܂�肪�{�����s���ɑ������邩���u�W��s�h���v�ɋL�����B�W��͖{��2�s�����i���������9�|�{��3�����Ȃ���2�����\�\���҂̍��݂ɂ��Ă͌�q�\�\�ŁA�q�Ό��r�Ȃǂ�2���W���3�{�h���A3���W���4�{�h���A4���W���5�{�h���A�Ƃ�������j�B�ʏ�͂��̂���1�s�A�L�Ŗ{���J�n�����A�W��̂܂��ɃA�L������Ď��т�Ŗʒ����Ɋ邱�Ƃ����Ă���B���Ȃ킿�u�W��s�h���v�́A�W��܂��̍s�A�L�����₳��Ă����Ă���B
�@3�s�F0�s�A�L�{�W��2�s�h���{1�s�A�L
�@4�s�F1�s�A�L�{�W��2�s�h���{1�s�A�L
�@5�s�F2�s�A�L�{�W��2�s�h���{1�s�A�L
�@6�s�F3�s�A�L�{�W��2�s�h���{1�s�A�L
| ���єԍ� |
�W�� |
�{���s�� |
�s���ipt�j |
�s�A�L�ӏ� |
�s�A�L�ipt�j | �W��s�h�� |
| �@�E1 |
�t |
10 | 8 | 3 | ||
| �@�E2 | �� |
7 | 8 | 3 | ||
| �@�E3 | �H |
12 | 4.5 | 4 | 15 | 4 |
| �@�E4 | �~ |
6 | 8 | 3 | ||
| �@�E5 | �V�q�̉� |
5 | 11 | 4 | ||
| �@�E6 | ���̏Ɏq |
8 | 7 | 2 | 15 | 4 |
| �@�E7 | �Ό� |
4 | 11 | 5 | ||
| �@�E8 | ����ЂƂ� |
5 | 8 | 5 | ||
| �@�E9 | ���� |
7 | 8 | 1 | 15 | 4 |
| �@�E10 | �������� |
9 | 4.5 | 3 | 15 | 4 |
| �@�E11 | �b�� |
7 | 8 | 1 | 15 | 4 |
| �@�E12 | �ʎт����b |
12 | 5 | 1 | 18 | 3 |
| �@�E12 | �k�ʎт����b�l |
9 | 5 | 1 | 18 | 0 |
| �@�E13 | ���� |
6 | 7 | 4 | ||
| �@�E14 | �f�� |
2 | 7 | 6 | ||
| �@�E15 | �������� |
8 | 7 | 2 | 15 | 4 |
| �@�E16 | �˂̉� |
5 | 4.5 | 2 | 18 | 6 |
| �@�E17 | �ljَq |
5 | 9 | 5 | ||
| �@�E18 | �a�� |
8 | 7 | 2 | 15 | 4 |
| �@�E19 | �����G�߂P |
7 | 8 | 4 | ||
| �@�E20 | �����G�߂Q |
9 | 8 | 3 |
�ώG�ȕ\�����A�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j���ڂ́s�����G�߁t�����e�ɂ��āA���̐��l�Ńy�[�W���[�N�A�b�v����s�����G�߁t���{�̑g�̍ق��Č��ł���A�ƍl��������i��f�̐}�Łq�ʎт����b�r�Q�Ɓj�B�ʏ�A�{���͎��̂悤�Ȑݒ�Ŋ�{�Ŗʂ����܂�B�R�����i�F�j�ȉ��͍����Id�́u���C�A�E�g�O���b�h�ݒ�v�ɂ�����s�����G�߁t�Č��̎��ĂŁA�u���ԁF2.25�|�@������F11.25�|�v�͖{�������A�L�̂��Ƃł���B
�@�g�ݕ����F�c�g��
�@�t�H���g�F���˖���Pro M�k���������{�̏��̂ł͂Ȃ��B�ѓN�v������q�����G�߁r�Łu���͓̂����z�n���Ő�������9�|�C���g�����́i����44�N���j�Ƃقړ���̂悤���v�Ƃ��Ă���B�l
�@�T�C�Y�F9�|
�@�i���������䗦�j�F100��
�@�i���������䗦�j�F100��
�@���ԁF2.25�|�@������F11.25�|
�@�s�ԁF4.5�|�@�s����F13.5�|
�@�s�������F20�@�s���F15
�@�i���F1
�@�V�F45mm�@�m�h�F32.15mm
�@�n�F48.419mm�@�����F19mm
�@�T�C�Y�F����78.581mm�~��69.85mm
�ꗗ�\�̐��l������킩��悤�ɁA�s�Ԃ�4.5�|�i�{������9�|�̓�����A���Ȃ苷���j�E5�|�E7�|�E8�|�E9�|�E11�|�A��6�p�^�[��������B�ӂ��Ȃ�l�����Ȃ��B�s�A�L��15�|�E18�|��2�p�^�[��������B�U���ł���ȑg�݂̖{������������ڂ����������Ȃ肻�������A�s�����G�߁t�̔Ŗʂ���͂قƂ�Lj�a�������Ȃ��B���͂����قǂ���A���̍s���i�s�A�L���܂ށj�ƍs�Ԃ̊Ԃɑ��֊W������͂��Ȃ����Ɛ������ɂ�ł���̂����A�v�Z����������ł��Ȃ��B�����炭�����������Ƃ��낤�B1�y�[�W�i�ܒԂ�������A���m�ɂ͒��̃I���e���E���̈���j�Ɉ�̎��т���������1���̔����ɏ��邩�̂悤�Ɏ��݂ɕz�u�������ʁA�����Ȃ����̂��B�����傫���̔�����2�s�����Ƃ���12�s�����Ƃ��ł́A���̑傫������s�̋l�܂��܂œ����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����̏ꍇ�A�{���̑傫�������Ȃ͎̂����ł����āA���Ƌߎ��̌��ʂ��o�����߂ɂ͍s�Ԃ�s�A�L�A����ʒu�Œ������邵���Ȃ��B���������Ŗʂ�Nj������������A�ꗗ�\�ɂ�����������G�ȁA���ۂ̌����ڂ͂��������Ȗ{�����g�݂��������̂ł͂���܂����B�͂����ċg���́A������ЂƂЂƂw�肵���̂��B����Ƃ����e���܂Ƃ߂������ŁA�N���ʐl���g�Ŏw�肵���̂��i�{���ɂ͂��Ƃ������Ȃ��\�\�g���́A���Ƃ��������M���ׂ������ɗՎ����W�����n�d���Ƃ��Ĕn�̈������w��ł����\�\�ǂ̂悤�Ȑ���Ԑ����������킩��Ȃ��j�B����ɖ`����4�сA�q�t�r�q�ār�q�H�r�q�~�r�̕W��̎��������9�|�{��3���������A���Ƃ�16�т݂͂�2�����A�ƈقȂ�̂͂Ȃ����B���̖�ɑ��āu�`��4�т̎��M�i�j�̎������ق��ƈႤ���ߓ��ꂳ��Ă��Ȃ��v�Ƃ������������藧����ŁA�u�`��4�т͋g���̎w��ňȉ��͕ʐl�̎w�肾�����v�Ƃ������Ԃ��l������B��N�A�g���́s�����G�߁t�̐�����ӂ肩����Ȃ���A���W�ɑ}������Ă����q�莆�ɂ��ւār�Ƃ��������܂�܂���p���Ă���A���̕��ɂ́u�k���l�Z�N�l�Z���ܓ��B���V�̔ޕ��ɕx�m���O�p�ɋP���Ă�܂����B�F�̎�Ƀm�I�g�̎��W�u�����G�߁v���̂����ďo���v�i�q�킪�������W�s�t�́t�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���܃y�[�W�j�Ƃ���B�����炭��ЂŏĎ����Č������Ă��Ȃ����낤�s�����G�߁t�̃m�I �g�́A�r������́i���e�p���̂悤�ɂ͖��ڂ̐��Ă��Ȃ��j���̂ŁA�W�肪�������������ʂ��ɂ�����Ԃ������̂ł͂Ȃ����B���������|����͂��܂�ɏ��Ȃ��A���ܕ]�҂̎苖�ɖ{���̌��{�͂Ȃ��B�s�����G�߁t�͋g�����̒P�s���W���A����̋H�Q�{�Ȃ̂��B
�g���������̖{�������W�߂��W����͍��܂łɊJ���ꂽ���Ƃ��Ȃ��c�c�ƍl���Ă�����A�q����R�c�́q�{�r�W�r��Y��Ă����i������������A�g�����P�Ƃ̑����W�ł͂Ȃ��j�B���W���C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��q�b�g���Ȃ��̂ŁA�����ڂ����������Ă������B�K���Ȃ��ƂɁA�������苖�ɂ�������B�܂��q����R�c�́q�{�r�W�r�ē��n�K�L�̕��͂��N�����i�n�}�͏ȗ��j�B
���q�y�[�p�[�M�������[��� ���W
�e�N�X�g�ɂ����ā^��ƂƑ���ƂƁ^����R�c�́q�{�r�W
1994�N3��22���i�j�`4��1���i���j
10:00AM�`6:00PM�q��������x�r
���q�y�[�p�[�M�������[���
��104 �����s��������3-7-12 ���q�s���Y�r��1F
TEL.03-3567-7790
�������APM5:00�`7:00�܂ŁA�����₩�ȃp�[�e�B�[������܂��B���ł������������B

�q����R�c�́q�{�r�W�r�ē��n�K�L�̈����ʁi���̕��ʂ̕����́u�e�N�X�g�ɂ����āk�c�c�lTEL.03-3567-7790�v�j�Ɠ��W����p���t���b�g�̕\��
�W����̃p���t���b�g�͂a�T��6�y�[�W�̊����O�܂�ŁA�o�i�ژ^����ю���6�l�̕��͂ō\������Ă���B���Ȃ킿�A�@�u����̖{�����E�Ɠ����A�v�Ǝn�܂�r�V�Ď��q���E�̖�r�A�A�u�{�̌��^�͊��������Ǝv���B�v�Ǝn�܂鍂�����q�q�֗~�I�Ȗ��r�\�\���W�Ȃǂł͂��낢��Ȗ`�����ł���̂����A�k�c�c�l�ǎ҂ɕ��Âȓǂ݂̂ł��������̂��������ł���\�\�Ƃ�����߂́A���̂܂܋g�������{�̖{�����˂ʂ��Ă��悤�A�B�u�ǂ��܂ł��{�ł���A�v�Ǝn�܂�F��M��q�{�r�A�C�u��\�̂Ƃ��ɏ�������i�u���فv�ɁA�v�Ǝn�܂�Ґ��v�q���̖{�A���̃u���g���r�A�D�u�l�Ԃ��{�ނ��ƁA�v�Ǝn�܂�O�c�p���q�{�ނ��Ɓr�A�E�u����R�c�́q�{�r�Ƃ����A�v�Ǝn�܂�g�������q���q�̎�r�B�����炭�Ӑ}�I�ɁA�}�ŁE�ʐ^�͈�_���f�ڂ���Ă��Ȃ��i����āu�}�^�v�ł͂Ȃ��j�B�ژ^��3�y�[�W�ɂ킽���Ă���A�u�����E���ҁE����E����E���s�N�E�E�v�v�̂��ƂɁA�P�s�{81�^�C�g���E�u���q 1�`8�v�E�u���C�g�E���@�[�X 1�`9�v�E�u� 1�`9�v�E�u�邵���� 1�`�v�E�u��Ԃ�ǂ邵���� 1�`�v�i13�^�C�g���j�E�u�K�[�g���[�h�E�X�^�C���̖{ 1�`�v�i6�^�C�g���j�E�u�g���X�^���E�c�A���̍�i 1�`�v�i6�^�C�g���j�E�u�|�W�v�i6�^�C�g���j���f�����Ă���B���ɁA�g�����Ɋւ��̂���^�C�g����P�s�{�E�u���q 1�`8�v�E�u� 1�`9�v�E�u�邵���� 1�`�v�E�u��Ԃ�ǂ邵���� 1�`�v�̏��ŋ����悤�i�k�@�l���͏��т̕�L�j�B�E�v����*��ɂ́u�ɐ�ŁA�����肷�邱�Ƃ��ł��܂���v�Ƃ̒��L������B�{�p���t���b�g�́A�n��15���N�𗂔N�ɍT��������R�c�̏o�Ŗژ^�����˂Ă����̂ł���B���Ȃ݂ɁA���\���̃N���W�b�g�́A����R�c�Ɖ��q�y�[�p�[�M�������[����̘A���ŁA���������s�́s�{ ����R�c����\�\1994.3�t�Ƃ������^�����̏o�Ŗژ^�̗��\���ɂ́u�{���͐V���q�����̐V���i�n�j�~���[�Y������́i�z���C�g�m�j���g�p���Ă��܂��v�ƋL����Ă���B
| ���� | ���� | ���� | ���� | ���s�N | �E�v | |
| ���������\�\����C���̂��߂� | ����R�c | �z�A���E�~�� | 1979 | 14 | �k�g���͒Ǔ����q�u�Ɣ�������v�r�i�H�E27�j�����l | |
| �|�[���E�N���[�̐H�� | �g���� | ����R�c | �ЎR�� | 1980 | *18 | �k�ЎR���ɂ��\���̑����W���l |
| �t�@�����Ɂi�����Łj | �剪�M | �g���� | 1981 | 25 | ||
| �ԉ� | ������b�q | �g���� | 1983 | 30 | ||
| ��� | �g���� | �g���� | 1983 | *31 | �k���̎w�莆�Ƒ����{��W���l | |
| �q���M�r�Đ��̂��߂̃m�[�g | ��B�� | �g���� | 1986 | *37 | ||
| ���[���h���b�v | �g���� | �g���� | ���e���O�Y | 1988 | *47 | �k�\���̑���i���e���O�Y�̃X�P�b�`���j��W���l |
| ��̉� | �������Y | �g���� | ������ | 1988 | *48 | �k���̎w�莆�ƃX�P�b�`�i�����{�ɑւ��j��W���l |
| �u���q 1�`8�v | ����C�� | |||||
| �ٗ�� |
�g���� | 1974 | *84 | |||
| �u� 1�`9�v | �e�n�M�` | 1984�`1987 | 99�`107 | �k�g����2���Ɏ����q���[���h���b�v�r�i�K�E10�j�����l | ||
| �u�邵���� 1�`�v | �e�n�M�` | 1989�` | 108 | �k�g����5���Ɂq���L ���l�Z�N�r���A6���Ɂq���L ���l�Z�N�k����l�r�����l | ||
| �u��Ԃ�ǂ邵���� 1�`�v | ���� | |||||
| ���܂�͂����L | �g���� | 1990 | 109 |
�o�i�ژ^�ɂ͋L����Ă��Ȃ����A�g���������ɂȂ�V��ޓ�Y�́u���q 2�v�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k����101���̓��l�t�i1974�N9��1���j���W������Ă����B���̓W����J�Â̏��́s���{�o�ϐV���t�̃R�����q���������r���Ȃɂ��Œm�����̂��낤�B�����̋L�^������ƁA�ŏI����4��1���Ɋςɍs���Ă���B20�N�߂��O�̂��Ƃ��������ăf�W�^���J�������Ȃ��A�ʐ^�ꖇ�B���Ă��Ȃ��̂��ɂ��܂��B����ɁA�g���̎w�莆�̂��肳�܂�`����ׂ��p���t���b�g�Ƀ������Ă���B�u�X�P�b�`�u�b�N�ɉ��M�ŃX�P�b�`�i��K�g�p�j�A�`�b�v�i�F���{�A�p�����{�j�A�ʐA��J�b�g�̃R�s�[���e�[�v�łƂ߂āA�w��̓u���[�u���b�N�̃y���ŁA�A�L�̐��@���͐ԃC���N�̃y���i�H�j�Łv�B1991�N10��12���́q�g�������Âԉ�r�i�E�ؔn�فj�ł��A����R�c�̊��s���i�������c���Ă��炸�������킩��Ȃ����A�s��ʁt���������j�̑������e���z���̂����W������Ă�������A����R�c�͋g�����̑������e���ɕۊǂ��Ă��邱�Ƃ��낤�B����ׂ��s�g�����S�W�t�̌��G�ɂ́A���ЃJ���[�ő������e�̎ʐ^���f�ڂ��Ăق������̂��B�������A�d�オ��̏��e�ƂƂ��ɁB���͖{���〈�Ԃ��̗p���A�\���̃N���X�Ȃǂ̎��ނ̖����܂ŋL�����g���������{�̎d�l�̈ꗗ�\���Ă���B
�k�t�L�l
�s�y���F��t�́q72 �w�a�߂镑�P�x�����r�ɂ́A�g���������̃v���Z�X�Ɋւ���ł��ڂ������L�̋L�q������i�q�g�����̑�����i�i2�j�r�Q�Ɓj�B���̓��L�̋L�ڂ̗L���ɂ�����炸�A���͋g���������̑�\��̂ЂƂƂ��ās�a�߂镑�P�t�������邱�Ƃ��S�O���Ȃ��B�ł́A����R�c�ł̋g���������̑�\��͂Ȃɂ��Ɩ����A�f�ނ̌������ł́s���[���h���b�v�t�����\�\�s�g�����S�W�t�̑�����z������ɁA�s���[���h���b�v�t����ыg�������������s�����d�M�S�W�t�̔��W�`���l�����悤�\�\�A�I���W�i���e�B�n�o�̖ʂ���u�s��ʁt�����v�Ɠ��������B�s��ʁt�͂����ς����g�������̋ƐтƂ��Č���邪�A�g���������̒��_�Ƃ��Ă��L�������ׂ����B
�҈䋪�̍ŏ��̎��W�s�s�m���Ȓ��t��1955�N12���A�ɒB���v�̏��惆���C�J���甭�s���ꂽ�B�g�����́s�Õ��t�i���ƔŁj�����N8���̊��s������A�܂��ɓ������̎��I�o���ł���B�҈�̑�W�s�ٖM�l�t�i1961�j�����惆���C�J���甭�s����Ă��āA�����炭�����W�̂��ƂƎv����L�ڂ��g���̓��L�ɓo�ꂷ��B�u�[���A�����C�J�֍s���ƁA������s�Əo��B���h���I�ɒ҈䋪�ƈɒB���v�����W�̑ō������B�l�l�ŋ|���ɂ䂭�B�ݓc�q������ꂽ�B��̒m�l�̃V�����L���킯�Ă��炤���ƂɂȂ�B�z�q�̔O�肪���Ȃ����v�i1960�N3��17���j�A�u���h���I�ňɒB���v�A�琴��Ɖ�B�L�̗���ׂ̂�B���W�̑薼������Ɖ]����v�i5��26���j�B�V�����L�̂��Ƃ͉��x�����L�ɓo�ꂷ�邪�A�g�����҈�̎��W�ɑ薼���������͕s���B�҈�͑S���W���s���̃C���^�r���[�q���オ�˂��t������̂ƑΛ����ār�ŁA�s�s�m���Ȓ��t���o���Ă����ɓ��l�����q�����r�ɎQ�����������̗l�q�����āA�u�ѓ��k��A�剪�M�A������s�A���ꂩ�畽�ѕq�F�c�c�A�݂�ȁu�����v�̉�ŏ��߂ĉ�܂����B���ꂱ�����͏������Ȃ��Ă݂Ȃ���厍�l�̌������Ƃ��Ă����Ƃ��������ł��B�g������������܂������A�g������͂�����ƕʊi�݂����Ȋ����łˁc�c�B�u�����v�͂���Ȃɒ����͂Â��Ȃ��������ǁA�݂�Ȑ����������Ă��܂�����v�i�s�҈䋪�S���W�t�A�x�A�v���ЁA2009�N5��25���A��y�[�W�j�Ɠ����Ă���B�҈�Ƌg���̓f�r���[���������鎍�F�Ƃ͂����A�����ɂ͈،h�̔O�������Ă���悤�Ɍ�����B�҈�̎���߂̒P�s���W�s���Ƃ��Đጎ�ԁt�i�y�ЁA1985�N3��30���j�́A�O�̎��W�s���߂��t�i�v���ЁA1982�j�ɑ����ċg�����̑����ƂȂ����B�q���@�r��ǂ����݂ň������B�Ȃ��A9�s�߂́u�ԙ��v�͑S���W�ł́u���A�v�ɉ��߂�ꂽ�B
����Ɂ^���ׂĂ�����͂��������̂Ɂ^�N�₩�ȐF�ɍ炢�Ă��܂����^���@�̉Ԃ��@�킸���Ɋ�㵂ɐ���̂́^�����炭���̂��߂��^�����ɂ����C���Ɓ@�p�����Ɓ^�܂��c���Ă���]�݂̂�������g�y�ɓn���ā^���ׂ��݂͑���Ȃ��^���������ԙ��ɏW���Ă���̂Ƃ͋t�Ɂ^���߂炢�Ȃ��狫�E�𑖂�v�҂́^�Ђ낪��@���S�ւƏ����Ă䂭�^��������^���z�͕���ā^���߂鎛�����̂Ȃ��ɂ��^�����낤�ɂڂ₯�����̑�͂��������^���F�ɂ����₢�ā^�ߋ��̂��̂ƂȂ����̂Ȃ��Ɂ^���m�����Ȃ݁n�͎v���o���䂪�߁^���͎��^��x�����̏���ԁ^������ς������𗧂Ăā^�n���Ă䂭�ߐ��̂ЂƂƂ��^�s�͓D����F�f���z�������^���̂�����֕Ԃ����Ɩ����ŗ��ł���^�܂�ʼn��J�ȂǂȂ��������̂悤�Ɂ^���e����Ȃ�^�u�[���ȑ��݂Ƃ͖������Ȃ��̂ł��邩�v�^�Ƃ����ď����낤�^�܂��t�͉ԂɂȂ�Ȃ�����^���̏�Ɏ����c���^���̂悤�ɐ��������Ǝv���̂́^���@���^����Ƃ��F���̖�����鴁m���ȁn���ꂽ�l�ł��邩�^���ʂ̂��Ȃ��܂Ђ�^�_�����������܂����^��̋�Œ[�������₩���Ă���̂́^���R���������������Ă��邩�炩������Ȃ��^���������Ȃ����̂Ȃ��ɏ�����̂́^�܂悢�̕��ւƉj�������ā^�₪�ċ�֓���邽�߂�������Ȃ��^���߂鎛�����Ƃ����^�{���̂��������Ɏ��������^���낱�������͊�]�̔��f�^�������㵂̎d���Ȃ̂��^���悢������ɉԂ͂�����^���s���Ƃ܂ǂ��ā^���͓������̂ƂĂȂ�

�{���̎d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���E��O��y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�̓N���X�A���͎��j�E�g�����ɓ\���Ӂi���̔w�����́u�҈䋪���W�v�ŁA�����͕��ɂ����L����Ă���j�B���t�̍ŏI�s�Ɂu���@��\�\�g���@���v�Ƃ���B�ǎ��Ɏ����\���̉ԕ��͗l����́A���Ă̓V�V�ޓ�Y���W�s���P�l�t�i�y�ЁA1980�j��剪�M���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�j���z�N�����B�҈�͑O�f�C���^�r���[�ŁA�s���Ƃ��Đጎ�ԁt�Ɓs���E���E���̖ڂɟ��t�i����R�c�A1987�j�ɐG��āu���̒��Ԃ���́A�u�����͂ǂ����悤���Ȃ��v���Ċ����ƁA�u�ǂ��ɍs�����Ⴄ�̂��ˁA�܂�����݂�킯����Ȃ����낤���v�Ƃ��A�u����A��������݂�킯���Ȃ���v�݂����ȁA����ȊS�̎����ꂩ����������Ȃ����ȁB�剪�M���Ƃ��a��F�コ��A�g��������Ȃ́A�ڂ��̂��Ƃ�ςȂ���Ǝv���Ă�����Ȃ����ȁB�����ł��ςȂ���Ƃ����ӎ�������������A���̂܂܍s���Ƃق�Ƃ��ɕςɂȂ����Ⴄ��������Ȃ��Ǝv���āA����ł�����x���_�ɖ߂�K�v������ƍl������ł��v�i���O�A���y�[�W�j�ƌ���Ă���B�����̋g�����҈�i�̎��j���ǂ��v���Ă������͕s�������A�s���߂��t�Ɋr�ׂĂȂ��炩�Ȏ����ɂȂ������Ƃ͂��������B�����Ƃ�����́A�P�Ɂu������x���_�ɖ߁v�������߂��B��ނ��ʂ̐i�H�ւƑǂ�����̂́s���Ƃ��Đጎ�ԁt�̎���s���E���E���̖ڂɟ��t�ł����āA�҈�́s���߂��t�Ɓs���Ƃ��Đጎ�ԁt�̉s���u���ɐ܂��H�����A�g�����Ƃ������F�ɂ��đ����Ƃ̍�i�̂��A�����ŕ������悤�Ɍ�����B���ꂪ�Ӑ}�������̂������̂��A���R���������͂ɂ킩�Ɍ��߂��������B
�҈䋪���W�s���߂��t�i�v���ЁA1982�N11��1���j�̑ѕ��ɂ́u�m�������n�łȂ���Ώ����Ȃ���肪����v�Ƃ������̂��ƂɁA�u�������ꂽ�Õ����ɂ́u�����Ȑ��̂Ȃ��ɋ��F�ɋP���邪����Ă���̂������v�ƋL����Ă���B��������������̂������̂��A���͌��e�������̂��B�k�Í���ǁl�Ƃ������I�p�Y���̃X�������\�Ɋ��\������Úg�̎��l�҈䋪�̒��я��������W�B�v�Ƃ���B�����́q���̑��Ձr�Ɗ����́q�K�̃O���f�B�G�[�V�����r�ɋ��܂��`�ŁA�q������r�q�ǂ��ꂽ���r�q��̐_�a�r�q�邪�����r�q���ꂽ�Έ�ˁr�q��̂Ȃ��̐N�r�q�o�Ɂr�q����ꂽ���r�q���������r�q��̒�r�q���N�͔p�ЂŗV�ԁr�q�������r�q�r�₦�����r�q�R������W�r�q�Â��ȍL��r�q�����Ă䂭��ԁr�q�_��ꂽ�j�̖��r�q���ꂽ���̔�r�̑S20�т����߂��Ă��邱�Ƃ��l����A�_�̂悤�Ȉ�{�̒����Ƃ������́A����畡���̎��т���Ȃ钷�ю����낤�B�q�ǂ��ꂽ���r�������B
�ǂ̌��͍ǂ��ꂽ
���`�����Ƃ͂ł��Ȃ�
�͓̂r��
�c���ꂽ�ʑt�ቹ�͎��f�𓊂�������
�����͂��������Ȃɕς�
���p�͌����Ȃ���ʼn��t�����
��������������墩��m�Ƃ��n�̏��
������ʊႪ�Ȃ���͔̂j�ꂽ��
�ʂ����ق̗���
�����̍Y����������
���l�̉h���钬�ŋ��`�͎��ł���
�����ŋP���𑝂��̂͐M���@��
����̂��Ȃ��L��̕~�͗₦
��O�Ɍq���ꂽ�n��
�������Ě|��
���z�����铺�ł��r��������
�����̊�ś�������
���@��Y�ꂽ�N��L�̂悤��
���f���ꂽ����肪����
�ˑR�@�\�����ꂽ�m������
�����Ȃ�
�D�삪���]����
�̗t���͌������̍�
�_�a�͂����炭���̉��ɂ���
�L���̋�ɌQ��Ă��������_�͏�����
�A���R��͌`�ɂȂ�Ȃ�
�B���̐����������ł���̂�
�n�ꂩ�甇������Ă���Ԃ���̉��
�����a����ĉ���������
���������Ė����̉��o���͂��܂�����
���͐Â���
�l�X�͖������Ă���
�ǂ�Ȉٕςɂ��S���Ȃ�
�V�����ǂɌ������Ƃ͑g�D����Ȃ�
������f�����
�L��ɂ͍��̔�J�������c��
���̉��Ŏ��Ƌ��ɎK�тĂ䂭���̂�����
�����ɂ͏���߂����āA���邱�ƂƉ��y���D��Ȃ�����Ԃ�����B�����������͂˂ɎՂ��A�y�Ȃ͎��Ȃ��܂��Ƃ����邱�ƂȂ��A�������ܕʂ̂��̂ɂƂ��đ�����B�u�̗t���͌������̍��v�Ƃ������N�₩�ȁi�N�₩������j�C���[�W�́A�o�ꂷ��₢�Ȃ�u�n�ꂩ�甇������Ă���Ԃ���̉���v�Ƃ����A�a�Ȏ���Ɉ��݂��܂��B�u�m�������n�łȂ���Ώ����Ȃ����v�Ƃ́A�������������Ă͏��������Ă͏����̕���i�̍\���ɐZ���������ʁA�����炳�ꂽ�K�R�ł͂Ȃ��������B�������Ƃɂ���Ă̂݁u���݁v����u�s�݁v�̏�B
 �@
�@
�҈䋪���W�s���߂��t�i�v���ЁA1982�N11��1���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ��s��{ ���߂��t�i�q�r�ЁA1991�N7��1���j�̊O���k���{�F�쓇�r�O�l�i�E�j
��{�̏o�T�F���₫���X�u���Q�W�O�A�N�����P�[�X���O���@�M�y�������������@���O�����Ɂ@����E�����ĔV�^���i�F12,000�~�v
�{���̎d�l�́A���Z�~��O�܃~�����[�g���E����y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�W���P�b�g�E�g�����i�ڎ����Ɂu����\�\�g�� ���v�ƃN���W�b�g������j�B���̔����A�f�ނƂ����A�����E���Җ��̕��͋C�Ƃ����A�g�������̈ꎞ����悵���s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�ƍ������Ă���B�g���͂��̎����ɂ��������������܂��|���Ă��Ȃ�����A���҂���̗v�]��������������Ȃ��B���́s�T�t�����E�݁t�̂悤�Ȋ����������A�ƁB�Ȃ��A�g
���f���1991�N�Ɂs��{ ���߂��t�������{�ŏo�Ă��邪�A�����B�s���߂��t�����ƒ�{�̏������L�����s�҈䋪�S���W�t�i�v���ЁA2009�N5��25���j�́q���r�������i�����A��l��Z�y�[�W�j�B
�w���߂��x
��㔪��N�\�ꌎ����@���s�ҏ��c�v�Y�@���s���v���Ё@�����s�V�h��s�J���y�����O-��܁@����~���~��l�Z�~���@���Z�Ł@�㐻�N���X���@�۔w�@�J�o�[�@�@�B�����@����g�����@�艿��l�Z�Z�~
�������{�w��{�@���߂��x
�����N��������@���s�Ґ쓇����q�@���s���q�r�Ё@�����s�a�J��a�J��-���-���@��l�~���~��㎵�~���@���Z�Ł@�\���I�t�Z�b�g���F�������@���Ԃ��Z�F���@�A�N�����P�[�X�@�\���@�����i�_���{�[���j�@�\���Ӂ@���{�쓇�r�O�@���撆���ĔV�@����Z���@�艿��l��~
�҈�ɂ́A���W�Ɠ���̒��я����s���߂��t�i���Y�t�H�A1998�j������B���҂̊W�ɂ��āA�C���^�r���[�q���オ�˂��t������̂ƑΛ����ār�Łu�������O���g���ď����������Ă���̂ŁA�����̂ق��͎��W�w���߂��x�̎U���ł��Ƃ������������������ł����肵�Ă��܂����A�����܂ł͂��Ȃ�̎��Ԃ��o���Ă��܂�����A�����e�[�}�̎U���łƌ����̂͂�����Ɩ�������������������Ȃ��i�j�B�e�[�}�̋��ʐ������邩�ƌ����A�Ȃ��킯����Ȃ���ł����ˁB���z���݂����Ȃ��̂������Ă��܂����Ƃ����F���������ɂ������āA���̗��z�������̂Ȃ��ɒ���ł����ɒu��������ꂽ�B�k�c�c�l���̎��W�Ȃ̓J�t�J�̍�i��ǂe��������܂��ˁv�i�s�҈䋪�S���W�t�x�A�Z�y�[�W�j�Ɠ����Ă���B
�ѓ��k�ꎍ�W�s�{�Át�i�y�ЁA1979�N6��10���j�́A�g�����̎��W�s�Ẳ��t��4�ӌ��قǂ܂��ɓ����Ō����犧�s���ꂽ�B�Ƃ��ɁA�g���̂���܂ł̎��W�́s�m���t�i1958�j�������Ă݂ȃ\�t�g�J���@�[�i��Ƀt�����X���j�ŁA�y�[�W���������ނ�100�y�[�W�ȉ��������B���ꂪ214�y�[�W�́s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�œ�x�ڂ̃n�[�h�J���@�[�d�l�ƂȂ�A�ȍ~�̒P�s���W�͏E��W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�������āA�݂ȏ㐻�{�̍d�\���ƂȂ����B�{���p���̑��ɂ���邪�A100�y�[�W�����ɂ��Ă���ȉ����t�����X���̃\�t�g�J���@�[�A����ȏオ�㐻�{�̃n�[�h�J���@�[�A�Ƃ������ݕ����ł���B��ʓI�ɏ㐻�{�̕\���p���ނɂ͊v�E�z�E�N���X�E���Ȃǂ����邪�A�{���͑S�ʕz���ł���B�剪�M���`����悤�ɁA�g���������̖{�Ɏg�������āA�����ł���Ă݂����Ǝv���قǂ̃v�����Ƃ��āA���̑S�ʕz�����������ƌ���B�s�{�Át�Ɓs�T�t�����E�݁t�́A�f�U�C���i������ꂽ��������ѐ}���j��ʂɂ���ƁA�㐻�۔w�z���A�W���P�b�g�A�g�����A�сA�Ƃ܂����������\���ł���B�s�T�t�����E�݁t�̕z�͂��̃T�t�����̉ԐF�̐F����D�悵���������A�f�ނ̎����͂��܈���������B���n�̑ł����݂��Â��Ƃ������A�ɂ��Ƃ������B�g���͂��ꂪ�s���Ō��y�d���������A����͐F���͗��O�̂��ƂƂ��đf�ނ�I�������̂ł͂Ȃ����i�s�T�t�����E�݁t�ɃT�t�����̉ԐF�̂��̑f�ނ�p���Ă�����ǂ����������낤�j�B�g���͖{���̑����ł��肤�ׂ��肵�s�T�t�����E�݁t�̃u�b�N�f�U�C���Ɍ����������B���̂����ŁA�\���ɐ��e���O�Y�̉���������Ƃ�����_�������Ȏ��݂�ʂ��āA�s�Ẳ��t���s�T�t�����E�݁t�̒P�Ȃ鉄���ł͂Ȃ����Ƃ����������B����ɂł��ł��邱�Ƃł͂Ȃ����A���ґ����ɂ�鎩���ւ̔�]�s�ׂƂ�����B
 �@
�@
�ѓ��k�ꎍ�W�s�{�Át�i�y�ЁA1979�N6��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���ƃW���P�b�g�i�E�j
�{���̎d�l�́A���Z�~��l��~�����[�g���E��Z��y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�W���P�b�g�E�g�����B�ڎ��̗��Ɂu����@�g���@���^�ʐ^�@����@�ҁv�Ƃ���B�W��ɂƂ�ꂽ�q�{�Ár��q�ӂ����ы{�Ár����\�삾���A�����ł́q�m�̂��Ɓr�������B
�܂����W���o������
�m�̂��Ƃ��v���o��
�킽���͂��j���Ƀz�e���̃o�[��
�₢�r�[��������
�F�����Ə������Ă���
���������ʁ@�m�̂��Ƃ�
�v���o������
�m���Â������ɂ��Ⴊ��ł���
�a�@���@����Ƃ����̐�̂���R���̒���
����̓�K��
�Ƃ������m���Â��Ƃ���ɂ���
�V���̕Е��ɂ킽��������
��������ɂm������
�킽���������������
�������m�̂ق��͒���ōs��
�m�̂ق����̂�������
�ނ̐��͕����Ȃ�
�����C�z�����邾����
�m�Ƃ͈��l���N
�����N���X�̍��Z����
���Ƃ������̂����邱�Ƃ������Ă��ꂽ�l����
�F��`�̋u�̏��
�����R�̕���ɂ�����
����������̋���������
�킽�������炵�����̂�������悤�ɂȂ�����
�ނ͐��_�̕a���̒���������悤�ɂȂ���
������Ԃ�������
�H��Ɍ��e��������c�c�c�c�B
�ނɕ��Y���ĕa�@�֍s��
�������@�̔ނƁ@��f���̑O�Ŏ��U���ĕʂꂽ������
��x������Ă��Ȃ�
�킽���͂��ƂŌ��e�����邱�Ƃɏn������
���l�Ƃ������̂ɂȂ���
�{���̌��e�Ȃnj�����
�ӂ邦�킭���Ƃ��낤
�{���̌��e�������m��
�����ɕ����߂�ꂽ
�������Z�ɓ���
���̗ǂ������m�̂��Ƃ�
�킽���͔N�Ɉ�x����x
�����ƂƂ��Ɏv���o���B
�����������Ƃ́i�Ђ��Ă͐����邱�Ƃ́j���߂����A�s�C����������قǗ����ɏq�ׂ����������ɑz���o�����Ƃ͓���B�Ȃ��g���́A�{���ȍ~���ѓ��̒��������Ă��邪�A���W�Ƃ��Ắs�{�Át���Ō�̍�i�ƂȂ����B�g���������ɂ�����ѓ��k�ꎍ�W�̋��ɂ̌`�Ƃ����悤���B
�s��{ �߉ϑ��Y���W�t�i���V���X�A1978�N7��30���j�́sETUDES 1941�`49�t�A�s�������� 1950�`57�t�A�s���y 1957�`65�t�A�s�͂��� 1965�`73�t�̎l�^�C�g���Ɓq���эזځr�����߂�B�X�I�Ɋe�^�C�g���ɇT����W�̔ԍ���U��ƁA�T��1949�N����U��1955�N�܂ł̋g�����̎��W���s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�A�U��56�N����V��58�N�܂ł��s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�A�V��59�N����62�N�܂ł��s�a���`�t�i����ɁA1962�j�A�V��62�N����W��66�N�܂ł��s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�ł���B��l�̋��ʓ_�́A�߉ς̎��W�sETUDES�t�Ƌg���̎��W�s�m���t�Ƃ��������̏d�v�ȍ�i���Ƃ��ɏ��惆���C�J����o�Ă��邱�Ƃ����ł͂Ȃ��B�v���Ђ����s���y�t�Ɓs�a���`�t�i���m�ɂ͎v���Д����j�������̍قŁA�g���ɂ�铯�H�̑����ŏo�����Ƃ́A�����̓�l�̐e�������悭�\�킵�Ă��悤�B�s��{ �߉ϑ��Y���W�t�̑������g�����S���������Ƃ��A�������������̂悤�Ɏv����B�{���̎d�l�́A���܁~��l���~�����[�g���E��y�[�W�E�㐻�۔w�p���\���i���F�N���X�A�w�F�v�j�E�\���i�}�[�u�����ɑ�ⳓ\�j�E�{�[�����̃P�[�X�i���ɏ����ق����L�ڂ�����ⳓ\�j�B����980���i5�Ԗ{�j�B�{���O�̕ʒ��a���ɒ��ҖѕM��������B���ݍ��݂́q���^�r�i�����͐������g�p�j�ɐ��e���O�Y�E���c���E������s�E�剪�M�E���Ñ��Y�̕��͂����߂�B
 �@
�@
��L
���������������������킟�@���킟�@����
�˂����l���̂˂���̂˂ނ�̂˂˂�
�˂��S�t�̂˂�F�̗����̂��Ȃӎp�Ԃ�
�ʂ߂�̂ʂ��܂̈ł̐�̂��т�̕g��
�O�فm�Ђ����n�̓��̂���߂��̂���߂��̂���Ȃ�
�̑��Â��������₭�̋ʂ̏��̒��m�����܂��n��
�|��̉��Ï�̌�������̔��Ԃ̂��˂��
�����̂��߂�����̂��߂��̂Ȃ܂߂���
�����������킟�@������킠���@���킟
�s�͂����t�̊�����i���������B�{�т�����킩��悤�ɁA�s��{ �߉ϑ��Y���W�t�Ɍ����ȓ����͖{���̗p���E�p��ŁA���t�Ό��y�[�W�ɂ͎��̂悤�Ȓ��L������B
ETUDES�@�@�@�@���܁Z�N�܌��@���惆���C�J��
�K������h�@�@���l�N�㌎�@���惆���C�J���u�D�㎍�l�S�W�v��ꊪ����
�@�@�@�@�U�@�@���܋�N�\���@���惆���C�J���u���㎍�S�W�v��l������
���ف@�@�@�@�@���Z�ܔN�����@�v���Њ�
�͂����@�@�@�@��㎵�ܔN�\���@��y�Њ�
�{���W�́A�E�L�̊e���W���{�Ƃ��A�S�Đ���������ɝ����B
���сq�L�r�����������A�V�t�gJIS�ʼn\�Ȍ���̐������g���Ă݂��i���L�ł́u�S�v�u���v�u���v�u���v�u���v�u�Ёv�u���v���\���ł��Ȃ������̂ŁA�V�����g�p���Ă���j�B�����őz���o�����̂́A����N�v�́q������v�Ǝ��r�́u�������W���s���̌o�܁v�̈�߂ł���B��Ⓑ�����A���惆���C�J�ƈ�����̊Ԃ̎����`����M�d�ȏ،��Ȃ̂Ōf����B
�@�w�@����Ƃ��s�x�́A�k�c�c�l�B�{���̑g�ݕ���A�J�b�g�̓�����ɂ��Ă��A������������낢�날���B�������Ӗʓ|�Ȃ�����̗��݂��A�ɒB�k���v�l����́A�{�����Ȃ�����A���ǂ́A�قڊ��S�ɂ����Ă��ꂽ�\�\������̂��Ƃ����������āB���̂�����̂��ƂƂ��ӂ̂��A�����Â��Ђ̖�肾���̂ł���B�ɒB����̌��Е��̗v�|�͎��̂₤�Ȃ��Ƃ����B
�@�u�i�N���|�����肪���Ă���o�ŎЂƂ͈�āA�����̂Ƃ���̂₤�Ȏ����o�ŎЂł́A���|���ɓ�ꂽ������ƒ���I�Ȏ�������邱�Ƃ͕s�\�ŁA���̏����Ȉ�����A�����͍L����Г���∥�A��ȂǍ��Ă�������ƁA���̓s�x�������āA�d���̍��ЊԂɊ��荞��ŁA��Ƃ�Ă���ӂ��ƂɂȂ�B�������āA�g����������Ȃɒ����u���Ă������Ƃ��o�����A�Z�������Ԃ������ĉ��x������Ƃ��ӂ��Ƃ͂ƂĂ��]�߂Ȃ��B��������������������ł́A�������ӂ��̂̐������猾�āA������V�����ɂȂ���ł��܂Ă�āA��������g�܂���ƌ�A���₽��ɑ����B���ۂɂ��̂₤�ȋꂢ�o�������Ă��B�����͉��Ƃ��Ă��A�����Â��Ђ͐V�����Ƃ��ӂ��Ƃɂ��Ăق����B�v
�@�w�@����Ƃ��s�x�̉����Â��Ђ́A���e�̒i�K�ł́A�S���Љ����̍�i�O�тɂ��Ắu���ォ�ȂÂ����v���g�ӂ��A����ȊO�̊�����������̍�i�ł͂��ׂė��j�I�����Â��Ђɂ��邱�ƂɂȂĂ�₤�Ɏv�ӁB�������A����Ȃ�̍l�ւ��āA�������߂Ă���Ƃ�����A�����A���Ƃ��Ȃ�Ȃ����ƁA�����˂��B�������A���̈�_�́A�ɒB������傢�ɂ����A���ǎ��́A�[��������ꂽ�`�ł��̓��͕ʂꂽ�B�����A���̔ӂ̂����ɁA���́A��͂�[���ł��Ȃ��Ƃ��ӎv�Ђ��̂�A�����A�܂��o�����čs�āA��p�����̂��߂ɑ����͂�����ł��ǂ�����Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����ƁA���������B�����C�J�̃f�X�N�̂��錚���̌��Ђ̋i���X�ŁA�R�[�q�[��O�ɂ��āA�ɒB����͂��Ɩق荞��ł��܂��B�������A��͂Ђɂ��ĂɐU��Ȃ����B�������������炴��Ȃ����B
�@�v�����Y��Ă���������o�܂��A�����Â͂���ƐS�ɕ�����ŗ����B�������A���������A�T���ق����C������B�����Ŏ��l�̓߉ϑ��Y�ɓd�b�����Ă݂��B�߉ς���́A����肽������A�O�N�O�ɁA�����C�J����A���j�I�����Â��Ђ̎��W���㈲���Ă��B���̎��Ɉ� �B���牽�����͂�܂���ł������A�g���u���̂₤�Ȃ��Ƃ͂���܂���ł������A�Ƃ��ӎ��̖�ɑ���߉ς���̓��͑嗪�����ł����B
�@�u�������ɁA�ɒB����A�V�����ɂ��Ă͂ǂ����Ƃ��Әb�͂����B�������A�����͐V�����͐�ɔF�߂��Ȃ��̂ŁA���F�̂悵�݂����āA���ւė��j�I�����Â��ЂŐi�߂Ă�����B���̌��ʂ́A���Ȃ�r��������A�̂���{���o�����B�ɒB�����������ւĂ�B�v
�@�k�c�c�l
�@ �ȏ�̂₤�Ȃ��Ƃ����Ԃ荇�͂��čl�ւĂ݂�ƁA��͂�A�����̎������̏o�ŎЂŖ{���o���ꍇ�ɗ��j�I�����Â��Ђ�p��悤�Ƃ���ƁA���X�����Ă���ւ��A������������Ȃ�A�悵��Β��҂ɗ��j�I�����Â��Ђ̗͂��\���ɂ��Ă��ւ��A���Ȃ�̌�A�̃��X�N���o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��ӎ������я�Ă���B
�@���̏ꍇ�ɁA�ɒB���A�����Â��ЂɊւ��Ă͂Ђɐ܂�Ă���Ȃ����̂��A�Ђ�Ƃ�����A�߉ς���̎��̑̌����S�ɂ����̂����m��Ȃ��B���Ă݂�A����́A�ɒB����̗���Ƃ��ẮA�ނ��됸��t�́A���ɑ���e�ł����̂��B���ЂȂ�Ɉ����āA��A���炯�̖{����邱�Ƃ��āA��ǐS�I�ȏo�Ŏ҂Ȃ�A��������킩��Ȃ��̂�����B�i�ےJ�ˈ�Ғ��s������v��ᔻ����k�������Ɂl�t�A�������_�V�ЁA1999�N10��18���A��l���`��ܓ�y�[�W�j
���p�̌㔼�ŏȗ������ӏ��̘b��́A�ЂƂ͂���܂łɂ����x���������g�����̗�i�s�Õ��t�Ɓs�m���t�s�g�������W�t�̌��e�̕\�L�Ɗ��{�̕\���j�ɂ��Ăł���A�����ЂƂ͓������������Ă������l�G���̃A���\���W�[�i���惆���C�J���j�̎���̎��т��u���ォ�ȂÂ����v�ɂȂ��Ă������Ƃɂ��Ăł���B���܂���ƁA�s��{ �߉ϑ��Y���W�t�̒�{���鏊�Ȃ́u�{���W�́A�E�L�̊e���W���{�Ƃ��A�S�Đ���������ɝ����v�Ƃ������L�̕\���ɐs���邾�낤�B�߉ϑ��Y�͒˖{�M�Y�ƕ���ŁA�����͐����A���Ȃ͐��������Ђ��@�Ƃ��錴���I�ȍ�҂ł���i���Ȃ݂Ɂs��{ �߉ϑ��Y���W�t�̈�����́A�ÓT�̕����{��˖{�̒����𐔑�����|�������ƂŒm���銈�ň���̖���A�����Ђł���j�B������������`�ł��A��f�̓���N�v�⓯���̕Ҏ҂ł���ےJ�ˈ�́A�����ɂ��Ă͓��u���R�Ɏg�Ђ��������g�ė����B���̂ɂ��ẮA���قނː��Ԃ̏펯�ɏ]�ĐV���̂̂�����͓̂K���ɂ���𗘗p���A�Ȃ����̂ɂ��Ă͐����i���Ƃ��Ă͑����j��p��B�������A�V���̂����Ă����ʂ̊����ŁA�ǂ����Ă�����ȏꍇ�ɂ́A���߂�͂������ɂ��Ă�����i���̂₤�Ȏ��́A�����Đ������͂Ȃ��j�v�i���O�A��O�y�[�W�j�Ə����悤�ɁA����Ӗ��Ō����I�ȍs�������ł���B�t������A���̋g�����͊����͐V���i��K���ɗ��p���A�Ȃ����̂ɂ��Ă͂�����N�����T�̂�p���\�\�������͈�����ɂ͋��e���j�A���Ȃ͌��ォ�ȂÂ����A�Ƃ���1960�N�ォ��70�N��O���ɏ����E��������������̂悤�Ȑl�Ԃɂ͎����Ƃ�������\�L�@���̂��Ă����B�������A���a�̏��N���邢�͑��O�ɋ�������g����˖{�A�ےJ�A�����͈Ⴄ�B���ƂȂ��ẮA�g������Ɩʒk�̂���ɕ\�L�@�ɂ��Đu���Ă����Ȃ��������Ƃ�����܂��B�u�g�����v����u�g�����v�ւ̓]���ɂ��Ă��q�˂Ă����ׂ��������B�{���̖ڎ����ɂ́u���@�g�����v�Ƃ���B
��
�߉ϑ��Y�͂��т��ыg�������ɂ��ď����Ă��邪�i�Ƃ�킯���̏����j�A�g���͓߉ς̒������������ŁA ���̎����قƂ�Ǖ]���Ă��Ȃ��B�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������k���k��l�q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r����g���Ɠ߉ς̂��Ƃ�������B
�u�g���@�߉ς���k�́w�͂����x�́l�A��ւ�Ȗ���Ȃ�ł�����ǂ��A����N�v�N�Ƃڂ��ƂŃC�`�������������̂ˁB���҂����Џ����Ă���Ƃ������ƂŁc�c�����鉹�y�I�Ȏ��̂ق��̂Ƃ��낪�o�ė���������Ƃ�����������̂��ȁB�ڂ������͂Ȃɂ�߉ς���ɒ����������̂��Ȃ��c�c�B
�߉��@���Ԃ�V�̕����̌��݂����Ȍ`���s���������Ǝv���܂��B�c�c����������������G�ɂ�����Ƃ������Ƃ������ł��傤�B
�g���@�����Ƃ����̂͂Ђ炪�Ȃ������ˁB�v�i�s�Z�́t1975�N2�����A����y�[�W�j
����N�v�Ƌg�����͓߉ϑ��Y�ɒ��ځu�����������v�悤�ŁA�ڍׂ͕s�����B�����Ƃ��A����ɂ͕��肪�q���݉���^�u�킪�o�_�v�u�͂����v�r�Ƃ����߉ςƂ̋����s�d�t�`���ɂ�鎍�̎��݁t�i����R�c�A1979�N11��25���j������̂ŁA�܂�������|���肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�����A���������ŐG�ꂽ���͓̂���́s�͂����t�ł͂Ȃ��A�߉ς́s�킪�o�_�t�ł���B�߉ς͓����i�y�[�W�j�œ���́q�킪�o�_�r�̇Z�̈ꕔ�����̂悤�ɉ��삵�Ă���B
��H�̎�̂Ȃ���������������ł���
�@�@�u���ւĉ������@�킽���͂ǂ���
�@�@�s���̂ł����@��̂ǂ���
�@�@�ǂ��ց@�ǂ��ց@�ǂ��ց@�ǂ���
�@�@�E�v�p�@�N�N�t�A�@�t�h�t�h�m��14�n�v
�߉ς͒���14�Ɂu���܂��̃��`�C�t���B���A����s���̂��������߂邱�Ƃ��Î�����B�u�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�v�͋g�����̍�i����̈��p�B�ނւ̈��A�v�i�����A�l�܃y�[�W�j�Ə����Ă���B����ɓ����̓߉ρE����Βk�q���_�u�킪�o�_�v�r�ɂ͂�������i���݉���̏��o�́s���㎍�蒟�t1977�N3�����ŁA�g���̍�������܂͂��̑O�N��12���j�B
�߉��@�Z�̃p�A�g�́A���₤�Njg������́w�T�t�����E�݁x���������܂ɂȂ��Ƃ��ӂ₤�Ȏ����I�Ȃ��Ƃ����āA����͓��ɋg������Ɛe�������A�g������̂���ǂ̎��W����q���āq�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�r�Ɠ���Ă݂���ł��B
�����@����͂Ȃ��Ȃ����������Ȃ��ł������B���̌`��肾���Ԃ悭�Ȃ��Ǝv�Ђ܂��B���������ł�����A�q�t�h�t�h�r���o�Ă���̂́A�l�����@���Ƃ̊ւ͂�i�l�����@���́u�ł̏����Ɛ���̕���v�ɁA�����R�I�ȗ͂������t�h�t�h�Ƃ��Ӓ����o�ė���j�����܂ЂƂ��߂�Ӗ��ł��A���������Ȃ��ł������B�i�����A��Z�Z�y�[�W�j
���́u�E�v�p�@�N�N�t�@�@�t�h�t�h�v�Ƃ�������́u�F�V���F�̃~�N���R�X���X�v�Ƃ��������̂���q���e�j�i�O�m�[�����j�r�i�G�E27�j����̈��p�����A���������g���͂�����F�V�̃G�b�Z�C�q�������ւ̈��r�i�s�ӓ��̒��̐��E�t�����j������p���Ă���A�F�V�͓������M���[���E���E�N���[���s�_���������t�i1852�j��V���[���E�h�E�t�[���j���@���s���̓������t�i1860�j�Ƃ������H�������Ď��M���Ă��邩��A�u����s���̂��������߂邱�Ƃ��Î�����v�̂Ƀt�b�v���A���́u�_��I�Ȓ��v�i�F�V�j�قǂӂ��킵�������͓�Ƃ��邢�܂��Ǝv����B�Ƃ���ŁA�g�����u���݉���v����Ƃ�����N�Ƃǂ̍�i�ɂ��邩�ƍl����Ƌ����͐s���Ȃ����A���e���O�Y�́s�߉́t�i1969�j���Ԉ������g�����I�s�V�� �߉́t�͓ǂ�ł݂��������B���鐼�e�́s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j��c��܂����s�V�� �_��I�Ȏ���̎��t�łǂ����낤�B�g�������̐����ɗ���������2000�s�́s�߉́t�𗽉킷�钷���ɂȂ����ɈႢ�Ȃ��B
��
�F�V���F�́A�q�������ւ̈��r�ŁA�t�b�v���ƃl�����@���ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�t�b�v���́A���e����ł̓E�v�p�A�Ñ�G�W�v�g��ł̓N�N�t�@�A�w�u���C��ł̓h�L�p�e�A�V���A��ł̓L�N�p�A�����ăA���r�A��ł̓t�h�t�h�Ƃ������A��������A���̖����ɂ��Ȃ�Ŗ��Â���ꂽ���̂Ǝv����B�A���r�A��́u�t�b�g�A�t�b�g�v�́u�������A�������v�̈Ӗ��ŁA�n���̐����������o���Ƃ����A���̒��̕s�v�c�Ȕ\�͂ɂ��W�����邾�낤�B
�@�l�����@���́w�o���L�X�x�ł��A�t�b�v���̓A���r�A�ӂ��Ƀt�h�t�h�ƌĂ�鐸��̈ꑰ�ŁA�A�h�j�����ƃo���L�X�Ƃ̉^���I�Ȍ��т���\������A���̐_���������炷��ڂ��ʂ��B�l�����@���l�̈��̊�]�ɂ���āA���̒��ɂ͂���߂ďd��Ȗ��������������Ă����̂ł���B�i�s�ӓ��̒��̐��E�t�A�y�ЁA1974�N10��1���A��l��y�[�W�j
��ʂɎ��W�̔��s�����͑����Ȃ��B�ׂ��Ȑ����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���̑唼�͏��Ő��S���������Ă��ꂫ��A�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B�ނ���O�͂���B���ŁE���������������B�������J��Ԃ��B�V���ł��o��B�����Ȏ��l�̎���W�Ƃ������b��삪����ɓ�����B���łƂ͕ʂɔł����߂čēo�ꂷ�邱�Ƃ�����B���鎞��◬�h�m�G�R���n���܂Ƃ߂��p���A���l�̌l�����������I���W�i���ɂ������j��S���W�B�����ɑS�т������͏��^�����߂��邱�Ƃ͂悭������B���j�I�Ȏ��W�ɂȂ�Ȃ�قǁA�����͏��łł͂Ȃ�����������łœǂ�ł���B���͔����Y�́s���ɖi����t�̎��т��A�ŏ��͍����w�Z�̌��㍑��̋��ȏ��i�}�����[���s�̂��̂������j�œǂ݁A�V�����Ɂi�͏�O���Y�ҁj�œǂ݁A��g���Ɂi�O�D�B���ҁj�œǂ݁A�p�앶�Ɂs���ɖi����t�œǂ݁A�����Y�S���W�ł��ǂ��A���Ŗ{�ł͓ǂ�ł��Ȃ��B���{�ߑ㕶�w�ق́q���������S�W�r�́s���ɖi����t����ɂ��������ł���B�s���ɖi����t������ɉ߂���Ȃ�A���e���O�Y���W�sAmbarvalia�t�͂ǂ����B���������Z�̋��ȏ��Łq�V�C�r�Ȃǂ́q�M���V�A�I�R��r�ɐG����A�V�����Ɂi����l�Y�ҁj�œǂ݁i���Y���P����̓p���Ɏ����Ă����������Ȃ����{��̖{�̈���ɖ{���������Ă����j�A���㋳�{���ɂ̌��J�K�M�Ғ��́s���e���O�Y�t��ǂ݁A���Ő��e���O�Y�S�W�œǂ݁A���e���O�Y�S���W�œǂ݁A�u�k�Ђ̕��|���ɂœǂ݁A�܂�ɍP���Ђ̕����łœǂނ��A���ł���ɂ����̂͐��N�O�A�s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�̓����W�̍��ڂ��������߂ɍ�������}���ق̐}���ʎ��i�������{�����邱�Ƃ��ł����j�Œʓǂ����Ƃ������ł���B�K���Ȃ��ƂɁA���͋g�����̂��ׂĂ̎��i�́j�W�����łœǂނ��Ƃ��ł������A�ӂ���Q�Ƃ���̂͋g�����S���W���B�e�L�X�g����ɂ��邩����A�Z�����������肵�Ă���Ε��ɔłł��������ɍ����x���Ȃ��Ǝv���B����̐Ί_��W�s�����t�͏��Łi�����j�̂��ƁA�P�Ƃ̎��W�Ƃ��ē�x�����s����Ă���B����͒��������Ƃƌ���˂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿����3���ł���B
�Ί_��W�s�����t�i�Ԑ_�ЁA1979�N5��9���A�����F�g�����j
�s���W �����k�Ί_���3�l�t�i�Ԑ_�ЁA1987�N11��20���A�����F�F�J���l�j
�Ί_��W�s�����t�i���b���A2001�N6��12���A�����F���c���Y�j

�Ί_��W�s�����t�i�Ԑ_�ЁA1979�N5��9���j�̖{���E�W���P�b�g�Ɓs���W �����k�Ί_���3�l�t�i�Ԑ_�ЁA1987�N11��20���k�����F�F�J���l�l�j�ƐΊ_��W�s�����t�i���b���A2001�N6��12���k�����F���c���Y�l�j���W���P�b�g
�k1987�N�ŁE2001�N�ł͌����}���ق̏����{�ŁA�W���P�b�g�Ƀt�B�������\���Ă���l
�{���̎d�l�́A��Z���~��l��~�����[�g���E��O���y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�W���P�b�g�B�W���P�b�g�̕\�����݂��ނ悤�ɃO���V����������Ă��邪�A�Ɩ��Ŕ��˂���̂ŎB�e���ɊO�����B�������܃O���V���Ə������̂͂������O���V�����̂��Ƃ����A�E�B�L�y�f�B�A�ɂ̓O���V���iglassine�j�́u�����Ԓ@�����������_�p���v�������Ƃ��A�X�[�p�[�J�����_�[�Ƃ��������̃��[���[���g���ĉ��H����B���̉ߒ��ŁA�p���v�̑@�ۂ͈��k�E����������A���Ԃ������v�Ƃ���B�����y�[�W�̃p���t�B�����̐����ɂ́u�p���t�B���X��h�z�E�Z�����������ł���B���ɂȂ鎆�Ƃ��ăO���V�����g�������̂��������߁A�O���V���ƍ�������邪�A�ʕ��ł���B�O���V�����������p���t�B�����́A�P�Ȃ�O���V�����������D��Ă���B�P�Ȃ�O���V�����p���t�B�����Ƃ��Ĕ����Ă��邱�Ƃ�����̂ŁA���ӂ��K�v�ł���v�ƋL����Ă��āA�u�O���V�����������p���t�B�����̗p�r���قƂ�Ǔ����v�Ƃ���Ȃ��Ɂu���ɖ{�̃J�o�[�i�ŋ߂ł͂��܂�g��Ȃ��j�v�ƌ�����B�v�́A�O���V�������p���t�B���������Ђ̉���h�~�Ɏg�p����A�p���t�B�����H���ꂽ�O���V���f�ނ̎��̕����㓙���Ƃ������Ƃ��낤�B�����Ŏv���o�����̂��A�剪�M�q���w�I�f�́r���`����g�����́u�p���s���v���B
�@�g�����ɓd�b����B
�u���́A�ق�A���ɖ{�Ȃɂ��Ԃ��Ă�����̔������̎��ˁA����A�Ȃ�Ă��������H�v
�u�Ȃ��A���̃p���s���̂��ƁH�v
�u���b�A�������A�p���s�����Ă����ˁB�����A�����B�p���s���A�p���s���v
�@�k�c�c�l
�@����Ȃ��Ƃ��v���Ă��邤���A���͎��������̎��̖��O��Y��Ă��܂��Ă���̂ɋC�Â����B�g�����̉Ƃɓd�b�����̂́A�ނ��{�̐��Ƃ����炾���A�ނ��u�p���t�B���v�Ƃ��킸�A�u�p���s���v�Ƃ������̂́A�����ɂ��g���I�ɋ����Ă��ꂵ�������B���邢�́A�o�ŋƊE�ł݂͂ȃp���s���Ɣ������Ă���̂�������Ȃ��B�������A���̍ہA�u�p���s���v�͂܂������g���I�ɋ������B�ނ̓q���V�Ƃ��������ł��Ȃ��A�]�˂̐E�l�̖���Ȃ̂��B�i�qXVII�r�A�s�ʎ��L�\�\���w�I�f�́k�����C�J�p���l�t�A�y�ЁA1972�N1��15���A���܁`���Z�y�[�W�j
�剪���̒�����́u����Ȃ��Ɓv�Ƃ����̂́u����ƂƂ��A����������ƂƂ��f�U�C�i�[�Ƃ�������B���������l�X�́A������������\���┠���A���̔������̎��ł���܂�A�Q������������炵�Ă���̂����Ă��A���Ƃ��v��Ȃ��̂��낤���v�i���O�A���Z�y�[�W�j�����A�u�p���s���v���̑f�ނɎw�肷�邱�Ƃ����������g���ɑ���ꌾ�Ƃ����M�v�ł͂Ȃ��B�ǂ����剪�������Ă���̂́A�w�p���Ȃǂɂ݂���N���X���̃n�[�h�J���@�[�̕\���ɒ��ځu�p���s���v�������Ă����Ԃ������悤���B�Ƃ���ŁA�g�����̑�����i���Љ��ɍۂ��āA�����Ӑ}�I�Ɍ��y���Ă��Ȃ��������Ƃ������B��͑т̗L���A��������u�p���s���v�ȂǏ��Ђ̉���h�~�p�̖��n�̑f�ނ̗L���ł���B�����w�I���n����́A��҂͂Ƃ������A�сi�����͐��E����ҏW�҂ɂ��̔����i�p�̎��A�c�Ə�K�v�ȗ��ʏ�L����Ă���j�ɐG��Ȃ��͎̂ד����낤�B�����A�g���������{�̏Љ�Ƃ������n���炷��ƁA�g�����т̐���Ƀ^�b�`���Ă��邩���f�̂��Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂł���B������A�u���E�сv�u�W���P�b�g�E�сv�ȂǂƋL���ƁA�����ɂ��g�������삵���悤�ɂƂ�ꂩ�˂Ȃ��B�Ȃ����V���ōw�������̂łȂ��ꍇ�A�܂�Ï��œ��肵���ꍇ�i�苖�̋g���������{�̑唼�͌Ï��j�A�т̂Ȃ����Ƃ������ɑт��t���Ă��Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ȃ��B����Ȃ炢�������y���Ȃ����Ƃɂ��悤�A�Ƃ����̂�����܂ł̎��̎p���������B���̓����s�q�g�����r�́u�{�v�t��������ɓW�J����ۂɂ́A���Ȃ��Ƃ��сk�̕��ʁl�ɂ͐G��邱�ƂɂȂ邾�낤���B�b�x��B�����܂��ɁA�Ί_�́q�_�y��r�i�̂��̖��������q�������r��z�킹����̂�����j�������B
�����o�ŃN���u�̋A��݂�
�ѓc���w��������
�ЂƂ�ō������Ă䂭�ƁB
�����������R�V��������
�����~�܂����B
�������
�w���Ŏ������Ă����炵���B
�s�v�c�ɂ₳����
�傫�Ȗڂ̐l�������͂�����
���̃A�^���ɁA�Ə��H�̉����w�������B
�u�w���~���E�L�`���Z��ł��܂����v
�ЂƂ��Ƃ����Ƃ��Ƃ̋L���������������B
���́u���̃A�^���Ɂv�Ǝw�����Ă݂�B
�R�V�����������Ă����A�ƁB
���J�K�M�s���l ���e���O�Y�t�i�}�����[�A1983�N7��1���j�́q���Ƃ����r�i�����Ɂu���a�\���N�Z���ܓ��A���l�̈�����Ɂv�̓��t�����j�̍Ō�̒i���ɂ́u���̖{���o�����@�͕��|���u�C�v�ɏ������u���e���O�Y��z�v�ł���B�����ҏW���̋{�c�{�h�A�������A�≺�T���̏����ɁA�܂��ҏW�ɂ������ĉ��������}�����[�̕��Ԍ������A�e�Ȓ�����Ղ������{���Y���ɂƂ��ǂ����ӂ��܂��B���h���鎍�l�g����������������������ĉ����������Ƃ�L��A�������v���B�g�����Ɛ��e���O�Y�Ƃ̐�ʉ����v���ƁA������~���[�Y�̔z�܂̎����̂�������Ȃ��v�i�{���A��y�[�W�j�Ƃ̎ӎ�������i����������Ƌ��{���Y����͎��ɂƂ��Ă������������������A��l�Ƃ��S���Ȃ�ꂽ�j�B�����ɁA�g���������ɑ��钘�҂̔������L�����M�d�ȏ،�������B��ˎ闝�s�g�����̏ё��t�i�W���v�����A2004�N4��15���j�̈�߂ł���B
�@�܂��g�������̒m����O�̂��ƁA��������㔪�O�N�̂��Ƃ������Ǝv���̂����A���J�K�M���̂���ɂ��ז����Ă��낢��Ƃ��b�����������Ă���Ƃ��ɁA�v��ʂ��Ƃ���g������̖��O���o�Ă������Ƃ�����B���̑O�N�A���e���O�Y���̋��A����J�ő剝���𐋂����B���N�A�u�C�v�O�����Ɍ��J����͕S��\���́u���e���O�Y��z�v�����قǂň�C�ɏ������낵���̂����A���̕��͂𒆐S�Ɉ���̖{���҂܂�邱�ƂɂȂ����Ƃ����B�}�����[����̊��s�����܂�A�g�������������Ă��ꂽ����A�����{�ɂȂ邾�낤�ƁA���J����͂������䖞�x�ł������B���̂Ƃ��̌������Ă߂�ꂽ���ȐM���́A�����͂܂�����ƂƂ��Ă̋g�������܂������m��Ȃ��������ɕs�v�c�ȋ������������B���ꂪ�A���ɂƂ��Ă͎��l�A�g������������肪���邱�Ƃ�m�����ŏ��̏u�Ԃł��������B���̔N�̎����Ɂw���l�@���e���O�Y�x�����s�����B
�@�������A���̂���̎��ɂ͒��̗����������J�o�[�ɔZ�̑т����炳�ꂽ���̖{�́A�Ђ�����n���ɉf�����悤�ȋL��������B�܂����{�⎆�̂��ƂȂǁA�낭�ɉ����m��Ȃ��������߂��낤�B�����A���ꂩ��A����Ƃ������́A�Ђ��Ă͋g�����̑���Ƃ������̂��ӎ�����悤�ɂȂ����̂́A�ԈႢ�Ȃ����Ƃł���悤�Ɏv����B�i�q�{�r�A�����A�ܓ�`�O�y�[�W�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�l�y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�W���P�b�g�B���G�꒚�i�ʐ^��_�j�B������Ɂu����@�g���@���v�Ƃ���B�\���̕z�́A���e���O�Y�Ō�̎��W�s�l�ށt�i�}�����[�A1979�j�̂�����������D�ΐF�ŁA�g�����s���e���O�Y�S�W�t�i���A1971-73�j�ł͗����������Ԍn���̃N���X���̎��ނɑI���A����ȍ~�͗����C���J���[�ɐ������B�S�W�̐Ԃ́sAmbarvalia�t�i�ł̖؎ЁA1933�j�̃��C�����b�h�̎c�����낤���A�͐Ԃ̕�F�ł���B

���J�K�M�s���l ���e���O�Y�t�i�}�����[�A1983�N7��1���j�̖{���ƃW���P�b�g
�g���́s���l ���e���O�Y�t�����s���ꂽ6�N��A���J�K�M�̒����q�u�P�l�v���������Ȃ��ցr�i�s���㎍�蒟�t1989�N3�����j�������Ă���B���J���S���Ȃ����̂�1989�N1��16���ŁA���O�́A���a�V�c�����䂵��1��7���ɂ͎��Z�̒��v���a�f���Ă���B�g���ɂ͑������[�ȔN�����������B
�@�u�i���̗��l���e���O�Y���E�G�悻�̎��Ӂv�W���A���N�̏t�A�V���s���p�قŁA�Â���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��ˁB���J�K�M�m��������n����A���́u����̓��v�����邱�ƂȂ��A���Ȃ��͐����Ă��܂��܂����B�����͂��߁A���̉����������Ă����F�l�����́A�����������ɂ����v���ƁA�Ƃ܂ǂ����o���Ă���܂��B�Ȃ��Ȃ�A���Ȃ������̒��S�I�l������������ł��B
�@��N�̏��Ă̓܂����ߌ�A�ő��́u���сv�Ƃ������ؔѓX�ŁA�ŏI�I�ȑō����̉�������܂����ˁB���Ȃ��͑��ς炸�A�R�J�R�[�����W���[�X������ł��܂����B���C���Ȃ��悤�Ɍ����܂������A�y�����b�������܂����ˁB���ꂪ���J�K�M�Ƃ̍Ō�̕ʂ�ɂȂ�Ƃ́A���͎v���Ă����܂���ł����B
�@�ܔN�O�̂��ƁA���W�w��ʁx�̗�����^���̓��A���Ȃ��͏j���̌��t���q�ׂɁA�������Ă���܂����ˁB��ŕ����A���@���Ò��̕a�@���o���āA����ꂽ�Ƃ̂��ƁB���̗F�b�̌����̂ɁA�����Ȃ������������܂����B�����炭�A�F�l���ׂĂɑ��Ă��A���Ȃ��͂��̂悤�ɐڂ��ė������ƂƎv���܂��B���łɁA�u�ÐF���R�v�Ɛ��������t�A�u�P�l�v�B�\�\���J�K�M�A���Ȃ��́u�P�l�v�ł����B
�@��N�̕�A���Ȃ������ʂ̎莆���A�Ⴂ�܂����B�������V���W�w���[���h���b�v�x�̕ԗ�Ƃ��āB�k�c�c�l
�@���̎莆�̏I��ɁA�ߓ����ɏo�ł�������̏����̂��Ƃ��A���肰�Ȃ��F�m�������n�߂��Ă��܂��B���_�w�m�ԁE�V�F�C�N�X�s�A�E�G���I�b�g�x�ƁA�w���e���_�̃G�b�Z���X�x�ł��B�������Ȃ��́A��ɂ��Ȃ��܂܁A���̐��������Ă��܂��܂����B���������S�c��̂��Ƃł��傤�B
�@���J�K�M����A�����⎄�����͐S�Â��ɁA���Ȃ��́u�Ō�̑����v��҂��Ă��܂��B
�������N�ꌎ�\���
�g���́u�ߓ����ɏo�ł�������̏����v�Ə����Ă��邪�A�O�ҁA���e���O�Y�i���J�K�M�ҁj�s�m�ԁE�V�F�C�N�X�s�A�E�G���I�b�g�t�i�P���ЁA1989�N5��20���j�́q�ҏW��L�r�̓��t���u���a�Z�\�O�N�\�\�ܓ��v������A��҂͖����ɏI������̂��낤�B�����A�܂�������|���肪�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B7�y�[�W�ɂ킽��[�������O�҂́q�ҏW��L�r�̏I���߂��ɁA���̋L�ڂ����邩�炾�B
�@�����āu�k�v���t�@�k�X��PROFANUS�l�v�u�����R��`�v�u���̏��Łv�u�����R���̉��l�v�i�w��������`���_�x�����j�A�u��ʒ������I�v�l�v�uSatura�̕��w�v�u�i�^���́k�������l���v�i�w�V�k�������l�����A���X�����w�_�x�����j�A�u�q�l�̏k�����Ёl�v�u�ւ̂��鐢�E�v�u���w�N�̐��E�v�i�w�ւ̂��鐢�E�x�����j�A�u���̊��o���v�u���̓��e�_�v�u�I�[�x���W���̋����v�u���l�̊�F�v�i�w��������x�����j�A�u���Ɗ�̐��E�v�u���̗H���v�u���́k�����O�l�ʂƁk�O�����l�ʁv�u���w���{��`�v�i�w���̏��x�����j�A�u���㎍�̈Ӌ`�v�u���̎���ɂ��āv�u�i���k�i�i�V�j���ցl�̉����v�u�l�������������́v�i�w�Γ��̖��M�x�����j�A�w���w�x�u�|�C�G�e�X�v�u�]���̓��L�v�u�䓁�Ɨь�v�i�w���e���O�Y�S�W��܊��x�����j�Ȃǂ�ǂ߂A�m�Ԃ̌y�݂Ɏ����E�B�b�g���~悂Ŏ���̃g�[�^����h�肱�߁A�T�ł������O���̋��n�����߁A�܂��u���̉h�v�u���̑s��v���������̋ɒv�Ƃ���Ɏ��������̎��l�̗��O���z�����Ă���B����͐��e���O�Y�̏ꍇ�A�|�l�Ȃ��ɂ��̎��݁A���݂��悭�����Ă��邪�A���_�A���l�_�͍�i�������x������傫�Ȓ��q�̖����ʂ����Ă��邱�Ƃŏd�v�ȈӖ���S���Ă����Ƃ�����̂ł���B�i�����A�O��Z�`�O�㎵�y�[�W�B�薼�E�������{�̐��e���O�Y�S�W�ɍ��킹�čZ�������j
���g�̕a�̓Ă����Ƃ�������Ҏ҂́A���e�ɂ�鎍�l�_�Ǝ��_�̂����A���_�͍\�z�����ł������Ƃ߂Ă��������Ɗe�т̕W�����f�q�ҏW��L�r�ɏۛƂ����B�����炭�͈⏑�Ƃ��āB�����́q���o�ꗗ�r�Ɂu���@�{���́A��㔪��N�Z����芧�s���ꂽ�}�����[�Łw���e���O�Y�S�W�x�i�S�\�j���^�̂��̂����e�Ƃ����v�i�����A�O����y�[�W�j�Ƃ��邩��A�e�l�͂��ꂼ��̐��e���O�Y�S�W����s���e���_�̃G�b�Z���X�t��a�������D���̂��i�s��{ ���e���O�Y�S�W�t�ł����A��5���E��6���̏��т��s���e���_�̃G�b�Z���X�t�̒�{�ƂȂ�j�B���J�K�M�́A���̖͔͉��������B
�k2018�N5��31���NjL�l
�{�����G�̕\���ɂ́A���m�N���Ő��e���O�Y�̏ё��ʐ^���f�����Ă���B2�_�߂̉����̎ʐ^�ɂ́u�� ��ӐM�ꎁ�B�e�i1965�N12�� ������ɂāj�v�ƃL���v�V����������̂ɁA1�_�߂̏c���̎ʐ^�ɂ̓L���v�V�������Ȃ��B�����������z�����l���Ƃ炦���A����U��̂������̎ʐ^�́A���J�K�M�̎B�e�ɂ��̂ł͂���܂����B�O���f����Ȃ̂ŃL���v�V���������ɂ����ɂ��Ă��A�B�e�N���W�b�g���Ȃ��̂͒��҂̊�㵂��Ȃ����Ƃ�������Ȃ��B
�ےJ�ˈ�s�݂݂Â��̖��t�i�������_�ЁA1985�N3��25���j�́s���̂Ԃāt�i�����ЁA1966�j�A�s�R�����u�X�̗��t�i�}�����[�A1979�j�ɑ����ےJ�̑�O���|�]�_�W�B�ےJ�͕��w�Ɍ��炸�A�W�������ɑ��銴�o���l���݊O��ĉs�����A����͎��g�̎��M�����⒘��̂܂Ƃ߂����ɂ����f���Ă���B�s�R�����u�X�̗��t�́q���Ƃ����r�ɂ���A�s�㒹�H�@�t�i1973�j�Ɓs���͓ǖ{�t�i1977�j�͒��ѕ]�_�A�s���{���w�j���킩��t�i1978�j�͒Z�߂̒��ѕ]�_�ɂ��������^�̂������́A�s���{��̂��߂Ɂt�i1974�j�͐����_�I�ȃp���t���b�g�A�s���߂��ˁt�i1975�j�͉������W�߂����́A�s��̂����t�i1975�j�͕��Y���]�A�s�V�ю��ԁt�i1976�j�͒Z�����͂̃X�N���b�v�u�b�N�݂����Ȃ��́A�Ƃ�������̋K�肪�����Ⴞ�B�̂��ɕ҂܂��s�ےJ�ˈ��]�W�k�S6���l�t�i���Y�t�H�A1995�`96�j�̊e���^�C�g���́A�@���{���w�j�̎��݁A�A���������ĐV�Í��A�B�ŋ��͒��b�U�A�C�ߑ㏬���̂��߂ɁA�D������̍�Ƃ����A�E���{��Ő�����A�ŁA�{���s�݂݂Â��̖��t���^��11�т̂�����6�т���]�W�Ɏ��߂��Ă���i�W��́k�@�l���͏��т̕�L�A�ے������͎��^��]�W�����j�B
�@�@���{���w�j���݂킽���\�\�@
�@�@�j�����ɂ��Ă̕��w�_�\�\�@
�@�@�������̏]�Z�킽���\�\�C
�@�@��您�O�͍��Ȃ̂�����k�x����w�_�l�\�\�D
�@�@���J�k�ΐ�~�_�l�\�\�D
�@�@�i�n�ɑ��Y�_�m�[�g�\�\�D
�܂�A�̂��Ȃ������̂�
�@�@���̏��N�̃n�[���j�J
�@�@�l�������̉����ٔ���R������ᔻ����
�@�@�剪����
�@�@�����a�̓��
�@�@�@���̍�
�@�@�@���̂ԑ�
�@�@���芅�сk�V�F�C�N�X�s�A�́s���炵�t�_�l
��5�сB�q�剪�����r�͇D�ɊY�����邪�A�q���̏��N�̃n�[���j�J�r�Ƃ����s�������`�t�_�ȂǁA��]�W�ɎM���Ȃ������ŁA���p���ŏI���錋���̗]�C�͗ނ��݂Ȃ��B�{�������́q���芅�сr�͖`���́q�j�����ɂ��Ă̕��w�_�r���Č����Ȍ��ʂ������Ă���B���́q�j�����ɂ��Ă̕��w�_�r�i���o�́s�Q���t1983�N2�����j�ɁA�g�������W�s����t�i1938�N����40�N���߂ɂ����Ď��M���ꂽ�a�̂Ɣo��̏W�ŁA�̏W�́q�`�W�r�A��W�́q�z���r�Ƒ肳��A���s�͟f���2002�N�j���l���邤���ŏd�v�Ȏw�E������B
�@�ŋ����Ă����ł����B�����ېV�ȍ~�̑�\�I�Ȍ���Ƃ���l������Ƃ���A�^�R�ʂƂ��ӂ��ƂɂȂ�Ǝv�Ђ܂����A�ނ̎ŋ��ł͉��ƒj�������������Ƃ��B���Ƃւw�]�ˏ鑍�U�x�̖���ł́A�������U���]�ލ��[�ŏ����[�炪�R���S���Y�̗�������肵�߁A�u�{���{���Ɨ܂𗬂��v�B�S���Y�������B�w���R�]�˂�����x�̖���ł́A����c��́u�×܁v�ׂ���x�ł����A�R���S���Y�́u��n�ɗ�������đ��߂ɋ����v�B�ނ́u���T�����T�c�c�v�Ɖ��x�������A�₪�āu�l�X�݂ȋ����A�݂ȟ`�W���āc�c�v���ƂȂ�܂��B�k�c�c�l�^�ς����Đ^�R�ʂЂƂ�Ɏ~�߂܂����A�������Ӌ��������̎�͌���Ƃ����̍ł����D����Ƃ���ł����B�����āA�ނ炪�j�̟�������Ȃӂ��ɗ��p�����̂́A���q������������܂��A�ނ��늽�}��������ł���A���̔w�i�ɂ́A�q�ł���j�������������ɂ����Ă悭�������Ƃ��ӎ�������Ǝv�͂�܂��B�i�{���A���`��y�[�W�j
�̏W�q�`�W�r��1940�N�A�g���̍ŏ��̒����ł��鎍�̏W�s�����G�߁t���^�ɂ������Ď肪�����������A�q蜾蠃�k�X�K���l��r�Ɖ��肳�ꂽ�B�X�K���Ƃ̓W�K�o�`�̌Ï̂ŁA���̏������X�K���I�g���ɚg������悤�ɁA�e�[�}�͏������B�u�����苃���v����u�����v�ցB�q�`�W�r�̑莫�u�����˂������͕��v�Ё^�ʂ��܂̖�͂�����Ɂ^�˂݂̂�������@���v�͕W��̓T�����낤�B�˖{�M�Y�Ɉ˂�u��E��̛���ɂ����̕\���͔���W�ɂ��ɑ�������B�\��m�悵�̂ԁn�̕S�l���́u��͔R����͏����v���A���̈��ł��炤���A���̍�͑���܂ł���A��O��ȉ�����ƚd���ɕ������A���Ɉ�r�m���n�̎v�Ђ�瞁m�قƂ��n�銴����B�u���͂ޓ������̓��ƒm�炸��Łm�Ƃ���݁n�ɂ��Â�̓��܂Ō�m����n���Ћ��m���n��ށv�����쒆�̂��́B�ßT�ŔߜƂȒ��ׂ͔�����̂�����v�i�s�������k�y�R�[�S�ȕ��Ɂl�t�A�y�R�[�A1983�N4��27���A�O�Z���y�[�W�j����A�`�W�Ƃ������ԚL�ɋ߂��B���̑莫�A�s�����G�߁t�̋g������́q���́r�u���邩�Ȃ��݂Â��^�Ȃ���邤�������^�̂�����肠�͂��^�킩���Ђ̂�߁v�Ɠ�����ڂ�S���Ă���B�g���͂Ȃ��薼��ύX���A�莫�Ȃ������̂������ւ����̂��B��̂̍s�ׂ���A�e�[�}�Ƃ��Ă̋q�� �ցB
�@�Ƃ��낪�A���c�k���j�l���w�����j�k�x�Ƃ��Ӎu�������Ă�����\�N��A���{�l�͂���Ɉ�i�Ƌ����Ȃ��Ȃ����A�j�������͔��ɂւ��B���̌��ʁA���Ƃւΐ^�R�ʍ�́A�����ƜԚL�ɂ݂����ŋ����Ⴂ�̕�����҂�������ƁA���҂����Â炳�������A�q�̂ق����V������₤�ɂȂ��B�Ȃ��������ӕ����̕ω������������ƌ��ւA���{�l�̌���\�͂�����I�ɍ��܂�����ł���܂��B���Ƃւk�c�c�l����o�ł̖{���o���B�������ӏ͂��ƂւΏ��a�\�N��̓��{�Ƃ���ׂ�Α��Ђł���܂��āA�����S�̂̌���\�͂̑���͋^�ӗ]�n������܂���B�܂����ł͂͂���Ƌ����Ȃ��Ȃ�A�����ł͖��炩�Ɍ���\�͂��㏸�����̂ł�����A���t�ŕ\���ł��Ȃ����狃���̂��Ƃ��Ӗ��c�̐��̐������́A�����ɗ���������Ă��킯�ł��B�����āA�Ȃ����{�l�̌���\�͂����܂����Ƃ��ӂƁA����͂��܂��܂̗v���̕����Ƃ��ĂƂ�ւ邵���Ȃ��ł����B�i�q�j�����ɂ��Ă̕��w�_�r�A�{���A���y�[�W�j
�s�����G�߁t���s��1940�N�͏��a15�N�A�����m�푈�J��̑O�N�ŁA�Ȃ�قNJےJ�̎w�E�̂Ƃ���A����o�ł̖{���o�����Ƃ͍������͂邩�ɍ���ł���A�����������̕��w�N�����l�G���ł͂Ȃ��A���Ɣł̒����𐢂ɖ₤���Ǝ��́A�������������낤�i�g���́s���܂�͂����L�t1939�N5��15���̏��ɓy�����F�k�̂��̘I�������ƁE���J�^�l�̒�E�y���S�F�́s������m�t�Ƃ��������������Ă��̕��˂�ɂ���ł��邪�A�����͗��F�����S�ƂȂ��č�������낤�S�F�́u��e�W�v�ł���j�B����͂Ȃɂɑ����ꂽ���ʂȂ̂��B�ЂƂɂ͋g�������m�F�ƌQ��ǂ����ƂȂ��A�����̒��q������̏����ɂ��邱�Ƃ����������ł���A�ЂƂɂ͂���܂ł̋Ζ���̓�R���i��w�̐�发�s����o�ŎЂ������j������o�ł��\�ɂ��������������ł���A�t���I�ɂ́A�o���ɍۂ��ėF�l�����������p�����S�ʂɖ��������ł���B�������A������d�v�Ȃ̂͐�n�ɕ����܂��A�����苃�������Ɏ��̂����̂������ƁA���q�������Ƃ��ꎩ�̂ł���B���̂Ƃ��g���͎����𒆐b���ɂȂ��炦���s����t�i�́q�`�W�r�j����A��������̒�ɒ��߂Ď��Ƙa�̂̏W�s�����G�߁t�i�́q蜾蠃��r�j�Ɉڍs�����B�g���͎���̌���\�͂݁A���l�ł��邱�Ƃ�I�������̂ł���B

�{���̎d�l�́A����~��O��~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�㐻�۔w�����E�W���P�b�g�B�ڎ��̗��Ɂu����@�g ���@���v�Ƃ���B�{�e�����M����ɂ������āA���ɔłŏ\���N�Ԃ�ɑS�эēǂ����B�ےJ�̂��̎�̖{�ɕK�����鏉�o�ꗗ���Ȃ��̂��b�����v�������A�͂����Č��łɂ͂����ƍڂ��Ă���B���ɖ{�̉��t���L���i�{���A���t�̂��Ƃ̃y�[�W����䊄�ɍ��킹�邽�߂̒����v�f�j������Ăł��A���o�ꗗ���ق��������B��قǂ̂��Ƃ��Ȃ���ΒT�����Ă܂ŏ��o��ǂނ��Ƃ͂Ȃ����A�u��҂����ǂ�Ȕ}�́i�ǂ�ȓ��W�j�ɔ��\�������v�ɂ́A���Y��i�������Ɏ��܂��Ă����Ԃ���͂킩��Ȃ����ׂȁA��������I�ȂȂɂ����܂܂�Ă���B
���k����l�I�̈��B�W�K�o�`�Ȃ̎���I�m�������n�̌Ö��B�����A���ƕ��Ƃ̋����ׂ��A�u���זI�v�Ƃ��Ă�A�p�͂������肵�Ă���B�l���i���Ȃǁj���E������Ⴢ����Ēn���̌��ɓ���Ă��痑���Y�݂��A���̗c���̉a�ɂ���B���̂��߁A�����ł́A����I�͑��̒��̗c�����Ƃ��Ă��āu��Ɏ���v�ƌ����Ď����̎q�Ƃ��ė{���Ƃ����A���{�ł�����I�͕߂炦������n���̑��ɂ��킦���ݗ{���K��������Ƃ����`��������B�q�G�̐��r�i�J�E2�j�́u�킽���͒���������@�O�r��S���Ł^�f�R�̏�ɗ��^�����āu�����鉳���v���B�����v�́u�����鉳���v�́A�I�̂悤�ɂ��A���̂悤�ɂ��v����B
�k��߁l�@�X�K���̂悤�ɗe�p���[��ł��邳�܁B���u���ʁm�ނȂ킯�n�́@�䂽�����ᖅ�m�킬���n�@���ׂ́@蜾蠃�k�{�y�l���q�m���Ƃ߁n�́@���̎p�m���فn�́@�[���m���炫��n�����Ɂ@�Ԃ̔@�v�q���t �ꎵ�O���r�B�u���|�m�݂͂Ȃ��n�́@���̑т��@���сm�Ђ����сn�Ȃ��@�ؑсm���炨�сn�Ɏ�炵�@�C�_�m�킽�݁n�́@�a�̊W�m���炩�n�Ɂ@��m�Ɓn���ām�����n��@蜾蠃�k�y�l�̔@���@���ׂɁ@������Ёv�q���t �O�����r
�A�l���B�k�c�c�l
�k�Q�l�l�����̉̊w���w���_�䏴�x�ɂ́u���c�c������A�ٖ���v�Ƃ���B�쐶�̓��{���͑����ׂ��A�S�̓I�Ɍ��Ă��[���ł���Ƃ����B�w�Í��W�x�́u������Ȃ��H�̔����������ė��s���l�����Ƃ��܂��ށv�q�O�Z�Z�r�̃X�K���́A��i�Ȃǂ��玭���w���ƍl������B�i�����A�Z�O�܃y�[�W�j
�쌴��v�s��㵂̐l�\�\��z�̌Óc��t�i���Y�t�H�A1982�N10��25���j�́A�}�����[�̑n�Ǝ҂ɂ��ď���В��̌Óc��i1906-73�j�����^�ӂ��ɉ�ڂ����������낵�����B���łɌÓc�̈�����������Ă܂Ƃ߂�ꂽ�A���̖����s��z�̌Óc��t�i�}�����[�A1974�j�\�\�V�ł͉P��g�����s���̂ЂƁ\�\����o�Ŏ҂̏ё��t�i�a���[�A1980�j�\�\���������B�����ƁA�Óc�̔��t�̗F�ł���P�䂪�ѕ��Ɂu�������o�c�̐ӔC�҂Ƃ��Ă̌Óc�ɂ͔ᔻ�I�ȋC���������Ă���l�́A����ɐG��Ȃ��Óc�]�̂ɂȂ��������킹��C�ɂȂ�Ȃ��Ɩ쌴�N�Ɍ������v�Ɗ��{����ɂ��ēǂ߂A�Óc��̑S�e�͂قڂ��߂�B�쌴�͐��A�V���Ёi�ҏW�҂Ƃ��đ��Ɏ��́s�Ηz�t��S���j�A�p�쏑�X�A���j���[���o�āA1953�N�A�}�����[�ɓ��Ёi�g�����̓��Ђ�1951�N�j�B�����A�s������{���w�S�W�t��ҏW�ӔC�҂̕S�����o�̂��ƂŒS�������B�̂��ɌÓc�̖����āk��1���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���E�ʊ�1�l�t�i1955�N10��15���`1956�N9��20���j��ҏW���Ă���B�����́u���v�i���Ȃ킿�쌴���̐l�j�͑��Ɏ��S�W�̏����ɂǂꂭ�炢�����邩�Óc�������āA����������B
�u������厖�Ȏd���͖{���Z�����Ǝv���܂��B���e�̎c���Ă����i�͌��e�ɂ܂�����˂Ȃ�܂���B�Ȃ����͔̂��\�G������͂��߂āA���Ŗ{�A�ĔŖ{�A���x�Ăɓ����āA���̊Ԃ̈ٓ��グ�˂Ȃ�܂���B���̏�Œ�{�m�����ق�n�����ɂ��邩�����߁A�ق����Q�Ƃ��Ė{�������肵�Ă����˂Ȃ�܂���B���̍�Ƃɂ��Ȃ�̎萔��������Ǝv���܂��B���e�Ə��Ŗ{�A�ĔŖ{�͉�����̂�����Ƃɑ����Ă���悤�ł����ǁA���\�G���͓���̐}���قłł��T���o���˂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�{���Z���ɁA�ꊪ������ꃕ���A�ꃕ�����A����A�����Ƃ����邩�ȁB����������́A���ۂɍ�Ƃ��͂��߂Ă݂Ȃ��Ɓc�c�B���ꂩ��A�U�Â��Ă��鏑�Ȃ␏�M�ނ��W�߂�̂���d���ł��v�i�{���A��Z�Z�y�[�W�j�B
�q�s�}�����[ �}���ژ^ 1951�N6���t���邢�͕S�����o�̂��Ɓr�Ŏw�E�����悤�ɁA�P��g������旧�Ă����s������{���w�S�W�t�͒}���̌l�S�W�̕ҏW�E����̕��������K�肵������A�ҏW�Ҏ哱�̏o�ŎЂ̊�b�͂����Ōł܂����Ƃ����邾�낤�B��10��̎В��߂��e�r���Y�́s�c�Ƃƌo�c���猩���}�����[�k�o�Ől�ɕ����l�t�i�_�n�ЁA2011�N11��30���j�Łu�ǂ����Ă���Ђ̓���������҂̂ق��Ɋ炪�����Ă��܂��A���҂̌����Ȃ�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B����͑n�Ǝ҂̌Óc����̈ӎ��ƕ��j���炫�Ă���킯�ł���B���҂̌����Ȃ�Ƃ����̂́A���҂��Ђ����痧�ĂĂ����{����邱�ƂŁA���Ɏ��ڂ����Ȃ��Ƃ�������Ӗ��ł̈������`���������Ǝc���Ă��܂����B���ۂɂ��������ł����{��������ǂ��A����������������̂ł��B����Ō����\���o�����肵�Ă��A�����ł��Ȃ��킯�ł��v�i�����A���y�[�W�j�ƌ���Ă���B����́u�u�����ɖ{�y�����邩�����҂ɑ���o�ŎЂ̐ӔC�ł���v�Ƃ����c�Ƃ̘_���v�i���O�j��D�悷��Ȃ瓖�R�̔����Łi�e�r�͉c�Əo�g�҂Ƃ��Ē}���ŏ��̎В��j�A�Ǐ����������悵�Ƃ��镗���ɗ����ꂪ���ȕҏW�S���҂Ƃ̑Η��͔������Ȃ��B����S���҂̗����ʒu�����ɂȂ�B�}�����[�Œ������씨������쐳�v�̉�z�s�l�͏��N�Ј��\�\���ׂĂ̏��N�Ɖi���ɏ��N�̐S�����l�ɑ���t�i���|�ЁA2000�N12��1���j�ɂ�������B
�@���i�i�{�j�̐i�s���`�F�b�N���Ǘ����邽�߂ɁA���암�ł́u�i�s���v�Ƃ����m�[�g�����Ă����B���Ƃ��A�`�Ƃ����{�̏��Z��߂��Ĉ�T�Ԍ�ɍčZ���o�邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ��́A���ۂɏo�Ă��邩�ǂ�������T�Ԍ�Ƀ`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̐i�s�`�F�b�N�̎d���ɂ��Ă��g�c�k�L�l�������Ă��ꂽ�B
�@��Ɂu������{���w�S�W�v�̓��F�̂Ƃ���ł��q�ׂ��Ƃ���A�ƒ��}���قł̒����ɂ킽��ۊǂɑς�����悤�A��v�ł������肵���{������߂����Ă����}�����[�́A�u�i�������Ɋ����邱�Ƃ���ڂƂ��āA����E���{�E�p���Ɍ���ō��̋Z�p�����p����v�Ƃ������j���т��Ă����B���������āA���{�ɂ͔��ɐ_�o�������Ă����B�p���ɂ��Ă��@�ۂ��������Ȃ₩�Ŗڕ��̏d�������m�Ƃ��Ák�}�}�l���n�̗p�����g�p���Ă����B
�@�{��������Ƒ����Ă��邩�ǂ����ׂ���@�ɂ��Ă����낢�닳���Ă��ꂽ�̂ł���B���Ƃ��A�{�̔w���͂����ƕ����邪�A����т�ׂ����ŒԂ����Ă���̂�������B������u�����莅�v�Ƃ����A�����Ă��̖{�͎O�{�܂��͎l�{�̂�����ɂȂ��Ă���B���R�A�O�{���l�{�̂ق�����v�Ɍ��܂��Ă���B�{�̌��{�{�m�݂ق�ڂ�n���Ǝ҂̕��������Ă����Ƃ��́A�K���u������v�̃`�F�b�N���Y��Ȃ��悤�Ɍ����Ă����B
�@�O�{�g�p�̏o�ŎЂ������������A�}���̖{�͂��ׂĎl�{�ł������B���̂��Ƃ͐��{�Ǝ҂̊Ԃł͈Öق̗����ɂȂ��Ă����B
�@����Ƃ����{�{�̓_�������Ă��āA�����莅���O�{�ɂȂ��Ă��邱�ƂɋC�Â����B�̂���o���肵�Ă���Ǝ҂Ȃ�A�Ƃ��Ɍ���Ȃ��Ă��������Ă���̂ŁA����ȊԈႢ�͂Ȃ��͂��ł���B�u���������ȁv�Ǝv���Ă�����A�r������Q�����Ă����Ǝ҂������Ă������̂ł��邱�Ƃ����������B�����莅�̎��̂́A���̂Ƃ����ŏ��ōŌゾ�����B�i�q�}�����[�͍ŏ�̖{������߂����Ă����r�A�����A���O�`���܃y�[�W�j
���́u�l�{�̂�����v�𐽎��Ȏd���ƌ��邩�A�ߏ�i���ƌ��邩�͏o�ŎГ��ł��������Ƃ��낾�낤�B�������ЂƂƂ��Ă��A�����̕p�x��ŏI�I�ȍ��蕔���͌o������т����Ƃɂ����\���l�Ɉ˂�Ȃ���v���邵���Ȃ�����A���ʂƂ��Čʂ̃P�[�X�̉��͂��肦�Ă��A���O�Ɉ�ʓI�ȉ����p�ӂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B����Ŋ�������P�s�{�ł�����������݂̃p�����[�^�[�͐������B�܂��đS�W�i���邢�͑p���j�Ƃ��Ȃ�A����z�{�ƍŏI��z�{�ł͕������傫���قȂ�̂��ӂ����B����������������Ƃ����āA�V���[�Y�̊��s�r���Ŏd�l�⎑�ނ�ύX����킯�ɂ͂����Ȃ��B���삪�d�v�ƂȂ鏊�Ȃł���i�}�����[���l�S�W��s������{���w�S�W�t�Ȃǂ̑p���ŏo�ŊE�ɒn�����߂Ă������Ƃ́A���߂Ďw�E����܂ł��Ȃ��낤�j�B�����ƃ����N���������v�Ɨ��ނ��߁A�����������]�͓�����낤���A���ꂩ��͋g�����������ӏ��̖ʂ����łȂ��A�p����N���X�Ȃǂ̎��ޖʂ��ڏq����K�v�����邩������Ȃ��B�s��㵂̐l�\�\��z�̌Óc��t�̎d�l�́A�ꔪ���~��O��~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�����E�W���P�b�g�B���t�̑Ό��y�[�W�Ɂu�J�o�[�E���J�b�g�@�����v�A���t�Ɂu����ҁ@�g�����v�Ƃ���B�S�̂̈�ۂƂ��ẮA
����Y��Y�E���Ò��v�E���|���L�s�a��Ɗ���̂������\�\�@�_�S�C��ǁt�i�}�����[�A1985�N6��10���j
�ےJ�ˈ��s���̉́t�i�������X�A1987�N8��15���j
�J�c�����s��z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�N4��25���j
�푺�G�O�s���{���V�L�t�i�}�����[�A1989�N6��20���j
�Ƃ������l�Z���E�㐻�E�W���P�b�g���̒P�s�{�ɋ߂��B�Ƃ�킯�s��z ���̕��w�t�̃J���[�R�[�f�B�l�[�g�́A�u��z�`�Z�s�A�F�`���F�n�̐F�ʌv��v�Ƃ����{���Ɠ����v�l��H���琶�܂ꂽ�悤�Ɏv����B�W���P�b�g�́��m�܂�n�ɒ��i���ɂ��F�m���������n�Ɍ�����j�̃J�b�g�́A����͂�������f�U�C���������̒}�����[�̃}�[�N�ƂȂɂ��W������̂��낤���B�Ȃ��悤�Ɏv����B������ɂ��Ă��A�g���������ɂ����镶�|���̒�ԃX�^�C���̈���ł���B
�k�NjL�l
���ҁq���Ƃ����r�Ɂu���̖{�������ɓ����ẮA�k�c�c�l�Óc��̎��ӂɂ����}�����[�̑����̐l���������ނ������Ă����������B�i�}�����[�̋��Ј��A���Ј��͂��ׂĉ����ɂ����Ă�������B�j�v�i�{���A����y�[�W�j�Ƃ���B�u�L�����̐ӔC�҂̋g�����v���A���Ј��E�g�����̉������낤�B

�����ƁE�a�c�F�b�i1906-77�j�͔����t�i1872-96�j�̌����Ƃł�����A�s�N���ɂ͉��c�Ǖ��Ƌ��҂��s��t�S�W�k�S7���l�t�i�}�����[�A1953-56�j�A�ӔN�ɂ͐ӔC�ҏW�҂Ƃ��ās�����t�S�W�k�S4���S6���l�t�i�}�����[�A1974-94�j�A�Ɠ�x�ɂ킽���Ĉ�t�̑S�W��҂�ł���i����ȑO�ɂ��A�V���ДŔ����t�S�W�Ɋւ���Ă���j�B�����̈�t���������Ă���a�c�����A�咘�s��t�̓��L�t�i�}�����[�A1956�N6��30���j�́A�s��t�S�W�k�S7���l�t�̈�t���L�܂��ď������낳�ꂽ�B�q���Ƃ����r�����̗���������ė]���Ƃ��낪�Ȃ��̂ŁA�S����^����i�{���A�O�l���`�O�l���y�[�W�j�B�����͋����������\�L�����A��N�̕��ɔłɕ���ĐV���V���Ȃɉ��߂��B
�@���́u�����t�̓��L�v�i���a�\���N�㌎��\�����s�A�����̖��Њ��B�̂��A�����̌��ʁA�I���ЂƂȂ�A��������Ĕł��ꂽ�B�j�́A�u��t�̓��L�v�Ɖ���A�������āA���a��\��N������\���A���c���[���犧�s�����B�u�����t�̓��L�v�́A�������낵���B
�@���x�̒}�����[�Łu��t�̓��L�v�́A�薼�������c���[�łƓ��������A�܂������A�V�����������낵�����̂ł���B
�@���a��\���N�����\���ɔ��s���ꂽ�}�����[�́u��t�S�W�v�i���c�Ǖ����ҁA�S�����j�́A���݁A�ŏI��z�{�̍Z�������B���̒}�����[�Łu��t�S�W�v�̕Ҏ[�ɁA���ۂɂ��������̂́A���a��\���N�H���炾����A�����܂łɑ��|���ܔN�����������ƂɂȂ�B
�@���͕Ҏ[�����S���҂Ƃ��āA�e��������x�ƁA�c���K�j�Ǝ����̊O�A�m�����̑����̊�b���������邱�Ƃ��ł����B
�@�܂��A������w�}���فA���}���فA�����V���G�����ɁA���c�Ǖ��E���{����Y�E�g�c���ꏔ���������̊O�A�����̋M�d��������@��Ɍb�܂ꂽ�B
�@���́u��t�S�W�v�̂��߂ɁA�͂��k�}�}�l���Ă��ꂽ�l�B�̖��́A�ƂĂ��A��������Ȃ��قǂ��B
�@���̎d���͒n���ł���������A�����A�����̊�@�ɂ��炳�ꂽ���A�����̐l�B�̉��������ŋ~���Ă����B���́A�u��t�S�W�v�W�̎d�����I���悤�Ƃ��āA�]���悤�̂Ȃ��[�������Ɣ��������Ă���B
�@���́A�}�����[�́u��t�S�W�v�ɏ]���Ȃ���A�V���Ђ̈ꎞ�ԕ��ɂɎ��߂��u�����t�v�ƁA�}�����[�̓��{���w�A���o���̒��́u�����t�v�����s�����B���̊O�A��N�̏t�ɁA�p�앶�ɂ̈�t���L���̕ҏS�������B���ɖ{����̗\��ŁA�r���ɂ́A����܂ŕs���ł��������L�̐l�ԊW�����ė��L�����B���Ƃ��ẮA���́u��t�̓��L�v�����s�����O�ɁA���R�A�o�ł������̂ƍl���Ă������A���̉č��Ɋ��s�̗\�肾�������B���̂��߁A���܂�d�v�łȂ��l�ԊW�́A���̏ꍇ�A�G��Ȃ������B
�@���́u��t�̓��L�v���A�܂��A�u��t�S�W�v�̕��Y���Ƃ����Ă悢�B
�@��t�̓��L��ǂ�ł��Ȃ��l�B�ɂ́A�s�s���Ȃ��Ƃ����낤���A��t�̓��L�̈��p�́A�����ŏ��ɏ������u�����t�̓��L�v�̏ꍇ���͏��Ȃ��B�܂��A�����Ɉ��p�������L�̌��T�́A���ׂāA�}�����[�Łu��t�S�W�v��O���A��l���Ɏ��߂��u���L�v�ɋ������B���ꂪ�@���ɂȂ��āA��t�̓��L��ǂ�Ō��悤 �Ǝv����l���A�ЂƂ�ł��B�����璘�҂̂����킹���B
�@�u��t�̓��L�v�́A��t�̐����N�ŏ͂��킯�Ă���B�S���A�ǂݒʂ�����A�����͏d������ӏ������낤���A���̔N�����ǂ߂A�ق��̔N�ׂȂ��Ă����ނ悤�ɂ������߂��B
�@���̒��������s����邽�߂Ɍ��ӂ������ꂽ�}�����[�̓y��ꐳ���ɐS���犴�ӂ������܂��B
�@�@�@���a�O�\��N��\����B�����s�`�斃�z�X�����O���ڏ\�Ԓn�@�a�c�F�b
�g������1951�i���a26�j�N�ɒ}�����[�ɓ��Ђ��Ęa�c��m�����o�܂́A�q�a�c�F�b�Ǒz�r�ɏڂ����B�����ł́s��t�S�W�k�S7���l�t�̑����ɐG��Ă��邾�������A�̂��ɋg���̍ȂƂȂ����a�c�̒����E�z�q�́q���W�w�Õ��x�̂��Ɓ\�\�e�{�̊ɂ������ār�Łu���a��\��N�ꌎ�A���͒}�����[�ɓ��Ђ����B�k�c�c�l�^���o�̒��u�V�����E��Ō˘f�������m��Ȃ����Ј��̋g��������́A�]�˂��q�ŐE�l�C���̗ǂ��l����v�ƕ����������B�w��t�S�W�x�̕ҏW�Œ}�����[�ɏo���肵�Ă����̂œ��e���{�����A���{���肪�����g���Ɛe���������̂ł���B��ɕ��̒����w��t�̓��L�x�̑�������Ă���v�i�s���{�ߑ㕶�w�فt190���A2002�N11��15���A���y�[�W�j�Ə����Ă���B�{���̎d�l�́A�ꎵ���~���Z�~�����[�g���E�O�����y�[�W�i�����A������l�y�[�W�k��������t�m���u���ʼn��g�l�j�E�㐻�۔w�z���i���������j�E�\���B�����ȊO�̒P�s�{�̑����Ƃ��ẮA�O���A���E�O���[���i�ےJ�ˈ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A1952�N5��20���j�Ɏ����A�ł����������̋g���������{�ɂȂ�B�s�s�Ǐ��N�t�͓�g�c���N�̉��\�����痠�\���܂ʼn����V�ȑ������������A�s��t�̓��L�t�̓��B�W���A���v�f�����������Ȃ��B�B��A���̔w���}�����[�̃}�[�N�i���a15�N�A�n�Ƃ��L�O���ĐR��Y������͂�������f�U�C���������́j�������Ɠ�����F�ō����Ă���̂��ڂ��䂭�B���̕\�S�́A�E���ɏ������u�}�����[�Łv�Ƃ���̂݁B�\���́A�w�\���Ƀ}�[�N���Ȃ��A���\���ɋ����Ă���B�{���̏��̂��\���┟�̖����̂ɑ��Ğ����́i���������Ȃ�Õ��ȁj�Ȃ̂́A�g���������ِ̈F�Ƃ����Ă����B�a�c�͏����ƁE�����҂ł���܂��ɏ����G���⏑�Ђ̕ҏW�ҁi�����ւ́s�쓇杁t����|�������ƂŒm����j����������A�{�Â���ɂ��D�݂����낤�B�{���̏��̂͘a�c�̎��������Ȃ��B�{���͓��{�|�p�@�܂���܌�A���肵�ās�����t�`�\�\��t�̓��L�k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1960�j�A���ɕ����ās��t�̓��L�k���|�I���l�t�i�������X�A1983�j�A����ׂ́q�⒍�r���f�ڂ����s��t�̓��L�k���� �� �Ɂl�t�i�������X�A1986�j�A�s��t�̓��L�k�u�k�Е��|���Ɂl�t�i�u�k�ЁA1995�j�A���V���Łi2005�j�ȂǁA���x���ł�ς��A������V���ɂ��Ċ��s����Ă���B�R�{���g�͖{���́q����r�Łu�����炭�A�����Ɉ�t�ɂ��Ă���ꂪ�m�肤�邱�Ƃ̂��ׂĂ��A������Ă���B���|��]�Ƃ��Ă̈�t�_�Ȃ�A�O�ɂ�����������肤�邾�낤�B��t�̓`�L�Ƃ��ẮA���ケ��ȏ�̂��̂��o��Ƃ��Ă��A��������ďo�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�v�i�a�c�F�b�s�����t�`�\�\��t�̓��L�k�V�����Ɂl�t�A�V���ЁA1960�N6��15���A�O���y�[�W�j�Ɨ\���������A�������˂Ă��悤�B���̘a�c�̈�t�����ƂƂ��Ă̑�\��́A�ŏ��̒����ł���s�����t�t�i�\�������X�A1941�j�ƂƂ��ɁA�s�a�c�F���S�W ��l���k��t�����l�t�i�͏o���[�V�ЁA1978�j�Ɏ��߂�ꂽ�B�����̕ۏ����v�q��i���r���u�a�c�F�b�̈�t����̂���܂��v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j���L���āA�ϋȂ�s�����Ă���B
 �@
�@ �@
�@
 �@
�@ �@
�@
�{���́A��ɐG�ꂽ�悤�ɁA��t�̓��L�Ɋ�Â����́u�`�L�v�ł���B�ł́A�a�c�͈�t�̓��L���ǂ��Ƃ炦�Ă����̂��B�a�c�̃G�b�Z�C�W�s���̘c�݁t�i������w�o�ŕ��A1969�N7��25���j�����́q���u�r�i���o���̕W��́q�����t�_�r�j�ɂ�������B
�@��t���l���邽�߂ɁA��ւ�d�v�Ȉʒu�����߂���L�́A��t���ӎ����Ȃ��ŁA�����̎p�������������҂Ɏ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���̓��L�ɏo�Ă���l�Ԃ��ܕS�l�ɂ��܂�A��t�ƕ������Ă����l�����̑����́A�ׂ�ߏ��̖����Ȑl�B�̂��Ƃ�����A���̐l�ׂ邾���ł��e�ՂȂ킴�ł͂Ȃ��B���������ϓ_���炷��ƁA�g���́s���܂�͂����L�t�i1990�j�̓ǂݕ��ɂ��܂����낢��ȉ\�����c����Ă��邱�Ƃ��킩��B�s���܂�͂����L�t����ɂ����`�L�̎��݁B�g�����O�����́s����t�i1938�N����1940�N���߂ɂ����Ď��M�j����ŏ��̒����s�����G�߁t�i1940�N�̏H�Ɋ��s�j�֎���A�g�����O�j��ՂÂ��邱�Ƃ����̃n�C���C�g�ɂȂ邾�낤�B
�@�܂��A���̓��L��\�ʓI�ɂ����ǂ�ŁA�͂͂��A�������ƍˎq�Ԃ����A���Ȃ����������邾���Ȃ�ȒP�Ȃ��Ƃ����A�[�����ׂĂ䂭�ƁA���т̎������Ƃ��l�����邱�̓��L�́A�������킩�点�Ȃ����邽�߂ɏ����ꂽ���̂ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă݂����Ȃ�قǂ��B
�@���܂������Ƃɂ́A���̓��L�ɂ́A��ւ�d�v�Ȃ��Ƃ�������Ă��Ȃ��B�d�v������A�����Ȃ��̂��Ǝv����B�i�����A���y�[�W�j
�k�NjL�l
���{�ߑ㕶�w�ُ����s��t�̓��L�t2���̂���1���́A���t��1956�N8��30�����s�́u�ĔŁv�ŁA���Ԃ��Ɂu�a�c�F���^�����H�q�l�k�ӂ̉��́u���v�l�^�����v�Ə����E���������鍂�����{�B����1���́A1957�N9��30���u�l�Łv�Ɖ��t�ɂ�������{�i��o�̑��ژ^�ł́u���y�Łv�j�B�����Ƃ̑���́A�\�����W���P�b�g�i���̋�F�̃x�^����ɂ͋��������j�A�\�����z���������i�J�b�g�͔~�j�A���Ԃ����N���[���F���W���F�A�{���͂܂������ʂ̃f�U�C���i�����{�̕����g���{���̍앗�ɋ߂��j�B���ُ����̉����{�i������͒}�����[�̊ɂȂ�j�́A���t����������Ō�̈꒚����Ď��̂����A�����Ό��̌��Ԃ��y�[�W�ɓ\���t�B�s��t�̓��L�t�̏��e�݂͂ȏ����{�ŁA�����{�̏��e�������Ă��鏑���͌������Ƃ��Ȃ��B�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�j�ɁA���̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B
��t�̓��L�@�a�c�F�b��
�@�@�@�@�a�U���^�㐻�E�����^376��
�@�@�@�@1956�N6��30���@480�~
��t�̓��L�i���y�Łj�@�a�c�F�b��
�@�@�@�@�a�U���^�㐻�^376��
�@�@�@�@1957�N4��5���@280�~
����܂���ƁA�i1���j��1956�N6��30���̏����{�k���Łl�A�i2���j��8��30���̏����{�u�ĔŁv�A�i3���j��1957�N4��5���̉����{�k���Łl�A�i4���j��9��30���̉����{�u�l�Łv�̂悤�Ɏv����B���R�͕s���Ȃ���A�����{�u�l�Łv�́i3���j�̉��t���꒚��ʼn��������{�̉\���������B
�Ǔ��u����@�g�����v�̎O�D�B����W�s�`�̉ԁt�̋����t�^�ɂ́A�剪�M�ɉ����A������l�́s�k�t�̓��l�ł��鐴����s�����M���Ă���B�s�k�t���������x�~���Ė�15�N�B���𗣂ꂽ��c�G�̎p�͎O�D�B���̎��ӂɌ����Ȃ����A������R�Ƃ����悤���B
�������O�D�B����
�S�g�ŌǓƂ�����킵�Ă���
�����Ɂ@���т����̉�肪������
�킽���́@�O�D�B���ɔᔻ�I����ɂ��������A
���̌ǓƂɑ���
�b���������ɂ͂����Ȃ�����
�����̓�������c�c�B
 �@
�@
�����ւƏ��������̂��߂̐É��ƁA�˂ɗ��\�\�����߂��̓��]�́A�l�Ԃ̎ړx�ɍ������A�K�v�Ƃ���Ύq���̎�̎ړx�ɂ������������B���͂����A���������Ƃő��₦�邱�̔g�̂Ȃ��ł����A�^���������I�����Ȃ̂��B�����ł������̉^���͂��Ȃ����̒���͂�ڊo�߂����A���Ȃ����ɂ�����킢��ł���̂��B�^���̂Ƃ��A�����T�ɔ������g�͂ǂ����Ăӂ��ꂠ���炸�ɂ����悤���B�ǂ����ĊC�͋��̕�����ۂ��Ă����悤���B�����Ă��܂�A�r���A���[���A�A���A���Ȃ����Ɍ������Ăӂ��ꂠ����A���Ȃ����̂ق��ւƉ����Ă���B�i�q���i�̗͊w�����r�A�{���A���y�[�W�j�s���݂錠���k�}���p��309�l�t�i�}�����[�A1987�N3��20���j�͏����̎��^�𗬗p�����A���̉����{�ł���B���p���̃T�C�Y���P�s�{�ōł������l�Z���ɑΉ��������̂ł���̂́A�o�ό����̖ʂ���l����Γ��R�̂��Ƃ��B�q��҂��Ƃ����r�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�ɂ�������i��㎵�Z�N�̓��t�̂��̂́A�������Ƃ����̖����j�B
�k�c�c�l�܂��}�����[�ҏW���̒W�J�~�ꎁ�ɂ́A�₦������珕�͂��A�I�n�����b�ɂȂ����B�����ɁA�S����̎ӈӂ�\���Ă��������Ǝv���B�k�}���p���l�ɓ��������ƂŁs���݂錠���t�����Z�̒n�����Ɍ������B�����A1992�N�ɓ��p���͏I�������B���̌�A��҂�1998�N�ɟf�������N�A�k�����܊w�|���Ɂl�Ɏ��߂�ꂽ�i���Ȃ݂ɁA�p���ł�1�N�����1988�N9���ɂ�͂�W�J�~��̎�Łk�}���p���l�ɓ������g�����́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�́A�k�����܊w�|���Ɂl�ɂ��A�k�����ܕ��Ɂl�ɂ������Ă��Ȃ��j�B�s�̎��w�t�i���肩���[�A1990�j�̖�ҁE�{�ԖM�Y�͓����ɂ́q����r���u�{���́A�o�V�����[���̎v�l�▲�z�����܂��܂ȗ̈�ɂ����Ď��݂ɔ�������A��҂̖���Ƃ������܂��āA���z���߂���o�V�����[���̕����ʂ�̍D���ƂȂ��Ă���ƌ����邾�낤�B�k�c�c�l�����Ė`���ɂ��G�ꂽ�悤�ɁA����̔łɂ����Ė{���̑�ꕔ�ɐV���ɑ����̐}�ł̑g�ݓ��ꂪ�����������Ƃ��A���ɔłƂ��ēǎ҂̎�ɂƂ�₷���������Ŋ��s�����_�ƍ��킹�āA�Ƃ�킯�Ӌ`�[�����ƂƎv������ł���v�i�s���݂錠���k�����܊w�|���Ɂl�t�A�}�����[�A1999�N8��10���A�O�l�Z�y�[�W�j�ƌ���ł���B
�@�@�@��㎵�Z�N�\��\��
�a��F��
�@�{�̏��Ŋ��s�ȗ����傤�Ǐ\�N�B�M�S�ȓǎ҂���̎����I�ȗv�]������Ȃ���v�����i���ԂɂȂ��Ă������A���̓x�ҏW���̂��肪�����z���ɂ���Ē}���p���̈���ɉ������邱�ƂɂȂ����B���̏\�N�̂������ɂ��v���̌�ւ͑��ς炸�߂܂��邵�����₩�ł��邪�A�u�l�Ԑ��̍Ő[���̂����܁v�����Ă���A�u�F���ɐG���@��v���͂�����Ɨ^���Ă����悤�ȐS�̂ւ̊����͂��悢�拭���Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���̂悤�Ȋ����ɉ�������̂Ƃ��āA�{��������ɑ����̓ǎ҂Ɍ}������Ȃ�K���ł���B
�@�@�@��㔪���N�\��
���
���㎍�l�o�����V���[�Y�͗�1963�N�܂łɑS10�������s���ꂽ�悤���B��6�������R�ꐶ�́s���`�̂�������t�i1962�N11��1���j�A��7�����p�c�����́s�ߏցt�i1963�N10��1���j�A��8�������]�r�v�́s20�̎��ƒ����́t�i1963�N12��1���j�A��9����������^�́s��ˁt�i1963�N12��25���j�A��10�����Ό��g�Y�́s�T���`���E�p���T�̋A���t�i1963�N12��25���j�ŁA�����̎��W�̑����̓V���[�Y�����F���ł���B���̎ʐ^�����Ă킩��Ƃ���A��c�́s���]�̐푈�t�ƐΌ��́s�T���`���E�p���T�̋A���t�������p�����Ƃ͎v�����A�P�s���W�ƌ�����Ă���ނ����Ȃ��B�u�l�Z���E�㐻�p�w�E�W���P�b�g���v�Ƃ����d�l�����ʂ��邾���ŁA�W���P�b�g�̃f�U�C�����܂߂āA�����̓t���[�n���h��������������Ȃ��i�\���ƌ��Ԃ��ɓ��n�F�̗p�����g���_�����ʂ���j�B
�a�U���㐻
�ȉ�����
�����@�����v�Y�^���݁@�O�Z�Z�~�k1961�N5��1���A�����F�����ǑT�l
�����@������^�l�Ԓa���@�O��Z�~�k1961�N10��1���A�\���f�b�T���F����S���A�ʐ^�E����F������l
��O���@���ā^�����̂ɂ����`���@�O��Z�~�k1961�N8��1���A�����F�~���L�l
��l���@�I���܂��q�^�����@�O�Z�Z�~�k1962�N5��1���l
��܍��@��c�G�^���]�̐푈�@�l�Z�Z�~�k���ۂ̒艿�͎l���Z�~�l
![��c�G���W�s���]�̐푈�t�i�v���ЁA1962�N7��1���j�̖{���ƃW���P�b�g](image/zunounosenso.jpg) �@
�@
����[���@�̂̌��܂́^�[�������Ȃ�ƈꐺ���Ԃ����Ɂ^�ق����Ȃ�@�����Ȃ�@����ǂ��Ȃ�^�ڂ��̎��Ƃ��̂ЂƂ̂����т��K���ɂނ��ԁ^�������[�g���̓d���ɂȂ�@�ق��̖́^�݂�ȔR���Ă�@��s�̃J�i�����̂悤�Ɂ^�v�����@�ڂ���ӂ���́I�q�i�v�v���r�őz���������̂�1960�N4��4���̋g���̓��L�ɏo�Ă���q�k�p���r���B�u�Z������k�̉�B�q�k�p���r��\�����s����B�����͊�c�G���W�s�i�v�v���t���͋g�������W�s���C���b�N�E�K�[�f���t�B�O���ځA�剪�M�̎��ƃG�b�Z�C�W�s���̃p�m���}�t�B���͔ѓ��k�ꎍ�W�s�����t�B�܍��ڂ͐�����s�������W�B���a�U���O�\��ł̏����q�v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���O�y�[�W�j�B�k�̉�͂����ɓo�ꂷ��ܐl�̓��l���琬��A�q�k�p���r�ɂ͑���C�����W�̊����������Ă����B�������s�k�t�̔��s���E���惆���C�J�̈ɒB���v�̋}���ɂ��A���p���͈�������ɏo�邱�ƂȂ��I������B���W���s�̃^�C�~���O���炢���āA��c�́s�i�v�v���t�͖{���Ɂ\�\��c���s�k�t�ɔ��\����10�т̂����A�q�i�v�v���r��q����I�ȉS�r�Ȃ�7�т��s���]�̐푈�t�Ɏ��^����Ă���i�����A�n�쎍���ڂ��Ă���̂͊�c�����ЂƂ�j�\�\�A�g���́s���C���b�N�E�K�[�f���t�́s�a���`�t�i����ɁA1962�A�J�b�g�F�^�甎�j�ɁA���W�I�����𐋂������̂ƍl������B�������A���сq���C���b�N�E�K�[�f���r�i�I�E3�j�́s�a���`�t�ɂ͎��^���ꂸ�A1980�N�A����R�c���̏E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�܂ŒP�s���W�ɂ͓���Ȃ������B
�N���ނ����͂������@�ڂ���ӂ���́^�Â������݂̂Ȃ��Ő���������^�������͂��������ɂł肪����^�Ђ�킢�j�͈�ӂ��̖I�̑��ɂ�������Ɓ^������ɂڂ���̌҂����������@���̂ЂƂ́^�̎����ŗ��������@������͂ނ������^�g���J�c�̂悤�ɋᖡ����@���|��炻���^�v�����@���l�̂��߂́I
�����Č��@�����т��������@�Ԑl�ǂ����^���̒ꂩ�������J���U�V���E���Ƃ��^�ڂ��͂ӂ����ѓ��˂ɂ��̂ЂƂ����Ă邾�낤�^�e�w�������@����o���@�җ�ɂ�߂����낤�^�u���ׂĂ̓��͘V�k�ɓ���I�@�����������^���̂����R���ɂ������Ă���@��������^�v�����@�i�v�v�����I�v
�@����A���̔N�k1962�N�l�A�P�s���W�Ƃ��ẮA��c�G�́w���]�̐푈�x�������A�g�����́w�a���`�x���㌎�ɏo�ł����B�g���̂́A���ƔłƂ��ċg������������̂̔��s�A�����������������������k���t�ł́A���s�͑���ɂŔ������v���Ёl�A�v���Ђ�������Ă��������������Ƃ����ԂɊ������Ă��܂����B�₳������Δ����A�ނ����������͔̂���Ȃ��A�Ƃ����̂͂܂������̑������A�Ƃ������Ƃ����͂��܂���O�\��A�O�N�O�A�����o�ł��͂��߂ĊԂ��Ȃ�����ɑ̌����A����Ă��܂����̂ł���B�i���c�v�Y�s��㎍�d���j�t�A�V���ЁA1995�N2��25���A��l��y�[�W�j1961�N1��16���̈ɒB���v�̎��́A�ܐl�̓��l�����c�v�Y�̎v���ЂƂ̊W��[�߂Ă䂭���������ƂȂ����B���Ȃ݂Ɂs�k�t���l���ꂼ��̎��Ƃ��W�������u�S���W�v�́A�q�k�p���r�Ńg�b�v�o�b�^�[��������c�G�́s��c�G���W�t�i�v���ЁA1966�N4��15���j���ŏ��ł���B
���O�O�N����x�葱�����^�A�X�e�A�ƃ��W���[�X�́^���Ȃ₩�ɂ��ꂠ���Ȃ���S���Ă����^�J�ɍ~���ĕ����߂��ā^�����ɂ���̂͑f�G�Ȃ��Ƃ��^�����ɂ���̂͑f�G�Ȃ��Ƃ��@�Ɓ^�n�ӕ��M�̋ߊ��Ɂs�ړ��j�Փ��\�\�w����x�ցA�����āw����x����t�i�v���ЁA2010�N11��25���j������i���Z�y�[�W�ɂ�1968�N8��20���A�a�J�̃l�C���B�E�N���u�ŊJ���ꂽ�V��ޓ�Y�̃t�����X���w������ł̓V��E�g���E�剪�M�̃X�i�b�v�ʐ^���f�ځj�B�s����t�͓n�ӂ��n�����l�̂ЂƂ肾���������ŁA�g���͓���15���i1966�N10���j�Ɂu�Q�X�g��i�v�Ƃ����q�q�����r�i�E�E13�j����e���Ă���B�g�������̏��o�Ƃ��Ă͂����炭�ł��ȈՂȃ^�C�v����ł���ɂ�������炸�A��������������Ȃ����ʂɂȂ��Ă���B�g���́s����t�ɂ���1985�N3��2���̓��L�Ɂu���J�B��A�_�y��̒������֍s���B�V��ޓ�Y�̍�����܂̓��j���̉�B�u����v���l�̂ق��́A�剪�M�A����N�v�A�a��F��A������b�q�E�v���q�A�R�{���q�����āA�y���F�ƈ���r�q�Ƃ����A�����ȏj���v�i�s�y���F��t�A�ꔪ��y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A�n�ӕ��M�ɐG�ꂽ���͂͌�������Ȃ��B
�����ɋ����ꂽ�^�ؗ�ȉ��C��Ł^�����邳���₫���^�S�̂悤�ɖ鎞�̉~�W�̓����Ɂ^�����߂�ꂽ�ڂ������́^�ʂĂ��Ȃ������f��̂����܂Ɂ^�������胏�C�������^���W���[�X�ƃA�X�e�A���v���ā^��������x�����^
�ڂ������̕��i���߂����ā^�������Ƃ�ǂ�ł������Ԃ́^�s�ӂɁ^�P������������˂ēޗ���������^����Ȗ�X���킽���Ă������߂Ɂ^�ǂ�ȉ����łڂ��������o��������^�m�炸�ɔ����邫�݂̑O�Ł^�L�����M�^�[�̂悤�ɂ����炵�^�Â��S�̃p���f�B�����悤�^�q��Ӓ��ł��x�ꂽ�낤�Ɂr�^�q���m�����݁n�̔ޕ��֍s���ꂽ���̂��r�^
���K���X��J�����߂ā^���C���������j���̌ߌ�^���ꂪ�@�f�G�ł����Ă��Ȃ����Ă��^�ڂ������́@�����ɂ����^���̐��E�ɕ����߂��ā^���ƂȂ����a���̂悤�Ɂ^�Ђ�����ƍ����Ă���

���ѕq�F���W�s���ӂ̌��@��㔪���N�~�t�i�̒��ЁA1988�N6��1���j�́A��ꎍ�W�s�p�Ёt�i���惆���C�J�A1951�j�ɑ����s��q�Ɣj�Ёt�i���A1954�j�ȗ�34�N�Ԃ�ƂȂ������т̑�O���W�B���̃C���^�[�o�����ǂ�قǒ����������Ƃ����ƁA�g�����̐��ŏ��̎��W�s�Õ��t�i1955�j���琶�O�Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�܂ł́\�\�܂�g���̐��̑S���W�ɂقړ������\�\�N���ɕC�G����B�{����2���ɕ�����A�q�`�r�́u1987�`1988�v�̍ŋߍ�A�q�a�r�́u1955�`1958�v�́A��W�ɂ��̂܂܂Ȃ��鎞���̍�i�����߂�B�q�a�r�̖`�����сq�t�r�̖���3�߂������i��o���㎍���ɏ����̃e�L�X�g�́A���s�ӏ��⎍��̈ꕔ���s���ӂ̌��@��㔪���N�~�t�Ƃ͈قȂ�j�B
����͏������Ђ炭�@�������Ԗт̐����Ă����
���̎������łׂ��Ƃ�͂������
����͒܂��͂����@�Ђ炽���Ȃ߂��@�ꖡ�����y�[�p�[�i�C�t
����Ƃ��낼��@�A���̊C�֏o���肷����ȘA���ɍs����̂�
�j�̂������@�A�C�ȏ����x�b�h�w�ǂ����@�ׂɂ��݂��蒎�𓊂���
���`�������\�������܂Ł@���߂ĐÂ��Ȏ��Ԃ�@�����ɒu���Ă���
�����ЂƂ�@�j�O�̉��y�Ƃ͂��������Ȃ�@���܂�
�����͒P�Ɂ@����̗��l������������Ƃ������R��
���̂�������Ԃ��Ă���̂�
�ǓƂ���@�U�P�҂���@���܂��Ɏ��l���您��́@�Ƃł�������
���̒j�̎����S�݂͂������̂�����
���E�̂�����͂��������@����͕���
����̕s�K�͎̂Ăɂ�����������������ł��邱�Ƃ�
�Ȃ̂ɉ��ꕨ�̒��ɂ����@�����������������������Ƃ�������Ȃ�
���݂͂����Ă݂�@�N�̂����Ƃ����킸���݂͂����̂��v����
�����Ȃ��M�̏�Ł@�ᔻ�������������������ăi�C�t���g���Ă���
����͒�q�ɂ̂ڂ��ā@���������낷
�ǂ̉Ƃ̃h�A�ɂ������Ă�����
�~�[�ł͏������������������𐁂��Ă���
���������E�́@�����������炵��
�����͔������������̂قǂ������Ȃ��@�Ԃ߂��~�����Ɗ������낤
���̂Ƃ�����́@�����Ă�鎨�������Ȃ��@���ꂩ��͂��Ԃ�
��l����l�ł����邾�낤
���ꂽ���͂����炵������̕\���̎肴�����@��z����
�����Đ^���Ɂ@���邢���m�̐X�ɓ����Ă����̂�
�{���̎d�l�́A��Z��~��l���~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�㐻�۔w�N���X���E�W���P�b�g�B���M���ׂ��͕ʒ��{���̃��C�A�E�g�ŁA�ʏ�Ȃ牡�g�Łu���ѕq�F���W�^���ӂ̌��@��㔪���N�~�^�k�J�b�g�l�^�̒��Ёv�Ƃł��������ȂƂ�����A�u���W�@���ӂ̌��@��㔪���N�~�@���ѕq�F�@�̒��Ёv�Ƃ��ׂĂ̗v�f���c��s�ɑg�����A�J�b�g�܂Ŏ��߂Ă���_���g���������ɂ��Ă͒������B�{���̍���F�́u���W�v�ƃJ�b�g�����F�A�ق��͊D�F�B�����̗��Ɂu����@�g�����v�u�J�b�g�@�����v�Ƃ���B�������̈������Y���W�s��̉��t�i����R�c�A1988�N6��10���j�ƕ���ŁA�Ō�̗����J�b�g���g���������{���Ǝv����B�����́q�o���r�Ɂu���̎��W���o��_�@��^���Ă��ꂽ�̂́w�킪�f�E�J���I���x�̎��l���c�[�L���̗F��ł��������A�����ď������Ă������������c�O���A������킸��킹���g�������A����ɂ��ď������������������c�v�Y���̈���Ȃ�ʂ����ӂɑ��Đ[���ӈӂ�\�������v�i�{���A����y�[�W�j�Ƃ���B����A���㎍���ɔŎ��W�́q�G�b�Z�C�r�Ƃ��ď������낳�ꂽ���͂ɂ́A���̂悤�ɂ���B
�u���ӂ̌���㔪���N�~�v�Ƃ����V���W�̃^�C�g���ɂ͈���̌������߂ċN���オ�鎩���̎v�������߂��B����͋g�������肪���A���c�O���ꕶ�����B���m�̒����^��Y��u�����v�̒��Ԃ��o�ŋL�O��ł��ꂼ��̊��S���q�ׂĂ��ꂽ���A���̖�s���ŏo�Ȃł��Ȃ������c������́u�i�����فA���l�ɂƂ��ĕK�v�Ȃ��Ƃ́A���̒��ق����̕�قɂȂ邱�Ƃł��傤�B���ꂩ��͂��̐��n�����āA���������Ǝ��������Ă��������B�������g�̂��߂ɁA�����̒��̑��l�ɂނ����āv�Ƃ������b�Z�[�W�́A�ӑĂȍΌ������������Ă����ڂ��̋��ɂ��݂��B�i�qMemorandum�r�A�s���ѕq�F���W�k���㎍����142�l�t�A�v���ЁA1996�N9��1���A��O���y�[�W�j���тɂ́s�풆��� ���I����̏،��\�\1935-1955�t�i�v���ЁA2009�N1��10���j�Ƃ����J�삪����B�풆���̋g�����ɂ��āu���̌�̋g���̓`�`�n���A�n���s���Ɗe�n�̕�����]�X���A���l�ܔN�l���A���F���璩�N�����̍ϏB���֓n�����B���łɔs�풼�O�A��ĎR���ֈړ����Ȃ���Q�������̂����߂ɁA�˂ꂽ�R�n�̎r�����ނ��ڂ邱�Ƃ����������Ƃ����B�����Ăނ����������\�ܓ��B�g�����̎��̑����ɂ����܂������̉e���܂Ƃ����Ă���̂́A�ӎ����邩�A���Ȃ����͕ʂƂ��āA�ނ���Ȑ푈�̌��̌��ɂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������������邾�낤�B�^���n�ŕČR�ɕ����������ꂽ�g���́A���̔N�\�ꌎ�ɕ����B�p�ЂɂȂ��������A���Ă������A�ނ��R�������̑唼���߂��������F�Ɏc���ꂽ�����̏��������́A�N�U�����\�A�R�̕ߗ��ɂȂ��āA�V�x���A�w����ꂽ�v�i�����A���`��O�y�[�W�j�ƁA�䂫�Ƃǂ����M�ŏ����Ă���B

�ѓN�v����̃u���O�sdaily-sumus�t�i2008�N10��12���j���q��⸂ƉԎ]�r�ɂ�������B�\�\�]�X���F���W�w��⸂ƉԎ]�x�i���ЁA��㎵��N�j�B�g��������B����͓��a�葸�v�B���̏����ؔʼn�̍�Ƃɂ��Ă����a�葸�v�̖،��ؔʼn��Ƃ����T�C�g�ɏڂ����B�������������ɓ��������\�N��̒����ɂ͂��傤�ǔ��o���̔ʼn�Ƃ������悤�Ɏv���B�������̂ǂ����̉w�i���������Ƃ���v������ł����̂����A���M���Ȃ��Ȃ����j�̓쑤���������A��L�Ȃǂ��肻�����Ȃ��悤�ȏꏊ�̏����ȉ�L�ŌW�������L��������B��҂����ɂ����B�݂傤�ɂ͂�����Ƃ��̏�ʂ��o���Ă���B�����ؔłƂ����Z�@�����̌��z�I�ȍ앗�����Ȃ�ڐV�������̂������B�\�\�g�����͍]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�t�i���ЁA1971�N5��1���j�ɂ��G��Ȃ���A�]�X���F�̎��Ƃɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���i�����͋�Ǔ_���R���}�E�s���I�h�����̉��g�����A�e���E�}�������ɉ��߂��j�B
�Ñ�̏��̈�͋�\�\�W���̗t�̗ނƐl�ނ͓������́\�\�Ƃ������O���A�]�X���F�͐M�Ă���悤���B�Ȃ��Ȃ�A�������т����т��āA���R�Ɛl�ԂƂ̌�����搂��Â��Ă��邩�炾�B������Ǝ��̏��@�ŁA���I�z���͂ƉȊw�I�m����Z�������A��i�̏d�w�������݂Ă���B�s��⸂ƉԎ]�t�́q�R��r�͂��̑�\��Ƃ����悤���B�������ϔO�I�ȗv�f�������A����Ȉ�ʂ��������ɂ���̂��B���m�I��O���f������s�Ԃ߂�ҁt��s�Ԏ]�߁t���o�āA�����̈��ƃG���X���r���s�c�����сt���A�������x�~���ƂȂ�B�����āA���܂ł̍�i�c�ׂ̏W�听�Ƃ������ׂ��A�A�쎍�s�R���t�������ꂽ�B�\�\�����̂����ɑّ����ꂽ�A����\�\�B�i�s�]�X���F���W�k���㎍����84�l�t�A�v���ЁA1985�N12��1���A�\���S�j
�s��⸂ƉԎ]�t�́q�R��r�i���o�́s�����t14���A1963�N10���j�����5�߁i���s�ӏ��́^�ŕ\���j��1�s�����̍ŏI�߂������B���̐L�т₩�ȕM�Â����́A�g���̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j��z���N��������B�Ȃ��A�u�s���́q���݁r�̒����ɉԍ炩�����́t�v�̎R���ʁi�s�@�t�Ɓq�@�r�j�̓t�����X��̃M�������Ȃ킿���Ȍ^�̈��p���ɕ�����R���������p�@�ŁA�������g�����⎄�̂悤�ɏ������i���ɗp����̂́A���{��ł͈�ʓI�łȂ��B
�r���̋ЂT�����̑O�t�̗̂��Ł^�Y�̗͂��T�O�O�{�̋����𗆐���̓��c�Ƒ@�тɂ܂�ĉj�����^�ꕶ�̚��̗��q�ƕ��ڂ��đ��z�̂������Ȍ���������^�����K�v�Ƃ���A���̔����������_�֊J�ԕ����������^�����ł���삪�@�킩���Y�ǂ̏����ˋN���䂷�肠����^倕ꑐ�Ɨ��g���̂������ɂƂ������𗬂��Ċ݂ɂ悹��^����钆�S�Ń��C�Z�c�Ȓ��������������閺�����I�^�����^�i�@�q�r�X�J�X�̐Ԃ��ԕف^�W���F�̃r�j�[�����̎������̂������j�X�q�^���̂̎O�̕����������_�C���Ōq�������m�W�����s���O�E���c�N�n�^�����R��Ƃ������ɒ��g���̂������ĐO����Ђ炭�^�������{�m���Ƃ����n�^���̉����@���̏��̔��͓��F�̘@�Ԃ̂悤�ɍ����@�[���F�Ɋ�����u͓����܂Ř@�Ԃ̂悤�Ɂ^�u�̕ӂ̌��b�����^�������ɏ��N����������Ł^�ӂ����炵�����т������ɕ��ׂ�^�I�����W�̍�����ԏ�̂��ŏ��ɔG�炷�Ƃ��^�����̓���ɏ��N�����������Ă�^῝g����Ɣނ̓��ڂ͕ϐF���@���₪�^���̖��ɓ��F�̗ւ������˂�^�t�̕���������̒��ڂ̎h���ɂ��Ƃ����q�d�̏�������Ă݂�@����͂����銴��̊�b��
�s���́q���݁r�̒����ɉԍ炩�����́t
�s��⸂ƉԎ]�t�̎d�l�́A���l�~��O�l�~�����[�g���E��Z��y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���ɓ\���ӁB�ڎ��̖����Ɂu�ؔʼn恁���a�葸�v�v�u���ꁁ�g���@���v�Ɠ�s�ɂ킽���ăN���W�b�g����Ă���B�s��⸂ƉԎ]�k����Łl�t�̎d�l�́A���O�~��O��~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�p�w���v�m�o�b�N�X�L���n���i�I���W�i���ؔʼn���I�t�Z�b�g����������Ђ�\�t�j�E�\���B����54���i������t�y�[�W�̗]���Ɂu����54���V���^�恛�ԁv�Ɓ��̐������i���o�����O�}�V���ň������Ђ�\�t�j�B���҂Ɣʼn�Ƃ̏�������ʒ��ƃI���W�i���ؔʼn�̕ʒ��A�v���{���i�ʏ�łƓ������̂ŁA�~���J�b�g�͔��̊G�̈ꕔ���g���~���O���ė��p�j�̑O�ɓ����Ă���B�{���p���͒ʏ�łƂ͕ʁB�\���\�t�̊G���Ɠ����I���W�i���ؔʼn悪�u������v�Ƃ��ēY�t����Ă���B
�̂��ɕ��Ђ��犧�s���ꂽ�s�����d�M�S��W�t�i1972�N3��7���j���ʏ�łƌ���ł̓��ނ�����A���ނƂ��g���������ł���B�Ƃ���ŁA�ʏ�łƌ���ł��{���E���Ԃ��E�\���E�W���P�b�g�┟�Ƃ������O�������قȂ�Ƃ����̂́A�Ȃɂ��x���ꂽ�悤�ȋC�����Ȃ����낤���B����ł͉����{�ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B�{���̔ł������Ȃ̂͂����Ƃ��āA�I���W�i���̔ʼn悪���G�ɓ���悤�ȓ����ł̏ꍇ�A�{���p�����ʏ�ł��O���[�h�̍����A����Ȃ�̂��̂ł����Ăق����Ǝv���͎̂������ł͂Ȃ����낤�B���̓_�A�{���k����Łl�͑��v�p�w�ɂ�������炸�A�{���p�����ʏ�ł������炩���ĊJ�����������悭�A�ʏ�łƕʂɂ����Ƃ̊�т����킦�����ɂȂ��Ă���B�{���Ό��̃I���W�i���ؔʼn悪�{���̐��E��L���Ȃ��̂ɂ��Ă��邱�Ƃ́A���߂Ďw�E����܂ł��Ȃ��B�ɂ��ނ炭�́A���t�̌���L�Ԃ������ŐF���肷��Ƃ������ׂ��Ȕz�����ق��������B
![�]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�t�i���ЁA1971�N5��1���j�̔��ƕ\��](image/emori_01.jpg) �@
�@![�]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�k����Łl�t�i���ЁA1971�N5��1���j�̔��ƕ\��](image/emori_02.jpg) �@
�@![�]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�k����Łl�t�i���ЁA1971�N5��1���j�̖{���E���G](image/emori_03.jpg)
�]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�t�i���ЁA1971�N5��1���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��k����Łl�i���A�����j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ����̖{���E���G�i�E�j
�s��⸂ƉԎ]�t�̃t�����X���̕\����Ɓs��⸂ƉԎ]�k����Łl�t�̓\���̉�͓������̂ŁA���a�葸�v�ʼn�W�s�K�N�Y�t�i���p�o�ŎДʼn�F�̉�A1970�j�S12�_�̖،��ؔʼn�i����100���AA.P.10���A���@�F27.5�~23.0cm�j�̂�����1�_���]�p����Ă���B�s��⸂ƉԎ]�t�ɓ��a�葸�v�̖ؔʼn悪�p����ꂽ�̂́A�����̑��݂��^���đ傫���������̂Ǝv����B
�k2020�N4��30���NjL�l
�K�v�������ĕ��Д��s�̎����s�s�G���^�t��11���i1971�N4���j���J���Ă�����A�s��⸂ƉԎ]�t�̎��Џo�ōL�����ڂ��Ă����B���̍��̖ڎ��͕ʒ��F��4�y�[�W��2�E3�y�[�W�߂����A�F����1�y�[�W�߁i���Ȃ킿�\���Q�̑Ό��y�[�W�j�Ɂq���Ђ̎����r�́u�����v4�^�C�g���E�u�ߊ��v4�^�C�g�����ڂ��Ă��āA��҂̖`���������ł���B�u���]�X���F���W�u��⸂ƉԎ]�v�q����E�g�����r�^�`�T��160�ŁE���a�葸�v�I���W�i�����ʼn��������50��/���y�Ł@�\��1,300�^���W�C�܂��͎��L�̊C�ւ̊��v�I������Ƃ苑�ݑ����Ċ��N���C���ɂ��܁C�����ɁI�v�i�������g�j�B�����Ďl�Z�y�[�W�̉��i�i�{����2�i�g�j�Ɍr�݂͂Ŏ��̂悤�ɂ���i������͏c�g�j�B
�@�����Ћߊ��\��
�q�l�������r
�]�X���F���W
��⸂ƉԎ]
���ꁁ�g�����@���恁���a�葸�v
�`�T�ό^��Z�Z�Ńt�����X�������^�\����O�Z�Z�~
�����{������\�l�ԍ����^���v���^���a�葸�v�I���W�i�����ʼn���^�\���܌܁Z�Z�~
�@���㎍�d�ɂ����āA����قǂ܂łɑ�ꎍ�W�̏㈲��M�]���ꂽ���l�͂��Ă��Ȃ������Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�����ɖx�쐳������Ƃ̎����u�Áv�A����сu�O�c���w�v�ȗ��̐��ʂ̎��34�т����^����B
�o�܂͕s�������A�q���Ђ̎����r�́u���a�葸�v�I���W�i�����ʼn��������50���v�A�q���Ћߊ��\���r�́u�����{������\�l�ԍ����^���v���^���a�葸�v�I���W�i�����ʼn���^�\���܌܁Z�Z�~�v�́A�������{�̉��t�ł́u����54���v�u�艿�@7000�~�v�ƕ\������Ă���B�����܂Ō��܂��Ă��Ȃ��牿�i���g�������̂́A���ނ����������̂��A�����A�g���u���ł����������̂��B�Ȃ����^����34�тł͂Ȃ�35�тł���B
�g�����͈ɒB���v�̏��惆���C�J����s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�����s����1959�N8���A�ѓ��k��i1930- �j�E��c�G�i1932-
�j�E�剪�M�i1931-
�j�E������s�i1922-2006�j�ƂƂ��ɓ��l�����s�k�t��n�������i�I����1962�N9���̑�10���j�B�s�k�t���l�̎��Ƃ��W�������ŏ��́u�S���W�v
�͂��ꂼ��s�ѓ��k�ꎍ�W�P�E�Q�t�i���X�A1978�j�A�s��c�G���W�t�i�v���ЁA1966�j�A�s�剪�M���W�t�i�v���ЁA1968�j�A�s������s���W�t
�i�v���ЁA1968�j�A�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�ŁA�ѓ�����10�N�قnj�ɂȂ��Ă��邪�A1971�N��2���{�u�S���W�v�̑�1�������o������
������B�ѓ��k�ꎍ�W�P�s���l�̋�t�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1971�N10��20���j������ŁA����q�ѓ��k��E�l�ƍ�i�r�ɕҏW�����u���炭����
�����������܂����B�ѓ��k��S���W�i�S���j�̂����ѓ��k�ꎍ�W�P�w���l�̋�x�������肢�����܂��B�Ȃ����t�ɂ͔ѓ��k�ꎍ�W�Q�w��������́x�Ƃ��Ď�
�W�w�邠���ꎞ�ԑO�̌܂̎��@���x�w�O�̒������̖�x�w���L���ɂ���G�X�L�X�x�w�v���e�x�w�֎q�̋L���@���x�ɖ������т������A����ɑ剪�M����
��鏑�����낵�̖{�i�I�Ȕѓ��k��_�����߂��Ċ��s�̗\��ł��A�����҂��������v�i����A��Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B��2�����o�Ȃ��������R�͕s
�������A���X�ł͖{�����g�[�������̂ƍl������i�����͋g���ł͂Ȃ����A�\���̃J���o�X�n�̃N���X���Ƃ����A���̐F�Ƃ����A�����ɏI���������
���A�������悤�ɉf��j�B
�{���̎d�l�́A�ꔪ�Z�~��~�����[�g���E��l��y�[�W�E�㐻�۔w�N���X���E�@�B���B�{�̂��J�b�`�����Ă��銄�ɁA���͊ȑf��
�߂��悤�i�_�c�̌Ï��X�ŋ��߂���{�͂��Ȃ菝��ł���A�\���̂ق����悩�����j�B���̕\�S�ɂ́uSan-Rio�v�ƃ��S���L����Ă��邪�A���s����
1973�N�܂ł͎R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��̖��ŁA74�N�ȍ~�̓T�����I�o�ł̖��Ŋ����𑱂��Ă���B
��g���Y�́q��z�̔ѓ��k��r�ŋg���ɐG��
�Ă���B�u���l�N�A�͂邩�����Ă̓��B�����w�����x���o��������̍��ŁA���ѕq�F�A�R���m�q�̕v�w���̂����ΊF�Ƃ�҂́A�������낻�됶���𗧂Ă�
�Ȃ�ʒ[�����̋x�ɂ��A���ꂼ��̎d���Ŋy����ł����悤�Ɏv���B���̍��ѓ��͒}�����[�ŃA���o�C�g�����Ă������A�u�}���ɂ͋g����
��Ƃ����A�������������������l�����邼�v�Ƃ�����Ɍ����Ă����B�ނ����̐������悤�Ɍ����Ă������̋g�����g�����ł����āA�������ɂ���͔�
���ł������v�i�{���E����A��Z�y�[�W�j�B����ɂ͋��q������J��r���Y�i�q�Ăт����鐺�r�Ɂu���{��̂ނ����Ƀt�����X�ꂪ�����Č����Ă����l�ԂƁA��
�{�ꂵ���������Ȃ������l�ԂƂ̂������\�\���ł����͎��X�ѓ������{��̔\�͂Ɏ��Ȃǂ̂����Ƃ̂ł��ʌ��z���A�Ƃ����Ă�邯��Ζ��������Ă���̂ł�
�Ȃ����Ǝv�����Ƃ�����v�ƌ�����j�����͂��Ă��āA�����i������Ɂu���ꁖ�g���@���v�Ƃ���j���܂߂Ē��҂̈ӌ������f�����l�I���낤�B�ѓ��́q��
�Ƃ����r�ŁA�u�����̎����ڂ��͈�l�ŏ������ȂǂƂ͌���Ȃ��B���낢��ȃO���[�v�ɉ�����Ă������A�ڂ��͂�͂��㎍�l�̒��ԂȂ��ɂ͏����Ȃ���
���B�ڂ��Ɠ����悤�ȕa����a��ł������l���̐l�X���B���������ē�������������̂��Ƃ͂����̎��l������m�����Ƃ������Ƃ�������Ȃ��v�i�{���A
�k��l�Z�y�[�W�l�j�ƁA�{�����^�̎��W�s���l�̋�t�s�킪�ꉹ�t�s�����ցt�q�E�C���A���E�u���C�N�������o�����r��U�肩�����Ă���B
�ѓ��k�ꎍ�W�P�s���l�̋�t�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1971�N10��20���j�̔��A�\���A����̍ŏI�y�[�W
���c�ȎO�i1927-2003�j�͎��g�̒���W�̂܂������q���p�ɂ��ār�����̂悤�ɏ����������Ă���B�u�O�X����A��������A���̏��������̂���E���̑S�W�ŏo���Ă����������Ƃ��A�݂������[�Ɩ��Ă����B�����̕���ł͂Ȃ����A���ڂɁu�͐��A����v�A�����Ă����Ɏ������B���������u�S�W�v�Ȃ���̂���E���Ɍ��肵���̂́A�����Ⴂ�����瑸�h���Ă����[������̎���̑S�W�̌`�ɒP���ɕ���������ł������B�[�����̑S�W�́A���̒n���Ȑl���ƁA����ɑΉ������Ǎ�Ƃ��悤�ɁA���̔��w�ɂ�������炸�������ŁA�g�������̕i�i���鑕��̉��ɒ}�����[����ڗ����ʌ`�Ŋ��s���ꂽ�̂������B���́i�s�E�r�E�G���I�b�g�̉��߂̈ꕔ�������āj�A�������������������ɂ��₩�肽���Ǝv���Ă����̂ł���v�i�s�ېV�̐��_�k���c�ȎO����W4�l�t���ݍ��݁A�݂������[�A1997�N5��23���A��y�[�W�j�B�����́u�[�����̑S�W�v�́A�������͓��؏��O�ҁs�[����W�k�S2���l�t�i�}�����[�A1968�N9��25���E10��30���j�ł���B���c���͋g�����́u�⁁����Ɏc���������̂́H�^���������A�����K���ɂ��g�����S�W�ł��o����A���W����̂ق��ɁA�U���W������~�����Ƃ����A�����ւ��I�Ȋ肢�͂���܂��v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��l�Z�y�[�W�j�Ƃ������Ƃ��z�N������B���̔����͓���1968�N�̉āA�����r�Y�̃C���^�����[�ɉ��������̂�����A����������Ƌg���́A��E���́u�g�����S�W�v�Ƃ��́s�[����W�k�S2���l�t���d�˂čl���Ă����̂�������Ȃ��B
�{�W�̎d�l�́A��ꎵ�~��l���~�����[�g���E��1���l���y�[�W�A��2���l���y�[�W�i�ʒ����G�ʐ^�e��t�j�E�㐻�N���X���i�w�����͍��̐F�������j�E�\���B�g���������ł͂��Ȃ�d�h�Ȏd�オ��ŁA���̈͂r�������āA���������̑����I�v�f���Ȃ��B�����Ƃ��A�{�������������Łu�[����W�@��ꊪ�@���؏��O�ҁ^�}�����[�v�Əc��s�ɑg��ł���̂́A�u�k�c�c�l�܂����̌����ȖM���̉������c�ɉ��߂��āA�Ƃ������{���ɕғ����邱�Ƃ��o�����͎̂��̐[���x�ł���v�i�q����p���w�̉ۑ�r���A�{�W�E��1���A�Z�y�[�W�j�Ƃ������҂̍D�݂ɔz����������ł͂Ȃ��A�P�ɑ����I�v�f�����邾���̃X�y�[�X���Ȃ��������炾�낤�B
 �@
�@
���؏��O�ҁs�[����W�k��1���l�t�i�}�����[�A1968�N9��25���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ��k��1���l�E�k��2���l�i���A1968�N10��30���j�̕\���i�E�j
�[����͒}�����[����h�[�\���́s�����̔ޕ��Ɂt�i1941�j�A���C�X�́s������ގႫ�l�X�̂��߂Ɂt�i1955�j�A�s�I�[�f�����W�t�i1955�j�A�h�[�\���́s�v���̐��E�j�t�i1963�j�Ȃǂ̖̂ق��A�ђB�v�s����I���_�t�Ƃ̋����ƂȂ����s���ʊ��o�k������{�]�_�I�l�t�i1954�A�����F�����j�A�s�G���I�b�g�k�ӏܐ��E�����I�l�t�i1954�j�A�s���{�̍����̂Ȃ��Ɂt�i1957�A�����F��g�~�Y�j�A�s����̎��S�t�i1958�A�����F�ɓc叕�j�A���M�W�s���̂ݐl�`�t�i1960�j�Ƃ������������o���Ă���B�ŏ��̒����s����p���w�̉ۑ�k���{���Ɂl�t�i�O�������[�A1939�j�ɋ��V�������؏��O�́A�{�W�́q�ҎҌ�L�r�Ɂu�ߑ�̉Ȋw�Z�p�����݂�����������`�ƕ��͘_���A�܂����̌��ʂƂ��Ă̈������i����`�̒�������Љ�̒��ɂ����āA�����ɂ���đa�O����Ă��܂������Ȏ��g�̍��Ɗ�����A���w�A���݂̍�ǂ�����A�@���ɂ��ĉ��������邩�B�l�Ԃ��@�B�̎x�z�̂��Ƃɂ�����P�ʂƂ��Ĉ����A�l�Ɛl�Ƃ��������Q�ŎZ�ɂ���Č��сA�܂������Ƃ������_�̍����̒��ɂ����Ĕ@���ɂ��ĐS�̒ʂ��̋��m�ӂ邳�Ɓn���A���ʊ��o�����������邩�B�^�[������͌���ɐ�����v�z�l�Ƃ��āA���̉ۑ�ɗ����������B���̂Ƃ��ɏ����A�Ƃ��ɓ{��A�Ƃ��ɐ�]���Ȃ���A����s�ގ��l�Ƃ��Ĉێ������v�i��2���A�ܓ`�ܓy�[�W�j�Ə����āA�[�������������B���؏��O�f�㊧�s�̐[����Ƃ̋����s�������ȁt�i�}�����[�A1983�j�́A�{�W�Ɋr�ׂĂ͂邩�ɕ��|���炵�������������d�オ��ŁA����Ȃ��g�����������v�킹��B�������A�����͋g�����}���ގЌ�̊��s�ł���A�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��Ƃ��������ƁA�g���̍앗�܂����Г����Ȃ̂��낤���B
�Ƃ��ɁA�s���{�̌Ö{���t�Łs�[����W�t�����������9�����q�b�g����i2011�N6��12�����݁j�B1��������1���݂̂����A�ق��݂͂�2�������Œl�i��6,000�~����17,000�~�B�����[���͔̂��̏�Ԃ̋L�q���B�H���A�����w���P�^���Ȃlj���^���w�Ƀ��P����^���w�Ɍo�N�����̃��P�@��1�����ɏ��݁^���ɂ͌o�ߔN�������̓��Ă��^���^�����P�^�������w���P�L�^�����Ă��E�C�^�~�E����L�B�Ï��œ��肵���ʐ^���̑�1�����A�\���Ă��鎆���p�⏬���Ő�āA����ł���B�c�̃{�[�����ɖ��͂Ȃ�����������A�\�ʂ̎����������ア�������̂�������Ȃ��i�f�ނ��̂��̂̋��x�ȊO�ɁA�����ɂ�����Ј�����Ƃ̍I�ق��e�����Ă��悤�j�B�\���͐j���Ԃ��̋@�B�������o�N�ω������Ȃ����A����ł����Ă��Ȃǂ̏��݂͔������Ȃ��B�����ւ����Ɩ{�̂͂��傤�ԂŁA�ʐ^�E��2���i�V�h�旧�����}���ُ����{�j�Ƃ��A���قǗ����������Ȃ��B
�z��p���q��i1901�`1996�j�͎��̎t�ł���B����c��w�݊w5�N�߂�1979�N4������1�N�ԁA���{�G�f�B�^�[�X�N�[���̕ҏW�җ{�������Ȃŏ��ЂÂ�����w�B�z��搶�͎��Ƃ������Ă��Ȃ��������A�u���̂悤�Ȍ`�Ŏ�u���ɘb�����ꂽ�B�z��p���q��s�{�̎��Ӂt�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1979�N1��10���j�͂��̔N�̏��߂ɋg�����̑����ŏo�Ă��邩��A��w�������X�N�[���ōw���������̂��낤�B�g���̑������e�������o�ŕ��Ɏc���Ă����̂Ȃ�A�����Ă��炦�Ηǂ������A�ƍ��ɂ��Ďv���B�X�N�[�����ƌ�A���ł̈���������ۂɎ肪����@��͂قƂ�ǂȂ���������A���̋g���������̏����I�A�v���[�`�i�����܂ł��Ȃ��A�g���̒����͟f�㊧�s�́s�g�����S���W�t�ɂ�����܂ŁA�قƂ�ǂ��ׂĂ��{�������g�łɂ��ʔň���ł���j�ɂ́A���̂Ƃ��̌��s�������Ȃ�Ƃ��𗧂��Ă���B
�z��p���q��s�{�̎��Ӂt�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1979�N1��10���j�̔��ƕ\��
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�O�����y�[�W�E�㐻�۔w�N���X���E�\���i�X�~�Ɛ̓�F����j�B�\���͍��F�̃N���X�ɋ��������ŁA�g���������ɂ�����ł��w�p���I�ȑ����̂ЂƂ��낤�B�{���͔��̕\�P�Ɠ����f�U�C���ŃJ�b�g�̍��F�����ԂɕύX�A�����̑傫���͔��̔w�����Ɠ������B���Ɩ{�̂̔w�ɕ\������Ă���̂͏����ƒ��Җ��A�o�ŎЂ̃}�[�N�����A�o�ŎЂ��}�[�N�Ȃ͖̂��́i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��j���œ����ɂ͒����������߂��B30���N�Ԃ�ɏ����{����ɂ��Ă݂āA���̔w�����Ă��Ă�����̖̂{���p���͂܂�����ŁA���{�͂������肵�Ă���A�����ɂ��}�������{�G�f�B�^�[�X�N�[���̖{�Ƃ�������������i����͌����ЁA���{�͏��x�Ёj�B
�s�{�̎��Ӂt�͓����A1978�N�H�ɒ}�����[���犧�s���\�肳��Ă������A���̒��O��7��12���A���Ђ���ЍX���@�̓K�p��\�����Ď�����|�Y�A�v��͓ڍ������B�̋}�ςɔ����A�u�P���Ƃ��āA�}�����[�Ƃ̊Ԃň��̌����������b���i�߂��A���̌��ʁA�o���̉~���ȗ����̂��ƂɁA���k�����{�G�f�B�^�[�X�N�[���l�o�ŕ����甭�s����邱�ƂɂȂ����v�i�q���Ƃ����r�A�{���A�O�Z�Z�y�[�W�j�̂ł���B���̂悤�ȃL�����I�ȏo�������{�������A�g�����Ƃ̂�����������Ȃ��̂������B�u���̋C�܂܂ȘA�ڂ�����Ȃɂ������������̂́A�������w�����܁x�̕ҏW�҂Ƃ��ēy��k�ꐳ�l����A���ł͋g��������̈���Ȃ�ʔz���ɂ�邪�A����Ƌ��ɁA���̂悤�ȓǎ҂̎x��������������ł���v�i���A�O�Z�l�y�[�W�j�A�u�Ō�ɂȂ������A�����ɖ������������X�̂���l����l�ɑ��A���͏d�˂Ă����\�グ�����B���ɁA�����Ȏ��l�ł���A�����ꂽ�����Ƃł�����g�������A�A�ړ����̐e�Ȕz���ɉ����āA���̑�����S�����Ă������������Ƃ��A�܂��Ƃɂ��肪�����v���v�i���A�O�Z���y�[�W�j�Ƃ���q���Ƃ����r�́A���ꎩ�g���u�{�̎��Ӂv�ł���A�{���̐������߂���M�d�ȏ،��ƂȂ��Ă���B�Ō�ɖ{������������B�g�����ҏW�S���ƂȂ����s�����܁t�̍ŏ��̍��i1971�N1���̑�21���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�q�{�̎���21�@�������e�̘b�r�̌���ł���B
�@�Ƃ����Ă��A���e�Ȃ���͎̂G���Ȃ菑�ЂȂǂ̊�b�I�ȑf�ނɂ����Ȃ��B���ꂪ�ǂ�ȏ�Ԃł��낤�Ƃ��A������ɂȂ��Ă��܂��A�p�͏����A��l�Ɋ����̕����ɕς��Ă��܂��B�������A�����̏���������킩��悤�ɁA���ꂼ��̎��w�ɂ́A�M�҂��邢�͒��҂̐��̕������e�A�܂����ɂ͂���Ɏ��G�ꂽ�ҏW�ҁA���I�W�A�A���W�A�Z���W�Ȃǂ̂Ђ����ȐS�Ɗ�����������Ă���B�Ǐ��ɍۂ��āA���̕ӂ�z�����Ƃ́A�����ɂ�镶���A���́A���e�Ɉ��̖�����������̂ł͂Ȃ����낤���B�i�{���A�Z�Z�y�[�W�j
�k�NjL�l
�z��p���q��͗ђB�v�E���c���l�Ƃ̕Ғ��s��ꏑ�[ ���J�얤�V�g�t�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1984�N9��14���j�ŁA���_�q��ꏑ�[ ���J�얤�V�g�\���U�Ǝ��Ɓ\�r�������`�Ƌ������M���Ă���B�q�g�����Ƒ�ꏑ�[�r�͂����ꏑ���Ă݂����e�[�}�����i�q�P�b�Z���́s����t�Ǝ��сq�����r�r�ŏ����G�ꂽ�j�A�ȉ��ɑ�v�ۋv�Y�ҁq��ꏑ�[���s�}���ژ^�r�̖}��i�����A��Z��y�[�W�j��^���āA����ɔ��������B
�k2021�N4��30���NjL�l
�}�����[�ŋg�����̌�y���������{���Y�i1932�`2005�j�́A���{�o�Ŋw��u�z��p���q�厖�T�v�ҏW�ψ���i�ҁj�s�z��p���q�厖�T�t�i�u�z��p���q�厖�T�v���s��A1998�N1��29���j�́q��@�l�ƋƐсr�ɂ�����q�Ҏ[�Ǝ��M�r�Ƃ����p�[�g�́q�w�{�̎��Ӂx�r�̍������̂悤�Ɏn�߂Ă���i�����A�㔪�`���y�[�W�j�B
�@�u���̖{�̐��藧���ɂ��ẮA���Ҏ��g���u���Ƃ����v�Ɉύׂ�s���Ă��āA�ԑR����Ƃ��낪�Ȃ��B���������Ƃ����̂���{�Ƃ����ׂ��ł���B
�@�}�����[�̌����o�q���w�����܁x�̑n�����i���Z��i���a�l�\�l�j�N�܌����j�����\�O���i��㎵���i���a�\��j�N�ꌎ���j�܂ŋ�Z��ɘj���Ď��M�A�ڂ��ꂽ���̂ł���B�n���ɂ������ĒS���̓y��ꐳ�������������k���ĕ��������A���̈�l���z�삳��ł������B�o�q�����s�̖ړI�͎��Ђ̓ǎґw���g�傷�邱�Ƃɂ��邪�A����ɂ͂�������������ƍL���{��������l�̊S�ɑi����ׂ��ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃŕz�삳��Ɂu�{�̎��Ӂv���߂����Ęb��̒����肢���邱�ƂɂȂ����B�����l���́A����u�ق�E���̖ڂŌ�����j�v�i���x���́j�̘A�ڂ��n�܂��Ă��邱�Ƃɂ��M����B
�@�y��͓�Z�����炢�S���������A���҂ǂ���̂��̂������Ă��炦���A�Ƃ����B�A�ڂ͍D�]�ŁA���̂��Ǝ��l�̋g�������S���������A�����炭�����������������Ă��������Ƃ������ƂɂȂ����낤���A���҂ɂ��ォ��ォ�珑���������Ƃ��o�ė��������B�В��̌Óc��ɖ{�ɂ��Ē}������o���悤���߂�ꂽ�Ƃ����B�Óc�͑n�ƈȗ���g�ɒǂ������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă������A�����ł̎d���̌o���̒~�ς��d���ւ̐������ƂȂ��܂��ɂȂ��Č���ꂽ���͂Ɋ��������̂ł��낤�Ǝv���B�Óc��̍����Ԃ�͌��`����Ă��邪�A�n���Ɏd���֑ł����ސ����ɐS��z��אS�̐l�ł��������B���̌Óc�͈�㎵�O�i���a�l�\���j�N�ɋ}���������A�A�ڂɋ�肪�����Ƃ��A���R�̂��ƂƂ��Ċ��s�\��ɑg�ݍ��܂�Ă����B
�@���ۂɌ��e��������ɓn�����̂͘A�ڏI���̗��N�̘Z���ł���B��N�����Ԃ�����̂͒��҂��_囊���̎�p�̂��ߓ��@��������ł������B���e�̈ꌎ��A�قڑg�ݏ�������A�}�����[�͉�ЍX���@�K�p��\������Ƃ������Ԃɗ����������B�ۑS�Ǘ��l�̉��ōČ��̉\����T��ߒ��Ŋ��̌������s��ꂽ���A���̂悤�Ȍ������̗����Ȃ��̒��ŁA���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ������ւ肵�Ă����b�ɂ܂Ƃ܂����̂ł��낤���B���̔N�̏\���\�O���ɒ��҂͊�����}����̂ł�����߂����Ċ��s����͂��������̂ł���B�v
���}�����[�Ј��̋��{���Y�́A�}���ŕҏW����������s�����܁t�̕ҏW�����C�����W�Ŗ{�������M���邱�ƂɂȂ����Ǝv�����B�s�z��p���q�厖�T�t���s��1998�N�����A�g�����͂��łɖS���Ȃ��Ă��邪�A���{�̕����炷��ƁA�y��ꐳ�͑����������悤���B�g���Ɠy��̊W�ɐG�ꂽ�q�s��ʁt�����p�J�[�h���邢�͓y��ꐳ�̂��Ɓr���Q�Ƃ��ꂽ���B
�s���Ɏ��S�W�k��12���l�t�i�}�����[�A1958�N9��20���j�́A�k��1���l�}�����[�ő��Ɏ��S�W�i1955�N10��15���`1956�N9��20���A�S12���E�ʊ�1�j�̕��y�Ł��k��2���l�}�����[�ő��Ɏ��S�W�i1957�N10��25���`1958�N9��20���j�̍ŏI��z�{�ŁA�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����g���������Ǝv����B�{���̑ѕ��Ɏ��̂悤�ɂ���
�k�\�P�l
���Ɏ��S�W�^20���I���{���w�̊��葾�Ɏ��̑S��i�����߂�����Ł@�S12���^���y��/290�~/�}�����[
�k�w�l
��\�O��z�{�i�S�������j�^������i�^���E�N��
�k�\�S�l
�S�e�^��ꊪ�@�ӔN�̈�A���@3���^�k�c�c�l�^��\�@������i�E�����^�ʊ��@���Ɏ������^����������s/�e�����Z�~
���Ɏ��S�W�@���ؔ�/�S12���^�e���l��Z�~
���R�����^���Ɏ������^�l���Z�~
���Ł��k��1���l�}�����[�ő��Ɏ��S�W�́u���ؔŁv��搂��A���y�ł̒艿290�~�ɑ���420�~�B���R���ҁs���Ɏ������t�i1956�N6��30���j�͉��i���قȂ邽�߂��P�s�{���������i���{�E�����͌��łɏ�����j�A���y�łł͕ʊ��Ƃ��ās���Ɏ��S�W�t�ɑg�݂��܂�Ă���B�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��O��~�����[�g���E�l�O��y�[�W�E�㐻�۔w�����E�W���P�b�g�i���^��i�S�т̕W����f�ځj�B�W���P�b�g�̏����Ɩ{���̊����̎�F�\���͌��Łi���̎��^��i����w�\���̏����j�̂���P�������̂��B���y�łƂ͌����Ȃ���n�[�h�J�o�[�ł���A�������Ȃ����̂́A�����ɂ킽��ˑ���z�肵�Ă���̂͌������i�������A�{���p���͌��łɊr�ׂĂ��Ȃ茩��肷��j�B
�˂��b���Ɏ�
�@�@�@�@�@�@�@�_�}�c�e�����o�����ău�V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߊ�c�e�s�P�o���Q�����m�_
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�\����߂�
�@��̑������ꂽ���Ȃ�˂��͂ǂ����炩��Ę҂Ē�̎R���Ԃ̉��ŋ����肵�Ă��B�m�`�������Ă��F�l�̓y���V���łȂ����Ǝ��ɂ��Â˂��B���͂��Ă˂����炤�ƌ����Ēu�����B
�@�˂��͒N�ɂ��Ȃ��Ȃ����B
�@���������������̈���Ă��Ă���̂˂������̂����ɋ������B���������ɏo�Ăɂ₠�Ɠ��ւ��B
�@�˂��͋N�������Ď��̕��ւ��邢�Ę҂��B���͈����C�Ȃ��Ă���B�˂��͓����������ЂȂ�������ׂ��̂��B���̋��͘Q�����B�킪���͗e���ꂽ��B���͒�ւ��肽�B
�@���Ȃ��̂��낢�т��\����˂��͎��̏��w�̕������܂ł���T�Ɗ��ݗ��B�i�{���A�O����y�[�W�j
�q���r�Ɏ��߂�ꂽ�{���ł�����Z����i�ł���i�����͋������g�p�j�B�u����߂�v�Ƃ́A�L�̂܂��̖����낤���B�Ȃ��A���y�ł͌��ł̎��^�𗬗p���A���������́q�˂��r�i1�y�[�W���j�A�q�����܂������́r�i4�y�[�W���j�A�q�t�r�i2�y�[�W���j�̌v7�y�[�W�̖{���₵�Ă���A��p�́s���Ɏ��S�W�t�̂��肩����\��������B�ŋ߂́k��10���l�}�����[�ő��Ɏ��S�W�̎R���ˎj�ҁq�����r�͂��̕��y�Ł��k��2���l�}�����[�ő��Ɏ��S�W���u���Ɏ��S�W�@�S�\�E�ʊ��ꊪ�@�}�����[�Łv�̌��o���̂��ƂɁA���̂悤�ɋL���Ă���B
���a�O�\��N�\����\�ܓ��`���a�O�\�O�N�㌎��\�����s�A�}�����[�i�����s���c��_�c���쒬��m���A�Óc��j�B�l�Z���A�J�o�[�E�ѕ��A���G�ʐ^�e����t�B�{���X�|�g�B�艿��S��\�~�B
�k���l��}�����[�őS�W�B�ʊ��̂݁A���G�ʐ^��t�A�{���W�|��i�g�A�艿�O�S��\�~�B�S�\�A�e�����Ɂu��L�v�A�u���Ɏ��S�W����v���B�i�k��10���l�s���Ɏ��S�W�k�ʊ��l�t�A�}�����[�A1992�N4��24���A�l��O�y�[�W�j
���S�W�́u�\�v�i���Ȃ킿�{���j�́u���a�O�\�O�N�㌎��\�����s�B�ڎ��ܕŁA�{���l���Łi�N����ܕŁA��L�ܕŁj�v�i���O�A�l��Z�y�[�W�j�Ƃ���A����Ɏ��^���얼�S�т��ȗ����邱�ƂȂ��f���Ă���̂͌h���ɒl����B���Ȃ�u���őS�W��12����30�т̂��ƂɁA�q�˂��r�q�����܂������́r�q�t�r��3�т�V���v�Ƃ������ȂƂ�����A�����Ă������Ă��Ȃ��̂ł���B�������A�����̎l���y�[�W�����őS�W�́u�\�v���u�{���l���Łv�Ƃ��Ă���̂́A�{�������ŏI�y�[�W�̒��t�����f������j���̂��Ă���̂�����A�u�l��O�Łv���������B
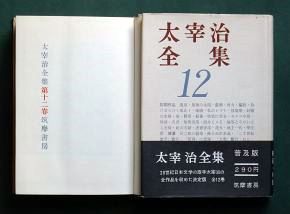
�k��2���l�s���Ɏ��S�W�k��12���l�t�i�}�����[�A1958�N9��20���j�̖{���ƃW���P�b�g
�k�NjL�l
�����ɂ���ẮA�k��1���l�Ɓk��2���l�Łs���Ɏ������t�̈������قȂ�i���Ƃ��ANDL-OPAC�́k��1���l�́s���Ɏ������t��P�s�{�Ƃ��Ĉ����j�B�����s���Ɏ������t�̔w�����́u���Ɏ������v�A�{���́u���Ɏ������@���R���ҁ@�}�����[�v�ŁA�����Ɂu���Ɏ��S�W�k�ʊ��l�v�̕����͌����Ȃ��B����́k��1���l�����ߑS12���Ŋ�悳��A���s�r���Ɂs���Ɏ������t���lj����ꂽ���Ƃɂ����̂Ǝv����B����́q�ҏW��L�r�i�����������A�쌴��v�̕M�ɂȂ邩�j�ɂ�������B
�u�{�S�W�̌�L���P�Ȃ�q�ϓI�����̋L�ڂ݂̂ŕ�����Ȃ��Ƃ�����ӌ��̕�������������̂悤�ł����A�k�c�c�l��i�̉���͓ǎҌl�X�X�ɂ����ĂȂ���ׂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����A���Ɏ��_�A�����͍�i�_�A��ƌ����A���̑�����ɗނ������̂ւ̓ǎҏ��Z�̗v�]�����Ȃ苭���̂ŁA���݂܂łɏ����ꂽ���̎�̕]�_�A�G�b�Z�C���W�听���A�{�S�W�̕ʊ��Ƃ��āA�����͑��̑̍قɂ����āA����Łw���Ɏ������x�����@��I��Ŋ��s�������ł���܂��v�i�k��1���l�s���Ɏ��S�W�k��3���l�t�A�}�����[�A1955�N12��20���A�q����R�r�A���y�[�W�j�B
�܂����N10��15���́k��1���l�q����P�r�ɂ́u��挈��A�ҏW�̃X�^�[�g�����N���ȏ�̌������₵�A���̊ԁA���搶���̌䉇���A�䋦�͂̂��ƂɁA�ҏW�ɍZ���ɁA���ށE���{�ɁA�܂��͖��S�̓w�͂��͂��������ł���܂��v�Ƃ���A�{�S�W�ɓq����o�Ō��̈ӋC���݂������Ă���B
�@�g���̎�ɂȂ鑕������������Ă݂悤�B����ɕt��������ׂ����Ƃ͂Ȃ��B�����ċ�����A�s���Ɏ��S�W�t�̓��e���{�̒n����F�Ȃ̂ŁA�u���^��i�����ԃC���N�ō����Ă���v�̂́A���邢�͐ԃC���N�^��F�����C���J���[�ɐݒ肵�����߂��i���e���{�͌��������ɂ��A�g���̎�ɂȂ���̂��s���j�B�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��O�l�~�����[�g���E�l�y�[�W�i�����A�ʒ����G�ʐ^����t�����̎l�y�[�W�j�E�㐻�N���X���i�w�����͎�̐F�������j�E�\���B�g���̒}���ɂ�����S�W�����̑O��A���c�Ǖ��E�a�c�F�b���s��t�S�W�k�S7���l�t�i1953�N8��10���`1956�N6��20���j�ɔ�ׂāA������i�Ƃ��đf�ޖʂł��ӏ��ʂł��}���ɐ��n�������Ƃ����������錩���ȏo���f���ł���B�}�����[����t�������ɂ̑S�W�Ɍ����ꂵ�����Ƃ����낤���A���̏o�ŏ̕ω���������㉟���������ʂ����邾�낤�B
�@�����̎d���ł���w���Ɏ��S�W�x�i�}�����[�A�k���l�܌ܔN�j�́A���Ɏ����Ȃ���ł���B���ɂ��\���ɂ��C���X�g�̂悤�ȑ����I�ȗv�f����Ȃ��A���������ɂ��\���B���ƕ\���̃^�C�g���̓��^�����O�ɂ�鏑�������i���Ƃ����������̂ł��낤�A���킢�̂��鑾�������́j�ł��邪�A���Ƃ͊����ɂ��\���ł���B�B��̃A�N�Z���g�Ƃł����������Ȃ̂��A���ɔz�������^��i�����ԃC���N�ō����Ă��邱�Ƃ��炢���B
�@�܌ܔN�Ƃ����A�͓��R�̊���ŊX���e���r�ɐl�X���Q�������N�B�����̐i����M���āA�l�X�������Â߂ɓ���������A���{�Љ���ʂ̉��l�ς�������������ł���B�������������w�i�ɁA���̑���́A��ӂ����̏����r�����A�{��������߂��d�グ�ƂȂ��Ă���B���ʁA�h�肳�͂Ȃ�����ǁA�������A�����������i�i�������Ă���A�}�����[�̘H������������Ɠ��܂��Ă��邱�Ƃ����������Ƃ��B�i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A�Z�O�`�Z�l�y�[�W�j
 �@
�@ �@
�@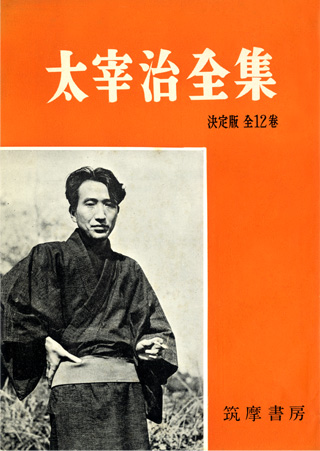
�s���Ɏ��S�W�t�̖{���ɂ��ẮA�ֈ���j�́q���Ɏ��ƃe�N�X�g�r�i�k��11���l�s���Ɏ��S�W�k��13���l�t�A�}�����[�A1999�N5��25���A�q����13�r�j�ɊȌ��Ȑ���������B����ɋ���A���ɂ̒���E���k�E���ȁE������ԗ���������i�������ďW�听��������I�ȁk��1���l�A�{���Z�����s�Ȃ�꒘��̖{�����������ăe�N�X�g�̕ϑJ������������ł́k��7���l�A���M�N�㏇�ɒ����Ґ����ďڍׂȉ���t���������Ҍ����̏��o�ł́k��10���l�A���Ɏ��f��50�N���L�O���Ċ��s������ʓǎҌ������k��11���l�����M�����B����Ɋֈ�͂��������B
�u���̌\�N�ԂɁw���Ɏ��S�W�x�̃e�N�X�g���邢�͏����E�����͋����قǐ�������A��ɂƂ��Ă̏����͑������B�����������������Ƃ́A�e�N�X�g��ǂލs�ׂ𗣂ꂽ������`���Y�ށB����͉ߋ��̗��j������Ă���B���������Ƃ��d�v�Ȃ̂́A�e�N�X�g�͎���̂Ȃ��œǂݑւ����A���j���[�A������Ă������Ƃ��������ȔF���ł���v�i�O�f����A���y�[�W�j�B
�����g�����̃e�N�X�g�E�����E�������������A�S�W�Ƃ����u��Ɂv�Ȃ�ʁu�e��Ɂv�̍\�z�Ɍ�������Ƃ�i�߂Ă��������B���̂Ƃ��A����̏o�ŎЂ�50�N�ɂ킽���Ċ��s���Ă���11���ɂ킽��l�S�W�̕ҏW�E���{�̂��������w�Ԃׂ��_�͐������B
�V�V�ޓ�Y�s���̋��\�\���t�����i�ց@��i���猾�t�ցt�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1972�N12��25���j�͓V�V�̍ŏ��̔�]�_�W�s���̋��\�\���t �����i�ց@��i���猾�t�ցt�i���_���[�A1968�N11��10���j�̍Ċ��ł���B���_���[��1969�N�ŐV���̔��s���~�܂��Ă��邩��A��O��] �_�W�s�����̍\���\�\��i�s�ט_�̓W�J�t�i�c�����X�A1972�N10��25���j�̊��s�ɍ��킹�āA�ʂ̔Ō�����Ċ��������̂��낤�B�q�����̂��Ƃ����r�̖����ɂ�������B
�@�����̔��s���A���_���[�͏��ł��A��łɂȂ��Ă����{���������ɍĂъ��s�����̂͐��R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��̍D�ӂɂ����̂ł���B�I��ɁA���� �Ă̗��_���[�̕ҏW�҂ւ̎ӈӂ��L���Ă����B�i�{���A�O�l�l�y�[�W�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ�܁~��~�����[�g���E�O�ܔ��y�[�W�E�����E�����ŁA�{���͑O�f�����̎��^�𗬗p���Ă���B�����̖ڎ����ɂ́u���{�@���c����v�Ƃ���B�����ƍĊ��̈Ⴂ���r���邱�ƂŁA�g���������̓������m ��悤�i�ڎ��̗��Ɂu���ꁖ�g���@���v�ƃN���W�b�g������j�B�����̎d�l�́A���Z�~���܃~�����[�g���E�O�܁Z�y�[�W�E�㐻�p�w�E�����B���̑��{�������ς���Ă���̂ŁA�ڂ������悤�B���Ƒ莫�Ŗ{���p��2���A���G�ʐ^���h�H����܂��2���A��F���̖{���Ɩڎ��Ɣ��܂łŖ{���p��4�����A���̎��̃m���u ���u13�v����ŏ��̕��́q���ƌ��t ���]���Z���r���n�܂�B�����͂����炭�A�{���p��8�y�[�W���i4���j�̐ܒ��̒J�܂Ɍ��G��\�肱�`�ɂȂ� �Ă���B����A�g���������̍Ċ��͖��n�̌��Ԃ��i�����͉�Ƃ̑������������āA�G�����������Ă���j�̂��ƁA�ʒ��{���i��F�������A�X�~�ƔZ���Ȃ̂ł� �Ƃ�Ǎ����Ȃ��j�A�����Ɠ������G�A�ȉ��{���p���������B�܂����������ăV���v���Ȃ��ƁA���̂����Ȃ��B�������m���ӂ��̓W�J���Ƃ���A�Ċ��̓I�[�\ �h�b�N�X�Ȗ{�M�̏��Ђ̏����ł���B�O�t�ƌ�t�̑g�łŌ����ȈႢ�́A�����̖ڎ����n�����A���җ����E���t���Ŗʂ̉������ɕz�u����Ă���̂ɑ��āA�� ���̖ڎ��E�����ژ^�i���җ������������j�E���t�Ƃ��V�����i�O�q�́u���ꁖ�g���@���v�����n�����j�ƁA����܂��I�[�\�h�b�N�X�̋ɂ݂̂悤�ȑg�łɂȂ��� ����B�Ċ��̑O�t�E��t���w�肵���̂��S���ҏW�҂��g�������s�������A����Ȃ�Ȃ�����ł���B�{���ɂ́A�q�g�����_���ڂ������r�� �O�ɂ��g�������ւ̌��y��������B�}�����[�́s���̖{�t�ɔ��\���ꂽ���͂��������B
�k�c�c�l���Ƃ��g�����̎��W�w�m���x�S�тi���Ƃ��Đ��������Ă�����̂̑啔���́A�������Ȃ�������̂��ɍd���Ȍ��O �ł���Ƃ����悢�̂��낤�B���łɌ����A�q�������Ȃ����̂�����r�Ƃ����̂��g�����̍����I�Ȏ��@�ł���A�g���̍�i�ɂ����鉹�y���̔閧�͂����� �炫�Ă���B�����Ă���͋g���l�̓����Ȃ̂ł͂Ȃ��āA���̎��@�ɂ���Ĕނ̎���i�́A�������̎��̕\�ʂ֑ł��������Ă���Ƃ����ׂ��ł��낤�B �i�q���̂͂��܂�E���̉^���\�\�|�����_�̎��݁r�A�{���A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j

�V�V�ޓ�Y�s���̋��\�\���t�����i�ց@��i���猾�t�ցt�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1972�N12��25���j�̕\��
�V�V�ޓ�Y�s��i�s�ט_�����߂āt�i�c�����X�A1970�N5��25���j�͋g���������������ŏ��̓V�V�ޓ�Y�̒����B�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j �̕ҏW�ψ��߂��ѓ��k��E�剪�M�E����N�v�E�����r�Y�̎l���l��������A�ł������̋g���������̒����������㎍�l���V�V�ŁA�{�����܂߂�8�� ����B���s���Ɍf���悤�B
�i1�j�s��i�s�ט_�����߂āt�i�c�����X�A1970�N5��25���j
�i2�j�s�V�V�ޓ�Y���W�t�i�y�ЁA1972�N2��5���j
�i3�j�s�����̍\���\�\��i�s�ט_�̓W�J�t�i�c�����X�A1972�N10��25���j
�i4�j�s���̋��\�\���t�����i�ց@��i���猾�t�ցt�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1972�N12��25���j
�i5�j�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����Łl�t�i����R�c�A1974�N9��1���j
�i6�j�s�s�{�V�����t�_�t�i�}�����[�A1976�N11��30���j
�i7�j���W�s���P�l�t�i�y�ЁA1980�N5��10���j
�i8�j�s�s�{�V�����t�Ӂt�i�}�����[�A1986�N9��30���j
�i3�j�́i1�j�́A�i8�j�́i6�j�̑��ғI�ȏ����ŁA�i4�j�́s���̋��\�\���t�����i�ց@��i���猾�t�ցt�i���_���[�A1968�N11��10���j �̍Ċ��ł���i�s��i�s�ט_�����߂āt�́q���Ƃ����r�́u�{���͍ŏ��̏����i�K�ł́w��i�Ό���x�Ƃ������� �����肵�Ă������̂ŁA�����Ƃ��Ď�������]�_�W�w���̋��x�i���Z���j�Ȍ�ɏ������G�b�Z�C�̑啔�����A�킪����m�A�A�n�ɂ���i�m�A�A�n�ւ̑Ό� �Ƃ����݂��ɂ����ďW�߂Ă݂����ʂł���v�Ǝn�߂��Ă���j�B���_���[��1969�N�ŐV ���̔� �s���~�܂��Ă��邩��A�i3�j�̊��s�ɍ��킹�ĐV�����Ō�����Ċ��������̂��B�{���̎d�l�́A�ꔪ���~���Z�~�����[�g���E�O�l��y�[�W�E�����i����j�����B���\���ɋ�����b�q�ɂ��200�����A����̕��͂��f�ڂ���Ă���B �J�b�g�i�\���E�{���ɓ����G��F�Ⴂ�œW�J�j�͒��� ���ق�A�ڎ��̍Ō�Ɖ��t�̓�ӏ��Ɂu����ҁ@�g�����v�ƃN���W�b�g������B

�V�V�ޓ�Y�s��i�s�ט_�����߂āt�i�c�����X�A1970�N5��25���j�̕\��
�s��i�s�ט_�����߂āt�̕��͂ł��Ј��p�������̂��q�f��ɂ������i�s�ט_�\�\������ �Ɛ����f��𒆐S�Ɂr�i���o�F�s�C�t1970�N4�����q���W�E��]�̌��Ƃ��Ẳf��r�j�̈�߂ł���B
�@�|�[����u���|�̐U�q�v�Ȃǂ̋��|�f��̐E�l�Ƃ��Ēm���郍�W���E�R�[�}���̐����Ȃ��������́A���̃}�]�q�X�e�B�b�N�Ȏ��O �ɂ���ăI���W�i�� �e�B���m�ۂ��Ă���B�u���˂������e�v�i���� The Gunslinger�j�̃q���C���A�r���@���[�E�K�[�����h�͎E���ꂽ�ۈ����̍ȂŁA�߂������e�̎���ł���B�`���A�v�̖����̃V�[���A����q�̒��ɂ� ���ꂱ��ł������ʂ̎艺���l���A�ڂɂ��Ƃ܂�ʑ��˂��œ|�����ޏ��́A�V�C�̕ۈ���������܂ł̊ԁA���̕ۈ����ɏA�C���A�v�̕��Q���Ƃ��悤�Ƃ���B�� ����������ޏ��͈��ʂ̎�́i�W�����E�A�C�A�����h�j������Ă��܂��B��l�߁A�������R�ɒǂ��߂��ޏ��́A��F���������Ɉ��������������ƁA�͂��� ���˂������̖��A������ˎE����B�悭���ꂽ���������A�ޏ��͂ЂƂ�n�Œ����o�悤�Ƃ��āA�V�C�̕ۈ����Ƃ��ꂿ�����B�ۈ����͉����m��ʂ܂܁A�s�Â��� ���ł��ˁt�ƈ��A����̂ł���B
�@���̉f��̃N���C�}�b�N�X�A��R�ł̎˂������́A���炩�Ɉ��̐�����ʂł���A���ɂ��j�̎ˎE�́A���̍�i�̍�i�s�בS�̂���ʂ��}�]�q�X�e�B�b �N�Ȏ��O�̃I���K�X���ł���B���̈Ӗ��Łu���˂������e�v�̓|���m�O���t�B�I�z���͂̓T�^�I�ȍ�i�ł���A���W���E�R�[�}�����r���@���[�E�K�[�����h�Ƃ� ���q���C���ɂ��߂��\���̖ڂ������Ƃ���́A�u�j���G���̌��t�k�s�G�[���E���C�X�́s���Ɛl�`�t���f�扻������ɂ��ă��b�g���E�t�����Z�[�Y�̋L�҂Ɍ�������t�l���̂܂܁A�s�܂������悤�Ȋ��\���t�A�s���̎��Ȗʁt�́A�P�����B�ȕ\�o�Ȃ̂ł���B �i�R�[�}���͑��Ɂu�r��̑ҕ����v��Ƃ�킯�u������E���v�ɂ����ē������O��Nj��������A�u���˂������e�v�ɂ�����悤�ȓO�ꐫ�A�P�����B�ȃ|�G�W�[�� �����āA�Ƃ肩�����悤���Ȃ��g�U�������݂ɏI���Ă���B�j�i�{���A��Z���y�[�W�j
�������������̂͂ق��ł��Ȃ��A�V�V���s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����t�i����R�c�A1996�N11��30���j�Ɋ����т��q�\�\�� �邢�́s���˂������e�t�r������ł���B�����͂��̌�A�l�ӏ��̒������{���Ď��W�s�����P���̂��߂Ɂt�i�v���ЁA1999�N7��20���j�Ɏ��^���ꂽ���A�q�f��ɂ������i�s�ט_�r�̓V�V���͌�N�̓V�V���̓ǂ݂ɂȂ�玑����Ƃ���̂Ȃ��A�����Ȃ��̂ł���B�������k�s���̂���������������Ă����t�f�ڌ`���s�����P���̂��߂Ɂt�f�ڌ`�l�ŕ\�킵 �āA���сq�\�\���邢�́s���˂������e�t�r�������B
�@�r��Ŗl�����̔n�Ԃ��P�����\���k�������̃O���[�v�l�́A�k���������i�g���j�l���l�ł����B����̗͈͂��|�I�ł������A�l���������������Ŗh�킵�A���� ���˂������̂����k�i�i�V�j���Ɂl���l�Ƃ��˂��܂������A��������ȂƎo�ƁA�c�����q���E����A�Z�v�w������ŁA�C�����Ɛ����c�����͖̂l�����ł����B���̑O���ƌ㔼�i�k�i�x�^�j���i��s�A�L�j�l�̑O��j�Ŋ�ɂ˂���Ă��āA�ǂގ҂ɂ��ǂ������z���� ������̂́A��҂��s�m���t�̂���̋g�������܂������̂��B �k�i�x�^�j���i��s�A�L�j�l�̎����́A���̒f�����苭�łȂ炵�߂邽�߂̑[�u�������悤�Ɏv����B
�@�r������܂���̕��������A����Ƃ������܂�n�Ԃ̌������ɉ������c�c�Ƃ݂�܂ɂ���͂����ڂ������̒ʂ�ŁA��l��l�A�ʍs�l�������܂��B�͂��Ƃ��� �������֕���������ƁA�ʂ���l�e���ӂ��Ə����āA�l���͂����߂�A�������̂܂܂̍r��ł��B�ƁA�܂��n�Ԃ̕��֊��������ƁA���̌������ɒ������c�c�� ����������A�ߊ��܂ł��Ȃ��ӂ��Ə����܂��B�����A凋C�O���A�������̋C�̂������c�c
�k�i�x�^�j���i��s�A�L�j�l
�@���������ɂ܂��n�Ԃ̕������܂��ƁA����ǂ͂��̂����������ɐԂ��W�����p�[�������̂́A����͎o�̖����A�����Ă��̂��I�@�������āu�����I�v�Ƌ킯�� �낤�Ƃ��Ȃ����u�A���̗��ɖÂ��ꏏ�����������H�@�Ǝv���܂����������Ȃ��������c�c
�@�����Ƃ������֖ڂ����������͖ڂɂ��Ƃ܂�ʂ��₳�Ńx���g����K���������ʂ����ܔ��˂��āA�e�͒j�̐S������ʂ��܂����B
�@���͗p�S�[������������܂킵�Ȃ���߂Â��Ă��āA�����ɓ|�ꂽ�j�̐g�̂��u�[�c�Ōy���R���Ă��炱���������̂ł����\�\
�u�܂���l�A�����c���Ă��̂ˁB�낢�Ƃ��������B�v
���l�Ƃ��Ă̈����Ƃ������ƂŎv���o���̂��A���l�̋g��������Əa�J�����������X�ʼn��x����������ۂ̂��Ƃ�ł��B�����̍ŏ��̎��W�w�V�g�x���o������ł����̂ŁA�g�������Șb�Ԃ�Ŋ��z��`���Ă����������̂ł��B�u����N�v�N�̃p���f�B�[���ʔ����������ǁA��ԋC�ɓ������̂́u�J�t�J�̂��킳�v���ˁB�v���̕]���ӊO�ł������A�u�L�~�̎��̃X�^�C���͈����Ɏ��Ă����v�ƌ���ꂽ�Ƃ��������܂����B�Ƃ������A������͈����Ƃ����ƒ��w�Z�̓Ǐ����z���œǂ܂��ꂽ�w�����x��w�V�����O�x�̍�Ƃł�����A���l�Ƃ��Ĉӎ������Ă��Ȃ������̂ł��B�ォ��Q�Ăāw�k���x�Ȃǂɖڂ�ʂ��܂������A�����P�X�W�W�N����̌��㎍�̌���ς���s���A���h�G�N���`���[�������������ł�������A�������̃V���v���ŎU�����l�̕��̂Ƃ����̂́A�u�Â������v���́B�����g������A�����g�͔ӔN����ȏd�����|���I�ȕ�������h�������̂ɁA���l�Ƃ��Ă̈�����]�����Ă��āA�{�̑������������肪����ꂽ�悵�ł����B�g������A��㎁�Ƃ��ɋS�Ђɓ����āA�ނ�̎d�������Ή��H�ł���悤�ɂȂ�܂������ȁB����ɂ��Ă����o�����u�ǂݍI�ҁv�������g������̕]�A������x��䍂��܂��傤�B�э_�����W�s�V�g�t�i����R�c�A1988�N10��30���j�̋g���]�������[�����i�Ƃ�킯�q�t�����c�E�J�t�J�̂��킳�r�̌��j�A�u���l�Ƃ��Ă̈�����]�����Ă��āA�{�̑������������肪����ꂽ�悵�ł����v�Ƃ���̂͂ǂ̖{���w���̂��B�g�����}�����[��ގЂ������Ƃ̑����ɂ̓N���W�b�g������͂�������A���m�̋g���������̈����{������Ƃ����1951�N����78�N�܂ł̒}�����[�ݐВ��ɓ��Ђ���o���P�s�{���낤�ƌ��������Č�������ƁA�ȉ���7�^�C�g���A8�����q�b�g����B�����ƂƂ��Ɋ��s�����f���A�R�����g��t���B
���W �^��
���a42�N6��25���A�}�����[���s�@�`�T�ό^���@���@�сi�ɓ����u�u�^�́v��v�j�@84�Ł@����E���Ԋ��@�艿�U�T�O�~
�������@�V���ȁ@���^���ѐ�26
�m���e�n�^�́A�얾��A�����i�A��A���J�A�z�^���A�O���A�����ǂ��A�C��A�����t�v�搶�̎��A�C�A������d��āA�����̊X�A�e�A���́A�J姒�̏��A�����֎~�n�сA��сA�t�̓��L����A蝐������قɂāA�ʗ��A�~�V�V�b�s�́A�H�̂͂��߁A�D�a�����A�����S���l�A��^���Ƃ����i���\���t�L�j
������Ł@�����A���Д��s�B�W�O�O���L�ԏ�������A���A�O�����A�P�R�O�O�~�B�i�����A���O�O�y�[�W�j
 �@
�@ �@
�@
蝐������قɂāb�����������Ғ��s�����m�[�g�t�i�����[�A1978�N3��26���j�ق����Q�Ƃ���ƁA�}�����[���s�́s�����W�k�V�I������{���w�S�W 21�l�t�i1959�j�͑����F���n�F�l�Y�A�⑺�E�Ƃ̋����s����k�O���[���x���g�E�V���[�Y 15�l�t�i1963�j�Ɠ��s����k�}�����{�I 8�l�t�i1971�j�̑����҂͕s���A�s�����W�k���㕶�w��n 60�l�t�i1963�j�͑����F�^�甎�A�s�����t�v�E�H�열�V��E�����k���{�Z�ѕ��w�S�W 25�l�t�i1967�j�͑����F�Ȑ܋v���q�A�s�����W�k���a�������w�S�W 26�l�t�i1973�j�̑����҂͕s���ł���B�s�����E�i�䗴�j�W�k������{���{��n 86�l�t�i�}�����[�A1969�N4��5���j�͋g�������������i�q�g�����̑�����i�i60�j�r�Q�Ɓj�A�э_���́u���l�Ƃ��Ă̈�����]�����Ă��āA�{�̑������������肪����ꂽ�悵�ł����v�Ƃ����،��̃j���A���X�Ƃ͔����ɐH���������B���W�s�^�́t���s��21�N���1988�N5���A�s�V���t�̑n��1000���L�O���i85��5���j���A�g������������͑剪�M�ƂƂ��Ɏ��т��Ă����\�\�g����i�́q�ӏ��r�i�K�E15�j�A�����i�́q�V�U�̑��r�i�s�T�ώҁt�A�W�p�ЁA1988�N6��10���j�\�\�B�O�l��������\���鎍�l�Ɩڂ��ꂽ�̂ł���B
蝐��m�����n�����قł܂�������̐��ֈē����ꂽ�B���̎�^�̖��邢�����̒��ɂ͉������ɋr�m���₽�n���g�܂�A�J���҂������V��̕ǂ�h���Ă����B���̓V��̉��̍L�����ɂ́A�\�����̐Ώb�������v���v���̕��p�������āA�قړ��Ԋu�ɔz����Ă������B�Ⴆ�Ă�����́A�ق��Ă�����́A�z���Ă�����́A�����̂����M���Ă�����́A�����̎��p�Ԃ��\�����X�ł������B�҂̔��ɂ͔����ۂ������A���m�����n�߂鎂�q�̖ʂ͕������A�n�̑S�g �͉��y�ɐ��܂��Ă����B�Ղ̊�ɂ�㟁m�Ђсn���͂���A�z��鎂�q�̌�r�͎O�ɐ܂�A�O�r�̈�{�����O�ɍ����Ă����B
���q�̓�͓��A��͓����A�҂Ɖ狍�ƌՂ͂���������A���\�͐�鰁A���n�͐������B�嗤�e�n����ŋ߂����ɉ^��ė������̂���ł���B
���͈ē��l�̋��𗣂�A�������Ԃ��ė����Ώb�����̊Ԃ�������B����������B���V�̐��Q�̉���������́A�����B��Ƃ������ǂ�ŕ������B
�͓��p����s�E���K���b�e�B�S���W�t�i�}�����[�A1988�N1��1���j�́A�A�����E�~�V���I���L���X�����E���C���ȂǁA�g�������������������Ȃ��O�����l�̖W�̂ЂƂŁA�Ȃ��ł��ł��{�i�I�ȑ��{�ł���B��ˎ闝�́s�g�����̏ё��t�i�W���v�����A2004�N4��15���j�Ɏ��̂悤�ɂ���B
�@�w�E���K���b�e�B�S���W�x�͊D�F�̃N���[�X�����������{�����A���������肢����ƁA�����łȂ�����ƌ����āA��̌��Ԃ��ɏ������T�C�����ĉ��������B��ɕҏW��S�����ꂽ�}�����[�̒W�J�~�ꎁ�ɂ��̘b�������Ƃ���A�g������͑���ҕ��̓��������āA���̂����̈�������ɉ����������Ƃ�������A�������B�i�����A�܋�y�[�W�j
��ˎ��̃u���O�A2005�N9��13�����q���̎��l�̖��́r�ɃA�b�v���ꂽ�ʐ^�̕M�Ղ́u��ˎ闝�l 1989.11.27�@�g�����v�Ɠǂ߂�i�T�C���̓��t�́A�g����1990�N5���ɋ}�����锼�N�قǑO�ɓ�����j�B�{���̎d�l�́A��Z���~��l���~�����[�g���E�ܓ��y�[�W�E�㐻�p�w�N���X���E�@�B���B�قړ����̐��e���O�Y���W�s�l�ށt�i�}�����[�A1979�j�����邱�ƂȂ���A�D�F�̃{�[�����̋@�B���Ƃ����A�n�̃J���o�X�n�̊p�w�\���Ƃ����A�{��~�s���p�̐D���t�i���A1975�j���霂�����d�オ��ɂȂ��Ă���̂́A��҂���v�]�ł��������̂��낤���B
�R���b�E���K���b�e�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ܔN
�R���̖����ɂڂ��͕ʂ̑�^���̉����Ă���
��҂ɂ��q����r�ɂ́u���̂��сw�E���K���b�e�B�S���W�x�̏o�ł�S�苭���������Ă����������A�}�����[�ƕҏW�S���̒W�J�~�ꎁ�ɁA�܂��킴�킴����̘J�������Ă����������A���h���鎍�l�g�������ɁA�k�c�c�l�����Ȃ���A�[�r�̎ӈӂ�\�����Ă��������v�i�{���A�܁Z���y�[�W�j�Ƃ���B����ɁA����͋g���f��̊��s�ɂȂ邪�A�{���̑����P�����͓��p����s�N�@�W�[���h�S���W�t�i�}�����[�A1996�N3��31���A�����҂̃N���W�b�g�Ȃ��j�̖�ҁq����r�ɂ́u�}�����[�́A��ɁA�ҏW���W�J�~�ꎁ�̂��s�͂ƁA�g�������̋C�i�̂��鑕���ɂ���āA�w�E���K���b�e�B�S���W�x�i�����j���A�u�܂��Ɏ��������A�l�Ԃ��ł���̂��v�Ƃ����ǎ҂ւ̒掫�Ƌ��ɁA���ɑ���o���ĉ��������B�k�c�c�l�ȗ����N�A����ȃN�@�W�[���h�Ɏ��i���A���̂悤�ȁw�S�W�x�̑̍قŐ��ɑ���o����̂́A��d�ɁA���ԒW�J�~�ꎁ�̂��͓Y���̎����ł���B���߂ċL���A���N�̕ҏW�����̍Ō�̍Ō�܂Ŏ����ĉ�������������ɂ���\���グ��v�i�����A�l�O��y�[�W�j�Ƃ���B�s�N�@�W�[���h�S���W�t�́A���t�̓��t������킩��悤�ɁA���N3��25���Ɋ��s���ꂽ�s�g�����S���W�t�ƕ���ŁA�}�����[�ł̒W�J���Ō�̎d���Ƃ����邾�낤�B��������i�N�̌��Ă������B
 �@
�@ �@
�@
�͓��p����s�E���K���b�e�B�S���W�t�i�}�����[�A1988�N1��1���j�̔��k�\�l�ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��k���l�i���j�Ɖ͓��p����s�E���K���b�e�B�S���W�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2018�N4��17���j�̃W���P�b�g�i�E�j
�k2018�N5��31���NjL�l
�{����2018�N4��17���A��g���ɂƂ��čĊ����ꂽ�B��g���ɕҏW���ɂ��k�ҏW�t�L�l�ɞH���A
�{���͉͓��p����w�E���K���b�e�B�S���W�x�i�}�����[�A��㔪���N�j�ɉ��������̂ł���B
���̂����A���s��s�����Ȃǂ̌����A�����̕\�L��ς��A�̂����ꕔ�����߂��B�܂��A���̌�̌����̐��ʂ܂��A��Ƃ��āu�N���v�ɁA����ƘA�����ċ͂��Ȃ���u����v�ɁA���M�C�����{�����B�i�����A�k�ܔ����y�[�W�l�j
���Ȃ킿�A���ł�ҏW�����W�J�~��Ƒ��������g�����ւ̎ӎ��́A��ҁq����r�i�ܘZ�O�y�[�W�j�ɂ��̂܂c����Ă���B

�ӌ������̉̏W�s���Ղ�̎V���t�i�v���ЁA1981�N4��20���j�́A���̏W�s��̍��k�V�s�̐l�p���l�t�i�p�쏑�X�A1976�j�㈲�ȍ~��4�N
�Ԃ̍�
�i
�����߂����̏W�B��́q
�ӌ������̉́r�́A�p�쌹�`�̒����ł��钘�҂��������ォ��m��R�{���g�ɂ��B�u�Z�̂ɂ��o��ɂ��A���₠���镶�w�ɂ��|�p�ɂ��A���ꂼ�ꎞ���̑���������B���ꂪ�@��
�ɐV��
������A�V�����v���̑����ł����Ă��A�����ɂƂǂ܂邩����A���̐S�ɑi���邱�Ƃ͂Ȃ��B�Ⴂ�ӌ�����ɂ��A�V��������̔g�������Ԃ邱�Ƃ͔�����������
�����A���x�̉̏W�����Ă��A����ɂƂǂ܂�Ȃ��A�ӌ����g�́u���̂��v�̂���߂����A�����Ȃ��ǂގ҂̋��ɂЂт��B�����Ă��̂����������A���Ĕޏ�
�����݁A���炪���A�R���Â����S�����`�ւ̐�X�̎v���ł��邱�Ƃ́A�قڊԈႢ����܂��B����قǂ��̉̏W�́A�����ΖS���ւ̎v�����J��Ԃ��q�ׁA��
��͂��ƂɌ㔼�ɂ����č��܂��Ă���v�i�{���A��Z��y�[�W�j�B
���҂́q���Ƃ����r�̖������u�܂��A����̋g�������A�т̉��䗲���ɂ��J��ς͂����B�v��
�Ђ̔��ؒ��h���ɂ͏o�ł̈�̂����b�����B��
���Ƃǂ����z�������Ă����������ƂɊ��ӂ̈ӂ�\�������v�i���O�A��Z���y�[�W�j�ƌ���ł��邩��A�����ɋg�����N�p�����͔̂��̔��Ă�������
�Ȃ�
�i���Ȃ݂Ɏ��́A�{���̑O�N�Ɋ��s���ꂽ�g���̏��̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�̒S���ҏW�ҁj�B���J���̖ڎ������y�[�W���āA�u����-�g�����v��1�s����
��
�g��ł���B���䗲�̑ѕ��q�߈���壉ΔR�������悤�c�c�r���������i�R���}�ƃ}���̋�Ǔ_�͌����̃}�}�j�B
���ڂ��鐅�ɂ������ޜW�m������݁n�̂ނ��������̑傫�����B���������啿�̉̂��r�� ���l�ł���B�݂Ђ炯��̂킽�ݑ���������N��̟D���ȁC�ƟD���Â��Ēu���āC�p�̉ԍ炭�C�Ɖ̂������߂�B�̂��������ȏ��l�͋�肾���C���̐l���� �����̗����ɂ͔߈���壉̔R�������悤�d�����������g�����Ă��āC�������ǂ��܂�������̂��B
�����̈��́u��˂͉Γc�@�����ތ{�ɉA�m�قƁn�Â���~�肵����~���܂ʂȂ�v�ŁA�g���̎���m��҂́q��r�i�B�E14�j�́u�{�v��z���o����
�ɂ͂����Ȃ��B
�{���̎d�l�́A���Z�~��O�l�~�����[�g���E�ꎵ�Z�y�[�W�E�㐻�۔w�z���E�@�B���B���̈ӏ��́A�g���́s�_��I�Ȏ���̎��k���y�Łl�t�i����R�c�A1976�N8��15���j��ѓ��k����s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����t�i���A���N3��
15���j�Ɠ��H�����A�ʔň���̓�F���i�����Ƃ����X�~�����̕W��Ƃ����Ԃ̉Ԗ͗l�̃I�[�i�����g�j���s�T�t�����E�݁t�̔��ɂ悭�����p��
�Ƒ��܂��āA�����Ȍ��ʂ������Ă���B���������ɐD�F�̕z���\���Ƃ����̂͗������̂��錤�����ӂ��ŁA�Z�̂ł����Ă��n��W�Ƃ��Ă͒n�������A������
�͕\���̕��ɐ��������Ŕ��������Čy�₩�Ɏd�グ
�Ă���B���ꂪ���傩�u���@�̃����v�v�̂悤�Ɍ�����̂��ʔ����B
�@�@�����Ɏ��ЂȂ炳�ꂵ鱏�m���Ёn���ւ����̂̎���ڂӂ����ӂ�������i�q�����g�t�r�j

�s���m��ʒ��Łt�i�v���ЁA1983�N11��1���j�͔ѓc�P���̑�O���W�B�ѓc�ɂ͂ق��Ɂs�i���V�[�̊Z�t�i����R�c�A1979�j�A�s�~�Ղ̌܌��t�i���A1982�j�A�s�l�~�ɂāt�i�s�����@�A1998�j�A�sGahlway�̏������t�i�v���ЁA2001�j�ƁA�S����5���̎��W������B�{���͏����̑�\��ŁA�q������ʒ��Łr�ȂǑS31�т����߂�i�ڎ��̍Ō�̍s�ɔѓc�̎��тƓ��������Łu���ꁁ�g�����v�Ƃ���j�B6��83�s�́q�V�ƒn�\�\�y���F�Ɂr��ǂ����݂ň��p���悤�B�i�@�j�̎g�����ƁA�k�����q�̂���ɂ������ꕶ���ʼn��s���Ă������@�i�Ƃ�킯�Ō�̐߂Ɍ����j���ڂ������B
�i�V�j�̂Ȃ��ɂ͐l�Ԃƒ�̔�������������^�i�n�j�̂Ȃ��ɂ͎����Ɣ�т���̉�������^�������Ɂ^�ЂƂ́^�i���@�@�ǁj�^�F��̓��̊K�i�͂˂ɗp�ӂ���Ă���^�^
�ނ����̖ϑz�͕��ʂ̊��m�ł������^�_�̐v�}�ɂǂ�ȖϔO���y�Ȃ��^�i�c�Ȃ��ꂤ�鎩�R�ȋ�ԁj�^�Ƃ����^�i�v�z�j���^�Ƃ����^�킷��^�����Ɂ^�ȁ^��^�i�c�ȁj���ꂤ��Ƃ����^�i�v�z�j�ɂȂ����G�ӂ��^�������^�^
���݂��^���Ɂ^�Ȃ����^�������^���^�́^�i�c�Ȃ��ꂤ���ԁj�^�Ƃ����^�i�v�z�j�Ɂ^���R���^�Â��^���̂��^���^�^
���܂́^����Ɂ^������g���^�����Ă���^�́^���^�^
�i�N���Ă䂭���̎��R�j�^�Ƃ����^�v�z���^��^�i�F��̌`�Ƃ��Ă̂������̓��̌��z�j�^�܂ł́^�����́^�����ā^�Ƃ����^�ȁ^���^�^
�i�����Ȑv�}�j�^����^���E�^���^�n���Ȃ��������Ƃ��^���݁^�́^���݁^���^�F�邱�Ƃ���F�����^���ꂩ��^���̂Ƃ��^���^��^�i�F��̌`�Ƃ��Ă̓��j�^�Ɓ^�i��e�����ԁj�^�́^���^�ȁ^��^���^�ȁ^�i���R�j�^�Ɓ^���^���^�i�����j�^�ց^�D�����^�C�����^�����Ɂ^�������^��
�ѓc�ɂ͂ق��Ɂq�������̓V�\�\���Z��N�H�@�̃o���L�_�C�g�E�J���̓y���F�Ɂr�i�s�l�~�ɂāt�̊������сj������i�u�o���L�_�C�g�E�J���v�́u���]�哥�Ӂv���j�B�g���ɂ͐�Ɂq�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�Ƃ����y���F�̔�V�Ɋ����т����邵�A�s���m��ʒ��Łt�̐܍��ɕ����Ă���ѓ��k��ɂ́s���̊쌀�m�R���f�B�n�t�i�v���ЁA1988�N7��15���j�����̒Ǔ����q�m���̔����\�\�y���F�̂��Ɓr������i���������g���ɓy�����������킹���̂��A�ѓ����̐l�������j�B�ѓc�Ɠy���̌�V���ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ����A��l���F�V���F��r�c�����v�A�ѓ���g�����������������m�T�[�N���n�ɑ����Ă������Ƃ͊m���ł���B
 �@
�@
�ѓc�P�����W�s���m��ʒ��Łt�i�v���ЁA1983�N11��1���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ����k�����Łl�i�v���ЁA1985�N4��1���j�k����200���A�A���J�b�g�i�A���I�[�v���h�j���E�y�[�p�[�i�C�t�t�A�ʐF�C�j�V�����J�b�g���A�i���o�[���ʍ��I���W�i�����ʼn�1�t�A�v�w���l�i�E�j
�{���̎d�l�́A��Z�Z�~���܃~�����[�g���i�r���͒n�܂����ϒf�����Ă���k�܂�A���I�[�v���h�ł͂Ȃ��l���A�V�ƑO�����̓A���J�b�g�ŁA�y�[�W���J��̂ɂ킸�������R����^���邱�̎d�l�͂͂����ċg���̔��Ă��낤���j�E��Z��y�[�W�E�����E�W���P�b�g�E�\���B�܍��̎��M�҂͓c������E�ҖM���E�ѓ��k��E�a��F��E���ÕׁB���t�̊��s���ł͏{���قǑ����g���́s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j�̃T�C�Y�i��l�܁~�ꎵ�O�~�����[�g���j������傫�������悤�Ȕ��^�ł���B�������{���̔��^�����߂��̂��g���Ƃ���̂͑��v���낤�B�܂��s��ʁt�̔��^���m�肵�������̕��������͂����B���̗����ƑO�N���s�̔ѓc�̑�W�s�~�Ղ̌܌��t�i����R�c�A1982�N7��10���j�̖{���p���̃T�C�Y�W�͎��̂悤�ɂȂ�i���@��mm�j�B
�c �� �c�^�� �~�Ղ̌܌� 226 173 1.31 ��� 245 173 1.42 ���m��ʒ��� 260 195 1.33
��ɂȂ�قǃT�C�Y�͑傫���Ȃ�A�ѓc�̎��W�͋g���̎��W�����u���l�܂�v���B�s�~�Ղ̌܌��t�͔ѓc�̎����ł���A���̎��W�����̎��W�s���m��ʒ��Łt�ɉe���������낤���Ƃ́A���^�����肵���̂��ѓc�ł���g���ł���i���邢�͏o�ŎЃT�C�h�ł���j�A�傢�ɂ��肦��B
�k�NjL�l
�s���m��ʒ��Łt�͊��s��܂��Ȃ��A�v���Ђ̊̂���ŏo�ŋL�O��J���ꂽ�悤���B�Ƃ����̂��A�q�Ï������� | catalogue ��26�� ��� �Ï��̎s�r��
73 �v���Ј� �o���t��75�t�ꊇ
�ѓc�P�����W�w���m��ʍ��Łx�̏o�ŋL�O��p�@1983�N������@�ȉ��͏����������M�Ŏ�Ȃ��́E() ���̓��b�Z�[�W�s�� �G�����O(5)�A���J�Y��(6)�A�剪�M(9)�A����F��(2)�A����S���A�g�����A�҈䋪�A���c���A�k�����Y(5)�A����M�v(2)�A�ѓ��k��(3)�A�g�������A����N�v�A���J�K�Y�k�}�}�l(2)�A���c�ɗY(3)�A�l�c�m��(4)�A�����㕺�q(4)�A�����o��(5)�A�H�R�S�����q�A�����^��k�}�}�l�A�����A���c�؏G�Y(4)�Aꠕ��F�@��
SOLD OUT
���o�i����Ă������炾�B�s���{�̌Ö{���t�Ō�������ƁA�ѓc�P�����Ă̏����{�i�g���̒����ł́s�Ẳ��t��s�|�[���E�N���[�̐H��t�s�̖{�j���Ï��Ƃ��ďo�Ă���A���̏o���t��75�t���A�����ƂȂ����o�ŎЂ��������Ĕѓc�ɓn�������̂��Ȃ�炩�̎���ŗ��o�������̂��B�g���̗t���͎ʐ^��i�̉E����2�Ԃ߂����A��̒��L�ɂ��Ώ��������Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ŁA�c�O���B�g�����ѓc���Ɍ��y�������͂��Ȃ������ɁA�s���m��ʒ��Łt�̊��z�͓ǂ�ł݂��������B
���ĐΊ_��W�s�\�D�Ȃǁt�i�v���ЁA1968�N12��25���j�̑������Љ���Ƃ��ɁA�s�₳�������t�t�i�Ԑ_�ЁA1984�N4��21���j�́q���Ƃ����r�����������A����͂��́s�₳�������t�t�����悤�B�g�������o�ꂷ�銪���̎��сq�勴�Ƃ����Ƃ���r��ǂ����݂ň����B
�� ���́@���Ԃ�����^�g��������̏Z�ލ���́^�������肩�Ǝv����B�^�^���a���N�^�ʐ�d�Ԃ��a�J�����������ā^�����s���Ɓ^�E��ɘA���Ȃǂ��������^ ����@�ڍ���̉͌��Ɂ@�q�ꂠ��^�c�N����@���͘A����Đ܁X���Ƃ��ꂽ�B�^�^�������������̕@�ʂ����߂��@�ʂ�ʂ��^�x�O�d�Ԃ̈������ݐ����܂����^ �q���̖��^�����q����T�q�����ƗV�B�^�^����͂�����炭����^��l�����@�ЂƂ����܂�ɂȂ��ā^�܂��̌����̖�����@�˂���^�u�̔ޕ� �@�ڎw�����B�^���͌�ɏ]�����^���̉����B�^�^���ꂪ���̍s����^�����ւ̕��p�ł������Ƃ́B�^��l�����̖ړI�����͊o���Ă���^�����������ɍs�����̂� ���^�������Ł@���̐l���M�������B�^�^���܂͂����m�^��U�������U�蕪�����@�Z��̖��W�n�с^���̌�����^�쌴�̌������֍s���������^�ƂڂƂڕ����Ă� ��͂����Ȃ��B�^�^�����́@�������^�勴���B
�s�₳�������t�t�́q�勴�Ƃ����Ƃ���r��q���]�\�\���R���������W�r�i�g�������M�N���œ��W�ɐG��Ă���j���܂ޑS39�т����߂�B�Ȃ��Łq�o �ρr�̏��o�L�^�ɂ�������̂����ڂ����B
�@�o�ρ@��㎵��N��@�n���S�u�_�{�O�w�v�ǖʂɌf���^�s���Z�N��֊X�����̎��݁t
�n���S�u�_�{�O�w�v�͐������́u�����_�{�O�w�v�Ƃ���ׂ������A�s���Z�N��֊X�����̎��݁t�Ƃ����\�L���C�ɂȂ�B�q�o�ρr���Ę^�������̃A���\��
�W�[�s�n���S�̃I���t�F�t�i�I�[�f�X�N�A1981�N4���k���t�L�ڂȂ��l�j�ɂ��A�����ɎQ�������g�������q��r�i�H�E21�j�����߂��s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j�́q���o�ꗗ�r�ɂ��A�P�Ɂs�X�����̎��݁t�Ƃ��邩�炾�B���т��n���S�u�����_�{�O�w�v�ǖʂɌf������Ă�
���Ԃ̎ʐ^�̒T�����܂߂āA�����ꂱ�̂�����̂��Ƃ��ڂ������ׂ����i�g���́u�����v�A�Ί_�́u��O���v�ŁA�����Ɍf������Ă����킯�ł͂Ȃ��j�B
�{���̎d�l�́A��Z���~��l���~�����[�g���E����y�[�W�E�㐻�p���\���i���E���A�w�E�z�j�E�@�B���B���̎����A�g���́u�s��ʁt�d�l�v�Ƃł��ĂԂׂ���
���X�^�C�����m�����āA�{���������b�q���W�s�ԉt�i��
��R�c�A1983�N4��25���j�ɓK�p���Ă���B��̓I�ɂ́A������̃{�[�������@�B���ɗp���āi�s�₳�������t�t�́s��ʁt�Ɠ������Еt���j�A�����⒘
�Җ��E�o�ŎЖ��A�J�b�g�A�艿�E�h�r�a�m�R�[�h���X�~�ō������F���ɑ��ӓ\�肵�A�{�̂Ɍp���\���i�����͕������Ŕw���z�A�g���̎��W�ł́s�Ẳ��t��
���j���̗p�����㐻�{�Ƃ����\���ł���B�t�����X���i�{�������\�y�[�W�K�́j�ƕ���ŁA�u�s��ʁt�d�l�v�����g�������������B���������ɂ�����X�^��
�_�[�h�Ƃ����悤�B

�Ί_��W�s�₳�������t�t�i�Ԑ_�ЁA1984�N4��21���j�̔��ƕ\��
������b�q���W�s�ԉt�i����R�c�A1983�N4��25���j�́u���{�����ő����͎l���e�O�S���\�ܕ����ꂽ�v�i���t�̖����j�Ƃ���悤�ɁA�\����4��ނ̈قȂ�F�ƕ��́A��㎆�ӂ��̎���p���Ă���B���^���т́q�ԉr�q���̏�r�q�s�l�`�̉Ɓt�̂��߂̃m�[�g�r�q���₩�Ȗ����݁r�q�~�̓��L�r�q�L�̂������̖��H�̊X�Łr�q�ԉr��7�тŁA�U���\�L�̍�i���قƂ�ǂł���B
�q���������r�̂��Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ׂ��R�C����̖��{�Ɛ��@�Ɏ�肩���܂ꂽ�t�̓����̓����Ƃ������˂��ݐF�̉e���A�����̌����J�̂悤�ɂ���ƈ������ğ��݂Ƃ���z�����܂��q���̑@�ۂ̑��r�������Ă���B�����ׂ����������͂��ꂽ�h��铵�ƌX�����i�����܂������ӂ��ꂠ���錌�ǂł���킻���ƁA���͕K�����j�́q�\�����Ȃ������r�Ɂq�h������I�r�_�炩�ȖтƏ_��ȁi���A�ׂČ������A���j�ؓ��̑��B�i�q���̏�r�́u10�@���̏�̓����v�j
�q�s�l�`�̉Ɓt�̂��߂̃m�[�g�r�ɂ́A�莫�Ƃ���
�i���ۑ����\�Ȃ��
�܂䂭�J��
�U��s���ʂ̂Ȃ���
�Ƃ����q�Â��ȉƁr�i�E�E16�j�̎��傪������Ă���B�g���̑莫�Ɠ���N�v�̑ѕ��u�����ɂ��s���t�炵���Ȃ����ł��镪�����A���͂����̎��т��P���̂�����B�����������́A�����̖��₩�Ȗ��x�ɔ��Έȏ�g���䂾�˂����Ă��҂����Ɉ��Ăď����ꂽ�D�����D�������ӂ̉S�A���Ȃ͂����A����邱�Ƃ̂Ȃ����̉S�Ȃ̂�����v����ƁA�{���͂��Ȃ���u�̂̕ʂ�v�ł���B���ہA����́s�}�_���E�W���W���̉Ɓt�i�v���ЁA1971�j�A�s������b�q���W�k���㎍����55�l�t�i���A1973�j�A�s�t�̉�̊فt�i���A1973�j�A�����Ė{���̂��Ƃ́A�����܂Ŏ��W�����s���Ă��Ȃ��B
�{���̎d�l�́A��ꔪ�~����~�����[�g���E�㔪�y�[�W�E�㐻�p���\���i���E���A�w�E�z�j�E�@�B���B���t�ɂ́u����g�����v�A�����āu����H����������{�R�{���{���������z���퐻�쏊�v�Ƃ���B�����̐����Ђ́A�{���̔��N��Ɋ��s���ꂽ�g�������̎��W�s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j�Ƃ܂����������z�w�ł���A�@�B���i�s�ԉt�Ɓs��ʁt�͓����f�ނ����A�O�҂̓z�`�L�X���߂ŁA��҂͌Еt���j�ɓ\����ӁA�����̌p���\���A�ƂقƂ�Ǔ���̑����R���Z�v�g�Ȃ���A�s�ԉt���s��ʁt�̃~�j�`���A���\�s���K�̂悤�Ɍ����Ă��܂��̂͂�����Ƃ����������B���������̖{���́A�s��ʁt���������Ȕ��^�ɂ�������炸�A���ʂ����Ă��܂��Ă���悤�ɂ���������B

������b�q���W�s�ԉt�i����R�c�A1983�N4��25���j�̖{��
�k2020�N4��30���NjL�l
�����őz���ɂ���A�\���̎��̕���4��ނ���̂́A�����҂ł���g���������҂ł��������b�q�Ɍ��{�Ƃ��Ē���4�킪�Ȃ�炩�̎���łЂƂɌ��߂��Ȃ��������߂ł͂Ȃ����B���Ƃ��A��1500�����܂��Ȃ������̐��ɑ���Ȃ������A�Ƃ��B���҂��ЂƂɍi�肫�ꂸ�A�������̂��Ƃ��ׂĂ̈Ă��g���Ă��܂��A�Ƃ��B���̂Ƃ��A��ɋL�����{���̕s���肳���u�l���e�O�S���\�ܕ����ꂽ�v���Ƃ����e�����̂ł͂Ȃ��������i���Ȃ킿�A���̃M�~�b�N�Ƃ��āj�B���͖{�����A�������ɐ����S�ݓX�r�ܓX�̂ς낤��Ō������A�q�v�m�V�X���A�[�g���[�N����|�������b�h�E�c�F�b�y�����́sIn Through the Out Door�t�\�\1979�N8�������̃A�i���O�Ղ̃A���o���W���P�b�g��6��ނ����āA�N���t�g���̊O�܂���o���܂łǂ̃W���P�b�g��������Ȃ��d�g�݂������\�\���Ⴀ��܂����A4��ނ�����̂͂Ȃ����낤�A�ƕs�R�Ɋ��������̂��i���ǁA���̂Ƃ��͐̊O����I��ōw�������j�B�g���͂��̔��Ȃɗ����ās��ʁt�̖{���̃��C�A�E�g�ƕ\���̑f�ނ��ᖡ�����̂ł͂Ȃ��������B
 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@

������b�q���W�s�ԉt�i����R�c�A1983�N4��25���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�\���i����2�_�j�Ɠ��E�I�[�N�V�����ɏo�i���ꂽ�l���i�E�j�k�Ƒ��{�͍���ƉE��ƉE���̕��̂��́B�Ȃ��A��������}���ُ����{�͍����̕��̂��́l
�ےJ�ˈ�s���̉́t�i�������X�A1987�N8��15���j�́A�s�݂݂Â��̖��t�i�������_�ЁA1985�j�ɑ����ē�x�߂̋g���������̊ےJ�]�_�ƂȂ����B�g���͏��Y���P�E��������Ƃ̓C�k�q��b���Șc�݂̖��́r�ŁA���Y����u�����̂��d���̂ق��͂������ł����B�l���c���F�̒��㌒���_�̑����͂ƂĂ��悩�����ł��ˁv�Ɛu�˂��āA�u����͂����J�b�g���I�ׂ��̂ˁB���ꂩ��ےJ�ˈꂳ��́w���̉́x�Ƃ��A���N�͂��Ƒ����̎d���������ĂˁB���ꂩ��E���K���b�e�B�̑S���W�������ł���B�w�y���F��x�����āA���ǖl���������邱�ƂɂȂ����Ⴄ�킯�����B������A���N�͂ǂ���珬�����ɂ͍���Ȃ��i�j�B���N�͂��������d�����Ȃ��āA�Ɠ����珬������������Ă������ǂˁi�j�v�i�s�����C�J�t1987�N11�����A��Z��y�[�W�j�Ɠ������B�����Œ�����A�u�l���c���F�̒��㌒���_�v���s�M��Ɠ]���t�i�V���ЁA1987�j�A�u�E���K���b�e�B�̑S���W�v�͉͓��p�����s�E���K���b�e�B�S���W�t�i�}�����[�A1988�j�̂��ƁB�u�����J�b�g���I�ׂ��v�Ƃ����̂́A�g�����ҏW�S���������s�����܁t69���i1975�N1���j�̐���ׁq��x�]�b�r�Ɖ~�q�C���q�P���[�j�C�́w�Ñ㏬���x�r�̃J�b�g�𗬗p�������Ƃ��w�����A�s���̉́t�̃J�b�g�̓N���W�b�g���Ȃ��B�������X�̊��s���ŋg������������|�����͖̂{�������ŁA�����炭���҂���u�����͋g�����Łv�Ƃ����v�]���������̂ł͂���܂����B�q���Ƃ����r�ɋ���s���̉́t�̕ҏW�S���͋���3���ɖS���Ȃ������c���ł���B�g���Ƃ́s���Y�t��s�C���t�Őړ_�����肻���Ȃ��̂����A�g���̐��z�Ɏ��c�͓o�ꂵ�Ȃ��B�{���̎d�l�́A�ꔪ���~���܃~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B�g���������̑�\��ɐ����Ă����{���́A�s���b�U�Ƃ͉����t�i�u�k�ЁA1984�j��3�N��Ɋ��s����A�O������Ȃ�B
�@�T�^��ؐ����Ƌߑ�j��
�@�U�^���y�Ɗ����̂��߂Ɂ��^���w�̌����Ƃ͉�����
�@�V�^����ٔ������̓nj�Ɂ^���O�̋����̂��ƂȂǁ^�������i����F���̉́j�^��̊��^�����h�q�Ɠ���j�g��
�����t����4�т́s�ŋ��͒��b�U�k�ےJ�ˈ��]�W��3���l�t�i���Y�t�H�A1995�j�Ɏ��߂�ꂽ�B���������̐��ː�Ҏ��i1948-99�j�ƊےJ�̑Βk�q�w�ŋ��͒��b���x���߂����ā\�\��]�̕��@�Ə����̕��@�r�͌�肨�낵�ł���B���̑Βk�̐l�I�́A�ےJ�����ː�ɂ��s���̉́t�Ɓs���b�U�Ƃ͉����t�̕]�q���Â̍Ղ�r�i�s���z�̌����t�A���쏑�[�A1993�j�𑽂Ƃ�������ɈႢ�Ȃ��B
�@ �w���{���w�j���킩��x�ɂ��Ă��A�w���b�U�Ƃ͉����x�ɂ��Ă��A�l�ւ����ď����Ă�邠�Ђ��A�킽���͏[���������X�𑗂邱�Ƃ��ł����B���ꂪ�����ƌ���]�Ƃ̍K���ŁA�킽���͂��̍K���ɖ������Ă��B�킽���͂��̎�̕]�_���Ƃ��ǂ������Ȃ���A�����̍�i�����ʂ̓ǎ҂̊��ɍ�p���A���̉�H�ɂ�ĕ����̐��i�����߂邱�Ƃ݂����ł����̂ł���B�Ђ�Ƃ���Ƃ��̓ǎ҂����ɂȂ��ɂ́A�₪�Ęa�̂�̕��ꂪ���̊w�҂ɂȂ鏭�N��������邩������Ȃ��B�i�q���w�̌����Ƃ͉����r�A�{���A���O�y�[�W�j

�ےJ�ˈ�s���̉́t�i�������X�A1987�N8��15���j�̖{���ƃW���P�b�g
����N�v�͐��e���O�Y�ɂ��āA���g�̎��W�s�Â��y�n�t�i���R���A1961�N10��15���j�������āA���̂悤�Ɍ���Ă���B�u�k�c�c�l�ڂ����ꏊ�����ǂ�ŁA�����炭�e�����Ă���̂́w����ꂽ���x�ł��ˁB����ɂ͐��������b�ɂȂ����悤�ȋC�����܂��B�ڂ��̎��W�ŋ�̓I�ɂ͂����萼�e����̉e�����o�Ă���̂́w�Â��y�n�x�ŁA�ӎ��I�ȃp���f�B��������ǁA�ނ���N������đ~���ꂽ���Ă�������������܂��B�w����ꂽ���x�ł͂���ȃG�s�\�[�h������������A���ƂȂ��^�C�ɂȂ����悤�ȋC���������������ł��v�i�g�����E�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�q��ނȂ����I���݁\�\���e���O�Y�Ǔ����k��r�A�s���㎍�蒟�t1982�N7�����A�O���y�[�W�j�B
�s����ꂽ���t�̃G�s�\�[�h�����́q����ꂽ���r�ŕ₤�ƁA1960�N���̂�����A�}�����[�̎Ј��Ƃ��Đ��e�@��q�˂����Ζʂ̓���ɏ�@���̐��e�͂��낢��b�������B�u�k�c�c�l�b��̓l�����@���̃I�[�����A����G���I�b�g�̍r�n��W���C�X�̃t�B�l�K���Y�E�E�G�C�N��G�s�t�@�j�A�ցA����ɂ̓_���e�̒n����t�����`�F�X�R�E�R�����i�̃q���v�l���g�}�L�A�ւƔ��W�����B���ɐ��̃e�[�}�A����������������̃e�[�}���A�b�̂��Ď��ɂȂ��Ă��v�āA�b�͏ꏊ���ڂ����������ł��������B�u���͎����̋C�������Ȃ��炸�V�g���Ă���̂������Ȃ���A�r�ɂ����B�݂��݂��A�悵�A���̐��̃e�[�}�A����������̃e�[�}�Œ�������������������B�������������͂��߂āA��J�����炢�����Ă���Ă݂悤�A�Ȃǂƍl���Ă����B�^����ǂ��A���̒����͂Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ɏ��炸�A�f�ГI�ȃ������������ł��������ŁA���X���������B���e�@��K���Ĉ�J�����肽�����Ƃ��A���܂��܁A���X�Ŏ��̎G�����߂����Ă��āA�����Ǝ��͐����o�����B���e�搶�́u���v�Ƃ��������ڂ��Ă����̂��B�k�c�c�l���R�A���̒����͗��Y�ɏI��A���������̒f�Ђ́A���̂̂��ɏ������������̎��̒��֎l�U���čs�����v�i�s��{ ���e���O�Y�S�W�k��11���l�t����A�}�����[�A1994�N10��20���k���f1973�N1���l�A�Z�`���y�[�W�j�B������i�q���j�r�̍ŏ��̐߂�ǂ����݂ň������B
�ގ��͑��̗ގ��ށ^�ޏ����̂Ă悤�Ƃ���̂͂ЂƂɂ���̎�q�ł���^�ޏ��̎��̉e�͍��ꂽ���Ƌ��ɂЂ낪��^�����ā@�y���Ƌ��ɑ|���悹����^�ޏ��̓��͖̂��Ɂ@���₫�̖̂悤�ɂ͂���ɂ���^�A�ė���̂̐l�X�̂��߂̖ڕW�Ƃ����^���Ԃ̒n�w���瓐�ݏo���ꂽ�j�̉������^�ޏ��̖���@���G�ЂƂȂ�^�������ȋL�����@�ޏ����Â��J���^�̂悤�Ɍ��点��^���̂������������̂悤�ɔ�ь��Ă���^�ޏ��̍�
�{���̎d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���E����y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���B����300���B�ڎ��̍Ō���Ɂu���{�v�Ƃ��āu�J�b�g�@�����^�\���@�g�����v�Ɠ�s�ɂ킽���ăN���W�b�g����Ă���B�s�Â��y�n�t�͋g���������t�����X�����W�̌n��ɂ����āA�g�����s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̐����i�l�Z���j���Đ����i�`�T���j�ƂȂ��Ă���B�̂����s�a���`�t�i����ɁA1962�j�Ɠ߉ϑ��Y���W�s���y�t�i�v���ЁA1965�j�����E�͂قڂ`�T�������i��l���~�����[�g���O��j�A�㉺����Z�Z�~�����[�g�����̂`�T���V�n��̕ό^�Ȃ̂́A�{���W�̐����d�オ����Ȏ@�������ʂ��낤���B

����N�v���W�s�Â��y�n�t�i���R���A1961�N10��15���j�̔��ƕ\��
�ɗǔg���j���W�s���b�N�����[���t�i��o�ŁA1981�N2��20���j������сq���A�r�������B
���͖����B
���Â����L��Ԃ��ǂ��܂ł��ǂ��܂ł�䩁X�ƍL����A�n��́A���y�̓����̂悤�ɗH���Ɏ����A��O�ɁA�ꖳ�������肪�݂����B���͖����A�ƌ����̂ɁA�s�v �c���s�v�c�B�ꖳ��������ɁA��X�ƋP���������f���o����č݂����B�����甲���o��������l�̉����A��̂̉����ɂ݂��Ă����B
�����o�������A��̂̉����ɂ݂��Ă���ƁA�l�����̂��̕�̂́A���Â�������Ɋ����𗬂��āA���錩�邤���ɗn�����A�قǂȂ����ł����B
�����o���l�����̉��́A��̂̉��̏��ł��Ŋ��̍Ŋ��܂Ō��ɂ߂�ƁA���x�́A�ዅ�����̕��̂Ƀw���Q���āA��̂̉��̂��Ȃ����y�̈ł��A���܂ł��A���� �܂ł��ɂ݂��Ă����B
�� �����Ⴆ�Ⴆ�Ɵ��݂킽��悤�ȍ�i�����A����Łq���̉e�r�̂��Ƃ����I�Ɣ����M���̂悤�ɉ����悹��U����������B�q���Ƃ����r�ɂ͖��v�ւ̎ӎ��� ������̂́A�g�����ւ̌��y�͂Ȃ��B�g���ɑ������˗������͔̂��s�l�̔��Ă�������Ȃ��i�����y�[�W�̉��t�Ɂu����g�����v�ƋL����Ă���j�B�{���̎d�l �́A��ꎵ�~��O�l�~�����[�g���E��Z���y�[�W�E�㐻�z���E�@�B���B�\���̕z���͐F�Ƃ������G�Ƃ����A���e���O�Y���W�s�l�ށt�i�}�����[�A1979�j��f�i������i�����Ƃ��p�w�A���Ԃ��������n�j�~���[�Y�R�b�g ���ŁA�Ӑ}�I�Ɏ��������̂��j�B�s�T�t�����E�݁t�Ɠ��H�̔��ɂ́A��ւ�係̃J�b�g���ؔʼn�̂悤�ȏd���ȕ������œʔň������Ă���B
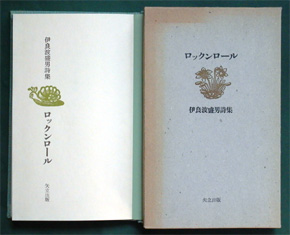
�ɗǔg���j���W�s���b�N�����[���t�i��o�ŁA1981�N2��20���j�̖{���Ɣ�
�k�t�L�l
��o�łƂ����s���ޒʐM�t���B��ˎ闝�s�g�����̏ё��t�i�W���v�����A2004�j�́q���Ƃ����r�Ɂu�u���l�̏ё��@�g�����v�́A��o�ŎЎ�A���
�k�}�}�l�v���̗U�����A����̂���ŏ����n�߂����M���������A�v�������Ȃ������������āA�\�z��蒷���Â����ƂɂȂ����v�i�����A��ܔ��`��܋�
�y�[�W�j�Ƃ���B�A�ڑ�1���11���i1994�N3���j�ɂ́q�g�����r�̗\�����o�Ă���B
�@�@��ˎ闝���ҏW���^���b�N�E�����q�N���r
�@�@�g�������@�@�����@section rural �P�@�V���@\1500�^�g������̏���25�ł͕K�ǁ@��\310
�@�@�g���@���@�@�����@section rural �Q�@�@�@�~���s
���b�N��1994�N2��22���Ɂq�g�������r���o������̂悤���B��L�Ɠ��l�̗\����12����19���ɂ��o�Ă��邩��A���̌�Ȃ�炩�̎���Ŗ����ɏI
��������̂��B�s���� section
rural�t�͑S�я������낵��搂��Ă��������ɁA��ˎ闝���ҏW�́q�g�����r�����̊��Ɖ������̂͐ɂ��܂��B
�g�����͋Ζ���̒}�����[�i1951�N���ЁA1978�N�ގЁj�Ŏ�ɍL��������݁A�V���Ɍf�ڂ��鏑�ЍL���u�O���v�̎���Ƃ��Ă��̐��E�Œm��ʎ҂̂Ȃ����݂��������A���ЍL����������������ꂪ�ڂɂ��邱�Ƃ̂ł���g���̈₵���d���́A�傫���ӂ�����B�ЂƂ͏��Ђ̑��{�E�����ł���A�����ЂƂ͂o�q���s�����܁t�̕ҏW�ł���B���������Б�����1952�N����S���Ȃ�O�N1989�N�܂ł́A�ގЌ���܂�37�N�ɋy�Ԃ̂ɑ��āA�s�����܁t��ҏW�������Ԃ�1971�N1������1978�N7���܂ł�7�N���A�܂葕���̖�5����1�ƌ����Ē����Ƃ͌����Ȃ����̂́A�ݎЊ���27�N���ł̔�d�͂���Ȃ�ɑ傫���B���Ȃ݂Ɂs�����܁t�́u���V�ȕ��͂Ə��Ђ̊��s�ē����ڂ����Ǐ��Ƃ̂��߂̌������v�i�����A��112���k������1���l�A1980�N7��1���j�ŁA�g���́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t��2�x�A�s�����܁t�Ɍ��y���Ă���B�q�剪�M�E�l�̒f�́r�́u�R�v�i���o�F�s�剪�M����W�t��14������i�y�ЁA1978�N3��31���j�́q�剪�M�E��̒f�́r�j�Ɓq���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u11�@�⌾���v�i���o�F�s�V���t1982�N8�����́q���e���O�Y�A���x�X�N�i�Ǔ��j�r�j�ł���B��҂͒}���ގЌ�̕��͂Ȃ̂ŁA�O�҂����悤�B
�@ �����o�q�G���q�����܁r�̕ҏW�ɁA����������āA���A���N�ɂȂ邾�낤���B�Ȃɂ���`�T���O�\��ł̏����q�ł��邩��A�Ƃ��ɕҏW���j���Ȃ��A��A�O�l�̐M���ł���Ⴂ�ҏW�҂̏������Ƃ����A���Ƃ͎��̓ƒf�ŁA��l�ŋC�܂܂ɂ���Ă���B�����玞�X�A�F�l��m�ȂɎ��M���˗����邱�Ƃ�����B����Ȃ̂ɁA�Ȃ�����Ԑe�����剪�M�ɁA���e�������Ă���Ƃ͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B�ނƉ���ĎG�k�����Ă��邤���ɁA���܂�ɂ����Z�Ȃ��Ƃ��킩���Ă��܂����炾�����B
�@������A���e�������Ă����悤�Ɍ�������A�ނ͂��ꂵ�����Ɂu�������ĖႤ��v�Ƃ̕Ԏ��ɁA���͂ق��Ƃ����B
�@���a�\�N�܌����́q�����܁r�̊������������A�剪�M�̃G�b�Z�C�́u�܉Y�s�v�������B���͈�ǂ��āA�f���������͂ɕҏW�҂Ƃ��Ċ��������B�����ɂ��̂悤�Ȉ�߂�����B�@�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@�剪�M�́u�܉Y�s�v�̌��e��n���Ȃ���A���ɂ����������B�u�܂��܂��ڂ�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��V�S�̉p���_�����������A���܂��S�̂̍\�z�͏o���Ă��Ȃ��v�ƁB�܂����̂悤�Ȃ��Ƃ��������悤�Ɏv���B�u���́u�܉Y�s�v�����������Ƃɂ���āA�Ƃ������肪�ł��A�ЂƂ̓����������v�Ƃ��B
�@�k�c�c�l�i�����A�}�����[�A1988�A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
�s�����܁t��1969�N5���n���A����ҏW�ҁE�y��ꐳ��1�N8�����Ԋ��s�̂��ƁA�ҏW���g���Ƀo�g���^�b�`�����B��20���i1970�N12���j�́q�ҏW�����r�Ɂu�n�����ȗ��\���͒������ق�A�J�b�g�͍��؏����S�����Ă��܂��B�ҏW�҂͈ꌎ������܂��B�ҏW���j�ɕς�͂���܂��A�S���҂����ƁA�����q�Ȃ�ɁA��͂�����ȕω���������Ă���Ǝv���܂��B�䈤�ǂƂƂ��Ɍ䒉�����܂��悤���肢�������܂��v�i�����A���y�[�W�j�Ƃ���A���������21���i1971�N1���j�ɂ́u�O���ł��m�点�������܂����悤�ɁA�V�t�����ҏW�S�����ւ�܂����B�O�C�̓y��ꐳ���̘J�𑽂Ƃ��A�����̕ҏW�Ӑ}�����p���Ȃ���A�������ʎ�鏬���q�ɂ������Ǝv���܂��v�i�����A�O��y�[�W�j�Ƃ���B�ǂ���������͂Ȃ����A�M���������̂͑O�҂��y��A��҂��g�����낤�B�q�s�����܁t�ҏW�ҁE�g�����r�ɏ��������A�g���ҏW�����̖{���ɂ͒ʏ�A�ҏW��L���Ȃ��i�y��ꐳ����ɂ́A�ǎ҂̔������܂Ƃ߂��q�ǎ҂���r�ƕҏW��L�q�ҏW������r���قڏ�݂���Ă����j�B�g������́s�����܁t�̐��i�𖾂炩�ɂ��鎑���Ƃ��āA�̋L���i����т��̕W����L�����ڎ��j�ɗD����̂͂Ȃ��̂��B����͋g�������ҏW��C�Ƃ��ĒS�������S91���́s�����܁t�i1971�N1������21������1978�N7������111���܂Łj�̖ڎ����A��L�E��A�Ǝv������̂����������i����������A��21���́q�����̃��_���}���فr�͖{���̕W��q�����̃��_�������فr����������́j�A���̂܂܌f����B�����őg�ŏ�̑̍ق��q�ׂ�A�ڎ��͕\���S�ɉ��g�A���]���G�Łu�W�薼�v�A�A�L�̓i�����L�A�K�]���G�Łu���M�Җ��v�i�����̊ԂɎ��A�L�̂�����̂���ϑ��I�ɂ��邪�A�x�^�ɂ����j�\�\�u�m���u���v�i�ȗ������j���f�ڂ���Ă���B�����͋������܂߂ĉ\�Ȃ������{�̌`�������������A�A�ډ�\�킷�̊������͑S�p�ɑւ����B�e�s�ɂ͎����Ŕԍ���t���A�W�薼�Ǝ��M�Җ��̊Ԃ��{�ɂ͂Ȃ��R���}�i,�j�ŋ�����̂ŁA�f�[�^��\�v�Z�\�t�g�ɓǂݍ���ŕ��ׂ�����Εʂ̖ʂ������Ă��悤�B���̖ڎ��ꗗ��f�ނƂ��ė��p���A���낢�남�����������������B���Ƃ��ẮA�g�����ҏW�́s�����܁t�ɓo�ꂵ������436�l�ɋy�Ԏ��M�҂��}������o�������Ђ̃��X�g���A�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�j��NDL-OPAC�Əƍ����Ȃ���쐬�������B�������́A�g���̎Г�������i��T�����邽�߂̒����p�c�[���ł���B�\�\�������܂ޒ�������������}���قɏ�������Ă��Ȃ����M�҂�������A�H�R�_���i�É��s���邪���H�[��l�j�E�r�c����i�~����E���o�Ɓj�E�C�V�u�i���c�@�l�����ٖ������w�|���j�E���c����i��t�j�E�ؓc�V���Y�Ȃǂ̏���������B�Ȃ��i�@�j���͎��M���̌������B
�g�����ҏW�s�����܁t�S91���ڎ��ւ̃����N�i�����͒ʍ��j
21�@22�@23�@24�@25�@26�@27�@28�@29�@30�@31�@32�@33�@34�@35�@36�@37�@38�@39�@40�@41�@42�@43�@44�@45�@46�@47�@48�@49�@50�@51�@52�@53�@54�@55�@56�@57�@58�@59�@60�@61�@62�@63�@64�@65�@66�@67�@68�@69�@70�@71�@72�@73�@74�@75�@76�@77�@78�@79�@80�@81�@82�@83�@84�@85�@86�@87�@88�@89�@90�@91�@92�@93�@94�@95�@96�@97�@98�@99�@100�@101�@102�@103�@104�@105�@106�@107�@108�@109�@110�@111
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
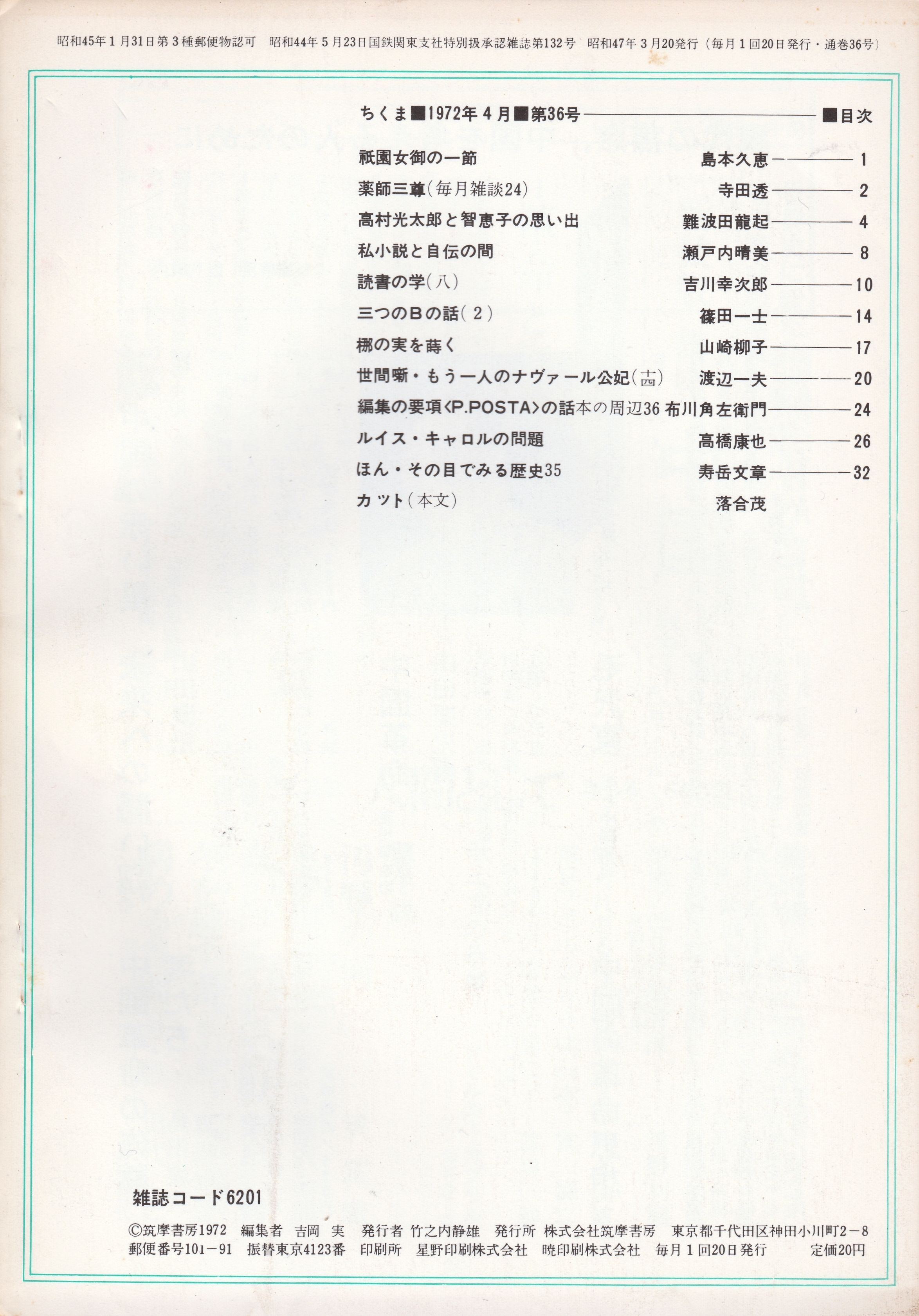
�s�����܁t��36���i�}�����[�A1972�N4���k���s���F1972�N3��20���l�j���\���f�ڂ́q�ڎ��r
�s�����܁t�ڎ��̏��̂͊�{�I�ɃS�`�b�N�ŁA�A�ډȂǕW��̈ꕔ�ɖ������g�p����Ă���B��f�ʐ^����36���ł���������ƁA���̂悤�ɂȂ�i�����n�̕����ɉ�����t�����j�B
�V�́u���a45�N1��31����3��X�֕��F�@���a44�N5��23�����S�֓��x�Г��ʈ����F�G����132���@���a47�N3��20�����s�i����1��20�����s�E�ʊ�36���j�v�͖����́A�ڎ��{������́u�����܁�1972�N4������36���\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\���ڎ��v�̓S�`�b�N�́A�r�݂͂̉����́u�G���R�[�h6201�v�̓S�`�b�N�́A���̉����u©�}�����[1972�@�ҏW�ҁ@�g���@���@���s�ҁ@�|�V���×Y�@���s���@������В}�����[�@�����s���c��_�c���쒬2-8�@�X�֔ԍ�101-91�@�U�֓���4123�ԁ@������@������������Ё@�ň��������Ё@����1��20�����s�@�@�@�艿20�~�v�͖����̂őg�܂�Ă���B����́A�\���܂�肪�ʐA�E�I�t�Z�b�g�A�{���i���ʁj�����łł���B�Ƃ���ŁA��Ɂu�{���ɂ͒ʏ�A�ҏW��L���Ȃ��v�Ə��������A�ʊ�100���ɂ͗�O�I�Ɍ�L���ڂ��Ă���B�܂�����Ȃ��g�����̕M�ɂȂ���̂Ȃ̂Łi�O�f�q�剪�M�E�l�̒f�́r�́u�R�v���Q�Ƃ��ꂽ���j�A�s�����܁t��100���i�}�����[�A1977�N8��1���A�O��y�[�W�j�k�R�����l�̑S���������B
�@�ҏW������
�@�����q�����܁r���{���������āA�S���ƂȂ�܂����B�ЂƂ̐߁A�ЂƂ̗������o�����Ƃ����܂��傤���B�����ɉ��߂āA����܂ł̑����̎��M�҂̕��X�ƁA���w�lj����������ǎ҂݂̂Ȃ��܂ɁA�S���炨��\�グ�܂��B
�@�L�O���Ƃ������ʂ̂��̂ł͂���܂��A���ЂƉ��̐[�����Ҋe�ʂ����ʂ̐��M���A����ŏ���܂����B�܂����j�̈ӂ����߂āA�\�������F�ō���܂����B
�@�悢�@��Ȃ̂Łq�����܁r�̗��j�߂������̂�\���܂��ƁA�n���͏��a�l�\�l�N�̏t�ł�����A����Ƌ�N�ڂɓ����������ł��B�������A���Ђ̂o�q�����͂��łɏ\���N�O�Ɉ�x���݂��Ă��܂��B����͏��a�O�\�l�N�̏t����A�^�u���C�h���l�ł̏{�����q�}���r�����s����Ă��܂��B���e�́A��ƖK��E����E�C�O�ʐM�E���Џo�ňē��ȂǁB��܍�����q�}������Ԃ�r�Z�łƑւ��A��\�ꍆ����q�Ǐ��W�]�r�Ɖ���A���N�����̓�\�������āA�I���ƂȂ��Ă���܂��B��ʓǏ��E�ɓ���̂Ȃ��^�u���C�h���A����Ə{���Ƃ������s���@�̂��߁A�Z���Ԃō��܂������܂����B
�@���āA�q�����܁r�Ƃ����������̂��o�q�I�ȏ�ɁA�`�T���O��łƂ��������q�ł�����A���e�͏o���邾����`�L�̂Ȃ��ҏW���j���A�S�����Ă��܂��B�Ȃ��n���ȗ��A�\���̃f�U�C���S���́A���А��쎺�̒������ق�ł��B
�i�l�j
���ʓI�ɕҏW�҂Ƃ��ās�����܁t�ɏ������Ō�̕��ƂȂ����q�ҏW������r�́A�g��������قǂ܂łɏ����I�������L�q�������Ƃ͋�O�ɂ��Đ�ゾ�A�Ƃ����_������M�d�Ȉ핶�ł���B���̌�s�����܁t����100�����s�̗�1978�N�A7������111���������ċx���̂�ނȂ��ɂ��������B�}�����[��������|�Y�������߂ł���B�̂��ɏ��������j�̑דl�A���x���͂��s�����܁t�̘A�ڂ��܂Ƃ߂������́q���Ƃ����r�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B��Ⓑ�����A���M�ґ��̋M�d�ȋL�^�Ȃ̂ň��p����B
�@��U��@�ɕm�����}�����[���������Ƃ���ǂ��A�Ăёn���{���̖ʖڂɂ����A�����̂́A���Z��i���a�l�\�l�j�N�ł������ƋL�����邪�A���̐����Â��̈���ւƂ��āA�����[�ł͈�ؑ��X�̏o�ŕ��̍L�����̂��Ȃ������[�����̏o�Ŋ����̌����o�q���u�����܁v���o�����ƂɂȂ����B�����W�������̂o�q���́A��g���X���͂��߁A���̏o�ŎЂ�����o�Ă������A�o�ł̉c�ׂ��̂��̂Ɩ�������L������A�����A�ڂ��邱�ƂɁA���X�̂Ƃ͈ꖡ�����Ⴄ���̂ɂ��悤�Ɗ�悵���Ƃ���ɓ��F���������B�����ē�̘A�ڂ��̂̂����A�i�`�j��͕\������𗘗p���Đ}�^�Ƃ��A���̐�����{���ŋ����[������Ђ낰�A�i�a�j������͂Ђ낭�o�łɂ܂�錾��Ύ���Ă����́A���x�̒m�I������e�Ƃ���A�Ƃ̕��j�����܂�A���M�҂Ƃ��āA�i�`�j�͎��ɁA�i�a�j�͂��Ƃ��ƒ}�����[�Ƃ͊W�̐[����g���X�̒��V�i�z��p���q��Z�ɂ��܂����B�����ĕz��Z�́A�u�{�̎��Ӂv�Ƒ肵�āA�n����ꍆ�����x�������������������k���p�Ғ��\�\���m�ɂ͑�50�E51�E90����3���͋x�ڂŁA1977�N1������93���܂ł̑S90��A�ځl�A�����̈ꎞ�p�����@�Ɉ���̖{�ɂ܂Ƃ߂����A���͂����܂Ōċz���������A�܂�����w�_�ȁx�̖|��ɖv�����˂Ȃ�Ȃ�����������āA�l�Ԃ̊җ�ɑ�������Z�\��i��㎵�l�N�܌����j�ňꉝ�ӔC���������Ă�������B�i�s�}�� �{�̗��j�k�G�f�B�^�[�p���l�t���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1982�N2��10���A�ꔪ�O�`�ꔪ�l�y�[�W�j
�ŏI�I�ɓ��{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ����瓡�X�P�v�̑��{�ŏo���{�������s�����܂ł̌o�܂������[���i�����ʼn�L���o�c����o�Ŏ҂��A�t�����X�ɍ݂������J�쌉��������ʼn�����鋖�܂Ŏ��������A��L�̎�����œڍ������Ƃ����j�B���x�́q���Ƃ����r�ɂ́u�����āA�ҏW�̂������킹�̂��߂ɁA���ܗ��K�����ҏW��C�̓y��ꐳ����A���̂��Ƃ������Ď�C�ƂȂ����g��������ƁA�o�łɂ܂������ܘb�ɉԂ��炩���̂��y���������B�g������͓���ِF�̎��l�ł�����̂ŁA���Ƃ��Ǝ��̂����Ȏ��́A�����Ƃ̌�炢����A���ɂƂ��Ă͂���܂Œm��Ȃ����������̂��̂��̂��A���肪�������Y���ł������v�i���O�A�ꔪ�Z�y�[�W�j�ƌ�����B�s�����܁t�̕ҏW�ҁE�g�����̎p��`���鐔���Ȃ��،��̂ЂƂł���B
�k�t�L�l
�`���ŐG�ꂽ�g���̐��z�ɂ����鐼�e���O�Y�́u�⌾���v�́q�~�̃V�����\���r�ŁA������́s�����܁t1981�N3�����ɔ��\���ꂽ�i�ҏW�҂͔��������A���s�҂͒}�����[�̊Ǎ��l����\������ƂȂ����z��p���q��j�B�g�����g�͓���1987�N2�����ɁA�������S�������y���F�̈╶�W�s���e�̐�t�i1987�N1��21���j�̃v�����[�V�����̂��߂Ɂq���{�̎R���̈��r���Ă���i�̂��s�y���F��t�Ɏ��^�j�B�Ȃ��A���e���O�Y�̒S���҂ł����������{���Y�ҏW�̓���1990�N7�����́q�ҏW������r�́A���l�ɂ��ās�����܁t�̕ҏW�ҁE�g������Ǔ����镶�͂ƂȂ��Ă����i���j�A��8�����ɂ͏a��F��ƒ|�����q�i�|�������Ē}�����[�̎Ј��������j�̒Ǔ������f�ڂ��Ă���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@���܌��O�\����A���l�̋g�������S���Ȃ����B�g������ƌĂԂ̂͒������Ђɂ�����y������ł���B�����̐l�������̂Ŏ�����ƌĂԐl�������B���W�w�m���x�w�a���`�x�̍�����m���Ă���B���鎞�����́u�����܁v�̕ҏW��S������Ă������Ƃ�����B���h���ׂ����l�ł���O�ɁA��O�̓����̉����̏����C���́A���C�ŏ���Ȃ��A �ǂ�����������������������l���ɐe���݁A�����Ԃ�Â������Ă����������B���ʁA�E�l�C���Ƃ������ׂ���ł��C����������������Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�L���ɂȂ��Ă���́A���l�Ɖ���������y�Ƃ̂ǂ���ɑ��ׂ����������Ƃ�����������ǂ��A���ǂ͋��m�̌�y�Ƃ��ċ����Ă��炦���悤�Ɏv���B�ʖ��V�ɏ��w�Z�̓��������F�Ƃ��������������������ꂽ�͉̂��̋g������̂��߂Ɋ��������Ƃł������B�i�s�����܁t��232���A�Z�Z�y�[�W�j
�߉ϑ��Y���W�s���y�t�i�v���ЁA1965�N7��10���j�ɂ��q�g�����̑�����i�i6�j�r�ŐG�ꂽ���A���̂Ƃ��ɂ͂ق��̔ł����邱�Ƃ�m��Ȃ������B����A1966�N2��5�����s�̓����W�u���y�Łv�i���t�ɂ��j��m��A�����������肵���B���y�łɂ��N���W�b�g�͌����Ȃ����A�g���������ɊԈႢ�Ȃ��B�����1965�N���s�̏����u����400���v�i���O�j�{�Ɨ��N���s�̕��y�ł��r���āA�g���������̃t�����X���ɂ��āi���x�߂��́j�l�@�����Ă݂����B���y�ł́A�d�l�i��Z��~��l���~�����[�g���E��Z�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���j�E���ށi�{���p���F�k�z�����A���[���F�|���m���X�j�Ƃ�����łƓ���ŁA�����E�⍲���{�Ƃ��������Ђ��������B�������O���V���̗L���E�`�قȂ�B
|
�t�����X���\���̃O���V��
|
�@�B���̃O���V��
|
|
| ����� |
�L�����\���Ɠ����傫���ŁA�d�˂��܂ܐ܂�Ԃ�
�i���O���Ȃ��j |
�\���̂悤�ɓV�n���Ђœ\�肠�킹�A�J�����Ő܂�Ԃ�
�i�Ō����{���ɂ͖����H�j |
| ���y�� |
�V�n�͕\���̎d�オ��Ɠ����A�����Ő܂�Ԃ�
�i���O����j |
����
�i�������疳���H�j |
����ł̋@�B���ɃO���V�����������͍̂w����̌Ï��X�i�_�ے��E�c�����X�j�̉\���������̂ŁA�����Ώۂ��珜�O����B�t�����X���\���̃O���V���ɂ��ẮA�ȉ��ŏڏq����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���i������j���łƂ߂��@�B���j
�\���i�t�����X���ɂ�邭��ݕ\���j
 �@
�@
�߉ϑ��Y���W�s���y�k���y�Łl�t�i�v���ЁA1966�N2��5���j�̖{���Ɣ��̕\���S�i���j�Ə�F���k����Łl�i���A1965�N7��10���j�Ɖ��F�k���y�Łl�̕\���̈ꕔ�i�E�j
����ł̕\���i�d�オ���204�~151�~�����[�g���j�̗p�����L����ΓV�n313�~���E416�~�����[�g���Ȃ̂ɑ��āA���y�ł̗p���͓V�n267�~���E390�~�����[�g���ŁA�܂�Ԃ��͌���ł�54�~�����[�g���ɑ���41�i�����j�E32�i�V�ƒn�j�~�����[�g���ƁA���Ȃ�Ȃ��Ă���B�p���͂ӂ��̔łƂ����������E�A�ʂɌ����邪�A�{�̂Ƃ̐ڒ��̓x�����i�ʐρj���قȂ�B����ł͐܂�Ԃ��ꂽ�\���S�ʂɃO���V�����|�����Ă��āi�O�����ȊO�̎��͂��ЂÂ��j�A�ڒ������͔w�����݂͂łĂ��邽�߁A�\�����ܒ�����������ێ����Ă���B����A���y�ł̃O���V���͐ڒ������Ɋ|�����Ă��Ȃ��̂ŁA�\�����̂قڔw���ɂ����Ђ�������Ă��邽�߂��낤���A�Ï��X�i���n�E��M�����X�j�ōw�������Ƃ��A�\�����{�̂��犮�S�ɊO��Ă����B�������A�ڒ����������Ȃ����ƂŃm�h�̊J���͗ǂ��͂����i����}���ُ����̕��y�ł���ɂ����Ƃ���A�g�������W�s�a���`�t�̊J��������ł̒��ԂƂ������z���������A�ǂ������Ŏ����Ȃ��ƕ��Ă��܂������j�B
�ʐ^�ł͂킩��ɂ������A�\���͓�ӏ��ŏC������Ă���B�@�\���P�̒��Җ��́u�Y�v����������V���ɁB�A�\���S�̊��s�N�́u�P�X�U�T�v���u�P�X�U�U�v�ɁB����ł̕\���P�ȊO�A�u�Y�v�͂��ׂĐV�����������牸���ȑ[�u�����A���s�N�̏C���Ƃǂ���̔�d���傫���������͌y�y�ɒf���ł��Ȃ��B
�O���Ԃ��i�S�y�[�W�B�{���̑�1�܂̃m�h�ɌЂÂ��B�������ɑ�������ق��̌��Ԃ����t�����X���̑O�����̑��̉��ɐ���j
�{��
�H�́E�E�E8
��i�` 12
��i�a 14
��i�b 16
�� 18
�� 22
�˂ނ�̊C 26
�����p�C�v�̂��ނ�̔g�� 32
�t�H�I�g���G�̒� 36
������ 40
���с��̃��`�C�t�ɂ�鈽��W����̂��߂̃G�X�L�X 48
�����Ȓ��� 54
�����Ɋ� 58
���@����Ђ͎� 62
�C 66
�]�� 70
���i 72
�Ă̂Ђ�̕��i 74
�A�����C�̉J 76
�� 80�J�b�g�E������
���т����J���ŋN������@�́A���̋g���������g�̎��W�ň�т��č̂��Ă������̂Łi��O�̓W�A�s�����G�߁t�Ɓs�t�́t�̊������т͂Ƃ��ɉ����k��y�[�W�N�����l�j�A�s���y�t�����̗�ɘR��Ȃ��B�s�Õ��t�Ɏn�܂�s�a���`�t�Œ��_���ɂ߂��g���̖{���g�́A�{���̑����ƂƂ��ɁA�߉ς̗F�l�ł��������ɒB���v�i1950�N�̓߉ς̑�ꎍ�W�sETUDES�t�͏��惆���C�J�̎����o�ł�����Â����j�ւ̉��Ԃ��ƂȂ������Ƃ��낤�B�Ȃ��q��r�́A���l�������g�̎��тƈقȂ���̂́A�{���Ƃ܂��������������E�g�̍قŁA�����ɋg���̖��m�Ȉӎu��������B
�㌩�Ԃ��i�S�y�[�W�B�{���̍ŏI��6�܁k��5�܂�8�y�[�W���āA��6�܂�16�y�[�W���āl�̃m�h�ɌЂÂ��B�������ɑ�������ق��̌��Ԃ����t�����X���̑O�����̑��̉��ɐ���j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�s���{���㎍��n�k��13���l�t�i�͏o���[�V�ЁA1976�N7��15���j�͑剪�M�҂́q�����i�O�j�r�ŁA�s���y�t�̑S19�т���5�сi�q��i�`�r�A�q���r�A�q�����́r�A�q�q�сr�̃��`�C�t�ɂ�鈽��W����̂��߂̃G�X�L�X�r�A�q���i�r�j���̂��Ă���B�����Ɏ��̏���������B
�k�u���فk�}�}�l�E�߉ϑ��Y���B���Z�ܔN�����\���A�v���Д��s�B�̍فE199�~149�����B�J�b�g�E�����B�ڎ��O�ŁA�{�����ܕŁB�艿�Z�S�~�l�i�����A���Z�y�[�W�j
�q�}��r�i���A��O�y�[�W�j�ɏ]���u199�~149�v�͉�����~���A�c��l��~���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂�����A�����́u149�~199�v���낤�i���̍̐������u�V�n��Z��~���E��l���~�����[�g���v�Ƃ͔����ɈقȂ邪�A������ɂ��Ă��`�T���V�n��̕ό^�T�C�Y�ł���j�B���āA�{���W�ōł��l�����Y�t���Ă���̂́q���r�i���o�́s���w�t1961�N1�����j�̎��̎��傾�낤�B
���������������������^�ւ������ڂ�����
�剪�M�͑O�f���́q����r�ŁA�g�����Ɠ߉ϑ��Y�ɐG��āu�������������I�Ȋ��o���A�k�c�c�l�܂��g�����ɂ́A�����I�Ȓ���̈�����ł������A�u�~���̎����v����Ă邽�߂́u��`�̉Ɓv�ւ̖�����点��i�u�r���v�j�̂ł���B�^�߉ϑ��Y�̎��W�w���فk�}�}�l�x�́A�����Ă݂�����������o�̃G�b�Z���X�����ڂ肠���A���������悤�Ȍ��t�̌Q�ŏ�����Ă����v�i���A�O���`�O���y�[�W�j�Əq�ׂĂ���B�߉ϑ��Y�́q���r�͋g�����́u�������Ă����܂��͗l�́^�̂̂̂̂́^�̂��ꎀ�����F����v�i�q���ār�F�E8�j��7�N�O�ɔ��\����Ă���B
�k���y�ł̔��Ɋւ���NjL�l
���W�s���y�t��1965�N12���ɑ�5���Ґ����l�܂��A��66�N2���ɑ�17��ǔ����w�܁i���́E�o�啔��j����܂��Ă���A���y�ł̊��s�͂���ɍ��킹�����̂��낤�B�Ƃ���ŁA�O�����w�ٓ��ʊ��W�s�߉ϑ��Y�\�\�q���r�̎��w�t�i�����Y�L�O�E���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2008�N10��11���j�̎��W���e������ƁA����ł͔����A���y�Łi�тɁu�ǔ����w��܁^���N���̓��{���w�̍ő�̎��l�v�Ƃ���j�͕\�����f�����Ă���B���y�ł̒艿��500�~�ł���A�\���̃O���V���|�����ȗ������A������߂ăR�X�g�_�E����}�����\�\�䂦�ɔ��͓�������Ȃ������A�Ƃ��ׂ����낤�B�`���ŐG�ꂽ���y�ł̔��́A�\�����O���̂�h�����߂ɌÏ��X������ł��痬�p�������̂��ƍl����A�N���́u�P�X�U�T�v�ɂ��[���������B�Ƃ͂������̂́A���̒��B�擙�̓�͎c��B
��
�e���O�Y���M�W�s������Ƃ������t�i�}�����[�A1969�N11��28���j�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ����A�Г��������Ƃ��ċg�������S�������ƍl����
���B���e��1969�N10��10���̓��t�̂���{���́q���Ƃ����r���u���̖{���o�ł���̂ɒ}�����[�̈��B�O�N�����ߋg�����N��܂��ҏW�Z���Ȃlj�c
�j�Y�N�⌮�J�K�M�N�ɔ��ȍ��܂�������Ă��܂����B���T�Ő[�����ӂ̈ӂ�\�������v�i�{���A���O�y�[�W�j�ƌ���ł��āA�O�N1968�N���s���s���{�t��
�������B�O�̊��ŁA�g���Ɖ�c���Г��̎�����S�������Ǝv�����B�قڏ������낵�������s���{�t�ɑ��Ċ����\�̐��M���W�߂��{�������A�q���Ƃ����r��
��@����ɕҏW�E����̓X���[�Y�ɂ͂����Ȃ��������B�����Ƃ��d�オ������邩����A��l���ǂނɂӂ��킵�������������{�Łi�{��10�|38���l15�s�E�s�ԑS�p�A�J���[���G�ɐ��e�̖��ʁq�k�C���̗��r�j�A���̏o���ɂ͒��҂������������Ƃ��낤�B
�{���̎d�l�́A���܁~��l���~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�\���B�ӏ��Ƃ��Ē��ڂ������̂����ŁA�Ђ炪�Ȃ���̏����́u�Ɓv��Ԃɂ���
��A���e�̎�ɂȂ�X�P�b�`����i�I�ɂ����炤�Ȃǂ��āA�g���������̂Ȃ��ł͏������`�������݂�����ƂȂ��Ă���B

���e���O�Y���M�W�s������Ƃ������t�i�}�����[�A1969�N11��28���j�̖{���Ɣ�
�g�������e�Ɋւ��鐏�z���W�������q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́q�R�@���ϒn���̎��Ӂr�ɂ�
�k�c�c�l ������ܔN�O�̏H�̏��߂��낾�����B���e�搶�͏o��������̐��M�W�s������Ƃ������t�ɏ������邽�߁A���Ђ��ꂽ�B�S��\���ɃT�C�������܂���Ƃ� �����Ɏ�ɂ��Ȃ����ƁA���e�搶�͋���ꂽ�B�����ċ}�Ɏv�����ꂽ�悤�ɁA�O�c�ɋC�ɓ��������݉������邩��s�����Ɖ�c�j�Y�Ǝ����^�N�V�[�ɂ� �����B�c���w�߂��ō~���ƁA��ʂ�ɖʂ��Đ^�����X�\���������B����͕����ʂ荕���Ƃ����𑠂ł������B�܂��l������Ƃ����̂ɁA���D���̋q���K���� �����Ă���̂������������������������ɂ��������B���̌X�����됼�e�搶�͏����U�����悤�ƌ���ꂽ�B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����y�[�W�j
�Ƃ���A�������q�S�@���L���r�ɂ͎��̂悤�ɂ����āA�s������Ƃ������t����s�߉́t�ւƌ������Ă����A�����̐��e�̒}�����[�ł̂��肳�܂� ���ʂ���Ă���B
�@���a44�N9��1���^���e�搶���ЁB��c�j�Y�Ɠ�Z�Z�Z�s�̎��̕ҏW�ɂ��Č��B�s�߉́t�Ƃ��������ƌ���ꂽ�̂ŁA��l�Ƃ������� ��B�搶�ɂ����A�\�\�Ƃ���Łs�߉́t�Ƃ͉��ł����H�@����͓y��@���ĉS�����Ƃ���B�y�l�̍�̖�̂��Ƃ��B
�@�@�@�@�@9��3���^���e�搶������B���s�̎��A��s����Ȃ����Ƃ��킩��A���������ɂ����Ƃ̂��ƁB�O�����V���R�[�Œ��H�B���ꂩ���c�j�Y������ �̂ŎO�l�Ńo���[�ɍs���A����k�`�B����ƃM���V�A��Ƃ̋��ʓ_�����߂āA���Ɍ܃��N�ɋy�ԂƂ��B�搶�ЂƂ�ňꎞ�Ԃ�����B�i���O�A��O��y�[�W�j
�c���x�́s���惆���C�J�̖{�t�̊��������q���惆���C�J�o�ő��ژ^�r�ɂ́A�g�����̒����Ƃ��ās�m���t�i1958�j�Ɓs�g�������W�k�����̎��l�o���l�t�i1959�j�A�i�g���̖��O�͂Ȃ����j�����Ƃ��ās���㎍�S�W�k��3���l�t�i1959�j�Ɓs���{���W�E1960�t�i1960�j�A������i�Ƃ��ăA�����E�~�V���I�i���C�i���j�s�v�����[���Ƃ����j�t�i1959�j�ƕА����q���s�L���X�����E���C�����W�k�C�O�̎��l�o���l�t�i1960�j�̌v6�_���f�ڂ���Ă���B���ژ^�́s�v�����[���Ƃ����j�t�̋L�ڂ́u�k���a�l34.9.20�@�v�����[���Ƃ����j�@�A�����E�~�V���I�@���C�i���@�����E�g�����A�}��E���ҁA���[���X�E�A�����v�i�s���惆���C�J�̖{�t�A�y�ЁA2009�N9��15���A��t��Z�y�[�W�j�ŁA�����̖{���ɂ͂�������B
�~�V���I�w�v�����[���Ƃ����j�x�i���a�O�l�N�A�}42�j�́A�\���Ђ�Ɉ�����Ă��镶�����V�ƒn���ꂼ��̃M���M�����B����Ȉʒu�Ɏw�肳�ꂽ��A�������{���������������₪�邱�Ƃ��낤�B���~���̃Y�����v�����ɂȂ邩�炾�B���̈ʒu�����̎������̖ڂɐV�N�ɉf��̂́A����̈�����{�ł͂�����������̎����h������A���܂�s���Ȃ������ł���B��������Ă��x��̂Ȃ��f�U�C���A��Ԃ������炸���������ł������c�c����Ȃ��Ƃ�Nj����邩��A���X�̓X���ɕ��Ԗ{�݂͂ȁA�ǂ�������悤�Ȋ�ɂȂ��Ă��܂��B�i�q�@�ׂȎ��W�Q�̒a���r�A���O�A���E��l�y�[�W�j
�\�����L�����Ƃ���́u�}42�v�i���O�A��O�y�[�W�j�̓��m�N���ʐ^�ŁA����Ɂu�w�����łЂ炪�ԂƂ�����i�v�i���O�A���y�[�W�j�Ƃ��������Ə�f������A�\���̉���Ƃ��ĕt�����킦��ׂ��_�͂Ȃ��B�����ĕt������Ȃ�A���Y�N���u�b�N�f�U�C���́s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�̖{���̍���ʒu���V�M���M���̎w��ŁA�g�����i���҂Ƃ��ā^�����ƂƂ��āj�����ł������悤�Ƃ������Ƃ��炢�ł���B�{���̎d�l�́A��Z��~��l���~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�p���\���i���E���A�w�E�N���X�j�E�W���P�b�g�B��҂̏��C�i��́q���Ƃ����r�Łu�k���G�́l���F�ł̓~�V���I�̎���W�w�G��ƃf�b�T���x���̂����B���O��N��B���̃��[���X�E�A�����M�̃~�V���I�̏ё���m�|���g���n�́A�u�����₩�Ȓj�v��ǂ܂ꂽ�ǎ҂ɂ́A�ɂ߂ċ����[���v���邱�Ƃł��낤�v�i�{���A��O��y�[�W�j�Ə����Ă���A�����̃r�W���A���̑I��ɖ�҂̈ӌ������f���Ă������Ƃ��킩��B�W���P�b�g�̉�̃N���W�b�g�͂Ȃ����A���C�i��s�A�����E�~�V���[�]�`�t�i�����ЁA1998�N7��30���j�̌��G�Ɍf�ڂ���Ă���u�w�v�����[���Ƃ����j�x�̑}��i1930�N�j�v�i�����A�k���y�[�W�l�j�������悾����A�W���P�b�g�̓~�V���[�ɂ����̂��낤�B
 �@
�@
�A�����E�~�V���I�i���C�i���j�s�v�����[���Ƃ����j�t�i���惆���C�J�A1959�N9��20���j�̕\���i���j�Ɠ��E�{���ƃW���P�b�g�i�E�j
�s�v�����[���Ƃ����j�t�Ɏ��߂�ꂽ�̂́q�v�����[���Ƃ����j�r�q�u�`�v�̏ё��r�q���i�ꖋ�j�r��3�сB���C�͌�N�A�ʂ̖W�́q����r�ɂ��������Ă���B
�u�~�V���[�̑n�������ˋ�̐l���v�����[���́A�����Ă���ԂɉƂ𓐂܂�A�Ȃ��Ԃ�瀂��E����āA�������Ɛl�Ƃ��Ď��Y��鍐�����B���ɏo��A�Q���f����A�̍����Ƃ��������A��Ԃ���͕���o�����B�����A���X�Ɖ�������U���ɂ��A�ނ͋C�キ�]�����肾�B�K���s�\�҂̌��{�A�v�����[���́A�l�Ԃ���͂ޓG�ӂ��鏔�́A�������h�����瓦�꓾�ʂ����l�ԑ��݂̋Y��Ȃ̂ł���A����͂��̂܂܌���ɂ�����l�Ԃ̏������Î�����v�i���C�i���s�A�����E�~�V���[���W�t�A�\�����[�A1977�N6��30���A��l�y�[�W�j�B
���Ɂq�v�����[���Ƃ����j�r�́q�X �u���K���A�l�̖�r�̖`�������������̂́A�g���́q�����r�i�F�E5�j�́u���ƊO���ł������ā^�u���K�����l�̒j���͗����^�E���̉H�͎U������^����ǂ����[�����^�o�N�V��������C�@�֎Ԃ����ʂ�������Ă���v�Ƃ�������ƕ��u�����������߂ł���B
�@�s�����̒ʂ�A�킽�������͋A��r���ŁA��������D�Ԃ��ԈႦ����ł��B����ŁA������u���K���A�l�ǂ��ƈꏏ�̎��p�ɂȂ�����ł����A�z�炪�����킩��Ƃ��A�ԂԂԂ₢����A�n�I���������g�̂������肷�������A���Ɍ����m���܂�n���������Ȃ�����ł��B�킽�������̓s�X�g�����ēz����˂����B�z��͐M�p�o����A��������A�����Ȃ������܂����Ƃ����킯�ł���B���͂Ƃ�����A�z��ɐ킨�����ċC���Ȃ������邱�Ƃ��A�悸���Ƃ�������ł��傤���B�z��͎c�炸�x�_���ꂽ�悤�ł������A�S��������u���K���A�l���ēz�́A�M�p���Ă͂Ȃ��̂ł��B�t�i�{���A��Z�y�[�W�j
�g�����̓A�����E�~�V���[�Ɍ��y���Ă��Ȃ����A�������сq�A�d�r�i�s���㎍�t�k�Ώ��[�l1956�N7�����j�́s�v�����[���Ƃ����j�t�̃~�V���[�̐��E�ɋ߂����̂�����������B�q�A�d�r�͂��̋��Ӑ������邱�ƂȂ���A�g�������ɂ��Ă͕s�C���Ȃ܂ł̔����i�u�S�C�́v�A�u�S�₳�����L�v�Ɓu��̐܂ꂽ�L�v�j���ِF�̎U���������A�q�A�d�r���\��1956�N�͌�́s�m���t�̏��т����߂ēo�ꂵ���N�ł�����B���̔N�A�q�����r�i4���j�A�q�쌀�r�i5���j�A�q�A�d�r�i7���j�A�q���r�i11���j�A�q�d���r�i12���j�����\����Ă��邪�A�g���͋��ӂƔ����̕����ɍ�i�̑ǂ�邱�ƂȂ��A�{�т����W�s�m���t�Ɏ��߂��邱�Ƃ͂Ȃ������B�������Ȃ���A�s�m���t��19�ђ�9�тƎU�����^�̎��т������̂́A���C��̃~�V���[���т��e�����Ă���̂�������Ȃ��B���C�i��͑O�f�s�A�����E�~�V���[�]�`�t�ŁA���{�ɂ�����~�V���[�̎��̉e���ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�ꎞ���m���ɁA�~�V���[�̎��́A�قƂ�ǂ킽���̖�ʂ��āA���{�̎��l�����ɂ��������L���e����^�����B�~�V���[�͎�Ƃ��ĎU�����������Ă���A�e�����قƂ�ǂ��U�����̗̈�Ɍ�����B�����{�̎��ɂ�����U�������s�̊�Ղɂ́A�~�V���[�̕���I�U��������̎h�����������Ɓi���Ȃ��Ƃ����̎�v�ȗv���̈�ɂȂ����Ɓj�킽���͍l���Ă���B�~�V���[�̎��̖��͂Ɗ����͂́A���{�ɂ����Ă͂���قǂɑ傫�������v�i�����A�O�����y�[�W�j�B
���惆���C�J�Ƌg�����̂Ȃ���́A�`���ɋL�����Ƃ���A�x���o��ɂ�������炸�Z���Ȃ��̂��������i���l�����s�����t��������s�����C�J�t�Ƃ��������惆���C�J���s�̎G���́A�g�����f�r���[�Ԃ��Ȃ����_�ōł��d�v�Ȕ��\�}�̂������j�B����A�~�V���[�̏����̖M���́A���惆���C�J�����s���鏬�C�i���Ő�߂��Ă����B���Ȃ킿����3���ł���B
�s�v�����[���Ƃ����j�t�ȑO�̂����~�V���[���W�i�̂����ꂩ�j�ɋg�����G�ꂽ���Ƃ́A�u�ǓƂȍ��̉F����`�������v����s�Õ��t����u�l�Ԃւ̈��ƕs�M�ɍʂ�ꂽ���v����s�m���t�ւ̕ϖe����l���Ă��A�[���������Ƒz����B���C�i��ɂ��q�v�����[���Ƃ����j�r�̖́A�s�v�����[���Ƃ����j�t�i�����ЁA1970�j���s���ɖ�҂̎肪����A���̖{�����s�A�����E�~�V���[�S�W�k��1���l�t�i�y�ЁA1987�j�Ɓs���C�i��|���W�k��1���l�t�i�ۑP�A2008�j�Ɉ����p����Ă���B
�k2017�N8��31���NjL�l
�ɒB���v�ҏW���s�́s�����C�J�t�́A1959�N11�����́q���]�r���ɓ���N�v���N�p���āA�{�����v�����[�g���Ă���B����͓����̖������u��҂̃~�V���I�ւ̌X�|�Ɨ����Ƌ����͂��̖ɂ��䂫�킽��A�g�������̑���Ƃ����܂��āA���̈ꊪ������߂Ĕ��������̂Ƃ��Ă���B�~�V���I�̍�i�ɋ��������҂̕K�ǂ̏��Ƃ����邾�낤�v�i�����A�Z�Z�y�[�W�j�ƒ��߂������Ă���B���Ȃ݂ɁA���̍��̕\��2�̎��Џo�ōL���́s�g�������W�k�����̎��l�p��5�l�t�Ɓs�v�����[���Ƃ����j�t��2���ł���B
�����r�Y�s���Ƃ�����t�i���X�A1978�N10��10���j���s���l�̌��t�i���A1977�j�A�s���̂̑��q�t�i���A1978�j�ɑ�����O�̎��_�W�ŁA�O����̊����сB�u�����ɂ܂Ƃ߂��u���Ƃ�����v�A������u�����߂����āv�Ƃ����B�����́u���l�̌��\�����߂����āv�A�u���̂̑��q�\�����߂����āv�ƕ����āA��������܂ŏ����ė�����v�ȃG�Z�[�͂قږԗ������B���͂��ꂩ����c���₢���Â��Ă������낤���A���̖₢��
�Ђ��Â��A���̎��Ɠ��Ɨ��Ƃ̎O�p�`�Ɋ��邱�Ƃ��ł������ł���v�i�q��r�A�{���A��Z�Z�y�[�W�j�B�{���̎d�l�́A���Z�~��~�����[�g���E�l
�y�[�W�E�㐻�N���X���i�N���[�������������F�j�E���B�ڎ��̗��Ɂu����@�g ���@���v�B�S14�т��W���ɕ������A�z����B
�@�T�@���Ƃ�����^���J�����x���߂����ā^�ɐ�������
�@�U�@�����ċA��ʁ^���d�u���^�e�҂̌��̋L���^���E��E�ԁE�_
�@�V�@���̂��镗�i����^�s�ɂ��ā^���̃j���[���[�N�n�}�^���̓V�g
�@�W�@�n���C�̃o���o���X�^���R�A�\�X�ւ̓��^�I�[�P�A�m�X�̂قƂ�
�q�n���C�̃o���o���X�r�i���o�F�s�C�t1969�N11�����j�ɁA���߂ăN���^���肵���Ƃ��̗l�q��������Ă���B�u�O�����A�C���N���I����`�ցB�A�e�l��
�z�e���ŏЉ�ꂽ�A�g�����`�X�Ƃ����A�C�������n���ȃz�e���ɓ��h�B�C�֏o��B�˒�̐�ɏ\���R�̍Ԃ�����B�p�̌������A�͂邩���̎R�R�̏�ɂ��т���
�O�p�`�̎R�́A�C�_�R���낤���B�˒�̓�����ɂ���������D�����B���ނ�̏��N���������������Ɏ�������B�����Ń��|�j�X�A���|�j�X�Ƃ����₢�Ă���v
�i�q�Z����\�����@�A�e�l���N���^�r�A�{���A��㎵�`��㔪�y�[�W�j�B�����āq�Z����\�����@�N���^�r�ɂ́u�N�m�b�\�X�A�~�m�X���{�B�ߑO�㎞�̔p�Ђɂ�
��Ɛl�v�����̂ق��ɂ͒N�����Ȃ��B�K�i���~���ƁA�������H�̂͂��܂肾�B�A�e�i�C����l�g�䋟�̎�҂�����A��ė����g�҂������������̐��ޖ��{��
�v�����̂��������v�i���O�A��㔪�y�[�W�j�Ƃ���B�����͎O����������ӂ肩�����Ă���B
�@ �ڂ��̌o���̏Z�܂��Ɍ���ꂽ���J�삳��́u�G�Z�[�W���o�������̂ł����A����������̌��e�͂���܂��v�Ɛ�o�����B���������͂ڂ����悭������ ����B�ڂ��́A�u�O�����Ȃ炠��܂��v�Ɠ������B���́k���l�Z��N�̏㋞�ȗ�����܂łɏ��������̂������Ȃ�ɂ܂Ƃ߂��Ƃ���A�X���̈قȂ�O�̃O ���[�v�ɕ�����Ă����̂������B�^�k�c�c�l�^������ق����̂ŁA�O�����͂ǂ����A�Ƃ��������ڂ��͗\�z���Ă����B�Ƃ��낪���J�삳��̓��́A�ł͎O���o�� �܂��傤�A�������B�����āk�c�c�l�O�����o���B���ꂼ��A�A�ԁA���̕z���k�}�}�l��������͋g��������̑��ꂾ�B�i�q���J���v�̊��\�\��N�ƃA�N ���[�r�A�s�F�B�̍����\�\�����r�Y��Friends Index�t�A�}�K�W���n�E�X�A1993�N9��22���A�O����y�[�W�j
���҂Ə��X�̕ҏW�҂ɂ��Ĕ��s�ҁE���J���v�Ƃ̂��Ƃ�ł���B�����X�̋g���������{�̒��҂͓߉ϑ��Y�ƍ����r�Y�̓�l�����ŁA�{���̑����� ���҂́u���w���v��������Ȃ��B
 �@
�@
�����r�Y�s���Ƃ�����t�i���X�A1978�N10��10���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ��E���_�W�O����̔w�\���i�E�j
�����r�Y�s���̂̑��q�t�i���X�A1978�N2��20���j���s���l�̌��t�i���A1977�j�ɑ������̎��_�W�B�q���̂̑��q�����\�\�M���V�A�_�b�ɂ݂��܂̌����r�ȂǁA�����G���[�X�ɂ��ẴG�b�Z�C24�т����߂�B���͖{���� ��A���������l�̈�l�������s�����t�̑n�����i1976�N5���j�ɋg�����������сq���N�r�i�G�E29�j��z���N�����B���́u�R�v��Ǎ��݂ň������B
���R�͂�����ł����^���N�̂����Ȉł̂Ȃ��ɂ́^���̂悤�Ȃ��́^���`�̂悤�Ȃ��́^����炪���݂���^�u�j���̐ؒf�ʂ��琶����b�U�ǁv�^ ���̂�ɂ���^�_�v�̖��������^�킽���͔M���n�̕��𗁂т�
�{ ���̎d�l�́A���Z�~����~�����[�g���E��ܔ��y�[�W�E�㐻�N���X���i�ԁj�E���B�ڎ����Ɂu����@�g ���@���v�Ƃ���B�{���̕����̃J�b�g�́A�����̎��W�s�����̍\���t�i���X�A1982�N2��20���j�́q�������̊�{��b�r�̕t�L�̈�߂�������� ����悤���B�u���������Ñ�̓s���Ղ̈�Ցw�����w�ɂ��d�Ȃ��Ă���悤�ɁA���̍��̌���w���d�Ȃ��Ă��邹�����낤���A���̒����玀�\�\��\�\��̎O �p�`�̏d���������������Ƃ́A����قǍ���ł͂���܂��v�i�����A��ܔ��y�[�W�j�B���̕\���E���Ԃ��A�n��F�̖{���̑����͕ۓc�t�F�����A���̉��t���L�� �ɔ�����ɂ����g���������̎O���삪�ڂ��Ă���B����3���łЂƂ̐��E���`������\�z�����҂Əo�Ŏ҂̊Ԃŗ�������Ă������ƁA��������o�I�ɓW�J�� ��v�����������҂ɋ��߂�ꂽ���ƁA�Ƃ��ɑz���ɓ�Ȃ��B���̈ӌ��́A���E�{���̐}���̑I��ɏ[��������قǔ��f���Ă���B

�����r�Y�s���̂̑��q�t�i���X�A1978�N2��20���j�̖{���Ɣ�
�{�������́q����Ƃ������Ɓr�ɂ́A�s�n���t�̓��l�E�А����q�i�s�L���X�����E���C�����W�t�� ��ҁj�Ƃ̏o���������Ă��āA���ꂾ���ł��d�v�����A�����̍Ō�̈�߂��O��s���l�̌��t�̊����G�b�Z�C�ƑΉ����Ă��邳�܂́A�X�������O�ł����� ��B�����Ŏ��́A���ɉ�A���ė���r�[�g���Y��v���O���b�V�����b�N�O���[�v�̈�A�̃R���Z�v�g�A���o����A�z���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@ ���̓w�u���I�l�ł��A�M���V�A�l�ł��Ȃ��B�������A���������̐��������̒��S�Ɏ���I�сA���l�ł��邱�Ƃ�I�Ƃ��A���͎����̐��������̎w�j�Ƃ��� �u���͓��̂ƂȂ��āA�������̂����ɏh�����v�̐����I���ƂɂȂ�B������A�u���l�̌��\�\�܂��͏C���ɂ��āv����сu�m��ꂴ�� poesie ���߂����āv�́A�k�u���l�v�̃M���V�A��\�L�l�Ƃ��Ă̎��̎��I�M���̔��l�ł���ƂƂ��ɁA���̐M�����ł�����A�ƌ������Ƃ��ł��悤�B�i�{���A��l�� �`��l��y�[�W�j
�����ɂ́u�_�b�̐X���ꡂ��Ȃ���A���̌��z�̎n���ւƑk�s���� ���I�G�b�Z�C�v�́s���̂̐_�b�w�t�i�͏o���[�V�ЁA1991�N6��10���j������B�����́A�p�`���R�i���́A���̗V�Y�I�j���������u�g�����Ɂv�������� ���āA�������͂����ōĂэ����\���́\�g���̎O�p�`�ɂ܂݂���B
�� ���r�Y�s���l�̌��t�i���X�A1977�N8��20���j�͒��ҏ��̎��_�W�B�q��r�Ɂu�薼�́u���l�̌��v�́A�W�����E�R�N�g�I�̒����ȉf��Ƃ̒��ڂ̊W �͂Ȃ��B����Ƃ����s�ׂ͂��Ȃ炸���l�݂�����̌����ȂĂ����Ȃ��ՋV�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ́A���̎���ςɋ������܂ł��v�i�{���A��܌܃y�[�W�j�Ƃ� ��B�u������̎���ς�ʂ��āA�M���V���ߌ��A�w�Î��L�x�ȂnjÓT�Ñ㎍�ɐG��Ȃ���A���̔����̌����T��A�|�G�W�[�̐[���ɐ��_�̐�����Җ]�̎��_ �W�v�i�ѕ��j����܂������Ȃ�A�f�͌`���́q���l�̌��\�\�܂��͏C���ɂ��ār�ł���i�̂��́q�m��ꂴ�� poesie ���߂����ā\�\�A�i���W�[�ɂ�鎍�w�����r�̘_�|���A�t�H���Y���ɋÌ������Ђ���܂ł̉́A�������̂��ƐS�n�D���j�B���̒f�́u�����̓����̉ߒ� �ɂ����鎍�l�̌��Ƃ́A�C���ɂق��Ȃ�Ȃ��v�i�{���A�y�[�W�j�́A�{�т̕W��Ɠ����ɏ����̃X���X�ƂȂ����B�Ƃ���ŁA
�k�c�c�l�T���g���[�j�̕������ЂƂ�Ɨ����Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ́A�N���[�e�[���k���o�F�N���^���l�N�m�[�\�X�̂�����~�[ �m�[�X���{�̕lj��Ɣ�r����A�����ł���B��ɋ������p��̊C�ؐ}�͂���Ƃ܂��������������~�[�m�[�X���{���܂̊Ԃ̕lj�Ɍ��邵�A�Q ���}�̉����ԟ��v���m�N���c�J�X�n�̏W�ҁm���߁n�Ƃ��ēo�ꂷ���B�i�q�ޕ��Ȃ�A�g�����e�B�X�r�A�{���A��Z���y�[�W�B�����͏��сj
�̏��o�́s�Y�p�V���t1973�N4����������A���N7�����\�́q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�ɂȂ�炩�̉e����^�����Ƃ��l�����悤�B�{���͊e����
��3�т��琬��W���\���ŁA�W��ɂ͎��ς��M����B
�@�@�T�@�m��ꂴ�� poesie ���߂����ā^���l�̌��^�o���^�U�[��
�@�@�U�@�I�C�f�B�v�[�X�^���l���ɂ��ā^�ԁE���E���E��
�@�@�V�@���̊G�^������ϑz�^�M�헬�����߂�����
�@�@�W�@�ޕ��Ȃ�A�g�����e�B�X�^�����Ƃ��Ă̕\���^�����̎v�z
�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��~�����[�g���E��Z��y�[�W�E�㐻�N���X���E���B�ڎ��̗��Ɂu����@�g
���@���v�Ƃ���B�{���̐���͌Ñ��Ղ̕��ʐ}�̂悤�ŁA�����̋g���������̃J�b�g�Ƃ͎�Ⴄ�B�\���̓u���[�O���[�̕z�N���X�ɏ����E���Җ�����F�Ŕ�
�������Ă���A���̍̂肠�킹�͋{��~�s���p�̐D���t�i1975�j���s�T�t
�����E�݁t�i1976�j��z�킹��B�@�B���̐Ԃ̊G���̓M���V�A�����ʂ��̔ʼn������������X�֕����낤���A����炵�����̂���������ƌ�����B

�����r�Y�s���l�̌��t�i���X�A1977�N8��20���j�̖{���Ɣ�
�` ���Ɉ������q��r�́u�u���l�̌��v�A������u�����߂����āv�Ƃ����B�Â��āA�u���̂̑��q�����k�}�}�l�c�����߂����āv�A�u���Ƃ�����c�����߂����āv ���A���������X����㈲�̗\��ł���B������������\���N�̎��_�ł���A�Ƃ�܂Ƃ߂āA�n����̂����قڎ��̂��ׂĂƌ������Ƃ��ł���B�ʓǂ������� ��A���ꂵ���v�i�{���A��܌܃y�[�W�j�ƌ���Ă���B���������̏��ԂŁA���Ȃ킿�{���s���l�̌��\�\�����߂����āt�i1977�j�A�s���̂̑��q �\�\�����߂����āt�i1978�j�A�s���Ƃ�����\�\�����߂����āt�i���j�̏��ŁA�g���������̎O��������Ă䂫�����Ǝv���B
�� �����q��s�L���X�����E���C�����W�k�C�O�̎��l�o���W�l�t�i���惆���C�J�A1960�N11��20���j�̑����ɂ��ẮA�c���x�̘A�ځs���惆���C�J�̖{�t �̑�15�ӂ�s�����Ă���̂ŁA���p����B�u�o���ł���Ȃ���A���ʂ���͔̂��^�����ŃW���P�b�g�f�U�C�������ׂĈقȂ�̂��u�����̎��l�o���v�� �u�C�O�̎��l�o���v�ł���B�^�W���P�b�g���f�U�C�������l�̖����L����Ă���ꍇ�ƋL����Ă��Ȃ��ꍇ�Ƃ����邪�A�킩��͈͓��Ō����ƁA�w�������j�� �W�x�i1957�N�j�͑�����F�f�U�C���A�w�g�{�������W�x�i1958�N�j�̎ʐ^�͖ї������B�e�A�w�g�������W�x�i1959�N�j�͕l�c�ɒÎq�f�U�C���A�w�� ���k�ꎍ�W�x�i1960�N�j�͈ɒB���v�ɂ��R���[�W���A�w�L���X�����E���C�����W�x�i1960�N�j�͋g�����f�U�C���ł���B�^�����Ɍf�������̂͂��ׂ� �������^�ł���A�W���P�b�g�͂�����t�����X�����ɂȂ��Ă���B�^�t�����X���u���v�ƌ������̂́A�ʏ�̃t�����X���ł���ΐ܂荞����\���Ƃ��ď� ���̖{�̂̔w�̕����ɌЕt�����Ă��܂��Ƃ�����A���̑o���ł͌Еt�������A�ق���̕\���ɔ킹�ăW���P�b�g�̌`�ő������Ă��邩��ł���B�������Ă��� �A�ԕi����Ė߂��Ă����{�ɁA�W���P�b�g���������ւ��čďo�ׂ��邱�Ƃ��\���v�i�q�S�W�Ƒo���̃f�U�C���r�A2005�N11��5���j�B
 �@
�@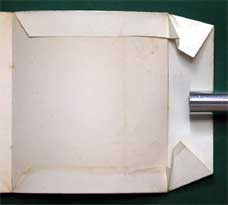
�А����q��s�L���X�����E���C�����W�k�C�O�̎��l�o���W�l�t�i���惆���C�J�A1960�N11��20���j�̕\���^�W���P�b
�g�i���j�Ɠ��E�\���^�W���P�b�g�̑����J�����Ƃ���i�E�j
�{ ���̎d�l�́A��Z�Z�~��l���~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�����t�����X���i2000�N7���A�����[�����삵�������ł������Ŋ��s����Ă��邪�A�����j�B�� ���Ɍ����ƁA�s�L���X�����E���C�����W�t�̕\���^�W���P�b�g�i�\�Q�j�̑����ɋL���ꂽ�N���W�b�g�́u�\���@�g�� ���v�i�c�����j�ł���B�k�����̎��l�o���l�Ɓk�C�O�̎��l�o���l�̔����牜�t�܂ł̊��t�i�f�U�C���Ƃ��������A�Õ��Ɂu���t�v�ƌĂт����j�͏��惆���C �J�̎Ў�E�ɒB���v�̑n�ӂ��낤����A�N���W�b�g�ɂ���u�\���v�́u�\���\���v�܂��͓c�����̌����悤�Ɂu�\���f�U�C���v���Ӗ�����ɈႢ�Ȃ��B���B�W�� �A���́A���̏㔼�g���̃|�j�[�e�[���̌��p�̏����i���҃��C���̏ё��ł͂Ȃ����낤�j���g�������̂����Ƃ͎v���Ȃ��B����ɂ��Ă��A����͊G�Ȃ̂��낤 ���A�ʐ^�Ȃ̂��낤���\�\�����āA����͒N�́i���f���ɂ���A��҂ɂ���j�B�^�C�|�O���t�B�ʂł́A�uKATHLEEN�v�́uA�v�ƁuT�v�̊Ԃ��������� �l�߂����Ƃ��낾�B�Ƃ��ɁA�k�C�O�̎��l�o���l�ɂ͏��А���ł̏d��ȃ~�X������̂ŁA�����̓s����A�{���̉��t���L�����烉�C���i�b�v��]�L����i�̂� �����g�p�A�s���́k�@�l���͏��Ŕ��s�N�����j�B
�C�O�̎��l�o��
�P�@�v�����F�[�����W�^���}���L����k�����ɂ�1959�N�Ƃ��邪�A�����l
�Q�@�A�����E�~�V���I���W�^���C�i���k1958�N1��15���l
�R�@���l�E�V���[�����W�^�E�c�ʖ��k1958�N8��10���l
�S�@�J�~���O�Y���W�^���x�ےj��k1958�N8��10���l
�T�@�S�b�g�t���[�g�E�x�����W�^�[�c���k1959�N3��31���l
�U�@�����O�X�g���E�q���[�Y���W�^�ؓ��n��k1959�N11��30���l
�V�@�L���X�����E���C�����W�^�А����q��k1960�N11��20���l
�W�@�f�B�����E�g�}�X���W�^���Y���k�ȁ����l��k1960�N8��30���l
��
�Җ��̌�A�����u����Ă��邱�Ƃ���킩��悤�ɁA���̍L���͂�����ςȂ��������悤���B���ۂɊ��s���ꂽ�Ƃ��̑o���̔ԍ��́A���l�E�V���[�����S�A�J
�~���O�Y���R�A�Ɗ������Ă��āA�{���L���X�����E���C���͂W�Łi�\���^�W���P�b�g�A���A���t��3�ӏ��Ƃ����ׂĂW�j�A�V�͂Ȃ������Ԃł���B��������z
�������̂́A���s�̏��Ԃɍ��킹�ē����̃��C���i�b�v�̃V���[�Y�ԍ���t�������Ă����ہA�Ȃ�炩�̎�Ⴂ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B��
�l�E�V���[���ƃJ�~���O�Y�̂Ƃ��͈�R���Ȃ������̂ɁA�L���X�����E���C���ƃf�B�����E�g�}�X�i���s�������̂ŁA�{���Ȃ�V�j�̍��������~�X��������
�̂́A�ɒB���v�̌��N�ɖ�肪���������߂��낤���i�ɒB�͗�1961�N1��16���ɕa�f���Ă���j�B���s�̏��Ԃ��O�サ�Ă���ɂ�������炸�A�s�k�W���b
�N�E�l�v�����F�[�����W�t�͂P�ŕs�����������Ƃ��l����\�\�{�o���ɐ旧��1956�N2��10���A���}���L����s�W���b�N�E�v�����F�[�����W�t�����Ђ�
��P�s�{�ŏo�Ă���A�v�����F�[���̖W�ɑ��銧�s�҂̋����z��������������\�\�s�L���X�����E���C�����W�t���A�����̔ԍ��ǂ���A�V�̂܂܂łƂ���
�s�s���͂Ȃ��������낤�ɁB
���҂̃L���X�����E���C���i1908-2003�j�̓C�M���X�̏������l�B�E�B���A���E�u���C�N��v�E�a�E�C�F�C�c�̌����҂Ƃ��Ă��m����B�{�W����
�̎��W�s�ޏ��t����A�^�C�g���|�G���������B
�ޏ��b�L���X�����E���C���i�А����q��j
�\�W�����E�w�C���[�h�Ɂ\
���́@���̎ւɂ��܂Ƃ�������
�����`�͒j�̏h��������o��
������q�b�͑�n�̌����痬��o��
�_�X�͎��̈ł̒��Ō`���Ȃ�
�܂���̂���B���̖ӂ����q�{���炷�ׂẲ����͂�����
���̕悩�玵�l�̖�����̂��\������B
�܂�����Ȃ��d���͂��Ƃ��Ƃ�
�ڂ����܂��Ắ@���̖��ƂȂ�
���̒��ɂ��ɖ��������
�������Ȃ����l�͂Ȃ��B���͂��̋�����@���ꂽ�R����ꏊ
�j�ƕs�������Ă��s������鏊�A�����Ď��̒Ⴂ�����ꂽ�x�b�h����
�V�������q�@�V�������z
�V�����a������B
�g ���̎��тŌ����A����́q�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�r�i�D�E14�j�����q�����r�i�C�E19�j���霂������i�ł���B�ނ��A���C���́u�ޏ��v�́u�����v �ł͂Ȃ��A���́u��v�̕������B�u�����߂�ꂽ�r���̐��E�Ɂ^�s���~�b�h�̒��_���킸���Ɍ�����^����قǏW���Ă͂��߂ā^�S���̕�e�̂����܂����̂� ���Ɂ^�����炵���N��^�����̐��������߂���v�i�q�����r�[�߂̖����j�B
�k�t�L�l
�{���̉��t���L���̍������́k�����̎��l�o���l�ŁA�ŏI�s�͖����ɏI������u�W�@�O�D�L��Y���W�^����@�c������v�ł���B�剪�M�ɂ��u�V�@�剪�M��
�W�^����@���c���v�i1960�N12��20�����j�́A���惆���C�J���o�ł����Ō�̏��ЂƂȂ����i�ɒB���v�s���l�����\�\�����C�J���t�́q����r�Q�Ɓj�B
�����Ƃ��A���t�ɋL�ڂ��ꂽ���s���ł́A�R�{���q���W�s�āt�i1961�N�k�����̋L�ڂȂ��l�j�̕����剪�M���W�������ƂɊ��s���ꂽ���ƂɂȂ��Ă���B
�k2009�N9��30���NjL�l
�c���x�s���惆���C�J�̖{�t�i�y�ЁA2009�N9��15���j�́q���惆���C�J�̖{�ׂ�r�Ɂk�C�O�̎��l�o���l�̔ԍ��Ɋւ��錩�����L����Ă���B
�@ �V���[�Y�J�n�����\�肵�Ă����w�X�y���_�[���W�x�͌��e�����������A�S�Ƃ��Đi�߂Ă����w�J�~���O�Y���W�x���J��グ�ĂR�Ƃ��A�T�Ƃ��Ċ�悵���w�u���q �g���W�x�����NJ��s�Ȃ炸�A�w�S�b�g�t���[�g�E�x�����W�x�w�����O�X�g���E�q���[�Y���W�x�����s�����B���̌�A�w�L���X�����E���C�����W�x���V�A�w�f�B�� ���E�g�}�X���W�x���W�Ƃ��ē����i�s�Ő��삵�Ă������A�w�f�B�����E�g�}�X���W�x�̑g�ł����������̂Ɂw�L���X�����E���C�����W�x�̌��e���x���A�������� �����s���������ւ������Ƃ��킩��B�w�f�B�����E�g�}�X���W�x���A�ŏI�I�ȍL�������łȂ��{���Ɖ��t�ɂ��u�W�v�ƋL����Ă���̂͂��̂��߂ł���B���� �����Čォ����W���P�b�g�����́u�V�v�ƈ�����Đ��ɏo�����B�^�ȏ�̂悤�Ȍo�܂𐄎@���邱�Ƃ��ł���B�i�����A��Z�O�`��Z�l�y�[�W�j
�c �����͖c��ȃ����C�J�{����������A���́s�L���X�����E���C�����W�t�̉��t���L���Ɓk�C�O�̎��l�o���l�̊e������|����ɂ��āA�قړ��l�̌��_�ɒB�� ���̂������B�Ȃ��s�v�����F�[�����W�k�C�O�̎��l�o���P�l�t�̊��s���́A���́q���惆���C�J�o�ő��ژ^�r�ɋ����1958�N1��10���ł���i���O�A��t ���y�[�W�Q�Ɓj�B
�O�D�B�����W�s�S���т̂̂��t�i�}�����[�A1975�N7��30���j�́A�O�D�̏\�O����ɍ�������W�s�`�̉ԁt�i���A1976�N6��30���j�̑O�N�ɁA�O�D�Ō�̒P�s���W�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B �����Ƃ����W�Ƃ��Ắs�S���т̂̂��t�̏��o�́s��{�O�D�B���S���W�k����Łl�t�i���A1962�N3��30���j������A�g�����ɂƂ��Đ��e���O�Y���W�s��̖���t�i�ԗj�ЁA1979�j�̑����̂Ƃ��Ɠ������Ԃ������ł��N�����킯���B�{������ ��т�I�ԂȂ�A�q�����Ó��́r�ł���i�u�^�v�͉��s�ӏ��j�B
�����̖�̉痴�~�^�������ā@�����@�������^���������ƂȂ�ʁ^�����������ܐ�Ƃ����^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂�Ȃ�͂�Ȃ�
�䂭�t�̂Ȃ����Ԃӂ��^�Ԃ̂���h������������^�×����m�ӂ�Ƃˁn�̐��ɂȂ����^�s�X�q�e����܂�����
���[�g���܂�̉Ԃ̏�^���Ђ�����Ӓx�����́^����ĉ����̂��ց^�����������ܐ�Ƃ����^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂�Ȃ�͂�Ȃ�
�g
�����̐��z�q���ƏҊ��r�i���o�́s���㎍�蒟�t1981�N5�����j�ɂ�������B�u�\�N�قǑO����A���ƍȂ͖��N�̂悤�ɁA�����̓������ɍs�����B��������
�����N�A���݂̂��Ƃȓ��g�̉��ɗ����Ă͂��Ȃ��B�N�X�X�A���[���Z�����Ȃ�Ƃ̂��Ƃ�����A���낻�댩�[�߂ɂ��̌܌��ɂ͍s���������̂��Ǝv���Ă���B
�^�o�s���Ȏ��������͂��ƁA�����܂œ������ɍs���悤�ɂȂ����̂́A�����S����ł͂Ȃ��B���܂��܍Ȃ̐e�����F�������A�t�����s��̊��Ƃ������ɏZ��
�ł������炾�����B���̌�����́A�ق�̐����ŁA��������ΉԖ[���Z�����A�x�������[���������Ȃ��̂��B�����G�߂�����ƁA���̗F�����́A���w��
�̖������]�ԂŒ�@�ɂ��B�����ꂽ�뉀�̕��z���ɁA���̍炫���`�������Ă���̂��B�Ȃ��Ȃ�A�뉀���͈�؉Ԃ̏����������A�����������Ƃ�A��
��������q�����邾�������炾�����B������d���Ȃ���������Ȃ��A�Ȃɂ���엿������ȂNJǗ�����ς炵�����炾�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����
�Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�`����y�[�W�j�B�g�������̐��z�Łq�����Ó��́r�Ɍ��y���Ȃ������̂́A�`���ɉi�c�k�߂̖���u���[�̓r�����s�N��
��������v�����������߂��낤�B
�{���̎d�l�́A��Z���~��Z�Z�~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�㐻�p���\���i���F���̃N���X�͒��O�ɑ��������s�����Y�S�W�t��
�ӎ��������̂��B���̂��ڂݕ����Ɣw�F���̃N���X�j�E�z�\���B����Z���Z���L�ԁB���s�����A�g���͒}�����[�ɍݐЂ��Ă������A�\�艜�t�ɂ́u����@�g���@
���v�Ƃ���B�����Ŗڂ��䂭�̂́A�����E���Җ��̋��ȏ��̂̊����ł���B�g���̓^�C�g���܂��ɍD��œ����������g�p��������A�{���̏��̂͌��̗͂̔���
���悤�ȁA���₩�Ȋ���������B�g�����ӔN�̎O�D�̎��Ɋς��̂��A�R��ɂ�����K�͓I�ȂȂɂ��̂���������������Ȃ��B

�O�D�B�����W�s�S���т̂̂��t�i�}�����[�A1975�N7��30���j�̔��ƕ\��
��
��~�E�ےJ�ˈ�E���{�G���Y�E�剪�M�s��މ̐�t�i�W�p�ЁA1988�N7��10���j�́q�̐�r�Ɓq�̐�̐��E�r��2�����琬��B�ΐ�~�E�ےJ�ˈ�E�剪�M
�q�����̊��r�A�ΐ�E�ےJ�E���{�G���Y�E�剪�q�g�t�̊��r�A�ΐ�E�ےJ�E�剪�q�[�g�t�̊��r�A�ےJ�E�剪�q���i�̊��r�̎l�̉̐傪�O���̖{���ŁA�̐��
�e�L�X�g�ɘA�����c���Ɍ�����̂��㔼�̒��߂ł���B�̐�̈ꕔ���������Ă��A��̗l�q�͂킩��Â炢�̂ŁA�q�̐�̐��E�r������p����B
�u�k�c�c�l�o��Ƃ����̂́A���q�̔o��Ȃ���������ǁA�ςɃC���q���[�}���Ȋ���������ł��傤�A���������Ė��S�ŁA�l�ԂƂ��Ă����̈���
�悤�Ȋ����v�i�ےJ�ˈ�A�{���A�����y�[�W�j�́A�ےJ���q�e�Ȃ܂��r�ʼni�c�k�߂̋���u�k�c�c�l�̐�̔���ɂȂ邭���X�Ƃ��Ă��ƌ��Ђ������A����
�����͂����ł͂Ȃ��B�������ɈЕ�������Ӌ����傾���A�s�g�ȋC�z���a�X�Ƃ������߂Ă�āA���̓_�Ŕ���ɂ͌����Ȃ��v�i�s�V�ю���2�t�A��a���[�A1980�A�Z�l�y�[�W�j�ƕ]�����̂��v�킹��B����͂܂��A�剪�M�́u�k�c�c�l����o������낢��l���Ă݂āA���̂���������Ƃ��ĘA����n�߂Ă�
�悤�Ǝv���B��������ƁA�t���ɂ����傪�����悤�ȋC�������ł��ˁv�i�{���A��l��y�[�W�j�ɒʂ��錻��o��ςł���B
�̐�̈ꕔ�ł͂Ȃ��A�܂Ƃ܂����{��������̂ɂ͎��̉ӏ����œK���B�q�[�g�t�̊��r���u�ɍ�����ĂӂĂӂ̕��Ӂv�i���V�j�Ƃ����j���̋���ŏI������
�ƁA�O�l����������ł���Ƃ���֏����́A�����������Y�̏������o���B�ےJ���Y��ɔ��������ƁA�剪������ɕt���A�Ō�ɐΐ삪�t���āi���������ΐ�
�̕M�ɂȂ�j�A�O�����ł����B���Ȃ킿�A
| �@���ɓ��R�̏�������������̂��� | ||
| �� �� �� �N �� �] �� �� �� �t | |
�ߒ� |
|
�@�� �� �� �C �� �� �� �� �� �u ��
|
�M | |
| �V �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� | ���V |
��
�����y�[�W�̂��ꂪ�A�{���Ō�̑��t�m�g�D�b�e�B�n�ł���B������́A1987�N��11���Ɂq�[�g�t�̊��r�Ɠ����O��ʼn̐�������͂��������B���ꂪ�ΐ�
�~�̎����ɂƂ��Ȃ��A�͂��炸���ےJ�ˈ�Ƒ剪�M�̓�l�ɂ����V���{�e�N�̐�q���i�̊��r�i1988�N3���j�ƂȂ������߂��B
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��~�����[�g���E��l��y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B���t�Ɂu�����ҁ@�g
���@���v�Ƃ���B�Ό��y�[�W�Ɂu�\���J�o�[�k�W���P�b�g�̂��Ɓl�^�剪�M�M�u�g�t�̊��v�̐�T�����v�Ƃ���Ƃ���A�̐�̏��\�i6��j���W���P�b�g�̕\
4�܂藠�\���ɁA�����i12��j�����\1�܂�\�\�����瑳�ɂ����āA�v18�傠������Ă���B�m���ɁA�E���獶�֗����}�����E�J���i�c�g�݁j��
�{�̃W���P�b�g�ɂǂ��z�u���邩�͔Y�܂�����肾�B�g���̓W���P�b�g���L�����Ƃ����̂܂܂Ȃ���悤�Ƀ��C�A�E�g���A������ʂ��Ă���i�ʏ�́A��
�łقډB��Ă���j�B
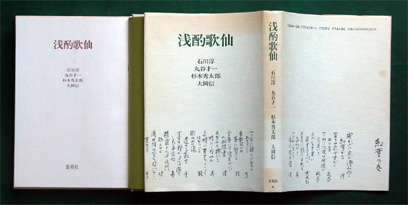
�ΐ�~�E�ےJ�ˈ�E���{�G���Y�E�剪�M�s��މ̐�t�i�W�p�ЁA1988�N7��10���j�̖{���ƃW���P�b�g
�`�P���]�_�W�s�Ԃƕ��t�i�}�����[�A1972�N9��25���j�͕W���������ɁA�S8�т̕]�_�����߂�B�k�@�l���ɏ��o�L�^��t���āA�{���̌��o���� �f����B
�Ԃƕ��\�\���{�̉i���ɂ��� �k�s�t�H�t1970�N10�����`1971�N10������12��A�ځl
�@�@��
�J�菁��Y�_ �k�������낵�l
��[�N���\�\�p��̔� �k�s���{�Ǐ��V���t1972�N5��1�����l
���s�E�r���E��� �k�ӔC�ҏW�E���c�E���Y�s�����|�p ��16���k���s �����r�� ������Ɓl�t�A�������_�ЁA1972�N6��25���A�q����19�r�l
�@�@��
���������^�P�� �k�s�|�p�����t1969�N11�����l
������������ �k�s���u�Ў���t1969�N12�����l
��������̇��قُ݇� �k�s�t�H�t1970�N5�����l
���O�_ �k�s�w�l���_�t1970�N9�����l
�@��
�q�J
�菁��Y�_�r�̈�߂Ɂu�������͎�p�I�ȍ\������������Ĉ�����ʂȔ��I��Ԃ�������őI�����邿����A���̏�Ԃ֎���Ƃ��čs�����Ƃ�����̔��I�\
�͂ƂȂ��ė����B��̍s�ׂ��A���Ƃ���J��Ԃ��Ă݂���A����͐����Ƃ������̂̈Ӗ��Ƃ�������I��ɂ��Ă݂��邽�����Ɉ��̐_�߂�ł��莩�Ȏ�����
�������B�����������Ƃ͑�������G�̉������\���Č����邱�ƂȂ̂ł������v�i�{���A��ܓ�y�[�W�j�Ƃ���B�u�������v��������������āu�G�̉���
���\���Č����邱�Ɓv�ɂ�����_�ɁA���̇��������������؏��O���̐S��������z��������B
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��܁Z�y�[�W�E�㐻�z���E�@�B���i���̃X�~�����ƓV�n�̖G���A�����̊`�̐F�т̎�肠�킹�́A�莮����z�킹
��j�B�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�`猎q�쐻�q�P�s�{�����r�i�`�P���s�l�x�̑�t�A��S����A1985�N1��1���j�ɂ͂�������B
�u(9)�Ԃƕ��@�@�]�_�W�@���a�l�\���N�㌎��\�ܓ��@�}�����[�@�l�Z����S�l�\�O�Ł@�㐻�z���@�������@����E�g�����@�艿���S���\�~�@
���^�i�k�c�c�l�j�v�i�����A�ꔪ���`�ꔪ���y�[�W�j�B
�q�i���݁j�̖{�r�̃G�b�Z�C�V���[�Y�̑�2���͂��̒P�s�{�Ƃ͕ʕҏW�́s�Ԃƕ��E�B���i�����肭�j�E�Ȃ̒�t�i1990�N3��5���j�ŁA�E�F�u�T�C�g�s��� �` �P���̕��w�Ɛ����t��
�q�̖{�̎��r�Ɂu�Ԃƕ��Ƃ̓����c���ɓǂݍ��݂Ȃ���A�����Ñォ�璆���ւ̗�����̑f���ɑ����Ĕ�]�I�ɉ����čs���B���|�Ƃ��Ă̔�]�A���
�̔�]���ӎ����Ė����Ă������҂̑�\�I�ȕ��́B�G���u�t�H�v�ɓ�N�A�ځB�u�B���v�͈Ȍ�̖����w�I�ȑn��̎p������肵�������̔�]�B�u�w�l���_�v��
���o�B�u�Ȃ̒�v�͖����V���Ђ̍��ؖ{�w�ؒ�x���������G�b�Z�C�v�ƏЉ��Ă���B
![�`�P���]�_�W�s�Ԃƕ��t�i�}�����[�A1972�N9��25���j�̖{���Ɣ�](image/hanatokaze.jpg)
�`�P���]�_�W�s�Ԃƕ��t�i�}�����[�A1972�N9��25���j�̖{���Ɣ�
�V �V�ޓ�Y�s�����̍\���\�\��i�s�ט_�̓W�J�t�i�c�����X�A1972�N10��25���j�́s���̋��t�i���_���[�A1968�j�A�s��i�s�ט_�����߂āt�i�c���� �X�A1970�j�ɑ���3���߂̘_�W�B�Ȃ������ɐ旧���ās�{���̔ޕ��Ɂt�i�v���ЁA1968�j�����s����Ă���B�s�����̍\���t�͇V�����琬��A�T �͈ꋴ�V���ҏW���ɂ��C���^�����[�q��i�s�ט_�Ƃ͂Ȃɂ��r��`���ɁA�q���ꇁ�̎��A���邢�͕��w�̂͂��܂�r�ق�11�т̘_�l�A�U�̓W�����A���E�O ���b�N�s�X�̃o���R�j�[�t�ق�11�т̏��]�Ǝᏼ�F��s�Ƃ��ꂽ���߁t�ق�4�т̉f��]�A�V�́q�w���t�̕���x�ɂ�����s����t�̖��r�����߂�B�T�̍� ��́q���d���]�\�\'70�`'72�r�����A���́q71�E11�E4�r�ɋg�����ւ̌��y������B
�@ �g�����̒��ق̂����ĂɁA���̗�������������͖ڂɂ��Ă���B�ЂƂ́A���肩�������s���ꂭ�肩�������������ǂ݂��������Ƃ̂ł���ނ̍�i�Q�� ����B����ǂ܂��A�ނ���O�A��\��̂Ƃ��o������ꎍ�W�w�t�́x���A���쏑�[���燀�p���n���鋛���̑����Ƃ��ĕ������ꂽ�B���l��N�\�ɕS���� ������ꂽ���̌��{����͈��܋�N�̃����C�J�Łw�g�������W�x�ɏ\��҂������^����A����ȊO�͎������̖ڂ��瓽����Ă������A���x�͏��Ŗ{�̒ʂ�A�O �\��ґS������������Ă���B���݂̒��҂�������݂ās�t�فt�Ƃ�Ԃ����̏������т́A�����ɂ��Ђ��₩�ȁA�Ђ��т��Ƃ����A��������E�������t��̈� ���ɂЂ�����ċ��̂悤�Ɍċz���Ă��錾�t�̂ނ�́A�����ꂳ�܂��܂ȋ[�Ԃ�ϐg����o�āA�w�Õ��x����w�m���x�̐��E�ւƉj���o�Ă����̂ł��邪�A���� ���Ɉ�ۓI�ȂЂ��₩���A�����犦���́A�|�G�W�[�Ƃ������̂̉������v���C�x�[�g�Ȓa�����̂��̂̊��G�ł���B�i�{���A����y�[�W�j
���Ȃ݂ɂ��̕��̏��o�̐V���L���i�s�����V���k�[���l�t1971�N11��4���j�́A�g���i���邢�͗z�q�v�l�j�̎�ɂ���ċg���Ƒ���SCRAP
BOOK�i�i�ԁF�R���N�g S-101�j��
�\���Ă���B�����A�g���͎�����x�M���ŁA�V�V�͂��̈��p�̑O�Łu�g�������������뎍���قƂ�Ǐ����Ȃ��̂́A�������܂��A�g�����̃v���C�x�[�g�ȗ�
�R�ɂ��̂ł���A����A�Љ�A�����Ƃ̊i���̂��������́A���̃v���C�x�[�g�Ȑ��ʂɔ��������Ȃ�ʊW�̓����コ��������ɂ����ďd�v�Ȃ̂ł�
��v�i���O�A���Z�`����y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�g���͋Ζ���̒}�����[�ŏo�ōL����S�����Ă��āA��ʎ��╶�|�G���ɂ͓���I�E�Ɩ��I�ɐڂ��Ă���
�͂�������A���̎��]�����Ώo�Ől�Ƃ��āA���Ύ��l�Ƃ��Ėڂɂ������̂��낤�B���̕������߂��V�V�̒��������Ђ���o��ɂ������ċg��������������
�����߂��肠�킹�́A�l���Ă݂�Εs�v�c�Ȃ��Ƃł���B
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~���Z�~�����[�g���E�O�O�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B���t�Ɂu����ҁ@�g�����v�Ƃ���B�W���P�b�g�E�{���̊��L�̃C���X�g
�́A���Ƃ��Η����̃^�b�`�ɔ�ׂ�Ə������f�l���݂Ă��āA�e�̏����ȂǓ����̌���̉e�����ɂ���悤���i��Җ��̋L�ڂ͂Ȃ��j�B

�V�V�ޓ�Y�s�����̍\���\�\��i�s�ט_�̓W�J�t�i�c�����X�A1972�N10��25���j�̖{���ƃW���P�b�g
�� ���r�Y���W�s�p���с@������ЂƂ��Ӗ��̒n�ɂāt�i����R�c�A1979�N9��25���j�ɂ́u���ܔ��\�\���Z��v�Ƃ����A�����炭�͎��т̐�����Ԃ̔N ���\���������āA�g�����̎��W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j�́u1959-62�v�̂���Ƃقڏd�Ȃ�B�����͏����Ɋւ��āA�����́q�L�r�Łu�����͂͂� �߁A��i���̈�т̖����Ƃāu�m�h�ɂāv�Ƃ��������̂����A���邢�͈Ӗ����`�͂�Ȃ����Ƃ����邩�Ǝv�ЁA�ŏI�I�Ɂu������ЂƂ��Ӗ��̒n�ɂāv�Ƃ� ���v�i�{���A���Z�`�����y�[�W�j�Ə����Ă���B�{���W�́qCHRISTPHER�r�q���l�̈��r�q�����Ȏ��r�q���l�r�q��r�q���r�q����r�q���N�Ɂr�q�Z ��r�q�J�C���r�q���Y�̋G�߁r�q�����r�q�h���r�q�C�V�X�r�q�m�h�ɂār�q�֎q�r�q������r�q������r�q�Z�Z�N�~�r��19�т��琬��B�q�����Ȏ��r��ǂ��� �݂ň����B�Ȃ��A���т̕\�L�͐����E�����������ł���B
�����Ă悲�ꂽ��Љ�//�n�҂̂��߂Ƀp�����//�̃e�[�u���̂��ւ̐�����ꂽ�R�b�v//������//���̊O�̐Η��̖�//�܂��@�� �̂₤�Ɍł����̂Ȃ铍�̖�//���̂��ց@���łɂ���Ă����ł̒���//�������Ӌq�Ǝ�l[���邶]
�e����̓C���[�W�̃X�i�b�v�V���b�g�ł͂Ȃ��B�u���݁v�ɕ�d���邽�߂̖����~�߂��A1�s�Ƒ��ւ��Č������B�����Ƃ��A��Ҏ��g�ɂ�邱�̎��W
�̕]���͕K�����������Ȃ��B
�u�����Ȃ��Ƃ����n���Ȃ珑���Ȃ���ΓO�ꂵ�Ă���B�������A���͂��̒n���̏\�ܔN�ԂɁw��x�w��̉��x�w�����T�x�w�����U�x�̎l���W�A���łɏK�쎞��
�̏E�⎍�W�w������ЂƂ��Ӗ��̒n�ɂāx�܂ŏo���Ă���B���̂��Ƃɂ���Ēn���̂�肫��Ȃ��͂������Đ[�܂����B���̌��W������ŁA���̗����́w����
����҂͂���ɉ��ꂽ�邱�Ƃ��Ȃ��x�Ɓw�����̍\���x�܂ŁA�ł���Ύ����̗�������i�v�Ǖ����Ă��܂������B����ǂ��A���ꂪ�ł��Ȃ��̂������Ƃ�������
�炵���B�^���̒n���̎���̋͂��ȈԂ߂͋g��������Ƃ̐e���ȕt�������������낤�B������̂���������ΏP�������A�ߐ�̒}�����[�����������K�˂��v
�i�q���]�̐l�r�A�s�����E�V��ޓ�Y���W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1993�N10��10���A��ܘZ�y�[�W�j�B
���̓V��ޓ�Y�_�̈�߂́A�s�p���с@������ЂƂ��Ӗ��̒n�ɂāt�Ƌg�����Ƃ̊W���ԐړI�Ɍ���Ă�����̂ł͂Ȃ��낤���B
�{���̎d�l�́A���l�~�ꎵ�O�~�����[�g���E��Z�y�[�W�E�����t�����X���B���ň��800���B����R�c����̏E�⎍�W�Ńt�����X���E����800���A�Ƃ���
�̂́s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j�Ɠ����A�܂��{���̍��E�ꎵ�O�~�����[�g���Ƃ����T�C�Y�́s��ʁt�i����R�c�A1983�j�Ɠ����ł���i�V�n��
�s��ʁt�������j�B�����͂܂������̋��R�̂悤�ɂ��A�Ӑ}�������̂̂悤�ɂ��v����B
����̏���F�i�́A�g����������i�ł͖{���������낤�B���̌����T�C�g�s����F�i�ˋ�
��L�t��
��1979�N�̍��Ɂu�W�u�����v�@�����@�R�@�M�������[���^���v�Ƃ��邩��A�{���̕\����͂��̈�_���B���͊G�{�s��̂Ђ�̂˂��t�i���E�M��
���q�A�ЁA1983�j�ł��A���Ɖe�̐D��Ȃ��@�����Ȍ��z���E�����m�N���[���ŕ`�������Ă���B�{���\���̐��ʂ����������A�G�{�ł̎��R�̕����A��
��킯�[�f���̉_�̎p�́A�F�ʂ��Ȃ������ɂȂ��̂��Ɣ������B
 �@
�@
�����r�Y���W�s�p���с@������ЂƂ��Ӗ��̒n�ɂāt�i����R�c�A1979�N9��25���j�̕\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�V�V�ޓ�Y���W�s���P�l�t�i�y�ЁA1980�N5��10���j�́A�g�������s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j��剪�M���s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�j�ƕ���ŁA�p���\���̎��W�ɂ�����g���������̑�\��̂ЂƂB�{���̎d�l�́A���Z�~��l�܃~�����[�g���E��O��y�[�W�E�㐻�p���\���i���E���A�w�E�z�j�E�@�B���ɓ\���Ӂi�O���[�̃N���t�g�{�[���ɉ��̐F���Ƃ�����肠�킹�́A�̂��́s���[���h���b�v�t�Ɠ����j�B���J���̖ڎ����A���̑Ό��y�[�W�Ɂu����@�g�����v�ƃN���W�b�g������B�{���͕\���́q���P�l�r�ȉ��A�q�}�X�N�ƃW���b�L�r�q���q�ҁr�q�x��ɉ����ār�q���ʌ��̎��݁r�q�^�͂ɉ����ār�q�q�V���r�ɂār�q�J�̉́r�ȂǁA�S22�т����߂�B�g���͑�11�����܂̑I�l�ψ��̂ЂƂ�Ƃ��āA�q���z�r�̈�߂Łs���P�l�t�ɐG��Ă���i��܍�͈������Y�́s���̒��̍Ό��t�j�B
�@�������������Ǝv�������W�́A�V��ޓ�Y�s���P�l�t�A���c�q���q�s�@�тƁt�A��؎u�Y�N�s�킽�����̗H��t�����āA�������Y�s���̒��̍Ό��t�̎l���ł������B�������A�\�I�͎O���Ƃ������ƂȂ̂ŁA�s���P�l�t���O������Ȃ������B�ߗ��V��N�͎��Ȃ̍z�������A�����ꂽ�U���`�̎��������Ă���Ǝv���B�����s���P�l�t�̒��ɂ͏퓅�����ꂽ��i������B�s���҂̍ԁt�́q�X��l�܂Łr�q���V���r�̂悤�Ȏ�����A�O�т���Ǝv�����B�i�s���㎍�蒟�t1981�N2�����A��O�y�[�W�j
�s���҂̍ԁt�i����R�c�A1977�j�́s���P�l�t�̑O�̎��W�B�g���̋����Ă���q�X��l�܂Łr���u�����͔ѓc���w�̋߂��Ƃ��ڂ����A�ΒY�F�̍��ː����ޕ��ɖڂł��ǂ邱�Ƃ��ł����v�Ǝn�܂�A�u����̏��͂܂����������炵����ʔZ���ȉ��ςƃh���X�ɒ������Ă��Ă��炭���̖T�ɋt���𗁂тĉ������݂��������ō����Ă������A���̐H�����i�ނɂ�Ă��悢�捕�X�Ɨr㻂̂悤�Ɉłɓ������Ȃ��炻�̖ڂƌ��Ƃ͂��悢������ƋP���o���A���̐H�����I��Ύ��͔ޏ��̐H���Ɏ����g���������炵�����Ƃ͂��悢��m���Ɏv��ꂽ���A�Ȃ������͋t�ɂ���Ă����ꂸ�A�w�ɂ����\�[�X���Ȃ߂Ȃ���A���X�ɋ���ȉe�ƂȂ��ĐH����������炨�����Ă����̂������v�ƏI���̂ɑ��āA�s���P�l�t�́q�s�A�s�r�́u�g�Ƃ͔ѓc���̂�������O�ł킩�ꂽ�v�Ǝn�܂�A�u�������������U��ނ��E�C���Ȃ��܂܂ɁA�����������߂�O�ɈӖ����Ȃ��ԗ������ڂ����̂������Ȃ������̂��ȁA����Ȃ��Ƃ������Ȃ��������͂��Ƃ���������̂ɂ͒x�����Ă��A���̐��H�ۂ���т�����Ǝ��X�ɐڂ������ʂ��������H�X�̂ǂ����̂����Â���ŏ����Ƃ����̋����͂ǂ��ɂ��ł����̂ɂƁA������������C�����v���ōl���Â����v�ƏI����Ă���B
�g���̌����u�퓅�����ꂽ��i�v���ǂ���w���̂��킩��Ȃ����A�m���Ɂq�X��l�܂Łr�̂��ƂɁq�s�A�s�r���o�ꂷ��̂ł͋ꂵ���B�`���́q���P�l�r�́A���`�t�Ƃ̗މ�������������i�V�V�ɂ́q���`�t�o���r���������j�B�g���́u���P�l�v���痴�{���h���S���̑��݂𒊏o���ĕ\���p���̑I��ɂȂ������̂��낤���A��������肾�����}���̑��ӂƖ{���ɗ��p���Ă���B
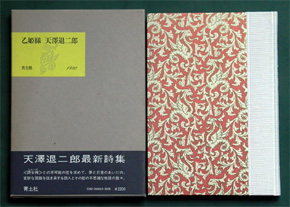 �@
�@
�V�V�ޓ�Y���W�s���P�l�t�i�y�ЁA1980�N5��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�V�V�ޓ�Y�s�s�{�V�����t�Ӂt�i�}�����[�A1986�N9��30���j�́A�s�s�{�V�����t�_�t�i���A1976�j�A�s�s�{���t���t�i���A1997�j�ƂƂ��ɁA�s�{�V�����t�O����𐬂��B�s�_�t�́A���̎ʐ^�̂悤�ɖ{���i����єw�����j�̕z�u���s�Ӂt�Ƃ܂����������ł���A�N���W�b�g�͂Ȃ����̂̋g���������ƒf�������B�V�V�́s�Z�{ �{�V�����S�W�t�i�}�����[�A1973�`77�j��s�V�C �{���S�W�t�i���A1979�`80�j�̕Ҏ҂Ƃ��ċ{�V�����̈₵���{���̐����ɐs�����������A�����̌����W�̕��͂��Ă���A���̂قƂ�ǂ́s�{�V�����t�O����ɂ܂Ƃ߂��Ă���B����́A���ɑS�W�̕Ҏ҂߂�����N�v�̌����֘A�̎咘���s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t�i�}�����[�A1991�j����Ȃ̂ƍD�ΏƂ��Ȃ��B�V�V�͖{���`���́q����o��ҁr�Łu�s�{�V�����t�v�����̂悤�ɒ�`���Ă���B
�@ �������q��i�r�̏��i�K���z���ꂽ���Ɍ����Ă͂܂�������Ȃ���̂��Ă����c�݂̔w��ɁA���邢�͌��ɁA���ݐl�������ł��Ȃ���Ҍ����ł��Ȃ��A���������҂ƌ����Ė��W�ł��肦�Ȃ����݁\�\����͂Ƃ��ɘb�҂ł����l���ł���A����ɂ͎��ݐl���̂��Ƃ�[�A�A�A�A]�ł����҂̂��Ƃ�[�A�A�A�A]�ł����肤�鑶�݁A�I���݂̂��Ƃ�[�A�A�A�A]�ł���Ȃ���Ս݂ł���A��l�̂̐��̏敨[�A�A]�ł��邩�̂��Ƃ����݁A����ł��Ă�͂薼�O[�A�A]�������̂ƌ��Ȃ��ɂӂ��킵�����݁\�\������Ƃ肠�������́s�{�V�����t�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ������̂ł���B�i�{���A���y�[�W�j
�����́q���ڂ������r�ɂ́u�O���w�s�{�V�����t�_�x���A����ɐ旧�w�{�V�����̔ޕ��ցx�i�v���ЁA���Z���j�Ȍ㎄�������������W�̕��͂̂قڂ��ׂĂ�ԗ��������̂Ƃ��ď㈲���Ă���A�������\�N���o�߂��悤�Ƃ��Ă���B���̊ԁA�������X�̐V���G���ɔ��\�A���邢�͘_�W���Ɋ�e���������W�̕��͂̂قڂ��ׂĂ�ԗ������̂��{���ł���v�i�{���A�O�����y�[�W�j�ƌ�����B�{���̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�l�Z��y�[�W�E�㐻�z���E�\���B�ʒ��{���̗��Ɂu����@�g�����v�Ƃ���B�\���͍��̒ۂŐ̓��̐��M�W���v�킹��B����Ɍ��Ԃ��p���́A�ӔN�̋g�����D�ƒ������ق鎁���،�����V�}���ŁA�������ւ��ăV�b�N�Ȃ��Ƃ��̏�Ȃ��B
�g�����s�Z�{ �{�V�����S�W�t�����Ă���ɂ�������炸�A�{�V�����ɂ��ĂȂɂ������̂����Ă��Ȃ��B���₽����сA���z�q�Ђ�߂��r���������B�g���͂����Łu����N�v�A�V��ޓ�Y�������T��A�O���Ђ́q�{���S�W�r�ҏW���ɁA�d���ɗ��Ă���B���܂ɎO�l�ŐH�����鎞�́A���쒬�����_�߂��̍����ɂ䂭�B�߂��݂������~�ɏ���ĎG�k�ł���̂��悢�B���ς��H�����邪�A�����ł͂������H���B�����Ă݂����Ȃ��̂ł���B���H�Ƃ̓V��N�̐���y��_�����Ă���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�A�v���ЁA1980�A�Z�O�y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A�������ӂɖ����Ȃ��Ƃ������R����s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�ɂ͎��߂Ă��Ȃ��B
�g������|�����V�V�ޓ�Y�̕]�_�W�⎍�W�̉������́A���҂ɂ�鑕���҂́u��w���v��������������Ȃ��B�s�s�{�V�����t�Ӂt�́A��A�̓V�V�{�Ō�̋g���������ƂȂ����B

�V�V�ޓ�Y�s�s�{�V�����t�Ӂt�i�}�����[�A1986�N9��30���j�̔��E�{���Ɠ��s�s�{�V�����t�_�t�i���A1976�N11��30���j�̖{��
�k�t�L�l
�V�V�ޓ�Y�͋g�����ҏW���s�����܁t104���i1977�N12���j�Ɂq���e�̐X���o�ā\�\�w�Z�{�{�V�����S�W�x�����E�G���ʊ��r���āA�S�W�̊��������j���Ă���B���̍Ō�̒i�����O�f�q�Ђ�߂��r�i���o�͋g���̕������N�����j�ɑΉ����Ă���̂ŁA�����B�u���Ă��čŌ�ɁA���̎��N�ԁA���������Z�{�S�W�̎d���̓��ɁA�}���̋߂��Œ��H���Ƃ����X�X�́A���Ȃ��̐�V�ɂ͂��܂��āA�m�H�Ђ����A�V�Ղ�сA�����i�������H�����j�A�����̋g��ƁA�����`�����A�H�ɃR�b�N�h�[���A���V�������T���t�@���A�ؐ��I�Č��c�̂Ƃ�ۓ��X�B�H��̃R�[�q�[�́A�֓��i�ŋߏĂ����j�A����n�E�X�A�G�X���C���A�A�}�m�A�k���A�T���E�~�b�V�F���A���X�ł������v�i�����A���y�[�W�j�B1980�N�㔼�A�����sThe INTER�Z�p�_���W�t�i���[�E�s�[�E���[�j�̕ҏW�Ɍg����Ă�������A�ҏW�����������_�c���쒬�̗��ԏ��[�r���̌����Ɂu�m�H�Ђ����v���������B�����ł悭�v���v���i����؏ē��h�q�ݖ����j��H��H�ׂ����̂��B�g���̐��z�ɂ��o�ꂷ��u�Ђ����v�́A���͂Ȃ��B
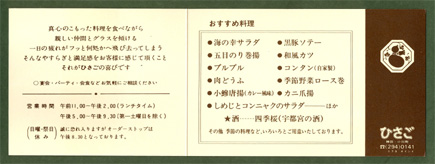
�u�Ђ����v�̓�܂�J�[�h�^�c�ƈē��i�������ߗ����Ƀv���v��������j
���e���O�Y�E���q�����ďC�s���̖{�t�S3���i�}�����[�j�́A�q�T ���̌����r�i1967�N10��20���j�A�q�U ���̋Z�@�r�i11��20���j�A�q�V ���̊ӏ܁r�i12��15���j���琬��B����52�l�̎��M�҂�i���Ė������s���邠����A�o���L�x�ȕҏW�҂̎d�������A�N���S���Ȃ̂��킩��Ȃ��B�g�����͎Ј��Ƃ��Ė{�������A���l�Ƃ��đ�U����400���l12���قǂ́q�킽���̍쎍�@�H�r���Ă���B�g���̃L�����A�ŗB�ꎍ�_�ƌĂׂ���̂ł���A�g��������ǂ݁A�l���悤�Ƃ���҂ɂƂ��Ĉ킷�ׂ��炴�镶���ł���B���g�̍쎍�@���������Ƃ̍���́A��U���́q�U �킽���̍쎍�@�r�̑��̎��M�҂����i����S���E�k�����q�E�c������E���c�O�Y�E���J�열���E���c��v�E�֍��O�E��c�G�E�Ί_���E���c�O�j�̊��l���\�����Ă��邪�A�q�킽���̍쎍�@�H�r�͂��̔ے莫�̑����ōۗ����Ă���B�`�����̔ے莫�͂������i�����͂��̂��Ǝ��������Ƃ��́u�p���v�Ɉڂ��Ă����̂����A�O�ߒi���̍ŏ��܂łʼn��ɋ����Ȃ������Z���e���X�͂킸���ɓ���B�Ȃ�������/�͘_�ҁj�B
1 �킽���ɍ쎍�@�Ƃ�������̂��ʂ��Ă��邾�낤���A�r���^�₾�Ǝv���Ă���B�����Ȃ�Ӑ}�ƕ��@�������Ď�������݂���悢�̂��A���܂��悭�킩��Ȃ��B2 ����ɁA�킽���͍����Ɏ���܂ŁA���Ȃ̎��̔��z���炻�̌`���Ɏ���ߒ����A���Ȃ��[������������A�܂�����I�Ȃ��̂����������Ƃ��Ȃ��̂��B�킽���ɂ��玍�т̍ו��̕ϑJ�\�\�v�l�A���t�̑I���ƗN�o�A�����Ă݂�Α��B�^���̔閧�͉𖾂ł��Ȃ���Ԃł���B/3 �킽���͎��������ꍇ�A�e�[�}�₻�̍\���E�\�������炩���ߍl���Ȃ��B���[���猋�����킩���Ă��܂����̂��킽���͎��Ƃ��n���Ƃ������Ȃ��Ǝv���Ă���B /4 ������킽���͎蒟�����������Ȃ��B�i���X�ŁA�X�p�ŁA�ӂ��ɑf�������Ǝv���鎍��Ȃ�Ӑ}������ł��킽���͏������߂��肵�Ȃ��B�i����`��ܔ��y�[�W���甲���j
�e�ׂɌ���ƁA/4�́u������v���������肱�Ȃ��B1 �����ɂ͊m����쎍�@���Ȃ��B2
�쎍�̃v���Z�X�⎩��̉��������C�ɂ��Ȃ�Ȃ��B/3
�ŏ����猋���̂킩��悤�Ȃ��͎̂���Ƃ͂����Ȃ��\�\�����͔[���ł���B�������A����Ɓu�蒟�����������Ȃ��v���Ƃ͒��ڊW�Ȃ��͂������A�g���͍쎍�ɂ�����u�������[�^�u���E���T]�v����ɕK�v�Ƃ��Ă���B�����������Ƃ́A�u�f�������Ǝv���鎍��Ȃ�Ӑ}�v�ɗ��邱�ƂȂ��A���M�����ӎ��̎����ɑς��A���̋�s�̉ʂĂɖK�������ЂƂʂ̐��E�ɓ��낤�Ƃ��邱�Ƃł���Ƃ��A�u�킽���͂����̕����ֈ�̖��𑖂点�Ă��̎��I��i�̍Ō�����邾�낤�v�i�����A��ܔ��y�[�W�j�Ƃ����͋傪�����Ă���B
�S3���̎d�l�́A�ꔪ�܁~���O�~�����[�g���E�l�{�O�ꔪ�{�O��Z�y�[�W�E�㐻�z���E�W���P�b�g�E�@�B���i�\�P�E�w�E�\�S�Ɍׂ���Ӂj�B���ӂƃW���P�b�g�ɂ͂��ꂼ�ꈯ�J�𐁂��p�[�����`����Ă��邪�A��҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��i�É悩�Ȃɂ����g���[�X�������̂��j�B�@�B���ɑ��ӂƂ����̂́A��������̔������₩�ŁA�\���ɂ͂Ȃ����������킢�������āA�g���͎����̎��W�ł��s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�ɍ̗p���Ă���i�����ɂ́A�u�@�B���v�̒��ł��V�n�̕�����j���ŒԂ���������ł͂Ȃ��A�ڒ��܂ŒԂ�����u�g�����v�j�B�s���̖{�t�S3���́A�\��������̎����ɕς������Ȃ��́u�V���Łv��1974�N10��20���ɏo�Ă��邪�A�g�����������͂킩��Ȃ��B

���e���O�Y�E���q�����ďC�s���̖{ �U ���̋Z�@�t�i�}�����[�A1967�N11��20���j�̔��Ɩ{���ƃW���P�b�g
�ҏW�ψ��F�������v�E�X��p�A�A�ҏW�E�Z���F�S�i���`�s�����֑S�W�k�S3���l�t�i�}�����[�A1976�j�͒����ցi1909�`42�j�̑�3���S�W���B��1���͓����}���́s�����֑S�W�k�S3���l�t�i1948�`49�j�A��2���͗B��}�����[�ȊO����o���s�����֑S�W�k�S4���A�⊪1�l�t�i���������X�A1959�`61�j�A�����Ċ��s�����u����Łv�Ə̂������̑�3���S�W�����āA��4���������ܕ��ɔŁs�����֑S�W�k�S3���l�t�i1993�j�A��5�����s�����֑S�W�k�S3���A�ʊ�1�l�t�i2001�`02�j�ł���B��������Ă��A�����ւ��}�����[�ɂƂ��Ĕ����t�⑾�Ɏ��A�{�V�����ƕ��ԏd�v�ȏ�����ł��������Ƃ��킩��B��1���S�W�ɂ��āA�a�c�F�b���s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�j�Łu���a��\�O�N�\�����痂�N�Z���ɂ����āA�u�����֑S�W�v�S�O�������s�����B����ő�O��̖����o�ŕ����܂����B�}�����[���犧�s���ꂽ���̂̒��ŁA���ꂪ�ŏ��̎�܍�i�ɂȂ����B�k�c�c�l�u�����֑S�W�v�̑��{�ɏ���������Ȃ������}�����[�̗ǐS�Ԃ肪�A������葐�Ɏc���Ă���v�i�����A�Z�Z�`�Z��y�[�W�j�Ə����āA���e�E���{�Ƃ��ɗD��Ă���_�����������B
�s�����֑S�W�k��1���l�t�i1976�N3��15���j�̎d�l�͈���~��l���~�����[�g���E�Z���Z�y�[�W�E�㐻�E�z���E�\���B�����q����P�r�Ɂu�{�S�W�̔��E���ɗp�������̃J�b�g�́A���n��W�w���ƕ��Ɩ��x�̕\���ɕ`���ꂽ���̂ŁA���̑���҂͌ɓc叕���ł��v�i���A���y�[�W�j�Ƃ���B�}���͒����̏��̑S�W�����łȂ��A���̏����o�ł���|���Ă����̂��B�g���������̌l�S�W�ɂ����āA�{�S�W�͒��̃J�b�g�i���̐F����A�\���̋��̒������ɔ����ł��Ƃ�����ۂ�^����j�������Y�S�W�ƁA�̕\���f�ށi�F����ގ��͂��Ȃ�قȂ邪�j���{�V�����S�W�ƒʂ���B�{���́A���ł̋җʂł͔��������̂��i���G�ʐ^�������Č�����j�A�����{�ł͌����Ȃ藠�������Ȃ��Ȃ����B�Ȃ��A�s���������t�i�}�����[�A1978�N12��25���j�͖{�S�W�Ɠ����̍فB
 �@
�@
�s�����֑S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1976�N3��15���j�̔��k�\�l�ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��k���l�i�E�j
�@ �ꌎ[�ЂƂ�]���O�A�����̑̓��̏���ւ̈��ɏA���āA�i�g�̖͌^�}�⓮����U�̎��̂��ƂȂǂ��v�Е����ׂȂ���j���̏��݂̂�����������Č��ẮA���̑傫���A�`�A�F�A����H���A�_�����A�Ȃǂ��A�ڂ��Ԃđz�����Č����B�k�c�c�l���̎��́A���Ƃ��ӂ��A���ڂɁA���Ƃ��ӌl���`�����Ă��E���̈݁A���̒��A���̔x�i���́U�A�������������̊�ցj���A�͂���Ƒ��̐F�A���ЁA�G�����ȂāA���̓����Ă��p�̂܁T�ɍl�ւČ����B�i�D�F�̂Ԃ�Ԃ�ƒo�܂�A�X���ǂ�A�O���e�X�N�ȃ|���v�ȂǁB�j����������ɂȂ��A���Ȃ蒷���ԁ\�\�w�ǔ����\�\�������B����ƁA���Ƃ��Ӑl�Ԃ̓��̂�g���ĂĂ��e�����ɒ��ӂ��s���j��ɂ�A����ɁA���Ƃ��Ӑl�Ԃ̏��݂�����Ȃ��Ȃė����B���͈�̉����ɂ���H�@�V�͉����A������]�̐����ɏڂ����Ȃ�����A���A���ӎ��ɏA���Ă̍l�@��m��Ȃ�����A����ȗc�t�ȋ^�₪�o�ė�����ł͂Ȃ��炤�B���Ɨy���ɓ��̓I�ȁi�S�g�I�ȁj�^�f�Ȃ̂��B�i�{���A���܁`���Z�y�[�W�k�����͐V���ɉ��߂��l�j
�k2014�N9��30���NjL�l
�s���������t�̏��e�ƒNjL���f����B�g�����͖{�����s�̔N�A���Ȃ킿1978�N11��15���ɍݐE27�N���̒}�����[���ˊ�ގЂ��Ă���A�s���������t�͎Ј��Ƃ��đ��������Ō�̈�����낤�B�������A��ЍX���@�\����̎c�������ɒǂ��Ă����g���̑���ɁA�ЂɎc������y�����̎d�������������\�����Ȃ��͂Ȃ��B�T�^�I�Ȓ}�����[�̎Г����ł���B

�������v�E�X��p�A�E�S�i���`�ҁs���������t�i�}�����[�A1978�N12��25���j�̖{�̂Ɣ�
�{���͘Z�����琬��B�l���܂ł̎��M�Җ���������B
�@�T�@�������v�E���c�~�E�[�c�v�\�E���i���F�E�g�c����E�ɓ����E�R�{���g�E�����p�v
�@�U�@���쏺���E�R�{���g�E�������v�E�͏�O���Y�E��c��j�E�R�{���g�E�g�c����E�����p�v�E��쐳���E�c��m�E�R�{�����E���i���F�E�����E����v�Y
�@�V�@�X��p�A
�@�W�@���q�E�B�{�v�t�E�������v�E�k������E�R����j�E�c�ӏG��E�y���v���E��O�~��Y�E�[�c�v�\�E����S���E��������
�������v��X��p�A�A�[�c�v�\�A���i���F�A�g�c����A�R�{���g�A�����p�v�Ƃ������]�_�Ƃ⏬���Ƃ����т��ђ�����_���Ă���B�W�ɂ́q�����֑S�W�ʐM�r�q��\�܉�H��ܑI�]�r�q��O���o�ŕ����ܐR�����]�r�̂ق��A��3���q�����֑S�W�i����Łj���E�̎��r�����߂��Ă���B�T�́q�����ցA���̐��E�̌���}�r���Ïk�������i���F�̐��E���q��������r�������B
�@�Ⴍ�������Ƃ͒N�����A�ޓ����ʂ����Ƃ̏o���Ȃ����������v�ӂ��Ƃň��ɂ��͂܂�Ȃ����A�����ւ̏ꍇ�͓��ɂ��̊����[���B�ނ͑�w���o�ď��w�Z�̋��t�ƂȂ�A���t����߂ē�m�̃p���I�w�s���A�A�����ĕ��ɂ�ė����ӂ������Ƃ���ŁA�������B���������̍�i�́A����ɜ߂��ꕨ�ɜ߂��ꑶ�݂ɜ߂��ꂽ�v�z�I�ȏ�������A���E�̈��ӂ�̞y�̂Ȃ��ɑ��ւ��q�ϓI�ȏ����܂ŁA����������i�͂��̊����x�ɂ�āA�����̍�i�͓����Ɋ܂܂ꂽ�\���̗ʂɂ�āA���ׂč������ꂽ�₤�ɐV�N�ŁA���������ɌÓT�ƌĂԂɂӂ��͂����B���̐��߂���́A����̕��w�I�ӓׂ̖��ɂ����₭�A��̂���ׂ̐��ł���B�i�{���A�O��l�y�[�W�j
�X�ƇY�Ɋւ��ẮA�{���̕ҎҌS�i���`���q�ҏW��L�r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u����܂ł̑O���͒������w�ւ̈ē����ł��邪�A�㔼�͏������ςւāA���͂�錤�����Ƃ��Ă͗ނ̂Ȃ����Ƃł��邪�A�ʂ̕��@���ƂĂ݂��B���Ȃ͂���u���Ƃ��āA�����ւ̈ꑰ�Ɋւ��ďo���邾����̓I�Ȏ��������߂����Ƃł���B���͎U�킷����̂����炤���Ǝv�ЁA���̋@��ɂȂ�ׂ������̎�����|�����Ă��������ƍl�ւ����ʂł���B�^�k�c�c�l���͂��̐l�k�ʐU����␁l�̒��ɒ����Ƃ̉Ɗw���p������Ă��Ǝv�ӁB�����R�́u�T�c�O�搶�`�����L�v�₵���J��́A�܂����̐l�̓Ď��Ȑl���Ɗw��Ƃ������ɍł��ӂ��͂�����Ǝv�͂��̂ŁA��Y���Ƃ��Ď��߂邱�ƂƂ����v�i�{���A�l�܈�`�l�ܓ�y�[�W�j�B�{���̎d�l�͈���~��l���~�����[�g���E�l���Z�y�[�W�i�������m�N���̌��G���l�y�[�W�j�E�㐻�E�z���E�\���B�V�n��̂`�T�ό^���A�㐻�E�z���E�\�����̎O���{�S�W�i�s�����֑S�W�t�j�Ɍ��������ꊪ�i�s���������t�j�B���̊����ĂɁA���肤�ׂ��s�g�����S�W�t�̎p������z��������B
�s������{���{��n�k�S97���l�t�i�}�����[�A1968�`73�j�̑����ɂ��āA�����Ƃ̒������ق鎁�̓C���^�����[�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�ł����،����Ă���B
�\�\�@��������Ƌg�����k�Г��́l����ŋ�����Ƃ��ꂽ���Ƃ͂���܂����B
�����@��ƂȂ�A���ƂȂ�ł���`�������Ă��������܂����B���Ƃ��Ή��F���N���X��\���Ɏg�����w������{���w��n�x�i�S�㎵���A���Z���\���O�N�j�Ȃǂ������ł��ˁB���̃}�[�N���A�g�����u����Ȃ̂ǂ��H�v���Ă��`���ɂȂ����̂ł���B
�\�\�@���^��Ɩ��͏��������A���̑��̕����͎ʐA�ł��ˁB
�����@ �����ł��ˁB������������ȑS�W�̃^�C�g���͏��������ł����ˁB�w���E���w�S�W�x�i�S�Z�㊪�A���Z�Z�\���Z�N�j��w�}�����E���w��n�x�i�S���㊪�A��㎵��\�㔪�N�j�������ł��B�S�����炢�̑S�W�͏��������ɂ���̂��A�Ȃ�ƂȂ����܂莖�̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�i�s�����C�J�t2003�N9�����A��l�܃y�[�W�j
�C���^�����[�L���̌f�ڎʐ^�L���v�V�����Ɂu�w������{���w��n�x��41���@�}�����[�A1972�N�A���v�i�����A��l��y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�����Ō��y����Ă���̂́s��ƌ����E�R���钹�E���m�K���Y�E�����y�V���E����Ď��Y�E�x����{�E�g�c���E���e���O�Y�W�t�ł���A����ʐ^���ڂ����s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�A5���F1977�N5��30���k���ŁF1973�N4��5���l�j�̃^�C�g���̏��������́u���㎍�W�v�ł���B�ȉ��ɖ{�S�W�̊e���^�C�g�����f����B
���������E�ؓ�疗y�E��t���l���W�^����@�g�E���]�����E���x�h��E�O����E���q�V�S�E�����ӎO�W�^����g�t�E�L�Ö��Q�E���c�D���E�֓��ΉJ�W�^�K�c�I���W�^�����t�E�����������w�E�ԏW�^�k�����J�E�R�H���R�W�^�X���O�W�i2���j�^���y�b�ԁE�؉����]�W�^�����q�K�E�ɓ�����v�E���ːߏW�^���ؓc�ƕ��E�c�R�ԑW�^�y��Ӑ��E���c��俁E�����L���E�ɗǎq�����E������J�E�͈���䪁E�O�ؘI���E�����ԔV��W�^���蓡���W�i2���j�^���c�H���W�^���@�����W�^�Ėڟ��ΏW�i2���j�^���l���q�E�͓��Ɍ�ˏW�^���c���j�W�^���A�E�^�R�ʁE��i�����E�ߏ��H�]�W�^�K���H���E��͐�E�c����_�E�吙�h�E�r�������E�͏㔣�W�^�i��ו��W�i2���j�^�^�Ӗ슰�E�^�Ӗ쏻�q�E��c�q�E�؉��ۑ��Y�E�g��E�E���R���O�E���c�G�Y�E���o�C�W�^�k�����H�E�ΐ��؏W�^���������Y�E�{���W�^��R�q���E���c����E�E�c���E�O�c�[��E�y��P���E��c���E�ѓc��━E�����H���q�E�R�����q�E�������c�j�E������絁E�Γc�g���W�^��؎O�d�g�E�X�c�����E���c�ЕF�E���c�S��E�������W�^�J�菁��Y�W�i2���j�^�H�c�J���E���얢���E�ؓc�����E�c���r�q�E���і��z���W�^���ҏ��H���ďW�^�u�꒼�ƏW�^�L�����Y�W�^���^�P�Y�E���퐶�q�W�^�������E�v�ۓc�����Y�W�^�֓��g�W�^���ؐԕF�E���[�E�������g�E�y�������E�؉������E�Ð��~�E��Ô����W�^���Z���b�E���{�\���E�������Y�E�a�ғN�Y�E���c���]�E�q�c�S�O�E���J��@���ՁE�ҏ��W�^��ƌ����E�R���钹�E���m�K���Y�E�����y�V���E����Ď��Y�E�x����{�E�g�c���E���e���O�Y�W�^�����t�v�W�^�H�열�V��W�^�R�{�L�O�E�e�r���W�^����둾�Y�E�L���^�u�Y�E�v�Đ��Y�E��������Y�E�����ؖ��W�^�F��_��E�L�Øa�Y�W�^�����Ґ��E�����Y�W�^���F��E�Ԗ�e�E���}�Òj�W�^�����P���E���n�O�E�{�n�ØZ�E�Ñ��E���E��蒷���Y�E�؎R�����W�^����m�Y�E��m���Y�E�ڑ�����ǏW�^��������E�ɓ����W�^��[�N���W�^��Ŏ��Y�E�ݓc���m�E��c�L�Y�W�^�Џ�L�E���я��V��E��G�g�E�{�{�����E�����Ґl�W�^�{�{�S���q�E���ё����W�^�t�R�Î��E�����`���E���т����q�W�^����d���E������q�W�^���R�m�`�E�v�ۉh�E�^�D�L�E�O�D�\�Y�W�^�O�c �͍L��Y�E���i���E�ɓ��i�V��E���h�W�^���яG�Y�W�^�і[�Y�E�T�䏟��Y�E�ۓc�o�d�Y�E�@�c�P���W�^�q��M��E��_����E�\��J�`�O�Y�E���{���E���͗^��E�������W�^�����Y�E�O���ɁE�����֏W�^�x�C�Y�E�O�D�B���W�^�䕚����E��ыŏW�^�͏�O���Y�E�R�{���g�E�g�c����E�]���~�W�^���q�����E���F�G�Y�E�k��~�F�E����\�O�Y�E�����V�g�E���������Y�E�R�V�����E�ɓ��×Y�E��������E���������E����S���E����l�Y�W�^�����Y�E���R�`�G�W�^�ѕ����q�E�F����E�K�c���W�^���c�ّ��Y�E���،���E�D�c��V���E�h��Y�W�^�������E�~�n���q�W�^�O�H���Y�E���{���̎q�W�^�����m��E�ۉ����E�c�{�ՕF�E���J��l�Y�W�^���������E�͐��D���E����D�v�E�K�����v�W�^�ΐ�B�O�E�Ζ숯���W�^�ΐ�~�E�������[�E��]���O�Y�W�^���Ɏ��E�������W�^�������v�E���؏��O�E�P��g���E�|���D�W�^�{���H�܁E���쌪�E�r���l�E���J�Y���E���c�؏G�Y�W�^�Ŗ��َO�E�~��t���W�^��ԍG�E���c�~�W�^��������E�����^��Y�E���i���F�W�^�X�{�O�E�؉�����E�c����ѕv�E�ёW�^�ԓc���P�E���Y�����E�J�����E���c���W�^�剪�����E�O���R�I�v�W�^�����E�i�䗴�j�W�^�x�c�P�q�E��������E�������W�^����O�V�E���쏁�O�E�]�숻�q�E�k�m�v�W�^�[�Y�E�O�Y���E�L�g���a�q�E����W�^�����q�Y�E�����M�v�E�����͑��Y�E�g�s�~�V��W�^���㖼��W�i2���j�^���㎍�W�^����̏W�^�����W�^���|�]�_�W�^����]�_�W
�s���㎍�W�t�͕x�i���Y�A�����~�ʁA�팩�P�g�A�c���~��A�|����A���A�ێR�O�A���Ɏ��A�k�����ʁA�J��r���Y�A�|�������Y�A�ѓ��k��A�R�{���Y�A�J���A����M�v�A�c������A�剪�M�A��c�j�Y�A�g�����A������s�A��c�G�A�������j�A�V�V�ޓ�Y�A�������A���V�N�v�A�Ί_���A�F�V�F��̎��W�A�c��m�q����r�A��t�����q�N���r�����߂�B�c��3800���߂����₵�āq���r�i�C�E3�j�ɐG��Ă��邪�A�g���͂����ڂɂ��Ăǂ�Ȋ��S�����������낤���B
�{���̎d�l�́A��ꔪ�~��l���~�����[�g���E�l�O�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�\���B�������͑O�f�C���^�����[�Łu�\�����J�����Ƃ���ɂ��錩�Ԃ��ɂ��ẮA�g������͒W�N���[�����E���ȂǁA�����N���[���F���D��Ŏg���Ă��܂����B���܂�͂����肵���F�̌��Ԃ��͍D�܂�Ȃ�������ł��B�i�`�������ȁA���邳���Ȃ����B��ʓI�ɂ͕\���̐F�Ƃ̃o�����X�ŁA���Ԃ��ɂ͂�����ƐF�̂�������p���邱�Ƃ������̂ł����A�\�����J������A�������炷�łɖ{�����n�܂��Ă���Ƃ����ӎ����g������ɂ͂������Ǝv���܂��B����ƑS�W�͂����Ă������ďd���̂ŁA��͂��v�Ȏ��łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��������ł��傤�ˁB��N�́A�t�@���V�[�E�y�[�p�[�ł̓V�}���������D���ł����ˁv�i�����A��l�O�y�[�W�j�A�u��قǂ��\���グ���悤�ɁA�ϋv��������A��������Ƃ����d��������Ƃ����̂��傫���ł��ˁB�u�{���Ă��̂͏d���Ȃ�����v���āA�g������A�悭����������Ă܂����B�����������Ђ̑����{���o���オ��ƁA�܂��d������ŗʂ��ł���B�u���̏d�݂������v���āi�j�B�����āu�O�������Ȃ��A���ǂ��Ȃ��A���N�����Ă����I�ɒu���Ă��邳���Ȃ��{�������v�Ƌg��������������Ă����̂͊o���Ă��܂��v�i���O�A��l�܃y�[�W�j�ƌ���Ă��邪�A�m���Ɍ��Ԃ��p���͔����N���[���F�ŁA�{���̏d�ʂ�900�O����������B�}�����[�̕��w�S�W�ɂ�����g���������̑�\��Ƃ�����{�S�W�ɂ��G��
�u�����i����̃}�[�N�I�j���Z�߂��Ă��āA�u�g���D�݁v���т��p�����s���e���O�Y�S�W�t�Ȃǂ̌l�S�W������ꍇ�ƕς��Ȃ��B�Ȃ��\���̕��Ɣw�̃}�[�N�̊ۂ́A�������邱�Ƃ̂ł������Łi1973�N4��5�����j��5���i1977�N5��30�����j�͐Ԃ����A11���i1981�N11��1�����j�͍��ŁA�����Ȃ�Ӑ}���s�������A���鑝���̎��_�ŕύX�������̂Ǝv�����B

�s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�A5���F1977�N5��30���k���ŁF1973�N4��5���l�j�̔��Ɩ{��
�g�����������E�V���Ȃ́s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�̎�̎������������s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�͐V���E�V���Ȃ��̗p���āA��́s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�̒�{�ɂ��Ȃ������A�{�S�W�ɂ͂��̎v���ДŎ��W���{�ɂ����s�m���t�S�т����߂��Ă���B�s���㎍�W�t�ł́s�m���t�̖{�����s������{�����W�听11�t�i�����n���ЁA1960�j�ł̂���ƈقȂ�A������ׂ��Z�����Ă���B���Ȃ݂ɁA��{�̎v���ДŎ��W�͂Ђ炪�Ȃ̏������g�p���Ă��Ȃ����s���㎍�W�t�ł͎g�p���Ă���A��{�͎U�����^�̍s���ɂ���S�p�A�L�����e���Ă��邪�{�S�W�ł͋��e���Ă��Ȃ��A�Ƃ������g���̊�{���j�̈Ⴂ������B�ׂ������Ƃ����A�ȉ��̊����Ɉٓ�������i�Ȃ��k�g�l�́s�g�������W�t�A�k���l�́s���㎍�W�t�A�k�S�l�́s�g�����S���W�t��\�킷�j�B
�@1. �R�ԁk�g�l�\�R�x�k���l�\�R�ԁk�S�l�i�q�Ō`�r�C�E11�j
�@2. �K�w�k�g�l�\�D�w�k���l�\�K�w�k�S�l�i���O�j
�@3. �����k�g�l�\�����k���l�\�����k�S�l�i�q��́r�C�E13�j
�@4. ���O�k�g�l�\���O�k���l�\���O�k�S�l�i�q�r���r�C�E15�j
�@5. ���a�k�g�l�\���y�k���l�\���y�k�S�l�i�q�l���r�C�E17�A��ӏ��Ƃ��j
�@6. �y�����k�g�l�\�������k���l�\�������k�S�l�i�q�����r�C�E19�j
�s�m���t�e���т̌��e�i�z�q�v�l�̓��e���e�j�̖{���A���o�`�E���Ō`�E��e�`���ꂼ��̈�����i����т��̍Z�����j�̖{�����r���邱�Ƃ́A���W�s�m���t�̐����������������ꏕ�ƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B���́s���㎍�W�t�̖{���́A��e�`�̈�ώ�Ƃ��ďd�v�ȕ����ł���B
�\��̌㔼����A���N�ĂɂȂ�Ɛ��e���O�Y�̎����ǂ݂����Ȃ�B1975�N�̐��Ăɓǂs���e���O�Y�S�W�k��1���l���W�T�t�i�}�����[�A1971�N3��5���j�́A���߂ĐG�ꂽ�������l�̑S�W�������B���́s���e���O�Y�S�W�t��1971�N����73�N�ɂ����đS10���Ŋ��s���ꂽ�B���e�𗪋L����B
�@�k��1���l���W�T�i1971�N3��5���j
�@�k��2���l���W�U�i1971�N5��6���j
�@�k��3���l�W�i1971�N7��6���j
�@�k��4���l���_�T�i1971�N10��15���j
�@�k��5���l���_�U�i1971�N12��20���j
�@�k��6���l���w�_�T�i1972�N2��25���j
�@�k��7���l���w�_�U�i1972�N4��28���j ����ɋg�����q�f�Ўl�́k�̂��q���e���O�Y�A���x�X�N1�r�Ɖ���l�r���f��
�@�k��8���l���w�_�V�i1972�N6��30���j
�@�k��9���l���w�_�W�i���g�j�i1972�N8��30���j
�@�k��10���l���w�_�X�E���M�E�������сi1973�N1��20���j
����10���{�S�W�̑�10����҂݂Ȃ����A��11���ƕʊ��₵���̂��A1982�N6�����痂�N7���ɂ����Ċ��s���ꂽ�s����
���e���O�Y�S�W�t�ł���B�ύX���E���╪�̓��e�𗪋L����B
�@�k��10���l���w�_�X�E���M�i1983�N3��19���j
�@�k��11���l���W�E�������сE�E�⎍�сE�G�сE�ق��i1983�N4��25���j
�@�k�ʊ��l���e���O�Y�A���o���E��v�������W�E���e���O�Y�����i1983�N7��20���j �g����
�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�����^
1993
�N���A���a100�N�L�O�o�łƂ��ās��{
���e���O�Y�S�W�k�S12���E�ʊ�1�l�t�̊��s���n�܂����i�����S�����L���Ă���̂͂��̔Łj�B���e���{�ɂ͑��{�E�̍قƂ��āu�`�T���E�㐻�E�N���X���E�\
�����E����656�ŁE���G�꒚�E����8�ŁE�艿�e���s���v�ƌ����A�q�{�S�W�̓��F�r�ɂ�������B
�@�E����łł͑�1��w���e���O�Y�S�W�x�Ȍ�ɏW�߂�ꂽ���܂��܂Ȏ�ނ̒����X�I�ɑ�11���Ɏ��߂����A��
��1���������邱�Ƃɂ���Đ�������i�ʂɔz���\�������������B
�@�E���ɂ��Ă͑���łł͂Ȃ��A���S�Z�������w��{���e���O�Y�S���W�x�Ɋ�Â��Ď��^�����B
�@�E��3���Ɂu���e�m�[�g�v�i��80���j�����߁A���܂Œm���Ȃ��������e���̐��ȉߒ��̈�[�𖾂炩�ɂ���B
�� �ŁE����ŁE��{�̊e�S�W�ɂ́A���R�Ȃ���s���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1963�j�Ɓs��{ ���e���O�Y�S���W�t�i���A1980�j�̐��ʂ����f����Ă���B�����̂Ȃ��ŋg������������S�������̂����őS�W�ł���B���̑��{�E�̍فA�u�`�T���㐻�\ �����E�\���o�N�������E�{��9�|1�i�g�E����600�ŁE���G1���E����8�ŕt�v�i���e���{�j�͂��̂܂ܒ�{�S�W�Ɉ�������Ă���i�{���g���A��ŐG�ꂽ ���̈ȊO�͊�{�I�ɗ��p�̂悤���j�B���̌��őS�W�̓��e���{�͂a�T���E���Ԃ��E12�y�[�W�E�\���̂�2�F�̗��h�Ȃ��̂ŁA���E���\�\�剪�M�A����l�Y�A�� ���C���A�����ّ��Y�A����M�v�A�r�c�����v�i�剪�́q���e���O�Y�̐��E�r�ƒr�c�́q��̏d�݁r��������{�S�W�̓��e���{�ɓ]�ڂ���Ă���j�\�\��3�y�[ �W���߁A�ȉ��A�ɓ��M�g�́q���e���O�Y�̌̋��r�A�S�����e�E���e���O�Y���N���Ɓi���̊Ԃɏ��e��ё��ʐ^�Ȃǂ�����j�A�l�S�W�̏����q�^���e���{�̓T �^�̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��邪�A���̏����q�̃��C�A�E�g���g�����̎�ɂȂ邩�͕s�����B���Ȃ݂ɒ�{�S�W�̓��e���{�̎d�l�́A�a�T���V�n�J�b�g�E�ω��� ��E8�y�[�W�E4�F/2�F�ł���B
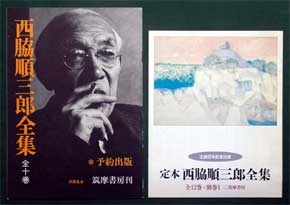
�s���e���O�Y�S�W�k�S10���l�t�i1971�`73�j�Ɓs��{
���e���O�Y�S�W�k�S12���E�ʊ�1�l�t�i1993�`94�j�̓��e���{
�s�� �e���O�Y�S�W�k��1���l���W�T�t�̎d�l�͓��Z�~��l���~�����[�g���E�Z���y�[�W�E�㐻�E�N���X���E�\���B�\���̐Ԃ́A�͂邩�ɐ��e���O�Y���W �sAmbarvalia�t�i�ł̖؎ЁA1933�j�̔��E�\���̃��C�����b�h��z�N������B�]�k�Ȃ���A75�N�O�Ɋ��s���ꂽ���̈��̖����W�͍�������} ���قŎ�ɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A���̂���{���p�������Ă��āA�y�[�W���J��͂�����ق�ق�ƕ��ꂨ���������B�{�S�W�̃J�b�g�́A���̉Ԃ̊G���� �߂āA���ׂĐ��e�ɂ����̂��낤�B�P�c�����́q�g�����E�Ȑ܋v���q�\�\�o�ŎЂ̃J���[�����������́r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�����ЂƂg���̑��������Â���̂́A�J�b�g��G���u�����̍I�݂Ȏg�����ł���B
�@���������ƃJ�b�g�ނ����ʓI�ɋ������킹��Z���X�́A���łɐG�ꂽ�悤�ɋg�������`���o�ɂ�����Ă������ƂƁA�G��⒤���Ɏ����I�ȊS���Ă������Ƃ��傫�����������Ă���B
�@�����́w���e���O�Y�S�W�x�i�S�\���A�}�����[�A����N�j���Ƃ����Ă悢���낤�B���e�Ƃ͂�����t��W�ɂ������킯�ł͂Ȃ����A�����Ƃ��ɂ������͒����A�ӂ���͌����M���W�Ō���Ă����悤���B���e���O�Y�S�W�ɂ͐��e���g�̃y���悪���ƕ\���Ɍ��ʓI�ɃA�����W����Ă���B����̓��_����̉~�^�̂Ȃ��ɁA���≡�����̕w�l����`�������̂ŁA�{�S�̂̂Ȃ��ł݂��Ƃɏœ_������ł���B���e�Ƌg���A����ɒS���ҏW�҂̋�����Ƃ̌ċz���҂�����ƍ������A����������߂��d�オ�肾�B���̑S�W�́A�g���炵���Ɠ����ɁA�}�����[�炵�����\�S�ɔ�������Ă���悤�Ɏv���B�i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A����y�[�W�j
�P�c����́A�g���������̓����̂ЂƂ߂Ƃ��āu�k�c�c�l�����g���́u�O���k�O�i�����̐V���L���l�v�ɒ��ڂ���̂́A����ɂ����Ă��⊶�Ȃ����̖��l�|�Ԃ肪��������Ă��邩�炾�B�ӂ��̖��l�|�������Ŏx���Ă�����̂́A�Ђƌ��ł����u�O���v�̎�v�f�ނł�����������A����������̂ւ̕Έ��ł���v�i���O�A�Z�O�y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A�������B
�Ƃ���ŁA�g�����s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j��s��ʁt�i����R�c�A1983�j�ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂻ�̎��́s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j��s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�̑����ɐ��e�̑�����N�p���Ă���̂́A���e�̊G�Ŏ��g�̎��W�����邽�߂������̂ł͂Ȃ����B�����́u�J�b�g��G���u�����v�ł͂Ȃ��A���W���u���v�����߂́u��v�������B
�k2013�N9��30���NjL�l
��������}���فi�����فj�����̐��e���O�Y���W�sAmbarvalia�t�i�ł̖؎ЁA1933�j�́A���̌�f�W�^���f�[�^������A����͍��̂Ƃ���ٓ��ł̂݉{�����\�B�{���ŐG�ꂽ���{�́u���p�s�v�̈����ŁA���ݎ�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i���فE�����{�����̈�{�����l�j�B
 �@
�@
�s���e���O�Y�S�W�k��1���l���W�T�t�i�}�����[�A1971�N3��5���j�̔��E�\���i���j�Ɩ{���E���i�E�j
�s�u���v���̂ق��̎��t�i�v���ЁA1977�N4��15���j�́s�Â��y�n�t�i���R���A1961�j�ȗ��A�v���Ԃ�ɋg������������������N�v�̒P�s���W���i���̊Ԃ�1973�N�A�y�Ђ���S���W�s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1970�t���o�Ă���j�B�{���W�ɂ́u�g�������ցv�ƌ����̂����т����^����Ă���A����܂��ċg���������ƂȂ������̂��B���Ɩ{���ɂ��鑃�̒��̒��̗��̃J�b�g�́A����W�s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�j�̋����ҁE�����ł���B
�g���Ɂu�h�A�̃m�u�̂��炩�����|�v�Ƃ���������܂ށq�؍݁r�i�E�E7�j�����邪�A���j�I����������p����悤�ɂȂ�������ɂ�����Ɓu��͂炩�����|�v�ƂȂ�A���ꂪ�g����������̈��p�ł��邱�Ƃ��������߂Ɂs�@�t�Ŋ����Ă���B���͋g���ɕ���Ď��т̑薼���q�@�r�Ŋ����ĕ\�L���邩��A�R���ʂ̘A���ɂȂ�̂����������������������A�q�s��͂炩�����|�t�r�S���������āk�@�l���ɓT���ƂȂ����g���������f����i�{�т��s�����C�J�t1973�N9�����́k�g�������W�l�ɔ��\���ꂽ�Ƃ��̃^�C�g���́q�s���炩�����|�t�r�ŁA�����͂Ȃ������j�B
�s��͂炩�����|�t�k�q�؍݁r�E�E7�l�\�\�g�������ցb����N�v
���Ƃւ@���̈�тɂ��Ă��炪�@�Ȃ�
�s�������Ƃ͊W�Ȃ��t�k�q�t�̃I�[�����r�E�E10�l
�������@�����ɂ��Ȃ����̂ЂƂ�
�s�������炾�S�̂ɒ���o���āt�k�q�͎ʁr�E�E4�l�j���ł���
���Ƃ��炽�߂Č��ӂ܂ł��Ȃ��@�����
�����ȂɂƂās�̂��ނƂ���łȂ��@���ޏp���Ȃ��t�k�q�����r�D�E3�l
�s�i�N�̌o������t�k�q�����r�C�E18�l�˂ɂ��Ȃ���I�m�Ɂs����t�k���O�l���肩
���̈�т���@���̈�тց@�����Ă���Ɏ��ւ�
�s�����т́t�k�q�����r�C�E19�l��s�@���I�ȂȂ���t�k���O�l���J��o����
����́s�X�C�J�t�k�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�F�E6�l���������
���̉ʂɗӌ�����C��s�s�̖����킫�N����
����قNj���ׂ���̂̓q���������ɑ����ĉ\�ł��炤��
�����ɂ́@���ł��s�����ȉΎ�������
�M�ƕ�������ꏊ�����t�k�q�T�[�J�X�r�I�E2�l��
���̂��������@���ЂĐ�������Ȃ��
�s�����֕R�����炵����
�_��I�ȌC�t�k�q�Ă���H�܂Łr�F�E2�l
���̌C�̓B���s�`����I�����t�k�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�F�E6�l�ɑł����
���ˏ��I�@�S�̉��n�ǂ���
������x�o�T�����Ă݂悤�B�C�E18�A�C�E19�A�D�E3�A�E�E4�A�E�E7�A�E�E10�A�F�E2�A�F�E6�A�I�E2�B�E�́s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1967�j�͓��{�т����M�������_�ł̋g���̍ŐV���W�����A��������̈��p�������̂��ڗ��B�F�́s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�͂܂���{�ɂȂ��Ă��炸�A�F�E2�ƇF�E6�͂����炭�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�́q�������т���r����̈��p�ŁA��L9�т͂�����������Ɏ��^����Ă���B�E�ƇF��5�тŁA���p���ꂽ���т̉ߔ������߂Ă���A�ߍ�̋g�������ɑ������̐e�t���݂�z��������B
�s�u���v���̂ق��̎��t�̎d�l�́A���l�~��O��~�����[�g���E�㔪�y�[�W�E�㐻�p���\���i���E���A�w�E�N���X�j�E�\���ŁA���s���͋��R���낤���g����58�̒a�������B�ßT�ȃO���[�̗p���i���U�b�N�j�Ƒ�_���אS�ɑI�ꂽ�[�g�̃N���X���A���܂��܂ȏ��@����Ȃ�19�с\�\�{���̑тɂ́q���@�̒m�I�\���r�Ƒ肵�āu���l�ȋ��܂����m�I�\���ɂ���āq����i�r�̐[�����@�肳���A���̃t�B�[���h�������ɒT��A�Ǝ��Ȏ��@�̖��H�Ɩ��͂�W�J���钘�҂�4�N�ԁk���W�̔��ɂ́u��㎵�O�`��㎵�Z�v�Ƃ���A�g���́s�T�t�����E�݁t�̎��M���ԁi1972�`1976�j�ɂقړ������l�ɂ킽��V��19�сv�Ƃ���\�\�𑩂˂āA��ۓI�ȑ��{�ł���B�N���X�̐[�g�́A�ݒ�ᇂɂ��f����z�킹�Ȃ��ł��Ȃ��B
��҂ɂ��s�u���v���̂ق��̎��t�́u����ĊJ��̍ŏ��̎��W�B�\��Ɂs�يC�m�t�Ƃ�������܂ގ������т���܂����A����͓����������ݒ�ᇂ̂�����ł��B���^��̐���́A��㎵��N����n�����{����e�S�ʓI�Ē����ƐV�S�W���s�̎����ɏd�Ȃ��Ă��܂��v�i�s�k�O�����w�ٓ��ʊ��W ��10���Y��ғW���� ����N�v�W�}�^�l����N�v�\�\����N�v�̃o�b�N�O���E���h�t�A�����Y�L�O���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2003�N9��15���A�O�Z�y�[�W�j�Ƃ������ƂɂȂ�B���̐}�^�ɂ͎��W���J���[�̃L���k�L�ʐ^�Ōf�ڂ���Ă��邪�A���̏��e���Ɣ����W���P�b�g���\�����킩��Ȃ��B�����ɑ����Җ��̋L�ڂ��Ȃ��̂��ɂ��܂��B�q���W�r�̔��̔����ʐ^�i���Ȃ�傫�Ȋp�Łj���A7���i�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t�s�Y�ӏM�t�s���Ӌt���́t�s���҂����̌Q���镗�i�t�s�S�t�s砂����y�t�s�킪�o�_�E�킪�����t�j�ȂǂƂ��킸�S20���A������v���|�[�V�������킩��悤�ɔw�\������ׂđ�����Ƃ������H�v�������Ă��悩�������낤�B
 �@
�@
����N�v���W�s�u���v���̂ق��̎��t�i�v���ЁA1977�N4��15���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�s��B�玍�W�k���㎍����58�l�t�i�v���ЁA1974�N10��1���j�Ɂu���`�v�Ƃ��ď����ꂽ�q�⑫�I�Ȏ�̃����r�́q�T��i�Q�r�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����i�ꕔ�A�\�L�����߂��j�B
�@���̍�i�Q�́A���̏̊m�F�̎d���ɉ����āA�����A���̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł���Ǝv����B
���[�@�@�x���g�E�V�F���Ɋւ����́i�����j�A�A�V���g�I�����i���f�j
���I�i���h���@�B���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�i�����j
�ヌ�I�i���h���@�C�R�ĂɊւ���O�̒f�Ёi�����j�A�D���X�ɊO�ւق��i�����j�A�E�[��Ƃ��̎��Ӂi�G�b�Z�C�W�E�����j
�����@�F�ؓ����Ɋւ��鏔�f�ЌQ�i�����j�A�G�l�B�ɂƂ��ă`�[�Y�Ƃ͉����A����уz���f�C�E�s�N�j�b�N�i�����j�@���̂����A�C�q�R�āc�c�r�ƇD�q���X�ɊO�ցc�c�r�Ƃ͍�i�q��O�̒f�Ёr�����Ƃ��ĂQ���ň�̍�i�Q���\������B�i�����A����y�[�W�j
��B��̏�L�̍�i�Q�����߂����Ђ̏����͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�@�F�s��B�玍�W�t
�@�A�F����
�@�B�F�s���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�t�i�v���ЁA1969�N4��10���j�k�s��B�玍�W�t�ɑS�ю��^�l
�@�C�F�s�R�ĂɊւ���O�̒f�Ёt�i����R�c�A1971�N3��15���j�k����l
�@�D�F�s���X�ɊO�ցE�ق��t�i�v���ЁA1972�N10��20���j�k�s��B�玍�W�t�ɏ��^�l
�@�E�F�s�[��Ƃ��̎��Ӂt�i�v���ЁA1973�N6��1���j
�@�F�F�s�}�C�N���E�R�Y���O���t�B�̂��߂�13�̏������t�i�y�ЁA1977�N11��10���j
�g���������������s���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�t�̊��s�Ɋւ��ẮA�s������Ӂt���l�̍]���a�����q�t�ւ̉�A�r�ŐG��Ă���B�u�ނقǎ��W�o�łɗD�_�s�f�Ȏp�����Ƃ葱���A���͂��₫�������������l�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�݂����眔�ގ��ɂ���قǎ��o�������Ȃ��玍�W�ɂ܂Ƃ߂�C�͂Ȃ��̂������B�k�c�c�l�������A����͂ڂ��Ȃǂ̂���Ȃ���i�\���̎菇�ɂ��Ă̔ނ炵�����w�I�W�J�̋������鎞�Ԃ������̂��Ɣ������̂͂����ƌゾ�����v�i���O�A��l���`��l���y�[�W�j�B
�s���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�t�́q�����ɂār����q�@�؎��ɂār�܂ł̑S13�т��琬��B������薼���炾�����ނ���ƁA���̂`�`�c�̎l�ɂȂ�B
�@�`�F�c�c�ɂāi3�сj
�@�a�F�c�c�̑z���o�i4�сj
�@�b�F�c�c�f�Ёi5�сj
�@�c�F�c�c�ڎ��i�P�сj
�����́q���r�i�v�͖ڎ��ł���j�Ɍf����ꂽ�薼�ƔN���ɁA���̂`�`�c�������ĕ\�������
�ƂȂ�B�P�s���W�ł͉����̕ʒ��s�܂肵���q�D�Ɋւ���f�Жڎ��r�i���j���܂Ɛ܂̊Ԃɓ\�荞�܂�Ă���B�s��B�玍�W�t�ł�8��9�Ƃ�����ւ���Ă��邩��i�ʒ�����߁A�ʏ�̖{���g�݁j�A8.
�b�F�q�����Ɋւ���f�Ёr�A9.
�c�F�q�D�Ɋւ���f�Жڎ��r�Ƃ������я����A���{�̐����Ƃꂽ�����̍\�z�ł͂���܂����B�q�@�؎��ɂār�̂܂��̌��J���̓m���u�����Ȃɂ��Ȃ����S�Ȕ��y�[�W������A13��ʊi�Ƃ��Ĉ����A1�`12�́u���w�I�W�J�̋��v�������Ă���B
�{���́A1955�N����68�N�ɂ����Ď��M���ꂽ�i�g���ɂƂ��Ắs�Õ��t����s�_��I�Ȏ���̎��t�̊Ԃɑ�������j���т����߂āA���Ɋ��s���ꂽ�B�]�����͑O�f���ł��������Ă���B�u���Z��N�l���A�ނ̑�ꎍ�W�w���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�x������Ɨz�̖ڂ��݂��B�^�����t�����X����66�ł̋�Ԑ��ɕx�Ȍ��Ȗ{�������B����N�v�A������q�A����ɋg���������̐s�͂������B�܌��̉��{�A�ނ��㋞���u������Ӂv�̒��Ԃ͂Ђ����Ԃ�Ɋ���������B����̇��L�����r�A�z�[�����ɐ����������������̎��W�����C�~��Č����A�������炢���ɂ�����Ђ炢���Ƃ��̈�u�܂Ԃ����������Ƃ�Y��Ȃ��v�i���O�A��l��y�[�W�j�B
�{���̎d�l�́A����~��O��~�����[�g���E���l�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���B�{���ɓ\���݈꒚�B����250���i���ł͊��ň�������A���ň���ɂ�镜����250��������A���t�Ό��y�[�W�Ɂu���Z��N�\�ꌎ����@�����œ�܁Z�����s�@�����ŔЉ����Z�Z�~�@��������I���G���^���E�R�s�[�v�����g�Ёv�ƒNjL����Ă���j�B�\���Ɣ��̕\4�ɕd�̃J�b�g�������Ă��邾���ŁA�\�\����{���Ƀ��B�W���A���v�f�͊F���A���n�ɖ������������́u�������{�v�ł���i���W�莆���̃m�h���ɂЂ�����Ɓu����@�g�����v�̃N���W�b�g������j�B�{���̈���E���{��S��������t����Ɗ⍲���{�́A�g���́s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�Ɠ���������E���{�������A�S�̂̈�ۂƂ��Ă͋g���̐^�̏o���ƂȂ����s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�ɋ߂��A��̏������W�ւ̋g���̑z������������i�g���́s���㎍�蒟�t1961�N2�����́q�A���P�[�g�u�Z��N�x�Ɋ��҂���V�l�v�r�ɁA��B��ƎR�{���q�̓�l�������Ă����j�B
�s���X�ɊO�ցE�ق��t�͖{����3�N����Ɋ��s���ꂽ��̑�O���W�����A�g���������{�ł�����݂̗����̃J�b�g��i���āA���̎d�l�i���Z�~��O��~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���j�͖{���ɍ�������B�����������҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��A�g���������̖{���܂����o�Ō��ɂ����̂Ǝv����B
�i���j�̂��Ɂq�q�D�Ɋւ���f�Жڎ��r�̂��߂̃����r�i�s�V�t8���A1975�N4���j���F�́s�}�C�N���E�R�Y���O���t�B�̂��߂�13�̏������t�́q������11�@���邢�́^�ؐ����ւ̒��r���[�Ȑڋ߁r�̒��Ƃ��ē����Ɏ��߂�ꂽ���ʁA�B�i�{���j�ƇF�́A�`���ŐG�ꂽ�q�T��i�Q�r�̐}�ɂ���悤�ɁA�����������m�ȊW�����B
 �@
�@
��B�玍�W�s���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�t�i�v���ЁA1969�N4��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��s���X�ɊO�ցE�ق��t�i�v���ЁA1972�N10��20���j�̔��ƕ\���i�E�j
���c�Ǖ��E�a�c�F�b�ҁs��t�S�W�k�S7���l�t�i�}�����[�A1953-1956�j�͋g�����������������̑S�W���Ǝv����B�g���́q�a�c�F�b�Ǒz�r�i���o�́s�V���t1978�N7�����j�ɂ�������B
�@���͏��a��\�Z�N�ɁA�}�����[�ɓ����āA�V���́s���w���S�W�t���A��y�̈�l�ƒS�������B�������Ԃł���A���Ԃɗ]�T�����������߁A�}���ژ^�����邱�Ƃ𖽂���ꂽ�B���܂��܂��̏o�������肪�悩�����̂ŁA���̌l�S�W�s��t�S�W�t�̓��e���{������悤�Ɍ���ꂽ�B�^���͂��̎��A�͂��߂Ęa�c�F�b�Ȃ�l�Əo������̂��B�������������������A���e���{�������Ƃ��Ă͗��h�Ȃ��̂��o�����B���ꑢ�{�܂ŁA���͎肪����悤�ɂȂ��Ă��܂����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꎵ�܁`�ꎵ�Z�y�[�W�j
�����́u���̌l�S�W�v�́A�����炭�͋g�����肪�������̑S�W�̈ӂł����āA�}�����[����t�̑S�W�ŏ��߂Čl�S�W�̏o�łɏ�肾�����킯�ł͂Ȃ��i1948�N���痂�N�ɂ����Ċ��s���ꂽ�B�{�v�t�ق��ҁs�����֑S�W�k�S3���l�t�����łɂ���j�B���́s��t�S�W�t�ȑO�Ɋ��s���ꂽ��t����Ďq�̎�ȑS�W�ɂ͈ȉ��̂��̂�����i�s������{���{��n ��5���k�����t�E�����������{�E�ԏW�l�t�A�}�����[�A1972�A�����̊֗Lj�쐻�q����ژ^�r�ɂ��j�B
�{�S�W�̕⋭������ړI�Ƃ��Ċ�悳�ꂽ�s�����t�S�W�k�S4���l�t�i�}�����[�A1974-1994�j�̐ӔC�ҏW�҂Ƃ��āA�a�c�F�b�͑�1���́q��L�r�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�}�����[�Łu��t�S�W�v�S�����k�c�c�l�́A�N�ƂƂ��ɔł��d�ˁA���^�����ł������ߐ�ł̂�ނȂ��ɂ��������B�^�k�c�c�l�^���́u��t�S�W�v�k�s�����t�S�W�t�̂��Ɓl�́A��s����A�ǂ́u��t�S�W�v�Ƃ���ׂĂ��A�����Ҍ����Ǝv����B���e�����́A�\�Ȍ���ʐ^�ɎB��A��������Ɍ��e�p���֏��������āA�s�����ȓ_�͌����e�ɂ��ĉ��������B����͑S�W�̏ꍇ�A���R�ȑ[�u�����A����܂ł́u��t�S�W�v�ł͕����I�ɂ����Ȃ�ꂽ�ɉ߂��Ȃ������B�i�s�����t�S�W�k��1���l�t�A�}�����[�A1974�N3��20���A�ܘZ���`�ܘZ���y�[�W�j
�͂��炸���{�S�W�̌��E����Ă��邪�A�a�c�͐V�őS�W�̊�����������1977�N�ɐ������B�g���́q�a�c�F�b�Ǒz�r�ŁA�����`���Ƃ��Ċx�����瑡��ꂽ��t�̒Z�����Љ�Ă���B���̉̂́s��t�S�W�k��5���l�t�i1955�N1��31���j�́q�̍e���r�ł́u����@107�@�K��Ƃ����Ђ����Ƃ͋��Ă��ӂ̂Ȃ����ɂ��͂�Ƃ�݂��v�i�q�X�@����Ə����F���Z�����̉́r�A�����A�O���Z�y�[�W�j�ƃV���v�������A�q�a�̇V�r�����߂��s�����t�S�W�k��4���i���j�l�t�i1994�N6��20���j�ł�
�@�@�@�@�i����j
33�@�K�́m�i�j�n��Ƃ����Ђ����Ƃ͋��Ă��ӂ̂Ȃ��m�i���j�n���ɂ��͂�Ƃ�~���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ďq
�@�@�@�k���l�̘a�c�F�b�������B�������ځB����B�Z���B�i�q�Z���E�x�r�A�����A�ܔ���y�[�W�j
�Ƃ����������ɁA�{�����ڂ����Ȃ��Ă��邾���łȂ��A���L���[�����Ă���̂��������B
 �@
�@
���c�Ǖ��E�a�c�F�b�ҁs��t�S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1954�N6��20���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ��s��t�S�W�k�S7���l�t�i�}�����[�A1953�N8��10���`1956�N6��20���j�̔��i�E�j
�s��t�S�W�k�S7���l�t�̎d�l�͈ꔪ�Z�~���Z�~�����[�g���E�㐻�E�N���X���E�\���B��2724�y�[�W�B�����́u��t�S�W�v�́A���̕��ȊO�A���̔w�A�\���̔w�A�{���Ƃ��M�ɂ�鏑���������B���������̃N���W�b�g�͂Ȃ����A��o�E�֗Lj�ҁq��t�����r�Ɂu�w�����͋�C�́u�����ژ^�v�ɂ��v�i�k��7���l�A1956�N6��20���A��Z�Z�y�[�W�j�Ƃ���A�b���̕\���N���X�Ɏ����̔w�������N�₩���B�S�W�̖{���͑�6���܂ł���t�̒���ŁA��7���́q���r�i�������t�̒��삾���j�Ɓq�����E�����r���琬��B�l�S�W�ŏI���ł̂����������݂́A�V���ДőS�W�ʊ��̘a�c�F�b�ҁs�����t�����t�i1947�N4��15���j�ƕ���ł��̐��ƌ�����̂ŁA�ȉ��Ɂq�����E�����r�̖ڎ���^����B
��t�a���@�a�c�F�b
���������猩����t�@���c�Ǖ�
��t�����̕��́@�������
��t��������l�@�֗Lj�
����Ďq�̏W�����l�@�������
��t�������j�@�֗Lj�
��t�����@�֗Lj��
��t���������@�֗Lj��
�w��t�ɗ^�ւ��莆�x���@�a�c�F�b��
��t�N���@�֗Lj��
���L�l�������@���c�Ǖ���
��7�������̓�l�̕Ҏ҂ɂ��q��t�S�W�̖��Ɂr�ɂ́u�ŏ��́A�ҏW���̓y��ꐳ�����A���ځA���̑S�W�̒S���҂ɂȂ�A���̂̂����R�Ҏ������p���Ŋ��������v�i�����A�l��Z�y�[�W�j�Ƃ�����߂����邪�A�����E���{�ɂ��Ă̋L�q�͌������A�\���܂��≜�t�ɂ��N���W�b�g�͂Ȃ��i�t�Ɍ����A��������Г������ł��邱�Ƃ��M����j�B�a�c�F�b���M�A�g�����������s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j������ƁA
�a�c�͐푈���ɏo���V���ДŁu�����t�S�W�v�ɂ��W�������A����ǂ́u��t�S�W�v�͖{���Z���ɗ͂���ꂽ���߁A�\�z�O�̓�����������A����̔z�{�͗��N�̔����ɂȂ����B�ŏ��̌v��̘Z���̊O�Ɂu���A�����E�����v�т���������S�����ɂȂ������A��������܂łɑ������ܔN���������B�^�k�c�c�l�^�Óc��́A���̍��A���؏��O�Ƃ�������Ɏ���ۂ݂Ȃ���A�u�I��𗧔h�ɂ��Ȃ���v�����ȂɂȂ��Ă����B�}�����[�́A�����A���߂��ƁA�Óc�͓��S�o�債�Ă����B�^���ƂɂȂ��āA�y��ꐳ����A�u��t�S�W�v���A�Óc�̍l���ł́A�}�����[�̏I����������̏o�łł������Ƙa�c�͕������ꂽ�B�^�k�c�c�l�^�u��t�S�W�v�͒}�����[���肪�����A���{�̍�Ƃōŏ��̖{�i�I�Ȍl�S�W�ł������B�i�����A�ꔪ�܁`���Z�y�[�W�j
�Ƃ��邩��A�g��������܂��Ė`���̐��z�����������Ƃ͏[���ɍl������B
��
���B��́s�q���D�Đ��r�̂��߂̃m�[�g�t�i����R�c�A1986�N3��15���j�́u���W�v�Ƃ�搂��Ă��Ȃ����̂́A�u���D�͍Đ������邩�B�����������肵��
���ו��͂����܂��Z�n���A�m��s�\�Ȃ��̂��\�z����B���D�����悤�Ƃ��鎋���͈ł̂Ȃ����肾�Ă��Ȃ����V���邾���Ȃ̂��v�i����R�c�̃T�C�g����j
�Ƃ�����傩�炤��������悤�ɁA���W�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B
�{���́q��̃m�[�g�r�Ƃ����p�[�g�́q�q���D�Đ��r�̂��߂̓�̃m�[�g�r�Ƒ肳�ꂽ��i�\�\�����т͂���Ɂq�T �L�q�r�Ɓq�U
���߁r�Ƃ��琬��A�O�҂ɂ́q�� ���D�̊O�`�r�A�q�� ���D�̓����r�A�q�� ���D�̊O�����r�A�q�� ���D�̊O�����ɂ��Ă̕⑫�r�A�q��
���D�ȍ~�ɂ��Ă̎�̕⑫�k�q�` �����̋L�q�i�n���L���́j�r�Ɓq�a
���h�t�X�L�[�̋L�q�i�O�f��170-171�Łj�r�Ƃ������p�i���̂��̂ł͂Ȃ����j���琬��l�r���A��҂ɂ�1����12�܂ł̔ԍ���t���ꂽ�߂��܂܂��
�\�\�Ŏn�܂�i�q�c�c��̃m�[�g�r�ɑ�����т́q�q���D�Đ��r�̂��߂̕⑫�I�ȃm�[�g�r�j�B�q��
���D�ȍ~�ɂ��Ă̎�̕⑫�r�̃��h�t�X�L�[�̏��́q��
���D�̊O�`�r�̒��ɓo�ꂷ��o�[�i�[�h�E���h�t�X�L�[�i�n�ӕ��M��j�s���ق̍H�������\�\�m��ꂴ�錚�z�̔������t�i�����o�ʼn�A1981�j�ŁA�����͊�
�����т���сq�q���D�Đ��r�̂��߂̑�l�̃m�[�g�r�̐����ɗ^���đ傫�����̂�����B��B��͎��_�q�o���ցr�ł��������Ă���B�u�k�c�c�l���ɂƂ���
�́A����e�N�j�J���E�^�[���̈Ӗ������̃e�N�j�J���ȊW�̓K���ȓ��e�͈͓��ɂƂǂ߂Ă������Ƃ́A��ɂ����Ԃ鍢��Ȃ��Ƃ������̂ł���v�i�s���̎��_
��S�t�A�v���ЁA1995�N6��1���A��Z�y�[�W�j�B����ɕ킦�A����s�Ȃ����̂̓��h�t�X�L�[�̔��D���u�K���ȓ��e�͈́v�̊O�ɘA��o���s�ׂɂق�
�Ȃ�Ȃ��B
�{���̎d�l�́A��ꔪ�~��l�܃~�����[�g���E��Z���y�[�W�E�����t�����X���E���B���ő���750���B�Ȃ��A�s�q�g�����r�́u�{�v�t�Ɍf�ڂ���g��������
��i�̎ʐ^�́A�����Ƃ��Ď苖�̌������B�肨�낵�Ă��邪�A�{���͒T���𑱂��Ă���ɂ�������킸����ł��Ȃ����߁A�\���́A�旧�}���ٌo�R�Ŏؗ������s
�������}���ُ����{���B�e�����B�ׂ�̔��i�@�B�����j�̎ʐ^�́A����R�c�̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă���摜�ł���B�{�����s������s���W�k���y�Łl�t�i�v���ЁA1970�j�Ɠ��l�̐��{�l�������A����15�~�����[�g��
�ƓK���Ȃ��߁A�����̂����Ă�����_�����قNjC�ɂȂ�Ȃ��i�`�����ׂꂪ���Ȃ̂́A������Ƃ����������j�B�\���J�b�g�\�\����N�v���W�s���҂����̌Q���镗�i�t�i�͏o���[�V�ЁA1982/1983�j���蕶�Y���W�s�K���X�̋��t�i�������[�A1983�j�ɒʂ���G���͐������낤���\�\�̃N���W�b�g�͂Ȃ��i���肵���{�̏��e��lj������k2011�N2��28���NjL�l�j�B
 �@
�@ �@
�@
��B��s�q���D�Đ��r�̂��߂̃m�[�g�t�i����R�c�A1986�N3��15���j�̔��k����R�c�̉摜�l�i���j�Ɠ��E�\��
�i�E�j
��B��́q�g�����̌��t�ɂ��Ă̎��I�ȃ����r���u�g��������ɂ��āA���܉����������̂́A�Ђǂ��h�����ƂɎv����B�Ƃ����̂��A�g������́\�\�����F�l�B�������\�\�����e�����ʎ������w��ǗB��̎��l�ł��������A����ɉ������A���ݎ����،h����w��ǗB��̎��l����������v�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�A����y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���B�s�q���D�Đ��r�̂��߂̃m�[�g�t�̑����҂͒��҂̊�]�ŋg���ɂȂ����̂�������Ȃ����A�q���Ƃ����ɂ����ā\�\��̗����̃m�[�g�r�ɐ���W�̋L�q�͂Ȃ��A�o�܂͕s���ł���B
������s�́s�k�t�i�S10���A���惆���C�J�k��10���̂ݘk�̉�l�A1959�N8���`1962�N9���j�̓��l�Ƃ��āA�ѓ��k��E��c�G�E�剪�M�E�g�����ƍs���Ƃ��ɂ����B�g���������́s������s���W�t�i�v���ЁA1969/1970�j�́A�s�k�t�ɔ��\���������܂Ƃ߂��s����k������{���W4�l�t�i�v���ЁA1962�A�����͐^�甎�j���܂ށu�l�������W�v�A���Ȃ킿1969�N�����̑S���W�ł���B�s�k�t�i��9���܂ł̕\���̘k�̃J�b�g�͐^�甎�A��10���͗����j�Ɍf�ڂ��ꂽ�g�����Ɛ�����s�̎���i���f����B
�E1959�N�k���a34�N�l
�@8��10���k1���l�@�q�����r�i�D�E3�j�\�\�q�^�钆�r�i�s����t�����j
�@9��20���k2���l�@�q�a���`�T�r�i�D�E4�j�\�\���x�[���E�f�X�m�X�q�����̉Ԃɂ��ā@�܂��ڏZ����n�����ɂ��ār�k�l
�@10��20���k3���l�@�q�ҕ����鏗�r�i�D�E8�j�\�\���x�[���E�f�X�m�X�Z����сq�C�U�x���ƃ}���[�r�q�y���J���r�k�l
�@11��20���k4���l�@�q���̕a�C�r�i�D�E11�j�\�\�q�d���Ɨ��l�r�k���e���ꂽ�O�����q����ӂꂽ��ցr�i�s����t�����j�Ɂl
�E1960�N�k���a35�N�l
�@1��10���k5���l�@�g�������͋x�ځ\�\������s��i�͋x��
�@2��10���k6���l�@�q���́r�i�������сE9�j�\�\������s��i�͋x��
�@3��30���k7���l�@�q�a���`�U�r�i�D�E5�j�\�\�q�v�����F�[�����̎���\�p���f�B�r�k���e���āq����Ȃ��Ƃ́r�i�s����t�����j�Ɂl
�@5��30���k8���l�@�q���̂��肠����r�i�D�E13�j�\�\������s��i�͋x��
�@10��30���k9���l�@�g�������͋x�ځ\�\�q�v���o���Ă͂����Ȃ��r�i�s����t�����j
�E1962�N�k���a37�N�l
�@9��20���k10���l�@�q���̂��߂̃g���̎��݁r�i�E�E1�j�\�\�q�}�k�J���̍s�i�\��N�̎蒟�̒��̃�������r�i�q�}�k�J���̍s�i�r�Ƃ��ās����t�����j
�{���͊����Ɂu���������̂̉^�������ǂ邩�̂悤�Ɂ^�Ⴍ���Ă��̐����������^�^�m�Ɂ^���݂Ƃ̓�\��N�̐����ɍ炢���^�����̕n�����ԉԂ��v�Ƃ���悤�ɁA1968�N��41�ŖS���Ȃ����Ȃ̐^�m�ɕ�����ꂽ�B�s�k�t�O�ォ��s������s���W�t�܂ł̋g���Ɛ����̎��Ƃ��r�ׂĂ݂�ƁA���̓ˏo�������ւ̉�A�A���惆���C�J�i�ɒB���v��1961�N�ɟf���Ă���j����v���Ђւ̃V�t�g�A�����Ƃ��Ă̑S���W�̊��s�A�Ƃ������_�ŋ����[���ΏƂ��Ȃ��Ă���B
�@�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�\�\�s�X�������t�i���惆���C�J�A1959�j
�@�s�a���`�t�i����ɁA1962�j�\�\�s����t�i�v���ЁA1962�j
�@�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�\�\�s�l�G�̃X�P�b�`�t�i�����ЁA1966�j
�@�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�\�\�s������s���W�t�i�v���ЁA1969�j
������s�́s�k�t�ɂ��āu���̔N�k���܋�N�l�̔����A�V�������l�����u�k�v���g�����A�ѓ��k��A�剪�M�A��c�G�A�����Ď��̌ܐl�Ō��������B���ꂼ��̗��������͈ق邪�A�Ȃ�炩�̌`�Ŋ֖�Ƃ��ẴV�������A���X���ɂ������O���[�v�ł������낤�B���т��яW�܂��Ă���ׂ�A���݁A�����Ɣ��������肩�����A�e�Z���ŏ�����ɉ�������A�݂Ȃŏ����s�����A�����Ă݂�Β����悷�������߂ɁA�O�N�قǂŎ��ł����v�i�q���̗������r�A���z�W�s���R�̂߂��݁t�A���{�o�ϐV���o�ŎЁA2007�N6��15���A���Z�y�[�W�j�Ə����Ă��邪�A1960�N�ケ��������s�Ƌg�������ł��ڋ߂����G�߂������B���̝{��������̂��A�����ɂ��q�g�����̎��i��㎍�ւ̈���7�j�r�i�s���w�t1968�N1�����j�ł���A�g���ɂ��{���̑����ł���B�s������s���W�t�́A�k������l1000����1969�N11��25���ɁA�k���y���l1500������1970�N1��31���ɁA�k����������l55������1970�N12��1���Ɋ��s����Ă���A�����́q���ڂ������r�Łu���M�Ȃ���A���l�_�̍Ę^�ɂ��ċg�{�������ɁA�{���̂��߂̐V�������l�_�ɂ��ĎႢ�r�p�ł���F�����Ď��ɁA����ɂ��ċg�������ɐ[�����ӂ���v�i�{���A�O���y�[�W�j�Ə����Ă���B
��b������s
�킪�߂͐@���̗���ɂ��Ȃ���
�{�������́q�����K��r�̈�сi�̂����W�s�~���L��t�v���ЁA1988�A�Ɏ��^�j�́A�������Ɂs�����G�߁t�i����ɁA1940�j�̎��̈�т�z���N��������B
�f�́b�g����
�킪������ɂȂ�݂͂Ă�
��������ɂ����̂킭
�{���́k���y���l�̎d�l�́A��Z��~��l���~�����[�g���E�l�Z�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���B�f�ނƂ��Ă̗p���̑I���́A�����Ȃ��猩�����B���Z���ڂ̃N���[���F�̕\���ɑ����āA�Ð��̌��Ԃ��Ɓi�Ăсj�N���[���F�̖{���͂����炭���������E�җʂ̐F�Ⴂ�ŁA�{����11�~�����[�g���l���̊����őg�܂ꂽ�����������ƕێ����Ă���i����̃A�X�e���X�N�̓A�N�Z���g���j�B�g���������̃t�����X���ɂ͂������̃p�^�[�������邪�A����͍L�����\���̊p���߂ɝB�����Ƃ��āA�V�n�Ƃ��܂荞��ԂŖ{�̂̔w�ƌЂÂ����A�\���̏������͊p�����Z���`���[�g���d�Ȃ���4���ɂȂ�悤�ɐ܂��Ă���i���������Ċp�͂��Ȃ��v���j�B�㐻�{�̂������ɂ�������̌��Ԃ��́A�����������\���̑��̉��ɂ����銆�D���B�`���͖�3�~�����[�g�����邩��A900�O�����̎��d���x����̂ɁA�c���̓����Ă��Ȃ���d�̕\���ł͎シ����B�܂��u�p�w�v���������`���A㆓ǂ���ɂ�ăy�[�W���قǂ̏���������o���Ă���̂́A�t�����X���̍\���I�ȓ�_���B�����Ɍr�������ꂳ�����Ă��āA����̃{�[�����̋@�B���𗯂߂Ă���j���ƐڐG����̂��F�����Ȃ��B�`�T����500�y�[�W����{���̏ꍇ�A�艿3000�~���k������l�i�������A�w���v�̌p���\���̊۔w�E�㐻�{�j�ɑ��āA�艿1800�~���k���y���l�ł����Ă������͏㐻�{���]�܂��������B
 �@
�@
�s������s���W�k���y�Łl�t�i�v���ЁA1970�N1��31���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɓs������s���W�k��������Łl�t�i�v���ЁA1970�N12��1���j�̎���E�����Ɣ��k�Q�����т̉摜�l�i�E�j
�k��������Łl�̏o�T�Fhttp://www7a.biglobe.ne.jp/~naniwashorin/photo/430359.jpg?
�{���́k��������Łl�͖��������A�Q�����т�18,900�~�ŏo�i���Ă���̂ňȉ��ɘ^����B
������s���W�@��������55���@�摜����^������s�A�v���ЁA��45�A1���^��������55���@����E�������@��d���t�@�ɔ��@���Z���n�������A�������œ\������B�@�y��������5�s�E�������B����E�g�����B���v���㐻�{�B�z�������BA5���B
�Ȃ�������s�ɂ́A2007�N2��14���ɉ^�c���J�n�����s������s�E�����T�C�g�t������A�{���s������s���W�t�́k��������Łl�����A�����q�����r�ɏڍׂ��L�ڂ���Ă���B
�k2015�N3��31���NjL�l
�s������s���W�k����Łl�t�i�v���ЁA1969�N11��25���j����肵���̂ŁA���e���f�����B�{���̎d�l�́A��Z��~��l���~�����[�g���E�l���y�[�W�i�{���̑O�Ƀy�����������p�a���꒚�j�E�㐻�p�\���i���E���A�w�E�v�j�E�\���E�A���p�O���ɓ\���ӁB�s������s���W�t�i1969/1970�j�́A16�N��ɓ����v���Ђ��犧�s���ꂽ�s������s�S���W�t�i1985�N10��28���j�́q�S���W�̂��߂̂��Ƃ����r�ɂ����Ē��҂���u�ߋ��Ɍ܍��́w������s���W�x�������Ă���킯�ł����A���̂����A���Z��N�Ɋ��s�i���Z�N�ɂ��ʂ̑��ꑢ�{�œ�ʂ芧�s�j�̑�^�{���A�S���W�œI�ȓ��e�������Ă��܂����v�i�����A�Z�O��`�Z�l�Z�y�[�W�j�Ƒ�������Ă���B�s������s�S���W�t�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ��A�v���Ђ̎Г������Ǝv���邪�A�\���܂������邱�ƂȂ���A���ނ��{���g���g���������́s������s���W�t�ɋy�Ȃ��B��_�͂��������邪�A�s�X�������t�̉����V���̊G���ēx�\���ɗp�����̂ƁA�q�ڎ��r��2�i�őg�̂͂Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��������̂��B�O�҂́A�z���\���ɊO��\�肵���G�����݂₷���B�������W���܂ޏ��e���A���G���{���̔����ɓ����̂͂ǂ����낤�B���G�Ȃ�A���łɂ��郂�m�N���̒��ҋ߉e��1�y�[�W�߂ɁA2�`3�y�[�W�߂�4�F�ɂ��Ĕ���\���Ȃǂ̊O���̎ʐ^���A4�y�[�W�߂͍ĂуX�~1�F�ŁA�e���W�����˂ɕ��ׂĔ���\���̔w���B��B��҂́A���Ёk����Łl�̂悤��1�i�ŁB�ǂ����Ă�2�i�ɂ��ăy�[�W�����炵�����Ȃ�A���W����i�����ɂ��āA�r�������炤�Ȃǂ��Ă͂ǂ����B�ڎ��̓t�����X�̖{�̂悤�Ɋ����Ɂi�����߂̊����őg��Łj�ڂ���Ƃ����������B������ɂ��Ă��A�g���̎d���Ɋr�ׂĂ����Ȉ�ۂ͔ۂ߂Ȃ��B
�{�e���������߂ɁA�v���Ԃ�Ɂk���y�Łl���Ђ��Ƃ��Ă݂��Ƃ���A�k����Łl�̑g�ł����̂܂ܗp�����͂��́k���y�Łl�ɂ����r������B�O��͐G��Ȃ��������A��͂�w�E���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂��i�Ȃ��A����͎苖�̈�{�̏�Ԃł���A���{�Əƍ������킯�ł͂Ȃ��j�B
�@�E�q�f�p�[�g�̒��̎U���r�i�s����t�j�̓���y�[�W�O�s�߁u�K�������M���Ȃ�����Ƃ��́@�Q�O�̒����v�́u�Q�O�̒����v�����̍s�Ԃɂ���Ă���i�k����Łl�͖��Ȃ��j�B
�@�E�q������r�i�s�l�G�̃X�P�b�`�t�j�̎O����y�[�W��s�߁u�ڂ��̐S�������݂����āv�́u�ځv���ɂȂ��Ă���i�k����Łl�͖��Ȃ��j�B
�@�E�F�����āq������s�_�r�̌܁Z�O�y�[�W�O�s�߁u�ŋ߂̍�i��ǂނƂ����ł��Ȃ����A�v�́k����Łl�Łu���߂̍�i�c�c�v�ƌ�A����Ă������A�k���y�Łl�ł������Ă��Ȃ��B
���������g�ŏ�̖��_�́k��������Łl�ł͉������ꂽ�̂��낤���B���̒NjL���M���_�ł͖����Ȃ̂ŁA�킩��Ȃ��B
 �@
�@
�s������s���W�k����Łl�t�i�v���ЁA1969�N11��25���j�̊O���Ɣ��ƕ\���̕��i���j�Ɠ��E�w�i�E�j
�k2017�N10��31���NjL�l
�s������s���W�t�̎O�ł̂����A�s������s���W�k��������Łl�t�i�v���ЁA1970�N12��1���j�������������킯�����A���̂قǔO�芐���āA���E���c�̓V�����X����25,000�~�œ��肵���i��ɂ���āu���{�̌Ö{���v�Ō��������j�B�Q�����т̂Ƃ��͎苖�s�@�ӂŎ�ɓ�����Ȃ��������A55���{�Ȃ猩�����Ƃ��Ɏ��ł��Ă����Ȃ��ƁA���ɂ����ڂɂ�����邩�킩��Ȃ��B�{���̎d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���E�l�l�y�[�W�i�{���̌�Ƀy�����������p�����꒚�j�E�㐻���v�\���E�z�\���ɓ\���ӁE�A���p�O���ɓ\���ӁA�\���t�ɋL�ԁi�����{�͑�34�ԁj�A�Љ�9,000�~�B���̗A���p�O���A�s������s���W�k����Łl�t�̂悤�Ȓi�{�[�����ł͂Ȃ��A�����Č������ŁA�܂���H���v�w���ӂ��ş����Ă���i���͖{���ȊO�ł��̗l���m�X�^�C���n���������Ƃ��Ȃ��j�B�\���̊v�́k����Łl�̔w�v�Ɠ������̂̂悤�ŁA�d�オ��͔��ɔ������B���ꂾ���ɁA�O��́k�NjL�l�Ŏw�E�����k���y�Łl�̑g�ł����r�����P���ꂽ�̂́A�ɂ��݂Ă��]�肠��i���S�ł͂Ȃ����A�k����Łl�̖{�����x�^�[�ł���j�B�����܂��Ɂs������s���W�k��������Łl�t�̏��e���f���悤�B�Ȃ��A�O�f�s������s�E�����T�C�g�t�ɂ͖{���̊O���̎ʐ^���f�����Ă��āA�����Ɂu������s���W�m�����k�}�}�l����Łn�^������s�^�{�́F537�ŁA����F�g�����^1970�N12��1�����s�m����55���n�^�v���Ёv�Ƃ����L�ڂ�����A�q�ڎ��r��]�ڂ��Ă���B
 �@
�@
�s������s���W�k��������Łl�t�i�v���ЁA1970�N12��1���j�̊O���Ɣ��ƕ\���̕��i���j�Ɠ��E�w�i�E�j
���e���O�Y�Ō�̎��W�s�l�ށk���y�Łl�t�i�}�����[�A1979�N11��15���j�́A�s�l�ށk����Łl�t�i�}�����[�A1979�N6��20���j��5������Ɋ��s���ꂽ�B����ł͖{���̗��Ɂu����@�g�����v�ƁA���y�ł͉��t�Ɂu����ҁ@�g�����v�ƃN���W�b�g������B�s�l�ށt�͎l���\���ŁA
�T�F1970�N7������1972�N8���܂łɔ��\���ꂽ23��
�U�F�s���e���O�Y�S�W�k��10���l�t�i�}�����[�A1973�j�̂��߂ɏ������낳�ꂽ25�сk�s�l�ށt�ł́q�h�[�E�r���q�ցr�̌㔼���番���Ɨ�����26�сl
�V�F1973�N1������1975�N4���܂łɔ��\���ꂽ12��
�W�F1975�N12������1978�N5���܂łɔ��\���ꂽ5��
�ȏ��66�т��琬���Ă���B���e�̒P�s���W�Ƃ��Ă͍ő�̕ѐ��ł���A�s��{
���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1981�j���^���W���ő��̍s����i����B�s�l�ށt�́q��L�r�͊Ȍ����B
�u�{���W�́A��㎵�Z�N�ȍ~��㎵���N�܂ł̍�i���W�߂����̂ł���B���̂����A�T����V�܂ł́A��ɒ}�����[��芧�s���ꂽ�w���e���O�Y�S�W�x��\������сw���e���O�Y�@���Ǝ��_�Y�x�́u�������сv�ɏ����̂��̂ł���B���W�ɂ܂Ƃ߂�ɍۂ��A��̒����ƍ폜���s�Ȃ����B�W�͂���ȍ~�ɔ��\���ꂽ���̂ł���v�i�S���A�{���A��㎵�y�[�W�j�B
�q��L�r�ɏ����͂Ȃ����璘�ҁE���e���O�Y�ɂ��ƌ���ׂ������A�}�ݍ��ݕt�^�q���W�l�ނɊār�f�ڂ̑����S���ҁE�g�����́q�s�l�ށt�o���r�Ǝ��W�Ҏ[�ҁE�V�q�r��́q���e�ƒ�e�̂������r��ǂނƁA�V�q�ɂ��悤�ɂ��v����i�V�q���ɂ́u���āA���̓x�̎��W�w�l�ށx�́A���̑啔���i�T�`�V�j�͂��łɒ}���Łw�S�W�x����сw���Ǝ��_�x�Ɂu�������сv�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ���̂����A���W�ɂ܂Ƃ߂�ɍۂ��ē��R�A��̕ύX���������v�Ƃ���j�B���������ď��R����V�K���^���т́u�W�F5�сv�ƂȂ�A�������ɔ��\���ꂽ���сi���Ȃ킿�s��{ ���e���O�Y�S�W�t�����́q�������сr�j�́A�g�����ҏW���Ă����s�����܁t�f�ڂ́q�~�̃V�����\���r�ȂǁA6�т𐔂���݂̂ŁA�s�l�ށt�ɂ͐��e���O�Y�ŔӔN�̎������]���Ƃ���Ȃ����߂��Ă���B
���W�̐��肽���Ƃ��ẮA����1979�N��11���Ɋ��s���ꂽ�s��̖���t�Ƃ悭�����o�܂����ǂ��Ă���B����A���Ԃ͋t���B�O�f���ŋg�����u���e�搶�́k�c�c�l�A�s�l�ށt�͍Ō�̎��W����ƌ���ꂽ�B���͍m����ے�����Ȃ������v�Ə������̂́A���Łs���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1963�j�Ɏ��߂�ꂽ�����́q���W
��̖���r���ꊪ�́s��̖���t�Ƃ��邱�Ƃ�\�����Ă������߂ł͂Ȃ����B�����W�́s�l�ށk���y�Łl�t�ɒx��邱�Ɣ����A�ԗj�Ёi�V�q�r���s���e���O�Y �ϗe�̓`���t���o�����j����A�������g���������Ŋ��s����Ă���A�P�s���W�̊��s���ł����A�s��̖���t���u���e�Ō�̎��W�v�ƂȂ�B
�X�J���|�b���e���O�Y
�ꖇ�̃X�J���|�̗t�����߂Ă���
���̉Ă̖閾����
�l�Ԃ̎�q��
���ǂ����Ă���
�s�l�ށt�ōł��Z�����̂ЂƂł���B���̎�����悭����ƁA�����W�̒��ю��q�L�T�T�Q�r�i���o�́s�����C�J�t1972�N4�����ŁA�g���̘A�����q�t�r�������Ɍf�ځj��4�s�u�k�c�c�l�^�ꖇ�̃X�J���|�̗t�����߂Ă���^���̉Ẳ��g���^�l�Ԃ̎���^���ǂ����Ă���v�ɍ������Ă��邱�Ƃ��킩��B�q�X�J���|�r�̏��o�͑S�W�k��10���l�i1973�N1��20���j�����A�q�L�T�T�Q�r�Ƃǂ��炪��Ɏ��M���ꂽ�̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ��B������ɂ��Ă��A���e���̐������l���邤���ŋ����[������ł���B
����A�g���ɂ�8�s���琬�鎍�сq�f�z�r�i���o�́sCURIEUX�\�\�����t4���A1978�N11���j
�ނ炳���F�Ɏ����߂���
�u���v���čs���@���v�v
�������������H�̖��̊C�ł���Ȃ��
�ւ����������ɑ�n���݂�
�K�̍��@�����@�ÌC�@��
�L���̏��w�̔����̂Ȃ��ł������Ă���
�u��ƒ܂������ʂ��́v
����牼��̐��̉��̑��m�������n�͍����������c�c
���q�H�v���r�i�J�E8�A���o�́s�����C�J�t1982�N12���Վ��������j�ɕω��z�������Ⴊ����B
�s�l�ށk���y�Łl�t�̎d�l�́A��Z��~��l�O�~�����[�g���E�O�Z���y�[�W�E�㐻�p�w�z���B�\���̋��̃X�P�b�`�Ɣw�����͋��������B����ł͓������㐻�p�w�ŁA�p���\���i�w�́s�Ẳ��t�̔w�Ɠ���̕z�A���͊D�ΐF�̃N���X�j�A�{���O�̕ʒ��Ƀy�����������B���Ԃ��i�ю��Ɠ������ŁA�\���Ƃ̑g�݂��킹���▭�ł���j�E�{���E�{���̗p���͗��łƂ��ɓ����B����ʼn��t�ɂ͈���ɂ��u����
1,200���̓��v�̉����Ƀi���o�����O�}�V���ɂ��L�ԁA����ɉ����Ɂu���v�̉�悳��Ă���B�V�q�O�f���ɂ́A�{���̐}���ɂ��āu���̔��Ɏg��ꂽ��͂́A�u�q���K�z�v�̖����̎��s�ɂ��Ȃ�ł���i�u�Ƃ���ł��Ȃ��͖�͊w���^������Ƃ�������ł��悤���^���̐ԖV�����ׂ悤�Ƃ��Ă���^�ւ̖�͉��Ƃ����܂������ˁv�j�B���̐����Ȗ��͔O�̂��߁qSerpent vorant�r�ł���v�i�q���W�l�ނɊār�A�l�y�[�W�j�Ƃ���B
�g�����͂��̍ŔӔN�Ɂu���e���O�Y�̍Ō�̎��W�́w�l�ԁx�Ƃ����薼�ł��������A��Ɂw�l�ށx�Ɖ��߂��āA���s���ꂽ�B�X�P�[���̑傫�ȁA�f�������薼���Ǝv���B�^�㈲���ꂽ�V��W���A�w�l���x�Ɩ��Â����Ă���̂�m���āA���͂ӂƎv�����B���̎��l�ֈ،h�̔O�������Â����k�߂��A�Ђ����Ɍĉ������Ă���̂��Ɓ\�\�B�w�l�ށx�����I�Ƃ�����Ȃ�A�w�l���x�͂܂������o�~�I�ł���v�i�s�Ս��t445���A1989�N2���A�܃y�[�W�j�Ɓq�k�ߋ�W�w�l���x�\�����r�ŏ����Ă���B���e���O�Y���W�ւ̋g���Ō�̌��y�ł��낤�B
 �@
�@ �@
�@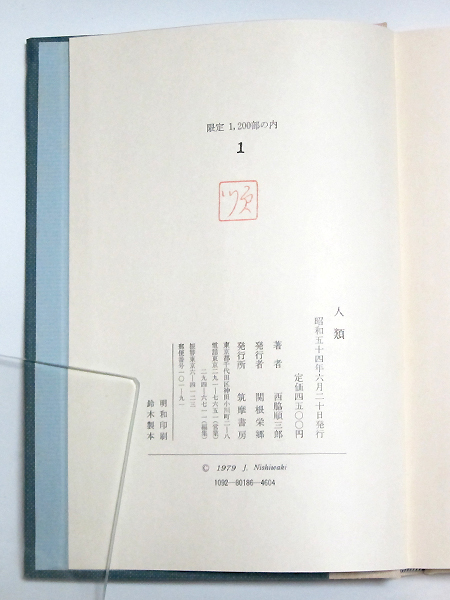
���e���O�Y���W�s�l�ށk���y�Łl�t�i�}�����[�A1979�N11��15���j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ����Ɠ��s�l�ށk����Łl�t�i���A1979�N6��20���j�̕\���i���j�Ɓk����Łl���t�i�E�j�k�o�T�F���e���O�Y���W �l�� (1�Ԗ{/���e�Ƌ���) ���� ���� �� �� - ���t�I�N!�l
�k2014�N9��30���NjL�l
���e���O�Y���W�s�l�ށk����Łl�t����肵���̂ŁA���e�������ւ����B�g���̑O�f�q�s�l�ށt�o���r�ɂ���Ƃ���A�{���͒}�����[��1978�N7���Ɏ�����|�Y�����ق�1�N��Ɋ��s���ꂽ�B���R�Ȃ���A�o�Ŋ��͌������R�����ꂽ���낤�B���������Ȃ��ŁA�����ɂ͗\�Z�̐��������ŁA�o�łɓ�������p���Ȃ�ׂ���������������A����ɓK������ɂ������Ƃ����v���������B�����k����Łl�ɂ͔���Ȃ̎p���͔��o���������Ȃ��B��ɂ������Đ�捂ŁA�����Ȃ������܂��������Ă���B5������́k���y�Łl�̊��s�́k����Łl�̔���䂫���㉟���������ʂ��낤�B�k����Łl�͒艿4500�~�~����1200����5400000�~�K�͂́A�k���y�Łl�͒艿2400�~�~�����s���̋K�͂̏��ЂƂȂ����B���Ȃ݂Ɂk����Łl��1200���́s�X�L�t��s�߉́t�A�s����t�i��������}�����[���j�Ɠ������ł���B
�u�����̔錍�́v�ƕ����Ă݂�ƁA�k�g������́l�u�ڂ��̓f�U�C�i�[����Ȃ�����A�錍�ȂȂ���v�ƏƂ�Ȃ��瓚�����B
�@�u�g����͈͓��ŁA��Ԃ������ނ�I�Ԃ��ƁB���Ƃ͕����ƃV���{���i�J�b�g�j�̃o�����X�A���ꂾ�����ˁv�u�X���Ŕh��Ȗ{���D�������ǁA�ڂ��̍��{�́A�ƂɎ����Ă��ė��������ēǂ߂���̂ɂ������v�i���c�N�v�q�g��������r�A�s���������Ȃ�\�\�ڂ����ҏW�Ґl���ŏo����������Ȑl�����t���w�فA2014�N9��3���A���l�`���܃y�[�W�j
�g���͐��e���O�Y���W�s�l�ށk����Łl�t�Œ}�����[�ݐЎ��ƕς��ʁA���₻��ȏ�ɂ݂��Ƃȑ����������B�k����Łl�Ɓk���y�Łl�̊ԂɊ��s���ꂽ�g���̎��W�s�Ẳ��t�i1979�N10���j�����e���O�Y�̑���ŏ����Ă���B�^�C�g���|�G����������ꂽ�Ƃ͂����A���e���ʊǂ��������w�i�ɂ́A�s�l�ށk����Łl�t�̑����ɑ���ԗ�̈Ӗ������߂��Ă�����������Ȃ��B
�V�q�r��s���e���O�Y �ϗe�̓`���t�i�ԗj�ЁA1979�N9��25���j�̉��t���L���ɂ͐��e���O�Y�s�G�k�̖閾���t�A���i�ވ�s���ɒ����t�ƂƂ��ɁA���e���O�Y�������W�s��̖���t�̗\�����ڂ��Ă���B�����W��11��30���ɂ͊��s����Ă��邩��A�s���e���O �Y �ϗe�̓`���t�ƕ��s���Ċ�悪�i�s�������̂Ǝv����B�{�����t���L�����炻�̕�����^����B
���e���O�Y�^��̖���^�������W
���a�\�l�N�\�����s�\��^�l�Z���ό^�E������
���^���с^�R�b�v�̉����@�C�^���A�@�C�^���A�I�s�@���[�}�̋x���@�ʐ^�@����݂̖@�o�@������@�֎q�@��@�܂�����@�L���̂��߂Ɂ@�������@�G�s�b�N�@ �R�̌ߌ�@�o�[���ґz�@�_�̂ӂ邳�Ɓ@��̖���
�{ ���ɋ��݂��܂ꂽ���O�܂�́q�ԗj�� �o�Ŗژ^ 1980�N�Łr�ɂ́A�����W�̐����Ƃ��āu���a�O�\���N�A���l���\�̔N�ɏ������낵�����я\���сk�}�}�l�B���e���Ɉ�т��ė�����~悂ƗH���̋ɒv��\ �킷���W�Ƃ��Ċ��s���҂��ꂽ�Җ]�̈���B�����ɂ͎��l�̖��ʉ�u�T���E�}���R�̒��v���B���l�g��������ɂ��M�d�Ȏ��W�B�@�N���X�������艿�� �Z�Z�~�v�Ƃ���B����������ƁA�{�����s�̎��_�Ő��e���W�̑����̎d�l���u�l�Z���ό^�E������v�Ō��܂��Ă������Ƃ��킩��B����1979�N �́A6�����s����t�� ��9�N�Ԃ�̐��e�̎��W�s�l�ށk����Łl�t���Ăыg�����̑����ŌÑ��̒}�����[����i�s�l�ށk���y�Łl�t��11�����j�A10���ɂ͐��e���`�����낵���G�� ���ƕ\���E���\���ɂ���������g���̐V���W�s�Ẳ��t�i���Ҏ����j���y�Ђ���o�Ă���A�g�����Ɛ��e���O�Y�̉i���ɂ킽��𗬎j�̂Ȃ��ł��A�ЂƂ���Z ���ȔN�ƂȂ��Ă���B
 �@
�@
�V�q�r��s���e���O�Y �ϗe�̓`���t�i�ԗj�ЁA1979�N9��25���j�Ɓs���e���O�Y
�ϗe�̓`���k����V�Łl�t�i���[�A1994�N1��15���j�̃W���P�b�g�i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�{���̕W��s���e���O�Y �ϗe�̓`���t�́A�q�w�A���o�������A�x�\�\�p�E���h���Ɂr�̎��̈�߂��痈�Ă��悤�B
�� ���G���I�b�g�̎t���ł�����G�Y���E�p�E���h�k�c�c�l���g���u�����̎���Ƀ_���e�́w�_�ȁx�̂悤�ȍ�i�������͍̂���ł���v�ƌ����Ă���B�����A���� �悤�ȌÓT�Ǝ����Ƃْ̋��W�A�s�f�̈��p�ƕϗe�A�܂臀�����ւ����Ă����w�͂����A���w�̓`���Ƃ����Ӗ��ł���A�n���Ƃ������Ƃł���B�^�^���{�̌� �㎍�l�̂����ŁA�����ϋɓI�Ɏ��H���Ă����̂́A���e���O�Y�ł��낤�B�i�{���A��l�l�y�[�W�j
�{���̎d�l�͈ꔪ���~��~�����[�g���E�O���y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B�N���[���F�̒n�ɐ�F�ŊG�����������W���P�b�g�̑��ɂ́u�W���� �W���[�l�u�t�F�g�E�V�����y�[�g���v�v�ƃN���W�b�g������A����Ɋւ��Ē��҂͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�{ ���̃J�o�[�̊G�͐��e�搶�̈��D�̃W�����W���[�l��u�t�F�g�E�V�����y�G�g���v�ł����āA���̑�ɂ��g���Ă���B���̂��Ƃɂ��Ă͖����́u�G��̐� �E�v�łӂꂽ�B���̂悤�Ȕ�������������l�̋g��������ɂ��Ă������������Ƃ́A��ς��ꂵ���B�i�q�͂��߂Ɂ\�\�W�����E�R���A�K��L�r�A�{���A���y�[ �W�j
�q�G��̐��E�\�\�������ƃ��B�W�����r�ɂ́u���̃W�����W���[�l��
�u�c���̑t�y�v�́A�G�h�D�A�[���E�}�l���u����̒��H�v�i�ꔪ�Z�O�N�j�ɂ��̃��`�[�t���ؗp�������ƂŗL���ŁA�k�c�c�l���̊G�ɂ��Ă̓s�J�\���}�l�[
�k�}�}�l�̃J���J�`���A��`������A���ɂ��p���f�B�̃p���f�B�������ȂǕϗe�̗��j�ɖ����Ă��āA���e���O�Y�����̊G���p���f�B�̑ΏۂƂ����̂͌d��
�Ƃ����悤�v�i�{���A��y�[�W�j�Ƃ��邪�A�����͋g���́q����̔ӎ`�r�i�G�E13�A���o��1974�N4���j��z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B
��������15�N��A����V�ł����[�Ƃ����ʂ̔Ō�����o�Ă��āi�ҏW�S���҂͓��������ʎ��j�A�����ɐV�e�q���e���̌��݁\�\�L���Əے��̎��w�r���lj�
���ꂽ�B����V�ł̑����́A�����ł͖{���Ɍf�ڂ������e�̃X�P�b�`�q���k�X�r���W���P�b�g�ɂ����Ă������߁A�{���������g�݂����ɂȂ����i���ڂ̗p���̂�
���ŁA�m�h���g�ł��Ă���̂͊��S���Ȃ��j�B�Ȃ��A����V�łɑ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B
�w�|�j�ƁE�X�L�O�i1895�`1985�j�́s�����ӏ����t�i�}�����[�A1988�N11��20���j�́A�{�M�̉��ْk��s�����L�L�t�Ȃǂ̎x�ߎ�ɍނ�40�т��琬�鏬�i�W�B�{����S�ю��^�����s�X�L�O����W ���ҁt�́q�ҏW��L�r�ɂ�������B
�@�u�����ӏ����v�́A���a�Z�\�O�N�\�ꌎ�A�}�����[���o�ł��ꂽ�P�s�{�ɁA�G���w�����������x���a�O�\�N�㌎���ɔ��\���ꂽ�u�ĉ�v�̈�т�V���ɕ������B�P�s�{�͂`�ܔ��ό^�i�c��Z�܇_�~����܌܇_�j�B�ڎ��l�ŁA�{����Z��ŁA�ҏW��L�i���o���m�j�O�ŁA�艿��Z�Z�Z�~�B�����g�����B�Ȃ��u�L�������Әb�v�k17�т̑薼�l�u�L�v�̏��т́A��s�̒P�s�{�w����ԁx�k���䏑�@�A1943�E�\�����[�A1984�l�ɁA�u��Ձi���̈�j�v�k7�т̑薼�l�u�s�v�c�ȊG�M�v�̏��т͓�������s�̒P�s�{�w���M�W �m�x�k�Z���o�ŁA1986�l�ɂ��ꂼ����߂�ꂽ�B�i�����K�F�E���q���F�E���o���m�ҁs�X�L�O����W���ҁk��15���l�t�A�������_�ЁA1995�N2��20���A�܋㔪�y�[�W�j
����W���{�ɂ��ď��o���m�ҁs�X�L�O���U�t�i�����ЁA1996�j������5�т₵���̂��s�V�� �����������k�u�k�Е��|���Ɂl�t�i�u�k�ЁA2005�j�ŁA�}���ł⒘��W�Ƃ͎�r�ς���Ă���B���z�{�̂��߂̑[�u�Ƃ͂����A�V���ȂÂ����ɉ��߂�ꂽ�͎̂c�O���B�X�L�O�́s�ÓT���{���w�S�W35�k�]�ː��z�W�l�t�i�}�����[�A1961�j�Ŏ������q�x��G�b�r�ق����o���Ă��邪�A���O�ɒ}�����[���s�̒����͂Ȃ��B�Ō����{���̑�����N�Ɉ˗����邩�̓t���[�n���h�ɋ߂������낤����A�u�}���炵���{���v�Ƃ������ƂŁA�Г������o���̒����n�a�̋g���ɔ��H�̖���������B�S�̓I�ɁA��̎푺�G�O�s���{���V�L�t�i�}�����[�A1989�j��ܒJ���m�s�F�V���F�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1990�j�Ǝ������͋C�ŁA�{����嗋����_�Ώ̂Ȃ̂́A���Y�N���ɂ���s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�̎�@�܂������̂��B�W���P�b�g��\���ɗp����ꂽ�a���̗m���̑I�����������B���^�ѐ����قȂ邪�A�e�ł̎d�l�̊T�v��\�ɂ܂Ƃ߂Ă����B
| �Ŗ� | ���s�N | �ѐ� | ���^ | �{���m���u�� | �{������ | ���l�߁~�s���i���������Łj | ���o���E�z�u |
| �}���� | 1988 | 40 | �`�T�� | 3-201 | 10�| | 41�~16�i656�j | 6�s�ǂ�E���� |
| ����W | 1995 | 41 | �`�T | 389-520 | 9�| | 50�~18�i900�j | 3�s�ǂ�E�Ǎ��� |
| ���|���� | 2005 | 46 | �`�U | 11-207 | 12Q | 40�~17�i680�j | 7�s�ǂ�E�Ǎ��� |
 �@
�@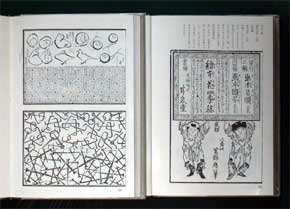
�X�L�O�s�����ӏ����t�i�}�����[�A1988�N11��20���j�̖{���ƃW���P�b�g�i���j�Ɖi�c�����ďC����s�k�ւ̊G��{�܁t�i�����p�ЁA1986�N10��12���j�̖{���i�E�j
�{���̎d�l�́A����~��l���~�����[�g���i�O�f�q�ҏW��L�r�ƈقȂ�̂́A�{���y�[�W�̓V�n�E���E���@�̂��߁j�E����y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B�W������Ɂu����E�g�����^�i��E�k�ցj�v�ƃN���W�b�g������B�k�ւ͖{���ɂ͓o�ꂵ�Ȃ�����A�}���̑I���͑������ɂ����̂��낤�B�֘A���ɂ��������Ƃ���A�i�c�����ďC����s�k�ւ̊G��{�܁t�i�����p�ЁA1986�N10��12���j�ɖ{���ƃW���P�b�g�ɗp����ꂽ�悪�f�ڂ���Ă����̂Łi���l�E��ܓ�y�[�W�j�A�g���������ƕ��ׂČf���Ă����B�Ȃ��A�g���́q���L���\�\���Z���r�Ɂu�l����\�O���^�������Ŗk�֓W������B���M�́A�S�ւ̋C�i�ɗ��Ǝv���邪�A�ʼn�͓V�˂̍삩�Ǝv����B���Ƃɕx�ԎO�\�Z�i�͐�i�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���y�[�W�j�Ə����Ă���B
�g���́q���L ���l�Z�N�r�i�s�邵����t5���A1990�N1��31���j�Ɂu�ꌎ��\�ܓ��@�X�L�O�s�n�ӛ��R�t�B�k�c�c�l�v�Ə����Ă��邩��A���̓��A�s�n粛��R�k�n���I���l�t�i�n���ЁA1941�j�������ǂ������̂��낤�B�g���͂����ȊO�ŐX�L�O�Ɍ��y�������Ƃ͂Ȃ����A�s�����ӏ����t�́u��v�i�{�M������̘b�j�̎O�Ԃ߂ɒu���ꂽ�q���m�r����ɈႢ�Ȃ��B���������̒i���͂������B
�@�̖{���ɁA��[���₤����]���m�Ƃ��ӊ�ň��g�̂��鉻�����o���������B�^�ÂȔӂɁA���̂Ƃ������c��������R�ƌ���āA�����̑O�O�l�ڔT�����Ԃ̂Ƃ�����s���B�l�e�͂Ȃ��āA�������ۂ���Ɩ��邭�A���₤�lje�G�ɉf���o���ꂽ���̂̂₤�ɁA�Èł̒����ӂ�ӂ瓮���čs���̂������ł���B�i�{���A���y�[�W�j
�g���͖{���̐��܂ꂾ����A����Ȍ���ꂩ�畷������Ă�����������Ȃ��B�q���m�r�ɂ́u���̂����́A�{���̓��ł��A�Ό��ӂ��犄�����̕ӂ܂ł̏\�]���l���̂Ƃ���ɏo���Ƃ��͂�Ă���v�i���O�A��O�y�[�W�j�Ƃ���B�܂��u�����Ȃ��k�ԁ��F�i����W�ȍ~�A�ύX���ꂽ�j�l�ɍ炭���Ɩ����������̂Ƃڂ��̒���̉ԁv�i�{���A�܋�y�[�W�j�Ƃ�������{�����ɔz�����q����r�́A�X�L�O���q�������ɏ������q���_�r�i�s�Ԃ����t1927�N6�����j���v�킹����т��B�g�����q�����k�ցr�i���O�A4�����j��ǂ��́A�킩��Ȃ��B
�k2013�N8��31���NjL�l
�C���X�g���[�^�[�ŁA�������悭����G�b�Z�C�X�g�̓�L�V���s�����V���t�i2013�N3��10���j�́q�v���o���{ �Y��Ȃ��{�r�Ƃ������ŁA�{���i�}���łƕ��|���ɔŁj�ɐG��Ă���B���́q���_�ɋ�����������杁\�\�X�L�O�w�V�� �����������x�r�œ�́u���͍]�˂⒆���̉��k���D���ŁA����Ȃ��̂��Ⴂ���������A����Ƃ��߂�悤�ɔ����Ă��āA���X�A��������o���Ă��ēǂ肵�Ă��ł��B�^�������������w�V�ҁ@�����������x�͕��ɖ{�ł��B�͂��߂ɍw�������̂͒}�����[�ł̒P�s�{�ŁA���l�̋g�������k�֖���̊G��z���đ��������A����ꂽ�{�ł����B�u�ł���Εi��łȂ��{���v�Ƃ��������Ȃ�ŁA���ɂ̂ق��ɂ��܂������A���邢�͂����������ɐ�ł�������܂���v�i�����A��l�ʁj�Ƃ����Ă���B�g�������̒}���ł́A��L�V�̑����ł����Ă����������Ȃ��앗���Ǝv���B
����A�y���F�̈╶�W�s���e�̐�t��S���������c�N�v�́A��L�V�Ƃ̑Βk�q���c�~��r�Łu�R�O�N�ȏ�ҏW�҂�����Ă��邯�ǁA�l�����̐��E�ɓ����������āu�����ƒ��Җ��������Ă�������B�]���Ȃ��̂͂���Ȃ��v�Ƃ����ҏW�҂͑��������ł���B�������A�D�ꂽ����Ƃ͉������A�g�������Ď����Ă����l�����܂����B�Ⴆ�A�}�����[�ɂ������l�ł�����g��������̑���͍D���������B�w�k�Z�{�l�{�V�����S�W�x�w�����Y�S�W�x�i�}�����[�j�ȂǁA�f���炵������ł���ˁv�ƌ���Ă���B
���e���O�Y�́s���{�t�i�}�����[�A1968�N2��29���j�́q���Ƃ����r�i�����Ɂu�k���a�l�\�O�N�l�O���v�Ƃ������t������j�̈�߂ɋg�����̖����Ƃǂ߂Ă���B
�@���̌v��̎��s�͂܂�O�N���������B���Ă͒}���̈��B�O���ł������B�k�c�c�l��N�̉ĂɂȂ��āA�}���̉�c�j�Y�N��g�����N�Ɛ_�c�Ńg�R���e�������Î����݂̂Ȃ���u���w�v���������̂ł������B�i�{���A�O�Z�O�y�[�W�j
�{���͏������N��1969�N3��31���ɂ͑������s���w�k�}���p��136�l�t�Ƃ��čĊ�����Ă��āA�����ŏ��ɓǂ̂������炾�����B�}���p���ł́q�ڎ��r����q���Ƃ����r�܂ł̑g�łɌ��ł̎��^�𗬗p���Ă�����̂́i�O�t�E��t�ɂ����ꕔ�lj�����j�A�����ɐV����5�y�[�W�ɂ킽��q�l�������r���t����Ă���A�����Ƃ��Ă̌��\�͒}���p���ł̕��������Ă���B
���ł̎d�l�́A�ꔪ���~����~�����[�g���E�O��l�y�[�W�E�W���P�b�g�i���e���O�Y�̕M�Ǝv��������ŏ����Ă���j�E�㐻�N���X���E�@�B���ɓ\���ӁB�����҂̃N���W�b�g�͂ǂ��ɂ��Ȃ����A�}���ɍݐВ��̋g�����̑����Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ����낤�B�{���Ɠ��l�̃O���[�̋@�B���i�z�`�L�X���߁j�́A�{��~�s���p�̐D���t�i�}�����[�A1975�j�ł��g���Ă���B
�ѕ��ɂ́u3�N�]�̍Ό����������������J��^�L���Ȋw�B�Ɛ[���o���������E�I���l��3�N�]�̍Ό��������A���߂Đ��ɖ₤�Ƒn�I���w�B�|�G�W�C�Ƃ͉����B�|�G�W�C�̖������ǂ��l���邩�B���������̔閧�����Ƃ��Ƃ��Ђ炢�Ă݂��閼���^�艿850�~�E�}�����[�v�Ƃ���i�{�f�B�R�s�[�������S�`�b�N�̂��j�B�V�q�r��́s�]�`
���e���O�Y�t�i�c��`�m��w�o�ʼn�A2004�N11��10���j�ɂ́u���a�O�\��N�l������c��`�m�v�ۓc�����Y�L�O�u���u���w�v���n�܂�A���̏��N�x�͍����t�v���O���ŁA����͐��e���\�肳��Ă����B�k�c�c�l���e�͏\���������\��ɂ킽���ču�`���s�����B���̍u�`�����������ƂȂ��āA���a�l�\�O�N�i���Z���N�j�ɒ}�����[���w���w�x�����s�v�i�����A��O���y�[�W�j�Ƃ����āA�{���̐����ߒ���`����B
 �@
�@
���e���O�Y�s���{�t�i�}�����[�A1968�N2��29���j�̔��Ƌg�����Ɉ��Ă������̂��錩�Ԃ��i���j�Ɠ��E�\���Ɓs���w�k�}���p��136�l�t�i�}�����[�A1969�N3��31���j�̕\���k�����F���O�i�m�c�b�j�l�i�E�j
�g���͐��e���O�Y�Ǔ����т́q���́r�i�J�E13�j�Łu�����͂͐��e���O�Y�w���w�x��菴�o�����v�ƒ����Ă���̂ŁA���т́u2�v�̑S�����������B
����̐��E�͈�̗��h�ȉ��̏ے��̐��E�ł��邩��A�u�q���[�^���v�Ƃ������͂����ɂ����̂́u���b�v�m����n���悭�ے����Ă���悤�Ɏv����B����������͓��{�l�����ł����āA���{���m��Ȃ��l�ɂ͂��̉��͉����u���v�̂悤�Ȉ�ۂ�^���邩���m��Ȃ��B���Ƀt�����X��̃O���h�igourde�j���Z�\���̓t�����X���m��Ȃ��l�ɂ́A���̉��͂ނ���u�����ނ��v���悭�ے�����Ǝv�������m��Ȃ��B
�q�A�|�R�y�r
���́u2�v�́A���Ɍf����s���{�t�́q11�\�\���̐��E�r�̈�i�����قƂ�ǂ��̂܂܈��������̂��B�O�̂��߂ɋg���̉��ωӏ���������A�@�u���b�v�ɂӂ肪�ȁm����n��t�����A�A�O���h�igourde�j�Ɂ��Z�\����NjL�����A�B�Ō�Ɂq�A�|�R�y�r��u�����A��3�_�ł���B
�@ ����̐��E�͈�̗��h�ȉ��̏ے��̐��E�ł��邩��A�u�q���[�^���v�Ƃ������͂����ɂ����̂́u���b�v���悭�ے����Ă���悤�Ɏv����B����������͓��{�l�����ł����āA���{���m��Ȃ��l�ɂ͂��̉��͉����u���v�̂悤�Ȉ�ۂ�^���邩���m��Ȃ��B���Ƀt�����X��̃O���h�igourde�j�̓t�����X���m��Ȃ��l�ɂ́A���̉��͂ނ���u�����ނ��v���悭�ے�����Ǝv�������m��Ȃ��B�i�{���A��Z�O�y�[�W�j
�s���{�t�̊��z���q�ׂ悤�Ƃ���ƁA��ؓ�ł͂����Ȃ��B�u���I���͂ɂ́A���Q�������̂ł��������A���z�ًȂ̔����������A�]����悷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�l�y�[�W�j�Ƃ͋g���́s�߉́t�]�����A�������������{���ɐi�悵�����Ǝv���B�H�ɂ́u�q���[�^���^���b�v�Ɋ֘A���āu���̎���ɂ����R���̐��E���͂��肱��ł���B����ʼn��̖�肪������B���͂��͂���̉C���ɂ��l���͗p���Ȃ��B�������낢��̎q�C�ƕ�C�̘A���̑g�������炭�邢�낢��̉��̃C�}�[�W����I�ӎ��ɂ���đI������B�u�q���[�^���E�t�N�x�m���C�v�Ƃ��v�i�{���A����y�[�W�j�̂悤�Ȏ����d���ׂ���߂����邪�A�����Ă��̓y�[�W���߂����Ă��߂����Ă��_���O�ɐi��ł����Ȃ����ǂ��������o����i���e���s���{�t�œW�J���Ă��鎝�_�́A�{�����s�̗��N���\�́q�䓁�Ɨь�r�ɃR���p�N�g�ɂ܂Ƃ߂��Ă���j�B
�s���{�t��ʓǂ����Ƃ���A�u�_��I�v�Ƃ����ꂪ47�y�[�W�ɂ킽���ēo�ꂷ��i����͖{��6�y�[�W��1��̊����ŁA�_��E�_���`�E�_���`�҂��p�o����j�B����������ƁA�g���̎��сq�_��I�Ȏ���̎��r�i�F�E11�A1968�N10�����\�j�̃X���X�̂ЂƂ��B�܂��A�}�������͖{���Ń{�[�h���[���Ɏ����Ō��y�̑������l�����A���́u��i�G�j�O�}�j�v���o�ꂵ�Ă���i13�E109�E160�y�[�W�j�A���сq�y���r�i�H�E1�A1976�N���\�j�̖����u��m�G�j�O�}�n�^���͍݂�v��z�N�������ɂ����Ȃ��B
�ʐ^�̋g����������ѕM��������̐��e���O�Y�s���{�t�͈����[�ŋ��߂����̂����A1�ӏ����������݂��Ȃ��A��f���p���̃y�[�W���܂�����ł���B1982�N6��5���̐��e������A�g���́s���㎍�蒟�t1982�N7�����̑剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�Ƃ̒Ǔ����k��q��ނȂ����I���݁r�ɏo�Ȃ��A�s�V���t8�����ɒǓ����q���e���O�Y�A���x�X�N�i�Ǔ��j�r�����M���A�s�����C�J�t7�����Ɂq���́r�i���o���A�����ɂ́u�i��㔪��E�Z�E��Z�@�ʖ�̓��j�v�Ƃ��������A���W�ł͏Ȃ���Ă���j���Ă��āA���̒Ǔ����ɂ���قǑ����̎��Ԃ��������Ƃ͎v���Ȃ��i�g���͎��������ɂ�1�ӌ����œK���Ƃ˂Âˌ����Ă����j�B�������݂̂Ȃ�����{����́A�ؔ��������ԓ��ŒǓ��������M�����g���̋C�����̂悤�Ȃ��̂��`����Ă���B
�g�����͋{��~�s���p�̐D���t�i�}
�����[�A1975�N3��20���j�����A�{��~�Ǔ����сq�D���̎O�̒[�z�r���s�G�s�X�e�[���[�t�i1978�N11�����j�ɊA�����ǗY�E�����O�E��
���G�O�E�L�����E�����C��ҁs�{��~����W�k�S3���l�t�i���p�o�ŎЁA1980�`81�j�̑�����S�������B�{����W�̎d�l�͓�Z���~��l���~�����[�g
���E�㐻�p�\���i�w�̓N���X�A���͕z�j�E�\���B��1���i1980�N5��1���A�Z�O�l�y�[�W�j�A��2���i1980�N10��25���A���Z�l�y�[�W�j�A��3��
�i1981�N9��15���A���Z���y�[�W�j�B�ʒ��{���̎��̔����Ɂu����@�g��
���v�ƃN���W�b�g������B�{����W�̐V���Łi�S��1999�N9��20�����j�̑����͒��_�M�v�Ȃ̂ŁA�V���ł̓����y�[�W�ɂ���u����@�g��
���v�̕\���͌��ł̑����҂Ƃ������Ƃ��B����Ƃ��g�����{���g�łɂ��֗^���Ă����̂��B���Ȃ݂Ɍ��ł̖{���̈���͊��ł����A�V���ł́i���ł̐��������
�����N�������H�j�I�t�Z�b�g�ł���B�\�\�g������������|�����O���{�̑S�W�Ƃ������s��
���d�M�S�W�t���z�������Ԃ��A�{����W������ׂ��s�g�����S�W�t�͂�����Ƒz�������錩���ȏo���f���ł���B
����A�{��~�͋g�����̎��ɑ��āA1963�N�́q�G�߂͂���E�r���b�t�F�W�r�i�s������w�V���t4��17���j�Łq�ߋ��r�i�B�E17�j�ɐG�ꂽ�̂�M��
�ɁA1968�N�́q�w�g�������W�x�r�i�s���㎍�蒟�t1�����j�ł́q�Õ��r�i�B�E4�j�A�q��r�i�B�E14�j�A�q���̂��肠����r�i�D�E13�j�A�q���w�r
�i�D�E7�j�A�q�P���r�i�C�E9�j�A�q�t�̃I�[�����r�i�E�E10�j�A�q�W�����O���r�i�B�E13�j�Ɍ��y���A�q�|�p�̏��ł͉\���r�i�s�������}�ԁt6�����j
�ł͍Ăсq��r�ɐG��A7���́q����̌��ƈŁr�i�s�G���R���t8���j�ł́q���w�r�A�q�`���r�i�C�E5�j�A�q���r�i�B�E7�j�A�q��r�A�q�Õ��r�A�q�҉́r
�i�B�E12�j�A�q���鐢�E�r�i�B�E5�j�A�q���̂��肠����r�A�q�t�̃I�[�����r�Ɍ��y���Ă���i��������{����W�̑�2���Ɏ��^�j�B
 �@
�@
�s�{��~����W�k��1���l�t�i���p�o�ŎЁA1980�N5��1���j�̔��Ɩ{���i���j�����E�\���Ɓs�{��~����W�k�V���ŁE��1���l�t�i���p�o�ŎЁA1999�N9��20���j�̕\���k�����F���_�M�v�l�i�E�j
�q�D ���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�ɓo�ꂷ��u�@�v�Ɓq�@�r�Ŋ���ꂽ���p�����A�{��~�̃e�N�X�g�Əƍ����Ă݂�B�g�����̎���c�c�{��~�̕��́A������ �i�@�j���́s�{��~����W�t�����̏����A�W��A����W�̊����k���[�}�����l�E�y�[�W�m���u���k�������l�E�s���k�A���r�A�����l�̏��B�Ȃ������тŒn�̎��� �Ƃ��ċL����Ă��邪�A�u�{�삪�p�p�������t�������v�i�����r�Y�q�ӏ܁r�A�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��l�y�[ �W�j�Ƃ���́u�\�ʁm�A�A�n�^�\�ʓI�m�A�A�A�n�^�\�ʉ��m�A�A�A�n����v�����p���Ɠ���Ɉ������B
�� �u�C�}�[�W���͂����������ց^�������܂������Ɂ^�Ӗ��������Ƃ���v�^�{��~�c�c�C�}�[�W���͂����������ցA�������܂������ɁA�Ӗ��������Ƃ���B �i�k�s���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]���߂��鈢���ǗY�Ƃ̉������ȁr�A�V�E�Z�Z��E12-13�j
�� �u�i���̐ςݘm�����F�ł���j�̂́^���ɂ��������邩�炾�v�c�c���̐ςݘm�����F�ł���͎̂��ɂ��������邩�炾�\�\���삵�Ď���̊��o��ǂ��Ă䂭���� �ɁA�ނ�̓t�H�������F�ʂ��P��s�ς̗^���ł͂Ȃ��A�����̕ω��̂܂܂ɍ��X�Ƃ��낢�䂭���ΓI�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ�����B�i�k�s���p�j�Ƃ��̌��� [�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q�Z�U���k�ƃX�[���r�A�V�E�Z���E8-10�j
���u�d������y�݂ց^��n�I�Ȃ��̂���^��C�I�Ȃ��̂ցv�c�c���Ȃ킿�A�d������y�݂ցA��n�I�Ȃ��̂����C�I�Ȃ��̂ցA�����ă}�`�G�[���� ���\��������ɂ��\���ցB�i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q�K��ɂ��ā\�\�O�ݍD���Y�ƍ����S�O�r�A�T�E���܁E7-8�j
���u��Ԃ̂Ȃ��Ɂ^�J�����^�����ЂƂ̋�ԁv�c�c��Ԃ̂Ȃ��ɊJ�����A�����ЂƂ̋�ԁB�i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q���ɂ��ā\�\ �W�����W���E�u���b�N�r�A�T�E��Z��E11-12�j
���u�����邱�Ƃ������ꂽ�^�i��ԁj�ł���v�c�c�k���ځl
�� �q�����Ό�������̂́^�����ł���^�����r�c�c���ɂ����ĂȂɂ�\�����悤�Ƃ����̂��A�Ƃ����₢�ɓ����āA�u���b�N�́u�����Ό�������̂͋�� ���ł��钹���B����͋��`����ƂɂƂ��đ傫�ȗU�f�ł���v�ƌ���Ă���B�i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q���ɂ��ā\�\�W�����W���E�u���b�N�r�A�T�E��O�E8-10�j
���u�����͎����Ɏ��Ă���v�c�c����́A���̎���Ƃ��Ă͂ނ����O�I�ȍ��ł���w���F�̃e�[�u���E�N�� �X�x�i���O�ܔN�j�ƂƂ��ɁA�����قƂ�ǎ����Ƃ����Ă悢�قǂȂ̂��B�i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q���ɂ��ā\�\�W�����W���E�u���b�N�r�A�T�E�� ���E16-18�j
���u���邱�Ƃ͓����ɒE�����ā^������^���̂я�点��v�c�c���邱�Ƃ͓����ɒE�����āA��������̂��я�点��B�i�s���ЂƊ፷�Ƃ� �������Ɂt�A�q�L���w�̗]���Ɂr�A�T�E��܈�E9�j
�� �\�ʁm�A�A�n�^�\�ʓI�m�A�A�A�n�^�\�ʉ��m�A�A�A�n����c�c�s�\�ʁt�ɂ��čl���Ȃ���A���Ƃ��Ε\�ʂƂ��̂��܂��܂Ȕh���I�ȕ\���ɂ��āA�\�� �m�A�A�n�A�\�ʓI�m�A�A�A�n�A�\�ʉ��m�A�A�A�n����c�c�B�i�s���ЂƊ፷�Ƃ̂������Ɂt�A�q���l�E�}�O���b�g�̗]���Ɂr�A�T�E���O�E2-3�j
���u�������ǂ��Ł^���Ȃ��Ƃ���ł��邩�炾�v�c�c�k���ځl
�� �u�t�ɑ��݂͉�������^�s�݂̂���߂��v�c�c�v���U���X�Ƃ������ƂA�����Ɛ��m�ɂ����A�C�}�[�W���̃v���U���X�Ƃ����A���ݘ_�I�ɂ��������炭���� �����g�����ɂ��Ă����A�ڂ����g�Ƃ��ẮA�ӎ��̂�����i���Ȍ��O�j���w���̂łȂ����Ƃ͂������A���݂������̑O�ɂ�����邠��������{�k �t�H�A�I�Ȃ��Ƃł��Ȃ��A�t�ɑ��݂̉�������A�s�݂̂���߂��A�C�}�[�W���̖��f�����u�����V���I�ȗp�@�������̂�����ǂ��B�i�k�s���p�j�Ƃ��̌��� [�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]���߂��鈢���ǗY�Ƃ̉������ȁr�A�V�E�Z���l�E21-�Z���܁E4�j
���u�I�ꂽ�r�v�c�c����������A���̋r���̂��̂��I�v�Z�b�V���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�C���[�W���̂��̂̃I�v�Z�b�V�����̂ЂƂ̃��`�[�t�Ƃ��ď� �̋r�������Ă���̂ł���B�i�s���p�̐D���t�A�q���̊X�̃A���X�����@���ׂ�@�A�����E�W���[���Y�r�A�T�E�O���E6-7�j
���u���̗~�]�̃��[�^�[�͓Ɛg�҂̋@�B�́^�Ō�́i�����Ƃ��^�ˋN�����j�����ł���v�c�c���̗~�]�̃��[�^�[�͓Ɛg�҂̋@�B�̍Ō�̕����ł� ��B�i�s���ЂƊ፷�Ƃ̂������Ɂt�A�q�}���Z���E�f���V�����̗]���Ɂr�A�T�E��O�O�E14�j
�� �q���������i�܂��͑܁j�̂Ȃ��ɛs�܂�Ă���悤�Ɂ^���ׂƂ�����O�̂Ȃ��Ɂi�L���E��i�j���^�s�܂�Ă���r�c�c����Ƃ����̂��A�ނɂƂ��āu�|�p��i �Ƃ́A���������̒��ɂ͂�܂�Ă���悤�ɁA���ׂƂ�����̒��ɂ͂�܂�Ă���v���炾���A�������ނ͂���ɁA���̍��ׂƂ�����̂Ȃ��ɖ�����Ă��� �v�z�m�ɂ��悤�Ƃ���B�i�k�s���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q�ے��h�r�A�V�E��O�E13-��l�E1�j
���u�ԉłƂ����^�V�������[�^�[���o������v�c�c�܂�ԉłƂ����V�炵�����[�^�[�̏o���𗧏���K�v�B�i�s���ЂƊ፷�Ƃ̂������Ɂt�A�q�} ���Z���E�f���V�����̗]���Ɂr�A�T�E��O�l�E4�j
�� �q�d���@������́@�͂̂��������^���r�c�c�k�c�c�l�S�[�M�������͂��߂ău���^�[�j���ɂ����ނ��A���̉ԛ���̓y�n�ޖ،C�̉��ɁA�ނ��G��̒��ɋ� �߂Ă����q�d���A������́A�͂̂����������r���������N�A�k�c�c�l�i�k�s���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q�ے��h�r�A�V�E��Z�O�E6-7�j
���u�߂Â����Ƃ̂ł��Ȃ��^���̏����ȊO�ʂ́^�P���v�c�c���̔w��̂Ȃ������ȊO�ʂ̋P���i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q�Q�l�}��22�r�A�k�� ��W�ɂ͐}�ŁE���Ƃ����^����Ă��Ȃ��l�j
�� �u�P���̑Η��������ā^�j���^�̑Η��ƂȂ��Ă���v�c�c�����̃M���V���_�b�̉p�Y�����́A�����������Έ��Ɠ����E�҂��������A�����[�ɂ����ẮA���� ��̎��͂����A�P���̑Η��������āA�j���̑Η��ƂȂ��Ă���B�i�s���E��ԁE�C�}�[�W���t�A�q�_�b�ɂ��ā\�\�M���X�^�[���E�����[�r�A�T�E�Z���E7-8�j
�`���̈��p�i�莫�ł���j�Ƌɂ߂ċ߂��u�C���[�W���܂��˂Ɏ����ƈӖ��Ȃ����ے��� �̊Ԃ̗h�ꓮ����{���Ƃ���̂ł���B����͂˂ɈӖ��������Ƃ��邪�A�_�b�I�ȃR�[�h�̑̌n�Ȃ��ɂ͌����ďے��ɂ܂ł͒B�����Ȃ��v�i�T�E�l��l�E15-16�j�Ƃ�����߂����q�X�^���o���X�L�[�̗]���Ɂ\�\�����[���߂�����p�ƒ��r�́A�g�����ҏW�S�����s�����܁t�� 50���i1973 �N6���j�Ɍf�ڂ���A�̂��Ɂq�M���X�^���E�����[�\�\�X�^���o���X�L�[�̗]���Ɂr�Ɖ���̂����A�{��̈⒘�s���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]�t�i������ �_�ЁA1978�N4��20���j�Ɏ��߂�ꂽ�B�������^�̏��т́A�s���E��ԁE�C�}�[�W���k���p�I���l�t�i���p�o�ŎЁA1967�N3���j�A�s���ЂƊ፷�Ƃ� �������Ɂk�p���G�p�[���P�l�t�i�G�f�B�V�I���E�G�p�[���A1974�N3���j�A�s���p�̐D���t�i�}�����[�A1975�N3���j�̐��O���s��3���Ƃ͈قȂ�A�s�{��~����W�t�ł͒P�s�{�Ƃ��Ĉ����Ă��Ȃ��B
�k�NjL�l
�{��~�̃f�r���[��q�A���t�H�������Ȍ�r�i1963�j�̈�߂��q����杁r�i�H�E17�A���o�́s�C�t1979�N5�����j�`���̎���i�������u�@�v��q�@�r
�Ŋ����Ă��Ȃ��j�̃X���X�Ƒz����̂ŁA���Ɍf����B
����҂ŋ킯�^�������s���̏��N���������Ƃ�����c�c�܂�A�����́q��҂ɋ킯�āA�������s���̃A�L���E�X�r�ł���A�����̊G��̓[ �m���̖�Ȃ̂��B�i�k�s���p�j�Ƃ��̌���[�f�B�X�N�[��]�t�l�A�q�A���t�H�������Ȍ�r�A�U�E���E16-17�j
�{�e�ł́A�{��̕��͕͂X�I�Ɂs�{��~����W�t�ŏo�T��\���������A�g�����q�D���̎O�̒[�z�r��q����杁r�������ۂɎQ�Ƃ����{���́A�����܂� ���Ȃ���f��4���̏��Ђł���B
�k2008�N12��31���NjL�l
�{����W���e���{�̍ŏI�y�[�W�Ɂs�{��~����W�t�̎d�l���L����Ă���̂ŁA�����B
�̍ف\�`�T���@�㐻�{�@�\������
���\�����P�����C�h�A�N���[��
���Ԃ��\�O�����f�[�A�l
�\���\�p�\���i�q���E���z�@�w�E�A�[�g�J���o�X�j
�O���\�L�������[�E���T�C�N��
�e�����ςU�T�O��
����\�g����
�ʒ��{���p���̖��������P�����C�h�̔��́A�̂�����28���{���s�|�[���E�N���[�̐H��k���� ����Łl�t�i����R�c�A1980�N11��9���j�̖{���p���Ɏg�p���ꂽ�B
��
���r�Y�͋g�����̎��сq�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�́q�ӏ܁r�Łu��҂Ƌ{��̊ւ��͋{��̐����������̈���ł���w���p�̐D���x�̑��B����҂��S
�����A���̏o���オ����{�삪���Ƃ̂ق���A�Ƃ����W�����̂��v�i�s�g�����k����̎��l1�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��ܓ�y�[�W�j��
�����Ă���B�}�����[�ݐЎ��̂��߃N���W�b�g�͂Ȃ����̂́A�{��~�s���p�̐D���t�i�}�����[�A1975�N3��20���j�͋g���������̑�\��̂ЂƂł�
��B
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��O��y�[�W�i���͖{�������j�E�㐻�N���X���E�@�B���B�ʐ^�ł��킩��̂悤�ɁA���̑f�ނ͓��Ă����₷��
�\�\�}�����[�̏��Ђł́A���e���O�Y�s���{�t�i1968�j���㋆��Y�s�K���}�[���̉Ɓt�i1980�j�̔��ɂ����̎�̊D�F�̃{�[�������g�p����Ă���
�\�\�A���I�ɔr�˂��Ă����������ł����̂悤�Ȃ��肳�܂��B�l�Z���E�p�w�i�{���Ɋ۔w�͎����킵���Ȃ��j�̂����ӂ��̑̍ق����A�J���o�X�i�܂��ɐD
���j�̃N���X�̂��炴��Ɨ������������Ȃ�Ƃ����ɉ�������ł���B
�{���̔��k�\�l�̕��͖͂{���́q���p�ɂ��ār����̔��������A�����O�E�L�����q���E�Z�فr�ɂ��A���k���l�͖{���̖{���ɂȂ��u���҂̎�ɂȂ�v
�i�s�{��~����W�k��1���l�t�A���p�o�ŎЁA1980�N5��1���A�Z��l�y�[�W�j���͂ł���B�u�{�̑��ݗ��R�͂����ɕ����߂�ꂽ�Ӗ��̖S��ɂł͂�
���A�{�̋�Ԃɂ���ׂ��ł͂Ȃ����낤���B�v�Ǝn�܂锠�g�݂�201�����́A�g���̑����Ƃ������܂��āA�{����������ۂÂ���i���̕��͂҂ɏ�������
�̂͒N�Ȃ̂��낤���j�B
 �@
�@
�{��~�s���p�̐D���t�i�}�����[�A1975�N3��20���j�̔��k�\�l�ƕ\���i���j�Ɠ��E���Ɣ��k���l�i�E�j
�{���̑����ɂ��āA�P�c�����͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@ �{��~���w���p�̐D���x�i�}�����[�A���ܔN�j�́A���̒艿�\���̃S�V�b�N�����������O�Ƃ��āA���A�\���A���A�ڎ��̂��ׂĂɂ킽���āA�����A���Җ��A�o �ŎЖ��Ɏg���Ă���̂͋��������n�̖��������i�I�j�ł���B�����āA���������ɂ��\���̂Ȃ��ŁA�B��̃A�N�Z���g�ƂȂ��Ă���̂��A���ƕ\���̒����� �z����Ă����ӏ\�~���̔��l�p�ł���B���̔��l�p�͖Ƃ����߂ł���ł��낤�B�܂��Ɋ��ň���ɌŗL�́u��^�̒����v�Ɉˋ������f�U�C���ł���B �i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A�Z�l�y�[�W�j
�u���̔��l�p�v�͖{�����ɂ��o�Ă��Ă��āA�ʏ�Ȃ�u���k�A�X�e���X�N�l�v�i�x�C�Y�Ȃ�O�̃A�X�e���X�N���u�i�v�̎��̌`�ɕ��ԁu�A�X�e���Y ���v�j�����肪�S�������ȁA�i���̋������������ڂ��ʂ����Ă���B
��
�g���͋{��~�ւ̒Ǔ����q�D���̎O�̒[�z�r�i���o�́s�G�s�X�e�[���[�t1978�N11�����j�ɂ��āA������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B �N�V�����ƌ����̍����ցr�ł�������Ă���B
�����@�O�ɁA���p�ɂ��܂������t�����p�ł���l�ƁA����܂�ł��Ȃ��l�Ƃ�����Ƃ����b�����Ă܂�����ˁB
�k�c�c�l
�g���@ �k�r�c�����v�̕��͂́l���ۓI�ł��Ȃ����ǁA���ɖ����ō��ɂ��������B�k�c�c�l�ڂ��ɂƂ��ĈӊO�Ȍ��t�ƌ������A���̌��t���K�v�ȂB���ꂾ�ƍ�� �����B������A����܂蕶�͂�����������������G�b�Z�C����́A���ɂƂ�ɂ����B�{��~�Ȃ͂��̍ł�����̂ˁB�{��~�͂Ƃ�Ƃ��낪���ɂނ����� ���킯��B������A���́A�O���̉�Ɓk�W�����W���E�u���b�N�l�̌��t�Ƃ����������̂��U��߂Ȃ��Ƌ{��~���͐��藧���Ȃ������B
�����@�{�삳��̕��͂��̂��̂����p���琬�藧���Ă���킯�ł����̂ˁB
�g���@�{��~�̂��߂́u�D���̎O�̒[�z�v�A���ꂪ��Ԃނ������������Ȃ��B�܂������炭���܂��������ĂȂ���Ȃ����Ǝv����B�� �i�Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂�������Ƌ^��ɂȂ�B
�����@�{��~������p�ł������Ȍ��t�Ƃ����̂́A�{��~���g���Ă��錾�t����Ȃ��Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��ł����ˁB
�g���@�����������Ƃ����邩���킩��Ȃ����ˁB���܂�ɂ����I�ȕ��̂ł��邽�߂ɂ������̊������ĂȂ������B�i�s���㎍�蒟�t 1980�N10�����A��Z�`�㎵�y�[�W�j
�q�D���̎O�̒[�z�r�ɓo�ꂷ��u�@�v�Ɓq�@�r�Ŋ���ꂽ���p�����A�{���s���p�̐D���t�̃e�N�X�g�Əƍ����Ă݂�ƁA����炵�����̂͂킸����ӏ� �����Ȃ��B�i�@�j���͕W��A�{���̃y�[�W�m���u���k�������l�E�s���k�A���r�A�����l�B
���u�I�ꂽ�r�v�c�c����������A���̋r���̂��̂��I�v�Z�b�V���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�C���[�W���̂��̂̃I�v�Z�b�V�����̂ЂƂ̃��`�[�t�Ƃ��ď� �̋r�������Ă���̂ł���B�i�q���̊X�̃A���X�����@���ׂ�@�A�� ���E�W���[���Y�r�A���l�E9-11�j
�g�����͋{��~�̟f��ɕ҂܂ꂽ�s�{��~����W�k�S3���l�t�i���p�o�ŎЁA1980�`81�j�̑������S�����Ă���̂ŁA���сq�D���̎O�̒[�z�r�̈��p���̃X���X�ɂ��ẮA������W�̑������̂肠����Ƃ��ɉ��߂ĐG��悤�B
�q�g�����̃��C�A�E�g�i4�j�r�� �������悤�ɁA�g�����̏�����ł��鎍�̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j�̏o�ōL�����s���Y�Ę_�t1941�N1�����Ɍf�ڂ���Ă���B�ٕ��̎��M�ɍ� ���āA���Y�����m�F���邽�߂Ɍ��㎍�������ҏW�ψ���ҁs���㎍�������E�\�\�s�s���_�j�Y���̌��Ɖe�U�t�i���O�A�\�V�G�[�c�A1998�j���J�����Ƃ���A�q�l�������i�L���j�r�́u�g�����v�́s�����G�߁t��1�������������B���A�悭�悭����Ƃ���1�s��Ɂu�g����v�ƌf�ڂ���Ă���ł͂Ȃ����B������k�� ���B�l�������������A���̖{���y�[�W�u��12����3���@1942�N3��1�����s�v�́u�L���v�̍��ɂ�
�k�c�c�l�g����w�t�́x�i����Ɂj�̍L�����f�ځB�k�c�c�l�i�����A�O��O�y�[�W�j
�Ƃ����āA���ꂼ�ԈႢ�Ȃ��g�������W�s�t�́t�i����ɁA1941�N12��10���j�̏o�ōL���ł���B�s���Y�Ę_�t1942�N3�������{�������� �ŁA�T�����L���B
 �@
�@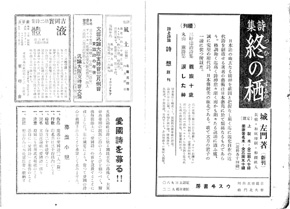 �@
�@
�s���Y�Ę_�t1942�N3�����̕\���i���j�Ɠ��E�\��2�`�\��2�Ό��y�[�W�i���j�Ɠ��E�g�������W�s�t�́t�L���̃A�b�v
�i�E�j�k����������m�N���R�s�[�l
�� ���@��`�����\���Ɂu���[�v��搂��Ă���3�����́A�q�S���{�������W�r�ł���i�O�N1941�N��12���A���Ȃ킿�s�t�́t���s�̌��A���{�͑����m�푈�� �˓������j�B�{���́A�ۓc�o�d�Y���������������A����l�Y�́q�������r�ȉ��A�|����E�ߓ����E��{�C�U�E�⍲����Y�E���R�ȎO�Y�E������Y�E���c�P�Y�E�| ���Ă��E��������E�]�ԏ͎q�E������m�E���c���ʒj�E���c�ہE�鍶��̊������l�ƁA����ɂ��32���̎���i�������W�q�S���{�������W�r���`�����Ă� ��B�ҏW�E���s�l�̊⍲����Y�́q�ҏS��L�r���u�폟�ɋP�����{�̏t�O���B�v�i�����A���Z�y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���A���Ƃ͐����Ēm��ׂ��̕��������ʂɖ� ��B���������Ȃ��ɂ����āA�g���́s�t�́t�̏o�ōL���͈⒘�̂悤�ȐÂ�����ۂ��Ă���B���Ă̕������N�����Ă������B
�g������W
�t�@�@�
��蟬�q��
�S������{�b���b�O���@����@���a��
�b���b�\���@���m�q�I�t�Z�c�g�ܐF��
�b���b�{���@������܁Z���G�k�m�����n�l�Ɂu�����G節�v���㈲���A�����C���Ȃ�G�X�v���������̎��ݖz���Ȃ�\���ɑ�Ď�者���Ӗڂ����߂��g�����N�͍��䏢�ɜ䂶�đ嗤�ɍ݂�B�ᓙ��著者�̈Ϛ��ɂ��ŋߍ�O�\���сA�����ɋ������ő���̔���{�ƂȂ��č]�ɖ{��������B������̖{�ł��邪�A�ނ̎��������Еz����]�������͐��웉��\�A�����\�A�����L�֑�����B �i��者���ї��A�r�c�s�V���k�}�}�l�j
�@�����s�{�����X����m�O�k�}�}�l�@�g����
�@�@�@�@�@���@�@蟬�@�@�q
��
��̍L������ɋg���{�l���֗^���Ă���\���͒Ⴍ�A��l�́u�Ҏҁv�ɂ�鎷�M�E�w��ł��낤�i���W�́q���Ƃ����r�����ї��E�r�c�s�V�����j�B�Ƃ���ŁA���̍L���̍��F�͎�F�ł���B�{���̕\��1�E4�̓X�~�Ǝ�i���F�j��2�F����ŁA�\��2�E3�ƁA�{���O�̓\����4�y�[�W�i�L��1�y�[�W�A�ڎ�2�y�[�W�A��
�m1�y�[�W�j����ŁA���F�͖����ւ�����B�\���ݎd�l�̖ڎ��́A���N5�����ȍ~�A�X�~����̖{���y�[�W�Ɋi�������ꂽ���i1�����ȍ~�A�{���y�[�W���̏�
�ЁE�G���̏o�ōL�����Ȃ��Ȃ����j�A�펞�̉e���͒[�I�ɑ��y�[�W���Ɍ�����B�s�����G�߁t�L���f�ڂ�1941�N1������120�y�[�W�������̂ɑ��āA����1942�N3�����͎O���̓��80�y�[�W�Ɍ����Ă���B
���W�s�t�́t�̔����͂ǂ��������̂��i1941�N���F�֏o�������g���́A�����ɂ��ď����Ă��炸�A�Ǝ��ɒT�����邵���Ȃ��j�B����{�������s���Y�Ę_�t�͓��{
�ߑ㕶�w�ق̏��������ŁA1942�N��2������8�����������̂��ߌ����Ȃ��������A6�����i���W�q���Ĕ�
������{���W�r�j�́q���d���]�r�Ŗk�����ʂ��u���W�v�Ƃ������o���Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���̂��ڂɗ��܂����B
�@ �ŋߎ����͖��m�̎��l�ɂ�ď㈲���ꂽ����̎��W����ɂ��邱�Ƃ��o�����B�����Ă����̎��W�̂Ȃ��ɂ͒��҂̑����̕��S�Ɉ˂č��ꂽ���̂����� �ł��炤�ƌ��ӂ��Ƃ�e�Ղɑz�����邱�Ƃ��o������̂���O�ɂƂǂ܂�Ȃ����B�����������������W�̂Ȃ��ɂ͖��ĂɎ���̕��S�Ɉ˂ď㈲���ꂽ���̂� ����ɂ��S�炸����A����͖ܘ_�A��i�̔z�ɏ[���̌������s�͂�Ă�Ȃ����̂������₤�ł���B�����������W�ɑ��Ď����͈ÑR�ƂȂ炴��� ���B��i�̖������A�����̐��e�͒n���I�ȗ��R�A�����̏��������ӂł��炤�B�R�������̑召�A�s�ԁA���Ԃ̋ύt�A���ꓙ�͔@���Ȃ鈫�����̂Ȃ��ɉ��Ă����� �̌��ʂ������邱�Ƃ��o����̂ł���B���̂₤�ȈӖ��ɉ��āA�B�P�ɖ{�̌`�ł��肳�ւ���悢�A��i�͓ǂނ��Ƃ��o����悢�A�Ƃ������W�ɑ��ē� �҂͕��S�ȏ�̘J���ł��ւ��邱�Ƃ�m��ׂ����ƍl�ւ�B
�@�k�c�c�l
�@�������������ɋ���������Ȃ����l��z�����邱�Ƃ��o����ł��炤���B���ӂ����ł���B
�@���l�͂��₪��ɂ�������ǂ݁A���������������̒m����L�x�ɂ���Ɠ����ɑ��{��̗��z�����߂�ׂ��ł���B����͎��l�̕����I�`���ł���A�����ɋ��{ �ł�����ł��炤�B�܂�����̍�i�ɑ����҂̍ŏI�̈���Ȃ̂ł���B��X�͎��܍��X�ƌ��Ƃ����̎�������W����ɂ��鎞���̓��e���Ⴕ���n�ȏꍇ �ɉ��Ă��W�����d�̐S�����ݓ��Ȃ��̂ł���B�i�s���Y�Ę_�t1942�N6�����A���y�[�W�j
�� �n�ɍ݂�g���ɑ����āA���сE�r�c�̗������k�����Ɂs�t�́t�𑗂������Ƃ͊m���ł���i�s�t�́t�o�ōL�����f�ڂ����s���Y�Ę_�t1942�N3������k�� ����ɂ��Ă��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��j�B���p�����Ō�̈ꕶ�����W�s�t�́t�̕]�ł����Ă������������������Ȃ��A�ƍl����̂͂ЂƂ莄�������낤���B
�k2013�N4��30���NjL�l
2013�N3�����q�ҏW��L 125�r�ŐG�ꂽ�悤�ɁA�k�����q�ɂ��s�t铁t���]���s�V���_�t60���i1942�N5���j�Ɍf�ڂ���Ă���̂ŁA���p����i�����͐�����V���ɉ��߂��j�B
�@���W�i�I�̐��j�鍶�咘�B�k�c�c�l
�@���W�i�ԕ��j��㑽��O�Y���k�c�c�l
�@���W�i�t���j�g�������B�O�����ߑO�̕��Ƃ��A�㔼���ߌ�̕��Ƃ��ĎO�\��т̍�i�������߂��Ă��B�ߑO�̕��͊����B���ȓ_������A�Z�p�����s�[���ł��邪�A�ߌ�̕��ɉ��Ă͒��҂̍˔\���[���Ɏ�����Ă��B���Ɍߌ�̕��̍ŏ��̐��т͊��S�ȍ�i�Ƃ��Đ��܂���ɑ������̂ł��炤�B���炭�Ⴋ���l�Ƃ��ď����𒍖ڂ��ׂ������m��Ȃ��B�����҂������������߂ɏ��сE�r�c�̗��F�l�����̎��W�̊��s�ɓ������Ƃ��t�L����Ă��B�`��ܔԌ^�E�S������E�E����Ɋ��B�i�q���]�r�A�����A���`��y�[�W�j
�s�t铁t�͂�͂�k�����q�i1902-78�j�ɑ����Ă����B�u�`��ܔԌ^�v��A5���̂��ƂŁA�k���͊ԈႢ�Ȃ��{������ɂ��Ă���B�u�ߌ�̕��̍ŏ��̐��сv�Ƃ́A�q�����ȉԑ��r�i�A�E17�j�A�q���M����[�Ɂr�i�A�E18�j�A�q���i�r�i�A�E19�j�A�q�Ђ₵�r�i�A�E20�j�A�q�Ԓx�����̉́r�i�A�E21�j�����肩�B�s���Y�Ę_�t1942�N6�����́u���X�ƌ��Ƃ����̎�������W�v���s�t铁t���w�����Ƃ��܂������Ȃ��B�Ⴋ�O���q�Y�i1920-2001�j�́A���̐푈�o��ŎR�����q�i1901-94�j���猃�܂������A����Ȃ��Ƃ��z�N�����B�g���͂��̏��]���n�ɂ��������\�����͂������A1978�N�ɖk�����f�������Ƃ��i����A�Ђ���Ƃ���Ɛ��U�ɂ킽���āj�m��Ȃ������̂ł͂���܂����B�����m���Ă���A�s�t铁t��k���ɂ܂�鐏�z�̂ǂ����ŁA���т�邱�ƂȂ����̎������L���Ă��悤�i�풆���̍������̂��ƂƂāA��l�̗F�l���k���̕]���g���ɓ`�����Ȃ������̂�������Ȃ��j�B���Ȃ݂��k���̏��]�́A�g�����̎��W�Ɍ��y�����ł����������̕��͂ł���B
�k�t�L�l
�k�����q�́A��f���ɐ旧���A�s�V���_�t57���i1947�N2���j�́q���]�r�����ɂ����������B
�u��������͂��̗����������ē��Ɍ��Ђ�����̂ɂ������Ǝv�Ă��B���W���Ɏ��Ɋւ��鏑���̒��҂͂Ȃ���ҏW�ҁk����l�Y�Ɩk���l�̉��ꂩ�ɒ����̊܂��͕̘J���Ƃ�ꂽ�����̂Ǝv�ӁB�ܘ_���]�S���҂͌����ȑԓx���������č˔\���鎍�l�̔����ɓw�͂���҂ł��邪�A���]�̕łɂ͌��x������A�܂����܂�ɐ����̒Ⴂ�����ɏA���Ă͔�]���s�͂Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ͗\�ߊ܂�Œu���Ē����x���Ǝv�ӁB�^�^�ŋߏ��]�̃������̍r�ӂ��v�Ђ����ɐV���_�����]�ېV�����s���邱�Ƃ͌���̎��ɑ����̍v�����邱�Ƃ�b�ӂ���ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł���v�i�����A��y�[�W�j�B
�g���̗����a���鏬�сE�r�c���������̐錾�ɗE�C�Â���ꂽ���낤���Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ��B
����S�����W�s���ʁt�i�}�����[�A1974�N10��10���j�́A�s����S�����S�i�t�i1973�N5��25���j�Ȍ�̔N�����W�̍ŏ��̈���ł���i�s����S�����S�i�t�̑������g�����j�B1978�N5���Ɋ��s���n�܂����s����S���S�W�k�S12���l�t�i�}�����[�A�`1984�N5���j�́A��1��z�{�̑�1�����s�����1978�N7���ɔŌ���������|�Y�������߁A��2���ȍ~�̊��s�͑啝�ɒx�������B���W�s���ʁt�͑S�W��3���Ɏ��^����Ă���̂ŁA���ˉ�v�E�R�{���Y�́q���r�������B
�w�����x�^���a�l�\��N�\���\�����s�@�}�����[���@�`�T�ό^���i��Z�Z�~��l��m/m�j�@�N���X���\�����@����E�g�����@�ڎ����Ł@������Ł@�{����Z���Ł@�o�����T�U���Ł@�艿�O���Z�Z�~�@�����Z�Z�Z���^���^��i���͘Z�\���сB�{���͌܂̃p�[�g�ɕ�����A�T�\�Z�сA�U��сA�V��\�ܕсA�W�\�сA�X�Z�тƂȂ��Ă���B�^�Ȃ��A�{���́w���S�i�x�ȍ~���N���s����邱�ƂƂȂ����N�����W�̍ŏ��̂��̂ŁA���ҘZ�\�����玵�\��܂ł̍�i�����^����Ă���B�i�s����S���S�W�k��3���l�t�A�}�����[�A1982�N4��15���A�l���O�y�[�W�j
���Ȃ݂ɑS�W��2���́q���Ҋo�����r�ɂ́u�^�ƕx�m�R�̎��l�ȂǂƁA�悭���͂ꂽ�菑���ꂽ�肷��B�k�c�c�l�ǂ�ȕ��Ɍ��͂�Ă������Ē��y�͊����Ȃ����A���\���̍����ɂȂĂ��u���ʁv�́gZigzag Road�h���ǂ���玩���ɑ��������ے��I���W���̂₤�ȋC������v�i�s����S���S�W�k��2���l�t�A�}�����[�A1981�N9��20���A�ܓ��y�[�W�j�ƌ�����B
�{���W�����́q���̍E���r�͈�ǖY�ꂪ�������т����i����N�v�҂̊�g���ɔŎ��W�ɂ��̂��Ă���j�A�q���ɏA���ār�⎟�Ɉ����q�����������ƂɏA���Ă̎����r�i��㎵�O�E��E��l�j�́A����S���̏���z�N���Ȃ���ǂނƊi�ʂ̖��킢������i�g�����S���̏��Ɋ������Ă����j�B
�[�����āB
�ׂ��������G�p�̕M�̕��ɂ��Ղ�n���ӂ��܂��B
�����ɐ[���h���������B
���Ǝ肩��͗͂��ʂ��B
��悾����������Ƌ����B
���鎞�͐��B
���鎞�͉����B
���n����̐l�ԁB
���̈����������� communication ���`�ɂ������B
�C���B
�̂̔����̏�[������]�����̂܂܂ɉ��߂Ď��Ȃ^�������B
�i���܂̎����͂���ȊE�G��������Ă��B�j
�y���ȓ����B
yah ya doh�B
�{���̎d�l�́A����~��l���~�����[�g���E��O��y�[�W�E�㐻�N���X���i�p�w�j�E�\���B�n�M�������B���t�Ƀi���o�����O�}�V���ɂ��L�ԁA����B�{���p���̐��@�͎苖�̈ꏑ���̐��������ʂŁA����~���Ƃ����̂͂����ɂ����r���[�Ȃ��߁A�q���r�̓�Z�Z�~���ɂ������̂͂�܂�܂����A��㔪�~���v������~���ɂȂ����̂������ꂸ�A�����Ă��̂܂܂Ƃ���B
�{���̕\���Ɩ{���ɂ���Ɩ�̗�[��イ��]�̂悤�ȃJ�b�g�͂Ȃ낤�i�ۂ͒��Ԃ����тꂽ�`��������������̊ߋ�̂ЂƂŁA����Ȃ炳�����߃f�B�A�{�����j�B���ꂪ�s���ʁt�i�I�E�g�c�Ɠǂނ̂��A�{�R�f�R�Ƃł��ǂނ̂��j�Ƃǂ��W����̂��A���Ȃ��̂��A�悭�킩��Ȃ��B�u���ʁv���w�I�Ȏ��ʂȂ����ɁA���܂�}�Ă̂悤�ȃJ�b�g�łȂ��ق����悩�����̂ł͂Ȃ����B���Ȃ��Ƃ��{���Ɂu�ۖ�v�͕s�v�������Ǝv���B���̃N���X�ɋ��������Ƃ����̂͑z��������������ڂɉЉЂ����A�p�w�̒������������āA�g���������ِ̈F��Ƃ��������ł���B
 �@
�@
����S�����W�s���ʁt�i�}�����[�A1974�N10��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��i�E�j
�@�s���ʁt�Ɏn�܂�S12���̔N�����W�\�\�A�s�S�V�t1975�A�B�s�A���������t1976�A�C�s�����t1977�A�D�s�����t1979�A�E�s�_�C�t1980�A�F�s�����t1981�A�G�s���ہt1982�A�H�s�����t1983�A�I�s���V�t1984�A�J�s���i�t1985�A�K�s���⑼��t1986�i��������}�����[���j�\�\�͋g���������́s���ʁt�ȊO�A���ׂĒ��҂ɂ�鎩���ł���B�����݂͂ȁA�ڎ��̃t�H�[�}�b�g��m���u���̏��́A�{���̊�{�g���s���ʁt�ɕ���Ă��邪�A�\���̃N���X�̐F��ގ���ւ�����A�F�ȍ~�͖{�̂����F�̃C���N�ō������肵�Ă���B���̒��ɂ����āA�A�͊D���̃N���X���\���Ƀx�^�ۂ����܂��Z�d�̓��S�~��z���i�u�S�V�v���C���[�W����j�A�{���̃J�b�g�Ƀx�^�ۂ�u���ās���ʁt�P���Ă���B�B�͔Z�̃N���X���\���ɏ��}�i�S���̊G���j��z���A�{���̃J�b�g�ɂ͒����v�̂˂������̂悤�Ȍ`�̑o�t��u���āA����܂��s���ʁt�P���Ă���B�S�����g����������E�p���āA�I���W�i���e�B������͇̂C����ł���B������ɂ��Ă����Ҏ����̔N�����W�́A�S���̏���G���\������G�ɔz���邱�ƂŁA�ӑR������̐��E�肾���Ă���B
��
�g�����́s�m���t�łg���܁A�s�T�t�����E�݁t�Ŗ����܁i����ށj�A�s��ʁt�œ����L�O����܂����ꂼ���܂��Ă���A�����̂��ׂĂɑ���S�����ւ���Ă���̂�����ł���B
������̖�A���ˉ�v����d�b���������B�w�T�t�����E�݁x���u�����܁v�ɑI�ꂽ�ƌ����B���d�Ɏ��ނ������Ɖ�������A�S�O���Ƃ��������ŎƂ߂��悤���B�u���e���O�Y�A����S���������^�����Ă��邩��A��������v�ƁA�Ď��Ȓj�͂��ǂ��nj����āA�Ђ�������Ȃ������B�^��\���قǂ��āA�d�b�������B����߂ĉ��܂������ŁA�u���́w�����܁x�̑I�l�ψ��̃j�V���L�W�����U�u���E�����A���̏܂��Ă��ꋋ���c�c�v�ƁA�����B�������Ɏ��͈�u�A���t�ɋ������B�Ȃ��Ȃ�A��y�̎��l�Ƃ��ẮA������e���̂���������炾�B��������Ȃ��悤�ɁA��̗��R���q�ׁA���ނ������̂ł���B�������ɂ����ȂɁu�����ւ�����ˁ[�v�ƁA����ꂽ�B�^���̓�����A���炭�̊Ԃ́A����I�Ȃ����肪�c��A���������ɉ���Ƃ�����Ă����B����A�Ȃɂ��̐܂�ɁA�S������ɉ������A�u���̎��A�I���͐��e���������Ă��A���߂��Ǝv������v�ƁA���Ă����B�i�q�S���f�́\�\�u�g�������v�ق��r�A�s���㎍�ǖ{�\�\������ ����S�����鑒���t�A�v���ЁA1989�N3��1���A���y�[�W�j
�g�����͐��e���O�Y�Ɋr�ׂđ���S���Ɍ��y���邱�Ƃ����Ȃ��������A�{���W�s���ʁt�̑����͐S���ւ̐e�t����Ă��܂肠��B�Ƃ���ŁA��f���̃T�u�^�C�g���͕ҏW�����������̂ł͂���܂����B�g���͒f�͌`���̎U���ɂ��Ă��̎�̕�������Ȃ��������A����g�����g�������̂Ȃ�A�����́u�T�[�r�X�v�������悤�Ɏv����B
�k2021�N9��30���NjL�l
�}�����[�s�V���j���[�X�t1974�N10��������肵���B�l�y�[�W�߂ɖ{���W���Љ��Ă���̂ŁA�摜���f�ڂ���B�����A�g�����͂o�q���s�����܁t�̕ҏW��S�����Ă������A�L�����Łs�V���j���[�X�t�̐���Ɋւ���Ă������͕s���B�܂��A�{���W�Љ�̕��Ă͑���S���̒S���ҏW�҂ɂ����̂�������Ȃ��B�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�j�q�t�^�r�̃L���v�V�����ɕ킦�A�{�����̎d�l�́u�V���j���[�X�@1974.10�@�^�e182�~���@��ܓ�t8�Łv�ƂȂ�B�l�Z���̏o�ŕ��֓������ޔ̔����i�p�̍��q�ł���B���̃f�U�C���t�H�[�}�b�g�́s���e�̐X�t�ꔪ�܃y�[�W��i�̑傫�Ȑ}�Łi1973�N8�����j�Ɠ������B
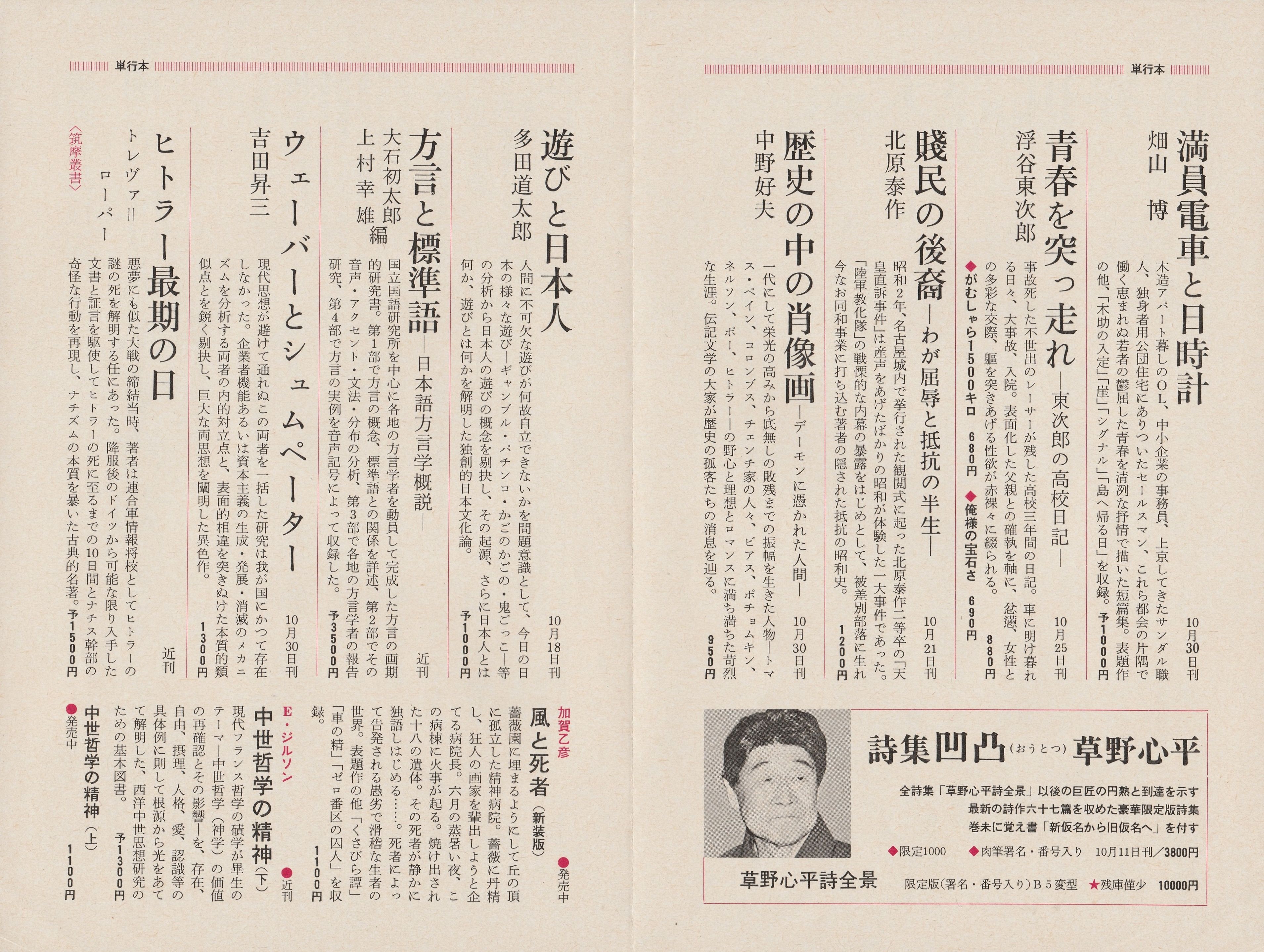
����S�����W�s���ʁt�i�}�����[�A1974�N10��10���j�̊��s�����m����}�����[�s�V���j���[�X�t1974�N10�����̃Z���^�[���J�� �k�u���W���ʁi�����Ƃj�v�A�u10��11�����^3800�~�v�Ȃǂƌ�����l
���҂��������ɏ㈲�����s�����d�M�S��W�t�i���ЁA1972�N3��7���j�ɂ́A�����Ŏ�肠����s�̖{�̂ق��ɁA�����{�ƕ����ł̌v3��ނ�����B�O���q�Y�́q���r�������B
���a�l�\���N�i��㎵��j�O�������A���Њ��B�������E�o��]�_�Ёi�����s�a�J��㌴�O���ڎl�ԏ\�O���j�B�e���O�S���\�Z�ŁB�ܕS������ŁB�����Z�\�����k�}�}�l��ł̓����{�͔Љ��ꖜ�~�B�l�S�l�\������ł̎s�̖{�͔Љ���甪�S�~�B���e�́A������W�w���\�T�x�����̊e��W�A����ь���e�ɂ���܋�W�w�o�x�k�c�c�l�A��������Z��W�w��������x�k�c�c�l�����^�B�k�c�c�l�����́u�o���v�͒��ҁB����A�g�����B����A���c���j�B�ʍ��t�^�u�����d�M�E�o���v�ɁA�u�f饁v�˖{�M�Y�A�u���̏I��v���q�����A�u���@�I�o�l�v��������A�u�����d�M�̋ߍ�k���́l�ق��v�剪�M�̂��ꂼ��ꕶ�����Ă���B�i�s�����d�M�S�W�k��ꊪ�l�t�A�������[�A1985�A�l�Z�Z�`�l�Z��y�[�W�j
�����ɋ���A�{���ɂ͓����A�o��]�_�Њ��́u�����ܕ����Łv�i35������Łj�����邪�A������͋g�����̑����ł͂Ȃ��悤���i���Đ_�ے��̌Ï��X�ŁA���̔����a���̑��{����ɂ������Ƃ�����j�B�{���ɂ��Ē������q�͂��������Ă���B
�w�����d�M�S��W�x�i��܋�W�j
�@���s�������O�o�B�u�����Ό���v�����q�o�r�̏���́A���܂�ɍ\�z����ɂ��������߁A�x�X�Ƃ��Đi�܂��A���k�}�}�l�ɖ����ɏI�����v�Ɗ����̊o���Œ��҂͏q�����Ă���B
�@���Ȃ��A�{�W�Ɏ��^���Ă���u�o�v�u��������v�́A�w���\�T�x�ɂ�����u�ߎ��A���n�v�Ɠ������A�����͊��s���l���Ă������ύX�ƂȂ�u��O�I�Ɋ�悳�ꂽ���ʌ���ł̎O�ܕ��i�����̌ܕ����ꊇ���Ĉ�P�[�X�Ɏ��߂����́j�������ƁA���k�}�}�l�ɓƗ������������Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ��v�Ƃ������҂̋L�q�ǂ���ɁA�P�Ƌ�W�Ƃ��Ă͑��݂��Ȃ����ƂL���Ă����B�i�s�����d�M�̐��E�k���a�o�啶�w�A���o���Q�l�t�A�~�����[�A1991�A��Z�O�`��Z�l�y�[�W�j
�g���ɂ́A�܂��s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j�Ƃ��Ĕ��\�������W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j�����邪�A�����ɂ͒P�s�{�̌`���Ƃ�Ȃ���W����������A�Ƃ������ƂɂȂ�B�g���͍����̋�W�̕҂ݕ��ɂ��āu�d�M�͂Ȃ����A�V������𒍓����A��W��҂ݑւ��A���B�����A��́w��i�W�x���\�z���Ă���̂��B��҂̕K�R�I�ȉc�ׂƂ��ė����ł��邪�A��ǎ҂Ƃ��Ăǂ����ǂ݂ɂ���������B���͔��Ɂw���W�x�͈ꊪ�Ŋ�������悤�ɁA���݂Ă��邩��A�Ȃ�����Ȃ̂����m��Ȃ��v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�ꎵ�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�s�����d�M�S��W�k�s�̖{�l�t�̎d�l�́A����~��O�~�����[�g���E�O��Z�y�[�W�E�㐻�p�\���i�w�͊v�A���̓N���X�j�E�\���B�n�M�������B�w�v�̍��́A�g�����ŏ��ɏo����������̋�W�s���\�T�t�i��玕�k�J���l���A1956�j�̐Ԃ����ӂ�\�����������i�ѓ��k��s���l�̋�t���������j���痈�Ă���̂��낤���B�����̋g�����i���̂ق��{���ɂ��ʂ̊G�����f�ځj�̎��c���j�ւ̌��y�͂Ȃ����̂́A�����́q�o���r�̈�߂Ɂu���́w�����d�M�S��W�x���A���Ď�����Ă݂�ƁA���ǁA�����̗F�l���y�����̋��͂𐏏��ɕK�v�Ƃ������A�o��`���Ƃ̂������̒��Ő��܂������܂��܂Ȑl�ԊW�ƁA���̉��ɂ��āA���߂Ďv����[�߂邱�ƂƂȂ��v�i�����͐����B�{���A�O����y�[�W�j�ƐG��Ă���B
�Q�����т��s�����d�M�S��W�k�����{�l�t���o�i���Ă���̂ŁA���e���f�������Ă��炤�B�����̐����ɂ́u��������60���@�n�M��E�������@�v�w���t�@�ɔ��B�@���̔o�l���E���Ҏ��M�͂����Y�t�B�u�܂Ȃ��r�ꂽ���܂����̏I�肩�ȁ@�d�M�v�B����E�g�����A����E���c���j�B�V���B�����v���㐻�{�B�y�V�ԉ��j���E���Ҋo���B�u�����d�M�o���v�˖{�M�Y�����Y�t�BA5���v�Ƃ���A���i��42,000�~�B���̓����{�͖��������A�������Ə��e����@����ɁA�v�w���̈ӏ��͓\���Ɠ����ŁA�\���͎s�̖{�p�\���̔w�v��S�ʂɗp�������̂̂悤���B�s�����d�M�S��W�t�́A��y�[�W�Ɉ��i�i�����͎l�s�\�L�j�Ƃ����g�̍قƂ����ւ��āA���S�Ȕo��F�������Ă���B
�Ȃ����ҟf��̓�Z�Z��N�ɂ́A�s�O���\�N�t�q�O���\�N�E���k�����ʁA�H���E���l�r�s���q�t�s���ݗ́t�s�ߎ��A���n�t�s�o�t�s��������t�s�R�C�W�t�q���{��W�o���r�s���{�C�R�t�q���{�C�R�E���r�s�R���v��W�t�q�R���v��W�E���r�����^�����A�����ǂ���́s�����d�M�S��W�t�����ώɂ��犧�s����Ă���B
 �@
�@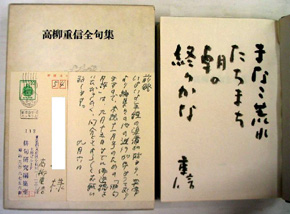
�s�����d�M�S��W�k�s�̖{�l�t�i���ЁA1972�N3��7���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�����{�̕v�w���Ɩn�M��E�����i�E�j�k�Q�����т̉摜�l
�����{�̏o�T�Fhttp://www7a.biglobe.ne.jp/~naniwashorin/photo/410473.jpg?
 �@
�@
�s�����d�M�S��W�k�����{�l�t�i���ЁA1972�N3��7���j�̕v�w���ƕ\���i���j�Ɩn�M��E�����i�E�j
�k2014�N10��31���NjL�l
������E���̂悤�ɂ��āA�g���������{�́A�Ƃ�킯�����{�̏N�W��i�߂Ă���B�s�����d�M�S��W�k�����{�l�t�i���ЁA1972�N3��7���j����肵���̂ŁA���e��lj�����B�����̎d�l�́A����~��O�~�����[�g���E�O��Z�y�[�W�E�㐻���v���E�V���E�v�w���B�n�M��E�������B�\���t�̋L�q��^����B���s���^�Œǂ������A�����͉��g�̍��E�������킹�ł���B
���a42�N3��7���^ᢍs�^�����d�M�S��W�^ �T�O�O������{�^�P�`�U�O�����{�^�U�P�`�T�O�O�s�̖{�^���E���y��M�z�^����E�����d�M�^ᢍs�E���Ё^����E�~�J����^��̌��^�o��]�_�Ё^�����s�F�J���㌴3-4-13�^�ЙJ�@�P�O�O�O�O��Shift JIS�ŕ\���\�ȋ����͎g���Ă݂����A���t�̕\�����e�i�Ƃ��������́j���W���ɂ����āA���������̋����\�L�ƃo�����X���Ƃ�Ă��Ȃ��B�u�����s�F�J���v�Ƃ�����u�㌴�O���ڎl�ԏ\�O���v���낤���A�u�~�J����������Ёv�Ƃ�����ɐ����Ж��ł��������B�{���͓������̓������������p���i�A�������j�ɍ����Ă��āA�����̗m���D�݂f���Ă���悤���B���̑��v���̓����{�i�g�������̒����ɂ͂Ȃ����A�s�Õ��t�̉����{���Ԃƍ��̊v��2��ŁA�{���Ƃ̊֘A���������킹��j�́A�g���̎���Ēu���̃v�����������ɈႢ�Ȃ��B�Ԃƍ��́A�ԂƐƕ���ŁA�g�����D�\���ޗ��ɂ������ł���B
�߉ϑ��Y�s�����Y���̑��t�i���V���X�A1975�N4��20���j�́A���W�s���y�t�i�v
���ЁA1965�j�ɑ����g���������ŁA�߉ς���͋g�����Ǔ����Łu���́k�g�������ɂ��}�����[�ōY�S�W�́l����A���X����o�����]�_�W�w������
���Y���̑��x���A�w��{�߉ϑ��Y���W�x���A�ނɑ��ꂵ�Ė���B�w�����Y���̑��x���l��ܕS�����o���̂́A�����̍Y�u�E���̂���������炤���A�܂��ނ̑���̗͂ɕ��ӂƂ���傫�����Ɉ�ЂȂ��Ǝv�Ӂv�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����A�O�O�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�g�����͖{�����ǂ̂悤�ɓǂ̂��낤���B���Ɉ����q�Y�̎��̊T�ρr�̈�߂́s�L�t����s�X���t�ւ̈ڂ�䂫��]���Ă��邪�A�g���̐��z�q�u�z��
�͎͂��@�z������v�r�i���o��1977�N5���j����肵�Ă���悤�ŁA�����[���B�\�\�q���Ƃ����r�̖����Ɂu��������Ă��ꂽ�g�������ƁA����
��Ő���������ɂ�Ă��̖{�����Ă��ꂽ���V���X�Ɋ��ӂ���v�i�O�Z�܃y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�{���͊����ɐ����i�����j��p���Ă��邪�A�ȉ��ł�
�V���ɉ��߂Ĉ����B
�w�� �ɖi����x����u�L�Ȍ�v�Ɏ���Y�̌��ꎩ�R���̃X�^�C���́A���ꎩ�̂��Ȃ�̈ڂ�ς�ƓW�J���݂��Ȃ�����A���قނˌ������z�ɂ����I���A���Y ���Ƃł��ꊇ�̂��Ă悳�����ȁA�C���F�W�̑��^�ɁA���̖ڂ��܂��������������B���������܂͂��̑��ʂȌ��o�͕��Ђ��Ă��A���͂߂đ����I�ȁA�����S�Q �����ɓ]�����̂ł���B����͂�͂�u�L�v�����ɂ����Ĕނ̐��F�����ϔO�I�ɌŒ艻����ɂ�A���R�ނ̝R����܂������ق��Ȃ��A���͂�������� �ł�₤�ȃ��B�W�����̑n���͂��������A�]���̃X�^�C���̂܂܂ł͂����炭����W�J���čs�����Ƃ͕s�\�ƂȂ����߁A�قƂ�ǂ�ނʂȂ�䂫�A���� ���͋��]�̈��Ƃ��āA�����I�����ł̎��Ȍ������͂���A����I�|�I�Y�ŁA�u�h���v�ւ̎��Ȕ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂Ǝv�͂��̂��B�i�{���A���y�[�W�j
�{���̎d�l�́A���܁~��l���~�����[�g���E�O��Z�y�[�W�E�㐻�z���E�\���B�\ ���E�w�����̒��Җ��u�ρv�̈ꕶ�������Ȃ����Ă���̂́A�ʐA�i�������͋��łł͂Ȃ��A�ʐA��ʼn��ɂ��Ă���悤���j���\�肵���Ƃ��̕s����낤 ���B�G���u�����Ɏ����\���̃J�b�g�́A�{���̐}���̒��S�����̗��p�ł���B�\���̃J�b�g�A�{���̐}���Ƃ�������{�̂��o���Ȃ���Ό����Ȃ�����A�Y�� �z�N������C���[�W�ł���K�v�͂Ȃ��B����A�ڎ��̌�Ɂu����@�g�����^������@�c�����g�^�w���ɖi����x�}����v�ƃN���W�b�g����Ă���悤�ɁA���� �͂̂����s�u�� ���v�Ƃ����G�t�i�v ���ЁA1980�j�Ɠ��l�A�n�œc�����g�̊G��������Ă���B�{�����u�u���ɖi����v�����𒆐S�Ɍ����������Y�ւ̑씲�Ș_�l�v�i�ѕ��j�ł��邱�Ƃ� ��˂Ŋ��m�����߂邽�߂ɁA�s���ɖi����t�̑}��ȏ�̂��̂͂Ȃ����낤�B�����Ƃ��A���ɋ��g��p����A�C�f�B�A�́A�s�����Y�S�W�t�̑������Ă������������悤�ɁA�߉ς���ɂ����̂�������Ȃ��B
 �@
�@
�߉ϑ��Y�s�����Y���̑��t�i���V���X�A1975�N4��20���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���ƌ��Ԃ��i�E�j
���ѕq�F�����q���퉺�̎Ⴂ���l�����r�i�s���㎍�蒟�t2007�N3�����̃����[�A�ځq�킽���̎��؏W�r�j�ŁA�g�����̏�����s�����G�߁t�i����ɁA1940�N10��10���j�̏o�ōL�����G���s���Y�Ę_�t1941�N1�����Ɍf�ڂ���Ă���Ə�����Ă���B�����ɓ�����܂��ɁA���㎍�������ҏW�ψ���҂́s���㎍�������E�\�\�s�s���_�j�Y���̌��Ɖe�U�t�i���O�A�\�V�G�[�c�A1998�N7��27���j�̐l���������J���Ă݂�ƁA�u�g�����w�����G�߁x�i�g�����j�̍L�����f�ځv�i�����A�O����y�[�W�j�Ƃ����L�ڂ�����B�s���Y�Ę_�t���{�������̂ŁA�T�����L���B
������1941�N1�����́q���W ���㎍�l�W�r�ł���B����i���Ă���u���㎍�l�v�͈ȉ���29���B��{�z�Y�E�x����{�i���j�E�c���~��E�|����E����l�Y�E�H�R�C�O�E�k�����ʁE���V�����E�ߓ����E���萴��Y�E�����~�q�E���c�ہE���얞�E�O�쐳�E�R�{�a�v�E���c�P�Y�E���c�쎵�E�U���L��Y�E�R���U���E�_���o�u�t�E������Y�E��������E�������E�ܓc�^���Y�E�哇�����E����e��Y�i�j�E�⍲����Y�E�]�ԏ͎q�E�鍶��B�����t�v�������̕��͂��A�ߐ{�C���E������E���茪��Y�E�X�{���������������Ă���B�ڎ��ɂ͍��V�����q���d���]�r�̂ق��A�ǎ҂̓nj㊴�q�e�l�e���r�A����ɂ́q�ҏS��L�r�̃y�[�W�m���u���܂ŋL�ڂ���Ă���B���B�W���A���ʂ́u�莚�c�c���n�F�l�Y�v�u�\���G�c�c���c�����v�u�ڎ��J�c�g�c�c�{�c�\���Y�v�ƋL����Ă���A�[�������z�w�ɂȂ��Ă���B���āA�g�����s�����G�߁t�̏o�ōL���͎��̂悤�Ȃ��̂��B
 �@
�@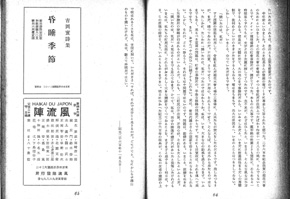 �@
�@
�s���Y�Ę_�t1941�N1�����̕\���i���j�Ɠ��E64�`65�y�[�W�i���j�Ɠ��E�g�������W�s�����G�߁t�L���̃A�b�v�i�E�j�k����������m�N���R�s�[�l
�g���̉��i�ɂ���̂́s�����w�t�i���Y�Ę_�Д��s�̔o��G���j�̍L�������A���́i�S�`�b�N�j�̑I����l���̔{���A����ɃX�y�[�X�̏������������āA�Ȃ�Ƃ���肿�炩������ۂ��B����ɑ��āA�s�����G�߁t�̍L���͐V���̎O���i���ЍL���j��f�i������������ł���B�N��������w��i���C�A�E�g�j�����̂��낤���B���ю��͖`���ŐG�ꂽ���͂ł��������Ă���B
�k�c�c�l���܂��܂ڂ����ڂɂ����u���|�Ę_�v���a�\�Z�N�ꌎ���i���s���͑O�N���j�Ɏ��W�w�����G�߁x�̎l���̈�ōL�����f�ڂ���Ă����B�ʼn��̓v���͂����̂������肵�����C�A�E�g�ŁA���s�����͂Ȃ��A�����ɉ������Ōl�̏Z���Ɓu�g�����v�̖�������B�F�l������ɏo�e�����Ƃ������ł��邪�A���̎��_�ŋg���͏��W�����ɂȂ��Ă���A�܂������m��Ȃ������Ƃ͎v���Ȃ��B���́u�Ђ����ɓǂ܂�邱�Ƃ����҂��Ă����v�Ƒz������̂����R���낤�B�i�s���㎍�蒟�t2007�N3�����A��l�܁`��l�Z�y�[�W�j
�s���Y�Ę_�t�́q�ҏS�����r�ɂ́u������L���v�Ƃ��āu�{���̍L���ʌ䗘�p�̏����̂��߂ɁA�{�Ђ͍ŏ��̎���ōő�̌��ʂ��鎏�ʂ���Ă���܂�����A���L���Ɍ�g�p����Ƃ�ؖ]�������܂��B�L�������\�͗X���O�K�����̏エ�\�����ݎ���A�i��\�グ�܂��B�U�֗p���������ɔ����������܂��v�i�����A����y�[�W�j�Ƃ���A�g�������s�����G�߁t�̊��s�����A�V�����m�Ƃ��ďo�e�����L���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����̎w����Č�����A�ȉ��̂悤�ɂȂ낤�i�������ق�̏�����т��������z�u���G��ł���j�B
�@�@�@�g�������W�k�l���l���A�L�l
�@�@�@�����G�߁k�l���A�L�l
�@�@�@��S������o�Ł^�a���ܒԔ��Z�Ł^�V�l�Z���J�ƚ��k�W�|�x�^�E���g�l
�@�@�@�����s�{�����X����m�\�O�@�g�����k�U�|�x�^�E���g�l
�s���Y�Ę_�t�̍L�����C�A�E�g���ǂ̂悤�ȃV�X�e�����������͕s�������A���ꂾ���Ïk�������Ă̎��M�A�������ꂽ�����̎w�肪�g���{�l�ȊO�̎�ɂ���ĂȂ��ꂽ�Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B�����Ƃ��A���̍L�����t���������ƂȂ�Ƙb�͕ʂŁA���ю����O�f���p�ɑ����āu���ƔłƂ��Ă͈ٗ�̍L���܂ŏo�������̎��W���A�ڂ��̒m����蓖���܂������b��ɂȂ�Ȃ������̂��s�v�c�ł���v�i���O�A��l�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���Ƃ���A�s���Y�Ę_�t�ł̔����͎����́q���a�\�ܔN�x�@���W���ځr�Ɂu�������G���E�g�����i���ƔŁj�v�i�����A1941�N2�����A�㔪�y�[�W�j�Ƃ��邾���̂悤���B����o�łł��邱�Ƃ�錾���Ă��邩�̂��Ƃ��o�ōL���i�ɂ�������炸�A�}�S�̎���o�ŕ��łȂ����Ƃ͍L�����̂��Y�قɌ���Ă���j�͓������ǂ��Ă������l�����Ɍ������A�������������̎�҂���̎��ȏЉ������������Ȃ��B�\�\�g������N�q�؉��[���Ƃ̕ʂ�r�i���o�́s�����V���k�[���l�t1979�N5��18���j�Ŏ��̂悤�ɏ������Ƃ���B
�@���a�\�ܔN�̏H�A���W���ꂽ�̂��_�@�ɁA���͏������߂����Ɖ̂��s�����G�߁t�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B�K������ɏ��W�����ɂȂ����̂ŁA����o�ł��āA�F�l�m�Ȃɔz�����B�؉��[�������������ʔ������ƂɁA��\�т����鎍�ɂ͂ӂꂸ�A�O��قǂ̒Z�̂������Ď]�߂Ă����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��ꔪ�y�[�W�j
�z���g�����g���̐��z�ŁA���Y�Ę_���W�܂���܂����؉��́s�c�ɂ̐H��t�i�����w������A1939�N10��20���j�ւ̈����Ƃ����`�Łs���Y�Ę_�t�ւ̌h�ӂƐe�t���������Ă����B
����N�v���W�s���҂����̌Q���镗�i�k����Łl�t�i�͏o���[�V�ЁA1982�N10��5���j�́A�Y�͂��琬�钷�јA�쎍�B�сi�\1�j�ɂ͉��g�Łu���҂������A���̖ڂ�ʂ��ā^�̗[�f���߂Ă��B�^�܂��Ă��B�^���̉��̐K�̂₤�ɂ܂ԂȂ܂Ԃȉ_�����āA�^���܂ɂ͏ցA���҂�B�v�Ƃ����{���̎���ƂƂ��ɁA�u����������{�^����\�g�����^�͏o���[�V�Ёv�Ƃ���i�ҏW�҂����������̂��낤�j�B�������N�̎�ɂȂ邩�ѕ���搂��Ă���̂́A���Ȃ蒿�����B�{���ɓo�ꂷ��u���҂����v�͈Ӑ}�I�ɌŗL�������邳��Ă���A���Ƃ��Ă͋g�����������s�l�����@���o���t�i�Ԑ_�ЁA1984�j�ɂ��Ă̕���ǂ�ł��炦��Ώ[�����B
�{���̎d�l�́A���Z�~�ꔪ��~�����[�g���E����y�[�W�E�㐻�N���X���E�\���ɓ\���ӁB����700���B���ҖѕM��������B�p�w�̃N���X���̎�G��⊈�łɂ��{���g�݂́A����N�v�̎��т̂Ђ���Ƃ����M�C�ɒʂ�����̂�����B�Ȃ��A����ł̗�1983�N2��25�����s�̕��y�̂��߂̐V���Łi�d�l�͓���~��܁Z�~�����[�g���E���Z�y�[�W�E���������A��{�I�Ɍ���łƓ����e�����A�����p��1�����I�~�b�g���āA�{���̎ʐA��ł������Ă���j�̑������g���ł���B�剪�M�̎��W�s�t �����Ɂt�i����R�c�A1978�j�Ƌg���������̓��s�t �����Ɂk��������Łl�t�i���A1981�j�ɏƂ炷�Ƌ����[���̂����i���Ȃ݂ɁA�s���҂����̌Q���镗�i�t�́q�U ���˂ցE���˂���r�́u�S�̂��剪�M�w���˂ցE���˂���\�\��l�̎��҂̂��߂̎l�́x�̈��p�ł���v�I�j�A�{��������łƐV���ł̔��^���قȂ��Ă���B�V���ł��g�ł͓���������A���̔��^�͌���ł̍��E���g���~���O�������D�ŁA���{��̊����͍���ʒu�̎w��ł���B���͍ŏ��A�{����V���łœǂ��i�V���ŏo�������A����ł�����ł��Ȃ������j�A���E�̃A�L���������Ǝ��������łœǂނƁA12�|�̖{���g�݂��N�₩�ŁA�g���̃��C�A�E�g�̌���������������B
�u�����L���̊��������āA�傫�Ȑ�̂₤�ɁA���͐l�ƌ��m�킩�n��悤�B�v
���̈�s���D���ōD���ŁA���̂����u�L���̊��v�Ƃ́A���ꂪ�u������v�Ƃ�
�ǂ����ӂ��Ƃ��A���������炸�Ɂc�c�B
�����Ĕ��Ă₵�Ȃ�����ǂ��B
�i�q�Y �s���Ăɏt���E�t�����̂�Ȃ����ĂɁt�r33�ߒ���1�߁j
���W�s���҂����̌Q���镗�i�t��1983�N�A��13�����܂���܂����B�g���͑I�l�ψ��̈�l�Ƃ��āu�I�l��͂��܂�ƁA���́k���������l�w�����x�Ɓk�����a�l�w���{�̎��͂ǂ��ɂ��邩�x�����ē���N�v�w���҂����̌Q���镗�i�x�̎O���𐄂����B�k�c�c�l�^����N�v�w���҂����̌Q���镗�i�x�ւ̎�k�}�}�l�܂����肵���B�N������\�����Ă������Ƃ����m��Ȃ��B���Ă̖���w�킪�o�_�E�킪�����x�����������܂Ɖ����قǁA���̒��јA�쎍�́A���҂Ɛ��҂̌������A���G����ɏ��q���Č����ł������v�i�s���\�\���������w�U������tVol.1�A1983�N3��10���A�Z�y�[�W�j�ƑI�]�q���֊�]�����Ă��c�c�c�r�ɏ����āA�{���W���]�����B
 �@
�@
����N�v���W�s���҂����̌Q���镗�i�k����Łl�t�i�͏o���[�V�ЁA1982�N10��5���j�̔��ƕ\���i���j�Ɓs���k�V���Łl�t�i���A1983�N2��25���j�̕\���i�E�j
����R�c�́q��������Ŏ��W�̌�ē��r�Ƃ�����܂�̃p���t���b�g�i���ʂɂ́u��㔪�Z�N�\���v�t�̒A���������܂܂��j�ɂ��ẮA�q�g������ �����{�r���s�|�[���E�N���[�̐H��k��������Łl�t�ł��G�ꂽ���A�����Ɍ�����͎̂��̎O ���ł���i�����������Ďd�l�W�̂ݘ^����j�B
�t�̖����\�\�X���r�Y���W
�k�c�c�l
�I���W�i���E�G�b�`���O��t���ԍ�O�D
�����Ō����\�����^�a�T���ό^�㐻�{�\���}�[�u�����R�r��w�p�R�[�l���t���z�\������^���ҏ�������
�\�ꌎ�\�ܓ����^�艿��A���Z�Z�~�|�[���E�N���[�̐H���\�\�g�������W
�k�c�c�l
���ҏ����������
�����Ō����\�����^�e���ό^�㐻�{�\�����v�R�r��g�~�k�p�l�{���������P�����C�h�z�\������
�\�ꌎ�O�\�����^�O��A�Z�Z�Z�~�����S���\�\���E���썑�v�^��E�i�C
�k�c�c�l
�����\�ܕ��^���썑�v�E�i�C��������
���썑�v�ɂ��I���W�i���E�G�b�`���O��t�t
�a�T���ό^���^�{���u�����S���v�\�\�{���A���V�����g�p�{���̂��߂̊��ŐV�g����i�C�I���W�i���E���g�O���t�\��t����\�����v�㐻�{�R�r��g�p�V�� �^�ʍ��u���ƍ��u�v�\�\���썑�v�������G�Z�C�ɉ�l�_����������Y�t�^�����ĕz�\���i�i�C�I���W�i���E���g�O���t��t�\�j����^���B�E�i�C
�\�\�����^�艿��܁Z�A�Z�Z�Z�~
�� �Ȃ킿1980�N10�����_�ŁA�剪�M���W�s�t �����Ɂk��������Łl�t�i����R�c�A1981�N12��30���j�̓��C���i�b�v�Ɋ܂܂�Ă��Ȃ��B���Łs�t �����Ɂt�i����R�c�A1978�N12��5���j�͂��łɑ�7���܂���܂��Ă��邩��A��L��3���ƂƂ��Ɂq��������Ŏ��W�̌�ē��r�ŗ\������Ă����� �����Ȃ��̂����A�܂����ɏ���Ă��Ȃ��������B
 �@
�@
�剪�M���W�s�t
�����Ɂk��������Łl�t�i����R�c�A1981�N12��30���j�̃P�[�X�Ɣ��ƕ\���i���j�Ƒ剪�M���W�s�t
�����Ɂt�̌��Łk��l�Ɠ�������Łk���l�̖{���y�[�W�i�E�j
�ȉ����q�g�����̓����{�r�̑̍قɕ���āA�{���̉��t�y�[�W�̋L�q�i���g�j��]�ڂ���B
�u �k�u�R�c�v�̈�̑̍ق̓ʔŁl
���W�@�t�@�����Ɂ\��������Ł����ґ剪�M����㔪��N��O�Z�����s������g���������s�l��؈ꖯ���s������R�c���l�s���捂����\���\��\���Z��
�d�b�Z�l��(�l�O)�O�܋㔪�^�Z�O(�㔪��)���l�Z��������H��������G�p�Ж�菟�ꐻ�{���{�ێO���艿�l���Z�Z�Z�~���{���͌���O�\�����́@�\�@�ԁv
�{
���̎d�l�́A�{����F���i�{���g�͌��ł�90���T�C�Y�ɑ����j�E��Z��~��O��~�����[�g���E����y�[�W�E�㐻���v���E�\���E�i�{�[���P�[�X�i�w�ɏ���
�ق����A���ɋL�Ԃق����L�ڂ�����ⳓ\�j�B����38���B���ҖѕM����i�u�����ʃ����m�^�X�i�n�`�����^�ʃ����^�����^�X�i�n�`�Ύ��v�j�A�ѕM��������A��
���B
�g���́s�|�[���E�N���[�̐H��k��������Łl�t�i�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��j�Ƃ悭�����V���v���ɂ��č����ȑ����ŁA�Ƃ�킯�v�̐ԐF���������B�����c�O
�Ȃ��ƂɁA�{���̃C���L�i�X�~�E���F�Ƃ��j�̏�肪�����A�Ƃ������y�[�W�ɂ���Ă͂�����C���̂Ƃ��낳������̂́A�ō��̎��ނɍō��̈���ɍō��̐�
�{�A�Ƃ�����������ł̌�������O�����̂ƌ��킴��Ȃ��i�������A�����́u�\�ԁv�{�����������Ȃ̂ŁA���̖{���ǂ����͂킩��Ȃ��j�B���������
�ڂ������̂��A�{���Ŗʂ̍���ʒu�ł���B���ł̃m�h�͂����ł͂Ȃ��̂����A�����{�̓m�h���̍s���y�[�W���܂����ő��̍s�ԂƓ����Ɍ����邭�炢��
���z�u����Ă���i�ʐ^�Q�Ɓj�B���v�˂����\���̃m�h�͎����۔w�\���̂�����͂邩�ɊJ���ɂ�������A���̎w��͉ߌ��ł���B�ʏ�Ȃ�m�h����1�s
�͍���āA���s�m���u���i�m�h����2�s�߂ɑ������u�B���m���u���v�j�̏�ɍ��킹�Ĕz�u����Ƃ��낾�B�{���́q���r�������B
�w�t�@�����Ɂx
��㎵���N�\�ܓ����s�@���s�ҎR�c�k��@�_�ސ쌧���l�s���捂����\���X�J�C�r����K�@����R�c�@��O�Z�_�~�ꎵ�܇_�@��Z�Z�Ł@�����t�����X���@ �\���G�����ĔV�@�艿��Z�Z�Z�~�@�{���V�������ȁ@�܂��{���ɂ͎��̓�������{�����ꂽ�B
�����{�w�t�@�����Ɂx
��㔪��N�\�O�\�����s�@���s�җ�؈ꖯ�@�_�ސ쌧���l�s���捂����\���\��\���Z��@����R�c�@���Z�_�~��l�Z�_�@��Z�Z�Ł@�㐻�瑕�@�۔w�@ �r�j�[���J�o�[�t�@�N���X�����@�_���{�[���ی�J�o�[�t�@����g�����@����O�\�����@�艿�l���Z�Z�Z�~�@�{���V�������ȁB
�i�s�剪�M�S���W�t�A�v���ЁA2002�N11��16���A�ꎵ�O���y�[�W�j
�g �����͑�9�����܂̑I�]�Łu�k�c�c�l�����ǂ���A�剪�M���W�s�t�@�����Ɂt�̔��s�����A�\�ܓ��ɂȂ��Ă���̂ŁA���O����Ƃ̕����B���N �́A�\��̐l�̎��W�ɁA�����ꂽ���̂����������������A���͂Ђ����ɁA�s�t�@�����Ɂt�𐄂��l���ł����̂ŁA�Ƃ܂ǂ��Ă��܂����v�i�q���z�r�A�s���� ���蒟�t1979�N2�����A��Z�Z�y�[�W�j�ƌ��łɌ��y���Ă���A�����]�����Ă������Ƃ�����������B�g���͑剪�̂��̎��W�ɁA�����܂ł͂Ȃ��������܂� ����Ă��炢���������ɈႢ�Ȃ��B���������z�����Ă߂āA���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j�̑����̗]���������Ė{���̑����ɗՂł��낤���Ƃ́A�قڊm���ł���B�W���ł́q�n��������������r�\�\�Ȃ�Ƌg���� �I�ȑ薼���낤�I�\�\�Ƃ������т��D�܂����B
��
���k��s���l�̏��t�i�p�쏑�X�A1980�N6��30���j�͉��������{�ł���B1970�N��̖��A���͑���c��w�̃t�����X���w�Ȃő���e��Y�搶���瑲
�Ƙ_���̎w�����Ă����i�����̃{�[�h���[���s���̉t���i�H�����肵���悤�Ȃ��̂��j�B�Ƃ����Ă��搶�͂����炩�ŁA�D���Ȃ悤�ɂ������Ȃ����Ƃ�
�����q����������A���͌������ɂ������Z�̑��v���A�|���l�[���S�W�����ڂŌ��Ȃ���A������w�̔ѓ��k�ꂳ��̃A�|���l�[���̉��K�ɂ����肱�B�v��
�C���[�h�ł̃A�|���l�[���W�͎��W�ƎU���W���Q�l���x�ɓǂ�ŁA�����o������̐y�ДŖM��S�W��A�s�G�[�����}���Z���E�A�f�}�̃A�|���l�[���`�A����
�Ă������ѓ�����́s�A�|���l�[���t��������ɂ��āA���W�s�A���R�[���t�ɂ��đ��_���܂Ƃ߂������̂������B
������w���o���N�Ɋ��s���ꂽ�̂��{���ł���B���̂��߂����ʏ������ɁA�����͂��Ă��Ȃ��i�����Ƃ��A�ڎ��ɂ́u���u���l�̏��v�ɓo�ꂷ�鎍�l����
�������ď����o�ꂷ��A�O�v�̖����������Ōf���Ă���A�����Ǝ����悤�Ȗ������ʂ��Ă���j�B���ǎ��̎��͎����p�̍���������Ă��āA�ӂ���̎��l�̓o��
����y�[�W�����ЂɃ����������Ă���B���l�̂ЂƂ�̓M���[���E�A�|���l�[���ł���i�u9�`18�A34�A36�`37�A40�A77�A88�A103�A140�A143�A176�A180�v�j�A�����ЂƂ�͌����܂ł��Ȃ��g�����ł���i�u215�A234�A238�`240�v�j�B
�@�g�����͈����N����B���c�O�Y�A���ˉ�v��Ɠ��N�ł���B�����ɐ��ꂽ�B�\��̏I�肩�玍����͂��߁A�k�����q�ɉe������ ��B�풆���n�d���̈ꕺ�m �Ƃ��Ė��F�e�n��]�X�Ƃ����B���A�ނ͂قƂ�Lj�l�Ŏ��������Ă��āA���W�w�Õ��x���o���A�������锽�����Ȃ��A����̕������l���Ă����Ƃ��ɁA���R�� ���Ƃɂڂ��͔ނƏo������B�Ȍ�ނ͑����̎��W�����s�����B
�@�g�����̎��ɂ͏I�n�ٗl���~悂����܂Ƃ��B�G���`�X�����˂ɂ���Ɠ��s���Ă���B�����ł́u�m���v�̂����͂��߂̕��������p���Ă������B�i�{���A�� �O���y�[�W�j
��
������́q�m���r�i�C�E8�j����P�ƂQ�����������ƁA�u���c�O�Y�̎��̃��[���A�A�k�c�c�l�g�����̎��̏��̗v�f�A�݂Ȏ�ނ��ق�B���������̎��̂���
�ꂽ�������݂ȏ��̗v�f�ƒ������Ă��邱�Ƃ��킩��Ǝv���B�g�����̎O�N�O�́w�T�t�����E�݁x�́A��㎍�O�\�N�̞���������悤�Ȏ��W���������A�S�сA�����ȁA��������[���A�ɂ݂��Ă����ƌ����ĉߌ��ł͂Ȃ��v�i�{���A��l�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B�p�쏑�X�́s�Z�́t�ɁA��f���p���܂ޑ��́i�I���
����ӂ��߂̏́j������������A�{�����g�����̑����ŁA�Ƃ����ѓ�����̈ӌ����ł܂����̂��낤���B
�{���̎d�l�͈ꔪ���~���Z�~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B����̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�Ƃ���ŁA���̃W���P�b�g�̕����̐F�g�����ʔ�
���B���͏������X�~�����A���Җ����F���������A�w�ł͂��̋t�̔z�F�ɂȂ��Ă���̂��B�{��������ƁA�����݂͂ȔZ���D�F�i�X�~�ł͂Ȃ��j�ŁA�J�b�g�i����
�낤���j�͑N�₩�ȃI�����W�F�B�W���P�b�g�̕����A�X�~�����E�F�����E�Z���D�F�̃J�b�g�E�X�~�����ƁA�{���Ɠ��l�̐F�g����W�J���邱�ƂŁA�S�n�D�����Y
������������B

�ѓ��k��s���l�̏��t�i�p�쏑�X�A1980�N6��30���j�̖{���ƃW���P�b�g
���e���O�Y�̎��W�s����t�i�}�����[�A1970�N7��10���j�́A2000�s�̒��ю��s��́t�i�}�����[�A1969�j�ɑ����A���{��ɂ����Ԃ߂̒P�s���W�B�тɁu���݂@�������z���ĉi�����[������Ɠ����~悂Ɛ[�����D�̐��E�B�����ŐV�̎���O�\��тɏ������\�т����߂����ؔŎ��W�v�Ƃ���B����C���ɗ^�����q�e���Q���W����r�A����l�Y�ɗ^�����q�����l�r�A�X�J�ς�Ǔ������q��ǁr�ƕ���ŁA�u���V�L���̃��V�I�J�̂悤�ȁv�Ƃ�������̂���q���V�L���r���܂�1967�N����70�N�܂ł̎��т����߂�B���������ň��������̂́A�����̂�����ł��Ȃ��q���U�r�ł���B
���U�b���e���O�Y�����Ȃ��
�t�����̍���
�͂Ă��Ȃ��߂���
���̖쌴�ɂ����炤
�l�Ԃ̂��߂�
�������̓y�̔t��
���̑�������������
�����̓V��̌�����j��
�Ȃ�Ƃ����h��
���̂����������
���������̂قƂ���
�݂Ȃ��Ƃ��Ђ����ɏj��
����������̂Ȃ�����
���l�͂ӂ邦��
�ӂ邳�Ƃ։i���̉�A��
�V�N���������̔������́A��ނ��Ȃ��B���͂��āu�t���̂�����h�⊟������߂̉��Ƃق���ӂ�������Ӂv�i�̏W�s�ʑt�ቹ�t�A���Y��ԁA1985�j�Ȃ�����A�{�т���n�o�������̂��B
�{���̎d�l�͓�Z���~��l��~�����[�g���E�ꔪ��y�[�W�E�㐻�p�w�p�\�����i�w�E�v�A���E�N���X�j�E�\���B�ʒ��{���̑O�ɁA�y�����������p�̔�����t�B����1200���A���t�Ƀi���o�����O�}�V���ɂ��L�ԁA�u���v�̉���B�{����12�|��12�s�Ƃ������g�܂�A�Ђ炪�Ȃ͎̂Ă��ȁi�����j���g�p���Ă��Ȃ����߁A�N���ƂɊ�̐�����������҂ɂƂ��Ă͂܂��ƂɐS�n�悢�g�łł���B�}�����[�ݐВ��̑��������ɑ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�g�����́q���e���O�Y�A���x�X�N 8 �s�l�ށt�o���r�Ɂu���W�s����t�����s����Ă���A��\�N�̍Ό����o���Ă���B���x���܂��������{�E�����C����ꂽ�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O��y�[�W�j�Ə����Ă���B

���e���O�Y���W�s����t�i�}�����[�A1970�N7��10���j�̔��ƕ\��
�X �仂́s�L���̊G�t�i�}�����[�A1968�N11��30���j�́q��L�r�ɂ́u���e�����̋L�v�Ȃ镛�肪����B�u���̂��сA���́i�L���̊G�j�Ƃ����{���o���� ���ẮA�g�������̂����͂��킸��킵���B�����A���͂����čځk�}�}�l�����̂ɁA��ςȂ��������������錋�ʂƂȂ����B���Ƃ����l�Ԃɉ����Ƃ��ł��� �肠���l�X�͒N�ł��A��ςȖ��Ȃ��Ƃ��������������ƂɂȂ�̂ł���B���x�̏o�łɂ��Ă͂ǂ�Ȗ��Ƃ��N�������Ƃ����ƁA���̔@���ł���B�g���� �������Œ������x���A���̕����̋߂��̎@��Ƃ����i���X�ɂ��o�łɂȂ���ɁA�{�̑���̂��Ƃ����A�Ő�����������Ȃ��̂�₤���߂̏��������\�сi�O �\�����j���o�����A�v�i�{���A���O�y�[�W�j�ȉ��A�g�������q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�ň��p���Ă���悤�ɁA�X�������������e�i1966 �N2��17������6��15���܂Łs�F�{�����V���t��100��A�ڂ����q���X�̑z���r�ɐV�e�����������́j�����e���O�Ɏ����A��S�̂������e���Đ��A�Ђƌ� �x��œ��e�����̂������B�g������ɑ������肪�����s���̖X�q�t�i�}�����[�A1957�j���s�C�̉��t�i���A1958�j�ɂ͌�L���Ȃ�����A�{���Ɂq��L�r���t���ꂽ�̂͏��߂̌��e���� ���Ȃ���������������Ȃ��B���āA�{����������Ȃ��͂�q���r���B
�V�N�ȗ��́A�U���U�������^���Ȋk�̐F�́A�p�g�����q�̕\�ʂׂ̍��ȁA���̂���C�A��A�����Ȋ��F������A�������̌����̋P���A�Ȃ��Ɠ����悤�ɁA�y���� ���̐H��ւ̗U������߂Ă��邪�A���lj�̊X�̉Ƃ̂悤�ȁA�t���W�B���ȁi�����ア�A�����j���ށA�嗝�ɂ���悤�ȁA���ڂ낰�Ȕ������i���_�j�̂���A�K�N�F�����т����ށA�Ȃ��̃`���{���̊k�̐F���A�����䂫����B���ׂ�̂ɂ͑��ސF�̂����������A�K�N�F�����тāA�������̂���̂͂��Ƃɔ����������A�y���ނ��߂ɁA�^���̂������Ă���B���̐H��ŁA����A�ɗ���������Z���A���F�̗��́A�d�݂̂������������lj����鎞�A�M�̏�̗��̊k���A��q��߂� �ق̖��邢�����̂悤�ɓ����Ă���̂�����̂́A���̐H��̍K���ł���B�i�{���A�l���`�l��y�[�W�j
�X�仂͋g�������s�����܁t�̕ҏW���ɂȂ����ŏ�����21���i1971�N1���j�Ɂq�X�̒��̖̗t���r����
������i��1972�N8������40����
���q�}�h�D���A�[���A���E���E�r����e�j�B��������q�ɂ��{���q��L�r���́u���҂Ƌ߂Â��ɂȂ����l�ŁA���炩�̓��f�T�����f�𖡂�����l������Ǝv
�����A���̒��_�ɗ��̂��g�����ł���B���l�̋g���������ʂ����Ôg�̂悤�ȍГ�̑O�ɂ́A���̐l�X�͖ق��ĒE�X���邵���Ȃ��B���҂̒��炵���ꏟ�Ȋ���
�̕��͂��A������悭�`���Ă���v�i�s�X�仑S�W�k3�l�t�A�}�����[�A1993�N9��20���A�Z��l�`�Z��܃y�[�W�j���l�����킹��ƁA����͋g���̌��e
�˗��ɉ�����`�ŁA�X�Ȃ�ɕԗ炵�����̂��B
�{���̎d�l�͈ꔪ���~����~�����[�g���E��O�l�y�[�W�E�㐻�����E�\���B����E�����B�X�̖{�ł́s�C�̉��t�ȗ���Z�N�Ԃ�̋g�����������A���̊Ԃŏ�
�Ђ̈���Z�p�͑傫���ω������B�{���͖{�����������i���Łj��������A���͎ʐA�E���ň���ւƑւ�����B�\���̕��̃J�b�g�i�e���g�E���V�j�Ɣw�����͋���
���������{���Ă���A���ޖʂł��A�P�s�{�̂���ՊE�������Ă���B

�X�仁s�L���̊G�t�i�}�����[�A1968�N11��30���j�̖{���Ɣ�
�X�仂́s�C�̉��t�i�}�����[�A1958�N10��20���j�́A�R�c����Ƃ̗����̌o�܂������ӂ��ɏ������q�L���̏����r�ȂǁA�S10�т����߂���� ����W�B�g�����͑O��s���̖X�q�t�i�}�����[�A1957�j�ɑ����āA���{�E������S�����Ă���B
�@���ɂƂāA�u�X���O�v�Ƃ��ӂ��̂ɂ��ď������Ƃ͂Ђǂ�����B���́u�X���O�v�Ƃ��Ӑl���A�悭����Ȃ�����ŁA����B�� �O�ɂ��ď����̂ɂ́A�� �͂��܂�ɉ�������Ȃ��B���̒m�Ă��̂́A���̕G�ɏ�đ̂�h��A���тɖ����ċ��Ɋ�肩�������ŁA�����B�����̃x���`�ɍ��������A�������� �������݂ɍm�����āA���𑤂֏��ԕ��ŁA�����B�������e�k�}�}�l�߂̔w���Ɏ�����肩���点���ԂŁA����ŏ�����ǂޕ��ŁA�����B�i�{���A�y�[ �W�j
�g
�����q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�ňꕔ�������Ă���q�X���O�\�\���O�Ǝ��q�r�̖`���̒i�����B��̂ɐX�仂ɂ͖��ȏ��œǓ_��łȂ�����A���͂��́u�ŁA���v�̂悤�ȑł������D���łȂ��B�u���́u�X���O�v�Ƃ��Ӑl���A�悭����Ȃ�����ł���B�k�c�c�l���̒m�Ă��̂́A���̕G�ɏ�đ̂�
�h��A���тɖ����ċ��Ɋ�肩�������ł����B�����̃x���`�ɍ��������A��������������݂ɍm�����āA���𑤂֏��ԕ��ł����B�������D�߂̔w���Ɏ�
����肩���点���ԂŁA����ŏ�����ǂޕ��ł����v�̂ق����A��قǃG���K���g�ł͂Ȃ��낤���B
�{���̎d�l�͈ꔪ�Z�~���܃~�����[�g���E���Z�y�[�W�E�㐻�����E�\���B���t�͑O��Ƃ͈قȂ�A�{���p���Ɉ������Ă���B�������ꂪ�A�E�y�[�W�ŏI
������{����ɂ܂�܂�꒚�i�\���̃y�[�W�j�̔��������āA�{���̍ŏI��Z��y�[�W�̑Ό��ɂł͂Ȃ���Z�܃y�[�W�߂ɔz����Ă���̂͂ǂ��������Ƃ��낤
�i��Z�O�y�[�W�߂Ȃ�����ŁA�Ȃ�̖����Ȃ��j�B
�{���̑������s���̖X�q�t��
���P���Ă���B�Ƃ���ŁA�X�仂͑�����O����W�́s�Z�D�F�̋��t���}�����[����1959�N12��15���ɏo���Ă���B���N1�����s�Ƃ����n�C�y�[�X���B
�s�Z�D�F�̋��t�̑����͓Ȑ܋v���q�����A�{���̕��������͋g���́s���̖X�q�t�s�C�̉��t�Ɠ����ŁA�O������Ӑ}���Ă���ɈႢ�Ȃ��B����A�\���̃J�b�g
�i�g��������2���͕\���ɏ��������j�ɂ͓Ȑ܂炵���H�v�����炳��Ă���B�Z�D�F�̉����s��`�̐F�ʂɋ��̌`�ɂ�������֊s��`�����݁A���Ɂu�����͂��@
����́^�����ȁv�ƂЂ炪�Ȃŏ����Ă���̂��i����E���������Ƃ����k�L�j�B
�s�C�̉��t�̉��t���ɂ́A�g�������C�A�E�g�������̂Ǝv�����O��̍L�����ڂ��Ă���̂ŁA�f���Ă����B�g���́A���̔N11��20���ɏ��惆���C�J����s�m
���t���o���Ă���A���҂��g����}�����[�̎Ј��ł���Ɠ����ɁA���l�Ƃ��ĔF�߂����Ƃ��낤�B�Ȃ��{���́A�ѓN�v�s������[�����肫]100�t�i�݂��̂�
�o�ŁA2006�j�ɁA���E�\���̏��e�ƂƂ��Ɍf�ڂ���Ă���B
 �@
�@
�X�仁s�C�̉��t�i�}�����[�A1958�N10��20���k�ʐ^�͓��N11��30�����s�̓���l�j�̖{���Ɣ��i���j�Ɠ��E��
�t���L���i�E�j
�X
�仂́s���̖X�q�t�i�}�����[�A1957�N2��15���j�́A���d�f�r���[�̂��������ƂȂ������z�W�B��������q�́q���r�Ɂu�^�Ӗ슰�E���q�̎�ɂ���Z
�̎G���u�~���v�ɁA���҂͎O�\�����琏�M������A���O�I�W�̌���ȂǂɁA���O�ɂ܂��c���̎v���o���������肵�Ă����B�����ɖ����\���e��
�Ă܂Ƃ߂�����ł���v�i�s�X�仑S�W�k1�l�t�i�}�����[�A1993�N7��20���A�Z�O�܃y�[�W�j�Ƃ���B���Ђ��犧�s����邱�ƂɂȂ����̂́A�W���̈�
�сq�u�����v�r���s������{���w�S�W�k��7���l�t�i�}�����[�A1953�j����ɔ��\���ꂽ���Ƃ����������������̂��낤���B�\�\�킽�����q���̖X�q�r����
�㍑��̋��ȏ��œǂƂ��A���O�͂ނ��m���Ă������仂͖��m�̏����肾�����B�ȗ��A�X�仂̔M�S�ȓǎ҂łȂ����߁A�{���ɂ܂�钘�҂̏،����ڂ�
���ɂ��Ȃ��͎̂c�O�ł���B
�g�����́u���͉������āA�����o�ł́w���̖X�q�x�ƁA����ڂ́w�C�̉��x�̑��{�E������A�肪���Ă���B���a�O�\��N����̂��Ƃ�����A�v�����������
�m�荇���Ƃ������ƂɂȂ�B��ɐe�������Ă����킯�ł͂Ȃ����A�g�ӂ�����ʐl���Ƒn�����_�ɂ́A�S�䂩��Ă����v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}
�����[�A1988�A�O�l���y�[�W�j�ƁA�Ǔ��̈ӂ����߂āq�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�ɏ����Ă���B
�s���̖X�q�t�̎d�l�͈ꔪ�Z�~���l�~�����[�g���E��Z���y�[�W�i���t�͌㌩�Ԃ��̖{���Ό��y�[�W�ɓ\�t�j�E�㐻�����E�\���B�{���̑�����̃|�C���g��
�u�E�v�i����[�Ȃ�����]�j�̎g�����ɂ���B���̕��ɂ͉������Łu���̖X�q�E�X�仁^�k�ʎ��̃J�b�g�l�^�}�����[�E1957�v�A�ʒ��{���ɂ͏c�����Łu�X
�仁E���̖X�q�k�Ԃň���l�E�}�����[1957�v�Ƃ���i�Ō�́u�}�����[1957�v�́A���s���Əo�ŔN���s�Ɋ����Ă���̂��������j�B�X�仁A���̖X
�q�A�}�����[�̎O�v�f�͌������Ȃ�����i�{�̂┟�̔w�����͂����Ȃ��Ă���j�A1957�������Ă����Ƃ��A�����l�𒆍��Ŋ��邱�Ƃŗv�f�������炵��
���C�A�E�g�������̂��B
�@���̕��������͂����A�Â������B�Ă̐^���A��̐��Ɉ͂܂ꂽ�Ƃ̒�������āA���̒[�̕����ւ����ƁA�����{��ǂ�ł�B �����k���D�߂ƁA�����m�� ���𒅂����͕G�𑵂ւč���A��ɍn�����Ă��B�J�����{�̕ł̒[���ۉ�F�̎肪�y���A�}�ւĂ��B�]��[���B��Ȃ��^���Ȓ܂������w���A�{�̕ł��� �Ă߂���B�����A�U���U���������̏�ɂ͍������Ԃ�峂̂₤�Ȏ����A峂̋���Ղ̂₤�Ȗ͗l�𔒂��c���Ă�����ƁA����ł��B�����K�N�F�Ɍ��� �L�k�̊D�M�̏�ɂ́A�����D�̐ς��t�����A�ڂĂ��B�D�߂̔w���Ɋ������ƁA�������̂₤�Ȑ����Ȕ畆�̓��Ђ������B�i�{���A��O�y�[�W�B ���r�͏ȗ������j
���́q�c�����X�r�Ɍ��炸�A�X�仂̕��͂͋����œǂ݂����Ƃ��낾���A�V���ɉ��߂Ă����̍��C�������Ȃ��̂͌����Ƃ����ق��Ȃ��i�s�X�仑S�W�t�� ����āA�u峁v���u���v�Ƃ��Ȃ������j�B

�X�仁s���̖X�q�t�i�}�����[�A1957�N2��15���k�ʐ^�͓��N10��25�����s�̎l���l�j�̖{���Ɣ�
�� ������s�v���[�X�g�E��ۂƉB�g�t�i�}�����[�A1982�N8��30���j�́A�}���Z���E�v���[�X�g�̔��w�̖G��������̔��p��]�ɋ��߁A�v�z�ƕ��̂̐����� �������ǂ邱�ƂŁA���s����ꂽ�������߂āt�a���̔閧�ɔ���v���̏��ł���B�ۊ����͖{���̑��тƌ�����s�v���[�X�g�E���̕��@�t�i�}�����[�A1997�N1��25���j�́q���Ƃ����r�Ɂu��㎵�O�N�ɁA�͂��߂Ă킽���̏������u�����܁v�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��W�J�k�~��l����̈˗�������������ŁA�����ҏW���������g�����������̏����ɂ��ĘR�炳�ꂽ���z�������Ƌ����Ă��ꂽ���ƂȂǂ��A���܂��ɂ͂�����Ɗo���Ă���B����̂��Ƃ̂悤���Ƃ����� ���A�R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�i�����A��l��`��܁Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B�����s�����܁t��55���i1973�N11���j �f�ڂ̕��͂́q�v���[�X�g�̏o���_�r�ŁA�ۊ����͎��g���s�v���[�X�g�S�W13�k�W�����E�T���g���C���V�l�t�i�}�����[�A1985�N7��30���j�́q�� ���\�\�w�W�����E�T���g���C���x�̂��߂Ɂr�ň��p���Ă���B�{���Ɍ������钅�z�́A�ł��������_�ɂ�����\�����낤�B
�ށk�v���[�X�g�l�͎ړx���Ȃ��đ��݂��v�ʂ��Ȃ��B���m�̊�ŊO�E��l�Ԃ̐S�I���ۂ��n�����đΏۂ̖��C�Ȑ������������悤�ƌ� �ӂ���B�i�����j�^�f�J�� �g�I�ƌ`�e���Ă��������̕��@�I���ӂ́k�c�c�l�ΏۂƂ̒��ړI�ڐG�ɂ��ׂĂ�q�����Ƃ̎d���Ɏ䂫�����Ă䂭�K�R�������炩�ɂ��Ă���B�������̕� �@�̎��o�͏\�����I�̉�ƃV�����_���̊G�̔閧�͂��邱�Ƃł͂��߂Ĕނɗ^������̂ł����āA�w�V�����_���x�i�ꔪ��ܔN�㌎�j�������グ��Ɣނ� �����Ɂw�W�����E�T���g���C���x�ɒ��肷��B�܂���@�̎��H�ł���B�����Ă��̏����̎��M�̉ߒ��ŏ��q�A�\���A���̓��̖�肪��̓I�Ȍ`�Ō����Ă��� ���낤�B�������Ĕނ̒����͍����n�܂�B�v���[�X�g��\�l�̏H�ł���B�i�����A�O���Z�y�[�W�j
�V
��ޓ�Y�́u�ꎞ���}�����[�́u�����܁v�Ƃ������G���̕ҏW���g��������Ă܂������A�ҏW�҂Ƃ��Ă����ɏW���Ă��镶�͂ɑ��ĂЂ��傤�Ɍ�������]
�������Ă��܂�����ˁv�i�s���㎍�ǖ{�\�\������
�g�����t�A�v���ЁA1991�A�l���y�[�W�j�ƌ���Ă���A�q�v���[�X�g�̏o���_�r�ɂ��Ă̋g���̊��z�͏�������ە�����ނ̂��̂������ɈႢ�Ȃ��i�ۊ�
����1978�N2���ɂ��A�g���ҏW���s�����܁t��106���Ɂq�g�c���ꎁ�Ǖ�r���Ă���j�B���Ắu�����v
����قڏ\�N��A�}�����[��ނ��Ă����g���ɖ{���̑������˗������̂́A�S���ҏW�҂̒W�J���낤�B
�s�v���[�X�g�E��ۂƉB�g�t�̎d�l�͈ꔪ���~����~�����[�g���E�O�Z�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�W���P�b�g�B�Z���̃N���X�ɃO���C�̔w��������捂Ȃ�
�����܂���������\���́A�g���������̂Ȃ��ł����M�ɉ�����B����Ɋr�ׂ�ƁA���W���P�b�g�͂��܂�Ɋȑf�ɂ����悤�i���ɂ��ꂪ�A�\���������ςĂق���
�Ƃ��������҂̓ǎ҂ւ̖ڔz���ł������ɂ��Ă��j�B�{���̐}���́A���X�L���ɂ��X�P�b�`�i�{�b�e�B�`�F���`���Ƃ���̃G�e���̖��j���J�肩�����R�s�[��
�����߂��A�~���̂Ȃ��ʼn�̂悤�Ȏd�オ��ɂȂ��Ă���B�Ȃ��A1997�N10�����̂����܊w�|���ɔŁs�v���[�X�g�E��ۂƉB�g�t�̃W���P�b�g�ɂ́A�V��
���_���̖��ʁq�삢�������ār���f�ڂ���Ă���B
 �@
�@
�ۊ�����s�v���[�X�g�E��ۂƉB�g�t�i�}�����[�A1982�N8��30���j�̃W���P�b�g�ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�剪�M���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j�͋g�����������������߂Ă̑剪�M�̒����ł���B���̂�����̂��Ƃ�{���̒S���ҏW�ҁE���ؒ��h�����̂悤�ɏ����Ă���B�u�剪�����悻��N�ԁA�t�����X�ƃA�����J�ʼn߂����\��œ��{�����O���O�A�g�����Ǝ��͐[�厛�̂����K�˂��B�o���܂łɁw���{�x�̑���v�������A�ǂ����Ă��剪�Ɍ����Ă������������B���̓��̋g������͑���҂Ƃ��ē��s���ꂽ�B�k�c�c�l����ɂ��ẮA�g�������Ȃ��ƂЂ����Ɍ��߂Ă����B�g������̂�������Ƃ�������͒�]������B����������l�͌Â�����̐e�F�����A�剪����̐����钘���̂����A�܂�������g������͑��ꂵ�Ă��Ȃ������B�^�u���[�̉Ԗ͗l�̗A�������v�������ĕ\���Ɏg���A���̔w�N���X�A�O���C�̂����Ƃ����X�}�[�g�Ȕ��B�X�P�b�`�ƌ��{���Ɍ�����A�剪����͐^��ł��Ȃ����A�C�ɓ����Ă��ꂽ�B�^�A��ɁA�g������Ƃ����u�w�O�̋i���X�ɓ������B�u�C�ɓ����Ă���āA�z�b�Ƃ�����B�v����M���������Ȃ���A����Ƃ͈��g����f���ɂ���킵�āA�R�[�q�[�����������B�^�剪����ؕ����Ɂw���{�x�͂ł����������B���W�̂ł�������ɂ́A���҂�����Ƃ��Ƃ��ɖ������Ă����������v�i�s���l�Y���m�[�g�t�A����R�c�A1986�N8��25���A���`��O�y�[�W�j�B����A�剪�M�͎��̂悤�ɋL���Ă���B
�@���͂������Č\�ɂȂ����B���̒��d��Ƃ��Ă��̎��W���܂Ƃ߂邱�ƂɁA���ʂƂ��ĂȂ����B����ŁA�ؗF�g�����Ɏ��W�̑�����˗������B�ނ͒}�����[�Β����瑕����肪���Ă��āA�ސE��̍��͂��̐�������Ƃӂ��Ă���B�g������ɑ�����A�Ɗ���Ă���l�X�����Ȃ��Ȃ��B���͉����̈Ӗ��Ŏ��ɂƂ��ċL�O���ׂ��{�̎��ɔނɗ��ނ���ł����B�w���{�x�Ƃ������W�͂���ɋ߂��B�^�g�����͉������Ă��ꂽ�B�����Ԗ͗l�̗A�����̌������Q�ŁA�킴�킴�ّ�ɑ����^��ł���A����v�����̐}�ƂƂ��ɁA�����Ȃ��Ƃ����T���������Ă��ꂽ�B�����{���ł��邱�Ƌ^���Ȃ��Ƃ����v�����������B�^�u�����̖{�Ɏg�������ĂȂ�B�����ł���Ă݂����Ǝv�����̂łȂ����Ⴀ���v�^�g�����͂����������B�����A�����B�^���͍��܂ł��A���[�����A�F�����\�i�A�����ĔV�ȂǁA�h�����Ă�܂ʉ�Ƃ̗F�l�����ɖ{�������Ă���������Ƃ������B�������������������Ƃ�����B�g�����̑���́A�����Ƃ͂܂��ʂ̏��F�����B���͍K�����������B�i�s�l���C�̊D�\�\�܁X�G�L�t�q�F�B�̑���r�A�Ԑ_�ЁA1982�N11��25���A�܌܁`�ܘZ�y�[�W�j
�{���̎d�l�͓��l�~��l��~�����[�g���E��Z��y�[�W�E�㐻�����i�w�N���X�̌p�\���j�E�@�B���ɓ\�O��B���сq壉Ε{�r�̎���u�}���^���n������̒������c�����v�̃}���^�ƃn���́A�莫�ɑ剪�M���������g���́q�~���̓����r�i�H�E28�j�̖{���ɂ��o�ꂷ��B
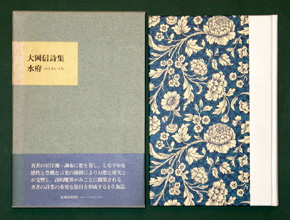
�剪�M���W�s���{�@�݂��Ȃ��܂��t�i�v���ЁA1981�N7��1���j�̔��ƕ\��
�O�o�u�v�̏W�s㊕��I�t�i���ʏ��[�A1977�N11��10���j���ŋ߂܂Ō��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�g���Ƒ��̑�����i�L�^�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�ŔN����҂ލۂɁA�g���z�q���炨�肵�������̂ЂƂj�ɁA�N���ƔŌ��������ŏ����s����1�����������B�Y������N��̔��ʏ��[�̊��s�}��������}���قŒ��ׂĂ݂����̂́A�q�g���������r�́q������i�ژ^�r��҂ގ��_�ł͂��Ƃ߂��Ȃ������B����A�C���^�[�l�b�g�̌Ï����Ŗ{���̑������g�����ɂ����̂��ƒm��A���������w�������B���Ȃ݂ɖ{���͍���}���ق�NDL-OPAC�ɂ͌������A�s㊕��I�t�Ō�������ƁA���^���Ƃ��ās�O�o�u�v�̏W�t�i���V���X�A1981�j�A�s�ꕶ�I�k�Z�̐V���Е��Ɂl�t�i�Z�̐V���ЁA1994�j�A�s����Z�̑S�W�k��16���l�t�i�}�����[�A2002�j��3�����Y������B
�g�����́A�}�����[�ł̋Ɩ��������A�e�������l���Ƃ���˗�����đ������邱�Ƃ����������킯�����A�{���̂悤�ɒ��҂������͏o�Ŏҁi�ҏW�ҁj����̈˗��ł��̈�_�����g���������Ƃ����P�[�X������������B���҂́q���Ƃ����r�́u���̏W�ɝ��߂��̌ܔ�����́A���a�l�\�Z�N�H����A���Ƃ��t�܂ł̎��N�ɂ킽��Ԃɏo�҂����̂ł���B�w�q�ߐ��̖��x�A�w�ˈًL�x��㔂���O�W�ł���v�i�����A��O�Z�y�[�W�j�Ǝn�܂�A�u���̏W�̂��߂ɁA���̙����{���Ă����������l�̋g�������ƁA���ӂ����Ă��̖{�Â�����ݒ[�̓w�͂�ɂ��܂�Ȃ����ΐ����Y���ɁA�S���犴�Ӑ\���グ��B�^���a�\��N�㌎ᶓ��^�g��R���̊��q�ɂā^�O�@�o�u�v�v�i�����A��l�l�`��l�܃y�[�W�j�ƏI���B�����E�����Ȃɂ��{���\�L�́A�O�o�u�v�̒[���ł���Ɠ����ɖҖ҂��������̂ɂӂ��킵���Ǝv����i�ȉ��A�����͐V���ɉ��߂Ĉ����j�B
��s�̍̉Ԃ����ēV���n�����낭�܂肫���ւ̓���
���̘[���s���Ă�ӂ����[���Ă���]���肫�Ȃ��������
�킪�z[�ʂ�]�ɛƂނׂ������݂�Ȃ݂̐X�ٌ̈`�͋łɌ���
�J�[���ɂ���]�̂��n��ɂ݂��Ȃ��݂͏t�̊�ԂɓH���܂�
���̏���ƂтƂтɂ���[�Ђ����̒�q�ƂȂ�䂭�Ђ���
�{���̎d�l�͓���~��l��~�����[�g���E��ܔ��y�[�W�E�㐻�z���E�\���B�Z�̐V���Е��ɔŁi1994�N12��25���j�̗��W���P�b�g�ɁA���̃��m�N���ʐ^�ƂƂ��Ɂu���a52�N11��10�����ʏ��[���s�B�`�T�ό^���㐻����246�Œ艿3500�~�B�P�łR��g588����^�B���B�E�g���@���v�Ƃ��邪�A����i���E���Ƃ������G���j������ɂ����̂��A�{���ɂ��L����Ă��Ȃ��B�����Ƃ��������̂̕����Ɲh�R�����p�I�ȃJ�b�g�́A��������̎�ɂȂ���̂�������Ȃ��B

�O�o�u�v�̏W�s㊕��I�t�i���ʏ��[�A1977�N11��10���j�̔��ƕ\��
�ѓ��k�ꎍ�W�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����t�i����R�c�A1976�N3��15���j�́A���N8�����s�̋g�����̎��W�s�_��I�Ȏ���̎��k���y�Łl�t�ƂقƂ�Ǔ����̍قŊ��s���ꂽ�B�ѓ��͑O�N�ɍs�Ȃ�ꂽ�g���Ƃ̑Θb�q���I�t�̌�䊁r�ŁA����������Ă���B
�@�����A����R�c�łˁA�w�E�C���A���E�u���C�N�������o�����x�Ƃ����ґ�Ȏ��W������������ǁA����́A�Ȃ��y�ł����肽���Ƃ�����ł���B����͕S�����������ǁA�������{����������A�ڂ���������Ƃ��ꂵ�����ʁA�������肵�ĂˁB���h�Ȗ{�ł�����܂荂���ƂˁA�ȂP�`�����Ƃ����Ⴄ��ł���B����ɕS������������A����������������K���Ȓl�i�łƂ����̂ŁA����͂܂��^�����ĂˁB�����A����Ȃ��{�������Ă����������Ȃ�����c�c�v�����āA�u�E�C���A���E�u���C�N�������o�����v���Ă����������������X�g�ɂ����āA���̑O�̎������[���ƏW�߂Ă݂���ǂ����낤���Ƃ�����łˁB���傤�Lj��ܘZ�N������Z�Z�N�܂ł̂قڏ\�N�ԂˁB���̒��S�Ɂu�k�v�̎��オ�����ł�����ǁA���������\�N�Ԃ̎��W�Ƃ����̂ɂ�������ł���B������w�����ցx���O�̎��������킯�B���܂Ŏ��W�ɓ���ĂȂ��̂������ł���B�u�k�v�̑n�����ɏo�������Ƃ��ˁA���������̂����Ăڂ������傤�Ǔ�\��̔��ŌܘZ�N���Ă����Ƌg������Ə��߂ĉ�����Ƃ��Ȃ�ł���B�i�s�����C�J�t1975�N12���Վ��������A����`���O�y�[�W�j
����ł����Ă��Ȃ��̂ŗ��҂��r�ł��Ȃ��̂��c�O�����A�P�ɑ�����ς��������łȂ����e���V�����Ȃ��Ă���悤���B���̊Ԃ̎����ѓ��́q��i�m�[�g�r�ɏ����Ă���B�u���W�w�E�C���A���E�u���C�N�������o�����x�́A��㎵��N�\���A�R�c�k�ꂪ�Ў傾�������̏���R�c�i�����s�䓌��꒚�ځj���珉�ł����s���ꂽ�B�ŏ��A�]�_�W�w�V�������A���X���̔ޕ��ցx�Ɏ��߂Ă��������u�v���e�v�́A����̂̂��A����ɂ��̎��W�Ɏ��߁A����ɂȂ���������Ă悤�₭�{���̌`�ɒ蒅�����B�^���̎��W�͍ŏ��͔��Z���̌���ŁA�̂���㎵�Z�N�ɑ���g�����ɂ��A�w�����ցx�▢���̎��u�������������́v�ȂǂƂƂ��ɁA����łƂ��Ėڍ��掩�R���u�Ɉڂ�������R�c����Ċ��s�ƂȂ�B�����ɂ́u�k�v�̍��̎������������Ă���v�i�s�ѓ��k��E���ƎU��2�t�A�݂������[�A2001�N2��1���A�O�ꔪ�y�[�W�j�B�{���W�ɂ͐�����s�ɂ��s�����ցt�̉�����Ę^����A�����ɑ剪�M�Ɣѓ��̑Θb�q�u�k�v�Ƃ��̎��Ӂr���Y�����A�g�����̑����A�Ƃ��Ắs�k�t�̓��l���i��c�G�������āj����Ŋ�𑵂����B
�����Ɋւ��ẮA�P�c�������u�ѓ��k��́w�E�C���A���E�u���C�N�������o�����x�i����R�c�A���Z�N�j���O�ꂵ�Ė����̂��g���Ă���B�g���̍D�t�����X���ł��邪�A�����ł̑����v�f�́A�n���Ȉ݂͂̏���P�C�ł���B���͐A���͗l�̃P�C�ł���A�\���͎h�J���l���̃P�C�Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A���ɍC���������A��̂悢�d�オ��ƂȂ��Ă���v�i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A�Z�l�y�[�W�j�Ə����Ă���B�{�����c���̕ό^���Ȃ̂́A����������Ə������s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����t�Ƃ��Ȃ蒷�߂Ȃ̂ƊW�����邩������Ȃ��i�{���͏����Ɋ��c��s�x�^�g�ŁA�F���̏������X�~�����̒��Җ��Əo�ŎЖ��ɂ͂��܂�Ă���j�B�d�l�͓���~��O�Z�~�����[�g���E�ꎵ�Z�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���B�s�_��I�Ȏ���̎��k���y�Łl�t�Ɣ�r���邽�߁A���҂̈Ⴂ��E����B
�{���y�[�W�̍��E1mm�̈Ⴂ�͐��{��̌덷���낤�B�O�҂̓m�h�̋�10mm�قǂŁA��⋷��������B��������P�����̂��낤���A��҂ł͖�15mm�ƍL���Ȃ��Ă���B�O�������łȂ��{���g�ł܂ŋg���̎�ɂȂ���̂��肩�łȂ����i�����炭�������Ǝv�����j�A���̑[�u�͑t�����Ă���B
�k�t�L�l
�s�A�����J�t�i�v���ЁA2004�j�͔ѓ�����̍ŐV���W�����A���̈�сq�����h�q�@����r�̌�Ɂu���O�́w�k�������x�������̌�ǂ�ł��āA�������������Ƃ�����̂ŋL���Ă����܂��B�����̐^�����ƌ����g�����̕揊�ł����A�����̕�������^�����ɂ���A�����[�ڂ��߂�]�͗��R�z�ɂ��Ƃ����v�i�����A��l�O�y�[�W�j�ƌ�����B
 �@
�@ �@
�@
�ѓ��k�ꎍ�W�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����t�i����R�c�A1976�N3��15���j�̔��ƕ\���i���j�Ƌg�������W�s�_��I�Ȏ���̎��k���y�Łl�t�i���A���N8��15���j�̔��ƕ\���i���j�Ɣѓ��k�ꎍ�W�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����k����Łl�t�i����R�c�A1971�N10��28���j�̔��ƕ\���i�E�j
�i�E�j�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����k����Łl�t�̎d�l�́A��O�Z�~��Z�܃~�����[�g���E�Z���y�[�W�E�㐻�۔w�p�\���i�w�F�A�C�{���[�̊v�ɏ��������������A���F�A�C�{���[�̖��n�̎��j�E�\���B�{���Ə͔��A���t�͓��F�A�J�ƃX�~�̓�F���B�{���̑O�̒��ɖn���ɂ�鏐���B���t�͈������T�B����͖H����������A���{�͊ݓc���{�B����80���L�ԁi���e��70�Ԗ{�j�B�艿7,500�~�B���́k�NjL�l�̕��o���q�ӏ܁r�ɂ��鎍7�т����߂�B�Ȃ��q�v���e�r�ɂ́u�\�\����C�����Ɂv�ƌ���������B
�k2006�N6��30���NjL�l
�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����t�̌���łɂ��āA�s�ѓ��k��k����̎��l10�l�t�i�������_�ЁA1983�N10��20���j�́q�ӏ܁r�ŕ��o�����������L���Ă���B�܂��{�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Łk���̌�A�ѓ��k�ꎍ�W�s�E�C���A���E�u���C�N�������o�����k����Łl�t�i����R�c�A1971�N10��28���j����肵���̂ŁA���e�ƃL���v�V�������f�ڂ����B�i2018�N9��30���j�l�A�Y���ӏ������p�����Ă��������B�u���W�w�E�C���A���E�u���C�N�������o�����x�͈�㎵��N�\���A����R�c������蔪�\���Ŋ��s���ꂽ�B�u�֎q�̋L���v�u�E�C���A���E�u���C�N�������o�����v�̓�͂��琬��A�O�҂ɂ́u�֎q�̋L���v�u��Ԃ��̂̋L���v�u�s�s���s�̈ӎ��v�u���̓s�s�v�u�H��̗\���v�̌ܕсA��҂ɂ́u�E�C���A���E�u���C�N�������o�����v�u�v���e�v�̓�т����߂��Ă���v�i�����A�l���y�[�W�j�B�u��㎵���N�Ɋ��s���ꂽ�A���̎��_�ł̑S���W�Ƃ����ׂ����X�Łw�ѓ��k�ꎍ�W�x�ł́A�k�c�c�l����N�Łw�E�C���A���E�u���C�N�������o�����x�Ɏ��߂�ꂽ�A�^�C�g���E�|�G���������S�Z�т��Ɨ����āw�v���e�E�֎q�̋L���x�Ȃ�͂����W�Ƃ��Ă��炽�ɗ��Ă��Ă���v�i�����A�l���y�[�W�j�B
����N�v�s�l�����@���o���t�i�Ԑ_�ЁA1984�N10��25���j�ɂ͑z���o������B�q�g�����̘b�����r�Ɂu�����ɖ�����w���l��̖Y�N��i1984�N12��9���A�����E���k��j�ł̃X�s�[�`�̘^��������̂ŁA�����̃e�[�v����N�����Ă݂悤�B�^�i��҂́u�����͖��厍�l��̂��߂킴�킴�����ł��������܂��āA���肪�Ƃ��������܂����B����ł����q�̌��Ƃ������ƂŁA����k�N�v�l�搶�Ƌg��������ɂЂƂ��Ƃ����肢���܂��v�̌���̂��ƁA����Ō}����ꂽ�g���͈ꕪ�O�Z�b�قǃX�s�[�`�����Ă���v�Ƃ���܂��ɂ��̓��A���߂Ă��ڂɂ��������ɏ������Ă��������ׂ����Q�����̂��A�{���������B���͑��Ƙ_�������A�|���l�[�����������A�l�����@���ɂ��傢�ɊS������������A�����͌������Ƃ��ēǂ悤�Ɏv���B����{�����ēǂ��āA�u�l�����@�������O�\�N�̉ʎ��v�i�ѕ��j�ł���̂͂܂�����Ȃ����̂́A���l�E����N�v�̍�i�Ƃ����v����[�������B���сq���̊C�ӂŁr�i���W�s���҂����̌Q���镗�i�t�ł́u�\�\���܈�l�̎��҂̂��߂Ɂv�������莫���u�\�\Gerard de Nerval�Ɂv�Ƃ��������ɉ��߂�ꂽ�j�������Ƃ��Čf�����Ă���A�������猤�����Ƃ͔����ɒ��q���قȂ��Ă���B���҂��u�ԊO�̏́v�ƌĂсA�u�l�����@���ƃ��t�J�f�B�I�E�n�[���Ƃ̊Ԃ̈����b�������Ԃ��v�i�{���A��Z��y�[�W�j���q16�\�\���_�̓��ɂār�̏͂́A����܂ł̊e�͂𒆋�Ɉ��������Ă���b�̂悤�ŁA�Ƃ�킯�S�ɟ��݂��B�������́A�{���̕ʂ̈�߂ɜɂ����B
�܂��A�i�E�Z�k���G�쐻�̏ڂ����w�l�����@�������x�i���܋�j�ł��A���̎��k�q�V�������Z���̖��z�r�l�̏��o���A�k�c�c�l�ꔪ�l���k�c�c�l�Ƃ��Ă���A���̌�A��\�N���Ƃɏo������́w���x�ɂ����Ă��A���̓_�̒����͂Ȃ���Ă��Ȃ��B�������Ȃ���A���łɖ{���̂Q�͂Ŏw�E���Ă������悤�ɁA�ꔪ�l���͌��ŁA�ꔪ�l��[�A�A]�Ƃ���̂����������Ƃ��A�������͌�������̃R�s�[�Ŋm�F���Ă���B�k�c�c�l�s�V�����̏ꍇ���A�����������œ��t����ɂ��������̂�����A������i�߂č����}���قɂ��錻���ɓ����Ă݂�悩�����̂ɂƎv���B�i�{���A��O�Z�`��O��y�[�W�j
�{���̎d�l�͈ꔪ��~��O�Z�~�����[�g���E�O�Z�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�W���P�b�g�E�\���i�\���Ӂj�B�ʒ��{���̂��ƂɁA�i�_�[���B�e�̎ʐ^�����ɋN�������l�����@���̏ё������G�Ƃ��Ĕz����Ă��āA�тƓ��������F�ŃW���P�b�g�ɍ���ꂽ�����̏ё��i�l�����@���ɂ�鉔�M�f�b�T���q�A�V�[�k�r�j�Ƒ��Ȃ��Ă���B�����ɂ́q�l�����@�����N���r�q�l�����@���W�M���������r�q��v�l�����Ԉꗗ�r�܂ł����āA�������Ƃ��Ă���R���Ȃ��B
�q���Ƃ����r�ɋg�����̖��͌����Ȃ����A������Ҏ҂̈�l�ł���s�l�����@���S�W�k�S3���l�t�i�}�����[�A1975�`76�j�̊��s���g�����㉟���������Ƃ������āA�{���̑������˗������̂ł͂���܂����i�s�l�����@���S�W�t�̑����͓n�ӈ�v�j�B�s�l�����@���o���t�́A�J���o�X�n�̃N���X�i���̐F�����́A���ւ���������}���̑S�W�ł��A�l�����@�����b���ł͂Ȃ��A�g�������������Z�{�{�V�����̍��������Ă���j�̂�������Ƃ����A�܂��ƂɍD�܂��������ł���B

����N�v�s�l�����@���o���t�i�Ԑ_�ЁA1984�N10��25���j�̔��ƃW���P�b�g�ƕ\��
���萴��Y�i1900�`1986�j�ɂ͍����A�ȕւȎ��W���������炸�A������x�܂Ƃ߂č�i��ǂ����Ƃ���ƁA�g���������������s���萴��Y���W�t �i�v���ЁA1970�N7��1���j������ɗ��邵���Ȃ��悤���B�����Œm���鉪�肾���A�������W�s�l���V�s�t�̒Z�����������B
���ʁb���萴��Y���ʂ���[��]��g�����
�w�̌҂Œ����C�₷��B
�s���萴��Y���W�t�̎d�l�͓��Z�~��܁Z�~�����[�g���E�l�Z�Z�y�[�W�E�㐻�p�\���i�w�v�E�����j�E�\���E�i�{�[�����i�\���Ӂj�A����700���L�ԁB�\���┟�Ɍ�����J�b�g�̊G���́A���W�s���K�N�فt�́q��c�~�r�̈�߁u����郁�W���E�T�ł����t�Ă͂Ɓ^���̗��l�߂͜�[����]�邨���鋎�N�̑p[�����ނ�]���̂����Ă���܂����@�͂��Ă��Ăǂ�Ȃ��̂ł����ˁB�v�i�s���萴��Y���W�t�A�O�Z�y�[�W�j����̂������̂�������Ȃ��B�{���Ɏ��^����Ă���͎̂���12���W�ł���B
�� ���A���҂́q��L�A�o���r�ɋ�����ꂽ���W�͏�L�̎��^��i�Ɠ���ł͂Ȃ��A�������W�s�V�A�O���̐a�m�t�Ɏn�܂�ŐV���W�s�×d�t�i�������X�A1969�j �Ɏ���30���ɋy�ԁB���Ȃ킿�s���萴��Y���W�t�͐�O�̖������W�𐔑����܂ށA�I���W�������̂ł���B1970�N�̎��_��30�^�C�g���Ƃ͂Ȃ�Ƃ����Y �Ȏ��l�����A�f��ɂ͑S5���E3000�y�[�W�ɂȂ�Ȃ�Ƃ���s���萴��Y�S���W�t�i���ώɁA1987�`1989�j���o�Ă���̂�����A�����ɂ͂������ ���B�g���������萴��Y�̎����ǂ��ǂ��m�邷�ׂ��Ȃ��͎̂c�O���Ǝv���Ă�����A�����́q���ȏW�r�ɋM�d�ȏ،����������B
�@����l�̎��͐�O���爤�ǂ��A�w�l���V�s�x����قƂ�ǂ̎��W�������Ă���܂��B���̑S���W�i�w���萴��Y���W�x�̂��ƁE�ҏW �����j�ɂ���āA����l�� ���̂悳���A�L���Ⴂ�l�X�ɂ��킩��悤�Ɋ肤���̂ł��B�o�ŎЂ̎藎�ŁA�����̖�������҂Ƃ��ĂȂ��̂��A�c�O�ł��B�悢�L�O�Ȃ̂ɁB�i�s���萴��Y�S ���W�k��5���l�t�A���ώɁA1989�N7��1���A�������y�[�W�j
�����A�s���萴��Y���W�t�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ��̂ł���B�Ƃ���ŁA�E�F�u�y�[�W�q�ʉp�����X �m���r�� �g��������Ɉ��Ă��������̎��W�s�m���t���f�ڂ���Ă���i���i��130,000�~�j�B���t�̋L�ڂ͂Ȃ����A���Ԃ��̕M�Ղ����邩����A���s���ĊԂ��Ȃ� ���{�Ǝv�����B�g���͎����Ă̍Ō�̃n�K�L�Ɂu���萴��Y�̎����u�ߑ㎍�v�̏��a�O�\�l�A�ܔN�Ɏ��\���Ă��܂��v�i1990�N4��17���t�j�Ə��� �Ă���A����q��ȁr�i�������сE8�j�̑��݂͋L���ɂ������i���o�s�ߑ㎍�t27���̖����u���ܔ��E���E�l�v�̔N�́A�z�q�v�l�ɂ��u���܋�v�� ���j�B������{���̑����̂��Ƃ��l����ƁA���萴��Y�͋g�������h�����鎍�l�̈�l�������Ǝv����B

�s���萴��Y���W�t�i�v���ЁA1970�N7��1���j�̔��ƕ\��
�g�����͎��W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j�ő�7�����܂���܂����B���̂��߂����ł͂Ȃ����낤���A�����H�q�ɂ��s���t���t��Ɂu���̂قǁu�������܁v���v���Ђ̎�𗣂�ĂЂƂ���������邱�ƂɂȂ����̂������ɁA���������w�U����̉��Ƃ��āA�����̂悤�ȏ����q�u���v��n���������܂����v�Ƃ����13��̓����܂����m����s���\�\���������w�U������t�n�����i���������w�U����A1983�N3��10���j�̕\����S�����Ă���B
 �@
�@
�s���\�\���������w�U������tVol.�T�i���������w�U����A1983�N3��10���j�̕\��
�n�����̎d�l�͂`�T���E�l�Z�y�[�W�E���Ԃ��B�\���͑S�ʎʐ^�ŁA�������k�L�B����͔w�オ�����Ƃ�ł��邽�ߓǂ݂ɂ����B�ڎ����ڂƃN���W�b�g�i�����A�k��y�[�W�l�j�������B
��13��u�������܁v����
����W�w���҂����̌Q���镗�i�x���
����N�v�@��܂̌��t
�\�\�I�]�\�\
�@�g�����@���֊�]�����Ă��c�c�^�������@�L�`�Ȏ��̐��E
�@�c��m�@���Ȃ�Ԃ��́^�g�������@���̂����炵���F��
�@���J�열���@�����͐V�������ł����剪�M�@�������^��������
�\�\�����܂̎��l�����\�\
�g�������@����ȊC�ǂɌ����ĕ����čs����
�O�ؑ�@���͒ɂ��S�͌y��
���J�h�s�@��ȉו�
���]�r�v�@������E��
�g���K�q�@���Ɩ@���Ƃ��їl���c���@���ʁ\�\�Ǔ��E�h���ɒj
�����^��Y vs �����H�q�@�Βk�E���㎍�̖�������߂�
�����a�v�@�O���u���������ցv�̑O��
�@�U����j���[�X
�@�ҏW��L�\������@�g����
�ʐ^�\�\���E�{���\�@���g
�莚�\�����܂̎��l�����\�@�����^��Y
�q�U����j���[�X�r�Ɂu��\�O��̑I�l�������ĔC���ܔN�𗹂����g�������v�i�����A�O�܃y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�g���͂��̉���Ō��1979�N�̑�9��ȍ~���߂��I�l�ψ���ނ��Ă���B
���N�̑�14��́A�O�D�L��Y���W�s�Ă̕��t����܂����B�s���t��2���i1984�N3��5���j�ɂ͎ʐ^�E�莚�E�J�b�g�̃N���W�b�g�����Ȃ��āA�u�\������v�����ꂩ�킩��Ȃ��i�n��������ɁA�ҏW�����s�Ȃ����̂��낤���j�B���̍��́q�����܂̎��l�����r�͔ѓ��k��A�g�����A�����N����3�l�B�g�����M�́q�u��ܑO��v�̑z���o�r�́s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j�Ɏ��߂�ꂽ�B�g���̎ʐ^�i���}�Q�Ɓj���܂߁A���l�̏ё��͍��g�ɂ��B�肨�낵�ŁA���Ԏ���́q�ҏW��L�r���B�e�̗l�q��`���Ă���B
����A�g�������́u�ʐ^�͂�����}�B���炭�l�������Ă�v�B����͂قƂ�ǎB�e���ۂɋ߂����B�O������A�u���Ȃ������̔M�ӂɕ������v�Ǝp�����킵�Ă����������g������A�����Ȃ�����ǂ��ɂł������A�ǂ��ł�������B������������������J�����̑O�ɐg�����炷�̂́A�����炭���ꂪ�Ōゾ�v�ƁB�l���݂�D������̂ڂ�A�I���͊ՐÂȌ����̃x���`�B�ʂꂬ��A���l�́u���͓�v�̌��t���̂����A�q����Ɠ�Ƃɐg���܂����r�邩�̂悤�ɁA�ӂ����ѓs�s�̎G���̂Ȃ��Ɂc�c�B�i�����A�l�Z�y�[�W�j
���̂Ƃ��B�e�����ʐ^���A�s���㎍�蒟�t1990�N7�����q���W �Ǔ��A�g�����r�́q�g�����A�a�J���s���r�Ƃ���6�_�̎ʐ^���琬��y�[�W�ɂȂ����悤���B���̍ŏ���1�_�́s���t�Ɠ����J�b�g�ŁA�u�@������u�g�b�v�v���̏��H�v�i�����A�k��Z�y�[�W�l�j�Ƃ����L���v�V�������t���Ă���B
 �@
�@
�s���\�\���������w�U������tVol.�U�i���������w�U����A1984�N3��5���j�̕\���i���j�Ɠ��E���ʁi�E�j
�Ƃ���ŋg�����́A���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j���������Ɍ��悵�Ă���i�����͌��݁A���{�ߑ㕶�w�ُ����j�B���������g���ɂ��ď��������͂ōł��d�v�Ȃ��̂́q���Ɋւ��郁���r�i�s���{�E�t1959�N11�����j�ŁA����͂����n�܂��Ă���i�����͐V���ɓ��ꂵ���j�B
�@�u�����C�J�v�̈ɒB���v�ɉ�Ď����A�����߂��܂������W��ǂ݂����������Ȃ����Ɩ₤����A�g�����́u�m���v�������߂�ꂽ�̂́A���N�̂͂��߂̂��Ƃł����B���͂����ǂ�ł݂��B����͂܂��Ƃɂ߂��܂������W�ł����B���ɂƂĂ��̎��W��m�����Ƃ́A�߂��܂����̌��ł����B�i�����A���l�y�[�W�j�������́u�߂��܂����v����悤���`����Ă���B�g�����s�T�t�����E�݁t�Ŏ�܂��Ė{�]�������낤�B�u�\�\�����I�l��Łw�T�t�����E�݁x�ɍ������܂������悤�Ƃ������ƂɂȂ�����A��낱��ł������B�����Ď��͍���������h�����Ă��邵�A�����܂̑I�l�ψ����M�����Ă邩��A���ނȂ�ĂƂ�ł��Ȃ��v�i�s���tVol.21�A2003�A�O�O�y�[�W�j�Ə��c�v�Y���g���̑Ή��������Ă���B
�� �蕶�Y���W�s�K���X�̋��t�i�������[�A1983�N7��15���j�́A�����I�ɂ͍ŏ��̎��W�ł���s��蕶�Y���W�t�i�v���ЁA1975�j�ȍ~�̎��Z���т����� ��B�u������鋫�̕��Ɨ��l�W���Ŏ������^���q���̒|���������̊D�ɂ������Ă������߂������v�Ǝn�܂鐏�z���́q���Ɨ��l�W���r�̂悤�Ȏ����� �Ă��������A�K�������{���W�̓����I�ȍ앗�łȂ����߁A�����ł͋g�����Ƃ̊֘A�Ŏ��̓�т��������B
�m�[�x���܍�Ɓb��蕶�Y�O�l��n�̋߂��̃��X�g������
�ЂƂ�R�[�q�[������
���������ꂽ�e�[�u����
�������O�l�H����������
���̈�l��
���̐��Ȃ�ʔ������Ɏ䂩�ꂽ
���ʂ܂Ŕ������������Â����m�[�x���܍�Ƃ��ӂƎv����
�l�Ԃ̔߂���
�̂悤�Ȃ��̂��S�ɂӂꂽ
���ꂩ��u�������
�C�ɋ߂���ʂ�������
�����Ȃ�Ԍ�������
�h�C�c�I�ȑ������Ɛ[���݂�
�C�����������������
�����z�e����ʂ肷���Ă���
�`�ɉ����������ɓ�����
�g�~��ɋ����ȑD���悱������Ă���
���܂ɂ����t����悤�ȋC������
�u�i���̗��l�͋A�炸�v
�V���l�̎��傪�������ďo��
�ʂɈӖ��͂Ȃ��\�\
���邭�����ӂ���
�g�����ƃK�X���̊X�̕����������q�����\�\���b��蕶�Y
�����@���Ƃ���
�������Ȑl�Q�ꂾ�낤
�V�v�w������
���l���m������
�q���Â�̈�Ƃ�����g������
�݂�ȁ@���܂���
�~�т�����������Ă���
�A�����[�E���\�[�̊G�̂悤��
��l���q����
���݂�悤��
���ǂ��Ȃ�������Ă���
���������̂悤��
�����Ƃ�Ɨ����������i�ł�����
�q�m�[
�x���܍�Ɓr�́u�i���̗��l�͋A�炸�v�͌����܂ł��Ȃ����e���O�Y�̎���B�u���ʂ܂Ŕ������������Â����m�[�x���܍�Ɓv�͐�[�N���ȊO�A�l������
���B�����w�҂Ƃ��Ă��m��ꂽ��莁��1991�N�ɖS���Ȃ������A�{�����t�L�ڂ̌��Z���͉��l�s��q��c�ƂȂ��Ă���B�O�l��n��R�������͎��̃z�[���O
���E���h�������낤�B�q���q�����r�̐������т��іK�ꂽ�̂��낤���B��莁�̕M�ɂ�����ƁA���̒n���܂���㐟�v�ӂ��ٍ̈���ɖ������ꏊ�ƂȂ�B
���Ȃ݂ɁA�g������1949�N1��30���A�~
�̐���s���Ă���B
1983�N5���̓��t�����q���Ƃ����r�́u�I��ɂȂ������A�{�W���s�ɓ������z��Ղ���������Y������ё���̘J���̂�ꂽ�g�������ɑ��āA�[��
���ӂ��鎟��ł���B�v�ƌ���Ă���B�{���̎d�l�́A���Z�~��l���~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�N���X���E�\���B���E�\���̋��̃J�b�g���s���ؒ��h���W�\�\1960�`1982�t�i����R�c�A1982�j�̃J�b�g���v�킹��B
���̒��Җ����B���̂����������߂��낤���A�т̕�����⋷���悤�Ɋ�����B�ѕ��u�Ǎ��̊w�������҂̌������[�������ɗN���o�Â鐴�w�̝R��B���܁A����
����P�����I��Ԃ���������ׂ̂�B�v�̖`���ꎚ�����ɂ���a�����o����B�����͂ǂ��������ēV�c�L���낤�B���Ԃ��̗p���͎��W�s���[���h���b�v�t�i����
�R�c�A1988�j�Ɠ��������A�V�}���̌Ð��i�������җʂ̓��������N���̎l�Z�q100�r�j�B�g���̓����ށi���݂͔p�i�j�ւ̈����̂قǂ��Â���B

��蕶�Y���W�s�K���X�̋��t�i�������[�A1983�N7��15���j�̔��ƕ\��
�N ���N�n�͉���ɍs�����Ƃ��܂܂Ȃ炸�A�����ɓ����ă~�J���ł��ނ��Ȃ���A�푺�G�O�s���{���V�L�t�i�}�����[�A1989�N6��20���j���J���B�ѕ��ɞH ���u�]�˂Ƃ��܁@���݂ɋ삯��@���w�ҁ^���䂯�@����Ƃ���Ɂ@��k����^���ɐ����@���̍��ɗU���@�������v�B�ڎ����������B
��@�����������܂���q���n�߂���K�����r�̏I���߂��Ɂu���̖�͗��ÂɈꔑ�A�����͐V���A�������o�āA�����Ɍ��������B��H��敂͂����́A���܂͌����ɂȂ��Ă����ڊ�[�� �䂤����]���̏h�ʼn��������������܂��������̂������B�����V�c�����@���������Ƃ������B�������獲�n�̐Ԕ��܂ł̏\�ꗢ���B���̎�Ɏ��悤�Ɍ������ ���̓��͐���悢�ł�����ł����v�i�{���A����y�[�W�j�Ƃ���̂��������i���͂��̐Ԕ��̎Y�Ȃ̂ł���j�B�{����ǂ݂Ȃ���A���s�ɐ旧���̔N�̏t�A�g �������O��̍��n��K�ꂽ���Ƃ��v���o�����B
��@�H�t�H�C�܂��ꗷ
�O�@�k�����킢���݂̂���
�l�@���n�߂���K����
�܁@�Ό���R������������
�Z�@���|�l���k�F�C��
���@���C�������������L
���@�G�L�]�e�B�b�N���˓��C�I�s
��@�ɓ���������Y���L
�\�@�R�A�������z�Ƃ�
�\��@�ʕ�͐Q�đ҂ĉ��B����L
�\��@�F����������������
�\�O�@�]�˂̓��䂫�����������

�푺�G�O�s���{���V�L�t�i�}�����[�A1989�N6��20���j�̖{���ƃW���P�b�g
�g ���������̎l���c���F�s�M��Ɠ]���t�i�V���ЁA1987�N8��20���j�͒��т̒��㌒���_�ł���A�l���c���̍ŏ��̕��|��]���ł���B���s��9�N��A���� �����Łs�M��Ɠ]���E���㌒���t�i�V���ЁA1996�N8��30���j���o�Ă���A���̊Ԃ̎���҂́q��������łւ̏��r�ł��������B�u�{���́A��㔪�� �N�����ɐV���Ђ�芧�s���ꂽ�w�M��Ɠ]���x�ɁA�V���ɑ�͌㔼�ȉ����܂ł������A�{���A���A�����̑S�̂ɂ킽���ĉ������{���A�薼�����炽�߂����� �ł���B��s���鏑���Ɩ{���̊Ԃɂ́A��̏o�����A���Ȃ킿��ƒ��㌒���̚�܂Ƃ��̌l�S�W�̊�������������Ă���v�i�s�M��Ɠ]���E���㌒���t�A�k��y�[�W�l�j�B�s�M��Ɠ]���E���㌒���t�͏����́s�M��Ɠ]���t��啝�ɑ��₵�Ă���A�s�M��Ɠ]���E���㌒���k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2001�j�ɂ������ẮA�g�̍ق��قȂ�Ƃ͂����A�����̂قڔ{�ɋ߂��y�[�W���ɂȂ��Ă���B
���㌒���͑S�̂��\�����Ȃ��B�����A���x�̕������ڂ�����̉ߏ肾����M���Ă���B������A�_�u�����ɏZ�܂��A�T�Ȏs������ ��f�`����Z�҂Ɏn�܂� �āA�w�����V�[�Y�x�ւƕs�t�I�ȕϗe���Ƃ����W�F�C���Y�E�W���C�X�B���邢�́A���ȃ~���[�W�J���̏��ȁw�}�C�E�t�F�C���@���b�g�E�V���O�X�x��f�� �ɁA���t�̂��т��Ƃɍی��̂Ȃ��ĉ��߂������A���ɂ͌��Ȃ̐��\�{�̎��Ԃ������������s�ׂ��s�Ȃ��ɂ��������W�����E�R���g���[���B�w���̗́x�Ɏ��^�� �ꂽ�G�b�Z�C�̂Ȃ��ŁA���オ���҂��ׂĂ��邱�Ƃ͋����[���B����Ƃ͐���[�����f�B]�Ɏ��Ă���B�������тƂȂ��������A���߂ɉ��߂��d�˂āA�܂��� ���ʂ̍�i��n�����邱�Ƃ����Ȃ̂��B�i�s�M��Ɠ]���t�A��܁Z�`��܈�y�[�W�j
�f ���Ƃ���ɐ��m�ɑΉ������̐����B���ꂪ�l���c��]�̍ő�̖��͂ł���B���͎l���c���́q�����̊L�ƊO���̑܁\�\�g�����̊C�m�����w�r�i�s���㎍�� ���t1980�N10�����k���W�E�g�����l�j��ǂƂ��̏Ռ����Y����Ȃ��B�g�����͎l���c���́q�g�c�����ւ̎莆�\�\����̓�k�ɂ��ār�́u������ �͐��ނ��A���҂ɂ�����Ȃ��ߕt�����ƂŁA�������������Ƃ�̂��낤���v�i�l���c���F�s�N�w���ȁt�A�N�w���[�A1987�N4��20���A�Z�܃y�[�W�j�� �����͋傩�瓾��
�u�����҂͐��サ
�@���҂ɂ�����Ȃ��ߕt���v
�� ����������q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�ɏ����Ƃǂ߂Ă���B�{���̎d�l�͈���~��O��~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B��g�~ �Y�̑���́A�\���ƃW���P�b�g�̕\�P���߂��A�{���ƃW���P�b�g�̕\�S���g�t�����`�[�t�ɂ������́B��������Łi�����͐V���Б��ꎺ�j�ƕ��ɔŁi�W���P�b�g �f�U�C���͉��������Y�j�̐}�ł́A�^�C�̕������@ Wat Khongkharam �̕lj�ŁA���̗̍p�͎l���c������������ł�ʂ̐V���������Ƃ��Đ��ɑ��肾�����Ƃ������Ƃ̏ł���B
![�l���c���F�s�M��Ɠ]���t�i�V���ЁA1987�N8��20���j�Ɓs�M��Ɠ]���E���㌒���t�i���A1996�N8��30���j�A�s���k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2001�N7��10���j�̃W���P�b�g](image/kishutotensei.jpg)
�l���c���F�s�M��Ɠ]���t�i�V���ЁA1987�N8��20���j�Ɓs�M��Ɠ]���E���㌒���t�i���A1996�N8��30���j�A�s���k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2001�N7��10���j�̃W���P�b�g
�k2009�N3��31���NjL�l
�l���c���F�s�Z�k�l���c�\�\The Greatest Hits of Yomota
Inuhiko�t�i�ʗ��ЁA2009�N2��10���j�̒��҂ɂ�鏑�����낵�̃R�����g�Ɂu���㌒���ɂ��Ĉ�N�Ɉ�͂��A����S���̍�Ƙ_�����M����B
�k�c�c�l�����ň�㔪�O�N���甭�\���Ă�������_��Z�߂��̂��A�{���ł���B�������g��������ɂ��肢�����Ƃ���A��Ԏ��ň����Ă����������v
�i�q�m�M��Ɠ]���n�r�A�����A��l�`��܃y�[�W�j�A�u�\���ɂ̓^�C�̎��@�̕lj��p�����B�o���R�N�̏o�Ŏ҂ɋ����Ƃ낤�ƘA���������Ƃ���A�����W��
�����Ȃ�g�p���͂���Ȃ��ƁA�C�O�̂����Ԏ����߂��Ă����v�i�q�m�M��Ɠ]���E���㌒���n�r�A���O�A��l��y�[�W�j�Ƃ���B�s�Z�k�l���c�t�́A�l���c����
100���߂̒����Ƃ��Ă���܂ł�99���̖���ʂ�����I�т������u�|�[�^�u���E�����^�v�����A�����ɏ�f�u���㌒���͑S�̂��\�����Ȃ��B�k�c�c�l������
�тƂȂ��������A���߂ɉ��߂��d�˂āA�܂������ʂ̍�i��n�����邱�Ƃ����Ȃ̂��v���܂ވ�߂����^����Ă����̂ɂ́A�킪�ӂ��z���������B
�� ��Y��Y�E���Ò��v�E���|���L�́s�a��Ɗ���̂������\�\�@�_�S�C��ǁt�i�}�����[�A1985�N6��10���j�͓C�k�Ƃ����`���Ȃ���A�@�_�i1421 -1502�j�̏i�����̏n��j���߂����发�̎����B�u�@�_���ƋႵ���i����j�܍��݂̘A�̕S�C���A�A�̖̂ʔ����𖡂킢�Ȃ���ǂށB�a �������ɒu��������|��ҏ@�_�̑�������̒��ɒ��߁A�a��Ɗ���̊W���l����v�i�ѕ��j�B�{���̖ڎ��������Ă������B
�u�a
�̂ł͂Ƃ��Ɋ��ꂪ��������A�m�������A�̂���܂Ƃ��Ƃʼnr�ނƂ����a�̂̓`�����������ł�����̂ł�����A�����Ŋ�����g���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ́A��
���ɊO���̍����ł�����ǂ��A���̊O���̍����������Ă���Ă݂�Ƃ����Ƃ���ɁA�V�тƂ��Ă̘A�́A�o�~�Ƃ��Ă̘A�̂�����v�i���|���L�̔����A�����A��
�y�[�W�j�Ƃ���������A����ɂ�����g�����̊���ɑ���p���Əd�Ȃ���̂�����i�q��́r�̎���u�a�H����v�ɐG�ꂽ�q�킽���̍쎍�@�H�r��z�N��
��j�B
���|���́q���Ƃ����r�ɂ́u�I�n�A��c�ɗ��������A�X�����ĉ��������ҏW���̔����������A������q���A�j�����厁�k�c�c�l�v�i�����A�O�y�[�W�j�ƌ�
���A�g���ɂ͂����̕ҏW�҂��瑕���̈˗����������̂��낤�i�̂��ɒ}�����[�̎В��߂邱�ƂɂȂ锐�����́A�o�q���s�����܁t�̕ҏW������A�ҏW��L�Łs�g�����S���W�t�̉���ɐG��Ă���j�B
�s�a��Ɗ���̂������t�̎d�l�͈ꔪ��~����~�����[�g���E�O�Z�Z�y�[�W�E�㐻�z���E�W���P�b�g�B�W���P�b�g�Ɩ{���̃��B�W���A�����ʐ^�łȂ̂́A�g��
�̑����ł͂�肠���������B�\���̂����̕z�n�Ƌ�̔������́A�����}�����[�̃V���[�Y�q���{���l�I�r�ɂ悭���Ă���i�����Ƃ��q���{���l�I�r���g��
�̑����ł���m�͂Ȃ��j�B�\���������сE�W���P�b�g�E���Ԃ��E�{���̗���́A�̂����J�c�����s��
�z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�N4��25���j���v�킹����̂�����B�����̕ҏW�E����̎����́s�a��Ɗ���̂������t�̏j�������S������
����B

����Y��Y�E���Ò��v�E���|���L�s�a��Ɗ���̂������\�\�@�_�S�C��ǁt�i�}�����[�A1985�N6��10���j�̖{��
�ƃW���P�b�g
�g
�����͉��_���S���W�̑��������Ă���i�s������s���W�t�A�s��{�߉ϑ��Y���W�t�Ȃǂ��v�������ԁj�B�s�V�V�ޓ�Y���W�t�i�y�ЁA1972�N2��5���j��
���̈���ŁA�q�������� 1950�`1956�r�q���� 1956�`1957�r�q������� 1957�`1959�r�q���̉�
1959�`1961�r�q�钆���璩�܂� 1961�`1962�r�q���ԍ��� 1962�`1965�r�q���Ɩ��
1966�`1969�r�����߂��܈�l�y�[�W�̃t�����X���͑s�ςƂ����Ă����B�O��Љ���q���{��
�i�_�r�V���[�Y��
�t�����X�����A�\���p���̔w�ɂȂ镔���̓V�ƒn�ɐ肱�݂���ꂽ�����O���V���|�������Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�{���͐肱�݂���ꂸ�ɃO���V�����|���Ă�
��B�܂肩�������\���̏������������Ԃ��ɔ킹�Ă���̂ŁA�\���ƌ��Ԃ��̂Ȃ��݂͂悢�B�{���ƕ\���̔w�ł̐ڒ����A������~�����[�g�����邽�߁A��
�����͂Ȃ��B�J�肩�����ǂނƔw�̒��p���ۂ���Ȃ��͔̂@���Ƃ������������B�d�l�͓��Z�~��l��~�����[�g���̂`�T�ό^���E�@�B���i���n�̂܂܂̊D�F
�̃{�[��������ۓI���j�B
�g�����͈��Z���N�A�剪�M�E���J�열���E������s�E���c�O�Ƃ̍������W�s����
����n�R�t��
���т����^����ɍۂ��āA��i�̑I���V�V�ޓ�Y�Ɉς˂Ă���B�g���́q��������r�́u���͉ߋ���\�N�ԂɎl���̎��W�����s�����B����������Ȃ̑I����
�����̂ł���B����ǁA���̐M������Ⴋ�F�E�V��ޓ�Y���S�����߂ĕ҂�ł��ꂽ�B���сq�m���r�Ɓq�����r�����邱�Ƃ��B��̒����ł���B�ʂ��Ă���
�Ȃ��i���̂��A�����Ȃ�z������݂�̂��A�킩��Ȃ��B�V�N�ȕs���Ƃ��̂��݂�����v�i�s���㎍��n�R�t�A�v���ЁA1967�N3��1���A���l�y�[
�W�j�Ƃ����̂��S���ł���B����������Ɓs�V�V�ޓ�Y���W�t�̑����́A���̂Ƃ��̕ԗ炩������Ȃ��B
�{������u�����ĂɁv�ƌ����̂���q�P�Â����r�i���W�s���Ɩ�� 1965-1969�t�����j���������B
�܂����낯�P�̐l�ʂ�邬
�~�肿��ǂɃJ�M�����̂���������
����̌��t�͂Ƃ���ɂƂ���
��邷�ȕP��@�w�x��ɂ킪�w���Ƃ��点
���Ђ��ЂƂ����鐅���킹��
���߂͂Ƃђ��˂�`�Ȃ����̋Ɉ�
���߂͋@���`������ɒ��˂܂���
�����ɂ͐A���̂���[�A�A]����ǂ�
������̂ɉf�鉖�h��
������̂Ă���[���邵]�Ȃɂ���P�Ԃ��͒��̂ЂƑ���
���ꂭ�炢�C�̂������z�����߂�
���ɂ���Ⴙ��āI
�����G�点�ʔ��w������[�A�A�A]
�c�o���̂Ȃ܂���n������
�ׂ�����ʂ������ĕ�������
���炪�P�̍g�����n�ɂ�
���ǂ��̖A���u�c�u�c�e����
�������������N����ē�
�䂤�ꂢ��[����]���߂��I�@������
���Ԃ��o�����ǂ��ʼn^�т܂���
�����ƌ�����������Ԃ��P���Ԃ�
��邷���邱�Ƃ̂Ȃ��ƋR�s�Ȃ��
�P���o�����͂����V�N�ł��炩���킢
���Ԃ��P�̉�����o���̓X�S�C�I
�킪��͂����Ă�����ގ�͂Ȃ��̂�
���݂����Ă��ĉf�鋾��
�����̏��b�t
�P�Ȃ�����C���t�̂��ݎ��
�P�b�̂Ȃ��玄�߂̌��t��
�L�^���������\����܂���
�����ŋ��������P���낵�|�Ђ��Ă͂Ă���͓��j�ł���������
�ЂƂ��̂Ȃ��E�l�̔��ь���
�����Ă������Ă����M�̂悤��
�h��Ď��߂͕P�̒�
�����Ȃ�Ύ��L���ĐQ��}�������l��
�Ȃ����ڃ^�C�c�̃Q�o���g�P��
���ׂĐH�����܂��P���Ԃ��
���߂͕P�ɂ����g�ł����
���ꂩ��ЂƂ�P�₮��̂Ă����
���čŏ��̉����������ЂƂ�����
���́q�P�Â����r��сA�����悤�Ȏ����̎��M�i���W�s���Ɩ�t�́q���ڂ������r�ł́A1966�N����69�N�ɂ����ĂƂ����킩��Ȃ��j�Ƃ������� �������āA�V�V�ޓ�Y�ɂ������q�� �����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�̂悤�Ɏv���邪�A���������낤���B

�s�V�V�ޓ�Y���W�t�i�y�ЁA1972�N2��5���j�̔��ƕ\��
�˖{�M�Y���S���Ȃ��āA�܂���ɂ����̂����I�̏W�s���́t�i�ԗj�ЁA1987�j�Ƌg���������́s�����\�\���������̂̔ߌ��t�i�����ЁA1981�j�������B�s�����t�̑����ɂ��ẮA�P�c���������Ƃɏڂ��������Ă���B
�@���̏���P�C���g��������́A�����Ђ��犧�s���ꂽ�t�����X���́q���{���i�_�r�V���[�Y�ł����ʓI�Ɏ��݂��Ă���B���̎茳�ɂ́A���̂Ȃ��̒˖{�M�Y���w�����x�i����N�j�����邪�A�O���͕ʎ��ɑ��Ӂi�����ł����ׂĖ��������́j�������Ă���A������A�\���A�w�A���\���Ƃ����Ń��x���\�肵�Ă���B���̑��ӂ̎l����A�����l�̗D���ȏ���P�C���₳�����͂�ł���B���ŁA�\���́A���������̏����ƒ��Җ��̂������ɁA��Z���`�قǂ̕��̎q�����P�C������A���̂Ȃ��𔒔����ŎO���̏b���ƐA�����l��g�ݍ��킹���������̓��قȊG�������߂Ă���B���̊G���͂��Ԃ��W����̂�ꂽ���̂ł��낤�B����P�C�́A����ɁA���ɂ����Ă��ʂ̐A�������`�[�t�Ƃ������̂������́w�����x���ނ悤�Ɏg���Ă���B���������Ə���P�C�ɂ��O�l�̕ϑt�����ɃG���K���g���B�i�s���ꎞ��t�A�����ЁA1999�N10��5���A�Z�l�`�Z�Z�y�[�W�j
����Ɂs�����t�����^�����s�˖{�M�Y�S�W ��\�O�� �]�_�Y�t�i��܂ɏ��[�A2001�N2��15���j�̖k���A�q�E�x�z�m��Y�q���r�́u���a�\�Z�i��㔪��j�N�\�\���@�����Ё@�l�Z���ό^�i�t�����X���j�@�\�����i�ѕ��j�@�S��\�l�Ł@����E�g�����@�艿�E��ܕS�~�@�{���g�E�O�\�����~�\�O�s�v�Ƃ����d�l�֘A�̋L�q��₦�A���Ƃ��Ă͂���ɉ����ď������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��i�T�C�Y�͈ꔪ���~���Z�~�����[�g���j�B�ȉ��ł͔����Ђ́q���{���i�_�r�V���[�Y�𑍗����悤�B���s���ɋ�����B
�@�ѓ��k��s�`���\�\���̔畆�̔j���Ƃ���t�i1981�N9��10���j
�A����p�v�s��n�\�\�I��Ȃ����҂̗��t�i1981�N10��8���j
�B�F�V���F�s��\�\���z�ƌ����̃��j�������g�t�i1981�N11��9���j
�C�˖{�M�Y�s�����\�\���������̂̔ߌ��t�i1981�N12��10���j
�D�r���I�s����\�\���̐_�̗����߂���t�i1982�N10��25���j
�E�ԍ]�e�s�C���\�\���̐��̖����̐^�G��t�i1983�N8��10���j
�F���J����s���\�\�������ɐ��ތ������t�i1984�N8��23���j
�G�F�씎�q�s�ǁ\�\���ŋ��E�l�����t�i1984�N9��25���j
�H��o���Z�s���\�\�͂邩�Ȃ��蕔�t�i1984�N11��22���j
�S9���̃��C���i�b�v���ŏ��́s�`���t���s�̎��_�Ŋm�肵�Ă������s�������A4���߂́s�����t�܂ł͑������s�Ƃ��Ĉ�A�̑������˗����ꂽ�ł��낤�B���҂̔ѓ��k��E����p�v�E�F�V���F�E�˖{�M�Y�́A��������g�����ɂƂ��ċ��m�̏�����A�Ƃ��������m�F�ł���B�����e���̑����̍��ق�������͂�����킩��̂��A�P�c���̌����\���́u���������̏����ƒ��Җ��̂������Ɂv����u��Z���`�قǂ̕��̎q�����P�C�v�߂�G���Ɣ��̏���P�C�̔z�F���B
![]() �@
�@
�ѓ��k��s�`���t�i1981�j �\���Ɣ��k������������l
 �@
�@
����p�v�s��n�t�i1981�j �\���Ɣ��k������������l
 �@
�@
�F�V���F�s��t�i1981�j �\���Ɣ��k������������l
![]() �@
�@
�˖{�M�Y�s�����t�i1981�j �\���Ɣ��k������������l
![]() �@
�@
�r���I�s����t�i1982�j �\���Ɣ��k������������l
![]() �@
�@![�ԍ]�e�s�C���t�i1983�j ���k�����l](image/akae_t.jpg)
�ԍ]�e�s�C���t�i1983�j �\���Ɣ��k������������l
 �@
�@
���J����s���t�i1984�j �\���Ɣ��k������������l
 �@
�@
�F�씎�q�s�ǁt�i1984�j �\���Ɣ��k������������l
![]() �@
�@
��o���Z�s���t�i1984�j �\���Ɣ��k������������l
���̃t�����X�������A�g�����Ȃ�����𑽗p�����̂��m���邱�Ƃ͂킩��Ȃ��B�����Ƃ��q���{���i�_�r�V���[�Y�Ō��̔����Ђ͐l���m��t�����X��E�t�����X���w�̐��o�ŎЂ�����A�ҏW�S���̘a�C�����g���Ɂu�����̓t�����X���Łc�c�v�ƈ˗��������Ƃ͑傢�ɂ��肤��B�g�����Ɩ��ő��������}�����[�̏o�ŕ��͑S�W��p���������A�㐻�E�۔w�̃n�[�h�J���@�[���嗬�������B�ӂ��㐻�{�̎w��ɂ͑����{���쐻�����蔓�����̑f�ނ�����������ƁA�{���̎w��Ƃ͕ʗl�̍�Ƃ�����K�v�����邪�A�t�����X���Ȃ玆�Ɖ��M��������ł���B�{���A�O�����̖{����Ƃ��Ĉ������Ƃ��ł��A���ۂɎg�p����\���̎�������ł���A�����܂��ă_�~�[������̂��B���W�ȂǁA��r�I�y�[�W���̏��Ȃ��{�ɗp������̂��t�����X���̓����ł���B�q���{���i�_�r�V���[�Y�S9���̃y�[�W���͕���184�y�[�W�i11.5��j�ŁA�t�����X���Ƃ��Ă͑��̂��镔�ނ����A����قǖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B��_��������A�{���ƕ\�����w�ŌЂÂ�����Ă�����̂́A���߂̌��Ԃ��ɔ킹�����߂̕\���i�{�����ɐ܂����\���͓V�ƒn�̔w���肬��ɐ肱�݂�����A�{���J���邽�тɌ��Ԃ����X���C�h����j�̂Ȃ��݂������A�\�����J���߂�������ƌ��ɖ߂�Ȃ��Ȃ邱�Ƃł���B�������{�ł͂܂��Ȃ����A�����\���ƌ������Ԃ��̑g�݂��킹�̂ق����������ɏ���i�\���̂ق����X���C�h����j�B������ɂ��Ă��ϋv���ɗD�ꂽ�l���łȂ����߁A�J�肩�����Ђ��Ƃ������ɂ͓K���Ȃ��B�\���S�ʂɃO���V����킹�Ă��̂܂ܐ܂����͂̌ЂÂ��Ȃlj��n�������Ė{���̔w�ɐڒ�����ƁA�O���V������Ă��镪�����V��n�̐ڍ��������キ�Ȃ�̂����ł���B�ނ��q���{���i�_�r�V���[�Y�ɃO���V���͓\���Ă��Ȃ��B
�k2005�N9��30���NjL�l
�s�o�Ń_�C�W�F�X�g�t��1177���i�o�ň���o�Ń_�C�W�F�X�g�ЁA1986�N9��11���j�́s�����Ђ̖{�I�t�́q�c�ƕ������r�Ɂi�r�j�Ƃ��������ł���ȋL�����������B�u�����ꂽ�͂��̑q�ɂ̒��Ŗ��ɋC�ɂ�����Ƃ������A���������ȋz���͂�Y��킹�Ă���{���A����B�w���{���i�_�x�V���[�Y�Ȃǂ͂��̍ł�����̂��B�k�c�c�l�����B�X���鎷�M�w�B�w��n�x�w���x�Ƃ��������z�̂Ȃ��^�C�g���B�����k��l�����n���ȑ����B�܂������ɂȂ��Ă��Ȃ����́A�����܂ł̐��������Ŋ�قȈ�ۂ�������邾�낤�B�����ЂƂςȓ���������B�T�u�^�C�g�����₽��ɋÂ��Ă���̂��B�ЂƂ����Љ��Ɓv�i�����A�Z�y�[�W�j�ƁA��ɋ������Ă���̂��˖{�M�Y�́s�����t�ł���B����ɂ��Ă��u���������ȋz���͂�Y��킹�Ă���{�v�Ƃ����]�́A�g������傢�Ɋ�������Ƃ��낤�B
![�����Ђ́q���{���i�_�r�V���[�Y�E�S9���̔��B�ѓ��k��s�`���\�\���̔畆�̔j���Ƃ���t�i1981�N9��10���j�A����p�v�s��n�\�\�I��Ȃ����҂̗��t�i1981�N10��8���j�A�F�V���F�s��\�\���z�ƌ����̃��j�������g�t�i1981�N11��9���j�A�˖{�M�Y�s�����\�\���������̂̔ߌ��t�i1981�N12��10���j�A�r���I�s����\�\ ���̐_�̗����߂���t�i1982�N10��25���j�A�ԍ]�e�s�C���\�\���̐��̖����̐^�G��t�i1983�N8��10���j�A���J����s���\�\�������ɐ��ތ������t�i1984�N8��23���j�A�F�씎�q�s�ǁ\�\���ŋ��E�l�����t�i1984�N9��25���j�A��o���Z�s���\�\�͂邩�Ȃ��蕔�t�i1984�N11�� 22���j�B](image/nihonfukeiron_1.jpg)
�����Ђ́q���{���i�_�r�V���[�Y�E�S9���̔��B�ѓ��k��s�`���\�\���̔畆�̔j���Ƃ���t�i1981�N9��10���j�A����p�v�s��n�\�\�I��Ȃ����҂̗��t�i1981�N10��8���j�A�F�V���F�s��\�\���z�ƌ����̃��j�������g�t�i1981�N11��9���j�A�˖{�M�Y�s�����\�\���������̂̔ߌ��t�i1981�N12��10���j�A�r���I�s����\�\���̐_�̗����߂���t�i1982�N10��25���j�A�ԍ]�e�s�C���\�\���̐��̖����̐^�G��t�i1983�N8��10���j�A���J����s���\�\�������ɐ��ތ������t�i1984�N8��23���j�A�F�씎�q�s�ǁ\�\���ŋ��E�l�����t�i1984�N9��25���j�A��o���Z�s���\�\�͂邩�Ȃ��蕔�t�i1984�N11��22���j�B
�� �c�j�T��W�s�����Ă����k��玕�p���l�t��1983�N8��25���A���R�s�̎蒟�ɂ��犧�s�B�ݓc�t���́q���r�͂����n�܂��Ă���B�u����A��{�_��搶�̌� �H�̂��j�̉�ɎQ�����B���̐Ȃł��܂��ܑ剪�M����A���W�G����Ɗ���������B�Z�����A�̂����ɘb���j�T����̋�W�̂��Ƃɋy�B�u���͍����������� ����ł���v�Ƒ剪����B�u������v�Ɛ�肳��B���������Ă���l�Ƃ����ꂵ�����Ȋ炳��Ă���B����ɑ���͋g��������Ƃ����������o�[�B����Ȃ� ���܂ꂽ��Ƃ͂܂�����ʂ��낤�v�B�{���́A���a46�N���珺�a58�N�܂ł�230������߂����҂̑���W�ł���i���̌�A����W�s�\�Ӂt�i�q�r�ЁA1987�j�Ƒ�O��W�s�ۂ�t�i�p�쏑�X�A1998�j������j�B
�@�@����قǕ��c�肽��ԃ~���U
�@�@�����[孂̌ߌ㖾�邭��
�@�@���Ղ���x�͕��Ė{�J��
�@�@�ĉ����Ƃ��Ⴋ�Ƃ�����
�@�@��������Œ��M�̍���
�@�@�ς݂����Ĉ�F[�ЂƂ���]�ɂ��ėь甄��
�@�@�O���̊������ė����ዾ�@��
�@�@�~��ɍ~��^��̐��M����
�@�@���N���N���l�Ă�錮�̓�
�u�P�э������тĐ��Ђɂ���v�������Ȃ����A���͌f�ڋ�̂悤�ȍ삪�D�����B�Ƃ���ŁA�g�������������P�s��W�͑z���̂ق����Ȃ��āA�s�����Ă�
���t�ȊO�ł��O�D�B����W�s�`�̉ԁt�i�}�����[�A1976�j �����邭�炢���B����
�ӔN�A��W���J���Ȃ����͂Ȃ������Ƃ����g���z�q�v�l�̏،����炷��ƈӊO�����A�����Ƃ�����Ƃŋ�W�̐���Ɋւ��������R����ǎ҂̗���ɏI�n����
�������A�ƍl����ׂ����B�g���͉i�c�k�߂̒P�s��W���瑕�����Ă��Ȃ��̂��B
�q��玕�p���r�͖{���폑�X�Ⓦ�发���Ȃǂ���A������40�шȏ�o�Ă���B�s�����Ă����t�͉��т߂��L�ڂ��Ȃ����̂́A���s�����炷��Ƒ�6�тɓ������
�����B�{���̎d�l�́A�ꔪ��~��ꔪ�~�����[�g���E��Z�l�y�[�W�E�㐻�z���E�\���B�\���̗����F�A���̃N���[���F�A�т̗ΐF�̑g�ݍ��킹������s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1978�t�i�y�ЁA1979�j���z�N�����B
�g���͖{�����s��1983�N�A�s��玕�t5�����Ɂq�܌��̋�\�\�k�߂̋傩��r�Ƒ肵�Ċ����G�b�Z�C���Ă���B�u�܌��̋�v�͘A�ڃ^�C�g��������A�g��
���t�����W��́u�k�߂̋傩��v���낤�B�g�����g�̕҂s�k�ߕS��t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�j�A�u���̈������A���́u�t�̋�v�𒊏o���Ă݂悤�v
�i�����A��y�[�W�j�ƁA�i�c�k�߂̋�16��400���l���e�p��3�������Z�߂��o�偁�������z�ł���B�{�т͋g�����������s�U�������A��
�捠�܂Ŗ����������핶�ł���B
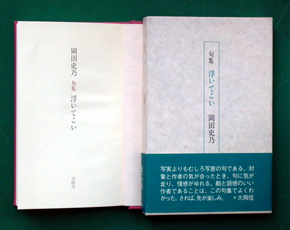
���c�j�T��W�s�����Ă����k��玕�p���l�t�i�蒟�ɁA1983�N8��25���j�̖{���Ɣ�
�ɓ��M�g�s������e���ЂƁ\�\�����Y�̉��y�����t�i�m���[�A1971�N11��30���j�͕���̂Ƃ���A�����Y�̃~���[�W�b�N���C�t��ʂ��Ă��̎��̐����̔閧�ɔ��鏑�����낵�]�`�B�`�łƂa�ł�2��̊��{������A�Ƃ��ɋg�����̑����ł���B�`�ʼn��t�Ό��y�[�W�ɂ́u����350��//�S���{���f�J���R�b�g�����g�p//�`��70���@��x�Y���o�N�X�L�����^���Җ{�i�`�`�e�j�@�s�̖{�i1�`64�j�^�{���͂��� 2 �Ԗ{//�a��280���@�A�[�g�L�����o�X���^���Җ{�i�`�`�s�j�@�s�̖{�i1�`260�j�^�{���͂��́@�@�Ԗ{�v�i�^�͉��s�A//��1�s�A�L�j�Ƃ���B�{���ɂ͈�t�́q�m���[�����ē��r�����݂��܂�Ă���̂ŁA�d�l�𒆐S�Ɉ��p���悤�i�{���̖{���p���T�C�Y��191�~146�~�����[�g���j�B
�ɓ��M�g���@�������낵�]�`
������e���ЂƁ\�\�����Y�̉��y����
����E�g�����@�`�T���ό^�܍��g164�Ł@�{���f�J���R�b�g�����@������
�`�Ŏ��Z���i�s��1�`64�j�����o�N�X�L�����v���E�۔w�E�V���E�\�����������E�v�w�����E���M�o����i�Еz���N�ꌎ�j�@�U�T�O�O�~��100
�a�œZ���i�s��1�`260�j�Z�ԐF�A�[�g�L�����o�X���E�\���h�C�c�������E�����F�r�ڎ��\�����E���G�Y�y����t�@�R�O�O�O�~��100
�k�c�c�l�{���͈ɓ��M�g���̏d���A���~�n�����M�ɂ��u���y�̒��̎��l�v�t�Y�ւ̒�������i�ŁA���l�g�������̑���ɂȂ�y������ȏ������{�ł��B�k�c�c�l
�߉ϑ��Y�i�ɓ��M�g�ƂƂ��ɒ}�����[�Ŕ����Y�S�W��҂j�́q���y�̎��l�E�����Y�r�Łu�ށk���Y�l�͂̂��̃G�b�Z�C�u���y�ɂ��āv�i���a�\�N�O���j�̒��ŁA�u�l�̐N���̂��ׂĂ̗��j�́A�S�����y�̂��߂ɋ����₤�Ȃ��̂ł����B����̓V���Ȃ����ĉ��y�̌m�ÂɔM������قǁA�N���ɂ�����ő�̎��ԓI�Q��͂Ȃ��A�ƃj�C�`�F�͌����������Ă�邪�A�l�̏ꍇ�����x���̒ʂ�̘Q��ł����B�v�Ə��������A�ނ́gA WEAVING GIRL�h�i�@�D�鏭���j�̍�Ȃ̂ق��A�������̕ҋȂ�A�����W�Ȃ��c���Ă���A���̉��t�����̑f�l�̈��E���Ă�Ƃ��Ӂv�i�s���{�̎� ��V�� �����Y�W�t�A�W�p�ЁA1978�N10��25���A��l���`��l��y�[�W�j�Ə����Ă���B�{���̌��G�ɂ͍Y���M�̊y���iA Weaving
Girl�j���ʐ^�łŌf�ڂ���Ă���A�g���͕ʒ��{���̒n�ɂ������~���Ă���i�`�ŕ\���̃J�b�g�͍Y���g�D�����S���h���m�y��̃}�[�N�j�B
�g�����́s�k�����q�S���W�t�x�Ɋ��q�f�͎O�ƈ�т̎��r�i���ώɁA1983�N4��3���j�ɂ��������Ă���B�u�킽�������́A�s�ł����t�����̃e�L�X�g�k�q���l�̔����ё��r�l�ɑI���́A��̎v���o�����������炾�B���Ԃ�A�l�\�܁A�Z�˂̒a�����̎��ł������낤�Ǝv���B�Ȃ��瑡��ꂽ�̂��A���́s�ł����t�ł������B�Ƃɂ������Ï��ژ^�̂Ȃ��ŁA���̎��W�Ɏ����Ԃ�������Ă������̂��A�Ȃ͌����Ĕ������߂��̂ł���B���c�J�~���u�̌Ï���q�����[�r�́A�d�������ŎႢ��l�����҂��Ă��ꂽ�������B���̐l�́A��ŏ��������ƂƂ��Ēm����A�x���B�v�ł���v�B�g����46��1965�N�Ɏ���3�т������\���Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��z�q�v�l���瑡��ꂽ�k�����q�̎��W���������̂��A�̂��̖{���̊��s�ҁE�x���B�v���������킯�ł���B
 �@
�@
�ɓ��M�g�s������e���ЂƁ\�\�����Y�̉��y�����k�`�Łl�t�i�m���[�A1971�N11��30���j�̕v�w���E�\���Ɠ��k�a�Łl�̕\���i���j�Ɠ��k�a�Łl�̖{���Ɓq�m���[�����ē��r�i�E�j
�k2013�N12��31���NjL�l
�ɓ��M�g�s������e���ЂƁ\�\�����Y�̉��y�����k�a�Łl�t�i�m���[�A1971�N11��30���j��157�Ԗ{����肵���i���Ȃ݂Ɂu47.2.19�v�̉���̂��鍑������}���ُ����{�͂a��218�Ԗ{�ŁA�{���O�̕ʒ��ɂ͒��ҏ����ɓY���āu���܂�������v�A�������苖��157�Ԗ{�ɂ́u�Â����̉̂��v�Ƃ���A�`��2�Ԗ{�̎��M�o��́u���ʂĂʐ�������߂����݂��ʁv�ł���j�B�����@��Ȃ̂ŁA�a�łōēǂ��Ă݂��B�܂��A�Y�ɂƂ��Ẳ��y�́\�\
�@�̂���̌Â����K�̔Z���O���ɏZ�ލY�ɂƂāA���y�͂��̓s��I�n�D���[�����A��̊���������A���̖��͂łƂ炦�ĕ����ʂ��̂����B����ɂ����A���̘f�M���Ƃ����ĉ��y�̉��F�Ɂu���m�v�������A�����������̂Ƃ��Ắu�ߑ�v������̂ł���B�`�����y�ƈقȂ鉹�F�ɁA�V�N�ɂ��ĊÔ����Y�p�I�����𖡂���̂ł���B�����̍Y�̉��y�I��M�̋A������Ƃ���́u���m�v�ł���u�ߑ�v�ł���A����ɂ�Ď����̎��͂Ɉ���Y�p�I����ݒ肷�邱�Ƃ����B�i�{���A�l��`�l�O�y�[�W�j�S���h���̃}�[�N�i�O�o�A�`�ŕ\���̃J�b�g�j�ɂ��Ắ\�\
�@�S���h���m�y��̖��̗̂R���ɂ��āA���݂˂́u�Z�͏̂��Ă�����S���h����y���ƌ��Ă����B�S���h����y���Ƃ́A���̋������ցi�Z�̏��ւ͒�̈���ɂ������u����������������ϋ������ł����j����A�������܂����S���h��������A�z�������߂ł��낤���A�v�i�u�Z�ƃ}���h�����v�j�ƌ��Ă���B������l�����邱�Ƃ́A�T���R���[�k�C�^���A�l�̉��y�ƁA�I�y���̃e�i�[�̎�l�ɏK�����Ƃ���A�C�^���A�n�����Ƃ����ӎ��������낤�A�Ƃ������Ƃł���B�ǂ�ȋȖڂ�������Ȃ����A�吳�l�N�Ɏ���Łu�ɑ����h�̉��y���W�v���Â����̂��A���̌n���ӎ��ɂ�邱�Ƃ��낤�B�܂��S���h���m�y��̓���ē����ɂ́A�g�ɕ����ԃS���h����}�ĉ�������y���̃}�[�N��������Ă���A���̉E�㕔�Ɂu�f�v�̕������z���Ă���B�i��Z��`��Z��y�[�W�j�����āA�{���̌���́\�\
�@����܂ŒǂĂ������y�Ɣ����Y�́A���̉��y�����Ȃ�тɎ��Ƃ̂��������߂����ʂ�̂��Ƃɉ߂��Ȃ��B�����L�̎苖�Ɉ�Ă����u���y�m�[�g�v��A���l���̎�ɓn���Ǝv����y����A���̂ق��̎������ڂ���������A�͂邩�ɑ����̉��y�I�b�����邱�Ƃ��ł���B�Y�Ƀ}���h������M�^�[���K���l�����ɂ��A���ꂼ��̎v���o�����邾�낤�B�}���h�������t�c�̎w���҂������Ƃɂ������̘b�肪���邾�낤�B�͂₢�����̒n�������^���Ƃ����ʂɂ��b�肪���邾�낤�B���̂��̕��͉͂��y�Ɣ����Y�̑S�e����������̂ł͂Ȃ��B�a�ł̎d�l�́A����E�~��l�Z�~�����[�g���E�ꎵ��y�[�W�E�㐻�p�w�z���E�\���i���Ԃ��̗p���͂`�ł���ύX�B���G�͂`�ŁE�a�łƂ������j�B�O�f���t�Ό��y�[�W�̃N���W�b�g�A���t�i�ɓ��̌����\�t�j�ɒ��҂Ɣ��s�l�ɋ��܂�āu����@�g���@���v�Ƃ���̂́A�`�łƓ����B�\���́u�Z�ԐF�A�[�g�L�����o�X�v�̐F�Ǝ�G�肪�f���炵���B�g���͂̂����߉ϑ��Y�s�����Y���̑��t�i���V���X�A1975�j�̕\���ɂ��Ԃ��i�������a�ł������Ȃ薾�邢�j�z�����̗p���Ă���B�{���̕\���܂��͌��������A�{���̊e���y�[�W�̌��o���ɕ��̂��������Ă���͔̂[�����������B���������A�����ڂɔ������Ȃ��B�g���͌����Ă��̂悤�Ȏw������Ȃ������B
�@�������悤�Ƃ����̂́A���̉��y�I����A���̎��I���U�ɂǂ̂悤�ɂ�����荇�����A�Ƃ������Ƃł���B�����Ď��́A���̉��y�I�˔\�≹�y�I�Z�킪�ǂ̒��x�������ɂ������Ȃ��A�Y���H�ȉ��y�̒��̎��l���Ǝv���B�ߑ㎍�ɂ����鎍�Ɖ��y�̔��w���A�Y�͂��Ƃ��Q�֓I�ɁA�����Ă����炭�ŏI�I�ɑ̌��������l�����̂ł���B�i��l���y�[�W�j
�������i�ޗǁE���g�쑺�j�̑O�Z�E�ŁA���l�̑�����2005�N3��16���A69�ŖS���Ȃ����B������͖����w�҂ł�����A�����I�ϓ_����̎��l�Ƃ��Ċ����BNDL-OPAC�Œ��ׂ�ƁA����̂قƂ�ǂ͖�����O�@��t�A�܌��M�v�Ɋւ��錤�����ŁA���W�̐��͑����Ȃ��B�g�����́A������̎��W�s�����������t�i����ЁA1960�N5��1���j�����Ă���B���W��8�т��琬��q�T ������܂��r�Ɓq�U �}���A�̉́k�S40�сl�r�q�V �R�X���X�k�S9�сl�r��3���\���B�����́q�~�r���D��Ă���B
�~�b��������
�}�j�L���A�����肪
�H��ɂȂ�ׂ�ꂽ
�j�͐������݂̂���
�͂������Ђ������s�X�g�����ɂ��肵�߂�
���̊�́@�͂Ă��Ȃ���������
�����ȏ���̃T���v�����@�Ƃ�������
�₪�ā@�E�C���i�\�[�Z�[�W�ɂɂ�
�g���\�̐،����݂������
���@�s�X�g���͂ނȂ���
���̎��Ԃ𗧑̉�����
�����̂��Ƃ����ɂ́u���W�s�����������t�Ƃ́q���ɂ������j�r�܂�A������̈ӂł���܂��B�^������q�����������c�c�r�ƁA�Â��̂��Ƃ́A�킽�����̂��т�����炢�ł��B�^�k�c�c�l�^���܂Ƃ肠�����A���̎��W�̂��߂ɁA�،��F��A�g�����A���c�v�Y�A��쐴���Y�̊e���ɁA������������������邵�����ł���܂��v�i�qNOTE�r�A�����A�㔪�`���y�[�W�j�Ƃ���B�Ō��̐���Ђ́A���s�҂̏��c�v�Y���s����t�̌p���㎏�Ƃ����s���㎍�蒟�t��n�������o�ŎЂł�����B �{���̎d�l�͈�Z���~��l��~�����[�g���E��Z��y�[�W�E�㐻�N���X���E�@�B���B���ڂ��ׂ��́A�����́u�����������v�̍��e�ɓ������̂Łu�����������v�Ɖ��F���n�ɍ����Ă���{�����B����ȂǁA���Ď҂��g�������c�v�Y�����f�̓���Ƃ��낾�B���̔w�����u�����W�E�����������v���S�`�b�N�Ȃ̂��A�g���������ł͒������i�������̕\�P�ł͖������g�p���Ă���j�B
 �@
�@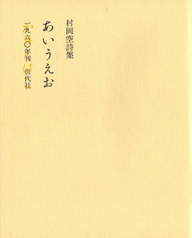
�����W�s�����������t�i����ЁA1960�N5��1���j �̖{�̂Ɣ��i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�k2017�N10��31���NjL�l
����A�C���^�[�l�b�g�̃I�[�N�V�����ő����W�s�����������t�s�����������t�����s����Ă��邱�Ƃ�m�����B���D�ł��Ȃ��������A2���Ƃ�����}���قɏ�������Ă���̂ŁA�s�����������t�����Q�̂����A�{�������i�s�����������t�̓f�W�^��������Ă��邪�A�s�����������t�s�����������t�͌������{���ł���j�B�܂��ڂ��䂭�̂́A�s�����������t�����̂܂܂Ȃ������悤�ȑ��{�E�����ł���B�s�����������t���b���ɑ��āA�s�����������t�͓݂����F�A�s�����������t�͒��ΐF�̕z���ŁA�s�����������t�̃N���X���Ƃ͍ގ����قȂ�B�{����2���Ƃ����ō��́s�����������t��͂��Ă��邪�A�ʐA�E�I�t�Z�b�g����ɕς�����B�ނ��A�s�����������t�ɂ́u�����������v�́A�s�����������t�ɂ́u�����ĂƁv�̐F�������Y���Ă���B�{�����ɂ́u���k�����l�ה錮�S�@��苗��s���a����������ӑ����O�W�O����v�ƁA����������������̂ł��邱�Ƃ��L����Ă���i���s���͂ǂ����2006�N3��16���ŁA���s���͔����Ёj�B�����Ėڎ��̍Ō�ɁA
�@�@���@��^�g�� ���i�w�����������x��͍�j
�@�@���}�G�^�^�� ���i�w�����������x�𗬗p�j
�Ƃ���B�\�\�{���̑��݂�m�����̂́A�I�[�N�V�����u���ƔŔi�w�����W�����������x�w�����������x2�� �^�������m���₵�����Ɛ��z ���ꁁ�g�����v�Ɉ˂邪�A���̐����Ɂu���O�A�����g�����W�w�����������x�i1960�N�j���o���Ă��܂����A�{���W�͂���ɕ���ĕ҂܂ꂽ���̂ŁA�g�����̑����^�甎�̔��}�G���w�����������x�P���Ă��܂��v�Ƃ���Ƃ���A�N���m���W�[���炢���ċg���������ł͂��肦�Ȃ��\�\�B����}���ُ����{�͖{�̂����ŁA�����Ȃ������r�ł��Ȃ��������A���̎d�l��f�U�C�����s�����������t�P�������̂��낤�B�s�����������t�i����Z��y�[�W�j�ɂ́A�q���̉́r�̘A��7�т�M���ɁA�S51�̎��т����߂��Ă���B�s�����������t�i����ꔪ�y�[�W�j�ɂ́A�q�������r�Ɏ�12�сA�q�_�S���r�ɓ�����12�сA�q���낢��ȕ����܁r�Ɏ��ƃG�b�Z�C���琬��12�сA�q�قƂ��ɏo��r�ɓ�����12�т����߂��Ă���B�s�����������t���^��i�́A�������ŔӔN�ɑ����@�̎G���s�T�̗F�t�ɘA�ڂ��Ă������́B�������ďC���������s�x���Ɣ��s�҂̑����s�����́A���҂̐e���Ȃ̂��낤�B������̖����s���т��A�s�����������t��͂������W�Ɏd���Ă�Ƃ́A�����Ԃ�Ɵ��������Ƃ��������̂��B�Ȃ��A�{�̂Ɏ��ۂ̑����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B
 �@
�@
�����W�s�����������t�i�����ЁA2006�N3��16���j�̕\���i���j�Ɠ��s�����������t�i���A�����j�\���i�E�j�k�����������}���ُ����{�̃J���[�R�s�[�l
�s�F�V���F�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1990�N2��20���j�́A�ܒJ���m���F�V���F�ɂ��ď�������l�т̕��͂����߂Ă���B�{������g�����Ɍ��y���Ă���ӏ��������B
�@���̌�A���Z�Z�N���ʂ��āA�ށk�F�V���F�l�Əo��@��͑��������B�����Ă��͕�����ŋ��̂͂˂����Ƃ́A�����̐Ȃł������悤�Ɏv���B���R�r���Y����A�����������A�y���F����A�g��������A�푺�G�O����A���\�Y����A���̑��������̉��l�A�V�ˁA�������X�g�̎푰�ƁA���������m�肠���悤�ɂȂ����B����ȂȂ��ŁA�F�V����͂Ȃ�ƂȂ����S�ɋ�������Ă���Ƃ��������������āA���ꂪ�A�̂��ɂ�����A�Z�Z�N��̈���i�ł��������̂��낤�B�i�q�F�V����\�\��z�L�r�A�����A�ꎵ�y�[�W�j
�@ ��������{�̊��͂��������A������܂Ƃ߂��Ƃ͂������Ɛi�B���̊ԂɁA���̂����Ƃ��h�����鎍�l�E�g�������̏����邱�Ƃ��ł����̂́A�v���̂ق��̊�тł������B���͑�����������������ɂȂ�A�����ԂI�Ȏ�̏����ɂ������Ƃ����Ђ��₩�Ȋ�]��e�ꂽ�����ŁA�ނ���ÓT�I�Ƃ��������F�V���F�̃C���[�W���܂Ƃ킹�Ă����������B���̂��Ƃɂ��āA�����Ɋ��ӂ��������Ă��������B�i�q���Ƃ����r�A���O�A��O��y�[�W�j
�{�������ɂ́A���y�[�W�ɂ킽��q�F�V���F����ژ^�E�����r���t����Ă���B����́A��ɛܒJ���m���ҏW�ψ��̂ЂƂ�ƂȂ����s�F�V���F�S�W�k�S22���E�ʊ�2�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1993�`1995�j�̕ҏW�S���ҁE�������ᎁ�̍쐬�ɂȂ���̂ŁA�}��ɂ����镶�͂͂��Ј����Ă��������B
�@�����ɂ��F�V���F�̒����E�E�Ғ��C����т��̍�i���ꕔ�ɂӂ��ޏ������\�����Ƀ��X�g�A�b�v���C�����X�ɂ��Č��y���Ă���{�����̃y�[�W�����ׂĎ������D�Ȃ����o�����ڂ̂��ɂ͏��ŒP�s�{�̃W�������C���s�N�C�o�Ō��Ȃǂ��L���C����ɁC���̌�Ɋ��s���ꂽ�����̃��@���G�[�V������N�㏇�ɂ܂Ƃ߂Ă���D/�͂�����x���Ƃ̓��e�ƃ^�C�g���̂܂܂ōĊ����邢�͍Ę^����Ă���ꍇ�C//�͈ꕔ���邢�͑S�̂��I�W�ȂǂɍĘ^����Ă���ꍇ���Ӗ�����D�i���O�A���y�[�W�j
�g���͖{���̃W���P�b�g��\���E���Ԃ��E�{���𔖒��n�ł܂Ƃ߂Ă���B���̐F�g�����J�c�����s��z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�j�ɋ߂����A�ό`���i�`�T���̓V�n���J�b�g�j�̂��߈�ʓI�ȕ��|���Ƃ͈�����y���Ȋ���������B�d�l�͈��܁~��l���~�����[�g���E��l�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B���Ԃ��p���͋g���̍Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j�Ɠ����V�}���B�g�����͖{�����s��O�ӌ����܂�ŖS���Ȃ��Ă���A�s�F�V���F�l�t�͂��̍Ō�̑�����i�ł���Ɠ����ɁA�g�������ɂ�����W���P�b�g���E�n�[�h�J���@�[�{�̓��B�_�ł�����B

�ܒJ���m�s�F�V���F�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1990�N2��20���j�̖{���ƃW���P�b�g
�k2018�N1��31���NjL�l
�{���s�F�V���F�l�t�͍\���Ɠ��e�����̂܂ܕۂ��A���M�E�C���̂����A�ܒJ���m�s�F�V���F�_�R���N�V�����T �F�V���F�l�^���`�Ɖ�z�t�i�א��o�ŁA2017�N10��6���j�ɍĘ^���ꂽ�B���ł́q���Ƃ����r�̍Ō�ɂ́A�e�߂̔��ɔz�����ʐ^�ɂ��Ă̐������NjL�̌`�ŏ�����Ă��������A������e���̎ʐ^�L���v�V�����ɐU��킯�A�����Ɏ��̕��͂��f����ꂽ�i�����Ɂu��Z�ꎵ�N�����O���v�Ƃ���j�B
�@�NjL�\�\�E�L�̂悤�ɁA�w�F�V���F�l�x���ł̑���́A�g�������ɂ����̂ł���B���͓��{���\���鎍�l�ł��邾���łȂ��A�D�ꂽ����Ƃł�����A�ҏW�҂ł��������̂����A���̖{���o�Ă���킸���O������́A����Z�N�܌��O�\����ɖS���Ȃ����B�w�F�V���F�l�x�͂����炭�A���̍Ō�̑����i�ł���B�����ɂ��̎ӎ��������A���炽�߂Č̐l���Âт����B�i�����A��ܓ�y�[�W�j
�u�����i�v�Ƃ����\��������ƁA���҂�2005�N�̖{�e���Q�ł����悤�ɂ��v����B�Ƃ��Ɂs�R���N�V�����T�t�̌�t�ɂ́A���҂ɂ��q��L�r�A�q�w�F�V���F�_�R���N�V�����x�S�܊��ɂ��ār�A�q���o�ꗗ�r�A�q�F�V���F��������r���������Ă���B���́q��L�r�Ɉ˂�A�����s�F�V���F�l�t�����́q�F�V����\�\��z�L�r�́u���܂����Ȃǂ݂̂Ȃ���A�I�[�g�}�e�B�b�N�ɕM�𑖂点�Ă�����قȃG�b�Z�[�v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�ŁA����P�̂ő�T�͂ɂ���Ƃ����\���́A�g�����̃A�C�f�B�A�ł��������Ƃ����B�Ȃ��g�����g�́A���G�b�Z�[���f�ڂ��ꂽ�s�����C�J�t1988�N6���Վ��������F�V���F�Ǔ����ɂ́A�������сq��L�i�L�����E�t�@���^�X�}�j�r�i�K�E17�j���Ă���B
�s���E����N�v���W�k���㎍���Ɂl�t�i�v���ЁA2005�N1��25���j���o���B�q�킪�o�_�r�Ɓq�킪�����r��y�[�W�ɕz�u�����A���ĂȂ��g�����V�N���B�g�����͓���N�v�̂��̂Ƃ��ǂ��́u�S���W�v���x�A�������Ă���B�s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1970�t�i�y�ЁA1973�N3��30���j�Ƃ��̑�������łƂ�������s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1978�t�i�y�ЁA1979�N5��1���j���B
�s1951�`1970�t��3���\���ŁA�T�Ɂs�Ď��̉t�i���惆���C�J�A1958�j�A�s�Â��y�n�t�i���R���A1961�j���A�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t�i�B���ЁA1965�j�A�s���Ȃ��ؑl�̉S�t�i�y�ЁA1971�j�A�U�Ɂs�� ����Ƃ��s�t�i���惆���C�J�A1955�j�A�s�� ����Ƃ��s�E���t�i����R�c�A1971�j�A�V�Ɂs�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�j�A�s�킪�o�_�E�킪�����t�i�v���ЁA1968�j�A�s���̍\���ɂ��Ă̊o�����\�\�ڂ��̎���i����t�i�v���ЁA1968�j�����߂邪�A�Ȃ�Ƃ����Ă��s���̍\���ɂ��Ă̊o�����t�̑��݂��ٍʂ���B���ꂳ�����q���r�Ƃ���̂�����N�v�̐��E�Ȃ̂��B�s1951�`1978�t��3���\�������A�T�ɂ́s�u���v���̂ق��̎��t�i�v���ЁA1977�j���������A�V����s���̍\���ɂ��Ă̊o�����t���Ȃ��A�����Ɂs���č������Y�Ɩ�����l�ւ̋�A�̎U�����t�i�y�ЁA1978�j�������Ă���i�ȏ�̂����A����̒P�s���W�͋g�����̑����ł���j�B�g���͂��̌���A����̎��W�s���҂����̌Q���镗�i�t�i�͏o���[�V�ЁA�����1982�E�V����1983�j��s�l�����@���o���t�i�Ԑ_�ЁA1984�j�Ȃǂ̒P�s�{�̑��������Ă���B����������҂̈˗��ɂ����̂ł��낤�B
�d�l�́s1951�`1970�t����Z��~��l���~�����[�g���E���O���y�[�W�E�㐻�z���i�Z���j�E�\���i��F�j�B�s1951�`1978�t����Z��~��l���~�����[�g���E�����y�[�W�E�㐻�z���i���F�j�E�\���i�N���[���F�j�A����1000���B�����Ƃ����E�\���E�{���ɁAꌂ̂悤�ȓ����̃J�b�g���G���u�����̂��Ƃ��z���Ă���B�{���p�����قȂ邱�Ƃ������āA16�y�[�W�Ƃ����y�[�W���̈Ⴂ�ȏ�Ɂs1951�`1970�t���s1951�`1978�t������������B���Ȃ킿�u��������Łv�̕��������Ȃ��̂��B
�o�N�ω��̂��߂ɂ킩��ɂ������A�s1951�`1978�t�̕\���z�͋g���́s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�Ɠ��������Ɍ�����B����̖{�͑���45mm�قǂ����ĕ\���z�̑e���D���C�ɂȂ�Ȃ����A�s�u�����v�Ƃ����G�t�͖�26mm�����Ȃ��A���喡�Ȋ���������͔̂ۂ߂Ȃ��i�����ӂ���ǂށs�u�����v�Ƃ����G�t�̔������̔w�����������������Ă���̂��A�\���z���������j�B�����ƕ��ׂ�ƁA�������n�ł��������s���E����̂����͂Ă̗̈�t�i�n���ЁA1976�j�̕����Z�����F�ł���B
 �@
�@
�s����N�v�q���r�W���\�\1951�`1970�t�i�y�ЁA1973�N3��30���j�Ɠ������s1951�`1978�t�i���A1979�N5��1���j�̔��Ɩ{�́i���j�Ɓs1951�`1978�t�A�s�u�����v�Ƃ����G�t�A�s���E����̂����͂Ă̗̈�t�A�s1951�`1970�t�̔w�i�E�j
����N�v�́s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1978�t�ȍ~�������̎��W���o���Ă���A���s�N�����ɓ����̂��ׂĂ̎��W�����^�����s���V�N�v�q���r�W���\�\1951�`1994�t�i�y�ЁA1996�j�㊪�E�����̓���{���A���헲�F�����Ŋ��s����Ă���i�s1951�`1978�t�ɑ��₳�ꂽ�̂́s���̎�̂���O�\�̏�i�t�i����R�c�A1979�j�A�s�p�k���t�i�Ԑ_�ЁA1981�j�A�s�t�̎U���t�i�y�ЁA1982�j�A�s���҂����̌Q���镗�i�t�i�O�o�j�A�s���Ӌt���́t�i����R�c�A1988�j�A�s�́\�\�ςւ��́t�i����R�c�A1988�j�A�s���̍���t�i����R�c�A1989�j�A�s�Y�ӏM�t�i�v���ЁA1994�j��8���W�j�B�����ł���B
�� �݁A�������̒���W�i�S6���j���y�Ђ��犧�s�������A�g�����͒��������㎍�ɂ��Ę_�����s���E����̂����͂Ă̗̈�t�i�n���ЁA1976�N8��30 ���j�����Ă���B�{���ɂ́q�V ��̎��l�����Ǝ�̎��W�r�̏͂̂��ƂɁs�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j�̏��]�����߂��Ă���B�����ŏ���������A�����́q��L�r�Ɂu���\���������������͈�X�̕��̖͂����ɕt�L�����Ƃ���ł���v�i�s���E����̂����͂Ă̗̈�t�A�O�Z�l�y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA���o�� �킩��₷���L�ڂɂȂ��Ă���̂͂����̂����A�Ȃ������́q�w�g�������W�x�r�͂��ꂪ�R��Ă���B�O�̂��߂Ɍf���Ă����A���o�͋G�����s�߁t6�� �i1960�N1���j�ł���B���āA�������̏��]�ŃA���_�[���C���������͎̂��̂悤�ȉӏ����B
�u�g���̓�\��̏������W�w�t�́x�́A�w�m���x�̎��l���l���鎞�A���낵���n�����o���ł͂Ȃ��������Ǝv����B�v
�u�k�q��́r�́l�����������I�̌��́A�ǎ҂ɂƂ��Ă͒T���Ƃ̋L�^���Ђ��Ƃ��悤�ȍV�����o��������B�������A���܂�ɖ`��杂��݂Ă͂��Ȃ����낤���B �Ђ���Ƃ���ƁA���̎��l�́A�����̒T���Ƃ������ł���悤�ɁA���낵���ӎ��I�ɖ��v�z�A�������Ȃ̂ł͂Ȃ����B�v
�u�w�t�́x����w�Õ��x�ցA�w�Õ��x�̕����߂�ꂽ���E����w�m���x�̉^�����鐢�E�ցA���̎��l�͏o�����݂��Ă����B�͂����č��x�ǂ������o�����݂� ���邩�A���͍ő�̊S�������Ē��ڂ���B�v�i�����A��l�O�`��܁Z�y�[�W�j
�g
�����̎��Ƃ��[���F�߂������ł́A�h���̕]���Ƃ����Ă������낤�B���т̈��p�i�q���i�r�q�t�̇T�r�q�Õ��r�q���鐢�E�r�͑S�сA�q�쌀�r�q�m���r�q��́r
�͕����j���I�m�Ȃ����ɁA�����̔����ɂ͐����͂�����B�{���̑����𒆑��̕�����g���Ɉ˗������̂Ȃ�i�O�f�q��L�r�ɂ��������L�q�͂Ȃ��̂����j�A��
�̏��]�ɂ͎��M���������̂��낤�B
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��~�����[�g���E�O��Z�y�[�W�E�㐻�z���E�\���B�e���D�̕\���z�͔Z���Œ��F�ŁA��G��Ƃ����A�w�����̋��������Ƃ����A�̂�
�̋g�����g�́s������v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�j�̑�����f�i������B�Ƃ���ŁA�����̏������W�s�����́t��1950�N9��30���ɏ��惆���C�J��
��o�Ă��邪�A���̎l�Z�{�������{�̍��q���g���������s�ٗ�Ձt�̓������̒Ԃ������Ƃ܂�
���������Ȃ̂ł���i����ȕR�́s�����́t�̕�����┖���j�B�g�������ɒB���v�̎肪�����s�����́t�̑��{�����������ł��낤���Ƃ́A����߂č����m�x��
�f���ł���B
![�������̕]�_�W�s���E����̂����͂Ă̗̈�t�i�n���ЁA1976�N8��30���j�̖{���Ɣ�](image/nakamura.jpg)
�������̕]�_�W�s���E����̂����͂Ă̗̈�t�i�n���ЁA1976�N8��30���j�̖{���Ɣ�
�q���s�ٗ�Ձt���r�ł��G�ꂽ�悤�ɁA�V��ޓ�Y�̎��W�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����낵�ɂ��p��
���q�Q�l�t�́A1973�N10��10���̏����̂��ƁA�g�����̑����ɂ������ł��g���́s�ٗ�Ձt�����Łi1974�N7��1���j�Ɠ��l�̎d�l��1974�N9��1���Ɋ��s����Ă���B�ʏ�ł́s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�̂ق����s�ٗ�Ձk�����낵�ɂ��p��
���q�R�l�t������Ɋ��s����Ă��邩��A�����ł͋g���̎��̊��Ői�s�������̂Ƃ݂���B�Ƃ��Ɂq�����낵�ɂ��p��
���q�P�r�̑���C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���t�ɂ͌���35�������Łi�v�\���E�a������E��������E�ܓ���j�����邻�������A�g���̑����ł͂Ȃ��悤���i�ʏ�ł̑����҂ł����������g�̋C������j�B
�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�Ɓs�ٗ�Ձt�̓����ł́A�܂̎���������قȂ���̂́A�傫���E�y�[�W���Ƃ������d�l�ŁA�o�����̂悤�ɂ悭���Ă���B���҂̂�����̑���͕\���̊G���ŁA�N���W�b�g�͂Ȃ����V��̑o���b�A�g���̎��̌��b�Ƃ��ɗ����̃T�C��������B�����[�����ƂɁA�s�ٗ�Ձt�́u���v�͂����葁���A�g�����ҏW���Ă����s�����܁t��50���i1973�N6���j�Ɍf�ڂ���Ă���i�{��~�q�X�^���o���X�L�[�̗]���Ɂr�̖{���J�b�g�Ƃ��āj�B�g���́s�����܁t�p�ɕ`���Ă�������u���v���C�ɓ������̂ŁA���g�́s�ٗ�Ձt�����łɓ]�p�����̂�������Ȃ��B
�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁t�̓����ł́A�\���E�{���Ƃ��ƃX�~�̓�F���i���t�̌���ԍ��̂ݎ�F�ň���j�B���t�A���J�b�g�̖{���i�V�n228�~���E150mm�j�������Ȃ��U��̕\���͘a���d���Łi�V�n260�~���E165mm�j�A�����̓V�n������ɐ܂肱��ł��珬���������ɐ܂肱�݁A���߂Ɍy���ł���Ȃ��猘�S�������B���̑��{�̌Ăі���m��Ȃ����A�a���̃t�����X���A�Ƃł������������낤���B�{�����O���Œ��Ԃ��������F�̕��R�́A�w�̒����ŌŌ��т��ĊO���猩����悤�ɂ��Ă���B�����y�[�W�ɂ́u�V��ޓ�Y�v�ƍאg�̃T�C���y���ŏ������Ă���A�\���̑o���b���k���ȃ^�b�`�ƍ����Ă���B�{���p����������N���������Y�A����101���L�ԁB
�g���͂ǂ����Łi���܌������������炸�A���m�Ȉ��p���ł��Ȃ��j�\�\�ӔN�͗I�I���K�A�D���ȍ�Ƃ̍D���ȍ�i���o������{������肽���\�\�ƌ���Ă������A���ꂪ�������Ă�����A���̑��q�����ł̂悤�ȃI���W�i���̖{�����������܂ꂽ���Ƃ��낤�B
�k2006�N8��31���NjL�l
�g�������ҏW���߂Ă����s�����܁t������}���قŌJ���Ă�����A�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����Łl�t�̕\���Ɠ����G�����������B�s�ٗ�Ձk�����Łl�t�́u���v�Ɠ��N�A1973�N2������46���̖{���J�b�g�E�����Ƃ��Čf�ڂ���Ă��邩��i�{���L���͉F�����p���q�J�菁��Y�̐G�o�I���́\�\�w�t�Տ��x�ēǁr�j�A�{�����܂��s�����܁t�p�̉�e��]�p�������̂Ǝv�����B���Ȃ݂Ɏ��M�҂̉F�������́A�킪���Y��Ԃ̓��l�E�F�����X�g�̕��N�ł���B
�k2011�N10��31���NjL�l
�ߑ㕶�w�V�N�i����W�����s�ʉp���H�Q�{���ځt306���i2011�N10���j�ɑ���C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���t�i����35�������Łj���f�ڂ���Ă���B�\���̏��e�����邩����A��͂����{�l�̑����̂悤�ł���B�ʉp���̃T�C�g�̋L�ڂ�^����B�uNo. 42493 ���ƍ��Ɠ��^���^����C�� 1�� ���i: 160,000�~�^����35���@�ѕM�������@�A���J�b�g�@���v���@���Ԃ��}�[�u�������@���܁^����R�c ��48�v�B
![�V��ޓ�Y���W�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����Łl�t�i����R�c�A1974�N9��1���j�̑܂ƕ\��](image/amasawa.jpg) �@
�@
�V��ޓ�Y���W�s�u�]�`�I���t�F�v�̎��݁k�����Łl�t�i����R�c�A1974�N9��1���j�̑܂ƕ\���i���j�Ƒ���C���s���ƍ��Ɓ\�\���^���k�����Łl�t�i����R�c�A1973�N6���j�̕\���Ƒ܁i�E�j�k�o�T�F�ʉp�����X�l
�g���������Ɏ����ǂ��ǂ̂��A���̂Ƃ���悭�킩��Ȃ��B���̕��w�ɂ��ĂȂɂ������̂����Ă��Ȃ����炾�B�����A���ɂ̈�̂��������ꂽ1948�N6��19���̗����̓��L�i�q�����i���l���N�E�ė�j�r�j�ɁA���̂悤�ɂ���̂����ڂ����B
�u�q���r�^�ߌ�ɂȂ��Ă��J���Â��^�ӂ��Ă���J�͂��Ȃ��ɔ������^�����Ǖ֏��̂��ɗ��������͂����Ƃ������^���Ɏ��̏�̂����������i���̋L���̂��钩�����ʂ�Ă���j�^�ɂ܂�������^���ꂽ�V�֏��炸�^�J���Ԃ���֏���^�����v�i�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����t�A����R�c�A1996�A��y�[�W�j�B
���̋L�q����A�l���ɑ��鈣���̔O�ȊO�̂��̂�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ͓���B���Ȃ݂ɋg���́A���̓��̖�A���e���O�Y�̎��W�s���l���ւ炸�t��ǂ݁A���ɑ����Ď�������݂Ă���B�g���̓��ɂ́A�����u���v�̂��Ƃ����Ȃ������̂�������Ȃ��B
�s���Ɏ��S�W�t�͍����܂łɂ��܂��܂Ȕłŏo�Ă���B��߂ȁs�V�����{���w���T�k��������l�t�Ɉ˂�A���_���X�Łi1948�`1949�A�S18������15���Œ���j�A�n�|�ДŁi1952�`1955�A�S16���j�A�}�����[�Łi1955�`1957�A�S12���E�ʊ�1�j�A���i1959�`1960�A�S16���j������A�s��{���Ɏ��S�W�t�Ƃ��Ē}�����[�Łi1962�`1963�A�S12���E�ʊ�1�j������B�����}���̑��Ɏ��S�W�����ł��A��L�̂ق��ɒ}���S�W���ڔł₿���ܕ��ɔł�Ȃɂ₩�₪�����āA��O���ɂ͂��ꂼ��ǂ�ȓ��F������̂��悭�킩��Ȃ��B�����u�}�����[�ő��Ɏ��S�W�扽���v�ł����Ă��A����ނ̃V���[�Y�����݂��Ă��āA���s�N�ȂǂL���Ȃ��Ɩ{�������ł��Ȃ��̂��B
�����ɂƂ肠����k��5���l�s���Ɏ��S�W�t�͑S12���E�ʊ�1�ŁA1967�N4��5������1968�N4��30���ɂ����Ē}�����[���犧�s���ꂽ���́i�O�f�s�V�����{���w���T�t�ɂ͋L�ڂ���Ă��炸�A����ȑO�̑��Ɏ��S�W�̐V���łƂ������Ƃ��납�j�B�Г����̏�Ƃ��đ����Җ��̓N���W�b�g����Ă��Ȃ����A�܂��ԈႢ�Ȃ��g���̎�ɂȂ���̂��낤�B���̓V�ɂ҂����荇�킹�āA�w�E���ւƉ��\�O��̏������V�N���i�����̃J�b�g�\�\�W���P�b�g�ɂ������G����������\�\�̓X�g���[�g�ɂ����邫�炢�����邪�j�B�d�l�͈��Z�~��O�Z�~�����[�g���E�e����O��Z�y�[�W�E�㐻�z���E�W���P�b�g�E�@�B���B���܂��͓\�O��i�X�~�Ɛ��F��2�F���j���܂߂āA���ׂēʔŁi�����j�ň������Ă���B
���Ȃ݂ɁA��ɋ������}�����[�̑��Ɏ��S�W�i��{�S�W���j�́A�����ܕ��ɔňȊO�݂ȋg�����̑����̂悤�Ɏv���邪�A�ɂ킩�ɒf���ł��Ȃ��B

�k��5���l�s���Ɏ��S�W�k��6���l�t�i�}�����[�A1967�N9��2���j�̔��ƃW���P�b�g
�k2019�N2��28���NjL�l
�s�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�́k��5���l�s���Ɏ��S�W�t�̑�v�����̂悤�ɋL�ڂ��Ă���B
���Ɏ��S�W
��1���ł����ɉ����E����@���ȏW�̂ݐV��2�i�g
�S12���ʊ�1�k��5���l�@1967�N4���\68�N4��
��11���́q���ȁr���܂�12���܂ł͂悵�Ƃ��悤�B���́A�ʊ��̉��쌒�j�ҁq���Ɏ������r�ł���B�Ăсs�}�����[�}�����ژ^�t�̋L�ڂ��f����i�Ȃ�������4���̐����́A�}�����[�Г��̐����̂��߂́u���{�ԍ��v�j�B
�ʊ��@���Ɏ������@���쌒�j��
�����̕��w�E���Ɏ��Ę_�i���c�����j�@���Ɏ��_�i�P��g���j�@���Ɏ��_�i���쌪�j�@���Ɏ��_�\�\�l�ԑ��Ǝv�z�̐����i���쌒�j�j�@���t���i�T�䏟��Y�j�@�Ηz�̖��i�_�����j�@���Ɏ����V�i�ΐ�~�j�@�s�Ǐ��N�ƃL���X�g�i�������j�@�����̗F�i�܌��M�v�j�@��\���I�ɂ�����|�p�Ƃ̏h���i�ԓc���P�j�@�t�ʊ�Ƃ̓��Ёi���J�Y���j�@�`�i�|�R���Y�j�@�������̕��́i�����͑��Y�j�@���{�Ƒ��Ɏ��Ɓw�Ηz�x�i�h�i���h�E�L�[���j�@���Ɏ��ƃL���X�g���i���Ï���Y�j�@���Ɏ��ƃR�~���j�Y���i���n����j�@���l����s�E���Ɏ����̕��w�i�ۓc�^�d�Y�j�@���Ɏ����_�i���@�����j�@������㵒p�Ɓi��㏇��j�@����i�䕚����j�@�H��܁E�H�L�̕��˂ق��i�����t�v�j�@���ɂƕ�����a�@�i�R�݊O�j�j�@�M�C�s�i�h��Y�j�@�ߌ������i�ɔn�t���j�@�ɗ��̔�i������j�@���Ɏ�����̂��ƁE���Ɏ��搶�Ɂi�c���p���j�@���e�i���R���j�@�O�鎞��̑��Ɏ��i�ʏ������j�@�v�Џo�̒f�Ёi�Ó����m�q�j
���Q�l�����i���쌒�j�E�����~��ҁj�@��L�i���쌒�j�j
1968�N4��30���@436�Ł@�@�@�@�@�@�@3183
 �@
�@
 �@
�@

���쌒�j�ҁs���Ɏ������t�i�}�����[�A1968�N4��30���j�̔��̕\�ƕ\���i���j�Ɠ��E���̔w�Ɣw�\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��̗��i�E�j
�{���̎d�l�́A�ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�l�l�Z�y�[�W�i�ʒ��{���E���G�꒚�j�E�㐻�z���E�i�苖�̌Ï��̓W���P�b�g���������A���͂������ɈႢ�Ȃ��j�E�@�B���B�ʐ^�ł킩��Ƃ���A�s���Ɏ������t�̂ǂ��ɂ��u���Ɏ��S�W�v�u�ʊ��v�̕����͌�������Ȃ��B�ڂ����q�ׂ�Ȃ�A�@�B���̔w�́u���Ɏ������@���쌒�j�ҁ@�}�����[�v�A�\�O��̕\�S�́u�� �T�W�O�v��CHIKUMA�̑�̃}�[�N�ł���A�{�̕\���̔w�́u���Ɏ������v�A�ʒ��{���͉��g�Łu���Ɏ������^���쌒�j�ҁ^�}�����[�v�A�q�ڎ��r�̂��Ƃ̔��́u���Ɏ������@���쌒�j�ҁv�A���t�̏����́u���Ɏ������v�i�u���ҁ@���Ɏ��v�Ƃ���͕̂s���ŁA�u�Ҏҁ@���쌒�j�v�Ƃ���ׂ����j�ł���B�����ŋ����[���̂́A���t���L���Ɂk��5���l�s���Ɏ��S�W�t�̊T�v���L����Ă��邱�Ƃ��B�v���ɔŌ��́A�k��5���l���O�̑��Ɏ��S�W�������Ă���ǎ҂ɂ͐V�K�̒P�s�{�m�A�A�A�n�Ƃ��āA�k��5���l�s���Ɏ��S�W�t�������Ă���ǎ҂ɂ͓��������̑��Ɏ��S�W�ʊ��m�A�A�A�A�A�A�A�n�Ƃ��āA�{��������������̂ł͂���܂����B��������2��ނ̑����ŏo���킯�ɂ͂����Ȃ��������A�{���̋@�B���i��W���P�b�g�j���O���A�l�Z���̒P�s�{�Ɍ�����Ƃ���������i����Ƃ����H�j���Ă����̂͌����������B������ς���A�{���͒P�s�{�́s���Ɏ������t���s���Ɏ��S�W�t�̊O���ŕ���́A�Ƃ�������킯�����B

���쌒�j�ҁs���Ɏ������t�i�}�����[�A1968�N4��30���j���t���L���́k��5���l�s���Ɏ��S�W�t�̊T�v
���t���L���́s���Ɏ��S�W�t�̊T�v�ɂ́A�{�����u�ʊ��@���Ɏ������i���쌒�j�V�ҁj�Q�l�����v�ƋL����Ă���i�����̐�����V���ɒ������j�B���́u�V�ҁv�Ƃ����̂́A���삪���ł�5�N�O�́s��{ ���Ɏ��S�W�t�̕ʊ��i1963�N3��15���j�Łq���Ɏ������r�i412�y�[�W�j��҂�ł��邩��ł���B���āA�k��5���l�s���Ɏ��S�W�k�S12���l�t���g�����̑����ƌ�������ɂ́A���̕ʊ��m�A�A�n�������͒P�s�{�m�A�A�A�n�������g���̑�����i�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͖{��������Y�p�w���O�̍������[�̕S�~�ψ�̒I����E�����̂����A�I�����̔w�������u�ԂɁu�g���������������k��5���l�\�\�Ƃ͕����Ȃ��������\�\�s���Ɏ��S�W�t�̒[�{������v�Ǝv�������炢������A���t���L���Ɓs�}�����[�}�����ژ^�t�Ɍh�ӂ�\���ĉ��쌒�j�ҁs���Ɏ��S�W�k�ʊ��l���Ɏ������t�i�}�����[�A1968�N4��30���j�Ƃ���̂������Ȃ��B���Ȃ݂Ɂs���{�̌Ö{���t�Łu���Ɏ������@�}�����[�@1968�N�v����������ƁA3�����q�b�g�����B���i��1200�~����3090�~�ŁA�����́u���Ɏ��S�W�ʊ��i���Ɏ������j�v�u���Ɏ������v�u���Ɏ����� �S�W�ʊ��v�ƁA�����ł͑S�W�ʊ��̈������D���������B���łɁA���������ɂ��āq��������}���كT�[�`�r���s���Ɏ������t���������Ă݂�ƁA�u��������}���كf�W�^���R���N�V�����v�ɏ����������āA���Ɏ��S�W�̕ʊ����Ƃ͋L����Ă��Ȃ��B�����I�ɂ͂��ꂪ�����ȏ����낤�B
�Ί_���̎��Ɂq�������r�i�s�����V���i�[���j�t1994�N5��6���j������B�O���̐߂͂������B
�����E�a�J�̉w�r���\����
���D���Ə��X�X�����ԎE���i�ȒʘH������B
���ݍ����Ƃ��͕Б���Ԑ��̃g���l���̂悤��
�l�̌Q��͓�̗���ƂȂ��čs���Ⴄ�B
���ł��������A���̔g����̒���
���l�̋g������������������B
����������Ԃ��Ȃ�����
���������������������Ƃ��v���Ȃ������B
�قǂȂ��g��������]��������B
�ȗ����Ȃ��ʘH��
���Ƃɋg������̕����ė������������ǂ�Ƃ�
���݂͂傤�ȋC���ɂȂ�B
���̏ꏊ���A�킩�肻���ł킩��Ȃ��B��̓I�ɓ��肵�ɂ����悤�ɏ����Ă���Ƃ���������B������ɂ��Ă��A���l�������̈�V�[�����Ƃ����͑N�₩�ł���\�\�Ǝv���Ă���ƁA����1�s�Č㔼�̐߂ɓ���B
���s�E���ߎs�ɂ��鏼�����ł�
�܌������̖@�v�ɒ����Βi���̂ڂ��Ă䂭��
����Ⴄ�Q��̒��Ɍ̐l�ɂ悭�����炪����Ƃ���
�R�A���̎Ԓ��Ŏ��ɂ����b�B
���̂Ƃ����s�����Ⴂ������
�����\�̎��ɎQ��܂��傤�A�Ɩ����B
���ꂩ�牽�N�������낤
�v���Ԃ�ʼn�����F�͎��̘b���o���Ă���
����Ǎs���Ă݂܂��A�Ƃ����B
������
���Ȃ����Βi������ė���Ƃ�
�������Α����牺��ė����肵�āA�Ƃ�����
�܂��܂��Ⴂ�ޏ��̓L���b�Ə��������B
�Ί_���͉Ǎ�Ȏ��l�ŁA�g�����Ɠ��N�y�Ȃ���A�I���W�i���̒P�s���W��4���Ƌg����3����1�ɖ����Ȃ��B�g���͂��̂�����3���A�s�\�D�Ȃǁt�i�v���ЁA1968�j�A�s�����t�i�Ԑ_�ЁA1979�j�A�s�₳�������t�t�i�Ԑ_�ЁA1984�j�ƎU���W�s���Ɏ���������āt�i�}�����[�A1980�j�����Ă���B

�Ί_��W�s�\�D�Ȃǁt�i�v���ЁA1969�N5��1�����̍ĔŁk���ł�1968�N12��25�����l�j�̖{���ƃW���P�b�g
���W�́q���Ƃ����r�ɂ͂�������B�u�w�\�D�Ȃǁx�̑���������ĉ��������g������́A�ӂ��������Ȃ����̊肢�����̓x����������ĉ������܂����v�i�s�����t�A����y�[�W�j�B�u���{�ɍۂ��ċg�������u���������������܂��傤�v�ƌ����ĉ������܂������A��炵�̏�ŁA�g���ނ��Ƃ͂��Ă����邱�ƖR���������Ό����A�v�킸�U��Ԃ�܂����v�i�s�₳�������t�t�A���܃y�[�W�j�B���W�s�\�D�Ȃǁt�́A�W���P�b�g�〈�Ԃ��������F�n�̂Ȃ��ŁA�邪�ЂƂ���N�₩���B�d�l�͓��Z�~��l���~�����[�g���E��O�Z�y�[�W�E�㐻�����E�W���P�b�g�B����E��t����A���{�E�⍲���{�́A��͂���Z���N�v���Њ��̋g���̎��W�s�Â��ȉƁt�Ɠ����ł���B�Ί_���͖{���W�Ŏ��d�̐V�l�܂ł���g���܂��A�g������܂�����Z�N��Ɏ�܂��Ă���B
�k2006�N1��31���NjL�l
�O�f�q�������r�́A���̌�s���㎍�蒟���W�� �Ί_���t�i�v���ЁA2005�N5��20���j�́q���W�����^���с\�\�w�₳�������t�x�Ȍ�r�Ɏ��^���ꂽ�B
�k2014�N9��30���NjL�l
�ѓN�v����̃u���O�sdaily-sumus2�t���q�\�D�Ȃǁr���f�ڂ���Ă���B�`���̈�߂������B
�Ί_��W�w�\�D�Ȃǁx�i�v���ЁA���Z��N�܌�����ĔŁA���ꁁ�g�����j�B�����������{��T���o���đ����Ă�������U�����蒸�Ղ����B���̎��W�A��̂ǂ����������̂��H�@���̉����U����̃����ɔC����B
U����Ɉ˂�A�����͉��E�������X��105�~�ψ�I���瓾���ĔŁi�W���P�b�g�̐���\����1968����1969�ɕύX����Ă���j�ŁA����\�t���B���łɂ͂����̌�A�͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃł���i�ĔŖ{�ɂ́u�����ҁH�ɂ���ĊY���ӏ����G���s�c�Œ�������Ă��܂��v�j�B���̎苖�ɂ���̂��ĔłŁA����\�����t���Ă��Ȃ��������A�O�̏��L�҂��L�������Ǝv�����������A���l�Ɏ{����Ă���B�т���ɃR�����g�𑗂邽�߂Ɂq�g�����̑�����i�i17�j�r��ǂ݂������Ă݂�ƁA�s�\�D�Ȃǁt�̓��e�ɂ܂������G��Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����B����A���߂Ď��W��ǂ݂Ȃ������B�q�V�W�~�r��q�\�D�r�A�q�R�r�Ƃ����������Ȏ��т��������A�q���w�r�̌����Ɏ䂩�ꂽ�B
���w�b�Ί_���
����������
��ɔ����z���������B
�o�����������H���̎x�x��
�����ӂ���������悤�ɁB
�݂�Ȃ���������
�͂���A��������̖��͂܂�����
�܂����ڂ��قǂ��܂�Ȃ��̂���
�ƁA�킩�����B
���܂ɂ��ꂳ�������
�����z�������Ă�낤
����͖l�������H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ�
�O�x�̂��͂�݂����Ȃ��̂��B
�����Ŗl�����ʓ��ɂ�
�l�͂����Ə��Ɏ��ʂ�
�����z�̉���
�㓙�ȗ����̂悤�ɁA���B
����@�{��@�b��
����Ȃɂ������������������ɂ���������B
�Ί_�̋�Ǔ_�i�⎚�j�͂��ɂ݂��Ƃɓ����Ă��邪�A�{�тł����̂��Ƃ��悭�킩��B
��
�g�͌������s�ԓ`���t���ł́A�����̟f��܂��Ȃ���㎵��N��ꌎ��Z���A�����o�ł��犧�s���ꂽ�B���g�͌��G�ɂ��q���Ƃ����r�ɂ́u�\���͓ɂ��A��ꕔ�ɂ͈��Z�Z�N���́w���̉ԁx�i�u�k�ЃC���^�[�i�V���i���j�Ɏ��߂����������́u�ԓ`���v���A��ɂ́A���O�O�N���s�́w�r���x�ȍ~�A���ׂĂ�
�@�֎��A�P�s�{�A�w���u�`���猵�I�������Ƃ��A���ꂼ����^���Ă���v�i�����A��O�y�[�W�j�Ƃ���A�s���̐Ö��Ɏ��i���邱�Ƃ���t�i���쏑�[�A1976�j�������ɐ������y���F�̈⒘�s���e�̐�t�i�}�����[�A1987�j�̍\�����v���������B
�u�����Ȃ�����l�͍��|���Č���A�����Č���B���܂��܂Ȋp�x���玩�R�Ɏ��������Ă邩��A�����Ȃ����Ă��炢����������d�v�ȃ|�C���g�͂ЂƂ�
���m��Ȃ����A�����Ƃق��ɂ����낢��̎������ӎ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA����ꂪ������Ƃ��A�����Ă������A�����đ̂����R�ɓ������A����
�Ԃɑ��Ă��낢��̏o���_�����������������Ă˂Ȃ�Ȃ��v�i�s�ԓ`���t�A���l�y�[�W�j�Ƃ��������̂��Ƃ���́A�g�����́q�킽���̍쎍�@�H�r���z�N
�����B
�g�����̑����́A���҂̍�i�q���R���ɂ悹�ār��O�f�s���̉ԁt�Ɍ�����u�ԓ`���v�Ƃ����莚�i�g���ɂ��Ă͒������O���t�B�J���ȏ������{����Ă�
��j�A�\���i�������������ʓI�ł���j�A�{���i���Җ��E�����E�o�ŎЖ����A�����ɃZ���^�[���킹�łȂ��悤�Ɍ�����j�ɔz���邱�ƂŁA�����́u��v������
������B
 �@
�@
���g�͌������s�ԓ`���t�i�����o�ŁA1979�N11��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�d �l�͓��Z�~��O���~�����[�g���E��ܔ��y�[�W�E�㐻�����E�@�B�����i�{���ɂ͈�㔪�Z�N�������̌O�ܕ�����ł�����j�B�Ȃ��g���́A�����o�ŕ� �́s�����ȑ����t�Ɏ��сq�ԁE�ό`�r�i�I�E14�A1966�N5���j�Ɛ��z�q���C�����r�i1977�N6���j�̓�т��Ă���B
 �@
�@
���g�͌������s�ԓ`���k����Łl�t�i�����o�ŁA1980�N2��21���j�̔��ƕ\��
�s�� �z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�N4��25���j�̒��ҒJ�c�����́A���V���Џo�ŕ����E�s�V���t�ҏW���ŁA���Ђ́q�����w�����낵���ʍ�i�r�̊��҂ɂ� �āA�x�C�Y�̌����҂ł�����i�ҏW�҂Ƃ��Ắs�����t�s�ǂ��q�t�s�×��t�s�X�ƌ̂܂�t�s���̉ԁt�s���̏��t�s���فt�ȂǁA���w�j�Ɏc�鏬���̒P�s �{����|���Ă���j�B�����N���܂�Ƃ�������A�g�����Ɠ�����ƌ����Ă����B�q���Ƃ����r�̖����ɕҏW�҂炵���ׂ₩�ȋL�ڂ�������B
�@�{�����M�̋@���^���A�I�~�k�}�}�l��܂��ĉ��������Γc���v���A�w�����V���x�������̒S���L�҂Ƃ��Ė��e���ڍׂɃ`�F�b�N�������������I���O���A�A�ڒ��ɖ{���o�ł��m�āA���X�nj㊴��`���ĉ�������������q����A�ҏW�E����̎��� �Ɍg���č��܂��ĉ��������j���r�厁�ƁA��������Ă����������g�������ɐS���炨��\�グ��B�i�����A���܃y�[�W�j
�{ ���t�^�́q������r�ɂ́A��������E�g�s�~�V��E�����^��Y�̏��������߂��Ă���B�����Ƃ��e�����ҏW�҂̒����Ɋ镶�͂̌��{�ł���B���҂̖{�ӂ� �͂Ȃ���������Ȃ����i���̎�̂��̂́A�o�ő����u�ҏW�Ҍ����v�ň˗����邱�Ƃ������ƕ����j�A�ǎ҂ɂ͂��肪�����v�炢���B���̌��ʁA�ѕ��͖{���̓��e �Љ�ɐ�O�ł���B
�l�тƂ̑��Â�������������q���ꊴ�o�r�䂽�Ȃ����w�j
�x �C�Y�@���i���F�@���ҏ��H���ā@��ԍG�@�ēc�B�O�Y�@�ΐ�~�@�K�c���@�ێR���@������@�ɓ����@�����Ґ��@���c�~�@����d���@��]���O�Y�@�V�c���Y�@�i �n�ɑ��Y�@�������[�@�L�g���a�q�@��������@���������@�x�c�P�ʁ@�O�H���Y�@�����^��Y�@�g�s�~�V��@������q�@�e�����@�����M�v�@�~�n���q�@�Ñ��ߎq�@ �g�����@����M��@�R�{���g�c�c

�J�c�����s��z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�N4��25���j�̖{���ƃW���P�b�g
�s��
�z
���̕��w�t�́A���|���Ƃ��ăI�[�\�h�b�N�X�Ȏl�Z���㐻�W���P�b�g���B����������ԓI�Ȗ{�قǁA�����œ������o���͓̂���낤�B�g���͒��F�����C���J
���[�ɁA�{�����茘���܂Ƃ߂Ă���B�W���P�b�g�Ɩ{���̃����|�C���g�̃J�b�g�͎������A��҂̖��͋L����Ă��Ȃ��B��ˎ闝�s�g�����̏ё��t�i�W���v��
���A2004�j�Ɂu�f�p�ɂ܂�Ȃ����A�ނ̎�ɂȂ�{�́A���ɖ{�炵���ʍ\�������Ă���B�܂��A���ܗp�����钹�◳�Ȃǂ̊ȗ������ꂽ�͗l�̂悤�Ȃ���
�́A�䎩���ŕ`�����̂ł͂Ȃ��A�����̌Â��}�Ă���I�ꂽ���̂��ƕ������v�i�����A�܌܁`�ܘZ�y�[�W�j�Ƃ��邪�A���̎��̏ꍇ�́u�ȗ������ꂽ�͗l�̂�
���Ȃ��́v�Ƃ��������J�b�g���낤�B�{���̎d�l�͈ꔪ���~��~�����[�g���E�㐻�E�W���P�b�g���A��O�Z�y�[�W�B
�Ȃ��g���́A�J�c�����ҏW������́s�V���t�ɁA���сq�����r�i�H�E2�j�ƒǓ����q�a�c�F�b�Ǒz�r�̓�т��Ă���B
�O
�Z�N�قǂ܂��A��w�ɓ����Ă����Ɏ��݂����Ƃ��ӂ�����B�ЂƂ̓v���[�X�g�́s����ꂽ�������߂āt��M��Œʓǂ��邱�ƁA�����ЂƂ́s���e���O�Y
�S�W�t�Ő��e���W��ǔj���邱�ƁA�ł���B�w���̐}��������肾���āA�ċx�ݒ�������邪���ǂ���������B����ȓǂݕ��������������낤���A�s��
��̋��b�t�ȍ~�̐��e�̎��͊�ɘA��������ۂ��c�����i�ǂ̎��т��ǂ̎��W�̂��̂��킩��Ȃ��Ȃ�A����ȁq���e���r�ƌĂԂ����Ȃ����̂ɂȂ����A��
�����Ă��������Ƃ��j�B���̌�s��{
���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1981�j����肷��ɋy��Łi���e���͂ӂ�������ς炱��œǂށj�A���e�̒P�s���W�͂����������˂ɑ������A�s���ނ�
��肠�t�Ɓs���l���ւ炸�t�������A�g�����������������ȊO�قƂ�ǎ苖�ɂȂ����肳�܂��B
�g�����������������e���O�Y���W�̂Ȃ�����A����́s��̖���t�i�ԗj�ЁA1979�N11��30���j����肠����B���Z��i���a�O���j�N�A�Z���̐�
�e�́u�Z���\������玵���l���܂ŁA�A���^���A�q��̏����ŃC�^���A�ɗ��s�A���I�}�A�t�B�����c�F�A���F�l�c�B�A�����V���A�E���K���b�e�B��Ɖ�v�i��
�ϑ��Y�ҁq�N���r�A�s���e���O�Y���W�k��g���Ɂl�t�A��g���X�A1991�A�l�����y�[�W�j���A�s��̖���t�͂��̃C�^���A���s�̎Y���̖ʂ�����B
�V�q�r��ҁq�����r�ɂ́u�����̍�i�k�w��̖���x�l�͏��a�O�\���N�O���O�\�����s�̒}�����[�Łw���e���O�Y�S���W�x�̖����ɒP�s�{���W�̈����Ŏ��^
����Ă���̂ŁA�{�S���W�ł����̏��o�N��ɏ]�����v�i�s��{
���e���O�Y�S���W�t�A��l�`��܃y�[�W�j�Ƃ���B�g�����܂ސ��e���̓ǎ҂́A�P�s���W�s��̖���t�ȑO�Ɂs���e���O�Y�S���W�t�Łq���W
��̖���r�ɐG��邱�Ƃ��ł����킯���B�s�g
�������W�t�Ɓs�Â��ȉƁt�̊W���������������A���������ꍇ�A�͂����đ������₷���̂����ɂ����̂��A���ɂ͂悭�킩��Ȃ��B
 �@
�@
���e���O�Y���W�s��̖���t�i�ԗj�ЁA1979�N11��30���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���ƌ��Ԃ��i�E�j
�s��̖���t�̎d�l��
�ꔪ���~��~�����[�g���E��Z���y�[�W�E�㐻�z���E�\�����B�g���͖{���W�̐F���������E���F�n�œ��ꂵ�Ă���B�܂��т͒W���̐F���ɃX�~�����B�\����
���̖͗l�ƃX�~�����̓�F����B�\���͌��̂悤�Ȍ���̔Z���̕z�ɋ��������B���Ԃ��p���͐��ʒn�͗l�́u�ʕ~�v�ŁA�F�͓����B�ʒ��{���͎��ƃX�~�̓�F��
��ŁA�\���Ɩ{���̐���J�b�g�́i�N���W�b�g�͂Ȃ����j���e�̎�ɂȂ�B�����āA���ҕ`���Ƃ���̌��G��t�i�q�T���E�}���R�̒��r�j�������B
�����ŋg�����ɂ����鎇�ɂ��čl���Ă݂����B�����ɑz�������Ԃ̂��u�T�t�����̉Ԃ̒W�����v�i�q�T�t�����E�݁r�G�E1�j�Ƃ�������ł���B���̎�������
�����W���s�T�t
�����E�݁t��
�肳��āu�W�����v�̕z�ő������ꂽ�̂́A�l���m��Ƃ��낾�B��ˎ闝�s�g�����̏ё��t�i�W���v�����A2004�j�ɑ����Ǝ��F���߂���L�q������B�u����
���A�g��������V�������N�������̑���ɗp�����̂́w���[���h���b�v�x�����߂Ăł͂Ȃ��B�w��ʁx�ɂ������I�Ɏg���Ă��āA�C�^���A���̐[�݂̂���
�F�����̎��F�̕\���Ɣ������Δ�𐬂��p�w�̔����z������ł���v�i�q�{�r�A�����A�l�y�[�W�j�B
���e�́q�T���E�}���R�̒��r�́A���@�炵������������悤�ȕM�v�ŕ`������i�ŁA�܂��ɐF�ʂ���g�������n��ł���B���G�ʼnE�[�̃I�����W�����������̐F
�ʂɎ����Ŋ�������̂��A�W�����̐F���B�g�������E���F���s��̖���t�̃��C���J���[�ɑI�ő�̗v�����A���ꂾ�낤�B�����A��ɏq�ׂ��悤�Ȃ��Ƃ�
�l������ƁA�u�N���^�̒W���v�ƂƂ��Ɂu�C�^���A�̎��v�Ƃ������z�����g���̂Ȃ��ɂ�������������Ȃ��B
�O �D�B����W�s�`�̉ԁt�i�}�����[�A1976�N6��30���j�́A�\�O������L�O���ĕҎ[���ꂽ�O�D�B���S��W�Ƃ������ׂ����B�g�����ɂ������W�s�z���t �i����R�c�A2003�j�ɑ�������ꊪ�ł���B�{�����s�����A�g���͒}�����[�ɍݐЂ��Ă�������A�{���Ȃ�N���W�b�g����Ȃ��Ƃ��낾���A�u����@�g�� ���v�Ɖ��t�ɖ��L����Ă���B��W�s�`�̉ԁt�ꎵ�Z�傩��A�D���ȋ��������B
��������̒��Ɖ����ׂ�����͂���
�T���̂ЂЂȂȂ�ǂ����̏㉺
�_���������܂͂�̉Ԃ���ق�
�ᒠ�Ƃ��Ӑ��E�ɂ͂��ԉ̏��o��
�Ђ邪�ւ�݂̂Ƃ͂��ւǐ͂���
��
�܂��ܒ��Ƙ@�̋傪�����A�O�D�̎��o�ƒ��o�̍Ⴆ�͕|�낵���قǂł���B���̋�W���܂߂ċg�����O�D�̔o��ɐG�ꂽ���͂͂Ȃ�����ǂ��A���W�s�t��
���t�i�n���ЁA1939�j���̏��Ƃ��Ă����g���́A���l�Z�N�O����O���A�O�D�̎��̍��b��܂̎��������˂��u������Ă���B�i�s�u�����v�Ƃ�
���G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z�O�y�[�W�Q�Ɓj

�O�D�B����W�s�`�̉ԁt�i�}�����[�A1976�N6��30���j�̔��ƕ\��
��
�W�s�`�̉ԁt�́A���̑��ӂƕ\���̔������ɎO�D�̏��������炢�A�c�����̗��������\���܂��ɂȂ��Ă���B�����t�^�ɂ́A����S����M���ɘa�c�F�b�E��
���ρE�剪�M�E������s�E�Ό����������M�B���Ԃ��͌���̎荗���a���ŁA�����{�������Ȃ̂��䂩�����B�\�艜�t�̈͑啐���l�B����܁Z�Z���L�ԁB���
�͐����ЁA���{�͗�ؐ��{�B�d�l�͈��Z�~��l���~�����[�g���E�㐻�z���E�\�����A�ꎵ���y�[�W�B�g���������́u�a���v�̑�\��ƌ����Ă������낤�B
�g���́A�O�D�B���̍Ō�̎��W�s�S���т̂̂��t�i�}�����[�A1975�j�̑������S�����Ă�
��B
�c��m�́s���{�̌��㏬���t�i�W�p�ЁA1980�N5��10���j�ł́A�s���Ƃ̐l�тƁt��s����t�A�s�N�̊t�ȂǁA�����{�̒��я������_����
��Ă���B���́A�c���s���̓��t����肠�������i���F�̏����ɂ��āA�g������Ƙb�������Ƃ�z�������B
����Ƃ��A�D���ȏ����Ƃ̘b�ɂȂ�A���͕��i�̖����������B�g������̕Ԏ����U����Ă����B�����A���������Ă��H�@�ӔN�͕a��ŁA���Ƃ͑�w��
�搶�A��i�͂���قǑ����Ȃ��A�Ǝ��͂��ǂ���ǂ�̕ԓ��������B�����̕��i�A���̋g���A�Z�̂̒˖{�M�Y�A�o��̍����d�M�A�Ɓu�吳���܂�v�̑n��҂���
�ɐS�ꖣ�����Ă������́A�g�������i�����̔M�S�ȓǎ҂ł͂Ȃ��̂��c�O�Ɏv�������Ƃł���B
�s���{�̌��㏬���t�͕]�_�ɂ��Ă͑唻�̖{�ŁA�\���̍ގ���F�g�����s��{
���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1981�N1��20���j�ɉZ��ł���B�����A�s��{�t�ɂ͑����N���W�b�g���Ȃ��A�N�̎�ɂȂ�̂�����Ȃ��i�g������
�����Ƃ����������Ȃ��̂����j�B���N���X�̌��Łs���e���O�Y�S���W�t�i�}�����[�A1963�j�̑����́A���J�K�M�Ɉ˂�A�Ȑ܋v���q���Ƃ����B
�s���{�̌��㏬���t�ɂ́s���{�̋ߑ㏬���t�i�W�p�ЁA1988�N2��10���j�Ƃ����o���т�����B��㎵�O�N�́s���{�̋ߑ㏬���t�ƈ�㎵�ܔN�́s��
���{�̋ߑ㏬���t��������{�ŁA�����ł��g����������S�����Ă���B �\���z�̐ԂƐ̐F�́A�g���̎��W�s�|�[
���E�N���[�̐H��t�����E�ĔŁi����R�c�A1980�j�Ɠ������ꂾ�B���̃J�b�g�̍���F�ɂ������ڂ������������B����Ƃ��A�d�l�͓�ꔪ�~��l��
�~�����[�g���E�㐻�z���i�p�\���j�E�\�����B�s���{�̌��㏬���t���܌l�y�[�W�A�s���{�̋ߑ㏬���t���ܓ��y�[�W�ł���B

�c��m�s���{�̌��㏬���t�i�W�p�ЁA1980�N5��10���j�Ɓs���{�̋ߑ㏬���t�i���A1988�N2��10���j�̔��Ɩ{��
�s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j�́u�}�����[�̍ŏ��̏o�ł́A����d���́w����d�����M���x�ŁA���̉��t�ɂ��A���s�͏��a�\�ܔN�Z���\�����A���s���͑ז����w�Z�̑O�ɂ����铌���s�����������Z���ڎl�Ԓn�ŁA���s���`�l�͌Óc��ł������v�i�����A�O�y�[�W�j�Ə�����������Ă���B���M�͋g�����̊x���ł����鏬���Ƃ̘a�c�F�b�����A���Җ��̕\���͂Ȃ��B�����������Ƃ������đ����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����̂́A�������ق�̃C���^�r���[�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�ɂ���悤�ɋg���̑����ł���B
�u�w�}�����[�̎O�\�N�x�͂����{�ł��ˁB���̕\���͖{���Ȃ�ł��B�\���p�̕z�Ƃ��Ă͍ō����i�̂ЂƂł���ˁB���ꂾ���̖��̐�����̎������c���Ă��āB�c�c���A���̌��Ԃ��͐V�ǎ��ł��ˁB�����V���̎q�B�g������炵���B�v�i�s�����C�J�t�A2003�N9�����A��l�Z�y�[�W�j
�Óc��͈�㎵�O�N�A�S�؍[�ǂŋ}������B���N�̈�����������ās��z�̌Óc��t�i�}�����[�A1974�N10��30���j�����s���ꂽ�B�ԕz�ɂ�����܂Łs�}�����[�̎O�\�N�t�ƂقƂ�Ǔ����̍ق̖{���ɂ������҂̕\���͂Ȃ����A�g�����̎�ɂȂ�ƌ��č�����������܂��B���M�҂��L����ƁA�ΐ�~�E�䕚����E�P��g���E�����Ëg�E��R���E���؏��O�E�͏�O���Y�E��ыŁE����S���E���яG�Y�E���������E�a��邁E�����Ꮥ�E�������n�E�|���D�E���c�~�E��˕x�Y�E���������E����d���E����D�v�E�������v�E�����h��E�ێR�^�j�E����F�q�E�g�c����E�n�ӈ�v�E�a�c�F�b�ȂǁA�����l�����B
�a�c�́q�v���o�����Ɓr�́u�Óc���Ȃ��Ȃ����Ɠd�b�Œm�点�Ă��ꂽ�͎̂��l�̋g�����������B�g�����͒}�����[�̎Ј��ŁA���̖����ł���v�i�����A��Z�Z�y�[�W�j�Ǝn�܂�B���яG�Y�́q�Óc�N�̎��r�͖{�����s�̗���ꌎ�A�g�����ҏW�����s�����܁t��67���ɓ]�ڂ���Ă���i����Ɉ�́s���Y�t�H�t�ɂ��Ę^����Ă���j�B
����Ƃ�����͐����ЁA���{�͖���{�ŁA�d�l�͈ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E�㐻�z���E�\�����A�i�B�s�}�����[�̎O�\�N�t���O��Z�y�[�W�A�s��z�̌Óc��t���O�Z���y�[�W�ł���B
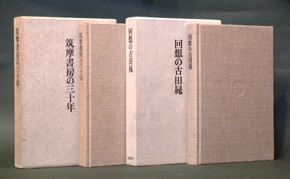
�s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j�Ɓs��z�̌Óc��t�i���A1974�N10��30���j�̔��Ɩ{��
�k2006�N6��30���NjL�l
�ѓN�v�s������[�����肫]100�t�i�݂��̂�o�ŁA2006�N6��4���j�Ɂs�}�����[�̎O�\�N�t���f�ڂ���Ă���B�{�e����̈��p�����邪�A���e�i�т���B�e�̃��m�N���ʐ^�j���f���炵���B
�k2016�N5��31���NjL�l
�s�ےJ�ˈ�S�W�k��12���l�t�i���Y�t�H�A2014�N9��10���j�́q�V �������]�r�ɂ́s�����V���k�[���l�t�́q��g���g�r�ɏ�����139�{����18�{�����߂��Ă���B1971�N1��22���q��g���g�r�́q�}�����[�̎O�\�N�r�̕M�Җ��́u�ӂ��낤�v�B���̍ŏ��ƍŌ�̒i���������B�u��N�A�܂菺�a�l�\�ܔN�́A�}�����[�̑n�ƎO�\���N�ɓ����邻���ŁA�a�c�F�b���M�̎Ўj�u�}�����[�̎O�\�N�v���z��ꂽ�B���p�T��ȑ��{�������ɂ����̖{���ɂӂ��킵�����A�a�c�̏������Ўj���̂��̂͂����ƒ}���炵���B����͂���A�Ўj�̖͔͂Ƃ������ׂ������ȏo�����������Ă���B�^�k�c�c�l�^�܂肱�̖{���́A�Ўj�̂Ƃ����悢�{���o�����ƁA�������ꂾ��������Ă���킯�ł���B���������}�W���ȏo�ŎЂ́A���������̐i�W��S����F��v�i�����A�l���`�l��O�y�[�W�j�B�u���p�T��ȑ��{�v���g�����̎�ɐ��邱�Ƃ��ےJ���������Ă������͕s�������A��N�̃G�b�Z�C�q�o�ŎЂ̎Ўj�r�i�s���ƃ������t���Y�t�H�A2008�j�́A�a�c�́s�}�����[�̎O�\�N�t�ƕS�ڋS���O�Y�́s�V���Д��\�N���j�t��_���ĊԑR���鏈���Ȃ��B
�g�����́s�y���F��t�́q44�@�{���r�ł��������Ă���B
�@�q���L�r�@��㎵�l�N�܌��\�Z��
�@�ߌ�A�y��Չ���w���ԂƉi���x���o�����̂ŁA�S���҂Ƃ��ď\���������āA���c�̓y��Ƃɍs���B���얢�S�l�Ɩ��̍��ۏ�͊�сA������O�ɋ�����B�� ���ɏZ�ޑ���҂̓c�����������āA�V�����p���ŏj�t��������B��Ƃ͎Ⴂ���A�y���F�Ɠ��������̉��Ő�����������A�����ւ�e���������Ƃ̂��ƁB���̎��A�{���́u �ĎR����� �v���ƒm�炳���B�������N�ɂ������܂��A�ނ͉i���Ɂu�y���F�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂�����B�i�����A�����y�[�W�j
�s ������������A�ŋ߂܂œy��Չ��s���ԂƉi���t�i�}�����[�A1974�N5��10���j����ɂ������Ƃ��Ȃ������B���̗��R�Ƃ��āA�g�����g�ɂ���Ė{ ���̑����҂��c�������ƋL����Ă������Ƃ���������B�g������|�����{�ł͂����Ă������{�łȂ����߂ɁA�ǂނ̂���ɂ���Ă����̂��B�Ƃ��낪�A�F �V���O�s�C�܂�����p�فk�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA1996�j�́q�y��Չ��\�\�f�`�ƕ��Q�Ƌ��C�Ɓr��ǂނɋy��ŁA�悤�₭�{������肷��Ɏ������B�F �V���́u�挎���̉�L�œy�䎁�̑f�`�W���J�����Ƃ��A���S�l����Ղ����v�u�y��Չ�掁�̈�e�W�v�i�����A���Z�y�[�W�j�́q ��l�̐��E �� �ے����E �r��ʋΓd�Ԃ̂Ȃ��œǂ݂ӂ������A�Əq�����Ă���B�������̓y��̐�M����ǂ݂͂��߂��B
�@��ʂɁA�Q�[�e�̎���̔������͌��t�ƌ��t�̗���ɂ����A�ނ��뎍��Ǝ���Ƃ̊ԁA�s�ƍs�Ƃ̊ԂɁA���ꂴ�钾�قƂ����� ����ŋɂ̂�����Ă� �鋕���I�ȏœ_�Ɍ��o�����B�_�X�̌��t�́A���قƂ���������ł�������Ȃ��B�i�s���ԂƉi���t�A��O�l�y�[�W�j
�y ��Չ��͂��̂悤�Ɂu����̔������v�����v���҂������B�q��l�̐��E�Əے����E�r�́s���ԂƉi���t�̎O���̈�ȏ���߂钷��Ș_���ŁA�܂��Ǘ����� ���Ȃ��B�������A�g�����̎�|�����{���F�V���O�����āq�y��Չ��r���������邫�������ɂȂ������Ƃ́A�̂ɖ������B�c�O�Ȃ��ƂɁA�y�䐙��́q���Ƃ� ���r�ɂ́u���̏������������ɂ��ẮA�}�����[�̉�̌Óc�莁���͂��ߒ|�V���×Y���A���B�O���A���Ñ��Y���A�g�������A�W�J�~�ꎁ�A�揼�P���� �k�c�c�l�̌����ƌ�x�������������Ƃ������ɏ����L���ĉi���L�O�������Ǝv���v�i�����A�O��Z�y�[�W�j�Ƃ��邾���ŁA�g������̓I�ɖ{���Ƃǂ��W����� ���͂킩��Ȃ��B���҂ɑ��Ă͏o�ŎЂ̑����Ƃ��āA�O���̑����҂�Г��̕ҏW�S���҂����Ď��ɓ��������̂��낤���B

�y��Չ��s���ԂƉi���t�i�}�����[�A1974�N5��10���j�̔��ƕ\���k�莚�F�V���S�A�J�b�g�F���ҁA����F�c��
���l
�g�������s�Ȃ����Βk����k��́A�܂���{�ɂ܂Ƃ߂��Ă��Ȃ��B���O�ɏo�ł���Ȃ������̂͋g�����g�̈ӌ��ɂ�낤���i���������̕ҏW�҂������為�������Ɋ�悵���j�A���ЂƂ���y�Ȍ`�œǂ݂������̂��B����́A�g�������o�Ȃ����Βk�E���k��̊ȒP�Ȍf�ڋL�^�ƋL���̏����o����E���邱�ƂŁi�����ŋL�ځj�A�ˋ�̏����s�g�����Βk�E���k��W�t���T�ς��悤�B�Ȃ��A�o�Ȏ҂��̂��̂��u�Βk�v�A�O���̂��̂��u�C�k�v�A�����葽�����̂��u���k��v�Ƌ敪���āA�N�㏇�ɕ��ׂ��B
���Z�O�i���a�O���j�N�ꌎ�@�V�t�Βk�k�V��ޓ�Y�Ƃ̑Βk�l�i���㎍�j
�k�����o���Ȃ��l
���Z���i���a�l��j�N��Z���@�͌ЂƂ������E���k����N�v�Ƃ̑Βk�l�i���㎍�蒟�j
�����������ƂƎ��_����������
��i�̕ω��ɂ���
�g�����̎��̏o��
�g�����̎��̌��t
��i�ƌ����Ƃ̂�������
�����̏�Ԃ��珑���n�߂�
��㎵�O�i���a�l���j�N�㌎�@���`�̐��E�����k�剪�M�Ƃ̑Θb�l�i�����C�J�j
�g�����O�j�����߂�
���N���̏����Q
�����o�ꂷ��
�o�傩��̒E�o
���܂��܂ȏo����
�����ł��邱�Ƃ��K�v��
�X�g���b�v�̉F��
���꒤���̌���
�U���̗����
�ŗL�����̐��E��
������Ȃ��E�炷��
��㎵�܁i���a�܁Z�j�N��@���I�t�̌���k�ѓ��k��Ƃ̑Θb�l�i�����C�J�E�Վ������j
�u�k�v�̎���
�ɒB���v�́u�����C�J�v
�u�m���v�̎���
�u�_��I�Ȏ���̎��v
�u�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́v�Ɓu�V�N�̎莆�v
�^�c�ƃV�������A���X��
�u���{��A�v�̖��
�\���Ƃ��Ă̖g
���q�����Ɛ��e���O�Y
70�N��̎��l����
���I�t�H������
�w���q�V�S�x
�w���X�B�Ɓx
��㔪�Z�i���a�܌܁j�N��Z���@��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍������k������b�q�Ƃ̑Βk�l�i���㎍�蒟�j
�̌��Ƒz����
�o��E�Z�̂ƌ��㎍
���p���ɂ���
�J��Ԃ��������
�����I�Ȍ��t
�ڂ̐l
�ۂ��Đ��Â܂�̂���
��ؐV�������̂͂Ȃ�
�u��́v�ւ̎u��
���Z��i���a�O�Z�j�N�l���@�ǎ҂Ɩ{�̌��т��\�\�o�ōL���͂ǂ�����ׂ����k�S��V�閾�E���{�R�ʕ��Ƃ̍��k��l�i�}���V���j
���ɂɕ�������\�\���ʂ̂���L���A�Ȃ��L��
�h���I�Ȕz���@�\�\�\�f��Ɏ������@�I�Ȑ��i
�V���͕`�����\�\�o�ŎЁ@�t�F�e�B�V�Y���j��
�Ǐ��l���͂ӂ���\�\�̔������𗘗p������
�\���̏��]�����\�\���j�I�ǎ҂����ނ���
�V���͌��������ā\�\�����I�Ȃo�q�ŋ��͂�
��㔪���i���a�Z��j�N��ꌎ�@��b���Șc�݂̖����k���Y���P�E��������Ƃ̑Θb��]�l�i�����C�J�j
�k�����o���Ȃ��l
���Z�O�i���a�O���j�N�@����o��]�_�ܑI�l���k���k���q�����E�_�c�G�v�E��{���g�E�����d�M�E�������q�Ƃ̍��k��l�i�o��]�_�j
�n���m�Ύq
���{�퐶
���c���j
�O��O��
�|�{���i
�u����
�Ăѓn���m�Ύq
�����P��
�n���m�Ύq�ƒ|�{���i
����_�i
�剪��i
�Ƃɂ����i�낤
����ł͂ǂ�����
���Z�O�i���a�O���j�N�����@��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k���k������Y�E���ˉ�v�E�g��O�E���C�i��E�H�J�L�E�����ρE����l�Y�E����S���Ƃ̍��k��l�i���w�j
�I�l�o��
��㎵��i���a�l���j�N��Z���@����o�偁���̒f���k�����؍K�j�E���q�����E�����d�M�E���c�Îq�Ƃ̍��k��l�i��j
�o��Ƃ̏o�
�Z�̂�����Ƃ��������������
�w�O���\�N�x�̂���
���͓I�Ȏʐ^
�����܂������R
�����鎩�R���͂܂�Ȃ�
�{�L���u�����[�̕s��
���݂Ƃǂ܂��Č���
�o�d�͂�������
���Ђ̎�Ɏ�
��i���������߂̊����H
�s�Îq��L�t
��㎵�܁i���a�܁Z�j�N�@�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�k��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������Ƃ̍��k��l�i�Z�́j
���{��̎��l�E���e���O�Y����
������|�̉�
�o���E�ߋ��E�C��܂𑖂�
����̉̐l�Ƃ��̎���
�O���R�I�v�E��オ���O�ɂԂ�����
��㎵�܁i���a�܁Z�j�N�܌��@�v�z�Ȃ�����̎��l�k�ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�Ƃ̍��k��l�i���㎍�蒟�k���W�E��؎u�Y�NVS�g�������l�j
�g�̎��l��؎u�Y�N
��̓I�����𗹉�����
�U���ɑ���N���Ȉӎ�
���킢���l�A�����Ȏ��l
���g�����\�����x�点��
���ɂ�����U�����Ƃ͉���
��т̒��ю��ւ̖�
��㔪�Z�i���a�܌܁j�N�܌��`��㔪��i���a�ܘZ�j�N�l���@����o�������k�ѓc�����E�剪�M�E�����d�M�Ƃ̘A�ڍ��k��l�i�s�ӏ܌���o��S�W�E�S��t�������[�E����j
�����q�K�̏ꍇ
�q�K�ɂ�����m�Ԃƕ���
�q�K�ɂ�����o��ƒZ��
�E���Ȑl�̗E���Ȃӂ�܂�
�q�K�̏����̉���Ȃ�
�q�K�̘A��ے�̈Ӗ�
�o�傾���łȂ������q�K
�Ăюq�K�̉���
�q�K��Z���^�ɐ�O����������
�Z�ʖ��V�������q�K
�O�l�O�l�̎�
�Ɍ�˂Ƌ��q
�Ɍ�˂̉���Ȃ�
�Ɍ�˂������Ă����q�K
�����錩�ǂ���̂����ƂȂ���
���q�̕��@
���q�̔o�啜�A�̌���
�Ɍ�˂̖����S��`
�Ɍ�˂̔ߌ�
���ł���o��A�g�̂ł���o��
��│̔o��
�����Ƃ����l
�ΓC�̖���Ȃ�
�S��̌�����
�]�˂��q�o�l���b
�C���e���o�l�l�r�̓o��
�o�d�O�����ꂽ�l�r
�����̔o�d�E�̒d�E���d
�o�����X���Ƃ������q
�l�l�̐}���A�l�l�̋��ʓ_
����I�ȐV�N��
�f�\�̕��@
���̓��F
��q����ĂȂ��o�l
���݂ɂ����V���o��̎���
�V���o��^���Ɛ푈
����̓����ƒZ�́E�o��̊W
����ւ̔��R�̑�֕��H
���@�ӎ��̓���
�u�����Ė�v�̈Ӗ�
��^���d���V���o��
�V���o��Ǝ��R���o��
���Q�̎��l
���Ƃ��A�R����
�V���o��Ǝ��R���o��̋��ʐ�
���c�j�̖���
�g���ɂ���
��終Ɓu�o�v
��終̈�̑̎�
��終Ƒ��c�j�̊�H
��O�̏����A���̏���
�鏗�Ɛԉ��j
�鏗�Ƌv���E�����q
�E���q�Ȃ�
��O�̔o��E���̔o��
���o�l�ɂ����ʂ��c�c
�o��`���ւ̏�M���c�c
���厩�����߂�����
�������ɂ���Ɓc�c
��㔪�Z�i���a�܌܁j�N�㌎�@�V���|�W���E�� �i�c�k�߂̐��E�k���q�W�E�����d�M�E�O���q�Y�E�����r�Y�E�i�c�k�߁E��ؘZ�ђj�E���c�q���q�E�j�M�q�E�߉��P�v�E�Í��a��E��������E�������q�E�ѓ����q�E�����O���q�E���×��E��ؔ��E��ˏ~�v�E����o�X�q�E�Ԕ����q�Ƃ̍��k��l�i�o��j
�͂��߂�
�u�Q�߉ށv�̋�ɂ���
�}���s��̋�
�u�ߊC�Ɂc�v�̋�
���ݑ��G���`�V�Y��
�u���̐��Ɂv�̋�
�G��Ƃ�������
�u���E������v�̋�
�d�w�I�ȓǂ݂���
���_�̎��݂�
��d�̎��摜
���͂Ƃ��Ă̖���
��㔪��i���a���j�N�����@��ނȂ����I�����k�剪�M�E�߉ϑ��Y�E����N�v�E���J�K�M�Ƃ̐��e���O�Y�Ǔ����k��l�i���㎍�蒟�j
�l����Ɛ��n
���e���O�Y�Ƃ̏o�
�v�l�ƕ\���̉ߒ�
���W�ɂ�����鎍�I���E�̓W�J
�ꗬ�Ƃ��ẴC���[�W�Ɖ���
���ɂ�����\�z���ꂽ����
��㔪�܁i���a�Z�Z�j�N�ꌎ�@����Ǝn���k�I�N�^�r�I��p�X�E�剪�M�E�a��F��E�g�������Ƃ̓��ʍ��k��l�i���㎍�蒟�j
���{���Ƃ̏o�
�`�����ƌ��㎍
�c�̃A�����J
�|��Ǝ�
�u�j���G���Ɖf��
�A�W�A�ւ̎��_
�ȏ�̂ق��Ɏ��̌����Ƃ����L�������邩������Ȃ��B�������ĐU�肩�����Ă݂�ƁA�g�������ꏑ�������ɂӂ��킵�����e���O�Y�E�i�c�k�߁E�y���F�Ƃ��������l�E�o�l�E�����ƂƂ̑Βk���c����Ă��Ȃ��̂��A���Â��ɂ��܂��B�������s�y���F��t��������܂ł��Ȃ��A�g���̕M�������̑Ώۂ��݂��Ƃɕ`�������Ă��邱�Ƃ��������҂��ׂ��ł��낤�B���̑S���삩�炻�ꂼ�ꂪ�g�������s���e���O�Y�A���x�X�N�t��g�����ҁs�k�ߋ叴�t��ǂ݂Ƃ�悢�̂�����B
�k2010�N5��31���NjL�l
�g�����Ɛ��e���O�Y�̑Βk����k��ق�Ƃ��ɂȂ������߂Ē��ׂ��Ƃ���A�ѓ��k��̐��e���O�Y�Ǔ����q�ӔN�̐��e����r�ɂ���������߂��������i�������Ō�́u����ڂɂ͋g���������Ȃ����v�Ƃ����ꕶ�͏��o�́s�C�t1982�N8�����ɂ͌����Ȃ��j�B
�킽���͍��k1981�N�l�H����ł��l�x�����e����ɂ͉���Ƃ��ł����B�����z�[���Ő��e����̊G�̑��ړW���J����邱�ƂɂȂ�A����ɂ��Ȃ�ŎG���w�����x�Łi�����ɂ͐��e����Ɛe�������ǔ��̊C�����o�j��������j�A���e����ɃC���^�����[�����Ă���Ȃ����ƌ���ꂽ�̂��B�V����C�Â����āA����������ē���̃C���^�����[�ƂȂ�A�O��l���Ԃ��킽���͎��l�̘b�����Ƃ��ł����B����ڂɂ͋g���������Ȃ����B�i�s�ѓ��k��E���ƎU���Q�t�A�݂������[�A2001�N2��1���A���O�y�[�W�j
������̋L���́q�킽���̌ÓT�m20�n���e���O�Y�\�\�Ñ�M���V�A�̎��Ӂr�i�s�����t138���A1981�N10���j�ŁA�N���W�b�g�Ɂu�C���^�����[�E�� �ѓ��k��v�Ƃ���Ƃ���A�ѓ��̎��M�ł���B������́q�ӔN�̐��e����r��ǂ��ƂȂ�A�s�����t�f�ڋL���̒n�̕��́u�킽�������v�u�����v��e�̔����́u���݂����v���ѓ��Ƌg���i�Ɓs�����t�ҏW�E���s�l�̊C���j�̂��Ƃ��ƒm��邪�A�C���^�����[�L����ǂ����ł͒N���w���̂��킩��Ȃ��B������ɂ��Ă��A�ѓ����ɋg�����͓o�ꂵ�Ȃ����A�g�����������ł��낤������m�邷�ׂ��Ȃ��B
���́k�NjL�l�f�ڂɕ��s���āA�g���������O���\���������ɂ��S�������s�g�����g�[�L���O�t�ɕ҂B�{���A���Ȃ킿�g�����͂��߂Ƃ���b�҂����̔����������āA�Ҏ҂̎��M�ɂȂ�O�t�E���E��t���q�����{���������s�g�����g�[�L���O�t�r�Ɍf�����̂ŁA��������������Ƃ��肪�����B
�g�����̑��������Ƃ��A�u�����|�C���g�̐}�āv�i�ѓN�v�j�ƕ���ŖY��ĂȂ�Ȃ��̂�����̑��݂ł���B����͋g�������ɂƂ��ăg���[�h�}�[�N�̊���������B�g�����g�̎��W�̃J�b�g�E����̕`���������A�s�Õ��t�s�a���`�t���^�甎�A�s�Â��ȉƁt�s�ٗ�Ձk�����Łl�t�������A�s�T�t�����E�݁t�s�|�[���E�N���[�̐H��t���ЎR���A�s�Ẳ��t�s���[���h���b�v�t�����e���O�Y�Ƃ������z���i�Ƃ�����s�t�́t�̑���͒N�̎�ɂȂ�̂��낤�B�ʊǂ��������̂́A�g���{�l���j�B���������l�l�̂Ȃ��ŁA�g�������g�ȊO�̒��҂̖{������Ƃ��A�������N�p�����`���肪�������������Ǝv����B����͋g���������E�����Α���{�̂Ȃ�����A�������Y���W�s��̉��t�i����R�c�A1988�N6��10���j�����悤�B

�������Y���W�s��̉��t�i����R�c�A1988�N6��10���j�̔��ƕ\���k����F�����l
�s��̉��t�͌��蔪�Z�Z���A�d�l�͓�܌܁~��Z�܃~�����[�g���E�Z�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�p�\���k�w�F�b���̃N���X�A���F�n�j�T���h�J���[�l�E�g�����B���t�ɂ́A�Ǎ��Łu����ҋg��������җ����v�Ƃ���B�ѓ��k�ꎍ�W�s�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́t�i�y�ЁA1974�j�̑����҂ł�����������Y�́A���W�s��̉��t�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����ā^����Ă���B
�@���̘A��Ŏ�����Ă��̂́A�����g�̂����ɂ܂����Ă���A����s��`�Ȃ��́A�ӎ��Ɩ��ӎ��̒��ԂɕY���Ă��Ăǂ�Ȍ��t�ɂ��\�������t���Ȃ��悤�Ɍ������Ȃ��̂��A���Ƃ����ĕ\�o���邱�Ƃ������B����͗��R�̂Ȃ������̂悤�ł�����A���ӔC�ȕ@�S�̂悤�ł������āA�������C���������قǂɎ��ɂƂ��Ď��Ԃ��̂��Ȃ����̂ł���B�i�q���Ƃ����r�A�{���A�ܘZ�`���y�[�W�j
�@�w��̉��x���������̂́A�O�̎��W�k�w���̊X�̂ق�т�Ƃ��x�l�Ǝ����I�ɂ͂قƂ�Ǐd�Ȃ�܂��B�o���̂͂������̕���������ƒx�������ł��ˁB����́A�g��������̑��ꂾ����A���ꂢ�ł��傤�H�@�g��������Ă����͎̂��l�ŁA�}�����[�ɂ����l�ł����A����͂��܂������ł��ˁB���v�̊G���J�b�g�ɂȂ��Ă��ł���B���̎��v�𗎍�������Đl���`���āA���̃y�[�W�ɂ��Ƃ���ǂ���ɕ`���āA�S���j���Ⴄ�́B�܂�A���v�͓����Ȃ��ǁA�����͂܂���Ă���Ă��ƂŁA�j���Ⴄ��ł��B�Ƃ����������낢�G�������Ă܂��B�i�s�k�O�����w�ٓ��ʊ��W �掵���Y��ғW����}�^�l�������Y�\�\�w�H�̒����x����w�߂���̉́x�܂Łt�A�����Y�L�O�@���ƗƎ��̂܂��@�O�����w�فA2000�N3��4���A��O�y�[�W�j
�g���́s��̉��t�̈ȑO�ɂ��A�������Y���W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̑��������Ă���i�������A���̍�Ƃ̒��S�͓\�����j�B���l�Ƃ��ẮA�����̎��ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�Ö{���̎G���Ȃ�͐ς̈ł���A���͈���̔����{���A���̂Ȃ��֒����o���A�ԕ�����B�܂��^�V�����A����͈������Y�̏������W�s�H�̒����t�ł������B���i���F�̊��q���r�̌��t���A���̎��l�̎v�O�̖{�����A�I�m�ɑ����Ă���悤�Ɏv����B�k�c�c�l�����œ��ȓI�Ȃ��̎��l�́A�i�����Ԃ��������A�s�M�� ���̉́t���A��ߒ��Ƃ��A�₪�Đ��n�����A��i�s���̒��̍Ό��t��n��グ���B�i�s�������Y���W�k���㎍����79�l�t�A�v���ЁA1983�N4��1���A���\���k��Ǔ_���R���}�E�s���I�h�i�C�D�j����e���E�}���i�A�B�j�ɉ��߂��B�l�j
�g���������O�Ɋ��s���������̎��W�̖{���̊�{�Ŗʂׂ邱�ƂŁA���W�v�̓�����T���Ă݂����B�Ȃ��A�I�́s�|�[���E�N���[�̐H��t�͘��߂� ��鑕�������A���Ҏ����ɏ�������̂Ƃ��ē���Ɉ����B�ŏ��Ɏ��̕\�������������������B
| �� | ���� | �V�n | ���� | ���l | �ŏ� | �V�� | �n�� | ���E | �s�� | �s�� | �ŕ� | ���� | �m�h |
| �@ | �����G �� | 172 | 9 | 20 | 63 | 46 | 63 | 121 | 14 | 5.25 | 68 | 20 | 33 |
| �A | �t�� | 210 | 10.5 | 17 | 63 | 37 | 110 | 148 | 17 | 5.25 | 92 | 30 | 26 |
| �B | �Õ� | 188 | 10.5 | 30 | 111 | 49 | 28 | 131 | 11 | 10.5 | 77 | 34 | 20 |
| �C | �m�� | 190 | 10.5 | 27 | 100 | 35 | 55 | 145 | 13 | 10 | 90 | 30 | 25 |
| �D | �a���` | 202 | 10 | 27 | 95 | 45 | 62 | 150 | 13 | 10 | 88 | 36 | 26 |
| �E | ���� �� | 210 | 9 | 27 | 85 | 39 | 86 | 148 | 14 | 12 | 99 | 31 | 18 |
| �F | �_��I �Ȏ���̎� | 236 | 10.5 | 26 | 96 | 46 | 94 | 140 | 12 | 10.5 | 85 | 37 | 18 |
| �G | �T�t�� ���E�� | 220 | 10 | 34 | 119 | 33 | 68 | 142 | 14 | 8.5 | 88 | 37 | 17 |
| �H | �Ẳ� | 220 | 10 | 27 | 95 | 42 | 83 | 142 | 14 | 9 | 90 | 33 | 19 |
| �I | �|�[ ���E�N���[�̐H�� | 192 | 10.5 | 25 | 92 | 38 | 62 | 97 | 10 | 5 | 53 | 29 | 15 |
| �J | ��� | 245 | 12 | 33 | 139 | 37 | 69 | 173 | 15 | 9 | 108 | 43 | 22 |
| �K | ���[�� �h���b�v | 218 | 12 | 35 | 148 | 28 | 42 | 143 | 13 | 7 | 84 | 37 | 22 |
| ���� | 209 | 10.4 | 27 | 100 | 40 | 69 | 140 | 13 | 8.5 | 85 | 33 | 22 |
�q���l�r�̂����v�Z���̂Ȃ����ڂ́A�e���W�̏����������������ʁE���l�ł���i�������K�́q������ܒf�����сr�̂܍��k10.5�|�l��܍s�g�j�B
�O�̂��ߕt��������A�����͑g�ł̊�{�v�ł����āA�����Ȃ�u�e��v�ł���B�S�̂��T�����Ă݂悤�B
�{���y�[�W���i1�j�V�n���@�͂`�T���i�V�n�k��l210�~���E�k���l148mm�j���O�ŁA�i7�j���E���@��
�Z�߂̂`�T���������B�g�����W�̔��^�͋K�i���@�i�������j�����Ȃ��āA���������c���̕ό^�����ߔ����߂�B�c���̔䗦�̍������Ɏ��W����ׂ�A�I�A�F�A�G�ƇH�i���䗦�j�A�K�A�B�A�@�Ŏ����B�����͇A�A�E�i�Ƃ��ɂ`�T���j�œ���B�t�ɐ����������������ɕ��ׂ�A�J�A�D�A�C�̎O���ƂȂ�B
�i2�j�����|�C���g�͖{���̎g�p�����̃T�C�Y�ŁA��{�I��10�|���܍������A�J�ƇK��12�|�Ȃ̂����ڂ����B�܂��E��9�|�Ȃ̂͐�s�����s�g��
�����W�t�i�v���ЁA1967�j�̑g�ł𗬗p�������߂ŁA�P�s���W�̂��߂̐V�g�Ȃ�10�|���܍����̗p���ꂽ�͂����B
�i3�j���l���ŁA�@����s20���Ȃ̂͌��e�p���Ɠ����ɑg���߂��B��N�A�g���͎��M�Ɂu����Ɂv�̖�����̓������e�p���i32���~20
�s�j��p�������A�����Ă��㉺���ď����Ă���B
�i4�j�ŖʓV�n�̓x�^�g���قƂ�ǂ̂��ߌv�Z���ŏo�������A�����Ɍ����·A�͎��Ԏl���A�L�ł���A���ۂ̐��@��63mm�̖�1.25�{�ɂ�
��i�@�����Ԃ������Ă���j�B
�i5�j�V�̃A�L���i6�j�n�̃A�L���r����킩��悤�ɁA�Ŗʂ͊�{�I�Ƀy�[�W�̒���������ɔz�u����Ă��钆�ɂ���
�āA�B�������Ӑ}�I�ɉ��ɒu����Ă���B
�i7�j���E���@�ł͇J����O�I�ɑ傫�����A�i8�j�s��������Ƒ��̎��W��肻��قǑ����킯�ł͂Ȃ��B�܂��A���E���Z������
�����{�i�t�����X���j�A��������{���{�i�n�[�h�J�o�[�j�Ƃ����킯�ł��Ȃ��悤���B
�i9�j�s�ԃ|�C���g�͇I�������Ė{���̓ȏ�ŁA�S�p�s�Ԃ̂��̂������i�B�A�D�A�F�j�A�����Ă������Ƒg�܂�Ă���B
�i10�j�Ŗʍ��E�ł��J���ڗ��i�I�̖��{����j�B
�i11�j�������@���i12�j�m�h���@�ł́A�@�������ď����̕����L������Ă���i�@�̃m�h���L���̂́A�ܒԂ��ł��邱�Ƃ��e
�����Ă��悤�j�B
�� ���̎��W�̕��ϒl����ɂ��āA���ۂɊ�{�Ŗʂ�v���Ă݂悤�B���^�͂`�T�ό^���̓V�n209�~���E140mm�i�V�n�قڐ����ŁA���E���J�b�g�����c�� �{�j�B�{�������͌܍��A�s�Ԃ�8.5�|�B���l�߂�27���A�s����13�s�i1�y�[�W�Ɏ��e�ł��镶������351�j�B����ʒu�͓V����40mm���i�n���� 69mm��j�A�����̃A�L��34mm�i�m�h�̃A�L��22mm�j�B�m�h�A�����A�V�A�n�̏��ɍL���Ȃ銆�D���B�������A�g���������̂悤�ȔŖʂ�v������ ���ł͂Ȃ����A�P�s���W�����s����ɂ������ăC���[�W�������̂̂����悻�͂��߂邾�낤�B���Ɍ��J���y�[�W�̃_�~�[���f����B

�g������12���̎��W�̕��ϒl����ɐv������{�Ŗʁi���J����ԁj
��L�̕\�q�g�������W��{�Ŗʁr�̐��l����́A�V�n�Ɣŏ�i�s���j�̔䗦�A���E�Ɣŕ��̔䗦�A�y�[�W�ƔŖʂ̖ʐς̔䗦�Ȃǂ��Z�o�ł��邵�A�q�g���������r���q�g �����N���k��i�сl�r�� �Q�l�ɂ���A���ꂩ�玍�W���܂Ƃ߂����ƍl���Ă�����ɂ͑g�Őv�̖ڈ��ƂȂ邾�낤�i���W�v�̗v���́A���e���ʂ��Ȃ킿���s���ɂ���̂����j�B���� �͖{���̊�{�Ŗʁi�Ƃ��̍���ʒu�j�̕��͂ɏI�n�������A������m���u����W��܂��ɂ��Ă������������ł���B
�ѓN�v����́q�F�\�\�g�����̑���r�i�s�Ö{�X�P�b�`���t�A�|�ЁA2002�j�͒Z���Ȃ���A���ꂽ�g���������_�ł���B
�@�g���{�̓����͂܂����̃Z���^�[���킹�̃��C�A�E�g�ɂ���B�����E���Җ��i�c�g�݉��g�݂ɂ�����炸�j�A�����|�C���g�̐}�āA�Ō����A�����K�v�ŏ����̗v�f��\������уJ�o�[�̏c�̒���������Ƃ��Ă��Ƀo�����X�悭�z�u����B����́A�t�����X�̉��Ƃ��{�̉e���������͂��邩������Ȃ����A�N�����v�����A�N�ɂł��ł��邱�Ƃł����āA���̈Ӗ��ł͂܂��ɃA�}�`���A�I�ł���B�����āA�N�ɂł��ł��邱�Ƃ��݂��Ƃɂ���Ă̂���قǂނ����������Ƃ͂Ȃ��B�g���̓T�b�Ƃ���Ă̂��A���������̂�����Ȃ邽�����܂�������������B
�@���܂ЂƂ̓����A�V���̂��̂Ƃ����v���Ȃ����o�̔��I�́u�F�ʁv�ł���B���E�J�o�[�E�\���E���Ԃ��E���A�����Ė{�����B�����ЂƂЂƂ̃}�e�B�G�[���ƐF�������g���łȂ���������Č��W�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȑg�ݍ��킹�ɂȂ��Ă���B�i�����A��l�O�y�[�W�j
�t�������邱�Ƃ�����Ƃ���A�g�����̃��C�A�E�g�̍����ɂ́u���v�����������낤���Ƃ��炢�ł���i�Ⴋ���ɒ����Ƃ݂ĉʂ����Ȃ������g���́A�����q���������̖����F���m�̎�`�������Ă���j�B

�s�H�열�V��S�W �}���S�W���ځk��2���l�t�i�}�����[�A1971�N4��5���j�̔��ƕ\��
�����Ɍf�ڂ����s�H�열�V��S�W �}���S�W���ځk�S8���E�ʊ�1�l�t�i�}�����[�A1971�N3��5���`11��5���j�ɂ͑����҂̃N���W�b�g���Ȃ��B�т�����O�f���̎ʐ^�q�}�����[����i1951-78�N�j�ɋg���������ꂵ���Ǝv����S�W�ނ̈ꕔ�r�ɂ͖{���������Ă��Ȃ��i�s�H�열�V��S�W�t�͂��邪�j�B���ɂ́A��g���X�́s���{�ÓT���{��n�t�Ɏ��������F�̃N���X��\���Ⳃ̗̍p�Ȃǂ���A�g�������̂悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B����������āA�{�����s�g���������t�́q������i�ژ^�r�Ɍf�����B�d�l�͈ꔪ���~��O�Z�~�����[�g���E��2���͎l�O�Z�y�[�W�E�㐻�E�@�B�����B
�g�������s�u�� ���v�Ƃ����G�t�́q���Ƃ����r����������ŁA�S���ҏW�҂ւ̎ӎ��Ƃ��Ă���B
�@�����l�A�ܔN�̊ԁA����߂đӑĂȎ������������B���サ�A�U�킵�����͂�O�O�ɏW�߁A�ҏW���Ă��ꂽ���ؒ��h�Ɋ��ӂ���B�i�����A�O�l�܃y�[�W�j
���ؒ��h�͎v���Ђ̕ҏW�҂Ƃ��ċg�����̎U���W����|��������łȂ��A�G���Ƃ��ď��́u�g�������W�v��g��ł����B���Ȃ킿�A�s�� �㎍�蒟�t���Z���N��Z�����́q���W�E�g�����̐��E�r�ł���B�����̌�L�q�ҏW�̂��Ɓr��������B
�@�g�������̑S���W�����s�����̂��@�ɁA��㎍�l�̂Ȃ��ł��A�ۗ����ē��قȈʒu���߂Ă���ɂ�������炸�A���ʂ����ĂƂ� �������邱�Ƃ̏��Ȃ��� �����̎��l�ɂ��ē��W�����B�Ƃ�킯�A���̂悤�ȏꏊ�Ŏ��Ɋւ��Ă̔���������邱�Ƃ��w�ǂȂ������g�������g�ɁA���߂ēo�ꂵ�Ă�������Βk�́A���� �[�����ǂ݂���������Ǝv���B�i�����A��O��y�[�W�j
�� �ؒ��h�͎��l�ł���B���Z��N�́s����ɂ��̉S�t�ȍ~�̎��W�Ɩ������т��܂Ƃ߂��̂��A�s���ؒ��h���W�\�\1960�`1982�t�i����R�c�A1982�j ���B���蔪�Z�Z���A�d�l�͓��Z�~��~�����[�g���E��㔪�y�[�W�E�㐻�E�W���P�b�g�E�@�B�����B��؎u�Y�N�ƂƂ��ɖ{���̕ҏW��S�����������r�Y�� �q�㈲�܂Łr�Łu���B���g��������ɂƂ����A�C�f�B�A�͏���R�c�Ƃ̑ō����̒��ŏo�ė����B�g������Ԏ��ň��Ă������������Ƃ͊����������v �i�����A���Z�y�[�W�j�ƐU�肩�����Ă���B�����ł́A�Ñ�̚�̖͗l�̂悤�ȁA�s���̒J�̃i�E�V�J�t�^�C�g���o�b�N�̒ԐD�̂悤�ȃJ�b�g�i�N���W�b�g�� �Ȃ����A�N�̎�ɂȂ�̂��낤�j������䂭�B
 �@
�@
�s���ؒ��h���W�\�\1960�`1982�t�i����R�c�A1982�N4��30���j�̔��ƃW���P�b�g�i���j�Ɠ��E�{���ƌ��Ԃ��i�E�j
�������ق�q�g�����Ɓu�Г�����v�̎���r�i�s�����C�J�t�A2003�N9�����j�́A�n���ɏ[�����A��������Ƃ��낪���ɑ����C���^�r���[�L���ł� ��B���Ƃ��A�g���̍�ƌ����m�鑕���ƂȂ�ł͂̎��̔����B
�@�\�����J�����Ƃ���ɂ��錩�Ԃ��ɂ��ẮA�g������͒W�N���[�����E���ȂǁA�����N���[���F���D��Ŏg���Ă��܂����B���� ��͂����肵���F�̌��Ԃ� �͍D�܂�Ȃ�������ł��B�i�`�������ȁA���邳���Ȃ����B��ʓI�ɂ͕\���̐F�Ƃ̃o�����X�ŁA���Ԃ��ɂ͂�����ƐF�̂�������p���邱�Ƃ������̂ł� ���A�\�����J������A�������炷�łɖ{�����n�܂��Ă���Ƃ����ӎ����g������ɂ͂������Ǝv���܂��B����ƑS�W�͂����Ă������ďd���̂ŁA��͂� ��v�Ȏ��łȂ��Ƃ����Ȃ��Ƃ������Ƃ��������ł��傤�ˁB��N�́A�t�@���V�[�E�y�[�p�[�ł̓V�}���������D���ł����ˁB�i�����A��l�O�y�[�W�j
�ǂ����Ă�����\���E�{���ɖڂ��s�����������A�u�\�����J������A�������炷�łɖ{�����n�܂��Ă���v�Ƃ������Ԃ��ςɂ͓��S���������B
 �@
�@
�s�����V�g�S�W�k��1���l�t�i�y�ЁA1982�N7��15���j�̔��Ɩ{�́i���j�Ɠ��E�{���ƌ��Ԃ��i�E�j
����́A�q�q�g �����r�����r�ł��G�ꂽ�����V�g�̑S�W�����悤�B�g���͍����S�W�̓��e���{�ɐ��E���q�킪�V�g�]�r���Ă���i�P�s�{�����^�j�B�S���������B
�@�킽�����������V�g����̎��ɁA�G�ꂽ�̂́w�����V�g�̎��W�x���ŏ��������B������A���a��\�l�N���̂��Ƃł���B���̂Ȃ��Ɏ�ʁu�邷�v���������B�� �ꂩ��w���́x�܂œǂ݁A����u�b�v���߂łA�V�g����̎��ƕʂꂽ�B�킽�����͒N�Ƃ��ʂ��B
�@���̓`���I�Ȏ��l�Əo��A�l�ԓI���͂ɖ�������B���R�Ȃ���A�����Ăѓǂ݂͂��߂��B���̎��I�F���͍L���A�_�_�C�Y�������т���A�T�@���͂�ސ��X �̍�i�Q������B���ƍ��\�\���邢�͓łƖ����������A�������A�������Ă���B���Ⓘ�����Ă���̂����킩��Ȃ��B����ł���Ȃ���A�s�v�c�ƑN���ɁA���� ���ԂƁA�v�z�̊j���A������̂��B�i�s�����V�g�S�W�t���e���{�A1982�N1��1���A�y�Ёj
�g���́s�����V�g�S�W�t�i�����Z�Z�Z���A�d�l�͓���~��܈�~�����[�g���E�㐻�E�\�����j�ɂǂ̂悤�ȑf�ނ�I�肵�����B�\���͒��̕z�N���X�� �i�s����N�v�q���r�W���E1951�`1978�t��g�����s�u�� ���v�Ƃ����G�t�������邢���F�j�B�g���ɂƂ��Ē}�����[�ȊO�̔Ō�����̑S�W�ł́A�s�� ���d�M�S�W�t���ł��[���ւ��Łi�ҏW�ψ��E�����S���E���M�j�A���e���{���M�E�����S���́s�����V�g�S�W�t�͂��̎��Ɉʒu����B�Ǖ��ɂ��ċg �����ƍ������̊W���q�ׂ����͂�m��Ȃ����A�s��ʁt�ȍ~�̎��Ƃƍ����̕��ƂƂɐ�ʈ�����������͎̂��������낤���B
�߉ϑ��Y�͒Ǔ����q�g�����Ǒz�r�ŋg�����̐l�ƍ�i��U�肩����A���̑����ɂ����y���Ă���B
�@���Z�ܔN�A�������W�w���y�x���o���Ƃ��A���s���̏��c�v�Y�ƈꏏ�ɔނ�K�˂đ���𗊂B�ȑO�ɏo���ނ́w�a���`�x�Ɠ��^�̃t�����X���ł���B�薼�ɂ��Ă��A�����ɎO���R�I�v�̏����Ɂw���y�x�Ƃ��ӑ肪����A���������C�ɂȂ�w�g�́m�A�A�n���y�x�Ƃ����Ƃ��t����������A�Ƃ��������A�ނ͌����ɁA����w���y�x�ōs���ׂ����ƒf�肵���B�w�g�́x�����ւ���A���̑薼�ɂȂ����炤�B
�@��㎵�O�N����n���Y�S�W�̕ҏW�����̐��N�Ԃ́A�}�����[�Ŗ��T�̂₤�ɔނƊ�����������̂��B�S�W�̑���ɂ��ẮA�w��{�L�x�\���̉��F�ƁA�w���ς̐��`�x����̃f�U�C���̃A�C�f�B�A���o���đ��k������A�ނ�������ɂ����A�����ʼn����Č����ȑ���Ɏd�グ�Ă��ꂽ�B�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����A�O�O�y�[�W�B�̂����z�W�s���̒�t�i���V���X�A1992�j�Ɏ��^�̍ہA�����ɉ��߂��Ă���j
 �@
�@
�߉ϑ��Y���W�s���y�t�i�v���ЁA1965�N7��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ƌg�������W�s�a���`�t�i����ɁA1962�N9��9���j�̔��ƕ\���i�E�j
���W�s���y�t�͌���l�Z�Z���B�d�l�́A��Z��~��l���~�����[�g���E��Z�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���i������E���{���Ƃ��s�a���`�t�Ƃ͈قȂ�j�B�J�b�g�����B�S�̂̃e�C�X�g���炢���ĊԈႢ�Ȃ��g�������������A�����҂̃N���W�b�g���Ȃ��B�c�O�Ȃ��ƂɁA���E�\���Ƃ��u�߉ϑ��Y���W�v�Ƃ������g�̊����̕��т��o�����X�������Ă���B���̂̉������낤���A�c�g�ł͋C�ɂȂ�Ȃ��u���v�̎����傫������̂��B���ɓ߉ϑ��Y�������Ắs�����Y�S�W�t�ɓo�ꂵ�Ă��炨���B

�s�����Y�S�W�k��1���l�t�i�}�����[�A1975�N5��25���j�̔��ƕ\��
�d�l�͂`�T���E�㐻�E�\���B�{���̑����Ɋւ��Ắq�����ł��˔\�������鎍�l�̋g�����r�ɋg�����̃R�����g������B�u����A�Y�S�W�Ȃ�����Ǝ����Ȃȁv�u�����Ă̂͊ԈႤ�ƐԂ��ۂ��Ȃ����蔒���ۂ��Ȃ����肵�āA�ނ������v�i�s�����V���k�[���l�t�A1976�N4��27���A���ʁj�B�\���p�N���X�i�A�[�g�J���o�X�j�̐F�ɂ����G��Ă��Ȃ����A���́u�����Y�S�W�v�Ƃ��������g�͊������B���ƕ\���ŁA�s���ς̐��`�t����̈ʒu���Ⴆ�Ă���̂ɂ����ڂ������B
 �@
�@
�q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�s�ʍ����㎍�蒟�t��2���A�v���ЁA1972�N6���j�̔��i���j�Ɠ��E���ʁi�E�j
�N ���W�b�g�ɂ́u�{�����C�A�E�g �c�ӋP�j�v�Ƃ��邪�A�s�ʍ����㎍�蒟�t�i��1����2���A�q���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�r�A�v���ЁA1972�j�Ɍf �ڂ��ꂽ�q���C�X�E�L��������T�����@�r�i���O�A����`��Z�l�y�[�W�j�́A�L�������̎ʐ^���ނɁA�g�������ƃ����^�[�W���݂̂Ȃ炸���C�A�E�g�܂Ŏ�| �������̂�������Ȃ��B����A�ʐ^�B�e�̂��߂ɐV���Ɉ�{�w�����Ƃ���A�O�ɋ��߂����̂����I�����W�F�����������ɑւ���Ă����i���̕ʍ��͉��x������ ����Ă���j�B�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߂̎��сq�����r�ŁA���́q���C�X�E�L��������T�����@�r�ɐG�ꂽ�ӏ�������̂ŁA����𐳂��Ĉ��p���� �i�s���Y��� ���t��24���A1994�A�q�u�����̖��̂͂�ݕ��v�r���j�B
�@���o�q���C�X�E�L��������T�����@�r�́A���q�ł͂��������ق��̔��̖{���p���Ƃ͕ʂ̉��������������ɍ����A���̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă����B
�@�E��y�[�W�߁@�^�C�g���q���C�X�E�L��������T�����@�r�i�`�������̓L�������Ɍh�ӂ�\���Ă̂��̂��B�q�����ۂ��������A�g���̎�ɂȂ邩������� ���j�A���M�Җ��B������
�@Photo by Lewis Carroll
�@Poem & Montage by Minoru Yoshioka
�Ƃ��āi����͎ʐ^�̃L���v�V�����A�܂���������ӎ��������C�A�E�g�Ɍ����Ȃ����Ȃ��j�A���̍��ɃL�������B�e�ɂ���H�̏����ɕ������A���X�E���f�� �̑S�g���́u���v�B
�@�E��`�O�y�[�W�߁@�q�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�ƍ��v���l�́u�A���X�����v�̎ʐ^�k��o�sLewis Carroll�\Photographer�t�̐}�Ŕԍ�32�A54�A34�A60�A17���m�[�g���~���O�A42�A29�l�B
�@�E�l�`���y�[�W�߁@�q�����`���r�ƁA���v��ܓ_�̎ʐ^�ɕ����߂�ꂽ�u�A���X�����v�k������15�A53�A5�A49�A37�A59�A4�A16�A51�A39�A43�A30�A13�A44�A40�A28�A36�A14�A10�A3���m�[�g���~���O�A50�A46�A52�A26�A62���قƂ�ǃg���~���O���Ă��Ȃ��l�B
�@�ʐ^�̏��������̕\��͈�l�ɈÂ��B�˖{�M�Y�̃A���X�_�Ɍ�����`�ʂ����u���Ƃւ}���[�E�~���[�͓Ɩ[���Ȃ���̕����̋��ɁA�ǂЂ߂�ꂽ�g ��͐s�������ɂ��Âق�A�ؚ��ȋr���ɓ����o���Ă�邪�A���̗e�e�̓W�����k�E�����[������B�܂��A�A���X�E�W�F�[���E�h�k�}�}�l�L���͓�K�̏o���� ��E�o���悤�Ƃ��ď��E�҂��ǂ��ɑ@�����q�ɋr�������Ă��Ƃ���B�G���U�x�X�E�q���b�Z�[�͂��䂰�ɐQ�֎q���ςꂩ���āA���̛Z���܂��ڂ̓I�_ ���X�N�̕���ł���v�i�˖{�M�Y�s�����̏H�t�A�l�����@�A1974�A�����y�[�W�j�ŁA���̗ނ̎ʐ^���s���O�O�_����B
�@�g�����͍����N��Ɂq�����`���r�̍쎍�@����������Ă���B�u�w�s�v�c�̍��̃A���X�x��ǂ�ł܂��������A���Ɂw���̍��x��ǂA����������A�� �Q�����B���́A�����Ŏ~�܂��Ă����̂��A���܂��܌K���Εv�N�Ɂw�ʍ����㎍�蒟�L���������W���x�̂��߂ɏ������Ă������ꂽ�̂ˁB�����Ŏ푺����́w�i ���Z���X���l�̏ё��x�̒��̃L�������_��ǂ肵�Ă��邤���ɁA�����J���Ă����B�Ƃɂ����A�L�������̎B�������������̎ʐ^�����̏�ɕ��ׂĂ����āA�� �O�������o���Ă݂��B�����Ă��̃L���v�V�����݂����Ȃ���Ŏ��������Ă䂯�����Ǝv���ƁA���̋C�y�����N���Ă��āA�����ȃX�s�[�h�Łu�����` ���v�������オ������ł��B���̖��O�Ƃ����̂��A���Ȃ茈��I�ȏd�v�����ڂ��ɑ��Ă����ƂɂȂ�̂ˁv�i�����N��s�m���Z���X��S�t�A�����ЁA1977�A�O�ܔ��`�O�܋�y�[�W�j�B��㐢�I�C�M���X�̓��b��ƁE�ʐ^�ƂƓ�Z���I���{�̎��l�E�����Ƃ��o�������u�Ԃł���B
�@�Ƃ��Ɂu�L�������̎B�������������̎ʐ^�v�Ƃ͋�̓I�ɂȂɂ��B�푺�G�O�́s�i���Z���X���l�̏ё��t�i�|�����X�A1969�j�ɂ́u�L�������̎ʐ^�i�w�h �E�x�����B�E��̓L�������j�v�i���O�A��܁��`��܈�y�[�W�j�Ƃ�����ɎG���̕��ʂ����J���ōڂ��Ă��邪�A�����̃J�b�g�͑S���ŋ�_�k14�A42�A15�A36�A29�A39�A50�A51�A17�l�Ə��Ȃ�����A�g�����˂����͖̂�쐟�q���q�s�ł̏����r�ŐG��Ă���u�w�����[�g�E�Q�����V���C�����w�ʐ^ �ƃ��C�X�E�L�������x�B���Z��N�h�[���@�[�̐V�łŁA�����͎l��N�Ƀ����h���Ŋ��s����Ă���v�i�s�ʍ����㎍�蒟�\�\���C�X�E�L�������t�A�ꔪ��y�[ �W�j���A���̃R�s�[���낤�B�V�ŁiGernsheim, Helmut�sLewis Carroll�\Photographer�t, Dover Publication, 1969�j�͂�肠���e�Ղɓ���ł��邩��������ς�Έ�ڗđR�Ȃ̂����A���͕S�N�ȏ�O�̒j�́A�����ւ̊�̗~�]�ɋ����E�]�V���ւ����Ȃ������B�O���O ���A��̐l�ł������g�����������̎ʐ^�Ɋ������Ȃ������ƍl���邱�Ƃ͕s�\�ł���B
�@���ю��M�̏����́A�����炭�q�����`���r�̇T�ɑ����ćU��������i���̂Ƃ������̎��傩�瑍�肪���܂ꂽ�\��������B�{�������i�s���}�����o���̕� ���ڎ��������ȑ薼�q���C�X�E�L��������T�����@�r�ƈقȂ�A�P�Ɂq�L��������T�����@�r�ƂȂ��Ă���̂́A���肪�����͂₭���Ă̂܂ܕҏW�҂ɓ`����� �����ʂ��j�A����Ɋp�앶�ɔŁs���̍��̃A���X�t��ǂ݂Ȃ����A�s�킯�́q�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�������ꂽ�A�Ƃ����z���낤���B
�sLewis Carroll�\Photographer�t�͂��̌�A�M�o���B�w�����b�g�E�K�[���Y�n�C�����s�ʐ^�ƃ��C�X�E�L�������t�i�l�����i�E���V�~�q��A�� �|�ЁE�ʐ^�p���A1998�k��{��1949�N���̌����l�j�ł���B�h�[���@�[�̐V�łɎ��^����Ă���L�������B�e�̎ʐ^���A�i���G�ł͂Ȃ��j�{���Ɍf�ڂ� ��Ă��邪�A�L���v�V�����̒����y�[�W�ȂLjꕔ�Ƀg���~���O���{����Ă���A�g���̃����^�[�W���f�ނƂ܂����������G���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�k2004�N2��29���NjL�l
�K���Εv�q���C�X�E�L�������̎ʐ^�p�r�̎��̋L�ڂɁi�Ăсj�o������B�u���Ȃ݂ɁA�����̎ʐ^�́A�g���������g�����C�A�E�g�����A���̃y�[�W�̗p����
�ł����g�őI�ꂽ�B�I�̂͋I�B�㎿�̃T�[�����s���N�ł������v�i�s�f�������t1996�N9�����A�Z�y�[�W�j�B�S���ҏW�҂̂��̏،��ɂ���āA�g����
�̃��C�A�E�g�ł��邱�Ƃ��͂����肵���킯���B��̕��������ɂ������āq���C�X�E�L�������̎ʐ^�p�r���Q�Ƃ��Ȃ������i���m�Ɍ����A�����̐�����������
�A�N�Z�X�ł��Ȃ������j�̂�����܂��B
�t�����X���́A�\���Ƀ{�[�����̐c������㐻�{�Ƃ͈قȂ�A�ǂ����Ă����x���o�ɂ����B�{�����d�����̂ɂ͌����Ȃ��̂��B�v���Д��s�g�������W�t�̃u�b�N�f�U�C���͐��Y�N�������A���ꂾ���̃{�����[���ɂȂ�ƕ\���̗p���������Ȃ�A�t�����X���{���̌y�����͂Ȃ��B��Z�Z�y�[�W�ɖ����Ȃ��P�s���W�ɂ����A�t�����X���͂ӂ��킵���B�g�����̎��W�ł����s�Â��ȉƁt�̂悤�ȁB�����̎��W�����̂悤�ɑ��������A���Ă͂��Ћg���ɑ������Ă��炢�����A�ƍl���鎍�l���o�Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B�����ɐ�����q�̎��W�s�Ҏ��ԁt�i�v���ЁA1974�N6��1���j������B����O�Z�Z���B�d�l�́A�`�T���E�Z�l�y�[�W�E�����t�����X���E�@�B���B�Ȃ��o�ŎЁ��v���ЁA���������t����ЁA���{�����⍲���{���Ƃ��s�Â��ȉƁt�Ɠ����ł���B
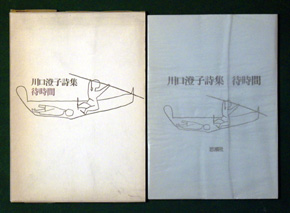 �@
�@
������q���W�s�Ҏ��ԁt�i�v���ЁA1974�N6��1���j�̋@�B���ƕ\���i���j�Ƌg�������W�s�Â��ȉƁt�i���ЁA1968�N7��23���j�̋@�B���ƕ\���i�E�j
�g���̈��ܔ��N���������̓��L�Ɂu����N�v�A������q�Ƃ����ނ�ŐH���B�f�~�A���ł����B�v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��ꔪ�y�[�W�j�Ƃ��邪�A����͓����A�g���ƂƂ��ɒ}�����[�̎Ј��������B�Ǎ�̎��l�������悤�ŁA�s�Ҏ��ԁt�͈��Z��N���玵��N�ɂ����Ă̎����т����߂�B5�߂���Ȃ�U�����q����r�i���Z��N�����j�́u1�v�������B
�H��D���o�Ă䂭�Ƃ��@��ɂ͎O�̑��z���������@�`�͍Ձ@�����X�J�[�g�������r�ŖD�����킳���@����̉��ł́@�q�������̓���Ł@�����̂������F�̊����ꂽ�@�Â���ǂ����ꗎ���@���̉��̒r�Ł@�V�l�����������ɗ��ł���@���̂Ƃ��@�H��D�̐��v�����́@���h���P�����Ȃ���Ђ����ɕd��������@���̒��ɂ́@��̊C�����B����Ă��Ȃ��@����̂��邵����d��
����͎��W�����Ȃ��āA����ȑO�ɂ́s�V�������t�����邭�炢���B�\�\��N�ɂ������͂��邪�A��O���W�s�C�����̓��ɂāt�i�v���ЁA1986�j�͖������i�{�����t�����X�����Ƃ����j�B�Ȃ�Ƃ����ās������q�S���W�t���o�Ȃ����̂��낤���B�Ə������Ƃ���ցA�C���^�[�l�b�g�Œ������Ă����s�V�������t�i������ӎЁA1962�N7��22���j���͂����B
�k2021�N5��31���NjL�l�Ō��́u������ӎЁv�͍�������}���ق̏����Ō������Ă��q�b�g���Ȃ��B�v���ɁA���Ђ͂�����ӂ̉�s�̓��l�G���s������Ӂt�֘A�̐}���̔��s���ł���A���W�s�V�������t������̎���o�ł������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ����̂��s���{�̌Ö{���t�Ō������Ă��u������ӎЁv�Ńq�b�g����͎̂��W�s�V�������t����������ŁA�����s���n��h���́u�������[�i�{�X�j�v��1���ƁA�����s�r��搼���闢�́u���� �c���v��2���ł���B��҂ɂ́u����200���E���E�������p���t�E�R�{�P�i�����̉�E������ӌn���l�j���������@�ǍD�@A5���@�g�������@��ꎍ�W�v�A�u����200���E���E����l�Y���������@�����P�X���@�����p���t�B���Ɍo�N���P�@�������]��L�@A5���@�g�������@��ꎍ�W�v�Ɛ���������B
�͂����邩�ȁA���W�s�V�������t�̑������g�������B�d�l�́A�e���E���l�y�[�W�E�����t�����X���E�i�{�[�����ɓ\�O��̋@�B���A�����Z�Z���B�����ɂ́q���상���r������A���ܓ�N�����́q�A�J���C�r������Z��N�O���́q�킽���Ɣn�r�i�q�g��i���Ɏ~��r��z�킹��Y�сj�܂ł̓�Z�т����쏇�Ɏ��߂��Ă���B������q�i1935�`2002�j�ɋg�����ɐG�ꂽ���͂����邩�ڂ炩�ɂ��Ȃ����A��������̎��W�̑����𗊂��Ƃ����ׂĂ���Ă��悤�B

������q���W�s�V�������t�i������ӎЁA1962�N7��22���j�̋@�B���ƕ\��
�k2021�N5��31���NjL�l
�i�]�N�s�}�����[ ���ꂩ��̎l�\�N 1970-2010�k�}���I���l�t�i�}�����[�A2011�N3��15���j�ɕҏW�҂Ƃ��Ă̐�����q�̋Ɛт��T�������L�q������B
�@��㎵�Z�i���a�l�܁j�N�Ɏn�܂����u���{���l�I�v�i�S�O�Z���A�����j���A���f�I���ʂ̂ЂƂ������B�V���[�Y�������邩����A���}�ȍ����w�n�̕]�_�W�Ɍ�����B�����A���M���Ă��钘�҂́A����ɂ킽����̈悩���䏊�E�C�s���W�߂��Ă����B�剪�M�w�I�єV�x�i��7���^��㎵��N�j�A�g�{�����w�������x�i��12���^��㎵��N�j�A�ےJ�ˈ�@�w�㒹�H�@�x�i��10���^��㎵�O�N�j�Ȃljz���I�ȑg�ݍ��킹�����邩�Ǝv���A�����w�̂Ȃ��ł���s�ȓlj��������Ă���v�c�����w�L�I�̗w�x�i��1���^��㎵��N�j�A�����M�j�w���o�鏴�x�i��22���^��㎵�Z�N�j�Ȃǂ̖��O�������āA�o�����X���݂��Ƃł���B
�@������q�i���O�܁\��Z�Z��N�j�ɂ��ꖡ�s����悾�������A�c�O�Ȃ��ƂɊ����ɂ͎���Ȃ������B�k�c�c�l�i�q���́@���Z�Z�N��A�������Ɋ��͍L�������r�́u�u���f�v������Q�v�A�����A���y�[�W�j
������q�́A�k�g�����̑�����i�l�Ƃ��ďЉ����B�玍�W�s���I�i���h�̑D�Ɋւ���f�Е⑫�t�i�v���ЁA1969�N4��10���j�i�g�����̑�����i�i57�j�Q�Ɓj�A�R�{���g�́s���̎��o�̗��j�\�\�������̎��l�m�����тƁn�����t�i�}�����[�A1979�N2��25���j�i���i110�j�Q�Ɓj�A����Y��Y�E���Ò��v�E���|���L�́s�a��Ɗ���̂������\�\�@�_�S�C��ǁt�i�}�����[�A1985�N6��10���j�i���i28�j�Q�Ɓj�A�J�c�����s��z ���̕��w�t�i�}�����[�A1988�N4��25���j�i���i15�j�Q�Ɓj�Ƃ��������ЂɁA��B��Ɠ����O���[�v�̎��l�Ƃ��āA�}�����[�̕ҏW�҂Ƃ��Ċւ���Ă���B�i�]�O�f���ɂ�1966�N11��17���́u�S�З��s�v�̏W���ʐ^�i�����ɌÓc��A�O�l�����ċg�����B����109�l�j���ڂ��Ă���i�����A����y�[�W�j�B�����͑S�̂̎O���̈�قǂ����i����h�̘a�������A�����̗m���̕��������j�A���ꂪ������q�Ȃ̂��͂킩��Ȃ��B
�g�����͖����s�̎U���q�c��m�Ǒz�r�i�s�����C�J�t1989�N6�����k�Ǔ����c��m�l�j�ŁA���������Ă���B
������A�ҏW�҂h�k���Ɏ����W�s���D�t�̒S���҂ł��������Έ䗧�i���j�Ǝv����l����l�̐N����Ă����B�߂����s����|���̑��{�E����̑ō����̂��߂��B���ꂪ�ےJ�ˈꂾ�����B�����܂�舒B�Ȑl���ɂЂ���A�ȗ��A�e�����G�k����悤�ɂȂ����B�₪�āA�O���A���E�O���[���́w�s�Ǐ��N�x�i�u���C�g���E���b�N�j���o�ł��ꂽ�B��g�c���N����̐V�N�ȃt�����X���̖{�Ɛ������B�i�����A�Z���y�[�W�j
�O���A���E�O���[���i�ےJ�ˈ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A1952�N5��20���j�̎d�l�́A�a�U���E����y�[�W�E�����t�����X���B�{�����ɂ́u����@��g�c���N�v�ƃN���W�b�g�����邪�A�g���̕��͂��炷��Ɓu����@��g�c���N�v�A�u���{�E����@�g�����v�Ȃ̂��낤�B
 �@
�@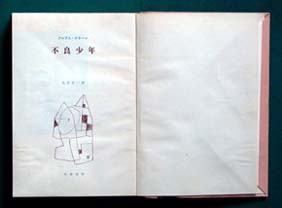
�O���A���E�O���[���i�ےJ�ˈ��j�s�s�Ǐ��N�t�i�}�����[�A1952�N5��20���j�̕\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�ےJ�ˈ�s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�͋g�����̑����ł͂Ȃ����A�g���̓��L�Ɂu�k���a�O�\�ܔN�l�܌�����@�ےJ�ˈ�Ƃ����B�s�G�z�o�̊������āt�Ƃ��Ƃ��o�ł���邱�ƂɂȂ�B�v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���O�y�[�W�j�A�g���̎��M�N���Ɂu�ےJ�ˈ�Ɖ�Ћ߂��̋i���X�ʼn�A�w�G�z�o�̊������āx���o�ł���邱�Ƃ���ԁB�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j�Ƃ���̂ŁA�֘A���Ƃ��Ă����Ɍf����B���͂��̌���{�𗴐����т̃I�����C���V���b�v�œ��肵�����A�ق��ɂ��ےJ����g���ɁA�ӂ���̌�F���悤�ɁA�ŏ��̕]�_�W�s���̂Ԃāt�A�������낵�̒��я����s��������l�̔����t�A�������낵�̒��ѕ]�_�s�㒹�H�@�t�i����͒}�����[�������A�g���̑����ł͂Ȃ��悤���j�Ȃǂ������Ă���B
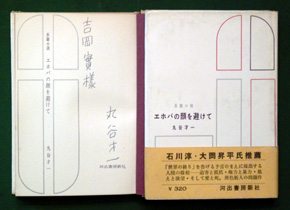
�ےJ�ˈ�s�G�z�o�̊������āt�i�͏o���[�V�ЁA1960�N10��10���j�̖{���ƃW���P�b�g�k�����������l
�k2009�N4��30���NjL�l
�ےJ�ˈ�́s���A�͂����ւt�i�����V���ЁA2001�N6��1���j��ǂ�ł�����A�q����V���Џ����ɂ��ār�ɁA�ŏ��̒��я����s�G�z�o�̊������āt�́u���i���F���͏o�̍�{��T����ɂ������āA�o��₤�ɂȂ���ł��B���̂Ƃ������^��Y�����Џo���āA�o�ŋL�O�����J���Ă��������܂����B�ΐ�~���X�s�[�`�ŁA�u�ےJ�N�̖{�͏\�N������ƕ����܂������A�\���N������ΐe�̋w�����Ă邩������Ȃ��v�Ƒ\��Z��ɂ����Ă̈��V�Ԃ��ł����v�i�����A�����y�[�W�j�Ƃ������B�ނ��W��́u����V���Џ����k�V�������ł͂Ȃ��l�v�͒��ё�5��́s��������t�i���Y�t�H�A1993�j�ŁA�ےJ�̃X�s�[�`�́s�G�z�o�̊������āt�ȗ��A2�x�߂̏o�ŋL�O��ƂȂ����u�ےJ�ˈꂳ��Ɓw��������x�̉�v�ł̂��́B
�i���j�@�ےJ�ˈ�i1925.8.27�`2012.10.13�j�̈⒘�s�ʂ�̈��A�t�i�W�p�ЁA2013�N10��10���j�̍Ō�̏́q�X �Ō�̈��A�r�́q�����̕��w��n��r��2012�N8��28���A�R�[�g�E�h�[���ŊJ���ꂽ�u���̒S���ҏW�҂�������v�ł̈��A���f�����Ă���B�`���́u�킽�����͂��߂Č���҂��ҏW�҂́A�O���A���E�O���[���w�u���C�g���E���b�N�x�̖|����w�s�Ǐ��N�x�Ƃ��ӑ�Œ}�����[����o���Ƃ��̒S���A�Έ䗧����ł����B���a��\�Z�N�̂��ƁB�m�I�ŁA���{�̂���A���w���D���ȁA�S�̗D�����W���[�i���X�g�ŁA�ŏ����悩���������A�Ȍ�A�D�G�ȁA�����̂悢�ҏW�҂����Ƃ����ӂ��ƂɂȂ�܂����v�i�����A�O��܃y�[�W�j�ł���B�a�c�F�b�́q���̐l�Ɋ��҂���\�\�ےJ�ˈ�r�ŐΈ䗧�i1923�`1964�j�̍��ʎ��ɐG��Ă��āi�a�c�͂����ŊےJ�Əo������j�A�Έ�Ƃ͒}�����[�u�̑O�̐E��ŁA��������ɓ��������Ƃ�����v�i�s�ےJ�ˈ�k�Q�� ���{�̍�� 25�l�t���w�فA1997�N3��20���A���O�y�[�W�j�Ƃ�������A�}���ł��x�e�����̕ҏW�҂������悤���i�a�c�F�b�͒}�����[�ŕҏW�҂��������Ƃ͂Ȃ����A�����̗z�q���}���̎Ј��ƂȂ����B�̂��̋g�����̍Ȃł���j�B�ѓN�v������q�Έ䗧�̎d���r�ɂ́u�G���w�W�]�x�̕ҏW����X�^�[�g���A�ŏ��Ɏ肪�����P�s�{�͑��Ɏ��w���B�����̍ȁx�i���l���N�����ܓ��A�ѕ����q����j�ł���B���ɂƂ͂��Ȃ�e�����t�������Ă����悤���B�v�Ƃ���A�q�ł��邩����悫�{�@�Έ䗧�̎d���Ɛ��̕��w�k�O�ҁE��ҁl�r�i�s�k�C�w����w�w���_�W�t145���E146���A�k�C�w����w�w�p������A2010�N9���E2010�N12���j���Љ�Ă���B�k2013�N12��31���E2020�N12��31���NjL�l
 �@
�@
���Ɏ����W�s���D�t�i�}�����[�A1957�N6��20���j�̔��ƕ\���i���j�����E�{���i�E�j
���Ɏ��̎��W�s���D�t�i����500���j�̎��сq�Ɛl�r�i1957�N2��8���E�e�j���A�g�����́q�ߋ��r�i�B�E17�j�Ɠ���̎�Ȃ̂ŁA�Ǎ��݂ň��p���Ă݂����i�����͐V���ɓ��ꂵ���j�B
�R�}��̓��Ђ��^�r�j�[���̑傫�ȑ܂̒�����^�����Č�����B�^�N���܂��Q�N�������`�Ղ̂Ȃ��x�b�h�̏�ɁB�^�^�^�������^�ǂɂ����܂ꂽ�����B�^�����́^�z�e�����A�^�a�@�̈ꎺ���B�^�₽�����Ɂ^�g���K�N�̉ԂƁA�^�s����U���������Ă���A�^�Ȃɂ��̊i���̐Ղ̂悤�ɁB�^�^�l�͐��̉�U�̎c�[���g���ā^�����֓����Ă����̂��낤���B�^����Ƃ��N���ɂ�������������āA�^���̏����ɍ����Ă���̂��낤���B�^�ǂ���ɂ��Ă��A�^�A���o�C�̌����ʂ����ɁA�^�؋���Ζł��Ȃ���Ȃ�ʁB�^�^�����Ɩ��V�a�҂̂悤�Ɂ^��������O�֔��������ƁA�^��̑O�Ɂ^�傫�ȉ͂�����Ă���B�^�ł������A�^���̂قƂ�ɂ́^�N�����Ȃ���D�̂ЂƂƂ��B�^�����ց^���̏؋��̕i�𓊂����Ă悤�Ƃ�����A�^�܂̒��̃R�}�ꂽ�����^�����ɋ��т������B�^�\�\�߂͏����I�^�\�\�M�l���Ɛl���I�^�\�\�߂͏����I�^�\�\�M�l���Ɛl���I�^�^�����̐����́A�^�l�́^��������^�O����������Ă����B�^�^�l�́^���͂悶��A�^�_�o�͂��̒ɂ݂̂��߂Ɂ^���Ƃ��Ƃ��ڂ��o�܂��A�^��̑O�����́A�^�g���l���̒��̂悤�ɐ^���ÂƂȂ����B�^�����ĉ����ւ����Ă��ʁA�^���̑傫�ȑ܂��������ɒu�����܂܁A�^���܂ł��͂̂قƂ�Ł^��Â����B
���Ɏ����W�s���D�t�i�}�����[�A1957�N6��20���j�ɂ́A�g���ݎЎ��̒}�����[�̖{�ɂ͒������A�u����@�g�����^�}��@���R�c��Y�v�Ƃ����N���W�b�g��������̂́A��d�͌�҂ɂ���B�d�l�́A�`�T���ό^�i����~��l���~�����[�g���́s�m���t���ق�̏�����Ԃ�j�E��O�l�y�[�W�i�}��Z�t�j�E�㐻�۔w�N���X���E�\���B���́q���Ƃ����r���u�Ȃ����̎��W�o�łɓ����āA�}�����[�̐Έ䗧�E�g�����̗��N�̋��͂����Ƃ������납�犴�ӂ���B�v�i�{���A���܃y�[�W�j�ƌ���ł��邪�A�g���ɂ͚��ɐG�ꂽ���͂��Ȃ��悤���B
�ȉ��́k�NjL�l�ɚ��Ɏ��i1897�`1975�j�̍Ō�̒P�s���W�ł�����f�㊧�́s�V����t�i���⏑�[�A1976�N8��25���j�̏��e���f����B�����̎d�l�́A�e���i���Z�~��ܓ�~�����[�g���j�E��O�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�z���E�\���B���J���̖ڎ������y�[�W����ƁA���W�����f���������i��y�[�W�j�̑Ό��y�[�W�i�����y�[�W�j�ɂȂ邪�A���̃m�h���Ɂu����@�g���@���v�ƃN���W�b�g������B���Ȃ݂ɁA�g���͓W�Ƃ��\���ɗΌn�̐F���̗p���Ă���B
�k2014�N9��30���NjL�l
���Ɏ����W�s�V����t�i���⏑�[�A1976�N8��25���j�ɂ͓��������[���犧�s���ꂽ���������100���{������B��ŏЉ�����y�Łi�Ƃ����\���͂Ȃ����j�����t�̖����Ɂu�㐻�@�艿�@��܁Z�Z�~�v�Ƃ���Ƃ���A��������ł́u�����@�艿�@�O�Z�Z�Z�~�v�Ƃ���A���̏㕔�ɂ́u��������100���̂����^�{����51�ԁv�Ɖ��g�ň���i�u51�v�͎�̕M�����j�A����Ɂu��v�̎�悵�Ă���B���̉��t�y�[�W���قȂ邾���ŁA�{�̂͗��łƂ����Ԃ��̗p�����܂߂ē����d�l�̍قł���B���Ⴗ��̂́A�\���i�ΐF�̕z���ɑ��A���F�̊v���j�A�\���i�����N���[���F�̗p���ɗΐF�̃J�b�g�ɑ��A�W���O���[�̗p���ɒ��F�̃J�b�g�j�̊O��肾�����B�O���[�̔��͖{���̗����Ɋ��s���ꂽ�s�T�t�����E�݁t�i�g���̎����j�̂�����A���F�̊v���\���͎��W�s�_��I�Ȏ���̎��k���Ҏ��Ɩ{�l�t�i���쏑�[�A1974�N10��20���j�̂���i�����͋g�����A���쐬�ꂩ�j��z�킹�邪�A�s�_��I�Ȏ���̎��k���Ҏ��Ɩ{�l�t���苖�ɂȂ����ߔ�r���邱�Ƃ��ł��Ȃ��͎̂c�O���B
 �@
�@
���Ɏ����W�s�V����t�i���⏑�[�A1976�N8��25���j�̓\���ƕ\���i���j�Ɠ����k��������Łl�̓\���ƕ\���i�E�j
 �@
�@
���Ɏ����W�s�V����k��������Łl�t�i���⏑�[�A1976�N8��25���j�̖{���i���j�Ɠ��E���t�i�E�j
������@�Ɂs�V����t���ēǂ������A�܂������V��ɂ��鎍�l�́A�����������������Ƃ�����B���������ɂ͎��̎��̋C���̕����D�܂����B���Ɏ��́q�������r��Ǎ��݂ň����B
���܂��܂ȐF�Ł^�敪�����ꂽ�A�^�Ԗ͗l�̂悤�Ȑ��E�n�}���A�^���ꂽ�C�̐��Ɂ^�n���Ă��܂����B�^�傫�ȍ����^�����ȍ����A�^�嗤���^�������A�^���⍻�����^�T�����炵���悤�ȓ��X���A�^�킽���̎��E�����������A�^�ݕӂ̂Ȃ��L��ȊC�̏���A�^���^����Ȉ�H�̍����������ł���B�^����͂Ȃ�Ƃ��������A�^���̖��͒m��ʂ���ǂ��A�^�܂�ʼni����ڎw���ā^���ł���悤���B�^�����z�A�^���̐��̍Ō�̐����c�肩���m��ʂ��A�^�����z�̏I�������͂�����̂́^���������N�ł��낤�B
���W�̉��т��ɖS�Ȃ��o�ꂷ��B���̍Ȃ́s��\�l�̓��t�̏����ƚ��h�����A1967�N�ɓ����E������{�̌F�J��@�ŖS���Ȃ��Ă���i���N67�j�B���͒����ʂ�ɖʂ������̈�@�̑O��ʂ邽�тɁA���h���A���Ɏ���z�������ׂ�B
 �@
�@
�s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فA1981�N11���j�̕\���i���j�Ɠ��E���ʁi�E�j
�g�����̃��C�A�E�g�Ƃ��Ēm�����i�͏��Ȃ��B���́s���e���O�Y�̊G��t�́A�������p�فi�����E�`��j�ŊJ���ꂽ�q���e���O�Y�̊G��r�W�i1981�N11��9���`30���j�̐}�^���B�d�l�͂a�T���E��l�y�[�W�E���Ԃ��B�\���̂݃J���[�B�g���́q���e���O�Y�A���x�X�N 13 �G�͔������u���[�E���ʂ�r�Ő��e�̎��сq�_�X�̉����r�����������ƁA���������Ă���B
��N�̏\�ꌎ�ɑ������p�قŁA�u���e���O�Y�̊G��v�W���Â��ꂽ�B�k�c�c�l���āA���p�������́A�ē��ژ^�̔��Ɍf����ꂽ���̂��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�Z�y�[�W�j
���͂��̓W����͊ςĂ��炸�A�u�ē��ژ^�v����ɌÏ��œ��肵�����̂��B�u���ʁv�ʐ^�̉E���ɂ́A���́s�Ẳ��t�̑�����f�ڂ���Ă���i�����̊G�ɂ́A��N�A�V���s���p�قőΖʂł����j�B
�k���e�搶�́l���{��̕M���g���A���̖ڂ̑O�ŁA�O�l�̏��_�����ŗx���Ă���G��`���ꂽ�B����͂܂��ɁA���̎��ɂӂ��킵���G���`�b�N�ȕ���������B�i���O�j
�g�����̓t�����X�����������B�����o���s���� �G�߁t�ȍ~�A�����̎����Ƀt�����X�����̗p���A�˗����ꂽ�����ɂ������ꂽ��i���₵���B�y���F�́s�a�߂镑�P�t�����̑�\���낤�B�d�l�͋e���E�{����O�l�y�[�W�E�����t�����X���E�\���i�\�O��j�B
 �@�@
�@�@
�y���F�s�a�߂镑�P�t�i�����ЁA1983�N3��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
 �@�@
�@�@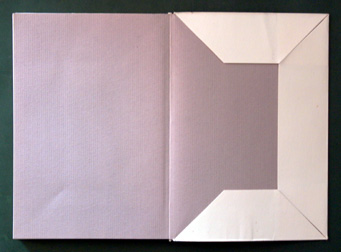
�y���F�s�a�߂镑�P�t�i�����ЁA1983�N3��10���j�̖{�̂Ɣ��i���j�Ɠ��E�\�����߂������Ƃ���i�E�j
�g ���́A���N�Ԃ�ɓy���F�Ɖ������㔪��N���Z���̓��L�ɂ��������Ă���B�u�k�ҏW�S���́l�a�C���ɂ��Ȃ�����A�w�a�߂镑�P�x�̑��{�E����̑ō� ���ƂȂ������A���ׂĂ܂����ꂽ�悤�ŁA���������ӔC���d���Ǝv�����v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A��l��`��l�O�y�[�W�j�B�ȉ��A����������� �̂́A�g���������g�̑����Ɋւ��ď������ł����ׂȌ��ł���B
�k�c�c�l�a�C���Ɖ�A�A�X�x�X�g�ق֍s���B�y���F�͋��ԂɂЂƂ肢��B�k�c�c�l�t�����X���̑����{����������A��������C�ɓ������悤���B�i1983�N2��3���j�e���r�œ������ۃ}���\�����ς�B���ÑI��D���B������O�ɏo���A�w�a�߂镑�P�x�̑���ɖv�����A�[��O���Ɋ����B�i2��13���j
���߁A������g�b�v�Řa�C���Ɂw�a�߂镑�P�x�̑���̕����A�J�b�g�y�ѐF�Ȃǂ̎w�菑��n���B�i2��14���j
���}�v���U�l�K�̃p�[���[�j�V�����ŁA�a�C���Ɖ�A�\���A���A���̊O��\��̐F�Z���ȂǁB�i2��24���j
�ߌ�A�v���U�̃j�V�����ŁA�a�C���Ɖ�A�w�a�߂镑�P�x�̌��{�������B�������{�ɂȂ����Ǝ���������A�y���F�̔����͂��܂ЂƂ� �������炵���B�����ꂻ�̂����C�ɓ��邱�Ƃ��낤�B�i3��10���j
�y���F�̎g���̎҂���������{�Ƒ�㉮�̍Œ��ꔟ�͂��ɗ����B�i3��30���j
����Z�N�A�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�̑ł����킹�ŊďC�̕��o������A�ҏW�̑�������j����Ƌg���Ƃ�K�₵������A�p���`�ŋ��ɕR�ŊȈՐ��{�����y���F�̘A�ڂ����ɂɂ���̂������B����͑������˗������܂����łɁA�g���i���邢�͗z�q�v�l�j���肸����܂Ƃ߂��蔲���������̂��낤���B�A�ڂ̑攪��i�s�V���t1977�N12�����j�ɂ́A�g������㔪��N��s�����C�J�t�Վ��������ɔ��\�������сq�H�v���r�i�J�E8�j�̖����u((�l�Ԃ͂������ЂƂ�ŏĂ��ł���))�v�̃X���X�Ǝv�����u�k�c�c�l�V�k�́A��������l�ŏĂ��ł��Ă���k�c�c�l�v�Ƃ����s��������i�y���F�s�a�߂镑�P�t�A�����ЁA1983�A����y�[�W�Q�Ɓj�B
�k2011�N4��30���NjL�l
�u�g�������̑���P�����A���蕜���ŁI�v�̓y���F�s�a�߂镑�P�t�i�����ЁA2011�N3��15���j�����s���ꂽ�B�ō����i4,200�~�B�Ȃ��q�g�����Ɠy���F�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�g��������|���������ȊO�̑��������s���Ō��Ă������B�܂��͕ҏW�ψ��{�Z�E�V��ޓ�Y�E�����O�V�E����N�v�E���c�O�E����r�Y�E�x���j�E�X���ߒr�̕Ҏ[�E�Z���ɂȂ�s�Z�{ �{�V�����S�W�k�S�\�l���i�\�܍��j�l�t�i�}�����[�A��㎵�O�N�܌���ܓ��`��㎵���N��Z���O�Z���j�B����͋g�����}�����[�ɍݐЂ��Ă�����㎵�O�N�܌����犧�s���n�܂��Ă��邽�߁A�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A�g���������\������̂Ƃ����Ă悢�B�d�l�͂`�T���E�㐻�E�N���X���E�\�����E����t�B
�u���e�̂��ׂĂ�����ɂ��A���m�ɒ��鑐�e�{�ʂ̑S�W�v�i���������́s�V���j���[�X�t�j�Ƃ��āA�J��Ԃ��ǂނ̂ɂӂ��킵�������������d�オ��ɂȂ��Ă���B���S�W�̌���Ɉ˂�u�攪�{����R���N�[���ŁA�{�S�W�����{�}���ً���܂���܁v���Ă���B��҂͒}�����[�Ȃ̂��낤�B�Z�{�S�W�̓ǎ҂��s�����܁t�Łs�L�����t�Ƃ̗ގ����w�E���Ă����̂ŁA���݂ɗ��҂���ׂ��ʐ^���f����B
 �@
�@
�s�Z�{
�{�V�����S�W�k��7���l�t�i�}�����[�A1973�N5��15���j�̔��Ɩ{�́i���j�Ɠ����ƐV���o�ҁs�L�����k���Łl�t�i��g���X�A1969�N5��16���j
�̔w�\���Ɣ��i�E�j
�������ɖ{�̂̃N���X�Ɣ��̐F�����ʂ��Ă���B�����A�Ζ���̒}���̍L�����Ɂs�L�����t�����������Ƃ͊m�������A�g���͂��łɁs���e���O�Y�S�W�t�i��㎵��`�j�ŐԂ́A�����Ő́A�̂��́s�����Y�S�W�t�i��㎵�܁`�j�ʼn��̃N���X���g�p���Ă���i���c�N�v�Ɂq�g�����A���邢�͓����N���X��������̊��r�Ƃ��������_������j�B�s�L�����t�ɂ́u���� ����\���Y�v�Ƃ��邪�A��g���X�Œ������{��S�����A�s���{�ÓT���{��n�t�Ȃǂ���|�������X�P�v�̑��{�v�ł���ƕ����B
�k��Z��O�N�㌎�O�Z���NjL�l
�ȏ�̕��́A��Z�Z�O�N�ꌎ�A�q�g�����̑�����i�r�̑���Ƃ��ď������B�u�g��������|���������ȊO�̑��������s���Ō��Ă������v�Ƃ���̂́A�u�����v���q�g���������r�ŕʂɈ����Ă��邽�߁B�{�e�ł̎d�l�̐����͊ȗ��ɉ߂��邵�i����������������̈����ʂ��j�A�Ώۍ�i�̖{���̊T�v�ɂ��G��Ă��Ȃ��B���Ȃ�A���M�̍\�z�i�K�i���e�ȑO�j�̂��̂ł���B�ӂ��A����ɒʓǂ������͏E���ǂ݂������z����ѕ��͂̈��p�A�������e�̑��̏��{�i���̏ꍇ�A���̌����S�W�A�Ƃ��ɐ�s���铯�ДőS�W�j�Ƃ̔�r�A�d�l��f�U�C���E���C�A�E�g�̔�]��ς݂����Ă����āA���͂ɂӂ��킵���ʐ^���B�肨�낷�B���̈Ӗ��ŁA�{���Ǝ��T����ׂ��Ӑ}�͈����Ȃ��B���̂悤�ɁA��N�̎��M�p���Ƃ��Ȃ�قȂ镶�����A�����̈ӂ����߂āA�����̂��肳�܂������ĂƂǂ߂Ă����B
�k�͂��߂Ɂl�@�g�����̒����ɂ͂��Ȃ�̐��̓����{������B���̂��ׂĂ���Ɏ�����킯�ł͂Ȃ����A��������@��̂��������̂ɂ��ď����Ă݂�B ���{�̊��s���ł������B
�g�����̓����{ �ڎ�
���W�s�t�́t�@���W�s�Õ��t�@���s�ٗ�Ձt�@���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�@���W�s�T�t
�����E�݁t�@���W�s�Ẳ��t�@�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�@��
�W�s��ʁt�@���L�s���܂�͂����L�t�@�������[���k2004�N2��29���NjL�l�k�����2020�N6��30���NjL�l
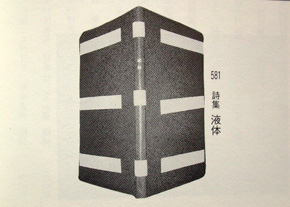 �@
�@
���W�s�t�́k�����{�l�t�̕\���k�s�����������Ï��ژ^�t�i2003�N3���j����B�Ȃ�������200,000�~�l�i���j�Ɠ����̉��t�Ό��y�[�W�ƒ��ҏ����y�[�W�i�E�j�k�o�T�F�g�������W �t�� ���v������8���{ �����l
��������Z�Z��N�ɐ_�c�E�_�ے��̓c�����X�ŁA�����ē������ʉp�����X��K�̋H�w�{���[���Ŏ�ɂ������A���z�Ȃ��ߍw�����Ă��Ȃ��B�c�����X�̃V���[�E�B���h�E�ɂ������̂����܂�ɒ����������̂Őu���ƁA�X��̉����W�ꂳ������߂Ĉ������Ƃ̂��Ƃ������B�ʉp�����X�ł͂������ƌ���ꂽ�B��Z�Z��N�������_�ł̓��X�̃E�F�u�T�C�g�ɂ͂����������B�u����8�� �ѕM������ ���v�� ���쏑�[ ��46 �p���u�n���鋛�vNo.2�v�B�����͓�Z���~�B�s�t�́t�Ċ��{�̕\����ς��āi����Ƃ����\�������Ԃ��̂悤�ɓ\�肱��ŁH�j���邪�A�\���̐ΐF�̑��v�ɑ��߂̔����v�т��O�{�A�A�N�Z���g�Ƃ��Ĕz����Ă���B���{�̉��t�Ό��y�[�W�ɖn���i���쏑�[��l�̎�ɂȂ���̂��j�̉������Y�t���Ă���B�ȉ��ɂ��̋L�q��]�ڂ���B
�i�Ȃ��E�̃J���[�ʐ^�́A2016�N�A���t�I�N�ɏo�i���ꂽ���́B�u���a46�N9���A���쏑�[������8�����s�̂���6�ԁB�v�o���h�t�����v���A�������B�p���u�n���鋛�v�̈���Ƃ��Ĕ��s���ꂽ���̂̌���8���{�ł��B���͒i�{�[���̓����ł��B�v�j
�u�{���͔����Ɍ���
�����{�������
���쏑�[�k�A���l�@�V�v
 �@
�@
���W�s�Õ��k�v���{�l�t�̔��ƕ\���k���c�唪�������l�i���j�Ɠ����̕ʃJ�b�g�k�ʐ^�F���܂��莁�l�i�E�j
����ɂ��Ă͋g�������g�����ܔ��N�����l���̓��L�ɏ����Ă���B
�u�s�Õ��t�v���{�܍��ł���B������A�ԎO���B�x�E�v�ɍ��B�唪�A�k��ɐԂ�B�v�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A��ꔪ�y�[�W�j
�����N�i��Z�����������ꌎ��l���܂Łj�A�����_�ސ�ߑ㕶�w�قŁq���{�̎��̓W�\�\���E�Z�́E�o��̈�Z�Z�N�r���J�Â��ꂽ�B�����ɏo�i���ꂽ�̂����v���{�́s�Õ��t�ł���B�������ɞH���u1955�N�i���a30�j8��
���ƔŁ^����́A3�N��ɍ�����v���{5���̂�����1���v�B���͂����W�����Ƃ��Č������A�߈��̎��W�Ƃ��������������B�����̃t�����X���̕\�����v�ɂ������̂��낤�B
�k2005�N11��30���NjL�l���c�唪�����̐Ԋv���{������@����B�{���̂܂��̈꒚�ɁA�u�唪�Ɂ^���v�ƕM�Ō��提��������B���t�ɂ́A�ق��̖{�Ō������Ƃ̂Ȃ���悳��Ă���i�ʐ^�Q�Ɓj�B
 �@
�@

���W�s�Õ��k�v���{�l�t�̌��提���y�[�W���J�����c�唪���k2005�N11��30���l�i���j�Ɠ������t�y�[�W�ɓ悳�ꂽ���k�ʐ^�F���܂��莁�l�i�E2�_�j
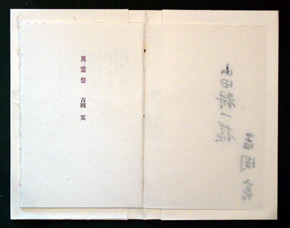
���s�ٗ�Ձk�����Łl�t�i����R�c�A1974�N7��1���j�̖{��
�c�����X�ōw�������Ƃ��̓��L�i����ܔN������Z���j������̂ŁA�ʂ��Ă݂�B
�u����A�v���Ђ��猻�㎍�蒟2�����f�ڂ̋g���������̌��e��18,000�~�i20,000�~�ɑ��Č���10���j�����؎�ő����Ă����B������
14���͂��~�Ƃ������Ƃ������āA�����̐^�����ɂ���Q��ɍs���Ă��������ɁA���肠�킹�̖���������B�����ŁA���˂đ_���Ă����s�ٗ�Ձt�����ł�_��
���̓c�����X�ōw�������B�\�̃E�B���h�E����X�̐l�ɏo���Ă��炤�������A��l�Ƙb���B�S���W���o�邱�Ƃ��m���Ă����B�u�����A���Ȃ��͔N��������Ă���
��ł����ˁv�B
�\�\�s�����G�߁t���ܔ��c�Ŕ������l��m���Ă��邪�A�S���Ȃ����B����܂�D���l����Ȃ��������ǁA���̌�A�o�Ă��Ȃ��ˁB
�\�\�����炮�炢��������ł����B
�\�\500,000�~���ȁB�g������̖{����A�������B
�W�J�����g���v�l�̘b���o���B50,000�~�̂Ƃ���A2,000�~�����Ă�������B���肪�����B
�Ђ����łՂ�Ղ�̒��H���B���A���͂���Ă��炸�A���O���ŋ����H�Ƃ����Ȃ����B���̂��ƁA�G�X�E���C���ŃP�[�L�ƃA�C�X�R�[�q�[�B���쒬�̘H�n�͉�
���B�v
�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q��]�ڂ���B
�u�ٗ��
����101���̓�
�k�L�ڂȂ��l
�k�u���q�v�̈�̑̍ق̓ʔŁl
���q3
���a�l�\��N����������s
�u�ٗ�Ձv
���ҁ��g����
���s�ҁ��R�c�k��
���s��������R�c�@�����s�ڍ��掩�R���u��m���m��Z�i���R���u���r���O�K�j
�@�@�@�@�@�@�d�b�^�����i03�j����O�\���Z���@�U�����^������Z������
�����������ЖH���������
���{���ݓc���{��
�艿��蔉~�v
 �@
�@
���W�s�_��I�Ȏ���̎��k���Ҏ��Ɩ{�l�t�̛�i���j�Ɠ��E���Ԃ��i�E�j
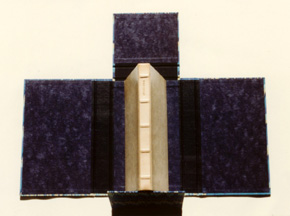
���W�s�_��I�Ȏ���̎��k���Ҏ��Ɩ{�l�t�̛エ��і{��
�� ���������������Ҏ��Ɩ{�́A�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�ŏ�����҂ލۂɁA�g���z�q���璘�Җ{�����肵�ĂԂ��Ɍ����B�{�̂͏㐻�����v�p�w�˂����\���A�t�H�[���X�o���h�i���N�܂j�B�w�̏� ���ɏ��������������B�����p�ʒ��a�����J���\���B�{���p���i�����ɓ����j�̉��t�Ό��y�[�W�ɓ\���t�u���Ҏ��Ɩ{8���v�Ƃ���A�A���r�A�����ɂ��L�ԁB�g ���Ƒ��{�́u1�v�B���Ԃ��͕ЖʌܐF�i���E���y�E���E��E���j�}�[�u�����߁B�Ԑ�Ɍ��Ԃ��𗬗p�B��͌ܐF�i���E���E���E���y�E���j�}�[�u�����߂� ���̎l����B���W�\���Ȃǂɍ��̘a���B

���W�s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�i���쏑�[�A1975�N6��1���j�̕\���ƛ�
���̏�����������ł́A�����N�܌��O�Z���A�g�����O����̐^�����ɂėz�q�v�l���璸�Ղ������́B�{���͓�F���ŁA�����t�����X���i�\���͍��菲���ɂ��I���W�i���ؔʼn�ŔZ�ΐF�ɍg���N�₩�j�B�p�\���̛�i�w�͗����������F�̊v�A���͔��̊v�A�v�R�ǂ߁j�B�{����12�|�ł������Ƒg�܂ꂽ���{�����A�ɂ��ނ炭�͌�A������B�Ȃ��A�����E���̓��{�ߑ㕶�w�قɂ͋g�������������������B �ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q��]�ڂ���B
�u�g�����̎��W�u�_��I�Ȏ���̎��v�����{�͏��a�\�N�Z���������S�\�������s����B���s�҂͓��쐬��A����͖��É��s�����̒|�c����A���{�͋��s�����̐A�c�R���A�ےÎs�����{����̎O�̓�l���쏑�[�����s����B
No.129�v
 �@
�@
���W�s�T�t�����E�݁k�����{�l�t�i�y�ЁA1977�N1��15���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�\�����J�����Ƃ���i�E�j
�� �s�E���䏑�[�̌Ï��ژ^�Ɂu���@�w�v�E���[���b�p�X�ё��v�Ƃ���������B�����g����������Ҏ[����1990�`91�N�����A�g���Ƃł͌��Ȃ��������A�W�� �P�b�g�ŕ����Ă��ē����{�ƋC�Â��Ȃ������̂�������Ȃ��B�{���͎s�̂́s�T�t�����E�݁t�O���{�i�y�ЁA1977�N1��15���j�̔��i�тȂ��j�E�W�� �P�b�g�E�{���͂��̂܂܂ɁA�T�t�����F�̕z�\�����p���\���i�w�E�v�k�w�����́u�T�t�����E�݁@�g�����v�Ǝs�̖{��菬�U��ɋ┓�����l�A���E���[���b�p�X �сj�ɁA�ЎR���`�����Ԃ���Z���s���N�̖��n�̗p���ɕς��������{�i�ԕz�͉��Ǝ�ɕύX�A���̞x�R���t�����j�B���t�͎O���{�ƑS�������ŁA�u�����{�v�� �\������Ɋւ���N���W�b�g�͂Ȃ��B�{���̍�����Ɂu�b�v�Ɖ��M�������Ă���A��������܂��L�O���Ă������������삵�����̂Ƒz����B
 �@
�@
���W�s�T�t�����E�݁k�����{�l�t�i�g�ԎɁA1977�N1��15���j�̛�ƕ\���i���j�Ɠ��E����J�����Ƃ���i�E�j
�u�����Łv�Ƃ����ď̂ł͂Ȃ����A�n粈�l����̏���g�Ԏɂ̌ܕ������{������B������s���㎍�ǖ{�t�̎�����҂ލۂɒ��Җ{�����肵���B�\��
�́A���������s���s�k
�ߕS��k�����Łl�t�ɍ������Ă���B
�c�����X�̃E�B���h�E�ɏ����Ă�����{�����������A���z�Ȃ��ߍw���ł��Ȃ������B�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q��]�ڂ���B
�u�����{�@�T�t�����E��
���a�\��N�ꌎ�\�ܓ����s
����ܕ��̓��{���͑���
���ҁ@�g����
���B�@�n粈�l
�@�@�@�@�\���̒O�g���z�ɗp���������͍��J�a���g��
�@�@�@�@�D�͉͌��O��q�@���s�X�c�a���̋��͂ɂȂ�
����@����
���{�@�{�쐻�{��
���s�@�g�Ԏ��v
 �@
�@
���W�s�Ẳ��k�����Łl�t�i��h���ǁA1982�N4��15���j�̔��ƛ�i���j�Ɠ��E�\���ƛ�Ɣ��i�E�j
��
����������ł��B�V���A�㐻�a���p�w���p�[�`�����g���A��i�w�p�[�`�����g�A���X�сj�A�X�ѓ\���A�ѕM�����Ŗ{���g�ŁE�p�����́s�Ẳ��t��������
�i���сq����杁r�̕s����C���j�ɓ����B�{�e���M���_�ŁA�ʉp�����X�ɓW������Ă���i�ܔԖ{�j�B���X�̃E�F�u�T�C�g�ɂ��u�g���� ����15��
�ѕM������ ���v�� �V�� ��h���� ��57 ���Ƃ� ���v�ŁA�����͎O�ܖ��~�B�ȉ��ɒ��Җ{�̉��t�y�[�W�̋L�q��]�ڂ���B
�u���W�@�Ẳ�
&c1982, Minoru yoshioka
��㎵��N�\����\�����
��㔪��N�l���\�ܓ����s
�����\�ܕ��̓��{���͑�P��
| ���@�� | �g���@�� | |
| ����� | �n粈�l | |
| ���s�� | ��h���� | �_�ˎs���ɋ�r�c���l���ڏ\���ԏ\�l�� |
| �d�b�Z�����\�܈��\���Z����@�U�_�ˎl�Z���O | ||
| ����� | ���z��� | |
| �n���� | ||
| ���{�� | �{�쐻�{���v |

�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��k��������Łl�t�i����R�c�A1980�N11��9���j�̖{���Ɣ�
��
���ŏ��ɍw�������g�����̓����{�B�������G���̍L���œ�������ł̗\���t���������B�������ܐ\�������߂��A��Ԃ������B�y���������A�����{�̎����
���сq�c�O�~�r�����̓�s�B����R�c�́q��������Ŏ��W�̌�ē��r�Ƃ������������i��A�𐳂��āj�����B�u�����Ō����\�����^�e���ό^�㐻�{�\�����v
�R�r��g�p�{���������P�����C�h�z�\������v�B�����͒��Ԃ̐��߁B���{�͓˂����۔w�B�^�g�̕z�\����A���p�i�{�[���P�[�X�i���ɏ������̕\������
�\�j�Ɏ��[�B������g�����̓����{�̂Ȃ��ōł��[���Ȉ���B�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q�i�㔼�͔��g�j��]�ڂ���B
�u �k�u�R�c�v�̈�̑̍ق̓ʔŁl
�����\�����̓�
��Q��
�|�[���E�N���[�̐H��^��������Ł����ҋg���������a�\�ܔN�\�ꌎ������s�����\����������ЎR�������s�l��؈ꖯ���s������R�c�_�ސ쌧���l�s����
������\�\��\��\���Z��d�b�Z�l�܁i�l�O�j�O�܋㔪�^�Z�O�i�㔪���j���l�Z������������C�i�o�I�|�А��{�������{���{�����艿�O��A�Z�Z�Z�~�v

�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��k���ƔŁl�t�i��h���ǔ����A1993�N5��9���j�̛�̕\�ʁk�ʐ^�F�ѓN�v���l
�G����e���r�Ō��Ȃ����������@��̂Ȃ������{�����A�����̔Ō��ł����鏑��R�c�̂����ӂŌ��邱�Ƃ��ł����̂ŁA�V���ɍ��ڂ𗧂ĂĒNjL����B
�܂��A����Z�N������A�m�g�j����e���r���f�s���j���p�فt�́q�����̃��[�g�s�A�\�\�������{�����߂ār�ɐG��Ă������B�����Ŏ��l�ɂ��đ�����
�̍�i�Ƃ��Ďs�̖{�s��
�̉��t �s���[
���h���b�v�t��n粈�l�̎��Ɣ��s��
�ʁt �s�|�[
���E�N���[�̐H��t��
�ǂ��Љ�ꂽ�̂��B�ԑg�͖{�̏͗��Ăɕ�����\���ŁA�q���́@���
���{�̒a���r�̏��惆���C�J�Ɏn�܂�B�������j�Ƌ��N�Y�̎���W�s�����ǂ肦�t�ɑ����āA�g���{���o�ꂷ��B���l�̋i���X���h���I�ɁA�g�����W�̐���
���~�̐����̂悤�ɂ���߂��A�i���[�^�[�̍�����Â����͂��߂�B
�u�������I�ȃC���[�W���d���ȕ��̂ŕ\���������l�E�g�����B�ނ��܂����惆���C�J���琢�ɏo�������̎��l�����̂Ȃ��̈�l�ł����B���l�ɂƂǂ܂炸�A�D��
�������Ƃł��������g�����́A�����̒���Ɏ���̎�ő������{���܂����B
���l�E���e���O�Y�̌y���ȊG��\���Ɏg�����s�Ẳ��t�Ɓs���[���h���b�v�t�B�V���{���b�N�ȃp�^�[�����g���������ȂǁA�g���͓Ɠ��̃X�^�C����z��������
�����B
���̋g�����̎���܂��Ȃ��A�ނ̒��������V���ɍ���܂����B���Ԃ��ɗF�T�k�ɐ�㎆������������s��ʁt�B�N�₩�ȃ}�[�u��������ۓI�ȁs�|�[���E�N
���[�̐H��t�B��������̖{�́A�����ƂƂ��đ��h����Ă����g�����ւ̒Ǔ��̈Ӗ������߂č���܂����B
�s�|�[���E�N���[�̐H��t�B���̖{�̂Ȃ��ɂ́A�ז��Ȑ��ō��܂ꂽ�N���[�̏ё��悪����܂��B���̔ʼn�̍�҂̖��͕��V�V�\�\�v�Ɣԑg�́q���́@�ʼn��
���V�V�r�ւƈڂ��Ă����B
���V����Ƃ͔~�؉p�����ʼn�W�̃I�[�v�j���O�ŏ��߂Ă�����āA�u�N���[�̏ё���͈�l����ɂ����Ԃ�O�ɓn���Ă�����ǁA�ށA�Â萫������Ȃ���
���{���ł��Ȃ��݂����Łc�c�v�Ƃ����������B���̌サ�炭�l�q�����߂Ȃ��������A�s�G����ԁt��Z���i����O�N�k�~�l�j�̏��їf�_�B�e�q�{�̓�����
�\�\��h���ǂ̔��{�r�Ɖ����W��q��h���ǎ�E�n�ӈ�l�̖{����r�����āi�ǂ�ŁA�ł͂Ȃ��j�����ɓc�����X�ɋ삯�������A���ʂ邩�ȁA�s�|�[���E�N
���[�̐H��t�͔���Ă����i�����œ��肵���̂��s��ʁk���ƔŁl�t�ł���j�B�q�g���������r���̍쐬�ɂ������ēn粂���ɖ₢���킹���Ƃ���A�c���͂�
���Ƃ̂��Ƃʼn��t�̃R�s�[�����������A�Ȃ�Ƃ�����Ō��e�����������̂��B�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q�i�Z�s���g�j��]�ڂ���B
�u �k��ۓ���y�����Ɂu��h�v�̌���l
���W�|�[���E�N���[�̐H��@���Ɣŏ\�l���̓��{���͑�Q�Ԗ{�@����O�N�܌�������s�@���ҋg�����@�ؔʼn掩���������V�V�@�}�[�u�����e�B�j�E�O�Y�@����
��؈ꖯ�@���B�n�ӈ�l�@��������h���ǖ��Ύs�����꒚�ژZ�\�O�l�d�b�Z�����\����\�l���l�l�@��������E�n���Ё@�������{�{�쐻�{���v

�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��k���ƔŁl�t�i��h���ǔ����A1993�N5��9���j�̕\���Ɣ��ƛ�̗��ʁk�ʐ^�F��
�N�v���l
�T�C�g�J�݂̂��m�点��ѓN�v����ɂ����������Ƃ���A���������y�[�W���������������A�_�ː{��o�C���_���[�i�{�쐻�{������{�쐽�ꎁ���ʂ�Đ� ���j�Ŗ{������ɂ����Ƃ��̎ʐ^�𑗂��Ă����������B���̍��Ɍf�����ʐ^������ł���i�Ȃ��q�g���������r�ɂ́A�����B������ ���ʐ^���ڂ����j�B
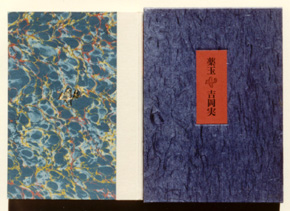
�s��ʁt�͓����ł̂܂��ɒ��ҕʑ��{������B�����́A�����}�[�u�����̌p���\���ŁA�\������B�����̉��t�̏�ɓ\���t�i�O�s�̔��g�̉��Ɂu���v�̌�
��j������B
�u��ʁ����ҕʑ��{��㔪�l�N�����ܓ����s����\�����v
�g���̈�㔪�l�N�㌎�����̓��L�Ɂu����r�q�Ɠy���F�ɉ�A���Ɨp�{�w��ʁx��B�v�i�s�y���F��t�A�}�����[�A1987�A�ꎵ�O
�y�[�W�j�Ƃ���̂��A���̒��ҕʑ��{���낤�B

���W�s��ʁk��������Łl�t�i����R�c�A1986�N4��15���j�̔��ƕ\��
������������łŁA�{���p���͎��t�̊�玆�B�㐻�˂����۔w�̌p�\���i�w���v�A�������얃�����ɂ���`���̕z�j�B�z�\���B�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L
�q�i�l�s���g�j��]�ڂ���B
�u �k�u�R�c�v�̈�̑̍ق̓ʔŁl
��ʁ\�\��������Ł����ҋg���������s��㔪�Z�N�l����ܓ�����l�\������`�����얃�������s�җ�؈ꖯ���s������R�c�����s�L�����r�ܓ�\���\�܁\�O
�Z��d�b�Z�O�\�㔪���\���l�Z��������H������������{���{���{�����{���͑�@ ��@ �ԁv
�z�q�v�l����ؗ��������Җ{�ɂ͏����ƂƂ��Ɂu���Ă݂�ΏH�^�����͗���̌�����^�₵�����̏�̌��i�v�̐��M���������B�̂��ɌÏ��ōw��
������
�O�\���Ԗ{�ɂ́u�쐶�̓Ől�Q�͐����^�F�͑�������v�Ƃ���B

���W�s��ʁk���ƔŁl�t�i��h���ǔ����A1993�N5��31���j�̖{���Ɣ�
��
���ċg�����f��ɁA�n粈�l����̓�h���ǂ��玄�Ɣł����s���ꂽ�B�{���p���͍��J�������t�i�r�����ϒf���j�A�㐻�˂����۔w�i�ܞ��o���h�j�R�[�l����
�̕\���͍��i�w�Ɗp�͎q���v�A���͏��Ԍ^���ߎq���v�j�A���Ԃ��F�T�k�ɐ�㎆�i�����Ԃ��̂Ď��z�\�葕�j�A���͉��ŏ��Ԍ^���ߎq���v�i���\�͎R�r�o�b�N�X
�L���j�B�ѕM����ⳓ���B����p���͐�ۓ���y�����B�����炭������g�����̓����{�̂Ȃ��ōł����Ȉ���B�ȉ��ɉ��t�y�[�W�̋L�q��]�ڂ���B
�u���W�@���
��㔪�O�N�\����\�����
����O�N�܌��O�\������s
���Ɣœ�\�̓��{���͑�19�Ԗ{
| ���� | �g���@�� | ||
| ���� | ��؈ꖯ | ||
| ���B | �n�ӈ�l | ||
| ���� | ��h���� | ���Ύs�����꒚�ژZ�\�O�l | |
| �d�b�Z�����\����\�l���l�l | |||
|
�H��������� | ||
| �n���� | |||
| ���{ | �{�쐻�{���v |
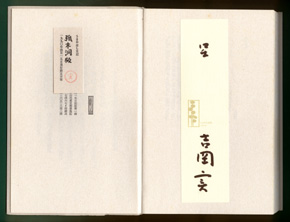
���L�s���܂�͂����L�k�ʖؓ��Łl�t�i1990�N4��15���j�̉��t�Ə����
�g�������O�Ō�̒����ƂȂ����s���܂�͂����L�t�ɂ́A�����Ɠ������s�̌ʖؓ��ł�����i�ʖؓ��͌�N�A���W
�s����t�̔Ō��ƂȂ�j�B�{�ւ̏����͂Ȃ��A��p�̏���ⳂɃ}�[�J�[�y���ŋL������Ă���B����͎����g�����珉�߂Čb���ɂ����������{���B
�����������z��F�߂����̂��i�g������ւ̍Ō�̕ւ�ƂȂ����j�B
�\���Ɩ{���ɃW���P�b�g�Ɠ��l�̐F�̗p�����g�p���Ă���B�\���t�ɂ͎��̂悤�ɂ���i�u�ʖؓ��Łv�̕����͋g������̕M��������N���������̂̂悤���j�A��͂��邪�A�L�Ԃ͂Ȃ��B
�u���܂�͂����L
�ʖؓ���
����Z�N�l����ܓ����s����S���v
 �@
�@
���W�s�_��I�Ȏ���̎��k�����l�t�̉����{�̃W���P�b�g�i���j�Ɠ��E�\���i�E�j�k���ш�Y�����삵�����̂ŁA�������[���ł͂Ȃ��l
�����{�Ƃ͈قȂ邪�A�s�̖{�̕\�������������������[�������_������悤���B�g�������i�c�k�߂Ɉ��Ă����ȁi��㔪�Z�N��Z�������t�j��������B�u���āA�����v���̃������[���w�����x���A���ŕ����Ȃ���A���ɓ���{���Ɗ��S���Ă���Ƃ���ł��B�����ɂ�������{�̃������[���́w�m���x������܂��B�������A�\������삵���̂͋����ł��B�k�ߓ����{�ِ̈F�ł��ˁB��ɂ������܂��B�v�i�s�Ս��t�l��ꍆ�A1986�N11���A�ꔪ�y�[�W�j�B���̌�A�Ȑ܋v���q���s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t���������[�������̂��G���Ŕq���������A�g���{�̃������[���Ȃ�܂��ق��ɂ����肻�����B�������̂����́A���Ђ�������������B
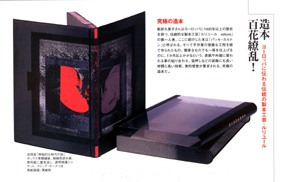
�Ȑ܋v���q�ɂ��s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�̃������[���k�sDTPWORLD�t2001�N1�����f�ځl
�O�f�s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�̃������[�����sDTPWORLD�t���ɏЉ��Ă����B���̎d�l���L���v�V�����ɋL�ڂ���Ă���̂ŁA���p����B�u�g�����w�_��I�Ȏ���̎��x�@�{�b�N�X�v�z�����A�×ΐF���ߎ��A���a����d���Ԃ��A�����ی�W���P�b�g�A�X���b�v��P�[�X���@�\���ʼn�F���菲�v�i�����A2001�N1�����A���l�y�[�W�j�B���̂����k�����Łl�R���̎d�l�́u�×ΐF���ߎ��v�́u�\���ʼn�F���菲�v�����ŁA�ʐ^�Ɍ�����i�V�j�����̐��߂Ȃǂ��Ȑ܂���̑n�ӂł���B
�k�����2020�N6��30���NjL�l
1994�N3��31���i�j����4��5���i�j�ɂ����āA�V�h�E�I�ɚ�����L�Ń����g�[�E�ǎq�ƓȐ܋v���q�ӂ���̃������[���̓W����J���ꂽ�B�c�O�Ȃ��ƂɎ��͂��̌W�����̂��������A�sRELIURES�t�Ƒ肷��}�^�œ��W�̊T�v��m�邱�Ƃ��ł���B�}�Ŕԍ���31�͏�f�́s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�ł���B�}�Ŏʐ^�����J�b�g�Ȃ̂ŁA�sDTPWORLD�t���͓������e�̎ʐ^���e���肽���̂Ǝv�����B�sRELIURES�t�Ɍ�������{��E�t�����X��E�h�C�c��̃L���v�V�����������i�sRELIURES�t�̉��t�ɂ́u�|��F�����g�[�E�ǎq�v�Ƃ���j�B
�g�����s�_��I�Ȏ���̎��t
�{�b�N�X�v�z�����D�×ΐF���ߎ��C���a����d���Ԃ��D�����ی�W���P�b�g�C�X���b�v�E�P�[�X�t���D
�\���ʼn�E���菲�D
Minoru Yoshioka �sPoesie du temps mysterieux�t Dos et bords box noir. Sur les plats une estampe d'Akira Kurosaki. Doubles gardes de papier vert fonce et noir. Chemise transparente. Etui.
Minoru Yoshioka �sGedichte aus geheimnisvoller Zeit�t Halbfronzband mit Rahmeneinfassung, Boxcalf, umlaufender eingesetzter Holzschnitt von Akira Kurosaki, doppeltes Vorsatz, dunkelgrun u. schwarz, durchsichtiges Chemise, Schuber.
�Ȃ��A�����́q�ژ^�@�Ȑ܋v���q�r�ɂ́u31�@�g�����s�_��I�Ȏ���̎��t���쏑�[1975�N���s�D����150���̓���132�ԁD�^���{�b�N�X�v�z�����D�×ΐF���ߎ��C���a����d���Ԃ��D�����ی�W���P�b�g�C�X���b�v�E�P�[�X�t���D�^�\���ʼn�E���菲.�^237�~175 1990�v�i�^�͉��s�ӏ��j�Ƃ���A�sDTPWORLD�t���̃L���v�V�����͂���Ɉ˂��Ă���B�s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�̃������[���̑n��N�ł���1990�N���g�����̟f�N�ł��邾���ɁA�Ȑ܂��g����Ǔ����ĂȂ������́A�Ƃ����z�����̂Ă���Ȃ��B
�q�g�����r�́u�{�v�@��
| �����N�̓g�b�v�y�[�W�s�g�����̎��̐��E�t�ɐݒ肵�Ă��������B | ||||
| ���ӌ��E�����z�Ȃǂ̃��[����ikoba@jcom.home.ne.jp�܂ŁB | ||||
| Copyright © 2002-2021 Kobayashi Ichiro. All Rights Reserved. | ||||
|
�{�E�F�u�T�C�g�̑S�����邢�͈ꕔ�𗘗p�i�R�s�[�Ȃǁj����ꍇ�́A
���쌠�@��̗�O�������āA���쌠�҂���я��ш�Y�̋������K�v�ł��B |
||||
![[Brought to you by LaCoocan]](image/ym_hanga_03_A.jpg)