 �@
�@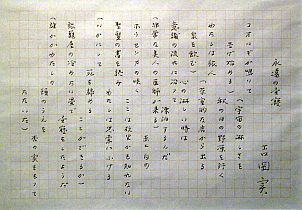
�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l������Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi���j�Ɠ��E��ցi�E�j
�ŏI�X�V�� 2021�N9��30��
 �@
�@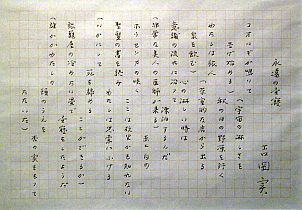
�g�����̎�ցk���сq�i���̒��Q�r�̐������e�l������Ɍf�������z�O�̕Ҏ҂̏��ցi���j�Ɠ��E��ցi�E�j
�{�y�[�W�s�q�g�����r�����k���O�l�t�ɂ́A�s�q�g�����r�����t�́q�g�����S���сk���o�`�l�i2019�N4��30���j�r�ɑ����L�����ڂ��Ă���܂��B�ЂƂ̃t�@�C���Ƃ��Ă͒����Ȃ肷�����̂ŁA���łɕʃy�[�W�Ƃ��Ă����q�g�����S���сk���o�`�l�r�i�`�S���c�ʒu�ň������ƁA��294�y�[�W�j�����蕪���܂����B�k���O�l���鏊�Ȃł��B�Ȃ��{�y�[�W���q�ڎ��r�́A�s�q�g�����r�����t�̖`���Ɍf���Ă���܂��B���̃y�[�W�Ɠ��l�A�W��̉��ɃJ�b�g�ʐ^���Ȃ��Ƃ��т����̂ŁA�s�q�g�����r�����t�Ɠ���2�_�̃J�b�g�ʐ^���A���E�����ւ��Ĕz�u���Ă���܂��B�i2021�N5��31���j
�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r��1980�i���a55�j�N�̍�����A�K�X���p����B
�u�܌��A�E�⎍�W�w�|�[���E�N���[�̐H��x���Ŕ��܁Z���A����R�c��芧�s�B�Z���A�ĔŔ��Z�Z�����s�B�����A���ؒ��h�̕ҏW�Ő��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�v���Ђ�芧�s�B�u���㎍�蒟�v�\�����ő��œ��W�E�g�����B�\���A�@���ߕv�ȁA�ēc���q�A�ȁk�z�q�l�ƓޗǍ��������قŐ��q�@�̕��ς�B�������p�فA�������̍���فA����������B�v�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A���Z�O�y�[�W�j
�g���́k���M�l�N���Ɍ�����s�NJ��W�t���Ȃ������ɁA�u�k�ޗǁl�������p�فA�������̍���فA����������B�v������B���s�����Ȃɂ��،��ł���A�M�d���B�܂��A�������̍���قł́A1967�N�H�Ɂi���R�̋@��Łj���߂Ă܂݂������C�����Ƃ̍ĉ���ʂ��������Ƃ��낤�B
�@���a�\�ܔN�@��㔪�Z�N �Z�\���
�y#15�z�O�z�{�X�ŁA�NJ��W���ς�B�V��啗�B�k�W����̃^�C�g���́s�v��S�\�N �NJ��W�t�l
���a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j�^������ꁁ�����O�z���p�فA�����1980�N7��29���i�j�`8��10���i���j��
�y#16�z�H�A���q�@�q�ϓW�Ȃǂ��ςāA�@���ߕv�ȁA�ēc���q�Ƌ���։��B
���s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j�^��ꁁ�ޗǍ��������فA�����1980�N10��26���y���z�`11��9���y���z��
�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪�Z�N�i���a�\�ܔN�j �Z�\��v�̍��Ɍ�����W����W�̕��������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�O�y�[�W�j�B
�y#15�z�k�L�ڂȂ��l
�y#16�z�\���A�@���ߕv�ȁA�ēc���q�A�ȂƓޗǍ��������قŐ��q�@�̕��ς�B
��
�y#15�z�a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j �k�W����̃^�C�g���́s�v��S�\�N �NJ��W�t�l
�}�^���G�̑������q�V��啗�r�́A�q�ڎ��r�ɂ��f����ꂽ�݂��Ƃȍ�i�i�̍�i�́A�ʏ�A�ژ^�ȂǂŖԗ��I�ɋL�ځE�Љ��邱�Ƃ͂����Ă��A�ڎ��Ɍf�����邱�Ƃ͋H�ł���j�B
�@�NJ���n�̒��ł�������_�̑����m�������n�Ƃ��ėL���Ȃ��́B����𑠂��Ă��������Ƃ̎�l���A�Éi�Z�N��ؕ���ɏ����Ă�������R�������ꕝ���ɍ�������Ă���B�R�����ɂ��ƁA���Ƃ������i�����s�j�ɑ���̗NJ��ɁA��l�̎q�����������̂�����Ɨ���ŏ����Ă���������̂��Ƃ����B
�@���̎����݂Ă���ƁA�����ɂ��������炵���Z�X���������āA���́m�E�E�n�ɂȂ肫�������|���݂�B���͉����m�����݁n�Ƃ������Ύs���J�Y�̋�����v�Șa�����g���Ă���B���q�_�Ў���̍�i�ł��낤�B�i�{�h��������͏������F���M�́q����r�A�{���A���Z�y�[�W�j
�NJ��́u���q���v�́A����13�N�`����9�N�i59�`69�j�B�u���{�m���Ƃ݂�n�̐X�̉����m������n�̂��Â����Ɂ^�����ƂĂ킪��ڂ�����^�^���[�̋}�ȎR��̓o��~�肪�V���̐g�ɂ����������Ƃƌ܍������V�����������Ƃ������āA�����\�O�N�i�ꔪ��Z�j�NJ��́A���q�_�Ђ̑����Ɉڂ�Z�B�����ł̏\�N�Ԃ̐����́A�NJ��|�p���ł��~�n�E���g���������ŁA���̏��͓_�𑽗p����ȂLj�w���ʂȕω����݂���悤�ɂȂ�B�v�i���O�A�ܘZ�y�[�W�j�B
�܂��u���k�������l�\�O�N�NJ��́A�܍�����菭���[�ɉ��������q�_�ЖT�ɂ�����Ɉڂ�Z�ނ悤�ɂȂ�B�����ɏZ�����邱�Ə\�N�A�NJ��̏����͈�i�Ƒ��ʂȕω��Ɛ[�x���܂��čs���A�~�n�����������z�����B���ɕ����O�A�l�N������́A�NJ��̏��́A���R�Ŗ��邢�A�����釀�NJ������Ƃ�������Z��m�Ђ傤���n�Ȏ�����������̂ɂȂ�B�k�c�c�l���̂悤�ȏ����ɂȂ����̂́A�NJ��̐S�������邭�ł����肵�Ă������Ƃ��傫�ȗv���ł��낤���A�ω��ɂƂ��f�́u�玚���v��u���`�V�@���v���w���Ƃ��e�����Ă���Ǝv����B�v�i���O�A���܃y�[�W�j�B
�����E��㺔V�i�k303�`361�l�j�Ɋւ��ẮA�����t�˂̖����F���m����`�����Ⴋ���̋g�����A���R�Ȃ��炻�̏������w���낤�B���͋g���������̍��i�ɂ��́u���v������ƌ���҂����A���ɏڂ��������Ƃ�]�_�Ɓi���邢�͑����ɏڂ������Ɓj�����̊ϓ_����g���̑�����_���Ăق����ƔM�]����B
���؏��O�i1904�`1980�j�́A�g�����̎��M�N���ɒ}�����[�ɓ��Ђ��Ēm�����Ƃ��邾�������A�ނ�̒����ɂ͐e�����Ƃ��낤�B�P��g���ƎR�{���g���ďC�����k���{���l�I�l�̓��؏��O�s�NJ��t�i�}�����[�A1971�N1��25���j�ɂ�������B
�@�\��颔��בm���@�\��颔��m����͂n���đm���m��������n�ƂȂ�
�@�����ە��L�N�z�@�����m�͂����n�ە��m����Ղ��n�A�z�m�����n�ɔN����
�@�������|�����M�@�����m�ɂ���n�A����|���M������
�@�������̌������@�����m���n�ӁA�̂������A���m�܁n������������
�@���̎��ɂ����Ă͗NJ����A���⎍�����߂鐢�l�����邳���Ă�邱�Ƃ��������͂��B�Ɠ����ɁA�������A�M�����Ă��Ȃ�ɛ�����s������⎩�}�̎�ŏq�ׂ��Ă��B�R���������߂鐢�l��P�ɂ��邳���Ƃ��Ă�킯�ł��Ȃ��B��́u�V��啗�v�Ǝ����ĕ��m�����n����炤�Ƃ���q�����o�ւ����̂̔@���́A���̏������猩�Ă����X�Ƃ��ĕM�������₤�Ɏv�͂��B�i�q�NJ��ɂ�����̂Ə��r�A�����A����`��ܔ��y�[�W�j
 �@
�@
�a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j�̕\���i���j�Ɠ����k���G�l�̑������u�V��啗�v�i�E�j
��
�y#16�z�s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j

�y�Q�l�z���ʓW�s����ɗV�Ԕo�l �i�c�k�߂̐��E�t�i��ꁁ�P�H���w�فA�����1996�N10��4���`11��24���j�}�^�̕\��
���ʓW�s����ɗV�Ԕo�l �i�c�k�߂̐��E�t�i��ꁁ�P�H���w�فA�����1996�N10��4���`11��24���j���J���ꂽ�̂́A�������������N�̏H�������B���̏H�A���ɗ����āi�t�̐V�����s�͔����j�A��l������ĕP�H����ς����ƁA���͍k�ߓW�܂ŋr�����������̂��B�K�^�Ȃ��ƂɁA���s���ɖ��N�P��́s���q�@�W�t���ޗǍ��������قŊJ����Ă����i�g�������W���ς�16�N��ł���j�B���W�����邱�ƂȂ���A�������̕����i���v���J�H�j���L���Ɏc���Ă���B
���āA1980�N�́s���q�@�W�t�œW�����ꂽ�Ȃ��ōł��ڂ��������̂́A�s���q�@�W�ژ^�t�̉���Ɂq52�@�g�坛�Z���q�m���������邫���n�i���ۉ�̌�j�@�ܖ��^53�@���坛�Z���q�m�����邫���n�i���ۉ�̌�j�@�ܖ��r�i�e�a1.6�A��0.8�kcm�l�j�Ƃ���k�q�̕��B���Ɍf�����ʐ^�̃L���v�V�����͐}�^�̂�������������̂����A�O�f����Ƃ́A�ԍ��ƐF�̕\��������ւ���Ă���B�ǂ��炪�������̂��낤���B���m�N���ʐ^�̂��߁A�F���킩��Ȃ��̂��c�O���i�C���^�[�l�b�g�ʼn摜�������Ă݂�ƁA�J���[�̎ʐ^���������q�b�g����j�B�吨�ɂ͉e�����Ȃ��̂ŁA����ɏ]���ĉE���q52�@�g�c�r�A�����q53�@���c�r�Ƃ��Ă����B����{���̑O�����������B
�@���ƍ�����g�ƂȂ�悤�ɁA������g��ƍ������g�ɂ��Ďg�p�����B
�@�܂��ۉ�Ō�Ό`�����肱����g�F�ƍ��F�̓��ɐ��ߕ������̂��A����������ʂɝ��Z�i�͂˂ڂ�j�̎�@�ʼnԋ�����킵�A�X�ɍg���߂ɂ͔��Ɖ��A�����߂ɂ͐ԂƉ��̍ʐF��_���ĉؗ�Ȍ�Ɏd�グ�Ă���B�i�{���A�l���y�[�W�j
���́u�ԋv�A���W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j�́i���y�Ł����F�̕\���ɋ��ŁA��������Ł��\���̍��F�̕z�ɂ�͂���Ŕ����������j���̃J�b�g�̒���z�킹�Ȃ����낤���B�ĂԌ����͔�������ǂ��B�f�ڎʐ^�̓X�L�����������̉𑜓x�̂܂k�����Ă���̂ŁA�E�F�u�u���E�U�Ŋg��\�����āA�ׂ����_�܂ł�������Ƃ����������������i�ԋ̎p�����E���g�Ŕ����ɈقȂ�̂��������j�B�s��ʁt�̕\���̗p�����u�C�^���A���̐[�݂̂���F�����̎��F�v�i��ˎ闝�j�Ȃ̂́\�\���ƍg��������Ǝ��I�\�\�P�Ȃ���R���낤���B
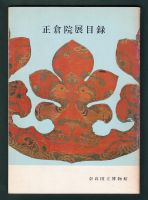 �@
�@
�s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j�̕\���k����́q42�@�Ԓn�������с@Fragment of a Buddhist Banner�r�l�i���j�Ɛ}�^�̐}�ŃL���v�V�����ɏ]���u52�@���坛�Z���q�@Blue-Stained Ivory Go Pieces�^53�@�g�坛�Z���q�@Red-Stained Ivory Go Pieces�v �k�}�^�̉���ɂ���悤�ɁA�������͉E��5�����q52�@�g�坛�Z���q�r�A����5�����q53�@���坛�Z���q�r���낤�l�i�E�j
�k�t�L�l
�g�����E�z�q�v�Ȃ��ޗǍ��������قŐ��q�@�̕��Ƃ��Ɋς��@���߁E���v�Ȃ����A�@���߁i1919�`2006�j�Ƃ���u�����v�ł���B�@���g�͋g���̍����ɂ��Ă��قǑ���������Ă��Ȃ����A���̂�����̂��Ƃ͏�ˎ闝�́q�����r�i�s�g�����̏ё��t�A�W���v�����A2004�j���Q�Ƃ��Ȃ���A������ڂ������Ă��������B
�i�i��S���F�����r�Y����j
�@������������ďo�Ă��������Ă��邩���́A�K���������߂��炿���Ƃ��肢���Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�}�ɂ��肢���邩��������܂����A�Ȃ�ł��A�ꌾ�ł����������ł����炨��������Ă��������B���A����Y����B
��
�q�킽���̋g�����r�y����5�z�\�\����Y����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j
�i����Y����A�o�d�j �k����F�u�����Ă��鎞�����łȂ�����ł��������v�l
�@�K�i������Ƃ����A�悽�悽���Ă��܂��܂��B����ł��������đ�ɗ��ƁA�悽�悽�����Ă����܂���A�݂Ȃ���̎x�����c�c�����������b�����Ƃ��ɁA�Ȃ�ƂȂ��A�搶����N�O�ɖS���Ȃ����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ȃ��ł��ˁB�g��������v���������Ƃ܂������Ă���悤�Ȋ��o�̂Ȃ��ŁA�g������̘b�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A����Ȃ悤�Ȋ��������ɂ������킯�ł��B�g���搶�c�c���ߐ�ɊԂɍ���Ȃ��āA�ς��ς��ςƒu�����i�H�j�Ƃ����̂�����܂��āA���̂Ƃ��ɂȂ�ƂȂ��c�c����܂�������Č��_�߂������Ɓc�c���������Ȃc�c����Ȃ悤�Ȃ��Ƃɂ��āA�����Ă𐂂��c�c�����Ă���c�c�܂��B���ꂩ��c�c2���Ԃ������A���߂āc�c����܂�b���ł��Ȃ��Ƃ����܂����ˁA�c�c�肪�k���܂��Ă��܂��悤�ȁc�c�b�����āA�c�c���̂Ƃ������āc�c����Ȃ悤�ȁc�c���������悤�ȉ��Łc�c�u�����Ă�c�c����ł��������v�Ƃ����悤�Ȑ����ǂ�����Ƃ��Ȃ��������Ă��āA�c�c�u����ł��������v�Ƃ����Ȃ�ƂȂ��`����Ă��܂����B�c�c���������c�c�u�����Ă���Ƃ������łȂ��A����ł��������v�\�\���̂ӂ��������S�̂Ȃ��Ō������āc�c���ꂪ�Ȃɂ��A�搶�������Ă���̂��A�S���Ȃ����̂�������Ƃ킯���킩��Ȃ��悤�ȁc�c�ʐ^�c�c���Ă���c�c���������Ɓc�c�����Ă���̂����̂��킩��Ȃ��A���܁A�����Ă��܂��B�������Ȃ���A���̋����Ȃ�ƂȂ����̏ꍇ�ɂ͂Ȃ��Ȃ����悤�ȋC�����ŁA�c�c���������́c�c�Ƃ����Ƃ���ŁA�݂Ȃ���̂܂��Łc�c�����b�ɂȂ�܂����B�S���Ȃ钼�O�܂ŁA2���Ԃ�������Ă��b���c�c�B
�i���A����j
�k�t�L�l
����Y����́s���㎍�蒟�t1990�N7�����́k�Ǔ����W�E���ʂ� �g�����l�ɒǓ����q�������r�������Ă���B�����Ɂu���������Ă�����@�g���搶�Ɍ����v�Ƃ���q�������r�i�����A�O�Z�`�O��y�[�W�j����A�K�X���p����B
�ǂ܂��Ē�������{�͋C�����Ȃ������Ɏ��X�Ǝ��̓����ɍ��݂��܂�̂悤�ɏ��������L���Ă���܂��B�������ɂ�z�����̂�S���ɂ݂܂��B���������Ƃ����搶�Ƃ̑ΖʁB�搶���C�ł����c�c���C����Ƃ̐����҂��Ă��܂��B
���͍������������Ƃ��Ă���̂��낤���B�g���搶���璸�������b�ɂ������������\���q�ׂ����̂ł��B���̂��߂ɏ����Ē��������͐g�߂��Ȃ��ƂƂ��āA�܂�ŕ�̗r�������܂��Ē����Ă�l�Ȃ������ł��B
���͌䋳���������@�̕����Łu���l�v�ɏo��܂����B�o��x���Ƃ����z�����u�f�b�T���v���悩�����̂ł��B�z���߂��z������������O�o����Ƃ��o���Ȃ��Ƒz��������ł��B
�搶�̂����C�Ȏ��w���[���h���b�v�x�i����R�c�j�����X�܂ŁB�o�������Ȃ����Ƃ͉������Ă���̂ɁA�������Ȃ����Ƃ͂킩���Ă���̂ɂ�����悯���ɋ��X�ɂ܂ŐG��Ă݂��������̂ł��B�܂݂�Ă��܂����������̂ł��B�u�����Ă��鎞�����łȂ�����ł��������v�B�Ƃǂ��炩��Ƃ��Ȃ��`����Ă��܂����B
�ꂪ�A���w���`�[�i�����̒��ɍ݂��Ă�����܂���^���ĉ�����l�ɐ搶�͂�����܂���^���ĉ������܂��B
�搶�̍Ō�ɂ�������͎̂l�����i����Z�N�j�C�^���A�����ɏo�����钼�O�ł����B���x�݂ɂȂ��Ă���ꂽ�̂ɋN�����A�ԋ߂������b�Ȃ����܂����B���߂�Ȃ����B���蓾�Ȃ��܂܉��l�̌�S�g���������O�l�ł��b���������܂����B�����Ă����邾���ł������̂ɐ����ƐF�X�̂��Ƃ����b���Ē����܂����B����̒��̎��Ԃ̂悤�ɑz���o�����Ƃ��Ă��z���o���܂���B���߂�Ȃ����B
���������Ă��܂��āB�ǂ����Ă����蓾�Ȃ������̂ł��B���߂Ă̂��K�˂ł������ڂ��P�������b���Ē����܂����B
�O���ł̌����̎��ɂ͐搶�̎����v�����g���������������Ă���܂����B���X�ɂ܂Ŏ��̒��Ƀv�����g���ċ��ɕ����x���Ɗ���Ă���܂��B�������悤��
�����́u�C�^���A�����v�́A����Y�N���ɏƂ炷�ƁA�N�����i�̃|���L�G�b������ł́q�Ԓ������r�̂悤���B�܂��A�Ǔ����ɂ́i���M����́j6��8���E9���Ɂq���@�r�̉��l����������Ə�����Ă���B�u�H�삪�H��Əo����Ƃ��o�����炱��ȍK�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�v�i����Y�j
������
�i�i��S���F�����r�Y����j
�@���V������͂������ł��傤���B�@
���́s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�����^�����e�[�v�������������o�܂��q�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��r�i2021�N5��31���j�ɏ������B���̌�A�S�̂����������Ƃ͂����A����A�f�ڂ��ׂ����e��p�ӂ������A����̉�������i�߂Ă����B�Ƃ��낪�A���͕|�낵�����Ԃ������Ă������ƂɋC���t���Ă��܂����B����Y����̊��̂��ƁA�i��̍����r�Y�����V������̓o�d�𑣂������A���V����͌���Ȃ������B����1991�N10��12���̂��̓��A���V����͂������������̂��낤���A�ȂǂƂڂ���l���Ă����ɂ����Ȃ��B�����ď��c�v�Y����̘b���Ƃ��Ȃ������Ă��Ă��A���̌��͉����Ă���A�ȂǂƂ̂ɍ\���Ă����������B�Ƃ��낪���̗�������̘b���n�܂����Ƃ��A���͜��R�Ƃ����B����A���|�����B�e�[�v�������������̏u�Ԃ܂ŁA���͓o�d�𑣂���Ă�����Ȃ������̂͗������Ƃ���v������ł����B��������́A��������ł͂Ȃ��A���V�������B���͑z������B���ŃJ�Z�b�g�e�[�v���Ȃ���A�b�ɒ������邠�܂�A���҂̎��������������Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ď��V������̖��O�̘e�Ɂu�o�d�����v�Ƃł����������肪�A���N���o���ē����̋L�����W���Ȃ��Ă���A�g�����̟f��̔N�����L���ۂɁA�������o�d���Ȃ��������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł͂Ȃ����B��������̘b�����ł��܂����̂́A�����炭���O�̏��c����̘b�i�k����F�q�����܁r���ނ̂��Ɓl�j�̈�ۂ��������āA�n���[�V�������N�����������ł���B�e�[�v�������������s���s���ŁA�����������Ȃ������Ƃ����Ԃ�����Ɉ����������B�����̋����͂��ꂭ�炢�ŏ[�����B��������ɂ͂����ւ�\����Ȃ����Ƃ������B���O�̗��������̂��Ƃ���������������A�\���J���̂��悤���Ȃ��B���Ƃ��ẮA��������̊������Ȃ��f�ڂ��邱�Ƃł��������������������A�Ɗ肤���肾�B���������āA����܂Ōf���Ă����o��l���̈ꗗ�̈ꕔ�͌��ŁA
�@�k�c�c�l
�@����Y����
�@���V������i�o�d�����j
�@���c�v�Y����
�@��������
�@�k�c�c�l
�������ɑ������������`�ƂȂ�B���������˂āA���̏����ĐS���炨�l�т�\��������B
�Ǐ����́s�Ɗw��S�\�\��Ɂu�w�Ԃ��Ɓv��������߂����Ȃ��l�̂��߂�55�̋Z�@�t�i�_�C�������h�ЁA2020�N9��28���j���b�肾�B�����A���ꂩ�珑�����Ƃ͓Ɗw�ɂ��Ăł͂Ȃ��A�����Ǐ����ɂ��ŏ��̒����s�A�C�f�A��S�t�i�t�H���X�g�o�ŁA2017�N2��1���j�̈ꍀ�ځA���Ȃ킿�����̕���ɂ���u�n���͂ƃu���C�N�X���[�ݏo��42�̃c�[���v�̂����́q06 �����_���h���r�i�����A�l���`���y�[�W�j�ɂ��Ăł���B�ȉ��A�u�@�v���͓�������̈��p�B
���҂͂܂��A���ڃ^�C�g���́u�����_���h���v���u���R���e�R�ɁA�g���z����ŌÂ̑n�����Z�@�v�ƃp���t���[�Y����B���̔��y�[�W�ɂ͂�������B�u��Փx�v�F5����1�k5����d���̂����A�ЂƂ��_���l�A�u�J���ҁF�s���v�A�u�J���ҁF�G�h���[�h�E�f�{�m�iEdward De Bone, 1933- �j�v�A�u�Q�l�����v�F�k�c�c�l�B�u�p�r�Ɨp��^���A�C�f�A�ݏo���̂��S�O����Ƃ��B�^�������̕Ȃ����ς�����A������\���ɔ��z���L�������Ƃ��B�v
���͂����ł܂œǂƂ��A���ꂪ�g�������ɂ����锭�z�@�i�����x��������Â���j�ɒʂ��Ă��邱�Ƃɂ܂������C���t���Ȃ������B�������́u���V�s�v�̇@�`�C��ǂނɋy��ŁA�g�������������Ƃ��̗��V���̂��̂ł͂Ȃ����A�ƒ��������i�����������A�\�L�k�L���l���ȗ�������j�B
�@ ���Ƃ͖��W�Ȏh����I�ԁB
�@�@�������͂̕������邢�͖ڂɉf����́B
�@�@�@�����ӂ��������́B
�@�@�@���f�^�����ɊJ����������{��G�����W��ʐ^�W�̃y�[�W�B
�@�@�@��Wikipedia�̂��D�����B
�@�@�@���������T�C�R����Z�m���n�B
�@�@�@�������_���Ɉ������^���b�g�B
�A �h�������B
�B �h���Ɩ������т��āA���R�ɘA�z����B
�C �A�`�B��K�v�Ȃ����J��Ԃ�
�ނ��ɍۂ��āA�g���������̂��ׂĂ����݂��킯�ł͂Ȃ��B�����A�u���͂̕������邢�͖ڂɉf����́B�v�u���ӂ��������́B�v�u�f�^�����ɊJ����������{��G�����W��ʐ^�W�̃y�[�W�B�v�ɋ߂���肩�������p�������Ƃ͋^����e��Ȃ��i���P�j�B���āA�g�������g�̍쎍�@�ɂ��ĉ��^�I�Ɍ�����̂��q�킽���̍쎍�@�H�r�i���o�́s���̖{�k��2���l�t�́q���̋Z�@�r�i�}�����[�A1967�N11��20���j�́k�킽���̍쎍�@�l�Ƃ����p�[�g�j�������B�܂�ҏW���́A�����g�̍쎍�@�ɂ��Ď��M���Ă��������A�Ƃ����˗��ɑ��āA�u�킽���ɍ쎍�@�Ƃ�������̂��ʂ��Ă��邾�낤���A�r���^�₾�Ǝv���Ă���B�����Ȃ�Ӑ}�ƕ��@�������Ď�������݂���悢�̂��A���܂��悭�킩��Ȃ��B����ɁA�킽���͍����Ɏ���܂ŁA���Ȃ̎��̔��z���炻�̌`���Ɏ���ߒ����A���Ȃ��[������������A�܂�����I�Ȃ��̂����������Ƃ��Ȃ��̂��B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�����y�[�W�j�ƁA�͂Ȃ͂��Ԃ�����ڂ��Ɏn�߂邵���Ȃ������B���������Ȃ��B���ۂ̍�i�������āA���т̐�����U�肩�����Ă݂邱�Ƃɂ��悤���\�\�Ƃł��l�������낤�g���������������݂��̂��A�s�m���t�̉����q��́r�i���o�͏���p�g���A���s�́s���㎍�t1958�N6�����j�ŁA�����́q�킽���̍쎍�@�H�r�̂Ȃ��قǂɑS�s���f�����Ă���B�g���́q��́r�̈��p�ɑ����āu�Ȃ�������Ƃ肾�������Ƃ����ƁA�킽���̒��ňِF�����i�ł���Ɠ����ɁA����̈��ŏo�����B��̂��̂ł���B�킽���͓���G���Ȏ����̉ƂŁA�������H��Ɍ����Ă���������ԂɂȂ��B�v�i���O�A���y�[�W�j�Ə����Ă���B�u�킽���̒��ňِF�����i�v�Ƃ́A�]�R����̖��F�ł̌o�����قƂ��Ă��邱�Ƃ��w���̂��낤�B���ۂɋg���́A���̎�̎��т͂������A���������̂��鎍�s���i���̑̌��̏d�v���A�؎����ɔ䂵�āj�قƂ�Ǐ����̂����Ă��Ȃ��B���ꂾ���ɂ����̈Ӗ�������̂͑傫���d���B�����A�����Ō����������̂́u����̈��ŏo�����B��̂��́v�ł͂Ȃ��A���̑��A�命���̎��\�\�P��I�Ȏ��\�\�̕��ł���B�q�킽���̍쎍�@�H�r�݂̂��߂̒i���ɂ͂�������B
�@�k�c�c�l�킽���͎����������́A�Ƃ̒��Ŋ��̏�ŏ����ׂ��p���ŏ����B�����Ă݂�A����߂Ď����I�Ɏ����͂���ōs���B�����璤���Ƃ��ƁA�����d���̐E�l�ɗގ����Ă���Ƃ����悤�B��ÂȈӎ��ƍ\�}���������ɟ���A���A���e�B�̊m�����I��ƁA�₪�Ĕ��M��Ԃ�����B���ӂ��K���B��]������B����G�悪������B���̂��z�������B�T�̍b�̌ł������ɂӂ��B�̏������Ă���j������B���Ɂu����ԁv�̌`�ԂƁu��v�Ƃ������������яo��B�L���x�c��ʃl�M�A�Ԃǂ��A�Ƃɂ������`�̂̎����݂̂����N�����B����ȘA�z���Ȃ���B�ǂ����ď�����Ԃ�V���s�݂Ȃ̂��H�@�킽���̒��̓���Ԃ͏��֒��ނׂ��^���p�ɕK�v�Ȃ̂��B���̂��Ɉ������Ă������ƍl����B����̓w�b�h���C�g�ɏƂ炳�ꂽ�A�J�P�̓�l�̈����i���Ȃ��̂��ƒf�肷��悢�̂��B�������ӎ��̂Ȃ���͒N�̒��ɂł��L���ɗ����B������~���邱�Ƃ�����A���Ȃ킿�����̈�s��s�ɒ蒅�����邱�Ƃ��B���������C���[�W�����̂܂܂����ǂ邱�Ƃ���ł���B
���܂�ɂ��l�����Y�t�����ӏ��Ȃ̂ŁA���p����̂��C�������邪�A�s�Â��ȉƁt�i1968�j��s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�̂���\�\�Ƃ����ӂ��ɁA���������肷�ׂ����Ǝ��͍l����\�\�̎���̎��ɂ��āA����قǗ����Ɍ�������͂��ق��ɒm��Ȃ��B
�k�c�c�l
�҂����z�e���̗������o�Ȃ���
�킽���͍l����
�J�P�̂Ȃ��̏����Ȉ���
�������鎩���Ԃ̃n���h��
���֍��ւƂ�����
�@�@�@�@�@�\�\���сq�؍݁r�i�E�E7�A���o�́s���㎍�蒟�t1964�N4�����j
�k�c�c�l
�~���k���������
�����ޖ��
���֒��݂䂯
�V�k�̓���ԌQ
�߂��炵���ނ炳���F��
�ق���
�k�c�c�l
�@�@�@�@�@�\�\���сq�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�A���o�́s���w�ҁt1967�N8�����j
�s�A�C�f�A��S�t�́q06 �����_���h���r�ɂ́A�u�T���v���v�Ƃ��ē�́u����v���������Ă���B���Ȃ킿�u�j���[�g���̃����S�v�Ɓu�_�[�E�B���̐i���_�ƃ}���T�X�w�l���_�x�v�ł���B�����āA�Ǐ����ɂ��u���r���[�v�ɂ́u�������_���h��������Ɏc���Ă��闝�R�v�Ƃ��āA�l�ފw�҂̃��[�A�Ƒg�D�i���j�_�̃��C�N�̍l�@�\�\�i�X�J�s���́q�ӎv����r�̎��̂悤�ȗ��_�����B���p���悤�i�����͊ے������ł͂Ȃ��A���ׂā����A�����̂��߂ɕύX�����Ă�������B�j�B
�@�������s���Ă��A�N���ɗ݂��i����قǂɂ́j�y�Ȃ��B
�A��s�\���ȂƂ��ł��A���肪�������B
�B��ֈĂ̊Ԃł�������Ⴂ���Ȃ��Ƃ��ł��A���킸���肪�������B
�C�i�����ւ̕��ׂ����U���邱�ƂŁj�{�g���l�b�N����������邩������Ȃ��B
�D�i���̎肪�ǂ߂Ȃ����߁j�����҂���������B
�E��ֈĂ̐����i�����I�ɂ́j�����ɂȂ�B
�F�菇���������B
�G����͏�ɑ��₩�ɉ������B
�H���ʂȋZ�\������Ȃ��B
�I������������Ȃ��B
�J���̉ߒ��ɃP�`�̂��悤���Ȃ��B
�K�t�@�C���₻�̕ۊǏꏊ������Ȃ��B
�L�ۛ��m�Ђ����n�̂��悤���Ȃ��A�ǂ̑�ֈĂɂ��������d�݂Â����Ȃ����B
�M�����Ɏ���_�����s�v�ł���B
�N�^�̐V����Ăэ��ނ��Ƃ��ł���B
�O�ǂݕ���ς��邱�Ƃɂ���āA�c�L��ς�����B
�P�ߋ��̎��̉e�����Ȃ��B�������̉��Ƀh�W���E��T�����\�\�Z���I�ɂ͌����ł����Ă��A�����I�ɂ͎������͊�����������Ȑ헪�\�\������邱�Ƃ��ł���B
�Q�l�Ԃ�W�c�����ӎ��Ƀn�}��I�D�╪�́A�v�l�̃p�^�[���ɂ��e�����Ȃ��B�����Ζ쐶�����͐l��葬�����̃p�^�[�����������������̂ŁA���̗���������B
�Ȃ��ł����ڂɒl����̂́A�@�`�D�A�G�A�K�`�L�A�N�A�P�A�ł���B�����Ŏ�����S�I�Șb��Ȃ̂́A�u�l�C�e�B�u�A�����J���ł���i�X�J�s���ł́A���V�̓J���u�[�i�g�i�J�C�j�̌��b���m�������n�Ɍ��ꂽ�q�r��ǂ݁A��l�����͂���ɂ���Ď�������ꏊ�����߂�B���[�A�ƃ��C�N�ɂ��A�i�X�J�s���̂��́q�ӎv����r�͎��̂悤�ȗ��_�������Ă���v����ł����āA���сi�Ƃ�킯����ɂ�鎩�R���j�Ƃ����u�쐶�����v�����쎍�s�ׂ́A����Ύ��Ȃɂ��āA��������R���Ɏ��Ȃ��J���A���z���Ăт��ނ��ƂŊJ�n�����B�Ȃ����A�ŏI�I�Ɂu������~���邱�Ƃ�����A���Ȃ킿�����̈�s��s�ɒ蒅�����邱�Ƃ��B���������C���[�W�����̂܂܂����ǂ邱�Ƃ���ł���v�Ƃ����ǖʂɐg������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�u�����_���l�X�Ƃ����s�m�������킴�Ɠ��l���邱�ƂŁA�s�m�����̍����ۑ�ɑΏ�����Ƃ������̃A�v���[�`�́A�`���I�ȍH�w�A�v���[�`�Ƃ͐����ł͂��邪�A���C�N�ɂ��A�q�g�̔F�m�\�͂ƐӔC�\�͂��z������������ӎv����ɂ��āA�����őP�́A���Ƃ��ėB��́A�����@�ƂȂ肤��v�Ȃ�A�쎍�Ƃ͂����������E�H�w�I�ȃA�v���[�`�Ȃ̂��Ƃ������̔F���́A����܂Œm���Ă��������ɐV���Ȍ��Ă邱�ƂɂȂ邾�낤�B���Ȃ킿�A���R�������m���ł���Ƃ����A���̌��āB���Ƃ�����ꂪ�g�����̎���̍H�[�ɗ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B������������\���邱�Ƃ́A���邢�͉\��������Ȃ��B�Ɗw�ҁi�Ɍ��炸�A�L�����̂��Ƃ�T������ҁA���l���܂܂��j�������ׂ�10�i�K�̂����A0��1�������ɍ���́A�Ǐ������Ƃɐ������ł���B
��
�Ǐ����́s�Ɗw��S�t�ɂ́u�����_���h���v���q�����r�i����xxxiv�y�[�W����j�Ɍf�o����Ă���B�{��������Ɓu�|�A���J���̓C���L���x�[�V�����ɂ���ăA�C�f�A�����܂�闝�R���A�x�݂Ȃ��������p�����閳�ӎ��ɑ�����C���邱�ƂɂȂ邩�炾�ƍl���Ă����B����ł͕ʂ̍�Ƃ��s�����ƂŁA���ɒ��ڊ֘A����ȊO�̏��ɂ��Ă��������g�U�k���F�����L���Ɋi�[���ꂽ���́A���̎g�p�p�x�������قǁA�܂��g��ꂽ�̂��ŋ߂ł���قǁA�����o���₷���Ȃ邪�A������������ƌĂԁB�k�c�c�l�������͒����L���̃l�b�g���[�N��`���čL�����Ă������A���̌��ۂ��������g�U�ƌĂԁB�l�������邱�ƁA���Ƃ͊֘A�̂Ȃ������_���h���ɎN����邱�ƁA����܂ł̊ϓ_�̌Œ����痣�E���邱�Ɠ��ɂ�邱�Ƃ��킩���Ă���B�v�i�����A���O�y�[�W�j�Ƃ���B�u���Ƃ͊֘A�̂Ȃ������_���h���ɎN����邱�Ɓv�ɂ��}����ꂽ�u�C���L���x�[�V�����v�́A�Ǐ����̐��������u�V�������z�����܂��������|�A���J�����g�̌o�����璊�o�������̂ŁA���ݏo�������A�C�f�A�ɂ��čl����������A�A�C�f�A�Ɋւ��邱�Ƃ��痣��ĕʂ̍�Ƃ�������x�������ƁA�A�C�f�A���Ђ�߂����Ɓv�i���O�A����y�[�W�j�ł���B
1958�N�A�s�����C�J�t�̕ҏW�ҁE�ɒB���v���璷���̎��M���˗����ꂽ�g�����A�̂����q�����r�i�C�E19�A���o�́s�����C�J�t1958�N7�����j�ƂȂ鎍�тw�i��
�@���ɂ͐��Z���Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B�u���̐풆���v�����ɑI�B����Ȃ�A���������悤�Ɗy�ς����B�e�[�}�����炩���ߌ��߂邱�Ƃ́A���ɂƂ��Ď����������̂����̞~���ɂȂ�B�����玄�͏o���邾�������Ă������A���x����͎����i��A�W�J���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������̂��ƂŎl�Z�����A����Y�܂����̂͂��̎������������B�i�q�u�����v�Ƃ����G�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�B���o�́s�����C�J�t1971�N12�����́k��㎍�ւ̈����l�j
�Ə������悤�ɁA�g���͂��̎��i�Ǝ��M�̎菇�j�̗ՊE�ɐڋ߂���Ɠ����ɁA�|�A���J���́u�C���L���x�[�V�����v�������_���h���ɂ��܂Ȃ��N����邱�ƂŁA���́q�����r����������Ă����B�X�^���`�b�`�̊G��q�����r�i1955�j�Ƌg���̎��сq�����r�Ƃ̊W�́A���̓_�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�H���K�l�́q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŁA�u����ł́A�g�����́A�����A�����ŁA�ǂ������������ŁA�w�����x�Ƃ����G�Ƒ����������̂��������B�X�^���`�b�`�Ƃ͉��҂������̂��B���̂Ƃ�����́A���̕ӂ肩�炵�Ċ��ɞB���Ƃ��Ă���B�v�i�s�g�����A���x�X�N�t�A����R�c�A2002�N5��31���A��y�[�W�j�ȉ��A19�y�[�W�ɂ킽���āu�D���Ƃ̂��߂ɏ����₷�A���̑F���̋L�^�����˂��䂪�nj��̐��X�v�i���O�A�O�y�[�W�j���J��Ђ낰�Ă���i���ȂǁA�������߂��́u�D���Ɓv�̕M�������j�B�H���͂����ŁA���сq�����r�ƊG��q�����r�A���ȁA�L���g�������Ɣ��p��i�ɂ��u�����_���h���v�Ƃ̊W���l�@����ۂ̍D�̎������Ă��ꂽ�B�S���H���́u���̏�ɗ����āv�����������l���邱�Ƃ́A�����ɂƂ��ĉx�����`���ł���B
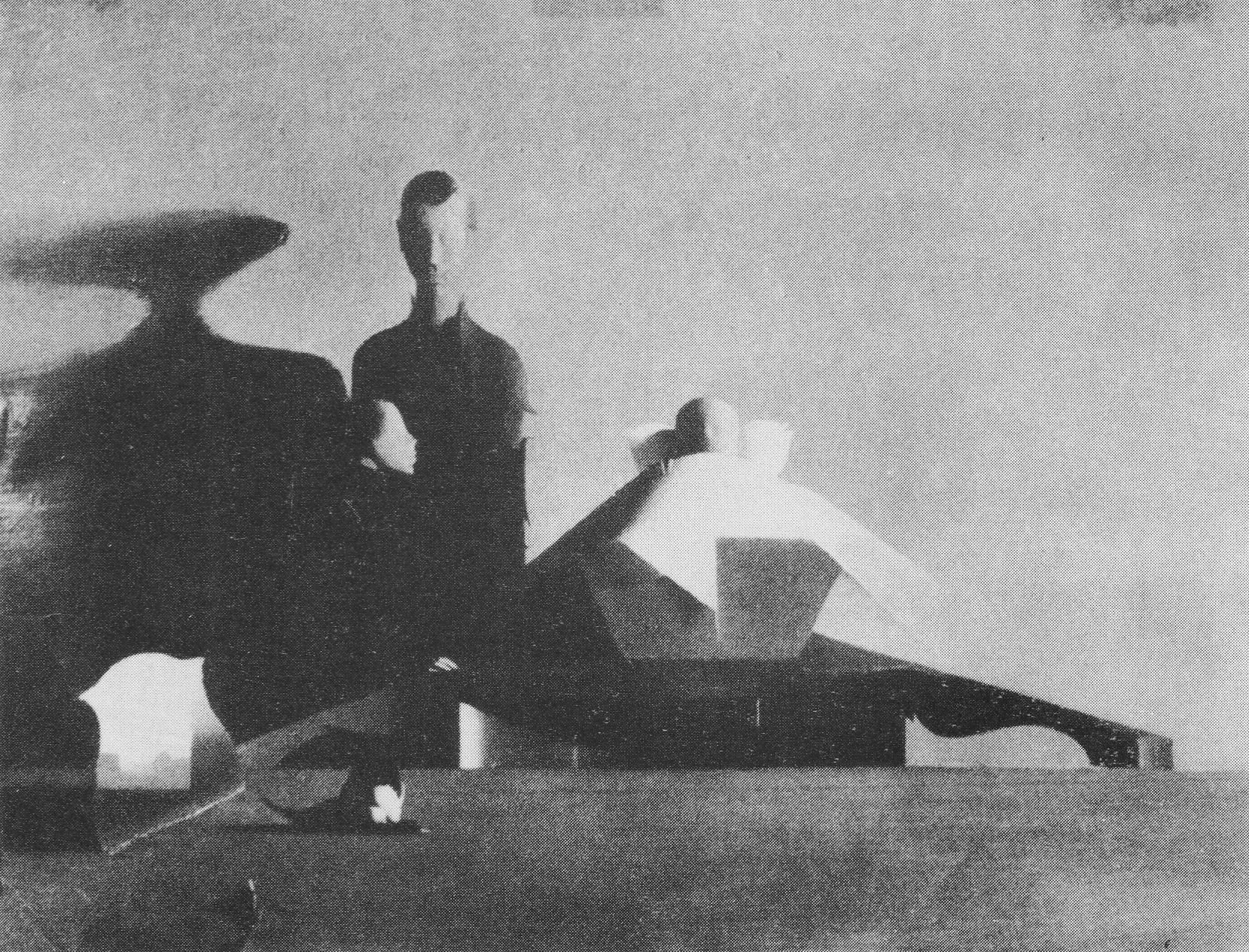
�u�X�^���`�b�`�u�����v1955�v �k�o�T�F�g�����s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���G�l
���L�̕����ԍ��I�́u���M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x����Ŋ����ʗt�ʐ^�v
�ȏ�̂悤�ɏ������Ƃ���ŁA�H���K�l���q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŋ����Ă���s�݂Â�t1957�N7�����Ɓs���p�蒟�t�i���j����肵���B���s�͂ǂ�������p�o�ŎЂł���B�ӂ����苖�ɒu���A�H���́q�����r�_�ɃR�����g���Ă������B�܂��A���_�ŏH�������y���������i�g�����̕M�ɂȂ鎍���������j�̏������q�����r�_�̖{���ƒ����甲���������邪�A�����Ĉ��p���ꂽ�����̌��T�ɓ�����Ȃ������B�����́i�@�j���̐����́s�g�����A���x�X�N�t�̌f�ڃy�[�W�m���u���B�Ȃ��������⊇�ʗނ̕\�L�͏H���̂��̂d�������A�����Ƃ��Đ�������悤�ɏH���̕��������ւ����ӏ�������i�H�́i279�j���Ȃǁj�B�k�@�l���͏��тɂ���L�ł����i���Q�j�B
�@�u�݂Â�v�����N�������i�ʊ���Z��l���j���S�u�����ƊG��E��l����{���۔��p�W����v�@�i273�j
�A�u���p�蒟�v���N�������u���W�E��l����{���۔��p�W�E�s�J�\�ʼn�W�v�@�i274�j
�B���ؐT��u�]�����̔��p�^��l����{���۔��p�W�^�C�M���X�A�h�C�c�A�I�[�X�g���A�A���[�S�X���r�A�A�X�C�X�̍�i�v�u�����V���v�����N�܌���\�Z���B�@�i294�j
�C����C���u��O����{���۔��p�W�v���܌ܔN�B�k�o�T�̋L�ڂȂ��l�@�i294�j
�D��g�c���N�k�́u�݂Â�v�f�ڕ��l�k�W��̋L�ڂȂ��l�@�i276�j
�E��㒷�O�Y�k�́u�݂Â�v�f�ڕ��l�k�W��̋L�ڂȂ��l�@�i277�j
�F�u�|�p�V���v�i�V�����s�j�����N�������@�i277�j
�G�x�i�y��E�c�ߌ��O�E�͖k�ϖ��E���{�����Y�E���ؐT�ꓙ�̍��k��u���۔��p�W�x�X�g�E�e���v�k�u�|�p�V���v�����N�������f�ځl�@�i277�j
�H�c�ߌ��O���u���p�蒟�v�����N�������ɔ��\�����w�����x�̊ӏ܁��c�ߌ��O�u��i����`�E�C�O��Ƃ̕��E�q���[�S�X���r�A�r�E�X�^���`�b�`�v�u���p�蒟�v�����N�������i�ꕔ��A��������Ĉ��p�����j�B�@�i279�j���i295�j
�I���M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x���ŊO���E����Ŋ����ʗt�ʐ^�@�i285�j
�J���M�u�w�����x�Ƃ����G�v�̏��o�G���u�����C�J�v��㎵��N�\�����\�ܕŁk�̒P�F�̕����l�@�i285�j
�K��e�W�w���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����x����Z�N�B�@�i285�j���i295�j
�L�����r�Y�u�ӏ܁v�w����̎��l�E�P�E�g�����x�B�@�i295�j
�M�u���㎍�蒟�v��㎵���N�\�����̓��S�u��㎍��10�сv�́u�A���\���W�[�E���I�ɂ���㎍��10�сv�̗��@�i290�j
��n�߂ɇH�́u�ꕔ��A��������Ĉ��p�����v�Ƃ��������ӏ��̓��������悤�B�H���͎��g�̕��ŃX�^���`�b�`�̊G�̕W����w�@�x�Ŋ����Ă��邪�A����ɍ��킹�ēc�ߕ��̃X�^���`�b�`��i�́u�@�v�\�L���w�@�x�ɉ��߂Ă���B�����ʂł́A�c�߂́u�����v�u�̂��o���v�u�v�o�v�����ꂼ��u���Ȃ��v�u�̂������v�u�v���o�v�Ɖ��߂��i�ӂ��߂́A���邢�͌�L�E��A���j�B�u����̔p�����J�ɂ܂Œʂ���a�I�Ȑ_�o���݂������Ȃ̂ɔ����āA�v�́u�p���v�i������C���������ꂨ�Ƃ낦�邱�Ɓj���u�r�p�v�i����͂Ă邱�Ɓj�Ɖ��߂��̂́A�H���̂����u��A�̒����v�����u�Z�{�v�ł͂���܂����B���p�ɍۂ��Ĉꌾ�����Ă�����ׂ��ӏ����Ǝv���B�����A���������ŏd���������̂́A�c�ߕ��̑�l�i���i�u���̉�Ƃ͂��̂ق��ɂ��u�o���X�f�B���̒ʂ�v�Ƃ����X�i��`�ʂ��āA���̊Ԃɂ����Ԃ݂��\�\�Ƃ����������ł݂��������̊X�ł�����悤�ȐÂ��ȕ`�ʂ����݂Ă��邪�A���̖����I�ȊՎ�͂��́u�����v�̉�ʂɂ�������Ă���B�v�Ƃ����ꕶ�j�̖����ɑ�ܒi���̖`���i�u��ʂ͒P���ȗ����̒Ⴂ�D�F�ɂ܂�Ă���B�v�j��ǂ����݂ő����ĂЂƂ̒i���ɂ��Ă��鏈�ł���B���͂����ɁA�H�����قƂ�ǖ��ӎ��̗��ōs������ƂɁA���́u�P�F�̕����v�̔ޕ��ɍʐF�̎{����Ă���u�X�^���`�b�`�@�����@1955�^M. Stancic Dead Child�v���Ȃ�Ƃ����Ċς����Ƃ����~�]�A�Q���̂悤�Ȃ��̂�������B�����܂����̋Q�����o�����l������ł���B�������Ȃ���A������V���Ў�Ás��l����{���۔��p�W�t�i��ꁁ�����s���p�فA�����1957�N5��23���y�z�`6��15���y�y�z�j�ŊςȂ��������낤�g�����Ɠ��l�A�H���K�l�͎G����g���̐��z�W�̃��m�N���}�łł����ς邱�Ƃ��ł��Ȃ������i���R�j�B�H���̓X�^���`�b�`�q�����r�������ǂ݉������B�������A�d�v�ȉӏ��Ȃ̂ŗ������Ɉ����B
�@�w�����x�̎����́A�O�ɂ��L�����ʂ�A57�~72�Z���`�A���Ȃ킿�قڎl�Ό܂̔䗦��L���Ă���B��Ƃ͂��̏c57�Z���`���قڌܓ������āA������ܕ��̈�̂Ƃ���ɁA��ʂ����E�Ɋт��������������A�����艺���e�[�u���̏�Ƃ����B�e�[�u���̌��������قڒ����ɂ́A���x�͉�ʂ̉��Ɍ����Ă�����A���䂪�����ג����䂪�u����Ă���B�����͎ʐ^���画�f�������ɂ߂Ă��ǂ������Ƃ���Ȃ̂����A�ǂ�����̗��[����ׂ͍��r�̗l�Ȃ��̂���O�̃e�[�u���Ɍ������ĐL�тĂ��Ă���A���̘r�̌������ĉE���̉����͑����I�ə��蔲����Ă���B���������䂪�A�e�[�u���Ƌ��ɉ�ʈ�t�ɑ傫�ȎO�p�`�𐬂��Ă���̂ł���B���̎O�p�`����O������猩���낷�Ƃ���A���_�͂����ɐ݂����Ă���B���ꂪ���̊G�̃p�[�X�y�N�e�B���ł���B�e�[�u���̏�ɂ́A�����猾���āA�w�ʂɎ��t�����r�������o�����Ƃő��ɐ����u����悤�ɂȂ������A�����炭�͈�ւ̉Ԃƌ�������́A�����Ă�����̂قڒ��ԂɁA��ʂ̎�O�O���牜�ւƌ������ĐL�т���{�̖_��̕��̂��L��B�������悹����̘r�Ɍĉ����邩�̂悤�ɃA�[���E�k�E���H�[���ɎO��������^�ɔg�ł������́A��ʐ��ʂɑ��Ăقڎl�\�ܓx�̊p�x�ɒu����A���̋��ʂɂ͉�ʉE���̕ǂɗL��Ƃ��ڂ���������̊X�i�����邭�h���Ă���B���̊G�̌����́A�]���āA��ʂ̉E���ɍ݂�B���ɉf�������̑��̋��̈�_�A��������قډ�ʔ����̍����܂őΊp����������A���̒��_����Ăщ�ʉE���̋��ɂ܂ʼn��낳�ꂽ�Ίp�����`���ӎO�p�`�̓����ɁA���ɐL�т���͂����ۂ�ƓU��悤�Ɉʒu���A���̏�ɁA�����̉������Q���炵�����̂��������Ă���B�܂�l�Ό܂̒����`�̒��ɁA���̌܂��ӂƂ��A�l�̓��̓�̒����܂ł������Ƃ���ӎO�p�`���A���_�����E�ɂ��炵�Ĕ[�܂�A���̎O�p�`�̓�������ӂ̗֊s�́A�����̐g�̂Ɋ|�����č��E�ɐ��ꉺ�������z����A�����܂ł��Ȃ����ю��u�����v��T�͑��s�ŋg�������s�悾�ꂩ���t�ƌ��Ȃ������̗̂Ő��Əd�Ȃ��āA�X�ɒ��_�ɂ͏����Ȏ����̓������d�Ȃ�A�Ƃ����������A�����Ă��̒��_�̂�≺�A�܂蒚�x�����̊�̍����ӂ肪�A�p�[�X�y�N�e�B���̏����_�ƂȂ邩�����ł���B��{�I�ȍ\�}�͋ɂ߂Ĉ��肵�Ă���B
�@�ӎO�p�`�ɊO�ڂ��������ɂ́A���x�͉�ʏ㕔���牺�Ɍܕ��̈�قlj������������܂ŁA���ʂ��������j���`����Ă���B���ꂪ�A�����炭�́A�����̕��e�ł���B���̂�⍶���A�j�̋����̍����܂ŁA������l�̐l���������A������̓v���t�B�[���������Ȃ���Q�����悹�����ɉE���˂��āA�܂Ƃ��Ɍ����Ɋ�������Ă���B�j���͂��ؚ��ȓ��̌`����A����͏��A���Ȃ킿�����̕�e�Ȃ̂��낤�Ǝ@������킯�ł���B���͔ޏ��̗����Ă���ʒu�͉�ʂ̉��ɐL�т���̈�Ԏ�O�̒[�Ƃ��ڂ����A��������̓����݂̍�ʒu�͂��̓�����̈�ԉ��̒[�Ƃ��ڂ����̂����A���҂̊Ԃ̋�Ԃ͂����ƋÏk����ĕ`���ꂽ���߁A�ꌩ����Ɠ�l�͊�Ɗ�Ƃ������킹�Ă���悤�ɂ�������B��B����ȋ�ɕ`���ꂽ�X�^���`�b�`�́w�����x��O�ɂ��Ď����ŏ��Ɏw�E���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂́A�܂��Ɋ���͂��߂Ƃ������̐l�������̌`�Ԃ̍ו��ɏA���āA�������B�����ɕ`���ꂽ�O�l�̐l�������͂���������m�ȕ\���t�^����Ă��Ȃ��B�ޓ��́A�Ⴆ�Β����̑e���̒i�K�ɂł��݂邩�̂悤�ɁA�P���Ȋ�@�̍ݏ����ŏ����ɂڂ���Ǝ����Ă��邾���Ȃ̂������B���̕\��̌�����₤���̂悤�ɁA�����̖T��ɗ������v�w�͉�ʍł����̕ǖʍ����ɂ��낮��ƈӖ��L�肰�ȉe�𗬂��Ă���̂ł���B�ނ��l������ł͂Ȃ��A�����ł̓e�[�u������������̐Q�����A�����炭�͋��̏㕔�Ƒ�̘r�̙���`�̐��ȊO�͎������A�`�ʂ�������P���Ȓ����ƋȐ��ɋ��闧�̂ɊҌ�����ĕ\�킳��Ă���B�������瓱���ꂽ�̂��u���ẪR���g���X�g����ɂ�����i�ł���ō\���ȂL���[�r�Y���݂����Ȃ����v�Ƃ������ؐT��̕]���������B�����āA�c�ߌ��O�̕��͂ɋ���A�ȏ�̑S�Ắu�P���ȗ����̒Ⴂ�D�F�ɂ܂�Ă���v�炵���̂������B�i�s�g�����A���x�X�N�t�A��`�܃y�[�W�j
�H�����u�u���p�蒟�v�����N�������Ɓu�݂Â�v�����N�������A�y�ѐ��M�W�w�u�����v�Ƃ����G�x���ŊO���E����Ŋ����ʗt�ʐ^�ɉ����āA�����̐��M�u�w�����x�Ƃ����G�v�̏��o�G���u�����C�J�v��㎵��N�\�����\�ܕłɌf�ڂ��ꂽ�A��������e���Ƃ����Ă悢��ނ̒P�F�̕����Ɋ���Â炷����A���ɉ��邱�Ƃ͂����܂łł���B�������A��l����{���۔��p�W�̉��Ɏ��ۂɑ����^��ł��̊G�ɐڂ����킯�ł͂Ȃ������ȏ�A�ǂ����g�������Ŕj���������̂������炭�͂���Ɗ����ς��Ȃ��������Ƃ��낤�Ƃ������Ƃ͍l������B�v�i�����A�܃y�[�W�j�ƒV�����悤�ɁA�X�^���`�b�`�q�����r�͒��炭���m�N���}�łł����ς邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�����A�Ό��Ƃ����̂͂�������ɗ���邾���ł͂Ȃ������B���͂��̂قǃX�^���`�b�`�q�����r�����p�قɓW������Ă���i�Ǝv�����j�J���[�ʐ^���摜�������邱�Ƃ��ł����B���Ƃ�茴����ςĂ��Ȃ����ɂ́A�F�������ł��Ȃ��B�g�p����摜�\�t�g����������3��ނ̐F���i���}��A�EB�EC�j�ɕϊ����Čf���邪�A�I���W�i���̉摜�́uhttps://keineahnung.tistory.com/57�v�ł����������������B�Ȃ��uMiljenko Stancic Dead Child�v�ʼn摜��������ƁA���@���A���g�Ǝv�����qdead child�r�i�U�O���u�ߌ�����p�ّ��j������B���ꂪ���������V�A���E�N�[�g�[�����̂��́A�Ƃ��Ƃ��̐l���i�����̕�e�H�j���A���̂悤�ȁu�悾�ꂩ���v��z���Ă���̂́A���������ǂ��������Ƃ��낤�i�uhttps://www.flickr.com/photos/mrshultgren/6066438880�v�Q�Ɓj�B�g���͂�����́qdead child�r��m��R���Ȃ��̂�����A�u���R�v�Ƃ������z�͂ق�Ƃ��ɕ|�낵���B
 �@
�@ �@
�@
�X�^���`�b�`�q�����r�kA�l�i���j�A���kB�l�i���j�A���kC�l�i�E�j �k�����摜�f�[�^�ɂ��ꂼ��F���C�����{����3��ށl
���p�ق̕ǖʂ̐F�i�����ނ˖��ʐF�j���l���ɓ����ƁA�kA�l�i���j���kC�l�i�E�j�����ۂ̐F���ɋ߂��悤�Ɏv����B���āA���̉摜���f�ڂ����y�[�W�̖{���i���p�ق̖K��L�Ǝv�����j�̓n���O���ŏ�����Ă��āA�c�O�Ȃ��玄�͓Ɨ͂Ŕ��ǂł��Ȃ��B���P�̍�Ƃ��āAGoogle�|���ʂ��đ�ӂ����B�M�҂͂����ŁA�G��Ɖ��i����ъG��̉���j�̊W�ɂ��čl�@���Ă���B�ށ^�ޏ��́A�N���A�`�A�암�̃X�v���b�g�i�_���}�`�A�S�̎�s�A�A�h���A�C���C�݂̏����Ȕ����Ɉʒu����j�ɑ؍݂����Ō�̓��A�������s�X������āA������x�ς悤�Ƃ��ē��������p�فi�L�ڂ͂Ȃ����A�X�v���b�g�s�������ق��j�ŁA�����̋����[����i�̂Ȃ��ł��L���Ɏc���i�̂ЂƂ\�\Miljenko Stancic�̍�i�\�\�̂܂��ɗ��iMiljenko Stancic�i1926�`1977�j�̓��[�S�X���r�A�̉�ƁE�O���t�B�b�N�A�[�`�X�g�B�p���Wikipedia���@�B�|��ƁA�J�^�J�i�\�L�́u�~���W�F���R�E�X�^���`�b�`�v�ƂȂ邪�A�ߋ��̖M�������ɂ́u�~���G���R�E�X�^���`�b�`�v�Ƃ���j�B�ǂ����X�^���`�b�`�̍�i�͔��p�ق̍쐬����}�^�i������̂����悭�킩��Ȃ����j�ɉ�����L����Ă��Ȃ��悤�ŁA�M�҂͉�ʂɂȂɂ��`����Ă��邩���߂����Ĕϖシ��B
�u�܂��A�u�^�C�g���v��\���ɂ���B�^�C�g���͍�Ƃ̈Ӑ}�����S�ɉ���������Ɩ����ɖ𗧂��Ă��Ȃ��ȏ�̍�Ƃ̂��̂ł��邱�ƂɈႢ�Ȃ��B���̍�i�ł́A�uDead Child�v�Ɩ������ꂽ�B�u���q���v�́A�摜�ɓo�ꂷ��3�l�̂�����l�ł���\��������܂��������Ă����l���l����ƁA�h�肩���ɉ�������Ă���Ԃ���u���q���v�ł���m���������B�������A�����ōl�����ׂ����Ƃ́A��b�͂����u�^���v�������Ă��Ȃ��_�ł���B���I�ȍ�Ƃł���A���]�������Ă��邩������Ȃ��B�iSF���A�V�b�N�X�Z���X���ł͂Ȃ����낤���j�A�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃɍ����̂悤�ɉB����Ă��邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�Ƃɂ����A���̂悤�ȉ\���������A���̍�Ƃ́u���q���v�����ɗ����������̓�l�̎p��g�����g�[���ŕ`�������̂ł���B�i���̂悤�ȓ_�Ɏ����z���l�I�ɁuUntitle�v���ł��D�܂Ȃ��j�v�iGoogle�|��j�B
�摜�i�M�҂��B�e�������̂��낤�j���f�����Ă���ȏ�A��������ƂłȂ��邱�Ƃ��Ă��Ȃ��̂�s�R�Ɏv���K�v�͂Ȃ����A���⎀���̈Ӗ����鏈���Ȃɂ��́A���АG��Ăق��������B�������̊G���J���[�Ŋςčŏ��ɋ������̂́A�H�����u�����炭�͈�ւ̉Ԃƌ�������́v�Ƃ��ĂƂ炦���̂��A���L�H���g���ĉ�������H�̒��i�J�T�T�M�ɂ��Ă͉H�̐�܂ō����j���������Ƃ��B�������X�^���`�b�`�����́u�����̒Ⴂ�D�F�v�i�c�ߌ��O�j�ƒ����F���x�[�X�ɂ����قƂ�ǃ��m�g�[���̉�ʂɔ��ƍ��̒��ƁA���ƊD�F�̋���z�����ɂ��Ă͖��m�ȈӐ}���������ɈႢ�Ȃ��B���̓����𖾂�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ɂ���A���̂��ƂɐG�ꂸ�Ɂu�����܂ł���i���ӏ܂��āA��30���ȏ�A���̑O�ɗ����čl�����摜�ƃ^�C�g���̊W���B�v�iGoogle�|��j�Ƃ��߂�����M�҂̏،����A�M�҂̎v�l�̍q�Ղ��A���͐ɂ��ށB
�v��ʊ�蓹���������D�����A�H���K�l���g�������ς邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ������X�^���`�b�`�q�����r�̃J���[�}�ł̏Љ�Ƃ������Ƃł������������������B�q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ɖ߂낤�B���_�̍Ō�ŁA�H���͎����q���������r�i�C�E16�A���o�͎��W�s�m���t�A���惆���C�J�A1958�N11��20���A���M��1958�N�j�̒��قǂ��i����ɒ����̂����j���p���Ă���A���̂悤�ɏ����B
����́A���ɂ��A��́s�[���I�t�ɂ��ʂ���g�\���������Ĉ�̃��@���G�[�V�����Ƃ��ď����ꂽ�A�u�����v��⋭���鑤�ʂ������������������B�����Ȃ���s���̎g���t�������Ƃ���I�ɂ́s�l�ނ̂̂��ꂽ�L���t���҂ݏグ���k�Ȃ�ʁs�t���t�����Ղ�����Ȃ������g�Ɏ��狖�����G�S�e�B�Y���iegotisme�j�̋L�^�A�s����̓G�ł��t�s�����ł��ȁt�������ƍ��͖]���o���鉓�����̎���̗�]�B���ю��u�����v�̎��w�Ɍ��������ׂ��́A�s��a��㵒p�t�����m�̏�́A�������������_����тт������҂ɋ߂��p���������悤�Ȃ̂ł���B�}�炸���s���҂����̏K���t���悭�s�n�m����t�ɋy��ł����g���ɂƂ��ẮA�������āu�����v�̎��M�͈�́s�ǓƂȋV���t�ɒ^��ɂ��������A������s�Ȃ��t�邱�Ƃ͒N�ɂ������Ȃ����Ƃ������̂��B�i�s�g�����A���x�X�N�t�A����y�[�W�j
�H���́q�����r�_�́A�J�肩�����A�g���̎��сq���������r�Ɍ��y���ďI���B���͂��́q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�i���o�́s�����g���E�o���Y�tVol.5�A1999�N7���A����́q�g�����Ǝ����Ƃ����G�r�j�̏��ǂ̂Ƃ�����A�H�����v��Ɋ������Ă����B�����őz���o�ɂӂ��邱�Ƃ������Ă��炤�Ȃ�A���͏H�����疈��A���o���s�����g���E�o���Y�t���b�����������Ă����B���̂NJ��z��F�߂����A�������{�_�Łu�Ō^�v�ƋL����Ă����̂��A�ł�version�ŁA���̏ꍇ��size�̔����Ə������悤�Ɏv���B�u���^�v�̓v���̏�����ł��ԈႤ���Ƃ������p��ŁA�Ǐ����s�Ɗw��S�t�i�����ł���j�ɂ��u�Ō^�v�Ƃ���̂͐ɂ��܂��i������2�ӏ��j�B�ҏW��Z���̒i�K�ł��`�F�b�N���ׂ��������B�b�x��B�����A����̒T���łق�Ƃ��ɋ������̂́A�g�����H���������ŃX�^���`�b�`�q�����r���ς����낤�s���p�蒟�t�i1957�N7�����j�ɁA���̐}�ł��f�ڂ���Ă������Ƃ��B
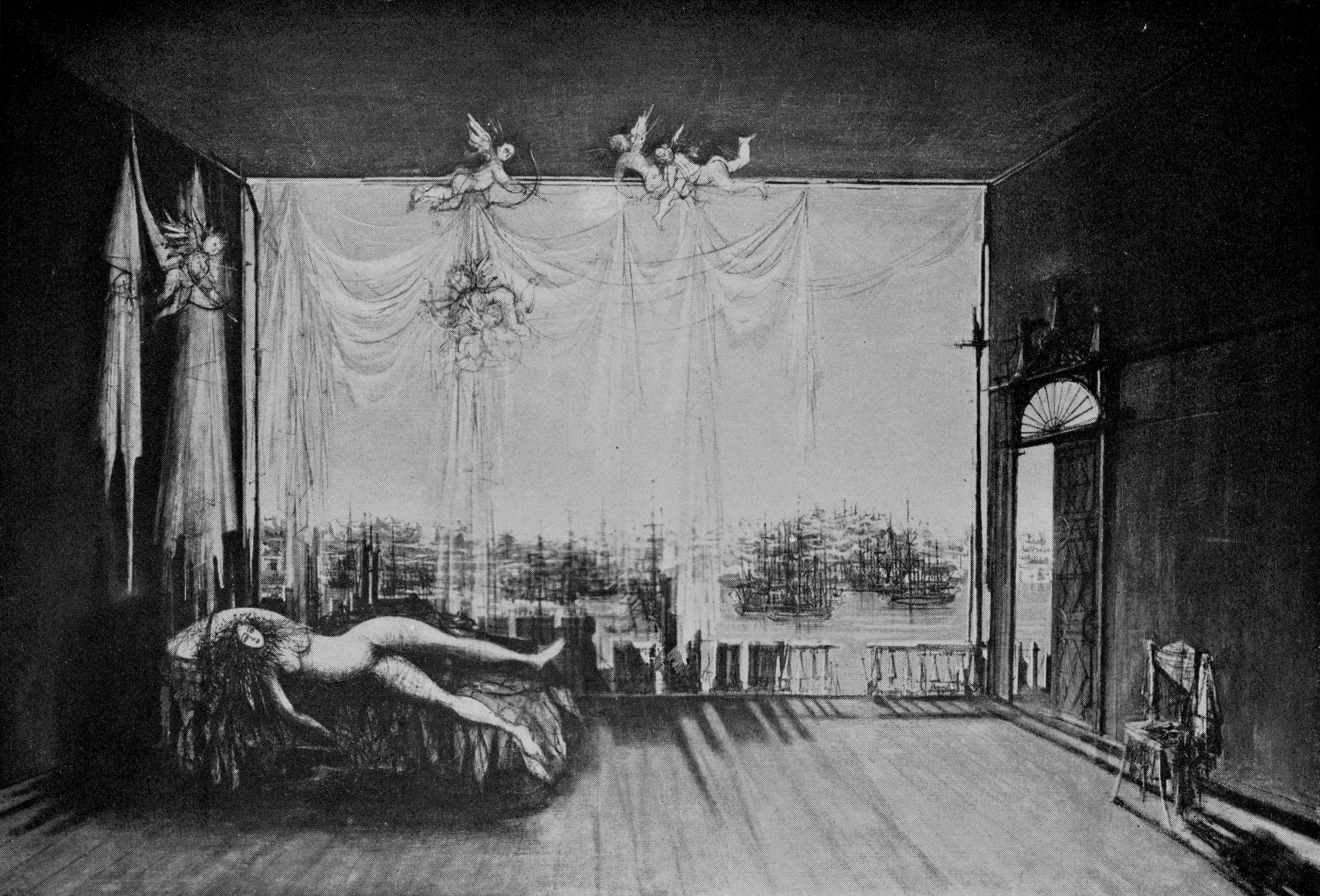 �@
�@
�u�J���Y�[�@���������@130�~195cm�@1955�v �k�o�T�F�s���p�蒟�t1957�N7�����A���y�[�W�l�i���j�Ɓu�J���Y�[�@���������@1955�@130�~195cm�@�@�@�@�@�@Carzou�@�@Le Beau Voyage�v �k�o�T�F�s�݂Â�t1957�N7�����A�܈�y�[�W�l�i�E�j
�J���Y�[�iJean Carzou�A1907�`2000�j�ɋg�������y�������Ƃ͂Ȃ��B�܂��Ă�A�g���̎��сq���������r�ƃJ���Y�[�̊G�q���������r����ׂ����͂́A���̒m�邩����A���݂��Ȃ��B�s���p�蒟�t1957�N7�����k���W�E��l����{���۔��p�W�l�́A�ʒ��̔��h�H���S�ʂ��₵�āA���m�N�����G�ɃJ���Y�[�̊G�q���������r���f���A�Ό��̖{���y�[�W�S�ʂ𓌖�F���́q����r�ɏ[�Ă��B���̈����́A1�y�[�W�ɐ}�ł�������������߂�ꂽ�X�^���`�b�`�Ƃ͒i�Ⴂ���B��l��������ςȂ������͂����Ȃ��i�������A�唻�́s�݂Â�t���N�������ɂ́A�J���[�Ōf�ڂ���Ă���j�B�H�����J���Y�[�̊G�q���������r�ɐG��Ȃ������̂́A���邢�͋g�������ɕ�������߂��B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�g���͑剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�j�́u���꒤���̌���v�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
�g���@�k�c�c�l�ڂ������������ꍇ�A���܂�Ă����J�����ŗǂ̊��ԂȂ́B��J���̂�����\���Ԃ͗V�Ԃ킯��A�S�̈�_�ɂƂ߂āB���Ƃ̎l�A�ܓ����w�Ɋ��B
�剪�@���ɂ��̋����B
�g���@�Ƃ������A�������c�c�B��������̏\�����炢�O����A������ŎG���ǂ�{�ǂ�A������ƋC���������̂�ǂށB�ł���nj��e�p���Ɍ����A����ŁA�܂����ƈ�C�ɏ����Ă�B�����Ǐ����Ă��A�����Ȃ��B�Ƃ����̂́A����܂�l�������Ă͂����Ȃ��B���͎����ōl���ď�������ǂ��A����Ƃ��납��A�_������Ƃ������A�^�����邱�Ƃ��o�Ă��銴��������B���̍ŏ��ɏo�Ă������Ƃ��ł��邾����ɂ������B�����v������A�����ŏ����������Ƃ����Ȃ��B�����������A�ʂ̍l�����܂������œ����Ă��ď��x���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�����ŁA�����̓z�ɐ����𗊂݁A�������ɂ��đ҂B��������ƍr������̌����I�Ȏ��̑��e���o�����킯��B����Ɏ�����Ă�����Ƃ𑱂���B������O�炢�J�Ԃ��čŌ�̎O�����炢�łЂƂ̂��̂�����������B�����炫�݂��������A�����ł��Ă�Ȃ������Ă̂́A�܂��ɂ������B���́A�ŏ��̈�s���炠��܂�l���Ă����Ă͓������Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�������܂��ꂽ���t�̕��u��������A���̎��͓����o���Ȃ��Ǝv���B�܂�Ȃ����̍s���A�����ޓ��̂悤�ɝp�܂邱�Ƃ������_��ɂ��āA�^�̃��A���e�B��ۗL�����邱�ƂɂȂ�B�Ƃڂ��͐M���Ă���B�Ƃ͂����Ă��A�܂��P���Ȃ�ˁB�i�����A��܌܃y�[�W�j
�����z���̐����̏��͂����Ԃ�[�܂����C���������āA������k�b�����A�q�R���̊��z�i�o��j�\�\�n���\���N�L�O�S����� �^���Ձr�i�s�o��]�_�t78���A1968�N3���j�ł͂��ڂ�������Ă���B
�@�܂��A���{�I�ɂ����āA���̏������ɂ͂��낢�날��܂����ǁA�i�c�k�k�߁l���A�������������悤�ɁA���R������Ƃ͈̑�ł���Ƃ������ƁA�܂��ɂ���Ȃ�ŁA����͓���A�Εׂ��Ă��ʖڂ��낤���A�Εׂ̋łɁA��̋��R�ɂԂ��邩������Ȃ��\�\�B�l�Ȃ��������ꍇ�A�l�͔��ɕς��Ă܂��āA�Ƃ̃`���u��\�\�A���͂��܊�������܂���̂ŁA�������疳����ŁA�����Δ������ł����ǁA�������P�c�j�ɏZ��ł��ŁA�`���u��ŏ����Ă܂����ǁ\�\�B�l�͎��������Ƃ����ꍇ�́A���Ɏp�����͂����肵�܂��āA���Ƃ��A����Ƃ��납�玍�𗊂܂��ƁA���Ԃ͒�����Β����قǂ�����ł����A���������ꃕ���ȏ�O�ɗ��܂�Ȃ��Ɓ\�\�B�Ȃɂ����ɂ͈ꃕ���Ȃ������ĂȂ���ŁA���������т��炵�āA�p�`���R�������A�f��֍s������A����Ŏ��͏����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ȃ��ƁA�������C�ɂ͂��Ă���B�C�ɂ��Ă��āA����������T�Ԃ��炢�O����A���悢����肪�������\�\�A���������Ȃ����Ⴂ���Ȃ��ƁA���Ɍ����A�����������̂�ǂށB�G�̖{��ǂ�A�������āA��������O�����炢�ŁA���ׂď����Ă��܂��B���̂����Ƃ����p���\�\�A�o���Ƃ̕��͏����Ⴄ�Ǝv���܂����ǁA�l�͂͂����肵���A���̂����p���Ƃ������̂��A���ɑ厖�ɂ����ł��B���͍̂��Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B���͎̂��肾�Ƃ����A�͂�����Ƃ����ӎu�������č���Ă䂭�B�i�����A��l�y�[�W�j
�g���̃p�`���R�D���́A���l���Ԃł��L���������B�z�q�v�l�ɂ��A�Ζ���̒}�����[�ŋg����m����1954�N����́A��Ђ̋A��ɖ����ɂ悤�Ƀp�`���R���Ɋ���Ă��āA1959�N�Ɍ������Ă���͐^�����A���悤�ɂȂ������A���j���ɂ͋߂��̃p�`���R���ɍs���Ă����Ƃ����B�����āA��ł����łȂ��Ȃ����Ƃ��i�S���I�ȓd���_�C�������n���h���̉��ւ����a48�N�j�A�p�`���R���ʂ�����߂��Ƃ̂��Ƃ��B���̏��a48�N�A�g����54���}����1973�N�́A�g�������ɂƂ��Ă�����𐬂����N�������B�̂��Ɂs�T�t�����E�݁t�i1976�j�Ɏ��߂���9�с\�\�}�_���E���C���̎q���i1���j�A������܌�b�сi2���j�A�w�A���X�x���i5���j�A�T�t�����E�݁A�s�N�j�b�N�i7���j�A�c���i9���j�A�����i10���j�A�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�A�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i11���j�\�\�������ꂽ�̂ł���B�g���̓p�`���R�̓S�̋ʂ̊��G�����łȂ���A�����̎�ʂ̎��т݂������̂������B�g�������ɂ�������̃s�[�N���Ȃ����W�s�T�t�����E�݁t�́A�킯�Ă���ソ��R�����\�����邱���̎��т��B

���R��v�s�p�`���R�k���̂Ɛl�Ԃ̕����j 186�l�t�i�@����w�o�ŋǁA2021�N6��25���j�̃W���P�b�g �k�����q�p�`���R�N�\ ���w�r�ɋg�����Ɋւ���L�q��4�ӏ�����l
�i���Q�j�@�H���K�l���q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�ŋ����������ŁA�X�^���`�b�`�̊G�q�����r�̌��J���ɐ}�ł��f�ڂ����͕̂����ԍ��̇@�ƇA�����Ȃ̂ŁA�H���͗��҂��r�������������A�g�������q�����r�������h���ƂȂ����͇̂A�́s���p�蒟�t�������Ɛ��_����B�����炭����͐������B�X�^���`�b�`�́q�����r���߂��錾���ɂ����钆�S�I�Ȕ��p�]�_�Ƃ̓�l�A���ؐT��i1931�`2011�j�Ɠc�ߌ��O�i1903�`1989�j�̂����A�H���͐������������Ă���悤�����A�A�́s���p�蒟�t�f�ڂ̓c�߂̊ӏܕ��́A�Z���܂ł��Ă��̑S�т������Ē��ӂ����N���Ă���̂��B�����H���́A�g�����q�u�����v�Ƃ����G�r�Łu������A���p�G�������Ă���ƁA��ȊG���������B����ɂ́i�X�^���`�b�`�@�������܌܁j�Ə������������Ă����B�[���I�@�Ƃ͂������������A���͂��̎��u���̐풆���v���u�����v�Ƃ����薼�ŏ������Ƃɂ����̂ł���B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�j�Ə������A�u��ȊG�v���f�ڂ������p�G�����s�݂Â�t�Ȃ̂��A�s���p�蒟�t�Ȃ̂��A�f�肵�Ȃ������B���͂������Ǝv���B
�\�\�g����1957�N7���ȍ~�̂�����A�K���I�ɔ��p�G���s�݂Â�t�i624���j����Ɏ�����B�}�����[�������Ƃ��Ē���w�ǂ��Ă���G���ł���B�����̓��W�́k�����ƊG��l�A�u��4����{���۔��p�W����v�Ƃ���B���͓����s���p�فA�����5��23������6��15���܂ŁB���������A��Ђ̋Ɩ������Z�Ŋςɂ����Ȃ������Ȃ��A�ƙꂫ�Ȃ���A�ς�ς�ƃy�[�W���J��B��ȊG������A�q�����r�B�u�����V��v�A�u�����̗�𐔂���v���c�c�B���͗���A��1958�N5�����߁A�����C�J�̈ɒB���v�Ɛ_�ے��̋i���X���h���I�ŃE�C���i�����T���Ă�����A�����������Ɨ��܂ꂽ�B400�s�͌������̂�300�s�ɂ��Ă���Ɠ������B���������܂�100�s���鎍�����������Ƃ��Ȃ����A�s���͂̂���肾�B�����o���ĈɒB�̏��֍s���A200�s�ɂ܂��Ă�������B���āA���ɐݒ肵���u���̐풆���v�������̂ɂǂ��������̂��B�ӂƏ��I������ƁA���p�G����蔲���ē\�����u��ȊG�v������B�q�X�^���`�b�`�@�����@1955�r�B���ꂾ�I�@�������X�^���`�b�`�Ƃ͂����������҂��낤�B�q�����r�Ƃ����͉̂��B�s�݂Â�t�̊����ɂ͔��p�o�ŎЂ̎G���̕ʍ��`�T���̐V���ē����ڂ��Ă���B�s���p�蒟�t�̓��W�ɂ́u��i����`�C�O��Ƃ̕��v�Ƃ��ăX�^���`�b�`���Љ��Ă���炵���B�悵�A�����̒��x�݂ɂł��x�͑䉺�̌Ï��挹�쓰��`���āA�o�b�N�i���o�[��T���Ă݂悤�B�Ï��X�Ȃ��Ђ�������Ă������B�������āA�s�݂Â�t�ɑ����ās���p�蒟�t���苖�ɑ������B�\�\�ȏ�́A�g���̐��z��k�b����Ɏ����z�������ꖋ�����A�����ɋg�����g�ɂ��M�d�ȏ،�������B�����q�����r���Ę^�������{���|�Ƌ���i���{���W�ψ���j�ҁs���{���W�t�i���惆���C�J�A1960�N1��10���j�ɕt�����q��i�m�[�g�r�ł���B�����̎U���ɂ��A�k�@�l���ɍZ�����{���đS���������B
�@�u�����v�ɂ͐���̋�Y�ƁA�ЂƂ�̏��ւ̈���[�߂��v���o������B����͈��ܔ��N�k�����܁l����\�O���̖邾�B��Ƃn�̉ƂɁu�����v�̉������������āA�ޏ��Ƌ��ɔ������B�ڂ������~�̏������Łu�����v�̊������߂������B�ޏ��͂n�̉Ƒ��ƃA�g���G�ŗV��ł����B�ނ���ҋ@���Ă���̂��B���̈�����o����Ɣޏ����Ăя����̂B���M�����̌��e�ő��l�ɂ͔��ǂł��ʂ悤�Ȃ��̂��A�ޏ��͗v�̂悭�܂Ƃ߂��B�����̖�܂łɍŏI�̈�����̂����݂̂ɂȂ����B�ޏ��̏��������c�ɂ���āA�����̎����݂邱�ƂɈ��̐������Ɨ�Â����ۂĂ��B���ꂩ���T�ԂقNjꂵ�݁A�k�と�Z�l���Z���̋łɍŏI�̗����ł����B�ꐇ�����Ȃ����������܂��疰��Ȃ��B���ĂȂ������ƍV���̂����Ɍ{�̖��̂����B�����Ă����ޏ������ɂ��Ȃ��̂������䂩�����B�ޏ����Ђ��ς�������Ă���Ȃ�������A�u�����v�͂����Ƃڂ��̎�����������A�ʂ̂��̂ɂȂ��Ă����낤�B�i�����A����y�[�W�j
�q�f�ЁE���L���r�́u�k���a�O�\�O�N�l�Z���\�ܓ��@�����C�J�������o���B���ю��q�����r�f�ځB���s�삩���m��ʂ��A�Ǝ��Ȗ���Ǝ�������B�݂�������j���B�v�i�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t�A�v���ЁA1968�A��ꎵ�y�[�W�j�����Ă��킩��悤�ɁA�g�����q�����r���������̂�8������9���ɂ����āA�Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��i�q���сq�����r�̐�����r�Q�Ɓj�B���Ȃ݂�1958�N5��23���͋��j���A6��6�������j���B6��15���͓��j���B�u��Ƃn�v�͑��c�唪�A�u�ޏ��v�͗�1959�N5���Ɍ������邱�ƂɂȂ铯���̘a�c�z�q�B�q�f�ЁE���L���r�ɂ́A�悭���j���ɗ��n�̑��c�Ƃɔ��܂�ɍs�������Ƃ��o�Ă���i���̂�����̂��Ƃ́A���قȂ������_�A�p�x���琏�z�q�u�����v�Ƃ����G�r�ɂ�������Ă���j�B�����A�g���̉��h�̂������]�Óc�́A�����r�ܐ��ŗ��n�w�ׁׂ̗̗A�r�܊��̊w���X�ł���B

���́s�݂Â�t1957�N7�����E66�`67�y�[�W�̌��J�� �k�E�y�[�W�̉��i���X�^���`�b�`�q�����r�l�A�E�́s���p�蒟�t1957�N7�����E27�`26�y�[�W�̌��J�� �k���y�[�W���X�^���`�b�`�q�����r�Ɠc�ߌ��O�ɂ�������l
�g�������p�G������蔲���ăe�[�v�œ\����Ă���������́A�O���r�A�ł́s�݂Â�t�̂���ł����āA�ʔłŖԓ_�̖ڗ��s���p�蒟�t�̂���ł͂Ȃ������ƍl������B
�i���R�j�@�s���{���۔��p�W�t�̕�I�Ȍ������ɁA���{�ߌ�����p�j�̎R���W���ɂ��s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�\�\���̕ϑJ�Ɓu���p�v���x��ǂ݉����t�i�n���ЁA2017�N12��20���j������B�s���{���۔��p�W�t�̑�1��i1952�N�j����I�����}������18��i1990�N�j�܂ŁA�{���⎑���ŕ��L�����y���Ă��邪�A�{���ɂ̓X�^���`�b�`���q�����r���o�ꂵ�Ȃ��B�Ȃ��{�e�ŋ������ȊO�̕����Ƃ��āA�G���s�O�ʁt1957�N7���������邪�����B�s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�ł́A���W�ɐG��āq��O�� �u���{���۔��p�W�i�����r�G���i�[���j�v�čl�^���� �u���{���۔��p�W�v�̍\���Ƃ��̖����^�R �u�������v���]���镑��̌`���r�ŁA�s�݂Â�t�̕\�����e���f���āA�x�i�y��q���p�Ɩ����r�A���{���Y�q�������Ɛ��E���r�����p�����ق��A���̃^�C�g���Ƃ��āA�j����Y�q�`���ƑO�q�\�\�O�q�����͓`���̒S����ł���r�A�{��ЗY�q���p�ɂ����閯�O�r�A�ѕ��q���p�Ɍ��閯���̑̎��r�A�A������q���{��d�̈ʒu�r���Љ�Ă���B���̂��ƎR���́A
�@�����̌����́A���{���Y�����ɋ����w�E���Ă��邪�A��]�̃x�N�g�����P�Ȃ鐢�E�����������̂ł͂Ȃ��A��ɓ��{�Ƃ�����̖��A�����ɂ��Ε��y�▯�����ւ̎u���������Ă����B���R�A���ۂɂ͂ǂ��ł������̂��Ƃ�����肪���邪�A�܁Z�N��͂܂��C�O�̍�ƁE��i���[���Ɋӏ܂ł���悤�Ȋ��ł͂Ȃ��A���܈�N�ɓ����E���̍������Łu�s�J�\�W�v�i�ǔ��V���Ў�Áj���J�Â���A����ɓ������������قŁu�}�e�B�X�W�v�i�ǔ��V���Ў�Áj�A�����Ė����V���Ђɂ��u�T�����E�h�E�����{�W�v���J�Â���A�悤�₭�C�O��Ƃ̍�i�����荞��ł���悤�ɂȂ����������B�����ɁA��v�Ȕ��p�G�����n������n�߂鎞���ł���B���̂悤�Ȕ��p�E�̍Đ����Ɂu���{���۔��p�W�v�͒a�����A�C�O��i�Ɠ��{�̉�d�S�̂Ƃ��A����ΐ��ʏՓ˂����ݏo�����Ӌ`�͑傫���B�i�����A����`���O�y�[�W�j
�Ƒ������Ă���B�Ȃɂ�瓖������20�N��A1970�N�㏉�߂̉p�ă��b�N�~���[�W�V�����̗������b�V����f�i�����邪�i�����Ƃ��r�[�g���Y�͂��ł�1966�N�ɗ������Ă���j�A������Ɋւ��Ă͑����`�V�q�����~���[�W�V�����E���b�V���̑b�ƂȂ�����㖜���r�ɏڂ����B�R���́s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�́A���������u��ォ�獂�x�o�ϐ������Ɏ���܂łɕϗe���Ă�������^���p�W�̑g�D�E�I���E��i�A�����Ĕ�]�̉��l����𖾂��A���̌���ʂ��A�����{�̔��p�j�u�`���ߒ��v��ǂ݉����v���Ƃ��u�����Ă���B����ɑ��āA�g���̃X�^���`�b�`�q�����r�ւ̊S�́A���{�́u���p�j�v����{�Ɛ��E�́u���y�▯�����v�Ƃ������ϓ_����͂܂�������������Ă���B�s��l����{���۔��p�W�t�J�Î��A�g�������ɑ����^�Ƃ��Ă��A���m�N���}�ł́q�����r���狝���Ƃ����ȏ�̎��n�\�\�ہA�͂����茾�����A�Ռ��\�\���͂����Ă��������B�^�₾�B
�k�t�L�l
�R���W���s���{���۔��p�W�Ɛ����p�j�t�̊����ɕt���ꂽ�q�y�����Q�z�u���{���۔��p�W�i�����r�G���i�[���j�Ɋւ��錾���̌f�ڏv�r�i�����A�O���i10�j�y�[�W�j������ƁA��1���18��܂ł̂��ׂẲ�Łs���{���۔��p�W�t�̐}�^�����s����Ă���B�������s���p�}���ى��f�����iALC search�j�t�́q�W����J�^���O�E�}���iExhibition Catalogues and Books�j�r�Łu���{���۔��p�W�v����������ƁA�������۔��p�فi���j�Ɂs��l����{���۔��p�W�t�}�^�������́q�}�����ڍׁr���f�ڂ���Ă���B���R�̂悤�ɑݏo���͂��Ă��炸�A�{�����\�łȂɂ��Ɩʓ|���B�R���i�Ђ̉e�����낤�B���p�}���ق̏��������͖������Ƃ��āA����߂��̌����}���قő��ݑݎ̉\����Őf���Ă݂���A�����s��23��̐}���قɏ����͂Ȃ��A�ߍx�̑�w�}���فi������w�A�����Y�p��w�A���q���p��w�������j���{���݂̂ŁA���������݁A�w�O����̗��p�͍s���Ă��Ȃ��Ƃ����B�����B�O�̂��߂ɁA�s���{�̌Ö{���t��������x�������Ă݂�Ɓi�O�Ɂu��l����{���۔��p�W�v�Ō��������Ƃ��́A�ɐꂾ�����j�A�����L�ڂ���Ă��Ȃ����̂́A���p�W���J�Â��ꂽ�N�A1957�N���s�́s���{���۔��p�W�t�̐}�^���o�i����Ă���ł͂Ȃ����B���ꂱ���T�����߂Ă����W����J�^���O�ł���B���������A�k��B�s�̍��䏑�X������肵���B
�{���̎d�l�͂`�T��44�y�[�W�E���Ԃ��A�\���̓X�~�ƐE�Ԃ̓��F����A���ʂ͊���16�y�[�W�̖{���A�ʒ����G12�y�[�W�̐}�ŁA�����Ċ���12�y�[�W�̂���8�y�[�W���q�o�i�ژ^�r�ŁA���Ƃ�4�y�[�W���o�ŎЂ̏��ЍL���i�\�R�͖{�}�^�̐����Ђł�������p�o�ŎЂ̏o�ōL���j�ł���B���p�W�̉��E����A���t�̋L�ڂ͂Ȃ��B���͖M���Ɖp���̕��L�Łu��4��/���{���۔��p�W//�����V���Ёv�uTHE FOURTH INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF JAPAN/1957/THE MAINICHI NEWSPAPERS�v�B�������J���͖����V���ЎВ��̈��A�A����11�y�[�W���q�e����d�W�]�r�ŁA�e���̎��M�҂́A�A�����J���R�c�q�O�Y�A�I�[�X�g���A���Ö���Y�A�x���M�[���A������A�u���W�������V��Y�A�C�M���X������C���A�t�����X���x�i�y��A�h�C�c���y�����A�C���h�������W��A�C�^���A�������ӑP�Y�A���L�V�R���k�������A�X�y�C�����{�{�O�Y�A�X�C�X�����厛���p�A���[�S�X���r�A���c�ߌ��O�A���{�������B�c�߂́q���[�S�X���r�A�̍�i�r�̈�߂ɂ�������B
�@��Ƃ͂�������킪���ɂ͏��߂ďЉ���l�X�ł��邪�A���̒��ł͂��ƂɃX�b�s�T��������Ă���B�k�c�c�l����Ɂu���[�X�������v���܂����̔w�i�͂Ƃ��Ƃ������A�������߂̏��͖ڂ������āA��ʂ͐l���̒f�ʂ�����ǂ��Ƃ炦��ƂƂ��ɁA����̗d���ł��ʂ��Ă���悤�ł���B����ɑ��ăX�^���`�b�`�͒������I�ȃ��`�[�t���������Ă��邪�A���������̌X���ɂ��肪���ȕa�݂��ꂽ�A�S���Ȃ��B��ʂ͂ނ��떾�N�ŁA�����Ȑ�������V�����Ȃ���A���̎v���������Ȃ����E�ɂ݂��т��āA�͂��Ȃ����W���⛌�̒��ɁA�u�����v���߂��錶�z��A�����ɂ����܌������i�ɂ������u�o���X�f�B���̒ʂ�v���ʂ��Ă���B�i�����A��l�y�[�W�j
�}�ł́A�V���K�[���i�t�����X�j�Ɣ~�����O�Y�i���{�j��4�F�ł���ق��͂��ׂă��m�N���ŁA���[�S�X���r�A����͌��̃X�b�s�T�q���[�X�������r������1�_�A�f�ڂ���Ă���i��f�s�݂Â�t1957�N7�����E66�`67�y�[�W�̌��J���̉E�y�[�W�̏�i������i�j�B�����́q�o�i�ژ^�r�̃��[�S�X���r�A�̕�����~���G���R�E�X�^���`�b�`��3��i���ׂĂ��������A�c�߂̕��͂Ɍ�����q�o���X�f�B���̒ʂ�r���������Ă��Ȃ��̂͂ǂ������킯���낤�B�L�ڂ́A�i�o�W��i�̘A�Ԃɑ����āj��Ɩ��k�ȗ��l�@���@����N�@�傫���i�W�j�A�̏��ł���B
�@�@����@�@�@�����Ɖԁ@�@�@���l�@�@�@�Z��E�܁~�l�E��
�@�@����@�@�@�������@�@�@�@�V�@�@�@�@�@�@�Z��~�l
�@�@���O�@�@�@�����@�@�@�@�@���܌܁@�@�@���~����
�g�������{�}�^��W�����œ��肵�����Ƃ͂Ȃ������͂����B�����A�o�ŎЂ̏��ЍL���̂�����1�Ђ͋g���̋Ζ����Ă����}�����[�ŁA�s�q���q��㉁t�ق��̔��p�����ڂ��Ă���B�����������Ƃ������āA�g�������̍��q����ɂ������Ƃ��܂������Ȃ������Ƃ͌�������Ȃ��B�����A�̐S�́q�����r�̐}�ł��Ȃ�����ɂ́A�܂��u�}�^�v���u���p�G���v�łȂ��ȏ�́A�g���̎��q�����r�ƃX�^���`�b�`�̊G�q�����r���r����ɍۂ��āA�{���������Ƃ��x��͂Ȃ��B

�}�^�s��4����{���۔��p�W�t�i�����V���ЁAc1957�k�N5��23���l�j�̕\�� �k���ɂ́u��4��/���{���۔��p�W//�����V���Ёv�uTHE FOURTH INTERNATIONAL ART EXHIBITION OF JAPAN/1957/THE MAINICHI NEWSPAPERS�v�ƕ��L����Ă���l
�}�����[��ސE����1�N���܂肪�߂���1981�i���a56�j�N�A�g������62���}�����B���̔N�̎���i�́A�q�ɂ�Ƃ�r�i1���j�A�q�G�m����n�̐��r�i9���j�A�q�G�̂Ȃ��̏��r�i10���j�A�q����r�i11���j��4�сB�������т́q�G�̂Ȃ��̏��r�������āA����������W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j���\������d�v�ȍ�i�ł���B����̏[���Ԃ�ƘA������悤�ɁA���̔N�Ɋς��W����������A�g���́k���M�l�N���ł�6��𐔂���B
�@���a�\�Z�N�@��㔪��N �Z�\���
�y#17�z���~�A�������������قŁA�Ӑ^�a�㑜��q�ς���A���̐Î��B
���s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N1��15���y�E�j�z�`2��1���y���z��
�y#18�z�ɐ��O�V�قŁA�u�s�J�\�鑠�̃s�J�\�v�W���ς�B
�����K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j�^�����W�F��ꁁ�ɐ��O���p�فA�����1981�N3��5���y���z�`4��7���y�z��
�y#19�z�z�t�A��썑�����m���p�قŁA�u�A���O���W�v�i�u��v�ɖ�������j�B
���������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j�^�����W�F��ꁁ�������m���p�فA�����1981�N4��28���y�z�`6��14���y���z��
�y#20�z�������������ق։��A�u���R���������W�v�A���̍��̏o�y�i�Ɋ�������B
���������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N3��17���y�z�`5��5���y�E�j�z��
�y#21�z�ӏH�A������قŁA�u���e���O�Y�̊G��v�W�֍Ȃƍs���A�a��F��A�������Y�A�O�D�L��Y�A�߉ϑ��Y�ƒk����B
���s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j�k���C�A�E�g�F�g�����l�^��ꁁ�������p�فA�����1981�N11��9���y���z�`30���y���z��
�y#22�z���������ߑ���p�ق́u�����N�W�v���ς�B
�����������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�^��ꁁ���������ߑ���p�فA�����1981�N10��9���y���z�`11��23���y���E�j�z��
�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪��N�i���a�\�Z�N�j �Z�\��v�̍��Ɍ�����W����W�̕��i�́j�������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�O�`���Z�l�y�[�W�j�B
�y#17�z�������������قŊӐ^�a�㑜��q�ρA�����V���q�̓X�Ɋ��g�R�����߂�B
�y#18�z�ɐ��O���p�قŁq�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W�r�B
�y#19�z�k�L�ڂȂ��l
�y#20�z�������������فq���R���������W�r���ςČ��̍��̏o�y�i�Ɋ�������B
�y#21�z�\�ꌎ�A�������p�ق́q���e���O�Y�̊G��r�W�֍s�����e����v�Ȃɏ�����ď\���l�Ő��e�Ƃ�K�₵�A�×{���̐��e���O�Y�ƌܕ��قlj�i���ꂪ���l�Ƃ̕ʂ�ɂȂ����j�B
�y#22�z���������ߑ���p�قŁq�����N�W�r���ς�B
��
�y#17�z�s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j
�g���͐��z�q�w���W�x�f�z�r�i���o�F�s����Z�̑S�W�k��6���l�t�q����10�r�A�}�����[�A1981�N3��25���j�ʼn�Ô���̒Z�̂ɐG��A�Ӑ^�a�㑜�Ɍ��y���Ă���B
�@�@���قĂ�̂܂낫�͂���̂����������ɂӂ݂��̂�����������
�@�@�Ƃ����ւɂ˂ނ�Ă��͂����قĂ�̂��܂̂������ɂ����Ȃ��ނ��
�@���m���̓������r����̂����̓��ł���B�ނ����́A�����͂ޕ����Ȃ��A�K�ꂽ�l�͋C�܂܂ɁA�����ɓ��ꂽ���̂ł������B�u�厛�̉~�����v�ƕ`�ʂ��ꂽ�A�����̑��d�ȂƂ�����m�A�A�A�A�n�`�ɂӂ���������ɁA�����u�I�v�̔��v�����������̂��B�����H���q�́u寂Ȃ��ē����t���Â��v�̈��̂悤�ȐÎ�Ɩ��́A�ɂ������͎���ꂽ���Ƃ��낤�B���ڂ́A���m�Ӑ^�a�㑜���r���̂ł���B����܂łɎO�A�l�x���̎���K�ꂽ���A�c�O�Ȃ��Ƃɘa�㑜���ς邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������A�������ƌ�ɓ��{���̍������ŁA���e�̉Ԃɕ�܂��悤�ɁA���u���ꂽ�Ӑ^�a�㑜���q���邱�Ƃ��ł����B����Ȃ��������ɁA�S�ł��ꂽ�B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z��y�[�W�j
�g���̏����u�������ƌ�ɓ��{���̍������ŁA���e�̉Ԃɕ�܂��悤�ɁA���u���ꂽ�Ӑ^�a�㑜���q���邱�Ƃ��ł����B�v�Ƃ����̂����̂��ƂȂ̂��A�u�ꌒ��Y�̘J��s�S�ݓX�̓W����\�\���a�݂̂�����1945-1988�t�i�}�����[�A2018�N3��20���j�ɓ������Ă��\�\���������q�������Ђ̓W����i1951�`54�j�r�ɂ́A�����E�����V���Ў�Ấs�ޗǓ����W�t�i��ꁁ��쏼�≮�A�����1953�N1��16���`2��1���j�Ƃ������e�̋L�ځi�����A��l��y�[�W�Q�Ɓj�͌�������̂́\�\�A�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��킩��Ȃ������B�Ȃ��u�ꌒ��Y�́A�u���̓W����m�����W�n�������ām�S�ݓX�ł́n�ޗǂ̑厛�̓W����͂����܂��ł��낤�v�i�����A�O�l�y�[�W�j�Ƃ������c���q�ޗǓ����W�r�i�s���������كj���[�X�t��69���A1953�N12���j�̈ꕶ���Љ�A�����A�L�����Ђ̌�J���������̓���҂��W�߂��A�Ƒ������Ă���B
 �@
�@
�s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j�̕\���i���j�Ɠ����E��y�[�W�́k�Ӑ^�a�㑜�l�i�E�j
�g���́k���M�l�N���ɂ͌����Ȃ����A�g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�ɂ͖{�W�ɑ����āu�����V���q�̓X�Ɋ��g�R�����߂�B�v�Ƃ���B���̌��͌������ꂽ�g���̓��L�␏�z�ɂ͂Ȃ��A�z�q�v�l�̋L�^�������͋L���Ɉ˂�Ǝv����B���E�r�V�[�ɂ���L�E�g�R�̘V�܂́u�����v�B�g���́A�Ⴊ��ԃt�@�C���A�[�g�̂ق��ɂ��A��Ǝ肪��Ԃ��������H�|�i���������i���P�j�B
��
�y#18�z���K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j
�s�J�\�ɂ��Ă��q�g�����ƃs�J�\�r�i2017�N4��30���j�Łi�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�����������ɏo���āj�������̂ŁA�t��������ׂ����Ƃ͂Ȃ��B����ɂ��Ă��A���Ɩ���Ɍ��Ă���悤�ȁq���̂��锯�̏��r�̊�́i�������j�������B�L���r�X���̐��Ƃ����悤�B
 �@
�@
���K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j�̕\���k�f�ڍ�i�͐}�^�{���ɂ͌����Ȃ��l�i���j�Ɠ����́q109�@���̂��锯�̏��@1946.6.14�^Femme aux cheveux lisses�r�i�E�j
��
�y#19�z�������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j
�{�����m�N���y�[�W�q�J�^���O�r�́q54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X�r�i�q��r�̎p����f�i������j�̍��i�������g�B�M�������j�������B���M�͍������m���p�يw�|�ۂ̌������E�L�쎡�j�B
54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X
1807/08�N��
���`���[�N�@�@38.3�~28.5cm
�������݂���
�����g�[�o���C�A���O�����p��
�k�c�c�l
�@���̑f�`�ł́C���B�[�i�X�̑S�g���𒆐S�ɁC���r�̈ʒu�̂��܂��܂ȉ\�����T���Ă���B�E�r��ɉC���r�Ŕ��ɂ��炵�Ċ������Ă���悤�Ȏp�����ŏI�I�ɍ̂��邱�ƂƂȂ�B�C����オ��������́C�܂�㵂��炢���m��ʃ��B�[�i�X�̎p�ł���B�A���O���̏K��f�`�̂����ł��C�ł����������̂̂ЂƂɐ������悤�B
���p�j�Ƃ̒r��p�m�́s���\���p�j�\�\�k�[�h����閼��̓�k�����܊w�|���Ɂl�t�i�}�����[�A2014�N11��10���j�́q���� ���B�[�i�X�\�\���\�̎x�z�ҁr�́u��݂����������Â̔��_�v�Ƃ����߂ŁA�q��r�̃J���[�}�ł��f���āA�L���v�V�����Ɂu�k�c�c�l�ނ͖{��i�̑O�ɁA���̃��f���Ƃقړ����|�[�Y���Ƃ�q���B�[�i�X�̒a���i������オ�郔�B�[�i�X�j�r�i�V�����e�B�C�A�R���e���p�فj���`���Ă���A�C�^���A�̓����̍�i�Q����\�}���w���Ƃ͖��炩�ł���B�v�i�����A��l�y�[�W�j�ƋL���āA�}���w�I�Ȍn���𖾂炩�ɂ��Ă���B�R���f���p�ق̃A���O����i�́A���P���������Ă��Ȃ������������p�ŁA��Ƃ������ɂ��̍\�}�ɌŎ����Ă�����������������i�C���^�[�l�b�g�ŗe�Ղɉ摜�����ł���j�B
�g�������y�����A���O���̍�i�͂��́q��r���������A���́q�h�[�\�����B�����ݕv�l�̏ё��r�i1845�j�́A�Ƃ�킯���̋����I�ł�������ߕ��̃^�b�`����A�����q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�i�G�E17�j�̑�O�߂�z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�u�ߌ��̏����ɂ͂ӂ�ނ��^�̐��ʂ��Ȃ��^���F�̃X�J�[�g�̍����悶���ā^�˂���֒��̔�Ԃ̂����Â���v�̂́A�����炭�A���O���̕`�����ݕv�l�ł͂Ȃ����낤�B�����A�|�낵���܂łɃt�H�[�J�X�̍�������ʂ̂悤�ȋg���̎���́A���́u�V�ÓT��`�̑�Ɓv�i�r��O�f���j�̊G�M���肽���̂悤���B�g�������ɂ����Ė{�������ĕM�������ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ�����ł���B�Ƃ���ŁA�W����̓��ꌔ�ɂ͂�����̌Ăѕ���i���f�ڂ��邱�Ƃ������i�}�^�̕\�������l�j�B����́s�A���O���W�t�́A���R�̂悤�Ɂq��r�i1820�`1856�j���g�p���Ă���B���ꌔ�́q��r�̗��e�ɔz�����ׂ��F�т́A�\���Ɠ�����������ŁA�G���̐V�N���̂悤�ɍ����B
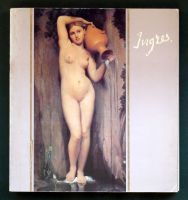 �@
�@
�������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j�̕\���k�A���O���̍�i�́q56�@��r�l�i���j�Ɠ����́q54�@�u���B�[�i�X�E�A�i�f�B�I���l�v�̂��߂̏K��F���B�[�i�X�r�i�E�j
��
�y#20�z�������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j
�g���́k���M�l�N���Łu�z�t�A�k�c�c�l�������������ق։��A�u���R���������W�v�A���̍��̏o�y�i�Ɋ�������B�v�Ə����Ă��邪�A�������ɂ���͒��ڂɒl����W��������悤���B
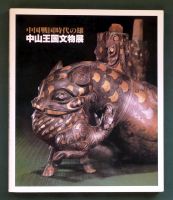 �@
�@ �@
�@
�������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j�̕\���i���j�Ɠ����́q1 �O�N���`��r�i���j�Ɓq40 �\�ܘAᵐC��r�i�E�j
�k���F�}�Łl�́q18 ����ۛƛ�������u����H���Ձv�r�́A�i���j�̕\���̎ʐ^�Ƃ͕ʃJ�b�g�̑S�g���ŁA�}�^�̂Ȃ��ł��Q�����݊��������Ă���B�\���Ɣ����f�U�C�������͖��v�i1906�`1999�j�����̑���I�̂�������B
�i���j�̎ʐ^�A�q�O�N���m�����n�`��r�͊����̃J���[�}�łł���B�\�\�u�u�R�v���`�����Ă���Ƃ��납��C�ȑO�́u�R�v���`��Ƃ��ĂB�㕔�͎O�̐�N�C�������[�͉��тĉQ�����������𐬂��B���������ɉ~�`��銎�m���悤�n������C�o�y���ɖ؊D���c���Ă������Ƃ���C�{���C�ؒ��̏�ɑ}������Ă������Ƃ��킩��B��^�̓����`�ł���Ƃ��납��u�O�N���`��v�Ɩ��t����ꂽ�B�v�i�������g�B�q��i����r�A�{���A��܈�y�[�W�j�B����Ƃ��A�[��̂m�g�j�a�r�v���~�A���̋I�s�ԑg�s���� ���͌����ւ̗��t�ŁA�O�N���`��Ƃ悭�����Պ���������ØV�����{������_�̈�{�ɐG���ƁA��҂����������ɂ���ɌQ����V�[�����ς��B2300�N���̎����āA���Ȃ���̂��������肽�u�Ԃ������B
�i�E�j�̎ʐ^�A�q40 �\�ܘAᵐC��r�́A�C��ɂ܂Ƃ����������̎p�䂦�A�������q�����̑����_�^���V�L�_�Ō��y���Ă���A�G�b�Z�C�W�s�����̓T�����ȁH�t�i���{���|�ЁA1992�N7��3���j�����́q�}��XI�E���R������o�y�̈�i�r�ɂ́A�����炭��f�ʐ^�Ɠ��J�b�g�̃��m�N���ʐ^���f�ڂ���Ă���B����܂��A���V����ق��Ȃ���i�ł���B
�`���ŐG�ꂽ�悤�ɁA�g���͔N�n�́q�ɂ�Ƃ�r�i�J�E1�A�̂��q雞�r�Ɖ���j�����������ƁA���炭���т̔��\�͂Ȃ��A����͖{�W��́s���㎍�蒟�t1981�N9�����́q�G�m����n�̐��r�i�J�E2�j�������i���X�̎G�������ŏ��o��ǂƂ��́A�v���Ԃ�ɐڂ����g���������傫���ς�낤�Ƃ��Ă���̂�\�����āA�k�����j�B�q�G�̐��r��
�u�S�͊Ձm�����n���ɂ��ā@�ڂ���������v
������̂���߂�͗l�̋�̂��Ƃ����܂悤
�@�@�}�b�`������Ɓ@�킽���̍D���ȁ@����ʂ�
�@�@��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Ԃǂ��̕\�ʁj
���̋��̂́u���Ɣ������ƈŁv��
�O�̑w�ɕ���Ă���
�Ǝn�܂�B�{�W�̐}�^�ɓ�ʁi�u�ʂ̈��B�p�M�Α��z�����琬��B�ח��k���ȓ��p�M���琬����͖̂��F�A�z�N���琬����͈̂×ΐF�ŁA�����ΐ܂����Ő��Ə̂���B��j���ォ�����ʂɗp�����v�k�s�L�����t�l�B�l�t���C�g��nephrite�j���Ő��͓o�ꂵ�Ȃ��悤�����A����́A�ۂ�ǂ�A�˂�������̂��̂�i�r�ցH�j��̂��̂��J���[�}�łɌ�����B�g�����̎��т́A���Ƃ��ΐ��e���O�Y�i1894�`1982�j�̔ӔN�̎��т�����߂ē��^�ɋ߂����̂ł���̂ɑ��āi�������A�i���̑��̂��Ƃɂ����Ē��߂�ꂽ����j�A���悻���^�ӂ��ł͂Ȃ��̂����A��f�̂悤�Ȏ���ɓW����ł̊��������߂��̂�������Ȃ��B�킽�������͂��łɁA�s�Ẳ��t�i1979�j�́q�~���̓����r�i�H�E28�j�ɂ����āA�s�{�i�E�h�E�}���f�B�A���O�W�t�̍�i������ɂƂǂ߂�ꂽ���Ƃ����Ă����i�q�g�����̈��p���i2�j�\�\�剪�M�s���q�V�S�t�r�Q�Ɓj�B�g�����́u�����v�̂��鎞�_�Ł\�\�����炭�s�T�t�����E�݁t�i1976�j�̌㔼�𐬂����т������Ă�������\�\�A���̑z���͂̂����܂���앗�ɂ����āA�����������i���̎����D��܂��邱�Ƃ���i�̃��A���e�B��ۏ���ƍl����悤�ɂȂ����悤���B���l�̏͋�i��{�I�ɁA����͔�������j���c���Ɉ��p�����A������g�����́u���p���v���O������g��������⋭������̂��Ƃ���A�����������g�̌����́A���́u���v�Ƃ��Ă����A�������Ƃ��Đ���������u���@�v�Ƃ��āA�����炭���o�I�ɑ��тƂ�ꂽ���̂ł͂Ȃ����B���ɂ́A���̐���ʁ��Ԃǂ��̎O�w�u���Ɣ������ƈŁv�����ꂼ��A���p���ꂽ�͋�A�z���͂̂����܂��鎍��A���i���̎���A�̎O�Ɍ�����B
��
�y#21�z�s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j
�s���e���O�Y�̊G��t�̐}�^�͖{�T�C�g�̑n�ݑ����A�q�g�����̃��C�A�E�g�i1�j�r�i2003�N3��31���j�ŏЉ���B���W�͉�ꁁ�������p�فA�����1981�N11��9���`30���B�}�^���\���Ɂu�ʐ^�F���c�F�F�@�� 44, 59�͎���[�V�@���C�A�E�g�F�g�����v�Ƃ���B���̐}�^���ʁi�����A�k��Z�`���y�[�W�l�j�̒��i�E�A���i�E�̐}�ł͂��ꂼ��q61 �w�Ẳ��x����i1�j�r�Ɓq62 �w�Ẳ��x����i2�j�r�����A�\�R�́q�o�i���X�g�r�ŏ���₦�A�i1�j�i2�j�Ƃ��ɁA����N�́u1979�v�A�ގ��́u���ʁv�A�T�C�Y�́u37.5�~28.0cm�v�ł���B�{���s���e���O�Y�̊G��t�́A�g�����f�U�C���E���C�A�E�g�Ŋւ�����B��̔��p��i�̐}�^���Ǝv����B���e���O�Y�͖{�W�J�Â̗�1982�N��6���A88�şf�����i���Q�j�B
 �@
�@
�s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j�̕\���k���e�̍�i�́q52 �k�C���̗��r�l�i���j�Ɠ��E���ʁi�E�j�k���C�A�E�g�F�g�����l
��
�y#22�z���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j
�\��㔼�̎��ɂƂ��čł��e���������Ƃ������ܖ؊��V�́s�ܖ؊��V��i�W�k�S24���l�t�i���Y�t�H�A1972�`1974�j�̃��B�W���A���Ɂq���сr����сA���i���F�s���̓��k��E���l�t�̐V�����ɔŁi1976�j�̓W���P�b�g�Ɂq�C�݂̓�l�̏��r�q�ڕ��r�̃J���[�}�ł��f���Ă����B�}�炸���A�o���Ƃ��G�h�����h�E�����N�̔ʼn�ł���i�q���сr�̓��g�O���t�A�q�C�݂̓�l�̏��r�Ɓq�ڕ��r�͖ؔŁj�B�g���������q����r�i�G�E23�j�\�\�u�����������N�̊G�̎��Ɂ^�q�a�߂鏭���r�^�Ƃ����̂�����v�Ǝn�܂�\�\�ŐG�ꂽ�q�a�߂�q�r�ɂ́A�h���C�|�C���g�A�G�b�`���O�A���g�O���t�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�@�̔ʼn悪������肩�A���ʂ܂ł����āA�g�������̂ǂ��z�肵���̂����߂������B
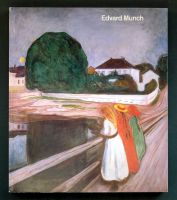 �@
�@ �@
�@
���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�̕\���k�����N�̍�i�́q102�^�V���̏��������^The Girls on the Bridge�^1901�r�l�i���j�Ɠ����E��l���y�[�W�́q122�^�a�߂�q�^The Sick Child�^1894�k�h���C�|�C���g�l�r�i���j�Ɠ����E��l�܃y�[�W�́q125�^�a�߂�q�^The Sick Child�^1896�k���g�O���t�G��ʐF�l�r�i�E�j
�k2021�N9��30���NjL�l
�g�����{�W���ς��̂́A�q����r�i���o�͔o���s��t1974�N10�����j�����M����7�N�ゾ�����B����A�q����r���\�̔��N�قǂ܂��ɁA�Ζ���̒}�����[����j�b�N�E�X�^���O�i��x���F��j�s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�i1974�N3��25���j���o�Ă���B�g�����{����ǂ��s�������A�����̕ʒ����G�Ɂq�a�߂�q�r���J���[�Ōf�ڂ���Ă���i�u���G�P�F�a�߂�q�D���G�C1885-86�D�v�j�B�}�ł͑O������B����ɂ��Ă���̂ŁA�i�{���ɓ\��ꂽ�m�h�����܂߂āj�������ꂽ����������ƉE��3mm�قNj����Ȃ��Ă���B����͂Ƃ������A�g�����q����r���������Ƃ��A���̖��ʉ�q�a�߂�q�r��O���ɒu���Ă����\���͂���߂č����B���Ƃɂ��ƁA1981�N�́s�����N�W�t�ɑ����^�̂́A�{����ς�i�m�F����j���߂������̂�������Ȃ��B�������A���������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�ɖ��ʂ́q�a�߂�q�r�͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�X�^���O�́s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�͖��ʁq�a�߂�q�r�ɐG��āu�k�c�c�l�ߌ����܂��K���B�\�܍̃\�t�B�G�k�����N�̎o�l�̓��a�����ƁA�ꔪ�����N�ɂ�����ޏ��̎��́A���ɕx�\�l�̏��N�����N�ɂƂ��āA�����܂����̌��ƂȂ����B�����N�́A���̐l�ԓI�̌��Ɉꐶ��������A���ꂩ�玩�Ȃ�������邱�Ƃ͂��ɂł��Ȃ������̂ł���B�����N�̎�v��i�A�u�a�߂�q�v�i���G�P�j�Ɓu�t�v�i�t�}�U�j���A�������ꔪ���Z�N��̌㔼�Ɋ������Ă��邱�Ƃ́A���̌o���Ɋ֘A���Ă��邩������Ȃ��B�v�i�����A��Z�y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�쑺���Y�i�s�����N�k�V�����p���Ɂl�t�j�ɂ��A�gMunch�h�ɂ̓m���E�F�[��Łu�m���v�̈ӂ�����Ƃ����B

�y�Q�l�z�����N�q�a�߂�q�r�i1885�`86�N�@�J�����@�X�@���ʁ@119.5�~118.5cm�j �k�o�T�F�쑺���Y����s�����N�k�V�����p���Ɂl�t�i�V���ЁA1979�N7��25���j�B�{�}�́s�]�` �G�h�����h�E�����N�t�̌��G�ƈႢ�A�g���~���O����Ă��Ȃ��l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@������b�q�͋g�����́k�ё��l�ł���q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�Ɂu�u����Ȃɍ����͂Ȃ�����ǁA����ł������͍����l�i�v�̒O�O�ɑI�ꂽ�A�����ɂ��g���ƓI�Ȋȑf�ŒP���Ō`�̔������\�\�g�����͏��N�̍������Ǝu�]�ł��������̂����A���̌`�̂Ǝ�G��ɁA���ł��ƂĂ��s�q�����A������������̉s�q���ɑ��ĉs�q���\�\�Ƌ��H��v�A�u�肪���̓��Ɠe�̌`�̉����炵���A����Ȃɍ����͂Ȃ����NjC�ɓ������̂�������̂ɋ�J�����ƌ������̂ݒ��q�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��ꔪ�y�[�W�j�Ə����āA�g���̕s�f�g���̕��ɑ���p���������Ă����B
�i���Q�j�@�{�W�I�[�v�j���O��11��9���̖�A���e�@�ŏ��O�Y�Ɖ�����̂��A�g����������l�u�搶�v�ƌĂ��l�Ƃ̕ʂ�ƂȂ����i�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u13�@�G�͔������u���[�E���ʂ�v�Q�Ɓj�B�Ȃ��A�g���̐��z�q�y���Ȃ�́\�\��ؒf�z�r�i���o�́s�ΐ��ؑS�W�k��4���l�t�q����r�A�}�����[�A1980�N3��10���j�Ɂu���͐_�c�_�ے��ɂ���y�Ђ֍s�����B�V���W�s�Ẳ��t�̊����͂��邱�ƂƁA�������邽�߂������B��Ƃ��I�邱��A���łɊX�͕��Ă����B�k�c�c�l���͑���Ɏg�������e���O�Y�搶�̊G�ƁA�V���W�܍������A�Ö{���X��������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l���y�[�W�j�Ƃ���B�V���W�̑���ɗp����Ƃ������ڂŁA�g���͐��e��2�_�̐��ʉ��`�����낵�Ă��炤���Ƃɐ��������̂��B�s���e���O�Y�̊G��t�W�̔��N��A�{�W���L�O���邩�̂悤�ɁA���̖����s���e���O�Y�̊G��t�i�P���ЁA1982�N5��30���j�Ƃ����唻�̉�W�����s���ꂽ�B���e�͂���1�T�Ԍ��1982�N6��5���A�̋��̐V���E����J�̕a�@�ŖS���Ȃ��Ă��邩��A�{����ڂɂ��邱�Ƃ��ł������ǂ����B���t�O�̑Ό��y�[�W�Ɏ��̃N���W�b�g������B
�@�@�\���������J�b�g�@���e���O�Y
�@�@����@�@�@�@�@�@�@�ѓc�P��
�@�@�I���@�@�@�@�@�@�@�ѓ��k��k�ѓ��͊����̃G�b�Z�C�q��ƂƂ��Ă̐��e���O�Y�r�����M���Ă���l
�@�@�ҏW�@�@�@�@�@�@�@�C�����o�j
�@�@����@�@�@�@�@�@�@���Z���v
�@�@��i�ʐ^�@�@�@�@�@���c�F�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����[�V
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i45�����56�j
�s���p�蒟�t�̕ҏW�����������Z���v���͂��߁A����琼�e�G��Ɋւ�����X�^�b�t�S�����A���U�[�ɔ��������҂ɖ{���������ׂ������������Ƃł��낤�B���Ȃ݂ɔ��s�҂̍P���ЁE�r�c�P�Y�́A���e�G��̃R���N�^�[�ł�����B�g�����́A�{���Ɍ��́s�Ẳ��t�̑���ŋ��͂��Ă���B
 �@
�@ �@
�@
�y�Q�l�����z�s���e���O�Y�̊G��t�i�P���ЁA1982�N5��30���j���^�́q62 �w�Ẳ��x����i1�j�r�i���j�Ɠ��E�q63 �w�Ẳ��x����i2�j�r�i���j�Ƌg�������W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�N10��30���j�̔��ƕ\���k�����F�g�����l�i�E�j
�i�i��S���F�����r�Y����j
�@�]�X���F����A���肢���܂��B
��
�q�킽���̋g�����r�y����4�z�\�\�]�X���F����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j
�i�]�X���F����A�o�d�j �k����F�ӔN�̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e�����c�c�l
�@���m�킽�����n�������̂��̉���I��ł����������ӔC�̐l�A���ꂩ����̐l�ɂ����b�ɂȂ��Ă���܂��B
�@���͋g������Ɠ�����Ђɂ������������Ȃ肠��܂��āB�ŋ߁A��Ђ̌i�C�������Ȃ��ēs�������܂��āA���O�̕��ɁB���O�Ɉڂ���3�N�ɂȂ��ł����ǁA�ڂ��Ă����X�ǂցA2�A3���̂����ɍs���܂��āA�����Ǝv���āA����́w���܂�͂����L�x�̋g������̏������t�q�Ƃ��������ɂ�����ƁB����ŗX�ǂ��o�āA�����X���m���܂���n�ɂȂ��ł����ǁA�X���̋��̏�łςς��Ə�����������B�ŁA���ꂫ��B�ڂ��͂�������イ�X�ǂ֍s���܂����A���ꂩ�����Ɉ�x�͉X�����s�����藈���肵�Ă܂����ǂ��A���ɂ��̏����ɂ͂��̌�A����Ă���܂���B
�@��Ђ̂Ȃ��ŋg������Ƃ̕t��������\���܂��ƁA�w���e���O�Y�S�W�x�Ƃ����傫���d��������܂��āA���������b�ɂȂ�܂�������ǂ��A��c�j�Y�Ƃ������y�̎��l���S���ŁB���e����A��������イ�V�тɗ����ł�����ǂ��A��Ђ̔�p�Ƃ����܂����A�ҏW��ł����͐��e�����A��ĕ����Ȃ��B������e����c�j�Y�A�g����������y�����邱�Ƃ����܂ɂ͂������ł��傤����ǂ��B�ڂ��͂ǂ����Ă�ł��炦�Ȃ��A��������ɘA��čs���Ă��炦�Ȃ��킯�ł��B�ڂ��͗���ԂƂ������Ƃł��B����Ɨ����A�g�������C�Ȃ��u�]�X����v�ƁA���q�߂����T�C�g�E�R�[�q�[�Ƃ����Â��X�������ł�����ǂ��A�����֘A��čs���Ă���Ăł��ˁA�G�k���܂��āB
�@�ڂ��̍ŏ��̎��W����g������ɑ��������肢���邱�Ƃ��ł��āA�����ւ肪�����A�Ƃ����ӂ��ɂ��݂��݊����Ă���܂�����ǂ��B
�@���������̋@��Ȃ̂ŁA�����Đ\�������܂��ƁA�u�]�X����͖{������v�ƌ����Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����B���̖ڂ��������Ƃ����āA�u���ꂪ�u�{�����v�ƌ������Ƃ́A������������͂Ȃ���v�ƌ����܂����B�ڂ�`������ŁB
�@�����ЂƂA���������̃`�����X�ł�����A�E�C���ӂ���Đ\�������܂�����ǂ��A�ӔN�̋g������̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e���������Ȃ����i���A�݁j�A�Ǝ��͎v���܂��B�ǂ����A���肪�Ƃ��������܂����B
�i���A����j
�k�t�L�l
�g���������̍]�X���F���W�s��⸂ƉԎ]�t�i���ЁA1971�j�ɂ��ẮA�����́k����Łl�ƂƂ��ɁA�q�g�����̑�����i�i94�j�r�ŏЉ���̂ŁA������������������������B�����ł́A�g���ɂ��]�X�]�ɂ��G��Ă���B
����̉������������̂����u�ӔN�̋g������̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e���������Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂��B�v�Ƃ��������͂����ւ�d�v�ŁA���͂����q�g�����ƃI�N�^�r�I�E�p�X�r�i2005�N3��31���j�Ńp�X�Ƌg���̊W�ɐG��Ȃ���u���ɂ͋g�����p�X�̎����ق�Ƃ��Ɂu�[�����������v�̂́A1983�N�́s��ʁt���s�̂��ƁA1984�N�̃p�X�̗����O�̂悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B�����������_���܂߂āA�s��ʁt���`�̐����Ɋւ��Ă͍e�����߂ďq�ׂ����B�������R�ƁA�g�����u���\�I���сv�́q�R �w鍎q�ꝱ�x�r�ŐG��Ă���}�������A�i���푽�l�Ȉ��p���ɂ��Ắj�]�X���F�̓������̎��сA�����ĂȂɂ����g�����g�́q雞�r���o�`�Ǝ��W���^�`���r��������K�v������A�ƍ��͊����Ă���B�v�Ə����������ŁA���̐��W�J�����Ă��Ȃ��B�킪�Ӗ���p����B�s��ʁt���^�ƍ]�X���Ƃ̊W�ɂ��ẮA�������������Ƃɂ������B
�]�X���F�ɂ́A���W���U���W���A���̒������M���Ɋr�ׂ�Ƌ����قǏ��Ȃ��B����ȎU���̒����̈���Ɂs�z���͂Ǝ��R�t�i�|�ЁA1983�N3��31���j������B��f�̎v���o�b��₤�Ӗ��ł��A���́q�_�c�_�ے��̐��e����r�����p���Ă��������B
�k�c�c�l�킽�����w���e���O�Y�S�W�x�̊��s�ɉ�������Ƃ��āA��c�j�Y�A�g�����̌�ɂ������Ĉꏏ�����Ă������������e������͂ޏ�̂��������A������l������t���������߂��点�Ă����B�k�c�c�l�i�����A�ꎵ�܃y�[�W�j
�@�w�S�W�x���s�̍��̌��C�Ȑ��e����A��������s�A���̋����B��������J�ւ̈ꔑ�̗��A�����āA�ق�Ƃɂ悭�_�c�ւ���������B���쒬�̌Âт��Љ��̌��ւɌ����鐼�e����Asoft�X�ɉĂ�panama�A�_�ے��ɂ͐��e���͂��߂ď㋞���ꂽ�Ƃ����܂�����߂��X�q�����܂����̂܂܂̓X���J���Ă����B�Óc�В��͐l���m�肷��l�ŁA�Ƃꉮ�ŁA���e������w�҂Ǝv���������h���ċ����������Ă����B������e���������Ȃ��Ƃɉ��v����ł��Ȃ������낤�B�ł���c�j�Y���g�������s�݂ł킽��������������ł͂܂�Ȃ��v��ꂽ�͂����B���̂킽�����O�o���Ă��ċA���Ď�t�̏�������A�搶�������������āc�c�Ƃ������t�����ꂽ���Ƃ��������B����ȂƂ��A���̓T��ȂƂ�����a�m�̐g�n�݁A���Ăɂ��㉺�A�l�N�^�C�𒅂����A�X�e�b�L����ɂ��������������p���v���̂������B��t�̏����̂��̌������A�{���ɂ��C�̓łɁ\�\�Ƃ킽����ӂ߂�ӂ��Ȃ̂��B�i���O�A�ꎵ�Z�`�ꎵ���y�[�W�j
�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j��1975�N3��19���̋g���́q���L�r�ɂ́A�u�[���A���e���O�Y�搶���ЁA�H����U���邪�A���̂ō]�X���F�ɑւ��ĖႤ�B�v�i�����A���܃y�[�W�j�Ƃ���B�Ȃ��A�s���e���O�Y�S�W�t�́A���҂̐��O�Ɂk�S10���l�i1971�N3��5���`1973�N1��20���j���A�f��Ɂk��10���l�k��11���l�k�ʊ��l�₵���Łi1982�N6��25���`1983�N7��20���j���o�Ă���B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�j�̋g�����k���M�l�N����1982�N�̍��Ɂu�ӏH�A�_�c�̃��h���I�ŁA��c�j�Y�A���J�K�M�A�V�q�r��A�]�X���F��ƏW�܂�A�u���e���O�Y�N���v�̊m�F������B�v�i�����A��O�Z�y�[�W�j�Ƃ���̂́A���̑���őS�W�̂��߂̂��̂Ǝv����B
�@���a�\���N�@��㔪��N �Z�\�O��
�y#23�z�N���A���{���̃c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����ŁA�n�ӌ��l�̎ʐ^�W�u�t�|�s�s�v���ς�B������b�q�E�v���q�A���o����Ɖ�B
���n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�k�}�^�͖����i�����s���j�l�^��ꁁ�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����A�����1982�N1��18���y���z�`30���y�y�z��
�y#24�z���c�}�S�ݓX�Łu���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�v���ς�B
�������V���i�ҁj�s���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�t�i�����V���Ac1982�k�N4��9���l�j�^�����W�F��ꁁ���c�}�O�����h�M�������[�A�����1982�N4��9���y���z�`21���y���z��
�y#25�z�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́u�����̊G��v�W���ςĈ��|�����B
�����ʓW�s�č������p�ُ��� �����̊G��t�i�������������فA1982�N10��4���j�^��ꁁ�������������فA�����1982�N10��5���y�z�`11��17���y���z��
�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪��N�i���a�\���N�j �Z�\�O�v�̍��Ɍ�����W����W�̕��i�́j�������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�l�y�[�W�j�B
�y#23�z�ꌎ�A�n�ӌ��l�ʐ^�W�q�t�|�s�s�r����{���̃c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����Ŋς�B������b�q�A����v���q�A���o����Ɖ�B
�y#24�z�k�L�ڂȂ��l
�y#25�z�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́q�����̊G��r�W���ςĈ��|�����B
��
�y#23�z�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�m�������n�s�s�t�i�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����A1982�N1���j�̐}�^�@�����i�����s���j
���̏�����C���^�[�l�b�g��̏���T�����Ă��A�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j�̐}�^�̑��݂͊m�F�ł��Ȃ��B��҂̎ʐ^�ƁE�n�ӌ��l�i1947�` �j�͐l�`��ƁE�l�J�V�����i1944�` �j�̎��킾���A�g�����Ɩʎ����̂��V�����o�R�ɂ����̂����킩��Ȃ��B������ɂ��Ă��A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j������8�y�[�W�ɂ킽��ʒ����G�ʐ^�Ɍv5�_�̃��m�N����i�����̂��A�g���Ƃ̍ł��d�v�ȃR���{���[�V�����ł���B�����ɂ́A�p���Ǝv�����C�O�̓s�s�ƂƂ��ɁA�����̒��H���a�J�E��X�̏Z��X�̕��i���������Ă���B�Ƃ��ɁA�s�t�|�s�s�t�Ɋւ��Ă͋ߔN�A���ڂ��ׂ��������o�ꂵ���B�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@1973-2018�@�S7��t�̂����A���́s��3�� �s�s�A�w�t�|�s�s �T�E�U�E�V�x�W�t�i���FAG+ Gallery�A����F2018�N2��1���`17���j�Ƃ����W����̐}�^�����ЂƂ��Ċ��s���ꂽ�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�iAG+ Gallery�A2018�N2��28���j������ł���B�c�O�Ȃ��玄�́A�W������ςĂ��Ȃ��B�����ɂ́A�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j���̂��̂Ɋւ���ڍׂȋL�ڂ͂Ȃ����i���P�j�A�}�ԗI�M�q�������̑o�ዾ��凋C�O�\�\�n�ӌ��l�ɂ�镗�i�_��H��r�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����i���͊��������j�B
�@�u�t�|�s�s�v�i�������Ƃ��j�́A�n�ӂ�1982�N�A83�N�A84�N�ƘA�����ăc�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����Ŕ��\���A���ꂼ�ꂪ�u�t�|�s�s�v�A�u�t�|�s�s�U�v�A�u�t�|�s�s�V�v�Ƒ肳��Ă���B���̊e�X���G���w���{�J�����x1982�N2�����A��1983�N4�����A��1984�N3�����ɂ����ăO���r�A�y�[�W�œ��W���ꂽ�B�k�c�c�l�A�܂��́u�t�|�s�s�v�̕��@�_���݂Ă݂����B���m�N���̂U�~�U�Z���`�T�C�Y�̃X�N�G�A�t�H�[�}�b�g�ŁA�A�C���x������قڐ����Ɏ莝���ŎB�e���s���Ă���B�i�������g�B�����A�O�y�[�W�j
�������̍��q�Ŏ䂩�ꂽ�̂́A�g�����ς�1982�N�́q�t�|�s�s�r�ł͂Ȃ��A��83�N�́q�t�|�s�s�U�r�S22�_�̂����̎���2�_���B���߂ė��R���q�ׂ�܂ł��Ȃ��B�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�̍ŏ��ƍŌ�̍�i�i��������A�V�n�~���E���ق�110mm�̐����`�ɋ߂��d�オ��j�ɍ������Ă��邩��ł���B�ǎ҂͂�낵���A���҂��r���ꂽ���i�q�t�|�s�s�U�r��2�_�̓V�n�~���E�͂ق�140mm�j�B

 �@
�@

�n�ӌ��l�q�w�t�|�s�s�U�x���r�i1983�j �k�o�T�F�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�iAG+ Gallery�A2018�N2��28���A��܃y�[�W�j�l�Ɠ� �k�o�T�F���O�A�O�܃y�[�W�j�l�i���̂ӂ��j�Ɠn�ӌ��l�ɂ��s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j���G�ʐ^�̍ŏ��ƍŌ�̍�i�i�E�̂ӂ��j
�������A�q�t�|�s�s�U�r�ƌ��G�ʐ^�Ƃł́A��ʑ̂��قȂ�B�����A�����̉��ォ�猩�ĉ�ʂ̒����ɐ�������u���t���[�~���O�Ƃ����A��O�̐Ώ���Ȃ߂āA�Αg�̕ǂɐ����ꂽ�o������𑨂����@�Ƃ����A�܂����������B�e�m�Z�b�V�����n���������Ƃ̏��ł͂Ȃ����낤���B�g�����ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�i1982�j���ς����_�ŁA���̑I���W�̊�悪�������̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ��B�����A�����Ɏʐ^���f�ڂ���ɂ������āA�n�ӌ��l�̍�i���I�ꂽ�̂͋��R�ł͂Ȃ������͂����B���́A�ʐ^�̌f�ڂ́k����̎��l�l�V���[�Y���ʂ̊��ł����i���Q�j�B�g���̒���Ɂ\�\����Ɍ��炸�g������|����������i�ɂ��\�\�ʐ^���o�ꂷ��̂͂���߂ċH�ł���B�ߋ��ɂ́A���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�̋@�B���ɓޗnj��ꍂ�̂��ꂪ�p����ꂽ�������낤�i�q���W�s�m���t���r�́k2015�N2��28���NjL�l�Q�Ɓj�i���R�j�B
�����܂ŏ����Ă����Ƃ���ŁA�s���p�蒟�t1982�N3���������A�{�ǂ����B�n�ӌ��l�������́kPHOTO GALLERY�l�̃y�[�W�Ɂu�ʐ^�ƕ��v���Ă���̂ł���B�W��́A�ނ��q�t�|�s�s�r�B���߂Ɍf�����Ă���u���v���猩�Ă������B
�@�s�g�ȗ~�]�s�s�B
��n�̈����Ƌx���B
�ς镨���A�ς��Ȃ������B
�̓s�s�ł��艋�̕����ł�����B
���s�҂͖��z�Ƃł���A�܂��A�ƍߎ҂ɂ��Ȃ肤��ُؖ@�I�̈�B
�@�f���̎��͂��܂��ɖ��J�̏�Ԃ̂܂܂ŁA�����̎��������₷��B
�r������P���߂B
�J��Ԃ����^���Ƌx���A�L���Ƒ��u�A�����I�z���͂ƁA�o���B
���B�����Ԃ��A���A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�ɕ������B
�~�̒f�ГI�����A�f�Ђł���A�����ł����Ȃ��s�s�̕��i�́A�t�|�ɂȂ��������i�B
���ꂪ�`���̈��Z�y�[�W�̖{���ŁA�Ό��̈���y�[�W�ɋ߂��m�h���ɁA�����Łu�����G�̓c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����ł̌W�i�ꌎ�\���\�O�\���j����ނ��܂����B�v�Ƃ���B�ȉ��A4�y�[�W�ɂ킽���āA�ʎ��i���Ȃ킿�u���G�v�j�Ɏʐ^��i4�_���f�ڂ���Ă��邪�A�ǂ���^�C�g�����͂��߃N���W�b�g���m���u�����Ȃ��B�y�[�W�^�́A������Ɋp�ł̎ʐ^���u����Ă��邾�����B�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�ɉ��_�̍�i���o�i���ꂽ���킩��Ȃ��B�����A����4�_���������\���邱�Ƃ͊m�����낤�B��ʑ̂����t�łȂ���̂͋����A���������Ȃ��A���݂Ă݂悤�B
�@�E���˂��牌��f���H��i�Ŕ���u�V�����v�Ɠǂ߂��������A�����Ƃ͔��Ǖs�\�j
�@�E�h���C�N���[�j���O�x�m���̓X�܂𒆐S�ɂ����X�p�i�����s�n�c��������j�̕��i
�@�E�o�X�P�b�g�{�[���̃S�[���|�X�g�Əۂ̃I�u�W�F���Ћ��ɒu���Ă���w�Z�̍Z��
�@�E�����r�r���K�[�f���i�����s��c���瑩���j�t�߂̕������̘e�ŕ��ɗh����
�ʐ^�̓��m�N���[���A����������l�ŁA�n�ʂ̉e���̉_�̗l�q���ς�ƁA�������̎B�e�ł���\���͔ے�ł��Ȃ��B�d�オ��̓V�n���E��121mm�̃X�N�G�A�t�H�[�}�b�g�A���̔䗦�͗�1983�N���\�̏�f�q�t�|�s�s�U�r��2�_�Ɠ����ł���B�����u�̓s�s�ł��艋�̕����ł�����v�A�u�����ł����Ȃ��s�s�̕��i�v�́A�x���Ƃ�1983�N�ɂ͐��삳�ꂽ�͂��́s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�ɂ����̂܂܈����p����Ă���悤���B
�����āA�}�ԗI�M�́q�������̑o�ዾ��凋C�O�r�������Ă���s���{�J�����t1982�N2�����́q�t�|�s�s�r�A��1983�N4�����́q�t�|�s�s�U�r�A��1984�N3�����́q�t�|�s�s�V�r���ς悤�B�ȉ��A�i�@�j���̐����͎G���e���̌f�ڃy�[�W�̃m���u���A�y�@�z���̐����͑O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�f�ڃy�[�W�̃m���u���B
�g��������o���╽�o���Ɗς��A�V���[�Y�̏���q�t�|�s�s�r�͂������i�s���{�J�����t1982�N2�����A��O�`�O�Z�y�[�W�j�B�B�e����͓����s���Ɛ��肳���B
�uCITY'S MICROCOSMOS�^by KANENDO WATANABE�v�A�V�n���E152mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^�k�r���l�^�t�|�m�������n�s�s�v�i23�j�y15�z
���p�Ŏʐ^�u2�v�i24�j�y9�z
���p�Ŏʐ^�u3�v�i25�j�y11�z
���p�Ŏʐ^�u4�v�i26�j
���p�Ŏʐ^�u5�v�i27�j
���p�Ŏʐ^�u6�v�i28�j
���p�Ŏʐ^�u7�v�i29�j
���p�Ŏʐ^�u8�v�A�r���ɉ��g�����Łu�f�[�^�F�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�E�ꕔ�ԃt�B���^�[�g�p�v�B����ɉ��A�m�h����2�s�ɂ킽���āu�n�ӌ��l�ʐ^�W�u�t�|�s�s�v1��18���i���j��30���i�y�j�^�����E���{���E�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����iTel.03�]246�]1370�j�v�i30�j
�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�������G�ł͓n�ӌ��l�������t�|�m�������n�s�s���\���Ă��܂����A�n�ӎ��͂P�X�S�V�N���܂�̐V�i�ŁA�N�w�I�Ȏv�l�ɂ��s�s�̕��i��ǂ������Ă���ʐ^�Ƃł��B����̍�i�͓s�s�̒��̏��F�����ʂ��Ƃ邱�Ƃɂ��A���̊O�ɍL����s�s�̎p��\�����悤�Ƃ������̂������ł����A����ȈӖ��͂��Ă����Ă��A�܂��ƂɎʐ^�I�ȁA��Ԃ��X�g���[�g�ɂƂ炦���ʐ^���Ǝv���܂��B���̃V���[�v�Ȋ��o�̓j���[�����h�X�P�[�v�Ƃ��Ē��ڂ������̂ł��B�v�i�����A�O�Z�Z�y�[�W�j�Ƃ���ق��A�k�����̌��G�l�Ƃ����R�����g�̃y�[�W�ɂ́A�n�ӎ��g���q�����\�\�t�|�s�s�r�Ƃ����ꕶ���Ă���i�O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�ɍĘ^�j�A�ҏW���ƍ�ґ��̑o�����A�W�s�����̊X�t�Ɏ����n�ӂ̖{�i�I�Ȏʐ^�W���㉟�����Ă���B
���Ɂs�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�Ɠ������̎B�e���Ǝv����q�t�|�s�s�U�r�i�s���{�J�����t1983�N4�����A��O�`�O�Z�y�[�W�j�B�B�e����́A�p������у����h���Ɛ��肳���B
�uCITY'S MICROCOSMOS:�U�^by KANEND WATANABE�v�A�V�n���E156mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^�k�r���l�^�t�|�m�������n�s�s�F�U�v�i23�j
���p�Ŏʐ^�u2�v�i24�j
���p�Ŏʐ^�u3�v�i25�j
���p�Ŏʐ^�u4�v�i26�j
���p�Ŏʐ^�u5�v�i27�j�y22�z
���p�Ŏʐ^�u6�v�i28�j
���p�Ŏʐ^�u7�v�i29�j
���p�Ŏʐ^�u8�v�A�r���ɉ��g�����Łu�f�[�^�F�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�E�ꕔ�ԃt�B���^�[�g�p�v�i30�j�y39�z�͉E�Ƀp�������ʃJ�b�g���A�g���~���O�Ⴂ�̓��J�b�g���B�{�V���[�Y�Ɍ��炸�A�n�ӂ̓v�����g��������e�ɂ���ہA��{�I�Ƀg���~���O���Ȃ��悤���S�j�B��������ƁA�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^��2�Ԃ߁A3�Ԃ߁A4�Ԃ߂̌��J���ق���̉��ʒu�ʐ^�́A�g���~���O�������ʂł͂Ȃ��̂��B�s�A�T�q�J�����t1982�N5�����̖ؑ��ɕ��q��ܑ���́q�X�̒��̊X���Ђ̒��̊፷�r��11�y�[�W���琬�邪�A�G����90�x�����ނ�����ԂŁA���ʂɂ͉����̎ʐ^���ق���ōڂ��Ă��邵�A�����̗�1983�N10�����́q⦅�����̂̌��i�ł��Ȃ�⦆�r10�_���A���x�͔��n�ɓ��l�̍�i���p�łōڂ��Ă��āA������ɂ́u�~�m���^CLE�E���b�R�[��28�_�E�C���t�H�[�h�p��F�v�Ƃ���A35mm�t�B�������g���Ă���B���G�ʐ^�̎g�p�@�ނ͕\������Ă��Ȃ����A��L��3�_�͂���Ɠ������B
�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�������G�ł͖ؑ��ɕ��q�܍�Ƃ̓n�ӌ��l�������t�|�s�s�E�U���\���Ă��܂��B�s�s���i��V�������o�Ŏʂ��o���n�ӎ��́A�{����N�Q�����œ������e�[�}�ɂ��������̍�i�\���Ă��܂����A����̓p�����ʂ������̂ł��B�v�i�����A�O��l�y�[�W�j�Ƃ���B��L8�_�̃Z���N�g�͎ʐ^�Ǝ��g�ɂ����̂��낤���A�����[���̂́A�O�f���s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�ɂ����߂�ꂽ2�_������8�_���Ɍ����Ȃ����Ƃł���B����������́A�_�j�Ȏʐ^�S�W�Ɏ��^���ꂽ�n�ӌ��l��3�_�̂�����2�_�Ȃ̂ł���B�s���{�ʐ^�S�W 7 �s�s�̌��i�t�i���w�فA1987�N5��20���j�́q�P�X�U�O�N��ȍ~�i��j�r�́u171 �p���@���A�[���v�Ɓu172 �����h���@�o���N�T�C�h���d���v�����ꂾ�i�Ȃ��A�ʐ^�̃^�C�g���͎B�e�҂����L�������̂ł͂Ȃ��j�B�ʐ^�S�W�ɂ�����2�_�̃L���v�V�����͎��̂Ƃ���B
�u�u�t�|�m�������n�s�s�U����@�n�ӌ��l�m�킽�Ȃׂ��˂�ǁn�@���a57�N�i1982�j�@�����肤�ׂ��A���肦�Ȃ��s�s�����̓s�s����ǂ����߂邱�̍�҂̍�i�̂Ȃ��ŁA�p���ƃ����h���Ƃ������j�ƕ���ɏ[�����ꂽ�s�s�Ƃ̏o��ɂ���Đ��삳�ꂽ���̃V���[�Y�ł́A��ғ��L�̊A�a�����p�������Ă���B���邢�͂��̓�̓s�s���A��҂̋��߂釀���̓s�s���Ɏ��Ă����̂ł��낤���B���݁A�p���̃��A�[���̍H������͂��łɋ���ȃV���b�s���O�E�Z���^�[�ւƎp��ς��Ă���B������ꂽ�p�Ї��Ƃ��Ă̂��̎ʐ^�����A��҂��ǂ����߂釀���̓s�s���Ƃ̈�u�̑����ł������̂�������Ȃ��B�ו��`�ʂƉ��ߖ@���I���Ɏg���āA�s�s�̃~�j�`���A��n�肾�����Ƃ����҂̓��������������������i�ł���B�v�i�k���M�҂͏d�X�O�����A���؎����A����Ƃ����̒S���҂�����ł��Ȃ��l�ʐ^�L���v�V�����A�����A��l�O�`��l��y�[�W�j�B
�o���N�T�C�h���d���͌��z�ƃW���C���Y�E�M���o�[�g�E�X�R�b�g�i1880�`1960�j�̃f�U�C���ɂȂ���̂ŁA��͂�X�R�b�g����|�����o�^�V�[���d���ƉZ����B�s���N�E�t���C�h�̃A���o���s�A�j�}���Y�t�i1977�j�̃W���P�b�g�ʐ^�A�o�^�V�[���d�������ԓ����肱�܂�Ă���g�Ƃ��ẮA���b�h�E�c�F�b�y�����̃A���o���s���Ȃ�فt�i1975�j�̎ʐ^�Ƃ�z�N���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��i�q�v�m�V�X�Ƒ�n��ɂ��Ă��q�ҏW��L 157�i2015�N11��30���X�V���j�r���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�Ō�Ɂs�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j�̌��G�ʐ^�ƕ��s���ĎB�e�����\��������q�t�|�s�s�V�r�i�s���{�J�����t1984�N3�����A���܁`���܃y�[�W�j�͂������B�B�e����͓����i�����p���ӂ̐��ӂ������j�Ɛ��肳���B
�V�n���E160mm�̐����`�̊p�Ŏʐ^�u1�v�A�u�n�ӌ��l�^CITY'S MICROCOSMOS:3 by Kanendo Watanabe�^�t�|�s�s �V�v�i75�j
���p�Ŏʐ^�u2�v�i76�j
���p�Ŏʐ^�u3�v�i77�j
���p�Ŏʐ^�u4�v�i78�j
���p�Ŏʐ^�u5�v�i79�j
���p�Ŏʐ^�u6�v�i80�j
���p�Ŏʐ^�u7�v�i81�j
���p�Ŏʐ^�u8�v�i82�j�y47�z
���p�Ŏʐ^�u9�v�i83�j
���p�Ŏʐ^�u10�v�i84�j
���p�Ŏʐ^�u11�v�̂������Ɂu�~�m���^�I�[�g�R�[�h�E���b�R�[��75�~���E�g���C�w�v�̃L���v�V�����A�r���ɉ��g�����i��f�̃L���v�V�������͑傫�߁j�Łu�n�ӌ��l�ʐ^�W�u�t�|�s�s�V�v�^3��21��(��)�`4��7��(�y)�^�����E���{���E�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����v�k�^�i�X���b�V���j�͌����B���s�ӏ��ł͂Ȃ��l�i85�j
�����̕ҏW�l�E�������j�ɂ��q�ҏW��L�r�ɂ́u�n�ӌ��l���́u�t�|�s�s�V�v�́A���̃V���[�Y�̂R��ڂł����A�n�ӎ��Ȃ�ł͂̓s�s�������̓N�[���ŁA�������V���[�v�Ȍ��������������܂��B����̍�i�͑S�̂ɂ�┒���n�C�L�[���̎ʐ^�œ��ꂳ��Ă��܂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ����ʓI���Ǝv���܂��B�v�i�����A�O��Z�y�[�W�j�Ƃ���B
�ȏ�́q�t�|�s�s�r�Ɓq�t�|�s�s�U�r�A�q�t�|�s�s�V�r���Љ���G���f�ڂ̌v27�_�̂Ȃ��ɁA�s�g�����k����̎��l�P�l�t�̌��G�ʐ^�Ɠ����B�e�m�Z�b�V�����n�Ǝv������̂͂Ȃ��B�s�t�|�s�s�t�V���[�Y�̎ʐ^�W�̑S�e�͂��߂Ȃ����̂́i1980�N��̎G���f�ڍ�i��2017�N�̎ʐ^�W�̐}�^�����Ќf�ڍ�i�𖼊���ƁA�T��16�_�A�U��28�_�A�V��16�_�j�A�v���ɁA�n�ӌ��l�̂Ȃ��Ō��G�ʐ^�͂����܂ł��s�t�|�s�s�t�V���[�Y�̎ʐ^�W�Ƃ͕ʂ́i���Ȃ��Ƃ����C���u�����h�ɑ���T�u�u�����h�̂悤�ȁj�v���W�F�N�g�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă����̂ł͂Ȃ����B������ɂ��Ă��A�q�t�|�s�s�r�Ɓq�t�|�s�s�U�r�A�q�t�|�s�s�V�r�̂Ȃ��ł́A���̃��`�[�t�̋��ʐ�����́q�t�|�s�s�U�r���ł��މ������������āA�q�t�|�s�s�V�r������Ɏ����B�u����g�������v�i�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t�j�̊J���������邱�̎����ɓn�ӌ��l���B�������G�ʐ^�́A�܂������R���{���[�V�����ƌĂԂɂӂ��킵���A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�Ɏ��߂�ꂽ�u�����v�܂ł̋g�������i1955�N���́s�Õ��t�`1979�N���́s�Ẳ��t�j�Ƃ̐▭�Ȏ�荇�킹���ւ��Ă���B

�y�Q�l�z�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�����̊X�t�iAG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�o�ŋǂ̋����o�ŁA2015�N10��31���j�Ɓs�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�U�@�s�s�@�@�����̊X�t�iAG+ Gallery�A2017�N11��30���j�̕\��
����500�����s�̓n�ӌ��l�ʐ^�W�s�����̊X�t�iAG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�o�ŋǂ̋����o�ŁA2015�N10��31���j�́u�\���E�e�L�X�g�v��S�������^�J�U���P���W�́A�����́q�ʐ^�W����ɂ��Ă̕t�L�r�ɂ��������Ă���i�������g�B�����A��O�܃y�[�W�B���͊��������j�B
�@�w�����̊X�x��1973�N����1980�N�܂ŎB�e���ꂽ�ʐ^��i�ł���B1980�N�ɋ�����b�q�̏����Ƃ̋����Ƃ��ĐV���Ђ��犧�s����Ă���A�w�����̊X�x�Ƃ����^�C�g���͂��̂Ƃ��ɓn�ӂƋ���Ƃōl�����^�C�g���ł���B���̗��N�A�n�ӂ͒P�Ƃœ����̎ʐ^�W���j�R���T�����ŊJ�����B�P�s�{�ƓW����͍����]�����A�n�ӂ͑�7��ؑ��ɕ��q�ʐ^�܂���܂��Ă���B
�@�n�ӌ��l�͌��݂�1�`2�N��1�x�̓R���X�^���g�ɐV��W���J�������̎ʐ^�Ƃł���A�{���ł�����̍ŐV������s���ׂ��Ȃ̂��낤�B�������A�n�ӂɂƂ��Ďʐ^�W�́A�����ƂƋ����́w�����̊X�x�Ƃ������̏����q��ʂɂ���A2003�N���s�́w�n�ӌ��l�x�i���s������p�� ���K�فj�݂̂ŁA����������͓W����̐}�^���B�����ŁA�ɓށk�p���l�Ƒ�R�k���i�l����n�ӂ̖{�i�I�Ȏʐ^�W���o���Ƃ����������ꂽ�Ƃ��A�܂��͓n�ӂ̏����̑�\��ł���A���݂܂ő�����i����̌��_�Ƃ�������w�����̊X�x���ʐ^�W�ɂ��ׂ����ƈӌ����q�ׂ��B����͂��̊��Ɋւ�����l���ׂĂ̎v���ł��������悤���B���ʂƂ��āA�{���͒P�s�{�ƓW����́w�����̊X�x�����ƂɁA���݁A�n�ӂ̎茳�ɂ���l�K�t�B�����̂Ȃ�����A�\����S�����������V���Ɏʐ^��I�B1980�N�̒P�s�{�Ɏ��^���ꂽ53�_�̂���4�_�̃l�K�����݂����A���^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A�����^�A�����\�̎ʐ^�������������_�ł́u���S�Łv�ł���B
�@���{�̎ʐ^�Ƃ̑����͎ʐ^�W���u��i�v���ƍl���A�W����ȏ�ɏd�Ă����B�������A�n�ӂ͂������������ɂ͖��S�������悤�Ɍ�����B�n�ӎ��g�͎ʐ^�W�ɂ��Ă�������Ă�B
�@�u�ʐ^�W�̂ق����D���Ȃ�ł���B���ɂ킴�킴�o�����Ă�����āA���Ƀv�����g�����Ă��炢�����B�����A��������R�������āA����͔������Ȃ���������B�ʐ^�W������܂��傤�Ɛ���������قǔ������Ȃ������i�j�v
�@�A�C���j�[�����߂��������͓n�ӓ��L�̂��̂����A�n�ӂɂƂ��Ďʐ^�v�����g���̂��̂��u�ʐ^�v���Ƃ������Ƃ��낤�B�������ɓn�ӂ̃v�����g�͓Ɠ��̔������O���[�g�[���ɓ���������A����ōČ�����͓̂����������Ȃ��B�������A�n�ӂ̍�i���L���m���Ă��炤���߂ɂ��A���̎ʐ^�W�����������ɓn�ӂ̎ʐ^�W�������邱�Ƃ����҂������B
�������炤��������̂́A�n�ӌ��l�̎ʐ^�W�d���A�ʐ^�W�y���Ƃ�����{�I�ȃX�^���X�ł���B�ʐ^�W�ɏd����u���Ȃ��ʐ^�Ƃ��ʐ^�W�̐}�^���쐬���Ȃ��̂́A�Ȃ��̂��Ƃ��肦��i3��ɂ킽�����s���{�J�����t�ւ́q�t�|�s�s�r�V���[�Y�̌f�ڂ��A���ʔ��\�Ƃ������́A�ʐ^�W�J�Â̍��m�Ƃ������ʂ̕����傫�������̂ł͂Ȃ����j�B�ʐ^�W�s�����̊X�t�̃X�~�ɓ��F�O���[�������������ׂȐ��ŁE����͏[���ɖ��͓I�����i����E���{�͊�����Б�ۃO���t�B�b�N�X�j�A����ɂ����Ƃ���Ŏʐ^�v�����g�ɋy�Ȃ����Ƃ͕�����Ȃ��B�^�J�U���P���W���ʐ^�W�s�����̊X�t�Ɋ��q�u�����v�Ɓu�����v�̂������Łr�ɂ́A���̂悤�ȏd�v�ȉӏ�������B
�@�n�ӂ͓��������ʐ^���w�Z�Ŏʐ^��������̂��A1973�N�ɏ��W�u�Í��̖��z�@�W���b�N�E�U�E���p�[�Ɋւ���f�ГI�����v���J���B�ʐ^�W�̃`���V�ɓn�ӂ͂���ȕ��͂��Ă���B1888�N�Ƀ����h���ŋN������I�ȘA���E�l�����ŁA�E�l�S�W���b�N�E�U�E���p�[����Q�҂̖ڂ��������������ƂɐG��A��Q�҂������u���������ǂ̗l�Ȍ��i���A���i��ڌ������̂ł��낤���B�v�Ɩ��z�����Ƃ����B
�@��i�͉��o���������B�e�ɁA�t�H�g�E�R���[�W������g�����\���I�Ȏʐ^�������Ƃ������A�^�C�g���Ƃ����A�W����Ɋ���҂̌��t�Ƃ����A���̓����̓n�ӂ��ʐ^���g���ĉ�����\�����悤�Ƃ����ӎ������������Ă������Ƃ�����������B�n�ӂ̌Z�A�l�J�V�����͒����Ȑl�`��Ƃ����A1960�N��̉����V�[�������������u�A���O�������v�̑�\�I���c�̈�A����̊Ŕ��҂ł��������B�n�ӂ̎��͂ɂ͌Z�̊W�ŕ\���Ɋւ��҂������A���̉e������G���X��O���e�X�N�ȂǂɊS���������悤���B���Ȃ݂Ɂu�Í��̖��z�v�W�ɂ́A���{�Ƀh�C�c�\����`���Љ���ƕ��w�ҁA�|��Ƃ̎푺�G�O�����͂����B
�@�������A�n�ӂ͎ʐ^���g���ăC���[�W���\�z���邱�ƂɈ�a����������悤�ɂȂ��Ă������B�Ƃ��Ɂu�Í��̖��z�v�W�̌�A�u����̓A�J���ƁB�Ⴄ�Ȃ��A�Ƃ��������ł����ˁB�v���̌�A���݂܂œn�ӂ́u�Í��̖��z�v�܂ł̍�i�Ă���B
�@�u�Í��̖��z�v�܂ł̎�@�ƌ��ʂ����n�ӂ��A�ŏ��Ɏ��g�V���[�Y�����́w�����̊X�x�ł���B�u�Í��̖��z�v�W�I�����ォ��B�e���n�߂��Ă���B�������A�V���[�Y������Ȃ��A���\���邠�Ă��Ȃ��܂܁A�B�e��7�N��ɋy�B�i�����A��O��y�[�W�j
�u�n�ӂ̎��͂ɂ͌Z�̊W�ŕ\���Ɋւ��҂������v�ɂ́A�����ɖ��O�̋������Ă���푺�G�O�i���T�j��A���\�Y�A������b�q�A�g�������܂܂�邾�낤�B�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�ł̓n�ӌ��l�̋N�p���ǂ̂悤�Ȍo�܂łȂ��ꂽ�̂��A�ڍׂ͂킩��Ȃ��B�����A����Ɠn�ӂ́s�����̊X�t�����̏d�v�Ȍ_�@�ƂȂ������Ƃ͋^���Ȃ��B1981�N�́q�����̊X�r�ɑ����n�ӂ̎ʐ^�W�����A��1982�N����́q�t�|�s�s�r�V���[�Y�������B�s�����̊X�t�ɑ����n�ӌ��l�̎ʐ^�W�Ƃ��āA�s�t�|�s�s�t���\�\���ꂱ���u�����^�A�����\�̎ʐ^�������������_�ł́u���S�Łv�v�̌`�Ł\�\���s���ꂽ�łɂ́A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�Ɍf�ڂ��ꂽ�ʐ^�������V���ȑ��e�������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
����A������b�q�̑��ɂ͎��̂悤�ȕ���������B����Ɠn�ӌ��l�̋����s�����̊X�t�́A�����N�j�҂ɂ��q���r�i�s������b�q�S�Z�чU�t�A���{���|�ЁA1992�N3��3���A�Z�l�܁`�Z�l���y�[�W�j�̂����A�n�ӌ��l�̎ʐ^�ɂ��Č��y���������𒆐S�Ɍf����B
�����̊X�@��㔪�Z�N�㌎��\���A�P�s�{�w�����̊X�x�Ƃ��ĐV���Ђ�芧�s���ꂽ�i�����낵�j�B�\���ɂ͋�����b�q�E�n�ӌ��l�̖��������傫���ŕ��ԁi�n�ӌ��l�̉E���ɏ�����photograph�j�B���t�ɂ́s���ҁ^������b�q�m���Ȃ��݂����n�E�ʐ^�^�n�ӌ��l�m�킽�Ȃׂ��˂�ǁn�t�Ƃ���i�����������j�B�{����l�Z�y�[�W�̂����ʐ^���܈�t�A�Z���y�[�W���߂Ă���B
�@�u�����V���v��㔪�Z�N�\�ꌎ�\��������ɏ��]�i�������j������B���o���́s��i���߂铮���A��i���t�i�ȉ��A�S���j�B�s�u�����v�\�\�S���w�p��A�t�����X��̃f�W���E�����̖�B��x���o���������Ƃ��Ȃ��̂ɁA�����o�������Ƃ�������������悤�Ȋ��o�������B�k�c�c�l�^���̖{�́A���́A�����Ƌ�����b�q�Ǝʐ^�Ɠn�ӌ��l�̈��̋�������ɂ����̂ł���A�قƂ�ǑS�y�[�W�ɁA����̓W�J�Ƃ͈ꌩ���W�Ȉ�A�̓s�s���i���}���i�����ɂイ�j����Ă���B�����������̎ʐ^�́A�l���̂܂������o�ꂵ�Ȃ�����߂Ė��@�I�Ȃ��̂ł��邾���ɁA�������āA�ǂ����Ō������i�Ƃ�����������������B���������ʐ^�ƏƉ������Ȃ��珬����ǂނ̂́A�Ȃ��Ȃ����z����������̂��B�t
�@�k�c�c�l
�@�u�݂����v��㔪��N�ꌎ���u��㔪�Z�N�Ǐ��A���P�[�g�v�i�s�\�\��㔪�Z�N���ɂ��ǂ݂ɂȂ��������̂����A�Ƃ��ɋ�����������ꂽ���̂��A�ܓ_�ȓ��ŋ����Ă��������܂��悤�A���˂����������܂����t�j�̈����ǗY�̍��Ɏ��̂悤�ɂ���i�Q�ȉ��͗��j�B�@�P�@������b�q�E�n�ӌ��l�w�����̊X�x�A�V���ЁA��㔪�Z�B
�@����ǂ��Η��W���Ȃ��D�������ݐZ������U���Ǝʐ^���A�Ȃ������u�f�W���E�����[�v�̓s�s�������̐S�ۂ̒��ɑh�点�Ă��ꂽ���Ƃ��A���ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���̂Ɖf���̒[�����ɂ���āu�X�^�C���v�̕����̎�����Ă��邱�Ƃ������ɃV�������A���X���̐������v�킹��ƁA�������Ƃ͋t���ɉ߂���ł��傤���B
����́q�����̊X�r�����^�����u�k�Е��|���ɂ́s�s�N�j�b�N�A���̑��̒Z�сt�i�u�k�ЁA1998�N12��10���j�̊����q����r�́A�x�]�q�K�́q�s�`����w�I�ȉ���t����̎����r�ł���B�`���̒i���������B
�@�����ő��������ڂ��Ȃ��Ȃ��������ɁA�C�𗚂����Ă�����ƌ����Ȃ���A�����Ȃ�s���Ɋ���߂Â��āA�X�g�b�L���O�z���ɐO���������Ă��t���Ȉ�̘b���҂��畷������Ă������肪�A�\�N��A���܂⏉�V�̒j���ƂȂ������̎��Ȉ�̂Ƃ���Ŏ��Â��A�s�ӂɂ��̃G���e�B�b�N�ȑ}�b���v���o���u���̉��v�́A�s�W���N���[���ƔZ���K�N�F�̂܂���̉ʎ��t�ł��铍�ƃs���N�F�̎��s��f�@��̂����ŘA�������A���ꂾ���ł����\���ɑN�₩�Ȉ�т����A�ȑO�����ɓ���������܂����˂Ƃ����₢�����ɑ��鎕�Ȉ�̉́A��㔪�Z�N�㏉���܂ł̋�����b�q�̓����������Ɍ������ĂĂ���悤�Ɏv����B���͍����Ȏ��l�ł��������A�ǂ����g������A�z�����Ȃ����Ȃ����Ȉ�́A����Ȃӂ��ɂ�������̂��B�s�c�c���̖���Ԕ�����������̂́A�ʎ����n���ăN���[���F�̕������Ԃ��F�Â��āA���ꂪ�����ȓ���̂悤�ɖ����鎞�Ȃ�ł��B�����F�̎Y�тɏ���ꂽ�����̕��̂悤�ɁA��������P���Č�����ł��傤�B�G���ƌ`����w�I�ȉ�����������ł��t�B�i�����A�O���`�O���y�[�W�j
������b�q���s�����C�J�t1973�N9�����̋g�������W�Ɋ��G�b�Z�C�́q���\���邢�͉����ցr�ŁA�W��ɂ͏����Łu�g�����ցv�ƓY�����Ă������B�����܂ł��Ȃ��A�u���v���u�����v���g���̎��̑薼�ł���i�q�����r�ɂ́u���m�Ȍ`����̉���������v�Ƃ�������܂ł���j�B����A�q���̉��r�i���o�F�s�Q���t1976�N1�����j�̑莫�͐[�Y�ŁA����́q���\���邢�͉����ցr�ɂ��A��蒷���`�Ő[��́q�����ҁr����u���Ď��́A�̂ǂ��Ȑ����́A�̂ǂ�������t�̓��ɁA�s���N�̉Ԃ��炩���������̎��̂Ȃ��ɁA�Â������N���āA�n���āA��������悤�ɁA�����Ƃ����ЂƂ̃X�^�C�������s���悤�Ƃ����̂������B�v�������Ă����i�O�f�s�����C�J�t�A����y�[�W�j�B�u�@�v���̐Ԏ��ɂ����������q���̉��r�̑莫�ŁA���̈�_�������Ă��A�x�]�q�K���q�s�`����w�I�ȉ���t����̎����r�ɋg�������������Ă���̂͗��Ɋ����Ă���B�Ȃ��A�x�]�́q����r�ɂ́u�n�ӌ��l�̎ʐ^�Ɲh�R���邩�����ŏ������낳�ꂽ�[�����̏G��w�����̊X�x�v�i�O�f���A�O�ꔪ�y�[�W�j�Ƃ���B
��q�̂悤�ɁA����̏����q�����̊X�r�͏������낵�̏�����1980�N�ɐV���Ђ���o�����ƁA1992�N�Ɂs������b�q�S�Z�чU�t�ɁA1998�N�Ɂs�s�N�j�b�N�A���̑��̒Z�сt�Ɏ��߂�ꂽ�B��������A�Ę^���ɂ͓n�ӌ��l�̎ʐ^�͎��߂��Ă��Ȃ��B����A�n�ӂ̎ʐ^�q�����̊X�r��1981�N3��3������8���܂ŁA�j�R���T�����i�����E����j�ł̌W�̂��ƁA���炭������Ƃ��Ă܂Ƃ߂��邱�Ƃ��Ȃ��������A���łɏq�ׂ��悤�ɁA2015�N10��31����500������̎ʐ^�W�s�����̊X�t��AG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�o�ŋǂ̋����o�łŏ��߂Ċ��s���ꂽ�B�����ׂ����ƂɁA���ꂪ�n�ӌ��l�̍ŏ��̖{�i�I�Ȏʐ^�W�ł����i���U�j�B
���Ȃ݂ɁA�����s�ʐ^���p�فi���M�E�ďC�j�s���{�ʐ^�Ǝ��T�\�\�����s�ʐ^���p�ُ�����Ɓk�����s�ʐ^���p�ّp���l�t�i�W���ЁA2000�N3��27���j�́q�n�ӌ��l�r�̍��i���M�͒����~�s�j�Ɍf����ꂽ�ʐ^��i�́s�����̊X�t�̈�_�ł���B�n�ӂ́q��7��ؑ��ɕ��q��Ҕ��\�r���f�ڂ��ꂽ�s�A�T�q�J�����t1982�N3�����Ɏ�܂̂��Ƃq�܂��A�����͂��߂�r�����M���Ă��邪�A�����ɂ��̎ʐ^�i�����A���Z�y�[�W�j���B�����Ƃ��̂��ƂƂ��ڂ����������Ƃ߂Ă���B�����́s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�U�@�s�s�@�@�����̊X�t�ɍĘ^����Ă���A���̎ʐ^�́i���l�ɂ���Ď��сq��́r�����_�q�킽���̍쎍�@�H�r�Ɋ��т悹��ꂽ�悤�Ɂj�ʐ^�ƂɂƂ��ĉ�S�̈�_�������ɈႢ�Ȃ��B
�g�����͓n�ӌ��l�̎ʐ^�ɂ��ď����̂����Ă��Ȃ��B�����A�O�f�s�A�T�q�J�����t�́u�i���j�v���ƕҏW���E���{�����ɂ��u�掵��ؑ��ɕ��q�܂��n�ӌ��l���Ɍ��܂�܂����B����l���n�ӎ��̎ʐ^�����āu���{�̓s�s�̕��i�Ȃ��ǃ��[���b�p���ǂ����݂����Ɍ�����v�ƌ����Ă����̂���ۓI�ł����B�����A��G�A���ׁA����}�c�c�B�����������{�̓s�s�̃C���[�W�ɁA�n�ӎ��̎ʐ^�͒��ڂɂ͂Ȃ���Ȃ���������܂���B�����������ʂ��o���Ă���̂͂܂�����Ȃ����{�̓s�s�ł��B��������{�I�Ȃ���̂𒊏o����̂ł͂Ȃ��A�t�ɋ��₵�悤�Ƃ���Ƃ��납�牽�������Ă��邩�B�����Ɏ��̎ʐ^�̂������낳������܂��B�v�i�q�ҏW������r�A�����A�O�l�O�y�[�W�j�Ƃ����w�E�́A�s�m���t������������̋g���̎p���Ɗ�Ȃ܂łɈ�v���Ă��āA�g���̓n�ӕ]���ǂ̂悤�Ȃ��̂����������l����_�@�Ƃ��Ȃ�A����͐s���Ȃ��B
��
�y#24�z�����V���i�ҁj�s���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�t�i�����V���Ac1982�k�N4��9���l�j
���h���t�E�n�E�Y�i�[�i1914�`1995�j�̓I�[�X�g���A�̉�ƁB�g�����͐��z��k�b�ŁA�������̂Ƃ����C�ɓ���̉�ƂɌ��y�����B�������A�n�E�Y�i�[�͋g���́k���M�l�N���Ɂu���c�}�S�ݓX�Łu���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�v���ς�B�v�Ɠo�ꂷ�邾���ŁA���̉�Ƃ̍�i���ǂ̂悤�ɎƂ߁A���̉�Ƃ��ǂ̂悤�ɕ]�������̂��悭�킩��Ȃ��B�n�E�Y�i�[�́A�}�^�̕\�����������q�W���ɋ߂Â��A�_�� �T�r�i1972�j�̉敗�Œm���邪�A�f�ڍ�i�́q��Ɓr�i1980�j�͂킪�֓��^��i1922�`1994�j�̎��摜�ɂ��ʂ���ǏD��Y�킹�āA�ِF�ł���B���Ȃ݂ɋg���͍֓��́q�����q ��̕Ќ��r���������Ă����i�J���[�}�Łq�g�����̏����ȕ����r�A�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�A����R�c�A1996�A�k��܃y�[�W�l�j�B
 �@
�@
�����V���i�ҁj�s���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�t�i�����V���Ac1982�k�N4��9���l�j�̕\���k�n�E�Y�i�[�̍�i�́q26�\�\�W���ɋ߂Â��A�_�� �T�@1972�^Adam to standard �T�r�l�i���j�Ɠ����́q50�\�\��Ɓ@1980�^The painter�r�i�E�j
��
�y#25�z���ʓW�s�č������p�ُ��� �����̊G��t�i�������������فA1982�N10��4���j
�g���́k���M�l�N���Ɂu�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́u�����̊G��v�W���ςĈ��|�����B�v�Ə����Ă���B���Ȃ킿�A�s���R���������W�t�i�������������فA1981�j��1�N����A�Ăѓ������Œ����̕����ɐڂ����킯�ł���B�����Ŏ����g�̒����G��̌������Ȃ�AJR���̔ѓc���w�Ɛ������w�̒��Ԃ�����̓����̃r���ɉ�Ёi���[�E�s�[�E���[�̃��f�B�A���ƕ��j������������A�r���̗��͓����F�D��قŁA����ɂ��̗��͏��ΐ��y���������B�s�G�X�N�@�C�A���{�Łt�̐���S���҂Ƃ��āA�G���̕ҏW���ƈ�����i����{����j�̊Ԃɂ����āA���e���e��Z������̃`�F�b�N�������i����L���̐i�s�Ǘ����S���A�Ƃ�������ƂƂ��Ă͂����炪�傾�����j�B���̂��ߒ��H�́A���܂������Ԃɐۂ�Ƃ������́A�d���ɋ�肪�����Ƃ��ɐH�ׂɏo��Ƃ����`�������B�ѓc���w�i��O���B�u�O�B���v�̏ċ���H�j�␅�����w�i�n���ɍ~���u���g�v�̃g���J�c�j�܂ő���L�����Ƃ�����A�����F�D��ق̒��������X�u�����v�ōς܂��邱�Ƃ����������i���т̃g���^�����ԓ����{�Ђ̐H���A�Ƃ��������������j�B���x�ݎ��Ԃɗ]�T������ƁA�����F�D��ق̔��X���Ђ₩������i���܂ɂ�⽍��W�̏��Ђ��w�������j�A�W����ł�����̂������肵���B�����Ƃ��u����́v�Ƃ�����i�͏�������Ȃ��������B�G���o�y�i�̓W�������A���������������i�L�^���Ă��Ȃ������̂ŁA��ۂ���邵���Ȃ��j�B��͂�A���͒����̂��̂ɂ͓G��Ȃ��Ɗ������B�G��́A���̌�A�k���̌̋{�����@�Ŋ��\�������A�}�^���G�t�����苖�ɂ͂Ȃ��A�͂����Ă����łȂɂ��ς����̂��B��͂�A�}�^�ɂ͂���Ȃ�̉��l������B
 �@
�@
���ʓW�s�č������p�ُ��� �����̊G��t�i�������������فA1982�N10��4���j�̕\���i���j�Ɠ����E�O��y�[�W�́q9 �����J���} �`�����r�i�E�j
���̓W����Ɉ��|���ꂽ�g�����ǂł��낤�}�^�̕��͂��ӏ��A�����B
�@���̂��ш�A�̓��ĕ����𗬂̏d�v�ȍs���̈�Ƃ��āC�N���[�u�����h���p�ق���тv�E�q�E�l���\�����p�ق̐��Ȃ邲���ӂɂ��C���ُ����̒����G��281���������肢�������C�����ɂ��炵�����ʓW���J�Âł��܂����Ƃ�S�����тƂ�����̂ł���܂��B
�@�k�c�c�l����W������闼�ق̍�i�͓��N�ȏ�ɋy�Ԓ����G��j�̑S�ʂɂ킽���Ă���܂����C�Ȃ��ł��v��Ȍ�̍�i�͎��ʂƂ��ɏ[�����C�n���I�Ȓ���\�ɂ��Ă���_�ŁC�ӏォ��������̖ʂ���������]������������̂ƐM���܂��B�i�������g�B�������������فq�͂��߂Ɂr�A�{���A�k�O�y�[�W�l�j
�@�k�c�c�l����̍]��ɂ����������C�쓂�Ɏd���������C���R�����n�R����`���Ă������C�ؖk�̊e�n�ɂ́C�����̍����������ēƎ��ȉ敗���J�Ă����R����̋������o�����Ă����B�����̌t�_�C����������C�֓��C䗊���ł���B�ޓ��̉敗�ɂ͂��ꂼ��̐��������n�����ɂ��Ƃ����i�ς̑���Ȃǂ��F�߂�����̂́C���ʂ��āC���n��̃��A���ȕ\���̎�i�Ƃ��Ă̑��ʂ���g���āC��ϓI�C�\���I�ł���Ȃ���C����߂Ďʎ��I�ȎR����̑�l������肠�����B�ޓ��̉敗�͉����M�C�����J��ɂ���Ėk�v�̒����Ɍ}�����C�ꐢ���r���C�₪�Ėk�v�㔼���̊s���ɂ���Ď���Ɨ��_�̗��ʂŏW�听�����B�i���B�C�V�����Y�q�����G��̗���r�A�{���A��O�y�[�W�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�̃V���[�Y�́A�����c�|�m��������݁n�̒������c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����̑n�ݎҁE�Ό��x�Y�i1941�`2016�j�̕]�`�s�ʐ^���A�[�g�ɂ����j�\�\�Ό��x�Y�ƃc�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����t�i���w�فA2016�N10��16���j�̊������X�g�q�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����W����S�L�^�r�i���싦�͂́A�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����̖쑺�j�i�j�ɁA���̂悤�ɋL�ڂ���Ă���i�����A315-3�`314-4�y�[�W�j�B
�@�@1982�N1��18��-30���@�t�|�s�s�i�n�ӌ��l�j
�@�@1983�N3��22��-4��9���@�t�|�s�s�U�i�n�ӌ��l�j
�@�@1984�N3��21��-4��7���@�t�|�s�s�V�i�n�ӌ��l�j
�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�̋g�������L�ɂ́A1982�N2��22���i�܂�g�����n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t���ς������j�ɁA���̂悤�Ȓ��ڂ��ׂ��L�ڂ�����B���Ȃ킿�u�[���A����̐؉�L�֍s���B�l�J�V�����l�`�W�k�q�����[���E�����[���r�l���ς�B���������̗��`�̎O�̂ɂ́A���_�����犴����ꂽ�B�߂��̋i���X�ɐȂ����炦���A�����r�Y�A�n�ӌ��l�A����v���q�����Ƃ�����ׂ�B�x����F�V���F�v�ȂƋ��q���`������ꂽ�̂ŁA�����ȉ����₮�B�v�i�q67�@�V�����l�`�r�A�����A��O��`��l�Z�y�[�W�j�B�s�y���F��t�ɓn�ӌ��l���o�ꂷ��B��̏�ʂł���B
�i���Q�j�@���Ƃ��s�剪�M�k����̎��l11�l�t�i�������_�ЁA1983�N5��20���j�̌��G�͎R�I�M�ɂ��5�_�̃J���[�ʐ^�ŁA�Ō��1�_�́k����̎��l�l�V���[�Y���s�ɐ旧���Ă��̓��e���{�ɂ��g�p���ꂽ�i���f���͏��D�̐X�����q�j�B�s�g�����k����̎��l1�l�t�́q�ӏ܁r�͍����r�Y�́A�l���_�ł���q�ё��r�͋�����b�q�̎��M�A�q�ʐ^�r�͂����܂ł��Ȃ��n�ӌ��l�̎B�e�ł���i�{���ŏq�ׂ�悤�ɁA����Ɠn�ӂ́s�����̊X�t�̋����ҁj�B����A�s�剪�M�k����̎��l11�l�t�́q�ӏ܁r���O�Y��m�A�q�ё��r���ҖM���A�q�ʐ^�r���R�I�M�Ƃ����z�w�������B�����̐l�I������ɂ�锭�Ă��������͂Ƃ������A���҂ƕҏW�҂̍��ӂ̂��ƂŌ�����݂����Ƃ͂����܂ł�����܂��B
�i���R�j�@���Ҏ����̋g�����s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�́A�I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�j������Ŋ��s���ꂽ�������낵�����A�W���P�b�g�Ɩ{���ɒ����ĔV�́i�����ő���ꂽ���O�r�[�{�[���قǂ̗��́j�I�u�W�F�̎ʐ^���f�ڂ��Ă���B���t�ɂ́u�I�u�W�F�@�����ĔV�v�ƂƂ��Ɂu�ʐ^�@����ρv�Ƃ���B���̎ʐ^�͂�����u�u�c�B��v�ŁA��i�Ƃ��Ă̎ʐ^�ł͂Ȃ��A�����܂ł������̃I�u�W�F������������B�����Ƃ��A�G��ʂ����ʐ^�����ꎩ�́A�u�����v�ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���̂ɑ��āA��ʑ̂ł���I�u�W�F�����̂������Ɍ����邩�ɂ́A�ʐ^�Ƃ̑n�ӍH�v�̗]�n���c����Ă���B
�i���S�j�@�n�ӌ��l�́A�������猻�݂Ɏ���܂ŁA��т��ă��m�N���v�����g�̌`�ō�i�𐢂ɖ₤�Ă����B�ߔN�̐���̗l�q�́s�A�T�q�J�����t2020�N3�����́q�v�����g�ŕς��ʐ^�̗́\�\�t�B�����ҁr�ł����������Ƃ��ł���i���E�r�J�C��k�����ҏW���l�j�B�n�ӂ͂��́q�v�����g�����݂ɂ����ɒ��邩�r�Łu�ł�����A�悢�l�K�����Ȃ�������Ȃ��B��{�I�ɂ́A�܂��Ă���A����Ă��闼������t�B�����̂Ȃ��ňꏏ�ɂ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ���ł��B���Ƃ��A����V���[�Y�Ȃ�܂�̓��ɂ����B��܂���ł����B�܂��~�J���Ȃ�A�������߂�B�^�Ẵs�[�J���Ȃ�������߂�B�ł�����l�K�̏�ԂŃV���v���ɘI�o��S�����낦��悤�ɂ���킯�ł��v�B����Ɂu���ׂ�60����1�b�ŁA�i�肆8�ɂ��낦�Ă��܂��B���܂͕����Ă������ق����悢�̂��ȂƎv���Ă��A�����Ă��̂܂Ă��B����͂�����̂����̂܂Ă���������B��������ʂɋZ�@�I�Ȃ��̂Ƃ��͎����ł͂Ȃ���ł��B�B�e�����͂ǂ����邩�Ƃ��A�J�����͉����g�����B���̑I�����炢����Ȃ����ȁB�v�i�����A�㎵�y�[�W�j�ƌ���Ă���B���̊m�M�ɏ[�������@�́A50�N�ɋy�ԑn�슈���S�ʂɂ킽���č̗p����Ă���̂ł͂Ȃ����B���Ȃ݂ɁA�����f�ڂ̐V��q�ɐl�r�œn�ӂ̎g�p�����@�ނ́A�t�W�f�v690�V�E�g���C�w�i�h�r�n320�j�ł���B
�i���T�j�@�푺�G�O�̈⒘�s�f�Ђ���̐��E�\�\���p�e�W���t�i���}�ЁA2005�N8��8���j�ɂ́q�~�]�̉����߁\�\�n�ӌ��l�r�i���o�F�s�|�p�����t1973�N12�����j�����߂��Ă���B�ҏW�l�ꓯ�ɂ��q�ҏW��L�r�Ɂu��l�͂ł́A�\����A���o�ꂢ�����������p�Ƃ̕��X�ɍ�i�ʐ^�̒����肢�����Ƃ���A�ЂƂ�̗�O���Ȃ��A�������͂��Ă������������Ƃ́A���p�ɐe���ނ��Ƃ�̊�тƂ����̐l�ւ́A�����̂͂Ȃނ��ł������Ɗ��ӂɑς��Ȃ��B�v�i�����A�O���O�y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�푺�̕��͂ɂ͐}�Łip.344�@�n�ӌ��l�s�Í��̖��z �W���b�N�E�U�E���p�[�Ɋւ���f�ГI�����t1973�N�j�̎ʐ^����_�A�f�ڂ���Ă���B���̒m�邩����A�n�ӂ��B��Ę^���������s�Í��̖��z�t�i�j�R���T�����j�̍�i�ł���B
�i���U�j�@�{���Łs�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�V�@�s�s�A�@�t�|�s�s �T�E�U�E�V�t�iAG+ Gallery�A2018�N2��28���j���Љ���B���V���[�Y�́s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@�U�@�s�s�@�@�����̊X�t�iAG+ Gallery�A2017�N11��30���j��2015�N�ł̎ʐ^�W�s�����̊X�t�̂̂��ɁA�ʐ^�W�s�f�ГI�����E�n�ӌ��l�̐��E�@1973-2018�@�S7��t�̂����A���́s��2�� �s�s�@�w�����̊X�x�W�t�i���FAG+ Gallery�A����F2017�N11��9���`25���j�̐}�^�����ЂƂ��Ċ��s���ꂽ�B�����́q�����̊X�ց\�\��������ʐ^�Ə����r���}�ԗI�M�͂����n�߂Ă���i���͊��������j�B
�u�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����̕L�ɔ����R���N�V���������Ă����Ƃ���A1981�N�Ƀj�R���E�T�����ł����Ȃ�ꂽ�n�ӌ��l�̌W�u�����̊X�v�ɏo�i���ꂽ���B���e�[�W�E�v�����g��18�_���������B���炭�s���s�����������̃v�����g�́A���̓x�u�n�ӌ��l�E�f�ГI�����v�W�ɏo�i����35�N�Ԃ�ɓ��̖ڂ𗁂т邱�ƂɂȂ����B�����̃v�����g�́u�����̊X�v�̒��ł��A1982�N�ɓn�ӂ������̍�i�ő�7��ؑ��ɕ��q�ʐ^�܂���܂���ȑO�ɔ��\���ꂽ�ŏ����̂��̂��B�u�����̊X�v�́A�ʐ^�W�����łȂ��A������b�q�Ƃ̋����Ƃ��ďo�ł��ꂽ�����i�w�����̊X�x�V���ЁA1980�N�B�ȍ~�V���Дłƕ\�L�j�ɂ�����e�N�X�g�Ɠ����̎��i�����ʐ^�������Ƃ��Ă̍�i�ł���B�܂��A�ؑ��ɕ��q�ʐ^��܂ɍۂ��ĎG���̃O���r�A�y�[�W�ɓ��W�f�ڂ��ꂽ�A��ł�����B���ꂼ��ɍ̘^���ꂽ�ʐ^���������قȂ��Ă���A�u�����̊X�v�Ƃ����^�C�g���͈�A�̍�i�Q�̑��̂ƌ�����B��̓I�ɋ�����ƁA�V���Дłɂ�55���̓n�ӂ̎ʐ^�ƁA14�͂���Ȃ����̃e�N�X�g�����^����Ă���B�܂��A�G���w�A�T�q�J�����x1982�N3�����ɂ͐V���Дłɂ��f�ڂ���Ă����i��13���ƁA������6�����V���ɒlj����ꍇ�v19���̎ʐ^�ō\�����ꂽ�B�ߔN�AAG+ Gallery�Ɠ��������ʐ^���w�Z�������Ŋ��s����93���̍�i�����߂��d���Ȏʐ^�W�ɂ��A�����̃^�C�g�����t�����Ă���B�k�c�c�l���āA�`���̍Ĕ������ꂽ�v�����g�̂����A����̏o�ŕ��ɂ���������Ă��Ȃ��ʐ^��8�_���݂��Ă������Ƃ����������B���̂悤�ɔ��ɑ����̃o�[�W���������u�����̊X�v�����A�k�c�c�l�B�v�i�����A�O�Z�`�O���y�[�W�j�B
�n�ӌ��l�́s�����̊X�t�̃|�C���g�͑傫���܂B�@������b�q�Ƃ̋����o�Łi1980�j�A�A�ʐ^�W�J�Ái1981�j�\�\���W��1981�N�x�̑�7��ؑ��ɕ��q�ʐ^�܂�1982�N3���Ɏ�܁i�I�l�ψ����q�u�I�l���I���āv�̋L�����o���r�F�������[�q��ɉߏ[�d���ꂽ���i�r�A�Ό��ה��q���l�Ȏv�������ʐ^�r�A�d�X�O���q�������I�ȃC���[�W�r�A�n�Ӌ`�Y�q�q�����r�̒��ɓƎ��́q�����r�r�A���{�����q�����̕��L���ʐ^�����̒�����r�j�\�\�A�B�ʐ^�W�o�Łi2015�j�A�C�ʐ^�W�J�Ái2017�j�A�D�}�^�����Џo�Łi���N�j�B�A�ƇC���ςĔ�r�������邱�Ƃ́i���ꂩ��V���ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ������Ɂj����߂č���M�d�ł���B�������āA�n�ӌ��l�̏ꍇ�A�ʐ^�W�����ʐ^�W���ς�Ƃ��Ƃ̏d�v�����ۗ����Ă���B�������Ȃ��A�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�͂܂��o�����Ă��Ȃ��̂��B
������b�q�Ɠn�ӌ��l�̋����s�����̊X�t�i�V���ЁA1980�N9��20���j�̊��ҏW�S���͐V���Џo�ŕ��̈ɓ��M�a�q�A�u����^�{�����C�A�E�g�v�͟N�䏺���B�{�e�̖{���E���̈��p�����ɂ����āA�����̓n�ӂ̎ʐ^�_�����܂��܂������i53�_�^�܈�t�^55���j�A�����������Ƃ��낱�����B�O����1�_�i���n�ɃX�~�����̔��ƁA�X�~�n�ɔ��k�L�����̃W���P�b�g�ɁA�����p�Ŏʐ^���g�p�j�A���Ό��i�B���m���u���̓�y�[�W�ɑ�������ӏ��j�Ɋۂ��g���~���O����1�_�\�\�}�ԗI�M�q�����̊X�ցr�ɂ��u���͖������}�������8�K�̌ܓ��v���l�^���E���ɂ������J�[���E�c�@�C�X���̓��e�@�v�i�O�f���A�l��y�[�W�j�\�\�A�{���i�܁`��l�܃y�[�W�j�̊Ԃ�53�_�̊p�Ŏʐ^�B�ȏ�̌v55�_�B
�i�i��S���F�����r�Y����j
�@����A���肢���܂��B
��
�q�킽���̋g�����r�y����3�z�\�\����N�v����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j
�i����N�v����A�o�d�j �k����F���сq�J�J�V�r�N�ǁl
�@�������������R���f�B�V�����̓��ɁA��������W�܂��Ă��������āA�ق�Ƃ��Ɍ��������\���グ�܂��B�k�����͑䕗���ڋ߂��鈫�V��l
�@���܂���l�̂�����������������A�Ƃ��ɔѓ���������������悤�ɁA�g������̂��Ƃ́c�c���Ō��̂͂Ђ��傤�Ɍ��ɂ����A�Ƃ����z��������܂��B�������A�����������Ƃ͌�����B��̓I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��āA���ۓI�Ȍ������ɂȂ��Ă��܂��܂�����ǂ��A�Ƃɂ����ڂ����ŏ��̎��W���o���ĊԂ��Ȃ��ɁA�g�������m���āA�g������ɒm���Ă��������ā\�\����͌��ǁA���̐��E�ɋg�����o��Ȃ������̂Ƃقړ��������ɂȂ�킯�ł�����ǂ��\�\���ꂩ�炨�S���Ȃ�ɂȂ�܂ł������Ă��������Ă����킯�ł����A���̊Ԃɂǂ��������Ƃ����������ƌ����A�z���o���Ă݂�A���x���ڂ����������Ƃ��ɋg�����琺�������Ă����������B���̐��͈ꐺ�ł��邱�Ƃ�����A�J��Ԃ��ł��������Ƃ�����B����łڂ��͗������ꂽ�A�Ƃ������Ƃ��ق�Ƃɉ��x�������āB����́A�������c�c�������łڂ��͎��߂Ă��܂���������Ȃ��������Ƃ��A���x���v���Ƃǂ܂������Ƃ�����܂��B1970�N�Ɂq����N���r�Ƃ�����̎��������܂��āA���̂��ƂŁu���̐l�́A�����A���߂邩������Ȃ��v�u���߂�Ȃ玫�߂Ă������v�Ǝv���Ă��Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă���ł�����ǂ��A���ꂪ�킽�������Ƃ����ӂ��ɂȂ����ɂ��ẮA�g�����ЂƂ��Ƃ���������Ă܂��B�����������Ƃ�����܂����B�܂��A����Ȃ悤�Ȃ��Ƃ������܂����ł́c�c�B�g�����������c���c�������Ƃ������Ƃ́A�g������̒Z�������ЂƂ���܂��̂ŁA������Ă��������āA����ł����A�ɑウ�����Ă��������āB
�@�q�J�J�V�r�Ƃ����A�J�^�J�i�ŏ������\�\�薼�̓J�^�J�i�ŁA���g�͂������Ђ炪�Ȃ⊿���Ł\�\����͏\��A�O�s�̎��ł��B
�i���сq�J�J�V�r�̘N�ǁB�Ȃ��e�N�X�g�́s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A���l�`���܃y�[�W�j
�V�W�~�̉��̏o��
���c�̎��͂���Ă͐���
�j�Ə��̉���������
�u������������Ă���ҁv
�̐��ޏ��ł�
���̌Q��������ς�
�r㼂̂悤�ȎR�̕��ւ䂭
�u�ċ�
�@���̎ς�
��сv
�̐H���͏I��
���݂�ׂ��l�݂͂Ȃւ��ܒI�̉��ɏW��
���̑����ł͌���ƂƂ���
�ډB���̛����̂Ȃ���
�Ԃ�V�����܂��
�i���A����j
�k�t�L�l
�����q�ҏW��L 44�i2006�N6��30���X�V���j�r�Ɂu�I���W�s�g�����t�������M�����B1991�N10��12���A�E�ؔn���ŊJ�Â��ꂽ�q�g�������Âԉ�r�ŁA����N�v���g�����̎��сq�J�J�V�r�i�G�E28�j��N�ǂ������A���̂Ƃ��̃e�N�X�g���m���{���������B���N���X�̏��U��ȏ㐻�{�́A��������Ǝ�ɂȂ��ޑ���ł���B�v�Ə������B�N�ǂ���ɂ́A���̒������������W���Ă���B�����A�����ă��_���ȁs�T�t�����E�݁t������{�т����œǂ��Ƃ́A���ɋ���Ȉ�ۂ��c�����B����Ƌg���A���҂̊W�ɂ��ẮA��l�̒P�s���W��ʂ��čl�@�����q�g�����Ɠ���N�v�r�����ǂ݂������������B�����́A���̒Ǔ�������N�v�ł���B
�u��k�灩�X�l�͊F�A
�`���̑قɉ���Ɠ����ɁA
���𗢂̋��̗҂����Ό����瓾���̂ł���k�i�i�V�j���B�l�v�k���̎O�s�A�����̑莫�m�G�s�O���t�n�ł́u�@�v�i�ꊇ�ʁj�Ȃ��ŁA�ǂ����ݓ�s�̎����𑵂��Ă���l
�Ƃ��Ӗ����w�ҁk���c���j�i1875�`1962�j�l�̌��t���A
�k�s���y�t�s���̉ԁt�Ɏ����l�O�ڂ̒��я����k�s�Y�p�̉́t�l�Łk�I�����l�́k�q�m�����n�̉͌��m�����n�r�l�̔��Ɉ��������̐�B�k���i���F�i1918�`1979�j�l���A
�錩�̐��E�ւƍQ�����킯���čs���B
�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�̖{���̊����́A�k���c�l�q���ȐN�Ƃƕϗe���d�˂��|�p�ƍ��\�\�w�����G�߁x����w���[���h���b�v�x�܂Łr�i�����A��Z�`�l��y�[�W�j�ŁA�剪�M�i1931�`2017�j�E����N�v�i1931�`2018�j�E�V��ޓ�Y�i1936�`�@�j�E���o���i1950�`�@�j��4�l�ɂ��A�����ł��ł��n���ɕx�i�_�̗��t����K�v�Ƃ��Ȃ��j�_�l�������B�����̋L�ڂɂ��A���c��1990�N11��15���i�j�ɂȂ��ꂽ�B����́k����F���сq�J�J�V�r�N�ǁl�̂قڈ�N�O�̂��Ƃł���B�����ɂ͂���Ȃ��Ƃ肪����i�����A�l�Z�y�[�W�j�B
�����@����ς�k�g�����������l���������Ȃ������ł͂�������ł���B����N�A����N���́B�ڂ��������Ȃ���������ǁB
�V���@�ڂ��������Ȃ�������ł����A�g���������Ȃ��̂͒��ق����ƌ����A�ڂ��������Ȃ������̂͊����ꂽ�ƌ���ꂽ�i�j�B
�剪�@���ꂷ�����i�j�B
���o�@�ڂ��Ȃ͏����n�߂������Ȃ�ł����A�݂Ȃ�����Ȃł�����A�����ٗl�Ɏn�߂ɂ�����C������܂����i�j�B
�����@�ڂ����u����N���v�̏����Łu�����W���[�i���v�ɏ������̂�����N�̈ꌎ�ŁA���ꂩ��O�N�Ԃ��菑���Ȃ�������ł��B���̍��݂͂�Ȃ��������v������������ł���B
�g�����u���فv�ɓ���܂��̎��́A1969�N10�����M���q�R�����r�i�F�E18�j�ł���B����A�u����N���v�̎��́A�q���Ȃ�v�����[�O�\�\�܂����Ă���藈�����N�̂͂��߂Ɂr�B���̖{���i�P�s���W����яW���ɖ����^�j�Ƃ��̔w�i�́A�q����N�v�u���Ȃ�v�����[�O�v���a46�N�i1971�N�j | �l���͖�X�[�v�`�A�G���G���̃u���O�A�܂��͌ߑO0�����ߌ�3�������X�V�̒j�r�ɏڂ����B������܂��A�u�ߑO0�����ߌ�3�������X�V�̒j�v�ɂ��ɐȒǓ����ł���B
�k���W���g�������i�g���j�l
�s��k�큨�́l�炩�����|�t�b����N�v
�k�i�i�V�j���@�\�\�g�������ցl
���Ƃւ@���̈�тɂ��Ă��炪�@�Ȃ�
�s�������Ƃ͊W�Ȃ��t
�������@�����ɂ��Ȃ����̂ЂƂ�
�s�������炾�S�̂ɒ���o���āt�j���ł���
���Ƃ��炽�߂Č��ӂ܂ł��Ȃ��@�����
���Ȃ��ɂƂās�̂��ނƂ���łȂ��@���ޏp���Ȃ��t
�s�i�N�̌o������t�˂ɂ��Ȃ����k�K���I�l�m�Ɂs����t���肩
���̈�т���@���̈�тց@�����Ă���Ɏ��ւ�
�s�����т́t��s�@���I�ȂȂ���t���J��o����
����́s�X�C�J�t���������
���̉ʂɗӌ�����C��s�s�̖����킫�N����
����قNj���ׂ���̂̓q���������ɑ����ĉ\�ł��炤��
�����ɂ́@���ł��s�����ȉΎ�������
�M�ƕ�������ꏊ�����t��
���̂��������@���ЂĐ�������Ȃ��
�s�����֕R�����炵����
�_��I�ȌC�t
���̌C�̓B���s�`����I�����t�ɑł����
���ˏ��I�@�S�̉��n�ǂ���
�Ƃ���ŁA���鎞���܂ł̓���͎����т����������B�}�����[�ŋg�����Ɠ�������������̎ʐ^������킩��B���ꂪ�����͂킩��Ȃ����A��w�ōu����悤�ɂȂ��Ċw���̑O�Œ���ۂɁA�����ڂ̖������邱�ƂȂ���A����̈������C�ɂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����B����́u�v���o�b�v�́A�����������ꂽ�ɂ�������炸�A����قǂɒ����Ƃ�ɂ����B��f�k�b�Łu�c�c�v�ƂȂ��Ă���Ƃ���́A���������ł͂Ȃ��A�������ɔ������Ă���̂����A�����Ƃ͒����Ƃ�Ȃ��ӏ��ł���B����A�g�������́u�N�ǁv�Ƃ������Ƃ������āA�\�L�i�����₩�ȁE�J�i�A���ʗށj�͂Ƃ������A���s�ӏ������Ăɔ��ʂł���A�N�N���鋿�����Ă���B�܂�ŕʐl�̂悤���B�g��������邱�Ƃ͎��Ȃ���邱�Ƃł����āi����N�v�͂�����D�܂Ȃ������j�A�����̔����͂��ׂċg���̎��ɕ������Ă���A�Ɓu�v���o�b�v�̂��̃g�[���͍����Ă���悤�ł���B
�q�k�g�������M�l�N���r�́A������1983�N10���Ƃ������t�i���M�����j�����A�g�������������Œ��́u�N���v�ł���B���̏I���̕��́i���Ȃ킿1983�N�̍��j�́u�k�c�c�l���u����v���w�����x�I�����ɔ��\�B���āA���ˉ�v�����B�����B�w��ʁx�̌��e���A����R�c�̗�؈ꖯ�A���j���v�Ȃ֑����B�H�A�������������ق́u�؍��Ñ㕶���W�v���ς�B�\����\���A���W�w��ʁx���s�����B�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��O���y�[�W�j�������B���W�Ɏ��߂�ꂽ�ŐV�̍�i�́A���̔N9���ɔ��\���ꂽ�q����r�i�J�E16�A���o�́s�Ԑ_�t�H�E3��3���j����������A���N6�����\�̘h���ɒj�̒Ǔ����q����r�i�J�E17�A���o�́s�����t�āE10���j�́A�g���ɂƂ��ē��ʂȎ��т������̂��낤�B�g���Ɠ��N���܂�̒��ˉ�v�i1919�`1983�j��8��11���ɟf�����ۂɁu�����v�Ƃ́A���V�ɂ͎Q�Ȃ������Ƃ������Ƃ��B���̌�A�s��ʁt�̌��e������R�c�ɓn���A�������������قœW������ςāA10��20���ɂ́u����g�������v���\���鎍�W�s��ʁt�����s�����B���āA����1983�N�i��10���܂Łj�ɋg�����N���ɏ����Ƃ߂��W����͎��̎l�ł���B
�@���a�\���N�@��㔪�O�N �Z�\�l��
�y#26�z�����̔��R�L�O�قŁA�J�@�c��̕M�Ɠ`������u���L�v���ς�B
���s���a�\���E�\���N �H�G�E�~�G�W�ω�L�t�i���R�L�O�فAc1982�k�N10��1���l�j�^��ꁁ���R�L�O�فA��������a58�N�~�G�W�F1��8���y�y�z�`3��15���y�z��
�y#27�z�������������قŁA�{�X�g�����p�ُ����u���{�G�於�i�W�v���ς�B���q�V�S�∤�́u��Г��������v�ɋ��Q����B
���������������فE���s���������فi�ҁj�s�{�X�g�����p�ُ��� ���{�G�於�i�W�}�^�t�i���{�e���r�����ԁAc1983�k�N3��15���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1983�N3��15���y�z�`5��8���y���z��
�y#28�z���āA�������������قŁu�O�@��t�Ɩ������p�W�v���ς�B���哶�q�����i���������j�̘Z軀�ɖ�������B
�����s���������فE�������������فE�^���@�e�h����{�R��E�����V���Ёi�ҁj�s�O�@��t�Ɩ������p�t�i�����V���ЁA1983�N3���k19���l�j �^��ꁁ�������������فA�����1983�N5��24���i�j�`7��10���i���j��
�y#29�z�H�A�������������ق́u�؍��Ñ㕶���W�v���ς�B
���������������فE�����V���Ёi�ҁj�s�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t�Ɓs�V���C������g�������t��2�����i�����V���ЁAc1983�k�N8��2���l�j�^�����W�F��ꁁ�������������فA�����1983�N8��2���y�z�`9��11���y���z��
�Q�l�܂łɁA�̂��̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�u��㔪�O�N�i���a�\���N�j �Z�\�l�v�̍��Ɍ�����W����W�̕��i�́j�������i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�N3��25���A���Z�܃y�[�W�j�B
�y#26�z�����̔��R�L�O�قŋJ�@�c��̕M�Ɠ`������q���L�r�B
�y#27�z�������������قŃ{�X�g�����p�فq���{�G�於�i�W�r���q�V�S�∤�́q��Г��������r���ς�B
�y#28�z�������������قŁq�O�@��t�Ɩ������p�W�r�B���哶�q�����i���������j�̘Z軀�ɖ�������B
�y#29�z�H�A�������������قŁq�؍��Ñ㕶���W�r���ς�B
�ȉ��Ɂ��i�A�X�e���X�N�j�ŋ���āA���ꂼ��̐}�^�̕\���ƁA�}�^�{���ɃJ���[�̐}�ł�����ꍇ�͂����ɂ���i�g�������y���Ă����i������A�������D�悵���j��I��Ōf����B�Ƃ��ɂ���炪�Ȃ��Ă��A�֘A����b�肪����Ƃ��́A�{���̐}�ł�1�`2�_�A�f�����B
��
�y#26�z�s���a�\���E�\���N �H�G�E�~�G�W�ω�L�t�i���R�L�O�فAc1982�k�N10��1���l�j
 �@
�@ �@
�@
�s���a�\���E�\���N �H�G�E�~�G�W�ω�L�t�i���R�L�O�فAc1982�k�N10��1���l�j�̕\���i���j�Ɠ����E�O�Z�y�[�W�́q���a�\���N �~�G�W�@1 �h��@�{��@�o���r�i���j�Ɓy�Q�l�z�J�@�c��́q�����}�r�i�E�j
�g���́q�k�g�������M�l�N���r�Ɂu�J�@�c��̕M�Ɠ`������u���L�v���ς�B�v�Ə��������A�{�}�^�ɓ���͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�g���̐��z�Ȃǂ���Ɏ��̌o�܂�ǂ��ƁA1980�N����A�������������قœW�����ꂽ�J�@�c��́q�����}�r���ς����Ȃ������̂́i�F�V���F���܂��A�ς��т�Ă���j�A�K���Ȃ��Ƃɂ���ȑO�Ɂu�����v���x�A�ςĂ���B����Ƃ��i1980�N�㏉�߂��j�A��Ƃ̒����ĔV����A�`�J�@�c��M�q�L�}�r�ɏՌ������ƕ�������āA���߂āq�L�}�r�̑��݂�m�����B�����́q�L�}�r�̌f�ڂ��ꂽ�}�^�i�k���Ûܕҁl�s��\�\�v�c�݉��t�A���É듩���A1980�N10��1���j�𑗂��Ă��ꂽ�B�}�ł́q�L�}�r�́u��C�ɂ������v���v�̂����g���́A�����q�L�}�r��q�݂����Ɗ肤�܂łɂȂ����B�ȏ�̋g���̐��z�q�J�@�c��u�L�}�v�r�́A1982�N6��28�����s�́s�ڂ̊�t1982�N7�����ɔ��\����Ă��邩��A���ꂩ�甼�N�قǂ��āq�L�}�r�ƑΖʂ��邱�Ƃ��������킯���i�q�g�����ƍ�������r�Q�Ɓj�B
�}�^�́q���a�\���N �~�G�W�r�`���́q1 �h��@�{��@�o���r�ł���i�E���h��A�����{��j�B�����͒��l�喼�̏����s���i1751�`1818�j�B���h��@�T�M�i1730�`1790�j�́q�Ԃɖ���r�Ǝ��{��@�ҐM�i1753�`1808�j�́q���ɏZ�^�r�͋�Ԃ������������w�ȍ�ŁA�g�����ς��q���a�\���N �~�G�W�r�̌Ăѕ��̂ЂƂ������̂��낤�B�����Ƃ��A���]�����q�L�}�r���߂��Ă̋g���ɂ͕�����Ȃ������͂����B
��
�y#27�z�������������فE���s���������فi�ҁj�s�{�X�g�����p�ُ��� ���{�G�於�i�W�}�^�t�i���{�e���r�����ԁAc1983�k�N3��15���l�j
 �@
�@
�������������فE���s���������فi�ҁj�s�{�X�g�����p�ُ��� ���{�G�於�i�W�}�^�t�i���{�e���r�����ԁAc1983�k�N3��15���l�j�̕\���i���j�Ɠ����́q2 ��Г������� ��������i11���I�j�r�i�E�j
�u�������������قŁA�{�X�g�����p�ُ����u���{�G�於�i�W�v���ς�B���q�V�S�∤�́u��Г��������v�ɋ��Q����B�v�i�q�k�g�������M�l�N���r�j�B�{�X�g�����p�يْ��̃����E�t�H���e�C���̊����_���q�{�X�g���̓��{���p�R���N�V�����̂���݁\�\�G�����Ƃ��ār�ɂ́u�܂��A���q�k�V�S�l���{�X�g�����p�قƂ̂Ȃ��肪�ł���ȑO�Ɏ��W�������I�R���N�V�������̖��i�̊���́A�ނ̎��̎��N��ɁA���q�̈⑰���甃���グ���A���ق̎����i�ƂȂ����B���̒��ɂ́A���{�����G��̍ō�����ɐ�������u��Г��������v�i��}�j�����邪�A����͉��q���L�O���āA�k�E�B���A���E�X�^�[�W�X�E�l�r�Q���[���w�����A���قɊ������̂ł���B���̉摜�����q�̎��I�R���N�V�����̍ł��D�G�ȕ���ł������悤�ɁA�ّ��i�ƂȂ������c��́u���ӕ�F���v�͉��q�����̍ō��̓��{���������ł������ƌ����悤�B�����̍w���́A���q�̌�C�A�W�����E�G���[�g���E���b�W�̓��m�����ݔC���ɍs�Ȃ�ꂽ�B�v�i�����A���y�[�W�j�ƌ�����B���}�͊����́q��i����r�ɂ́u���q�V�S�∤�́m�A�A�A�A�A�A�A�n���̉摜�́A�����炩�œ��X�Ƃ����앗�������A�\�ꐢ�I���O�����ɑk��l�������Ȃ������i�B�v�i�T�_���p�ҁB�����A��܁Z�y�[�W�j�Ƃ���A�O�f�g���N���̋L�ڂ͂��̕����܂������̂Ǝv����B
��
�y#28�z���s���������فE�������������فE�^���@�e�h����{�R��E�����V���Ёi�ҁj�s�O�@��t�Ɩ������p�t�i�����V���ЁA1983�N3���k19���l�j
 �@
�@ �@
�@
���s���������فE�������������فE�^���@�e�h����{�R��E�����V���Ёi�ҁj�s�O�@��t�Ɩ������p�t�i�����V���ЁA1983�N3���k19���l�j�̕\���i���j�Ɠ����E�O�y�[�W�́q144���b�����q�����m�������ǂ�����イ�����n�i���哶�q�����m�͂������ǂ�����イ�����n�̂����@���������r�i���j�Ɠ����E�ꎵ���y�[�W�́q144�����哶�q�����m�͂������ǂ�����䂤�����n�@�Z軀�^�e�ؑ��ʐF�@������܁E��`��Z�O�E�Z�^���q����@�\�I���^�a�̎R�@���������r�i�E�j
���m�N���ʐ^�̃L���v�V�����́A��i������u�G��k誐���q�@�b�쓶�q�@�b�����q�v�A���i������u�����ޓ��q�@��㹗����q�@�����u�v�B���}���Ȃ킿�q144�����哶�q�����m�͂������ǂ�����䂤�����n�@�Z軀�^�e�ؑ��ʐF�@������܁E��`��Z�O�E�Z�^���q����@�\�I���^�a�̎R�@���������r�́q�P�F�}�ŁE����r�ɂ́u���v��N�i���㔪�j�Ɍ������ꂽ�s�����̖{���s���������i143�j���ő��m�����n�B������軀���̂��̂����A�c��̓�軀�͎�������̌��ł���B����������肬�݂̑�軀�̗v�����悭�������߁A�z�X�m���n�����j�q�̕��e��������B�ʊႪ�L���ɐ�������A���ۂ̐l�Ԃ��v�킹�鐶�X�m�Ȃ܂Ȃ܁n�����̉��ɁA�s�����ő��炵���D�u�Ƃ����\�������������A�w����t�H�x�ɂ����^�c��Ƃ������͂��Ȃ����ɔے�ł��Ȃ��B�w�����ߎʐ^�ɂ��A��㹗����q�̑����ɁA�^�c��̑��̕����ɔ[������Ă������̂Ɠ��`�̌��`�؎D�������Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B�v�i�����A�ꎵ���y�[�W�j�Ƃ���B
�g���́q�w���W�x�f�z�r�i���o�F�s����Z�̑S�W�k��6���l�t����10�A�}�����[�A1981�N3��25���j�ʼn�Ô���̒Z�̓��������Ă���A
�@���̓��́A�V��t���̋����̕������r���̂ł���B���̍��͂��̎��֍s���l�͂قƂ�ǂ��Ȃ������悤���B�������͂ǂ����Ă��\��_���������ς����̂ŁA�t����̓m���牡�������炭�������B�r�ꂽ�z�n�ň͂܂ꂽ�����ɓ��������A�Q�q�̐l�͈�l�����Ȃ������B�����c�@�̌����ɂȂ�ƌ�����A�V���̌Î��́A���т�ʂĂĂ����B���͔Ԑl�ɔ����J���Ė���āA���Â������ɓ������B�����ɂ́A��t�@������삷��悤�ɁA�\��_�������~�`�ɗ�������ł����B�܂�ŊD�����Ԃ����悤�ɁA�����������B�ЂƂ��킷���܂�����e�̔��ܗ��m����n�叫���ɁA���͐S�������Ă��܂����B��Ô���͉��̂ɂ��̑��̂��Ƃ��r�܂Ȃ������̂��낤���\�\���闅�����\��_���̏ے��ɂ��Ă���̂��A�s�v�c�Ɏv�����B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z���`�O�Z���y�[�W�j
�Ə����Ă��邪�A���ĎU���Łq���哶�q�����r�ɐG�ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�����A�q�����q杁r�K�E4�j�́A�Ƃ�킯�u4 �t�v�͂����Z軀�̓��q����������������Ƃǂ߂Ă��͂��Ȃ����B�u1 �āv�u2 �H�v�͂Ƃ������A�u3 �~�v�Ƃ��́u4 �t�v�̐߂́A�s���[���h���b�v�t�i1988�j�̏���̂Ȃ��ł͂���߂ās��ʁt�i1983�j�ɋ߂��앗�ŁA���ɂ�1983�N���Ă̂��̓W����g���ɑ傫�Ȋ�����^�����䂦���Ǝv����B�Ȃ��g���́A�ѓ��k��Ƃ̑Θb�q���I�t�̌�䊁r�i�s�����C�J�t1975�N12���Վ��������q��i�����W ���㎍�̎��� 1975�r�j�ŁA�^�c�ɂ��Č�肠���Ă���B���́q�^�c�ƃV�������A���X���r����A�͂��߂̕������������ēr����������B
�g���@�ڂ����A�������N�ԂŊς������ōō��̊��������̂́A��N���炢�O���ɏ�씎���فk�������������ق̂��Ɓl�ł������u���㓹�߉�W�v�B�ڂ��̍D���Ȗو��́u�l���}�v�Ȃǂ��o�Ă�Ƃ������Љ��ǂ�ŁA�Ɠ�����čs������A�ٓ��ɐ��l�̋q�������Ȃ����т����B�ڂ��ɂƂ��Ă͖و���ό��̐��n���悩�������A�Ȃ�Ƃ����Ă���P�G���B������`��P�u���R�E���v�Ƃ����L���ȉ�Ƌv���Ԃ�őΖʂ�����B������͂���͂����A�܂��Ɋ�P�B��̐^��Ƃ����u�S����寐�l�v�̑̈ꕝ�B����͂�������ׂ��G�ȂȁA���E�̎��Ǝv�����B
�ѓ��@�����̂��̂͂�����Ȃ�������B�����̔����قŁu���q����̒����v�Ƃ����̂���Ă��ł����ǂˁA�^�c�A�X�c�A�f���������̂ł��ˁB�^�c�Ƃ����̂͂������̐����͂ɖ����ĂāA���Ă�Ƃ����炪�����ꂻ���Ȋ��������邮�炢�ˁB
�g���@���ɍ�i�͏�����Ȃ��B
�ѓ��@����ł������W�߂��ق��炵���B���܂ł͉^�c����Ȃ���Ȃ����Ƃ���ꂽ���̂ł��A�ŋ߂̌����ʼn^�c���Ƃ������ƂɂȂ������̂����Ă�B�^�c�ɂ��Ă��]��ɂ��r�X�����Ƃ������̂������Ă���ǂˁB����ɂ��܂����ĂˁA�r�X��������ɂ��܂Ȃ�B����͂�����Ƌ������ȁB�s��������������V���B
�g���@��������ƁA�����钆���Ƃ����痈�������ƈ�����Ӗ��Łc�c�B
�ѓ��@����Ă�ł��傤�ˁB�ڂ��͂��������ق��͂���܂�m��Ȃ����ǁA���{�̂��̂ɂȂ��Ă�낤���ǁA���̃G�l���M�[����₷�炵�����̂ł��ˁB�����̂���ł��傤�A���ꂪ������������͂��������̐��C�����߂��Ă��āA���ĂĈ��|�����B���q�̒X�c�ɂȂ�ƁA�X�c�͓�O�������ĂȂ����ǁA���������Ƃ₳�����Ȃ��āA�m�I�ɂȂ��Ă���Ă������ȁA���l�ȂȁB�����������ł���A������Ɣ�����V�Ȃi�����Ƃ��ĂĂˁB���ꂪ�Ⴄ�ȁA�e�q�ŁB�^�c�̗͂��Ă̂͐����ł���A���{�̂��̂ł�����Ȃ��̂����邩�ȂƎv���ĂˁB���������_���̊�������c�c
�g���@���Ⴀ�ςȂ�����ˁB�^�c����\��ƂɂȂ�킯�H
�ѓ��@�����ˁA���̎���̂ˁB
�g���@�u�\���q�v��������̂́A����͉^�c����Ƃ��X�c�Ȃ́B
�ѓ��@�Ⴄ�ł��傤�B�Ɋy���̂��������B
�g���@�����Ƃ����c�c�B
�ѓ��@�^�c�̓R���K�����q�Ƃ��Z�C�^�J���q�Ƃ����B��������C�ɂ݂������q���łˁB
�g���@����͂����f�������Ǝv���Ă���ǁc�c�B
�@������e�[�}�Ɏ��͂ł��Ȃ��H�@�����̎����Ă����̂́B
�ѓ��@����A������Ƃ����A�^�c��X�c����ڂ��ɂ��Ă��������@���Ȃ��ł����ǂˁB�ł��A�ڂ��͂Ȃ�ƂȂ����܂̓����̊X�ˁc�c���������ƑO���炾���ǁA�Ȃ�ɂ�������̂��Ȃ��ȁA�r�������Ȃ��āB���������ɂ͂Ȃ�ɂ��Ȃ��ł��ˁB�����^���[�ɕ�����ق��炢�����Ȃ����Ǝv�������ǂˁB�����������̂�����ȁB���q��ޗǂ���^��ł��Ă�킯�����ǁB
�g���@�ߗ��̂���͊ς��̂��B
�ѓ��@�ς��̂ł��ˁB���ꂾ�����|���ꂽ�̂́B���㒤���Ȃ��Ĉ��|���ꂽ���ƂȂ����ǁA���̉^�c�̗͂��Đ�������ł��ˁB���̒����̂Ȃ��ɐ��_�͂��A�������肠��Ɗ�����B
�g���@�����炳�A���鐸�_���Ⴄ��Ȃ��́A�͂����茾���āB�����_�l������Ƃ����A����������Ă����p���ł��傤�B��������p�i������Ƃ���i����Ƃ����p���ƈႤ���������ʂɟ��ݏo�Ă��Ȃ����ȁB
�ѓ��@�ł��A���̓W������ł��A�ق��̕����������ς����邯�ǁA����ɂ͂���܂�͂������Ȃ��B�ŏ��̕����ɉ^�c������łāA��������Ă�ƁA���Ƃ͂Ȃ��ɂ��ƂȂ������̂�������ˁB�^�c�͌��Ă���Ɣ��A�܂��͂�^������B�ق��͔��܂��A�܂���R���Ȃ��B
�g���@���Ƃ��ˁA�ѓ����^�c�������Ȃ��Ƃ������ƁB�ȂV���������������Ƃ��Ă�ƁA���{�I�����ɂ킸��킳�ꂿ�Ⴂ���Ȃ����Ă����ӎ����A�ڂ��̂Ȃ��ɂ�����킯�ˁB����͐V�����O���̒����̂ق������ɂ����ق����V�����Ȃ�Ƃ����A���o�Ȃ̂����킩��Ȃ����ǁA����̂ˁB
�ѓ��@������ƍ��o���������ȁB�i�����A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
�͂��߂ɕ⑫���Ă����ƁA�g�������ɂ�����u�ڂ����A�������N�ԂŊς������ōō��̊��������̂́A��N���炢�O���ɏ�씎���قł������u���㓹�߉�W�v�B�v�ɂ��ẮA�q�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����y#13�z�r�̓��ʓW�ρs���㓹�ߐl����t�ŐG���\�肾�B���āA�ѓ�����f�Θb�Łu�����̔����قŁu���q����̒����v�Ƃ����̂���Ă��ł����ǂˁA�^�c�A�X�c�A�f���������̂ł��ˁB�v�Əq�ׂĂ���W�����{�A�ڂ̏����ŋL���A
�y#13-post-01�z�H�A�ѓ��k��ƍs�����Θb�q���I�t�̌�䊁r�ŁA�ѓ����瓌�����������قŊJ�Ò��́u���q����̒����v�����߂���B
���������������فs���ʓW ���q����̒����t�i�������������فA1975�N10��2���j�^��ꁁ�������������� �{�ّ�1�`9���A�����1975�N10��7���y�z�`11��24���y���E�U�x���z��
�ƂȂ�B���}�^�ɂ̓��m�N���̐}�łŁA�q14�@�����ޓ��q�m���������ǂ����n�E��㹗����q�m����ǂ����n�E�����u���m���悤���悤�т������n�i���哶�q�����̂����j�@3軀�^�a�̎R�E�����j�r���f�����Ă��邩��A�ѓ��̊��߂ɏ]���ċg�������W���ς��̂Ȃ�A�s�O�@��t�Ɩ������p�t����7�N���قǑ��������^�c��Ɠ`�����鑜�ɐG�ꂽ���ƂɂȂ�B���邢�́A���́s���ʓW ���q����̒����t�ł̊�����������x���키�ׂ��A�s�O�@��t�Ɩ������p�t�ɂ��r���^�ƍl�����Ȃ��͂Ȃ��B�J�@�c��́q�����}�r���ςɁA���̂��тɓW������K�ꂽ�悤�ɁB
��
�y#29�z�������������فE�����V���Ёi�ҁj�s�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t�Ɓs�V���C������g�������t��2�����i�����V���ЁAc1983�k�N8��2���l�j
 �@
�@ �@
�@
�������������فE�����V���Ёi�ҁj�s�V���C������g�������t�Ɓs�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t2�����̕\���Ƃ�������߂锟�i�����V���ЁAc1983�k�N8��2���l�j�i���j�Ɓq38 ���X���ʁE���� 13�r�i�s�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t�A�O��y�[�W�j�i���j�Ɓq1 ���͎��r�r�i�s�V���C������g�������t�A�k��܃y�[�W�l�j�i�E�j
�s�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t�ɂ́A���Ȃ��܂ȋ����̏o�y�i��ʂ̂ق��A�q145 �����\�ӕ�F���摜�r�q155 �����\�ӕ�F���摜�r�Ƃ������݂��Ƃȕ������f�����Ă���B�g���͂��āA���z�q�匴�̙֎썹�r�i���o�F�s�O�c���w�t1962�N1�����j�̍Ō���u�����Ė����A�������͗������̐Β���A���@�̒���A�����čL�����̖��ӕ�F�����邾�낤�B���̂����Ƃ������邠�̖��ӕ�F�B�s�ˎ����ŁA�������w��܂�ꂽ���̉i���̑��E���ӕ�F����v�ґ����A�ȂƋ��邾�낤�B�l���͌��������^�N�V�[�̂Ȃ��ŌÓs���s�̏H�́A�����������邱�납��͂��܂�Ǝv�����B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��܃y�[�W�j�ƒ��߂��������B�؍��̌Â����p�i�i�ƌ������A�����ƌĂт������j�͈��D�Ƃ̋g���ɂƂ��Ă͍ł��e�������̂ŁA�O�o�q�g�����ƍ�������r�Ɉ�������ˎ闝�́q�����r�ɂ��A�u�k�c�c�l�w���邩�A�����邩���ċg���Ƃɉ^�э��܂ꂽ�炵�������v�̂����u�{�l�����߂��̂́A�����ނ˗����̂��̂���v�A�u�ނ�������ꂽ�炵���̂��A�k�����́l�؍H�i��Ε��A����Ȃǖ��炩�ɖT���̂��̂���v�i�s�g�����̏ё��t�A�W���v�����A2004�N4��15���A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j�Ƃ������ƂɂȂ�B����������ƒ��N�����̔��p�i�́A�W�����Ŋς���̂ł͂Ȃ��A�R�⋞�s�E�ޗǂ̍������̓X��Ŗڂɂ�����̂������̂�������Ȃ��i�������Ƃ͊G��ɂ��Ă������āA�g���͂ق�Ƃ��Ɉ������i�͉�L�ōw�����Ă���A���̂��Ƃ͍�i�̕]���ɂ��������Ă��悤�j�B
�g�����͑����m�푈�i1941�`1945�j�̖����A�鍑���R���n�d���Ƃ��Ė��F�E�V�����璩�N�E�ϏB���ɓn�������A�����͐V���̂��钩�N�����̐���[�����90�L�����[�g���̓��{�C�E���V�i�C�E���C�̊ԂɈʒu����B���Ȃ݂ɖ{�W�́A�g�����k���M�l�N���Ō��y�����B��̊؍����p�W�̓W����ł���B
�i�i��S���F�����r�Y����j
�@�ѓ�����͂������ł��傤���B
�@������ƁA�����������킷��܂������A�ŏ��ɗ����܂����̂́A�������F���킩�肾�Ǝv���܂�����ǂ��A�y������́q�m���r�̘N�ǂł��i�q�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��r�Q�Ɓj�B����͏��a49�N�ɂm�g�j�ŁA�q���|���W�r�ł��傤���A����Łs�g�����̐��E�t�Ƃ����̂��������ꂽ�̂ŁA�g������͖{���A���̘N�ǂƂ������Ƃ��܂������F�߂Ȃ����������Ȃ�ł�����ǂ��A����Ɋւ��Ă͂n�j�����Ƃ������킭���̂��̂ł��B���ꂩ��A������\���킷��܂������A���r�[�ɋg������̐����e�A����ыg���������̐��e���O�Y����A�ЎR������A���ꂩ�璆���ĔV����̍�i�Ȃǂ��W�����Ă���܂��̂ŁA���Ƃł܂��������������B�k���ꂼ��A�����̑����ɍ̗p������i�\�\���W�s���[���h���b�v�t�̃f�b�T���A�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�̉��M��A�]�`�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�̃I�u�W�F�\�\���������B�l
��
�q�킽���̋g�����r�y����2�z�\�\�ѓ��k�ꂳ��̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j
�i�ѓ��k�ꂳ��A�o�d�j �k����F�X���q���Ȃ����n�ɍs�����̂��l
�@�ؔn���Ƃ����̂�m��܂���ŁA���Ȃ�̏����낤�Ǝv������ł����ǁA�z���ȏ�c�c�A�ڂ��͑z���͂��n���Ȃ����ŁA�ӂ������Ȃ��悤�ȏ��ŁA�Â��Ă��Ȃu�I�y�����v�Ƃ͂���Ȃ��Ă��A���܂ŗ�����u�������ꂪ�c�c�v�Ǝv���āA���ɓ�����������Ƌ����āB�ł��ʔ��������Ǝv���Ă���܂��B���̂Ƃ���́A���낢��̒�������Ȃ������̂ł�����A���̉�͑S�R�A�ق�Ƃ�4�A5�N�ԏo�Ă���܂���ŁB�����͂������猩�āA�Ђ��傤�ɂ݂Ȃ���̊炪�悭�����܂��āA���������悤�ȋC�����܂��B
�@�g������ɂ��Ă͘b���������Ƃ��R�قǂ���悤�ł��āA�������A�l�ԂƂ����͍̂D���Ȑl�ɂ��Ă͈ӊO�ɘb�����Ƃ��Ȃ��B�����Ȑl�ɂ��Ắi���A�j�A�v���o���B�Q�悤�Ǝv���Ă͎v���o���āB����͂ڂ��������Ⴀ��܂���ˁB���̂������m�荇��������O�V����Ƃ�����Ƃ́A�����Ƃ��������Ƃ����̂ŁA�u�����������v�ƌ�������A�u����A�{�������v�ƌ����܂��āB���̍�Ƃ͂��܂��܂ڂ����匙���������̂ŁA������������߂�ꂽ�B���삳��͖ʔ����l���Ȃ��Ǝv���āA��ӂ�������ɂ���������ł�����ǂ��B�g������ɂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ������ς�����悤�ŁA����ς�D���Ȑl���Ă����̂͂ق�Ƃ��ɑz���o�������ł��ˁB��ʏ�ʂɁA���ɂ����ł��B�Ƃ������ƂŁB
�s�v�c�Ȃ��̂ŁA���w�Z����A�D�����������̎q�̊���Ȃ��Ȃ��z���o���Ȃ��B���O�͂����Ɖ����Ă��܂����ǁA�炪�ǂ����Ă��z���o���Ȃ��āB�ڂ��͔��Q���ꂽ���̐l�̊炪�D���ŁA���w�Z5�A6�N�̂��납��i���A���߂��j�B�ł��A�D���������������̏��̎q�̊炪�ǂ����Ă��z���o���Ȃ��B
�@�g��������ق�Ƃɂ������b�����������Ƃ������ł�����ǂ��A�������l�����̂́A�g������Ƃ����l�͔�s�@�ɏ���ĂȂ���Ȃ����Ǝv����ł��ˁB��s�@�ɏ��Ȃ��l�Ƃ����̂́A�y���F�����������s�@�ɏ���Ă��Ȃ��āA�k�C���֍s���Ƃ��ɁA�����牽�N�O�ł������A��s�@�ɏ��߂ď��܂��āA�����ւ������B�ڂ��̏��ɁA�k�C���̑傫�ȊG�t��2�����ɔ�s�@�ɏ�����Ƃ������Ƃ������āA���炢�܂�������ǂ��B�y���F�Ƃ��g������́A���Ԃ������Ȑl���ƁB
�@�ڂ��̒m���Ă���l�ł́A�ʐ^�Ƃ̓ޗnj��ꍂ�Ƃ����l�����܂����A���̐l�́\�\�ǂ��������͂���܂�D������Ȃ����ǂ��\�\���x1�����[�g���̏���������D�����ƌ����Ă��āA�n��ł��ǂ��ł��Ȃ��s�v�c�ȏ��ɂ����Ƃ���Ƃ����o��������D���ȂA�ƌ����Ă���B���ꂩ���Ƃ̎�ѕ����́A����͒n�����Ђ��傤�Ɏ�������ł��ˁB���̐l�́A���N�O�ł������A�t�����X�֗��w������ł�����ǂ��A���̂Ƃ��Ȃɂ�����̂��Ɛu������A���A�Œn���ɂ�������Ă����ƁB�t�����X�̓��A���A�������A�ɐ���܂����Ƃ����̂ł��B���̓��A�ɐ����Ă���Ƃǂ������������Ɛu���܂��ƁA�ǂ��炪�V���ǂ��炪�n���킩��Ȃ��Ȃ�B�܂�ŋt�������Ă���悤�ȋC������ƌ����B��ѕ����́A�Ђ��傤�ɒn������������ł��ˁB
�@�܁A�����Ȃ�ƁA�g������Ƃ����l�͊X���D���Ȑl�ŁA�X���������B������A���������̂悤�ȉ����̊X�������������B���̏Z��ł�����n�Ƃ��A�ĐΔԖ�Z��ł����ʂƂ��A�����������͂���܂莗����Ȃ��B�ق�Ƃ��ɁA�X���q�Ƃ����C������B���̊X���q���A�S���Ȃ邵�炭�O�ɍ��n�ɍs�����Ƃ�����ŁA���ꂪ�ڂ��͂��܂��ɓ�ŁB���̐l�ƍ��n�Ƃ����̂͂ق�ƂɎ�����Ȃ��i���A�݁j�B�܂��A���s�Ȃ狖���邯�ǁA���n�Ƃ����̂́A�Ȃ��A�Ƃ�������������B�ق�ƂɁB�u���Ԃ�A�����ł͂Ȃ����v�ƋC���t���ꂽ���������܂�����A���ЂƂ������Ă������������ƁA���������ӂ��Ɏv���܂��B����ł́A�ǂ����B
�i���A����j
�k�t�L�l
���̖{�ɂ��ƁA�e�[�v�N�����i�^�������k�b���ɋN�������Ɓj�ɂ́A�@�f�N�����A�A�P�o���A�B�����Ƃ����O�̐����������āA���̒k�b�Ɓi����ɕt������A�l�b�g�ɃA�b�v�����肷��j���͂̊����́A�@���A���B�̏��ňڍs����B���́u�e�[�v�N�����v�̍�Ƃ��Ȃ��Ȃ�����B�����t�o�t�ň�����̕ҏW�����Ă�������A�L���̑唼�͒k�b�͂ɂ������̂ŁA���e���˗����Ď��M���Ă��炤���Ƃ͂قƂ�ǂȂ������i�^�l�C��Ƃɂo�q�̕��͂��˗����悤�Ƃ��āA400���l1���̌��e����10���~�łȂ��Ə����Ȃ��ƌ���ꂽ�������������A���̍�Ƃ��r�[���̂s�u�R�}�[�V�����ɏo�Ă���̂��������͂����ɂ��̂��Ƃ�z���o�����j�B�b�҂������Ă���̂��킩��悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ�����A�����������̐l�����M�������̂悤�ȕ��͂ɂ��邱�Ƃ��������i���̏ꍇ�A�u�i�k�j�v�Ə����̂��{�Ȃ̂��낤���j�B
�s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r�́A�b�҂������Ă���悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��邪�A���̐����͇A�P�o���ƇB�����̒��Ԃ��炢���B�u�����v�Ƃ��u�����v�Ƃ��A�����܂������⌾����ǂ݂́A�����I�ɒ����B�y����1�z�\�\�������Y����̘b�͂ƂĂ������₷���i���O�ɏ[���������ꂽ�̂��낤�j�A�e�[�v�N�������X���[�Y�ɂł����B����̔ѓ��k�ꂳ��̘b�́A�܂Ƃ߂�̂ɓ�a�����B�v���̂ЂƂ́A�ѓ�����̘b���Ԃ�ɂ���B��������̘b���������Ƃ���A�ѓ�����̘b�͍s���Ƃ����������ŁA�����Ă���Ԃ�ɂ͂������A�����ɋN�����ƂȂ�ƁA�i�b�ɔ����������O�̏������������肵�āj�ׂ����j���A���X���E���Ȃ��B���������킯�ŁA��O�i���́u���w�Z����A�D�����������̎q�̊���Ȃ��Ȃ��z���o���Ȃ��B�v�ȉ��A���Ȃ�Ҏ҂̂����炪����ćB�����ɋ߂��d�オ��ɂ��Ă���B�v���̂����ЂƂ́A�ѓ����ؔn���ɓ��������̂��o�d���钼�O���������ƂŁA������b���Ԃ�ɉe�����Ă��悤�B
�w�i�̐����͂��ꂭ�炢�ɂ��āA�y���F�̔�s�@�̌���⑫����B�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�́q17�@���ΘH�ΔȂ���̊G�t���r�́A�y�����g���Ɉ��Ă����Ȃ̈��p�ł���B������870���قǂ����āA�s�a�߂镑�P�t�ɑ�\�����y�������M�����U���Ƃ͈قȂ�iWord�ɓǂ݂���ł��Ȃ�̖����Ȃ��j�A�������Ă킩��₷���B�Ō�̒i���������B���Ȃ̖����ɂ́u���Z��E�Z�E��Z�@���ΘH�ΔȂɂā^�y���F�v�Ƃ���B
�@������֎Q��܂��̂ɏ��߂Ĕ�s�@�ɏ��܂������A���������ł����ɋ����͏������Ȃ�܂����B���A���̌�������s��A��܂����玄�̎��ӂɂ��A�����邳���������n�܂�̂ł����A�������������Ă���Ə\���ɔ[���̂������̂�����܂��B���A���X�g������Ɍ䋳���肤���̂������Ǝv���܂����A�ǂ�����낵�����肢�\�������܂��B���Аّ�ɂ��V�тɂ��炵�ĉ������B������ɂ�낵���B�˂��ɂ��B�i�����A�O��y�[�W�j
�g�����̊G�t���Ɣѓ��Ɉ��Ă��Ƃ����G�t��������ȂɈ�������ʂ��Ƃ͍l���ɂ������A���̕��ʂ���͔ѓ��̒k�b�Ƃ͂����ԈقȂ�����ۂ���B�����Ƃ��ѓ��́A�g�����q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u13�@�G�͔������u���[�E���ʂ�v�Łu���e�搶�������ƁA�֎q�ɍ���������ƁA���f�����ѕz�ŁA軀���B�v���Ԃ�ł�����鎄�ɂ́A�V�����ꂽ�搶�̊炪�܂�ŁA���k����̂悤�Ɍ������B������߂��Ȃ���A�u���̂���͏��ւ����炷�v�ƁA�B�ꌾ�Ԃ₩�ꂽ�B�Ԃ��Ȃ��A�ӂ邦�������̂ŁA�Q���A��ꂽ�B���ꂪ�A�킪���l�Ƃ̕ʂ�ƂȂ��Ă��܂����̂��B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l���y�[�W�j�Ə������̂ɑ��āA���e�́u���̂���͏��ւ����炷�v�Ȃǂƌ���Ȃ������A�Ƃǂ����ŏ����Ă����i���o�T�����ł��Ȃ��j�B�ނ���l�Ƃ��������ɋ����킹���킯�����\�\�g���z�q�҂́q�N���r�ɂ́A1981�N11��9���u�������p�ق́q���e���O�Y�̊G��r�W�֍s�����e����v�Ȃɏ�����ď\���l�Ő��e�Ƃ�K�₵�A�×{���̐��e���O�Y�ƌܕ��قlj�v�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A���Z�l�y�[�W�j�Ƃ���\�\�A���傹��l�̎Ƃ߂����͂��ꂼ�ꂾ�A�Ƃ������ƂȂ̂��낤���B����Ƃ��P�ɁA���܂��܋g���̐Ȃ̕����ѓ��̐Ȃ������e�ɋ߂������A�Ƃ��������̂��ƂȂ̂��낤���B
2014�N���q�g�������ɂ�����G��r�������A��������x�����ׂ��A2018�N�ɂ��q�q�g�������y���`��Ɩ��E��i�������r�̎��݁r���������B�q�����r�̂悤�ȍH��́A�Z���ԂŊ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�����܂łɂ́A�����I�ȉ��M�E�C����Ƃ�K�v�Ƃ���B�����A����قǒ������������u����Ă������R�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��B���̂��Ƃɂ��ď������B�g�������ς��W����̐��́A�c��Ȃ��̂ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��i���P�j�B���������́A����k���Ă��̓W������ς邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���p�̈��D�ƂƂ��Ă͋g���̑����ɂ��y�Ȃ������A�W����̐}�^�Ƃ����⏕�I������p���Ă����Ǒ̌�����̂́A�����܂ł����P�̍�ł���i�����ɂ́A�f����i���f��ق̃X�N���[���Ŋς�̂ƁA�s�u��o�b�̃��j�^�[�Ŋς�ȏ�́A�傫�Ȋu���肪����j�B�W����ɐ}�^�Ŕ���̂͂悢�Ƃ��āA���̋�̓I�ȃA�v���[�`���ǂ����ׂ����B�܂��́A�q�k�g�������M�l�N���r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��O�Z�`��O���y�[�W�j�\�\�g�������M�����ł��ڂ����N���ŁA�����Ɂu�i���Ҏ��M�E���a�\���N�\���j�v�Ƃ���\�\�ɓo�ꂷ��W�����n�߂�̂����a���낤�B���̔N���́A�܂��Ɏ��W�s��ʁt�̊��s�i1983�N10��20���j�ƕ��߂����킹�āA�����W�̕ҏW���i�����j���������ꂽ�����ɏ����ꂽ�Ǝv�����i���Q�j�B���Ȃ݂ɁA�g���̏��ւ��B�����ʐ^�ɂ��̎�̐}�^�͌����Ȃ����i�}�^�͑唻�������A�����Ă����I�̍ʼn��i�Ɏ��������j�A���N�������M����ɓ������āA�������������⎩�g�̓��L�A�����\�̐��z���Q�Ƃ������Ƃ��낤�B�܂�A�L���ƋL�^�Ɉ˂�Ȃ���B
�ȉ��ɁA�q�k�g�������M�l�N���r�̔N���ƔN������̂܂܌��o���ɗ��ĂāA�W����Ƃ���ɏ�������̂Ɋւ���L�q��E����i�e���̖`���Ɂy#00�z�̂悤�ɒʂ��ԍ���U��A���������āA�O���E�����E�㗪�������k�c�c�l�͋L�ڂ��Ȃ��j�B����ɑ����āA�}�^�̊ȗ������i�k�Ҏҁl�A�W��A���s�ҁA���s�N�����j�ƁA�W����̉��E������L�����i�o���Ƃ��A�}�^�̋L�ڂ��Ȃ�ׂ������ɍČ����邱�Ƃ�S�|���A����́y�@�z���ɗj���������j�B�Ȃ��A�g���̋L�ڂƋ�ʂ��邽�߂ɁA�������珑������������������E����́A����ŋ��ݐԎ��ŕ\�������B���ꂪ�A�u�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����v���č\�������A�{�e�ȍ~�ŏڏq����\��̕��͂́q�ڎ��r�ƂȂ�B
�@���a��\�l�N�@���l��N �O�\��
�y#01�z������≮�ŁA�~�����O�Y�E����]���Y�̑�\��W���ς�B
�������V���ЁE���≮�s�~�����O�Y�E����\���Y���I�W�o�i�ژ^�t�i�k���≮�l�Ac1949�k�N5��11���l�j�^��ꁁ������≮�A�����1949�N5��11���y���z�`5��30���y���z��
�@���a�O�\�ܔN�@���Z�Z�N �l�\���
�y#02�z�t�k4��17���i���j�l�A�������ŁA�u���������S�I�v���A�ȂƊς�B
���s���������S�I�W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1960�k�N4��5���l�j�^��ꁁ���{���������A�����1960�N4��5���y�z�`17���y���z��
�@���a�l�\��N�@���Z���N �l�\����
�y#03�z�������ŁA�͈䊰���Y���W���ς�B
�����{���|�فi�ҁj�s�͈䊰���Y���W�t�i�匴���p�فAc1967�k�N5��2���l�j�^�����W�F��ꁁ���{��������8�K�A������k1967�N�l5��2���y�z�`7���y���z��
�@���a�l�\�O�N�@���Z���N �l�\���
�y#04�z�t�A���E�̃V�~�Y��L�̋��q�����W�ŁA�E�c�ʜ\�Ɖ�A�����N��Ə��߂ĉ�B�k�{�W�ł͐}�^�����삳��Ȃ������Ƃ݂���B�ڍׂ͖{�����Q�Ƃ̂��Ɓl
���s���q�����W�t�k�}�^�̓i�V�l�^��ꁁ�V�~�Y��L�i�����E���E�j�A�����1973�N5��10���y�z�`23���y���z��
�y#05�z�H�A�|���̓��������ߑ���p�قŃw�����[�E���A�W���ς�B�k���������ߑ���p�قł́s�w�����[�E���[�A�W�t��1968�N�ł͂Ȃ��A��1969�N�ɊJ�Ál
���w�����[�E���[�A�W�J�^���O�ψ���i�ҁj�s�w�����[�E���[�A�W�t�i�����V���ЁAc1969�k�N8��27���l�j�^��ꁁ���������ߑ���p�فA�����1969�N8��27���i���j�`10��12���i���j��
�@���a�l�\�ܔN�@��㎵�Z�N �\���
�y#06�z��{�ɓ�Y�W�A
�������V�������{�Њ�敔�i�ҁj�s��{�ɓ�Y�Ǔ��W�t�i�����V�������{�Њ�敔�Ac1970�k�N3��20���l�j�^�����W�F��ꁁ�����E���{�� ���}�A�����1970�N3��20���y���z�`4��1���y���z��
�y#07�z�x�{���g�W�ȂǁA�ȂƊς�B
�����������ߑ���p�فi�ҁj�s�x�{���g���W�t�i���s�����ߑ���p�ٕx�{���g���W�ψ���Ac1970�k�N4��1���l�j�^��ꁁ���������ߑ���p�فA�����1970�N4��1���y���z�`5��10���y���z��
�@���a�l�\�Z�N�@��㎵��N �\���
�y#08�z���c�}�S�ݓX�ŁA�]���J���A�����b��A�ɓ���t��ْ[�̉�Ƃ̊G���ςĊ�������B
�����{�o�ϐV���Е������ƕ��i�ҁj�s�ߐ��ْ[�̌|�p �J�����b��𒆐S�Ɂt�i���{�o�ϐV���Е������ƕ��Ac1971�k�N6��26���l�j�^��ꁁ�����V�h�E���c�}�S�ݓX�\��K�����Î���A�����1971�N6��26���y�y�z�`7��13���y�z��
�@���a�l�\���N�@��㎵��N �\�O��
�y#09�z�H�A���s���������قŁA�u���Ɣ[�o�v�S�����ς�B��ڈ���B
�����s���������فi�ҁj�s���ʓW���� ���Ɣ[�o�ƌ����̔��t�i���s���������فA1972�N10��7���j�^��ꁁ���s���������فA�����1972�N10��7���y�y�z�`11��5���y���z��
�@���a�l�\���N�@��㎵�O�N �\�l��
�y#10�z�ӏH�A���q�̋ߑ���p�قŁA�f�E�L���R�W���ς�B
���J�^���O�ҏW�ψ���i�ҁj�s�f�E�L���R�W�t�i�����V���ЁAc1973�k�N11��2���l�j�^���q�W�F��ꁁ�_�ސ쌧���ߑ���p�فA�����1973�N11��2���y���z�`12��16���y���z��
�y#11�z���l�������ŁA���]�v�����O�䎛�i���鎛�j�́u���s���v���ς�B
�����鎛���w���i�ҁj�s�`�@�L�O �������s �O�䎛��œ��ʊJ���t�i�k���{�o�ϐV���Ёl�Ac1973�k�N11��8���l�j�^��ꁁ���l���������K�k���ݟl����A�����1973�N11��8���i�j�`20���i�j��
�@���a�l�\��N�@��㎵�l�N �\�܍�
�y#12�z�V�t�A�������œS�֓W���ς�B
�������V�������{�Њ�敔�i�ҁj�s�v��\���N �x���S�֓W�}�^�t�i�����V�������{�Њ�敔�Ac1974�k�N1��10���l�j�^��ꁁ���{���������A�����1974�N1��10���y�z�`1��15���y�E�j�z��
�@���a�\�N�@��㎵�ܔN �\�Z��
�y#13�z���t�A�������������قŁA�و��u�l���}�v�Ɠ`��P�u���R�E���v�A�^�ցu��尓S���}�v���ςċ��Q����B
�����ʓW�ρs���㓹�ߐl����t�i�������������فA1975�N1��29���j�^��ꁁ�������������فA�����1975�N1��31���y���z�`3��2���y���z��
�@���a�\�l�N�@��㎵��N �Z�\��
�y#14�z�ӏt�A���������ߑ���p�ق̊ݓc�����W���ς�B
�����������ߑ���p�فi�ҁj�s�v��50�N �ݓc�����W�t�i�����V���ЁAc1979�k�N4��6���l�j�^������ꁁ���������ߑ���p�فA�����1979�N4��6���i���j�`5��27���i���j��
�@���a�\�ܔN�@��㔪�Z�N �Z�\���
�y#15�z�O�z�{�X�ŁA�NJ��W���ς�B�V��啗�B�k�W����̃^�C�g���́s�v��S�\�N �NJ��W�t�l
���a�r�m�V�����p�فE�����V���Ёi�ҁj�s�NJ��W�}�^�t�i�����V���ЁAc1980�k�N7��29���l�j�^������ꁁ�����O�z���p�فA�����1980�N7��29���i�j�`8��10���i���j��
�y#16�z�H�A���q�@�q�ϓW�Ȃǂ��ςāA�@���ߕv�ȁA�ēc���q�Ƌ���։��B
���s���q�@�W�ژ^�t�i�ޗǍ��������فAc1980�k�N10��26���l�j�^��ꁁ�ޗǍ��������فA�����1980�N10��26���y���z�`11��9���y���z��
�@���a�\�Z�N�@��㔪��N �Z�\���
�y#17�z���~�A�������������قŁA�Ӑ^�a�㑜��q�ς���A���̐Î��B
���s���ʓW�� �����Ӑ^�a�㑜�t�i�������������فAc1981�k�N1��15���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N1��15���y�E�j�z�`2��1���y���z��
�y#18�z�ɐ��O�V�قŁA�u�s�J�\�鑠�̃s�J�\�v�W���ς�B
�����K�G���E�_�g�h�O�i�ďC�j�s�s�J�\�鑠�̃s�J�\�W ���a100�N�L�O�t�i�s�J�\�W���s�ψ���Ac1981�k�N3��5���l�j�^�����W�F��ꁁ�ɐ��O���p�فA�����1981�N3��5���y���z�`4��7���y�z��
�y#19�z�z�t�A��썑�����m���p�قŁA�u�A���O���W�v�i�u��v�ɖ�������j�B
���������m���p�فi�ďC�j�s�A���O���W�t�i���{��������Ac1981�k�N4��28���l�j�^�����W�F��ꁁ�������m���p�فA�����1981�N4��28���y�z�`6��14���y���z��
�y#20�z�������������ق։��A�u���R���������W�v�A���̍��̏o�y�i�Ɋ�������B
���������������فE���{���������𗬋���E���{�o�ϐV���Ёi�ҁj�s�����퍑����̗Y ���R���������W�t�i���{�o�ϐV���ЁAc1981�k�N3��17���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1981�N3��17���y�z�`5��5���y�E�j�z��
�y#21�z�ӏH�A������قŁA�u���e���O�Y�̊G��v�W�֍Ȃƍs���A�a��F��A�������Y�A�O�D�L��Y�A�߉ϑ��Y�ƒk����B
���s���e���O�Y�̊G��t�i�������p�فAc1981�k�N11��9���l�j�k���C�A�E�g�F�g�����l�^��ꁁ�������p�فA�����1981�N11��9���y���z�`30���y���z��
�y#22�z���������ߑ���p�ق́u�����N�W�v���ς�B
�����������ߑ���p�فi�ҁj�s�����N�W�t�i�����V���Ac1981�k�N10��9���l�j�^��ꁁ���������ߑ���p�فA�����1981�N10��9���y���z�`11��23���y���E�j�z��
�@���a�\���N�@��㔪��N �Z�\�O��
�y#23�z�N���A���{���̃c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����ŁA�n�ӌ��l�̎ʐ^�W�u�t�|�s�s�v���ς�B������b�q�E�v���q�A���o����Ɖ�B
���n�ӌ��l�ʐ^�W�s�t�|�s�s�t�k�}�^�͖����i���邢�͖����s���j�l�^��ꁁ�c�@�C�g�E�t�H�g�E�T�����A�����1982�N1��18���y���z�`30���y�y�z��
�y#24�z���c�}�S�ݓX�Łu���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�v���ς�B
�������V���i�ҁj�s���h���t�E�n�E�Y�i�[�W�t�i�����V���Ac1982�k�N4��9���l�j�^�����W�F��ꁁ���c�}�O�����h�M�������[�A�����1982�N4��9���y���z�`21���y���z��
�y#25�z�������������قŃN���[�u�����h�A�v�E�q�E�l���\�������p�ُ����́u�����̊G��v�W���ςĈ��|�����B
�����ʓW�s�č������p�ُ��� �����̊G��t�i�������������فA1982�N10��4���j�^ ��ꁁ�������������فA�����1982�N10��5���y�z�`11��17���y���z��
�@���a�\���N�@��㔪�O�N �Z�\�l��
�y#26�z�����̔��R�L�O�قŁA�J�@�c��̕M�Ɠ`������u���L�v���ς�B
���s���a�\���E�\���N �H�G�E�~�G�W�ω�L�t�i���R�L�O�فAc1982�k�N10��1���l�j�^��ꁁ���R�L�O�فA��������a58�N�~�G�W�F1��8���y�y�z�`3��15���y�z��
�y#27�z�������������قŁA�{�X�g�����p�ُ����u���{�G�於�i�W�v���ς�B���q�V�S�∤�́u��Г��������v�ɋ��Q����B
���������������فE���s���������فi�ҁj�s�{�X�g�����p�ُ��� ���{�G�於�i�W�}�^�t�i���{�e���r�����ԁAc1983�k�N3��15���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1983�N3��15���y�z�`5��8���y���z��
�y#28�z���āA�������������قŁu�O�@��t�Ɩ������p�W�v���ς�B���哶�q�����i���������j�̘Z軀�ɖ�������B
�����s���������فE�������������فE�^���@�e�h����{�R��E�����V���Ёi�ҁj�s�O�@��t�Ɩ������p�t�i�����V���ЁA1983�N3���k19���l�j�^��ꁁ�������������فA�����1983�N5��24���i�j�`7��10���i���j��
�y#29�z�H�A�������������ق́u�؍��Ñ㕶���W�v���ς�B
���������������فE�����V���Ёi�ҁj�s�؍��Ñ㕶���W�\�\�V����N�̔��t�Ɓs�V���C������g�������t��2�����i�����V���ЁAc1983�k�N8��2���l�j�^�����W�F��ꁁ�������������فA�����1983�N8��2���y�z�`9��11���y���z��
�����Ő}�^�_���B�S�ݓX����p�فE�����قŊJ�����A���ꗿ�����قǂ̊��W�̑����́A�}�^�i�W���������ɉ��Ŕ̔������J�^���O�j���쐬����B�f�[�^�ƂƂ��ɁA�W����i���J���[��m�N���̐}�łŌf�������A�W����J�Â̈Ӑ}��Ӌ`���q�ׁA��҂��i�A���̔w�i�ƂȂ鎞��ɂ��ĉ������\�\�Ƃ����̂���ȓ��e�ł����i���R�j�B�ʏ�̉�W�ƈقȂ�̂́A�f�ڍ�i�̌������ꓰ�ɏW�߂Ċϗ��ɋ����邱�ƂŁA�܂��Ɂu�W����v�ł����i���S�j�B��L�i���W�̈����������Ă��A�}�^�Ƃ����قǑ啔�Ŗԗ��I�Ȃ��̂͏��Ȃ��j�ȂǂŌ�������肷��̂łȂ�������A��i�ɐG�ꂽ�L���͐}�^���W���ς邱�Ƃ��S��B���邢�́A��i���ς��Ƃ����L�����S��B�Ƃ���ŁA���̐}�^�̔��ɂ͂����Ă��W����̉��i�����̉��������K�͂Ȋ��̏ꍇ�A�����W�E�����W�E�~�~�W�ȂǂƂ��邪�A�����ݏZ�̋g���������ȊO�Ŋς��m���Ȃ�������A�������Ƃ��Ĉ����A�����̋L�ڂ͊��������j�A�����Ă��̉�����L����Ă���B����͂���ł����ւ������Ȃ̂����A����܂������̏ꍇ�A�}�^�̉��t�ɔ��s�N�������L����Ă��Ȃ��i�Ђǂ��̂ɂȂ�ƁA���s�ҁ\�\��Îҁi�̂����̂ǂꂩ�j�������̂����\�\�̋L�ڂ��Ȃ����肩�A���t���̂��̂��Ȃ����̂�������B�����̂����A��������}���ق̏������Q�l�ɂ��Ȃ����������̂�����j�B���s���������Ă���ꍇ�͓W����̊J�Ï����ł��邱�Ƃ��������A���L����Ă��Ȃ����̂́A�J�Ï����̔N���̂����i���Ƃ��u�����2021�N5��31���`2022�N4��15���v�Ȃ�uc2021�v�j�B���̂����ŁA�k�@�l���ɊJ�Ï������L�����B
����ȍ~�A�Ȃ�ׂ������N�̓W������܂Ƃ߂āA15��قǂ̘A�ڂł���炷�ׂĂ��Љ�����ł���B�\��ǂ���ɂ����������A���ׂĂ̐}�^���苖�ɑ����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���s���i���ƂтƂсj�̌f�ڂɂȂ邩������Ȃ����Ƃ����炩���߂��f�肵�Ă����B
��
��A�E�Z����_���A�G��̌����Ɛ}�ł̊W��������ѓN�v�i��Ƃɂ��ĕ��M�ƁE�����Ɓj�̕��͂́A�W����ƓW����J�^���O�̊W���l���邤���ł������[���B
�@�����̌��͂܂������B�Ƃ������|���鑕��m�����Ă��n�ɂ͐F�̍Z���Ƃ������̂�����A���ꂪ�܂��ЂƂ�����Ȃ̂ł���B�F�ʊ��o�ɂ͂͂�����Ƃ����l��������B���̍��������ł����߂邽�߂ɐF���{�����݂���B����F���w�肵�A���̐F�̃`�b�v��Y����A�C���L�̍����䗦�ɂ���ĒN�ł��ς��������F���Č��ł���A�͂��Ȃ̂����A�ǂ��������ł͂Ȃ��炵���B���ɋ��Ԉ�Z�Z���Ȃǂ̌��F�ł����Ă��f�U�C�i�[�A�ҏW�ҁA����ҁA�����ēǎҁA���ꂼ�ꂪ���ꂼ��̐F���Ŏ���Ċ��S�Ɉ�v���邱�Ƃ͂Ȃ��B�F���ꎩ�̂̑��ɁA������鎆����Ɩ����Ⴆ�܂������ʂ̐F�Ɍ����Ă��܂��Ƃ�����ւ�����B�܂��G��Ȃǂ�����ꍇ�ɂ́A��قǍ����Ȕ��p����ł��Ȃ�������A�����͎����A�}�ł͐}�łƊ�����čl�����������ł��낤�B������F�Z���d�˂Ă����ۂɂ͈������邷�ׂĂ̍ו��ɂ킽���Ă��̎����ێ����邱�Ƃ͎���ł���B������������ꂽ�}�ł̕�����������������͌����Ē������Ȃ��̂�����B�i�q���o�C�P�i�C�A���N���������V�r�A�����P���i�Ғ��j�s����� ��A�ǖ{�k�����ܕ��Ɂl�t�A�}�����[�A2013�N6��10���A�ꎵ�Z�y�[�W�j
���l�̂��Ƃ́A�E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ���}���ɂ��Ă�������B�������́q�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����r�Ɍf�ڂ���}�^�̕\���ʐ^�́A�s�q�g�����r�́u�{�v�t�Ɍf�ڂ����g����������i�Ɠ������A�莝���̃f�W�^���J�����ŎB�e�������̂��u�f�ށv�Ƃ���i�܂�Ƀv�����^���p�̃t���b�g�x�b�h�X�L���i�Ŏ�肱�ނ��Ƃ�����j�B��������������������ł��邽�߁A�B�e�̏ꍇ�͂��قǂł͂Ȃ����A�X�L���������ꍇ�͉𑜓x�������ƃ������������Ă��܂��i������̖ԓ_�m���݂Ă�n�̂����ł���j�A���������ו��܂Ō����悤�Ƃ��Ă��t���ʂȂ��Ƃ��܂܂���B�������{�͂قƂ�Nj�`�ŁA���̓V�n���E�����s�łȂ��ƌ��Ă��ċC�����������B���̂��߁A�����́u�f�ށv�𐅕������ɒu�������̂����A���̋�`����������Əo�Ă��Ȃ��Ɛ��x���ۂĂȂ��B���ɍT����̂́A���́u�F�v���B���͖{�i�I�ȏƖ��Ȃǂ����ɓܓV���̎��R���ŎB�e���邩��A�F�͂ǂ����Ă������݂����ɂȂ�B������o�b��ŕ����̂����A�����i�ł��������j�Ƃo�b��X�}�z�̉�ʂŌ��邻�̉摜�i�����Ă��E�F�u�y�[�W�p�̒�𑜓x�Łj�͑�Ⴂ�ł���B���������A�q�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����r�S�̂�ʂ��ĂȂ�ׂ��������q�ɂȂ�悤�S�|���邪�A�摜�̐��x�ɂ��Ă͂��̒��x�̂��̂��Ƃ������������������B
��
���p�ق́A�����Ă��֘A�����i�}����J�^���O�Ȃǁj����������}�����݂��Ă���B����قǑ����̐}������K�ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A���������S�����̂́A���c�E�k�̊ی����̓��������ߑ���p�ق̃A�[�g���C�u�����ł���B�����ŁA�r�c�����v�̏����̓W����̃J�^���O�i��������}���قɂ��Ȃ��j���{�������B���Ȃ킿�q�r�c�����v���ʼn�W�r�̐}�^�ł���B�g�����ς������Ȃ̂Łi����Ɉ˂��āA�r�c�ɕ����鎍�q�Ă���H�܂Łr�\�\���o�莫�u�r�@�c�@�� �� �v�^���ʼn�W�ژ^���v�k�^�͉��s�ӏ��l�\�\���������j�A��f�}�^�̏����Ōf����B
�y#0702-1967�z���сq�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�j
���s�x�l�`�A�E�r�G���i�[�� �O�����E�v����܋L�O�@�r�c�����v���ʼn�W�\�\1956-1966 M. IKEDA�t�i[�����S�ݓX]�Ac1967�k�N1��13���l�j�^��ꁁ�V�h �����S�ݓX 7�K��Ï�A�����1967�N1��13���y���z�`25���y���z��
���͂����q�u���ƕs�M�̑o�e�v�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i2�j�\�\�q�Ă���H�܂Łr�r���u�X �q�ҕ����鏗�r�Ɓs��ʁt�^�q�Ă���H�܂Łr�v�Ɂu�s�x�l�`�A�E�r�G���i�[�� �O�����E�v����܋L�O�@�r�c�����v���ʼn�W�t�i�k���L�Ȃ��l�j�͈��Z���N�ꌎ�A�����E�V�h�̋����S�ݓX�ŊJ���ꂽ�q�r�c�����v���ʼn�W�r�i��ÁE���p�o�ŎЁj�̃J�^���O�ŁA�d�l�͂قڐ����`�̂`�T���ό^�E�y�[�W�E���Ԃ��A��y�[�W�Ɉ�_�̃��m�N���}�Ōv��ܓ_�����߂�i�\���̐}�ł́qSomething�i�T�j�r�j�B�v�Ə������B�{�e�����M����ɂ������āA���}�^���Ï��œ��肵���̂ŁA�\���ƍ�i�̐}�ł��f����B����ȍ~�A�{���Ɍf�ڂ���}�ł��A�����ނ˂��������`�ɂȂ邾�낤�B���̈Ӗ��ŁA����͌��{�m�T���v���n�ł���B
![�y�Q�l�z�s�x�l�`�A�E�r�G���i�[�� �O�����E�v����܋L�O�@�r�c�����v���ʼn�W�\�\1956-1966 M. IKEDA�t�i[�����S�ݓX]�Ac1967�k�N1��13���l�j�̕\���k�r�c�̍�i�́qSomething 1966�r�l](image/no_0702-1967_1_1.jpg) �@
�@
�y�Q�l�z�s�x�l�`�A�E�r�G���i�[�� �O�����E�v����܋L�O�@�r�c�����v���ʼn�W�\�\1956-1966 M. IKEDA�t�i[�����S�ݓX]�Ac1967�k�N1��13���l�j�̕\���k�r�c�̍�i�́qSomething 1966�r�l�i���j�Ɠ����́q�y���Ɏ����@1965�@40�~36�@���F�l�`�A�E�r�G���i�[���W�@�j���[���[�N�ߑ���p�ف@��P��N���R�E�r�G���i�[���W�r�i�E�j
�}�^�Ɍ�����j����Y�i1925�`2010�j�́u�r�c����v���n�����c�c�v�Ŏn�܂閳��̕��͂́u����ɂ��Ă��A�Ƃ�킯�A�����J�ł̐������A����̊��̐U�����A���Ƃ߂��܂����g�債�����Ƃ��낤�B�����ɂ͌��㕗���̒f�Ђ��Î�����C���[�W���A�ʎY���ꂽ�H�Ɛ��i�̂悤�ɂ���߂��Ȃ���A�����I�ȋ�Ԃ̐�ɂ��͂��������ł��Ă���B�N�[���ȃ��_���E�W���Y�̒ꂩ��A���ǂ남�ǂ낵���^���^���̂Ђт������肠�����Ă���B�v�i���}�^�A�k�Z�y�[�W�l�j�Ƃ�����߂́A�����������сq�Ă���H�܂Łr�i�F�E2�j�����߂����W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�̃^�C�g���|�G����]�����悤�ŁA�����I��̂���ɂ��ǂ�ł��I���˂Ă���B
��
���Y�̂��߂ɁA��L�̊e�W����i�q�k�g�������M�l�N���r�̋L�ڂł͂Ȃ��A�}�^�i���T�j�Ȃǂ̎�Îґ��̎����Œm�肦�����Ɉ˂�j���A���̑Ώۍ�i���y���{�z�y�k���{�ȊO�́l���m�z�y���m�z�̂ǂ��ɑ����邩�A����ӂ��Ĉꗗ�ɂ��Ă݂�B�}�^�̂Ȃ��A���邢�͊m�F�ł��Ȃ��W���������̂ŁA�ȉ��ɍ̂����̂͐}�^�̕W��ł͂Ȃ��A�W����̖��̂ł���B�Ȃ��s���q�����W�t�Ɓs�w�����[�E���[�A�W�t�́A�N��������Ė{���̉ӏ��Ɍf�����B���킹�Ă��́q�q�k�g�������M�l�N���r�̓W����r�V���[�Y�Ɍf�ڂ����L���ɂ̓����N���āA�ȗ��Ȗڎ������˂�B
�y���{�z
�y�k���{�ȊO�́l���m�z
�y���m�z
�k�ӎ��l
�{�e�̖{���⒐�����M����ɂ������Ĉ��p���������ȊO�ɂ��A�������s�W����J�^���O�ē��kP-Vine BOOks�l�t�i�u���[�X�E�C���^�[�A�N�V�����Y�A2010�j�⍂������s���p�ق̕��䗠�\�\������W��������ɂ́k�����ܐV���l�t�i�}�����[�A2015�j����L�v�ȏ����B�L���Ďӈӂ�\���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@������b�q�̓C���^�r���[�L���q���̎��݂�ۏ��Ă��ꂽ�g�����\�\�����o��������������r�i�s���{�E�t2021�N2���k�n����Z�Z�Z���L�O���卆�l�j�Łu�g������Ƃ͂��̌�������Ɛe��������܂������A���⏬���̘b�����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��āA�ǂ�ȓW������ŋߌ����Ƃ��A���\�Y�̎ŋ��̂��ƂƂ��A����Șb����ł����ˁB�g������͂��܂�{��ǂ܂Ȃ��l�ł������A�����Ȑl�ɓ��}����́w�c�a�L�y�x���g������Ȃ�C�ɓ���͂������Ă����߂��ēǂ�ŁA�r�̒��̓��킪���������Ȃ�Đ�₾���Č����Ă܂����ˁi�j�B����ƁA���p�D�������Ă��Ƃ𐏕M�ɏ����Ă���̂ɁA���̔N�ɂȂ�܂ŁA�{�b�V����m��Ȃ������Ƃ����̂��A�ǂ������Ă�����āi�j�B���b�q�͓��}�Òj�Ȃ�ēǂނ́H�@�ƁA�v���v���{���āi�j�B�g������͕ҏW�҂Ƃ��ĐX�仂����S���������Ƃ������āA����͋g��������X��������������A�g�����G�b�Z�C�ɏ������̂��ǂb�Ȃ�ł����A����Ƃ��A�g�������e�����炢�ɂ���ɂ�������X�仂��ÐV�����ɍ������ăS�~�ɏo����������ƌ�����ł��B����œ�l�ʼn��k�イ�̃S�~�W�Ϗ������K�ˉ���āA���ɏW�ϐ��˂��~�߂Č��e�������������Ȃ�ł��B�g������͕ҏW�҂����Ă����炢�����瑽���}�V�Ƃ͌����Ă��A��l�Ƃ������I�Ȕ\�͂�������Đl����Ȃ��ł�����A�悭�˂��~�߂܂�����ˁB�g������́A�悭�䖝���ċ߂Ă����Ȃ��Ǝv���܂��B�v�i�����A�l�l�y�[�W�j�ƌ���Ă���B�{�e�Ɋւ��邩����A���p����̂͘b�̑O�i�����ł����̂����A��i�̐X�仂̌��e���W�ϐ�Ō������Ƃ������́A����̑z���Ⴂ�ł͂Ȃ����낤���B�g���͐��z�q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�Łu�Ō�ɍs�����̂́A�W���Ԍɋ߂��̋��Ƃ����d��ꂾ�B�����̓����Ə�ɂ͐l�e�Ȃ��A���܂����Ƃ���̕�Ƃ������˂��B�S�̖���������Č��ւɓ���B�Ƌ�A���x������s�̂悤�ȉƁB����������ƁA�u�n�C�n�C�v�Ɖ����邪�A�N�������Ȃ��B���~�̂Ȃ������������ƁA�Ă̋㊯�����Ԏ������Ă���̂��B�仂���Ǝ��͂��̉Ă̈�����A�k�J�ɗ������̂�������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܁Z�y�[�W�B���o�F�s��t1988�N2�����j�Ə����Ă��邩�炾�B���z�͐X�仂̟f��A�Ǔ����̂悤�ɂ��ď����ꂽ���A���p�ӏ��̈ٗl�Ȃ܂łɗՏꊴ�ɏ[�����M�v�́A�g���������i���M��20�N�O�j�̓��L�̋L�q�܂������ʂ��ƍl������B
�i���Q�j�@�s��ʁt���s��4�N�O��1979�N�ɒ}�����[��ނ����g���́A1983�N�����A64�B�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j�����̎��`�q�f�ЁE���L���r�̖����ɕt���ꂽ�q�q�f�ЁE���L���r�ɂ��ār�Łu���`�I�Ȃ��̂��܂����������ł��Ȃ��B�܂��A�N���I�Ȃ��̂�����ώG���ɂ��ς����Ȃ��B���܂��܋������L�̒f�Ђ�����̂ŁA���������̎��̕��͋C��`����Ƃ�������o���A�Ԃ荇���Ă݂�B���L�������Ȃ������N�オ�����A�������̂ɂȂ��Ă���B����́A���ɂƂ��Đ��X�̑�Ȏ����������Ă��܂������A�����ɍH�삷�邱�Ƃ�������B�v�i�����A���܃y�[�W�j�Ə�����15�N�O�Ƃ͑傫���قȂ鋫�n�ɂ������B�f�㊧�̋g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�j�ɂ��A�������瑽���̎������̂��Ă���B�ނ��A�����҂������́q�g�����N���r�����l�ł���B
�i���R�j�@��r���w�E��r���������̍����f�q�̕Ғ��s�W����J�^���O�̖����݁t�i������w�o�ʼn�A2003�N6��11���j�̑�1�́q�W����J�^���O�Ƃ͉����r�ō����́A���{�̓W����J�^���O�̂قƂ�ǂ͌����ɂ͏��Ђł͂Ȃ��A���ɏ��X�ł͔����Ȃ��Ƃ����d�v�Ȏw�E�����Ă���A���̂悤�ɊT������i�������g�B���ԍ��͏ȗ������j�B
�@�킪���ł͒��쌠�@47���̋K��ŁC�W����J�^���O�́u�ϗ��҂ւ̓W����i�̉���E�Љ��ړI�Ƃ���q�����q�r�ł���v�Ƃ���Ă��āC�ӏ҈ȊO�̎҂ɂ͎s�̂ł��Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��D���̑���C��i�������̂Ƃ��������q�͈̔͂łȂ�C�����I�ɂ͒��앨�i���p��i���j�̕����쌠�҂̋����Ȃ��ł���i�܂蒘�쌠����Ə������j���߁C�ϗ��҂Ƃ��Ă͎荠�Ȓl�i�ōw���ł���킯�ł��D���Ăł͕��ʁC�W����J�^���O�͔��p�قƊW���邢�͒�g����o�ŎЂ���CISBN�i���ەW���}���ԍ��j�̕t�������ЂƂ��ďo�ł����̂ŁC���ɂ͓W����I���������Ȃ��ɁC�悤�₭�J�^���O�����ڌ������邱�Ƃ��������C�ɂ̂�����菑�X��ʂ��Ĕ����܂��D���݂ł́C�A�}�]���E�h�b�g�E�R���iamazon.com�j���n�߂Ƃ���C���^�[�l�b�g���X�őS�Č����ł����C�ނ��덑���̂��̂�葁����ɓ���邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă��܂��D�܂�ISBN���t���Ă��邽�߁C�����}���ق��w�}���قŁC��ʏ��Г��l�C���W�E�ۑ�����Ă��܂��D
�@����ɑ��ē��{�̃J�^���O�́CISBN�̕t����������Ƃ������ЂƂ��Ċ��s����邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��C����Ή��̏o���t�߂Ŕ������Ⳃ�L�[�z���_�[�Ɠ������u�L�O�O�b�Y�v�̈�Ƃ��Ă̒n�ʂɊÂĂ��܂����D������݂ł��C�W����̐��i�ɋ����Ắi�ƂĂ��u�����q�v�Ƃ͌����Ȃ��j���Ȑ}�ł���̂Ƃ��C�G�b�Z�C�Ȃǂ�t�����݂̂́u�ӏܗp�v�}�^�����삳���@��͏��Ȃ�����܂���D����������ŁC�Ƃ�킯1960�N��ȍ~�C���[���b�p�����k���ȃJ�^���O���M�@�ɑ���C��i�f�[�^�i�^�C�g���^����N�^�f�ނƐ��@�^�����^�����^�����^�����^��i���́j�����C�����C�Q�l�����C�������ʘ_���Ȃǂ��ԗ��I�Ɏ��^���ꂽ�u�w�p�I�v�J�^���O���C�P�Ȃ�u�}�^�v�ɂƂǂ܂�Ȃ����z�^�Ƃ��āC�ڎw�����悤�ɂȂ��Ă��܂����D�ŋ߂ł̓I�t�Z�b�g����̌���C����ɂc�s�o�̏o���ɂ���āC�����y�[�W��ɁC�}�łƑ��ʂ̕������i�a���{�����j�����C�A�E�g���C�����ɍZ�����邱�Ƃ��e�ՂƂȂ�C�����̌���ƍ��킹�āC�J�^���O�̗l�����i�i�̈Ⴂ��������悤�ɂȂ�܂����D�Ȃ��ɂ͉��\�����Ƃ����P�ʂŔ������̂�����C�u�B�ꂽ�x�X�g�Z���[�v�ƌ�����䂦��ł��D�ŋ߂ł́C��������ʏ��ЂƂ��Ă�����J�^���O���o�Ă��܂����̂ŁC����͂��̓����������K�v������ł��傤�D�i�q�P �J�^���O�͖{�ɂ��炸�r�́u�{���Ŕ����Ȃ��{�v�A�����A�O�`�l�y�[�W�j
�{�V���[�Y�ł͓��ʁA�}�^�͊J�Â��ꂽ�W����̌��������Ƃ��Ĉ������Ƃɂ��āA�}�^���̂��̂̎d�l�\�\�T�C�Y�E���{�l���E�y�[�W���E��������E�F���E���l�i���^��i���܂��͌f�ڐ}�œ_���j�Ȃǁ\�\�ɂ͐G��Ȃ��\�肾�B�������A�A�ڊ����̂������ɂ́A�O�f�s�x�l�`�A�E�r�G���i�[�� �O�����E�v����܋L�O�@�r�c�����v���ʼn�W�\�\1956-1966 M. IKEDA�t�̂悤�ȁy�Q�l�z�}�^���܂߂āA���̎d�l���ꗗ�ɂ��Čf���邱�Ƃ��ł���A�Ǝv���B���Ȃ݂ɁA�s�W����J�^���O�̖����݁t�̓W����J�^���O�]�́q�C���[�W�ƃe�N�X�g�r�̏͂ŎR���^�R������肠���Ă���q�u����C���̑��`�I�����v�W�r�̊O���ʐ^�\�\���邩��Ɂs���I�����t���ӎ���������ɂȂ��Ă���\�\�̘e�ɂ́u�x�R�����ߑ���p�فi2001�N7��19��-9��24���j�^�a�J�旧�������p�فi12��4��-2002�N1��27���j�D�J�^���O�́C�x�R�����ߑ���p�فi����G���j�E�a�J�旧�������p�فi���c�R���j�ҏW�E���s�C2001�N�C24.5�~20cm�C���Ő�236.�v�i�����A��l�l�y�[�W�j�Ƃ���A�T�C�Y�ƃy�[�W���͕K�{�ƌ�����B
�i���S�j�@�W��������\����ɂ́A�����Ƃ̑Λ��������̏�ԂƂ��āA���O�ɂ��̍�i���҂Ɋւ�����A���Ȃ킿�\���m������肷�邱�Ƃ��������Ȃ��\�\�g���́s�����V���t�̓W����m��s�|�p�V���t��s���p�蒟�t�Ƃ��������p�G���̂���ɖڔz����������Ȃ������i�`�S���y���̃`���V�m�t���C���[�n�͎��}�́E���m�c�[���̒�Ԃ����A����ɂ��̎���͎�Î҂����M����E�F�u�T�C�g�̏��\�\�R���i�Ђɂ����ĊJ�Ó����̕ύX�Ȃǂɂ��_��ɑΉ��ł���\�\�ł���j�B�g�����l���ȏ�ɓW����ɑ����^�̂́A�Ζ���ōL����S�����Ă����Ƃ����Ɩ���̗v�������������낤���A����ɂ͂��̎�̂��̂��u�ς�v�̂������̍D�݂������A�Ƃ����ӂ��ɍl����̂��������B�������g���ɐ}�^���˂ɓ��肷��K�������������ǂ����A�͂����肵�Ȃ��i���L�␏�z�ɂ́A�����ΓW����̐}�^���o�ꂷ�邪�j�B�C�ɓ��������̂Ȃ�A�L���ƋL�^�Ɏ�������̂Ƃ��čw�������̂ł͂Ȃ����B���͂قƂ�ǂ��Ȃ����i�Ƃ������Ƃ́A�����H�ɂ͂��̂����j�A���Ƃɂ��ƓW�����Ō������ςāA�}�^�Ŋm�F���āA�ēx�������ς�A�Ƃ������Ƃ���������������Ȃ��B�����z������A�u���邱�Ƃ͈�u�ɂ��Đs�����v�i�q�Y��i�ނ��сj�r�K�E1�j�Ƃ���ɁA��ˎ闝�Ɓq�ߒq��}�r���ς������Ƃ��̂悤�ɁA�g���͂��������ƓW��������ɂ�����������Ȃ��B��˂́s�g�����̏ё��t�i�W���v�����A2004�N4��15���j�ł��������Ă���B
�@�k�c�c�l�u��˂̓V�ˁv�B����̓I�k�����u�l�W�F�N�e�B���B�Y������o�����A���t�������̂悤�Ɏ���Ƃ��ĘA�˂��A�����J���̋����A�v�E�b�E�E�C���A���Y���P�l�X�E�o�[�O���]�������t�ł���B�g�������܂��A��˂̓V�˂ł͂Ȃ��������B
�@���̂��Ƃɂ��Ă͑N�₩�Ɏv���o����邱�Ƃ�����B���a�Z�\�N�l�������A������̂s�n�o�ł��������A�R�̍��Ô��p�قɌ�ꏏ�������Ƃ��������B�J�Â���Ă����ّ̂͊��̖��i�W�B�O���ɕ�����ꂽ�W�ς́A���̓��͑����̍ŏI���ł���A�g������͂��˂Ă���������݂邱�Ƃ��O�肾�����u�ߒq��}�v�����邽�߂ɕ������̂������B
�@�����A�g�����͂��̊��q����́A�ȗ��������ۊG��̂��Ƃ���m�����ނ��n�������o���H������ꕝ��O�ɂ��āA�Ȃ�ł����킯�ł͂Ȃ������B
�@�킸���ɑ��͎~�߂����̂́A�\�b�قǑ����~�߂�悤�ɂ��Č��߂�ƁA�T��ɂ��鎄�Ɂu�����ƌ������Ǝv���Ă��v�ƌ�肩���A�Ăь��߁A�ق�̐��b��ɂ́u�ߒq��}�v�̑O�𗣂ꂽ�̂������B�i�q��r�A�����A���O�`���l�y�[�W�j
�i���T�j�@���͔��p�j�̐��Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�{�e�Łu�}�^�v�ƌĂ�ł����W����J�^���O�ɂ��āA���p�j�Ƃ̌��������ł��������B���{���i1947�`�@�j�́s���p�J�^���O�_�\�\�L�^�E�L���E�����t�i�O���ЁA2005�N7��30���j�͂��̕��ʂ̐��I�Ȓ��������A���́q�v�����[�O�r�Ɏ��̂悤�ɂ���B�i�@�j���̐����͌f�ڃy�[�W�B
�@���p�J�^���O�̓J�^���O�E���]�l�k������u��i���ژ^�v�l����ł͂Ȃ��B�ނ���A������͐��Ƃ�揤�A�N�W�ƌ����ŁA���p�̃J�^���O�Ƃ����A�ŏ��ɐG�ꂽ�W����J�^���O���v�������ׂ�l�����|�I���낤�B���̑��������A�����܂߂Ĕ��p�j�����҂ɂ͏��Ȃ����ƂȂ��Ă���̂ł���B�i13�j
�@���̌X���k�W����J�^���O�̐}�ʼn��A�}�ł̑}���ɂ��{�����[���E�A�b�v�A���w���l�����݂ɑ����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A���݂ł͓W����i���ׂĂ��ʐ^�}�ʼn�����J�^���O�����ʂŁA����ɍו��ʐ^�܂ʼn����ă��B�W���A�������͂����Ă���B�J�^���O�̓{�����[���E�A�b�v����킯�ł���B���̂悤�ɏo�i�삪�ʐ^�}�ʼn�����Ă��܂��ƁA�W����ɍs���Ȃ��Ă��J�^���O�����Ă��邾���ōs�����C�����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ��Ȃ��ł͂Ȃ��B�}�łɂ��W����o�i��̑��ژ^���ł���B���ہA�W����ɍs�����Ƃ��Ă��J�^���O�ɂ��L���̂ق����������Ƃ͂܂܂���B�Ƃ������A���p�j�����ɂƂ��ēW����ł̔��I�̌����_���ɔ��f����邱�Ƃ����Ȃ��̂��B�ƂȂ�ƁA�W����ɑ����^�Ԃ̂́u�����������v�Ƃ������̈��S���̂��߂Ƃ��Ȃ�A�����ɂƂ��Ă̓J�^���O�̂ق����d�v���Ƃ������Ƃ��łĂ���B
�@�W����̂��̂̌o���������ɔ��f����Ȃ��Ă��A�J�^���O�͕ʂł���B��Ƃ���p�ق̃f�[�^���S�̃��]�l�Ƃ͈قȂ�\�\�������A�o�i��̃f�[�^�`���̓��]�l�̂���ɋ߂����\�\�A�ߔN�̓W����J�^���O�ɂ͍�i���߂��_�����i����̂������Ōf�ڂ���A�����ɂ͓W����̃e�[�}�ɉ������ׂ��ȏ������t���Ă��邩��ł���B���������W����J�^���O���������o�ꂵ�Ă���͓̂�Z���I�㔼�������Ԃ��Ă��炾���A���ꂪ���݂̓�ꐢ�I�܂ʼn������Ă����̂ł���B�Ƃ������A�W����J�^���O�̘_���́A���e�͕ʂɂ��āu�ŐV�́v���ł��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��̂ŁA�����҂͎��R�A�J�^���O����ɂ��邱�Ƃ𔗂��Ă��܂��킯�ł���B�������A���������ŐV���͍�i�̏��ł��邱�Ƃ͏��Ȃ��āA��i�ɂ��Ă̕��͂�^���ł���ꍇ�������A�Ƃ肽�ĂēW����ɏo�i����Ă��Ȃ��Ă����\�ł�����́A�W����Ƃ����C�x���g���_�@�ɃJ�^���O�ɔ��\���ꂽ�����Ȍ����_���Ȃ̂ł���B�������āA��K�͂ŗD�ꂽ�W����ł������قǃJ�^���O�͐}�łƘ_���ɂ�鎩���������h�Ȍ������ƂȂ�A�W����̂��̂���u���邱�ƂɂȂ�B
�@�����������݂̓W����J�^���O����ɂ���ƁA��Z���I�O���܂ł̕s�N���Ȑ}�ł��I������Čf�ڂ��ꂽ�f�[�^���S�̊ȗ��ȃJ�^���O�̕����A���ۂ̓W�����z�����邱�ƂɂȂ��čK���ȋC�����ɂ͂Ȃ�B�������z���������Ă�L�^�A�����ċL���Ƃ��Ắu�W����J�^���O�v�������Ƃ������Ƃ����A���܂�J�^���O�͎������n�߁A�W����̃J�^���O�ł���Ȃ��炻���łȂ��Ƃ����V�����W���n�܂��Ă���B
�@�����A�����ɂ�����W�ς��ꂽ���p�i�ށA��������J�^���O�Ƃ����{���̋@�\���炷��A���݂̓W����J�^���O�͗��j�I�ɂ݂�Γ���Ȃ��̂ƌ�����̂��B�����������ʂɓW����J�^���O�ƌĂ�ł��鏑�Ёi�����j�̒��ŁA�{���I�ȈӖ��ł̃J�^���O�́A�}�ł������ƈꕔ�̐��Ƃ������Ă͂���قǏd�v������Ă��Ȃ��悤�ɂ��v���B���ꂪ�悢���Ƃ��ǂ��Ȃ̂��̔��f�͍����T����Ƃ��āA���݁A�������ƃJ�^���O�̊W�͖{�i�I�ɕω����n�߂Ă���Ɗ�����B�i14�`15�j
�������Ɏ����ڂ����}�^���A�ߔN�̂��̂ɂȂ�قnj������R�Ƃ��Ă��Ă���A�Ƃ�킯����܂łɊJ�Â��ꂽ�W����̋L�^�́i���ꎩ�g���ŐV�̓W����ɂȂ�킯�����j�A�ق��̔��p�j�̐�发�̋L�ڂ𗽂����̂������B���������}�^�̓��e�ʂɉ����āA����ʂɂ�����ʐ^���łƃI�t�Z�b�g����̐��x�̌��オ����B����������{�Ƃ������Ƃ������܂��āA����̔��p�����W���������ȓ_���������Ȃ��B����ŁA�W����J�^���O���s�̂̏��ЂƂ��ė��ʂ��邱�Ƃ�����B����2019�N10�����{�Ɋς���ړW�m���g���X�y�N�e�B���n�s�G�h���[�h�E�S�[���[�̗D��Ȕ閧�\�\Elegant Enigmas: The Art of Edward Gorey�t�i��ꁁ���n�旧���p�فA�����2019�N9��29���`11��24���j�Ŕ̔�����Ă����̂́A�u���{���A�W��������}�^�v��搂������ЁA�s�G�h���[�h�E�S�[���[�̗D��Ȕ閧�t�i�͏o���[�V�ЁA3���F2019�N1��20���k���ŁF2016�N4��30���l�j�������B���Ȃ݂ɓ����́A���s��ISBN-13�Łu978-4-30-927707-3�v�����A�������ɂ́u978-4309277073�v�Ɠ��ꂽ�����q�b�g���₷���悤���B
�k�͂������l
�ٕ��s�g�����N���k������2�Łl�t��1991�N�i����3�N�j10���̏��Ɂu�E�ؔn���Łq�g�������Âԉ�r���J�����i���N�l�ѓ��k��A�剪�M�A����N�v�A�푺�G�O�A�����r�Y�j�B��ꕔ�͎i����r�Y�Œm�F�����̎v���o�b�i�������Y�A�ѓ��k��A����N�v�A�]�X���F�A����Y�A���c�v�Y�A�����A���q���`�A���X�؊��Y�A�����L�A���c�q���q�A�푺�G�O�A�߉ϑ��Y�A�����ĔV�A�ĐΔԖ�A��쐟�q�̏\�Z�l�Ƌg���z�q�j�A��͌܊X���_���̗���A��O���͐��L������̃X�g���b�v�V���[�A���r�[�Ɏ�ւ���̌��悪�W�����ꂽ�B�v�Ƃ���B��ꕔ�̎i��́A�����ɂ���悤�ɍ����r�Y����ŁA���̑I�����͎푺�G�O����A�S�̂̉^�c�͒}�����[�̒W�J�~�ꂳ���������B
���̉�ɂ��āA���͂��т��ѐG��Ă��āA�ŋ߂ł��q�ҏW��L 216�r�i2020�N10��31���X�V���j�Ɂu���g�����Ƒ��c�q���q���������B���c����̎p�����A�b�����̂́A�{���ł��G�ꂽ�E�ؔn���ł̋g�������Âԉ�ł̂��Ƃ������B���̂Ƃ��̎i��͍����r�Y���������A�����߂Ă����̂͒}�����[�ŋg�����̕ҏW�S���������W�J�~�ꂳ��ŁA����ɘ^���Ă͐\����Ȃ��̂ŁA�W�J����ɒf���������ŁA�o�d�������̘b���J�Z�b�g�e�[�v�Ɏ��߂��i�R���T�[�g���ł̃I�[�f�B�G���X�^���ł���j�B���Ȃ烔�B�f�I��X�}�z�ŊȒP�ɓ�����L�^�ł��邪�A30�N���܂����ƁA���������킯�ɂ͂����Ȃ��B���̃e�[�v�A��ɂ��܂��������ŁA�������Ȍ�����Ȃ��B���c����̘b���̘^�����������̂����B���܂́A�Ƃɂ��������̑{����S�|���悤�B�v�Ə������B
���̃J�Z�b�g�e�[�v���v�������Ȃ�������o�������B�����APC�̑O�ɍ����ĉ��y�����߂Ɏg���Ă���A����̏��I�ɒu����CD/MD�v���C���[�̘e�ɁA�J�Z�b�g�e�[�v�̃��x���������Ȃ��悤�Ɂi�{�ł����ΑO���������ɂ��āA���̎�������͌r�����n��������悤�Ɂj���ׂĂ������̂��B����CD/MD�v���C���[�A�ق��ɂ����W�I�iFM/AM�j�ƃJ�Z�b�g�e�[�v��������B�����A�������J�Z�b�g���Đ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�e�[�v�̏�ݒu����͐Q����p�̃I�[�f�B�I�X�y�[�X������A���������܂Ȃ��T���Ă݂���Ȃ��ƂȂ�ƁA����ł���グ�������B�Ȃɂ��̉�����CD/MD�v���C���[���g���Č��̃J�Z�b�g���Đ������̂��A�܂������L���ɂȂ��B������ɂ��Ă��A�T�������������Ăق�Ƃ��ɂ��ꂵ���B

1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r��^�������J�Z�b�g�e�[�v�i���2���j�Ƃ�����_�r���O�����~�j�f�B�X�N�i����2���j
�����q�푺�G�O���������r�i2004�N9��9���E�e�j�Łu�푺�G�O�����锪�������ɖS���Ȃ�ꂽ�B�g�����Ɠ������N����������B��l�N�O�̋g������̑��V�̓��A�Ƃ���̂��Ƃ肠���������E�^�����ɋ삯�������A�č��̂��߂ɕ��̂����܂��푺����̌�낾�����B�����N��Z�������́q�g�������Âԉ�r�i�E�ؔn�فj�ŁA�푺����͂����悻���̂悤�Șb�����ꂽ�B�v�ƌ�����q�ׂĂ���A�푺����̘b�����̃e�[�v����N�����ĒǓ����̊�ڂƂ����B���������Ӗ��ł́A���c�q���q������܂߂āA�܂��ق��̊e���̎v���o�b�q�킽���̋g�����r���I���Ă��Ȃ��B���牽�ɂ킽���āA�݂Ȃ���i�Ǝi��̍����r�Y����j�̘b���Љ���Ă����������Ƃɂ������B�o�d�������ŁA�܂��������Y����́i�g�����̑��{�E�������e�[�}�ɂ����j�b���f���邪�A�����Ŗڎ��ӂ��Ɋe���̏Љ�����Ă����i�sWikipedia�t�ɋL�ڂ����邩���ɂ́A�����Ƀ����N�����j�B���킹�āA�v���o�b�ɉ����t���Ă݂��B
���@�����r�Y�i1937�`�@�j�E���l �k�i��l
�@�@�������Y�i1934�`�@�j�E���l �k����F�g�����̑��{�E�����l
�A�@�ѓ��k���i1930�`2013�j�E���l �k����F�X���q���Ȃ����n�ɍs�����̂��l
�B�@����N�v�i1931�`2018�j�E���l �k����F���сq�J�J�V�r�N�ǁl
�C�@�]�X���F�i1933�`�@�j�E���l �k����F�ӔN�̎��̎p�E�`�ɂ́A���̎��̉e�����c�c�l
�D�@����Y�i1906�`2010�j�E������ �k����F�u�����Ă��鎞�����łȂ�����ł��������v�l
�E�@���c�v�Y�i1931�`�@�j�E�o�ŎБn�Ǝ� �k����F�q�����܁r���ނ̂��Ɓl
�F�@�����i1929�`���j�E�}�G���
�G�@���q���`�i1936�`2015�j�E���
�H�@���X�؊��Y�i1947�`�@�j�E���l
�I�@�����L�i1935�`�@�j�E�ʐ^��
�J�@���c�q���q�i1930�`2003�j�E���l
�K�@�푺�G�O�i1933�`2004�j�E�]�_��
�L�@�߉ϑ��Y�i1922�`2014�j�E���l
�M�@�����ĔV�i1935�`2016�j�E���p��
�N�@�ĐΔԖ��i1955�`�@�j�E�o�l
�O�@��쐟�q�i1930�`2002�j�E���l
�P�@�g���z�q�i1930�`�@�j�E�g�����v�l
�Q�@�܊X���_���i1948�`�@�j�E�����s�n�c��o�g�̗����
�R�@���L�����i���`�@�j�E�X�g���b�p�[
��
�q�킽���̋g�����r�y����1�z�\�\�������Y����̊��i1991�N10��12���A�����E�̖ؔn���ɂ�����s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�j
�k�͂������l�ŏq�ׂ��e�[�v�́A�I�[�v�j���O�̓y���F�i1928�`1986�j�ɂ��q�m���r�i�C�E8�j�N�ǂŎn�܂�B���ɗ��ꂽ�̂̓��W�I�ԑg�s�g�����̐��E�t�\�\1974�N10��12���̌ߌ�9��5������55���ԁA�m�g�j���W�I�������s���|����t�́q���Ǝ��l�r�V���[�Y��2��Ƃ��ĕ����\�\����̃G�A�`�F�b�N�ŁA����N�v�����̉����Ɉ˂������̂Ǝv����B�q�m���r�́u1�v���珇�ɑ����N�ǂ́A�y�����u8�v�ƌ������^�C�~���O�ŃJ�b�g�����i���Ԃ̓s���ɂ����̂��j�B�����āA�i��S���̍����r�Y�����A�����˂���̌�����q�ׂ����ƁA�����肾���B
�u�܂������́k�g�������Âԁl��̂��Ƃł����ǁA����́k1991�N�́l3���ł������A�g���z�q�v�l�̂��˗��ŁA�u��������ǂ����悤���v�Ƃ������ƂŏW�܂�܂����Ƃ��ɁA�u���������Â���������ق���������Ȃ����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��āA�푺�k�G�O�l����̊̂���ł��������邱�Ƃ̂Ȃ����̂ł����A��߂Â��܂����̐S�̂Ƃ��ɁA�ڂ���40���قǃt�����X�ɍs���Ă���܂������̂ł�����A���̔��Łu���܂��A�i������v�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ�ł�����ǂ��A�i��ȂǂƂ������Ƃ͂ł��܂���̂Łc�c�B
�����̉�Ȃ�ł����A�܂���ꕔ���A�݂Ȃ���Ɂq�킽���̋g�����r�Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁA�����������ЂƂ���3���\�\������Z���Ă������Ă����܂�Ȃ���ł�����ǂ��\�\�����t�����������܂��āA���ꂪ�I�����30���قNjx�e�Ƃ������ƂŁA�����ň��ݕ����o�܂��B���̂��ƁA������푺����̊̂���ŁA�e�����܊X���_���t���ɗ������Ȃ��Ă��������܂��āA���̂��Ƃɋg������D���ŁA��������Ȃ��Ă��������ɂ͒ʂ����Ƃ����V���[���ӂ��قNJςĂ��������܂��B���̂��Ƃł��͓�p�ӂ��Ă���܂��āA�������������Ƃ������͖̂��Ȃ�ł�����ǂ��A����������u�����������l����v�Ƃ����ӂ��Ɍ����Ă���܂��āA�����ւk�Ȃ�ł�����ǂ��A��ɂ��o�ɂȂ���A��������āc�c�i���A�j�B
�i�I�t�j���ǂ����Ő����Ă���l���c�c�B
�ł́A����������ꕔ���B����́A�K�����������Ȃ��Ă��Ȃ���ł�����ǂ��A50�����Ƃ������ƂɈꉞ�Ȃ��Ă���܂��āA�������Y����v�B
�i�������Y����A�o�d�j �k����F�g�����̑��{�E�����l
�@�g������́A���鎞������S���Ȃ�܂ł����Əa�J�ɂ��Z�܂��ł�������ǂ��A���Ƃ��Ƃ͓����̉����̂����܂�ł�������A�����̂��̉��͋g��������ÂԂ̂ɂӂ��킵��������Ȃ����ȂƎv���܂��B�g������Ƃ��������́A����ς肻�����������̉����̕��͋C�������Ǝ����Ă���ꂽ�������Ǝv���܂��B�����ł��ˁA�H�n���ŐE�l���Ȃ�����Ă���A���������^�C�v�̓����̉����ł��ˁB���������ӂ��Ȍ����������܂��ƁA����Ӗ��ł͂����ւ�������ꂽ���̂��������������g������Ƃ͂�����ƈႤ�悤�ɕ������邩������܂��ǂ��A�킽�����͂����v���Ă��܂��B���̋g������̂������������Ȃ���̂��A���Ԃ�͂������������E�����̎����ȐE�l�ӂ��̐����������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�@�g������̂����������i�������ȏ��Ɍ���Ă��āA���Ƃ����d���Ԃ肾�Ƃ��A����������Ύ����������ɂȂ�̂͂��܂��J�Ȃ���Ȃ�����ǂ��A�G�b�Z�C�����������ƁA�ȂM���a���Ă����Ԃ��J�Ȃ������Ƃ����ӂ��ɂ��������Ă��܂�����ǂ��A�����������ɂȂ����ꂪ����Ă���B�܂�A�ꌾ�Ō����u���ق�M���Ȃ��v�Ƃ����Ƃ��낪����킯�ł��ˁB�ł�����A�g������̍�i�����������A���������Ӗ��ł͂�͂肻�������A�E�l�����悤�ȁA�l�ڂɂ₽��ɗ��̂��A�ڗ��̂������ŁA�����ŁA����Ӗ��ł͉��a�ƌ����Ă��������炢�A�������Ă����ւ�X�g�C�b�N�������A�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B���̋g������́A�X�g���b�v���̃|���m���̂��A�����Ă������ł͂Ȃ�������ŁA�������������ɃX�g�C�b�N�Ƃ����̂͂��������悤�ł�����ǂ��A�X�g���b�v��|���m�ł����X�g�C�b�N�Ȋy���ݕ��Ƃ����̂͂����ŁA�g������͂��Ԃ������y���ݕ����Ȃ����Ă���ꂽ��ł͂Ȃ����ƁB
�@���������g������̓������A�g������̂Ȃ����������̖{�̑����\�\�g������͑����ƂƂ��Ă������ւ�����̂��d�����Ȃ������\�\�ɂ�����Ă����Ǝv���܂��B�����͋g������̎�������Ă������邩������������������Ǝv���܂�����A�킽�����͋g������̑����ɂ��Č�肽���Ǝv���܂�����ǂ��A�g������̑����Ƃ����̂́A��ڌ���Ɓu�����A����͋g������̍�i���ȁv�Ƃ������Ƃ������킩��悤�ȁA���̓��������������̂ł��B�܂��A�������������͕`�������Ȃ͎g�킸�ɁA�����ƕ�^����@�B�I�ɑł��o�������������g���ɂȂ�B���̊����̑傫�����܂��A�傫���炸�������炸�A�Ȃ�Ƃ������o�����X�Œu����Ă��āA�傫�ȕ\���̖ʐς̂Ȃ��ɂ������������������u���Ă������ł�����A�ꌩ�����������Ɍ����܂����ǂ��A�����ĂČv���Ă݂�Ƃ��������傫���̂��g���Ă���A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��悭����܂��B���ꂩ��F�͂��������A�����ł��ˁA���̐F�Ȃ��I��ł��������ł�����ǂ��A�Ƃ��O���[�𒆐S�ɂ������F�n�𑽂����g���ɂȂ����Ǝv���܂��B�킽�������g�����͋g������ɖ{��2�_�A���肢�������Ƃ������āA����͍��ɂȂ��Ă݂�A�킽�����ɂƂ��Ă̈��̕ɂȂ��Ă���܂��B�����̖{���g������̑����ŏo�����Ƃ����̂́A�킽�����ɂƂ��Ă͂����ւ_�Ȃ��Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B
�@�g������͂������������Ƃ̂Ȃ��ŁA�Ƃ�킯���{�ƂƂ��āA�����Ȃ��Ƃ����l���ɂȂ�܂����B�Ƃ�킯�A�{�̊e�y�[�W�̊��t�Ȃ́A�����Ԃ�g�����\�\�Ƃ����̂�����Ǝv���܂��B���Ƃ��A�ӂ����{�̓`���I�Ȗ{����ł��ƁA�����i���n�߂�͍̂��y�[�W����n�܂�̂������Ȃ�ł����A������E�y�[�W����n�߂āA�Ȃ�ׂ����J���Ŏ����ǂ߂�悤�ɂ��悤�ƂȂ������Ƃ����̂́A���Ԃ�g�����n�߂�ꂽ���ƂŁA���݂ł͂����Ă��̎��l������P���Ă܂�����ǂ��A���Ƃ��Ƃ͂����ł��B�킽���������͑����{�������Ƃ�����܂�����ǁA�킽�����͐���y�[�W����n�߂悤�Ƃ����`����`�҂Ȃ��̂ł�����A���͋g�����̂ق���������ł��ˁA�ǂނ͓̂ǂ݂₷���ł��B�ł�����ܒ����܂��āA�ŏ���1�т������y�[�W����n�߂āA��������y�[�W�Ɏ��߂āA2�Ԃ߂̍�i����͉E�Ŏn�܂�悤�ɍH������A�Ƃ����ӂ��Ȏ�������Ύg���Ă���܂��B
���̂ق��ɋg������́A���̂Ȃ���1�s�Ƃ����̂������ł��ˁA�߂Ɛ߂Ƃ̊Ԃ̔����B����͂ӂ�1�s��ł����A�����2�s��A�Ƃ������Ƃ������Ԃ�n�߂�ꂽ�������낤�Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A1�s�ł��ƁA�y�[�W�̐�߂֗���ƁA�������Ă��ĂȂ����킩��Ȃ��ł��ˁB2�s�Ă���ƁA���Ƃ��y�[�W�̐�߂֗��Ă��A�������Ă���Ƃ������Ƃ���ڂł킩��B����Ȃ��Ƃ��A�g�������{�̎��̑��{�̐��E�ł��n�߂ɂȂ������Ƃ��Ⴀ��܂����A�Ǝv���Ă���܂��B���������͂��邩������܂��A�g�D�I�ɂ��n�߂ɂȂ����̂͏��߂Ă��낤�Ǝv���܂��B
�@����Ȃ킯�ŁA�킽�����͋g������̎����������ł�����ǂ��\�\�Ƃ�킯���������炻���œW�����Ă�������łŁs��ʁt�̈ꕔ��ǂ݂������āA�����ȂƎv������ł����\�\�����������ł�����ǂ��A�g�������{�p�Ƃ����̂������璷�����Ԃ��o���ĐU�肩����ƁA���傤�ǖk�����q����̑����p�������ł������悤�ɁA�l�l�Ɂu�����A���������{��l�������v�ƁA���������ӂ��Ɏv���������悤�ȁA�������������̂��̂��Ǝv���Ă���܂��B�Ƃ肦������ȂƂ���ŁA3�����炢�o�����̂ł͂Ȃ����ƁB
�i���A����j
�k�t�L�l
�������Y�̎��Ǝ��W�ɂ��Ắi��������ŏq�ׂĂ���g�����ɂ��2�_�̑����Ƃ����߂āj�A�q�g�����̑�����i�i122�j�r�ł���Ԃ�Ɍ�����̂ŁA�t��������ׂ������͂Ȃ��B�ЂƂ���������Ƃ���A�u���̐F�Ȃ��I��ł��������ł�����ǂ��A�Ƃ��O���[�𒆐S�ɂ������F�n�𑽂����g���ɂȂ����Ǝv���܂��B�v�Ƃ��������́u�v�͎��W�s�D�� ���̉́k�ʐ��Łl�t�i�v���ЁA1973�N4��25���j�̓\���́A�u�O���[�v�͎��W�s��̉��t�i����R�c�A1988�N6��10���j�̔��̐F�ł�����_���낤�B�����Y��鏈���������A��������ɂ�鑕���̑�\��͔ѓ��k��̍���������W�s�S���̃t�@�[�X�g�E�l�[���́t�i�y�ЁA1974�N5��5���j�ł���B���Ȃ݂Ɂq�g�����̑�����i�i122�j�r�́A���́s�q�g�����r�́u�{�v�t�̂Ȃ��ł��i�����炭�͂�����j�͂̂����������̂ł���A�s�q�g�����r�����t���q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�ƕ���ŁA�����̐[����тł���B���́s�g�������Âԉ�t�ł̎v���o�b�q�킽���̋g�����r���A�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�ł��������V���[�Y�ɂȂ�A�Ɗ肤�B���̉�ł��b�����������ėǂ��肻���ȕ��́A���̂ق��ɉ��l�������ł��B�v�����܂܂ɋ����Ă��A�ܒJ���m����A�剪�M����A�}��b����A������������A��؎u�Y�N����A���o������A����ɕҏW�W�҂��܂߂�A��؈ꖯ����A���ؒ��h����A�a�C�������̂����O�������ǂ���ɕ����ԁi�������A�W�J�~�ꂳ��ɂ����b�������������������j�B���ۂɁA�����̊W�ł����łɂȂ�Ȃ������������낤�B���l�E�|��Ƃ̊�c�G����A���l�E�����Ƃ̐�����s����͂��Ắs�k�t�̒��Ԃ����A�g���Ƃ͂̂����Ԃ���������A��ɂ͏o�Ă��������Ȃ������̂��낤�B�c�O�������������Ȃ��B
�{�e�̏��߂Ɍ܊X���_���t���Ɛ��L��������̂����O���������B�ʘg�����A���̓�l�ɂ��Ō�ɂ��o�ꂢ�������āA�ق�Ƃ��̂����܂��Ɏ��i���ш�Y�j���Ȃɂ��ЂƂ��Ɛ\���グ�邱�Ƃɂ������B�������Y������1��Ƃ���ƁA�S20��̒�����ɂȂ銆�D���B�����ǂ���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���@�k�����̟f�N�ɂ��āl
����N�v�s�킪�o�_�E�킪�����t��1968�N4��1���A�v���Ђ��珉�ł����蔭�s����A��1969�N2��15���Ɂu���y�����Łv���o���i���������Ă���̂͂���j�B�i�{�[���̃P�[�X�Ɋ|���������L�̑тɁu��20�� �ǔ����w��܁v�Ƃ���A���ł������ɕi��ɂȂ������߂̑����������Ǝv�����B����A�Q�l�̂��߂ɐ����旧�}���ُ����̈�{���肽�Ƃ���A���t�ɂ́u���Z���N�l��������Ŕ��s�@���Z��N��k�}�}�l�����y�Ŕ��s�@��㎵���N�܌���������Ŕ��s�v�Ƃ������B�����ƌ����Ƃ���A�Ƃ��ɔł�ς����悤�ł��Ȃ��A�P�Ȃ鑝���Ƃ������ӂ��ł���B�����ɑ��āA2004�N7��10�����s�́u�����V�Łv�͂܂������V�łŁA������O�̊e�ł������ɂ�銈�ň���������̂ɑ��āA�����炭�����̂Ȃ��ō���̗ǂ����̂𐴍���Ƃ��Ĉ����āA�ʐ^���ł̂����A�I�t�Z�b�g������Ă���B���̂��߂��낤�A���t�O�̑Ό��y�[�W�Ɉ�s�A�u�{���͈��Z���N�l��������s�i���莵�Z�Z���j�̕����V�łł��B�v�ƃN���W�b�g������B���́k�����V�Łl�ɂ͂`�T��24�y�[�W�A���ݍ��݂́q�����W�r���Y�����Ă���A����͂��̍ŏI�y�[�W�Ɂq�����V�ł��Ƃ����r���������낵�Ă���B�����̌㔼�ɁA��������B
�@���W�Ɋւ��āA���ɂ͏��Ŗ{��⍋�ؖ{�n�D�͂Ȃ��A�{���̓��e�����ς��Ȃ���A�{�̑��肪�ǂ��ł��낤�ƈ�����܂�Ȃ��ƍl����ق������A����ł��A���́w�킪�o�_�E�킪�����x�ɂ��Ă����́i����Ƃ�������A�̗����Ύ��Ƃ̍���́w�����Q���n���X���̓��x�����邪�j�A���̂܂܂̎p�œǂ�ł��炢�����C�����̂Ă���Ȃ������B�{���ƒ��̃e�N�X�g�����Ȃ�A���̌�A��A��̃A���\���W�[���Ɏ��^���ꂽ���A��͂�A���̍�i�́A�����܂邲�Ƃ̂������ŎႢ�ǎ҂ɂ��͂��Ăق��������B����̕����͂��̊肢���\�S�ɂ��Ȃ��Ă������̂ł���B
����N�v�E���������̎���W�s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�N7��1���j���܂��A�����ł�1977�N4��20���ɏ���R�c����1000������ŏo�Ă���B�����{����������s���}���ُ����{�́A�{�̂�����W���P�b�g���ƃu�b�J�[�ŕ����Ă����āA�т┟�i���������Ƃ��āj�Ȃǂ̕t�����͂Ȃ��B���ł̉��t�������Ă����͖̂{���̍ŏI�y�[�W�ŁA�u�q�����Łr�v�̉��t�̎��Ђ��Ό��̌��Ԃ��̗V�ю��ɓ\���Ă���B�����ɂ����ғ�l�̗����Ȃǂ͋L����Ă��炸�A�����̑f���͝��Ƃ��Ēm��Ȃ��B���̗����́A1991�N�́q�g�������Âԉ�r�ɏo�Ȃ��āA�s�킪�o�_�E�킪�����k�����V�Łl�t�̏o��2004�N7���ȑO�ɖS���Ȃ��Ă����̂��B�������ꂪ���Ȃ̂��A���R�Ƃ��Ȃ��B��������ɟf�����g���͂Ƃ������A�������̎��ɐG�ꂽ���͂��A���͂ق��ɒm��Ȃ��B
 �@
�@
�W�����W���E�T���h�A�{���Y�i��j�s�J�t�̂ނ�i�㊪�j�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A�u���a��\�ܔN�\��\���@�掵���v�A���ŁF1937�N10��15���j�Ɠ��E�i�����j�i�u���a��\�Z�N�܌���\���@�掵���v�A���ŁF1939�N5��2���j�̕\���i���j�Ɠ������2�����Ɠ����i�㊪�A13���j�Ɓi�����A11���j�k�������1989�N3��17�����s�l������2�����̕\���Ɣw�\�� �k�{���̃y�[�W���͂ǂ�������������A1950�N�E51�N�̔ł͗p���̎����e���ł���l�i�E�j
�g�����́A���z�⏑�]�Ƃ��������A��N�̂���ɓǂ{�̉�z�Ƃł����������q�����w�����Z�L�x�r�i���o�́s�����W���[�i���t1982�N3��26�����́k�ēǖ��ǁl�A����́q�����@�����Εv��w�����Z�L�x�i���O���N�j�r�j�����̂悤�Ɏn�߂Ă���B
�@�N���̎��̈��ǂ����{�̈�ɁA�����́w�����Z�L�x���������B��������̖����̈ꋳ�{�l�̎��`�������B
�@��Z����̎��́A�����̕����ŁA�����̖|�w���A�ǂ݂������Ă������̂ł���B�Ƃ��Ƀt�����X�̏������D�݁A�W�����W���E�T���h�w�J�t�̂ނ�x��X�^���_�[���w�p�����̑m�@�x�����ăA���h���E�W�C�h�̏���i�ł������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�y�[�W�j
�A���h���E�W�C�h�i1869�`1951�j�́u�i���̎��_�̓W�C�h�ƃ����P�̏�������Ղ����v�i�q�ʕ��̏I��r�D�E2�j�Ƃ������傪���邭�炢������A�g���͂����Ƃ��ǂ݂��Ǝv�������A�W�����W���E�T���h�i1804�`1876�j�ƃX�^���_�[���i1786�`1842�j�ւ̌��y�͂ق��ɂ͂Ȃ��悤���B�Ƃ���Ō����}���ق́A����ꂽ�X�y�[�X�Ɨ\�Z�͈͓̔��ł͂��邪�A�������V��ӂ�}���ď��������̓���ւ����s���Ă���B���̂��߁A�V�K�̎�����r�˂���̂Ɠ����������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̕��o��͎�ɁA�֘A�{�݂̑��قɏ�����ւ���̂ƁA���T�C�N�������Ƃ��Đ}���ٗ��p�҂ɖ����Œ���̂ƁA���Ƃ������̂Ƃ��Ĕp������̂ƁA�݂̂��ł���B�����̊قɂ̓��T�C�N����������ׂ鏑�I�������āA�Ⴆ�u��l�܍��܂Łv�Ƃ����悤�Ȑ����͂�����̂́A���R�Ɏ����čs���Ă����悤�ɂȂ��Ă���B���̒I�ɂ͐}���ق����o�������������ȊO�ɁA���p�҂��{�݂Ɋ������I�ʂ̌��ʁA�����ɂ͂Ȃ炸���T�C�N�������ƂȂ����{��G���i�܂�ɂ͂b�c�j�����Ԃ��Ƃ�����B
2021�N��3���^���A���n�旧�̂���}���ق̃��T�C�N���I�ɁA�q�g�������y�����E��i�������k���t�l�r�ŋ������u�{���Y��s�J�t�̂ނ�. ��,�����k��g���Ɂl�t�i��g���X�A1937�N10��15���E1939�N5��2���j�v������ł����B���m�Ɍ����ƁA�㊪�́u���a��\�ܔN�\��\���@�掵�����s�v�A�����́u���a��\�Z�N�܌���\���@�掵�����s�v�̌���{�ŁA�}���ق̏��������������ł͂Ȃ��A���p�ҁi������N�z�̓ǎҁj�̏������������낤��{�ł���B�ނ��A�����ɓ��肵���B�ʐ^�̂悤�ɗ��Ă�����̂́A70�N�O�̔��s�ł��邱�Ƃ��l����A�ǂނԂ�ɂ͂܂�������ɂȂ�Ȃ��i�O���V�������Ȃ����{�������̂ŁA��߂̎����u�b�N�W���P�b�g�Ƃ��Ĕ킹���j�B���̎���́k��g���Ɂl�Ȃ瓖�R�����A�{���͐����E�������\�L�B���́A�`������ŐV���E�V���ȕ\�L�̋��ȏ���ǂ܂���Ă������A���Z�̂���A�V�������Ö{�̂ق������������̂Ŕ������A�������V�����ɂ̃w�~���O�E�F�C�s����悳��t�������E�������\�L�������C������i�苖�ɂȂ��̂Ŋm�F�ł��Ȃ��j�B�Z�́E�o��͕ʂɂ��āA�������ɋ������ŕ��͂�Ԃ鎩�M�͂Ȃ����̂́A�ǂނԂ�ɂ͂Ȃ�̕s�ւ��Ȃ��B�������̎q���̐���͂�������A����菭���Ⴂ�N��̐l�����������E�������\�L�̖{�ȂǁA���Ƃ����Ŏ�ɓ����Ă��A�ǂ����Ƃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���́A�g�������N���Ɉ��ǂ����{���i����{�ł͂��邪�j�����łœǂނ��Ƃ̂ł���K�����������B
�s�J�t�̂ނ�i�㊪�j�t�́A�`���́q�E�E�W�F�G�k�E�����x�G�����Ɂr�Ƃ����W��́A�����Ƃ������ׂ�4�y�[�W�̕��͂Ŏn�܂�B���Ȃ݂ɁAEugene-Louis Lambert�i1825�`1900�j�́u�T���h�̒��j���I���X�Ƌ��ɘQ���h�̋����h���N�����̖剺�Ɋw�ь�ɔL�̉�ƂƂ��Ĉ�Ƃ��Ȃ����B�v�i�����A����y�[�W�j�Ɗ����́q���r�ɂ���i�Ԃ���m�F���悤�ƃC���^�[�l�b�g�Ō��������Ƃ���A�uLouis Eugene Lambert�v�������̂悤�ŁA�L��`���������̊G�悪�q�b�g����j�B�T���h�͂��̊����̕��ŁA�{�����G�`�G���k�E�h�p���f�B�E�̕���ł��邱�Ƃ�錾���āA�u�ꔪ�O�N�l���\�����@�m�A���ɂāv�ƒ��߂����钼�O�ŁA�u���͂��̏������A�������̑��̕��J�̉����J�̉��̂₤�ɁA���Ȃ��̂��Ƃ֑���܂��\�\�̗t���G���A�����K��A�����Ď��R�̏t�̍G��ȍՓT����ɊJ����悤�Ƃ��Ă�邱�Ƃ����Ȃ��Ɏv�Џo�����邽�߂ɁB�v�i���O�A�Z�y�[�W�j�ƍ��炩��搂��B�Ȃ��s�J�t�̂ނ�t����̈��p�́A�����͐V���ɉ��߁A���ȂÂ����̓}�}�B
���͖{�T�C�g�̋L���������Ƃ��A���Ƃ�����{�̓��e�ɐG���ꍇ�A��i�Ȃ�i�Ȃ�ׂ��j�ʓǂ��Ă���A�]�_�⌤���Ȃ�i������ڎ�����|����Ɂj�K�v�Ǝv����ӏ����ڂ����ǂ�ł���A���Ȃ킿���e�������̊S�̈�ɂ�����ׂ��}�b�s���O���Ă���A���M�ɓ���B���ԓI�Ɍ��Ă��A�܂��͉����ȕ��@���낤�i���P�j�B�������A�����ł͏�������`�����Ă݂����B�����������߂ēǂށs�J�t�̂ނ�t�Ȃ̂�����A���O�̏��i�o��l�����̑e���̓����⌻�݂̕]�����́j�ɂ͖ڂ����ꂸ�A�Ђ�����䗬�Ɂi�܂莩���̊S���ɂ̂ݒ����Ɂj�ǂ�ǂ��Ȃ邩�B����́A�Ǝv�����i����K�X�A���p���Ă݂悤�B���p�ӏ��͂������قǓǂ���̏����B�i�@�j���̐����̓m���u���B�܂��͏㊪��������B
�@�u�����ȂA�܂������̒ʂ�Ȃv�ƃW���[�t�͂킵�k�G�`�G���k�l�Ɍ��ĉ]�����A�����̍l�ւĂ����Ƃ����̗��h�Ȗ��������ɑ�Ă킵�ɂ킩��₤�ɘb���Ă����̂��Ă�����C���x�܂��l�q�����B�u���̒ʂ�Ȃ��A�R���܂��]�З����Ă邱�Ƃ�����B����≽���Ă��ӂƁA�u�������b�g�����̑��ɂ����������ĂĂ����Ă��Ƃ��B�������������ƂĂ��D�����A�ƂĂ������ŁA�������ʂ肿�Ƃ��Ԉ�ւ��ɉ̂ӂ��A���ɂ����q���̍�����A�u�������b�g�̉̂��̂������̊y���݂ɂ��Ă������Ȃv�i73�j
�@�����]�����Ǝv�ӂƁA�̂₤�Ȋ�������āA�M�a�ŏĂ��قĂĂ�₤�Ȋ���ŁA�����Ȃ肻�̓J�𐁂��o�����B
�@�������ǂ�ȋȂ����Ɛu����Ă�����B�����ɂ₿�Ƃ͕����o���̂���Ȃ������ǂ����m��Ȃ����A�킵�Ƃ�����Ă�ŕ����o���̂Ȃ��ȂŁA�����m���ɗ�̎��S���ŕ�������J�k�����q���r�ɂ́u���ʃo�b�O�E�p�C�v���͕��J�ƌĂ��y��v�Ƃ���l�̋ȂƂ���Ȃ����̂̂₤�ȋC���������������B�R���A���̎��͂Ȃɂ���Ђǂ������Ă�̂ŁA�I���ɂ��܂Ђ܂ŕ����Ă�Ȃ�Ăǂ������Ȃ����B�ŁA���̋Ȃ����Ƃ��ƒ����Ȃ����̂��A����Ƃ��W���[�t������Ɏ����̍���߂��܂����̂��A�W���[�t�͂��Ղ�\�ܕ������Ƃ��J�̎���x�߂��ɁA�w����ƂĂ���p�ɓ������āA�ꑧ�����������A���̂����L���b�J�łƂĂ��傫�ȉ��𐁂��炷�̂ŁA���ɂ��ƁA�O�̑�J����x�ɐ����Ă�̂��Ǝv�ӂ������B�܂����ɂ��ƁA�ƂĂ��D���������o���āA�Ɓm�����n�̒����婂����Ă�̂��A�O�ʼn������Ă�̂��͂��蕷���邭�����B�ŁA�W���[�t������ȕ��ɗD�������������ɂ�A�����ɉ]�ӂƁA�킵�������C���ɂȂ����A���̂���������S���Ђ���߂čl�ւ�ƁA�킵�炪�ӂ�������Ă���̂Ƃ͂Ă�Ŏ��Ă������Ȃ��̂ŁA�킵�ɂ₻�ꂪ�C��Ђ̔n�������Ă��ӕ��Ɍ������B�i82�`83�j
�@�����G���͘b�𑱂��ā\�\
�@�u�����炳�A�G�`�G���k�A���͂Ȃɂ����O�����̕邵�𑱂��čs���̂����ꂱ��]�ӂ킯����Ȃ��B�����A���̕邵���̕������Ɩʔ��������邵�A���̐��ɍ��Ă�Ă��ӂ̂��B�܂��A����肾����A������ċ߂Â��ɂȂ�āB���ꉴ�ɗp�ł��ł�����A���ł��Ă�ł���B�����A���O�̕��ł����Ƃ���Ȃ��ɂ��Ă���Ȃ�Ă��Ƃ͗��܂Ȃ����B�Ȃɂ���A���n�ɏZ��ł�A���Ă�́A�g���̂���Ƃ��F�B�Ƃ��ɗp���ł��ď\��O���̓�������Ă��Ă��ƂɂȂ�ƁA�i�Ղ���ɜ��������āA�����ƈ⌾�����Ă���o���������ȁB�������̕��͂���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����ւł��܂�ʼn��݂����ɔ��ł����A����������䂤�����łł��������ɋ��ւ�Ă��Ă����������B��������܂���͂����B�����A������炵�Ă���B�ŁA����A�����S�������ĂċC��������������₤�Ȃ��Ƃ�������A�u���{���l�G�̍�����Ă�ł����]�Ă���B���ƖY��Ȃ��ł�邺�A���O�̔w����J�ɂ��Ĉ�Ȑ������̂������C������Ȃ������A���O�̗E�C�Ɋ��S���Ă����Ƃ������肵���Ă��Ƃ��ȁv�i121�`122�j
�@����ɁA�����l�̓J�t���ƁA�x��̎n��ƏI��������������𐔂ւ���A�߂��߂��̑g�����X�E�Â���Ԃ����Ƃ҂����߂��܂ӂ��A��͐����o�������Ǝv�ӂƂԂ����ɂ��Ղ�\�ܕ������������Ȃ���A�����łǂ����̂����X�ɐ߂�ςւčs�āA�Ȃɂ���A��̐߂���ʂ̐߂Ɉڂ�̂���ڂ��Ă�ł킩��Ȃ����B���܂��ɂ����͂������Y��Ȃ̂͂Ȃ��Ă�����Y��ȃu�E���̋ȂŁA�ǂ�����̂ւ���╷�������Ƃ̂Ȃ�����肾�����A���ꂱ���������Џ�肳���ȂƂĂ����q�̂����x�肢����Ȃ�ŁA�킵��͂����Ő��̏�ŕ��Љ�Ă�Ȃ�Ă��ӂ���A�܂�ŋ�ł����ł�₤�ȋC�������B�i135�`136�j
�@���̃u���{���l�G�̑�J�̂܂�ŗ��݂����ȑ傫�ȉ��������n�āA�����s���܂����̂Ƃ���v�Ă�途n�t���܂��A�ė����̂�����ƁA�L��ɂ�A���݂͂�ȂǂƐ��������āA���ꂱ���ǂ�ȂɊ��������肵�����A�����͂�����]���ĒN���{���ɂ��Ȃ������B�Ȃɂ���A�݂�Ȃ����C���������₤�ɗx��Ȃ��炻�낻�남���܂Ђɂ��悤�Ǝv�Ă����ɁA��̓J�t�̐̏�Ƀ����G�����p���������Ă킯���B�ŁA���炭����ƁA���ꂱ���܂�ŋC��Ђ݂����ȑ����ɂȂ��܂āA�݂�Ȃ�����l�ÂƂ��l�l�ÂƂ����ӂ����Ȃ��A���l���\�Z�l������Ɏ���q�����āA���˂���A��߂�����A����A������₽�ƂА_�l���Ĉꌾ�m�ЂƂ��Ɓn���������錄�͂���܂��Ă��ӗL�l�����B
�@�ŁA���ꂩ�班�����ƁA�N�����Ⴂ������A�܂���������m��Ȃ��Ԃ�V���A������ɑ��̗����Ȃ��c���m�����n����A�����A�̕��Ɏ�Ԃ葫�Ԃ�x�肾���k����A�����A���q�Ă�ɂ���܂łǂ����Ă���Ђ��Ȃ����s��p�ȎႢ�O���A�݂�Ȉꏏ�ɂȂđ̂��䂷�Ԃ�n�߂邵�A���������ő��̏��O�̏��܂ňꏏ�ɗx��o���Ƃ��낾���B�Ȃɂ��낱�̓J�̋ȂƗ�����A���̂ւ�̘A��������������Y��ȋȂŁA���܂��ɂ����������Ɨ��Ă�B���̏�A�܂�ň����������ł����Ă�₤�Ɍ������Ă��ӂ̂��A������̃����G���͈�x���㉹���͂����A�݂�Ȃ������ւƂւƂɂȂ��܂Ă����Ƃ����������Ȃ����B�\�\�u���݂͂�Ȃ������܂Ђ����I�v�ƁA�����x�ނ₤�ɂ݂�Ȃ����߂�x�ɁA��͓{���B�u���͑����䂤�̐l�Ԃ��ւ����܂ӂ܂ł�邺�A���̏o�ɂ�݂�Ȃ܂������ɂ��₤�ɂȁA�������ĉ��͌��C�œ˂��Ă邵�A�����͂��������Ă���ĉ��ɗ���ł�̂��v�\�\����������A��͓J�𐁂����A�킵��݂͂�Ȃ܂�ŋC��Ђ݂����ɒ��ˉ��Ă킯���B�i146�`147�j
�@�R���킵��͂܂���ƁA�x���C�̈�ԍ����Ƃ��ɑ����Ă鉺�u���{���l�G�ւ͂�������ŁA�����������G���ɕ����ƁA���̓y�n�͂��Ə�֏�ւƍ����ȂăI�I���F���j���܂ő����Ă�Ęb�����B�X�͎��Ɍ����Ȃ���ŁA�݂�ȁA���̂Ȃ��ł���ԗ��h�Ȕ��ނ��т���Ɛ������Ă��B�X�̂Ȃ��ɂ���X�ɐ삪����ĒJ�Ԃ���Ă�邪�A�������ӂƂ��͂ق��������߂ۂ��āA�Y�m�͂�̂��n�Ƃ����Ƃ����k�m�͂���Ȃ��n�Ƃ����ӎ��������Ă�邵�A���ꂪ�݂�ȂƂĂ��傫�Ȃ����肵�����ŁA�킵��̍��ɂ����ȂƂĂ������Ƃɂ������Ȃ������B�킵�͂܂����̐X�ŁA����ď��߂āA���̐悪�����Ď}�Ԃ�̂ƂĂ������ȁA�킵��̍��ɂ���Ȃ������������A�����͎R�џO�m�Ԃȁn�Ă��ӎ������B�킵�̍l�ւ���A�����͞ނ̎��ɂ���̂Ȃ��̉��l�ŁA���h�Ă��Ƃ���ނɂ₩�Ȃ͂Ȃ��ɂ��Ă��A���̑�肸�Ɗ��D�������ĉ]�Ă����������B���̐X���₱���ɂ͂܂��ق�̎����܂����o���͂��Ȃ������A�����G���̘b����A�����̓u���{���l�G�̊��x�^�܂ōs���Ȃ��₤��Ɩ��Ƃ���͌����Ȃ��Ă��Ƃ����B�i204�`205�j
�����āA������������B
�@�u�Ȃ��A�W���[�t�A���̒��̂��Ƃ́A�N�������c�邩�N�����ʂ��킩��Ȃ��B�����������悢�损���ł��ʂꂾ�B���O�ɉ]�͂����A�ق�̓�O�����������������A���ɉ]�͂����A���O�͂��Ɖi���ʂ�Ă����Ȃ̂��B�����A�_�l�ɉ]�͂����A�Ђ�Ƃ���Ɖ������₱����������ւȂ������m��Ȃ����B�܂��A���̕���ڂł߂��߂������̕��p�ɕʂ�čs�����ɂ�A���ł������v�Ă��Ԉ�Ђ͂Ȃ����B�ǂ����܂��A����傽���̂��Ƃ��悭�v�āA�ʂ�čs�Ă���B���̕����A���O�ƍ����ɂ�邨�O�̗F�B��������C�ɓ��Ă�B�����A�����͓e���p�Ƃ��āA��Ԋ̐t�ȂƂ���͂��O�ɉ��y�����ւ�Ă��Ƃ����킯�����A���O�����a�C�����Ă�����r���ł�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ă��ӂ̂́A���Ƃ��Ă������S�c��ȂB���ꂳ�ւȂ���A���O���̂��w�҂Ɏd���ĂĂ�ꂽ�Ȃ�ĉ]�ӂ����Ȃ����B�����̒��ɂ�A�j�⏗�̂������ӊw�҂���āA�������̒m������Ȃ��y��m�Ȃ���́n��炵����A���₤�ǖ{�ɏ����Ă��錾�t��ǂނ₤�ɁA�̂̐߂����ɏ����ēǂ肵�Ă邪�ȁB����A�Ⴂ�����ɏK����@�̂̂ق��ɂ�A�������Ӊ��y�̂��Ƃ͂���܂�m��Ȃ����A�܂������̒m�Ă邾���̂��Ƃ͂��O�ɂ����ւƂ����B�܂�A���q�Ƃ��A���F�Ƃ��A���q�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ����̂����B����A���Əڂ������Ƃ��m�肽���Ȃ���A���X�̑傫�Ȓ��֍s�Ă݂邱���B���������A���@�C�I�����e�m�Ёn�������k�G�b�g�Ƃ��J�h���C���Ƃ����ӋȂ����ւĂ�����B�����A���O������Ȃ��Ƃ����Ė��ɗ����ǂ����Ǝv�ӂ��ȁA�����o�āA�S���邵�͂�����߂��܂ӂĂ��ӂ�Ȃ�ʂ����v�i022�`023�j
�@�u�����G���̂���A�m���Ɋ������邵�A�V�������邳�B�\���œJ�t���̖Ƌ����Ƃ��������A�����ɂ������ĂȂ����A�����Ɖ��`���S���Ă��r���m���Ȃ��B�����A�G�`�G���k�A��炨�O�������]�Ă���Ă��A�Ȃ��o����l�Ԃƍ��l�ԂƂ���A�����ɂ���������Ђ�����B���Ԃɂ�A�w�����������Ă��̊o�����m���ŁA�l�ɏK���Ȃ��C���悭�̂ĕ�������l�Ԃ�����B�R���A�Ȃ��ɂ�A�l�ɏK�ӂ������₿�Ƃ����S�����A�p��ɐV�����v�Ђ���{���Ȃ��炮����l�ł�čs�āA���Ƃɗ���J�t�S���Ɏ����̌��������̂������Ă��₤�Ȑl�Ԃ�����B�Ƃ��낪�A����͂��肳���]�ӂ��A�W���[�t�͂܂肳�����ӕ��̐l�ԂȂB���܂��ɂ��ꂾ������Ȃ��A�����̐g�̂����ɂ�A�ƂĂ����h�ȓV�����������B��͂܂肠�������ꂽ���n���痈��V���ŁA�������痎�����������Â��Ȏv�Ђ��N���ė�����A������͉������̕��̗т�u���痈��V���ŁA�����͂��Ƃ���ЂƂ�łɂ킩�ė��������A��������܂�S�̐[���A�������A���̈������v�Ђ��N���ė����킯���B�������́A�����ƕ������̂�����̂��猩���A�����̓c�ɂ̓J�t����ȂƂ͂܂�ŕʕ��ȂB�܂肻�ꂱ���̂����₤�Ȗ{���̓J�t���ŁA��Ԙr�̂����J�t�A���ł��ꐶ�����ɂȂĕ������A���̗g�傱��܂ł̏K���m��������n��������ςւ������܂ӂ₤�ȁA�������Ӑl�ԂȂv�i164�`165�j
�@�u�Ƃ���ŁA�����N�����A�Z��I�v�ƃ����G���͉]���B�u���͉�������x���Ȃ��܂��B�����]�Ă��A���O�ɂ�Ȃ�̂��Ƃ��킩��܂��B�Ƃ��ӂ̂��A�����͌܌��̎O�\����ŁA�������̕�����A���̓��͎����̍D���Ȗ��̉Ƃ̖���ɉԑ������m��́n�ւ���K���m��������n�ȂA�܂茎�̍���m�������n�ɂ��������Ȃ����A�����������킯�Ȃ��B�ŁA�������Ƃ�����A�N���ɐ���z�����Ă��ӂ₤�ȋC���Ђ́A�܂��Ȃ��킯���B�Ȃɂ���A�������A���̖��Ƃ��O�̏]�o���������ɔ������m�Ă���̂͂Ȃ����A����ɑ��A���̂ւ�̑����₱�́w�Ăі߂��x�̉ԑ��Ă�͂��Ȃ�����ȁB�����A���ӂ̓�l�͂�������o���Ă邩���m��Ȃ����A����܂��ԑ����̞y�m���܂��n�ɂ��Ȃ������ɕ�������o�ė���ꂽ�肵����A���ꂱ����������ӂ����̈��Ђɂ���邺�v�i194�j
�@��J�̎�͂��̋Ȃ����ߐ�Â킵��̒m�Ă�ʂ�̐߂ł��ƁA���̎��ɂ͏�����ւāA���ƗD�������Ɨ҂������q�ł��A�����Ƃ����܂Ђɂ≽���牽�܂ł�����ςւāA����ɒ��q��ςւ���A��������Ȑ߂����肵�Ă��o�������A���ꂪ�ǂ����Č���肪����ǂ������Ȃ��A�p�Ă��̗��������₤�ȑ~���������₤�Ȓ��q���Ȃ�Ƃ��]�ւ��D�����āA�����Ă邤���ɒm�炸�m�炸����݂肵���C���Ɉ������܂ꂸ�ɂ����Ȃ��������B���̂����ɍ��x�͂��Ƌ������ƌ��������q�ɕςւ��Ǝv�ӂƁA�܂�Ől������ňЂ�����݂̂����Ȓ��q�ł��o�����̂ŁA�u�������b�g�́A��l�����O�֏o�Ėx�̉��ɗ����ǂ܂��܂܁A���ɂ����̖x�̂Ȃ��ɉԑ��𓊂����܂��Ƃ������āA���ɐS�����߂��˂Ă�̂����A���̋Ȃ̋����ĂĂ鉅�߂������Ȓ��q�ɂ���Ƃ����₤�ɁA�v�͂���������シ����������B����Ƃ��̎��A���ƌ��Ƃň�����������Ȃ���A�x�̌��ӂ̉��ɃW���[�t���p���������Ǝv�ӂƁA���ꂱ���̂₤�Ȋ�������Ă��̂܂ܓJ�𐁂������Ȃ���A�܂�ŁA�u�������b�g�������ɂ���ȂЂǂ����Ƃ�����̂��v�ЂƂ܂Ă���Ȃ���A���ꂱ���ǂ�ȂɒV���߂��ނ��m��Ȃ��Ɖ]�āA�����̓J�̉��Ɗ���ňЂ����Ă��₤�����B�i201�j
�@�u���ꂾ�������āA���⍟���A�ė����B�܂����A�������s�^�Ȃ���v�Ɓu�哪�v�͉]���B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@���̔ӃW���[�t�͂��ƊO�ɏo�Ă����A����܂łɂ�����Ȃ��Ƃ͉��x�������B����ɁA�����͑O����C�����Ă����A�݂�Ȃ����̂��̂̌Â��̂�J�߂�̂��A��͎��X���Ǝ��m��n���Ă�₤�ȕ��������A���₤����ז��ɂł��Ȃ��∫���Ǝv���̂��B���ɂȂāA�܂����ƔM������₤�Ŋ��C�����Ă����A�����ɋN���ďo�����čs�đ��ʼn\���ƁA���̖x���ő�J�̚ʂꂽ�̂��E��������Ęb���B���⑁�������킯���Ă��̑�J�����Ă݂����A�m���Ɍ��o���̂����Œ����킩���B�ŁA���̑�J�������Ă��Ă��ӏꏊ�ւ�čs�āA�x�̕X�����Ă݂�ƁA�����蓀������A��̂ނ����炵�����[���o�ė����B�̂ɂ₿�Ƃ���r�Ȃ��Ƃ����ꂽ�₤�ȍ��m���Ɓn�͂Ȃ������A�J�t�A�����A�W���[�t�Ƃ͊m���ɑ�������ꗢ����̂Ƃ��ŕʂꂽ���A�ʂɌ��Ѝ��ЂȂ����Ȃ��␌���Ă���Ȃ����ĉ]�ӂ̂��B����ꐶ��������l��{���Ă݂����ʖڂ����B���̂ւ�͂ƂĂ��҂����Ƃ��ŁA����̖�l���S����|���Ă邵�A�S���̕��́A�|�����͈̂��������ȂB�ŁA�������̂��܂��܂����n���L���b�Ŕ[�����ċA�ė�����d�����Ȃ����̂��B���̂ւ�̑�����A���ꂱ��������{�C�ł����v�Ѝ���ł�B����Ƃ܂����̂�����Ŏv�Ă�̂Ǝ����₤�Ȃ����A�܂肩�����ӂ��Ƃ��\�\�J�t�ɂȂ�ɂ�A�ǂ����Ă������̐��E�ɍ���n���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ŁA�x���ꑁ����A�����͖����m�T�^���n�����̓J�t�̎肩���J���������āA������w���ɒ@�����Ěʂ����܂ӁB��������ƁA�J�t�͂���œ����ςɂȂāA������C������܂āA���̗g�傽���Ƃ������Ŏ�����܂ӂĂ��ӂB�܂�A�J�t�A�������ԓ��m�Ŏd�Ԃ��������肳�ꂽ�肵�Ă�̂��A���Ԃŏ���ɍl�ւĂ���ȕ��ɉ]�Ă�̂��B�Ƃ��낪�A�J�t�A���̕��ł��������������Ȃ��Ƃ͖ő��ɉ]�͂Ȃ����A���ɂ��Ă݂��A�������Ƃ���l�ɂ��|�����邵�A���Ƃ̖ʓ|���������킯�ȂB������A���Ԃ̕��ł��A�����ƂĂ������v�āA�Ђǂ��|���ĂāA�������]�Ă��N���b���Ă������̂͂Ȃ����A����ǂ��납�A�����肻�̓y�n�ɉi���������A���̉��������ň������Ăяo���đ��_�̒j��Е������Ȃ�ĉ]�͂ꂳ���Ȏn���Ȃv�i314�`316�j
�s���Ɗv���\�\�W�����W���E�T���h�`�k�����܃v���}�[�u�b�N�X�l�t�i�}�����[�A1992�j�̒��҂ŁA�T���h�����҂ł����{���́s�W�����W�����T���h�k�l�Ǝv�z141�l�t�i�������@�A1997�N8��28���j�́q�c�������r�̏͂ł��������Ă���B�u����ł͂����ŃT���h�̓c���������ڂ������Ă݂悤�B��ʂɔޏ��̓c���l����ƌĂ��͈̂ꔪ�l�Z�N�́w���̏��x�A�l���N����l���N�ɂ����Ĕ��\���ꂽ�w���q�m���Ă��n�̃t�����\���x�A�l���N�́w���̗d���x�A�����ČO�N�́w�J�t�̂ނ�x�ł���B�k�c�c�l�v�i�����A��l���`��l���y�[�W�j�B�D���@�����A�s�J�t�̂ނ�t�ɂ��Ă̌��y�������Ă������i���Q�j�B
�@�c�������̍Ō�̍�i�w�J�t�̂ނ�x�͎l����̒��ł������A�����Ȃ肱�݂��������̂ƂȂ��Ă���B
�@�m�A�����̏��N�e�B�G�l�ƃW���[�A�����ăe�B�G�l�̂��Ƃ��̏����u�������b�g�͗c�Ȃ��݂̒��ǂ��ł������B�v�t���ɂ͂������e�B�G�l�̓u�������b�g�ɗ�����悤�ɂȂ�A�W���[�́A�u���{�l�n���������Ă������o�Ђ��̐N�����G���̂������ŁA�����ɉ��y�̍˔\�����邱�ƂɋC�Â��B�����G���́A�����̕��ł���J�t���̂��Ƃɍs���ēJ���K���悤�ɂƃW���[���������B
�@�ꔪ������A�u���{�l�̐X�Ń����G����Ƃƕ�炵�Ă����W���[���a�C�ɂȂ�A�e�B�G�l�ƃu�������b�g�͔ނ̂��Ƃɂ�������B�W���[�́A�e�B�G�l�̖��A���ꂢ�ł�������҂̃e�����X�Ɋŕa����Ă����B�₪�āA�����G���̓u�������b�g�ƌ������A�e�B�G�l�̓e�����X���Ȃɂ���B
�@�����ۂ��W���[�́A�����ɓJ�t�́u�g���v�ɓ���ēJ�t�ƂȂ�A�����G���̕��ƂƂ��ɗ����̓J�t�Ƃ��ċC�܂܂Ȑ����𑗂��Ă������A��������ɂ悻�̓y�n�ł����̓J�t�����Ƃ����������������ĎE����Ă��܂��B
�@�w�J�t�̂ނ�x�̃W���[�́A���̌����҃t�@�f�b�g��̂Ďq�̃t�����\���Ɠ��l�A�l�X�ɔF�߂�ꂸ�������鑶�݂ł���B���Ԃ����͔ނ̂��Ƃ��A�C�ł������낭�Ȃ���Ƃ݂Ȃ��Ă������A���͔ނ̒��ɂ͔��ɂ�������l���݈ȏ�̊����������̂��B�W���[�́A���y�Əo����Ƃɂ���Ď����̑��ݗ��R�����A�����̓��ɂ���u���v��\�����邷�ׂ��w��ł������̂ł������B�ނ͕���̏I���ł݂��߂Ȏ��ɕ������邪�A����͑��̎O��i�Ƒ傫���Ⴄ�_�ł���B�����ɂ́u�|�p�Ɓv�u�V�ˁv�̃e�[�}������o���Ă���A��҂̕��w�I�S���_���̐�����`�����Ƃ���܂��ʂ̂��̂Ɉڂ��Ă������Ƃ��Ă���̂����邱�Ƃ��ł��悤�B
�@�ȏ�̂悤�ȓc���l����́A�T���h�̖c��ȍ�i���ň�ʓI�ɂ�����ǂ܂�A�R���X�^���g�Ȑl�C��ۂ��ƂɂȂ�̂ł���B�i�����A��O�`��l�y�[�W�j�B
���̓W�����W���E�T���h�́s���̗d���t����G�v��́k�����Е��Ɂl�i1966�N12���j�œǂ�ŁA�[�����������B�g�����s�J�t�̂ނ�t��ǂ�\�����Ⴂ�A���Z���̂��낾�B���܌��{����������Ȃ��̂����A�����ڂ����u���v�̖�́A�Z�����āk�������Ɂl�i2005�N6��25���j�Ɏ��߂��Ă���B
�@�R�b�X���̃o���{���₶�͕�炵�ނ��������͂Ȃ������B�k�c�c�l�^�u�������̂Ƃ��肾������ˁv�ƃo���{���₶�͎��̂Ƃ���������Ȃ��猾�����B�u���̎q�͂������Č������Ȃ���Ȃ����ƐS�z���ˁB�����āA�́A�ӂ뉮�̃N�����B�G�[�����������Ă��낤�B���̎q�����ɂނ��イ�ɂȂ�����A����قǒ�ɂ����Ď��������肵�Ȃ����낤���ĂˁB���ꂩ��A��������������A�V�����B�l�͂ˁA���܂芴���������邵�A��M�Ƃ�����A�ꐶ�ɂЂƂ�̏����������Ȃ����낤���Ăˁv�i�������ɔŁA���E���l�y�[�W�j
�s���̗d���t��ǂނƁA���ł��������߂�����B�Ƃ���La petite Fadette�i�����ȁ^�����t�@�f�b�g�����̗d���j��������Z�̃V�����B�l�ƒ�̃����h���́A�ꗑ���o�����������B�o�q�̎��́A���̐l���ɂ����Ă��傫�Ȃ��̂ƂȂ邪�A���̂Ƃ��͂܂��Ȃɂ��m��Ȃ��B�����A����ɂ��Ă͕ʂ̋@��ɁB
��{�������M�҂̂ЂƂ�ł���A���{�W�����W���E�T���h�w��i�ҁj�s�Q�O�O�N�ڂ̃W�����W���E�T���h�\�\���߂̍Ő�[�Ǝ�e�j�t�i�V�]�_�A2012�N5��25���j�ŁA����m���q�́q���Ɖ��y�̉z���\�\�w�J�t�̂ނ�x���߂����ār�������Ă���B���̒m��ł����V�ȁs�J�t�̂ނ�t�_�ł���B�Ȃ��A�_�������ɂ́u���{�͂́A�٘_�u�W�����W���E�T���h�ƃx���[�n���\�\�w�J�t�̂ނ�x���߂����āv�i�w���O���ꌤ���_�W�x���O���A��Z���N�j�����e�������̂ł���B�v�ƌ�����B���_�����͂������B
���y�Ɨ���ʂ����قȂ镶���̗Z�a
�@�I�ՂŁA���Ԃ̓W���[�t�̒����ǂ���ɁA�����āu�O�l�̖؏��v�̉̂ǂ���ɂȂ�B�����G���̓u�������b�g�ƌ������A�G�`�G���k�͂��Ĕn�s����̋A��ɏo����u���{�l�o�g�̖��e�����X�i���̓����G���̖��������j���Ȃɂ���B����W���[�t�́A����f�O�����y�̓����Ƃ�B�C�Ƃ̍b�゠���ĒN�����F�߂�r�O�ƂȂ����W���[�t�́A �x���[�̓J�t�̑g���ɉ����A�哪�o�X�`�����ƂƂ��ɕ��Q�̗��ɏo��B�Ƃ��낪�����A�W���[�t�͌|�p�ƋC���炵����ł��̂��߁A���鑺�̓J�t�����Ƃ����������N�����A�E����Ă��܂��B�~�̒��A�x���[���牓�����ꂽ�������@���i�u���S�[�G�j�������ɂ���L��ȐX�юR�n�j�ŁA�W���[�t�̈�̂����������B�����Œɂ߂���ꂽ�͂��̑̂ɂ́A�Ȃ���������������Ȃ������B�ނ͐l�Ԃ̎�ŎE���ꂽ�̂ł͂Ȃ������̂��낤���B�u�J�t�ɂȂ�ɂ͈����ɍ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����A�������@���n���ɌÂ�����`��錾���`���ǂ���̂��Ƃ��N�������̂�������Ȃ��B
�@�k�c�c�l
�@�T���h�́w�A���W�{�[�̕��Ђ��x�ł́A�u�����ɂ��K���̗Z�a�v��`�����B�����Ă��̔��N��́w�J�t�̂ނ�x�ɂ����ẮA�u���y�v�Ɓu���v���\�ɂ���u�z���v�ƁA�����ʂ�����̈قȂ�y�n�̕����̗Z�a�A����Ɍ����ł��̗Z�a����g�̃J�b�v���́u�����v�Ɓu���������v�ɂ���ă��[�g�s�A�Ɍ�������Ƃ����s��ȕ�����������̂ł������B����A�N�����|�p�̓V����L���Ă����W���[�t�́A�܂��ɂ��̓V���ƂЂ������Ɂu�����ɍ���v�A������Ă��܂��B�����C�Ƃւ̏o���Ƃ����ނ́u���v���������̕���̔��[�ł�����A�u���̎ҁv���u�X�̎ҁv�Əo��킹�A�����̗Z�a�������炷���ƂɂȂ����B���̈Ӗ��ŃW���[�t�́u���v����͂�A���̍�i�ɂ�����u�z���v�̏d�v�Ȕ}��Ƃ��Ă̈Ӗ���S���Ă���ƌ����悤�B�i�����A���Z�`����y�[�W�j
�`���Ɉ������q�����w�����Z�L�x�r�̂ق��ɁA�g�����s�J�t�̂ނ�t�ɐG��Ă��鏈�������ЂƂ���B�g�������L��1949�N�i���a��\�l�N�j�u�ꌎ�\���@�W�����W���E�T���h�́s�J�t�̂ނ�t�߂��܂œǂށB�������c�����B�v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�N9��1���A���O�y�[�W�j������ł���B�O�N�i1948�N�j11��12���ɂ́A��͂�q�����w�����Z�L�x�r�ɓo�ꂷ��X�^���_�[���́s�p�����̑m�@�t��Ǘ����Ă���B�ǂ�����ēǂł��낤�B���Ȃ݂ɋg���͓����A���m���Ƃ����o�ŎЂɋΖ����Ă���B�u�ꌎ�\���v�i���j���ł���j�̌ߑO2���܂œǂނƂ����V�g�́A��͂肱�̍�i�ɍ��ꂱ��ł̂��Ƃ��낤�B�s��㐔�N�̂��̎����A�V���{�����ꂵ�Ă������Ƃ�����B�����A�s�J�t�̂ނ�t�ɂ��Ă��s�p�����̑m�@�t�ɂ��Ă��A�g������\����ɓǂ��낤�Ƒ��{�́A1945�N�̋�P�ŗ��e�̏Z��ł������ƂƂƂ��ɏĎ������͂����B���N11���A�h������n����A�҂����g���́A����1949�N�ɂ͎O�\���}����B���ǂ̏\�N�̂̂��A�s�J�t�̂ނ�t��s�p�����̑m�@�t�i�����炭1935�N��1937�N�ɏo���O�쌘�s��̏�E�����́k��g���Ɂl�j�����������ǂ̂悤�ȑz���œǂ݂��������̂��낤�B�����ɂ́A�]�l�̑z�����y�y�����������̂������Ȃ������̂��̂�����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�W�����E�O���V�����i����t����j�s�u�O���[�g�E�M���c�r�[�v��ǂ��t�i�������_�V�ЁA2020�N10��10���j�Ɏ��̂悤�Ȃ����肪����B��l���̃u���[�X�E�P�[�u���́A�t�����_�ŏ��X���c�ދH�Q�{���W�Ƃ����A�����Ƃł���ȏ�ɓǏ��Ƃł����āA�������{���̖��͂ł�����B�u�`���Ƃ܂ł͂����Ȃ��ɂ���A����͔ނɂƂ��ĂЂƂ̏K���ɂȂ��Ă����B�y�C�E�u�b�N�X�͏T�ɓ��A�Ƃ��ɂ͎O��T�C������Â��Ă������A���̒��҂����X����O�ɁA�ނ܂��͔ޏ�������܂łɏo�ł����{���A�u���[�X�͎c�炸�ǂB�ނ͎����×~�ɖ{��ǂB�ނ̍D�݂͌������钘�ҁ\�\���ۂɉ���āA�̔����i����`���A�e�����Ȃ�A����܂ł�������悤�ȑ���\�\�̏������������������A�����ɂ͌��炸�A�`�L�⎩�Ȍ[���m�Z���t�E�w���v�n�{�◿���{����j����A�Ƃɂ��������������Â�悤�ɓǂ݂܂������B���ꂪ�ނɂł���Œ���̂��Ƃ������B�ނ͂����钘�҂��h���������A�����ނ̓X���킴�킴�K��āA�ꏏ�ɐH�����������������A����Ȃ��Ƃ����Ă�����Ƃ�����Ȃ�A����̍�i�ɂ��Ĉӌ������킹�邾���̏��������Ă������ƐS�����߂Ă����B�v�i�����A���܁`���Z�y�[�W�j�B�t�B�b�c�W�F�����h�̒��M���e�����߂��e��̕`�ʁi�O�l�l�`�O�l�܃y�[�W�j���������B��҂��肮���ˈ����ČJ�肾�������B
�i���Q�j�@�s�J�t�̂ނ�t�́q����r�Ɏn�܂�q��O�\���r�ɏI���B�G�`�G���k�������������Ƃ��Ă��A�Ђƌ��ȏォ���銨�肾�B���āA�s�J�t�̂ނ�t�̖́A�M��E����E�R�~�b�N�ŁE�q�������̍Ęb���܂߂��30��ȏ�ɂ��Ȃ�s���̗d���t�\�\���̖͋{���Y�ɂ��\�\�Ɋr�ׂāA�킸���ɋ{���Y��̈��ށB�ق��ɂ͘a�c�B��s�X�̓J�t�t�i�|�v���ЁA1951�j�𐔂���݂̂��B���́s�X�̓J�t�k���E���앨�� 11�l�t�͖��������A��������}���كI�����C���̏����ڍׂɂ́u�W�����W���E�T���h ����, �a�c�` ��, �c���� �G�v�Ƃ���ق��A���肪�������ƂɁq�ڎ��r���̘^����Ă���B�ȉ��ɁA�y�[�W�m���u���̋L�ڂ𗪂��Čf���邪�A�����̍[�T�Ƃ��ēǂ߂�B
�ʂ���݂̓��ŕ�������������
�T���E�V�����`�F�̐X�ł̏o����
�W���[�t���b�J
�u���{���l�F�̐X���炫��途n�t�̃����G��
�����n�l�̍Ղ�̖�
�߂��������
���ɕa�ރW���[�t���~���Ƀu���{���l�F�̐X��
���b�V���̐X�̋��낵��途n�t
�����ꂽ���̏���
�X�̌���
�䂭���m��ʗ���
�X�̉��F�A����̉��F
��̎q��
�V���b�T���̂���̐X
�߂����J�t
�X�̒j�A����̖�
�J�t�̘r�����
�������̏t
�J�t�ɂȂꂽ���j��
�Ï�̌��q
�J�t�̗���
����4��15���͋g�������a������102�N�߂̓����������B�ڂ݂�A�ŋ߂͖{�T�C�g�ŋg���̎����̂��̂���肠����@������Ȃ������B�����ō���́A�g�������̎��^�ɂ��čl�@�������B����ɂ��g�������́A�P�s���W���^��262�сA����}�̂ɔ��\�������̂̒P�s���W�ɂ͎��߂��Ȃ�������������21�сA���e����������Ă���2�сA�̍��킹��285�т��m����B�{�e�ł͑O��҂̌v283�т�ΏۂƂ���B���Ȃ킿�A�g���������O�ɔ��\�����S���тł���B���āA���̋g�������ނ���̂ɁA���܂��܂Ȏ����ݒ�ł���B����ɂ����́i���������j�ƌ���ɂ����́i�命���j�A�����i�A���r�A������[�}�����j��A�X�e���X�N�Ő߂���������́i���قǂ̐��ł͂Ȃ����A�����ɑ���������j�Ƃ����łȂ����́A���ׂēV�c�L�i�������Ȃ��j�̍s�����̂��̂Ǝ������̂���s�����̂��́i������u��ʎ��^�v�j�A�{���̑O�Ɍ�����莫�����̂Ƃ����łȂ����́A���l�ɖ{���̌�ɒ��L��E�e���ƌ�������t�����̂Ƃ����łȂ����́A�����B���e�Ɋւ����̂Ƃ��čł��d�v�Ȃ̂́A����ɑ��҂���̈��p��������̂Ƃ����łȂ����̂ŁA����ɂ��Ă͋g�����̈��p���Ƃ����e�[�}�ł��т��ј_���Ă����i���P�j�B�\�L�ʂɌ����Ă��A�u�@�v��i�@�j�Ȃǂ̊��ʗނ��g�������̂Ƃ����łȂ����́A�B�i��_�j��A�i�Ǔ_�j���g�������̂Ƃ����łȂ����́A�I�i���Q���j��H�i�^�╄�j���g�������̂Ƃ����łȂ����́A�\�\�i�_�[�V�j��c�c�i���[�_�[�j���g�������̂Ƃ����łȂ����́A�Ȃǂ�����B�������^�Ƃ����ʂɌ���A�������ȓ����ɂ�镪�ނ́A�s�����̎��Ǝ������}�X�Œǂ�����ő�����U�����^�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B�U�����^�͋g�������́u�����v�i�s�����G�߁t�Ɓs�t铁t�j�Ɓu����v�i�s��ʁt�Ɓs���[���h���b�v�t�j�ɂ����Ă͂���قǁA�Ƃ������قƂ�nj����Ȃ����A�u�O���v�i�s�Õ��t�`�s�Â��ȉƁt�j�ɂ͕p�ɂɗp���������ŁA�u�����v�i�s�_��I�Ȏ���̎��t�`�s�Ẳ��t�j�ɂ͐�����A�X�e���X�N�Ő߂���������́i���Ȃ�Ȃ��p�ꂾ���u�ߕ������^�v�ƌĂԂ��Ƃɂ���j�̈ꕔ�̐߂ŗp����ȂǁA�ό����݂ɋ�g��������ɓ]���Ă��āA���z�̐��n�Ƃ͓Ɨ������n�Ƃ��āA�����[�����ʂ������Ă���B���̂̏����Ƃ��āA�ǂ̍�i�����R����U�����^�Ȃ̂��A���Ă݂悤�B���т́A���o�`�̔��\���ł����i���Q�j�B�y�@�z���̐����́A��e�ɂ����Ĉ�}�X�����s�ƌ����Ă��Ƃ��̍s���A�܂莍��̐��B
01 ���鐢�E�i�B�E5�j�y24�z
02 �����i�C�E2�j�y28�z
03 �쌀�i�C�E1�j�y37�z
04 �A�d�i�������сE6�j�y23�z
05 ���i�C�E3�j�y25�z
06 �P���i�C�E9�j�y40�z
07 �Ō`�i�C�E11�j�y47�z
08 ���i�C�E12�j�y41�z
09 �`���i�C�E5�j�y30�z���M��1956�N
10 �~�̊G�i�C�E6�j�y41�z���M��1956�N
11 ���������i�C�E16�j�y35�z���M��1958�N
12 �x�����i�������сE7�j�y21�z
13 �����i�D�E3�j�y43�z
14 �a���`�T�i�D�E4�j�y22�z
15 ����i�I�E5�j�y14�z
16 ����i�������сE8�j�y24�z
17 �ҕ����鏗�i�D�E8�j�y30�z
18 ���w�i�D�E7�j�y35�z
19 ���̕a�C�i�D�E11�j�y34�z
20 �a���`�U�i�D�E5�j�y22�z
21 �~�̋x���i�D�E12�j�y21�z
22 ���̂��肠�����i�D�E13�j�y44�z
23 ��`�i�D�E19�j�y36�z
24 �C���Əȗ��i�D�E22�j�y47�z
25 �n�E�t�̊G�i�E�E5�j�y32�z
26 ���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���i�G�E11�j�y67�z
27 �l�H�ԉ��i�I�E19�j�y58�z
�u�O���v�́s�Õ��t��1�сA�s�m���t��9�сA�s�a���`�t��10�сA�s�Â��ȉƁt��1�сA�u�����v�́s�T�t�����E�݁t��1�сA�E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t��2�сA�������т�3�т̌v27�сi���O�ɔ��\�������ёS���̖�1���j�����A�q���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���r�i�G�E11�j�́u�T�v��
�h�W�\���Ƃ̎o�����C�U�@�}�[�K���b�g�@�w�����G�b�^�@�Έ��֑��肱�ޔn�@�Ǐ����Â��鐷���̎O�l�@����Q���̂Ȃ��͊��L�O��
��
���W���[�W�E�}�N�h�i���h�͂Ђ����̂��@���������[�̐O�́@�C�`�W�N�̏`�ł悲���@�w�l�X�̉�����c�^�̗t��点��p��@���ɕ���ā@���̑����̂��
��
�A�O�l�X�E�t�������X�E�v���C�X�͍�������̑傫�Ȑl�`������@�����̂���������ٔ����̎p�������l�`���@�킽���̍߂��āI�@�Ȃ̉��������Ă��邱�Ƃ�
��
�G���U�x�X�E�n�b�Z�[�@�悢������Ƃ��ςȖ��@���o�[�E�n�b�Z�[�����̖��@���̃\�t�@�[�։�������ā@�ߌ�͕��҂@��͈�҂�҂@��͕���҂@���҂����@�킽���͑҂@����������Ղ�҂�
��
�����A�C���[���E�E�B���\���E�g�b�h��@���ɐ����ꂽ���̒���������̖������@���낵�����Ƃɖ̊�����邵�Ă���@����ł���@�����Ă���@�@���Ȃ�̌҂��@���q�ւ������ČZ�̎��݂�����
��
�����猩����G�t�C�[�E�~���G�[�@���ƕ�Ɩ������̑������т����̂��@�ォ��̂������悤�ȋC������
��
�t�t�t���t�����N�����v�l�̖�����Ɏ��Ă���@���ނ��o���̂Ȃ��̃��[�Y�@�q��S�͎����ʼnS���̂�@�o���新��Ȃ���I
��
�}�����A�E�z���C�g�̔����}�������낪���Ă䂭�@�~��Ƃ��낪���邾�낤���@�����x�X�E�p���X�̑��d�Ȗ�Ŏ~��@������������ďf�������߂�����
��
�}�f���C���E�L���T�����E�p�[�l���@���������D���@�����т��D���@���炪�D��
��
�b�E�o�[�J�[�q�t�̖����C�͈֎q�̏�֗����Ă���@�C�̂܂܁@���̘T�S�̜����@�\��ɂȂ������т����
��
�����[�N���X�}�X�@�a�߂��@�a�߂鎵�ʒ��̐��@�킽���̓��A���[�E�}�N�h�i���h�@�W���[�W�E�}�N�h�i���h�̖��@�������܂��Ǝo�@�������������炢
��
�G���E���j�A�E�E�C���A���Y�@�L�����ق����ő|���@�ǂ��܂ł��ǂ��܂ł��Â��Ɓ@�����͍����́u�����v�ƂЂƂ��Ɖ]����
��
��ȍٔ����f���}�����̖��O���C�X�E�f���}���@�̊K�i�̈�ԉ����ޏ��̌e���̐��E�@�d���傫�ȒȂŐԂ��J�j���ꌂ������@�����鏗�̐S�ɂ����Â�
��
���͌|�p�ƃA�[�T�[�E�q���[�Y�@����ꂽ���̃A�O�l�X�@�E�T�M�̂悤�ɖт̂��镞�𒅂ā@���������������Ȃ�@�t����Ă܂Ł@�L�d�^�̒I�̉��̏��g�����̗�
�Ƃ����悤�ɁA���i�A�X�e���X�N�j�ŋ��ꂽ���ꂼ��̐߂��U�����^���Ƃ��Ă���i���́A�u�ߕ������^�v�̎U�����^�Ƃ����X�^�C���͋g�������ł͖{�т����j�B���������́u�U�v�����قȎ��^�Ȃ̂ŁA�ȉ��Ɍf����B�\���Ȃ���A�{�т͋g�������ɂ�����Œ��̎U�����^�ł���Ɠ����ɁA���R���邻�̎��^�ŏ����ꂽ�Ō�̍�i�ł�����B
�e�j�\���v�l�̖ÃA�O�l�X�E�O���C�X�E�E�F���h�͐Ԃ���n���Ђƃ}���g�𒅂��@�n�̂�����ɗc���F�������Ăԁ@�N���t�g�q�t�ق̎g�p�l�̖��@�w���́u�R�[�c�v�@�����̖��G���U�x�X�E�n�b�Z�[�@�|�p�Ƃ̖��G�~�C�E�q���[�Y�@�s�E�a�E�X�g�����O���m�̖Ã]�[�C�@�W���[�W�E�}�N�h�i���h�̖��@�������܂��Ƃ����Ȃ��A�C���[���@���̎o���A���[�@�p�g�j�[�̋���q�t�̖��x�A�g���X�E�w�����[�@�G�����E�e���C�̖������}���I���ƃt�������X�@���|���m���̖��t���[�����X�E�r�b�J�[�X�e�X�@�s���[�W�[���m�̑����P�C�e�B�[�E�u���C���@�W�����E�~���[�̖����A���@�N�����{�[������q�t�̖��f�B���t�i�E�G���X
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x��Ă����̂͒N�H�@����x�߂̖��̕��������A���N�T���h���E�L�b�`������@���Ƃ��̃N�V�C�[�@���������݂ɍs���ā@�ŏ��Ɍ����̂͂Ȃ�Ȃ́H�@���̋�����Ƃ��M�𑆂��_�v�@����߂����̉��̖ԁ@�������Ă�@�x�߂̃E�O�C�X�͂ǂ�Ȗ��������邩�H�@�y���V���͗l�̔��̔��̏�Ł@���݂�N�V�C�[��@��̂قƂ�ōŌ�Ɍ������̂͂Ȃ�Ȃ́H�@�@���Ȃ����g�̓��́@���̉e�ɐS������悤�Ł@�Ȃ��悤�Ɍ�����@�Ȃ܂߂��������c�������H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�݂�Ȃł��ꂩ��L���������������T���̂�@����͕�тŊ����ꂽ�H��Q�̂Ȃ��Ł@�����ԑ����������l����I
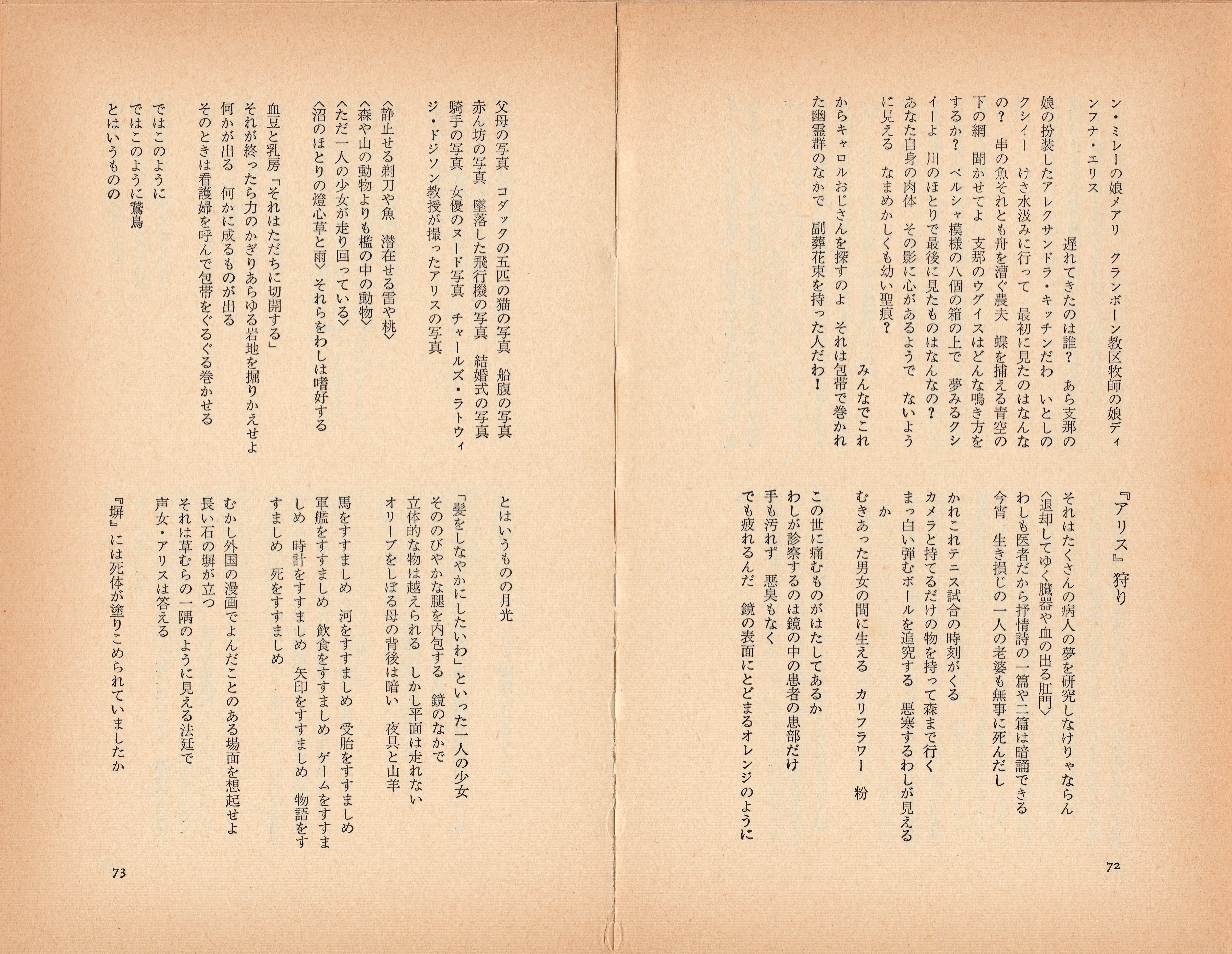 �@
�@
�s�V�I�g�������W�k�V�I���㎍����110�l�t�i�v���ЁA��2���F1979�N10��1���k��1���F1978�N6��15���l�j�́q���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���r�i�G�E11�j�́u�U�v�����Ɓq�w�A���X�x���r�i�G�E12�j�`�� �k�q�����`���r�̎��l�߂́s�T�t�����E�݁t�A�s�g�����S���W�t�A�{���Ƃ���25���B����A�q�w�A���X�x���r�̎��l�߂́s�T�t�����E�݁t�A�s�g�����S���W�t�ł�28���A�{���ł�25���i2�i�g�̕��ɔłƂ����A���ʂ��炭�鐧��ɂ��j�B�l�i���j�Ə��o�q���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���r�́u�U�v�i�`���j �o�T�F�s�ʍ����㎍�蒟�@���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�t�i�v���ЁA1972�N6���k1��2���l�A��Z�O�y�[�W�j �k�u�_�C���t�i�E�G���X���^���������������������x��Ă����̂͒N�H�@����x�߂́v�i���͈�}�X�������j�̋Ǝ������̊W�ɂ����ڂ������������B�l�i�E�j
�u�x��Ă����̂͒N�H�v��10�������A�u�݂�Ȃł��ꂩ��L���������������T���̂�v��19�������͐�Βl�ł͂Ȃ��A���o������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA���ꂼ�ꂻ�̑O�̎���u�N�����{�[������q�t�̖��f�B���t�i�E�G���X�v�A�u�Ȃ܂߂��������c�������H�v���܂ޑO�s�̕������i���o�ł�10����19���j�Ƃ����̂���{�\���ł���B����͉����ɂ�鎍�Ō���������s�̎d���Ȃ̂Łi�g����������M�����Œm�����̂ł͂Ȃ����j�A�����炭�ŗL�̌Ăі�������̂��낤���A�s���Ȏ��ɂ͂킩��Ȃ��B�Ȃ��A���̓_�ɂ����~�������q�g�������W�s�T�t�����E�݁t�{���Z�فr�̖������Q�Ƃ��ꂽ���B����A���ёS�̂ł͂Ȃ��A�ꕔ���ɎU�����^���p�����Ă����i�͈ȉ��Ɍf����6�тƂ������ƂɂȂ�B�ŏ��́q���b�r�i�B�E15�j�́A�U�����^�i�����Ȃ����ƁA20���l�߂Ő܂肩�����������̂ӂ��j�ƍs�����̍��������A�ق��ɂȂ����قȃX�^�C���Ȃ̂ŁA�S�����f����B�Ȃ��A���p���т̕W��̂܂��ɂ́����t�����B
�����b�i�B�E15�j
�����̐�C��墁@�ƂяI��@�����n���̗ނ́@���݂̈Â��肩��@���Ƃ����肵�ā@��i�Ɛ[�����E�֒��݂䂫
�Ԃ߂̂Ȃ��@�^�Ă̎d����@������̏d�����@�������ɂ邳���@���S�ɏ�߂�ꂽ��ԁ@���łɐl�Ԃ̂͂������̉����Ƃ�������
�����̓X��̒�����̂����Ɂ@�����Ȃ������Ȃ��@��̓��̌��^�@������ꂽ�悤�Ɂ@�悱�������
���ׂĂ̂��̂̎�����ꗧ��
���ׂĂ̂��̂̐オ������鎞
��ɂ��ꂩ��͂��ꂽ�Î��̓��̐_
�������ߋ��@���̐^���̋�݂悤�Ƃ���
�@�@�Â����z�Ƃ݂ǂ�̑��@���D�̒��ŋP���@��
�@�@�Ɛ����@�p�̊Ԃւڂ��ڂ������Ƃ��@����
�@�@����l���̉��Ł@�݂����[�Ẳ_�@������
�@�@�E���@���̘m�̒��Ł@�˂ɔ�䍂����@��
�@�@��̃G�N�X�^�V�C
�@�@�n���̒[���@���ꂽ�@�Â�Ŗ`���@�����ȏ�
�@�@���Ɓ@�����̟��@�Ƃ��ɖĂ̐K�̌��@�_�Z��
�@�@�g�̍������@�`�R���Â��ق��߂Ă䂭
�@�@���\�\�����ʂ́@�������A�̊C
��l�̔L���̂����ʁ@���߂����[��̃z���]���g�@���Ȃ킿�X��̕�������`�̏��Y��������܂��@�ꂽ���̈ߑ��̂�������@�G�����ꂽ���́@�ˑR��������݂�����@�݂�݂�`�����ꂾ���@���̉����̑�
�ւ�������Ł@�邠���܂ł݂Ԃ邢����@�����̐�C���
�ȉ��A�Y�����鎍�т̎U�����^�̕����𒊏o����i�k�c�c�l�̏ȗ������͍s�����X�^�C���j�B
���^�R�i�G�E2�j�̑�2��
��
�k�c�c�l
��
�^�R�̐��B�͂ƂĂ����ꂽ�t�H�[����������@����͔G��ėꂽ�P�̂悤�ȓ��̎U���ɂ������@�^�R�̃I�X�̎��̑��͐���������ށ@�����Ďc���ꂽ������ׂ�̈�̑��������̊튯�̖�ڂ�����@������ƌ���Ɓ@�C�̕R�̂悤�ɂ݂��ڂ炵���@�^�R�̃��X�̏����ȍE��T�����߂ē��肱�ށ@���ꂪ��ڂƂ����邾�낤���@���͋N�����ĂȂ����@�����Ȑ��E�ł͉x�т��Ȃ��ː��͏I��@�������Ƀ^�R�̃��X�݂̂Ђ炩�ꂽ�Ⴊ����@����ɂ͔Đ_�_�I�Ȉ��ӂ���������@��ق���^�R�̃��X�͊C�̒�̐̑��ւ������A���čs���@��\�����̓����ȗ��ނ��߂Ɂ@���ꂩ���H��Ԃ̂܂܁@�u�h�E�̖[�̂悤�ɂ��ꂳ�������܂̗��Q�ց@�K���ɖA�𐁂��Â���@����͌ċz�ɕK�v�Ȏ_�f�𑗂邽�߂��@��炮�C���̂����Ł@�^�R�̕�e�͂�����x�̔r���ŕ�������ւƑւ�
��
�k�c�c�l
���t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�i�G�E17�j�̑�4��
�k�c�c�l
��
�G�X�L���[�͂ǂ����ĔL��`���Ȃ��̂��낤�@���J�i�_�E�G�X�L���[�W������Ȃ���@�킽���ƍȂ͂ӂ����Ɏv�����@�����̓��m�N���[���̂����炵�Ƌ��ł���@���������ނ��o���ā@�X�̎R�̒��Ɂ@���̂悤�ɋP���Ă��邹�������@���̂ق��͂ӂ��낤�̊G���肾�����@�n���ɖ��鋛�̗t��������ā@���̂���H���Ђ낰�Ă����@���̊�͏��̋����̕\������@�Â��Ԃ̌Q���̂Ȃ��Ł@�܂ꂽ����~���Ă���@������H�̑傫�Ȃӂ��낤���݂߂Ă���Ɓ@�₪�ĔL�ɕϖe����悤�Ɂ@�킽���ƍȂɂ͎v�����@�����̃G�X�L���[�̍��ɂ́@���Ƃ͎q���ƌ������Z��ł��Ȃ��̂��낤
��
�k�c�c�l
���w�A���X�x���i�G�E12�j�̑�4�E9�E15��
�k�c�c�l
����̎ʐ^�@�R�_�b�N�̌ܕC�̔L�̎ʐ^�@�D���̎ʐ^�@�Ԃ�V�̎ʐ^�@�ė�������s�@�̎ʐ^�@�������̎ʐ^�@�R��̎ʐ^�@���D�̃k�[�h�ʐ^�@�`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\���������B�����A���X�̎ʐ^
�k�c�c�l
�n�������܂��߁@�͂������܂��߁@��ق������܂��߁@�R�͂������܂��߁@���H�������܂��߁@�Q�[���������܂��߁@���v�������܂��߁@���������܂��߁@����������܂��߁@���������܂���
�k�c�c�l
�킵�̒m���Ƃ�
�u������l�̃A���X�͏\���ɂȂ��Ă��@�p��̔���ɐK��
�ڑł���@����Ƃ��̓Y�b�N�̑܂ɋl�߂��ā@�V��ɒ݂�
�����@���������̃A���X�E�~���[���C�c�c�v
�k�c�c�l
�q�w�A���X�x���r�i�G�E12�j��3�ӏ��́A�q�^�R�r��q�t�H�[�T�C�h�Ƃ̔L�r�Ƃ͈�������z�ŏ�����Ă���B�����̏��o�͖q�_�Њ��́s�A���X�̊G�{�\�\�A���X�̕s�v�c�Ȑ��E�t�i1973�N5��1���j�̓��`��l�y�[�W�i���Ȃ킿���J���ӂ��ł͂Ȃ��j�ɁA�u�A���X���̂��߂̃A���X�H�[�@Alice workshop for the hunting of Alice�v���̈�тƂ��āA1�߁�4�s��19�ߑS76�s�̎��Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�B76�s�ɐߊԃA�L��18�s���������94�s�ƂȂ�A�u�A���X���e�[�}�ɁA100�s�̎����v�Ǝ��M�˗����ꂽ�̂�������Ȃ��B����͂Ƃ������A�g����100�s�̎��������̂ł͂Ȃ��A
�@����͂�������̕a�l�̖����������Ȃ����Ȃ��
�@�q�ދp���Ă䂭����⌌�̏o�����r
�@�킵����҂�����R��̈�т��т͈��u�ł���
�@�����@���������̈�l�̘V�k�������Ɏ���
�Ǝn�܂�
�@�Ă̋�̐F�����鎞
�@�킵�����l�����炽�܂ɂ͌`����I�ȉ���������
�@�����@���������̈�l�̏����́w�x��Ǒz����
�@���܂��鉮���̏�̐l�@����͓������m�ꂸ�H
�ƏI��錆����������B���̎��̍ŏ��ƍŌ�̐߂�4�s���琬�邱�Ƃ��K�R�I�ȋٖ��ȍ\�����Ƃ��Ă���B����A�u����̎ʐ^�@�R�_�b�N�̌ܕC�̔L�̎ʐ^�@�D���̎ʐ^�@�Ԃ�V�̎ʐ^�@�ė�������s�@�̎ʐ^�@�������̎ʐ^�@�R��̎ʐ^�@���D�̃k�[�h�ʐ^�@�`���[���Y�E���g�E�B�W�E�h�W�\���������B�����A���X�̎ʐ^�v�́u�c�c�̎ʐ^�v��9��A�u�n�������܂��߁@�͂������܂��߁@��ق������܂��߁@�R�͂������܂��߁@���H�������܂��߁@�Q�[���������܂��߁@���v�������܂��߁@���������܂��߁@����������܂��߁@���������܂��߁v�́u�c�c�������܂��߁v��10��J�肩������Ă���A�������4�Ŋ��肫��Ȃ��i���ꂪ����8��ł���A�u�c�c�̎ʐ^�@�c�c�̎ʐ^�^�c�c�̎ʐ^�@�c�c�̎ʐ^�^�c�c�̎ʐ^�@�c�c�̎ʐ^�^�c�c�̎ʐ^�@�c�c�̎ʐ^�v�Ƃ��邱�Ƃ��A���邢�͂ł������낤�j�B�܂肱����28���l�߁i�O�f�s�V�I�g�������W�k�V�I���㎍����110�l�t�ł�25���l�߁j�Ƃ������̔��Ɉ�}�X�ŋ��������𗬂�����ŁA���ꂪ���܂���������4�s�ɂȂ����A�Ƃł��������z�\�\�����̉ߒ��ɂȂ��Ă���B����́u�킵�̒m���Ƃ�v�������ꂽ3�s�\�\�s��权N���u�k�Վ��������l�t�i�����[�A1953�N12��20���j�f�ڂ̃T�f�B�E�u���b�P�C�Y�i��ȐV��j���|���m�����s�A���X�̐l���w�Z�t�̎�l���̖��́u�A���X�E�~���[���C�v�ł���\�\���u�@�v�i�ꊇ�ʁj�Ɍ����Ă����̂ł��邱�Ƃɓ������B����ɂ���́A��@�Ƃ��Ắq���b�r��20���l�߂Ő܂肩�����������Ɠ������B
�u�@�v�Ŋ���ꂽ����́A���́q���J�̎p������r�́u�q���z�̋{�a�r�Ƃ����ٌ`�̓��́@�O�\���N�������ā@�V�����@���Ƃ����X�֔z�B�v���@���X�̎d���̓r���@���Ђ낢�@�����ς�Ō��Ă����̂ł���v�Ɠ��l�A�i�o�T��T���ł��Ă��Ȃ��̂����A�����炭�j�����̋�Ǔ_����}�X�ɒu�������Ĉ��p���Ă���͂����i���R�j�B����͂��łɋ������q�l�H�ԉ��r�i�I�E19�j�̎���ꂪ��Ǔ_����}�X�ɕύX�����̂ƋO����ɂ���B�܂�A���l�̕����̈��p�A�����̋���̏C�����킸�A�U���i�\�L�j�����ɓ]����ɂ������ċg���̍̂�����@���U�����^���������킯�ł���B���̐��F�͂ǂ��ɂ��邩�B����́A�����q�g��i���Ɏ~��r�̍ŏI����11�߂Ɍ��邱�Ƃ��ł���i���T�A���p���̌����Ɋւ��Ă��q�q�g��i���Ɏ~��r�{���̂��Ɓr���Q�Ƃ̂��Ɓj�B
�����J�̎p������i�H�E14�j�̑�7��
�k�c�c�l
7
�k�c�c�l
�u�q���z�̋{�a�r�Ƃ����ٌ`�̓��́@�O�\���N�������ā@�V�����@���Ƃ����X�֔z�B�v���@���X�̎d���̓r���@���Ђ낢�@�����ς�Ō��Ă����̂ł���v
�k�c�c�l
��������ܒf�����сi�K�E12�j�̑�W��
�k�c�c�l
�W�@�̉��lj�
���́i�[���j�Ő��܂ꂽ�̂��^�퐶�̓܂�����̉��Ł^���̔閧�͕��ꂵ���m��Ȃ��^�����i���̗������j�^���C�̂悤�ȁi���́j�𒅂����ā^���߂ĎY����������^�݂ǂ育�ɐ���^�u���L�̍��ŕЌI�������ɗ������܂��^�ØI�I�^������r����������t���^�����̎q���֕ς�^�ق�Ƃ��ɗ₦���������D���^�Ă̂Ђ邳����^�o�Ƃ͓ˑR�Ɂi�Ɓj���炢�Ȃ��Ȃ���̂��^
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������č~��ė���^���[���O�̖ʂ̏��Ł^����ł���T�^�������Ȃ��玀��ł���l�����^���̂��킮���Ɍ����ā^�����鏤�l������^���e�͂�����i�_�i�j�Ƃ��đ厖�ɂ���^���̗t����̗t�̏�Ɂ^���낪��H�ʁ^�܂����[�œ]��ł���V�l�����������^���͔̂������ꂽ�ʂɁ^�N�������Ł^�e�̊G��`���^���łɁi���A�j���^�����������c�������Ă���^���������^���͔��������N�ւƁ^�g�̏䂪�L�т�^�Ȃ܂Ȃ܂����ւ̔����k�^
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̎��ʒ����z���z���Ɩ��^���������ꂽ�^���̂悤�ɐ��サ�Ă���l�̐��^�I�̏ォ�珵���L���]����^�Â����\�ւƂ�ł����鐝�^�V��̖ʂ₨���߂̖ʂ��|����ꂽ�^�e���ǁ^�G�ꂽ╁^�Q���ɓ���Ɓ^����ނ��ā^�`�ȂǚT���Ă���^�ԉŎp�̐l��z���^���̍��́i���̒��b���̂悤�Ȏ��j�^
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ݖ��r�̊ԂɁ^����ꂽ�w偂̑����j�ꂽ�^���Ǝ�@�̂ɂ����̂���^��e�̌��ɂ����^�̊Ԃɒu���ꂽ�^䪉ׂ͗҂����^�j�K���̌������i����j�^�ǂ�ǂ�F�̕ς��Ă䂭�^�I�����Ă���Z�^�Â��Ђ̂悤�ȁ^�L���̂���^�|�����̗��^
�@�@�@�쉱�̎�����^���邨����킯���^���Ȃ�Ԃ������̓��{�̏��������^���]�̍��C�^����ł䂫�^�l���炢�̉��͐[���^��C�ŏo���Ă���悤�Ɂ^������ꂽ�^���̔ӏH�^�J�͕��́i����j�ɍ~�蒍���^
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���͂��܂ł́i���_�j�̟������炵�Ă���^�l�̂̓~�^���Y�̂悤�ȕa�C�̒j���^�����Ƃ̕��ۂŐ��������Ă���^�i�����j���i����j�^����^�n������ɎN����Ă�����i�^���S�̉ΉԂ���^�i�l�ԁj�͉Ύ�����ė���^���͈ꐶ�J���������Ă��ā^�邵�����Ǝv������^���̊�����^�Ƃ̂Ȃ��ŕ��������ʂ��݂�^���L���o�n�����Ő��Ă���^�i���ԁj�^�i���ɏI��Ȃ����́\�\
�k�c�c�l
���́q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�ɂ����鎚�����̌������A�O�f�q���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���r�����o�`�ō̂�����@�Ɠ����ł���B�������A�q�����`���r����}�X�Ŏ��������Ă����̂ɑ��āA�q������ܒf�����сr�́^�i�X���b�V���j�ŋ���Ă����i���S�j�B����ɂ��A�s���ɋ�肪����ꍇ���A�u�@�v�i��}�X�j�����u�^�v�i�X���b�V���j�̂ق�����R�������Ȃ��Ȃ�B�ǂ�Ȏ��l�߂ł��A�ŏI�s�������A��`�̉�𐬂������u���b�N���ێ������B
���Ă����̊��S�E�U�����^�ƕs���S�E�U�����^�̎��Ⴉ��A�Ȃɂ������邾�낤���B�܂�����̖��x�̖�肪����B���Ƃ���
��͂��������������ɂ���
���̂Ȃ���
����ɒu���ꂽ
��������
���̂���C���ʂ�����
�M�̂�����
�Ђ����ɉ�̂���
�����
���̎M�ֈڂ�
�����ɐ��̋Q��͋��������
���̎M�̂��ڂ݂�
�ŏ��͂�����
���ɗ����Ăѓ����
�Ƃ����I���W�i���ƁA������U�����^�ɕς���
��͂��������������ɂ���@���̂Ȃ��Ɂ@����ɒu���ꂽ�@���������@���̂���C���ʂ������@�M�̂����Ł@�Ђ����ɉ�̂���@����́@���̎M�ֈڂ�@�����ɐ��̋Q��͋��������@���̎M�̂��ڂ݂Ɂ@�ŏ��͂������@���ɗ����Ăѓ����
�Ƃł́A�傫����ۂ��قȂ�B
�\�\�Ƃ��ɁA���l�œ��{�ߑ㕶�w�ٖ��_�ْ��̒������́A���ٗ����������2002�N4���A�g���z�q�v�l����g�����̎��W�s�Õ��t�̍e�{�i���W����p���e�j�����ꂽ�B��f�́q�Õ��r�i�B�E2�j�͓����A�e�{�Œ����u�T�@�Õ��v�̂������Ƃɒu����Ă����A������e���ɂ�����s�Õ��t�̊������тł���B�����́A�ߒ��s���㎍�̊ӏ܁t�i�y�ЁA2020�N12��15���j�́q�g�����r�Ŗ{�т�S�s�����Ē��J�ɓǂ݂Ƃ��Ă����i���T�j�B�u�u���ɋH��Ȃ鎍�̓ǂݎ�v�Ǝ��̂��Ă���v�i�g�����q���z�r�A�s���㎍�蒟�t1980�N2�����k��\�����ܔ��\�l�A��y�[�W�j�����ɂӂ��킵���ǂ݂Ԃ�ł���B�����u�g���������܌ܔN�Ɏ��ƔłŊ��s������ꎍ�W�w�Õ��x�́w�m���x�ɔ�ׁA��قLj�ʂ̓ǎ҂ɂƂ��ēǂ݂₷�����W�ł���B���̖`���Ɏ��߂�ꂽ��i�u�Õ��v���܂��ǂނ��ƂƂ���B�ȉ��̂Ƃ���ł���B�v�i�����A��l���y�[�W�j�A����Ɂu�����������̖{���ł���A������݂�A�����͍����܂Ƃ��Ă���]�v���ɂ����Ȃ��B�������������Ă������߂ɋ]���ɂȂ��Ă��鋛�̍��i���Ȃ����̎��_���珑����Ă��邩��A�M�ɍ��������c��A���̎��͓ǎ҂Ɉ��D������������B�����čŌ�ɗ���������Ď����ɂ����V�������̒a�����������Ă���B�g�����̑�ꎍ�W�̊�����������ɂӂ��킵������ł���B�v�i��l��y�[�W�j�Ɓu��ꎍ�W�v�u�`���v�u�����v���������Ă���̂͂������Ȃ��̂��B�����̔��ĂŁs�Õ��t�̍e�{�����{�ߑ㕶�w�قɊ��ꂽ���Ƃ́A���M�发�����B�����āA�e�{����ɂ��Ċ����������낤���Ƃ��z���ɓ�Ȃ��i�������قōe�{�����邱�Ƃ��ł����Ƃ��́A�g�����̎��M�̎����Ƃ��āA����ȏ�̂��̂͑��݂��Ȃ����낤�Ɗ������j�B�����A�����܂ł������́s���㎍�̊ӏ܁t�����{�́s�Õ��t�i�g���́u��㏉�̎��W�v�ł���j��Ώۂɂ���ȏ�A���́u�����v�̎����q�Õ��k��̊�̍d���ʂ̓��Łl�r�i�B�E1�j�ł��邱�Ƃ͓����Ȃ��B�\�\
�q�Õ��r�i�B�E2�j�ɖ߂낤�B�u��͂��������������ɂ���^���̂Ȃ��Ɂ^����ɒu���ꂽ�^���������^���̂���C���ʂ������^�M�̂����Ł^�Ђ����ɉ�̂���^����́^���̎M�ֈڂ�^�����ɐ��̋Q��͋��������^���̎M�̂��ڂ݂Ɂ^�ŏ��͂������^���ɗ����Ăѓ����v�ł͕ʂ̎��̊�����������B�Ƃ��������A����͍s�����������p����ہA�X�y�[�X�̊W�ʼn��s�ӏ����^�ŕ\�������Ƃ���ۂ������B�����Ȃ̂��A�U�����^�̍ŏ��̈�ۂ͍s�����������s�����ɒǂ������сA�Ƃ������̂ł����i���U�j�B��������́A�����ɔے肳���B�U�����^�̋�`�̉�䂦�ɁB�s���S�E�U�����^���O����s�����̎��ň͂܂�Ă������Ƃ�z�N���悤�B�܂�A�g���͂��鎍�тŁA�ÏW���ׂ����߂ɎU�����^��p���āA�s�����̎��Ɉٕ����������̂ł���B�U�����^�ɂ͂��̋�`���\�����ׂ��A���̎��l�߂��ݒ肳���i�g���́A��i�ɉ����āA�������s�����1�s������̃X�g���[�N��ς��Ă���j�B����ƁA��̍s�����̎��̎���̉������x���鉽�}�X���̃X�y�[�X���I�悷��B���́A��s�̂𐄂��������C�̂悤�Ȏx�������A���m�ȏd�ʂ��������s�����̎��̎���������Ȃ��Ȃ���x���Ă��������������B���������āA������Ӑ}�I�ɑ��삷��u�������܂����Ƃ��Ɂu��ʎ��^�v���o�������̂́A�g�������̓W�J��A�K�R�ł������i���V�j�B
��
�c������̏������W�s�l��̓��Ɩ�t�i�����n���ЁA1956�N3��30���j�͇T�`�W�̃p�[�g���琬��B�T�́q��������l�r�Ȃ�6�сA�U�́q������r�Ȃ�9�сA�V�́q�l��̓��Ɩ�r�Ȃ�8�сA�W�́q���l�Z�N��E�ār�Ȃ�3�тŁA���W�͂�����26�тō\�������B���^�͇U��9�т��U�����^�ł���ق��́A�s�����̎��ł���B�U�̍ŏ��ɒu���ꂽ�q������r�������B
������b�c������
�@�h�C�c�̕�����ł݂����镗�i���@���ܔނ̊�O�ɂ���@����͉��������ɓ��Ă䂭�Ñ�s�s�̘��Ր}�̂悤�ł�����@���邢�͐[�邩�疢���ɓ�����Ă䂭�ߑ�̌��R��͂����ʎ���̂��Ƃ��ɂ��z��ꂽ
�@���̒j�@�܂莄�����͂��߂��ނ́@��N�ɂ��ĕ����E�����@���̏H�@��e�͔�������������
���̎��͓�̐߂��琬�邪�A���ꂼ��̖`���͈ꎚ�����ŁA���ꎩ�͎̂��������Ђ���ڂɂ���U���̌`���Ɠ����ł���i�g�����́A�U�����^�ɂ����Ĉꎚ���������Ȃ��j�B���̃X�^�C���́A�߂̊Ԃ̈�s���܂߂āA�U�Ɏ��߂�ꂽ���̎��с\�\�q���߂鎛�r�q�������z�r�q�H�r�q���r�q�\���r�q�c��r�q�~�̉��y�r�\�\�������ł���B�����A�U��7�Ԃ߂ɒu���ꂽ�q�C���W�r�͂���Ƃ͌`�Ԃ��قɂ���B�S���������B
�C���W�b�c������
���̓H��A
���̓ΐF�̓s��́A
�J�̒��̂˂��ꂽ���̌Q��A
�����啎P�́A���ł����o���̗���B
�@���̒j�́A�킽���̕��ł͂Ȃ��A����ɁA�킽���̌ǓƂȗF�l���Ƃ����킯�ł��Ȃ��B�����킽���́A�ނƓ������݂ł���A�o���ł���A�܂������̃C���W�������̂ɂ����Ȃ��B�����āA�킽���͔ނ̂悤�ɁA���̑��̂Ƃ�����A���̑��ł��Ǝ���ł��܂��̂��B
�@�֎q���|���悤�ɓ|���I�@���ꂪ�킽���̌Â��C���W�ł���A�D�̒��ɂ���Ⴊ���݂����ւ̊�]�����B
�@������ꂽ��A�Ђт�ꂽ���̊z�A���̖т̂ɂԂ�����A����ɁA�C�Ɩ\���J�Ƒ傫�Ȍ��e�ɔG�ꂽ�����ߕ�����A���̓�j�l�́A�Â��ȋ������A���r�����Ђт����āA�T���̖�́A�H����~�ɂ����ė���閶�̒�����ނ������Ă���Ƃ��A�킽���͋������ɂ͂����Ȃ��A�u���݂͂ǂ����痈���̂��I�v
�@�킽���͌��̂悤�ɐ�𐂂炵�Ă���B
���߂�4�s�͍s�����̎���A�u���̒j�́A�k�c�c�l�v�Ɓu������ꂽ��A�k�c�c�l�v�Ɓu�킽���͌��̂悤�ɐ�𐂂炵�Ă���B�v�̎O�̐߂́A�U�����^�ł͂Ȃ��B�`�Ԃ����邩����A�ꎚ�����Ŏn�܂�A��Ǔ_�Ɗ��Q�������u�U���v���̂��̂ł���B�c���͂Ȃ�
���̓H��
���̓ΐF�̓s���
�J�̒��̂˂��ꂽ���̌Q��
�����啎P�́@���ł����o���̗���
�ƕ����̋�Ǔ_����肳��`�A�����̂������}�X�ɂ���`
�@������ꂽ��@�Ђт�ꂽ���̊z�@���̖т̂ɂԂ�����@����Ɂ@�C�Ɩ\���J�Ƒ傫�Ȍ��e�ɔG�ꂽ�����ߕ�����@���̓�j�l�́@�Â��ȋ������@���r�����Ђт����ā@�T���̖�́@�H����~�ɂ����ė���閶�̒�����ނ������Ă���Ƃ��@�킽���͋������ɂ͂����Ȃ��@�u���݂͂ǂ����痈���̂��I�v
�Ƃ����ӂ��ɂ��Ȃ������̂��B���͂����̎��̏��o�`�����Ă��Ȃ��̂����i���������āA���̔��\�������m��Ȃ��̂����j�A����������Ɓq�C���W�r�͇U�̂Ȃ��ōł����������ɏ����ꂽ���т������̂ł͂Ȃ����i���W�j�B�g���́q���b�r�Ɓq���鐢�E�r�̊W����A���͂���Ȃ��Ƃ𐄑�����B��̂Ƀ��_�j�X�g�ɂ͍�i�̌`����\���ɕq���Ȏ҂������i���Ƃ��Ώ����ƁE�ےJ�ˈ�j�A�g�������̗�ɘR��Ȃ��B�{�e�ł͂��܂܂ŐG��Ȃ��������A������U�����^�ɂ́A�傫�������ċ�Ǔ_���܂ށA�������͒ʏ�̎U���Ƃ܂����������^�ƁA�g�������̂悤�Ȉ�}�X�邱�ƂŎ���̋��Ƃ���^�̂ӂ������낤�B�O�҂͂ӂ��A�u�U�����v�ƌĂ��B�\�\���Ƃ��������i1907�`1991�j�̍�i�\�\�B��҂́u�U�����^�v��������A�N�ɂ���Ďn�߂�ꂽ���ڂ炩�ɂ��Ȃ��B�z���������܂�������A�g�����͂����炭�s�r�n�t�̎��l�����̍�i�\�\���Ƃ��Γc������i1923�`1998�j�̂���\�\���Q�ς��āA�������̍����Ă������^�o�����̂ł͂Ȃ����B�c���̍앗���v�킹��q���̏ё��r�i�B�E16�j�̂����܂��ɍŏ����̎U�����^��i�̂ЂƂq���b�r�i�B�E15�j���u����Ă���̂��A���̈�ۂ����߂Ă���B����ɋg�����Ɠ�����́A���̎��l�����\�\�O�D�L��Y�i1920�`1992�j��k�����Y�i1922�`1992�j�\�\�̍�i���ڂ������Ă������Ƃ��ł���A�Ȃɂ����킩��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�k�t�L�l
�c������́A�Ƃ��Ɍ�N�ɂȂ�قǁA���тɎ��݂̐l���i�₻�̍�i�j��o�ꂳ���邱�Ƃ������Ȃ����B���̕M���͂����炭���e���O�Y�i1894�`1982�j���낤�B�s�V�N�̎莆�t�i�y�ЁA1973�j�́q�s��`�̔L�r�ȗ��A�u���O�Y�搶�Ɂv�ƌ����̂���q�D�F��俁r�i���j�A�s����t�i�͏o���[�V�ЁA1976�j�́q�t�����r�A�s����t�i�W�p�ЁA1978�j�́q�ċx�݁r�A�s�X�R�b�g�����h�̐��ԏ����t�i�y�ЁA1982�j�́q�킪�̋��̈̐l�Ƃ��̋Ɛсr�A�s�z�C�Ȑ��I���t�i�͏o���[�V�ЁA1983�j�́q��̊�r�A�s���C�����b�h�̉Ď��t�i�W�p�ЁA1985�j�́q�Ď�����~���܂Łr�Ɓq���C�����b�h�̉Ď��r�Ɓq�����߁r�A�s�n�~���O�o�[�h�t�i�y�ЁA1992�j�́q���̗��n�ɂ́r�A�s�D�F�̃m�[�g�t�i�W�p�ЁA1993�j�́q�D�F�̃m�[�g�r�A�s1999�t�i�W�p�ЁA1998�j�́q���̖r�A�s�A���Ă������l�t�i�����V���ЁA1998�j�́q���r�A�����āq�X�q�̉��ɂ͊炪����r�Ɓq�閾���̗��l�r�i�P�s���W�����^���сj�ȂǁA�����Ɛ����������ł�15�т�����B����2�тƏ��Ȃ��Ȃ���A�g�����i�Ƃ��̍�i�j���c�����ꎍ�ɓo�ꂵ�Ă���B
�������]�����b�c������
��
����ɂ͍���������̂��낤��
����������Ȃ�
���̍����ɂӂ��킵���Q�䂪����
�k�c�c�l
��
�E���͂₵���j
��
�p�̃^�o�R���Ń^�o�R���ċȂ����Ǝv������
�s���s���ɂȂ���
�ސE����������������Ă���
�����S�̂悤�Ȏ��l��
�T�t�����E�݂̏����̎��������͂��߂�
�V�ዾ�����������N��
�}�U�[�E�O�[�X��Ȃ���
���ׂ��Ђ���
�b��ɐÖ����˂����Ă��������
���E������悤�Ȑk��������
����Ăĕ�e��
�������⌾��������
�����
���m�Ȃ��炢���m��
�ߎS�Ȃ��炢�ߎS��
������
�l�Ԃ͐����Ă�����̂�
��
����������
����͖���݂肠���Ă���邪
���̂܂ł݂͒肠���Ă���Ȃ�
������
�l�Ԃ͐Q�䂩�痎���邭�炢���ւ̎R��
��
�����]����
�M�ƇO�b�c������
�����̓c�ɂł��܂ꂽ�ڂ���
14�Ԑ���16�Ԑ��̎s�d�̂����b�ɂȂ���
�c�ɂ͇M�ƇO�̎n���w
�M�́u�N�̖��́v�Ƃ��������h���}�̐�����ʂ��ĐV���̓y���ł����܂�
�c�ɂ��n���œy�����I�_�@���ꂾ����
�ނ����͓y�l�����������������Ǝv���ł��傤
���\�������Ȃ��Ă���Ɠy���˂̏㉮�~�Ղ������ƋC������
�O�͓`�ʉ@�������Ĉ�C�ɍ���������ďt�����@���ꂩ�瓒���̔��~�̍���̂ڂ��
���N�܂ł͍]�˂̓��̖{���O���ڂ�ʉ߂���
���L���H�@�ނ��s�E�m�r������������
�ڂ��͎��@���̒r�ɂ܂�܂Ɨ�����
��͏��≮�Ƃ����f�p�[�g�ɂƂт���ʼn�������Z�Y�{���܂Ŕ����Ă���
�Ă���������悩������
��k���@���ꂩ��O�ؒ�
�O�̎��ɖ���������O�ؒ�
�X���͏I�_�Ł@���킵�����Ƃ͋g�����ɂ������������ꂽ��
�Ђ낢�����@���䂦����
���������@���䂦�Ђ낢
�u�����ȔN���v���Ă������炢�H
����������\���A����
�q�������]�����r�́s�X�R�b�g�����h�̐��ԏ����t�ɁA�q�M�ƇO�r�́s�D�F�̃m�[�g�t�Ɏ��߂�ꂽ�B��҂́u�Ă���������悩�����ˁv�܂ł͂قƂ�ǎU�����A������c��������鐏�z�̕��̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�A�㔼�́u�k�c�c�l�O�ؒ��^�O�̎��k�c�c�l�v�Ƃ��������肩��]�����āA�����i����Ƃ��]�ˁH�j�̔N���Ƃ̗��Ɏ�������B�g���z�q�v�l�ɂ��ƁA���e���O�Y�́u�������N����d�˂邲�ƂɁu�N���v�̔N��������Ȃ��Ă����v�Ƃ�����|�̔������������������A����͐^���ŁA�܂������������B�]�ˎ���Ȃ�Ƃ������A���ǂ��́u��\���A���v�Ȃ疺���B���������Ƃ͂��Ă����A�����ɑ}�܂�̂��u�X���͏I�_�Ł@���킵�����Ƃ͋g�����ɂ������������ꂽ���v�ŁA�q�M�ƇO�r�̏��o�������͂킩��Ȃ����̂́A1993�N�́s�D�F�̃m�[�g�t���s���A�g���͂��łɖS���Ȃ��Ă��邩��A���̎���͋g���Ō�̒����s���܂�͂����L�t�i1990�j�ւ̕ԗ�̈��A�Ȃ̂��낤���i��ɂ���ēc���́A�g���̑��V�ɎQ�Ă��Ȃ����A�Ǔ����������Ă��Ȃ��j�B�s�����̎��ɂ��u�U���v�͐���ł���B�c������̏����ƔӔN�̎���ǂ�ŁA�Ƃ�킯�����v���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�g�����̈��p���Ƃ����e�[�}�Ŏ�������܂Ř_���Ă��������ȕ��͂�
�@�g�����̈��p���i1�j�\�\�����r�Y�q�ӏ܁r�i2016�N11��30���j
�@�g�����̈��p���i2�j�\�\�剪�M�s���q�V�S�t�i2016�N12��31���j
�@�g�����̈��p���i3�j�\�\�y���F��^�i2017�N1��31���j
������B���̂ق��A���܂��܂ȏ��ŋg�����̈��p������p����ċg�������̎���ƂȂ��������̏o�T�ɂ��Č��y���Ă���B���Ƃ��A
�@�q���l�̔����ё��r�i2003�N5��31���j
�@�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�i2008�N2��29���j
�@���сq�▋�r�Ɣ~�؉p���̓��ʼn��i2009�N5��31���j
�@�g�����Ƒ���C���i2�j�i2010�N3��31���j
�@�g�����Ƒ���C���i3�j�i2010�N4��30���j
�@�g�����ƃ}�O���b�g�i2015�N5��31���j
�@�g�����Ɠ���N�v�i2019�N5��31���j
�Ȃǂ�����ł���B
�i���Q�j�@�Q�l�܂łɁA�P�s���W�Ɏ��߂�262�сA��������21�т̊��s���ɕ��ׂ����̂��ȉ��̈ꗗ�B�y�@�z���̐����Ɋւ��ẮA�{�����Q�Ƃ̂��ƁB
�@���鐢�E�i�B�E5�j�y24�z
�@�쌀�i�C�E1�j�y37�z
�@�����i�C�E2�j�y28�z
�@���i�C�E3�j�y25�z
�@�`���i�C�E5�j�y30�z
�@�~�̊G�i�C�E6�j�y41�z
�@�P���i�C�E9�j�y40�z
�@�Ō`�i�C�E11�j�y47�z
�@���i�C�E12�j�y41�z
�@���������i�C�E16�j�y35�z
�@�����i�D�E3�j�y43�z
�@�a���`�T�i�D�E4�j�y22�z
�@�a���`�U�i�D�E5�j�y22�z
�@���w�i�D�E7�j�y35�z
�@�ҕ����鏗�i�D�E8�j�y30�z
�@���̕a�C�i�D�E11�j�y34�z
�@�~�̋x���i�D�E12�j�y21�z
�@���̂��肠�����i�D�E13�j�y44�z
�@��`�i�D�E19�j�y36�z
�@�C���Əȗ��i�D�E22�j�y47�z
�@�n�E�t�̊G�i�E�E5�j�y32�z
�@���C�X�E�L��������T�����@�\�����`���i�G�E11�j�y67�z
�@����i�I�E5�j�y14�z
�@�l�H�ԉ��i�I�E19�j�y58�z
�@�A�d�i�������сE6�j�y23�z
�@�x�����i�������сE7�j�y21�z
�@����i�������сE8�j�y24�z
�i���R�j�@�t�����X���w�҂̓n�ӈꖯ�i1932�`2013�j�́A1978�N4������7���ɂ����āA�g�������ҏW���߂�}�����[�̂o�q���s�����܁t�Ɂq�u���z�{�m�p���E�C�f�A���n�v�K��L�r��4��i�T�`�W�j�ɂ킽���ĘA�ڂ����B���Ȃ݂Ɂq�u���z�{�m�p���E�C�f�A���n�v�K��L�W�r���f�ڂ��ꂽ1978�N7���̑�111���́A�}�����[�������A������|�Y�������Ƃɂ��x���O�̍Ō�̍������A�n�ӂ̕��͂̍Ō�Ɂu�i�I�j�v�i�����A���y�[�W�j�Ƃ����āA�A�ڂ͊������Ă���B���������̘A�ڂɂ́A�g���̎��́u�q���z�̋{�a�r�Ƃ����ٌ`�̓��́@�O�\���N�������ā@�V�����@���Ƃ����X�֔z�B�v���@���X�̎d���̓r���@���Ђ낢�@�����ς�Ō��Ă����̂ł���v�̓T���ɓ����镶�͂Ȃ��B�Ƃ͂����A���N5���A�G���s�C�t�ɔ��\���ꂽ���сq���J�̎p������r�i�H�E14�j�̂��̐߂��A�n�ӂ́q�u���z�{�m�p���E�C�f�A���n�v�K��L�r����G�����ꂽ���Ƃ͋^���Ȃ��悤�Ɏv����i�����͂̂��ɓn粈ꖯ�s�����ꡁt�i�u�k�ЁA1978�j�Ɏ��߂�ꂽ�j�B�n�ӂ̘A�ڂɁA�͂Ȃ͂������[����߂�����B
�@�����Ƃ��t���[�h�}���k�~�V�F���E�t���[�h�}���́A�V�����@���̌ːЕ�⋳��̋L�^�����ās�X�֔z�B�v�V�����@���̔閧�t���������ҁl�́A�V�����@�������ɃA���X�Ɩ��������͓̂�������̏o������́w�s�v�c�ȍ��̃A���X�x����Ƃ����̂��ƒf�肵�������ŁA�u���z�{�m�p���E�C�f�A���n�v���݂��V�����@�����v���������̂́A�����̖��̃A���X�ɂ��u�s�v�c�ȍ��v���Ă�낤�ƍl��������ł͂Ȃ����Ɛ�������B����������ɂ���A���ăA���v�X�̕X�͂��������������ϓy�ɂ������Ă��邱�̒n�������܂��܂Ȏ�ނ̐ɕx�݁A�V�����@���̖��̌`�������������Ƃ�������́A���̍ۋ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂��B�������Ĉꔪ����N�A�l�\�O�̃V�����@���ɂ́A�����X�֔z�B�����Ȃ���T���Ă��������A�߂̂��������艟�Ԃ��Ђ��ĂƂ�ɂ����Ƃ����A�܂������V�����������͂��܂����킯�ł���B�i�q�u���z�{�m�p���E�C�f�A���n�v�K��L�V�r�A�s�����܁t��110���A1978�N6���A��܃y�[�W�j�B
�g�������n�ӈꖯ�̂��̌��e�����ǂ��킩��Ȃ��B�����A�ѓ��k��ɕ����鎍���\�z���Ă���Ƃ��ɁA�X�֔z�B�v�V�����@���̂��Ƃ��������G�b�Z�C�̌��e�ɐG��A����ɂ����Ƀ��C�X�E�L�������́s�s�v�c�̍��̃A���X�t���o�ꂷ��Ƃ́A�Ȃ���R�ł��낤���B�����Ƃ��n�ӂ́A���łɃA���X�������т����\���Ă������l�E�g�����Ɏ��삪�ǂ܂�邱�Ƃ��[�����m���Ă������낤�B�Ȃ���N�A�s���z�̉�L����t�i���p�o�ŎЁA1967�j�Ɏ��߂�ꂽ�F�V���F�q���z�̏�\�\���h���B�q�ƗX�֔z�B�v�V�����@���r�i���o�F�s�V�w�l�t1965�N10�����j�́A�킪���ɃV�����@���̗��z�{���Љ���ł����������̕����̂ЂƂ����A�����ɂ��g���������������͌�������Ȃ��B�\�\�F�V�͂܂��A�q�V�����@���Ɨ��z�̋{�a�r�i���o�́s�₩�ȐH�����t��a���[�A1984�N9��10���B���M��1981�N������1982�N�����ɂ����ĂƐ���j�Ɂu�t�F���f�B�i���E�V�����@���͈ꔪ�O�Z�N�A�h���[�����̃I�[�g�����ɋ߂��V�������Ƃ��������ɐ��܂ꂽ�A�Ȃ�̍��Y���Ȃ����̔_�v�̎q�ɂ����Ȃ��������A�X�֔z�B�v�Ƃ����E�Ƃ̂������A�����ŏE������O�O�ɏW�߂ẮA��������Z�����g�Ōł߁A���ɂ��̑O�㖢���̃��j�������g�����������̂������B����͕����ʂ�s���̐��_�̎����ł���B�v�i�s�F�V���F�S�W�k��20���l�t�A�͏o���[�V�ЁA1995�N1��12���A�l���y�[�W�j�Ə������B�����͓����A�ʐ^�ƁE��c��v�����B�肨�낵���V�����@���́q���z�{�r�̎ʐ^�ƂƂ��ɁA�����\�m���}�Ђ��n�����鑎���ʐ^���Ɍf�ڂ���\�肾�����i�G���͑n�����ꂸ�j�B�Ώۂ�`���F�V�̕M�͎芵��Ă���A���R�̂��ƂƂ͂����A�g�����Ɍ����镶���͑��݂��Ȃ��\�\�B�t������A��艳�Y�s���z�̌��z�k�r�c�I���l�t�i�����������o�ʼn�A7���F1991�N2��28���k1���F1969�N4��5���l�j�́q�{�a�r�ɂ��Ȃ��i�{���̍��q�ƂȂ镶�͂̏��o�́A�G���s�r�c�t��1968�N1������12���ɂ����Ă̘A�ځj�B�i�N�A�V�����@���̗��z�{�̌����𑱂��Ă��鉪�J����́s�X�֔z�B�v�V�����@���̗��z�{�t�i�͏o���[�V�ЁA2019�N3��30���j�ɋ�����ꂽ�����ꗗ�́A�i�C�́s���D���̖��t�i���X�A1978�j�܂ł��������L�͂Ȃ��̂����A���������ǂ��Ă݂Ă��A�g�������тɈ����������͌�������Ȃ��B�������āA�o�T�̒T���͂͂����������ʂ��グ�Ă��Ȃ��B
�i���S�j�@�g�����̎��ɂ����ā^�i�X���b�V���j���ŏ��ɓo�ꂵ���̂��A���́q������ܒf�����сr�i1986�N6�����\�j�́u�W�@�̉��lj��v�ł���B�g���͂���1�N����A���Y���P�E��������Ƃ̑Θb��]�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t1987�N11�����j�ɃQ�X�g�Ƃ��ďo�����āA�u�k�c�c�l���Ҏ��̍\����������A�����Ȃ��̂����Ă����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��킯�����ˁB���Ƃ��Β�������̎��W�wopus�x�̍\���́A���������X�^�C�����ǂ����ɓ��ꂳ���Ă�����Ăˁi�j�B�v�i�����A��Z�Z�y�[�W�j�ƌ�������A���̒������W�sopus�t�i�v���ЁA1987�N9��1���j�ɂ�
�^�ف[�ف[�^�܂��͂ق��ق��Ɓ^����e�܂����݂���߂ʍ����}���g�[�^�̓��t�^�g�b�g�^�g�b�g�Ƃ����ǂ��j���g���̓�H�O�H�^��������邱�Ƃ����ށ^������̓��悪�����^�ɂ����ā^���͍g���Ƀr�^�~���^����Ȃ�������^����^�ق��ق��^�̓p�p�́^�Ƃ͔ޏ��̕v�^�̂��Ƃ����^�̌��ȁ^�j���g���̈�H�̓��^�N�V�^�̂��Ƃ�^������H�^�������Ⴂ�̂����̎q�^�Ȃ́^�Ȃ�Ɓ^�}�f�ȁ^�����܂킵�^���̐����́^�ޏ����v���Ă���قǂɂ͂��̊G����^�Ă͂��܁^���^���^�͎��^�l�����^��킩�^��̂����^���̌����͔ޏ��̔��e���^����^�����Ă���^�ޏ��^���g���G�M���ɂ����^�Ă�������Ƃ����^�����������܂Ƃ��Ɂ^����^�������̂��^�����Ƒf���Ȍ��^���^�������킢�^���܁^�̔ޏ��̎v�^�l���x�z���Ă�����́^�Ƃ����^�Β���⑁���^�̃W���M���O�̂��Ɓ^�����̃e�^�j�X�̎�����^���T���^�����ƂɂȂ��Ă���V���K�^�[���̃��g�̂��Ɓ^����^�炪���~�̖c�^���Ɨ}�^���̂����^���Ȑ��_�^���^�͂���^�𗝉��^���悤�Ƃ��Ȃ��̂��^���^�̂͂��^�܁^�Ł^����^�݂���^�Ă���^�����^���̓���^���^���̌ߌ�̂ЂƁ^�Ƃ��Ƃ��Ȃ����^�炢�̋��C���͂�^�݁^���̌ߌ�̂Ё^�ƂƂ��^�Ƃ��Ȃ�����^���^���Ł^����^���Ƃ����͂킩�^�邱�Ɓ^�͂ȁ^�����낤�^�������C�͎��^�̋��C�Ɓ^���Ă��^�����Ă������^���͑��^�𐮂��^�ā^���̊G�̌��_�^���^�ޏ��̌��^�_�Ƃ��ā^���^�ނ��Ă݁^��^�ЂƂ^�\�}���f�^���^���^���t���^���j���g������^���^�ɕ`���^��ā^���^��^�ӂ��^�F�ʂ��n���^�}���g�[�̍��Ɠ�H�̃j���^�g���̉��Ɛԁ^�����^�݂��^�^���߁^�@���^�w�^��Ă��^���^�j���g�����^�t���^�����^�����^���^�͑����^���^���ā^���̘b���^�Ɂ^���^�S���^��ӂ�^������^�����^�Ǝ���^�܂��^�͂ق��ق��^�܂��͂قف[���炵���ł��ȁ^
�Ƃ��������傪������i�u71�v�S���j�B
�\�\���W�sopus�t�ł́u71�v�̎��l�߂�1�s��25���A���і{����31�s�ŁA�����ȋ�`�𐬂��B���Ȃ݂Ɂu01�v�́u�J���~��Â����̂͊��ӂ��������A�Ђ����Ԃ�ɂ���k�c�c�l���ނ��Â��A�Ȃɂ��Ђ��̂����Ƃ��Ă���̂��v�Ƃ����A����܂�25���~17�s�́A�܂�������`�𐬂��B�����sopus�t�͎U�����^�̎��т����ō\������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���W�ɂ͎U�����^�ƍs�����̎��т����݂��Ă��āA�U�����^���A�u01�v�̂悤�Ɏn�܂��ďI�����̂�����A�u71�v�̂悤�ɖ`���Ɩ������^�i�X���b�V���j����߂���́A�����ɂ͈����Ȃ����A�u13�v�̂悤�ɖ`���Ɩ������m�@�n�i�u���P�b�g���p���ʁj�Ŋ�����́A�Ƃ������������ɑ��l���ɂ߂�B�����́sopus�t�ɐڂ����g�����A�����̖�ῂ����@����h���������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B�\�\
�u71�v�́^�i�X���b�V���j�����s�ƌ����Ă�ƁA�����鏈�ɋ�ׂ�i�A���W�����u�}���j�������āA�g���́u�W�@�̉��lj��v���ߌ��ȗp�@�ƂȂ��Ă���B����ɂ��Ă������́u���^�͎��^�l�����^��킩�^��̂����^���̌����͔ޏ��̔��e���^����^�����Ă���v�́A�g���́u�킵����҂�����R��̈�т��т͈��u�ł���v�A�u�킵�����l�����炽�܂ɂ͌`����I�ȉ��������v�i�q�w�A���X�x���r�j��z�킹�āA�Ȃ�Ƃ������[���B
�i���T�j�@�������i1927�` �j�́A����g����������������s���鐔���Ȃ��������l�ƂȂ����B�{���ŐG�ꂽ�s���㎍�̊ӏ܁t�i�y�ЁA2020�N12��15���j�́q�g�����r�ł́q�m���r�i�C�E8�j�A�q�Õ��r�i�B�E2�j�A�q�҉́r�i�B�E12�j�A�����āq�����r�i�C�E19�j�����p���Ȃ���i�s�Õ��t��2��͑S�сA�s�m���t��2��͏��^�j�A�䂫�Ƃǂ����ӏ܂��{���Ă���B�����́q��L�r�ɂ́u���M�ɂ������āA���㎍�͂��ɒ��ю����������Ƃ�Ɋ������B�̂�グ���i�͎��ʂ̓s����A��r�I�Z����i��I����Ȃ������B������A�̂�グ�����l�̖{������������݂Ƃ邱�Ƃ̖W���ƂȂ��Ă���͂��ł���B�v�i�O���Z�y�[�W�j�Ƃ����w�E������B���́A���㎍�����ю��̎��Ɉʒu����̂��A���㎍���U�����A���ƌ����Ă����̂ł͂���܂����B�����Ƃ��A���㐏��̃N���V�J���Ȏ��l�ł��钆�����̍�i�i���̑唼�́A�s�����̏\�l���m�\�l�b�g�n�ł���j�ɎU�����͂Ȃ��悤�����B
�i���U�j�@�s�Õ��t�i1955�j�̊��s�ȍ~�A�g���͂̂��Ɂs�m���t�i1958�j���\�����鎍�тl������s�̂̎����ɗ����Ɣ��\���͂��߂�B�V�i�̎��l�ɂƂ��āA��i�̌f�ڃX�y�[�X�́A���т̔��z�E�����ɑ傫���e������B�g���̐��z�q�u�����v�Ƃ����G�r�ɂ́A�u����Ƃ��A���h���I�ňɒB���v�Ƃ������̂�ł�����A�ˑR�A�q�����C�J�r�̏\�ł����O�ɂ�邩��A����ю��������ƌ��l�Ȗʎ��ł��肾�����B����͓�i�g�Ŏl�S�s�ʂ̒����ɂȂ邾�낤���B���͎O�S�s�ɂ��Ă���Ȃ����ƌ�������A�悩�낤�Ɣ������B�������ꃖ���ȏ�̎��Ԃ�^���Ă��ꂽ�B�������A�������ɂ�A���̕s���͂̂���肾�����B���܂܂łɁA�S�s���z���悤�Ȏ��͏����Ă��Ȃ����A���̎��@�ł͂ǂ��l���Ă��s�\���Ǝv�����B����Ő������ƁA�ɒB���v�̂Ƃ���֍s���A��S�s�ɂ��Ă���Ɛ\���ꂽ��A�S�s�l��ꂽ���Ƌ�����B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���Z�y�[�W�j�Ƃ���B�t�Ɏ���̑��ʂ�����������A�ǂ��Ȃ邾�낤�B40�s�̍s�����̎��̂���ł�����A�������V�܂���60�s�ɂȂ����Ƃ�����B���ʂ͌Œ肳��Ă���B���̒����̎��ŁA���ڂ͂��肦�Ȃ��B�Ȃ�Ƃ��܂肠�������邽�߂ɁA�s�����̎���̉��s�ӏ�����}�X�Ēǂ�����ł�������A�w��̃y�[�W�Ɏ��܂�̂ł͂Ȃ����B���������`�����I�ȑΏ��@���A�����̋g���ɐ△�������Ƃ͎v���Ȃ��B�S���ӏ���Č��t���炸�A�ł͂Ȃ��A���t����ď����炸�A�Ƃ��������N�����˂Ȃ��قǎ��z���c��ނ��Ƃ́A���l�̐��U�ł������x���K��Ȃ����낤�B�u�O���g�������v�́A�܂��ɂ������������̏��Y�������B
�i���V�j�@�э_���́q�L�����������ꃂ�m�ƂȂ������t�r�i���o�ł���s���{�Ǐ��V���t1983�N12��26�����́s��ʁt���]�ɂ�����W��́q�����̋P�����Y�o����q���t�r�r�j�ŁA�s��ʁt�̎���Ŋۊ��ʂ��p�ɂɗp�����Ă��邱�Ƃ��w�E�������ƂŁA���̂悤�Ȓ��ڂ��ׂ��������q�ׂĂ���B
�@�����ЂƂ��킾�������@�Ƃ��Č����Ƃ��ĂȂ�ʂ̂́A�s�������������낦�čs�Ȃ�ꂸ���t���I�����Ƃ��납��V�����s���͂��܂��Ă���Ƃ������Ƃł���B���̂��ߎ���͂Ђ炢���y�[�W�S�̂Ƀp�m���~�b�N�Ɋ���t����ꂽ�ς�����B���������Ă���͂�����J���O�����̒ʑ����ɑ����ĂȂ����Ȃ��B���̃Y���V�͕����m�ق����n�Ȃ��̂ł͂Ȃ��d�ʂ̖@���ɂ��Ȃ������̂Ɠǂނ̂��ӂ��킵���B�܂莍�ꂶ�����̎��ʂ����͂���đ傫���̂Ŏ��s�͎���̏d�݂ɂ��炦���˂ăY���Y���Ƃ��ꉺ�����Ă䂭�̂ł���B�J��Ԃ��悤�Ɍ��t�̎��ʂ�ł���̂͋L�����e�̏d�X������͂������Ɉ���̂ł͂Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA���t�����������u���F�ɋP���_�����e�}�v�̂��Ƃ��ɕϖe����A����L�����������ꃂ�m�ƂȂ�A�����ł̌��t���d�����킯�ł���B�����ɋ���������Ă��邪�䂦�̏d�����B�g�����́A���ɂ��H�ȍގ������������t�������ɎY�݂��Ƃ����悤�ł���B�i�s�����J���E�N���C�iLyrical Cry�j�\�\��]�W1983-2020�t�A�_�n�ЁA2020�N9��10���A�O���`�O���y�[�W�j
�u���̃Y���V�͕����m�ق����n�Ȃ��̂ł͂Ȃ��d�ʂ̖@���ɂ��Ȃ������̂Ɠǂނ̂��ӂ��킵���B�܂莍�ꂶ�����̎��ʂ����͂���đ傫���̂Ŏ��s�͎���̏d�݂ɂ��炦���˂ăY���Y���Ƃ��ꉺ�����Ă䂭�̂ł���B�v�\�\����͎����ǂނ��Ƃ̂ł����u��ʎ��^�v�Ɋւ���ł���s�Ȏw�E�ł���B�Ƃ���ŁA��Ɂu�����ɂ�鎍�v����̉e�����������Ă��������A�������̂���Ɂu�d�ʂ̖@���v�͓����Ȃ�����A�g�����Q�Ƃ����̂͂��̖|�c�ɑg�܂ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ낤�B���āA���̋�̓I�ȏo�T�́H�@�}���������s鍎q�ꝱ�t���z�N����邪�A�g�����u���m�̐l���瑡��ꂽ�w鍎q�ꝱ�x�ŁA���͏��߂āA���̓���Ȃ鎍�т�ǂƂ������A�����̂������B�����̂��ƂȂ̂��A�ɓ��T��Y��̏����q�ɂ́A���s�N�������s�������L����ĂȂ��̂ŁA�킩��Ȃ��B���ڂ낰�Ȃ�����A�ٗl�ȏ��@�Ɓu���̖����}�v�ɋ��Q�������̂������B�v�i�q�u���\�I���сv�G���r�́u�R�@�w鍎q�ꝱ�x�v�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�Z���y�[�W�j�Ə����Ă���u�ɓ��T��Y��̏����q�v�́A�i�N�̒T���ɂ�������炸�����ŁA�c�g�^���g�̕ʂ����킩��Ȃ��B��l�ɘւ������B
�i���W�j�@�c������̎��т̏��o�Ɋւ���ԗ��I�ȋL�q�͂Ȃ��悤���B���Ȃ킿�s�c������S���W�t�i�v���ЁA2000�j�ɂ��A�s�c������S�W�k��6���l�t�i�͏o���[�V�ЁA2011�j�ɂ��A���o�ꗗ�͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B���낤���Č�҂́q�c������ �N���r�i���яr���E�쐬�j�ɎU���I�Ɍ�����L�ڂ��E���A���̂悤�ɂȂ�i1948�N����A1956�N�̎��W�s�l��̓��Ɩ�t���s���܂łŋ���ēE����j�B�u���\�v�͏��o���A�u���^�v�͍Ę^��\���ƌ�����B
���a��\�O�N�@���l���N�@�@��\�܍�
�ꌎ�A�u���Y��{�v��Ɏ��u������v�Ȃǂ\�B�����A�u�r�n�v��܍��Ɏ��u�~�̉��y�v�\�B�A�u���w�v��A�O���������Ɏ��u�c��v�\�B�܌��A�ucendre�v��Ɏ��u���Ӂv���A�u���l�T���X�v��㍆�Ɏ��u�j���v�\�B
���a��\�l�N�@���l��N�@�@��\�Z��
�ꌎ�A�u���������v�ꌎ���Ɏ��u�����v�\�B�l���A�u���w�v�l�����Ɏ��u���́v�\�B
���a��\�ܔN�@���܁Z�N�@�@��\����
�ꌎ�A�uVOU�v��O�\�l���Ɏ��u������́v�\�B
���a��\�Z�N�@���܈�N�@�@��\����
�ꌎ�A�u���w�v�ꌎ���Ɏ��u�����v�\�B�����A�N���A���\���W�[�w�r�n���W���܈�x�i���쏑�[�j�Ɂu������v�u�c��v�u���߁v�Ȃǂ����^�B�ҏW�͖k���k���Y�l�Ɠc���B
���a��\���N�@���ܓ�N�@�@��\���
�ꌎ�A�u���w�v�ꌎ���Ɏ��u��������l�i���̈�j�v�\�B
���a��\���N�@���O�N�@�@�O�\��
�ꌎ�A�w�r�n���W���O�x�i�r�n�o�ŎЁj�ɁuNu�v�Ȃǂ����^�B
���a��\��N�@���l�N�@�@�O�\���
�A�w�r�n���W���l�x�i�r�n�o�ŎЁj�Ɂu��������l�i���̓�j�v�u���сv�Ȃǂ����^�B�����A�w���Ǝ��_�Q�x�i�r�n�o�ŎЁj�Ɏ��u�l��̓��Ɩ�v�\�B
���a�O�\�N�@���܌ܔN�@�@�O�\���
�l���A�w�r�n���W���܌܁x�i�r�n�o�ŎЁj�Ɂu�O�̐��v�Ȃǂ����^�B
���a�O�\��N�@���ܘZ�N�@�@�O�\�O��
�O���A�����n���Ђ̕ҏW�҂Ŏ��l�̒m�O�Ċ�̊��ŏ������W�w�l��̓��Ɩ�x�i�����n���Ёj�����s�����B�i�s�c������S�W�k��6���l�t�A�܈ꎵ�`�܈ꔪ�y�[�W�j
���̂����A�s���Y��{�t��2���i1948�N1���j����肷�邱�Ƃ��ł����B�s���Y��{�t�͑�{�����Д��s�̌������|���i�`�T���E�{��64�y�[�W�j�B��2���͏���4�сA��5��i�i�|���Ă�q�A���q�����A�O�D�L��Y�A�c���A�j�Z�V��j���f�ڂ��Ă���B�ڎ��̓c����i�̕W��́q�J�D�̒m���l�r�B36�y�[�W�ɂ͂��̕W��Ɓq������r�i���W���^�`�ɓ����j�A37�y�[�W�ɂ́q�����r�A38�`39�y�[�W�ɂ́q�D�r�i�ȏ�A��������U�����^�j�A������I���Ɂu�k��l��l���N��ꌎ�v�Ƃ���B���͏����w�����Ƃ��ɂ͓c�����ɐ��ʂ��Ă��Ȃ��̂����A���́q�����r���s�c������S���W�t�́q�P�s�{�����^���чU ���1946�`1969�r���^�`�ƈقȂ�̂́A�Ȃɂ����R������̂��낤���B���̑��߁u�k��}�X�l�⍓�ȃt�[�K�@�k�c�c�l�@���̉H�͍��ɂ����v�͓����B���`�O�߂́u�k��}�X�l���e�����̉Ƃɕs�C���Ȓ��ې���^�ւ��@�K���̉Ƒ������͂��남��Ɩ���̎���ɏW�Ă���@����͌�����̂Ȃ��Ŏ���ɒ��̌`���Ȃ����@��e�͖���ɐV�����}�т������@���e�͘V����������Ė���̊z�Ɏ��u���@�悤��Ǝv�t���ɓ�������̖��͏������t�����炵�Ė�������@�������ނ͉i���ɐ��߂đ��̊O�ɗ��@���͑傫�Ȑ��ŏЂ������v�i�����͐V���ɉ��߂��j�B�ٓ��́A���o�̂̂��ǂ����ɍĘ^���������`���̂������߁A�ƍl����Δ[���ł��Ȃ��ł��Ȃ��B�����A���̎��сq�D�r���s�c������S���W�t�Ɍ�������Ȃ��̂͂ǂ������킯���낤�B�e�߁i��߂��琬��j�̍ŏ��ƍŌ�̎���͂������B
�D�b�c������
�@�܂�ʼn��̂₤���@�k�c�c�l�@���������͉J
�@���̖�@�k�c�c�l�@�N�̐O�ɖl�̐O�Ėl�����Ĕj�ł����߂�I
�c�����ꂪ���������́A���W�Ɏ��߂�ꂽ���т��A�����s���т��A�g�����̂���Ɗr�ׂęˑ�Ȑ��ɂȂ�B�ׂ������ׂ��킯�ł͂Ȃ����A���Y�������Ė鐼�e���O�Y�������킷��̂ł͂Ȃ����B��������m�Ō����̂����A���J���v�̕҂͏o���[�V�Дł́u�S�W�v�i���̂́A�f�ȗ�n�܂ŏW�߂��S�W�͂��납�A���ЂƂȂ�������ł��A���W�������āA�U���́u�I�W�v�ł���B���Љ�����Ă��Ȃ��U�����E���Ă���Ă���̂́A���肪���������肾���j��₤�Ӗ��ł��A�Ƃ�킯�������т̏��o�L�^�̏[����v�]����B���̌����ɂƂ��āA�K�{�̍H����m�c�[���n�Ȃ̂�����B���삿���i���j�A�Ė傠�����i�ҁj�s���삿�������W���k���╁�y�Łl�t�i���[�F���ł������� ���݂̂ق��A���s�F���s�䊧�䏑�[�A2021�j�̂悤�ȁA���ق̖ԗ����͊�ނׂ����Ȃ��Ƃ��Ă��B
�{�Z�E�V��ޓ�Y�E����N�v�E���c�O�E�I���ցE���Y�Ái�ҁj�s�V�Z�{ �{�V�����S�W�k�S16���{�ʊ�1�i�S19���Z�b�g�j�l�t�i�}�����[�A1995�N10���`2009�N3���j�́u�{�V���������ɋ��������������Ă��w�Z�{�{�V�����S�W�x�̓��F�������p���Ȃ���A���̌�̐V���������E�������ʂ܂��A20�N�Ԃ�ɑS�ʓI�Ȗ{������E�Z����Ƃ̂�蒼�����s�����A���������̐V���Ȋ�ՂƂȂ�S�W�B�v�i�}�����[�j�ŁA�S���̍\���́A�Z�́E�Z����1���A����6���A���b��5���i�Ō�̊��́u���b�E�� ���̑��v�j�A�o���E�蒠 �m�[�g�E������1���i2���\���j�A�G�[��1���A���ȁ�1���A���E���� �N���E���E�`�L������1���i2���\���j�A�������ʊ��i2���\���j�A�ƂȂ��Ă���B�����Ƃ�킯���Q����̂́k��16���i��j�l�́q���E�����r�Ɓk��16���i���j�l�́q�N���E���E�`�L�����r�A�����āk�ʊ��l�́q�����r�ł���B�����𐳊m�Ɍf����̂��Ȃ��Ȃ�������������A���t�̕\�L�����̗��V�ŏ����Ɓs�y�V�z�Z�{ �{�V�����S�W�k��\�Z���i���j�l���E���� ���E�`�L�����сt�i�}�����[�A2001�N12��10���j�̊����ɂ́A�ȉ��̃N���W�b�g�������đs�ς��B���ꂼ��̃^�C�g���̂��ƁA�ق�1�y�[�W�߂鏬���Ȋ����ɂ��ŗL���̃I���p���[�h�Ȃ̂��B
�m�Z�{�{�V�����S�W�����ҁE���͎Җ���n
�m�V�Z�{�{�V�����S�W�����ҁE���͎Җ���n
�m�V�Z�{�{�V�����S�W�ʐ^�ҁE���͎Җ���n
�ȏオ�A�V���Z�{�{�V�����S�W�̕Ҏ[�ψ��i���Z�{�S�W�̕Ҏ[�ψ��́A�{�Z�E�V��ޓ�Y�E�����O�V�E����N�v�E���c�O�E����r�Y�E�x���j�E�X���ߒr�j��o�Ŏ҈ȊO�̊O���̌l�i�{��Ƃ̐l�l���܂ށj��c�̗̂��Ƃ���A���̓�͏o�Ŏ҂̐���X�^�b�t�ł���B�S���������i�����A�k�l�l�O�y�[�W�l�j�B
�m�Z�{�{�V�����S�W�}�����[�S���ҁn�q�ҏW�r��c�j�Y�@�{�c���@�q�Z�{�r��Ǝ��@�ΐ쐴�l�@�R�q�v�@�������q�@�q����r�X�R�r��
�m�V�Z�{�{�V�����S�W�}�����[�S���ҁn�q�ҏW�r�ؐ^���@�ΐ쐴�l�@�����Y��@�q�Z�{�r�ΐ쐴�l�@���R�����q�@�y�����q�@�q����r���i��
�����ɂ͐V���Z�{�{�V�����S�W�̑����S���҂��������Ă��Ȃ����A�s�Z�{ �{�V�����S�W�t�͋g�����i�S�W���s�����A�}�����[�̎Ј��̂��߁A�{�̂ɂ̓N���W�b�g�Ȃ��j���A�s�V�Z�{ �{�V�����S�W�t���ԑ��r���i�{�̉��t�ɃN���W�b�g����j���������Ă���B�s�Z�{ �{�V�����S�W�t�̕ҏW�S���u��c�j�Y�v�͂��̎��l�̉�c�ł���i�u�ؐ^���v�͂o�q���s�����܁t�̕ҏW���߂����낤�j�B���ē�������S���̘X�R�r�ꂾ���A�s�o�Ńj���[�X�t1986�N8����{���i�ʍ�1399�j�Ɂq�ҏW�҂̓��^�i��121��j�r�������Ă���̂��A���������́u�X�R�r��v�ł���i�Ȃ��A������ł́u�X�v�͂�����������j�B
��
2021�N�t�����E�̓R���i�Ђɂ���B��������}���ق͂�������炸���ꐧ�������Ă���A����������Ă܂ŏo�����Ē��ׂȂ���Ȃ�Ȃ��ً}�Č��ł��Ȃ��B�����ŏ��߂āA��L�̕����̃R�s�[��X�����Ă��炤�ׂ��˗����Ă݂��i�u���u���ʁv�Ƃ����炵���A��ƌ���̍�������}���ٕ��ʎ���Z���^�[�͋��s�{�ɂ��邪�A�d�q�t�@�C���̃n�[�h�R�s�[�Ȃ�ǂ��ŏo�͂��悤���������j�B��������}���ق̃E�F�u�T�C�g����\�����̂�2��19���B3��1���ɁA���ꂩ�甭������Ƃ������[�����������̂́A���ۂɓ͂����̂�3��5���B�v���̂ق����������������̂́A�a�S���̃R�s�[�p�����܂�Ȃ��悤�ɁA��38�~29cm�̑唻�̕����ő����Ă������߂��B�w�肵���y�[�W�͕\���E�ڎ��E�{���i1�y�[�W�j�E���t�����A��������}���ي��ٕ����ە��ʑݏo�W�́q���u���ʐ\�����i�T���j�r�Ƃ����Z����̗p���Ɂu���\���ݎ����̉��t�́A���\���̔w���ɂ������Ǝv���܂����A�������{�ɂ��B��ĕ��ʂł��܂���ł����B���������������B�v�Ƃ���A���v3�y�[�W�i24�~�~3����72�~�j�B�ق��ɔ��������萔��200�~�ŁA���v272�~�B����ł�27�~�A������220�~�ŁA���v���z519�~�B�ʓr�A�R���r�j�ł̐U���萔����66�~���������B���߂�585�~��B�u���E�W���O�̗v�i���Y�����̒��g�̊m�F��A���ӏ����������Ă������߁j���������肵�Ȃ���A�Ȃ����ً}�x�������Ȃ���A�[�����ɗ��T�[�r�X�ł���A������@�����Η��p���邾�낤�B
�����ł悤�₭���̎����̘b��ɂȂ�B�\���ɂ́u�o�ő����� �o�Ńj���[�X�^��3�s�^8�����{���@1986�@�o�Ńj���[�X�Ёv�Ƃ���B�����ڎ����d������̂́A�Ƃ��ǂ��{���y�[�W�̕W��⏐���ƈقȂ邱�Ƃ����邩�炾���A����͖��Ȃ��i�ق��̃y�[�W�̍\����m�邱�ƂŁA���Y�L���̈��������m�ɂȂ�ꍇ������j�B�����Ė{���B�f�ڂ̓��y�[�W��5�i�g�ŁA��3�i���́q�o�ŊE�ł��܁r�Ƃ����������̃R�����́u���v�ŁA���������i�����[�r����@�̔�������Ёw�A�X�e�x�ҏW�l�j�́q�o�q���ʼn���\������̂��\�����[�r���̂̔F�m�ƕ��y�\�r�B��2�i�����q�����[�`���^�ҏW�҂̓��^�r�Ƃ����������̃R�����́u��121�v�A�u�X�R�r��i�_�C�G�[�w�I�����W�y�[�W�x�ҏW�������j�v�ŁA�L�����̂��̂ɕW��͂Ȃ��B10�N�ȏ�܂��́s�Z�{ �{�V�����S�W�t�̐���S���҂͒}�����[�𗣂�āA�G���s�I�����W�y�[�W�t�Ɉڂ��Ă����BWikipedia�ɂ́A�u1985�N�Ƀ_�C�G�[�̏o�ŕ���Ƃ��Đݗ�����A�w�I�����W�y�[�W�x��n���B���V�s�{����W�̃��b�N�{�Ȃǂ����s���Ă���B��s���Ă���w�N�����b�T���x�ƃ^�C�g���̏��̂��ގ����Ă��邪�A�����͐����S�ʂ��ނƂ�����̂ɑ��āA�{���͗������V�s�̌f�ڂ����S�ł���B�v�ƊT�v���L����Ă���A�X�R���͓����̑n���Ɋւ���Ă����̂�������Ȃ��i�o�ŎЂ�G���Ђ̂Ȃ��ŎG����n������̂ł�����ς����A���ʃO���[�v��Ђ̏o�ŕ���ݗ��ƕ��s�����V�G���n�������A�����̂��Ƃł͂Ȃ��j�B�u���O�A�苷�ɂȂ����������̈ړ]���������Ă���Ƃ��A�m���A�h���X�̑�e�[�u�������̃I�t�B�X�E���C�A�E�g�ɂ��āk�����@�탁�[�J�[�̐l�Ɓl�b�������Ƃ�����B��������Ƃ����Z���g�����E�t�@�C�����O�E�V�X�e���B�������Ȃ���e���̇��釁�Ƃ��Ċm�ۂ��ꂽ�v���C�x�[�g�E�R�[�i�[�v�\�\�����A�u�X�y�[�X�̊W��A�v���C�x�[�g�E�R�[�i�[��������ƍ��A�Ƃ��������������̂��ƂŁv�A����������Ɏ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B�����āA�u�k�c�c�l���̂�������A���r���[�͂܂�Ȃ��c�c�B��Z�E���l�����Ă̑��D��͓����̊ԑ����������B�v�Ƃ����̂��A�q�����[�`���^�ҏW�҂̓��^�r�̌��ꂾ�B�����ɁA�S�W�̐����G���̕ҏW�̘b�͏o�Ă��Ȃ��B�����A���M�Ƃ̐����e�⎖�����̍�ƃX�y�[�X�Ƃ����������������ɂ��ėL�����p���邩�A���S���邠����ɁA���҂��т����ʂ������ӎ��������Ă���A�Ɠǂ߂Ȃ����Ȃ��B�[�ǂ݂ɂ����邾�낤���B
��
���͋{���i1896�`1933�j�̂悢�ǎ҂ł͂Ȃ��B����N�v��V��ޓ�Y�����������͂��A�{��{�l�����������͂����M�S�ɓǂނ悤�Ȑl�Ԃ��悢�ǎ҂̂͂����Ȃ��B����ł��Y��ȃW���P�b�g�̐V�����ɂ��o��A����Ɏ���Ă��܂��B������ŋߔ������{��̖{�́A���̐��̃W���P�b�g�E�т́s�V�� ��͓S���̖�k�V�����Ɂl�t�i�u�ߘa��N�l���\�ܓ��@���\�O���v�j���B���Ȃ݂ɂ��̊��s���́A�g������101��߂̒a�������B�������W���́k�����ܕ��Ɂl�őS�W��W���[�E�p���o�[�X���|���s�p��œǂ� ��͓S���̖�k�����ܕ��Ɂl�t�ł������Ă���B�ɂ�������炸������肵���̂́A����{�ƈꏏ�ɓǂ݂����Ȃ������炾�B���Ȃ킿����N�v�i�ďC�E����j�s�{���u��͓S���̖�v�̌��e�̂��ׂāt�i�{���L�O�فA1997�N3���k���t�Ȃ��l�j�����ꂾ�B���ē���́s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t�i�}�����[�A1991�N7��25���j�ɂ����������B
�@�\�\�k�c�c�l
�@�܂��A���z�{�Ƃ͕ʂɁA�����҂̂��߂̊��{�Ƃ��āA�S���\�O���̌��e�Ƃ���ɂ܂�郁���ނ̂��ׂĂ��ʐ^�łɂ�����ɓǂ݉�����Y�����{���o����邱�Ƃ��A���ꂾ���̓��e�Ƒ����̖��_���͂��ł��邱�̍�i�̏ꍇ����߂Ė]�܂������Ƃł��B
�@�\�\����炪�������Ƃ��A�u��͓S���̖�v�́A���S�ɖ��l�̂��̂ƂȂ�̂ł��ˁB
�@�\�\�܂��������̒ʂ�ł��B�i�q�u��͓S���̖�v�̖{���̕ϑJ�ɂ��Ă̑Θb�r�A�����A�ꎵ���y�[�W�B���o�F�u���{�������w�ʍ� �{�����b�̐��E�v��㎵�Z�N�j
�E�u�w��͓S���̖�x�̖{���̕ϑJ�ɂ��Ă̑Θb�v�@�@���̕��̏I�肿�����ŏq�ׂ��Ă���u���z�{�v�́A���̌�A�V�C�ŁA�����ܕ��ɔł̓�S�W���̑��Ŏ��������B���e�̏ڍ���t���S�t�����́A�܂����݂��Ă��Ȃ��B�i�q�o�����r�A�����A�l�����y�[�W�j
�q�o�����r�͓����̂��߂ɏ����ꂽ�A���Ƃ����ɑ������镶�͂ŁA�����Ɂu�����N��������@���ҁv�Ƃ���B�q�Θb�r�������Ă���21�N�A�q�o�����r����ł�5�N���ȏ�̍Ό�������Ă���B����̔O�肪���Ȃ��āA�悤�₭���ꂪ���������̂��B
�@�{���L�O�ق́A�����̐��a�S�N�̈���Z�N�ɓ�����A������L�O���āA�u�w��͓S���̖�x�̌��e�̂��ׂāv�̃^�C�g���̂��ƂɁA���́s���{�ߑ㕶�w�̎���t�Ƃ������ׂ��M�d�Ȏ��M���e�̑S�ʓI�W���E���J���s�����i����Z�N�l���`�㎵�N�O���j�B����͌��������j�̏�ł�����I�Ȏ��݂ł������B�{�}�^�́A���̊��W���̈�Ƃ��Ċ��s�������̂ł����āA���e�S�t�Ƃ��̗��ʂ̎ʐ^�ŁA����т����ɂ��Ă̊ȗ��ȉ�����琬���Ă���B�i����N�v�q���Ƃ����r�A�s�{���u��͓S���̖�v�̌��e�̂��ׂāt�A����y�[�W�j�B
�}�^���s�́A�W����̊J�Ï����m�A�A�A�A�n�ł͂Ȃ��A�I���ԍہm�A�A�A�A�n�ɂȂ��ꂽ���̂̂悤���i�W����̉���́A��L�q���Ƃ����r�ɂ��邾���ŁA�ʏ�̐}�^�̂悤�Ɂ\�\���F�{���L�O�فA����F1996�N4���`1997�N3���\�\�Ƃ������L�ڂ͂Ȃ��j�B���ɕ��w�ق����s�����}�^�͐�������ǁA���������̂��������Ƃ��Ȃ��B����͊��W�����u���������j�̏�ł�����I�Ȏ��݁v�ƍT���߂Ɍ����Ă��邪�A���Ȃ�u���W���́v�Ƃł������Ƃ��낾�i�W����͊ςĂ��Ȃ����A���ꂭ�炢�̂��Ƃ͂킩��j�B�����ɓ��ւ�����s�Z�{ �{�V�����S�W�t�����w�҂̌��e�i����ъ��{�j�������������ɂ��j�i�̈�����ł������悤�ɁA�{�}�^���܂����w�҂̌��e���������}�Ł��ʐ^�ɂ��j�i�̈�����Ƃ�����B�u���ꂳ������A���юO�t�͂�����v�Ƃ������ނ̌���������B�}�^���u����v���u���сv���͂Ƃ������A����ɐV�Z�{�S�W10���E11���́q��͓S���̖�r�e�e�̖{���тƍZ�ٕт��苖�ɒu���A���e���Z�{�^��i�{���^���{���߂���l�@�̎�|����͖����ɂ���B���͂���������Ȃ���A�g�����̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̎��M�e�{�i�����E�ڍ��̓��{�ߑ㕶�w�قɂ���j�̂��Ƃ������ƔO���ɒu���Ă����B
 �@
�@
����N�v�i�ďC�E����j�s�{���u��͓S���̖�v�̌��e�̂��ׂāt�i�{���L�O�فA1997�N3���k���t�Ȃ��l�j�̕\���i���j�Ɠ����E�܃y�[�W�́u�������t�ԍ��P�v���f�ڂ������ʁi�E�j
�k�NjL�l
�{���i���j�A���W���[�E�p���o�[�X�i��j�s�p��œǂ� ��͓S���̖�\�\Kenji Miyazawa's Night On The Milky Way Train�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A1996�N3��21���j�́q��҂��Ƃ����r�ɂ�������B�O��𗪂��Čf����B
�@��㔪�O�N�A�����w�p�������x�iMainichi Daily News�j�̊w�|���L�҂Ƃ��ē����Ă����ڂ��́A�����ɂڂ��́w��͓S���̖�x�̖|����V���[�Y�Ōf�ڂ��悤�ƐS�Ɍ��߂��i�����āA�C���X�g�͖{���ł������b�ɂȂ����e�F�̂g�`�s�`�n�ɂ��肢���邱�Ƃɂ����j�B�ڂ��͏\��N�O�̖|�����������o���A���J���|���Ă���Ɏ���������B�����Ă��̔N�̏H����~�ɂ����A�ڂ��́w��͓S���̖�x�̖|�߂ł����w�p�������x�Ɍf�ڂ��ꂽ�B
�@�k�c�c�l
�@�w��͓S���̖�x�̖|��ɍۂ��A�ڂ��͎��̂悤�Ȃ��Ƃ������S�̒��řꂢ�Ă����B�u�����������p��ŏ����Ƃ���A�ǂ�ȕ��̂��g���A�ǂ�ȒP���I�Ԃ��낤�B�ǂ�ȉ��Ɏ䂩��A�ǂ�ȉ��ɐ_�鐫�������邾�낤�B�����̎��R�ςɒʒꂷ��悤�Ȃ��̂��͂����ĉp��̒��Ɍ��o���邾�낤���c�c�v
�@�ڂ���͐S�ɗ��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B��ƂƂ������̂́A�_�̖����L�^���鎞�A�g�k�������ɂ����Ȃ��̂��B�{�����琁���Ă���u����炩�Ȑ�̑�n�v�̕����A�ڂ��͂��̔��ɂ����Ɗ����Ă���B�i�� �㐙���l�B�����A��l�l�`��l�܃y�[�W�j
�����q�����q杁r�i�K�E4�j�́A�g�������u���k�c�c�l�i2�j�́u�p�������j���[�X�v�ɔ��\�������̂ł���B�v�Ƃ��̏��o�i�s�����C�J�t1984�N12���Վ��������j�Œ��L�����悤�ɁA�q���ȁr�i�sMainichi Daily News�t�k�����V���Ёl1984�N9��17���k22128���l��ʂ́q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�A20�s�A���[�}���\�L�qShookyoku�r��Roger Pulvers�ɂ��p��qA Short Piece of Music�r��t���j�̑S�s��ω��z�����Ă���B�g���́q���ȁr�i�Ƃ��̉p��qA Short Piece of Music�r�j�́A�{���́q��͓S���̖�r����L�̂悤�Ȏp���ʼnp�����W���[�E�p���o�[�X�i1944�`�@�j�ɂ���Đ��ɑ��肾���ꂽ�B�{�ьf�ړ������A�����̊w�|���L�҂߂Ă����̂ł��낤�B�Ȃ��A�s�p��œǂ� ��͓S���̖�t�����́q����r�ɂ́u�c�c�����A�ނɍI�݂ɂ������āA�J��r���Y�E���c���Y�u�̗����ƂƂ��Ɂu�~�j�E�G�b�Z�[�v�������A�����ނ��p�āw�p�������x�ɘA�ڂ������Ƃ��������B����͂��ƂŁw���p�Ώƃ����[�E�G�b�Z�[�x�i��C�ُ��X�j�Ƃ��Ė{�ɂȂ������A���Ƃ��Ă͒J��E���c�������̖����Ɍ[��������ςȂ��A�����ă��W���[�̒���Z�I�I�a���p��p�Ɋ��Q�����ςȂ��́A�y�����o���������B�v�i�����N��q�z�������M�\�\���W���[�E�p���o�[�X�̃O�����v�X�r�A�����A��l���y�[�W�j�Ƃ���B�p��Ɋ��\�ȍ����N��ł����A�p���o�[�X�̉p��̂�������ɂȂ��Ă���Ƃ͋������B���̃G�b�Z�[�W�ɑ���ɁA�c�O�Ȃ���q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�̃V���[�Y�͍����܂ŏ��Љ�����Ă��Ȃ��i���j�B
 �@
�@
���сq���ȁr�i�sMainichi Daily News�t�k�����V���Ёl1984�N9��17���k22128���l��ʂ́q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�A20�s�A���[�}���\�L�qShookyoku�r��Roger Pulvers�ɂ��p��qA Short Piece of Music�r��t���j�f�ڎ��̃��m�N���R�s�[�k�q�g�����S���сk���o�`�l�r�f�ڂ́s���[���h���b�v�t���o�t�@�C�����̂��́l�i���j�Ɠ��E���� �k�g���Ə����̐蔲���B�E���ɂ͋g�������M�̔}�̖��ƔN�����̋L���i�u�p�������j���[�X�@1984�E11�E17�v�j�����邪�A���ۂ̌f�ڔN�����́u1984�E9�E17�v�l�i�E�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@���ǂ������J��r���Y�E���c���Y�u�E�����N��ER. �p���o�[�X�s���p�Ώƃ����[�G�b�Z�[ Words in Transit�t�i��C�ُ��X�A1985�N10��20���j���{�������Ƃ���A�p���o�[�X�́q�܂������r�i�����Ɂu1985�N9���v�Ƃ���j��
�@1982�N���猻�݂܂ŁA���́w�����f�C���[�j���[�X�x�̕����ʁiMoaday Arts�j�̕ҏW��S�����Ă��܂��B���̗��̂��߂ɁA�J��r���Y�A���c���Y�u�A�����N��̎O�l�̗F�����ɒZ���G�b�Z�C�̘A�ڂ����肢���邱�Ƃɂ����̂͂��傤��2�N�O�̂��Ƃł����B������������̂Ȃ��ɃE�C�b�g������߂��O�l�̃G�b�Z�C���A�A�̂ӂ��ɑ����Ă��炨���Ƃ������ł��B���̃V���[�Y�́gAssociations�h�Ɩ��Â����A���ꂼ��̓��{���ɂ킽���̉p���Y���邱�ƂɂȂ�܂����BAssociations�ɂ́u�A�z�v�Ɓu���ԁv�̗����̈Ӗ������߂�����ł��B
�@�k�c�c�l
�@�ЂƂƂ���ɒ���Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��A���̒��ԁm�A�\�V�G�[�V�����Y�n�̘A�z�m�A�\�V�G�[�V�����Y�n�����Ȃ����Ƃ�������܂���B���������Ă��邩��Âт邱�Ƃ��Ȃ��A���������ČŒ肳���悤�Ǝ��݂Ă��A���̂܂ɂ�����ʂ��Ă����ł��傤�B���Ƃ�����̈Ӗ�����E���A�{���̐��������߂��̂́A�������g�����W�b�g�ɂ���Ƃ��Ȃ̂ł��B�i�������g�B�����A�B�E�D�y�[�W�B��i�q��j
�Ƃ������B����4�l�ɂ�銪���́u�l�l�g�V�k�v�A�q���t���؋��m���Ƃ̂܂��傤�n�r�ł̃p���o�[�X�̓��{�ꂪ�B�҂Ȃ̂ɂ������B�J��E���c���E�����Ƃ������Ҏ҂����ƁA�ʟ����������Ē������~�̓��{��^�p��k�`������̂ł���B����Ȃ�A�g���������邱�ƂȂ��p���o�[�X�Ƃ̉�b���͂����Ƃ��낤�B
�������ƃT�C�g���^�c���ĕ��͂������Ă���ƁA���Ƃœǂ݂������āA���̂���̂��Ƃ��v�������ԁB�Ƃ���Ŏ��́A��w�̕��w���Ńt�����X���w�ȂǂƂ������悻���ԂŖ��ɗ��Ƃ��v���Ȃ����̂��w���A��_�̓k�ł͂����Ȃ��Ɣ��N���āA���{�G�f�B�^�[�X�N�[���̒��ԕ��ɒʂ����B��w5�N�߂̂��Ƃł���B�����̃X�N�[���̍u�t�w���B�B�����G��ŁA���l�������O��������A���X�P�v�A�z��p���q��Ƃ������o�ŊE�̏d����A�ڐ�Ëv�q�A������q�Ƃ����������m��������x�e�������猾�������Ȃ��قǂ�������̂��Ƃ��Ƃ����B���Ƃ��Γ��X�搶�́A�v���{�������Ă�����@�̎������傢�ƕt����A�ƌ������B���Ƃ��ڐ�搶�́A�����l�ƕҏW�҂͓������A���키�����łȂ����̂���Ă����鏈�ɑz����v���A�ƌ������B����搶�́A��⏺�@�����ҍZ���őg�ł�Z���ɖ��f��������Ȃ��悤�ǂꂾ���אS�ɐԎ�����ꂽ���A������i�Z���҂͌��e������ē�K�����э~���A�Ƃ��j�B����������{�l�͂���قǑ�Ȃ��Ƃ�����������͂Ȃ���������Ȃ��B�悭����ł͂Ȃ����B�F�l�Ɛ̘b�����Ă��āA���܂��͂���Ȃ��Ƃ����������ǂȂ�قǂƎv�����A�Ƃ������̊̐S�̓��e�����������l�͂܂������o���Ă��Ȃ����Ƃ��B�����玄���A����ȍ��ׂȂ��Ƃ͏����L���܂ł��Ȃ����낤�A�Ǝv���邱�Ƃł��A�w�߂ď����Ƃ߂Ă������Ƃɂ��悤�B����ɓǂޑ��ɂƂ��Ė��v�Ȃ��Ƃł��A���Ȃ��Ƃ��̂��̎������g�ɂ͂Ȃɂ��̖��ɗ���������Ȃ��\�\�ƌ����Ă��瑱����ƁA�܂�Ŗ��ɗ����Ȃ����͂ƎƂ�ꂻ���ō���̂����A���C�Ȃ��ǂ݂͂��߂��F�V���F�́s�ς̂���Ԃ���\�\�킽���̏��N����k�͏o���Ɂl�t�i�͏o���[�V�ЁA1997�N2��4���j���߂��ۂ��ʔ��������i�ܒJ���m���I���F�V���F��3���͇@�t���[���ꡁm���傤�悤�n�A�ߕ������B�ӓ��m����݁n�̒��̐��E�A�Ŗ{���͓����Ă��Ȃ����A�A�̑I���������Ă���j�B�����[���ӏ������������p���悤�B�^�i�X���b�V���j�͉��s��\���B�i�@�j���̐����̓m���u���B
�E���Z�قɋ߂Â��ƁA�^�N�V�[�̑���������m�A�A�A�A�n����������B���܂͂ǂ����m��Ȃ����A�����͓X��ɃC�m�V�V�����C���݂邵�Ă������B��������������ƁA�u���A�����������Z�ق��ȁv�ƕ����āA�S�����ǂ��Ă���̂ł���B�i�q�Ȃ�������S�P�r�A48�`49�j
�E�吳���N���甭�������ґ�ȗc�������G�G���u�R�h���m�N�j�v�̏��a��N�������ɁA�k�����H�́u�`���E���b�v�����v�Ƃ��������ڂ��Ă���B�}�G�͌䑶�����䕐�Y�ł���B�i�q�ς̂���Ԃ���r�A59�j
�E������ɂ��Ă��A���̉̂�m���Ă���ЂƂɎ����ЂƂ���o��������Ƃ��Ȃ��Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă��s�v�c�Ƃ��������悤���Ȃ��A���邢�͎������̓��̂Ȃ����琶�܂ꂽ�ϑz�ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����C�����Ă���قǂł���B�ǂȂ��ł��������A�����䑶���̕�����������A���Ђ��m�点���肢�������̂ł���B�i���O�A68�j
�E�����Ă����A���̕��͏C�Ƃ̑����́A�悤�₭�����ǂ߂�悤�ɂȂ����Z�A���̂��납��A���́u�̂炭��v���̂悤�ɏn�NJߖ��������Ƃ������A�Ƃ����Ă悢��������Ȃ��B���ꂭ�炢�u�̂炭��v�ɂ͑ł�������Ȃ̂ŁA�����܂��A�p�������Ȃ����ˎ������Ɠ��l�A�Ђ����Ƀm���N�����W�[�i�̂炭��w�j�́u���Ёv�������Ă݂�����C���Ă��鎟��Ȃ̂ł���B���܂ł����炷����u�ł���悤�ȁu�̂炭��v�̃Z���t���A���ɂ͂����ς�����B�i�q����I���p���[�h�r�A98�j
�E������A�����悤�ȗ�������Ă��������B��͂�푈���̍����̗w�ł���B�^�^����m��������n�͂�ĉG���^�Ԃ��[���̍��������^�v���Δ߂��@����̂��^�r��̘I�Ə����͂Ăā^���͖��邩�@���̋u�Ɂ^�^�����������B���ǂ����̍���������̉̂��낤���A���̑�O�傪���̎��ɂ́u�v���A�n���炵�A����̂��v�ƕ����Ă��܂��B�����ɂ��푈�Ŏ��ʂ͔̂n���炵���Ƃ������̎��̂悤�ɕ����āA�ւ�ȋC�������̂����͂��ڂ��Ă���B�i�q�ւ��̂��낢��r�A145�j
�E�����ɂ����āA�������̐���́A���O�Z�N��̃h�C�c�̃E�[�t�@�[�f�悾�́A���a�f�悪������ɗA��������������̃t�����X�f�悾�̂��A���̎��_�Łm�A�A�A�A�A�n�y���ނɂ͂��܂�ɂ��c�������B�������́A�e�ނ̂��Z����₨�o�����A���邢�͋ߏ��̕s�ǃ}�_���̌�����A���P���E�����[���Ƃ��A�����E�_�S�t�@���Ƃ��A�c�@���E���A���_�[���Ƃ��A�W���Z�t�B���E�x�[�J�[���Ƃ��A�}���^�E�G�b�Q���g���Ƃ��̖��O����яo���̂��Ȃ�����������ǂ��A���ۂɂ����̃X�^�[���▋�̏��R�[�h�̂Ȃ��Ŋm�F�����̂́A���͐��ɂȂ��Ă��炾�����B�i�q���E�p���}���r�A163�j
�E���������A���a�\�N�㏉�߂̏��N��y���Ȃɂ́A�悭�V���������̃V���{���݂����Ȍ����Ƃ��āA���a�\��N�ɗ��������鍑�c�������́A���a�\��N�ɏv�H�����鎺�����فi���݂̍��������فj���́A�k�ЋL�O�����́A�������̐��F�����̂Ƃ����������̎ʐ^�̏o�Ă��邱�Ƃ��������B�����_�ЁA�����_�{�A��x���Ȃǂ������̖ڂڂ������������������̂�����A�����̊��o�ł͗������ɂ������낤�B�i�q��s�����Ƃ��D�u�Ɓr�A234�`235�j
�E�b�����ǂ����B���͂ǂ����m��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ������q�ǂ��̂���́A�f�p�[�g�̉��オ�q�ǂ��̗V�я�݂����ɂȂ��Ă��āA�����Ŗؔn�ɂ̂����莩���Ԃɂ̂����肵�ėV�Ԃ̂���̊y���݂ɂȂ��Ă����悤�ȋC������B�^�ȒP�ȓ������݂����Ȃ̂������āA�������ɏ��̏��≮�̉���ɂ́A�K���X�̐����̂Ȃ��ɃJ���E�\�������Ă����̂����ڂ��Ă���B�̏����̉���ɂ́A�P�[�u���J�[�������Ĉ����������B�^���{���̎O�z�ł́A���܂������Ƀp�C�v�I���K���̉��t�������āA���͊K�i�̓r���ȂǂŔw�̂т��Ȃ���A����������Β��߂Ă������̂������B�i�q���̓��{���r�A252�j
�{�T�C�g�́A�����ċg�����̓ǎ҂Ȃ�A�v��������߂����邾�낤������n���ł���i�������m�ŋ�����Ȃ�A�������A�k�����H�ƕ��䕐�Y�A���B���ǂ����̍���������̉́A�c�@���E���A���_�[�A�鎺�����فi���݂̍��������فj�A�̏����Ɠ��{���̎O�z�j�B��������F�V�́A����Ȃ��Ƃɂ͂��������ɓڒ����邱�ƂȂ��A�u�킽���̏��N����v����ڂ����B�g���ƌ��킵���̌��ɂ���炪�o�ꂵ�������m��R���Ȃ��i���Ȃ݂ɁA�g�������F�V���F�ɂ��Βk�L���͑��݂��Ȃ��B���ʂ𒆐S�ɁA�q���̗V�тɂ��Č���Ă���Ă�����I�j�B�����A1919�N�i�吳8�N�j�A�����̉����ɐ��܂ꂽ���l�ƁA1928�N�i���a3�N�j�A�����������̎R�̎�ɐ��܂ꂽ�U���Ƃ��A������C���z���A����������ڂɂ����Ƃ��������͂��̂����Ȃ��M�d�ł���B���Ȃ݂ɁA�g���͊��x�Ŏ��̎O�����i������ɂ͑剪�M�E����N�v������j�A�F�V�͖S���E�����Y�̂ЂƂN���B�����������ēǂނ��Ƃ̂ł���A���a���\���鏑���肾�����B
�O��A�s�y���F��t�̓T�����q�S�i�����̓y���F�]�r���������B�S�i�����͂��ċg�����Ɍ��y�������Ƃ��Ȃ��悤�����A�ҏW�҂̓n糈�l�i1947�`�@�j�͉�������̌�V�^�s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�N10��19���j�̉���q�����̓��X�r�œ����ɓo�ꂷ�鏔���ɒ��߂��{���A�u�y���F�i���`��㔪�Z�j�H�c���܂�B�����ƁB���܋�N�u�F�m�����n�v�ɂēƎ��̃X�^�C�����m���B��N�A�Í������h�������A�킪�M�̃A���_�[�O���E���h�|�p�̋��c�I���݂ƂȂ����B��n�ւ��𑣁m���悭�����n�ɕ���A���ِ̈F�̃_���T�[�������m�݂��n�߂��̂��O���R�I�v�B���㔪�N�ꌎ�A�͏o���[�V�Ђ��w�y���F�S�W�x�S�����s�B�����ɂ́u�˂������Ă���l�v�Ƒ肷���������_�����^����Ă���B���ɔ����N�㌎�ɒ}�����[���㈲���ꂽ�g�������w�y���F��x�Ɠ�Z�Z��N�܌��ɉ͏o���[�V�Ђ��㈲���ꂽ�푺�G�O���w�y���F�̕��ց@���̂�60�N��x�͕K�ǂ̕����B�����y������Ƃ�����鎞�͌��܂��ČS�i���������g�������ꏏ�������B�]��������X�̒�q�ɏI�n�B���������Ƃ���̓O���Ɉ��̏C�����m��Ȃ��B���₩�Ȋ፷���̓y�������������v������ł���B�v�i�����A��㎵�y�[�W�j�Ə����Ă���B���̓n糂���|�����k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�̑�1���́A�S�i�̉ו��_�������B�u�_�v�Ƃ͂����Ă��A���̕��͕̂]�_�ł��A�܂��Ă⌤���ł��Ȃ��A���z�E���M�ɋ߂��i����Ƃ��A�g���̗p����S��āu��v�ƌ��������j�B���͂ɁA�����Ɖ��Ȃ̊W��D�肱��ł����ƁA�ǂ����Ă������Ȃ炴������Ȃ��̂��B���������Ȃ肻���ɍs���܂��ɁA�V���[�Y�S�̂���Ղ��Ă������B�R�[�x�u�b�N�X���́k�ߑ㕶�w�ꡁl�͑S8������Ȃ�B���Ȃ킿�A
�@����@�S�i�����s�ו��ʂ�t�i1976�N9��25���j���i��ו��i1879�`1959�j
�@����@�E�c�ʜ\�s���l�A�t�i1976�N9��25���j�����A���i1873�`1920�j
�@���O�@��������s����t�i1976�N10��25���j������C���i1903�`1979�j
�@���l�@�i�c�k�߁s���Ⴊ�ނƂ܂���t�i1976�N10��25���j�����e���O�Y�i1894�`1982�j
�@���܁@�r���I�s�V�瓴�H�q�L�t�i1976�N11��30���j���q��M���i1896�`1936�j
�@���Z�@�c�m�a��s�y��̑�Q�t�i1976�N11��30���j�����c�S閒�i1889�`1972�j
�@�����@�{�i���F�s�킪�t�v���t�i1977�N3��25���j�������t�v�i1892�`1964�j
�@�����@�ݓc�T�q�s�����̉̐l�t�i1977�N3��25���j���˖{�M�Y�i1920�`2005�j
��_���Ă���B���s�����疾�炩�Ȃ悤�ɁA2���������Ɋ��s���A�p���̃V���[�Y�������ł��o���Ă���i�ŏI�̑�4��z�{�͖{���A1976�N12��31���̗\�肾�������j�B���������V���[�Y�̏ꍇ�A���҂Ƙ_����Ώۂ̑g�݂��킹�͂���߂ďd�v�ŁA���̐��ۂ͂����ɂ������Ă���Ƃ����Ă������B�����̒��҂ƁA�_����ꂽ�Ώۂ��g�����ɐe�������Ƃ͋����قǂł���B���҂ł́A�c�m�a��i�l�����@�������Œm����j�Ɗݓc�T�q�i�̐l�j�ȊO�A�Ȃ�炩�̌`�Ŋւ�肪���邵�i���P�j�A�_����ꂽ�Ώۂł́A���A�Ɠ��c�S閒�ȊO�́A����܂��Ȃ�炩�̌`�Őړ_�������i���Q�j�B�����ĂȂɂ�������8�����琬��k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�̊��̌��_�ɁA�g�����I�E����̑I��W�s�k�ߕS��t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�N6��21���j�̑��݂��������Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�ނ���Ř_�����Ă���͉̂i�c�k�߂̋�ł���A��҂̉i�c�k�߂ł���B���Ȃ킿�A
�@����@�g�����s�k�ߕS��t�i1976�N6��21���j���i�c�k���i1900�`1997�j
�Ȃ�ꏑ���z�������̂��B���Ȃ����ς����Ă��A�k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl���O���ɏ�����̂́A�g�����k�߂̔o���S��I��ʼn����t���Ƃ������݂��A�R�[�x�u�b�N�X���o�Ŋ��Ƃ��ăe�[�u���ɍڂ��Ĉȍ~�ł͂Ȃ����i�S���͓n�ӈ�l�j�B�{�p���̊�{�Ŗʂ�31���~9�s�A�{���͕��ϖ�80�y�[�W�ŁA400���l�ߌ��e�p������56���ɑ�������B���ɋg������f�̑Ώێ҂̂Ȃ����玷�M����Ƃ���A���e���O�Y�̂ق��ɂ͂��肦�Ȃ��B���Ȃ݂ɋg����10�N�ɂ킽���ď����ɏ����������z�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����`��l���y�[�W�j�͖�45���A�p���̑̍ق���66�y�[�W�ɑ�������B�s�k�ߕS��t�̐i�����A�g�����k�߂Ɉ��Ă����ȂŌ���ƁA���̂悤�ɂȂ�i����������̍Ę^�j�B
�E�i�c�k�߂Ɉ��Ă��g�����̏��ȂŁA�ŏ��Ɂu�k�ߕS��v���o�ꂷ����Z���N�Z��������̂͂�������\�\�u�k�ߕS��v��������܂��B
�E��ʂ߁A���N��Z����O������̂͂�������\�\�����㋞�����Ƃ̂��ƁA���̏�A�M�d�ȁu���Áv������������Ƃ͌��Ăł��B�ĉ�̓��������炽�̂��݂ɂ��Ă��܂��B�����I�̍k�ߕS��́A������˂ƐS�ɂ��߂Ă��܂����A�����������Ԃ��������B
�E�O�ʂ߁A���N��ꌎ��O������̂͂�������\�\�ĉ�ł��Ă��Ƃ��킸���ł��A���������݂��킷���Ƃ��ł��āA���ꂵ���v���܂����B���̏�A�ƂĂ��M�d�ȋ�W�u���Áv�����������A�����̂�����ł��B�k�ߕS��I�����Ȃ���ƁA�v���܂����B
�E�l�ʂ߁A�����Z���N�㌎��O������̂͂�������\�\�O��́q�k�ߕS��r�Ȃ�Ƃ����N���ɂƎv���Ă��܂����A�d�����Z�A�N���̈��z���Ȃǂ�����̂ŐS�z�ł��B
�E�ܒʂ߁A���̗����Z��N��������̑��B�͂�������\�\���莆�Ƌ�W�s�����t�����܂����B���ς������ȑ��{���ꂵ���v���܂��B�k�ߕS��Ȃ�ƂȂ��S������܂��B
�E�Z�ʂ߂ɂ��čŌ�A���s�̑O�N��㎵�ܔN������������̂͂�������\�\����ǂ̐_�ˍs���ŁA�c���ł��������Ԃ��A��ԏ[���������Ԃł����B�{�����w�ŁA�k�߂�������܂������āA�\��Ȃ��v���Ă��܂��B�n�ӈ�l�N�Ƃ́A���s�܂ňꏏ�ŁA�s�k�ߕS��t�̑ō������������܂����B
���āu�k�ߕS��v�������s�k�ߕS��t�ɂ܂łȂ������ƂɊ��S���o����B
����A�S�i�́s�ו��ʂ�t�ɂ��ǂ낤�B�y���̕�����_�������͂Ƃ͂����Ԃq�̈قȂ邱�Ƃ��킩��i�k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl����̈��p���́A���ȂÂ����͌����̂܂܁A�����͏�p�����ɂ�����̂͂�����g�p�����j�B
�@�吳��N�́A���̐��ꂽ�N�����A���̔N�ɔ��\���ꂽ�w�U�����[�h�x�Ƃ��������́A���̂Ƃ��́A�w�Y��҂̎��x�Ƃ����̂ł������B������F�́A�V�ۂ̉��v�ɂ����āA�w�c�Ɍ����x�̕M�Ђɂ����A�T�Ƃ��āA���̎���������ꃖ���Ԃ́A����͂������ϓ����݂��邻�̊Ԃ̐S����`�������̂ł��邪�A�ו��̂Ȃ��̍]�˂��݂�̂ɂ́A�w�]���Y�p�_�x�Ȃǂ��A���������[�I�ɁA���̏����̕����A���̊j�S�ɔ��邱�Ƃ��ł���悤�Ɏv���B
�@�ꌾ�ɂ����āA�ו��̍]�˂́A���܂ɂȂ��Ă݂�A�܂������̍����̂ɂ����Ȃ��B�܂��ƂɁA���̍����̂�����������ʂ��߂́A���邢�͎���\�����߂̎����Ȃ�]�ˌ|�p�_���͂��炳��Ă���̂�m��B�k�c�c�l�i�����A���`���y�[�W�j
�@�k����Օ��l���m�̘b�ɁA�������A�����́u����y�v�̏����m�����݁n�ɉ������K�������Ƃ�����Ƃ���ꂽ�B���́u����y�v�̏����Ƃ����̂́A�]�ˍŌ�̕����G�t�ł����������F�N�̖��ŁA�ꒆ�߂ł͓s��~�𖼏��A�����̖���ł��������B���̍��́A�����݂̂����l�͂Ȃ��A�݂ȌËȂ����������˂Ă����̂ŁA�����͂��߂Đ�L�ɓ��債���Ƃ��A����܂łȂɂ����Ȃ���������Ƃ����邩�ƕ�����A����A�Ȃɂ��Ȃ��Ƃ����ƁA�N�Ƃ��Ă����ӋC�Ȑ�L�́A�����͂��낢��ȉ��Ȃ̋Ɋy�̖��ɂ����̂��A�M�������k�S�i�Ƃ��̗F�l�l�̂悤�Ȃ̂͂͂��߂Ă��Ƃ����ăP���P���Ə��̂ł���B�̂��ɂ́A���̉��Ȃ̉��n�́A�Ȃɂ��Ȃ�����A����ł����O������̂ق����G��C�Ȃ��̉�������Ƃ����悤�ɂȂ����B�ו��̉����́A���ȓ��y�̖��ɒH������Ƃ����_�ł͖{�i�I�ł������B�i�����A�Z�Z�`�Z���y�[�W�j
���͖M�y�ɏڂ����Ȃ��̂ŁA�֘A�̂b�c����ĕ������B���Ȃ킿���c�@�l �Ëȉ�ďC����S12���g�s�ËȂ̍��t�i���c�@�l ���{�`�������U�����c�A2006�N9��6���j���^�̋{���߁i4���g�j������ŁA�q���ӎR�r�Ȃ�9�Ȃ����߂�B�|�����h�́q����r�Ɉ˂�A���Ȃ́u���J�����̒�D�V���ƕ����̐S�����s�B���炽�߂Ă����܂ł��Ȃ��{���߂̑�\�Ȃł���݂̂Ȃ炸�A�ߐ����{���y���\���閼�Ȃ̂ЂƂł���B����͖����ł���A�����̗��s��S�̖����������A����ɒn�̂Ƌ`���v���ȋC���ƕ��͋C���I�݂ɑg�ݍ��킳��Ă���B�v�i��������A�܋�y�[�W�j�ł���B�s�M�^�[�Ŋo���鉹�y���_�\�\�m�M�������ăv���C���邽�߂Ɂt�i���b�g�[�~���[�W�b�N�A2005�j�̒��ҁE�{���M�́A���m�̃W�������̉��y�ɐ��ʂ���ɂ́A���̃W�������̖���10�q�����ނ��Ƃ��Ɗ��j�����B����ɕ���āA���ʁq���ӎR�r�i��30���j�����ނ��Ƃɂ��悤�B�̕���̌����҂Ƃ��Ȃ�A�����i�{�ØH�����m�݂₱�����̂͂��n��c�Ƃ����ڗ����y�̌ËȂ̂ЂƂB�{���߁A�����߂Ƃ��j�̂ЂƂ�ӂ��A�X��Ȃ���Αʖڂ炵���B
����A�E�c�ʜ\�́s���l�A�t�́A���̐����ɂ��Č�����q���Ƃ����r������ɔ@���͂Ȃ��B�Ȃ��A�����ɂ́u���a�\��N�����^�E�c�ʜ\�v�Ƃ���i�����A���O�y�[�W�j�B
�@���͊��A�Ƃ������l�̏�M���D�����B��M�͍������ł����B�ނ̐l���ϓI���z�ɂ͂��̂悤�Ȍ�����������A���͂ƂȂ�B���͐��N�O�ɒZ���ȖA�Ɋւ���G�b�Z�[�������Ă���i�w�����C�J�E���{�̐��I���x���a�l�\�ܔN�\���j�B����ӂ����іA�ɂ��ď����@���^����ꂽ�̂ŁA���e��S�ʓI�ɉ��߁A�V���Ȉ�т��㈲���邱�Ƃɂ����B�R�[�x�u�b�N�X�n粈�l���Ɋ��ӂ������B
���O�A��������s����\���邢�͖��ٕ̈��t�i���R�j�ɂ́A���l�Ɣo�l�������݂Ɍ�肠�����i���`����Ă���B
�@���l�͎���̋净�����̓{�茩�����菬�h�ꖪ�������A���S���V���Ɏv���o���Ă����B����͏��a�\�Z�N�A������V�������A���X�������Ň��S�����̈��A�����炭�킪�ŏ��̔o��炵�����̇��������B�������Ȃ��G��߁A�ł����グ�̎�蒲�ׁA���͂��}�ɒ��������ɂ�錾�_�����Ȃǂւ̓{�肪�قƂ���o�Ă������ꍆ�B���l�͂ǂ��ɂ������Ă����ꏊ�̂Ȃ��{����A�͂��߂āA���ɂԂ������Əq�����Ă���B��҂͉��߂Ă��܁A����A���]�肾�����ȁA�Ɛ�����݂��߁A�j���ق�����Ă���B�����̖��Ŏv���o��������ǁA�Ԗ�̂ЂƂ�Ƃ��āA�w�����x�ɏ\��傩��̔��傪���W�����Ƃ��̏䑐�̈��u��������ė�����̏������ȁv���A�ӂ��ƁA�������ďo�Ă����B�q���̍��̏䑐���͂��߂č�����Ƃ�����͂������A�u���債�ď͂�ɂ��荡���̌��v�Ƃ��������[�����X�ȋ傶��Ȃ��������ȁA�Ƃ��B�����āA�푈�����̏��a��\�N�ɋ���Ŏ�ɓ��ꂽ�䑐�W�́A��c�ʓV�O�҂ɂ��嗈�g�Ў��ł̂����̈���̑吳�{�ł��������ƂɋC�Â����B�����ĂȂ��A�H��́w���]���G�L�x�ɂ́u�䑐�̎��v�Ƃ����Z���̂��������Ƃ��B�i�����A�O�O�`�O�܃y�[�W�j
�@�䑐�͂����������A�C���̐搶�i�ɓ��鏇�O�Y�Ƃ����z��o�g�̎��l���Ђ˂�o����������E�������Ƃ�����B�u���̓V�͐��ꂽ���J�M�v�u����O�邶�Ⴘ�݂�̑������ڂ炯�v�u�����̖̎������̏h�v�u�̎��Ƃԉ䂪�ӂ邳�Ƃ̗[�ׂ��ȁv�ȂǁB���̎��l�́w���l���ւ炸�x�Ƃ������W�ɂЂ�����Ƃ��Ⴊ��ł���n�C�J�C���ɂ��������ꂽ���A�u�m�Ԃ̋�ɂ͋��ƒ��̂��Ƃ������̂͑��q����̘A�z�����m��Ȃ��B�v�Ƃ��A�u�m�Ԃ̂����ꂽ���l�I�˔\�͂ǂ��ň�Ă�ꂽ�����ɂ͒����Ԃ킩��Ȃ������B�������K���ɋ��R������ǂ݂������Ƃ��ɁA���̒j�͂��炵�����l�ł��邱�Ƃ������B�v�Ƃ������͂ɐڂ����Ƃ��A�킵��Ԗ�̘A�O�͊�F�������������B�i�����A�l�O�`�l�l�y�[�W�j
��������́A�̂��Ɋ�g���ɂŁs�H�엳�V��o��W�t�i2010�j�Ɓs�ו��o��W�t�i2013�j��҂�ł���A�����䑐�ɋ�����ɂ��܂Ȃ����V��̋�������]�����Ă���B
���l�A�i�c�k�߁s���Ⴊ�ނƂ܂���\���e���O�Y�����t�́A���e���O�Y�́s���l���ւ炸�t�̓�тɏœ_�ĂĂ���B
�@���a�l�\���N�Z����\����A���͐��e���O�Y���W�w���l���ւ炸�x���Ŗ{�i�Ĕł����������ǂ����͒m��ʁj������i�������Ï��X�ŘZ��ܕS�~�œ��肵���B�����I�Ȏ��i�̎��i�ȂǂȂ��܂܁Aꡂ��ɂ��̂��납��Ƃ������ƂȂ��ɁA���i�̋[�Ԃ��y���݂Â��Ă���،h�����̑厍�l���e���O�Y�̋M�d�Ȏ��W�Ȃ̂��B�w���l���ւ炸�x�͎��㐔�X�o�ł��ꂽ�u���e���O�Y���W�v�₻�̊ӏܖ{�ŏo����Ă������A���������w��lj��ꏝ�݂̂Ȃ����{�ɏo�������낱�т͉�Ȃ��疳�ނł������B�i�����A���y�[�W�j
�k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�z�{�̃y�[�X���炢���āA�k�߂��{�����M�O�ɑO��z�{�̉�������́s����t��ǂދ@����������ǂ����B������ɂ��Ă��A�����̖{��ǂ��Ƃɍk�߂̖{��ǂނ��Ƃ́A����߂Ď��R�ȗ��ꂾ�B�k�߂������������炾�B
�@�ؗF��������́A�V���|�W�E���u���̊��сv�i���e���O�Y�A��������A���J�K�M�A�E�c�ʜ\�A�߉ϑ��Y�j�Ƃ����{�̂Ȃ��ŁA��f�ꎍ���u�ǂނ��тɁq���Ⴊ�ށr�Ƃ����̂��g�������āA�������Ă������Ă������Ȃ��Ȃ���������v�ƍ��X�{�S���Ԃ��������Ă��Ĕ����ł���B�悸�͂��̖��͂́u���Ⴊ�ޏ��v�̔ڑ����ɍ����Ă��锤�́u���ݑ��G���`�V�Y���v�ł������ɈႢ�Ȃ��B�k�c�c�l�i�����A��܁`��Z�y�[�W�j
�u�܂���v�Ɋւ����߂͊������āA���̉ӏ��͂��Ќ��Ă��������B
�@���e���O�Y�̎��_��G�b�Z�C�ɂ͎�|�̌J��Ԃ��������B���̌J��Ԃ������ɂ͂��܂�Ȃ��������B�������n���̊������������ŁA�����悤�ȕ��߂ɉ��ׂ�o����Ă��O����Ƃ������Ƃ��Ȃ��B���̂��낤�B����͐��e���O�Y�������D��������Ȃ̂��B���X�D���Ƃ������Ƃ����邪�A��������镶�߂����x�̑f�p���ŁA�^���̃p���h�b�N�X��D�V���Ă��邩�炾�낤���B�T���w������k燂̍ł�����̂Ƃ��邻�̗����̍����[���傫���ɍ���ڂꂷ��B�m�Ԃ̌Òr�����~悂ƊŔj���邱�̔j�i�̊�͂ɂ́A�u�o�łȂ����̂�o�Ƃ��邱�Ƃ͍ō����~悂ł���v�Ƃ���������̌x�����^���ł���̂ɁA���킸�ɉ��ɐS���ł���B�_��Ƃ���͂����ނˋ���I���E�ɖʔ����Ȃ��肪��������A�t�炤�]�n���Ȃ��̂��B�قȂ�����̂��̂���Ɍ��������A�u���͂��ُ̈�ȊW�����������Ƃł���v�Ƃ����A�u�D�ꂽ���͂ǂ����ύt��Ɉ����قȂƂ��낪�K������v�Ƃ����x�[�R���̌��t���x�X�N�p���ꂽ�肷��̂��������Ă��܂�ʂ̂́A���ꂪ����I���E��ʔ����h�g���Ă��邩��ł���B�k�c�c�l�i�����A���l�`���܃y�[�W�j
�g���͂��āA�u���ю��сw�߉́x���s�́A���e�搶���\�Z�̎��̏������낵��i�ł���B�������̐����ߒ��̂����ꕔ���������A�_�Ԍ����ЂƂ肾�B���I���͂ɂ́A���Q�������̂ł��������A���z�ًȂ̔����������A�]����悷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�i���ԁA�����璷�ȍ�i�Ƃ�����ۂ����c���Ă��Ȃ��������A���x�ʓǂ��Ă݂āA�F�������߂��B�Ɠ��́u���������v�ɏ��A�u���O�v�̖��x�ɐZ���̂��B�v�i�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u12�@�嗝�̎ցv�B���o�F�s�V���t1982�N8�����A����q���e���O�Y�A���x�X�N�i�Ǔ��j�r�B�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�l�`��l�܃y�[�W�j�Ə������B���͒��ю��s�߉́t�����A���e�̎��_�s���w�t�ɂ�����������B�����A��҂͂��������Ȃ��̂�����A���܁s���w�t���ēǂ���A�k�߂́u�������n���̊������������ŁA�����悤�ȕ��߂ɉ��ׂ�o����Ă��O����Ƃ������Ƃ��Ȃ��v���������邩������Ȃ��B�|���悤�ȁA�������悤�Ȃ��̂ł���B
���܁A�r���I�s�V�瓴�H�q�L�\�q��M��t�͖q��̒Z�я����q�V�瓴�H�q�L�r�i�u���X�\���܂ł��Ȃ����Ƃ����A�܂����l�ɂ͕v�X�l�X�ȕȂ�����ł͂Ȃ����A�n�_�䂷�肾�Ƃ��܂����ނƂ��A��̕���������Ƃ��A�����đ���̊�����Ȃ��œ��ӂƂ���Ɍ��Ă͂Ȃ�������Ƃ��A���ł�伂��i���Ƃ��\�\�Ƃ��ꂱ��������硂͂Ȃ��B�k�c�c�l�G�Ȃ����ɐ���n����ł́A��H�̓��~���I�ȋ��т������āA�I�X�����ւ�`���Ă�B���A���͎����̊��Q�̋��тƂ������̂́A�ǂ�����ӓ̐����Ԉ�ւ����̂ł����炵���B�v�j�ɂ��̕W��ƕ��̂���Ă���B�h�C�c���w�ҁA�G�b�Z�C�X�g�Ƃ��Ēm���钘�҂́A�����ƂƂ��Ă̑��ʂ𖾂炩�ɂ����Z�тƌ��邱�Ƃ��ł����i���S�j�B
�@�Ƃ����������́u�V�瓴�H�q�L�v�Ɩ��ł����B�ؗp�����ɂ��Ă��A���̕\��͎v�������B�܂��ɕ��w�I�H�q�Ƃ��āA�Ƃ��ɐ�́u�H�q�L�v�ӎ����s��p�ɖ͕킵�A�܂�Ȃ����Ƃ����������ɁA���̔w�ʂɂ̂т̂тƎ葫��L�����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��B���͖q��M��̂₳�����C���Ɣ����ȐS�Ƃ��̉���̑����˒m�����������킹�Ă��Ȃ��̂����A�Ƃ����������鈫�Ȃ���́A���_�A���̈��Ȃ̗R�X�����͊r�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��ɂ��Ă��A�Ƃ��ɂ���Ǝ����ɂ����������A�ł��������������������̗U�f�ɐg���܂����邱�Ƃɂ����̂ł���B����ɂ��Ă��A���͂��܈�A���������������������ł���B�܂�A��ʂɂ�����j��̐l�����l����Ƃ��A���̏ꍇ�A���鎞���́A���邢�͂����̒�܂����l�������̐l���̂��̂ł���ƒ�܂��Ă�����̂��B���Ƃ��A�`���̃o�C�����͔��e�̐N�ł����āA�u���b�V���O�g���v�l�̒m�ȂɂȂ������̉����̏o�����Â̒j�ł͂Ȃ����A�g���X�g�C�͏�ɋЍL�̑т����ɒ��߁A�c�ɒ�������陂�����̘V�_�v�ł���B�����Ď��ɂƂ��āA�q��M��͂��������V�瓴�̐H�q�ł������B���͔ނɏ�X�V�瓴�̐H�q������B����͈�u����Ƃ������p�ɂƂǂ܂�Ȃ����A�������A���̐H�q�ȊO�ɂ͌����ĂȂ肦�Ȃ��̂ł���B���Ȃ킿�A�܂��ɂ��̐H�q�������������悤�ɁA�����������ŕς�͂��Ȃ��̂ł���B�i�����A�O�Z�`�O��y�[�W�j
�u��i�͔��\���z��Ƃ��A��ɍŏ����̓��b�E���@���^�B���̐����ƑS�e�����߂Ă����炩�ɂ���v��搂����s�q��M��S�W�k�S6���l�t�i�}�����[�A2002�`2003�j�́A�����g�����������������A���������c���Ƃ��낤�B���Ƃɂ������A������������������������Ȃ��B
���Z�A�c�m�a��s�y��̑�Q�\���c�S閒�̉��فt�͕S閒�_�ł���ƂƂ��ɁA�H�열�V��_�ł�����B�u����̗F�A�H��͋@�q�̍j�n������āA�ꍏ�������l���̉��������o�����Ƃ��Ă����B�S閒�͂��̂Ƃ��A�D��Œx�^畏����A���|��\�����Ȃ��炠���ċ̈łɐZ���āA���l�����@���ɂӂ���Ԃ��Ă����B�v�i�����A�ꔪ�y�[�W�j�B
�@���l�͏�l�ɂ͌����Ȃ����ق̐��E������B���ق̐��E�͂��̈��|�I�ȋ��낵���Ɛ^�����������Č����̐��E�������Ă��܂��B���ق̐��E���ЂƂ��т̂����������̂͗e�ՂȂ��Ƃł͌����̐��E�ɖ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�H�ɂ�������߂��Ă������̂͗\���҂̂悤�Ɍ����Ȃ����E�����͂��߂�B�S閒�͋��C�����Ԃ炩���A��ȂÂ��āA���ɏꏊ���������ɏo�����Q�̗�����������Ƃ��Ȃ��߂��Ă���B�������A�\���҂̌��͂��̂܂܂ł͂��̐��Ɏ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�\���Ƃ͌�����ے肵�A�]����������̂����炾�B�����Ŕނ��~悂������Ă��̋���ׂ��^���̑����݂Ȃ��瓹���t�ƂȂ��āA�ފ݂̕��w����邱�ƂɂȂ�B���������̐��̎v���o�͂��Ƃ��Ƃɔ]���ɂ�݂������āA���������������̂͂��Ȃ��Ƃ������܂Ԃ���A���܂�ɂ������炩�Ɍ�������B�������Ƃ͂��͂�₢�߂��i�ł͂Ȃ��A�s����J���L�`�����ĊO�ւق��肾���A���ӂ�����ĖY�ꋎ���i�ƂȂ�B�������Ƃ̑O�ɂ͘b�����Ƃ����邾�낤�B�i�����A�O�`�l�y�[�W�j
�c�͐���V�i�����A���́u���v��Y��Ă͂����Ȃ��j�Ȃǂ̓������S閒�̉��ق̐��E�̏d�v�Ȕ����ł��邱�Ƃ���������B����͂Ƃ���Ȃ������A�g�������ɓo�ꂷ�铮���̈Ӗ����čl����ƂΌ��Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤���B
�����A�{�i���F�s�킪�t�v���t�͂��̑p���ł͒������A���o���������Ă���B�q��@�S�Ɩϑz�r�ł͎O���R�I�v�̔�]�i�Ə����j����|����ɂ��āA�q�ǁ@�t�v�Ƒ���r�ł͕����ǂ��荲���t�v�ƈ�_����Ƃ̊m�����ڏq���A�q�Q�@�c���̗J�T�r�ł͏t�v�̍�i�j�ɂ����铯��̈ʒu�̊낤����_���A�q��@�V�c�܂Łr�ł͔ӔN�̍�i�Q��Q���A�q���������r�Ɓs�}��W�t���̗g���ĕM�𝦂��B�Ō�́q�ށ@�����t�v�G��ꗗ�r�ł�28�̍�i�������Đ������Ă���B
�@���˂��ˎ��́A��l�̕��|�̍������Ȃ����̂͏������ł͂Ȃ��炤���ƍl�ւĂ����B�x�����D��S�A�����ڂ݂Ȃ����菟�肳�A�c���Ȋώ@��A�ƑP�I�����c�ȋ�z�ȁc�c���ɔ|�͂ꂽ�A���V�a�҂̖����V�s�ɂ���������惝怳�̎���ȂǂƋL���Ɨv�̂����Ȃ����A�ނ�̑ԓx�͏����ɝR��I�ȐR����`�i����̒���Ɂw���̂͂��Ȃ��x�Ƒ肷���т���j�Ƃł��\���ق��͂Ȃ��A��l�͋��ɓ��b�m�����q�G���n�̗̓y����o�������̂ł���B���ꂪ�A�t�v�ɂ����Ă͂˂Ƀ����h���}�e�B�b�N�ȕ\�����Ƃ�A����ɂ��Ă͓N�w�I���w�I�ȌX����L����B�����āA���̍���́A��i�̏�ɔ@���Ɍ���Ă��B���p�A���z�A�T��y�ї��i�t�v�H���\�\��I�Ƃ��ӕ����͎������Acuriosity hunting�̖��Ƃ��đ��ꂵ���j�A���C�A�@���c�c���ւ̊S��屢屢�t�v�̑n��̓��@�ƂȂĂ�邪�A�����⑫��̍�i�͎��m�̂��Ƃ����N���ƓV�̚n�D�Ɣ�s�Ǝu�]�Ƃɂ�Ďx�ւ��Ă��B���̑��Ⴊ���̂܂ܓ�l�̌��ʂ̈��ł�����A�ނ�ׂ̈������|�̎�F�ł�����B�w���lj匢�̉Ɓx�Ɓw����b����x�̊Ԃɂ͂������鋗����͂Ȃ����B�R���A���䂪�w����b����x����o�����āw�\�Ӂx�̍��݂ւƏ�m�̂ځn���̂ɑ��āA�t�v�́w���lj匢�̉Ɓx�̋��n���Ȃ����Ɛ\���悤�B�ނ���A�J���}�����ӂ�������B�i�q�ǁ@�t�v�Ƒ���r�A�����A�l�l�`�l�܃y�[�W�j
�����������Ȃ��_����A���҂́u�\�N�]�ɘj�Ĉ��ǂ��Ă��������t�v�ɂ��ċL�����������A�������瑊�I�Ȓ��q��тт����ƂɁA�܂Î����ŋ����Ă��B�ǂ���瑼�l�ȏ�̑��݂Ǝv�Ђ��ނƁA�����Ǐ]�̗ނ͉e���Ђ��߂Č��ɂ����O�ӂƂ���ɕM�����肽������̂炵���B�v�i�����A���Z�y�[�W�j�Ƒ������Ă���B���ꂱ�����u�킪�t�v���v�Ȃ̂ł���B��N�̋g���͔��H�̒Z�̂ƂƂ��ɁA�t�v�̎������u�����B�{���Ő{�i�́A�t�v�����l�Ƃ��Ă͐��U�ꗬ�Ǝ]�����B
�����A�ݓc�T�q�s�����̉̐l�m�����тƁn�\�˖{�M�Y�_�t�ɂ����o���������Ă���B�q���́r�q�т�̉ԁr�q����͂������r�q�v���ʂ̈��r�q�n���͂r�q�����G�m�͂����݁n�r�q�I�́r�B�ݓc�͖{���ŁA�˖{�𒆓��̎��l�E����i791�`817�j�ɂȂ��炦�Ă���A�����������̒˖{�M�Y�_�Ƃ͈قȂ��Ă��鏈���B
�@�ނ̋S�ˁA��̋S�ˁA���Y�͗����̌ǁm���n�Ȃ�C���̖��ł���A���I���̑n�n�҂ł���B����͐l�𖣂�����Ɠ����ɂ͂˂����Ղ������������Ă��B���̊i���̍������A����ł��邱�Ƃ��A�ЂƂɂ͉C���ւ̑S���Z�I�A�ӂ��ɂ͂��̖��I���ɂ����̂ł���B�����āA���ׂĂ͂䂽���Ȍ��z�̔c���̂����炷���̂ł����B���̔�������h���ɗ�����ɂ́A����ɑ��銴�����āA���ꂽ���z�̊j�ɂӂ�A�Č��z�����݂�ق��Ȃ��̂ł���B�i�q�I�́r�A�����A�����`����y�[�W�j
���Ȃ݂ɒ˖{���g�́A����̓����̒Z�̂ɐG���
�@��҂͐��Ԃ��Ȃ��A���̑��̏W�w崉ԁx�ŁA�^�C�g���ɂ����������g�̐S�������߂āA���̂悤�ɉ̂����B���̌���A����A�����̂�����͈�i�Ƃ����܂����A���邢�͂₳�����A�O�\�ꉹ�C�͈ꌷ�Ղ��Ȃ���ɐ�������l�ɓ`�����B�i���ԏW�s����S�̉��\�\�����ɂЂ炭���t�A�ԗj�ЁA1990�N7��20���A��y�[�W�k�V���E�V���ȕ\�L�͌����̃}�}�l�j
�ƋL���Ă���i���̉ӏ��̈��p���ł����q�����̏W�s崉ԁt�̂��Ɓr���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�Ȃ��A�p���̑����ɂ͂Ȃ��������A���̑�8���ɂ̓R�[�x�u�b�N�X���s�̏��Ђ̍L���ł���x�i�\���Ɉ���j���������܂�Ă����B�{�i���F�́s�Ŏ��сt�Ɗݓc�T�q�̉̏W�s�闍�t�i�莫�ɂ͗��ꂪ������A�����ɂ͐{�i������������Ă���j�̓ł���B
���́k��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�S8�����s���{�̌Ö{���t�o�R�Ő_�c�_�ے��̖^�Ï��X�i�Ƃ��ɖ���邷�j����w�������B�����̊��ɂ͂���قǍ����ł͂Ȃ��������炾�B2020�N6���̂�����A���J�ɍ���ꂽ�S�����䂤�p�b�N�œ͂���A�܂��͒˖{�M�Y��_�����ݓc�T�q�́s�����̉̐l�m�����тƁn�t���J�����B�Ƃ��낪���́u158�Ԗ{�v�����̂̌����ɗ����{�������̂ł���B����ɂ킽�邪�A�������悤�B�{����8�y�[�W��1�܂�ŁA���̂悤�ȑ䊄�ɂȂ��Ă���i�m���u���́A�����̌r�����ɁA�u�܁v��u��Z�v�̂悤�ɁA�������ŏc�ɑg�܂�Ă���j�B
1�܂�i01�`08�j������1���i01�`02�j�E�{���^�����i03�`04�j�E�莫�^�����i05�`06�j�E�{���k�܃y�[�W�߁l�^���k�Z�y�[�W�߁l�i07�`08�j
2�܂�i09�`16�j���{���k���y�[�W�߁l�^���k���y�[�W�߁l�i09�`10�j�E�{���k��y�[�W�߁l�^���k��Z�y�[�W�߁l�i11�`12�j�E�{���k���y�[�W�߁l�^���k���y�[�W�߁l�i13�`14�j�E�{���k��O�y�[�W�߁l�^���k��l�y�[�W�߁l�i15�`16�j
3�܂�i17�`24�j���k�c�c�l
4�܂�i25�`32�j���k�c�c�l
5�܂�i33�`40�j���k�c�c�l
6�܂�i41�`48�j���k�c�c�l
7�܂�i49�`56�j���k�c�c�l
8�܂�i57�`64�j���k�c�c�l
9�܂�i65�`72�j���k�c�c�l
10�܂�i73�`80�j���{���k����y�[�W�߁l�^���k����y�[�W�߁l�i73�`74�j�E�{���k���O�y�[�W�߁l�^���k���l�y�[�W�߁l�i75�`76�j�E�{���k���܃y�[�W�߁l�^���k���Z�y�[�W�߁l�i77�`78�j�E�{���k�����y�[�W�߁l�^���k�����y�[�W�߁l�i79�`80�j
�����܂ł͂����B�����A�ȉ�������
11�܂�i81�`88�j���{���k����y�[�W�߁l�^���k���Z�y�[�W�߁l�i81�`82�j�E�{���k����y�[�W�߁l�^���k���Z�y�[�W�߁l�i83�`84�j�E�{���k����y�[�W�߁l�^���k��Z�y�[�W�߁l�i85�`86�j�E�{���k����y�[�W�߁l�^���k��Z�y�[�W�߁l�i87�`88�j
12�܂�i89�`96�j������1���i89�`90�j�E���t�k��O�y�[�W�߁l�^�����k��l�y�[�W�߁l�i91�`92�j�E����1���i93�`94�j�E����1���i95�`96�j
�ł���B�i�d���ɂ͖ڂ��Ԃ�Ƃ��Ă��A�j�{���k����y�[�W�߁l���瓯�k�����y�[�W�߁l��8�y�[�W�����������Ă���̂��B����͘a���Ɋ��łň�������܂蒚����Œ����������߂ɁA�܂蒚����肿���������ʂ��Ǝv�����i���T�j�B�{���̂悤�Ȍ���łł͒v���I�Ȍ��ׂ����A�ʏ�łł��������킹�����Ă����Ƃ���͂�������A�Ȃ������������̂��N�����̂��킩��Ȃ��B���i�Ŕ��o���Ȃ������̂��D�ɗ����Ȃ��B�Ï��X�������{�ƒm���Ēl�t�������Ƃ͎v�������Ȃ����A�m���u�����p���p�����邭�炢�͂��邾�낤����A������悭�킩��Ȃ��B������茾���Ă��Ă��A�������{���͓ǂ߂Ȃ��B���R�̂悤�ɁA�ߗׂ̌����}���ق͏������Ă��Ȃ��̂ŁA���ݑݎœ����s�������}���ُ����̈�{���肽�i�u357�Ԗ{�v�j�B�{���k���Z�y�[�W�߁l�̌��J���ȍ~�����m�N���R�s�[���āi�J���[����1��50�~������j�A�ْf���Еt�������u�ʍ��v���萻�ł����ė��������Ԃ����B��Ԃ͂����������A�{�����ǂ߂������ł��P���Ƃ��悤�B����ɂ��Ă��A�����Ő܂蒚�����Ԃ��Ă����Ƃ������Ƃ́A�u158�Ԗ{�v�̋ߕӂ̕ʂ̖{�ł�����ւ���Ă���킯�Łi���{�ƊE�ł͂������A�u�O���v�ɂȂ��Ă���A�ƌ������j�A������̕����C�ɂȂ�B�����@�����A�����̉��t�i�k��O�y�[�W�߁l�j��^���Ă������B�k��h�p���l�̕\�����Ȃ��̂͂Ƃ������A�������Ȃ��̂ɂ͋������A�{���ɂ͑o���Ƃ�����B�����͐����g�p�����A��p�����̂�����̂͂���Ŋ��ق��Ă��炨���B
�ߑ㕶�w�ꡁ@����
���@�ҁ@�ݓc�T�q
���s�ҁ@�k����Y
����ҁ@���㖯��
���{�ҁ@�{�쐽��
���s���@�_�ˎs���c��O�{���꒚�ڈ�Ԓn�@�R�[�x�u�b�N�X
������@�_�ˎs���c�扺�R��ʌܒ��ړ�\�O�Ԓn�@�n����
���a�\��N�O����\�ܓ���s����ܕS���̓�357�Ԗ{��
�ȏ�͗]�k�̂悤�Ȃ��̂����A����͌���ł�����ŗL�̋L�Ԃ̃Z�b�g�i���Ƃ��u158�Ԗ{�v�j�Łk�ߑ㕶�w�ꡁl��ǂނ킯�Łi�s����500�������ʂ���A�ǂނɒl����{�ł���Ȃ�A�K�����ɂ��邱�Ƃ��ł��悤�j�A�s�̖{�������ɑ�ʐ��Y�̍H�Ɛ��i�Ƃ͂����A�ŗL�̈���ł��邱�Ƃɂ����͂Ȃ��B�Ƃ���ŁA�����̂��̃T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�́u���ш�Y�������E���q�E�쐬����A���l�E�����Ƌg�����̐l�ƍ�i����������y�[�W�B�g�����̒����������ʂ���⊮���A�ӏ܂ƌ����Ɏ�����B�N���E�����E�Q�l�����ژ^�ق��v�ŁA���̓T���̑��́A�����܂ł��Ȃ��g�����̎��W�A�Ƃ�킯�s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�ł���B�����̉��t�ɂ́u����Z�N�O����\�ܓ��@���ő������s�v�Ƃ��邪�A�����Ɍ�������͔��y�[�W�Ɂq�t�r�������C���łŁA�u���ő����v�ɂ́q�t�r���������̂ƁA���̖{�̂悤�Ɂq�t�r���܂ނ��̂���������B�s�����V���k�[���l�t1996�N7��20���̃R�����s��g���g�t�́q���ň���̊��G�r�Ƃ������͂��f���Ă���B�M�Җ��u�����v�́A�ނ��g���̎��сq�����r�i�C�E19�j�ɂ��₩�������́B
�@�]���́u�g�����S���W�v�i�}�����[�j���A�������������Ă���Ɠ��肵���B�ꖜ���~�����鏭�����̍��ؖ{������A�������X��������͓̂��R�����A���ו������X�Ɣ��ꂽ�X�����������B�g���l�C�̂�������B
�@�������W�̈�т��E�����ď��ł���������������v��ʐ�`���ʂɂȂ������B���邢�́A�}�������ň���ŏo���Ō�̖{�Ƃ̂ӂꂱ�݂��A�D���Ƃ̊S�����������B���ł͋g���̈�u�ł������悤���B����Ƃł�����A�}���̎Ј��Ƃ��Ė{����ɂ��邳�������g�����{�]���낤�B
�@���ň���͂����B�����ʂ��Ȃł�Ɗ������������ʉ���������B�A���H�����H�̎��Ƃ��W�J�ɓ`���悤���B���̕����t�������H������ŗ���C���ɂȂ�B�{�͐G����̂ł�����̂��B���͐V�����n�ߎʐA�������펯�ɂȂ��Ă��܂����B�����{�ň��������ɂ͂Ȃ��݂ɂ������A�����ɂ͋t���Ȃ��B������������́A���̖{���J���Ċ������₷���Ƃɂ��悤�B
�@���^��������{���p�������������{�ɂ͏����s�����B�܂��A�{�̃J�o�[���j��₷���B�܂��A�n�̃n�i�M���������ɐH�����݂����Ă���̂��C�ɂȂ�B��A�O�̗F�l���������{���������������B�g���Ȃ牽�ƌ������B
�@�Ō�ɗv�]�����A�U���̕�������W�����Ăق����B�g���́A������̑S�W�������Ă������l�ł���B �i�����j
���͋g���z�q�v�l�����{����������A�C���ł̎s�̖{�͐_�c�{�X ���������X�ōw�����Ă���i96-04-30 14�F32�j�B���t�y�[�W�ɂ��̂Ƃ��̃��V�[�g������ł���̂��B

�萻�̃W���P�b�g�ł�������́s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j �k���t�ɂ́u����Z�N�O����\�ܓ��@���ő������s�v�Ƃ��邪�A�{���͔����������y�[�W�Ɏ��сq�t�r�i�@�E1�j�������C���Łl
�u�{�̃J�o�[���j��₷���v�́A�������ɂ��̂Ƃ��肾�B���͕\���̏�Ɍ���̉��ώ���1���킹�A���̏�Ɂu�{�̃J�o�[�v�������t���A���̓���ǂ����̃J�����_�[�̗��ʂ̔�����\�ɂ��Ă���ݍ���ŃW���P�b�g�ɂ��Ă���i��f�ʐ^�j�B�u�n�̃n�i�M���������ɐH�����݂����Ă���v�Ƃ����̂́A�ԑ��r��s�ޕ��̖{�t�i�}�����[�A2018�j�ȂǂɊr�ׂ���������A�V�̃n�i�M����������������ŁA���قNjC�ɂȂ�Ȃ��B���͖{�����ׂ̂܂��Ȃ��ɎQ�ł���̂ŁA���ɂ͂��܂킸�A�O��������Ɍ����w�S�̂Ŗ{���x����悤�ɂ��ď��˂Ɏ��߂Ă���B�ʏ�̒u����������ƁA�{���̂Ȃ��قǂ�400�y�[�W�����肪���ꂳ�����Ă���̂��i������D���̂́A�\���S�����ɁA�\���P����Ɍ����Ęa�{�̂悤�ɂ��Ēu�����Ƃ����A������ꏊ�����j�B�Ƃ���Łs�g�����S���W�t�{����������З�ؐ��{���́A��Ƀn�[�h�J���@�[�̒P�s�{���肪�������傾�������A���͑�w���o�čŏ��ɓ������ɏ��o�ŎЂŌ��K���̂悤�Ȃ��Ƃ����Ă����Ƃ��A�����������̂��߂ɁA��Ђ��ۊǂ��Ă����\���p�N���X���{���Ɏ��������Ƃ�����B�x�e�����̐E�l�����тŌГ��ꂵ�Ă���̂�O�����ɒ��߂����̂��B1980�N�̂��Ƃł���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�S�i�����͋g�����́s�y���F��t�ɓo�ꂷ��i�q�S�i�����̓y���F�]�r�Q�Ɓj�B�g���͌E�c�ʜ\�Ɍ��提������́s�T�t�����E�݁t���Ă���i���s�コ�قnjo���Ă��Ȃ�����A����c�̌Ï��X�\�\���������������\�\�Ō����j�B����������q�g�����Ɖ�������\�\�ӂ���̓��L�𒆐S�Ɂr���q�g�����Ɖ�������r�Q�ƁB�i�c�k�߂��q�s�i�c�k����\�\�q�莆�r�Ɓq���r�Ɉ˂�t��҂�Łr�Q�ƁB�g���͒r���I�̒����s����\�\���̐_�̗����߂���k���{���i�_�l�t�i�����ЁA1982�N10��25���j�����Ă���B�{�i���F�́q���w�E���l�Б��o���r��q���Ƃւg������r�A�q�U���̕a�C�\�\�F�V���F�Ǝ��́r�Ȃǂŋg���Ɍ��y���Ă���B
�i���Q�j�@�i��ו����q�s�y���F��t�Ɖו��́q�ljԗ]���r�r�Q�ƁB����C�����q�g�����Ƒ���C���i1�j�r�A�q�g�����Ƒ���C���i2�j�r�A�q�g�����Ƒ���C���i3�j�r�Q�ƁB���e���O�Y���q�g�����Ɛ��e���O�Y�r�Q�ƁB�q��M��́A�g�������L�̏��a��\�O�i1948�j�N�A�u�ꌎ��\�O���@�o�ɘZ�S�~��āA�s�q��M��S�W�t�S�O�����B�v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����19�l�t�v���ЁA1968�N�A���Z�y�[�W�j�Ƃ���B���́s�q��M��S�W�t�́A1937�N�̏������A1939�N���̃t�����X���i������������j�̑�ꏑ�[�ł��낤�B�����t�v���q�g�����ƍ����t�v�r�Q�ƁB���͋g�����Ƃ̗��݂Œ˖{�M�Y�ɂ��Ă��낢��Ə������炵�Ă������A���܂��ɐ��ʐ��āu�g�����ƒ˖{�M�Y�v�������Ă��Ȃ��B�Ƃ肠�����q�g�����Ɖ��䗲���邢�͐��c�����̑����r�������A������ׂ������̂����A������q�g�����ƒ˖{�M�Y�r�������ƖĂ����B
�i���R�j�@�s���������i��W�V�\�\���������L�E�G�b�Z�C�E��V�^�t�i����A���X�A2016�N7��16���j�́q�������r�Ɉ˂�A�s����t�̍��͂����ł���i�����A�ܓy�[�W�j�B
�w����� ���邢�͖��ٕ̈��x
�@���a51�E10�E25���s�B�R�[�x�u�b�N�X�B����܁Z�Z���B�`�T���ό^�E�㐻���E�����i�ѕt�j�B�{����F���B���ŁB�艿�O�܁Z�Z�~�B
�@��h�p���ߑ㕶�w�ꡑ�����O���B����C���I�}�[�W���B����[��A�V���[�����A���X���̎��l�ŁA���p�]�_�Ƃł������C���̖��̒��ɁA�]�ˎ���̔o�l�ŁA�m�Ԃ̒�q�ł�������䑐���K��Ă��āA��l�͐S�����킵�A�o�~�ɂ��āA���ɂ��āA���̂悤�Ɍ�肠���B
��������s����\���邢�͖��ٕ̈��t�Ɓk��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�S8���̏��e���f����B
 �@
�@
��������s����\���邢�͖��ٕ̈��k��h�p���\�ߑ㕶�w�� ��3���l�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�N10��25���j�̔��E�\���i���j�Ɓk��h�p���\�ߑ㕶�w�ꡁl�S8���\�\�k��1���l�S�i�����s�ו��ʂ�t�i1976�N9��25���j�A�k��2���l�E�c�ʜ\�s���l�A�t�i�����j�A�k��3���l��������s����t�i1976�N10��25���j�k�\���̔w���l�A�k��4���l�i�c�k�߁s���Ⴊ�ނƂ܂���t�i�����j�A�k��5���l�r���I�s�V�瓴�H�q�L�t�i1976�N11��30���j�A�k��6���l�c�m�a��s�y��̑�Q�t�i�����j�A�k��7���l�{�i���F�s�킪�t�v���t�i1977�N3��25���j�A�k��8���l�ݓc�T�q�s�����̉̐l�t�i�����j�\�\�̔��̔w�i�E�j
�n�ӈ�l�́A�{���̖`���Ɉ�������������s��������^�t�̉���q�����̓��X�r�ŁA
�@�{���̏��ł��R�[�x�u�b�N�X����㈲���ꂽ�͈̂�㎵�Z�N�����A���̑O��A�����ҏS�ɂ����������������̏����͈ȉ��̔@���B
�@�@��W�w���叴�x��㎵�l�N�\���O��
�@�@��F�^�w��������^�x��㎵�Z�N�l���O�\��
�@�@��Ƙ_�w����x��㎵�Z�N�\����\�ܓ�
�@�@��W�w���C�C�m�������낵�n�x��㎵���N��\����
�@�@���]�W�w���̑�nj��x��㎵���N�O���\�ܓ�
�@�v����ɁA���Z�N��͉����������Ɠ������҂Ɋ|���Ĉ��ݕ������B�����V�����C���A�����Q���m�������n�A��[�Q���m���������n�B�����K�N�Ȃ�ʁA�h���ƌ�ႂ̓��X���߂������B�i�����A�O�Z��y�[�W�j
�Ɖ�ڂ��Ă���B�����Ė{�p���̊��ҁE�ҏW�҂Ƃ��āA����I�ȕ�������������B���Ȃ킿�A�u�������ɂƂ��ĉc�݂̂��ׂĂ͒����ꂽ��i�̓����ɂ������݂����A��ƂƂ͏����Ƃ����s�ׂ��̂��̂�B�ꐶ����̂ł���B����������A�����̐��ɔw���A�������͐����̂��̂����p����Ƃ����A�����Ȃ܂łɉߍ��ȃA���K�[�W���̌J��Ԃ����K�v�Ƃ����B����͈���A���Ⴊ�ނ��ƁA�܂��邱�ƁA�Q�m�����n�邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B������f���B���Ȃ��}�f�̓k�͌������߂邵���Ȃ��B�v�i�����A�O���y�[�W�j�ƁB�����̒��߂�����ŁA�����̒���4�_�\�\�s��������k���㎍���Ɂl�t�i�v���ЁA1971�j�A�s��{���������W�t�i�l�����@�A1975�j�A�s���������W�k����o�l���Ɂl�t�i���������[�A1994�j�A�s��������o��W���t�i���ώɁA2000�j�\�\�������āu�{���̓ǎ҂ɂ����ẮA�K����E������ㆁm�Ђ��Ɓn���ꂽ���B�v�i���O�j�ƜϜȂ��Ă���̂́A�e�ȔO�����ɉ߂��Ȃ��B
�i���S�j�@�l�����I��A�r���I�͎�����U�肩�����Ď��̂悤�ɏ����B�肵�āq���̖{�r�B
�@�u�t�V�M�Ȗ{�ł���B�Ö{�ƊE�ł́u�a���d���Ĕ��{�v�ȂǂƂ����̂ł͂���܂����B�{���͂�����́A�������F�����т��a���A�����ɒW���_�C�_�C�F�̃P�C�������Ă���B�O�܂��ɂ������P�C�����Ă��āA�����͓�d�ɂȂ��Ă���A�܂�ŕł��ƂɃV�������������J�����悤���B
�@�����͂��蔲���̊��łŁA�N�b�L���Ƃ��Ĕ������B�\���̔w���Ɠ���̋��̓����b�R�v�̑���{�ɂ݂�悤�ȎO�p�̏�����A�������ɐ��ʂ𗬂����悤�Ȃ��炩�����������Ă���B����ɘa����\�荇�킹��������B��قǂ̖{�D��������ɂ����Ă����炦���̂��낤�B�w�ɋ�������������Ă����āA�^�C�g�����w�V�瓴�H�q�L�x�B
�@�q��M��̓ǎ҂Ȃ�A�ނ��A�Ƃ����ɂ��Ȃ��݂��B�܂������ނ̒Z�т̈�B���̂͂������A���̘a���d���Ė{�͂����ł͂Ȃ��̂��B�u�r���I���v�Ƃ���B�܂�A���ł���B���Ɂk��h�p���\�\�ߑ㕶�w疗y���܁l�Ƃ���B���a�\��N�\�ꌎ�̊��s�B���͎O�\��̔��������B
�@���Ȃ���A�悭�킩��Ȃ��B�v���o�����Ƃ��Ă��L�����������Ă���ӂ₾�B������A��������������ł������Ƃ͂������ł���B�킪���̋ߑ��Ƃ���l���Ƃ肠���Ĕ��\���قǏ����Ăق����B���������̖{�ɂ���B���l���ɓ����˗������Ă���̂ŁA������ߑ㕶�w���߂���p�������܂��͂��ł���\�\�B
�@�k�c�c�l
�@�p���f�B�Ƃ����̂́A�ӂ��A�ЂƑ����ӂ����̒Z�����̂����A�킪�u�H�q�L�v�͌�����������̂��B���������Γ����A���悻�N���ǂ݂����ɂȂ��G���ɁA�������́u�����m�v�����������u�w�����m�x�ٕ��v��A�ԓc���P�ɂ�������āu��앜�����̐��_�v�Ə̂�����̂������Ă�������A�����Ƃ���Ȓ��Ŏv�������̂��낤�B�ق��̂��ׂĂ͐l�̖ڂɂӂ�Ȃ��܂܁A���ꂢ�����ς�������������A�q��M�����͐����ȏo�Ől����������Ɍ`�Ƃ��āA����������Ԃ鍂��Ȍ`���Ƃ��Đ��ɂ̂������B
�@����A���ɂ̂������Ƃ������Ȃ����낤�B���t�ɂ́u����ܕS���̓���@�Ԗ{��v�Ƃ����āA�����Ɏ�F�Łu���ҁv�Ɠ����Ă���B���̒m�邩����A���̒��Җ{��������邫��B���Ƃ��ǂ��Ȃ����̂��A�܂�Œm��Ȃ��B���܂Ƃ��邩��ɂ́A�ق��Ɏl���o�Ă���͂������A����ɂ��Ă������m��Ȃ��B�u��h�p���v�͏��a�����Ɏ��l�����ԔV���悵���V���[�Y�ł����āA�������������o��������Œ��₵���B���܂ЂƂ��т̊�Ă���h�̖��ŏI������炵���B�킪�茳�ɂ͐��ɂ��t�V�M�Ȗ{�ƁA���̂悤�ȒW���L�����������B�v�i�q����3�r�A�s�q��M��S�W�k��4���l�t�A�}�����[�A2002�N6��20���A��`��y�[�W�j�B
�q��̒Z�я����q�V�瓴�H�q�L�r�́A�g�����ǂƎv�����ꏑ�[�őS�W�ł͑�3���Ɏ��߂��Ă���B�����Ɂq���Ս�ɂār�Ƃ������M�����^����Ă���̂��Í��߂��Ă��āA�����[���B
�i���T�j�@�����Ɍ����A11�܂�i81�`88�j�ȍ~�̎��̖{�i�ƌĂ��Ă��炤�j�Ɩ{������ׂ����K�{�i�ƌĂ��Ă��炤�j�́A���̂悤�ɑΉ�����B���ڂ́u�܂�@�{���y�[�W�@���̖{�k�{���̒��t���l�����K�{�k�{���̒��t���l�v�ł���B���̖{�́���8�y�[�W�����d���i��荞�݁j�ƌ����i���R��j�̖��ӏ��ŁA���K�{�́����8�y�[�W�����{������ׂ��p�ł���B���������Ď��̖{�ɂ́A13�܂�i97�`100�j�ɑ�������܂蒚�����݂��Ȃ��B
�@�@11�܂�@81�@�{���k����y�[�W�߁l���{���k����y�[�W�߁l
�@�@11�܂�@82�@�{���k���Z�y�[�W�߁l���{���k���Z�y�[�W�߁l
�@�@11�܂�@83�@�{���k����y�[�W�߁l�����{���k����y�[�W�߁l��
�@�@11�܂�@84�@�{���k���Z�y�[�W�߁l�����{���k����y�[�W�߁l��
�@�@11�܂�@85�@�{���k����y�[�W�߁l�����{���k���O�y�[�W�߁l��
�@�@11�܂�@86�@�{���k��Z�y�[�W�߁l�����{���k���l�y�[�W�߁l��
�@�@11�܂�@87�@�{���k����y�[�W�߁l���{���k���܃y�[�W�߁l��
�@�@11�܂�@88�@�{���k��Z�y�[�W�߁l���{���k���Z�y�[�W�߁l��
�@�@12�܂�@89�@����1���y�I�z���{���k�����y�[�W�߁l��
�@�@12�܂�@90�@����1���y�E�z���{���k�����y�[�W�߁l��
�@�@12�܂�@91�@���t�k��O�y�[�W�߁l���{���k����y�[�W�߁l
�@�@12�܂�@92�@�����k��l�y�[�W�߁l���{���k��Z�y�[�W�߁l
�@�@12�܂�@93�@����1���y�I�z������1���y�I�z
�@�@12�܂�@94�@����1���y�E�z������1���y�E�z
�@�@12�܂�@95�@����1���y�I�z�����t�k��O�y�[�W�߁l
�@�@12�܂�@96�@����1���y�E�z�������k��l�y�[�W�߁l
�@�@13�܂�@97�@�k�i�V�l��������1���y�I�z
�@�@13�܂�@98�@�k�i�V�l��������1���y�E�z
�@�@13�܂�@99�@�k�i�V�l��������1���y�I�z
�@�@13�܂�@100�@�k�i�V�l��������1���y�E�z
���K�{�łȂ���A�u�˖{�M�Y�����A�㐢�̏O�ٔ���҂܂ł��Ȃ��A�����Ă��̉��l���]�ւ���ɑ���Ɛւ����̐l�ł���B��͑����������A�M�Y�͐����Ă���ɉ~�n���A���Ȃ��݂̋ɂ݁A���z�̋��݂��Ȃَ���ɁA����Ђ͐��ɒ��Â��Ă䂭�ł��炤�B�v�i�q�I�́r�A�����A���O�y�[�W�j�Ƃ����ݓc�Ӑg�̌����ǂ݂����Ȃ����������B
�q�S�i�����̓y���F�]�r�̏��߂̂ق��ɁA�u�������Ȃ��ƂɁA�g���͌̈��p���̌�ɂ��̎��M�Җ����L�������ŁA���p���̕W��������Ă��Ȃ��B�k�c�c�l��̗�������悤�B�q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�́A�g�����g�́q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i���o��1968�N8��1�����s�́sANDROGYNY DANCE�t1���A�̂�1980�N���́s�u�����v�Ƃ����G�t�Ɏ��^�j�������E�ق������͂Łi���R�Ȃ���o�T�͋L����Ă��Ȃ��j�A���̂��Ƃ�1�s�Ď��̈��p������B�v�Ə����Ă���A�g�����������܂܂̌`�ʼn��������
�@�u�w�Q�X���[�E�e���Q�_�x�Ɏ^���o�������Ƃ��A�S���̑O�̕����̉H���̐�ł킸���ɉB���Ȃ���▭�ɗ����Ă����y���F�̔������́A���܂Ȃ��قɏĂ��t���Ă��ė���Ȃ��B��~�܂ʔ���ɉ����ăr�[�g���Y�E�i���o�[�w�C�F�X�^�f�C�x���a�f�ɂ���Ԃ��Ȃ���A�A�_�����v���o�������X�v�[�`���̂��Ƃ����j���̏D�����A�A�����B�[�i�X�̒a���ŗ�����܂��Ƃ��镗��ɌX���Ȃ��痧���Ă����B�v
���f�����B����������́u��������̂��̕��͂͂ǂ����œǂ��Ƃ�����B�����A���ꂪ���Ƃ����}�̂̂ǂ��ɍڂ��Ă������A�ǂ����Ă��z���o���Ȃ��B�v�Ƃ����̂́A������t�̈��ŁA�T�����ǂ����͐捏���m���Ă���B���������́A�s�y���F��t�́i�g�����g�Ɠy���ȊO�́j�ŏ��̈��p���炵�āA���łɏo�T���킩��Ȃ����Ƃ��������邽�߂̕��ւ������B���Ȃ݂ɁA�g�����������͉̂�������̌�V�^�s��������^�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�N4��30���j���s��������^�k�����Łl�t�i��h���ǁA�����j�́q�y���F�̊��r�i��l�y�[�W�j�ł���i�g���́k�����Łl��ꂽ���j�B�Ȃ����łł��A�s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�N10��19���A�O��y�[�W�j�ł��A��������̌����͖`���Ɂu���N�O�A�����z�[���ł́v�������āA�u�r�[�g���Y�E�i���o�[�́w�C�G�X�^�f�C�x�v�ł���B�������ɁsHelp!�i���M��F4�l�̓A�C�h���j�t�i1965�j�Ɏ��߂�ꂽ�I���W�i���̉����ł́A�|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�̉̐��́u�C�F�X�^�f�C�v�ƕ������邪�A�����͂�͂��]�L�E��A�ƍl����ׂ����낤�B
���āA����̖{��͐��z�q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�ƕ]�`�q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�ق��̍Z�ف���r�ΏƂł���B�����O�����o�q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i�sANDROGYNY DANCE�t��1���A1968�N8��1���B�g���Ə����̐蔲�����ʂɈ˂������߁A���ʂ��͕s�ځ\�\�{�e�����̎ʐ^���Q�Ƃ��ꂽ���j�A�P�������q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�A�v���ЁA1980�N7��1���A���Z�`����y�[�W�j�A�g���Ę^�q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�Ɓq4�@�u�ϋ{�̐l�v�r�i�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�N9��30���A���`��y�[�W�A���`���y�[�W�j�A�Q���Ċ��q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�N9��25���A��Z�Z�`��Z��y�[�W�j�Ƃ���B
�@�}��b�����̑O�Ɏp�����킷�O�ɂ́A���R�Ȃ���y���F�̋���ׂ��y�O�P�����Q���z�ʂ��������߂Ă���B���̂��Ƃ��Y�ꂽ���A����̓喜�ʼn�������́y�O�q���P�Q�s�z�`����w�y�O�r���P�Q�t�z�̍Ґ��܂��j����������B��͏����ȕ����ŁA�C�̍��������y�O�P�u���Q�m�z�����ƎG�k�ɐ����Ă������A�e�����l�̂����Ȃ����͂ЂƂ藣��Ăڂ��肵�Ă����B���̒��x�����ɒ����������l�����Â��Ɏ����̂�ł���B�ꐡ����C�ɂȂ鑶�݂������B���̂����ˑR�A���Ƃ��炫���ѓ��k�ꂪ�吺�������āA���̑�̑O�֍����āA�����݂̂͂��߂��B�����������l���Ǝ������������t�����킳�Ȃ��̂ōk��́u�ȂA�y����m��Ȃ��̂��y�O�P�H���Q�i�g���j�z�v�B���͖��O�͂Ȃ�ƂȂ��m���Ă������A�y���F���y�O�ށ��P�Q���z�̕������m��Ȃ������B�ނ́y�O���́q���P�Q�s�z�m���y�O�r���P�Q�t�z�����ɓǂ�ł���Ƃ������B���ꂩ�炤���Ƃ��Đe�����������A�ނ̌|�p��m��˂Ȃ�ʂƎv�����B
�@�l�\��N�l������ߌ�A������ق֓y���F�����q�Q�X���[�E�e���Q�_�r�����͂ЂƂ茩�ɂ������B�v�����ԁA���͕��������邱�Ƃ��Ȃ������B���炭�A�R���b�g�E�}���V�����́q�����r�ȗ��̂��ƂƂ����邾�낤�B���ɂ���������o���G�ɐ^�̓��̂��l�Ԃ̑��݂��A�G���`�V�Y����������ꂸ�����Ɏ���܂ŕ����Ɂy�O�P�i�i�V�j���Q�́z�S���Ȃ��������炾�B�y���F�̕������q�Q�X���[�E�e���Q�_�r�ɁA���̂������A�n���̐S���A�Ȃɂ����Ȃ܂Ȃ܂������݊��������y�O�I�@���P�Q�B�z���ɂ��f��ɂ����ɂ����ĂȂ��A�V�������E�������܂݂āy�O�ց��P�Q�Ɂz�R�Ƃ����B�Ȃ��ł������ʂ���ې[�������B���̑O�̌��y�O�����P�Q���z�̃V�[���������āA�����Â���捂ȕ���A�E�̕��Ɂy�O�W���P�Q�C�z�[�[���ɑ傫�Ȕ����J���o�X�i���j���u����A�V�䂩�生������Ă���ƁA�ˑR�A��ԑO�̋q�Ȃ̒����ɂ��������֎q�̏�ɂ̂�A���C�g�̒��łӂ�ނ����B���h�y�O�P�i�i�V�j���Q��z�̊�Ɉ�����g���G��������ٗl�Ȕ������B�x�ߕ�����o���ׂ��r�B�����n�ɒ����Ǝ��q�������Ă���炵���B�Q�����Ƃ��A�ȂԂ邲�Ƃ��A�������Â��ȗx��Ƃ������s�ׂ��B�y�O�i�i�V�j���P�Q���炭���āA�z�����J���o�X�̂�������r�r�y�O�b�[���P�Q�[�b�z�Ƌْ�������C���ӂ�킹�A����Ȕ�����ˑR��Ԃ��āy�O�i�i�V�j���P�Q�A�z�����߂�����������܂ɕ���ꂽ�r�B�y�O�i�i�V�j���P�Q���ꂩ���̐��E���J�����̂������B�z���͏I�������ƁA���̗x��͉��҂��낤�y�O�P�B���Q�H�@�z�y���F�̓��ɑ��ĐÂł݂��ƂɎ~�߂����̏����̐l�́A�N���낤�Ǝv�����B���ꂪ�}��b�����̑O�ɏo���������ł������B
�@��x�ڂ͓s�s�Z���^�[�ł̐V�s�����Ƃ̉�Ły�O�P�ށ��Q�}��b�z�́q�n��̕���r�������B�y�O�P�}��b���Q�ށz�̗x��ȊO�́A�P�Ȃ�^���̂��肩�����Ɏv�����B�ނ́q�n��r�͔��Ɗ��m���������������G���`�V�Y����Y�킹�Ă����B
�@����y�O�Ƃ����P�Q���z�A�}��b�����������˂Ă����B�f��̔ނ͈ꌩ���ʂ́A�_�o�������ȐN���B�����w�@��w�y�O�w���P�Q�i�g���j�z���ł��邱�Ɓy�O�ɂ������������P�Q�A���o���U���Ă�̂��ӊO�����z�A����������N���Ƃ�����A�W���[�i���Y���W�̎d�������������瑊�k�ɂ̂��Ă���Ɖ]���āA���͂Ƃ܂ǂ��Ă��܂����B���Ɂy�O�i�i�V�j���P�Q�Ɓz���āA�y�O�Ɓ��P�Q�i�g���j�z�n��ł���A�x�ߕ��̔��̌����������Ȑ��E�ւ���Ă��āA�A�E����Ȃ�čl�����Ȃ��B���̋H�L�ȍ˔\���z���C�g�J���[�̔g�̂Ȃ��ɂ��܂�čs���̂��������Ȃ��v�����B���͖��ӔC�Ȃ��Ɓy�O���P�Q�i�g���j�z�����A�y�O�}��b�͉����H��Ȃ������P�Q�A���o�C�g�����Ȃ�����z�x��Â��ė~�����̂ŁA���킵�������s�����Ƃ������߁y�O����Ȃ������P�Q�i�g���j�z���B
�@�l�\��N�\���O�\���[���A�}��b�ƕ������q�����ւ̏����r����ꐶ���z�[���ōÂ��ꂽ�B���͂͂��߂čȂ���čs�����B����́A�ނ̏������猻�݂܂ł̑�\��i���܂߂����̂ŁA�q�y�O�����P�I���Q���z�Y����r�A�q�n��ւ�杕��r�A�q�K�N�̐��r�A�q�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁr�A�q�ϋ{���r�A�q�̉Ԃ̒j���Ɂr�ȂǂŁA�ǂ̈���Ƃ��Ă��A���炵���A�܂��ɖ��̋����Ƃ�����B���̂��Ⴕ��Ɍ�����y�O�끨�P�Q軀�z�ŁA���ɓԗx��Â����}��b�̐��_�͂Ɉ��|���ꂽ�̂́A���ЂƂ�ł͂Ȃ��������낤�B
�@�����₦�����̃��X�g�ŁA����ɉ���������܂܁A������ꂽ�ԑ������ɒ@�����Ȃ���A�Ԃт���U�炵�Ă����p�́A������������H�S���A���͕ϋ{�̐l�ł͂Ȃ����낤���B
�g�����g���s�y���F��t�́q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�Ɓq4�@�u�ϋ{�̐l�v�r�����M����ɂ������āA�P�������q�ϋ{�̐l�E�}��b�r���Q�Ƃ����ƍl������B�����̉ߋ��̕��͂��u�Q�Ɓv����Ƃ����̂����Ȍ������������A�i����͂����܂ł����̒����ɉ߂��Ȃ����j���g�̉ߋ��̓��L��f�ނɂ��Ė{���́q���L�r���������̂Ɠ��l�ɁA���z�q�ϋ{�̐l�E�}��b�r��]�p�����̂ł͂Ȃ��낤���B����������A�����l���邵���Ȃ��B�����O��ɁA�P�������q�ϋ{�̐l�E�}��b�r���g���Ę^�q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�Ɓq4�@�u�ϋ{�̐l�v�r���A��f�O���P���Q�́q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�S���̎����Ƃ͕ʂ̌n���Ƃ��āA�y�P �� �g�z���i����ɂȂ�̂ŁA�P���g�̕����͕\�������Ɂj�f����B���Ȃ킿�����P�������B�܂��A�O���́q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r����B
�@�y�}��b�����̑O�Ɏp�����킷�O�ɂ́A���R�Ȃ���y���F�̋���ׂ����ʂ��������߂Ă���B���̂��Ƃ��Y�ꂽ���A��� �� ���a�l�\��N����̗[�A�z�n�z�̓喜�ʼn�������́s�`����w�t�́y�i�i�V�j �� �����z�Ґ��܁y�i�i�V�j �� ��܁z���j����������B��́y�����ȕ��� �� ���܂����~�z�ŁA�C�̍��������y�u �� �m�z�����ƎG�k�ɐ����Ă������A�e�����l�̂����Ȃ����͂ЂƂ藣��Ăڂ��肵�Ă����B���̒��x�����ɒ����������l�����Â��Ɏ����̂�ł���B�ꐡ����C�ɂȂ鑶�݂������B�y���̂����ˑR�A���Ƃ��炫�� �� �����Ԓx��āA�吺�������Ȃ���A�z�ѓ��k�ꂪ�y�吺�������� �� �����z�A���̑�̑O�֍����āA�����݂̂͂��߂��B�����������l���Ǝ������������t�����킳�Ȃ��̂ōk��́u�ȂA�y����m��Ȃ��̂��H�v�y�B �� �i�g���j�z���͖��O�͂Ȃ�ƂȂ��m���Ă������A�y���F�����̕������m��Ȃ������B�ނ́s�m���t�����ɓǂ�ł���Ƃ������B���ꂩ�炤���Ƃ��Đe�����������A�ނ̌|�p��m��˂Ȃ�ʂƎv�����B
�@�y�l�\��N �� ���̋@��͈ӊO�ɑ�������Ă����̂������B��J����́z�l������y�ߌ� �� �̌߂�����z�A�y�i�i�V�j �� ���͐R�́z������قցy�y���F�����q�Q�X���[�E�e���Q�_�r�����͂ЂƂ茩�ɂ����� �� �s�����z�B�y�i�i�V�j �� �����ď��߂āA�y���F�̕������H�@�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�i�K����������ސ��j���ς��̂ł���B�z�v�����ԁA���͕����y�i�i�V�j �� �Ȃ���́z�����邱�Ƃ��Ȃ������B���炭�A�R���b�g�E�}���V�����́y�q �� �u�z�����y�r �� �v�z�ȗ��̂��ƂƂ����邾�낤�B���ɂ���������o���G�ɐ^�̓��̂��l�Ԃ̑��݂��A�G���`�V�Y����������ꂸ�y�i�i�V�j �� �A�z�����Ɏ���܂ŕ����ɊS���Ȃ��������炾�B�y���F�́y������ �� �i�g���j�z�y�q �� �u�z�Q�X���[�E�e���Q�_�y�r �� �v�z�ɁA���̂������A�n���̐S���A�Ȃɂ����Ȃ܂Ȃ܂������݊����y�i�i�V�j �� �A���́z�����y�i�i�V�j �� �悤���z�B���ɂ��f��ɂ��y�i�i�V�j �� ���z���ɂ����ĂȂ��A�V�������E�������܂݂ĜɑR�Ƃ����B�y�i�i�V�j �� �i���s�j�z�y�i�i�V�j �� �i�S�p�A�L�j�y���F����x�قǁA�������̂ɂ͈ӕ\�����ꂽ�B�z�y�Ȃ��ł������ʂ� �� �������z��ې[�y�������B���̑O �� ���̂́A���܂Łz�̌����y�� �� �I�ȁz�V�[���y�i�i�V�j �� �̌�z���y�� �� ��z���āA�y���� �� �n�܂����z�Â���捂ȕ���y�A �� ���B�z�E�̕��ɃC�[�[���y�i�i�V�j �� ������A����z�Ɂy�傫 �� ����z�Ȕ����J���o�X�i���j���u����y�A �� �Ă���B�₪�āz�V�䂩�生���y�� �� �~�z��Ă���ƁA�ˑR�A�y��ԑO �� �őO��z�̋q�Ȃ̒����ɂ����y�i�i�V�j �� �Ⴂ�z�����֎q�̏�Ɂy�� �� ��z��A���C�g�̒��Ły�� �� �U�z��ނ����B���h�y�i�i�V�j �� ��z�̊�Ɉ�����g���G�y�i�i�V�j �� �́z��������ٗl�Ȕ������B�y�i�i�V�j �� ������蕑��ɏ��A�Ⴂ���̂܂Ƃ��z�x�ߕ�����o���ׁy�i�i�V�j �� �����z���r�y�i�i�V�j �� �Ȃ�܂����z�B�����n�ɒ����Ɓy�i�i�V�j �� �A�z���y�q �� ���z�������Ă���炵���B�Q�����Ƃ��A�ȂԂ�y�i�i�V�j �� ���z���Ƃ��A�y�������Â��� �� �������̂���܂�ȁz�x��y�i�i�V�j �� �A�z�Ƃ������s�ׂ��B���炭���āA�����J���o�X�̂�������r�r�[�b�Ƌْ�������C���ӂ�킹�A����Ȕ�����ˑR�y��� �� �j�z���āA�y�����߂� �� �i�g���j�z����������܂ɕ���ꂽ�r�y�i�i�V�j �� �������߂��z�B���ꂩ���̐��E���J�����̂������B�y���͏I�������ƁA �� �i�g���j�z���̗x�y�i�i�V�j �� ��z��͉��҂��낤�y�i�i�V�j �� ���z�B�y���F�̓��ɑ��āy�i�i�V�j �� �A�z�Âł݂��ƂɎ~�߂����̏����̐l�́A�N���낤�Ǝv�����B�y���ꂪ �� ����́z�}��b�y�����̑O�ɏo���������ł������B �� �ł���A����Y�̒�q�Ƃ̂��Ƃł���B�z
��f�ɑ����āA�P���q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�ɂ͎��̂悤�Ȋ}��b�̃v���t�B�[�����������B
�@��x�ڂ͓s�s�Z���^�[�ł̐V�s�����Ƃ̉�Ŕނ́q�n��̕���r�������B�}��b�̗x��ȊO�́A�P�Ȃ�^���̂��肩�����Ɏv�����B�ނ́q�n��r�͔��Ɗ��m���������������G���`�V�Y����Y�킹�Ă����B
�@������A�}��b�����������˂Ă����B�f��̔ނ͈ꌩ���ʂ́A�_�o�������ȐN���B�����w�@��w���ł��邱�ƁA���o���U���Ă�̂��ӊO�����A����������N���Ƃ�����A�W���[�i���Y���W�̎d�������������瑊�k�ɂ̂��Ă���Ɖ]���āA���͂Ƃ܂ǂ��Ă��܂����B���ɂƂ��āA�n��ł���A�x�ߕ��̔��̌����������Ȑ��E�ւ���Ă��āA�A�E����Ȃ�čl�����Ȃ��B���̋H�L�ȍ˔\���z���C�g�J���[�̔g�̂Ȃ��ɂ��܂�čs���̂��������Ȃ��v�����B���͖��ӔC�Ȃ��Ƃ����A�A���o�C�g�����Ȃ�����x��Â��ė~�����̂ŁA���킵�������s�����Ƃ������߂��B
���̃u���b�N�́A�g���s�y���F��t�ɂ͍̂��Ă��Ȃ��B����Ƃ����̂��A�P���q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�͊}��b����肾�������A�y���F�����ł���{���ɂ͂�����Ȃ��ƍl�������炾�낤�B�y�P �� �g�z�̌㔼�𑱂���B�q4�@�u�ϋ{�̐l�v�r�ł���B
�@�y�l�\��N�\���O�\���[�� �� �u�����W���l�v�̉���J����Ɂz�A�}��b�ƕ������y�q �� �u�z�����ւ̏����y�r �� �v�z����ꐶ���z�[���ōÂ��ꂽ�B���́y�͂� �� ���z�߂čȂ���čs�����B�y�i�i�V�j �� ���ҐȂɂ͏�A�̂ق��A����C���Ɗv�W�����p�[�p�̎O���R�I�v���������B�z����́A�ނ̏������猻�݂܂ł́y��\��i���܂߂����̂� �� ���ʂł���z�A�y�q �� �u�z�y�I �� ���z�Y����y�r �� �v�z�A�y�q �� �u�z�n��ւ�杕��y�r �� �v�z�A�y�q�K�N�̐��r�A �� �i�g���j�z�y�q �� �u�z�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁy�r �� �v�z�A�y�q �� �u�z�ϋ{���y�r �� �v�z�A�y�q �� �u�z�̉Ԃ̒j���Ɂy�r �� �v�z�ȂǂŁy�A �� �������B�z�y�ǂ̈���Ƃ��Ă��A �� �ǂ���z���炵���A�܂��Ɂy���̋����Ƃ����� �� �����̈�[�ł���z�B�y�i�i�V�j �� �Ƃ��Ɂu�n��ւ�杕��v�͔��Ɗ��m���������A�������G���`�V�Y����Y�킹�Ă����B�z�y���̂��Ⴕ��Ɍ�����軀�� �� ������������ߏւ�ւ��z�A�y�� �� ���z�ɓԁy�i�i�V�j �� ���z�x��Â����y�i�i�V�j �� �A�z�}��b�̐��_�͂Ɉ��|���ꂽ�̂́A���y�ЂƂ� �� ���������z�ł͂Ȃ��������낤�B�y�i���s�j �� �i�ǂ����݁j�z�y�i�S�p�A�L�j �� �i�g���j�z�����₦�����̃��X�g�ŁA����ɉ���������܂܁A������ꂽ�ԑ������ɒ@�����Ȃ���A�Ԃт���U�炵�Ă����p�́A������������H�S���A���́y�i�i�V�j �� �u�z�ϋ{�̐l�y�i�i�V�j �� �v�z�ł͂Ȃ����낤���B
�u�u�����W���l�v�̉�v�́A�O���q3�@�u�����W���l�v�r�́u�q���L�r�@���Z���N������\�����v�Ɂu��Z�����A����J�̑�ꐶ���z�[���֍s���B�y���F�̒�q�Έ䖞���̃��T�C�^���u�����W���l�v���ς�B�k�c�c�l�}��b�ƍ����v�q��U���ėL�y���ŐH�����A�ϓ։��ł��������B�v�i�s�y���F��t�A��Z�`���y�[�W�j�Ƃ��ēo�ꂷ��B�u�����₦�����̃��X�g�ŁA�k�c�c�l�H�S���A���́u�ϋ{�̐l�v�ł͂Ȃ����낤���B�v�Ƃ����Ō�̈ꕶ�́A��������u4�v�̕W�肪�̂��Ă���Ƃ���i���邢�͋t�ɕW��ɍ��킹�Ă����Ɏ����ꂽ�Ƃ���j�A�y���F����s�Ŏh���т����u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���\�\�y���F�v�ɕC�G����E�����傾�Ǝv���B���̂��߂ɂ��A�ǂ����܂��ɁA�ꕶ�ň�i�����\�����錳�̌`���]�܂��������B���݂ɓǓ_�ʼn��s���Ă݂悤�B
�����₦�����̃��X�g��
����ɉ���������܂�
������ꂽ�ԑ������ɒ@�����Ȃ���
�Ԃт���U�炵�Ă����p��
������������H�S��
���́u�ϋ{�̐l�v�ł͂Ȃ����낤��
�g���̎��сq�g�ҁr�i�H�E18�j�ɂ́u�}��b�̂��߂̑f�`�̎��v�Ǝ���������B���́u5�v�͂����ł���B����ɂ����āA�łƌ���ό����݂Ɍ���������g�����O�͂́A�ق�Ƃ��ɕ|�낵���B
�u�J�̂悤��
�T��̓��̂���������
���ɂ�����
�킽���̓��̂͏��X�Ɍ��x��ቺ������
���Ɉł̂����ɏ���������v
�܍߂��̂��̂�
�ϔO�Ɖ������낤
�A�X�g����
�A���x�X�N
�A���[�o�̂��Ƃ�

���o�q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i�sANDROGYNY DANCE�t��1���i1968�N8��1���j�̎��� �k�g���z�q�v�l�ɂ����t�̋L���̂���蔲���L���̃��m�N���R�s�[�l
�k�t�L�l
�P�����������ɂ��āA�g���Ę^�̖{���ɂ��邽�߂̎�����_�ҁ����т��Ԏ��ōČ������ŏ��̌��J���i226-227�y�[�W�j�́A�g���ɂ�镀��̂��Ƃ��������A�C���̓������{���ł���B�Q�l�܂łɁy�P���Q�z���f���邪�A�㔼�̂�����̌��J���i228-229�y�[�W�j�̎����͌y�����B
 �@
�@
�P�����������ɂ��āA�Q���Ċ��̖{���ɂ��邽�߂̎������Č��������J���i���j���P�����������ɂ��āA�g���Ę^�̖{���ɂ��邽�߂̎������Č��������J���i�E�j �k�ǂ���̐Ԏ����_�ҁ����тɂ����́l
�O����s�y���F��t�{���Z�فi���j�ł́A�قڏ������낵�́s�y���F��t�ŗ�O�I�ɋg��������s���ĎG���ɔ��\�������͂̏��o�`�`�Ę^�`�`��e�`�̍Z�ق����݂��B�����A�s�y���F��t�͕���Ɂu�\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�v�Ƃ���Ƃ���A�y���F���̐l���܂ޑ��҂̕��͂̈��p�ƁA�g�����g�̓��L�����q�Ƃ��Ă���B�g�������L�̌��{�͌��邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ����A���҂̕��͂́A�����Ƃ��Č����ƈ��p���Ƃ̔�r�ƍ����\���B�������Ȃ��ƂɁA�g���͌̈��p���̌�ɂ��̎��M�Җ����L�������ŁA���p���̕W��������Ă��Ȃ��B�����́q���p�����r�ɂ��A�y���̒����ƕ����ʐ^�W�A����Y�̒����̑薼�̂ق��́A�������̎G���E�J�^���O�E�V���̑荆�Ɣ��s�N�������������Ă��邾���ŁA�q���p�����r�̖����́u���̑��@�����̃p���t���b�g�A�`���V�A��{�ȂǁB�v�i�����A��l�l�y�[�W�j�ƁA�͂Ȃ͂��������Ȃ��B��̗�������悤�B�q2�@�o��E�u�Q�X���[�E�e���Q�_�v�r�́A�g�����g�́q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�i���o��1968�N8��1�����s�́sANDROGYNY DANCE�t1���A�̂�1980�N���́s�u�����v�Ƃ����G�t�Ɏ��^�j�������E�ق������͂Łi���R�Ȃ���o�T�͋L����Ă��Ȃ��j�A���̂��Ƃ�1�s�Ď��̈��p������B
�@�u�w�Q�X���[�E�e���Q�_�x�Ɏ^���o�������Ƃ��A�S���̑O�̕����̉H���̐�ł킸���ɉB���Ȃ���▭�ɗ����Ă����y���F�̔������́A���܂Ȃ��قɏĂ��t���Ă��ė���Ȃ��B��~�܂ʔ���ɉ����ăr�[�g���Y�E�i���o�[�w�C�F�X�^�f�C�x���a�f�ɂ���Ԃ��Ȃ���A�A�_�����v���o�������X�v�[�`���̂��Ƃ����j���̏D�����A�A�����B�[�i�X�̒a���ŗ�����܂��Ƃ��镗��ɌX���Ȃ��痧���Ă����B�v�@�i��������j
��������̂��̕��͂͂ǂ����œǂ��Ƃ�����B�����A���ꂪ���Ƃ����}�̂̂ǂ��ɍڂ��Ă������A�ǂ����Ă��z���o���Ȃ��B���Ƃقǂ��悤�ɁA�u�y���F���̐l���܂ޑ��҂̕��͂̈��p�v�̏ƍ��E�Z�ق́A�܂��͂��̏o�T�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͑O����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A����l���i���́u�S�W�v�ɂ́A���肪�������Ƃɐl���������������Ă���j�̕��͂̏o�T��T�����邱�Ƃɂ������B
�S�i�����i1913�`1998�j�͉̕��ꌤ���ƁA�����]�_�ƁBWikipedia�Ɂu1954�N�ɔ��\�����w���Ԃ��E�l���Ɠ`���x�i1955�N�x�|�p�I��������b��܁j�́A�̕��ꌤ���ɖ����w�̐��ʂ����A�|�Ԃ̎����_�\���Ɍ��Ă��_�ʼn���I�Ȓ���B�k�c�c�l���㉉���E�����ɂ����w���[���A���̕��ʂł̔����������B�v�Ƃ���悤�ɁA�Í�������y���F�����т��ј_���Ă���B���̂̏����Ƃ��āA�g�����s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�ɓo�ꂷ��S�i���������Ă������B����4�ӏ��ł���B�Ȃ��A���o���̎��́i�@�j�͌f�ڃm���u���B
�@�@�@29�@�A�[�g���B���b�W�ɂ��i51-52�y�[�W�j
�@�k�c�c�l
�@�u������́A����܂ł̕��x�ɔ�����p�ԂɁA�D���ɑ���X��������B�K�j�ҁA���܂����w�A�k�葫�A�����炭���x�̔��ɔ����邱���̑̈ʂ́A�ǂ����甭�z���ꂽ���B�ǂ��Ƀ��[�c������̂��Ƃ������ƂƁA�����̑��݂�F�ߓ��邩�ǂ����Ƃ������ƂɌW���Ă����肪����B���������F�߂Ȃ���Ε����͑��݂����Ȃ��̂ł���B�������A�����������p���ɔ���F�߂�v���́A���́A�`���������邩�Ԃ��ɂ���̂ł���B����A���w�́A���łɁA�ؓ�疗y���A�S���Ɣ��̔��ƌ��т��āA�������Ԃ��̔��𐬗������߂Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�Í��������A���m�̊Ⴉ�炩�Ԃ��Ƃ�����v���͂����ɂ��낤�B���x�̃^�u�[��Ƃ��Đ������������̓��{�̍Ĕ����������ɂ���B���������ꂪ���{���y��˂������ē��B���Ă���̂��A�َ��̎p���ł���A����ɂ����鉅�O�̎p���ƂȂ��Ă��邩��ł��낤�B�v�@�i�S�i�����j
�@�@�@36�@�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\��Í������h�����L�O�����i58-60�y�[�W�j
�@�k�c�c�l
�@�u�w�v�杁x�ɂ��ẮA���́A����ɁA�vጂ̎��_�̕����Ȃ̂��낤�Ƃ݂Ă������A�y���̖H���̎X��ʂ��ς̂Ȃ܂߂������́A�w�������x��z���o������̂ɏ\���ł������B�B��̓��̐_������ɂȂ�V�ޏ��́A�ߏւ̂Ȃ��̓��̗̂d�����́A���̎X��ʂ̎�̐F�Ɏ��Ă����B�_������Ƃ́A���̓��̂ɁA�_�����ڂ�A���肱�ޜ����ɂ���̂����A�����A���̓��̂̂Ȃ���`�����ނƂ���A�y���̜����̕����ɂȂ�̂ł��낤�B�v�@�i�S�i�����j
�@�@�@56�@���h��̋N���i108-109�y�[�W�j
�@�u�Í������c�́w���h��x�̎��̂��݂Ă�ƁA�ǂ̒��ɕ����߂�ꂽ���������Ă���̂͂Ȃ�Ȃ̂ł��낤���B���������āA���t�̍߂̔��̐F�Ȃ̂��Ƃ��z�����肷��B�����܂ł��Ȃ��A���̔����́A�����Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��B���̗��`�̒�ɂ́A�ł̍��߂Ă��āA�ٗl�ɉB���̓������������߂Ă���̂ł���B
�@���Ƃ��Ɓw���x�́A�Ȃ��̐F�Ȃ����E��\�킷�A�w���̐��E�x�̕\���ł���ꍇ�ƁA���z�̔������w������w���̐��E�x�̕\���ł���ꍇ�Ƃ̗��V�������̂ł���Ƃ����悤�B
�@�Í������c�́w���h��x�̐��E�ł́A�����D�����Ԃ����Ƃ�����ۂ��悢�B�����炭�A�����ɂ́A���̊D�����Ԃ��������Ƌ��ʂ���S�ۂ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������B���͂����炭�́A�����ɂ́A���҂̔����̘A�z������B�v�@�i�S�i�����j
�@�@�@90�@�u���������^�W���v�J���i176-178�y�[�W�j
�@�k�c�c�l
�@�q���L�r�@��㔪�ܔN���
�@��J�B�[���������֏o��B�L�y���̃}���I���̒����z�[���ɍs���B�₰�郍�r�[�̕ӂ�B�u�O���O��Ձv�ł̓y���F�A�S�i�����̍u���ƈÍ������̃X���C�h��f���ς�B�e�L�X�g��O�ɂ����Ƃ͂����A�y���F�͎l�\���ȏ���������B�\��̃e�[�}�́u����̂̍̏W�v����߁A�u������܁v�Ƃ������n�̑̌��Ɓw���{��ًL�x�̈�߁A�m�i���̖��̘b�Ƒ}�����čI�݂ɂ܂Ƃ߂��B�I���āA���X�g�����A���X�J�ŁA�y�H�p�[�e�B�[�ƂȂ�B�y���F�͕��C���ł��Ă����B�ѓ��k��A�F��M���ƎG�k���A�\�ꎞ�ɋA��B
�S�i�ɂ́A���O�Ɂu�I�W�v�Ƃ������ׂ��s�S�i��������m����Ă��n�W�k�S6���l�t�i�����ЁA1990�`1992�j������B���́k��3���l�́q���e�̓��r�Ƒ肳��A�i�S�i�剺�̌È�ˏG�v�Ɓj���x�]�_�Ƃ̎s���́i�s���j�����������Ă��邱�Ƃ�����킩��Ƃ���A�S�i�̕��x�_���܂Ƃ߂����ɂȂ��Ă���B�k��6���l�ɂ���A200�y�[�W�߂������ǂ���̘J��A�q�S�i��������W�������r�ɂ��A�u�y���F�v�͂��̊���7�ӏ��ɓo�ꂷ��B�S�i�̕��͂̕W����f����ƁA
�@�@�L�т�E����
�@�@���̂Əے��ɂ���
�@�@�j���̂Ȃ��̍��V�\�\���x�ւ̓�
�@�@�y���F�Ƃ����ÓT����
�@�@�����Ƃ������x�̋G��
��5�тƂȂ�B����ɂ�����k��3���l�����́q���o�ꗗ�r�̔��\�N�����̏��ɕ��ׂ�����ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�i�s���ɐԐF�Ŋے�������U�����j�B
�@�y���F�Ƃ����ÓT�����i�u���Ƃ����ÓT�����v����j
�@�u���p�蒟�v���a48�N2�����@�w���Ɛ���x���^
�A�j���̂Ȃ��̍��V
�@�u���㎍�蒟�v20��4���@���a52�N4��
�B�L�т�E���ށi�u�s�L�т�t�Ɓs���ށt�Ɓv����j
�@�u��z�v9�@���a58�N7��
�C�����Ƃ������x�̋G��
�@�u�����V���v���a60�N2��19���[��
�D���̂Əے��ɂ���
�@�u���x�w�v10�@���a62�N12��
�s�S�i��������W�k��3���l���e�̓��t�i�����ЁA1991�N4��20���j����A�@�`�D�̏��ŁA�Y������ӏ��������B�W��Ɂu�y���F�v���܂��@�͑S�тł���B
�@�ނ��Ö��̑O�ŁA�����ȃA�N�����̌��ŁA���X�ɁA��{����I��ŗ��ƁA���̃G�N�X�^�V�[����т��������B�܂�ŁA���_�̗x�肪�͂��܂낤�Ƃ���悤�ȗ\��������A����́A�G���`�b�N�ł��炠�����B
�@�ނ̓��̂́A�݂�������܂����ӂ߂ʂ���Ă��āA���̗̌��̓��k�̍r��c�ނ̂Ȃ��ŁA��݂���ɑł��ӂ���ė��A���ɂȂ����j��ĎR�q�����������������B
�@���̐g�̂́A���̂Ƃ�������̂ƑΌ����Ă���A���Ƃ����ÓT�̌`�ۂɔ����āA�͂Ȃ͂��Ô��ȍ��̕����̖����̉��y��t�ł͂��߂Ă����B�܂��ƂɌ����ȌÓT�����Ƃ����ق��͂Ȃ��B
�@�������A�y���F�́A���A�̒���ʂ肷���Ă䂭�悤�ɁA���̂̓��������X�Ɣ`���Ă��āA�����̓��̂ł��āA�����̓��̂łȂ����̂����Ă���悤�ȁA�����ɂ́A������E����Ƃ������W�͐��藧���Ă��Ȃ��悤�ł������B�������A�y���̗x���Ă�����̂��݁A�y�����A���̓��̂����Ă��āA���̏�̕���|�p�ƁA���̏��قɂ��邩�̂悤�ł���B�قƂ�ǂ͎Ⴂ�����ł��邪�A���̔����̎d���́A�܂�ň���I�ŁA���̚X��̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���B�������ӎ��I�Ȏ�p�̍r��Ƃ����ق��͂���܂��B
�@����͖����|�\�̂����ɂ����݂��������Ƃ̂ł��Ȃ���ނ̂��̂̂悤�ɂ�������B���Ƃ��A�V����㗬�̎R�Ԃ̗���ŁA�^�~�ɍs����u�ԍՁv��u��Ձv�̕��l�ƌ����̂������ɂ́A����E������Ƃ����W�͐��藧���Ă��Ȃ��B����҂͑����҂ł����āA�ǂ��o�����B��̐��E�𐬏A���邽�߂ɂ͓����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������������̂ł���B����E������Ƃ������W�ł́A���܂ł��|�p�͕s�тȂ̂ł��낤�B
�@����́A���̕����Ƃ����̕����Ƃ����������d���̂Ȃ����̂ł��낤�B�N�����Ȃ�̕��x���\����݂�̂����A�����Ă������������Ƃ��Ȃ���A�قƂ�ǂ͖Y�ꋎ���Ă��܂��̂����A�����炪�������������Ƃ��Ȃ��Ă��A�ӂ��Ǝ��E���悬��̂́A�ԍՂ̉Ήe�̂Ȃ��̕��Ɠy���F�̂���ł���B���̂Ƃ��A���̓y�̓����̂悤�Ȃ��̂��������߂�B�ԍՂ̂���́A��ɔG�ꂽ�z���R�̗�Ƃ������y�̓����A�y���̂���́A�����L�����̂̐o�����������畑���オ������ł������B
�@�Ⴂ���������̔����́A���̎�p�̉������̂�Q���A���ۂ��A�����炤�A����ł������B���́A����Ȕ����̎d���������A�����ɂ��ޔ���͂��������Ƃ��Ȃ��B
�@�����A���x�݂��̂́u�v�杁v�Ɓu�����ߋʁv�̓�{�ł���B�s��낪�A�̏��Ҍ����A��⋻�����Ă��ꂽ�̂ŁA�ؕ��͔��킸�ɂ����A�Ⴂ�F�l�ɍs�Ă�����āA���Ƃ��A�ǂ���獘�����Ă݂邱�Ƃ��ł����B���ƎO���A�ؕ�����������݂��ɑ���Ȃ��B���Ҍ���������Ă��A���x��Ȃǂ́A�݂����Ȃ����̂������̂ɁA�������ɁA�y���F�̕����́A�H�~��������艞��������̂��B
�@�����ɂ́A����܂ł̌|�p�I���x�Ƃ�������̂Ƃ͈قȂ�A����Ȃ��̂��F�Ă��܂��A�����āA�o�߂Ă��镑�x�̌̋�������B���́A�ނ̕����́A�V�����̂łȂ��A�����ɐG�ꂽ���䂦�ɁA�l�Ԃ̌ÓT������̂��Ƃ������B
�@�����͂��߂āA�ނ̕��x���݂��̂́A���q�S��̃k�[�h���x�i�H�j�u�������v�̖V��ł������B���́A�ނ̖��O���L�����Ă��Ȃ��������A���̗��V��̓��̂͂͂�����Ɗo���Ă����B���ꂪ�y���F�ł������ƒm���āA���܂́A���̏Ռ����傫���B�������f�I�Ȏ��̏�����n���̂悤�Ȓj���I�Ȕ��������̂ƁA���܂́A���ɂւ���Ă����̋ؓ��̓��̂Ƃ��A����l���ł������̂ł���B�����炭�A�ނ̓��̊v�����A���̕����v���̍����ɂȂ����Ă���̂ł��낤���Ƃ́A����ɂ���Ē����I�Ɏ@���邱�Ƃ��ł���B
�@��Ɂu����g���v�Ȃǂ̕�����A��A��x�݂͂Ă���̂����A�����Ƀ��K�̍s�҂̂悤�ȂƂ����ُ킳�݂̂���ۂɂ̂��������A���ꂪ�A�u�������v�̂Ƃ��̒j�����x�ƂƂ͎v�������Ȃ������̂ł���B�u�Í������h�v�Ƃ��A�u���]�哥�Ӂv���Ƃ��A�킯�̂킩��ʁA���������ŋ��̊Ŕ݂����Ȍ��́A���̃��b�e�����낤����ǂ��ł��������A�Í��v�z�Ƒٓ������т��A���́u�������v�̓��́A���̓���ٓ��ƌ����Ă����q�̔��z�����������������ɂ͂����Ȃ��B
�@�u�v�杁v�ɂ��ẮA���́A����ɁA�vጂ̎��_�̕����Ȃ̂��낤�Ƃ݂Ă������A�y���̖H���̎X��ʂ��ς̂Ȃ܂߂������́A�u�������v����������������̂ɏ\���ł������B�B�̐_������ɂȂ�V�ޏ��́A�ߏւ̂Ȃ��̓��̗̂d�����́A���̎X��ʂ̎�̐F�Ɏ��Ă����B�_������Ƃ́A���̓��̂ɁA�_�����ڂ�A���荞�ޜ����ɂ���̂����A�����A���̓��̂̂Ȃ���`�����ނƂ���A�y���̜����̕����ɂȂ�̂ł��낤�B
�@���̓_�ł́A�|�p���x�m�A�n���͂���ȑO�̕����m�A�n�̂ق����ӂ��킵���B���̂�f�ނƂ����|�p�łȂ��A���̂��̂��̂�H���s�ׂ��̂��̂��x�Ȃ̂�����A���̕����Ȃ̂ł���B
�@�y���̕������A���k�̂��Ԃ��ȂǂƂ���������������̂��Ƃ������A�����炭�A���܂̂��Ԃ��Ȃǂ̒m�������Ƃł͂���܂��B�������{�l�̑ٓ��̂����߂����A���Ԃ��Ƃ����Ȃ�A�����̂��Ԃ����A���Ƃ��Ƃ��E�������Ă��������́A���̓�����E�����߂āA���m���n�������e�Ȃ̂ł��낤�Ƃ������B������ÓT�Ƃ����Ȃ�A���̌ÓT�̍����́A�����炭�ނ̐��܂�̓��k�ɂ��邩��ł���B
�@�ނ̌ÓT�̂��̈�́A�ǂ����Ă����ꂳ��łȂ��A�k����̎p���ɂ���B�������A���k�̍��̋Ȃ��������k����̗������ւ̎p���Ƃ��Ȃ����m�ł���s���́u�^�v�ɂ���B����͔��Q�̗͘���݂��鈰��r�q�Ɉڂ���Ă݂��ƂɊJ�Ԃ��Ă���B�܂��ƂɁA����́A�ᓹ�ŁA���k���A��łЂ˂肾���Ĕ����Ă��鎆�̑��Ԃ̍g�F�̂悤�ɔ������B�l�H�̋ɂ��݂���B
�@����͂��������A���k����Ƃ������g�̓��̂��A�������ȑ��݂������Ɏ��Ă���B�������N�̓��ɏo�������̌��i���A�������������������̂����A����͐����s���悤�Ƃ���Ƃ��̃G���`�V�Y���ɂ���B���[�ŁA�O�����݂ɂȂ������k���A���j���ɂȂ��āA�����̐����A�����Ȃ��悤�ɐK�̏�ɂ������グ�邽�������A�����ė��G�ɗ���������A�p�����������ƁA�@�������Ђ��A���ꍜ�̐�ɁA�Ђ����Ă��āA���̌ҊԂ�ʂ肷���镗�̂������ȋ�ԁA����́A�܂��Ƃɓ��{�̘V�k�̓T�^�I�ȁA�܂̓���悤�Ȓn����̌ÓT�Ȃ̂��Ƃ������̂����A�y���́u�^�v�ɂ́A�����ɔ�����̂�����B���̕����́A���̓��k�̓��ɎE���Ă��܂������i���A�x���Ă���悤�ɂ������ĂȂ�Ȃ��B
�@�y���̑O�����݂̔L�w�ɂȂ�p���́A�p���������ɂ͂ɂ��݁A�D�����̋ɂ��݂��邪�A���̓r�[�A�n�����琁���Ă��镗���A���̂����݂�t�ł�B���̗D��Ȏ��́A�얭�ȉ��y�ƂȂ��ė�������B
�@�����ɂ́A���̏�̓��̂̏C���Ƃ������̂��Ȃ��B�\���A�f�ނƂ��������̂̏C�����������g�����ł��铮�������邾���ł���B�C���A�ςݏd�˂Ƃ������}���J�V���Ȃ��B
�@���N�̓��ɁA���k�n���̂Ȃ��ŁA���������g�̎��Ƃ������l���݂Ă��܂����ނ̐��̓��X�́A��������͂��܂��Ă��邩�̂悤�ł���B�ނ��A�����������Ꮧ�ɏo������ЂƂ�Ȃ̂ł��낤�B����͂������ɏ��N�̓��̎��ɂȂ����Ă��悤�B�����ɂ͘V�k�Ə��N������B�������������E�\�����A�ނ̕������x���Ă���悤�ɂ�������B����Ƃ����ǓƂȒn���ŁA�ނ́A���܁A���X�ɏ��X�ɁA���̕Б��ŁA�������ɗ����Ă���̂ł���B������ÓT�Ƃ���Ȃ���A�Ȃɂ������Ė��Â���̂��B�����ɁA���k�̌����{�l������B���Ƃ����s���Ȃ��̂�����ɔw�����Ă䂭�ނ�����B
�@�x�[�g�[���F����V���p���Ƃ����ÓT����������A�u�q�_�̌ߌ�v�̃j�W���X�L�[��������悤�ƁA�ፑ�����鏗���o�⏗�Y�̌Q���W�����K���߂ƂƂ��ɒʂ肷���悤�ƁA�ڏ��̌Q���A�O������e���ĉ߂��悤�ƁA�݂Ȃ��Ȃ����k�̌ÓT�ɂ������Ȃ��B
�@���ƂɁA�O�юp�̓c�ɏ��Y�������A�т�����A���ʂ�炵�āA���n�̂悤�ɁA��������肩����։���\���͈�ۓI���B�����ɂ܂Ԃꂽ����r�q�̊�́A�����ƒ����Ă��āA����𐘂����p�Ԃ͉p��̏��G���Ȃ���ł���B
�@�n���̋����́A�^���ɂ���āA���Ă����n���ʂ肷����B�������̑��ʂ̋����́A�n�̒��̉��ƌ������āA���̍s�i�Ȃ��ቌ��������āA�~�����Ă���l�Ԃǂ��̓�����߂��Ă䂭�B���N�̓y���́A�����ƁA�������炵�ē��y�̒n�w�̉��ł�������W�̉��Ƃ��ĕ����Ă���B
�@�ڏ��S�ƃW�����K���̎O�����̋����́A���k�̃x�[�g�[���F���ł���A���̗t�̎q�ʂ�̒i�̋��P�́A�C�W�R�i�h�Ձj�ɓ����āA���ꗬ���̗c���̓��̃V���[�x���g�̎q��S�ł���B�葫�̗��������Ă䂭�AჂ�̉S�ł�����A���ɕ����Ă䂭���Ƃ́A�m���ȃL���X�g�̌��h�̖��݂�悤�ł�����A�����̖F�N�̕`�����u��\���O��v�̌��̉��̂悤�ł��������B
�@�C���̈����́A�A�~�[�o�̂悤�ɁA�g�����Ă䂭�����ł���A�`�̂Ȃ��\�H�̓����̂��������ɂ���B�܂����s�t�̃C�J�K���V�T�́A���̉��o�̂������낳�ɂ���B
�@�Ƃɂ����A���́A�y���F�̕����ɁA���X�ɓ��̂�����ł݂���Ƃ��ɁA�G���X�����U����A���̌ÓT�����A���Ă䂭�̂��݂��B�i253-258�j
�A���x�̃C���[�W�́A�Í������h�̕������͂��܂��ĕς�����Ƃ����Ă悩�낤�B�����́A���܍����}���g��㕂��Ėڂ̑O�ɂ�����Ă���̂́A���Ē����̐�����ʂ肷�����u���̕����v�̍ė��������킹��B
�@�₩�ł���ׂ�������́A���܂≩���̍r��̐��Ղɏꏊ���ڂ��A�鐂̉��ʂɁA�傫�ȑ�������ガ���ĂāA���̉������t�ɁA�ǓƂȕ���t�ł�C���[�W�����������āA�邩�ɐ��̔ɉh�̑�s����̒n���ɁA�[���̕����܂��ďZ�݂������̂悤�ł���B
�@�y���F�̕����̂��ꂪ�A���ɋ�藧�Ă��h�ڂ̉��ƓV�g����������Ƃ��A�d�Ȃ�A��d�̐������Ȃ��āA���ߔ��ʂ̒j�ǂ����A�Ђ��Ђ��Ɨ����オ��A�ڂ������������������ɔ������Ƃ��A�V���������̈Ӗ����͂��܂����̂��A�������ɏ؋��Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
�@���q�S�A���A�k�[�h�\�������Ă��āA�ÓT�̕��̌��Ђ��A���������������艺�낵���ڊo�܂������́A�Ӌ`���������Ă��A���x�̎Љ�I�����T�O��@����ڂ��ʂ������B����́A��O���̑��E����̔j���łȂ��A�\���ɁA�ÓT�I�`���̐[�������Ɠ���͂���������̍s�ׂł��������ƂɈӋ`������A�ÓT��ƌɂƂ��āA�����Ƃ��āA�݂�����̐��E��ł��j�낤�Ƃ����_�ɐ��I�ȓ������������Ƃ��ׂ��ł��낤�B
�@���q�̂��������`���h����݂����s�Ɣj���s�ׂ́A���̕��x�j�̏o�����Ӗ����A������̂ł������ƕ]�����邱�Ƃ��ł���B���Ԃ����x�ɑ��Ă��A����G�q�Ƒg�����́u���n�v��u�~��v�̂��Ƃ����x��i��A���h��قł݂����u�������v�̂��Ƃ��́A���̉��ߓI�Ӌ`�͂Ƃ������Ƃ��āA���̕��x�Ƃ����s�ׂɂ́A�������E���Ă��Ȃ��j������Ƃ��ɂ݂���V�N�ȉΉԂ��������̂�Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�y���F���A���̕��q�́u�������v�ɎQ�����Ă��āA�V��顂ŁA���̂Ȃ���A���炵�����`�̓��̂���g�����x���݂��ďo���������Ƃ��o���Ă���l�����邾�낤���B����́A�y���̕��������܂��A�`���ÓT�̔j���̂Ȃ��ʼnc�܂ꂽ�A���{���x�ƃ��_���_���X�Ƃ̏ے��I�ȍ��V�̎��ł������̂��ƁA���܂ɂȂ��Ă�����������̂ł���B
�@���̕��q�́A�ʂɕ����Ƃ�������g���Ă���킯�ł͂Ȃ������B����́A�V�������̂ݏo���O�̈��̔j���s���Ƃ������ׂ����̂ł������̂ł��낤�B�y���́u�����v�́A���̍r���y��Ƃ��Đ��܂ꂽ�A�����Ȃ�Í��̎q�ł������B
�@�y���F�̕����́A���x�̐����Ȏq�łȂ����Ƃ��A���疼�̂肠�����A����̍��ʌ�ł��낤�B�]���̈��ՂȂ镑�x�Ɍ��ʂ�錾�����ǎ����邱�Ƃ��֎��������q�D�ł��낤�B�u�����v�Ȃ��́A��������V��������ƂȂ����r��ɏo�����邱�ƂƂȂ�B�i239-240�j
�A���������āA�����́u�����v�́A�����̕��������m���x�Əo������p�ł������B������������ؓ�疗y�́u���x�v�́A�`���̕����Ɩ������ɌĂт�������ł������B���������̕��x���A�V���x�^�����߂���ƁA���ՂȔɉh�ɗ���č����Ɏ����Ă���B���̕��x�̈��Ղ��A�����������āA������̐V���E�����܂͂��܂��Ă���B���ꂪ�V��������Y�E�y���F�E�}��b�E����r�q�E���g�͌��O�Y��́u�����v�̓y�낾�Ƃ������Ƃ��ł��邩�ǂ����B���������A���Ԃ������ĕ����̍s����ǐՂ��Ă݂����B�i245-246�j
�B�͂��߂ēy���F�̕����ɐڂ����Ƃ��A����܂ł̕��x�Ƃ����T�O�̑O�ŁA�u�����v�Ɓu���f�v���������B���ɂƂ��ẮA����͈�̖��͂ł������B�������A������u�V�����v�����Ǝ��ɂ́A�S�O������A�܂�����������ނ̋����ł͂Ȃ������B�i79�j
�B������������Ɋւ����A�m�����ɏ��a�l�\�N�ォ�炠���ꂽ�A������Í������Ƃ�����V�l�����A����Y�A�y���F�Ȃǂ��o���_�Ƃ��镑���̗���́A�m��������o�����߂ɁA�]���̓��{���x�Ƃ́A�Ȃ��W�Ȃ��ɁA���{�l�̕������J�������Ƃ�����B�������A���̍����ɂ́A�{���A�L���A�����Ӗ��́A���{�����̍���𗬂��u������݁v�̓��̕��x���������Ƃ����悤�B�i84�j
�B�����A���Ԃ����x�̗���̐V���x���A���c����Ă��܂������H����A�����オ�邽�߂ɂ́A�������x�̏����ɗ����߂炴������Ȃ��낤�B�Í������́A�����������ʈł̔ޕ�����K��͂������A�₪�ē��̓�����ꏊ�ɓo�ꂵ���Ƃ��A���̑̎��͂ǂ��ς��˂Ȃ�Ȃ��̂��B����Ɉُ��̌��ۂƂ��āA�₪�ď��ł���^���Ȃ̂��A���E�ɗ��o���Ă������܂܂ɂȂ�̂��B����A���́u�E���v���Ƃɂ���čĐ������Ȃ�����{�I�s�ׂȂ̂ł��낤�ƐM�������B�i86�j
�C�u�����Ƃ������x�v�Ƃ��������́A���{��ł͐������Ȃ����A���[���b�p�ł́u�u�g�[�E�_���X�v�͂��łɒ蒅������ƂȂ��Ă���͈̂Ӗ�������B
�@���a�Z�\�N�A�����O��ՂƂ��ē�\�����܂ŁA���{�������c���́u���������^�W���v�i����u���l�̋G�߂Ə�v�j�Ƒ肵���A�Í������ƂƂ����鎵�l�̕����Ƃ����ɂ�镑���t�F�X�e�B�o�����\�l��ɂ킽���ē����L�y���̒����z�[������ѐV�h�����Z���^�[�ŊJ�Â��ꂽ���A�ُ�Ȑl�C�ŁA���ꌔ�̓��肪����Ƃ�����悵���B�u�����v���A����ɕ��x�̕��삾���łȂ��A�V�����|�p�̐��E�ւƁA�ꋓ�ɐ����i�߂Ă��������ӎ��̊v���Ƃ������̂��A���܂�F�߂Ȃ��킯�ɂ͂䂩�Ȃ����낤�B
�@���łɓ�\�܁A�Z�N�̍Ό���ꗬ���Ă����A���̓��{���܂�̈Í��������A���܁A�n���̗����ʼn����p���A�������{�l���A�Ƃ܂ǂ����`�Ŏe�ꂴ������Ȃ��Ȃ������A�ǂ���������悢�̂��B
�@���̃t�F�X�e�B�o���ɁA���̐��E�̋��g�Ƃ����y���F���u���������^�W���v�Ɩ��������̂́A�����������{�̐��_�����̜����^�ƂȂ��������̓����Î����Ă���悤�ł���B�i263-264�j
�C����Y�̕����́A�ǂ�����Ƃ����A�����I�ȃn�C�J���ȓ����ȃX�^�C���������Ă���B����̏o���͂Ȃ����A����ɔ����ēy���F�̕����́A���̍��̓y���I�ȓ��k�̕��y�Ƒَ��o���ɍ������Ă���Â��Ƃ��낪����B�������A���̓�l�́A���قƏH�c�̏o�g�ł���A����ɂÂ����̌܈�P���k�C���o�g�ł���B�i264�j
�C�Í������Ƃ̓��̂ɂ́A�����Ε��o��A���邢�͓���̐l�̗삪���݂��Ă���X��������B����Y�ɂ͕ꂪ�A�y���F�ɂ͎o�����݂��Ă����B������C�^�R�i�ޏ��j�����`���I�ȕ��y�Ȃ̂��Ƃ�����B
�@�������A�����́A���x�ƊW�Ȃ��A�`����f���A���邢�͖��������Ƃ���ɂ͂��܂����B�����ɂ͋ߑ㐫����̂Ă����E������B�ނ炪�A�Í��̍��ɉ��~����Ƃ��A�`�[�������`����f���Ƃɂ���ē`���̌p�����͂��܂������Ƃ�F�߂ʂ킯�ɂ͂䂩�ʂ��낤�B
�@�s���́A�����ɁA�����h�ƌ`���h�̑Η������邱�Ƃ��w�E���Ă���B����͂����炭�V���̌[�����������l�Ԃ̓��̜̂���Ɩ��S�̓�������������^�̑���Y�h�ƁA�l�Ԃ̓��̂̌��`���ł̕��y�َ̑��̖ڂ��݂�������Nj�����y���F�h�Ƃ̓�̌X�����w�������̂ƍl�����邪�A������ɂ��Ă��A�푈�A�s���̌��������{�l�̓��̂��v���m�炳�ꂽ�A���{�̕��y���琶�܂ꂽ����ɔ��������̂ɂ���������܂��B
�@�����Ƃ́A�푈�Ƃ����\�͂̂��Ƃɂ̂������A���Ɣ�̓����ɗ������ł̂Ȃ��ŁA�l�Ԃ��l�Ԃł��邱�Ƃ������D�����̕\���ł͂Ȃ������̂��B���E�y���̕����ɂ́A������悤�ȗD�����������Ă��A������̐���̎Ⴂ�����Ƃɂ݂��鋺�����悤�Ȗ\�͓I�ȕ\���͂Ȃ��B�܂������ɂ́A�n���Ƃ�����Ƃ����Ƃ������C���������h�͂Ȃ��B�����ɋߑ�Ɛ₷��V�����������݂���B�i266-267�j
�D���̍��̕��x�̂��߂̐g�̂́A�P�������K�v�Ƃ�����̂ł��邪�A���̓��̂́A���̏h�Ƃ��ׂ��H���̊�ƂȂ邱�ƁA������E�������ނׂ����߂ł����āA�L���Ȋ��S����ړI�Ƃ��Ă��Ȃ��B���݂������Í������Ɠy���F���������u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���v�Ƃ����̂��A���m�̐g�̗̂��O�ł������̂ł͂Ȃ��낤���B�i234�j
�������đf�ނƂ��Ă̎������o����������ŁA�s�y���F��t�ɓo�ꂷ��S�i�����Ƃ��̕��͂̏o�T�ɂ��āA�܂Ƃ߂Ă������B
�q29�@�A�[�g���B���b�W�ɂār�Ɉ����ꂽ�S�i�́\�\�u������́A����܂ł̕��x�ɔ�����p�ԂɁA�D���ɑ���X��������B�k�c�c�l���������ꂪ���{���y��˂������ē��B���Ă���̂��A�َ��̎p���ł���A����ɂ����鉅�O�̎p���ƂȂ��Ă��邩��ł��낤�B�v�\�\�́q�����Ƌ֊��r�i���o�F�u���㎍�蒟�v28��6���@���a60�N6���j����B�s�S�i��������W�k��3���l�t�́q�����Ƌ֊��r�́u��@���݂Ƃ������Ɓv�̖`���̒i���͂����ł���B
�@������́A����܂ł̕��x�ɔ�����p�ԂɁA�D���ɑ���X��������B�K�j�ҁA���܂����w�A�k�葫�A�����炭���x�̔��ɔ����邱���̑̈ʂ́A�ǂ����甭�z���ꂽ�̂��A�ǂ��Ƀ��[�c������̂��Ƃ������ƂƁA�����̑��݂�F�߂��邩�ǂ����Ƃ������Ƃɂ�������Ă����肪����B���������F�߂Ȃ���Ε����͑��݂����Ȃ��̂ł���B�������A�����������p���ɔ���F�߂�v���́A���́A�`���������邩�Ԃ��ɂ���̂ł���B����A���w�́A���łɁA�ؓ�疗y���A�c���Ɣ��̔��ƌ��т��āA�������Ԃ��̔��𐬗������߂Ă��邱�Ƃ�����Ă���B�Í��������A���m�̊Ⴉ�炩�Ԃ��Ƃ�����v���͂����ɂ��낤�B���x�̃^�u�[��Ƃ��Đ������������̓��{�̍Ĕ����������ɂ���B���������ꂪ���{���y��˂������ē��B���Ă���̂��A�َ��̎p���ł���A����ɂ����鉅�O�̎p���ƂȂ��Ă��邩��ł��낤�B�i251�j
�q36�@�u�l�G�̂��߂̓�\���Ӂv�\�\��Í������h�����L�O�����r�Ɉ����ꂽ�S�i�́\�\�u�w�v�杁x�ɂ��ẮA���́A����ɁA�vጂ̎��_�̕����Ȃ̂��낤�Ƃ݂Ă������A�y���̖H���̎X��ʂ��ς̂Ȃ܂߂������́A�w�������x��z���o������̂ɏ\���ł������B�k�c�c�l�_������Ƃ́A���̓��̂ɁA�_�����ڂ�A���肱�ޜ����ɂ���̂����A�����A���̓��̂̂Ȃ���`�����ނƂ���A�y���̜����̕����ɂȂ�̂ł��낤�B�v�\�\���@�q�y���F�Ƃ����ÓT�����r����B
�q56�@���h��̋N���r�Ɉ����ꂽ�S�i�́\�\�u�Í������c�́w���h��x�̎��̂��݂Ă�ƁA�ǂ̒��ɕ����߂�ꂽ���������Ă���̂͂Ȃ�Ȃ̂ł��낤���B�k�c�c�l���͂����炭�́A�����ɂ́A���҂̔����̘A�z������B�v�\�\�́q�����Ƌ֊��r�i�O�o�j����B�s����W�k��3���l�t�́q�����Ƌ֊��r�́u��@���̋��|�v�͂����n�܂�B
�@�Í������c�́u���h��v�̎��̂��݂Ă���ƁA�ǂ̒��ɓh�肱�߂�ꂽ���������Ă���̂͂Ȃ�Ȃ̂ł��낤���B���������āA���t�̍߂̔��̐F�Ȃ̂��Ƃ��������肷��B�����܂ł��Ȃ��A���̔����́A�����Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��B���̔������`�̒�ɂ́A�ł̍��߂Ă��āA�ٗl�ɉB���̓������������߂Ă���̂ł���B
�@���Ƃ��Ɓu���v�́A�Ȃ��̐F�Ȃ����E������킷�u���̐��E�v�̕\���ł���ꍇ�ƁA���܂��O�̔������Î�����u���̐��E�v�̕\���ł���ꍇ�Ƃ̗��`�������̂ł���Ƃ����悤�B
�@�Í������c�́u���h��v�̐��E�ł́A�����D�����Ԃ����Ƃ�����ۂ��悢�B�����炭�A�����ɂ́A���̎��̊D�����Ԃ��������Ƌ��ʂ���S�ۂ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������B���͂����炭�́A�����ɂ́A���҂̔����̘A�z������B�i247-248�j
�g���́A�@�̏��o�f�ڎ��s���p�蒟�t1973�N2�����ɓy���́u�q�n�����Ŕ҂������Ȃ�r�v��莫�Ɉ������q������܌�b�сr�i�G�E8�j���Ă���B�܂��A�s���㎍�蒟�t�͑n�����ȗ��A���l�E�g�����ɂƂ��ăz�[���O���E���h�̂悤�ȎG���ł���B�g���́A�S�i����̈��p�Ɍ����Ă݂�A�L���������ʂƂ��������A�g�߂ȕ�����ǂ݂������ŁA���̐����𒊏o�������̂Ǝv�����B���Ɂq�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�́u18�v�ł́A�u���͖��f�ł���߂Ēf�ГI�ɁA�����̕��X�̕��͂��u���p�v�����Ē������B�����A�����e�̂قǂ��B�F�l�ɐ[�����ӂ������܂��B�܂��L�������Ɋ��ʂ��Ă��Ȃ��䂦�A���������M�d�ȁu�،��v���A����������Ǝv���邪�A����������Ē��������B�v�i�s�y���F��t�A��l��y�[�W�j�Ǝߖ����Ă���B�g����������������ۂ��āA�s�S�i��������W�k�S6���l�t�i�����ЁA1990�`1992�j����ɂ����Ȃ�i�g���ƌS�i��Ō��Ƃ̊W���琄�@����A���{���ꂽ�͂����j�A��f���@�`�D���͂��߂Ƃ��邠����������A�S�i�ɂ��y���]���s�y���F��t�ɑ��₵���̂ł͂���܂����i�q56�@���h��̋N���r�̈��p�����Z���������j�B���Ƃ��A����ł�V�łƂ��������ЂƂ��Ă܂Ƃ߂邱�Ƃ͂Ȃ��Ă��B
�q90�@�u���������^�W���v�J�Ár�ɂ��āA�S�i���C�q�����Ƃ������x�̋G�߁r�œ��t�F�X�e�B�o���Ƃ��̖����҂ł���y���F�Ɍ��y���Ă���B�Ȃ��A�g�����G��Ă���y���̍u���q������܁\���������^�W���r�́s���㎍�蒟�t1985�N5�����Ɍf�ڌ�A�s�y���F�S�W�k�U�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1998�N1��21���j�Ɏ��^���ꂽ�B�g���ɂ��A�y���̍u���́u�e�L�X�g��O�ɂ����v���̂����������A�܂�ʼn��N�̑�̎�̃��T�C�^���łł����邩�̂悤�ɁA�����ʼn��������y���߂����Ă���B�s�y���F��t�ł́A�ʓr�q28�@�y���F�̗c���N���́q���I�̌��r�r��������Ïk���āA�蒅���Ă���B
�@�k�c�c�l���͂悭������ł����A���͎��̐g�̂̒��Ɉ�l�̎o���Z�܂킵�Ă����ł��B����������i�����ׂ��M�����܂��ƁA���̑̂̂Ȃ��̈ō����ނ����Ĕޏ��͂����K�v�ȏ�ɐH�ׂĂ��܂���ł���B�ޏ������̑̂̒��ŗ������ƁA���͎v�킸���肱��ł��܂��B�����]�Ԃ��Ƃ͔ޏ����]�Ԃ��Ƃł���B�Ƃ����A������肠���ȏ�̂��̂��A�����ɂ͂���܂��ĂˁB�����Ă���������ł��ˁB�u���O���x�肾�̕\�����̖��䖲���ɂȂ��Ă���Ă邯��ǁA�\���ł�����̂́A�����\�����Ȃ����Ƃɂ���Ă�����Ă����Ȃ��̂����B�v�Ƃ����Ă����Ə����Ă䂭�B�����狳�t�Ȃ�ł��ˁA���҂͎��̕������t�Ȃ�ł��B�k�c�c�l�i�q������܁y�u���z�r�A�s�y���F�S�W�k�U�l�t�A���Z�y�[�W�j
�Ƃ���ŁA�S�i���D�́q���̂Əے��ɂ��ār���s���x�w�t�ɔ��\�����̂́A�s�y���F��t�i1987�N9���j���o��3�ӌ���ł���B�����Ɂu�u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���v�v�������Ă���̂́A�g���ɑ��āu�s�y���F��t�A�ǂ݂܂�����v�ƈ��A�𑗂��Ă���̂ɓ������B�Ȃ��Ȃ�A�y���̂��̃e�[�[�́s�y���F��t�̑莫�Ɍf����ꂽ���ƂŁA�����Ă��ꂪ���̂܂ܑсi�\�P�j�̕��Ɏg��ꂽ���ƂŁA�y���F���Í������̗��O��[�I�ɕ\�����t�m�N���h�n�ƂȂ�������ł���B����́A�y�����g�����S�i�Ɠ`�����邱�ƂŁA�u���F�v����Ă������ƌ����悤�B�Ȃ��A�u�u�����Ƃ͖������œ˂����������̂ł���v�v�̏o�T�ɂ��Ă��q�g�����Ɠy���F�r���Q�Ƃ��ꂽ���B
�Ō�́A�s�y���F��t���s�̈Ӑ}�Ҏ��g�Ɍ���Ă��炤�̂��A������D�����낤�B
�@�u�y���F�Ƃ͉��ҁH�v�N���������v���Ă���ɂ������Ȃ��B���̐l���Ɠ�\�N�̌𗬂�������̂́A���ɂ͂��́u��̓V�ˁv�k�i�F�V���F�j�l���A�\�S�ɑ����邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�B�����Ŏ��͎����́u���L�v�𒆐S�ɋ����A�y���F�̎��ӂ̗F�l�A�m�Ȃ̏،����S��A�����ĕ����Ƃ�⼌��I�Ȍ��t���A�K�X�}������A�\�������݂��B�܂������A�u���L�v�Ɓu�،��v�Ɉ˂�u���p�v�́w�y���F��x�ł���B�i�q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�́u18�v�A�s�y���F��t�A��l��y�[�W�j
�s�_��I�Ȏ���̎��t�ȍ~�́A���Ȃ킿�u�����g�������v����сu����g�������v�ɂ�����y���F�̉e���͐r�傾�B����͂Ȃɂ��A�y���ɕ������������т������āA����ȁi�g�������ł́q�g��i���Ɏ~��r�Ɏ����Œ����j�Ǔ���������A�Ƃ������������w���̂ł͂Ȃ��B�y���F�̐��݂����������Ƃ��̌��ꂪ�A�g�����̎��̐��E��k�������̂ł���B�s�y���F��t�ɐ旧�A�g�����̓y���F�]�͂������B�S���������B
��Z�N�قǑO�ɁA�����������̏o�ŋL�O��������Ȃ��A�喜���ēX�̍��~�ŋ��R�������̐Ȃɍ������̂��y������Ƃ̏o����������i���j�B���ꂩ��ނ̕���͖w��nj��Ă��邵�A�y������̂��Ƃ�����̎��ɂ��������B����A�y����^���猾�t�����ĂˁB���̓ǂݎ�Ƃ��Ă����킢�l�ł���B�ގ��g�̏����Ă��錾�t���A���ł��Ȃ�������ł��Ȃ��A�܂������Ɠ��̂��̂ł��傤�B�����Ƃ����A����܂łȂ��������̂��������y������́A���̓��{�ɂ����ꂽ�ЂƂ�̓V�˂���ˁB�i�k�k�b�l�q�����{�̈��V�ˁr�A�sW-Notation�m�_�u���E�m�[�e�[�V�����n�tNo.2�k�ɒ[�ȍ������y���F���[�f�B���O�l�A1985�N7��23���A����`����y�[�W�j
��������S�ɓǂނȂ�A�g���͓y���Əo�����1967�N2���ȍ~�A1986�N1���ɓy���̎����}����܂ŁA�y���F�ɓǂ܂�邱�Ƃ̋��|�Ɯ����̂����Ɏ��������Â����B�����āA�s�y���F��t�i1987�j�̗�1988�N���s�́s���[���h���b�v�t�͒Ǔ����q������ܒf�����сr�����߂āA�g�������O�Ō�̎��W�ƂȂ����B�u�����v�ȍ~�̋g�����������ׂēy���F�̑��݂Ɍ��т���킯�ɂ͂����Ȃ��B�������A���̉e����x�O�������g�����_�͐��������Ȃ��B���݂̉e���W�͏[���ɍl�@����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�g�������y���F�ɗ^�����e���͑傫���B�����A�g�������y�������ɗ^��������͌v�����Â炢�j�B�s�y���F��t�ɂ́A���̎�|���肪����B�g�������Ƃ����傫�ȓ�̒T���ɕ����ɂ������āA�{�����g���䂭���Ƃ͂����ǎ҂ЂƂ�ЂƂ�̐Ӗ��ł���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@��������̓��L�q�����̎� �W�ȍ~�\�\1960�i���a35�N�j�`1974�i���a49�N�j�r�ɂ���悤�ɁA�����1967�i���a42�j�N2��9���i�j�A��{���g�̓喜�ŊJ���ꂽ�����̎��W�s�`����w�t�o�ŋL�O��̓�ł̂��Ɓi�q�g�����Ɖ�������\�\�ӂ���̓��L�𒆐S�Ɂr�Q�Ɓj�B�������A�������L�ɂ͑O�N�A1966�i���a41�j�N12��8���Ɂu���A�����Ґ��܂̎�܂̒m�点����B�v�i�s���������i��W�V�\�\���������L�E�G�b�Z�C�E��V�^�t�A����A���X�A2016�N7��16���A��ܔ��y�[�W�j�Ƃ��邩��A�����ł����Ƃ���́u�o�ŋL�O��v�i�������L�A�g���k�b�j�́A���Ȃ킿�u�Ґ��܂��j����v�i�g���q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�j�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�s�����{ ���߂Ƌ��ނ̌����t�i���a58�k1983�l�N4���Վ��������j�́k�ߑ��ƔN���W���l�������[���B���͍����܂ŁA�w��Ƃ��ċߑ���{���w���C�߂����Ƃ��Ȃ��i���ň���ł̏��Б������{�G�f�B�^�[�X�N�[���ŁA�i���u�K��������w�Ŏ�u���������ŁA���Ƃ͓Ɗw�ł���j�B��w�ł̐�U�̓t�����X���w����������A�ނ���œ��{�̕��w�҂̔N���̍������K�����o�����Ȃ��B����ŏ����Y���Ɠ��l�������A���P�����Ɠ��l�G�����o���ԂɁA�n��⌤�����u�������̓�����̐l�l�����Ă����B�̐l�̏����S�q��A��N�}����������v���q�����������Ȃ��ɂ����B�Ƃ���ŁA�����̑ΏۂƂȂ镶�w�҂Ɖ�������Ƃ����邩�ǂ����͂��Ȃ���Łi��������炦�炭�āA��Ȃ��������炾�߂Ƃ����킯�ł͂Ȃ��j�A1984�N�ɋg�����Ɩʎ������Ƃ����ɑ傫����p���Ă��邱�Ƃ͋^����e��Ȃ��B���e���O�Y�A�i�c�k�߁A�y���F��撊P�ɐڂ����i�Ƃ������A���̎p�������j���Ƃ��傫���B�g����1990�i����2�j�N5����71�ŖS���Ȃ��Ă��邩��A���O�̋g����m��l�̔N��̉����͂����炭���a30�N��i1955�`64�N�j���܂�ŁA����50��㔼�ȏゾ�B��������Ⴂ����́A���O�̋g������m�邱�Ƃ��Ȃ��A�{�l����͂̐l�̏،���ʂ��Ă��̐l������`���ق��Ȃ��B���̂Ƃ��A�{�l�̒���Ɏ����ŏd�v�Ȃ̂��A���̎��т��܂Ƃ߂��N���ł���B�����g�������̌������n�߂�1970�N�㖖�A��������������2���̎G���̋g�������W�������Ȃ������B�����͋M�d�Ȃ��̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ����A�����m�肽���Ǝv�������Ƃ͍ڂ��Ă��炸�A�͂��炸�����璲���E�������邱�ƂɂȂ����B�����K�v�Ƃ��Ă����̂́A�g�����̑S���M��i�̏ڍׂȃ��X�g�i������u����N�\�v�u����N���v�j�ŁA�ނ��͎U���⎍�ٍ̈e�i����ɂ́A�G�N���`���[���ɂ��炴��k�b�����j���܂ދg���̑S�����ǂނ��߂̒T���p�c�[���ł���B���āA�s�����{ ���߂Ƌ��ނ̌����t�́k�ߑ��ƔN���W���l�ɖ߂�A�ΐ��̎��ؓI�����Œm������V���i1923�`1995�j���A�����́q�N���̍����r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���i���g���q�ΐ��r�̍���S���j�B���Ȃ݂Ɋ����́A�T�_�ӂ��̍g��q�Y�q�N���T�A�l�ւ̈���r�B
�@�N���̍����ɂ͂��낢��̕��@�����邪�A�v�͑ΏۂƂ����Ƃƌ�����̂̎����ɍł��K�������@���l���o���A���C�悭�`�L�I������ςݏd�˂āA���m�ȔN������邱�Ƃ���ł���B
�@���ʁA�N���̍����Ƃ��Ă͌܂̒i�K������B���̑��͍�Ƃ̓��L�A���Ȃ𒆐S�ɂ��āA�N���̍��i���Ȃ����S���������グ��d���ŁA�k�c�c�l�B
�@�N���쐬�̑��̒i�K�͍�Ƃ̐��������ׂ邽�߁A�ƌn�◼�e�̌o����T��d���ŁA�k�c�c�l�B
�@�N���쐬�̑�O�̒i�K�́A���N������N���ɂ����Ă̓��Â𖾂炩�ɂ��邽�߁A�w�Z���������d���ł���B�k�c�c�l
�@�N���쐬�̑�l�̒i�K�͍�Ƃ̕��w�I�o���𖾂炩�ɂ��邽�߁A�N���̕��w�����Ƃ��̔w�i���Ȃ��O���[�v�⌋�Ђɂ��Ē��������{���邱�Ƃł���B�k�c�c�l
�@�N���쐬�̑�܂̒i�K�́A���U�̕��w�����𐳊m�ɋL�^���邽�߁A���o�����̒�������Ƃ���ڍׂȒ���N�������d���ł���B��ꂩ���l�̒i�K����Ƃ̓��ÂȂ����o������Ƃ��Ă���̂ɑ��āA��܂̒i�K�͍�i�����̉ߒ��𖾂炩�ɂ�����̂ŁA���̗��҂����܂��Ă͂��߂ĔN������������B
�@���o�����ׂ�ɂ͂܂����L�A���Ȃ���A���̍�Ƃ���i�\�����Ǝv����V����G����T���o���B���̑��G���̒Ǔ����W�A�`�L�A�S�W�̉��A�����̔N���Ȃǂ��Q�l�ɂȂ낤�B�������Ė��炩�ƂȂ������o�����͌��݂ǂ��ɏ�������Ă��邩�����A�����ɂ������āu��i���v�u���\���̊����v�u���\�̓��t�v�u�����v�u���s���v�Ȃǂ��L�^���A�����N���ɏ�������ł䂭�̂ł���B���\��i�̍Ō�Ɏ��M�����L������Ă���ꍇ�͂����N���ɏ�������ł����Ƃ悢�B
�@�ȏ�A���̑̌��ɑ����ĔN���̍������ܒi�K�ɕ����ďq�ׂ����A�����������A�����̏o����͈͂��������A�H�v�ɍH�v���d�˂ē`�L�I������ςݏd�˂Ă䂭�ƁA�����̔N���P�����Ƃ��݂�����̗͂ŐV�����N������邱�Ƃ��ł��悤�B�k�c�c�l�i�����A����`���O�y�[�W�j
�k�ߑ��ƔN���W���l�̓����́A���̕\�����̂ɋL����Ă���B�u�ؓ��ꡂ���O���R�I�v�܂ŁA�ߑ���{���w���\����51�l�̍�Ƃ̔N�������̈���Ɏ��߂�!!�@�ŐV�̎����Ɣ����Ɋ�Â��N���Â���̌���ŁI�@��Ƃ��ƂɁk�����̋l����݂��A���݂̍菊�������I�v�B���̐l�ł͖k�����H�┋���Y�A�֓��g�Ȃǂ��ڂ��Ă��邪�A�{���ɋg�����͓o�ꂵ�Ȃ��B�܂��A�Q�l�ɂ��ׂ��f�ڍ�Ƃ͒N�ł��悢�A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�����ł́A���̐푈�̌������g�̕��w���`�������剪�����i1909�`1988�j�̍��̖������������B1983�N���_�i�剪�͂��̔N�A74�B10�ΔN���̋g����64�j�ł́u�ŐV�̎����Ɣ����Ɋ�Â��N���v�ł���B�Ȃ��A�剪�N���̎��M�҂͒r�c����B
�k�����̋l
���剪�Ƃ̌����̓O��I�T���B
���R�w�@�A���鎞��ɂ����镶�w�I�Ȏ��Ȍ`������F�W�����Ƃ��Ė��炩�ɂ��邱�ƁB
�����`�ō�҂��G��Ă��Ȃ������A���ɋ��s����E�_�ˎ���ɂ��Ă̒����B
�����C�e������ł̊����ɂ��ď،������W���邱�ƁB
�k�Q�l�l�@�S�W�Ƃ��ẮA�������_�ДŁw�剪�����S�W�x�S�\�܊��i��48�E10�`50�E8�j�B��\�܊��Ɂu�N���v�u����N�\�v�u�����ژ^�v���^�B��i�W�Ƃ��ẮA��g���X�Łw�剪�����W�x�i��57�E6�`�j�B�e���́u����v�ɍ��ݑq�E�r�c����҂́u�Q�l�����ژ^�v���^�B�i�����A��ꔪ�y�[�W�j
�g�����́k�����̋l�́A1940�N�ĂɗՎ����W���i�����Ŕn�̈������Ȃǂ��w�j�A��1941�N�Ăɂ͏o���A1945�N�H�ɕ��������R������ɂ���B�g���́A���M�N���̑����m�푈�u����́u���a�\���N�@���l�O�N�@��\�l�v�̍��ɁA�������������i�S���j�B
�Z���ܕ����̌R���ՂŁA�Ԗт��̃V���m�E�h�E�x���W�����b�N�̃p���f�B�[���㉉����B���{�̏T�Ԏm����o�ꂳ�������������߁A�t�c���̋t�ɂӂ�A���Ҏ��l���������������֓]����������B�i�q�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��O��y�[�W�j
���̋L�ڂ́A�z���̂ق��d�v�ł���B���W�s�m���t�̑S�т����߂��s������{�����W�听�k11�l�t�i�����n���ЁA1960�N9��10���j�ɕt����425�����́q���`�r�ɂ��łɓo�ꂵ�Ă��邩�炾�B
���`�b�g����
�@�����N�����{���̐E�l�̉Ƃɐ����B���䑾�Y�A�ꂢ�ƔӔN�̎q�B�o�E�Z�̎O�l�Z��B�����q�포�w�Z�ɓ��w�B���̂��납��悭�Z���p�j�B�`�����o���V�т̈���̊����B�ƂɈ���̖{���Ȃ��A�F�����̖{��ǂ݂�����B�{���������w�Z���ƌ�A�㏑�o�œ�R���ɕ���B�Y�w�l�Ȑ}�����݂ăV���b�N��������B��͏��Ɗw�Z�֒ʂ��B�����Ƃ݂ĉʂ����B���ƍ����t�˂̉e���Ŕo��Z�̂����݂�B���l��N�ďo���B���W�w�t�́x����o�ŁB�x�E�m�Ƃ̗�����������ŁB���B�����̌R���ՂŁA�V���m�E�h�E�x���W�����b�N���쌀�����ď㉉�A�t�c���̋t�ɂӂ�]���B�ϏB���ŏI��B���ꂷ�łɖS���B�Ƃ莍������B���܈�N�}�����[�ɓ��ЍL����S���B���܌ܔN���W�w�Õ��x����o�ŁB�s�E�h�Ƃ̎l�N�Ԃ̗����ɏI�~���B�ѓ��k���m��A�w�����x�ɓ���B�͂��߂Ď��l�����Ƃ������B���ܔ��N���W�w�m���x���s�B���܋�N�܌��A�a�c�z�q�ƌ����B����g��܁B�u�k�v���l�B�w�g�������W�x�����C�J��芧�s�B�i�����A�O��Z�y�[�W�j
���̙�Łu�]���v�������A���̌��ʁA�u�ϏB���ŏI��v���}���ĕ��������̂ł���B����{�鍑���R���n�d�S���A���W���E�g�����̉^���͂����ő傫���ς�����i�������́A���g�̎�ŕς����j���ƂɂȂ�B�ƂȂ�g���́A�k�����̋l�̊��Ԃōł��d�v�Ȍ�����15�N�̎��_�\�\�u�����k1960�l�N�A���W�s�m���t�ɂ���āA���͂悤�₭���ɔF�߂���悤�ɂȂ����B�v�i�q�؉��[���Ƃ̕ʂ�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����y�[�W�B���o�́s�����V���k�[���l�t1979�N5��18���j�\�\�ł�����ׂ������L�����킯�ŁA�͋Ȃ���A�ł͂Ȃ������B���Ă݂�ƁA�s�m���t�͋g���́sAmbarvalia�t�������̂��A�s���l���ւ炸�t�������̂��B
���ׂẮs�ʉp���H�Q�{���ځt335���i2021�N2���j�Ɏn�܂�B����2����{�A�s�ʉp���H�Q�{���ځt�́q�V�N�i���I��S�\�i�\�\���w��i�E�ߑ�M�ՁE�ÓT�Ёr���͂����B�����͒��؏�܍�R���N�V�����̓��W�ŁA���q�͖{��36�y�[�W�Ȃ���I�[���J���[�B���̂ݍ������������Ƃ��Ȃ������i�W�j�̏��e�ڂ��Ă��āA�����Ƃ��Ă��M�d���B����14�y�[�W�߂ɂ����������āA�����Ǝv�����B�u089�v�̏��e�Ɛ������Ɉ�������̂��B
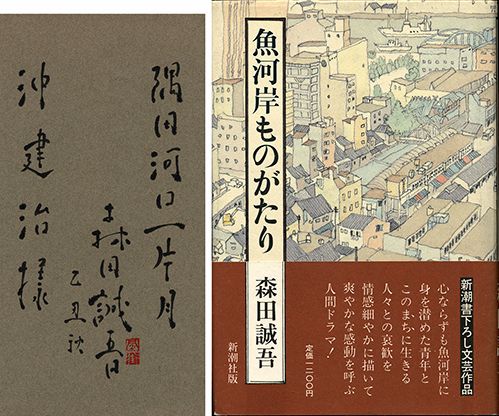
�u089�@���݂͊��̂�����^�X�c����@���Ł@�M�y�����掯��u���c�͌���Ќ��v�����������@���楈������@���؏܁@�O���V�~�@�J�o�[�E�єw�����P�@�V���Ё@��60�^1���@\13,200�v �k�o�T�F�s�ʉp���H�Q�{���ځt335���q�V�N�i���I��S�\�i�\�\���w��i�E�ߑ�M�ՁE�ÓT�Ёr�A2021�N2���A��l�y�[�W�l
�X�c�����i1925�`2008�j�́A���я����s���݂͊��̂�����t�ő�94��i1985�N�������j���؎O�\�܂���܂����B���͂��̓����g�����̑z���o���������������Ɗ肢�Ȃ���A���ɂ��ڂɂ�����@��Ȃ������B���O�̎v���ɂ����A�q�X�c���ᎁ�������i2008�N10��20���E�e�j�r�����������̂��B�ނ��s���݂͊��̂�����t�͐V�����ɔłň��ǂ��Ă����B�q�u���؏܁v���̂�����r�i�s������M���t�A���Y�t�H�A1987�j�ɋg�������o�ꂷ�邩��ł���B
�Ƃ���ŁA���������^�ԌÏ��X�͂���قǑ����Ȃ��B����ł��ߐ悪�����������ɂ���������́i���쒬�̕l���r���A�䒃�m���̌����Ѓr���A���쒬�̗��ԏ��[�r���\�\�����ɂt�o�t�̕���������������A��Â����C���F���g�̑ł��グ�Ŏ������㌒���̎p�����]�����\�\�Ȃǁj�A�_�ے��ɂ��悭�ʂ����i�V�����X�́A�Ȃ�Ƃ����Ă����������X�j�B�c�����X��M���ɁA���{�R���X�A���₫���X�A�����ʂ������Ŕ��Α����R�c���X��ᔪ���[�A�����Ă�������ʉp�����X���B�ʉp���̕i�����ɂ͈،h�̔O�������������̂��B
��f�̏��e�Ŗ��炩�Ȃ悤�ɁA���̈�{�͉������Ɍ������Ă���B�X�c����̏����{�𐔑������Ă��Ȃ��̂ŐS���ƂȂ����A�M�ŏ����̂͂���Ȃ�̌h�ӂ̕\�ꂾ�낤�i�����͂����炭����j�B�ȑO�A�a�J�E�{�v��̒������X�ŋg�����̎��W�s��ʁt�̏����{���������Ƃ�����i�����{������������A�K����Ɏ���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�B���ꂪ��͂艫�����Ɉ��Ă��n��������肾�����B�L���Ɍ�肪�Ȃ���A���o�l�̏Z����ΐF�œ悵���S����Ƌg���̎��M�������L����������蔲�������Ђ�����ł������i���������������Ƃ��낤���j�B���̂Ƃ����������Ȃ�l�������������N�Ȃ̂��A�C�ɂ͂Ȃ������A�������蒲�ׂ������ł킩��͂����Ȃ������B�����֗��āA���x�́s���݂͊��̂�����t�̌���E�������̏����{�ł���B�g���ƐX�c�̌�F�W��ɉ������サ���킯�����A��������}���ق̏����������������Ă��A���҂Ƃ��Ă͏o�Ă��Ȃ��B�ƂȂ�ƁA�g�����ւ��̂���A�X�c����̐��Ƃ������o�ōL���W�̐l���Ȃ̂��낤���B�����v�����A�O�̂��߂Ɂs���{�̌Ö{���t�Ō������Ă݂�ƁA�������X�̃y�[�W��
���_�Ɨt��
\16,500
�������� �y������9�s �u�N���M�S�Ɉ��ǂ��ĉ�����R �V���ł��o����T�C�����đ����ďグ�܂��傤�v�u�l�͖Z�����̂ł낭�ɕԎ��������Ȃ�����ǁA����ł��悩�������B�ւ���������B�l�����N����ɂ͑嗢�s�ɏZ��ł�����������o�b�e���E�E�v�����t���Y
�Ƃ���ł͂Ȃ����i���P�j�B�܂����⒆�����X�ł���B���_���i1898�`1983�j�́s���_�ہt�i1926�j��s�^�k�W���K�[�l�̊�t�i1928�j�A�s���������Ёt�i1935�j�ȂǂŒm���鏭�N�����̑��l���i���Q�j�B���̍��_�̖{�̈��ǎ҂ŁA��B�i�k��B�s�H�j�ɏZ��ł��āA�X�c�Ƌg�����ߖڂƂȂ鎩���i�����Ⓖ�؎O�\�܁A�����ⓡ���L�O�����܍�j�����悷�鉫�����Ȃ�l���́A���������N�Ȃ̂��B�T���͎n�܂�������ł���B
�k2021�N3��31���NjL�l
���_�ƍ�i�ɐG�ꂽ���Ƃ��Ȃ������̂ŁA�u�k�Ђ́k���N��y�����Ɂl�ōĊ����ꂽ�s���������Ёt�i1975�N10��16���j��ǂB�ӂ��̈Ӗ��ŋ������B�ЂƂ͏��������̓ǎ҂ł��鏭�N�i�⏭���j�����̊��x�̍D���ł���A�����ЂƂ͂���40�N��ɍĊ����ꂽ�{���A����ɂ���46�N��ł��y���߂����Ƃ��B���Ȃ݂Ɂs���������Ёt�̏��o�́s���N��y���t1935�N1�����`12�����A�ځB���ł͑���{�Y燘��u�k�ЁA1935�N11��10�����B���t���炷��A�A�ڊ����Ɠ����̏o�łƂ������ƂɂȂ�B�����āA���_�ƍ�i�̐l�C�̂قǂ�����������B

���_�Ɓs���������Ёt�i�����F����{�Y燘��u�k�ЁA1935�j�����������k���������ŏ��N��y������S�W�l�i�u�k�ЁA1970�N5��30���j�̕\���ƃW���P�b�g�k��F�ɓ���v���l
���āA�{���́q�������Ȏҁm�������́n�r�̈�߂ɂ�������i�ӂ肪�Ȃ��ꕔ�A�ȗ������j�B
�@�u���b�A�a�l�A�ǂ��Ȃ����܂����H�v
�@�ԋS�k�]����̉Ɨ��l�͂т����肵�Ėڂ��݂͂�B���A�]����m�������������n�͂���ɓ����Ȃ��ŁA�Z�e�m�s�X�g���n���s�^���ƓV��Ɍ�����ƁA�����Ȃ�Ԃ����܂����B
�@�S�I�b�A�r���r���b�ƁA�ӂ��܂��q���ӂ�킹�āA�Ђт��킽�����̂͂��̂������e���ꔭ�I�@�₪�ďɉ����������ƁA�V��̔������ؖڂ��A�ނ���ɑł���ʂ����e���̂�Ԃꌊ����A�A�b�A�J����̂��Ƃ̂悤�ɁA����܂ɂɂ��ݏo��܂����Ȍ������I�@�]����͂�����ɂ��ŁA�����j�ɗ₽�������ׂ܂����B�i�s���������Ёk���N��y�����Ɂl�t�A���Z�E����y�[�W�j
���l�̋A�ƌ��������܂ł����A�g�������̓ǎ҂́q�m���r�i�C�E8�j�́u2�v��z�킸�ɂ͂����Ȃ����낤�B
�l�l�̑m��
�߂��߂��̖��߂ɂ͂���
���l�`�����낵
���ɖċ����f��
��l����l�̓�������
����l���F����
���̈�l����������Ƃ�
�[��̐l�����牟���悹�镪�̍^��
�l�l�����������ɗ���������
�s��̎l�̃A���u����
�������ǂƓV�䒣��
�����Ɍ���������
�J���ӂ肾��
�s���������Ёt�̏��������A�g���͖�16�B�㏑�o�ŁE��R���ɕ������2�N�߁A���łɏ��N�����Ɏ䂩���N��ł͂Ȃ��B�������ꂾ���炱���A�s�u�k�S�W�t���]�ː에���̏��N���ɐe���������������ŁA�{������ɂ��Ȃ������Ƃ͂�����Ȃ��B�����Ƃ��g�����́A���_�Ƃɂ��ĂȂɂ������̂����Ă��Ȃ��̂�����ǁB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@���̌�A�������X����w�������̂����̂͂����B
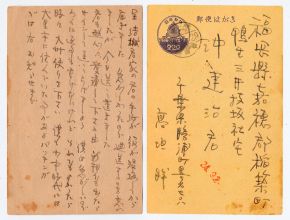
2�~�̗X�ւ͂����@�m����n���Y�@24 8 29�k1949�N8��29���l
�m�����ʁn
�����p��S��z��
�����@�O��Z��Б�
�@�������N
�@�@��t�����Y���n�����Z��
�@�@���_�@��
�m���ʁn
��@����N���̌N�̎莆���@�ނ��A�₵�Ă���
�͂��܂����@�}�����������̂ʼn�������̂�Y��
�܂������@���������Ēu���܂���
�N���M�S�Ɉ�椂��ĉ�����R�@�V���ł��o����
�T�C�����đ����ďグ�܂��傤�@�l�͋}�������̂�
�낭�ɕԎ��������Ȃ�����ǁ@����ł��悩������
���X�@��B�ւ���������@�l�����N����ɂ�
�嗢�s�ɏZ��ł�����������o�b�e���K
�ł͉E���m�点�܂�
�i���Q�j�@���_�Ƃ̏����́A1975�`76�N�ɂ����āA3�тƂ��u�k�Ђ́k���N��y�����Ɂl�ōĊ�����Ă���B�W���P�b�g�̑��Ɂu���̕��ɂɂ́A���\������҂ƂƂ��ɏ�M�����߂č�i������ꂽ���攌�̑}�G���ł��邩���葽�����^���܂����B�v�Ƃ���Ƃ���A���̎�̏����͑}�G����i�̈�ۂ����肷��Ƃ����Ă������B���_�́s�^�k�W���K�[�l�̊�k���N��y�����Ɂl�t�i�u�k�ЁA1975�N12��16���j�̂��߂̌�L�ŁA�u�}�G�͈ɓ��F���N�B���ꂪ�܂��A�O���ɂ����{�ɂ������悤�ȁA�Õ������M�C�̂قƂ���悤�ȁA�܂������Ɠ��̃^�b�`�̊G�������̂ŁA����͂��̑}�G�ł��������É��Ŗ����I�m�ނ���Ă��n�ȉA�e��Z�������B�^���ꂪ�܂������̓ǎ҂����ɎɎ��悤�ŁA�\�N�߂����������Ȃ��A�M��ȃI�[���h���t�@���̕��X���炨������������������A�킴�킴���Y�̌��݂̏���։�ɗ��Ă���������X��������قǂ��B�v�i�����A�܃y�[�W�j�Ɖ�ڂ��Ă���B�ɓ��F���i1904�`2004�j��90�N�O�̊۔����L�ƈ����ׂ����A�۔����L������̈ɓ��F���ƌĂԂׂ����B���̊G�̂͂�ދْ����͖��ނł���B
����A���ɂ����Ă�����i�Ƃ����Ε������͂������A��ɂ���ĒT���������Ă����ɂ����Ȃ��j�A�R�N�����u�t-11 B5S�v�Ƃ����s���N�F�̃t���b�g�t�@�C���i�^�C�g���́q�y���F��@1987�r�j�ɁA�g�����̕]�`�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�Ɋւ���R�s�[���Ԃ����Ă���̂��o�Ă����B���e�́A�����s�y���F��t�̏��o���̃R�s�[�ɒ�e�`�Ƃ̈ٓ���Ԏ��ŏ��������́A���̑��ł���B�܂��A���̑��̕����猩�悤�B���́s�y���F��t�́u���ő����v�i1987�N9��30���j�Ɠ��u���ő����v�i1987�N12��10���j���������Ă���i�u���ő�O���v�ȍ~�͌������Ƃ��Ȃ��j�B�����ł�����Ƙe���Ɉ���B���ĕ��i���F������̖^���ƒk���Ă��邤���ɁA���i�{�̏����̂��ƂɂȂ����B�����܂ł��Ȃ����i�̒���_���́A�g���̂���̐��{�ɋy�ԁB�N���������ւ�ł��傤�A�Ǝ���������ƁA�ł������b�ł�����悤�Ɂu���ɔł́s���̉ԁt�̍���̈Ⴄ�{���W�߂Ă��܂��v�Ƃ̂��Ƃ������B����͖ڂ̒������������B�s���̉ԁt�̐V�����ɂ́A���������i�{�ōŏ��ɕ��ɂɓ������͂������A�s���̂����݁t��s���̓��t���V�����ɂ̃J�^���O����Ȃ��Ȃ��Ă������̂тĂ���i�����炭�͗B��́j���i�{�̃����O�Z���[�ł���B�����̊O���̓O���V���|���̌Õ��ȃX�^�C���ŁA���̌�A�W���P�b�g���ɂȂ�i�ߔN�͌���ɏ��M�̉�I�j�A�{���������̊��ň������A�ʐA�E�I�t�Z�b�g����ɕς���Ă���B���ɂł�������͂���Ȃ�̒l�i���낤���A����ȍ~�̍���Ȃ�100�~�ψ�ɕ���ł��Ă����������Ȃ��B���̂��ׂĂ̍���𑵂����Ƃ���Ő��\�������A�����͂Ƃ��������A�����̔N��������s���̉ԁt�̎�e���ՂÂ�����i��������Ȃ��j�B�c�O�Ȃ���A�g���ɂ͕��i�́s���̉ԁt�ɑ��������i�͑��݂��Ȃ��B�Ƃ������A���������P���̕��ɖ{���ȈՐ��{�̂`�U���̑p�����Ȃ��i���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�́k�����܊w�|���Ɂl��������҂���j�B���͎v���Ђ́s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t��100�~�ψ�ɂ���Ζ��킸�w�����Ă��邪�A�ŋ߂ł͂�����������Ȃ��Ȃ����i�����ő厖�ɂ��Ă���̂́A�g�����̏������菉�łƋg���������N��Ɉ��Ă�6����{�j�B�b���s�y���F��t�ɖ߂��A�u���ő����v�́A�������݂̂����Œʓǂ���ɂ͓ǂ݂ɂ����Ȃ�A�ҏW�S���̒W�J�~�ꂳ��Ɩʎ����ł��Ă���A�u���ő����v�̓ǎ҃n�K�L�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���i���̃R�s�[���A�t�@�C������Ă����u���̑��v�j�B
�i�{���ɂ��Ă̂����z�����������������B�j
���s��A�����ǂ݁A'88�N1���A�_�˂̑���Y���̌����k���F����Y�����������쐬�́y�N�\�z�ɂ���u1987�N12���A�A�X�x�X�g�َ�ÁA�_�˃V�A�^�[�|�V�F�b�g�فu�ِl�║�����z���Ƃ��炾�v�i���́E�Ս��o���j�ɎQ���B�v�����ꂾ�낤�l�ɂ͐V�����̎Ԓ��œǂݕԂ��A���̌�����������ǂ݂܂����B�s�_��I�Ȏ���̎��t�ɂ��ē��l���̉��ɏ��������̂�����܂��̂ŁA�ip.4-6������j�������܂��B�i�g������ɂ������肵�Ă���܂��B�j�悢�{�����肪�Ƃ��������܂��B
�s�y���F��t�̏��o�`�ق��́A���̂Ƃ���B����ȉ��́A�s�y���F��t�ł̕W��B

���l�����s�i�فt7���i1985�N6��25���j�̕\���A�����ǗY�E�o�Ӗ앶�q�ҁs�o���e���X�t�i�����ЁA1986�N6��20���j�Ƌg�����s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A�u���ő����v1987�N12��10���k�u���ő����v1987�N9��30���l�j�̃W���P�b�g
�@A �o���`���X�̊G���ςɂ䂭�A�ā\�\�i���L�j84�N���i�s�i�فt7���A1985�N6��25���j�@���@83 �o���`���X�̊G���ςɂ䂭�A�ā\�\�q���L�r�P�X�W�S�N���
�@B ���_�̂��Ƃ��\�\�����i�s���㎍�蒟�t1986�N3�����j�@���@107 ���_�̂��Ƃ��\�\����
�@C �_���Ռ����i�s�����C�J�t1986�N3�����j�@���@98 �_���Ռ���
�@D �o���e���X�̊G���ςɂ䂭�A�āi���L�j84�N���i�����ǗY�E�o�Ӗ앶�q�ҁs�o���e���X�t�����ЁA1986�N6��20���k�q�����АV���j���[�X�rNo.490�ɂ́u�����̐}�łƊe�E��苐���Ɋ�ꂽ�I�}�[�W���ł����ēW�J�����o���e���X�̑S�e�B���s�v�c���Ƈ��G���K�����ɂƂ����₷���l�ɂ́A���܂�Ȃ����͓I�Ȗ{�ł���B�v�Ƃ���l�j
�@E ���{�̎R���̈��i�s�����܁t��191���A1987�N2���j�@���@76 ���{�̎R���̈��
A�́q�o���`���X�̊G���ςɂ䂭�A�ā\�\�i���L�j84�N���r�́s�i�فt7���i�����̓��W�́u�莆��`�v�j�́kessais critiques�l���Ɍf�ڂ��ꂽ���J���̕��́B�Ƃ������A�����ǂ���A1984�N7��2���i���j����19���i�j�ɂ����Ă̋g�����̓��L�ŁA���̒��S�I�ȃC���F���g�́A7��11���i���j�̋��s�s���p�قŊς��s�o���`���X�W�t�ł���B����ɉs�����������̂�D�̕ҎҁE�����ǗY�ŁA�s�o���e���X�t�́q���Ƃ����r�ɂ́u��㔪�l�N�Z�����玵���ɂ����ċ��s�ōs�Ȃ�ꂽ�W������@��ɏ����ꂽ���͂͐��������A���̂Ȃ����玟�̘Z�_��I�B�^�X���z�u�o���e���X�A�ʂ�̌��������̕��i�v�A�����q���u�\��\�፷���\���\�\��v�A�w�A�[���E���B���@���x12���A��㔪�l�N�l���B
�^���c���F�u���ՓI�ŁA���тȂ������v�A�푺�G�O�u�i���ɒʉ߂����Ɓv�A�w�A�[�g'84�x�A��Z�����A��㔪�l�N�\���B�^������b�q�u�s�X�H�t�̃f�B�A�[�i�ƃA�N�^�C�I�[���v�A�w�ӂ�x��㔪�l�N�������B�^�g�����k�c�c�l�v�i�����A��O���y�[�W�j�Ƃ���B���p�G����s�ӂ�t�͂Ƃ������A�Ⴂ���l�����̓��l���ɂ܂Ŗڂ�z���Ă����̂��Ƌ������A�l���Ă݂�Έ����ǗY�́s�i�فt���l�̏��Y���P�̉��t������A���Y�̂����ЂƂ�̎t�ł���g�������o���`���X�^�o���e���X�i�����͂�����̕\�L���̂邽�߁A�g�����͓����ł̓^�C�g�����܂߂āu�o���e���X�v�ƂȂ��Ă���j�̊G�ɂ��ď��������͂������ɑ������ƂāA�Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��B�����̂����A�u7��11���v���̍Z�ق��f����B���ƂȂ�A��D����сs�y���F��t�iH�Ɨ��L�j�ŕύX���ꂽ�ꍇ�A�yA �c�c��D �c�c��H �c�c�z�ƕ\�L����B
�@�yA 7��11����D H �����\����z�@���B���c��v�̎�����m��B�������F��B��\���N�O�A�yA ����D ������H ���z��x�A���������B�������ʂ��̂����ƁA���������j���ł���B����ւ��Ă����Ԃ��A�yA �R�z�d�ԁi�H�j��D H �R�A���z���yA ����D �Ƃ���H ���z����ʉ߁B��������B�Ⴂ�A���́A�������܂ŋN���Ă����������B�ЂƂ�ʎ��ŐQ���āA�悩�����Ǝv���B�܂��l�e���Ȃ��n��������A�^�N�V�[���ɕ��悵�A�O���䒬�֏o��B�C�m�_�R�[�q�[�{�X�͂������ɕ��i������B��������߁A�R�[�q�[���̂ށB���x�̗��̖ړI�\�\�s���p�قōÂ���Ă���A�o���yA �`��D �e��H �`�z���X�W���ς�B�yA �܂���D �i�g���j��H �܂��z�ߑO���Ȃ̂ŁA���G���Ȃ��A�������ςĉ��B�yA �����ā�D H ���āz�A�}�łŌ����yA �u�X�v��D �s�X�H�t��H �u�X�v�z��yA �u�M�^�[�̃��b�X���v��D �s�M�^�[�̃��b�X���t��H �u�M�^�[�̃��b�X���v�z�yA �A��D �i�g���j��H �A�z�yA �u���v��D �s���t��H �u���v�z�Ɉ˂��āA�������ꂽ��Ƃ̍�i�������ɍ݂�B�yA �u�X�v��D �s�X�H�t��H �u�X�v�z�͂Ȃ����A����ɁyA ��G��D H �C�G�z����yA �u�R�����X�E�T���^���h�����H�v��D �s�R�����X�E�T���E�^���h�����H�t��H �u�R�����X�E�T���^���h�����H�v�z����̑O�ɂ���A�yA �u�M�^�[�̃��b�X���v��D �s�M�^�[�̃��b�X���t���u�M�^�[�̃��b�X���v�z�͂Ȃ����A�͍�yA �u�����v��D �s�����t���u�����v�z�ŁA�[�������ł���B�ё���̌���yA �u�A���h���E�h�����̏ё��v��D �s�A���h���E�h�����̏ё��t��H �u�A���h���E�h�����̏ё��v�z�͂Ȃ����A�ނ���A�������yA �u�z�A���E�~���Ƃ��̖��h�����X�v��D �s�z�A���E�~���Ƃ��̖��h�����X�t��H �u�z�A���E�~���Ƃ��̖��h�����X�v�z������ł͂Ȃ����B�yA �u�����v��D �s�����t��H �u�����v�z��yA �u�q�������v��D �s�q�������t��H �u�q�������v�z�A�yA ����D ���́�H ���z�J���ɖ��鏭���ƁA�l���œǏ����鏭���́yA �u�q�ԁv��D �s�q�ԁt��H �u�q�ԁv�z������B�y���F�����Q�̐����A���������Ă���B����ȁyA �u�R�i�āj�v��D �s�R�i�āj�t��H �u�R�i�āj�v�z�̓��������悢���A�yA �u���������X�v��D �s���������X�t��H �u���������X�v�z�̓T��ł����F���͐[���B�苾�Ɍ�����yA D �Ⴂ������H �����z�́u�Áv�ƁyA �g爐��D ���F��H �g�F�z�d�����ׂ锼���̒j�́u���v�̑Δ�B�܂������A�薼�̂悤�Ɂu�����������v���������o����Ă���悤�Ɏv���B�\�\�O�֏o��ƁA�z���܂Ԃ����A���߁B��T���̉��O�w�^�N�V�[�𑖂点��B���̐����ʂ�����~�ɏ��A�yA D ����H �i�g���j�z���������ƃr�[���ŁA�o���yA �`��D �e��H �`�z���X�̊G��b��ɂ���B�t������ɐÂ܂�r�B�������A�F�̐S�͍V�g���Ă���悤���B�������@�̉Ԃ��yA D ࠁ�H �s�z���Ă���悤�ɁB��A�O�g�̋q�����Ȃ��A�������낮�B����炢�����������悤�ƁA�������։��B�����Ă��u����v�̖ؑg�݂̑��`���ɂ͋����B���X�ł��r�[���̊��t�ƂȂ�B���R�A�F��M��̃t�����X���w����̗F�l�̎Ⴂ�������ʂ肩����A�ꏏ�ɂȂ�B���ꂩ��ؔ��a�}�̗U���ŁA�_���̌��P�Ŋ���A�����q�Ŋ��g���ǂ��H�ׂ�B�u�S�v���u���v���[���B�������yA ���ꁨD �N��H ����z������J���Ă���悤���B
�������T�ς���ɁAA�͂����炭�g�����̏��������e�̂Ƃ���Ɂi�f�ڎ��̕ҏW���͍Z�{�����Ɂj�g��ł���B���Əo�ŕ��Ȃ�A�u�R�z�d�ԁi�H�j�v�͕ҏW�҂�Z���҂��s���Z�{�̑Ώۂł���A�X���[���邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B�u�g爐�v��uࠁv�͂����炭�g�������̂悤�ɏ������̂��낤�i�g�����̎��M���Ȃɂ́A�������������݂���j�BD�͔Ō��̔����Ёi�����́q���Ƃ����r�ɂ��A�S���҂͎R�{�N�j�̃n�E�X���[���Ɓs�o���e���X�t�̕Ҏ҂̈ӌ������������ʁA�u�g爐�v�́u���F�v�ɁA�e��i���́u�@�v�ł͂Ȃ��A�s�@�t�Ŋ����Ă���B���o���́u�X�v�i�s�o���`���X�W�J�^���O�t�ł�����j���s�X�H�t�ƂȂ����̂́A�s�o���e���X�t���̗p���������q�o���e���X��i�֗��r�̖M��薼�ɍ��킹�����߂��낤�B�g���́A�����炭�s�y���F��t�̒��ҍZ���ŁA�u�Ⴂ�����v���u�����v�ɒ������B����ɂ��A�����܂ł̃o���`���X�̊G�̐l���ɂ������������āA���͂̍Ō�ɓo�ꂷ��u�F��M��̃t�����X���w����̗F�l�̎Ⴂ�����m�A�A�A�A�n�v�Ƃ͋�����u�����ƂɂȂ����B�v����ɁA���e�Ɋւ��������D�łقƂ�ǏI����Ă���B��e��H�ł͍�i�����u�@�v�Ŋ�������ɖ߂��AD�́s�X�H�t���u�X�v�Ɓi�u���āA�}�łŌ����v�Ƃ��̑薼�Ɂj�߂����B�u�����������v���u���������v�Ƃ����̂́A�G�߂��炢���Ă��A�����Ȏ���ꂾ�낤�B
 �@
�@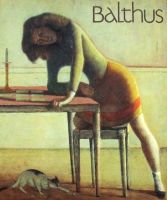
�s�o���`���X�W�t�i���F���s�s���p�فA����F1984�N6��17���`7��22���j�̃|�X�^�[ �k��i�͖��ʁq�R�����X�E�T���E�^���h�����H�r�i1952-54�j�l�i���j�ƍ��K�G���i�ďC�j�E���s�����ߑ���p�فE�����V���Ёi�ҏW�j�s�o���`���X�W�J�^���O�t�i�����V���ЁAc1984�k�N6��17���l�j�̕\�� �k��i�͖��ʁq�p�V�A���X�V�сr�i1954-55�j�l�i�E�j
B�́q���_�̂��Ƃ��\�\�����r�͏��o�̎G���f�ڌ`�Ɓs�y���F��t�̒�e�`�Ƃ̊Ԃɂ́A�\�L��̓���̂ق��́A�قƂ�Ljٓ����Ȃ��B���ڂ��ׂ��͎��̓�ӏ��B
�@�@B �u������ܒf���сv��H �u������ܒf�����сv
�@�@B �u�ˁv��H �u�M�r�v
���āu������ܒf���сv�́A���Ắq������܌�b�сr�i�G�E8�j���甭�z���ꂽ����ƌ���ׂ����낤�B�u�ˁv��1985�N9��30���́A�u�M�r�v�͓��N3��31���̋g���́q���L�r�ɂ��o�ꂷ��B���o�̏����ԈႢ�������Y�q�����ؒ��h�ɂł��i����Ƃ��ҏW�S���̒W�J�~�ꂩ�j�w�E���ꂽ���B�q�����r���M�̌o�܂́A�s�y���F��t�́q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�́u3�v�ɏڂ����i�����A��O�܃y�[�W�j�B����A���o�̃R�s�[�����߂Ėڂɂ��āA���銴�S�ɂƂ��ꂽ�B����́A�g���̒����̑Ό��y�[�W�Ɍf����ꂽ�O�D�L��Y�̒����q�y���F�𓉂ށr�̌��тł���B
�k�c�c�l�Í��Ƃ͐����邱�Ƃ̎����̐[�������ɂ�����錾�t�̂悤�Ɏ��ɂ͎v���܂��B���I�Ȕ����͎Ƃ鑤�̌��ɉ����ĉ��߂��ꏟ���Ő[�ǂ݂������܂����A���͎��Ȃ�Ɋ��ĂЂƂ̌��t����������Ǝv�����̂ł��B����́A���ɂƂ��Ď����܂����ɂ̌��t�Ɏ��낤�Ƃ���ӎu�̕\���ɂق��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����g�ɂނ����Ă����������������錾�t�ł���܂��B
�@���ꐶ�ꐶ��Đ��m���傤�n�̎n�߂ɈÂ�
�@���Ɏ��Ɏ���Ŏ��̏I��ɖ��m����n��
����͋�C�̔鑠���o�̏��ɓ�����̍Ō�ɒu���ꂽ����ł���܂��B
�F����A���炩�ɖ����ĉ������B�i�s���㎍�蒟�t1986�N3�����A�k�y�[�W�l�j
�����ŔO�̂��߂ɕ⑫���Ă����A�g����
�@�@((����@����@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����āi���m���悤�n�j�̎n�߂ɈÂ�))
�Ƌ�C�����p�������сq�C�g�r�i�J�E19�j�\�����̂́A�O�D�̒����ɐ旧��1983�N6���̂��Ƃ������B���̂Ƃ��̎O�D�̔]���ɂ́A�g��������reminiscence���������Ă������B
C�́q�_���Ռ����r�����o�̎G���f�ڌ`�Ɓs�y���F��t�̒�e�`�Ƃ̊Ԃɂ́A�\�L��̓���̂ق��́A��������ٓ����Ȃ��B���ڂ��ׂ��͎��̓�ӏ��B
�@�@�y���F�́kC �V�����\����H �V�������E�g���l�́u�u���v�l����ȏ��]���āA�Â��ɂ�����Ă����B
�@�@��̑O�ɁA�ςݏグ��ꂽ�悤�ȁkC �i�i�V�j��H �Ǝ��́l��̊�i�ƁA���J�쓙���̉��G�Ő��ɒm���Ă���B
����ɂ������Ĉ�ۓI�Ȃ̂��A���̎����ł���B�����́u���P�X�W�T�N�Ă̂��ƁB�v�̏��o�`�͏������ł����������B�u�����̋_���Ղ̗��͍�N�̉Ă̂��ƁB���̑O�N�̉āA�y���F�Ƌ��s�Ɂu�o���`���X�W�v���ςɍs���Ă���B������x�Ɠy���F�Ɨ������邱�Ƃ͂Ȃ��B�v�i�s�����C�J�t1986�N3�����A�܌܃y�[�W�j�B�g�����͂ӂ���A���̎U���ɂ����ăp�Z�e�B�b�N�ɂȂ邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ������B�����A���o�`�́u������x�Ɠy���F�Ɨ������邱�Ƃ͂Ȃ��B�v�Ƃ����ꕶ�́q�Ǔ����y���F�r�̖{�������ꂾ�����悤�ŁA�G���f�ڎ��ɂ͂���͂���ňӖ����������B������ɁA�s�y���F��t�͑S�т��q�Ǔ����y���F�r�Ȃ̂�����A�Ȃ����͓̂K�ȑ[�u�Ƃ����悤�B
E�́q���{�̎R���̈��r�́A���o�̎G���i�s�����܁t��191���A1987�N2���j�f�ڌ`�Ɓs�y���F��t�̒�e�`�Ƃ̊Ԃɂ́A�\�L��̓�����������̒���������������BE��H�̒�e�`�Ƃ̊Ԃ̈ٓ����ꕶ�̒P�ʂŒ��o���āA���Y�ӏ����y�c�c���c�c�z�Ŏ����B�Ȃ��A�F�V�Ƒ���̖��O�i�����̖��̕��j�̋����̈ٓ��͊����B
�@�@�Ȃɂ������́A�ɓ����y�i�i�V�j�����q�z�̋����Ƃ̂��Ƃ������B
�@�@���R�r���Y�ƈ���r�q�Ƃ���ɂ���̂��������̂ŁA���ƍȁy�����́z�Ő��̒�֏o���B
�@�@����`�����ƈ���r�q���������^��A�y⍁����z�ׂ��肩�����������ӂ�܂����B
�@�@�܂��N�y�ꁨ�i�g���j�z�����A�뉀�̎����͂ǂ����Ă���̂��A�ƕ�������A�ɓ����̒�t�v�w�������p���ŁA�~�n���ɏZ�܂킵�Ă���Ƃ�������A���̉Ƃ̍��s���͐����Ēm��ׂ��A�Ƃ����Ƃ��낾�B
�@�@�u�������낻���ˁv�ƌ����Ȃ��炱�̎R���̕���l�����y�����i�g���j�z�̐Ȃ���������̂������B���R�r���Y�͐��y�i�i�V�j�����z�Ԃ�Ă��܂������A�C���������ꂽ�푺�G�O�v�ȁA�O�D�v�l�A����r�q�Ǝ������́A�₦��������فX�ƐH�ׂ��B
�@�@���X�Ɠ����y�҂͖������ɁA���𗹂����҂��z��C���Ė߂��Ă���B�o�X�^�I���ꖇ�ŁA�����獘�܂ŕ��ŁA�₦�����ւ̃\�t�@�[�ɐQ�Ă��܂����A�����z�q�̓V�^ࣖ��Ȏp�ɁA�N�y�ꁨ�i�g���j�z�����y�S�́��i�g���j�z�₷�炬�����o�����y�悤�����i�g���j�z�B
�@�@���˂Ă���A���̃K�j���̌^�ɋ����������Ă���y���F�́A�u�y�g�������V�I�J�z������ĕ��C�ɓ���A�K�̌���v�Ɛ錾���Ă���̂ŁA������Ȃ��Ă����B�܂��y�����i�g���j�z�����͂��܂����������݂āA��l�œ��ɐZ�邱�Ƃ��o�����B
�@�@�y��ȂɁ��ǂ��ɂ��z���̎p�������Ȃ��̂��A���Ԃ����������ė����������B
�@�@�����v�l�͐Q���Ȃ��ƌ����āA�y���́��܂��z�Ȃɉ�������B
�����āA�����\�\�B
�@�@�y�i�悵�����E�݂̂�@���l�j�����P�X�W�R�N�T��15���̂��ƁB�z
�g���́k���Y���P�E��������E�g�����i�Q�X�g�j�̑Θb��]�l�q��b���Șc�݂̖��́r�i�s�����C�J�t1987�N11�����j�ŐV���́s�y���F��t���M�̔w�i�����̂悤�Ɍ���Ă���B
�����@�k�c�c�l���̂ւ�ŁA�g�������Ȃ����Ă��邨�d���ɂ��āA������Ƃ��f����������ł����ǁB
�g���@�l�͋��N�̉Ă���A����Ƃ��͒��f���Ȃ�����w�y���F��x�Ƃ����A�y��������]������̂�����̖{�ɂ܂Ƃ߂Ă�����ł���B����͋��N�̉Ăɏ������܂��āA�����ƂĂ������Ȃ��Ƃ����C�ɂȂ��ĕ������Ă�����A�o�ŎЂ̊��ɒʂ��Ă��܂��āA�ǂ����Ă���炴������Ȃ��Ȃ���������i�j�B�ł����N�͑S�R���Ȃ��āA���N�̎O�����炢����܂���肾�����̂ˁB�ł��l�́A�������̂Ƃ����̂͂����炭�����Ȃ��Ǝv�������A�ǂ�����ď������炢����������Ȃ��Ă��낢��l���܂�����B�ŁA�y���Ƃ̌𗬂Ƃ����̂͂��̂��������邩��A�܂����L�ׂĔ����o���čs�����́B���̓��L�𒆐S�ɂ��āA����ɓ�����̐l�����̏،��Ƃ������A�y���̗x���s���ɂ��ď����ꂽ���͂��ł��邾���T���Ă��āA��������p����B���Ƃ́A�y���F���g�̌��t�Ƃ������ƂŁA���̎O�ō\�����Ă�������ł��ˁB���L�𒆐S�ɂ�����ŁA�ނƂ̏o�����n�܂��Ď��Ԃ����[���Ɨ���Ă����āA���R�̂̏��q�ɂȂ�A�������W�J���čs�����̂ˁB
�����@�������S���Ō��e�p����܁Z���ł������H�@�����ł���ˁB
�g���@�l�����ŏ������͈̂�Ԓ����̂ŏ\�Z�����炢�ŁA���ꂪ�l�̌��E���������ǁi�j�A�Ȃ��ē��L������܂�����ˁB���Ƃ͐l�̌��t�𒊏o���A�y���F�̌��t���E���A�܂��Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ǝv�����ˁB���ꂪ�A���ƔłƂ������ȏo�ŕ��������甪�Z�y�[�W���炢�̏����q�ł����낤���ǁA�}�����[�Ȃ�ł����������Ȃ��Ȃ�������āB����ς�{�ɂȂ�̍قƂ����̂�����܂�����ˁB�i�����A��ܘZ�`����y�[�W�j
�g���́u�ł����N�k1986�N�l�͑S�R���Ȃ��āA���N�k1987�N�l�̎O�����炢����܂���肾�����̂ˁB�v�Ƃ��������́A�����炭�q���{�̎R���̈��r��1987�N���߂ɏ������Ƃɂ���āA�s�y���F��t�̏������낵�̕����\�\���g�́u���L�v��y���F���܂ޑ��҂̕��͂́u���p�v�ȊO�\�\�̒��q�m�g�[���n������ŁA���M�ɒe�݂��������̂Ɛ���������i���j�B�g���͂���ȍ~�A�s�y���F��t���\�����镶�͂��G�����ɔ��\���邱�ƂȂ��A���ׂĂ����̏������낵�ɒ������ƂɂȂ�B
�Ō�ɁA��f�����Z���i�Z�فA�ł͂Ȃ��j���Ă������B�u�C�m�_�R�[�q�[�v�́A�������́u�C�m�_�R�[�q�v�B�T�a�c���i1949�`�@�j�͂��̃o���G�e�B�u�b�N�s�G���Ɉ�Ă�ꂽ���N�t�i���E�ЁA2018�N11��30���j�Ől�i1956�`�@�j�Ƌi���X���e�[�}�ɑΒk�����Ă���B�肵�āq�J�t�F���i���X�����炢�̂��I�r�i���o�́s�{�̎G���t2010�N11�����j�B
���@����_�͑S�ʓI�ɃR�[�q�[�̃��x���������Ǝv���B�_�˂̘V�܂́u�ɂ��ނ�����v���D���ł��B�������Â��킯�ł͂Ȃ����ǁA���[�j���O����������t���Ă�̂������ł��ˁB
�T�a�c�@�u�C�m�_�R�[�q�v���Ɛ�͉����ׂ��ł��������H
���@�l�̓r�[�t�J�c�T���h���D���Ȃ�ł���B
�T�a�c�@�������̓T���h�C�b�`������������ł���ˁB���ƁA�i�|���^�����A���j���[�̖��O�̓X�p�Q�e�B�C�^���A���Ȃ́B
���@�z���C�g�\�[�X���̂���{���Z�i���Ă����B�Ӗ���u������A�C�^���A�̌��Y��ȓs�s�̖��O�����āB�k�C�m�_�R�[�q���l�����w�̑�ۂ̏�ɂł�������Ȃ��ł����B���܂Ƀ{���Z�i���Փ��I�ɐH�������Ȃ�Ƃ����ɍs���i�j�B
�T�a�c�@�C�m�_�̃i�|���^���͐�i�ł���B���{�ɂ����Ȃ��i�|���^�����āA�ꎞ���o�J�ɂ���܂�����ˁB�p�X�^����Ȃ��ăX�p�Q�e�B����̈╨���āB
���@���i�|���^���������Ă܂���ˁB�Ⴂ�q���킴�킴�H�ׂɍs���Ƃ��B�i�|���^���݂����ȋi���т��Ă����ƃs�U���ȁB�����ƑO����������L�����e�B�Ƃ��ɂ͂������낤���ǁA�l��̂Ƃ���ɍ~��Ă����̂́u�W���[�v�ł���ˁB�i�����A����y�[�W�j
���Ȃ݂ɁA���͂܂��C�m�_�R�[�q�ɍs�������Ƃ��Ȃ��B���s�ɂ��A�����ɂ��B
�����\����@���B���������ɋN��B�z�q�̓n���h�o�b�O��̌y���ŁA�o���`���X�W���ςɋ��s�֍s���B�Ӑ}��悵�A�Г������ꖜ���~���⏕����B�ߌォ��V�h�̊X������B�[���B�a�J�֖߂�g�b�v�ŃR�[�q�[�B�_��̖F���ŐH���B��\���߂��A�z�q�ЂƂ藷����߂�B�܂��A�C�m�_�R�[�q�[�{�X�֍s���A�R�[�q�[�ƃT���h�C�b�`�̂Ђ�߂��B���ꂩ��A�o���`���X�̊G�̂����������A��������ς��Ƃ����B���߂Ă̌o������ŁA�����������炵���A�[��܂ŁA���s�̈���ƃo���`���X�̊G�̂��Ƃ��A���Â���B�݂₰�̉_���́A�����̒��̒������B�i�s�y���F��t�A��Z��y�[�W�j
D�ł̓n�E�X���[���Ɋ�Â��\�L�̕ύX�������邪�A�����̈Ⴂ�͂Ȃ��̂ŁA��f���L�̍Z�ق̌��ʂ͏ȗ������B��̓I�ɂ́AA��H�ł͓��t�̏��������ς���������i�A���r�A�������������j�B���Ȃ킿�A�g����D�̉��ς�F�߂Ȃ������A�������͋g�������}�����[�̃n�E�X���[���ɏ]�����B
�k�t�L�l
�������܂܂łɁs�y���F��t�ɂ��ď��������͂́A�s�g���������t�́q�]�`�s�y���F��t���r�������A�q�s�y���F��t�Ɖו��́q�ljԗ]���r�i2005�N1��31���j�r�i����͕����ǂ���̏����j���q�s�y���F��t�́q40 �u�Â��ȉƁv�r�̍\���ɂ��āi2016�N8��31���j�r�ł���B���̊ԂɁA�s�y���F��t�́q�l�������r���쐬���Ă���iPDF�t�@�C���\�\�y���F��E�l�������k�g�������s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�t�^�q�l�������r�l�\�\���J�F2012�N12��31���j�B�Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂����_�l�ɂȂ�Ȃ��̂��c�O�����A�s�y���F��t�̐��������w�I�œ��肭�����̂��̂ł���ȏ�A�����������B�i�ق̉ۑ�́A������Ƃ̈�Ƃ��āA���p�����̏o�T��T�����邱�Ƃł���i�g�����̏��ւ��Č�����̂łȂ�������A���ׂĂ����߂邱�Ƃ͕s�\���낤���j�B���g�̓��L�Ǝ��т��ˋ������A�ӔN�̋g�������������ő�̎U����i�́A����4�N�O�Ɋ��s���ꂽ���W�s��ʁt�ƕ���ŁA�T���ɒl���鏑���ł���B���Ƃ��A�u�q���L�r�@��㔪�O�N�ꌎ��\�����^���B�~�Ȃ�ǒg�������B�V�h�̃p���X���Ŏ��Ԃ��Ԃ��A�ʐ���ŐH�������A�n���S�Œ���x�m�����w�֏o��B�����ȋi���X�ŃR�[�q�[���̂݁A���C���X�y�[�X�E�v�����a��T�������B�k�c�c�l�v�i�q71�@���C���X�y�[�X�E�v�����a�r�A��l�l�y�[�W�j�B�p���X���Ŋ|�����Ă����i�|���m�j�f��́A�s�҂��t�Œ��ׂ�Ȃ������킩�邾�낤�B����x�m�����w�͎��̏o�g���Z�̍Ŋ��w������A�u�����ȋi���X�v���~�����\�\�h�A�ɃJ�E�x�����Ԃ炳�����Ă����\�\�������炷�����ȁA�Ǝv���i�������̋m�Ƃށn��y�������œ����Ă����j�B�����āA���C���X�y�[�X�E�v�����a���C���^�[�l�b�g�Ō�������Ɓu�����s�����퐶��4-26-20 ���i�[�N����B1�v�Ɍ�������B����͂����ǒT�K���˂Ȃ�܂��B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�g�����͐��z�q�剪�M�E�l�̒f�́r�́u3�v�\�\���o�́s�剪�M����W�k��14���l�t����i�y�ЁA1978�N3��31���j�́q�剪�M�E��̒f�́r�\�\�ɂ��������Ă���B
�@�����o�q�G���q�����܁r�̕ҏW�ɁA����������āA���A���N�ɂȂ邾�낤���B�k�c�c�l
�@������A���e�������Ă����悤�Ɍ�������A�ނ͂��ꂵ�����Ɂu�������ĖႤ��v�Ƃ̕Ԏ��ɁA���͂ق��Ƃ����B
�@���a�\�N�܌����́q�����܁r�̊������������A�剪�M�̃G�b�Z�C�́u�܉Y�s�v�������B���͈�ǂ��āA�f���������͂ɕҏW�҂Ƃ��Ċ��������B�����ɂ��̂悤�Ȉ�߂�����B
�@�@�k�c�c�l
�@�k�c�c�l��w�����Ƃ��āA�]�_�ƂƂ��āA���l�Ƃ��āA�܂������V���̕��|���]�̎��M�҂Ƃ��āA�ނ͖Z�E����Ă����B���̂����ɁA�����낵�]�`�s���q�V�S�t���A�߂Â��̊����܂łɁA�d�グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
�@�剪�M�́u�܉Y�s�v�̌��e��n���Ȃ���A���ɂ����������B�u�܂��܂��ڂ�ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��V�S�̉p���_�����������A���܂��S�̂̍\�z�͏o���Ă��Ȃ��v�ƁB�܂����̂悤�Ȃ��Ƃ��������悤�Ɏv���B�u���́u�܉Y�s�v�����������Ƃɂ���āA�Ƃ������肪�ł��A�ЂƂ̓����������v�Ƃ��B
�@���̔N�̏H�A�剪�M�́s���q�V�S�t�͊��s���ꂽ�B���̖���́u���@�܉Y�s�v�ł͂��܂��Ă���B���̏��q�̎��݂ȓW�J�ƌ����݂͂��Ƃ��Ǝv���B���͂Ђ����܂�āA��C�ɒʓǂ������̂��B�k�c�c�l�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
�͂��炸�������s�����܁t�i�}�����[�̌����o�q���j�\�̕���ɂ��āA������剪�́q���@�܉Y�s�r�i1975�N5���E��73���j���A������g���́q���{�̎R���̈��r�i1987�N2���E��191���j���A�i�قځj�������낵�̕]�`�s���q�V�S�t�Ɓs�y���F��t�̌`�𐬂����������ƂȂ����Ƃ��������ɂ́A�P�ɋ����[���Ƃ����ȏ�̂��̂�����B�g���́A�O�҂ɂ͕ҏW�҂Ƃ��āA��҂ɂ͎��M�҂Ƃ��āA���̑}�b�ɓo�ꂷ��B
�s�g�����Q�l�����ژ^�t�ɂ́A�����������������i�����Ƃ��Ĉ�����B�C���^�[�l�b�g�ゾ���Œm�肦�������܂܂Ȃ��j���̘^���Ă���B�Ⴆ�A�I�����q���㎍�̖��́\�\���̂R���r�̏��o�́s�����V���t�i2016�N6��12���j�ŁA�����V���o�Łi�ҁj�E�a�c���i��j�̒P�s�{�s�킽���̃x�X�g�R�\�\��Ƃ��I�Ԗ�������t�i�����V���o�ŁA2020�N2��29���j�Ɏ��^���ꂽ�B���o���A���͓������w�ǂ��Ă��Ȃ������̂ŁA�C���^�[�l�b�g��̏������ǂ��Đ}���قʼn{�������B�P�s�{�̕��́A����܂��}���ق̐V���{�̏������u���E�W���O���Ă��āA����������Ď�o�����Ƃ���A�܂��ɓI�������B�����̏ꍇ�A�C���^�[�l�b�g��̏��͌����c�[���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�q���㎍�̖��́\�\���̂R���r�́s�킽���̃x�X�g�R�t�ł̃^�C�g���́q�I�����E�I�@���㎍�r�ŁA���̎O�����I��Ă���B�u�@�T���`���E�p���T�̋A���i�Ό��g�Y���^�v���Ёj�^�A�ߑ㎍���猻�㎍�ց@�����A�吳�A���a�̎��l�i����M�v���^�v���Ў��̐X���Ɂj���P�^�B��㎍�@�����V�[�Y�̕s�݁i���R�C�i���^�u�k�Е��|���Ɂj���P�v�i�����A�Z�y�[�W�\�\�u���P�v��2020�N1�����ݕi��\���j�B�����Ƃ��A�I�����͓����ŋg�����ɒ��ځA���y���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�g���́A���R�C�i���������u��㎵�l�̎��l�v�̂ЂƂ�Ƃ��ēo�ꂷ��B
�@���R�C�i�w��㎍�x�́A���Z�ܔN���s�B�Z�̂⎍�������A����ƁA���o�ƂƂ��Ă����Ђ낭�������҂ɂ��A�����m�߂������n�Ȏ��_�B�s���ď_��Ȏ��_�ƕ��͂́A���܂��F�����Ȃ��B�����́u�������ɂ��邱�Ƃ��玍����͂��߂�����v�ɑ�����A�ƋL���B�u��㎵�l�̎��l�v�Ƃ��ĒJ��r���Y�A��c�G�A���c��v�A�g�����A�����O�S�A�˖{�M�Y�A����N�Y��������B�u���ɗ����v�͂Ȃ��Ă��u����𗧂Ă�S�v�͂���A�Ɠǎ҂�����B�i���O�A��y�[�W�j
�s�킽���̃x�X�g�R�t�́q�T ����ɗV�ԁr�q�U �킽����������{�r�q�V ���vs��Ɓr�q�W �e�[�}�œǂށr�̎l�����琬��A�I�����́q�W �e�[�}�œǂށr�̍Ō�Ɏ��߂��Ă���B���Ȃ݂ɁA�{�V�Ўi���I�ԃf�B�b�N�E�t�����V�X��3���͇@�����É��̊���A�N���B�����i�q�T ����ɗV�ԁr�j�B���ꉳ�F���I�ԑ剪������3���͇@��·A���C�e��L�B�ԉe�i�q�U �킽����������{�r�j�B�ܒJ���m���I���F�V���F��3���͇@�t���[���ꡁm���傤�悤�n�A�ߕ������B�ӓ��m����݁n�̒��̐��E�i�q�V ���vs��Ɓr�j�B�ےJ�ˈꂪ�I�Ԙa�c����3���͇@���ԗ��s�A���������B���ȁi����͔ԊO�тȂ̂��낤�B��ˎ����A�K���V�A�E�}���P�X�A���{�����ƂƂ��ɁA�a�c�ɂ͓�̃Z���N�V����������A�ےJ�̂ق��ɘa�c����3����I������l�͎O�J�K��j�B���āA�����܂ł͖{���̏Љ�����˂��O�u���ł���B�ȉ��ɁA�{�e�̃^�C�g���u���ш�Y���I�ԋg������3���v���L���B
�@�m���i�s������{���{��n93�k���㎍�W�l�t�����^�}�����[�j
�A�_��I�Ȏ���̎��i����R�c�j
�B�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�i�}�����[�j
�@�`�B�Ƃ��ās�g�����S���W�t�i�}�����[�j�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i���j�A�s���܂�͂����L�t�i����R�c�j�A�Ƃ����ʈĂ��l�����B�������́u���̎�v�́A��萳�m�Ɍ����Ȃ�u�����v���낤�B����āA���˂Ă��玄�̒���敪�ł���u�O���g�����v����͉����́s�m���t���A�u�����g�����v����͕ϑ��́s�_��I�Ȏ���̎��t���A�u����g�����v����͏������낵�́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t��I�B3���Ƃ������H���Ōł߂�Ȃ�A�A�́s�T�t�����E�݁t�A�B�́s��ʁt�ƂȂ낤���A����Ȃ玄���I�Ԃ܂ł��Ȃ��i�����͂�������A���W�ɗ^������܂����g�����̑�\���W�ł���j�B�s�m���t�́A�g�������l���������łȂ��A���d�W���[�i���Y���ɂ����т\���͂��߂������̍�i���W�߂����W�ŁA�g��������������тő�\������Ȃ炱�ꂵ���Ȃ��Ƃ������сq�m���r�������ɑՂ��o����i�㐢�́A�g�����s�m���t�̎��l�Ƃ��ċL�����邾�낤�j�B�������ɂ�����O���킯�ɂ͂����Ȃ��B�A�́s�_��I�Ȏ���̎��t�́A�g�������ɂ�������p���A���掍�̑���Ƃ������ׂ���i���܂݁A�����̎��тȂ����Ď���s�T�t�����E�݁t�̉ؗ�ȓW�J�͂��肦�Ȃ������B�ӔN�̋g���́A���܂��܂ȃX�^�C���̍������琬��u������e�[�}�Ƃ��钷�ю��v�z���Ă����B���̔]���ɂ̓����P��G���I�b�g�̒��ю��i�s�h�D�C�m�̔߉́t��s�r�n�t�j�����������A���ɂ�����������Ƃ͂��Ȃ�Ȃ������B�U���ł͂��邪�A�y���F��̑��Ƃ���u�Í������v�Ƃ̊ւ����W�听�����s�y���F��t���A���̈⍁��Y�킹�Ă���B�Ō�ɁA�g���������ʂ�O�l�Ƃ����A���N�̏��Ɏ��l�̐��e���O�Y�i1894�`1982�j�A�o�l�̉i�c�k�߁i1900�`1997�j�A�����Ƃ̓y���F�i1928�`1986�j�ł���B�g�����Ƃ������l�Ɓq�g�����r�Ƃ�����i�̊W���߂����āA�k�߂Ƈ@�́s�m���t�A���e�ƇA�́s�_��I�Ȏ���̎��t�A�y���ƇB�́s�y���F��t���l�����킹��Ȃ�A�����3���͂���Ȃ�P����тт邾�낤�B
�g�����Ƒ剪�����Ƒ肵������Ƃ����āA���҂ɋ�̓I�Ȃ��邢�͕��w�I�Ȍ����������킯�ł͂Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��g�����剪�Ɍ��y�������Ƃ͂Ȃ����i�������A�g�����ҏW�������1975�N12���A�s�����܁t��80���͑剪�́q�u���N�v���ڂ�b�r���f�ڂ��Ă����k���P�l�j�A�剪���g���ɂ��ĂȂɂ������̂����Ă���̂��������Ƃ��Ȃ��k���Q�l�B���O�̓�l��m�������b�q�́q���l�̌��t�r�������n�߂Ă���B
�@�܂�ʼn����ʂ̕��̉��̂悤�Ɏl�p���������̂����A����ł����̈���̏����̂Ȃ��Ɏ��l�̑S��i�͎����Ă��܂��̂����A�g�����̑��̒���Ƃ����A���z�W�́w�u�����v�Ƃ����G�x�Ɓw�y���F��x�w���܂�͂����L�x�̎O�����������邾�����B
�@�������A�ɂ��W���O���[�E�x�[�W���̐������ȁw�g�����S���W�x�ɂ́A�\����̎��W�Ɩ������сA�̏W�w�����x�������Ă��āA�v���Ԃ�ɓǂގ��W�̂��ׂā\�\�g�����̎��Ɍ��炸�A�u���v��ǂނ͈̂�N�Ԃ�ł͂Ȃ����낤���\�\�́A�u�n���������̂ɂ��x����ꂸ�ɑ�C���ɕ�����ł���悤�ɁA���̕��̂̓��I�ȗ́m�A�A�A�A�A�A�A�n�ɂ���Ă݂����畂����ł���v���Ƃ��t���[�x�[�����������u����������Ă��Ȃ��{�v�̈�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A���߂Ď��ɋC�Â�����̂����A���Ƃ��A�u�����Ɓv�Ƃ������̂��A���̏o�����琶�U�̏I��܂łɏ����Â������͂��W�߂��S�W�i�剪�����S�W�E�S��\�O���ʊ���j���A�����̕����ɐςݏd�˂Ēu���Ă���A�`�T�k�Ł����l�̓�\�~�����\���~���قlj����ł���w�g�����S���W�x�̈���́A�قڑ剪�����S�W�̈�����̌����Ɠ����ł���B
�@���Ɉ⌾�Œ}�����[����S�W���㈲���邱�Ƃ�`�����Ƃ����_�������A�قƂ�ǂƌ����Ă����قNj��ʓ_������Ƃ͎v���Ȃ����l�Ə����Ƃ̑S�W���d�Ȃ��������ɓǂނ��ƂɂȂ����̂́A���̎d����̓s���ɂ����Ȃ��̂����A���̂����ɂ������ƌ����鎍�l�Ə����Ƃ̊�ȋ��ʓ_�Ƃ�������v�_�����������Ƃ��v���o���̂́q���l�̌��t�r�ɂ��ĂȂ̂��B
�@���x�A���镶�w�V�l�܂̓��I��̈ꕔ�ɁA���l�̕��͂����̂܂܁u����v����Ă������Ƃ��V���ő傫�ȋL���ɂȂ������ŁA������ӎ��I�Ȉ��p�m�A�A�n�i���^�t�B�N�V�����m�A�A�A�A�A�A�A�A�n�I�����Ȃǂł͂Ȃ������̂Łj�ƌĂׂ͂��Ȃ�����ǁA�u����v�ƌĂԂ��Ƃɂ͓���I�������剪�������́A�w����̏ؖ��x�Ƃ����{���w�X�I���z���I�ɂ������������������āA�q���l�̌��t�r���A����̗B��̍�҂ɑ����ĂȂǂ��Ȃ��m�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�n���A�����I�ɖ����̍�҂������Ă��邱�Ƃ��ؖ������̂��������A���̒���ɂ������������A�q���l�̌��t�r�f�Ŏg���Ă����̂́A�������Ⴀ�m�A�A�A�A�A�n�A�܍s�܂Łm�A�A�A�A�n���ȁA����ȏ�g�����͏o�T�����Ȃ�������Ȃ��A�Ƃ��������̂������B
�@����A�����A�w�T�t�����E�݁x���������̎��l�́A���̍���͂�X�L�����_���Ƃ��Ęb��ɂȂ��Ă����\�\�ƌ����Ă��A�V�l�����܂̓��I��̍�҂��J�����̘b���m�A�A�A�n�w�Ă̈Łx�̈ꕔ���������菑���ʂ��A����ɑI�l�ψ����܂������C�������ɂ����A�Ƃ����قǂ̃j���[�X���͂Ȃ������悤���������\�\���鎍�l�̖S��ւ̔҉̂Ƃ��ď����ꂽ�����A�ʂ̎��l�̍�i�̓��삾�����A�Ƃ��������ɐG��A���R�ƈÑR�����荬�����ʎ����ŁA�܂��ĖS���Ȃ�������������ւ̔҉̂Ȃ�A�����Ȃ���A�l��l���ˁA�Ƃ��������A���̌�ŁA�q���l�̌��t�r�����p���Ă����̂́A���̏ꍇ�m�A�A�A�A�n�A�O�s�܂Łm�A�A�A�A�n���ˁA����ȏ�͑ʖځA�Ɛ^�ʖڂ��k�}�}�l����Ȃ���̂ł������B
�@
�@
�@��̔����͂قړ��������i�����Ă���A�O�N�̊Ԃ̏o�����������Ǝv���j�ɕ����Ă��āA�ǂ��炪�悾�����̂��ゾ�����̂��A�͂�����v���o�����Ƃ͏o���Ȃ��̂����A����A�剪����̉Ƃ�K�₵����̋A�蓹�ŁA�o�Ǝ��͂قƂ�Ǔ����ɁA���������A�g�����A�ƁA���l�̎O�s�������v���o���A�͂��ڂ��͂��炸���̐^�����ő�����Ă��܂����̂������B
�@�P���Ɍv�Z����ƁA���ƎU���̈Ⴂ�́A��s�m�A�A�n�́q���l�̌��t�r�Ȃ̂ł���B�i�s���̂���������������Ă����\�\�Ǔ��E�g�����k�邵����ʍ��l�t�A����R�c�A1996�N11��30���A��O�`��l�y�[�W�j
�ȉ��A����́q���l�̌��t�r�̎傽�镔���ŁA�q�y���r�i�H�E1�j��q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE15�j�A�q�����`���r�i�q���C�X�E�L��������T�����@�r�G�E11�j�A�q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�A�q�^�R�r�i�G�E2�j�A�q�Ẳ��r�i�H�E20�j�A����̂��Ƃ��莫�Ɉ����ꂽ�q�����r�i�H�E6�j�Ƃ��������тɐG��Ȃ���A�g��������_���Ă����B�����A�����ł͋��䂪�������剪�����̒Z�я����q����̏ؖ��r��ǂ�ł݂悤�B�u�i���̍�i�͍�N�x�̂���V�l�܂ŋN�������p���ƁA���X�؊�ꎁ���\�̈ӌ��y�ђJ��i�ꎁ�̂���ɑ���ᔻ�i�u�Ǐ��l�̉��V�v�����j�Ƀq���g�Ă��܂����A�����̌o�߁A�l���A�n�����̑��A���ׂăt�B�N�V�����ł��B��ҁj�v�Ƃ͏��o�i�s�����V���ʍ��t1979�N4���́k'79�t�l�j�̖����ɕt����Ă����S�������A����̏����u�V�l�����܂̓��I��̍�҂��J�����̘b���m�A�A�A�n�w�Ă̈Łx�̈ꕔ���������菑���ʂ��A����ɑI�l�ψ����܂������C�������ɂ����A�Ƃ����v���ɐG������Ď��M�������������ꂾ�����B
�s���k�A�[�J�C�u�X�t2019�N6��22�����q�ƉB���@�o�ł̗��j����u��������v�������Ȃ����߂Ɂ@��1��r���Q�Ƃ���ƁA���́u�V�l�����܂̓��I��v�́A�u�k�Ђ����s����s�Q���t�̐V�l���w�܁i1978�N�x�̑�21��j�ɂ����Ē����́q�C�������鎞�r�ƂƂ��ɓ��I������������́q�i���Ɉ���r�ŁA�u�剪�����́w�ŏ��̖ڌ��ҁx�i�W�p�Е��Ɂj�Ɏ��߂�ꂽ�u����̏ؖ��v�́A���́u�i���Ɉ���v�����ɑ剪���C���X�s���[�V�����������グ���Z�҂ł���B�����͏����ɂ͂Ȃ������A��ƂƂ��Ă͏����Ă��܂����̂ł���B�v�Ƃ����̂��s���k�A�[�J�C�u�X�t�̌���ł���B���Ȃ킿�A�����́q�i���Ɉ���r�͏��Љ�����Ă��炸�A����ɂ��ł͏��o���f�ڂ����G���ȊO�ł͑S����ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��̂��B���䂪�`����剪�́u�q���l�̌��t�r�f�Ŏg���Ă����̂́A�������Ⴀ�A�܍s�܂Łv�����������邽�߂ɂ��A�����́q�i���Ɉ���r��ǂނɔ@���͂Ȃ��B���Ȃ݂ɓ�����f�ڂ����s�Q���t1978�N6�����́k���쌪�Ǔ����l�ł�����B
�s�Ă̈Łt�i�V���ЁA1972�j���ɓǂ�ł��Ȃ����ł��A�q�i���Ɉ���r�͒B�҂ɂ����āA�N���́i���ꂪ�J�����������킯�����j���|�I�ȉe�����ɂ��鏬���ł͂Ȃ����Ƃ����^�O�͂����ǂ���ɕ����ԁB���̌���_���������ɁA�s���k�A�[�J�C�u�X�t����肠���Ă���I���T��Y�s�q����r�̕��w�j�\�\�s��E���f�B�A�E���쌠�t�i�V�j�ЁA2008�N6��30���j������A�ߔN�ł͍���^��s����̌���w�\�\�\���̃I���W�i���e�B�[���l����k�W�p�АV���l�t�i�W�p�ЁA2015�N5��20���j������B����́m����ꂽ�����n�Ƃ����߂ł����q�ׂ�B
�@��ɏЉ���剪�����́u����̏ؖ��v�ɂ͋����[�������肪����B���̍�i�ɂ����ẮA���ߐM�s�Ƃ���������Ƃ́u�����̃o���[�h�v�Ƃ�����i���A��O�̐�_�u���x�̎q�������v�����삵���Ƃ����������������Ƃ����Ƃ��납���i���W�J���Ă����B�����āu�Z��Ƃ����Ă��������炢���Ă���v�u���s�̕��́v�i�Z�O�Łj�����ۂɋ������Ă���B����͂������剪���������������ł���B
�@�k�c�c�l�i�u�����̃o���[�h�v�j
�@�k�c�c�l�i�u���x�̎q�������v�j
�@�u����̏ؖ��v�ł͐�_�́u��Ɂw�����̃o���[�h�x��ǂ�ł��܂���v�i�Z�l�Łj�Ǝ咣���A���Ɏ��E���邱�ƂɂȂ��Ă���B�剪�����͋Â����u�����v��p�ӂ��Ă����B����́A��̕\���́A�Ƃ��ɃJ�~���́w�y�X�g�x�i�{���Y��A�V���ДŁj���u���ʂ̑c�^�v�i���ܕŁj�Ƃ��Ă������̂ŁA���ړI�ȊW�͂Ȃ������Ƃ�����̂ł���B�剪�������u�c�^�v�Ƃ����͎̂��̕��͂ł���B�u�����̃o���[�h�v�Ɓu���x�̎q�������v�o���ɂ݂���ӏ��ɖT�����Ă݂�B
�@�k�c�c�l�i�w�y�X�g�x��O�O�Łj
�@�u���ʂ̑c�^�v�͒��ړI�ɂ́A�u�����̃o���[�h�v�̕��͂ɂ��A�u���x�̎q�������v�̕��͂ɂ����܂莗�Ă��Ȃ��B�������剪�����̎�r�Ƃ����Ă��悢�B�剪�������u����̏ؖ��v���ǂ̂悤�ɏ��������Ƃ������Ƃ��炢���A�܂����́w�y�X�g�x�̕��͂�I�сA��������Ƃɂ��āA�����炭�u�����̃o���[�h�v�̕��͂�����A���������ɂ��Ƃɂ��āu���x�̎q�������v�̕��͂��������̂��낤�B�w�y�X�g�x�́u�c�^�v������A�u�����̃o���[�h�v�ƒ��ړI�ɂ͂��܂莗�Ȃ��悤�ɂ���A�u�����̃o���[�h�v�Ɓu���x�̎q�������v�͋�̓I�ȕ\���ɂ����ėގ����Ă���悤�ɂ���B���镶�͂����Ƃɂ��āA����Ƃ̗ގ����w�E�ł��Ȃ����炢�ގ����Ă��Ȃ����͂����邱�Ƃ��ł��邵�A����������͂����邱�Ƃ��ł���B���w��i�������Ă����Ƃɂ͂��̂��炢�̂��Ƃ͊ȒP�ɂł���̂��Ƃ������Ƃ�剪�����͐g�������Ď������B�i�����A�Z�Z�`�Z��y�[�W�j
�̐S�̑剪�̏����Ɍ�����{���̕��͂́A��Ɉ����ɂ������āA�����ďȗ������i�����͋ߔN���s�̐V��������A�e�Ղɓǂ߂邾�낤�j�B�����ł́A�剪���]�_�ł͂Ȃ��A�����Ƃ����`�Łi�J�~���́s�y�X�g�t�Ƃ����N�����ǂ݂����s��i���u�c�^�v�Ɏ�āj�|�̂������s�����Č��������Ƃ��m�F����Ώ[�����B�Ƃ���ŁA�剪�����͏��o���̌㒐�I�ȕ������܂߂āA��������Ƃ��q�i���Ɉ���r�Ƃ��A�J�����Ƃ��s�Ă̈Łt�Ƃ������Ă��Ȃ��B��f���ɂ����������b�q�́u�V�l�����܂̓��I��̍�ҁv�u�J�����̘b���m�A�A�A�n�w�Ă̈Łx�v�Ə����Ă��邪�A��l�̏����Ƃ́A���g�̒Z�я�����g�����_�ŁA�����̏����ƂƏ�����i�̖��O��������̂ɐT�d�������B����A�_�]���闧��̍��X�؊��ƒJ��i��́A�Ƃ��ɖ��O�������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B�����őz�N�����̂́A�g���Ƌ��䂪�Βk�Łq���p���ɂ��ār��������ł���B
�����@�w�Ẳ��x�̎��ł������ȏ��]���o�āA�N�����������Ă������͊o�����Ȃ����Lj�ʓI�Ȉ�ۂƂ��āA���̎��W���u�~�n�v�Ƃ����`�Ŕ�]�������̂������������Ǝv����ł���B�a��F�コ��Ȃ͂��������������͂��ĂȂ��킯�����ǂ��B�~�n�Ƃ����̂́A����Ӗ��œ������Ă��Ȃ����Ȃ��낤���ǁA����ς肻���������t�ŋg�����̎��������Ă��܂��̂ɂ͒�R������킯�ł��ˁA�ǎ҂Ƃ��āB
�g���@�����ˁB�~�n�Ƃ����̂͏܂ߌ��t�ł���Ɠ����Ɉ�̌����������ł���Ǝv���B�����A���p�̎d�����芵�ꂽ�Ƃ������Ƃ͂͂����肵�Ă�Ǝv���̂�B
�����@�芵��Ă��܂��ƁA�����Ă��Ėʔ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͓��R����ł��傤�ˁB�V������C�̂Ȃ��ł̌ċz���̂ݍ���ł��܂��Ƌْ����Ȃ��Ă��ނ��ǁA����Ƃ����̂́A��͂�댯�ȂƂ��������킯�ł��ˁB�Ƃ���ŁA���̈��p�ł����ǁA���ʂɓ����Ă��镶�͂����Ȃ炸�������p�ł͂Ȃ����A���ʂɓ����Ă��Ȃ������ł��A���p������킯�ł��ˁB
�g���@�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB
�����@�����ł���ˁB�����犇�ʂ̒��ɂ͂����Ă���̂����͈��p����Ȃ����̂����Ȃ肠��Ǝv���܂��B
�g���@�����Ȃ̂ˁB��������Ȃ��ƁA�����������A���e�B���������Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�����Ŋ��Ď����̎�������ʂɂ����ƃ��A���e�B����������Ƃ������o������Ă���킯���B
�����@����͂ƂĂ��ނ��������ł��ˁB�ł��A�����Ă��̕��������l�Ԃ́A�����͂�����A����Ȃ��ƌ������肵�܂���ˁB�ӎ����Ă���̂����Ă��Ȃ��̂��A�킩��܂��ǁA���������`�ł̌��t�Ƃ̑Ό������������A�Ȃ��߂��肵�Ȃ���A�ĊO���C�Ȋ�����Ă���B���̊��ʂ͉��ł��傤�ˁB�ŏ��͂��������p�ł��邱�Ƃ����邽�߂Ɏg���������Ƃ����̂���Ȃ��Ǝv����ł����ǂˁB
�g���@�S�`�ł������킯�Ȃ��ǁA�ŏ��͓��`�I�ɂЂƂ̌��t�ł��邱�Ƃ��������߂Ɏg�����̂�����ǁB���b�q��`�����u�����v���A�N�̌��t�����ł́A���܂������Ȃ��̂ŁA���͔ѓc�P���̃G�b�Z�C���������ؗp���Ă���B�����A�ڂ��������Ă��������̂́A������̎��т����傩��͂Ƃ��ĂȂ���B����݂͂�ȑΏۂɂȂ����l�̃G�b�Z�C����Ƃ��Ċ��ʂɂ���āA��������ɂ����Ă��Ă���B��������̗�O�́A�������ɕ������u�Ɣ�������v�����͂ǂ����Ă��A�������́u���t�v�����ō��Ȃ��Ȃ��āA���傪��A�O�͂����Ă���B
�����@�O�ɁA���p�ɂ��܂������t�����p�ł���l�ƁA����܂�ł��Ȃ��l�Ƃ�����Ƃ����b�����Ă܂�����ˁB
�g���@�����A���ꂪ�s�v�c�łˁB�r�c�����v�̂��������Ƃ����̂ˁA����������ɂނ��������킯�B���p�́A�y���F�̌��t����Ԉ��p�������̂ˁB
�����@�����A����͎��ɓƓ��Ŋ�ȕ��͂ł����̂ˁB
�g���@�����B����Ő��m�Ȃ܁n�Ȃ́B�������̂��̂̌��t�ȂB�����ǖ����v�Ƃ����͓̂���������ŁA���͂������Ȃ́A������ӊO�Ɉ��p����������킯�ˁB
�����@����A����B�킩��܂��ˁB�y������̌��t���Ă����������I�ȁA��̓I�Ȍ��t�ŁA�g������̎��Ƃ����̂��A�������ϔO�I�œ���Ȏ��ƌ����邱�Ƃ͑����킯�����ǂ��A���t�̈��͔��ɋ�̓I�ŕ����I�Ȍ��t�����łł��Ă��鎍�ŁA�ϔO�I�ł͐����܂���ˁB
�g���@������ڂ��̂̓V���[�����A���X���ł����ł��Ȃ��Ă��A��s�A��s�k�}�}�l���ׂă��A���e�B���Ƃ��������͂���̂ˁB����̏W�ςł�����ƈٗl�Ȃ��̂��ł��Ă�͂�����B
�����@�r�c�����v�̕��͖͂���������Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB�ƌ��������ۓI�Œ��ɔ������Ƃ������ƂȂ�ł��傤���ˁB
�g���@���ۓI�ł��Ȃ����ǁA���ɖ����ō��ɂ��������B�ŁA�y���F�̂ق��ō��₷�������͔̂ѓ��k��B����܂���Ȍ��t���Ă���킯�B�ڂ��ɂƂ��ĈӊO�Ȍ��t�ƌ������A���̌��t���K�v�ȂB���ꂾ�ƍ�肢���B������A����܂蕶�͂�����������������G�b�Z�C����́A���ɂƂ�ɂ����B�{��~�Ȃ��̍ł�����̂ˁB�{��~�͂Ƃ�Ƃ��낪���ɂނ��������킯��B������A���́A�O���̉�Ƃ̌��t�Ƃ����������̂��U��߂Ȃ��Ƌ{��~���͐��藧���Ȃ������B
�����@�{�삳��̕��͂��̂��̂����p���琬�藧���Ă���킯�ł����̂ˁB
�g���@�{��~�̂��߂́u�D���̎O�̒[�z�v�A���ꂪ��Ԃނ������������Ȃ��B�܂������炭���܂��������ĂȂ���Ȃ����Ǝv����B��i�Ƃ��Ăǂ��Ȃ̂��Ƃ�����Ƌ^��ɂȂ�B
�����@�{��~������p�ł������Ȍ��t�Ƃ����̂́A�{��~���g���Ă��錾�t����Ȃ��Ƃ������Ƃ����邩������Ȃ��ł����ˁB
�g���@�����������Ƃ����邩���킩��Ȃ����ˁB���܂�ɂ����I�ȕ��̂ł��邽�߂ɂ������̊������ĂȂ������B
�����@���̐��X�����ƌ������A���t�������Ƃ��ė������Ă��锧�����̂悤�Ȃ��̂��{�삳��̕��͂��猩���悤�Ƃ���ƁA����͂�����ƍ���ł͂���悤�ȋC�����܂��ˁB
�g���@���ꂪ�ڂ��̒��ɂ͂�����\���Ă���̂ˁB
�����@�g������̑I�Ԍ��t�Ƃ����̂́\�\�������P��Ƃ�����Ȃ��Ď��Ƃ��U���S�̂̂��ƂȂ��ǁA�S���肴���Ƃ������G�o�I�ȑI�ѕ������Ă���Ǝv����ł���ˁB
�g���@�܂��{�\�I�Ȃ��ǁA����ς肻���������t��I��ł���Ǝv���B�i������b�q�E�g�����k�Βk�l�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W���g�����l�A��܁`�㎵�y�[�W�j
���̌��͂��܂܂łɂ����x���{�T�C�g�Ɍf�������Ƃ����邪�A����̓���^���p�Ƃ������_���猩��ƁA�ܒ~�ɕx���Ƃ�ł��邱�Ƃ��悭�킩��B�����ŁA��L�Βk�́s�Ẳ��t�ɂ����錣���̑Ώێ҂Ƃ��̍�i�����āA���p���ƁA�֘A���鎄�̕��͂������Ă������B
�@������b�q�ւ��q�����r�i�H�E6�j�\�\������b�q�i�莫�E�{���j
�@�@�@�q�g�����ƃN�����g���邢�́u���Ƃ��Ă̖��v�r�Q��
�@����C���ւ��q�u�Ɣ�������v�r�i�H�E27�j�\�\����C���̌��t�Ǝ���i�莫�E�{���j
�@�@�@�q�g�����Ƒ���C���i3�j�r�Q��
�@�r�c�����v�ւ��q���̖��{�r�i�H�E9�j�\�\�r�c�����v�i�莫�E�{���j
�@�@�@�q�u���ƕs�M�̑o�e�v�\�\�g�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�]�߁i2�j�\�\�q�Ă���H�܂Łr�r�Q��
�@�y���F�ւ̌����́s�Ẳ��t�ɂ͎��߂��Ă��Ȃ��i�{���̎���Ƃ��Ĉ��p����Ă���y���̌��t�͂���j�B
�@�@�@�q�g�����̈��p���i3�j�\�\�y���F��^�r�Q��
�@�ѓ��k��ւ��q���J�̎p������r�i�H�E14�j�\�\�ѓ��k��i�莫�E�{���j
�@�@�@�q�g�����ƃG�Y���E�p�E���h�r�Q��
�@�{��~�ւ��q�D���̎O�̒[�z�r�i�H�E16�j�\�\�{��~�i�莫�E�{���j
�@�@�@�q�g�����ƃ}�O���b�g�r�Q��
�T�@�ށi���j�̕��́E�G�b�Z�C���������p�������c�c�q���J�̎p������r�A�q���̖��{�r�A�i����͒r�c�̔ʼn��i�̑薼�̈��p�����j�q�Ă���H�܂Łr
�U�@�T�ɉ�����ɁA���l�̕��́E�G�b�Z�C�����p�������c�c�q�����r�i����{�ѓc�P���{�G�S���E�V�[���j�A�q�D���̎O�̒[�z�r�i�{��{�W�����W���E�u���b�N�j
�V�@�T�ɉ�����ɁA�ށi���j���g�̎�������p�������c�c�q�u�Ɣ�������v�r
�Βk�ł͌��y����Ă��Ȃ����A�ѓc�P���ւ��q�`�͕s���̉s�p�������c�c�r�i�H�E11�j�͊�{�I�ɇT�A���đ���C���Ɍ������q�ǎ�̏��r�i�G�E22�j�\�\�q�g�����Ƒ���C���i2�j�i2010�N3��31���j�r�Q�Ɓ\�\�́q�u�Ɣ�������v�r���l�A�V�ɕ��ނ����B�����͂��������Ȃɂ���Ă���̂��낤�B�u�����@�g������̑I�Ԍ��t�Ƃ����̂́\�\�������P��Ƃ�����Ȃ��Ď��Ƃ��U���S�̂̂��ƂȂ��ǁA�S���肴���Ƃ������G�o�I�ȑI�ѕ������Ă���Ǝv����ł���ˁB�^�g���@�܂��{�\�I�Ȃ��ǁA����ς肻���������t��I��ł���Ǝv���B�v�Ƃ���悤�ɁA���M�Ɓ^���`��ƂƂ����敪�ȏ�ɁA�u���̐��X�����ƌ������A���t�������Ƃ��ė������Ă��锧�����̂悤�Ȃ��́v�i����j����l���̌��t�͈��p�����₷���A�����łȂ��l���̌��t�́u���ɂƂ�ɂ����v�i�g���j�Ƃ������ƂɂȂ�B�g�����g�A�������]�I�����ӂƂ��Ȃ��Ǝ��o���Ă���ӂ�������B����������A��̓I�Ȃ��̂𗣂�Ē��ۉ����邱�Ƃɑ��āA�˂Ɍx���S������Ă���B�g���̌��t�i���̏ꍇ�A����i�j�Ƃ̐e�a���������̂͂ނ���̐��̂��錾�t�̕������A�ꌩ����ƁA��������̂��g���Ȃ̂�����ȊO�̐l���Ȃ̂��́A�u�@�v�i�ꊇ�ʁj�ł������Ă��邩���Ȃ��������̂悤�ȏ��������āA���Ɂu�@�v�����͂���Ă݂�A�n�̕��i�g���ɂ�鎍��j�ƈ��p����Ď���ƂȂ������҂̕����Ƃ̍��ق������ɂ����ꍇ���A�܂܂���B����ɁA���g�̏�����������u�@�v�ň͂��p�i�H�j�Ɏ����ẮA��������̂��N���Ƃ����₢�͌�i�ɑނ��āA�����肪�ǂ��̒N�Ƃ��m��Ȃ��҂̌��t�����p�����Ƃ��������������O�ʂɂ���o���Ă���B���́u���o�v�ƌ����悤���B�s�Ẳ��t�̊������сq�y���r�i�H�E1�j�̖`���͂����������B���o�́s���㎍�蒟�t1976�N8������������B
���͂�������p����
���l�̌��t�ł����p���ꂽ���̂�
���łɉ�������
�u�A���̑S�̂͗n����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̉����̉�������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԁX�͐��܂��v
�k�c�c�l
�g�����͖{�т\����1976�N7���̎��_�ŁA���̔N�̏H�ɏo�鎍�W�s�T�t�����E�݁t�Ɏ��߂����ׂĂ̎��т����������Ă���i�����炭���W�̕ҏW���A���g�ɂ�鑕���������āA�藣�ꂵ�Ă���j�A�q�y���r�͎��̃t�F�C�Y�ɓ��邱�Ƃ̐錾�����߂����тƂ��ǂނ��Ƃ��ł���B�`���Ɉ���������́u����A�����A�w�T�t�����E�݁x���������̎��l�́A���̍���͂�X�L�����_���Ƃ��Ęb��ɂȂ��Ă����k�c�c�l���鎍�l�̖S��ւ̔҉̂Ƃ��ď����ꂽ�����A�ʂ̎��l�̍�i�̓��삾�����A�Ƃ��������ɐG��A���R�ƈÑR�����荬�����ʎ����ŁA�܂��ĖS���Ȃ�������������ւ̔҉̂Ȃ�A�����Ȃ���A�l��l���ˁA�Ƃ��������A���̌�ŁA�q���l�̌��t�r�����p���Ă����̂́A���̏ꍇ�m�A�A�A�A�n�A�O�s�܂Łm�A�A�A�A�n���ˁA����ȏ�͑ʖځA�Ɛ^�ʖڂ��k�}�}�l����Ȃ���̂ł������B�v�̂́A���łɁq�y���r�������Ă�������ł͂Ȃ��������B�Ƃ���Ŏ��́A���́u�ߐ��̏��A���w�ҁv����̎O�s�̈��p�̏o�T�����o�����Ȃ��ł���B�\�\�u�ڂ��̒��ł��A�⑫�͎����ō���Ď����Ŋ��ʂɂ����ƁA���A���e�B���o��ȂƎv�����Ⴄ�B�S�����l�̌��t�Ƃ͌����ĂȂ��킯�B���ς������邵�c�c�B�ŁA���̍s�Ƃ��̍s���Ȃ��ɂ͈��p������Ȃ��ƁA�Ƃ��������ŁA�����ō�������p�����ꂴ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ˁB�v�i�g���j�\�\���̂Ƃ��A�u�@�v�Ŋ���ꂽ����͓���^���p�̎����𗣂�āA���̖̎ʁm�p�X�e�B�V���n�̗l����ттĂ���B�R���[�W���ɓK���ȑf�ނ��Ȃ��Ƃ��A��Ƃ͂���ɑւ��f�ނ����삷��̂ł͂Ȃ��A�����ŕ`�悷�邾�낤�B���l�͂�������삷��B�����Ƃ́u����v��n�삷��B
��
�g�����Ƒ剪�������ԐړI�Ɍ��т��鍀�������ЂƂ���B�A�����J�o�g�̉f�揗�D�A�����������C�Y�E�u���b�N�X�i1906�`1985�j�ł���B�g�������C�Y�E�u���b�N�X�ɐG�ꂽ�̂́A�s�����C�J�t1976�N6�����̐��z�q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r�ɂ����ĂŁA�����̍Ō�̒i���́A�u���̓�l�̏��D�v�Ƃ��ăx�e�B�E�A�[�}���kBetty Amann�l�i1907�`1990�j�ƃ��C�Y�E�u���b�N�X�������Ă���B�����Ƃ��g���́A���C�Y�����x�e�B�ɁA��葽���M���₵�Ă��邪�B
�@�����̏��D�͊��{���̉f��ŁA���т��яo����Ă���̂��B�����čD���ɂȂ�A�Y�ꋎ��A���܂���Ƒz���o�������肾�B���ɂƂ��Ă̌��̏��D�́A�u�A�X�t�@���g�v�̃x�e�B�E�A�[�}���ł���B���̍�i�̓T�C�����g�f��̍ŏI�����閼�тƂ����Ă���B��ΓX�Ŗ������������A�x�@�֘A�s�����r���A�Ⴂ�x���������̕����Ɉ�������A�Z�Ԃ̂�����������āA�x����U�f���A�j�łւ̓�����܂���A���G���U�\�x�e�B�E�A�[�}���̓��̂̍��C�ɁA���͖�������Ă��܂����B�ޏ��ɂ͑��Ɂu�����v�Ƃ����f�悪���邮�炢�Ȃ��̂ŁA�u�A�X�t�@���g�v���c���ꂽ�����łȂ����낤���B���a�\�N���뎄�͌����悤�Ɏv���B���ꂩ�������l�A���̏��D��������Ȃ�A�u�p���h���̔��v�̃��C�Y�E�u���b�N�X�������Ȃ��k���R�l�B���N���݂��������ϔ��̔ޏ��̔������d���������܂��Y����Ȃ��B��l�̏��D�Ƃ��B��{�A�B���̂͂��Ȃ��߂��肠���́A�������������v����̂����m��Ȃ��B���͂��傹����^�̏������A�ǂ����d��Ȉ����^���D���Ȃ悤���B���āA�����̐��̏��D�̂Ȃ�����A������l��I�ׂƂ���ꂽ��A�u���W�b�g�E�o���h�[�𖼎w���邾�낤�B���܂܂łɎ��͔ޏ��̑S��i�����Ă���B�����Ă��̔��������ɁA����������a���ł����B���̊�̑O����A�f���Ȉ����o���h�[�̋������f���������邱�Ƃ��F��A�V�c�����炷���Ƃ̂Ȃ��悤�ɁB���̂Ȃ��̌��̏��D�ƂȂ邽�߂ɂ́A���̂��炢�̋]�����ė~�������̂ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꔪ�`���y�[�W�j
 �@
�@
�剪�����s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�i�������_�ЁA1984�N10��20���A�f�U�C���F�c���T��j��3�y�[�W�k���G�l�Ɍf����ꂽ�̂Ɠ����J�b�g�i���j�Ɓs�A�X�t�@���g�t�i1929�j�ɂ�����x�e�B�E�A�}���k�g���́u�A�[�}���v�ƋL���Ă��邪�A�ߔN�̒ʗp�`�́u�A�}���v�l�i�E�j
����ɑ��đ剪�́A�q����A���`�E�X�^�[�\�\���C�Y�E�u���b�N�X�́u�����v�r�i�s�C�t1984�N1�����j�ƁA���̒����ƕ������˂��q�u���b�N�X�ӂ����сr�i���E3�����j�������A���������킹�A�s�����𐳂������̂ɑ����̎ʐ^�Q�����āA�唻�́s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�i�������_�ЁA1984�N10��20���j�Ƃ��Ċ��s�����i�{�т̌�ɁA���C�Y�E�u���b�N�X��E�l���c���F��q�M�b�V���ƃK���{�r�q�p�v�X�g�ƃ����r��2�т�t���j�B�q���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�r�͑S�W�k��21���l�Ŗ{��42�y�[�W�́A�����Ē����ł͂Ȃ���т����A�����͑剪�����A�S�W�ł͖{�тɑ����Ď��߂�ꂽ�A�q�킪�t�̃X�N���[���E�����@�[�r�A�q�Đ�Í]�@�C�m�Z���g�Ȋ፷���r�A�q�u���b�N�X���ہr�A�q�u���C�Y�v����u���C�[�Y�v�ցr�A�q���ƒm���̂܂₩���̖��́r�A�ƃ��C�k�[�l�Y�E�u���b�N�X�֘A�̕��͂��������c���Ă���B
�@�������\�\�l���c���Ǝ��\�\�͓�x�A�u�p���h���̔��v�����܂����B��x��84�N�t�A�h�C�c�����Z���^�[��Ấu�h�C�c�f����ړW�v�ł̃h�C�c�̃C�M���X�A�o�ŁA������x�͓��{�̃t�B�����Z���^�[�̃A�����J�łł����B�J�b�g�͑O�҂̕������Ȃ������悤�ł��B
�@�������̓t�B�����Z���^�[�ł��A�w��ǂЂƂ��܂ЂƂ��܂݂āA�l�S���̎ʐ^���Ƃ�܂����B���̒�����l���c���Ɠ�l�őI�̂��A���̎ʐ^�Q�ł��B�����������߂Ċ��S�����̂́A���C�Y�̕\��ω����ɂ߂đ��l�ŁA���ʂȖ��͂��܂܂�Ă��邱�Ƃł����B����炪���̖��ӎ��̗̈���h�����A�ޏ���Y�ꂪ�������Ă����炵���̂ł��B�A�C�X�i�[���j�̂����悤�ɁA���x�̒m���ɂ�鉉�Z�ł���A�����ɔޏ��̔������̊J�Ԃł����������Ƃ͂������ł��B�������͂��̊�т�ǎ҂Ƌ��ɂ킩�������̂ŁA�ʐ^�͂ł��邾���������^���܂����B�܂���t�B�����Z���^�[�̎��ɂ��A���̖{�ɋL�^�I���l������邱�ƂɂȂ�܂����B�i�q�����Ɂr�A�s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�A���Z�y�[�W�k�����F���g�l�j
�Ƃ��ɁA�剪�����C�Y�E�u���b�N�X�ւ̈������\�����̂́A�g���̐��z�������������k���S�l�B
�@�Ƃ���œ��{�̏��N���ق�Ƃɂ����̃��@���v�k���u���ƍ��v�Ń��@�����`�m�̕����铬���m��j�ł�����j�^�E�i���f�B�A�u�N���I�p�g���v�̃Z�_�E�o���l�ɖ��f���ꂽ���Ƃ����ƁA�����ł��Ȃ��߂�����B����͒J�菁��Y�̏����̏����ɏo�ė��鈫���Ɠ������ƂŁA���N�����͎�������������Ȕ�����O�l�̏���ɂ���`�����X�͉i���ɂȂ��A�ƒm���Ă���̂ł���B���炭�����̑�l�ɂƂ��Ă������������̂ŁA�����Ŏ�͂₪�ē����ė���h�C�c�f��u�j�[�x�����Q���v�̃N���[���q���g�ɂȂ閺����A�u�v���[�O�̑�w���v�̑�����̃A�X�^�E�j���Z���w�ڂ邱�ƂɂȂ�B�u�֕P�v�̃i�W�����@��O���^�E�K���{�̗J���炪���{�l�̃T�C�Y�ɍ����Ă���B�����������ƂɂȂ邪�A���̈�ԋC�ɓ������O�����D�́u�p���h���̙��k�}�}�l�v�̃{�[�C�b�V���ȃ��C�Y�E�u���b�N�X�ł���B�i�s���N�\�\���鎩�`�̎��݁t�A�}�����[�A1975�N11��30���A�O�Z�܃y�[�W�j
�@�k�c�c�l�i�O�ɏ������悤�ɁA��\��̎�����ԍD���������f��X�^�[�́A�{�[�C�b�V���ȃ��C�Y�E�u���b�N�X�ł���B�j�i���O�A�O�l�Z�y�[�W�j
�g���͂͂����đ剪�̂��̎��`�������A���C�Y�E�u���b�N�X�ɐG�ꂽ��߂��A�ǂ�ł����̂��낤���B�剪�͓����́q���Ƃ����r�i�����Ɂu��㎵�ܔN�H�^���ҁv�Ƃ���j�̍Ō�̒i���Ɂu��ށ\�\����Ȍ��t�����\�\�ɋ��͂��ĉ����������w�Z�⒆�w�Z�̋��F�����A���̂ق������̕��X�Ɍ������\�グ�܂��B�����Ԏ��̂킪�Ԃɂ������Ă��ꂽ�u���|�W�]�v�̒C���l�Y�N�A���G�Ȓ����e�����Ă��ꂽ�ҏW���̓��c�֎q�A������q���N�ɂ������ł��B�v�i�����A�O�Z���y�[�W�j�Ə������B�}���̕ҏW�ҁE������q�́A�����܂ł��Ȃ����W�s�V�������t�i������ӎЁA1962�j�A�s�Ҏ��ԁt�i�v���ЁA1974�j�\�\�q�g�����̑�����i�i5�j�r���Q�Ƃ��ꂽ���\�\�̎��l�ł���B
�k�t�L�l
���ʓW�s�剪�����̐��E�W�t�i���F�����_�ސ�ߑ㕶�w�فA����F2020�N10��3���`11��29���j���I���߂�11�����{�̏T���Ɋς��B�N�z�̒j���q���ڗ��������A���Ƃ�葽���̐l�����l�߂����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�������ŁA��������ς邱�Ƃ��ł����̂͂��肪�����B�{�W�͓����A���N��3��20���i���E�j�j����5��17���i���j�ɂ����ĊJ�×\�肾�������A�܂���̃R���i�Ђ̂��߁A�قڔ��N�x��̊J�ÂƂȂ����i��o�}�^�̉��t�ɂ́A�����̉�����L�ڂ���Ă���\�\���Ȃ킿����Ȃ���������͎{����Ă��Ȃ��j�B�����ł́A���C�Y�E�u���b�N�X�֘A�̂��Ƃ������L���B�qSPOT�\�\���y�E�f��r�Ƃ������R�[�i�[�ɂ́A���v���c�@�l�_�ސ앶�w�U����i�ҁj�̐}�^�s�剪�����̐��E�W�t�i�����_�ސ�ߑ㕶�w�فE���v���c�@�l�_�ސ앶�w�U����A2020�N3��20���j��58�y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă���P�s�{�s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�i�������_�ЁA�k���R�A���łł��낤�l�j�̂ق��ɁA�����[�����̂��W������Ă����B�s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�ɂ͌f�ڂ���Ă��Ȃ��A�_��I�Ƃ������郋���̎ʐ^�ł���i���ʐ^�ł͂Ȃ��A��������|�X�g�J�[�h���j�B���ꂪ�G�t���T�C�Y�́A������̒��F�̖ؐ��t���[���i�ʐ^���āj�Ɏ��܂��Ă���̂��k���T�l�B�C���^�[�l�b�g�ʼn摜�������Č��������̎ʐ^�����Ɍf���A�W�����̐����������p���邱�ƂŁA�L���v�V�����ɑウ��B�ނ����͎B�e�֎~�Ȃ̂ŁA���͂��̏�Ŏ�������������Ȃ��炱��������Ă���̂����A���̉摜���悭����ƁA�G���͓W���̊G�t�����ʐ^�Ɠ��������g���~���O������Ă��āA���Ŋς����̂̓����������ƍ��Ɋ���Ă����悤�ȋC������i���̂ق����f�R�A���͓I���j�B�m�͎��ĂȂ�����ǁB
�Ƃ���ŁA�s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�́A�剪�̐���������̂Ȃ��ňӊO�ɏd�v�Ȉʒu���߂Ă���悤���B�Ƃ����Ă��A���͓�̗�������邵���Ȃ��̂����A��͒������_�ЂŁs�C�t�̕ҏW���߂��{�c�{�h�i1936�` �j�̏،��ł���B�{�c���s�lj��̍�Ƃ����k���t�V���l�t�i���Y�t�H�A2004�j�̑剪�����̑z���o�̂Ȃ��G��Ă���̂́A�s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�����Ђ���o�����Ƃ��l����Εs�v�c�ł��Ȃ�ł��Ȃ��̂����A������l�A���Y�t�H�Łs���{�E�t�̕ҏW���߂�����L�i1938�` �j���s�剪�����̎���t�i�͏o���[�V�ЁA2019�N9��30���j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���̂ɂ͒��ڂ�������B�u�剪�́A�l�E�g�k���N����̗��̑Ώہl�𐫗~�̑ΏۂƂ��čl�������Ƃ͂Ȃ������A�Ə����Ă���B�����ޏ��̂�����Ə䂪�L�т��p���D���������B�U�蕪���ɂ������`�ƁA�����Z���j�̎q�݂����Ȋ������D���������B����ɁA��\��ň�ԍD���������f��X�^�[�́A�{�[�C�b�V���ȃ��C�Y�E�u���b�N�X�������ƒ��߂��Ă���B�^��㔪�l�N�A�w���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�x�Ƃ����|��ʐ^�W�̂悤�Ȗ{���A�剪�����͏o�ł��Ă��邩��i�l���c���F����j�A���ƂȂ��j�܂����Ȃ�B�v�i�q��Z�� ���N����̈Ӗ��r�A�����A��O��y�[�W�j�B�\�\����́u����v�Ə������A�剪�̒��q�ɁA�u���b�N�X�̕��͂��l���c����2�т^�������̂ŁA�剪���|�Ă���킯�ł͂Ȃ��B����A�g�����́A�ƌ����s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�̌��G�ʐ^�́u�����̐l�A�����t�q�B�v�͒f���ł��{�[�C�b�V���ł��Ȃ����i���ꂪ1940�N�A�g���̏o���O�ɗt�q����n�����ʐ^�Ȃ�A�ނ���N�����A�Ƃ����������N��ȏ�ɐ��n�������Ɍ�����j�A�g���̑z���̂Ȃ��ł́A�����t�q�Ƃ������݂̓��C�Y�E�u���b�N�X�ɒʂ�����̂��������̂�������Ȃ��B
 �@
�@
�u���C�Y�E�u���b�N�X�̏ё�����ʐ^�����^�剪�������������́B�^�l���v �k�s�剪�����̐��E�W�t�i���F�����_�ސ�ߑ㕶�w�فA����F2020�N10��3���`11��29���j�ɂ�����������l�i���j�Ɓs�剪�����̐��E�W�t���̌����_�ސ�ߑ㕶�w�فi�E�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�k���P�l�@�u�u���N�v�̍Z�����I���āA�������肵�Ă���Ƃ���ł���B�v�Ǝn�܂�剪�́q�u���N�v���ڂ�b�r�̓�߂̒i���́u��N���u���|�W�]�v�ɘA�ڒ��A�ҏW���̒C���l�Y�N�ɁA�Ȃ�ǂ�����}���ق֒ʂ��Ă�������B��������ɋ�\�㗢����̋��F�̊O�R�ܘY��K�˂��肵���B���́u���`�v�̏������́A�����̋L�������ɂ͂�炸�A�\�Ȃ����蕶����،����W�߂āA�L�����C�����邱�Ƃ������̂Łi���̕��@���������������͖�킸�A��������Ă��܂����̂ŁA���Ԃ��悤���Ȃ��j�悯���C���N���킸��킷���ƂɂȂ����̂ł���B�v�i�s�����܁t��80���A1975�N12���A�Z�y�[�W�j�ŁA�����̖����ɂ́A�V�n����i�g�̉��i���A���E���{��4�s���̃X�y�[�X�Ɍr�݂͂Łu�剪�����@���N�@���鎩�`�̎��݁^�艿��܁Z�Z�~�^�i��������ŋߓ����s�j�^�}�����[�v�Ƃ������ЍL��������i�k��������Łl�̑������i�C�j�B���̂��Ƃ��画������悤�ɁA�q�u���N�v���ڂ�b�r�́A�剪�����̔N11���Ɋ��s�����V���s���N�\�\���鎩�`�̎��݁t�̃v�����[�V���������˂Ă��āA�s�����܁t�̌��e�˗��͑剪�̒S���ҏW�ҁE�C���l�Y����Ȃ��ꂽ���̂ł͂Ȃ����낤���i�q�u���N�v���ڂ�b�r�͒P�s�{�s���N�t�ɋ��ݍ��݂́u�t�^�@���a51�N1���v�\�\175�~111�~�����[�g���̓�܂�4�y�[�W�̖����Ɂu�i�������a50�N12�������j�v�Ƃ���\�\�Ƃ��čĘ^����Ă��邪�A���������̂́u���a�\��N�O���O�\����Z���v�{�ŁA�O�N11��30�����s�́u�����v�ɕt���Ă������͕s���j�B���Ȃ݂ɒC���́A������b�q���G��Ă���s�剪�����S�W�t�i1994�N10���`2003�N8���j�̒S���ҏW�҂ł�����B�s�剪�����S�W�k��23���l���E�G�[�E�����t�́q����24�r�̏I���Ɂu�i�ҏW���j�v�Ƃ��Ď��̂悤�ɂ���B�u�ŏI��z�{���\�O�������͂��v���܂��B�����܂łɔ��N�\������v�������ƂɂȂ�܂��B�ǎ҂̊F�l�ɂ͂����ւ��f���������v���܂����B�S��肨�l�ѐ\���グ�܂��B�^���̊Ԃɖ{�S�W�ҏW�ψ��̏��J�Y������A�g�c凞������������܂����B���߂Ă����������F��\���グ�܂��B�^�{�S�W�ɗl�X�Ȍ`�ł����͂����������F�l�y�ъW�@�ւɐ[������\���グ�܂��B�v�i������A���y�[�W�j�B�Ȃ����S�W�̕ҏW�ψ��́A��]���O�Y�E���쏺���i��l�͂��̍ŏI���̌���ő剪���w�ɂ��đΒk���Ă���j�A�����ď��J�Ƌg�c�̎l�l�ł���B
�k���Q�l�@�q���l�̌��t�r�Łu�قƂ�ǂƌ����Ă����قNj��ʓ_������Ƃ͎v���Ȃ����l�k�g�����l�Ə����Ɓk�剪�����l�̑S�W���d�Ȃ��������ɓǂނ��ƂɂȂ����̂́A���̎d����̓s���ɂ����Ȃ��̂����v�Ə�����������b�q�́A�}���Łs�剪�����S�W�t�́k��22���l�ɉ���q�u�����Ɓv�ł��邱�Ɓ\�\���邢�́u�Ђ�����Ȍ��݁v�r���Ă��āA���́k��22���l�̎傽����e�́s���邾���t�O����ł���B�剪�́s���邾��� �U�t�i���Y�t�H�A1983�j�Ɏ��̂悤�ɏ������B�����̂��߂ɁA�i���̏��߂Ɋے�������U��B
�@�k��㔪��N�l�ꌎ�\����@���j���@��
�@���A��l����g�̐���N����A����W�ō����B�ŏ��͕]�_�V���[�Y�������b���A����������������W�ƂȂ�B�������N�O�������_�ДőS�W�̍ۂɂ́A���Z�ɂāA�ו����������Ƃ͂ł����B���܂͎d�����Ȃ���A��������������Ƃ��B������i�͏��o�ɂ��ǂ��A����͒����B
�A����A�V���Д~��N�Ɂw�Ȃ������x�̒����e��n���B�����v���Y�����s�̃K���ŕ��W�w13���S���x���̉��c�����M�̕��́A���~�q���w�����v���Y��13���S���x�ɂ���B�����͐V���Њ��s�Ȃ�Γ����W�ؗp�A���̑���⎁�̖{���̎g�p�������ށB�V���A�ڒ��X�y�[�X�Ȃ��Ȃ�A�Ȃ�����}�b�Ȃ�B��⎁�ډ��C�O���s���B
�B�\�Z���A�u�k�Џo�ŕ��A�����N�A�u�Q���v�ē��N����B�����N�Ɂw�����A����̎��x�𗊂ށB�M�҂͎��l�Z���^�t�u���㎍�蒟�v�\���ɕ֗����A���N��ւ��Ă���B�����Ɂu�N�ԉ�ڍ��k��v���̂����펟�n��������B���N�����N������M�v�A�g�{�������̑Βk�Ȃ�B�Ƃ���ō��N�͑Βk���������ۂ��B���q�����̐펞���̕���s�A���͎��̖�肠��B�w�����A����̎��x���́u���l��c�v�Ȃ���̂́w���d�̎O�\�N�x�̋L�q�ԓx�A�g���܂��߂���Ȃ܂������̘b�ނ���������Ƃ����B�펟�n���������āw�����x���Q�����̂̂Ȃ�B���d�̔h���̊ԂɌނ��Ď����ҏW�҂́A��J�A���d�̔�ɔA�Ƃ̂��ƂȂ�B�@�����x�܂��c�肠��ɔ�B
�C�k�c�c�l
�D�k�c�c�l
�E�k�c�c�l�i�s�剪�����S�W�k��22���l�]�_�\�t�A�}�����[�A1996�N7��23���A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
�{�e�̎�|���炢���Ă��A�A�Łu���k�~�q�l���̖{���̎g�p�������v�߂Ă��闥�V���ɂ͊��V������Ȃ��B�������A�������̓��̋L�ڂɊS�����̂́A�B�Łu�w�����A����̎��x���́u���l��c�v�Ȃ���̂́w���d�̎O�\�N�x�̋L�q�ԓx�A�g���܂��߂���Ȃ܂������̘b�ނ���������Ƃ����v�Ɍ�����u���d�̔h���v�ɑ���剪�́u�펟�n�����v���B�ނ��͋g�������������A���̈ꌏ�ł���i�q�u�g�������v�Ɩk�쑽��q���W�s���t�̂��Ɓi2012�N1��31���j�r�̖������Q�Ƃ��ꂽ���j�B�剪���^�Ō㗪�����C�`�E�̒��S�I�Șb��́A�剪�́s�V�n�g�t�ƁA���̐����ɓǗ����������͑��Y�́s����杁t�ŁA�剪�͌��ǁA�g���̖��������Ă��Ȃ��B
�k���R�l�@�s���܂�͂����L�t�Ɉ˂�A�g���̓��C�Y�E�u���b�N�X�́s�p���h���̔��t��1939�i���a14�j�N5��13���̓y�j���A�_�c�̓얾���ŊςĂ���B�ڍׂ��q�s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ��f��\�\�g�����Ɖf��i2�j�r���Q�Ƃ̂��ƁB
�k���S�l�@1996�N�H�A�_�ސ�ߑ㕶�w�قŊJ�Â��ꂽ�s�剪�����W�t�ɍ��킹�đ剪�̐l�ƕ��w�ɂ��Č�����l���c���F�́q�剪�����ƃt�B�����w�p���h���̔��x�r�Łu�����k�w���N�x�Ƃ������`�l�ő剪�����C�Y�E�u���b�N�X�Ƃ������O���������͈̂�㎵�ܔN�A���̂Ƃ������Ԃ�͂��߂Ă������Ǝv���̂ł����A�ޏ��ɂ��āA���ꂩ��\�N�قǂ����Ă���A�ނ͂ق�Ƃ��ɂ��M�������āA�Ȃ�ƈ���̖{�������グ�Ă��܂��܂��B�v�i����F���ҁs�剪�����̎d���t�i��g���X�A1997�N3��12���A��O��y�[�W�j�Ǝw�E���Ă���B�l���c�͂܂��A�剪�����s���w�̉^���k�u�k�Е��|���Ɂl�t�i�u�k�ЁA1990�N2��10���j�̐l�ƍ�i�ɂ��Ẳ���q�N���҂̓��f�r�Łu����Ƃ��A�킽�������͎��Ԃ�҂����킹�āA�ނ������I�قǑO�Ɋς�����Ƃ����p�u�X�g�́w�p���h���̙��k�}�}�l�x���t�B�����Z���^�[�Ŋς��B���������ƂɁA�����������Ό����o�߂��Ă���Ƃ����̂ɁA�剪�����̍ו��̋L���͂͏��������ނ��Ă��炸�A�ނ��t�B���������������O�Ɏ��M�����G�b�Z�C�͂قƂ�lj�����������]�n���Ȃ������B�v�i�����A�O��Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B�����g�����̐��z��ǂނƂ��Ɋo����̂��A����Ɠ��������ł���B�������q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r�����̗�ɘR��Ȃ��B�剪���l���c�́s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t����ɂ����ɈႢ�Ȃ��g���́A�͂����Ăǂ�Ȋ��������������낤���B
�k���T�l�@�����炭���̊G�t���ɂ��āA�剪�����́s���C�Y�E�u���b�N�X�Ɓu�����v�t�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u�u�p�v�X�g���v�̕���̓t�����X�̉f�掏�u�|�W�B�e�B�t�i�z��j�v�k19�l58�N2�����ɍڂ��Ă���B����͔ޏ��̓n���̔N���ƈ�v���Ă���A�\���ʐ^�͎Ⴋ���̔ޏ��ł���B���炭1930�N�Ƀt�����X�ŎB�����u�~�X�E���[���b�p�vPrix de Beaute�̈�R�}�ł���B����������ŁA���܂����֒�����Č�����i���̍�����ޏ��̓��قȗe�e�����ڂ��ꂽ�炵���A�s�[�^�[�E�O���n�����w�f�掫�T�x1963�`68�N���̕\���ʐ^���u�p���h���v�̈�R�}�ł���j�B���݂Ȃ��A�ޏ��̃u���}�C�h���G�t���Ƃ��Ĕ����Ă��āA���͂��̓�@���k�d�F�l�����炢�����������A�u�Ō����L�v�ƒ��L����Ă���B���̉f�悩��̕��������炾�낤�B�p���͐�Ђ��Ȃ������̂ŁA�p�v�X�g�̓�̍�i�k�u�p���h���̔��v�i1929�j�Ɓu�˗��̏��̓��L�v�i���N�j�l��肢���R�s�[���c�����Ǝv����i83�N���A�����J����A������]���O�Y���ɂ��A�T���t�����V�X�R�Łu�p���h���v�̂��ꂢ�ȃR�s�[���������ꂽ�Ƃ����j�B�v�i�����A�O��y�[�W�j
 �@
�@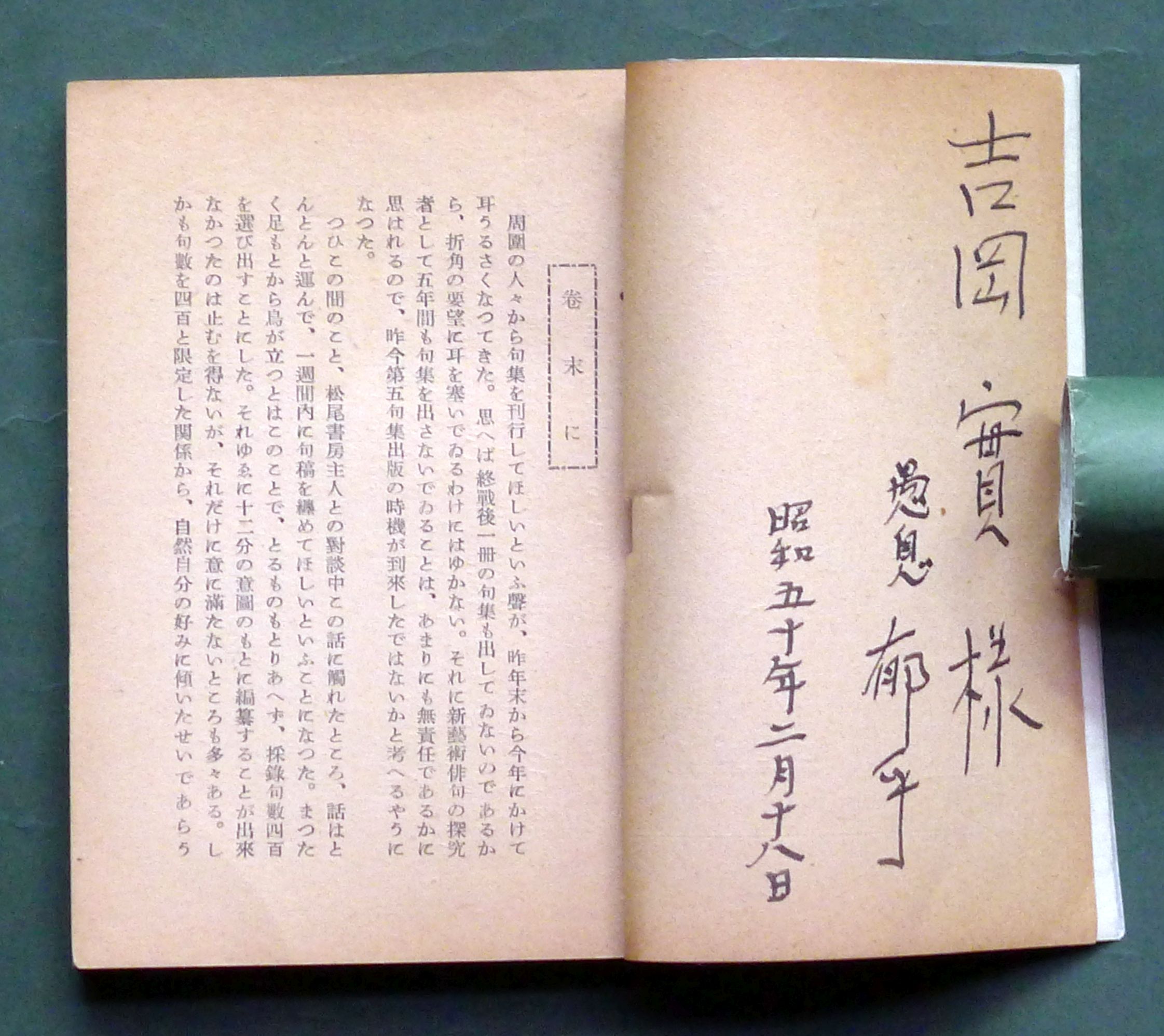
�������M��W�s���A�k�������Ɂl�t�i�������[�A1950�N6��25���j�̕\���i���j�Ɠ��E��������ɂ��y�������̌���E�����y�[�W�i�E�j
2020�N7���A�s���{�̌Ö{���t�o�R�ŏa�J�̒������X����������M��W�s���A�k�������Ɂl�t�i�������[�A1950�N6��25���j���w�������B�{�����Z�y�[�W�̕��ɖ{�ŁA�����Ɂu�g�����l�^�� ����^���a�\�N�\�����v�ƃy�������œ��t����̌���E����������B�厏�s�t���t����ɂ������M�������f�i1904�`1950�j�̎q���E����������g�����ɑ�������{�ł���B�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�{���͔��i���̗��Ɍ���E����������j���߂���ƁA�����Ȃ�q�����Ɂr�Ƒ肵�����҂̕��͂�����i�����ɂ́u���a��\�ܔN�O���\����^���ҁv�Ƃ���j�B�ȉ��ɁA������V���ɉ��߂Čf����B
�@���͂̐l�X�����W�����s���Ăق����Ƃ��Ӑ����A��N�����獡�N�ɂ����Ď����邳���ȂĂ����B�v�ւΏI������̋�W���o���Ă�Ȃ��̂ł��邩��A�܊p�̗v�]�Ɏ����ǂ��ł��킯�ɂ͂䂩�Ȃ��B����ɐV�|�p�o��̒T���҂Ƃ��ČܔN�Ԃ���W���o���Ȃ��ł�邱�Ƃ́A���܂�ɂ����ӔC�ł��邩�Ɏv�͂��̂ŁA������܋�W�o�ł̎��@�����������ł͂Ȃ����ƍl�ւ�₤�ɂȂ��B
�@�k�c�c�l
�@�@��A���̋�W�͑���W�u�X�сv����W�u����̂��ނ�v�A��O��W�u��Áv��l��W�u���{���v�̂��Ƃ���������܋�W�Ƃ��ӂ������ɂȂ邯��ǂ��A�����ȑ�܋�W�̗�����͂Ȃ�A�t�������ԐV�|�p�o����A�������M�̋ߋƂ𗝉����Ă����U����낵���Ƃ��ӂƂ���ɁA�{��W�u���A�v���s�̈Ӌ`��u�����ƁT�����̂ł���B���̓_�Ɋւ��āA���̋�W��ㆂ��Ă���A�t���̔o��|�p���A�����ŋ߂̔o�l���M���ޖ��Ɍ������Ăق����Ɗ�Ă�鎟��ł���B
�@�Ō�ɖڎ��Ɏ������匩�o���ɂ��Ĉꌾ���Ȃ���Ȃ�ʂ��A�u�_���T�v�͓�\�l�N�̍�A�u�S�]�т��v�͓�\�O�N�̍�A�u��������v�͓�\��N�̍�A�u�D���v�͓�\��N�̍�ł���B�܂��N�X�X��邽�߂ɁA�E�̂₤�ȕ\���݂����ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�i�����A�k�O�`�܃y�[�W�l�j
�����ɂ���u�ڎ��Ɏ������匩�o���m�A�A�A�A�n�v�͖{�����̔��ɋL����Ă��邾���ŁA�匩�o���Ƃ��̃m���u�����f�����q�ڎ��r�͂Ȃ��B��f���p���Œ��������ӏ��ɂ́A�������[��l�i�����P�q�j�Ƙb���Ă��邤���Ɂu��T�ԓ��ɋ�e���܂Ƃ߂Ăق����Ƃ��ӂ��ƂɂȂ��v�Ƃ���A���҂͏[���Ȑ���E������Ԃ��Ƃ邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���̕��́i�����^��H�j�Ŏ��M�͎����̌��N��ԂɐG��Ă��Ȃ����A���M����8�ӌ����1950�N11��5���ɟf���Ă���̂ŁA�Ȃɂ��ɋ}�����Ă���悤�ɂ��ċ�W���܂Ƃ߂����Ɍ�����B�e�\��ɂ�����`���̋�������B
�������Ƃ��ɐ��҂̂Ђ��肠��@�@�i�q�_���T�r�j
�t���O�͂��炳��k�����F���̎��_�l�N������������@�@�i�q�S�]�т��r�j
�����֓��ւ֑��������@�@�i�q��������r�j
���z�͂����ɏ��ׂ̑D�����ʁ@�@�i�q�D���r�j
��Ȃ��Ƃ����A���́u�������������ŕv�w�炵�v�i�q�_���T�r�j�̋傩��A�g���́u��҂̎��̊O�ꂽ�Ƃ���Ł@���߂đ����璭�߂悤���^�̉Ԕ��̂Ȃ܂Ȃ܂����v�w�Q���v�i�q�t�r�G�E4�j�Ƃ��������z�N�����B�����Ƃ��A���̋���܂߂ċ�W�̂ǂ��ɂ��i�g���ɂ��j�������݂͌����Ȃ��B�Ƃ���ŁA�������M��W�s���A�t�������������g�����ɑ���ꂽ�ɂ��ẮA���̂悤�Ȍo�܂��������ƍl������B�܂��A�g�����E��������E�߉ϑ��Y�E�ѓ��k��E�g�������ɂ����k��q�����������錻��̎��\�\���k�`���ɂ����W�q�����̉́E����̎��r�r�i�s�Z�́t1975�N2�����j�́q�o���E�ߋ��E�C��܂𑖂�r�̃p�[�g�̈ꕔ�������B
�g���@�������͂ǂ��ł����A�o�g�́B
�����@����A�ڂ��͉�Â��ƌ����ė������A�C���`�L�ł���B���܂ł��A���k���ƐM���Ă�F�l������炵���ł��ˁB���܂�͓����Ȃ�ł��B�킽���͖ڔ��̋߂��B
�g���@��������A�����Ȃ�B�ڂ��́A�������l���Ǝv���Ă��B
�����@�C���`�L���D��������ˁB��Õق��q���̍��Ɋo���Ă����Ŏg�����肷���ł���B���x�A���Ђ����_���������Ƃ��ɋ����ň�����ƃo�����܂�������ǂ��ˁB�����Ȃ�ł���B������͖̂L�ʌS�ƌ����Ă�����ł��ˁB�����{�c�c�{�̒��ł��s�O�Ȃ�ł���B
�g���@��������̑ォ��ł����B
�����@�e���͉�Â̐l�Ԃł��B���ꂪ�]�˕��w�Ȃ̂ɔ��Ց����_�Ȃ�ł���B������A�q���̂Ƃ��ɂ͑��܂͂͂����ĖႦ�Ȃ����ˁB�u���Ց��̎q�����ȂI�v�ȂI�@���Ă��������āA�~�����̂ɑ��܂��͂��Ȃ�������ˁB���������X�p���^���炾���Ȃ��ɂ���܂�����B�����Ďq���̂Ƃ�����e���̐��ƂƉ��������Ă��܂�������A��ẤB����Ő����ς�����肷��Ɖ�ÕقŃC���`�L�V�т�����ł���B
�g���@�������ɕ��������Ƃ�������ǃT�A���̊ԌÏ��W�ł�������̋�W�w�X�сx�Ƃ����̂��܂����B
�����@�w�X�сx?!�@�E���b�[�I
�g���@�킩��Ȃ��A���O���B���M�͒m���Ă������ǁA���ꂪ����̂������A�����E��E���t�����Ă��킩��Ȃ��B�����̂��̎����Ȃ���B�t�����Ƃ����̂ˁB
�����@����͐e���̑���W�ł���B�O�\�������ł��傤�B
�g���@����͉�������̂�������Ȃ����Ǝv���ēǂ݂܂����B�o�l���̐l���A�q�������܂��Ƌ��̂�����ł��傤�B����Œ��ׂĂ�������A�Ƃ��Ƃ���������B���a�l�N�̂Ƃ���ŁA�ꌎ�O������o�����u��x��x��������V�Ɏ��Ă���q�v�B
�����@����͂���́A�e�q�ɂ킽���Ĕ����Ă��������Ă��肪�Ƃ��������܂����B�i�j�e���A���ł��܂���B�i�����ł^�����āj
�g���@��W�̑O���̂ق��������ȂƂ������������ł��ˁB���x�������ɃT�C�����Ă��炨�����ȁB
�����@���F�̔��́c�c�B���̂���ł͒��J���]�q�̖��@�����肵�Ă��܂��ˁB
�g���@�ŁA�Ⴍ���ĖS���Ȃ�ꂽ��ł����B
�����@�����A�킽���̂��Ɠ�Ŏ��Ⴄ��ł���B�l�\���Ŏ��ɂ܂����j�ł�����ˁB��䑴�p�Ƃ����o�l������ς�l�\���Ŏ���ł��܂��B�����݂ł�������ˁc�c�B���ΓC�̒�q�̂Ƃ�������܂����B
�g���@����͂ق�Ƃ��ɋ��R�̏o��ł��ˁB
�߉��@�ΓC�̒�q����A���������Ȃ��Ă܂��߂ȁc�c�B
�����@�����A�����c�c�B�i�j���ܐe����������A�Ԃ�Ȃ����Ă��܂���A�s�т̘�́B�i�j�D���ȋ傪�ΓC�ɂ͂���܂��ˁB�q������ɖ�e�̐����ꋏ��r�q�H����͗l�̂����ӎM��r���������̂��ΓC�ł��ˁB���̊ԐΓC�搶�̖��S�l�Ƃ͂��߂Ă��b��������ł����A��N���炢�����Ė���Ă����炵���ł��ˁB
�g���@�����Ɨ�����������́A��������́B
�����@�����Ȃ�ł���B�H�����߂���������ł��傤���ǂˁB�_�҂ɂȂ�ƐH�ׂ��܂�����ˁB�o�~�j����������̂��R�����Ƃ������܂̐X�L�O�搶�ȂƓ����ō]�˕��w�Ȃ��̂ł����炫���Ɩ�������ł���B�g���N�݂����ɁA���߂�낤���A�ǂ����悤���ƁB���߂�����̂���s�N���B����Ō��ǂ͔o�~�ɍs���킯�ł��ˁB�Ƃ��낪�A����Ȋw��������Ȃ��Ȃ����V�H���Ȃ�����A�_�҂ɂȂ����������ł���B����ŏ������H�ׂ���悤�ɂȂ��āA�����ō��߂����̂悤�ł����B��́A���w�ȂI�̂œc�ɂ̉Ƃ��������ꂽ�j�ł�����B
�߉��@���������Ƃ���͂�͂茌�ł��ˁB�i�j
�����@�o�~�t�Ȃ�Ĉ��ł�����ł���B�ѓc�����ɂ͂Ȃ���ǂ��A��┐搶������A�����c�c�B������Ƃނ������Ƃ���������ǂ��B�i�j���q�ɖ������āA���엧�q�����ĂȂ��Ă�������ǂ��A���w�͈�ォ����A�o�~�Ȃ�Ă����̂́A�������ł�����ł���B������O�̏��m�ł���Ȃ��ƂɂȂ����Ⴂ�܂����B
�g���@�����ǁA�e����o����A�o���̂ق܂�Ƃ͌����Ȃ����낤���ǁA����͂���������Ă��A���傤���Ȃ���A��������Ɉ�������ǂ��B�i�j
�����@�e����m���Ă�l�����́A��̂킽���̂��Ƃ��������낭�Ȃ��炵����ł��ˁB�c�c���܂ɖ@���Ȃʼn�ƁA�������Ⴄ���ǂˁB�i�����A���Z�`����y�[�W�j
���q�̈���́A�t�������M�̋�W�s�X�сt�����߂ēǂ�ł����g���Ɍh�ӂ�\���āA�������M�Ō�̋�W�s���A�t���������킯�ł���B�v���g���́A1966�N2��1���Ɉ���Əo��܂��A���́s��铊��S�t���s�����ƂՂ炷�܁t�����łɔ������Ƃ߂ēǂ�ł����̂�����A��������̔o��D���������Ƃ����悤�B�s���A�t���率�M�̋��������B
䕏n��T���̒���͎q�̂��̂�
���C���c�N�炯���~��ΐ��~���
������ԕ��̂��Ƃ����ɂق�
�@�@��Q�A�Ⴊ�q������藈�锤�Ȃ�������Ɍ�����
�H�̕������Ĉ�q��҂ƂȂ�
��l���Ĉ�l�����q�₦�Ă���
�������M�̑���W�s�X�сt�͗e�ՂɌ��邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ��̂Łi��������}���فA�o�啶�w�فA���{�ߑ㕶�w�قɏ����Ȃ��A�q���{�̌Ö{���r�ɂ��A�qAmazon�r�ɂ��o�i���Ȃ��j�A�ւ����t�������M�s�o��O�\�u�t�i��c�ו����A1931�N10��3���j�����߂��B�Ō�̋�W�����ǂ����ł́A�Ȃ�Ƃ��S���Ȃ��̂��B
 �@
�@
�t�������M�s�o��O�\�u�t�i��c�ו����A1931�N10��3���j�̕\���i���j�Ɠ��E�{���i�E�j
�O�f���k��̉�������̔����ɂ��o�ꂷ��ѓc�����i1920�`2007�j�ɂ́A�s�o�����O�\�O�u�t�i�u�k�Њw�p���ɁA1986�E�u�k�ЁA2015�k�{���g�ł͍u�k�Њw�p���ɔłɓ����l�j������B�����̔o�厏�s�_��t�̗��̎���w���̂Ȃ�����I�肷�������o�_�E�o�b�i�s�����o�勳���t�s�����o���@�t�s�����o��ӏ܁t����33�т�҂̂͊w�p���ɕҏW���j�������I�ȏ�O�̎��M�̏����Ǝ��Ă���̂́A���R�ł���Ƃ��������A�������낵�ł���������̔��ł���A�ЂƂ�̔o���Ƃ����g�̍l����o��̑S�̑��������ƂȂ�ƁA�����Ɓu�o�偛���u�v�Ƃ����`���Ƃ邽�߂ł͂Ȃ����B���M�́s�o��O�\�u�t�́q�ڎ��r�͂����ł���B�i����͏��т��t�������́j
��@�o��̊T�O
��@�ǂ�Ȉ�ۂ��o����\�����邩
�O�@�ǂ�ȕ��Ɍ�����o��ɂȂ邩
�l�@�o��̌��t�ƕ����̎g�p�ɂ���
�@�@�@�� �V����ɂ��ā@��
�܁@�G��i�G��j�ɂ���
�Z�@���̏o�����܂�
���@�o��������ɂ���
���@������r�ޔo��ɏA��
��@�V�����r�ޔo��ɏA��
�ꁛ�@�n�����r�ޔo��ɏA��
���@�l�����r�ޔo��ɏA��
���@�@�����r�ޔo��ɏA��
��O�@�������r�ޔo��ɏA��
��l�@�A�����r�ޔo��ɏA��
��܁@�o��ɋ��n�Ƃ��ӂ��ƂɏA��
��Z�@�o��̎���ɏA��
�ꎵ�@�����̔o��ɏA��
�ꔪ�@���z�I�Ȕo����r�ނɏA�ā@��
���@�o��̖͕�ɏA�ā@��
��Z�@�o��̕i�ɏA��
���@��m�B�n�E���ȁm�B�B�n�ɏA��
���@�o��̉����ɏA��
��O�@�@��ԏ�D��̔o�吧��ɏA��
��l�@�o��݂̍�Ƃ���
��܁@�����̂���o���
��Z�@�g�ł��Ȃ��o��@��
�@�o��ɉr�ޔ��͂ǂ����Đ���ė��邩
�@�o��̏�B���v��l�͂悭���͂�����
���@�o��]�߂̎d���ɏA��
�@�@�@�@�i�C�j�o���]�߂���l�̒���
�@�@�@�@�i���j��Җ{�ʂ̕]�߁@��
�@�@�@�@�i�n�j��i�{�ʂ̕]��
�O���@�o��]��
�@�i���^�j
�@�@�@�o��G��ꗗ�\
���́����t�����u���Ƃ�킯�����[���ǂi�q��Җ{�ʂ̕]�߁r�ȂǁA��Ƙ_�Ə̂��Ă��镶�M�Ƃ̍�i�Ɛl����T�����悤�Ƃ���l�ԂɂƂ��āA����̈�j�ł��낤�j�B�ȉ��ɁA���̓����I�Ȓi����������B���̎��_�͂��ȂɊJ�����B�i�@�j���̐����͖{���̌f�ڃm���u���B
�q�V����ɂ��ār
�@���ɖ�L�ɗ��s���o�����Ƃ���̐V����ɏA�Ĉꌾ�\�グ�܂��B���̂ɗ��s���Ă�邩�Ɖ]�Ђ܂��Ƃ����ɂ͓�̗��R�����݂��ċ���܂��B���̈�͔o��͗]��ɂ����t���Z���߂��邩��܊p���Е\�͂��������Ƃ��Ɍ��Њ܂߂邱�Ƃ��o���Ȃ��B�����Ŏ~�ނȂ����玩������ɏn��Ȃǂ����Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�܂��B������͎����̔o������ɂ��čݗ��̕�����p�ЂĂ�Ă͂Ȃ��Ȃ����l�̊�������Ȃ��B�����Ŋ�ȏn��Ȃ���������ɍ�Ă䂭�Ƃ��ӂ��ƂɂɁm�}�}�n�Ȃ�܂��B�������Ӑl�͏o�L�ڂȏn�����Ă�Ȃ���A���������Ɠ��Ȕo���Ԃݏo�������̂₤�ɓ��Ӗ��ʂł�܂��B�i52-53�j
�@�v����ɔo�����炤�Ƃ���l�̉b�q���X����l�֏o���Ď������������邱�ƂɓK���������t�ɍ��グ��̂ł���܂�����A�]���̒��ӂ͂Ȃ��Əo�L�ڎ��Ȃ��̂ɂȂ菟���ł���܂��B��ɕ��Ր����Ȃ���Ȃ�܂��A�꒲���悭�Ȃ��Ă͂����܂��A�����ɕs���a�ȂƂ��낪���Ă͂Ȃ�܂���A�����N���ǂ�ł������Ė����Ȃӂ����Ȃ��āA�v�͂������̌a�ɓ����₤�łȂ��Ă͂����܂���B�i55�j
�q���z�I�Ȕo����r�ނɏA�ār
�@���̌��z���킴�킴��藧�āT�����ɖ��Ƃ������Ɖ]�Ђ܂��ƁA��҂̖����Ă��₤�ȐS�����悭�\�͂��̂ł���܂�����A���R���l�̔��ʂ������邱�ƂɂȂ�̂ł���܂��B�����ēǎ҂������z�E�ɗV���Č����Ƃ��ӂ��ƂɂȂ�܂��B���ݔ���ȕ��ʎʐ��̋�ɖO���Ă��l�X�ɂ悫����k�����Č����ł��炤�Ǝv�Ђ܂��B�ǎ҂ɂ��悫������^�ւČ����Ȃ����͂��悫��i�ł��邱�Ƃ��܂��B���ɉr�܂ꂽ���z�̔o��͋���������ǎ҂ɓ�������ł��炤�Ǝv�Ђ܂��B�i313�j
�@���z�̔o�����炤�Ƃ���ӎ��Ȃ����Č��z�����܂ꂽ��ꍇ�ɔV��o��ɉr�܂��Ɠw�߂邪�X�����̂ł���܂��B����Ȃ��Ƃł͖قĂ�Č��z���N���͂��Ȃ��ł����Ƌ^�͂�T�������邩������܂���ǂ��A�����Č��z�E��`���o�����Ƃ��Ȃ��Ƃ����z�E�͓Ƃ�łɗN���Ă��邱�Ƃ��x�X����܂��B���̂��Ɖ]�Ђ܂��ƁA�o����r�܂��ƂȂ�����X�͂��낢��Ȃ��Ƃɒ��Ӑ[���ώ@����A�����Ă��ꑊ���ɋ��n��[�߂₤�Ɠw�߂ċ����܂�����A���鎖�����[���Ȃ��Ē����Ɍ��z�E��ڂ̂�����ɕ`���o����T�₤�ł���܂��B�����ܘ_�����Č��z��W�J���₤�Ƃ���C�͂Ȃ��Ƃ����R�ɓW�J������̂ł���܂��B�i319�j
�q�o��̖͕�ɏA�ār
�@�}���͕�Ɖ]�Ђ܂��Ă����x�̖��ł���܂�����A���l�̔o��ƑS�������o������l�����邩�Ǝv�ӂƁA�ꎚ�݈̂ق��o������l������A���͂ق�̋͂���^������ʂ̐l������܂��B�ܘ_�A�͕킷��Ƃ��ӈӎ��ϔO���Ȃ��Ė͕킵���₤�Ȕo��ɂȂ��̂ł���Βv����������܂��A���ꂪ�ǂ�����A���ꂪ�悢����Ɖ]�Đ^�������o��ł����Ȃ����͐r���s�^�ʖڂȌF�x�̔o��ł���A��i�̉��l�͗�ł���܂��B�͕�����̂₤�Ȗ͕�ł���܂��Ȃ�A���̐l�����Ȃ̋��n��[�߂�ׂ߂̘H�łȂ���Ȃ�܂��犸�ċꌾ��\�グ�邱�Ƃ͏o���܂���B��ւΖ^���Ɏ��i���Ă�邪�ׂ߂Ɏ��R�^���̔o������邱�Ɠǂނ��Ƃ������Ȃ�A���͖ʐڂ���₤�ȋ@������Ď�X�Ɣo��̘b�Ȃǂ����ċ���Ƃ��납��A�s�m�s���̊Ԃɖ^���̋啗���ڂ�A�������r�ލ�i�ɂ��^���Ɠ��̕\���@�Ȃǂ��M���͂��Ƃ��ӂ��Ƃ�����܂��B����͂₪�Ď����̋��n��A�����̋啗�����Ă�ׂ߂̓����ł���܂��B���̐l�͖^���̒��������ȂĎ��Ȃ̋��n��[�߂�Ƃ��Ă��̂ł���܂��B�i328-329�j
�q�g�ł��Ȃ��o��r
�@�@���Ɋς��ꍇ�A��ɉf�����ۂ△���Ȃ����Ē����ɃA�^�}�ɓ͂��ċ傪����ė���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B��͒P�ɉf�邾��������O���̈��������Ŏ悷��ɉ߂��܂���B���ꂪ�\����������ēZ�߂�ƁA�������́T�ł��Ĕo��Ƃ͂Ȃ蓾�܂���B��̂�����̎��z������o���Č���Ȃ��Ɣo����Ȃ��܂���A���T�ɒ��ӂ��邱�Ƃ���ł��B��Ǝ��z�̃A�^�}�Ƃ̋����Ɋu��̒����l�́A�Ⴕ�ڂɉf������̂��ꎩ�g�������Ɍ��́U����Ȃ��ɃA�^�}�w�͂��Č���邾���̗͂���ւĂ����̂����琢�b�͂Ȃ��̂ł����A��̑R�炴��ꍇ�̕��������Ƃ��Ӑl�X�͎~�ނ܂���A�ڂɉf�����̂�������x�ϒ������邱�Ƃł��B��������Ɨǂ��ꈫ�����ꉽ���A�^�}�w��ۂ���Ƃ��낪����܂��B�i396-397�j
�q�o��]�߂̎d���ɏA�ā\�\��Җ{�ʂ̕]�߁r
�@��Җ{�ʂ̕]�߂͂悭��҂ׂĕ]�߂������̂ł���܂�����A�Z�����Ȃ����Ɖ]�Ђ܂��ƁA�����Ă����ł͂���܂���B���ɏ��w�҂���Җ{�ʂ̕]�߂ɌX���ꂽ�錋�ʐ����镾�Ƃ��ẮA��i�̉��l�@�������O�ɂ��č�҂��̂��̂��ߏd�����邪�ׂ߂Ɍ���]�߂�^�ւ邱�ƂɂȂ�̂ł���܂��B
�@������҂��悭�m�ċ���܂�����A�N����̍�ł���Ȃ�Ή���肾�Ƃ��A�^�͔o�d���r������̐l�ł������牺��ȍ�i���Ȃ��Ƃ��A�ނ͎��ɐ^�ʖڂȐl���ł������犊�m���݂��o��Ȃǂ͍��ʂƂ����ӈӎ��̉e���������āA�o��̕]�߂Ɏ�������ʂ����ɍ�҂̖��������U���ő�}��҂̉��l�����߂Ă��܂ӂ��Ƃ�����܂��B
�@�����]�ɉe������ď��w�Ҏ�������Ȃ�Ȏ@��Y�p���Ă��܂ӂ��Ƃ�����܂��B�N�̔o��͏��ł���Ƃ��ӈꏑ�������������Ɏ^�����A���͒m���̎m���N����̔o��͐[���ł���Ɖ]�ւ����N����̔o��Ƃ��Ӕo����F�[���ɂ��Ă��܂ӂƂ��ӌX�����Ȃ��ł�����܂���B
�@����͔o��ɂ̂���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�G��E�����E���w�����Ă����ł���܂��B�N����̍�i�������w���Ɍ���Ƃ��ӂ��Ƃ����X����܂��B���ꑦ���������ӏ܊���������Ȃ�����ł���܂��B�Ⴕ��҂̖��O�����ււ��U���ō�i�̉��l���㉺����₤�Ȃ��Ƃ������Ȃ�A���ꂱ���L�蓾�ׂ��炴��s�v�c�ł���܂����B
�@���w�҂͎Ⴕ��҂ׂĔo��̕]�߂��Ȃ���Ȃ�A�ȏ�̂₤�ȕ��Q�Ɋׂ�ʂ₤�[���̒��ӂ͂�T���Ƃ��K�v�ł���܂��B
�@�M�Ă��̍�Җ{�ʂ̕]�߂͔��Ȃ��p�Ǝ��ԂƓw�͂Ƃ�v������̂ł��ď��w�҂ɂ͂����߂������Ȃ��Ɛ\�q�ׂ܂����̂͊O�ł�����܂���B��Җ{�ʂ̕]�ߑ������j�I�������o�Ă���̕]�߂ƍ�i�{�ʂ̕]�߂͑S������قɂ��ċ���܂��B��Җ{�ʂ̕]�߂̕��͗��j��H�m���ǁn��̐l��T�m���n���邱�ƂɎ�Ȃ�Ӌ`������A����������̂ł���܂��B����Ώ��w�҂��������o���i�̊ӏ܂ɂ��Ȃ炸�A�o��̏�B���v��ׂ߂ɂ��𗧂Ƃ��낪�����̂ł���܂��B���j�I�Ȍ�����[���ς���Ƃ��Ď��Ȃ̋��n���₩�ɐ[���Ȃ�A�����ɉ�����r�ݓ��邱�Ƃ��o���邩�Ɖ]�ւA�����ł�����܂���B��ɏ��w�҂̏ꍇ�ɂ͍�i���̂��̂�M�S�Ɋӏ܂�������@���ɖ𗧂�����܂���B�ώG�ȘJ���X������������ɏq�ׂ₤�Ƃ����i�{�ʂ̕]�߂ɗ͂�v����T�������w�҂ɂ͗�����Ƃ����Ȃ���̂����邾�炤�Ǝv�Ђ܂��B�i436-437�j
�ŏI�u�́q�o��]�߁r�ł́A�\��������Ă��鉳��i1756�`1823�j�̕]���������B���ɂ́u����ہT���ڂɌ����s�Ɖԁv�̋�Ƃ��̕]�߂��D�܂����i���j�B�����ɂ́A�قƂ�ǃN�����g�I�ȍK����������B
�]�߁B����ہT�̉Ԃ�����̏t���\���Đl�ڂ̓͂����ׂĂ̂Ƃ���ɓ_�Ԃ��Ă��B���R��M�����Č���l�A���R���ς�ɔ삦��������L���Ă��l�͍����ɂ��ꂾ���̐��������R����͂ނ��Ƃ��o����̂ł���B����ہT�̉Ԃƌs�Ƃ���ڂɌ�����Ƃ��������Ă͂�Ȃ�����ǂ��A����䂯�̋͂��ȕ����̗����ɂ͐s���Ȃ��i����d���邱�Ƃ̏o���鎍���\�\���`�ł͂��邪�A���������������̓���������n�Ă��̂ł���B�����]��ɖL�x�ȋ�Ɛ\���Ă����z�͂Ȃ���������ʂ��A�P�Ɍ��t�̉]�ЉɈ˂Ĉ������̏�ɉ]�Е\�͂������ēǎ҂Ɏv�Ђ�[���炵�߂�Ƃ��ӂ₤�ȑ�����̂��炾�������Ă���ɕt�����钅�����X�̑��g��͓ǎҁX�X�ɐ��@������Ƃ��Ӕo��Ƃ͈ق�A�\������Ă͂�Ȃ����A�\���̖��`�I�ȕ������]���Ė�����������\�����Ă����̂ƌ��Ă�낵���B���₤�ȗ������邪���߂ɓǎ҂ł��鎄�̊���ɖ������m�}�}�n�̂ł���B���̋�ɂ̓I�X�J�[���C���h�̃M���V���̎��ɒʂӊ���̈�[������Ă��B�����Ȗ��Ȏ��R�`�ʂ����邱�Ƃ����Ȃ��̂ŁA���̋�Ȃǂ������Ɛ[���ώ@�̉��ɍ�傳�ꂽ���̂����������B����������������̍�i�Ƃ��Ă͐��Ɉ���[�����Ă��o��ł���Ƃ��Ă�낵���B��҂ɂ͌��n�����肽��ہT�̉Ԃƌs�̓�����F�����͂�ł��傫�ȏt�̐F������Ȃ������������̂ł��炤�B�i459-460�j
�t�������M�̎U���ɂ����鏬�C���悢�f��̐ς݂����˂́A���q�̉�������ɂ��̂܂܈����p���ꂽ�悤�Ɍ�����B������܂��A���͂ɍ��r���ӂ�����o���Ƃ������B
�@�k�c�c�l�u���̖̂|��Ƃ��ӂƁA���炫�����̊��o�̂Ȃ����X�����Ȃǂ̎荇�Ɍ��Đ����������o������A�啔���̖͊�����т��p����������ɕ�n�̂₤�ɗ�ׂ����̂ɂȂ�v�ƁA�����ԔV�����������̂͂��������b����Ȃ��B�k�c�c�l��������l�Ƃ����ΎR���������́w�ߑ㉐�B�ҁx�ɍ��ꂱ���ЂƂ��������A�w�R��������W�x�ɂ��J�V���͌����A�u�ҏW������s�N���E�_�یܖ�́A�����̘_���̏��o���������m���ߓ����s���̂܂c���A����ژ^�͈ꗗ�\�ɂ������o�s�ւȏ��������̗����ł��܂��A�����͂����_���̎�̑I���̗��R�⎖��������Ȃ��B���̂�����ʕҏW�Ƃ����ׂ����낤�v�ƁB�܊p�A�����\�̗͍�u���a�̈�l�v�Ȃǂ����߂�ꂽ����W�����������ɁA���҂𗠐�ꂽ�ǎ҂̕s�����]�̐��͂��܂ɋL���ɐV�����B�i�Y���a�F�E���c���q�ҁs���̂悤�Ɂ@�Ԃ̂悤�Ɂ\�\�J�V�i��Ǔ��W�t�A�_�n�ЁA2013�N3��8���A��O��`��O�O�y�[�W�j
���k��ł̈�������ɓo�ꂷ��R�����i1884�`1932�j�\�\�s�R��������W�k�S6���l�t�i�������_�ЁA1972�j������\�\���s�N���i1908�`2001�j�Ɍ��y�������]�q���͐����̇���V�Ȑl���\�\�w���{ ���Ԃāx�w�傠��a�x�r�́u�A�J�f�~�Y���̎��ԁv�̈�߂ł���B���Ȃ݂ɎR�����́A���M�́s�o��O�\�u�t�Ɂq�����r���Ă���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@����ɂ��ł��e�ՂɌ��邱�Ƃ̂ł��鉳���W�̈���{�́A�{�c���M�E��؏����Z���s�����V�۔o�~�W�k�ÓT�o���w��n16�l�t�i�W�p�Ёk�ҏW�n���Ёl�A1971�N5��10���j�Ɏ��߂�ꂽ�q��������W�m���悤�������ɂق����Ӂn�@�t�@���́T�����e�m���������n�r���낤�B�����Ɉ˂�A�f���
�@�@�����p�m����ہT�n���ڂɂ݁m���n���s�Ɖ�
�ŁA�i�m�@�n�́j���r�̈ٓ��́s���́T�����e�t�̂��́i�����A���܁E��O�Z�y�[�W�j�B���M��������u��ڂɌ����v�Ƃ����̂́A�͂����Ăǂ̖{�Ɉ˂����̂��A�c�O�Ȃ��璲�ׂ����Ȃ������B�Ƃ���ŁA�g���́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�́q84�@����ۂۂƔ��̋�r�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���i�����A�ꎵ�Z�y�[�W�j�B
�@�q���L�r�@��㔪�l�N������\�O��
�@���\�ꎞ�A�y���F�̓d�b�ŋN�������B�u����ۂہv�Ɓu���v�̔o����\�傸�A�������Ăق����ƌ����B�����p�u�`�̃e�L�X�g�̂��߂ɁA�K�v�Ƃ̂��ƁB�\��́u�p�������v�ւ̎������߂āA�����A��W�A�G���A�Ύ��L�ׂ�B�u���v�̏G��͂����ɒ��o�ł������A�ӊO�Ȃ��ƂɁu����ۂہv�͂ǂ����Ă��A�܋債���̂�Ȃ��B���łɗ[��B�������[�̏@�c�����ɓd�b�ł����������߂�B��\�ꎞ�A�������āA�A�X�x�X�g�ق֑������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���L���ɂ�����u��Д��G��悱���͂鎀�a���ȁv�O���R�F�q�B
�u����ۂہv�̌܋�ɂ́A����̔�����܂܂�Ă������낤���B
2020�N4���A���l�̑��c�q���q�i1930�`2003�j���g�����Ɉ��Ă��̏W�s���|�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1975�N4��30���j���A���s�̊ØI���[����w�������B�{���̗��Ɂu���c�q���q�̏W�^���Җ{�S���̓��^���\���ԁv�ƎO�s�ɂ킽���āA�r�݂͂ŋL����Ă���i���̂����u��\���v�͎��F�̎菑���̕M���B���Ȃ݂ɖ{�������̔��́A���������������̓�F����B�����Ă���j�B��������}���ق�OPAC�����Ă��u����Łv�Ƃ��邾���ŁA���Җ{�ȊO�̕����́i���̏�������́j�킩��Ȃ��B�{���̎d�l�́A��O�܁~��O��~�����[�g���E�Z���y�[�W�E�㐻�p�w�E�z���i�w�ɏ�������ӓ\��j�E�\���B�c���̂���߂Ă������肵�����ʁm�y�[�W�n�́A����{��12�|�����i���Ԃ�1�|�Ŋ����Ă��邩�j�ŁA�r���܂�Ԃ����ɒ��������āA��y�[�W���g�݂ɂ��邽�߂Ɍ���t�����B
 �@
�@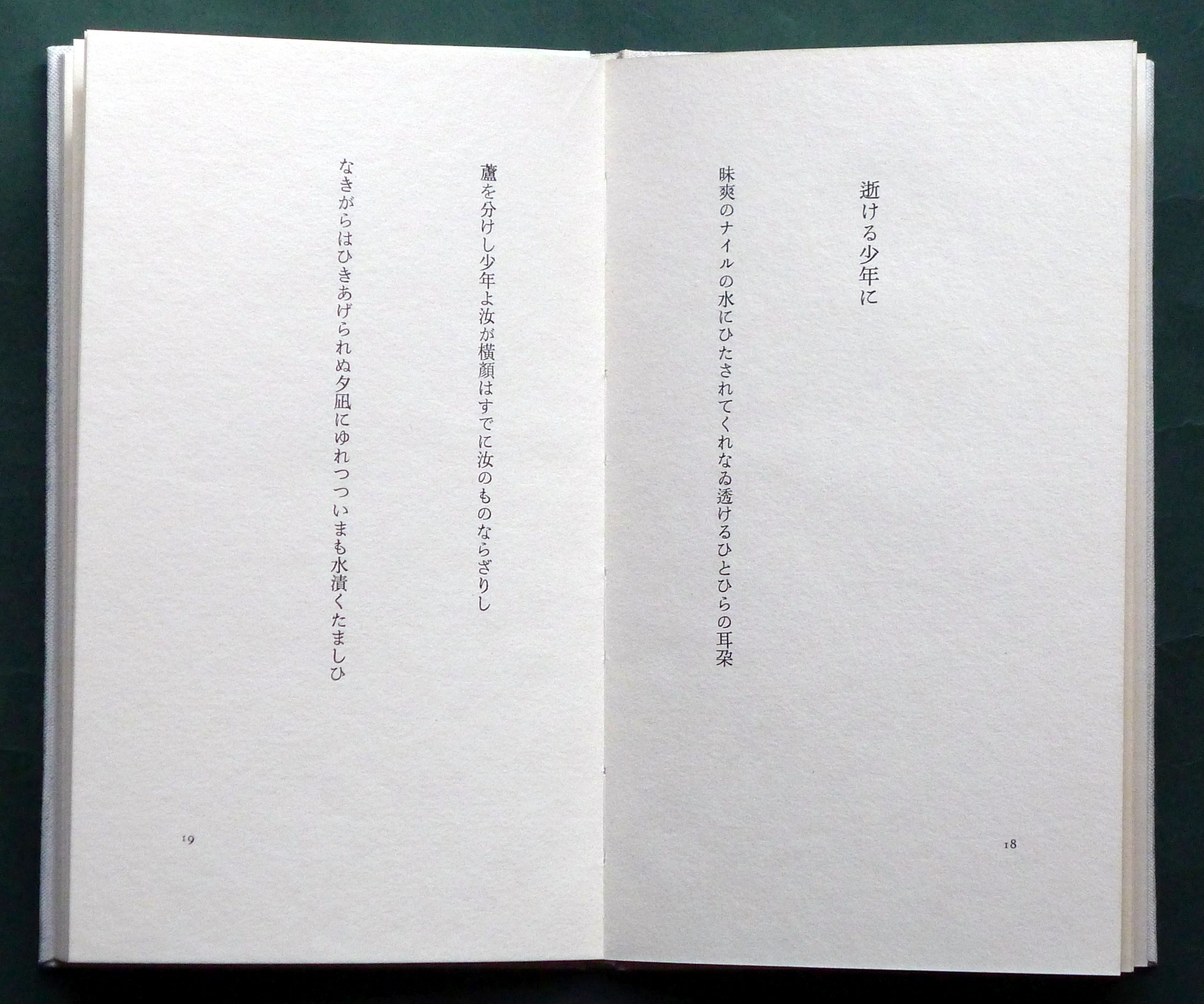
���c�q���q�̏W�s���|�k���Җ{�l�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1975�N4��30���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���y�[�W�k�q�����鏭�N�Ɂr�̌��J���l�i�E�j
�o�Ō��̃R�[�x�u�b�N�X�́AWikipedia�ł͗�������Ă��Ȃ����A��������i1929�`2012�j�A�i�c�k�߁i1900�`1997�j�A�v���\���i1902�`1957�j�A�{�i���F�i1946�`�@�j�A�E�c�ʜ\�i1926�`2003�j�A���́i1931�`2015�j�A�W�����E�W���l�i1910�`1986�j�A�W���[���E�o���x�[�E�h�[�����B�C�i1808�`1889�j�A�S�i�����i1913�`1998�j�A�c�m�a��i1943�`�@�j�A�����d�M�i1912�`1995�j�A�O���q�Y�i1920�`2001�j�A���R�S�j�i1935�`�@�j�A���ڌ���i1896�`1970�j�̒�����̏o�Ō��Ƃ��Č��y����Ă���B
�g���̕҂s�k�ߕS��t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�j���o�ꂵ�Ȃ��̂́A�������̃x�[�X��������Wikipedia���q�g�����r�̍��ɁA�g���̒��������L�ڂ��Ȃ��������炾�B�R�[�x�u�b�N�X�̏o�����{�̒��ҁE��҂�����ɂƂǂ܂���̂łȂ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���ɁA�������ɑ��c�q���q���q�b�g���Ȃ������̂����̏؍��ł���B
�̏W�́q���e�r�q������r�q�Ď��r�q�����鏭�N�Ɂr�q�����ڂ́r�q�����Ȃ́r�q�~������r�q�����́r�q�������r�q���肬���r�q���̕掺�r�q�Ȃ���r�q�����r�q���|�r��14�̏͂��琬��i�S84��j�B�q���e�r�̈��߁A���Ȃ킿�����̂́A
�@�@����̐��ɂЂ낪�鍕���̂ЂƂ��h��đ�肢�Â�
�ł���A�q���|�r�̘Z��߁A���Ȃ킿�����̂́A
�@�@�r���̈łɗ������͂�Ď₩�Ȃ藷�H�̉ʂ̌��̑�
�ł���i�Ȃ��A�{���͐����E�������\�L�����A�V���ɉ��߂��j�B�̏W�́A��Ɏn�܂�A��ɏI���B���̊Ԃɂ́A
�@�@���m�Ђ��n������������ΐU����m���n���ċ�����������h���Ƃ��ށ@�@�q�����ڂ́r
�@�@�l�̎ւ̋P�������ނ�ɏ����ĐՂȂ����ӂ��߂��ʁ@�@�q�����Ȃ́r
�@�@�ޗ��̎M�܂낭�ʂ��ЂĂ݂��������ʈ����̂킪�ዟ�ւ��߁@�@�q�~������r
�@�@�����Ƃق�܂邫�߂��˂������Č��铧���Ƃق�܂邫�߂��˂���������l���@�@�q�����́r
�@�@���U��ҔN�̂ɕ҂ނׂ��⏶�m�ān�ɐÖ��̍s���������@�@�q�Ȃ���r
�@�@���|�͔����̂��Ƃ����������݂ė��Ă��̂����͂ā@�@�q���|�r
�Ƃ��������i���Ђ�����ƒu����Ă���B�{���ɂ́A����Z�̂���̉e�������A�O���鏗�̋�ɒʂ��鏗�̂�肵����������B���邢�͉����M���V�A�̌Î��Ɏ����A�Ȃɂ��̂����B�Ƃ��ɑ��c�q���q�́A�t����̎��t���̎荗���a���ɍ��������A��Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���̈�N�ԁA�ӂƓ�����H�ӂ₤�ɂ��ĎO�\�ꕶ�������Ă�����ł��ς�ŁA���͉�X�̑c����X�x�z���������̌���ɁA����Ȃ����������Ă�����Ă��̂ɋC�������B
�@�ނɒ�����ᶂ�������A���̌`���ɐS���ڂ����Ƃ͎v�Ђ����ʁB��������ɍ��܂���W�߂��̂́A���̕n������{���ȂĐꉡ�Ȍ���ւ̕������Ƃ��A���̎x�z������̖����E�o����Ă̂��Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
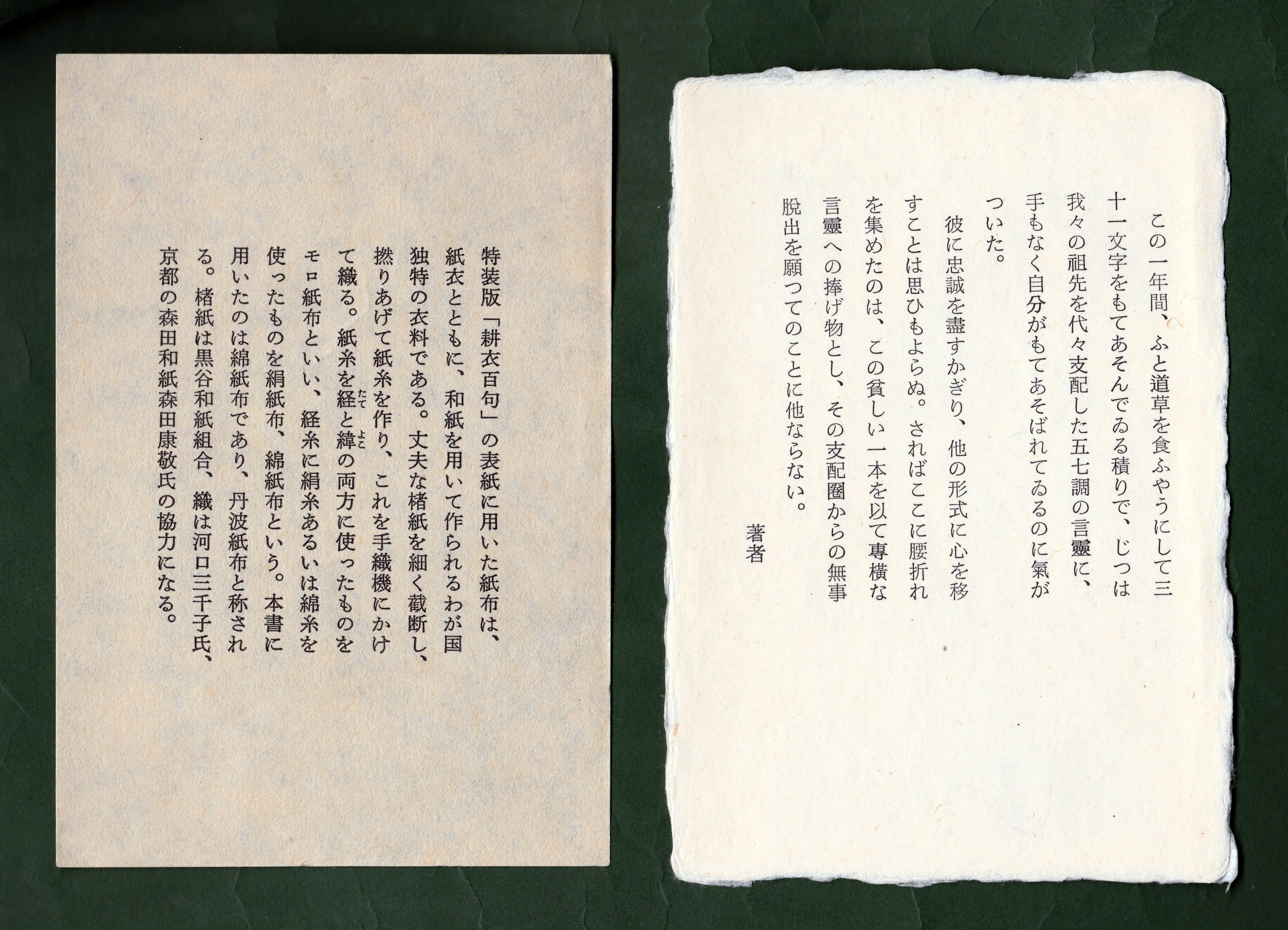
�g�����ҁs�k�ߕS��k�����Łl�t�i��h���ǁk�R�[�x�u�b�N�X���l�A1976�N6��21���j�ɓY����ꂽ�����ŕ\���u���z�v�̐������k�����͂Ȃ����A�n�ӈ�l�ɂ����̂ƍl������l�Ƒ��c�q���q�̉̏W�s���|�k���Җ{�l�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1975�N4��30���j�ɓY����ꂽ���A��
��f�ʐ^�A�E�͌��̑��c�ɂ�鈥�A���A���́i�����炭�j�n�ӈ�l�ɂ��������B���t���̎荗���a���Ɨt������Y��ɒf�����a���̈Ⴂ�͂��邪�A�{���͂Ƃ��Ɍ܍������A20���~10�s�i�s�Ԃ͈قȂ�j�B�����āA�{���̉��t�͈ȉ��̂Ƃ���ł���i��s�߈ȉ��͔��g�݁j�B
�@�@���c�q���q�̏W���|�@����
�@�@�@�@���a�\�N�l���O�\���@����o��
�@�@�@�@�_�ˎs���c��O�{���꒚�ڈ�Ԓn
�@�@�@�@�R�[�x�u�b�N�X�@�k����Y�@���s
�@�@�@�@����@�n���Ё@���{�@�{�쐻�{��
�Ȃ������܂ŏڂ����{�������Ă������Ƃ����ƁA�̏W�s���|�t���s�̗����a�\��i1976�j�N�Z�������ɋg�����ҁA�i�c�k�ߑI��W�s�k�ߕS��t�i���莵�Z�Z���L�ԁA�ق��ɓ�h���NJ��̌��蔪�Z���́k�����Łl������j���Ō����R�[�x�u�b�N�X�A��������n���ЁA���{�����{�쐻�{���Ƃ����A�{���Ƃ܂����������z�w�ŏo�Ă��邩�炾�B���c�q���q�����t���̎荗���a���̈��A��̕\�ʂɌ��提����n�����������łȂ��A����Ƃ͕ʂɃy���ŏ����F�߂��̂́A�s���|�t���s�����A�s�k�ߕS��t�̐��삪�[�����s���Ă�������ł͂Ȃ����B���͂��ās�k�ߕS��t�Ɋւ��āA�i�c�k�߂Ɉ��Ă��g�����̏��Ȃ̂��Ƃ������������B
�u�k�c�c�l�Z�ʂ߂ɂ��čŌ�A���s�̑O�N��㎵�ܔN������������̂͂�������\�\����ǂ̐_�ˍs���ŁA�c���ł��������Ԃ��A��ԏ[���������Ԃł����B�{�����w�ŁA�k�߂�������܂������āA�\��Ȃ��v���Ă��܂��B�n�ӈ�l�N�Ƃ́A���s�܂ňꏏ�ŁA�s�k�ߕS��t�̑ō������������܂����B�v�i�q�I��W�s�k�ߕS��t���r�j�B
�̏W�{�̂���͂��������Ȃ����A�s���|�t�̒S���ҏW�҂��n�ӈ�l�ł��邱�Ƃ͕�����Ȃ��̂ŁA���c���g���Ɂs�k�ߕS��t�̌��Ŗڔz�����Ă���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�\�\�킽���͂������āu�̂̂킩��v�������̂�����A�g��������k�߂���̑I��W�A�͂₭�����Ă��������ˁ\�\�ƁB�u�f�l�̕M�̂����сA�܂��Ƃɂ��p�������̂ł������܂����A���Ђ܂Ȑ܌䍂��������K���ɑ����܂��D�@�@�@�@�@���c�q���q�v�B���ɂ��̕����������ɋ��ʂ̂��̂������Ƃ��Ă��A�Ƃ����g���́A���c�Ɠn�ӂ��ЂƂʂ̃t�F�[�Y�ɓ������Ǝ����������Ƃ��낤�B�ނ�c�́A�g���Ɂs�����t�i1959�A1973�j�����邱�Ƃ�m���Ă����͂����B���̉̏W���A�͂��ߋg�����Ƙa�c�z�q�̌�����I���ŗ�Ȏ҂̋L�O�ɂȂ���̂Ƃ��Ĕz��ꂽ���Ƃ��A�g���ɂƂ��Ắu�̂̂킩��v�ł��������Ƃ��i���P�j�B
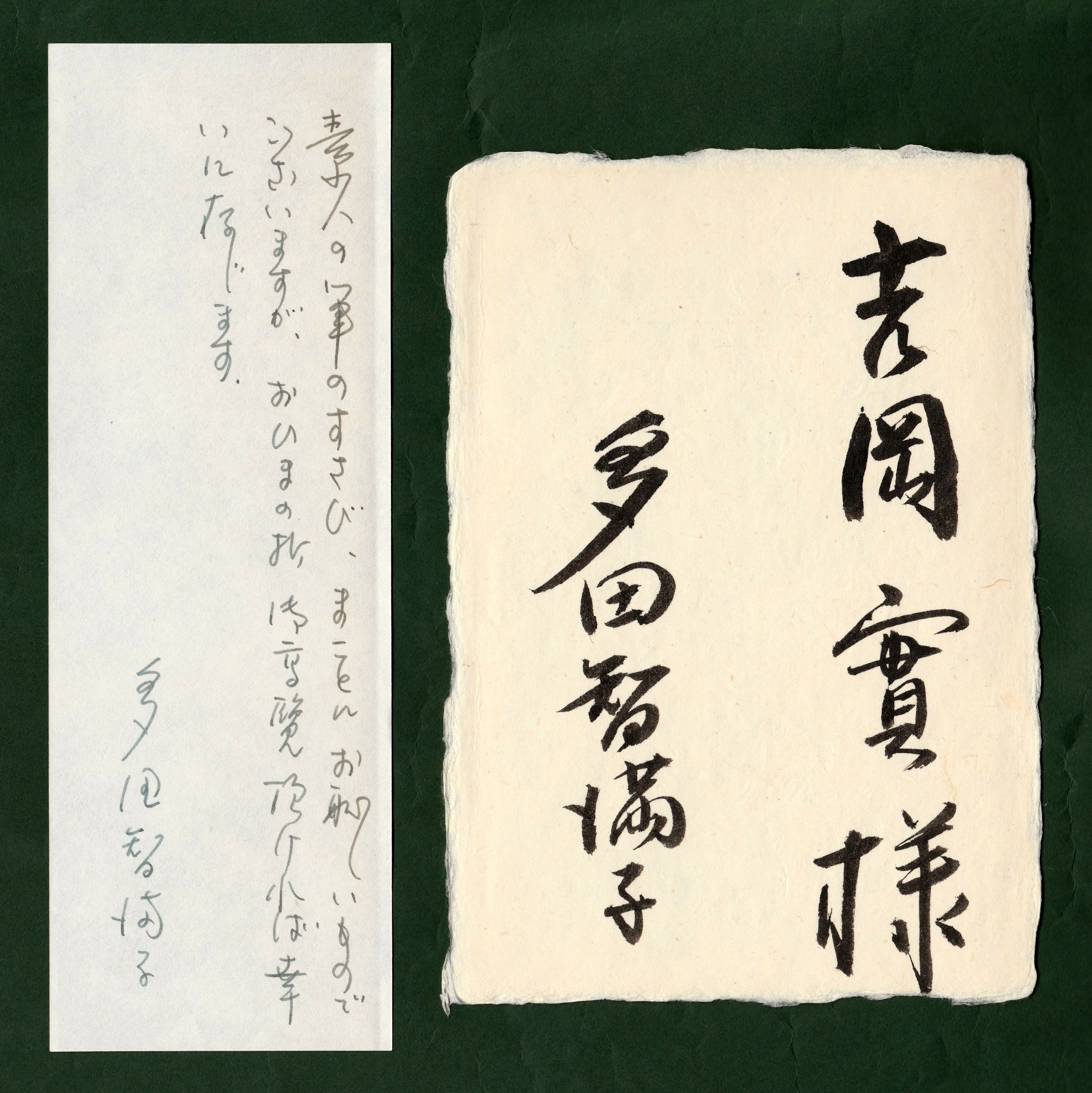
���c�q���q�̉̏W�s���|�k���Җ{�l�t�ɓY����ꂽ�g�����ւ̏���i�y�������j�ƌ��提���i�M�����j
���l�̑��c�q���q�̑�ꎍ�W�s�ԉt�i1956�j�A��W�s���Z��t�i1960�j�͂���������惆���C�J���甭�s���ꂽ�B��҂Ɏ��߂�ꂽ�q�D�̂��Ƃr�ɂ́A�g���̎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�Ƌ�������̂�����悤�Ɏv���B�G���f�B���O��2�߂������B
9
���̈Î��ɂƂ����߂���
���̉����g�͂������ɓ����Ƃ����Ă���
�G���̂悤�ɊJ����������肷��D���̃g�r������
��������������������Əo���肵�͂��߂�
���ǂ̂悤�ɂ܂��肭�˂����ʘH�ɂ�
����Ȃ��V���v�����Ⴊ�݂���
��ʂ��ǂ��J�j�����܂��Ă���
�����Ă��̂��̒��������l��
�O�̂߂�ɂȂ��Ă�炢�Ȃ���ʂ肷����
�₦�������@�֎��悤�����ʑǂ�
�Ȃ����̂ւ�����
����ȂɍV�R����p�����Ă���̂��\�\
10
�鉤�؊J���邽�߂�
�`�͎���҂��Ă����̂�
��p��̏�̏��̂悤��
�ς��邵�����ׂ̂Ȃ������\�\
���ɂނ����đ����ɂЂ炩�ꂽ�D�y����
���̂Ȃ܂����������[������
�N���[���͂̂�̂�ƑD�ׂ�~ং���
���̑̉��Ƒ̏L�Ƃ����َ���
���X�ƒ݂肠��
�����Ɛl�X�̎����Ƃɂ��炵�ċs�E��
�����ăR���N���[�g�̊�ǂɓ������낷
�\�\���͓ˑR�d�ʂ�����
�h�������X�J�[�g�̂悤�ɂ��藎����̂�������
���������̋��E�͒��Â����Ȃ�
�V�����ωׂɂ���ď[�U����
���͂ӂ����ѐg�d�ɂȂ���
���肠����g�̂Ȃ��ɂ̂߂肱��
�o�`��������D�J��
��ꂽ�b�̙������
�D��ɂւ�������т����������y������
�V�����q�C�̊��҂�
��낱�с@���������ɂ����߂�
�s�m���t�����������A�����ɋg���́s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̎c�������Ƃ́A����قǍ���ł͂Ȃ��i�����Ƃ��A���c���ǂ̂�1959�N�ɏ��惆���C�J����o���s�g�������W�t��������������Ȃ��j�B��������A�̂��Ɂs�a���`�t�i����ɁA1962�j�ɂ܂Ƃ܂鎍�тƂ���߂ċ߂��������������Ă��邱�Ƃɋ����B�g���͑��c�Ƃ̏o��ɂ��āA����ɂ͏����̑��c�̎��ɂ��ď����̂����Ă��Ȃ��͂������A�ǂ̂悤�ɓǂ̂��A�����Ă݂��������B
���c�q���q���g�����̂��Ƃ����������͎͂��̎O���낤�B
�@�q�H�̃T�t�����r�i�s�����V���k�[���l�t�A1979�N11��20���j
�@�q�f�p�ȗl�œK�m�Ȗ����r�i�s�T���Ǐ��l�t�A1980�N9��8���j
�@�q�g��������̑��V�̓��r�i�s�������_�t�A1990�N8�����j
�܂��A�g�����f������1991�N��10���A�E�ؔn���ŊJ���ꂽ�q�g�������Âԉ�r�̑�ꕔ�A�m�F�����̎v���o�b�œo�d���Ă���i���Ȃ݂ɁA���c�q���q�A��쐟�q�A�����ċg���z�q��3�l�́A�������1930�N���܂�j�B�q�H�̃T�t�����r�i�V���̗[���́k���_�l�Ƃ����R�����ɔ��\�j�̈�߂ɂ͂�������B
�@�T�t�����́A�M���V���A���A�W�A�̌��Y���Ƃ����B�N���[�^���̈�ՁA�N�m�b�\�X�{�a�̕lj�ɁA�T�t������E�ގp���`����Ă���B�g��������̎��Ɂu�T�t�����E�݁v�Ƃ����̂����邪�A�Ñ�̉�Ƃ��lj�ɕ`�����悤�ɁA���̃T�t�����E�݂̏��N���A���̂Ȃ��ɁA�I�݂Ȏ���œh�肱�߂����̂��B
�@�k�c�c�l
�@�Ƃ�����A�̂���͔|���ꂽ�����̐A���������ł���悤�ɁA�T�t�����́A�������ƂƂ��ɁA����̂䂦�ɒm���Ă����B�N���[�^���̏��N�������E�̂́A�ԏ���ɂ��邽�߂��A����̂���肾�����̂��\�\�B
����A�g�������c�ɐG�ꂽ�̂́s���㎍�蒟�t1981�N2�����k��\������ܔ��\�l�́q���z�r�ŁA���c�̎��W�s�@�тƁt�i����ь牮�A1980�N10��10���j�����̂悤�ɕ]���Ă���B
�@�k�c�c�l
�@�������������Ǝv�������W�́A�V��ޓ�Y�s���P�l�t�A���c�q���q�s�@�тƁt�A��؎u�Y�N�s�킽�����̗H��t�����āA�������Y�s���̒��̍Ό��t�̎l���ł������B�������A�\�I�͎O���Ƃ������ƂȂ̂ŁA�s���P�l�t���O������Ȃ������B�k�c�c�l���c�q���q����́s�@�тƁt�́A�����ɂ͒��������m�I�ɍ\�����ꂽ�ǂ����W���Ǝv�����B������O���̓��w���ȍ�i�����O������A���W�̓��ꂪ�Ƃ�ċ��������Ǝv�����i���̈ψ��k�c��m�E�������E�ѓ��k��E�g�������l�����ӌ��j�B�k�c�c�l
�@���͂��낢��ƍl���A�������Y�N�́s���̒��̍Ό��t�𐄂����ƂɌ��߂��B�Ǎ�Ȏ��l�Ɉ˂��Â���̎��W���Ǝv�����B��J�N�Ƃ�������������Ԃɂ���ꂽ�A�����j���A���X�̈Ⴄ���т��I�k�ɔz�A�݂��Ƃɓ��ꂵ�����W�ł���B��ш�т̎��͂���قNj����Ǝv���Ȃ��̂ɁA�S�̂Ƃ��Č���ƁA�ӎu�i�ӎ��j�̋�����������B���Ȍ����������m��Ȃ����A�����ɂ͓��ς̔�������B�i�����A��O�y�[�W�j
�����Ŋ�蓹�����āA�s��{ ���c�q���q���W�t�i���q�����[�A1994�N3��10���j�����́q����ژ^�r����ɁA���c�q���q�̎������T�ς������i�Ԏ��ŕ\�������j�B�����ɁA�g���������O�Ɋ��s����������Wikipedia�̋L�ڂ�������ĕ\������B
�@�@���̏W�s�����G�߁t�i����ɁA1940�j
�@�@���W�s�t�́t�i����ɁA1941�j
�@�@���W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j
�@�@���W�s�ԉt�k1950�`55�l�i���惆���C�J�A1956�j
�@�@���W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j
�@�@�̏W�s�����t�i���ƔŁk����͏��惆���C�J�l�A1959�j
�@�@�I���W�s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�j
�@�@���W�s���Z��t�k1956�`59�l�i���惆���C�J�A1960�j
�@�@���W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j
�@�@���W�s�K�N�F���t�k1959�`63�l�i���X�ЁA1964�j
�@�@�I���W�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�j
�@�@���W�s���̒����邢�͊�̐X�t�k1965�`68�l�i���X�ЁA1968�j
�@�@���W�s�Â��ȉƁt�i�v���ЁA1968�j
�@�@�I���W�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�j
�@�@���W�s��̔N��L�t�k1963�`70�l�i�R���V���N�Z���^�[�o�ŕ��A1971�j
�@�@�s���c�q���q���W�k���㎍����50�l�t�i�v���ЁA1972�j
�@�@���q�ٗ�Ձr�i����R�c�A1974�j
�@�@���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j
�@�@����F������U�����W�s�l�ʓ��t�k1970�`74�l�i�v���ЁA1975�j
�@�@�̏W�s�����t�k1973�`74�l�i�R�[�x�u�b�N�X�A1975�j
�@�@���W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�j
�@�@�I���W�s�V�I�g�������W�k�V�I���㎍����110�l�t�i�v���ЁA1978�j
�@�@���W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�j
�@�@���W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�j
�@�@���W�s�@�тƁt�k1975�`80�l�i����ь牮�A1980�j
�@�@�G�߃e�[�}�̑I���W�s�G��k���㏗�����I���W�p��4�l�t�i���ώɁA1983�j
�@�@���W�s��ʁt�i����R�c�A1983�j
�@�@�I���W�s�g�����k����̎��l1�l�t�i�������_�ЁA1984�j
�@�@���W�s�j�t�k1980�`86�l�i���X�A1986�j
�@�@���W�s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�j
�@�@�p�c�q���q�I���W�ktranslated by Robert Brady, Kazuko Odagawa, Kerstin Vidaeus ; introduction by Ooka Makoto�l�sMoonstone woman : selected poems and prose�kAsian Poetry in Translation, #11�l�t�iKatydid Books(supported by Oakland University(MI), University of Michigan, UNESCO, etc., c1990�j
�\�\�s��{ ���c�q���q���W�t��o��
�@�@���W�s��̂قƂ�Ɂt�i����R�c�A1998�j
�@�@���W�s������̂��隠�t�i����R�c�A2000�j
�\�\�f��o��
�@�@�k�����r�Y�ҁl���W�s�����Ɓt�i����R�c�A2004�j
�@�@�k�����r�Y�ҁl�̏W�s�V���̐l�t�i�W�S���ɁA2005�j
��L�̊ȗ������ꂽ����������A���낢��Ȃ��Ƃ����Ď���B�g���̐�O��2���i�s�����G�߁t�s�t�́t�j�͏����A�ӂ����1950�N�㔼�A�قړ������Ɏ����I�ȑ�ꎍ�W�����s���A�����ł��߂��������Ō��͈ɒB���v�̏��惆���C�J�������B���̌�͎v���Ђ́k���㎍���Ɂl�ȂǂŃn���f�B�ȃA���\���W�[���܂Ƃ߂����A�̏W�����s���Ă���BWikipedia�ɍڂ��Ă��Ȃ��̂ŏ�̏����ɂ͂Ȃ����A�g�����i�ѓ��k��Ƃ̓�l�W�����j�p��I���W�sCelebration In Darkness�\�\Selected Poems of YOSHIOKA MINORU�t���A���c�̂���Ɠ����V���[�Y�́k#6�l�Ƃ���1985�N�ɏo���Ă����i���Q�j�B1980�N��A90�N��A2000�N��ŗ��҂ɋ߂������Ō��͏���R�c�ł���B�ȑO�A�q�g�����Ɠ���N�v�r�ŕ\�`���̑�|����ȑΏƏ�����W�J�������A �{�i�I�ɑ��c�q���q��_����ꍇ�A�g���������N�v�i���c�̌��㎍���ɔŎ��W�̗��\���ɂ͓���̉��₩�Ō���ȁm�A�A�A�A�A�A�A�n���͂��ڂ��Ă���j�ł͂Ȃ��A�h���ɒj�⍂���r�Y�Ƃ̑ΏƏ������s�����낤�i���R�j�B���āA���̎��W�s�@�тƁt�����A�U�́qespressivo�@�@�\��䂽���Ɂr�̏͂ɁA���сq�����{�r������B�ŏI�߂������B
�����̊��L�ł��鎄��
����Ȋ��L�ł��鐢�E�̂Ȃ���
���Ƃ��Ƃ��늪���ւɓۂ݂��܂ꂽ嗋��̂悤��
�Q�������̊ǂ̉��ւ̂�̂�ƈړ�����
�i��̂��ϗe���g���˂���Ȃ���̒n���~��j
�ǂ�قǎ�����̂��@�ϗe������
���E�̒��ǂ̓��ǂ�����Ƃ����
�n�����������@���Ȃ������݂̎���Ă���
���ȂǁA�����ǂ�ł������Ɂi����N�v���ƂƂ��Ɂj�g�����q�����`�r�i�H�E11�j��z�N����̂����A�g���́u�����ɂ͒��������m�I�ɍ\�����ꂽ�ǂ����W�v�Ƃ����]�͂��̎���ɂ��[�Ă͂܂�̂��낤�B�����Ƃ����Ǝv���B�������́A�u��O���k���c�̎��W�ł͇V�́qscherzando�@�@�V�Y���Ɂr�̏́l�̓��w���ȍ�i�v�̂Ȃ��ł��ِF�̎��̎��т�����Ȃ�������B
���I�̐����b���c�q���q
�O�p�`�̉Ƃ̒���
�N���r���E������
�q���g�����������悤
�ԕr�̊���鉹������
�L���������炱�낰������
�i�܂����L�@���b�����ĖĔL���j
�E�l�����������̂̓L�c�c�L�ł���
�c�O�~�͌�������ł���
�r�݂͂Ȃ�����
���܂��O����ꂪ�Ȃ�����
���Ă��̌��I�̖�
�N���r���E������
�ނ͎Ⴉ�����������ւ����������
���̂����ނ͂��Ƃ��Ǝ���ł����̂�
�����ЂƂq���g�����������悤
�����̌��z�͘Z�Z�x��
�L�̌�z�͂�����x
�ԕr�̂�����͎���������
���́A�����Y�̂悤�ȁA��_����̂悤�ȁA�i�����ċg�����̂悤�ȁj�m���Z���X�Ȗ��킢�͖��ނ��B���Ȃ݂Ɏ��W�s�@�тƁt�ɂ́q����ꂽ�����\�\�w�L���̏��x�̍�҂Ɂ\�\�r�i�h���ɒj�j�A�q��p�Ɂ\�\������ÓT�w�҂Ɂ\�\�r�i���Έ�j�A�q�ڗ��ʂ��߂���₢�\�\�w�͂ꂽ�ڗ��ʁx�̍�҂Ɂ\�\�r�i�x�쐳���j�A�q���̎�̂���O�\��Ԗڂ̏�i�\�\�w���̎�̂���O�\�̏�i�x�̍�҂Ɂ\�\�r�i����N�v�j�A�q���\�\�w�P�̕��x�̍�҂Ɂ\�\�r�i�����r�Y�j�Ƃ����A���掍�E�Ǔ��������߂��Ă���B�i�@�j���͏��тɂ���L�ł���B�����̎��т��A�s�@�тƁt�Ƃقړ������̋g���̎��W�s�Ẳ��t�i1979�j��z�킹�āA�����͐s���Ȃ��B�P�s�{�́s�@�тƁt�ɂ��A�����W�����߂��s��{ ���c�q���q���W�t�ɂ����т̏��o�L�^���Ȃ����A�g���́q�����`�r�i���o�́s�C�t1977�N5�����j�Ƒ��c�́q�����{�r�Ƃł́A�ǂ��炪��ɔ��\���ꂽ�̂��낤���B
 �@
�@
���c�q���q���W�s�@�тƁt�i����ь牮�A1980�N10��10���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{���Ɣ��i�E�j �k�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ����A���s�҂̋g��j�傩�l
�k�t�L�l
�s��{ ���c�q���q���W�t�ɋ��݂��܂ꂽ�x�ɂ́A��쐟�q�A�����r�Y�A�O�}�a�q�A�r���I�A�R���q�b�q�A�r�V�Ď��A6�������͂��Ă���B�����Ƃ̎O�}�a�q�i1929�`2003�j�́q�A���e�~�X�̉��g�r�Ɏ��̂悤�ȋL�ڂ�����B���c�q���q�Ƌg�����ɐG�ꂽ�����Ȃ����͂Ǝv����B
�@�k�c�c�l
�@���Ƒ��c����̂������́A�����[�����ł͂Ȃ��B���͂��Ƃ��Ǝ��l�R���v���b�N�X�������Ă��āA��������Ȃ苭�����̂ŁA���ꂾ����ƌ����킯�ł��Ȃ����A���Ǝ��l���ł��邾���u�����Ă������Ă���B���Ǝ��l�̂������ɐ����闎���������g�����߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���Ƃ����̂����m�ȕ\����������Ȃ��̂����B�����玄�Ɏ��l�̗F�B�͂��Ȃ��B���̈Ӗ��ł͑��c����͗F�B�ł͂Ȃ��B
�@�������A���ɕs�v�c�Ȑl���B���c����Ɋւ��Ă����́A���̈ӎ��̂Ȃ��Ɏ��Ǝ��l�̂������ɐ����闎�����Ȃ��B���c����̗����U���������Ă���ƁA���c����̎����̂��̂������Ă���悤�Ȋ�������B�������Ȃ�����A�����̂��̂������Ă���悤�Ȋ������邩��A�F�B�ɂȂ�Ȃ��̂�������Ȃ��B�������������������āA���߂�悤�ɂ��Ă������Ă���B
�@�����A�Ƃ�������ǁA�����n�I����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ŏ��̏o��͑�ォ�ǂ����ŁA�ǂȂ����̃p�[�e�B�ŁA���̂Ƃ��͊m�������V���x�ŁA���܂���𗘂��Ă��Ȃ��B���c����͔��������O�h���X�������ƒ��āA���������̃K�u�ۂ݂����Ă���̂ɁA�u�����f�B�E�O���X��Â��ɗh�炵�Ă����B
�@��x�ڂɉ�����Ƃ��́A���Ȃ蒝�����B������_�˂̂ǂ����ŁA�ǂȂ����̃p�[�e�B�ŁA���̂��Ƒ��c�������������݂ɍs�����ƂɂȂ����B���̂��g���������ꏏ�������B�g�����͉��˂������ŁA�����ǂ����ֈ��݂ɍs���܂��傤�A�ƌ������ɂ�������炸���艮�ɂȂ����B����ɒ��Ԃ������B�g�����́A���̊��o�Ō����Ύ��Ǝ��l�̂������̗����̓��Ɍ������l�ŁA���͂قƂ�nj��𗘂����Ƃ��ł��Ȃ������B����b���������o���Ă��Ȃ��B���ꂩ�炠�Ƒ��c����Ɠ�l�ł܂��ʂ̋i���X�֒�q�����B���͐��ɐ��������B���c����̂��Ƃ͊o���Ă��Ȃ��B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l�i���x�A���`���y�[�W�j
���́u�_�˂̂ǂ����ŁA�ǂȂ����̃p�[�e�B�Łv�́A1980�N5���̐_�˘Z�b���ɂ�����i�c�k�ߎP���L�O��ł̂悤�Ɏv���邪�i�g�������̎�̃p�[�e�B�ɏo���̂́A�k�߂��Ԕ����q�̉�ɈႢ�Ȃ��j�A����͂Ƃ������A�u�g�����́A���̊��o�Ō����Ύ��Ǝ��l�̂������̗����̓��Ɍ������l�ŁA���͂قƂ�nj��𗘂����Ƃ��ł��Ȃ������B����b���������o���Ă��Ȃ��B�v�Ƃ����A�g���Ə��߂đΖʂ����O�}�̊����͂��ɋ����[���B���c�Ƌg�����ǂ�ȉ�b�������̂��A�O�}���ڂ��������Ă��Ȃ���������ƁA�����炭�k�߂����q�̂��Ƃ���o����߂���l���R�b�������̂ł͂Ȃ����i���c�̎��W�s��̂قƂ�Ɂt�́q�،͂炵�r�̍ŏI�߁u���E���������R�͂̈���^�����r���̏�����ā^���̂킽���@�ЂƂ̎���ƂȂ����v�́A�g�����s�k�ߕS��t�ɑI���������ȋ�����~���ɂ��Ă���j�B����Ƃ��A�����Ɛ��b�ɍӂ����ߋ����������A���ʂ̗F�l�i��쐟�q�⍂���r�Y�j�ɂ��Ă̘b�肾�������B�g���́q�c������E�f�́r�ɂ��������Ă���ł͂Ȃ����B�u�k���Ɠc������Ƃ̂͂��߂Ă̏o��́l�L���͂��ڂ낰�Ȃ����S�����Ă���B�ꏊ�͐_�c���쒬�̃f�~�A���Ƃ��������ȋi���X�ŁA�����Ŏ��͈،h����s�l��̓��Ɩ�t�̎��l�Ƃ͂��߂āA���t�����킵���̂������B���������������Ɏ��̘b������قǁA���ł͂Ȃ������B�����Ƃ�������Ȃ��b��ɏI�n�����B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�ꔪ�O�y�[�W�j�ƁB
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@2020�N10�����s�̋ʉp���H�Q�{���ځs�ߑ㕶�w�S�Z�\�i �V�N�E���i�������i���W�t�i�ʉp�����X�j�ɂ́A�\���Ɣw�̐蔲���J���[�ʐ^�ƂƂ��ɉ̏W�s�����t���f�����Ă���B���Ȃ킿�u056 �����^�g�����̏W�@���Ɣ�70���@���Ҏ����@�t�����X���@�i�@�O�����V�~�@���p���@���^�{�@�n����@�a�c�z�q���s�@��34�@�������̈����o���Ƃ��Ċ��s���ꂽ���ƔŁB���s�l�̘a�c�z�q�͐V�w�ł���B�^1���@110,000�~�v�i�����A���y�[�W�j�B�q�̏W�s�����t���k2014�N10��31���NjL�l�r���M�̎��_�Łu151,200�~�v����������A�������Ɂu���i�������i�v�ł���B
�i���Q�j�@�{���Ō��y�����p�c�q���q�I���W�ktranslated by Robert Brady, Kazuko Odagawa, Kerstin Vidaeus ; introduction by Ooka Makoto�l�sMoonstone woman : selected poems and prose�kAsian Poetry in Translation, #11�l�t�iKatydid Books(supported by Oakland University(MI), University of Michigan, UNESCO, etc., c1990�j�ɐ旧���āA�剪�M�EThomas Fitzsimmons���҂́sA Play of Mirrors: Eight Major Poets of Modern Japan�kAsian poetry in translation. Japan; #7�l�t�iOakland University KATYDID BOOKS�A1987�j�ɁA�剪�M��introduction�qTada Chimako�r�i��Җ��s�L�ځj�Ƒ��c�̎��т̉p��qDead Sun�r�qMe�r�qWind Invites Wind�r�qA Poetry Calendar�r�qSong�r�iKoriyama Naoshi and Edward Lueders��j�A�qKing's Army�r�iKirsten Vidaeus��j�A�qThe Odyssey or �gOn Absence�h�r�iKoriyama Naoshi and Edward Lueders��j�A�qUniverse of the Rose�r�qLost Kingdom�r�iKirsten Vidaeus��j�qJungle Gym from The Territory of Children�r�iAkai Toshio��j���f�ڂ���Ă���A���ꂪ���c���q�q���̍ŏ��̉p������Ȃ��B
�i���R�j�@���c���h���ɒj�A�����r�Y�Ƒn���������l���s�����t�i����ь牮�A1976�`1983�j�́A��1�������10���i�h���ɒj�Ǔ����j�A���ʓ��l�ł����������Έ��Ǔ�����Վ��������̑S11�������s�B�g���͓����̑n�����i1976�N5���j�Ɏ��q���N�r�i�G�E29�j���A�I�����i1983�N6���j�Ɏ��q����r�i�J�E17�j���Ă���B�n�����ŁA���̕ҏW��L�ɑ�������q�ł����낲���r�Ɂu�O�l�̓��l�͎���тƎU����т\����`��������B���q�l������l�A����l�ɂ͎����A����l�ɂ͎U�������肢����B�ق��ɁA���l�O�l�����ɑ��h������Έ�搶�ɘA�ڌ��e�Ղ���c�c�ȏオ��������̌v��ł������B�g�����A���P�v�����A����Ɍ��搶�̂������āA�n�����ɂӂ��킵���[���������e�ɂȂ����B���Ɍ��搶�ɂ́u�q�́v���Ȃ����l�Ȃ܂ł̑啔�̂���e���܂��ƂȂ��u���܂̂͂Ȃނ��v�ɒ��Ղ����B�v�i�����A��O��y�[�W�j�Ə����̂́A�����̕ҏW�l�ł��������u�i�l�j�v���ƍ����r�Y�ł���B�g���͑n�����̊�����i�Ƃ��������Ɂq���N�r�������ĉ������B
2020�N2���A�g���������x�ےj�i1928�`2017�j�Ɉ��Ă��n�K�L3�ʂ��A�������s�̉i�y��������肵���B���߂�15,000�~��B���ʂ����m�N���Ōf���A���ꂼ����e�L�X�g�ɋN�����Ă������B
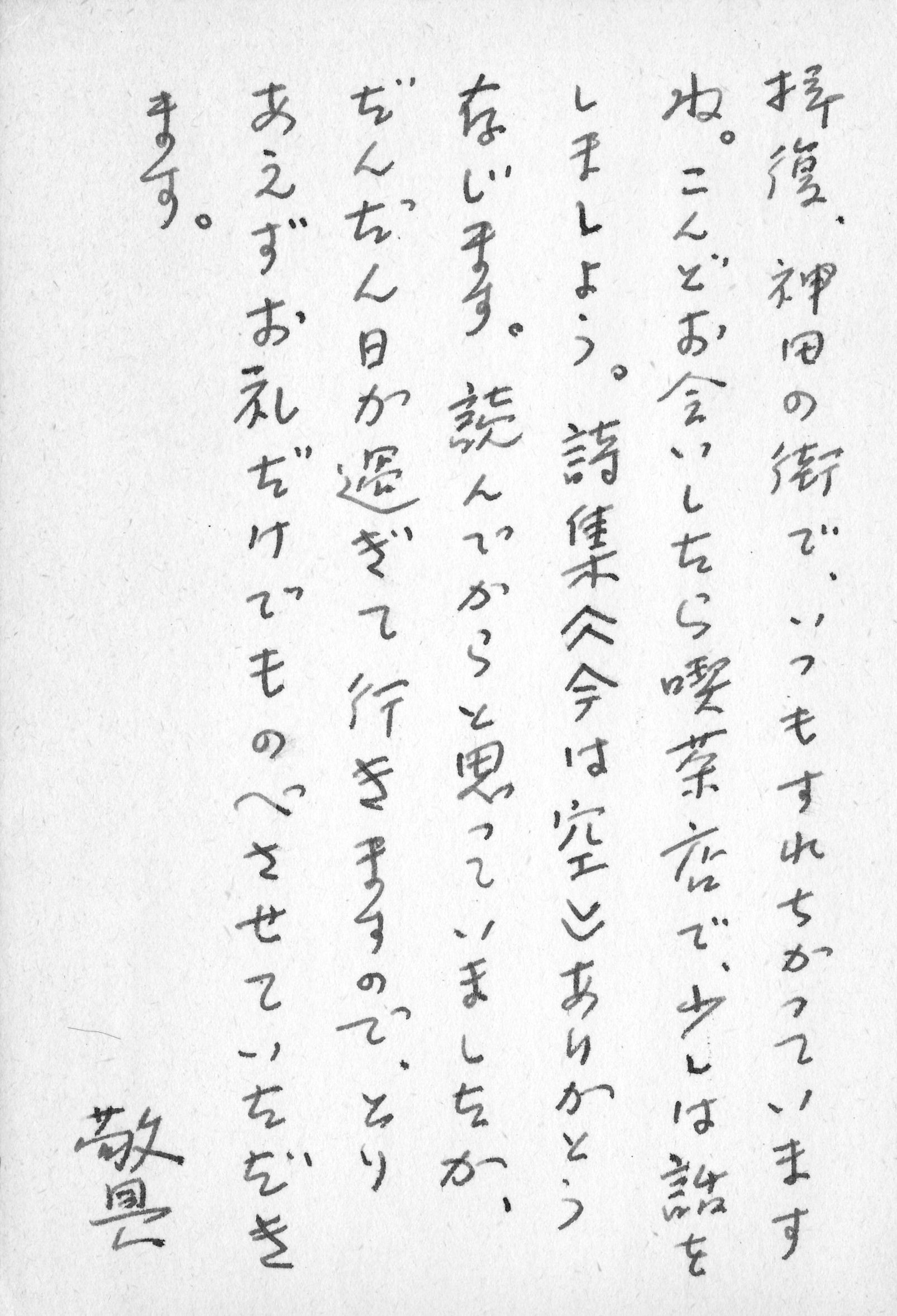 �@
�@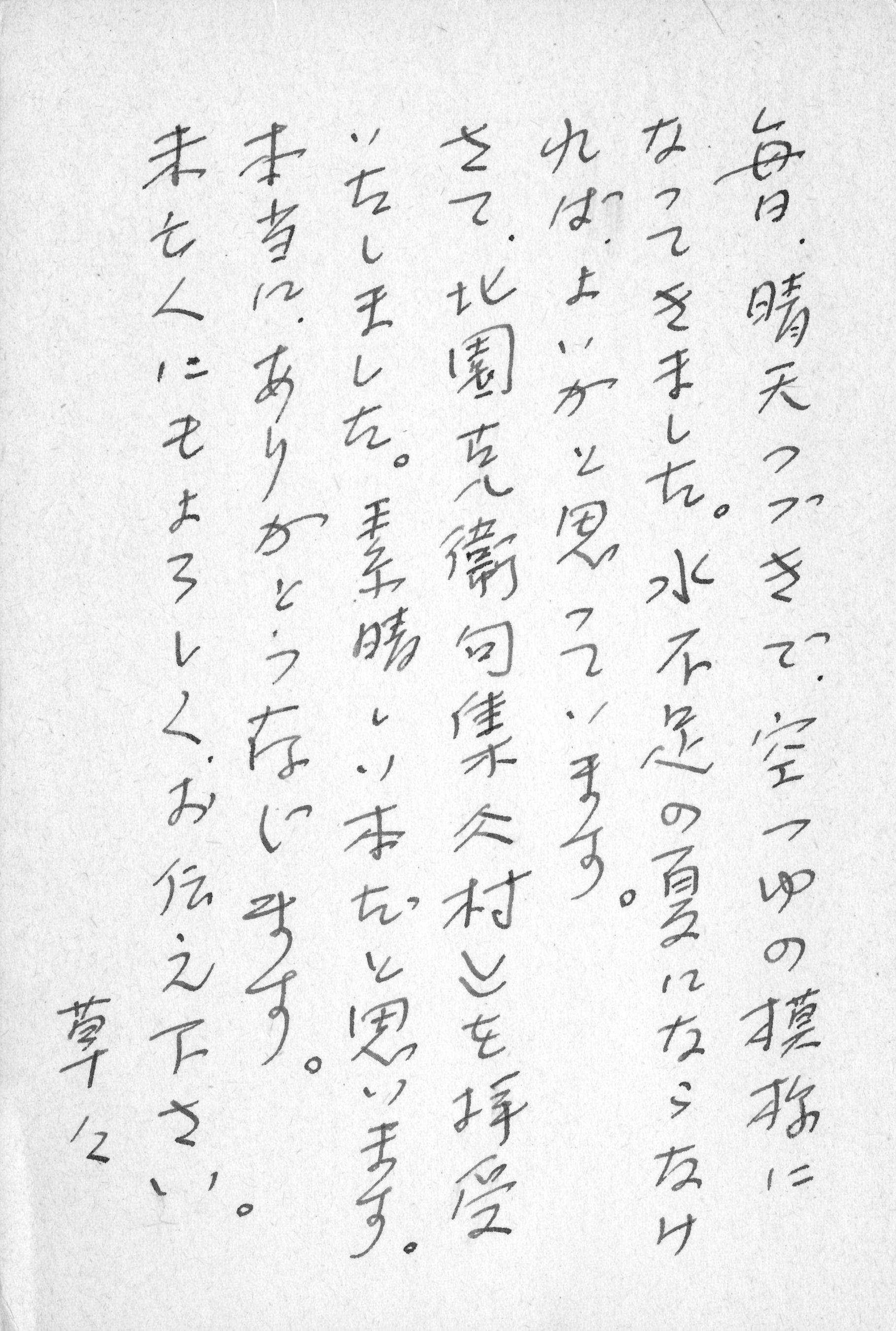 �@
�@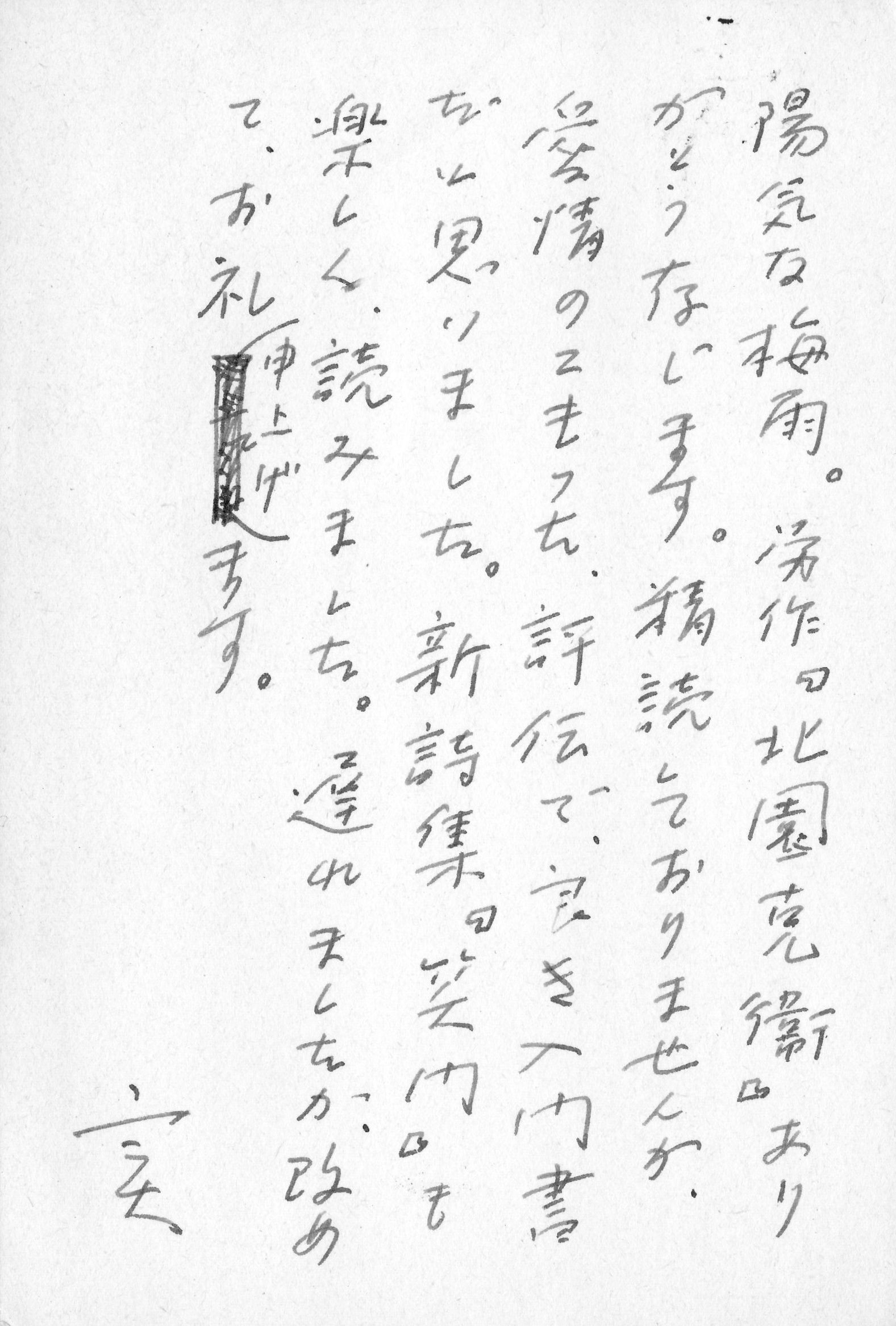
���x�ےj�Ɉ��Ă��g�����̃n�K�L�̕��ʁ@�@�m����n�ڍ��� 17.10.72�i���j�ƇA���E�a�J�� 80.6.25�i���j�ƇB���E�ڍ��� 83.6.22�i�E�j
�@10�~�̗X�ւ͂����@�m����n�ڍ��� 17.10.72 18-24�k1972�N10��17���l
�ڍ���t��̋g���̎����ڍ�����u�̓��x�̎���ɑ����Ă���B
�m���ʁn
�q���A�_�c�̊X�ŁA�������ꂿ�����Ă��܂�
�ˁB����ǂ��������i���X�ŁA�����͘b��
���܂��悤�B���W�s���͋�t���肪�Ƃ�
�����܂��B�ǂ�ł���Ǝv���Ă��܂������A
��������߂��Ă����܂��̂ŁA�Ƃ�
���������炾���ł��q�ׂ����Ă�������
�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h��
�A20�~�̗X�ւ͂����@�m����n�a�J�� 80.6.25 12-18�k1980�N6��25���l
�ڍ���t��̋g���̎����ڍ�����u�̓��x�̎���ɑ����Ă���B
�m���ʁn
�����A���V�Â��ŁA���̖͗l��
�Ȃ��Ă��܂����B���s���̉ĂɂȂ�Ȃ�
��A�悢���Ǝv���Ă��܂��B
���āA�k�����ʋ�W�s���t��q��
�������܂����B�f�������{���Ǝv���܂��B
�{���ɁA���肪�Ƃ������܂��B
���S�l�ɂ���낵���A���`���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X
�B40�~�̗X�ւ͂����@�m����n�ڍ��� 83.6.22 2-18�k1983�N6��22���l
�ڍ���t��̋g���̎����ڍ�����u�̓��x�̎���ɑ����Ă���B
�m���ʁn
�z�C�Ȕ~�J�B�J��w�k�����ʁx����
���Ƃ������܂��B���ǂ��Ă���܂��A
����̂��������A�]�`�ŁA�ǂ����发
���Ǝv���܂����B�V���W�w�Ζ�x��
�y�����A�ǂ݂܂����B�x���Ȃ�܂������A����
�āA����\�グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�͂��߂ɏ����I�������܂Ƃ߂Ă����B���x�ےj�̒P�s���W�͏��������s�Ƃ�������������āA�����䂦�A�s���x�ےj���W�S�i�t�i���ώɁA2008�N11��25���j�x�́q���x�ےj���W�S�i�@���r�Ɉ˂�B�Ȃ��A�t�\�\�Ƃ�����x�͌�����������Ȃ����\�\�̖k�����q��1978�N6��6���A75�ŖS���Ȃ��Ă���B
���x�ےj���W�s���͋�t
�`�T�ϔ��t�����X���A���J�b�g�@58�y�[�W�@����12�^��㎵��N�i��47�j�v���Њ��^�艿�@��A��Z�Z�~�@�i������ܕ��j�^���{�@���c�v�Y�i�q���x�ےj���W�S�i�@���r�A��y�[�W�j
�k�����q��W�s���t�i�������A1980�N6��6���j
�D�ؐm�E���x�ےj��
�����F���������Y
�u���a55�N6��6���A���������B�艿�甪�S�~�B�a�Z�ό^���A��l�ŁB�莚�����M�B�ʐ^�ܗt�i�{�����ɑ}���j�B�v�i�k�ҏW�ψ��l�R�{���g�E�X���Y�E���Ԏ��F�E�ѓc�����s����o��W���ʊ���k���l�o��W�l�t�A�͏o���[�V�ЁA1983�N1��30���A�k�O��O�y�[�W�l�j
�u���x���̋�W�w���x�����������Y�̎�ۂ̂悢�\���ŏo��������̂��A�v���N�ڂ̖����A�Z���Z���ł������B���̓��A�Z�{�́u���Z�g�v�Ƃ��������X�ɂ́u���́A�k�����q���Âԉ�v�ŏW�܂����l�l�������B�����ɂ��̋�W�͔z��ꂽ�B���̐܁A�h�v�l�Ɩ��v�����o�Ȃ���̐l���ÂԈ������������̂ł���B�o�Ȃ͏��s���ŁA����È�A�R�c�엝�v�A���������Y�A�D�ؐm�A�ߓ����A���J�K�M�A���ёP�Y�A�z�K�D�A�c��m�Ƃڂ��ł������B�v�i���x�ےj�s�k�����q�k�ߑ㎍�l�]�`�l�t�A�Z�y�[�W�j�i���P�j
���x�ےj�s�k�����q�k�ߑ㎍�l�]�`�l�t�i�L�����A1983�N6��10���j
�a�T���㐻�����@�ʒ��{���E���m�N�����G8�y�[�W�E�{��300�y�[�W�i�����q�l�������r6�y�[�W�j�E�\��
�u�k�����q�̈�A�̎�������������ƁA�ނ�����J�����̓Ƒn�I�����ēƑ��I�ȕ��݂́A�o���̏�ɋL�q���̂��ď����Ȃ����ƂŁA�܂��n�@�o�A�g�E���[�h�̌����u�|�p�̍ň��̓G�͘A�z�ł���v���A������������l�ł���ƌ�����B�ɘ_������ƁA��o����`�I��@�Ő}�����邢�͐}�`�̎����������Ƃ������Ƃ��ł��悤�B�v�i�q���Ƃ����r�A�����A��y�[�W�j
���x�ےj���W�s�Ζ�t
�a�T�ϔ������@70�y�[�W�@����20�^��㔪��N�i��57�j�_�X�����^�艿�@��A�Z�Z�Z�~�^���{�y�ё���@���������Y�i�q���x�ےj���W�S�i�@���r�A��y�[�W�j
�g�����͓��x�ےj�̎��ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�����O���@���j�^�k�c�c�l�^���x�ےj���W�w���@�̉Ɓx����݂Ȃ���˂�B�v�i�q���L���\�\���Z���r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�y�[�W�B���o�́s���Ɣ�]�t1967�N9�����k����q���L�r�l�j�B
���̎��W�����x���g���ɑ��������̂��B����Ƃ��A���s��������o���Ă��鏈���݂�ƁA�g�����Ï��œ��肵�����̂��B�����ŁA�s���@�̉Ɓt�i�a�U�ϔ��ό^�����@73�y�[�W�@����40�^���Z�l�N�i��39�j�|�p��������^�艿�@�O�Z�Z�~�@�i�����O�Z���j�^����@�V������\�\�q���x�ےj���W�S�i�@���r�A��y�[�W�j����A�u�m���v���o�Ă����т������Ă������B
�[�b���x�ےj
�[�Ă��������@���̈ߑ��𒅂ĒK����ĎR����m���������Ă���
�K�͒����v�̂悤�Ȋ�����Ă��邪�@����͈�t�̂�ł����̂�
�����͑��ł́@�ق�����Ȃ̂Ŏq�������͂ǂ����Ă��������Ă��S���₩�܂���
�m�����@�֎Ԃ̂悤�ɊP�������@�q�����������������ɓ����Ђ낰�ĎU���čs����
�K�̔����[�z�𗁂тĊC�V���F�ɂ����Ă���
�W��́q�[�r�͕K�������u�[�v��\���Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̎��W�Ɏ��߂�ꂽ�ق��̎�������킩��̂����\�\���s���u����́v�Ǝn�܂鎍�́q���r�Ƒ肳��Ă���\�\���̖�����Ƃ��A�������Ƃ�������@�B�I�ȑ���́A�������̂��Ɖ����B�q���̎��W�̂��Ƃɂӂ�ār�Ƃ����s���@�̉Ɓt�̂��Ƃ������f����B�Ȃ��A�����ɂ́u���Z�l�N�^���x�ےj�v�Ƃ���B
�@�ڂ��̒Z�����A���Ȃ킿�X�P�b�`�ɑ������鎍���܂Ƃ߂��̂��A�{���W�ł���B
�@�����̂����i�́A���̎��W�̂��߂ɉ��삳��A�܂�������̂͏\�N�ʂ��O�̂��̂܂܂̍�i�ł���B����ɎG���̏�ɔ��\���ꂽ���ɂ���ꂽ���L���́A���̂����S����肱�킳��Ėڎ��ɂ���悤�ȁA����߂Ėڗ����Ȃ������̊��̕����̈ꎚ��t�������̑�ɉ��߂�ꂽ�̂ł���B
�@���x�A�V������N�̋��͂Ă��̎��W���o��悤�ɂȂ������Ƃ�ނɊ��ӂ������B
�g���͑O�f���L�ɂ��̎��W�̊��z���L���Ă��Ȃ��B�����炭�ǂ݂Ȃ���Q�Ă��܂��āA�N�����Ƃ��ɂ͖Y��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���͂�����A���x�̎��ɑ���ŏ�̖J�߂��ƂƂ��ď����Ă���B����ɂ����x�ےj�����ł��e�Ղɓǂނ��Ƃ̂ł��闬�z�{�̂ЂƂɂ́A���̂悤�ɂ���B
�u���x�ےj�͌��t�̂Ȃ��Ɍ��������L�₩�ŁA��������̂���悤�Ȑ��E������ٔ\�̎��l�ł���B���̐��E�ł͌��t���̂��̂��҂���������A������A�܂�Ől�Ԃ̂悤�ɐU�����B���_�j�Y���̌n���ɘA�Ȃ�������������A���[���A�A�T�^�C�A�A�C���j�[�Ƃ������~悖��ɂ����������̎��т́A�����ւ̒ɉ��Ȉꌂ�ł���ƌ����Ă悢�B�����āA����͋ߑ�I�ȕa���Ƃ������鎩��̉�̂����݂鎍�I�����Ȃ̂ł���B�v�i��ˎ闝�q���x�ےj�i���`�@�j�r�A��ˎ闝�E�쑺��a�v�ҁs��㖼���I�T�k���㎍���ɁE���W�łP�l�t�A�v���ЁA2000�N5��30���A��O��y�[�W�j
�I���ɁA�s���t����k���̋��������������B�Ȃ��A���R�Ë��i1909�`1986�j�͑O�o�s����o��W���ʊ���k���l�o��W�l�t�̖{��W�́q����r�Łu���l�k�����q�́A��O�A���\�����́u�����w�v�ɉ����A�⍲����Y�E�鍶��E����l�Y�玍�l���ԂƋ�삵�Ă���ɔ��\�����B���́u�����w�v�̒��Ԃɂ͔o�����鎍�l�������A��o�c������Ă����B���q�����̒��Ԃ̈�l�ŁA�{���͓����̍����Ƃ��ďW�߁A�v��A���x�ےj�ɂ���ďo�ł��ꂽ���̂ł���B���̎��l�Q�̔o��́A���l�炵�����R�z���̔o��ł͂Ȃ��A�Êi�����A���a�ɂ��ēT��A�p�̐������o������Ƃ���ɁA�ۗ��������F������B�v�i���Q�j�ƕ]���āA�s���t����u�苾�ɂ��肬�肷����R�̏h�v�Ɓu�ɏ��肩�����䂭�͓����ȁv�̓��������Ă���i�����A�l�O��y�[�W�j�B
�Z�\�̂��т�ĉ��鏋������
���������T�T�ЂƂ����ǂ�����
�������A����̑�X��
�ӂ闢��ꡂ��ɂ���ʔB�̏`
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@1980�N6��6���̖k�����q�̎O����ɏW�����l�l�i���̑����͎��l�ł���j�ɔz��ꂽ��W�s���t�́A���x�ےj�̎�ɂ���āi�����炭�j���l���̔o�l�ɂ�����ꂽ�B�C���^�[�l�b�g�ʼn摜��������Ɖi�c�k�߁i1900�`1997�j�̗�q�b�g�����̂ŁA�ȉ��Ɍf���A�|������B�k�߂Ƌg�����k���̋�ɂ��Č�������Ƃ͂������̂��낤���B
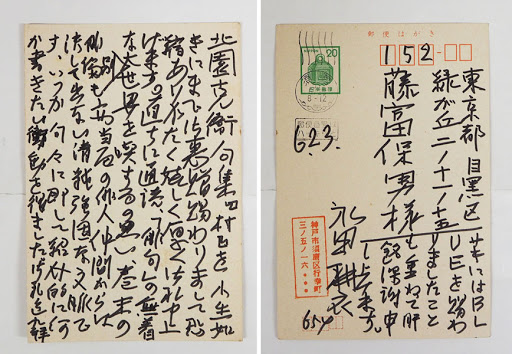
���x�ےj���ĉi�c�k�ߏ��ȁi�k1980�N�l6��23���t�n�K�L�j �o�T�F���{�̌Ö{��
��20�~�̗X�ւ͂����@�m����n�{���� �k���t�s�ڂȂ�ǁA1980�N6����23����24�����l 9-12�@�_�ˎs�{����̉i�c�k�߂̎����ڍ�����u�̓��x�̎���ɑ����Ă���B
�k�ʐM�ʁl
�k�����ʋ�W�w���x�������@
���ɂ܂Ō�b������܂��ċ�
�k���肪�����������������\��
���܂��B�����ɒʓǁA�u�o��v�̖���
�ȑ�ʐ��E���i����v���A������
�o��������ʂ̔o�l���Ԃ����
�����ďo�Ȃ��������łȕ�����
���B������X�ɑ����ďЉ�I�ɉ�
�����������Փ��܂����B��疘��q
�k�����ʁl
�T�L�ɂ͂a�k
�t�d������
��܂�������
���d�˂Ċ�
���[�Ӑ\
���グ�܂��B
�i�c�k��
654
�k�Z����l
6.23.
���Ȓ��́u�����̔o��v�́A�q�o�吡�_�ق��r�Ȃ鑍��́q�o�吡�_�r�q�o��r�q���傢���傢�^�r�q�o��ߊ��r�Ƃ����l�̎U�����w���A�������u�a�k�t�d�v�́A�k�����q���W�sBLUE�t�iEDITIONS VOU�A1979�N6��6���j�\�\���Ȃ킿�k���̈�����ɍۂ��Ċ��s���ꂽ�Ō�̎��W�\�\���w���B���͌������Ă��Ȃ����A���W�sBLUE�t�����R�A�g���ɑ���ꂽ���Ƃ��낤�B
�i���Q�j�@���͂����g�����̃��C�A�E�g�i4�j�i2007�N4��30���j�ŋg�������W�s�����G�߁t�̏o�ōL�����Љ���B�����Ɍf�����i���j�̎ʐ^�ɂ��āA�u�g���̉��i�ɂ���̂́s�����w�t�i���Y�Ę_�Д��s�̔o��G���j�̍L�������A���́i�S�`�b�N�j�̑I����l���̔{���A����ɃX�y�[�X�̏������������āA�Ȃ�Ƃ���肿�炩������ۂ��B����ɑ��āA�s�����G�߁t�̍L���͐V���̎O���i���ЍL���j��f�i������������ł���B�N��������w��i���C�A�E�g�j�����̂��낤���B�v�Ƌg�����̎�ɂȂ邾�낤���Ƃ�\�z���āA���̂��Ƃł́u�s���Y�Ę_�t�̍L�����C�A�E�g���ǂ̂悤�ȃV�X�e�����������͕s�������A���ꂾ���Ïk�������Ă̎��M�A�������ꂽ�����̎w�肪�g���{�l�ȊO�̎�ɂ���ĂȂ��ꂽ�Ƃ͂Ƃ��Ă��v���Ȃ��B�v�Ɛ��f�����B�������̍l���ɕς��͂Ȃ����A�g���͂͂����Ă��̂���o���s�����w�t��ǂ�ł������낤���B�x�V�ԉ��j��M���Ƃ��铖���̔o���s���́t�̔o�l�ɂ��ċg���͌�N�A���т��ѐ��z�Ō��y�������A�s�����w�t�ɋ��������l�����̔o��ɂ͐G��Ă��Ȃ��̂��B�k�����q�̔o��ɂ��Ă����f�ł���B����̒��������ɘւ������B
�g�����̍�i�i���тƎU���j�́A1968�N�ɃC�^���A��ɖꂽ�̂�Ƃ��āA�����܂łɉp��i180�сj�A�t�����X��i15�сj�A������i7�сj�A�C�^���A��i6�сj�𐔂���i�ق��Ƀh�C�c���A�l�p�[�������ƕ����������j�B��i�̐��́A�����G���ɔ��\���ꂽ�̂����ꂪ���ЂɎ��߂�ꂽ�ꍇ���ʂɃJ�E���g�����ق��A�����ȍ�i�i�q�Õ��r�̘A���q�m���r�A�q�T�t�����E�݁r�j�́A��������ł������̖�҂ɂ��|���݂���̂ŁA�ꂽ��i�𖼊���ƁA���̐��͑��v���������Ė�108�тƂȂ�B��������ꂪ�����i�Ƃ��Ɏ��сj�𖡓ǂ��Ĕ�r�������邱�Ƃ́A�g������i������ł�����{��œǂނ̂Ƃ͂܂��قȂ������������ыN�������낤�B���{��Ɩ|�ꂽ����̑o���Ɋ��\�Ȗ�҂ɂ�釀�ǂ݇�����݂��Ă��邽�߂ł���B�ȉ��ɁA���̏W�s�����G�߁t�i1940�j�Ɏn�܂莍�W�s���[���h���b�v�t�i1988�j�Ɏ���g�����̑S���s���т͂������A�q�C�̏́r�i�������сE1�j����q����r�i���E21�j�܂ł̖������сi1947�`90�j�̂��ׂĂ̔��\���т�ΏۂɁA�Ή�����g�������̊O�������ꗗ�ɂ����i�U���E�a�̂�t�ڂ����j�B�Ȃ���i�̖͌����Ƃ��Ė{�T�C�g�ɂ͌f�ڂ��Ă��Ȃ��B���ʓ|�����A���{�E�G���E�V���i�ꍇ�ɂ���ẮA�����Ɠ����ɖ�҂̃E�F�u�T�C�g�ɍڂ��Ă��邱�Ƃ�����j�̖ɓ������Ă���������Ƃ��肪�����B�f�[�^�̌��ɂȂ����s�g���������t�́q�T�@�����ژ^�r����сq�V�@��v��i���^���ژ^�r�ق���{�e�����ɍĘ^�����̂ŁA�ڍׂ͂�������Q�Ƃ��ꂽ���B
�y�}��z
�t �k������l �i�@�E1�j �k���ے������͋g�����̉��Ԃ߂̎��W�����A�A���r�A�����͂��̎��W�ł̌f�ڏ��i�������т̏ꍇ�͔��\���j�������l
Spring �k���ꂽ�薼�l�@���@[Five] Factorial �k�����̖�����߂�������G�����E�V�����̊ȗ��\�L�B�����N��̓f�[�^���̏����l
�� ��������̒��ł́A���ꂼ��̖�\���ɕ��ׂ��B�y�p�z�͉p����A�y���z�̓t�����X����A�y���z�͒�������A�y�Ɂz�̓C�^���A���\���B
���W�s�����G�߁t�i1940�j
�t�i�@�E1�j
Spring�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�āi�@�E2�j
Summer�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�����G��1�i�@�E19�j
A Season of Stupor 1�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�����G��2�i�@�E20�j
A Season of Stupor 2�@���@[Five] Factorial�y�p�z
���W�s�t铁t�i1941�j
�҉́i�A�E1�j
Elegy�@���@Lilac Garden�y�p�z
Elegy�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�ԗ₦�̖�Ɂi�A�E2�j
The Night When Flowers Grow Cold�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�n����ԁi�A�E4�j
Melting Flowers�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�q�́i�A�E10�j
Pastorale�@���@Lilac Garden�y�p�z
Pastorale�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
�����������}�i�A�E13�j
Dry Wedding Picture�@���@Lilac Garden�y�p�z
�Y�ꂽ���J�̝R��i�A�E16�j
Lyricism of the Forgotten Flutist�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�i�A�E19�j
Landscape�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Landscape�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�@���@���{���㎍�I�i�����j�y���z
�t�̇T�i�A�E26�j
Liquid I�@���@[Five] Factorial�y�p�z
�t�̇U�i�A�E27�j
Liquid II�@���@[Five] Factorial�y�p�z
���W�s���t�i1955�j
���i�B�E1�j
Natura morta�@���@La protesta poetica del Giappone�y�Ɂz
Still Life�@���@Anthology of Modern Japanese Poetry�y�p�z
Still Life�@���@Lilac Garden�y�p�z
Still Life�@���@Contemporary Japanese Literature�y�p�z
Still Life�@���@Modern Japanese Poetry�y�p�z
Still Life�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
Still Life�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�Õ��@���@���{���㎍�I�i�����j�y���z
La natura morta�@���@Sei Budda di pietra�y�Ɂz
NATURE MORTE�@���@PO&SIE�y���z
�Õ��@���@���{���㎍�I�i�A���Ԗ�j�y���z
Still Life�@���@[Four] Factorial�y�p�z
���i�B�E2�j
Still Life�@���@New Writing in Japan�y�p�z
Still Life�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Still Life�@���@Lilac Garden�y�p�z
Still Life�@���@Contemporary Japanese Literature�y�p�z
La natura morta�@���@Sei Budda di pietra�y�Ɂz
NATURE MORTE�@���@PO&SIE�y���z
Still Life�@���@[Four] Factorial�y�p�z
���i�B�E3�j
Still Life�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Still Life�@���@Lilac Garden�y�p�z
NATURE MORTE�@���@PO&SIE�y���z
Still Life�@���@[Four] Factorial�y�p�z
���i�B�E4�j
Still Life�@���@Lilac Garden�y�p�z
NATURE MORTE�@���@PO&SIE�y���z
���鐢�E�i�B�E5�j
Certain World�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�B�E6�j
Tree�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�B�E7�j
Egg�@���@Anthology of Modern Japanese Poetry�y�p�z
The Egg�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
The Egg�@���@Lilac Garden�y�p�z
L'uovo�@���@Sei Budda di pietra�y�Ɂz
Egg�@���@[Four] Factorial�y�p�z
�~�̉́i�B�E8�j
The Winter Song�@���@Lilac Garden�y�p�z
�Ă̊G�i�B�E9�j
Summer Picture�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�i�B�E10�j
Landscape�@���@Lilac Garden�y�p�z
�]�́i�B�E11�j
Hymn�@���@Lilac Garden�y�p�z
Praise�@���@[Four] Factorial�y�p�z
�҉́i�B�E12�j
A Funeral Piece�@���@Anthology of Modern Japanese Poetry�y�p�z
��i�B�E14�j
Snow�@���@Lilac Garden�y�p�z
Neve�@���@Sei Budda di pietra�y�Ɂz
���̏ё��i�B�E16�j
Portrait of a Dog�@���@Lilac Garden�y�p�z
�ߋ��i�B�E17�j
Il passato�@���@La protesta poetica del Giappone�y�Ɂz
The Past�@���@Japanese Poetry Now�y�p�z
Past�@���@New Writing in Japan�y�p�z
The Past�@���@Lilac Garden�y�p�z
The Past�@���@Modern Japanese Poetry�y�p�z
The Past�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
The Past�@���@101 Modern Japanese Poems�y�p�z
���W�s�m���t�i1958�j
�쌀�i�C�E1�j
Comedy�@���@Lilac Garden�y�p�z
A Comedy�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
Comedy�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�����i�C�E2�j
Confession�@���@Lilac Garden�y�p�z
Confession�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
Confession�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���i�C�E3�j
Island�@���@Lilac Garden�y�p�z
The Island�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
�d���i�C�E4�j
Work�@���@Lilac Garden�y�p�z
�`���i�C�E5�j
Legend�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Legend�@���@Lilac Garden�y�p�z
Legend�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
Legend�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Legend�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
�~�̊G�i�C�E6�j
Winter Picture�@���@Lilac Garden�y�p�z
Winter Painting�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
�q�́i�C�E7�j
Pastorale�@���@Lilac Garden�y�p�z
�q�́@���@���{���㎍�I�i�����j�y���z
�m���i�C�E8�j
monks�@���@Lilac Garden�y�p�z
Monks�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Moines�@���@Anthologie de Poesie Japonaise Contemporaine�y���z
Monks�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
Moines�@���@Pris de Peur�y���z
Monks�@���@101 Modern Japanese Poems�y�p�z
�P���i�C�E9�j
Simple�@���@Lilac Garden�y�p�z
Simple�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
Simple�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�āi�C�E10�j
Summer�@���@Lilac Garden�y�p�z
�Ō`�i�C�E11�j
Solid Form�@���@Lilac Garden�y�p�z
Solidity�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
Solid�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�i�C�E12�j
Convalescence�@���@Lilac Garden�y�p�z
Recuperation�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
��́i�C�E13�j
Coolie�@���@Lilac Garden�y�p�z
Coolie�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���Ƒ��i�C�E14�j
The Holy Family�@���@Japanese Poetry Now�y�p�z
The Holy Family�@���@Lilac Garden�y�p�z
La Sainte Famille�@���@Pris de Peur�y���z
�r���i�C�E15�j
Mourning Dress�@���@Lilac Garden�y�p�z
Habits de deuil�@���@Pris de Peur�y���z
���������C�E16�j
Beautiful Trip�@���@Lilac Garden�y�p�z
The Lovely Journey�@���@The Modern Japanese Prose Poem�y�p�z
�����i�C�E18�j
Sentimentality�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Sentimentality�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
�����i�C�E19�j
Still-Born�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Still-Born�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
���W�s�a���`�t�i1962�j
�V�l��i�D�E1�j
Ode to the Old Man�@���@Lilac Garden�y�p�z
Ode to an Old Man�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
In Praise of the Old and Senile�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
In Praise of the Old and Senile�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
ELOGE DU VIEUX�@���@PO&SIE�y���z
�V�l��@���@���{���㎍�I�i�A���Ԗ�j�y���z
�����i�D�E3�j
Diarrhea�@���@Lilac Garden�y�p�z
Diarrhea�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
Diarrhea�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
DIARRHEE�@���@PO&SIE�y���z
�a���`�T�i�D�E4�j
Spindle Form: I�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Spindle Form: I�@���@Lilac Garden�y�p�z
Spindle Form I�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�a���`�U�i�D�E5�j
Spindle Form:�U�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Spindle Form: II�@���@Lilac Garden�y�p�z
Spindle Form II�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�A��i�D�E6�j
Negative�@���@Lilac Garden�y�p�z
Negative�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���w�i�D�E7�j
Nude Woman�@���@Lilac Garden�y�p�z
Nude Woman�@���@Contemporary Japanese Literature�y�p�z
�́i�D�E9�j
Antithalamium�@���@Lilac Garden�y�p�z
�c�Ɂi�D�E10�j
Countryside�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Countryside�@���@Lilac Garden�y�p�z
�~�̋x�Ɂi�D�E12�j
Winter Vacation�@���@Lilac Garden�y�p�z
���̂��肠����i�D�E13�j
The Swelling of Water�@���@Lilac Garden�y�p�z
�ޏ��\�\���邢�͏Ȏ@�i�D�E14�j
Sorceress�@���@Lilac Garden�y�p�z
�����́i�D�E15�j
Requiem�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Requiem�@���@Lilac Garden�y�p�z
���i�D�E17�j
Sufferings�@���@Lilac Garden�y�p�z
����鏗�\�\�~���̊G����i�D�E18�j
Hunted Woman�@���@Lilac Garden�y�p�z
����ɂāi�D�E20�j
At the Lighthouse�@���@Lilac Garden�y�p�z
���E�H�̊G�i�D�E21�j
Marsh: An Autumn Picture�@���@Lilac Garden�y�p�z
�C���Əȗ��i�D�E22�j
Amendment and Omission�@���@Lilac Garden�y�p�z
���W�s�Â��ȉƁt�i1968�j
���̂��߂̃g���̎��݁i�E�E1�j
An Attempt at Stage Directions for a Play�@���@Lilac Garden�y�p�z
���߁E�L�߁i�E�E2�j
Innocent: Guilty�@���@Lilac Garden�y�p�z
����i�E�E3�j
Coffee�@���@Lilac Garden�y�p�z
�n�E�t�̊G�i�E�E5�j
Horse: A Picture of Spring�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�n�E�t�V�I�G��@���@���{���㎍�I�i�A���Ԗ�j�y���z
������i�E�E6�j
Ode to the Holy Mother�@���@Lilac Garden�y�p�z
�؍݁i�E�E7�j
Sojourn�@���@Lilac Garden�y�p�z
�₳�������Ζ��i�E�E9�j
Gentle Pyromaniac�@���@Lilac Garden�y�p�z
Tenderhearted Firebug�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Tenderhearted Firebug�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
�X�[�v�͂��߂�i�E�E11�j
Soup Gets Cold�@���@Lilac Garden�y�p�z
���I�ȗ��S�i�E�E12�j
Inner Love Song�@���@Lilac Garden�y�p�z
�q�����i�E�E13�j
Flounder�@���@Lilac Garden�y�p�z
������G�i�E�E15�j
Painting in Love�@���@Lilac Garden�y�p�z
�Â��ȉƁi�E�E16�j
Quiet House�@���@Lilac Garden�y�p�z
Quiet House�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j
�����͂ǂ��ɂ��邩�H�i�F�E6�j
OU EST LE PILIER BLEU?�@���@PO&SIE�y���z
�������i�F�E10�j
Holy Girl�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���W�s�T�t�����E�݁t�i1976�j
�T�t�����E�݁i�G�E1�j
Picking Saffrons�@���@Japanese Literature Today�y�p�z
Saffron Gathering�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Saffron Gathering�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
CUEILLETTE DE SAFRANS�@���@PO&SIE�y���z
��擷�ԍg�ԁ@���@���{���㎍�I�i�A���Ԗ�j�y���z
Picking Saffron Flowers�@���@101 Modern Japanese Poems�y�p�z
�^�R�i�G�E2�j
Octopus�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�i�G�E9�j
Family Photograph�@���@Celebration In Darkness�y�p�z
Family Photograph�@���@A Play of Mirrors�y�p�z
�ǎ�̏��i�G�E22�j�k�����l
The Helmsman's Book�@���@Japanese Love Songs�i���{�̗��́j�k�^�������̃��C�i�[�m�[�c�l�y�p�z
���@�q�ǎ�̏��r�k1�E5�E6�߁l�����̃��[�}���\�L����щp��́A�약��Y��Ȃ́qDashu no sho, for voice and alto saxophone�r�i2003�j�̉̎��B
���W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i1980�j
�|�[���E�N���[�̐H��i�I�E1�j
Paul Klee's Dining Table�@���@Lilac Garden�y�p�z
Paul Klee's Dining Table�@���@Contemporary Japanese Literature�y�p�z
���C���b�N�E�K�[�f���i�I�E3�j
The Lilac Garden�@���@Ten Japanese Poets�y�p�z
Lilac Garden�@���@Lilac Garden�y�p�z
Lilac Garden�@���@From the Country of Eight Islands�y�p�z
���W�s��ʁt�i1983�j
雞�i�J�E1�j
Rooster�@���@PRISM international�y�p�z
Rooster�@���@Kusudama�y�p�z
�G�̐��i�J�E2�j
The Vertical Voice�@���@Kusudama�y�p�z
�e�G�i�J�E3�j
Shadow Pictures�@���@Kusudama�y�p�z
�}�сi�J�E4�j
Collection of Green Branches�@���@Kusudama�y�p�z
�NJ|�i�J�E5�j
Tapestry�@���@Kusudama�y�p�z
�s���i�J�E6�j
Cuckoo�@���@Kusudama�y�p�z
����i�J�E7�j
Pilgrimage�@���@TEMBLOR�y�p�z
Pilgrimage�@���@Kusudama�y�p�z
Pilgrimage�@���@Poems for the Millennium�y�p�z
�H�v���i�J�E8�j
An Autumn Ode�@���@Kusudama�y�p�z
�V���i�J�E9�j
India�@���@Kusudama�y�p�z
��ʁi�J�E10�j
Kusudama�@���@TEMBLOR�y�p�z
Kusudama�@���@Kusudama�y�p�z
�t�v���i�J�E11�j
A Spring Ode�@���@Kusudama�y�p�z
�������i�J�E12�j
Mother�@���@TEMBLOR�y�p�z
Mother�@���@Kusudama�y�p�z
���́i�J�E13�j�k���l
from Elegy�@���@PRISM international�y�p�z
���́i�J�E13�j
Elegy�@���@Kusudama�y�p�z
�ØI�i�J�E14�j
Nectar�@���@Kusudama�y�p�z
�����i�J�E15�j
East Wind�@���@Kusudama�y�p�z
����i�J�E16�j
Turkish Delight�@���@Kusudama�y�p�z
����i�J�E17�j
Wild Geese Descending�@���@Kusudama�y�p�z
�H���i�J�E18�j
Land of Eternal Youth�@���@Kusudama�y�p�z
�C�g�i�J�E19�j
A Crescent Wave Pattern�@���@Kusudama�y�p�z
���W�s���[���h���b�v�t�i1988�j
�킾�݁i�K�E3�j
MERS�@���@PO&SIE�y���z
�����q杁i�K�E4�j�́k2 �H�l
A Short Piece of Music�@���@Mainichi Daily News�y�p�z
�� �q�����q杁r�͖{�тɐ旧���Ĕ��\���ꂽ�q���ȁr�i�sMainichi Daily News�t�k�����V���Ёl1984�N9��17���k22128���l��ʂ́q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�A20�s�A���[�}���\�L�qShookyoku�r��Roger Pulvers�ɂ��p��qA Short Piece of Music�r��t���j�S�s��ω��z�����Ă���B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�˒�ɂāi���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�j
On the Jetty�@���@Lilac Garden�y�p�z
�����i�̏W�s�����t�j
Creel�@���@Lilac Garden�y�p�z
�ϏB���i���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�j
L'ile de Cheju�@���@PO&SIE�y���z
��̎��W�̂͂��܂Łi���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�j
Entre deux recueils�@���@PO&SIE�y���z
�� �sTen Japanese Poets�t�ɂ͏�f�p�т̂ق��ɁA�U���q���W�E�m�I�g�r�q�킽���̍쎍�@�H�r�q�͌ЂƂ������E�ցr�q�g��������76�̎���r�ȏ�̉p���琬��q�g�����r�����߂��Ă���B
�����̊O�����̂Ȃ��œ��M���ׂ��́A��͂�Hiroaki Sato�i�����h���j��̉p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t��Eric Selland��̉p�W�sKusudama�t��2���ł���B�O�҂͋g������������߂ďW�������P���Łi�㐻�{�ƕ����{�Ƃ�����j�A��҂͌��݂܂ł̂Ƃ���B��̒P�s���W�̉p�ł���B����炪1970�N��㔼����90�N��̏��߂ɏW�����Ă���̂́A�g�����́u�����v����u����v�ɂ����Ă̊����ɑ�����Ă̂��Ƃł���A���̟f��ɑ傫�ȃv���W�F�N�g���Ȃ��̂͗҂����B�s��ʁt�̉p�W������ȏ�A�s�m���t�\�\�q�l���r�i�C�E17�j�ȊO�̂��ׂĂɖ|���݂��邪�\�\��s�T�t�����E�݁t�̑S�і�i�p��Ɍ��炸�A�t�����X��ł�������ł��C�^���A��ł��h�C�c��ł��l�p�[����ł��j���o�ꂵ�Ă��������Ȃ��B�����͕K����A�g�����������{��ɂ����炵���Ռ��Ɠ����́i���Ƃɂ������A����ȏ�́j���̂��䂫�N�����ɂ������Ȃ��B�܂��A�e��������|����ɂ����A�q�Õ��r�A���q�m���r�A�q�T�t�����E�݁r�Ƃ��������т̔�r���������҂����B������M���ɁA��s�����ƌ㑱�����Ƃ��r���邱�Ƃ́A�����[�������e�[�}�ƂȂ邾�낤�B�{�e�����̈ꏕ�ƂȂ�Ȃ�������B
���͍����̓��{���w�̖|��ɖ��邢�҂ł͂Ȃ��B1999�N�āA�����̒��t�ŊJ���ꂽ���������̐�[���w�����̃V���|�W�E���ɁA���Y��Ԃ̌��P�̗U���Ő��s�����Ƃ��̂��ƁB�����炢����o���Γ��{��̕��w��i�̒������𐿂������A�Ƃ�����k�߂�������Ă𒆍����̌����҂��畷�����B��p�̕��S��������A�g�������̒�����˗��ł���A�Ƃ����̂��i���͑���ɂ��Ȃ��������A�o�X�ňē��W�����Ă����Ⴂ�����l�j���ɋg�����̍��uJ�g�v�ɂ��Đu�����Ƃ͖Y��Ȃ������j�B�����ɂ���|���i�ɂ���ɗނ����w�i�����������ڂ炩�ɂ��Ȃ����i���ɂ���ẮA���Ό��I�ȍ����ʂł̕⏕�����������낤�j�A�x�X�g�Z���[�����҂ł��鏬���ȂǂƈႢ�A�C���̖|��ɂ͂���Ȃ�̋�J���t���܂Ƃ����Ƃ͗e�Ղɑz���ł���B������ɂ��Ă��A����I�ɂ����e�I�ɂ������ĊȒP�Ƃ͂����Ȃ��g�����������ꂾ���������|�ꂽ���ƂɈ،h�̔O���o���A��҂̕����Ɋ��ӂ������B�����h�����`����u�t�����X���l�ɓǂ܂ꂽ���v�Ƃ����g���̊肢�́A�q�Õ��r�i�B�E1�`4�j�A�q�m���r�i�C�E8�j�A�q���Ƒ��r�i�C�E14�j�A�q�r���r�i�C�E15�j�A�q�V�l��r�i�D�E1�j�A�q�����r�i�D�E3�j�A�q�����͂ǂ��ɂ��邩�H�r�i�F�E6�j�A�q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�A�q�킾�݁r�i�K�E3�j�Ƃ��������т�A�q�ϏB���r�A�q��̎��W�̂͂��܂Łr�Ƃ��������z�̃t�����X���ɂ���Ď��������̂�����A�g�����{�]���낤�B
�k�t�L�l
���̑��݂��m���Ă��Ȃ���A���ݕs���̂��߂ɖ����̋g�������̔�|����2�_����B���{��̎����������킩���Ă��Ȃ����A���Y�̂��߂ɋL���Ă����B�ЂƂ̓l�p�[����́s���{���㎍�A���\���W�[�E��̕�t�ŁA���܂ЂƂ̓h�C�c��_�����́s�Õ��t�s�m���t����I�i�����炭�́j�h�C�c���́A�ő�Ŗ�20�тł���B
�O�҂́A���X�؊��Y�s�J�g�}���Y�E�f�C�E�h���[���t�i�ܖ����@�A1993�N4��24���j�́q���Ƃ����r�Ɂu�k�l�p�[���̎��l�A�`�F�g���E�v���^�b�v�E�l�A�f�B�J�����͓��{�ɑ؍݂��Ă��邠�����Ɏ����̖{�̖|����I�����B�ނ̗����܂���́k���l���N�H�ɂ́A�u�q�}�������Ɂv�̑����z�{�Ƃ��āA����̃l�p�[����̖{���J�g�}���Y�ŏo�łł����B�w���{���㎍�A���\���W�[�E��̕�x�i���^���l���c������A�g�����A�剪�M�A�J��r���Y�A�x�����b�q�A�g�������A�����r�Y�A���X�؊��Y�A�ɓ���C���j�ƁA�w�{�V�����E��͓S���̖�x�B�v�i�����A�ꎵ�O�y�[�W�j�Ƃ���̂����ꂾ�B����1993�N�ȗ��A�܂�ɐG��Ă͒T�������݂�̂����A�����Ɏ��^���т̑薼�����킩��Ȃ��Ƃ͕s�b��Ȃ��B���X�؎���2012�N12���A���W�s�����t�i�v���ЁA2011�j�ő�20���Y�܂���܂��A������L�O���ās���X�؊��Y�\�\�����t�W�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA����F2013�N7��20���`9��8���j���J�Â��ꂽ�B���̓W����}�^�ł��锋���Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�ٕҁs���X�؊��Y�\�\�����k�O�����w�ٓ��ʊ��W�E��20���Y��ғW����l�t�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2013�N7��20���j�́A�����ʂ��瓯����l�ɔ���W����ɘA�������o�ŕ������A���́q�I�s�r�̃R�[�i�[�Ɂu�l�p�[���v�̍��������āA�O�f���́q���Ƃ����r�����^����Ă���B����ɂ����ɁA�i�N�T�����߂��s���{���㎍�A���\���W�[�E��̕�t�̏��e���i���́k�q�}�������Ɂl�ƂƂ��Ɂj�f�����Ă���B���̓l�p�[����ɕs�ē��ŁA���ꂩ��̒T�����ł��Ă��Ȃ����A������ڂɂ��������������̕M���ł���B

�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�ٕҁs���X�؊��Y�\�\�����k�O�����w�ٓ��ʊ��W�E��20���Y��ғW����l�t�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2013�N7��20���j�Ɍf�ڂ��ꂽ�k�q�}�������Ɂl�̏��e�i�����A�Z�܃y�[�W�j �k��i������1992�N�H���s�́s���{���㎍�A���\���W�[�E��̕�t�ŁA�Ėڟ��s�ڂ������t�Ɛ��˓��⒮�s�Ă̏I���t�͑����z�{�i1993�N3�����j�l
��҂́A�o�[�o���R���́q�g�����_�r�ŁA��͋g�����M�́q�N���r�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�j�B���́u���a�\�Z�N ��㔪��N �Z�\��v�Ɨ��N�̋L�ڂ���ɂ܂Ƃ߂��̂��A�g���z�q�҂́q�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�j�́u��㔪��N�i���a�\�Z�N�j �Z�\��^�k�c�c�l�āA�h�C�c��̏C�m�_���u�g�����v���������ƂŎ莆�����Ă����X�C�X�l�o�[�o���Əa�J������̃g�b�v�ŏ��߂ĉ�B�w�Õ��x�w�m���x����I���Z�т̎��ɏA���ĕv�A�R�����̒ʖ�Ɉ˂���Ԃɋy�Ԏ������B���������{���̕M�ւ��o�[�o���̎��M�ƕ����ċ����B�v�Ɨ��N�́u�A�X�C�X�̃o�[�o���R������h�C�c��_���u�g�����v�̃R�s�[�͂��B�v�i�����A���Z�l�y�[�W�j�ł���B���͂��āAWorldCat�ʼn����̊W������{���������A�o�[�o����1982�N�̃h�C�c��ɂ��C�m�_���q�g�����_�r�����ł��Ȃ��ł���B����Ă��̌��Ɋւ��ẮA���̕҂��s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�̎��̋L�ڂ��ŐV�A���ł��ڂ����Ƃ������ƂɂȂ�B
�o�[�o���R���̏C�m�_���q�g�����_�r�i�h�C�c��j�B�g���́u�k��㔪��N�l�āA�a�J������̃g�b�v�ŁA�X�C�X�l�o�[�o���Ə��߂ĉ�B�w�Õ��x�A�w�m���x����I���\�тɏA�āA�������v�Ə����Ă���B�C�m�_���́q���{�̐�㎍�l�A�g�����r�iYamanaka-Hiller, Barbara: Der japanische Nachkriegslyriker Yoshioka Minoru (Lizentiatsarbeit). 1982. Japanologie. Prof. Dr. Cornelius Ouwehand.�j�Ǝv���邪�A�ڍוs���B�������B
�u�w�Õ��x�A�w�m���x����I���\�сv�A����炪���ׂďC�m�_���Ō��y����Ă��邩�͂킩��Ȃ����A�o�[�o�����Q�Ƃ����ɈႢ�Ȃ��p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t�́uFrom Still Life�v��14�сA�uFrom monks�v��16�т�����A�����30�т̂Ȃ�����I�ꂽ�ƍl���Ă��A���Ԃ��炻�������͂Ȃ����낤�B�����Ď��́A���̂����̂������\�\���Ƃ��q�Õ��r��q�ߋ��r�A�q�m���r��q���Ƒ��r�\�\���o�[�o���̘_���̂Ȃ��Łi�h�C�c��ɖ�āj�f����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�ȉ��A�s�g���������t�́q�T�@�����ژ^�r����сq�V�@��v��i���^���ژ^�r�ق�����̍Ę^
 �@
�@
�p���sLilac Garden�t�����̃W���P�b�g�i���j�Ɠ��E���� �i�E�j
�p���sLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�t�����@��㎵�Z�N�m�t���n�@Chicago Review Press�i811 West Junior Terrace, Chicago, Illinois 60613�j���qthe third volume in the Floating World Modern Poets Series�r�@The Swallow Press�i811 West Junior Terrace, Chicago, Illinois 60613�j�����@�艿�㐻��Z�h���i�����l�h����܃Z���g�j�@��ҍ����h���@�ҏWBurton Watson�@���Z�~��O��@������Ł@�㐻�۔w�N���X���E�W���P�b�g�i�����͎����j�@�W���P�b�g���{���}��r�c�����v�@�����^�C�|�O���t�BClaire J. Mahoney�@�O���s�g���Ł@�A�����J���O���ɂĈ��
�k���e�l���L�i���t�j�@�����@���G���Ҏ�ց@�qTranslator's Note�r�i�����h���j�@�ڎ��@�qIntroduction�r�iJ. Thomas Rimer�j�@�qNotes to Introduction�r�@���ьv�Z�Z��
From Still Life (1949�]55)
Still Life / Still Life / Still Life / Still Life / Certain World / Tree / The Egg / The Winter Song / Summer Picture / Hymn / Landscape / Snow / Portrait of a Dog / The Past
From monks (1956�]58)
Comedy / Confession / Island / Work / Legend / Winter Picture / Pastorale / monks / Simple / Summer / Solid Form / Convalescence / Coolie / The Holy Family / Mourning Dress / Beautiful Trip
From Spindle Form (1959�]62)
Ode to the Old Man / Diarrhea / Spindle Form: I / Spindle Form: II / Negative / Nude Woman / Antithalamium / Countryside / Winter Vacation / The Swelling of Water / Sorceress / Requiem / Sufferings / Hunted Woman / At the Lighthouse / Marsh: An Autumn Picture / Amendment and Omission
From Quiet House (1962�]66)
An Attempt at Stage Directions for a Play / Innocent: Guilty / Coffee / Ode to the Holy Mother / Sojourn / Gentle Pyromaniac / Soup Gets Cold / Inner Love Song / Flounder / Painting in Love / Quiet House
From Liquid (1940�]41)
Elegy / Pastorale / Dry Wedding Picture / Lyricism of the Forgotten Flutist / Landscape
From Uncollected Poems (1968)
Paul Klee's Dining Table / Lilac Garden / On the Jetty
Creel (1959)
�qBooks of Related Interest from CHICAGO REVIEW PRESS�r
�W���P�b�g�̗��\���ɒ��ҏё��ʐ^����ђ��ҏЉ�
�����h����ɂ��g�����̉p���sLilac Garden�t�́A�g���ɂƂ��čŏ��̒P�Ƃ̉p�W�ł���i�{�����t�y�[�W�ɁuSome of these translations first appeared in Chelsea, Chicago Review, Granite, The Prose Poem, Ten Japanese Poets, and WORKS�v�Ƃ���悤�ɁA�p�т͂���ȑO�ɂ����������h����Ŕ��\����Ă���A�sLilac Garden�t�����߂ĂƂ����킯�ł͂Ȃ��j�B�W��Ɋւ��āA�����͋g�����Ǔ��̕��q�t�����X���l�ɓǂ܂ꂽ���r�Łu�ٖ�{�̑�� Lilac Garden �Ƃ����͓̂���̎������ɂڂ��𖣗����������ł���v�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����A�Z�l�y�[�W�j�Ə����Ă���B�ł͖{���̎��т̑I���͒N�������̂��B�g���͌�N�A���k��q����Ǝn���r�ŃI�N�^�r�I�E�p�X�Ǝ��̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���i�����A1985�N1�����A�l��`�l�O�y�[�W�j�B
�p�X�@�|�ꂽ�Ō�̂��́kCreel (1959)�l�A����͔o��ł����B
�g���@�|��Ă�����̂͒Z�̂ł��B
�p�X�@�U���̌`���ɂȂ��Ă��܂����ǁB
�g���@�Ō�ɒZ�̂����������ꂽ��ł��B
�p�X�@�Ȃ��Ȃ��ʔ����Ǝv���܂����B�M���V�A�̃G�s�O�������v���o���܂����B�k�c�c�l�V�����Z�̂͂ǂ̂悤�Ȍ`�ɂȂ�̂ł��傤���B�ǂ������ӂ��Ɍ��㉻����Ă�����ł��傤�B
�g���@����́A�l�Ȃ͒Z�́A�o��Ɍ��炸����悤�Ƃ��Ă��ł����ǁA�剪�M�͂�����Ƃ������B
�p�X�@�ł��g������͍Ō�ɒZ�̂������ꂽ�B
�g���@�����B�q���̍��ɂ�����܂������瑲�Ƃ��܂����B
�p�X�@���������Ȃ���ł����B���́A�܂��Z�̂ɖ߂�ꂽ�̂��Ǝv�����̂ł����B
�g���@�����A�܂��߂�Ȃ��ł��B�K�v�Ȃ���܂����ǁi�j�B
�[�ǂ݂���ƁA�g������i��I�������悤�ɂ��ǂ߂邪�A�o�[�g���E���g�\���̕ҏW�ɋg�����ǂ̒��x�ւ�����̂��A���f���邾���̍ޗ��Ɍ�����B���t�y�[�W�ɁuThese poems were translated with permission of Libraire Shichosha Co., Tokyo, Japan�v�Ƃ���悤�ɁA�{���̒�{���s�g�������W�k���㎍����14�l�t���v���ДŁs�g�������W�t�ł���B���́s�g�������W�k���㎍����14�l�t�ɂȂ� Certain World �i�q���鐢�E�r�B�E5�j��Inner Love Song �i�q���I�ȗ��S�r�E�E12�j�Ȃǂ���ڂ���Ă������A�g�������̑�\��q�����r�i�C�E19�j��q�ǓƂȃI�[�g�o�C�r�i�E�E14�j�Ȃǂ����^����Ă��Ȃ��Ƃ��������ƁA�g���͍�i�̑I��ɂ͐ϋɓI�ɂ�������Ă��Ȃ���������Ȃ��B�Ƃ���ŁA�����{���̑��݂�m�����̂́s�ǔ��V���t�́q�蒠�r���̏Љ�L���ł������B���ӂ̈ӂ����߂āA�ȉ��ɂ��́q�g�������̉p�W�D�]�\�\�A�����J�Ŋ��s�r�i�������j�̑S���������B
�@�g�������̉p�W�u���C���b�N�E�K�[�f���v�iLilac Garden: Poems of Minoru Yoshioka�j���A�����J�Ŋ��s����D�]���Ă���B�p��҂͖k�Ăʼnp���l�Ƃ��Ċ��Ă���q���A�L�E�T�g�E���B���̖W�ɂ́A�}��i�������j���r�c�����v���ɂ���ĕ`����Ă���B�܂��A�����Ƃ��ă��V���g����w�i�Z���g���C�X�j�����i�E�g�[�}�X�E���C�}�[�������l�Ǝ���_���������k�}�}�l����e���Ă���i�V�J�S�E���r���[�E�v���X�Њ��j�B
�@���̕\��ɂȂ��Ă���u���C���b�N�E�K�[�f���v�́A�g�����́u�E�⎍�сv�̈�ҁB���̎����͂��߂Ƃ��A�g�����̎��͂���܂łɐ����̖�҂ɂ���ĉp��A�e��̃A���\���W�[�ɒf�ГI�ɏЉ��ė����B�������A��l�̖�҂ɂ���Ė\�҂��ꊪ�{�ɂ܂Ƃ߂��Ă݂�ƁA����܂ňȏ�ɒ��ڂ������A�����̊ӏ܂̎d����|��̂�������߂����āA�w�p�G���ł͘_�����n�܂��Ă���B
�@�g�����́u���������ꍇ�A�e�[�}�₻�̍\���A�\�������炩���ߍl���Ȃ��v�Əq�ׂĂ��邭�炢������A�|��ҋ������̎������Ȃ��Ȃ��B����̖W�̑S�̂̏o�������̎^���Ȃ�����A�I�n�C�I�B����w�������W�F�C���Y�E�q�E�����^���́u�r���v�̓ǂݕ��Ɩ��ɂ��āA�ߊ��̊w��@�֎� Journal of the Association of Teachers of Japanese�ňًc�������Ă���B�u�r���v�͓�\��s�̎��ŁA��Ǔ_���i�����Ȃ��B��҂͂��̎��̂قڒ��قǂ̏\��s�ڂňꉞ�������ĉp�Ă���B�Ƃ��낪�A�]�҂͈�C�ɓǂ݉������Ƃ��咣���Ă���B����̘_���̔��W�͗\�������Ȃ����A�k�Ă̌��㎍�����̖��x�̍��܂���������Ƃ����悤�B�i�s�ǔ��V���k�[���l�t�A1979�N10��20���j
�����h���͑O�f�Ǔ����Łu���̉p��Ɋ֘A���ċg��������ꂽ���ƂƂ��Ă悭�o���Ă��邱�Ƃ͓����B��͎莆�ɏ����ꂽ���ƂŁA�u�q�́v�i�_�̏��j�Ɋւ���ڂ��̎莆�ɓ����āu�����̎��̂قƂ�ǂ��A�O�ƌ�Ɋ|����悤�ɏo���Ă��܂��v�Ƃ������Ƃ��B�|��҂ɂƂ��Ă���͋ɂ߂đ�ȓ_���Ǝv�����̂ł��̎w�E���܂߂��莆�̕����͎ʐ^�ɎB���ĉp��{�̈ꕔ�Ƃ����v�Ə����Ă���i���Ƃ̈�́A�u�t�����X���l�ɓǂ܂ꂽ���v�Ƃ����g���̊�]�B�Ȃ����̒Ǔ����������h���s�A�����J�|�ҏC�s�k�ۑP���C�u�����[�l�t�i�ۑP�A1993�j�Ɏ��߂�ꂽ�ہA�q�g�����̎莆�̈ꕔ�r�Ƒ肵�Ė{����iv�y�[�W�S�̂��ʐ^�łŌf�����Ă���j�B
�{���W���P�b�g�ɞH���uHe�kYoshioka�l is one of Japan's greatest living poets, celebrated for his verbal music and his ability to fuse Western ideas with his country's vital poetic tradition�v�B�p���sLilac Garden�t���p��������鐢�E�̓ǎ҂ɋg��������m�炵�߂����т͌v�肵��Ȃ��B��Ɂs��ʁt�S�т��p���G���b�N�E�Z�����h�͌����ɋy���A�h�C�c��ŋg�����_���������ƂɂȂ�o�[�o���E�R���q�����[���A���Ƃɂ������{���ŏ��߂ċg�������ɐG�ꂽ�̂�������Ȃ��B�Ȃ��A�V�q�r��͖{���̏��]�q�g�����̉p�W�r�i�s�p��N�t1977�N12�����j�Łu��㎍�l�̂����ł�����ȃC���[�W�̎��l�Ƃ��Ēm���Ă���ނ��A���ɉp�ꌗ�ɒP�s�{�ŏЉ���ɂ����������Ǝv���ƁA���S�ЂƂ����ł���B���܂Ō��߂��ꂪ���ł�������㎍�̏d�v�Ȉ�ʂɁA����ŏƖ������Ă��邱�ƂɂȂ낤�v�i�����A�l���y�[�W�j�Ə����āA���Ƃ��Ė`�����сqStill Life�r�������Ă���B
���o�́s�����C�J�t�k�y�Ёl1984�N12���Վ��������k16��14���l��Z�`��Z�y�[�W�A�{��9�|22�s1�i�g�A�k1 �āl�k2 �H�l�k3 �~�l�k4 �t�l83�s�B���o���L�Ɂu���i1�j�͕ʍ��u�w�l���_�v�A�i2�j�́u�p�������j���[�X�v�ɔ��\�������̂ł���B�v�Ƃ���悤�Ɂq���N�@���邢�͏H�r�i�s�ʍ��w�l���_�t�k�������_�Ёl1984�N10���k�H�E5��4���l�O���O�y�[�W�A14�s�j�Ɓq���ȁr�i�sMainichi Daily News�t�k�����V���Ёl1984�N9��17���k22128���l��ʂ́q20:20�\�\20 Poems by 20 Poets in 20 Lines�r�A20�s�A���[�}���\�L�qShookyoku�r��Roger Pulvers�ɂ��p��qA Short Piece of Music�r��t���j�̂��ꂼ��S�s��ω��z���B

�p���sCelebration In Darkness�\�\Selected Poems of YOSHIOKA MINORU�t���� �\��
�p���sCelebration In Darkness�\�\Selected Poems of YOSHIOKA MINORU�t�����@��㔪�ܔN�m�ꌎ���n�@Oakland University KATYDID BOOKS�iRochester, Michigan�j���qAsian Poetry in Translation: Japan #6�r�m�ѓ��k��sStrangers' Sky�t�Ƃ̍����n�@�艿��Z�h����܃Z���g�@�Ҏ�Thomas Fitzsimmons�@��Ҕ������ǁ@����~�ꎵ���@����Z���Ł@�{���������@���������@�����}��Karen Hargreaves-Fitzsimmons�@�O�O�s�g���Ł@�A�����J���O���ɂĈ��McNaughton & Gunn, Saline, Michigan
�k���e�l���L�@�ڎ��@�����qModern Japanese Poetry�\Realities and Challenges�r�i�剪�M�AChristopher Drake��j�@�qYoshioka Minoru�\�gCelebration In Darkness....�h�r�i�߉��P�v�j�@���ҏё��ʐ^�@���ьv�ꎵ�сi�p��M���Ƃ��j�@�M��s�ł̏j�Ձt�͒��Ҏ��M
Still Life / Solid / Octopus / Comedy / Simple / Tenderhearted Firebug / Legend / Horse: A Picture of Spring / Sentimentality / Spindle Form I / Spindle Form II / Diarrhea / Monks / Saffron Gathering / Still-Born / Family Photograph / In Praise of the Old and Senile
�Õ��^�Ō`�^�^�R�^�쌀�^�P���^�₳�������Ζ��^�`���^�n�E�t�̊G�^�����^�a���`�T�^�a���`�U�^�����^�m���^�T�t�����E�݁^�����^�킪�Ƃ̋L�O�ʐ^�^�V�l��
�k�ѓ��k��sStrangers' Sky�t�̏����͏ȗ��l
�p���sCelebration In Darkness�t���
�sCelebration In Darkness�t���C���^�[�l�b�g�Ō�������ƁA��㔪�ܔN�ꌎ�������Ƃ����L�q�����邪�A�{���̊��L�Ɉ�㔪�ܔN�Ƃ����L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�����ɂ́m�ꌎ���n�ƋL�ڂ����B��㔪�ܔN�܌������́s�ǔ��V���k�[���l�t�́q�ЂƁr���Ɂq���p����œǂ߂�c�����ꎍ�W�o�Łr�Ƃ����L�����f�ڂ��ꂽ�B
�@���{��Ɖp��œ����ɓǂ߂�u�c�����ꎍ�W�v�A�p��^�C�g���gDead Languages�h���I�[�N�����h��w����o�ł��ꂽ�B��O�S�n�ň��l�Z�N���獡�N�̓ǔ����w�܂���܂����u�z��̊��сv�܂łɏ��������҂̒�����A�u���t�̂Ȃ����E�v�u���|�̌����v�u�̎v�z�v�u���́v�u���́v�Ȃǂ����߂��Ă���B���W�͊J���ĉE�̕\��������{��̌��������сA���̕\������p��̎����z��Ă���B
�@��ɓ��������̂́A�n�[�o�[�h��Łu���߁v�̃h�N�^�[�_���������A�Ռ����q��ʼnp��������Ă���N���X�g�t�@�[�E�h���C�N����B�c������́A���̑I�����h���C�N����ɂ��ׂĂ܂������B���̓��ꎍ�W�̓V���[�Y�ɂȂ��Ă��āA���łɔѓ��k��A�g��������̎��W���o�ł���Ă���B
�@�k�c�c�l�i�����A11�ʁj
KATYDID BOOKS�́qAsian Poetry in Translation: Japan�r�̓g�}�X�E�t�B�b�c�V�����Y�̕҂ɂȂ�V���[�Y�ŁA��Z�Z�Z�N�̎��_�ŁA�g�������A���ÕׁA�剪�M�A�؉��[���A�c������A�g�����E�ѓ��k��i�{���j�A�g�}�X�E�t�B�b�c�V�����Y�A���X�؊��Y�A�ܓ�����q�A���c�q���q�A�ێR�O�A����S���A�J��r���Y�A�҈䋪�A�ؓ��n�A�R�{���g�Ȃǂ̎��E�Z�́E�_���y�[�p�[�o�b�N�Łi�^�C�g���ɂ���Ă̓n�[�h�J���@�[�ł��j�o�Ă���B��l�W�͖{�������ŁA�g���ɂ͂��łɍ����h���̉p���sLilac Garden�t�iChicago Review Press�A1976�j������ɂ���A�������猩��g�����ň���i���j�ƂȂ鎍�W�́s�T�t�����E�݁t�Ɓs�Ẳ��t�j�A�ѓ��k��ň�����]�܂��������B
Within the hard surface of night's bowl�i�����h����j
night comes and inside the hard surface of the vessel�i�������ǖ�j
����̉p���̖`���̈�s�i�u��̊�̍d���ʂ̓��Łv�j���B�{���Ɏ��^���ꂽ���т́s�Õ��t����s�T�t�����E�݁t�܂ł̎��W����I��Ă��邪�A�s�_��I�Ȏ���̎��t����̑I���͂Ȃ��B�܂��s�m���t����̎��т��ڂ������i����ɂ��Ă��A���т̃I�[�_�[�ɂ͂ǂ�ȈӐ}������̂��낤�j�B���Ȃ݂ɁsLilac Garden�t�Əd�����鎍�͈��с\�\�Õ��i�B�E1�j�^�Ō`�i�C�E11�j�^�쌀�i�C�E1�j�^�P���i�C�E9�j�^�₳�������Ζ��i�E�E9�j�^�`���i�C�E5�j�^�a���`�T�i�D�E4�j�^�a���`�U�i�D�E5�j�^�����i�D�E3�j�^�m���i�C�E8�j�^�V�l��i�D�E1�j�\�\�ł���B

�sA Play of Mirrors: Eight Major Poets of Modern Japan�t �\��
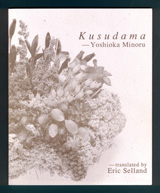
�p�W�sKusudama�t���� �\��
�p�W�sKusudama�t�����@�����N�@FACT International�Ёi2-2650 West 1st Ave. Vancouver B.C. V6K 1G9 Canada�jLeech Books���@��� Eric Selland�@��Z���~�ꎵ��@���ܓ�Ł@�����@����ݕ\���@�{���p���Đ����@�f�U�C��Steven Forth�AYoshie Hattori�@�\���R���[�W��Yoshie Hattori�@�ʐ^Stan Douglas�@�J�i�_�ɂĈ�� Press Gang
�k���e�l���L�@�����@���сs��ʁt�S��
Rooster�k雞�l / The Vertical Voice�k�G�̐��l / Shadow Pictures�k�e�G�l / Collection of Green Branches�k�}�сl / Tapestry�k�NJ|�l / Cuckoo�k�s���l / Pilgrimage�k����l / An Autumn Ode�k�H�v���l / India�k�V���l / Kusudama�k��ʁl / A Spring Ode�k�t�v���l / Mother�k�������l / Elegy�k���́l / Nectar�k�ØI�l / East Wind�k�����l / Turkish Delight�k����l / Wild Geese Descending�k����l / Land of Eternal Youth�k�H���l / A Crescent Wave Pattern�k�C�g�l
Afterword / �k���ҏЉ�E��ҏЉ�l
�sKusudama�t�͋g�����̒P�s���W�B��̉p�B�g���̐��z�q�������܁r�ɖ�҃G���b�N�E�Z�����h�Ƃ̌�F��������Ă���i���o�́s�V���t1985�N11�����j�B
�@�k�c�c�l�G���b�N�͊w������ɁA�p�W�w���C���b�N�E�K�[�f���x�i�����h���Җ�j�Ŏ��̎���ǂ݁A�S���������悤�ł���B�^��N�̏t����A�G���b�N����w��ʁx��|�����ƍl���Ă��邪�A���ӂ��Ă���邩�ƌ����A���͋����Ă��܂����B���̎��W�͍��܂ł̍�i�Ƃ͎��`���ق�A���Ƃ̉�������u�y���v�̂悤�ɎU��߂��A�����Ă݂�u�����v�̂悤�Ȃ��́B���̂����A�Ì�╧���p��𑽗p���A�ՋV�I�Ȑ��E�����Ŏ��݂Ă���B�F�l�A�m�Ȃ̂Ȃ��ɂ���ǂł��Ȃ��ƌ����l������B��������{��̊��\�ȃG���b�N�ɂ��A�s�\�Ȃ��Ƃ��ƍl���A���͂��Ȃ����Ă���������ǂƁA�����܂��ȕԓ������Ă����B�^�A�����J�̎G���qPRISM international�r�ɓ�т̎����f�ڂ��ꂽ�ƁA�G���b�N�E�Z�����h���������������ė����B��o�����l�A�ܕт��炱�̓�т��̗p���ꂽ�Ƃ̂��ƁB����́u雞�v�u���́v�Ƃ������ł���B���ɂ͂��̐��ʂ̂قǂ͂킩��Ȃ����A���̎Ⴂ���l�̎��O�ɑł����B�u���́v�̍ŏI�����f���Ă݂悤�B�@�@�u�L�ł���Ɠ����ɖ��ł��鐢�E�v
�@�@�M�ɂ���ރ{�^���d��
�@�@�ɂ���Ƃ肪��
�@�@���̐��ԏ����̋ňł���
�@�@�����ɒ�▅�����܂�o��
�@�@�܂�ɂ�
�@�@���l�����܂�o��
�@���Ȃ݂ɁA���̈�т͐��e���O�Y�ւ̒Ǔ����ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��㎵�`��㔪�y�[�W�j
�q���́r�i�J�E13�j�̎���ɑΉ�����p����sKusudama�t��������B
�gWorld at once being and emptiness�h
Clematis clinging to the underbrush
The rooster crows
From the gloomy dawn of this watermill
Little brothers and sisters are born
On rare occasions
A traveler is born�i�{���A�O�O�y�[�W�j
��тɑ����āA�Z�����h���́sTEMBLOR: Contemporary Poets Issue 4�t�i1986�j�Ɂq����r�i�J�E7�j�A�q��ʁr�i�J�E10�j�A�q�������r�i�J�E12�j�̉p��\�A���W�s��ʁt�S��Ɍ�����簐i�����B�����̊�e�ҏЉ�ɂ́gERIC SELLAND lives in Tokyo and is seeking a publisher for his translation of Minoru Yoshioka's Kusudama.�h�Ƃ��邪�A�g���͖{���̊��s���������Đ������B�sKusudama�t�����Ɍf����ꂽ��҂̌����gThis translation is dedicated to the memory of Yoshioka Minoru 1919-1990�h���A���̖��O��������Ă���B
�g�������͍����h�����͂��ߑ����̖�҂Ɍb�܂�A�����̉p���\����Ă������A�s��ʁt�̎��т̓G���b�N�E�Z�����h�ȊO�A��|���Ă��Ȃ��B�ߔN�A��҂́s�����G�߁t��s�t�́t�A�s�Õ��t�Ȃǂ̏����g�������̉p����i�߂Ă���A�s�g�����S���W�t�̊��҂����B�Ȃ��{���́q�C�g�r�i�J�E19�j�A�q�}�сr�i�J�E4�j�A�q雞�r�i�J�E1�j�̎O�т�duration press�̃T�C�g�œǂނ��Ƃ��ł���B
![�sPris de Peur, le numero 5 [Poesie d'aujourd'hui au Japon]�t �k�qMinoru Yoshioka�r�̖`�����J���y�[�W�̃��m�N���R�s�[�l](image/Pris de Peur_1.jpg)
�sPris de Peur, le numero 5 [Poesie d'aujourd'hui au Japon]�t �k�qMinoru Yoshioka�r�̖`�����J���y�[�W�̃��m�N���R�s�[�l

�sPoems for the Millennium: the University of California book of modern & postmodern poetry�t �\��

���ɑΖW�sSei Budda di pietra�k�Z�̂̐̌䕧�l�t �\��

�sPO&SIE numero 100�\�\Poesie Japonaise�t �k�qYOSHIOKA Minoru�r�̖`���y�[�W�l
![�s[Four] Factorial�k�l�̊K��l�t �\��](image/factorial.jpg)
�s[Four] Factorial�k�l�̊K��l�t �\��
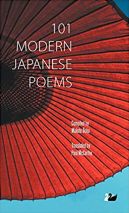
2020�N1���A���t�I�N�I�ɕx�R�̎��l�A�B�c俕��Ɉ��Ă��g�����̔N��o�i���ꂽ�i�c�O�Ȃ���A���D�ł��Ȃ������j�B�k���a�l40�N1��3�����q�Ǐ���̔N��n�K�L�Łi�����Ƃ����t�͂͂�����Ƃ͓ǂݎ��Ȃ��j�A�\�ʂ̏Z���∶���̓u���[�u���b�N�̃y�������A���̕��ʂ͂��ׂĈ���ŁA�u�P�X�U�T�v�Ƃ����N���ɁA�ԂŊ��x�̃w�r�̃J�b�g�����݂��A�u�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��v�A�����s�k�����̏Z���A�u�g�����E�z�q�v�B�ȏ�͂���������g�݂ł���B�s���ɂ��ĕB�c俕��̎��Ƃ�m��Ȃ������̂ŁA�s�B�c俕����W�k���a����n�l�t�i�ُo�ŁA1977�N5��1���j����肵���B�攪���W�s�X�͂̒܁t�i�v���ЁA1963�j�̈�т��������B
����m�i���L�c�\�X�n�̏��N�b�B�c俕�
�����킯�čs��
�N���b�J�X�̉Ԃ̏��
�r�������ė���
���炫�̓Δ��m�����͂n�̉Ԃ̖T��
���R�r�Ə���������
�A�ꂾ���ė���
�X�~����q���V���X�̖��
�\�\�Ƃ���Ŕn���킯�ė���̂�
����̉Ԃ̏��
���N�̎�j��
�͂�����Ȃ���
�i�M���V���̃j���t�̖�
�@�̂悤�Ƀi���L�b�\�X
�@���Ӂm���Ăȁn�������݂����Ȃ���j
�B�c�̎����u�s�v�c�ȃ^�y�X�g���[�v�ƌĂ̂͒J��r���Y�ł���i�s�S�ԁt4���A1954�N3���j�B�������ɂ��̒Ԃ�D��ɂ��A�����ȃG���e�B�V�Y�����Y���Ă���B���������ɂ́A�g�����̎��сq�T�t�����E�݁r�ɂ���f���[�j�b�V���Ȃ��̂͌����Ȃ��B���ꂪ�B�c俕����̎������Ȃ̂��낤���B�s�B�c俕��S�W�k��1���l�t�i�ُo�ŁA1978�N12��20���j�́A�����ɑ�ꎍ�W�s�ԁt�i���K�N�ЁA1948�j���A�����ɑ掵���W�s���̏��t�i��玕�ЁA1957�j���A���ꂼ��S�ю��߂Ă���B�O�҂���`���́A��҂���{���̎��т��f���悤�B
���̉ԁb�B�c俕�
���̉Ԃт炪�h���Ƃ�
���̓��̉Ԃ��h���Ƃ�
���̒�����q���̏Ђ�
����������͏�����������
�Ԃт炪�����ӂ肩�T���
�����̔����͂�͂炷��₤��
���N�̎������炫��̂����l��
�q���̏Ђ�������
����͏����������Ă���
���̕����b�B�c俕�
����M�̂Ȃ���
�ʎ��̂悤�ɊÂ�������
�����@���͏n��Ă���
�������`����S�̐F��
���{�C�̍��Ɂk�P���T�l����j�̐S��
�����@�����ƂȂ荂�Ă���
�ޓ��̘r����{
���ɉ炵�ď\���ɏd�Ȃ�
�����̐��E�̂悤��
�G�W�v�g�̋Ղ̂悤��
���̐��E�ɒ��݂Ȃ���
�����@��̒���݂�҂Ă���
1948�i���a23�j�N�̋g���́A�̂��ɏ������낵�̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�Ƃ��Ă܂Ƃ܂鎍�������͂��߂�O�N�ɂ���B1957�i���a32�j�N�ɂ́A�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j���`�����鎍�т����G���ɗ����Ɣ��\���Ă���B����ɂ��Ă��A�B�c������9�N�̊Ԃ�7���̎��W���o���Ă���̂ɂ͋��������B��f��2�тɂ́A�s�Õ��t�Ɓs�m���t�̊Ԃɂ���ȏ�̑傫�Ȋu���肪����B
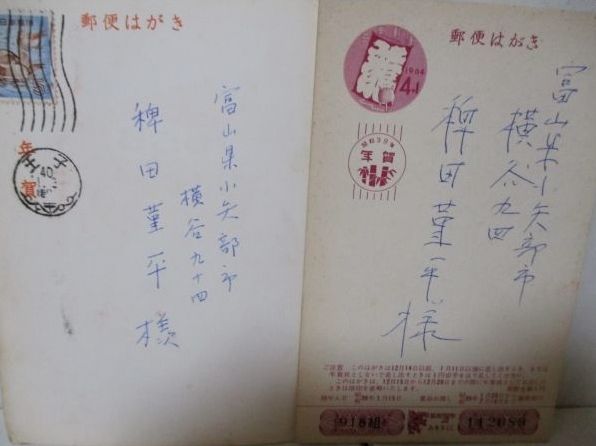 �@
�@
�B�c俕����̋g�����ƍr�ؓ�O�̔N���i2���Z�b�g�j�̎��M�ɂ�鈶���ʁi���j�Ɠ��E����ɂ�镶�ʁi�E�j�@�k�o�T�F���t�I�N�I�l
���Ȃ݂Ƀ��t�I�N�I�ɂ͕B�c俕��Ɉ��Ă��A�ȉ��̐l�l�̏��Ȃ��o�i����Ă���i2020�N1�����_�j�B�r�ؓ�O�E�鏬�O�A���c�וF�A����M�v�E���ˉ�v�A����@�i�A�F�����A��������A�ΐX���j�A�z�K�D�A�_�ی����Y�A���n���A�������v�A�^�ǐm�A�k��K����A�V�쒉�A���V�A����m�A���쓹�v�A���̂��イ�����A��������A�����V�g�A����l�Y�A�_�ی����Y�A�����Ȍ��A�a�c�O�O�A��絕���Y�A���B���{�������w�ҋ���A�x�R���������w����A���{���l�N���u�A�x�R���㎍�l��A�x�R�ߑ㕶�w������ɏ������A�x�R���������w�������߂��B�c�����ɁA�����̎��l�⎙�����w�҂Ƃ̌𗬂ɂ͖��Ȃ���̂��������悤���B
�ѓN�v����̃u���O�sdaily-sumus2�t�́q���ƍ��r�i2015�N11��17���j�ɂ́u���ފt�̌Ï��ژ^�w�N�ӂ肽�c�c�x19�������璆�ɓ͂��Ă����B����܂ł����x���Љ�Ă��邪�A���������[�����e�B����͕B�c俕��Ƃ������l�̋�������������Ƃ������̂��B�B�c�������s�҂��璼�ڂ�����Ă���G���⎍�W�ނ͊ȒP�Ɏ�ɓ���Ȃ����̂��������ŁA�������Ă���l�����ɂƂ��Ă͐����ł͂Ȃ����B������̓^�C�g���ƒZ��������ǂݎ���Ăǂ�ȎG���Ȃ낤�Ȃ��Ƒz�����邾���B����ł��ʔ����B���s�W�����낢��o�Ă���B�wRAVINE�x�s�����O�\�O���Ƃ��w�R���{�E���b��e�L�X�g�x�O�����{�Ƃ��w���l�ʐM�x�����O���Ƃ��w���x�s�����l���Ƃ��B�N�{���v�ҏW�́w�w偁x����ƁwONLY ONE�x�O��������B�v�ƌ�����B
�N���̏��a40�i1965�j�N�����A�g�����ƕB�c俕��ɂǂ̂悤�ȕt�����������������A�ڂ炩�ɂ��Ȃ��B�B�c�́q����N�\�r�ɂ�
���a�O���N�i���Z��j�O�Z�B�l���A�w�̂Ԃ����b�I�W�x�i�݂������[�j�ɓ��b�ܕт\�B�����A�w�N���̏W�x�ɒZ�̈�\�B�㌎�A���̏W�w�R���؏��x���o�ŁB��ꌎ�A�w�x�R�y���N���u���z�W�h�x�Ɂu����̉́A�o�l�Q���̐��U�v�\�����B
���a�O���N�i���Z�O�j�O���B�܌��A��O�̏W�w�^�������x�𔒂ƍ��Ђ��o�ŁB�㌎�A�攪���W�w�X�͂̒܁x�𓌋��v���Ђ��o�ŁA���̔N�̑�\���W�ɑI�ꂽ�B��Z���A�w�x�R���l�x�i63�j�Ɂu���t�ɂ��āv�\�A���̍�����x�R���㎍�l��̊�����������ɂȂ����B��ꌎ�A�V���o�ҁw���N�������w���y�L���s�x�ɔo�傪���^���ꂽ�B��B�j�b�|���[������Łw�X�͂̒܁x��莍�Z�т��������ꂽ�B
���a�O��N�i���Z�l�j�O���B�O���A�w�������{���l�x��l���Ɂu���t����Ɂv�\�B�����A�w���������x�Ɂu���̉́v�㌎�A�w�x�R���l�x�i64�j�Ɂu��̎��v�A�O�䐳�G�ҁw���Ɩ�Y�̂����x�Ɂu�ē�́v�\�B��w�N���̏W�x�Ɂu���ԏ��v�\���^���ꂽ�B�i�s�B�c俕��S�W�k��1���l�t�A��Z���y�[�W�j
�Ƃ��邩��A�B�c���玍�W�s�X�͂̒܁t��ꂽ�g�����A���W�s�a���`�t�i����ɁA1962�j��A�N���̂���肪���������̂��i�s�a���`�t�́u���s�v�͑���Ɂk�g���̎���l�����A�u�����v�͎v���ЂŁA�B�c�́s�X�͂̒܁t�Ɠ����Ō��ł���j�B�g���ɂ͕B�c俕��ɐG�ꂽ���͂��Ȃ��A�B�c�̑�����g�����Ɍ��y�������̂ł����Ȃ�������A���҂̊W�͂͂�����Ƃ킩��Ȃ��B�Ō�Ɂs���̐l�����T �V����2�Łt�i���O�A�\�V�G�[�c�A2002�N7��25���j�̋L�ڂ��������B�C���^�[�l�b�g�̏��Ɉ˂�ƁA�B�c俕���2014�N�ɖS���Ȃ��Ă���B
�B�c俕��@�Ђ����E������@�@���l�@�u�q�l���w�v��Ɂ@�k���N�����l�吳15�N4��8���@�k�o���i�o�g�j�n�l�x�R������s�@�{�����B�c�����@�k�w���l�X�������@�k�o���l�������o�āA���l�ƂȂ�B�x�R���������w�������߂��B���W�Ɂu�ԁv�u�����v�u�X�͂̒܁v�u�z�g�g�M�X���ĂԝR���ԁv�A���w�W�u���邷�ׂ�̉ԂƐl���v�A���b�W�u���R�̂Ăv�A���b�W�u�R�̐_���܂̂����v�ȂǁB�@�k�����c�̖��l���{�������w�ҋ���A�x�R���������w����A���{���l�N���u�A�x�R���㎍�l��A�x�R�ߑ㕶�w������i�����A���Z�`����y�[�W�j

�s�B�c俕��S�W�k��1���l�t�i�ُo�ŁA1978�N12��20���j�̔��ƕ\��
�k�NjL�l
�q�l���w�E��̉�ҁs�B�c俕��S�W�����L�O���k�q�l���w�ʍ��i�ʍ�68�W�j�l�t�i�B�c俕��S�W���s��A1983�N10��1���j�́A�`�T������38�y�[�W�̏����q�i�����Ɍ��G�ʐ^1�_�j�B�x�R�����}���ُ����̓����́q�ڎ��r�ɂ͂�������B
�@�m�C��c�c�c�c�c�c�A�����c�c�c�c�c�c�c2
�@�l�Ԃƌ|�p�c�c�c�c�ؑ����O�c�c�c�c�c�c6
�@��➁c�c�c�c�c�c�c��c�F���Y�@�ق��c�c7
�@�j��L�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c17
�@�@�@�@�@�@��L�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c30
�i�����͂Ȃ����j�B�c俕��ɂ��q��L�r�̑O���Ɂu���͍�N�̉āA�i�N�̔O��ł������ْ���W�w�B�c�����S�W�x���ꉞ�����ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂����B�܂����N�̏t�ɂ́A���̍�W�ɑ��ĕx�R�V�������܂����������܂����B���̏�A��y�⓯�u�̊F���ܕ��ɂ�鐷��ȗ�܂��̏W�������ɂ����čÂ��đՂ��܂����B���ɂ͂Ƃ��ɉߕ��̂��Ƃł���܂����B���̐܂ɂ��܂��܂����j���̂��������ƁA�ߋ��̍�i�ɑ��Ă������������Ȃǂ̈�[��������Ȃ���܂߂����Ă�����āA�����₩�ȋL�O����҂݂܂����B�v�i�����A�O�Z�y�[�W�j�Ƃ���悤�ɁA�B�c�̎��W�w�ԁx�i���a��\�O�N���j�Ɋ���c�F���Y�Ɏn�܂�q��➁r�����A�{���̒��ł���B�ΏۂƂȂ������ЂƕM�Җ����f����B
���W�w�ԁx�i��23�j�@��c�F���Y
���W�w�����x�i��25�j�@������
���W�w��ƘF�x�i��26�j�@�ێR�O
���W�w�ӓ��̋Ձx�i��27�j�@�⍲����Y
���W�w�K�N�̕^�x�i��28�j�@�J��r���Y
���W�w��̗��x�i��31�j�@���]�r�v
���w�W�w���邷�ׂ�̉ԂƐl���x�i��33�j�@�؉��[��
���w�W�w���������X�C�Z���̞��x�i��35�j�@���˕���
�̏W�w����x���x�i��35�j�@��؎�
���W�w���̏��x�i��36�j�@�c���~��
�̏W�w�R�[�؏��x�i��37�j�@�z�K�D
���W�w�X�͂̒܁x�i��38�j�@�،��F��
�̏W�w�^�������x�i��38�j�@������
���W�w��̏��_�x�i��41�j�@�㑺��
�̏W�w���̉��x�Ǝ��W�w�W�̂����݁x�i��43�j�@�ēc���O
���N���W�w��ԃJ���V�J�̏t�x�i��43�j�@�ΐX���j
���W�w���q�̉́x�i��43�j�@�i�c����Y
�̏W�w����R���x�i��43�j�@�a�c����
���W�w�z�g�g�M�X���ĂԝR���ԁx�i��44�j�@���i�ވ�
���W�w�[��̂Ђ炭�[�ׂ̘A�́x�i��45�j�@���n��
���a����n�w�B�c俕����W�x�i��52�j�@�����
���W�w�ꡋL�x�i��51�j�@�{�茒�O
���ƃG�b�Z�C�W�w�����L�x�i��53�j�@�A����
�w�x�R���㎍��T�x�i��56�j�@�v��N�Y
�̏W�w���C���_��x�Ƒ��ӗr�����w�I�w�����炭����x�i��58�j�@�哇���Y
�w�B�c俕��S�W�x�i��57�����j�@��c�F���Y
�O�f���M�̏�����̉��l�����܂ޕB�c俕��̕��L����F�W���������킹����肩�A�B�c��i�Ƃ̎�肠�킹�\�\���w�W�w���邷�ׂ�̉ԂƐl���x���؉��[���A���W�w���̏��x���c���~���\�\���Ȃ�Ƃ������[���B�Ȃ��A���́s�B�c俕��S�W�����L�O���t�ɋg�����̖��O�͌����Ȃ��i���Ȃ݂ɋg���́A�{�����s�Ɠ���10���Ɏ��W�s��ʁt���o���Ă���j�B

�q�l���w�E��̉�ҁs�B�c俕��S�W�����L�O���k�q�l���w�ʍ��i�ʍ�68�W�j�l�t�i�B�c俕��S�W���s��A1983�N10��1���j�̕\���k�J���[�R�s�[�l
��2019�N12���A�}�����[�̂o�q�������s�����܁t1969�N4���̑n��������2017�N8����557���܂ł̑������A���x�O����̐ΐ_�䏑�т���w�������B�n����1969�N�����A���͒��w2�N���ŁA�}�����[�̏o�ŕ��������炭������ǂ�ł��Ȃ��i�N���u�͓�e�j�X���ŁA�u���X�o���h�ł͑Ŋy���S�����Ă����j�B�Ǘ������{�̋L�^�����͂��߂��̂́A��w�Ɏ��s���āA���������̂��œ��{�̌��㏬����ǂ����Ă����Q�l�̂��납��ŁA���w������ɂǂ�Ȗ{��ǂ��܂������L���ɂȂ��B�Ȃɂ����Ă����̂��B�ɂ���������b�N�̃��R�[�h���āA����ɍ��킹�ăK�b�g�M�^�[��~���炵�Ă����i�G���L�͕s�ǂ������̂������j�B���ǂ��Ă����̂́s�����t�̏W�p�Ђ��o���Ă������y���sGuts�m�K�b�c�n�t�i�\���Z�p�o�Ŋ�����ЁF�ҁj���B�������o�Ă����̒m�炸�ɁA�ŐV�����Ŋ��̖{���Ō������i�\�����ΐ쏻�̍��j�A�Q�Ăđn��������̃o�b�N�i���o�[�������B�u���b�N���e���Ȃ���A���܂��̓C�����v�Ƃ��������蕶���A�E�b�h�X�g�b�N�t�F�X�e�B���@���̏ڕ�A�s�A�r�C�E���[�h�t�̊y���ɋ����������̂��B����ɁA�悤�₭�o�ꂵ�͂��߂��o���h�X�R�A�ɂ͋��삵���B�G���s�����܁t�̘b�������B�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���j�́q�t�^�F�}�����[�o�Ŋ֘A�����}�Łr�ɂ́A�n������M���Ɂs�����܁t���x������1979�N��1980�N������1970�N����2014�N�܂ł̊e�N��1�����i�\���G��ҏW�҂��ւ��̂͂�������1��������j�Ȃǂ̏��e��52�_�f�ڂ���Ă��āA�s�ς��B�n�����i�u1969�N5�����@�ҏW�ҁ��y��ꐳ�v�j�̕\���ʐ^�̘e�ɂ͎��̏���������B
�o�q���@�����w�����܁x
��P��
1969.4.20-1978.7.1
�\�����������ق�
A5���@�{���L��32�Ł{�L��
��Q��
1980.7.1-�p����
�\���f�U�C�����g�c�čO�{�g�c�_���i1998.1-�j
A5���@�{���L��32�`80�Ł{�L��

�o�q�������s�����܁t�̏��e�@�o�T�F�P�c�����s���e�̐X�\�\�}�����[�̑��� 1940-2014�t�i�݂��̂�o�ŁA2015�N5��3���A�ꎵ��y�[�W�j�@�k2�i�߂̉E�E�����ѓN�v����ɂ��\���G�l
���҂̉P�c�����́A�s���e�̐X�t�́q���Ƃ����r�Łu�k�c�c�l�����́s�t�^�t�ɂ����āA�}���ژ^��V���j���[�X���̃t���C���[�i�����́j�A���e���{�A�e��̞x�m������n�Ȃǂ̊֘A�����A����ɂ܂��A�o�q���w�����܁x�̑n���ȗ��̐V�N���S�����Љ�ł����̂��т���̒���э��z�̂������B�v�i�����A��Z���y�[�W�j�Ə����Ă���B���̒��O�ɂ́u�ѓN�v����́A�}�����[�n�Ɗ��Ȃǂ̋M�d����܂�Ȃ����{�̒������������B�Ƃ��ɐR��Y�A��䍎�V�A�n�ӈ�v�A�g���������ꂵ���폑�H���ɂ��A�܂����������̏d�݂���������v�i���O�j�Ƃ���A�����Ƃł���т��n�Ɗ��̋H�����������Ă���͔̂[���ł��Ă��A�u�}���ژ^��k�c�c�l�e��̞x�v�܂Ŏ��W���Ă���̂ɂ͊��V������Ȃ��B�����Łs�����܁t�ɖ߂�A�k��P���l��1������20���܂ł͏�����y��ꐳ�ҏW�A21���i1971�N1���j����111���i1978�N7���j�܂ł��g�����ҏW�ŁA���̂�����̂��Ƃ�10�N�O���q�g�����ҏW�s�����܁t�S91���ڎ��ꗗ�r�ɋL�����B�Â��ؕ��̂悤�ŋ��k�����A���̂Ƃ����q�ҏW��L 88�r�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B�����̕��͂������̂́A�J��ɂ���ł̂��Ƃł͂Ȃ��B���̌��Ɋւ��邩����A���̌�A�����͐i�W���Ă��Ȃ��̂��B�����̈Ӗ������߂A�K�X�A���s���Čf����B
���q�g�����ҏW�s�����܁t�S91���ڎ��ꗗ�r���������B�{�����ł��G��Ă���q�s�����܁t�ҏW�ҁE�g�����r���f�ڂ����̂�2003�N10������������A����6�N�ȏ�O�ɂȂ�B�����̖����Ɂu���̓����A�g�����ҏW�́s�����܁t�S����ǔj���������̂��v�Ə����Ȃ���A���܂��ɉʂ����Ȃ��͎̂c�O�����A����A�W����ƍ����Ȃ���{�����E���ǂ݂ł����͎̂��n�������B�����Ƃ��A�����̖ڎ����X�g���炾���ł����낢��Ȃ��Ƃ��킩��B
�E�o����ł������̂́H�\�\�z��p���q���70��B���̘A�ڂ͋g�����������s�{�̎��Ӂt�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1979�j�Ƃ��Ĉ�{�ɂȂ����B
�E�u��g�~�Y�v����Ƃ��u��g�~�Y�v�H�\�\NDL-OPAC�ł́u��g�~�Y�v�ƂȂ��Ă���B
�E�i��j���邢�́i��ځj�Ƃ͂���H�\�\��ڌ���ł��낤�B
�E�s�k�t���l�Ŏ��M���Ă��Ȃ��̂́H�\�\��c�G�B
�E�A�ڂ����������̂́H�\�\�g�����ҏW�ȑO����̂��̂��܂߂�10��ȏ�̘A�ڂɂ́A�z��p���q��́q�{�̎��Ӂr�i90��j�A���x���͂́q�ق�E���̖ڂł݂���j�r�i60��j�A���c���F�́q���p�U���r�i50��j�A���c���́q�����G�k�r�i44��j�A�g��K���Y�́q�Ǐ��̊w�r�i39��j�A�����Ɉ�́q�t�ďH�~�r�i26��j�A�x�m��p�Y�́q��鵂���b�r�i25��j�A�n�ӈ�v�́q���Ԕ��E������l�̃i���@�[�����܁r�i24��j�A�����Б��Y�́q�Ǐ����^�r�i18��j�A�������Y�́q�u���G���v���@�r�i12��j�A��C�m�`�́q�͏㔣�ƒ����̎��l�����r�i12��j������A�Ƃ�������ɋ����͐s���Ȃ��B
����ł��킩��̂悤�ɁA�����A���͋g�����ҏW�́s�����܁t��[�{�ł������肵�Ă��炸�A�i�c���̍�������}���ق���̓��{�ߑ㕶�w�قʼn{�����āi�ڎ��̓R�s�[������āj�A�L�������M�����̂������B�ҏW�ҁ^�����Ɓ��g�����ɑ���S�����S�ƂȂ邾�낤�s�����܁t�����̊J�n�ɂ������āA����́A40�N����k��Q���l�́s�����܁t�̂Ȃ�����1����I��ŁA���Ă݂����B�����2009�N7����460���ŁA�����̕\���G��`���A�\���Q�i�\�����j�̘A�ځq�ӂ�ق�̂ق���r��7��́q�����r���������̂́A��Ƃő����Ƃ̗ѓN�v����ł���B�����̌㔼�������B
�@�k�c�c�l
�@����l���\�ܓ��A�ӂƁA�����ɌÖ{���֍s�������Ȃ����B���͏���ɂ킪�Ƃ����ԋ߂��Ö{�������ē����o�����B�d�Ԃɏ���ď\���]��B�Ƃ��낪����ȓ��ɂ������Ėړ��Ă̓X�͒I����������₵���Ȃ��Ă����B�ԋ߂�������O�ł̑�����̂��߂ɉב��肵�Ă��܂����̂��낤�B���҂̕��D�ʂ��V�����V�����V�����b�ƈނށB�ǂ����Ă���Ԃ�ł͋����A�݂傤�Ɏ��E���悭�Ȃ����X���������܂����_�����Ă���ƁA����܂ŋL���ɂȂ�������Ђ�����ƍ�����Ă������B�����Ɣ����o���B�g�����̐��z�W�w�u�����v�Ƃ����G�x�i�v���ЁA��㔪�Z�j�B�\���͏��惆���C�J�̈ɒB���v�ɂ��Ẳ�z�ł���B�c�O�Ȃ���S�~���S�~�ł͂Ȃ��������A�������������Ƃ͎����B�����炱����E���ǂ݂������Ȃ�����������������̂��ɉ������悤�ɒ���ɍ����o�����B
�@���̖�A���̘b���u���O�Ŕ�I�����B����Ƌg�����̏ڍׂȏ������l�b�g��Ō��J���Ă����鏬�ш�Y����莟�̂悤�ȋ����̂��w�E�������������B
�@�u�Q�O�O�X�N�S��15���́A�g���̐��a90���N�i�I�j�����ł��B���́w��ʁx�̎���ǂ�ŁA�ЂƂ�j�t�������܂����B�v
�@�w���������Ă��ꂽ�̂͋g���̗�c�c�܂����B�Ƃɂ������������R�������B�����܂ł��Ȃ��g�����͖{���̕ҏW�����������Ƃ�����B�i�q�ӂ�ق�̂ق���7�\�\�����r�A����460���A2009�N7���A�k�\���Q�i�\�����j�l�j
���@��o�A�ѓN�v�s�ӂ�ق�̂ق���t�i�����낸���A2019�j�ł́A�{���̌r���ɗ��O���̂悤�Ȍ`�Łu�w�u�����v�Ƃ����G�x���������Ö{���͍�}���s���E�����V�_�w�ɂقNj߂����h�j�J���ɁB�v�i�����A���y�[�W�j�Ƃ����NjL������B
�т��s�����܁t��S�������̂́A2009�N��2010�N��2�N�ԂŁA�����̕ҏW�҂͐ؐ^�����B�q�ӂ�ق�̂ق���r�͒��炭�G���f�ڂ̂܂܂��������A2019�N7��26���A�����낸������s�ӂ�ق�̂ق���t�i����500���j�����s���ꂽ�B�u�b�N�f�U�C���́A�����܂ł��Ȃ��т��g�ł���B�����ɂ͘A�ڌ��e�ɉ����āA�܂������ɑ�������V�e�q�ق�����r�A���Ƃ����ɑ���q�ӂ�ق�͕��r�i���o��2009�N1���́scoto�t17���j��2�тƁA�e�{���L���̑Ό��Ɏʐ^�i���́q�����r���Ɓu�w�g�������W�x�i���惆���C�J�A1959�j���G�ʐ^���g�����v�j�ƁA�q�f�ڎ��w�����܁x�\���ꗗ�r�Ƃ����A�S24���̏��e���t���ꂽ�B���Ȃ݂ɏ�����50�Ԗ{�ɂ́A�\���Q�ɗт���̒��M�Łu�I�ԗ��M���悢��肪�������v�Ƃ����傪�A�����E�����ƂƂ��ɔF�߂��Ă���B
 �@
�@ �@
�@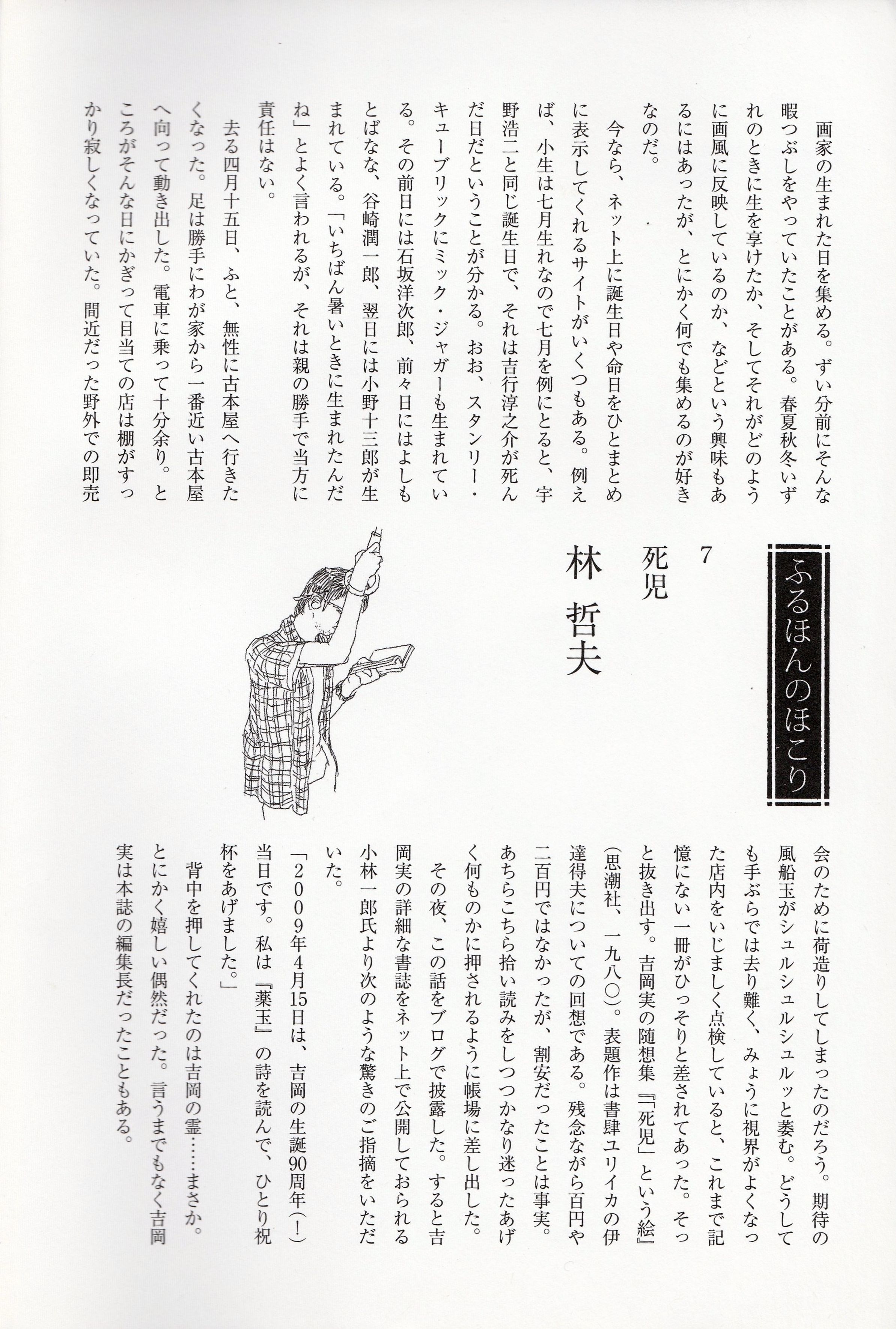
�ѓN�v�s�ӂ�ق�̂ق���t�i�����낸���A2019�N7��26���j�̕\���k�G�́s�����܁t2009�N1����454���̕\���Ɠ����l�i���j�Ɓs�����܁t2009�N7����460���̕\���k�\���G�F�ѓN�v�l�i���j�Ɠ��E�\���Q�i�\�����j�i�E�j
�s�����܁t2009�N7����460���́q�ڎ��r�i�����A�k��y�[�W�l�j���Č����Ă݂悤�B�f�ڃm���u�������̂܂܋N�����Ă݂�B
�������@��460����2009�N7�����ڎ�
�\����
�m�ӂ�ق�̂ق���n7�E�����b�ѓN�v
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�������M
�m�l�ԁA�Ƃ肠������`�n130�E�k���N�Ɛ̂̓��{���d�Ȃ�b�Ȃ����Ȃ��c�c�c�c2
�m�e���r�����فn12�E�l�߂ƍٔ����b��������c�c�c�c�c�c�c�c�c4
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���`�t�̓łɐ����b�����ȕ��c�c�c�c�c�c�c�c�c6
�����ċ߂��]�˂̑��b�n�ӏ��u�c�c�c�c�c�c�c�c�c8
��́u���E���S�v�b�����͂��߁c�c�c�c�c�c�c�c�c10
�l�E���̎����b�͍����Y�c�c�c�c�c�c�c�c�c12
�쐶�̃G�`�J�b�������c�c�c�c�c�c�c�c�c14
���З\��̐S�����b�ēc�āc�c�c�c�c�c�c�c�c16
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�V�A��
�m�킽���́A��������n1�E�����w����n�܂�b���ѐM�F�c�c�c�c�c�c�c�c�c20
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�A��
�m���ɂ��֓����Ύ��L�n24�E���[�Ƌ��b��ؗ����c�c�c�c�c�c�c�c�c22
�m��ނӂӣ�̐l�n10�E�f�N�m�{�[�Ƣ���_�أ�b���Џ@�v�c�c�c�c�c�c�c�c�c24
�m����Ȃ�ɐ����Ă���n23�E�����Ƃ�n�ł����悤���Ȃ��b�Q�悤���c�c�c�c28
�m�����R���f�B�A���j�n23�E�u�쌀���v�����܂Łb�V�c�����c�c�c�c�c�c�c�c�c32
�m���������䂭�n11�E��O�Z�Z�N�̗��j��ۂޓޗǂ̖�b��㗝�Îq�c�c�c�c36
�m�⋩�ψ���n40�E����Ȕ��Ȃ��^����b�䑺�O�c�c�c�c�c�c�c�c�c40
�m�哇���Ɠ��{�n18�E���߂鏗�����b�l���c���F�c�c�c�c�c�c�c�c�c42
�m�_���N�Ў����n12�E�Y�������Ƒ�t�����̐[�w�b�ۍ㐳�N�c�c�c�c�c�c�c�c48
�m�l�ɂ��^�C�v�n89�E�ω��b�ݖ{���m�q�c�c�c�c�c�c�c�c�c54
�m�����̕x�n4�b����k�l�O�c�c�c�c�c�c�c�c�c56
�m�O�b�h�E���b�N�n20�b���c���q�c�c�c�c�c�c�c�c�c62
�m�s�X�^�`�I�n15�b���؍����c�c�c�c�c�c�c�c�c68
�m�t�̌�䊁\�\�ٍˁE��������̐��U�n26
�@�@�@�@�@�@�掵�́w���ꕔ�����N�j�x���߂�����(���̈�)�b���Y�a���c�c74
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�R����
�m�E���̖{�I�n3�E���n�̓����b��ؖM�j�c�c�c�c�c�c�c�c�c79
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
���\�Z�Ɏ��܁@��i��W�c�c�c�c�c�c�c�c�c18
�ҏW������c�c�c�c�c�c�c�c�c80
�\����i�@�ѓN�v
�\����{���f�U�C���E�J�b�g�@�g�c�čO�E�g�c�_��
�g�������ҏW���Ă����k��P���l�́s�����܁t�Ɋr�ׂČ��e�̖{�����i�i�ɑ����A�y�[�W������3�{�ɑ����Ă���i�{����80�y�[�W�A�����́q�V���ē��r��16�y�[�W�A�\���܂�肪4�y�[�W�̍��v100�y�[�W�j�B����܂邲�Ɓs���Y�t�H�t��ǔj�����Ŗ����̌�������킯�ł͂Ȃ����A���͂����̂悤�Ɏd�������Ȃ��炱��460����ʓǂ���̂ɁA�ق�3���Ԃ�v�����B�@������āk��Q���l�s�����܁t�̖ڎ����f�[�^�x�[�X�����������̂��B�����A���ꂱ�����ɂȂ���̂��B���Ȃ݂ɁANDL-OPAC�ł́i���O�C������j�n�����̏ڍ������{���ł���B�ߔN�̍����A���̂ɂ���Ắq���̍��̋L���r�����邱�Ƃ��ł���B���݂ɁA460���̂�����f���Ă݂悤�i�Ȃ����A�т���̐��z�͍̘^����Ă��Ȃ��j�B�{������N�������O�f�q�ڎ��r�Ɣ�r����̂��ꋻ���낤�B
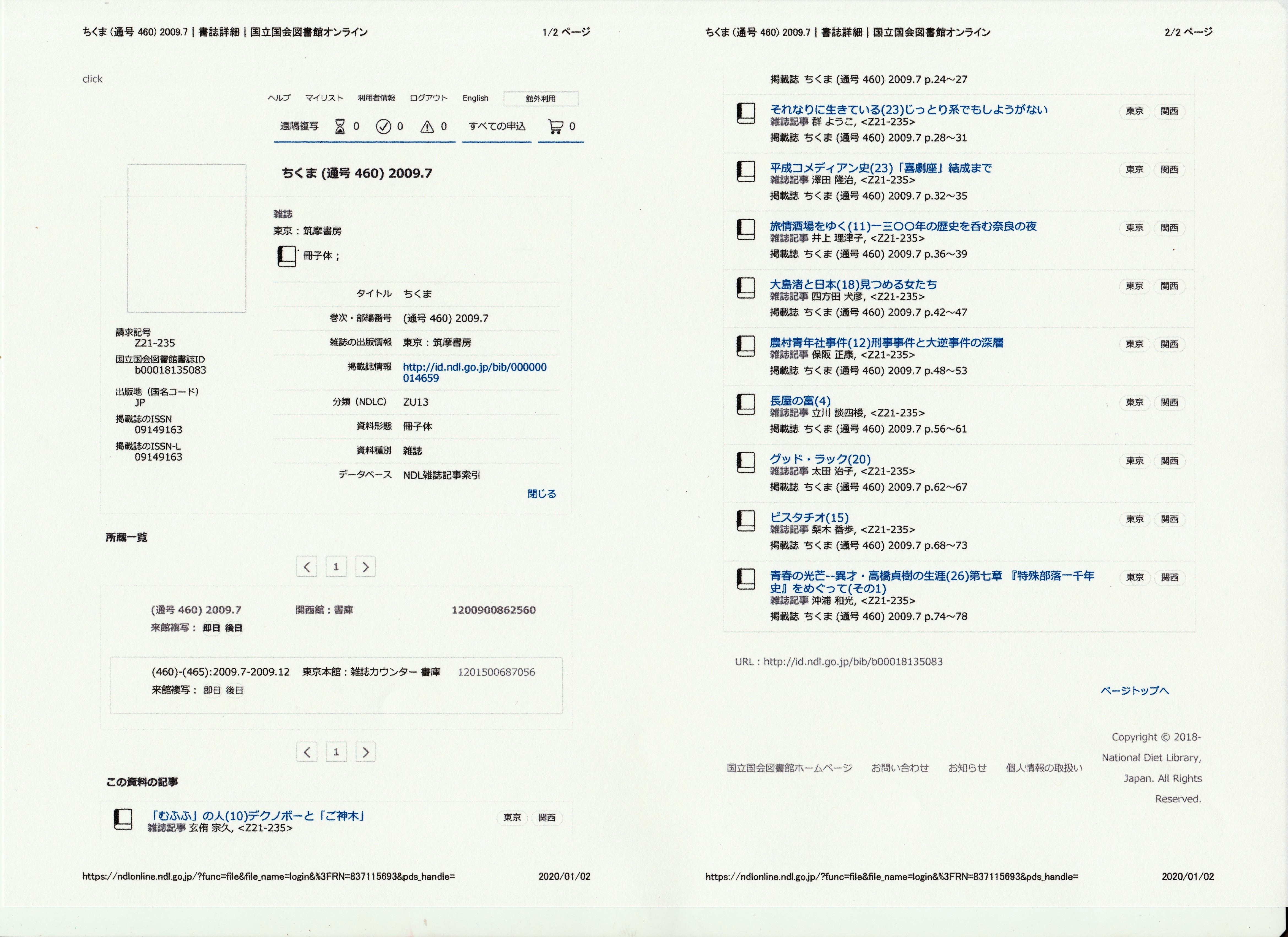
��������}���كI�����C�� | National Diet Library Online�Ō��������q������(�ʍ� 460)2009.7�r���o�͂�������
�o�ŎЂ̂o�q���ɂ��Ă����Ƃ���M�I�Ɍ�����̂́A�ؓ��S�O�i1958�`2020�j�ł���B���́s���̑̂�ʂ�߂��Ă������G�������t�i���o�́s�����V���t2002�N2�����`2004�N11�����j�́q�o�ŎЂ̂o�q���̂��Ƃ��Y��Ă͂����Ȃ��r����A�s�����܁t�ւ̌��y�̂���i�������������āA�����̓s����A�ԍ���U���Čf����B�k�@�l���͏��тɂ���L�B
�@�}�����[�́w�����܁x�����������B�ނ���k�ؓ��̑�w����i��㎵���N�`��㔪�O�N�j�l���������[�����Ă��邩������Ȃ��B����ǂ�����ƘA�ڕŁm�y�[�W�n�����߂��銴��������B�A�ڕł������ƃX�^�e�B�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B����ɁA�A�ڕ����肾�ƒP�s�{�̂��߂̔��≷���Ɍ����Ă��܂��B
�A�k�ؓ����_�ے��̋߂��̗\���Z�ɒʂ��Ă����Q�l���i��㎵���N�j�̂���l�ȗ����́A�o�ŎЂ̂o�q�������ǂ��Ă���B�w�}���x�A�w�����܁x�A�w�g�x�A�w�{�x�A�w�t�ƓǏ��x�A���̌��������̃��W���[���m�A�A�A�A�A�n���������A�����̎G���͂��ׂČ����i���P�j�ɏ��X�ɕ��ԁi���̔��s���͍����ς�Ȃ��j�B���ׂām�A�A�A�n�����Ə��������A���́A�o�鏇�Ԃ͔����ɈقȂ�B�������w�{�x�w�t�ƓǏ��x�w�g�x�w�����܁x�w�}���x�̏��������Ǝv���i����A�w�{�x�Ɓw�t�ƓǏ��x�̏��Ԃ͋t��������Ȃ��j�B���͂����̎G�������X�Łi���ɐ_�ے��̊�g�u�b�N�Z���^�[�Łj�A���������Ă���̂��D���������B���X�ɒu���ꂽ����Ɍ����Ȃ��ƁA��肻���˂Ă��܂����Ƃ�����B���Ɂw�����܁x�̔��s�����́A�����A���Ԃ����������Ə��Ȃ��A���͂悭��肻���˂��i��w�ɓ��w������A�����̂悤�Ɋ���o�����啶�w�������̏��X�Ŏ�ɓ���悤�ɂȂ肻�̐S�z�͂Ȃ��Ȃ����\�\�Ə����Ă�����Ɏv���o�����̂����A�}�����[�͎�����w�ɓ��w�������|�Y����������w�����܁x�����炭�x�����Ă����͂����j�B
�B����ǁA�Ⴆ�w�����܁x�́A���̉Ƃɑ����ė���������ۂ̔��s�����������x���̂ŁA���A��g�u�b�N�Z���^�[��a�J�̈����ŁA���������̓��ɂ��������Ă��܂��B�k�c�c�l
�C�w�����܁x�͓�\�����c�����B
�@��㔪��N�㌎���ɂ͕tⳁm�ӂ���n�������Ă���B
�@�J���Ă݂�Ƙ@���d�F�̃G�b�Z�C�u�f��ɐ����c���������ɂ��āv�ŁA����ȉӏ��ɐԐ��������Ă���i�T�_�͌����j�B
�@���������f��̔����m�A�A�n�Ƃ́A�������̂𔒂��B���������̂��̂ł͂Ȃ��̂��B�`�������Ƃ���ɂ��ƁA���́w��Ձx�̂܂䂢�܂ł̎����̔��ǂ𔒂��m�A�A�n�Ƃ��ăt�B�����ɒ蒅�����邽�߂ɁA�J�[���E�h���C���[�͕ǂƂ����ǂ�s�C���ȃs���N�F�ɓh�点�Ă������Ƃ����B�@�₪�ė���j���[�A�J�I�Ȃ��̂ɁA�o�ŎЂ̂o�q���̒��ŁA��ԘA�����Ă����̂��w�����܁x�������B��㔪�O�N�ꌎ���ɂ͎R�����j�ƑO�c���̑Βk�u�s�s���w�_�̐V�n���v���ڂ��Ă���B�R�����j�ƑO�c���͎G���w�����{�x�̐X���O���W���ł����l�̑Βk���s�Ȃ��Ă���A����͐l�����@����o���R�����j�̑Βk�W�Ɏ��^���ꂽ���A���̑Βk�͏��o���̂܂܁A�Ȍ��l�̒���ɂ͖����^������M�d���B
�D�w�g�x���w�����܁x�Ɠ������炢�̍������c�����B�w�����܁x�ɔ�ׂ�Ɓw�g�x�̓I�[�\�h�b�N�X�ȕҏW���������A���͂��̃I�[�\�h�b�N�X�������ł͂Ȃ������B�i�s���̑̂�ʂ�߂��Ă������G�������t�A�V���ЁA2005�N2��20���A���l�`����y�[�W�j
�g������1969�N5���n���́s�����܁t�̕ҏW��C�i���Ȃ킿�ҏW���j�߂Ă����̂́A�O�ɂ��q�ׂ��悤��1971�N1���̑�21������1978�N7���i�����A�}�����[�͎�����A�|�Y���Ă���j�̑�111���܂ł̑S91���������B�A�́u�}�����[�͎�����w�ɓ��w�������|�Y����������w�����܁x�����炭�x�����Ă����͂����v�́A�܂��ɂ��̂��Ƃ��w���B�܂��A�ؓ����C�ŋ����Ă���1981�N9�����A1983�N1�����Ƃ��A�ҏW��C�͂̂��ɒ}�����[��\������߂����������i1939�`�@�j�ł���B�������A���������N���m���W�[�͏����ڂ������ׂ�ΒN�ɂł��킩�邱�Ƃł���A�ؓ��̒B���͇@�́u�A�ڕł������ƃX�^�e�B�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B����ɁA�A�ڕ����肾�ƒP�s�{�̂��߂̔��≷���Ɍ����Ă��܂��B�v�ł���A�A�́u���Ɂw�����܁x�̔��s�����́A�����A���Ԃ����������Ə��Ȃ��A�v�ł���A�B�́u�w�����܁x�́A���̉Ƃɑ����ė���������ۂ̔��s�����������x���v�ł���A�C�́u�₪�ė���j���[�A�J�I�Ȃ��̂ɁA�o�ŎЂ̂o�q���̒��ŁA��ԘA�����Ă����̂��w�����܁x�������v�ł���A�D�́u�w�����܁x�ɔ�ׂ�Ɓw�g�x�̓I�[�\�h�b�N�X�ȕҏW�������v�ł���B
�ؓ����u�Ǐ����D���ɂȂ��Ă��������Z�����炢�̎����炻�̎�̂o�q�G���R�Ǝ�ɂ��Ă����v�i���O�A���܃y�[�W�j���傤�ǂ��̂���A���͑�w���ŁA�V���Ђ́s�g�t�����ǂ��Ă����B�������܂܂łɔ������V���̕��ɖ{�ōł������̂͂����炭�V�����ɂ��B�܂�A�P�s�{�͍������A�ǂ�Ŏ苖�ɒu���Ă��������悤�ȍ�i�\�\���Ƃ��Ε��i���F�̏�����G�b�Z�C�\�\�͕��ɂő��������̂��i�V���Ђ���o�����i���O�́q�S�����r�A�f��́q�S�W�r�Ƃ��S������肵�A�S�W�����^�̍�i���e�Ђ̒P�s�{�ő��������A�����ɂ܂��Ƃ��ȕ��i�_�������Ă��Ȃ��j�B�����ЂƂA�V���Ђ͒����ȕ��M�Ƃ̍u�����V�h�E�I�ɚ����z�[���Ŗ������J�Â��Ă��āA���̍��m���s�g�t�Ɍf�ڂ��ꂽ�B���������A�͂����ʼn��債�āA���I���������̂ł͂Ȃ����i�s��Ƃ�w�҂̋M�d�ȍu��������������T�[�r�X�J�n�I | News Headlines | �V���Ёt�ɂ́u���ĐV���Ђ�1966�i���a41�j�N�`96�i����8�j�N�A�����E�V�h�̋I�ɚ����z�[���Ŗ����u�V���Ђ̕����u����v����Â��Ă���܂����B�܂�1980�i���a55�j�N�`91�i����3�j�N�ɂ́A�����r�܂̃X�^�W�I200�Łu�V�������u����v���Â��A���݁A�������킹�Ė�800�{�̍u��������ۗL���Ă��܂��B�v�Ƃ���j�B�����g�����̎��ɐG�ꂽ�̂́A�剪�M�i1931�`2017�j�ɂ���Ăł���A�剪�̒���ɐe���ނ悤�ɂȂ����̂́A�V���Ђ̘A���u���i���������N�ԑ������j�̂������ł���B�����ł����Q�����̂͌ܖ؊��V�i1932�`�@�j�ِ̕ゾ�����B����Ƃ��o�d������ꐺ�u�R�[���h�p�[�}�������܂����v�́A���܂ł����̐��̒��q�ƂƂ��ɉ����Ă���B�������ʓ|�ŁA�R�[���h�p�[�}���Ƃ��ꂪ�����Ԃ�ɘa�����Ƃ����悤�ȁA�{��Ƃ͊W�̂Ȃ��b��Ȃ̂����A�Ƃɂ������́u���݁v�͔��Q�������B���̓_���炷��ƁA���M�̈���A��w�ŋ��ڂ��Ƃ��Ă����剪�ɂ��Ă��ҖM���i1925�`1999�j�ɂ��Ă��A�����ƒ����ȃG�b�Z�C�ӂ��Łi�m�Ԃ���P��_�����҂̘A���u���ɂ͑��e�������āA���������Љ�����\�肾�ƕ��������A���̌�ǂ��Ȃ����̂��낤���i���Q�j�A�ܖ̘b���V���Ђ́s�g�t�Ȃ�A�剪��҂̂���͒}�����[�́s�����܁t�Ƃ����������������B
�ؓ��ɂ��o�ŎЂ̂o�q���_�̒_�͎��̉ӏ����B�\�\���Ƃ��V���Љ�ł����Ă��A�������������O�V���b�g�łƂ炦�āA�ܔN��\�N��̍ēǂɑς�����̂��ڂ��Ă��炢�����̂��B����͕M�ґ��̐ӔC�ł���ȏ�Ɂi�Ǝ�����I�ɏグ�Č����j�A�˗����鑤�̕ҏW�҂̐ӔC�ł���Ǝv���B�^���ꂮ�炢�A�o�ŎЂ̂o�q���Ƃ́A�ڗ����Ȃ�����ǁi�ڗ����Ȃ����炱���j�A�v���Ƃ��Ă̗͗ʂ��K�v�ȎG���Ȃ̂ł���B����A�ҏW�҂Ƃ��Ęr�̌������̂���G�����B�\�\�i�s���̑̂�ʂ�߂��Ă������G�������t�A���܃y�[�W�j�B���̌����ɂ́A7�N���ɂ킽���ās�����܁t�̕ҏW����|�����g��������m����ɈႢ�Ȃ��B
���͂t�o�t�ɂ�������A�������Ŏ��Ђ̔}�́i�q�����ȓǎ҂Ƃ���A���̂o�q���j�̕ҏW��S���������Ƃ�����B��ނ��Č��e�����M����̂͂Ƃ������A�����ǂ����Ă邩�A�ƂĂ���J��������������i���̍��͂悤�₭���ڂ���͂��߂��C���^�[�l�b�g�̓��W�������j�B�o�ŎЂ̂o�q���Ȃ�A�Ȃ����������낤�B
�k�NjL�l
�q�ق�E���̖ڂł݂���j�r��60��ɂ킽���ās�����܁t�ɘA�ڂ������x���́i1900�`1992�j���������{�ɂ܂Ƃ߂��s�}�� �{�̗��j�k�G�f�B�^�[�p���l�t�i���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1982�N2��10���j�́q���Ƃ����r�Ɂu�����[�ł͈�ؑ��X�̏o�ŕ��̍L�����̂��Ȃ������[�����̏o�Ŋ����̌����o�q���u�����܁v���o�����ƂɂȂ����B�v�i�����A�ꔪ�O�y�[�W�j�Ə������悤�ɁA�x���O�́k��P���l�s�����܁t�i1969.4.20-1978.7.1�j�́u�{���L��32�Ł{�L���v�ŁA���Ђ̏o�ōL�����f�ڂ��Ȃ������B111���i1978�N7���j�͋g�����ҏW����|�����Ō�̍������A�ےJ�ˈ�⍂���N��̎t���������䐳��i1911�`2005�j�́q�~���g���Ƃ̏o��r�̖{�������ɁA���Ђ̋ߊ��Ƃ��ă~���g���i���䐳���j�s���y���t�̌r�݂͂�3�s�L���i�{��2�i�g�̉��i���j�����邾���ŁA�{���g�ݍ��݂̍L���͈�Ȃ��B����A�k��Q���l�s�����܁t�i1980.7.1-�p�����j��460���i2009�N7���j�ɂ́A178�~38�~�����[�g���i���Ȃ킿�V�n�͒i�����A���E�͖{��10�s���j�̑��Ђ̏o�ŕ��̏��ЍL���������{�A�ڂ��Ă���B�Ō����������Ă����B��g���X�A�@�U�فA�@����w�o�ŋǁA�c�����X�i�Ï��X�j�A�������o�ŁA�t�H�ЁA�Q���ЁA���}�ЁA�y�ЁA�����ЁA���{�Ï��ʐM�ЁA�}�����[�B�����ɂ�16�y�[�W�̕ʍ��莩�ЍL���i�s�}�����[ �V���ē��t�Ɠ������e�j�����āA�\���R�ɂ͕��Y�t�H�A�݂������[�A�g��O���فA�m�s�s�o�ł̃��m�N���o�ōL���i85�~50�~�����[�g���̌r�͂݁j������B�\���S�i���\���j�ɂ́APILOT�̍��������{�[���y���̃J���[�L���������āA�w�ɋ߂������ƌr���ɂ͉��t�ɑ�������L�ڂ�����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�ӔN�̋g���Əa�J������X�g�b�v�i�u�g�b�v�X�v�Ə����l�����邪�A�u�g�b�v�v�ł���j�̓�����X���������w�O�X���������Ŋ��k�̂���A�u�k�Ђ́s����PENTHOUSE�t�i1983�`1988�j���x���ɂȂ����o�܂�u���ꂽ���Ƃ�����i���l�����̃k�[�h�ʐ^�\�\�������ł���W�p�Ђ́s�����v���C�{�[�C�iPLAYBOY���{�Łj�t�̂���Ɋr�ׂĐ���I���������A�s���v���t��2008�N11���ɋx�������\�\������݂ɂ��Ă����悤���j�B�����A�������s�G�X�N�@�C�A���{�Łt�̐���i�s��S�����Ă������Ƃ������āA�����ҏW���ŏ����ɋ��������`���������̂��B�G���S�̂�����𑱂��Ă��鍡���ł��������Ǝv�����A�s�̂̌����G���̔������́u�����v�A�Ƃ�킯25���ɏW������B����͑���̕�҂̋������Ă���ł̕���ŁA�s�G�X�N�@�C�A���{�Łt�̔������́A�掟�X�Ƃ̌��̌��ʁA����24���ƂȂ����B���Ȃ݂ɎG���ƊE�ł́u�������v�Ƃ͌ĂȂ��B���ʂ�L���̖ʂ���́A�������i���t�ɂ��锭�s���A�ł͂Ȃ��j���ł��d�v�ŁA�u�k2020�N�l7��24�����m����n�v��u7/24���v�Ȃǂƕ\������B�]�k�����A����ʂł�4�����i3/24���j���������ւ����B2����28����29�������Ȃ����炾�B���́A2���Ȃ���3���̍��͑傫���B�{�T�C�g�s�g�����̎��̐��E�t�̍X�V�������������Ȃ̂́A�g�����̖������u31���v�Ȃ̂ƁA�������ās�G�X�N�@�C�A���{�Łt��S�����Ă������Ƃ̖��c�肩������Ȃ��B
�i���Q�j�@1994�N3�����痂95�N2���܂Łs�����܁t�i�����̕ҏW���͔��������j�ɖ���4�y�[�W�f�ڂ��ꂽ12��̘A�ځq�K�N�̒��ف\�\�����P�_�̎��݁r����{�ƂȂ����ҖM���́s�K�N�̒��ف\�\�����P�_�̎��݁t�i�}�����[�A2000�N1��20���j�́A���ҟf�㊧�̈⒘�B�A�ڍŏI��̖����ɖ{�����������������Łu�\�\�k�c�c�l�Ȃ��w�K�N�̒��فx�͑啝���M�̂����A����ܔN�H�ɒ}�����[���㈲�̗\��B�v�i�s�����܁t287���A�O��y�[�W�j�Ɨ\�����ꂽ���A�Ȃ̒ҍ��ێq�͓����́q���̂Ȃ��̂�����̕����\�\���Ƃ����ɂ����ār�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B�u�k�{���́l�A�ڏI���̒��コ��Ɉ���������낵�A���炭��ɁA�ׂ��������ŏ����ꂽ���Ђ�\����ĂقڑS�ʓI�ɉ��M���A���p�����Ȃ葝�₵����ŁA���݂̌`�ɂȂ������̂ł���B�v�u�ŏI�͂����M�ł��Ȃ������Ƃ����_�ł́A���̏����͖�������������Ȃ��B�k�w�h�D�C�m�̔߉́x�l��\�̖`���̂��܂�ɂ����l�Ȉ��ɓ�����āA�u�F���̉ʂĂɗ��v���Ƃ́A�����炭���̂����Ȃ����܂܂ł͕s�\�������̂ł͂Ȃ��낤���B���Ƃɂ́u���فv�����c��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł́A�w�K�N�̒��فx�͎��������k�ҖM���͈����N�̂��̓��A�}���l�̌ߑO�Ɋ������A���A�����̂��Ǝv�������B�v�i�����A�ꔪ�Z�y�[�W�A�ꔪ���y�[�W�j�B����ɁA�u�k���l�����N�ɂ́A�u��Ƃɂ����鑶�݂Ɩ��i���̐��܂��ꏊ�j�v�Ƃ����Z��̘A���u�����s���A���̂����̑�O��������P�ɂ��ĂĂ���i�u�p�����z������́B�����P�̏ꍇ�v�j�B�ڂ����N���Ɋ�Â��āw�}���e�x����w�I���t�H�C�X�x�Ɏ��鎍��̕ϑJ��H���Ă���A����I�ȉ��l�ς��z���Đ[�����_�́u���݁v�Ɏ���Ƃ�����|�́A�{���̊�{�I�Ȏp���Ƃ����ʂ��Ă���i���e�����ƍu���e�[�v�̏����N�������c��j�B�v�i�����A�ꔪ�O�y�[�W�j�B���̍u���̎�Â��V���Ёi�s�ҖM���S�W�t�\�\�k��15���l�i2005�N8��25���j�Ɂs�K�N�̒��فt�����߂�\�\�̔Ō��ł�����j�ŁA17�N��̃����P�_�̎G���A�ڂ��s�����܁t�A���̒P�s�{�̔Ō����}�����[�A�Ƃ����͎̂��́u�o�ŎЂ̂o�q���v�̈�ۂƂ܂��������v����B�Ȃ��A�ҍ��ێq�̑O�f���Ɉ˂�A�����̒S���ҏW�҂͒C���l�Y�A�����͒������ق�i�����A�ꔪ���y�[�W�j�ł���B
�]�ː에����e���O�Y�̂悤�ɓ��L�������Ȃ������҂�����\�\�����̓\�G�N���A���e�̎����̂��̂����L�̖�ڂ��ʂ������\�\�A�g�������������̂悤�ɓ��L���₵���҂�����B�{�e�i�ȑO�ɂ��q�g�����Ɖ�������r�������Ă���̂ŁA�q�g�����Ɖ�������i2�j�r�ɑ�������j�ɐ旧���āA��������̓��L�q�����̎� �W�ȍ~�\�\1960�i���a35�N�j�`1974�i���a49�N�j�r�i�s���������i��W�V�\�\���������L�E�G�b�Z�C�E��V�^�t�A����A���X�A2016�N7��16���j��ǂ�ŁA���͋g�����̓o�ꂷ����̋L�ڂ��e�L�X�g�f�[�^�����āA�o�b�Ɏ�肱�i�{�e�Ɉ������u�g�����v�u�g���v�͐Ԏ��ŕ\���B�Ȃ��A�g�������L�␏�z�ŐG��Ă��鎖���Ɋւ��Ă��A����������L�̋L�ڂ��E�����j�B�g�������ł��e������������̂́A���l�̐��e���O�Y�i1894�`1982�j�A�o�l�̉i�c�k�߁i1900�`1997�j�A�����Ƃ̓y���F�i1928�`1986�j�����A�g���ɗ�炸�o�l�̉���������܂��A���̎O�l�ƔZ���Ɍ�������B�����ŁA�g���Ɖ����̓��L�␏�z�ɂ����̐l�l���o�ꂷ����𒆐S�ɁA�g���̋L�q�������Ōf���A�u��������v�u����v�͐��ŕ\�����Ă݂��i����ȉ��́A���тɂ��R�����g�j�B��������͓��L�{���̊����ɐ������g�p���Ă��邪�A�C���^�[�l�b�g��ł͂��ׂĂ��Č��ł���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�g�������g�����v�̂悤�ɐV���ɉ��߂��B�������A�u�F�V�v��u�ܒJ�v�͖{�l�̗p�@�d���Č����̂Ƃ���Ƃ����B���������́A�̂ĉ����̎g�p���܂߂āA�����̃}�}�B�Ƃ��ɁA���Ď����q�g�����N���r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�j���쐬����ۂɍs�����̂́A�g�����g�̕��́A���Ȃ킿�����E�����̐��z�A�����̓��L�A�����J�̂��̂��܂ޏ��ȂȂǂ̏��������Y������N���Ƃɔz�u���āA������ɂ݂Ȃ��當�͉����邱�Ƃ������B�E�菃��s���F�e���q�C�L�\�\�F�V���F�`�t�i�����ЁA2019�N11��15���j�����́q��v�Q�l�����r�ɂ́A�u�S�W�E�N���E���͏W�����E���W�G���A���b�N���E�����v�����ď��Ȃ��������Ă���B���̓`�ł����A�g�����`�ɂ�����u�N���v�́A���J�K�M�E�V�q�r��ҁq���e���O�Y�N���r�i�s��{ ���e���O�Y�S�W�k��12���l�t�A�}�����[�A1994�N11��20���j��ܒJ���m�ҁq�F�V���F�N���r�i�s�F�V���F�S�W�k�ʊ�2�l�t�A�͏o���[�V�ЁA1995�N6��26���j�ɂȂ�킯�����i�k�߂Ɠy���ɂ͂��̃��x���̔N�����܂��Ȃ��j�A�E����u�����v�Ƃ��ċ����Ă���u��������w���������i��W�V�x����A���X�A��Z��Z�N�v�́A�������̋g�����N�����������Ƃ��ɂ͂܂����s����Ă��Ȃ������B���N���ɔ��f����Ă��Ȃ��V�K�̏��Ɋւ��ẮA�������L�̖{���̂��ƂɁA�\�\�i��{�_�[�V�j�ɑ����ŋg�����N���̕��̂ɑ����ă����C�g���Ă݂��B���̓����g�����N�����������@�����A���̋L�ڂf���������Ǝv���B�Ȃ�����́A�����ł͑S�p�A�L�����A�������L����̈��p�ł��邱�Ƃ��킩��₷���悤�ɂƁA�����ĕt�����i�����̍s�͈�s�A�L��\���j�B���o���́k�N�l�����̎��́y�@�z���̗j���́A�����ɂȂ����߂ɏ��т���������́B
��������q�����̎� �W�ȍ~�\�\1960�i���a35�N�j�`1974�i���a49�N�j�r
�k1962�i���a37�N�j�l�\���\����@���j
���k�c�c�l
��
���g��������莍�W�w�a���`�x�𑗂���B�i�������L�A�l�Z�y�[�W�j
���@�g���̑���W�s�a���`�t�i����Ɂj��1962�N9��9���̊��s�B����͓��L�̓��܂łɏ�����W�s��铊��S�t�i1959�j�Ƒ���W�s�����ƂՂ炷�܁t�i1962�j���o���Ă��邪�A�g���ɂ͌��{���Ă��Ȃ��B
�\�\1962�i���a37�N�j10���@��������Ɏ��W�s�a���`�t�𑗂�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1966�i���a41�N�j�l����y�Ηj�z
����[�A���e���O�Y���̒a�����̉�ɂ��Ă䂭�B�喜�B���\�l�Ƃ͎v�ւʂ�ƏЂɈ��Ă��Ƃ����Ƃ���B�g�����Ə��߂Ĉ��Ћ��̂̂��ƂȂǂ�B��{���g�ɗU�͂�ė��������l���Ĕ����o������̃��[�U���k�Ƃ��ӓX�ɘA��Ă䂩���B�剪�M�Ɠ��L�̐������ɉ�ӁB����̉�̂��Ƃ��]�ӂƑ剪�M������Ȃ��琼�e���������ƃ��}���e�C�c�N������Ɣᔻ����B�팛�ƃ}�_���Ƃj�Ƃ��ӏ��̎q�Ǝl�l���ďa�J�̉��ΐ�ɂ䂭�B���J�A���������킢�킢��Ă�T�Ő����������Ȃ���ꎞ����܂ň��ށB���J�A���āA�z�K�D����v�䒬�ɗ��Ĉ��ށB���㎍�̈������ɂ�Ďn�߂Č����ɂ݂ȋA��B
���u���W�b�g�E�t���[�t�B�u��̕�����v�B�i�������L�A��O�O�y�[�W�j
�@��������Ǝ����͂��߂ďo������̂́A���������낤���B����͑�Ȃ��ƂȂ̂ŁA���A�L�������ǂ��Ă���̂����A�͂�����Ƃ͉]���Ȃ��B����������́A�喜�ł̐��e���O�Y�搶�̒a�����̂��j���̖邾�����Ǝv���B���̓��A�搶�͎��j�̈Ӗ������߂��Ă��A�V��̎����I���ꂽ�̂������B�ԍ��ɂȂ��āA�����Ă����A�������̐����e���ǂ݂������̂��B����́q���r�Ƃ������ł������B���@�u�u���W�b�g�E�t���[�t�B�u��̕�����v�v�́A�u���W�b�h�E�u���[�t�B�i�ےJ�ˈ��j�s��̕�����k�l�Ԃ̕��w22�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1966�j���낤�B
�@�@�L���̓��}�f���{�E�Y�̉h�������c��Ȃ�
�@�@�k�c�c�l
�@�@�u�{���V���E�v�̉���
�@����͂��̂Ȃ��قǂɂ����߂ł��邪�A�搶�͓Ɠ��ȗ}�g�̂��鐺�ŁA�u���}�f���{�E�Y�v�́A�R���̖V��łȂ��A�A���̈��ł���A���̎��̎��́A�^�ł��n���̍ő�Ȑl�Ԃ̋L���́^�u�{���V���E�v�̉����^�Ƃ�����s�ɂ��߂��Ă���Ɨ͐����ꂽ�̂���ۂɎc���Ă���B�q���r�́A�u�����v�̏��a�l�\��N�t�G���ɔ��\����Ă���B���̎ԍ��̒�����������͂����̂��B�N�ɏЉ�ꂽ�̂ł��Ȃ��A��u�̏o��������B���ꂩ��͉����I��܂ŁA���炭�ԋ߂�����ƌ��Â����B�s���̊��S�t���s�����ƂՂ炷�܁t�����łɔ����߂āA�ǂ�ł���Ƃ̎��̌��t�ɁA����͗�V���������k�����B
�@�@����̌�����Ђ邷���ۂ�Ƃ���
�@�@�k�c�c�l
�@�@�V�����H�m�^�[�W�n�̓V�̑���炵
�@�����ْ[�̖���̍�҂ƈ�[�ɂ��āA���͒m�ȂɂȂ����̂ł���B�i�q�o��\�\��������r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��㎵�`����y�[�W�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l�\���y���j�z
�����A�u�`����w�v�̏o�ŋL�O�����Ė�ӁB�喜�B���e����A�F�V���F�A�r�c�����v�Ȃǂ����Ă����B��{���g�̍D�ӂŌ\�l�ʂ̂�������O�\�l�ʂ����Â���̍��~�ŎG�k�B�i������J�K�M����Ă����B�a�J�̉��ΐ�ɏo�����Ĉ��ށB��v�䒬���F�V�v�ȁA�쒆�A�r�c�A�y���A�ѓ��k��A���R�r���Y�A�O�c�A�g�{���������Ē��܂ň��ށB
�����炵���Ⴊ�~�Ă�āA�Ђ鍠�N���Đጩ���B�Ȃ�ƂȂ����낲�낵�Ȃ���G�k�B�݂�Ȃ��̐�̒��ɑ���B�i�������L�A��Z�Z�`��Z���y�[�W�j
�@�}��b�����̑O�Ɏp�����킷�O�ɂ́A���R�Ȃ���y���F�̋���ׂ����ʂ��������߂Ă���B���̂��Ƃ��Y�ꂽ���A����̓喜����������́s�`����w�t�̍Ґ��܂��j����������B��͏����ȕ����ŁA�C�̍��������m�����ƎG�k�ɐ����Ă������A�e�����l�̂����Ȃ����͂ЂƂ藣��Ăڂ��肵�Ă����B���̒��x�����ɒ����������l�����Â��Ɏ����̂�ł���B�ꐡ����C�ɂȂ鑶�݂������B���̂����ˑR�A���Ƃ��炫���ѓ��k�ꂪ�吺�������āA���̑�̑O�֍����āA�����݂̂͂��߂��B�����������l���Ǝ������������t�����킳�Ȃ��̂ōk��́u�ȂA�y����m��Ȃ��̂��v�B���͖��O�͂Ȃ�ƂȂ��m���Ă������A�y���F�����̕������m��Ȃ������B�ނ́s�m���t�����ɓǂ�ł���Ƃ������B���ꂩ�炤���Ƃ��Đe�����������A�ނ̌|�p��m��˂Ȃ�ʂƎv�����B�i�q�ϋ{�̐l�E�}��b�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�Z�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l�l���\�����y�Ηj�z
�����A���[�����̌W�̃I�[�v�j���O�ɂ䂭�B���L�B�F�ʂ̃G���e�B�b�N�Ȕ×��Ƌ��ӂ̋��ق����Đ����B���ꂢ���ȃ@�Ɖ]����A�ނ���x�m�R�̂₤�Ȃ��Ƃ��]�ӂƏ͂ꂽ�B����C���A�g�����A�剪�M�A�쒆�����ƒ���B���É�����n��x�g�N���������Ă�Ĉ��݂Ȃ���o��̂͂Ȃ��B�e���r�ǂɖ߂āu11�o�l�v�ɏo������A�y���F�̃��t�@�[�T���ɗ������ӁB�u�o�m�A�l�n����̗x��v�Ƃ��ӌ����@���g�����Í����x�B�I�Ă���A�y���A����Y�A���c�l�A�}��b�A�Έ�̏�������v�䒬�ɗU�Ĉ��ށB�y���Ƒ�쎁�Ƃ̕s�v�c�ȑΏƂ����Ă��ƁA����͂������ۉ�̂₤�ȃ_���X���B�O�����݂ȋA��B�i�������L�A�ꎵ�O�y�[�W�j
�@�l���\�����@���j
�@���c���a�q�̃I�u�W�F�W�ւ䂭�B�����d���̔��w�B�l���Ǝւ���̐l�`�̚삵���Q�B�w�̐�قǂ̏��́A�֑̂̂т�l�B���Ζʂ̔ޏ��͔��̒����J�����Ȑl�B��i�l�_���߂�B�������̓d�b�œ��L�։��B���[�����́u������k�́l�I�v�W�B�剪�M�A����C�����Ɖ�B��Ŕ������F�ʂ̐��E�B���[�����ɏЉ���B�i�q���L���\�\���Z���r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l�܌��\����y���j�z
����[�A�u�����̕����Ɓv�t�F�X�e�B�o���ɂ䂭�B�s�s�Z���^�[�E�z�[���B�g�����A�O�D�L��Y�A�y���F�A�쒆�����A�����v�q�A�������������ƈ��ӁB�}��b�N�́u�n��̔閧�v�����Ƃ�ƌ���B�n���Ȋϋq�����̂��߂ɁA�ނ̉ؗ�ȃj�q���Y�����A�Ӗ����Ȃ��͂�邱�Ƃ�|���B�݂�Ȃŏa�J�̉��ΐ�ɍs�Ĉ��ށB�y���̃X�^�a�I�ɂ䂭�B���Ǝ��l�̂͂Ȃ��B�݂�ȋA�����ƁA�q���ĐQ���y���F�̂��ɐQ��B
���Ђ鍠�A�N���o���Ď�B�ނ̐��Ԃ��Ȃ����̍r�����鍰�Ɠ��̂̕�����B�����A�ʂ�Đ_�ے��̏��X�Ђɂ��ǂ���B�X�J�ς����~��Ĕѓc���ő҂����킹���������v�q�Ɉ��ӁB�\���ޏ����Ƃ̋߂��܂ő��ĕʂ��B�i�������L�A�ꎵ�Z�y�[�W�j
�\�\1967�i���a42�N�j5��11���@�q�����̕����Ɓr�t�F�X�e�B�o���i�s�s�Z���^�[�E�z�[���j�Ŋ}��b�s�n��̔閧�t���ς�B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l�����l���y�Ηj�z
�����A�u�`����w�v�����������A�Z�����A�I�ɚ����z�[���B�J�����X�A�ʊy�̎�����Ȃ��ɋ��ނł킪���炪�X���C�h�ʼnf����āA�����ŕςȋC���B����x�q���������ēy���F�A����Y�A�}��b�̗x�肪�X�L�����_���[�X�ȗ��������Ƃ���o���Ă䂭�B�I����A�ڍ��̓y���F�̃X�^�W�I�ɍs�Ĉ��ށB�F�V���F�A����C���A�X�J�ρA�������O�Y�A��쐟�q�A�쒆�����A�x�����b�q�A�O�D�L��Y�ȂǁB�X�^�b�t�̖ʁX�l�\�l�ʂ��x����̂��肵�Ē��܂Œ���B�x�����b�q�𑗂ċA��B
����̋�A�������t�̑��s�A�A���p�̌����W�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���勴��v�����W�u���쌀�v����B�i�������L�A�ꔪ��y�[�W�j
�@�����O���@���j
�@�[���A�O�D�L��Y����B���[������H���ċI�ɍ����z�[�������B�߉ϑ��Y�A�F�V���F�Əo��B�����J���A�y���A�}��N�����̕������u�`����w�v�n��B�N���I�p�g���E�^�J�C�A�A���N�T���h���X�E�I�I�m�A�w���I�K�o���X�E�J�T�C�A�l���E�q�W�J�^�̊���ɂ��ēT��A���C�Z�c�ɂ��č��M�A�R�b�P�C�ɂ��Č��l�Ȃ�Í��̏j�ՁB���̕����ґ���Y�̌|�ɐڂ������͍̂K�^�B�n�T�~�������ėx�苶���V�l�̎p����͂Ȃ낤�A�n���̎g�҂��A�l�Ԏ����̐��̂��B�����̓Ԕ��B�y���F�̌���ɔ���B�߉ϑ��Y�A���������Ƌ߂��̋i���X�ňꎞ�ԂقǎG�k�B�\��������ʂ��B���x�ےj���W�w���@�̉Ɓx����݂Ȃ���˂�B�i�q���L���\�\���Z���r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O�`��l�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l������\����y�y�j�z
���㋞���̎D�y�̘h���ɒj������A����d�b������A�����A�����V���̖{�Ќ��ւň��ӁB�}�t�B�A�̐e���Ƃ������������̂����A��͂�K�����₤���B��Ă�邪�A�}�����A���炫���S���a�ɔY�܂���Ă��Ƃ̂��ƁB�߂��̋i���X�Ńv���e�B�m�X�̂��ƂȂǒ��Ă��A�}�Ɋ炪�����߂Ă����̂ŋ����B��[�������Ȃ��Ƃ��ӂ̂ŁA�����ɏo�āA���X�ЂɎԂ����B���h���I�ŐX�J���⍂���r�Y�N�������ăr�[���B���̂������g�����A����Èꎁ����Ă���B���ƍ��J�B�������A�h�����𑗂�B���c�O�Y�A�����ρA�؎R�������Ə�������ł���A�}��b�A�����v�q�̗��l�ƐV�h�ɏo�āA�m�A�E�m�A�ň��ށB
���F�V���F����u�z���E�G���e�B�N�X�v�A���c�q���q����u�T���E�W�����E�y���X���W�v����B�i�������L�A�ꔪ�l�y�[�W�j
�\�\1967�i���a42�N�j7��29���@�D�y����㋞�����h���ɒj�ɐX�J�ς������������ƂƂ��ɉ�B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l������\����y�Ηj�z
�����A�Έ䖞�����̕��x�����u�����W���l�v�����ɂ䂭�B��ꐶ���z�[���B�����x��Ă����̂ŁA�Έ䎁�̓������y���F���A�������܂Ă��ς�ƐČ�����ꂵ�߂��Ƃ��ӏ�ʂ����Ȃ����̂��c�O�B��������ėx���Ƃ���͓y���̂Ȃ��̌O���Ƃ����ӂׂ��������B�I�Ă���y���X�^�a�I�ɂ��Ĉ��ށB����Y�A�F�V���F�A���\�Y�A�쒆���������ƒ���B�ߏ��̘A�������邳���̂œd�b�����炵���A�x�����l�l���藈�āA�Â��ɂ���Ɖ]���炵���B�\�l���肪�c�Ďl�����܂ň��ށB
�����@���^�[�E�V���~�[���́u�w�����[�E�~���[�v��ǂށB�i�������L�A�ꔪ�Z�y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N������\����
�@��Z�����A����J�̑�ꐶ���z�[���֍s���B�y���F�̒�q�Έ䖞���̃��T�C�^���u�����W���l�v���ς�B�J���\�\����̍���̑O�ŁA�Ɩ�������ƁA�����̌Պ���̓����A�y�փJ�~�\���œy���F���r�X�����A���͂��߂�B�ߎ������o���A�����Ȃ���o���B�Ó]�\�\�q�Ȃ̕��܂Ŋg���鋐��Ȕ����z�����Ԃ��������������A��������ƁA���h��S���ʼnA�s�̓o���F�ɐ��߂��Ă���A�������C�̗x��B�܂��Ђƕ���������r�N�^�[�̌����A����̒����ɒu���A���̉�������V�[���́A���������i���B�������������ɕ��薞���͏����čs���̂��B���̌�̂����Â��w�i�ɒu���ꂽ�����X�̊Ŕ���������t���āA���₩�ɉ���Ă����c�c�B�I���ĊO�ɏo��ƁA�F�V���F�v�ȁA��������A�쒆�����̊炪�������B�}��b�ƍ����v�q��U���ėL�y���ŐH�����A�ϓ։��ł��������B�i�q3�@�u�����W���l�v�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A��Z�`���y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1967�i���a42�N�j�l�\���O�\���y���j�z
����A�}��b�̕������������ɂ䂭�B��ꐶ���z�[���B�a���̍����v�q�����Ŕ������B����M�V���ƈꏏ�ɕ���Ō���B�Ǐ��V���̍���N���畑���_�𗊂܂��B�ԋ߂��A�ؗ�Ŏ�X���������̑g�ȂɁA�v���Ԃ�ɗx��炵���x��̌O���̂₤�Ȃ��̂ɐ����B�I�Ă������C���A�F�V�A�y���A�쒆�A�x���A�ܒJ�����̖ʁX�ƁA�Ȃ�ƂȂ�����Œ���B�V�h�̃m�A�E�m�A�ɍs�āA�������ƃu���g���̘b�������肵�ċA��B�i�������L�A����y�[�W�j
�@�u�����W���l�v�̉���J����ɁA�}��b�ƕ������u�����ւ̏����v����ꐶ���z�[���ōÂ��ꂽ�B���͏��߂čȂ���čs�����B���ҐȂɂ͏�A�̂ق��A����C���Ɣ�W�����p�[�p�̎O���R�I�v���������B����͔ނ̏������猻�݂܂ł̐��ʂł���A�u���Y����v�A�u�n��ւ�杕��v�A�u�q�_�̌ߌ�ւ̑O�t�ȁv�A�u�ϋ{���v�A�u�̉Ԃ̒j���Ɂv�Ȃǂł������B�ǂ�����炵���A�܂��ɖ����̈�[�ł���B�Ƃ��Ɂu�n��ւ�杕��v�͔��Ɗ��m���������A�������G���`�V�Y����Y�킹�Ă����B������������ߑ���ւ��A���ɓԂ��x��Â����A�}��b�̐��_�͂Ɉ��|���ꂽ�̂́A�����������ł͂Ȃ��������낤�B�����₦�����̃��X�g�ŁA����ɉ���������܂܁A������ꂽ�ԑ������ɒ@�����Ȃ���A�Ԃт���U�炵�Ă����p�́A������������H�S���A���́u�ϋ{�̐l�v�ł͂Ȃ����낤���B�i�q4�@�u�ϋ{�̐l�v�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A���`���y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�ꌎ�\����y���j�z
���}�����[���g������K�˂āA�߂��̋i���X�Ŏ���o��̘b������B�u�g�������W�v���ӁB
���[���A�j���[���[�N�ɂ䂭����C�����𑗂邳���₩�ȏW�܂�B�V�h�u�ƂƂ�v�B�쒆�����A��m�G�A�ܒJ���m�Ƒ������̌ܐl�ŁA�������̎Ⴋ���̘b��A�_���̉ƂŃf���V�����Ɉ������b��A�u���g���̋��Ԃ̖͗l�Ȃǂ��B�u����C���̎��I�����v���ӁB����A���j�R���ƕ����ĎO�����ɕʂ��B���������V�������A���X�g�ƌĂԂ̂͊ȒP������ǂ��A���ʓI������B�v���X�`�b�N�̓N�l�̉e�����炿�炵�Ă��B���Ȃ��͋�w��m�Ă�܂����A�ƕ����ꂽ�Ӗ��̂Ȃ��ɂ́A���ɑ��鎍�I�łȂ���C�����߂��Ă�ɂ����ЂȂ��B�i�������L�A��㎵�y�[�W�j
���@�u�u�g�������W�v���Ӂv�́A�����̑S���W�s�g�������W�t�i�v���ЁA1967�N10��1���j���낤�B
�\�\1968�i���a43�N�j1��19���@���Ђ�����������Ɂs�g�������W�t��A�߂��̋i���X�Ŏ���o��̘b������B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�ꌎ��\����y���j�z
������A���߂ɓ����w�̉��{����t�H�[�����g�����Ƒ҂������āA�F�V���F�̉Ƃɂ䂭�B�g�������x�[�S�}�ɏڂ����̂ɋ����B��Ƃ̎R�c�N���A�L���̃J�L�����Č���A���̂����ɍ��������q��������B���c�k�쎁�����Ă����Ƃ��ӏt��W���J������A�u�S����_���_�v���S���肵�Ă�邤�������B�����A�\�߂��ɉƂ���̓d�b�ŋN����āA����v���Ђ̐�m�A�r��N�ƃ^���z����W�̃��X�g�E�A�b�v�̌����v�Џo���A�}���ŋA��B�����K�q����v�ۂ��珉�߂Č����āA��m�N�ƈꏏ�Ɂu��Ɓv�Ȃǂ̎��������ɍs�Ă����B�[���A�F�A��B
���T�q���k�C������y�Y�ɂ��Ă����I��H�Љ߂��āA�Q�Ȃ���A�~�b�V�F���E�t�[�R�[�́u���E�̎U���v��ǂށB�i�������L�A��㔪�y�[�W�j
���@�F�V���F�̐��z�q�g�����̒f�́r�i���o�́s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�j�Ɍ�����O�S����߂�����Ƃ�͂��̂Ƃ��̂��́B��������q�ꎚ�̎t�A��x�̗F�r�i�s�����C�J�t1975�N9�����k���W���F�V���F ���[�g�s�A�̐��_�l�j�̈�߂Ɂu�o��̘b�Ƃ����A����k���a�l�\��N�l�����N��̐����̏I�鎞���A�g������U���ėV�тɍs�����Ƃ���A��l�͒f���Ƃ��ĎO�S���m�́u�����v�̋��F�߂悤�Ƃ��Ȃ��B���K�o������������Ɗ撣��ʂ��B�₽��ƕ������O�S�t�@���̋g�����Ǝ�����������ǁA�w�m���x�̎��l�����ʂ̖��l�|���I����ɋy��ŁA����܂ł͓����R�̎���ʂ̑�\�݂����U�����Ă������ʂ̃`�����s�I���́A�݂�݂邤���Ɏ��M�r���̂Ă��B�u��ˁv�����̓c�����ꗬ�k�i�V���̂ł�l�Ŕ�r���������݂�A����́A�{���ň���Ēb���ɒb�����g�������N�́u�����v�^�ƁA�F�V���F�⎄�ǂ����ӋC�����Ă����u�R�̎�v�^�Ƃ̕����̍��Ƃ������̂��낤�B�v�i�����A��Z��y�[�W�j�Ƃ���B
�\�\1968�i���a43�N�j1��28���@��������ɗU���Ėk���q���F�V���F��K��B�x�[�S�}�����A�P�������I����B�����O�S�́u�����v�̋��_���A�[��̎������F�V������́q�S����_���_�r���̂��B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�\�����y���j�z
�����A����_�i�N�̋�W�̏o�ŋL�O��A�o�ŃN���u�B�g�����A�����d�M�����ƒ���B�g���A�g�{���V��U�ăm�A�E�m�A�ň��ށB�g�{�N����v�䒬�ɔ��߂�B
���Ђ�O�ɁA�Ӓ��œ��@���̑O�c���u�N��V�h�a�@�Ɍ����ӁB
��
���o�^�C���́u�L�ߎҁv��ǂށB
������A���c�����Y�����u�z�C�b�g�}�����W�v�i�O�}�Łj���Ƃǂ��ĉ�����B�i�������L�A��Z��y�[�W�j
���@����_�i�̋�W�́s�ԓ��فt�i�Ս��o����A1967�N5��30���j���B
�\�\1968�i���a43�N�j2��17���@����_�i�̋�W�s�ԓ��فt�̏o�ŋL�O��i�o�ŃN���u�ɂāj�ɏo�ȁB�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�O���O���y���j�z
���}��b�N�ƍ����v�q�N�̌������ɂ䂭�B�ԍ�v�����X�E�z�e���A���߁B�y���F�A�g�����A�F�V�v�ȁA�X�J�ρA��Z�����Y�ƈ��ӁB�Ȃ�ƂȂ��}�C�N�̑O�Œ��炳���B�v�q�N�ɁA���͖��ꂽ�����ƕ������炠�̂͂�ڂ����������܂�����P�������肵���B���l�̑���Y����ƁA�����̂͂Ȃ����ł���B�{�}���c�I�̎ʐ^�W���R���E�T�����Ɍ��ɂ䂭�B�O���r���ɓo����A���C�I���Ńr�[��������A�R�꒚�ڂ̃O�����ň��肷��B�ڍ��w�O�̈����ɂ������͏\���A�y���A�F�V�v�ȁA�X�J�ρA�쒆�����A����x�q�����B�F�V���Ɋ��q�ɗU�͂�āA�^�N�V�[�ɏ�āA�T�[�c�Əo������B�r���ǂ��Ńr�[���ƃR�[���Ĉ��B�k���q�͐�B������Ɉ��ށB��Ă邱�Ƃ̂ł���̂́A�F�V���F�Ɩ�쐟�q�������B�i�Z���L�j�i�������L�A��Z��y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�O���O��
�@���̐ߋ�B�}��b�E�����v�q�̌������I�����s����A�ԍ�v�����X�z�e���֍s���B�}�A�͑���Y�v�Ȃ������B�킩�Ȓ�����A�S�[���f�����[���ŏj���͂��܂�B���t�̉������w������āA���������Q�Ă��B舒B�ȋv�q���ԑ����A�}�䖢�S�l�ɓn���Ƃ��A�����������̂���ۓI�������B����֏o�ă��C�I���œ�B�[��������ŎO����ƂȂ�B�X�J�ρA�y���F�A�F�V���F�A��������A����x�q�����ƃt�O��H�����̂ށB�b�E�v�q�̐V���������тȂ���ɂ��Ȃ���B�i�q5�@���܂�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A���`��O�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�O����\���y���j�k�t���̓��l�z
������̌ߌ�A������Ԃ�Ԃ炵�Ă���A�s�J�f���[�Łu�p���̂߂��舧�Ёv������B�L�����f�B�X�E�o�[�Q���Ƃ��ӏ��D����ς��ꂢ�A�ʑ��ɗ�������̂������낳�ɁA�v���Ԃ�ɐ����B�m�Ă鏗�Ɍ��������~�]������B�[������̓y���F�ƍ]�p���̎ʐ^�W�ƃI�[�v�j���O�̂��߁A�j�R���E�T�����ɂ䂭�B�����ׂ��y�Ɛl�Ԃ̏o���Ђ̎ʐ^�W���B�]�A�y���Ƒō����A�i����O�؏~���Ǝ��ƂłƗ��܂��B�����ɊJ��A�ʐ^�Ƃ̕��͎O����ɗ���ŁA��������F�V���F�A����Y�A����C���A���c���j�̏����ɒ��Ă���ӁB�I�ăX�L�����͓̉ؗ����u���v�ň��ށB�}��N���n�l�E���[���Ŏ����N���������ŁA���a�������ނ킯�ł��Ȃ����A���⏗�̌��Ȃǂ̂͂Ȃ��B�V�h�ɏo�āA�Ȃ�Ƃ����i�ň��ށB�F�V�A�y���A�����ĔV�Ɩڍ��ɏo�ăX�i�b�N�Œ���B�������F�V���F����͂��߂Đ��q����Ƃ̗����̂͂Ȃ����B���߂��܂Œ������A�����m�b���������A�A��B
��
���������痧����������邱�ƂƂȂ�A�l�����A�����̕��ꂪ��Ă��Ă����B�����ł�Ǝv����A���Ă��܂Ă��B�y���F����d�b���F�V���F�̌����]�Ă��邪�A�����������Ԃ��o�Ă���̕������������Ȃ����炤���ƕԎ�����B
���哇���̃V�i���I�W�u�i���Y�v���Ƃǂ��Ă����B�i�������L�A��Z�O�`��Z�l�y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�O���\���
�@�[��B����̃j�R���T�����֍s���B�]�p�����O�N�قǂ����āA�B�����y���F�̉f���W�ł���B��������u��v�܂ŕϗe�����镑���Ƃ̓��̕\���p�Ɋ��Q���B�n���ɂ��锪���Ƃ����X�ŏj���B�]�p���Ə��߂ĉ�B����C���A�F�V�v�ȁA�O�D�L��Y�A�����r�Y�A���R�r���Y�����Ɖ�B�����ē�͐����̑��ŁA�ӂ�����A�Ђ���ł������k�B�푺�G�O�Ə��߂ĉ�B�\���X�Ő�~�̊�����B��쐟�q�珗�������͋A�����B�O����͐V�h�̂ނ炳�����i�ւƉ݂͊�������B�O�K�̍��~�ł���Ƃ��낮�B�����ĔV��r�c���Y�Ɠy���F�͊G��_���͂��߂�B���̒ɗ�Ȕᔻ�ɑ��A�r�c���Y�͒��ق����������ĔV�͔������A�����ԓ{�����悤�������B��ꂽ�̂ŁA�\�߂��}��v�ȂƋA�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���W����̃^�C�g���́u�ƂĂ��Ȃ��ߌ��I�Ȋ쌀�v�B�i�q6�@�u��ꌁv�ʐ^�W�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A��O�`��l�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�܌���\�l���y���j�z
��������\�[��������H�ׂĂ��B
�������ɂ��Ɠ������т��Ƃ��ӊ�����m���肷��B
���O�c�V���́u�^���z�[�g�s�A�v�i�\���j�������B
��
���u���j�R�[���v�̑n������ǂށB�\�z�ȏ�̏o���f���ɖ����A�G�b�Z�[�Ɋr�ׂč�i�����܂�Ⴆ�Ă�Ȃ��B
���������ۈ珊�ō��̖j���Ђ~����Ă���B�T�q�����q���Ďa���̗^�O���ƏӁB
���g�������Ɠd�b�A���j�R���̗���b������A�C�N���I�ł����l�Ɗ��ł����B��B�i�������L�A����`���O�y�[�W�j
�\�\1968�i���a43�N�j5��24���@�d�b�ʼn����������q���j�R���̗��r�̓^�����A�C�N���I�ł����l�Ɗ�ԁB5��22���́q���j�R���̗��r�́A�푺�G�O�s�����̃��[�g�s�A�t�o�ŋL�O��̓���A�V�h�̃��j�R���œ��\�Y�Ƒ���������������1960�N��̓`���I�ȗ������B�Ԃɓ���������͘]����܂��Ă���B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�㌎����y���j�z
���O�\����̖�A�}��b�̕��������u�t���V���q�v�ɂ䂭�B�����N�����z�[���B�y���ɍs����S���ŁA���炾���ɂ����낢��h�Ă��Ƃ���A�A�s���^���ɂ��āA����������Ă��B���炵���Y��Ȋ�����ėx�Ă���A�Ȃ��ł��A�I���K���̏�őS���ɂȂĎ����̓��̂Ɛ�ЁA�������A����Ă䂭�x��́A���̒����̉x�y�B�I�Ă����쐟�q�Ƌv���Ԃ�ɉJ�̂Ȃ����A���܂Œ���Ȃ�������B�F�V���F���A���܁A���߂č��ŕ����]�ӂ��Ƃ��Ɉ����Ă��̂��Ɖ]�ӁB�Ȃ�Ƃ����i�̓�K�ŁA���s����A������Ƃ����F�V���F�ƒ���B���c�k��ƈ�_�����K�˂���A�^���z�����̂��Ƃ�F�����Ɖ]�Ă��ƏӁB�y���A���[�v�ȁA�r�c�v�Ȃ����ƃ��j�R���ɂ䂫�A�푺�G�O�����C�����ƒ���B���É����炫���n��x�g�N��A���̊Ԃɂ����ꂽ���R�r���Y�ƈ��ށB���R�Ɠ�l�����ɂȂāA�y���F�ɗU�͂�Ėڍ��ɂ䂫�A�i�|���I�������Ԃ��Ԉ��ށB
���C�������璋���ŁA����삪���Ă��ꂽ�I�J�d�ň��ށB���̂����ɗ[���B�Ȃ�ƂȂ��r�c�����v�Ɉ��Ђ����Ȃēd�b��������n�E�j�B�y���A���R�A����̖ʁX��U�đ�X�̑��c�}���V�����ɏo������B�r���܂Ō}�ւɂ��Ă��ꂽ�r�c�ɘA����ē�K�̕����ɂ䂫�A��l�̋q�����ƈꏏ�Ƀ��[�����̗����ň��ށB�r�G���i�[���ɏo�i����Ƃ��Ӕʼn��֏��╗�C�����ĉ��B����Ȃ炵���̂��\�����A���ꂩ��m�A�E�m�A�ɍs�Ĉ���x����B���R��x��ɗU����A�����㵂������s�ׂ����邭���Ȃ玀�����܂����A�Ƃ����B�ł̐V�h��y���ɎԂő��Ă���ċA��B
���Ђ�߂��ɋN���āA�y���F�̕����L�O�̖{�̂��߂̎����l�ւ�B�����Ǝ��́A���Ə��̊W���B�̂߂荞��Ŏ������Ƃ��Ƃ�ʖڂɂ��Ȃ���Β͂߂Ȃ��B�L���ł̔��ӎ��ȂA�v�������Ńw�h���o��B������g���̕⋋�řI�Ȑ��E���l�ւ�B�i�������L�A���Z�`����y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�����O�\���
�@�}��b�̕����̗[�ׁB�u�t���V���q�v���ςɗz�q�ƐV�h�̌����N���z�[���֍s���B�Ô��ȗ\���B���䂩��˂��o���ꂽ������A��������Ă����}��b���N����������ݏo���B�V�䂩��݂�ꂽ����ȌՂ̊G�A����͎l���܂ɕ���Ă���B���̉��ŁA�����������Ǝ�̒��@�ق��܂Ƃ��Ă����t�����ЂƗx�肵�āA�ς��ƒE�����āA���h��̑S���ƂȂ�A�����P���s�A�m�̏�ɏ��B�l�ԂƂ͎v���Ȃ��d�������\���I�@�܂������t���̖����̓��̂̐��炯���c�c�B
�@�����߂��I��A�����̂ނ炳�����i�̎O�K�̍��~�ŏ����ƂȂ�B�F�V���F�A��������A�����r�Y�A��쐟�q�A�r�c�����v�E�������B�߂��炵���A�x�����b�q���������B���̐ȂɎv���Ђ���A���W�w�Â��ȉƁx�̌��{���͂��B�\�ꎞ�����A�ѓ��k��ƋA�����B�i�q10�@�Ղ̊G�̉��Łr�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A���y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�\������y�Ηj�z
���k�c�c�l
���[���A�ƂɋA�ēԂقǖ��Ă���A�g�����������u�Â��ȉƁv��ǂށB
���F�V���F���r�A�Y���[�́u���_�̊فv�𑗂Ă����B�i�������L�A���l�y�[�W�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�\���\����y���j�z�k10��10���͑̈�̓��l
�����A�y���F�̕���������ɂ䂭�B���{�N�فB�v���Ԃ�ɔނ̉ؗ�Ȃ�x��i�����B�}�����Ė��f�I�ȃe�N�j�V�������B�_���X�Ƃ��Ӗ��͔ނ̓��̂̑��̂ł���A�Í��Ƃ��Ӗ��́A����𖾂邭���Č�����ʖ��ł���₤�ȓԁB
���r�c�����v�Ɠ�K���ʂŌ��Ă���A�I�Ă�����ꂽ�l�Ɠ����ɏ��B�a�J�̑叼�Ƃ��ӎ��i���ň��ށB�����Ƃ̔ѓc�P�����ƒ���B�x�������Ŗ��҂����Ă�b��A�]���l���V���^�C���̗l�q�Ȃǂ��B��c�O�u���ɋT�R�����痊�܂�Ă��o�C���X�̉�W�𗊂ށB�V�h�̃p�j�b�N�ɍs�āA��쐟�q�A�쒆�����A����x�q�����Ɨx��B�̕��꒬�̃W���Y�E�o�[�ɂ䂫���ށB�y���F�����ƕʂ�A���E�A�n��x�g�����Ɠ�A�O�������ċA��B�r�A�X�́u�H��v�̏��]�������ĐQ��B�i�������L�A���l�y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�\���\��
�@�q�G���|�p�r�����͂��B�u�_��I�Ȏ���̎��v�f�ځB�[���A�z�q�Ɛ_�{�O���̓��{�N�قցu�y���F�Ɠ��{�l�\�\���̂̔����v���ςɍs���B������̘e�ɂ͚삵���Ԃ������Ă���B���̑O�Ɍq���ꂽ�����n�����J�̂Ȃ��ɗ����Ă����B��t�œy���v�l���Ăяo���A���ꗿ���B���ꂪ���Ζʂ��B�O�����ŁA�z�q�̂��Ƃ��c���I�j�E���q�Z���ƁA�������݂̂Ȃ���J���҂B��������������Ɖ�����B�����n�܂�̂��낤���A���̋�Ԃł́c�c�B�S���̓y���F�����F�̋[���j����u�N�����āA�݂艺����ꂽ�����̑傫�Ȑ^�J�̊Ԃ��A�x�苶���B���̃A�N�V�f���g��\�����A�ϋq�͋���������肾�B�����ă��X�g�́A�葫�����[�v�Œ݂�グ���A���Ȃ��瑧���₦�����ɁA�L���X�g�̔@�����V����c�c�B�I����A�W�̐l�X�ƁA�叼���i�ŏj���ƂȂ�B�\�ꎞ�߂��A�ѓ��k��Ɣ����o���ċA�����B�i�q12�@�u���̂̔����v�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A��l�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�\�ꌎ�ܓ��y�Ηj�z
����[�A���L�ɂ䂫�A����C�����ƈ��āA�f���V�����̉�W�W�̐������B�f���V������������ɑ����Ƃ��Ӂu���[�Y�E�Z�����B�v�̊Ŕ�A�ނ̎���`�ւ�v�l�̓d��Ȃǂ����ĉ��B����F���ƈ��ăE�B�X�L�[�����ށB�������ƃo�X�ŏ����O�܂ł䂫�A���t��L�̐��e���O�Y�W�̃I�[�v�j���O������B���e����̊G�͋����قǏ�肾�A��Ƃ��u�]���������̂��Ƃ͂���ƒr�c�����v�ƒ���B�F�̎g�Е����N���ŕs���a�̒��a����Ă�肵�āA�ƂɊp�y�����B
�����e����Ɂu��ƂɂȂ�ꂽ��悩���ł��ˁv�Ɖ]����u�{���ɂ����ł��ˁv�Ə͂��B�y���F�A�r�c�v�ȁA�g�����A�ѓ��k��A�剪�M�����ƃX�L�����̃t�O������뇁�ɍs�Ĉ��ށB�V�h�̃��j�R���A�p�j�b�N�ƕ����A�r���̂ǂ����ň�����q��G�ƒ��܂ň��ݕ����B�i�������L�A���Z�y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�\�ꌎ�l��
�@�T���g���[���C������{�������āA���Y�t�H��L�̐��e���O�Y��W�ɍs���B���ʁA���ʁA�n�G�A�G�b�`���O�A�F����W���B�Ȃ��ł����G�͔������B�搶�͋q�ɂ����܂�āA��������낵���B�����������L���A���푽�l�Ȋ�Ԃ�ŁA���͂����ς��������B�v���Ԃ�ō����V�g�A����l�Y�A�������j�����Ɖ�B�x��Č���ꂽ�y���F���A�剪�M�ƂЂ����킹��B��̂��Ƃ����Ŏ��ƂȂ����B�y���F�͎�̖��̗t�͗l�̃`�����`�����R�p�����Ă���B�ѓ��k����剪�M�������ƂƑ傢�Ɉ���A��������B�i�q13�@���l�̊G��W�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A��Z�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1968�i���a43�N�j�l�\�ꌎ��\�O���y�y�j�k�ΘJ���ӂ̓��l�z
���[���A�y���F�̃z�[���ɂ䂭�B�ނ̕����L�O�̎���W�u����܁v�̏��������邽�߁A��ƘZ���A���l�Z�����W�܂�B�F�V�A�g���A�ѓ��A���\�Y�����ƈ��ށB���̂����ɒr�c�����v�ƃ������A��q��G�A���R�r���Y����������Ă��āA�R�̂��o�n�߂�B�������ƃA�����J��X�y�C���̎����A�낢�p��Ɠ��{��Œ���B�j�Ə��Ȃ�āA���Ƃ��ʂ�����̂��B�x���������Ƃ��ӂ̂͑S���m��Ȃ������A�ߑO�l���߂��ɁA�ׂ�̏Z�l�Ƃ��ӏ����A���邳���Ė���Ȃ��ƍR�c�ɗ����̂ŁA�Ȃ��߂ĕԂ����B����C�������A�����A���̘A���͈���ɋA�炤�Ƃ��Ȃ��B�i��\�ܓ��L�j�i�������L�A��`��y�[�W�j
�k1968�i���a43�N�j�l�\�ꌎ��\�l���y���j�z
������A���̂Ȃ��ŁA��q��G�Ƃӂ��肾�����Q���Ɉ���Œ��Ă���ƂɂȂ�B
�������B���̎q�����X�`������Ă��ꂽ�̂Ŋ�����ׂĎ��ƈꏏ�ɂÂ���B��Ԃ�����ƌ��ƁA�y���A�F�V�A�g���A�푺�G�O�A��q�A���R�A����x�q�̖ʁX�B
�����̂����ɗ[���ɂȂ�A�ѓ��k�ꂪ����A�����O�Îq�A�������A�Έ䖞�������Ă��B�F�V���F�̉����Łu�S����_���_�v���������A�������Ɨx�����܂ł͊o���Ă�邪�A���Ƃ͂킩�炸�B�i��\�ܓ��L�j�i�������L�A��y�[�W�j
�@�q���L�r�@���Z���N�\�ꌎ��\�O���E��\�l��
�@�ߌ�x���A�ڍ��w�ő҂ĂǁA���ɔѓ��k��͗��Ȃ��B�n�}�𗊂�ɖ��ʂ̃A�X�x�X�g�ق������˂�B���łɁA����C���A�F�V���F�A��������A�O�D�L��Y�̂߂�߂�́A�����ɖv�����Ă���悤���B�܂���Ƃ����̂����A�����ĔV�A���[�����A�r�c�����v�A�쒆�����A�c������A�O�ؕx�Y�A�����G�Ȃǂ́A����ɗ]�O���Ȃ��悤�Ɍ�������ꂽ�B�������ŋx�e���A���ƂȂ�B��q�������肩�A�y���F��v�l����`���āA�������͂��肵�Ă���B�����ɂ͓��\�Y�̂ق��A�����A�������A��쐟�q�Ə����Q���Ԃ�������̂������B��q�̏�ɂ́A�܂���̎h�g�A�������A���ɁA���i�����Ƃ������y���̎R���B�r�[���A�E�C�X�L�[�A���Ɗe���D���Ȃ��̂����ނ̂ŁA���̓��₩�Ȃ��ƁB��ɂȂ��ẮA��ƍĊJ���܂���ς������B���U���Ă����i���A���̈ʒu�ɖ߂�����B���l�Ɖ�Ƃ̊Ԃ��q�������䂫�����A���X�Ǝd���G�Ə����������ʂ悤�ɁA�������čs���B�[��ɂȂ��Ă��I�炸�A�݂�Ȕ�J���A�s�@���ɂȂ�����B���̊Ԃɂ��A�ѓ��k��A�푺�G�O�A���R�r���Y�A��q��G�̊炪������B���߂��������ɔ�ꂽ�̂Ŕ̊ԂɐQ���B���ꂩ���z�c�������Ă��ꂽ�悤���B�ߏ��̐l�������{�荞��ŗ����̂ŁA������܂��A�ł̎l���������B�ǂ����w����܁x�͂��ׂĊ��������B�������炢�̐l�͋A���čs�����B�����Ďc�����҂͂��났�A�\���ԁm���͂��n�̏��w���́A�R�́A�����A���H���������B���ߋ߂��A�傫���d���w����܁x���������ċA��B�i�q15�@����W�w����܁x�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A�`���y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1969�i���a44�N�j�l�܌���\�Z���y���j�z
������ǂ̊��̑�̉Ƃ���ڊ����̐����w�܂Ŗ�ܕ��A�����w����s���J�w�܂ŎO�\�ܕ��ʂ����B
���s���J�c���̎v���Ђ�K�˂�B�쐼���Ƃ���Ǐo�����W�ɂ��Ă̑ō����A���؎��ƌ��㎍�̗[�ׂɂ��Ă̘b�ȂǁB�r�[�������݂Ȃ��珬�c�v�Y���ƃZ���E�|�G�e�C�b�N�̘b�ȂǁB��������ƑO�ɐM�Z���̗����u�����v�ɂ䂭�B�����ɎO�z�ŊJ�����i�c�k�ߎ��̏���W�̑��k�ŁA��Ԋى�L�̊C�㎁�ɂ���B�g�����A�����d�M�A���c�@�b�����ꏏ�ŃV���u�V���u��H�ׂȂ��甭�N�l�̘b�Ȃǂ���B�g���A��������U�ĐV�h�ɏo�āA���j�R���A�J�v���R���A�i�W���ƕ����A��X�؏㌴�̍�����ň�t��Đ����̉ƂɋA��B�i�������L�A��l�l�y�[�W�j
�܌���\�Z���@��A�M�Z���̌����ŁA����A�d�M�A����Ə��Ζʂ̊C���b�A���c�@�b���Ɖ�B�����ɎO�z�œW�����i�c�k�ߓW�̑ō����B�������A��������҂̈˗��̕��S�A�ē���̔����Ȃǂɂ��āB�㎞�ꉞ����B�����̕���������A�u���̛����A�|���̓��M�����炵���B����A�d�M�ƐV�h�̃��j�R���B���ꂩ��J�v���R���Ŏ��ƃs�U�p�C�B���[�\�N�̓��̒��ŁB�Ō�̓i�W���ւ䂭�B�I�l�G���t�̃o�[�e�������B�ꎞ���A�^�N�V�[������A�d�M���X�k��l���ł��낵�A������֖߂�B�i�q���L���\�\�k�ߓW�Ɋւ��鎵�́r�A�s�Ս��t235���i1969�N11���j�A�܃y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1969�i���a44�N�j�l�����l���y���j�z
���䕗���ڋ߂��Ă��Ƃ��ŁA�ɂ킩�J��������B
����X�V���g�[�Ƃ��ӂƂ���ɁA�s�s�o�ŎЂ̊J�Əj�Ђ̃I�[�v�j���O�ɂ䂭�B���̂�����̓}���V�������炯�Ŗ�ł͌��������ɂ����A���������ĕ����T�����B�c������A��q��G�A�g�����A���R�r���Y�����ƈ��ށB���c���������N�����͂��ꂩ�炪��ς��A�����t�v�܂ł͎��͊y�����A�Ƃ��ӂ̂����ɂ����ւ�B
���t�����\���E�t�H�X�J�́u���w�҂Ɣ��p��]�v��ǂނ��A���I�����āA���ɂ܂��{�B�i�������L�A��܁Z�y�[�W�j
�\�\1969�i���a44�N�j8��4���@��q��G���ݗ������s�s�o�ŎЂ̃I�[�v�j���O�p�[�e�B�[�i��X�V���g�[�ɂāj�ɏo�ȁB�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1969�i���a44�N�j�l�㌎��\�ܓ��y�ؗj�z
����[�A�J�̐ԍ�ŏ��R�r���Y�Ƒҍ����āA�y���F�̃V���[�����ɃX�y�[�X�E�J�v�Z���ɂ䂭�B���܂��t���A�[�ŋ��������ɏ��O�l�A�j��l�̗x��肪�x�Ă���A����m�q�Ƃ�����l�̏��ɂ�郌�X�r�A���E�����̏�ʂ͂��܂���Ԃ����ʓI�Ɏg�Ă�B�F�V���F�Ɨ��q����A�g�����A�푺�G�O�A�O�D�L��Y�A�����O�Îq�ƒ���B�O���R�I�v������Ă������A����Ό���قǂ��̂ЂƂ͖�ڂő̍ى��ł��邱�Ƃ��킩��B���N�����邱�Ƃ����̔������ŔώG�D�݂̍�Ƃ��܂�Ȃ����Ă��₤�����A�X�g�C�b�N�ȕ��w����g�U���悤�Ƃ��Ă킴�Ƃ炵���ڑ��I�ɐU���Ă��̂͋C�̓łȂ����̓w�͂Ԃ肾�B�y���F�ɗU�͂�Ėڍ��̔ނ̉Ƃɂ䂫�A�҂Ă�r�c�����v�ƃ������ƈ��ށB�����A�����̉Ƃ��F�V�A���q����A���R�A�푺�A�����A�y��T�q�����U�Ĕ���������Ĉ��ށB�݂�Ȃ��A���̂�m�炸�[���N���ĕ����R�l�́u�����u�����`�v��ǂށB�i�������L�A��O�y�[�W�j
�@���Z��N�̋㌎��\�l���́A���ɂƂ��ĖY����Ȃ����ɂȂ邩���m��Ȃ��B�J�̗[���������B���e���O�Y�A���J�K�M�����ĉ�c�j�Y�̎O���Ɛ{�c���߂��̉��O�֍s�����B�v���Ԃ�ŐH�ׂ��V�����������������A���ɂ͂��܂��Ƃ͎v���Ȃ������B�����炭���炾�̕s���̂����������낤���B�������ŁA�ԁX�Ƃ������̐F�ƌÕ��ȍ��~�̕��͋C�ɁA���͂����ԂS���₷�炢���B������̔��Â����ւɗ��ƁA�V�����̉H�т��H���ɕY���Ă���B�����ĕ��ׂ�ꂽ�C��J�P�ɂ��H�т��t�����Ă����B�������͉J�̌������Ȃ����O�֏o���B
�@�W�H���̒n���S�����O�ŎO�l�ƕʂ�A���͐ԍ�̃X�y�[�X�J�v�Z���������B�y���F�ƒ�q�����̕�����������͂����B�܂������Ƃ��������Ȃ̂ɂ��̊E�G�͐^�Â����H�ƍ�B��x�������������̘N�ǂ��ɂ�������Ȃ̂Ŗ������B�����n���֓���ƁA�V��S�̂��������̋��̂ŕ���ꎺ���͗₽�����̂Ȃ��ɂ������B��g�قǂ̒j���̋q�������������l�Ћ��Ŏ�������ł����B
�@�킽�������̊O�ɒN���Ă�Ă���̂��A��l�ɂ��悭�킩��Ȃ��̂ŁA���ɗ������Ȃ��ЂƂƂ��������B�V���[���n�܂鏭���O���납��A�q�����͂��߂�B�O�D�L��Y�A���R�r���Y�A�푺�G�O�����������B�������F�V���F�Ɨ��l�炵������������ꂽ�B
�@�낤�����̉���ڂ炵�����̂̉e�B����r�q�𒆐S�ɏ��O�l�A�j�O�l�̍��~�T���Ȋ�قȗx�肾�B����������́A�y���F�������̐l�ԂɌ�������Í��I��V�ɂ���ׂ�A�V���[�I�ŃG���`�b�N�ȃ_���X���B�炢�̑傫���̐^�J�����݂Ɏg���āA�����������Ɖ����̃��Y���ɂ̂��ď��̗������݂͂��肷��V�[���͂������납�����B�_�������Ƌ���Ȑn�Ƃ��]����^�J�̌����́A�ςĂ���҂�₦���͂�͂炳����B�������̂̍d�����ȁI�@��Ȃ̋q�͂�����������������ꂽ���Ƃ��낤�B
�@�₪�ďI��ƁA�y���F���킽�������̐Ȃւ����B�������ɔ�ꂽ�̂ŁA���͑��ڂɋA�낤�Ƃ������A���̂ǂ�߂��Ɏ������͋C������ꂽ�悤���B�O���R�I�v����l�̐N����ē����Ă����B�ނ͋��m���F�V���F��y���F�̐Ȃ֒������B
�@���˂Ă���A�O���R�I�v�����̎����Ђ����ɓǂ�ł���Ƃ������Ƃ��A�����r�Y���畷���Ă����̂ŁA���̓����ނƉ�������̂��Ǝv���Ă����B���̋��R�͓����ׂ��łȂ��ƁA���͋A�邱�Ƃ���ߎ����̐Ȃ֖߂�A�O���R�I�v�Ə��߂Ĉ��A�����킵���B���Ɖ��y�̂Ȃ��ŁA�c�O�Ȃ���e�����b������ł͂Ȃ��A�������ʒu�����������������B���͔ނ�舒B�ȕ\������Ă����B�����̃V���[���I�����̂͏\�ꎞ���낤���B�O���R�I�v�͗���ׂ̂ċ������B���ꂪ���������̍ŏ��ōŌ�̏o��ł������B
�@���̖�A�ڍ����_���̈ړ]��������̓y���F�̉Ƃ֎Ⴂ�A���Ǝ��͗��Ă��܂����B�܂��������͂��܂�B���Ƃ��璆���ĔV��r�c�����v����������悤�Ɏv���B�y���v�l�ƃK�������͐Q�ɂ䂫�A�Ⴂ����������������͂���ł����B�y���F���s�݂Ȃ̂ɊF���C�t�������A�ނ͉f��̎d���ŋ��s�����Ă����炵���B���͋}�ɔ����o���A��l�̏��ւ֓����ĐQ�Ă��܂����B
�@�ł̌�����A�Ⴂ�A���̚������������������Ǝv���ƓˑR�A�����̂悤�ɋ����Ă��܂����B�ނ�̏K���Ȃ̂��낤���A���̏������̌������Ɏ��͋������B�����ɓƂ�Ƃ�̂�����ĘT�����A���l�̉ƂɐQ�Ă���߈����A���邢���̌��Ɍ�����B���̉Ƃ͂��ƃc���R�~���قł������炵�����������肭��ł��āA�v�l���`���̐l�̕�����T���Ă��킩��Ȃ��̂��B���͓�K�֖߂����B
�@���ւ̎��̕������̂����ƁA���������ŋ��̏����̂悤�Ɉ�i�������ɁA��ȍ��~������̂��B�����ɂ́A�҂��҂��̓Ó��I�Ȑl���̒j�������Ă����B����͂킪�s���l�t�̎O�D�L��Y�ł͂Ȃ����B���͂���Ƌ~��ꂽ�v���ɂȂ�B�����ŗ]�T�̏o�����͂܂��܂��ƈ��͉��̂��Č���̂��B�܂�Ń��l�E�}�O���b�g�̊G�̒��̐l���̂悤�ɁA�����ׂ��j����������ƌŒ肳��Ă���悤���B�i�q20�@�X�y�[�X�J�v�Z���̗[�ׁ\�\��ȓ��̂��Ɓr�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A�O�l�`�O���y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1971�i���a46�N�j�l�Z����\�l���y�ؗj�z
������A�R�������̌W�����ɂ䂭�B�V���̔Ԓ���L�B�R���N�Ə�������B
���C�X���G����g�قɖ�c�N��N�ƃh���b�g��̌������ɂ䂭�B�r�c�����v�A�������A��c�O�u�A����F���ƈ��ށB�V�Y�̖�c�N���v�[���ɗ��Ƃ��Ă���A�r�c�A����Ɠ������܂��B�t���h�V�꒚�ɂȂĂ����炩���э���ł��B�����点�����ׂŕ@���܂Ă�ĉj���Ȃ��B
���_�ے��ŊF���҂Ă��Ƃ��ӓd�b�������O�Îq���炩����A�o�����Ă䂭�B�푺�A���R�A���c�k�����ƈ��ށB���������ƃi�W���ɂ䂫�x�����ꎁ�Ƃ���ǂ̎��W�u�j�����@�M�i�v�̑���̑��k�B�r�c�����v�A�������ƈ��ЁA�U�͂�Ď֕��̉Ƃɂ䂭�B��Ƃ̐쓇�Ҏ��ƈꏏ�B�������ƃ��b�N��x�Ĉ���Ŕ���B
�����A�\�����N���ăr�[���B�Ȃ�ƂȂ��A���Ń����\�o�����������ɂȂ�B��p�̒���Ƃ��Ӑl��������A�g�����������肷��B�������Ɨx��B��ɂȂ�B�\�����A�g�����ƈꏏ�ɃT���i���B�ނ�U�ĐV�h�ɂ䂫�A�u�������v�ň��ށB����i�q�N���������O�l�Ɉ��āA�ǂ������m��Ȃ��X�i�c�N�ɘA��čs�����B�g���͂�����Ȃ��B�i�q�N��U�āA�u�M�̖v�ɂ䂭�B�u�i�W���v�ɂ䂫�A�N��ނ�ƈ��ށB�����A��q��G�ƌ��܂̒�����������ŕʂ��B�i�������L�A��`���Z�y�[�W�j
���@���������V�^�s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�N10��19���j�́q�r�c�����v�̊��r�Ɂu�֕��̒r�c�����v�̃A�g���G�ŁA�������A�g������ƁB�i���a46�N6���j�v�Ƃ����L���v�V�����̂����ʐ^���f�ڂ���Ă���i�����A�Z�܃y�[�W�j�B
�\�\1971�i���a46�N�j6��24���@�ڍ����ڍ��E�֕��̒r�c�����v�E�������̉Ƃɍs���B��������Ǝ����ĐV�h�́u�������v�ň��ށB
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1971�i���a46�N�j�l�����\�����y�Ηj�z
�����A���L�ꏑ��W�ɂ䂭�B�����Ԋى�L�B���e�搶�A�g�����A���J�K�M�ƈ��ӁB��㎁�ɊC���b����Љ��A�u�ԁv�����̈ꎚ�ɂ��ڂ����R�Ȃǂ��B�C���b�ɏ�����āA�߂��̃o�[�ɂ䂭�B����̌ߌ�A�o�����Ắu��铊��S�v�𐼉��N�������Ă��Ă��ꂽ�̂��I�B�g�������A��㏉�߂Ă̌����Șa�Ԗ{�Ƃق߂Ă����B�C�㎁�ɏ�����ĐR�́u�o�b�^�v�ɂ䂫�A���ށA���e�搶�������肵�A���J�K�M�Ɖ��k��̎ŎR���Y�̉Ƃɂ䂭�B�W�������ݎl�����A���J���A�����̂����͂��āA�Ђ�����Ԃ�B�����A�N���Ă����q�v�l�Ɏ����Ă��Ė�ӁB�����N���ĂԁB�r�[���Ƌ��Ɍ��ꂽ�̂Łu��铊��S�v�̏j�Ў��B�v���ЂɎŎR�A�����N�ЁA�O���~���B�V�h�́u�������v�Ŏv���Ђ̖k�Ǝv���Ђ݂̍���ɂ��Ē���B�ŎR�A�����N�ɕ������T�ւ��Đ����̗��ɋA�ҁB�i�������L�A����y�[�W�j
�\�\1971�i���a46�N�j8��16���@�����Ԋى�L�̈��L�ꏑ��W�ɍs���B�ł�������̉��������W�s��铊��S�k����Łl�t�i�����Ɂj���u��㏉�߂Ă̌����Șa�Ԗ{�v�Ƃق߂�B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1971�i���a46�N�j�l�\�ꌎ��\�����y�y�j�z
���u�r����v�u�V�q��ԁv�u�q�̃������v�u�j�����@�M�i�v�u��铊��S�v�u����������W�v�̏o�ŋL�O��B�V�h�ԉ��_�ЂɁu���ɒJ�v���o���B�ߌ���A�i����������Ă��ꂽ���J�K�M�������ɗ��Ă���đō����B�����A�ԉ��_�В��B���É�����T�R�܁A�u�����A�Q�n���牖�����j�̊炪������B����C���������t�̉������Ƃ��Ă����B�S�l�ʂ��Ƃ��Әb�A�������B
����́u���j�R���v�B���������ƃe�[�u���̏�ŗx���Ă�ē]���B���e���O�Y�������̉���ς܂��Ă��痈�Ă����B�u�i�W���v�ɍs�������͂��Ȃ����B���Z�����A�ɓ����Y�N�ɑ����Đ����ɋA��B�i��\�����L�j�i�������L�A���܃y�[�W�j
�y�g�������F�V���F�i2007�N5��31���j�́k2019�N12��31���NjL�l����і{�e�����Ɍf�ڂ̏W���ʐ^���Q�Ƃ̂��Ɓz�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1973�i���a48�N�j�l�㌎�\�ܓ��y�y�j�k�h�V�̓��l�z
���u���сv�̎��������Ă�邤���ɁA�Ɏq���̊O�����邭�Ȃ����B���v������ƁA������Ɖ߂��A�x�b�h�ɉ����͂邪�A���[���V�A�̃X�e�b�v��_�̍s��Ȃǂ��A���̂Ȃ��ɂ�����āA���炭���ꂸ�B
���\�����O�ɋN����B�T�q�ƃJ���[�̒��H�B���߂��܂ŁA�������B
���n�C�{�[��������ŁA�a�J�̃p���R�ɏo������B
����K�̐�������œy���F�́u���]�哥�Ӂv������B�y���Ŕ��h��̓y���F�Ƌv���Ԃ�Ɉ��ӁB�O���Ԃ���̑��A����̂Ђ낪��A����Ȃ��̂��ς߂ċC�����Ă��܂������ȁA���̕����Ƃ̗͂ɉ��߂Đ�������B�ƂȂ�ɍ������ї��l���ɗU�͂�āA�V�h�́u���b����v�Ɉ��݂ɂ䂭�B���̑�܂ő����Ă��ꂽ�ю����A�ƂɗU���ĎO�������܂Œ���B�u�����ƂՂ炷�܁v�Ɓu�I���́v���o�Ă����̂ŁA�����グ��B�i�������L�A�O�O��y�[�W�j
�@�q���L�r�@��㎵�O�N�㌎���
�@�k�c�c�l�^�����\�ܓ��E�ߌ�ꎞ����A�p���R�̃E�G�A�n�E�X�ŗz�q�ƃR�[�q�[���̂݁A�k�����p���R�l����֍s���A�u�Â��ȉƁv��т��ς�B�O���ԋ߂��A�ْ����������镑�䂾�����B�\�\������|�p�Ƃɂ͂��Ă̎��Ȃ̍�i���A���p���A�ό`���A���B���Ă䂭�Ƃ����A�c�ׂ�����B���̍�i�ɂ����ꂪ����悤�Ɏv��ꂽ�B�߂��炵���A�N�Ƃ���킸�A��t�̓y���v�l�Ɉ��A���ċA��B�i�q40�@�u�Â��ȉƁv�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A����`����y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1973�i���a48�N�j�l�\����\�����y�y�j�z
���l�J�V�����l�`�W�ɗ[���A�o������B����؉�L�B��L�̋߂��ŁA�����ė������R�r���Y�Ƌv���Ԃ�ɏo���ӁB�\��_�̐l�`�̂��ׂĂ��A��̎q�{����o�ė����݂����Ŋy�����Ȃ�B�������̓X�Ńp�[�e�B�[�B����o�ė����u�������K�˂ė���B����C�����ƒ���B������A�l�J�V�����A����o�������Ɨׂ�̎��i���ň��݁A�n���S�ŐV�h�ɏo�āA���N�������ŕ�������ցB�u�i�W���v���F�V���F�Ƌv���Ԃ�Ɉ��ށB
���閾���̉J�ɔG��ċA��B�i�������L�A�O�O�܃y�[�W�j
���@���̓��͎l�J�V�����l�`�W�q�����Ɖߋ��̃C���r�̃I�[�v�j���O�B�g�����u�{�C�Ő^�ʖڂɍ��̂Ƃ���A������F�V������ԋC�ɓ����Ă��邩��ˁv�ƌ����A��������F�V���u���̂Ƃ���A�����v�Ƒ�������Ƃ���������b�q���`����G�s�\�[�h�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�������_�ЁA1984�A���l�y�[�W�j�́A���̂Ƃ��̂��Ƃ��B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1974�i���a49�N�j�l�ꌎ��\�����y���j�z
���������O�\�����̐V�����Ő����Ήw�Ɍ��ӁB�i�c�k�ߑS��W�u��Łv�̏o�ŋL�O��B�����Ήw�ŋ��R�ɂ��L������̍��R贎q����ɏo��ӁB�ꏏ�ɕ��q�w�ɏo�āA�ԂŁu���q�r���v�܂ōs���B�k�ߘV�ƈ��ЁA�u�k�߃m�[�g�v�ւ̌����Ɏ�炳���B���J��A���܂ꂽ�g�����Ƙh���ɒj�̏Љ�i�������B�i�c�k�߂̑T�@�I�Ȑ��E���j�ӂɂӂ��͂����A���̌��ӂ̊C�̂��˂肪�A���܂�Ȃ��ʔ������߂�ꂽ�B
���v���Ԃ�ɓ��×��ƈ�K�̃o�[�Œ���B��ɏo�āA��ؘZ�ђj�A���c�q���q�����ƒ���B�l�K�̕����ŎႢ�ЂƂ����ƈ��ށB�Ⴂ�ЂƂ����Ɛ_�˂ɎԂ����āA���Ƃ����ӓX�ʼn͓�H�ׂ�B�l�����A���q�r���ɋA�ĐQ��B�i��\����L�j�i�������L�A�O�O��y�[�W�j
���@�g���͉i�c�k�ߑS��W�s��Łt�i�����ɁA1973�N6��15���j�́q�c�����́r�Ƃ����x�ɐ��z�q�q�ΘŁr�Ɓq�������_���r�r���Ă���B�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1974�i���a49�N�j�l�ꌎ��\�����y���j�z
�����\�����A�����ɂ̐����N�ɋN�������B�������Ă��ꂽ���C�ɂ͂�āA�ڂ�����̂��Ƃ��v�Џo���B���r�[�ō����d�M�A���q�W�ɕʂ�������āA�����N�Ɛ{���̍k�ߎ���K�˂�B��q���g�����A�̂̔o��Ȃǂ�A�E���X�L�[��A�R�����E�h������y���ɂȂ�B���ꂪ�Ŗ@�ɂ��܂����B��̂�����A�Ђ邷���A�R�z���̐{���w�őҍ������q�v�Ȃƈ��ЁA���R�̈�_�����K�˂�B��{�����čs�����A�v�l�̘b�ɂ��A����������݂͂��߁A��ɂ�ďd�ԁm�A�A�n�B�����A�Q������ĂԐ������āA�ׂ�̕����ɍs���ƁA�Њ�����Ŗc�炵������������ɂ�[�Ǝ���o���B�t���������߂Ă���Ȃ���A�w�Ȃ̂ЂƂ��͂���̂Ă��ꂽ�肷��B�敨�̎��Ԃ��ƒm�炳��A������ƑO�ɂ���Ȃ�B�q�v�ȂɁA�܂��܂����s�w�܂ő��Ė�ЁA�V�����ɏ��B�A��Ă���A�H�ׂ����X�`�̂��܂��A�T�q�ɖ����̊��ӁA�ޏ��̍�������ĐQ��B�i��\����L�j�i�������L�A�O�O��`�O�l�Z�y�[�W�j
�\�\1974�i���a49�N�j�l1��28���@�{���ɉi�c�k�߂�K�˂�B���Ƃ����������A�����ɂ̐������ǂ�����B
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1974�i���a49�N�j�l�l���\����y�ؗj�z
����ʃ[�l�X�g�Ń^�N�V�[���E�ւ܂��Ǝv�������o������B�̓`�@�@�B���e���O�Y�搶���`���ꂽ�Ƃ��Ӂu���Ձv�Ɓu�x�m�R�v�̊G�̊J��̏���B�K�Ђɂ������X���ɏo���r�[�ɐe�ȎԂ��݂���B
���n�`�ŕ`���ꂽ�Ə͂�鐼�e�搶�ɃR�c�v���ŏj�t���グ��B�ׂ�̊C���b�ƁA�L�݂����ȌՂ��ˁA�ȂǂƋ�B�����Ƃ����̒��ɏo�āA�u�X�G�q���v�ŃX�L�Ă�H�ׂȂ���A���c�O�A�z�K�D�A�g�������N�����ƒ���B�Ȃ�Ƃ����Ӓʂ�̓X�ň��ށB�C��A���J��U�Đԍ�ɍs���A�u�W���C�v��T�����Ă����̂́A�X�g�ŋx�݁B�ʂ�ċA��B�i�������L�A�O�l�܃y�[�W�j
�@��N�̏t�l���̂��Ƃ������B���̓��͎��������҂��ɑ҂��Ă��������B���e�搶�̕`�����u���̐}�v�Ɓu�Ղ̐}�v�Ƃ��A�܂��ɓV��@�����R���̑��{�V�`�@�@�̏��@�̊ԂőΖʂ��A�������e�����҂ɔ�I����邱�ƂɂȂ��Ă����B�u���̐}�v�͂��łɎO�N�O�Ɋ������Ă����B���Ɖ�c�j�Y�͐搶�̂���ŁA�d�C���ӂ��n�݂����ȁA���̎p��q�����āA�Ȃ�Ƃ�������悢�̂����S���f�������̂������B������̕x�Ԑ}�́A�}�S�̕x�m�̊G�����ɂ���������閼�삾�B���̕��������Ƃ悢��˂Ɖ��l�͔����ꂽ�B
�@�������c�O�Ȃ��ƂɁA�����̓[�l�X�g�łƂĂ��܂ōs���Ȃ����낤�ƁA���͂�����߂Ă����B�����ċC�����ɁA�ȂƋ������֍��̉Ԃ����ɍs�����B�A��݂��Z�i�R��ʂ�j�ɏo��ƁA�l�^�N�V�[�������Ă���̂������āA�x���J�ōȂƕʂ�A���͐������B
�@�`�@�@�ɂ́A�����̋��c�O�k�����A���c�͔d���ɋ��Z�l��l�A�ܐl�̐搶�̃t�@�������Ă����B�搶�͉�c�j�Y�Ƌ��ɐz�K�D�̂���܂Ŗ��������Ă���B��������A�C���b�A���J�K�M�A�R�c�k�ꂻ��ɎႢ�g�����������Ă����B���R���L�҂̊F�����������A�a�C�Ŏ����̂܂��Â��ɂ��Ă����B
�@��������Ɍ����āA�u���v�u�Ձv�͓V�䂩�猜���Ă����B���͏��߂āu�Ղ̐}�v�����グ���B�u�Ձv�͂܂�ŁA�e�ƔL�̂����̂��݂����Ɏv��ꂽ�B�~悂Ƃ͂��̂��Ƃ��낤�B�W�����҂͎������݁A�����Ă���悩�����̂��B���̂�������ׂ����ƂɁA�u���v�Ɓu�Ձv�́A���������֊���ނ��Ă���B�������Λ����邱�Ƃ́A�i���ɂȂ��̂��B�Ȃ�ƒ����I�ł���A���m�ł���u���e���v�̐��_���ے����Ă���悤�ŁA�ꓯ�傢�ɏ������̂ł���B
�@�搶�͉v�X��������킵���A�a���ɕM����߂āA�����╶���������ꂽ�B�߂��߂��C�܂܂ɂ�����B�������A���̏o���搶�́A�u�Òr��^�Ƃт��މ�������v����������͂��߂��B���͂���ł͂��̂���Ȃ��̂ŁA���̊G�����]�����̂͂������A�܂�ʼn��M�݂����ȗ����o������Ă��܂����B�������l���悤�ɂ��A�H�L�Ȃ间�Ƃ����邾�낤�B���̂ɂ͒������N���������Ă����B����͑�ϋM�d�Ȃ��Ƃł���B�搶�͓��N���\�ɂȂ��Ă����B
�@�[�z�������߂Ă���B�������Z��̊��y�X�Ɉ͂܂ꂽ���Ƃ͎v���Ȃ��قǐÎ₾�B�ЂƂ��Ƃ̉��Ȃ�������̉Ԃ̉��ŁA�搶�𒆐S�ɋL�O�ʐ^���B��A�����������܂ŕ������B�������͓`�@�@������t�̂��钖�����L�O�Ɉ�������A�̘A���������������߂�Ɛ搶�̍�i������A��̓��ɋP���X�֏o���B����Ȍ�ʊW�ɂ��߂����W�����҂����́A���悢��ʂꂪ�����A��̏ꏊ��T�����߂��̂������B�i�q���e���O�Y�A���x�X�N�\�\�T�@�`�@�@�́u���Ր}�v�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��O��`��O�O�y�[�W�j
���������V�^�s��������^�k�����Łl�t�i��h���ǁA1976�N4��30���j�́q�ᒆ�̃A���o���r�Ɍf�ڂ̎ʐ^�u���a49�N4���A���e���O�Y���̊G�u�x�m�R�v�u���Ձv�J��̏W���A�`�@�@�v�i�����A�k��Z��y�[�W�l�j�k�E�����l�ߋg�����A�O�l�����Đ��e���O�Y�A��l�����ĉ�������l�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1974�i���a49�N�j�l�㌎��\�Z���y�ؗj�z
���Ђ邷���A�����w�O����o�X�ŏa�J�ɏo�āA�Ԃ��E���Ăm�g�j�����Z���^�[�ɂ䂭�B�y���F�ƃ��a�I���g�����̘b�̘^���B�E���X�L�[�����݂Ȃ���Ԃ����B����N�ǂ�������B
���߂��̃��X�g�����œy���F�ƈ���m�q�ƎO�l�Ńr�[�������ށB�ʂ�Ă���[���A�߂��̑�X�؏㌴�̍����d�M��K�˂Ē���B�V�h�ɏo�āA�u���̋�v���̑��l�A�܌��n�V�S���Ē����A��B�i�������L�A�O�ܔ��y�[�W�j
�@���a�l�\��N�@��㎵�l�N �\�܍�
�k�c�c�l�ӏH�A�m�g�j���W�I�Łu�g�����̐��E�v����������A��������A�V��ޓ�Y�A�剪�M�炪�N�ǂ��Ă����B�y���F�̋��璺��I��������ۓI�B�i�q�k�g�������M�l�N���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O�l�y�[�W�j�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�k1974�i���a49�N�j�l�\���\����y�y�j�z
���㎞���N����ƉJ���~�Ă��B
���T�q�Ɛԍ�̃z�e���E�j���[�E�I�[�^�j�ɏo������B�����h�����̃l�N�^�C�A���̃V���c�A�L�c�Ă̎���ȂǂЁA�a�J�ɒn���S�ŏo��B�����f�p�[�g�őփY�{���ƁA�O�O�A���H�D�ӁB�ߍ��͊O�o���邱�Ƃ������̂ŁA�a���̕��ɊႪ�䂭�B
���a�J�p���e�I���Ƃ��Ӊf��قŁu�X�e�B���O�v������B�Ŗ@�ʔ����B�O�\�N��̈ߏւ𒅂����o�[�g�E���c�h�t�H�[�h�Ƃ��Ӗ��҂����T�B�ܘ_�A�|�[���E�j���[�}�������ɐU�����Ă�B���}��ق̒��ؗ����X�œ����ɒ��H�B�o�X�ŋA��B
����A�m�g�j���a�I�̑��������g�����̎���ǂނ��Ƃ��̃v���O�������B�������A����Ȑ��Ȃ̂��A�Ƃ������^��͂����Ɠ����B���l�̎���ǂނ̂͏��߂Ă����A��A�O��A�オ����Ă�B�i�������L�A�O�Z��y�[�W�j
�@�q���L�r�@��㎵�l�N�\���\������@1974�N10��12���i�y�j�A�ߌ�9��5������55���ԁA�m�g�j���W�I�������s���|����t�́q���Ǝ��l�r�V���[�Y��2��Ƃ��āq�g�����̐��E�r���������ꂽ�B�Q�X�g�͓y���F�E��������i�Βk�j�ق��B�Βk���̎ʐ^���s��������^�k�w���l���Ɂl�t�́q�y���F�̊��r�Ɂu�m�g�j���W�I���ł̓y���Ƃ̑Βk�B�i���a49�N9���j�v�Ƃ����L���v�V�����ƂƂ��Ɍf�ڂ���Ă���i�����A�O��y�[�W�j�B
�@�܁B�[���A�z�q�ƖF���ŐH���A�i�|���I���ŃR�[�q�[�B�J�ƂȂ�B��㎞�A�m�g�j���W�I�Łu�g�����̐��E�v���B��������A�剪�M�A�V��ޓ�Y�̘N�ǂƋ�����b�q�̂�����ׂ�B�Ȃ��ł́A�y���F�̋��璺��I�Ȕ����́u�m���v�N�ǂ����삾�ƁA�z�q�Ə��Ă��܂��B�����͏o�����Ȃ��̂ɁA�F��o�����Ă��ꂽ�݂�ȂɁA���ӁI�i�q45�@���璺��I�N�ǁr�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A�}�����[�A1987�A�����y�[�W�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�������ĉ�������̓��L�ɓo�ꂷ��g����������ƁA1970�N�㏉�߂̋x�M�̊��Ԃ�����ŁA����ȑO�̓y���F���������������{���̎���ƁA����ȍ~�̂����ɍ����d�M��i�c�k�߂Ȃǂ̔o�l�Ƃ̉�ň���Ɗ�����킹�鉸�₩�Ȏ���ɑ�ʂ����悤���B���̂�����̋@���́A�{�e�`���ł��G�ꂽ�E�菃��s���F�e���q�C�L�\�\�F�V���F�`�t�����̂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă���B
�@�����k����㎵��N�\�ꌎ�l��\�����A�V�h�ɂ���ԉ��_�Љ�قʼn�������̏o�ŋL�O���X�I�ɊJ����A�F�V�͗��q�ƂƂ��ɏo�Ȃ��Ă���B
�@�]�p�����B�e�����A���\���ɂ̂ڂ�Q���҂��ꓰ�ɉ���L���Ȏʐ^���c���Ă���B�����ɂ́A�F�V�̈��Z�Z�N��̌�F�W�̊j�����������o�[�̊炪�قƂ�ǂ݂�ȁA��������Ɏʂ��o����Ă���B�����A�y���A���R�A�푺�A�r�c�A���A�V�����A�o���A�ܒJ�A���A�쒆������A����ɁA����C���A�g�����A����p�v��A�����O�Îq�̊��������B��������܂�œ�����̎ʐ^�̂悤�ɂɂ��₩�ȏΊ炾�B�����A���̎ʐ^���������₩�Ȋ�͎��̂悤�Ȏ������t���I�Ɏ����Ă͂��Ȃ����낤���ƁA��c�ޏ����͎w�E���Ă���B���Ȃ킿�A�Z�Z�N��̂悤�Ȕނ�̔Z���Ȍ�F�W�A���邢�͋��ƊW�́A���łɉߋ��̂��̂ɂȂ����Ƃ��������ł���i�w�y���F�@���̓��́x�j�B�i�s���F�e���q�C�L�t�A�O�Z��`�O��Z�y�[�W�j
�g�����Ɖ�������A���҂̓��L�ł��̌�F�����ǂ�����������߂�����ɂ́A��͂��������o�ŋL�O��̏W���ʐ^���ŏゾ�낤�B�ܒJ���m�i�ďC�E���j�s�F�V���F ���z���p�فt�i���}�ЁA2007�N4��12���A�ܔ��`�܋�y�[�W�j�̌��J���ʐ^�͑傫���Č��₷�����A�m�h�ɂ������Ă���B�����ł́A�������Ę^�����ܒJ�́s�F�V���F�_�R���N�V�����t����������B�ܒJ�͂��́s�F�V���F�_�R���N�V�����V�\�\�F�V���F ���z���p�ف^�F�V���F�Ɓu���v�̒��ԁt�i�א��o�ŁA2018�N1��15���j�����̓����q��� ���Z�Z�N��̊����r�́u���܂��܂Ȍ�F�v�̖{���ŁA�u��㎵��N�H�A�V�h�̉ԉ��_�Љ�قōÂ��ꂽ��������̏o�ŋL�O��̐܂ɁA�]�p���̎B�����L���ȋL�O�ʐ^������i47�y�[�W�j�B���Ȃ�Ԕ��\�]���̑����������E�F�V�E�y���̋��ʂ̗F�l�ł���A�Z�Z�N��̌�F�W�̑傫�ȕ����������Ɏʂ����܂�Ă���B�v�i�����A�l��y�[�W�j�Ə������B�ܒJ�͂܂������ŁA��ʑ̂ł���Q���Ґ��l���s�b�N�A�b�v���ďЉ�Ă��邪�A���͍]���B�����ʐ^�̏��o�i�s�A�T�q�J�����t1972�N2�����́q�k�A�ځi��j�\�A�l������� ���l�r�j�Ɍ��y�����q�g�������F�V���F�i2007�N5��31���j�r�ł���ɏڂ����Љ���B��������S�����܁A������m��ǂȂ���������炷�ׂĂ̐l�l����肵�Ă����Ɗ������̂����B�i���̉摜�́A�E�F�u�y�[�W��400���Ɋg��\�����Ă���������𑜓x�ɂ��Ă������j
![�]�p���@��������̏o�ŋL�O��ɏW�܂����l�X�i�u�m�l�̏ё��v���j1971�N](image/katoikuya_kai_2.jpg)
�]�p���@��������̏o�ŋL�O��ɏW�܂����l�X�i�u�m�l�̏ё��v���j1971�N�k�o�T�F�ܒJ���m�s�F�V���F�_�R���N�V�����V�\�\�F�V���F ���z���p�ف^�F�V���F�Ɓu���v�̒��ԁt�i�א��o�ŁA2018�N1��15���A�l���y�[�W�j�l
�V�h�ԉ��_�ЂŊJ���ꂽ���̏o�ŋL�O��̑ΏۂƂȂ�������A�s����������W�k���㎍����45�l�t�i�v���ЁA1971�N10��20���j�͓����̉����̋�ƁE���Ƃ̂قƂ�ǂ����߂���S���������A���������́q��i�_�E���l�_�r������̉��t��m�F�����������Ӗڂ��ׂ����e�������B�f�ڏ��ɋ�����A�푺�G�O�E���e���O�Y�E�g�c����E��_�����E�g�����E�y���F�E�h���ɒj�E�F�V���F�E�u�����E�E�c�ʜ\�E���J�K�M�E���R�r���Y�E����p�v�E�r�c�����v�E���������E���R���O�Y�E�ŎR���Y��17�l�i���\���̃R�����g���哇���j�B���͖{�e���������߂ɓ��������߂ĕ�������T�������o�Ă��Ȃ��̂ŁA�a�J�̒������X�Łu�ޒ�@���ҁv�̞x�����܂������ł���肵���B����͒��҂������N��ɑ��������̂ł͂Ȃ����i�m�͂Ȃ����j�B�Ƃ����̂��A�������X�Ő�ɍw�������A�g�����������ɑ��������㎍���ɔŎ��W�̍ŏI�y�[�W�Ɂu���W�y�^�������^5400�v�Ɖ��M�����̃���������A����������W�ɂ́u���X�y�^300�v�Ƃ�����肩�A�����ɂ���V�~�܂ł���������Ă���B���Ȃ݂ɍ����N��i1932�`2002�j�̎p�́A�o�ŋL�O��̏W���ʐ^�ɂ�������B����A�����������������V�^�́s��������^�t�i�R�[�x�u�b�N�X�A1976�j�Ƃ��Ĉꏑ�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B���߂�Ƃ���15���B��_����i1900�`1977�j���A�g�c���i1898�`1973�j���A���e���O�Y�i1894�`1982�j���A�F�V���F�i1928�`1987�j���A�y���F�i1928�`1986�j���A�r�c�����v�i1934�`1997�j�A���������i1931�`�@�j�A�E�c�ʜ\�i1926�`2003�j�A���R�r���Y�i1930�`2014�j�A�X�J�ρi1897�`1969�j�A�T�R�܁i1907�`1989�j�A�c������i1923�`1998�j�A�}��b�i1943�`�@�j�A�����d�M�i1923�`1983�j���A�g���N�O�i1934�`2002�j�B�����̑���ł���s��������^�k�w���l���Ɂl�t�i�w�K�����ЁA2001�j�ł́A�ѓ��k��i1930�`2013�j�Ɩ�쐟�q�i1930�`2002�j���̊�����������i�s���������i��W�V�t�Ɂq��������^ ���r�Ƃ��čĘ^���ꂽ���ɂ́����t�����j�B�c�O�Ȃ��ƂɁq�g�����̊��r�͏�����Ȃ��������A�g���́q���e���O�Y�̊��r���╪�ɓo�ꂷ��B�s���������i��W�V�t�́q�������r�Ɉ˂�A�s��������^�t�̒ʏ�ł́u���a51�E4�E30���s�B�R�[�x�u�b�N�X�B������܁Z�Z���B�e���ό^�E�z���E�����i�ѕt�j�B�ꔪ��ŁA�����ʒ��ʐ^��l�ŁB���ҁu��L�v�B�艿��܁Z�Z�~�B�v�ŁA�k�����Łl�́u���s�������B��h���ǁB����܁Z���B�z���E�V���E�����B�v�i�����A�ܓy�[�W�j�ł���B
 �@
�@
���������V�^�s��������^�k�����Łl�t�i��h���ǁA1976�N4��30���j�̔��E�\���̕��i���j�Ɠ��E�w�i�E�j�k����50���L�ԁA�{���a�������\���V�����E�ѕM�������l
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
20���I�����_�ł̉�������̑S��W�Ƃ������ׂ��s��������o��W���t�́A2000�N�ɉ��ώɂ���500������Ŋ��s���ꂽ�i10��W�S2938����^�j�B�Ō��̉��ώɂ́A2���̉�������_���o�������Ƃł����ڂ����B�m�����́s��������_�t�ƈɓ��M�́s��������V�_�t������ł���B�m�����́s��������_�t�i���ώɁA2003�N10��15���j�́q��l�� �w�q�̃������x�r�Łu������M���ǂ܂�Ă������̎���v�ɂ��āA���̂悤�ɏ����Ă���B���Ȃ݂�1960�N��㔼�Ƃ́A�g�������W�s�Â��ȉƁt�i1968�j���܂Ƃ߁i����͋g�������������s�Â��ȉƁt�N10��2���ɓǂ�ł���j�A�̂��Ɂs�_��I�Ȏ���̎��t�i1974�j�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��鎍�т��c�c�Ƃ��ď����Ă�������ł���B
�@���̎���Ƃ́A���Ȃ킿�Z�Z�N��̌㔼�ł���B�|�p�I�Ȃ���̂��߂��铖���̎���I�ȏ́A�ЂƂ��Ƃł����A�����̉��l�ς����ꂩ�畢����������B���������Ɠ���������邩������Ȃ����A�ǎ����镶���l����݂�A�悤����Ƀn�`�����`���Ȃ��̂����X�Ɍ|�p�Ƃ��Ė����o�Ă����̂ł���B���������́A�����Γ���ƕ]���ꂽ���A�ق�Ƃ��͓���ł��Ȃ�ł��Ȃ��B���ܐU��Ԃ��Ďv���ɂ́A�����b���u�ʑ��v�i���܂ЂƂK���Ȍ��t���Ȃ��̂ŁA�J�b�R���ł��̌���g���j�������̂ł���B�����̈�ʓI�ȉ��l�ς���́A�ǂ��݂Ă��u�ʑ��v�Ƃ����v���Ȃ������B�ɂ�������炸�A����炪�|�p�𖼏�邱�Ƃ�����������̂��B
�@��\�I�ȗ��������A������������q���`�̊G��B����A�V��V�~�A����c������Ȃǂ̉����i�i���g����͋��q���`�Ƃ�������ɏ���̎ŋ��ɏo�Ă����̂��j�B�y���F�A����Y�A�}��b��̕����B�l�J�V�����̐l�`�B���݂ł͂����A�l�͂������R�ɂ������u�|�p�v�Ƃ��Ď���Ă��邪�A�ނ�̌|�p���Ӑ}�����̂́A���́u�ʑ��v�̕����ł������B���킭�����A���Y���ł���A�������I�ł���A�G���`�b�N�ł���A�y���I�ł���A�܂茠�ГI�Ȍ|�p�ς��u�ʑ��v�����Ă������̂̑��̂��A�܂��ɔނ�̐V�����|�p�\���ł������B
�@���܋�������͂ǂ���A���݂ł͂��łɁu�|�p�v�Ƃ��Ďs�����Ă��邩��A�n�`�����`���Ȃ��̂Ƃ����C���[�W�͓`���ɂ�����������Ȃ��B���̎���̌|�p�I�𐳊m�Ɍ�邽�߂ɂ����������͈͂��L���āA�f������������ɏo���Ă݂�B��ؐ����́w��������ҁx�A�ᏼ�F��́w�Ƃ��ꂽ���߁x�A��a�����́w�r��̃_�b�`���C�t�x�ȂǁA�����͊����̉��l�ς��炷��A����Ɋ�����|���m�Ƃ��ĕЕt��������e�ł���A�܂��Ɂu�ʑ��v�Ǝ���d�̌���ł������B�܂��Έ�P�j�́A�ǎ��l����G���O���Ɣ���Ȃ���A�w���삢�ꂸ�ݎt�E�ӂߒn���x�Ȃǂٌ̈`�̌�����B���Ă����B�����̍�i���A�����Ȑ��E�I�ȁu����v�̊T�O�ł͒ʗp���Ȃ��A�܂������V�����|�p�̈Ӗ����咣�����̂ł���B
�@�����̕���ł��A�]�ː에���A���I�����Y�A����v��Ƃ������u�ʑ��v�̍�Ƃ������������A�܂��A���Ԃł̓G���{�ƌĂ��u��权N���u�v�i�킽���Ȃǂ͊��Ԃ�߂Ĕ��������̂��j�ɘA�ڂ���Ă��������O�́w�ƒ{�l���v�[�x���A�O���R�I�v���v��ɂ���Ĕ����̂��ƂɌ@��o���ꂽ�B�����āA���̎�����ے�����G���Ƃ������ׂ��F�V���F�ҏW�́u�����K�N�v���A�u�G���e�B�V�Y���Ǝc���̑����������v�Ɩ��ł��Ĕ������ꂽ�i����͂����ɏ����u�S���k�y�l�v��A�ڂ��Ă���j�B������������̒����̂Ȃ��ŁA�w�q�̃������x�̍�i���܂������ꂽ�̂ł���B
�@����l�́w�q�̃������x��]���āu���ӂ����v���Ƃ����B�킽���͂�������Ƃ���ے肵�悤�Ƃ͎v��Ȃ��B����ǂ��A�u���ӂ����v�����牿�l���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B������������͍ŏ�����u���ӂ����v�̏������ł���̂��B�܂��Ɂu���ӂ����v�̕��w�Ƃ��āA�w�q�̃������x�͉���I�Ȃ̂ł���B�����Ă���ɂ�������A�u���ӂ����v�Ƃ͈���ɂƂ��āA���Ȃ킿�o�~�̂��Ƃł������B������w�q�̃������x�Ƃ́A�o�~���u���ӂ����v�ƌĂԂ悤�ɂȂ��Ă��܂�������ɂ�������A����̒ɗ�Ȕ���Ȃ̂��Ƃ����Ă������B�i�����A���Z�`����y�[�W�j
�u���̎���v�̗v��Ƃ��Ăقډߕs���̂Ȃ����̂Łi���y�V�[���ɐG��Ă��Ȃ����A�����܂ł��Ȃ��W���Y�ɑւ��r�[�g���Y�ɑ�\����郍�b�N�̝������������悤���A���ꂾ���ăW���Y�Ɋr�ׂ�u�ʑ��v���j�A����͂��̂܂��l�E�g�������Ƃ�܂������I�ł��������B�������瓱���������̂́A���������W�s�q�̃������t�i���ʎЁA1970�j�Ƌg�������W�s�_��I�Ȏ���̎��t�i���쏑�[�A1974�j�Ƃ̔�r���������A����͖{�e�̃e�[�}����B
�Ï��R�������s�����T�K�t�i���m�o�ϐV��ЁA2016�N11��3���j�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����B
�@�k���҂̒ʂ��Ă�����w�̂������ɂ������A�x���X�Ƃ��������ȌÖ{���́l����������{�̊Ǘ����@���Ɠ��������B�q����{�����ƁA�X��͂`�T���̃m�[�g�ɂЂ����玞�n��Ɏ菑���Œ��Җ��Ə����������A�˂Ă����̂��B�����āA���̖{�������Ɖ��Ƀ`�F�b�N�}�[�N������B�������ꂾ���ł���B��قlj�]�����Ƃ͂��������A�t�ɔ���؈ȊO�͂��������ȒP�ɔ��ꂸ�A���I�Łu�Q��v���Ƃ����������̏��i�ł���Ö{�ŁA���̂悤�ȊǗ������Ă�����A���ʂ͂����܂��p���N���Ă��܂��B���ꂪ�ł��Ă��܂��̂͂Ƃ���Ȃ������A���ʂł������Ȃ�ɒ����ԐQ��͂��́u����؈ȊO�v�̌��߂̖{���A���̓X�Ɍ����Ă͔�Ԃ悤�ɔ���Ă����Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B���������̋C��ō��͂�����̂́A��̈ꌎ�ň�����炢�̃y�[�X�Ńm�[�g�͂����ς��ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���B��������ƔN�����A�����I�ŘZ�Z�Z���ȏ�̃m�[�g�����݂��Ă���͂����B
�@��w�𑲋Ƃ��Ă���͂x���X�Ɋ���o����p�x�͑��������A�܂��n���ɖ߂��Ă���͔N�ɐ����������ɂȂ��Ă��܂������A����ł�����o�����тɁA���X��͖��ʂ݂̏��ׁA�����́u�ǂ����[�I�v�Ƃ������邢�吺�ň��A�����X�ɁA���̉����璼�߂̃m�[�g�����o���A�u����`�z���g�ɂˁB�������P�킩��Ȃ��ł���v�ƌ����Ȃ���m�[�g���L���A�ŋߓ������{��S�������Ă����A���ꂪ���[�e�B���ł������B�u�ق���ƂɂˁA�����͓���Ȃ��ȁ`�Ȃ�čl���Ă�ƃl�A��������Ă��������B����Ȗʔ����������Ă����肷��ł���ˁB����`�z���g�ɂˁB�������P�킩��Ȃ��ł���v�Ƃ�������t���Ŕq������ƁA�ڂ�����ނ悤�ȗǏ��������Ə����A�˂Ă���A�l�I�ɂ͔߂������ƂɁA�����قƂ�ǑS�ĂɃ`�F�b�N�}�[�N�����Ă��܂��Ă���̂ł���B�������܂ɁA�Ⴆ�g�����w�m���x���Ƃ��A�X�J�ДŁw�e�I�t�B���E�S�[�`�G�����I�W�x�i�S�O���j�ȂǁA���傤�ǂ��̓�����������̂悤�Ȃ��̂�����ƁA����̌ܕ��̈ꂩ���Z���̈�̒l�i�Őɂ������Ȃ������Ă����������̂������B����A�w�m���x�Ȃ�āA�^�_�ł��ꂽ��Ȃ�����������B�i�q����Ö{���̎v���o�\�\�X��Ƌq���Ȃ��m�[�g�r�A�����A��O�O�`��O�l�y�[�W�j
�����Ė{���̉��i�ɂ́u�g�����w�m���x�i�����C�J�j�v�Ƃ����L���v�V�����ƂƂ��ɁA�^�_�ł�������i�H�j�s�m���t�̏��e���f�����Ă���B�ʐ^�Ō��邩����A���̔w���Ă��Ă�����̂́A�{���ɓ��Ƃ��v���Ȃ��B���Җ��́u�Ï��R�������i�������܁E�������j�v�̓y���l�[���ŁA���N������J�����A�{�����琄�肳���40�Αゾ�Ƃ���A�x���X�X�傪�����Ă��ꂽ�̂͂���20�N�Ԃقǂ́i�܂�2000�N�ȍ~�́j�o�������낤�B���̊Ԃ́s�m���t�̌Ï����i�̕ϓ���ǂ��قǂ̍ޗ����������킹�Ă��Ȃ��̂ŁA2020�N5�����{���_�ł́s���{�̌Ö{���t�̏o�i�����Ă݂�i���s���j�B
�@��93,500�~�B�u���Łi����400���j�@�����P�E���L�Y�@����\��������@���Ԃ��ɏ����������Ձ@�������i�����̏�Ɏ��\�t�j�@A5���@���ʐ^�E�ޗnj��ꍂ�@H���܁v�i�����闢�̏���c���j
�A��71,500�~�B�u����400���@���ʐ^�E�ޗnj��ꍂ�@��9��g���܁@���ɋ����ҊǗ��ԍ���L�@�����V�~�w�����P�v�i�_�ے��̋ʉp�����X�j
�B��73,000�~�B�u�����Ă����߁A���X���L�B�}�����[�L�����Ζ����̋g�������h�t�B�{�̕\���Ԃ��Ɍ��提�����B���A�{�̌o�N���B����400���B�艿300�~�B�v�i�~�s�̌Ï������c�j
�C��38,500�~�B�u����400���@�ʐ^�E�ޗnj��ꍂ�@H���܁^�������P�E�C�^�~�@��ⳏ��C�^�~�^�{����ԗǁv�i������s�̂��Ă�Ɂj
4���̍��v��276,500�~�A�������ς�69,125�~�B����7���~�Ƃ���ƁA�x���X�́u����d���i�v��7,000�~�`14,000�~�B�����ށB�ʏ�A���̉��i�œ���ł��Ȃ����Ƃ͉�����������炩���B�Ƃ���ŁA�@�`�C�̒�����w������Ƃ�����A���͇B��_���B�u�}�����[�L�����Ζ����̋g�������h�v���t���Ă��邩�炾�B�����A�s�m���t�͂��ł�2�������Ă��邵�i1���͌��提������A����1���͔ӔN�̋g������ɏ������Ă������������́j�A���h1����73,000�~�͓������Ȃ��B
�g�����̎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�͊��s��A���N���o���Ȃ���1959�N4��6���ɑ�9��̂g����܂����܂������߁A���ł�400���i�L�Ԃ͂Ȃ��j�͂��̎��_�ł����Ƃ����ꂽ�͂����B���Ȃ��Ƃ��A�s���{�E�t1959�N11���������W��g��ŋg�����u�[�����N�����Ō��ɂ��Ȃ��Ȃ����A�ƈɒB���v�́q�g�����ٕ��r�i���o�F�ɒB���v�s�����C�J���t�ɒB���v��e�W���s��A1962�N1��16���j�ʼn�z���Ă���B�\�\�g���́u���ƈɒB���v�̌�F�́A����߂ĒZ�����̂������B�ӔN�̌܁A�Z�N�ɂ����Ȃ��B����Ȃ̂ɁA���̈�f�ʂ��A�u�g�����ٕ��v�Ƃ������͂ʼni���Ɏc���ꂽ�͍̂K�^�Ȃ��Ƃ��B���Ԃ�́A�q�V���r�Ɉ˗�����ď��������̂����A�����̗��R�Ŗv�ɂȂ������e�������Ǝv���B���͈�e�W�̍Z�����͂��߂Č��āA�ɒB���v�̊ώ@�̉s���̂ɋ������L��������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�}�����[�A1988�A�Z��y�[�W�j�Ə����Ă���B�\�\�ɒB�͂���ɁA�s�m���t��S�ю��߂��s�g�������W�k�����̎��l�o��5�l�t�i���惆���C�J�A1959�N8��10���j�������ɑ����ɂȂ����A�Ƃ������B����Ȍ��60�N�ԁA�����m�푈�ȑO�Ɋr�ׂāA��Ђ��傫�Ȏ��R�ЊQ������قǂȂ��������߁A400���̂������Ȃ�̕����͌������Ă���̂ł͂Ȃ����i�O�S���\���H�j�B�ނ��g����܂�����t���Ă��āA�g�����g�u�s�m���t�͓ǎ҂ɑ厖�ɂ��ꂽ�{������v�Ǝ��Ɍ�������Ƃ�����i���������тꂽ�Ï������Q�����Ƃ���A�g������́u���ш�Y�l�v�ƋL���̂��Y��Ȗ{�ɂ���������܂����x�A�Ǝ��������Ă����p�[�J�[�̃u���b�N�Ł\�\�g������͂ӂ���u���[�u���b�N���g�p�\�\�������Ă����������̂����A���ꂫ��ɂȂ��Ă��܂����j�B���\������������}���ق�e�n�̕��w�فA��w�}���قȂǂɎ�������Ă���Ƃ���A�l����300�����炢���낤���B���ܔ���ɏo�Ă���̂����̂�����4���Ƃ����̂́A�͂����đ����̂����Ȃ��̂��B�܂��A1��7���~�Ƃ���ƁA2100���~�͂͂����Ĉ����̂������̂��B���Ȃ݂Ɂs�m���t�ɓ����{�͑��݂��Ȃ��B���A�s�̖{�̕\�������������������[��������悤���i�����j�B�g�����i�c�k�߂Ɉ��Ă����ȁi1986�N10��8���t�j�ɂ́u���āA�����v���̃������[���w�����x���A���ŕ����Ȃ���A���ɓ���{���Ɗ��S���Ă���Ƃ���ł��B�����ɂ�������{�̃������[���́w�m���x������܂��B�������A�\������삵���̂͋����ł��B�k�ߓ����{�ِ̈F�ł��ˁB��ɂ������܂��B�v�i�s�Ս��t421���k1986�N11���l�A�ꔪ�y�[�W�j�Ƃ���B�����A�g���̐g�߂Ń������[������|����l�ނ������Ƃ���A�}�����[�Ō�y�������Ȑ܋v���q�����[���Ăق��ɂȂ��B����A�������[���́s�m���t���s��Ɍ���悤�Ȃ��̂Ȃ�A����͎����ł���B�����ǂ���A�V���̌ǖ{�Ȃ̂�����B�Ȃ��A�Ȑ܋v���q�ɂ�郋�����[���Ɋւ��ẮA�q�������[���r�́k�����2020�N6��30���NjL�l���Q�Ƃ��ꂽ���B
 �@
�@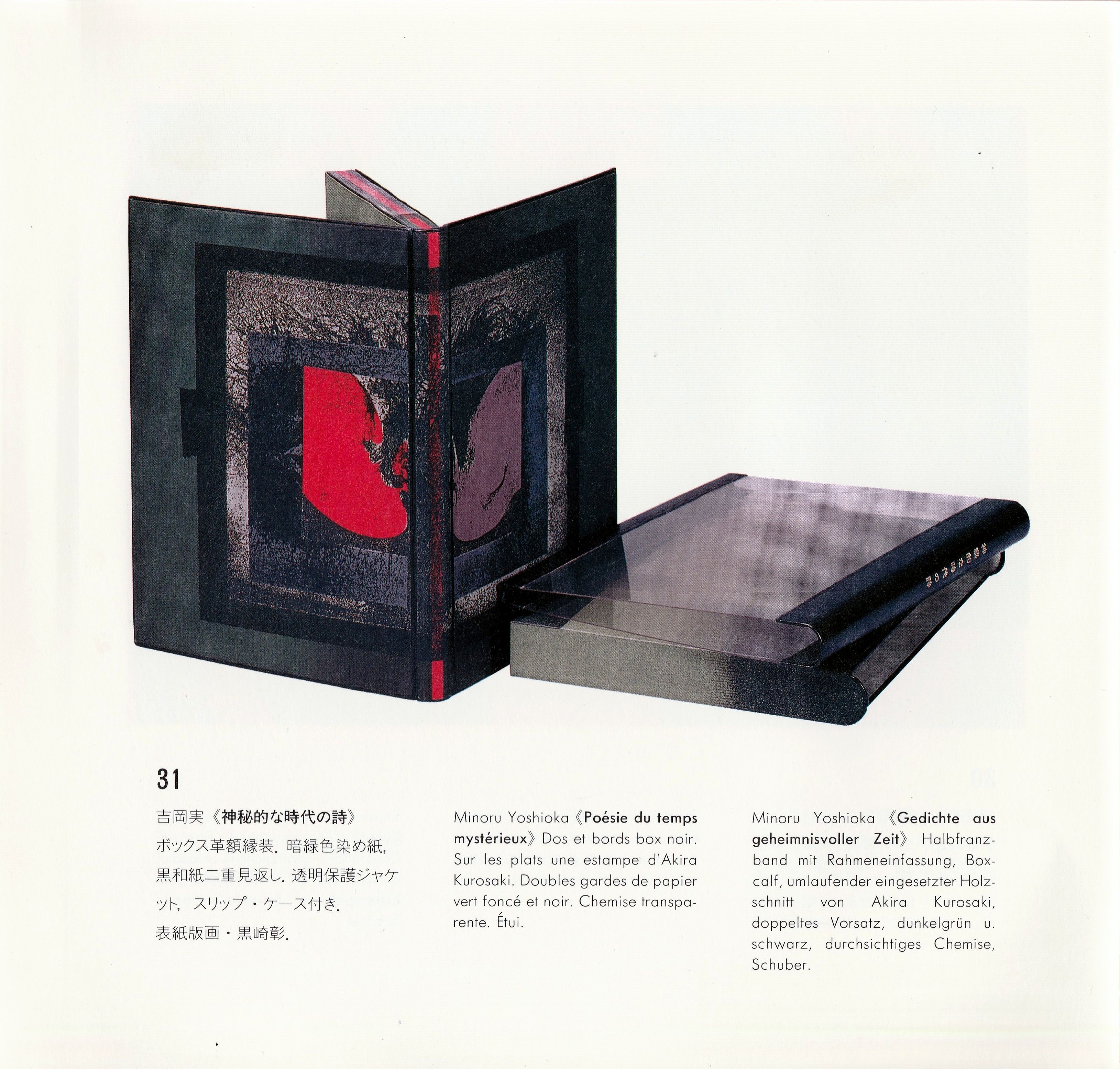
�Ï��R�������s�����T�K�t�i���m�o�ϐV��ЁA2016�N11��3���j�̃W���P�b�g�i���j�ƓȐ܋v���q�ɂ��s�_��I�Ȏ���̎��k�����Łl�t�̃������[���k�o�T�F�����g�[�E�ǎq�ƓȐ܋v���q�̓W����}�^�sRELIURES�t�i���s���̋L�ڂȂ��Ac1994�N3��31���A�k�O�l�y�[�W�l�j�l�i�E�j
���̂������Ȃ������݂Ȍ��t���A�R��ׂ��ꏊ�ɒu�����Ƃ��A�˔@�Ƃ��ċP���������߂��B�N�̉f�����P���̂��������߂��ɂ���ĂłȂ���Ȃ�ʁB�\�\���x�[���E�u���b�\���i���Y���P��j�s�V�l�}�g�O���t�o���\�\�f��ē̃m�[�g�t�i�}�����[�A1987�N11��15���A��܌܃y�[�W�j
�E�菃��s���F�e���q�C�L�\�\�F�V���F�`�t�i�����ЁA2019�N11��15���j�͏��̖{�i�I���F�V���F�`�����A������14�y�[�W�ɂ킽���ĕt����ꂽ�q�����r���A���̖{�̊i����i�ƍ����炵�߂Ă���B�傽��Ώۂ͌Í��a�m�̐l���ŁA�����ɕ��ɖ����܂ޏo�ŎЖ���D�肱�ނ�����A�������s��ҏW�����s�����̉F�����\�\�F�V���F�����ژ^ COSMOGRAPHIA LIBRARIA�t�i�������s��A2006�N10��20���j�̕Ҏ[�҂����̂��Ƃ͂���i���̋��ق̖ژ^�̏����́A�F�V�́s���̉F�����\�\�R�X���O���t�B�A �t�@���^�X�e�B�J�t�ɂ��₩���Ă���j�B�q�����r�ɓo�ꂷ������邾���ł��A���̐l�����F�V�̊W���z������āA�����͐s���Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�g�������o�ꂷ��̂�17�ӏ��ŁA�g�s�~�V��Ƃقړ����ł���i���R�̂��ƂȂ���A�T�h��݂�y���F�A�O���R�I�v�A�������F�V���F�S�W�̕Ҏ҂�������ʂ��߂�j�B���́q�����r�ɓo�ꂷ��l���̂Ȃ����F�V��S�������e�o�ŎЂ̕ҏW�҂��܂܂��̂́A�������s����F�V�̒S���҂��������҂Ȃ�ł́A�Ƃ����悤�B�g�����͒}�����[�̕ҏW�҂ł��������킯�����A�{���ł͂��̑��ʂ͔����A�����蒇�ԂƂ����ʒu�Â����قƂ�ǂł���B�������āA�}���ł��F�V�S���͒W�J�~��Ƃ������ƂɂȂ�B�W�J���q�����r�ɓo�ꂷ��2�ӏ������悤�B�ǂ�����q��[�� �L���̉��ߖ@�r�́u�Q�b���a�\��N�^�w�v�l�̖�͊w�x�^�t�����X�E�X�y�C�����s�^���E���w�W���v�̍��ɂ���B
�@�k��㎵���N�l������\�����A�}�����[�́q���E���w�W���r�̍ŏ��̎��Ă��A���Ђ̕ҏW�ҒW�J�~��ɓn���Ă���B
�@�F�V���F��l�̍D�݂ɂ��҂܂ꂽ���E���w�S�W�Ƃ������̃v�����́A���Ƃ��Ƃ͒}�����[�T�C�h�����Ă��ꂽ�b�������B���͂��̔N�̏��߂�蓮�������A�ŏ��͑S�O�\�Z���̋K�͂ō\�z����A�̂��ɂ͓�\�����ɂȂ����B
�@�q�W���r�Ɋւ����F�V�̎��ẮA���̎����ɍ쐬���ꂽ�O�\�Z���Ă��͂��߁A�l�قǎc����A�������F�V�̎��̗��N�i��㔪���N�j�ɂȂ��āu�ʍ����z���w�S�@�F�V���F�X�y�V�����T�v�ɁA�W�J�̃C���^�r���[�ƂƂ��Ɍ��\���ꂽ�B�ЂƂ܂��̍ŏI�ĂƂ��ڂ����u��\�l�����āv�͕��ɖ{�i�w�������|��]�W���x�j�ɂ����߂��Ă��邩��A��㎵���N�i���a�\��j�\�ꌎ��\����̓��t�����u�S��\�����i���āj�v�̕��������ł͋����Ă������B�i�����A�O�ܔ��y�[�W�j
�@�\���l���A�g�������}�����[�̓����̒W�J�~��ƂƂ��ɗ��K�B�F�V�͋g�����D���ȃ|���m�����낢�댩���āA���̂��Ɗ��q�w�O�̓V�Ղ牮�Ђ�݂ŐH���������B�i���P�j�i�����A�O�Z�l�y�[�W�j
����ɁA�W�J�̖��O�͏o�Ă��Ȃ����A�u���́k��㎵���N�l�O���A�}�����[�́q�}�����E���w��n�r�ɁA�F�V��̃T�h�u�����̕s�^�v�������^�����B���E���w�S�W�ɃT�h���������̂͂��ꂪ���߂Ă��������A�܌��ɂ́A�u�k�Ђ����s���Ă����q���E���w�S�W�r�ɂ��A��͂�T�h�́w�H�l�����s�L�x�����߂��Ă���B�v�i�����A�O�O�y�[�W�j�́q�}�����E���w��n�r���F�V���T�h��S�������̂��W�J�������B�s�ʍ����z���w�t�̒W�J�̃C���^�r���[�L���́A�ҏW�҂Ƃ��ĂقƂ�Ǖ��͂��c���Ȃ������W�J�~��̐����Ȃ��،��ŁA�C���^�r���[���܂Ƃ߂��͓̂����ҏW�l�̓���v���낤�B���̕��́A�q���̃V�u�T���Ő��E���w�S�W�r�̖`���͂����ł���i�����́u�W�J�~��i�}�����[�ҏW�ҁj�v�Ƃ���j�B
�@�F�V���F�l�ҏW�ɂ�鐢�E���w�S�W�̊�悪�����뎝���オ�����̂��A�Â����Ƃł��̂Ő��m�ɂ͕�����Ȃ��̂ł����A���茳�ɂ���w���E���w�W���x�S�O�\�Z�����ĂɈ�㎵���N�������Ƃ������t�������Ă��܂�����A�����炭���̔N�̎n�߂���ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B
�@�����F�V����Ǝd���������Ă����������̂́A�����N�O�����s�́w�}�����E���w��n23�@�T�h�@���`�t�x�ɁA�T�h�̏����_�̐V�e�������������̂��ŏ��ł��B�l�I�ɂ͂���ȑO����A���Ԃ�w�_����فx�����肪�ŏ����Ǝv���܂�����ǂ��A���i�Ƃ����قǂł͂Ȃ��ł����A�F�V����̂������ɂȂ���͍̂D���ł悭�q�����Ă�����ł��B����ƁA���l�̋g���������̉�Ђɂ���ꂽ�����ɁA���͂��̕�����̉e���������Ԃ�܂��āA�������̂悤���F�V����Ƌg������͂��Ȃ�e�����F�l�W�ɂ���܂�������A���������Ƃ���ɘA�Ȃ����F�V�@�ɂ����������Ƃ����܂����B�]�k�ł����w�T�h�@���`�t�x������Ă����Ƃ��Ɂw�����̉h���x�S��̘b���o����ł��B�܂��Ă��Ȃ������ɂ́A�o���Ɗ�Ȃ������ƁA�璷�ދ��ȕ����Ƃ��邯��ǂ��A�����܂߂đS�āA�O���{���炢�̐^�����ȑ����̖{�ɂ��ďo�������ƁA�\��o�ł̌`�ɂ�����������̔��ɂ��Ђ�������Ȃ���Ȃ����A�Ȃ�āi�j������݂����Șb�������Ԃ����̂ł��B�i�s�F�V���F�X�y�V�����T�V�u�T���E�N���j�N���k�ʍ����z���w�C�l�t�A1988�N11��1���A��Z�l�y�[�W�j
�s�����̉h���t�̑S��̏��ȂǁA�W�J����́A�^�ʖڂȊ�����ď�k�������Ƃ��̂���������ۂ��ڂ����v��������ŁA���������B����1990�N7���A�g�����̎l�\����@�v�̂Ƃ��A���߂ĒW�J����ɂ��ڂɂ�����A�q�g���������r�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�N4��15���j��҂ލۂɂ́A�_�c���쒬���瑠�O�Ɉړ]���Ă����}�����[�ɒW�J�����K�˂āA���낢��ƕX��}���Ă������������̂��i�����ł́A���{���Y������b�������������j�B���āA3�y�[�W�ɂ킽��C���^�r���[�L���̂����܂��͂����ł���B
�@���������킯�ňꎞ�͏o�鐡�O�݂����ȕ��͋C�ɂ܂łȂ�����ł��B���O�ɉc�ƕ���ʂ��āA�����������̂̍D���ȏ��X����Ɉӌ������肵���Ƃ����A�����\�������������Ƃ��A���Ȃ�D���������Ԃ��Ă��Ă��܂������B����ŎГ��I�ɂ��]���͍���������ł����A����ŁA���댯�Ƃ������A�F�V����̖{�����݂̂悤�ɕ��ɂł�������o��Ƃ������ザ�Ⴀ��܂���A���ɓ���ȑw�Ɍ����ďo���S�W�Ƃ����C���[�W���ǂ����Ă�����܂��āA���������w�ɑ��Ă��������S�W�݂����Ȃ��̂������̂��ǂ����ƁB����ɓ�\�l���Ȃ�ŃX�^�[�g����ȏ�ǂ����Ă��Ō�܂ŏo���Ȃ��Ƃ����܂��A����͓����̏��ЂɂƂ��āA���Ȃ�̖`���ł����B���������Ǝv���܂����A�������N�̎����ɏ��Ђ͓|�Y����킯�ł��B����ȏ�Ԃ̂Ƃ��ɁA�Ȃ��Ȃ����������q���͏o���Ȃ��Ƃ������ƂŁA�ی��ɂ͂Ȃ�Ȃ�������ł�����ǂ��A���炭���s���݂��킻���Ƃ������ƂɂȂ�����ł��B��ЍX���@�ŎЋƍĊJ��������Ƃ����ɂȂ����܂܁A���Ƃ��Ă����������M�S�ɐi�߂Ă������������������o�����A�F�V����ɂ͔��ɐ\���킯�Ȃ����Ƃ������Ƃ����v��������܂����̂ŁA�����F�V�@������������������āc�c�B
�@���́A���̂����F�V���S���Ȃ��āA�Ƃ��Ƃ������ʂ����Ȃ������Ƃ����\���킯�Ȃ��C���ƁA�������������F�V����ɂ��肢���邱�Ƃ͓�x�Əo���Ȃ��Ȃ����̂��Ƃ������������Ȃ��C���Ƃ��ꏏ�ɂȂ�܂��āA���炩�̌`�ł�����o���Ȃ����Ƃ������Ƃ��A���܍l���Ă�Ƃ���Ȃ�ł��B���߂��F�V�u�[���Ƃ�������悤�ȏ���݂�ƁA�ނ��댻�݂̂ق����������₷���悤�ɂ��v���܂����ˁB
�@�Ƃ��낪�\�N�o�߂������߂ɁA�����͖{�M����ł����Ă��A���łɖ|�o�Ă��܂������̂Ƃ��A�����]�����ς�������̂Ƃ�������܂����A����ɂ��Ƃ���\�l���Ă��̂�Ƃ��Ă��A���߂ł͂��Ȃ葽���Ƃ�������������܂��̂ŁA�o����Ί����������̏\����\�܊����炢�ɍi�肽���B����������肪����܂��̂ŁA���̈Ă����̂܂�������ɂ́A��͂菭�X�����������ł��ˁB�������F�V����Ƃ��e�����A�ǂ������҂ł����炵���o���T�O����Ǝ푺�G�O����A����ɏ������Ⴂ�Ƃ���śܒJ���m����ɕҏW���͎҂Ƃ����`�ʼn�����Ă��������āA����Ή����ł̂悤�Ȍ`�Ŋ��s���邱�Ƃ��l���Ă����ł��B����������O������̈ӌ�����݂����Ȃ��Ƃ́A���łɎn�߂Ă���܂��āA���������F�V���������ł���A���������ł��낤�Ƃ������Ƃ�z�肵�A������x�̎�́\�\�܂����懁���͇��̇��ɂȂ�܂�����ǂ��\�\�������Ȃ����ƂŁA���s�������ق�̏��X�n�܂����Ƃ���Ȃ�ł��B�܂��A���ۂɂǂ��������̂ɂȂ邩�͕�����܂���ǂ��B���Ƃ��Ă��A���Ƃ�����ōߖłڂ��̉��\���̈ꂩ�͏o���邾�낤���Ȃ��Ǝv�����肵�Ă����ł����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iS63�E4�E25�@���_�c���쒬�A�}�����[�j�i���O�A��Z�Z�y�[�W�j
�g����1978�N7���̒}�����[�|�Y�̂��ƁA11���Ɉˊ�ސE���Ă��邩��A�Ɩ��Ƃ��ĒW�J�̊�������ˌ����邱�Ƃ͊���Ȃ��������낤�B�����ŁA�F�V���F���}�����[���犧�s�����������ꗗ���Ă������B�s�k�n��50���N�l�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�f�ڕ����A�����W���Ď����B
�E�i����͖|���j�W���x�[���E�����[���s�T�h��݁\�\���̐��U�ƍ�i�̌����k�}���p��172�l�t�i1970�N9��30���j
�E�i�ژ^�̍����ɂ́A�F�V���F�ł��T�h�ł��ڂ��Ă��Ȃ����j�s�}�����E���{��n 23�\�\�T�h�@���`�t�t�i1977�N3��30���j�ŃT�h�̍�i�q�i�ՂƗՏI�̒j�Ƃ̑Θb�r�q�����̕s�^�r�q聖[�N�w�r�q�ߎS����r�q�����_�r�A�W�����E�|�[�����ɂ��q�T�h��݂Ƃ��̋��Ǝ҂��邢��㵒p�S�̕r��|�A����q�T�h�\�\��ƘS���r�����M���āA�q�T�h�N���r��҂�ł���B
�E�s�T�h��݂̎莆�t�i���ŁF1980�N12��10���A�k�����ܕ��Ɂl�F1988�N1��26���j
�E�ҏW���� �o���T�O�E�푺�G�O�E�ܒJ���m�s�F�V���F���w�فt�i�}�����ژ^���s�����A�S12�������s���B�s��4�� ���[�g�s�A�̔��t1990�N5��21���A�s��5�� �Y杂̔��t1990�N5��21���j
���߂ās�F�V���F���w�فt�S12�����������Ɍf���Ă����B�l���͂��̊��̕҉���S���ҁB
�@�@���l�T���X�̔��i1993�N3���j�@�͓��p��
�A�@�o���b�N�̔��i1991�N6���j�@�K���ꔎ
�B�@�E���̔��i1991�N3���j�@�x�m��`�V
�C�@���[�g�s�A�̔��i1990�N5���j�@�ܒJ���m
�D�@�Y杂̔��i1990�N5���j�@�푺�G�O
�E�@�_���f�B�̔��i1990�N9���j�@�o���T�O
�F�@�~悂̔��i1991�N8���j�@�����N��
�G�@���I���̔��i1990�N6���j�@�o���T�O
�H�@�Ɛg�҂̔��i1990�N7���j�@���J����
�I�@���{�̔��i1990�N9���j�@�r���I
�J�@�V�������A���X���̔��i1991�N2���j�@�ܒJ���m
�K�@�Ō�̔��i1991�N10���j�@���R�r���Y
�F�V���V���ɖ��T�h�́q�����_�r�����߂��s�}�����E���{��n 23�t�t�^�i�v�͌���ł���j�́q�ҏW��L�r�ɂ͎��̂悤�ɂ���B�����͂Ȃ����A�W�J�~��̕M�ɂȂ���̂Ǝv����B
�@���҂������Ă���܂����攪�\��z�{���\�O���w�T�h�^���`�t�W�x�����͂����܂��B���̓�l�̏\�����I�̍�Ƃ��{���̂悤�Ȍ`�ŏЉ���̂͏��߂Ă̂��Ƃ��Ǝv���܂����A���Ƀ��`�t�E�h�E���E�u���g���k�ɂ��ẮA���̎�v��i���قƂ�ǂ��|��Ă��炸�A���{�ꕶ��������Ȃ��̂Ɍ����邽�߁A����̌���ł́u�Q�l�����v���������A����{���ő��p�I�ȃ��`�t�̑��я�点�邱�Ƃɓw�߂܂����B�Ȃ��Q�l�܂łɁA����v���ДŁw�p���̖�x�i�A�c�S����A���Z��N�j�̊����ɂ̓��`�t�̎�v����E�������ڂ̃��X�g�ƒ����̉�����t����Ă���A���c�k�쒘�w�邳�܂�x�i�l�����@�A��㎵�ܔN�j�ɁA�u���`�t�ƌC�t�F�e�B�V�Y���v�̕��͂����^����Ă��邱�Ƃ��L���Ă����܂��B����O�N�Ԑ��u�ɂȂ��Ă��܂����艿�����������Ē����܂����B���ʂ̎�����䐄�@�̏�A������ȏ��������B�x�X�̊��s�x�������l����ƂƂ��ɁA�ǎ҂̊F�l�ɂ͂��������̌�x���E�䈤�ǂ����肢�\���グ�܂��B�i���t�^�A��Z�y�[�W�j
�F�V���F����́s�T�h��݂̎莆�t�i1980�N12��10���j�́q���Ƃ����r�ɂ͎��̂悤�ɂ���B�Ȃ������̑����́A�̂��Ɋ��s�́s�F�V���F���w�فt�Ɠ��l�A�������ق�ł���B
�@���̎莆�̖|��́A��������}�����[�ŒP�s�{�ɂ���Ƃ����\��ŁA�G���u����v�z�v�̏��a�\�N�\��������\��N�������܂łɁA�\�O��ɂ킽���Ĕ�є�тɘA�ڂ������̂ł���B�������ʂ���Ă��ꂽ�y�Ђ́u����v�z�v�ҏW���O�Y��m����ɁA�S��肨���\���q�ׂ����B�P�s�{�ɂ���ɓ����ẮA�ǂ��������q�`���ɂ�����悩�낤���ƁA�S���̒W�J�~�ꂳ��ƂƂ��ɂ����Ԃ�Y�܂������̂ł��邪�A���ǁA���̎莆�̖����ɒ�������Ƃ����A������O�Ȍ`���ɗ��������B���̒x�M�̂��߁A���̒�������Ƃ�����Ƃɂ��ӊO�Ɏ�Ԃǂ��āA�Ƃ��Ƃ��ŏ��ɖ|��̕M���N����������A�ܔN�߂����̍Ό������ꋎ���Ă��܂����B���̊ԁA�I�g���炴�鉷�e�ő҂��Ă��Ă��ꂽ�W�J����Ɋ��ӂ���B���̎d�������ɂƂ��Ċy�������̂ł����������ɁA���ӂ̎v���͐[���̂ł���B
�@�@�@���a�\�ܔN�\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�V���F�i�����A��O�O�y�[�W�j
���s�̎����Ƃ��ẮA��L�F�V�֘A��2���̂������ɋ��܂邩�������ɂȂ邪�A�@���d�F�s�f���̎��w�t�i1979�N2��15���j�́q���Ƃ����r�ɂ͎��̂悤�ɂ���i�����A���܁`���Z�y�[�W�j�B
�@�k�c�c�l���߁A�\������n���[�h�E�z�[�N�X�_��t���b�c�E�����O�_����F��ς����ɎƂ��Ă����ҏW�҂Ɍb�܂ꂽ�Ƃ����̂́A�قƂ�NJ�ւɓ��������Ƃ��Ǝv���B�܂��A�O���w�������{��_�x�ɑ����ď����ɂ܂Ƃ߂邳���̔ώG�Ȏd����S�����ꂽ�}�����[�̒W�J�~��A�������\������y�[�W�̂��݂��݂ɂ܂ő@�ׂȐS����������đՂ�������̒������ق�̗����́A���̊�ւɊm���ȗ֊s��^���ĉ��������B����C�ԂȂӂ�܂��ɂ���čD�ӂɊÂ��Â����������A���܂��犴�ӂ̋C���������ȂǂƏ����̂��C���Ђ���̂ŁA���̋C���͂����Ƌ��̂����ɂ��܂�����ł����B
�@�k�c�c�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎵���N�Z���@�@���d�F
�@���炭���f����Ă����}�����[�̏o�Ŋ������ĊJ����A�Z�����̒i�K�Ŗ����Ă����w�f���̎��w�x�����̏����ɂȂ肻�тꂽ���Ƃ��A�����Ɋ�т����Ǝv���B��͂�A����͍K���ȏ����Ȃ̂��B�k�c�c�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��㎵��N�ꌎ
�ӂ��̓��t�̂������ɁA�W�J���k�b�ŐG��Ă����}�����[�̓|�Y�i1978�N7���j���������B�����Ř@���d�F�̑O���s�������{��_�t�́q���Ƃ����r�����悤�B�����̒P�s�{��1977�N5��19���̊��s�����A�ŐV�ł́k�����܊w�|���Ɂl�i2009�N7��10���j��������B�Ȃ��A�����ɂ͒E�e���Ǝv�����u��㎵���N�O�������v�̓��t������B
�@�����Ɂw�������{��_�x�Ƃ��ēǂ܂ꂽ�����́A���̕M�҂̏������Ƃ���ӎu�Ƃ͂قƂ�ǖ����̏�ŏ����������Ă��܂������̂悤�Ȍ��t��������Ȃ肽���Ă���B�����������Ƃ��������̒���ɂ܂Ƃ߂悤�Ƃ���C���͂Ȃ��������A���܂Ȃ����̋C���͂���߂Ċł���B�u���́v�ɂ�����u�p�X�J���ɂ�������āv�́A�}�����[���s�̌������w���ꐶ���x�̂��߂ɁA�ҏW���̒W�J�~�ꎁ�̂������߂ɏ]���āA������̂���Ŏ��M�������̂ł���B���ꂪ���ڂ̌_�@�ƂȂ�A�����ɈȌ�O��قǁA�܂��y�Ђ̌������w����v�z�x�Ɂu���ƂƂ��Ƃv�Ƃ��ď\���قǁA���̂Ǎ��x��������ŏI�肾�ƌ��ɂ��Ȃ��珑�������Ă��܂����B�ҏW��S�����ꂽ�}�����[�̋v�ۓc���A���c�|��Y�̗����A�Ȃ�тɐy�Ђ̎O�Y��m���ɂ́A���܂������ď����̂��������Ƃ낤�Ƃ��Ă��錾�t�����̐��a�����ӂ��ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ�����݂��܂����C���������ׂ����m��Ȃ��B�����������X�Ƃ��������Ă��邤���ɁA���������̌��t�������߂Ƃ��Ă��܂����Ƃ����̂������Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��ŁA���́w�������{��_�x�́A��Ȃ����ł��܂��M�҂̈ӎ����h�����Â��Ă���B�����Ȃ���A�������̂悤�ɂł��������Ă��܂��������Ȃ̂ł���B���̖��̂悤�ȑ̌����Ƃ��������������Ă�����ʂ����Ƃ��A���̖����͂��߂���I��܂Ō��܂����ĉ��������W�J�~�ꎁ�ɂ́A��t�ɕ�����ׂ����҂̎ӈӂ��Ƃ��Ă���������Ǝv���B�v�ۓc���A���c���A�O�Y���ɕ�������̂��A��͂薲������߂����҂̎ӈӂł���B
�@�����������X�̗��������̂��ƂɁA�����܂������܂��Ƃ��ď����Ă��܂������t�́A����܂ŕM�҂��������A�������Ƃ��ď��������̂��A�y���ɍD�ӓI�Ȕ�����ǎ҂̕��X�̂����Ɏ�N���邱�Ƃ��ł����B�G���f�ڒ�����A���邢�͒��ړI�ɁA���邢�͊ԐړI�ɔᔻ���������������X�ɂ́A�������Ĉ���ɂ܂Ƃ߂����Ƃł��̂��C���ɉ����������ǂ����B�������A����ɗނ��镶�͂͂��͂��x�Ə����܂��Ƃ����ӎu�����́A��������߂����܂��������Ɏc���Ă���B���̈ӎu���A����A�ǂ̂悤�Ȗ��Ƒ�������̂ł��낤���B�Ȃ��A�u�I�́v�́u�킪���U�̋P������v�́A�o���̌�ɖ���̕킵����������ꂽ���̂ł���B�i�����A�O�O�O�`�O�O�l�y�[�W�j
���ꂪ�S���ł���B�܂��A�k�����܊w�|���Ɂl�ł̊��s�ɍۂ��Ă��A�������炢�̕��ʂ̂��Ƃ������V���ɕt���ꂽ�B�����Ɂu��Z�Z��N�܌��O�\����^���ҁv�Ƃ���q�����܊w�|���ɔł��Ƃ����r�̍ŏI�i�����������B
�@�Ō�ɂȂ��Ă��܂������A�u�����ܕ��Ɂv�Ŏ��^�́u���Ƃ����v�ɋL�����l�l�̕��X�ɉ��߂ĎO�\��N��̌��̐S�������肽�����A����ҏW��S�����ꂽ�}�����[�ҏW�ǂ̓V��T�q����ɂ��A����ɗ��ʊ��ӂ̎v���������点�Ă��������B�i�����A�O�O�Z�y�[�W�j
�����Łs�}�����[�}�����ژ^�t�f�ڂ̘@���֘A�̏��Ђ��݂Ă������B
- �i�A�����E���u���O���G���A�V��ޓ�Y�Ƌ���j���N�}���G���o�[�g�Ł@�s�ł̏��\�\�V�l�����}���i1969�N2���B�@���͊����Ɂq�w�s�ł̏��x�܂��́A���錵���ȞB�����̉r�Ƃ������͂������Ă��邪�A����͉���ł���A�̂����邠�Ƃ����͂Ȃ��j
- �������{��_�i1977�N5���j
- �f���̎��w�i1979�N2���j
- �\�w��]�錾�i1979�N11���j
- �ē� ���È���Y�i1983�N3���j
- �\�w��]�錾�k�����ܕ��Ɂl�i1985�N12���j
- �������{��_�k�����ܕ��Ɂl�i1986�N3���j
- �i���c�Y�t�Ƌ����j���È���Y����k�����~�G�[���p���l�i1989�N6���j
�����ŔN��͔�ԁB�@���d�F�̎咘�s�w�{���@���[�v�l�x�_�t�i2014�N6��25���j�����́q�������̎ӎ��\�\���Ƃ����ɂ����ā\�\�r�ɂ͒W�J�~��̂��Ƃ��~�~�L����Ă���B�����Ȃ邪�A�������s�̌o�܂�m�邤���ł����p���Ă��������B
�@�w�u�{���@���[�v�l�v�_�x���M�̂��߂ɕ��ނ���Ă������̂��鉽�����̎����̒��ɁA���Ҏ��g�̕M�Ղł͂Ȃ������̏������܂ꂽ�ꖇ�̎��Ђ��t�@�C������Ă���B��s�ڂɁu�@���d�F�w�{���@���[�v�l�x�_�v�Ƃ����薼�炵�����̂̋L���ꂽ���̉��r�̃��|�[�g�p���ɂ́A���҂��w�{���@���[�v�l�x���߂����Ă���܂łɔ��\������т̃e�N�X�g�\�\�K�������A���ׂĂł͂Ȃ��\�\�̑薼���A���\�}�́A���\�N���A�l�S���l�ߌ��e�p���Ɋ��Z���ꂽ�����ȂǂƂƂ��ɂ������V�ɓ�s�����ɗ���Ă���A���̎��_�ł̌��e�����͍��v�Łu739�v���A���Ђ̉E���ɂ́u89.10.9�v�Ƃ����N�����炵�����̂������Ɠǂ߂�B
�@���o���̂��邻�̕M�Ղ��N�̂��̂��́A�������܌��������B���ꂪ�w�������{��_�x�i1977�j���炢���҂̏�����S�����Ă���ꂽ�}�����[�ҏW���̒W�J�~�ꎁ�̂��̂ł��邱�ƂɁA�^���̗]�n�͂Ȃ�����ł���B�����A��㔪��N�\������Ƃ������t�������̎��Ђ�����ړI�Ƃ��ď����ꂽ���̂��́A�܂����������ĕs���Ƃ����ق��͂Ȃ��B��㔪��N�Ƃ����A�ꌎ�����܂ł͂܂�����Ȃ����a�Ƃ����N���œ��X���������Ă����N�ɂ������Ă��邪�A���炩�̈Ӗ��ŏے��I�Ƃ������邻�̔N�̏H�ɁA�w�u�{���@���[�v�l�v�_�x�̊�悪�A�}�����[�̉�c�ŋc�_���ꂽ�̂��낤���B�ǂ��������Ƃ͎v���Ȃ��B�킽�������I�v�_���ȂǂŁw�{���@���[�v�l�x��_���n�߂��̂́A���Z�N��̂͂��߂̂��Ƃ�����ł���B���Ƃɂ��ƁA�Ƃ��̐̂ɉ�c�ŗ�������Ă������̊��̎��������߂ċ������Ȃ����ړI�ŒW�J�����҂ɒ��ꂽ���̂������̂�������Ȃ��B�Ƃ͂����A���ꂪ�A���A�ǂ��ŁA�����Ȃ�̂��ƁA�ǂ�Ȍ��t�ł����炳�ꂽ�̂��Ƃ����ڍׂ́A���܂��̏����̒��҂ƂȂ肨����������̒j�̋L������A���ꂢ�����ς艓�������Ă���B
�@�}�����[�ɓ��Ќ�̊Ԃ��Ȃ������ɁA��_�ɂ��w�t���[�x�[���S�W�x�i1965-1970�j����悵�A������݂��ƂɎ������ꂽ�W�J����ɂ��Ă݂�A���̌�A�w�{���@���[�v�l�̎莆�x�i�H���f�q�Җ� 1986�j��l�E�o���K�X�������TMario Vargas Llosa�́w�ʂĂ��Ȃ������\�\�t���x�[���Ɓu�{���@���[�v�l�v�x�i�H���f�q�� 1988�j�Ȃǂ̕ҏW�ɂ������ꂽ�悤�ɁA���{�l�ɂ��w�u�{���@���[�v�l�v�_�x���M�����҂��Ă���ꂽ�̂�������Ȃ��B���̖����̒��҂̈�l�Ƃ��āA���̑O�N�Ɂw�}�f�Ȍ|�p�Ƃ̏ё��\�\�}�N�V���E�f���E�J���_�x�i�y�� 1988�A�����܊w�|���� 1995�j���A�ڂ̂̂��ɏ㈲���Ă����킽�������A���낻��t���[�x�[���̍�i���܂Ƃ��ɘ_���ׂ��Ƃ������Ă���Ɗ����n�߂Ă����̂��Ǝv�����A���̂�����̑O��W�������ɂ��ǂ蒼�����Ƃ́A���܂̒��҂ɂ͂قڕs�\�Ƃ����ɋ߂��B
�@�H���f�q����ɂ��w���������̃��g���b�N�\�\�u�{���@���[�v�l�v��ǂށx�i������w�o�ʼn�j�͈��㔪�N�ɁA���V�a�G���ɂ��w�u�{���@���[�v�l�v��ǂށ\�\�����E���K�E�f���N���V�[�x�i��g���X�j����Z�Z�l�N�Ɋ��s����Ă���̂ŁA���{�ɂ�����w�u�{���@���[�v�l�v�_�x�́A���鎞���Ɋm���Ȑ��ʂ������������Ƃ����Ă悢�B�ɂ�������炸�A�킽�������g�ɂ��w�u�{���@���[�v�l�v�_�x�̊����ɂ́A�N�����肩�ł͂Ȃ����̐�������O�\�N�]�̍Ό�����₳��Ă��܂����B�l�����I�ɂ͂ƂĂ������܂�̂��ʂ��̎��Ԃ͌����ĒZ�����̂Ƃ͂����܂����A�����Ȃ炴������Ȃ�����������A�����ł��ƍׂ��ɏq�ׂ邱�Ƃ͂����ɂ����B�����A���̊ԂɒW�J���͒}�����[���N�ސE����k�Έ�M���q�}�����[�\�\�Ō�̎d���r�i�sAERA�m�A�G���n�t1996�N5��6���E13���������j�ɂ��A1996�N3��29���i���j�j���Ō�̏o�Γ��������i���Q�j�l�A�W�J���ƂƂ��Ɂw�ē� ���È���Y�x�i1983�j�̕ҏW�ɂ�����ꂽ�ԋ{���F���Ɋ�悪���ꂽ���Ƃ͏����Ă����˂Ȃ�܂��B
�@�����E��łȂ��炭�ꏏ�Ɏd�������ꂽ�W�J����Ɗԋ{����Ƃ͏\�߂��N��̍����������Ǝv�����A��w����̐�U�͂����܂ł��Ȃ��A����l�����܂������قȂ邢���ɂ��Ɠ��ȕҏW�҂��Ƃ����Ă悢�B����ł��Ȃ���A���̂���l�ɂ́A����ے肵���������ʓ_�����Ȃ���Ă����B�҂��Ƃ��������������Ƃ�ʁA�����ɂ����������͂�������������̂ł���B�W�J�������������悤�ɁA�ԋ{������Y�ꂩ���Ă�������s�ӂɓd�b�������ĉ�����A����Ƃ����Ă������Ă镗����Ȃ��A���낻�낢�����ł��傤���ƐÂ��ɂԂ₩���B�͂������������ɂ͏o��Ȃ������ɂ�������炸�A���̂Ԃ₫�������ǂƂȂ�����Ԃ��ꂽ�W�J����Ɗԋ{����ɁA�܂��A�S����̊��ӂ̔O����������B�i�����A����O�`����܃y�[�W�j
�ȏオ�`����2�y�[�W���ŁA�����Ɂu��Z��l�N�l���Ȃ��̂��Ɓ^���ҁv�Ƃ��铯���́A�S����12�y�[�W������B�@���́q�������̎ӎ��\�\���Ƃ����ɂ����ā\�\�r������قǒ����������̂͂ق��ł��Ȃ��A���͖S���W�J�~��i���͒W�J����̎���ܒJ���m����́s�F�V���F�_�R���N�V�����t�i���R�j�œǂނ܂Œm�炸�ɂ����j�̎��т�����Ă���قǂӂ��킵�����͂͂ق��ɂȂ����낤����ł���B���Ƃ��A��f���Ɍ�����s�ē� ���È���Y�t�i1983�N3��30���j�́q���Ƃ����r�\�\�����Ɂu��㔪�O�N�^���ҁv�Ƃ���\�\�̍Ō�̒i���́A���̂悤�ɂ����Ə�����Ă���B
�@�S�т͐V���ȍ\���̂��ƂɑS�ʓI�ɏ������߂�ꂽ���̂��Ƃ͂����A���̘_���̎��ƂȂ����̕��͂����\���ꂽ�G���i�k�c�c�l�j�̕ҏW�ɂ�������������X�Ɋ��ӂ������B�ʐ^�⎑�����ɂ��A�t�B�����Z���^�[��x�ؕۘY�����͂��߁A�����̕��X�̖����̒g�����͂��B�ҏW��S�����ꂽ�}�����[�̒W�J�~��A�ԋ{���F�̗����Ȃ�тɑ���̒������ق鎁�̏��͂ɂ́A�����̂��ƂȂ���A�S����̊��ӂ̋C������������Ǝv���B���܁A�������čŌ�̌��t���������߂Ȃ���A��\�N�O�̓~�̌����̓S���x���`�̗₽�����A���߂č��̉������݂������Ă���B���È���Y�́A�킽�����ɂƂ��āA�����Ď���ł͂��Ȃ��B�i�����A�Z�`��y�[�W�j
�u��\�N�O�̓~�̌����̓S���x���`�̗₽���v�Ƃ����̂́A1963�N��12���A�ٍ��̒n�ɂ����ď��Â̎����V���������́u�z�̍������Ƃ��Ȃ��I�낤�Ƃ������̊����ŗ₦�������S���̃x���`�v�i�q���� �V�Y�̋K���r�A�����A��y�[�W�j�œǂ��Ƃ��w���B���̗₽���ƁA���҂��ΏۂɊ�z���̔M���̑Δ�͈��|�I���B�����Ă���������̌`�ɂ��ׂ��x�����̂��A�}�����[�̒W�J�E�ԋ{�E������3�l�������B������20�N��Ɂs�ē� ���È���Y�k���⌈��Łl�t�i2003�N10��10���j�Ƃ��čĊ����ꂽ�B�����Ɂu��Z�Z�O�N��������v�̓��t�̂���q���⌈��ł��Ƃ����r�͂����n�܂��Ă���B
�@���ׂĂ͌����́u���Ƃ����v�ɂ���������Ă���A�q���⌈��Łr�̊��s�ɂ������ĐV���ɏ���������ׂ����Ƃ͂����킸���Ȃ��Ƃ���ɂ��Ă���B���̊ԁA���c�Y�t������������߂��݂ɂ��Ắu��\�N��ɁA�ӂ����сv�ɂ��G�ꂽ���A����ɗ��ʑr���Ƃ��āA�w�ē� ���È���Y�x�̎��M���A�Ŏx���Ă��ꂽ�W�J�~�ꎁ�����łɒ}�����[��ސE���Ă�����Ƃ������Ƃ�����B�O�l�A���́q���⌈��Łr�̕ҏW���ԋ{���F���̎���킸��킹�A����ɓ����������ق鎁�̂��͂�q���邱�Ƃ��ł����͍̂K�^�������B�����Ɍ��\���グ�鎟�悾���A���̎v�����W�J���ɂ��Ƃǂ��ƔO���Ă���B�i�����A�O�l�l�y�[�W�j
�q�������̎ӎ��\�\���Ƃ����ɂ����ā\�\�r�ɓo�ꂷ��H���f�q�Җ�s�{���@���[�v�l�̎莆�t�i1986�N7��20���j�́q���Ƃ����r�ɂ͎��̂悤�ɂ����i���S�j�B
�@���̖{�ł́A���i�ɑ傫���]�����Ƃ�A�����ɕK�v�Ȓm����₤���߂̃����A�̒��q�m�g�[���n���߂邽�߂̂��܂��܂̎�|��Ȃǂ��������B�܂������X�y�[�X�ɁA��i�̎莆���Ɋւ���lj��⒍�߂��L���A���̎莆���Ƒ��̃e�N�X�g�������킹���ꍇ�ɐ�����ł��낤���߂̉\������������悤�ɂ����B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@�t���x�[���̎莆�ɂ��ẮA�}�����[�t���x�[���S�W�̖|��Ɩ��瑽���̂��Ƃ�������ꂽ�B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@���̏���Ȋ�]�ɐh�����������X���A���������낢��Ɨ^���ĉ��������}�����[�̒W�J�~�ꂳ��A�����S�����ĉ��������������ق邳��ɐS���犴�ӂ������܂��B�i�����A�O�O��`�O�O�O�y�[�W�j
���i�X�y�[�X�ɑ傫�Ȕ�d�����������̃��j�[�N�ȔŖʁi��i9�|28���l�E���i8�|22���l�j�́A�ҏW�S���̒W�J�Ƒ��{�S���̒����ɂ��݂��ƂȐv���Ǝv���B��������A�l�E�o���K�X�������T�i�H���f�q��j�s�ʂĂ��Ȃ������\�\�t���x�[���Ɓw�{���@���[�v�l�x�k�}���p���l�t�i1988�N3��25���j�́q��҂��Ƃ����r�͍Ō���������߂������Ă���B�u���̕]�_�̖|��������߂ĉ��������c��m�搶�A�}�����[�̒W�J�~�ꂳ��A�����ĕҏW��S�����ĉ�����������V����ɁA�S���炨��\���グ�܂��B�v�i�����A��㔪�`����y�[�W�j�B���Ȃ݂ɁA�c��m�́s�t���[�x�[���S�W�k�ʊ��l�t���[�x�[�������t�i1968�N6��15���j�́q����r�������Ă����B�s�ʂĂ��Ȃ������t�́s�t���[�x�[�������t��20�N��A�y���[�̏����Ƃ̕M�ɂȂ镶�|�]�_�Ƃ��āA�W�J�~�ꂪ���琄�i�����Ō�̃t���[�x�[���W�̏����ƂȂ����B�ےJ�ˈꂪ�ŔӔN�ɕ҂s���y�Ƃ��Ă̓Ǐ��m�C�O�сn�k�����ܕ��Ɂl�t�i2012�N5��10���j�ɂ́A�s�{���@���[�v�l�̎莆�t�Ɓs�ʂĂ��Ȃ������t�i�ƁA����͏��������A�W�����A���E�o�[���Y�s�t���x�[�����_���t�j�̏��]�����^����Ă���B�W�F�C���Y�E�W���C�X���ےJ�䂦�A�W���C�X�̎t���ւ̊S�������Ȃ�ʂ��̂��������A�ƌ����ׂ����낤�B
���Y���P�s�f��n-1�t�i1987�N5��15���j�̊����ɒu���ꂽ�q�t�̘_�\�\�f��I�����Ƃ��̈ى��r�i���o�́s�����C�J�t1983�N5�����k���W���S�_�[�� �f��̖����l�j�̖`���\�\�����o���u���@�Ԃ����̖����邢�͉f������Ɓv�Ƃ���i�\�\�́u�����ɂ��Ė������B�v�i�����A�܃y�[�W�j�Ƃ����ꕶ�Ŏn�܂�A�������܋g�������W�s�Õ��t�̎��сq�ߋ��r�ɐG��Ă䂭�B���āA���̖����Ɂu��㔪���N�O���^���Y���P�v�Ƃ���q��L�r�ɂ͎��̂悤�ȉӏ�������B
�@�k�c�c�l�܂�Ƃ���A�f��́u�����v�Ɓu�͑��v�̑̌��Ƃ��ĕM�҂̓�\��Ɛ茋��ł����̂��ƌ�����B���̂��Ƃ̈Ӗ��́A�܂��M�Ҏ��g�ɂƂ��Ă��𖾂�������Ȃ��܂܂ł���B
�@���܁A�q�b�`�R�b�N�Ƌg���������[����[�܂ō����ɓǂ݂�������ł��̂����琢�E�̂��ׂĂ��ǂ݉�����͂����ƁA��������v���߂Ă����\���̏��N���v���o���Ă݂�B�܂��ƂɁA���m�}�j�A�b�N�ȕn�����t���������Ă����̂ł���B�k�c�c�l���̒��ɂǂ����Ă���Ȑ������Ɓm�A�A�n���N����̂��ƕ�R�Ƃ��Ȃ���A���������w�k�k���ɐi�H�����x��w�m���x�łȂ���Ζ�����������Ȃ��Ƃ��������X���������Ă����̂ł���B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@�����Ă��炶�炵���͂Ȃ����ӂ̎v������������ׂ��́A�܂��A�~���Ђɂ��炵�����ɖ{���̑c�^���Ă��Ă��������������x�Y���ɑ��Ăł���B�{���̎�q�́A���̔M�ӂ���ϜȂɂ���Ĕd���ꂽ���̂��B�����ĂقƂ�ǔ��肵�����Ă������̎�q�́A�������̂t�o�t�ւ̈ڐЂ̌�������āA�}�����[�ҏW���̒W�J�~��A����V�����̎�ŒO�O�Ɉ琬����A�������A�����ɂ悤�₭�������Ԃ��ƂɂȂ����B���̉ʎ��������Ԃ��ꂵ���Ȃ����̂ƂȂ肦�Ă���Ƃ���A����͗����̑@�ׂ����͓I�ȃG�f�B�^�[�V�b�v�ƁA�������ق鎁���{���ɗ^���Ă������������o�I�E�G�o�I�Ȑ����̎����ł���B�Ƃ�킯�����ɂ́A�����쐬�ȂǔώG�Ȏ����ʂł����Ԃ����f�������������B�܂��A�ʐ^�\���ɂ������Ĕ~�{�m��A���c���A�v�ۓc�Y��Ƃ������F�l���������Ă��ꂽ�����̏��͂�Y���킯�ɂ͂����Ȃ��B�{���̐��������̑��݂ɑ����ꏭ�Ȃ��ꉽ�炩�̂��̂��Ă���n-1�l�̐l�X���ׂĂ̖��O�������邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����ȏ�̕��X�ɁA��\���ĕM�҂̊��ӂ̔O������Ă����Ă������������Ǝv���B
�@���Ƃ͂����A���̏�����n-1�l�̓ǎ҂Ƃ̊ԂɍK���ȏo���̌����邱�Ƃ��肤�������B�i�����A��ܘZ�`����y�[�W�j
���Y�̂��̉f��_�W���́A�g���́s�Õ��t�Ɏn�܂��ās�m���t�ɏI���A�ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ��B
�����O�Y��s�}������ ���ƎU���k�}���p���l�t�i1987�N7��31���j�̖�҂ɂ��q���Ƃ����r�́A���̂悤�Ɏn�܂��Ă���B
�@�u�R���p�N�g�Ȉ���{�Ƃ����`�ŁA�}����������{�̓ǎ҂ɏЉ�鏑�����ł���Ƃ�낵���̂ł����c�c�v
�@�ዾ�̉��łЂ��ނ��Ȗڂ����������ƌ��Ȃ���A�Â��Ȍ����ŁA���̌��t���q�ׂ�ꂽ�̂��A���������Ė{�������܂�o�邱�ƂɂȂ������������̎��̂͂��܂�Ȃ̂����A����͂������M��w���@�����[�S�W�x�̊��s���������ԋ߂ƂȂ��Ă������̂��Ƃł��邩��A�ЂƐ̈ȏ�A�����炩�ꂱ��\�܁A�Z�N�قǂ��O�̂��Ƃł��낤�B���̂Ƃ��́A���@�����[�̖�e�̂ǂꂩ�ڂ��n�����邽�߂ɁA���S�W�̕ҏW�S���҂ł���}�����[�̒W�J�~�ꎁ�ƁA���̋Ζ���ɂقNj߂��i���X�ɗ��������āA�b�肪���܂��܃}�������̂��ƂƂȂ�A���������u�}�������蒟�v�Ƃ������A���̎��l�̗��n�}�߂������e�̏������쐻���閲�����ꂱ�������Ƃ���A�W�J���͑�Ԃ�̍��v�̎蒟���Ƃ�o����āA���̂Ƃ�Ƃ߂��Ȃ��b�̗v�_�������Ƃ߂��A���̗g��A�`���ɋL�����悤�Ȃ��Ƃ�����ꂽ�̂������B�k�c�c�l�i�����A���O�y�[�W�j
7�y�[�W�ɋy�Ԃ��́q���Ƃ����r�́A���̂悤�Ɍ���Ă���i�����ɂ́u��㔪���N�O���^�����O�Y�v�Ƃ���j�B
�@�u���Ƃ����v�̏��߂ɋL�����ʂ�A�{���̔��Ĉȗ��A���ɒ����Ό����߂����������A���̊Ԗ�҂̓x�d�Ȃ��Ԃ������e��ĉ��������A�ƍ��X�����̂����������قǁA�I�n�h���������₩�Ɂi�����H�ɂ͌������j������ĉ��������W�J�~�ꎁ�ɂ͉��߂Ă����\���グ�����Ǝv���B�ŋߓ�{���V���̖���ɂ��w�W�b�h�����@�����[�������ȁx�i�ނ��떼���Ə̂Ԃɂӂ��킵���w��I�J��j���Ō�ɁA���@�����[�Ƃ�������ȑ��݂���{��ɈڐA����Ƃ�����d���𐋂Ɋ����܂Ŏx��������ꂽ���̖��ҏW�҂́A�M���ۂ������̏�������荇���������Ƃ͈قȂ��ē����ɔ������̂̑��������e�ɐڂ���ɂ��A���͍Ό��̑��̑����ƌȂ�̋����̒x�X���邱�ƂƂɕ���ʂĂĂ��邪�A���͂����ɑ���o���{�������߂āA�}�������ɊS��������鐢�̓ǎ҂̕��X���ւ��Ȃ�Ƃ��L���}��������邱�Ƃ��Ђ�����F�����ł���B�i�����A��`����y�[�W�j
���s�̎����͑O�シ�邪�A��{���V��s�W�b�h�����@�����[�������� 2 1897-1942�t�i1986�N10��25���j�́q��҂��Ƃ����r�͂�������Ă���i�����ɂ́u��㔪�Z�N�����A�p�����k�x�R�����u�Ł^��{���V�v�Ƃ���j�B
�@�{����|��@���^���ĉ����������쏺�������A�W�b�h�ƃ��@�����[�̑��݂�傫�ȗ��j�̗���̂Ȃ��ɂ����A���݂̃t�����X�Ƃ����т��镶�͂��ĉ��������B���x�[���E�}���̏����Ɍ����Ă�����ʂ��������ĕ��ꂽ���Ƃ��A�S���炠�肪�����v���Ă���B
�@�܂��A���@�����[�̏��Ȃ̖|��ƒ����Ɋւ��A�����O�����A�Ő�[���s�����@�����[�����ƂƂ��Ă̊w���������݂Ȃ��������^���ĉ��������B���̉������Ȃ�������A���̏��ȏW�́A�Ƃ����Ƃ��Đ��ɂł�Ƃ���ł������B�[�����ӂ��Ă���B
�@�t�����X�ł́A�u���{��ł����E�ň�Ԋ����ȔłɂȂ�܂��ˁv�ƌ����ė�܂��Ă��ꂽ�J�g���[�k�E�W�b�h�v�l�A�k�C�C�s�̎���ʼn���ƂȂ��A��҂̎���ɓ����A�v���o������Ă��ꂽ�A�K�g�E���@�����[�����A�[���v�l�A���̓���Ƌ��ɁA�������Ȃ̉{����F�߂Ă��ꂽ�W�b�h�̎莆�̏��L�҃����T�b�h���A�h�D�[�Z���ɂł̎d���̕ւ��͂����Ă��ꂽ�t�����\���E�V���|���ْ��A����ɁA�\���N���A���T�̂悤�ɖ�҂̐����薳���^��Ɍ������ĂĂ��ꂽ�}�K���E�r�������v�l�ɂ����\���グ��B
�@�Ō�̍Ō�ɂȂ��Ă��܂������A�m���}���f�B�[�̓����̂悾��̂悤�ɁA�ی����Ȃ����炾��Ƒ�����҂̎d�����A����Ȋ���������Ɂi����́A���ۓd�b�̂����ŁA�����Ȃ������Ƃ������Ƃ�������Ȃ��j�A�������A���߂�Ƃ���͒��߂āA�`����ĉ��������W�J�~�ꎁ�ɂ́A����̌��t���Ȃ��B�i�����A�܈�܃y�[�W�j
�������ɂƂ��ĒW�J����́A�����܂ł��g�����̒}�����[�ł̌�y�ł���A�g����1978�N11���ɓ��Ђ�ނ������Ƃ́A���l�E�g�����̒S���ҏW�҂������B���Ƃ����Ɍ���W�J�~�ꑜ�̋ɂߕt���́A�����܂ł��Ȃ��g����2���̎U���W�ł���B
�@�@�@�@�@18
�@�u�������̂܂��ɂ́A�����y���F�̂悤�Ȕj�V�r�Ȑl�Ԃ������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B���̎����{�����オ���A�ނ��܂���̓V�˂ł����B�v�i�F�V���F�j
�@���̓y���F�̈╶�W�w���e�̐�x�̊��s�����ɎQ�悵�A�o�ŎЂ��}�����[�Ɍ��܂�A���ׂ̉����肽�B��N�̏t�̂��Ƃł���B���ꂩ��Ԃ��Ȃ��A�ݎЎ���̌�y�̒W�J�~�ꂪ�V�тɗ��āA�������܂łɓy���F�֕��������тƁA�U���A����Ɏ�̏������̕��͂������āA�����Ȗ{������܂��傤�A�ƌ����̂������B���ނ��ɂ��킹�A�B���ȕԎ��������̂������Ȃ������B��Ђ̐����Ȋ��ɂ̂��Ă��܂����̂ł���B
�@�k�c�c�l
�@���͖��f�ł���߂Ēf�ГI�ɁA�����̕��X�̕��͂��u���p�v�����Ē������B�����A�����e�̂قǂ��B�F�l�ɐ[�����ӂ������܂��B�܂��L�������Ɋ��ʂ��Ă��Ȃ��䂦�A���������M�d�ȁu�،��v���A����������Ǝv���邪�A����������Ē��������B�����炭�A�W�J�~��̜ϜȂ��Ȃ���A���̏����ȏ����͍���Ȃ����������m��Ȃ��Ǝv���B
�@�k�c�c�l
�@�@�@�@�@�P�X�W�V�N7��28���@�@�@�@�@�@�@�@�g�����i�q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�A�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�A1987�N9��30���A��l�Z�`��l��y�[�W�j
�@���x�A�W�J�~��̐s�͂ŁA�u�}���p���v�̈���Ƃ��āA�Ċ�����邱�ƂɂȂ����B���ẮA�ӂɂ݂��Ȃ��ܕт��Ȃ����B�u�p���v�ɓ��������ƂɈ˂��āA���̏������A�����炩�́A�L���ǂ܂�邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
�@�k�c�c�l
�@���̔��N�Ԃɏ��������͂́A�킸���ɕS�\�����炸�ł���B��������u���픽�f�̋L�^�v�ɂ����Ȃ����̂��肾�B���₵�āA�ŏI�͂Ɏ��߂Ă���B
�@��㔪���N������\�ܓ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�����i�q���Ƃ����r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A1988�N9��25���A�O���Z�y�[�W�j
�g���ɂ͂���2���̂��ƂɁs���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j������B�����A�W�J�~�ꂪ�g���Ɂs�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t���������낳�������т́A�����狭�����Ă�����Ȃ��i���T�j�B����ɒ��ҟf��̊��s������A������Ƃ����͂Ȃ��̂����A�W�J�~��͒}�����[���N�ސE����܂��ɏo�������Ɓs�g�����S���W�t�i1996�N3��25���j���g�����̎������ڑO�Ɋ��s�����i�S���W���o���Ȃ�}������A���g���̈⌾�������Ƃ����j�B�����ɂ́q�g�������W�o���r������A�u���O���s�̎��W���e���W���ƔN�㏇�Ɍf����B���s���ɍ����āA���̒��ɑI���W���܂߂��B�܂��{�S���W�̒�{�ɂ́����t�����B�v�i�����A�����O�y�[�W�j�Ǝn�܂�A���W�̏�����g�������M�̂��Ƃ����ނ��f���A�\�r�ł����������Ă���Ō�Ɂu�ҏW�� �ҁv�ƕ��ӂ̕\���������i���U�j�B�����āA�NjL�̂悤�Ȍ`�Ŏ��̕��͂��t����Ă��邪�A�����͂��ׂĒW�J�~��̕M�ɂȂ���̂��낤�B
�@���ш�Y���ɂ��u�g���������v�i�w���㎍�ǖ{�\�\�����Ł@�g�����x�v���Ё@�����N�l���j�A�w�g�����S���ѕW������x�i���Y��ԁ@����ܔN�܌��j�����Q�Ƃ����Ă��������܂����B�����Ɋ��ӂ̈ӂ�\���܂��B�i�����A�������y�[�W�j
�s�g�����S���W�t�����ɂ���������̃g���u���ɂ��Ă͂��ď������̂��i���V�j�A�����ŌJ�肩���������Ȃ��B������ɂ��Ă��A�W�J����̒}�����[�ɂ�����Ō�̎d���̂ЂƂ��{���̊��s���������Ƃ͖��L���Ă��������B�z���A���̃T�C�g�s�g�����̎��̐��E�\�\���l�E�����Ƌg�����̍�i�Ɛl���̌����t�̋L�ڂ̑唼�́s�g�����S���W�t�ւ̒���ȃR�����g�������悤�ȋC��������B�ҏW�ҁE�W�J�~��̋Ɛт����݂�䂦��ł���B
�M�{���n�́q�������ق�r�Łu���̒[�����ƃO���}���X���������ċg�����ƐΉ��l�q�̃n�C�u���b�h�Ƃ������ׂ�������L����̌����钆�����ق�̑���v�i�s�A�C�f�A idea�t368���k���W�E���{�I���^�i���_�� 1970-1994 �ے�`�̃u�b�N�f�U�C���l�A2014�N12��10���A��Z�܃y�[�W�j�ƕ]�������A�����̂��̑O�i�ɂ́u�k19�l85�N����͘@���d�F�ӔC�ҏW�̋G���f��G���w�����~�G�[���x�̂`�c��S���A�I����Ɏn�܂����s�����~�G�[���p���t�ł̓X�`�[�����ő���ɑ��d�����f��{�̊�{�`������B�@���Ƃ̎d���́w�������{��_�x�i�P�X�V�V�j����ŐV��́w�w�{���@���[�v�l�x�_�x�i�Q�O�P�S�j�܂ő����Ă���B�}���ł͒W�J�~��A�ԋ{���F�A���N�i�A����V�Ƃ��������r�ҏW�҂Ƃ̋��͂ȃ^�b�O�ɂ���Đ������̌��삪���܂ꂽ�B�v�i�����A��Z�l�`��Z�܃y�[�W�j�Ƃ���B�W�J�~��Ɏn�܂�}�����[���������ق鑕���̌n����]���āA�����ł��낤�B
��ɁA�W�J�~�ꂪ�ҏW�҂Ƃ��đz���o�����������Ƃ͂Ȃ��A�ƋL�����B������������}���ق̏�������������ƁA���̕��͂��q�b�g����B�W�J�����Ђ̔}�̂ɏ������A���܂̂Ƃ���B��m�F���ꂽ�Ɩ��p�̕��͂ł���i�����Ɂu�i�M�҂͒}�����[�ҏW���@�W�J�~��j�v�Ƃ���A����Ɍr�ł��������s���@�����[�S�W�k�S12���l�t��9�s�ɂ킽�鍐�m�L�����f�ڂ���Ă���j�B�S�����f����B
���@�����[�̃v���t�B�[���b�W�J�~��
�@�u���@�����[�͎��ɂƂ��āA�P�Ɏ��l�ł��A���w�҂ł��A���|��]�Ƃł��A�Ȋw�҂ł��A�N�w�҂ł������Ȃ��āA�����̐��I�Ȓm�I�̈�̑S�̂ɑ��āA��l�̐l�Ԃ��Ƃ蓾��ԓx�����肷���ӂ̌����ɂق��Ȃ�Ȃ������B���̌����Ƃ̏o��́A���ɂ͂��܂�ɋM�d�Ɏv��ꂽ�̂ŁA����w�Ƃ�Ԃ���Ȃ����́A���͂⎄�ɂƂ��Ăǂ��ł��悢���Ƃł������B�v�������ꎁ�͘A�ڏ����w�r�̉́x�̂Ȃ��ŁA���̑�w����̓Ǐ��̌������̂悤�Ɍ��܂��B�����m�푈�����Ȃ�̂���̎��ɂƂ��āA���@�����[�́u�����v�ł���A��́u�[���v�ł����B
�@�吳�̖����납��|��Љ��͂��ߓ��{�̒m�E�l�ɍL�����ǂ���Ă������@�����[�ł����A����ǐV���ɑS�W�����s�����̂��@��ɁA�ȒP�ɂ��̐��U�����ǂ��Ă݂����Ǝv���܂��B
�@�|�[���E���@�����[�͈ꔪ����N�i�����l�N�j��t�����X�̍`���Z�b�g�ɐ���܂����B���̒n���C�Ƃ������y�͔ނ̐��_�`���ɐ[���e����^�����Ǝv���܂��B�̂��Ɂu���͎����̐��ꂽ���Ǝv���ꏊ�̈�ɐ��ꂽ�v�ƌ���Ă��܂����w�C�ӂ̕�n�x��w�Ⴋ�p���N�x�̂Ȃ��Œn���C�̌��Ɛ����������r���܂��B�܂����̑O��ɂ́A��\���I�t�����X���w�̋��������A�N���[�f���A�W�b�h�A�v���[�X�g������Ă��܂��B
�@���@�����[�͗c�����ォ�玍������͂��ߌ��z��G��ɂ��S�������܂��B�₪�ĐN���ɒB�����ނ́A�����y���G�̖@�ȑ�w�ɓ��w���܂��B�����Ă��̂�����R�̋@��玍�l�s�G�[���E���C�X�ƒm�荇�������Ƃ��A�ނ̐��U���Ȃ��Ό���Â��܂��B�Â��ăA���h���E�W�b�h�Ƃ���F�W�����悤�ɂȂ�A�����y���G�o�g�̓c�ɐN�͒������d���狭���h�����܂����B�ނ̎��͂₪�ďے��h���w�̎t�}�������ɔF�߂��A������傢�Ɋ��҂���邱�ƂɂȂ�܂��B��������\�̃��@�����[�̐��_�̓��ʂł́A����v�����N�����܂����B
�@����́u�W�F�m���@�̈��v�Ƃ��ē`�������ꂷ�������炢�͂���܂����A���_�̈��]�@�ł��������Ƃ͊m���ł��B�ꔪ���N�H�̌��������̈��A����u�m�I�N�[�f�^�[�v�����s����A�Ȍ���\�N�ɂ킽���Ď��l�Ƃ��Ẵ��@�����[�͒��ق���̂ł��B�u�m���̋����v�ȊO�̈�̋��������ۂ��A�m���������ɂ݂��������邱�Ƃɐ�O���܂��B���̊ԃp���ɒ�Z���A���̒��ۓI�Ȏv���́w���I�i���h�E�_�E���B���`�̕��@�ւ̏����x����сw�e�X�g���Ƃ̈��x�Ƃ�����̏d�v�ȎU����i�Ƃ��Č������܂��B����͖��\�̓V�˃��I�i�k�g�����l�h��ʂ��Č|�p�I���@�_��W�J���A�����̉ˋ�̐l���e�X�g���ɂ������Ďv�l�̋Ɍ���Nj����Ă��܂����A�Ƃ��Ƀ��@�����[������̗��z������������̂ƌ����܂��傤�B���̂��돑���ꂽ�w���@�I���e�x�́A�̂��̑S�̎�`���Ƃ̏o����\���������ƂŗL���ł���A������������]�̍ŏ��̌����ł��B
�@�ꔪ�㔪�N�}�������̎��ɑ����A���d�Ƃ͂܂��܂��������Ȃ��Ă����܂��B�}�������ɂ͏I���[���X�|���A�܂��}�������̕��ł����@�����[�̂Ȃ��ɐ��_�I�Ȍ�p�҂�F�߁A���ʂȈ���𒍂��ł����̂ł����B��せ���N�����A�����ĒʐM�Ђ̘V�В��̔鏑�ƂȂ�A���S�Ȓ��قɓ���܂��B
�@���̂悤�ȁu���ي��v���烔�@�����[���Ăі߂����̂͐e�F�W�b�h�ł����B�����N�A�W�b�h���狌�������ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ������߂�ꂽ�̂����������Ŏl�N���ɂ킽���S�̂����A��\���I�R�R��̌���w�Ⴋ�p���N�x������܂����B���ɏ�������l�̏����̈��̈ӎ��̕ω��������������̍�i�́A���I�̎��l�̒a������������̂ł����B�Ȍ�����Ǝ�����Â��A���W�w���f�x�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��܂��B
�@���̂���В��鏑�̐E�����������@�����[�́A�Ȍ㕶�l�Ƃ��āA�����ۘA���m�I���͈ψ���ł̌��l�Ƃ��Ă̐�����������܂��B���߂ɉ����Đl�Ԃ̂����鐸�_�̈�̖��ɂ��Ĕ������A�t�����X���\����m���l�Ƃ��Ă̖������l�����܂��B���̔����́w���@���G�e�x�S�܊����̑��Ɏ��߂��A��\���I�ɂ������]�̐����ƌ����Ă��܂��B
�@����ɂ������ẮA���_�̎��R�����ʂ����Ƃ������l�Ԃ̑�����ۏ���ƐM���āA�����ƒ������ێ�����ӎu��\�����Â��܂����B���̂���ɂ͔ӔN�̐��݂������b�q�������Y�ȁw�䂪�t�@�E�X�g�x��������܂����A�����ɏI��܂����B
�@���l�ܔN�����A���@�����[�͉����̃p���Ŏ������A�h�E�S�[���Վ����{�͍����������Ă�����܂����B��[�͌̋��Z�b�m�́u�C�ӂ̕�n�v�ɖ����Ă��܂��B
�@���@�����[������œ�\�N���܂�A��\���I�ő�̒m���̐l�̐����͋P���𑝂��A���̍�i���E�̌����͊e���ł����߂��Ă��܂��B���w�����Ȃƒ����̎����ɂ���A�����ĕ����Ɛ��_���ˑR�Ƃ��Ċ�@�ɂ��錻�݂ɂ����āA�|�[���E���@�����[�̈₵�����_�̋O�Ղ́A�i���Ɍ�肩���Ă�܂Ȃ��̂ł��B�i�s�V���W�]�t1967�N5��1�����A��Z�`���y�[�W�j
�}�����[�ɂ�����ҏW�ҁE�W�J�~��̎d�����T�ς�����i���W�j�A�t�����X���w�i�Ƃ�킯��ҁE���҂Ƃ��Ă̘@���d�F���t���[�x�[�����F�V���F���T�h�j����ՂƂ���O�����w�A�����Č�����{���w�i�Ƃ�킯�����ҁE���҂Ƃ��Ă̋g�����j�̏����Q����O���ނ����B�}����ނ����W�J���炨�b�����������@��̂Ȃ��������Ƃ��A���X�̂悤�ɉ���܂��B�g�����̂��Ƃ������Ƃ����Ƌ����Ă����������������B�Ō�ɒW�J�~��ɂ��g�����Ǔ������f���āA�{�e���I���悤�i���̖͂����Ɂu�i�}�����[�@�ҏW���j�v�Ƃ���j�B
�g������̂��Ɓb�W�J�~��
�@�g������ɂ���ł����͓̂�\���N�Ԃɂ���ԁB�͂��߂͓��Ђ�����Ђ̐�`���̈�l�ł���ɉ߂��Ȃ������̂����A�܂��Ȃ����̂₹�Ă���ǂ��ڂ������l���A���́w�m���x�̎��l�ł���Ƃ킩���āA���ɂт����肵�Ă��܂����B��i�̏�����ɑz�������l�i�ƁA���ɖڂ̑O�ŁA�������ӂ����Ȃ���Ί�ʼn����ɁA�����ɂ������̍]�˂��q���Ɂi�Ə���Ɏv�����������������j�b�����l���Ƃ����܂�ɈႢ�������̂ł���B���̌��u�̑傫���̈�ۂ́A���ɍŌ�܂łقƂ�Ǖς��Ȃ������ƌ����Ă����B�������ƍ�i���E�͂܂������ʂł����āA�ǂ����ɋ��E�����������߂ɁA�Ⴆ�Ό��e�͂��ׂėz�q�v�l���������Ă���ꂽ�悤�����A���̕M�Ղ�������������Ƃ������Ƃ��Ȃ������悤�Ɏv����B
�@�g�����ҏW���Ɉڂ��Ă���A���鎞���ɂ͒��ڂ̏�i�ł������B�����ē����͂قƂ�ǖ����̂悤�ɃR�[�q�[�����������ɂȂ����B���̌�ގЂ���Ă���a�J�ł������Ƃ��͏�ɓ�����̃g�b�v�ł������悤�ɁA�g������̍s�����̓X�͂قڌ��܂��Ă����B�����Ă����u�z�b�g�v�ł���A�T�[�r�X�R�[�q�[�̂���X�ł͂��́u�T�[�r�X�v�ł������B����ȂɃR�[�q�[�D���ł����Ă��A����ŃR�[�q�[�����邱�Ƃ͂Ȃ������炵���B������Ƃӂ����ȋC������̂����A�R�[�q�[�𖡂키���͋C�S�̂��A�g������ɂƂ��ẴR�[�q�[�������̂��낤�Ǝv���B
�@�ҏW������̖Y����Ȃ��v���o�̈�̓l�����@���S�W�̊��s�ł������B�t�����X�ł̍ĕ]���C�^�������āA����N�v����ɑ��k���|��S�W�̊����o�����̂����A��x���ی��ɂȂ�A�g������ɂ悤�₭����ɂȂ����B�g�����l�����@��������Ȃɓǂ�ł���ꂽ�Ƃ��v���Ȃ��̂����A�N������قnj����Ȃ�A�Ƃ������o���Ă݂悤�ƌ����đS�O���̏o�ł����܂����̂ł���B���l�Ƃ��ẴJ�����������傫�������낤���A�ᑢ�̋�����]���܂����Ȃ��Ă���āA���̌�̃����C���N�����������Ƃ͎��ɂ��ꂵ�������B
�@�g������Ɋ��ӂ��ׂ��傫�Ȃ�����́A������Í��|�p�ւ̎w����ł��낤�B�y���F�̓��{�N�ٌ������͂��߁A�}��b�A����m�q�A�����Ă�̕����́A�����ʂ肱��܂ł̕��x�Ƃ����T�O���܂����������������̂ł������B���̓��̏Ռ����Ȃ������炻�̌�ڂ��邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤���E�̐��X�ɁA����Ă��Ȃ��t�ł���Â��ĉ��������B�y���F�ɂ��ẮA�̂��Ɂw�y���F��x�Ƃ��Č��������A�g�����̌������I��i�̒a���ɗ����������Ƃ��ł������Ƃ��ւ�������ď����Y�������Ǝv���B
�@�����҂Ƃ��Ă̋g������̖��l�|�ɂ��Ă����X�̑z���o������B���M���ׂ��͒��҂Ƃ��̍�i�ɂ��������ނ̑I�т����̖��������Ǝv���B�ɒ[�Ɍ����ƁA�\���N���X�̑I���ƕ����̔z�u�A�F�������u�Ɍ��܂��Ă��܂��Ƃ������A�Ƃ����܂��ꂽ���o�̈ꎞ�̏W����p�ł������B�F�⎑�ނ̌��{�Ƃ��āA����Ƃ��͐g�߂ɂ���Ⴆ�����̔��������肷�邱�Ƃ��������̂����A���ׂ����u�ɂ��čŏ�̒����������̂��������A�����o�邱�Ƃɂ���āA���̑����̂悳���X�ɐ����Ă���̂������B
�@�a�������������Ƃ��̂��Ƃ�������L���Ă��������Ǝv���B�o��������������̐V���{�����͂������Ƃ��̂��ƁA�J�o�[���Ƃ�͂����ĕ\�������A���̎肴�����������߂Ȃ���A�u��������i�����ҁj���Ȃ��Ȃ�������Ă���l�v�ƁA�����ꂽ���Łi���̂���͐������Ă̂悤�ɂ͏o�Ȃ��Ȃ��Ă����j����ꂽ���ƁA�u���̃N���X�͂ƂĂ��������ǁA�l�͌���������g��Ȃ��v�Ƃ͂����茾��ꂽ�B���l�̎d���ւ̉��l���f�Ǝ����̎d���̂����̊Ԃɂ͂�����Ƃ�������������ꂽ���ƁA�ǂ�Ȃɑ̒��������Ƃ������ׂ����Ƃ͌����Ƃ����A���A�������킸�\���҂̂����ʌ��ӂ��݂�v���������B�i�u�����s�l�����ʐM�t50���k�Ǔ��E�g�����l�A1990�N7��25���A�l�`�܃y�[�W�j
�W�J�~�ꂪ�g���̕a�C�������Ɏ��Q�����V���{�́A1990�N5��21�������t���s���́A�������ق鑕���́s�F�V���F���w�فt�̏���z�{�i��4���Ƒ�5���j�ɈႢ�Ȃ��B�ʐ^�ł͂킩��ɂ������A�\���̃N���X�ɂ̓S�b�z�`���Ƃ���̎����̂悤�ȉQ���͗l���G���{�X���H����Ă���B��4���͛ܒJ���m�̕҉���ɂȂ�q�T�h�i�F�V��j�^�t�[���G�i�ܒJ��j�r�B�т̕\�S�ɂ́A�E�菃�ꂪ�s���F�e���q�C�L�t�ň��p�����r���G�i���̑ѕ��ł���q�V�u�T���k�X�̐��E�ɒʂ��r�ɂ́u�����F�V���F�S�W�����邾���ł͑S������Ȃ��B�E���F�V���F���Ǖ��w�I�𑵂��āA�͂��߂ăV�u�T���k�X�̐��E�ɒʂ�����B�v�ƌ����A���̌����E��́s�����̉F�����t���㉟���������Ƃ��낤�j�Ɩ���Ƃ̑哇�|�q�̐��E���B�\�P�̑ѕ��u���̃V�u�T���Ő��E���w�W���v�Ƃ����A�W�J�̃C���^�r���[�L���̃^�C�g���́u�S�W�v���u�W���v�ɕς��������̎��ɂ́A���S�Ȃ��Ȃ��B
 �@
�@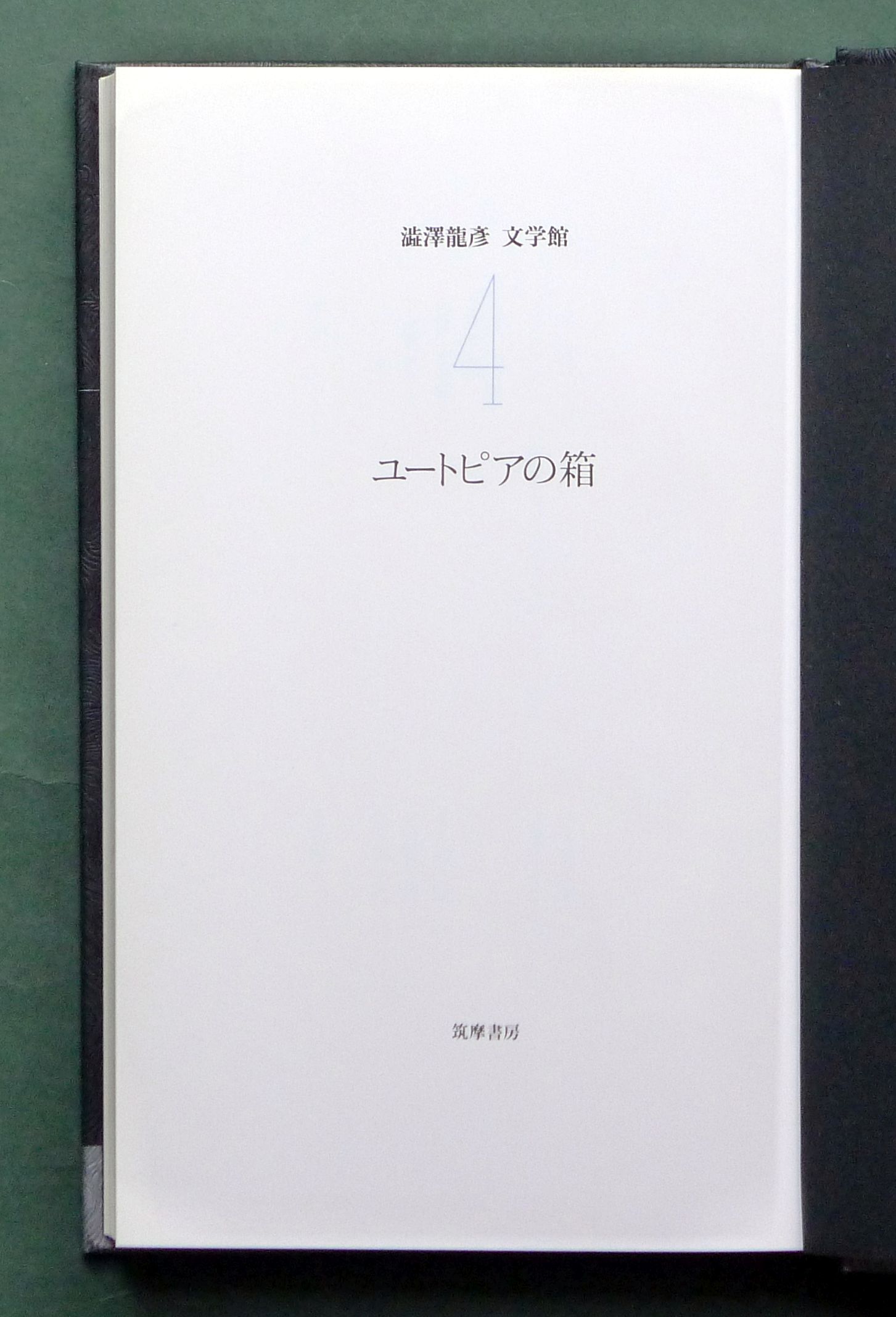
�ܒJ���m�i�҉���j�s�F�V���F���w�فk��4���l���[�g�s�A�̔��t�i1990�N5��21���j�̕\���ƃW���P�b�g�i���j�Ɠ��E�{���k�����F�������ق�l
�����܂��ɁA�W�J�~�ꂪ��|�����ܒJ���m�̒������������B�ܒJ�́s���[���b�p�̕s�v�c�Ȓ��k�����ܕ��Ɂl�t�i1996�N4��24���j�́A�W�J�����N3�����ɒ}�����[��ސE���������Ɋ��s����Ă���B�e�{�̔��s�́A�g�����f����3�ӌ����1990�N8���ł���B�u����Z�N�Z���ܓ��v�̓��t�̂���q���Ƃ����r�̖����������B
�@���M�ɂȂ������A�\�z�ȏ�Ɏ�Ԃǂ��Ă��܂������̕s�v�c�Ȗ{�̏o�ł̂��߂ɐS�₳�������s�͂��Â��Ă����������}�����[�ҏW���̒W�J�~�ꎁ�A��R�x�q���̂���l�ɁA���炽�߂Đ[�ӂ̈ӂ�\����B�i�k�����ܕ��Ɂl�A���O�y�[�W�j
����A�u����Z�N�O���\�ܓ��v�̓��t�̂���q���ɔł��Ƃ����r�̖����͂������B
�@����ȍč\����������݂�@����܂ꂽ�̂ŁA���̕��ɔł̎d���͎v�����������������̂ɂȂ����B���炽�ɕҏW��S�����Ă����������}�����[�o�ŕ��̉H�c�������ƁA��������k�ɂ̂��Ă������������{�̒S���ҁE��R�x�q����ɁA��������\�������Ă��������B�i�����A���Z�y�[�W�j
�s���[���b�p�́c�c�t�̎o���сs�A�W�A�̕s�v�c�Ȓ��t�i1992�N11��10���j�́q���Ƃ����r�i�u�����N�����O�\���v�̓��t������j�̖����ɂ́A�u���M�ɂȂ������A�O��Ƃ��Ȃ����{���̊��҂ł������}�����[�ҏW���̒W�J�~�ꎁ�ƁA�I�n�䂫�Ƃǂ��������b�����Ă����������S���̑�R�x�q���ɁA��������\�����������B�v�i�s�A�W�A�̕s�v�c�Ȓ��k�����ܕ��Ɂl�t�A2000�N5��10���A�O��l�y�[�W�j�Ƃ���B�Ȃ��A���ɔłł̒S���͕ҏW���E����F�j�B
�������Ă݂�ƁA�W�J���S���������҂̌n��ɁA�������ɋg�����\�F�V���F�\�ܒJ���m�Ƃ������C�������݂����Ǝv����B���̎O�ҁi�F�V�͂��łɖS���A�g�����قǂȂ������}����킯�����j�́A�W�J�~��ƒ������ق�݂̐�������\�\�s�F�V���F���w�فt�̏���z�{�ŏo������B����ɂ��Ă��A�Ǝ��͎v���B�W�J�~�ꂪ�ق�Ƃ��ɏo�����������̂́s�g�����S�W�t�������̂ł͂Ȃ����A�ƁB�s�y���F��t�Ɓs�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�����ās�g�����S���W�t�Ƃ����A�ӔN�Ɵf��̋g�������Ñ��̒}�����[����o����3���̖{���ׂĂ��W�J�~��̐s�͂ɂ����̂ł��邱�ƂɁA���炽�߂Đ[�����ӂ�������\�\�B
�k��L�l
�{�e�́A�g�����f��30�N��������2019�N�̏H���珀�����n�߁A��2020�N4���A�W���I�Ɏ����������B���̊ԁA�������W�J�~��Ƃ��镶�͂{�������ʁA�ȉ���2�т������B
�@�@�s�ӂ�蒟�iCahiers des etudes francaises�j�t��5���i1976�N11���j�́k�Ǔ� �n�ӈ�v�l�Ɏ��M�����q����W�ҏW���S���҂Ƃ��ār�i���X�j
�@�@�s�u�b�N�K�C�h�E�}�K�W���t�n�����i1990�N8���j�k���W �F�V���F���߂���u�b�N�E�R�X���X�l�̃C���^�r���[�L���q���ɂ��Ĕ��ɂ��炴�镶�w�فr�i���P�O�j
����ɁA����͒W�J�̎��M�ł͂Ȃ����A�k�}���p���l�̃W�����E�O���j�G�i��㋆��Y��j�s�Ǔ��k����V�Łl�t�i1991�N2��25���j�́q����V�Łi�}�����[�ň����N���j�ɂ��Ă̖�҂̃m�[�g�r�i�����ɂ́u����Z�N�㌎�\�l���^��㋆��Y�v�Ƃ���j�ɂ́u��㎵��N�\���̑掵���ȗ���ł̂܂܂ɂȂ��Ă����|�����X�ł̖{�����A����}�����[�ҏW���W�J�~�ꎁ�̍��]�Ɛs�͂Ƃɂ���ē����[�������V�ł��o�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�v�i�����A�ꔪ�l�y�[�W�j�ƌ�����B�s�Ǔ��t�͂̂��ɁA�O���́k�����܊w�|���Ɂl�i2019�N4��10���j���o���B�ً}���Ԑ錾�̂��ƁA��������}���ق��͂��߂Ƃ���e�ُ����̎������{���ł����A����ȏ��L�����ׂ��Ȃ����Ƃ��⊶�Ƃ���i�Ƃ��ɁA�n�ӈ�v����W�A��㋆��Y���v���[�X�g�֘A�j�B��������������B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���߂ɖ{�e�ȑO�ɖ{�T�C�g�Ō��y�����A�W�J�~�ꂪ�i�ҏW�Ɍ��炸�j�o�łɊւ�����}�����[���s�̏��Ђ����X�g�����Čf����B
�@�@�W�����A���E�O���b�N�i������L���j�s�A�T�Ȕ��N�t�i1970�N7��25���j�������낵�ɂ��p���q���q�r�̂���
�@�@�y��Չ��s���ԂƉi���t�i1974�N5��10���j���g�����̎�|�����{�i1�j
�@�@�K�X�g���E�o�V�����[���i�a��F���j�s���݂錠���t�i1977�N2��20���j���g�����̑�����i�i98�j
�@�@�ۊ�����s�v���[�X�g�E��ۂƉB�g�t�i1982�N8��30���j���g�����̑�����i�i37�j
�@�@�͓��p����s�E���K���b�e�B�S���W�t�i1988�N1��1���j���g�����̑�����i�i85�j
�@�@�͓��p����s�N�@�W�[���h�S���W�t�i1996�N3��31���j���g�����̑�����i�i85�j
�i���P�j�@�E�菃�ꂪ���̍������M����ɂ������ĎQ�Ƃ����̂́A�F�V���F�̐��M�q�V�Ղ�r�\�\���o�́s�����W���[�i���t1978�N5��5�����A�����́s�ߕ������t�i�����V���ЁA1979�N2��25���j�A�s�ߕ������t�́s�F�V���F�S�W�k��16���l�t�i�͏o���[�V�ЁA1994�N9��12���j�Ɏ��^�\�\�ŁA�W�J�~��́u�b���[�̂`����v�Ƃ��ēo�ꂷ��B���͂��̌���ǂނ��тɁA���m�̌Q�����B�����ʐ^�̃L���v�V�����ł����Ό�������u�����珬���ƁE�^�A���l�E�^�A�ЂƂ肨���ĕ]�_�ƁE�^�v�́u�ЂƂ肨���āv��z���o���B���̑����́A�����̓ǎ҂�㐢�̏o�Ől�ɂ͂قƂ�ǖ����̒S���ҏW�҂����ł���B�F�V�̋L�q�́A�}�炸���q�V�Ղ�r���G�b�Z�C�ł͂Ȃ��A���M�ł��邱�Ƃ𖾂����Ă���B����A�g�����͓������̂��Ƃ��q�������l�\�\�a�c�F�b�ՏI�L�r�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�j�\�\���o�́s�Q���t1977�N12�����k�a�c�F�b�Ǔ��l�\�\�ɋL���Ă���B���̂�����̂��Ƃ��q�g�����Ƙa�c�F�b���邢���F�V���F�̎U���r�́y���Q�z�ɏ����Ă���̂ŁA�Q�Ƃ��ꂽ���B�����ł͈��p���Ȃ��������A���̓��A�W�J�Ƌg�����k���q���F�V�@��K�ꂽ�̂́A�g�����ҏW���Ă����o�q���s�����܁t�̌��e���˗����邽�߂������i�f�ڂ��ꂽ���͂�ǂނƁA���͂Ƃ��ɒ��ꂸ�A���������Ă��悩�����悤���j�B�F�V�͓����̑�105���i1978�N1���j�Ɂq���E���̌��e�r���Ă���B�������F�V���F�s��ƘS���t�i�y�ЁA1980�N6��30���j�Ɏ��߂�ꂽ�B
 �@
�@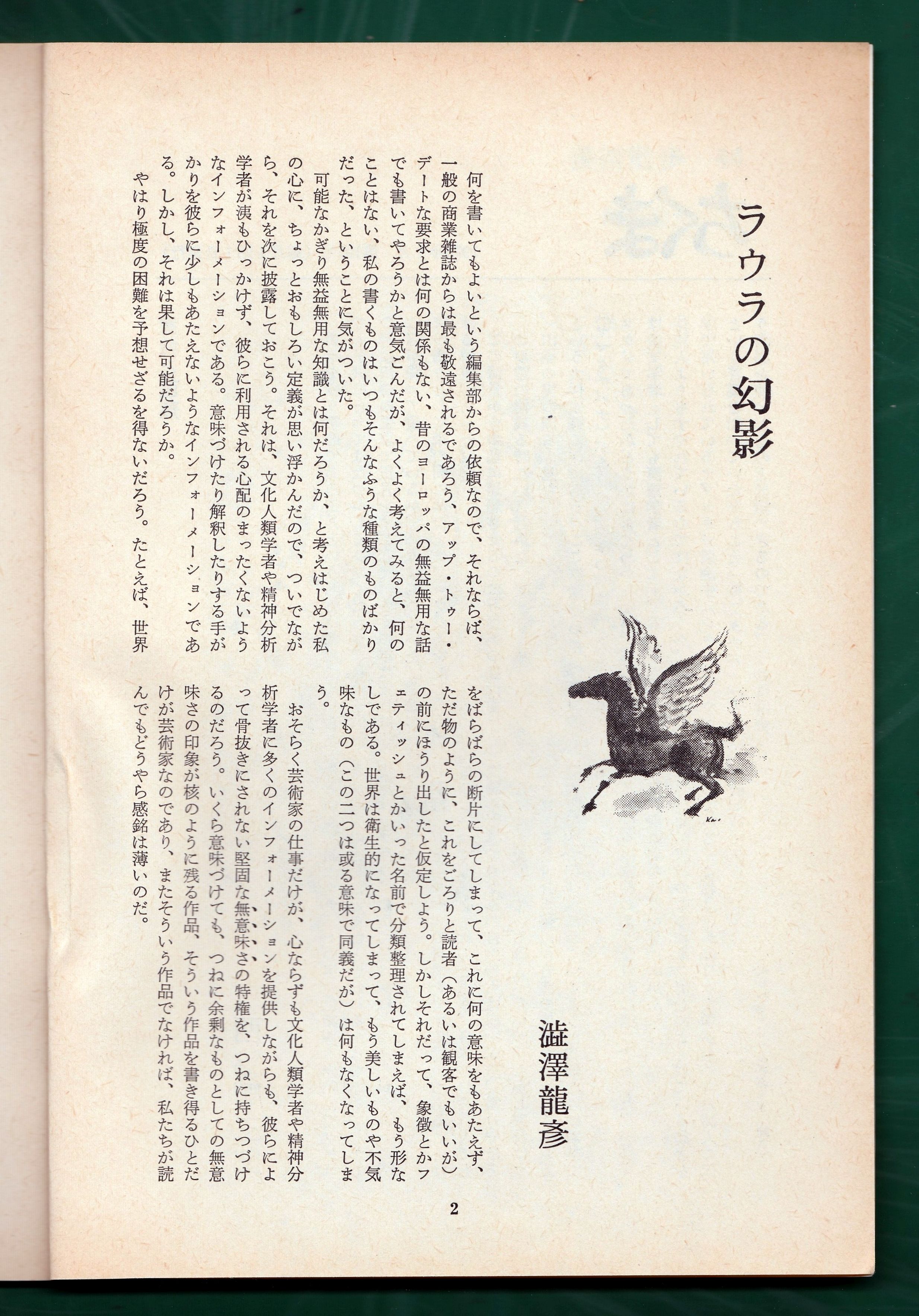
�g�����ҏW�̒}�����[�̂o�q���s�����܁t��105���i1978�N1���j�̕\���i���j�Ɠ����Ɍf�ڂ��ꂽ�F�V���F�q���E���̌��e�r�̖`���i�����A��y�[�W�j�k�{���J�b�g�F���{�y�m�Y�l�i�E�j
�i���Q�j�@�W���[�i���X�g�E�Έ�M���ɂ��550���قǂ̂��̋L���́A�Z���Ȃ���ސE���̒W�J�~����݂��Ƃɑ����Ă���B�S���������ɔ@���͂Ȃ��B
�i���R�j�@�ܒJ���m�s�F�V���F�_�R���N�V�����W �g�[�N�тP�\�\�F�V���F�����^�F�V���F�Ə����̐��E�t�i�א��o�ŁA2017�N12��8���j�́q��L�r�ɂ͎��̂悤�Ȉ�߂�����B���s����ɂ����ǂ��́A�u�}�����[�ҏW���̌́E�W�J�~�ꎁ�v�Ƃ������ɏՌ������B
�i���S�j�@�H�����X�̃E�F�u�T�C�g�ɒu���ꂽ�H���N�q�s�l���w�̉��߂��ˁt���q9�@�u�����v�Ɓu�����ς��v�r�Ɏ��̂悤�ȉӏ�������B�f�ڔN�����i2018�N5��28���j�͒W�J�̟f��ł���A�H���N�q�ɂ��W�J�~��Ǔ����̎����B
�u�т̕����͒��҂ł͂Ȃ��ҏW�҂����߂�v�̂��퓹�Ȃ�A�W�J���ҏW�҂Ƃ��Ď�|�����g���̒����\�\�s�y���F��t�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�s�g�����S���W�t�\�\���т̕������W�J�����߂����̂ɈႢ�Ȃ��B
�i���T�j�@�W�J���g�A�g���́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�ɓo�ꂵ�Ă���B���Ȃ킿�u�ӏH�̖�x���A�V�h�̋i���X�s�b�g�C���ŁA�����Ă̕����u��q�v���ς�B�Ⴂ�q���肾�������A�V��ޓ�Y�v�Ȃ�W�J�~��v�ȂƉ���Ăق��Ƃ����B�v�i�q14�@�����u��q�v�r�A�����A��Z�y�[�W�j�Ƃ����A1968�N11���̌����ɂ�����o��ł���B�ҏW���Ă���{�́A�q���Ƃ����r�ɂł͂Ȃ��{���ɁA�������g���o�Ă���Ƃ͂��������ǂ�Ȋ����Ȃ̂��낤�B���ɂ͑z�������Ȃ��B�Ȃ��A�g���z�q����ɂ��A�W�J�v�l�͒W�J���������ɖS���Ȃ����Ƃ����B
�i���U�j�@�s�g�����S���W�t�̕ҏW�ψ��͔ѓ��k��E�剪�M�E����N�v�E�����r�Y�̎l�l�i���т͐��N�̏������A�g�������m�������Ԃł�����j�B�����r�Y�́q��̐l�r�Łu�k�c�c�l�g�����O�̊�]�Œ}�����[����o���w�g�����S���W�x�����ɂ́u�ҏW�v�Ƃ��āu�ѓ��k��^�剪�M�^����N�v�^�����r�Y�v�̎l�l�̖�������ł��邪�A�����͓��}���̒S���ҒW�J�����ɁA�قƂ�ǓƂ�œ����������Ƃ��A���L���Ă������B�v�i�s���㎍�蒟�t2019�N2�����k�Ǔ����W�E����N�v�l�A�Z�Z�y�[�W�j�Ə����Ă���B
�i���V�j�@�s�g�����S���W�t�̊��s���ď������̂��q�s�g�����S���W�t���r�ŁA���͂����Łu�g�����̑S���W������Z�N�̎O�����ɔ��s������A�`���̎��сq�t�r�������Ă��邱�Ƃ��������A�Ō��̒}�����[�͓X������{������������A�������{���́u���Łv�𐧍삵���B�v�Ǝn�߂āA�u�{�͍��Ȃ����܂��A�Ƃ����}���̉p�f�ɂ͑ł��ꂽ�B�g������ɂƂ��Ă��g�����̎��ɂƂ��Ă��őP�̑[�u���������낤�B�v�ƌ���ł���B���̌o�܂�Ԃ��������Ƃ��āA�����Ă��ǂ݂���������Ƃ��肪�����B
�}�����[�\�\�Ō�̎d���b�Έ�M��
�@���̓��A�O����\����i���j�́A�قƂ�ǂ̉�Ђ̔N�x���ɓ�����B�}�����[�̕ҏW�ҁA�W�J�~��m����₶����n���i�Z�Z�j�ɂƂ��čŌ�̏o�Γ��ł���B
�@���啧���Ȃ��o�āA�O�\�l�N�Ԃ̕ҏW�Ґ����ŁA�ނ���|�����̂̓��@�����[�A�t���x�[���A�{�[�h���[���A�v���[�X�g�̊e�S�W��u���E��]��n�v�ȂǁA��d�ɂ��A�Ȃ�R���̗̈e�ƌ����Ă悢�B�Ō�̎d�����ܓ��O�ɓX���ɏo���w�g�����m�悵�����݂̂�n�S���W�x�������B
�@�����ɕ��đ��ʉ�ƂȂ�͂��́A�Ј��Ƃ��Ă̍ŏI���A�W�J���́w�S���W�x�̉���ƒf�ق̎�z�ɒǂ�ꂽ�B�`���Ɍf����ׂ����u�t�v�����^����Ă��Ȃ������A�悩��̘A���ŁA�O���ɂ킩�����B
�@���W�w�����m�����n�G�߁x�͋g���������l�Z�N�A�o���O�Ɍ���S��������o�ł������̏������W�B�W�J���͌��T�̃R�s�[����肵�Č��e�ɂ����B�������A�`�����u�t�v�̃y�[�W���R�s�[���e���甲�������Ă����B���Ƃ��Ɩڎ����Ȃ��B���{�ɓ�����Ȃ���A�W�J���Ȃ炸�Ƃ��m��悵���Ȃ��B
�@�艿�ꖜ���~�A��O�S������A��S�O�\�㕔�z�{�A������S���B�u�t�v�Ȃ��w�S���W�x�͌Ï��X�ł�����ɂȂ邩�H
�@��蒼����p��S���\���~�ُ̕���\���o������Ђ͍��̂Ƃ���Ă��Ȃ��B�R�Ȃ��ނ̋ƐтƁA�_�̋C�܂���̂悤�Ȏ��̂����Ă��Ă̂��Ƃł���B�i�sAERA�m�A�G���n�t1996�N5��6���E13���������A�Z���y�[�W�j
�@�F�V���F�͂��Ȃ葁����������A�A���h���E�u���g���̉e�����ɁA�����̐����I�ȕ��w�j�ł͂Ȃ��u���́v���w�j�i�w�����̂��镶�w�j�x�Ƃ������������̈�[���낤�j���\�z���A����ɂ��ƂÂ��u���E���w�W���v�̂悤�ȃV���[�Y�̊��s�z���Ă������B�̂��ɂ̓z���w�E���C�X�E�{���w�X�̑O����Q�l�ɂ��Ă������낤�B
�@�₪�Ē}�����[�ҏW���̌́E�W�J�~�ꎁ�����̖��z�������������Ɛ\���łĂ���́A�e���̎��^��i���X�g������A���x�������Ȃ������肵�Ă����B�����̎��ă����́w�S�W�x�̕ʊ��P�ɂ��ׂĎ��߂Ă���̂ŁA�K�v�Ȃ�Ή��ƂƂ��ɎQ�Ƃ��Ă����������Ƃ��ł���B�i�����A�O�Z��`�O�Z��y�[�W�j�B
�@�Ƃ����킯�Łu�����v�̂��b�ł��B������30�N�قǂ܂��A�킽�������߂ďo�����{�k�w�{���@���[�v�l�̎莆�x�H���f�q�Җ�A�}�����[�A1986�N�l�̑тɁu�����ƃG�N���`���[���v�Ƃ������t���傫���������Ă���A���t�̎R�c𣝣�搶�Ɂu�M���̂悤�ɂ�����Ƃ������w�l���A���̂悤�Ȍ��t���g���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����Ȃ߂�ꂽ�Ƃ����b�B���̂��Ǝ��̂́A���������v���o�Ƃ��āA�ǂ����ɏ��������Ƃ͂���܂����k�H���f�q�ҁs�_�W �@���d�F�t�i�H�����X�A2016�N6��30���j�́q�w���ݕv�l�x�Ƃ��̒��҂�_���邽�߂̌��͘_�f�`�\�\�Ҏ҂��Ƃ����r�Ɂu�́A����Ƃ���Ŏv�������āu�����v�Ƃ������t���g�����Ƃ��ɁA�S����h������l�ɁA������Ƃ������w�l���g�����t�ł͂Ȃ��ƗD���������Ȃ߂�ꂽ���Ƃ����������v�������B�v�Ƃ���l�A���͂킽�����g���A���̌��t�͂���Ȃ�Ƃ͒ʂ�܂��Ɨ\�����Ă����B����_�I�ɏd�v�Ȃ̂́A���́u�\���v�̕��Ȃ̂ł��B
�@����Ȍo�܂�����܂����B�S�����Ă����������̂́A�}�����[�̒W�J�~�ꂳ��B�w�{���@���[�v�l�x�����M���Ă��������̃t���x�[���̏��Ȃ����āA�����y�[�W�̉��i�ɉ����Ȃ���������A���̂��Ƃō�i����������v���Z�X�𗧑̓I�ɕ��コ����Ƃ����\�z�ŁA���[�v�����Ȃ�����ł�������A���M�����̌��e��W�J����ɉ��x�����Ă��������āA���̂��тɁA�J�t�F�Řb�������A�����Ƃ�����薾�m�Ȕᔻ�����������܂����B���傤�Ǒ�w�����̎���Ɋw���������킽�������̐���́A�_���w���炵�����̂������Ƃ��Ȃ��B����ŒW�J����́A���A��䍂��Ă݂�ƁA�����̃��X�N�������Ȃ��珑�����Ƃ̎�قǂ������Ă����������B���炩�Ɂu�����ƃG�N���`���[���v�Ƃ��������ɁA�킽���̎v�l�����ƈӐ}���Ă���ꂽ�Ǝv���̂ł��B
�@�_�l�̂悤�ȕҏW�҂ƌĂ�ł���l�������g�̉��ɂ͂����肵�āA���{�̖L�����ɂ͒�]������܂����B�������x����������āA�r�����Ȃ�����ȕ��B�u���̒��́A�������ď����Ă�����ł��傤�v�Ƃ����w�E���āA�u�{���ƒ��̒��������܂�Ƀo�����X�������Ȃ肻���Łv�ƌ�����ƁA�u�y�[�W�̑g�ݕ��Ȃǂ́A�킽���ǂ��ҏW�҂���J����悢���Ƃł������܂��v�Ƌ������������ɂȂ�B�т̕����ɂ��āu�w�����x�Ƃ������t�͊댯���Ǝv���A���ȁw�����x�ƌ���ꂻ���v�Ƃ킽�����y�э��̔���������ƁA�u�������̂悤�ɑт̕����͒��҂ł͂Ȃ��ҏW�҂����߂���̂ł������܂�����v�ƒf�ł���Ђƌ��B
�@�k�u�V�C�{���S�W�v�Ɓl��������A�����悤�ɁA�[���Ƃ���ŐÂ��ɐi�s���Ă�����悪�������B�u�}�����E���w��n�v�i�S���㊪�A��㎵��\����N�j�����̑�57�\59���w�v���[�X�g�T�x�w�v���[�X�g�U�x�w�v���[�X�g�V�x�ł���B���̎O���ɁA��Z���I�ő�̏����ƁA�v���[�X�g�i�ꔪ����\�����N�j�̑�\��w����ꂽ�������߂āx����㋆��Y�i���Z��\���N�j�̌l�S��œ���Ă��܂����A�Ƃ�����_�Ȏ��݂������B
�@��57���w�v���[�X�g�T�x�́A��㎵�O�i���a�l���j�N�Ɋ��s����Ă����B���𐄐i�����̂́A�}�����[�̃t�����X���w�W�����Ɉ����Ă����W�J�~��i���O�Z�N�\�j�������B
�@�v���Ԃ��A�}�����[�͉�Б��n��Ԃ��Ȃ����l��i���a�ꎵ�j�N�ɁA���łɁu�|�I���E���@�����C�S�W�v�i�S�ꎵ���j�̊��s���J�n���Ă���B���d�Ƃ���_�Ƃ������钧�킾�������A���Nj㊪�Œ���B���̌�A���܁Z�i���a��܁j�N�ɁA�S��܊��ƋK�͂��g�債�čĒ��킷����A�����ł���܂�����̂�ނȂ��Ɏ������B�悤�₭�u�ߊ�v���������̂́A���Z���i���a�l��j�N���犧�s���n�߂��u���@�����[�S�W�v�i�S��A�⊪��j�ł���B�����́A��㎵��i���a�l�Z�j�N�̂��Ƃł���B
�@�Ƃ�����ɁA�}�����[�ƃt�����X���w�Ƃ͐��Ă���Ȃ��������������B
�@���́A��ЍX���@�\��������ł��فX�Ɩ|���Ƃ𑱂����B��58������59��������ƂȂ��āA�`�E�a�̓���ɕ������ꂽ�B�����́A�u�|�Y�v����̈�㎵���N�����Ċ�����āA�S�܍��́w����ꂽ�������߂āx����������͈̂�㔪���i���a�O�j�N�̂��Ƃł���B�L�O���ׂ��A�咘�̌l�S��̊����������B
�@�w����ꂽ�������߂āx�́A���̌�S��Z���Łu�����ܕ��Ɂv�i��㔪�ܔN�\�j�ɓ������i�����\��O�N�j�B����́A�u�����ܕ��Ɂv�̂����Ƃ��D�ǂȎd���̂ЂƂƂ��āA�����Ɠǎ҂ɋL�������͂��ł���B
�@�v���[�X�g�̍�i�́A�̂��Ɂu�v���[�X�g�S�W�v�i�S�ꔪ���E�ʊ���A��㔪�l�\���N�j�Ƃ��ďW�听�����B���Ă͒W�J�A�S���͒C���l�Y�i���l��N�\�j�������B
�@�����ЂƂA�قړ������ɐi�s���Ă������Ɂu�{�[�h���[���S�W�v�i�S�Z���A��㔪�O�\��O�N�j������B�������W�J�̕ҏW�ɂȂ���̂����A�����ǗY�i���O��\��Z�Z���N�j�ɂ�鐳�m�E�B�ӂ̖ƁA�Ƃ�킯�����Ȓ��߂��傫�ȕ]�������������B
�@���Ȃ݂ɁA���̃W�������́A���̌�V�����ҏW�҂ɑ����ꂽ�B���N�i�i���܁Z�N�\�j�͒W�J�̎d��������ɓW�J���A�t�����X���w�݂̂Ȃ炸�A�u�~�V�F���E�t�[�R�[�v�l�W���v�i�S��Z���A���㔪�\����N�j�Ȃǃt�����X�v�z�̊������ՐȂ��̂ɂ����B
�@�ɂ߂��́A�u�}�������S�W�v�i�S�܊��j�ł��낤�B��㔪��i���a�O�j�N�Ɏn�܂�����㐢�I�ō��̎��l�A��Z���I�ɑ���ȉe���͂����������l�̍�i�W���́A��Z�N����������A��Z��Z�N�i�������j�ɐV�����Ռ����Ƃ��Ȃ��Ċ��������B�Ō�̔z�{�ƂȂ�����T���w���E�C�W�`���[���x�́A�|��s�\�ȃ}�������̌���F������{��ɒ蒅�����A�|��j�Ɏc��͋Ƃ������B
�@�u�}�������S�W�v�̔��������{�E����́A�{����̍�i�ł��邱�Ƃ������Ă���B�u�����Ƃ����F���v�̋���ł��낤�B�Г�����҂������������ق�i���l�l�N�\�j�̃������c����Ă���B�u���t�����X ������v�u�f�ނ��ƂĂ��Ȃ����́v�B�ЂƂ̎�������A�ے��I�Ȍ��t�ł��낤���B�i�����A�ꔪ��`�ꔪ�l�y�[�W�j
�}�����[�ɂ�����t�����X���w�����s�̗��j�A����ɂ����ƒW�J�~��̊W�����������ڂ��ׂ���߂ł���B�W�J�́s�}�������S�W�t�i�����O�Y�E���쏺���E�����O�E�����ǗY�E�n�ӎ�͕ҁj�̖�҂������t�������͂ɂ͓o�ꂵ�Ȃ��悤�����A���@�����[�̎t�ł���}�������̖M��S�W���̗��������Ɋ֗^�������Ƃ͋^����e��Ȃ��B
�i���X�j�@�W�J�����M�����q����W�ҏW���S���҂Ƃ��ār���f����B�Ȃ��f�ڎ��́s�ӂ�蒟�iCahiers des etudes francaises�j�t�́A�N1�s�A�ҏW�����s�҂��b�d�e�ҏW���i��\�ҁE��{�t�T�j�́A���J���S�щ��g�̃t�����X���w������厏�i�sNDL ONLINE�t�ɂ́u1972-1989�v�Ƃ���j�B��5���͌���1000���B
�@�n�ӈ�v����W�̒}�����[�ɂ�����ҏW���S���҂Ƃ��āC�܂����̌�̒P�s�{�w���Ԕ��E�퍑�̌��܁x����ш⒘�ƂȂ����w���Ԕ��E��{�ٕ��x�̌W�Ƃ��āC�搶�̂���ւ��f�������Ԃɒ��Ղ����Ȃ��ɁC��Â���̏|�^��͂�����D����W�̊��s���I��ɋ߂Â���1970�N5���ɁC�����쐻�S�����b�쓿�q����ƂƂ��ɂ��������C�ȗ��킪�A�p�[�m�̋��������ɂ����Ă���D
�@�c30�Z���`��25�Z���`�ʂ̖ؐ��ŁC�S�̂ɓ����ȃv���X�`�b�N�̃P�[�X�����Ԃ��Ă���C�����ɒu���ꂽ�傫�Ȕ����L���͂�ŁC�㕔�ɂ͖ؒ��̃n�[�g�^���O����ł���D���E�̓�͋��F�Ƌ�F�ɁC�܂�Ȃ��̂͑N���ȐԂɍʐF����Ă���D�����ɂ͖�͂̋Ȑ��ɉ����āC�˒[�����͗l�ɏ����ꂽ�i�b�Ƃ����C�j�V������p��ŁCA Vaillans Cuers Riens Impossible�Ɣ����������L����Ă���D���ɂ͌f���p�̎~�ߋ��ƂƂ��ɑ܂��\�����Ă���C���̒��ɘa����ⳂɔF�߂�ꂽ���㏑���Y�����Ă����D
�@�i�b�̓W���[�N�E�N�[���i1395�H�\1456�j�ł���C�V�����������Ɏd���C���������I�ɉ������C�S�N�푈��̍��ƍČ��ɂ��������ƁD�C�O�f�Ղŋ����̕x��z�������ƁD���̐M�C�ɂ��S�炸�C���߂̉A�d�ɂ��������̂̍߂ɖ���C�S���Y��v�����ꂽ���ƁD�̂��C�^�����w����ċ��c�ɗp�����C�͑����w�����C�o����ɂĕa�f�������ƁD���セ�̖��_�͉������ꂽ���ƁD�����āu�V���K�����o�ŁC��Ή����m���̂��߂ɗ��p���ꂽ��]���҂̈�l�Ȃ�ׂ��v�Ƃ���D
�@��͂̔����L��Coquille Saint-Jacques�C�n�[�g�^��Coeur�C�]����Jacques Coeur��\�ۂ��Ă���Ƃ̉��������C�����̓n�[�g�^����܂��͓�̂Ƃ�����C�O�ɂ����̂͐搶�̑n�Ăł������D
�����́u�Ԃ��S�v�́u���v���C���E�̋��E��́u�S�v�́C���ꂼ��u�L���E����v�y�сu�����E��Áv��\���D�@�搶�̒���W��1970�N6�����犧�s���͂��߁C��71�N��6���ɑS12���̊��s���I���Ă���D����1�����s�䂦�C�{���Ȃ��5���ɏI���đR��ׂ��Ƃ�����C�r����1�������x�݂����̂ł���D�������̒x�ꂪ�Ϗd�Ȃ��ė����ɂ��ꂱ�Ƃ��v����̂����C��̌����́u�����v�ɂ������D
�@�L��A vaillans cuers Riens impossible�i��Aux vaillants coeurs Rien d'impossible�j�́C�W���[�N�E�N�[���̍��E���Ƃ��`�ւ��C���̈ӂ́C�u��������Εs�\���Ȃ��v�Ȃ�ׂ��Dvallain(t)�ɂ́C�u�E���ȁE���h�ȁE���l����v���̑��`����C���߂́C���̍��E����p�Ђ�l�ɂ�Ĉق邱�Ƃ���ށD
�@���̒���W�ɂ̓G�b�Z�[�����߂�3�����������e�������ɂ��ׂč��������Ă���i�������w���u���[�G�l�x�㉺��������2�������܂Ƃ߂ĉ����Ɂj�D69�N�͂��߂��납�珀����i�߂Ă�������W�����ɗ]�T�͏\���������̂����C���������͑g����Ă���y�[�W�����̂鑼�Ȃ��C��萳�m�Ȗ{�������ɂƂ������ƂōčZ���g�p���Ă����̂ł���D
�@�����̃J�[�h�Â���C���e�쐻�́C�o���L�����b�삳��̒S���ł������D��Ƀt�����X���w�́C�������猻��ɂ킽�鉢������̂ɂ��������ɂ͑�ςȘJ�͂��v��͂��Ȃ̂ɁC����\��ʂ�Ɍ����ɐ������ꂽ���e���o�����C�搶�̖ڂ��o�ĕҏW���ɓ���Ƃ����菇�ł������D
�@�čZ�ō̂��Ă������߂Ɋ��s���x�ꂽ�̂Ȃ�C���Z�ō̂邱�Ƃɂ��܂��傤�C�Ɛ搶�͎����Ȃ��ɂ�����������D��i�K�O�̍H���ō̂�ȏ�C��A�͂���C�y�[�W���͓����C�Ɗ댯�͑����͂������C�������̂̌��e����эZ���E�ƍ��Ō��͏������邱�Ƃ��ł���͂����C����1�����s������ȏ�o������Ƃ���܂ł���Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��C�Ƃ̌�ӎu���ǂ݂Ƃꂽ�D
�@���҂̌��ӂ��Öق̂����Ɏ��͂����Ă����D�Ƃ�����ΒP���ɂȂ肪���ȍ����Ɩ{���Ƃ̏ƍ��̎d�����͂��߁C�����傫�Ȃ��̂ɓ˂����������悤�ɂ��āC������s�𑱂��邱�Ƃ��ł����̂������D
�@����W�̌��e�́C1970�N�̎��_�ł̂���Β�{������Ƃ������Ƃł���C���ꂼ��̘_���E�G�b�Z�[�ɂ킽���Ĉ�ԐV�����ł��I��C���ʂ������Ă��������Ă����D�s�ԁE���O�ɂ͎�M�C�݂̂Ȃ炸���G�ȉ��M����ʂ��邽�߂ɐM�C�ΕM���������C�e�т��ƂɐV���Ɂu���L�v���Y����ꂽ�D�܂��C�{���ɕ��������ڎ��C�[���C�N�\�C��L�C�}�ł̌��e�܂ł���x�ɑS�������ĉ�����̂���Ƃ����D���e�d�グ�̒��C�Z�����I������t����x�������ꂽ���Ƃ͂Ȃ������ƌ����Ă����D���ł������̂����Z������100�y�[�W���ς܂��ĉ����������Ƃ�������D��ɑO�֑O�ւƒS���҂��������čs���ꂽ�D
�@�u�܂����i�������܂����v�ƏΊ�ł��������D�s���̓_�C�^��̎c��Ƃ���͓O��I�ɒ��ׂ�ꂽ�D
�@�܂��Ƃɐ搶������vaillant�ɒl����l�C��͂̈Ӗ����邻�̐l�������D����W�̎d���̂��߂Ƃ͌����C����ꎞ�ԋ߂��C�搶�̋M�d�Ȏ��Ԃ��ʂ�Ȃ�Ƃ��ז����Ă��܂������Ƃ��낤�D����݂̂��Â��̍�肩����e�����B�̃v�����X�̘b����C���M���̗��j��̐l���̐V�����G�s�\�[�h�܂ŁC������ɂ͎��ɖL���ȂЂƂƂ��������D�l�͎����̐g��ɍ������傫�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��ȏ�C���̐搶�̋����������܂��Ɉ�̑S�̂Ƃ��Ă͎����ł��Ȃ��͓̂��R�����m��Ȃ��D�������Ȃ���C�����ǂ݂������C����̕\�ʂ̒[�X�Ɍ��ꂽ����ΕX�R�̈�p�������܌��������ł��C���̓r�����Ȃ������������͑z���ł����̂ł���D
�@�^��vaillant����搶�́C�Ō�ɕa����ɉʊ��Ȑ킢�܂ꂽ�̂��Ǝv���D����̑Ӗ��̂��߂ɒx��Ă����w��{�ٕ��x�̒S���҂Ƃ��āC�a���ɂ��K�˂ł������Ƃɉ��ƌ����ׂ����m��Ȃ��D�z�����z�����ꂵ�݂̒��ŁC�ǂݓ��Ȃ������Q�l��������L�ɋL���ׂ����ƂȂǂ��C�Ƃ���Ƃ���Ɍ���ꂽ���ƂɁC�^����ǂ����߂�l�̐������������悤�Ɏv�����D
�@����W���s���ɂ��肢���C�Ŏ�����搶�ɁC�u�o�������̂����珳�m���ĉ������v�ƌ����Ă��������C�}�����[�̑n���ҌÓc��̒Ǔ����W�ɂ�����������߂����p�������D�搶�����̑O�N7���̓��t�ł���D
�@�Óc����͊m���ɑ��E���ꂽ�킯�����C���ł��C�Ђ����K�˂Ă�����₤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��D���̗]���������͂Ȃ��������C���̊ԁC�ӂƌÓc���K�˂Ă�����₤�ȋC�ɂȂ邱�Ƃ��x�X���邾�炤�D���̂₤�Ȋ�����^�ւ�̐l�����l�����D�������ӕ��X�́C���ɂƂāC�܂������ċ����邱�Ƃɂ��Ȃ�D�Óc������C���̈�l�ł���D�i�s�ӂ�蒟�iCahiers des etudes francaises�j�t��5���A1976�N11��1���A����`���l�y�[�W�j
�W�J�~�ꂪ�Ō�Ɉ������n�ӈ�v�̕��͂́s��z�̌Óc��t�i�}�����[�A1974�N10��30���j�Ɏ��߂�ꂽ�q���̖ʉe�r�̍ŏI�i���ŁA�����ɂ́u�ijulliet 1974�j�v�Ƃ���B�Ȃ������̑����́A�N���W�b�g�͂Ȃ����A�g�����B�䑺�k�����q�l�\�\���[�����E�W�����s�l�����@���\�\���U�ƍ�i�k�}���p���l�t�i�}�����[�A1975�j�����N�v�Ƌ��Ă���\�\�́s�ӂ�蒟�t��5���́q�ҏW��L�r���u�ŋߊ��s���J�n�����w�n�ӈ�v����W����Łx����z�{�́C�{���ɂ��̏��Ő��쓖���̎v���o�������Ă����������W�J���̃A�����W�ɂ�錩���ȁs�F��̔���̑��m�X�s�L���M�E���E�A�~�L�e�C�G�n�t�^�Ƃ��Ă���D6�N�O�̂����C�ȓn�Ӑ搶�́C����Ȃɂ������̂����ꂽ���q�҂������Ă��炵���̂��C�Ǝ��͉��߂Ċ��Q���Ă�����ēǂ����D�v�i�����A��ܔ��y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���B���Ȃ݂ɓn�ӈ�v�剺�̑�]���O�Y��1935�N���B�䑺�����q��1935�N���A�W�J�~���1936�N���B
�i���P�O�j�@�s�u�b�N�K�C�h�E�}�K�W���t�́A�s�F�V���F�X�y�V�����T�V�u�T���E�N���j�N���k�ʍ����z���w�C�l�t�i���̂́u�V�u�T���E�N���j�N���v�j�̔Ō��E���z���w�o�ŋǂ����s���鏑�]�G���B�n�����́A�ܒJ���m�̃C���^�r���[�L���A�푺�G�O�̒k�b�ƂƂ��ɁA�W�J�~��̃C���^�r���[�L���q���ɂ��Ĕ��ɂ��炴�镶�w�فr�𒆐S�ɁA�u�F�V���F���߂���u�b�N�E�R�X���X�v���T�ς��āA���s���ꂽ����́s�F�V���F���w�فt�肽�ĂĂ������Ƃ�����W�������B�W�J���̖`���Ɩ������f����i�����́u�W�J�~��i�}�����[�ҏW���j�v�ł���j�B
�@�w�F�V���F���w�فx���s����܂ł̂������́A�w�V�u�T���E�N���j�N���x�̂Ƃ��Ɍ���������̂ŁA����͋�̓I�ȕҏW��Ƃɓ����Ă���̂��Ƃ����b���������Ǝv���܂��B
�@���̊����F�V����Ɍ䑊�k�����̂́k���l�����N�̂��Ƃł�����A���낢������������Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�ЂƂ͕��ʂ̖��ŁA�F�V����̌��Ăł͂����Ȃ������Ăł���\�l������B��\�����z����V���[�Y�Ƃ����̂́A���݂̏o�ŏł͂��Ȃ�ނ��������̂ŁA�v�����Ĕ����̏\�ɂ����킯�ł��B����ł���Ƃ̖��O�͂Ȃ�ׂ����炵�����Ȃ��B�����Ȃ�ƁA���Ăł͒��т���̂ł������A���̂��ƒ��E�Z�т𒆐S�ɏW�߂�`�ɕς���Ă����܂����B
�@�����ЂƂ́A�V���[�Y���̖��ł��B���Ă̒i�K�ł́q���E���w�W���r�Ƃ��q�������w�فr�Ȃǂ̖��O���o�܂������q���w�̔��r�͏o�Ă��Ȃ������B���̃l�[�~���O�͂�����Ђ́q���w�̐X�r�V���[�Y�܂��Ă���킯�ł����A����ҏW���͂����肢�����o���T�O�E�푺�G�O�E�ܒJ���m�̎O���́A���̓_�A�C�f�B�A�L�x�Ƃ������A�����ȈĂ��o�܂��āA���ڂ̖����҂͎푺�������Ǝv���܂����A�����������X���Ȃ�A������͇��뇁���ƁB�������뇁�ł͂��ア�̂ŁA���ɇ��������o�Ă����B���́A�F�V�I�ȃ~�N���R�X���X�̋�ۉ��ł�����܂�����A����Ɍ��肵���킯�ł��B�����́q�F�V���F�E���w�̔��r�Ƃ�����ł����A���܂�q���w�̐X�r�̐^��������̂��₵���̂ŁA������̓V���[�Y�E�^�C�g�����q�F�V���F���w�فr�Ƃ��āA�e���ɇ��`�̔����Ɩ��O�����܂����B
�@���ɁA���ꂩ��o�銪�ɂ��ė\���҂ӂ��ɂ��b�����Ă����܂��傤�B
�@�k�c�c�l
�@����Ɋւ��ẮA������{�ɂ��邩�ǂ����ł����Ԃ�����܂����B�q���w�̐X�r�ɔ�ׂ�A������͍����E�����Ҏu���ł����獷�ʉ����͂������ق���������ł����A���������܂┟�ɓ��ꂽ�{�͎�҂���ɂƂ�Ȃ��B����ŃJ�o�[���Ɍ��܂����̂ł����A���Ƃ������t�ɂ͂�������Ĕ��ɂ��Ĕ��ɂ��炴�鑢�{�Ƃ��������A���Ђ̑���҂̒������ق�ɉۂ����킯�ł��B�܂��J�o�[�㕔�̍����ۂ��e�A����͖{�̊O�Ɉʒu���锠�̓��e�Ȃ�ł��B����Ȃ�ׂ�ƕ�����܂����A�e�̈ʒu���Ⴄ�ł��傤�B�ꊪ���ƂɈړ����āA�ŏI���ł͉e���������邩���m��܂���B���ꂩ��{�̂̕\���́A���͔��̓W�J�}�Ȃ�ł���A������ƋC�����Ȃ����Ǝv���܂����B�тɂ��t�����X��ŃC�^�Y�������āk�т̕\���Q�ɂ́uC'est une boite.�v�A�\���R�ɂ́uCe n'est pas une boite.�v�ƌ�����l�A�������Ђ�����߂ć����ɂ��Ĕ��ɂ��炴�釁���Ƃ�ł��o��������ł��B�`�T�c���Ƃ������^�́A���ЂŗB����F�V����̒����ł���w�T�h��݂̎莆�x�ɂ��Ȃ��̂ł��B
�@�{��͂��ɂ����������Ƃ��A�������������������ł��懁�ƁA�F�V����̊��̏�ɓ�����Ȃ�ׂĂ����������̂ŁA�����ōŌh������āA�S�̒��ł��l�т�ꂢ����ł��B�ʂɂ���ōߖłڂ��ł����킯�ł͂���܂���ǁA�܂���Ȃ�ɂ��o���Ă悩�����ȂƂ������Ƃ͔��Ɏv���܂����ˁB�i�����A�ꔪ�`���y�[�W�j
���p���Œ��������u���ꂩ��o�銪�ɂ��ė\���ҁv�́A�S12���̂���10���ɋy�сA�{�L���̊�ڂł���i�W�J�̑O�̃y�[�W�ɂ́A�q�w�F�V���F���w�فx���e�ꗗ�r���f�ځj�B����z�{�́s���[�g�s�A�̔��t�Ɓs�Y杂̔��t��2���́A�����̂��ߐG��Ȃ��������̂Ǝv�����B�s�u�b�N�K�C�h�E�}�K�W���t�n�����̕\�����i�\���Q�j�ɂ́A�a�a�Ƃl�l�ɂ��Βk�`���́q���ꖟ�k�r���ڂ��Ă���B�Ώۂ̏��Ђ́A����z�{��2���A�ܒJ���m�s�F�V���F�l�t�i�͏o���[�V�ЁA1990�N2��20���j�ȂǁA�S����6���B�g���������ɂȂ�s�F�V���F�l�t�́A�u�a�a�@�k�c�c�l�B���V�u���˂��B�^�l�l�@�J�o�[�A�\���A���Ԃ��A���̐F���Ƒf�ނ������ɋ��������āA�����Ɩ{���ɓ����Ă�����\�\�V���v���E�C�Y�E�x�X�g�̂���{�̂悤�Ȗ{�ł��B�v�Ƃ���B�����͂Ȃ����A�����ҏW�l�̓���v�ɂ����̂��B�g�����͂��̔N�A1990�N5��31���A71�ŕa�f���Ă���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�k2020�N6��30���`2020�N8��31���NjL�l
�i�]�N�s�}�����[ ���ꂩ��̎l�\�N�@1970-2010�k�}���I���l�t�i�}�����[�A2011�N3��15���j�̊����ɂ́A�q�N���i1970-2010�j�r�����g�E���J����16�y�[�W�ɂ킽���Čf�ڂ���Ă���B�ꗗ�\�̍��ڂ́u�N�v�u�o�ŕ��i�P�s�{���j�v�u�o�ŕ��i�V���[�Y�j�v�u�o�ŕ��i�l�S�W�j�v�ŁA�Ō�̌��J���y�[�W�̕\�̗��O�Ɏ��̒��L������i�����A�O�Z�O�`�O�Z��y�[�W�j�B
�i��1�j�@�P�s�{���́A���̔N�̊��s���̂Ȃ�����I�����Čf�����B�������A���꒘�҂̍�i���Ȃ�ׂ��d�����Ȃ��悤�ӂ�p�����B���̈ꗗ�\�́A�}�����[�̊��s���̃o���G�e�B���������߂ɂ����Ă���B�x�X�g�Z���[�E���X�g�ł��Ȃ���A���Ȃ炸�����x�X�g�E�Z���N�V�����Ƃ������i�̂��̂ł��Ȃ��̂ŁA���̓_�������@�̂������������������������B
�i��2�j�@�P�s�{���́A�P�s�{�𒆐S�ɂ��Ă��邪�A���̑��V���[�Y�̂Ȃ�����I���������̂�����B�|�́A�������̗�O�͂�����̂́A�قƂ�ǎ��^���Ȃ������B�܂��A���ɂ����������܂܂�Ă��Ȃ��B�V���[�Y�E�l�S�W�́A���������\���̂��̂������Ăقڂ��ׂČf�����B��i���̖`���̐����́A���s�̌���\���B�܂��A��i���̖����̐����́A�����̔N�E����\���B
������������炩�Ȃ悤�ɁA�����X�g�́u�}�����[�̊��s���̃o���G�e�B���������߁v�̂��̂ŁA�s�k�n��50���N�l�}�����[�}�����ژ^ 1940-1990�t�i�}�����[�A1991�N2��8���j�̂悤�Ȗԗ����͊�ނׂ����Ȃ��i���Ȃ݂ɑn��70���N�ɓ�����2010�N�ɂ́q�}�����ژ^�r�̏o�Ōv�悪�Ȃ��\�\�Ƃ������A������ł̊��s������Ȃ�A�Ƃ����ӂ��ɓ����s�����܁t�ҏW���̐ؐ^������͗ѓN�v����Ƃ̒��b��Ŏ��̎���ɓ������\�\�}���̎Г��ɂ͊���ҏW�̂��߂̃f�[�^�x�[�X����������Ă���̂��낤���A��ʓǎ҂����p�ł���}�����ژ^�^�f�[�^�x�[�X�͌��J����Ă��Ȃ��j�B���t�ɁA�����ɋL�ڂ��ꂽ���ڂɖڂ��Â点�A�W�J�~�ꂪ���ЂŕҏW�����{�i1970�`1996�j�A�g���������������{�i1970�`1978�͎Ј��Ƃ��āA1979�`1990�̓t���[�����X�Ƃ��āj�������������Ƃ͕K�������s�\�ł͂Ȃ��B�������A���X�g��1970�`1996�ɂ́u�o�ŕ��i�P�s�{���j�v��242�_�A�u�o�ŕ��i�V���[�Y�j�v��110�_�A�u�o�ŕ��i�l�S�W�j�v��121�_�A�v473�_�f�����Ă��āA���������܂Ȃ���������ɂ͂�����ׂ����Ԃ�v����B����āA�ȉ��ł��q���Ƃ����Ɍ���W�J�~�ꂳ��r�i2020�N5��31���j�ȍ~�A�m�F�ł������̂𐏎��A�NjL���Ă����B
�}���ŕҏW��S���������ꂪ�t�����X���w�������W��A�W�J����|�������Ђ͂��������|�����S�ƂȂ�A���ꂪ���߂Ɂq�N���i1970-2010�j�r�ɂ��o�ꂵ�ɂ������ʂƂȂ����B�܂��A�|�̖�҂ɂ�邠�Ƃ����́A�n�앨�̒��҂ɂ�邠�Ƃ��������S���ҏW�҂ɐG���䗦�����Ȃ��悤�ȋC������B�����ŁA����҂��Ƃ����ɒW�J�~�ꂪ�o�ꂷ��ꍇ�́u1.�v�̂悤�ɐ��������\���ɂ��Čf���邪�A�����I�Ȍ��n����͒W�J�~����ҏW�{�Ǝv������̂́i�}�����[�͒S���ҏW�҂��N���W�b�g���Ȃ��j�A���Ƃ������Ɍ��y�������Ȃ������^�̏��ڇ��́A�~�ϑ[�u�Ƃ��Ė`���Ɂu��v��t���āA�ʘg�Ōf���邱�Ƃɂ���B�q�N���i1970-2010�j�r�ɍ̘^����Ă��鏑�ڂ́A�i���j���\�������B
�@�}���Z���E�v���[�X�g�w����ꂽ�������߂āx�̌l�S����������ꂽ��㋆��Y���́A���l�Z�N��㔼�A�����̑����G�����ɔ��\���ꂽ���I�Ș_�����܂ރv���[�X�g�_�W���̏o�ł́A�����������̎��̖��ł����B�����ɒ��҂̎��I�ɂ���Ċ����P�s�{�����^�̃v���[�X�g�Ɋւ���_���ƃG�b�Z�[���l���ɂ܂Ƃ߂��w�������������ɂ킽���āx��PROUST, POT-POURRI�Ƃ����j�܂�������̂��ƂɊ��s�ł��܂����Ƃ��ς��ꂵ���v���܂��B
�@�e��i�̏��o�Ɖ��M�Ƃɂ��Ă͒��Ҏ��g�̎�ɂȂ銪���̔N��\�������ɂȂ��ĉ������B����e��i���ꊪ�ɂ܂Ƃ߂�ɂ������ẮA�e�тɋ��ʂ̌ŗL�����A��i���A���p���̂������ɒ��҂ɂ���ĕ\�L�@�̓��ꂪ�Ȃ���܂����B�w����ꂽ�������߂āx����̖{�����p�́A���v�����[�h���ɔłɂ��v���[�X�g�S�W�\���̖�҂Ƃ��Ă̒��҂̖���ł���A�w�W�����E�T���g�D�C���x�Ɓw�T���g���u�[�u�ɔ��_����x����̈��p�́A�K���}�[���o�ŎЂ̃x���i�[���E�h�E�t�@�����łɂ�钘�Ҏ��g�̖ł��B���̑��̃v���[�X�g�̍�i����̈��p�����Ƃ��̂Ȃ����̂͒��҂̖ɂ����̂ł��B���̂��Ƃ́A�{���ɂ����߂�ꂽ���т������ꂽ�����̎������Ă��āA�e�т̓�������M�����̘g���z��������̂ł͂Ȃ����Ƃ��A���҂͓��Ɏ��ɋ�������܂����B�Ȃ��u�}���Z���E�v���[�X�g�̕��@�v�̈�тƈ��p�̈ꕔ�́A�G�����\���̂悤�ɁA�p���@�����o�̂܂܂ōĘ^����Ă��邱�Ƃ́A���o�ꗗ�ɒf�菑��������ʂ�ł��B
�@��㋆��Y���̃v���[�X�g�W�̒���ɂ́A�w�ʘ_���w�}���Z���E�v���[�X�g�̍�i�̍\���x�i�͏o���[�V�ЁA���Z��N�j�̑��A�w�Y���ꂽ�y�[�W�x�i�}�����[�A��㎵��N�j�A�w�K���}�[���̉Ɓx�i�}�����[�A��㔪�Z�N�j�A�w����Q�o�x�i�V���ЁA����Z�N�j������܂����Ƃ�\���Y���܂��B
�@�P�s�{�Ɏ��߂��Ă��Ȃ������v���[�X�g�Ɋւ��镶�͂������W�߂Ĉ���ɂ����͂��߂Ă̖{�A���炭���҂̌\�N�ȏ�ɂ킽��ł��낤�v���[�X�g�����̎��n�������ɂƂ�܂Ƃ߂�ꂽ���Ƃ�S�����낱�т����Ǝv���܂��B�i�O�����`�O�����y�[�W�j
9.�̋{�V���Z�s�Z�̃g�����N�t���s��10����ɁA�g�����s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�������W�J�~��̕ҏW�ɂ���Ċ��s���ꂽ�i1987�N9��30���j�B���́A�g���̏������낵�̕]�`�Ƌ{�V�̏��̃G�b�Z�C�W���قƂ�Ǔ����i�s���������ƂɏՌ����o����B�������A�{�V�́q���Ƃ����r�̖����́u���a�Z�\��N������\�����v�A�g���̂��Ƃ���
�q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�̖������u�P�X�W�V�N7��28���v�ƁA���N���������Ȃ̂��B�W�J�̂Ȃ��Ŋ�悪��ق����̂́A�ǂ��炪�悾�����̂��낤���B���Ȃ݂ɁA�W�J���g����K�˂āu���܂łɓy���F�֕��������тƁA�U���A����Ɏ�̏������̕��͂������āA�����Ȗ{������܂��傤�v�ƒ�Ă����̂́A�g�����y���F�i1928.3.9.�`1986.1.21.�j�̈╶�W�s���e�̐�t�i�}�����[�A1987�N1��21���j�̊��s�����ɎQ�悵�i�ҏW�S���͏��c�N�v�A�����̔��ĎҁE�g���͑������S�������j�A���ׂ̉����肽1986�N�̏t����Ԃ��Ȃ��̂��Ƃ������i�O�f�q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�j�B���̂Ƃ��̒W�J�̋�����u�x����ɁA�{�V�����̎���̕��͂���{�ɕ҂ނ��Ƃ��ł����̂Ȃ�A�y���F�̐S�F�ł���O�q���l����u���Ǔ��сv�i�s�}�����[ �V���ē��t�̕��������A�W�J���g�̎�ɂȂ邩�j�������Ƃ邱�Ƃ��A���邢�͉\�ł͂Ȃ����A�ƁB
12.�́s�n�ӈ�v���u���[���k�}���p��339�l�t���s�O�N��1988�N9���A�W�J�~��͋g�����̐��z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t���k�}���p��328�l�Ƃ��Ċ��s���Ă���B�g���͓����́q���Ƃ����r�̍Ō�̒i���Łu���̔��N�Ԃɏ��������͂́A�킸���ɕS�\�����炸�ł���B��������u���픽�f�̋L�^�v�ɂ����Ȃ����̂��肾�B���₵�āA�ŏI�͂Ɏ��߂Ă���B�v�i�O���Z�y�[�W�j�Ə����Ă���A�V�K���e�����Łi�v���ЁA1980�j�̕����Ă̊e�͂ɑg�݂��܂��A�u���₵�āA�ŏI�͂Ɏ��߁v���̂́A���҂ł���g���ƕҏW�҂ł���W�J�Ƃ��u�F�X����Ђ˂������A�ςȏ����H�͂�߂ɂ��v�����ʂł͂Ȃ����낤���B
�s�v���[�X�g�S�W�k��1���l�t�́q����\�\�P�r�㔼�́q�ҏW���r�̕��̂́A�{���Ɉ������s�}�����E���{��n 23�t�t�^�q�ҏW��L�r�i����A�W�J�~�ꎷ�M�j��f�i������B�����Ƃ����ꎩ�̂����̋Ɩ����͂�����A�W�J�ƒC���̂ǂ��炪���������A���̂̓������炾���ł͌��ߎ�Ɍ�����B�}���Ńv���[�X�g�S�W�́A�W�J�̑ގЌ�A�k���́E��ؓ��F�E�ۊ�����E�g���`�E�g�c�鑼��l�s�v���[�X�g�S�W�k�ʊ��l�v���[�X�g�����^�N���t�i1999�N4��25���j�Ŋ��������B�q����\�\19�r�́q��ҏЉ�r�ɑ����Ė����ɂ�������i�����������A�C���l�Y�̕M�ɂȂ邩�j�B�u�ŏI��z�{�w�v���[�X�g�S�W�x�ʊ������͂��������܂��B����z�{�w�X�����Ƃ̂ق��x�i�w����ꂽ�������߂āx���ҁA�S�W��ꊪ�j�̊��s����㔪�l�N�㌎�ł�������A�����܂łɏ\�l�N���J����v�������ƂɂȂ�܂��B�ǎ҂̊F�l�ɂ͂����ւ�Ȃ����f���������v���܂����B�S��肨�l�ѐ\�������܂��B�܂��A����ɂ��S�炸�Ō�܂ł��w�ǂ����������肪�Ƃ��������܂����B�^�{�N�ꌎ��\�O���A�{�S�W�ɂ����āw����ꂽ�������߂āx�l�����������܂�����㋆��Y�搶����������܂����B�����������F��\�������܂��B�v�i���y�[�W�j�B
�k2021�N6��30���NjL�l
���o���ďC�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�N4��15���j�̕ҏW�S���́A���̌�A�����V���Ɉڂ�����������j����ł���B���͓��������̋g�����������E���M�������A���������͎v���Ђŋg�����S���������킯�ł͂Ȃ��炵���i�ӔN�̋g����������e�������Ă����Ō��͏���R�c�ŁA���������͓����܂��o�Ă��Ȃ������g���̑S���W���Ă����菑��R�c����o����̂��Ǝv���Ă����j�A���̌��e�̍Z�{���g���ɋ߂��l�l�Ɉ˗����Ė��S���������̂́A�Ȃ܂��g�����̎��тɏڂ����Ȃ����������ɂ������čD��������������Ȃ��B���́q�g�����N���E�����E�Q�l�����r�͔����܂߂�39�y�[�W�����āA���������̜ϜȂōŌ�̃y�[�W�Ɂq�q�g�����r��T�����@�\�\�N���E�������쐬���Ȃ���r�Ƒ肷�邠�Ƃ������������Ă�������B�����{���ɂ���������Ԃ������������A���̕��͂ɂ������ԂԂ����������̂��B�ȉ��ɓ����̂����܂��̃u���b�N���������A���[�v����p�@�őł����Ƃ͂����A�d���7�|22���l33�s3�i�g��40�y�[�W�߂����e��W�J�~�ꂳ��Ɍ��Ă����������̂́A���܍l���Ă����肪�����A�K�^�Ȃ��Ƃ������Ǝv���i�q�g�����N���k��i�сl�r�̃^�C�g�����̎ʐ^�́q�g�����N���r�̑��e�j�B���z��������������������j����ɉ��߂Ċ��ӂ���B
�{�����̂����A�N���́q�g�����ڍהN���r�Ƃ������ɂ����g�������M�q�N���r�A�킽���́q�g��������ژ^1940�]1989���o�сr�𒆐S�Ɏ��M�����i�q����ژ^�r�������肵���Ƃ��ɖ����̓�̎��т̑��݂����w�E�����������̂��A�g������̍Ō�̕ւ�ɂȂ��Ă��܂����j�B�`�L�ɂ͈Í������Ɣo��֘A�̎������������A�ȂɂԂ�����Ȍ�̍�Ƃ̂��߁A�d�v�ȍ��ڂ��k��Ă��Ȃ����Ɯ����B���������ƍl������̂ŁA�����̂��������ژ^�͑��{�ʂ��ڏq�����B�Q�l�����ژ^�̍쐬�ɂ������Ắq��v�Q�l�����r�ق����Q�Ƃ�����Z�N���܂ł̂��̂{�������A�ԗ��I�E�̌n�I�łȂ����Ƃ����f�肵�Ă����B
�L�ډk��̕�A�g���Ə����k���i�̔����A�f�ڎ����┭�\�����̖��ڂ̂��̂̊m�F�A�V�����̔�����S�|���Ă���B����Ƃ��������₵�Ă䂫�����̂ŁA���C�Â��̕��̂����������肢����B
�����̎������ؗ������Ă����������g�����v�l�z�q����͂��߁A�ѓ��k�ꂳ��A���o������A���j������A�W�J�~�ꂳ��ɐ[�����ӂ������܂��B�i�����A�O�y�[�W�j
�킴�킴��������܂ł��Ȃ����A�ѓ��k�ꂳ��͋g�����̑��V�ψ����߂��g���̍ł��Â����F�A���o������͎��l�ɂ��Ė{���̊ďC�ҁi�ȑO�͉͏o���[�V�Ђ̕ҏW�ҁj�A���j������͋g���̒P�s���W�̑��������Ă��鏑��R�c�̒S���ҏW�ҁA�W�J�~�ꂳ��̂��Ƃ͖{�e�ŏڏq�����B�����͕s�v���낤�B�J�肩�����A�W�J����́s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�̒S���ł͂Ȃ��̂ł���B���̋g�����t�@�����������̌��e��ǂ�ł����������̂́A�ЂƂ��ɋg�����Ɓq�g�����r�ւ̌h���̂Ȃ���킴���낤�B���̂��ƂɐS���犴�ӂ���B
�k2021�N8��31���NjL�l�\�\���̂P
���q�h�F�s���̕Y����[�G�p�[��]�\�\����70�N��t�i�݂������[�A2006�N8��10���j��ǂ݂������Ă��āA�L�����i1935�`1989�j�̒����̂��Ƃ��v�����B�����ās���҂Ɓi���Ắj�Y�p�\�\���^�t�H�[�� ���^�����t�H�[�Y�t�i�}�����[�A1986�N11��28���j�̊����́q��r�i�����A�k�O��Z�y�[�W�l�j�ɂ��ǂ�����B���������Ȃ����A���҂̖L�����̃y���ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B�S���������B���Ȃ݂Ɂs���҂Ɓi���Ắj�Y�p�t�́u�����O�Ɂv�������Ă���B
�@�@�@�@�@��
�@�@�@�L�������[���Y�p���\�\
���̖{�̐����Ɏ����g�Ɓi�قƂ�ǁj�������^�����Ă��鑼�ҁi���ҁA���ҁj�����ɁB
�i�ނ�͂��Ȃ킿�����g�̖Y�p�A�����Ď����g�͂��Ȃ킿�ނ�̖Y�p�B�j
�@�@�@�Y�꓾�ʊ��ӂ��\�\
���̖{�̋��d�ҁA����҂ł�������
�W�J�~��A���N�i�A�������ق邳��ɁB
���q�́s���̕Y�����t�ɂ́q����C���̂��Ɓr�Ƃ����͂������āA�u���̎��͂ɂ́A����C���Ɛe�����l���������\�������炢���B�������A�����������Ɖ�����̂́A���Ȃ�x���B�g��������i�������j�Ȃǂ́A����тɁA����C���ɉ�ɍs���A�Ƃ����߂Ă��ꂽ���A���̂��тɎ��́A�����Ă����B�v�i�����A���l�y�[�W�j�Ƃ����{���ɕt����ꂽ���́A�{�����������Ȋ�����1�y�[�W���߂��������āA�q�g�����̂��Ɓr�Ƃ����{���̑ւ��ɂȂ��Ă���悤���i�g���́q�ѓ��k��̂��Ɓr��q�{��~�̂��Ɓr�̏͂ɂ��o�ꂷ�邪�A���̖{�ɐl�������͂Ȃ��j�B���́i�������j�́A�u�g��������Ƃ́A�����@���ł������悤�ɂȂ������v�������Ȃ����A�_�ے��ɂ������}�����[�ɖK�˂čs���ĎЂ̋߂��̋i���X�Řb������A���R�a�J�̊X�ŏo����Ă��������肵�Ă����B���Ԃ�A�ŏ��́A�ނ̎��W�̏o�ł����肢�ɍs�����̂��낤���A�b�͑��A���o�ŎЂ̑�ς��ɐG��āA��y�Ƃ��ĐS�z���Ă����Ƃ��������̂������B�v�i�����A��O���y�[�W�j�Ǝn�܂�B���q�͕ҏW�Ҏ���A���̏Љ�Ȃ��Ă��N�ɂł���ɍs�����Ƃ�������A�g����K�˂��̂����̓`���낤�B�c�O�Ȃ���A�{������͖L�����Ƌg�����������̊ԕ����������͂킩��Ȃ��i�L�肳�S���Ȃ������ƁA�g�����Ɖ�@����������A���̂Ƃ��̘b�̗l�q����́A�ʎ����Ȃ��悤�Ɋ�����ꂽ�j�B
�k2021�N8��31���NjL�l�\�\���̂Q
���ڂ̒S���ł͂Ȃ��悤�����i���p�����j�A�����Ɂu��㎵��N�����^�e�r�f��v�Ƃ���A���h���E���[�����i�e�r�f���j�s�A���N�T���h���E�f���}�t�i�}�����[�A1971�N10��5���j�́q��҂��Ƃ����r�ɂ����y������̂ŁA�Ō�̒i���������B
�@��҂��܂��w�����e�E�N���X�g�x�Ɓw�O�e�m�x���n�ǂ��A�W�����k�E�����[�́u�l�[�����v��u�����}���S�v�̉f��ɐS��������ꂽ�B�p�����Ŋς��G�h�E�B�W���E�t�B�G�[���̒֕P�͈��Z�Z�N�̃p���̊ϋq�ɗ܂𗬂����Ă���B���[�����ɂ��Ă��w�o�C�����`�x�̌Â��M��D���ł������B���������āA�u�[���E�~�b�V���̖{���Ŗ{������ɂ������A����Ă݂����Ǝv�����B���������w�ȃ��[�����̏��������͈͂ӊO�ƍ���Ȃ��̂ł������B�S�Ȏ��T�������͂��߂��炫�肪�Ȃ��B�莆�̂Ƃ���ɂȂ�ƑO��̎�����悭�킩��Ȃ��B�r���ʼn��x�������o���Ă��܂����B����Ō��ǁA���q�����A������j���A�q�������ɓr���̕����̉�������肢���A����ɍŌ�̂��߂�����ɉ������F�搶�܂ł���`�����肢�A�ŗL�����̓ǂݕ��܂Ō��Ă��������n���ł������i�����������搶�̌�w�E�ɂ��S�炸���{�̊���ɂ�������̂�����j�B�}�����[�̕��ł��A�o�ł̌������߂ĉ��������������͂��Ƃ��A�����G������͂��߂Ƃ��A�R�c�䎙����A�W�J�~�ꂳ����ւč֓��W����Ɏ���݂Ȃ���̌䐢�b�ɂ���Ă悤�₭�������邱�Ƃ��o�����B�������A���̑��̕��ɂ�����f�����������ƂƎv�����A��Ԃ̖��f�͓ǎ҂ł��낤�B�����ɋL���Ċ��ӂƂ��l�т̂��邵�Ƃ������B�i�����A�l�Z�l�`�l�Z�܃y�[�W�j
�k2021�N9��30���NjL�l�\�\���̂P
���̂Ƃ���g���������{�̒T�������˂āA1950�`1970�N��𒆐S�ɒ}�����[���s�̕��|���̒P�s�{�����Ă���i�{����ǂ�ł���킯�ł͂Ȃ��j�B�������W�J���ւ�������Ђɏo������B��ҁE���҂̂��Ƃ��������悤�B�܂��A�s�G�[�����A�����E�V�����i�˓c�g�M��j�s�l�Ԃ̏ؐl�����\�\��\���I�t�����X���w�_�t�i1974�N5��25���j�B�����Ɂu��㎵�O�N�\�ꌎ�v�Ƃ���q��҂��Ƃ����r�ɂ�������B
�@�{���̓s�G�[�����A�����E�V�����i���Z�O�\��㎵��j���w�l�Ԃ̏ؐl�����\�\��\���I���w�ɂ�����l�Ԃ̏����A�v���[�X�g�A�W�b�h�A���@�����[�A�N���[�f���A�����e�������A�x���i�m�X�A�}�����[�A�T���g���A�J�~���x�k�c�c�l�̖|��ł���B�k�c�c�l
�@�k�c�c�l
�@�k�c�c�l�Ȃ��A�{���̕���������Ĉ�ʓI�Ɂu��\���I�t�����X���w�_�v�Ƃ������A����ɂ���Ē��҂̈Ӑ}�����ɗ����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B
�@�Ō�ɁA�{���̊��s�ɂ������Ȃ݂Ȃ݂Ȃ�ʌ�z���������������}�����[�̒W�J�~�ꎁ�A�܂����e�̐������̑��Ō�ʓ|�����������������[�̎��c�|��Y���ɂ��̏������Ă������\�������鎟��ł���B�i�����A�O�l�܁`�O�l���y�[�W�j
���𗧈āE���i�����̂��W�J�~��A�ҏW������S�������̂����c�|��Y�i1942�` �j�Ƃ��������낤���B�v���[�X�g�`�J�~����9�l�̊�ʐ^���R���[�W�������W���P�b�g�̃f�U�C���́A�������ق�Ǝv�����B
�k2021�N9��30���NjL�l�\�\���̂Q
���c���s�s���̐U���t�i1990�N7��30���j�̂��Ƃ����q�s���̐U���������r�ɂ͂�������i�����Ɂu����Z�N�l����\�O���v�j�B
�@���Ȃ蒷�����Ԃɂ킽�肻�������ɏ������F�X�̎��̃G�b�Z�[���A����܂ł�����̖{���o���Ă��ꂽ�}�����[����܂��o�����ƂɂȂ��B�O�̒S���҂��a�C�őސE���������ŁA����ǂ̓��@�����[�W�̂����Ƃœ���݂̒W�J�~��N�̍��܂�ł���B
�@�k�c�c�l
�@�傫�ȏo�Ŋ��̂��߂ɏo�ŎЂ����s������e���{�ƌĂ�������ɂ̂����Z������ѓ���Ă���̂́A�S�W�Ɏ��߂�ꍇ�ł��Ȃ���A���ʂЂƂ̂��Ȃ����Ƃ��炤���A���̓��e�����҂Ƃ��Ă͂����ŏ��߂ď��������̂ł���A���������̌㔭�W�I�ɏ����@����������ɂ����̂́A���邱�ƂɁA��Ɍ�ǂ̕��Ƃ̊W����͏\���Ӗ�������ƌ��Ȃ��ꂽ����ł���B
�@���Z���I�ւāA���܂�Ԃ̓��Ă�Ȃ��Q���ɁA���Ȃ���ӊO�̊����Â����B�V���Ԉ�ӂƂ���܂ōs���\�����玸�����ʂ��Ǝv�ӂƁA���ł��������Ȃ��B�i�����A�O�O�܁`�O�O�Z�y�[�W�j
�Ō�̈ꕶ�͖��ǂɒl����B���c�����{���̂��Ƃ�����������1990�N4��23���Ɩ{�����s��7��30���̊Ԃɂ́A�g�����̟f����5��31�����������B
�f��͐�����^����ꂽ�G��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�@�@���w���}���E���@�����i�l���c���F�s�f��j�ւ̏��ҁt�i��g���X�A1998�N4��9���j�́q���p 1895-1998�r���u1919�v�̍��j
 �@
�@
�s�f��|�p�t1969�N3�����̕\���i���j�Ɠ����E���y�[�W �k�g�����̒k�b�L���̖`���l�i�E�j
2007�N12�����q�g�����Ɖf��i1�j�r�ł��G�ꂽ�g�����̒k�b�q�����ƍ��ׁ\�\��a�����ƐV������Ƃ����r�̏��o�́A�f��|�p�Д��s�̎G���s�f��|�p�t1969�N3�����k17��3����259���l���`��O�y�[�W�B�q�����̍�Ƙ_�r�̃R�[�i�[�ɁA��؎u�Y�N���M�́q���̕������߁\�\���������u��K�v���v�u�فv�r�ƂƂ��Ɍf�ڂ��ꂽ�i�����Ɂu�i�悵�����E�݂̂遁���l�j�v�Ƃ���j�B�g������l�̉f��ēɂ��āA���̉f���i�ɂ��Č��y�������Ƃ́A���̒k�b�ȊO�ɑ��݂��Ȃ��Ǝv����B�ȉ��ɂ��̑S�����Z�����Čf���邪�A���ꂪ�f�ڂ����ɂ��������o�܂͕s�ڂł���i�Ȃ��A�����ɂ͍����c�E�y���F�E��唪�E�R�{�W��̍��k��q�Z�b�N�X�ƌ|�p�\�\���{�r�d�w�f��ᔻ�r���f�ڂ���Ă���j�B�k�b�{�����̏d�v�Ȑl�����i���ɂ́A�����̒��i��ɃC���^�[�l�b�g��̋L�ڂ��������j�Ƀ����N���Ă������B
�@���Ƃ��ƁA�ڂ��Ƃ����l�Ԃ͔�]�Ƃ����s�����͂ł��̂����܂���B�y���݂Ō����Ⴄ�Ƃ��A���Ƃ��������ɂ����炷���̂����邩�Ƃ����C�����Ō����Ⴄ�B�s���N�f��͂��鎞�����Ă����̂ł�����ǁA��͂�A��̐ϗ��Ɋтʂ���Ă��āA���P�����ɋ߂��ϗ��ςœ������Ⴄ����A���ق炵���Ȃ��Ă����B��a������́u����̋G���v�́A�����łȂ��Ƃ����\��F�l���畷���Ă����̂ŁA����Ǝv���Č����B��̗L���ȃx�g�i���̐n���ŕ����h����Ă���ʐ^�Ə��������߂邱�ƂƂ̑Δ�Ƃ������A�S�̂ɃZ���t�������Ƃ�ɂ����̂ŁA�x�g�i���A��̕����Ȃ̂��A�ǂ������{�肪�łĂ���̂��A�Ӗ��͂悭�킩��Ȃ��������A���ꂪ�J��Ԃ���čs���Ԃɑ����̊����������܂����B�ׂ�����ʂ͂��ڂ��Ă��Ȃ��̂����A�J�E���^�[�̏�ʂŏ��������߂�Ƃ���Ȃ悩�����B���ɂ܂��߂ɍl���Ă���Ă��܂����ˁB�u�r��̃_�b�`���C�t�v�u�т́k�́����l�������e�v�Ɗr�ׁA�O�{�̒��ł́u����̋G�߁v����Ԕ��͂����Ȃ��ł����A�������Ƃ������Ƃɂ����Ă��A�x�g�i���Ƃ������̂ւ̈Ӑ}�Ƃ����Ӗ��ɂ����Ă��B�u�r��̃_�b�`���C�t�v���A�ڂ��̓G���e�b�N�Ȃ��̂����҂��čs�����̂�����ǁA����Ȃ��͍̂Ō�̍Ō�Ƀ_�b�`���C�t�炵�����̂��Q�Ă���Ƃ������ɓ˂��������`�����ŁA���Ⴍ�ɂ����قnj����������Ǝv�����B�������̃p���f�B�Ȃǂ�����Ă���ł���B���̂Ƃ��Ă͉������ǂ��啪����ȍ�i���ˁB�����ς̈�{�̖��ے������ĂˁB
�@�f����Ă��̂́A�ڂ��ɂƂ��Ă͋L�����悤�Ƃ����C���Ȃ����A���悩�������Ƃ��������ōς�ł��܂��B������ǂ����ǂ��Ƃ������Ƃ͂����Ȃ�����ǁA�����̍�Ƃɂ͂Ȃ��V�����͂��Ȃ肠��Ǝv���B
�@�u�т́k�́����l�������e�v�́A�V�h�̃A�[�g�E�V�A�^�[�ŁA�ѓ��k��Ƒ剪�M�ƎO�l�Ɗς���ł����A��͂����Ȃ������ȁA�ǂ����ǂ������̂��B����Ȃ����炢���Ƃ������Ƃ͂Ȃ�����ǁA����Ȃ����̂����Ƃ����l�͍D���Ȃ�ł��B�l�Ԃ̍l�����̒��ʼn���Ȃ��̂����l�Ƃ����̂͐������ƂŁA�ڂ����N�ɂ�����Ȃ������A�L���łȂ��āA���}�Ȍ���ō�肽���B�ł������Ă��܂��킯�ˁA�܂������Ă��܂��킯�ˁB�f�悾�ƁA����_����Ȃ����̂������Ȃ����Ƃ����C������B
�@�ڂ��́A���̐V�����f���ƂƂ����̂͒m��Ȃ�����ǁA���Ƃ��Ύ������ꍇ�A�ڂ��̏ꍇ�͐悪����Ȃ��B�n������܂��n��A�ǂ��Ŋ�������̂��ȁA�������A�����Ň��ƂȂ�킯�ł����A�f��̏ꍇ�̓V�i���I�Ƃ�������ňꉞ�̍\�}�Ƃ������A�i�s�w��������B���̏�őn��V�������z�Ȃ�A�C���[�W�B��������̂ł͂Ȃ����ȁB��a������̂悤�ȎႢ��Ƃɂ́A���A�B��c�c�Ƃ����悤�ȂƂ��낪�����Ȃ����Ƃ����C������B�B�邾���łȂ��ĕҏW�����邵�A�܂��f��Ƃ����̂̓��Y���Ƃ�����������ڂ��������}������ǂ����߂�B��������̎Ⴂ��Ƃ̓|�b�|�b�|�b�Ɛ��Ă������ɂ����������Ȃ����Ă������Ƃ�����B���������������悤�ɁA�ڂ��͉f����y���Ⴄ��������A��Ƃ̎����Ă�������ǂ����悤�Ƃ��������Ƃ͂��Ȃ��B�ނ��������Ƃ�����f��̂�����̂͊y���߂Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����B�����ł͐V������������Ă��Ă��A�f��ł͂��܂�ÏL���̂͌������A�����������Ԃ����܂������ė~�����Ǝv���B�������o�T�o�T���ĕ��G�Ȏv�l��D�荞�܂��ƍ����Ă��܂����Ƃ�����B�~�߂Ċӏ܂ł��Ȃ����E������B��a������͂������Ȃ�悤�����A����͂܂��A����������B�N�ł�����̂͂����Ƃ͂����Ȃ�����ǁA�l�ԂƂ����̂͂�͂�œ_���i���āA���̐l�̂͂��������ǂ�ł݂����Ƃ�����ł���B��a���f����A�����Ƃ����Ɗς����Ǝv���B���āu�k���ۓ��̎s�ꁨ���̂̎s���l�v�Ƃ������炵����i���������ь��̂��D���������B�g�C���̏�ʂ��������悭�āA����ȉf������l�������̂��Ǝv�����B�g�C���b�g�y�[�p�[�����̌��ɂ�����ł����s�ׂƁA���������[�Ɖ������ĂĂǂ�ǂ�Ɗ�����Ă����̂�����ƁA�ڂ��͎��o�I�l�Ԃł�����A���������l�Ԃ́k�i�i�V�j���{�\�l�Ƃ��������|�Ƃ����̂��悭�����k�{�\���i�g���j�l���B�h���C�ȍ���������̂��������Ǝv���B�ڂ��͗������������I�ɂȂ����Ⴄ��������B
�@��a������͂����ƁA�����Ȑl�Ԃ��Ǝv����Ŋ��҂͂��Ă��邪�A���̂łǂ��Ƃ����Ă��Ђƒʂ�̂��Ƃł͉���Ȃ���Ƃ��B�ᏼ�F���́u�َ���������k�Ƃ������l�v���ŋߊς�����ǁA������Ɛ����B���̂������A�u�n��v�̉e���Ȃ����邩������Ȃ�����ǁA���ꂾ���̂��̂������������Ƃ����̂͑��h�ɉ�����B��͂�ᏼ�̕������ǂ��Ƃ��������X���ɂ����ČZ�M���̂Ƃ��낪�����Ȃ����ȁB��a������̏ꍇ�́A���܂肵�����݂����Ȃ̂��Ȃ����A�����������č���Ă���Ǝv���B�u�_�b�`���C�t�v�Ȃ�Ă����̂͋t�ɂ͂���k�i�i�V�j�����l���ꂽ�悤�ȋC�����āA���X�g�̏��Y���̃_�b�`���C�t��������ƌ����āA�o�T���Ɛ���������Ȃ�Ă����̂́A���҂��Ă����̂ɃV���N�ɂ�������ǁA�����Ɍ������ȂƎv���܂��ˁB
�@�ڂ��́A���q����́u�������v���ƂĂ����삾�Ǝv���Ă���B�������A�f��̋Z�@�I�Ȃ��Ƃ͂悭����Ȃ�����ǂ����Ƃ��ꂢ�ɎB���Ǝv���B����}�Ȍ��ŁA�ӎ��I�ɉ��Ȃ��B���Ă���悤�����A���ꂪ�܂��ʔ������Ȃ��Ǝv������A�u����̋G�߁v�͂����ƈÂ����Ő[�x���������B�Ƃɂ��������̂悤�ȏ��s���I�l�Ԃ́A������x�����̂����䂤�G���e�B�N�Ȃ��̂��B�낤�Ƃ��Ă���l�Ԃɋ�������B�܂��߂ȍl�����ƕs�����ȍl�����ꏏ�ɓ����Ă���B�ᏼ��i�ł����A�]���ɂȂ����u�Ƃ��ꂽ�����v���u���̕��Q�v�̕����D�����B�R�J���j�̂��炵�����������I�@�Ă��Ȃ���ʂ̍����B���肤�邱�ƂȂ�ł���B�|�p�k�����Ál�����ݒ�����Ă��Ȃ��ȁB���Ă��Ȃ��āA�������[�݂�����B�u���r�~�v�͂��Ƃ̖{���ǂ�łȂ���������A�S�R�܂�Ȃ������B��a������̋r�{��������Ȃ����Ǝv���B�ςȂ���C���C�������B���Ă��Ă����̂������Ȃ畐�q�́u�����G�c�������v�̕��������B���Ă��Ď���������܂ł����Ώ������k�ꁨ�c�l���łȂ��Ȃ邯��ǁA�c�c�����l����Ɖf��Ƃ����͓̂���B���\���ꂽ�Ƃ������̂́A���Ɋւ��Ă����ƁA�����ł�����Ȃ����̂������ł����A�N���ڂ���⑫���Ă悭�݂Ă����l������̂ł͂Ȃ����Ƃ悭�v���B�f�悾���Ă������Ǝv���B�����ɂ����ĉ���Ȃ��Ƃ��낪����A�����厖�ɂ��Ă�����ł��傤�B���������ӂ��ɂ��č�҂͎��M�������Ă����A�|�p��i�͂��ׂċ~�ς���āA�悭�Ȃ��Ă����B���̈Ӗ��ŁA�u����̋G�߁v����ƍ��̔ނ��r�ׂ�ƁA���̂���́A�x�g�i���ɑ�����̐����S����ɗ���Ă��āA�����䂤�������Ȃ��_�o�̐l�Ԃ����������߂āA������y�����߂邩������Ȃ�����ǁA�ڂ���͂����ƂȂ�Ȃ�����A���ɍ��R�Ƃ����G���`�b�N�Ȋ�����������B��a������̒��ł́A��ԏ������Ă����i�Ǝv���Ă���B��ؐ����́u�E���������v���ς����A�u�r��̃_�b�`���C�t�v�Ǝ����g�[���̍�i���ˁB��a�����͎x����������Ƃł��B�i�k�j
1966�N�̌��J����11���������́A�s����̋G�߁t���f��قŊςĂ��Ȃ��B�����ō���A�{��̂c�u�c�i�c�h�f�A2017�j����肵�āA����̂o�b�̃��j�^�[�ƃw�b�h�t�H���Ŏ��������i�Ȃ�ׂ��Ȃ�A�ϋq���f��قŊς�悤�ɂ��Ăc�u�c���ӏ܂������̂����j�B�g�����͂u�s�q��c�u�c�ʼnf����ςȂ��������낤���A�e���r�ŕ��f�����f��͉ƒ�ŊςĂ����i���P�j�B�������ɕ키�킯�ł͂Ȃ����A���͎��⏬���i�≹�y�j�̂悤�ɂ́A���͓I�ɉf�������ӗ~���N���Ȃ��B

�s����̋G�߁t�̂c�u�c�i�c�h�f�A2017�j�́u��ʍĐ��v�̉��
��Ɍf�����s����̋G�߁t�̂c�u�c�́u��ʍĐ��v�̉�ʂ�6�����āA�u�A�҂����j�v�u�g�D�v�u���J��̉e�v�u�́v�u���q�̊�݁v�u�����v�ł���B�����m����c���F����k��Y�ҁs��a�����_�C�i�}�C�g����I �r��̃_�b�`���C�t�t�i�t�B�����A�[�g�ЁA1994�N6��19���j�ɂ́s����̋G�߁t�̎B�e��{�����^����Ă���B�{��̃��P���s��ꂽ�̂����J���ꂽ1966�N���Ƃ���A53�N�ȏ�O�̓����i�B�e��{����E���A�H�c��`�E�a�J�E�V�h�A�ق��j�����߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B�������t�B�����͔���������A�������Ɉٍ��́A�Ƃ܂ł͎v��Ȃ����A����ɂ����߂Ċς鎄�ɂَ͈��Ԃ̕���̂悤�Ɋ�������B�����A1960�N��㔼�Ɋς��g���͂����ł͂Ȃ������͂����B1975�N�ɏI������x�g�i���푈�͂܂������Ă������i���Ȃ킿�f��̂Ȃ��̎��Ԃ́u���`�v�ł���j�A�g��������{�鍑���R�̕��m�Ƃ��āi���N�̍ϏB�����o�āj���F����A�҂����̂́A��������20�N�O��1945�N�������B�܂肱�̍�i���A����܂ł̋g�����̐l���ɂ�����ł��ߍ��ȑ̌������ыN�����_�@�ƂȂ����A�ƍl���邱�Ƃ͋�����邾�낤�B
���́s����̋G�߁t���ς����ƁA1�T�Ԃقǂ��������J���ās��a�����_�C�i�}�C�g����I �r��̃_�b�`���C�t�t�̎B�e��{����ɂ��Ȃ���A���̉��������Ă݂��B����Ƃǂ����낤�B�Ȕ����B�e��{�Ƃقړ������̂͂�������A�����������ƁA������F����|�������y�̓}�����o��u���V�ɂ��h���~���O�Ȃǂ�p�������_���W���Y�n�̂���ŁA�d�q���ɂ��T�E���h�G�t�F�N�g���o�ꂷ��B����ȂǁA�f�������Ă���Ƃ��ɂ͂Ȃ��Ȃ��C�Â��Ȃ������B���������Ɏc��̂́A�K�b�g�M�^�[����ɂ����u���������̎�ҁi�P���j�v�i�����A�O�Z�y�[�W�j���S���u�P���ȃu���[�X�v�i���O�A�O��y�[�W�k�ȉ��u�i31�j�v�ƕ\�L�l�j�ł���B�̎����������B
�u�P���ȃu���[�X�v
〽���͂߂��߂�@�₽�����^�n��e���ȁ@���������Ł^���̐H�ׂ��A�o�����^�Ԃ��Ă�����^����͉��̂��A�Ɓc�c
〽�n��@�A�o���̂Ƃꂽ�n�^��P����ʂ鎞�́^������肤�Ȃ���čs���Ă�����^�Ђ��߂̉��Ł@���l������
〽��������R�ɂȂ�ʂ�^�n�����ȂȂ����␁���i31�j
〽��������R�ɂȂ�ʂ�^�n�����ȂȂ����␁���i35�j
〽�������@���̂���т�^�����ȁ^�b�艮���m�������^�������@�������
〽�j���A����������������A���[����т낤�ǂ��т��ɂ����A�ނ���炭����ꂦ�U�肭��܂������A�S��r���A��̂Ȃ肭�т���A�n�b�V�Ƃ��肢�藎�Ƃ���c�c�i37�j
〽���O�͌��邾�낤�₽�����^�~�J���̔��̂ӂ����Ƃ�^���̑O�Ł@�_�[�����^���O�ɂ�����@�S�̂���
〽��������R�ɂȂ�Ȃ�^�n�����ȂȂ����␁���i48�j
�u���Ă�����ꂽ�ŔB�^���̃x�g�i���̋s�E�̃V���b�g�k�c�c�l�v�i33�j�A�Ƃ��́u�ʐ^�p�l���ɓ˂������Đk����i�C�t�B�v�i40�j�A����ɒ��J�̂����u���C���̔ؓ��v�i46�j�́A�g������Ȕ��̂Ȃ��ŖڂɂƂт���ł���͋�ł���B�������̋ɂߕt���́A���J���P���ɂ����u�L���ڗ��v�i47�j���낤�B�����ł͒��J���n�Ӎj�m�킽�Ȃׂ̂ȁn�Ɍ����Ă��Ă��āA�M�^�[�������ꂽ�u�P���ȃu���[�X�v�ɂ͎O�������u�L���ڗ��k�̗�����l�v����肤���Ă���B���́A���o�ɂ�����u臉��m�o�m�T�u���~�i���n���ʁv�Ƃł������ׂ����o���哱�����̂��A�ēE�r�{�̑�a�����Ȃ̂��A����E���̎ᏼ�F��Ȃ̂��A����Ƃ����ēE�r�{�̓c���z���Ȃ̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ����A���ɂ�����ׂ����̂�����B
������G�i�E�E15�j
�@�@���o�́s���㎍�蒟�t�k�v���Ёl1967�N2�����k10��2���l�B
���鐶��
������Ԃ̃X�~��
��܂��ꂽ������̂��͂���
����o�T�~�E����o�T�~
����͖�̑�����
�����̖A�̏㏸����̂��ώ@����
������䍂����
�����^�C���̏�ł�
�l�����Ȃ����l����
���̎��̂Ȃ��̖I
�J�ӂ閃
�ڂ����N���C���������Ƃ�������
�ЂƂ�̏���������
����͂ڂ�����\�˂̂Ƃ�
���Ȃ����V�i�̏����Ɏ��Ă���
�삦��Ɠ����ɂ₹�钱
�Ђ낪��Ɠ����ɂڂ܂��
�����ł����H
�ڂ��̑z���K�P��
�C�ւ�����ōs���r��
����ꂽ���ƍ߂̐������I
�c�����畗�C�����炢��
���R�ȏ�Ԃ�
�ڂ��̊G�����܂��H
�a�C�̎q���̎牺�̂Ȃ�
�Đ����I�Ȗ�̂Ȃ���
���̏o��
�u���[�̋�
�R���N�̖̂Ȃ����т̓���
�J�P�������V�i�̕ꖺ
�������r���l���炵�čs��
������܂錩��
�����Œ��
���m�̂����Ȃ�
���ꂱ��������������̊G
������������̃r����E�j
������������̎�
�����ߗ��R���I
�������������
���̉E����������
�Ζ�ɂ��痁���܂ł���
������G
�F�ʂ̓����i�F�E4�j
�@�@���o�́sthe high school life�t�k�l�`�b�l1968�N8���k15���l�́k�R�����q����܂ӂ낶���Ƃ̂����r�l�B
�������錜�̉���
�����킽��
�킽���͕�D�����l
�����w���̐F��
���̂Ƃǂ��ʐ��E��
���Ẵt�N���E
�܂Ԃ�����̕���
�Â��Ԃ̂悤�ɂЂ낪��~
���̒��S�߂Â�
���N�̕֊�
�Ԃ��p��������
�Ō�w�̔��߂̂Ȃ���
�܂��
�������n�̕���
�����݂��������
���Ă͂����Ȃ��@�܂��ċ����Ă�
�����܂����������鎞�ゾ����
���ˊ�̐j��
�h���Ă���킽��������
������Ƃ���
������E�̂����
���_���Ƃ���
�����₭���ɉf��
�\������
�ɂ��ɂ���������
��U�}�̂���Â���������
�O���[���𑖂�
�葫�̂Ȃ������ނ̊����Ă���
�N�X�m�L�̉��܂�
�����Ă���Ƃ͂ǂ�Ȃ��ƁH
���ɂ������
�͂˂鐅
�f����
���������Ɛl
�����炠����G���
�i�C�t�ŗꂽ����������
�����ł��ׂĂ̎�����z���o���I
�����č��킽����
�E���̔��̂�����։����
���N����
�Ȃ܂Ȃ܂����������
����̑�
�g���́A���̗B��̎��_�q�킽���̍쎍�@�H�r�i���o�́s���̖{�k��2���l���̋Z�@�t�}�����[�A1967�N11��20���j�Łs�m���t�̎��сq��́r�i�C�E13�A���o�́s���㎍�t1958�N6�����j�����܂�邫�����������̂悤�ɏ����Ă���B�u�����ɁA�u��́v�Ƃ�����т�����B�Ȃ�������Ƃ肾�������Ƃ����ƁA�킽���̒��ňِF�����i�ł���Ɠ����ɁA����̈��ŏo�����B��̂��̂ł���B�k�c�c�l�Ɛg����̏��a�O�\�O�N����A�T���ɁA�C�������Ƃ悭�J�쉷��ւЂƂ�ŗV�тɂ��������̂ł���B���鎞�A���t���Ǝv�����A�O��͍��q�ɃA�x�b�N����g�����B���̓��́A�A�����B�����́A�J��̌k���������̂ڂ�A����ȗ���̒��ɕ���ł��镽��Ȋ�ɂ˂ĉp�C��{�����B���ق͂����Â��A����͉����A�邪�ӂ���ɂ�A���̉������������邤���ɁA�ς��������ǓƊ��Ƃ������A���C�����ɖ����ʏ�ԂɂȂ����B�ڂ̑O�̊R��ɔp���̑���������B�킽���͒�������܂ŁA�����������Ǝ��݁A�����āu��́v���ŋ߂����������B����͕����Ŏl�N�Ԃ����������F�̑̌��ł���B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���`��O�y�[�W�j�B����ɋT�����Đ펞�̋L�������o����킯�����A�q������G�r�ɂ����Ă͎��i�q��́r�j�Ǝ��_�i�q�킽���̍쎍�@�H�r�j����������I�Ȏ��_����肵�Ă���̂����V���B�q������G�r�́u���R�ȏ�ԂŁ^�ڂ��̊G�����܂��H�^�k�c�c�l�^���ꂱ��������������̊G�^�k�c�c�l�^������������́^���̉E����������^�Ζ�ɂ��痁���܂ł���^������G�v�������G���A�q�F�ʂ̓����r�ł́u�����炠����G��́^�i�C�t�ŗꂽ���������^�����ł��ׂĂ̎�����z���o���I�v�ƂȂ�B�킽���͌�҂��烋�[�`���E�t�H���^�i�̐�ꂽ�L�����o�X��z�N���邪�A�s����̋G�߁t���ς����Ƃł͑�a������z��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�x�g�i������A�҂������J���A���̒n�ŗF�l�̕ʐ^�ƁE���J��̉E�r�i����͎B�e���̃J�����������Ď�����Ȃ��j���a�肨�Ƃ����A���̃i�C�t���B�i�C�t�͂܂��A�L�����o�X�ɕ`���ꂽ�G�ł͂Ȃ��A����ȃp�l���ɓ\��ꂽ�ʐ^��˂������̂��B�����[�����Ƃɋg���́A�`���Ɍf�����k�b�\���锼�N�O�Ɋ��s�����s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA1968�N9��1���j�̍����r�Y�q�g��������76�̎���r�ŁA���̂悤�ɓ����Ă���B
���E�l�ɂ���
�⁁�x�g�i���ɂ��āB
�����ߎS�ł��ˁB�ꌾ�Ō����Ɓu�x�g�i���̓x�g�i���l�Ɉς���v�Ǝv���܂��B�����I�����͂ǂ������ӂł͂Ȃ����A�x�g�i���l�Ɉς����炻��ł��ނ��̂��ǂ����킩��Ȃ����B
�k�c�c�l
�����łɂ��������܂�
�k�c�c�l
�⁁���������f��́H
�����哇���́u���{�t�̍l�v�B�C���e���̒��ɓ��{�̒�ӂ��\������悤�ȍ��R�����i���Ǝv���܂����B�i�����A��l��E��l�Z�y�[�W�j
��҂́q�g��������76�̎���r�̍Ō�̖ⓚ�ł���B�����ő哇�̍�i�i1967�N2�����J�j�Ɍ��y���āA��a�����́s����̋G�߁t�����Ȃ������g���́A�s�f��|�p�t�ɗB��̉f��ē]����邱�ƂŁA��a���̉f��ɃI�}�[�W����������B
�k�t�L�l
��a�����́A1976�N6���A�s���|�����|�n���������t�B�����t�F�X�e�B�o���E�p���t�t�ɒZ���q�w����̋G�߁x�ɂ��ār���Ă���B�㔼���������B
�@���āw����̋G�߁x�̏��e�͓c���z���������A�l�������ď\��������Ƃ̗\���]��I�[�o�[�������B��グ���B�J���闢��́A���߂ĉ�������|���l�V�A���l���v�킹��v���|�[�V�����ŁA���̗��N�ȂǑ����Ȃ��̂��������A�E�߃V�[���̌���ŁA�u���I�y�V���Ȃ́v�ƃu���W���[�̓�d�A���p������O�����̂ɂ͏��Ȃ��炸�V���b�N�����B�������ޏ��͂悭������B
�@�l�̏�����́A�L���A���蕳�Ő��܂ȃZ���t�ɖ����݂��Ă����̂ŁA�n�o�`�F�[���̋��s�傽���͓�̑��B�u��q�b�g����v�Ȃǂƃz���𐁂��A�d�オ��������������������ł͑������̂��낤�B�ᏼ�F��͂����������Ɖ䖝���A�l�ɂ͉��ЂƂ��������]�킸�ނ̖���w�ǂ̒��̔鎖�x�ƕ����킹�Ŏ����f�ɂӂݐ����̂��B
�@����҂̔ނ�����`�r�����T���A�n���ł����ʐ^�p�l����l������q�Ȃǂ��S���A�������D�������ς����`���`�������āA�V�h�̒����s�i�����B�`���`���h���h�������Ȃ��������A���ꂪ���̍��̎ᏼ�v���̐�`���@�������̂��B�i��a�����f��_�W�s�����Ɉς˂�t�A���C�Y�o�ŁA1994�N1��16���A��O��y�[�W�j
���c�唪�i1918�`2016�j�́A�u���A�k�c�c�l�f�U�C���̎d�������邽�߂ɓ����ɋA���āu�X�^�a�I�E�g�[�L���[�v��ݗ������v�iWikipedia�j���A���̎������ݗ��̍��m�̂��߂̐�`����͂藇�ɋ߂������ɂ����Čx�@�����ɂȂ����b�����`�s���̃C���X�g���[�V�����j�\�\���ƃG���s�c�t�i�a�k�o�ŁA2009�j�ɏ����Ă����B�g�������c�唪�ƒm��̂͂��̂��ƁA���c���G�{����|����悤�ɂȂ��Ă��炾���A���̑}�b�͕�������Ă�����������Ȃ��B�g�����g�A�Ζ���̒}�����[�ł͐�`�L���������ł�������A��a���̓`����ᏼ�v���_�N�V�����̐�`���@��m�����Ȃ�A�ǂ�Ȃɂ�����Ƃ��낤�B����ɂ��Ă��u�n���ł����ʐ^�p�l����l������q�Ȃǂ��S���v�Ƃ́A�s����̋G�߁t�̖`���V�[�����̂܂܂ł͂Ȃ����i���Q�j�B
 �@
�@
�s����̋G�߁t�̂c�u�c�i�c�h�f�A2017�j�̃W���P�b�g�i���j�Ɖf��s����̋G�߁t�̃|�X�^�[�i�E�j�k�o�T�Fkmrt�l
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
��a�����k��܂Ƃ�E�����l1937�`1993�B�r�{�ƁA�f��ēA�o�D�B
���ь��k���₵�E���Ƃ�l1930�`2001�B�f��ēB
�ᏼ�F���k�킩�܂E�������l1936�`2012�B�f��ēA�f��v���f���[�T�[�A�r�{�ƁB
���q�S���k�������E�Ă��l1912�`1988�B�����]�_�ƁA���o�ƁA�f��ēB
�R�J���j�k��܂�E�͂��l1933�`2019�B�o�D�B
��ؐ����k�������E���������l1923�`2017�B�f��ēA�o�D�B
����̋G���@1966�N �ᏼ�v��
�x�g�i������A�������ʐ^�Ƃ̒��J�B�F�l�̒��J��͐��ŖS���Ȃ��Ă��܂����B���J�͒��J��̗��l���������q�̂��Ƃ��������A���J��̈₵���t�B��������ɓ���悤�Ƃ���g�D�����J�̌��ǂ��Ă���B�x�g�i���A��̕J�����}���ɉ����ꂽ�g���Q���h�B���̗����ɂ�����́A�����đ҂����ɂ̃��X�g�Ƃ́c�B��a�����ᏼ�v���ŎB�����ē�1��B
���F�ᏼ�F��@�ċr�F��a�����@�o�F����Y�O�^�J���闢�^�������v�^�]�����v�^��̐��|�q
��80���@BW
�Ȃ��A�����m����c���F����k��Y�ҁs��a�����_�C�i�}�C�g����I �r��̃_�b�`���C�t�t�i�t�B�����A�[�g�ЁA1994�N6��19���j�́s����̋G�߁t�̔��y�[�W�i�����A�k���y�[�W�l�j�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B
����̋G��
���Z�Z�N�@�ᏼ�v��
���m�N���E�V�l�X�R�@��f���ԁ����Z���@���J�����
���쁁�ᏼ�F��@�ē���a�����@�r�{����J�`���i��a�����A�c���z���j
�B�e���ɓ��p�j�@�Ɩ�����L��A������@���ē��c���z��
�o�����J��闢�A����Y�O�A�������v�A�R�J���j�A�����d�b�A��������
�r�f�I���n�~���O�o�[�h
�r��̃_�b�`���C�t�@1967�N ��a���v���E���f��
���̃{�X�Ɍق�ꂽ�Ⴆ�Ȃ��E�����B�^�[�Q�b�g�͔ނ̏����E�����j�������c�B���Ɍ������E�����̃V���[���Ȗϑz�I�f�r��`������a���ē̑�2��B
�ċr�F��a�����@���F�R���m��@�o�F�C���T�q�^�`�Y��^���Ԏ��^��v�ۑ�^�R�{����
��75���@BW
�т̐��������e�@1968�N �ᏼ�v��
�i�Y�́A����̗��l���P�����g�D�ɕ��Q���邽�߂ɁA�{�X���h���A���̎艺���������B�g�D�́A���Ə��Ƃ����E����2�l�g���ق��A�i�Y���n������悤������B�������A���Ə��́A�ǐՂ𑱂��邤���A�i�Y�ɐe���݂����ڂ��͂��߂�B
�āF��a�����@�r�F��R���l�@�o�F�g�^���ԙZ�^��v�ۑ�
��70���@�p�[�g��J���[�@�V�l�}�X�R�[�v
���̂̎s���@1962�N �����f��
�u�k���D�E������l�������яo���Ɨ��v����i�Ŏ剉�B�u�Z�{�ؑ��v�̎p��`���]�����ĂԂ��A���J����ɓE�����ꂽ�v�i�q���� �̕����r�j�B
�āF���ь�@�r�F�ĒJ���� ��ԓ����@�o�F����^��C�u�^����q�^�v�ؓo�I�q
��49���@�����@�V�l�}�X�R�[�v
�َ��������鎞�@1966�N �ᏼ�v��
�����ɂ������g�̒j���̋��ɂ̐��ƈ��i�T�h�ƃ}�]�A�ꐫ�ւ̓���Ƒ����c�j��`���������r�{�A�ᏼ�ē̑�\���1�{�B
�āF�ᏼ�F��@�r�F���������@�o�F�R�J���j�^�u���݂͂�
��75���@BW
�������@1964�N ��O�v��
�Ⴂ��ƂƗ��s�̎肪����҂Ŏ��Â��Ă��āA��Ƃ���҂ɔƂ���Ă���̎��ϑz����Ƃ����ؗ��ĂŁA���̐��`�ʂ��b��ƂȂ������q�S��ē�B81�N�ɓ��ēōĉf�扻�B
�ċr�F���q�S��@���F�J�菁��Y�@�o�F�H���ގq�^�Εl�N�^�Ԑ쒱�\�Y�^����N�q�^���я\���
��94���@BW�iC�j
�Ƃ��ꂽ�����@1967�N �ᏼ�v��
�Ō�w���ɕ��ꍞ�����N���ޏ���𗽐J���E�Q�A���̎��̂̒��ɂ������܂邳�܂��A���̃J��������g���Ȃ���`�����ᏼ�ē̑�\�I1�{�B�����ɋ߂��������\�Y�剉�B
�āF�ᏼ�F��@�o�F���\�Y�^������q�^�є����^�،˘e�Ҏq
��56���@BW�iC�j
���̕��Q�@1967�N �ᏼ�v��
���ȉƂ̃T�����[�}�����A�ۂ݂����ċA����тꂽ���Ƃ�����Q�̗��ɏo��B
�āF�ᏼ�F��@�r�F�o���o�i�������� �����M�j�@�o�F�R�J���j�^�V�v���q�^������j
��78���@ B&W/C
�����G�c�������@1968�N ���q�v��
�����G�t�������̖���`�������G�Ŗ����グ�悤�Ƃ��邪�c�B
�ċr�F���q�S��@�o�F�����엝�^���R����
��84���@C
�E���������@1967�N ����
�C�O����g�D�̕s��ۂ��ɂ����j���E�����Ȃ����E�������A�g�D�̎E���������ƑΌ�����n�[�h�{�C���h�E�A�N�V�����B�A�h�o���[�����g�����E���̃e�N�j�b�N��A�E�������m�̑Ό����X�^�C���b�V���ȉf���ƃu���b�N�ȏ��Ō�����B�b�̋��͉f���������Ƃ������A�t�B�������[�J�[�̎��M������B������������ق���邫�������ɂȂ�����i�ł�����B
�āF��ؐ����@�r�F����Y�@�B�F�i�ˈ�h�@���F�쌴���O�@�o�F���ˏ��^�쌴�G���^�^���A���k�^���얜���q�^�ʐ�ɍ��j�^���O�^�{�������^��A
��91���@BW
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�g�����͌f�ڎ��̕ҏW���ɂ��C���^�r���[�L���q�g�������Ƀe���r���߂���15�̎���r�ŁA�e���r�Ŋς�f��ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă���B
5�@������A�O���ɂ����ɂȂ����ԑg�́H
�@���ŋ߂����ǁA���������̂́u���̗��v���ăC�^���A�f��ˁA�i�`���̂́B�ڂ��͉f��قŊςĂ����ǁA�Ɠ��͊ςĂȂ��ĂˁB�����Ƃ��J�b�g����Ă���ł��傤���ǁA���������ˁB
6�@�ԑg�ɂ��A���Ƃ��j���[�X�A�h���}�A�̗w�ԑg�A�X�|�[�c���p�A�����ҎQ���ԑg�Ȃǂ��܂��܂Ȃ��̂�����܂����A�ǂ��������̂����D���ł����B���̗��R�́H�@��̓I�ɔԑg���������Ă��������B
�@�ڂ��͂����ƐV�����āA�ԑg�I��Ō���̂ˁB�X�C�b�`�����āA�f�����̂����̂܂����Ⴄ���Ƃ͂Ȃ��ˁB�ڂ��͉̗w�I�Ȃ͍̂D���Ȃ�����A�����̂�ɂ͋C�̓łȂȁB�̗w�ԑg���Ă̂͏��ɂƂ��ĈĊO�厖�Ȃ��̂炵���B����ς�f��Ƃ��e���r�A���f��Ƃ��A���S�����炢���ƁA�u�K�`�����v�Ƃ��A�u���ˉ���v�Ƃ��A�������Ȃ��Ǝv���̂�B�v�����ǁA�������Ȃ��Ƃ��ɂ�����������킯�ˁB�Ȃ̂������̂ŃV���b�N�邱�Ƃ����邯��ǁA�e���r�̌��p���Ă̂́A�����������S���Ď����Ƃ�����Ԃ��K�v�Ȃ�łˁB������A�u�K�`�����v�����ɂ͎���A�u���ˉ���v�����ɂ͎���̂ˁB�f��́A�ȑO�ɊςĂȂ�������A����킯�B
�@���ƍD���Ȃ̂́A�u�V���{�I�s�v�Ƃ��A�u�V���j�T�K�v�Ƃ��ˁB�����Ă���̂ł́A�u�����̉Ɓv���Ă�����A�������H�́B�����h���}�Ȃ��ǁA���ꂢ�ȂȁA���������ꂢ�ȂA�a���̐��E�ŁB
�@����ς�V���A�X�Ȃ��̂͂Ȃ邽���������Ⴄ�B��Ԉ��S�Ȃ̂́A�`����鞂��o�Ă��Ăˁc�c�A�r�����m�ł���A���^���ł���A����ł����킯�B�e���r�����鎞�́A����Ȑl�Ԃł����Ă��A�����Ӗ��ŏ����ɋA���Ă����Ȃ��B�������y�̂��Ă��Ȃ����āA�I���������Ȃ���B�ӂ��̓��킾�����玩���ł����G���ςɂ����Ƃ��A�̕�����֍s���Ƃ�������ǁA�e���r�ɂ͌ܖ��Ƃ��邩��A���̒����玩���őI�Ԏ��ɂ͐^�ʖڂƂ��A�[���Ȃ��͎̂��Ȃ���ˁB
�@���j���̓��N�U�f��Ƃ���{���Ď��Ă�ˁB���̂������́A���f�́u���q��`�v�Ƃ��A���V���Y�́u�����v�Ƃ��ˁB���Ƃ́A�u���j���p�فv�͂��ƊςĂ�悤�ɂ��Ă�B�������11�����炻������āA���̓j���[�X�ŁA���ƃo���[�{�[���Ƃ�����ł���B���ܖ싅���Ȃ�����ˁB
�@�i�����f����e���r�Ɖf��قŌ����ꍇ�̍��͂���܂����B�j
�@�e���r�ɂ͐��X�̐�����Ǝv���܂���B�����ǁA�e���r�ɂ���قǂ̊������͋��߂Ȃ�����ˁB�Y�ꂽ�f�B�e�[����Ǒ̌��ł���킯�ł���B���̂������́u���̗��v���A�f��قŊς��낤���ǁA�Ɠ��Ɠ�l�Ŏ��āA�悩������ˁB�����������p�͂����Ȃ��B
�@�����ǁA�����Ǝ��Ă��ˁB�Ȃ����̂��������Ǝv�����ǁA���X�Y��Ă����Ⴄ����ˁB�c�c���������A���鎞�́u�Y���R�����{�v�A���ꂩ��u�}�N���[�h�x���v������ł���B����Ƃ��A�V�哪�̌Y���c�c�u�Y���R�W���b�N�v�A����Ȃ悭���܂�����B�e���[�E�T�o���X�͂ނ���������������ˁB���ꂪ�����P�l�ɂȂ��Ă��A���̃X�[�p�[�}������B����ς茩���܂���B�i�s���㎍�蒟�t1978�N3�����k���W���e���r���ǂ����邩�l�A���܁`���Z�y�[�W�j
�O�̂��߉f��̃^�C�g�����L���A�C�^���A�f���s���̗��t�\�\�莫�Ɉ������s�f��j�ւ̏��ҁt�́q�S�@�t�@�V�Y���̖��f�r�Ŏl���c���F�́u�ߌ��͐푈�̏I���ɂ���ďI�����킯�ł͂Ȃ��B�k�c�c�l�����A�i�E�J���@�[�j�́w���̗��x�i��㎵�O�j���������e���ŏ�������ɐ��I�ȐS���I�O�������������A���̌㒷���N���̂̂��ɂ�����x�����悤�Ȋċ֏�Ԃɑ������A���E�̂Ȃ��Ń}�]�q�X�e�B�b�N�Ȝ����ɓ��B����Ƃ�����i�������B�v�i�����A��Z���y�[�W�j�Ə������B�g�����ς��ł��낤�s���̗��t�́A1978�N2��1���Ɂs���j���[�h�V���[�t�i���{�e���r�j�ŕ��f����Ă���iWikipedia�j�\�\�A���f���s���q��`�t�A���V���Y���s�����t�ŁA�e���r�ʼnf�����������ۂ̊�́u�f��́A�ȑO�ɊςĂȂ�������A����킯�v�u���j���̓��N�U�f��Ƃ���{���Ď��Ă�ˁv�Ƃ������ƂɂȂ�B�����āu�Y�ꂽ�f�B�e�[����Ǒ̌��ł���킯�ł���B�k�c�c�l�����������p�͂����Ȃ��B�^�����ǁA�����Ǝ��Ă��ˁB�Ȃ����̂��������Ǝv�����ǁA���X�Y��Ă����Ⴄ����ˁv�Ƃ���B�k���łŃC���^�r���[�����i1978�N2�����߂��j�̐V���̃e���r�������āA�g���̎������Ă����f����g�̔ԑg������ł���A���̋ߕӂŕ������ꂽ�f��̃��X�g����邱�Ƃ��\���낤�i�����e�ǂł́A���{�e���r�́s���j���[�h�V���[�t�A�s�a�r�́s���j���[�h�V���[�t�A�t�W�e���r�́s�S�[���f���m�挀��t�A�e���r�����́s���j�m�挀��t�A�e���r�����́s�ؗj�m�挀��t���������j�B�����Ƃ��A�g��������������������ǂ������m���߂邷�ׂ͂Ȃ��̂����B�Ȃ��A�s�a�r�̃e���r�h���}�s�����̉Ɓt��1978�N1��12������3��30���܂őS12��A�������ꂽ�B
�i���Q�j�@�݂������J�c����̃c�C�b�^�[�Ɏ��̋L�ڂ�����B�k�@�l���͈��p�ҁi���сj�ɂ���L�B
�k19�l66�N9��20������k29���܂Łl�V�h����������œƐ胍�[�h�V���[���ꂽ��a�����u����̋G�߁v�B�v���f���[�T�[�̎ᏼ�F����x�g�i���푈�̕ĕ��p�ŁA�x�g�R�����𒅂����D�̎u���݂͂�ƐV�h�X���Ő�`�r���z��B���[�h�V���[�Ƃ����ƕ������͂��������v�͓���𗝗R��OP�`�F�[���Ŕz����f��ꂽ���߁^�k�摜�l�^��ނȂ������f�����f������[�h�V���[�ƌ��������邠����͂������ᏼ�F���A�u����̋G�߁v�͎G���g�f��]�_�h����^�������W�L���̌��ʂ������Ă�����肾�����炵���A�O������̓��N12���k13���l�ɂ͐����OP�`�F�[���Ō��J�k���f�͘Z�M�f��̐V���F�q�ē�i�s�s��̐f�f���t�l�B�������ᏼ�ē�i�Ƃ��Č��J���ꂽ�̂́A�g���������h�ł͂Ȃ��g���́h�^�k�摜�l�^����͔z�����鑤�̔��f�ŏ���ɂ������Ƃ��Ǝv�����A�����̐V�l�ł����a�����̖��O�����ł͋q���ĂׂȂ��Ɠ��̂��낤�B�����́u�����᎖���v���܂��W�����ŁA�������ꂽ�������f�ϊ�̉e���ŒP�Ƀs���N�f��Ƃ��������ł͏W�q�ł��Ȃ�����������
�g�����s����̋G�߁t���ς��̂́A9��20������́u���[�h�V���[�v�i���Ԃ͎����f�j�������̂��A12��13������̂n�o�`�F�[���ł̌��J���������̂��A�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B�������ɂ͖`���̋g���̒k�b�ɏo�Ă���u�F�l�v��9���ɊςāA���̕]�������g����12���Ɋς��A�Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�\�\�����̐V���L���Ɉ˂�A��f�ق͒r�ܕ��|�n���E���p�[�N�E�V�h���E�ڍ����C�I���E�J�W�o�V���E�s���x�m�فE�������E�s������E��{�I�[�N���E���l�����A�ȂǁB�g���͐��z�q���}���E�|���m�f��G���r�i���o�́s�G�������~�G�[���t1���A1985�N9���j�́q�P�u�َ��������鎞�v�r�Łs����̋G�߁t���u���͏ꖖ�̃s���N�f��قŊςĂ���v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�O�܈�y�[�W�j�Ə����Ă���B�\�\���̏Ռ����琶�܂ꂽ�����q������G�r�i�E�E15�j�������Ƃ����̂͂ł��������낤���B�g�����̎��͂��̂�������ɁA�����A�����ȓ���i���u�Â��ȉƁv�j�ɐ푈�̋L���𑖂点��s���Ȏ���i���u�_��I�Ȏ���̎��v�j���邱�Ƃ������Ȃ�B�Ƃ��ɁA�G���s�f��]�_�t�́u�����d�b�ҏW�������1960�N��㔼�ȍ~�́A�Љ�S�̂̔��̐��I�ȕ��͋C���G������荞�݁A�ᏼ�v�����x������ȂǃA���O���H����W�J�B���������Ƃ���s�I�ȎG���̂ЂƂƂȂ����B�v�iWikipedia�j�Ƃ��邪�A�g�������������ǂ��Ă������ǂ����͂킩��Ȃ��B����A�g���̒k�b���f�ڂ����G���s�f��|�p�t�́u�]���̉f��G�������グ�Ȃ������A���O���f���|���m�f����ϋɓI�Ɏ��グ�ĕ]�_����悤�ɂȂ�B1960�N�㖖����1970�N��ɂ����Ă̏���k�O�l�ҏW������́w�f��|�p�x�́A�����d�b�́w�f��]�_�x�⏼�c���j�́w�f���]�x�ƕ��ԑ��݂��������A�u�����I�ɉ߂���v�Ƃ��݂Ȃ����B�v�i���j�Ƃ���B�����ɂ��ċg���́A�u���̉f�挩���̍s���͈͂͊g��������B���R���u���犗�c�܂ŁA�����̂��B�܂��߂��̎O�������▾��O�̉f��قɂ��A�����s���B��́u�f��|�p�v���p���ɂȂ�A���́u�҂��v�����������̂��B���̋ɍה��̊������A�ɂ߂Ȃ���A�Ԃ��{�[���y���ň������B�ς������̂������ƁA�I���ɍ����Ă��܂��B�܂�ŋ��n�̗\�z���ɉ������悤�ŁA���Ȃ�����Ă��܂��B�v�i�q���}���E�|���m�f��G���r�́q�S�u�l�ȏW�c�\�s�v�������v�r�A���O�A�O�l�y�[�W�j�Ə����Ă��āA�g���Ə���O�Ƃ̐l�ԊW���œ_�ɂȂ邪�A���̂�����̂��Ƃ��悭�킩��Ȃ��B��l�ɘւB
�Ȃ��A�݂������J�c����̃c�C�b�^�[�Ɍ�����u�G���g�f��]�_�h����^�������W�L���v�́A1966�N6�����́k���W�E�㔼�����{�f��ō��̎��n�E����̋G�ߕ��́l�i�������o�Y�q�u����̋G�߁v�\�\���̉��J�ɂ܂݂ꂽ���r���܂ށj�A����ɂ͓������N10�����̐��]�F�V�q����ɂ��ā\�\��a�����́u����̋G�߁v�r���w���Ǝv���邪�A��������}���ق�2020�N4��11�����痈�كT�[�r�X�x�~���̂��߁A�m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�q�g�����ƍ]�ː에���r�ł����������A�g�����͐��z�q�Ǐ����r�Łu���N�A�ċx�݂ɂȂ�ƁA�ǂԏL���{������`�̘H�n�𗣂�āA�s��^�Ԃ̏f��̉Ƃɍs���A���ɂ����܂ꂽ���A�������̕����Ă���r�̂قƂ��A�����̂Ƃ�ł��鑐�ނ�ŁA�����₩�ȓc�����������̂��B���̉Ƃ̖L�x�ȑ����ނ���킽���͂����w�u�k�S�W�x���ʂ������āA�ǂݒ^����B�p�Y�������瓁���A���l�܂ł������낢�b�͂��Ȃ��B����Z�S�ł�����Z�̕z���̖{�ŁA��A�O�\���ʂ������Ǝv���B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�܌܃y�[�W�j�Ə��N����̓Ǐ���U�肩�����Ă���B���́s�u�k�S�W�t�ɂ��āA���͂����s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�Ŏ��̂悤�ɏ������B
�s�u�k�S�W�t�͑S12���B1928�`29�N�A����{�Y�ى�u�k�Њ��B�k�c�c�l��1����1928�N10��1�����s�A�q���ˉ���r�q���쏯���r�̂ق�3�̒Z�т����^�A�S1214�y�[�W�A�Z�̕z���{�B�����́������B
�s�u�k�S�W�k��1���l�t�͉��N���܂��A���̏����E�����������߂ɍ�������}���قŎ�ɂ��������ŁA�c�O�Ȃ��璆�g��ǂގ��ԓI�ȗ]�T�͂Ȃ������B�����ō���A�s���{�̌Ö{���t�Łs�u�k�S�W�k��11���l�t�i����{�Y�ى�u�k�ЁA1929�N8��25���j���w�������B���^��i�́A���т��_�c�R�z�q�ˌ��m�B�r�A�_�c�����q�V��C�����r�A�哇�����߁q�Ή��Y�ҁr�A���c�吅�q�R�䐳��r��4�сA�Z�т������V���q�V���̎����r�A�c粓열�q��J�a��r�A����n�G�q���D�������U�r�A�_�c����q�F�씺�����r�A�_�c�����q�k�V�ƕ���r��5�тł���B�d�l�͎l�Z���E�㐻�z���E�S1240�y�[�W�E�@�B���B�{�̂̑��͖�55mm�ŁA�قƂ�ǒ��^�̎����̊��G�ł���B���т͌h�����āA����n�G�́q���D�������U�r��ǂ�ł݂��B���ꂪ���ɖʔ����B�����o�����E���Ă݂悤�i�����͐V���ɉ��߂��j�B�u�w��搂��Q�l���q�v�u�F�߂����S�v�u���Y�̐V�^�v�u�̋`�v�u���ܘY�̔����v�u�����̐e�v�u�Ҍ��˂��R�Ǐ��v�B����ɁA���̂̓��������邽�߂ɁA�`���Ɩ����̈�i���f����B
�@�������̔��㒬�ɒ��R����Y�Ƃ��ӁA�]�ˎO���̐U�t�̎t�����������܂����B�k�c�c�l�i��Z���y�[�W�j
�@�|���ƈ�{�B���������͖̂��l�A�����ƒm�ċ���܂��B���l�͖��l��m��Ƃ��ӂ͍̂��̎��ł������B���̗��ܘY�̔�������w�ȕ]���ŁA�]�˔��S�����̍D���Ƃ̌��������Ƃ��ӁA�����̗��ɂ͎z�̔@�����̋�S�������Ƃ��ӁA���������̈�Ȓk�A���ɂēǐł������܂��B�i���y�[�W�j
�����͐����E�������ŁA���������������r�\�\�m�ނ��Ӂn�m��₤�����n�́m���̂ցn�m���₤�n�Ɂm�Ȃ���܁n�m���n��m�炤�n�Ƃ����A�m���ǁn�O�m���n�́m�ӂ���n�́m�����₤�n���������܂����B�\�\�B���������āA�Ђ炪�Ȃ��ǂ߂�Ȃ�A�����̐��������ǂ߂�Ζ{�������ǂł���B�{�������q�̑��L���N���������̂��͂킩��Ȃ����A�����̈ꕶ�ȂǁA�u�k�̃��C���ł������悤�Ȗ����q�ł���i����A�Z��ڐ_�c���R���P�������_�c���V�傪�A�e���r�����̃g�[�N�ԑg�s���c���V��t�ŗ���́q���������r�͖{���A�u�k�̉��ڂ��ƌ���Ă����B����͗��ꂾ���A�Ƃ肠�����q�U��ڎO�V�������w���������x-rakugo-�r�Ƀ����N���Ă������m���P�n�j�B����n�G�q���D�������U�r�̖{����36�y�[�W�A����t��̉��3�_���߂�B�s������{���b���t�ŕs�l�C���������Y�ɐV�@�����o���ׂ��v�Ăɂ��ꂽ�����́A�����̖����l�ɓ��Q�B���Ȃ�ʉJ�Ɍ������A�J�h�肵���������ł̂��Ƃ����������i�u���Y�̐V�^�v�A���r�͊��������j�B
�@�H�Ђ������Ȃ������A���݂������Ȃ������o�ւĂ��ƁA�s�J���b�A�K���K���K���K���K���Ƃ��ӗ��A�r�[�Ɂw�����c�x�Y�o�c�Ɠ��ė����͔̂N���O�\�O�l�A��̃X�����c�Ƃ�������͐����ĕS��顂Ƃ��ӂقǂł��Ȃ����A�\�������̏��A���H��d�̐F�̑ڂ����䕞�A�������̑т����v�Ɍ���ŁA���̑召�A�����O�C�ƒ[�܂āA��c������A�����قǔj��Ă��ւ̖ڂ̎P�J���ɂ��ē��ė������A���֓���ƁA������ڂ߂ăT�c�Ɛ���ăO�C�ƍ����������ăj�����Ə��B���̗l�q���]�c�Ƃ���₤�ɐ����A������W�c�ƌ��Ă���������w�E�[���x�Ǝv�͂��X���B���̘Q�l�������̓����{���̋ю��x�ɋ���܂��Ďl�S�l�\����ċ���܂����{���ܐl�j�Ƃ��͂ꂽ�����{������g�Ƃ��Ӓj�B�i���Z�܃y�[�W�j
�����܂œǂ�Ńy�[�W������Əo�Ă���̂��A���Ɏʐ^���f�����}�G�i����t���j�Ɩ{���̌��J���ł���B���N����̋g���𖣗��������͍͂����̎��㏬���A����ނ��뎞�㕨�̖����f�i������B�{���ɓY����ꂽ��i�����A�{���͊e��i�ɂ��ꂼ��ʂ̉�Ƃ𗧂ĂĂ��邪�A�Q�O�̕`�����ɗD����Έ�H���ƃX�~�x�^�ɓ��قȕM�g�����������c�x�������сE�Z�ъe���A�ɓ���v�����Z�ѓ��������Ă���j���]�˂̕��������ʂ��Ă���B�ق����������A�ߓ����_�����M�������Ă���B��������Õ��Ȗ��������āA�������Ă��܂��m���Q�n�B
 �@
�@ �@
�@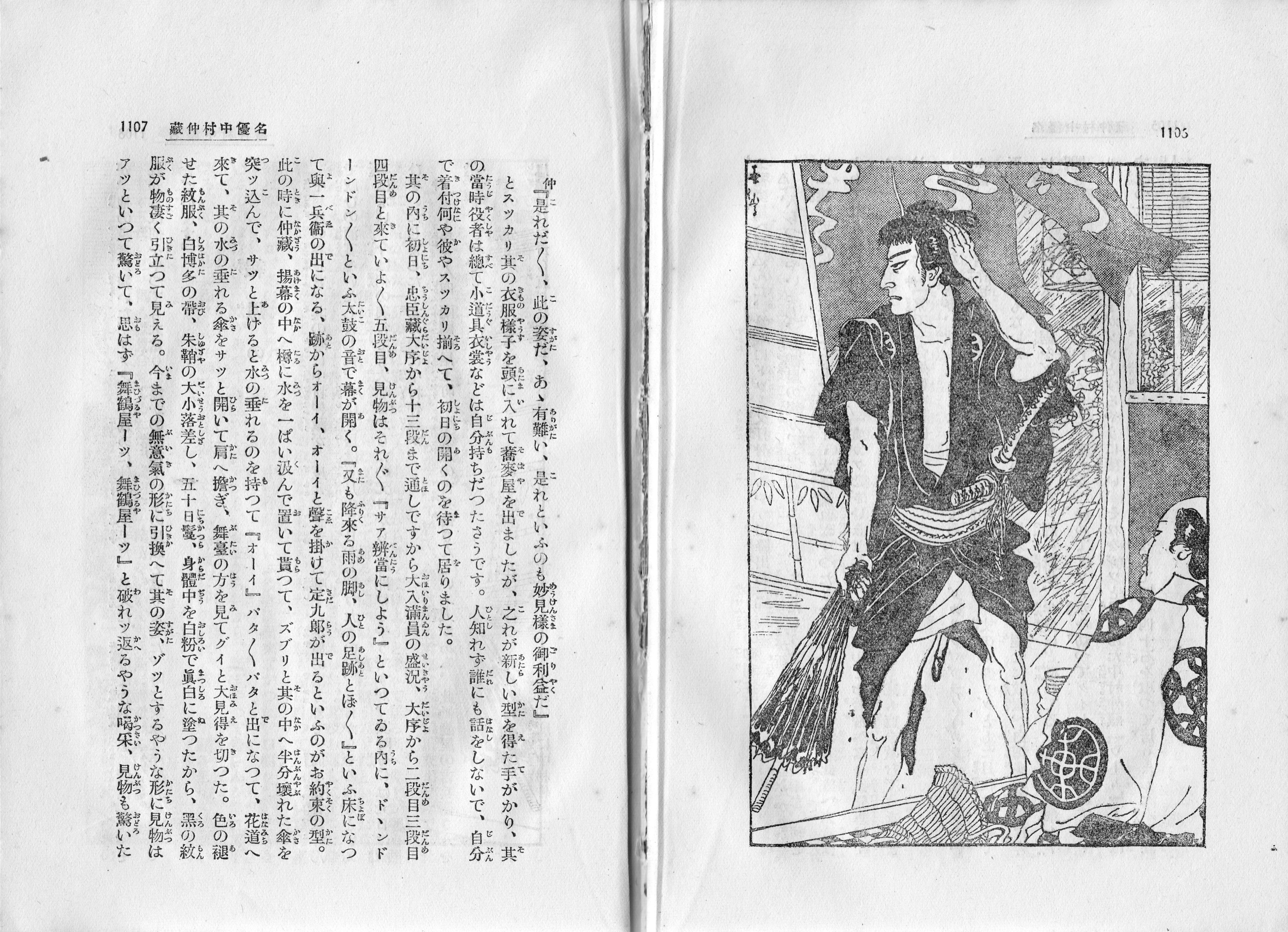
�s�u�k�S�W�k��11���l�t�i����{�Y�ى�u�k�ЁA1929�N8��25���j�̔��ƕ\���̕��i���j�Ɠ��E���̔w�i���j�Ɠ����i���Z�Z�`���Z���y�[�W�j�̛���n�G�q���D�������U�r�́u���Y�̐V�^�v�{���Ɩ���t��̉�̌��J���i�E�j
�������M�E�I
����������s�䂵����t
�R�{���ܘY���s�h�ԕ���t
�r�g�����Y���s���q�����t
�i�n�ɑ��Y�s���̏�t
���c��Y�s�g����Ə�t��
�R�c�����Y���s���Q�̒ʋ��t
�g�����s�V�瑈���t
���鏹���s�a�ɏ����t��
���J��L���s���y���O�Ƃ��̓��u�t
������R�s���F���t��
�]�n�C�s�R�̖��t��
���蓡���s�閾���O�t
����C�g�s���������}�t
�x�c�P�q�s�C��̒ꂩ��t
�c�{�ՕF�s����t
���{�����s���h�l�ʒ��t��
�D�˗^��s�ڈΒn�ʌ��t
���������s���b�p�Ꝅ�t
��R�O�Y�s��`�̖��t
�ܖ��쏃���s�푈�Ɛl�ԁt
�������q�v�E�I
������R�s���F���t��
���{�Y���s�����ߕ����t
���}�j�Y�s�_�B�㒏�t
�q��s��O�Y�̏G�t
�S�i���Y���s���j�b�|���t
�]�n�C�s�R�̖��t��
���J��L���s�җ��V���i�t
���{�����s���h�l�ʒ��t��
�ēc���O�Y�s�����l�Y�����T�t
���㌳�O�s�ЂƂ�T�t
�R�{���ܘY���s�[����y���t
�R�c�����Y���s�ɉ�E�@���t
���鏹���s�a�ɏ����t��
���ہs�������蓻�̗����t
�r�g�����Y���s�d�|�l�E���}�~���t
���Ђ����s�s���b���t
����������s�����̉t
���c��Y�s�g����Ə�t��
�����N��Y�s�e���q��t
���ɉĕF�s�o���ɉE�q��t
�����M�ƍ����q�v�̑Βk�s��������ƎR�{���ܘY�\�\���㏬����_�c�t�i�����V���ЁA2004�N11��30���j�����t�^�́q���㏬����Z�I�r�Ɍf����ꂽ���ڂł���i���E����͏��т��t�������́B�����ɂ���e��i�ւ̃R�����g�͏ȗ������j�B�^�C�g�����������������悤�ɁA��l�͓�������ƎR�{���ܘY�̍�i�Ƃ��āA�i�n�ɑ��Y�̍�i�i�Ƃ������A�ނ��낻�̓ǂ܂���j�ɋ^���悵�A�g��p���̍�i�͎���ɂ������Ȃ��Ƃ����ɉ��Ȕ���Ȃ̂����A���ܘY�Ǝ����̍�i�́s�h�ԕ���t�Ɓs�[����y���t�A�s�䂵����t�Ɓs�����̉t�Ƃ����ӂ��Ɋ���Ă���B�t�ɒ�����R�́s���F���t�A�]�n�C�́s�R�̖��t�\�\1947�i���a22�j�N�ɂ͉���s�R�̖��t�̑�ꕔ�q������鍑�r���A�g�����Ζ����Ă������m���̌Z���ЁE����������o�Ă���Ƃ����\�\�A���{�����́s���h�l�ʒ��t�A���鏹���́s�a�ɏ����t�A���c��Y�́s�g����Ə�t��5��i�͑o���̑I�ɓ����Ă���B���ɋ����[�����X�g�ł���B�Ƃ��ɁA���͎��㏬���E���j�����ɂ͂߂��ۂ��Â��A�����ɋ������Ă��邤���œǂ��Ƃ̂���͉̂��{�Y���s�����ߕ����t�A�R�c�����Y�s�ɉ�E�@���t�A���Ђ����s�s���b���t��3��ɉ߂��Ȃ��i���̌�A���ܘY�̒Z�сq�[����y���r��ǂj�B�����Ƃ����ܘY�́s���m�͎c�����t�ɂ͑���Ȋ����������A�r�g�����Y�́s�S���ƉȒ��t�͓����o�Ă������t���ɂ�S���ǂB�����A������A�����I�ȋ����E�S���Ȃ��܂܁A�����Ɏ����Ă���B���̒��ɂ͂��̎�̍�i�̓ǎ҂����܂����āA�g�߂ȏ��ł͐�N�S���Ȃ����`�ꂪ�����������i���a5�N���܂�ŁA���{�̖�����������Ă���A�Ƃ�킯�q������ǂ����j�B�ǂ��Ƃ��Ȃ��̂Ŗ���邷���A���錻���̎��㏬���Ƃ̍�i�ȂǁA�����}���ق̕��ɖ{���˂̒I��i�ȏ���L���Ă��邩��A������������ł���B
���������Ƃ͂��Ă����A�g�����Ǝ��㏬���ɖ߂낤�B�g���͎��㏬���i��O���w�j�ɂ��āA�f�ГI�Ȃ��Ƃ�������Ă��Ȃ��B�u���̂ق��́A�킪�Ƃ̋߂��̐}���ق֍s���A���X�ؖ��ÎO�A���}�j�Y�A�ѕs�Y�A�{�c���T�A�O�c���R�Ȃǂ̑�O���w����ǂ�ł����B�����Ĉ�ԍD���������̂́A���{�Y���́w�����ߕ����x�������B�{���������A���ˁA���J�Ƃ����n�����킽���̐����̒��ɂ���A���c�����ɂȂ�O�́A���˗l�ł���A�����_�Ђ͋��̌�O�ł������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�܌܁`�ܘZ�y�[�W�j�́A�O�f�q�Ǐ����r�ō]�ː에���ɐG�ꂽ�ӏ��ɑ������̂��B�Y���́s�����ߕ����t�͂����Ƃ��āA�g���͂����̏����Ƃ̂ǂ̍�i��ǂ̂��낤���B���ɂ́u�킪�Ƃ̋߂��̐}���فv�̉��{�Y���A�u���X�ؖ��ÎO�A���}�j�Y�A�ѕs�Y�A�{�c���T�A�O�c���R�Ȃǂ̑�O���w�v�́A�u���a��N�i���j�@�k�c�c�l�܌��A�w�����O���w�S�W�x�S�Z�\���i���}�Ёj���s�J�n�B��ň�~�̑���ŁA���䋪�ꂪ�S�ʓI�ɋ��͂��A�����̑�O��Ƃ����A���̑S�W�̐����ɂ��A�V�u�k���Ǖ����|����O���|�ƕϑJ�������̂���O���w�Ƃ��Ē蒅����B�v�i��c��j�q�N���r�A���c�J���w�ٕҁs���㏬���̃q�[���[�����W�t���c�J���w�فA1997�N10��18���A�ꎵ��y�[�W�j�Ƃ���s�����O���w�S�W�k�S60���l�t�i���}�ЁA1927�`32�j�m���R�n�������C�����ĂȂ�Ȃ��B�E�F�u�T�C�g�s���}�ДŁu�����O���w�S�W�v�S�U�O���@���X�g�t�̃f�[�^�Ɉ˂�Ȃ���A6�l�̎��^��i�������悤�B�����́A����40�����T-1�`�T-40�A����20�����U-1�`�U-20�̂悤�ɗ��L�����B
�E���{�Y���i1872�`1939�j�@�k�T-11�l �����ߕ����^�ʑ��O�^�Ō�̕���^�E�m�`�^�w偂̖�//���ҏ��`
�E���X�ؖ��ÎO�i1896�`1934�j�@�k�U-2�l �E��ߕ����^���Q���l�g�^�l�a��r���q//���җ��`
�E���}�j�Y�i1887�`1943�j�@�k�T-6�l �ӊ��ؑ]�V�^�O�r���^�Ԋi�q��Y�E�q��^�A�ΐ�l�^�����َ��^����@�t�^�̔閧�^���u���n�}�^�Z�\�N�̓�^�u���l�̉��~�A�k�T-33�l ���g�̎�~�^��Q�̂䂭�ց^�k�ւƗH��^�������̕^�V���J�����K��ρ^�V��t�̉��^�����x�̖��_�^ꌂ��ЁA�k�U-13�l �������^���l�n���^�_�鍩���ف^�V��V�O�`//���Ҏ��`
�E�ѕs�Y�i1900�`1935�j�@�k�U-1�l �V�ő剪���k�^�U��G�H��
�E�{�c���T�i1868�`1946�j�@�k�T-23�l �䟭������//���Ҏ��`�A�k�T-24�l ���S���̖��^�O�l�o���A�k�U-16�l �s��ԕ����j�^�R��錌���^���@�g�����^���ꒆ�[���^��k�ɉK���̍g�t�^���ۛ��g�팋�с^�� ���𗎋���//���Ҏ��`
�E�O�c���R�i1872�`1941�j�@�k�T-5�l ���Ԃ̕��^�s�m�^��M�̉^�[���A�k�T-30�l �R���Q���^�_���A�k�U-12�l �Ή�����`�^�]�˂̌�
���������Ă݂����̂́A�قƂ�nj��������Ȃ��B����Ƃ����̂��A�ѕs�Y�i�s�O�����V�t�͓ǂ�ł��Ȃ��j�̕ʖ��E�q��n�́s�����̉ԉŁt�i������1930�N�A�������_�Ёj�����u�����ŗ��ɂȂ��ā^��������ԉł����Ƃ���v�i�q�����r�F�E5�j��_����ۂɎQ�Ƃ������̂́A�Y���́s�����ߕ����t�ȊO�A�ǂ�����ǂ�����ł���B����Ȃ��Ƃł͖{�e�������Ȃ��A�Ɣ������ĕʂ̃A�v���[�`�����݂�ׂ��A�גJ���[�̊ďC�ɂȂ�s�ʔ����قǂ悭�킩�鎞�㏬������100�t�i���{���|�ЁA2010�N6��30���j����ɂ����B�k�w�Z�ŋ����Ȃ����ȏ��l�V���[�Y�̈�������A�\������ɂ́u�]�˂̐l��A�퍑�̌����A�M�����I ���a�����畽���̖�����Љ�v�Ƃ����āA���ȏ��Ƃ������͎Q�l�����낤�B�q��P�� ���a�̍����I��ƂƎ��㏬���̊���r�̏����Ƃ́i���͊�{�I�Ɂu�����Ɓv�Ə����āA�u��Ɓv�Ə����Ȃ��j�r�g�����Y�E�R�{���ܘY�E�i�n�ɑ��Y�E��������E���㌳�O�E��������Y�E�R�c�����Y�E�ēc�B�O�Y�E���c��Y�E�Ö{�z�E����|�}�E�i��H�q�E�{���o���q�E�ܖ��N�S�E���{���q�E�ҖM���E�������v�E�g�����E����~��E���Έ�Y�E���{�����E���ہE���˓��⒮�E�L�g���a�q�Ƃ������A��������l�S�W�����悤�ȑ�䏊�����B�g�������R�����̎��㏬���Ƃ̍�i��ǂ�ł��悤���A��̓I�ɍ�i���ɂ͌��y���Ă��Ȃ��B�N�ォ�炷��A�ނ���q��Q�� ���̒m�V�I�ÓT�I���㏬���̒a���r�ɓo�ꂷ���i�ɐG�ꂽ�\���������B��̓I�ɂ͈ȉ��̂Ƃ���B
�g��p������钟�E�{�{����
���{�Y���������ߕ���
�쑺�ӓ����K�`�����ߕ��T
������R�����F��
���䋪�x�m�ɗ��e
�C�������ܘY����������
�R������������ƍN
��Ŏ��Y���Ɣn�V��
�q���V�������C�M
���J��L���r�ؖ��E�q��
�R�����Y�������Y��
�p�c��v�Y���d���`
���}�j�Y���_�B�㒏�
�܂��Ɏ��㏬���̋��������̑�\��ł���B����A�s�ʔ����قǂ悭�킩�鎞�㏬������100�t�́q��R�� �����̎��㏬���u�[��������������͎҂����r�͎R�{��͂��獂�c��܂ł�25�l�ŁA���ꎩ�̂͋����[�����̂́A���a���I��������N�̕���2�N5���ɟf�����g�����������̏����Ƃ��������ǂ����Ƃ͎v���Ȃ��i�����Ŏ����ǂ��Ƃ̂��鎞�㏬���Ƃ́A�{���݂䂫�E���ɉĕF���炢�ŁA�{���I�ɂ��̃W�������Ɉ������Ȃ����Ƃ�I�悵�Ă���j�B�Ƃ����������A�M��Ȏ]���҂ł���{���݂䂫�̕҂��{�Y���s�����ߕ����\�\�]�˒T�����杁k�V�����Ɂl�t�i�V���ЁA2019�N12��1���j���o���B�Y���́s�����ߕ����t�͍u�k�Ђ́k��O���w�فl�Ƃ������ɖ{�œǂ��A20�N�ȏ���O�̂��ƂȂ̂ł�������Y��Ă���B���������ʓǂ��Ă݂�ƁA���ꂪ���ɖʔ����B�g�������܂��2�N�O��1917�N����A�ڂ��n�܂������������āA��������̌�b�ȂǁA����ɂ��������Ȃ�����o�ꂷ�邪�A�O��W����ސ��ł��邵�A�܂��Ȃɂ�����i�̐ݒ�A���̂̐��V�����������B�s�}���v��k���O����^���Ă���̂����Ȃ�����B�g��������O���w�Łu��ԍD���������v�Ƃ����s�����ߕ����t�m���S�n�ɂ́A���ˁA���J�A���˗l�̂ق��ɂ��A�g���̐��܂ꂽ���̋��A�ƕ��������������o�ꂷ��B�����y�̕Ғ��ɂȂ�s�����ߕ������T�t�i�������s��A2010�N1��25���j�͂������������ׂ�ۂ̍ŋ��̍H��m�c�[���n���B���Ȃ݂ɓ����̕ҏW�Ɍg������̂��E�菃������ł���B
�����̋��@�Ȃ��̂����@�{���G�}������ƁA��ȋ��������X��̓쑤�Ɂu���m�������v�Ƃ�������������������B�Â��͒��̋����ł��������A�����O�N�m�ꎵ��O�n�Ɍ����A�|���A�������A�����A���뒬�A���쒬�A�ܔV�����A����n���Ȃǂɕ����ꂽ�B��т͕��ƒn�Ǝ��@�ƒ��Ƃ����荬�����Ă���B�u�C�V��v�ɏo�钆�̋��́A�����Ɋ���������Ƃ������ƂȂ̂ŁA�{���G�}�Ɍ���u���m�������v�������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����͊G�}�Ɂu���m�����ď�v�Ƃ���悤�ɁA���E�l�����̒n�ɏZ��ł����̂ł��̖��������B�u������v�ɏo�镁�ݎ��͌������炸�n��ł��낤�B���܂̖n�c���ȋ����瓯����`�ɂ����Ă̒n�ɂȂ�B���k����̉B���\�E�q�傩�璬���̎��g�ԂւƂǂ��ďo���B��钆�̋��̐����ʍs�̐ܕ��ɁA���҂ɂ��ǂ��������āA�����̍��z��D�����ꂽ�����ɁA�ʕ��ɐ��P�����r���������Ɖ]���̂ł���B�i���ځj�l�B�k���̍��̏��~�⒆�̋��̂�����́A�i�t���́u�~��v�ɕ`���ꂽ���E�Ƒ����ς�Ȃ������B���̐��_�����܂킵���l�Ƃ��a��ɂÂ��āA������̓c��r�ł͉J����Ԃ悤�Ȋ^�̐������������������������B���a���ʂ̎����z�����܂��悤�ȓD�^���ꑫ�ʂ��ɒH��Ȃ���A�����͐����ɋ�����ꂽ�����̂܂��܂ōs�������B�i�C�V��j�l�B�k�����̕�͒��̋��̕��ݎ��ł���ƕ������̂𗊂�ɐq�˂Ă䂭�ƁA���̎��͂����ɒm�ꂽ�B�i������j�l�B�k�����͑��X�ɉƂ��o���B��ȋ���n���Ē��̋��ւ���������ƁA�������̂�����͓c�ɂł���B���ƂƂ����͖̂�����ŕS���Ƃ������B�i�V�J�`�j�l�B�i�����A�Z��l�`�Z��܃y�[�W�j
���ƕ��@�Ȃ�Ђ�@�{���G�}������ƉE�̒��قǂɁu�ƕ����v������A����Ɂu�쑠�@�v������B�G�}�ɂ͋L����ĂȂ������̋����ɋƕ��V�_�Ђ�����A�ƕ��˂��������B�������狴�������܂�A���̕ӂɋƕ��ƌĂԂ悤�ɂȂ����悤���B���܂̖n�c���ȋ��O���ڂ̓����ɂȂ�B�剪���k�̔����n���Œm��ꂽ�쑠�@�͏��a���N�m����Z�n�����擌�����ڂɈړ]���A���̂Ƃ��ƕ��V�_�Ђ͔p�ЂƂȂ����B���k�u�킽�������ƕ��̕��܂ł܂���܂��āA���̋A��ɐ��˗l�O������m���n�������������ւ܂���܂��ƁA��̏�͔��Â��Ȃ��ċ���܂����v�i���ƕ��j�l�B�i�����A�Z��O�y�[�W�j
�������̓n�@���܂���̂킽���@���܂̛����̋߂��ɂ͌���݂͊̓n�������Ȃ��A������������̂ł��낤�B�����͖������N�m�ꔪ���l�n�ɉ˂���ꂽ�B������݂͊̓n�@����܂₪���̂킽���@���k�A�邩�Ǝv������͖��������邭�Ȃ��āA�����̓n���z���邱��ɂ͑��������̐��������ė����B�i�C�V��j�l�B�i�����A�����y�[�W�j
������݂͊̓n�@����܂₪���̂킽���@�G�}�́u�䑠�v�k���Ɂu����J�V�n�V��v�Ƃ���B�������́u�O�D���v�Ɍ�������������ƂɈ��閼�ŁA�䑠�̖k����{���Ό��ւ̑D�n���ł������B���܂̑䓌�摠�O�ڂƖn�c��{���꒚�ڂ����сA���̛݂�������S���[�g���قlj����ɂ��������A�������N�i�ꔪ���l�j�̉ˋ��ɂ��p�~���ꂽ�B���k�����͂��̊Ԃɓ�O���p�B�����ė��悤�Ǝv���āA���X�Ɍ����̉Ƃ��o���B���ꂩ��푫�œ�O���܂���ēr���Ōߎ`�m�Ђ�߂��n��H���āA����݂͊̓n�ɗ����͔̂��i�ߌ�j�����O�ł������B�i���t���j�l�B�k�u���̖����悹�đ��O�̕��ւ������ōs���ƁA����݂͊̓n��̕�����c�c�v�i���˂��j�l�B�i�����A����`���O�y�[�W�j
�q���˂��r�͑O�f�s�����ߕ����\�\�]�˒T�����杁t�Ɏ��^����Ă���B�����y�̋���ɖ������咘�ɂ��q�s�����t�Ƌ��Ս�r�ŐG�ꂽ�O�c�̋��Ղ����̂悤�ɋL����Ă���B
���O�c�̋����@�݂��̂�����@���֊G�}�̍������A�א�z����̒����~�����Ɂu���Պω��v������A���̑O�̍�����Ս�A�����̒��Ƃ����ՑO�ƌĂ�ł����̂ŁA���̕ӂ���O�c�̋��ՂƂ������̂ł��낤�B���܂̍`�捂�ֈ꒚�ڂƓ��O�c�l���ڂ��ڂ���Ƃ���ɂȂ�B�w���]�N�\�x���i���N�m��Z�O�Z�n�\�̍��ɁA�u���Պϐ����A�O�c�̒n�Ɉ��u���i�J�R�@�_��l�A�L�O�m�Ԃ���n�̍����g�֗��鏊�Ƃ��Ӂj�v�Ƃ���B���Պϐ����͒���`���̓����ŁA�E��ɋ��̓������Ձi�āj�����B�����{���Ƃ��鋛�Վ��͂��܂��O�c�l���ڂɎc��B���k�u�O�c�̋��Ղ̋ߏ��ɒm��l������̂ŁA���x�����ɋ����킹�����g�Ƃ����q������āA�����ɂ܂��ł̕��ʂ}���ōs���ƁA�����Ɉ�̎������o��������ł��v�i�F���[�j�l�B�i�����A���Z���y�[�W�j
���{�Y���́s�����ߕ����t�́A���㏬���ɒT�㏬���̕������������ߕ����Ƃ����W�������̚���Ƃ����B�����y�͂��̍앗�������v��B�u�]�˂̏�i����A���������A���ɕ`����A���̎���̎j������݂̐l�����ߕ��b�ɂ��܂��Z�����Ă���B�e���̍]�˕ق��ǎ҂��]�˂̐��E�w�^�C���X���b�v�����Ă���܂��B�Ȕ������������Ƃ��Ă���̂́A����Ƃ䂦�̏��Y�ł��傤�ˁB�e���̘b�����t���A���肪���Ƃ⒬�l�A���邢�͗e�^�҂ƁA�l�ɂ���Ďg�������Ă���B��������ė}�������ȗ��ȕ��͔͂o��̍��肪���܂��B��ʂ̓]�����N�₩�Ȃ͎̂ŋ��Ƌ��ʂ��Ă��܂����A�ŋ��ɂ������栂����g�������̂������̂ЂƂŁA���̕ӂ��Y�����Ȃ�ł͂̐��E�Ƃ����܂��B�w�����ߕ����x�͂܂��ɍ]�˂�m��i�D�̓Ǖ��Ƃ����܂��v�i�q�ˋ�Βk�@�����e���ɐu���\�\�u���Ƃ����v�ɑウ�ār�A�s�����ߕ������T�t�A�㎵�܃y�[�W�j�B�g���������܂ꂽ1919�N��50�N�O��1869�N�A����2�N�ł���B������1923�N�̊֓���k�ЂŎs�X�n�̑������]�V�Ȃ�����āA�]�˂̕���͒n��|�������A����ł����₻��䂦�ɔ����I�O�ɖ����ƂȂ�ȑO�̎�����������ސS��́A���̉����ɐ��܂ꂽ���N�ɂ����Â��Ă������Ƃ��낤�B���ꂪ�Y���̕ߕ����Ƃ����A�]�݂���ō��̍�i�ł��������Ƃ͍K���������B�������܂�������āA���̉����̏�ƃ��_�j�Y���̍���̗Z��������i�ɐe���ނ��Ƃ��ł���B
�k�NjL�l
���㏬���̋ߐڃW�������Ɏ��㌀�i�f��E�e���r�j������B�g���͂���ɂ��Ă͂قƂ�nj��y���Ă��Ȃ����A���̋�����b�q�̕��i���́A�ł͂Ȃ��B�ꕶ���Ȃ킿�����Z���e���X�ł���j�������ɕx��ł���B
�k�c�c�l�܂��ʂ̂���A����͋g������̉Ƃ̃R�^�c�̒��ŕv�l�̗z�q����Ǝ��̎o���ꏏ�ŁA�H����������A�����A�y�ɂ����ق���������A��������A�}�N���o���āA�Ƃ����A���������̂̓R�^�c�ŃS���Q�����鎞�̐�p�̃}�N�����ނ�邯��ǁA��l�̕������邩��ˁA�ƐS�z���邱�Ƃ͂Ȃ���Ƃł����������q�Ő������A�z�q����́A�s���N�Ɣ��A�ԂƔ��̊i�q���̃}�N���������ꂩ����o���A�ǂ��������b�q�ŁA�ǂ������v���q�ɂ���H�@����������Ƃ����g�̂܂��̉��������肫�ꂢ�������肷�鏬����I�Ԏ��A���̐l�����ׂ�y���������^���Ȋy���C�Ȍ˘f���ׁA�g������́A�ǂ����ł�������A�ǂ����ł�������A�Ƃ��������ɁA�����ȑI���ɂ��Ȣf���Ă��鏗�q���Ɍ����A�����ă}�N�����S���ɂ����n��������������ŁA�����A�u����Ȃɍ����͂Ȃ�����ǁA����ł������͍����l�i�v�̒O�O�ɑI�ꂽ�A�����ɂ��g���ƓI�Ȋȑf�ŒP���Ō`�̔������\�\�g�����͏��N�̍������Ǝu�]�ł��������̂����A���̌`�̂Ǝ�G��ɁA���ł��ƂĂ��s�q�����A������������̉s�q���ɑ��ĉs�q���\�\�Ƌ��H��Ɉ͂܂ꂽ�����ŁA�G�k�����A�m�g�j�̑�̓h���}�w���R����x�̑��W�҂����Ȃ���A��l���̖k�𐭎q�ɂ��āA�u���͎͂����Ă��ƒ�I�ɂ͌b�܂�Ȃ��l���˂��v�Ƃ����A�肪���̓��Ɠe�̌`�̉����炵���A����Ȃɍ����͂Ȃ����NjC�ɓ������̂�������̂ɋ�J�����ƌ������̂ݒ��q�ŏ��܂߂ɂ����̗t����ꂩ���Ȃ��牽�t�����������݁A�������H�ׂ��痿���i�킴�킴�z�q���d�ԂŔ����ɏo��������̓�j�̎��́A���Ƃ��ӂ͕�������ė�����A�ق�A�ق�A����������Ȃ���ʖڂ��A�ق�A�����A�ق炱�����������������A�Ƒ����A����Ȃɂ���ĂȂ��������đ��v��A���邳��������A�~�C�����A�Ɨz�q����ɂ����Ȃ߂��A���낢��ƋC�������Ă��������������ɂ������̉����炿�炵����ނ��ʂ������H���̌�ł̂��������G�k�̂Ȃ��ŁA�ӂ��ɁA���݂��݂Ƃ����������ŁA�w�m���x�͐l�ԕs�M�m�A�A�A�A�n�̎�������˂��A�Â�������A�Ȃnj������肷��̂��B�i�q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�A�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��20���A��ꎵ�`����y�[�W�j
Wikipedia�ɂ��A�w���R����x�̑��W�҂͑�1�b�u�����N�v�i1979�N12��24�������j�A��2�b�u���ƖŖS�v�i��25���j�A��3�b�u���Α叫�R�v�i��26���j�A��4�b�u���Ɩ��S�v�i��27���j�A��5�b�u�R�E���q�v�i��28���j�ł���B�g���̌��U�肩�炷��A������b�q�����ƌ��Ă����̂́A1979�N12��28����������5�b�u�R�E���q�v���낤���B���̂m�g�j�̑�̓h���}�ɂ��ẮA���㌀�E�f��j�����Ƃ̏t������̕��͂���悤�B
���w���R����x�i�m�g�j��̓h���}�j
�����N�F�P�X�V�X�N�^�����ǁF�m�g�j�^���o�F�匴���ق��^�r�{�F�����䔎�^����F�i��H�q�^�o���F��_��A�≺�u���A���L�x�V�A���q�M�Y�A���㏼�ق�
�s����t�{��͌������i��j�E�k�𐭎q�i�≺�j�v�Ȃ����q���{�̎x�z�̐����m�����Ă����ߒ����`����Ă���B�����A�{��̋r�{��S�����������䔎�́A�ʂ̓�l�̐l�Ԃ��h���}�̊j�ɐ��m���n�����B��l�͐��q�̒�E�k���`���A������l�͒������n�삵���ˋ�̐l���E�ɓ��S�V�m�����䂫�n���B�����͂��̓�l�̐l�����I�݂Ɍ��������Ȃ���A���q�̌��Ɖe���Ǝ˂��Ă����B
�@�k�c�c�l
�@�����āA�Ō�͔��i�@�t�ƂȂ����S�V���u���ҕK���m���悤����Ђ����n�v�u���s����m���悬�悤�ނ��悤�n�v�Ɓw���ƕ���x���Ⴖ��V�[���Ŗ������B������̂́A���͓����̉ʂĂɑS�Ă������A������R�m�ڂ�����n�Ƃ��邵���Ȃ��q���C���E�k�𐭎q�������B����Ƃ��Ă̂��܂�̊����x�ɐk�����B�i�s���㌀�x�X�g�P�O�O�k�����АV���l�t�A�����ЁA2014�N10��20���A�Z���`�Z��y�[�W�j
�g�����́A���̃h���}���������ꂽ�O�N�A1978�N��11���ɉi�N�߂��}�����[���ˊ�ސE���Ă���B����ɁA���̔N�̏H�ɂ́u�����v�̝{�������鎍�W�s�Ẳ��t�i�y�Ёj���o���Ă���B������b�q���`�����̂́A����ȗI�I���K�̔N���̈�ꑂł���B���a�̖�ɂ́A��̓h���}�����㌀���ӂ��킵���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�m���P�n�@18���g�̂b�c�s�Z��ڎO�V�������̐��E�t�i���łd�l�h�A2002�jDISC6�́q���������r�́q��166�������O�V�������Ɖ���r�i�����z�[���A1974�N10��30���j�ł̎��^�B�t���́q���q�M�L�r�Ɏ��̂悤�ɂ���B
�@�͂����ė����̂��Ђ傢�b�c�c�i�ƁA����Ɓj��m�Ƃ��n����O�\��A�O�ɂ��Ȃ�܂��傤���A�F�̔����₹�����ȁA�w�F�̍����A����m���������n���X�̂悤�ɂ͂��Ă���܂��B
�@���m�Ȃ�n�͂Ƃ����ƁA���H��d�m�͂Ԃ����n�̈��������Ƃ����c�c���m���킹�n�̗����Ƃ�����A����֒�����̑сA�������m�����n�ׁi���v�B���t�̉��Œn�����ׁA�͗l�𔒂��c�������́j�̕@���̐�ʁm���c���n�����B�͂���ŁA�K�������[�܁m�͂���n��܂��āA�X�F�m�낢��n�����m�₯�n���̑召�𗎂Ƃ������ɂ��āA�j�ꂽ�ւ̖ڎP�@�����B�ۃH��Ƃق���o���āA���@�b�ƌ������������Ă��ƁA���炾�炾�炾�炾��@�b�ƁA������������܂��B�ԁm�����Ɓn���琞�ƁA�т���т���ɂȂ��������������c�c������ɁA���ڂ��Ă���B
�u�c�c���ꂾ�c�c���B���������ȃ@�c�c�Ȃ�قǁA���㑾�v�m�����䂤�n�̘���Y�B�_��������ł���V�m�����n��ŋ��ɍ���̂ŎR��X���Œǂ��͂����������A�ǂĂ�ŏo��킯�@�˂��c�c�����@�����B�ȃ@�B�ǂ������́A�ۂ��ۂ��ۂ��ۂ���������āA���������������c�c���炾�B�܂Ƃ����Ă�Ƃ��Ȃ@�ǂ����c�c���܂�Ȃ��ȃ@�ǂ����c�c�����b�A�����b�A�����b�A�����b�c�c�v�i�ʍ�������A��Z��`��Z��y�[�W�j
���̕����A����n�G�̍u�k�q���D�������U�r�́A�����ł����Βn�̕��ł��������b�𐄂������߂�̂ŁA����Ɋr�ׂĈ��k����Ă���B���C���ōu�߂������Ƃ��Ȃ����A�͂����Ď��ŕ����ď[���ɗ����ł��邩�B���Ȃ݂ɋg���́A���a20�N��㔼�̑z���o���u���͓�\���N�O�̂��Ƃ�z���o���Ă����B���̒n�����܂̉��̊␣�Ƃ����ƂɁA�Ⴂ��Ƌg�c���j�Ɖ��h���Ă����̂��B�Ǝ�͎l�\�܁A�Z�̌�Ƃ���ŁA�����Ԃ������ꂽ�قƊ�����Ă����B�~�̐[��ɁA�e�q�O�l�̐Q������Ȃ���A���͕֏��ւ���������̂��B�������͑䏊���o������ɂ��Ă����B���傤�ǂ����ɂ͌{�����������āA�^�Ă͕��m�ӂ�n�̏L���ɕ������B�_�o���Ȍ��j�͂��Ƃɂ��₪�����B�ނ͎q���̂����A�̕a�C�������Ƃ��ŁA���������ꂽ�������āA�s���҂̎�������̂������B��Ƃ�������n�̌����ɁA�܂��n�R�ȎO�V���~�����Z��ł������A�s�v�c�Ȃ��Ƃɗ�����Ă���̂������Ƃ͂Ȃ������B�^�߂��ɜh�q�̕揈���������̂Łu�{���m�ӂ�n�̍���ׂ�͎O�V���~���t�v�Ɠ�l�͏����B�������͑��p�́u�~������ׂ�͉����y�E�q��v�̃p���f�B�[�ł���B�v�i�q���e���O�Y�A���x�X�N�r�́u�R ���ϒn���̎��Ӂv�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A����`��O�Z�y�[�W�B���o��1975�N10��31���A�}�����[���́s���e���O�Y ���Ǝ��_�k��6���l�t�t�^�j�Ə����Ă���B�g�����O�V�������̍����ɐڂ������́A�c�O�Ȃ���킩��Ȃ��B
�m���Q�n�@�}�G�͎��㏬���Ɍ������Ȃ����̂ł���ɂ�������炸�A���̂�����̂��Ƃ��҂��ڂ�����������͂��قƂ�nj��Ȃ��B���������i1931�`2011�j�����N����ɐe����8�l�̑}�G��ƂɃC���^�r���[�����e�[�v���������ꂽ�A�Ƃ����͍̂K���������i����8�l�Ƃ́A���J�����A����V���A�c����A�a�c�M�V�A���c�x���A�x�i�����Y�A�u�������A������������j�B���̂����u���������q�g�����̑�����i�i136�j�r�̒��ɂ����āA���J��L�̒Z�я����W�s���@�ً��{�t�i�������A1948�j�̕\�����S��������ƂƂ��Č��y�������Ƃ�����B�����ɂ��C���^�r���[�̑���́u���������������v�Ƃ����p�����ӂ��̕������t�����q�吳�E���a�̓��{��O���|���x�����}�G��Ƃ����r�ł���B�{���́q�R �u�������m���ނ炽�݁n�i���Z���\��㔪�Z�j�r�́A19�y�[�W�ɂ킽���ē����̑}�G��ƂƂ̌𗬂⎞�㏬���ƁA���㏬���̏o�ŎЂ̗��b���I�����M�d�Ȃ��́B���̂Ƃ��ɎQ�l�ɂ���͉̂f���e���r�i�̎��㕨�j�ł͂Ȃ��A�̕��ꂾ�i�����A����y�[�W�j�Ƃ���������́A�Ȃ�قǂƎv�킹��B�C���^�r���[�̍Ōオ�A�����܂����͂�点�����A�ŏI���̂������Ă���B�u�������̋L���̖����ɂ́u�q��㎵�ܔN��l���@���c�J�̎u�������@�ɂār�v�i�s���������S�W���S�Łk��26���l�t�鐼���ۑ�w�o�ʼn�A2017�N4��30���A���Z�y�[�W�j�Ƃ���B�������q�ɂ��S�̂̂܂������ɑ������镶�͂ł́u�u����������́A�u���E�O�����V�v�̑}�G��R�{���ܘY�u�����Y����v�A�É��V���̉ԓo⟁u�טr�ɐ��L�v�̑}�G�ȂǁA�R��G��̒�q�炵�����l��ŗL���ȍ�Ƃł��B�v�i�����A��O�O�y�[�W�j�ƏЉ��Ă���B
�m���R�n�@�g�����3�ΔN���̏����ƁE�Α�p���Y�i1916�`88�j�́A�����Е��ɔŁs�����ߕ����k��4���l�t�i�����ЁA1986�N8��20���j�́q����r�Ɂu���A���{�Y������́w�����ߕ����x�ɐe����ŁA���łɁA�v�����B�^�Â��͕��}�Ђ̍��\���̌����O���w�S�W�̈���i����͂����{���{���ɂȂ��Ă���j�A����ɑ��쏑�[�ŁA�^�[�m�������ڂ��n�ŁB�o���̂����͕��ɔł��D�����Ƃ��ė��p���Ă���B�v�i�����A�O�Z��y�[�W�j�Ə����Ă���B���쏑�[�ł́s��{ �����ߕ����k�S3���l�t�i1955�`56�j�A�^�[�ł́k�^�I���l�́s�����ߕ����k�S5���l�t�i1966�`67�j�ŁA���ɔł͏��a���N�̏t�z�����X�A���쏑�[�́s��{�t������ɏo���p�쏑�X�i�S7���j�A1977�N�̉����Ёi�S7���j�̂ǂꂾ�낤���B�q�Ǐ����r�i���o�́s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8�����j�������������A�g�������肵�₷�������ł͐^�[�́k�^�I���l���p�쏑�X�̕��ɖ{�̂͂������A�i���̂���́A�_�ے�������̐V�����X�ŗ����ǂ݂��炢�����悤�Ɏv������̂́j���M���ɍēǂ������ǂ������܂߂āA�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B
�m���S�n�@���{�Y���s�����ߕ����k�S6���l�t�i�}�����[�A1998�N6��25���`11��25���j�́A�����ߕ����̑S�b�����߂Ă���B�����Œ��ڂ��ׂ��́A��ɑ�O���w�����܂ɋP�����s�����͎��݂����\�\�u�����ߕ����v�]�˂߂���t�i�͏o���[�V�ЁA1989�j����������Ⴊ�S���ɒ��E�����E�n�}�Ɗ������������M���Ă��邱�Ƃł���B�S���̑���E�}��͎O�J��n�B����ɂ�钐�����A�{���ň����������y�̂���Ɣ�ׂĂ��ʔ����B�Ƃ���ŁA�{���݂䂫�҂́s�����ߕ����\�\�]�˒T�����杁t�̒�{�͍ŐV�̔łł�������Ў��㏬�����ɂ̐V���łŁA�}�����[�ƌ����ЁA���Ђ̔����ߕ����S�W��������Ă���̂͐S�����B�\�\�����Ў��㏬�����ɂ́s�����ߕ����k�S6���l�t�i����F�s�}���v�E�X������E�˔N��E�Α�p���Y�E�����쎟�Y�E���{�o��j�́A�����i1986�`87�j�ƐV���Łi2001�j������i�u�V���Łv�͖{���E����Ƃ������ɓ������e�����A�����T�C�Y�E���l�E�s���Ƃ��ɈقȂ�u�V�g�v�̂��߁A�y�[�W�������đ傫�Ȋ����œǂ݂₷���B���͑S68�т��k��6���l�����̉��{�o��q�����ߕ��� ��i�N�\�r�̏��\�\�������N�́q�����Y�ρr�Ɏn�܂�c���O�N�́q�M���̖��r�Ɏ���\�\�ɏ]���āA�����œǂj�B�܂������ߕ����Ƃ͕ʂɁA�q���{�Y���Ǖ��W�k�������Ɂl�r���������_�V�Ђ���7���܂ŏo�Ă���B����ɂ��܂��Ċ�g���ɂɁs�������k �����v�̉��ɂāt�i1993�j�Ɓs���{�Y�����M�W�t�i2007�j�����^����Ă���̂͗��������B�Ⴂ����V���L�҂������̕����҂̏������ꐢ�I�O�̎��㏬�����A������̓ǎ҂Ɉ�������Ă䂭�B���̂��܂́A���j�����������̖{���ƍl���Ă����A���̃C�M���X�̈�҂��������T�㏬���̒����ɂ킽�闲����z�킹��B
�l���c���F�̏������낵�s���� ���c�f���t�i�͏o���[�V�ЁA2019�N5��30���j��ǂB���̂Ƃ���A�g�����Ǝ��㏬���ɑ�\������O���w�̊W���l���Ă��邹�����A���c�f���ē�i�s���F���t�i��ꕔ�F1957�A��F1958�A�����сF1959�j��_�����́i�w���F���x�j���Ƃ�킯�����[�������B�ق��ɂ��s������Ȃ��ȗ��t�i1962�j�́u���ρv�i�����A��Z���y�[�W�j�ɂ��ā\�\�g�������Ɂq���ρr�i�������сE16�j������\�\��A�s�Q��C���t�i1964�j�̏͂́u�ޏ��̌��J���ꂽ����͔������Ă���B�ޏ��͉����ɜ߂��ꂽ�悤���̉͌��₳�܂��܂Ȓn���̘b�����A�����M�m�܂����n��Ȃ���A�������ɜ����Ƃ����\�����ɕ����ׂ�悤�ɂȂ�B���Ȃ���y���F�́w�Í������x�̂悤�Ȍ��i�ł���B�v�i�����A��O�Z�y�[�W�j�Ƃ����L�q������A���낢��Ȃ��Ƃ��l��������ꂽ�B������ꌾ�ł����A�ߔN�A�f��Ƃ͂������育�������̎����A����20���I�ő�̌�y���|�p���u�̈̑傳�ɉ��߂Čh�����Ă���A�ƂȂ낤���B�Ƃ���ŁA�����̃��_�j�X�g�ł���g�����́A��O�A�ɂقNj߂��{����X���ɕ���ƕ�炵�Ă������Ƃ�����Amovie-goer�ɂ͂Ȃ�ׂ����ĂȂ����Ƃ�������B���͂�����q�g�����Ɖf��r�ɂ��ď��������ƔO���Ă��邪�A����͂��̊�b�����Ƃ��Đ�O�A��\�ΑO��̋g���̓��L�ɓo�ꂷ��f��̃��X�g���쐬���Ă݂�B���ڂ́A�s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�j�̓��t�i�y�@�z���ɗj����NjL�����j�����o���ɂ��āA���L�{���ɓo�ꂷ��f�您��щf��ɂ܂��L�ڂ����̂܂܈����A����̂��ƂɊȒP�Ȑ������f�����B�Ȃ��A�f���i�Ɗē�o���҂Ƀ����N�����ӏ�������i��ȃ����N���MovieWalker��Wikipedia�ł���j�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
���a�\�O�N�i1938�j
9��4���y���z�\�\�ߌ�A����B�e���܂ōs���B�����͑z�����Ă����u���̂悤�Ȑ��E�v�ł͂Ȃ��B�j�D���D�̎p������т����������B
���g���͑O����9��3������A��e�́u���Ɓv�Ƒc�t���J�呠�̑��c�Ƃ�K�˂Ă���B
���a�\�l�N�i1939�j
3��31���y���z�\�\�[���A���̂���C�܂����Ȃ�����������ƁA���O���ʂ�̔����ق։f������ɍs���B�q�͋ߏ��̂����݂���A�q���A���m�A�E�H����ɂӂ�ǂ������Ƃ������Ƃ���ŕ��͋C���D���B
���u��������v�͋g������`���������F�k�ނ������܁l���m�̎�A���������k�t�ˁl�B�g���͏��m�ɏZ�݂��݁A�Ƃ��ɂ͍��������Ƌ����Â����B
4��3���y���z�\�\�J�B������{�����֍s���B�u�]���v���W�����E�M���o���͑f�������B�ƂȂ�̏��w���������Ă����B�O�͊����ӂ邦���B��R���ւ͊�炸�A�Ԗ�܂ŎU���B
���g�������������s�y�y�E���E���R�i�]���j�t�ɓo�ꂷ��P���ʂɂ��ẮA�q�g�����ƃP���ʁr�ŏڏq�����B�u��R���v�́A�w�Ƃ��I���čŏ��ɋ߂��㏑�o�ŎЁB
4��26���y�z�\�\��A�x�m�قŁu�y�v������B���炵���c�����B
�����c�f���ē�i�B�u�������Ĉ��O��N�O���A�B�e�����O���l���A�Z�b�g���Z�ܔt�Ƃ����A�������\�L�̋K�͂̎B�e���I�������B�t�B�����͕����Ȃ̐��E���A�l����O���ɕ���ꂽ�B���ꂪ�����܂���q�b�g���A�O�T�Ԃ̃����O�����ƂȂ����B����A������肩�A���̔N�́w�L�l�}�{��x�x�X�g�e���ł����ʂɑI�o���ꂽ�B�ϋq�̂Ȃ��ł͍��w��w�̐�߂銄�����A���̃q�b�g��Ɣ�ׂđ傫�������B�w�y�x�͌��݂ł́A���O�Z�N����{�f����\����P�������ÓT�Ƃ��ĔF�m����Ă���B�v�i�l���c���F�q�w�y�x�Ɣ_����A�r�A�s���� ���c�f���t�A�O�ꎵ�`�O�ꔪ�y�[�W�j
5��13���y�y�z�\�\�J�̒����A�_�c�̓얾���܂ōs���B�u�p���h����➁k�}�}�l�v�����C�Y�E�u���b�N�X�ɖ��������B�Y�܂��������B
���g���́q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r�i���o�́s�����C�J�t1976�N6�����j�Ɂu���ꂩ�������l�A���̏��D��������Ȃ�A�u�p���h���̔��v�̃��C�Y�E�u���b�N�X�������Ȃ��B���N���݂��������ϔ��̔ޏ��̔������d���������܂��Y����Ȃ��B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A���y�[�W�j�Ə����Ă���B
5��14���y���z�\�\�ߌ�A�֍s���B���ۃL�l�}���u�X�e�[�W�E�h�A�v������B
���剉�̓L���T�����E�w�v�o�[���A�W���W���[�E���W���[�X�A�A�h���t�E�}���W���[�B
6��11���y���z�\�\���j�A�v���Ԃ�ő���c�̑S�����֍s���B�x�e�B�E�f���B�X���u�s�l�̈��v���悩�������A���r���[�T��f���u��ࣂ���E�l�v���悩�����B
���g���͂��̂��ƁA���c�쒬�̈˓c����i�����A�o�咇�ԁj�E�h�q�v�Ȃ̉Ƃ�K�˂Ă���B
6��25���y���z�\�\�J�̏��L���H�Ŏs�d���抷���A�V�l�}�p���X�ցB�u�掵�V���v�̃W���l�b�g�E�Q�[�i�͉��������B
���g���͂��̂��ƁA�F�l�Ƌʖ؍��Ŗ��˂����Ă���B
7��15���y�y�z�\�\�n���̊��̂ӂ��̂������B�[���A�_�c�֍s���B�얾���ɓ���A�㎞�߂��o�āA��X�̌Ö{��T���ĕ����B
���f��̓^�C�g�����L���܂ł��Ȃ��قǂ̓��e�������̂��B
7��25���y�z�\�\��A�X������s�d�ɏ��B�O�ؒ��A�|���A���L���H��ʂ�B�{�������u�k���灨�W�l�߂������v�̍��Ȃ�X�ヌ�����[�f��B��������u���t�v�ŁA�v�t���̏����̕���B�x�A�d�̂��Ƃ��v���B
���u�x�A�d�v�͓�R���̏��q�Ј��A�����t�q�Ɖp�q�i�����ځj�B
8��20���y���z�\�\�ڍ��L�l�}���u�\�N�l���v�B
���g�����f�������j���������Ă����j���Ȃ̂́A��`���Ă������m���x�݂��������߂��낤�B
8��28���y���z�\�\����S�����ŁA�u�^�Ă̖�̖��v�B
������c�ɂ��S����������Ƃ��������ƁA����S�����͓��n��̉f��ق��B
10��17���y�z�\�\�J�B�ߌ�x���A�t�˂���ƎO�ւ֍s���B�L�l�}�n�E�X�ŁA�_�j�G���E�_�����E�u�łɁk���ց��A�l��v������B�j�Ə��̐Ȃ͂��łɕ������Ă���B�҂������O�ցB
���g���́u�O�ցv�Ə����Ă��邪�A�����s�䓌��́u�O�m�ցv�ł��낤�B
10��29���y���z�\�\�얾�����u��������̈۔[�v�����ɏo������B
���g���͑����āu�A��̓d�Ԃ̒��Łk��P�l�x����B�v�Ə����Ă���B
11��7���y�z�\�\���{�ق��u�u���O����v�������B�����̓����B�\���߂��A��B
���g���͉f����ςɂ����܂��A���z�𗎂Ƃ��Ă���A�u�C���Ȃ����ɐ����B�v�Ə����Ă���B
12��5���i�Ηj�j�y�z�\�\��A���ۃL�l�}���u���D�i�i�v�������B�����c�߂Ă���B�A���i�E�X�e���̔��s���ɖ�����ꂽ�B
���g���̓]���i�F���L���j�̐V�����ɔŁs�i�i�k��E���l�t�i�V���ЁA1933�j�N�قǂ܂���5��18���y�z�ɔ������Ƃ߂Ă���A������5��19�����u��x���܂ŁA�w�i�i�x��ǂ݂ӂ���B�v�i�s���܂�͂����L�t�A�l��y�[�W�j�Ƃ���B
12��23���y�y�z�\�\���A�T�̓��ŗM���ɐZ��B��錩���u�n�o�l���v�k�u��̗U�f�v�l�̃c�@���[�����_�k�c�@���[�E���A���_�[�l�̔��������v���B
���~���̓��̂��߁A�K�����M�q����p�ӂ����̂ł���B
���a�\�ܔN�i1940�j
1��21���i���j�j�y���z�\�\����c�̑S�������u���N�̒��v������B
���g���͑O�N6��11���ɓ�������c�̑S�����Łs�s�l�̈��t�s��ࣂ���E�l�t���ςĂ���B
1��23���y�z�\�\�v���Ԃ�ł܂��V���U���ɂ���B�������O�k�m�l�ւ̃L�l�}�n�E�X�փo�X�ōs���B�f��͂܂�Ȃ���������B�����I�[�o�[�̃p�[�}�l���g�̎Ⴂ�����ׂɍ���B�q�Ȃ͂����Ă���̂ɂƁA�v�����B��{�ڂ̉f���u�j�̐��E�v�͌��Ă����̂ŁA�o�悤�Ƃ������A���̖����I�ł��B��������A�����t�q��B����ɋ����Ă��܂��B���̍����̂������ς̏����͂ǂ��ւ����Ă��܂����̂��B�����v�炵�Ă����A�����̂ЂƁB���悤�Ȃ�A��̖��B
���u�����t�q�v�́u�x�v�Ƃ��đO�o�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�g�����́s���܂�͂����L�k��Ԃ�ǂ邵����P�l�t�i����R�c�A1990�N4��15���j�́A���a�\�O�N�i1938�j8��31�����珺�a�\�ܔN�i1940�j3��6���܂ł́A����1�N���قǂ̋L�^�ł���B���̑��|��3�N���g���z�q�ҁq�k�g�����l�N���r�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�j�ł��ǂ�A���̂悤�ɂȂ�i�����A����Z�`�����y�[�W�j�B
���O���N�i���a�\�O�N�j �\���
�����A��R����ގЂ��X���̎��ƂɋA��B�X�֒������Z�~�ƑސE�蓖�O�Z�~�Ⴄ�B�㌎�A�����F���m�i�����t�ˑ�j�ɐg�����m����`���B�j��l�̐����B�q�������ɏK���������A�����A�|���A�����o��������B�t�˂���������ɂ̔��H�w�Ԋ~�x���Ȍ�A�\�]�N�����B���̍��t�˂�F�l�����Ɣo���Z�̂����B
���O��N�i���a�\�l�N�j ��\��
�ߏ��̎ʐ^�قŋL�O�ʐ^���B��B���̑��ŗ����X�Ɋ��V�哪�ɁB�ꈬ��̔����ɓn���B�{��������Œ��������B��퍇�i�B�V����肠�p���̍֓��j�w���́x�����ǁB��A���A�����F���m���o�Ď��Ƃւ��ǂ�B
���l�Z�N�i���a�\�ܔN�j ��\���
�A�������X�֓��ЁB�؉��[�����W�w�c�ɂ̐H��x��ǂ݁A��ǎ҂Ƃ��Ď莆���o���B���ꂩ���N�Ԃ̕��ʁB���W�w���ꂽ�Ɓx����B���āA�Վ����W�̂��ߖڍ��勴���n�d���ɓ���A������I����J�����ŏ��W�����ƂȂ�B�\���A���̏W�w�����G�߁x��Z�Z���A����ɂ�芧�s�B
���ɕ����O��A����̎��̂��u�⏑�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��g�����́A�Z������N�̏��m����`���A�o�咇�ԂƋ����Â��A�Ǐ��ɖ�����������A�ߗׂ≓���̉f��قɑ��ɂ��ʂ��A�m��𒆐S�ɑ����̉f����ςĂ���B
�@�ߋ��ɂǂ�قǂ̉f��ƃX�^�[�����ł������낤���B�����ł͗m��Ɍ����Ă݂�̂����A���͋L�����ĂыN�����߂ɁA�������l�́w���E�f�於��S�j�\�\��O�k�с��ҁl�x�����߂āA���ׂĂ݂���A���̂قƂ�ǂ����Ă���̂ɁA���Ȃ���������B�N���̎��͌�����������E�b����T���āA�͂��Ɩڍ��L�l�}�A�_�c�얾���A�������̃V�l�}�p���X�ւƌ��ĕ��������̂ł���B�i�q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�ꎵ�y�[�W�j
����́q�s���܂�͂����L�t�ɓo�ꂷ��f��\�\�g�����Ɖf��i2�j�r�ɂ�����f��̎��̒i�K�́A��f�̐��z�q�����̉f��r�ƁA�X�`���ʐ^�𑽐��f�ڂ����������l�i1911�`79�j�̉f��j�s���E�f�於��S�j ��O�ҁk���㋳�{���Ɂl�t�i�Љ�v�z�ЁA1974�j���{�ɂ��āA�g�������ς��i���낤�j�f��̑������쐬���邱�Ƃł���i�Ȃ��A�s���E�f�於��S�j�t�ɂ́u��O�ҁv�̗���1974�N12��30�����s�́u���ҁv�������āA�g���͂���Ɍ��y���Ă��Ȃ����A�����������Ɏ��߂�ׂ��ł��낤�j�B���̃v���W�F�N�g�́A�ŏI�I�Ɂs�g�������y�f������k���t�l�t�Ƃ��Č�������͂����B���̂��߂ɂ́A����A�f�ނɑ�������L�����q�g�����Ɖf��r�V���[�Y�Ƃ��āA�{�y�[�W�ɕ��ڂ��Ă����K�v������B
 �@
�@
�������l�s���E�f�於��S�j ��O�ҁk���㋳�{���Ɂl�t�i�Љ�v�z�ЁA1974�N11��30���k��34���F1992�N4��30���l�j�̃W���P�b�g�i���j�Ɓu���{���ɔł����̂܂܊g�債�A�����V���ɂ��Ĉ����łƂ����v�i�ҏW���j�`�T���E�n�[�h�J���@�[�A�������l�s���E�f�於��S�j ��O�сt�i�Љ�v�z�ЁA1983�N11��30���j�̃W���P�b�g�k�����E�C���X�g�F�ēc���l�i�E�j �k�g�������z�q�����̉f��\�\���̓�l�̏��D�r���M���ɎQ�Ƃ����̂͌��㋳�{���ɔŁl
�k�NjL�l
�����Ƃ��Ē������l�s���E�f�於��S�j ��O�ҁk���㋳�{���Ɂl�t�i�Љ�v�z�ЁA1974�N11��30���j�́q�ڎ��r���f����i�m���u���͏ȗ��j�B�{���̑g�̍ق́A�q��ꕔ�r��7.5�|43��18�s�i774���j�ŁA�e���͂����ނ�3�y�[�W����5�y�[�W�A�q��r��6.5�|24��21�s2�i�i1008���j�ŁA�e���͂����ނ�1�y�[�W�B�q��O���r��1910�i�����l�\�O�j�N����1944�i���a�\��j�N�܂ł�600�т̔N���Ƃ̃f�[�^�W�ŁA1938�i���a�\�O�j�N����1940�i���a�\�܁j�N�܂ł�3�N�Ԃɂ������č�i���̂f�o�����B��i���̂��Ƃ́���́A�g���������L�␏�z�Ō��y���Ă��邱�Ƃ������B
�@�͂��߂�
�q��ꕔ�r
�@�C���g�������X
�@�U��䂭��
�@�I�[�o�[�E�[�E�q��
�@�J���K�����m
�@�A���劈���u�����v�u�S�̒܁v�u�Ղ̑��Ձv
�@�捇�n��
�@���ƍ�
�@�b���̏���
�@�~�Ђ����߂�l�X
�@�Q���̃s�G��
�@�W�[�N�E�t���[�h
�@�o�O�_�b�h�̓���
�@�L�C��
�@��̓|�`�����L��
�@���C�h�̐l�C��
�@�L�b�h
�@�S�H�̔��K�N
�@�X�e���E�_���X
�@��
�@����������
�@���@���G�e
�@�{�[�E�W�F�X�g
�@�r�b�O�E�p���[�h
�@�掵�V����
�@���u�E�p���C�h
�@��������ُ�Ȃ�
�@�A�W�A�̗�
�@�Q���̓V�g��
�@�����b�R��
�@�b���̉����̉�
�@�Ԓ��w27��
�@�A�����J�̔ߌ�
�@���R���䓙��
�@�O���I�y��
�@�J
�@���̎E�����j
�@�l���ē�
�@�T�����C�Y
�@�Í��X�̊��
�@�L�k�Ƒm��
�@�O�����h�E�z�e����
�@�b����
�@�L���O�E�R���O
�@��������̏i��
�@�����̏o����
�@���D�e�i�V�`�[��
�@�ɂ�
�@�X�̓�
�@��c�͗x��
�@�����������y
�@�ʂ�̋�
�@��M�Ȃ��ƍ�
�@�O�l����
�@�t�̒��ׁ�
�@�A���i�E�J���j�i��
�@���������n
�@�}�Y���J
�@�I�y���E�n�b�g
�@�~���U��
�@�����͗��炸
�@��n
�@���_���E�^�C���X
�@�I�[�P�X�g���̏���
�@�X�^�A�a��
�@������̎蒟
�@�������t
�@�]����
�@�����̍ՓT
�@�Ō�̈ꕺ�܂�
�@�X�~�X�s�֍s��
�q��r
�@�v���[�O�̑�w��
�@�����̑n��
�@���ւ̓�
�@����ΐt
�@�َ��^�̎l�R�m
�@������钆�܂�
�@�h�N�g���E�}�u�[
�@�y�n��
�@�����N�w
�@�֕P��
�@�W�L�����m�ƃn�C�h��
�@�\�r
�@�I��
�@�s�[�^�[�E�p��
�@�~����Ȃ�
�@�_�[�N�E�G���W�F��
�@�M���̕�
�@������p�X�J��
�@�ʉe
�@�Ō�̐l
�@�C�̖�b
�@���̂̓�
�@���X
�@�R��̔g�~��
�@�A�b�V���[�Ƃ̖���
�@�A�X�t�@���g��
�@�A��
�@�e���[�Y�E���J��
�@�g�E���N�V�u
�@�s�X��
�@�z�C�Ȓ��т���
�@��n
�@���E�~���I��
�@�~�����̈��
�@�`�����v
�@�Y�B
�@�}�^�E�n����
�@����̗���
�@�����̏���
�@������O
�@��C���}
�@���悳���
�@�t��酉J
�@�J���@���P�[�h
�@�����̃����e�J����
�@�ĉ��v��
�@�^�[�U���̕��Q
�@���X�`���C���h
�@�j�̓G
�@���͑P�l��
�@�����̌�
�@�A����
�@�e�Ȃ��j
�@���~��
�@��������̈۔[��
�@����
�@�Ȋw�҂̓�
�@�H�쐼�֍s��
�@�����u�[���o
�@�n�̉ʂĂ��s��
�@�߂Ɣ�
�@���{
�@���j�͖�����
�@�V���o���G�̕��Q��
�@�������̓s���k�ѓ��k��Ƃ̑Θb�q���I�t�̌�䊁r�Ō��y�l
�@�`���ꂽ�l��
�@�֒j�̉�
�@��̓o�E���e�B���̔���
�@�n���P�[��
�@�䂪�Ƃ̊y��
�@�u���O���ꁜ
�@�f�b�h�E�G���h
�@�i�q�Ȃ��S��
�@�łɋA�遜
�@���N�̒���
�@�R���h��
�@���̍ՓT
�@�L���V����
�@�`���b�v�����̓ƍَ�
�@�w�n��
�q��O���r
�@�����l�\�O�N
�@�����l�\�l�N
�@�����l�\�ܔN�E�吳���N
�@�吳��N
�@�吳�O�N
�@�吳�l�N
�@�吳�ܔN
�@�吳�Z�N
�@�吳���N
�@�吳���N
�@�吳��N
�@�吳�\�N
�@�吳�\��N
�@�吳�\��N
�@�吳�\�O�N
�@�����\�l�N
�@�吳�\�ܔN�E���a���N
�@���a��N
�@���a�O�N
�@���a�l�N
�@���a�ܔN
�@���a�Z�N
�@���a���N
�@���a���N
�@���a��N
�@���a�\�N
�@���a�\��N
�@���a�\��N
�@���a�\�O�N
�@�@�Z�Ȃ��R�m
�@�@�Ђ߂���
�@�@�Ԃ����
�@�@�W�F�j�C�̉�
�@�@�W�����E�o���a����
�@�@�z�C�ȕP�N
�@�@�X�e���E�_���X
�@�@�e�X�g�E�p�C���b�g
�@���a�\�l�N
�@�@�Ƃ���杁m���̂�����n
�@�@�}���R�E�|�[���̖`��
�@�@��陔��l�ڂ̍�
�@�@���t
�@�@�n���C
�@�@�s�v�c�ȃ��B�N�g����
�@�@���E�{�G�[��
�@�@�^�[�U���̖ҏP
�@�@�w�M
�@���a�\�ܔN
�@�@�g�̗�
�@�@�����m�̗�
�@�@�q���ƋM�w�l
�@�@���@���G�e�̉���
�@�@���̐l�X
�@�@�J�b�X���v��
�@�@�O�l�̒���
�@�@������l�X
�@�@�S�[���f���E�{�[�C
�@�@����������
�@�@�I�N���z�}�E�L�b�h
�@�@�t�����P���V���^�C���̕���
�@�@�X�^�����[�T���L
�@�@�x��j���E�E���[�N
�@�@�C�m��
�@�@���̔n��
�@�@�c���ɍ���
�@�@�啽��
�@�@�X���
�@�@��O�̉e
�@���a�\�Z�N
�@���a�\���N
�@���a�\���N
�@���a�\��N
�@���Ƃ���
�@����
�ǎ҂́A�Ⴆ�ΐ��I�ȃp�m���}�ٓ��Ɏ�������ꂽ���̂悤�ɁA���������ϓ]����l�X�Ȍ��z�̗��ƂȂ��āA�������s�����t�̐g�������L�������邱�ƂɂȂ�킯�ł���B�i�H���K�l�q�g�����Ɓw�����x�Ƃ����G�r�A�s�g�����A���x�X�N�t�A����R�c�A2002�N5��31���A��Z��y�[�W�j
2019�N11�����s�ҏW��L�t�Ɋ۔����L�s�g�~�m�̒n���k�S4���l�t�iKADOKAWA�A2014�`19�j�̂��Ƃ����������A�����āA���ǂ������s�𒎁t�i�G���^�[�u���C���A2009�N11��6���k5���FKADOKAWA�A2015�N3��13���l�j����肵���B�W���P�b�g��\���Ɂu���� �]�ː에���v�A�u�r�F�E��� �۔����L�v�Ƃ���悤�ɁA�۔��������̒Z�сq�𒎁r���܂�܂�1���̒P�s�{�Ɏd�グ�����̂��i���o���́s�����R�~�b�N�r�[���t2009�N6�����`9�����Ƃ��邪�A���͂��̎G����m��Ȃ������j�B�q�𒎁r�͊�g���Ɂi�`�U���j�̕l�c�Y��ҁs�]�ː에����i�W �V�k�p�m���}����k�E�̑�Ȃ閲 ���l�t�i��g���X�A2018�N3��16���j�ł͂킸���ɖ{��28�y�[�W�����A�۔��́s�𒎁t�͂`�T����140�y�[�W�̗̈e���ւ��Ă���B�q�𒎁r�́AWikipedia�ɂ́u�������{����ȂɌ������Ƃ���A�u����炵���v�ƌ���ꂽ�Ƃ����B�܂��A�{���ǂ|�W�̂������l�����u���͂��������Ȃ��v�Ƃ��ڂ����Ƃ������B�v�ƋL����Ă���B���̍Ȃ�|�W���۔��̖{��������i�ǂ�j���������Ȃ�ƌ������낤���B�z�����邾�ɕ|�낵���B�����悭���p����旧�}���قɂ́A�s�𒎁t�Ɠ����R���r�ɂ��s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���A2008�j����������Ă�����̂́A�s�𒎁t�͂Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�אڂ��鑼��̐}���قɂ��Ȃ������B��g���ɔł͂����̂ЂƂ������ď������Ă��邩��A�����ς�۔��̉�̏Ռ����䂦�ɁA�s�𒎁t�͏�����������ꂽ�Ǝv�����B�Ƃ��������A��13���ˎ��������ܐV������́s�p�m���}���Y杁t���ٗႾ�����Ƃ����ׂ����i���P�j�B���āA�g�����͍]�ː에���ɂ��ẮA�q�Ǐ����r�i���o�́s�T���Ǐ��l�t1968�N4��8�����A����́q�R������ƃ����P�r�j�Ŏ��̂悤�ɋL���Ă��邾�����i���Q�j�B
�@���N�A�ċx�݂ɂȂ�ƁA�ǂԏL���{������`�̘H�n�𗣂�āA�s��^�Ԃ̏f��̉Ƃɍs���A���ɂ����܂ꂽ���A�������̕����Ă���r�̂قƂ��A�����̂Ƃ�ł��鑐�ނ�ŁA�����₩�ȓc�����������̂��B���̉Ƃ̖L�x�ȑ����ނ���킽���͂����w�u�k�S�W�x���ʂ������āA�ǂݒ^����B�p�Y�������瓁���A���l�܂ł������낢�b�͂��Ȃ��B����Z�S�ł�����Z�̕z���̖{�ŁA��A�O�\���ʂ������Ǝv���B�܂��N��̏]�Z�킽���̂����Ă����A�]�ː에���́w�Ǔ��̋S�x�w�������ʁx�w�ꐡ�@�t�x�����āw�A�b�x�Ƃ�������ׂ���i�܂ŁA�Ɛl�ɂ�����ēǂ��̂ł���B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�܌܃y�[�W�j
�]�ː에���i1894�`1965�j�̗��N���ɂ́A���a�Z�i1931�j�N�̍��Ɂu���}�Ђ�菉�̑S�W�����s�B�S�\�O���������������N�A��x�ڂ̋x�M�ɓ���B�i�O�\���j�v�i�s�]�ː에���S�W ��30���@�킪���Ɛ^���k�����Е��Ɂl�t�A�����ЁA2005�N6��20���A����Z�y�[�W�j�Ƃ���A���͋g�������z�ŋ�����������i�͕��}�ДőS�W�œǂ��̂ƍl���āA�����s�g�������y�����E��i�������k���t�l�t�ɂ����L�����i���}�ДőS�W�͖����j�B
�s�Ǔ��̋S�k�]�ː에���S�W. ��5���l�t�i���}�ЁA1931�N7��10���j
�@�]�ː에���̒��я����B������1930�N5���A�����ЁB
�s�������ʁk�]�ː에���S�W. ��10���l�t�i���}�ЁA1931�N9��10���j
�@�]�ː에���̒��я����B�����͖{�S�W�B
�s�ꐡ�@�t�k�]�ː에���S�W. ��2���l�t�i���}�ЁA1931�N10��10���j
�@�]�ː에���̒��я����B������1927�N3���A�t�z���B
�s�p�m���}����杁k�]�ː에���S�W. ��1���l�t�i���}�ЁA1931�N6��10���j
�@�q�A�b�r�͍]�ː에���̒��я����ŏ�����1928�N11���A�����فB
�����{�����Ƃ���A���}�Дŗ����S�W�̏��e���������̂ŁA�ȉ��Ɍf����B�o�T�͌�o���e�̃L���v�V�����ɋL�������A���{�̎ʐ^�̃L���v�V�����������A���̂Ƃ���ł���B
�w�]�ː에���S�W�x��1�� 1931(���a6)�N6���A��4��1931(���a6)�N8���A��8�� 1931(���a6)�N5���A��13�� 1932(���a7)�N5���@���}�Ё@������w��
�����@�������ɕۊǂ���Ă���①���B��1���́w�p�m���}���Y杁x���ځB�����ƍY���o������N�̊��s�B��4���͍Y�Ɨ������������t�����X���A�������̓o��l���A�W�S�}�A�t�@���g�}�A�v���e�A�̖����o�Ă��颋�C�j����ځB��8���́A�Y���m�[�g�ɋL������֒f���ꂽ���t��Ɠ������z�������࢈���ځB��13���͢�T�㏬���\�N������ځB��ؔn�͉�飂̍��ŗ������Y�ƐŖؔn�ɏ�������Ƃ���z���Ă���B
![�o�T�F�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�ٕҁs�k�����Y���a130�N�L�O�E�O�����w�ٓ��ʊ��W�l�p�m���}�E�W�I���}�E�O���e�X�N�\�\�]�ː에���Ɣ����Y�t�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2016�N10��1���A�k�܃y�[�W�l�j](image/ranpo_zenshuu_1.jpg) �@
�@![�s�p�m���}�E�W�I���}�E�O���e�X�N�\�\�]�ː에���Ɣ����Y�k�����Y���a130�N�L�O�l�t�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2016�N10��1���`12��18���j�̊۔����L�ɂ��s�p�m���}���Y杁t����W�i���A2016�N12��1���`2017�N1��9���j�̃|�X�^�[](image/panorama_poster_01.jpg)
�o�T�F�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�ٕҁs�k�����Y���a130�N�L�O�E�O�����w�ٓ��ʊ��W�l�p�m���}�E�W�I���}�E�O���e�X�N�\�\�]�ː에���Ɣ����Y�t�i�����Y�L�O ���ƗƎ��̂܂��O�����w�فA2016�N10��1���A�k�܃y�[�W�l�j�i���j�Ɠ��W�i���فA2016�N10��1���`12��18���j�̊۔����L�ɂ��s�p�m���}���Y杁t����W�i���A2016�N12��1���`2017�N1��9���j�̃|�X�^�[�i�E�j �k�c�O�Ȃ��玄�͑o���Ƃ��ςĂ��Ȃ��l
�g���͏�f�̐��z�ł͐G��Ă��Ȃ����A�����S�W�Łs�p�m���}����杁t��ǂ܂Ȃ������Ƃ͂Ƃ��Ă��M�����Ȃ��i�O�̂��߁A�����̏����̕W��͍����ł́q�p�m���}����k�r�ł���j�B�����͖{���U�肩�����āA�u�A�ڒ��͗]��D�]�ł͂Ȃ������B���߂̕��̐l�ԓ��ꂩ���̌��͖ʔ����ɂ��Ă��A���̏����̑啔�����߂�p�m���}���̕`�ʂ��ދ�����ꂽ�悤�ł���B�|�[�́u�A�����n�C���̗̒n�v��u�����_�[�̉��~�v�����̔O���ɂ������̂����A�o���オ�����̂́A�ӂ����ė͑���ʕ��}�ȕ��i�`�ʂł����Ȃ������B�������A���\��A�N�����ɂ�āA�`���z���D�]���悤�ɂȂ����B���ɂ������Y���A���̉Ƃ̓y���Ŏ����ށm���n�����Ȃ���A���̏������ق߂Ă��ꂽ���Ƃ�Y��Ȃ��B����ȗ��A���̍�i�ɏ�������ΊO�I���M�����悤�ɂȂ����B�v�i�q�w�p�m���}����k�x�\�\�킪�����r�A�s�]�ː에���S�W ��2���@�p�m���}���Y杁k�����Е��Ɂl�t�A�����ЁA2004�N8��20���A�l��O�y�[�W�B���o�́s�����V���t1962�N4��27���j�ƋL���Ă���A�Y�̕]�Ƃ������Ƃ�����������B�s�L���t�i1935�j�̎��l���{����̎]���邱�ƂɁA�Ȃ�̕s�v�c���Ȃ��B�����ł́A�F�V���F��M���ɖ{��̕]���͂���߂č����B�����́q�p�m���}����k�r�͑O�f��g���ɂł͖{��146�y�[�W�̒��т����A�۔����L�͂����272�y�[�W�́s�p�m���}���Y杁t�Ɏd���ĂĂ���B�۔������܂��܂ȕ�����f�悩����p�����}���i�p�X�e�B�V����p���f�B�j������ɂ���߂邱�Ƃ͂Ƃɒm���Ă��邪�\�\�u�����g�����v�I�\�\�A����͂܂�������w�E���Ă��Ȃ��͂������A�Ƃ�킯�L���Ȕ����i�����j�ƃt���[�N�X�i�����j�̊G�ɂ̓N�����B�X�E�g���C�����ӎ��I�ɍ̂肢����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�����Ă��̑ł��グ�ԉ��c�~�ɂ����Ă����f�悱���A�y���F���o�������]�ː에������E�Έ�P�j�ē�i�s�]�ː에���S�W ���|��`�l�ԁt�i���f�A1969�j�������i���R�j�B
 �@
�@![���� �]�ː에���A�r�F�E��� �۔����L�s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���A2008�N3��7���k10���FKADOKAWA�A2016�N10��7���l�j�q��́r�̔��G](image/panprama_05_01.jpg)
![���� �]�ː에���A�r�F�E��� �۔����L�s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���A2008�N3��7���k10���FKADOKAWA�A2016�N10��7���l�j�q�掵�́r�̔��G](image/panprama_07_01.jpg) �@
�@![���� �]�ː에���A�r�F�E��� �۔����L�s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���A2008�N3��7���k10���FKADOKAWA�A2016�N10��7���l�j��y�[�W](image/panprama_228_01.jpg)
�N�����B�X�E�g���C���́qSous le culte des Sorcieres en flirt�i�Z��ޏ��̍��J�̈��Ɂj�r�i1943�j�i���j�ƌ��� �]�ː에���A�r�F�E��� �۔����L�s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���A2008�N3��7���k10���FKADOKAWA�A2016�N10��7���l�j�q��́r�̔��G�Ɠ��E�q�掵�́r�̔��G�i���j�Ɠ��E�q�掵�́r�̓�y�[�W�i�E�j
�۔��̕`��͂ɂ͕|�낵���܂ł̂��̂������āA�s�p�m���}���Y杁t�̌㔼�̌����ɏ[�����V�[���ȂǁA�����炭���ĒN���Ȃ����Ȃ��������݂ɂ���B�۔��͂����ŁA�������܂߂����A���i���ڗ킵�����₨���܂����e�p�̒j�I�j��A���R��s�s�̌i�ρA��������s�������Q�O��`���ۂɂ��A���������̑Ë���r���ďc�����s�̃��`�G��ӂ��B����͂Ƃ�킯�A1�y�[�W��̃R�}��e�͂̔��G�ɂ����Ē������B�����̃y�[�W�ɂ��������邽�тɁA���͖O�����Ɍ�����̂��˂Ƃ���B���Ƃ��q�掵�́r�ŁA�ԓc���O�Y�ɂȂ肷�܂������Ƃ��I�������ƌ������l���E�l���A��́A��̐��ɟ����S���h���ōȂ̌ԓc���q���i�E����B���̙��߁A��ɋ���ȉԉ��y��B�p�m���}���̏Z�l�i�H�j�̔����N���u����!? �����v�ƌ����ƁA���������u����͉ԉł��v�Ɣۂށi�۔��������ʼn��~���ɂ����̂́A�|�E�ƃW���C�X���j�B���̎����A��Ɉ������{���ōł���ɓI�ȃy�[�W�ŁA�u���O�Y�v�͘@���Q�ɂƂ܂�u�ɋC�Â��āA���ɕ����ׂ����q�Ɍ������āu���E����������̂��v�ƌĂт�����B����ƁA���̔���j�ɂ��u���Ƃ܂��Ă���B���ꂪ�s�p�m���}���Y杁t�Łi��z�V�[���������āj���q���o�ꂷ��Ō�̃R�}�ł���B�g�������۔����L�́s�p�m���}���Y杁t��ڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��A�����ǂꂾ���c�O�Ɏv���Ă��邩�A���킩�肢�������邾�낤�i���S�j�B�Ƃ��ɁA�n��ɂ����Ă��ꂾ������Ȍ����͂ɂ��闐���Ƌg�����A�c�����̗V�т����Ƃ��A�����������̔����łł����邩�̂悤�ɂ��낢�����q�ɂȂ�̂͂܂��Ƃɋ����[���B�����Ɂq�r�C�ʁr�i���o�́s�g�b�v�t1936�N11�����j�Ƒ肷�鐏�z������̂ŁA���̒��قǂ�ǂ�ł݂悤�B
�@���N�����U��Ԃ��ăr�C�ʂɗނ�����̂��v���o���A�l�̏Z��ł������É��s�ł́A���̍��ցm���n�̎�Ƌ�ǁm����Ȃ�n�̎�����Ă����Ԃ��Ƃ����s���Ă��āA�l�ɂ͂��̓�̂��̂ɉ��炵�����D������B
�@�ւ̎��̔���ނ��ƁA���Ɋ�m�����n���̃Z�s���F�̍d���킪�͂����Ă���B���̎�̈��͂��傤�ǖ����m�݂���n�̑܂̂悤�Ȍ`�����Ă��āA�̏�ɓ����o���ƁA�����͉��ɓ|��邪�A���ɂ͂��̊ۂ���̕����ŕs�|���m���������肱�ڂ��n�̂悤�ɗ����Ă�����̂�����B
�@�����ŁA�q�������͖��X�m�߂��߂��n�̒ւ̎������o�������A��l������ŐU���Ĕ̏�ɓ����o���āA�ۂ���̕��ŗ����Ă������̂������Ƃ��ď����𑈂��A����Βւ̎�̊p�́m�������n�ł���B
�@�ւ̎�̒��ɂ͂����H�m�܁n��ɁA��̊ۂ����������ɍL���āA������U���Ă��K�������オ��s���g�m�ӂ��݁n�̂��̂��������B�����������̂������Ă���q���͑哾�ӂŁA�Ԃ�̎��m���邵�n�ł����ĕ\�ʂ��ʐF���āA���̍��̉��j�A�헤�R���Ƃ��~�P�J�m���߂����Ɂn���Ƃ��̖�����������A�֊p�͂̑�I��Ƃ��āA���̕�ɂ����������������������̂ł���B
�@�l���֊p�͂ł͖����ł������B���S������A�������ւ̎����ė��āA������s���g�̎킪�o�ė��₵�Ȃ����ƁA����������Č���̂��A�ǂ�ȂɊy���݂������낤�B�����āA������̍L���A�܂�ł��o�m���n�݂����Ȍ`�́A�����������Ȏ������ƁA���J�Ɏ��ł����ς��Ă��̂�����̊y���݂ł������B��������������Ƃ́A�����炭�t�����X�̎q�������́A�ԓ��̂悤�Ȏȁm���܁n�̂�������̃r�C�ʂɂ����Ȃ������ł��낤�B�i�s�]�ː에���S�W ��30���@�킪���Ɛ^���k�����Е��Ɂl�t�A�Z�܁`�Z�Z�y�[�W�j
�g���̐��z��ǂ��Ƃ�����قǂ̎҂Ȃ�A�N�����q�x�C�S�}���l�\�\���N����̂ЂƂ̑z���o�r�i���o�́s��t1983�N7�����j��z�N����ɈႢ�Ȃ��B
�@���͋C�ɓ������x�C�S�}����ɓ���ƁA�Q����݂̂��֘X��N��������n�������݁A�������������肵���B���鎞�A�d�����F�ʂ̃x�C�Ɍ����ꂽ�B����̎q�ɂ����˂�ƁA�Ό�������Ă߂��ƁA��@�����Ă��ꂽ�B�������A���̂悤�ȃx�C�S�}�́A���ߕi�ł���A�z���R�ɂ͎g�����̂ł͂Ȃ��B
�@�x�C�V�т̋ɒv�́A���A���l�ł��z���R�����ɂ���B�K�`�K�`�Ԃ��荇���A�ɂԂ��S�i�����j�̉��B�����x�C�Ȃ�A����c�炸�ɒe���o���Ă��܂��B�������x�C�����Ȃ̂��̂Ȃ�A�g�R����͂ݏグ��悢�B�S���Ղ����I�@�����ł́A���ʔ\�͂���Ȃ̂ł���B�������A���ꂽ��A���X���X�A�x�C�S�}�͑ւ��Ă���̂������B���������A����������x�C���A�R�������A���o�I�G�o�I�Ɋm�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�g�R�̒�������Ă��鎵�A���̃x�C�S�}�B�ǂꂪ���Ȃ̃x�C���݂�Ȃ킩���Ă���̂��B�i�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��Z���y�[�W�j
�q���̂���̗V�т������m��Ȃ��҂ɓ`���悤�Ƃ���ƁA��������������������ɂȂ�Ƃ����̂�����̐^�����Ƃ��Ă��A���҂̕M�̉^�тɂ͂���ȏ�̂��̂�����B�܂�A���g�̍�i�i�����ɂƂ��Ă̏����A�g���ɂƂ��Ă̎��сj�Ƃ͂܂邫��قȂ�J舂ȎU���̕��̂̂��Ƃ����������̂��B���͂Ђ����ɑz���B�g�������z�i���e�����̂ݎw�肪�����āA���e�͕s�₾�������j�̎��M���˗����ꂽ�Ƃ��A�����́q�r�C�ʁr��ǂ݂��������̂ł͂Ȃ����A�ƁB
�ȉ��ł́A�g���̐��z�ɏo�Ă��闐���̏����ɂ��ĐG��邪�A�K�������g���Ƃ̊W�ɂƂǂ܂�Ȃ��B�Ȃ��A�������͂��łɋL�����̂ŁA���o����t�L����B
�i�O�f���ŋg����������ǂƂ����u�s��^�Ԃ̏f��̉Ɓv�Ƃ͗鎭�ƂŁA���̎q�����A���Ȃ킿�g���ɂƂ��ăC�g�R�����́u������������q����b�����v�i�s���܂�͂����L�t�A����R�c�A1990�A�܈�`�ܓ�y�[�W�j������A�����{�������Ă����u�N��̏]�Z�킽���v�́u�������v�i�ʂ̌��ł́u���ꂳ��v�Ƃ���̂�����ƁA�鎭���ꂩ�j�u�������v�Ƃ������ƂɂȂ낤�B�s�u�k�S�W�k�S12���l�t�i����{�Y�ى�u�k�ЁA1928�`29�j�͏f�ꂩ���̕v�̏��L���낤���A�鎭�Ƃ͎q�������ɂ������S�W����������悤�ȉƕ��������B�j
�s�Ǔ��̋S�t�i1929�N1������1930�N2���܂Ŕ����ق̌������s�����t�ɘA�ځj�\�\�����\���͂̎コ���w�E����闐���̒��я����ɂ����āA�{��͂��̐���Ȃ���Ƃ�������W�J���ǎ҂̗\�����āA���ٗl�Ȕ��͂ނɎ����Ă��錆��B�����Ƃ��A�`���Ō���̌���i���g�̎Ⴗ���锒���ƍȂ̍��ɂ��鏝�Ձj���������̂ŁA���̓�l�����͖����ɐ��҂���̂��ƕۏ���Ă���̂����A�ǎ҂���ʂɎ�闐���̕M�́A�����̒��ђ��A����ł���B���āA�����ɂ͖���]�Ƃ������ׂ�����������B���͕����|�ǂƂ͈قȂ邪�A���ЂƂ˂��Ȃ����A�Ő��������Ă���悤�ȏ�ʂ͑z�����邾���őς��������A�{��㔼�̖`��杁i�Ƃ�킯�q�������M�m�炸�r�ȍ~�j�ł́A���x���y�[�W����ċC��킵�Ă���łȂ��Ƒ������ǂ߂Ȃ��������Ƃ���������B���ꂾ���Ɂq��c�~�r�́A�a���������Y�i�����炢�Â����j���Ŏ�������e����̎莆�́A�킸����s�Ȃ���A���̍��g�̔����Ƃ������ׂ�����ł���i���������ɗ����́A�����̈ꕶ�ő��������X�点��B���Ƃ��ΒZ�сq�x��ꐡ�@�t�r�i���T�j�́u���̗l�Ȍ������A�ω��x�m�ւ��ǂ�n�̉e�@�t���A�^���ɕ�����点�Ă����B�j�̎�ɂ���ۂ�������A�����Ĕގ��g��������A�Z���ȁA�����t�̂��A�{�g���{�g���Ɛ���Ă���̂����A�͂�����ƌ�������ꂽ�B�v������j�B���́s���̉ԁt�i1954�j�����������i���F�i1918�`1979�j���s�Ǔ��̋S�t���ǂ��ǂ̂��i�ނ��ǂɌ��܂��Ă���j�A�����ɒm�肽���Ǝv�������̂��B
�s�������ʁt�i1930�N9������1931�N10���܂ő���{�Y�ى�u�k�Ђ̌������s�L���O�t�ɘA�ځj�\�\�{��́A���̍ł����������̍]�ː에���̍�i�̃C���[�W���̂��̂ł���B���Ȃ킿�A�N���҂��܂ނ�����N��w�̓ǎ҂𖣗����闐���߂̘A�ŁB���q���ܘY�ƃA���Z�[�k�E���p���i�������ʁj�̈�R�ł��Ɨ���A��Ɋ�������V�[���̘A���ɂȂ�͕̂K�肾�B���p�����ւ̌��y�������̂��A���u�����̈��ǎ҂ɂ͂��������Ȃ���҂̃T�[�r�X�ł���B�����̕��͂̓ǂ݂₷���̗v���̂ЂƂɁA���R�ƌJ�肾�����^����������B
�@�Ԃ��Ȃ����̔������l���J�t�F�̊O�֎p�����킵���B�@���ɂ������B�����瑫�̐�܂Ŕ����m�����낢�n�œh��Ԃ����l�ɐ^�����B����E��������A�畆�����q�݂����ɐ^�������m��Ȃ��B�����Ƃ���䂯�́A���l�ɂ����炵���������B
�@�g�̂����l�̖��ɒp���ʈ̑�Ȃ��̂ł������B�Z�ڈȏ�̐g���ŁA�������p�́m�������n��݂����ɔ쑾�m�����ӂƁn���Ă���̂��B
�@�ނ̓J�t�F���o��ƁA�Ԃ��E�킸�A�u���u���Ƌ���ʂ�֕����čs���B
�@�����s�v�c�Ȕ��s�s�n�܂����B�擪�ɗ��͔̂����̂������R�����势�A���ꂩ��\�ܘZ�Ԃ�������u���āA�A���p�J���ዾ�̉��V�l�A�Ԃ����C�̉^�]��A�Â��ĕ������̔ԓ�����Ƃ��������D�̌Y���N�B�i�q�������l�r�A�s�]�ː에���S�W ��7���@�������ʁk�����Е��Ɂl�t�A�����ЁA2003�N9��20���A�O�y�[�W�j
�u��势�v�Ƃ͍����ł͂قƂ�nj������Ȃ������Ł\�\���̏�e�͂Ȃ������������Ă��A�u�|�b�`�����v�ȂǂƏ̂��邪�A�܂邫��ʕ��ł���\�\�A�g�����́s�_��I�Ȏ���̎��t�����́q�}�N���R�X���X�r�i�F�E1�j��
�@�k�c�c�l
�@��势�̂ڂ���̎o��
�@�o�����݂ɍs��
�@�����{�[�����̓������邩�ˁH
�@����������
�@�ڂ���̔��̎q���͗V�Ԃ�
�@�_���_��������̂�
�@��̃p�C�i�b�v��
�@�H�ׂ铍�F�̐l�H�l��
�@�l������������鎞�܂�
�@����ɂӂƂ�ڂ����势�̌Z��
�@�k�c�c�l
�ƁA��������܂����R�Ɓu��势�v��o�ꂳ���Ă���B�g�����s�m���t�̌��łȎ���̋C������E�o����ۂɁA�����I�Ȍ�b�̊��p��}�������Ƃ͂܂��Ƃɂ����ċ����[���B
�s�ꐡ�@�t�t�i1926�N12��8������1927�N2��20���܂Łs���������V���t�ɁA1926�N12��8������1927�N2��21���܂Łs��㒩���V���t�Ɍf�ځj�\�\�����̖{���ƌ����Е��ɔō]�ː에���S�W�ɕt���ꂽ���߂������B
�y�{���z�@
�@�ށk���і�O�m�����n�l�͌�Ԃ����ڂɌ��āA�������ӂɂ����Ȃ�Ȃ���A�Ȃ������s�𑱂����B�ꐡ�@�t�͑�ʂ肩�璆�̋��̂��܂��܂��������֓����čs�����B���̕ӂ͕n���A�m���n�Ȃǂ������āA�����ɂ�����ȏ������������Ǝv������A���G�Ȗ��H���Ȃ��Ă����B����͂��������x�ƂȂ��܂�Ȃ�̂ŁA�܂��܂����s������ɂȂ���肾�B��O�͌�Ԃ���O���������ʓ��ɂ���������n�߂Ă����B�i�q���l�̘r�r�A�s�]�ː에���S�W ��2���@�p�m���}���Y杁k�����Е��Ɂl�t�A�܁Z���y�[�W�j
�y���߁z�@
��90�@���m�Ȃ��n�̋��m�����n�@�����̒n�����[���Ɩ{����ɂ��������A�ꐡ�@�t����ȋ���n���Ă���Ă������ƂƁA�u�{���m�ق�n�v�Ƃ̂��ɖ��L����Ă��邱�Ƃ���{����̒��V���ƍl������B����͍]�ˊ����珺�a�ܔN�̒����ŁA���a�ܔN�Ɍ�ȋ���`�O���ڂƂȂ����B�����͖{���撆�V���|���m�������悤�n�i���s�̖n�c��j�ɑ吳�Z�N�Z������Z��ł����B�i���O�A���l�Z�y�[�W�j
�y�{���z�A
�l�͂��̗�����t�������āA�o���邾�����ׂ��̂ł����A��ȋ��̓��l�m�Ђ����Â߁n�܂ł́A�F�X�Ȑl�̋L�������o���āA�ǂ��ɂ������ɂ��Ղ����邱�Ƃ��o���܂�������ǁA���ꂩ���́A����n�����̂��A�͊݁m�����n���X���̕��֍s�����̂��A����Ƃ����ɐ܂�ċƕ����m�Ȃ�Ђ���n�̕��Ɍ������̂��A�ǂ����s���Ă�����Ȃ��̂ł��B�i�q���~�m���߁n�l�`�r�A���O�A�܌܈�y�[�W�j
�y���߁z�A
��97�@�X���m���܂���n�@���c��ɉ˂��鋴�̈�ŁA��ȋ�����`�����͂���ʼn����ɂ���B�䓌�摠�O�ڂƋ�`�ڂ̂������t���ʂ��n�c��{���꒚�ڂւƖ������N�ɑn�˂��ꂽ�B������\�Z�N�ɓS���ɁA���a�l�N�ɓS�R���N���[�g���ɉ˂��ւ���ꂽ�B��q�̋ƕ����m�Ȃ�Ђ���n�́A���݂̂��̂͏��a�ܔN�ɖn�c��ƕ��꒚�ڂ���ȋ��O���ڂ֑剡��ɉ˂��ꂽ���B�n�˂͊����m����Ԃ�n��N�i��Z�Z��j�ɂ����̂ڂ�A�t�߂ɂ������ƕ��V�_�̖�������Ė��t����ꂽ�B�i���O�A���l�O�y�[�W�j
�g���z�q�ҁs�k�g�����l�N���t�̖`���́u�����N�i�吳���N�j�^�l���\�ܓ��A�����s�{���撆�m���ƕ����ɐ��܂��B�g���䑾�Y�A���Ƃ̎O�j�B���͖����q�포�w�Z�̏��g�B�o���q�A�Z���v�A���Z���i�����j�B�v�i�s�g�����S���W�t�A�}�����[�A1996�A������y�[�W�j�ł���B�g���͂��̏����ɐ�X�����o�Ă���Ƃ���ȏ�ɁA�y�{���z�@�́u�ꐡ�@�t�͑�ʂ肩�璆�̋��̂��܂��܂��������֓����čs�����B�v�Ƃ����ӏ��ɑł��ꂽ�̂ł͂���܂����B�����̐��܂ꂽ�y�n��A���ݏZ��ł���ꏊ�������ɓo�ꂷ��A��҂������ɂǂ̂悤�ȋL���I�ȈӖ���t�^���Ă��邩�A��������C�ɂȂ邾�낤�B�Ƃ�킯���̍�҂ɐS�����Ă���ꍇ�́B
�s�A�b�t�i�����ق̌������s�V�N�t��1928�N8�������E9���E10����3��A�ځj�\�\�����͖{�тŁA�쒆�́u���v�Ə����Ɓu��]�t�D�v�ɕ��āA��҂��Y�扻���Ă݂���B���́u��]�t�D�̕s�C���ȏ����u�������̗V�Y�v�v���������g�́q�������̎U���ҁr�i1925�j���ق̂߂����Ă��邱�Ƃ́A�N�ɂł��킩��B
�@���͐Îq�̘b���Ă�����ɁA��]�t�D�̕s�C���ȏ����u�������̗V�Y�v���v�o���Ȃ��ł͂����Ȃ������B�Ⴕ�Îq�̕��������v�̉������o�łȂ��A�����ɏt�D���Ђ���ł����Ƃ���A�ނ͂��̏����̎v�������A���̂܂��s�Ɉڂ������̂ł���A���ɏt�D�炵�������ƍm�m���Ȃ��n�����Ƃ��o�����B���́u�������̗V�Y�v��ǂ�ł����䂯�ɁA���̐Îq�̈ꌩ�˔�m�Ƃҁn�Șb���A��ɕ������邱�Ƃ��o���Ȃ���������łȂ��A�����g���������|�������Ȃ��ł͂����Ȃ������B���͉������̈Èł̒��ŁA�^�ԂȂƂ�X�ƁA�������������������傤�̑�]�t�D���A�j���j���Ə��Ă��錶�o�������������B�i�s�]�ː에���S�W ��3���@�A�b�k�����Е��Ɂl�t�A�����ЁA2005�N11��20���A�܋��y�[�W�j
��ʂɎ��o�^�Ƃ���闐�������A���̉��̎g�����ȂǓ��ɓ��������̂��B�Ƃɂ����܊��̎h���̎d�������[�ł͂Ȃ��B�����ЂƂA�����ɂ������炵����߂��������B
�@�����ȑ��̑�����A�l�F�̋����Ă����B�d�Ԃ̋����ł��낤���A�����̕����痋�̗l�Ȃ��̂��A�����g�̎���ɍ����āA�I�h���I�h���ƕ����ė����B����͒��x�A��A�����̌R���������悹�ė���A�w���ۂ̗l�ɁA�C�������v��ꂽ�B���炭���̓V��ƁA�y���̒��̈ٗl�ȋ�C���A���B��l���C�Ⴂ�ɂ����̂ł͂Ȃ��������B�Îq�������A���ƂɂȂ��čl���Č���ƁA���C�̍����m�����n�ł͂Ȃ������̂��B���͂����ɉ�����Ă������Ă���ޏ��̊������S�g�߂Ȃ���A���X�m���悤�n�ɂ����̐����𑱂��čs�����B�i���O�A�Z�܌܁`�Z�ܘZ�y�[�W�j
�g�����`���̐��z�Łu�w�A�b�x�Ƃ�������ׂ���i�v�Ə����Ă���̂́A聖[�ł̕ڑł��s�ׂ�u���v�Ɓu�Îq�v�̌���Ȃǂ́A��Z��̓ǎ҂ɂ͎h���I�ȓ��e�ɂ�邽�߂��낤�B�u���鎞�́A�Îq�Ǝ��Ƃ́A�c���q���ɕԂ��āA�Âڂ����������~�̗l�ɍL���Ƃ̒����A���̗l�ɐ���o���āA�n�b�n�b�ƌ��ő������Ȃ���A���ꍇ���ċ킯������B�����͂����Ƃ���ƁA�ޏ��͂��邩�m�A�A�A�n�݂����ɐg�����˂点�āA�I�݂Ɏ��̎�̒������蔲���Ă͑������B�O�b�^���Ǝ��l�ɐd�Ȃ��ē|��Ă��܂��܂ŁA���B�͑�������ɑ��������B���鎞�́A���Â��y���̒��ɂƂ��Ă��Ĉꎞ�Ԃ��Ԃ��Â܂�Ԃ��Ă����B�Ⴕ�l�����āA���̓y���̓����Ɏ������܂��Ă����Ȃ�A�����炳���߂����ȏ��̂����苃���ɍ����āA��d���̗l�ɁA�����j�̎藣���̋��������A�����ԑ����Ă���̂����ł��낤�B�v�i���O�A�Z�O��y�[�W�j
�s�p�m���}���Y杁t�i1926�N10������1927�N4���܂Ŕ����ق̌������s�V�N�t�ɘA�ځj�\�\���̍ۂ�����A�g���̐��z�ɂ͓o�ꂵ�Ȃ��s�p�m���}���Y杁t�ɂ��G��Ă������i�ȉ��A��{�́s�]�ː에���S�W ��2���@�p�m���}���Y杁k�����Е��Ɂl�t�j�B��l���̍Ȃ�`�������̕M�́A���̖��^���܂߂āA�������B
�@�A��́A���O�Y�Ƃ��Ă̔ޏ��k���q�l�Ƃ̏��Ζʂ̌��i���A���㒷���ԖY��邱�Ƃ��o���܂���ł����B�k�c�c�l
�@�����āA�ނ̐g�̂��A���ւɒS�m���n�����m����n�����̂�Ҍ��˂āA���̏�ɂ�������A�����ԁA�e�ʂ̐l�B�������˂āA�ޏ���ނ̐g�̂�����������܂ŁA�g�����������ɋ����Ă��܂����B���̊ԁA�ނ͂ڂ��肵���\����āA�ʖсm�܂��n����{��{�Z�m�����n���邱�Ƃ��o��������A�ڂ̑O�ɔ������ޏ��̊���A�����ʖт��܂ɂӂ���݁A�n����ʓ��̗l�ɐ��߂��A�������сm���Ԃ��n�̌���j�̏���A�܂̐삪����āA�����āA�����F�̊��m�Ȃ߂�n���������A���l�ɘc�m�䂪�n�ނ̂��A�����ƌ��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���ł����B�������ł͂���܂���B�ޏ��̂����ȓ�̘r���A�ނ̌��ɂ�����A���ł��̋u�ˁm���䂤��悤�n���A�ނ̋���g�߁A���I�Ȃق̂��Ȃ鍁�C�܂ł��A�ނ̕@����������̂ł����B���̎��́A���ɂ��ٗl�ȐS�����A�ނ͉i�v�ɖY��邱�Ƃ��o���܂���B�i�����A�l�Z�O�`�l�Z�l�y�[�W�j
�۔��́s�p�m���}���Y杁t�ł����q�͂͂Ȃ͂����͓I�ɕ`����Ă���i����������ɂ���u��\��v�����N��Ɍ�����j�B�������قƂ�Ǖ`�ʂ��Ă��Ȃ������Ɋւ��Ă��A�m�����͂��߁i���o�ꎞ���܂߁A�O�o���͗m���������j�A�a���̕����`���킯�Ă��āA������ς邾���ł��{������ɂ��鉿�l�͂���B���̋ɂߕt�������A���t�@�G���O�h���O�ɂ������A���̃l�O���W�F�ӂ��̎������������B���o�I�ȋ����Ɗ�т��ق����Ƃ��́A�{�����J���Ɍ����i���U�j�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���P�j�@�����E�۔��́s�p�m���}���Y杁t�i�G���^�[�u���C���j�̐}���ُ����{�̉��t�ɂ́u2011�N10��7������6�����s�v�Ƃ���A2009�N�̑�13���ˎ��������ܐV����܌�̍��肾�����B�Ȃ��A�{���̔��s�����G���^�[�u���C������KADOKAWA�ɕς�����̂��ǂ̎��_�������̂��A���ׂ����Ȃ������B
�i���Q�j�@�������g������̐��z�q���̓Ǐ����r�i�s���{�Ǐ��V���t1952�N5��7���j�ŏ��N�����U�肩�����āA���̂悤�ɏ����Ă���B
�@���̓Ǐ��͏��N���ォ�獡�ɂ�����܂ŎU���I�ł���A���Q���s�I�ł���B�C�����������ɋC�����������̂�ǂށB������Ƃ̎U���ŋA�邱�Ƃ�����A�v��ʒ����A�������m�Ƃ���䂤�n�ɂȂ邱�Ƃ�����B
�@���N����ɂ͏��g�R�l�́u���E�������v�i���{�������ł͂Ȃ��B���q�▂�@�g�̏o����̂������j�A����t�Q�̖`�������A����܍��̖|���̎O�ɐS�������B���앶�ɂ��ǂ���ǁA�����̐l�X���]���قǂɂ͒^�ǂ��Ȃ������B���͐����u�����`�m�������ł�n�v���̖ʔ����������Ȃ����i�ŁA���앶�ɂɂ͂���Ƌߎ�������������������ł��낤�B���������Ď��͔����`���ʓǂ��Ă��Ȃ��B�i�s�]�ː에���S�W ��30���@�킪���Ɛ^���k�����Е��Ɂl�t�A�����ЁA2005�N6��20���A�O�Z���y�[�W�j
�Ėڟ��A�J�菁��Y�A�H�열�V��A�����t�v�A�X�^���_�[���A�u�[���W�F�A�W�[�h�A�����m�ԁA�Ȃǂ͋g���̓Ǐ����߂��鐏�z�ɂ��o�ꂷ�鋤�ʂ̍�Ƃ����A�����̂���ɂ͔m�ԈȊO�̎��̐l���o�ꂵ�Ȃ��B�����͔����Y�ƌ�F������A�k�����H������Ɍ��y���Ă��Ă��悩�肻���Ȃ��̂́A�����́q�l�������r�ɂ͓o�ꂵ�Ȃ��B���R�̂悤�ȋC�����邪�A���H���g���ɂƂ��Ắi�Z�̂́j���_�ł����������ɁA�Ȃ�ƂȂ��c�O�ł���B
�i���R�j�@�g�����́s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�i�}�����[�A1987�j�́q21�@�f��u���|��`�l�ԁv�r�ł��������Ă���B�Ȃ�1969�N11��7���͋��j���B
�@�q���L�r�@���Z��N�\�ꌎ����
�@��A�a�J�̓��f�Łu���|��`�l�ԁv���ς�B����ς�A�i�슪��H�ׂȂ���B�q�Ȃ͂��炪��B����̌㔼�ɂȂ��āA�y���F�ƎႢ�j���̒�q�����̑劈��ɂӂ���ő���B�g�b�v�ŃR�[�q�[���̂݁A���Ȃ���i���āA�\���߂��A��B�i�����A�O���y�[�W�j
![�s�]�ː에���S�W ���|��`�l�ԁt��DVD�������sHORRORS OF MALFORMED MEN�t�iSynapse Films�A2007�j�̃W���P�b�g](image/horrors_jacket_1.jpg)
�s�]�ː에���S�W ���|��`�l�ԁt��DVD�������sHORRORS OF MALFORMED MEN�t�iSynapse Films�A2007�j�̃W���P�b�g �k�y���F�̃J�b�g�����p����Ă���l
�Έ�P�j�ē�i�s�]�ː에���S�W ���|��`�l�ԁt��1969�N10��31������B����F���f���s�B�e���A�F��T�C�Y�F�J���[�E2.35:1�A��f���ԁF99���B�r�{�F�Έ�P�j�E�|�D���T�B�o���F�g�c�P�Y�A�R���Ă�q�A�y���F�A���O�Îq�A�����ʎq�A����G�A���r���Y�A�ߓ����b�A��؎��A�ق��BWikipedia�ɂ́u�������ʂł̉c�ƃT�C�h�̔����������A�̂ďT�Ԃł̌��J�ŁA�o���̗ǂ��Ȃ��|���m�A�j���k�s㊙���� �����G����t�l�Ƃ̕��f�ƂȂ�A�q�Ȃ̓K���K���A���X�g�V�[�����Â܂�Ԃ����B���s���т��S���U��킸10���ԂŌ��J�ł���B�v�Ƃ���B�Έ�P�j�́q�y���F���Ă�ŁA�V��ł��܂����\�\�w���|��`�l�ԁx�w�E�����l�ʒ��x�w�č��l�ʒ��x�w���k���藳�x�r�ŁA�u�k���́l�u�p�m���}����k�v�Ɓu�Ǔ��̋S�v����̂������v�u�\�o�ł������g�����Ƃ��낪�����ł��ˁB�\���[�g�����炢�o�[�b�Ɨ���ł���B�y������A����������o�ꂵ�Ă����ƂƂĂ��������ǂȂ��A�����ǂ������܂ōs���̂͊�Ȃ����Ȃ�Č����Ă邤���ɂˁA���܂��傤���ĂˁB�v�u�y������Ƃ����r���Y�͂��V�тŊy������Ă܂��ˁB�v�Ȃǂƌ���Ă���i�Έ�P�j�E���Ԍ���s�Έ�P�j�f�捰�t�A���C�Y�o�ŁA1992�N1��1���A��Z�Z�`���Z�y�[�W�j�B���́u�y���F�v�̒��Ɂu�f��͐Έ��i�ȊO�ɂ́k19�l69�N�̐��]�F�V�ēw�k�ւ��t�����`�t���l�x�A70�N�̒�����v�ḗw����ɂႭ�|���x�����ؘa�Y�ēw���{�̈���x�Ȃǂɏo���B���|�I�Ȍ��ŃX�N���[�����ٔ��������B�v�i�����A��Z���y�[�W�j�Ƃ��邪�A�g���̓��L�␏�z�ɂ����ւ̌��y�͂Ȃ��B
�i���S�j�@�۔����g�́s�����C�J�t2015�N8�����́k���W���]�ː에���\�\�v��܁Z�N�l�́q�ɑ�Ɣڏ��̑�p�m���}�\�\�����Ƃ�������r�Łu�����A���ƈ�Z�N��������Ă����悩�����Ƃ��������͂���܂��B���Ƃ��Ύ��������Y������ł��܂����A�v�����F���푺�G�O���A�}���K�]�_�Ƃ̕đ�Ô����S���Ȃ�܂����ˁB���̎l�l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����͖̂l�ɂƂ��Ă͂��������傫���B���̂ЂƂ����Ɍ����Ă݂��������ȂƂ����̂����������̂ł�����B�v�i�����A��l�܃y�[�W�j�ƌ���Ă���B
�i���T�j�@�s�p�m���}���Y杁t�A�s�𒎁t�ɑ�����������E�۔��r�F����̑�O�e�́q�x��ꐡ�@�t�r�i�۔����L��W�s�����p�m���}�t�A�G���^�[�u���C���A2010�A�����B���o���́s�����R�~�b�N�r�[���t2010�N4�����j�ł���B�����26�y�[�W�̒Z�тȂ���A�`�S���Ƃ����傫�Ȏ��ʂɃX�~�ƃA�J�̓�F����ŁA���̃G���`�b�N�ŃO���e�X�N�ȕ����͖��ނ��B�g�����̎��ł́u�����ȊX�ɂ͏����ȉΎ�������^�M�ƕ�������ꏊ������^�����ŃK�����͂ʂ��߂Ȃ��^�T�[�J�X���J�Â���v�Ǝn�܂�q�T�[�J�X�r�i�I�E2�j�������E�۔��̕`�������������̕��͋C�ɍł��߂��B
�i���U�j�@�l���c���F�́s����̂������v�z�t�i���o�ŎЁA2017�N6��20���j�́q�����|���̉x�с\�\�{���v�O�r���u�k���l���Z�N��ɂ͊۔����L�m�܂邨�����Ђ�n�Ƌ{���v�O�Ƃ����A��l�ْ̈[����Ƃ��{�i�I�Ɋ������J�n�����B�u�ْ[�v�ƋL�����̂́A���̕���̋ؗ��ĂɎ���ꂸ�A�����ς琸���ɕ`���ꂽ�ꖇ�G�̓����̔������ƃO���e�X�N�Ɏ���u����������ɍ�i�̊�b��u���Ă�������ł���B���肵�����悪����ƌĂ�A�o�ŎЂ����Ă������앨��̒P�Ȃ�}�����ւƑ��Ă��������オ�������Ă����B�ނ�̏o���Ɖߌ��Ȋ���́A���̒ǐ��������ʂ������̂��̂������v�i�����A��ܔ��y�[�W�j�Ǝn�߂Ă���B�u�۔����L�͐��̈Ŏs�ƃT�[�J�X�����̌������D��ŕ`�����B�Í������̉f���������R���[�W�����āA�d���I�ȕ`���̂��ƁA�����{�Љ�ƂɉB�����Ă�����}���I�Ȍ��ۂ��D��Ŏ��Ƃ����B�k�c�c�l�۔��̍�i�̍���ɂ���̂͗��₩�ɂ��ċ���ȃA�C���j�[�ł���B�^�۔��Ƌ{���k�c�c�l�͐���I�ɁA�w�b�n�l�x�̐V�l����Ɣ��@�̎����ɒx��A���Z�N��ɐN�R�~�b�N�������_�Ƃ��Ċ�����J�n�����Ƃ����_�ŁA����I�ɋ��ʂ�����̂������Ă���B���Z�N��ɔނ���x�����̂͐N�G�����掏�ł���A�w�K���x�ł������B�Ƃ͂������̂̔ނ�̍�i�������o���Ǝ��̃G���e�B�V�Y���ƃL�b�`����A���p�I�Ȑ��E�F���̂�����́A���̂Ƃ��떟��Ƃ����\�ۃV�X�e���̘g��傫���͂ݏo���Ă���ƌ��Ȃ��ׂ����낤�v�i�����A��ܔ��`��܋�y�[�W�j�B�{���v�O�̑�\��s�o���U���ƃG�[�e���\�\���M�t�i�͏o���[�V�ЁA2000�N4��20���j�̕W�肪�h�C�c�E���}����`���l�m���@�[���X�́q��̎]�́r�ɕ����Ă����悤�ɁA�۔����L�̋ߔN�̍�i�͍]�ː에���▲��v��̏����ɕ��������傫���B�����܂łɉf�扻�A�e���r�h���}�����ꂽ������i�͂�����������ǁi���݂�YouTube�Łu�]�ː에���v����������ƁA�N�Ǎ�i�E���W�I�h���}�E�e���r�h���}�E�f��\�\�s�]�ː에���S�W ���|��`�l�ԁt�̗\����������\�\�ȂǁA�c��ȃv���O�����������ł���j�A���扻���ꂽ������i�ƂȂ�Ί۔��̏�L3��A�s�p�m���}���Y杁t�s�𒎁t�q�x��ꐡ�@�t�r�ɂƂǂ߂������B

�۔����L�́q�����̎g�ҁr���f�ڂ��ꂽ�s�K���t�i1983�N2�E3���������j���\���̐ѓ��̎��Џo�ōL���k��i���Ђ������݂����́A���i���۔��̏��Ёl
�g�����Ƌg��O�ɂ��ẮA�����q�g�����̑�����i�i109�j�r�ŏ��������Ƃ�����B�����A�����Ŏ��Ɋւ��Ė{�i�I�ɘ_�����킯�ł͂Ȃ������B2019�N2���Ɋ�g���ɔŁs�g��O���W�t���o�����Ƃ�����A�����ʼn��߂ċg�����Ƌg��O�̎����l���Ă݂����B�Ƃ��ɁA�g��͂��́q�R�{���ܘY���_�r�������n�߂Ă���B
�@�R�{���ܘY�̕��͂́A�������o��قǍI�݂ł���B���͂̂��܂��Ƃ����_�ł́A�u�꒼�Ƃƕ��ԍ�Ƃ��ƁA���͎v���Ă���B�������R�{���̍I�݂ȕ��͂����肠���Ă��镨��̐��E�́A�����x�������鉽���̂����܂�ł���B�ȉ��ٕ̐��́A�R�{���ܘY�_�Ƃ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A���k���x�̂��̂ɂ����Ȃ����A�R�{���ɑ���h���Ƌ��ɁA�s���߂����C�����q�ׂ悤�Ƃ��ď������B
�@��A��N�O�A������Ƃ������Ƃ����������ŁA�R�{���̏�����ǂB���ɖʔ��������̂ŁA������ԁA�蓖�莟��ɓǂ���A�l�ɂ��A�R�{���̏����𐁒�����قǂɂȂ������A���������ƁA�S�̈���ŁA���������������������A�R�{���ܘY�I�ȏ������������낤�Ǝv�����肵���B���̂����A�R�{���̏����ɁA�����������قǂ̂��炾���������o�������Ƃ������ŁA�����͎R�{���ܘY�ɂȂ肽���Ȃ��A�ȂǂƎv������������B�i�R�{���̒�q�̐l����A�Ȃ����邩���m��Ȃ��I�j
�@�ܘ_�A���ɂ́A�R�{���̍\�z�͂����@�͂��܂��A���̖��͓I�ȕM�͂��Ȃ��B�������A�R�{���́A�����������Ă���ʒu�ɁA�������ɋ߂��Ƃ������Ƃ��A���Ƃ��������A�{�\�I�Ɋ�����̂ł���B������A���̗މ����́A�悸�ԈႢ�Ȃ��ɁA�����A�R�{���̈������炢�ɂ͂���ƁA���͎v�����̂ł���B
�@���́A�l�ɉ���Ă݂����Ɨ]��v��ʐl�Ԃ����A�R�{���ɂ����́A��x�A��������������A�ƍ��ł��v���Ă���B�V���ŁA�����]������āA�҂����������Ƃ��v���o���B�i�s�g��O���W�k���㎍����12�l�t�A�v���ЁA1968�N8��1���A��܃y�[�W�j
���́u�g��O�̎��́A�������o��قǍI�݂ł���B�k�c�c�l�ܘ_�A���ɂ́A�g�쎁�̍\�z�͂����@�͂��܂��A���̖��͓I�ȕM�͂��Ȃ��B�������A�g�쎁�́A���������Ă���ʒu�ɁA�������ɋ߂��Ƃ������Ƃ��A���Ƃ��������A�{�\�I�Ɋ�����̂ł���B������A���̗މ����́A�悸�ԈႢ�Ȃ��ɁA�����A�g�쎁�̈������炢�ɂ͂���ƁA���͎v�����̂ł���B�v�Ɠǂ݂����Ă݂����U�f�ɋ����B�����Ă���́A�ЂƂ莄�����łȂ��A���㎍���ɔł��g���ɔł̋g��O���W��ǂقǂ̐l�Ȃ�A���̑�����������̂ł͂Ȃ����낤���B��̗�������悤�B���͂��āA�g��O���������̂Ɠ������i�����Ă���i�q���Ƃ������r�̏��o��1999�N2���A�s�D�t33���j�B
���Ƃ������b�g��O
���Ȃ�ȑO�̂���
�u���Ƃ������v�Ƃ����Ŕ�����
���͓��]�����B
�����S���̈����։w�ɍ~�藧�����Ƃ�
�z�[���̗����ɕ������Ă��鑽���̊Ŕ̈��
�������ŏ�����Ă��������\�\���ꂪ
�u���Ƃ������v�������B
����������
�j���A�ǂ̂悤�ɋ����鋳�����H�@�ƍ��f
��u
�u�����Ƌ����v��ǂ݈Ⴆ�Ă������ƂɋC�t��
�������炦�ĕ����o�����B
����������ȗ�
���͂��̊Ŕɏo����т�
���Ղ�t�ł�Z���̂܂܂�
�j�̋Ր����I�݂ɑt�ł鏗�̋Z��
�����ƁA���̘r�̒��ɔ�߂��Ă���A��
���͎v���悤�ɂȂ����B
�u�����Ɓv�Ɓu���Ձv�Ƃ͏�����
�u�����Ɓv�ƕ������ɂ��������̍��_�͔���Ȃ���
�����ɊȒP�ɂ͍������낤�Ƃ��Ȃ���������
�Ђ����Ȍցm�ق���n�̂悤�Ȃ��̂�
�����Ƃ����̋L���ł́A�Ŕ��������̂͐����V�h���E���܉w�̍��c�n��w���̖k���ŁA���܂��̊Ŕ͂Ȃ��B�b���g�쎍�ɖ߂��A�g��Ɠ��l�A�݂��ƂɊŔ�ǂ݊ԈႦ�������嗪�Ō�̑�4�߂̂悤�Ȋ��S����������Ƃ͊m�������A���̑O�̐߂́u���Ղ�t�ł�Z���̂܂܂Ɂ^�j�̋Ր����I�݂ɑt�ł鏗�̋Z���^�����ƁA���̘r�̒��ɔ�߂��Ă���A�Ɓ^���͎v���悤�ɂȂ����B�v�Ɗ������킯�ł͂Ȃ��B���̊Ŕ����������̎��́A���w�Z��w�N����������B
���̎��i���W�s�k���]�t�����j���A�Ⴂ����ɂ͂Ȃ��Ȃ����킢�����Ȃ��������낤�B�Ȃ��g��́A1972�N�����ʌ����R�s�k���]�ɍݏZ�����B���́A�������鍪�����Ȃ����̎�����剪�����̏�����z�N����B�u�����̓ǂ݂����v��������Ȃ��B
�H�̏��b�g��O
�����܂����L��̂��̕��ƁA���͕�����
��݂ɂЂ낪��䍂�����̖݂�
����m�Ȃ��n��y���Ǝv����k���ӂ�܂���
�u�C�����Ȃ��Ə����܂���v
���̕����A���������������
����͈��̗t�̉s������̂��Ƃł�����
���́A����Ȃӂ��ɕ�����������
�u�l��M�p�������Ă͂����܂���v
�\�\�����Ȃ�A�������ւ̎��~�߁c�c
���͎�������߂��u�����̓ǂ݂�������I�v
���̖݂��ʂ����
���̕��͏��Ď�̍b�̏������Ɍ�����
�u�N�ɒ��ӂ��������ɖl�����Ă���v
���̕������U�������͎̂��������̂�
���͏���Ȃ�����
���̓��A���͏����ق�������
���̕��ƈ��̖݂�������m���ȏ؋���
���́u���v���A���̂����łȂ����_�̂���ł��鏈���A�Ȃ�Ƃ��G���e�B�b�N���i����ɂ��Ă��u���̖݁v�I�j�B�剪�����̎t�ł���X�^���_�[���͂������A�����Ƃ͍��̐G�ꂠ���Ɏn�܂�A���̂̐ڐG�ɏI���A�Ɗ��j�����B����Ƃ���́A�g��O�ɂ��s�����_�t�������̂��B�u���̕��v���g��ŁA�u���v���L�v�̏������Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�g��̎��ɂ͂��������h�L���Ƃ����镔���̂��邱�Ƃ�l�����܂薾�����Ȃ��͕̂s�v�c�ł���B
���̋g��̎��ɑ�������g�������͗e�ՂɌ�������Ȃ��B�g���͗��������قƂ�Ǐ����Ă��Ȃ��̂��B�������ɐ��z�q���֕������O�̎��r�i���o�́s����̊�t1961�N11�����j�ɂ͒����t�q�Ɍ������q�n����ԁr�i�A�E4�j�A�r�c�F�q�ɗ^�����q�~�̉́r�i�B�E8�j�A�x�E�v�\�\�̂��̍Ȃł���a�c�z�q�\�\�֕������q�ār�i�C�E10�j�����p����Ă���B�����A�����ƂĈ�ʓI�ȗ������Ƃ͂����Ԃ�l�����قȂ�B������ɂ����Ɂq�����r�i�C�E18�j��т�����B���ꂱ���͗����̌`����w��W�J�����A�g���B��̗������Ƃ����悤�B���̎��ɂ́u���v�Ɓu�����v�A�����āu�ڂ��v���o�ꂷ��B�����������̐l�ԊW�Ɉ����߂����͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A��l�����u�ڂ��v�A�l�ȁ��u���v�A�������聁�u�����v�������i�q�Ă͂߂邱�Ƃ͋�����悤�B����ɁA���т̐��E�𗣂ꂳ������A������b�q���q�g�����Ƃ����\�\�l�E��E���r�Łu�k�c�c�l�����Ǝ�Ђǂ������ɂ���ď����ꂽ�w�m���x�̍��A�}�����[�ňꏏ�ɓ����Ă����z�q���A�g������̂Ƃ���֏����������I�ɂ������ė���d�b�������A�z�q�����̎��̂��Ƃ��v���o���āA�{�C�ł��̏����̏����I�C�܂܂��m�A�A�A�A�A�A�A�n��{���āA�~�[�����{���ɂ��킢��������������A����ȏ��ł��A�킩��Ȃ��H�@����ł��傤�H�@���������_��I�݂����ȃ^�C�v�A�Ǝ������Ɍ����Č����Ȃ���A�g������ɂ܂�ŏ����̂悤�ɃC�[�b�Ƃ���������A�g�����Ƃ�āA����A�܂����A�ƌ����������肵�����Ƃ��A���ׂ����낤���B�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�N1��30���A���l�y�[�W�j�Ə����Ă���悤�ɁA�q�~�̉́r�̒r�c�F�q�Ɓq�ār�̂x�E�v���ʂɕ`������삱���q�����r�������A�ƌ��邱�Ƃ��ł���B���Ȃ݂ɋg���́A1958�N8��8���̓��L�Ɂu�q�����r�o���B����Ŏ��W�s�m���t�̏\��ъ����v�i�q�f�ЁE���L���r�A�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A����y�[�W�j�Ə����Ă���B�{�т̏��o�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�N11��20���j�ŁA���łɁq�m���r�i�C�E8�j��q�����r�i�C�E19�j�����������Ă����g�����A�ǂ����Ă����̎��W�ɓ��ꂽ�����т������B�S6��99�s����A�`���Ɩ����̐߂��������B
�����b�g����
�P
�Z�˂����낷
�ڂ��ɂ͏�l�̏K�����Ȃ�
���_�܂œS�̔��͂��ɂ���
�X��ʂ�K�X�ǍH�v�����R�݂ċL������
���̂Ȃ��ɓ��ꂽ��l�̒j
�֊�ɂ܂�����ڂ���������炤
�������ׂ������͂�����ނ�
�X�q���܂Ԃ������Ԃ�K�X�ǍH�v�̒Ƃ̈ꌂ��
�����̓��𐅓��Ő�킹��
�������݂̂Ȃ��Ƃ��Ă���������
�c���܂̎���
��l�����̊��̉Ă�m���
�����������͋킯���ނ��낤
�ڂ��̔��̉�
���ʂ̖@�����������b�^�̓����̒���������낤
����܂ŋx�Ƃ�
��������Q��܂ŎȔn�𑖂点
�y���L��h����
���łɉ����̈Â�
�k�c�c�l
�U
�ڂ��͐��@�̉Ԃ��Ăт̂���
�]�����s��ꂸ
���E�����������R�̂��ׂĂ�������Ă��Ȃ�
�^�����܂��
�Ԃ̐[����������������������݂̂�
�ڂ��͎����ƕs�K�������~�ς��ׂ�
���̑ڂ֎���ׂ̂�
�r���͖�ɕ���₷���`�ƐF������
���܂������Ԃ�����Ɗ���
���ꂩ���̂ڂ��͂܂��߂ȐX�Ԃ�
�����ނ�̂ЂȂ���Ă悤�ƌ��ӂ���
���ׂ����\�̐��ɕω��������̐���
�@���━���̂Ƃǂ��ʏ�����
�ڑ��Ȃ�����H�����玀�炳��
�ڂ��������U�߂Ă�����������̏�
���̑��̔��������������
�����͋P������
�����������
���̔��̏�ɑꂪ�������ē���
�ڂ��͗�Âɖ@�T�̉������̂����
���Ăڂ������ɂ͑�ς�����
�ߐ[�����͋��点�悤
�K�X�ǍH�v�ɏт��q����ē��������������𔗂�̂�
�ڂ��͋v�����҂�
�g���͂��̎��ɁA���Ɠ��̂̍��Ղ��i���ɂƂǂ߂��B�s�m���t���u�����v�Ɓu���v�ɒ��ڂ��ēǂ݂Ȃ������ƁA���ꂪ�g�����̍�i�j�ɂ����ē��قȂ��̎��W�̊j�ɐG��邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B��N�A�剪�M�Ƃ̑Θb�q���`�̐��E����r�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�j�Łu������A�w�Õ��x���w�m���x�ɖ߂��Ă����Ă����������������Ȃ����Ƃ����邯�ǁA����͂���A�������Ȃ��킯��ˁA�����B�����̓��͖߂铹�Ȃ̂��A�߂�Ȃ��s���������̓��Ȃ̂����킩��Ȃ����ǁA�s���������ł�����ł͂Ȃ����B�v�i�����A��ܔ��y�[�W�j�ƌ���Ă���̂́A���͂₠���������������������Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƌ����Ă���悤�Ɏ��ɂ͕�������B

�g��O�̑I���W�ł���܂ł������ǂ܂ꂽ���낤�s�g��O���W�k���㎍����12�l�t�i�v���ЁA��1���F1968�N8��1���k��15���F1980�N10��1���l�j�̕\���Ƃ��ꂩ�炢����i���ǂ܂�邾�낤���r����ҁs�g��O���W�k��g���Ɂl�t�i��g���X�A2019�N2��15���j�̃W���P�b�g�@���Ȃ݂ɍ����ƍK�����́s�g��O���W�k���㎍����12�l�t�\���̃E�j�̂悤�ȃJ�b�g���s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i1968�N9��1���j�Ɠ����G���ŁA�g���͓����Ɏ��߂��q�f�ЁE���L���r�̏��a�O�\�Z�N�Ɂu�����\����@�g��O����s�����t�Ĕł����炤�B�v�i���܃y�[�W�j�ƋL���Ă���B
���X�؊��Y�́q�ǂ�����a�����Ƃ炦�邩�\�\�g��O�Ǔ��r�i�s�����C�J�t2014�N6���Վ������k�����W���g��O�̐��E�l�j�ŁqI was born�r�Ɓq�^�R�r�������āA�g��O�Ƌg�����̎���Δ�E�������Ă���B�O���͂ނ��g��́qI was born�r�ɂ��ĂŁA�����ɂ������ċg�����o�ꂷ��B
�@�k�c�c�l�g��O�̎��ƑΔ䂳���āA�����̒a����`�����܂������ʂ̊p�x����̎��������ɒu���Ă݂悤�B
�@�g�����Ɂu�^�R�v�i�w�T�t�����E�݁x�����A��㎵�Z�j�Ƃ�����i������B���̎��ł́A�^�R�̕���܂��A�uI was born�v���堂̕�Ɠ����悤�ɁA�u��x�̔r���v�Ŏ��ʑ��݂Ƃ��Ă���B���ł́A�^�R�̗Y�Ǝ��̐��B���`�����B�a���͊��\����тт�ƂƂ��ɁA���ꂽ���̂Ƃ��Ă���B
�@�@�y���X�������Ɉ��p�����q�^�R�r�́A�k���߁l�̑S�s�A�U�����^�́k���߁l�̖�5�s���𒆗����āA�k��O�߁l�̏I���5�s���㗪�����`�\�\���ђ��z
�@�����炭�g�����́u�^�R�v�́A�^�R�̐��B�s�ׂƎq��Ă̐}�i���邢�͉f���j�����āA�������玍�̃A�C�f�B�A�����܂ꂽ�̂��낤�Ǝv����B�^�R�̗Y�͂����ł͎ː����邾���̑��݂��B�����Ď��̂Ȃ��ł́A�����܂��̂����Ɏp�������Ă���B
�@�u���Ɛ�����^�R�͏o�������̂��v�Ƃ����A�����ׂ���g�ŁA�a�����u�o���v�ƌ��Ȃ��l���́A�u���v�Ȃ���́A�u��v�Ȃ���̂��A�U���I�ȃC���[�W�ŎE�����Ƃɂ���Ă������܂�Ȃ��B
�@����͎q�ǂ��̗��e���z���āA�����̋N���֑k�邱�Ƃ�v������B�����ł́A�D�w�̃C���[�W�͍�i�̖`���ɂ���Ă��Ȃ��B�g�����́u�^�R�v�́A�����Ɏ��̓�s���u����āA�N��ȃG���`�V�Y���������������B
�@�@����͉ߋ��̂��Ƃ����m��Ȃ�
�@�@�Ẳ�����j����������
�@�uI was born�v�̖`���ł́A���́u������ւ���āv���āA�₪�āu�䂫�������v�B�������u�^�R�v�ł́A�ŏI�s�Łu��������v�̂��B���̎p��������Ă��钷�����Ԃ�����B
�@�l�ނ̎�Ƃ��Ă̌p���͖����ł���B���̖����z���A�L���̐g�̂ł���l���~�߂悤�Ƃ���Ƃ��A�������ǂ����Ō��邱�Ƃ��K�v���B�g��O�̎��͂��̖������ԁ��u�P�Ӂv�łƂ炦�悤�Ƃ��A����A�g�����͂��̖�����\���ԁ��u���Ӂv�łƂ炦�悤�Ƃ����B�ǂ�����_��I�ł���A���͓I�ŁA���̓�̑Δ��ʂ��āA�킽���͂킽�����g�́u���v�̗֊s���������Ǝv���B���Z���̂Ƃ��ɏ��߂ċg��O�̎��ɏo����Ĉȗ��A�ق�Ƃ��ɍ�҂��S���Ȃ��Ă���A���̎����킽���ɋ߂Â��Ă����̂ł���B�i�����A��܁`�y�[�W�j
���X�؊��Y�̘_�l�ɊԑR���鏈�͂Ȃ��A�t�����킦��ׂ����̂͂Ȃ��B����Ƃ���A�u�����炭�g�����́u�^�R�v�́A�^�R�̐��B�s�ׂƎq��Ă̐}�i���邢�͉f���j�����āA�������玍�̃A�C�f�B�A�����܂ꂽ�̂��낤�Ǝv����v�Ƃ����w�E�̂Ƃ���A�g�����g���u�q�^�R�r�Ƃ������́A���̒�������̌��̂Ȃ��ł����������̂ł���B�Ȃ��Ȃ炱�̎��̔��z�\�\�Ƃ��������̔����́A�e���r�̎��R�Ȋw�f�悩�瓾������ł���B���R�ς��^�R�̐��Ԃɋ��������ڂ��A��}���ŁA���肠�킹�̎��Ƀ������Ƃ낤�Ƃ������A�u���ɉ߂�����f���ƃi���[�V�����Ȃ̂ŁA�ŏ����̎����������ł���B���̖̂{�Ń^�R�̂��Ƃׂ邱�Ƃ��Ȃ��A���Ƃ͎��̑z���́i�n���́j�ň�C�ɏ����グ���B�����炱�̎��́A�Ȋw�I�ɂ͐��m�ł͂Ȃ��B���������ɂƂ��ẮA���A���e�B�̂����i�ɂȂ����Ƃ������������������ꖕ�̕s�����������B�v�i�q�����r�A�s�����t41���k����S�l�ꎍ���I�����l�A1977�N12���A��Z�Z�`��Z��y�[�W�j�Ə����Ă��邱�Ƃ��炢���B���X�̘_�̊�ڂ́u�g��O�̎��͂��̖������ԁ��u�P�Ӂv�łƂ炦�悤�Ƃ��A����A�g�����͂��̖�����\���ԁ��u���Ӂv�łƂ炦�悤�Ƃ����B�v�ł���B�ꌩ�A�Ȃ�̐ړ_���Ȃ����̂��Ƃ��g��O���Ƌg�������́A�Ƃ��Ɉؕ|���ׂ��u�����v�̂܂��Ŕw�����킹�ɘȗ����Ă���B���́A���Ǝ��ɑ���|��Ɠ���̂Ȃ����ɁA���͂ǂ����䂩��Ȃ��悤�ł���B
��

�悵�������낤�̃A���o���s���C�ł��B�t�iOdyssey/CBS Sony�A1972�j�̃��R�[�h�W���P�b�g
�g�c��Y�i�����́u�悵�������낤�v�j�̃A���o���s���C�ł��B�t�iOdyssey/CBS Sony�A1972�j�͔ނ̍ō����삾�Ǝv���B��Ȃ͂��ׂđ�Y���g�����A�S15�Ȃ̍쎌�́A���{������6�ȁA�g�c��Y5�ȁA�c���f�q�E�É��M�q�E����ǁE�y��P�����ꂼ��1�ȁA�ƕ��������Ă���B���{����|�����ȂɁq�Ղ�̂��Ɓr�i4��20�b�A�ƃA���o���ł͒��ځj������B���܂b�c�̃��C�i�[�m�[�c�i�̎��J�[�h�j���璍�ƂƂ��Ɉ����A���̂悤�ɂȂ�B
�Ղ�̂��Ɓb���{������
�Ղ�̂��Ƃ̎₵����
����ł�����Ă���̂Ȃ�
�k�c�c�l
�l�����ނ��p����
�l���ق߂���p����
�k�c�c�l
���X���Ԉ��������r���
�A���Ă䂯��ꏊ���Ȃ�
���X���Ԉ��������ʂ���
����ł��܂��ɑ�������
�k�c�c�l
�Ղ�̂��Ƃ̗҂�����
�����ɂ���Ă��
�k�c�c�l
�������ނ܂��A�������ނ̂͂悻��
�����̎��ɐ��������
�@���F�O�A�ځg���X���Ԉ��������r���h�͋g��O���̎��̈�s����܂����B
�g��O�̎��q���X���Ԉ����r�̎���́A���m�ɂ͌㒍�ɂ���Ƃ���u���X���Ԉ����^�����r���v�����A�����g��O�̖���m�����̂́A���Z����A���������ő�Y�t�@���������������Ē������k�o�Ɏ��߂�ꂽ�q�Ղ�̂��Ɓr�ɂ���Ă������B�v���Ԃ�ɉ����ɐڂ��āi�苖�ɂȂ��̂ŁA�}���ق���肽�j�A���̉��y�I�M�ʂɈ��|���ꂽ�B����ŁA�q�Ղ�̂��Ɓr�̎��^���ɁA�ނ����������Ƃ��ɂ͊����Ȃ��������ɗ�߂����G���o���āA���Ԃ������v�����B���{�����݁i1942�`2015�j�^�g�c��Y�i1946�`�@�j�̂��̍�i�̂킫�ɑ���t���i1949�`�@�j�̒��я����s�m���E�F�C�̐X�t�i1987�j��u���Ă݂�ƁA�u�Ղ�v�̂Ȃ邩���l����������Ȃ��B����͒P�ɐ����I�M���̋G�߂��Ӗ����邾���ł͂Ȃ����낤�B�u�Ղ�v�Ƃ́A1970�N�㏉�߂܂ł͂������ɑ��݂����A���y�I�M���i�̎��ƃT�E���h�̟ӑR��̉������A���쎩���̃A�}���K���j�̕ʖ��������̂ł͂Ȃ����B���̑�\�I���݁A�r�[�g���Y�́q�m�[�E�F�W�A���E�E�b�h�i�m���E�F�[�̐X�j�r�����߂��A���o���s���o�[�E�\�E���t�́A1965�N�̕�ɔ��\����Ă���B���Ȃ݂ɁA����́s�m���E�F�C�̐X�t�̃G�s�O���t�́u�����̍Ղ�m�t�G�g�n�̂��߂Ɂv�������B
�k�NjL�l
�����錻�㎍�Ƀt�H�[�N�n�̃\���O���C�^�[���Ȃ�t���邱�Ƃ́A����قǒ������͂Ȃ��B���Ƃ����c�O�Y�̒Z���q�����D�r�\�\���W�s�����ƍ����t�i�v���ЁA1964�j�����\�\�́A�Ԃ����̌㓡�x���Y����Ȃ������Ƃő����̐l�̒m�鏈�ƂȂ������AWikipedia���q���c�O�Y�r�̃y�[�W�ɂ́u����i�́A�����Ίy�ȉ�����邱�Ƃ������A�N���V�b�N��t�H�[�N�n�̍�ȉƂɂ���āA�Ȃ������ACD��������Ă���i�㓡�x���Y�u�����D�v�A���c�n�u�[���v�A�������u��Ɓv�j�B�v�Ƃ���B���́q�����D�r���㓡�ɂƂ��đ�ȋȂł��邱�Ƃ́A�u�t�H�[�N�O���[�v�Ԃ����̃����o�[�ł��������R�ב�ƌ㓡�x���Y�́A���O���[�v���U���O�Ɍ������A���U��ɕv�w�f���I�u���ӂ�����v�Ƃ��Ċ������n�߂��B�v�iWikipedia���q���ӂ�����r�̃y�[�W�j�ƃO���[�v���ɂ܂ł��Ă��邱�Ƃ��������������B�Ƃ��ɁA�g�����̎����̂ɂȂ������̂Ƃ��ẮA�q���X�r������Ȃ̋g�����̉̋ȁr�ŏЉ���q���́r�i�F�E3�j�Ɓq����̔ӎ`�r�i�G�E13�j�����邫��ł͂Ȃ����B�t�H�[�N�n�̍�ȉƁE��������45�N�ȏ�O�A�s�����C�J�t�i1973�N3�����j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��邪�A���̒m�邩����A���̋Ȃ͍����܂Ō��\����Ă��Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA�l���A�h�����Ă������̌��㎍�ɋȂ����邱�Ƃ��ł����̂́A�����̎����A���ɏo���ĉr�܂�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă͍���Ă��Ȃ��������炾�Ǝv���B�����ɂ́A�ڂœǂނ��Ƃł̃����f�B�[��Y���͂��邩������Ȃ����A����𐺂ɏo���Ă݂��ꍇ�̃����f�B�[��Y���͊Ȃ̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ƃ�������邩���m��Ȃ����A��͂肻���v���̂��B����䂦�ɔ�r�I���R�ɋȑz���邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̂��Ƃ������āA����i�̗D�����낤�Ƃ��Ă���킯�ł͂������Ȃ��B
�@�l�́A���Ȃ�ȑO����A�g��������i��ʎ����Ȃ��̂ŁA����Â����邢���͂Ȃ��̂����A���ɂ����悤���Ȃ��j�̇��m�����Ƃ��������̂ɂ������Ďd���Ȃ��̂����A�����ɂǂ����Ă��ł��Ȃ��B���l�l�̑m���A�뉀��������������B�Ȃ�����܂�����A���łɉ̂Ȃ̂ł���B����́A���m���y�̔��e���A�͂邩�ɉz���Ă��܂��Ă���̂ł���B���m���y�̏ꍇ�A���Y���Ƃ����̂͏�Ɏ������Ă���킯�����A���̏ꍇ�A���Y�����ӂ��Ǝ����Ȃ镔����������̂��B�����Ȃ�Ƃ����̂́A�~�܂�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������Ď~�܂��Ă͂��Ȃ��̂��B���m���Y���Ɣ�r�����Ƃ��A�����Ȃ�Ƃ����\�������ł��Ȃ��̂����A���̎����Ȃ郊�Y���̒��ɁA���{��̉̂̃q���g������悤�Ɏv���B���̂��Ƃ��͂�����F���ł��������߂āA���X�I�[�o�[�Ȃ�����������A�����Ȍ�̓��{��̉̂��A�����������ꎩ�̂ɐ����̂��������E���ܒ����A���m���y�ɂ���Ăӂ݂ɂ����Ă����D������A�����o�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B�i�q���㎍����Ȃ��邱�Ɓr�A�������Βk�W�s�|�b�v�X�k�c�t�A���}�n���y�U����A1975�N9��10���A��O��`��l�Z�y�[�W�j
�������Ȃ������Ȃ������̂��A�g�����̋ȁq�m���r�̌��\���m�Ȃ������̂��ڂ炩�ɂ��Ȃ����A�u�����Ȃ郊�Y���̒��ɁA���{��̉̂̃q���g������v�Ƃ����̂������̍�ȏp�̗v���Ȃ�A�u�������̌��㎍�ɋȂ����邱�Ƃ��ł����v���̋�̓I�ȋȁi�����́s�|�b�v�X�k�c�t�ŁA�J��r���Y�E��̂�q�E�ʖ����E���\�Y�E�x�����b�q�̎��ɋȂ�t�����ƌ���Ă���A�����ɂ͕x���Ƃ̑Βk�����^����Ă���j��A��ŐG�ꂽ���c�O�Y�́q��Ɓr��{���Œ����A�܂����ʉ̋ȁq�m���r��z���������˂Ȃ�Ȃ��B�\�\�ƁA�����Ă��āA�������̃t�@�[�X�g�A���o���s���͌��ɂ͍s���Ȃ����낤�t�i�x���E�b�h�A1971�j�̍Ĕ��b�c����肵���B���������́A�{�e�͈̔͂���B�F�삩�����̒��������i�W�i1978�j�ȂǂƗ��߂āA���������������B
��
1980�N���߂ɖS���Ȃ������c�O�Y�i�g�����Ɠ���1919�N���܂�j�𓉂g��O�̎��q�߂������Ă��܂��Ă���łȂ��Ɓ\�\�̍��c�O�Y���Ɂr�i���W�s�z�𗁂тāt�����j�́A�u�����g�������v�Ƃ͈قȂ�A�v���[�`�����A�܂�����Ȃ����p���тł���B�����āq�@�r���̈��p�����i���c�̎���j���������Čf����B���͋g��O�̐��������Ƃ��Ȃ��i�Ƒ��ƒc�R����g��̎p�́A���ؒ��h�̎B�����f���Ō������A�����������j�B�����A���̎�����������͋g��̐�����������B�u����Ȃ�^�g�삳��v�B
�߂������Ă��܂��Ă���łȂ��Ɓb�g��O
�@�\�\�̍��c�O�Y����
���W�w�������S�x��
�u�����߂����邽�߂Ɂv�Ƃ������̒���
�����������t������܂���
�@�q�k�c�c�l�r
���W�w�߉́x��
�u���ׂ��Ђ��āv�Ƃ�������
���������Ă���܂���
�@�q�k�c�c�l�r
�މ@���
���x��
�u���I���搧�ɔ����鎍�l�̉�v��
������킹�܂�����
�A��́A����̂��邠�Ȃ��ƈꏏ�ł���
�r���܂ŁA�d�Ԃ��ꏏ�ł���
���̌�A��A��a��œ��@����܂���
��x�މ@�̌�
�ē��@����
�s�A�̐l�ɂȂ��܂���
�߂������Ă��܂��܂�����
�߂������Ă��܂��܂����̂�
���ꂪ���ł��邩�킩��ʂ܂�
�����Ă��܂�������
����
����Ȃ�
���c����
���������q�g�����ƃJ���C�`�r�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W�E�g�����l�j�͂����n�܂�B
�@��㎵�Z�N�ɂȂ邿����ƑO�ł������Ǝv���B�킽���̂����w��������y�O���́u�J���C�`�v�������Ă����B
�@�����͋g��������Ŏ��l�́A���̍��}���K�������������̖��ł���B
�@�ޏ��͏��w�Z�ɂ����Ă��āA�킽���͋���̑���ǗY�̃f�U�C���������ɖ����A�R�s�[���C�^�[�Ƃ��Ēʂ��Ă����B
�@�����q�̔ޏ��̂Ƃ���ցA�g������͖{���o�邽�тɁA����������ĉ������đS�����낦�ĉ��������B
�@���̎��ȗ��A�킽�����܂����y�O���̃t�@���ɂȂ��āA�ł����N�Ŋ��������{�́H�@�Ɛl�ɒ������ƃJ���C�`�Ɠ������B
�@�����g������̑��݂����A�킽���Ɩ��ɂƂ��āA�E�҃J���C�ł͂Ȃ��������낤���B�i�����A���l�y�[�W�j
���ɂƂ��āA�g�����甒�y�O���̒��і����ꂽ���Ƃ͂�قNj���ȑz���o�������炵���A�g����Ǔ������q���e�̂悤�Ȃ₳�����r�ł��u���̍��A�킽���͐����̃A�p�[�g�ɂ��ď��w�Z�ɍs���Ă閺�Ɠ�l��炵�B�₹�ׂ��Č����q�������ޏ��̂Ƃ���ɃJ���C�`�������Ƃǂ����B�Ԃ��D������ݐԂ����������ꂽ�B�����̑�����������݂����ɂ₳�����v���[���g�͋g�������炾�����B�v�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����k�Ǔ����W�E���ʂ� �g�����l�A�ܔ��y�[�W�j�Ə����Ă���B�ނ��g���́A�i�����������ǂ悤�Ɂj���g���ǂ�ł��炱������̂��낤�B���͔��������̖���������������N�ゾ���A�����A���y�O���́s�J���C�`�t�͓ǂ�ł��Ȃ��B�������̂���ڂ�D���Ă����̂́s���l�̐��t�i����E������R�A��E���̂ڂ�j�ł���A�s8�m�G�C�g�n�}���t�i����E����a���A��E�K�c���Y�j�\�\��������A�s�k���N�̂���́u�v���o���挀��v�l�K�c���Y�̐��E�\�\�܂ڂ낵�T��E�������ʁE8�}���t�i�u�k�ЁA2009�N8��24���j���ڂ́q�̋ʍ��r�Ɓq���̓��{�b�g007�r��ǂ݁A������₵���\�\�������B�ǂ�����s�T�����N�}�K�W���t�̘A�ڂ��A�F�l����G������ĉǂ݂��������ŁA�s���l�̐��t���R�~�b�N�œǂ݂Ȃ������̂͐��l���Ă��炾�B�����A�s�T�����N�T���f�[�t�ɂƂтƂтɌf�ڂ��ꂽ�s�J���C�O�`�t�͓ǂL�������邩��A���ɂƂ��Ă̔��y�O���́A�������Ɓs�J���C�O�`�t�Ɓs�T�X�P�t�̍�҂������B���ꂪ���{�I�ɉ��܂����̂́A�l���c���F�s���y�O���_�t�i��i�ЁA2004�j��ǂ݁A���w�ق̃r�b�O�R�~�b�N�X�X�y�V�����s����� �J���C�`�S�W�m��ꕔ�n�t�i2005�`06�j��ʓǂ��Ă��炾�i�s�E�ҕ��|���\�\�e�ۓ`�t�͏��w�ٕ��ɔłœǂ�ł����j�B���̎l�Z���S15���{�͈��|�I���i�������̓ǂ�1967�N����71�N�ɂ����Ċ��s���ꂽ21���{�̃S�[���f���E�R�~�b�N�X�s�J���C�`�t�͐V���T�C�Y������A���������y���������낤�j�B�e��400�y�[�W���15���A6000�y�[�W�߂��B�\�\�l���c���F�s���y�O���_�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A2013�N9��10���j�̑�Y�͂͂܂�܂�s�J���C�`�t��_���Ă��邪�A���̖`���u�w�J���C�`�x�͌������w�K���x�Ɉ��Z�l�N�\������A�ڂ���A�������т��̋x�ڂ����݂Ȃ���A����N�������Ŋ��������B���G��l���Љ���܂߂�Ȃ�A�G���f�ڎ��ɂ����Č��㎵�łɋy�сA�����ʂ蔒�y�O���̍�i�̂Ȃ��ōő�̋K�͂����������҂ł���B�v�i�����A�Z�y�[�W�j�Ƃ���B�v���������ǂ�ł��Ȃ��������́A����������������������ēǂ��̂��B���Ɏ�����������w���̂���ǂƂ��Ă��A�r���ɕ��邾���������̂ł͂Ȃ����B�ЂƂɂ͔��y�̍�i�̌n���i�Ƃ�킯�s�E�ҕ��|���t�j�ɐe����ł��Ȃ����ƁA�����č]�ˊ��̓��{�̗��j���ڂ����m��Ȃ����ƁB�����w�I�Ȏv�l�@�Ɋ���Ă��Ȃ����ƁB����Ɂi���ꂪ�ł��̐S�����j�l���c�́s���y�O���_�t���Ȃ��������ƁB�q���̊�����lj�͂������т��Ă���킯�ł͂Ȃ����A���ɂ͂����v���ĂȂ�Ȃ��i���j�B�Ƃ���ŁA�g���{�l�́s�J���C�`�t�ɂ��Ă��A���y�O���ɂ��Ă��ꌾ���G��Ă��Ȃ��B���낤���Ď��̎��傪�A���y���`���Ă���^�c�K���z���̔E�҂Ɗւ��i�q�ʕ��̏I��r�D�E2�j�B
�k�c�c�l
�炢��̖������]�o�ɋ��炳��
�邢�ꂫ�̂��������f��̗⊴�Ő�ɂ���
���ւ̉�蓹
���B�ˑ��ւ̓��M�Ɖ��@
�Ƃ��������Y
�܂��ʂ̏����ւ̂₳�����ܟB
���R�ƍ^���͂��������N�̐g�̏�����肠����
�k�c�c�l
�l���c�ɂ��u�K���͑���ɏ}�������Ƃ���A���{�l�Ɠ��̔����ۛ��������A���Ԃɂ����ĕ]�������������B���̐l�C������I�Ȃ��̂Ƃ����̂́A�吳����Ɋ��s���ꂽ�w���앶�Ɂx�ł���B�����ł͍K���̔z���ł��鉎���A���B�ˑ��A�O�D���C�Ƃ������E�҂��A���d�s�v�c�ȔE�p��p���Ĉ��҂�ގ�����Ƃ��������ꂪ����A���̔g�p����Ȗ��͂����O�I�Ȏx�������B�v�i�s���y�O���_�k�����ܕ��Ɂl�t�A�ꎵ��`�ꎵ��y�[�W�j�Ƃ���B�q�ʕ��̏I��r�̏��o�́s������t9���i1959�N6���j������A���y�́u�^�c�E�Q�T�[�K�v�i�l���c�j���������A���ڂ̉e���ł͂Ȃ����A�吳���N���珺�a���N�ɂ����āA���N����̋g�����e���̂́s���앶�Ɂt�̖��B�ˑ��ł���A������ɋy��ł������痣�ꂽ�Ƃ����̂��u���B�ˑ��ւ̓��M�Ɖ��@�v�̈Ӗ����鏈���Ǝv����B�����A���y���悪����ΔM�������ɑ���Ȃ��B�s�J���C�`�t�Ɗւ��̂���g�����̍�i�Ƃ��āq蜾蠃��m�����邵�傤�n�r�Ɓq�G�̐��r�i�J�E2�j�������邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ����y�̍�i�́s�J���C�`�t�{�̂ł͂Ȃ��A1982�N����87�N�ɂ����ĘA�ڂ��ꂽ�s�J���C�O�`�m��n�t�ɑ�������A��̂����̈�сq�X�K���̓��r�i1982�j�ł���B�l���c�������Ă���悤�ɁA�X�K���̓W�K�o�`�i����I�j�̌Ï̂ŁA���y��i�ł͏������E�ł���B����A�g���͑O�f�̓�тɃX�K�����������̔�g�Ƃ��ēo�ꂳ���Ă���B�q�G�̐��r�i���o�́s���㎍�蒟�t1981�N9�����j�̎�����������B
���̌��҂̌��t��
�����킩�Ô��̔�g�݂������Ǝv��
�킽���͒���������@�O�r��S����
�f�R�̏�ɗ���
�����āu�����鉳���v���B����
�s����� �J���C�`�S�W�m�J���C�O�`�i�S11���j�n�E��3�� �X�K���̓��̊��k�r�b�O�R�~�b�N�X�X�y�V�����l�t�i���w�فA2007�j������ƁA��1�b�́q��������r�́u1982�N1��8���v�Ƃ��邩��A�g�����q�X�K���̓��r��ǂ�ł���q�G�̐��r���������Ƃ������Ƃ́A�N���m���W�[���炢���āA���肦�Ȃ��B�܂��A���y���g��������ǂ�ł���q�X�K���̓��r���������Ƃ������Ƃ��A�Ȃ��̂��Ƃ��肦�Ȃ����낤�B�g�������s�J���C�`�t�ȍ~�̔��y�O�����t�H���[���Â������́A�肩�ł͂Ȃ��B�����������������w�I�ȊS���A1980�N��̏��߂ɓ�l�̋����ɓ����ɋ������Ƃ������Ƃ́A�L�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ƃ���ŁA�g�����������s�J���C�`�t�͂��́m��ꕔ�n�ŁA�ŔӔN�̋g�����m��n�i�s�r�b�O�R�~�b�N�t1988�N5��10�����`2000�N4��10�����A�S168��A�ځj������œǂ�ł������ǂ����͂킩��Ȃ��B�m��n�������̏������낵���܂߂Ċ��������̂́s����� �J���C�`�S�W�m��n�E��12���k�r�b�O�R�~�b�N�X�X�y�V�����l�t�i���w�فA2006�N12��1���j�ɂ����Ă�����A�ނ��m��n�S�̂��ڂɂ��Ă��Ȃ��i�S�O�����琬��s�J���C�`�t�́m��O���n�͖{�e���M���_�Ŗ����\�j�B�����A�����Ɂs�J���C�`�t���ڍׂɘ_�����l���c���F�̕]����āA�g�����̐��E�Ƃ̗މ����ς邱�Ƃ͕s�s���ł͂Ȃ��B�l���c�́m��n�̓����������L���Ă���B�u�w��x�ł́A����܂ł̔��y����ɂȂ������قǂɁA�j�F�ƔO�҂̐��E���烌�X�r�A���A����ɃX�J�g���W�[�܂ŁA���܂��܂Ȑ����ۂ��o�ꂵ�A�G���e�B�V�Y���ƃO���e�X�N�E���A���Y���̌�������Ȃ�A�ٗl�Ȑ��E���f���o���Ă������ƂɂȂ�B�v�i�s���y�O���_�k�����ܕ��Ɂl�t�A�l�ܓ�y�[�W�j�B�u�G���e�B�V�Y���ƃO���e�X�N�E���A���Y���̌�������Ȃ�A�ٗl�Ȑ��E�v�����ŕ`�����l�Ԃ̈�l���g�����ł��邱�ƂɈّ��͂Ȃ����낤�B
�Ō�Ɏl���c���F�\�\���́u�w�J���C�`�x��̐_�b�Ƒh���`���̖{�C�̃E�H�b�`���[�v�i���������j�\�\�̔��������m�O���t�s���y�O���_�k�����ܕ��Ɂl�t�ŐV���ɕt���ꂽ�q���ɔł̂��߂Ɂ\�\���y�O���搶�Ƃ̈��r�̈�߂������āA�{�e���I�������B���ł̖{���Ɏ�̉������{�����k�����ܕ��Ɂl�ɂ́A���łɂ������q�ӎ��r�̂����ɁA���́q���ɔł̂��߂Ɂr���u����Ă���B
�@�搶�͂����悻���̂悤�Șb�����A���ꂩ�炢�������������ɂȂ����̂��낤�A�킽���ɘb���������B�����������̑������A�ǂ��`���Ă��������̂��˂��B�J���C�Ƃ��A���V�i�Ƃ��́A���ꂩ��ǂ��Ȃ��Ă����̂��낤�˂��B�킽���́A���V�i�͂₪�Ē���ŃI�����_��w���C�߂āA�����ł����u�����̈�ҁv�̂悤�ȑ��݂ɂȂ�̂ł͂���܂��Ɠ������B�J���C�͐����Ԃ����ԖڂƍŏI�I�ɑs��ȑΌ������A�����̑��q���傫�����邱�ƂɂȂ�B�������ł��傤�H�@�킽�����������ʂ��𗧂Ă�Ɛ搶�͞B���������A����ɋ������Ă����Ə�k�����ɂ���ꂽ�B�i�����A�܁Z�Z�`�܁Z���y�[�W�j
���āA�i�����Ԃ������Ĕ��y�O���̉��50���N�L�O�o�Łs����� �J���C�`�S�W�i�S38���j�k�r�b�O�R�~�b�N�X�X�y�V�����l�t�\�\�s�J���C�`�m��ꕔ�n�i�S15���j�t�A�s�J���C�`�m��n�i�S12���j�t�A�s�J���C�O�`�i�S11���j�t�\�\��ǂ��́A���ꂩ�����G���i�s���y�O�������t���w�فA1970�j�⒆�������i�s�V�E�J���C�`�̂��T�߁t����o�ŎЁA2009�j�A�c���D�q�i�s�J���C�`�u�`�k�����ܕ��Ɂl�t�}�����[�A2014�j�̏�����ǂ����Ǝv���B�������A���y�O����s�J���C�`�t��_�����{�́A�ǂ����Ă������݂ȐԂ��F�𑽗p����̂��낤�B�s�J���C�`�t���̂��̂͗ΐF���Ƃ����̂ɁB
 �@
�@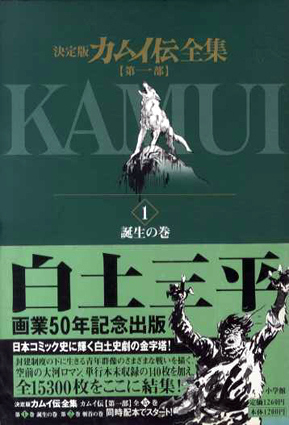
���y�O���s�J���C�`�E��1���i�S21���j�k�S�[���f���E�R�~�b�N�X�l�t�i���w�فA1967�j�̃W���P�b�g�i���j�Ɠ��s����� �J���C�`�S�W�m��ꕔ�i�S15���j�n�E��1���k�r�b�O�R�~�b�N�X�X�y�V�����l�t�i���A2005�j�̃W���P�b�g�i�E�j�@����������ė����͂�����͎̂R��i�m��܂����n�ƌP�ނ悤���j�ŁA�u���ꂪ���g���}���邽�тɂ������т��ˑR�ɏo�����A�u�J���C�I�v�Ƃ������ԁB����͐_���Ȃ���̂Ɍ�����ꂽ�A�ނ̊���̕\���ł���A�����ɋ����킹���҂������j�����������S���Ă���v�i�l���c���F�s���y�O���_�k�����ܕ��Ɂl�t�A�Z�y�[�W�j�B
�k�NjL�l
���Ď��́s���l�Ƃ��Ă̋g�����t�i���Y��ԁA2013�N9��28���j�́q�u�O���g�����v�\�\�s�Õ��t�Ɓs�m���t�r�́q�U �s�Õ��t�����̎��с\�\�q�ߋ��r�i�B�E17�j�r�����̂悤�Ɏn�߂��B�{�T�C�g�́s���l�Ƃ��Ă̋g�����t���̕��͂����A�o�c�e���������������J���ēǂނ̂��ʓ|�Ȃ̂ŁA�����N�͒��炸�ȉ��Ɉ��p����i�����A����`���O�y�[�W�j�B
�@���W�s�Õ��t�����̎��т́q�ߋ��r�i�B�E17�j�ł���B�����ŕ`����Ă���̂́A�Ԃ����̉�̂��B���͗̂��鋛��G�������������Ƃ͂��邪�A�Ԃ����͂Ȃ��B�o���҂ɂ��ƁA�Ԃ����̉�̂͑嗪�A���̂悤�ɂȂ�B
�@�\�\�G�C�̒��ԂŐH�p�ɂȂ�̂̓A�J�G�C�����ŁA���͍D���B�ʏ�A�������Ă����B�p�ӂ��钲�����͏o�n��A�傫�Șהi�K�����܂߂āA�S���͍ő�œ[�g���ɂ��Ȃ�j�A╁A�o�b�g�A�^�I���ȂǁB�ŏ��ɕ�ŕh�̂ʂ߂�����B�\��i�͂Ȃ��j������悤�Ȃ�A�ڂ̂�����̌E�݂�͂�ŌŒ肵�A�h�̊O���Ɍ������ĕ�̐n�ł������B���i�����瑤�̑��r�o�o�͏�������Ɏ��Ă���B���̂��߁A�u�X�鋛�v�̕ʖ�������j�����l�ɂ��Ăʂ߂�����A���Ő����B�����҂̊O���������悤�ɂ��ĕh��藣���B�G�C�͓���ނ����A�҂̂܂��̍��͕������Đ�Â炢�B�Ō�Ɋ̑��i�ϕt���ɂ���Ƃ��܂��j��E�o����B�̑����҂�����K���Ɋ����������ɂ���̂ŁA�h����菜��������������o���B�̑��ɂ͒_�X�����܂��Ă��邪�A�H�ׂ�Ƌꂢ�̂Ŏ�菜���B���≘������āA���n���͊����B�\�\
�����ɂ͒��ԍ����t���Ă����āA���̌㒐���f���Ă������ق�������₷�����낤�B
�@�G�C�̒����@�Ɋւ��ẮA��E�剮�N�A��E�ԍ�A�L���̃R�~�b�N�s��������ځk17�l�G�C�ƎL�t�i���w�فA��㔪���N�\����j�ɏڂ����B�����ł́A�L�ƂƂ��ɖk�C���Y�̃K���M�G�C�Ƌ�B�̃A�J�G�C�̃q���̒����@���Љ��Ă��āA�M�d���i�������A�G�C�̂������͓o�ꂵ�Ȃ��j�B�q�G�C�ƎL�r�ɂ́A�H�ނƂ��ẴG�C�ɂ��āA���̂悤�Ȑ���������B
�@�G�C�͌����ڂɏX���Łi�������猩��ƁA�G�C�̕����l�̊�݂����ŋC�����������j�A�����̎d���ɂ���ďL�݂��o�邪�A�����@�ɂ���Ă͎p����z���ł��Ȃ��قǂ��܂����̂ɂȂ�B�t�����X�����̋Z�@�Ƒ������悭�A���ؕ��ɐ����ɂ���Ə�i�߂���B�I�풼��̐H�����ɁA�z���̃G�C�̐�g���ݖ��Ŏς������̂�H�ׂ�����ꂽ�N��̐l�Ԃ́A�A�����j�A�L���Ă܂������Ƃ�����ۂ������悤�����A�l�ꂽ�ẴG�C�����ɒ�������ΏL���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�ނ���A�����̑f���炵�����[���Ɉ��������A�ŏ㋉�̋������̂ЂƂƂȂ蓾��B
�@�v����ɁA�N�x�̂悢�G�C���A��������ė�����������������̂ɂȂ邪�A���̐H������̈�������́A�����������߂����̉����Ƃ���Ă����B���Ȃ݂Ɏ��̖S��́A���a���N�ɍ��n�̑O�l�i�V���ɖʂ������j�ɐ��܂�A���㋞�������A�킪�ƂŃG�C���������Ƃ͈�x���Ȃ������B�����Ƃ��A�X�����̂�栂��Ɂu�A�J�G�C�k�́l���Ԃ��v�i���n�n���̘ی����j�Ƃ����ӂ��Ɍ���������A�A�J�G�C�̂Ȃ邩�͒m���Ă����͂����B
�{��͂�������ł���B��̕��͂�������2013�N�����ɂ͂܂��ǂ�ł��Ȃ������̂����A���Ҏ��g���B�e�����ʐ^�𑽐��f�ڂ����s���y�O���t�B�[���h�E�m�[�g�@�y�̖��t�i���w�فA1987�N11��20���j�ɃA�J�G�C�̒����@���ڂ��Ă���B�q�^���r�Ƃ������ڂ́A�傫�Ȏʐ^��3���̘A���ʐ^�̐����ɂ�������B
�A�J�G�C�̃^���B�G�C��L�͐g�������Ƃ�A�^���ɂ͍œK�ł���B��g�������ɒЂ��鎞�Ԃ́A�����G�߂͒��߂ɂ���B��������Q���قǂŁA�ǂ��^�����d���B������Ï��ɂ����āA�r�j�[���Ȃǂɕ��ł����Ɣ����J�r�������A����ɉA�����ɂ��Čł��d�グ��ƁA�����ۑ��ɓK���A�����ǂ��Ȃ�B�i�����A��Z�y�[�W�j
�@�A�J�G�C�̉�́B��^�̋��͑傫���ďd�݂̂���n�����g�p����Ƃ��₷�����̂ł���B�܂��̂̕\�ʂ̃k���ƃ��S�����Ă��˂��ɂ��������B���S�ɉ����č��E�ɐ��A�w���Ɠ������Ƃ�(�A�J�G�C�̔��ɂ͓Őj������̂Őؒf���ė����ɂ�����)
�A�����ēK���ȑ傫���ɐؒf���A���ɉ����ĕ�����A3���ɂ��낵�Ă䂭�B
�B���ɔ���ނ��āA�傫�Ȃ��͍̂D�݂̑傫���ɂ����g�ɂ���B�G�C�̍��͓�Ȃ̂ŁA�̂Ă��Ɉꏏ�ɏ���������B�l�ɂ���ẮA���̓�̕����D�ސl�����顁i�����A�㎵�y�[�W�j
�����āA�����Ɂu��㔪�Z�N�O���v�i����͒E�e�̎������A����Ƃ��G���f�ڌ����j�Ƃ���{���ɁA����������B
�@�u�^���Ƃ����͈̂��̕ۑ��H�ŁA����b�̓��̐�g�������ɒЂ��A�V���Ɋ��������̂ł���B
�@���^�̃A�W��C���V�Ȃǂō����ۊ��m�}���{�n����q���L�ƈ���āA�^���͂����ς�e��̎L�m�T���n��G�C�A�~�m�N�W���n�̂悤�ȑ�^�̕��̐�g�ō��ꂽ���̂������悤�ł���B
�k�c�c�l
�@�ނ�̊O���m�Q�h�E�n�Ƃ��ĎL��G�C�������鎞����������B����Ȏ��ɂ́A���Ă����v�����݂Ŏ̂ĂĂ��܂킸�ɁA���܂߂ɉ�̂��A��g�ɂ��ĊC���ɁA�i�C���̉��������傤�ǂ悢�j�ꎞ�Ԃ��Ђ��āA���̃N�V�ɂł��h���ĂԂ炳�����Ă����A�A��ہi�ꒋ�銱���ė����j�ɂ͌����ȃ^���������A�邱�Ƃ��ł���B
�@������Ï��Ɏ�荞�݁A�r�j�[���Ȃǂɕ��ł����ƁA���`�̂悤�Ȕ����J�r�������Ă���B������A�����ɂ������̂́A�����ۑ��ɑς��A���������������ꂽ���̂ƂȂ�B
�@������y�����Ԃ��Ď��̍�⒃�Â��̐g�ɂ���ō��ł���B
�k�c�c�l
�@�ނ�͋Z�p�����łȂ��A�ނ����l���ʂȂ��L���ɗ��p������p�m���ׁn��g�ɂ��邱�Ƃ��A�ނ�t�̎��i�̂����ɂ���B�v�i�����A�㔪�`���y�[�W�j
�����㒐�ŐG�ꂽ�u�G�C�̒����@�v�Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����Ⴂ���낤�B�t�����X�����⒆�ؕ��̒������R�U�炷���y�̖��ӂ�邻��́A�܂��Ɂu�ނ�t�̕ۑ��H�v�ŁA�g���̃A�J�G�C�����̂悤�ɎJ�����Ζ{�]��������Ȃ��A�Ǝv�킹����̂�����B�����ōĂюl���c���F�́s���y�O���_�t�����������ɏo���A���̎����I�ȍŏI�́q�\ ���y�O���̐H��r�ɂ́u�^���v�ւ̌��y�͂��邪�A���ꂪ�A�J�G�C�ł���Ƃ܂ł͏�����Ă��炸�A�������сq�ߋ��r�ɂ��ď����Ƃ��ɎQ�Ƃł��Ȃ������͎̂c�O�������B�{�e�Łk�NjL�l�̌`���̂��ĕ�������Ȃł���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�ї��r���͂��̓Ď��ȕ]�`�s���y�O���`�\�\�J���C�`�̐^���t�i���w�فA2011�N7��6���j�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@���A���炽�߂āw�J���C�`�x�̑S�̑��߂Ă݂�ƁA���̕��G�ȕ���\���ɑ��Ĉؕ|�ɋ߂��v��������͕̂M�҈�l�ł͂Ȃ��Ǝv���B
�@���́w�J���C�`�x�̐��E���A���y�O����m��Ȃ������Ⴂ����ɓǂp���łق����ƕM�҂͊肤���A���̂��܂�̒����ƕ��G���ɂǂ��ǂ�ł����̂������ǎ҂����邱�Ƃ��낤�B
�@�����ŁA�ᔻ�𗁂т�̂��o�債�āA�M�҂͂���ǂݕ����Ⴂ�ǎ҂ɐ��E���悤�Ǝv���B
�@������ʓǂ���̂���߂�̂��B�����āA���y�O�����Nj������e�[�}�Ɏ���敪��ݒ肵�A�w�J���C�`�x�ȊO�̍�i���܂߂āA�o���o���ɓǂ�ł����̂ł���B
�@�\�_��������Ȃ����A�ЂƂ̒�ĂƂ��Č�Љ�Ă݂悤�B�s���̐����͓ǂޏ��Ԃ������Ă���B�i�q�w�J���C�`�x����҂��ǂނ��߂Ɂr�A�����A�ꎵ���y�[�W�j
���Ȃ킿�i1�j�s�J���C�`�k��l�t1�`12���̃T���̕��ꂾ����ǂށA�Ɏn�܂�A�i10�j�s�T�o���i�t�S1���A�Ɏ���̂����̏���Ⳃł���B�����g�A���̂��ׂĂ�ǂ킯�ł͂Ȃ����A�͂��炸�����Ắs�E�ҕ��|���\�\�e�ۓ`�t�������ɁA�s�J���C�`�k��ꕔ�l�t�A�s�J���C�O�`�t�A�s�J���C�`�k��l�t�ƁA�قڔ��\���Ɍ�ǂ��Œʓǂ����i�D�ɂȂ�B�����Ă��̒���������i��U��Ԃ�ƁA῝�ɂ��������o������������̂�}���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�����E���Łs�N�����g�W�\�\�E�B�[���Ɠ��{ 1900�t�i�����s���p�فA2019�N4��23���`7��10���j��������̕����Ɋς��B�����`�P�b�g���āA����܂łɖ�30���B�V��̏����q������������ȏ���߂�A�������������������B�����O�X�^�t�E�N�����g�̌�����ς�̂́A�s�E�B�[���̈��Ɩ��\�\�N�����g�W�t�i�ɐ��O���p�فA1981�N1��29���`2��24���j�ȗ����낤���B���̂Ƃ��̓W����}�^�s�N�����g�W�t�i�����V���Ac1981�j�ɂ́q�A�b�^�[�Δȃ��@�C�Z���o�b�n�̐X�Ԃ̉Ɓr�i1912�j�������āA���܊ς�Ɛ[���������邪�A38�N�O�͂����ł͂Ȃ������B25�̒j�ɂƂ��āA�N�����g�͂����܂ł��q�ڕ��r�i1907�j��q�_�i�G�[�r�i1907�`08�j�̉�Ƃ������B
 �@
�@
�O�X�^�t�E�N�����g�̖��ʁq�A�b�^�[�Δȃ��@�C�Z���o�b�n�̐X�Ԃ̉Ɓr�i1912�j�i���j�Ɠ��q�w���[�l�E�N�����g�̏ё��r�i1898�j�i�E�j
����̌Ăѕ��́A�|�X�^�[�ɂ��Ȃ����q���f�B�g�T�r�i1901�j��q�l���̎O�����r�i1905�j�����A�N�����g�̍�i�ł́A�O�X�^�t�̑���������G�����X�g�̈⎙�A�w���[�l�i6�j�̐��^�Ȏp��`�����q�w���[�l�E�N�����g�̏ё��r�i1898�j�ɑł��ꂽ�B����ɁA��ɂ��q�ׂ��悤�Ɂq�A�b�^�[�m�[�[�n�̃J���}�[��r�ɑ�\����镗�i�悪���n�������B�ӔN�̊ےJ�ˈ�́A�N�����g���D�����`�̃L�����o�X�̓�������ׂ��A������̕����̕��i��������ɏ����Ă����Ƃ������A���ɂ���͉�����������Ȃ������B�ےJ�́q�N�����g�_�r�́u��������݂�^�l�p�̕��i�悪�������낢���A�ǂ����Đ^�l�p�Ȃ̂��ƋC�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��A�����ꂱ��ƍl�ւĂ݂�B�^�i�����j�v�i�s�ʂ�̈��A�k�W�p�Е��Ɂl�t�A�W�p�ЁA2017�N3��25���A�Z��`�Z��y�[�W�j�œr��Ă���B�ӔN�̊ےJ�ɂ́A��������������邾���̎��Ԃ��c����Ă��Ȃ������̂��i���j�B�����A����̓W���̂Ȃ��ɂ͂قڐ����`�̍��q�i�k�o���R�[�h�̃W���P�b�g����⏬�Ԃ�ȁA�����h�m�[�c�F�b�V�����n�̋@�֎��sVER SACRUM�i���Ȃ�t�j�t�j�������āA�\�������ς��Ȃ��������A���̓��قȔ��^�̈�������N�����g����ɂ��Ă����ƍl����ƁA�����ʂł���i�{�W����̐}�^�A�����s���p�٥�L�c�s���p�٥�����V���Е҂́s�N�����g�W�\�\�E�B�[���Ɠ��{ 1900�t�i�����V���ЁAc2019�j�Ɉ˂�A���m�ȃT�C�Y�́u29.3�k�c�l�~28.3�k���lcm�v�ŁA12�C���`���R�[�h�̃W���P�b�g����31.5�~31.5cm������A���q�Ƃ��Ă͂��Ȃ�唻�ł���j�B�Ƃ���ŁA������Ƃ��Ȃ�ƁA2500�~�̌����}�^�k�ʏ�Łl�͍D�]�̂��ߕi��ŁA����ł��Ȃ������B���������āA��ɋ�������i���́s�N�����g�k�V�����p���Ɂl�t�i�V���ЁA1975�N12��25���j�Ɉ˂��Ă���̂����A�������^�̍�i����Ɗ����̃G�b�Z�C�q���Ɛ��̓����\�\�N�����g�̐l�ƍ�i�r�������Ă���̂́A�����Ƃł��莍�l�ł��������ѓc�P���ł���B���ւ̉����҂�̎Ԓ��A�v���Ԃ�ɓǂ݂������Ă݂āA�����G�b�Z�C�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����̂������B
�@�N�����g�������������̂́A�ނ����R��������̂Ɠ����Ӗ��ɂ����Ăł������B�ނ͒j�������̂����ɑ傢�Ȃ鎩�R�������̂ł���A���̎��R�Ƃ��Ă̏����A���̖{���������Ƃ������ɕ\������u�Ԃ𐫓I�����̂����Ɍ����̂��Ƃ����悤�B�����ď��̖{���́A���R�̂���Ɠ��������ł���A���ł��邪�䂦�ɂ��������Ɛ��肤��Ƃ���́A���Ƃ��Ă̖��ł���B�����g�́A���Ȃ����҂ł��邩���������ĔF�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����A���͒j�ɂ���Ĝ����ɒB����Ƃ��A��̋P���m�A�A�n�̏�Ԃɓ��B����B����͖�����Ɋ܂݂Ȃ���A��������Ԃł���B������Ɋ܂݂Ȃ���A��������ԂƂ��Č�����̂������m�G�N�X�^�V�[�n�̓����ł���B�G�N�X�^�V�[�͈�̕��ՓI�ȏ�Ԃł���B�i�����A���Z�y�[�W�j
�����́u���Ƃ��Ă̖��v�Ƃ����͋�́A�������g�����W�̕��Ŗڂɂ�������������B�A��Ă��������s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W�E�g�����l�ׂĂ݂����A�ѓc�P���́q�q��m�G�j�O�}�n�r�Ɍ������ā\�\�w�Ẳ��x�𒆐S�Ɂr�ɂ͂Ȃ������B�������ŁA��Ήp���́q�u���Ƃ��Ă̖��v�\�\�g�����̃t�@���X�̐��E�r�������Ă���i�W��́A����ѓc�́q���Ɛ��̓����r������������̂��A�肩�ł͂Ȃ��j�B���Ȃ킿�A
�@���Ƃ́A�n�܂��s�I��ł���A�I���s�n�܂�ł���B���邢�́A����s���A����s���A�Ӗ���s���Ӗ��A���Ӗ���s�Ӗ��ł���B�����A���Ƃ́A���ꎩ�̂ł͐��ł����ł��A�Ӗ��ł����Ӗ��ł��A�n�܂�ł��I��ł��Ȃ��B����́A���͂�����̂��̂����������m�A�n�A�]�Q��ł���ɂ����Ȃ��B���Ƃ́A�u���́v�Ɏ��āA���Ȃ���̂����Ȃ���̂ւƃh���f���Ԃ����閳�Ƃ��Ă̓]�Q��ł���ɂ����Ȃ��̂ł���B�����A���Ǝ��A�Ӗ��Ɩ��Ӗ��A�n�܂�ƏI��A���������g�ɋz������ő��݂��闧�́A���Ȃ킿�u���Ƃ��Ă̖��v��}��Ƃ��Đ������鐢�E���̂��̂́A�傢�Ȃ�h���f���Ԃ��A�傢�Ȃ�`�e�����A�傢�Ȃ铯�ꔽ���A�t�@���X�̐��E�ł���B�u���Ƃ��Ă̖��v�Ƃ́A�g�����̎����̂��̂ł���B�i�����A��O�Z�y�[�W�j
����̋g�����_�̊̂ł���B�������A���ꂾ�����̂��Ǝv���A�ǂ����D�ɗ����Ȃ��B���ꂪ�Ȃ��Ȃ̂��A�悤�₭���������B���䉺�Â��Ƃ͂��̂��ƂŁA�u���Ƃ��Ă̖��v�Ƃ����͋�́A�g�����̎��сq�����r�i�H�E6�j�ɓo�ꂵ�Ă����̂��i�����j�B���́u�Q�v�Ɓu�S�v�������B
�Q
�u�Ñ�̐_���̂܂Ƃ�
���߂̎��v
�̂悤�ȓ��p�V����q���[���E�W�F���[�r
���Ȃ킿�~�Y�N���Q�̂ނ�
�����̎q�G�t�B��
�܂��������B�����ƂȂ�
�|���v
�[���̔g�Ԃ�
�u�����q�̓����̂悤�ȏ_����
�ۂ��N���̐��E�v
����
�ϔO��s��
�킽���͖����߂����ĉj��
�u���Ƃ��Ă̖��v
�Y���䂭�q���[���E�W�F���[�r
�����Ȃ����
�����
���_�G�A
�S
�킽���͂ʂ邢���M�ɂ���
�p�������������Ă䂭�̂�
�����Ȃ���
�u����鐅�̖ʂ̒��
�̂悤��
���̑��݂����킾������v
�G�S���E�V�[����
���U�Ə͋��z���o��
�u�l�͉Ă̐����
�H�̎�����������v
�܂�ł��̉Ƃ�
����̂悤��
�����炳�߂����
������
���t��
�݂��������Ă���
�����킦���
�����̉Ԃ̂͂邩����
�킽���͊ዅ�ɓ_�H����Ă���
�g���́A������b�q�Ƃ̑Βk�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�i�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W�E�g�����l�j�Łu�ŋߌ����G�ł́A�G�S���E�V�[���̓W����ɂ͂���ς�Ռ������B���ی����̂͂��̊Ԃ����߂ĂȂ��ǁA���b�q�́u�����v�ɂ̓G�S���E�V�[���̌��t��}�����Ă���B�v�i�����A���Z�y�[�W�j�ƁA�V�[���Ƃ̏o�������Ă����i�������j�B�����A�g�����V�[���̎t�E�N�����g�Ɍ��y�������Ƃ͂����ĂȂ������B�����Ƃ��ѓc�́u���Ƃ��Ă̖��v���s�N�����g�k�V�����p���Ɂl�t�i�V���ЁA1975�j�œǂ̂Ȃ�A���R���̍�i�̐}�ł��ςĂ���͂�������A�g�����ɂ��O�X�^�t�E�N�����g�]���Ȃ��̂́A�܂��Ƃɂ����Ďc�O�ł���B
�@�N�����g�͏����̓��̖̂��f�ɐ[���̂߂荞�ʂĂɁA�ޏ���̓����ɂ����߂��閧�̗~�]�̐[���ӎ��ɒ��o�����̂������B�����āA�ނ��������~�]�̌`�̂�����ɂ́A�l�Ԃ̉^����������Ă����̂��B�N�����g�͏����̔��������]�Q���A�������C�R���ɒ������邱�ƂŁA�ގ��g�̂������Ă��������낵���قǂ̌ǓƂƎ���̋����������݂ɉA�����Č������̂��B����͔ނ̏����p�Ƃ������A�ނ���A�ނ̃_���f�B�Y���ł������B
�@�V�[���ɂ̓N�����g�̂悤�Ȓj�炵����Ƃ�͖������������Ԃ��Ȃ������B�V�[���̗��̐_�o�͐[���T��Ɍ����Đ��ʂ���˂��h����ق��Ȃ������B�����̌����̊�ւ͂����ɐ��܂ꂽ�B�i�s�����C�J�t1987�N7�����k���W���E�B�[���̌��Ɖe�l�A�����y�[�W�j
�ѓc�P���́q�|���m�O���t�B�[����Ƃ��\�\�N�����g�ƃV�[���r�̌�����������B�ѓc�̃V�[���_�̊j�́u�V�[���́A���݂����E���A�������g���������Ǝ��Ɍ����ĉ��~���Ă䂭�^���ł��邱�Ƃ𗝉����Ă����B��������ɛs��ł��邩�炱���A�u���v����u���v�ւ̏u�Ԃ̘A���Ƃ��Ắu���v�́A�Â��̒��̋P�����A���p�̒�ɍ��M�����A�B�����̉��ɕs���̊m�������A�Ƃ��̓����ɔ�������قǂ̗͂��A�₵���̂���݂ɒ�m��ʊ�x���A�������Ȃ��悬�̐^�ɂӂ����ȉi���̂����������A�����݂̗��ɑł��ӂ���ʖ{�����A��߂Ă��邱�Ƃ��͂�����Ɗ����Ƃ��Ă����B�V�[���̊����̓����ł́A���Ɛ��A���Ǝ��́A�R�C���̕\�Ɛ^�̂悤�ɕ��������������ѕt���Ă����̂ł���A���������āA�ނ̊����̘_���ɂ��������A���������̂́A�K�R�I�ɁA�X�����̂����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����ł��A���������A���Y�����Î~�����Ă���悤�Ɂc�c�B�v�i���O�A���܃y�[�W�B�������A�T�_���Ȃ����j�ɂ���B�͂����ċg���͔ѓc�̂��̃V�[���_�̖����ɐk�����Ȃ��������낤���i�g���̓N�����g�Ɉ��S���ꂱ������A��ɂ������Ƃ͂Ȃ����낤�j�B���Ȃ݂ɋg���͓����ɁA1987�N6��8���̍����V�g�̍��ʎ��ŏq�ׂ������i�q�_�K�o�W�W���M�a����A���悤�Ȃ�r�j���Ă���B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�ےJ�ˈ�͂��́q�N�����g�_�r�Ƃ͕ʂ̂Ƃ���Łu�k�c�c�l�ŋ߂킽���́A�N���[����уN�����g�Ƃ��ӓ�\���I�h�C�c�̉�ƂɁA�����`�̉�ʂɕ`�����G���������ƂɋC�����ċ��������Ă�܂��B����̓��l�T���X�E�C�^���A�ɂ��A�I�����_�̉�Ƃ����ɂ��A�t�����X��۔h�ɂ������Ȃ����ۂł���܂��B�Ȃ�����ȌX�����������̂��B�^���낢��T�Ă�邤���ɁA��c�R���ӂ���́w�p�E���E�N���[�̕����G�x�Ƃ��Ӗ{�̂Ȃ��ɁA�N���[���n�C�}���̖��w�����̏���x�Ƃ��Ӗ{�����ǂ������Ƃ��o�Ă�܂����B���̂Ȃ��ɓ��̊ؖ��m�����n�����x����E�����ЁA���J����ĕs���ł������Ƃ��o�Ă���B����̓h�C�c���i�`�X�̎x�z���ɂ��āA�N���[���f���b�Z���h���t���p�w�Z�̋����E���������ƂƏƉ�����ł������A���Ȃ̂͊ؖ��̎��̑g�ݕ��ŁA��傪���A���ꂪ�\���̂��͂��܌��r���̎�����ÂZ�s���ׁA�����`�ɋ߂��`�ɑg��ł��B�N���[��N�����g�͂��̎��̖����u���邠�܂�A�����ɂ�鐳���`�̔������ɖ��f���ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł������B�^�������ӂ��Ƃ��l�ւ��Ƃ��A�킽���͂��Â��A���ː�Ȃ炱�̎v�Ђ����������낪�Ă��ꂽ�炤�ȁA�Ɖ����̂ł���܂��B�v�i�q�V�������ɒ��ޒm�I�Ȑl�ԁr�A�s�ʂ�̈��A�k�W�p�Е��Ɂl�t�A�O�l�l�`�O�l�܃y�[�W�j�ƌ���Ă���B����́A2011�N3��12���i�����{��k�Д����̗����I�j�A�鍑�z�e���ōs��ꂽ���ː�Ҏ�������Âԉ�\�O����ł̈��A�B����L�́q�N�����g�_�r�̉��A�q�������Ȃ������N�����g�_�r�Łu���Ȃǂ��l���Ⴂ���Ă������Ƃ�����B�ےJ����̃N�����g�_�̍\�z�́A���߂Ɏv�����悤�Ɉ�т̃G�b�Z�C�ōςނƂ����̂ł͂Ȃ������B�\�����Ă�����肸���ƋK�͂��傫���A�{�i�I�Ș_�l�ɂȂ���̂������B�S���Ȃ�����A�����j�̍������������̎��ӂɌ��o�m�݂����n�����u�\�z�����v���݂��Ă��������ƁA���̂��Ƃ�ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B�v�i�����A�ܓ�y�[�W�j�Ə��������ŐG��Ă��Ȃ����A���͊ےJ�̍\�z�������{��k�Ђ̔����ŕύX��]�V�Ȃ����ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɯu�x����B���Ȃ킿�A�k�ЂŖS���Ȃ������Q�ɑ������肵���l�l�ւ̒����̑z���ł���B�s���b�U�Ƃ͉����t�i1984�j�̍�҂��A�����Ɍ��y���Ȃ��ł��邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B�ނ��́A�{�i�I�Ș_�l�ł���s�N�����g�_�t�\�\�N�����g�̕��i��͂Ȃ��^�l�p�Ȃ̂��\�\�ɂ����Ăł͂Ȃ�������������Ȃ����B
�i�����j�@�q�����r�̏��o�́s���Y�t1977�N11�����B�g���͋�����b�q�Ƃ̑Βk�ŁA���p���ɂ��āu���b�q��`�����u�����v���A�N�̌��t�����ł́A���܂������Ȃ��̂ŁA���͔ѓc�P���̃G�b�Z�C���������ؗp���Ă���B�����A�ڂ��������Ă��������̂́A������̎��т����傩��͂Ƃ��ĂȂ���B����݂͂�ȑΏۂɂȂ����l�̃G�b�Z�C����Ƃ��Ċ��ʂɂ���āA��������ɂ����Ă��Ă���B�v�i�q��̌��t�\�\�t�B�N�V�����ƌ����̍����ցr�A�s���㎍�蒟�t1980�N10�����k���W�E�g�����l�A��Z�y�[�W�j�ƌ���Ă���B���Ȃ킿�A�u���Ƃ��Ă̖��v�́A�ѓc�P���̃N�����g�_�q���Ɛ��̓����r�i1975�j���g�����̎��сq�����r�i1977�j����Ήp���̋g���_�q�u���Ƃ��Ă̖��v�r�i1980�j�ƁA�]���𐋂����킯���B�g���́A�q�����r�ł͔ѓc�P���̖��O���������A���ꂪ�N�����g�ɂ��Ă̕��͂ł��邱�Ƃ��G�ꂸ�ɏ͋�����p�����B����A�ѓc�̏͋��莫�Ɍf�������сq�`�͕s���̉s�p�������c�c�r�i�H�E11�A���o�́s���㎍�蒟�t1978�N4�����j�ł́A���̎���u�����Ă킽���̓A�����E���[�����X�́^���t���v���o���^�q�l�͂������ӎ���\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��r�v����A�t�����R�E���b�\�[���ďC�s���[�����X�k�t�@�u�����E�����W 13�l�t�i���}�ЁA1972�j�ɔѓc�P����������q�A�����E���[�����X�r�̌���u�ށk���[�����X�l�́u�l�͂������ӎ���\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͌|�p�̈̑�Ȕ閧�Ȃ̂ł��v�ƌ��������C�ނ͒��ق̗̈�ɑ�������̂̕\�����i�����������Ƃ��悭�m���Ă����̂ł���B�v�ɗe�Ղɂ��ǂ����B���Ȃ킿�u�ѓc�~���[�����X�v�Ō�������A�ȒP�ɓ��Y���q�Ɉ�������B�g���̎���͂��ꂾ���̈Î��ɏ[���Ă���B
�i�������j�@�s�G�S���E�V�[���W�t�i�������p�فA1979�N4��27���`6��6���j�̐}�^�ł���s�G�S���E�V�[���W�t�i�����V���E�������p�فA1979�j�̔����ɂ́uEgon Schiele�\�\1890-1918�v�̕����������̂悤�ɂ���A���̉����ɃV�[���̏ё��ʐ^�A�����Ă��̃L���v�V�����̂悤�Ɂu���ʓI�ɁA�{���ƐS�ƂŁA�l�͉Ă̐���ɁA�H�̎�����������B���̗J�D�������͕`�������B�\�\�V�[���v���f�����Ă���B�g�����q�����r�Łu�G�S���E�V�[���́^���U�Ə͋��z���o���v�Ƃ��Ĉ��p�������U�Ə͋�̓T���͂���ɈႢ�Ȃ��A�ꌏ�����B�ƌ��������Ƃ��낾���A1977�N11�����\�̎���̓T����1979�N���s�̐}�^�ł���͂����Ȃ��B���߂ĕ�����T������ƁA�ѓc�P���̃G�b�Z�C�q�\���I���ݎ҂Ƃ��ẴG�S���E�V�[���r�i�s�݂Â�t1969�N9�����k�q���W�r�G�S���E�V�[���F�ӂ邦�鍰�̓Ɣ��l�j�̌���߂���
�@�ނ̑z���o�͂Â��c�c�D�k�c�c�l
�Ƃ������B�g�������̔ѓc���Ɉ˂������Ƃ͋^���Ȃ��B���Ȃ݂ɓ��}�^�̖����ɂ́A�O�q�̔����Ɠ��l�̃��C�A�E�g�ŃO�X�^�t�E�N�����g�i�V�[���͂��̃E�B�[�����p�̐�B���I���A�t�Ƌ����j�̏ё��ʐ^�Ɨ������f�����Ă���A���m�N���}�łƂ��ăf�b�T���𒆐S��13�_�̃N�����g��i���f�ڂ���Ă���B�g���̓V�[���W�̉��i���͂Ȃ������E�r�܂̐������p�فI�j�œ��R������ڂɂ����͂����B�c�O�Ȃ��ƂɁA���͂��̃V�[���W�����̂����Ă���B
�@�k�c�c�l
�@�u���ʓI�ɁC�{���ƐS�ƂŁC�l�͉Ă̐���ɁC�H�̎�����������D���̗J�D�������͕`�������I�v�i�����A���y�[�W�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�{������ђ��ŋg�������̓T���Ƃ��ċ������ѓc�P���̃G�b�Z�C�̏��o�A���Ȃ킿�q���Ɛ��̓����\�\�N�����g�̐l�ƍ�i�r�q�A�����E���[�����X�r�q�\���I���ݎ҂Ƃ��ẴG�S���E�V�[���r�́A����������̌�A�ѓc�̒����s�����Ȃ������t�i���X�A1977�N3��20���j�Ɏ��߂�ꂽ�B�g���������q�����r���M�̍ۂɓT���Ƃ����̂͂���珉�o�`�ł͂Ȃ��A�����炭�ѓc���瑡��ꂽ���낤�P�s�{�̕��������ɑ���Ȃ��B�����A����ɂ܂��m����،����Ȃ��̂ŁA�{�e�ł͂����ď��o�`���f�����B
�{�e�ł́A�g�����Ɖ��O�X�ё��Y�i1862�`1922�j�̈ꑰ�Ƃ̂��������T�ς������B60�şf�������O�́A����3�������g���ɂƂ��đc���̐���ł���A�g���̐��܂ꂽ1919�N�ɂ͒鎺�����ّ����ɏA�C���Ă���B�\���Ƃ��āA���҂�����̊X�p�łł����ꂿ�������Ƃ��Ȃ������Ƃ͂����Ȃ��B���̉��O�̍Ȏq�����A��Ȃ̓o�u�q�i1871�`1900�j�Ƃ̂������ɒ��j�̉��p�i1890�N9��13���`1967�N12��21���j���A��Ȃ̎u���i1880�`1936�j�Ƃ̂������ɒ������仁i1903�N1��7���`87�N6��6���j�A�����̏��x�Ǔz�i1909�N5��27���`98�N4��2���j�A��܂������j�̕s���A�O�j�̗ށi1911�`91�j�����āA�햅�ɓĎ��Y�i1867�`1908�A�M���F�O�ؒ|��j�A���������q�i1871�`1956�j������B�g���́A���O�ɂ͗��j��̕��M�ƂƂ��Ă��̍�i�ɐڂ������������i���z����L�Łs��t��s�F�]���V�t�ɐG��Ă���j�A�X�Ƃ̐l�l�̂Ȃ��ōł��m���Ă���X�仂Ƃ͒}�����[�̕ҏW�ҁE�����҂Ƃ��Đe��������ł����B���z�q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�i���o�́s��t1988�N2�����j�ł͂��̎��𓉂�ł���B�܂��A�X���p�́s���e�Ƃ��Ă̐X���O�k�����ܕ��Ɂl�t (�}�����[�A1993�N9��22���j�̌��łł���s���e�Ƃ��Ă̐X���O�k�}���p��159�l�t (���A1969�j�����ɏo��ɂ������ẮA�g�����̐s�͂��������B����͂ǂ�Ȗ{���B�k�����ܕ��Ɂl�̃W���P�b�g�̗��\���ɂ�������B�u�X���p�͉��O�̒��j�ł���A��͉��O�Ɨ��ʂ�����Ȃł���B���p�́A�c��ɂ���Ĉ�Ă��A�̂����{�̉�U�w�̌��ЂƂȂ�B���̉��p���Ԃ������O��Ƃ̗��j�Ɛ^���B��Ƃ̒��Ƃ��Ẳ��O�ƕ��Ƃ��Ẳ��O�Ɛl�ԂƂ��Ẳ��O�����ʂ��ė]���Ƃ��낪�Ȃ��{���́A��ꋉ�̎����ł���Ɠ����ɁA�[����������Ԉ�̐l�ԋL�^�ł���v�B�����k�}���p��159�l�̊����ɂ́A���s�̑O�O�N�ɖS���Ȃ������҂̉��p�ɑ����āA�Ȃ̕x�M���q���Ƃ����r�������Ă���B���̖����������B
�@���p�͕\�ʏ_�a�Ȑ��i�̂悤�Ɍ����Ă��A�ǂ����ǂɈ�{�؋����ʂ��Ă����̂ł��傤�A���������͈��������ʂƂ�����ł�������܂����B�q���B�ɂ��傫�Ȑ��Ŏ��������Ƃ͂Ȃ������悤�ł������A���e�ɑ��Ă͂ǂ̎q���������ĉ�Ԃ��������ƂȂǏo���Ȃ������悤�ł��B������̉�ԂȂNj����Ă��ꂻ���ɂ�����܂���ł����B
�@����Ȏ�l�̂��Ƃ��v�����ׂȂ���ڂ��肵�����̒����ǂ���痎���A���������̓��������������͂��߂����͋}�Ɉ���̖{�ɓZ�߂Ă݂����ƁA�o���邱�ƂȂ�O����̍��܂łɂƎv�������̂ł��B���Ƃ����Ă��{�ɊW�̐[���仂𗊂�ɒ}�����[�ŋg�����ɂ��ڂɂ��������̂͏��Ă̍��ł����B�v�������Ȃ����̊肢���������ĉ��O�W�̂��̂�p���̈���Ƃ��ďo�ł��ĉ����邱�ƂɂȂ����̂͂��̏���Ȃ���тł������܂��B
�@�I��ɂ��̓x�Z�����̒��ɏo�łɂ����܂艺�������g���A����A����O�����тɒ}�����[�̂����ӂ�[�����Ӑ\�グ�܂��B�i�X���p�s���e�Ƃ��Ă̐X���O�k�}���p��159�l�t�A�}�����[�A1969�N12��20���A�O�܁Z�`�O�܈�y�[�W�j
�����̋g���͋g�������Ƃ��āA����͍���m�������n�C�A����͑��㐴���낤���B�X���p�̕��͂ł́A���O�Ə��l�Ƃ̊W���������������ڂ���邪�A�����ł͎��̈�߂������Ă������B
�@���͂��̎U���ŏ�ȕ��킸�ɊX�̌i�����ώ@���Ċy���ގ������ɋ������B�Ö{���ɕK�������B�ǂ��̓X�̎�l�Ƃ�����ɂȂ��Ă��ēX��ɍ������Ęb�����ށB�����ČÂ������{���R�̂悤�Ɏ��o���Č�����̂���X�I�蕪����B���͑ދ��ł��܂�ʂ��炻�̊ԁA�ߏ��̋�������G�������̓X�ŗV��ł͎��X���̕������ė����̂�҂B���ꂪ��X�ł���ƕ��͉����[�ɂ��Ⴊ��Ŗ{���������B�������ĉ������T���o�����{�������ċA��ƈ�X�����ɕ��ł����Ē��J�Ɏ��B�����ē����̋�������I��ŌÖ{��������ł�����A�Ԗڂ̂��̂͂Ƃ������A�j�ꂩ�������͎��ŕ���ď��I�ɔ[�߂�̂ł���B�i�q���̉f���r�A���O�A���Z�`�����y�[�W�j
�g���Ƒ��̃N���A�t�@�C���̈���ɁA���x�Ǔz���V���Ɋ��q�N���m��Ȃ��I�r�Ƃ������z�̐蔲�������߂��Ă���B�g���̃t�@�C���ɂ��Ă͒������f�ڎ�������t�̃������Ȃ��āA�o�T�����ł��Ȃ��B�N���A�t�@�C���̑O��̎������琄�肷��ƁA1980�N�㖖�̂��̂��B������Ă�����e����́A6�ΔN��̎o�E�X�仂�Ǔ��������̂��Ƃ킩��B�u�o�͗��z�̔������v�u�v�w�̎q�̂悤�Ɂv�u�₳���������Z�v�u�����v���o�̒��Ɂv�Ƃ���4�{�̌��o���������Ă��邪�A�u�₳���������Z�v�̒i�������悤�B���x�������ł����u�Z�v�́A�ٕ�Z�̐X���p�ł͂Ȃ��A�仂̕v�̎R�c����i1893�`1943�j�ł���B
�@�����Ƃ��Ă͋H�i�܂�j�Ɍ���O�c�䒬�́A���Ս�H�ɉ����A�����C�V���i���т���j�̖��������i��j�A����̂��镻���߂��炵�A�����i��������j�ŁA�L��ȉ��ڊԁA��K�ɂ́A�Z�̏��ւ�A�Q���̂���m�ٌ��ĂƁA�ꗬ�����Ƃ����������́A������L��ȓ��{���z�ɕ�������A�T���i���������j�������̐A�����݂�w�i�ɁA�Ő��̒z�R�m����܁n��A���̟��i���j�ꂽ�r�ɁA����H�̒߂̗V�Ԃ�����L��Ȓ뉀�����߂�ꂽ�B��͓��{�ق̓�K�ɁA�Z��A�o�ƐQ�������̂����A���w���̎��́A�钆�ɊႪ���߁A��ɍs�����A�|�낵���Ĉ�l�ł͍s���Ȃ��B�o�͌Ă�ł�������܂��Ă���Ȃ��̂ɁA�Z�͊�q�i�߂��Ɓj���N���āA�K���̈Â��A�����L������ɘA��čs���A�܂��A�A��߂��Ă����̂ł������B
�u�H�i�܂�j�v�̂悤�ɓǂ݂��Ȃ��p�[�����Ŋ�������́A�V���Ɠ��̕\�L������ڂ��Ԃ�ɂ���i����ɂ��Ắu�z�R�m����܁n�v���s�ԃ��r�Ȃ̂������Ȃ��j�A�ނ�݂ɓǓ_�̑����A�s�K�v�ɒ����Z���e���X�͂��鎞���ȍ~�̐X�仂̂���̂悤�ŁA�̎^�ł��Ȃ��i�`���́u�����Ƃ��Ă͋H�i�܂�j�Ɍ���v�͂��������ǂ��ɌW��̂��낤�j�B����Ƃ����x�Ǔz�͂����ŁA�S���o���Â�Ńp�X�e�B�V�������݂Ă���̂��낤���B�g�������x����蔲���ĕۑ������̂͂Ȃ����낤�B���R�̂ЂƂ͐X�仂̒Ǔ����ł��邽�߁A�����Ă����ЂƂ͏�f���Ɍ�����u���Ս�v�䂦�������̂ł͂Ȃ����i�q�s�����t�Ƌ��Ս�r���Q�Ƃ��ꂽ���j�B�f�ڂ��ꂽ�̂������킩��Ȃ��̂ŁA�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ����A�q�N���m��Ȃ��I�r���仂̟f����1987�N6��6�����炳�قNJu�����Ă��Ȃ������ɔ��\���ꂽ�Ǝv�����B�����āA�s��t1988�N2�����́q�����w�L���̊G�x�\�\�X�仂̑z���o�r�́A�Ǔ������˗����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���z�𗊂܂ꂽ�g�����i��ŕM�����������̂Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B���̂Ƃ��g���́A���x�Ǔz�̕��͂��u���������m��Ȃ��v�X�仂̑z���o���������߂̓��ؔŁm�X�v�����O�{�[�h�n�ɂ����̂ł͂Ȃ����B
�@���̓��W��ʂ̌v�������Ēu���Ȃ������͍̂���U�w�҂��鎄�̓��Ɉ⊶�Ƃ���Ƃ���ł���B���������ʂƑ��ʂƂ̎ʐ^�͂��邩�瓪�W�̒������A�������A���ʊp���͂�����x�̊m�R��������������������͂��ł��邪���ݎ苖�ɂȂ����瑼�̋@��ɂ䂸��B����ɂ��Ă����̎��̍ێ����������Ȃ��������߂ɉ�U�ɕt�����A���̔]������������ɊD�ɂ��Ă��܂����̂͂����Ԃ�c�O�ł���B�i�X���p�q���̉f���r�A���O�A��܃y�[�W�j
�g�����̎U���́A�X�Ƃ̐l�l�̂Ȃ��ł́A�����͂��ƂȂ����[���A��Y�킹��X���p�̂���ɋ߂��A�X�仁E���x�Ǔz�o���̌n���ł͂Ȃ��B

�g���Ƒ��̃N���A�t�@�C���ɕۑ�����Ă����A�f�ڎ����s���̏��x�Ǔz�̐��z�q�N���m��Ȃ��I�r�̐蔲���k���m�N���R�s�[�l
�k�NjL�l
���x�Ǔz�̏����E���M�W�i�Ɩ{���ɂ͂���j�s�t�t�i�����o�ŁA1947�N4��20���j�́A��ɂ���č]�Óc�͓����Y�p�w���O�̍������[�œ��肵���B�{���̗��Ɂu�\���G�E�J�b�g�@�؉��ۑ��Y�v�Ƃ���A�Ό��̖{���y�[�W�̏��߂ɂ́u���̏����̑��c���Y�搶�ɕ����v�ƌ���������B���O�̕��Ƃ��u�e�G�x�X�S��̑�s�v�Ə̂����ۑ��Y�����c���g�A�G�ɗD��Ă������Ƃ́A�q�ۑ��Y�ƕ��i�̃T�t�����̃X�P�b�`�r���݂Ă��炦��킩��Ǝv���B
 �@
�@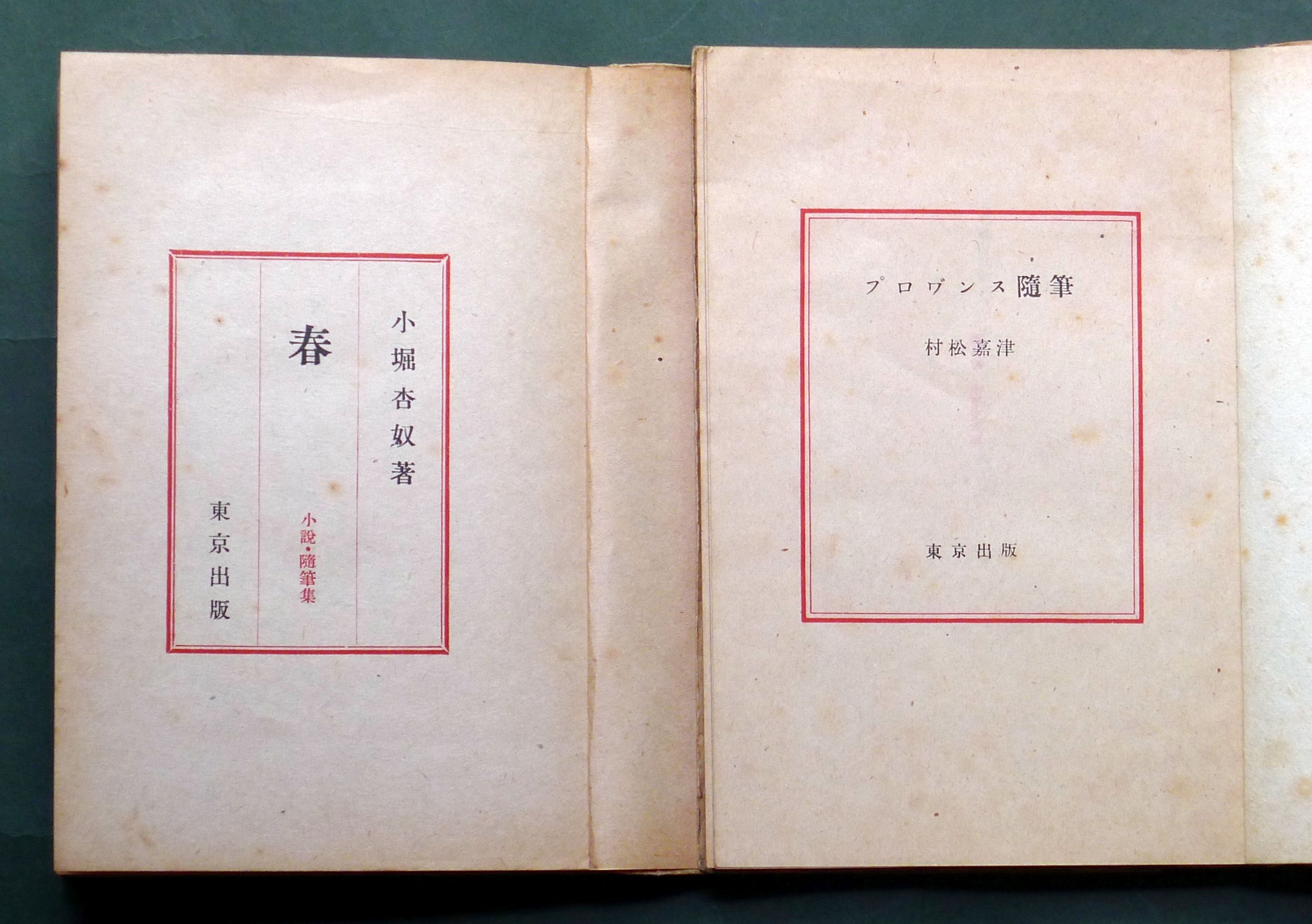
���x�Ǔz�̏����E���M�W�s�t�t�i�����o�ŁA1947�N4��20���j�Ƒ����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�i���A1947�N8��20���j�̕\���k�ǂ�����\���G�͖؉��ۑ��Y�̎�ɂȂ�l�i���j�Ɓs�t�t�Ɓs�v��ヷ���X笕M�t�̖{���i�E�j
�����o�ł͏��x�Ǔz�⑺���ÒÂ̖{�̂ق��ɁA�g�������ɂƂ��Ă���߂ďd�v�ȓ���̎��W�A���Ȃ킿���e���O�Y�́s���ނ��肠�t�i1947�N8��20���j�Ɓs���l���ւ炸�t�i���j���o���Ă���B�g���͓����������ӂ肩����B�u�����ÒÁw�v��ヷ���X���M�x���o�ł��ꂽ�̂́A���a��\��N������\��k�}�}�l���ł���B���������ɋ߂��������҂̂��̖{���A�ǂ��������@�Ŏ�ɓ���A�����Ď��͓ǂ̂��낤���B���܋L�������ǂ��Ă݂�ƁA���a��\�O�N���I��߂����낾�Ǝv���B���͏��p�œ����o�Ŋ�����ЂɊW����m�l�������˂��B���̂�����ɁA�ǂ�ł��ǂ݂������̂����������A�O�������čs���Ƃ���ꂽ�B�r��ł����A���������ς܂ꂽ�ԕi���炵���{�̒�����A�O���̂������{��I�B����́A�w�v��ヷ���X���M�x�ł���A���̓���́A���e���O�Y���W�w���ނ��肠�x�Ɓw���l���ւ炸�x�ł������B���͋��R���̂Ƃ����e���Əo�������B�����āA���_�̂��܂�Ȃ����̎����_�͂��̓���̋L�O��I��i�ɑN��ȏՌ����������Ƃ�����B�������ʂ̈���A�����ÒẤw�v��ヷ���X���M�x�́A���̓��̂̋Q�����������������߂Ă��ꂽ�̂ł���B�v�i�q�w�v��ヷ���X���M�x�̂��Ɓr�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��l�`��܃y�[�W�j�B�����ǂނƁA�g���͂��̂Ƃ����łɏo�Ă������x�́s�t�t����ɂ��Ă��Ȃ��悤���B���āA�s�t�t�̏��x�Ǔz�i�����A39�j�̕��͂́A�X�仂ӂ��̔ӔN�̑O�f������͉����A�ނ��둺���ÒÂɋ߂��Ɗ�������B�q�b���̘b�r�ɂ���������߂�����i�Ȃ��A�����͐V���ɉ��߂��j�B
�@�����͂ӂƂ���������A�b���ŐH�ׂ���T���_�̎����v�Џo�����B
�@�傫�Ȑ��˕��̔��ɁA�T���_���P�A�|�R�����̊����ɓ���A���A�Ӟ��A���͐h�q���Ŗ��t������B
�@�������āA�ʂɂ悭��āA������A�X�����T���_�̗t�����āA�ؐ��̑傫�ȍ��ƃt�H�[�N�ŁA�[���ɘa�ւĐH�ׂ�̂ł���B
�@���̒��ɂ��ŗ��̗�����鎖�������B
�@�ؗt�͏o���邾�����C��������D���̂ŁA��Œ�₤�ɂȂĂ��j���ŏo�����������W���ɃT���_�����A�����ԍ��E�ɂ����Ă�U��Ȃ���[���ɐ��C���Ƃ�B
�@���x�b���̘J���ҊX�ɂ�̂ŁA�[���ɂȂ�ƕ��X�̑����烀�c�V���E�����˂��o���āA����ɂ������Ă�B
�@�j�̐l���䏊����`�ӏꍇ�A�N�ɂł��o����ȒP�Ȏ��Ȃ̂ŁA��Ԃ������炳���炵���B
�@���鎞�t�I�[���E�x���W�G�[���w�s����A�������[�̍��Ԃɂ�鐡���̒��ŁA�A�p�[�g�̏�ʂ�������������B
�@�Z�c�g�ŏo�����A�p�[�g�̑�����A�������l�̕����������q�������g��o���āA�ߋ�̂₤�ɏ������T���_���Ă�ɐU��B
�@�ƂĂ��������o�Ă�āA�����l�͊F���Ŏ���������Ă�B�i���x�Ǔz�s�t�t�A���`���y�[�W�j
�����͂������̂́A���x�ɂ͂��킢���������A�����̕��͕͂��O��Ă���B�s�v��ヷ���X笕M�t�`���̈�сA�q�ɂ�ɂ��r�̃n�C���C�g���������i�����͐V���ɁA�X�i���̎��_�j�͊����ɉ��߁A��̎��_�₭�̎��_�͂��Ȃ�J�i�ɕς����j�B
�@�ɂ�ɂ���p��ł��L���ȃv��ヷ���X�����̓A�C�I���[���B����͂��̒n���̖L���ȃI���[�����Đ��ɂ����\�Ȍ�y���ƂȂ�B����Ă̓��A������������R�g�R�g�Ƃ��Ӊ���������ɑ����̂ŁA���̂��������Ɣ����Č���ƘV�X�������l�̂��̂̒��ɓ��_�l�̂��̂��ȂČ����ɝȂ��Ă��B�����̓A�C�I���[�����悤�Ƃ��ӂ̂ł���B�킽�����ɂ������Œ��ՁA�Ƒ�ē��_�����炤�Ƃ��������ւāA�u�����Ƃ��M���͍���a�C�ł͂Ȃ��ł����ˁv�Ƃ��ӁB�q�ꂽ�҂��G��ƃA�C�I���[�͕���Ă��܂ďo���Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��ӂ̂ł���B�u����͐̂̔n���C�����Ƃ��Ƃ���ł�������ǁA�����낳�����ӌ��Г`�ւł�����ˁc�c�{���ɐ̎҂͔n���Ȃ�ł���v�Ɣ����Ȃ�����^�����B�������ăA�C�I���[�̍��������ւČ����B��Ô��̒��Ɉ�l�����ؕЂ̊��łɂ�ɂ�������B����ɂ��̒n���Ő��p����闱��̉�����A�咆���ƎO�������B�傫���͕̂��m�y�[���n�A���ʂ͎̂q�m�t�C�X�n�A�������̂͐���m�T���e�X�v���n�ƌĂ�ŎO�ʈ�̂ɋ[����̂��Ƃ��ӁB������R�g�R�g�ӂ��đ�̍ӂ����痑�̉��������A���ꂩ�珙�X�ɓH�X�ƃI���[���������ւȂ���₦�������܂͂��Ă���ɃR�b�e���Ɨ���グ�čs���B�����������ꂪ�ł炸�ɗ����Ă��܂ӁB�����b���ɂ�ɂ�����̃}�C���l�[�Y�Ȃ̂����A�����|����ꂸ�ɖ������œW���čs���̂ŁA���܂Ђɂ͖_�������Ȃ��Ȃ���ł��ȂāA�R�̂₤�ɐ�����B�M�[�����̍��̌Â������ׂ������́A�}�C���l�[�Y�̎��s�ɂ������_��I�Ȃ��̂𗍂߂ĕs�������A�O�ʈ�̂ɌĂт�����Ƃ��낪���ł͂Ȃ����B���ꂳ�֏o����Ό�͂��₪�����A�l�Q�A�K�A�����̋��A�������A��ł����̂��R��M�ɐ��ċ�����B�l�l�͍D�݂̂��̂ɃA�C�I���[�����ĐH�ׂ�̂��B�ɂ�ɂ��̏L���͖ܘ_�җ��A�H�n�߂�ΑS�������Ȃ��ȂāA��������A�����̋ɒv�ł���B�v��ヷ���X�̐l�l�͂�����ς��H�ׂĂ���A���L�������ƂĔZ���R�[�q�[��ۂ݁A��₵��������������B���ꂩ������̒��֎q�ɋ����z������ď����̒��Q�m�V�G�X�g�n�ɓ���B�앧�̑ӑĂȘa�₩�ȉĂ̏��͎ƎƃA�C�I���[�Ɍq�����B�i�����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�A�Z�`���y�[�W�j
�����́q�ɂ�ɂ��r���Ȃ��Ȃ��ƈ������̂́A�ق��ł��Ȃ��B�g�����O�f�̐��z�q�w�v��ヷ���X���M�x�̂��Ɓr�ň��p���v�������̌������A���܂�ɂ��f���炵������ł����i���j�B�g���̊Ȃɂ��ėv�����͂��A����ɗ�炸�������B�ǎ҂́A�g���̐��z�Ƒ����̌������Ė��ǂ���Ƃ��B�Ȃ��A���҂�������������s�V�� �v�����@���X笕M�t�i�哌�o�ŎЁA1970�N3��15���j�̖{���́A�c�O�Ȃ��ƂɁA�����̊Ȍ��Ȃ��玠�����ӂ�鋫�n����͈����ނ������̂ƌ�����Ȃ��B��f���Ɠ����ӏ����A�i���̐�ڂ܂ň����i�����łЂƂ������i���́A�V�łł́\�\�����ɉ��M��������̂́\�\�l�ɕ������Ă���j�B
�@�ɂ�ɂ���p��ł��L���ȃv�����@���X�����̓A�C�I���[�ŁA����͂��̒n���̖L���ȃI���[�������ȂāA���ɂ����\�Ȍ�y���ƂȂ�B����Ă̓��A�䏊����R�g�R�m�Ƃ��Ӊ���������ɑ����̂ōs�Č���ƁA�V�X���[���̂₤�Ȋ�m����n�̒����A�ׂ��Z���_�A�܂菬���Ȃ��肱�m�A�A�A�A�n�̂₤�Ȃ��̂ł�����ɝȂ��Ă��B���̂��������Ɛu���ƁA�����̓A�C�I���[�����̂��Ƃ��ӁB�킽�����ɂ������Ē��ՁA�Ƒ�Ă��̂��肱�m�A�A�A�A�n�����炤�Ƃ���������Ăĉ��ցA�u������͍���a�C�ł͂Ȃ��ł����ˁv�Ɛu���B�g���q�ꂽ�����G��ƃA�C�I���[�́u�����āv���܂ďo���Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��ӂ̂ł���B�u�̂̔n�������l�ւ��Ƃ���ł�������ǁA�����낳�����ӌ��Г`�ւł�����ˁc�c�{���ɐ̎҂͔n���Ȃ�ł���v�Ɣ����Ȃ�����^���炵���B���ꂩ��A�C�I���[�̍��������ւČ��ꂽ�B�i�����A�Z�`���y�[�W�j
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�����ÒÁs�v��ヷ���X笕M�t�̖ڎ����f���邱�ƂŁA�����̓��e�Љ�ɑウ��B
��
�ɂ�ɂ�
��e
�ݑ�
�����ނ�i�G�X�J���S�[�ƃ��}�\���j
���i�����k�T�t�����ɂ��ďڂ����q�ׂ���߂�����l
�A�}���h
�s�X�^�b�V��
���̗ь�
�����m�e�C���[���n
��
��ؗ���
�m�G��
�Ö�
�I���[��
��������
���{�̗���
�v��ヷ���X���w�ƒn���C����
�v��ヷ���X�n����`�m���W�I�i���Y���n
��
�����́q��r���u�X�Ɏ����̈�Ԃ̊�т́A���̏������̑��c���Y�搶�̌�M�ɐ��鑐�Ԃ̐}���Ȃď���ꂽ���Ƃł���B�����ԕ���Â��Ȃ���A�Ђɐe�t������̒Z�������g�̕s�K�́A����Ɉ˂Ĕ��~�͂ꂽ�S�n�ł���B�^�����ɂ��̊�т������ꂽ��⑰�̌�e�Ɍ������\�グ��B�v�i�����A����y�[�W�j�ƌ���ł���B���O�\�ۑ��Y�\�ÒÂƘA�Ȃ�n���Ƃ��āA�����Ƃ��̒�����{�e�ɓo�ꂳ���邱�Ƃɕs�s���͂Ȃ��͂����B
�Ȃ��A�s�v��ヷ���X笕M�t�͏����ȍ~�A�s�V�� �v�����@���X笕M�t�i�哌�o�ŎЁA1970�N3��15���j�A�s�V���� �v�����@���X笕M�t�i���A2004�N6��30���j�Ɣł�ς�������ς��Ċ��s����Ă��邪�A���Ԃ��Ȃ����ނ̖R���������ɏo���������ł����킢�[��������Ƃ���̂́A�����ۛ��ڂ��낤���B���������{�����A�u�k�Ђ̊w�p���ɂɂł������āA�i���L���ǂ݂��ꂽ�炢���̂ɁB����ɂ́A�l���c���F�̏������낵���A�W���P�b�g�ɂ͏����̖؉��ۑ��Y�̕\���G���g���āA�t�^�ɂ́i�����I�O�̎����Ƃ��āj�Ċ��̌_�@�Ƃ��Ȃ�����㋆��Y�Ƌg�����́q�������@�r�̕��͂̍Ę^���A���ЁB
�s�V�� �v�����@���X笕M�t��34�N��Ɋ��s���ꂽ�s�V���� �v�����@���X笕M�t�����A�k�V���Łl�́k�V�Łl�̑�����V���ɂ��������̔łł͂Ȃ��A�Ƃ����̂��o�ŎЂ̐G�ꍞ�݂��B���Ȃ킿�A�{���ŏI�y�[�W�̑Ό��y�[�W�ɒNjL���ꂽ�q憁k�}�}�l�W��L�r�i�����A�k��Z���y�[�W�l�j��
�{���́A���a�l�\�ܔN�O���ɕ��Ђ�芧�s�������̂ł��B���̂��ѐV���ł����s����ɂ�����A�{�����̌�A��������A�܂����Ō��Ԃ̒��҂ɂ��X�P�b�`��u�K���o���w���ւ�I�[�o�[�j���̒��v�A�u�K���o�����i�v�͊������܂����B
�Ȃ��A�{���̌��݂̒��쌠�҂̘A���悪�s���Ȃ��߁A���O�ɒ��쌠�҂ɕ��ł��܂���ł����B���쌠�҂̕��A�܂��͂��S����̂�����͕��Ђ܂Ō��������B
�Ƃ���B�������̌���������A��A�͒�������Ă��Ȃ��B�䂦�ɁA�k�V���Łl���P�{���Ɛ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������悤�B�`���́q���r�̒��قǂɏo�Ă���u���j�I������Ёv�i�����͐V���ɉ��߂��j�́u���j�I�������Ёv�ɒ�����Ă��Ȃ��B�u憏W��L�v�i�u憁v�̓S�`�������I�j���ɂ����A������͒ɂ��ǂ���̘b�ł͂Ȃ��B�������̂��ƁA�k�V���Łl�́k�V�Łl�̊O����ς��������Ł\�\���ۂɋ@�B�����W���P�b�g���ɉ��߁A���҂����������\���E���Ԃ��E�{���̑�����V���ɂ��Ă���\�\�A���҂��̐l�ł��邱�ƂɊӂ݂āA�{���́k�V�Łl�̊��ň���ɂ��Ŗʂ����̂܂ܕ��ň���ōČ��m���v�����g�n�����A�Ƃł������ق����悩�����̂ł͂Ȃ����B�ȏ�͖{���������邪�䂦�̋ꌾ�����A������茾���Ă��Ă����������Ȃ��B�k�V�Łl�̑ѕ��i�����͉��g�݁j�́A�̂ӂ��������ǂɒl����̂ŁA���p���Č������悤�B�����ł��A�����͐V���ɉ��߂��B
�y�\�P���z
�������ȂĐl�ԍō��̌|�p�̈�Ƃ����u���A���T���@�����̊i���҂͈����Č����A
��b�͕������B�l�Ԃ͐H���B�ЂƂ�G�X�v������l�݂̂����o��m��
��V���������̔����͐����̔��������l�ނ̍K���Ɏ����鏊���傫���v
�G�X�v�����钘�҂̖��o�N�w�͔������^�̓k�ɑ���̋�����^�����E�̐H�ʂ��m��ʃv�����@���X�����ɖ��f����鎖�ł��낤�B
�y�\�S���z
�z��������앧�v�����@���X�n���͊D�F�̖k���b���Ƃ͎���ق�Ɠ��̕������`�����Ă���B
�ؕ����N�A�v�����@���X���w�ɐ��ʂ��钘�҂��A��O�E���̕ϖe���䂭�v�����@���X�̎�X�������A���w���Љ�A���o��������̐��M�͓ǂ�ł܂��Ƃɖ������B�������Í������Ɍ݂�w���Ə����Ȋi���̍������͂́A�Ǐ��q�𖣗����[����^�����ɂ͂����Ȃ��B
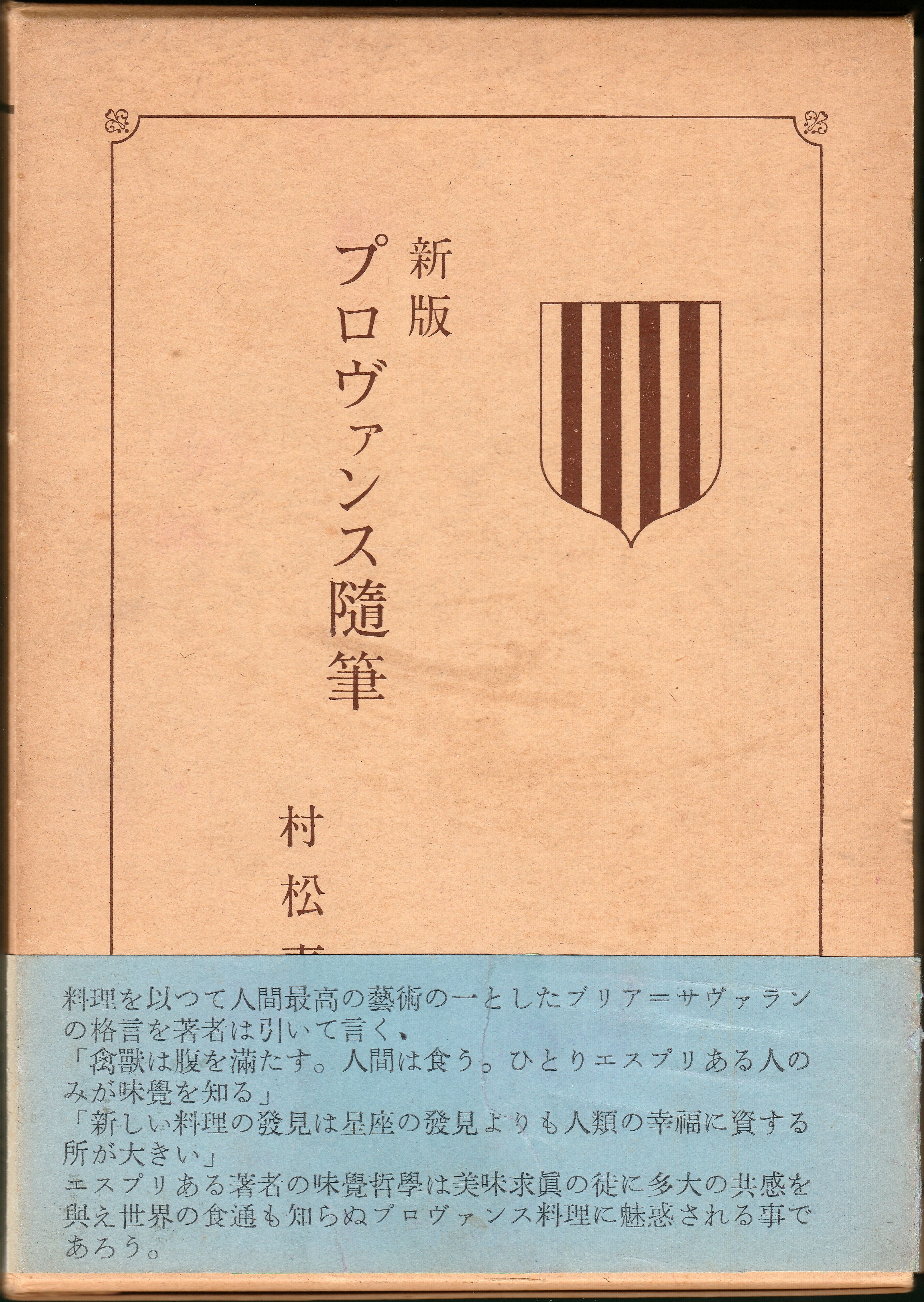 �@
�@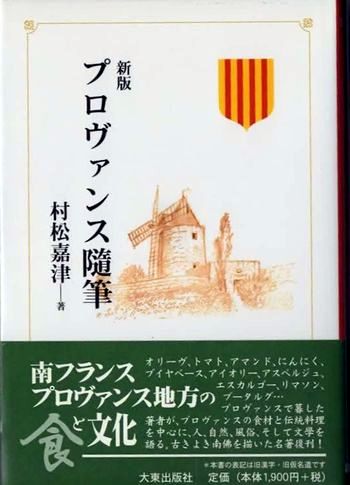
�����ÒÁs�V�� �v�����@���X笕M�t�i�哌�o�ŎЁA1970�N3��15���j�̔��i���j�Ɠ��s�V���� �v�����@���X笕M�t�i���A2004�N6��30���j�̃W���P�b�g�i�E�j�@�k�V���Łl�ł́A��������k�V�Łl�̖��P������爟������ɁA��������������ł��畽�łɕς���Ă���B�Ȃ��A���ƃW���P�b�g�Ɍ������͂̓v�����@���X���Ƃ̂���ł���B
�ѓN�v����̃u���O�sdaily-sumus2�t�͓������ǂ��Ă��邪�A�u�̋i���X�A���a�F���X���O���\�����������ĕX����Ƃ����j���[�X�����������ɏo�Ă��ċ����B�z�[���y�[�W�Ŕ��\�����Ƃ̂��ƂŁA�m���߂Ă݂�ƁA�Ȃ�قǂ����f������Ă���v�Ǝn�܂��q�A���a�F���X�@�X�̂��m�点�r�i2019�N2��19���f�ځj�͎������������B�g�����̓��L�ɓo�ꂷ�邱�̋i���X��K�˂邱�Ƃ́A���ɂƂ��ďh�肾��������ł���B�ɍs���̂́A�ꂪ�܂��O�o�ł���25�N�قǑO�A��l�Ő��ɏ��w�ɍs���Ĉȗ����Ǝv���i���1996�N��68�ŖS���Ȃ����j�B�Ƃ����ƁA���̂��Ƃ�z���o���đ��������ɂ����ꏊ���������A�A���a�F���X���X���܂�����ƂȂ�s���˂Ȃ�܂��B�����āA�S��̏ˌ�������3��8���\�\�т��sARE�t��6���i1996�N�j�̓��W�k�F�V���O�Ƃ����j�l�̂��߂ɃA���a�F���X�̊O�ς��B�e�����̂��A��������̔N��3��8���������Ƃ����\�\�A�J������S���ŃA���a�F���X�T�K�Ƃ͂Ȃ����B�܂��ŏ��ɁA�g�����́q�f�ЁE���L���r�����Ă������B
�k���a��\�l�N�l�܌�����@�����@�Ǝl�c���A�̍ˈ��B�̉Ƃ֍s���B�ނ̕��͂��Ȑl�������B�ՏI�̏��ŁA�ˈ�ɖ����Ƃɂ��Ȃ��Ŏd�������Ă�Ɖ]�����Ƃ����B�����S�������B�ނ͐V�������l���o���A�Y��ł���B�O�l�Ő֏o��B�R��������v���o���B�V���֊O�o�̎��A�悭�O�l�ŗV��A���l������H������B���܂ɂ͊Â����̉��̎O�g��ŐH�������������̂��B�A���W�k�}�}�l�F���X�ŃR�[�q�[�B�i�s�g�������W�k���㎍����14�l�t�A�v���ЁA1968�A���l�y�[�W�j
����������B�@�̔����͎R�������B�u�k���a�\�l�N�l�\�ꌎ�\�O���@�ߌ�A�{��������֕����̌��ōs���B�R�������̉ƂɊ�����B�������[���؏��̎��^�����͂��܂�B�O���ɗ������B�A��͂܂��V�A�����Y�ƈꏏ�ɂȂ�A�Ό����́u���v�ɓ����āA�R�[�q�[�ƃp����H�ׂ��B�߂��܂��V�͂��Ԃ����ƈɓ��֗V�тɍs���ƌ����B�b�퍇�i�̂��Ԃ����͗�������ɓ��c���邻�����v�i�s���܂�͂����L�t�A����R�c�A1990�A�����`����y�[�W�j�B�A�̎l�m����n�͓����E�����̒n���B�l�c�؉w�͋����d�S������̉w�i������l�؈꒚��1��1���j�B�B�̍ˈ�͕���ˈ�B�ߑ��̕���p�ꂳ��ɂ��A�u�吳8�N6���A�����͖{���̐��܂�ł��B���Ƌg������Ƃ̂��t���������ǂ̂悤�Ɏn�܂����̂��A���͕����Ă��܂��A���܂ꂽ�N�Əꏊ���߂������̂ŁA�R���ňӋC�����������̂ł��傤���B�g�����S���Ȃ�܂ŁA���Ƃ͐e�F�Ƃ��Ă��t�������������悤�ł��B���͏��������c���Ă��Ȃ��̂ŁA���ƂȂ��Ă͉������ׂ悤������܂���v�B�u���̑c���k�g�����Ɍ�����ˈ�̕��l�͏��a24�N4��17���ɖS���Ȃ�܂����B�����A���͎l�c�ŃZ�����C�h�̎d�������Ă��܂����B���L�͂��̎��A��������ƈꏏ�ɕ����Ԃ߂ɗ���ꂽ���̂��Ƃ�������Ă���̂ł��傤�B��������́A�R����������̎��ł��B���̐�F�̈�l���Ǝv���܂����A���a14�N11��13���́u���܂�����L�v�ɎR����������ƋL����Ă���̂ŁA�g������Ƃ͌Â�����̗F�l�����������m��܂���B���̕��ƎR������́A�g�����S���Ȃ���܂Őe�������t���������Ă��܂����B���D���������悤�ŁA�悭�O�l�W�܂��ăA���a�F���X�֍s������A�H���������肵�Ċy����ł��܂����B�g�����S���Ȃ�����A�c���ꂽ���ƎR���������ԋC�������Ă����̂��v���o���܂��B���̎R��������S���Ȃ��܂����v�i�q���̐�F�A�g�����r�ɂ��j�B
���̓A���a�F���X�̌��[�߂Ƃ������ڂŁA�l�����I�Ԃ�ɐ�K�ꂽ�i2004�N�ɉX����������Ƃ����A�ɂ͑��������Ȃ������j�B�����āu����Ƃ��Ă̐v�Ƃ������S���������B�A��Ă����������̏o�T�ׂ�ƁA�����r�Y�q�g�����������L�r�̖����ɂ܂�����Ȃ�����͍ڂ��Ă����B�����Ƃ��u����v�͐ł͂Ȃ��A��ȋ���n�����g���̐��n�ł���{�����������B
�@�z�q�v�l�ɂ��ƁA�g������͎O�\�N�̌����������A�܂ŗ��Ă��z�q�v�l���ċ��̂������ɗ������Ƃ͈�x���Ȃ��A�Ƃ����B����قǑ�ɂ����c�N����̐���ւ̎v���͈⒘�w���܂�͂����L�x�ɋÏk���Ă���B�N���w���܂�͂����L�x���f��ɂ��Ă݂悤�Ƃ����A�ӗ~����ē͂��Ȃ����B�u���N�����v�u�ߏ��s�v�̑�p�̌�F���ēł͑ʖڂ������A�ȂǂƎv���v�����Ă���B�i�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�A�v���ЁA1991�A��ܘZ�y�[�W�j
 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�i������j�i���X�A���a�F���X�E�S�i�@���E�����@���E�Ŕ@���E��K�@���E�����@���E�`�[
�����A���a�F���X��K�˂��̂́A2019�N3��8���i���j���j��15������B�X�O�̕����ɂ͐Ȃ��̂�҂l�����l����ł���B�h�A�̓\�莆�Ɂu�t���[�c�|���`�@�~�_�b�`�R�[�q�[�@�~�A�C�X�e�B�@�I�����܂����v�Ƃ���i�s�����Ƃ��̓P�[�L�ނ��i�ꂾ�����̂ŁA��Ԃ̗m�َq�E�A���a�F���X�ɂ͂�����Ȃ��������A�ĉَq�́u���c�u�b�V�F�v��y�Y�ɔ������Ƃ��ł����j�B���̍��̓\�莆�͕X�̂��m�点�B�X�̑O�̏��H��l�͎Ԃ��s�������B�e�[�u���ɂ́A1981�N2��3���ɗ��X��������ƁE��ˎ����̃T�C������F���i�R�s�[�j�B���̓��A���̂́A��O�̃_�b�`�R�[�q�[�i620�~�j�\�\�l�q����ɂ��U���ɂȂ����ƃX�^�C���\�\���i�� �A���a�F���X �m�����E�n�r�Ɂu�������������̂ŃA�C�X�R�[�q�[���I�[�_�[����ƁA�R�R�͂�����ƒ��l�N�^�C����߂��V�E�F�[�^�[���A�X�̓������O���X�ɂ��̏������𒍂��ł����B�ꖡ���V���L�b�ƌ������A���Ɏ|���A�C�X�R�[�q�[���B�����āA���ɗ��̂͒�Ԃ̗m�َq�E�A���a�F���X�B�o�^�[�N���[���̕����Y�����^�̃��[���P�[�L�ŁA����𖡂키���тɁA�ӂƎq���̍��̃N���X�}�X�̌��i���v��������ł���B�k�c�c�l�l�����������A�C�X�R�[�q�[���T���g�X�𐅏o���������@�̂��̂ŁA����͑��Ƀ_�b�`�R�[�q�[�ƌĂ�Ă���i���j���[�ɂ́u�~�_�b�`�R�[�q�[�v�Ƃ����A���̓X�Ɠ��̂��̂�����j�v�i�s�����ӂ��̋i���X�t�A���}�ЁA2010�N5��17���A����`��O�Z�y�[�W�j�Ƃ���\�\�Ɖ��̃~���N�e�B�i550�~�j�A�����ă`���R���[�g�p�t�F�i770�~�j�B�R�[�q�[�D���̋g�����́A�����Ŕ~�_�b�`�R�[�q�[���_�b�`�R�[�q�[�ł����̂ł͂Ȃ����B����A�E�A���a�F���X�I�@73�N�ԁA����J���܂ł����B�����āA�����������܁B
��
�ѓN�v���O�f�u���O�ň��p���Ă���F�V���O�́q�G��r�́A�F�V���O�E��ĉ��E�O�����T�E��q�G�ق��s�F�V���O�@�G�̂���ꐶ�k�Ƃ�ڂ̖{�l�t�i�V���ЁA2007�N10��28���j�́q�������́u�C�܂�����p�فv����I�r�ɂ��o�ꂷ�閼�сB�A���a�F���X�̋��͂ĐV���Ёi�s�|�p�V���t�ҏW���H�j���B�肨�낵���ɈႢ�Ȃ��ʐ^�́A���X�̓������ʂ����ł����ׂȈꖇ�ƂȂ����i�����A�k��O�y�[�W�l�j�B�L���v�V�����ɂ́u�I�����W�ʂ�̋i���X�u�A���a�F���X�v�\�\�т����̏F�V���O�������ΖK�ꂽ�X���ɂ́A�X�F�Y�A���C����̍�i���B�ǖʂ�2�_�͐X�F�Y�̍�i�B�����q�e���X�̏��r�@1953�@���ʁA�J�����@�X�@44.8�~37.2cm�v�i���O�j�Ƃ���B
�k2020�N10��31���NjL�l
�X�܂�݁s�����Ђ����ē��k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A2010�N4��10���j�́q�� �̂Ȃ���̂��܂����̓X�r�ɃA���a�F���X���o�Ă���B�u�I�����W�ʂ�́u�A���a�F���X�v�֍s���B�`�@�@�ʂ�Ȃǂ�������e�[�}�p�[�N�ɂȂ��Ă��܂����̂ɁA��������͑S�R�ς���Ă��Ȃ��B���a�O�\�N��̓��{�l�͏����������̂��ȂƎv�����Ԃ�̖̃e�[�u���ƈ֎q�B�O�K�֏オ��N���[���\�[�_�𗊂ނƁA�����V���c�ɒ��l�N�^�C�̃x�e�����E�F�C�^�[���Ƃ��Ƃ��オ���Ă���B�u�O�K�ł��߂�ǂ��ˁv�Ƃ����Ɓu�l�K�Ƃ���ꂿ�።��܂����ˁv�Ƃ��������B�u����A�����l�K������́v�Ƌ����ƁA�u����܂����v�ƃj���b�Ƃ���B���̑����̂܂��������������Ȃ̂��B�����������݂����ȒႢ���A���̃V�F�[�h�̊Ԃ��牺���̂����ƁA�l�͎Ԃ������q���悹�Ă���Ă���B�u��������ʐ^���|�����C�h�ŎB���āA�I�_�Ŕ���̂������ɂ�����v�Ɠ��s�̖����v�����B�v�i�����A��l���y�[�W�j�B���Ȃ݂ɕX�ԍۂ̃A���a�F���X�ւ́A�������Z���Ƃ��T�����q����A��čs�������A�p�t�F�ƍg����������������ŁA�s�����Ђ����ē��t�Œn�}�����������҂̖��E�쌴���q����̂悤�ȟ������v�����͕������Ƃ��ł��Ȃ������B
�i�����Ƌg�����֘A�̎�����T�����Ă���ƁA�������т�P�s�{�����^�̕��͂�V���ɔ�������̂������ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�ƌ��i�f��30�N�Ƃ��Ȃ�ƁA�ނ��돑�ȗނɓ�����������j�B����ł��A�����̏����W�͌������Ȃ��B�I�[�N�V�����ɏo�i�����ƃ��[�����͂��悤�ɂȂ��Ă��邪�A�Ï��X�̏o�i�͍��q�̂�C���^�[�l�b�g��̃f�[�^���u���E�W���O����K�v������B����A�������[�h�F�u�g�����v�Łs���{�̌Ö{���t�ׂ��Ƃ���A�ޗǁE����̃L�g�����ɂ��A���ҁF�u�O�썲���Y�E�c�����ȁE�֓�����E�g�������v�ŁA�s���{�̐l�t�i��11��1�`3�E6�E9�����j���o�i���Ă����B���̒m�邩����A�g�����O�썲���Y�̎�ɂ���s���{�̐l�t�ɏ��������Ƃ͂Ȃ��͂����B����͐V�����̎����ł���\���������B�G���́u��35�A5���^�����P�@*���v�ŁA���i��\1,750�B�����ɒ������Ă��D�������̂����i�̂��ɒ��������j�A�ꍏ�������������ƈ��A5�����{�A�i�c���̍�������}���فE�V�قŃo�b�N�i���o�[�i���{�ł͂Ȃ��A35�~���̃}�C�N���t�B�����j���{�������B�f�W�^���̃r�����[���g���Č���̂͏��߂Ă������̂ŁA����Ɏ�Ԃǂ�B�ē��W�ɋ����Ȃ���A1960�i���a35�j�N9�����ɍڂ��Ă����g�����̕��͂̃R�s�[���Ƃ����B�����́A�\�����܂߂đS68�y�[�W�B����4���ȏ��28�y�[�W���u崉Ԕ�]�W�v�i�ڎ��̋L�ځj�ɓ��ĂĂ���B����A�{���y�[�W�ł̂��̃^�C�g���́q�̏W�u崉ԁv�]�r�B�ڎ��̋L�ڂ͓����A���Ȃ킿���i�K�̃^�C�g���ŁA�˗��������e�����ۂɏW�܂������_�ŐV���ɕt���i�Ȃ����j���^�C�g�����A�q�̏W�u崉ԁv�]�r�������̂ł͂Ȃ����B����̋g���̕��͂́A���̂Ȃ��̈�тł���B�v15�{�̕]�̎��M�Җ��ƕW��������悤�B�T�䏟��Y�q崉Ԓf�z�r�A�ۓc�^�d�Y�q崉ԓnj㊴�r�A�֓���Y�q�E�J�̉́\�\�����̏W�w崉ԁx�r�A����M��q�ǓƂ̐S�ە��i�\�\�����̏W�u崉ԁv�r�A�ΐ�M�v�q�N�X����y�V�~�Y���r�A�x������q�̏W�u崉ԁv�̂��Ɓr�A�������b�q�q崉ԁr��r�A�R��ɓ���q�����̏W��崉ԇ��Ɋr�A�唺���q�q���l�̜ԚL�r�A�R���q�b�q�q�̏W�u崉ԁv�Ɂr�A�g�����q������̉̏W�u崉ԁv�̂��Ɓr�A�Β˗F��q�̏W�u崉ԁv�r�k�i�o�厏�u�߁v�܌������]�ځj�l�A�v�ۓc�����q�ЂƂ�̉��r�k�i�u�}���V���v���]�ځj�l�A�c�����ȁq�߂�������崉ԁr�A�ē�����q�����Ƃ�����������̑ԓx�r�B�����āA�������̏Љ�L���q�̏W�u崉ԁv�r�k�i�u����{�V���v���]�ځj�l�ł���B�Ȃɂ͂Ƃ�����A�g�����̖����s�U����ǂ�ł݂悤�B
 �@
�@
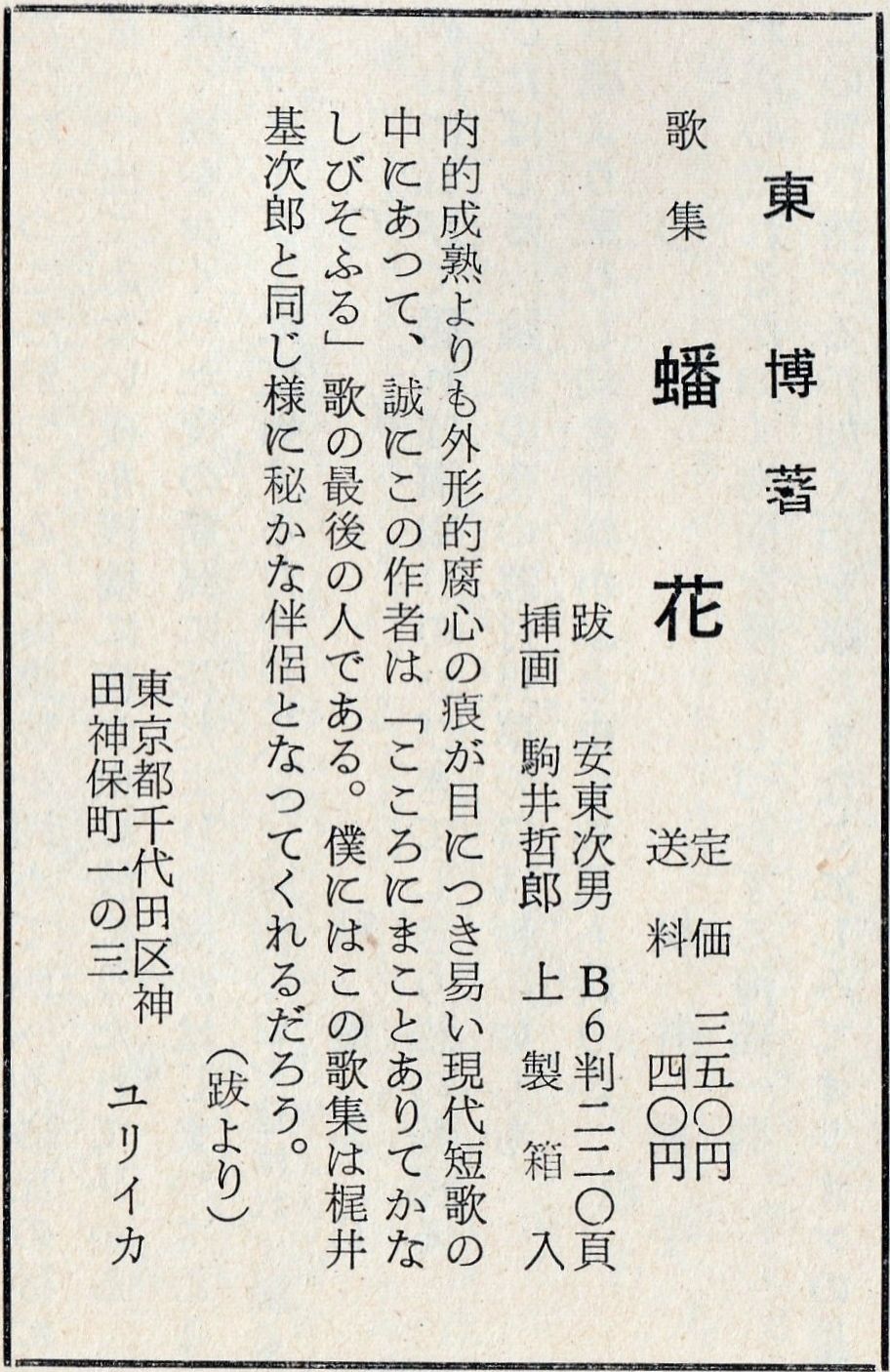
�s���{�̐l�t1960�N9�����̕\���k��͓����u���l�i���j�Ɠ����f�ڂ̓����̏W�s崉ԁt�o�ōL���i�E�j
������̉̏W�u崉ԁv�̂��Ɓb�g����
�@������ܔN�O�A�ڂ��̎��W�u�Õ��v�ɂ��āA�����S�̂��������z�������Ă��ꂽ�B����ǂ́A�ڂ����u崉ԁv�̊��z���������ƂɂȂ��B��]���܂������Ƃ͂ƂĂ��ł��Ȃ��̂ŁA�v�����܂܂��ׂ̂悤�B������̓�\�N�̐��_�̗��j�ł����邱�̏����̏W�u崉ԁv�͈������W�Ƃ����̂��ӂ��킵���B�^�͒Z�̂ł��邪�A�������ʂ������Ă݂�����S���l�Z����ϐĂ̂Ƃꂽ���������҉̂Ƃ��ēǂނׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�ʁm����n�Ȃ��ė������̂ɂ��т�����킪��N�̓��͌X�m�����ԁn�����@����Ƃʂ������ł݂Ă��A�A�����M�h�̎����ϓ��I�ȉ̕����牓���B�ʂ̂��Ƃʼn]�������ւ�ϔO�I�ȉ̂Ɏv����B���������ɋ�X�����Ȃ��̂͐S�̉e�������ɗ���Ă��邩�炾�낤�B�ڂ������N���Ɋ���̂��������A�P���ȏ��i�̂�����߂Ȃ����B����Ō��z�I�Ȑ��E�����߂Ď��ֈڂ��̂����A������͂ނ��댶�z�����߂��A����̐����Ȑg�ӂ̃��A���e�B��S���I�ɑ����āA�݂݂����Ȃ��A�i���������A���������̂�����グ�Ă���B
�����̉ʂĂ̐S�̒f�ׂ������݂������ꂵ���_�p�m���n�݂̂���
�ӂ邳�Ƃɉ��R�������ė������ɂ��Ȃ����̎R
�ǂЂ߂Ă킪�����̐���V���ւΐS�ɐG���ԂЂƂȂ�
�@�ڂ������̒m�Ă���A���ׂĂɂ��т���������̐S�̉��ɁA�ϔY�̐l�A�����̎��l�̈�ʂ��M���Ă��ꂵ���B
�@�D���ȉ̂����������Ă݂�B���Ƃ̈��Ђ𑁁X�ɐ�グ�ăW���[���F���ɗ����ނ������@�����ɐ푈�̏W�����߂�������̎��M�A�ǎ��ɂ��ǂ낭�B�ǂ̉̂����Ă������������B�������Ȃ̐��_���U�炸�A�̌����ɂ���V���̎��l�ł��邱�Ƃ����Ă���B�i�����A�ܔ��y�[�W�j
�݂��̂��̂��͂ł��̂Ԃ̔E�ԗ��ɍ��߂�݂��̂��тƂ�
�ĂɌ����Ƃ萷��Ȃ��t�����̊��m����n�т̎��߂��ɂ���
�������̏��l�̂��̂�����m�܂Ȃ��Ёn�ɔR���Ă��܂����ɔZ������Ȃ��i�S�ϊω��j
���̂ӂ��ӓ~������Ȃ镨�v�Љ��������Ƃ��܂������
�V���m�炤����n�̏㓧�m���n���~���R�����ꂠ�܂��ւ��̊z�m�ʂ��n�ɓ͂���
�`���́u������ܔN�O�A�ڂ��̎��W�u�Õ��v�ɂ��āA�����S�̂����������z�������Ă��ꂽ�v�̂��A�ǂ��ɔ��\���ꂽ���Ƃ������͂Ȃ̂��킩��Ȃ��B�g�����O�썲���Y�ɏ��߂Ė{�i�I�Ɍ��y�����̂́q�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�i�s�Z�̖̂{�k��ꊪ�l�Z�̂̊ӏ܁t�A�}�����[�A1979�N10��20���j������A�{�e�̕M���������̂́A�����̕ҏS�l�ł������������Y�̐������A��肢�����������̏W�s崉ԁt�̔Ō��E���惆���C�J�Ў�̈ɒB���v�̐��������̂ł͂���܂����B����ɑz���������܂�������A���҂���g���ɉ̏W�������A�g��������ɗ�������A���҂���u崉Ԕ�]�W�v�Ɏ��M�̈˗����������A�Ƃ������ꂩ������Ȃ��B
 �@
�@
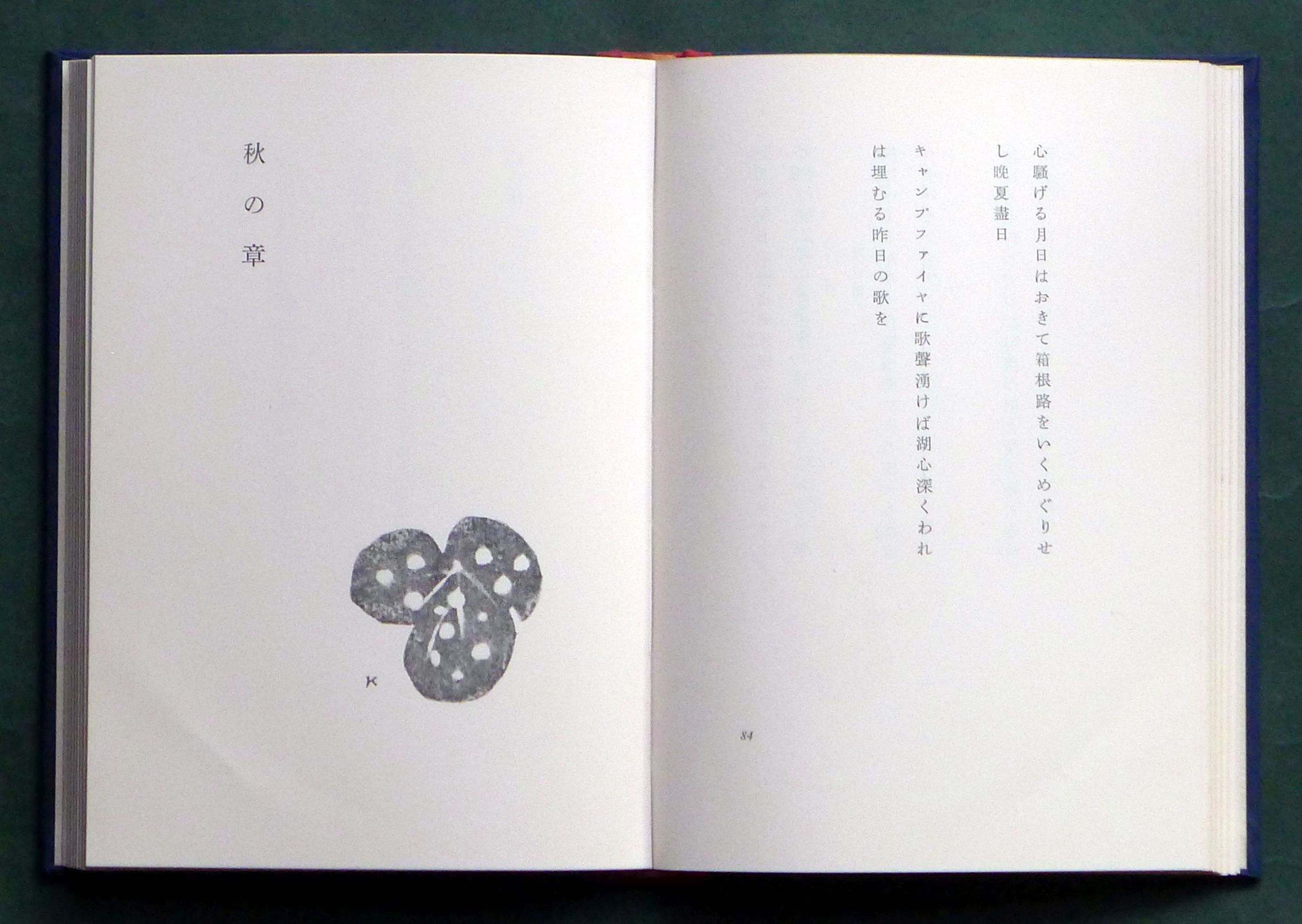
�����̏W�s崉ԁk���{�̐l�p���l�t�i���惆���C�J�A1959�N12��20���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�����k�}��F���N�Y�l�i�E�j�@�Ȃ��{���̑O���Ԃ��ɂ́A�y�������Łu�O���ɞ�^�A���^�����v�ƌ���E����E����������B
�����̏W�s崉ԁk���{�̐l�p���l�t�i���惆���C�J�A1959�N12��20���j�̎d�l�́A�ꔪ�Z�~��~�����[�g���E����y�[�W�E�㐻�p�w�p�\���i�w�͐ԁA���͌Q�̃N���X�j�E�@�B���B�ʒ��{���B�����҂̃N���W�b�g�͂Ȃ��B�q�ڎ��r���Ɂu�����a�\�ܔN�^�����a�O�\��N�^�l�Z��v�Ƃ���B�q��\�\�̏W�u崉ԁv�̂��Ɓr�͈������j�A�q�}��r6�_�i�{�����܂ށj�͋��N�Y�B���̎���W�s�����ǂ肦�t�i���惆���C�J�A1960�j�̃R���r�ł���B�g���́q�k���M�l�N���r�́u���a�O�\�ܔN�@���Z�Z�N �l�\��v�̍��Ɂu�H�A�������j�E���N�Y�̎���W�wCALENDRIER�x���B�v�i�s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�������_�ЁA1984�A��O��y�[�W�j�Ə����Ă���A���惆���C�J�̏o�Ŋ����ɂ͎x����ɂ��܂Ȃ������B���̏��惆���C�J�̖{�ɂ��Ēm�肽���Ȃ�A�c���x�s���惆���C�J�̖{�t�i�y�ЁA2009�N9��15���j�ɂ��̂�������ł���B
�@�k�p���\���́l�w�����łЂ炪�ԂƂ�����i������B�����w崉ԁx�i���a�O�l�N�A�}62�k�O��Łl�j�A�����ă~�V���I�w�v�����[���Ƃ����j�x�i���a�O�l�N�A��O�Łj�B�i�q�@�ׂȎ��W�Q�̒a���r�A�����A���y�[�W�j
�k�g�����̑����ɂȂ��s�v�����[���Ƃ����j�t�́A�������Ɂu�w�����łЂ炪�ԂƂ�����i�v�����A�Ȃ�Ƃ������Ƃ��낤�A�s崉ԁt�͏�f�ʐ^�̂��Ƃ��u�w���ԁm�A�n�łЂ�͌Q�m�A�A�n�v�ł͂Ȃ����B�����Ɍf����ꂽ2�_�̏��e�͖{�����i���������ꂽ�y�[�W�j�̃��m�N���}�ł��������߁A����������肿�������������̂��낤���B�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@������Z�N��ꌎ�A�A�g���G����i���j�Łu���惆���C�J�̖{�v�W���J�Â������A���̓W���{�̃��X�g���쐬����i�ɂȂ��āA���͐_�ے��̘V�܌Ï��X�A�c�����X��K��Ă����B�K���X�P�[�X�̒��̋g�����w�m���x�i���a�O�O�N�j�������Ă��炤�ƁA�������̌��提�����{����Z�Z�Z�Z�~�ł���B�����Ȃ��̕ʖ{�������Ă��ꂽ���A�ǂ����Ȃ珐�����{���~�����B�����̖��̓����C�J�̉̏W�w崉ԁx�i���a�O�l�N�j�̒��҂Ƃ��ċL�����Ă����̂ł��������ƁA����l�̉����W�ꂳ�u�}�����[�ŋg���Ɠ����������l�ł���v�Ƌ����Ă����B�N���W�b�g�J�[�h�Ŏx��������ł����Ƃ���A�萔���������̂Ō����x�����̂ق������ɂȂ�Ƃ����B�������ɂ��̋��z�����������قǕs�p�S�ł͂Ȃ��B�䒃�m���w���̋�s�܂ōs���Ĉ����o���Ă���ēx���X�����Ƃ���A�t���l�����Z�Z�Z�~�l�������Ă��ꂽ�B���̖{�ŁA�����C�J�{�̈��������w���z�̍ō��l���X�V���Ă��܂����B
�@���Ȃ݂ɓ����́w崉ԁx�́A������ܔN�����ɎЉ���قōÂ��ꂽ�a�m��ōw�����Ă���B���N�Y�̑}�悪����A���O���V�����̌��提�����{�����A�Ï����͓�Z�Z�~�ł������B�o�i�X�͔g����ޏ������X�i�_�ے��j�ł���B�i�q�R���N�V�����W�����������Ɂr�A�����A���O�`���l�y�[�W�j
�Ȃ�قǁA�s�}�����[�̎O�\�N�t�i�}�����[�A1970�N12��25���j�����́q�Ј��ꗗ�\�i�l�\�܁k1970�l�N�Z���\�������݁j�r�ɂ́u���{���w�ҏW�����@���@���v�i�����A���O�y�[�W�j�Ƃ���B���łȂ���A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�i�}�����[�A1988�j����͏Ȃ��ꂽ�g���̐��z�q��c�j�Y�w�c�x�o�ŋL�O��L�r��
���̉�����ɂ��āA��c����ɑ��k�����Ƃ��A�]�������̂��u��Ȃ�Ăǂ��ł������A�����݂̂Ă��v��c����̊�]�ŁA�e�����D���Ȏ���ǂނ��ƂɂȂ����B����������̘N�ǂȂ͂��߂Ă������Ǝv���B���������̐l���I���Ƃ��̓ǂ݂������A�t�قȂ����ɂ��s�v�c�ƈ��̖����������B���ƂɈ�ۓI�Ȃ̂́A���R�k�ҁl����́u���v�̘N�ǂ��B�܂��ɉ��R����ɂ͊��̕��i�����邩��B�ꉞ�����ɋL�^���̂������B�R�c�k�䎙�l�u��C�̂��߂̏K���v�B���k���l�u��H�����v�B�g�c���u�c�v�B�a�c�k�z�q�l�u�`���v�B���c�k�މ��Y�l�u��v�B�����k�a�v�l�u���v�B�쌴�k��v�l�u�X���v�B�g���k���l�u�A�����̔��v���ł������B�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�A�v���ЁA1980�A����`��ܔ��y�[�W�j
�Ɓq��H�����r��N�ǂ����u���v���A�������̐l���낤�B�����̏��o�͒}�����[�̘J�g�@�֎��s�킽�������̂���Ԃ�t�i1957�N5��17���j����������A�Г��̐l�Ԃɂ͐������Œʂ����̂��낤���A���́q�Ј��ꗗ�\�r�Ŗ��O��₢�Ȃ���A��f�̂悤�ɓǂB���v�������̂����A�������s�Õ��t�ɂ��ď��������͂́s�킽�������̂���Ԃ�t�ɍڂ����̂ł͂Ȃ����B�Ȃɂ����A�g�����q��c�j�Y�w�c�x�o�ŋL�O��L�r�Ɂu�k�����N�l�O����\�����̖�A��c����̎��W�̏o�ʼn���Â����B����͓�N�O�ɁA�l�́w�Õ��x�̂����₩�ȏo�ŋL�O���������A�k��̓����������B�v�i�s�u�����v�Ƃ����G�t�A����y�[�W�j�Ə����Ă���̂��A�������������������B�}�����[�́i���w�D���́j�Ј����W�����g�������W�s�Õ��t�i���ƔŁA1955�j�̏o�ŋL�O��ɓ������o�Ȃ����\���́A����߂č����i���̂Ƃ��̏o�Ȏ҂̋L�^���Ȃ��͎̂c�O���j�B�i���j
�Ƃ���ŁA�����͉Ǎ�̉̐l�ŁA�ƏW�͌�o�s�����c�ԏW�t���܂ނ킸��2���A�����ł̉̏W���s�����W�\�\���{�̐l�V�I�\��l�W�k���{�̐l�p���l�t�i���ە��������o�ŕ��A1950�N12��20���j���^�́q�lj��r�i�����j�A�����̏W�s���}�ԁk���l�I�W�l�t�i�ŏ��[�A1951�N10��3���j���^��47��𐔂���݂̂��i�������j�B���̗����͊e��̕��w���T�ɂ��L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�s崉ԁt�����̈������j�́q��r�Ɍ�����L�q����悤�i�s���}�ԁt�����ɂ́q��җ����r�����邩��A�����Čf����j�B
�@�����ɁA���̓��{�I㵒p�̕\���̍Ō�̎c�Ƃ��ڂ����l�Ɉ������ł��낤�����̓ǎ҂̂��߂ɂ������Ă����A��҂͑吳���N�\����ł���B�M�҂�莵�J���̔N���ł���B�Z�̂ɋ������o�����̂͒��w�̓�N�����A����@���ł����B���Ŕ��H�A�E�A�q���A�����A�g��������邪�A�����̉̐l����Ƃ��Ɉ�l�����o���Č���I�e�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��悤�Ɍ�����B�����Ă����A��҂����a�\�Z�A���N�����t�������O�썲���Y�̉e����������i��҂͂����肳���A�̏W�w����Ȃ�x��ǂ�ŌX�|�A���̍��O���ɂ́w���{�̐l�x�ɎQ���A�����ē������̒ؖ�N�v�́w�S�ԁx�A����È�́w�r�}�x�Ɋ��������ƌ�Ă���j�B�Ƃ������Ƃ͂��̍�҂́w�A�����M�x�I�Z�̂ւ̔����̈�̂��邵�ł��āA�ނ̍�i���炨�̂��ƐF�Z���M���閖�����t�\�V�Í��I�[���͂����������ƂɊW���Ă��悤�B���R���̍�҂͓����̕ۓc�^�d�Y�̏���ɂ��[���X�|�����B���̕ӂ�ɏ��a�\�N��̕��w�N�́A��̓T�^���N�₩�ɕ����肳��Ă���̂ł���B���a�O�\��N�ɂ͑���w���{�̐l�܁x���Ă���B�����ɍ����̏W�w�����W�x�i���a��\�ܔN�j�A�������w���}�ԁx�i���a��\�Z�N�j������B�i�s崉ԁt�A��Z���`��Z���y�[�W�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�����\�\�吳���N�����A�������ɐ���B�������ȑ�w���B���Z���A�����s�����捂�~���k�c�c�l�A�ԕH���B�u���{�̐l�v���l�B�i�s���}�ԁt�A���y�[�W�j
�������j�������悤�ɁA���a31�i1956�j�N�ɂ͑�1����{�̐l�܂��A�R���q�b�q�ƂƂ��Ɏ�܂��Ă���B�����͎�҂����\���ꂽ1�����Ɂq�S���܂��A���J�f�B�A�Ɂr�i35��j�ƂƂ��Ɂq��҂̌��t�r���Ă���B���̈�߂ɂ́u�̂͌��m��ʐl�ւ̕ւ肾�B�����m��ʐl�֖ȁX�Ə����Ԃ�ւ肾�B���̒��̂����̈��ł��A��l�̐l�Ԃ̐S�ɋ������A�Z�̍�҂���҈Ȃ��҂��ׂ��ł��낤�B�v�i�����A��܃y�[�W�j�ƌ�����B��⑽�����A�g���ɕ���ē����̏W�s崉ԁt���玄�̍D���ȉ̂������Ă݂�B�Ȃ��A�����͐V���ɉ��߂��B
�q�t�̏́r
�u�ԁv
�炫���Ă������ۂ��ʉԂȂ��ӂ����܂��Ă܂������ނƂ�
�u�����v
��N�̓����X���ĉ̂Ђ����~�ɐF�Z���Ԃɂ��@�m���n����
�u�C�R�̂����Ёv
�t�����m�������n�̂˂ނ�ɂ��ڂ�߂����m���n�͒N�m���n���q���ʉe�тƂ�
�����m���������n�̋�̈��m�����ˁn�ɗN�����Ƃ��C�R�̂����Аl�ɍ�����
�u����̔@���v
���X�̔��сm�ʂ����n�̎U��ڂЂĈ���m�ЂƂЁn�̍K���͂��肪���Ȃ�
�u�t�̐���v
��������O�m�Ɓn�̖ʁm���n�̐�ɂ��̓����Q��܂���䂭�S��C��
��ɓ���ĊO�m�Ɓn�̖ʁm���n�͏t�̐Ⴕ�܂��S�ɂƂ����ЂƂ��m�Ёn�̂���
�u�ߑ���璲�m���܂₤�Ȃ����Ԃ��n�\�\Fraulein Mignon gewidmet�v
�킪�ׁm�ȁn�����킪�ׂ����肵�������̉��m����n�����ɂ��t�H�̉�
�u���U�̉́v
�؉k���m������сn��~�����߂��U�̉̂Ȃ���䩁X�O�\�O�N�̖�
�u���̂��Ɓv
���킽��ƐS�m����n�̔j��ɕG����p�F��Ɏ�����ƌ��ӂ�
�݂��̂��̂��͂ł��̂Ԃ̔E�ԗ��ɍ��߂�݂��̂��тƂ�
�q�Ă̏́r
�u����l�v
�N���̑m���Ɓn����l�m�тƁn�ƂȂ�Ă��킪���̉ʂ̂���߂ނ炳��
�u���Ɏ��ɕ�����҉́v
���݂����m���Ɂn�̐Տ��m���Ƃǂ���n���Â����K�m�Ɓn�߂䂫�ĉQ�Ȃ����Ɏ����邵����
�u�������v
�킪���̉������m�Ƃق��ق���n���@���v�Ђ�邪���Ȃ͂��T�����X�L�[�E�R���T�R�t
�u���C�E�W���[���F�v
�M���o���悵�W�����E���C�E�o���E������悵�W���[���F�ɔ@�m���n�����S�ʂӂ���
�u�i���v
��̈�ыL���ɂƂǂ߂��̂܂܂Ɋo�ނ�Ȃ�����~�m�فn�肷�����
�u�������v
�l�ЂƂ苎�炵�߂�����̔߂��݂��ȂׂĂ̕ʗ��m�킩��n�����͂��ė���
�u�W���^�̊X�v
�̂т���������m�䂫�����n���͂ʐS�����Ă����Ђ��˂�����m�ЂƂЁn�̂��납
�u���������v
�������苹�˂��グ�Ĉꂹ���ɂȂ���䂭��̉Đ[�݂ǂ�
�u��z�̗��v
�@�ɓ�
�ɓ��̐��˓c�m�ւ��n�̍`�����łĂ�藷�Q�d�˂�����̂Ȃ���
�@�ޗ�
�������̏��l�̂��̂�����m�܂Ȃ��Ёn�ɔR���Ă��܂����ɔZ������Ȃ��i�S�ϊω��j
�q�H�̏́r
�u�r���v
�z�͂˂ǂ܂����ւ肭�邨�������̂킪�ڂɟ��݂ĉ���������
�u������v
���݂̂Ȃ̌ǓƁm���ǂ��n�ɂЂ��ސ^��m�܂�n���N���ĉ��Ɓm�Ȃɂ킴�n����ނЂƂ�̂�����
�u�������R�u�ˁv
�ЂƐF�̉��ɋ����͂Ă��a�t�m�킭��n�ɗz���Ƃǂ��˂��炶�߂肷��
�u�����̐�v
�z�̉��ɉ��V�������̂����N�Ɩl�Ƃ̂��T�߂���
�u��t���v
�����̓J�������A�m�Ƃ��n�����납�������Ȃ炷���̐߂≽
�u���o�v
��𐂂�Ă��ӌ���[���ނ����G�߂̓��䂫���䂫
�u�X�̒J�v
������߂Ă��Ȃ��݂ǂ�����������Đl�ƍs�����ӂ���m�킩�n��Ȃ�
�q�~�̏́r
�u�������v
�킪���ɓ��肭��Ԃ̊��X�Ƃ����Ɍ�������ām������n�̒J
�u���C�v
�H���̗N�����邲�Ƃ��͂��Ȃ��Ƃ��ƂȂ�����Đ^��m�܂�n���˂�����
�u�C���v
�g�̂܂͂�ЂƐF�̕��������ꉹ�m�ˁn�ɗ����̂͒m��ʐl��
�u�t��g��\�\�L�֓��g��\��v
�N�v�m�Ƃ��Ђ��n�̂��̌W���Ɏ����肵���ڗ~�m�فn�肹���Ђ����肯��
�u�S���܂��A���J�f�B�A�Ɂv
�ׂ��s���F��邲�Ƃ��V���w�����m�͂������n�̎}������̌����
�u�w�M�v
�҉̎l���m����n�ɖ����Ď��t���邩�����Ɉ��͎��ɂ��Ȃ炸��
�k�NjL�l
�����ɂ́s崉ԁt��20�N��Ɋ��s���ꂽ���̏W������i�Ō�̉ƏW���j�B�s�����c�ԏW�m����ꂤ���킵�Ӂn�t�i�K�C�R���ɁA1979�N3��20���j�����ꂾ�B�K�C�R���ɂ́A�������j��X���v�̋�W�Œm����Ō������A�̏W�͓����̂�����܂߂Đ��_�����Ȃ��悤���B�����̎d�l�́A���Z�~��O�Z�~�����[�g���E��Z�Z�y�[�W�E�㐻�p�w�z�\���E�\���i�\�P�Ɋ����ɂ�鏑���̓\���Ӂj�B�ʒ��{���i�����́u���Ӂv���M�����͉�c�j�Y�j�B�����҂̃N���W�b�g�Ȃ��B�{�����O�̔����Ɂu�����a�O�\�l�N�^�����a�\�O�N�^�O�S���v�Ƃ���B��y�[�W�ɓ��g�i���l�߂�21���j�B������A�������j�������̉̂Ɋ�q�����m�c�r�������ɏ����Ă���B����l����A�s�����c�ԏW�t�͋g�����ǂ�ł��Ă��������Ȃ����A�����ւ̌��y�͌�������Ȃ��B�s崉ԁt�Ɠ��l�A�D���ȉ̂��f���悤�B�Ȃ��A�������]����q���w�\�\���c�a��������Ӂr�ɂ͊��Q���邪�A���������ŋ�����K�v�͂Ȃ����낤�B�܂��A���a�\��N�u���j�A���A����a�ށB�y���e�X���a�B�v�̎��������q�~�͒��r�́A�ߒɂɉ߂��āA�����ɔE�тȂ��B
 �@
�@ �@
�@
�����̏W�s�����c�ԏW�t�i�K�C�R���ɁA1979�N3��20���j�̔��ƕ\���i���j�Ɠ��E�{�̂Ɣ��̔w�i���j�Ɠ��E�{���k�u���Ӂv�F��c�j�Y�l�i�E�j�@��������}���ُ����̓����͓�������̊{�ŁA�u54.4.28�v�̎���悳��Ă���B
���a�O�\�l�N
�q�C��r
��������m�\���E�x���n�߂�����m�\���E�g���X�g�n���܂����݂͜�قǂ̗���肹��
���a�O�\�Z�N
�q�R�����~�r
�����̗��n�����ǂ�͂˂ēD�m�ȂÁn�݂Ă͐l�Ȃ�ʂ��̂����߂�
���a�l�\�Z�N
�q�_�H�r
����Ɉ���o�ł��I�m���܁n���K�N�m��n���̂��X�m�����ԁn���܂łɏH茂��ɂ���
�q��a�s�r
�Â�Đ��������Ȃ�˂��������ɏH�̗̔z��ῂ݂���
���a�l�\���N
�q��̖���r
�Ȃ��q�����Q�m�Ђ邢�n�����̂����������j�R���E�v�[�T���̉�W�͂�����
�q�u���v�r
�m�����炬�n�ɐጩ�ʂ��Ƃ̂��т�������̋��͂���t�̐ᗈ��
���a�l�\���N
�q���N�����g�r
�t���ĉԂ����Ȃ̍��ɂނ������邵�Ŗ�̏��N�̗�
���N�n�C�̓V���̑�͑z�ւǂ��A�h���A�̊C���������Č�͔ӔN
�q��㎵�O�E�āE����r
���̑S�m�܂��n���ސl�͒������Ƃ���ޖ�����߂Ď��ߐS���͂��ɗ�����
�@�Y��O�o�u�v
�������R�������ӂ藐���e�ʁm���炽�܁n�̓o�u�v�͍���̖�ɗY���m�������n��
���a�l�\��N
�q�g��r
�������������̖������ւ�����Ȃނ����͂ł����������̂Ȃ�����
���a�\�N
�q���������Y�r
�߂���b�Ђ̍�肱�Ƃ����K�̏t�ɂ����āA�g���]�p���B�퐶�����̋���A�t���܂���܂炴��ɁA�����Y�₩�Ɏ��������A��M������B�s�S�Ȃْ��L�ɂƂǂ܂邪�@�����A�t���Ȃ����X����B�^�w�����������͎O�\�L�]�N�̐́B�N�͂����|���̂��Ȃ��A���ʘO���̐l�ƂȂ�Bↂ��ɂ����ӁA�f���������́A�W���ɂ��炸�A�����ɂ��炸�A�S�̂����Ȃ�C���̂݁B����
�g�Ɏ��Ђ��C��������肽���Ԃ��ܔ����l�ɂ��܂͂₷���
�q���ɐG��ār
�i���g�ɉJ���~��ƉS�Ӄo���o��������߂ĉK�̉ԕ��m�����n���������ڂ���
���a�\��N
�q�H�����r
�m������͎��҂݂̂ɂ��Ă킪�݂菈�m�ǁn���͓���ǂЂĐg�̂��ڂ�Ȃ�
�����A�O�o�u�v�A�˖{�M�Y�\�\�s�����c�ԏW�t�̏��a�l�\���N�q���a���i��j�r�ɂ́A�˖{�́u���ꈣ���m�X�^�o�g�E�}�[�e���n�̒�ɂӂƖفm�����n������̎�g�̂ӂ��s���ݕz�m�J���[�n�v�ɏ��a���������\�\�Ƃ������s���{�̐l�t�̏r�G�����i���������j�́A�g�����ɂ��e�����A�قړ�����̉̐l�����������B�g���͔ނ�̎t�E�O�썲���Y�ɂ��āu�����Y�̒Z�̂ɂ͂�����ł��A�ߑ�l�̗J�D�\�\�����Ă݂�A�ǓƂȍ��̙������o�����Ƃ��o����B�����Đ��F�I��i�����߂�A�����Y�́s���ɖi����t�̎��тƂ������ƂɂȂ낤���B�v�i�q�ǓƂ̉́\�\���̈��u����l�l�̉̐l�r�́u�R�@�O�썲���Y�v�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A��ܘZ�y�[�W�j�Ə����Ă���B�܂��ɁA�g�����i���������͎��ɓ]���邵���Ȃ��j�Z�̂̋ɂ݂܂œ������̂������Y�ł���A�ނ̒�q�����͂���ł��Ȃ��Z�̂ɓ��݂Ƃǂ܂��āA���̂��̂��ǓƂŁA�������L���Ȑ킢�������̂������B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@�s���{�̐l�t1960�N2�����́q�b��r���Ɂu崉ԏo�ŋL�O��v�Ƒ肷�鎟�̍��m���ڂ��Ă���B
�@�����̏W�u崉ԁv�̏o�ŋL�O��͎��̒ʂ�J�Â���B���҂��͂�ł��̘J���˂���Ђ��̌����j�č���̔��W���F�肽���B�����̉���͌J�荇�͂��o�Ȃ����₤��]����B
�@��A�����@�O����\�����i���j�ߌ�ꎞ
�@��A���@�L�����z�e���i�n���S���͐����d�ԂɂĖL�������ԁA�L��������������j
�@��A���@�O�S�~
�@��A�o���@�O�X���܂łɓ������{�̐l���s���܂Ō�A���̂��ƁB
�@�����͑O���ɏ㋞�o�Ȃ̗\��B�i�����A�l���y�[�W�j
����ɓ����q�ҏS��L�r�ɂ́A�O�썲���Y���u���ʌf�b��̒ʂ�O���A�l���͍s���������B���Â�̉�ɂ����₩�ɏo�Ȃ��ė~�����Ǝv�ӁB���͎O�����{�ɏ㋞����B���炭�Ԃ�œ����̉�������ɂ��߂ɂ������Ƃ��̂��݂ɂ��Ă��B�v�ƁA�܂����̍��̕ҏS������S�������Ǝv�����{��q�b���u���ʒ��m�}�}�n�̂Ƃق�O����\�Z�m�}�}�n���i��l���j�j�𓌔����̉̏W�u崉ԁv�o�ŋL�O��ɂ��܂��B�v�X�ɐ搶��㋞�̂��Ƃł͂���A�S���Q�����Ē��҂��j�����������̂ł��B�Ȃى��ւ͐V���A�ڔ��A�V�h�w�����A���~����肻�ꂼ��o�X���o�Ă���܂��B�v�Ə����Ă���i�����A�܈�y�[�W�j�B�ɒB���v�͂��̏o�ŋL�O��ɏo�����낤���i�̍d�ςŋ}������̂́A��1961�N��1���j�A�g�������o�Ȃ������ǂ����͂킩��Ȃ��B
�i�����j�@�`���Ɂu���̟���͖l�ܑ̌̂̋��X�ɂ����݂���ŗ���Ȃ��B���X��������鐶���̕s�������邱�ƂȂ���A���_�I�r�p�ɔ�J���ނ��Ă��̂��B�k�c�c�l��w�̐����őO�삳��̖��@���Ă���\�N�B�������̂��B�����Ă܂��l�̕��݂̉��Ƃ̂낢���Ƃ��B�v�i�����͐V���ɉ��߂��j�Ƃ�����450���̎U�����f���������́q�lj��r�́A�q�t�̏́r�i18��j�A�q�Ă̏́r�i23��j�A�q�H�̏́r�i14��j�A�q�~�̏́r�i23��j�̑S78��Ȃ�A�����̍�i�i���Ƃ��u�킪���̉������m�Ƃق��ق���n�����Ƃ��v�Ђ�邪���Ȃ͂��T�����X�L�[�E�R���T�R�t�v�j���A�����̏W�s崉ԁt�Ɏ��߂��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����̏W�s�����W�t���^�̍�҂ƍ�i���́A���̂Ƃ���B
�����q�lj��r
�D�ÒY�q��́r
�����P�v�q�Ԃ̏d�ʁr
�ʈ�Ǝq�q��b�r
����b���q�Łr
�˖{�M�Y�q�N���X�^���C�h�r
�r�c���v�q�ߓV�r
�R�����q�����r
�ԏ���s�q�q���O��r
�����q�C�̕��ցr
��a���q�q���̉́r
�R���h��q���Ӂr
�O�썲���Y�q��L�r
���{�ߑ㕶�w�ُ����́s�����W�t�̑O���Ԃ��ɂ́A�y�������Łu�����^�����Ύ��l�^�b���v�Ə����E����E���ꂪ�L����Ă���B���Ȃ݂ɁA�����̉��t�ɂ́u����ҁ@��\�@�����v�Ƃ���B
�i�������j�@�����̏W�s���}�ԁk���l�I�W�l�t���^�̍�҂ƍ�i���́A���̂Ƃ���i�����͐V���ɉ��߂��j�B
���R���F�q�t�̂����r
�����q�t�̐���r
���c���q�����r
�R���q�q�q�ԕ܁r
���c���q�X���䂭�r
�~�c�^�j�q��]�r
�O��F�Y�q�A���i�v���i�r
�������q�͂Ȃ܂��r
�k�������l�q���Ƃ����r
�����̃p�[�g��13�y�[�W����n�܂��Ă���B���̃y�[�W�͔��ŁA�~���̃��B�[�i�X�̃o�X�g�A�b�v�̊p�Ŏʐ^�̉��Ɂu�����v�Ƃ����āA�W��͂Ȃ��B14�y�[�W�͔��B15�y�[�W�̍ŏ��̍s�ɂ̓^�C�g���́u�t�̐���v�i�l�������j�������āA�ȉ�17�y�[�W�܂ł�12��B17�y�[�W�ɂ́u�������R�u�ˁv�i12�|�j�ƃ^�C�g���������āA�ȉ�19�y�[�W�܂ł�10��B19�y�[�W�ɂ́u�ߑ���璲�m���܂₤�Ȃ����Ԃ��n�\�\Fraulein Mignon gewidmet�v�i12�|�j�ƃ^�C�g���������āA�ȉ������܂���24�y�[�W�܂ł�25��B�{���q�������r�ł������̍�i���́q�t�̐���r�Ƃ���A�`���̘A��̑薼���u�t�̐���v�\�\���������9�s崉ԁt�q�t�̏́r�́u�t�̐���v�i�S11��j�ɍ̂�ꂽ�\�\�Ƃ��ׂ����낤�B�u�����c�c�v10��́s崉ԁt�q�H�̏́r�̓���̉��ɑS10�i1��߂�2��߂̏��Ԃ����ւ��āj���^����A�u�ߑ���璲�c�c�v25��́s崉ԁt�q�t�̏́r�̓���̉��ɁA1����Ȃ���24���^����Ă���B�s���}�ԁk���l�I�W�l�t�̒��҂̊�Ԃ�́A�s���{�̐l�t�̓��l�������Ԃ݂����s�����W�t�Ƃ͈���āA�u�������Ă����B���l�͏������Ђ��E�O�قɂ��Ă�邪�A���R�̂��ƂȂ���傩�����Ȋw�ɂ��Â��͂�҂����ł���B�v�i�q���Ƃ����r�A�{���A�㎵�y�[�W�j�Ƃ���B���҂́s�Z�̕����t�̓��l��5�l���߁A�s���{�̐l�t�̓��l�͓����ЂƂ�ł���B���̂Ƃ�����ق�5�N��̋g�����́A�s�V���W�t��s�����t�Ƃ��������l�����ɗ����Ǝ��т\���Ă���A�����̍�i�͎��W�s�m���t�i���惆���C�J�A1958�j�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ�B

�����̏W�s���}�ԁk���l�I�W�l�t�i�ŏ��[�A1951�N10��3���j�̕\���@���̓����s���}���ُ����{�\�\����J�}���فu��28.1.31�v�̎����\�\�͔��̕\�������A�R�ŒԂ��Ȃ����Ă���A�w����������Ă���B
�i���������j�@���{�ߑ㕶�w�فE���c�ؐi�ҁs���{�ߑ㕶�w�厖�T�k��܊��l�t�i�u�k�ЁA1977�N11��18���j�́s���{�̐l�t�̍��͈������H�̎��M�ŁA�������u���݁A�k�c�c�l�����ȓ��l�́A�ΐ�M�Y�A�{��q�b�A�O��A�����P�v�A�R���q�b�q�A�����A�O�o�u�v�A�Ð쐭�L��B��v���l�̈�l�A�֓��j�͓Ɨ����āu���^�v��n���A��h���Ȃ����B�v�i�����A�O�Z���y�[�W�j�ƌ���ł���B���̂����ΐ�M�Y�A�R���q�b�q�͑O�f�q�̏W�u崉ԁv�]�r�ɕ��͂��Ă��邪�A�O�o�u�v��֓��j�͓��̉̂ɂ��āA�ǂ����ɏ����Ă���̂��낤���B����A���Ԃ��Ȃ�1947�N�A�s���{�̐l�t�ɓ�����˖{�M�Y�́A�Z�̂̊ӏܕ����̎��ԏW�s����S�̉��\�\�����ɂЂ炭���t�i�ԗj�ЁA1990�N7��20���j�ɁA���́s�����c�ԏW�t����u�m�����炬�n�ɐጩ�ʂ��Ƃ̂��т�����c�c�v�����ł��āA�����̌㔼�Łs崉ԁt�Ɍ��y���Ă���B
�@�E�킪���̉����������Ƃ��v�Зh�邪���Ȃ��������X�L�[�E�R���T�R�t
�@�E�ʁm����n�Ȃ��ė������̂ɂ��т�����킪��N�m���₭�˂�n�̓��͌X�m�����ԁn����
�@�E���̏I�艓��m�Ƃقˁn�ɂ����Ԃ����_���ɂ͐h���ЂƗ�������
�@��҂͐��Ԃ��Ȃ��A���̑��̏W�w崉ԁx�ŁA�^�C�g���ɂ����������g�̐S�������߂āA���̂悤�ɉ̂����B���̌���A����A�����̂�����͈�i�Ƃ����܂����A���邢�͂₳�����A�O�\�ꉹ�C�͈ꌷ�Ղ��Ȃ���ɐ�������l�ɓ`�����B�i�����A��y�[�W�k�V���E�V���ȕ\�L�͌����̃}�}�l�j
�����ŋC�ɂȂ�̂́u���Ԃ��Ȃ��A���̑��̏W�w崉ԁx�Łv�́u���Ԃ��Ȃ��v�ŁA�s崉ԁt���s��1959�N12���͂���ɊY�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���p�̂́u�������Ƃ��v�́A�˖{���Q������1950�N12�����̍����̏W�s�����W�t�ł̕\�L�ŁA�s崉ԁt�ł̂���́u�����@���v�ł��邱�Ƃ��^����[�߂�B���Ȃ킿�A�s�����W�t�̊��s�����u���Ԃ��Ȃ��v�������Ƃ����F�����A���̂Ƃ��˖{�ɓ����Ă��Ȃ��������B�C�ɂȂ邱�Ƃ͂܂�����B�Ō�́u�O�\�ꉹ�C�͈ꌷ�Ղ��Ȃ���ɐ�������l�ɓ`�����B�v�́A���̂Ƃ����łɓ����i���N�͋g��������1�N����1918�N�j���f���Ă���悤�ɂ����ǂ߂�̂����c�c�B���Ȃ݂Ɂs���{�̐l�t��1991�N7�����́k�O�썲���Y�Ǔ����W�l�������i�����Y�͑O�N1990�N7��15���A88�ŕa�f�j�B���R���Ă��������Ȃ������́A���̍��Ɏ��M���Ă��Ȃ��B
�k2021�N5��31���NjL�l
�i�]�N�s�}�����[ ���ꂩ��̎l�\�N 1970-2010�k�}���I���l�t�i�}�����[�A2011�N3��15���j�͂����ւ�ȘJ��Łi�ق��ɖJ�߂悤���Ȃ��咘���u�J��v�ƌĂԂ��Ƃ����邪�A�����͕����ǂ���u�͍�^�w�͂��Ă����d���v�̈Ӂj�A�{���̖`���͎��̈ꕶ�ł���B
�@�a�c�F�b�i���Z�Z�\�����N�j�ɂ��Ўj�w�}�����[�̎O�\�N�x�i���̂��ѕ����ɍۂ��A�w�}�����[�̎O�\�N 1940-1970�x�Ɖ��肵���j�́A�ЂƂ̏o�ŎЂ̋L�^�������āA���セ�̂��̂��L�^���邷���ꂽ���w�ł���B�i�����A��O�y�[�W�j
�u�i���Z�Z�\�����N�j�v�́A�����i�������c�g�j�ł͊��������̏�������s�g�B�a�c�F�b�N���X�́A�l�����T�╶�w���T�A�sWikipedia�t�ɍڂ��Ă���悤�Ȑl���Ȃ�A���f�N�̕\���ɋ������Ƃ͂Ȃ��B�����{���ł͊�{�I�ɁA�o�ꂷ��l���i�����͒}�����[�̎Ј��j�̏��o�ɂ��̕\�����{����Ă���B����͋��Q�ɒl����B���y�����{�̔��s�N�������m�F�����J��m�鎄�������̂�����A�ԈႢ�Ȃ��B�ނ��A����͒��҈�l�łȂ��������Ƃł͂Ȃ��B���M�����̒}�����[�̋e�r���Y�В��ȉ��A�����̎Ј���n�a�̋��͂������Ă������������̂ł���B�ƖJ�߂Ă����Č����̂��Ȃ��A�{���ɂ͐l���������Ȃ��B�����������Ȃ����A��\�I�ȏo�ŕ����s�b�N�A�b�v�����q�N���r�͂��邪�A�����������Ȃ��i���ꂾ��������������{�Ȃ̂ɁA���������Ȃ��j�B�Ƃ����킯�ŁA���������̐��f�N���������̂́A�{�e�q�����̏W�s崉ԁt�̂��Ɓr���f�ڂ������ƁA�{�����ēǁi�O�ǁH�j���Ȃ���A�g�����䂩��̐l���̐l�����������삵�Ă����Ƃ��̂��Ƃ������i���Ȃ݂��W�J�~�ꂳ���͖{���ł͑����ɂȂ��Ă���j�B
�@�������ŒԂ��������e�A�����Њ����őł��ꂽ�W�|�O�i�g�݂̃Q���Ȃǂ��A���̏�ɂ����ɂ��R�Ɛς܂�Ă����B�k�ҏW�l�����͒��N�̌����w�N���قƂ�ǂŁA���Ɏ��i���Z��\�l���N�j�̈�̂�{�������l���쌴��v�i�����\���N�j�A�������i�ꔪ�����\��㔪�O�N�j�Ɛ�����͂ސl�������i���ꔪ�\��Z�N�j�A�x�C�Y�i���Z�l�\�O�N�j���S�l�̐M�������l���������j�i���l��N�\�j�A�����ĊO���d�b���Ƃ�ƁA�u���E�̈䕚�ł��v�Ɛ������L�i���O�܁\�����N�j���Ăяo�������c�c�B��㕶�w�����C�u�ł���A�Ƃ������͋C�������B�i�q��T�́@�Óc������r�́u���{�ƈً�ԁv�A�����A�����y�[�W�j
2019�N2�����q�s��ʁt�����p�J�[�h���邢�͓y��ꐳ�̂��Ɓr�ɋg�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�̂��Ƃ����������A���̂���͋g���������N��ɑ������������I�[�N�V�����ł悭���������B�C���^�[�l�b�g�̃I�[�N�V�����ł͂Ȃ����A���N�̏��߁A�a�J�̒������X�ŋg���������Ɉ��Ă��s�g�������W�k���㎍����14�l�t�i�v���ЁA�u��㎵��N�㌎�\�ܓ���Z���v�j���������̂ŁA������͍w�������i���e���q�����N�父�g�������ȁi1976�N4��13���t�����j�̂��Ɓr�Ɍf�����j�B���提���ɗp����ꂽ�M�L�p��͒������{�[���y���ŁA�g���̕M���͔��ɍ����A�͂����߂ď��������Ƃ��킩��B���ꂩ�甼�N�قnjo�������݁A�֘A����u�c�̏o�i����i�������悤�Ȃ̂ŁA�u�g�����@�����v�Ō��������C���^�[�l�b�g��̉摜�����Ă݂��B
�Ƃ���ŁA������l�ɑ���Ƃ��ł��ȑf�Ȃ̂́A�{���̂��̂ɉ���������������̂܂ܓn���Ȃ�A����Ȃ肷�邱�Ƃ��낤�B�����A�������邱�ƁB���̎����A�����鑊��̖��O�ɏ����i����ɂ͎���j��Y���邱�ƁA�ƂȂ낤�B���邢�́A��������ȒP�Ȃ̂��u�ޒ�@���ҁv�Ƃ������ނ̞x��̈������O���Ԃ�������ɋ���ő��邱�Ƃ��i���j�B����Ɏ肪����ł���ƁA�Ǝ��̈ē����n����Ƃ������ƂɂȂ��āA���̋g���́s��ʁt�����p�J�[�h�͂���ɑ�������B�X�����z�̏ꍇ�A���Ȃ��Ɗ��D�����Ȃ����̂��B���M���������܂�������ǁA�n�K�L��̊��s�ē��߂������蕨�ł���������邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂��i�g���́s��ʁt�̂���ŁA�J�b�g���������I���e�ʂɌ��提�����L���Ă���j�B�Ō��́A������������������邱�Ƃɂ����Ă̓v���ł���B
�������ɏo���̂͋C�������邪�A�ٕҁq�g���������r�����̊������߂�s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i�v���ЁA1991�j�́A�����Ζ����Ă������[�E�s�[�E���[�̏�i�⓯���ɍw�ǂ����߂邽�߂Ɂi���Ҋ����Ɠ����l�i�Ŕ����Ă�������j�A�q���㎍�ǖ{�g�����i�����N�l���v���Њ��E�艿��A�Z�~�j���s�̂��ē��r�Ȃ�^�C�g���̕��͂��A���[�h�v���Z�b�T�[�̏o�͂�ʼn��ɂ��āA�����n�K�L�ɍ������B�������̂��g�����ƌ𗬂̂������A�ʎ��̂Ȃ������ɂ��X�����āA���l������͂��������Ȃ����Ԏ��������������B����ȋ@��łȂ���ΐl�ڂɐG��邱�Ƃ��Ȃ����낤����A���ʂ��f���Ă����B
�@�݂Ȃ��܂ɂ͂��ς��Ȃ����߂����̂��ƂƐ��@�������܂��B
�@���āA���̂��сs���㎍�ǖ{�g�����t�����s����܂����B����́A��N�̌܌��ɋg�������S���Ȃ��āA�ŏ��̖{�i�I�Ȗ{�ł��B���͉������Ċ����́q�g�����N���r�q�g���������r�q�Q�l�����ژ^�r�����M���܂������A��Z���I�㔼�A���a������\���邱�̎��l�̋Ɛт��ڂ݂�ׂ��A���N���܂��S�������܂����B
�@�������ɖ������Ĉȗ��A�g������̎��͂˂ɍō���Ɉʂ�����̂ł����B�ӔN�̐��N�ԁA�����݂��������l�Ɖ��x�����b������@��̎��Ă����Ƃ��A���͂��肪�����v���������܂��i���[�E�s�[�E���[�́s�_�u���E�m�[�e�[�V�����t�y���F���W�����g������́s�y���F��t�Ɋւ���Ă���̂����������v���o�ł��j�B
�@������@�ɁA�g��������̎����������̕��͂������A�����łȂ������A���́u���{��ɂ����فv�ɐG��Ă���������K���ł��B���̂Ƃ����́s�g������t���݂Ȃ��܂̎���ɂȂ�A����ɗD���т͂������܂���B
�@�����N�l����ܓ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�Z���͏ȗ��l�@�@���ш�Y
�g�����������玩���Ɉē����Y����悤�ɂȂ����̂��A�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��B���n�Ɂu�ޒ�@���ҁv�ƈ�����ꂽ�����̞x�͌������Ƃ��Ȃ�����A�n�K�L��̓����̈�����i���ʂ͂Ȃ��j�Ɍ��提�����L�����̂��A�s�T�t�����E�݁t�i1976�j����n�܂��Ă���悤���B�����̂��Ɂs�Ẳ��t�i1979�j�������������Ƃ��́A���ʂ̂Ȃ��n�K�L��̈�����ɕM�Ŏ��̖��O�Ə���������������i�ʐ^���q�u�g�����v����u�g�����v�ցr�Ɍf�����j�A�����p�J�[�h���苖�ɂ���A�{�ɒ��ڋL���̂ł͂Ȃ��A������g�������̂Ǝv�����i�Ƃ�킯���s���ɑ����̐�y�m�ȂɔŌ����瑗��ꍇ�A�J�[�h�ɏ����ق�����ƓI�ɂ��y���낤�j�B
���āA�����ł悤�₭�g���������N��ɑ������{�ɓY����ꂽ�����p�x�̘b�ɂȂ�B���t�I�N�I�ɏo�i���ꂽ�Ƃ��̎ʐ^�����悤�B�����܂��̎ʐ^�́A�����s���[���h���b�v�t�ɂ��Ă���������提���Ƃ͕ʂɂ��������������̞x�B�ŋ߁A�g���Ō�̎��W�s���[���h���b�v�t��ǂݕԂ��@������āA�N��̂�������ł͂Ȃ����낤���A�����̎��т��ȑO���͂邩�ɐg�ɐ��݂��B�����A�s���l���ւ炸�t�̂悤�ɁB���܂��A����͂Ƃ�ł��Ȃ����삾�ƍĔF�������B�s�_��I�Ȏ���̎��t�Ɠ��l�́i�����ł͂Ȃ��j�`���ŁA�S19�т̕]�߂������������̂��B
 �@
�@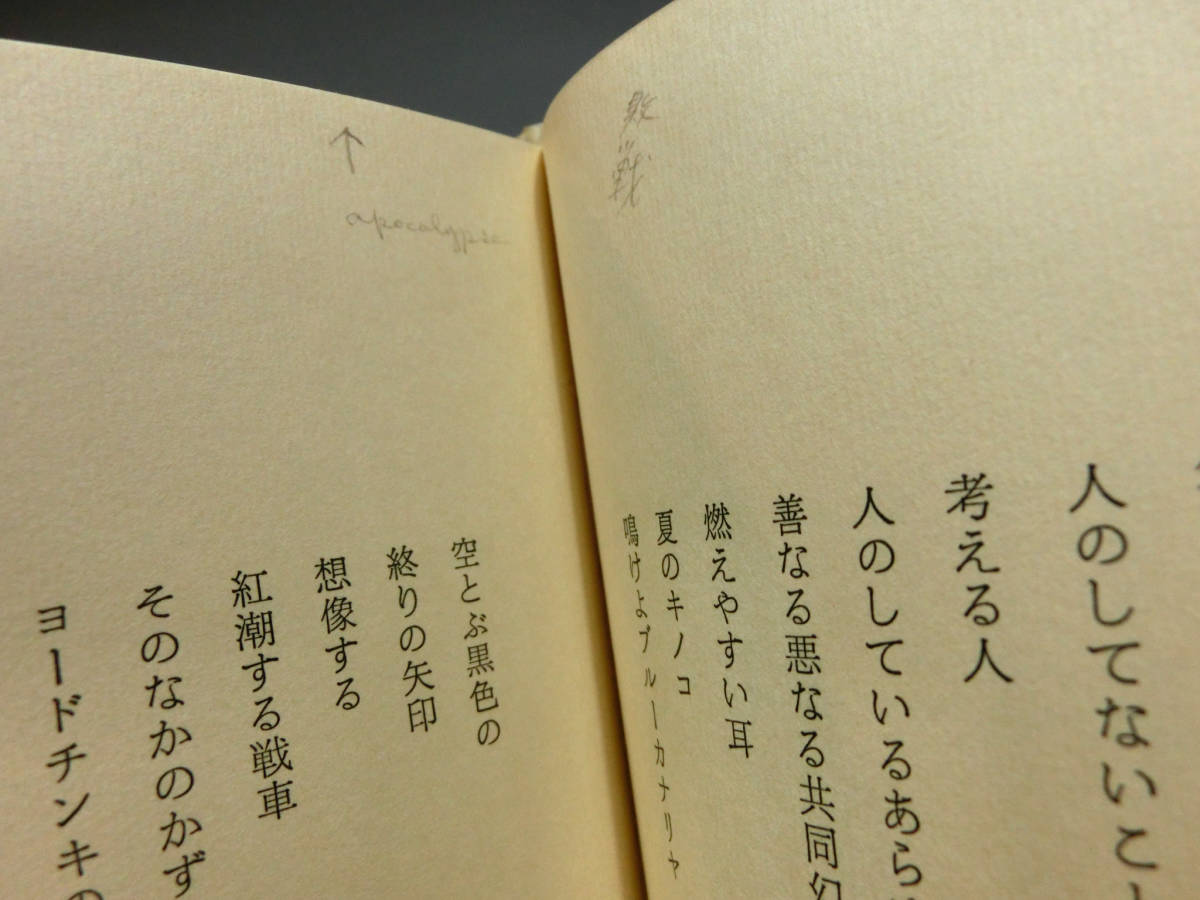 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@
�i�ʐ^�A������9�_�߂܂ł͋g�����������N��Ɉ��Ă��{�ƞx��J�[�h�j�F�` �s�_��I�Ȏ���̎��k����Łl�t�A�F�a ���O�A�G �s�T�t�����E�݁t�A�I �s�|�[���E�N���[�̐H��t�A�r �s�u�����v�Ƃ����G�t�A�J �s��ʁt�A�i5�j �s�g�����k����̎��l�P�l�t�A�K �s���[���h���b�v�t�A�t �s���܂�͂����L�t�A�K �s���[���h���b�v�t
�F�` ���W�s�_��I�Ȏ���̎��k����Łl�t�i���쏑�[�A1974�N10��20���j�����Ԃ��Ɍ���A�u1975.2.5�v�̎���A����
�F�a ���O�����сq�}�N���R�X���X�r�i�F�E1�j�ɍ����N��ɂ����̂Ǝv�������M�������ɂ��u�s��v�uapocalypse�v�̏�������
�G ���W�s�T�t�����E�݁t�i�y�ЁA1976�N9��30���j�������p�J�[�h�i�T�t�����̃J�b�g�j�Ɍ��提���k�ʃJ�b�g�̎ʐ^�ł͌��Ԃ��ɂ����提���l
�I �E�⎍�W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�i����R�c�A1980�N5��9���j������ⳁi�\���̕ЎR���̊G�𗬗p�j�Ɍ��提��
�r ���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t�i�v���ЁA1980�N7��1���j������ⳁi���̃X�^���`�b�`�̊G�𗬗p�j�Ɍ��提��
�J ���W�s��ʁt�i����R�c�A1983�N10��20���j�������p�J�[�h�i���E��ⳓ\�̒��̃J�b�g�𗬗p�j�Ɍ��提���k�����p�J�[�h�̕��ʂ��g���̎��M�ɂȂ鎍�W���s�̈ē��Q�Ɓl
�i5�j �I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�ЁA1984�N1��20���j�����Ԃ��ɕM�Ō��提���k�ʐ^�̉E�́A�o�i�҂̐����ɂ��u�����N��́A�g�����Ɋւ���p���G�b�Z�C�̃Q���������͌��e�H�Q���ƁA�p���o�Ŏ�St. James Editorial Ltd.�̌��e����炵�����̂P���v�l
�K ���W�s���[���h���b�v�t�i����R�c�A1988�N11��25���j������ⳁi180�~48mm�B���E��ⳓ\�̐��e���O�Y�̃J�b�g�𗬗p�j�ɕM�Ō��提��
�t ���L�s���܂�͂����L�t�i����R�c�A1990�N4��15���j������ⳁi170�~44mm�B�V��Ǝv�����J�b�g�e�Ɂu���܂�͂����L�^1990.4�v�Ɗ����ň���j�Ƀ}�[�J�[�ŏ����k�ʐ^�̍��͋g��������l
�F�`�́s�_��I�Ȏ���̎��k����Łl�t�����A�u1975.2.5�v�Ƃ������t���C�ɂȂ�Ƃ����C�ɂȂ�B���s����Ɍ��{�������ɂ́A���t���Ȃ�������������Ȃ��i�g�������c��m�Ɍ��������W�s�_��I�Ȏ���̎��k����Łl�t�Q�Ɓj�B
�F�a�̓����W�����́q�}�N���R�X���X�r�i�F�E1�j�̉��M�������ɂ��u�s��v�uapocalypse�v�̏������݂́A�����N�炪�s�_��I�Ȏ���̎��t�̏��]�Ƃ��āq���̂悤�Ȃ��̂��b���̂Ȃ��ցr�i�s�����C�J�t1975�N10�����́q������]�r���j�����M����ɂ������āA���W�ǂ����Ƃ��̂��̂��B�����̏��]�Ɂu�s��v�͓o�ꂵ�Ȃ����A�uapocalypse�v�́u�َ��^�v�Ƃ��Ď��̂悤�ɓo�ꂷ��B���킹�ď��]�̃|�C���g�ƌ���������Ă������B
�@���l�̌��������M�����Ƃ��A�u����v�͉��߂āu�_��I�Ȏ���v�A�܂�َ��^�I�ȏI���̎���ƂȂ�B�k�c�c�l�����āA���݂������َ��^���v�킹�A�n������s���\�\�u���n�ɐԂ����̂܂���߂ā^�݂ɂ��������ց^�킪�n�j�R���X�̓M�����b�v�I�v�G�́s�T�t�����E�݁t�̃J�[�h�̃J�b�g�́A���W�̔���{�̂ł͎g���Ă��炸�A�N���`�������킩��Ȃ����i�ЎR���̎�ɂȂ���̂ł͂Ȃ��悤���j�A���̈ē���̂��߂̐V�삩�B
�@�k�c�c�l���ǂ̂Ƃ���A���l�̎��������ʂ��Ă䂭�ɓ_�́A���̂悤�Ȏ���̒��Ŏ��������Ă��鎩�����g�ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������W�̕\�肪�w�_��I�Ȏ���x�ł͂Ȃ��A�w�_��I�Ȏ���̎��m�A�A�n�x�Ȃ̂��B���̏����́A���̍ł��[�������ɂ����ẮA�u�������Ɓv�i���l�̕Љ����D�݂�^���āu�G�N���`���[���v�ƌ��������j�ɂ��Ă̔��Ȃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�k�c�c�l���l�̂��̂����������}�I�Ȏ��摜�ɓ��B���邱��ɂ́A�ڂ������ǎ҂́A�ނ����́u���ꌶ�ł̎����v�ɂ����Ď��͂ǂ�ȂɈؕ|���ׂ�����̘B���p�t�ł��邩���A�\���ɒm������Ă���B�i�����A���Z�`����y�[�W�j
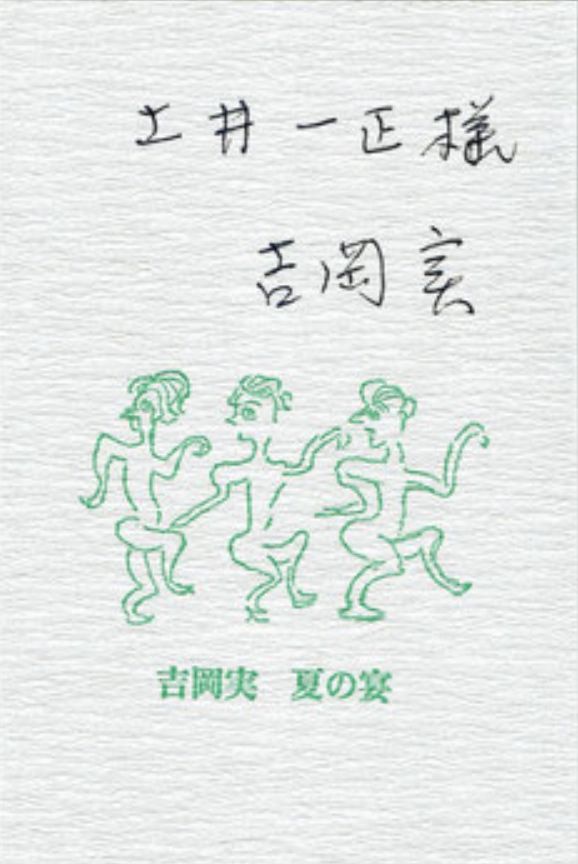
�g�������y��ꐳ�Ɉ��Ă����W�s�Ẳ��t�i�y�ЁA1979�N10��30���j�̏����p�J�[�h�i�y�������A���提������j�k�o�T�F�Ï���E�������m�����݂ǂ��n�l
�k�NjL�l
���̊Ԃɍ����N�炪�g�����ɑ������{���ނ��킯�ŁA2019�N4���A���t�I�N�I�o�i�̃n�K�L�����̂�����̎������Ă���B�摜���f���A���ʂ��N�����Ă݂悤�B
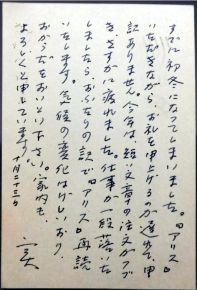
�g�����������N��E�N�Ɉ��Ă��n�K�L�̕��ʁi1985�N10��24���k12-18�l�ڍ��Ǐ���j�k�o�T�F���t�I�N�I�i�^�C�g���́q�g���� �����M���M �^�M �t���������N�� 猈������C�X �L������ �w�s�v�c�̍��̃A���X�x���w��ʁx �����܁��w�m���xH������l�r�j�l
���łɏ��~�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�w�A���X�x
���������Ȃ���A�����\�グ��̂��x��āA�\
��܂���B���N�́A�Z�����͂̒�������
���A�������ɔ��܂����B�d������i������
���܂�����A���ӂ���̖�Łw�A���X�x�ē�
�������܂��B�C��̕ω��͂���������A
�����炾�������Ƃ��������B�Ɠ����A
��낵���Ɛ\���Ă���܂��B�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\����\�O��

�����N��E����猖�ɂ�郋�C�X�E�L�������i�A�[�T�[�E���b�J���G�j�s�s�v�c�̍��̃A���X�t�i�V���فA1985�N10��5���k�����F�F�숟��ǁl�j�̃W���P�b�g�i�e�j�G���`���A���X�k�c���l�Ɋr�ׂāA���b�J���̂���k�����l�͖��ɂȂ܂߂������j
���́w�A���X�x�́A�����N��E����猖�ɂ�郋�C�X�E�L�������i�A�[�T�[�E���b�J���G�j�s�s�v�c�̍��̃A���X�t�i�V���فA1985�N10��5���j�ŁA�u��㔪�ܔN�������{�v�̓��t���������N��́q���Ƃ����r�Ɏ��̂悤�Ɍ�����B�����������A�����́s�A���X�t�ς������ȏ��Ȃ̂ŁA�����Ă��������i�U�艼���͏ȗ������j�B
�@�u�s�v�c�̍��̃A���X�v�́A�E�T�M���Ƀh�X���Ɨ������A���X����������ւƖ��������Ȑl�Ԃ⓮���⎖���ɏo����b�ł��B�A���X�́A���傤�ǎ��䂪�߂��߂��������Ƃ������A�����̐��E����̂��Ƃ̗������킩�肩���Ă����Ƃ������A���������N���̏��̎q�ł��B�c�N���͂����߂��Ă��邯��ǁA�܂��v�t���ɂ͂Ȃ��Ă��܂���B������u�펯�v�i�R�����E�Z���X�j���g�ɂ��͂��߂�����ǁA�܂�����Ōł܂��Ă͂��܂���B
�@���������A���X���A���̍��ŁA�u�펯�v�ɔ�����i�i���Z���X�ȁj�l����ł����Ƃɏo���킵�āA�߂������A�������낪������A���S������A���_������A�܂��i�����́u�펯�v�������ꂻ���ɂȂ��āj������҂�s������������\�\���܂��܂ȁu�`���v������̂����̕���ł��B
�@��҂ɑ����Ă����A�ǂ��ł��傤���B�L�������͂����ȓ�����l�ԂɎp�������āA�����鏭�����A�y���܂�����A���炩������A�ق�̏������킪�点���肵�Ă���̂�������܂���ˁB����Ƃ��������_�V�ɂ��āA�����̂Ȃ��̋�z���v�����蔭�U�������̂ł��傤���B
�@����͂Ƃ������A�������ǎ҂Ƃ��ẮA�ǂ�ȓǂ݂��������Ă����R�ł��B�A���X�Ɠ������炢�̔N���̓ǎ҂Ȃ�A�A���X�Ƃ�������ɂȂ��ď�����A��������A�{�����肷������B�����ƔN��̓ǎ҂Ȃ�i�A���X�̂��o��������̈�l�ł����j�A�l�������̊�Ȍ����ɏ����낰�Ȃ���A�����ɃA���X�̔������ώ@���邱�Ƃ��ł��邵�A����Ɂu�펯�v�Ɓu�i���Z���X�v�̊W�ɂ��Ă��낢��l�����߂��点��y���݂�����A�Ƃ������������ł��B
�@�m���Ȃ��Ƃ́A�����ł��B�ǂ�ȔN��̓ǎ҂��A���̕����ǂނƁA���₩�炾���ƂĂ����������Ƃ��Ă��܂��B���b�ɂ��肪���ȁu���P�v��u�����v�̏L�����A�����ɂ͂���܂���B�����ɁA�u�펯�v�̘g�g���䂳�Ԃ��A�͂������Ƃ��́A�Ƃق����Ȃ�������Ɓi����Ɨ����ȁj�s����������܂��B�������A����𖡂�������ƂŁA�������̓A���X�Ɠ����悤�ɂӂ����сu�펯�v�̐��E�ɂ��ǂ��Ă��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł����A���̂Ƃ��A�������̐S�ɂ́A���́u�`���v�̋L�����܂������Ȃ��c���Ă���͂��ł��B�i�����A�ꔪ���`�ꔪ���y�[�W�j�B
�����Ԏ��ɕς����ӏ��́A�ق��ł��Ȃ��A�������q�g�������A���X���ɏo������Ƃ��r�i�s�����C�J�t1973�N9�����k���W���g�����l�j�ŋg���̌��Ƃ��āu�����A�A���X�Ƃ����������̂��̂́A�w�A���X�̊G�{�x�̕��̎��k�q�w�A���X�x���r�l�ɏ��������ǁA�ڂ��ɂƂ��āu�v�Ȃ�ł��ˁA�u�����v�Ƃ������́B�L�������ɂƂ��Ă��A��������Ȃ����ȁA����̃A���X����t��������A�ۖ�������̂�����̂ɂ��Ă��Ȃ����̂ˁB�ʐ^�̕��͂��������݊������邯�ǁB�ڂ��ȂA�������Ɛڂ���@��͂Ȃ����ǁA�L��������������悤�ɁA���������������_�V�ɂ��Ă����Ă����C���ł��ˁB�v�i�����A��Z��y�[�W�j�Ə����Ă��鏈�ɂ��̂̌����Ɍĉ����Ă��āA�����̋g���ւ̖ڔz����������悤�ȋC������B���̍ۂ�����A�n�K�L�ɂ���u���N�́A�Z�����͂̒������Â��v�̕��̃��X�g�������Ă������i�����́���́A�g���̒����ɖ����^�̂��́j�B12���܂łɔ��\�����A���̔N1985�N�A���M���̎U���ł���B
1�̉i�c�k�߁A4�̓��c�Îq�A5�̍����d�M�A10�i�����I�ɁA�q���s�o��r�̍����d�M�E�q�~悂Ɨd�C�r�̈���_�i�E�q���H�����r�̐܊}���H�E�q�r���̏j���r�̉ĐΔԖ�A��4�сj�A13�̏@�c�����ƁA4���߂����o��W�̕��͂Ȃ̂������[���B�����}���I�Ɍ����Ȃ�A�g�����̊S�̈���̋ɂɂ́s�s�v�c�̍��̃A���X�t�ɑ�\�����m���́A����탂�_���ȕ���������A��������̋ɂɂ͂킪�o��i�Ƃ����Ă��`���I�Ȃ���ł͂Ȃ��A�O�q�ӂ��́j�������āA���҂��݂��Ɉ������������ʁA�ؓ��̂�����c����Ɏ��g�̎���i�����݂���Ƃ������ƂɂȂ�B�E�l�ӂ��̃��A���Y���ɗ��ł����ꂽ���_�j�Y���A�Ƃł����������̂��낤���B���̗��݂����A�Փ˂̂����������x�ɔ������ꂽ�Ƃ��̋g�������́A�V�����o�Ƃ����Ă悢�B��̗������������������낤�B���Ƃ��A���̖����q���C�X�E�L��������T�����@�\�\�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�k�����`���l�r�i�G�E11�j�̂悤���i�������j�B���邢���q���܂�����r�i�G�E30�j�̂悤�ȁB���邢�́c�c�B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�i���j�@���āA�����E�����̉��E�w����O�̌Ï��X�A��X���X�ŋ��߂�����N�v���W�s�S�\�\�����~�́t�i����R�c�A1997�N7��10���j�ɂ́A�u�ޒ�@���ҁv�ƈ�����ꂽ�x������ł������i���͘��߂̑����ɂȂ�A�t�����X���̂��̏����Ȏ��W���������Ă���j�B
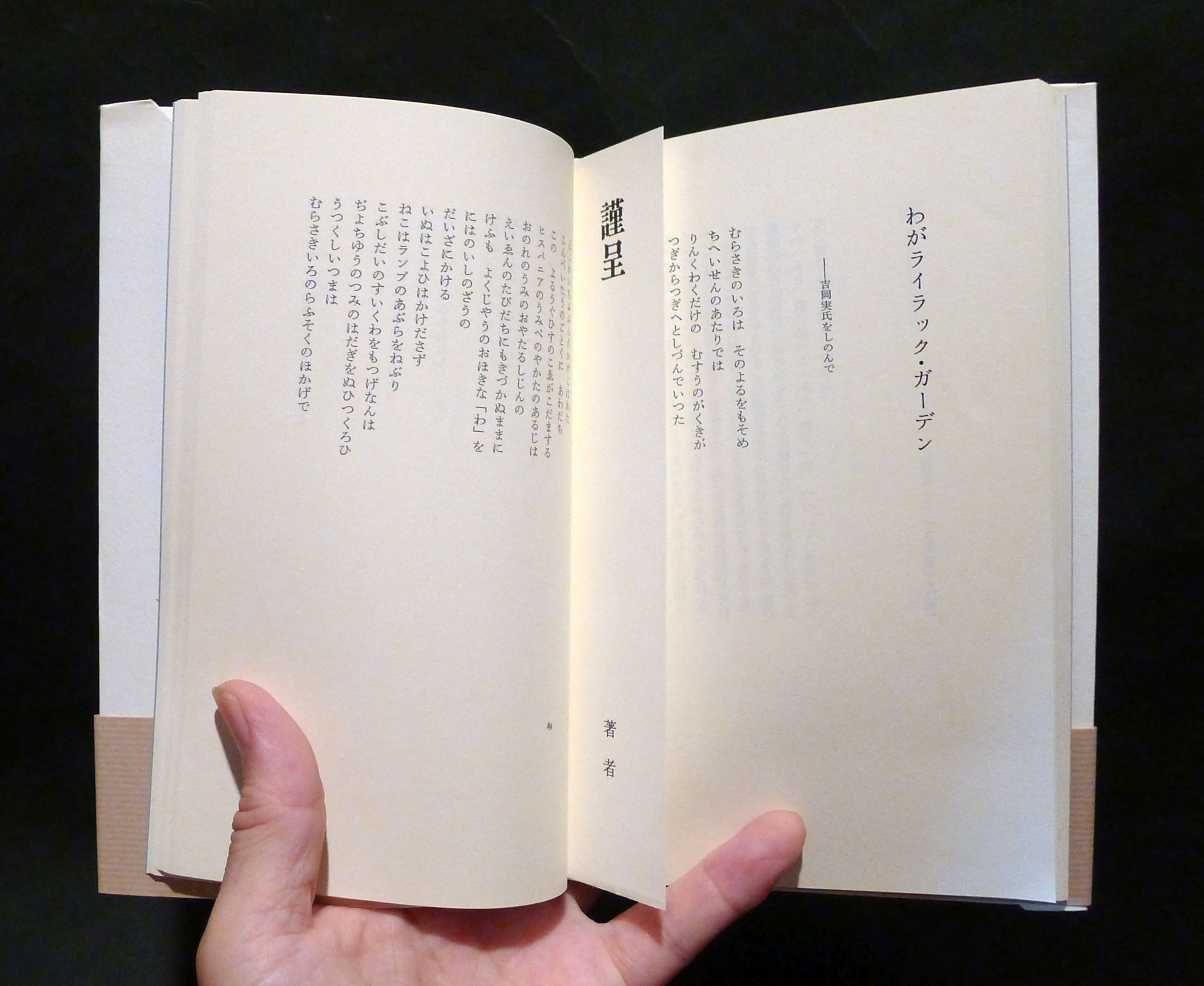
����N�v���W�s�S�\�\�����~�́t�i����R�c�A1997�N7��10���j�ɋ��܂�Ă����x�B190�~40mm�͎��W�{�́i190�~124mm�j�̓V�n�Ɠ����ŁA�����̈�����ł͂Ȃ��A�{���̂��߂ɂ��炦�����̂ł��邱�Ƃ��������킹��B
�i�����j�@���{�����钘���́A�ӂ���ǂނ̂͂ނ���̂Ȃ��ق������A������̋H�Q�{�͋g�������c�唪����Ɉ��Ă����W�s�t铁t�i����ɁA1941�N12��10���j�ŁA�������ɂ���͕��{���Ȃ�����A�ǂ����Ă����{�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��ȊO�́A�R�s�[���ĒԂ����ق���ǂށB78�N�O�Ɋ��s���ꂽ���̖{�̔w�́A�ׂ��Ԃ�������ĕ��O������i�P�ɖ{����ǂނ����Ȃ�A�����ς�s�g�����S���W�t���j�B2005�N11��30���A���c�����K�˂�����A���������ɂ������������́s�t铁t�ɂ́A���Ό��y�[�W�̃m�h��艺���Ɂu���c�唪�Ɂ^���܌܁E��E�Z�^�g�����v�ƃy�������̌���E����E����������i���̂Ƃ���������A�u�r�c�F�q�Ɂv���Ă����Łs�t铁t�����Ă���B�ʂꂽ�r�c�ɓn���Ă��炤�悤�ɁA�g�������c����ɗa�������̂��j�B���̑����̂Ȃ��ŁA�ł���Ȉ���ł���B
�i�������j�@�S�~��Y�́s���㎍�蒟�t�i2019�N6�����k���W�����̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�W�l�j�̃A���P�[�g�q���Ɓu���㎍�蒟�v�r�́A�����Ƃ̏o��A��ۂɎc���Ă��鎞�����W�́H�@�Ƃ����₢�ɑ��āA
�@���w�̉��Z�r���ɓ���т����Ă����A�����������ُ��X�Ŏ�Ɏ�����u�ʍ����㎍�蒟 ��� ���C�X�E�L�������v�i��㎵��N�Z���j�̏d�łŁA���Z�N���������Ǝv���܂��B���Ɗ����ƃC���L�łł����t�����X�L���������̂悤�ȁA���̐��Ȃ�ʑf�G�Ȃ��̂Ǝv���܂����B���v���A����̓A���O���ƃT�u�J���̊Ԍ��ɂ����Ƃ����݂��āA���̌�A�n�ォ�玸���Ă��܂����\���̂����܂�ł����B
�Ɠ����āA�ЂƂ̍��q�Ɍ��W���������N��E�K���Εv�E�g�����A�O�҂ɂ���O�̃R���{���[�V�����������B
�@���̕ʍ��Ɍf�ڂ���Ă���V�쎍�т͋g�����́u���C�X�E�L��������T�����@�v�Ɖ�������́u�A���X���N�v�����ł����A���l���g�̎菑���̑莚�ƃ��C�A�E�g�ɂ���āA���F�̃A�[�g���ɓʔł̐}�ō\�����y�[�W�Ƃ��Ĉ�����ꂽ�O�҂̋�����ۂƂƂ��ɁA�킽���ɂ͂��̖{�S�̂��ЂƂ̎��Ƃ��Ď����Ă��܂����Ǝv���܂��B��㎵�Z�A����N�Ɂu���㎍�蒟�v�ҏW���߂��K���Εv�́A���㎍�ւ̔ے�Ƃ��āB�ҏW�҂ɂƂ��ăe�N�X�g�͑f�ނł����Ȃ��A�{�����ɂȂ����ł����A�Ƃ������b�Z�[�W�Ƃ��āB�i�����A��O�Z�y�[�W�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\
�����N��ɂ�郋�C�X�E�L�������^�A���X���̒����E�ҏ��E���i�������������̂̂݁j
�����N��E�푺�G�O�ҁs���C�X�E�L�������\�\�A���X�̕s�v�c�ȍ����邢�̓m���Z���X�̖��{�k�ʍ����㎍�蒟�i��1����2���j�l�t�i�v���ЁA1972�N6��1���j�k�g�����q���C�X�E�L��������T�����@�\�\�k�킪�A���X�ւ̐ڋ߁l�k�����`���l�r�i�G�E11�j�\�l
�����N��ҁs�A���X�̊G�{�\�\�A���X�̕s�v�c�Ȑ��E�t�i�q�_�ЁA1973�N5��1���j�k�g���͑O�f�q�w�A���X�x���r�i�G�E12�j�\�l
�����N��ҁs�A���X���z�t�i���鏑�[�A1976�N11��10���j�k�s�����G�{�t�i1976�N7�����k���W���A���X�̍��ցl�j����̍Ę^���܂ށl
�����N��s�L������ �C�� �����_�[�����h�t�i�V���فA��4���F1980�N8��5���k���ŁF1977�N1��15���l�j
�����N��E��菇�V����s���C�X�E�L���������W�\�\�s�v�c�̍��̌��t�����t�i�}�����[�A1977�N12��20���j
���C�X�E�L�������i�����N�祍���猖�j�s�����ւ̎莆�t�i�V���فA1978�N11��15���j
�����N��Βk�W�s�A���X�̍��̌��t�����t�i�V���فA1981�N7��10���j
���C�X�E�L�������^�A�[�T�[�E���b�J���G�i�����N�祍���猖�j�s�s�v�c�̍��̃A���X�t�i�V���فA��2���F1987�N2��25���k���ŁF1985�N10��5���l�j
���C�X�E�L�������^�W�����E�e�j�G���G�i�����N�祍���猖�j�s�q�������̃A���X�t�i�V���فA�����ŁF1987�N5��15���k���ŁF1977�N�l�j
���C�X�E�L�������^�k�W�����E�e�j�G���G�l�i�����N�祍���猖�j�s�s�v�c�̍��̃A���X�k�͏o���Ɂl�t�i�͏o���[�V�ЁA1988�N10��4���j
�����N��s���B�N�g���A���̃A���X�����\�\���C�X�E�L�������ʐ^�W�t�i�V���فA1988�N11��25���j
�����N��E��菇�V����s���T�Ώ� ���C�X�E�L���������W�k�����ܕ��Ɂl�t�i�}�����[�A1989�N4��25���j
���[�g���E�m�E�R�[�G���i�����N��Ė�A���B�܂݁E�����e�q�E�O������j�s���C�X�E�L�������`�k��E���l�t�i�͏o���[�V�ЁA1999�N5��25���j
���C�X�E�L�������^�w�����[�E�z���f�C�G�i�����N���E�͍��ˈ�Y�ҁj�s�X�i�[�N���t�i�V���فA2007�N8��5���j
�ڍ������}�����[�Łs���C�X�E�L�������S�W�t�\�\�u����������g�������������Ă�����v�Ƒz�����邱�Ƃ́A�s�����ʋ����̌��肤��\�\�̂��Ƃ𐿂��ĐV���ق������I�ȃL�������̑n��S�W�̊e�����o���Â��Ă��邱�Ƃ́A����獂���N��̒��E�ҁE��ȊO�̓��Њ��̃L�������֘A�̏��ڂ������킽���A��R�Ƃ��Ă���B
6�����{�̏������A�����Y�L�O�E���ƗƎ��̂܂��O�����w�فi�Q�n�E�O���j�Łq���̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�r�i2019�N4��27���`6��30���j���ς��B�Ȃ�Ƃ����Ă��A�n�����ȗ��́s���㎍�蒟�t�i�Ց���ʍ����܂ށj�S���̓W�����������B�ʏo���\���̕\�������邾���ŁA60�N�̗��j���t���b�V���o�b�N����悤�ŁA῝���o����قǂ��B�W����Ǝ��̐}�^�͂Ȃ��āA�s���㎍�蒟�t�i2019�N6�����k���W�����̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�W�l�j������ɑւ��B�W���p�l��1950�N��́s�m���t�̉�����́A�����̖쑺��a�v�q1950-1959�r�̋L�ڂƓ����B�����N��E�푺�G�O�ҁs���C�X�E�L�������k�ʍ����㎍�蒟�l�t�i1972�N6���j�̋g����q���C�X�E�L��������T�����@�\�\�킪�A���X�ւ̐ڋ߁r�̃p�l���̉�����́u�g�����X�����v��E���A���p�̎��w�������i�߂邫�������ƂȂ����B�v�ŁA������́i�������쑺�́q1970-1979�r�Ɉ˂���j�{�W�����o���B�ق��ɁA���W�s�m���t�i�Q�n�����y�������L�O���w�ُ����j�Ɓs�T�t�����E�݁t���W������Ă����i�Y�W�����ɂ́A�g�������������}���ōY�S�W�����������A�����ōł����������̂́A�Ԏ��̓������s���ɖi����t�̍Z�����肾�����j�B
�u�O�����w�قւ悤�����v�Ƃ����m�[�g�u�b�N���������̂ŁA���̂悤�ɋL�������\�\�u�������痈�܂����B�g�����̂��ƂׂĂ��鏬�ш�Y�ł��B���ؒ��h����̎B����8�~���A�y�����q�����܂����B�����g������������߂��M�d�Ȏ����Ƒ����܂��B�i�s�u�ł́A�y���F�𑗂��F�V����Ƌg���̉f�������ꂽ���Ƃ�����܂����j�^�O��͓���������̍Y��܂̊��W�ł�����A�����Ԃ�v���Ԃ�ł��B�L����̂͂₢���ꂾ�����ς���Ă��܂���B�q���㎍�蒟��60�N�r�A���肪�Ƃ��������܂����v�B�����A�s���㎍�蒟�t�n�������苖�ɂ��鍡���A�������ق֑����^�̂́A�ЂƂ��ɂ��̉f�����ς邽�߂������B������̐V���W�s�₠�A���l�����t���Љ��s���㎍�蒟�t�i2019�N6�����j�́q�X�N�����u���X�N�G�A�r�Ɂu���̃e�L�X�g����̓ǂ݂��݂ƁA���ڂ̏o�����̊��G���D�肱�܂�Ă��鎁�Ȃ�ł͂̈�����B�J�Ò��́u���㎍�蒟��60�N�v�W�ł́A�����B�e�����W�~���̉f����������Ă��āA���̎��W�ŕ������Ă��鑽���̎��l���݂邱�Ƃ��ł���B�u�����Ă���v����M�v��g������́A���Ɍ�����ꂽ���炩�ȕ\�����A���̎��W�̍���ɂ�����̂�����������͂����B�v�i�����A����y�[�W�j�Ƃ���̂Ɏ䂩��Ċςɍs�����悤�Ȃ��̂��B���̉f���́s���l�����^1981.8�`�t�Ƒ肳�ꂽ�J���[�t�B�����i��t�@�C���ɂ��Ƃ������́j�ŁA�_�ے����a�J�������������X�i�o�b�N�Ɂu�R�[�q�[���k�̔҂�����v���Ă���܂��l�v�̕\����������j�̕Ћ��Ŏ����������𐁂����Ă���g������19�b�ԁA���^����Ă���i�����X�[�p�[�́u�g�����i�P�X�P�X�`�P�X�X�O�j�^�w�Õ��x�w�m���x�w�T�t�����E�݁x�Ȃǁv�j�B�����^���̉����͂Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�s�g�����S���W�t�̕ҏW�ψ��A�ѓ��k��E�剪�M�E����N�v�E�����r�Y�͓o�ꂷ�邪�A�q�k�r�̊�c�G�͏��e�����̓o��A������s�ɂ������Ă͓o�ꂵ�Ȃ��B�o��l���̏ڍׂ́A�s���㎍�蒟�t�i���O�j�́q�W���ژ^�r�Ɉ˂�ׂ����B
�@�f��
���ؒ��h�B�e�u���l�����v�i��11���j
�u���㎍�蒟�v�̕ҏW�����������ؒ��h���A��㔪��N��������A�d���ʼn�������l�������W�~���f�ʋ@�ŎB�e�������́i�����X�[�p�[�A�a�f�l�͑O�����w�ٍ쐬�j
�o�ꂷ�鎍�l����
�ɓ���C���A�����r�Y�A�n�ӕ��M�A�����l�A����N�v�A�r��m���A������v�A�@���߁A�ѓ��k��A���ÕׁA�����N�j�A������A�a��F��A��؎u�Y�N�A�J��r���Y�A�Ґ��v�A����F���Y�A���������A�������v�A����N�v�A�l���c���F�A����M�v�A���m�q�A�k�����Y�A�剪�M�A��c�G�i���e�̂݁j�A�e�n�M�`�i����Ɓj�A���c��v�A�g�����A�������q�A���Ñ��Y�i�]�_�Ɓj�A�R�������q�A�z�K�D�A�g���K�q�i�����A�ꎵ���y�[�W�j
�O�����w�و�K�̃~���[�W�A���V���b�v�ł́s���㎍�蒟�t�̃o�b�N�i���o�[��P�s�{�i�������1,000�~�ψ�j�̔̔����������̂ŁA�s����C���̎��I���� 1927�`1937�t�i�k�k���� ��4���F1991�N�l�j�\�\�苖�ɂ����{�͐��{���ɂ�ł��āA�ǂ݂ɂ������Ɛr�������\�\�Ɖ����߂��́s���㎍�ǖ{�\�\������ �g�����t�i1991�j���w���B���̂��ƃO�b�Y�����Ă���ƁA�Y���g�D�����S���h���m�y��̃}�[�N������������v���X�`�b�N���̞x���������̂ŁA�L�O�ɋ��߂��B���������A�g�����܂������C����������A�V�h�E�I�ɚ������X�Ō������X�J���x�i�Ñ�G�W�v�g�l���_���������b���������ǂ����G�W�v�g�̕�Β����j�\�\�ނ��I���W�i���ł͂Ȃ����v���J�\�\�������������Ƃ���A�ƂĂ�����ł����������i����ƕʂɁA⽍���i�悵�����Ƃ�����j�B�����ɂ��邳���g��������Ȏq�����܂��݂����ȃX�J���x��{�C�ɂ����Ƃ͎v���Ȃ����A�����������̂悤�ȋC�̗����Ȃ��j�̐���t�̍D�ӂ�ǂ��Ƃ��ꂽ�̂��낤�B�g������͎��M�̏��e�����������Ă��܂�������A�Ⴂ�����̂悤�Ȃ��̂ł���B
 �@
�@ �@
�@
�L����̍Y���̂����Ƃɂ������ޔ����Y�̑��Ɓq���̖����ց\�\���㎍�蒟��60�N�r�W���̑O�����w�فi���j�Ɠ��W���ɂ������u�O�����w�قւ悤�����v�Ƃ����m�[�g�u�b�N�i�E�j
2018�N12�����s�ŋ߂́q�g�����r�t�ɏ������悤�ɁA����N�v�����Ǔ����ׂ��A�{�e�������B�ŏ��ɁA����N�v���g�����ɐG�ꂽ�����̈ꗗ���f����B
����28�т́s�g�����Q�l�����ژ^�t������������A�ق��ɂ��nj��ɓ���Ȃ���������������ɈႢ�Ȃ��i�������́q���Á@�����R�@���r���܂ގ�4�т��g���Ɍ����Ă���̂́A���������g�������e���O�Y�ɋ@��邲�ƂɎ�����������Ƃ�z���N��������j�B����ɂ��Ă����̐��͌����ď��Ȃ��Ȃ��i��1�j�B�����炭�g��������Ɍ��y�����̂́A���̔����ɂ������Ȃ����낤�B����̕��͂̂Ȃ��ł́A�u�����g�����v�܂ł�����11.�q�g�����̓]���r��23.�q���ȐN�Ƃƕϗe���d�˂��|�p�ƍ��r�i����͋g���f��̔���������u����g�����v�܂ł��˒��Ɏ��߂�j���d�v���ɂ����Ĉꓪ�n���Ă���B���̂ӂ��ɂ͍��܂łɉ��x���G�ꂽ���Ƃ�����̂ŁA�����ł͈�����p�x����\�\���Ȃ킿�g�����Ɠ���N�v�̎��l�Ƃ��Ă̊W���A���҂̒P�s���W�̔�r��ʂ��āA�l���Ă݂����B���āA�g������1919�i�吳8�j�N�A�������܂�B1931�i���a6�j�N�A���]�ɐ��܂ꂽ����N�v����12�ΔN���ł���i���Ȃ݂Ɏ��͋g�������O���A��������艺�́A����������ΐ��܂�j�B1955�i���a30�j�N�A�g����8����36�Ő��ŏ��̎��W�s�Õ��t�i���ƔŁj���A�����6����23�ŏ������W�s�� ����Ƃ��s�t�i���惆���C�J�j���㈲���Ă���B���Ȃ킿�A12�̔N��ɂ�������炸�A���̎��I�o���͂قړ����������킯�ł���B���҂����s����������A���W���S�ɑ�������B
| ���� | �g���� | ����N�v | ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | �a�� | �N�� | �o�� | ���� | �N�� | �o�� | ���� | ���� |
| 1919 | �吳8 | �y0�z | �C15���A�����ɒa�� | 1919 | ||||
| 1931 | ���a6 | �y12�z | �y0�z | �J3���A���]�ɒa�� | 1931 | |||
| 1940 | ���a15 | �y21�z | �A�������X�ɓ��� | �I���̏W�s�����G�߁t | �y9�z | 1940 | ||
| 1941 | ���a16 | �y22�z | �F�o���^�G��A���� | �K���W�s�t铁t | �y10�z | 1941 | ||
| 1955 | ���a30 | �y36�z | �G���W�s�Õ��t | �y24�z | �E���W�s�� ����Ƃ��s�t | 1955 | ||
| 1958 | ���a33 | �y39�z | �G�o�Ė{���q�A���� | �J���W�s�m���t | �y27�z | �A���W�s�Ď��̉t | 1958 | |
| 1959 | ���a34 | �y40�z | �G���l�����s�k�t�n�� | �D�̏W�s�����t�^�G�I���W�s�g�����k�����̎��l�o���l�t | �y28�z | �C�}�����[�ɓ��Ёi���N�ގЁj | 1959 | |
| 1961 | ���a36 | �y42�z | �y30�z | �I���W�s���y�n�t | 1961 | |||
| 1962 | ���a37 | �y43�z | �J���W�s�a���`�t | �y31�z | �I����W�s�����Q���n���X���̓��t | 1962 | ||
| 1965 | ���a40 | �y46�z | �y34�z | �I���W�s�G�߂ɂ��Ă̎��_�t | 1965 | |||
| 1967 | ���a42 | �y48�z | �I�I���W�s�g�������W�t | �y36�z | 1967 | |||
| 1968 | ���a43 | �y49�z | �F���W�s�Â��ȉƁt�^�I���W�s�g�������W�k���㎍���Ɂl�t | �y37�z | �A���̍\���ɂ��Ă̊o�����\�\�ڂ��́q����i����r�^�C���W�s�킪�o�_�E�킪�����t | 1968 | ||
| 1970 | ���a45 | �y51�z | �A�I���W�s�g�������W�k���y�Łl�t | �y39�z | �B���W�s����N�v���W�k���㎍���Ɂl�t | 1970 | ||
| 1971 | ���a46 | �y52�z | �y40�z | �E���W�s���Ȃ��ؑl�̉S�t�^�F���W�s�� ����Ƃ��s�@���t | 1971 | |||
| 1973 | ���a48 | �y54�z | �y42�z | �B�S���W�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1970�t�^�D�s���̋t���t | 1973 | |||
| 1974 | ���a49 | �y55�z | �C���s�ٗ�Ձt�^�I���W�s�_��I�Ȏ���̎��t | �y43�z | 1974 | |||
| 1976 | ���a51 | �y57�z | �t�� �p���sLilac Garden�t�^�H���W�s�T�t�����E�݁t | �y45�z | 1976 | |||
| 1977 | ���a52 | �y58�z | �y46�z | �C���W�s�u���v���̂ق��̎��t | 1977 | |||
| 1978 | ���a53 | �y59�z | �J�}�����[���ˊ�ގ� | �E�I���W�s�V�I�g�������W�k�V�I���㎍���Ɂl�t | �y47�z | �B�s�V�I����N�v���W�k�V�I���㎍���Ɂl�t�^�E���W�s���č������Y�Ɩ�������l�ւ̋�A�̎U�����t | 1978 | |
| 1979 | ���a54 | �y60�z | �I���W�s�Ẳ��t | �y48�z | �D�S���W�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1978�t�^�E���W�s���̎�̂���O�\�̏�i�t�^�K�s���I�W�ɂ��Ă̊o�����t | 1979 | ||
| 1980 | ���a55 | �y61�z | �D���W�s�|�[���E�N���[�̐H��t�^�F���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�t | �y49�z | 1980 | |||
| 1981 | ���a56 | �y62�z | �y50�z | �E���W�s�p�k���t | 1981 | |||
| 1982 | ���a57 | �y63�z | �y51�z | �E���W�s�t�̎U���t�^�I���W�s���҂����̌Q���镗�i�t | 1982 | |||
| 1983 | ���a58 | �y64�z | �I���W�s��ʁt | �y52�z | 1983 | |||
| 1984 | ���a59 | �y65�z | �@�I���W�s�g�����k����̎��l�l�t | �y53�z | �I�s�l�����@���o���t | 1984 | ||
| 1985 | ���a60 | �y66�z | �@�� �p���sCelebration In Darkness�\�\Selected Poems of YOSHIOKA MINORU�t | �y54�z | 1985 | |||
| 1987 | ���a62 | �y68�z | �H�]�`�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t | �y56�z | 1987 | |||
| 1988 | ���a63 | �y69�z | �H���z�W�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�k�}���p���l�t�^�J���W�s���[���h���b�v�t | �y57�z | �G���W�s���Ӌt���́t�^�K���W�s�́\�\�ςւ��́t | 1988 | ||
| 1989 | ���a64�^����1 | �y70�z | �@�Z�g�����v�A���� | �y58�z | �J���W�s���̍���t | 1989 | ||
| 1990 | ����2 | �y71�z | �D31���A�����Ŏ��� | �C���L�s���܂�͂����L�k��Ԃ�ǂ邵����l�t | �y59�z | 1990 | ||
| 1991 | ����3 | �f��1 | ���p�W�sKusudama�t | �y59�z | �B�s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t | 1991 | ||
| 1994 | ����6 | �f��4 | �y63�z | �@�k�������q�ҁl�Z���W�s�y���̎v���o�t�^�E���W�s�Y�ӏM�\�\�킪�n��������t | 1994 | |||
| 1995 | ����7 | �f��5 | �E�I���W�s���E�g�������W�k���㎍���Ɂl�t | �y64�z | 1995 | |||
| 1996 | ����8 | �f��6 | �B�S���W�s�g�����S���W�t | �y65�z | �K�S���W�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1994�t | 1996 | ||
| 1997 | ����9 | �f��7 | �y65�z | �F���W�s�S�\�\�����~�́t | 1997 | |||
| 2002 | ����12 | �f��12 | �D���W�s����t | �y71�z | �E�s���ɂ������t�^���W�s砂����y�k�Ƃق��������l�t | 2002 | ||
| 2003 | ����13 | �f��13 | �C��W�s�z���t | �y72�z | 2003 | |||
| 2005 | ����17 | �f��15 | �y74�z | �G���W�s�A���{���[�_�t | 2005 | |||
| 2006 | ����18 | �f��16 | �B�U���I�W�s�g�����U�����\�\���_���Z�܂��ꏊ�k���̐X���Ɂl�t | �y75�z | 2006 | |||
| 2007 | ����19 | �f��17 | �y76�z | �J���W�s����̂���ˁt | 2007 | |||
| 2018 | ����30 | �f��28 | �m86�n | �I15���A�_�ސ�Ŏ��� | 2018 | |||
�܂��C���t���̂́A�g���̎��W�̐��ɑ��ē���̂��ꂪ�������Ƃł���i�P�s���W�Ɍ���A12����22���j�B�����ЂƂA����́s���V�N�v�q���r�W���t�Ƃ����`�ő������Ɏ���̎��3�x�i1973�A1979�A1996�N�j�A�S���W��҂�ł��邱�Ƃł���i�g����1967�N�Ɏv���Ђ��琶�O�B��̑S���W�\�\�������A���Ԃ͐��̍�i���d�������I���W�\�\�Ƃ��ās�g�������W�t���o���Ă���j�B�g���̎��т͓��ҏW�ψ��̒��S�ƂȂ��ĕ҂s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�ŁA����̎��т́s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1994�k�㊪�E�����l�t�i�y�ЁA1996�j�ƁA����ȍ~�́s�S�\�\�����~�́t�i����R�c�A1997�j�A�s砂����y�k�Ƃق��������l�t�i���A2002�j�A�s�A���{���[�_�t�i���A2005�j�A�s����̂���ˁt�i�v���ЁA2007�j�����낦��A���ׂĂ̎��W���^��i���J���@�[�ł���B
�ŏ��Ɍ���ׂ��́A�s�� ����Ƃ��s�t�Ɓs�Õ��t�ł���B�c��q�N��ҁq����N�v�N���r�i�s���㎍�蒟�t2019�N2�����j�ɂ́u���܈�N�i���a��\�Z�N�j�@��\�^�k�c�c�l�\�@�����A��B���̌ܓ���A��Ɂw�@����Ƃ��s�x�̒��j�ƂȂ��A�̎����ł���B�v�i�����A�����`����y�[�W�j�Ƃ���A�s�Õ��t�̐�����Ԃ�1949�`55�N������A��l��1950�N��O���A�����̂ǂ����ŏ������W���\�������i���������ł������ƂɂȂ�B�ނ��A���W���o���܂ő���̑��݂�m��Ȃ������͂����B���́u�W���W�����J�@���C���C�v�́q���莍�сr�Ŏn�܂����́s�� ����Ƃ��s�t�ɂ́q�҉́r�Ƃ����g���́s�t铁t�Ɏ��߂�ꂽ�q�҉́r�i�A�E1�j�Ɠ���̎�������A�s�Ď��̉t�ɂ��q���r�Ƃ����g���́q���r�i�B�E6�j�Ɠ���̎�������B�����̑Δ�������[���̂����A�����ł́q��r�Ɓq�d���r�i�C�E4�j�����Ă��������B�q�d���r�́A�܂��ɋg�����Łq��r�i����͂���ŁA����_�����ϑt�����Ƃ����v���Ȃ��̂����j�ł͂Ȃ����B
��b����N�v
�ޏ��̏Z���͎l�\�Ԃ̈ꂾ����
���Ŗl�͎l�\�Ԃ̓�֏o�����Ă������̂�
�l�\�Ԃ̓�ɂ́@�Зւ̉�������ł���
�`���[�u���牟���o���ꂽ�G��@���̂܂܂�
�܂����Ɍ��鎵�̉͂ɂ�����
�l�͕������@�����~����
�����~���ā@�����Ł@�͂�����
���Ŗl���������Ă����̂�
�V�����ɂ����̂ɂ���m�A�A�A�n������
�����̂ɂ���m�A�A�A�n�������@�ɂ���m�A�A�A�n������
�d���b�g����
�חg�n�͉J��
�ʔK�Ɛ^���̂Ȃ���
���̒j�͂����d���܂̉��ɂ���
���Ԃ͖Ӗڂ̎҂���
�D���炨�낷�ׂ̗�
���ׂČ`�����ɂ������̂�
�����ɂ����ł䂭
���肠�܂�A���̗�
�͂������Ɗ���
��݂��璊���o���ꂽ
��̒����ǂ�ʂ�ʂ�
���肱����
���̒j�͊��S�ɓ�v���ꂽ
�����K���̊�͊ώ@������܂���
�����Ă����S�{�̉��˂����n����p������
���̒j�͂��������ʼnƘH����
�Ƃ�̐H����ۂ�
���ȓV�̂�Q���Ɏ������ނ���
�L���V���c�̔w������
���̒j�͐�ɕ��s���ꂽ
�u�`���[�u���牟���o���ꂽ�G��@���̂܂܂Ɂ^�܂����Ɍ��鎵�̉͂ɂ����āv�Ɓu���̒j�͊��S�ɓ�v���ꂽ�v�u���̒j�͐�ɕ��s���ꂽ�v�Ƃ������傪���ꂼ��̍�i�̊̂����A�q��r��ǂނ��тɁq�d���r���A�q�d���r��ǂނ��тɁq��r���z���o�����̂́A�����ɓƐg�҂��т肪���������Ɨ������߂Ă��邹�����낤���B�\�\�Ƃ��������q�Ŋe���т����Ă������̂ł́A���肪�Ȃ��B��������͓���̒��ю��s�킪�o�_�E�킪�����t�ɍi���āA�g�������Ƃ̊֘A���l���Ă݂����B����ɂƂ��ċg�����q�g��i���Ɏ~��r�i�������сE10�j�����ʂȍ�i�������悤�Ɂi����N�v�q�u�g��i���Ɏ~��v�̎v���o�r�A�s�g�����S���W�t�t�^�A�}�����[�A1996�j�A�g���ɂƂ��ās�킪�o�_�E�킪�����t�͓��ʂȍ�i�������B�g���͔ѓ��k��E���c���F�E���X�؊��Y�Ƃ̍��k��q�v�z�Ȃ�����̎��l�r�́u��т̒��ю��ւ̖��v�A�����ē���N�v�Ƃ̑Βk�q�͌ЂƂ������E�ցr�ŁA���̂悤�ɔ������Ă���B
�g���@����ς�ڂ��͊�̕��m�A�A�A�n�̐l�Ԃł���B������A�S�e��������ɁA�G�݂����ɑ������Ȃ��ƍ���B�Ƃ͂����Ă��A���͎��ł��邩�炽�������������܂���B���{�ɒ��ю��ŁA����������i�́A����߂ď��Ȃ��ȁB���̂Ȃ��ł́A����N�v�́w�킪�o�_�E�킪�����x�������x�������Ǝv���B�G���I�b�g�́w�r�n�x�͌ܕS�s���炸�����ǁA����͂�͂肽���ւ�Ȓ��ю����Ǝv���B�i��2�j�i�s���㎍�蒟�t1975�N5�����k���W����؎u�Y�NVS�g�������l�A��y�[�W�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�g���@�ڂ��͉��s�Ȃ�ł���B���y���ӎ��I�ɂ��܂蒮���Ȃ��B�敪����Ă���Ƃ��A��������܂Ƃ܂������̂łȂ��ƐM�p�ł��Ȃ���ł��A�����̎��Ƃ��ẮB������A�ǂ����Ă��ł����̂ɂȂ����Ⴄ�B
�����@�Ƃ��낪�A�Е��ɗ���Ă���悤�ȁA�ڂ��Ă����ĕς��Ă����悤�Ȃ��̂�����Ƃ������ƂŁA�펯�I�ȉ��������Ă�Ƃ���A�g������͂��ƃV���[�I�Ȃ��̂����D���ł��傤�A�y���F�̂��̂Ƃ��A������������|�p�����D�����Ǝv����ł��B�����͉��y����Ȃ�����ǂ��A�͂��т�����B�������������Ă����āA���^�I�Ȃ��̂����Y�~�J���ɓW�J����Ƃ���́A�ĊO���̋g������̎��������Ă����̗v�f���ƌ������Ȃ����ȁB�܂�A�����I�Ȃ��́A�������ւ̊S�Ɠ����ɁA���I�Ȃ��̂łȂ��ăV���[�I�Ȃ��́\�\�������Ă��܂��āA���I�ȗ������݂����Ȃ��̂ɓ�����ē������́\�\�ɂƂĂ��䂩��Ă�����ʂ�����B
�g���@�y������̂��̂͂܂���������Ă��Ȃ����ǁA���̕��x�͖{���ɂт����肵���B�����������E�͂�͂莍�ł��G�ł��Ȃ����A�P�Ȃ�ŋ��ł��Ȃ��A�S�R��������̂ł���B�����������͂ł��邩�ǂ����킩��Ȃ����ǁA���セ�����������V�������Ƃ���ꂽ�����Ă݂����B�Ƃ���ŁA����N�́u�킪�o�_�v�͔��Ɏ����I�ȍ�i���ˁB
�����@�l�I�ȈӖ��ł͑厖�ȍ�i�Ȃ�ł��B�˂������čl���āA�����̍�i�̂Ȃ��ł������̂��ǂ����͂悭�킩��Ȃ��ɂ��Ă��B�i��3�j
�g���@���̎u�����鐢�E�͂ڂ����킩���ł���B�y������ւ̎��Łu�����͂ǂ��ɂ��邩�H�v�Ƃ�����i�������ł����A�������{�I�Ȃ��̗̂v�f��������ł���B�ڂ����y���Ȃ���A�������{�I�Ȃ��́A����͂��Ƃ��Ƃ����Ă������A�����Ă������E�����A���t�Ƃ��Í��̐��E�Ƃڂ������̌��݂̐��E�Ƃ̍������ł�����A�����������E�����肽���Ƃ��������Ȃ�ł���B�����������������{�̌ÓT���Ƃ肱��ł��������ƍl���Ă���B�i�s���㎍�蒟�t1967�N10�����k���W���g�����̐��E�l�A�ܘZ�`���y�[�W�j
�O�҂̍��k��́s�T�t�����E�݁t�́A��҂̑Βk�́s�_��I�Ȏ���̎��t�̏�����������ł��������̂��̂ŁA�g���ɂ͎����Ȃ�́u���ю��v�ւ̖�S������������i��4�j�A�s�킪�o�_�E�킪�����t�͉i�����Ƃ�����������ĂĂ�����i�������Ƃ����悤�B����ɁA�g��������̍�i�ɂ���قǎ����������R�́u���ю��v�̖ʂ����ł͂Ȃ������B����́u���p�v�̖��ł���A�u�T���v�̕��@�������ƍl������B�u���p�v�Ɓu�T���v�̕��͂̂��قǏq�ׂ�Ƃ��āA�s�킪�o�_�E�킪�����t�͋g��������Ƃ̑Βk�Ō��y�����y���F�ɍŌ�ɕ������Ǔ����q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�̎��ƍ\���ɑ傫�ȉe����^�����ƍl������B�����т́s�V���t�i1986�N6�����j�Ɂu���ю��\�\�y���F�Ǔ��v�i�W��̑O�ɂ���j�Ƃ��āA�k�T �����̔ߖl�k�U ���\�b�h�l�k�V �e�L�X�g�l�k�W �̉��lj��l�k�X �i����̂̍̏W�j�l�k�Y �҉́l�k�Z ���ƐΕ��l�k�[ ���ߐS���l�̑S196�s���f�ڂ��ꂽ�B�s�y���F��\�\�q���L�r�Ɓq���p�r�Ɉ˂�t�́q�⑫�I�Œf�͓I�Ȍ㏑�r�ɂ́A�{�삪1986�N4��15���i�g����67�̒a�����ł���j�Ɋ��������Ƃ���i�����A�}�����[�A1987�A��O��y�[�W�Q�Ɓj�B196�s�͋g�������ɂ����Ē��ю��q�g��i���Ɏ~��\�\�w�f�B���q�����A�W�A�T���L�r���r�i���̎����܂��A�g����41�̒a�����Ɋ��������j��11��257�s�Ɏ��������ł���A���ю��̖��ɒp���Ȃ����ł���B�q�g��i���Ɏ~��r�����̎����ɂ����T���ɂ��đS�̂��\�����Ă���̂ɑ��āA�q������ܒf�����сr�͖����Ɂu�����̍�i�́A�����ɓy���F�̌��t�̈��p�ō\������Ă���B�܂��ނ̗F�l�����̌��t����A�⏕�I�Ɏg�킹�Ė���Ă���B�v�ƒ��L������悤�ɁA�����ɋL���ꂽ���̂���ł͂Ȃ��A���́u�y���F�̌��t�v����肱��ł���B�����錻���ŋL���ꂽ�߈ȊO������ƁA�k�V �e�L�X�g�l�i�u���m���Â�n���m���Â��n�ď��̎���H�݁^�k�c�c�l�^�n���ɑ��ށv�j�͈Í������̃t�F�X�e�B�o���u���������^�W���v�ł̍u���̂��߂̃e�L�X�g������Ƃ��ɁA�y�����Q�l�ɂ����s���{��ًL�t�\�\���̓��{�̕������b�W�̎n�c�̒�{�͉����Ê�E�t���a�j�Z���s���{��ًL�k���{�ÓT���w��n70�l�t�i��g���X�A�����F1967�N3��20���j�ł��낤���i��5�j�\�\�ɋ���B�k�Y�@�҉́l�i�����Ӂ^��m���Ɓn�̂��Ƃ��^�N�͗����^�k�c�c�l�^�����m�����n�^�Ŗ�Ȃ��^�Ŗ�Ȃ��^�Łc�c�j�́q���́r�i�Ђ������́^�V�m���߁n�̉����m�������n��^���̏Ƃ�^���͂Ɂ^�����m�Ƃ��܁n�ɂ��n�鍔�m�����Ёn�j���A�o���Ƃ��ɖ��t�ʂ��ł���B�����̌Ì�ɂ��߂́u�y���F�i���g�j�̌��t�v�ł����Ȃ����A�k�V �e�L�X�g�l�́A�ق��Ȃ�ʓy�����s���{��ًL�t����������ӏ��ł���B�����āA�Î��ɑ��������̂̐����������g���̎���Ǝv�����q���́r�̖����u���m�����Ёn�v�́A�����̌Ö��ł���B�摖���Ă����A�u�Ñ�ɂ����ẮA���͗썰�����҂̍��։^�Ԃ��̂ƍl�����Ă����v�Ɓq�킪�����i�����j�r�ɏ���������́A���O�Ō�̑S���W�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1994�t�́k�㊪�l�����Ɂq�O�ۂ̉��\�\�����ɑ�ւār��u���āA�k�����l�����́q��L�r�ɒu�����s�Y�ӏM�\�\�킪�n��������t�ւ́u�t���v�ƂƂ��ɁA���҂Ɏ������ɐȂ��ƂƂ����B���ɂ́A�g����������N�v�́s�킪�o�_�E�킪�����t�̃��~�j�T���X�̂��ƂɁ\�\�Ȃ��Ȃ玍�т����M����܂��ɓǂݕԂ��܂ł��Ȃ��A�g���̔]���ɂ͂��̎��ƕ��@�����܂�Ă����ɈႢ�Ȃ�����\�\�y���F��Ǔ����钷�ю��𐬂����Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�����āA����N�v�́q������ܒf�����сr�ɂ�����u�썰�����҂̍��։^�Ԓ��v�ƁA�����ɂ͂Ȃ��u�M�v�ɂ���Ď��g�̑S���s������A�c�]�̎��W�͂��Ɂs���V�N�v�q���r�W���t�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B
 �@
�@
����N�v�s�킪�o�_�E�킪�����k���y�����Łl�t�i�v���ЁA1969�N2��15���A����E����F���R�r�v�j�̔��ƕ\���k���Łi����700���j�͓��A1968�N4��1���l�i���j�Ɠ��E�{�����y�[�W�i�E�j
�s�킪�o�_�E�킪�����t���Łi����700���j��1968�N4��1���A�v���Њ��B���̌�A����̌l���W�i�S���W��I���W�j�ɉ��x�����^���ꂽ�͓̂��R�̂��ƂȂ���A�s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�A1973�N4��5���j�ɂ́A���ł����������R�r�v�̑��������������̎��M�����A�q�u���Ƃ����v�r�܂Ŋ��S���^���ꂽ�i���Ȃ݂ɓ������^�̋g������i�́A���W�s�m���t�S�сj�B�����O�Ō�ɖڂ�ʂ����ł́A�r�V�Ď��l�ҏW�ɂȂ�s���{���w�S�W�k��29���l�ߌ��㎍�́t�i�͏o���[�V�ЁA2016�N9��30���j�ŁA�q�킪�o�_�r�Ɓq�킪�����i�����j�r�͑S�т����߂�ꂽ���A�q�u���Ƃ����v�r�͓����Ă��Ȃ��i�t������A1967�N4���Ɂq�킪�o�_�E�킪�����r�����\���ꂽ�G���s���Y�t�́A�ق��Ȃ�ʉ͏o���[�V�Ђ���o�Ă���j�B�s�ߌ��㎍�́t�͎��ƒZ�̂Ɣo�傩��I�ꂽ��i�ō\������Ă��āA���̑I�҂͒r�V�Ď����̐l�ł���B�����̒r�V�́q����r��������B
�@���̊��̋ߌ��㎍�̕����A�ڂ��̃Z���N�V�����ɂ��ẮA����܂łɓǂ�Őe����ł�������I�ƌ��������Ȃ��B����Έ�l�̖}�f�Ȏ��̓ǎ҂̋L���ɂ��鎍�тł���A�����͍L���m��ꂽ�A���\���W�[�E�s�[�X�ł���B�i��6�j
�@�k�c�c�l
�@���̎��X�ɏ����ꂽ����~���Ĉ��̐��ɂȂ������Ɉ���̎��W�ɂ���Ƃ����̂��ʗႾ���A�͂��߂��為���̍\�z�̂��Ƃɒ������������Ƃ��ł���B�������͈�̐��E�����o����B���������傫�ȍ\�z�̐��ʂƂ��ĎO�̎��W�����߂��B���Ȃ킿�\�\
�@�@����N�v�@�@�w�킪�o�_�m���Â��n�E�킪�����x
�@�@�J��r���Y�@�w�^���}�C�J�U���c荁m���n�x
�@�@�����r�Y�m�ނ��n�@�@�w�o�̓��x
�@����ƍ����̍�͂ǂ�����w�Î��L�x��w���y�L�m�ӂǂ��n�x�ȂǓ��{�̌ÓT�ɑ������Ă��āA�`�����p������p���������ƌ�����B���������y��̏�ɁA����͖S���Ȃ����F�l�̍������߂闷���o�_�ւ̋A�҂ɏd�ˁA�����͏����������ɂ����ꑰ�̌n�����Č�����B�J��͕����l�ފw�����ڂŌ��Ȃ���U�̃G�X�m�O���t�B�[�i�������j���\�z����B
�@���̎O��ɂ͂ǂ�ɂ��������t���Ă���B��\���I�̎��ł�����̌���Ƃ����s�E�r�E�G���I�b�g�́w�r�n�x�Ŏn�߂�ꂽ�����ŁA�{�������肬��܂ň������߂���ň�m���Ӂn�����̂��ǂ��ǎ҂Ɏ�n�����A���̍H�v�̈�ƌ�����B�ڂ������̑S�W�̑�ꊪ�w�Î��L�x�Ŗɋr�����������̂������v�����炾�������ƍ��ɂ��Ďv���B�����U���ŕ₤�Ƃ����Ӗ��ł͉̕���̍H�v�Ɍq�m�ȁn�����Ă���̂�������Ȃ��B�G���I�b�m�Ɓw�Î��L�x�̊Ԃɉ�H���ʂ���B���w�̕��Ր��͂����܂ōL�����Ă���B�i�����A�l�Z�܁`�l�Z���y�[�W�j
�Ƃ����킯�ŁA�{�e�ł́s�킪�o�_�E�킪�����t�̒�{�Ɂs���{���w�S�W�k��29���l�ߌ��㎍�́t����B���āA�q�킪�o�_�r��13�̃p�[�g�i�ȉ��ł͏͂ƌĂԂ��Ƃɂ���j���琬��B�S�т��Ƃ肠���邱�Ƃ͂��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�S�̂��\����͂Ƃ��āu�U�v�������B���������E�F�u�T�C�g�Ɉ��p����̂�����A�q�킪�o�_�r�{���̊Y���ӏ��Ƀ����N���āA�q�킪�����i�����j�r�ɔ�Ԃ悤�ɂ��Ă݂悤�B�Ȃ��A����̖}��I�ȕ��͂ɂ���悤�ɁA�q�킪�����i�����j�r���́u�L�v�́u�Î��L�v���A�u�I�v�́u���{���I�v���w���i�����̒�{�͊�g���X�́k���{�ÓT���w��n�l�ŁA�����K�F�̕\���̂��̑p���͋g�����̏��ւɂ��������j�B
�@�@�@�k�q�킪�o�_�r�l�U
���łɂ��āA��ւ��ˁm�߁n�̂悤�ȁA�o�_�̎̒��ɂڂ��͂���B �ām��ȁn�q�m���n��` �̊����H�́A�ق������̌��ł��ς����B�ٍ��̒j�����������ƕ����Ă���B���̒j���V���痈���B�̂Ђ��₵�������߂����j�B�w�L�̉E�̑�������˂��o�Ă����X�̖_�B���̑��ɂ������ꂽ�����̖_�B�����A���܂́A����Ȓj�ɁA��������Ă͂���Ȃ��̂��B�O�����͂��̎��ɂ��悤�B
����m�₵��n�A
�����m�₷���n�A
�ɐl�m�Ƃˁn�A
�呐�m�������n�A
�@�@�@�o�_���m��������n�B
���łɂ��āA�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���~��̍�
�@�ڂ��@�@���o�@�@�@�@�@�@�@�@���ɁA�^�Ԃ�
�@�@�_�́@�@�@�@�@�@�@�@���̎��̌���
�@�@�@�̒��@�@�𐼁@�@�@�@�Ȃ����������A
�@�@�@�@�ɑ��Ă���B�@�X�ɉJ���ĂсA
�@�@�@�@�@�t�����g�E�O���X������
�@�@�@�@�@�@����G�m�ʁn���B�܂��
�@�@�@�@�@�@�@�V���M�m���߂̂Ƃ�ӂˁn�B����A��
�@�@�@�@�@�@�@�@����A����
�@�@�@�@�@�@�@�M���ˁA�Ǝv����
�@�@�@�@�@�@�ɁA���̉J��������
�@�@�@�@�@�[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B
�@�@�@�i�C�Ⴂ�V�C���j�@�ӉF�m�����n����̖k
�@�@�@��C�@�@�̌��@�@�@�@�̂͂���A��
�@�@�����@�@�l���@�@�@�@�@�@�F�̐�������
�@�r���@�@���m����n���@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ�̓��m���n��C
�đ��Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɒ���������A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ނ��Ɂ\�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌��͂��B
�������ɏo�_�ɗ����̂��B�F�̂�������o�������Ƃ�Ƃ߂ɗ����̂��B�킪�F�A�����̗F�B���Ԃ́A���̒��ŁA�꒹�m�ɂ��ǂ�n�̂悤�ɂق̔������A�Ⴍ���ĔN�V�����_�B�݂����������ɓ��āA�r�R�m����܁n���M�����ɂƂ藎����A������ꂽ�Ƃ����A���̍����B
���ׂĂ����ׂĂƓ��荬��A�N�������A���̕��y��|�m�����n��Ă��ẮA�]�݂��ʂ������ƂȂǓ���ł��Ȃ��B�ڂ����悹���Z�h���b�N�́A���ɏ��]�̊X�ɓ���B�����A����B�킪�ӂ邳�ƁA�\�]�N�Ԃ�́B�����A�����ɂ��A���Ƃ��Đ����m���܂��n�̓��H�̐V�J���A�ƁX�͌��������������Ƃ����̂�����ŁA���̌��X�����藧�ĂĂ���B�v�ҁm�����n��Ԃ��ǂ���̂��Ƃ܂��Ȃ��A�����݂̊����ɂӂ����Ƃ���Ȃ��A�e�F�̍��m���܁n�܂��ɏ��o���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�ł̊C��
�@�@�@�@�꒹
�@�@�@�@�ق̔�����
�@�@�@�@�Ⴍ���ĔN�V����
�@�@�@�@�Ƃ藎�����
�@�@�@�@��������
�@�@�@�@����
�@�@�@�@�Ȃ���
�Ԃ͑傫���X���A��l�̂ǂԐ���n�āA
���̊�m�ɂ��n�̂ӂ邳�Ƃ̉��̉@�ւƓ˓�����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�k�q�킪�����i�����j�r�l�U
��ւ��ˁm�߁n�c�c�ق������̌��@�u�L�v��ɁA
�@�u���m�����n�ɍ��u�m�����n�̔������C�q�m��܂��̂��낿�n�Ȃ��A�N���ɗ��ċi�m���n�ӂȂ�B�����m���n�ꗈ�ʉm�ׁn�����Ȃ邪�́m���n�ɋ����Ɠ������m�܂��n���B���̌`�͔@���m�������܁n�ɂ��Ɩ�Ђ��܂ւA�ށm����n���ڂ͐ԉ���q�m�����������n�@�m�ȁn���āA�g��ɔ����m�������n�����m����n�L��B�v
�@�Ȃ��A���{�{�B�̌`����C����ށm�͂��䂤�邢�n�ɂ݂��Ă�A�o�_�n���͂��̊�̕����ɁA�����ē��ɒ��C�m�Ȃ����݁n�����m�����n�̕����͓��ɂ�����B
�@��͂ɂ������ɂ��ẮA�����Í��ɂ킽���ē`���͑������A���̕����������Ƃ��A�����z�������ׂ����̂̈�ɁA�L�v�����O�́w�H�쉮�~�x���������B
�Ďq�m��Ȃ��n��`�@���C�Ɠ��{�C���ւ��ĂĂ���ג����|���l�����ɂ��邱�̋�`�́A���q�����ۊ�n�̈ꕔ�ł���A���̂��ߒn����`�Ƃ��Ă͋��w�̐ݔ��̗ǂ����ւ��Ă���B�|�P�l�����́u���y�L�v�̎���ɂ́A���̍����Ŗ{�y���痣�ꂽ���F�m�����n�ł���A�u�錩�̓��v�ƌĂ�Ă����B�������̐_�b�ɂ����ẮA�������b��_�m����݂����݂��ق��݁n�̗p�����j�̈�{�Ƃ���Ă���B���݂͔����̐�[����A�t�F���[�{�[�g�œ����������[�ɂ�����ۊւɘA������Ă���B
�ٍ��̒j�c�c�̂Ђ��@�u�̂Ђ��v�ɂ͛��Q�m����n�́u��◁m�����n�́@����^���g���O���v�̃��~�j�b�T���X�������Ă����B�������A�����ł́u�N�s����◐��Ŕ߁^��颗Ί�m�A�A�A�A�n�Ӑl���v�ł��邪�B
�X�̖_�c�c�����̖_�c�c�O�����@�u�_��L�v���䂸��̒i����̎ؗp�B
�@�u�c�c����m�����݁n�����_�m�Ȃ����̂��݁n�A����m���т��̂��́n���薖�m���Ȃ���n���́m�����n���ė��āA�N���䂪���ɗ��āA�E�єE�тɔ@���m�����n�����ӁB�R�m�����n��Η͋��m�����炭��ׁn�ׁm���n�ށB�́m����n���m�܁n�Ñ��m���n�̌��m�݂ān�����ނƂ����B�́m����n�i���䗋�_�m�����݂��Â��̂��݁n���j��������炵�ނ�A���m���Ȃ́n�����X�m�A�A�n�Ǝ�萬���A���m�܂��n�A���n�m�A�A�n�Ɏ�萬���B�c�c�v
�@������܂��o�_���̓V�����ɑ���s�ނ̕���ł���B�Ďq��`�Ɋւ��Ă��̑}�b���z�N�����̂́A�ꏊ����`�ł��邱�Ƃ̂ق��A�O�L�̔@�m���Ɓn���t�F���[�{�[�g�ŘA�����Ă�����ۊւƌ����_�m���Ƃ���ʂ��̂��݁n�Ƃ̊֘A�B�V���獑�䂸��������߂�g���̐_���~�m�����n�����ہA�����͔��ۊցi�O���j���ނ�i���̗V�тƂ�������j�ɍs���Ă������A���点�������Ă������������̈ӂ�\���A���䖼���͑����āA������������B�������A���̌��������䖼�����A���͏o�_�{���̐_�ł͂Ȃ��A�u�L�v�u�I�v�����̍��ɏo�_�ɕ���ꂽ�̂ł���Ƃ�������B����m�₵��n�^�����m�₷���n�^�ɐl�m�Ƃˁn�^�呐�m�������n�^�o�_���m��������n�@���ォ��呐�܂ł́u�o�_�����y�L�v�ӉF�S�̕��̒n�����̗p�B�����́A��������Ďq�E���]�Ԃ̒��C�̓쑤�̌Â����������A�K�������Ďq���珼�]�ւ̃R�[�X�Ɉ�v�͂��Ȃ��B�����͌��݂͈����m�₷���n�s�B�o�_���m��������n�́A���]�s�����̈ꑺ�����������i���݂͓��o�_���o�_���m���������n�j�A���̓ǂݕ��̊���̂ɁA������ۂ�����̂ŁA�����ɕ����ėp�����B
���łɂ��ā^�ڂ��́c�c�@���̈�߂̕����ɂ���č��ꂽ�o�b�e���`�́A�_�Ђ̉����ɂ����m�����n�������ǂ������́B���Ȃ݂ɁA��́A��[���c�ɂ����ł�����̂͒j�_�̎Ђ��A�����ɂ����ł�����̂͏��_�̎Ђ��A���ꂼ��\�킵�Ă���B���m���Łn�͑f��Ɖ��ʁB
�^�Ԃȑ��̎��̌��@�u���̎��v�Ƃ����ȏ�A��͂�A�O�o�́u�ق������v�ł���͂������A�����Ŏ��̈ӎ��ɏ���Ă����̂́A�ނ��뎟�̈�����B
�@�@�u���̖�͈Â�������Ȃ��~�邪���Ƃ��Ԃ����m�Ȃ߁n�����o�����́v �i�k�����H�j
�@���Ĉ��ǂ����w���앗�m�����͂��n�x�̒��ł��A���̉̂̈�ۂ͂Ȃ�������ŁA�u��͂Ȃ߂̎����J�̂悤�ɍ~���v�i�u�Ηj���v�j�A�u�Ԃ��Ȃ߂̎��̖S�삪�ЂƂ�����~�肻�����Ƃ��v�i�u����̗��v�j���A���̍�i�̒��ɉ��x���e�𗎂��Ă���B�V���M�m���߂̂Ƃ�ӂˁn�@�O�o�́A�卑��_�̍��䂸��̍ہA�V����~�����g�҂́A�u�L�v�ɂ��Ό��䗋�_�ƓV���M�_�m���߂̂Ƃ�ӂ˂̂��݁n�i�u�I�v�ł͌��䗋�_�ƌo�Î�_�m�ӂʂ��̂��݁n�j�ł������B���̂悤�ɑ����M�̐_�i�����ꂽ���̂ł��낤�B�u�I�v�ł́A���ۊւ����_���ނ����ɍs���M���V���M�i�F��̏���m���낽�n�D�A���m�܂��n�̖���V���m���߂̂͂Ɓn�D�j�ł���B
�@�Ȃ��A�Ñ�ɂ����ẮA���͗썰�����҂̍��։^�Ԃ��̂ƍl�����Ă������Ƃɂ��ẮA��g��n�{�w�I�x��A�⒍�Q�\�Z�A�Q�ƁB���ڏM�@���c���j�u���ڏM�̘b�v�u���ڏM�̉����v��A�܌��M�v�m���肭�����̂ԁn�u�ɏo�œ�����́v�Q�ƁB���̍Ō�̂��̂ɂ́A���ڏM�Ɓu���݂Ȃ��ɂ��͂�v�Ƃ̊W��������Ă���B���ڏM�I���z�́A���łɃG�W�v�g�̃I�V���X�ƃC�V�X�̐_�b�ɂ�������B
��C�̌������l�̘r���c�c�@�u�I�v�Ė���ܔN�̏��ɁA
�@�u���m���̂Ƃ��n�A�o�_�����m���Â��̂��ɂ݂̂���n�k����荁m����n����l�ɖ��m���فn���āA�_�̋{���C���m����悻�n�͂��ށB�ρA���F�S�m�������̂��ق�n�̖m����ق�n�̎��m�Ɓn��銋�m���Â�n�̖������m���n�Вf���ċ��m���n�ʁB���A��m���ʁn�A���l�m�܂����ЂƁn�̎��]�m�����ނ��n�������Ёm���ӂ�̂₵��n�Ɋ��m���n�Вu����B�k�����A���m����n���Έɕ����y�u���v�Ɂu��v�z�m���ӂ�n�Ƃ��ӁB�V�q�̕��m���ނ����n��܂��ޒ��m�������n�Ȃ�B�l�v
�Ƃ���B�����ŁA�u�_�̋{�v�͏o�_�̌F���Ёi��o�j�̂��ƁB�u�����v�́A�u�L�v�Ɏדߊm�����Ȃ��݂̂��Ɓn�̃R�g�h���^�V�̒i�Ɂu�c�c���m���n�͂�鉩���Ǎ�m����Ђ炳���n�́A���A�o�_�̍��̈ɕ���m���ӂ�n��ƈ��ӁB�v�Ƃ���A���̈ɕ���Ɠ����ŁA���݁A���S�i���i�q�j�R�A�{���̗K���m����n�w�i���]���Ďq�����ē�ځj���߂Ƃ����B
�@�܂��A���́u�������m����n�������l�̘r�v�ɂ́A�G���I�b�g�́w�r�n�x�h�u���l�̖����v�̍Ō�̕����̑z�N������܂��Ă���B
�@�@�u��N�N�̔��ɌN���A����
�@�@���̎��[����肪�o�͂��߂������H
�@�@���N�͉Ԃ��炭���ȁH
�@�@����Ƃ��c�����s���̑��m�����n�ɂ��ꂽ���B
�@�@�I�[�A�l�Ԃ̐e�F�����A���𑴏��m�����n�ւ悹���Ȃ���
�@�@�Ƃ��A�܂��܂Ō@�肩�����Ă��܂���I�v �i���e���O�Y����j�ӉF�m�����n�̐��@�@���]�̓����Œ��C�ɓ����ŁA���݂̓C�E�K���܂��̓A�_�J�C�K���ƌ����B�u���t�W�v�ɂ́A���̐삨��т��̒������C���̂����啔���m���ǂׂ̂������݁n�̉̂����B
�@�@�u�K�F�m�����n�̊C�̉͌��̐璹���m�ȁn�����Ό�m��n�����ې�̔O�m�����n�ق�炭�Ɂv �i�O�E�O����j
�@�@�u�K�F�m�����n�̊C�̒����̊��̕ДO�m�������n�ЂɎv�Ђ�s���ޓ��̒�����v �i�l�E�O�Z�j
�@�ӉF�여��́A���Əo�_�����Ƃ̂������n�Ƃ��āA�Ñ�o�_�̐����I���S�n�ł���A�������⍑�{�������ɒu���ꂽ�B���݂ǂ�̓��m���n��C�m���݁n�@�O���̔@���A�u����C�v�͒��C�ł���B�����Ƃ��A�u�o�_�����y�L�v�ł́A���C�A�����Ƃ��Ɂu���C�v�ƌĂ�Ă���B�u���݂ǂ�́v�͗[�z�̊C�����A�����ɁA���o�̃��}�^�m�����`�̊�A����ю��̔@���`�ʂ̑z�N������B�i��������u�_��L�v�j
�@�u���m���n�̕�������A���m���Ƃ��Ɓn�ɏ�m���n��������ࣁm�����n�ꂽ��B�v
�@�u���̎ցm���낿�n���U�m�͂Ӂn�肽�܂Ђ����A��́m�Ђ̂��́n���ɕρm�ȁn��ė��ꂫ�B�v
�@�����āA�w�}�N�x�X�x��\��̗L���Ȃ���ӂ������o���܂ł�����܂��B�����^�Ё^���^�ނ��Ɂ\�\�@�{���̌�ӂ̂ق��ɁA�u�r�������ނ��v�̘A�z�������Ă���B
���̌��͂��@�@�u�c�c�͂�v����ŏ��Ɏv�������Ԃ̂̓��}�g�^�P���́u���Â܂͂�v�ł��邪�A�u�o�_�����y�L�v�H���m�������n�S�ɔ_���̏��ɂ́A
�@�u�V���y�u���v�Ɂu���v�z�Ó������m���߂݂̂��Ђ߂݂̂��Ɓn�A������s�m���n�ł܂������A�����m�����n�Ɏ���܂��āA�فm�́n�肽�܂Ђ����A�w�ɔ_�m���ʁn�͂�x�Əق肽�܂Ђ��B�́m����n�A�ɓw�m���ʁn�Ƃ��ӁB�v
�Ƃ���B���́u�ɔ_�͂�v�͊�g��n�{�w���y�L�x���ɂ��Ɓu�ɔ_�̐_���܂�ƒj�_�ɌĂт��������v�Ƃ����B�܂������`�����w�k�o�_�����y�L�l�Q���x�ɂ��B�u�ɔ_�͂�̈ɔ_�͏o�_�S�ɓw���̂��ƁB�i�c�c�j�v�_�̂�����o�_�S�̈ɓw����]��ʼn���̏����ꂽ�Ƃ����̂ł���v�ƁB�������ɏo�_�Ɂc�c�@���o�A�u�_��L�v�卑��_�̍��䂸��̒i�ɂ����錚�䖼���_�̖₢�̂������Ȕ��e�B
�F�̂�������o�������Ƃ�Ƃ߂Ɂc�c�@�s���m���܁n�܂��t�̃e�[�}�́A�{�т̏c���̈�����A���̃e�[�}�Ɋւ��Ă͂Ȃ��A���I�X�g�́w������I�������h�x�Ȃǂ��Q�ƁB
�����̗F�@�s�����ҁm�\�W�[�n�t���邢�́s���g�m�h�E�u���n�t�̃e�[�}�́A�×��e�����w�Ɏ��ɑ����������ł͓��Ɂu�L�v�u�I�v�̓V����q�m���߂̂킩�Ђ��n�̑��V�̒i�A����уE�F���M���E�X�w�A�G�l�[�C�X�x�i�Z�E����`���l�j�A�������b�́w�A�~�ƃA�~���x�A�l�����@���u�J���t�E�n�P���̕���v�i�w�������s�L�x�����j�A�|�I�w�E�B���A���E�E�B���\���x�����ӎ����Ă����B
���Ԃ́A���@�����ł͕K���������ڂ̊W�͂Ȃ����A�t�����X���la nuit des temps�́u��Áv�u�L�j�ȑO�̈Í�����v�̈ӂŗp������B�꒹�m�ɂ��ǂ�n�@�j�I�ȃJ�C�c�u���B
�@�@�u�꒹�m�ɂقǂ�n�̐��m���Án���r�������날��ΌN�ɌႪ���ӏ�m������n�����ˁv �i�u���t�W�v�l�E����܁j
�@�@�u�c�c�꒹�̂ȂÂ��Ѝs���@�Ɠ��m���ւ��܁n�́@�_���Ɍ����ʁ@�Ⴊ�v�ւ�@�S�a�m�ȁn����Ɓ@�������ā@���ނƎv�Ђāc�c�v �i���E�A��܁E�O�Z�j
�@�Ȃ��A�u�꒹�́v�́u���Â��v�u���Áv�u�ȂÂ��Ӂv���̂ق��A�u���ы��v�ɂ������閍���m�܂��炱�Ƃn�B�܂��u��̕����m�������n�v�͕s����Ȃ��̂̂��Ƃ��B�����Łu��v�͂܂��u���Ӂv�Ƃ̉��ʂɂ��A�u�ق̔����v�ւƂ�Ȃ�B
�@�����c�������ΗV�тɍs�������]��̖x�ɂ́A�����J�C�c�u�������āA���������蕂�肵�Ă����B���ł͂��̖x�����Ȃ薄���Ă��A�c���������ɂ́A���x�s���Č���Ɣ������j���ł����B�Ⴍ���ĔN�V�����_�c�c�@�ȉ���s�A�V����q�`�����̎ؗp�B
�@�V����q�́A�o�_�Ɏg���ɍ~��Ȃ��甪�N���������Ȃ��B�����ŗl�q�����ɗ���賁m�����n�̚j���m�Ȃ��߁n�����A�ނ͎ˎE���Ă��܂��B��͓V�ɂ܂łƂǂ��A�t�ɓ����Ԃ���āA�V����q�͂��̖�Ŏ��ʁB�V����q�̑��V�ɐe�F�̈��x�u�M�����q���_�m�������������Ђ��˂̂��݁n�����₷�邪�A���̓̐_�͎p�����ɂ悭���Ă����̂ŁA�⑰���玀�l�������Ԃ����Ƃ����������B���x�u�M�����q���͂���ɕ��𗧂āA�u��m�͂��n����\�d���m�Ƃ��邬�n���đ��̑r���m����n��蕚���A���ȁm���n�����K�m���n���������m��n�肫�B���m���n�͔��Z���̗����͂̉͏�̑r�R�m����܁n���B�v�i�_��L�j
�@�܂��A�����̕�������V���瓊���Ԃ���āA���������ʘb�́B�O�o�o�x���̓��̃j�����f�Ɋւ���w�u���C�Ó`���ɂ�����B
�@�܌��M�v�w���҂̏��x�ɂ��A�V����q�`���͑}������Ă���B
�@�{�[�h���[���u�J�T�v�̎��̎�����Q�ƁB
�@�@�u�l�͂��������J�ӂ鍑�̉��ɂ����Ă���B
�@�@�x�݂Ȃ��炵�����͂Ȃ��A�N�Ⴍ���������ɘV���āA�v �i���i���F����j�Z�h���b�N�@���Y��p�Ԃ̈�̏��i�������A�܂��A�o�[�l�b�g�́w���g���E���[�h�E�t�H���g�����C�x�̎�l���Ƃ��āA�O�o�u���ڏM�v�ɂ܂��s�M�q�V�s�E�M�l���Q�t�̃e�[�}�ƁA�������ɏƉ�����B
�����A����c�c�@�ȉ��A�����Y�m�͂���炳�����낤�n�́u���o�V���m�����ł���ǂ��n�v�̃p���f�B�B
�ł̊C�́c�c�@�ȉ��Z�s�́A�O�X�߂̃C���[�W�̕��A�����A�����ł͔m�Ԃ̋�̂����܂��ȃ��~�j�b�T���X�ɂ���čč\������Ă���B���Ȃ킿�A
�@�@�u�C����ā@���̐��@�ق̂��ɔ����v
�@�@�u���H�m���̂����n�́@���ŔN���@�_�ɒ��v
�@�@�u�H���т��@�薈�m�Ă��Ɓn�ɂނ���@�Z�֎q�m����Ȃ��сn�v
�@�Ⴍ���āA�N�V���āA�\�\�Ƃ藎����āA�\�\�������āA���薈�m�Ă��Ɓn�ɂނ���B�u����v�͂܂��u�����v�́u����v�ł�����B���̕����A�u���Y�v�ɔ��\�̎��́A�m�Ԃ̋���u�薈�m�����Ɓn�v�Ɗo���Ă����̂ŁA�u�N�V�����\�\�����ꂽ�\�\������ꂽ�v�ƂȂ��Ă������A�u�薈�m�Ă��Ɓn�v�����ʂ炵���̂ŁA�������߂��B�������Ȃ��u�c�c���v�ɂ������Ȃ��Ƃ��Ȃ��B
�@�Ȃ����d�_�m�₦�����n�_�Ёi��o�j�ɂ͔m�Ԃ̋�肪����A���̋�́A
�@�@�u�a�̂̐Ձ@�Ƃӂ�o�_�́@���d���m��ւ����݁n�v��l�̂ǂԐ��@�������͂���āA�x�̑������]�s����k�̒[�܂ōs���ۂɂ́A�傴���ςɌ����Ă��A�V�_��A�勴��A������A�k�x��Ȃǂ̐��x���z���˂Ȃ�Ȃ��B�������A�����ł͕K�����������̐��x���w���킯�ł͂Ȃ��B�����Q�ƁB
�U�̖͂{���Ǝ������f�������A���̍\�z�̑�Ȃ�Ɉ��|����Ȃ��҂��͂����Ă��邾�낤���B�Ȃ�Ƃ����Ă����̏͂ŋS�ʐl���������̂́A�����Ɂu���̈�߂̕����ɂ���č��ꂽ�o�b�e���`�́A�_�Ђ̉����ɂ����m�����n�������ǂ������́v�Ƃ����i�_�Ђ̐������ے�����j�̕����ɂ��Č��ł���B����͂�������������ǂ̂悤�ɔ��z���āA���M�����̂��낤���B���鎍�z�āA���ꂪ��̌`���Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B���邢�͐�̌`�������ԂƓ����ɂ��鎍�z���킭�B����͏u���ɓ�����P�����̂ł͂���܂����B���̐߂��n�l���d�˂ĂȂ����Ƃ́A�ǂ����Ă��v���Ȃ��̂��B�ł́A������ǂ��蒅���邩�B���Ȃ�܂��A���e�p���̕����ɂȂ�ׂ��}�X�������h���Ă݂�B
�������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�����@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�@�����@�@�����@�@�@�@�@�@������������
�@�@�@�����@�@�����@�@�@�@������������
�@�@�@�@�������������@�@������������
�@�@�@�@�@������������������������
�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@�@�@�@����������������
�@�@�@�@�@�@�@�@������������
�@�@�@�@�@�@�@����������������
�@�@�@�@�@�@��������������������
�@�@�@�@�@������������������������
�@�@�@�@�������������@�@������������
�@�@�@�����@�@�����@�@�@�@������������
�@�@�����@�@�����@�@�@�@�@�@������������
�@�����@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@������������
�������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������
���������{���ɂ͋�Ǔ_�i�B�A�j���̃p�[�����i�i�@�j�j���̂��܂܂�Ă��āA6������1�P�ʂƂ��邱�̃��j�b�g�̕��������̂܂܂ł͂Ȃ����A�����
���łɂ��āA�ڂ��͏o�_�̎̒��𐼂ɑ��Ă���B
�y���~��̍����ɁA�^�Ԃȑ��̎��̌����Ȃ����������A�X�ɉJ���ĂсA
�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B
�i�C�Ⴂ�V�C���j��C�̌������l�̘r�������đ��Ă���B
�ӉF����̖k�̂͂���A�ӉF�̐삪���݂ǂ�̓���C�ɒ���������A
�Ƃ������ʂ���͂������ē`����Ă��Ȃ��A�����A��p�I�Ȑ߂ł���B�\�\�b����₱��������悤�����A��f�̕�����͂ЂƂ̓ǂݕ��ɂ����Ȃ��B���c�����u���S���̎��s���E���獶���ɓǂ݉����Ƃ����A�E���獶��ɓǂݏ��Ƃ����A�E���獶�֓ǂݏ��r���ō��֓ǂ݉���Ƃ����A�l�x�Ƃ��L�Ӗ��ɓǂ܂��u�o�b�e���`�v��������A�v�i����N�v�s�킪�o�_�E�킪�����k�����V�Łl�t��A�v���ЁA2004�N7��10���A�k��y�[�W�l�B���o�́s���㎍�蒟�t1968�N7�����̓����̏��]�j�Ə�����
�@�@�@�E���獶���ɓǂ݉����Ƃ�
�@�@�A�E���獶��ɓǂݏ��Ƃ�
�@�@�B�E���獶�֓ǂݏ��r���ō��֓ǂ݉���Ƃ�
�̇B���킩��Ȃ��B����͉E���獶�ɕ����̂Ƃ��āA�����Ȃ�ɓǂނȂ�A
���łɂ��āA�ڂ��͏o�_�̎̒��𐼂ɑ��Ă���B
�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B
�ӉF����̖k�̂͂���A�ӉF�̐삪���݂ǂ�̓���C�ɒ���������A
�y���~��̍����ɁA�^�Ԃȑ��̎��̌����Ȃ����������A�X�ɉJ���ĂсA
�k�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B�l
�i�C�Ⴂ�V�C���j��C�̌������l�̘r�������đ��Ă���B
���łɂ��āA�ڂ��͏o�_�̎̒��𐼂ɑ��Ă���B
�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B
�i�C�Ⴂ�V�C���j��C�̌������l�̘r�������đ��Ă���B
�y���~��̍����ɁA�^�Ԃȑ��̎��̌����Ȃ����������A�X�ɉJ���ĂсA
�k�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B�l
�ӉF����̖k�̂͂���A�ӉF�̐삪���݂ǂ�̓���C�ɒ���������A
�����āA�Ō�i�ɂ��Ďl�ʂ�߁j�͂�△���Ȃ̂����A
���łɂ��āA�ڂ��͏o�_�̎̒��𐼂ɑ��Ă���B
�i�C�Ⴂ�V�C���j��C�̌������l�̘r�������đ��Ă���B
�t�����g�E�O���X���������G���B�܂�œV���M�B����A�ނ���A���ڏM���ˁA�Ǝv���ԂɁA���̉J�������ė[�z���܂Ƃ��ɏƂ����B
�y���~��̍����ɁA�^�Ԃȑ��̎��̌����Ȃ����������A�X�ɉJ���ĂсA
�ӉF����̖k�̂͂���A�ӉF�̐삪���݂ǂ�̓���C�ɒ���������A
�ƂȂ낤���B����ɓ���́AXII�͂̏I���ł�6������1�P�ʂƂ��郆�j�b�g�����̂悤�ɓW�J���āA�R�[�_��苿������B�{���Ǝ����������B
�@�@�@�����Ȍ��@��
�@�@�ꂪ�ڂ��̋��߂�
�@�������́@�킪�e�F��
���Ł@�ڂ��͂�����@����
�@���邨�����Ł@���̂�
�@�@�̂Ђ�Ɂ@����
�@�@�@�������グ��
�����Ȍ��c�c�@�ȉ��̎��s�ō��ꂽ�Z�p�`�́A�o�_��m��l�Ȃ�A�o�_��Ђ̐_��i�Z�p�`�̒��ɑ�m�A�n�̎��j��z�N����邩������Ȃ����A�_��Ƃ����Ȃ�A���͂ނ���_���_�Ђ̂���i�Z�p�`�̒��ɗL�m�A�n�̎��j�����������B�i�Ȃ��A���̐_��ɂ��āA�_���_�Ђ̈ē����ł́A�u�L�v�̎��͐_���̏\���m�A�A�n�̓��獇�����ꂽ���̂Ɛ������Ă���B�j
���q�킪�����i�����j�r�Ō��y������ȕ����͈ȉ��̂Ƃ���ł���i���o���̂f���A�ǂ݂��Ȃ͏ȗ����A��{�̕\���͊��������B�U�͂͏�ɑS�����������̂ŁA�ȗ��ɏ]���j�B
�u�o�_�����y�L�v
�u���L�v
�u���{���I�v
�T
���z���O�Y�w�o�_�_�b�̐����x
�u�i�s�L�v
�u���_�I�v
�u����k�����l�v
�u�_��L�v
�u�헤�����y�L�v
�u�o�_�����_�ꎌ�v
�����`���w�o�_�����y�L�Q���x
�u�_�y�́v
�\�u����v
��������u�[��v
�u�ɐ�����v
�_���e�w�_�ȁx
�����u�n���L�v
�V
�w�A�G�l�[�C�X�x
���Ït�Ɂw�M���V�A�E���[�}�_�b���T�x
�w�I�f���b�Z�C�A�x
�k�����l�Y�u�n�ʂ̒�̕a�C�̊�v
�m��
�V���o�w�����x
�W
�u�Ôn�y�v
�܌��M�v�w���҂̏��x
�R���Ԑl
��ё��ǁw���{�_�b�̋N���x
�V��u���n�l�`�v
�r���g�[���u���Ə����v
�u���������y�L�E�핶�v
�����L���u������_�v
�X
���_�w�m��ꂴ����{�̖ʉe�x
�ΐ�~�u���є@�D�v
�Y
�w�n�����b�g�x
���c���j�u��ڏ��m�v
�e�I�t�B���E�S�[�`�G�w����̗��x
�I�E�B�f�B�E�X�w�]�g����x
�{���u�k�珫�R�ƎO�l�Z��̈�ҁv
�l�����@���w�I�[�����A�x
�{���u�悭������Ƃ��炢��v
��K���e�w�V��������x
�܌��M�v�u���w�Ƌ����Ɓv
�O�i���p�u�A���l�̐_�b�v
�u���t�W�v
�[
�����ρu�Ñ�̏Ό��v
�\
�w�ȁu���c��v
�Q�[�e�w�t�@�E�X�g�x
�A�|���l�[���u�����čs�����p�t�v
�u�O�������b�W�v
�x�������O�E�O�E���h�w�����w�̘b�x
�]
�|�I�u�A���E�A�[���[�t�v�u�t�F�A���[�E�����h�v
XII
�{�[�h���[���u�����̖��v
�u�m���I�v
�W�C�h�w�e�[�[�x
�u���ˍ����y�L�E�핶�v
XIII
�O�D�B���u�t�̖��v
���e���O�Y�u���l���ւ炸�v
�u�d�������y�L�v
�E����������邾�낤���A����������i���E�����A�������ň��p�������͂̏o�T���͂����������̂������B�����[�����ƂɁA����́q�킪�o�_�r�{���̎���ɂ͈��p�ł��邱�Ƃ������ꊇ�ʁi�u�@�v�j�͈�ӏ����Ȃ��A�M�����i�s�@�t�j����b��\������A�����ł��邱�Ƃ�\������A���p�ł��邱�Ƃ�\�����肵�Ă���B����̂��̒��̕t�������́A�q�킪�����i�����j�r�̇U�͂ɂ��o�ꂷ��A���e���O�Y��̃G���I�b�g�w�r�n�x�̌����i���Ȃ킿���e��j�Ɩi���Ȃ킿���e���M�j�����킹�����̂̂悤�Ɍ�����B����ɑ��āA�g�������ɂ�������p�Ƃ��̏o�T�̕\���́A�ꊇ�ʁi�u�@�v�j��������̊��ʗނŊ����Ĉ��p�ł��邱�Ƃ����A�̎��т̂��Ƃ�
����Җ��i��Җ��j�s�����t�����p���Ă���B
�Ƃ����X�^�C������{�`�Ƃ��Ă��āA�ǂ��炩�Ƃ����G���I�b�g�s�r�n�t�̌��������ł���B���̓_�ɂ����ẮA����̂ق����ߌ��ł���A�g���̂ق����Ȍ��ł���B����������Ȃ�A�g�������\�\���Ƃ��Γy���F��Ǔ������q������ܒf�����сr�i�K�E12�j�\�\�ɓ�������̒���t����̂́A��҂̋g���ł͂Ȃ��A�ǎ҂̖�ڂ��Ƃ������ƂɂȂ�B��������̈��p�̃��x���܂ł͂Ƃ������A��s�����i�̃��~�j�T���X�̎w�E�́A�����ɂ��ĉ����̈���o�Ȃ����ƂɂȂ�B�����āA�p�ӎ����ɕt���ꂽ����̎������A�ǎ҂ɂ́u���������v��ǂނ��Ƃ����߂��Ă���킯�ŁA��ؓ�ł����Ȃ����ƂɊւ��ẮA�ǂ��炪�ǂ���Ƃ������Ȃ��B
��
�g��������̎��ɂ��Č��������قǑ����Ȃ������̒��ɁA�s�킪�o�_�E�킪�����t�̎��̎��W�s���Ȃ��ؑl�̉S�t�Ɏ��^���ꂽ���сq�w�}���s�M�[���̊فx�̂��߂̑f�`�r�ɐG�ꂽ���́A���Ȃ킿�q�ѓ��k��u��������́v�E���r�i�s���㎍�蒟�t1967�N12�����j������B�S�����ȗ������Ɍf���悤�B
�@���N�̖���͉����Ɩ���Ă��A�ȒP�ɓ������Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����ǂ�łȂ����A�O�����̍�i�Ŏ��O�������̂����邾�낤����B�L���ɂ���܂܂�����ƁA�A����s�̒��ю��\�����r�Y�s�]�́t�i���肵�āu��v�j�B���������sMy Tokyo�t�B�g�������s�g�̂�_���L�t�B��؎u�Y�N�́q�v�A�v�A���r�̏I���сs�ԊO�������I�v�L�A�v�L�A�ƒ�I��S���t�B����N�v�s�w�}���s�M�[���̊فx�̂��߂̑f�`�t�B��������Ԉ�ۂɂ̂���̂́A�ѓ��k��̘A�쎍�s��������́t�B����ɂÂ��A�ߍ�s���L���ɂ���G�X�L�X�t�ł��낤�B���W�s�����ցt�̑̌��I���E�����]���āA�V���[�����A���X���ւ̉�A�Ƃ������A�V�����ʂ���̉ʊ��Ȓ�������݂Ă���A��̘A�쎍�\�\�����I�s���肳�Ɗ�ɋϐ���ۂ��傫���琬����鎍�I�����𒍎����Ă���B�i�����A�Z�l�y�[�W�j
�s���㎍�蒟�t1967�N2�����Ɂu���ю��v�Ƃ��Ĕ��\���ꂽ����́q�w�}���s�M�[���̊فx�̂��߂̑f�`�r���g�����ǂ��ǂ��L����Ă��Ȃ��͎̂c�O���i���Ȃ݂ɋg���́A�������Ɏ����q������G�r���Ă���j�B�u1�@�\�v����u29�@�����v�܂ł̊e�p�[�g�̂����ŁA�����ɂ�����N�v���炵���p�[�g�́A���́u17�@��`�v���Ǝv����B
�@���Ƃ��A���̊ق��s�������܂ɂ��ꂽ�m�A�̕��M�t�ƒ�`����̂͂����ɂ��C�̂��������Ƃ̂悤�����A����͒�`�ɂ������Ȃ��Ă��Ȃ��B����A�����Ȃ��`�����͂˂̂��A�}���s�M�[���̊ق͒f�łƂ��Ď��݂���B���́s�݂邱�Ɓt�ɂ���āA�����̖����⓳���i�ƁA�ЂƂ̖ڂɂ͌����邱�ƁA�����Ȃ����ƁA�����Ȃ��ƌ����邱�Ɓj�����W���Ȃ���B
���́A�ꌩ����߂ăj���[�g�����ȎU���ƌ��������̂��Ȏ҂��B�g�����q�w�}���s�M�[���̊فx�̂��߂̑f�`�r�Ɠ��n��̐�s��i�s�����Q���n���X���̓��t���u�R���g�v�ł͂Ȃ��u���v�ƕ]�����̂͑쌩�������B������Y�E���ˉ�v�E�g��O�E���C�i��E�H�J�L�E�����ρE����l�Y�E����S���Ƃ̍��k��q��13����{���㎍�l��g���ܑI�l�ψ����k��r�i�s���w�t1963�N7�����k�g���ܓ��W�l�j�́u�I�l�o�߁v�ŁA�g���͂����q�ׂĂ���B
�@�g���@�ڂ��́A�l���̎��W��ǂ�ł݂܂������A�k�c�c�l���_�I�ɂ͓���N�̎��W�k�w�����Q���n���X���̓��x�l�Ƃ������܂����B���̎��W�́A�ŏ��̂��뎄�A�R���g���ƁA���������l���ł݂Ă���܂������A�悭�ǂ�ł݂܂��Ƃ܂�����Ȃ����Ȃ̂ł��B���łȂ���Ώ����Ȃ����т�������Ƃ������A�y���ȃ��[���A��������Ă��܂��B�ق�Ƃ��̈Ӗ��̃��[���A������͓̂���N�̎�����Ԃł��B�ꂢ���[���A�ł��邩���킩��܂���ǂ��I�n���̂��������Ă���B����N�̈ȑO�ɂ��������͋ꂵ��ł����Ă��܂������A���̎��W�͂��̂��݂Ȃ��珑���Ă��܂��B���́A�ꂵ��ŏ����̂�������ł�����ǂ��A�y����ŏ����A�ł������̂̊����x�������Ƃ������̂�����܂��B���������������N�͏����Ă���̂��Ƃ������܂��B����N���ǂ��������E��`���Ă���̂��͂���킩��Ȃ�����ǂ��A����ǂ̌��ɂȂ����W�̂Ȃ��ł͂��ʂ��Ă���Ƃ����ē���N�𐄂��܂����B�k�c�c�l�i�����A�l��y�[�W�j
 �@
�@
����N�v�E�����s�����Q���n���X���̓��t�i���ƔŁA1962�N7��1���j�̕\���ƃW���P�b�g�i���j�Ɠ��u7�v�̊G�i�E�j
�g���͂����ŁA�u�y����Ŏ��������v�Ƃ������悻�s�m���t�̂���̍앗����͐M�����Ȃ��悤�Ȏp���̓]��������Ă���B���̔����́s�a���`�t�i1962�j���s�̗��N�A�̂��Ɂs�Â��ȉƁt�i1968�j�ɂ܂Ƃ܂��i�������͂��߂�����ɂȂ��ꂽ���̂ł���A�s�m���t�i1958�j���l�ȂƂ̎����i�ޏ��͋g���̐e�F�E�g�c���j�̏����̐l�Ƃ��āA���j���N��̏����ƐS���������ƁA�g���̂܂��ɉ^���I�Ɍ��ꂽ���A���c�唪�v�l�E�\�l�q����Ɉ˂�A���̕v�̓C�g�R�������ߎq��������Ȃ������Ƃ����j�̂͂Ăɐ��݂��Ƃ��ꂽ�̂ɑ��āA�z�q�v�l�Ƃ́A40�Ƃ����ӂ��������o�ĉƒ�I�ɂ����������������琶�݂����ꂽ�A�Ƃ����Ⴂ�͑傫���B�Ɛg����́A�Q���ɕ������ɂȂ��Ď���ɖ{�̎R��z���Ď��삵���A�Ƌg���͂ǂ����Ō���Ă����B����A�ƒ�������Ă���́A�H��̂����Ɍ��e�p�����g���Ď����������Ƃ�����Ă���B���̎p���̈Ⴂ�͑傫���B���Ȃ݂Ɏ��́A���e�̎��M�ɂ̓p�\�R����p����B�l�͂ɏ��Ђ�G���A�R�s�[��Ԃ����t�@�C�������߂��I��߂��炵���A�I�|���̂��鎖���֎q�ɍ��邽�߂ɂ́A�e�P���[�T�[���R�b�N�s�b�g�ɐ��肱�ނ悤�ɂ��āA��ʒu�ɂ��ǂ���K�v������B�����̓��e�肱���e�́A�`�S�̗p����2�ʕt���Ńv�����g�����Q�����N���b�v�{�[�h�ɋ���Ԃɂ��āA�x�b�h�ɉ������Ȃ���i�Ƃ������Ƃ́A�����������A�Q�̑O�j�A�ԂƗ̐����{�[���y�����g���āA������Ă����B����������[�����o����̂́A���̏��Z�ւ̐ԓ���̂Ƃ����B���e�̎Y�݂̋ꂵ�݂́A�����ŕ����B�����킷�ꂽ���A���p����o�T�\���́A�c�����o�͂����v�����g�A�E�g�����M�̂Ƃ��Ɠ����p���ŁA�ƍ�����B�����A�����Ƃ��͐����ŁA�ǂނƂ��͐����ŁB�����̍�Ƃ̗���́A�g�������z�q�v�l�Ƃӂ���ōs�������̂Ɓi�p�\�R���Ǝ菑���̍��͂�����̂́j�A�傫���u���������̂ł͂Ȃ��B����I�ȈႢ�́A�������y�����������_�f���Ȃɂ��̂悤�ɕK�v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��B�����Ƃ��̂a�f�l�́A�b�c���l�c���X�s�[�J�[�Ŗ炵�A�ǂނƂ��̂a�f�l�́A�l�c�i�b�c�̃R�s�[�ȊO�ɁA�����ł������R���s���[�V����������j���w�b�h�t�H���ŁB�Ȃ��A�O�o�����܂߂āA�X�}�z�ʼn��y�͎������Ȃ��B�����{�i�I�ɓǏ����n�߂��̂����Z����A�Ȃɂ������͂��߂��̂���w�O�̂��낾�����̂ɑ��āA���b�N��|�b�v�X�ɖڊo�߂āA�M�^�[��������͂��߂��̂����w����B�a�f�l�ɂ����Ă��A���y�Ƃ͐����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����炭�g���ɂƂ��Ă̎��o�|�p�ɑ�������̂��A���̏ꍇ�A���y�Ȃ̂��B�����₨���납�ɂł��Ȃ��B
�����ŗ]�k�������B�قړ������Ɏ��I�o���𐋂����g�����Ɠ���N�v�́A���w�܂̑I�l�ψ��߂��ۂɁA�g���͓���́A����͋g���̎��W�𐄂��āA�܂̎�܂Ɏ������莊��Ȃ������肵�Ă���i�ڍׂ��q�g�����ƕ��w�܁r���Q�Ɓj�B
�@�@��q�̂悤�ɁA�g����1963�N�A��13����{���㎍�l��g���܂̑I�l�œ���̎���W�s�����Q���n���X���̓��t�𐄂������܂ɂ����炸�B
�@�@�����1976�N12���A��7�����܂̑I�l�ŋg���́s�T�t�����E�݁t�𐄂��Ď��܁B
�@�@�g����1983�N1���A��13�����܂̑I�l�œ���́s���҂����̌Q���镗�i�t�𐄂��Ď��܁B
�@�@�����1984�N3���A��4�̕��w�ُ܂̑I�l�ŋg���́s���[���h���b�v�t�𐄂����g������܂����ށB
��
�s���҂����̌Q���镗�i�t�S�Y�͂̂ӂ��߂́q�U ���˂ցE���˂���\�\��l�̎��҂̂��߂̎l�́r�B���і{���̂��Ƃɂ́A������
�i�{�͂͑S�̂��剪�M�w���˂ցE���˂���\�\��l�̎��҂̂��߂̎l�́x�̈��p�ł���B�j
�ƒ��L�̂���A���̏Ռ��B�剪�̏��������͂����g�̍�i�ɌJ�肱�ޓ���������A��������m�����剪���剪�ł���B���Ȃ݂ɂ��̓�l�͓��N�̐��܂�B
��
���̎����猩���g�����Ɠ���N�v�̊W�̑�v�́A��̂Ƃ���ł���B����ȍ~�A���́q�g�����r�Ɠ���N�v�̊W�ɐG��Ă��A掂��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B��������̒���ōł��e�������̂́A���̎��W����ł͂Ȃ��B���͎����p�����l�Ԃł���B���̃T�C�g�������̂����ɂ͂��łɂ��킩��̂��Ƃ��낤���A����́s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t�i�}�����[�A1991�N7��25���j�ł���B�����̔����q���W�w�t�ƏC���x�̐����r��ǂ܂Ȃ���A����Ɍە�����Ȃ���A�����q�g�������W�s�Õ��t�e�{�r�����̂悤�Ȍ`�ł܂Ƃ߂悤�Ƃ����C�͋N����Ȃ��������낤�B�����ɂ͎��l�E���_�ƂƂ��Ă̓���N�v�͂������A1�N���Ƃ����Z�����Ԃł͂��������A�}�����[�ŋg�����Ɗ�����ׂ��o�Ől�Ƃ��Ă̌o�����ۂ��Ɠ��e����Ă���B����̍ŗǂ̕������\�ꂽ���͂Ƃ��āA��������ɋ����鏊�Ȃ��B�����̓���N�v�́q�o�����r�i�����A�l���܁`�l��Z�y�[�W�j�͎��̂悤�Ȃ��̂ł���B�����{�T�C�g�Ɏ��M�������͂���{�I�Ɂs�G���t�ł���A���̂Ƃ��ǂ��́s���t�ł���_�A�q�o�����r�́u�⒍�v�\�\�d�v�Ȃ��݈̂̂������\�\�������i�p�ɂɁH�j���݂鎄�́k�NjL�l�̐��ł���_�ȂǁA������������肪�Ȃ��B���Ƃقǂ��悤�ɁA�����̍\���E�\���̓E�F�u�T�C�g�Ɛe�a���������̂ł���B
�@�����ɂ́A��������܂ŋ{���ɂ��đ����Ƃ����̏�ŏ������U���̂قƂ�ǂ��ׂĂ��W�߂��Ă���B�i�u�قƂ�ǁv�Ƃ������̂́A���܂�ɂ����y���f�ГI�Ȃ��̂�A���e�ɂ������邵���d���̂�����́A����ɑS�W��I�W�̉���Ƃ��ď�����Ă��Ė{�����Ȃ���ΈӖ��������Ȃ����̂ȂǁA�����������_�����Ȃ��Ă��邽�߂ł���B�j
�@�����̕��͂́A�ꌫ����i���ǎ҂̐܂ɂӂ�Ắs�G���t���A�����Ȃ���i���̂ق����ʓI�ɂ͗y���ɑ����̂����j�A��㎵�Z�N��ȍ~���x���̌����S�W�̕ҏW�ɎQ�������҂Ƃ��Ắs���t�ł����āA�����_���Ƃ��]�_�Ƃ��Ă��ɂ͉����Ȃ����̂���ł���B������A����ꊪ�ɂ܂Ƃ߂�̂́A���������āA�u���̌����_�v�𐢂ɖ₨���Ƃ����Ӗ���������ł͖ѓ��Ȃ��B��L�̂悤�ȓ��e���炢���āA���ꂪ�A�Ђ���Ƃ�����A�ߋ����獡���܂ł́s������e�̗��j�t�̈ꑤ�ʂɑ��āA����ꂽ�p�x����ł͂���A������x�̏Ɩ��Ă���A�����������Ӗ��ł́s�����t�ɂ͂ǂ���琬�蓾��̂ł͂Ȃ��낤���ƁA�ӂƎv��������ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���̊ϓ_�ŕ҂܂ꂽ�{���́A���ɑウ�Ċ����ɒu�����ꕶ�ƁA�����ɂ܂Ƃ߂��Z�����]�E���]�Q�Ƃ������āA���S�ɏ����ꂽ�����ɂ��������Ĕz��Ă���B�T����V�͕̏����́A�T�́A�����w�Z�{�{���S�W�x�̎d���Ɍg�������ȑO�Ɂi�܂�A�����̌��e�̎��Ԃɂ��āA�قƂ�ǒm��Ƃ���Ȃ��Ɂj���������́A�U�́A��L�S�W�Ɋւ��ҏW�Z����ƂƁA����ƒ��ڂɂȂ����n���̎����A�����ćV�́A����Ȍ㍡���܂ł̂��́A�Ƃ���������łȂ���Ă���B
�@���̂����A�U�ɑ�������̂ɂ́A����炪���܂��܂ɈقȂ����ꏊ�ɏ����ꂽ�s���t�ł���Ƃ������i��A���ꎖ���̌J��Ԃ���A�d�������������Ɍ����邪�A���܂�ɂ��r�������ӏ����������āA���̂܂܂ɂ��Ă���B������s�����t�Ƃ��Ắu���ꊴ�v���������������߂ł���B�܂��A�A�ڕ��̈ꕔ�ł��邽�߁A���ꂾ���ǂނƏ����o�������˂Ȋ���������Ƃ��������̂��A�����ĕ�����Ă��Ȃ��B�ُ̍�⍬��������邽�߂́A��ނȂ������͍ŏ����قǂ��������A�L�q�̓��e�Ɋւ��ẮA���݂̖ڂŌ��Ē�����v����Ǝv���ӏ�������������A�ȉ��Ŏ�̕⒍��������݂邾���ɂ���B�J��Ԃ����A���ꂼ��̕����A�ߋ��ɍs�Ȃ�ꂽ���@�����̕����̂��Ƃ����̂Ƃ��āi�����ɋL�������\�������l���ɓ���j���ǂݒ�����K���ł���B
�E�u�l�������E�̏C���v�@�@�{���͇U�̃p�[�g�ɑ����ׂ����́B���̕��Ɋւ��ẮA���q�������w�A�C���V���^�C���E�V���b�N�x�U�̈�l�y�[�W�ȉ����Q�Ƃ��ꂽ���B�@�Ȃ��A�����ɂ��ď��������邢�͈ꕔ���y�������͂̂����A���e�d�����̑��̗��R�ɂ��{���Ɏ��^���Ȃ��������͈̂ȉ��̒ʂ�ł���B
�k�c�c�l
�E�u�w��͓S���̖�x�̔��z�ɂ��āv�@�@�����W�̒��Łu�C�M���X�C�݁v���e�̃C���N�̐F�ɐG��Ă��邪�A���̌�̒����ɂ��A���͂���͊��ɐ����e�Ȃ̂ŁA�����Ō����Ă��邱�Ƃ͈Ӗ��������B�Ȃ��A�吳�\��N���̌����ɈӒ��̏��������������ǂ����́A���̌コ�܂��܂ɘ_������悤�ɂȂ������A���_�͏o�Ă��Ȃ��悤���B
�k�c�c�l
�E�u���ȋL���@�̂͂Ȃ��v�@�@���̓�́A���݂��܂������Ă��Ȃ��B���S������̕�������A���������������B
�k�c�c�l
�E�u���W�w�t�ƏC���x�̐����v�@�@�����ߒ��̐����Ɋւ��ẮA����Ɍ�o�́u�����v�i���Z�y�[�W�j�A�u�w�t�ƏC���x�����ߒ��Ɋւ���c�c�v�i�O�O�Z�y�[�W�j��A�u�w����ꂽ�����x�̂��Ɓv�i�O�����y�[�W�j���Q�Ƃ��ꂽ���B
�k�c�c�l
�E�u�w��͓S���̖�x�̖{���̕ϑJ�ɂ��Ă̑Θb�v�@�@���̕��̏I�肿�����ŏq�ׂ��Ă���u���z�{�v�́A���̌�A�V�C�ŁA�����ܕ��ɔł̓�S�W���̑��Ŏ��������B���e�̏ڍ���t���S�t�����́A�܂����݂��Ă��Ȃ��B�i��7�j
�k�c�c�l
�E�u��̒��Ԋ��ɒ����āv�@�@���̌������e�Ƃ̊ւ��ɂ�����ЂƂ̐ߖڂ����邵�Ă���Ƃ����_�ŁA���̈����̂��镶�́B
�E�u���̖{���̂��ƂȂǁv�@�@���̕��\���Ă���ł��A�����\���N�����o�����̂ɁA�����N�t���݁A��g���ɂ́w�{�����W�x�́A��������炸�Â����̑����`�̂܂܂ł���B
�k�c�c�l
�@�@�k�c�c�l
�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�I��ɂȂ��Ă��܂������A�����ŁA�{���̓��̖ڂ�����ɂ��āA���܂��܂ɂ����b�ɂȂ������X�ɐS����̌���\���q�ׂ����B���ɁA���ڕҏW�ɓ�����A�\�����̑��A�ʓ|�Ȃ��Ƃ����������Еt���A�����̍����܂ō���ĉ��������A�ҏW���R�{���r���ɂ́A���̐\���グ�悤���Ȃ��B
�@�@�@�����N��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����
�����ҏW�ψ����S���𒍂����s�Z�{ �{�V�����S�W�t���\�\���������u�Z�{�v�Ƃ͏���ٖ̈{���Z�����A���̖{���̈ٓ����������{�̂��Ƃ������\�\�A���̍Z�ق��A�ǂ̂悤�Ȏp���ŏ����ꂽ���ɂ��Ă����ŐG�ꂸ�ɂ��܂����Ƃ́A���ɂ͂ł��Ȃ��B
�@�k�c�c�l�u���ڂɌ������ɓ��������҂��A�M�����ċ��菊�Ƃ��邱�Ƃ��ł�����́v����悤�Ǝu�����Z�{�S�W�̍Z�ْS���҂́A���M�ɓ����Ă̈�v�����S���܂��i�Ƃ����������Ƃ������j�́A㋑�������܂��A�m���ŋ�̓I�ȁi��������j�������A�\�Ȃ�����ԗ��I�ɁA�����m�ɒ��邱�ƁA㋺�m���ŋ�̓I�ȁi��������j�؋��ɐ���ĂȂ���錵���Ȑ����ɂ���ĕK�R�I�ɓ����錋�ʈȊO�́A��̉��������т������ނ��ƁA㋩����ȊO�ʼn��炩�̕K�v�i���邢�͈��������̐����j�ɂ���āA���_���L������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̐��_�̘_�������A�������L�q���Łu�m���Ȏ����v�Ɓu���_�ɂ���ē���ꂽ���ʁv�Ƃ̋�ʂ���ɂ͂����肳���Ă������ƁA㋥�����̎�������͔���s�\�ȓ_�i���邢�͌������Ȃ������Ɋւ��鎖���j�ɂ��Ă͈��ՂȐV���𗧂Ă��A����������ɂ��ď]�����炩�̒ʐ�������A���������̒ʐ�������Ă���Ƃ����m���ȏ؋����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�ꉞ�ʐ����i���̂ނ˂��Ƃ���āA�f�������j�L�q���邱�ƁA�Ƃ����l�_�ɗv��ł��悤�B�k�c�c�l�i�q�w�t�ƏC���x�����ߒ��Ɋւ��鍲���������̐V���ɂ��ār�A�����A�O�O���`�O�O���y�[�W�j
���́q�g�����r�́A�k���o�`�l�Ɓk��e�`�l�L����12���̎��W�̖{���Z�ق�S���т́k���o�`�l�̖|�����A�����̍Z�{�S�W�Z�قɊw��ł��邱�Ƃ͕�����Ȃ��B���̐��ʂ̂قǂ��]�]����̂͑��̐l�ɔC����Ƃ��āA�q�g�����r�̖{���Z�ق�|�����܂���Ȃ�ɂ��g�p�ɑς�����̂��Ƃ���A����́A�����̍Z�{�S�W�Z�ق̊�{���j����l�{�������łȂ��A���̉^�p���߂��Ȃ���Εʂ̎��l�ɂ��K�p�ł��镁�Ր��������Ă��邱�Ƃ̏����낤�B��������N�v�́s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t����w�̂́A���������p���������B
�k�NjL�l�Ǔ��E����N�v
�����r�Y�́q��̐l�r�i�s���㎍�蒟�t2019�N2�����k�Ǔ����W�E����N�v�l�j�́A�u�l�ԊW�ɂ����Đq��̈���ĕs��p���v��������N�v������āA�Ռ���^�����B
�@�g������Ƃ̕t�������ł͎�������̂ق����Â��B�������������g������Əo������͓̂���̎��W�w�G�߂ɂ��Ă̎��_�x�̂g����܂��j����ɂ����ĂŁA���Ԃ���Z�Z�N�B����ɉ�����̂����̎����ŏ��������A�Ǝv���B����͂���ȑO����{���S�W�Ȃǂ̕ҏW�̊ւ��ŁA�}�����[�Ζ��̋g������Ƃ͐e���������͂����B���̓�����O���ĕt�������Ƃ��Ă͐V�����A���n�Ȏ����Ȃ��I���B
�@���̋^��͓��R����ɂ��������͂��ŁA���V�����A�⑰���ɗ����ĒN��������ɉ�҂��}���������̂́A�������B���̂��Ƃ��b�����v������҂��������悤�ŁA���C���������Ƃ܂ŏ��������͂��L������������Ȃ��Ȃ��낤�B���̓���̑ԓx�͎��ɂ́A���������V���s�҂���O���ꂽ���Ƃւ̖����̍R�c�̂悤�Ɍ������B���łɌ����A�g�����O�̊�]�Œ}�����[����o���w�g�����S���W�x�����ɂ́u�ҏW�v�Ƃ��āu�ѓ��k��^�剪�M�^����N�v�^�����r�Y�v�̎l���̖�������ł��邪�A�����͓��}���̒S���ҒW�J�k�~��l�����ɁA�قƂ�ǓƂ�œ����������Ƃ��A���L���Ă������B�i�����A�Z�Z�y�[�W�j
����1990�N6��3���̑��V�ɎQ����l�����A��������́u���V�����A�⑰���ɗ����ĒN��������ɉ�҂��}���������̂́A�������B���̂��Ƃ��b�����v������҂��������悤�ŁA���C���������Ƃ܂ŏ��������͂��L������������Ȃ��Ȃ��낤�B���̓���̑ԓx�͎��ɂ́A���������V���s�҂���O���ꂽ���Ƃւ̖����̍R�c�̂悤�Ɍ������v���Ƃ͂܂������L���ɂȂ��i�Ȃɂ����A�g������r���������݂Ŗڂ��������Ă����̂��傫���낤���j�A�����͂��������Ȃɂ����Ă����̂��Ƃ����z���ɉՂ܂��B�t������A���g�����������̂́A���}�����[�ɓ��Ђ���1959�N4����2�N�O�i�Ƃ������Ƃ�1957�N���j�A���̒��Ԃ̐�����q�����Ђɓ���A�s�Õ��t���o�������l�Ƃ��ċg�����̑��݂𐁒��������Ƃ����������������i����̒Ǔ����q�g������̎��r�Ɉ˂�j�B�{�e�`���́A����N�v���g�����ɐG�ꂽ�����̈ꗗ��1990�N�̒Ǔ��֘A��7�{������̂́i�Ƃ�킯�A8���́s�邵����t7���́q�g�����Ȃ��Ȃ�ꂽ�I�r�j�A�e�����玷�M�̈˗����������̂͂�������A�g���̎��ɂ������ĂȂɂ��ł��Ȃ������A�Ȃɂ����Ȃ��������Ƃɑ���Μ��̔O���Ȃɂقǂ������Ă������߂ł͂Ȃ��낤���B����N�v���ҏW�ψ��Ƃ��ČnjR�����i�H�j�����s�g�����S���W�t�i�}�����[�A1996�j�̊����̎��т́A�u����Ő[���Ȉ�ۂ��A�Y���c���Ă���v�i�O�o�q�u�g��i���Ɏ~��v�̎v���o�r�j���ю��q�g��i���Ɏ~��\�\�w�f�B���q�����A�W�A�T���L�r���r�������B�S���W�̕t�^��ǂ��́A����Ɂq�g��i���Ɏ~��r�̕������W�̘^���S�����B�������������Ă����������J�Z�b�g�e�[�v�Ƀ_�r���O���������ɂ͎莆���Y���Ă������̂����A�厖�ɂ��܂��������̂���������Ȃ��B���܂����Ɉ��p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�c�O���ɂł���B����́q�{���r�������Ȃ���A�������炭�͂��́q�g�����r�𑱂��邱�Ƃɂ��܂��B�q���r���A�q�g�����r��ʂ��Ď����ꂽ�����b�Ɋ��ӂ������܂��B�ق�Ƃ��ɁA���肪�Ƃ��������܂����B
�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�܂��A�g������������������N�v�̒����Ƀ����N���āA�s�q�g�����r�́u�{�v�t�̊e�L���ɔ�Ԃ悤�ɂ��Ă����B
�@�@�s���y�n�t�i1961�j
�@�@�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1970�t�i1973�j�Ɓs���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1978�t�i1979�j
�@�@�s�u���v���̂ق��̎��t�i1977�j
�@�@�s���҂����̌Q���镗�i�t�i1982/1983�j
�@�@�s�l�����@���o���t�i1984�j
�ҏW�ψ�����N�v�̋ƐтƂ��Ĉ킷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��s�Z�{ �{�V�����S�W�k�S�\�l���i�\�܍��j�l�t���g���̑����ɂȂ邱�Ƃ́A���߂Č����܂ł��Ȃ��B�����Ƌg�����́A�n�[�h�J���@�[�E�S�W���̂ɂ������\��s�Z�{ �{�V�����S�W�t�ɂ���Č㐢�ɋL������邱�ƂɂȂ邩������Ȃ��B
��1�@�ٕҁs�g�����N���k������2�Łl�t��1991�N�i����3�N�j10���̏��Ɂu�E�ؔn���Łq�g�������Âԉ�r���J�����i���N�l�ѓ��k��A�剪�M�A����N�v�A�푺�G�O�A�����r�Y�j�B��ꕔ�͎i����r�Y�Œm�F�����̎v���o�b�i�������Y�A�ѓ��k��A����N�v�A�]�X���F�A����Y�A���c�v�Y�A�����A���q���`�A���X�؊��Y�A�����L�A���c�q���q�A�푺�G�O�A�߉ϑ��Y�A�����ĔV�A�ĐΔԖ�A��쐟�q�̏\�Z�l�Ƌg���z�q�j�A�k�c�c�l�v�Ƃ��邪�A���̂Ƃ�����́A���A�̂��Ƌg���̎����q�J�J�V�r�i�G�E28�j��S�сi�Ƃ����Ă�15�s�����j�A�N�ǂ����B�Ǔ����ɖS���l�̎������p����悤�Ȃ��̂ł���B�e�L�X�g�͑I���W�s�g�����k����̎��l�P�l�t�i�������_�Ёj�������Ǝv���B�����ɂ́q�m���r�i�C�E8�j���q�T�t�����E�݁r�i�G�E1�j�����^����Ă���̂ɁA�����̎�������ƂɁA���͏Ռ������B
��2�@�u����͂�͂肽���ւ�Ȓ��ю����Ǝv���B�v�́u����v���w�킪�o�_�E�킪�����x�Ȃ̂��A�G���I�b�g�́w�r�n�x�Ȃ̂��킩��Â炢�B�����Ƃ��A�q�킪�o�_�r�̎����378�s������A�s�����琄���Ė{��433�s�́s�r�n�t�̕����ƌ����͂����B
��3�@����͋g���Ƃ̑Βk�̗��N�i1968�N�j���s�́s�킪�o�_�E�킪�����t�́q�u���Ƃ����v�r�ɂ��������Ă���B
�@�{���ƒ��Ƃ��琬�邱�́w�킪�o�_�E�킪�����x�̐���́A���ɂƂ��āA�������Ɉ�̃I�y���[�V�����ł������B�������A���̑S�̂��A����i�ƌĂ�ł悢���ǂ����́A���ɂ͔���Ȃ��\�\�Ƃ��������A���ɏq�ׂ闝�R�ŁA����͂����炭����i�ł͂��蓾�Ȃ����낤�B
�@���̕��c�̒n�́A�����l���̌����ɂقNj߂����ˍ�����s�̎R�̒��ŁA�o�_�����̔��i��ɐ�j�Ɛ������قړ�������������̏㗬�ɂ������Ă���̂����A�����g�́A���鎖������āA�o�_���̏��]�s�Ő���A���Α����ҁA���Γy�n���q�Ƃ��ď\���܂ł����ň�����B���́u��i���ǂ��v�ɂ����鎄�̈Ӑ}�́A���̂悤�Ȉ����̂���y�n�ւ̎��I�Ȉ�����s���̂悢�����ɁA�s���̍��E��̍��t�s���t�t�s�x�����t�s�퐪���t�s���������͂̒����t�Ƃ������e�[�}���̎��Ƃ��Ȃ���A�p���f�B�̃p���f�B��{���i���ǂ��j�ƒ��i���ǂ��j�Ƃőg�ݗ��āA�������邱�Ƃɂ���Ď��́u�����ꐫ�v�u���ȐN�I���v�̖����A���O�ɒǂ��߂Ă݂邱�Ƃ������B�܂�A���̗͓_�́A�u��i�𐬗������邱�Ɓv�ɂłȂ��A�u��i�̐����Ƃ͉�����₤���Ɓv�ɂ������Ă����B
�@���̈Ӑ}���ǂ��܂ł�ʂ���Ă��邩�͒m�炸�A������ɂ�������́A��҂��ǎ҂����ǂ͂��ǂ���ł��낤�u���Ƃ܂��A�n���Ȃ܂˂��c�c�v�Ƃ������A���E�A���邢�͒V���̌����ɁA�͂����ĉ����������Ă��邩�ǂ����A�ł��낤�B�Ƃ���ŁA���A�����g�Ƃ��ẮA���̃I�y���[�V�����ɂقڑS�͂𓊓��������Ƃ����A������Ɏ�������������ɂ͂��邪�A����ɂ��Ă��A�����̏o�_�����̈ӎ��ɂƂ��Ĉ��̑�ȁu�n���v�ł���悤�ɁA���́w�킪�o�_�E�킪�����x�́A����܂����́u�n������v�̑̌��Ƃ��āA�Y�ꂽ���Ă��Y����ʋꂢ�v���o�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@�Ȃ��A�{���ɂ��ẮA���̔@�����\�o�߂����ǂ��āA�{���i���a�l�O�N�����Ŗ{�j�ɂ����čŏI�I�Ɍ��肵���B�u�킪�o�_�i�G�X�L�X�j�v�i�u���Ɣ�]�v���a�l��N�������j���u�킪�o�_�i���̃G�X�L�X�j�v�i�u������Ӂv29���j���u�킪�o�_�E�킪�����v�i�u���|�v���a�l��N�l�����j���{���B�i�s���V�N�v�q���r�W�� 1951�`1994�k�㊪�l�t�A�y�ЁA1996�N12��30���A�O�Z���`�O�Z���y�[�W�j
��4�@��ˎ闝�͋g������Ǔ�����q���Ă̐l�r�i�s���㎍�蒟�t1990�N7�����k�Ǔ����W�E���ʂ� �g�����l�j�ɂ��������Ă���B�u�k�c�c�l�g������Ə��߂Ă�������̂́A���傤�ǁw��ʁx���㈲���ꂽ��̂��ƂŁA���̂Ƃ�����A�ނ́A�����꒷�҂̎������������ƌ���Ă����B������邽�тɁA�₪�ď������ׂ����҂̂��Ƃ��b��ɂȂ������A����͎���U�����݂̂Ȃ炸�A���L���n�ߚ삵�����p�ȂǗl�X�Ȃ��̂����݂�����̂ɂȂ�͂��������B�g����������C�ɂ���Ă����̂́A�����������s���炢�����Β��Ҏ��ƌ����邾�낤���Ƃ������ƂŁA���͂��̎��������邽�тɂs�E�r�E�G���I�b�g�́w�r�n�x�����������ɏo���āA�ܕS�s������Ƃ����������������B����ƁA�g������́A�������A�ܕS�s�ŏ[�����Ɗ��������Ȋ������̂������B���̒��҂����ɏ�����Ȃ��������Ƃ��A���͐ɂށB�v�i�����A�l���`�l��y�[�W�j
�g�����g�́s��ʁt���s�̗��N�A�k�ŋߊS�̂���e�[�}�l�����āu�������e�[�}�̒��ю��v�Ɖ��Ă���i�s������{���M�ґ厖�T77/82 ��l���i�Ё`��j�t�A���O�A�\�V�G�[�c�A1984�N8��25���A�Z����y�[�W�j�B�����āA�ӔN�̋g���������Ɂu���ю��v�ɐ[���S���Ă������A���������m��悤�B
��5�@�܂��k�V �e�L�X�g�l12�s�̍s���Ƀ��C�i�[�ƃ_�[�V�i�\�\�j��t���Čf���A�����Ê�E�t���a�j�Z���s���{��ًL�k���{�ÓT���w��n70�l�t�i��g���X�A��7���F1972�N10��20���k�����F1967�N3��20���l�j�̊Y������Ǝv�����ӏ���Ԃŕ\�����Ĉ����B�Ȃ��A�����͐V���ɉ��߂��B�܂��A���p�����̃Q�^�i���j�͂o�b�ŕ\���ł��Ȃ����߁A�����y�@�z���Ńp�[�c�ɕ����Đ��������B
01�\�\�u���m���Â�n���m���Â��n�ď��̎���H��
�E01�s�\�\���ȁm���̂��n�ɔӁm�N�n���j�V�N�l�\�]���ȂāA�X�ɊތA�m�C�n���n�ɋ���A���m���Â�n���m���n�A�����a�m�́n���A�����̐�🔁m���n�݁A�~�E�m�悭�����n�̍C���m�X�X�n�L�A�E���̙�@���C�K���A��ق̌��p����������B�i�s���{��ًL�t�㊪�q�E�����m�����₭�키�n�̙�@�m����قӁn���C���m������n���A�فm���n�������͂āA���ɐ�ƍ�m�ȁn��ēV�ɔ�ԉ��@���\���r�A�����A��O�܃y�[�W�j
02�\�\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���́i���m���Ђ��n�j���ςĐH�m����n�Ђ�
03�\�\�K�E���͎���
04�\�\�@�@�@�@�@�@�@�@�i𨳯�m�܂�n�j���z��
05�\�\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�i嬭�[�m���Ԃ��n�j�͒���
06�\�\�i�J�m���ځn�̌��j���
07�\�\�@�@�@�@�@�@�@�i�_���m���܂��Ёn�j�����点��
08�\�\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��فm����n�j����������
09�\�\�j�Ă₪�Ă�
10�\�\�@�@�@�@�@�@�i���r�Y�m�������˂��炷�݁n�j�̏��
11�\�\�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S�ہm�Ă������n�j��u���ēۂ�
12�\�\�n���ɑ��ށv
�E02�s�\�\�V�N�m�ЂƂƂȂ�n���ɂ��āA���ʂ�M�m���n���s�m���n�A������̗������߂āA�ςĐH�����Ɓm�킴�n�Ƃ��B�i�s���{��ًL�t�����q��ɒ��̗����ςĐH�ЂāA���Ɉ����̕�鉏�@��\�r�A�����A��Z���y�[�W�j
�E03�s�\�\�͓��̍��X�r�m�����n�̌S�n�Ám���܂��Ёn�̗��ɁA�x�߂�ƗL�m���n��B�Ƃɏ��q�m���݂ȁn�L�m���n��B�吆�m���قЁn�̓V�c�̂ݐ��ɁA�V���O�N�Ȉ�m���̂Ƃ�n�̉Ďl���A���m���n�����q�m���݂ȁn�A�K�ɓo��ėt�𑵁m���n���B�i�s���{��ًL�t�����q���l�A��ցm���낿�n�ɍ��m���Ȃ��n�͂�A��̗͂ɗ���āA����S�����邱�Ɠ��鉏�@��l�\��r�A�����A���O�y�[�W�j�^��O�N���o�āA儵�m�����n�k倐�m�܂��n�l�ɕa�A���I�͂鎞�ɗՂ݁A�q��𨳯�m�܂�n唼�m���n�ЂāA�z�����Ђ��B�i���O�A���܃y�[�W�j
�E04�s�\�\���A����ɍ����炭�u���m���n�̏��A�搢�Ɉ�m�ЂƂ�n�̒j�q���Y�ށB�[�����S�����сA���Ɂk���m���n�l�̎q��𨳯�m�܂�n�����y�u���v�Ɂu�W�v�z�m���n���B�i���O�j
�E05�s�\�\���m�ӂ��n�������m�n�n���^���R�m�傫�ɂ��āA���ˁm���܂ǁn�̔@������A�����^�m���݂���n����B�i�s���{��ًL�t�����q���l�m�ɂ�ɂ�n�A���m�~�_���K�n�n�V�N�Łm�Ƃn���āA�q����m���n�ɋQ��ނ邪�̂ɁA����鉏�@��\�Z�r�A�����A�O�Z��y�[�W�j
�E06�s�\�\�k�c�c�l�J�m�Ёn�̌��ɏ`�����B�i�s���{��ًL�t�����q���l�A��ւɍ��͂�A��̗͂ɗ���āA����S�����邱�Ɠ��鉏�@��l�\��r�A�����A���O�y�[�W�j
�E07�s�\�\���m���n���_�m���܁n�k���m���Ёn�l�́A�Ɓm���Ӂn�̈����ɏ]�ЂāA���m���n��͎֔n���������ɐ��܂�A��̈��_�ɗR��āA�ւƈׂ�Ĉ����m���Ȃ��Ёn���A����͉��{���ƈׁm�ȁn��B�i�s���{��ًL�t�����q���l�A��ւɍ��͂�A��̗͂ɗ���āA����S�����邱�Ɠ��鉏�@��l�\��r�A�����A���܃y�[�W�j
�E08�s�\�\���m���n�̎����тɏZ�ލs��哿�m���₤�������Ƃ��n�́A����t����F�̔����m�ւn�Ȃ�B������فm�߂Â�n�������Ȃ��B�i�s���{��ًL�t�㊪�q�O���M�h�m���₤�n���A����鉏�@��܁r�A�����A�����y�[�W�j
�E10�`12�s�\�\�@�Ԍo�ɉ]�͂��u���m�Ƌ�m�Ɠ����ʂɋ��邱�Ɠ��s�m���n�B���m�܂��n�����̔�u�m�т��n�́A���߁m�т₭���n�̔�餁m�͂т�n����s�m���n���Č��Ȃ�ƁA�ʂ�������������ėp��邱�Ɠ��s�m���n�B�Ⴕ���ЂĈʂ���҂́A���m�������ˁn�Y�m�A���Y�~�n�̏�ɓS�ۂ����m���n���ēۂ݁A�n���ɑ����v�Ƃ��ӂ́A���m���n��z�m���n������ӂȂ�B�i�s���{��ًL�t�����q�@�Ԍo��ǂޑm��呰�m�������n��āA���m���n�Ɍ�喎�m�䂪�n�݂āA�����̕�鉏�@��\���r�A�����A��O�O�y�[�W�j
��6�@�S�W�S�̂̕Ҏ҂ł�����r�V�Ď����s���{���w�S�W�k��29���l�ߌ��㎍�́t�i�͏o���[�V�ЁA2016�N9��30���j�őI�g�������́A�i�����ł��܂��j�q�m���r�i�C�E8�j����������A���]�ł͋g���́s�m���t�^�q�m���r�̎��l�Ƃ������ƂɂȂ�̂��낤�B���������Ӗ��ł́A������܂��s�킪�o�_�E�킪�����t�̎��l�Ƃ������ƂɂȂ�B������1968�N���s��5�N��A�s���㎍�W�k������{���{��n93�l�t�i�}�����[�j�ɑI�ꂽ���肩�A���I��i�I�j�ɂ��A���������\����v�v�̓��{���w�S�W�ɒJ��r���Y�⍂���r�Y�̒����ƂƂ��ɍ̂�ꂽ�̂�����B
��7�@�{�����s��ɏo������N�v�ďC�E����́s�{���u��͓S���̖�v�̌��e�̂��ׂāt�i�{���L�O�فA1997�N3���k���ɂ��̋L�ڂȂ��l�j�́A�����̂`�S���̖{���Ɂu�S���e�v�u�n�상�����e�v�u���e���ʁv���J���[�ʐ^�Ōf�ڂ��Ă���B����͂���旧����20�N�ȏ�܂��A�q�u��͓S���̖�v�̖{���̕ϑJ�ɂ��Ă̑Θb�r�i���o�F�s�{�����b�̐��E�k���{�������w�ʍ��l�t�A���鏑�[�A1976�N2���j�̖������u�k�c�c�l�^�܂��A���z�{�Ƃ͕ʂɁA�����҂̂��߂̊��{�Ƃ��āA�S���\�O���̌��e�Ƃ���ɂ܂�郁���ނ̂��ׂĂ��ʐ^�łɂ�����ɓǂ݉�����Y�����{���o����邱�Ƃ��A���ꂾ���̓��e�Ƒ����̖��_���͂��ł��邱�̍�i�̏ꍇ����߂Ė]�܂������Ƃł��B�^�\�\����炪�������Ƃ��A�u��͓S���̖�v�́A���S�ɖ��l�̂��̂ƂȂ�̂ł��ˁB�^�\�\�܂��������̒ʂ�ł��B�v�i�s�{���\�\�v���I�V���C�݂���̕t�A�ꎵ���y�[�W�j�ƒ��߂������āA���̏o����Җ]���Ă����B���́A���W�s�Õ��t�̋g�������M�̍e�{�\�\�g���́u�킽���̑�Ȃ��́v�Ƃ��āu���W�s�Õ��t�̌��e�i����͏������̂ɁA�B��̌��e�̎c���Ă�����́j�B�v�i�q�R���̃A���o���r�A�s�u�����v�Ƃ����G�k����Łl�t�A�}�����[�A1988�A�l�܃y�[�W�j�Ə����Ă���\�\���ʐ^�Łi�⌴�{�̑����⎆���܂ōČ����������j�̌`�Ő��ɏo����A�ǂ�Ȃɑf���炵�����낤�ƒV�����ւ����Ȃ������B
�k2019�N6��30���NjL�l
�{�e�̗����A6���Ɏ��M���������N��̊֘A�����̂Ȃ��ɁA�����Ɠ���N�v�̑Βk�q���t�V�тƂ��Ă̎��r�i���o�́s�b�̓��W�t1980�N11�����j���������B��l�͂����ŁA��́u�����ɂ���č��ꂽ�o�b�e���`�v�̓ǂݕ����߂����āA�ӌ������킵�Ă���i�Βk�̖{���́A�����܂ł��Ȃ��c�g������A�{�T�C�g�̉������\�����c�����ɕϊ����Ă��ǂ݂������������j�B
�@�����@��������ƁA���́~�m�o�c�n���`�̂Ƃ���́A���ʂ̍s�ւ��œǂނƁA�ǂ����������ł����B
�@�����@�܂��A�E�ォ�牺�Ɍ܍s�����A���ɉE�������̉��u�[�z���܂Ƃ��ɏƂ����v�܂ł����A����ɍ���܂ł����āA�Ō�͍����ɂ���B
�@����Ȃӂ��ɕ��בւ��鎞�ɁA�����̖��Ƃ��Ă͂�����Ԏ�炸�ł�����ł��B�������A���܂���ɁA��̗��e�ɓ������J���Ă��܂����A����͐_�Ђ̉����̏�ɂ����m�����n�̌`�̂���Ȃ�ł���B
�@�����@�����A��������ƁA���́~���`�͏o�_��Ђ̕����I�\�������f���ɂ��Ă����ł��ˁB
�@�����@�����A�o�_��Ђ̐�́A���傤�ǂ��̂悤�Ɍ����J���Ă����ł��i�j�B
�@�����@�`�̖ʔ����̂ق��ɁA�~���`�ɂ��Ă��܂��Ɗ��ʂ肩�ɓǂ߂邱�Ƃ̖ʔ���������܂��B�ǂ�����ǂݎn�߂Ăǂ����i�ނ��A�ǎ҂����߂�����B
�@�����@���������`�ɂȂ��Ă��܂��A�S�Ď��R�ł��B�ǎҎQ���Ƃ����܂����A����͂ڂ����ȑO���猾���Ă��鎝�_�ł������ł��B�v����ɓ��{�ł͂��܂�ɂ��A���Ƃ������̂��A��Ҏ��g�̎v�������Ƃ��̂��̂�`���铹��Ǝv��ꂷ���Ă���Ǝv����ł��B�����ł͂Ȃ��āA�������ɂ��ēǎ҂����g��������̂ł͂Ȃ����c�c���������v��������킯�ŁB�i�����N��Βk�W�s�A���X�̍��̌��t�����t�A�V���فA1981�N7��10���A�ꔪ�O�`�ꔪ�l�y�[�W�j
����ɂ��Ă��A���̑Βk������p���w�̐��G���ł͂Ȃ��A�ҏW���E���v�́s�b�̓��W�t�ɍڂ����Ƃ������Ƃ́A1970�N��̃W���[�i���Y���̒�͂������Ă���悤�ŁA�|�낵���قǂł���B
�q�g�����r�����k���O�l�@��
|
|
||||
|
�����N�̓g�b�v�y�[�W�s�g�����̎��̐��E�t�ɐݒ肵�Ă��������B |
|
|||
|
���ӌ��E�����z�Ȃǂ̃��[����ikoba@jcom.home.ne.jp�܂ŁB |
|
|||
|
Copyright © 2019-2021 Kobayashi Ichiro. All Rights Reserved. |
|
|||
|
�{�E�F�u�T�C�g�̑S�����邢�͈ꕔ�𗘗p�i�R�s�[�Ȃǁj����ꍇ�́A |
|
|||
|
|
|
|
|
|